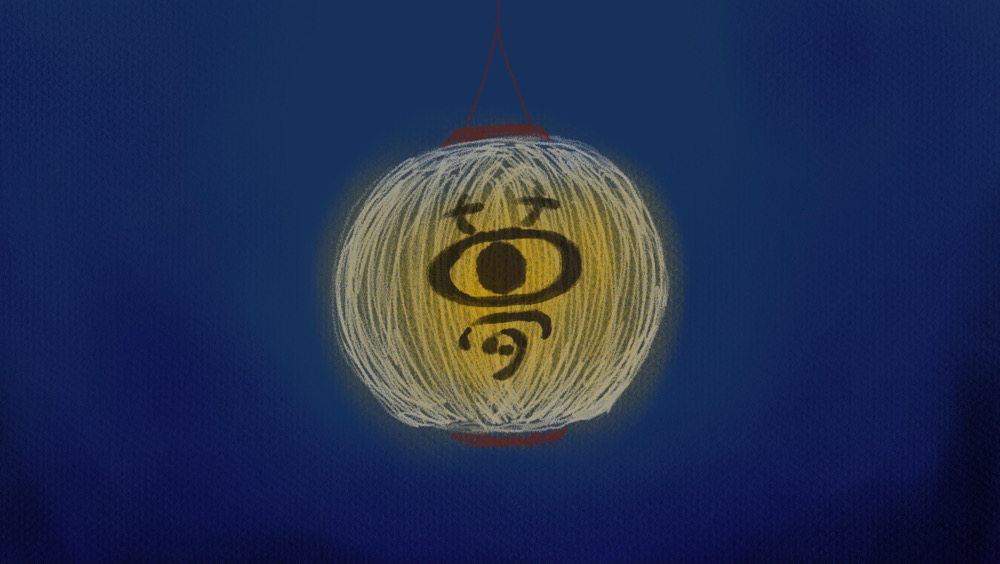
【夢見ノ記】第四話 夢の値段
【夢見ノ記】シリーズ
第一話→ https://slib.net/104460
第二話→ https://slib.net/105423
第三話→https://slib.net/107520
路地裏にひっそりと、その店は開業していた。店先に看板はない。象形文字のような、「目」の部分が強調して描かれた提灯がぶら下がっている。
初めてつれて来られた睡には、物珍しく映った。提灯に何が描かれているのか尋ねると、それは「夢」という字だと守は言った。
守は神妙な面持ちで、風呂敷包みを小脇に抱えて店の前に立っている。ふうっと呼吸を整えて、暖簾をくぐった。
守の後を追いかけて、睡は店へ入った。店内の商品棚には様々な品物が飾られて、値札がついている。雑多な物が統一感なく置かれていて、なかには枕や寝間着まであった。一体どんな客層へ向けて商売をしているのか謎である。
店内に客はおらず、受付台に店主らしき女が一人いるだけだ。
「おやまあ。あんた、ずいぶん可愛らしい子をつれているじゃないか」
丸眼鏡をくいと持ち上げて、年かさの女は笑った。波打つ白髪は肩口でばっさりと切りそろえられ、額の生え際は美しい弧線を描いている。
こんにちは、と睡は挨拶した。店主は睡をまるで品定めするかのように、じろじろと眺めている。
「いらっしゃいませ。うちは夢を扱ってる、夢専門の質屋ですよ」
質屋の店主は、にいっと笑んだ。細めた目元や口の端を引いた顔が狐に似ていた。
他人の夢を売り買いする、夢専門の質屋ということだ。夢を担保に金を借りるそうだが、そういう輩は十中八九買い戻しに来ることはない、と質屋は言う。
「それで? 坊やは何を持ってきたんだい?」
質屋が「坊や」と呼ぶと、守は嫌そうな顔をするが文句は言わない。どうやらよっぽど世話になっているようだ。
守は風呂敷包みを差しだした。質屋は受け取り、布を開いて中身の品をまじまじと見つめる。そこには、きれいに折りたたまれた着物があった。
質屋は鼻をつきだし、くんくんと匂いを嗅いだ。
「あんた、こりゃあダメだね。一文にもならないクズだ」
ポイッと投げ返されて、守は渋面を作る。
「どこの馬の骨から買ったか知らないけど、こりゃあんた騙されたね。何の面白みもないただの物だ。夢のかけらも残っちゃいないよ」
ずけずけとした物言いに、守は必死で堪えているように見えた。質屋はそれを分かっていてか、あえて嘲るように笑う。
「あんたのうちには、他に色々いい物が眠ってるだろうに。出し惜しみしてないで持ってきな」
「それは断る」
「はっはあ。じゃあ一昨日来るがいいさ」
質屋は興味を失ったようにそっぽを向き、手をひらひら振って返した。
帰り道は日が暮れていた。げんなり憔悴している守を横目に見ながら、睡は自分の影を追いかけるように歩く。
「俺、何か役に立てた?」
そろそろと様子を窺うように、睡は声をかけた。守は不機嫌そうに口をとがらせた。
「あの婆さんは、がめつくて有名なんだ。おんな子どもにはちょっと優しくなるんで……お前がいれば、あの婆さんの態度が少しでも軟化するかと思ったんだが。やっぱり食えない人だ」
はあ、と守は大きなため息をつく。
「守って、お金ないの?」
その言葉で、守の表情が固まった。
「俺、もう守の家で食ったりしないからさ……」
「馬鹿やろう! ガキがそんな心配するな!」
帰ったら飯にするぞ、と言う守。食べて行けと言うまでもなく、頭数に入れられていることに、睡はちょっと嬉しく思った。
暖簾をくぐり、睡は質屋へ「こんにちは」と声をかける。
「おや、嬢ちゃん。いらっしゃい」
「エバちゃん、これいくらで預かってくれる?」
今日は守に頼まれたお使いで来ていた。店の中は相変わらず閑散としていて、主人の質屋しかいない。お客はもっぱら夜が多いとのことだが、本当に儲けがあるのか疑わしかった。
目の前に出された品物を見つめ、質屋は鼻をひくつかせて嗅ぐ。しばらく吟味し、
「これならほれ、これくらいってところだね」
と、算盤をはじいて見せる。守が提示していた希望額にはとうてい及ばない数字を見て、睡は思わず声をあげた。
「エバちゃ~ん。もうちょっと、ね?」
「ふふふ。うちは慈善事業じゃないからねえ」
「そう言わずに! ね、お願いだよ~」
「いくら嬢ちゃんの頼みでも、こればっかりはびた一文まからないね。守にもそう言っときな。子ども使うなんて小細工はきかないよ、ってね」
そう言われてはしかたない、と睡もそうそうに諦めた。守に何を言われるか分かったものではないが、そんなこと知るものか。とりあえず粘ってみた、という体裁だけは繕ったのだから良しとしよう。
「あんながめつい婆さんの名前なんて、奪衣婆で十分だ」と、守が言っていたのを思い出す。地獄で亡者の着物を剥ぎ取る老婆が「奪衣婆」ということだ。質屋の顔馴染みは陰で皆そう呼んでいるらしく、質屋の本人も知っていて容認しているとのことだ。
親しみをこめて、睡は勝手に「エバちゃん」と呼び始めた。質屋は文句を言うでもなく受け入れているので、その呼び名を気に入ったらしい。
「嬢ちゃんは、夢へ行くのが得意なんだってね」
質屋が興味津々で話しかけてきた。睡は素直に答えた。
「得意というか、当たり前ってだけだよ」
「ほうそりゃあ、たいしたもんだね。立派な才能だ」
「でも俺、夢に行けるってだけで、そんなの気にしたことないから。逆に夢へ行けないってほうが……」
睡がぽろりとこぼした言葉に、質屋は目ざとく食いついてきた。
「それは、守のことかい?」
睡は口をつぐんだ。
質屋は懐から煙草を取り出し、「いいかい?」と睡に伺いを立てた。睡は頷く。一本取り出して火をつけ、質屋は煙草を大きく吸いこんで、ふううぅぅと長く吐いた。
「守は夢を見ない。あの子は生まれつきの体質だからね。そもそも夢を見るということが、どういうものか分からない」
と、質屋は言う。
「俺には夢に行けることが当たり前すぎて、難しいことだなんて分からないよ」
「じゃあ、アタシの夢に来てごらん」
質屋の言葉に、睡は目をしばたたく。質屋は目を細めて笑った。
「なかなか難しいよ。アタシの夢は特別だからね」
睡は自信があったので、あっさりと二つ返事で受けた。
ふぁ、と欠伸をもらしながら、睡は鳥のくちばしへ水飴をあげる。
昨夜は質屋の夢を探し続けて、眠りが浅くなった。結局見つからないまま諦めて、睡魔に襲われながらも守の家へ来た。
「なんだ。夜更かしでもしたのか?」
守は、お茶漬けを出しながら言う。梅干し、温泉卵がついていて「今日はこれだけだ」と、素っ気ない。そんな気を遣わなくていいのに、と言えば怒るので、睡はありがたく頂戴する。実際、おなかはペコペコなのだ。
「昨日は、エバちゃんの夢を探してたんだ。でも見つからなかった」
睡はお茶漬けをかきこんで、梅干しをつまんだ。すっぱくて、口がすぼまる。
守の顔色が曇った。
「あの婆さんが、お前にそんなことを言ったのか?」
「そうだよ」
「睡。その夢を探すのは、やめろ」
「どうして?」
「なんでもだ!」
思いのほか強い口調に、睡は少し驚いた。守も怒鳴ってしまったことが気まずかったようで、顔を背けた。
空になった茶碗を見つめて、睡は言った。
「守」
呼んでも返事がない。
「おかわり、ある?」
「お前……遠慮、って言葉知ってるか?」
夢で特定の人物を捜すとき、それは残り香を追うようなものだった。点々と落ちている目印を探すように、残っている香りを拾っていく。その人独特の香りが強い人もいれば弱い人もいて、釣り人や鳥飼いはわりと簡単に見つけやすかった。
今回のエバちゃんもそうだ、と睡は霧の中を進みながら思った。質屋が吸う煙草の香りがする。その跡をたどりながら歩いていった。
確かに香りがする方へ向かっているのに、行けども行けども辿り着かない。周囲は白い霧が立ちこめ、ぼんやりと景色の影が浮かぶ。何もない空間を歩いているようでもあり、森の中をさまよっているような気分でもある。
しばらく歩いて、睡は立ちどまった。
「ああ、まただ」
思わず言葉をこぼす。
また迷ったのだ、と睡は思った。
「全然見つけられない! どうして?」
睡はとうとう降参した。
質屋は楽しそうに笑っている。問題が解けなくて四苦八苦している生徒を見つめるような目で、睡の様子を眺めている。
あれから毎晩、質屋の夢を探すのだがどうしても見つからない。こんなことは初めてだった。何度か会った知り合いならば、いつもなら難なく夢を見つけられたのに。質屋に関してはお手上げだった。全く見つからない。
睡は素直に悔しがった。それを見て、質屋は満足そうに笑んでいる。
「エバちゃん、一体どこに隠れてるの? ヒントでも、ちょっと教えてよ~」
「ふっふ~ん。ただで教えちゃやらないよ」
「そんなこと言わないでさ~」
「じゃあ特別にヒントをあげよう」
睡の顔がぱっと明るくなる。
質屋は耳打ちして、自分の名前を睡に教えてくれた。
その夜は、いつもと違っていた。
質屋が教えてくれた名前のおかげか、今晩の夢は正しい道を歩んでいる確信があった。いつもと匂いが違うのだ。今までは煙草の香りが強かったが、今夜は石けんのような匂いがしている。
それが本来、質屋の夢の足跡なのだと、睡は気づいた。日中に質屋が吸っていた煙草は、香りによる目眩ましの効果があったのかもしれない。食えない婆さんだ、と毒づく守の気持ちを少し分かった気がする。
ふと視界が開けて、睡は裏木戸の前に立っていた。戸を開けて入ると、そこは民家の庭だ。花壇には花が咲き、陽射しがこぼれて木々の葉影を地面に落としている。
縁側に一人の女性が腰かけている。黒髪を結わえた三十代くらいの女性だ。
「おやまあ、驚いた。こんなに早く来るなんて」
と言う女性の声は、若く張りがあるが、聞き慣れた質屋のものだった。手招きして呼ばれたので、睡は縁側へと近づいた。
若くなった質屋は、睡を感嘆の目で見つめる。姿こそ見慣れないが、声と瞳は変わらず質屋のエバちゃんなので、睡は少し安心した。
これはなかなかの逸材かもしれないよ、と質屋は褒めた。
「ここ、エバちゃんの家?」
「そうだよ。そして、あれが旦那と子ども」
庭でシャボン玉を吹いて遊ぶ幼い子どもと、その子につきそう男の姿は若かった。
「ここはアタシの庭だ。夢という箱庭……ここには全てがそろってる」
まあ、ここへお座りよと、言われるままに縁側へ腰かけた。
庭では、子どもが吹いたシャボン玉がふわふわと飛んでいる。きゃっきゃっと笑う幼い声。父親の優しい笑顔が、木漏れ日のなかで眩しく映る。
質屋は睡の隣に座り、同じように庭にいる家族を見つめている。その眼差しは暖かい。
そこには親子の愛しさにあふれた光景があった。この景色が輝いて見えるのは、夢を見ている本人の願望が強いおかげだということを、睡は知っていた。ここはエバちゃんだけの夢なのだ、と。
「ねえ、嬢ちゃん。あんたも夢を見るだろう?」
質屋の言葉に、睡は頷いた。
「〈夢見〉は、自由に夢の行き来ができる。そして、自分の好きな夢を見られる。夢を作る、と言ってもいいかもねえ。それも飛びっきり都合の良い夢だ」
質屋が言わんとするところも、睡にはなんとなく分かった。
「虚構だと分かっていて、あえて自分に都合の良い夢を見るのはいいけど。これは下手すりゃ溺れて戻れなくなるからね。そのバランスを保つのが、夢見にとって一番難しい」
「エバちゃんは、俺に説教したいの?」
ふいに質屋は声を立てて笑った。
「ああ、いいねえ。あんたみたいな子は、好きだよ」
てらいもなく言われて、睡はどう答えていいのか困った。ほてったように体が熱くなる。質屋の言葉を、単純に嬉しいと思った。
質屋はクックッと笑いながら、
「アタシが言ったところで説得力なんてないだろうね。残りの人生、この夢のために生きてるような人間が……」
と自嘲気味にこぼして、庭へ視線を戻す。こちらへ手を振る子どもに、手を振り返す質屋を、睡はじっと見つめた。
「エバちゃんは〈夢見〉なの?」
「元は夢見で商売してたけど。今は、しがない質屋だよ」
「エバちゃんさ、もしかして守に何か根回しした?」
「おやまあ。どうしてそう思うんだい?」
「守が俺をエバちゃんに会わせたのにさ。守は俺に、エバちゃんの夢を探してほしくないって言うんだ。関わらせておいて、関わるなっておかしいでしょ。何か、エバちゃんから頼んだのかな~って」
「ふふふ。鋭いじゃないか。アタシがあんたに会いたいと言ったのさ」
おそらく脅したのだろう。容易に想像がついて、睡は思わず笑った。
「夢見の素質があるようだと聞いたら、気にもなるさ」
誰からとは聞かなかった。守が言うようには思えないので、おおかた鳥飼いあたりから情報を得たのだろう。
「あの坊やの傍に、あんたのような子がいるなんて。どんな巡り合わせか……不思議なもんだと興味がわいてね」
「どうして?」
「そうさね。これはアタシが言ったなんて内緒だよ」
質屋は声を低めた。夢の中なので誰に聞かれることもないのだが。
「守の夢を見られない性質は、夢見の相棒として適任なのさ」
質屋が言うことには、夢に全く関われないために、現実にしっかり根づいている人間が守なのだそうだ。それゆえに、夢から現実へ帰る道しるべとして最適なのだとか。帰るべき場所を照らす灯台のようなものだろうか、と睡は考えた。
夢で迷子になることが一番恐ろしいのだと、質屋は言った。迷いそうになったとき、現実と確かに繋がる命綱として、守の存在はかっこうの目印になるらしい。
それを聞いて、なんだか合点がいった。睡が今まで不思議に思っていたのは、夢を見ることがない守が、なぜ夢に関わっているのかだった。
「守には、夢見の相棒がいたの?」
「ああ、前はね」
質屋は懐かしむように口にする。
「アタシの弟子でね。才能のある、気立ての良い子だった」
「その人は今、守の相棒をしてないの?」
「そうだよ。夢に深入りしすぎて……死んだからね」
いくつものシャボン玉が空に浮かび、ぱちんと弾けて消えていく。
子どもの無邪気な笑い声が、明るく響いて聞こえた。
「ねえ、睡。アタシの弟子になって〈夢見〉の修行をしないかい。このまま生まれ持った才能だけで夢を見れば、いつか足もとをすくわれるかもしれない。夢はね、一歩間違えれば恐ろしいのだから」
「どうして俺に親切なの?」
「年を取ると、お節介がしたくなるんだよ。若い者が自分より先に逝っちまうのは、やりきれないからねぇ」
質屋は言葉をにごして、庭に飛んでいるシャボン玉を眺めている。寂しそうな横顔を見つめながら、睡は「考えとくよ」と返事をした。
*******
質屋の夢から戻った朝は、奇妙にすっきりとした目覚めだった。
睡がいつものごとく守の家を訪ねると、「手伝え」と言われて、空豆の皮むきをさせられた。
居間で二人、黙々と作業に集中する。
はたと手をとめ、睡は守に尋ねた。
「ねえ、守。エバちゃんって、家族は? 旦那さんとか子どもとか」
「んん? あの婆さんはずっと独り身のはずだぞ」
「……そう」
睡はうつむき、手元の空豆を見つめた。緑色の固い皮の中は、白いふわふわのわたが豆を覆っている。空豆は、まるで羽毛の布団にくるまれて眠るかのようだ。
質屋が見せてくれた夢は、彼女だけの秘密だった。
人にとって侵してはならない領域の夢がある。
それが誰にもあることを質屋は教えてくれた。彼女の過去は夢に包まれ、日々を生きていく糧になっているのだろう。
「守」と睡が呼ぶと、守は「なんだ?」と何の気なく返事をする。
「俺、エバちゃんの弟子になる」
「は?」
「夢見になるよ」
そう言って顔をあげ、睡は守を正面から見つめる。
守はあんぐりと口を開けていた。手元から、ころりと空豆が一粒ころがり落ちた。
面白い顔してるな、と睡は思った。
【夢見ノ記】第四話 夢の値段


