 星空文庫の作品リスト 129
星空文庫の作品リスト 129

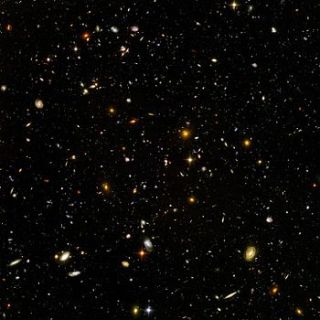
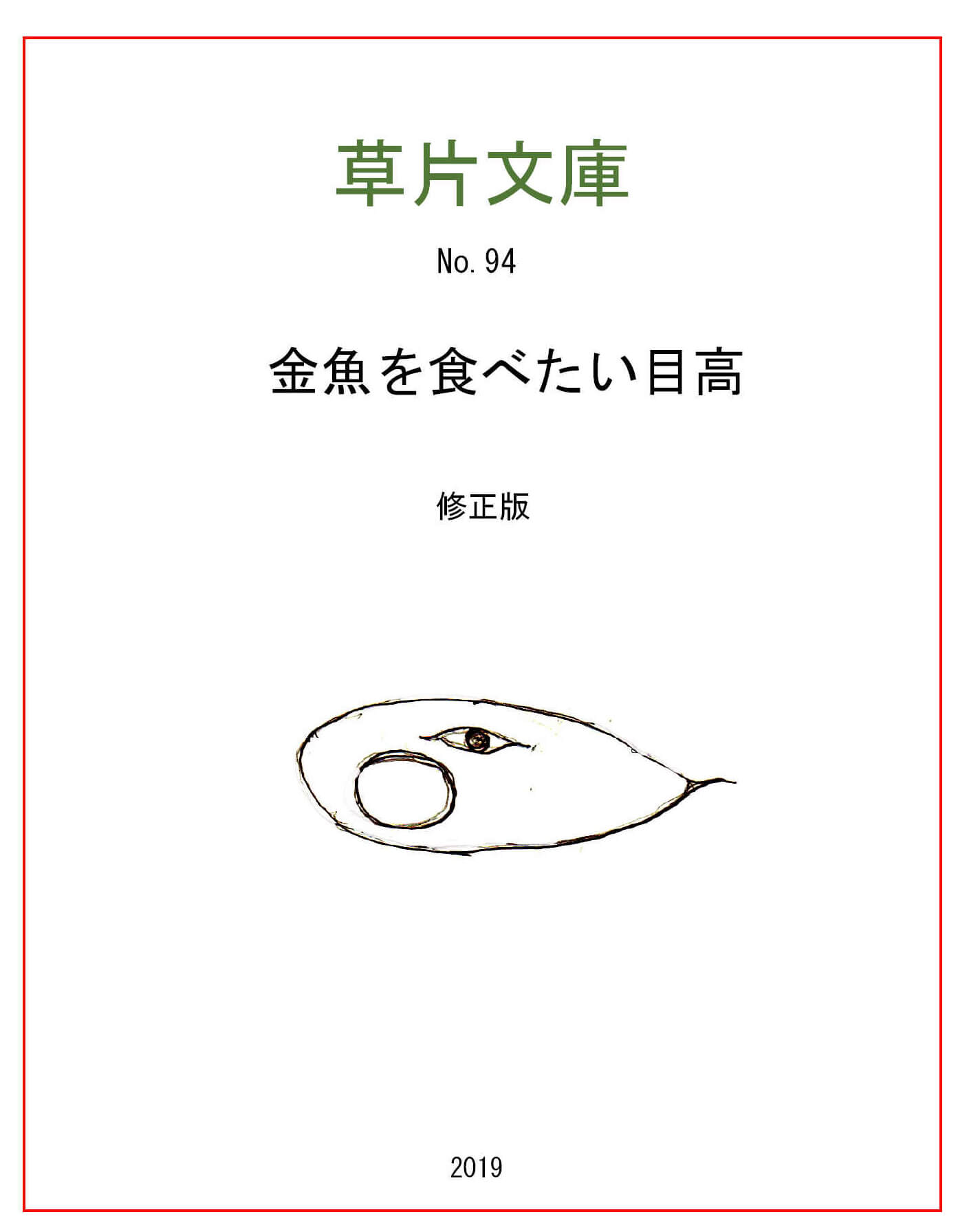

そういえば初めての男は父親だった。主体性がない、そうよく言われる。自分の意思を伝えないで、人に流されてばかりだから、きっとエイズにかかったのだ。頼まれると嫌といえない。客の要求するプレイはどんどんエスカレートしていく。私は嫌と言えない。言いたいのかもわからない。私はすずめのように群衆に紛れて、生きている。



僕は何かの用途を感じてこの店のドアを開いたはずなのに、それが何だったのか。もはやわからなくなってしまった。暗闇の中、僕が本当に望んでいたものは何だったのか。そして、これだったのか?

不定期シリーズ「死神機構」第3段。 アクの強い死神ツインズのお話。余談ですがデフィシエンシーは「欠乏症」という意味があります。
不定期シリーズ「死神機構」第2弾。 #0の後日譚。葬儀屋から可憐な少女の死体を貰ってしまった墓守。とりあえずお世話に徹するも、どうやら彼女は特別な存在のようで、、?
不定期シリーズ「死神機構」第0弾です。 今回は機構内でも肩を並べる、なんだかんだお偉いさんな死神2人のなんてことないお話。

帝国の端、国境線に接した街、グロウ・ゴラッド。 帝国から存在しないものとして扱われた、逃げ場のない街。 そんな街で生まれ育ったビーツァとシエレイ。久しぶりに再会した二人は、街の外れにある一つの酒場で酒を酌み交わす。そこは、無愛想な看板娘の名前を冠した、「血まみれジーニャ」という物騒な名前の酒場で。 ――この酒場で起こる波乱とその結末に、彼らの生き様が刻まれる。 そんな物語も、旧友たちが当たり前のように店に入るところから始まって……
恵まれない青春を送ってきた女の子、珠城柚子。ちっぽけな彼女が、小さな失恋を胸に《女王》へと成り上がっていく物語。 そして成り上がった後の愚痴。