
黄昏紅花
自然の化身をヒトとした「竜」の、古における神々との削り合いのファンタジー。
※R13程度の性描写があります
DragonシリーズD0でありながら、登場人物はほぼCry/シリーズの系譜です。
拙作で最も古い時間軸の話で、別作Cry/zero『雑種化け物譚』は多分この話の数百年後になります。
❖『女神の絵本』:DシリーズにおけるCry/シリーズ・雑種化け物譚の真相。
→エブリスタ作品紹介特典内掲載(P.11):https://estar.jp/extra_novels/25916859
❖『黄昏紅花』:魔竜の起源。古の反則が生み出した切ない物語。
→星空文庫限定掲載。濃厚関連作D3:https://slib.net/119597
update:2025.12.13
Dragon series常設場:https://www.novelabo.com/authors/4396/series/332
Cry/ series常設場:https://www.novelabo.com/authors/4396/series/328
❖女神の絵本
それは、魔物となった女のコと、「夜」の神様のあやまちのお話。
2023.10.13 雑種化け物譚挿話
遠い昔、天には一匹の空の獣と、三人の「空」の女神がいました。
「空」の女神は、仲の良い姉妹でした。秩序の光を灯し、正義の翼を生やし、平和の夢を咲かせる彼女達を、空の獣も愛していました。
けれど、空の獣は一匹だけです。女神達は朝と昼と夕に分かれて、空の獣と一人ずつ過ごしていました。
ある時、正義の女神の翼に、黒い夜が宿ってしまいました。正義の女神は、空の獣を独り占めしたい、そう思うようになり、それは「正義」ではないと苦しみ始めます。
たった一人で思い悩み、正義の女神は決めてしまうのです。自分達、「空」の女神が一つになれば、みんなが空の獣を独り占めできるのだと。
「それで……そらの女神さまたちは、どうなったの?」
海の近くに棲む、黒い竜の血をひく女のコは、この本が大好きでした。
小さい頃から、離れ離れになっていたお姉ちゃんが帰ってきて、お姉ちゃんは何度もこの本を読んでくれました。
「そうだねぇ。続きはまた今度ね? ミリィちゃん」
お姉ちゃんはいつも、同じところまで読んで女のコを眠たくさせます。
女のコはそのまま、寝かしつけられてしまいます。だからその物語の先で、正義の女神が、平和の女神と秩序の女神の命を奪ったこと。それで翼も服も真っ黒な夜になり、空の獣と離れていったことを知りません。
お姉ちゃんも女のコも、真っ黒な髪を持っています。しかしある日、大切な家族が急に引き離されて、お姉ちゃんも何処かへ行ってしまった後、女のコはお姉ちゃんの髪が真っ白になる夢を見ます。
「どうして……ピア……? どこに、いっちゃうの……?」
大人になったお姉ちゃんは、知らない赤い鎧を着ていました。
その鎧がお姉ちゃんの血で、黒く染まりました。何かと戦うお姉ちゃんを追いかけて、山の中まで走ってきた女のコは、倒れているお姉ちゃんに泣きながら縋りつきました。
「やだ、ピア、いなくなっちゃいやだ……!!」
その時、涙を流した女のコの片方の目から、とても熱い光が辺り一帯を包みました。
光が治まったあとには、女のコの涙を浴びたお姉ちゃんが、起き上がっていました。
お姉ちゃんはとてもびっくりとした顔で、座り込む女のコの顔を両手で包み、青くなった目と白い髪で女のコを覗き込んできました。
「どうして……ミリィちゃん……?」
女のコの目が、一つ、光を失って重い青になっていました。
けれどそれで、お姉ちゃんの怪我は治り、女のコのところに戻ってきてくれました。
良かった。女のコは確かに心から喜び、お姉ちゃんともう一度一緒に暮らす夢が叶ったのですが……。
それから数年後、お姉ちゃんは可愛い男の子を授かりました。
長く続いた隣の国との争いも終わり、子供を兵隊にとられる心配がなくなった良い時代になりました。
「おめでと、ピア。またすぐお仕事って、大変だけど……」
「うん、ありがと。トラスティが孤立しかかっててさ、今が一番大事な時期だと思うからさ……」
平和にこっそり貢献したお姉ちゃんは、国王様のお付きの人になっていました。お姉ちゃんの旦那さんは、双子のお兄さんを亡くした悲しみで修行の旅に出ていましたが、お兄さんのふりをして生きていくと決めて、お姉ちゃんと一緒に国王様の手伝いをするために戻ってきました。
「大丈夫だよ。ユオンとエルフィは、わたしがしっかりみてるからね」
お姉ちゃんには二人、可愛い子供が生まれました。
旦那さんの双子のお兄さんが、彼女は本当は好きでした。でもこの国を平和にする戦いの中、彼は命を落としてしまいました。
忙しいお姉ちゃん達の代わりに、二人の子供は命をかけても守る、と彼女は決めました。
たとえその後、お姉ちゃん達が無実の罪で、「神」の牢獄に幽閉されても。
その時、国王様が彼女を逃してくれました。
ただし、子供は一人しか連れていけませんでした。国王様はお姉ちゃんの娘を、彼女は男のコの方を預かり、必ず無事に育てると決めたのです。
「ユオン。いつかきっと強くなって、エルフィを一緒に迎えにいこうね」
昔に逃げた仲間のいる山奥で、彼女は男のコと暮らしました。
竜の血をひく男のコは、とても強い化け物でした。でも妹の娘はほとんど人間と同じで、山奥で過酷な生活をさせるわけにはいきませんでした。
「ミリア母さん。キラもエア母さんも、一緒に行きたいって。オレ達みんな、いつか、ゾレンに帰れるのかな?」
妹も、幽閉された両親も助けに行く。男のコはそれだけを願い、毎日剣の修行をしました。仲間の子供も男のコと仲良くしてくれて、助け合いながら山奥の暮らしはしばらく続きました。
彼女はずっと、お姉ちゃん達の行方を探していました。
そしてそのため、ある神託の洞窟に訪れた時から、彼女の運命は大きく変わっていきます。
「貴女、とんでもないお人好しだね? 貴女の運命を狂わせたのは、あの反則の『青夜』なのに」
未来を予言するという、「空」の神託を受けに来たはずなのに。
顕れたのは、彼女の「力」に引かれたという、「忘却」の「神」でした。
「わたしの……運命を、狂わせた?」
何故か彼女と同じ顔をしている、「忘却」の「神」は「白夜」と名乗りました。
「白夜」は言いました。彼女が「青夜」を助けなければ、彼女は独りぼっちにはならなかったのに、と。
「『青夜』は空の獣……飛竜を独り占めしたかったの。だから今、罰を受けて幽閉されている。貴女のお姉さんの髪を白く、目を青くした『青夜』は、禁を侵して人間に降りてきた『神』」
飛竜とは、お姉ちゃんの旦那さんです。でもそれがどうして、彼女の運命を狂わせたことになるのでしょうか?
「双子の飛竜は、どちらかが消える運命だった。貴女が『青夜』を助けなければ、貴女の大切な飛竜は消えることはなかったのに」
死んでしまった双子のお兄さん。彼女は咄嗟に、青ざめて耳を塞ぎました。それでも「白夜」の声は彼女の奥に直接響くように、心細い魂を揺さぶり始めました。
「ここから先の未来を訊きにきたんでしょ? 教えてあげる。まず、エルフィは助けられない。ユオンを守って処刑される。トラスティは貴女に嘘をついて、ピアのためにエルフィを奪った。ユオンは地の底で龍神に火竜として封じられて、遠い未来に自分の『竜の眼』でエルフィを人に戻す。かつて貴女が、『青夜』を自分の眼で助けたのと同じように。……これは全部、貴女が見た夢なのに、どうして貴女は覚えてないの?」
それは「白夜」が、彼女を器にできる「神」だからわかることでした。
彼女は毎夜、怖い夢を見ては忘れています。まるで「忘却」という名の「力」に、抜き取られているかのように。
わけがわからず、泣き出しそうになった彼女は、走って洞窟から出ていきました。
そのあと洞窟の奥から出てきたもう一人の、大きな黒い翼を広げる「神」に、「白夜」が笑いかけるのも知らずに。
「……これで、いい? 『悪夜』?」
「夜」の名を持つ三人の女神。それはかつて、死体になった「空」の女神の成れの果てだと、灰から三人を作った「神」以外誰も知りません。
既に元の「力」を失った女神達は、そうして地上で禍の芽を育てていきます。「空」がいずれ掬い上げて、世界の夢を分ける魔竜が女神を止めるまでは。
……そんな夢を見て、女のコはふと、目を覚ましました。
そこは知らない路地裏でした。林と反対側の街の方から、遠い悲鳴や何かの爆発するような音が沢山聴こえていました。
女のコはよく、怖い夢を見ます。目が覚めると忘れていきます。
夢が薄れる程に、暗い青の目は澄んでいきます。今まで夢を見ていたことを忘れた目には、灰色の髪――黒でも白でもないお姉ちゃんが、彼女と同じ青い目で、女のコを覗き込んでいることがすぐに映りました。
「なんで……ピア――……?」
家族を奪われ、家から出て行ってしまったお姉ちゃん。少女と同じだったはずの黒髪は灰色に、人間にはない青い目に変わり、無骨な赤い鎧を纏い、眠る少女を抱えて座っています。
「……アハハ。元気してた? ミリィちゃん」
大人になったお姉ちゃんは、家族を奪った相手と戦っていました。その相手が街を襲い、女のコも倒れてしまったのです。
女のコのことは巻き込みたくない、と病院に預けられた時、とても嫌な予感が女のコを襲いました。
「どうして、ピア……? どこに、いくの……?」
お姉ちゃんの赤い鎧が、何故か黒く染まって見えました。
山の中に消えていくお姉ちゃん。病院に残った女のコの眼に、倒れているお姉ちゃんの姿が浮かびました。
「やだ、ピア……いなくなっちゃ、いや……」
けれど、女のコはお姉ちゃんを追えませんでした。お姉ちゃんをかつて助けてくれた、優しい仲間のいる病室に留まりました。
「……ごめんなさい……」
女のコは何も覚えていません。真っ白な夜に消えていく夢を、器であるだけの女のコは覚えることができません。
――貴女が『青夜』を助けなければ、貴女の大切な飛竜は消えることはなかったのに。
けれど、黒い髪の女のコにこそ、その「夜」は潜んでいました。
お姉ちゃんも家族も、沢山大切な人を奪われ、「夜」はいつしか、女のコを魔物に変えていました。
――ねぇ……いなくならないでね、ライザ。
女のコは忘れてしまっても、魔物はその夢を見続けています。
だからいつも女のコは悲しい顔で、魔物が望む夢のために、魔物は女のコをお姉ちゃんの元に行かせませんでした。
――ごめんね――……苦しいの知ってるのに、ごめんね……。
そして、女のコの夢から、火の竜になる男のコが消えました。
遠いどこかで、男のコは妹を助けられません。そのための「竜の眼」を、剣になった男のコは残せないのです。
彼女にはまだ、「竜の眼」があります。お姉ちゃんを助けなかった彼女は、必ずその眼を男のコに渡す魔物になると決めます。
――……何で……母、さん――……?
「夜」は、それ自体は決して、魔物ではありませんでした。
「悪い夜」は、「悪」の翼があるから悪いことをします。けれど「悪い夜」も、「白い夜」が見る「空」の夢がなければ、ひとときだけの悪いことしかできません。
「白い夜」は、器になれる女のコの夢、失った自身の「空」の目から、「忘却」を作っていました。そして「空」を再び取り込んだ時、「夜」は白く悪い「夜」を止めるために、本当に魔物となることを決めます。
「自分の意味、正義を侵した『空』の女神は、同じ空に棲む『星』に光を奪われ、地上に堕ちて悪い神様になってしまいました。空の獣は女神を追いかけ、地上に降りて凍りついて、やがて死んでいきました」
お姉ちゃんはそんな悲しい物語を、最後まで読みませんでした。
女のコが自分で本を開けても、何故か紙は真っ白なのです。お姉ちゃんはいつもどうして、「空」の物語を読むことができたのでしょう。
「でも、あなたは、『白夜』に捕まらないでいて……どうしてあげればいいのかは、私もわからないんだけど……」
――それはミリィちゃんのせいじゃなくて――あたしのせいよ。
元は灰色だったお姉ちゃんの目には、その時何が映っていたのか。
魔物の女のコも本当は知っています。いつかまた女神は空の獣に出会って、そこで生まれる「魔竜」にすらも、お姉ちゃんは手を差し伸べてくれること。それは灰色と白色と黒色、どのお姉ちゃんでも変わらないこと。
白く悪い夜にはならず、無色の白でいると「星」に約束したお姉ちゃんも、未練の紅い花を残してしまいます。
魔の海に流れた「小さな星」と、女神とは違った「空」が彼女達を探します。それはきっと、魔物の女のコが、正しい運命を変えてしまったために。
――『魔』とはね――望みを叶えるためには、どんな酷いことでもする者が成る末路なの。
――それはほんとに……愛と認めちゃってもいいのかな?
それは、魔物になった女のコと、「夜」の神様のあやまちのお話。
「空」はいつでも、そこに在ります。小さな星の光と共に、様々な色に染まりながら。
-please turn over-
❖黄昏紅花

▼古代
▽・・・黄昏紅花
▼神暦:雑種化け物譚
▽・・・竜の仔の夜
▼宝暦:千族化け物譚
➺独唱∴三姉妹
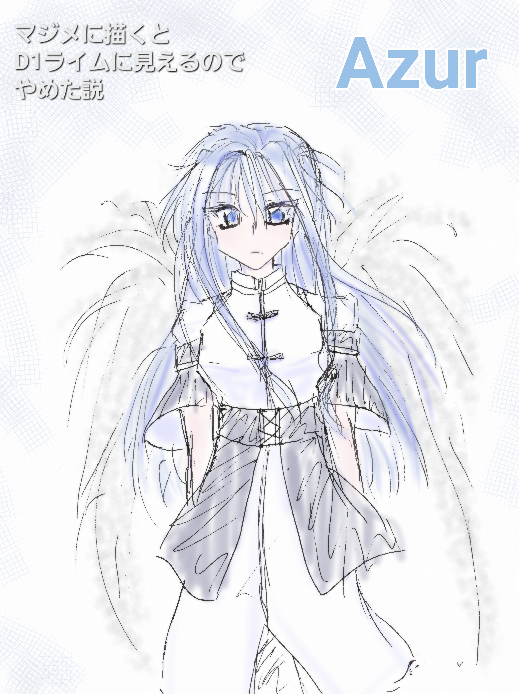
とどのつまりは、どこにいてもタダ働きだ。
何で引き受けちゃうの、姉さん、と恨めし気な青い目の双子に、彼女――近隣では異端の通称セリュンは、碧い海を眺めながら、くるくるに巻く髪と同じ軽い声色で返した。
「でも、こんなことでもないと、船に乗って違う大陸になんて一生行けないよ。アジュ」
隣で末の妹もいつもの無表情で、風に長い水色の髪を揺らしながら海を見つめている。背後では苦い顔の双子の妹が、両腕を組んで真っ直ぐな青の髪を指でいじっている。空の色そのものの青い髪が海風を受け止めている。
双子が難しい顔をしているのは、これから違う大陸に行く理由が嫌なことに加えて、船という旧世紀の人間の遺産が怖いからだろう。のほほんと海を見ている末の妹とは違って、船縁の柵には近寄ろうともしない。
「セレストが落ちたら姉さんが助けてよね。あたしは泳げないって知ってるでしょ?」
「あ、そっか。アジュは船が初めてだっけ。わたしは本当久しぶりだけど、生まれたのは竜宮だからなあ。まさかこんな形で里帰りするなんて、確かに思ってなかったけど」
旧世紀の燃料は失われているため、数多の船員が人力で漕ぐ船の足はとても遅い。もう少し風を起こそうか、とつい悩んでしまう。
船に乗る時、彼女達を迎えに来た大伯母は、天上人に見つかると厄介だから、「力」は何も使うな、と言い含めてきた。人間が不思議な文明の力で全世界を支配していた旧世紀を、自然現象という普通のことでぶち壊したのが彼女達の先祖だ。自然というものの支配には人間側も充分及んでいたはずなのに、自然の統括をする天上人の間に内乱が起こったために、過剰な「力」が自然側に与えられた結果だった。それをヒトは「竜」と呼んだ。
「『竜人』や天上人が自然の『力』を無遠慮に使うせいで、世界中の霊網が狂って土地の気の変動が起こりやすい……それでお母さんも、死んじゃったんだしね……」
隣にいる末の妹が、彼女に青い目を向けて無表情のままで首を傾げた。前髪で隠させている額に、紅い紋様がちらりと見えてしまう。
海から双子の方には振り返らない彼女に、双子は溜め息をついたようだった。
「自然そのものの『竜人』を弱らせるのは、自然に起こる自然の災いだけ。ディリノ全域に起こった干ばつと長い極光……母さんは、みんなに『暁』って呼ばれてたのに、水と光の竜だったんだよね? セリュン」
「うん。正確にはもうちょっとだけあるけど、お母さんの命を奪ったのは、水と光の消耗。これから帰る所は玄い水と風の『極夜』だよ。アジュとは相性が悪くないか、少し心配」
彼女にはある時から、数多の「力」の様を言葉で表せる特技があった。母曰く、父にも似た才能があったようで、物心つく前までに父は行方不明になったので実情は知らない。
そもそも父と母は竜宮で出会い、彼女達がいた隣の大陸に駆け落ちしてきた二人だった。父は風の気が強い大陸、母は寒冷の強い大陸で育ったものの、生まれは竜宮なわけだった。
「タダ働きの上に、あたしやセレストと相性が悪い地。何でそこまでわかってて、治安の管理なんて面倒な使命を了承しちゃう?」
「だって大伯母様、本当に困ってそうだし。相性が悪いってことは、二人の『力』も敵の弱味になるから、ディリノより重宝されるよ」
彼女達が今までいた山村では、家畜の放牧が主な生活の糧だったため、役に立てるのは賊や紛争の牽制くらいで、彼女達自身、厳寒の山地で生活するのは大変だった。
竜宮で行く予定の土地も寒くはあるものの、これまでの大陸ほどではない。危険な秘境が多い地でもあるために、双子はすっかり戦う力を身に着け、彼女達を守ってくれた。
「それにね、セレストには本当は『極夜』の土地の霊気が必要かもしれない。今でも十分可愛いコだけど、やっぱり、喋れるくらいにしてあげたいよね?」
う。と、末の妹の秘密を唯一知る双子が、困ったように黙り込んでいたのだった。
竜宮の無法者たちを力で抑えつけろ。長の家系な母の「力」を継ぐ彼女達に、大伯母はぴくりとも笑わず重厚に伝えた。殺せばよいわけではなく、従わせることが前提になる。
竜宮の北端、黒い水竜達が司る山岳地帯で、彼女達の居所は麓の海の近くに与えられた。
「あの……思ったより温かいんですね、ここ」
寒くて不便な山の上よりも、海にも森にも行ける川辺の茅葺きの家。連れてきてくれた大伯母の厳格そうな顔つきは変わらないが、彼女達への厚意はあるのだろう。
「貴女方の伯父が、強い光を持っています。困ったことがあれば相談しなさい」
それでこうも温暖なのか、と納得がいった。双子と末の妹も喜んでいる。治安管理者用の白装束が、人間の手製でかっこよかったのだ。
双子は決して好戦的ではないものの、竜の「力」を持ちながらヒトとしての戦闘能力も非常に高い。これから実際一番活躍するのは、白装束がぴったり似合う双子だろう。
「セリュン、セレスト、アジュといいましたね。人間の影響が残る余所の大陸に比べて、この地には何も法はありません。貴女達が、この竜宮の法となるのです。宜しく頼みます」
そうして手始めに決めた事は、彼女達以外原則殺生を禁じる認識だった。「神」以外には、日常の殺戮を止めるものがない世界なのだ。
ディリノという彼女が育った山村地域では、殺し合い以外で揉め事を解決する様々な教えがあった。けれどそれらを、試してきたのは彼女だけだ。大伯母には隠しているが、双子に限っては食事もいらず紛争の元が少ない。
双子も末の妹も世間知には疎い。それでも双子は重い顔で、最も心配なことを言う。
「そもそもセレスト、『無口』で通したけどさ。大伯母さん以外にもいつ不信感を持たれてもおかしくないんじゃ……」
「特に伯父さんってヒトは、会わせられないよね……大伯母さんに気付かれなかったのが、凄くびっくりなくらい……」
末の妹はただ、きょとん、と首を傾げる。
背丈のほとんど同じ彼女達は、彼女と双子が十八歳、末の妹が十六歳で通しているが、ディリノに居た頃には存在自体を隠していたのが末の妹なのだ。
「それでもわたしは……二人が大事だから」
末の妹の秘密について、ただ一人知る双子の妹。その双子も知らないことが他にあった。
全ては昔に、彼女が出会ってしまったから。玄い夜空に空の光が与えられた時に、淋しく存在を顕した青い空ろ。
竜宮を荒す多くの「力」について、そして彼女達は裁断に入った。ある蒼い空の獣が、その禁断の大地に降り立つまでは。
*
「世にも有り得ない青花」。末の妹がそんな二つ名を早速得ていた。ほのかに微笑む玉の顔を崩さない末の妹は、無法者を誘き寄せて、暴力性をあらわにさせる撒き餌になった。
「男も女も、下心か嫉妬ですぐに寄ってくる。そりゃセレストは綺麗だけど、喋れないのをいいことに好き勝手しようとしてさ?」
虫払いと称して、双子は手近な愚か者から制圧を始めた。見回り役の彼女が連れ歩く末の妹に近付く無礼な輩は、双子が叩きのめす。心配だから、と末の妹の姿を外套で隠すことも不自然でなくなってくれた。元々竜宮ではあまり顔を見られたくない末の妹なのだ。
彼女達の存在が目立ち始め、他の理由でも絡まれる事が増えたので、集団単位で次々に屈服させた。竜宮全域を見回る日々になった。
戦うのが双子だけなので勘違いされがちであるが、双子に戦い方を教えたのは彼女だ。山村生活で人間の護身術も習っていた彼女は、双子が不在時の暴漢には丁重に報いを与えた。
二年後のある日、そんな彼女の立ち回りを偶然眼にした旅人が、道端で連れる獣と従者まで立ち止まらせて見入っていた。
「……驚いたな。とんだ反則が存在している」
全身を黒い外套で覆い、赤い気配を纏った男。外套で体を隠した、馬くらいの大きさの獣を連れる。彼女こそ男の姿を視て驚く。
町外れに佇む黒い外套の男と、後ろで獣の手綱を引く黒い外套の従者は、どちらも顔を隠している。いかにも不審な集団は、世にも珍しく、天上人と悪魔の気配を持った一行であるのが彼女には判っていた。
「反則、って――アナタ達こそ、何者?」
双子は先程に懲らしめた暴漢を拘置所まで連れて行くため、しばらく別行動中だ。大小二人の外套の男と従者は、どちらにも強い「力」が視える。連れている獣は雰囲気だけなら大きな豹に見えるものの、何故か彼女の背を冷たい予感が走っていた。
この旅人達は何かが違う。存在をさせてはいけない狂気、災いの始まりがそこにあると。
竜宮という小さな大陸は、人間達の文明の遺産が最も少なく、暮らしは至って原始的だ。海の幸と山の幸が主な食糧資源で、自然の気が強ければ栄養はそう必要としない竜人達は、物資面での争いは少ない。しかし竜人以外の多くのヒトは、生存様式が違う竜人との間で互いの生活を乱すことが多い。
竜人の間での争いは、痴話喧嘩や縄張りの揉め事が多い。そこに異種の化生が加わると、素朴な竜人が思っても見ない欲望の芽を持ち、竜宮を支配しようと暴走した者もいる。
「何の目的で、こんな辺鄙な大陸に来たの? 天上人と竜は、互いに不可侵の条約を結んだはず……なのに後ろのヒトは、天上人では?」
真剣に問い質した彼女に、外套で顔を隠す悪魔の男は、唯一見える口元がふ、と笑った。
「竜宮に限定の条約ではあるが、そもそも、これが天上人に視えるか。惜しい眼力と言うべきか、それとも、言い得て妙だろうか」
どうやら本気で感心しているらしい口ぶり。彼女も確信は持てておらず、ただ従者らしき小さな相手には、隠されている光の結晶状の羽が一瞬視えた。そんな羽を持つのは天上人だけだ。しかしその羽は聖なる光が乏しく、天上人としてはおかしなこともわかる。
男が降参するように、両手を軽く上げた。何故か末の妹が彼女の後ろでぴくり、と体を揺らした。言葉一つも発さない娘であるのに。
「俺達は『空の光』を探しに来た。最近この大陸で、稀少な光を使う竜人の噂がある」
その一言を聴いて、彼女に激震が走った。双子がここにいなくて良かった。同時に双子に使わせる「光」が稀少な「力」なのだと、彼女は初めて知ることになる。
「『光』を探す……何のために?」
返答次第では、ここで男を排除しなくてはいけない。彼女の大事な家族に害を成し得る相手を見逃すことはできない。
彼女が食ってかかったこと自体が、相手に彼女と「光」の関係を疑わせる因となるのに、まだやっと成人間近の彼女には、その可能性に思い至ることはできなかった。
温暖でも冷たい風がふき始める彼岸の季節に、陽が落ち始めた市場の一画にはひと気も少ない。男との間に寒々しい空気が漂う。
男達を睨む彼女の剣幕に、外套の男は笑う空気を保ったままだが、後ろの従者が小さく声を出して、男の外套を引っ張っていた。
「……アステル。貴男の眼は節穴なのね」
小柄なので、子供だろうと思っていたが、声はとても大人びて落ち着いていた。天上人のような羽を持っているのに、光をほとんど失くしている不思議な黒い人影。
けれどそれより、彼女に大きな衝撃が同時に来ていた。後ろの人影はいったいつい今、何という名を口にしたのだろうか。
「出直しましょう。想定外のことがいくつも起きているから」
む、と僅かに不服そうに、男は従者の方に振り返った。その後一度彼女のことをじっと見たが、ふう、と息をついた後に、黒い外套の集団は場を後にしたのだった。
「……嘘……アステル、って……」
ずっと動揺で喋れなかった彼女の後ろで、末の妹が両手を胸元で握りしめた。そして、更なる異常事態が彼女を襲う。
「……あおい……そらの、けもの……――」
妹が喋った。彼女はハッと振り返った。
外套に隠された陰の中で、動かない笑顔の消えた末の妹が、青い目を震わせていた。
宿に先に戻っていた双子が、「あおいそらのけもの」をあれから何度も繰り返す末の妹に、落ち着かせるように両の肩を持って、寝台に座らせてから言った。
「セレストって、こんな声だったんだあ……結構違うものなんだね。ね、セリュン」
「…………」
先刻の異変をどう話していいやら、彼女は俯いたまま言葉を選ぶ。けれどいつも目敏く鋭い双子は、説明をできる前に彼女の動揺にすっと切り込んできた。
「まさか……父さんに会った? セレストを揺さぶれる存在なんて、それくらいしか」
双子はこうして、彼女が口にしない事でも非常なる察しの良さを生まれつき持っている。それは「空の光」の一端だといい、隠しても無駄なことはわかっているので、ふうと息をつくと、心を落ち着かせて口を開いた。
「アステルって名前らしい悪魔が、多分天上人の女のコと、貴女を探してた……アジュ」
「――は?」
「悪魔はわたしに気付かなかった……だから、アステルそのヒトじゃないと思う。でも……」
「死んだ母さんから聞かされてた名。父さんでしょ、アステルって」
そこまで聞いても何故彼女が、相手を父と思い難いか。それはひとえに、悪魔の「力」。
「力」を言い表せる彼女。外套の男を悪魔と思ったのも「力」を視てだ。旅がちの上に七歳から後には帰らなかった父の姿はおぼろで、「青い星影のヒト」と聴いている。
今日の男は赤い気配に包まれていた。赤は普通聖なる化生に多い色だが、男の場合核に闇を備えて、天上でなく地を行く高次の存在に思える。彼女の記憶にある父はもっと普通で、ちょっと正義漢なお人好しだった。
「あたしを探してる、ってどういうこと? そもそも父さん、あたしの存在自体知らないとセリュンが言ってたのに」
父が去って、母が死ぬ二年前に現れた双子。他ならぬ「空の光」がくれた大事な家族。
拙い時間でも、父と家族だった彼女に何も反応のなかった悪魔。彼女は父がいた頃には幼く、「力」を言い表せる眼も持たなかった。
光で「力」の中身に触れて、表現を変えて家族も作れる術を「空の光」が教えてくれたのだ。双子を人世に誕生させた十一歳の時に。
「アジュ……あなたに預けた光の力、当分、使わないで。悪魔が探してるのは、多分それ」
「そうなの? 別に、翼さえ出さなければ、隠すのはなんてことないけど……」
自然の竜は本来、翼などという天の徴を持つことはないもの。母にもあったこの例外について、今まで深く考えたことはなかった。しかし今は、胸騒ぎが治まってくれなかった。
寝台に座って、自分の肩を抱きながら下を向いていた末の妹が、そのままの状態で更に具体的な言葉を話し始めた。
「夜にだけ咲く、紅い光……三つの道を血で交じらせた、黒い十字架……私は……魔竜?」
隣から覗き込むと、末の妹の両目が青白く濁っていた。彼女はまたも冷や汗を感じる。
「これ……まさか、『預言』……?」
末の妹は元々、言葉を話せるほどの自我を持っていない。動物と同じような幼い本能で彼女達を慕い、ただ平和な微笑みを浮かべて、そこにいてくれれば良かった。たとえそれが、たった今儚く口に出されてしまったように、魔性のものに近い在り方であっても。
気が動転し過ぎて喋れない彼女の斜め前で、双子が気丈に、末の妹の両肩を叩いていた。
「何言ってんの、セレストはあたし達の妹! 誰が何と言ったって、たとえ天上人の戒めに触れたとしても、あなたはあたし達が守る!」
「……アジュ……」
それは彼女が言わなければいけない言葉。彼女の初心を守り続けてくれるのが双子で、父らしき存在の出現だけで揺れ動く彼女には、明日の指針も測り知れない。
「セリュンもしっかりしてよね、こんなのは外の世界に出た時から有り得た話じゃないの。まずは『アステル』が本当に父さんなのか、それを見極めるしかできないじゃない」
双子の言う通りだった。今までのように、無法者たちを取り締まりつつ自由に暮らして大丈夫か、それがまず彼女には不安だった。
夕べに出会った不審な黒い人影達が、実際何であるのか確かめないといけない。それはどういう事態であっても初手の話だろう。
「セレストも落ち着いて、ね? 喋れるならもっと、何でも他愛ないお話をしよ。あなたはセレスト、それでいいね。まずはあたし達、あたしと姉さんの名前を言ってみて?」
双子のまっすぐな青い目が、青白く濁った末の妹の目を覗き込んだ。やっと顔を上げた末の妹は、様子を窺って戸惑っていたものの、双子を何とか見返していた。
「……アジュール、と……セリュレエン……」
当たり! と、いつも鋭い顔付きの双子が、珍しく無防備に笑う。
「そう、どっちの名前も、父さんが姉さんに考えてくれた名前。母さんが選んで、それをセリュンがあたしに分けてくれたんだから」
まるで双子は、自身の出自をわかっているかのように簡単に言う。彼女は時々、双子のこういう底の無い直感に苦笑いが出る。
「空の光」と出会った後に、彼女は双子を連れて家に帰った。母はとても驚いたものの、彼女と似ていない双子を受け入れてくれた。
そして末の妹。母が死んだ後に出会って、無理やりこの世に生を受けさせた相手。
竜宮に連れて来たなら、物言わぬ末の妹が変化する可能性はわかっていた。それこそが移住する彼女と、双子の真の目的だった。
けれど実際に異変が訪れると、怖くなった。あの時の小さな黒い外套の従者は、彼女達の何を知っていて、男の眼を節穴だと言ったのだろう。どうしてこの竜宮に、異端の二人は訪れたのだろう。
「あたし達はみんな、水の竜だよ、セレスト。極夜は空にある水、その自然を司って、風を起こすこともできなくはないけど、それよりあたしは水を通じて熱を流す光が得意かな」
いつの間にか、寝台に三人並んで座って、すっかり双子が末の妹に現状を解説している。
言葉が通じる相手になった。双子はそれがとても嬉しいのだろう。末の妹は真摯な目でこくこくと聴き入り、彼女達が現在請け負う使命について理解を深める。
「人間も天上人もそれ以外も、竜とはあまり仲が良くなくてね。竜人が問題を起こせば、弾圧する口実にされてしまう。だからあたし達は、自分達で竜宮の治安を守るの。それができる力を『空の光』がくれた。誰が悪くて誰が暴れて、誰が秩序を乱しているのか……」
それらは全て、彼女が双子に説明したこと。この二年で双子はすっかりしっかりしていた。
なのに今更、彼女の方が迷い始めた。宿の外の黒い星空を、彼女は黙って見やっていた。
➺間奏∴心眼 闇
初めは光の存在しない、ただそこにある、数多の塵に過ぎなかった。暗くて自らの形も持たない、ただ集まっているだけの幽冥。
混沌のゼロが光と闇に分かたれたことで、形を持った混沌が大空と地上を世界に作った。どちらも闇でしかなかったのに、ある時光を与えられて、闇は自分の形を知ることになる。
彼が三人もの天上人の器から作った、黒い暁月夜の闇が、今日も生意気な口をきいた。
「意味がわからない。どう見てもあそこには『無色』がいたのに、どうして放置したの?」
今日は「神」の鬼子たる「反則」を視た、珍しい黄昏の夕べだった。
「神」とは、世の理を体現する存在であるのに、その破壊者がよりによって「秩序」の逆鱗を持っていた竜人に寄り添っているとは。彼の彩のない眼も驚く。
「あなたは相も変わらず、漢字が好きだな。竜宮でも一部でしか使われていない言語だが、あなたが学んだのは何処でなのやら」
露骨に話を逸らしてやったので、黒い児女は連れる獣にもたれて不貞腐れて座る。
馬屋を借りて宿にするのは、彼らにはもう慣れっこだった。藁をしいた土の上に座り、彼は丸太の壁にもたれて両腕を組む。外套を外してもつれた赤い前髪を一旦かきあげた。
「あれ単体に害は少ない。宿主に『預言』を強制的に与える、『空の光』に比べたらな」
ぼさっとした前髪の間の、黒い眼帯を児女が見つめる。「神」も含めた「力」全般を視る彼に比べて、「神」だけ視る眼を発現した児女は「神がかり」だ。
「神」とは通常、殺せないもの。「神」の命を奪った者は「神」に遷られ、「神」になるからだった。そうした「神」を壊し得る「反則」がいれば懸念するのは解る。
「その眼を奪ったのも、『無色』でしょうに。さっさとコレを『無色』に明け渡して、手を引いてもらう方が話は早いのでは?」
後ろの獣を見つつ言う。わざわざ獣の形をさせた「力」は、彼には弟のようなものだ。
最早いつからだったかも憶えていないが、彼はこの獣と地上を視て回っている。世には数多の闇――「力」が彷徨い、人間も旧世紀の遺産を掘り出すなど、不穏な「力」に彼は気付く眼がある。それが悪魔としての仕事だ。
竜人はその点、拮抗勢力を生み出す母体として近年新たに堕とされた世界樹も気にせず、「神」より紛争の少ない種族ではある。竜宮ではようやく自治の体制ができたと言うが、竜人同士では世界規模の争いを起こすことは元来少ない。「力」の強大さが過ぎて、個々の竜人が個人志向で、単独行動が多いからだ。戯れに災いが起こる事はあっても、世界まで巻き込む事変は少ない。
だから黒い暁月夜の児女は、馬屋で辛辣に息をついて、外の気配を静かに窺っている。
「力ずくで竜人達を私法に従わせるなんて、人間もびっくりのお粗末さだけど。彼女達、運命の女神だなんて、バカバカしい二つ名で呼ばれているみたい」
「それはあながち、間違っていない。言わば女神の成り損ないか。『神』に迫る逆鱗を持つだけでは、『神』とは到底言えないがな」
「『無色』がいるなら『反則の女神』でしょう。貴男も『無色』も本来世に在るべきではない」
この相手がそれを言うのか、と彼は嗤う。彼を慕った天女達を素に、この地上で呼吸をさせたかった女性――その成れの果て。
「反則」の話で日中に気付いた別のことを、彼の眼から逸らした児女には彼は気付かない。混沌とした心に隠れる、黒い暁月夜の十字架。
「それではクロアの見立て通り、メティアに『無色』の相手を願おう。『空の光』はオレがもう一度……今度こそ、必ず手に入れる」
これは長期戦ね、と児女が重く息をついた。さすがに今回は馬屋以上の滞在場を作ろう、と彼も少しは心を入れ替える。
座った体勢で仮眠をとって、夜明けが来る数時間後には、彼の短い髪は曇空の色と同じ白っぽい銀に変わっていた。眼帯の無い方の眼に、「運命の女神」と似た青を湛えて。
黒い暁月夜の児女が「無色」と呼んだ相手は、彼の血をひく実の娘の髪に宿っていた。昨夕は彼も驚いたのだが、娘も彼については何も言わなかったし、娘に竜の逆鱗の気配が何故か視つからず、娘だと確信できなかった。
彼は悪魔と契約した人間、というには歴史の古過ぎる存在。悪魔が彼を見つけなければ、彼の依り代となれる人間の体を奪えず、長い相方とする乗り物の「力」を獣の形にして傍にも置けなかった。
「それじゃあ、行くか……メティア」
運命の女神のねぐらとして有名な、竜宮の北の地に足を向ける。蒼い空の獣に乗って。
そうして彼が強い気配の主を探して、北山の麓に降り立った時には、実の娘は茅葺きの家に不在だった。親類に昨日の件でも報告に行ったのだろう。家の形と床がある分、彼らの馬屋や以前の貧しい山村よりは幸せそうだ。
蒼い獣と共に近くの平原に降り立った彼に、おかしな気配を真っ先に感じたらしい女神の一人が、焦って駆け付けてきた。
「何者、まさか、セリュンが言ってた――」
留守を預かる、空色の青の長い髪を持った白装束の女。手から伸ばす光の鞭が無法者を叩き斬ると噂で、武器の一つも持っていない運命の女神。彼はただ、そのあどけない乙女のいびつさに、青い笑みだけを浮かべた。
➺重唱∴月夜

最近、妹達の様子がおかしい。
言葉を話すことができるようになり、額にある紅の紋様が青く変わった末の妹もだが、「光」を隠して水竜としての「力」で戦う双子も、まだ鍛えが足りない、と焦りを見せるようになった。
「お姉様、焦らないで、落ち着いて。大気も、川の流れも動かせるお姉様に、勝てるヒトはこの竜宮にはいない」
末の妹はすっかり、元々おっとり過ごしていた姿を言葉で表すようになった。竜宮には末の妹の言う通り川が多い。双子の力の源が豊富で、そうそうの事では負けない。
けれど双子は、思い詰めたように項垂れてしまう。それは明らかに、彼女達の父が父としてこの度名乗りを上げて、蒼い気色の飛竜と北西の海辺に住むようになってからだった。
「何が父だか……セリュンとセレストをもし少しでも傷付けたら、絶対赦さないから」
彼女の方は、父が「光持ちの娘が今何処にいるか悪魔に見つけてもらった」と言うのをきいて、やっとこの再会に納得ができた。姿は若い父だが、彼女のイメージと同じ白銀の髪。眼帯のない方の眼には青い星影が宿る。
以前の山村と同様、末の妹の存在を双子と隠して、彼女と双子がたまに父に会いに行くようになった。それだけの変化のはずだった。
父は、彼女を探していたという。隣の大陸で待っていると思っていたのに、いざ迎えに行けばいなかった、と申し訳なさそうに言う。
「どうして姿を消していたの? お父さん」
「オレの心は変わってないよ。あまりに早く、アルンが天に召されたから、文句を言うのに力を貸してくれる悪魔をずっと連れてた」
寂しかった。彼女がそう怒ると、父は苦く笑って、だからオレの眼を一つ残していっただろ? と眼帯を指さす。
「まさかセリュンが、魔道の塊のオレの眼、あんな使い方をするとは思わなかったけど」
「だって、こっちでも向こうでも魔道なんて、さっぱり教えられたことないよ?」
それより実の父が瓶漬けの眼だけを残して失踪した時の、彼女のひどいショックを誰か察してほしい。優しい父がそこまでする別れ、とあれだけ動揺さえしていなければ、双子も末の妹も生まれることはきっとなかった。
双子はそれをうっすら悟って、父に反感を強く持っているのかもしれない。彼女的にはもう父に会えることはないと子供心に思ってしまったので、偶然出会った「空の光」から教わった「力」を駆使して、双子と末の妹の存在を作り出したのだ。
空の光と呼んでいるが、それはその無色の誰かが光で「力」を使うからだった。彼女に家族を作る術をくれた、名も無き反則の誰か。
とりあえず西に父が住むようになったとはいえ、彼女達の仕事は何も変わっていない。竜宮全域を歩いて回って、出会う無法者達や相談に対処する生活は続く。
末の妹には留守を任せて、誰が来ても顔を見せるな、と言い含めている。今では撒き餌など使わなくても、彼女達が無法者の裁定者ということは周知の事実になっているので、あと一人はもう隣の大陸に帰った、と念入りに噂を広めてもらっている。
「お父さんに、セレストのことだけは、絶対見せるわけにいかないよね……」
「あたし一人の存在でも、あんなに驚いてた。隠し通すしかないよ……姉さん」
双子が彼女を見ないままで、気まずそうな声で言った。久しぶりに双子と二人になれた道中なので、尋ねずにはいられなかった。
「あの、アジュ……お父さんにアジュのこと、何か、きいた……?」
「…………」
やはりこちらを見ようとしない。そもそも「空の光」の力で目敏さを持った双子なので、隠し立ては最早無駄なのだろう。父が目前に現れた以上、それは覚悟するしかなかった。
「……ごめんね、アジュ。アジュは……本当は、わたしの双子なんかじゃない……」
数歩先を行っていた双子が、立ち止まった。彼女も止まって、呼吸を整えてから続ける。
「お母さんがわたしに残した、『桃花水』の珠……それに、お父さんの眼から創った逆鱗を使って、わたしの竜の目も一つ分けて。皆の力で空の光が作ってくれたのがアジュで……わたしは、一人ぼっちが嫌で、アジュが何になるかなんて何も考えずに――」
「だったら……何?」
そこで毅然と、双子の妹が振り返った。
父の方に似た鋭利な顔立ちで、青い星影の逆鱗を胸に宿し、竜人に視えるよう作られた竜の目を持つ「力」の塊。
気が付けば背には、隠すように言っていた銀色の光の翼が生やされている。この翼は母と同じもので、ある時突然生えたものだった。
「こんな翼を持っているから。あたし、普通の竜じゃないことくらい、とっくに知ってた」
「……――」
「それでもあたしの目は、セリュンの目なんでしょ? それならあたし、セリュンの双子以外に、何て呼ばれればいいの……そのことだけはどうか、否定しないでほしい」
竜人には「力」ある化生としての、三つの象徴が存在している。特に強い血筋の竜には「力」の依り代となる竜珠が。普通の強大な竜には自らの「力」を制御するための逆鱗が。そして竜人を名乗るには竜の目という、自然の「力」をヒトにする力が必須となっている。竜人を竜人と成すのが竜の目の作用なのだ。
「うん……本当にごめんなさい、アジュ……」
母が生きている時に渡された竜珠と、父が残した眼を視た数年後に、作ることを決めてしまった双子。母が病床で失ったものと同じ翼が双子に生えたのは死後で、突然来た謎の他称双子に、母もさすがに戸惑っていた。
「何言ってるの。セリュンが反則で、世にも奇妙なヒトを創っちゃうことなんて、あたしはずっと知ってるでしょ」
言われれば全く、その通りでしかない現実。双子という夢を、見続けていたかった心が、彼女の胸の奥でじんじんと痛みを訴えていた。
彼女に家族はいない。そう嘆くかのように。
悪魔と契約した、などと言う父だが、理のない相手には本来厳しかった。「力」に簡単にヒトが殺される世界で、弱い者に義があれば進んで庇護する。竜人以外で自然を司る天が天災を放置し、それで母は死んだとも憤っていた。竜宮を守る彼女も偉いと言ってくれる。
「お父さんのそういうところ、アジュの逆鱗に顕れてるかもしれない。結構正義感が強いでしょ、アジュって」
「別にあたしは……そんなつもりは……」
珍しく顔を赤くする双子に、あれ、と彼女は違和感を覚えた。逆鱗が胸元にあることも含めて双子は異端の竜人なのだが、普通竜は、あまり感情の起伏を持たないものなのに。
彼女はこの時、その現実を想像するべくもなかった。母の心とも言える「力」、竜珠――「桃花水」と名付けられた透明のうっすらと紅い珠が、双子の心の在処であること。母と同じ翼まで持った双子が、父の青白い目には母の再来に見えてしまっていたこと。
父の眼を逆鱗という、外付けの手綱にしただけで、双子は父と似ていても血のつながりがないと言える。「力」の過重を防ぐために、血縁同士の交わりは世界では禁忌とされる。仮にも父に似た「彼女の双子」に、父が情を抱くとは予想もできなかった。そして双子の方も母の「力」である影響か、いつしか父に想いを寄せてしまったことも。
南西の地域で、珍しく人間が幾人も市場で鎖に繋がれていた。竜宮にいるのはほとんど竜人とその縁者なのだが、何の力もない人間が縁戚として住むことも少なくはなかった。
「ちょっと、奴隷なんて! 天上人や人間の醜い文化なんて取り入れないで、自分の生活くらいみんな自分で面倒みなさい!」
弱きも強きも、基本は自立しろという立場の双子が、奴隷商人もろともまとめて摘発をしてしまった。解放した人間の奴隷達が呆然と何人も残っていて、彼女は対処に困った。南西に住む伯父に相談を持ちかけるしかなく、彼女達は初めてその砦に訪れていた。
奴隷達の境遇をよく知る者として、彼女達より若い少年を伯父の砦に同行させた。隣の寒い大陸の出身という少年は、真っ黒な短い髪と深く黒い眼の持ち主で、外見は若いわりに坦々と冷静に奴隷の事情を話す。
「俺達をこの大陸に連れてきた商人は、同じやり方で世界中に人間の奴隷を売ってるよ。俺には人形を作るしか能がないけど、人間はあんた達より器用だって、それしか使い所がないって評判だから」
「ええっと……アシェ君、だっけ……?」
彼女はどうしても、その少年を視た時から、言いたくて仕方がないことがあった。伯父が来るのを待っている間につい尋ねてしまう。
「アナタ……わたし達のこと、多分、殺せる『力』を持ってるよね? どうして奴隷の身になんて甘んじてたか、教えてほしいな」
「――」
少年が黒い眼を見開いて、彼女を見返してきた。隣で双子もうんうんと頷いている。
「竜の大半は、水脈を力にするものが多い。南は火竜の縄張りではあるけど、アナタは、たとえ火の竜であっても、水を体に持つヒトなら殺せるんじゃない?」
「驚いた……あんた、『無色』の影がちらつくとは思ってたけど……」
「無色」? 双子と揃って彼女は首を傾げ、少年はやれやれ、と黒い眼を逸らしていた。
「俺も『無色』も、闇に隠れないといけない不秩序者だよ。でも『無色』は、仲間を作る願い以外に自我がないから。あんたの近くにいるなら、あんたも寂しいヒトなんだろな」
無愛想ながら憐れみを含んだ少年の声に、彼女はその「空の光」と出会った時のことを否応なく思い出した。
お母さんが、いなくなっちゃう。こわい、助けて。気が弱り続ける母の姿に泣いていた彼女の前に、姿を顕してきた透明な白い光。
「それにしても、随分とじじくさい話し方をするんだね、君は」
双子が不思議そうに言及していた。爺とはあんまりな言い方だが、確かに大人びている。
「あんたこそ? せっかくの白装束に、黒い怨嗟がまとわりついてる。竜人以外の化け物達も、多分遠慮なく罰してるな?」
「遠慮は……それは、平等にしてないけど」
「その調子だと、情状酌量とかも、ほとんど考えずに罪の重さで罰を決めてるんだろうな。その正しさは、どれだけ正しかったとしても、必ずあんたより弱い者達の呪いを招く」
竜人様は高潔だから、解らないだろうけど。そう締め括った少年の声は、戒めというより何処か諦観が色濃く刻まれていた。
「まあ、じじいの老婆心だと流してくれよ。俺、とっくに百歳くらいは越えているのに、老化も死ぬのもできない何かになったから」
それは確か、「無色」というらしき「空の光」も言っていたことだった。それらは滅びる事がない代わりに、変化をすることもできない。
それでも、彼女が手伝えば別、ときいた。伯父と奴隷の処遇について話して、最終的に奴隷の代表として少年と伯父を繋ぐ形で話が終わった後に、彼女は帰り道で少年に一つの提案を持ちかけていた。
「あのね、アシェ君。アナタには、灰で水を穢す少年、って言葉が浮かぶんだけど」
「さすがの『無色』の眼だな。おおむね多分、それで合ってるけど、それが?」
どうやらやはり、彼女の「力」の表現力は「空の光」のものらしい。それならと続ける。
「それ、水を穢す男、くらいにならできると思う。わたしは言霊を変えることくらいしかできなくて、反映されるにはちょっと、時間がかかるかなぁとは思うけど……」
「へ?」
思えばそれは、末の妹を彼女自身の願いで、この世に生み出した「反則」の業。父の眼を偽りの逆鱗にした、禁断の一手にしても。
「視えるだけじゃなくて……変えられる?」
少年はそこで、余程驚いているようだった。
母の珠を彼女の竜の目によって、ヒト型にした効果自体は「竜の目」の範疇を超えない。力が大きくて困難ではあるが、それより稀有であるのは、双子が己の意志を持ったことだ。
「俺を別物にする、ってあんたは言ってる。そんなことを……ただのヒトが、できると?」
末の妹が喋れるほどの意志を持つことも、そうなるようにしたつもりでも、かなり時間がかかってしまった。今では「預言」の力をますます強めるようになってしまい、末の妹自身が怖がって外の世界に出ようとしない。
「えーっと……そんなにもまずいことなら、別に無理にとは言わないんだけど……」
「……いや……本当かどうか、確かめる意味でもやってみてほしい。俺自身はそもそも、あんた達を咎める権限はないんだから……」
そんな縁で、彼女は少年を「男」に変えた。その後少年は夜の眷属と後の世で見なされる。
北の家へ帰るために、砂利を避けて湿地の草が生える、広い川沿いを双子と歩いた。
少年に使った空の光を、久しぶりに見た、と双子が大きなため息をついた。
「今見たら、確かに大分、不秩序だなって。秩序の下にヒトを裁くあたし達が、本当ならそれは、持ってちゃいけない光かもしれない」
「……アジュ」
「子供の頃には、そんなこと何も考えなくて済んだのにね。セレストのことだってそう」
既に陽が落ちかけていて、双子の白装束が赤く染まって見えた。竜宮での仕事の実働者として、多くの者を手にかけた双子。
やっぱり、この地に来るべきではなかった。うっすら感じ続けていた悪寒が、赤い夕陽の中で彼女の胸に蜷局を巻いている。
目敏い双子は、いつも彼女のことを第一に想っている。自身の感傷は置いて、くるりと彼女の手をとって元気づけるよう笑った。
「今日は父さんの所に寄って帰ろう。父さん、悪魔といる自分があたし達の足を引っ張るといけないって、あんまり会いに来ないし」
願ってもない提案だった。まだ二十の歳を超えたばかりの彼女に、本当は秩序や治安の話など荷が重いばかりだから、たまには何も考えずに家族と過ごすのは心が安らぐ。末の妹を長く一人にできない枷がなければ。
双子と突然二人でやってきた彼女達に、父はぽかんとしながら、今日はもう遅いから、泊まっていくといい、と促してくれた。
ヒトの少ない西海岸でひっそり暮らす父は、「悪魔」らしい外来物、蒼の飛竜だけが傍にいるのかと思っていたが、その深夜に初めて彼女は、父の現実の一端を知ることになる。
「えっ……貴女、父さんと暮らしてたの?」
「……」
飛竜と父が呼んでいる、大きなトカゲに羽が生えたような獣が、彼女は気に入っていた。森に繋いでいるときいていたので、夜更けに探しに来たら、黒い外套の児女がいたのだ。
最初に父と会った時に、後ろにいた従者。天上人の羽以外、「力」が複雑でよく解らない。この相手の持つ翼が彼女達に、どれ程影響を及ぼすのかを彼女は知らない。何故なら児女本人も、「神がかり」の己を知らなかった。
「貴女、悪魔と一緒にいた……天上人っぽいヒトだよね?」
「……ええ」
羽はずっと、外套の内にしまわれている。父が乗る時にはもっと大きなはずの飛竜を、馬のような体で木陰につないでいる。
「貴女と父さんは、どういう間柄なの? あ、わたしは、父さんが旅に出る前に一緒にいた母さんとの娘で……」
「知ってるわ」
すぱっと一言で答えられて、彼女は年甲斐もなくおどおどとする。強い「力」を持つ竜としてあまりヒトと関わらなかった彼女は、見た目より人見知りな面があるのだ。
うう、と押し黙る成人の彼女に向かって、従者の児女は頭巾をかぶったまま首を傾げた。怖がっていることを悟られたらしい。ああ、運命の女神とかいって情けないなあ、と彼女も想像の中で頭を抱える。
「…………」
笑顔だけを何とかはり付けていたら、目の前で児女が身動きを始めた。獣の斜め前で、外套の頭巾を脱いで素顔を晒していた。
「……夜みたいな……キレイな、黒髪……」
毛先がつんと硬くのびて、見た目は短い髪であるのに、襟足の髪がうっすら伸びる狼の首元のような髪型。翼があるのに気色は狼と言える鋭さで、紅い瞳が無表情を更に厳しく飾っている。黒の虹彩に金の眼光は、天上人より「神」の眼なのだと彼女は知らない。
何にせよ相手が顔を見せてくれて、彼女はちょっと嬉しくなっていた。児女の表情にも心なしか、目端に柔らかさが浮かんだ。
「……私はクロア。あなたの父親が契約した悪魔に育てられてる」
獣の手綱を放した児女がこちらを向いた。暗いので顔立ちが見え難く紅い瞳が目立つ。
「クロア。父さんの悪魔の、娘ってこと?」
「そう。私はあなたと同じ――私にも母さんがいないから、悪魔とずっと一緒にいる」
見た目の鋭さに対して、相手の声が意外に優しかったからだろう。彼女は突然、安堵と共に涙が出てきてしまった。
「あっ、ごめんっ……クロアも、お母さんがいないんだ、ってきいたら……」
児女がきょとん、としているのがわかった。彼女も再び、情けない、と両手を握りしめる。
「わたしなんて、大人になっても、淋しくて仕方ないのに。クロアはきっともっとだよね……しっかりしなきゃ、わたし……」
言いながら、ますます心細さが彼女を襲う。
父はこの児女を連れていたなら、どうして自分は一人、と全身が硬まる。言葉を失っていたら、児女がそっと近寄ってきた。
「……何歳になっても、それは悲しいでしょ。あなたのように、一人でみんなを引っ張ってきたなら、尚更だわ」
表情が無いままであるのに、児女の冷たい手が彼女の頬に触れた。間近で見えた相手の顔は、何故かどこかで見たような気がする。
「ダメな親を持つと、子供は苦労するわね」
「――へ?」
児女の手の冷たさは一瞬だった。くるりと彼女に背を向けると、獣の方へ帰っていく。
「アステル・シリュスに、気を許さないで。彼はあなたが感じている通り、ろくでなし。私はきっと、あなた達の穢れになる」
「……クロア?」
「朝になれば、メティアに乗って帰りなさい。そのままメティアを返さず、傍に。こっちの方が、あなた達を守りたいと願っている」
そのまま児女は、飛竜も置いて森に消えてしまった。月明かりしかない暗闇の中へ。
もっと話していたかった、と。脈打つ己の胸の底に、児女は額を押えて笑っていた。
「これは……新境地、かもね……」
誰の心かも知れない鼓動。微笑む紅い瞳の背後には、夜の残滓を纏う翼が広がっていた。
➺間奏∴怨念
運命の女神の二人を送った飛竜が、悪魔の居所に戻らなくなった。黒い暁月夜の児女の差し金だとは露も知らず、彼は機動力を失う。
「せめて、妹だけでもこっちに呼べないか? あの銀の翼はあんたの同類だろう」
「できると思うけど。あの怨念を私の同類と呼ばれることは、どちらにも失礼な話だけど」
彼の言う通り、竜人には本来無い翼を持つ「空の女神」は、児女とは重い宿縁を持つ。それは悪魔も気付いていない誤算で、竜宮で彼の最たる想定外は、彼が望んだものを実の娘が創製していたことだったろう。
「妹なんて言いながら、手を出す気が満々のくせに。アナタは自分の娘だと思っていないでしょう、あの『空の女神』を」
治安を司る責任者である、姉娘の髪が夕紅、実働者の妹が空色の髪であるため、姉は黄昏、妹は空の女神と呼ばれている。彼が隣の大陸で共にいた頃には、母似の茶髪だった娘は、「無色」に出会って髪色が薄まったと見えた。
「お母さんに会いたい。あのコのその苦しみに喚び出された『狂乱』が、まさか竜の珠に収められてヒトの姿をとったなんて」
黒い児女の言う通りに、「狂乱」は「母」を擁す怨念が集った闇だ。復讐者とも呼ばれる「神」紛いであり、天から堕ちた翼を持つ。
「あのコの光を使って双子のふりをし続けている……そんな健気な怨念をどうしたいの」
児女も冥府の「月」で、闇であれど起源は天だ。光ある天の者は「空」の系譜と呼ぶ。
天に起源のある「力」を持つ者達は、概ね世界の闇で「神」。闇には大きく「空」と「夜」の系譜があり、彼はどちらの系譜も持つ悪魔で、稀少なその眼は数多の闇の仕様を視抜く。
「拗ねているのか、クロアは。娘のおかげで俺はクロアを、消さなくて済んでいるのに」
「私、消えたくないと言った覚えはないけど。アナタが暁を望むあまり、実の娘も放って、黄昏と天空と夜の天女から私という暁の器を作った。残念だけど、失敗だっただけで」
「暁」というのは、彼らが愛した竜人の「力」。
髪を赤くし、悪魔に戻る。児女は「暁」とは違うどころか、「神眼」が降りてしまった者だ。光と空と夜は本来暁や黄昏以外で共存しないが、それらを全て呑んだ四つ辻の「暁月夜」。
「空の女神も成功とは言えない。オレの好みではあっても、俺にとっては扱い難い」
「本当に最低よね、貴男は。子供として扱う私には絶対に触れようとしないくせに、暁の『力』を持った空の女神は女として見ている」
嘲りの顔で言うこの児女が、無表情の紅い瞳で何を考えているかはわかったことがない。
最近、児女はよく喋るようになった。飛竜にしか心を開かなかったのが嘘のように。
児女に頼んで、「狂乱」を潜める空の女神を、理由も判らず西岸に来るよう喚んでもらった。児女と同じ銀の翼を持った乙女が、もう何度も乙女を口説き、魔道でもからかってきた彼に、夜の波打ち際で怒ってきた。
「貴男、いい加減、セリュンの父さんだって自覚を持ってよ! あたしなんかに言い寄る暇があれば、もっとセリュンの力になって」
「そんなこと言っても、あんたもオレのこと、セリュンに黙っててくれてるのに。実際にはオレ、悪魔の方がこの体の主で、セリュンの父親は正確には悪魔なんだけどさ」
彼はいったい、誰だと言えば良いのだろう。わかるのはいつも、彼は誰かの影にあって、この「星」の悪魔に気が付けば拾われていた。赤い異方の悪魔はそれで冷静さと義心を得て、彼にはヒトとして動かせる体ができた。
悪魔に宿られてしまった体の主は、まだ在る人間の心を悪魔が憐れみ、悪魔の眷属にして彼の相方、飛竜に遷して残している。
「あんたの預言は、そういうことがわかる力なんだろ? セリュンを悲しませたくなくて黙ってただけで、オレもそう。セリュンにはいいかっこをしたい――あんたと同じで」
「――……」
お母さん、と泣いていた娘に近付いた怨念。優しい形になったのは娘の心の反映だろう。
けれど本質はどろどろの怨嗟である乙女が、「正しさ」の逆鱗を得て裁定者をしている。無意識に血を望む者などに気高い「空の光」が宿れた点で、彼は乙女の本質に興味が沸いた。
「オレもあんたも、そういう奴ほど、内面は醜くて歪みだらけだ。あんたは違うって言うなら、オレを罰してここから立ち去ればいい」
少しずつ乙女を、砂浜の林道へと追いやる。
乙女は彼を拒めない己に気が付く。下弦の月夜が乙女を狂わせていくことだけを予感している。
「だから一緒に……オレと地獄に堕ちてよ」
ヒトの思慕をも感じ取れる預言の乙女は、彼の青白い隻眼からもう目を外せない。彼を映す瞳に熱が伝わり、赤い顔を隠せていない。
「何で……わたしみたいな、殺し屋……」
振り返れずに後ずさった結果、空の乙女は大きな木に行き当たって、退路を断たれた。
「……っ……」
黒い夜空に、紅い一縷の光が咲いた。彼を阻もうと竦む手には刃は宿らない。暴きたい青の目を覆うようにゆっくりと唇を奪った。
乙女から力が抜けていくので、常緑樹の根元にもつれ込んで膝の上に座らせた。裁きの白い装束を、彼の眼――逆鱗がある胸元まで解く。
「暁」は彼も悪魔も好いていたが、この乙女は悪魔の髪には吐息など溢さないだろう。柔らかな肌に指を深く落とすと、いつになく怯えてしがみつくのが愛しかった。
竜宮には、竜人だけがいるわけではない。世界でも指折りの神域である地で、特に竜人がよく生まれるから竜宮と名付けられた。
世界中に竜人は散在している。竜宮は北の水竜と南の赤竜が最大の勢力となっているが、天上人の末裔や名のある神魔、人間に鬼妖と、様々な化生が神域の力目当てに共棲している。そうした環境での「暁」の両親は、北の水竜と火の家の天上人が番った異端だった。
――貴男が、ソーマ姉様の四番目の旦那様?
「暁」の実の姉は、水竜の珠を継ぐ長姫。天の火を排さず映したために、珍しい「月」の徴を生まれ持った。兄にも強い光がある。
水も風も鬼火も持った姫は、母が早逝したので若い内から長となった。幾人もの子供を持ったが、天の血ばかりが濃く出て、竜珠を継げる竜人が生まれなかった。それで地上の様々な化生と後継ぎを作ろうと試みていた。
彼はそのため竜宮に招かれた者で、長姫と契りを交わすはずだったのだ。長姫と同じ翼の主の「暁」が、里帰りしていたのが因果で。
――貴男、母様みたいに大空を映す眼だね。私をあの光の中へ連れていってくれない?
踏み止まった彼と、躊躇わなかった悪魔。「暁」の翼が玄ければ何かは違っただろうか。
その日も竜宮の高い天頂、紅い兆しが闇夜に顕れていた。青く光った冷たい雲の上で。
➺変奏∴眠れる暁

実際は銀色の獣であるのに、天頂のような蒼い光を纏う飛竜が、すっかり女神の住処の番人となった。いつも扉の前で佇んでいる。
治安の維持をしている姉達の身柄は、常に反発者に狙われている。与えられた居所には大伯母が育てる、水竜の後継ぎが風の結界を施している。そもそもは伯母である前長姫が亡くなったことで、後継者が成熟するまで、治安の維持を「運命の女神」に託されたのだ。
「……アナタは……お姉様達の味方……?」
結界の家内に引きこもって、留守を預かる末の女神は、軒先の蒼い獣の肢に頬をよせる。
「姉」達の父に、決して会ってはいけない。ずっと隠れていないといけない。その理由を今では末の女神は、「預言」とやらの「力」で夢に見ていた。
世界を見下ろすものが、「空」。姉達はいずれも、稀な眼力を持つ。蒼い獣に抱きつく預言の巫女には青い逆鱗が浮かぶ。
「わたし、お姉様に……話した方がいい?」
まずもってどうしてこの空の獣が、女神の居所を守り始めたのか。最近は大伯母からも、北の地の気が乱れていると警鐘を伝えられた。
まるでそれは昔に、竜宮に魔の物が現れた時のようだと言う。例えば大気の水の気が主なこの地に、天の蒼の強い獣を置くことは、気候の寒冷化を進ませる影響が表れていた。
蒼は天と地、どちらにも通じる自然の色だ。地上の自然の気は青に集約することが多いが、蒼は青が光になった気色だと上の姉は言う。
「アナタも、アナタ自身は旅する氷なのに、空の上から地上まできたから……青から蒼になった、あおいそらのけもの……」
飛竜が首を少し動かし、ぽん、と軽く末の女神の頭に乗せた。撫でるような動き。空の獣はいつも優しくて、胸が熱くなってしまう。
光や水を媒体とする熱の移動を行う制御力が、蒼という自然の「力」で天威だ。大抵の天上人は光を翼に宿しているため、目が蒼くなる者が多い。竜人ではおおむね水竜の者が蒼を冠し、天候を操る脅威が散見されていた。
物言わぬ優しい飛竜。上の姉もとても気に入っており、父が竜宮に現れた当初などは、むしろ飛竜に会いに父の居所を訪ねていた。
長い時間を離れて育った父のことは、どこか気を許し切れない上の姉。そんな父が下の姉と情を交わしてしまったことを、末の女神は何も言わないでも夢を通して見知っている。
それは、大切な足場が揺らぐ戦慄。竜宮に来るまで無言で平和に過ごした巫女は、額の逆鱗が紅から青に変わった後こそ、どうにか忘れてしまいたい「心」を知りつつあった。
「姉さんが、わたしを守ろうとして……私の悪魔を、連れていってしまうつもりなの……」
そこに在る心の黒さ。それが見えてしまう。
青白い目を初めて覚ました時には、妹だと呼ばれる巫女は、上の姉に与えられた純粋さしか持たなかった。ただ母が恋しかっただけの上の姉は、「無色」と出会い、命の終わった母の体が自然に還らないよう、母の竜の目を変質させて固定してしまったのだ。
――お願い、目を開けて、お母さん。たとえ、本当のお母さんじゃなくなったって……まだお母さんの『心』は、ここにあるの……。
また、強い竜人が持つ逆鱗には、その竜人の生存を守るために本人に代わって「力」を制御する仮の心が存在している。
母の逆鱗に姉は自身の、白い逆鱗を混ぜた。母本人が死んでも体を混成の逆鱗で維持した。更には逆鱗の内に存在する仮初めの心を、妹と呼んで目を開けさせることにも成功した。母の記憶を何も知らない逆鱗の心が、母とは違う無垢な水色の髪で母の体を起こしたのだ。
「わたしはわたし……こんな心、忘れたいの」
今ここにある預言の巫女とは、「暁」の体で目を開けた逆鱗の心。けれど言葉まで話せるようになった理由は、母と姉の紅い逆鱗ではなく、今の自身の青い逆鱗に変わったからだ。
失われた「暁」の心は、「魔」でもなければ蘇らない。それなのに「暁」が恋い焦がれた悪魔が竜宮に現れたことで、預言の巫女の夢に「暁」の記憶が出始めてきた。あの悪魔が欲しい、傍にいたい、という黒さで。
上の姉が大伯母の所へ現状についての会合に行って、下の姉は無法者の討伐から帰ってきた。
姉達が治安を守ることが知れ渡っても揉め事を起こすような輩は、ここに来た当時に比べて問題の深度が深い。下の姉はヒトの命を奪うことが段違いに増えた。いつも手の返り血を川で洗ってから帰る。
しかし今日は、長く出ていたのは、また父との逢瀬だった。上の姉は父と下の姉の関係に気付いていないが、妹にはわかると目敏い姉なら勘づく。重い目で出迎えると、普段は強気に振舞う下の姉がついに弱音を口にした。
「あたし、どうしよう、セレスト……絶対、セリュンを悲しませること、しちゃってる」
こちらから話す前に、本当のことを言ってくれた。土間に並んで座り、少しほっとして、何も言えずに下の姉をじっと見つめる。
「あたしなんて、所詮母さんの代役なのに。アイツが笑うと、それでもいいって思っちゃって……こんなの全然正しくないから、今日こそは終わらせる、そう思って行くのに……」
「お姉様……」
「いっそ竜宮から追い出したいけど、飛竜をアイツの下に返すと、セレストの存在が多分アイツに知られてしまう。セリュンも飛竜のこと、凄く可愛がってるし……」
母の体を、今でも動かす巫女がいること。母を求めて下の姉と交わる父にそれを話すか。今度は妹が妹でなくなるかもしれない。母の記憶をうっすら知り始めてはいるが、預言の巫女は母ではない。大事な妹、そんな想いを姉達は心の糧にしたから竜宮に来たのに。
だから妹も本心を話したかった。隠してもこの黒い心が育てば、いつかは悟られるから。
「お姉様……わたし、お母様の記憶を、最近沢山夢に見るの」
「……知ってる」
「うん……お姉様もわたしも、お母様の欠片。お父様に惹かれることを止められなくて……私は、お父様の悪魔に会いたい」
「…………」
やはり気付いていたから、姉は話したのだ。事は最早、下の姉が素行を隠せばいい話ではなくなってしまっている。
「会ってはいけないって、夢で知ってるの。わたしはお母様の想いに引きずられる。今のお姉様のように」
「……はぁ。さすがは、『夜』の家系だよね、あたし達って」
極夜の名を冠する竜宮の北の地。人間達の言う極夜とは、陽が昇らない季節のことだが、竜宮においてはその気象はない。ただ元々、この地の「神」は「夜」だと伝えられていた。
「夜」とは、「空の光」を奪われて、冷たい水の集まった空。だから水と風の竜は極夜と呼ばれる。光のない大気を操る夜の極みだと。
「夜」が光を奪われたことで、光は天だけのものではなくなった。地上に注いで生物を育み、世界を今の形に押し上げている。
空は冷たく、地は温かく、「夜」は光を切望すると伝承は言う。光さえあれば「夜」は「空」に戻れて、温かさを得られるものだと。
「アイツは、光なんかじゃないけど……」
それでも下の姉も、そして妹も、この世にいなかったもの。自分という心が本当は拙い。
「飛竜はどう思う? セレスト、この体と顔でも、悪魔に会わせてもいいかな?」
目敏さが過ぎる姉は、ヒト以外の化生とも会話ができてしまう。蒼い目で姉を見返した飛竜の心を、ある程度理解できるらしい。
「……やっぱり反対だよね。あたしもそう。セリュンには話すらできない」
上の姉は、家族を求める寂しさのあまりに、死した母を留める禁じ手を使い続けている。それだけ心が崖っぷちにあるのだ。この中で最も危うさを抱えているのは上の姉だった。
「あたしが言えたことじゃないけど……一番大事なのは、絶対セリュンなの……」
顔を覆って声を潰す下の姉に、返す言葉が見つからなかった。正しき女神に見える下の姉は、上の姉の隣に立ってこその姿だ。妹を悪魔に会わせる気はない。それでいい、飛竜と静かに過ごしたいのが妹の心なのに、「暁」はここで、違う望みを持ってしまった。
結果から言えば、預言の巫女は悪魔に会う。飛竜を眠らせて、姉達の目を盗んで外に出る。
それは一つの頼みごとをするためだった。この時巫女は、悪魔の驚愕した顔を見ても、決して妹としての心を踏み越えはしなかった。
「貴女は……生きて……いたのか……?」
外套に隠れて、呼吸している「暁」を見て、姉達の前では白銀の髪であるのが、すぐさま赤い髪の悪魔に変わった。上の姉はこの姿を憶えていないが、こちらこそが「暁」の番だ。
「違うって、貴男の眼ならわかるでしょう。セリュレエンに、『力』を言い表せるあの眼と、魔の素因を与えた貴男になら」
言いつつ、この邂逅は「暁」の望みだった。預言の巫女は姉達の言う事をきき、大好きな飛竜と家で隠れていたかった。けれど「暁」には恋慕以上に、娘への大きな未練があった。
こうして「暁」の心でこの場に在るのが、魔物となる道だとわかっていた。それは世界から弾かれてしまう、滅びを否定する禁忌。
悪魔は「暁」の望みを承諾した。悪魔にも父としての想いは重く存在していた。
「……後悔していた。どうして、あの時に、セリュンを連れて旅に出なかったのかと」
「暁」は悪魔の予想より早く死んでいた。生き続けられる「暁」の器と共に戻る前に。
帰路についた預言の巫女の前に、その人影は現れていた。忘れたいと切望する巫女ほど禍を知るわけではなく、ただ反則の「暁」に気付き、悪魔と会わせまいとしていた児女。
「……どうして? 貴女がいることを知ってしまえば、アステルが今後に何をするかは、わかりきっているのに」
夜明けを前に、児女の背にある銀色の翼が透明に薄まっている。「暁」と同じその翼に、巫女は虚勢で微笑むしかなかった。
「……あなたと反対です。たった一人が長く苦しむ未来よりも、一人でも救われる未来を私は望みます……ソーマ姉様」
「…………」
これは悪魔も誤算だっただろうこと。「暁」の器を作るために、悪魔が生前の「暁」から預かった縁が児女が背にする翼だ。天の翼は「力」を宿すもので、命の受け皿とできる。
けれどその翼は元々、「暁」の姉が体の弱い妹に分け与えた片翼なのだ。夫候補の悪魔に本当は惹かれていた姉は、児女に植えられた己の翼に魂を誘われ、夭逝して悪魔の傍に降りた。
そんな児女の在り方は「魔」。姉の本体と共に滅びた残りの翼は、何故か空の女神に生えた。
「私に、アステルのことは渡さないと?」
「いいえ。あなた一人を、苦しめはしません」
背中を向けた巫女を、児女は追わなかった。「暁」の翼に宿る「夜」が、動き始めていた。
この夜の密会がなければ、預言の巫女には確かな罪は認められなかっただろう。まさかヒトと関わり合いになる機会のなかった巫女が、子を孕むとは誰も思わなかったのだから。
巫女自身も驚いたのだが、新たな命が「暁」の体に宿った。それは黄昏の女神には本当に、「妹」である存在になる。
「信じられない……セレスト……あの悪魔の子供、これ……?」
下の姉は呆然としてしまい、上の姉は何が何やら、と混乱し過ぎて、逆に冷静になった。突然身重になった預言の巫女を、姉達は必ず母子共に守る、と最初に言ってくれた。
下の姉はおそらく、気付いている。これは巫女と悪魔の子供ではなく、下の姉が本来は受けていた命だろう。悪魔から戻った父も、下の姉には弁解しているかもしれない。彼らは決して巫女には手を出していない、と。
これからどうなるかはわからなかったが、あの夜には悪魔と巫女の間には何もなかった。しかし巫女の体は元々「暁」のもので、下の姉は竜の目が一つだけの、物も食べられない人造の竜――「暁」が持っていた竜珠をヒトにした者。
きっと、「暁」の「力」である姉に宿った新しい命を、「暁」の本体が孕んでいた。下の姉に近親との交わりが疑われないよう、巫女は何も言わなかった。
「お父さんとお母さんの子供、ってことで、セレストの髪をお母さんと同じ色にして……生まれる子供は、わたし達の妹だよね」
竜人の子供は、早ければひと月で生まれる。困惑していた上の姉は、可愛い女の子が実際に生まれると見違えるように元気になった。
下の姉は最早、父とは全然逢わなくなった。何も気にしないでいい、と巫女に笑いかけて、生まれた子供を可愛がっている。
預言の巫女の身は、姉の母に扮した状態で大伯母にも紹介された。記憶を失くしていたから会えなかった、と嘘を重ねて。
「まだ本調子でないですね、アルン。貴方の娘はしっかりしている。養生しなさい」
これで事が終われば良かった。預言の巫女の存在を隠すこともなくなり、飛竜の馭者も父として女神達との関係を周知された。不穏の芽はほぼ断たれたはずだったのに。
本当はこうなると巫女にはわかっていた。飛竜を司る魔導師である前に、彼は悪魔だ。地上の不穏を視て回ることが彼の「意味」で、竜宮にいつまでも留まることはできない。
やがて死にそうな顔色になった上の姉が、現実の刻限を伝えに訪れていた。
「お父さんが、竜宮を出るって……セレストとロゼも連れていくって、そう言うの……」
父の出身地の言葉で名付けられた新たな娘。まだ赤子の娘を想う、悪魔の意志はわかった。
上の姉と下の姉は、父について竜宮を出ることを止められた。大伯母をはじめ、次代の極夜の長である従弟や、伯父にも反対された。
運命の女神なしに治安を保てるほど、今の竜宮の情勢は甘くなかった。父も本当は全員連れて行きたかったのだろうが、世界を巡る悪魔の業こそ彼が存在を赦される理由なのだ。
「わたし、お父さんに、やめてってお願いに行く……お母さんと、妹を奪わないで……」
一番動揺が大きかったのは上の姉だ。竜宮には守ってきた愛着も、責任感もあり、自ら出て行くことはできない。下の姉と共に父の所に向かうのを、巫女には止められなかった。これが悪夢の始まりだと知っていても。
預言の巫女が見ていた、二つの夢があった。一つは下の姉が、ロゼを自分の子供だとして、白銀の髪の父と娘を連れて去ること。それは追手もかかり、永く自身を責める道になるが、父と本当に結ばれていたのは下の姉なのだ。
妹も娘も公に生きられるようになり、下の姉は自らの想いを封じ込めた。それが最上の選択だと本人も信じていたのに。上の姉が父と話し合っている間に、下の姉は黒い児女に出会ってしまう。同じ銀の翼を持った相手に。
「……苦しいんでしょ。暁の『狂乱』」
黒い児女は、その怨嗟を解放してしまった。最早居場所の無い児女を葬ってもらうために。
➺終奏∴夜の魔物
妹である母と、本当の妹を連れて行かれる。黄昏の女神の動揺は想定内で、飛竜を置いていくこと、旅に出てもまた帰ってくること、永遠の別れではないとなだめれば良かった。
問題は空の女神と、暁月夜の黒い児女――悪魔を男として慕う火種の存在。空の女神は隠し続けるつもりでいても、「新境地」にいた暁月夜は根本的な解決を望んだ。悪魔の家に来た女神達から空の女神だけを、暗い夕刻に飛竜のいた森に喚び出していた。
児女が空の女神と、直に見えるのは初めてだった。それは終わりを意味するからだ。
「貴女は……ソーマ・イーシャの魔物……?」
児女の真情が、極夜の者であるために。空の女神はこの禍を見逃すはずがなかった。
「この地、それも長の血から魔物が生まれるなんて……貴女は、存在してはいけない……」
「貴女こそ。私の翼が魔なら、貴女も魔だわ」
そしてそれは、「暁」を騙る預言の巫女も、それらを創り出した黄昏の女神も。誰こそが「反則」なのか、誰もが目を瞑ってきた。
「アルンの願いを、ずっと守りたいのよね。貴女はそういう怨念だから。エリニュエス」
母を求めて泣く娘の下に顕れた怨念。それでもまだその女神は、「空」の系譜でもあった。
「空は夜に転じる。その翼はエリスに堕ちた」
正しさを望む逆鱗を受けて、星影との小さな愛も知って、「空の女神」は竜人でいられた。
本当は奪われるものを思う、「狂乱」。復讐には大義があるが、「奪われたくない」心は狂気に変わる。
「わかっているんでしょう? 私と貴女は、アステル・シリュスを愛憎する災いとなる。セリュレエンに、家族を返してあげなければ」
だから空の女神だけが、竜宮に残ればいい。何も持たない身になれば、何も奪われない。
苦しいのはお互い様だった。黄昏の女神と出会ってから、黒い児女には不思議な親心が芽生えて、女として悪魔の傍にいったはずが彼女の幸せを思い始めた。児女は所詮悪魔の娘でしかなく、また多くの子の母だったから。
黒い児女には、預言の「力」はなかった。だからここで児女を殺させることで、「狂乱」が真っ黒の夜となることまでは判らなかった。
「そんな……飛竜にセレストを守らせたのは、あなただったんだ……」
空の女神も、「今」しかいつも判らなかった。預言の巫女が怖れる黒い禍の夢。「空の女神」は夢に出ないことだけ感じて、禍が己だとは思いもしていなかった。それほど醜い黒い禍。
児女は正しい。優しくて、殺したくない。だから黄昏の女神の裁定まで待てなかった。
己を振り切ろうと、首を刎ねたところで――
銀の翼を生やす透明な「桃花水」に、本来玄だった翼が還った。二つの翼が一つに戻る。
「あはは……あ――は……」
光を映す月の「夜」の翼。極夜の長姫が妹に分けた時に、玄の片翼が銀の両翼になった。
他大陸に移住が必要なほどだった「暁」は、その翼で命を延ばせた。極夜の姉も「夜」の宿命、温かさへの渇望を抑えられた。翼の姿は天上の鳥――そう在りたかったのに。
「なにこれ、なんて、醜――……もういや、わた、あたし……どこ、せりゅん……?」
空の女神の翼が黒く染まった。
天の翼とは元来、命――「力」の受け皿。女神が奪った数多の命も受けて、「桃花水」の内にも黒い獣が宿る。混ざり過ぎた闇の四つ辻を月夜が映し出す。
破局は一瞬だった。黄昏の女神を置いて先に帰った空の女神が、預言の巫女の命を奪う。
「何処にも行かないで……母さん」
奪われたくなければ、この翼に奪えばいい。こうなるだろうと夢で見ていた預言の巫女は、赤子の娘を飛竜に託して逃れさせていた。
魔性の極夜は、自身だけでなく天女達の思慕をも宿していた。
母を早くに亡くした娘の慟哭。
一人残るべき空の女神自身の苦しみ。
そんな全てを余さず見つめてしまう預言の力。
結局、二人でも一人でも女神が竜宮に残れば、いずれ魔物は発生していただろう。残される生贄の寂しさによって。
竜宮に魔の竜が生まれ落ちた。
母が、娘が、温かさが欲しい。全てを奪い取る夜の魔物が。
➺後奏∴心眼 光

世界が終わった。そう感じてしまうほどに耐えられない悲しみの後でも、ヒトは呼吸を続けることを彼女は改めて知った。
「実際、どうして……私、生きてるんだろ?」
黒に穢れた竜珠を双子は暴走させた。本体である巫女の体を奪って動かし、双子本人は紅い光を放つ黒翼の獣と化した。大気を凶刃に変え、竜宮中の川を氾濫させたため、預言の巫女が魔の竜を喚んだと傍目には見られた。
双子がそこまでして彼女と悪魔も殺そうとしたため、父は悪魔だと知られてしまった。悪魔の子など孕むから魔竜が生まれたのだと。
彼女も双子を止めるために、自らを殺させ双子の命に潜り込んだ。父曰く「暁月夜」は月夜の「神」たり得る傑物で、「神」を殺した双子は「神」に祟られ、自分の心を隠されてしまった。偽りの逆鱗には「神」を止める程の力はなく、命を乗っ取る「神」は切り離すしかないと言うため、彼女こそ魂を奪う悪魔と化して、黒い翼を断ち切ったはずなのだ。
「お父さんも行方不明で……多分死んでるし。二人だけに、なっちゃったね。メティア」
彼女も死んだことになった黄昏の魔なので、姿を消した竜宮にはもう振り返らない。ただ彼女の後ろで、蒼い髪の青年が頷いてくれた。これだけが彼女の救いだった。
元々暮らしていた寒い山村に戻ってきた。ここの寒気なら氷を基盤とする「力」である青年を、ヒト型に保つ力を維持できるだろう。
彼は父が彼女のために、飛竜をヒトの姿に変えてくれた青年だった。母の願いだと言い、父の悪魔とかつて共調した人間の心らしい。魔物となった彼女より無害な優しい相手だ。
悪魔が連れていた飛竜は、起源は高い空に顕れた氷塵から作った獣。青年の心が飛竜に遷されたことで「力」だけの獣ではなくなり、父がヒトの姿にまでしたのは彼女への愛故だ。色々思うところはあるが、赦すしかない。
飛竜の青年が連れて逃げた赤子のロゼは、父がどこかに隠してしまったという。後日にその件は「無色」が本当の話を教えてくれた。
――あなたの体を復元するためには、悪魔はロゼの竜の目を使うしかなくて。小さ過ぎるロゼは、一つの竜の目ではヒトの姿を保てなくて、死んではいないけど人世にもいない。
今持つ竜珠に後継者ができたら、この眼をロゼに返そう。双子に奪われた自身の眼を、ロゼが竜の墓場という神域で受け取っていると彼女は知らない。
双子の黒い翼や魔という妹の骸に宿る闇の末路も、その辺りの処遇は父と、「無色」の動かす自分が決めていた。
「アジュは悪い神に、セレストは記憶を消す神に。二人の心は逃してくれたんだよね? アシェ君が力を貸してくれた、って聞いた」
空の光が夜に穢され、双子は正気を失って争いの「神」に成り果ててしまった。渦中で死んだ彼女の体は、「無色」が依り代にした。
彼女に昔、「力」を言い表せる眼をくれた「空の光」は、自分は飛竜の青年の仲間で、「無色」だと名乗った。古の夜に光が顕れた時から、夜と朝の境で空に浮かぶだけらしい。本来の「空の光」は地上に恩恵を遷し、「無色」には飛竜や青雲しか仲間が残らなかった。
飛竜の青年と暮らし始めて、「無色」は姿をうっすら顕すようになった。消えそうな白猫姿で寝台に座り、少し違う視点で魔竜を語る。
――『夜』の咎じゃない。アジュ……アザーは元々『神』に近くてすぐヒト型をとれたし、沢山ヒトを殺したからその念も積もってたの。
魔竜の事変は広く伝わっている。関係者と周囲に気付かれないため、彼女達は呼び名を変えた。まず彼女も夕紅の茶から「無色」の白髪へ、青い眼も悪魔の紅に変わったため、セリュンとして戻ってきたわけではなかった。
――私が今あなた、フューシャと話せるのは、アザーからあなたを奪って命が繋がったから、知性を取り込めたの。人の言葉は話せなくて、あなたが私の『意味』を視ている。私も『神』らしいけど、『神』には善も悪も心はないよ。
それならどうして、「無色」は彼女を助けてくれたのだろう。彼女に家族を与え、魔竜の事変後は「無色」も彼女の蘇生に寄与した。
父は飛竜を青年に変えたように、「力」でも物質的な面に介入が速い者らしい。「無色」は逆で存在の中身、言霊などを主に扱う介入者。どちらも揃っての彼女の目醒めだった。
「『無色』に心がなかったのなら、どうして、そもそも私と一緒にいてくれたの?」
ちらりと、夕飯を作ってくれる青年の後ろ姿を見て言った。青年が何故か達人なので、ほとんど家事は任せている。この生活を脅かすものがあれば、彼女はもう迷わず排除する。
――あなたには無色の私が視えた。私に近い眼を持って、あなたこそ一緒にいてくれたの。
飛竜の青年と二人だけの生活。彼女が先刻そう言ったのは、青年には「無色」が視えず、また「無色」を憶えてもいないからだった。
「無色」が猫の姿をするのは、青年が猫好きということを聴いてからだが、飛竜という「力」も実体なしには記憶が保たれないのだ。
――私の望みは、フューシャが憶えていて。暁の光も夜の紅花も、あなたが封じてるから……私は、何度忘れてもまた会えるように、あなたの眼を心にしてこれから地上を往く。
そして彼女は、時間をかけて飛竜の青年を人間に近付け、やがて三人の子に恵まれる。
一人が「桃花水」を継いだ。黒い珠玉の内に眠る悲しみは、誰にも知らされないまま。
黄昏紅花 了
夜を揺らす紅い極光。夜こそ「暁」の真情だが、熱なき夜明けが常の姿。月という光と闇を持つ姉の、おそらく余り物で生を受けた。
大気を雪解けさせるように、夜に紅い川を流す光が彼女。世界に降る「空の光」の一端らしく、幼少から妙にヒトの心には鋭かった。
――わたしをあの光の中へ連れていって。
悪魔や娘は、紅い竜を光として望んでいた。娘には「黄昏」、暁の紅より強い光があったが、姉の翼が馴染む暁は、自身で光を咲かせると消耗していく。それでもそう生きたかった。
母を求める娘があった。娘に身体を与えた母と、そして娘を奪われた母も。
娘は光を持つがために、「無色」に生き筋を奪われてしまった。
「無色」は元々、光と夜の「暁」に近い。娘の髪に宿る「無色」に気付いたのは双子を連れてきた時で、「反則」へと踏み込む娘が心配で人世を去り切れなかった。
かみ合わない道を交じらせたのは、闇にも光を映す月夜。蒼い空の獣を凍りつかせ、星々の戒めになった黄昏の娘が、夜の獣に触れて暁の光を灯す紅い花と化した。同じ空の獣を望む光の四つ辻が、黒い夜空の穢れとなった。
それはいったい、誰の罪だと言ったものか。初めから夜の光が一つであったのならば。
暁月夜の黒い獣は、争いを喰む空の女神の傍に永く佇む。真実が長い時で歪められても。
黄昏紅花
星空文庫掲載はお久しぶりです。ここまで読んで下さりありがとうございました。
本作DシリーズD0は、Cry/シリーズが全作生まれてから追加された挿話です。
本来Dシリーズは最も最初にできた正史のお話ですが、Cry/シリーズの誕生によりD3が大きく影響を受けています。
またCry/シリーズも当初の設定、zero/雑種化け物譚Rの主役が作成時は熱血少年だったはずが、D3改定後に絶食水属性に変わった経緯があります。
このDzero『女神の絵本』の火竜少年のまま雑種化け物譚を書けば、雑種化け物譚もDシリーズになったのだろうと作者の中で位置づけたため、同時掲載としました。
現在、創作活動がとても下火です。今回新作の『黄昏紅花』だけで息切れしていますが、たった3万字です。
それでも各所で細々読んで下さる方々がおられるようなので、何とか呼吸を続けております。
色んな事情で現在非公開にしている過去作品も、エブリスタなどではおおむね公開してあります。もしも探して下さる方があればよければ。
→https://estar.jp/users/107742416
あと一つ、本編で焦点を当てられなかった空の女神のR18オマケが、最後の画像サンプルのようにあります。
R18というほど過激な描写ではないのですが、苦手な人には駄目なくらいでもあります。
2026から新パスワードに更新しますので、続きが気になる方があって下さればこちらへ。
PDF置き場→https://xfolio.jp/portfolio/sky/fan_community
パスワード→https://fril.jp/shop/xsky
女神の絵本 初稿:2023.10.13
黄昏紅花 初稿:2025.12.13
※星空文庫内Dシリーズ本編(本作公開時点ではD1/D2非公開・不定期公開)
『竜の仔の夜➺D1』:https://slib.net/123537
『竜の仔の王➺D2』:https://slib.net/123963
『竜殺しの夜➺D3』:https://slib.net/119597


