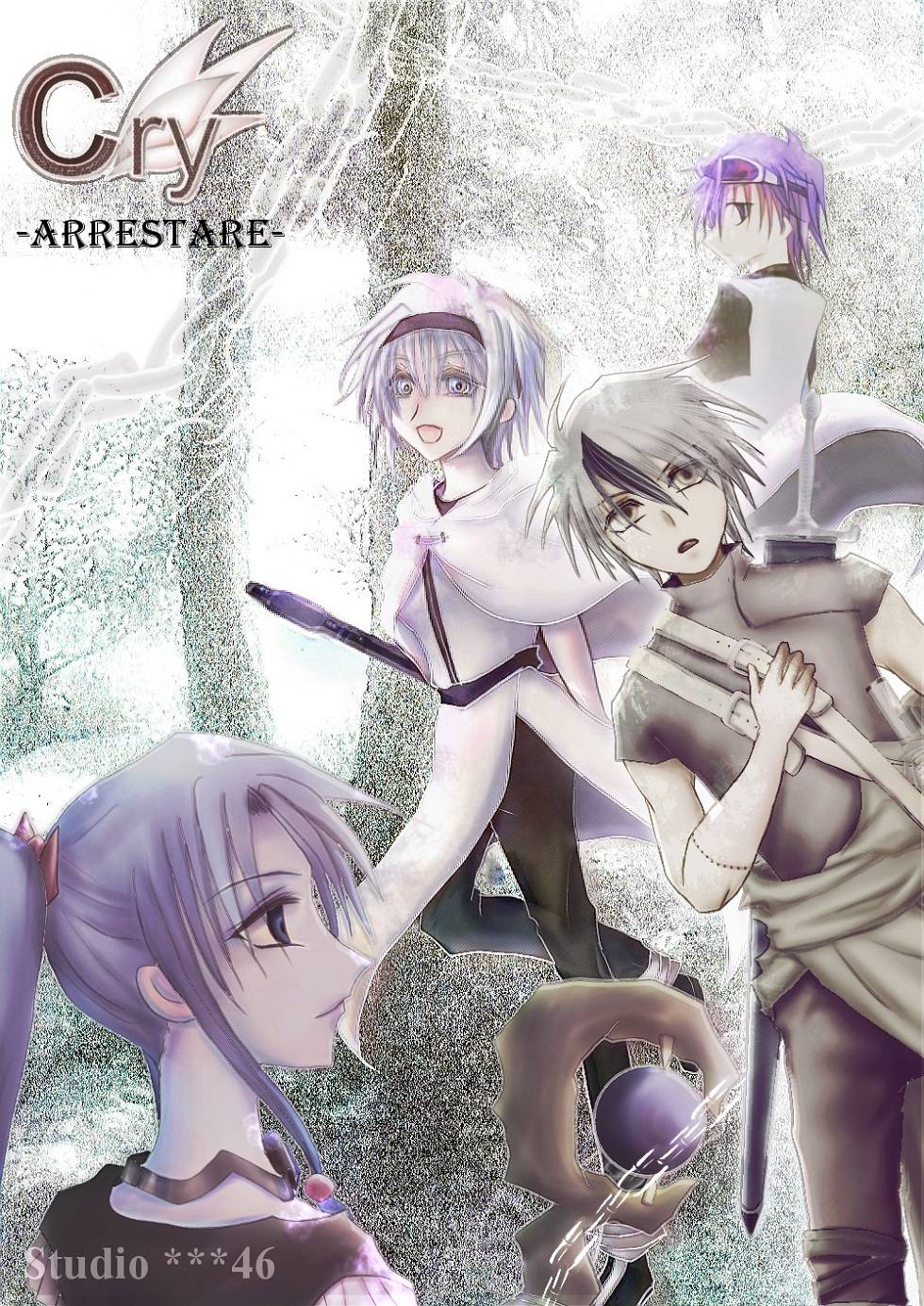
千族化け物譚❖Cry/A. -arrestare-
人の姿をしながら人ならぬ「力」を持ち、心は人間に近い「千族」達が、思わぬ前世の宿縁と時代の動乱に翻弄される召喚獣活劇ファンタジーです。
暗い要素が特に下篇に少なからずありますが、バッドエンドではありません。
28万字ある上下篇で、本作の上篇14万字だけでも一応終われる仕様です。
update:2023.8.13-24 Cry/AシリーズC1 別作DKL'sの後日譚
※C1下篇(不定期公開)→https://slib.net/119235
※DKL's→https://slib.net/119597
※千族化け物譚の続編で15年後・常時公開→https://www.novelabo.com/books/6717/chapters
❖上❖
物心ついた頃から、誰も傷付けずに生きられたらいいと思っていた。
それは綺麗事だ。化け物の力を持って生まれ、武器を持つ以上、戦いは避けられない事。
それが嫌なら人間のように、弱く狩られる立場にならなければいけない。
少なくとも剣など取ってはいけない。でもオレは、生まれた時から赤まみれだった。
前世なんてどうでもいいけど……きっと俺は、悪いことをしたんだ。
「オレ……ここにいない方が、よかったんだ――……」
五歳になる少し前の事だった。馴染みの悪ガキ三人で大人の目を盗み、初めて遠出した。
神聖な何処かの泉に迷い込んだと、気付いた時には後の祭りで。
「ごめんなさい……! あたし、ごめんなさい――……!」
きっとその時、オレは全ての穢れを知った。
あいつの泣き声を昏い水の中で聴いて、やっと少しだけ、赤まみれだった自分をキレイにできる気がした。
そして俺は、オレを置き去りにしたんだ。
幾度も繰り返すさだめ、兇獣の赤い腕と共に――
+++++
Cry per A. -arrestare-
千族化け物譚 C1上篇 『紫苑の少年』
~Wizard Aster~
上1:運命の黒
久しぶりに見た青い夢から、ゆっくりと浮上するように、彼は目を覚ましていた。
この夢を見るといつも気分が重くなる。ブルーの意味で青と銘打った夢だ。
「……今日は、里を出る日だからか……?」
シンプルな木製の寝床から体を起こすと、支えにした右手がぎしっと軋みをあげる。
しまった、と彼は重心を変えながら、小さな丸木小屋――海に最も近い質素な自宅から、初冬の寒気にもめげず、寝起きの恰好のままで岸壁へと出た。
白金の陽を受けた海原を見下ろす、高い断崖。深い森から北の海に続く出口で、潮騒を聞きながらぶらぶら歩くと、いつも自然と気分が落ち着く。
人間は滅多に来ない、深い山奥だ。彼のように隠れ住む化け物達の、聖域と言える。
ぽつんと崖の上に立った、袖の無い黒衣の彼は目立つのか、彼を見つけた同い年の悪友――十七歳の暑苦しい男の気配が近付くことに、程無く気が付いた。
「って、おぉーい、何やねんレイアス! まだそんな恰好しとんのか!」
全身を覆う枯色の外套を纏う悪友は、肩に大きな布袋を下げ、すっかり旅支度を整えている。碧い鳥頭の前髪からのぞく細い目で、彼の全身を改めてチェックしてくる。
彼の今の姿――前髪に一房だけ天然の黒髪が混じる、珍しい灰色の短髪の尖った頭と、シンプルな黒衣の上下という出で立ちは、寝起きそのものでしかない。
武器である長剣や短刀と、それを背中に掛けるベルトすら無い状態に、悪友は彼よりも濃い灰色の目を不満一杯にした。
「オマエなぁ、今日が何の日かほんまにわかっとんのか?」
「悪い、寝過ごした」
いつも通り無表情に、彼は淡々と言う。妙な訛りのある悪友が、覇気のある低い声で、顔色豊かに騒ぎ始める。
「せっかく晴れて、里を堂々と出られる待ちかねた日やねんで!? 一軍村で同世代やとおれらが一番乗りなんやからな!」
「にしても、タツクが朝早過ぎだろ。それに……」
この一帯は、海岸から内陸に向かって、一軍、二軍、補欠世帯などと俗称のつく三つの村に分かれる。それぞれ森を境にして、隠れ里にしては大きい集落だ。そこから最初に、外界に出ることを許された同世代者は、正確には彼らでないことを彼は思い出す。
しかしその話は、悪友に違うスイッチを入れるだけだと思い直した。
「……タツクは一番でなきゃ、長の息子としてどうかって話だし」
「オマエに言われたないし! とにかくはよ用意してこいや! オマエと二人やないと、出たらあかんて言われてんねんからな」
森との境、雑草が茂り出す山岸で、悪友が不機嫌に騒ぎ続ける。海に一番近い家を与えられた彼は、やれやれ、と背中を押されるしかなく――
そうして海に背を向けた彼らに、突然の暗雲が訪れるなど、誰も予想できるわけもない。
「ええか、外の世界は危険が一杯やねんからな!? 魔王に四天王、守護者や妖精に他の千族、吸血鬼に魔物に、警戒相手はアホ程おんねん!」
この小さな世界――「宝界」には、様々な神秘を起こす「力」を持つ化け物がいる。稀少なそれらは、最多の生物である人間から隠れるように、細々と存在している。
そうして人間と似ながら人間ならぬ「力」を持つ生き物を、まとめて「千族」といった。
彼も悪友も、その「千族」の一種だ。
「俺は……一番危ないのは、竜や精霊だと思うけどな」
「何でやねん、精霊魔法は確かに反則ものやけど、誰かに使役されんとまず現れへんし、竜なんて滅びた種族やんけ。いくら最強の『力』――自然の系統や言うても、そっち系はもう、今は『守護者』が鉄板やろ」
彼の家に向かい、わいわいと後にした断崖の遥か下方で、潮の動きがぴたりと止まる。同時に海面が青黒い闇をたたえ始めたことにも、彼らは気付いていない。
「『守護者』は十六年前、『地』が滅びてから消息不明だろ? でも竜は召喚士さえいれば、いつでも再現されるはずだし」
「あー、ないない。おれらん中にすらおらんのに、あんな莫大な『力』使役できる奴、現代におるわけがあらへん。せいぜいで、精霊使いの多い『妖精』に気ぃ付けるくらいが、オマエが言う方面やと現実的ちゃうか?」
そこで太陽が雲に隠れ、鳥の声が全て止んだ時点で、ようやく彼はその――
あまりに自然に渦巻き始めた、大陸規模の有り得ない大きな「力」に気が付く。
「……!?」
「――レイアス?」
立ち止まって海を振り返った彼に続き、不思議そうに悪友が振り返る。
その二人の青年の灰色の目に、次の瞬間映ったのは――
まるで、断崖から彼らを睨むような、渦巻き立った巨大な水蛇だった。
「なー!?」
「……!?」
海面の渦潮と繋がり、水の竜巻と言える激しい水柱。それはあくまで自然現象のためか、「力」が起こす空間の歪みは小さく、森より奥にいる里の者は気付かない異変だろう。
「竜、だろ、あれ……!!」
「な、んなアホなぁー!?」
しかしこの世界では、そう呼ばれる「力」。自然界の生きた脅威に唖然とする彼らだった。
それでも、彼らが通称一軍村に住まわされている理由を、彼はすぐに自覚した。
「――行くぞタツク! 何とかしないと、下手したら大惨事だ!」
「って――お、おう!」
最も海岸に近い区域に住まう者の役目は、海の外敵から里を守ること、それに尽きる。
再び山岸に戻る方へ駆け出した彼に、悪友もさっと外套を脱いで荷物を置き、動き易い淡褐色の武闘服でその後を追いかけていった。
彼らが岸壁につくと空も海も暗転し、「水」の竜を中心に激しい風が吹き荒れていた。
「何なんだこれ――これでまだ、発生途中だっていうのか!?」
「発生源は何処や!? 今なら止められるかもしれへん!」
どんどんと暗くなっていく周囲に、彼らは背中合わせで、崖の縁に立ち尽くすしかない。
「正直まずいで。修行の成果を見せたいとこやけど、おれら二人とこれは相性悪過ぎや」
彼らは主に、「火」に関係する「力」を持つ化け物だ。
ところが現状は、明らかに海から力を吸い上げて荒ぶる「水」の場であり、この里では一番強い彼らすら慄かせる「力」が、そこに展開しつつあった。
「発生、源……」
この規模の実戦にまだ巻き込まれたことがない彼は、止まらない冷や汗を感じながらも……広がり続ける荒れ狂った大気と海しか見えない、その暗い岸壁で――
「……え?」
それはまるで――悲しげな暗い空が、そのまま堕ちてきたような仄暗く澱む大気。
そうとしか思えないほど、不自然に玄く染められた場が近くの入り江に渦巻くのが、彼の彩の無い目にふっと映った。
どうしてそれが、この荒れ狂う「水」の源と思ったかは、彼にはわからなかった。
「タツク、あっちだ! ここよりあっちの方が大気の色が黒い!」
「って、それはほんまか!? 何処も気配は同じやけど――」
悪友にその玄は見えていないらしい。しかしそれは、彼らにはいつものことでもあった。
「この『力』は黒なんか!? レイアス!」
「――」
彼の言葉を信じて駆け出した傍ら、悪友は、彼の珍しい特技――本来は色などない「力」に、個別の色を見る彼の眼の所感を尋ねる。
激しい風と共に、叩き付けるように降り出してきた強い雨に打たれながら、彼は憮然と首を振った。
「色が無いんだ。だから黒に見えてるだけだと思う」
「……まずいで。そら本気で、純粋な『水』の化身とちゃうんか、五行的に」
驚く暇もなく、彼らの行く手に、突然新たに真っ黒で巨大な「力」の柱が立ち昇った。
「って――黒っ!! 黒のあれはまさか、んなアホな……!!」
悪友にも見えているその黒は、彼らが見知った「力」だ。悪友が衝撃を受けたように、その「力」の出現は、あまりに想定外だった。彼にも瞬時に、鮮烈な驚愕が走る。
「……あいつ!?」
ぎり。と一瞬、彼は強く顔を顰め……里と外界の境界である谷へと、飛び込んでいった。
雨滴に叩かれながら谷底に向かい、切り出された僅かな足場を慎重に飛び降りて伝う。そこから見える谷川の出口で、黒い激流が激しく渦巻き、「水」の竜を立ち上がらせている。
「――!!」
「うぉあ! いきなり『実体化』かいな!?」
その竜の源となる玄い渦に、まさに今、全てを呑み込む黒い「力」が襲いかかっていた。
激流の渕に巨大な口で丸ごと喰らいついた、ある黒い獣の姿を彼らはすぐに目にした。
「『フェンリル』か……!!」
口を開けた瞬間、大いなる咆哮を黒い巨獣が放つ。それは形だけを見れば、ただの狼と変わらない四本足の獣だ。
入り江そのものを喰らえる巨体の唸りは、周りの大気をも激しく揺らす。玄い場全てを飛散させるほどの「力」を、そのまま惜しみなく叩き付ける。
噛み千切られて海に還る竜と、喰らいつかれた激流は繋がりを断たれ、しばらく黒い獣の四足に打ち付け続けていたものの……雨風が止み雲が晴れ、太陽が再び顔を出した頃には、本来の静けさを思い出したような流れへ立ち戻っていくのが見えた。
とてつもなく面白くなさそうに、谷の途中で悪友が両腕を組んで呟いた。
「何や全く……アシュリンの奴に、先、こされてもーたな」
視線の先では黒い獣が、鋭く細い白眼で、静寂に戻る海面を見届けている。
巨大な黒い姿はその後薄まってゆき、最初から何もなかったように、獣も消え去ってしまい――
彼らはその入り江へ、谷底に着いてから急いで足を向けた。
「アシュー、何処や!? いるんやろ!?」
悪友の声色も硬いが、同じ相手を気配で探す彼も厳しい顔をせずにいられなかった。
それというのも……。
「……あれ――……あ、あれれ?」
ようやく見つけたその相手。絶壁の麓で座り込む、白い外套の似合う姿。
放心したような気弱な声に、彼らは揃って立ち止まった。
「何で、レイアスとタツクが……って、そっか――」
「あほう。ここは元々、二軍村のお前やのーて、おれらの管轄やろう」
「……あはは。そう言うなら、もうちょっと早く来てほしかったなぁ」
その無事を確認して、彼らは二人して安堵の息をつく。
そこには、白い無袖で腰巻つなぎ服の娘。耳を隠す硬質で短い白灰の髪をかき上げる、同い年の幼馴染みの姿が予想通りにあった。
何しろ、先程の黒狼は紛れもなく、この幼馴染みの存在を示すものなのだから。
怪訝そうな彼らを、困ったような笑顔で幼馴染みは見上げている。彼と同じ灰色の目を細める幼馴染みの横には、彼らの見慣れない誰かが倒れていた。
「……それ、誰だ? アシュー」
意識なく横たわる、外套で身を隠す人影。それをかばうように幼馴染みは苦笑う。
「さぁ、あたしもよくわかんない。偶然一緒になって、さっきまで同じ道を来てたコなんだけど……別れてからすぐ、あの変な渦巻きが起こったから」
幼馴染みはそうして、二軍村に帰る違う出口に向かっていたが、別れた相手が気になってこちらに来た顛末らしい。
そして出くわした、謎の荒れ狂う玄い場。それを治めてしまったのは、紛れもなく――彼らよりも早く一人で里を出ることを許された、この幼馴染みの「力」だった。
「だからって余計なことすんなや。『実体化』まで『力』使うて、どうにもならんかったらどないするつもりやってん?」
「……そーだよね。何か、このコが倒れてたの見て、あたしもわけがわかんなくなって」
難しい顔の悪友に、幼馴染みは座り込んだまま肩を竦める。
本来その幼馴染みは、荒事への対処を嫌がる――というより怖がる方だった。
幼い頃は近くに住んでいたものの、幼馴染みが二軍の村に引っ越してからは付き合いはほとんどない。基本的には、武勇談とは逆の噂を耳にすることが多い相手なのだ。
「んなこっちゃろーと思ったわ。凄い状況にパニくって、いきなりフェンリル呼んだんやろ」
幼馴染みとはいえ、久々に話すせいか、悪友は顔付きも硬いまま声色も厳しい。対して幼馴染みは昔とあまり変わらない、弱気な緩い笑顔だけを浮かべていた。
悪友はさらに、険しい顔付きで追い打ちをかける。
「あんまぽこぽこ『実体化』使うなや。どーせ物理攻撃しかようせーへん、でかいだけが取り柄の出来の悪い霊獣なんやからな」
それは昔からであるのだが、悪友は妙に、この幼馴染みに厳しい。
どういった形であれ、先程の場を治めた幼馴染みの功績に気が付いていないわけはない。
そもそも彼らに比べ、物理的な強靭さに優れた幼馴染みの「力」だからこそ、あの場を治められたこともわかっているはずだったが。
「これに懲りたら、当分は里で大人しゅーしてるんやな!」
「あはは……あたしもそうしたいけど、そういうわけにもいかなくてさぁ」
彼らよりも随分早くから、たった一人で里を出入りすることを許されている幼馴染み。
それは何より、そうした「力」の制御を、同年代の誰より早く熟練した実力の証だった。
昔から幼馴染みの母が頻繁に彼女を連れて里を出入りし、外の世界に慣れている事情も加味されてはいるのだが……彼らにはなかなか許されない自由を持つ相手に、いつも厳しい目を向ける悪友だった。
そうしたわけで、遠出先から戻る途中だったという幼馴染み。ところが山道で偶然に、横で眠る旅人――鉛色の外套に身を包み、青い珠をC型に囲む木杖を持つ流人に出会ったという。
「レイアス達はひょっとして……今日、初めて出る日だったの?」
倒れている旅人の様子を確かめながら、幼馴染みが彼らに尋ねる。
「そうやで。とんだ形で出鼻をくじかれたけどな」
立ち尽くしていた彼らも、ようやくしずしずと、倒れている者の横に集まって屈む。
その相手、頭巾付きの外套で顔を覆う者は、一見は同年代の珍しい姿だ。袖口と襟口を白いひらひらで飾る、肩を出す黒い筒型衣。人魚のように足の線が浮き出る白くて長い下衣も、彼らは滅多に見ない型の装い。派手ではないが質の良い生地を使われた服は、おそらく何かの魔法効果を付加されていることもわかった。
木杖を手にしていることからも、戦士よりは魔法使いの類の化け物だろう。このような山奥に、人間がまず、こんな礼装で来ることはめったにないのだ。
「…………」
久々に会った幼馴染みと悪友のやりとりを、ただ傍観していた彼は、何故か、その倒れている相手から目を離すことができなかった。
「んで、アシューもこいつも、怪我はないんか?」
「うん、多分大丈夫。さっきの変な渦、このコのことは避けてた感じだった」
「何やそれ、逆に胡散臭い話やな。それやとひょっとして、あれの発生源は――」
倒れた相手の背中側にいる悪友と、頭の方に屈んだ彼を横に、幼馴染みは意識のない者の外套に手をかける。
隠されている顔を出すよう、幼馴染みがそっと、その神秘のベールをずらすと……。
「……――」
息を呑む彼の前で、中から現れたのは、絹糸に似た優しい光沢のまっすぐな長い髪を高い位置で一つに束ねた、シンプルなポニーテール。
珍しい碧毛の悪友以上に、世にも稀な妙なる色合い――朝の空のような青い色の髪に、彼は不意に、よくわからない衝撃を受けていた。
「あははは。すっごい美人さんでしょ、このコ」
幼馴染みは、言葉にできない衝撃を受けた彼に気付くように、そんな風に緩く笑う。
確かにそこには、寝顔とはいえ、あまりに整った顔立ちと白い肌で安らかに目を閉じた幼げな美女……首元には不思議な、菱形の青い宝石を誂えたチョーカーを着ける旅人が、あどけない表情で眠っていた。
倒れている相手を見つめながら黙り込んでしまった彼に、向かいであぐらをかく悪友が、何やねんとニヤリとした目線を向けてきた。
「あれ程オマエ、自分の遠征は嫁探し目的やない言うてたのに、ひょっとしたら一番早く春が来たんとちゃうか?」
「――は?」
その声にむっと我に返った彼は、不服気に悪友に言い返す。
「一緒にするなよ。俺は最初から目的は一つだ」
この隠れ里――「霊獣族」という千族が潜む奥地には、若い化け物が少なくとも一度、外に出たがる大きな共通の理由がある。
血統の力が強く、異種と交わっても「力」を保つことができるここの化け物は、里という狭い世界だけでなく、広く出会いを求めて旅に出るのが普通なのだ。
「どーやろなぁ~。オマエみたいな奴が案外ムッツリなんは、よーある話やしなぁ」
悪友が妙な訛りを持っているのも、この隠れ里のある「西の大陸」とは対極に位置する、「東の大陸」出身の異種族の母を持つからだ。
悪友自身、旅に出るのは出会い目的と公言している。それが理由として認められるのも、この隠れ里ならではかもしれなかった。
向かいでにやにや、楽しげな悪友に、彼はげんなりする。
「そんなことより……このヒトはどうするつもりなんだ、アシュー」
まだ意識の戻りそうにない相手を再び見つめると、当然の疑問を幼馴染みに尋ねる。
幼馴染みはうーん、と、本気で困った顔付きで考え込んだ。
「寒いし濡れてるし、放っとくと風邪ひいちゃいそう。でも里は……連れて行き難いよね」
「そうだな。連れ込んでいいのは伴侶だけ、そうでなくても里から出さずに、誰かの伴侶にってことになりかねない」
一応隠れ里であるこの秘境では、それが異邦者に定められた処遇でもある。
やっぱりなぁ、と。幼馴染みは彼を見つめると、躊躇いがちに口を開いた。
「それじゃゴメンなんだけど……レイアスの家なら一番端だから、そう簡単にばれないと思うんだ。このコが目を覚ますまで、休ませてあげてくれない?」
「…………」
「ちょっとあたしじゃ、このコを運んで谷を上がれそうにないし。あたしもクタクタだし、少しだけ一緒に休ませてもらっていい……?」
幼馴染みの家は里と外界の南境付近で、中心部の補欠世帯を囲む少し遠い区域にある。
通りすがりに、成り行きで彼らにとって最大の「力」を使った幼馴染みが疲労していることも、彼には重々伝わってきた。
「別にいいけど……俺は、支度が済んだらすぐに出るぞ」
「ええ? って、戸締まりはどうするの?」
「アシューに結界の鍵、預けておくわけにはいかないか」
「ごめん、あたしも家に寄ったらまたすぐ出るつもりなんだ――……っていうか、そんな簡単に鍵とか預けちゃ駄目だよ、レイアス」
たはは、と苦笑う幼馴染みは、とても久しぶりに話した彼――一見こわもてな相手が本来の穏やかさで、昔と変わらぬ信頼を向けてくることに、逆に戸惑いを持ったようだった。
それほど彼らは、こうして互いに、気安く話をすることが久しぶりだったのだ。
そんな様子を見ていた悪友が、ええい、と不機嫌そうに立ち上がった。
「とりあえずさっさとレイアスん家行くで! いつまでこんな所で話し込んでんねん!」
狭苦しい谷底での、久しぶりの昔馴染同士の再会。
キッカケである突然の異変については、よくわからないままだが――
彼らがちょうど、初めて里から出る日にそうした事態が起こり、長く話していなかった者と顔を合わせられたこと。
そしてこの、空のような青い髪を持つ魔道士風の美女と出会うことになったのは……後から考えれば、この時こそが、運命の日の幕開けだった。
上2:空色の流れ人
狭く味気ない丸木小屋は、一人で住むにしても、彩りを備えるような余裕はなかった。
夫婦と幼い子供が、手狭に暮らすくらいの自宅。彼が十年前に父を亡くしてから、母と二人で移り住むことになった僻地は、彼らの隠れ里を外敵から守る最前線だ。
「へぇ……思ってたより本当に、小さい家だったんだね」
二軍の村に引っ越した幼馴染みは、その後に引っ越した彼の家に来たのは今日が初めてになる。彼の寝床に、外套を脱がせて横たえた行きずりの旅人――幼馴染み曰く謎の女のコの枕元に座り、服の上から体を拭いてやりながら家内を見回していた。
「おじ様が亡くなられて……おば様も実力者だったとはいえ、それでもひどい扱いだよね」
海に一番近いこの場所は、強力な化け物が多い外敵を最初に迎え撃たなくてはならない。そのために彼の母が、強い外敵と戦い命を落としたことは、幼馴染みの耳にも届いていたようだった。
昔から言葉を飾らず、沈痛な顔の幼馴染みとは対照的に、彼は淡々と返答していた。
「仕方ないだろ。蛮勇の夫、豪傑の女の肩書きに、拘ってたのは母さんの方だ」
「そーやで。大体レイアス自体、いつ暴れ出すかわからん鬼子やったんやから、親父かてこの一家の扱いには本当悩まされたんや」
彼から借りた手拭いを使いながらずばずば言う悪友は、この「霊獣族」の隠れ里の長の息子だ。彼らにはそんなやりとりは日常茶飯時なのだが……手拭いを肩にかける彼が床に座り、無表情に荷物を詰める横で、幼馴染みは改めて、困ったような顔で微笑んでいた。
「タツクは厳しいね、相変わらず。長はもっと、一見はお優しいのに」
「言うとけや。お前もなアシュー、あんま簡単に切札――霊獣の『実体化』を、軽々しく見せるもんやないで。元々手数少ないんやから、余計にな」
険しい顔付きの悪友は、長の息子だけあり、同郷者の基本的な実力を大体把握している。
幼馴染みは「力」の展開規模が、あの巨体の黒狼のように大きいこと、そしてその制御がヒトより早くできるようになったことは悪友も知っている。しかしそれは早かったことが重要で、特別優れた制御者でないことも、彼らは二人共わかっていた。
「でもあたし、手加減できる余裕ないよ。それに今日のは本当、たまたまだって」
「そーやな、普段はまず戦わんと逃げまくってるゆーし。それなら変に横から出てきなや」
「あはは。本当、タツクは厳しいなぁ」
それは一見、戦果を奪われて拗ねる態度に見えないことも無い悪友だったが。
しかし普段の悪友は、もっと和やかに同郷者達を指導している。「力」の素質も、戦う力もある次期長として、人望も大きな実力者だと彼は知っている。
「……タツクが厳しいのは、アシューにだけだろ」
呆れながら呟く彼を、オイ、と悪友が脇腹を小突く。彼の言葉の意味を全くわかっていない幼馴染みは、旅人の頭を撫でながら不思議そうに首を傾げる。
そこでちょうど、幼馴染みの細い手の下、旅人がぴくりと眉を顰めた。
あ、と幼馴染みが旅人の方を向く。彼も旅支度を中断してズリズリと膝立ちで寝床の横に行き、旅人の顔を斜め上から覗き込んだ。
物悲しげに眠る旅人の、長い睫毛の麓から、不意に一筋の涙が、つ――と頬を伝う。
「……――?」
本当に、キレイなヒトだな、と。その状況で、彼は何故か真っ先にそんな感想が浮かんだ。
「どうしたんだろ。苦しいのかな――」
涙の理由を心配そうに、幼馴染みが旅人を見つめる。その下で、やがてゆっくり旅人は、大きな目を静かに開いていく。
髪より暗い青の目を、ぼうっと滲ませながら、重い瞼をそっと上げたのだが……。
「……ゴメン、なさい……」
「……え?」
涙混じりで何かを呟いた旅人を、彼と幼馴染みが見つめたのと同じ瞬間。
旅人は、最初に見える位置にいた彼を捕まえるようにまっすぐに見つめ、そして――
「兄、さん……!」
胡乱だった目に精彩が宿り、悲しげだった顔が一瞬で、明るく破顔した。
「――え!?」
ばっと起き上がった旅人が、勢いのまま、何故か突然彼に抱き着く。顔を覗き込もうとした幼馴染みは、危うく旅人と頭をぶつける寸前だった。
「なななな、何なんやいったいー!?」
涙ながらに、彼に突然抱き着いた美女。唐突な状況に慌てて隣の悪友が立ち上がる。
膝立ち状態だった彼は、寝床から落ちる勢いで彼の首にしがみついてきた者に、姿勢を崩されてまさに押し倒された状態となった。
「やっと会えたよ、兄さん……!!」
さらにぽろぽろ、涙を零しながら、泣き笑いで相手は彼に抱き着く。
「……あんた、誰だ?」
茫然とした彼は、その、ごく当たり前の疑問を返すことしかできなかった。
立ち上がった悪友と幼馴染みの足下、美女がしがみつく謎の動揺。沸騰しそうな内心を押え、声は穏やかに、赤い無表情で彼は尋ねる。
ぎゅう、と抱き着いていた相手は、その声に気を取り直したのか少し力を緩める。そして腕の中にあった彼の顔を、青く大きな、鋭くも幼い双眸でじっと見つめた。
それから、キョトンとしたように、旅人はそれまでの微笑みを消した。
「……ごめんなさい。アナタ……兄さんに、似てる」
まだ涙を滲ませながら、落ち着いた笑顔で口にする。ようやく彼を細腕から解放すると、そのままキョロキョロ、と辺りを見回し始めた。
「えっと……ここは、何処なの? アシュリン」
見覚えのある顔に視線を合わせ、旅人がにこりと微笑んで尋ねる。
「あ、うん、あたしの仲間の家なんだ。ごめんね、寝てる間に連れ込んじゃって」
「そうなんだ。ありがとう、わたし、寝ちゃってたんだ」
おかしいなぁ、と、そこで困ったように旅人は首を傾げた。
「わたし、里に帰るねって言ったアシュリンと……別れてからのことが思い出せない」
何があったのかな、と。他人事のように呟く不思議な相手がそこにいた。
「それより――あんた、名前は?」
同道したという幼馴染みにも、それは先に尋ねたのだが……わりと適当な幼馴染みは、彼女のことはキレイな空色ちゃんと呼んだ、とふざけた返答をしていたのだ。
「そーやで。自分が何者か名乗るのが、まずは初対面の礼儀やろ、ねーちゃん」
声色はきつくないが、驚きが重なったために、詰問するように悪友も尋ねる。
それに、その空色の髪と目を持つ端整な顔立ちの相手は……――
にこにこと、普通は考え難い答を、あっさりと彼女は返した。
「わたし、自分の名前がないの」
「――は?」
「ふぉえ?」
だよね、と、そこでうんうんと幼馴染みが頷く。
「思い出した。だから、じゃあ空色ちゃんとかどう? って話になって……」
「――いいわけないだろ、それ」
「何やねんこの天然二人。あのなーあんた、ヒトをからかうんも時と場合を見て……」
呆れ顔になりかけた悪友に、彼女はううん、と至って無害そうに首を振る。
「ずっと呼ばれてる名前はあるけど、それはわたしの名前じゃなくて……本当の名前は、もう随分前から思い出せないの」
深刻な声ではないが、冗談ではない、と彼らをまっすぐに見た同年代の謎の美女だった。
「何やよーわからんけど……つまりあんた、記憶喪失なんか?」
「そうだと思う。昔のこと、何も思い出せないもの」
それじゃあ、と彼は改めて尋ねる。
「呼ばれてる名は? ひとまず教えてもらえないか」
「うん。わたし、ティアリス・アースフィーユ・ナーガ」
にこにこと答えながらも、少し悲しそうに微笑んで彼女は先を続けた。
「家族はティアリス、知り合いはアースフィーユって呼ぶけど。どっちもヒトから貰った名前で、わたしの名前じゃないの」
「……でも家族や知り合いがいるのは、記憶はあるのか?」
「勿論だよ。父さんや母さんのことも覚えてるよ」
……と、そのワケありそうな妙な相手を挟んで、彼は悪友と顔を見合わせる。
彼は軽く頭を抱えながら、ぼやくように言った。
「じゃあ俺達は、アースフィーユと呼ぶべきなのか」
そうだね、と穏やかに彼女は頷く。ちらりと幼馴染みを見た顔は、まるで空色というふざけた呼称の方が良かったように見えた。
それなら、とばかり、彼は気楽に、あっさり口にした。
「……長いから、アフィでいいか?」
「…………」
彼女はそこで、大きな青い目を丸くして、彼を見つめる。
「――うん。アダ名つけてもらったの初めて、嬉しい」
次の瞬間には明るく微笑み、両手を胸元で組んで嬉しそうな様子を見せた。
そんな不思議な彼女に、彼もしばし、ポカンとした無表情を返す。
とにかく、と仕切り直すように悪友が彼と彼女の間に出ていた。
「もうレイアス、出発できるやろ? あんたが誰かは知らんけど、ここに長くいてもらうわけにはいかんのや」
「そっか……そうだね、迷惑かけてごめんなさい」
「あんたはここからどうするんや? 元々何処に行く気やってん?」
真っ当に問う悪友に、彼女もうん、と神妙に頷く。
「わたし、ずっといない兄さんを探してて、友達にも会いたいと思ってた」
「ほんで? そいつらはこの近くにおるんか?」
しかしそこで彼女は、暗い顔付きになって俯く。
「会いに行きたいのに……どうしても、山を下りさせてくれないヒト達がいるの」
「――?」
「だから海を渡ろうと思って、ここまで来たんだけど」
それでひとまず、大陸の北海岸であるこの地に来た、と彼女は言う。
「それでもこの岸壁から船には乗れない。どうするつもりだったんだ?」
当然のことを訝しく尋ねる彼に、うん……と考え込んでしまった。
助け舟を出したのは、成り行きを見守っていた幼馴染みだった。
「とりあえずアフィちゃんのこと、『シャル』くらいまで、何も言わずに送ってあげたら? レイアスもタツクも、最初は多分そこに行くでしょ?」
幼馴染みが口にした、最寄りの商業都市の名。この里からは東にあり、海岸沿いで船も出ている盛況な土地として、里の者が憧れる都。彼らはまた顔を見合わせる。
「……そうだな。確かに最初は、そのつもりだった」
それは彼には肯定の意であり、悪友も特に異論はないようだったが。
「んなら、アシューはさっさと帰れや。後はおれ達だけで十分やろ」
その都市に行き慣れている幼馴染みの提案が、面白くないような顔を悪友が浮かべる。またそうして、幼馴染みにつれない態度を向ける悪友だった。
久々に話した昔馴染同士の、感慨にふける猶予もなく。
じゃあね、と幼馴染みが、あっさり別れを告げて出ていった後で。
「そんならアフィ、シャルまでよろしゅーな! おれはタツク、こっちはレイアスや」
幼馴染み相手とは随分違う気さくな悪友に、少し意表をつかれた様子の彼女も、うん。と笑って、差し出された手をしっかりと握っていた。
「別に喋りたなかったら無理に言わんでもえーけど、アフィは魔法使いなんか? 気配は確実に人間やなさそーやけど、わりと強い、どっかの千族さんか?」
軽いノリでも、しっかり者の悪友は、同行者の戦力を把握しておきたいらしい。青い珠玉を先端に誂えた木杖を持つ相手に、最低限の身上を尋ねる。
しかし彼女はまたも、普通とは言い難い返答をよこした。
「ううん。わたし、魔法はほとんど使えないの」
「――うぉ?」
「……は?」
丸木小屋を出て、家全体の結界に封をする程度の魔法道具しか彼には使えない。そんな彼の眼には、彼女はかなりの魔力の持ち主であると視えていた。
笑顔の多い彼女を包む、それとは裏腹な悲しげな色合い――玄い影を潜めながら大気に溶け込む、妙なる空色。力を色で視る彼には、とても印象が強いものだったのだが……。
それなのに、自分は魔法を使えない、と考えられないことを相手は口にする。
「んじゃーあんた……その杖は飾りなんか?」
「うーん……何て言うんだっけ、こういうの……」
答え方がわからない、と困った顔で笑う彼女。彼らは、世間知らず? と首を傾げる。
そこで話題を変えるように、彼女は逆に尋ねる。
「タツクとレイアスは? アシュリンの白黒猫さんみたいな、不思議な動物を使うの?」
白黒の猫。どうやら幼馴染みは、行きずりの旅人にも警戒なく、彼らの一族の「力」を見せていたらしい。改めて悪友が、大きなため息をついた。
彼女が見つからないよう早々に里の出口を出た後で、彼らは里を隠す鬱蒼とした獣道に入った。草の根をかきわけて進みながら、互いの話を続ける。
「おれらはまぁ、そーやな。特定の獣使いみたいなもんやと考えてくれればえーわ」
「普通の獣じゃないけどな。そこは詳しくは言えないが、それが俺達の『力』だ」
「力」とは、魔力や霊力等の才能があるヒトの内で、命から紡がれる「神秘」の総称だ。
彼や悪友は、魔力も霊力も大して持っていない。ただ、全ての生き物が持つ「気」は豊富で、魔力が必要な魔法などは使えないが、「気」を直接「力」にする類の千族と言えた。
「そうなんだ。アシュリンは大きな猫だったけど、タツクとレイアスは何を使うの?」
彼女が言うように、幼馴染みは普段、大型の猫を使う。それは耳と手足、尾だけが黒い白猫で、先刻に使った黒い狼はまさに「切札」の方の獣だった。
「おれは鳥やな。レイアスは……うーむ――」
そこで突然、にやにやと悪友は彼に軽く振り返り、後方を見ながら意地の悪い顔付きで話を続ける。
「あれは何て言うんやろな、レイアス? 結局名前は決まってないんか?」
「……旧い話を蒸し返すなよ。別に絶対、呼び名がいるわけじゃないだろ」
不機嫌そうな彼と、笑ってお腹を抱える悪友。不思議そうな彼女に悪友が解説を始める。
「コイツの獣はな、しょーじき何なんかよーわからへんねん。犬にも見えるし、でも何か角生えとるし、尻尾は妙に尖っとるしで。そんな動物、普通おらへんやろ?」
「……じゃあ、何かの神獣とか、魔物みたいってこと?」
「かもしらへん。だから昔から珍獣珍獣って、コイツはそれを気にしとんねん」
むす。と無愛想に輪をかける彼は、一言で呼べない自らの獣に悩んでいたのは本当だった。
世界でも有数の由緒ある「神獣」、そんな高次生物は滅多に扱えないため、多かったのは珍獣か魔物扱いだ。それも里を出られる実力を持った今では、遠い話でもあったが。
しばらく続いた険しい茂みを抜けると、岩肌が所々露出した急斜面に出た。
山の生活に慣れている彼らは良いが、謎の旅人たる相手は、ひらひらした風通しの良い服装からも、山歩きに慣れているようには見えなかった。
「……こけるなよ」
それなので彼は、左腕を軽く支えに差し出しただけなのだが――
「――うん、大丈夫!」
嬉しそうな声で、景気の良い返答をする。しかしそれとは裏腹に、そこで彼女は、ぴたっと彼の左腕を、両手で捕まえるようにしがみついた。彼はまた、意表をつかれることになった。
「……――」
斜面を下りる間だけかと思ったが、その後に平坦で緩やかな山道に入っても、にこにこと彼女は彼の腕を離さなかった。
「……――ふぉえ!?」
前方にいた悪友が、不自然に続く沈黙に立ち止る。振り返ってすぐ目に飛び込んだ光景に、素っ頓狂な声を上げた。
「オマエらいつの間に、何で腕組んでんねん!?」
衝撃のあまり、硬い顔で固まったまま率直に尋ねる悪友に、彼もバツが悪くなった。
「……いや。危なそうだった、から」
なるべくありのままを答えるが、彼の拙い声を打ち消すように、彼女の歓声が続く。
「きっとレイアスが優しいから、わたし、凄く嬉しいの」
彼にも謎な状況を、更に混乱させる返答。悪友が口をあんぐりさせるのも無理はない。
当惑の空気を彼女なりに察したのか、それでも微笑んだまま、彼を上目遣いに見つめる。
「レイアスは、迷惑?」
「…………」
その不自然に落ち着いた双眼の暗い青は、ともすれば、妖艶とすら言える深影が潜む。
そうしてはっきり邪魔か、と訊かれれば、何故か気分が重くなった。嬉しそうな彼女に水をさすように気が咎める。
「……すまないが、右が義手だから、左を塞がれると咄嗟の時に動きが遅れる」
彼にとってそれは里を出る最大の目的で、答えざるを得ない事柄だった。
「そうなの? ……ちゃんと動かないの?」
「いや、出来は良過ぎるんだ。でももう長いから、あちこちが傷んできてる」
ある出来事で、彼は五歳になる前に、右腕を肘の先から失っていた。
その時に特別な経緯で与えられた義手は、本当の腕と変わらない動きができる逸品だ。剣士である彼はなるべく義手に負担をかけないよう、右利きでありながら左手を軸にして、鍛錬なども続けてきたのだが……。
「このレベルの義手は、中々見つからないらしくて。外の世界で新しいのが見つかるまで、今はなるべく使わないようにしてる」
せいぜい日常の家事くらいだ、と息をついた彼に、彼女はそれまでの笑顔を消していく。しばらくじっと、澄み戻った空色の目を、彼の灰色の眼にまっすぐに向ける。
当惑はしつつも、不思議と、悪い気はせずにくっつかれていた彼でもあった。幼馴染み以外の異性と彼は、修行の場以外であまり関わったことがなく、純粋に反応に困るだけだ。
微笑む彼女のその目を、このまましばらく見ていたい。そんな風に思いかけるほど、そこには何かを訴えかける、透明な空色の青があり――
「――じゃあ、こっちにするね」
そうして彼がぽけっとしている間に素早く、今度は義手側の上腕を嬉しげに捕まえた彼女だった。
「……何かもう、つっこむ気も起こらんわ」
悪友も早々に、彼女の不思議な挙動を諦めたらしい。彼もそれを振り払うような意志の強さを、特別持ってはいなかった。
その誤解要素に溢れた光景に真っ当に切り込む、まともでない者達に遭遇するまでは。
それはひどく、深い山奥には似つかわしくない、気品ある口調だった。
「――やっと見つけましたわよ! アースフィーユ!」
びくり、と彼の腕に捕まる彼女が瞬時に体を硬直させ、その場に立ち止まる。
「全く……貴女にそこまで行動力があるとは思いもしませんでした……」
こちらは、驚くことに先程のものと全く同じ声色をしている。しかし話し方がぼそぼそとしているためか、印象がかなり違って聞こえる声掛けが続く。
「――何や!? あいつら!?」
二つの声の発生源は、彼らの遥か前方にあった。
背の高い雑草だらけの細い山道で、行く手を塞ぐように二人の女が立ちはだかっていた。
「アーニァ……フェネル……」
「……アフィの知り合いか?」
今までになく険しい顔で、震えるように彼女が呟く。彼は無意識に、彼女と女達の間に入るように軽く前に出た。
「――まっっ! まさかアースフィーユ、貴女という娘は……!」
女達は、気品ある口調の方は、長い前髪を耳にかけて金色の髪を腰まで下ろしている。尖った耳と紫の目、肩を出す白の礼装という、とても整った容姿をしていた。
「これは嘆かわしいですね。こんな思い切った家出の原因は、もしや……」
後ろの一人は、目を隠すほどに前髪を長く伸ばし、両肩で金色の髪を二つに括っている。やはり同じ尖り耳だが、侍従のような地味な恰好をしている。
女達二人は、顔を見合わせてうんうんと強く頷くと。
わけがわからず黙り込む彼らに向けて、前にいる女の方が高らかに言い放った。
「――その男が貴女をたぶらかしたんですの!? 何ということでしょう、あああ!!」
それは彼にぴったりくっつく彼女を見れば、当たり前の誤解だった。
「……は?」
出会ってまだ数時間の彼は当然、何だそりゃ、と顔を顰め、前方の礼装の女を睨んだのだが……。
「――ダメ! このヒト達に手を出したら許さないから、アーニァ!」
彼女は強く彼の腕を抱き締め、話をいっそうややこしくしていく。
「このヒトは大事なヒトなの! 兄さんにそっくりなの、やっと見つけたの!」
「はあぁ!? その無愛想のいったい何処が!? あのお方には似ても似付きませんわよ!」
「そうですね。彼はもっとこう、素晴らしいくらいに魔性の美形ですし。似てるとすれば……その前髪の黒メッシュくらいでしょう」
侍従のような女の方は、彼の一部だけ黒い前髪を見て、ふうと嘆息したようだった。
一連の流れを見るに、どうやら女達は、彼女の兄も知る保護者の立場らしい。彼も悪友も、顔を見合わせて悟ったのだが……それにしては強い彼女の拒否感に、進んで口を挟むことができなかった。
「……あれ、ひょっとして妖精とちゃうか、レイアス」
「……かもしれない。そうだとすると――まずいな」
ただ、目前の相手がかなり出会いたくない部類である可能性に、内心で頭を抱えた。
尖った耳と紫の目、華やかな金髪。さらによく見れば、背に小さな透明の翅という特徴的な容姿に加え、元々彼らの里自体、「妖精」たる敵対者の縄張りに近いのだ。
「妖精」は遊び心の化生――禁忌がない種と言われ、他の千族と相容れないものが多い。
化け物としての能力の高さは、折り紙付きの種族が妖精だ。そのためプライドが高く、そして誰もが癖のある変わり者らしい。他種族との争いも厭わず、仲間内ですら殺し合いも遊戯とすることがあると噂の、なかなか理解に苦しむ一派というのが常識だった。
「その『魔竜』をどうする気ですの!? そこの青二才方!!」
そして礼装の女が彼らに対し、苦く叫んだことに――その運命の到来を、彼らは知ることになる。
上3:赤い獣
その「魔竜」を、いったいどうするつもりなのか。
白い礼装の女の突然の詰問は、彼らには全く意味不明だったのだが……。
「命が惜しければアースフィーユには関わらないことでしてよ! 貴男方が何処の千族かは知りませんけど、みすみす禍を呼び込むことはないのではなくて?」
「姉上の言う通りです。それは貴男方の手に負える存在ではありません」
そもそも突然現れた空色の流人で謎の青花に、彼らは警戒心を持っていない。無防備さを責めるその言葉に、彼と悪友は改めて、顔を見合わせていた。
「……――そう言えば、なぁ」
「……確かにな。これは……」
女達を凝視して腕にしがみつく彼女を下目に、彼らもようやく、それを自覚する。
「魔竜」などと言われると、とてつもなく危ない存在かもしれない、と彼も悪友も思いはする。しかしその単語があまりに凶悪なためか、全く実感が持てなかった。
「アシュ―のせいだろ。あいつが全然アフィのこと、警戒してなかったしな」
「そーやな。アシュ―の目は確かやもんな、昔っからな」
普通なら、「妖精」らしき女達に嫌悪を感じるように、異種族間で警戒の無い化け物など少ない。そんな中、彼女の存在には疑問すら持たず、自分達の無防備さも気付かなかった体たらく。
「……?」
わけがわからず不安そうに彼を見上げた彼女に、一応現状を説明する。
「あんたが何なのかは知らないけど……俺達にも、あっちの方が悪く見える」
「外は危険が一杯て、おれも自分で言うとるのにな。不思議とあんたは、疑う気にならへん」
それは出会ったばかりの彼女の人柄というより、彼女と打ち解けていた幼馴染みへの、昔から変わらぬ強い想いだった。
――……なんで? べつにレイアスもタツクも、こわくなんてないよ?
荒事から常に逃げ回り、臆病者と名を馳せる幼馴染み。しかし幼馴染みは、里では一番強い「力」を持つ彼ら……二人の鬼子に屈託なく近付いてきた、唯一の子供だった。
その幼馴染みが、切札の霊獣まで使って保護した相手がこの彼女なのだ。
金髪の二人の女を前に、彼は改めて経緯を尋ねる。
「あいつらがアフィの言ってた、山を下りさせてくれないヒトか?」
「……うん。どうしてもわたし、妖精の森から外に出してもらえないの」
その問題は、「妖精」という化け物の近くで住む彼らも以前から頭を悩ませている。かの領域に踏み込んだ同郷者が何人も行方不明にされたことを、彼も悪友も思い返す。
ふう、と礼装の女は大きく派手な溜め息をつき、あざけるような顔で彼らを見返した。
「幽閉なんて当然の話でしてよ? 貴女という禍を、外に出すわけにはいきませんの」
「どうか手荒なことをさせないで下さい。禍とはいえ、貴女を傷付けるのは本意ではありません」
女達は至って辛辣で真剣で、彼女を連れ戻すには荒事も辞さない様子に見えた。
「……しかし妖精にしては、一見筋が通るマトモなこと言うとんなぁ、あいつら」
もしも禍という話が真実であれば、だが、彼も確かに、と彼女をかばいつつも頷く。
対応に困った彼らが沈黙し、立ち止まった状態に、礼装の女が唐突にしびれを切らした。
「ええい! とにかく貴女はこのアーニァの大事な玩具なのだから、帰ってらっしゃい!」
あ。と、実に妖精らしい礼装の女の発言に、妹の女が口元を歪めて姉を見つめる。
「姉上……それを言うと、こちらの方が悪者に――」
しかし妹が窘めを言い終える前に、姉はさらなる暴挙に乗り出してしまう。
「口で言ってわかりませんのなら、それがどれだけ危険か、自らご経験あそばせ!」
礼装の女が開いた胸元から、小さな卵らしき物を取り出し、一瞬で地面に叩き付けた。
「姉上、それは残数も少なくとても貴重な……!」
知りませんわ! と姉がふんぞり返る姿は、割れた物体から大量に溢れ出た乳白色の煙に、あっという間に隠されてしまい――
「何やこれ、吸って大丈夫なんか――!?」
「そんな、アーニァ、ひどい……!!」
女達と彼らの距離を、全くものともしない速度と物量で、少なくとも半径一キロ以上に煙が広がる。逃げる間もなく一瞬にして、彼らを飲み込んでいく。
「――手を離すな、タツク、アフィ!」
腕を掴む彼女をそのまま引き寄せ、悪友の外套も引っ張りながら咄嗟に彼は叫んだ。
「大事な物は絶対に、傍から離すな……!!」
この「場」は全てを白日の下に曝す――まるで真っ白なキャンバスのようだと。
そこに囚われた以上、己から遠く離した物は戻らないと、彼の眼にはそれだけが映る。
わけもわからず、何故か強い焦燥に襲われた彼が、とにかく同行者を必死に繋ぎ止めた数瞬後に。
霧の一部が晴れるように、ようやく、視界が少しずつ開けてきた――
その、直後のことだった。
「……!?」
最初に目を開けた彼は、ただそれを凝視する。
掴まり合う彼らを鎮座して見下ろす、再来してしまった有り得ない兇獣。
正確には、有り得てはいけない――鬼子と呼ばれた彼が、贖ったはずの罪。その忌まわしい具現を目の当たりにして。
「――な……!」
絶句する彼の横で、二番目に目を開けた悪友が、彼らの前に厳と在った巨体に気付く。
「……って、何やあああ!? レイアスオマエ、『実体化』つこたんか!?」
その異常さを知る者が故に、やはり唖然と声を上げる。
「あれ……ここは何処?」
昼間の山中であったはずが、暗い霧に包まれた狭い平野で、最後に目を開けた彼女はまず辺りを見回していた。
間もなく、彼らを頭上から睨む四本足の獣……輪郭がもやもやとし、コウモリのような翼で爬虫類じみた、人家ほど大きい真っ赤な異物を暗い青の目に捉える。
「――」
彼女はそこで、息を飲んで巨獣を見つめた。
「――俺じゃない! 来るぞ、走れ!!」
立ち尽くす悪友と彼女を彼がぐいと引っ張った直後に、音も無く立ち上がった赤い獣は、二枚の翼で激しい強風を起こしながら薄暗い空に飛び上がった。
「おわああ!!」
「あ――……!」
煽られて吹っ飛びそうになりながら、彼に捕まれて何とか留まった彼女だったが。
「待って――……!!」
何故かそれだけ、夕暮れ前の上空の赤い獣に、必死に叫びかける。
彼女を支えるだけで精一杯だった彼の横で、悪友が獣の次の行動をいち早く察知した。
「あかん! 突っ込んでくる!!」
その獣は決して、彼らの味方ではないと、悪友は悟ったのだろう。
「逃げぇレイアス、アフィ……!!」
彼と彼女を咄嗟に突き飛ばし、地面も抉る獣の特攻を、たった一人で受けた悪友だった。
「タツク!!」
道幅を軽く超える距離を飛ばされ、彼女を受け止め抱えた状態で、彼は強く腰をつく。
悪友がいた場所――小さなクレーターの内部を確認する余裕もなく、赤い獣が、今度は彼ら二人に首を向けて狙いをつけた。
「アフィ、やばい……!」
「――!!」
ごろん、と体勢を変えて彼女に覆い被さるように獣に背を向ける。地面を蹴って紙一重で追撃を避ける。間近を飛び抜ける獣の風圧を、一人で受けた全身に細かい裂傷が走った。
とにかく二人して立ち上がり、獣が大きく離れた隙をついて、彼女の手をひいて近くの森へと逃げ込んだ。
「レイアス、大丈夫!?」
「俺よりタツクだ――あのバカ、粉々になってなきゃいいが」
「……!!」
クレーターから悪友が出てくる様子はない。まず悪友の気配がほとんど感じられないことが、致命的な負傷を受けている証だった。
きっと悪友は、その赤い獣との交戦を躊躇い、防戦にまわる猶予もなかったのだろう。この状況の衝撃で彼の感情が麻痺していなければ、喋ることもできないような緊急事態だ。
「そんな――でも、あれが『魔竜』なの……!?」
呆然としている彼女が、自らを責めるような蒼白な顔色をする。
その顔を見て、冷静さなど消えていた彼は、上空を飛び回る獣の真実をすぐに明かしてしまった。
「違う。アレは俺の分身――にそっくりな……俺の昔の霊獣だ」
「え……?」
彼女はそこで、悪友が動けなかった理由を敏く感じたように、衝撃の声を呑み込む。
「アレを攻撃すれば、俺も傷付くかもしれない。やってみないとわからないが……」
彼自身、それがわからないこの状況に動揺を隠せず、実情を伝えるしかない。
「霊獣は俺達の……もう一つの体なんだ」
それは本来、本体たる彼と感覚を共有し、霊体として特定の獣の姿をとる「力」だった。
「でも霊獣のままなら、さっきみたいな直接攻撃はできないんだ。代わりに霊獣が攻撃を受けても、俺に傷が反映することはないが……それを『実体化』したら、話は別になる」
「力」のみを使え、「力」でのみ傷付けることができる霊体は、そのままなら映像でしかない。けれど実体となれば物理的干渉が可能となる代償に、本体もに負荷が共有される。
しかし現状が「実体化」によるなら、不可解なことがある。頭上で暴風のような咆哮をあげる赤い獣を、彼は苦々しく見上げた。
「アイツは実体の霊獣だ。でも俺と繋がりが無い……大体、俺がここにいるのに、アイツが現れること自体がおかしいんだ」
しかもそれは、彼が鬼子と呼ばれていた頃に、事あるごとに暴走させてしまった獣と同じ姿をしている。その獣は昔、ある事件で失われ、彼が「力」を制御できる今は違う姿をとるようになったはずなのに。
「……俺の右手と一緒に、アイツは消えたはずなんだ」
その混乱で悪友も、見知ったその獣が彼であるかどうか、一瞬の判断を迷ったのだろう。
実際に彼と獣で負傷が共有されるか、傷付けてからわかるのでは遅い、と。
「…………」
彼女はしばらく、硬く唇を引き結んでいたが……。
「あのね……ここはひょっとして、レイアス達の里の中?」
彼が思いもかけない事柄を、不自然に冷静な暗い青の目で、静かに尋ねてきたのだった。
「――」
煙に巻かれ、顕れていた平野は確かに、彼女が言うように彼らの里の修行場。幼い頃の彼が何度も、「力」を暴走させてしまった場所だった。
「言われてみればそうだ……でも何でわかるんだ? アフィ」
「……やっぱり。それならこれは――『てぃな・くえすと』の中のはず」
彼女が口にした謎の言葉について、彼が当然尋ね返そうとした時だった。
「――まずい、アイツ……!!」
不自然に滞空していた赤い獣が、その内に溜め始めた「力」に彼はすぐ気が付いた。
「ここを燃やすつもりだ! とにかく逃げるぞ!」
「……!!」
そうして彼らが森の奥に走った直後、赤い獣は口とおぼしき所を開くと、そこから派出に森に炎を噴きつけ始めた。
炎に追われて走りながら、彼女は息も絶え絶えに、その根本を伝える。
「あのね、レイアス……! ここはわたし達の――特にレイアスの魂が創った場所なの!」
「――!?」
「わたし達みんな、さっきの煙に分解されて取り込まれてる! 『てぃな・くえすと』は魂の解剖装置で、嫌な思い出や有り得る未来が、記憶から具現される娯楽だから……!」
その名もずばり、(T)魂の(I)色んな(N)生傷を(A)顕わにする、妖精独自のゲームなのだと、彼の妖精への嫌悪感が倍増される実態だった。
「取り込まれたわたし達は一番強い姿に再現されるけど、ちゃんと出口を見つけないと、無理にここを壊したら魂だけが一緒に消滅しちゃうって……! わたしも近いのを何度もさせられたから、多分顕れた課題をクリアしなきゃダメなの……!」
ということは――と、彼も息を切らしながら真っ先に尋ねる。
「じゃあタツクは、俺がこれをクリアすれば助かるのか!?」
「わからないけど、このままなら助からないかもしれない!」
どんどんと炎が燃え広がり、呼吸する大気も棘だらけのような状況で、彼女は可憐な見た目よりずっと図太いらしい。彼より余程荒事に堪える落ち着きで、そこまでをしっかり短く伝えた。
最早隠れられない炎の森を後に、この場所が里の具現と知った彼は、少しだけ思考力を取り戻した。近隣にあるはずの、水源の泉に足を向ける。
「炎だけでもとにかく防ぐ。アイツを倒せば、この課題はクリアなのか?」
走る彼らに気付いて、後を追ってくる赤い獣を振り返りながら、余裕がない彼は険しい目で訊いた。
「次の課題が出るかもしれないけど、まずはそれだと思う」
彼女も同じくらい厳しい顔で、頷きながら足を走らせる。
「本当はわたしの記憶を具現するはずだったと思うから。それがレイアスのになったのは……わたし以上に、危うかったってことなのかもしれない」
「魔竜」の危険さをその身で味わってこい、と。元凶の女が最後に残した声を思い出して、彼は何故か改めて不服を感じた。引っ張る彼女の手を強く握りながら、率直に疑問を口にする。
「……アフィはそんなに、本当に危険なのか?」
目的の小さな泉、ヒト一人が辛うじて禊のできる、馴染みの林の中の場所に辿り着く。湧き出る純粋な「水」を背にして、彼は彼女と並び立った。
「俺はアイツがいた頃は、少し気を抜けば意識がなくなって、気が付けば修行場一帯が焼野原だったけどな」
見上げる空には、黒ずみ始めた一帯を赤く染める、呪いの獣が差し迫ってきている。
「危険かどうかは……よくわからないけど」
彼女はそこで、それまでの表情と声色――暗い青の目を、不意に緩めていた。
「……わたしはいつか、消えるって。それは、何度も見せられたから知ってるよ」
ただ穏やかに笑い、そんなことを、彼と共に赤い空に対峙しながら微かに呟いていた。
それがいったい、どういうことであるのか。
そこですぐ問いかける余裕は、その赤い獣……幼い彼が何をしても制御の敵わなかった、呪われし兇獣を前にしてあるわけもなく。
泉の前で、彼は背の無骨な長剣を抜いた。
「――? ……レイアス!?」
驚く彼女の横で、唐突に彼は、元々裂傷を受けていた左上腕の内側をさらに抉った。
「っつ――ったく。早速、これをする羽目になるか……」
痛みに顔を歪めながら、剣全体にそこで、なみなみと血を纏わせる。
そのままその剣を、浅い泉に突き立てると……彼の血を受けた泉は、泉より大きい半径でやおら水を噴き上げ、彼らを赤い獣から隠すように覆い始めた。
「……アフィはこの中にいろ。アイツは多分突っ込んでくるから、そこを返り討ちにする」
「――え?」
「ここの水は今だけは、『力』として俺達を守る。それ以外俺にできることは……アイツを直に斬るくらいだ」
泉から抜いた剣を改めて両手で持つと、噴水を背に、守るように彼は前に進み出ていく。
勝算など無かった。自然に厳しく歪む顔に、素直な不安を載せずにいられなかった。
ごく簡単に考えても、彼の身長程もない普通の長剣で、巨体の獣を彼はこれからまともに受け止めようとしている。
本来なら現在の「霊獣」を使いたいところだが、赤い獣が場に出ているためか使えない。今彼にある戦う力はこの長剣と、後は長く愛用する質素な短刀くらいだった。
「でも、レイアス……!!」
それならせめて、「力」を色で視る彼のある特技で、彼女だけでも――獣の炎を食い止め、逃れられる余地を作っておきたかった。
彼女が制止する間もなく、「水」に守られた領域を後に、彼は獣を迎え撃ちに出る。
この循環する僅かな「水」の場で、彼女にできることなどほとんどないだろう。しかし彼女は、唯一の武器らしき青い珠玉を誂えた杖を、そっと強く握り締めていたのだった。
そして一人、自らの不始末と言える古い呪いと、彼は対峙する。
彼を見つけ、炎を纏いながら迫る赤い獣に、そもそも――と、一人ごちる。
「万一アイツを倒せたって……その後、俺はどうなるんだ?」
今の霊獣が使えないこと。それはつまり、あの赤い獣は結局彼であるわけなのだ。
まさか里を出て早々、悪友共々命の危機を迎えるなどとは。外の世界が危険と認識上は知っていても、思いもよらない過酷な状況だった。
「……危険をちゃんと避けられるのも、アシュ―ならではなのかもな」
彼らと違い、一人で里を出入りしても、幼馴染みはいつも無事に帰る。ヒトを見る目も含めて、その特殊な目敏さを彼は改めて思う。
昔に、彼らと共に危険な目に合って以来、疎遠となっていた幼馴染みを――
――ごめんなさい……! あたし、ごめんなさい――……!!
きっとこれは、走馬灯だろう。赤い獣が飛びかかる速さが、突然、極端に落ちた。
ゆっくりと彼は、剣を構える両手に「力」を込めながら、獣に纏わる青い夢を同時に思い起こしていた。
――あたしのせいでレイアスの手……なくなっちゃったよぉ……!
別に……と。彼は赤い獣に向かいながら、声だけは穏やかに、旧い想いを口にする。
「それでアシュ―やタツクが助かるなら……安いもんだろ」
脳裏には最早、現状と記憶が入り乱れ、そう呟いた自身に一人で笑った。
こんな赤い獣を身の内に持っていながら。それでも彼と屈託なく遊んだのは、彼と似た理由で同年代に恐れられた悪友と、元は一軍村の子供で、両親の都合で引っ越すことになった幼馴染みの二人だけだった。
――……やだ。あたし、ここにいたいよぅ……。
五歳になる直前に、幼馴染みの急な引っ越しを彼も悪友も不意に告げられた。
泣きながら彼らの所に、別れを言いに来た幼馴染み。その時、彼と悪友は揃って、それなら逃げよう! と三人で里を飛び出したことがあった。
それが今も度々夢に見る、幼い頃の青い光景で……遠出した先で謎の強大な敵に襲われ、幼いなりに戦った彼は、あえて己が「力」の暴走に身を任せたのだ。
そうして赤い獣を具現し、相打つように敵を退けた時、彼の右手は敵に食い千切られた。その後に彼は、生死の狭間をしばらくの間さまよい――
意識が戻った時には、幼馴染みは、とっくに引っ越していたのだった。
そこからは何故か、幼馴染みの引っ越し先に行った時も、すれ違っても目を逸らされるようになった。以前と同じように幼馴染みが接してくれることはなくなってしまった。
――なんやわからんけど、アシュ―……おれらんこと、キライになったんかもしれへん。
悪友は元々幼馴染みにつれない態度をしていたが、彼とは兄弟のように気安かったのが嘘のように、彼も悪友もわけがわからないまま距離を置く関係となってしまったのだ。
それから幼馴染みと、まともに話をしたことと言えば。
――……オマエ、ちゃんと闘えよ! アシュ―!
里で定期的に行われる、訓練中の子供達の武闘大会で、彼と幼馴染みが対戦した時のことだ。数年来のもやもやが爆発した幼い彼は、執拗に幼馴染みとの手合せに拘ってしまった。
その試合後に幼馴染みは、彼ら二人のことはずっと大切だ、と言ってくれた。それでも昔のように、屈託なく話せる状態に戻ることはなかった。
……今朝のように、特殊な状況で再会するという、運命的な偶然がなければ。
――とりあえずアフィちゃんのこと、何も言わずに送ってあげたら?
あんなにも自然に、彼らと笑って話す、懐かしい幼馴染みの姿。
その小さな約束は、できれば守りたい。そんな想いが、他種族との喧嘩も買ってしまう原動となったのは間違いない、彼らの旧い絆だった。
地が割れるように、義手が軋む。その音が彼を、虚ろな現実へ呼び戻した。
重い呪いの赤い獣を全身で受け止め、泉の「力」でも防ぎ切れない業火に、気が付けば彼は包まれていた。
アホだな、と、遠のく意識の中で自嘲する。
「……大体……アシュ―を好きなのは、タツクなんだし」
長年来、彼と悪友には、幼馴染みに必要以上に近付かない暗黙の了解がある。彼は悪友ほど幼馴染みを意識していたわけではないが、大切な相手であるのは間違いなかった。
ここで彼がいなくなれば、悪友は遠慮なく幼馴染みを狙い始めるだろう。
悪友が助かるなら、それでいいか、と。彼は改めて、命尽きるほどの「力」を長剣に込める。激しい炎から彼を守る最後の砦の、全身を巡る「気」が容赦なく削られ、カラに近付く。
……無意味無意義、無我こそが無害。
この赤い魔物――禍の鬼子、と。幼い彼に向けられた罵倒を、そのまま赤い獣に吐き出す。
燃え尽きるまで全ての力を剣に注げば、赤い獣を裂いてくれるか。その隙だけを彩の無い眼が探す。
……そうして彼が、自身と引き換えに、己が呪いを清算せんとした――長過ぎる一瞬のことだった。
「……そいつは、オレの獲物だろ?」
彼の背後で噴き上がっていた泉が、眩い星彩となったかのように、突然内側から破裂する。
驚く間もなく、竜巻のようにソレは、水面を引き裂いて激しく躍り上がった。
「――……!?」
水柱と共に現れた、両端に刃のつく長い武器を構える青い人影。
赤い光を纏うためか、全体としては紫の暗影、蒼く見えるその青年。手にした長物と共に、蒼い男は、獣を押し止める彼の頭上に鮮やかに跳び上がった。
そのまま、彼の呪いたる赤い獣を、両極の長い大鎌で――
完膚なきまでに、蒼い男が、その呪いの鼓動を切り裂いていった。
上4:紫苑の何でも屋
旋風の如き黒い両刃に、ことごとく裁断された赤い獣。それが舞い狂う泉に飲まれていった直後のことだった。
突然彼の身を襲った呪われし鼓動……激痛を伴う赤い憎悪が、心臓の底から溢れ出した。
胸から義手の右手まで、全ての血が噴き出しているかのようだった。
言葉にできない苦渋の加速に、両手と膝をついた彼は大声を上げる。
「ああああああああ……!!」
自らたる赤い獣が斬られた反動なのか。それともその蒼い男が――男の纏う赤い光が、炎に巻かれる彼を貫いて包んだ影響なのか。
――それじゃ……全て、終わりにしよう……。
宙に突き出した右手を染め上げる鮮烈な赤。それは紛れもなく、彼がかつて奪ってしまった命の原色。
取り返しのつかない痛みを流し込むその光は、耐え難い罰の赤い夢を彼に与える。
……救いだったのは、その責め苦は長くは続かなかったこと。泉が元に戻るにつれて赤い光も薄らぎ、蒼い男の内へ消えていき、併せて周囲の霧も徐々に晴れ出していった。
ずっと後ろにいた空色の流人の彼女が、青く光る杖を手に、彼の方へ駆け出してきた。
「レイアス……!! 大丈夫――!?」
四つん這いで苦しむ彼に、慌てて彼女も膝をつき、彼の顔を覗き込んでくる。
そしてその状況を招いた蒼い男……霧に包まれ、姿がはっきりとしない不意の乱入者は、彼が思わず耳を疑う声を出した。
「――怪我してんの? にーちゃん達」
突然の幼い口調。その口調相応に、声も少年のものとなった、謎の蒼い男の姿は――
霧が晴れると同時に、そこに在ったのは、短い紫苑の髪と目色の幼げな少年だった。
「……――な……?」
「――レイアス? 大丈夫、怪我はないの……?」
心配ながらも不思議そうな彼女が、彼の全身を見て首を傾げる。赤い獣の炎に包まれた火傷も、風圧や自刃の裂傷も、そこには全く見当たらなかった。
しかしそんな彼らに、ソレはにまりと、しゃがみこんで彼の体を見つめながら続けた。
「さっきの所で怪我したなら、見た目大丈夫でも油断しない方がいいよ。オレで良ければ、有料なら回復してやるけど?」
やはりどう見ても、声変わりすら来ていない幼い少年。
黒い上衣と、蒼く袖の無い上着に灰色の短い外套を纏い、腰に沢山道具袋を下げている。
七分丈の下衣に蒼いブーツで身長を水増しする小柄な相手は、そんな背丈にそぐわない、両端に刃のつく長い鎌を背中に担いでおり……巨大な赤い獣を分断した蒼い男とは似ても似つかない。
ひたすらぽかんとする彼に、紫苑の髪と目の少年は、慣れたように明るく笑った。
「ところでにーちゃん達……名前は?」
自称何でも屋。造って戦える天才職人ラスト君。尖り髪を押える額の大きなゴーグルが特徴的な、紫苑の少年が名乗ったのは、そうしたややこしい通称だった。
「オレもこの近く歩いてたら、急に変な白い煙に巻き込まれて、気が遠くなってさぁ」
気を失った悪友を見つけた彼が、悪友を介抱する横で、少年は旅慣れた様子であっさり火を起こす。そのまま、空色の流人の彼女の隣に座り、楽しげに事情を語り始めた。
「まさか妖精の道具で魂レベルに分解されたなんて、思いもしなかったけど! ぼけっとしてたらこのねーちゃんの声が聞こえて、声のする方に行ったらその時まさに、こっちのにーちゃんがあの火トカゲに食われそうになってたってワケ」
そうして彼を助けたという戦果を、少年が意気揚々と語る反面、助けられた彼は不可解としか言えなかった。
「……火トカゲって言うなよ、アイツを」
そもそも本当に、この少年に助けられたのか、彼は未だに納得がいかないままだった。
それらの話を一通り聞いた後で、彼女も穏やかな笑顔で首を傾げる。
「でもおかしいな。わたしが『水』を喚ぼうとした時、出てきたのはお兄さんだったよ?」
蒼い男の姿はどうやら、彼女にも見えていたらしい。
「それにわたし――ヒトを喚ぶ『力』なんて、持ってないはずなんだけど」
まずもって、「水」を喚んだという彼女は、その時いったい何をしていたのだろう。
魔法は使えないと言った彼女に、彼は無意識に、気になる視線をじーっと向ける。
草の上にあぐらをかく少年は、赤い獣を斬った鎌を手入れしながらにこやかに応えた。
「オレ一応、水属性近いからかな。妖精道具で招かれた精神世界なら、そーいう可能性もあるってコトじゃない? オレが実力相応のイケメンに見えたりとかさー」
あ、そっか。と、思い出したように彼女は、両手を打って微笑む。
「『てぃな・くえすと』で再現されるのって一番強い時の姿だっけ。それなら、大人の姿で出てきたっておかしくはないよね」
「…………」
その結論は確かに、彼女が納得したように、最も明快なものではあったが。
――……それでも……コイツみたいに、色まで変わるものなのか……?
「力」ある者に固有の色を視る彼の眼は、これまでの十七年、時間経過で色が変わった相手を見たことは無かった。
唯一の例外として、複数の己を持つ化け物……例えば「魔族」という悪魔に似た化生が、残酷で容赦なき人格へ、堕落する時に有り得るくらいだった。
彼らと話しながら、楽しげで軽いノリの少年には、「魔」のような紅い影は片鱗も見られない。むしろ少年がきらりと放つ紫の眼光は、「魔」と対極と言えそうな稀有のものでもあった。
――……。
何故か彼には、その紫苑の少年の笑顔が、目を離せない暗影を伴ったものに見えた。
赤い獣が滅んだ後の全身の異変も、今は僅かに気怠さが残る程度だ。それでも日頃の彼には考えられない体の重さが続いている。
――……本当の姿……なんてわけ、ないよな………。
一瞬だったが、あの不敵そうな蒼い男とこの人懐っこい少年の差に、思わずそう感じた不可解な彼だった。
それにしても――と。
空色の彼女が、少年に対してあるべき疑問にやっと立ち戻る。
「ラスト君は、こんな山奥でいったいどうしたの? 一人でずっと旅をしてるの?」
「ラストでいーって。オレもアフィねーちゃんって呼ばせてもらうからさ♪」
馴れ馴れしい少年は、ぴたっと彼女に甘えるように寄り添って嬉しげだ。眠る悪友を横に彼は不思議と、ますます不興が募る。
そこで少年が口にした、この山まで少年がやって来た目的は……驚くべき話だった。
「あのさ、にーちゃんやねーちゃん達はさ。この辺りに『霊獣』の村があるかどうかって、隠れ里の話とか知らない?」
何と少年は、ピンポイントで、彼と横たわる悪友の故郷を名指ししてきた。
「――って……何やってぇ!?」
そのたった一言に反応したのか、責任感の強い長の息子が、そこで目を覚ましていた。
うぉあ!? と悪友は、寝覚め一番に両目に涙を溜めて体をぶるっと硬直させる。
「何やこれ、全身がアホ痛いんやけど!? 人間の筋肉痛ってこんなんなんか!?」
「……元気そうだな、タツク」
一見外傷はなく、彼に近い状態らしい悪友に心底ほっとしたものの。
「何処が元気やねん、つかアレ、レイアスの霊獣は何処や!? オマエアレ、久々に暴走させよったんか!?」
「……その説明は、面倒だから、アフィから聞いてくれ」
安堵と同時に、強い疲労が込み上げ、彼はげっそりと答えた。
一通り、経緯を悪友が聞き終えた後で。
現在は紫苑の少年が手持ちの道具で結界を張ったために、女達に見つかることはない、と少年が多少の説明を加える。
「感謝しろよなー。オレがいなけりゃにーちゃん達、ホントにやばかったんじゃん?」
「何やねん、オマエもどーせ、レイアスを囮にアレを攻略しよったんやろ」
「あ、バレた? にーちゃん結構、のほほんとしてそうでも鋭いなー」
同じ異空間に巻き込まれた以上、誰かがそれを成し遂げなければ、誰も助からなかった――そんな、俄か運命共同体の彼らだったらしい。
そしてまた逸れてしまった話題を、にこやかに空色の彼女がしっかりと戻す。
「ところで、ラスト君はどうして、こんな山奥に来たの?」
「そーだそーだ。オレ、霊獣の村っていうのを探してたんだよ」
そこでぴくりと、彼と悪友の表情が固まる。
「そこから来たってねーちゃんに、コレ、借りたままになっちゃってさ。大事な物みたいだったから返さなきゃなーって」
「――お?」
「って……」
そこで少年が道具袋の一つから取り出したのは、彼も悪友も見覚えのある、小さな黒い布きれだった。
「……コレは……――」
「オレが怪我した時に、包帯代わりに使ってくれて、でもちゃんとキレイにしたからさ。あの白い髪に似合ってたし、大事なヒトに貰ったって言ってたしねー」
「白い髪て……ってオイ、コレまさかアシュ―の……!」
そして先に持ち主に思い当たったのは、ぶるぶると拳を震わせて座る悪友だった。
「アシュ―のヘアバンドやんけ、コレ! そういや今朝は、旅帰りなのに着けとらんな、珍しーなと思たら!」
「……そうだったのか? 俺はあんまり、着けたの見たことなかったな」
「うわあ。確かにアシュリンに似合いそうだね、これ」
「ホントに? にーちゃん達の知り合いなの? コレのねーちゃん」
少年から布きれを受け取り、まじまじと楽しそうに、隣の彼女が眺めている。
その反面、ぐぬぬぬぬと……悪友の雰囲気はまさに、不機嫌一色に染まりつつあった。
「オマエはアホかい! 里だとそれ何って聞かれるからて、旅の時しか着けへんけど大事にしとるって、セレンからきーたやんけ!!」
「そうだったのか……もうとっくに、捨てられてるかと思ってた」
彼にはそれは、正直なところ、ただ意外としか言えなかった。
面白くなさそうにする悪友を見て、彼女が珍しく、あまり笑わずに淡々と尋ねた。
「それ……ひょっとして、レイアスがアシュリンにプレゼントしたの?」
「ああ。昔に手合せをした時、本気で吹っ飛ばしたことのお詫びに……」
彼としてはひたすらバツの悪い、ちゃんと闘え、と幼馴染みに詰め寄った事件。雨降って地固まった、それなりに気恥ずかしい思い出の品でもあるわけだった。
ええー、と彼女は驚いたように目を丸くし、体勢を変えて座ったまま近寄ってきた。
「ひどいなぁ、アシュリンと本気で戦ったの? レイアスが?」
「そーやで。コイツ、準決勝でおれとやってボロボロんなった後、シードで上がってきたアシュリンにあっさり場外勝ちされて、根に持ちよったんや」
「……だからわざわざ、ヒトの旧い話をするなよ、タツク」
しかし彼の主張は、何なに? と身を乗り出した少年のせいで、悪友には届かなかった。
「ってことは、その時の優勝はあのねーちゃんになったってこと?」
「そうそう。アシュリンはあー見えても、武技は里の誰より優れとるんやで。でも二軍の村に行ってから爪を隠すようになってもーて、オマケに常時弱腰やから、すっかり里では臆病者扱いや」
「そっか、やっぱりなー。あのねーちゃん、タダモンじゃないと思ってたんだ、オレ」
紫苑の少年はそこで、先日に山村で山賊の騒動に巻き込まれた際に、彼らの幼馴染みと関わることになったという事情を彼らに語るのだった。
「ねーちゃんはヒェェって逃げ回ってたから、大体の敵はオレが倒したんだけどさ。一番ヤバい奴は、多分ねーちゃんがいなかったら苦戦してたね」
今まで里をほとんど出なかった彼らは、幼馴染みの意外な活躍談に呆然としかできない。
「……つか……何ちゅーことに関わっとんねん、アシュ―の奴は」
「伊達に一人で、何度も外に行ってないな、あいつ……」
そして彼はようやく、そこにいる少年について、形無き納得を得ることになった。
「それなら多分……オマエも、悪い奴じゃないんだろうな」
彼らの幼馴染みが気を許し、故郷のことまで話したらしい紫苑の少年。
いつの間にかすっかり少年と打ち解け、楽しげに話している悪友の様子も含め、いつも無表情な彼はいつになく穏やかに――……口の端を軽く和ませていたのだった。
両端に鎌のつく武器を易々と扱い、並々ならぬ戦闘能力を持つと見える紫苑の少年は、どうやったのかその長物を何処かにしまい、実に身軽な旅人姿だ。彼らを匿うための結界まで張ってくれたという、幼いながら頼りがいある少年に、彼と悪友は揃って旅の注意を説教される羽目になった。
「それじゃ、オレはもう行くけど。この辺ではこっからここらが妖精の影響力が強いって言うから、くれぐれも避けて通るようにね」
ずっとこの山に住む彼ら以上に、要注意千族の領域をよく知るらしい少年から、簡単な地図まで渡される。彼らはひたすら、感心の溜め息しかつけない。
「そのヘアバンド、本当にねーちゃんに渡してよ。じゃなきゃその地図、後でお金払ってもらうからな」
「オマエなぁ……ほんまに十三歳か? ちゃっかりしっかりしとんなぁ」
「にーちゃん達が世間知らず過ぎだろ。最近の千族は多いけど、そんなんじゃ人間の町に混ざった時に、あっさりばれちゃうよ?」
当然と言えば当然ながら、それだけ才覚のある少年も、何がしかの千族であるらしい。
「もう世界の三割も千族はいないって話だし、本当、気を付けろよな!」
妖精と遊んでる場合じゃないし! と、山道を駆けていく少年が笑いながら忠告を残す。
束の間の、化け物同士の交流を温めた紫苑の少年が、そうして去っていった後に。
改めて空色の流人の彼女が、少し俯きながら、彼の灰色の外套を掴んで拙く口を開いた。
「……ごめんね。わたしのせいで、二人を大変な目に合わせて」
これまで和やかな雰囲気だったので、彼と悪友は、へ? と同時にぽかんとする。
「レイアスの右手……もう、ほとんど動かないんじゃない?」
少年がいる間は明るくしていたが、彼女は暗い青の目で、シビアな現状に気付いていたらしい。それは確かに、彼も頭の痛い事柄ではあった。
その右腕は、赤い獣と圧し合いの後――最早ぎこちなくしか、動かなくなったことは。
しかし彼は、少年と話していた雰囲気のまま、あえて軽い口調で彼女に応えた。
「別に元々、時間の問題だったからな。外に出れば戦闘の機会はあるだろうし、いつもは剣も左手だけで使うから大丈夫だ」
「…………」
現実的には、右手は短刀を握ることすらできず、これでは着替えがまず苦労するな、と彼は内心で苦笑する。
「次に戦う時は霊獣を先に使う。だからアフィは気にしないでいい」
「せやで。さっきは不覚をとってもーたけど、おれらは強いんやからな!」
ともすれば死んでもおかしくなかった状況の悪友も、全く懲りずにそう言っていた。
「おれらもアシュ―みたく、世間の荒波にもまれなあかん。このままやったら、あいつに差ぁつけられたままや!」
「……俺は、新しい義手が見つかればいいけど」
悪友が基本暑苦しい性質であることを知る彼は、そっと自己主張を挟まずにいられない。
そこで出た名前に、彼女は思い出したように、軽く微笑んでいた。
「ところであのヘアバンドは、どうやってアシュリンに届けるの?」
彼らがそのために里に戻るなら、ついていくと言わんばかりの様子に、悪友はふふふん、と笑った。
「そーいう時こそ、おれの霊獣の出番や! かもーん、『才蔵ズ』!」
得意げに立てた指の隙間から指笛を吹いた次の瞬間、ばさりと大きな鷲が、その手の上に現れて悠然と停まる。
「……指笛の演出はいらないだろ」
冷静にツッコむ彼をものともせずに、悪友は鷲の足に黒いヘアバンドを括りつけ、勢い良くそれを大空に放り上げた。
「セレンに届けたらアシューに渡してくれるやろ。俺と同じ鳥使いやし、わかってくれる!」
「……直接アシューに届けても、わかると思うぞ」
二軍の村で、幼馴染みの数少ない友人の名を口にする悪友に、彼はただ淡々とツッコむ。
「あかん、それは何か、悔しーからな!」
結局どうにも、幼馴染み相手には素直に優しくできない悪友らしい。そんな相手でも、目敏い幼馴染みは、悪友が自分を嫌っていないことはわかっている節があった。
それがどうして、好意に気付くに至らないのか、つくづく彼は不思議なのだが……。
「……大事なもの、か……」
今更ながらに知った、幼馴染みが気に入ってくれていたらしい、素朴な贈り物。それを届けるために暗くなってきた空を飛び去っていく鷲を、珍しくほのかに微笑んで彼は見送っていたが、そんな自身には気が付いていなかった。
彼らのその様子を見守りながら、冷え込みが襲う夕暮れに隠れそうな鉛色の外套の青花は……一瞬だけ、僅かに口元を震わせ、悲しげな暗い青の目で微笑んだのだった。
「それにしても、不思議なコだったよね? ラスト君って」
それを彼らに届けた張本人。そんなささやかな物一つのために、この山奥に来たという紫苑の少年を思い、我が事でもないのに彼女は嬉しそうな笑顔を浮かべていた。
「ほんまやなぁ。色んな千族がおるゆーけど、あんな若いしっかり者は、頭が下がるわ」
これでも悪友は、長の跡継ぎとして同年代ではしっかりした方だ。その悪友にここまで言わせるあの少年は、確かに相当だ、と彼も頷く。
彼女はくすり、と嫌味の無い暗い青の目で笑い、歩き出した彼らに続いて山道に入る。
「きっとまた、会うんじゃないかな。何でだろう……そんな気がする」
それまで休んでいた小さな広場を振り返りながら、小さく呟く彼女だった。
さてさて、と悪友が、少年からもらったこの近辺の地図を広げる。
「ろくでもない妖精もおうたけど、おもろい奴にも出会って、外はやっぱ新鮮やな!」
「……あらまぁ。ろくでもない妖精とは、誰のことですの?」
そのまま見事、禁じられた藪をつつき、早くも災いに足を踏み入れた迂闊な悪友だった。
紫苑の少年が去ったことで、少年が張ってくれていた結界が無効となっていたことに、今更彼ら一行は気が付いた。今度は道の後方から現れた二人の女は、呆れた顔を隠さず、振り返った彼らを見つめていた。
「純正携帯型TINAをクリアしたからには、どんな実力派かと思いましたのだけど……無防備にもほどがありますわよ、貴男方?」
「あの試行性幻想どん底殺戮兵器を、その場の勢いで使う姉上の無謀にもほどがありますが。とりあえず無事そうで何よりです、アースフィーユ」
女達は最初に現れた時とは違い、彼らへの態度には何処か落ち着きが見られた。
それを見た彼女も、今度は彼に縋ること無く、一人で毅然と女達に向き直った。
「……わたしは兄さんを探しに行きたいの。ナナハならきっと、わたしと一緒に兄さんを探してくれる」
「それは無理だと思いますよ。あの娘はもう、昔とは違いますから」
坦々と答える妹の方に、彼女も今度は、動揺を見せなかった。
「……そういうことにして、父さん達には言ってくれたらいいの」
彼女を女達に預けた両親の意向。それがどちらも、気にしていた部分であるようだった。
「…………」
女達は揃って押し黙り、彼女の強い意志表明の続きを待っている。彼女は暗い青の目を伏せると、ふるふると杖を握り締めつつ、その真意の一端を口にした。
「わたしはずっと……兄さんを信じて待っていたから。だから後悔しないように――このヒト達と一緒に行くの」
そこで彼女は、ちらりと彼の方を振り返る。
その切なげな目に彼は、何故か不意に、胸を衝かれていた。
「……わかりましたわ。その男達であれば、貴女の守り人たり得ると――認めますわ」
へ、と。とりあえず彼女を最寄りの都市に送るつもりが、突然護衛認定された彼と悪友が、顔を見合わせる暇もなかった。
礼装の女がずかずかと、彼の前まで近付いてくる。
「それじゃ、この魔竜の暴走は貴男が責任を持って止めるんですのよ。アーニァ達以上に適任がいるとは思えませんけど、これでお役御免になるなら爽快ですわ」
女は強引に彼の右手を掴み、がしがしと強い握手を一方的に交わし――
「って……――へ!?」
その握手の直後に、義手である彼の右手の平から、まるで焼印を押されたような黒い煙がじわっと立ち上った。
「確かに渡しましたわよ。アースフィーユの最終制御防衛装置は」
「ってちょっと待て、何なんだ、この得体の知れない『力』!?」
慌てて右手を見た彼の眼には、掌底からまだ止まぬ煙を発し続ける、深く刻まれた黒い蛇のような謎の紋様。青い光をぐるぐると閉じ込め、渦巻かせる混沌の色が視えた。
……あらあら、と。それを渡した女の方も、異常に気付いたようだった。
「貴男、まさか――……それは、義手ですの?」
「まさかも何も、義手だったらどうなるんだ」
「……それはまずいですね。一度無機物に固着させてしまうと、今後元の形で受け渡しは……アースフィーユの父君に返すことを含めて、難しくなります」
気が付けば近くに来ていた妹の女が、悪びれもなく事実だけを彼に告げた。
しかし、一見はまともそうに見える妹の女も、そこでさらりと――
「まぁ、貴男が彼女の伴侶となるなら、問題は無いでしょう」
まだ続いていたらしい誤解を前提に、成る程、と女達は、勝手に納得し合ってしまった。
「って――……!!」
そして半瞬後には、女達の姿は唐突に場から消え去っており……。
ちょっと待て、と二たび叫んだ彼の悲鳴は、気まぐれな妖精には永遠に届きそうにない。
上5:空色と青と
幼少時に右の前腕を失った彼。その時与えられた、不思議な高性能の義手。
淡い小麦色の柔らかな外皮と緩衝材が、有り触れた金属で造られた骨格を覆っただけの右手は、上腕に根付くように片時も離れずに在った。
その上その義手は、彼の成長に合わせて自動的に接着面の口径が緩み、骨組みまでもが伸展されていく、驚きの拡張性だった。
――その右手は君の精神……魂に反応して動くそうだ。大事に使うんだよ。
死にかけた幼い彼が、意識を取り戻してから告げられたこと。それは義手の造り主からその話を言付けられた長、悪友の父の言葉だった。不便な部分はあったものの、失った事実を忘れるほど思い通りに動く手に、彼はすっかり、事の大きさなど頭に残らなかった。
――あたしのせいでレイアスの手……なくなっちゃったよぉ……!
だからそれが、どれだけ誰かを追い詰めていたか――ずっと思い至ることはないままで。
人間の人口が最も多く、通称「西洋」という西の大陸。その象徴の三大商業都市、海に愛された都と呼ばれる「シャル」には、霊獣族の隠れ里から二日でつける。
といっても千族の移動速度で、人間は恐れて立ち入らない山道を行けばの話だ。
「思ったより時間かかったわなあ。なあ、レイアス?」
「……それ、今するような話か?」
山を下りた後、わかりやすい道として北上し、海沿いに、四日かけて憧れの都市に来た彼らは……まず北端の港町にて、宿を求めて歩き回っていた。
「何か話さんでいられるかいな、この状況で! 何で……何でおれらが……!」
「…………」
「何でおれらが、警備隊に捕縛されなあかんねん、あほー!」
悪友が叫ぶ通り、湿っぽく寒気も厳しい土牢で鎖に繋がれた彼らは、背中合わせで地面に座ったまま、ガックリと項垂れる上弦の月夜だった。
事の発端は、早朝、初めて目にする港行きの馬車に乗ったのがケチのつき始めだった。
「ちょっとアンタら! 先に乗った方が奥に座って当たり前だろ、このチンピラ共が!」
「な……何やてぇ!?」
急に険しい声で、見知らぬ中年婦人に咎められたことが初めだった。着いた海港では、船の出入りを調べに乗船場に上がれば、朝から足音が煩い、と受付の男に偉く怒鳴られた。
気を取り直し、船が出るまでは時間があると、朝食を摂りに店に入れば、人間の町での初外食でも思わぬ事態に見舞われる羽目になった。
「何やねんホンマ……人間て神経質過ぎやろ……てか喰い過ぎやろ……」
人目を忍ぶ山奥で、家々も離れ、魔物や猛獣を狩って育った彼らは、物音を立てないようにする習慣など持っていなかった。
衣食の恵みも少ない土地で、成長期が過ぎれば多くの栄養を必要としない化け物である彼らは、食事量も人間より少ない者が多い。
「あんちゃん達、いいガタイしてんねぇ! よっしゃ、ここは奮発してやるよ!」
そのため、恰幅の良い女主人が出してくれた人間の男向けの食事に目を見張ることになる。
「……ゴメンね。わたし元々、あんまりご飯いらないの」
そもそも港に来た理由である、船に乗りたいと言っていた空色の同行者は、一早く戦線を離脱し……その世間知らずな一行は、出された食事を残して良いことすら知らず、昼までかかってようやくソレをやっつけたわけだった。
「船、出ちゃったね」
空色の流人の彼女はいつものように、ニコニコと端整かつ呑気そうに笑った。
「……だからアフィだけ、先に出れば良かったのに」
店では彼の苦手な牛肉や豚肉、悪友の苦手な鶏肉料理は出ず、海産物が中心だったことが幸いだった。彼らの奮闘に参加しない彼女に、彼は気にせず行くよう促したのだが……。
「でもこの町でも一杯お店あるみたいだし。義手のことを相談できる所、一緒に探そうよ」
彼女は綺麗に微笑んだまま、一人で去るわけにいかない理由を坦々と返してきた。
妖精の強引な握手で、彼女の大切なものという何かを、彼は義手に埋め込まれてしまった。
彼の右腕に、青黒い蛇の刻印のように視えているそれを、彼女に返す方法があるのか。もしくは新しい義手を見つけて、今の義手を丸ごと渡してやるしかないだろう事態に、彼は改めて大きく溜め息をついた。
義手に刻まれた紋様をやけっぱちに眺めながら、彩の無い眼で彼は尋ねる。
「これが無いとやっぱり、アフィは困るんだよな?」
「うん。『水』を喚ぶ時には、アーニァがそれで助けてくれてたと思う」
「水」を喚ぶ。妖精の遊戯道具に巻き込まれた時にも耳にした言葉に、その詳細を何となく追及すると、アハハ、と彼女は平和に笑った。
「本当は最初、自分で『水』を喚んで、海を渡るつもりだったんだ」
そんなことだけ答えるので、結局よくわからなかった彼が、さらに話を詳しくきこうとした時に――
「うぇぇぇぇん! お母さん、どこぉぉぉ!」
白い壁で木造と見れる商店が多く立ち並ぶ、素朴な土の道を歩いていた彼らのそばで、派手に泣く小さな子供が現れていた。
「――どうしたんだ?」
両手をぶんぶん振って泣きわめいている子供に、年下好きな彼は屈んで目線を合わせ、躊躇いなく穏やかに声をかけたのだが……。
「――きゃぁぁぁぁ! アタシの子供から離れてぇぇ!!」
建物の陰からひょいっと出て来た人間の女に――まさかそんなことを叫ばれるとは。
子供の頭を撫で、泣きやませようとしていた彼には、思ってもみない展開だった。
「……は?」
呆然とする彼だけでなく、悪友と彼女もわけがわからなそうに、ポカンと立ち尽くす。人間の女は彼から引き離すように、必死に子供を抱き寄せていた。
「ごめんね、一人にしてごめんね、いやぁぁぁ誰か助けてぇぇぇ……!!」
ぎゅうっと子供をしっかりと抱いた女は、そのまま崩れ落ち、彼が動けないでいる間、ひたすらそんなことを叫び……。
そうして、そこにいた彼と悪友は不審人物として、駆けつけた人間に捕縛されて現在に至るのだった。
……今から考えれば、基本無愛想で、剣を背負った全身外套姿の見知らぬ彼に、人間の女は怯えたのだろう。
人間の町では子供に声をかけて頭を撫でた程度で、不審者扱いされることがあると彼らは知るわけもなく……それ以上不審を増して、千族であると知られないため、大人しくお縄についた次第だった。
オマエの顔が怖いねん、アホ! と悪友に怒鳴られたが、あくまで悪気は無かった彼も、不本意だとしか言いようがない。
そうしたわけで、港町の不審者留置所に拘留された彼と悪友だったが。
「とにかく! とられた荷物は見つかったんか!? レイアス!」
「ヒトに探させて文句言うなよ……才蔵にも探させればいいだろ」
あかん、と即答で不貞腐れる悪友は、鉄格子の窓から見える半月を見上げる。
「透明チビ化する霊獣使えるなんてオマエくらいやんけ。ほんま何やねん、その妙特技」
そこから見える、暗い空を飛び回る何十羽の鳥という、不自然な光景を横目に口にする。
彼もちらりと、暗い窓の外を見ながら溜息混じりに呟いた。
「アフィはもう――船に乗ったのかな」
子供に近付いた不審者として、捕縛されたのは彼と悪友だけだ。彼女は元々、この町に来るまでだけの同行者であるし、何も関係はない、と彼らは口を揃えた。
――新しい義手が見つかれば、俺は里に帰るから。悪いがアフィも、用事が終わったら、困るならこれ、里まで取りにきてくれ。
彼女の大切なものが宿る義手を渡せないまま、船に乗るよう促すしかなかった。呆気ない上に後味が悪い別れになってどうにも無念だ。
悪友と二人でそうして捕まってから、既に半日が過ぎた現在だった。
「まぁ、それで正解やで。おれらだけならこんな牢、すぐに抜けられるしな」
武器を含め、荷物を全て取り上げられ、両手を縛る鎖と鉄格子の土牢。人間にはそれは有効かもしれないが、化け物である彼ら――それもある特性を持つ「霊獣族」には、鎖も牢獄も意味を為さない枷だった。
だから困るのは、荷物を没収されたことに尽きた。
「おれは武器はないし、一番は金やな。レイアスは短刀までとられたんか?」
「ああ。魔光石も霊光石も、軒並み取り上げられた」
彼の愛用の武器、長剣や短刀のみならず、新たな義手を手に入れるための資金源として、彼がコツコツ見つけてきた大量の天然石。それはともすれば、さらに厄介な事態を呼ぶ可能性のある代物と言える。
「多分開封はできないと思うが、あれを見られたら、千族だってすぐにばれるな」
「力」を発するものを、色付きで視れる彼だけの特技で、掘り貯めてきたそれらの石は、人間には未知の山奥でしか入手できない貴重で高価な鉱物だ。そのため魔物の胃で造った道具入れに、彼は厳重に保管している。
しかし道具入れごと没収されて、十年以上の苦労の結晶はあっさりと奪われてしまった。
「……とにかく短刀だけでも、絶対取り戻さないと」
さらには、決して他に代えることのできない最重要な手回り品は、真っ白な鞘と短い直刃の、一見大きな変哲はない小さな守り刀だった。
人間の町について早々、様々な困った事態にふう、と彼は抱えた膝に顔を埋める。
「……俺、そんなに怪しく見えるのか?」
彼は元々、子供が好きな方だ。彼自身は一人っ子だが、自分より弱いものが気になる年上気質と、里ではよく言われていたくらいだった。
「せやなぁ。きっと内面から滲み出てんねんで、危ない奴やて」
「何処がだ、何でだ。昔ならともかく、今は納得がいかない……」
「あかんな、それ本気で言うとるな、タッくんビックリやわ。自覚ない辺りが重症やで」
うぐ……と、かなり落ち込んでいる彼に、悪友はにやにやと追い打ちをかける。
「大体アシューくらいやろ、オマエのこと無害認定しよったのなんて」
「……それ、アイツの目が節穴って言いたいみたいだぞ」
「違いあらへん。アフィかて実際、本人無害そうやけど、妖精曰く危険みたいやしな」
「あのな……何が言いたいんだ、オマエ」
背中を合わせている悪友の顔は、彼には見えない。そんな悪口を叩きつつも、彼と長く付き合う悪友が、真意の解らない軽口を続ける。
俯いて視界を閉ざす彼に、今視えているのは、「もう一つの体」の視界。彼らを拘置する味気ない建物を飛び回り、一部屋ずつ荷物を探す彼の霊獣が、見ている光景だけだ。
もう一つの体――分身と言われる霊獣を持つ彼らの本領は、彼らと違う所にいる霊獣の感覚も共有できる点にあった。
その上に、人間に見つからないよう姿を小さく透明にできる彼の獣。そうした使役法は、生まれつき決まった形の霊獣を扱う彼らの「力」を超える、彼だけの特別な技能だ。
「オマエもアシューも、ひょっとしたらアフィも……おれらとは世界が違う気ぃするわ」
「はぁ?」
「だからアシューはオマエを一番頼りにしとんねん。オマエ未だに、わかっとらんけどな」
何やら突然、悪友が愚痴っぽくなった。霊獣側に偏らせた感覚の集中を解いて顔を上げ、彼がその言動を追求しようとした……ちょうど矢先のことだった。
「――タツクはアシュリンのこと、好きなの?」
形容し難い派手な音をたて、背後で悪友が、腕の鎖を派手に振り回して絡まれながら大きく引っくり返った。
「な――」
彼も呆気にとられ、唐突な爆弾発言の発生源を見つめる。
そこで開けられた彼らの牢の扉と、黙って入れ、と看守に背中を押されて、するりと中にやって来た者。その姿に、声を上げそうなくらいの衝撃が全身に走った。
「アフィ、何で……!!」
あはは、と笑いながら、そうして彼らと同じ所に拘置されたのは、昼間に別れたばかりの、紛れもなく空のような青い髪と目の彼女だった。
「ってアフィか!? 船に乗ったんちゃうんか!?」
ぺたんと隅に座った彼女に、悪友が当然の疑問を叫ぶ。
「船はもういいの。二人に会わせてって言ったら、ここに連れてこられちゃった」
微笑む彼女は彼らとの再会がとても嬉しいようで、杖も外套も取り上げられてほっそりした姿は、ただ可憐だった。
「当たり前だろ、仲間扱いされるに決まってる――」
「わたしが仲間じゃ、二人は迷惑?」
「そーいう問題とちゃう! アフィは行きたい所があるんやろ!?」
彼らの前に初めて現れた時、海を渡りたい、と言っていた彼女は……。
「海は、山を下りるために出たかっただけ。もう山は下りれたし、わたしの行きたい所は――『ディアルス』は、このシャルのお隣だって町で聞いたから」
そこで彼女が口にした、西の大陸屈指のある大国の名に――
彼と悪友の灰色の目に、揃って戦慄が走った。
「『ディアルス』……やって!?」
それは彼らが度々教えられた、最も注意すべき固有名詞だった。
「『千族狩りのディアルス』……そんな所に、アフィは何の用があるんだ?」
険しく尋ねた彼に、彼女はキョトンと目を丸くする。
「千族狩りって、何?」
あまりに平和な様子で聞き返す彼女に、悪友が頭を抱えながら、黙り込んだ彼の言葉を引き継いだ。
「ディアルスはな、世界中から千族を攫って奴隷にしとるっちゅー噂で有名な国や。千族の間じゃ常識やで、これ!」
「そっか……町で教えてくれた人も、あそこは危ない国だから近付くなって言ってたけど。二人の言うことと同じみたいだね」
ふむ、と彼女は考え込みながら、不思議そうに首を傾げる。
「でも、ナナハはそこにいるって、最後の手紙で教えてくれたんだけど」
「最後ってオイ。そっから先は、手紙は来てへんのか?」
ますます怖い話やんけ! と激する悪友に、うん、と彼女は他愛なく頷く。
「一人は嫌だなって思ったから……二人と一緒がいいなって思ったの」
そうした国に単身で行けなかったらしい。彼らは少し納得したのだが……。
「うううん。悪いけどおれらも、さすがにそこまではよう送ったらんで」
彼女の力になるのはこのシャルまでだ、とやんわりと悪友が言う。
「違うの、そんなつもりじゃないの。二人に守ってほしいなんて思ってないよ」
彼らの顔を交互に見ながら、彼女は初めて――憂いげに暗い青の目を伏せて俯いた。
そうして彼女が口にしたのは、彼らにとって、ずっともやもやしていたことの一つの核心だった。
「わたしはただ……レイアス達と一緒に、旅がしたいの」
その気配は薄々、この五日、道中でとても楽しそうだった彼女から感じてはいた。
しかし出会ったばかりの彼女が、それを望む理由がまるでわからない。何かはっきりとした思いを、彼女自身から語られるまで、何も言うなと幼馴染みに言われた彼らは触れ難い領域でもあった。
「……アフィ」
今はまだ、彼女が態度で表していたことを言葉にしただけの話だ。相変わらずその中身を言わず、黙り込んでしまった彼女を彼は無意識に見つめる。
何と言っていいのか、彼にも何故かわからなかった。
訊きたいことが彼もあるのに、それが何か言葉にできない――そんな思いだけが巡る。
俯く彼女と、それを見つめる彼の様子に、悪友がしばらく所在なさげにしていた。
「……要するにやな、アフィ」
彼女が牢に入る直前の衝撃の一声の、お返しとばかりに……悪友はそれを直球に尋ねる。
「アフィはレイアスのこと、好きなんか?」
悪友があまりに落ち着いた声で、平然とそんなことを言ったものだから。彼は一瞬、その問題発言を聞き流してしまうところだった。
「……――は?」
数刻遅れて悪友に振り返り、石像のように彼が硬直する。
「…………」
顔を上げて悪友を見つめ、言葉を失ったらしい彼女の、二つの視線が悪友にぶつかる。
悪友はバツが悪そうに頬をかいて、珍しく伏し目がちに、その発言の真意を呟いた。
「そーいうことやったら、別におれらについてきてもーてかまわんし……ただ、もやもやとしとんのは嫌なんや、おれは」
彼女はそれまでの笑顔も消して、ただまっすぐに、暗がりの訪れた青い目で悪友を見ていた。
「…………」
固まったまま異世界にいる気分の彼を、一度だけちらりと、彼女が見やる。
「……わたしは……」
頭痛を抑えるように、片手を額に添え――陰を受けた目は、さらなる暗い青に変わる。
彼らが黙ってしまった中で、彼女はやがて、いつかと同じ答を口にした。
「……レイアスは……兄さんに、そっくりなの……」
そこで暗い青の目を歪め、段々と呼吸は深く早くなっていき……。
「わたしはずっと――……兄さん……を、探し、て――……」
「……アフィ?」
その異変に気付いた彼が、咄嗟に鎖付きの手を差し出して半ば立ち上がった直後だった。
彼女は唐突に意識を失い、彼の腕の中へと、どさりと倒れ込んでいた。
「……何やぁ? えらい苦しそうやけど、おれやっぱ、悪いこときいてもーたんか?」
申し訳なさげに彼女を覗き込む悪友の下、彼女の青白い顔が汗ばんでいる。呼吸もまだ苦しげに、荒く続いていた。
「タツク……さっきのアフィの目、何色に見えた?」
唐突にそれを尋ねた彼の眼には、いつもは透き通る青の「力」を纏う彼女が、今は玄く澱んで見えた。それが何より不可解だった。
「ほえ? アフィはずっと、きれーな青い目しとるやんけ」
「青って言っても色々あるだろ。水色とか藍色とか、それで言ったら――」
「そら完全に水色やろ。アシューも空色ちゃんって呼んでたしな」
……と、彼女を鎖の両腕で抱えて膝で寝かせながら、彼は一層難しい顔をするしかない。
「俺には……たまに、夕暮れみたいな濃い青に視えるんだ」
「?」
どうやら彼女の、その暗い青が視えているのは彼だけらしい。
彼の腕の中、少しずつ息遣いが落ち着いてきた彼女からは、玄っぽい影も同時にひいていく。それで尚更彼は、彩の無い眼を厳しげに細めながら、自分でもよくわからない重苦しい気持ちで大きく息をついた。
あの暗い青の目を視る度に、わけもなく胸が詰まる。それは何処か、彼の大事な何かが揺らぎそうな怖れを伴っていた。
「過呼吸起こすくらいレイアスのこと好きなんやったら、そら色々と問題やわなぁ」
あぐらをかいて座り直した悪友の無責任な一言に、ごふっと彼は、その場で激しくせき込むことになった。
「レイアスはどーなんや? アフィのこと気になっとるんか?」
「待てってオマエ、さっきからだから何でそーなる……!」
静かに眠りについた彼女を、彼の外套を敷いた地面に横たえながら、悪友に喰いかかるように応える。
悪友こそ幼馴染みが好きなんだろう、と彼女の先の言を持ち出したい衝動にかられるが、それは悪友の次の一言であっさり封じられてしまった。
「オマエほんと、腕のことしか頭に無いから、里の奴らも苦労すんねん」
「は?」
「面倒見が良ぉて強うてのオマエを、気になっとる奴は一杯おんねんで? なのに全然、オマエはその自覚ないやろ」
「……?」
それは確かに、彼には全く心当たりのない話だ。本当に呆れたような顔の悪友に、咄嗟に何も言い返すことができなかった。
「少なくともアフィは、オマエに惚れとるか、どっかずれた強烈ブラコンのどっちかやで。……どーすんねん? 前者やったら」
「…………」
いつも軽いノリの悪友が真摯な目つきのせいか、彼の脳裏には何故か不意に、幼馴染みの姿……困ったような笑顔がそこで浮かぶ。
――だからアシューはオマエを一番頼りにしとんねん。
――大事なヒトに貰ったって言ってたしね。
何故か少し前の紫苑の少年の声まで思い出し、ぐるぐると混乱した頭のまま、不服気に考え込む。その感情の正体を、彼自身わかっていないのだから。
悪友は腕を組んで難しい顔で、話題を変えるように眠っている彼女の方に向き直った。
「それにしても……ちっとばかりこれは、脱出しにくうなってしもーたなぁ」
「…………」
「おれら二人だけやったら、こんな牢なんて無いも同然やったけど。アフィを連れてなら、こら本格的に、脱獄作戦を練らんとあかんで」
同じく彼女の寝姿を見つめる彼も、その必要性はわかっていた。
「おれらも遊んでばかりはおれんしな。旅だって期限つきなわけやし」
「それ――里を一ヶ月以上あけるなって、やっぱり無理じゃないか?」
外界に出る前、絶対条件として告げられた旅の期限。それへの不服を、ついでに悪友に返さずにはいられなかった。
「そーかそーか。オマエにはまだ、話しとらんかったな」
「?」
不意に、困った表情を浮かべた悪友に、彼は虚をつかれたように首を傾げた。
「おれも親父から、つい最近聞いたんやけど……うちの里には――一軍と二軍の村には、あまりエースが里をあけへん方がいい闇が存在すんねん」
「――はぁ?」
妙に真面目くさった言いぶりに、うっかり露骨な呆け声を出してしまった彼だったが。悪友が珍しく懊悩する目でもあることには、同時に気が付いていた。
「……だからアシューも、おれらにあんま、関わらなくなったんやで」
そこで悪友から聞かされた話は、彼には正直、あまりピンと来ないものだった。
「そんなこと気にしてたら、あいつ……身動きとれなくないか……?」
いつでも困ったような笑顔を浮かべているのが、引っ越した後に常態となった幼馴染み。
その苦悩の一端を、ようやく感じた彼の声は、静かに宵闇に消えていった。
上6:金翅の禿鷲
その夜、「海に愛された都」は北端の一部の港町に限り、「鳥に愛された都」へと様相を変えていた。
人の出入りの多い町での不審者の拘置所で、鍵番の男は壁際の机に向かって座りながら、窓の外を見上げて素っ頓狂な声を漏らすことになる。
「何だありゃ? こんな時間に何で……鳥の大群?」
拘置所を取り巻くように、灯りが届く範囲だけでも、大量の鳥が冬の夜空に舞っていた。
作戦を説明するで! と、空色の流人の彼女が起きた夜中に、悪友は揚々と話し始めた。
「静かにしろよ。看守が来たらどうする」
「おお、そーやな。まぁとにかく、アフィも連れて出るために、今から鍵を手に入れるで」
「…………」
寝ぼけ顔にも見える彼女は、暗い青の目で黙って彼と悪友を見つめて座る。
「レイアスがやっと荷物と鍵を見つけたから、こっからはおれの『才蔵』――の舎弟らが活躍するお時間や」
「……舎弟?」
不思議そうに目を丸くする彼女に、得意げに悪友は続ける。
「才蔵自身は霊体やから物には触れへん。でもおれのアイツは、別の鳥を使役できる特技を持っとるんや」
「数が多いだけが取り柄だしな」
「そーそー……ってレイアス、オマエ喧嘩売っとんかい!?」
だから静かにしろって。と呆れる彼の前で、少し前にお使いに出した鷲とそっくりな鳥を悪友が腕に乗せる。それ以外にも大量に集まった鳥に目配せするように、窓の外の夜空を強気そうに見上げた。
「レイアスの霊獣に目標の場所まで案内させて、ここの人間はコイツらに引き付けさせて、最後は番人の気を本命の才蔵が惹き付ける。その間に才蔵ズ舎弟が、鍵をゲットやで!」
「……荷物のことを忘れてないか、タツク」
「そんなん牢を出てから取りに行くしかないやろ。だからいかに、騒ぎにならないよーに鍵を手に入れるかが肝心なんやで」
大量の鳥がわさわさしていること自体、既に騒ぎでは、と彼は突っ込みたかった。彼にも代案があるわけではなく、不服ながらも黙って頷いた。
「それじゃ、これから……レイアスとタツクの共同作業なんだね」
にこにこと、段々目が明るくなってきた彼女が楽しそうに笑い始める。
「うわ、気持ちわる! 共同作業とか言いなや、こんな可愛げないムッツリ野郎と!」
「……それ、オマエに言われたくない」
元々、組み手以外で特に協力をしたことがない彼らは、居心地悪そうに互いを見返す。
そんなわけで、彼らの視界には、既に使いに出した霊獣達からの光景が届いていた。
「――」
「――!」
霊獣は本体と違い、喋ることができない。なのでパタパタと廊下を飛ぶ彼らが進路を変える時など、本体同士で相談するより、相手に体をぶつけるのが手っ取り早い。
「……!」
それで彼の白い霊獣――小さな羽と角の生えた小型犬らしき珍獣の、尖った尾につつかれた方はかちんとくるのか、悪友の霊獣である鷲はばさりと翼で彼をはたき返す。
霊体同士ならこうして干渉し合えるが、彼らの後をついてくる数羽の鳥は彼らに触れることはできない。逆に、彼らが触れられない鍵を運ぶための実体要員だった。
そうして、拘置所の周囲に集まる不審な鳥の群れに夜勤者の大半が外に出た中、鍵番の男は一人、軽く酒を飲みながら机に足をかけてダラリとしていたのだが……。
「それにしても、今日捕まえた奴らも、奴らのせいで夜勤になったおれも災難だよなぁ」
部屋の外まで聴こえるぼやき声に、僅かに開いていた扉まで来た鷲と飛び犬は、戸の上に停まってまず鍵番の様子を窺うことにした。
「どー見てもシロだけど、あんなに騒がれちゃ調べるしかないしよ。すぐに終わるだろと思ったら、どーやっても開かない道具袋とか何なんだよ、全くよぉ」
「…………」
「…………」
それでどうやら、彼らはここに拘置され続けているらしい。ほら、オマエのせいやんけ、と飛び犬をはたく鷲に、道具袋の持ち主である彼は応戦することもできない。
「アイツらは宿代浮いていいだろーが、おれは大事なデートが台無しだ、くそっ」
酔っているのかそんな愚痴をこぼす鍵番に、彼らは顔を見合わせる。
「……この上、コイツから鍵とか奪ってええんかな、おれら」
「でも道具袋の中身を調べられたら、多分クロ扱いされるぞ」
本体同士もしみじみと相談し、人の世とは難しいものだ、とバツが悪い心で頷き合う。
ひとまず初めの作戦通りに、そこで鷲の方が、鍵番の前の机にばさりと降り立った。
「――? 何だオマエ、何処から入ってきた?」
鍵番は不思議そうに、突然現れた鷲に物珍しそうに、机から足を下ろして体を起こす。それに合わせて鷲もトコトコ位置を変え、鍵番の視界から壁にかかった鍵束を排除する。
「今日は本当に鳥日和だな。あ、おい、待てよコイツぅ」
鍵番が捕まえようとしても、霊体である悪友の獣に触れることはできない。そんなこととは露知らず、鷲に触ろうとする鍵番に、鷲は巧みに飛びのいて気を惹いていく。
鍵番の背後では数羽の鳥が、いくつかの鍵束を一つずつ掴むのを飛び犬が見守る。
「ちくしょー、怖がってないなら触らせろよぉ。いっぺん触ってみたかったんだよー」
部屋の隅で天井の梁に停まった鷲に鍵番は夢中で、全ては順調と思われた……が。
「その頭、どんな手触りなんだよー。ツルツル? ざらざら? くあー、可愛いよなぁ、オマエみたいな奴ってさぁ」
……そこで飛び犬の方に、嫌な予感がすぐに走った。
「たまんねぇなー、そのツルピカ頭! ハゲワシ最高! ってか珍しー!」
鍵番はそれで、ここまでスムーズに気を惹かれていたわけだった。
「おんどらぁ……!! ハゲ言うなや、うぉああああ!」
「――ってタツク……!」
昔からの禁忌の一言に、思わず絶叫した悪友を彼は慌てて羽交い絞めにする。
しかし時既に遅く……声を聴き付け、外に出ずに残っていた看守が駆け付けてきた。
「何を夜中に騒いでるんだ! この人手の足りない時に!」
そして当然、悪友を背後から締め上げている彼の姿を、看守は目の当たりにする。
「――あ」
「オマエ……自分の仲間を殺す気か!?」
「……え」
咄嗟に何と言っていいかわからなかった彼は、横を向いて看守を見るくらいしかできない。その無表情な視線に看守は睨まれたと感じたのか、何と武器までを取り出していた。
「は、離せ、離してやるんだ! 離さないと撃つぞ!」
そんなに俺、怖いのだろうか、とまたショックを受けた彼はすぐに反論できなかった。
しかし、看守の動揺が、化け物の彼らには日常茶飯事のきつい組み合いにあると判ったらしい悪友が、締め上げられながら平然と出した声に、不意に場が鎮まった。
「……すみませーん。おれが寝ぼけて、コイツに殴り掛かってしまったんです」
にこにこと悪友は、彼に羽交い絞めにされたまま、穏やかな声で看守に笑いかけた。
「心配おかけしました。大人しく寝直すんで、看守さんも仮眠に戻って下さい」
看守はしばらく、釈然としなさげだったが、やがて武器を直し、出ていったのだった。
……びっくり、と。看守が行ってから、最初に喋ったのは空色の流人の彼女だった。
「タツクって、普通に喋れるんだ……」
彼から解放されて襟を直す悪友の、これまでにない姿……訛りのない言葉遣いに衝撃を受けたらしく、彼女はまじまじと悪友を見つめる。
「おれは元々、こっちで喋るんは、レイアスとか家族の前でだけや」
悪友にとっては、今の訛りを使う場の方が限定されていると、彼も知っていた。
そもそも異郷の母だけが話す訛りは、とても中途半端に受け継いだ悪友であり、周囲の普通の言葉と混じっておかしな言い回しになることも少なくない。
「東訛りやから、西の大陸のここで不審に思われてもあかんしな。余所行きの顔くらい、おれかて持ってるっつーねん」
「じゃあわたしには、最初から気安く話してくれてたんだね」
うるうると彼女が、本当に嬉しそうに両手を組んでいるため、ははは、と悪友も苦笑する。
「……タツクは大体、ヒトによって態度を使い分け過ぎだろ」
それが長の息子として、悪友のしっかりした部分であると彼はわかっているが。彼にはそうした器用なことはできないためか、たまにぼやいてしまう。
「言うとけや。ほら、才蔵ズがちょっとずつ来るから、今から順に鍵探すで!」
「…………」
どうなるかと思ったのは誰のせいか、と彼も不服だが、鍵番が口にした禁句のせいで悪友も不機嫌そうだ。そんな悪友に続き、彼も鳥達から鍵束を受け取りに向かった。
そうして何とか牢を出た後で。先程の看守を、スマンと謝りながら体術に長けた悪友が気絶させる。夜勤者達が鳥の大群にまだ気を取られた中、彼らはこそこそと荷物を探す。
拘置所を後にし、そのまま港町にも背を向け、ヒトに紛れるために「シャル」中心部の商都へ――夜の内に行くことに決めた彼らだった。
夜通し歩いて、何とか商都についたものの。華奢な体で空色の流人の彼女が疲労していないのか、人間ではないと言えど彼は気になっていた。
「すごーい、本当にヒトが一杯。これだとどうやって、気配を探れないヒトは知り合いを探すんだろう?」
港町も建物の並びは賑やかだったが、中心部は人口密度が違うらしく、休息のため噴水に並んで座った彼女は、楽しげに行きかう人々を眺めている。
悪友はざっと歩いてみる、と言って別行動を取り、帰ってき次第、まずは宿を探しに彼らは行動を再開するつもりだった。
「…………」
わあわあ、と彼女は、広場の石で造られた噴水を背に、西洋――西の大陸らしい恰好の者や白壁の建物群を見回し、ここまでの道中で気疲れしていた彼より元気そうだった。
「……お尋ね者とかみたいに、俺達、貼り出されなきゃいいけど」
「そうなったらなった時だよ。写真もとられてないし、大丈夫だと思うけどなぁ?」
彼らに同行するのがすっかり当たり前とばかりに、泰然とした彼女にも彼は困惑する。
「アフィは……ディアルスに行かなくてもいいのか?」
「――え?」
「……昨日の話。タツクの戯言はともかく、会いたい奴がいるんだろ?」
どうして彼らと、行動を共にするのか。何処までそうする気なのかも、彼は気になってしまった。
――アフィはレイアスのこと、好きなんか?
悪友の余計な言葉まで思い出し、思わず彼女から目を逸らして尋ねていたのだが……。
「昨日の話って――何?」
にこにこと彼女は……きょとんとしながら、背後の噴水よりも透き通る空色の目で応えた。
「何って……――アフィ?」
その様子に彼は、彼女が本気で、悪友との話を覚えていないらしいことを瞬時に悟る。
「わたし……ディアルスに行きたいって、二人に話したっけ?」
「…………」
「確かにナナハ――わたしの幼馴染みはそこにいるけど。別に急がないから、レイアスの腕のことを何とかする方が、わたしには先かなぁ?」
屈託のない笑顔と、澄んだ青の目には何の澱みも無く、それが今の彼女の真っ当な本心と伝わる。それならこの状況に何の違和感もないことが、かえっておかしかった。
それだけはっきり理由を持つなら、彼女は何故――昨夜はそう答えなかったのかと。
――記憶喪失って……そういう、ことか?
昔のこと、何も思い出せないもの。そう言った彼女の目がどちらだったか、彼は覚えていなかったが。
この透き通る空色の彼女は、暗い青の自分を知らない……現在進行形で忘れているのではないか。彼女達は「違う」のかもしれないと思うほど、その目の光は彼には異種に視えた。
もやもやと、形にし辛い疑念を抱えて、彼は少しだけその深奥に踏み込む。
「――あのさ。唐突だけど……アフィの兄さんって、どんな奴なんだ?」
「え?」
「俺に似てるって、少し前に言ってただろ?」
彼のことを探している兄にそっくりと言い、だからついてきたような、暗い青の目の彼女。この彼女はそれをどう思っているのか、確かめてみたくなったわけだが……。
そこでさらに彼女は、彼の疑惑をかき乱すことを答える。
「あははは。全然似てないけど、そっか――だからわたしは、レイアスが気になるのかな」
あくまで動じない彼女は、少ない荷物からひらりとすぐに、一枚の写真を取り出した。
「……コイツが、アフィの兄さん?」
渡された写真には、彼とは似つかない、彼女と同じ空のような青い髪の青年が映っていた。
しかしその前髪には、彼と同じ一房だけの黒髪が混じり、彼女曰くそれも天然のものといい――……そのせいか彼は、眩暈のような既視感を一瞬覚えた。
「兄さんは母さん似だから、父さん似のわたしとも顔は似てないよ。父さんや母さんには意地っ張りだけど、わたしにはいつも凄く優しくしてくれて、でもあまり帰ってこなくて……いつまでもレイアスくらいで年もとらなくて、今はずっと、行方不明中」
「……は?」
「兄さん、悪魔だからなぁ。人間と契約して何処かに行っちゃったんだって」
「……え?」
写真の兄の不敵な蒼い目を切なげに見つめる彼女が、兄好きであるのは確かなようだった。
「会いたいけど……いつかは戻ってくると思うよ。わたしが探しても、探さなくても」
それは再び、彼の内心を混乱させる発言……それなら彼女は、何を求めて旅に出たのかという、疑問の深まりでしかない。
黙り込んでしまった彼の横で、それにしても――と。気が付けば沈み始めていた夕陽を受けて、彼女は不思議そうに立ち上がった。
「タツク、遅いね……レイアス」
「――そうだな。さすがにこれは、遅過ぎるな」
はっとした彼は、ざっと歩いてくるだけのはずの悪友が、気配も全く近辺に感じられないことに今更気が付いていた。
「……霊獣をここに置いておくから、俺達は宿を探そう」
あのしっかり者の悪友が、遅くなるのに鳥づての連絡一つもよこさないこともおかしい。一瞬、背筋が寒くなるような悪い予感に襲われてしまう。
「大丈夫かな……? 霊獣、誰かに見つかったりしない……?」
「潜伏用に小さく透明にするから。アフィは心配しないでいい」
彼よりもっと不安そうな彼女に、務めて気丈に言う。その後、手の平サイズの飛び犬を噴水に残し、場を後にしたのだった。
それからは、宿で一旦腰を落ち着けるまでが、また一苦労だった。
「――絶対にダメ! レイアスのお金なんだから、わたしの分でそんなに嵩むのはダメ!」
「でも、アフィ――」
「タツクもいないのにさらにバラバラも嫌! 部屋は一つでベッドはレイアスが使って!」
空色の流人の彼女は、妖精の里謹製という服装は上等だが、路銀を零と言っていいほどに持っていない。人間とは違い、食事もほとんど必要がなく、沐浴も野宿も平気となれば何とかなるのはわかるが……彼としては多少値が張っても、別の部屋をとりたかった。
ところが彼女は頑として、一人部屋に雑魚寝で十分、と言い張るのだった。
悪友が妙なことを言うから、彼の方が変に意識してしまったのだろう。彼女と二人きりで同じ部屋というのが、彼は看過できなかった。
「アフィもちゃんと、ベッドで休めるようにした方がいいだろ」
「それなら二人部屋の安い宿を探そうよ。もう少し探せばきっとあるよ」
いや、それはさらにまずい気がする、と喉元まで出かける。しかしそう言えば、その意識自体がばれるのも困る。結局は彼女の勢いに押し切られることになった。
「……頼むから、アフィがベッドで寝てくれ。それだけは俺、譲れない」
「もう。それなら二人共、床でいいのに」
無邪気にそう怒る彼女に、もう少し警戒してほしい、と色んな意味でめげた彼だった。
「……手が動かないで、良かった」
今は荷物を引っ掛けるのがせいぜいの右手を、じっと眺めながら一人ごちる。
「俺だって男なんだし……自信ないぞ」
自身の着替えすら心許ないその手では、過ちも起こしようがないが。
未だに姿を見せない悪友への心配より前に、そんなことで気を揉む己につくづく、彼は頭を抱えるしかない。
それにしても――と彼女は、悪友を心配する不安そうな顔付きながら、床に座る彼を感心したように見ていた。
「霊獣って本当に便利だね。ここにいても、噴水でタツクを待っていられるなんて」
「……その気になれば、霊獣がいる場所なら、俺は一瞬で行くこともできるよ」
「ええ? それって、タツクやアシュリンもそうなの?」
「ああ。アシューはそれでいつも、霊獣を安全な場所に置いて、危険から逃げてるらしい」
そして悪友が、滅多に話さない幼馴染みのことをよく知っているのは、鳥の霊獣に度々観察させているからだと知っている彼だった。
「タツクも何かあったなら、才蔵なら一番逃げ足は速いはずだけど……」
それなら音沙汰がないのは、即死しているか故意ではないかと考えるほど、現状は異様だった。
「……俺も気配探知が苦手だから、何とも言えないけど」
化け物には生まれつき、互いを識別するための気配の知覚がある。
だから化け物からは、人間と化け物を気配で区別できる。鋭いものなら町一つは探索できるのだが、遠くのものや、気配が弱る、潜めているものは感じ難くなる難点もある。
ベッドに座った彼女も、真剣そうに言う。
「わたしもずっと探してるけど、やっぱり近くにはいないよ」
「……とりあえず休もう。何かあった時のために、体力を温存しておかないと」
「うん。明るくなったら町中を一緒に探そうね、レイアス」
ああ、と頷きながら、また義手のことは後回しか、と小さく溜め息をついたのだった。
――あまりエースが里をあけへん方がいいねん。
一カ月と制限された今回の旅では、大した成果は得られないかもしれない。
ごろんと横になり、外套を布団のように被りつつ、彼はすぐに寝入っていった。
昔からよく夢を見る彼は、眠りにつくのは早いが、浅いことが多い。
僅かな物音でふっと目を覚まし、まず気が付いたのは、同行者がそこにいないことだった。
「……アフィ?」
ベッドの上はもぬけの空で、狭い部屋の内に全くその影がない。気配探知の苦手な彼は、咄嗟に起き上がり、被っていた外套を羽織り直す。
「――何処に行ったんだ?」
部屋を出て落ち着いて気配を探ると、案外すぐに、その気配は近くに見つかった。
彼女のいる宿の屋上まで、何の疑問もなく、追いかけるように彼は足を向けた。
四階建ての宿の最上部、青白い月の下で。
寝着のままで、髪を下ろした彼女は町を見下ろすかのように――屋上の縁に手をつき、無言でよりかかっていた。
「アフィ……眠れないのか?」
静かに声をかけた彼に、ちらりと振り返った目は、眠りに落ちる前のように胡乱だ。
そして彼が、無意識に予想していた通り、とても暗い青に澱む目の青花がそこにいた。
「――……」
その悲しげとしか言えない遠い目……月の光を受ける横顔に、彼は咄嗟に胸を衝かれる。
彼女はそんな彼に、やがて町を背にしてゆっくりと振り向く。
普段とは違う悲しげな顔で、彼の目を切なげに見つめていた。
ようやく口を開いた彼女は、苦しそうな微笑みを浮かべた。
「……ゴメンね。ちょっと怖い夢を、見てるだけ」
「怖い……夢?」
何処となく、ふわふわとした声色で、暗い青の目の彼女は続ける。
「レイアスは……生まれる前のこと、覚えてる?」
そしてそんな、唐突な問いかけ。彼は彼女が、言葉通り夢の中にいるのだと何となく悟る。
「昔はね……私、覚えてたんだ。私がここにいるのは、大事な理由があるんだって」
でも今は、それを思い出せない、と――記憶喪失を自称する彼女が苦しげに笑う。
対して彼は、彼自身も驚くほどに、その与太話を真っ当に受け止めていた。
「そんなの――覚えてない方が、俺はいいと思う」
何故ならそれは、彼も通って来た事柄で――だから彼は、旧い答を伝える。
「俺は魔物と言われて育ったんだ。あの赤い獣が、その証拠だって」
世界の「力」は、不滅であるために。「力」の流転……転生は在る、と魔道では定義される。
全てのヒトはただ、「力」の器として存在し、同じ「力」を担う者は、時代が違えど同じ存在であるという。
そうは言っても、「力」は不変ではない。「力」がどのようにこの世界に具現されるかは、その「力」を担う化け物の制御力により、担い手が出生する際にリセットされる。ところが彼は、幼少より完成された赤い獣を持ち、それは先の世の「魔性」の業だと名付け親は言った。
「死んでもそのまま『力』を残して、その『力』を使うことができるなんて、魔物だけだ……そんな奴は、死んだとは言えない、『魔』なんだから」
「レイアスは……じゃあ、捨てたかったの?」
ああ、と。その決別と同時に失った右手を思いながら、彼は迷いなく答を返した。
「大切なのは今だろ。大切なものを傷付けるアイツは、いてはいけないものだったんだ」
「それが……大事なものだったとしても……?」
「……今、大切なものの方が大切だから。俺が何者だったとしても、関係はないよ」
そこまで聴くと、彼女はそう……と顔を伏せる。そのまま屋内に戻るように歩み始めた。
「……うん……。アナタは確かに……魔物じゃないんだよね」
すれ違い際に呟かれた声に、安堵と悲哀が狂おしく入り混じる。
ともすれば夢だったのだと思うほどに、あまりに儚い束の間の邂逅……。
しかしまだ、その長い夜は始まったばかりであると、再び目を閉じる彼は知る由もない。
上7:白黒の大猫
彼の呪いたる赤い獣を、蒼い男が旋風の如く切り裂いていったあの時。
男の纏う赤い光が最後に彼に与えた苦悶……昏く旧い夢の嘆きが、不意に再生された。
「……――ああああああああ……!!」
こんな苦しみに耐えられるわけがない。それは叫ばずにいられない光景だった。
大切なものが消えてしまった。その時から彼を襲うようになった、赤い鼓動――
――……何故――……殺した……!?
いっそ共に消えたかった。けれどそれを許さない、棘の鎖が彼を縛り上げる。
そんな彼を痛むように……何故か、とても懐かしい誰かの声が、暗闇の中に響いた。
「……バカだな。そんなに苦しいなら、もう捨てちまえばいいだろ?」
――それはできない。即答した彼は、自身の重い哭き声にはっとする。
「何だ、わかってんじゃねぇか。その鼓動は……大切だから、だってさ」
ずっと、捨てたいと思っていた。彼が彼となってからは尚更だった。
今、大切なものの方が大切だ、と、それが「彼」の答なのだ。
己を失い、周りを傷付けてまで引きずる「心」は、苦行以外の何でもなかったのだから。
――……なんて――……ない方がいい……。
言葉を呑んでこらえ続ける彼に、誰かは不意に、驚くほど優しい声で笑うように言った。
「それじゃ、ソイツは、オレが持ってってやるよ」
彼を救うように、その赤い光は閉ざされ、誰かへ融け込むように段々と消えていく。
「オレがいなくても……もう大丈夫だろ?」
そう、消えていく誰かは、ただ微笑みながら別離の言葉を残し……。
束の間の、互いに赤い光を纏う誰かとの邂逅。それがそうして、あっさりと閉じた後に。
改めて――その黒い彼女は、少し俯きながら、彼の灰色の外套を掴んで拙く口を開いた。
「……わかっていたのにね。それはアナタの……大切なものだって」
「……!?」
ずっと、昏い闇の中で膝をついていた彼が、そこで初めて顔を上げる。
「あんた――誰だ……?」
あどけない無表情と、無機質な幼声でそう言った黒い彼女。それは彼には、全く見知らぬ存在だった。
「誰でもいいんじゃないかな? だってこんなの……ただの夢だもの」
しかし、謎の少女たる彼女は彼を知っている。その声に隠せない大きな気安さが示す。
「……夢?」
「当たり前じゃない。いつもの青い夢……アナタが自分を、置き去りにしたあの日」
「……――」
あまりに真っ暗なこの世界に、溶け込む黒い彼女。それは酷く場違いだった。
ここが何処かはわからない。それでも彼だけの世界のはずだろう。
「あんたは……何処からここにきたんだ?」
「それは違うよ。アナタがあたしを――あたしとあのヒトを、その眼で視てるだけだよ」
幼げな彼女は少しだけ、悲しげにその答を返していた。
「だって誰も、あたしに気付くことなんて、ない」
小さく消えそうに色褪せた声。彼には何故か、知ったもののように聞こえ……。
「わたしは私を奪って、あたしを一人で残していった」
「――え?」
「アナタはあのヒトを連れていって、でも結局、あのヒトとは離れた」
黒い彼女は彼を見ずに、ある夢の始まりだけをそうして彼に伝える。
「あのヒトもあたしと同じ。いつも誰かのそばにいて……誰かの真似をしているの」
――最初から。彼らも彼女もそうだった、とそれは語った。
「でもあのヒトは……アナタ達を守るために、今生で全然、違うヒトの依り代になった」
「俺、達……だって?」
「二人いたでしょ? アナタの近くに――白いあのヒトと、蒼いあのヒト」
そこで彼にまた、あの赤い光に視せられた光景――彼と獣を結ぶ真実が襲いかかる。
――それじゃ……全て、終わりにしよう……。
赤い獣となったのは、元は白い誰かだった。
それは彼を守るため、蒼の魂を失ったもので――何より大切だったそれを、自ら貫いた赤い腕の感触……その憎悪の鼓動が、彼の忘れたい全ての呪いだった。
――じゃあ……トドメをさすのは、俺の役目か……。
赤い鼓動はそのまま、彼の心臓となった。震源である赤い右腕を失くす日まで、かつての彼がさらに大切なものを失い、憎悪に焼き尽くされる旧い夢を、赤い獣と共に見せ続けたのだ。
「……やめてくれ……――」
知らず、慟哭の呻きを漏らす。彼は物心ついた時から、ずっとそれを願い続けていた。
――俺はこれ以上、奪いたくない……。
何の不満も不遇もないのに、抑えられない自らの赤い獣。理由があるなら先の世の業と思うしかなかったが、その中身をわざわざ、知ろうとしたことはなかった。
「俺は……前世とかそんなの、どうだっていい……」
こんな光景、彼には何の関係も無いものだ。たとえ万一、彼と赤い獣の過去であっても。
そうでなければ己が保てないと感じるほどに――それは深い傷だったのだから。
変わることの無い彼の応えに、彼女は特別、失望した様子を見せるでもない。
いったいどうして、黒い彼女は彼に会いに来たのだろう。再び赤い光を振り切った彼は、改めて苦悶の顔を上げた後に――
「……アフィ……?」
その姿も「力」の色も、闇に融けて見えない残花。けれど思わず、彼はその名を呟いた。
「あんたは――……アフィの……?」
ただ、その黒が似ている、と思っただけだ。それだけで急に狂おしくなり、出てきた名前がそれだった。
しかし黒い彼女は、彼にだけ視えている自身……彼が求める旧い花を否定する。
「違うよ……あたしは、私がわたしの代わりに、連れていってくれたあたし」
黒い彼女がぎこちなく、何処かで見たような僅かな微笑みを浮かべた。
「アナタに会いたかったわたしは、離れていったから……あたしはただ、空っぽの残り滓」
何を言っているか、さっぱりわからなかった。この相手には、生きる場所がないことだけが伝わる。
空ろである故に、存在を奪われ閉じ込められた彼女。どうしてなのか、そんな気がした。
「だからあたしは……もう、―――じゃないんだよ」
それだけを伝えたかった、というように、黒い彼女は最後に儚く微笑む。
彼がもう一度その名を呼べる前に、黒い夢路に消えてしまったのだった。
……待ってくれ、と言う資格は、赤い獣を捨てた自分にはなかった。
今を生きると決めた時から、青い夢を見る度に、彼は己に言い聞かせていた。
あの赤い鼓動は、もう目覚めてはいけない――望んではいけない、旧い夢なのだと。
――オレ……ここにいない方が、よかったんだ――……。
ソレを連れ出したのは彼だという。未練だったのか、それとも贖罪だったのだろうか。
けれど結局置き去りにした。彼を終わらせるはずだった青い夢、昏く冷たい水の底に。
「……違うんだ……」
だから彼の嘆きは、ソレがずっと、最後まで彼をかばった痛みだった。
「いない方が良かったのは……俺だったのに――……」
それならせめて、分かたれることを望んだのは、彼の咎にしなければいけない。
そして彼は、自らを壊す古い傷に、二度と振り返りはしないと誓ったのだ。
たとえどれだけ大切な旧い縁が、彼の前に現れたとしても――
ううん、と長くうなされていた彼が、ようやく現に戻ろうとしていたその時に。
狭い窓から部屋に差し込む朝の光と、連なる小鳥の唄声の中で、彼は涙しそうになった。
「――リ、――……」
直前まで夢に視ていて、涙混じりに呼んだ名前。それはいったい誰のものだったか、思い出そうとしてしまった揺らぎに、まるで歯止めをかけるような衝撃が不意に続く。
「むにゃ……オレ、もー、お腹いっぱい……」
「――……は?」
目を開けた瞬間、横臥していた彼の目前に、幸せそのものの安らかな寝顔の紫苑の少年。
彼はこれまでの夢を全て忘れるほどに、その姿に真っ白になった。
「……な――!?」
がばっと床から起き上がり、咄嗟にベッドの方を見る。そこにもさらに、驚くべき光景があるのを見つける。
「って――『バステト』!? お前何で、こんな所で寝てるんだ!?」
丸まってまだ寝ている空色の流人の彼女の足下には、空いたスペースを占拠する大きさの白黒の猫。見知ったそれが、彼女と同じように丸くなって眠っていた。
思わず声を上げた彼の下で、不法侵入者の少年は目が覚めたらしい。寝転びながら目をこすって、ふわぁぁと大きな欠伸を始める。
「……あー。……おはよー、レイアスのにーちゃん」
「おはよーって……! オマエ何処から……というか何でここに!?」
眠たげに体を起こし、床に座った少年は紛れもなく、自称何でも屋。少し前に、彼らと共に妖精の道具に巻き込まれた相手だった。
「そんなにビックリするなら、せめて結界くらい張って寝ろよー……なー、ねーちゃん?」
不用心だなぁ、と、ベッドの足下の大猫を撫でながら、少年は呑気に口にする。
その状況に改めて、彼がある推測に至りかけた瞬間――
「……あれ? アシュリン……の大きな猫さん?」
大猫にベッドの三分の一を奪われていた彼女が、ようやく目を覚まして異状に気が付く。
「うわあ、会いたかったよう……久しぶりだね、本当久しぶりだね……」
首を起こした大猫に、彼女はぬいぐるみを抱くようにひっつき、暗い青の目を滲ませる。
彼はとにかく、大猫に抱き着く彼女を微笑ましげに見る少年に、険しく向き直る。
「……オマエをここに連れて来たのは、アシューなのか?」
大猫の姿をした霊獣の本体たる幼馴染みが、少年と知り合いとは聞いていたので、心当たりを口にしたわけだった。
「いやいやー。にーちゃん達がいるって見つけたのはねーちゃんだけど、ここで寝よー、って言ったのはオレだよー」
混乱する彼をおちょくるように、けらけらと少年が笑う。首にかけていたゴーグルを、額につけ直しながら不敵に彼を見る。
「ねーちゃんは情報収集に行くって、その猫残して行っちゃったけどさ。オレはひとまず、にーちゃん達にも事情を説明しなきゃ、と思ったしね」
「……?」
「聞いてビックリ、見てビックリ! 何とオレは、タツクのにーちゃんが『千族狩り』にあったかもしれない情報を持っているのだ!」
「――何だって!?」
彼らが二人だけでこの宿にいた理由。町を歩く、と言って帰らなくなった悪友の名前に、彼と彼女が揃って少年の方をばっと見た瞬間。
「こっから先は、情報提供料をいただきまーっす」
このヤロウ……と、彼が無表情にぶるぶる拳を震わせる前で。全く悪びれずに、手掌をすっと差し出した、ちゃっかりしっかりの相変わらずな少年だった。
少し前に彼らに出会った後、紫苑の少年は彼らより早く、このシャルに来ていたという。そして、彼らを追うようにやって来た幼馴染みと、昨日に偶然再会したらしい。
「アシュリンのねーちゃんは、アフィねーちゃんがどうなったのか気になるって言って、にーちゃん達を探してたんだよ」
「……」
宿を出て朝食を摂れる店に入り、大猫を机の下に潜めて、食卓の向かいに紫苑の少年を座らせる。情報料として、少年分の追加の宿代と、食費を賄うことになった彼は、不機嫌そうに温かい飲み物を摂りながら耳を傾ける。
「オレが見たのは、この人間の町で何でか、千族ばかり乗った馬車が都市長の屋敷に入っていくところ。シャルの都市長は隣国ディアルスの『千族狩り』売人と繋がりがあるって、最近噂になってるんだ」
「じゃあその馬車に、タツクも乗せられてたかもしれないの?」
「一瞬だったけど……知ったような気配があった気がした。でもあの馬車、乗った奴らの気配を隠すようにできててさ」
その時少年が、不意に強く顔を歪めた理由を、彼は知る由もなかった。
「オレ、気配探知はかなり得意な方なんだよ。でも全く中の気配がわからなくて、馭者が一度後ろを覗いて窓を開けた時、その匂いが漏れてきたんだ」
「……オマエは何で、何処からそんな馬車を見張っていたんだ?」
彼の当然の疑問に、少年は少しバツが悪そうに飲み物をとり、何かを誤魔化すような軽い口調で説明を続ける。
「オレは噂の真相を追って、都市長の屋敷の様子を見てただけさ……そこにそんな馬車が来たもんだから、今じゃほとんど確信してるけどね」
そしてその後に、今度は幼馴染みが商都をうろつく気配に気付いたらしい。再会までの顛末も語り終えてから、出て来たサンドイッチに威勢よくかぶりついた少年だった。
「じゃあタツクは、都市長さんの屋敷に閉じ込められてるのかな? レイアス」
「と言っても……アイツのことだし、一人なら脱出くらい簡単なはずなのに」
訝しむ彼に、少年が至ってあっさりと、仮説を投げかける。
「『力』を封じる部屋か、呪縛の道具を使われてるのかもね。あんな馬車を使ってる奴ら、それくらい持っててもおかしくないよ」
「って――人間が何で、そんな道具を持ってるんだ?」
妖精や吸血鬼など、技術の優れた千族ならともかく、と彼は首を傾げるが、少年はさぁ? とそれを流して勢い良く朝食を片付けていく。
「アシュリンのねーちゃんは、都市長の屋敷近辺に行くってさ。万一危なそうだったら、そいつの所に戻ってくるって」
机の下で大人しく座る、大きな白猫。金属製の細い首輪をはめて、四肢と耳、尾の先端だけが黒い大猫を下目で見つめる。その上で少年が懸念そうに、改めて彼に顔を向けた。
「でもこいつかなり目立つから、今は姿を隠す道具を使わせてるよ。オレにしてはホント、出血大サービスなんだけどね」
「……そうなのか。それでバステトの奴、こんな首輪をしてるのか」
「……?」
そこで空色の流人の彼女がちょうど、ある不思議に思い至っていた。
「そう言えば……バステトって霊獣、なんだよね?」
霊体であるために、霊獣と呼ばれるはずの「力」。しかしその大猫は物質である首輪を身に着け、彼女が抱き着くこともできた。つまりサイズ以外、紛れもなく普通の動物なのだ。
「……それがアシューだけの特別で、多分悩みどころだ」
憮然と言う彼に、彼女はまだ不思議そうに、透き通る青の目をぱちくりとさせる。
詳しく説明したものかどうか、少し悩んで目を伏せた彼の背後に、ふっと影が差した。
「……別に今は、そんなに悩んでもないよ?」
そこにはあまりにタイミング良く、黒いヘアバンドを身に着ける幼馴染みが現れていた。
その白灰の髪と灰色の目の相手の姿に、空色の彼女が真っ先に破顔していた。
「アシュリンだー……! 久しぶりだー……!」
「あはは。バステトの目からあたしはもう会ってたけど、久しぶり、アフィちゃん」
まだ一週間たってないけどねぇ、と相変わらず適当に緩く、幼馴染みが笑う。
「…………」
紫苑の少年と彼女が並んで座る向かい、彼の隣に幼馴染みが当然のように座る。内心の動揺を隠すように、彼は少し息を呑んだ。
里ではほとんど見たことのない、幼馴染みの旅姿。まっすぐな短い白髪をヘアバンドで落ち着ける外套の姿は、童顔な幼馴染みを、大人びてみせる効果を持っているようだった。
「もう都市長の屋敷の偵察は終わったの? アシュリンのねーちゃん」
「うわ。ラスト君ほんと馴染んでるね、違和感ないねー……レイアス達と知り合ったって本気だったんだね、びっくり」
そもそもそのヘアバンドが返ってきたのが、彼らと少年の出会いの結果とわかっているようだが、幼馴染みはマイペースに、彼らの空気に割り込んでくる。
「偵察とかとてもできないよ、とんでもないよ。ただ、あの屋敷に、タツクはいそうってことくらいかな?」
そうして弱気ながらも笑う姿は、里でのよそよそしさが全く嘘のようだ。彼はまたも、複雑な思いにとらわれることになった。
――一軍と二軍の村には、闇が存在すんねん。
――そんなこと気にしてたら……身動きとれなくないか?
「それにしても……長の息子が誘拐された、なんて言えば、里じゃ何て言われることか……」
もしや若者外出禁止令が出るかもしれない、と、有り得る展開を幼馴染みが困り顔で言う。
「……知られる前に助けないとだろ」
ぶすっと重々しく答えた彼に、今度は苦く笑って、そうだね、と応じた幼馴染みだった。
悪友はその屋敷にいそう、と言った幼馴染みに、紫苑の少年は、不可解と言いたげな目を遅ればせに向けた。
「あんな所で、にーちゃんの気配がわかったの? アシュリンのねーちゃん」
「ううん。あたしあんまり、気配探知は得意じゃないし……何となく、才蔵に近い鳥達が、あの屋敷の周囲に沢山いた気がしただけ」
「――そんなのわかるのか? 才蔵以外は基本、ただの鳥だぞ?」
少年と同様、彼は幼馴染みのその目敏さに、改めて驚きを隠せなかった。
「鳥を集められるくらいなら、タツクも自力で脱出してるはずだし……」
「そうだね。だから自発的に、タツクを心配して集まったんじゃないかな」
何でもないことのように笑いながら、幼馴染みはその、大きな疑問を改めて提示した。
「あの屋敷、おかしいよね。中の気配が漏れないようになってる感じだけど、人間の町でどうやってそんなこと、できるんだろ?」
「…………」
紫苑の少年がそこで黙り、ぐいっと飲み物を口にする。
彼も言うことがない中、空色の流人の彼女が話に入ってきた。
「誰か千族さんが協力してるとか、そういう可能性はないかな?」
「それが一番ありそうだよね……でも、タツクみたく実力のある奴を誘拐や、懐柔できるほど強い奴がいるとしたら、相当やばいと思うけど……」
怖々と話す幼馴染みに、彼も大きな不安を覚えた。
「それなら……かなり危険な場所かもしれないな、シャル自体が」
千族狩りのディアルスに気を付けろ。そう聞いていた彼らだが、そこに繋がる脅威が、まさか最寄りの人間都市に潜むとは考えたこともなかった。
「タツクのレベルの千族が他にも捕まえられてる可能性があるなら――下手に踏み入れば、何が起こるかわからない」
彼らが巻き込まれた事態は、思っているより深刻そうだ、と現実を実感し始めた彼の重い声だった。
ずしん、とした場の空気を、打ち破ったのは再び口を開いた少年だった。
「何てーかさ。ねーちゃん達ならともかく、捕まったのがあのにーちゃんって、イマイチ助けに行くぞ! ってやる気が出ないよね」
「それは言わないお約束。というかあたし達が捕まったらラスト君は助けてくれるの?」
「とーぜん! アシュリンのねーちゃんはまず、捕まらないだろーけどね」
「わあ、頼もしいな。ラスト君頼りになりそうだよね、ねぇアシュリン?」
にわかに女性陣の注目を惹いて嬉しげな少年に、取り残された彼は、オイオイ……と、何気なく机の下の大猫を見つめる。
「……」
大猫の雰囲気は、和やかな場よりずっと緊迫している。その本体である幼馴染みは、見かけより不安なのだろう、と彼は納得する。
そもそも荒事からは逃げ回る幼馴染みが、当然のようにこの場にいること。
紫苑の少年から悪友のことを聞き、危機管理も旅に出る本来の目的も置いて、幼馴染みはここにいる。おそらく強く――人間の屋敷から出て来ない悪友を心配して。
とりあえず。とそこで、紫苑の少年が現状の打開策を何故か提案した。
「オレと後一人くらい、あの屋敷に侵入してみる気、ある?」
「って……オマエ、情報提供だけじゃないのか?」
幼馴染みはともかく、少年に悪友を助ける大きな理由はないだろう。それでもわざわざ事に関わる少年に、彼は少し眉をひそめる。
少年は僅かに不機嫌そうに、彼を上目使いで睨むように返す。
「あの屋敷のことは、オレも探ってたって言ったろ? 一応無関係じゃないってこと」
それに幼馴染みは顔を暗くし、最早満面の不安を隠さなかった。
「でも――……タツクが逃げられないような所、危なくない、ラスト君?」
その目敏さが訴える、本能的な危機感。緊張した顔付きで少年をじっと見つめて尋ねた。
今度は空色の彼女が、おっとりと穿った作戦を提案する。
「もしも『千族狩り』なら、これからディアルスに運ばれるよね? それを待って、屋敷から移動させられる所を狙うとかはどうかな?」
しかしそれは、彼らには難しい相談だった。
「いや……あまりゆっくりはしていられないんだ」
なるべく一カ月程度で里に帰るように、彼と悪友は言われている。それが過ぎれば、何があったか少なくとも報告はしないといけない。
「タツクもどんな目に合うかわからないし。それなら……」
そして彼は、紫苑の少年をまっすぐに見た。
「オマエが協力してくれるなら、俺とオマエで、その都市長の屋敷に行ってみないか」
少年の提案には自分が乗る、と彼にとっては当然の結論をそこで告げる。
紫苑の少年は、何故かちらりと幼馴染みを見た後、改めて彼を見返してきた。
「オレは別にそれでいーけど。ねーちゃん達は……それでもいいの?」
「……」
「……」
この時の少年の問いの理由を、彼は後々、痛いほど知ることになる。
「アフィとアシューは、俺達が捕まった時は、アフィが言った方法でできれば助けてくれ。無理そうなら里に帰ってくれ、それだけだ」
「……うわぁ。さりげなくキラーパスするね、レイアスってば」
幼馴染みはたはは、と苦笑い、空色の彼女は珍しく無表情に沈黙している。
心配げな彼女達に、大丈夫、と少年は不敵な笑顔を向けた。
「オレがついてて、負け戦なんてさせる気はないよ」
本当に、既に緊張している彼より余程頼りになりそうな、紫苑の少年であるのだった。
上8:混色の屋敷
紫苑の少年、何でも屋の頼りがいは、長い両極の大鎌を自在に操れる戦闘能力ではない。
そうした武器や道具を自作し、様々にアレンジして扱えることだ、と、少年はシャル都市長の屋敷に続く夕暮れの林道で彼に説明した。
「色んな情報を集めておくのも、どんな道具が必要そうか、使える道具をどう生かすかの前哨戦ってわけさ」
「……何でも屋っていうのは、とりあえず凄いんだな」
彼が一番驚いたことには。港町で彼を不審者扱いさせた大きな要因、背負う長剣と大切な道具袋を、少年が何と――片手で持てる牙型のキーホルダーと、少年の腰にあるような、一見小さな皮袋に、その場で擬態させてくれたことだった。
「携帯型にした物は、気を与えれば元に戻るし、与えた気を抜けばまた小さくなるから」
千族としての少年の特技が、物に直接介入できる「力」を扱うことだという。それは、無機物ならば本質からいじれてしまう――携帯型に擬態できるような異業のようだった。
ということは……と。
彼は、悪友を探して人間の屋敷に乗り込む前に、どうしても少年に相談しておきたいことができてしまった。
「オマエ……何でも造れる何でも屋なら、俺に右腕を造ってくれないか?」
彼らを妖精から隠した結界道具や、少年が使う大鎌を見ると、それも可能だと思わせるほどの完成度がそこにはある。
紫苑の少年は、ふえ? と首を傾げながら、彼の右手が義手であることに、そこでようやく気が付いた様子だった。
「別にそれは――時間かかるけど、できないことはないけど」
しかし何故か、それまでの得意そうな様子から、少年の空気が一転する。立ち止まって彼の右手を検分しながら、不意に憂い気な顔付きで、少年が彼を見上げた。
「兄ちゃんは……その腕で、誰も殺さないと約束できる?」
「――何だって?」
紫苑の少年は、これまでの軽さが嘘のような目で、それを真剣に彼に尋ねる。
「そもそもオレ、武器屋じゃねーから。殺さないって約束できる奴か、余程守りたい相手じゃなきゃ、武器は――武器になるものは、オレは造らない」
言い切った少年の真摯さは彼にはとても意外で……そして何故か、ふっと胸が温かくなる、幼い少年の一面だった。
「……意外と言うか……物凄くイイ奴なんだな、オマエ」
「意味わかんねー! 何で嬉しそうなんだよ、キモチわりー!」
彼の右手を引っこ抜く勢いでぎゅううと掴み、少年はぼふっと赤い顔で彼を見上げる。その姿に彼は、不思議なほどに心が安らぐ。
そのまま穏やかな苦笑――彼には珍しいくだけた表情で、少年の問いかけに答を伝えた。
「できれば殺したくはないが……有り得ないとは、正直言えない」
「……それならオレはダメ。悪いけど他を当たってよ」
少年もそれはわかっていたのか、申し訳なさそうな声色ではっきり返答する。
「力」あるものなら、誰もが抱えるその可能性。何らかの争いに巻き込まれ易いだけでなく、幼い頃の彼のように、自らの「力」に呑まれる危険性……そうした現実を考えれば、彼の返事は誠実だろう。
「じゃあせめて、今の手がもう少しだけちゃんと動くように調整できないか?」
「うーん。でもこれ、兄ちゃんが言うほどには壊れてないけどな?」
彼の成長に合わせる仕様であることで、確かに強度は落ちて傷むだろう、とぺたぺたと義手を触りながら言う。しかし上手く動かないのはおかしい、と不可解そうにする。
そして、ぽつりと――
「……これ……――の仕事だ……」
その単純な造りと、精密さを併せ持った便利な義手に、少年は更に表情を暗くしていた。
「――?」
その後少年が喋らないので、とりあえず手を離して歩みを再開する。
「この紋様だけでも消す、というかアフィに返したいんだが、それも無理そうか?」
先日義手に刻まれてしまった青黒い蛇について、彼は最後の質問をする。
そこで顔を上げた少年の返事は、驚くほど早く、そして怪訝そうだった。
「多分無理。オレもこんなの初めて見たけど、いったい何処でこんな呪い受けたのさ?」
「――へ?」
「よくわかんねーけど、怨念とかそういう類の気配だよ、コレ。悪い夢とか見てない?」
「……――……」
そう言われれば、最近の夢見の悪さは覚えがあったものの。それならもう少し前から、昨夜のような悪夢を見てもおかしくないように彼は思った。
「これはアフィを守るものみたいだし――悪い感じはしないけどな?」
むしろ、とばかり平然と言う彼に、納得いかなさげに首を傾げる、多感な少年だった。
都市長の屋敷の裏側につき、林に面した塀を見上げる。隣の少年が不意に、外套を脱いで地面に敷き、その上に粉薬らしき包みをいくつも広げ出した。
「一応人除けの結界はしてるけど、万一誰か来たら、にーちゃんが気絶させてね」
「……オマエはこれから何をするんだ?」
「この屋敷の結界除けを造んの。思ったより凄く高度な結界を張ってるや……侵入したらそれだけで、操り人形にされかねないくらい」
え……。絶句する彼に、少年も座ってゴーグルを装着し、塀越しに屋敷をじいっと見上げ――難しい顔をして悪態をつき始めた。
「意味わかんねー。何この構成バカじゃねーの? どーやったらこんな無秩序になんだよ」
そのくせ秩序だって機能してんじゃねー! などと少年が、両手で頭を抱える。
「…………」
彼は何気なく、その……彼に視えていた単純な光景を、思わず口にしていた。
「ここを包む『力』なら、この粉とこっちの粉の色が近いと思うぞ」
「え?」
「多分だが、純度の高い『水』と色々混ざる『水源』が交互に折り重なってる。どっちも水だからややこしく感じるかもしれないが、用途別に分けられていそうな――」
ええええ!? と、そこで少年が上げた大声に、彼の言葉の続きは封じ込まれていた。
「この結界――視えてんの!? にーちゃん!」
「……オマエもそのメガネで、視えてるんだろ?」
「これはオレが感じた気配を視覚化してるだけ! それだってオレのレベルの気配探知ができてやっとなの! にーちゃんめちゃくちゃ、気配とか鈍そうじゃん!」
オレが横に寝ても気付かなかったし! と、彼に言われた薬包を取りながらも、少年はまだ半信半疑そうだった。
「直接危なくないものの色は、気にしないクセがついてるんだ。里だって結界だらけだし、それにこの色……オマエの結界にちょっと似てるぞ?」
彼のその言葉に、ぴたりと――不意をつかれたように少年が黙ってしまった。
「オマエの結界の方がずっと自然だし、オマエが何か造ってくれるなら、見つからないでいけるんじゃないか」
彼としては、それを言いたかっただけなのだが……。
その後少年は、黙々と粉同士の調合を始め、顔付きは一言で表せば不快そのものだった。
「……?」
彼は少年が言った通り、見張りに徹する。辺りが夜に包まれる中、少年の作業を見守ることしかできなかった。
やがて少年は、ゴーグルを着けたまま、彼と自身にその場で造った粉薬を振りかけた。
「やばくなったらお互い、自分を優先して自力で逃げることだよ」
「…………」
彼には不服な約束を口にする。その直後、塀を飛び越え、彼らは侵入を果たしていた。
裏庭らしき場所に着地した途端、彼に走った感情は、戦慄と言っても良かった。
「何だここ――化け物の気配だらけじゃないか」
「ホントだね。都市長は完全に人間なのに……」
「タツクもいるな……アイツ、ピンピンしてるのに何で出てこないんだ?」
身を低くして近付く屋内からは、慣れ親しんだ強い気配がありありと届く。結界の内ではそれは全く、隠されていないようだった。
「とりあえずにーちゃんのいる所に行こう。話はそれからだ」
何がそれからなのか、この時には彼は、少年の様子のおかしさに気付けなかった。
侵入した彼らが気付かれず、少年の結界除けが見事に機能しているはずの中で、未だにゴーグルを外さない少年には違和感を持ち始めていた。
しかしその感じに言及する暇もなく――その想定外の事態は訪れてしまう。
「……――って、何だ……!?」
「これは――まさか、オレ達以外にも侵入者!?」
突然屋敷中にけたたましい警報が鳴り響く。彼らのいる裏口ではなく、正門に近い方で、結界の色が黒く変色したように彼には見えた。
しかもその方向には、まさに……――
「何やってんだ、アシュー……!?」
「ってコレ、やっぱりねーちゃんの気配かよ!?」
少年もすっかり、ゴーグルの下でもわかるほどの大きな鋭い目を丸くする。
「何か嫌な予感はしたんだよオレ! あのねーちゃんが黙って待ってるはずないって!」
残留待機と決まった女性陣に、それで良いのか、ときいた少年の懸念を彼はやっと悟る。
ひとまず建物の内に何とか入りつつ、彼と少年は並んで頭を悩ませることとなった。
「多分、囮になるつもりなんだよ。危ない時は自分一人なら、いつでも逃げれるって前に言ってたし」
「それは確かだが、だからってこんな派手に――敵地に乗り込んだりするか、あいつ!?」
「にーちゃんはねーちゃんのこと、どんな風に見てるのさ?」
どんなって……と、彼は咄嗟に、その霊獣が見つけた幼馴染みの様子を探る。気配を探知した時点でその居場所へ向かわせた、透明な飛び犬が見る光景に集中力をずらす。
結界に引っかかるのを承知で、大きな木の上から屋敷に飛び込んだ幼馴染みは、入った途端に自身を襲った結界の力に、慌てながら物陰に身を隠していた。
「うわ、これやば、やっぱりアフィちゃん置いてきて正解だ……!」
どうやら逃亡用の安全地帯に、自身の大猫と空色の流人の彼女を待たせているらしい。彼女にはその場所の安全確保を、と言い含めでもしたのだろう。
「どうしよどうしよー! このぐらいじゃ洗脳なんてないけど、こんな結界張ってる所、ヤバ過ぎるって……!」
心底焦り、きょろきょろ周囲を窺う姿は、弱い侵入者なら骨抜きにする結界に侵されることもなさそうだ。
そのわりには、ただひたすらに……どの程度その場で頑張り、騒ぎを起こすか、逃げるタイミングを悩むばかりの小心な侵入者だった。
「……それなら来るな、バカ」
ずしんとする頭を抱え、俯きながら彼は視界を本体に戻す。最後の光景は、彼の飛び犬に幼馴染みが気付き、応援に安堵しつつ、ごめーん、と泣き笑いで謝る姿だった。
しかし少年は、彼の率直な感想に眉をひそめる。
「それだけ怖くても、来ずにいられないヒトなんだよ、ねーちゃんって」
少し前に、共に山賊と一悶着あったという少年と幼馴染み。その関わりを示すように、少年は苦い声色で……ともすれば、彼らより幼馴染みの内面を感じているようだ。足音を潜めて階段を昇りながら、背中越しに口にしていた。
「タツクが心配なのはわかるが……それなら初めから俺達と来ればいいだろ?」
もしくはせめて、事前に相談しておいてほしい、と彼はぶつくさ呟く。
「来るって言ったら、にーちゃんは連れて来てた?」
振り返りもせず淡々と言う少年に、ぐうと言葉を詰まらせて、そして納得した。
「……そうだな。だからあいつは、言わないで来たのか」
「オレの時もそうだよ。オレ一人で大丈夫って言ったのに、結局後をつけてきて……おかげでオレ、殺されずに済んだんだけど」
「……?」
「まさかあの時、ずっとガクガクしてたねーちゃんがくるとは思わなかった。あのさ……アシュリンのねーちゃんって、キレると別人にならない?」
不意に立ち止り、振り返って彼を見ながら、少年は何処か痛ましげに尋ねた。
「人質をとられたとはいえ、オレを殺せそうだった奴、ねーちゃんはその時……無表情にたった一撃で、ノックアウトしちゃったんだよ」
「…………」
黙り込む彼の視界には、逃げ回りながらまだ撤退しない幼馴染みの光景が届く。
「後できいたら、頭が真っ白になってたって言うけどさ。それまで凄い冷たい顔してて、オレも鳥肌たつくらいだったよ」
「……――」
少年の言は、彼には少しだけ――
彼に視える幼馴染みの「力」と、「水」の竜をも喰らった黒狼に思い当たる節があった。
「そうだな……アシューの奴、普段は白っぽい空気なのに、いつも何処かに黒い影がついてて……黒の方は底無しみたいな所はあるな」
一人の者が複数の色を持つこと自体は、そう有り得ない状態でもない。
しかし幼馴染みのように、はっきり白黒と分かれているのは、珍しいタイプではあった。
「戦わせたら強いのに、逃げ回ってるらしいし……俺も正直、あいつはよくわからない」
今も幼馴染みは、出会う警備者全てに、ひいいと出会った瞬間に愛用武器の棍を脳天に命中させ、姿も見られずに逃げ回っている。
全力で怯えてのことだが、結果だけ見れば一方的に殴られた気絶者の山と性質が悪い。
人間と千族と、対立せずに正体を隠したままで……一番難しい立回りをしているのは、幼馴染みかもしれない。
しかしいつまでも事がそう上手くいくと思えない彼は、少年と共に、悪友の気配がする上階を足早に目指す。
ここまで彼らが近付いていても悪友は気付かないのか、動く気配を全く見せなかった。
「さすがに鈍過ぎないか、アイツ……」
ついに間近、悪友の気配がしている一室の扉が見える位置に辿り着く。
赤い絨毯の敷かれる廊下と、高価そうな扉がいくつもある階で、窓際に対称的に並ぶ大理石の彫刻の陰に隠れる。少年と共に、部屋と周囲の様子をしばらく窺う。
「にーちゃんの霊獣を戻して、タツクのにーちゃんの方にやれない?」
当然ながら、悪友が自ら出て来てくれる方がトラブルは少ない。誰かを監禁するような部屋には見えず、山奥では見たこともない優雅な一帯は、彼にはかなり意外な展開だった。
「いや、アシューが心配だ。何かあれば俺は消えられるし、オマエはここで待っててくれ。俺があの部屋に入る」
彼も幼馴染みも、別の場所にいる霊獣の元に一瞬で行くことができる。
それを聞いていた少年は黙って頷き、見つかる覚悟の彼を見送り……。
鍵も開いていた部屋に突入した彼が、そこで見たのは――凄まじい光景だった。
……頭が真っ白になるとは、こういうことを言うのだろうか。
荒事は当然、悪友が帰らなかった時から覚悟していた。
人間の町で流血沙汰を起こし、たとえ追われる身になったとしても、必要なら戦いも辞さないつもりだった。
「うあああ、やめてぇぇー! ごめんなさいまじ本当! 勘弁して下さいってぇぇ!」
「何故なのですか……!? 何故この期に及んでアナタという人は、わたくしに真の姿を見せては下さらないのですか……!!」
……はい? と。ばたんと開け放った扉の内で、絶句して石化した彼をよそに……その客間と見れる、広いベッドと柔らかそうな長いソファが置かれた部屋の端に悪友はいた。
それも、高そうな礼服を着ている男の前に。肩までの褐色の髪を伸ばした若い男に壁に押し付けられて、悪友が大慌てをしている。
警報の鳴る外界の喧騒は無縁とばかり、今まさに彼の悪友と――何と唇を重ねられるほど、間近に顔を迫らせた若い男の後ろ姿が、彼の視界に最初に飛び込んできた。
「わたくしのものになってください! どうか……!」
「って、わ、やぁぁめてぇぇぇ……! おれにそういう趣味はないねんー!!」
ギリギリの距離まで悪友も理性を保ち、余所行きの口調で対応を続けていたようだが、ついに仮面を脱ぎ捨てて訛り付きの悲鳴を上げる。それに男は寸前で接触を止め、潤んだ焦茶の両目で悪友を愛しそうにそのまま見つめた。
「ああ……それです、そのお言葉です……我が初恋の君を偲ばせるのです……」
一見は高貴で真面目そうな、中肉中背で中性的な顔立ちの人間の男が、そこにはいた。
その後は黙って、放心状態の悪友と見つめ合っている人間の男だった。
「……あの。すみませんがそれ……俺の連れなんですが」
これでは悪友が自分に気付かないのも無理はない。妙に納得して彼はやっと声をかけた。
人間の男は、不法侵入者である彼に、不思議そうに硬い顔付きで振り返った。
「……この方が……貴男の連れですと?」
「――あ、はい。全然帰らないんで、探していたらここに来ました」
彼もこの場の衝撃に、上手い反応は全く思い付けず、ありのままを口にするしかない。
「何ということだ……アナタは既に……あの男の連れ合いなのですか……!」
ぐぐぐ、と男は両手を握り締め、ある誤解に彼はひやりと気が付く。ひええ、と悪友も、その隙にするりと逃げ出す。
「いやちょっと、俺はそんな――」
「このわたくし、ディーズ・シャル・ウェイリットの手中まで助けに来るほど! 貴男方は愛し合っているというのか!!」
のおおお! と言わんばかりに男は片手を額に当て、苦悩を示すよう上半身を海老反りにした直後に、床に四肢をついて嘆き始めた。
「うああああん! 助けてくれえ、レイアスー!!」
何だそれ、気持ち悪過ぎる……。現実逃避するように呆けていた彼の背中に、男から解放された悪友が涙ながらにしがみつく状態だった。
まだ苦悩を続けている男を前に、彼は逃走するという最低限の優先事項すら忘れていた。
「何があったんだ……タツク」
「それがなそれがな、話すと長いねんて! シャル案内所にどうぞゆー女の子のお勧めで馬車に乗ったらここに来て、壺買わへんか言われて断ったら何でか壺割れて、弁償するかカラダで払えってコイツが言うからずっと話し合いしとってんー!!」
動揺しながら的確に経緯を説明する悪友に、無事の安堵も湧き上がってきたが。
「それ……何か色々騙されてないか?」
要するに、体よく人間に嵌められたらしい悪友を、思い切りはたき倒したい衝動に一瞬かられた彼だった。
「だってだってだってぇぇ! 人間と揉め事、起こしたらあかんって思うやんけー!!」
うわあああ、と、色々な意味で恐ろしかったらしい悪友が喚く。
「そんなオマエのために、アシューはこの外で人間を撲りまくってるが……」
まだ警報の鳴り止まない窓の外を遠目に見ながら、それだけやっと呟き返すと……。
「――何やって!? アシューがここに来とるんか!?」
ぴたりと悪友が、瞬時に冷静さを取り戻したように、焦る顔付きで彼の外套を掴む。
同時に彼らの目の前でも、苦悩に堕ちていた人間の男が、気を取り直して立ち上がったところだった。
人間の男はそうして、改めて悪友と、侵入者である彼をまじまじと見つめた。
「……ミスティルは何をしているのだ。こんな異物に……ここまで侵入を許すなどと」
とてつもなく不愉快な様子で、本来あるべき反応を、嫌悪を載せた声と目線で表す。
「……!」
彼が咄嗟にひこうとすると、背後でばたんと、扉が閉まった。退路を断たれた彼らに、男は改めて近付いてこようとした。
そして、彼と悪友が並んで体勢を立て直し、男と向かい合おうとしたその瞬間に――
「……そいつは何処にいるんだよ? ――答えろ、そこのオマエ」
扉を閉めたのは、男の関係者ではなかった。廊下で部屋の様子を窺っていたはずの者の声が、彼らを盾に隠れて侵入した直後に不意に響き渡る。
「……!?」
特に何の力も感じられない弱い人間の男に、その紫苑の少年は――
殺気だけを浮かべた氷のような目で、両端に刃のある大きな鎌を、男の背後から喉元へ赤い糸をひく強さで突き付けていた。
突然の脅迫者の出現に、驚いたのは人間の男だけではなかった。
「――ラスト!?」
「ってオマエ――こないだのラっ君やんけ!?」
なるべく荒事は避けたかった彼らの前で、人間に容赦なく刃物を突き付ける少年。その剣幕に、咄嗟に二人して息を呑む。
紫苑の少年は、彼らを一目見ることすらもない。別人のような冷たく重い声で、彼らに離脱だけを指示した。
「にーちゃん達はさっさと行けよ!」
「……何だって?」
「オレはコイツに用があるんだ。にーちゃん達は帰すって約束したから……巻き込まれて死ぬ前に早く帰れ!」
「…………!!」
自分がついていて彼に負け戦はさせない、とここに乗り込む前に笑っていた少年。
しかし今は、暗いゴーグルの下では影しか宿さない目色で、最初からそのつもりだったように……自らだけがこの場に残ると、その無機質な変貌が彼には納得できなかった。
しかし少年のその気迫に、彼が反論できる前に――
「……!? アシュー……!?」
もう一つの彼の体、霊獣から確かにもたらされた、彼らの幼馴染みのある危機。
彼は歯噛みしながら、戸惑う悪友を引っ張って扉をぶち破るように開けた。
「――この借りは必ず返すぞ! ラスト!!」
少年を一人ここに置いていくことに、この上なく強い悔しさを感じながらも、振り切るように部屋から駆け出す。
思いもかけず、己が呪いと出会ってしまった幼馴染みの元へ……それとは知らず、ただ自らの分身が告げる悪寒に従ったまま、彼は場を離れたのだった。
上9:黒猫の娘
危うい状況に陥ったなら、安全地帯に置いた霊獣の元へ逃げ去ればいい。
臆病な幼馴染みは、いつも誰より、それを徹底していたはずなのだが……。
「――んニニニ? あなたいったい……何者なんですのニ?」
「……!?」
透明にして幼馴染みの傍につかせた、彼の霊獣の目が届ける異常な光景。
それまでずっと、見つかることに恐れ慄いていた弱気さからは考え難い姿。妙に冷静な、細い呼吸で立ち尽くす幼馴染みがいた。
この屋敷の者を引き付ける囮として、未だに幼馴染は踏ん張っていた。そこに並み居る警備者達を下がらせ、その異様な二人は現れていたのだが……。
「ミィの別荘を土足で荒らすなんて、とっても命知らずですのニ」
何が異様かと言えば、何処の訛りかわからない娘の口調だけでない。
口調に合った幼い声の主の、にこりと幼馴染みを見返す体は小さい。しかしぴったりと、肩から大腿まで体を縦に包む黒衣に桜色のショール、むき出しの両腕に連なる金属の腕輪、膝上まである黒いブーツという見た目は、あまり子供らしくなかった。
「でもあなた、にゃーんですのニ。ミィのお友達になるなら、許してあげるですのニ」
そして、猫を模したつもりらしい言葉遣い。同様に、大きな鈴付の首輪と黒い猫耳を、自身をミィと呼ぶその娘は着けていた。
「……意味がわからない」
珍しく険しい声で、それだけ呟いた幼馴染み。見ている謎の猫娘は、左側で一つに括る紫苑の長い髪と、耳を隠す長い横髪を軽く揺らし、ぱっちり大きな鋭い紫苑の目で、隣に立つ従者らしき女を見上げた。
「れんれん。あのヒトを捕まえてほしいですのニ」
「…………」
愛称で呼ばれた従者の女は、顔から胸まで隠す暗いベールの帽子を被っている。赤い胸当ての防具と、裾が広がる長袖の服で、古風な女魔道士の出で立ちだ。
「れんれん一人で難しかったら、きっきとひーりんを呼んでもいいですのニ。あのヒト、少なくともひーりんくらいには素早いですのニ」
その声に、小さく頷いた従者の女が、猫娘を守るように前に立つ。
正面から対峙した幼馴染みは、両端に霊光石を埋め込む長棍――霊気が力になる武器をまだ構えず、身を低くして相手を窺う。
小さく透明な彼の霊獣を肩に乗せながら、幼馴染みは、見たこともない真剣さを、本当は鋭く整う灰色の目にたたえていた。
「何……あの子……」
その緊迫――ここまで危なげな状況となっても、逃げずにそこにいる幼馴染みの理由。
「何で……ラスト君にそっくりなの……?」
先程まで目前に立っていた、紫苑の髪と目の幼い猫娘。その存在が、幼馴染みの目にはどうしても見逃せない姿をしているのだと、呻るように言う。
そう言われて初めて、霊獣を通す彼の眼にも、その二人の纏う色のおかしさがはっきり映った。
――この色……オマエの結界にちょっと似てるぞ?
屋敷を包む高度な結界、その主はどうやら、結界と同じ色を発するそこの猫娘と従者の女だった。
それは紫苑の少年の「力」とほとんど同じ色で、よくよく見れば猫娘と紫苑の少年は顔立ちも全く同じで、気が付かなかったことが不思議なくらいだった。
「まさか……ラスト君は……――」
それでも目敏い幼馴染みは、その違和感も見逃さなかったのだ。
様々な疑惑と衝撃を消化する時間は、与えられるわけもなかった。
「――!」
咄嗟に飛びのいた幼馴染みがいた地面に、重りと杭のついた投網が襲い掛かる。
従者の女は沈黙したまま、何かの魔道を構成せんと両手で印を組んでいた。
「――させるわけないでしょ!」
険しい顔を引きずる幼馴染みは、逃げるどころかそのまま棍を振り上げ、従者の女が攻撃に移る前に殴りかかる。肩から振り落とされた彼にも驚きの攻撃性を発揮している。
「……!?」
さすがに顔は避け、袈裟がけに胸部を強打せんとする。ところがその一撃は……。
「な――何……?」
まるで従者の女を包む透明な壁にめり込んだかのように、女の直前で幼馴染みの握る棍はぴたりと止まり、そこから全く動かなくなってしまった。
「え――……ちょっと……!?」
「……?」
それは従者の女にも、少し意外な展開であるらしい。ベールの前で宙に留まる長棍に顔を向け、不思議そうに首を傾げる。
――……!?
彼も空中で幼馴染みの後ろ姿を見ながら、次の瞬間……ある呪いを目にすることとなる。
そのベールの下には、従者の女のひらひらとした姿で、唯一硬さを持った赤い胸当てがある。だから幼馴染みも、重傷を避けてそこを狙ったのだろう。
しかし、幼馴染みの「気」が載せられて強化された棍は、その胸当てに填まる、漆黒の珠玉の直前で……珠玉から沸き起こる黒い煙に、絡め取られたように止められていた。
――あれは……!?
その頃彼の本体は、屋敷内の警備者を悪友と共に峰打ちしながら、幼馴染みのいる所へ向かっていたのだが――思わず本体の動きを止めて、霊獣の感覚に集中してしまうほど、彼にはそれが嫌な光景に視えた。
幼馴染みの動きを止めた、謎の珠玉。そこから溢れる黒は、あまりに忌わしく――
――あれに――捕まるな、アシュー……!
黒い珠玉からさらに溢れる黒い影は、棍を伝って幼馴染みへ触手を伸ばすように迫る。
「――」
ぴくりとも動かない自身の武器に、意識の時間まで止められたように、幼馴染みは呆然としていたが。
「にゃあ……あなた、まさか……」
その状況を見て、再び口を開いた猫娘の声に、はっとしたように我を取り戻していた。
「……!」
しかし次の瞬間、先刻に幼馴染みを狙って放たれたものと同仕様の投網が、今度こそ、とばかりその立ち尽くす場所に躍りかかる。
ぐるぐると金網に絡まれ、倒れ込むように幼馴染みは体勢を崩した。
「にゃーん♪ やったですのニ!」
地面に落ちた網の塊に、従者の女の後ろから猫娘が嬉しげにぴょこんと顔を出す。そうして、獲物の元へと駆け寄ってきたが。
「え……何処行ったんですのニ……!?」
しかしそこには、確かに絡め取られたはずの白灰の髪の侵入者は跡形もなかった。
「くそ……ヒヤヒヤさせるなよ……」
自身の霊獣の元へ、辛うじて逃げただろう幼馴染み。危うく悪友を置いて、霊獣の元に転位寸前だった彼は、それだけ呟いて自らの戦線に戻った。
捕えようとした幼馴染みが消えた後の場では、彼の霊獣がいることに気が付かない猫娘達の、にわか会合が始まっていた。
「こんな事態は初めてですのニ。かなり稀少な上級千族の出現と見ていいですのニ」
そこには従者の女だけでなく、物陰から幼馴染みを投網で狙った他の者も現れてきた。
「ミスティル様、お怪我はないですか?」
一人はふわりと、翡翠の色の髪を肩まで下ろした、猫娘と同年代の忍装束の少女だ。
「ちょっとォ、何がしたかったのさ、あの侵入者ぁさ」
もう一人も同じ忍装束だ。年は少し上と見えて、肩までの薄柿色の髪を頭の上で小さく二つ結ぶ強気そうな少女だった。
忍とは主に東の大陸で、素性を隠して護衛などの仕事を請け負う千族集団らしいが、この二人は顔も隠さず、人目を惹きそうな髪の色が宵闇の中で印象的だった。
総計四人の娘達は、従者の女は一言も喋らず、忍装束の二人と一番幼げな猫娘が主体で相談を続ける。
「何か屋敷の内部にも侵入者があったみたいだよ。そっちに来いって煩く呼ばれてら」
「えええ? そんなの全く、ミィもれんれんも感知してませんのニ」
「私、ここに残って輸送便の手配を始めますから。姉様はどうぞそちらに」
にこにこと、翡翠の髪の少女が自身の赤い小手を触りながら言う。姉様と呼ばれた方は少し不服気にした。
「でもあんた、さっき体調悪そうだったじゃん」
「大丈夫です、一瞬だけでした。よくわからないけど、今はもう腕も軽やかです」
ぺたぺたと、赤い小手の上から心配げに腕を触る薄柿色の髪の少女に、翡翠の髪の少女はただにこりと微笑む。
「ひーりんまで影響を受けたんですのニ? ……ますます怪しいですのニ」
その姿に猫娘は、何かを考え込むように、それきり黙ってしまった。
外にさえ出てしまえば、空を使える彼も悪友も脱出経路に不自由はしない。
いつまで紫苑の少年の結界が持つかもわからないので、彼の霊獣も四人組を後にすると、屋敷外で具現された悪友の霊獣と合流し、場を遠く後にするように飛んだ。
「あ、アシューとアフィがおったで。あまり屋敷から離れとらんけど、合流しとった方がええよな」
「そうだな。ラストのことも気になるし、出方を考えよう」
彼らの本体は屋敷裏で気配を潜めて隠れ、霊獣の感覚から転位先を探して待機していた。
行き先を決めると、そこで静かに目を閉じた彼と悪友、どちらの姿も唐突に――さも、夜に熔け込むように消えていく。
「――あ。レイアス、タツク……!」
次に彼が目を開けた時には、何処かの建物の陰でぺたんと座り込む幼馴染みに、横からぎゅううと抱き着く空色の彼女の姿が、真っ先に飛び込んできた。
「良かったあ、みんな無事だね、本当に良かった……!!」
「あはは……あーやば、まだ震え止まらないや……」
幼馴染みも彼と悪友の姿に安堵している。この場に逃げ帰ってから腰を抜かした様子で、猫娘達に対峙していた時のキレ具合は何処吹く風だった。
なので彼は真っ先に、それを口にせずにはいられなかった。
「――何でお前まで来たんだ、アシュー」
今回は一応事無きを得たものの……猫娘の所を離れる直前に、彼が最後に聞いたのは、嫌な予感しか残さない猫娘の言葉だった。
――これは……さっきのことは、あの方にご報告しておくべきですのニ。
幼馴染みもおそらく姿を覚えられている。その危機感は本人が一番解っているだろう。
彼の懸念を知るように、まだ立ち上がれない幼馴染みは、彼と悪友を見上げて苦笑う。
「だってさー。あたしが行かないと、アフィちゃんが乗り込むって言ってきかなくって」
「ウソ、違うよ、一緒に行こうって話してたんだよ。でもわたしはここで、アシュリンのバステトを守る留守番役になっちゃって……」
オイオイ、と、彼と悪友は黙って顔を見合わせる。
「どっちもあかんわ! 悪いんはおれやけど、頼むからそんな無茶はせんでくれ」
悪友がどさっと勢い良く、幼馴染み達に向かい合って座る。彼も建物にもたれるように腰を下ろし、大きく溜め息をついた。
「タツクが一言、無事って連絡をくれりゃ、そこまでしなくても良かったけどな」
「そうしたいんは山々やったけどな……あの屋敷、何かおかしいんや。中に入ってからは霊獣も出せんし、外の気配もわからんし」
「……俺は霊獣、使えたけど?」
「オマエはラストの張ってくれた結界があったんやろ? 多分そのおかげとちゃうか」
なるほど、と、それでやはり偵察の飛び犬も、最後まで見つからなかったのかと頷く。
「残ったラストは……あれからどうなったんだ……」
苦い思いでそう言った彼に、空色の彼女の腕からやっと解放された幼馴染みが、ばっと彼の方に向き直った。
「えええ!? ラスト君残してきたの、レイアス!?」
「アシューがあいつらに襲われたからな。あいつら、何か嫌な感じだったろ」
「ってあたしのせいか……! うわあ……レイアスの言う通りだけど、あの子達何か……凄く嫌な感じがして放っておけなくて」
暗い物陰で集まって座る一行は、事情がわからず首を傾げる彼女と悪友に、彼が改めて状況を説明する。
「――というわけで。ラストにそっくりな女の子が、あの屋敷の結界を造って……今からディアルスに向けて、タツクみたいに捕えた千族を送る輸送用の馬車を出すみたいなんだ」
あれから翡翠の髪の少女が従者の女とその段取りを話し、場に残っていた霊獣が聞いた内容。現時点では最も差し迫った情報がそれだった。
「その馬車にラストも乗せられるのかは……全然わからない」
紫苑の少年があの後、逃げられたのかどうか。しかし、少年にそっくりな猫娘の存在と、その屋敷に用があると言っていた姿を思い出すと、事が簡単に済んだとは思えなかった。
「でもあの男――タツクに迫ってた奴は、ラストがあの子とそっくりだとは、俺と同じで気付いてなかったはずだけど」
「うわ、思い出させんなや、キモチ悪い!」
そこで悪友は、ちなみにアレ、この町の現都市長みたいやねん。と、彼らを閉口させる新事実をトホホと続けるのだった。
その都市長におそらく協力している猫娘と、都市長に刃物を突き付けた少年が、同じ顔と気付かれないのはおかしな話でもあったが。
「それ多分……ラスト君のゴーグルの影響じゃないかな」
「へ?」
「あたしもしばらく気付かなかったけど、あれ着けてる時は、ラスト君の顔ってはっきり思い出せなくなるの。多分そういう魔法効果があるんじゃない?」
「そうなんだ……それならラスト君、自分でそう造ったのかな、あれ」
そう言われれば、屋敷に入る時から紫苑の少年はゴーグルを外さなくなった。自身の顔が、そこでは知られたものであるとわかっていた可能性が高かった。
ということは、と――
「ラスト君はきっと、最初からあの子を探すために、あの屋敷のことを探ってたんだよ」
幼馴染みが難しい顔で告げる推理に、この場で反論できる根拠を持つ者はいなかった。
「そこにたまたま、おれのことが重なったゆーわけか」
ふむふむ、と同郷の彼はともかく、何故少年が自分を連れ戻す手助けをしてくれたかが謎だったらしい悪友は、納得したように言葉を続けた。
「そんならどーする? ラっ君を助けよー思えば、ディアルス馬車についてってみるのが早いかもやな?」
あっけらかんと、あまりに当然の如くに、悪友がそれを言う。
「でもタツク……ディアルスは危ないって、わたしにも言ってたよね?」
そのため、空色の彼女も不思議そうに、場の疑問を代表して尋ねる。
そこでばしっと、胸の前で拳を手の平に打ち付けて、悪友は威勢良い顔付きで答えた。
「おれはかけられた恩義は絶対に忘れへん。アイツの目的が何であれ、おれらのこと助けてくれたんは変わらへんしな」
「……わー。タツクが珍しく、かっこいいこと言ってる」
「って、珍しーとか一言多いわ、アシュー!」
がーっと青筋をたてる悪友に、あははと笑い返す幼馴染み。しかしその手は地面の土をじりっと握り締めるように力が入り……悪友の提案は幼馴染みにとって、恐れ多いものであるのだろうと、彼はすぐに察していた。
そうして俄かに浮上した、「千族狩り」の国へ行こうという話だったが。
「わたしはナナハのことも気になるから、一緒に行きたいよ」
彼女はあっさり頷き、紫苑の少年が気になる彼も、異論はなかったのだが……。
「……アシューは怖ければ、無理はするな」
彼は静かに、彼らと幼馴染みが置かれた現状を考えて伝える。
「姿も見られてるし、本当ならお互い、里に隠れて大人しくしてた方がいいんだろうな」
「……」
図星をつかれたらしい幼馴染みが、無言で表情を消す。
彼の彩の無い眼を、同じ色の目で、何かを探すようにそこで見つめる。
――怖くても、来ずにいられないヒトなんだよ、ねーちゃんって。
その少年の台詞を裏付けるように、いつもの困った顔で、幼馴染みはたはは、と笑った。
「里でじっとしてるよりは……レイアス達と一緒に行くのも、たまにはいいかな」
「……――」
「――お?」
彼らにとって、幼馴染みのその一言は色んな意味があるとわかり、返って何も言えなくなる答だった。
「それじゃアシュリンも、一緒にディアルスに行くんだね」
素直に嬉しそうに、きゃっと幼馴染みの手をとる空色の彼女に、幼馴染みも笑う。
彼と悪友は複雑そうに、顔を見合わせることしかできなかった。
「まぁ別にアシューの一人や二人くらい、おれが本気出せば全然守れるし」
「あはは、誰かお尋ね者とかになったらすぐに逃げるよ。バステトも別行動させてるしね」
珍しく頑張った悪友の一言もひらりとかわす幼馴染みは、この数年はずっとそうだった。
正直なところ、真意がとても分かり難いのだ。
怖いなら来なければいい。霊獣で早くも、次の逃げ道を確保しているのはその証だろう。
「ラスト君のおかげで、バステトも目立たずに動けてるわけだし……」
紫苑の少年が造った首輪は、普通とは違う大猫の霊獣を隠してくれている。
彼や悪友とは違い、霊獣を霊体で動かすことの方が手間である幼馴染みに、それがとても助かる事柄であるのは彼にもわかった。
その紫苑の少年が気になるのか。それとも言葉通り、彼らと行動を共にしたいのか。
もしくはただ――里にあまり、帰りたくないのか。
きっと全てなのだろう。目前の光景、ディアルス行きの千族馬車を探して霊獣を飛ばす悪友や、空色の彼女と当座の相談を始めた幼馴染みを見て、彼は一人嘆息していた。
一軍と二軍の村の闇。それにずっと、単独で曝されてきたはずの相手の姿に。
「おれも親父から、つい最近聞いたんやけど……」
「――はぁ?」
シャルの港町の夜、悪友がそれを話し出した時、うっかり彼は呆けていたが。
「うちの里には――あまりエースが里をあけへん方がいい闇が存在すんねん」
悪友は本当に懊悩する目で、その概要を彼に伝えた。
「おれらの世代って、一軍は少ないやろ? おれとオマエと、後はまだ『実体化』ができへん同期が数人おるだけで」
「本来ならアシューも一軍だけどな。親父達に比べると、大分少ないらしいな」
霊獣族の化け物達は、「実体化」が完全に制御できるようになった時点で成熟と認められ、外界に出ることが許される。
一軍、二軍と村を分けるのは、生まれ持った霊獣の「力」があまりに違う相手と鍛錬を共にすると、危険だろうという現実的な事情だった。
「でもな。その区別をやめろて流れが出てるらしいねん、二軍村で」
彼らの素質は、具現された獣で判断される。
彼のように、普通には存在しない獣か。悪友のように普通より数多く使役できる獣か。もしくは幼馴染みの獣のように巨体など、普通でないものが一軍とされるわけだが――
「親父の世代が一軍も二軍も、早死にした奴が多いんもあるけど。素質の差を見てんと、ぴんと来ん連中に不満が溜まっとるらしい。一軍村だけ特別扱いとか、何か特殊な訓練受けてるんとちゃうか、とかな」
「……違うものはどうしようもないだろ?」
ぽかん、とする彼は、素質故に苦しんだ幼少期だった。もし二軍の者が同じ場で修行していれば、巻き込んで殺した可能性もある、と自然にその区別を受け入れていたのだ。
「それがわからんくらい、多分平和ボケしとんのもあるな」
特に大きな動乱も無く、人間に混ざって千族は減る一方の時代に、悪友は軽く息をつく。
「セレンにきーたら、単にみんな、おれやオマエと一緒に修行したいだけやって言うけど。わざわざ分けんのは差別ちゃうか、ってな」
言ってみれば一軍の彼らは憧れの対象で、嫉妬や羨望を受け易い。好印象を持たれた者と嫌われた者で、一軍村にいる相手への二軍以下の者の態度は大きく変わるらしい。
「だからおれらが、あんまり外でフリーダムにしてると、二軍村の反発が大きなるから。はよ帰ってくれ、って親父から言われてんねん」
実際にそれを、跡継ぎに話す程度には切実なものらしい、と彼もうむむと実感する。
「……そんな話、初めてきいたな」
「オマエは今は、好かれとるしな。でも途中から引っ越したアシューは、かなりマイナスからのスタートやったはずや、て親父は言うとったわ」
「…………」
「実体化」の完全な制御に、同世代で一番に到達し、実力は確かであるはずの幼馴染み。それを臆病者扱いする空気は、ともすればそうした不満――一軍と二軍に大きな差は無いという意識の反動が、見た目は弱そうな幼馴染みに向けられた可能性もあった。
「おれやオマエと仲が良かったこととか、それも抜け駆けやって反感くらったらしくてな。だからアシューも、おれらにあんま、関わらなくなったんやで」
そんな一連の話は、彼には正直、あまりピンと来ないものだった。
「そんなこと気にしてたら、あいつ……身動きとれなくないか……?」
「ほんまにな。群を抜いて強なっても反発きそうやし、弱くても臆病者言われるわけやし」
その孤立が実際どんな状態だったか、彼らも推し量ることはできなかった。
「大体おかしな話やんな……おれらに近付いたらあかん、て大人の言い付け、二軍の同期はひょっとして、意味わかっとらんかったんかな?」
一軍の内ですら、彼ら……特に彼が遠巻きにされたのは、純粋に危なかったからだ。
その実態を知られず、「力」の差を見る機会もあまり無い狭い世界で――しかし確かに、一つの大きな運命が動き始めていることを、今は誰も知る由もない。
上10:金紫の魔女
何の変哲もない禿鷲が、都市長の屋敷から出た大きな馬車の後をずっとつけていた。
それを追い、辿り着いたのは紛れもなく、通称炎と風の国「ディアルス」――西の大陸の北東端にある、逆三角形型の国土を持つ人間の大国だった。
「これは驚きやなあ……こんだけしっかりした国やのに、国境はフリーパスとか。結界の気配すら全くあらへん」
「シャルもそうだったな。人間の住む所って、それが基本なのかな」
彼らの故郷は、隠れ里であることもあるが、煩いくらいに結界が施されている。
住人であるかその付き添いがあれば結界に感知されることはないが、その結界を決して絶やさないのが、境界を囲む二軍の村の者の主な役目だった。
化け物を積んだ馬車も、化け物である彼らも、難なく踏み入れてしまった人間の国。
国境には膝の高さほどの分厚い外壁があり、それはぐるりと国の周縁を囲むらしいが、境界線として以外の機能はありようもない。
「ほんとにシャルのお隣さんなんだね……道を逸れたら、森には魔物も多そうだったけど」
「ちゃんと公道を行けば、それも大丈夫そうだし。あたしも初めて来たけど、何か噂よりずっと平和そうだなぁ……」
空色の彼女と幼馴染みは、ここまでの旅路ですっかり打ち解けたらしく、元々の仲間である彼と悪友より和やかだった。
「何も咎められんと、ここまで来れて良かったわ。アシューさまさまやな」
幼馴染みに聞こえないよう、こっそり呟く悪友の言う通り、旅慣れた幼馴染みの同伴で彼らは大分と旅の心得を体得しつつあった。外套と着る物を全て同時に洗う間抜けぶりなど、特に怒られたものだ。
「……にしても、バステトは何処まで離れる気なんだ?」
シャルからこちら、めっきり見かけない幼馴染みの霊獣に、彼は苦笑する。
国境から出ている馬車に乗り、王都についた頃には日が暮れかけていた。
「意外に狭い国なんだぁ。もう王都についちゃったし」
何処で手に入れたのか、世界地図を広げながら幼馴染みが感心した風に言う。
空色の彼女は、馬車での道中もずっと元気だった。
「本当にキレイな国だね。道も建物も、これ何だろう? 石みたいだけどシャルの建物ともまた違う古い石材なんだって」
風景を飽きずに最後尾で眺め、近くの者を捕まえては何かと話をしていた彼女だった。
「シャルがお伽の国の都なら、ディアルスは天上の神殿が集まる聖地みたいだね」
妖精の森で絵本を読んだというが、よくわからない喩えをする彼女でもあった。
「聖地か……何となく、言い得て妙だな」
馬車から降りて、案内所の外で大まかな街路図が描かれた看板を見ながら、彼らは当面の行先を相談していた。
「昔、一度だけ見た天使みたいな、赤い空気がそこら中に混じってる」
「ええ? レイアス、天使なんて見たことあるの?」
行先に関係なく、色々とつっこみどころのある彼の台詞に、彼女がまずそこに反応する。
「親父が半分人間だったからな。死んだ時に迎えに来てた」
「そうなんだ……実はわたしも、何回も会ったことあるんだよ」
「――へ?」
えへへ、と彼女はそこで口を噤み、彼の義手を何故か大事そうに両手で包む。刻まれた青黒い紋様を見つめ、透明な青の目がきらりと光ったようにも見えた。
「本当は内緒なの。でもこれでずっと、わたしを守ってくれてるんだよ」
そうして、元々謎めいた所のある彼女を、ますます不思議にする発言だった。
「でもレイアス、赤い空気って?」
「炎と風の国と言うくらいだ。少なくとも『炎』は本当なんだろ」
「力」の色が、常に視える彼には、それがここまではっきりした土地は初めてだった。
本来、この世界には様々な土地の「気」が存在する。化け物の多くは出生した土地でこそ、その「気」の後押しを受けて本来の「力」を揮えることがほとんどだ。
「北の端の国で、この季節なのに全然寒くないし。この『炎』の気のおかげじゃないか?」
「そうだね……わたしもここ、キライじゃないな、この空気」
彼女はふっと、道行く人々の流れを見回し……。
「それに、人間の国なのに、千族さんの気配が沢山するね? この国って」
「…………」
彼もそれは、王都につくまでの道のりで、既に感じ始めていた事実だった。
「……平和やな」
今後のことを相談するため、夕食がてら入った小さな酒場で、悪友の第一声もそれだった。
「イメージと違い過ぎるで、この平和さ。世界中から千族を狩って、奴隷みたいに扱うて独立を保つ人間王国やって、あれだけ言われとったんになぁ」
「少なくとも町のヒトは、千族も人間も普通に暮らしてるっぽいね?」
狭くとも和気藹々とした店の隅の席で、幼馴染みも飲み物を口にしながら淡々と応える。
「才蔵の舎弟が見たのはどの辺りなんだ? タツク」
「ああ、王都のあの高い塔やな。あそこに都市長の馬車は乗り入れて行きよった」
王都なら何処にいても見える白く円い塔に、一行はへえ、と頷く。
「それだと……海からは少し遠いね」
ディアルスは国境の大半が海と接する国なのだが、王都はその中央だった。何故か残念そうに、空色の彼女が軽く俯いていた。
「水のそばなら、わたしも戦えるのになぁ……」
意外に物騒なことを言う彼女は、ここまでの道中もその杖で何をするでもなく、魔物などが現れた時はいつも彼らに戦闘を任せる形だった。
「アフィちゃんは戦わないでいいよ~。そーいうのはレイアス達の仕事だって」
そして戦えるのに逃げ回る幼馴染みは、さりげなく彼女を守るようにも動いていた。
「とりあえず明日、あの塔に行くつもりやけど……アフィはどーするんや?」
「?」
「知り合いのこと、探さんでええんか?」
最早空気のように馴染んでいる彼女に、悪友が念のために尋ねている。
「ラスト君が無事かわかってからでいいよ。でも一応、手紙は出しとこうかな」
ここ最近は何度出しても返事がないので、出すこと自体やめていた、と彼女は続ける。
「そのヒトってどんなヒトなの? アフィちゃん」
何度かナナハ、と口にしていたものの、その実態はこれまで誰も尋ねたことがなかった。
「ナナハはわたしの、幼馴染みの妖精だよ」
彼女はさらりと答えて微笑む。「妖精」、その聞き捨てならない単語に、悪友と揃って彼女の方を向く。
「……まだいたのか? 妖精の知り合い」
「そんな奴、妖精がこんな国で何をしとんねん?」
よくよく彼らは、近所でありながら仲の悪いその千族と、何かと縁があるようだった。
「うーん……やりたい仕事ができたって言って、それから連絡が来なくなって……」
わたしもそれが知りたいの、と笑う彼女の顔は平和そのものだった。
仕事と妖精。どうにも結びつく実感の弱い単語だ。
「それならラスト君を見つけて、そのヒトにも無事会えれば、一段落って感じだよね」
元々、シャルに来ていたのは自身の用事と、空色の彼女が気になってのことらしい幼馴染みは、あっさりそう言って笑う。
既に半月経過した最初の旅の終わりは、そこに落ち着けば良い方だろう。
彼も薄々、この面々のこうした時間は限られたものだろうと、貴重さを感じ始めた、嵐の前の穏やかな酒場の一夜だった。
そして翌朝早々、その嵐は颯爽と訪れていた。
「……やっぱり――……アースフィーユ!?」
「……あれれ? ……もしかして、ナナハ?」
石造りの建物が多いディアルス王都ではまだ歴史が新しく、珍しい鉄骨の造りという塔。早くも屈指の観光名所化したという二股の建造物――「炎と風の塔」に、朝早くから宿を引き払って彼らはやってきたのだが……。
土台が二股の高い円形の最下階は、間の陰になる空間に二ヵ所の受付が設営され、東西それぞれの塔の入り口に向かう人の流れを調整していた。
そうした様子を、彼らが遠巻きに観察していた時のことだった。
「あれれ……この気配――……まさか――」
ぴたりと固まり、空色の彼女が呟く。その後方に、彼らが振り返るのと同じ瞬間。
「ちょっと、貴方……!」
彼女の背後からずかずかと、焦り顔かつ焦り声で近付いてきた、若い人影があった。
「どうして貴方……こんな所に……!?」
端的に表せば、その女はまずとても――華やかな知的美人だった。
「もしかして、ナナハ? うわぁぁ、ほんとにナナハだあ……!」
くしゃっと顔を崩して、女に抱き着いた空色の彼女が少女的なら、ふわりとした金髪を肩にかけて一つにまとめた鋭い紫眼の女は、とても大人びて見えた。
尖った長い耳、整う容姿と隠された透明の翅は妖精であることを一目で知らしめる。しかし服装は西の大陸――西洋で一般的な町娘といった姿で、自然な気品と落ち着きが漂う。
「アースフィーユ、どうやってここまで来たの!? 貴方、アーニァ様達の所にいたはずでしょう!?」
凛とした清楚な声はきつくも聞こえるが、どうやら空色の彼女には姉貴分といったところの、妖精の若い女だった。
空色の彼女は、妖精の女を両腕から解放した後に、改めてにこにこと見つめる。
「ナナハに会いに来たんだよ。ここまではレイアス達がついてきてくれたの」
そうして彼女より少し塔の側にいた彼と悪友、幼馴染みを見て笑った彼女だったが。
「何あれ、あんな野蛮そうな奴らと一緒に来たって言うの? 貴方、不用心過ぎるわ!」
どうやら歯に衣着せぬらしい女は、確かに見た目は小汚く、ここまでの道中で傷んだ外套を羽織る彼らに無遠慮な感想を口にする。
彼女は妖精の女の手厳しい口調に、慣れているようにふわっと微笑んで続けた。
「野蛮じゃないよ、レイアス達は優しいよ。わたし、ナナハと一緒に兄さんを探したくてここまで来たんだ」
「……はい? それは無理でしょう。そもそも彼は、もうこの世界にすらいないって――」
「うん、そうだね。それはわかってたんだけどね」
って早! と、言葉を挟めず見守っていた彼らは、そこで悪友がずっこけ、幼馴染みがたははと苦笑する。
「よくわかんないけど……向こうは何か取り込んでそうだね?」
目敏い幼馴染みの解釈を裏付けるように、妖精の女は彼女に諭すように言う。
「私はもう、昔みたいに暇じゃないの、アースフィーユ」
「うん。ずっと返事が来ないから、そうだろうなって思ってた」
そこで彼女は、はしゃいでいる見た目より冷静に事の次第を言及する。
「今日はナナハ――ここにいるのは、これからお仕事なの?」
ディアルスでやりたいことを見つけたという女が、この「炎と風の塔」に来ている理由。妖精の女は、元々厳しい顔付きの目をさらに細めると、改めてまじまじと、彼女に同伴している彼らを検分するように眺め始めた。
やがて妖精の女は、少しだけ躊躇いがちに、彼女と彼ら全員に向かって話しかけた。
「貴方達は……どうしてこの『炎と風の塔』に?」
「――え? いや、ディアルス観光ですよ、単純に」
悪友が余所行きの口調で、女を警戒するように咄嗟に答える。
妖精の女はそこで、彼らにとっても聞き逃せない情報を、不意に口にした。
「今日この時に、それだけの『力』を感じる化け物がここに来るなんて。『ストラグル』に出場したいとしか考えられない」
「ストラグル……?」
幼馴染みは眉をひそめて、旅慣れている故の反応をすぐに見せる。
「色んな千族を賭けの種に戦わせるって噂の、あの悪趣味な?」
「違うのかしら? 悪趣味なのは同意するけど、今日これから秘密裏に開催されるのは、紛れもなくその化け物ギャンブルよ」
「化け物ギャンブル……だって?」
彼にもそれは、捨て置けるような無関係の単語ではなかった。
「俺達は――ここに知り合いが連れて来られてないか、探しに来たんだ」
シャル都市長の屋敷で別れた紫苑の少年の行方……それがただ気になっていた彼は、女にまっすぐそうして向き直る。
「ここは千族を集めて、戦わせるような場所なのか?」
「わからないわ。私達もようやく、ここで二カ月に一度開催されると知っただけ」
「……あんたはそれに、参加するために来たのか?」
「そのつもりだったけど。でも――」
そこで妖精の女は、塔の方から女の元に駆けてくる二つの人影に気付くと、こちらだと手招きしながらとんでもないことを言ってきた。
「貴方達……戦える化け物なら、ちょっと出場して手伝ってくれない?」
彼は一瞬、女が何を言ったのかが、よく理解できなかった。
「な、何をいきなり!? おれ達にそんな化け物ギャンブルに出ろって!?」
まだまだ違和感だらけの普通口調の悪友が、女に思わず食ってかかる。
「どうやら手練れの武闘家と剣士とお見受けするわ。私も想定外だったんだけど、ここの闘技では魔法が使用禁止らしいの」
妖精の女は本当に誤算、とばかり息をつく。ちょうどその女の所に駆けてくる者達がいて、その連れらしき者達に振り返り、戸惑う彼らから視線を外した。
塔から駆けてきた二人組は、見た目はうら若く、気配は弱い人間の男女だった。
「やっぱり駄目でした、ナナハ! 参加者の付添いでなければ、闘技場への出入りは絶対許されないそうです!」
一人は長い赤毛を風に揺らし、いかにも魔法使いといった紫のローブ姿の人間の娘だ。
「これでは僕達、東闘技場にしか入ることができません。できれば西闘技場の様子も、確認するにこしたことはないのですが……」
もう一人は肩までの黒い髪の、僧侶のような黒い祭儀衣が重たげな素朴な青年。妖精の女は大きく溜め息をつきながら尋ねた。
「ファー達の参加登録は無事済んだの? ラフィル」
「それも実はちょっと難儀してるんです。なるべく三人組を優先するって、もしかしたら二人のままだと外されてしまうかもしれません」
困ったように言う素朴な青年に、隣で人間の娘が、先端が輪状の金属杖を握り締める。決意を固めるように妖精の女を見つめて口を開いた。
「ナナハ。やっぱり私、三人目として登録してもらいます」
「寝言は寝てから言って、リアラ。私達は全員、魔法以外に取り柄のない足手まといよ」
遊び心の欠片もない妖精の女に、彼は思わず、素直な疑問を抱いてしまった。
「……あんた、本当に妖精か?」
そこで妖精の女は心から不機嫌そうに、残念だけどね。と即答したのだった。
率直に言えば、自分は妖精が嫌いだ、と、場所を少し変えてから妖精の女はまず口にした。
「あんな悪戯ばかり考えてる奴ら、同類だなんて思われたくないわ」
「うわあ。ナナハまだ、妖精嫌い続いてたんだね」
空色の彼女は困ったように笑うが、彼らは共感できる女の言いぶりに、少し場の空気は和みつつあった。
少し離れた公園に来た一行は、現在、総計七人。木製のベンチに座る人間の娘と素朴な青年、その休憩所の屋根を支える中央の柱にもたれる妖精の女。所在なく立った彼、悪友、幼馴染みと、柵に気軽に腰かける空色の彼女という、何ともちぐはぐな集団だった。
まず人間の娘が無害そうに笑い、自陣営の紹介を始めた。
「私はリアラ、こっちは従弟のラフィルです。ナナハにはずっと良くしてもらってます」
そのぱっちりと大きな目は、従弟という素朴な青年と同じ薄青で、人間には珍しい鮮やかな赤毛は、彼にはこの国の空気に融け込むようにも見えた。
「不躾を承知でお願いします。僕達の代わりに、ストラグルに参加してもらえませんか?」
素朴な青年が申し訳なさそうながら、テキパキと要点を伝える。
「僕達は西闘技場で出場したいと思ってたんですが、魔法が使えないルールでは勝ち目がないんです。東闘技場にも仲間を出したいんですが、人数が一人足りなくて、そちらにも誰か人手をお借りしたくて」
「賞金は一試合ごとに出て、西闘技場の分は全て受け取ってもらって構わない。できれば勝ち残ってほしいけど、安全を優先してもらっていいわ」
冷涼と続けた妖精の女に、彼と悪友は悩みの顔を見合わせる。
ごく当たり前の質問を、幼馴染みが場に差出した。
「どうしてそんなに、ストラグルなんかに出たいの?」
「それは……ええとですね……」
ちらりと素朴な青年が人間の娘を見やり、人間の娘も少し困った顔となった。
「今回のストラグルでは、『水霊石』が優勝景品なんです……私、それがほしくて……」
幼馴染みの視線にたじろぎ、段々と声が先細りする。
「……父が! 病気の父が死ぬ前に一度見てみたいって、どうしても言ってるんです!」
前半はともかく、後半は妙に爽やかな顔で台詞に力が入り、目敏い幼馴染みが黙ったままで眉をひそめた。
「……うそっぽいなあ、あんたら」
悪友もつい呟いた通り、それはどうにも不審な、人間と妖精の珍しい一行なのだ。
何だかんだではあるが。その化け物ギャンブルが気になるのは確かな彼らは、胡散臭い人間達の依頼をそのまま受けることにした。
「それじゃ、悪いが……アシューは、東闘技場の方に加わってくれるか?」
「って……え、ええええっっ!?」
二手に分かれる受付の直前で、悪友と相談していた話を突然伝えた彼に、後ろを歩いていた幼馴染みは文字通り飛び上がった。
「あ、あたしも出なきゃいけないの!? ていうか何で東!? ひょっとしてそれ……!」
「一人足りないって奴らのチームに加わってほしい。西の方は俺とタツク、人数合わせでアフィにも登録してもらうから」
それでいくと、残った人手は幼馴染みだけになるわけだった。
「向こうの奴ら、それなりに戦える奴をよこせて言うとるんや。そうなるとアフィに頼むわけにはいかんやろ」
「って――無理無理無理、あたしなんか絶対足手まといで嫌がられるってぇぇ!」
あまりに動揺していた幼馴染みは、おろおろとする空色の彼女の横で、ぶんぶん長棍を振りながらあくまで嫌がる勢いだったのだが……。
突然、ぬっと、そんな暴走寸前の怯える子羊の背後に影が差した。
「そんなことないぜぇ? 見た所お嬢さん、なかなかの腕前の棍使いぽいしぃ」
幼馴染みの棍を後ろから白刃取りし、その背の高い庶民騎士風の男はにこやかに、唖然とする幼馴染みを見下ろして笑った。
「武器は貸出、魔法は禁止、一応殺害禁止となると、お嬢さんみたく殺傷力の低目な長物扱う奴が一番使えるんだよなぁ。なぁ、ファー?」
「…………」
金髪の鳥頭に鮮やかな赤い目の男。そしてそれと連れ立った、無言で佇む黒髪で赤眼の青年。肩で留める外套と簡素な防具を着けた、庶民的だが騎士風の若者達が、幼馴染みをいつの間にか取り囲んでいた。
おそらくその二人が、彼らに出場を依頼した人間と妖精の、そもそもの仲間だった。
金髪の騎士は手慣れた様子で、掴んだ棍を軸に幼馴染みをくるりと半回転させる。
「歓迎するぜぇ。野郎が来るよりは絶対おれ、こっちの方がいい」
そうして幼馴染みの棍を離し、そのまま身長差を利用して、呆然とする相手の額に軽く口付けしてさらに放心させる。
「――あかん! やっぱりおれが行く! 戦力バランス偏るけどやっぱ……!」
瞬時に沸騰した悪友を、慌てて彼は必死に抱えた。
「我慢しろよ、これが最善ってさっき納得したろ……!」
「離せぇぇぇ! ああああ、ごめんなアシュー、おれが武器使われへんばっかりに……!」
彼も自らが行くかと相当悩んだのだが……体術家の悪友と剣士の彼、棍使いの幼馴染みの、霊獣抜きでの実力を考えた結果がこれだった。
「俺とタツクは不安定だな……それにアシューなら、気付かれずに東塔の様子も霊獣で探れるはずだ」
彼と幼馴染みの霊獣は、人目につかずに行動させることができる。紫苑の少年を探すためにも、二つの塔で別行動が必要と、そこで踏み切った彼だった。
妙にスマートな金髪の騎士に、頭を撫で撫でとされてポカンと固まり続ける幼馴染みを、見かねた妖精の女が金髪の騎士との間に割って入った。
「……イソシギ、悪戯が過ぎるわよ」
「だってー、おれの大好きなナナハちゃんは、一人だけ西に付添い行っちゃうんでしょ? リアラに手出したらおれ、ファーに殺されちゃう」
ぎろりと黒髪の騎士が金髪の方を睨み、あははと金髪の騎士が改めて幼馴染みを見る。
「ほんじゃお嬢さん、よろしくな! おれはイソシギ、こっちはマブダチのファー」
硬直顔でぼけっとしたまま、辛うじて一度、幼馴染みは頷く。そして引っ張られるように東塔の受付へ、入り口で待っていた依頼者達も加わって、そのチームは登録に向かった。
「……アシュリン、ごめんね……」
ぽつりと一言、成り行きを見守るしかなかった空色の彼女が、申し訳なさそうに呟いて俯く。
「代わりにレイアスが行けばいいって、言えなかった、わたし……」
それも少々ずれたことを、彼女は何故か悪く思った様子だった。
同じく後味の悪さがあった彼は、結局よくわからないまま西闘技場の受付に、妖精の女、悪友、彼女と連れ立って向かう。
「……正味、アシューが一番、しっかりしてるしな……」
ぼやきこぼした彼の隣で、無念そうに閉眼して両腕を組む悪友も、黙って頷いていた。
とりあえず彼、悪友、彼女をチームとして、無事に出場登録は澄んだのだが――
「……えっ!? アフィって十八歳なのか!?」
「そうだけど――何かおかしい?」
登録簿に記された実年齢に、二人して驚いた彼らを前に、実は一つ年上だった彼女……儚げに愛らしい雰囲気が幼く見える相手は、キョトンと笑ったのだった。
上11:白 -幼馴染み-
二カ月に一度、有志の千族を集めて健全な闘技を行わせるという催し――「ストラグル」。
受付に来た彼らが人間でなく千族であると気付いた時点で、案内人は観光客相手と違う対応で説明を始めた。
「武器は全て、余計な細工や『力』を籠められない仕様にした物を当方より貸し出します。試合場にいる内は気配探知などの感覚型以外、全ての『力』を使用禁止とし、純粋に武技にて優劣を競いいただく仕組みです」
裏口から入った闘技場は、一般施設の土台にあたる最下層にあった。試合場となる広い正方形の硬石の台と、それを囲み観戦する階段状の質素な客席がある密閉空間だった。
「場外では場内に作用しないものであれば、回復魔法等を、試合終了後の闘者には使っていただいて構いません。ただしその回は、『力』を使われた者は再出場できません」
何処となく、裏社会を匂わせる全体像ではあるが、彼らを控室まで案内した男は至って平凡そうだった。場内外とも、殺害行為は禁止されており、死者を出すことを避けるべく決まりを作っているとも、案内人は淡々と後に続けた。
「……じゃあ、回復魔法とかがなくて、試合の怪我が元で死人が出た時は?」
「それは自己責任と受け止めていただきます。登録の際にも、念書を頂きましたしね」
ろくでもないな、と。案内人が去って控室の背もたれの無いベンチに腰を下ろしてから、彼は溜め息をつくように口に出していた。
「開催してる方も出る方も、何も問題なしって思ってるみたいだ」
「ほんまやで。おれと同じ馬車で、都市長の屋敷に行ったどっかの千族の奴もおったけど、良い仕事を紹介してもらえた、なんて言っとったからな」
一試合ごとに勝った方に賞金が出る仕組みは、彼らのように人里に出たばかりの千族で、人間の町に上手く解け込めない化け物には魅力的に映るようだった。
しかし悪友の不満は違う所にあるらしい。
「許されへん……何でカラダで払えって言われたの、おれだけやねん……!」
隣の給湯場でお茶を淹れていた妖精の女が、呆れたように控室に入ってきた。
「貴方達、意外にやる気そうね?」
続いてお盆に四人分のお茶を載せて、空色の彼女が戻ってきて座る。
「第一試合は夜からみたいだね。それまでどうしよう?」
ベンチの間に置かれた低い机にお茶を置き、四人で囲みながら、新鮮そうに彼女が控室を見回す。
彼らの控室は壁が青く、そう広くない部屋に寝転べるベンチが二つ向かい合って壁際に置かれ、後は荷物を入れる竹籠が数個ある程度だった。
反則を防ぐために、塔から出入りする際には身体検査を受けなければいけないらしく、それは面倒だと彼と悪友は少なくとも思っていた。
「俺は最低限、ここの中を見回ってから、ベンチを使っていいなら仮眠したいな」
「あー、おれもー。実質戦うのはおれとレイアスだけだし」
空色の流人の彼女と妖精の女は、再会したてで積もる話もあるのだろう。それでいいとすぐに話が決まると、彼らを邪魔しないように客席へ出て行った彼女達だった。
受付の際に選ばされた武器、貸し出し印が入る長剣を検分しながら、隅に置いた荷物を横目に彼は軽く嘆息する。
「別に今の武器が取り上げられるわけじゃないんだな。助かったけど」
「オマエあの短刀、ずっと大事にしとるもんな。ええんか? 借りたもんは普通の剣で」
右手が上手く動かない彼が、どちらの武器を借りるのか、悪友は気になっていたらしい。
「あれを使うのは右手だから、どっちにしても心もとない。先鋒で勝ち抜きしてくれよ、タツク」
「あのなぁ。確かに大将のアフィまで回すわけにいかんけど、おれに全部戦わせる気か」
それは無茶やで、と笑う悪友に、彼も苦笑いながら頷く。
「こういうのって――里の一年大会を思い出すな」
「せやなぁ。最後の大会の時やんな、オマエがアシュリンに負けてもーたの」
彼らの故郷では、十年前まで年に一度、訓練中の子供を集めて戦わせる催しがあった。
しかし彼の父が死んだような流行病で多くの大人が死に、何処となく余裕が無くなった空気の中で、段々と廃れていってしまったのだ。
「せっかく出るなら勝たんとな! 他にどんな奴らが来とんのか、さっそくチェックやで、レイアス!」
妖精の女の言う通り、悪友は夜が待ち切れないように、うずうずしている様子だった。
「で、情報収集は俺にしろってか……」
「しゃーないやろ、そのためにオマエ、こっちに来たんやんけ」
姿も存在も透明に近付けられる彼の霊獣を当てにする悪友に、ふう、と彼も溜め息をつく。
「万一見つかったら俺、その回の試合は出れなくなりそうだけど」
試合場外での「力」の使用は良いが、そのペナルティを思うと、彼と言えどかなり慎重に行動しなければ、と顔色が曇る。
出場登録されたチーム数は、東西の闘技場一棟につき四つだった。
いつもその程度の小規模な開催をしているらしく、彼ら以外の三つのチームはなかなか面白い様相をしている、と霊獣の視界から彼は程無く気が付く。
「二つはどっちも、吸血鬼ばかりのチームだ。俺達と最初に当たる方は随分弱そうだけど」
「へええ? 西の大陸のこんな端まで来よるんかい、あいつら」
霊獣の里の位置は、西の大陸の北海岸沿いで北縁の中央に近い。
ディアルスは北東端だ。西の大陸の特徴として、大陸中央よりやや東に位置する「メイ」という商業都市の以西は急速に過疎化し、魔物や吸血鬼の縄張りが広がる極端な人口分布がある。
人間に混ざる魔性の化け物の中、わりとよく見られる吸血鬼は、ほとんどが西の大陸の西部出身で、霊獣の里の南西にもその領域の広大な森が在る近隣種なのだ。
二つのチームの内、本日は彼らと対戦しない方で、不思議と彼の霊獣の気を惹く一つの気配があった。
「……凄い美人だな。吸血鬼や妖精は美形揃いって言うけど、それにしたって魔的だ」
「何や、そんな美人さんがおるんか? 戦えるの楽しみやなあ、それ」
――ふと。その銀色の髪を捻り括っている吸血鬼……鋭い切れ長の孔雀緑の眼で、肩と腕を出し、足にも大きなスリットが入る丈長の武闘服を着る、世にも美しい顔立ちの少女が、彼の透明な霊獣が留まる天井の隅を見上げてきた。
「……?」
気付かれているはずはない。それなら何か動きがあるだろう、と反則に近いことをしている自身を後ろめたく思いつつ、落ち着いた様子の美少女を彼もしばらく見つめていた。
偵察をやめるわけにいかない彼の、大きな驚きは――その美少女のチームと本日対戦する、最後の一つの三人組にあった。
「……ビンゴってところか。こいつら、都市長の屋敷で、アシューの前に現れた奴だ」
「何やてぇ!?」
「ラストにそっくりな猫耳の女の子と従者はいないが……他の二人がここに来てる」
彼らからは遠い控室で、最後の一チーム、三人の忍装束の娘達が休憩をとっていた。
一番背の低い翡翠の髪の少女、間の薄柿色の髪の少女。後一人の背の高い女は、彼は視たことの無い、鼠色の髪を小さく束ねる真面目そうな忍装束の女だった。
「こいつら……年長の二人は何かの魔族……多分だけど、鬼の類縁だな」
顔を顰めて言う彼に、なるほど、と悪友が大きく頷いた。
「東の大陸は多いもんな。忍も東が原産やし、下手したらおかんの知り合いもおりそうや」
東出身の悪友の母は鬼の血を薄くひく。それが幼い悪友……本当の鬼子も怖がられた理由だった。その色を覚えていた彼は、娘達が纏う色に改めて、嫌な予感を倍増させる。
鬼や吸血鬼。人間の生身や生き血を食らうことがある魔性の者は、魔族であるが完全な「魔」とは言えないらしい。だから存在を許されているのだという。
「悪魔を含め、『魔』は天使が排除する言うしな。でも『四天王』もそうやけど、グレーな奴らが本当沢山おるみたいやな、里で教わった所では」
「悪魔だって、はっきり『魔』と確定されて、やっと排除対象になるらしいしな」
本来、悪魔とされる化生はこの世界の生き物ではない。しかしその血をひくことが明らかな「四天王」という魔族が、世界の四方に一つずつ城を持って存在している。「力」の四大要素――地水火風を司るその家系について、千族は誰もが大事な注意を必ず教えられる。
「おれらも化け物の『力』であんまり騒ぎ起こせば、四天王が討伐に来る言うもんな。何つか、魔物に近い奴らに秩序を守られとるって、実はおかしな話やんなぁ」
地下に広い監獄を持つ城を統治する四天王は、魔性の者でありながら、言わば世界全体の咎人の裁定者だ。だから世に隠れ潜む千族には、最も目を付けられたくない相手と言えた。
「それなのにこんな、千族同士を戦わせる集まりなんて、本当に悪趣味だな」
「『力』が厳禁なのはその辺りやろ。でもどの道、見世物にされんのはええ気がせんわ」
一通り他のチームの様子を見終わると、彼も悪友もごろんとベンチに横になった。
「ラっ君はどうしたんやろなー。心配やなぁ」
「…………」
都市長の屋敷に連れていかれた千族や、屋敷を守っていた娘達がこの闘技場に来ている。それだけでもこの場所は、明らかにシャル都市長と関係があるはずだった。
「……何がしたいんだろうな、あの都市長」
その意味、化け物との繋がりがさっぱりわからず、彼はただ顔を歪める。
とりあえず唯一、良かったこととして。忍装束の娘達に顔を知られたはずの幼馴染みがこちらの塔にいなくて良かった、と、安堵しながら彼は眠りに落ちていった。
「魔」とは、ただの魔性ではない。夢現に彼に、その蒼い男は警告を囁く。
――ここ……本当の魔物がいるぜ。多分、――と同じ……。
そこで彼の脳裏にふっと浮かんだのは。
何故か遠い、「水」の色を纏う昏い人影――
不思議な夢を反芻する暇もなく、坦々と始まった「ストラグル」第一夜で。
あまりに呆気なく、その日の試合は幕を閉じていた。
「……何やねん。さすがに弱過ぎやろ、あの吸血鬼ら」
一人で勝ち抜いた悪友に、空色の彼女が強く感心する。
「凄いねタツク。どんなにきらきらな美形さんでも、容赦なく殴れるんだね」
「ああいうの、趣味とちゃうし。ていうか、二人は男やし」
それでもようやく、勝ち絵が見せれたで! と悪友は楽しげだった。
「うわああああん! オレの……オレの美しい顔がー!」
「――泣いちゃダメ! 泣いたらもっと不細工になるわ!」
「ふっ……今日のところは、これでひいておいてやろう」
ぼこぼこに負けながらそんな台詞を残し、軟弱な三人の吸血鬼は去っていった。
意外なことに、もう一つの吸血鬼チームは忍装束の三人娘を、先鋒と中堅の双子らしき吸血鬼だけで打ち破っていた。
早々と撤退する忍装束の娘達は、それほど強い化け物ではなさそうだった。相手が悪かったのかもしれないが、娘達はそもそも何のために来たのか、と彼は疑念に襲われる。
闘技場が閉まった後に、報告会のために人間の依頼者が用意した宿に来た。一階にある食堂で、東塔の面々も集まっている。
相談中の者達から離れて、隅の方で木製の椅子にもたれて、幼馴染みが一人で無表情に温かい飲み物をすすっていた。
「……へぇ。あの時の子の仲間が、そっちは来てたんだ」
「東の方では、何か変わったこと――ラストに関係ありそうなことはなかったか?」
「別に。こっちの対戦相手は、シャルから来た千族っぽそうってくらい」
「…………」
「先鋒だけで試合終わるくらい弱かったし。ラスト君の気配もなさげ」
彼の目を見もせずそれだけ伝えると、忍装束の娘達に気を付けろと言う間もなく、幼馴染みはさっさと自室に引っ込んでしまった。
「……アシュリン、怒っとるんかな?」
「……だろうな。……多分な」
しょぼんと戻ってきた彼を見つつ、半ば強引に別チームに入れた幼馴染みに、合わせる顔がないと逃げた悪友は、スマン、と両手を合わせた。
そのやり取りを聞いて、長い食卓で彼らの近くに座る赤毛の人間の娘が、不思議そうに彼らに無邪気に笑いかける。
「ええ? こちらではずっと、機嫌良さそうにされてましたよ?」
まだ余所行きの口調の悪友が、警戒を解いていない人間の娘に無愛想に答えた。
「そりゃ、あんた達に罪は無いわけですから……八つ当たりするような奴じゃないです、あいつは」
「罪は無いと言っても、元々無理をお願いしたのは僕達ですが……」
人間の娘の向かいに座る素朴な青年が、ひたすら申し訳なさそうに彼と悪友を一瞥する。
妖精の女がまとめた所によると、東も西も、次の対戦相手とは覚悟を持って戦った方がいいという結論だった。
「今日はどちらも、たまたま大したことない相手だったようだけど。明日にどちらも勝つことができたら、その時点で私達の目的は果たせるわけよ」
元々少ない参加人数なので、明日の試合に勝てば、明後日は早くも決勝戦となる。対戦者がいずれも人間の娘が依頼したチームなら、決勝はどちらが勝っても良いわけだった。
客席はなかなか、化け物同士の戦いを見守る人間の客で賑わってもいたが、試合自体は実に味気無く運営され、賞金もその日の内に渡されるなど、一見大きな問題は無かった。
「あれじゃ確かに、悪いことって感じはしないよなあ、この化け物ギャンブル」
一人で試合を制したらしい先鋒の金髪の騎士が、無言で隣で酒を飲む黒髪の青年と同時にぐいっと酒をあおり、無責任に本質的な皮肉をそこで挟んだ。
「何かおキレイ過ぎて、逆に怪しく感じちゃうよなあ」
他に気になることは? と最後に妖精の女が尋ねた時、彼は少し躊躇いながら、ずっと試合中から感じていたもやもやを口にした。
「……何だろうな。あのリング、見ていて嫌な感じがしたんだ」
「――嫌な感じ?」
「理由はわからないが……あそこでは正直、あまり戦いたくない」
今日は試合場に立たずに済んだ彼は、明日は塔の一階層上で、東と西両方の試合が観戦できる別の試合場が使われると聞き、軽く安堵していた。
妖精の女は、ぱっと見は軽く流しつつ、真面目に彼に応える。
「それなら、理由がわかったら教えて」
曖昧にしか言えない彼を馬鹿にするでなく、大きく気にすることもなく会合が終わる。
後はそれぞれ、明日に備えて、一人ずつ与えられた部屋に戻ったのだった。
柔らかなベッドにぼふっと横になると、真っ先に脳裏をよぎったのは、里にいる時に近いよそよそしさを見せた幼馴染みの姿だった。
「……様子見に行ったら、多分あいつ、気付くよな」
不思議な目敏さを持つ幼馴染みは、彼の透明にした霊獣にも気が付ける。それはシャル都市長の屋敷で、確信していたわけだが……。
「……別に、気付かれてもいいか」
忍装束の娘達を見たせいもあるだろう。ただ彼は、幼馴染みのことが気にかかっていた。
「まだ全然眠くないし……何か、暇だし」
昼間に仮眠をとったこともあり、冴え切っている目を閉じる。次の瞬間には小さな透明の姿で、真横に具現させた飛び犬の低い視界が彼に飛び込む。
物を透過はできない霊獣は、食事や読み物を差し入れるという、木製の扉の下方に空く穴から外に出た。冷やりとした石の廊下を飛びながら、幼馴染みの居室へ向かう。
突き当りを曲がった所で、見えたその部屋からはまだ灯りがもれ――
「えええ? イソシギとナナハって、そんなに仲が良いの?」
幼馴染みの部屋であるはずが、突然漏れてきた空色の流人の彼女の声に、彼はぴたりと空中で静止した。
「人聞きの悪いことを言わないで。ただ、彼は誰にでもそういうことを言うから、真に受けずに気を付けなさいって言いたいだけよ」
続いて妖精の女の声までが聞こえた。その中で幼馴染みは、少し緊張した声色ながらも笑いを堪えるように、来訪者たちへの好意的な反応を返していた。
「わ、わかってるってー……! 本気にするわけないじゃん、あんなの!」
どうやら彼にはさっぱり気が付いていないらしく、先刻の様子は何処へやらだった。
扉の穴から中を窺うと、そこには宿の寝着姿でベッドの枕元に座る幼馴染みと、同じ姿で足元に腰かける空色の彼女、化粧台の椅子に座る妖精の女が集まっていた。
何だこりゃ、と思いがけず女子会に遭遇してしまった彼は扉の外で固まり、中の様子をついつい観察を続ける。
「ナナハさんこそ気を許さない方がいいよ。あのヒト何か、凄く胡散臭いよ、ぱっと見」
「ナナハでいいわよ。誰があんな奴、心を許すものですか」
「でもナナハ、顔が赤いよ? 兄さんのことはもう諦めたの?」
誰が! と動揺しているらしき妖精の女や、それにきゃっきゃと沸き立っている彼女と幼馴染みは、楽しそうとしか言いようのない打ち解けぶりだった。
あまりに平和な光景に、彼はふっと――
――何か……里を出てから、一気に色々、あり過ぎたよな……。
とても当たり前のような気持ちで、今も荒事の渦中にある意識でもっていたが。
初めて来た国で様々な者に出会い、成り行きでも力を合わせて何かをしようとしている今、こんな光景はおかしくないはずだ、とやっと実感する。
――……気を張り過ぎなのかな、俺。
道中を楽しむ余裕も無く、目的や危険のことばかり、これまで考えていた。
初心者と言えばそれまでだが、幼馴染みのように、警戒しつつも楽しむ形もありだろう。
――本当に楽しそうだな……あいつ……。
里ではいつも遠慮がちな幼馴染み――存在感を消したいかのような姿が、彼の遠目には映っていた。
頻繁に旅に出ているのは、病に臥す父の薬の材料を買うためらしい。その資金となる天然石を、よく一緒に掘った幼馴染みの母から聞いたことがあった。
生ものの材料もあるから、一度に沢山は買えないの、と、不在がちの娘に少し寂しそうにその母は笑っていたのだが……こうして見ると、外にいる時の方が幼馴染みは幸せそうで、悪友から聞いた話も胸をよぎり、彼の心中は重くなっていく。
「力」に色を視る彼の特殊な眼は昔から、魔力や霊力のこもる魔光石や霊光石といった、貴重で高価な天然石を見つけ易い。彼といれば沢山それが掘り出せる、と幼馴染みの母は度々、彼についてきていた。
――昔のレイアス君は怖かったけど、今じゃすっかり、頼れる若手のホープねぇ。
そうしてその母から、意外な事実を聴かせてもらったこともあるのだ。
――あの子には、危ないから近付いちゃダメって言ってたのよ。でもきかなくってね。
里で遠巻きにされていた彼らに、唯一近付いてきた幼馴染み。本当は他の子供と同じように親にそれを止められていたのだ。
それなら何故、幼馴染みはそこまでして、彼らと仲良くしたがったのだろう。
奇しくも明るい部屋の内では、彼のことについて唐突に女子会の話題が及んでいた。
「アースフィーユはあの彼のこと、どう思ってるの?」
「――え? 彼って?」
「あ、あたしもそれ聞きたかった。レイアスに決まってるじゃん、そんなの」
どきん! と彼は、扉に激しくぶつかる勢いで動揺する。
霊獣なので音はたてずに済んだものの、あまりに不意な事態に、わたわたと無意味に滞空して辺りを見回す。
このままここにいてはいけない。それは聞いてはいけない話だと、霊体のくせに心臓が有り得ない警鐘を鳴らす。
「ええー。アシュリンこそ、レイアスのことどう思ってるの?」
さらなる被雷に、何処に飛ぶかわからない女子会話とはこんなにも体に悪いものか、とぷるぷると羽が震え出す。
もしかすると全員、彼がいるとわかって話しているのかと疑念にかられ、違う意味でも冷や汗がだらだらと流れ続ける。
幼馴染みはアハハ、と無責任に笑いながら、まるでその問いかけを待っていたように――
その旧い絆への、おそらく素直な思いを、初めて聞かせてくれることになった。
「何かね、レイアスって昔っから危なっかしくて。ほっとけばいきなり死んじゃいそうで、声かけずにいられなかったんだ、あたし」
それは驚くくらい優しく……そして気負いのない、昔通りの幼馴染みの声だった。
「両親にも怒られたし、結局あたしのせいでレイアスは右手を失くしちゃって。それからもう、付きまとうのはやめようって思って……レイアスもタツクも、あたしなんかのために、多分命だってかけてくれる馬鹿な奴らなんだよね」
その想いは十分を越えて、十二分に伝わり過ぎたのだと、彼はそこで思い知る。
「レイアスの右手がないのは、アシュリンのためだったの?」
「そうだよ。こんな奴にそこまですること、本当になかったのに」
幼馴染みは場に合わせた軽い口調で、さらりとそう口にしているが。
自分のせいで。そう思った幼馴染みが、彼にどんな負い目を感じていたのか――
ずっと大切に想っていると言いながら、彼らに背中を向けた理由がそこにあるとしたら……それはどれだけ孤高な闘いだったのだろうか。彼は不意に、胸が重くなった。
場がしんみりとしてしまう前に、幼馴染みはすぐ、気軽過ぎる問題発言を続けた。
「まぁそんな危ない奴だから。気を付けてあげてよ、アフィちゃん」
「――え? どういうこと?」
「……呆れた。それ、本気で言ってるわけ、アースフィーユ」
妖精の女の切り込みを最後に、話はまた違う方向へと移っていく。
抑え切れなかった胸の高揚が静まると、後には居たたまれなさだけが残った。
――……大丈夫そうだな、放っといても。
何だかどっと疲れが押し寄せた彼は、そのまま本体の意識を閉ざして、それに合わせて透明な飛び犬も場から消え去っていった。
上12:玄い水の者
「ストラグル」第二夜にして準決勝の試合は、縦長に連なる三領域を持つ「炎と風の塔」中間部――二股に分かれた最下層より一つ上の東西が繋がった階層で、西闘技場登録者、東闘技場登録者の順に、同じ試合場で行われることになっていた。
「んじゃー、おれたちゃ控室でのんびりしてるわん。頑張ってねー、若い青年達」
「…………」
次試合になる騎士風の二人は、彼らの試合に興味はないとばかり、すぐに引っ込んでいく。
「あたし、ちょっと外に出てくる」
昨夜の楽しげな姿が嘘のように、幼馴染みもフイ、と彼らを後にする。そうして試合場のある土台の空間から、一般向けの展望台に上がっていってしまった。
「うぉぉ……おれらの試合姿も見たくないほど、怒っとるんかなアシュー、レイアス……」
「いや……何か気になることでもあるんじゃないか?」
昨日彼らについて語っていた様子からは、さすがにそこまでの怒りはないだろう。彼はもうその点は気にしていなかった。
ただ、一人にするのは心配でもある。出ていく寸前の幼馴染みの肩に、小さな飛び犬を咄嗟に乗せる。
「――」
幼馴染みも別に、それを拒否するでもなく、彼の霊獣と連れ立って場を後にしていた。
感覚がそうして分散されるのは、これから戦う身にはあまり良くなかったが。
「ラストのこと、少しくらいは、何か掴めないか……」
勝利よりもそちらが優先だった彼は、昨日目にしたとてつもない美少女が大将のチームと悪友の試合が始まっても、探索する霊獣側の感覚の優先を続けていた。
とても大雑把な感覚で観客席に座っていた彼に、一番解りやすかったのは、空色の彼女が逐一実況をしてくれる応援歓声だった。
「ああ、タツク危ない、やっぱり鞭と素手じゃ無理があるよ――……って凄い、そのまま絡めとっちゃえ、頑張れー!」
先鋒は短い黒髪の吸血鬼の娘で、それなりに時間はかかったものの、鞭使いの鞭を逆に利用して場外に振り払った悪友の勝利だった。
「くそぉ……何でおれのかっこいい姿、アシューは見とらんねん……!」
闘者入れ替えで一度戻ってきた際、そんなことをぶつくさ言っていたが。忍装束の娘達に勝った相手でも危なげなく捌く勇姿は、確かに本来の実力をいかんなく発揮している長の息子だった。
次の中堅は、どうやら先鋒の吸血鬼の双子の兄であるらしい。草色の髪や顔付きは妹と全く違うが、戦闘スタイルは酷似していた。
「男やったらマジで容赦せーへん! 遠慮なくKOしたるわ!」
化け物では「力」の強さに関係しない性別について、差別ね、と妖精の女が呆れる。まあまあ、と人間の依頼者達がとりなす中で、一試合目より早く二試合目は終わっていた。
ノックアウトされた双子の兄を担いで、大将の元に連れて戻した先鋒の娘は、無愛想な表情でも幼げな声で、最後の一人――彼が魔的な美少女と称した銀色の長い髪の吸血鬼に、甘えるように寄りかかっている。
「うぇーん。やられちゃったよー、レイン~」
「あらら。私の出番が来るとは思わなかった」
無表情に答える大将の吸血鬼は、生身の両腕に黒い晒を巻き付けている武闘家と見えた。しかしその晒にある印が入っていることに、彼はこの時気付けなかった。
そしてその第三試合は――何と、開始十秒で勝敗が決まることとなる。
「……へ?」
身長分程の距離を置き、試合場の中央で闘技者同士が向かい合い、気の抜ける角笛での試合開始の合図後――……いったい何が起こったのか。
何故か突然後ろ向きに転んだ悪友は、すぐさま飛び込んだ銀髪の吸血鬼に両足を軽々と持ち上げられ、金槌を投げるようにぶんぶん振り回された後に、ぽいっと投げ捨てられてしまった。
「なっ……何か今、『力』使わへんかったかあんた……!?」
吸血鬼である相手に、ヒト一人を投げられる腕力と素早さはわかる。あからさまな隙を作られた最初の転倒が納得いかなかった悪友は、場外から吸血鬼に食ってかかった。
物静かな系統の美少女である吸血鬼は、口元に僅かな笑みをたたえる。
「――いいえ? さすがに何度も試合を見てたら、貴方の付け入り所くらいわかるわ」
括った髪一つすら乱さず、くすりと毒の無い声で答えた姿に、ぐおおと悪友は悔しげな声をひたすら呑み込んでいく。
実質的には大将である彼に、出番が回ってきてしまった。さすがに今日も悪友の完封は無いだろうと思っていたが、後が無い状況に緊張の火がともる。
「レイアス……大丈夫?」
彼の右手を見ながら、空色の娘の彼女は不安げな声を出す。
「剣と素手なら俺が有利だ。心配しないでいい」
当然の現状を口にしつつ、何故か彼にも、その相手からは一抹の恐れが拭えなかった。
そうして試合場で、彼の目前に立った吸血鬼は、悪友に向けたような微笑みをふわりと彼にも向けた。
「……――」
彼はこの試合場に立つ前から、最下層の試合場にも感じていた嫌な違和感を振り払えず、こうして実際にその領域に入ると、嫌悪はますます強くなった。
試合開始の角笛が鳴るまでの数十秒、銀髪の吸血鬼を真正面から彼は見据えた。
見た目は年端もいかず、あまりに整った麗しい面差し。年下には弱い彼の年上気質が、ふっと脳裏をかすめたのだが……。
――……吸血鬼は外見に関係なく怪力で俊敏だ。油断するな。
長寿であるため、年も彼より上のはずだ、と己に言い聞かせる。それでも何故か――相手が美少女であるせいなのか、妙な躊躇いが、むくむくと沸き起こりつつあった。
根拠の無い迷いを振り払うべく、開始直後にまっすぐ彼は吸血鬼に斬りかかった。
「――早いわね」
腰を入れた左からの一閃は、大振りで避けられるだろうと思ったが、何とその吸血鬼は彼と距離を開かないまま、身を反らせるだけでそれを回避する。
「…………!」
間合いに入られないよう逆に彼が下がり、今度は上段から叩き斬らんとするも――
「容赦ないのね、生身の相手に」
喋る余裕まである吸血鬼は、彼の攻撃を全て予知するかのように、避けた後の斬り返しまでことごとく見切って紙一重で躱す。
当たらない攻撃を止まずに続ける内に、彼は早くも悟りつつあった。
――手を止めれば――俺の負けだ。
全くおかしな状況ながら、相手が仕掛けてこないのは回避に専念している内だ、と。
この相手が動けば彼も、悪友のように手玉にとられる。それを確信させるほどに、その吸血鬼の挙動は無駄がなかった。
――何でそんなに、観えてるんだ……!?
彼がどんな攻撃を繰り出すか、あらかじめわかっているようにしか見えない。
そのあまりに敏い気配の探知で、吸血鬼の身体能力を極限に活かしている相手なのだ。
体術家の悪友がこの相手に遅れをとったわけを、否応なく理解した彼だったが。
「――!!」
折り悪く、霊獣からの重要な情報がそこで彼の集中を阻害した。
「――あら」
そして、その隙をも探知したらしい吸血鬼は、魔性の微笑みをそこで浮かべた。
まずい、と彼が思える余地すらも無かった。
開始直後に足元をとられた悪友のように――吸血鬼が瞬時に伸ばした黒い魔の一手が、彼の長剣を一瞬で絡め、その手から奪ってがらんと場外へ放り出した。
「……!?」
決定的な展開に客席が湧き、悪友や彼女が焦って立ち上がった姿を彼は見る余裕もない。
「『力』じゃないでしょ。これもちゃんと、れっきとした武器」
吸血鬼の手には、それまで腕に巻かれていた黒い晒。それは、この塔の貸し出し武器である証の印を端に見せながら、びんと弓をひくようにきつく張られていた。
丸腰となってしまった彼に、容赦なく吸血鬼は、自らの武器を払い投げる。
「ぐ――!!」
彼の一番の弱点である右の義手は、とっくに見切られていたらしい。そこにびちり、と黒い晒がきつく巻き付けられる。
義手をぎしりと軋ませる晒は、左手で掴んで緩めるしかない。両手が封じられた彼に、片手で晒の張力を保ち、もう片方にも同じ晒を持つ吸血鬼は、余裕の笑みで尋ねていた。
「体術戦は得意そうに見えないわ。深追いせずに、降参しない?」
「っ……!」
おそらく見破られている通り、彼本人より、晒の巻き付く義手をどうにかされる方が困る。自然回復はしない義手への危機感と、加えて今の彼には――
先程から届き続ける、霊獣が見ている光景への危惧があった。
彼の試合が始まり、ちょうど霊獣の感覚の鋭さが落ちた頃に。
闘技場を出て、塔からディアルスの夜の町灯りを見下ろしていた幼馴染みに、ふらりと近付いてきた見知らぬ人影があった。
「――こんにちは。こんな夜更けに何を見ているんですか?」
「……え?」
振り返った時から幼馴染みは、早くも無意識に、満面の警戒色をたたえていた。
「おやおや。いくら今日の対戦相手だからって、そんなに嫌そうな顔をしなくてもいいじゃないですか」
「……貴男……?」
そこにいた、二十代後半程に見れる雅な男……。
ふわりと長い薄茶の髪を首の後ろで一つに束ね、穏やかな笑顔によく合う碧の眼と、外套をつけない貴賓の普段着のような姿からは、特別警戒視する理由は無いようにも見えていたが。
――……アイツ、色……!?
彼にはその男……幼馴染み達の対戦相手らしき者の「力」は、決して見逃すことができない覚えがあった。
――シャル都市長の屋敷の……結界と同じ……!?
紫苑の少年に、その屋敷を覆う「力」について伝えた時に。純度の高い「水」と、色々混じった「水源」があると彼は口にしていた。
――アイツ……何て玄い『水』の持ち主なんだ――!?
紫苑の少年に近く見えたのは、「水源」の方の色だ。そしてもう一つの「水」とほとんど同じ色を持った男は、あの結界に助力していた者と考えて間違いはなかった。
その男がおそらくシャル都市長の協力者であると、幼馴染みはわかったわけもない。
「……あたしに、何の用?」
最早無意識のレベルで危険を察知したような幼馴染みは、本当に大したものだ、と肩の上で緊迫する彼も呆れる。
彼がひたすら気になったのは、男が幼馴染みに気付いているのかどうか。
結界で気配を感知する者ならあの日の侵入者と悟られている可能性が高いが、「力」を貸しただけなら、管理は猫娘任せであったかもしれないと悩まされる。
彼の本体も苦戦の真っ最中で、両手を塞がれた形で次に吸血鬼が何か仕掛けてきたら、可能な限り受け流すしかない詰みぶりだった。
「レイアス――全然集中できとらんな、どうしてん……!?」
悪友が観客席から身を乗り出す通り、ぎりぎりと腕に巻き付く晒を締め付けられる彼は、試合と幼馴染み、どちらも気になり次の動きが全くとれない。
不思議と吸血鬼は、彼が何かを迷っていることまでわかるのか、意志を決めるのを待っているようにも見えた。
もう少しこの試合を踏ん張りたい。彼の思いは、突発の謎の意地に尽きた。
「何を考えて……悩んでいるの?」
「――」
ふわりと楽しげに微笑む銀髪の吸血鬼を、必死に睨んだまま彼は視線を外せず――
本来ならば、諦めて幼馴染みの方に駆けつけるべきかもしれない。
「用なんてそんな。目を惹かれた可愛い方に声をかけるのに、理由がいりますか?」
のらりくらりと話を続ける結界の男が、危険かそうではないのか。
本能は前者、と警鐘を鳴らすが、今すぐ踏み出せるほどの根拠もまだ見つけられない。そして理不尽に溢れて止まらない、この試合場から降りたくないという、謎の執着心。
そうしてびしりと張られた黒い晒を間に、闘技者の動きが止まって時間が経っていく。
観客が段々と焦れてきたところに――それは不意に、彼らの間に割って入った。
「――!?」
「……――」
彼も吸血鬼も、想定外の事態に思わず息を呑んだところに――
絡め飛ばされたはずの彼の長剣が、回転しながら試合場に飛来し、黒い晒を断ち切って石の台に突き刺さった。
「はーい。場外からいらんことされたから、にーちゃんは反則負け」
「な……!?」
それを投げた張本人は、おいおい、と騒ぎ始めた観客席に、貸し出し武器である長い木杖を振り上げるように手を振った。
「後はオレ、大将のアフィ君十八歳にお任せ! 楽しみにしててね、観客のみんな!」
「って……」
見えるかー! と、思わず内心で盛大につっこんだ彼の前に……十八歳などとは有り得ない自称大将、大きなゴーグルを着けて観客席を見上げる、紫苑の少年の姿があった。
唖然、と動けなかった彼の元へ、よいしょ、と少年が試合場に上がってきた。
「だいじょーぶ。暗示は度胸と自信だよ、にーちゃん」
今も少年の姿をぼやけさせている効果があるらしき、例のゴーグルを軽く直す。そして、黒い晒が巻き付いたままの彼の義手を、大事にしろ、と言わんばかりにぽんぽんと叩く。
「ちょうどアフィねーちゃんが借りた武器も、長物でやりやすいし。任せとけって」
宣言通りに、大将……として登録した、空色の彼女の代わりをする気らしい少年。豪快な反則ぶりに、どうしたものか、と彼はただ固まっていた。
そこでまた、意外だったのは――
「……それ、面白そうね」
銀髪の吸血鬼が彼と少年に、美少女というより姉じみた顔つきで笑いかけたことだった。
「私の相手をしてくれるのは、アナタ?」
あの敏さで、少年のゴーグルの効果が通じているとは思えなかったのだが、吸血鬼は紫苑の少年を楽しげに見つめ、残った一つの晒を利き手に持ち直した。
そうして向けられた戦闘の意思に、少年もすっと木杖を翻して吸血鬼を見返す。
「ちっせーからって、バカにすんなよ?」
彼としては、少年の無事がわかった以上、依頼と言えどそこまで試合の継続に拘る理由もなかったのだが……。
「何か気になってるなら早く行きなよ、にーちゃん」
「……――」
試合の間は、紫苑の少年も銀髪の吸血鬼もここにいるだろう。それなら早く戻って来れば、少しは話もできるかもしれない。そうしたい、と何故か思い、黙って頷いてから、彼は闘技場を後にしていった。
背後では試合場で大将が向かい合い、はらはらした様子の悪友と彼女が、出て行く彼を首を傾げて見守っていた。
身体検査に僅かな時間を取られ、幼馴染みのいる展望台へ急ぎ足で向かう。
霊獣の元なら行こうと思えば一瞬で行けるが、幼馴染みに今話しかけている相手には、なるべく手の内を見せたくない気がした。
二股の最下層と細い最上層の間の展望台の、見晴らしの良い窓際で。
「水」の結界の男は透明な霊獣に気付かず、嫌そうな顔付きの幼馴染みに、めげずに声を掛ける。
「ディアルスには観光ですか? それとも『ストラグル』にだけご興味が?」
「……別に、どっちでも」
「ここは暖かくて良い国ですよね。その秘訣をご存知ですか?」
「――?」
何を思ったのか、結界の男は世間話にみえて、重い話題を口にし始めた。
「炎と風――二つの奇跡の珠玉。人ならぬ化け物の秘宝を祀り、化け物の血をひく人間が、この国の王家らしいんですよ」
「……は?」
「大陸北東の凍土において、国を温める奇跡の珠玉の、『力』の適合者が王家だそうです。……信じられますか? この温暖な気候が、そんな珠二つで保たれているなんて」
結界の男が話しているのは、ディアルスでは伝説とされていることだった。しかし真偽は、国政の中枢に携わる者しか知り得ないはずだとは、異邦者である彼も幼馴染みも判別できない。
ただその話が、千族にとっても人知を超えた領域であることだけはぴんと来ていた。
「……それで。それがいったい何なの?」
あくまで硬い幼馴染みも、肩の上の彼も、男がそんな話をする意図はわかっていない。
「そうですね。そんな珠はこの国だけでなく……他にも適合者を待ちながら存在するかもしれない、と言えば、興味はありますか?」
結界の男が、端整な顔でにこやかに尋ねたことに、彼の脳裏で電撃が走る。
――にゃあ……あなた、まさか……。
存在している。あれは果てしない「力」の塊だった、と彼は今更思い当たった。
幼馴染みの前に現れた猫娘。その従者が着ける胸当てから力を零した黒の珠玉――
それを思い出したと同時に、結界の男がまず間違いなく、都市長の屋敷に侵入した者とわかって幼馴染みに近付いていることを確信する。
「――アシュー。こんな所で何、油売ってるんだ」
ちょうど話がそこまで来た時、展望台に着いた彼は、有無を言わせず割って入った。
「……レイアス?」
幼馴染みは彼が、霊獣だけでなく本体まで現れたことに、不思議そうに眉をひそめる。
「おや? これはこれは、お連れの方がお迎えに来られましたか」
結界の男はあっさり下がると、彼に向かって笑顔のままで、軽く一礼までしてみせた。
「――別に連れじゃないし」
咄嗟に幼馴染みはそんなことを言い、結界の男や彼を睨むように目付きを変える。
男は気を悪くした様子もなく、くるりと彼らに背を向けて、一言だけを残していった。
「……やはり可愛い方ですね、貴女は」
その後ろ姿に、どこか言いようのない悪寒と、玄い影を漂わせながら。
男の気配が無くなった後に、幼馴染みが珍しくあからさまに怒った顔で彼を見てきた。
「ちょっとレイアス――何でこんなとこまで?」
「何でも何もない。アイツ、都市長の屋敷の結界を張った一人だぞ、アシュー」
人目を憚る小さな声でも、彼も幼馴染みも、厳しい声色で互いに詰め寄る勢いだった。
「アシューがあの時の侵入者って知ってたはずだ。何が目的かは知らないが……」
「……そっか。やっぱり相当、まずい相手だったか」
自身の第一印象に納得するように、難しい顔のまま幼馴染みは頷いて俯く。
そうして幼馴染みは、一際冷たい声で――
「……バカじゃないの? レイアスまで関わることないじゃん、共犯扱いされるよ」
彼が連れでない、と言い放った真意らしきことを、苦々しくそこで口にしていた。
黙り込む彼に、肩の霊獣を横目で見ながら、幼馴染みは無機質に溜息をつく。
「心配し過ぎ。あたしが自分の意志でやらかしたことなんだから、そのツケはあたし自身で払わなきゃいけないんだからさ」
魔物退治一つでも、常に逃げ回る幼馴染み。
その台詞からは、一人で背負えることのみをするという、臆病だけではない真情が見え隠れする。おそらく、里で孤立をやり過ごし、外の世界にも自己責任で行き来するには、そうした覚悟が必要なのだろう。
……まだ彼らは十七歳だ。だから彼は、思わずその孤高な大人びた姿に――
「でもそれは……ヒトのためだったんじゃないのか?」
都市長の屋敷では、彼らの行動を助けるために。
旅に出るそもそもが、病気の父のためであるはずの幼馴染みに、そう尋ねずにはいられなかった。
鬼子だった幼い彼に近付いたのも、彼の危うさが気になったからだ、と言った昨夜。
「お前、そういう奴だから。放っておけないよ」
今も彼を突っぱねようと目を逸らし、巻き込むまいとする姿が辛くて、彼は自然に、長い想いを口にせずにはいられなかった。
それと自覚しないまま、ずっと想い続けていた真心を――いつかの時と同じように。
――……オマエ、ちゃんと闘えよ! アシュ―!
幼かった昔のように、歪んだ伝え方をしたつもりはない。
それでも彼の問いかけ直後に全身を硬くし、幼馴染みは黙り込んでしまった。
彼と同じ色の目に滲んだのは、年齢相応の弱音に見えた。しかし決して、それを彼には見せない、孤高な幼馴染みでもあった。
その代わりに、不意に、幼馴染みの表情や雰囲気から棘が抜けていく。
そうして口元だけはふるふるとして、拙く噛み締められていた幼馴染みだった。
「……ありがと。レイアス……」
震えて途切れそうな声でも、それだけは確かに、彼に届くようにはっきり口にする。
それがどれだけ、大きな意味を持っていたことか。
この瞬間、幼馴染みが得ていた答。それは誰に知られることもないまま、ただその内に在った。
彼がいつか、幼馴染みと同じ夢を視る、ある運命の日までは。
けれども今は、踏み止まることしかできなかった、その相手は――
次に顔を上げた時には、いつもの困った笑顔に戻って、幼馴染みは軽く言った。
「でも、そんな余裕ないでしょ、レイアス」
闘技場に戻る方向にお互い歩き出しながら、首を傾げる彼に、何故かとても優しい目で幼馴染は微笑んでいた。
「アフィちゃんって、何だか危なげな子だよ。誰かが見ててあげないといけないと思う」
「――……」
それが、幼馴染みの答なのだと……遠回しではあるが、思いをきちんと彼に伝える。
その存在は決して、彼が無視することはできないものであると、古い夢を知るかのように。
彼はただ、少し不服ながらも、否定しないことしかできなかったのだった。
上13:紅の災い
身体検査を受けて闘技場に戻る道すがら。幼馴染みは、展望台へ出た意図――そこで確認したかったらしいことを、改めて話し出した。
「やっぱりここ、色々おかしいよ。リングもそうだけど、一般ゾーンでも何だか、疲れが溜まり易い変な感じがあったよ」
「疲れが……溜まり易い?」
「今、ラスト君が試合に出てくれてるんだよね? あんまり無理させない方がいいと思うよ」
それを彼に言付けると、自分のチームの控室へ戻っていく。
「…………」
結界の男のことについては何も言わず、一人で抱え込む気だと彼は悟るが、今すぐそれを相談する余裕は彼にも無かった。
戻った闘技場では、紫苑の少年と銀髪の吸血鬼の、まさに善戦が続いていた。
「何処行ってたの、レイアス? ラスト君凄いよ、あの女のヒトも凄いよ!」
「……みたいだな、どうやら」
試合場で一定の間合いで向き合う者達は、少年の攻撃を巧みに躱し、また晒で受け流す練磨の吸血鬼に、たまに隙をつかれるが持ち直す少年という拮抗戦だという。
これで黒い晒が二つとも健在であれば、吸血鬼の方が有利だったかもしれない。しかし吸血鬼は、それを反則事項として抗議するような小者ではないようだった。
くすり、と余裕の体で、吸血鬼は微笑みながら不意に少年に尋ねた。
「アナタはどうして、戦っているの?」
凄くワケありに見えるけど、と。ゴーグルで己の正体を隠している少年に、表面的な問いかけではないことを付け加える。
敏い紫苑の少年は、その意味をしっかり受け取ったようだった。
「そりゃーね。こうして武器を取ったからには、どんなに自分が傷付いても、守らなきゃいけないもの。大切な場所ってあると思うな」
吸血鬼と間合いを保って答える姿は、微笑む余裕こそないものの、台詞の端々に不敵さと強い信念が挟まれている。
その回答から、この相手は難儀だ、と吸血鬼は見極めたらしい。
「そう。それなら……この辺りが潮時かしらね」
突然。黒い晒を地面に落とすと、目を見張る少年にあっさりと背を向ける。
試合場の端まで行くと、しん……と沈黙した観客席に、笑いかけるよう一度だけ、その吸血鬼は周囲を見回した。
「疲れたから、私は降りるわ」
そして全くそう見えない端麗な笑顔で言うと、自ら場外に出て試合を放棄したのだった。
「――って……!」
真っ先に不服を叫んだのは、他ならぬ対戦相手だった。
「こらぁー、逃げるなよー!」
「やめておきなさい。これ以上続けるのは、下手に力を消耗するだけよ」
銀髪の吸血鬼は双子の元に帰りながら、振り返った顔に微笑みは浮かんではいなかった。
「このリングには戦いを続けたくなる効果が仕込まれてる。こういうやり方、あまり好きじゃないの」
ブーイングの中で、すぐに観客席を降りた彼にも、その声は届いてきた。
「……だから貴男も、私との対戦に拘ったんじゃない?」
ちょうど彼を見つけた吸血鬼は、美少女の見た目とは裏腹な鋭い晴眼。とても大人びた魔性の眼を彼に向けていた。
銀髪の吸血鬼と、何故か彼は話したい、と思い、距離をとったままで静かに尋ねる。
「……あんたはここで、棄権していいのか?」
「別に、世話になってる博士のために景品をプレゼントしようと思っただけ。身を削ってまでやることじゃないわ」
「身を……削る?」
「貴男達も気を付けることね。この塔はそのリングをはじめ、ヒトをじわじわ喰う悪趣味な仕掛けが、あちこちに埋め込まれてるみたい」
「――!?」
驚く彼に、うーん、と吸血鬼は体を伸ばし始めた。
「こんなに少しずつ、気付かれないように力を集めて、いったい何がしたいのかしらね」
後はそれだけ言うと、その眼の良過ぎる銀髪の美少女は、呆然とする彼に背中を向ける。そして合流した双子の吸血鬼と、闘技場を出ていってしまった。
ちょうど、不満げに試合場を降りてきた勝者の紫苑の少年が、そばにやってきていた。
「やっほ。改めて久しぶり、にーちゃん」
「改めてって、オマエ……」
「突然で悪いけど、力貸してほしーんだよね。にーちゃんのその眼がまた必要でさ」
は? と彼が目を丸くした時、悪友と空色の彼女、妖精の女が降りてきた。
「おーいラっ君! オマエいったい何やねん、今までどーしとってん!」
「ラスト君、有り難う! 凄かったよ、さっきの試合!」
歓声と共に駆け寄る悪友達に、正体――反則を隠すゴーグルをしたままの少年は笑み一つ見せることなく、少年の知る現実を彼らに告げる。
「……にーちゃん達。これからここで、多分大変なことが起きるよ」
そして俄かに「炎と風の国」――……「千族狩り」とも呼ばれる国に潜む仄暗い罠に、彼らは巻き込まれていくこととなる。
彼のチームに勝利を与えた紫苑の少年は、引き換えに、彼の力を借りたかったと言う。
「本当にそんなやばい魔法陣が、屋上に仕掛けられてるのか? ラスト」
「この塔の構造からは、それしか考えらんねー。オレもさっき、あの吸血鬼が言ったようなことで、やっと確信できたんだけど」
決勝戦が行われる塔の最上層に、勝ち抜きチームとして立ち入りを許された彼らは、足早に狭くて長い螺旋階段を駆け上がっている。
銀髪の吸血鬼が言い残した、ヒトの力を奪う仕組があるという塔内部。その起点と終点は最上部にあるはず、と忍び込んだ塔で異状に気付いたらしい少年は、厳しい顔付きで伝えていた。
「けれど何で――お前はわざわざ、そんなこと調べてたんだ?」
屋上には彼と少年だけで秘密裏に向かい、他の者はもう一チームの試合を見守りながら、様子を窺ってもらうことにした。少年の話を聞いた時に、人間の依頼者と妖精の女が酷く険しい顔になっていたのも、彼は引っかかっていた。
紫苑の少年はあっさり、所見を伝える。
「都市長の屋敷の結界を張った奴と、同じ奴の仕業なんだよ、ここの仕掛けは」
満面の不愉快さを隠さず、階段を駆け上がりながら吐き捨てるように言う。
「それを造ったのは、ひょっとして……オマエの知り合いなのか?」
紫苑の少年が一人、都市長の屋敷に残った理由を含めて。彼はその内面に踏み込んでいた。
「…………」
少年は足を止めないまま、否定の意はないことを背中で示していた。
「ミスティル――ミティは……三年前に離れた、オレの双子の妹なんだ」
少年と同じ、物造りの才を持つ者がいる。彼が問うた以上の深い事情を苦しげに返す。
「でも……オレのこと、わからなかったんだ、あいつ」
先日にはおそらく、その再会は叶わなかっただろうこと。それを彼も察するしかなかった。
紫苑の少年曰く、彼らがちょうど屋敷を脱出した頃に、猫娘とその従者、薄柿色の髪の忍装束の少女が都市長の元に姿を現したらしい。
「あいつらがもっと早く来てたら、にーちゃん達も脱出できなかった。引き付けてくれたアシュリンのねーちゃんに感謝した方がいいよ」
「…………」
「この塔もそうだけど、ミティの仕掛けが入る建物はどれも、その気になればもっと沢山、中にいる奴から力を奪うこともできる。アシュリンのねーちゃんが逃げられたのは、屋敷の外だったからだよ」
屋敷の中では霊獣が出せなかった、という悪友の話も、それなら頷ける。
幼馴染みに放たれた投網も、力を奪う仕掛けがあったはずだと言うが、目敏い幼馴染みはそれに絡まれる前に、本能的に逃げたのだろうと彼も思い起こす。
「……こんな仕掛けを造るミティが、何を考えてるのか、わからないんだ」
「…………」
「でもこのままじゃ、集めた力を使って何をする気かわからない。どんな理由があっても、オレはそんなの、絶対に止めたい」
ヒトを殺す可能性があるなら、武器も義手も造らない、と彼に断言した紫苑の少年。
そんな少年にとって、実の双子がヒト喰いとも言える様々な仕掛けを造っていることは、その信条の基となった痛恨事なのかもしれない。
そして彼らが、その塔の頂上に出た次の瞬間には――
少年が何故彼を必要としたか、彼は目の当たりにすることとなった。
「……何だ!? あれ……!?」
「力」を色として捉える彼の眼に映った、その異状。狭く円形な屋上に描かれ、様々な色を渦のように吸い込む大きな魔法陣が、闇の中、混沌としか言えない様相でそこに在った。
やっぱり――と少年は、自らの武器を取り出しながらぎりっと歯を噛み締めた。
「くそォ……! 双鎌で斬れるレベルじゃない……!」
両端に大鎌のつく少年の武器は、本来誰が使っても「力」をも斬ることができるという特殊仕様――たとえば霊体である彼の霊獣も、傷付けることができる代物だという。
双鎌との銘らしい長物を握り締めて、少年は、魔法陣の前に立ち尽くす彼にその依頼を説明する。
「この魔法陣の構成を教えて、にーちゃん! まず弱らせないと、これは壊せない!」
そのため少年は、今からこの場で、それに介入できる結界除けの類を造る気らしい。
「でもオマエ――そんなことしたら、術者に気付かれないか?」
これだけ大掛かりな事を仕掛ける相手に、目的もわからないまま下手に関わって良いか、彼の躊躇いも当然のものだった。
邪魔が入れば戦闘にもなるだろう。人間の国でそのような騒ぎを起こせば、最悪の場合秩序の管理者、四天王にも目を付けられるかもしれない。
「じゃあコレ、もうかなり力も溜まってるのに、放っとくって言うのかよ!?」
今おそらく、下で試合をしている幼馴染みのチームや、さらには一般観光客からも力を奪うヒト喰い魔法陣……悪趣味ではあるが、命に別状はないだろう事柄にどう反応していいのか。
「ストラグル」という化け物ギャンブルの存在も含めて、彼一人で判断するには事が大き過ぎた。
「……一旦戻ろう。壊すにしても、もっとやり方を考えるべきだ」
「っ――……!」
まっすぐな紫苑の少年には、彼の姿が情けなく映っただろう――
それでも彼は、ここにいる悪友や幼馴染み、他にも彼の仲間と見做されるだろう者――ひいては紫苑の少年に、何もわからないまま、無闇に大きな敵を作ることはしたくなかった。
……もしもその場に、その確実な敵たる相手が、姿を現すことさえなければ。
「……全く。こつこつ積み重ねてきた努力を、こんな形で邪魔をされようなどとは」
「――!?」
「オマエ……!?」
彼と少年が振り返った先、屋上の入り口と言える片隅の階段に、それらは顔を出した。
「にゃーん。何とも可愛らしい侵入者さん達ですのニ」
「……」
見た目は真面目そうな人間で、本日も礼服姿のシャル都市長と、それに従うように続く猫娘。加えてその無言な顔無き従者が、屋上に現れる。
「ミティ……!」
瞬時に顔を歪めた少年の、ゴーグルの下の素顔と、猫娘の顔立ちは確かに全く同じだ。髪も目も「力」すらも、幼い二人は世にも稀な、紫苑の光を纏っていた。
しかしそれは二人だけでなく、猫娘の隣で姿を隠す服装の従者も同じ空気を纏うことに、彼は少し違和感を覚えた。
現れた都市長は、顔を見知った彼に向かい、とても苦々しげな表情を浮かべる。
「貴男とあの方がここに来ているのは知っていたが、まさか我らの邪魔をするためとは。これもまた、運命ということか……」
彼は相変わらずついていけない、酔ったような口調。片膝をついてまで苦悩に頭を抱え、よしよし、と猫娘に頭を撫でられる始末の人間の男だった。
警戒や衝撃で、表情を固めて何も言えない彼らに、都市長は次の瞬間、行動に出ていた。
「見られてしまったからには仕方ない。予定より、少し早いが……」
ともすれば、大陸規模にも成り得る、有り得ないある事変。そんな悪夢がこの眼下に広がっていると、いったい誰が予想できただろうか。
それを到来させることを、あまりに気軽に、都市長はその場で結論していた。
「それでは始めようか。我が長年の望みのままに」
すぐ隣で、にゃっ! と、何も考えていないような猫娘が頷く。
瞬間、その混沌の円陣は成す術も無く、狂い始めた運命の覚醒を始めたのだった。
「っっ――!?」
「そんな、待てよミティ……!!」
起動だけで、突然強い衝撃を放った円陣から、彼と少年は屋上の端まで吹き飛ばされた。
「――? 誰かミィを呼んだですのニ?」
罪の無い顔付きで猫娘は首を傾げ、そこにそっと従者の女が、猫娘をかばうように袖の内に引き寄せる。
紫苑の少年は、まだ間を置いて飛散する衝撃波に煽られながら、すぐにも起き上がった。
「――オレだよ! 何で気付かないんだよ、ミティ!!」
今までは決して外さなかったゴーグルを、そこで投げ捨てる。都市長に顔を見られることも構わず、武器を軸に高く跳躍した少年は、都市長と猫娘達の前に飛び込んでいた。
「……んににニ?」
少年の掴みかかる従者の腕の中にいる猫娘は、明るく微笑んだままで首を傾げる。
「君は――……ミスティルと、同じ顔?」
「――……!」
少年が来た時点で都市長は数歩下がり、猫娘とその従者に対応を任せていたが。
その時、都市長だけでなく、従者の女も動揺したように彼には見えた。
全く何も感じていないのは、当の猫娘だけだった。
「オレだよ、ラスティルだよ!! こんな所にいちゃ駄目だ、ミティ!!」
紫苑の少年は従者の腕を払いのけ、猫娘に近付こうとする。
「――!」
しかし従者が取り出した細長い鎖を目にした瞬間、それを脅威と思ったのか、悔しげに後方に一転する。ちょうど、近くに駆け付けようとした彼と同じ位置に降り立っていた。
「これから何をするつもりなんだ!? オマエら!!」
最早憎悪を隠さない声と顔で、少年は都市長に呪うように問いかける。
驚いたな、と都市長は、少年をまじまじと見ながら呆れるような声で話し出した。
「ミスティルの関係者だったのか、君は。それにしてはとんでもない不作法ぶりだ」
都市長に以前、大鎌を突き付けた少年が、その後どうなったのかは不明ではあるが……都市長も嫌悪を隠さず、大人げない顔付きを浮かべている。
そして軽い口調で続けた内容は、とても良い大人の口にする事とは思えなかった。
「まあいい。この国と共に君達も、今夜で滅び去ればいいのだ」
「……!?」
「そんな――……まさかあの魔法陣……!」
彼と少年の背後で、魔法陣はどんどんと紅い光に満ちていく。それに呼応するように、都市長達の背後で、真っ黒な空に蠢き始めた沢山の影に……強過ぎる悪寒で、ここまで口を開けなかった彼は、さらに息を呑むことになった。
まるでこの塔を中心地点とするように、夜空に集まり始めた怪鳥の群れ。おそらくは大量の魔物を背後に、都市長はうっとりとした微笑みを浮かべた。
「わたくしは選ばれた人間なのだ。人間にしか叶わぬ奇跡を、この身は最高度に具現する」
「それじゃやっぱり、あれは悪魔召喚の最高密度の円陣……!!」
「……悪魔だって!?」
少年の叫びで嫌な予感に形を得た彼は、それが意味する差し迫った危機を知る。
「あれだけの力で喚び出す悪魔――……下手すれば町一つだって吹っ飛ぶぞ!?」
強い力で喚べば喚ぶほど、反動で何が起きるかわからない化け物。既にこの付近の魔物を、地の底からも招き始めた大きな「力」は、災害と言って良い類の規模のものだった。
「悪魔召喚」。そのよこしまな魔道は、人間の血を濃く持つ者にのみ可能と言われる。
悪魔は人間とのみ契約する化け物であり、契約者の魂を代償にその強靭さに応じた者が招かれ、契約者の望みを叶える形が代表的なのだ。
「アンタの望みは何なんだ!?」
知らず、紫苑の少年をかばうように前に出ながら、彼は声を張り上げた。
「知れたことです。わたくしはこの優れた御身をもって、四天王となる」
「……は!?」
都市長は両腕を組んで、普通なら考えられないような発想を、悠々とそこで答えていた。
「千族も人間も皆、わたくしに従えば良い。この国を制すのはただの手始めです」
その目に宿るのは狂気であるのか……それともそこまで、確信を持てる何かがあるのか。
塔を目指す魔物の群れがかなり近いことを確認し、都市長が猫娘と従者に目配せすると、従者が先程取り出していた鎖を屋上の石畳に円く広げた。
「――待て、行くなよ、ミティ……!!」
事態に気付いた少年が駆け寄ろうとするが、彼は咄嗟にそれを阻んで少年を捕まえる。
「離せ!! 離せよ畜生、ミティ……!!」
猫娘は最後まで不思議そうに笑ったまま、何一つ少年に応えるはことないまま……鎖の円環の中、突然現れた闇の沼へ、都市長、従者の女と共に飛び込んで消えてしまった。
「追っても無駄だ! 捕まるだけで助けられなくなるぞ!!」
まだ腕の中で暴れる少年に、彼はあえて、少年の通称を最後に強調して呼びかけた。
「この魔法陣を何とかするんじゃなかったのか!? ラスト!!」
猫娘に対して、ラスティルだと名乗った時点で、少年の意識はその名を使った頃に退行しているように見えた。だからこそ、彼が出会った何でも屋の名前を強く呼びかける。
「……!!」
未だに度々衝撃の波を叩き付けてくる背後の災いに、少年はようやく我に返ったように、ぴたりとそこであがくのをやめる。
冷静になったのか、不服そうに少年は、彼の腕を抜けてから武器を持ち直して尋ねた。
「いいのかよ。下手に触ると多分死ぬよ、あれ」
「悪かったよ。オマエの言う通り、ここに来てすぐ壊すべきだった」
彼は彼で短刀を取り出し、義手に逆手に、黒い晒を口で引いて括りつける。
彼のその応えに少年が何か言おうとした時、屋上に飛び込んできた別の人影があった。
「大変なの、レイアス!! この塔を目がけて沢山の魔物が……!!」
「って、やっぱり伝波発信源はここ!?」
「……アフィにナナハ!?」
最早下の階でも試合どころではなくなったようで、彼女達はここに来たのだろう。地上では地中から、大蛇程の魔物が次々顔を出す様態らしい。
灯りを消して硬く戸を締め、頑強な石の家に息を潜めている人間はともかく、外にいた人間の悲鳴がそこかしこで上がっていた。
「タツクのにーちゃんとアシュリンのねーちゃんは!?」
「リアラやファー達と一緒に外に行ってる! わたし達は空の魔物を倒しに来たの!」
そこで当然のように空色の彼女が叫んだことを、彼は危うく聞き逃す所だった。
「わたし――達?」
「当たり前でしょ。じゃなきゃあの子のバカ力、いつ使うのよ」
妖精の女は、普段は小さく目立たなくしている蝶のような翅を、今や体を覆えるほどに大きく広げている。それは魔法陣と似た紅い光を、僅かに発し始めていた。
「貴方達、邪魔だから。早く地上の手助けをしてきて」
腕まくりをして夜空を睨む姿は、そこに巻き込まれかねない彼らのことが足手まといと言わんばかりでもあった。
彼はひとまず、本来の山犬程のサイズの白い霊獣を、地上に送り込んでから女を見返す。
「魔物はともかく、この魔法陣を壊せる算段は?」
仮にいくら、妖精の女が強力な魔法使いだったとしても、元を断たなければきりがないはずだ、と冷静に問い返した。
それは確かに、と妖精の女は顔をきつく歪める。
「だからアースフィーユを連れてきたけど……これは思ったより、複雑そうね」
そして空色の彼女と共にここに来た理由を、改めて話し始めた。
「アースフィーユに力ずくで吹き飛ばしてもらえば、何とかなるかと思ったけど。これだと、塔を全て消失させるレベルでないと無理そうね」
「……は?」
「力ずくって……アフィねーちゃんが?」
呆気にとられる彼と少年をものともせずに、妖精の女と彼女は難しい顔を見合わせる。
「塔に避難してるヒトも沢山いるから、それはできないよ、ナナハ」
「わかってるわ。今考えてるから、ちょっと待って」
ていうか、と。ふっと妖精の女は、怒り顔で彼を見返してきた。
「貴方達には何か考えがあるわけ? 大体こんな事態になるまで何をしてたの!?」
まさに逆切れといった様子で、普段の冷静さを欠く姿は、ああ、やっぱり妖精なんだな……と、つい思ってしまう彼だった。
右手に巻き付けた短刀の柄を、胸の前で左手で押え、彼は彩なき灰色の眼で所感を告げた。
「魔法陣を弱めることはできる。今のあれは悪魔召喚の途中だから、一刻を争う」
「途中ってそれ……どれだけ強力なバカが来るのよ!? 魔王レベル!?」
普通なら一つの召喚に、そこまで時間はかからないのだ。それを知るだろう妖精の女が飛び上がるような中で、彼は努めて冷静にする。
「あれ、弱められんの!? にーちゃん!」
紫苑の少年が食いつくように、自身の武器を握り締めて、空いた手で彼の上衣を掴んだ。
「……消し切ることはできないと思う。でももし、オマエがあれを斬れるのなら……」
彼らが力を併せれば、その魔法陣を何とかできるかもしれない。やっとそう、話が固まりかけたところで。
天地を揺らがせる魔物の群れに、空色の彼女は、彼にさらなる試練を課した。
「……わたしに力を貸してほしいの。レイアス……」
そしてようやく、彼は彼女の、正体の一端を知ることとなる――
上14:彩のない眼
それは後に、千年王国ディアルス史上で五つの指に入る災いと呼ばれるほどの、大規模で唐突な魔物の襲来だった。
「それじゃ、死ぬ気で行くから――そっちも踏ん張ってくれ」
力を出し惜しむ余地など無い。
義手をも潰す覚悟で彼は、紅い光を放ち続ける魔法陣の一角に片膝をつき、自身の短刀を構える。
「炎と風の塔」の白く円い屋上で、中心に坐する魔法陣を三方から囲み、彼らは手分けして各々の役割を決めていた。
「言っておくけど、私の魔力も限りはあるのよ!」
彼の右前方に立った妖精の女は、足下に小さく浮かぶ自らの円陣――「力」の光を受け、四つの翅を大きく広げて派手な発光を始める。
「凄いや……魔力豊富過ぎじゃん、ナナハのねーちゃん」
紅く輝く妖精の女の周囲から、無数の強力な魔弾が、暗い夜空に向けて放たれ始めた。
「相変わらずナナハ、怖いな……」
魔法陣を弱らせた後、空色の彼女が役目を果たすという計画。それまでの間、防衛を請け負った妖精の女の先制攻撃に、傍らに立つ彼女が緊張の面持ちで呟く。
彼はひたすら、自らの意識を集中する。
――『火』と『土』、『水』と『水源』の複合属性……酷いな、本当に魔王喚べるな、これ。
足元の混沌、赤と黄金と玄と紫が入り混じる魔法陣に、詳細な解析を諦めて行動に移る。
――何でもいいから……まとめて、『無意味』になれ。
呪うほどにそれを念じた直後に――眼下の魔法陣に、力の限り両手で短刀を突き立てた。
静かな動作で深く短刀を突き刺した直後、魔法陣全体から激しく金の光が舞い上がった。
「づっ――……!! くそ――……!!」
抵抗は勿論予想していたが、彼が使えるぎりぎりの力を全て注いだ短刀に、魔法陣から逆に彼を侵蝕する力が跳ね返ってくる。
魔道の常識的に、完成された魔法陣には、力をぶつける程度で介入することはできない。
魔法陣ごと消し去る規模なら別だが、それも魔法陣の完成度で必要とされる量が異なる。妖精の女の言うレベル……塔を崩壊でなく、消失させるほどの力は、いくら「気」が豊富な種族の彼と言えども持ってはいなかった。
――いったいどうやって……この魔法陣を弱められるのさ?
心底不思議そうな紫苑の少年に、彼は彩の無い眼で淡々と答える。
――これを構成する『力』を『無意味』にしていく。全てはきついが、可能な限りに。
それは彼がかつて、右手を失くす前に――
幼少から「力」に色を視ていた彼に、幼馴染みが教えてくれた、その眼の使い方だった。
鬼子と呼ばれていた彼が、どうしても危うく見えて気になった。
そう言っていた幼馴染みは、制御できない霊獣を抱えていた彼に、笑いながら突拍子もないことを告げに来たのだ。
――レイアスならできるよ。きっとおもったとおりに、そのコもかえられるよ。
その無責任で、適当に過ぎた台詞が、彼が自らの霊獣を透明にしたり、小さく変容できる謎の特技を知るきっかけとなる。
――だってレイアス、みえてるんでしょ? まぜたりけしたりも、できるんでしょ?
「力」に色を視て、そして時に、直接触れることもあった彼に――
その特技の本質を誰よりも先に、目敏い幼馴染みは本能的に気が付いていた。
「凄い……てぃな・くえすとの泉と同じ、魔法陣がちょっとずつ変わってる……!」
隣でしゃがみ、苦痛に耐える彼の肩を支えながら、空色の彼女は誰より近くで、ある冒涜の目撃者となる。
「『力』にするだけじゃなくて……『力』でなくすることもできるんだ……!!」
彼はそうして、「力」である自らの霊獣をいじる特技。小さな泉の水を、赤い獣の炎に対抗する「水」の力と化したような、異端の能力を持っていた。
それはひとえに、視えている「力」の色を、彼自身の血や「気」を混ぜて染め変えることで可能な介入――彼の眼に映る世界への、些細で小さな変革だった。
魔法陣からの逆流と闘う彼の向こう、天の魔物を追い射つ妖精の女が冷や汗を流して、彼の姿を凝視していた。
「初めて実物を見たけど……あれが『心眼』……?」
妖精の女自身の、魔力の消耗による疲労もさることながら。
魔道を学び魔法を使う者として、それがどれだけ稀な力であるか。世界で不滅のはずの「力」を壊す反則の才能で、「神」をも冒す眼だと解る女が、戦慄の目を彼に向ける。
彼の左前方で出番を待つ紫苑の少年の、持てる「力」の大きさも、彼はある程度視えていた。
それは思わず溜め息をつくほどのもので、魔法陣に付け込む隙さえ創れたなら、少年は必ず、これを打ち破れると彼は確信していたが。
――……マズイ。穴が開くまで、俺の方が持たない。
彼の特技は「気」を使う場合、右手を介する必要がある。そのために使う短刀――彼の右手の骨から造られた武器は、気を込めて実体なき「力」に介入するのに最適なものだ。
そんな短刀に添える義手が、魔法陣からの抵抗で傷むのは勿論、短刀もみしりと軋み始める。それを緩和すべく、抵抗してくる力を引き受ける体は、既に半死の状態だった。
それだけ体を壊してでも、義手と短刀は守らなければいけない。
この魔法陣を穿てるほど強く介入するには、それらが必須であり――この事変を辛くも治める鍵は、魔法陣の消去以外に無いことを、この場にいる誰もがわかっているだろう。
死に体となっていく彼の霊獣が降りた地上で、くたんと飛び犬が座り込んでしまった。その傍らで、悪友と幼馴染みが膨大な数の魔物に取り囲まれている最中だった。
「ああもう、オマエ何しに来てん、レイアス!」
「もういいよレイアス、あたし達のことは気にしないで!」
魔物からぎりぎり身を守る二人は、人間の依頼者の切実な望み……付近の者を避難させるまでは派手な攻撃を控え、時間稼ぎをしてほしい、と頼まれたことを承諾していたのだ。
「霊獣を戻す力すらないんか!? 今どーなってんねん、オマエ!?」
その状況で彼を心配する悪友達も、途方もないお人好しだ、と彼もますます心配が募る。
悪友も幼馴染みも、巻き込まれただけで、ここまで戦う必要など無い。
それでもあくまで、弱い人間が避難している間、二人は背中合わせに防衛戦に徹する。
どれくらいの期間、そこにあったかわからないが。
こつこつ魔法陣に溜め込まれた力は、当初の視立てを遥かに超えるものであったことに彼は歯噛みしていた。
――こんなんじゃ――アフィの手伝いができないじゃないか。
彼の仕事をこなした後に、もう一つ待っている大切な役割。
それができなければここにいる彼女や少年、妖精の女が危険になってしまう、と自身の甘さを呪う。
予想以上にかかる時間に、魔法陣の元へと襲い来る魔物を迎え射つ妖精の女も、大きく消耗しつつあった。
「……やばいな。にーちゃんもねーちゃんも、かなりボロボロだし」
敏感な紫苑の少年が険しい顔をする通り、彼らの限界は激しく差し迫っていた。
……ぷつり、と糸が切れるように。彼は自らの役目を放棄しかけた――
あまりに大きな負荷に、体が強制的に意識に蓋をしにかかった。
――駄目だ――……あともう少し……!!
紫苑の少年が付け込める隙、魔法陣に穴を開けるにはまだ至らぬと、焦燥が総身を駆け抜ける。
そこで不意に……懐かしい誰かの笑う声が聞こえた気がした。
――……情けねぇな。手助けしてやっから、少し気合い入れろよ。
それと共に、何かが彼に流れ込む。そこで彼の体は、不思議なほどに気を取り直し――
その結果込められた、さらなる大きな力に、黒いヒビがひた走る魔法陣を彼は幻視した。
「ナイス、にーちゃん! 後は任せろ!」
その時何故か、全身から紫の気を発していた紫苑の少年が、愛用の長い鎌を振り上げた。
「時間かかるから、にーちゃんはアフィねーちゃんと次の手の準備!!」
少年自身はひたすら不敵に、魔法陣の中央に向けて大きく踏み出す。
その鎌に纏わされた、少年の稀有なる「力」……彼は「水源」と称した、水に由来する「精霊」の力を込められた刃が、少年が振りかぶった直後に彼の開けた穴に突き刺さった。
――俺は――一番危ないのは、竜や精霊だと思うけどな。
精霊とは、世界の自然全てから顕れ得る無我の化生だ。ヒトの魂を介して、自然の力をヒトに貸し与える、普通の魔法では最高峰と言われる強力な存在なのだ。
「レイアス……! 大丈夫……!?」
そして隣の彼女は、魔竜などと言われた謎の化け物……――
――いくら最強の『力』――自然の系統や言うても、竜なんて滅びた種族やんけ。
――でも召喚士さえいれば、いつでも再現されるはずだし。
魔法は使えない、と言った彼女は、「召喚」を主とする術士であることを彼は初めて知る。
「ゴメンねレイアス……! 後はわたしが頑張るから、義手だけ貸してくれない……!?」
魔法陣の抵抗のあまりの強さに、消耗し切って倒れた彼を彼女が膝に乗せる。彼女は涙の滲む青い目で、申し訳なさそうに彼の右手の紋様に触れる。
「……待てって。外すともっと壊れるから、手伝うから」
苦笑いしながら上体を起こした彼に、彼女は顔を強張らせて、涙を飲み込む。
ほとんど力の無い体で、それでも彼は、彼女を手伝うことに迷いはなかった。
「大丈夫だから一緒に戦おう。そういう約束だろ、アフィ」
「……レイアス……」
空色の流人の彼女は、「竜」専門の召喚士であると、妖精の女は彼に伝えた。
――アースフィーユはこの国でなら、『風』を喚べるはずよ。
本来は海など水場の近くで、水の流れを司る――「水」を喚ぶことを習ったという彼女は、「炎と風の国」の気を受ければ、「風」の流れをも司る素質を持つらしい。
「竜」とは、精霊以上に強力な、自然の脅威そのものが化け物と化した存在だ。
海にあっては激しい海流や渦巻きなど、彼と悪友が旅の初日に出会った異状。あれがまさに、今彼の右手にある刻印無しに力を使おうとした彼女の、暴発の結果だった。
――この屋上に風竜――竜巻を喚んで、あのバカ魔物達を蹴散らしてちょうだい。
その刻印は力の制御を助ける機能があり、大きな「力」を使う際には必須であるという。
紫苑の少年が魔法陣の中央を穿ち、穴を斬り広げるよう踏み止まり続ける中で。
彼は必死に立ち上がると、刻印の力と彼女を繋げるために、ほとんど零と言える力の残りを右手に込めて、隣に立つ彼女の左手を強く握った。
「これでいいか? そっちは片手で大丈夫か」
「……うん。アーニァもいつも、こうしてくれたから」
青い珠玉を誂えた木杖を、彼女は右手で高々と掲げる。
同じ頃に、地上でも大きく風向きが変わることとなった。
「――っしゃあああ! 人間みんな避難終了、そら確かやな!?」
「はい! もう思う存分戦っていただいて構いません!」
「それじゃ遠慮はいらん……! これぞ『実体化』のタイミングやで、アシュー!!」
「……あははは。タツク、素、出過ぎ」
駆け込んで来た素朴な青年に、ガッツポーズをとった悪友。
そのうなじと幼馴染みの胸に、一瞬の僅かな光が煌めいた直後に……突然その場から悪友も幼馴染みも忽然と姿を消す。
次の瞬間、場には二つの大きな「力」――彼らの切り札、「実体化」された霊獣が本性を顕わにしていた。
「うわあ……黄金の不死鳥と巨大な黒い狼……!?」
もしも喋ることができれば、その通称は「ガルーダ」と「フェンリル」なのだと、唖然とそれを見上げる素朴な青年は告げられていただろう。
夜に紛れ、地にはびこる魑魅魍魎を、踏み散らし、焼き払う。
圧倒的な存在感の差を見せ、卑小な魔物を喰らい尽くしていく二つの霊獣――……その「力」は、ヒトである彼らの二面性を体現する、「もう一つの自分」だった。
同じ存在でありつつ、異界に居を置く分身は、普段は己の影を霊体として現世に映し出す。そして時に、霊獣族特有の「霊骨」を媒介に、ヒト型の現身と入れ替わる「実体化」……存在をまるごと移す獣が彼らで、実体ではどちらか片方しか、現世には存在できなかった。
「凄い……! でもお二人はいったい何処へ……!?」
霊獣がいる所なら一瞬で行けるのは、この入れ替わりを応用したものなのだ。
本性たる「実体化」の獣こそ、最も強い「力」を発揮できる。それが完全に制御できるようになれば、彼らは成熟したと見なされる。
当然、消耗する力も大きいので、滅多に使われることはない。
凄いね――と。屋上から黄金鳥と黒狼を見つめ、彼女が彼の手を一層強く握った。
「全然違うのに……ちゃんと、二人がそこにいるってわかるね」
闇にかざし続ける杖の青い光。それを放つ珠玉は、自然過ぎて気付かなかったが、それも大いなる「力」の塊なのだと……こうして発動を始めて、やっと彼は気が付く。
光に侵される空は段々と歪み、黒く巨大な蛇が空に昇るように渦巻き始め――
やがて顕現された、まさに竜の名を持つ激しい大気の荒ぶり。生きた「風」の脅威。
巻き込まれる彼らには、足場を固定する魔法を妖精の女が施している。その竜は屋上を起点に天空に広がり、魔物だけを全身で屠り、叫喚の間もなく呑み込み始めた。
夜空の数多な魔物と共に、彼らの体力をも蹴散らす暴れ竜に、彼は彼女の手を握り返して拙く微笑む。
「こっちはとても――アフィとは違う奴だな」
召喚獣と言える竜と、異界に在る彼らの霊獣の違い。
喚び出した「力」と共にここに留まる彼女は、実体化の際は異界に消える彼ら――その場所の記憶はなく、獣の感覚に意識が統一される霊獣の徒とは、制御様式が異なる。
喚び出す「力」も自らそのものではない召喚士は、無理矢理繋がった「風」の仲間に、その暴走を防ぐべく全力を尽くして苦しげな重い呼吸をしていた。
「……うん。約束通りだね、兄さん……――」
これだけ大きな「力」を扱えば当然だろう。段々と胡乱になっていく声で、彼女は夢を見ているように、暗く青い目をじわりと滲ませ始めた。
「わたし、信じてたよ……兄さんが伝えてくれた、いつか会えるヒトのこと――……」
見上げる空には、何が映っているのか――……わかるのは、その手のかぼそさだけで。
彼女の召喚が成功した時点で、妖精の女は攻撃をやめて足場の固定に集中していたが、それも四人ものヒトを竜巻の中核に留める大仕事だった。
激しい風の中で魔法陣を斬り続ける紫苑の少年も、場の誰もが相当な無理をしていることが、彼の眼にはありありと映っていた。
そんなに長い時間ではないが。今この、色とりどりの神秘が、いかに稀少で有り得ない事態かを彼は直視する……平和なはずの国に投げられた、不吉な賽の目を思いながら。
「あーもー、こんにゃろおおおお!! ミティを返せ、ちくしょぉぉぉぉ!!」
彼と同じように魔法陣から抵抗を受けながら、それを使っていない方の鎌の刃に回して何とか身を守る紫苑の少年が、ついに魔法陣の端まで黒く大きな刃を届かせていた。
「何考えてんだよミティ……――それに母さん……!!」
そして少年は見事に、その円陣の循環を断ち切る長い一太刀を振るい遂げる。
その時「炎と風の塔」の頂に咲いた、光の花弁を散らす紅い彼岸花を、どれだけの者が目にしていただろうか。
溜め込まれた力はそうして吐き出され、再び世界の一部になるべく闇に還っていき……。
そして魔法陣のその置き土産、衝撃をすぐ傍で受けた彼らは、固定された足場で全員が倒れ込んでいた。
それは想定していたことだが、意識を失うほど力を使い切った妖精の女が防御壁の効果も付加してくれていなければ、彼らの命は危うかっただろう。
「っ……起きてるのは、俺とアイツだけか……」
空色の召喚士の彼女も彼の横で気を失っており、紫苑の少年も意識はあるが全く動けないようで、今の彼といい勝負の全身状態だった。
地上では、「実体化」を解いて戻って来た悪友と幼馴染みが、同様に疲労し切った様子で互いにもたれて座り込む。
彼の霊獣の隣で、幼馴染みが、震える呼吸を今頃整えていた。
「あはは……何かもう、やばすぎて逃げるどころじゃないや、これ」
恐怖の感覚が、幼馴染みは最早麻痺していたらしい。逃げずに頑張っていた幼馴染みに、悪友がぶつくさと、ぼやき声で文句を言う。
「阿呆。逃げるよりおれらとおった方が、安全やっつーねん」
ずっといた素朴な青年も、悪友達に温かな肩掛けを被せながら、穏やかに申し出ていた。
「そうですよ。皆さんどうか、国賓として城にお迎えさせて下さい」
彼はその言葉の意味がわからず、ふいっと、飛び犬が青年の方を振り返った時だった。
「皆さん……! 本当にご協力、有り難うございました!」
赤毛の人間の娘が、大勢の甲冑姿の人間を率いながら、場に駆け付けてきていた。
その姿を見て、既に事情を説明されていたらしい幼馴染みが疲れた顔で笑う。
「あははは。潜入の間、兵士さん達周囲に待機させてて良かったね? 王女様」
魔物の大群が現れた直後に、迅速に周囲の人間を守り、避難させていた者達の正体。
「おかげで我が国に巣食う不届きな賭け事も、これでやっと摘発できます……!」
そもそもこの塔にやってきたのも、王家としての使命感。「千族狩り」と言われてまでも、各地に残る千族達を保護して戸籍を与える国の、熱い志であったことを――
「人間と千族、どちらも幸せに共存していただくべき我が国で、このような闇を私は決して許しません!」
その誇りを、王女と呼ばれた赤毛の人間の娘は、兵士達にも言い聞かせるように改めて語る。
悪友と幼馴染みは、時間稼ぎの依頼を受けた時に真実を聞いていたらしい。
彼にとっては衝撃の事実を、彼たる飛び犬がそこで噛み締める隙間も無く――
「……え? レイアス?」
ふっと。唐突に気配が弱まり、彼の分身が儚く消えていってしまった。
あまりに弱々しい去り方に、虫の知らせを受けた幼馴染みが、青白い顔を強張らせる。
――時間はここで、僅かだけ戻る。
地上がそうして湧き立っている間、屋上でのびていることしかできなかった彼らの元に、ある来訪者……――
このタイミングで現れてはいけない、不吉な昏い影が差していた。
「おやおや……これは少し、高みの見物が過ぎましたかね?」
「――!?」
「…………?」
眠る彼女を介抱していた彼と、俯せに倒れたままの紫苑の少年が、緊迫した顔を必死に上げる。そこに現れた気配の、あまりの重さに、ただ驚いた視線の先に――
屋上の端に、たった一人。長い癖毛の髪を優雅に風になびかせながら、彼だけがわかる色を持った男は、歪んだ笑みをたたえて階段から訪れていた。
「まさかあの魔法陣を壊せる化け物が――『守護者』以外に存在するなんてね」
竜や精霊とはまた別に、自然の力を司り、密かに世界を守っていると言う「守護者」。そんな存在を脈絡なく口にする不審な男。
その男が纏うある色……純度の高い「水」と、全身に散らつく紅い魔性の光。この日中、幼馴染みに話しかけていた「水」の結界の男。
そこで彼はようやく、男の正体に思い至りかけたのだが……。
「せっかくの魔法陣を、壊したのは君ですか?」
にこり、と笑顔で尋ねた魔性の男に、この状況の有り得なさ……ある絶望を彼は悟る。
「……俺だ」
せめて、魔法陣のあった場所に突き立つ短刀を咄嗟に掴み、それだけを男に答える。
そうですか、と笑った魔性の男が、軽い動きで右手をゆっくり振り上げた瞬間。
膝をついていた彼の胸を――水の槍としか言えない無色の杙が、斜め上からあっさりと貫き通していった。
「――」
それでなくとも、これまでの事変で彼は消耗し、いつ倒れてもおかしくない状態だった。
止めようも無く、体のいたる所から、どんどんと抜けていく力。
同時に、全身を満たしていく冷たい虚無は、自身がどう倒れたのかもわからないほど、彼の存在の否定を容赦なく始めた。
「……他の役者は、色々ありそうなので、また次の機会に」
魔性の男は満足したように、その後すぐに、屋上から立ち去っていき……。
魔法陣が描かれていた場所を、染め直すようにじわりと広がる鮮やかな赤の中心地で。
仰向けに転がる彼の眼には……ただ、昏い空だけが映った。
――……――…………。
これと同じことが、前にもあった気がする。その時自身は、どうしただろう、と。
閉ざされる意識の中、水底に沈んでいく青い夢を――その終わりの記憶をかいま見る。
「――眠っちゃ駄目だ!! 後少しだけ、頼むから踏ん張れ兄ちゃん……!!」
……懐かしい声が、不意に聞こえてきていた。
そうだった、あの時もオマエに助けられた、と……彼の一部である赤い光が、消える彼を留めようと、自らを削る無茶を始めたことに苦く笑う。
きっと何度も繰り返すのだ。赤まみれの運命から、彼らは逃れられないのだろう。
ソレは時に怒れる腕となり、またある時は、その心臓の代わりに。
きっと、誰かの泣きじゃくる声を聴きたくないから。ずっと、それだけのために――
上15:黄昏 -縁-
ふと気が付いた、昏い世界で……潮騒の唄が聞こえた。
ここは何処だっただろう。横たわっているとしかわからない、不思議なほどに軽い体で、ゆらゆらと彼は目を閉じたまま――……懐かしく打ち寄せる鼓動に、じっと耳を澄ませる。
――ごめんなさい……――あたし…………。
そう言えば昔、ここに迷い込んだ。それきりいなくなった、大切な呪いと共に。
「……行っちゃうの? ――……」
誰かの声が不意に伝わり、彼は目を開けようとしたが、ぴくりとも動けなかった。
それも無理のないことだった。彼の心臓には風穴が開いていて、だからこんなにも全身が軽かったのだから。
「――を……置いていくの……?」
その赤を流し切ってしまった彼に、それはただ悲しげに、遠く尋ねてくるから。
応えることができない彼は、代わりにひたすら――在りし日に得た答を想う。
……言い残すこと。……心残りがないと言えば、嘘になるだろう。
やり残したこと、やらなければいけないことは、きっと沢山あった。
けれどそんなものだろう。いったいどれだけのヒトが、悔いなく去れる幸運を得るのか。
「それならどうして……アナタは望まないの……?」
そこは未練を望むものだけが集う冷たいところ。だから彼はいることができなかった。
そして置き去りにされてしまった、悲しげな遠い日の誰か。
「こんなにあの子が泣いているのに……アナタには聞こえないの?」
消えることを拒んでいない彼に、何故、と問う誰かに……彼はその、彩の無い眼でずっと、彼が視てきた世界の行く末を呟く。
望む方が、辛いことだから。叶っても叶わなくても、失くした時間はもう戻せない。
だからみんな――やり直しがきかないから、その時を大事にして生きるはずだ、と。
「……そんなの、潔良過ぎない?」
とても不服そうな誰かに、彼は思わずある声を思い出しながら、それは違う、と笑って伝える。
――オレがいなくても……もう大丈夫だろ?
それだけ大切なものなら、きっとまた出会う。
巡り合い、同じように大切になる。たとえ今の彼が残らなくても。
命とは、心とはそういうものだと……その縁だけは、何があっても消えはしないと。
「何それ。前向き過ぎるでしょ……」
けれど、確かに――と、誰かも少し、納得したように声を震わせた。
「それならずっと待ち続けるより……諦めて受け入れる方が、きっといいよね」
どうやらわかってくれたらしい誰かに、彼も安堵し、揺らぎの中に還ろうとしたのだが……。
しかしそこで、誰かは突然、戸惑ったような素朴な声をあげた。
「アナタ、今――何をみているの?」
何って。ありのままを言おうとした時、何故か彼に、不意に自ら歯止めがかかり――
「……しっかりして! アナタはそっちの世界のヒトじゃないよ!」
そう言えばそうだった。それを思った瞬間、彼の全身に急速に強い痛みが広がる。
「そっちに行っちゃダメ! アナタはまだここにいられるんだから!」
何だこれ、と激しく顔を歪める彼のことを……――
あろうことかそれは突然、爪をたてた肉球で、微睡む寝顔をびしりと縦に引っぱたいた。
「っつ――!?」
思わず飛び起きた彼の前に、偉そうに鎮座してきらりと凶器を掲げる白黒の影があった。
「やっと気が付いた。危なかった、ホントにレイアス、消えちゃうところだったよ」
「って――……お前……!?」
あまりに見覚えのある姿と、全く聞き覚えのない涼しげな愛らしい声に彼は絶句する。
「バステトが……喋った……!」
「バステト? 私はそんな名前なんだ?」
いったいそこは何処なのか、水気も無いのに潮騒が絶えず、薄明るくて何もない闇……彼と大きな白黒猫だけがいる世界で。
座り込む彼に、それをくるむよう四肢を折って座り、彼を見つめる白黒猫が、無表情にきょとんとする。
「って――……お前、アシューじゃないのか?」
「私が誰かはわからないよ。霊獣なんてそんなものでしょ?」
どうやらそれは、自身が霊獣であることだけはわかっているらしい。
しかし彼らの本性の具現と言われる霊獣が、人語を話した例は基本的になく……しかも幼馴染みとは違う存在らしきそれに、彼はわけがわからず閉口するしかなかった。
それは猫らしく動かない表情のまま、口も開かずに声だけを彼に届ける。
「アフィちゃんが泣きじゃくってるよ。可哀想だから早く帰ってあげて」
「……え?」
「せっかくラストが必死に助けてくれたのに、どうしてレイアスは起きようとしないの? このまま死んじゃうつもりでいるの?」
容赦なく心臓を貫かれたはずの彼に、それは有り得ない展開のように思えたが。
有料なら回復してやるけど? 初めて出会った時に、そんなことを言って笑った紫苑の少年……――その稀有なる神秘の眼光、精霊に関わる者の証たる純度の高い紫の色。精霊魔法という世界屈指の力なら、そんな奇跡の回復も可能らしい。
魔法陣を貫き、消耗した彼を助けてくれた一手もそれであると、ようやくそこで思い当たった彼だった。
「……俺、まだ生きてるのか?」
「どうして死んだと思ったの?」
即答した白黒猫に、彼は、ほう……と呆けたような溜め息をつく。
「……本当だな。今までずっと……永い夢を見てたみたいだ」
遠いいつかに、彼は命を失いかけた。失ったことすらあった気がした。
これでまた死んでしまった、とつい先刻までは何故か本気で思い込んでいた自身に……これだから旧い与太話は良くない、と不意に笑いが込み上げてくる。
「……アフィはそんなに、泣いているのか?」
穏やかに、けれど不可解気に、彼は苦笑いを浮かべながら尋ねた。
「まだ会って一カ月もしない奴に……何でそこまで?」
その彼女のため、早く帰れ、と言う白黒の猫。不思議と頷けない彼は、白黒猫にぼふっともたれかかると、気軽な声で問いかける。
白黒猫はとても呆れたように、長く黒い尻尾でぱしっと彼をはたいた。
「そんなの、レイアスが好きだからに決まってるじゃない」
しかし彼が、今も理解し難い彼女の感情……どうしても消化できなかった事項はそこにあった。
「アフィがどうして、俺についてくるのかわからない。義手のことや、兄さんに似てるとか、どっちも俺には納得できないよ」
「ふーん。それがずっと、レイアスの本音?」
「俺にはよくわからないけど。何か理由があるなら……それは、俺を好きというのとは違うんじゃないのか?」
彼女の言っていたこと――兄に似ているや、生まれる前の何かが、仮に関係するとしたのなら。
彼女が求めているものは、今ここにいる彼ではないとも言えるのだから。
白黒猫は、そこで彼の本当の不服を察したようだが――
「別にいいじゃない。要するに一目惚れでしょ? そういうことだってあるよ」
彼女が何を、意識していようといまいと。
大きな違いはないこと……それが「縁」だと訴える。
そしてさらに、ある悪戯を、白黒猫はそこで始めた。
「……何だよ。気に食わないのはそこかよ」
「……!?」
「俺に似せられた奴を探す。それの何処が悪いんだよ?」
それは誰の声で、そして、どうして白黒猫が知っているのか。
元々話すことに声帯など使っていない白黒猫は、誰を映して、彼に何を伝えようとしたのか。言葉を呑んで彼は白黒猫の彩の無い目を見つめ、続きを待っていたのだが……。
「――って、アフィちゃんのお兄さんなら言いそうな気がする」
あっさり元に戻ったそれに、がくっと心から挫けてしまいそうだった。
「バステトは、アフィの兄さんを知っているのか?」
「里の外で、一度会ったの。ずっと誰かを探してて、それで私達の所まで来たんだって」
「……?」
彼は全く知る由もないが、幼馴染みならそんな出会いも有り得るのか、と一応飲み込む。
「もう本当、素直じゃないヒトだったよ。色々とはっきりさせないアフィちゃんも、ああ見えて凄く、素直じゃない子なのかも?」
「……へ?」
「きっと照れくさいんだよ。一目惚れだからついてくなんて、言うのは勇気いると思うよ」
「…………」
本当に最初は、ただの家出だったんじゃない? 白黒猫は彼女の旅をそんな風に語る。
どうしてなのだろう。それは一番、彼の胸にすとんと落ちる現実だった。
「そうだな――……何か凄く、わかるな、それ」
それを確かめに、早く戻ろう。そう思えた彼は、唐突に姿が薄まり始めた。
「……理由なんて――……ない方がいい」
もう一度白黒猫の体にもたれると、薄明るい灰色の空を見上げ……最後に彼は微笑む。
「もう、ここに来ちゃダメだからね!」
異界から影を投げ、時に自らたるヒトと入れ替わる、霊という本質を共有する獣――
心配そうな白黒猫がかけてくれた声に、有り難う、と彼が心から口にした直後に。
「レイアスのばか……! いつまで眠ったら気が済むの、なまけもの……!」
今まではおそらく、潮騒に隠されて届かなかったのだろう。
白いベッドで横たわる彼の、包帯が巻かれた胸に突っ伏す、彼女の声がやっと聞こえた。
怠け者って、と。
目覚め一番、どうしてもつっこんでおきたかった所を、彼は最初に口にする。
「怪我しただけで、ヒドイな、それは……」
「……――!?」
空色の召喚士の彼女はばっと顔を上げると、くしゃくしゃの顔で、彩の無い眼を開けていた彼をまじまじと見つめる。
まだぼろぼろと、子供のように大粒の涙を落としながら、寝台の敷物をわしっと掴み、大きく強く抗議の声を返した。
「なまけものじゃないなら……うそつき……!!」
「――」
「大丈夫だって言ったのに! 一緒に戦うって約束したのに!」
そして、彼女達を守ろうとしただけの彼をも知るように、旧い縁をもう一度声に出した。
「守ってくれなくていいから……いなくならないで……――」
「…………」
もう一度彼の胸に突っ伏し、今度は安堵も混じる声色で、彼女はまだ涙を流している。
どうしたら、これを止められるだろう。彼女の頭を無意識に撫でながら、彼が感じていた思いは一つだった。
できれば彼女の悲しい顔は――もう見たくないと。
こんな時に、気が利いた台詞を思い付く性質でない彼に、できることは限られていた。
「アフィは……俺のこと、好きか?」
この状況を見れば、さすがの彼も、言わずとも実感するのだが――
あえて直球に言葉にした彼に、彼女はハッ、と虚をつかれたように顔を上げる。
ぴたり、と涙の止まった彼女の端整な顔に、高速度で赤みがさしていった。
「……っっっ……!!」
慌てて顔を隠したいように口元を押え、俯いて衝撃の声を彼女は呑み込む。
ぷるぷると真っ赤に震えているその反応は、これまでにない説得力と破壊力があった。
「――」
息を呑んだ彼が改めて見ると、彼女は本当に、類稀な美人であることがよくわかった。
彼より一つ年上のわりには、少女らしさをたたえる顔は、放っておけない危うさを伴う。
だからこそ、常なる微笑みが映えるのだろう。これと離れれば、すぐにも哀しみの色に変わってしまいそうな気がして、まさに穴が開くほど、彼は無言で彼女を見つめる。
「……わたし、は……」
おっとりと、落ち着いた普段からは考えられない、弱々しく細くなった声。
おそらく、想いを直接言葉にすることが、本当は苦手なのだろう。だからずっと、彼の傍らに在りたい意思を、行動で示してきた彼女なのだ。
「……なんで、そんなこときくの?」
不服気に顔中を赤くし、否定する気は無いようだが、どうしてもそれは言えないらしい。日頃の笑顔はどうやら、この頑固さを包む、自然な仮面と言えそうだった。
対して元々、見た目通りに器用でない彼は、素直な想いを伝える。
「俺達はこれから、里に帰るから。……アフィが嫌でなければ、一緒に来るか?」
いつも通り無表情に、けれど少しだけ赤くなりながら、静かに強い口調で尋ねた。
「……一緒に来たら、多分、伴侶扱いされるけど」
行動は素直に、間髪入れずに、こくりと彼女は頷く。そこでやっと、彼も笑った。
里に帰らなければいけない彼は、こんな彼女を置いていくのは、何だか忍びなかった。
義手に刻まれた刻印を、彼女に返さなければいけない思いもある。共にいる方が確実というなら、それでも良かった。縁とはそういうもの、と胸の内で潮騒がささやいていた。
この空のような青い目の彼女と、共に歩いていくのは、きっと爽涼だろうと――
胸の奥には、きっとその、愛おしさと言える感情を呼び起こした大本がよぎっていた。
――アフィちゃんって、誰かが見ててあげないといけないと思う。
否定できなかった誰かの言葉。それが彼らの答だった。
彼女のためというのもおこがましいだろう。彼女を悲しませたくない自分のためだ。
たとえその想いが、束の間の潮騒に打ち寄せられた、旧い日の鼓動だったとしても。
精霊魔法とは凄いものだ、と、彼がしみじみ実感したことには――胸の傷はほぼ完全に、包帯の下で、痕跡が残る程度に塞がっていた。
あれから一週間が経過していたことを、駆けつけた悪友と幼馴染みがすぐに言ってきた。
「もう帰り始めな、とてもやないけど一カ月の期限に間に合わへんで!」
「悪いけどあたし、先に帰らせてもらうね。レイアスはもう少しリハビリいるでしょ?」
ディアルス国賓として迎えられた彼らは、王城の客間という、高級宿のような一室で、ベッドの上とソファで相談する。
「でも一人やと危ないやろ、アシュー」
「大丈夫だって。バステトはずっと、もう里の近くまで辿り着いてたし」
元々実体化した霊獣を持っていた幼馴染みは、本性の黒狼と普段の白黒猫を、その気になればどちらも実体で維持することができる。
そうしてやはり、逃げ道は確保していた幼馴染みに、彼も悪友もふう、と……あくまで一人で帰る、という相手に溜め息をつく。
「……アシューにはその方が、都合がいいのか?」
彼は淡々と、気持ち、残念な思いで尋ねた。おそらくは彼らと共に里に帰る状況――……二軍の村で反発を呼びそうなことを避けている、幼馴染みの苦労性を感じてのことだ。
短くもわいわいと和やかだった、四人での道中を思いながら。
幼馴染みはそこで、少しだけ意外なことを、けろりと答えた。
「都合とかどうでもいいよ。レイアス達といると、ハラハラさせられて嫌なの」
へ? と目を丸くする彼に、胸元に細い指を突き付けながら、幼馴染みは心底から不服そうな表情で続ける。
「ちょっと目を離したらこんな大怪我してるし、一週間も目覚まさないし、ヒトを勝手に別チームに入れるし。あ、タツクはあんまり悪くないね、ゴメンね」
一気にまくしたてると、すっきりした、と言わんばかりに、台詞とは裏腹の笑顔を見せた。
主に悪い、と名指しされた彼は、困ったように笑い返すことしかできない。
「……怒ったのか? アシュー」
「怒ったよ。信頼してくれてるからだってわかるけど、あれはないよね」
そんな風に、本音を話す幼馴染みの姿は、これまで見ることのできなかったもので……悪友もよくわかっていないまま、これが悪い状況でないとは感じ、黙っているようだった。
「ま、里に帰ったら色々、めんどくさそうだけどさ」
そしてすっと、幼馴染みは笑いながら、ソファから立ち上がった。
「……今からでも……遅くなかったのかな」
不意にぽつりと小さな声で――そんなことを、独りで呟きながら。
耳聡くそれを聞き取った悪友が、同じく独り言のように自然なつっこみを入れる。
「アシューなら全然間に合うやろ。逃げ足でも何でも、とにかく早いんやから」
多分悪友は何も考えていない。彼も幼馴染みの言葉にどれだけ色んな意味があるかを、あえて追求する気は無かった。
そんな彼らに、扉に向かった幼馴染みは、安堵したように笑って振り返る。
「あはは。取り戻せたらいいな、ホントにね」
手をひらひらと振りながら、そうして一足先に、自身の歩むべき道に帰っていった――ずっと変わらず大切な、彼と悪友の旧い仲間だった。
後で悪友から聞いた所によると。彼の胸を貫いた者のことを紫苑の少年から聞いていた幼馴染みは、蒼白な顔で空色の彼女と彼に付き添っていたと言う。
その相手のことは、彼もおぼろげにしか記憶が無い。紫苑の少年もよくわからない、と言っていたらしく、そこで幼馴染みが何を思ったのかを、今は知る由もない。
別室で静養中という紫苑の少年は、屋上にいた者の中で最も衰弱が酷かったらしい。
彼の胸の傷の治療や、魔法陣を斬り開いた活躍だけでなく、その撃破の直前に、彼と妖精の女に精霊の力で回復魔法を使ってくれていたというのだ。
まだ歩行すら心許ない彼は、空色の彼女に連れられて、少年に会いに向かう。
「――へぇ? 兄ちゃん達も、里に帰んだ?」
「……も?」
部屋では、少年が床の上に、自身の武器と調整用らしき器具をいっぱいに広げていた。面食らった彼と彼女を、ベッドに座らせながら、少年は何処か儚げに笑う。
「オレ、里で殺されかけて追い出されたようなもんだし、帰る気は無かったんだけどさ」
魔法陣を斬る時に、かなり盛大にその武器は壊れたらしい。しかしこの短い療養期間で、少年はそれもほぼ直してしまったようだった。
「里にいたはずのミティが、何であんな奴らの所にいるのか。母さんは何をしてるのか、埒が明かないから直接きいてくることにした」
「それって……オマエは、大丈夫なのか?」
こうして武器を手入れするのは、命の危機がある場所に戻るのを覚悟しているのだろう。さらりと話してはいるが、過酷な生い立ちの少年に、彼も彼女も顔を暗くする。
「ラスト君……たった一人で、そこに帰るの?」
「そりゃ、気分は良くないけどさー。今のオレなら、あんな奴らに殺られることもないし、いっそお礼参りしてきたっていいくらいだしね」
不敵に笑うようにしても、無理をしていると丸分かりの少年に、彼は何を言っていいかしばらくわからなかった。
彼と彼女が黙っていると、重たい空気を嫌うように、少年からまた話し始めた。
「そういや兄ちゃん。うちの里、多分兄ちゃん達の里から意外に近いんだ」
「――へ?」
そこで少年から聞いた話は、彼にとって――
何かが腑に落ち、同時にわからなくなった。そんな彼と少年の、不思議な縁の物語で。
「……ま、そんなわけでさ。兄ちゃんの義手、次に会う時にまで、今のを越えるやつ――オレが造っといてやるよ」
「……――」
以前に頼んだ時は、武器になるものは造らない、と言っていた紫苑の少年だったが……少年に関わったことで彼がさらに義手を傷め、また致命傷を負ったことに、少なからず責任を感じているようだった。
「こないだみたく、いきなり死にかけられるとたまんないし。魔法陣壊そうって言ったの、一応オレだしね」
しかし彼が嬉しかったのは、少年が、義手を造ってくれると言い出したことではなかった。
「……そうだな。オマエとは絶対に、また会う気がするよ」
次に会う時には。少年は彼らと行動を共にする気がある……そうしたいと思っていると、当たり前のように口にした前提が彼の心を温める。
どうやら、義手を造っても良い仲間と認めてくれたらしいこと――本当はあまり素直でない少年の真意を、彼は穏やかに感じ取る。
部屋を出てから、空色の彼女も、彼と手を繋ぎながら横顔を覗き込んできた。
「ラスト君、元気になるといいね。ね、レイアス」
「アイツなら大丈夫だろ。放っておくのは心配だけど――また会えそうだし」
不思議と今は、義手はぼろぼろであるのに、里にいた頃のように動くようになっている。
その右手を見つめていたら、誰かの声が聞こえた気がして……彼は遠く笑い返していた。
上:終幕
その泉に辿り着くと。紫苑の少年は改めて、大きなゴーグルを額に引っ掛け直した。
「ここだよ、ここ。オレの里の神泉に繋がるワープゲート」
彼らが慣れ親しんだ深い山奥――霊獣の隠れ里から何とか、子供の化け物も辿り着ける距離にある小さな湧き水を、彼らは囲む。
それはかなり遠回りになるのだが……結局紫苑の少年はまっすぐ自身の里には帰らず、彼らの帰り道についてここまで来ると、最後の分岐のこの場所でしばらく名残惜しそうに留まっていた。
悪友はとても物珍しげに、一見何の変哲もない泉を、膝をついて覗き込んでいる。
「へぇぇ、ここやったんやなぁー。おれらが昔、迷い込んだ場所って」
「そう考えると、確かに近いんだね。レイアス達の里と、ラスト君の里」
自分は意外に近所の千族だ、とディアルス王城に滞在していた先日、少年が彼に話した真意は……彼が腕を失ったのは、何と、少年の故郷の神泉であるはずということだった。
「オレが生まれる前に子供が迷い込んで、そのせいで、泉が穢れてオレなんかが生まれた、なんて。アホな大人は言ってたんだけどさ?」
迷い込んだ泉で、幼い彼らは、泉の主のような怪物と出会ってしまった。
それを赤い獣で倒すと引き換えに、彼は右手を失ったが、怪物の存在に困っていたというその里の巫女は、彼を保護して、怪物討伐のお礼として右腕を造ってくれたのだ。
さらに言えば、泉の中から見つけられた右手を元に、彼の短刀を造ってくれていた。
「それ、オレの母さんなんだよ。うちの里はみんな、物造りが得意な一族なんだ」
彼の義手に込められた「力」の気配から、少年は、その製作者に気が付いたらしい。
紫苑の少年と別れた後で、泉を振り返りながら悪友が少し残念そうに笑った。
「アシューも連れて来たかったやんな、ここ」
「そうだな。案外あいつ、覚えてて一人で来てるかもだけど」
彼らにとって、それは辛い過去でも何でもない。
仲間を守り、知らない里の怪物を倒した武勇談とすら言え、里を出る前後から右腕の動きがかなり悪くなった彼も、その思いは変わらなかった。
そんな男共の様子に、空色の彼女は困ったものだ、と苦笑っていた。
「それ、あんまり行きたくない所じゃないかな、アシュリン」
やんわりそうして、彼らの相変わらずのすれ違いに、小さなつっこみを挟む。
森が深まる薄暗い領域に入っていくと、彼らの里まで、もう幾許の距離も無かった。
北上すれば、海に面した山岸に出る。それとも少し南寄りに帰り、二軍の村で幼馴染みに声をかけ、その後に長老に挨拶をしていくか、と悪友と悩む。
「とりあえずシャルには誰も行くなやて、親父から周知してもらわなあかんな」
「……そう言えば都市長はあの後、行方不明だったか?」
ディアルスの王女はシャル都市長に対し、少なくとも「ストラグル」への関与が様々な者の証言で足掛かりがあるので、自国の法廷で裁きたいと言っていたのだが――
大国と三大商業都市は元々、どちらも人間が中心の地域だ。しかし都市間で協定を結ぶ商人の集団は、孤高な大国とは折り合いが悪いらしい。
「匿われたりかばわれたりしたら、検挙は難しいやろう、と言うとった。人間はなかなか、ややこしいしがらみん中で生きとんなぁ」
「……里もそれは、少しあるんじゃないのか」
言いながら彼も、さすがにあれだけ大きな事を起こした都市長に、一見は悠長な人間の対応はどうなのか、と思うところはあったが。
そうしたことを考えながら、彼はぽつりと、素直な気持ちを口に出した。
「……もう当分、旅はいいかな……」
ここ最近が目まぐるし過ぎたせいだろう。里に帰り、久しぶりに自宅でお茶を淹れて、のんびりと過ごすことを想像すると凄く安らかな気持ちになれる。
しかし悪友は、そんな平穏はまだ不要とばかり、すっかり穏やかな彼に文句を付けた。
「あのなぁ、オマエは出会いがあって義手も手に入りそうでええけどなぁ! おれはまだ何もはっぴーとちゃうし、そこんとこよろしく頼むでほんま!」
「……タツクもアシューに、声かければいいだろ?」
ゆっくり後ろを歩く、空色の流人の彼女の気配を感じながら、彼は否定せずに答える。
悪友はまるで、長年の宿敵を見るような目でぎらりと彼を睨み返した。
「ああくそ、まだそんなこと言うとんのか! タッくんまじギレやし、セレンもアシューもこんな唐変木の何処がいいねん畜生!」
「……?」
常々何かを勘違いしている悪友だが、それを言っても、違うスイッチが入るだけだろう。
振り返ると、平和に笑っていた彼に気が付き、微笑みながら彼女が手を振っていた。
その透き通る青い髪と目がとけ込むような、懐かしい朝の空の下で。
+++++
了

それはいったい、いつのことだっただろうか。
気が付けばオレは、何も無い部屋の青白い扉にもたれて、どうしていいかわからず座り込んでいた。
「……閉じ込められたのか? オマエ」
誰もいない真っ白な部屋にオレはいたのに、突然現れて静かに訊いたソイツ。見れば、俺と同じ、珍しい前髪の黒メッシュで――……誰かいないか、と呼び続けていたオレに、気が付いてそこに来てくれた暇人らしい。
「どうしてここに――戻って来たんだ?」
お人好しなソイツは、オレを連れて出る、と言って聞かない。
オレは俺に置き去りにされた。俺はそれに気付いてないから、仕方ないことなんだけど。
でも、オレを連れて行けば、ソイツが苦労することは目に見えている。
いつだって、何処にいてもオレは、有り得ない存在という空ろな札をひくのだから。
仕方ないから、オレがソイツの呪いを、引き受けてやることにした。
「――憎しみの赤い獣? ……だっせーな、ソレ」
何故か段々、小さくなっていくオレの手をひきながら――赤まみれのソイツは笑った。
+++++
Cry per A. -arrestare-
千族化け物譚 C1上篇 『紫苑の少年』
❖閑話:灰色の獣❖

何処に行っても、自分は一人で歩くしかないのだろう、と。
彼女がそれに気が付いたのは、その居場所でやっと友達と呼べる相手ができた時だった。
「アシュリンって何考えてるかよくわからなくて。でも話してみたらいいヒトだった!」
自分が見てきた世界は、多分ヒトとは少し違うのだ。
友人に悪気がないことはわかっていた。そのまっすぐさを有り難いとも思った。
そして同時に、この場所は一生自分を受け入れない確信が痛いほどに浮かぶ。
「大丈夫! 私はお父様のこととか気にしないから! アシュリンはアシュリンでしょ?」
ああ……やっぱりみんな、知ってることなんだな、と。
本当はわかっていたその空気を、彼女は知らないふりをしてきたのに――
これでもう、「知られていることを知っている」振舞いをしなければいけない。
親の不始末なんてバカな話だ。その汚名が拭えないことはわかっていても、気付かない風体でいることはできたのに……。
向き合ったところで変えられないこと、負け戦からはいつも逃げる彼女を、この場所は臆病とだけ評する。いつまでも好きになれそうにはなかった。
だからずっと、自分が好きになられることもなさそうだ、とわかっていた。
発端は本当に下らない話だ。家庭の事情、それも彼女が解決できる類でもない。
しかしそのせいで彼女は、この二軍の村に引っ越すことになった。
「お父さんが病気なの、アシュー。私達、二軍の村に行くことにしたわ」
人間でありながら、類稀な武技の腕を持ち、霊獣族の母についてこの隠れ里へやってきた父。
どれだけ優れた技術者であっても、武技だけで人間が化け物に敵うことはない。父は母より弱いことを受け入れ、それでも母を愛し、ここに住み着いた人間のはずだった……あくまで母という、まっすぐな化け物の視点からは。
「アシューは凄いな。教えれば教えるだけどんどん伸びていく。父として誇らしいよ」
幼い頃から彼女にも、武技を仕込んでくれた人間の父。しかし人間という生き物は、彼女の母が思うよりずっと複雑で……父の目はいつも、その笑顔と言葉の内容ほどに笑っておらず、その理由をやがて彼女は知ることになった。
「腹立つよな、アシュリンの奴。俺らよりさぼってるくせに、何であんなに動けるんだ?」
二軍の村の者からは、その苛立ちはまっすぐ、引っ越したばかりの彼女に向けられた。
その目の影は父と同じで、彼らはつまり、彼らより少ない努力で大きな成果を手にする彼女の才能――生まれつきの不平等に憤っていた。
父と母のように、化け物と人間の間だけではなく、化け物同士でもそれは当然にある。しかし父に自覚はなく、そして娘がそれに気付いているとは、思いもよらないようだった。
強くなる度、父は彼女を心の何処かで疎む。本当は妻や娘より強く在りたかったらしい。
だからそれは――必然だったのだろう。
病の床に臥した父が、父のために薬の材料を買いに出る母が不在の間に……その材料で薬を作り、彼を介抱する村医者――化け物としては弱い女と、深い仲になってしまったのは。
どうしていつも、気付かなくて良かったことが見えてしまうのだろう。
家庭でも居たたまれなくなった彼女の大きな失敗は、彼女がそれを勘付いたと知る由もない父に、母が可哀相だ、と詰め寄ってしまったことだった。
「君には関係のないことだろう。何様のつもりなんだ、子供のくせに」
動揺した父は、初めて彼女の頬をその弱い手で張った。そしてそれに強く罪悪感を持ち、彼女によそよそしく当たるようになった。その態度が、罪の意識に根差すのを感じていた彼女は、父を嫌うこともできなかった。
できることはただ、母の代わりに、薬の材料を買いに出るようになることだった。
父は母がいない時の淋しさを、村医者と過ごすことで埋めているのもわかっていたから。
元々彼女は、一軍の村から来たこと――そこにいる憧れの対象だった長の息子や、鬼子と呼ばれても人気のあった少年と仲良くしていたことで、やっかみの的になった。
その上に父の醜聞と、彼女自身の天性への憤りが、彼女と周囲の間に大きな溝を作った。臆病者として馬鹿にされる時が、素直な自分を見てもらえている皮肉さでもあった。
――……そっか。みんなには……あたしが幸せ者に見えるんだ。
その羨望も、無理のないことではあった。
父が病気だから、と一人でも里を出ることを許された彼女。他の者達より短い時間で実体化を制御できるようになったのは、元々実体化した霊獣を持っていたなど、素質あってのことだろう。
でもそれが――何だと言うのだろうか。
父のことがなければ、そんな立場になってまで、外に出る条件である実体化の完全制御にこぎつける必要はなかった。彼女だってゆっくり前に進みたかった。
けれど本心を口にすれば、父の汚名を認めることになってしまう。もやもやとした村の空気の中で、それを決定付けたくなかった。
「お父さんを信じて、頑張っていこうね。アシュー」
母はいつも、そうして笑っていた。母のその気丈さは、彼女は今もわからないままだった。
――……母さんは、平気なのかな?
本当に父は潔白と信じているのか。それとも村医者との関係を知っていてそう言うのか。
後者のようでいて、本気で前者だと思わせるほど、母は理解できないひたむきさで……。
――平気じゃないのはあたしだけ? それとも……。
それを明るみに晒そうとすれば、母を徹底的に傷付ける予感がどうしても拭えない。
人間の父と化け物の母、本当に彼女はその中間なのか。どちらにも結局、本心で話すことはできなくなった。
村での付き合いも同じだった。とりあえず笑えば、無難に過ごしていける。
居場所は見つからないままで。内でも外でも、彼女は警戒の微笑みを絶やさずに過ごす。
いつしか、自身を知らない外の者にしか、短い間でも彼女は打ち解けられなくなった。
それはおそらく、大切なものを大切にできなかった自分への永い罰だろう。
「どんなに自分が傷付いても、守らなきゃいけない場所ってあると思うな」
外界で出会った、ワケありな笑顔の少年の言葉。彼女にはそれができなかった。
一軍の村に戻れることはない。戻ろうとしたら、また彼らに負担をかけるだけだ。それが怖くて、変わらぬ想いを向けてくれる者からもそっぽを向いた。
大切な彼らに向ける唯一の信頼……それは、笑わない姿を見せられることだけだった。
「アシュリンは偉いわ。お父様の薬を買いに出るために頑張ったなんて」
ただ一人、強くなるのは外に出るため、と心を伝えた相手は故郷で友人になってくれたが。
――……そっか。セイレーネには、あたしがそう見えるんだ。
見上げられるのも見下げられるのも、彼女は嫌だった。だからそこからも、笑って逃げた。
――……オマエ、ちゃんと闘えよ! アシュ―!
唯一同じ視界を、いつか叫んでくれた相手も。結局置いていくことを、彼女は決める。
+++++
❖閑話:紫苑の霊❖
いつからか、オレは魔法使いなんて呼ばれるようになっていた。
それは本当の所、大嘘なんだけど。オレがやってることは魔法と正反対の、魔道と言っていいかもよくわからない、母さん達は霊法と呼んでる独特の「力」だ。
「ラティちゃんは、精霊さんと話すの、とても上手ね」
妹――と言うと、いつもそいつは怒る。
体が弱くて、でも頭は良くて、色んな道具を思いつくけど、実際に造れる余裕はない。
それがオレの双子で、こうやって上から目線に姉貴面をするミティだった。
ベッドの上が居場所の姉貴は、肩から母さんが造ってくれたショールをかけて、本当に弱々しくてオレは気が気がじゃない。けれどいつも、全然関係のないことをオレ達は喋る。
「精霊使いって何て言うのかな。魔導士とかかな? オレ、霊法士より魔導士になりたい」
「使ってるんじゃないでしょ。精霊さんはお友達だよ」
姉貴は、しんどい時でもほとんどそんな素振りは見せず、オレが行くとこうして笑ってくれるのが嬉しかった。
「どうして霊法士はイヤなの? ラティちゃん」
「だってそれだと、ミティには敵わないだろ」
「でもお母様は、きっとラティちゃんに、後を継いでもらいたいと思ってるよ?」
この部屋にずっといて、本しか読んでいない姉貴は知らなかった。本来、生まれるはずのなかった男であるオレのことを、姉貴が受け継ぐべき精霊を奪った邪魔者だって――
姉貴と母さん以外の女達は、みんなオレを嫌ってるってこと。
この里にはそう、女しかいない。うちはそういう特性の化け物らしい。
でもオレと姉貴が生まれる前に、里を守る精霊を宿す大切な泉が穢されて、そのせいでオレなんかが生まれた、と婆様が言ってるのを聴いたことがある。
――だから最初から、あのような馬の骨は間引きするべきだったのでは?
――でも母上……それでミスティルに精霊が遷るとは限らないのです。
精霊に守られ、泉の精霊の子を巫女が宿すというふれこみがうちの里だった。
他の女達も、もっと下級だけど精霊の子供を宿すらしい。
――そもそも、泉が本当に変質したのはもっと以前からです。それはご存じでしょう。
母さんは婆様にそう反論し、オレも姉貴も大切に育ててくれた。
けれど婆様の勧めで、他の女達の前ではオレに冷たく当たるようにしていた。
「ごめんね、ラスティル……弱い母様を許してね……」
オレは別に、そんなのどうでも良かったんだ。
オレのせいで精霊の宿らなかった姉貴が、それで体が弱いのも知ってたし……母さんは他の奴らの前では冷たくても、その後はいつもウソみたいに、優しく笑ってくれたから。
一番大変なのは多分母さんだ。オレを守って姉貴も支えて、その上に他の奴らまで気を使わないといけない。
「ごめんね……本当にごめんね、ラスティル……」
だからオレは……殺されかけて里から逃げた日も、母さん達のことだけは恨まなかった。
オレの精霊を何とか姉貴に遷すのだ、とある日突然、オレは半殺しにされた。虫の息のオレを、母さんは泣きながら精霊の力で助けて、外の世界の怪しいおっさんに託した。
意識が無かったオレは、目が覚めたら変なおっさんの仕事場で、ひたすらビックリ状態だった。
「悔しかったら強くなれよ。男はどうせ、いつか一人立ちしなきゃならねーんだ」
「……」
オレはそれまで、一人になるなんて考えたこともなかった。
姉貴のそばにいるのが当たり前で、姉貴を守るんだって心に決めてた。
母さん以外の誰とも深く関われなくて、オレと同じ顔の目はいつ見ても寂しそうで――華奢過ぎる体は、少しでも触れたら壊れてしまいそうに危うかった姉貴。
でもおっさんは、ここにいて物造りの腕を磨け、とオレに言った。
「オマエのかーちゃんは大したもんだったぜ? オマエは剣や魔法、どんぱちの方が好きみたいだが、それで食ってくには今は平和過ぎる」
「……え?」
魔導士になりたい。ずっとそう思ってたオレを見透かすかのように、おっさんはニヤリと言いやがった。
「自分の生まれに反発なんて、ガキくさい真似はよせ。使えるものは全部使え。それがこの世界で、しぶとく生き抜いていく秘訣だ」
「……む……」
自分の中にいる精霊はともかくとして、うちの化け物独特の「力」――霊法を、本当は使いたくなかった。
でもそんなオレをガキと笑うおっさんがむかついて、そこからオレは、おっさんの弟子……というか小間使いみたいに、こき使われる日々が始まる。
おっさんはいつも、オレの特殊な物造りを見ては、魔法ってすげぇな、と感心するように言っていた。
「魔法じゃないよ。オレは魔法なんて使えないよ」
「どう違うんだ、それ? オマエ何で、褒めてるのに素直に受け取らないんだ」
この「力」を、相変わらずオレは好きじゃなかった。だから実は強かったおっさんの所で、武器の使い方を教えてもらうのが一番楽しかったし、暇があれば精霊と話して、そっちの「力」を上達させる方が早かった。
「魔法使いが嫌なら、魔導士なんてどうだ?」
にやにやとおっさんは、オレの昔の願望なんて知らず、ある日突然そんなことを言った。
「魔法使いは魔法だけだけど、魔導士は何でもできるんだろ? そう聞いてきたぜ!」
「……何だよそれ。何処できいてきたんだよ、そんな与太話」
何でもできる魔導士。魔道というのは確かに、色んな「力」のことを包括した概念って言うし、間違いではないんだろうけど。
でもその頃のオレは、色んな世間の風に当たって、適当にすれてきたお年頃なのだ。
「何でもできるなら、何でも屋とかで別にいーじゃん」
「なるほど、それがいーんじゃねぇ? オマエみたく、何でも頑張る奴にぴったりだろ」
「…………」
おっさんはずっとこうして、いつも軽い口調で、気が付けばオレを褒めてくれていた。
体を壊して隠居しちゃったけど、きっと趣味で何か造りながら養生してるに違いない。
それからオレは、何でも屋として、色んな商業都市を一人で渡り歩いて。シャルの都で化け物少女の違法道具の噂をきくまで、武器も精霊も、物造りの腕も磨き続けて生きていく。
+++++
千族化け物譚❖Cry/A. -arrestare-
ここまで読んで下さりありがとうございました。これにて上篇は終了となります。
下篇はやや暗めのため、不定期公開としています。
別作DKL'sと関連が深いのは下篇であり、星空文庫で非公開時には下記にもC1全編を掲載していますので、良ければどうぞ。
エブリスタのCry/A(C1)→https://estar.jp/novels/23724267
ノベラボのCry/A(C1)→https://www.novelabo.com/books/6333/chapters
初稿:2016.3.1 C1 Cry/A.
※2023年9月にC2、10月にC3掲載予定ですが、本作C1とは主役が変わります
※2024年11月下旬に、C1後日談のELIXIRを星空文庫に不定期公開で掲載するか検討中です


