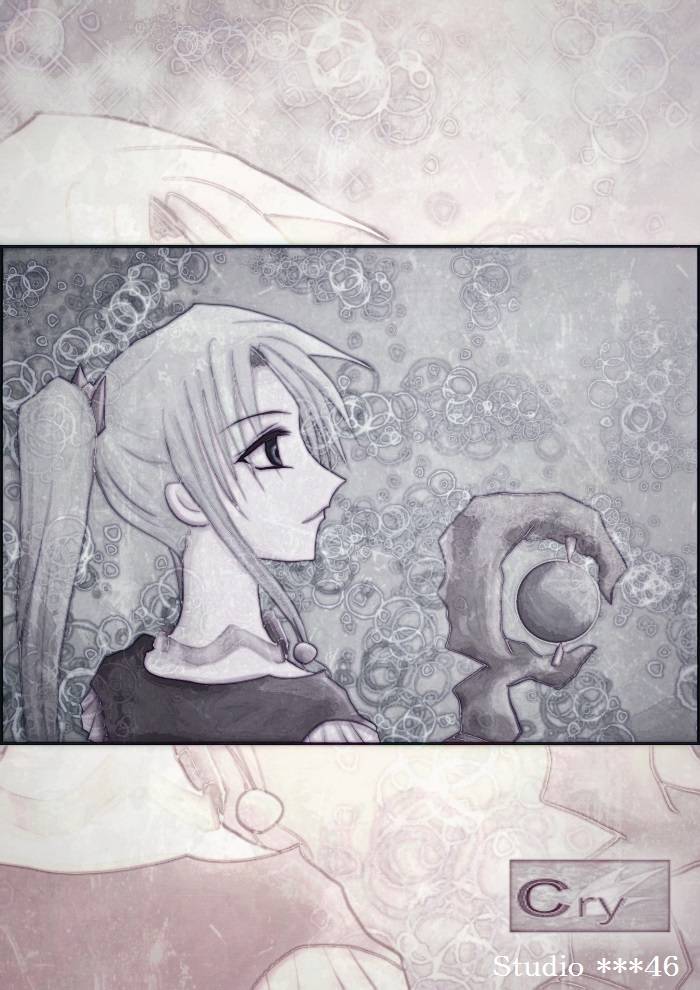
千族化け物譚❖Cry/A. 完結篇
人の姿をしながら人ならぬ「力」を持ち、心は人間に近い「千族」達が運命のいたずらや宿縁に翻弄される、召喚獣活劇ファンタジーの下篇です。
暗い要素が少なからずありますが、バッドエンドではありません。
エブリスタ版では特典にしかない閑話、「赤い道化と城の鼠」「黄雀雨」を収録しています。いずれも暗くはありますが、後の物語につながる話であるため、未来には希望が残っていると思っていただければ幸いです。
update:2023.10.27 Cry/AシリーズC1
※掲載形式検討中のため、一時公開中断する可能性があります
❖下❖

生まれる前に、わたしは私と小さな約束をした。
望みは一つだけだった。大切なものを、どうしても探しに行くために。
「それであたしから……居場所を奪ったの?」
望んだのが私、責めるのもわたし。
置き去りにしたくはなかったのに、そこには席が二つしか無くて、わたしは私を手放せなかった。
その席すらも、本当はわたしのものじゃなかった。
わたしは魔物だ。だからずっと閉じ込めてきたけど、そんなわたしに私は笑ったのだ。
「……大丈夫だよ。そうすればあたしも私も、みんながまた会えるんだから」
私は嘘をついた。わたしを外に出すために、あたしやみんなから顔を背けた。
でもそれは良かったことだって。たとえ私が、変わり果てて全てを奪ったとしても。
ずっと私は、わたしが幸せになることを、希んでいたのだから――
+++++
Cry per A. -arrestare-
千族化け物譚 C1下篇 『魔竜の巫女』
~Air-like summoner~
下1:白 -飛竜-
ごめんなさい、と聴こえた気がして、彼は薄暗い廊下を振り返った。
「……――?」
黄昏に包まれた古い城に、小さな出窓から赤い夕陽が差し込んでいる。
その狭い回廊にいるのは彼だけであると、暗い城中の鮮やかな光に改めて悟る。
「……空耳――だよな」
ここのところ心労が続いたせいだろう。すぐにそう納得すると、しばらくさまよった後に立ち止まった足を、再び目的の場所へと向ける。
日中に訪れたその白い古城は、滅多に客を迎えることはないらしい。
通された客間はあちこち埃だらけで、彼の故郷である西の大陸――通称西洋風であるが、石畳で広いわりには家具がほとんどなく、まず感じたのは冷たさだった。
「まさかこんなに早く……両親に挨拶とか、な」
歓迎されているとはとても思えない。半年前に出会った連れ合いの実家という場所に、思いがけず来ることになった彼は、大きく長い溜息をついた。
先にこの古い城の主、実の親に事情を説明すると言って、空色の長い髪と青い目の連れ合いは、同じ色合いで鋭い美貌の女性と共に別室へ行ってしまった。
一人取り残されて放浪していた彼は、約束通り、夕暮れ時に広間に顔を出す。
ポニーテールを揺らして駆け寄ってきた連れ合いの向こうにいたのは、二人の若い男女……どう見ても二十代にしか見えない者達が、並んで座って彼を待ち受けていた。
空色の青い髪と目の女性は、連れ合いを出迎えて付き添っていった美女で。
「ごめん、待たせた? 改めて初めまして、レイアス君」
さっぱりとした物腰で、長い髪をまっすぐ下ろした凛とした雰囲気と、美貌にそぐわない質素で動き易い軽装の佳人が、連れ合い曰く「母さん」らしい。
「ティアリスから大体話は聞いたぜ。うちの大事な娘に手ぇ出したのはてめーか?」
けらけら笑うもう一人の者。とても軽いノリで、歌い手のように洒落た風貌の、尖った銀髪に青白の目で鋭い顔立ちの男。それでも童顔なところが連れ合いによく似た者が、「父さん」とのことだった。
「……初めまして。アフィのお父さん、お母さん」
連れ合いは二つの名を持つという。ティアリス、と本名を呼ぶ二人と、通称を略した仇名を無愛想に呼ぶ彼に、両親という者達はそれぞれの表情で意味ありげに笑った。
完全に異邦者である彼は、一言で表せば、物静かで無表情な灰色の髪と眼の男。
上下とも軽装の黒衣がよく似合う彼を、連れ合いが改めてその両親に紹介する。
「レイアスだよ、父さん、母さん。これからよろしくね」
それだけか……とつっこむ暇もない連れ合いは、いつもの平和で端整な笑顔を浮かべる。
彼より一つ年上だが、幼げに見える連れ合いには、胸元と袖口が白いひらひらで飾られた黒い筒型衣が今日もよく似合う。洒落っ気のない母とは本当に似ていなかった。
「それでティアリス。私達にききたいことって?」
単刀直入に本題に入った無愛想な母に、隣の父が合いの手を入れるように続ける。
「さすがに、彼氏の紹介したくて来たわけじゃないだろ?」
「そんなことないよ。レイアスのことも知ってほしかったよ」
先に両親と話したことは、連れ合いが彼と会うまで預けられていた所を出た経緯と、彼の素性が主だという。彼と連れ立って実家に帰った理由は、まだあまり説明していないらしい。
「ま、レイアス君不幸属性強そうだし、うちの子の相方としてはストレート合格だけど」
「……それ、普通反対じゃないですか」
彼の人物評とその答に、真面目に考える彼は面食らう。大事な娘なら、幸せな相手と添い遂げてほしいものではないだろうか。
「ティアリスも大概不幸属性だからなー。お互いその方が気が楽ってもんだろ?」
ひたすら軽いノリの父が、向かいに座る娘に満面の笑顔を見せて、娘もえへへ、と笑い返す。
彼は彼で、普通ならそんな、親にも言われる不幸な娘を連れ合いにしたいとは思わないだろうが。
「……故郷も仲間も失いましたが。俺で良ければ、アフィは全力で守ります」
静かに厳しい覚悟で口にした彼に、うんうんと頷きながら、その両親は苦く笑った。
「同類同類。ここにもオレ達以外、ほとんど生き残りなんていねーんだからさ」
そうして彼は、この幻の場所に来ることになった理由を、強烈に痛ましく思い起こす――
大陸と島の中間のような規模のその地は、「竜宮」というのだ、と連れ合いは言った。
「父さんと母さんは最後の竜族として、ずっとここを守ってるの」
「……まだいたんだな。竜人の生き残りって」
用件が終わった後で、今日は泊まれ、と客間に戻された彼に、自室に帰る前に連れ合いが改めて素性を話し始めた。
「ここは昔、沢山のヒトから狙われる場所だったからって。父さんと母さんが封印して、今は幻の大陸になってるみたい」
それは本当に途方もない話で、故郷にいた頃の彼なら信じなかっただろう。
ヒトの姿をしながら人ならぬ業を持ち、千種を越える化け物、千族。それが司る世界の神秘――「力」を使う者の中でも、自然の脅威である竜とは、古い時代に最強と言われた伝説上の化け物だった。
「それじゃ二人は……ずっとこの城に、二人だけでいるのか?」
「うん。わたしや兄さん達は自由に生きていいって、外に出してくれたの。世界には危険が一杯だけど、悔いの無いように生きろって言ってくれた」
半年前に出会った連れ合いは、青い珠玉を先端に囲む仕様の木杖を持つ。その「力」は竜専門の召喚士……自ら竜と成れる竜人では無いが、竜たる自然の脅威を喚び出して使役できる破格の化け物なのだ。それが竜の娘である所以なら、彼も納得がいく話だった。
「後は『魔竜』のことだけ……できればいつか、聞いておきたいな……」
養家でそう呼ばれていた連れ合いが、客間を出ていった後に。
彼は一人、若過ぎる親を思い浮かべながら、ベッドにごろんと仰向けに転がって呟いた。
彼の故郷がある西の大陸は現在暑い季節だが、「竜宮」の夜はなかなか冷えるようだった。
世界地図に載っていないような所にいるせいだろう。眠れずに城を抜け出し、ぼけっと外を歩いていた彼には、ひどく現実感が無かった。
「森ばっかりなんだな、ここは……幻の大陸なんて、信じられないな」
ふわふわと落ち着かないままの頭は、半年前から続く激烈な痛みを、せめて今だけでも忘れさせてくれる。
「不幸属性……か……」
連れ合いも今日は、両親に会えた喜びで元気にしていた。けれどここに来るまでは彼と共に、暗鬱で慌ただしさに救われる日々を過ごし……一人の自室では泣いていそうだ、とふっと彼は顔を歪めた。
考えても仕方がないことなのはわかっている。それでも考えてしまう。
一刻も早く目的の場所へ行きたい。ゆっくり寝ている場合ではない。それでこうして、体を動かさずにはいられないのかもしれない。
「……もう半年……たってるのにな」
今更焦ったところで遅過ぎる、と彼も連れ合いも何処かでわかっている。
せっかく連れ合いは実家に帰ったのだから、一晩くらい両親とゆっくり過ごせばいい。だから彼はふらふらとさまよい、朝までの長い時間を見知らぬ暗い森で潰しているのだ。
そんな彼のことを、もしや見かねたのだろうか。
何かの縄張りたる森を侵した彼の元へ、その蒼い何かは、あまりに唐突に――悪戯としか言えない気軽さで、神々しさすらも伴う、不敵に整った姿を顕していた。
――よぉ、と。
重たい夜を蹴散らす強気な声を、獣道の先に突然現れた同年代の男が、気安く彼に放っていた。
「――……?」
夜の闇の中、鋭い目を蒼く光らせる男の姿は、彼の眼には白っぽい空気を纏うように視えた。しかしその空のように青い尖り髪は、とても見過ごせるものではなかった。
「よぉ。オマエがティアリスの連れて来た、俺にそっくりな彼氏って奴?」
やがて月明かりが森に差し込み、拙く照らし出された男は……彼の連れ合いと似た色の髪で、ひいてはその母にそっくりな、あまりに凛と整えられた顔立ちだった。
「――え……!?」
何より彼が驚いたことには、男の前髪には、一房だけ黒く染まる髪束があった。
生まれつき同じ位置に同じような黒い前髪を持つ彼は、髪の色と顔付きを除けば、男の言う通り背格好が男によく似ていた。
彼は自分の兄に似ている、と連れ合いは口にしたことがあった。それならそこにいる男のことも、一つしか考えられなかった。
「アンタは――……アフィの……?」
「おっと。俺はまだ、てめーのこと認めたわけじゃないんだからよ?」
男は楽しげに笑いつつ、両端に両刃の剣を誂えた長棍を取り出し、くるりと構える。
ちょうど間合いからギリギリ外れる距離の彼に突付けるように、片手で中段にそれを掲げた。
武器を向けて、妹に近付く彼を威嚇するかのような兄らしき男。彼は真面目に、彩のない眼で向き合うしかなかった。
「俺を認めるって……アンタは何が目的なんだ?」
「……そーだなァ、どーすっかなー。んじゃまず、俺のこと、お兄様と呼びな?」
「――誰が」
思わず即答した彼に、不真面目そうな存在の相手がククク、と笑った。
「いーのかねぇ、そんなこと言って。てめーは俺に、訊きたいことがあるんじゃねーの?」
「……?」
「ティアリスが何で、てめーについてきたか、気になってたんだろ? あいつ多分、何も言わないだろうしな」
あくまで軽口を叩くように言う男だが、その目の蒼には何とも、真意の掴めない奥深さがある。兄は別世界にいる悪魔だ、と連れ合いが言っていたことを彼は思い出した。
初めて出会った時に、連れ合いは彼を兄にそっくりだと言った。その後に、一目惚れに近い状態で、彼と行動を共にするようになっていたのだが……。
――わたし、信じてたよ。兄さんが伝えてくれた、いつか会えるヒトのこと。
いつか連れ合いが、無意識に口にした言葉を彼は覚えていた。無駄だろうと思いながら不可解過ぎたその事柄を、尋ねずにはいられなかった。
「……アンタは、俺のことを知っているのか?」
行方不明であるはずが、いったいどうして現れたのかわからない蒼い目の男は、呆れたように長物を下ろし、両腕を組んで彼を見据えた。
「ちげーよ。てめーのことを知ってたのは、俺じゃなくてあいつだよ」
「……え?」
「オヤジ達があいつの記憶を封印する前に、俺はあいつから頼まれただけだ。忘れた後のあいつに必ず、一番大事なことだけは伝えてくれってな」
連れ合いは自称記憶喪失だ。身内の記憶などはあるわりに、昔のことを覚えていない、と言っていたのだが……その仕掛け人は何と、あの実の両親らしい。
「大事な……こと?」
「そうそう。それが聞きたきゃ――俺を倒してみせな?」
そうして男はまさに悪魔の微笑みを浮かべ、武器を持ったまま両手を大きく広げ――
次の瞬間、何の前兆も無くソレは、驚愕する彼の頭上に白白と具現していた。
「な――……!?」
彼と男を月光から覆い隠す巨体を、無音で滞空させるその白い獣。
すらりと狐のようにしなやかな五体に、長く先の尖った尾を振り、鳥より固くコウモリより端整な翼をはためかせている、白銀の巨獣。
そんな獣を表せる言葉は、彼は一つしか思いつかなかった。
「これは――……飛竜……!?」
この世界には、大きく分けて、三種の系統の強大な「力」が存在する。
その三つが「獣」と「自然」、そして「神威」だ。最強の「力」が自然、最多は獣、最上が神威――神格の化け物である天使や悪魔と、千族の間では言われているのだが……。
「アンタ本当に、何なんだ――……!?」
氷という自然物で体を構成されているため、真っ白に見える獣を操る男は、連れ合い曰く悪魔だという。三系統全ての脅威を乱立させる相手に、彼は面食らうしかない。
白い飛竜の影を受けて、顔の見えなくなった蒼い目の男は、きらりと悪魔の目を光らせた気がした。
「てめーも『力』、出し惜しみしてんじゃねーよ。ここじゃそんな余裕は通用しねーぜ?」
「―――」
「俺達の可愛いティアリスに手を出す不遜な輩は、早い内に始末してやるよ」
「って――」
目前の相手がいったいどれだけ、妹を可愛がっているかはわからないが。
今まさに尖鋭な口から闇を震わす咆哮を放ち、彼を喰らわんと飛びかかる白い飛竜が、本気なのかと背筋に冷汗が走った瞬間……――
「こらぁー!! 何をしてるの、アナタ達―!!」
謎の脅威に全く動けなかった彼の真上で、白い飛竜はすんでの所でぴたりと止まった。
「もう、相変わらずイタズラばっかり! 兄さんはそんなに妹バカじゃないでしょ!」
珍しく大きな声を出して割り込んだのは、髪を下ろした普段着の連れ合いだった。
「……え?」
唖然とする彼の目前で、蒼い目の男は最後に一度、ク――と不敵な笑みを見せると……まるで夜露となったかのように、白い飛竜共々霧散してしまった。
男がいた場所を茫然と眺める彼の元に、連れ合いが浮かない顔で駆け寄ってくる。
「大丈夫? どうしてレイアス、ぽぴゅーんの森にいるの?」
「……ぽぴゅーん?」
はい? と彼は、無表情のまま大きく首を傾げる。連れ合いは近い茂みからひょいっと、白く丸々とした毛玉のようなものをあっさり取り上げた。
それは大きな丸い猫の頭に、小さな黒い手足と細長い尾が生えたような、ぬいぐるみにしか見えない謎の生物だった。
「ぽぴゅーんは竜宮にだけいる神獣で、見えて触れる幻を創ることができるの。わたし達には小さい頃からお友達だけど……ゴメンね、びっくりしたでしょ?」
「神獣……幻……??」
そこで彼はようやく、蒼い目の男に禁じえなかった違和感の正体を悟った。
「なるほどな……それで、力じゃないのに、『力』だったのか……」
「――?」
「危険でないのはすぐにわかった。でもじゃあ何なのかが、さっぱりわからなくて」
とりあえずそれが、本物の「兄」ではないことも感じて、兄さん呼びを躊躇った彼だった。
「……お兄様って、呼ばされてないよな? アフィ」
たとえ本物でも、それは嫌だ、と珍しく露骨に拒否感を浮かべずにいられなかったが。
連れ合いは謎の生物を何処かに解放した後に、彼の腕を取る。城に戻る方向に歩き出しながら、彼を見つめて穏やかに微笑んだ。
「兄さんは兄さんだよ。名前を呼ばれる方が好きそうだし、お兄様はないんじゃないかな」
「……」
良かった。と、彼が安堵したのも束の間のこと。
「でも呼べって言うかも。ヒトをからかうことが大好きだし、レイアスのことなんて一目で気に入っちゃいそう」
「――え」
くすくす、と連れ合いが、暗く青い目で最近はあまり見せなかった妖しい笑みをたたえる。
それもこの神獣の森の効果なのか、連れ合いは確かに本物なのだが、暗闇の中でさらりとなびく髪はまるで別人のように、何故か真っ黒に見えた。
「ぽぴゅーんはちゃんと、現実に即した幻を創り出すもの。悪ふざけは一杯するけど嘘は言わないし、わたし達に何かを伝えようとすることもあるよ」
それであるなら、あの蒼い目の男が、いくつか口にしたこと――
彼の連れ合いについての断片的な情報も、真実である可能性が高くなってくる。
――てめーのことを知ってたのは、俺じゃなくてあいつだよ。
幻である男に詳細は訊けなかったが、腕を組んでぴったり寄り添う連れ合いに、彼はひとまずそれを尋ねてみた。
「……アイツが、アフィは俺のこと、知ってたって言ったよ」
「?」
「アフィに何か、大事なことを伝えたんじゃないのか? アフィの本物の兄さんは」
「…………」
連れ合いがふっと立ち止まる。腕を離さないまま、上目遣いに彼の彩の無い眼を暗い青の目でじっと見つめる。
――聴かない方がいいよ、と。憂い気で静かな答を、連れ合いはそっと口にした。
「聴いたらレイアス……心配事が増えるだけだから」
月明かりも雲に隠れ、青い目はますます、暗い影を映して彼を見上げる。
「今はもっと、大事なことがあるでしょ? そのためにわたし達、ここまで来たんだし」
「…………」
ずっと変わらない笑顔の連れ合いは、彼には悲しげにしか見えず……彼は思わず、空いた手で連れ合いを強引に抱き寄せていた。
「……レイアス……?」
「……アフィのことだけは……何があっても失くしたくない」
胸の中で表情の見えなくなった連れ合いが、ぐっ、と息を呑む。そのまま彼は強く、後ろ頭ごと抱えた。
「次で駄目なら――もう諦めよう。……新しい所で、静かに暮らそう」
「でも……わたし、まだ……――」
彼の右腕を掴む連れ合いの両手に、義手であるその手を軋ませるほど、強い力が入っていった。
「まだ……諦めたくないよ、レイアス」
震える声は涙混じりで、諦観による平穏を望む彼とは違う、強い執着がそこにはあった。
故郷も仲間も失った。連れ合いの両親にそう告げた彼が、半年前の初めての旅――僅か一カ月の不在の後に、帰るべき場所を失くした現実を、連れ合いは知っている。
「……わたし、信じないから。……アシュリンがもう、何処にもいないなんて」
その時からずっと行方の知れない彼の幼馴染み。連れ合いとも打ち解け、数少ない大切な友である者の名前を……まるで彼と自らを鼓舞するように、改めて口にしたのだった。
下2:黒い夜明け
一寸先は闇。そうした人間の言葉が、それほどふさわしい状況は無かった。
まさかたった一カ月と少しの間に、留守にしていた里が何かに襲われ、化け物だらけの強靭な隠れ里が、帰った時には廃村になっていたなど。
そして彼らより少しだけ早くそこに帰ったはずの幼馴染みが、僅かに生き残った仲間達から揃って見放されていたのは、痛恨としか言えなかった。
「……何回占っても同じ結果よ。彼女はこの世にはいない、それだけ」
「…………」
連れ合いの旧い親友である妖精の女。現在は「ディアルス」という人間の大国で、顧問の魔女として働く者が厳しい顔をする。王城でありながら質素な客間のソファで、並んで座る彼と連れ合いは、黙り込んで俯いてしまう。
「私はあまり、占いは得意じゃないから。うちの親かアースフィーユのご両親なら、多分腕のいい占い師を知ってると思うけど」
一見つれない声色ながら、そうして彼らに竜宮行きを促したのが、その妖精の女だった。
女は肩で束ねた長く柔らかな金色の髪に紫の目、尖った耳に町娘の服装だが、実際には凄腕の魔女である珍しい妖精だ。自身の魔法にプライドを持つ女が、己の占い結果を貶めてまで口にしたのは、それだけ彼らが憔悴して見えたのだろう。
顔を上げた連れ合いが、苦しい顔で笑いながら妖精の女に礼を伝えた。
「ありがと、ナナハ。それじゃ直接、父さん達にききにいってみるね」
「……その後はディアルスに戻ってきなさいよ。ここで貴方達の戸籍を用意できるように、リアラ様は動いて下さってるから」
つんとした態度の裏で、できる限りのことをしてくれている相手に、彼らはただただ深く頷く。
妖精の女にそうやって占いをしてもらうまでに、幼馴染みが失踪してから既に五カ月が過ぎていた。
初めの一カ月は、里の存在する山中を隈なく探し回り、近くの妖精の森にまで乗り込み、行方探しに力を貸してもらったほどだったが……。
「残念ですがアースフィーユ……この近辺で反応は無いとしか言いようがありません」
「近辺どころか、世界中で無反応ですわよ。何処を探しても時間の無駄ですわ」
連れ合いの養親である妖精達は、口を揃えて諦めろ、と早々に口にしていた。
それも占いの結果であるが、占う媒介となった物は、荒れ野の里に不自然に落ちていた幼馴染みの持ち物だ。
彼が昔に贈り、大切にしていたという黒いヘアバンド。加えて、幼馴染みが常に連れている大猫――四肢と耳、尾の黒い白猫がしていた、金属製の首輪もあった。
その首輪を造った者は、彼らと知り合って間もない何でも屋で、短い紫苑の髪と目の少年も、酷く暗い面持ちで彼らに現実を告げた。
「これが壊れずに落ちてたのなら……『バステト』が消えて外れたとしか考えられないよ、兄ちゃん達」
首輪を着けていた白黒の猫が消える。その事態は、その猫と一心同体である幼馴染みが、力尽きたことを示して余りあった。
「じゃあどうして……里のヒトは誰も、アシュリンを見ていないの?」
そこはかなり規模の大きい里であり、全滅は免れたものの、生き残った者達は少ない。生存者はひたすら仲間の墓を掘りながら、憎悪の表情を浮かべていた。
事態が全て終わった後に帰って来た彼らや、何処にもいない幼馴染みに向けて、率直な感情を悪し様に言い放ったのも無理はないだろう。
彼らは全員、その凶事から顔を背けた……同郷者を見捨てて逃げ出したのだろう、と。
そうしたことを、夜の海を進む船上に響く潮騒の中で思い出しながら――
「半年待って、帰らない奴は……多分帰らないよな」
相変わらず眠れずに甲板に出た彼は、冷たいだけの潮風に吹き付けられる。
「十中八九――……アシューは死んでる、か……」
この船に乗る前に、連れ合いの両親から紹介された占い師に聞かされた視立て。黒い海面に消えそうな拙い声で、憮然と呟く彼だった。
一番痛切だったのは、彼や連れ合いと同道して里に帰った悪友、里長の息子が、鳥頭の碧毛を一晩にして銀髪にするほどの消耗ぶりだった。
――おれのことはええ……!! オマエらはアシューを探してくれ、頼むわ!!
元々親戚もなく、両親を早く亡くした彼とは違い、悪友は血縁を全て突然失った状態だ。しかしそれを悲しむ間も無く、状況確認と生存者の捜索に日夜走り回っていた。
責任ある長の息子として、彼や幼馴染み以上に、残った者の悔恨を一身に受けて罵られながら、一番の心配事――悪友には最も大切であるはずの幼馴染みの捜索を、彼らに託していた。
今も生存者の帰郷を待っている悪友を、彼は苦い顔で思い起こす。
――アシューが死ぬわけないやろ。あいつ、逃げ足だけは早いんやからな。
それはそれで、里を見捨てたのだと、生き残った者達の言う通りになってしまうが。
彼や悪友にそう思わせるのは、彼らと最後に別れる前に、幼馴染みが何処か遠い目線で言い残していった言葉にあった。
――里に帰ったら色々、めんどくさそうだけどさ。
自らの一部である白黒の猫、霊獣というもう一つの体――感覚を共有する獣を、幼馴染みは彼らより先に里の近くに向かわせていた。そして彼らと別れる直前に、真意のわからない独り言を口にしていた。
――……今からでも……遅くなかったのかな。
側面だけ長い短かな白灰の髪は、耳だけでなく幼馴染みの表情をも覆い隠した。
それがもしも既に、霊獣の目を通して、里の危機を知っていた言葉であるなら――
常に気弱に振舞い、荒事から逃げ回る幼馴染みが何を思ったのか。彼にも悪友にも何故それを告げなかったのか、疑問ばかりがいくつも残っている。
後一つだけ、気になることがあった。
そもそもあまり、里で良く思われていなかった幼馴染みと、唯一懇意にしていた同じ村の友人についても、行方がわからなくなっていたのだ。
――セレンの死体は誰も確認しとらんらしい。あいつの従兄のテルルもおらへんし、他にも二軍村では、いなくなっとる奴が結構おるみたいなんや。
霊獣族という化け物の里では、彼らのように強い獣を扱う力を持つ者が一軍、扱う獣が普遍的な動物である者が二軍と呼ばれていた。それぞれ居住地を分けられていたのだが、二軍の方の死傷者は明らかに一軍より少なかったのだ。
――いなくなった奴が逃げただけなら、いつでも帰ってきたらええ。アシューも他の奴らも、おれはここで待っとるからな。
二軍の村の者の力は、正直そこまで強いとは言えない。
そして一軍の力を持つ者は少なく、必死に戦ったようだが、ほぼ全滅している。他の非力な者達が恐怖で逃げ出したとしても、何もおかしくはないだろう。
「アシューは非力じゃないけど……怖がり、だもんな」
それでも生きていてほしい。もしやそれで幼馴染みは自らを恥じて、姿を消したのかもしれないと……まだしもその方がましな状況だった。
生き残った里の者は、非常時に不在だった彼らを、どの道罵り続けるのだろうから。
あの時どうして、幼馴染みを一人で帰してしまったのか。
先に帰ると言い張ったのは幼馴染みだが、彼も悪友も後悔せずにいられなかった。
「……里は安全だ、って、当たり前に思い込んでたな」
一軍の力を持ちながら二軍の村に引っ越し、そのために解け込めずにいた幼馴染みは、彼らにとって大切な旧い仲間で……しかし彼らと仲良くし過ぎると尚更反発を受けるため、里の内ではよそよそしい態度で接していた。
それなので、帰り道も彼らと一緒に行くのを避けた、それだけのことのはずで。
「俺があんな怪我なんてしなきゃ……四人で里に帰れたのかな」
里に向かうのが遅れたのは、ふとしたことでディアルスでの事変に関わった彼が重傷を負ったからだ。それが無ければ、里の危機にも間に合ったのかもしれない。
そう自身を責める彼に、再会した紫苑の少年はあっさり否定したものだった。
――これは兄ちゃん達だけの問題じゃないよ。何かやばいことが、世界レベルで起き始めてる……でないとこんな状況、有り得ないから。
幼馴染みを探すために、荒れ野となった里を出た彼と連れ合いは、再会を約束していた紫苑の少年とまず合流を考えた。そうして別れる時に教えてもらっていた、少年の故郷に向かったのだが……。
――そっか……オレんとこだけじゃなかったんだ、この焼野原は……。
そこで目にした光景は、彼らの隠れ里と同じように何者かに蹂躙され、白骨化した同族者の墓を一人で掘り続ける土まみれの少年の姿だった。
故郷で疎まれた身で、今まで帰っていなかったという紫苑の少年は、黙々と己を嫌った同郷者達を弔っていた。
――この辺りの有力な千族が、妖精や吸血鬼を除いて、軒並攻撃されたってことじゃないかな。大きな里を持ってるのなんて、もううちやそっちくらいだしね。
千族は現在、世界人口の二割に満たないと言われる。その中でもこうして、一大集落を構える種族は本当に少ない。それだけ有力だった種族が、同時期に二つ壊滅した現況は、世界規模と言って良いほど、近年稀に見る不穏な事態であるのは確かだろう。
それは最後に訪れた占い師からも、同じことを彼らは告げられていた。
連れ合いの両親が紹介してくれた占い師は、世界地図の中心にある島国「ジパング」という、独特の文化と言葉を持つ国に潜む化け物の老婆だった。
「これはこれは……珍しい客が、また来たものだのう」
千族同士は、言語の違いに関しては、気配や言葉に混じる外向きの念を感じ合える共通性を持つ。そのため、会話には苦労しなかったのだが――
「わしは悪いことならよく当たると評判じゃが、それでも良いのかの?」
「…………」
小さなテント張りの小屋の中、着物という民族衣装に外套を羽織る老婆は、ニヤリと笑った。
そうして老婆が告げた、幼馴染みの行方の占い結果は、身も蓋も無いものだった。
「残念じゃが、十中八九、この品々の持ち主は亡くなっておるよ」
「十中……八九?」
しかしそれを聞いた彼と連れ合いは、唖然と互いの顔を見ることになる。
「たった一でも、生きてる可能性はあるの? 梅おばあちゃん」
おそるおそる尋ねた連れ合いに、老婆は手持ちのカードを睨みながら、難しい顔で頷いた。
「この者は不思議じゃな……生死の境が酷く曖昧で、元々死を背負う様相をしておる」
十中の一でも、生存の可能性を聞かされたのは、初めての結果だった。
呆気にとられながら訊き返した彼を、老婆は細い緑眼で見つめる。
「死を……背負う?」
「お主ならわかるじゃろう? お主とこの者はいずれも、空ろな呪いを負って生を受けていたはずじゃ」
その時彼の脳裏に、真っ先に浮かんだのは――
幼い頃に鬼子と呼ばれていた彼は、制御できなかった古びた霊獣、暴走する赤い獣を抱えていた。五歳になる前に悪友、幼馴染みと遠出した先で怪物に遭遇し、瀕死となった彼は、呪いと呼んだ赤い獣をそこで失っていた。
「それは先の世の業、そう言われたじゃろう。でなければ本来、本性たる『力』を失ったお主が、生きていられる道理もないからのう」
「でもそれは……アシューも、なのか――?」
「この者も二つの顔を持ってはいなかったか? わしには詳しいことはわからぬのでな」
空気を強張らせて息を呑む彼に、そっと連れ合いが、膝の上の手を握る。
老婆はそんな連れ合いに視線を移すと、懐かしむような声で続けた。
「そなたについては幼少時に相談を受け、そなたの同胞と同じように、『魔』を背負うと伝えておるがね。どうやらそれと似て非なる呪いを、お主は持つようじゃ」
彼と幼馴染みは「呪い」を、連れ合いは「魔」を。
その違いを老婆は、「呪い」は他者との間に生じ、「魔」は自らの内に生じるものだ、と占い師としての長年の実感を持って説明する。
「これまではお主の方が危うかったようじゃが……今はそなたが非常に危うい。それには気付いておるかのう?」
彼と連れ合い、どちらも不幸属性と連れ合いの親が言ったように、老婆は特に連れ合いを心配して口にしていた。彼も全くもって同感で、ぎゅっと連れ合いの手を握り返した。
彼の故郷がなくなり、幼馴染みも行方不明になってしまった中で。ともすれば、彼より苦しんでいたのは連れ合いの方だった。
妖精の森という狭い世界に長くいた連れ合いは、身内以外にほとんど知り合いがない。そのためか、淡々とした見た目によらず、家族や仲間への思い入れが人一倍強い性質らしい。
彼もそれは同類なのだが、時に彼以上に、周囲への愛執を感じさせる連れ合いでもあった。
「そなたは自身で思っておるより、根の深い重い感情を抱えておる。その記憶はどうやら封じられたようじゃが、それでもそなたの一部であることに変わりはない」
「……その封印が、解けるかもしれないっていうこと?」
自らを記憶喪失と言う連れ合いは、封印されたものがあること自体は知っている様子だ。
首元の菱形の青い宝石を填めるチョーカーを触りながら、あくまで冷静に老婆に尋ねる連れ合い。その透明な青の目は、夜毎に思い出したように涙を浮かべる暗い青とは対照的で、この空色が続けば問題はないのかもしれない。
「それはわからぬ。封印の様式もわしは与り知らぬ次元だしのう」
その目色の違いがわかるのは、彼だけの特殊な特技で――
連れ合いの真の「力」を表しているのは暗い青の方だと、世界の数多な「力」に個別の色を視る眼を持つ彼には、今も悩ましい事柄だった。
疑問はいくつも、様々にあったが。その全てをすぐに消化するのは無理だと、老婆は彼らに現実的に伝えた。
「ひとまず、お主達が追っている敵は間違いではない。その敵はお主が探している仲間や、故郷の存亡に何かの形で関わっておる」
「……」
「心するが良い。お主達は今、世界を揺るがす何かの騒乱に巻き込まれておる」
いったいいつから、そんな事態に。
その答はこれから徐々に、明らかになっていくと。
幼馴染みを探すために里を出て紫苑の少年と合流し、ディアルスにいる妖精の女の元に行くまでの間に、彼らはある強行に出た。
幼馴染みの安否は紫苑の少年も心配しており、行方を探す手がかりとして、占い師が彼らの敵を伝える前に、少年はある人間の存在を挙げた。
――シャルの都市長の仲間が、アシュリンのねーちゃんに声かけてたんだよね? それならそこから当たってみようよ。
その都市は初めて旅に出た彼と悪友が、最初に向かった西の大陸三大商業都市の一つだ。
そこで悪友は都市長に攫われるというおかしな目に合い、助けるために彼や幼馴染みは都市長の屋敷に乗り込んだ。その時に、屋敷に結界を張っていた「力」の持ち主に目を付けられたのだ。
「……都市長の父親は、至って真っ当な人間だったけどな」
三カ月に渡って実行した荒事を、船の柵にもたれて夜空を見上げながら彼は思う。
「教えられた心当たり……全部探しても無駄足だったけど……」
彼らがディアルスで巻き込まれたある事変で、シャル都市長は黒幕と言え、事変後に行方不明になっていた。
その都市長の父親は隠居していたが、都市長の居場所を知るために彼らはその父を闇討ちした。ところが元々、息子と上手くいっていなかったらしく、逆に息子を探してほしい、と彼らに懇願したような人間だった。
――息子が悪い仲間と付き合っているのは知っていたが……その詳細は私も知らないのだ。
実の息子を探すためなら、と父親は、彼らが以前侵入した屋敷も何か手がかりがあればと遠慮なく調べさせた。その間に彼らは、様々な内情を耳にする。
――息子は酷い人間嫌い……もとい、女嫌いでね。周囲から早く結婚して跡継ぎを、とそれを毎度迫られることに、ほとほと嫌気がさしていたようだ……。
しかしそんな都市長が、いつからか四人の娘を屋敷に住まわせるようになったという。
――やっと女性に興味を持ってくれたのかと、私は安心していたのだが……それがほとんど年端もいかぬ少女ばかりとなると、ますます風当りは強くなっていたようだ。
現れた四人の内二人は、十代前半の朱い忍装束を纏う少女で、一人は鋭い黒目で気の強そうな、肩までの薄柿色の髪が印象的な者らしい。
もう一人の忍装束の者は、同じくらいの髪の長さでふわりとした翡翠の髪の妹分らしき少女が、屋敷の警備と言って二人で常駐していたという。
残りの二人は、大人と子供の女性コンビだった。大人の方は顔を隠すベール付きの帽子を常に被り、袖口と襟が広がる旧い魔道士風の女。特に目立ったのは、黒い珠玉の填まる赤い胸当てを常に装着していたこと。
その女は後一人の、小さな子供――横ポニーテールの幼げな娘に、始終付き従っていた従者らしい。
――最後の一人は、私も姿を見たことがあるのだが……猫のような耳と鈴の付く首輪を着けて、ぴったりした黒い服を着てる子でね。丸出しの肩にいつも薄い桜色のショールをかけていて、その中から色んな道具を、魔法使いみたいに取り出す不思議な子供で……。
従者の女は度々不在にしていたという。そのため、猫風の小さな娘が一人で自室にこもる姿を、都市長の父親は不憫に思っていた旨を口にする。
――いつもあの子は、一人の時は灰色の猫のぬいぐるみを取り出して、従者の女が着替えて置いていった服の上に置いて……ずっと話しかけ続けていたんだよ。
それは彼も連れ合いも、思わず眉をひそめてしまうほどの、狂気じみた淋しげな姿だった。
彼と共に都市長の屋敷に乗り込んだ紫苑の少年が、ずっと着けている大きなゴーグルの下の鋭い目を強く細める。
――……。
ゴーグルで隠された顔は、その猫娘とそっくりなことを彼らは知っている。
そうして、全く同じ紫苑の髪と目を持つ相手――双子の妹である猫娘の話を、少年は厳しい顔で黙って聞き続けていた。
赤い胸当てを台代わりに、灰色の猫のぬいぐるみをちょこんと置くと、猫娘はいつも、猫じみた独特の口調で語りかけていたらしい。
――こんにちはですのニ、アークちゃん。ミィの声、聴こえるですの二?
ぬいぐるみは当然何の反応も無い。しかし全くめげない猫娘は、何もすることがない時には、えんえんとそれとの話を続ける。
――大丈夫ですのニ、ミィがいるからアークちゃんは淋しくないですのニ。だからずっと、ミィに力を貸してお友達でいてほしいですのニ。
紫苑の少年はその姿について、やはり思うところがあったのか、しばらく黙り込んでしまった。
屋敷全体を調べ上げて、おそらく四人の娘達に仕掛けられた結界道具を全て取り外し、都市長の父親に教えられた息子の人脈を当たる内にどんどんと時間は流れていった。
ようやくシャルを後にした時には、幼馴染みが姿を消して五カ月近くが経過していた。
最後の当てだった占い師のいる島国ジパングから、北西に位置するディアルスに向かう船の上で。夜を徹して甲板にいた彼の元に、連れ合いが暗い青の目で静かにやってきた。
「……また眠れなかったの? レイアス」
心配そうな連れ合いは、いつもうなされるような顔で眠りについている。その重い表情の方が彼は気になっていた。
「アフィこそ。悪い夢、また見てないか?」
彼はこのところ、時間が短い分眠りが深くなっているようで、以前はよく見た幼い頃の夢もあまり見ないようになっていた。
どちらがいいのかは、難しいところだろう。互いに互いを案じるばかりの真摯な目線に、思わず拙く笑い合った彼らだった。
間近に迫るディアルスの港を見て、連れ合いは気合いを入れるように、空のような青い髪を高い位置で一つに括る。
「……ラスト、ディアルスで待ちくたびれてるかな。わたし達がジパングに行ってる間、情報を集めてくれるって言ってたけど」
「元はディアルスを狙ってたシャル都市長だしな。『炎と風の塔』も、シャルの工事業者が手掛けた建築物だというし……」
半年前に彼らが巻き込まれた、通称「炎と風の国ディアルス」での、大規模なある事変――
それは「炎と風の塔」という観光地に、大掛かりな悪魔召喚の魔法陣をシャル都市長が仕込み、天と地に溢れんばかりの魔物を呼び込んだ人外騒動だった。
彼らと紫苑の少年はそれに巻き込まれて大きく消耗した。その後故郷に帰った矢先に、焼野原で立ち尽くす現実は無残としか言えなかった。
「ラストも全然笑わなくなっちゃったね。当たり前だと思うけどね」
「そうだな。元はアフィの父さんみたいな、軽いノリが似合う奴なのに」
「あははは。そうだね、ラスト……父さんに似てるよね、そう言えば」
竜宮に行き、そこからジパングの占い師を訪ねた意味は、多分大きかったのだろう。
連れ合いはこうしてやっと、暗い青の目の時でも度々笑うようになった。
「このままシャルの都市長を探して……アシューの手がかりも何か掴めればいいな」
「うん。十分の一でも、生きてる可能性があるんだもの」
諦めるために向かったような短い旅は、辛くも微かな光明を彼らにもたらした。
そんな脆い希望に縋ることを、危うい状態とわかっていながら――
彼も連れ合いも望まずにいられない、昇り始めた朝陽を背にする淡い夜明けだった。
下3:白歴史
半年前の事変に関わったことで、恩人として彼らは、王家直々に戸籍を与えられた。
そうして母国となったディアルスで、最初に待っていたのは。同様に戸籍を与えられていた紫苑の少年との即時の再会……ではなかった。
「――というわけで、ディアルスは元々、ディレスという名の凍土でした。ここからは、我が国の重鎮ナナハさんの関係者である貴方達なので最重要機密をお伝えしますが、この温暖な気候を保っているのはある二つの奇跡の珠玉なんです。千年以上前に、ディレスに現れた竜の血を持つ方と、ディレス王家が交わったことで受け継ぐことになった炎と風の竜珠を、王家は代々守っているのです」
「へぇー、そうなんだぁ。だからわたしと相性がいいんだね、この国の『気』は」
「…………」
ディアルス戸籍を受けるに当たり、希望する職業の適性検査と、ディアルス概要講義を修了することが必須と言われてしまった。
半年前の事変で知り合った、ディアルス王女の実の従弟――重たげな祭儀衣が暑いのか、袖を捲り上げて張り切る青年が歴史書を抱えてやってきた。肩までの黒髪の素朴な青年を前に、彼と連れ合いはそれぞれのやる気で、王城の図書室の硬い椅子に並んで座る。
「ディレスがディアルスに国名を変えたのもその時です。王家が新たな血統を受け入れる祈念と言われていますが、そもそもディレスの王家は水の竜の血をひく人間でもあります。ディレスの建国時――もう数千年も歴史を遡ることになりますが、二人の英雄がディレスを守り、その内竜人の血をひく方が、ディレスの初代王女と結ばれた伝説が残っていますから」
「……――」
眠たげに話を聞いていた彼だったが、その辺りは不思議と、興味をそそられる内容だった。
というのも彼は、ある理由であまり、英雄伝説の類を好きになれない性質なのだ。
「英雄とかそういう奴って、大概ろくでもなくないか? 所詮ヒト殺しだし、家族のことも省みない奴だろうし」
彼の父は人間の血をひいている。それでも霊獣の里の一軍女に見初められ、蛮勇という己に拘り、自らを鍛えることばかり考えていたような千族だった。
そうして鍛錬に明け暮れて疲労した挙句に、流行病で彼が幼い頃にあっさり死んでしまった。そのために、強さを価値と考える普通の化け物の思考を、彼に疑わせる原因となった反面教師なのだ。
思わず口を挟んでしまった彼に、素朴な青年はいいえ、と心からにこやかに、伝説の英雄を尊敬しているように微笑みを返した。
「もう一人の英雄に関しては、ディレスがディアルスになっても続く、興味深い言伝がこの国には残っているんです」
「――?」
「もしも英雄の息子と名乗る者が現れたら、国を上げて歓迎しろ、と初代ディレス王女は末代までの遺言を残しています。いったいどういうことなのか、今でもディアルス研究者が持て余す謎の一つですが、そうして名も無き息子の存在が取り立てられるなんて……きっと英雄は家族想いで、初代王女に息子のことを頼んでいたのではないでしょうか?」
自らも歴史研究家という素朴な青年は、自身の仮説を嬉しそうに語る。
「英雄の息子かぁ。それって自称でいいのかな?」
不思議そうに尋ねる連れ合いに、はい、と講義者はためらいなく頷く。
「ディレス初代王である英雄はともかく、こちらの英雄はほとんど知られてない上、息子がいるなんて伝説、民間には全く残っていませんから」
だからもしも、自らがそうだと名乗る者がいた場合は、ディアルス研究者でもないのにそんなことを口にできるだけで信じて良い。と、言伝はそこまで指定するらしい。
そうしたディアルス歴史講義からようやく解放されたと思ったら、今度はディアルスの国内情勢について、それも顔見知りによる講習が待ち構えていた。
「おーっす、相変わらず暗い顔してんねぇ。まー無理もねーけど、この国はいい所だからエンジョイしてけよ!」
「あ。イソシギだ」
図書室を出た後に向かうように言われた小さな食堂で、騎士風の金髪の男が彼らを出迎える。立襟をかなり着崩し、片側の肩で留める外套を翻す金髪の男は、何もない机上に雑にディアルス国内地図を広げた。
「騎士団」という、ディアルス国内の治安維持を担当する一人の金髪の騎士は、それがこの国では軍にあたる、と赤い目を光らせながら本題に入った。
「ディアルスは戸籍をやる千族に、何かあった時は周りの人間を可能な範囲で守れ、と約束してるんだ。おれ達騎士団の方は戦争要員として、なるべく使わず温存しておきたいのが審議院側の常なる意向だな」
「審議……院?」
「ディアルスは昔から、王家と審議院の両立治国制でねぇ。審議院は民衆の代表って看板しょってるけど、支配欲の強い人間がほとんどだと思って正解だぜぇ」
とてもぶちまけ話をする騎士に、事情を知らない彼と連れ合いは何も言えない。
「今差し迫ってんのは、防備の薄い国境をどうにかしろっつー話なんだが。国境警備隊の創設をお前さんらが助けてくれないかナナハちゃんは画策してたぜ。こき使われないよう気ぃつけなあ」
「……さすがだなぁ、ナナハ」
ディアルス王女の顧問である妖精の女。連れ合いからは旧い親友は、妖精という種に似合わず勤勉な仕事人だ。審議院とは対立しているらしい、と本人からは語られない裏話まで聞かされる。
「何かわからねーことあったら、後はファーにきいてくれ。おれのお仕事はここまでです」
金髪の騎士には相方のような、黒髪で赤眼の寡黙な騎士の姿は今日は見えなかった。
「リアラに話したい時は、ナナハちゃんかファー、ラフィルに言えばお目通りできるぜ。あれでも王女様だから、その辺の段取りは守ってやってな」
寡黙な騎士は王女直属、金髪の騎士は妖精の女付きらしい。誰もが王女を気軽に呼び捨てにしているが、それほどこの国の王家は気さくなのだろう。
騎士団は審議院の管轄となるが、軍事行動の際の最終決定権は辛うじて王家にある。
それはディレスがディアルスとなり、王家が二つの奇跡の珠玉という「力」を手にした後からで、それまでのディレスは、凍土の自国に資源を求めて、周辺地域と争いを繰り返す苛烈な国でもあったという。
「リアラの笑顔からは想像できないな……そんな血塗られた歴史が存在するなんて」
「王家はホントは、平和主義なんだって。でも審議院は、自国をもっと豊かにしたいって、みんなの願いを代表する人間の集団みたいだよ」
半年前に初めて出会った赤毛の王女は、その辺の魔法使いに扮装して「炎と風の塔」に潜入し、そこで行われていた化け物ギャンブルを自ら摘発するような高潔な行動家だ。それでも治国が万事上手くいくものではないらしい。
「それだけ資源が必要な人間は、本当に大変だな」
千族にとっては、自らを後押ししてくれる土地の「気」さえ合えば、争いを起こすほど衣食住が不足することは少ない。
その代わりに特有の「力」の秘宝や、己が一族に合う土地を巡る争いは、一度起きれば惨憺たるものとなる歴史も存在している。それもこの「宝暦」ほど千族の減った時代となると、最早伝説の類となっていた。
……何故か突然滅ぼされた、彼らの故郷を除けば。
ディアルス戸籍のための必須事項を、ようやく大体消化できたところで。
「おそーい、兄ちゃん達! いつまで待たせんだよ!」
まだ居住地や職種の希望がない彼らに、当座の滞在場所として貸し与えられた半年前と同じ客間に、紫苑の少年が物造りの道具を派手に広げて待っていた。
「……ここ、俺達の部屋だよな?」
「当たり前じゃん。オレ一人に二台のベッドなんていらねーし」
「……じゃあ何でオマエは、盛大に持ち物を広げているんだ?」
ただ不思議で無表情に尋ねた彼に、少年はここぞとばかりの不服を満面に浮かべた。
「もー、本気で鈍いなぁ、兄ちゃんてば! 一カ月近く待たされたオレが、暇な時に何をやってたと思ってんだよ!?」
ポカンと黙る彼の右腕を、道具を広げた机の前のソファに座る少年ががしっと掴む。
「ちょうど兄ちゃん、十八歳になんだろ!? 最高の義手造って待っててやったんだから、付け替えるのも大掛かりなの!」
そうしてキラリ、と空いた手に持つ愛用らしい工具を光らせる。
半年前に彼が旅に出たのは、幼い頃に義手となった右手が時間と共に傷み、新たな物を探すためが大きかった。
それをプレゼントするという少年に、資金として掘り貯めて来た天然の稀少石を、彼は渡そうと思ったのだが……。
「これからアフィねーちゃんと二人暮らしすんだろ? 生活資金として置いときなよ」
あっさり断られ、彼はともかく無一文に近い連れ合いを思うと、世間ずれしている少年の厚意を有り難く受け取ることにした彼らだった。
「今から腕を付けるなら、わたし、ここにいてもいいのかな? 邪魔じゃない?」
「大丈夫だよ。ついでだからこの一カ月の進捗も、お互いに報告しよーぜ」
あまりにしっかりした少年の言うがままに、連れ合いも寝床に座る。
そのまま、ソファに並んで座る少年が彼の義手を付け替えながら、報連相の雑談が始まっていた。
「……そっか。『炎と風の塔』を造った業者さんは、塔の仕掛けとは関係無さそうなんだね」
「設計図を造ったのがミティぽいから、それで介入は十分だったんだ。下手したら他にも、ディアルスにはミティの手が入る建物があるかもしれねー」
双子の名前を口にする少年は、同じように物造りに長ける一族だという。
ヒトの力をじわじわ喰うような魔道の仕掛けを施した建物の造り主に顔をしかめつつ、彼の義手の調整を続ける。
「一応人が多く集まる建物の建築業者を調べといてって、ラフィルのにーちゃんに言ってあるけどさ。それを張って都市長の足掛かりを掴むのは、わりと難問そう」
「そうだな……追われてるとわかってる国に、現れる方がバカだろうしな」
あまり捗々しい結果はない少年の話しぶりだったが、彼らの方にも、幼馴染みが完全に死んだとは限らないことと、都市長を追う方向性は間違っていないという占いの結果があるだけなので、大差はなかった。
「まーつまり、八方塞がりに近い感じだよね」
「ハッキリ言うよね、ラスト……」
「仕方ないじゃん。オレも一刻も早くミティを探したいけど、探索系の魔法、あいつ全部結界で弾きやがるんだから」
「それ……アシューが死んだって占いで出るよう、偽装できる可能性もあるのか?」
「さすがにそこまではないと思うけどね。占いの偽装はつまり世界の現状の改変だから、兄ちゃんみたいな『心眼』持ちでもいない限り無理だよ」
その意味がよくわからなかった彼が訊き返す前に、少年は半ば諦観と共に言う。
「ラフィルのにーちゃんから何か新情報が入るまで、しばらく大人しく暮らせばいいよ。兄ちゃんもねーちゃんも、かなり疲れ溜まってんだろ?」
この後のペース配分まで考えている、本当に行き届いた少年に、彼らは頷くしかない。
こうして状況に流されている内に、旧い痛みは影を潜め、様々な執着も薄れて、新たな生活に解け込んでいくのかもしれない。
紫苑の少年が丁寧に付け替えてくれた義手が、大人になった彼にぴったりと合う強度と仕様で、とても快適に動く素晴らしい造りを実感し、彼は感心の溜め息だけをついていた。
「今までの義手はアフィねーちゃんに渡すか、万一の時のために、兄ちゃんがそのまま持っておくか、かな。壊さないよう外すのは大変だけど、付けるのは簡単なタイプだから」
「……確かに、予備があるのは心強いな」
「わたしはいいよ。使う時だけ貸してもらえたら大丈夫だから」
古い方の義手には竜の血をひく連れ合いの、大き過ぎる「力」を制御するための青黒い刻印――竜族独特の秘宝、「逆鱗」が埋め込まれている。
それは本来連れ合いの父が使い、大元は父にそれを託した叔母――連れ合いにアースフィーユの名を譲った、亡き人のものだという。色々あって、彼の義手という無機物に固着させられてしまった後は、元の浮遊状態に戻すことは難しいらしい。
「こっちもそうなの。『水』や『風』を喚ぶ時は、父さんに借りた方が使い易いんだけど、本当はわたし自身の『逆鱗』を使いこなせないと……頑張らないとだね」
連れ合いは首のチョーカーの青い宝石を指差し、そちらは元々自身の額にあった刻印を、あえて浮遊化させて固定したものだと説明していた。
「……そっちは玄く視えるけど、何の『力』の制御に向くんだ?」
それは彼には、とても珍しい質問だった。
というのも彼は「力」に色を視て、その「力」の「意味」も何となくわかる「心眼」の主だ。その彼にすらわからない、連れ合い自身の「逆鱗」とは。
「それがね、わたしも父さん達もよくわからないの」
だからそれを「魔竜」と呼ぶのだ、と、竜宮で彼は話を聴かされていた。
竜宮を後にする前、彼は連れ合いの実母に二つのことを問いかける機会があった。
――何か訊きたいこと、あるんでしょ? レイアス君。
連れ合いが父と連れ立って朝食を用意している間、広間でのんびりしていた青い髪の母は、遊びのない顔付きで彼を見つめた。
空のように青く海よりも深い目色は、黙る彼を奥底まで視通すかのように鋭かった。
――本当はそう簡単には教えないけど。君が望むものは、キレイに最低限ぽいし。
彼と同じで基本無愛想らしい母は、彼のことは前日の言葉通りに、何故か早くも認めた風体で無表情に呟いていた。
自分のことは自分で探せ。後で連れ合いに聞いた所、母にはそう言われて育ったらしい。
父はすぐにヒントをくれ、己が「逆鱗」を娘に預けるほどの過保護さで、母からも「力」の素となる青い珠玉の杖を渡されるなど、連れ合いは大事に育てられたようだが……。
――私達は全員、『魔』の因子を持った家族。今日は味方でも、明日は敵になることもある。
既に結構長い年月を生きたらしい母は、だから自分達には気を許すな、と言いたいように彼には見えた。
彼の質問にその母が二つまで答えた所で、連れ合い達が戻ってきたので話は終った。
問題だけ教えられた問答だったが、それは必要な話だった、と青い髪と目の女性は付け加える。
――有難うね。ティアリスのこと、よく視ててくれて。
言葉数は少なく、本質的なことだけ歪めないで伝えるために――謎かけのように色々答えてくれた女性の目の青は、暗く澱む時の連れ合いにそっくりだった。
義手の付け替えが終わり、貸し与えられている自室に紫苑の少年が戻ると入れ替えに、その気さくな王女は唐突にやってきていた。
「こんにちは、レイアスさん、アースフィーユさん! お部屋はどうですか、快適ですか!?」
「――……」
「ありがと、リアラ。居心地はとってもいいよ」
王族に謁見の際はまず臣下を通すように、と先程念を押されたばかりなのに、王女から来られてしまうとどうしようもない。
白い外套で寡黙な黒髪の騎士を供に、胸まである赤毛を結い上げ、王女はふわふわの檸檬色の礼装を纏い、彼らの居室に押しかけて扉の前に佇んでいた。
「……せめて座ってくれ。落ち着かない」
一つしかないソファから立ち上がり、難しい顔で言う彼に、いいえ! と、元気一杯の王女が薄青の目を細めて笑い返した。
「どうかお二人で並んでお座り下さい! お部屋はご一緒で良かったですよね? ね?」
妙にキラキラとした顔付きで、王女はさらにとんでもないことを続ける。
「宜しければこの際、ディアルスで婚姻の儀も行われてはどうですか? 私是非、仲人をさせていただきたく思っています!」
寝床に座り込む連れ合いが、きゃっと両手で赤い頬を隠す。その反応にますます機嫌を良くするような王女は……どうやら相当のお節介、というより色恋事に関わるのが大好きであるらしい。
「昨年の改築時に礼拝堂も大幅に直して、とても素敵なんですよ! それなのにナナハがなかなか使って下さらないから、私とても残念で……」
「……多分、ナナハは当分、その気はないと思うけどなぁ」
少し赤面したまま答える連れ合いは、王女が話に出した旧い親友の話題をいくつか耳にしていた。妖精の女は付き人の金髪の騎士には度々迫られて求婚までされ、女が仕切っていた城の改装に横槍を入れられ、礼拝堂も綺麗にするよう押し切られたなどの裏情報だ。
でもでも、と王女に押される連れ合いを見かねたのか、隣で黒髪の騎士が冷静そのものの赤眼で、不意に静かに言葉を挟んだ。
「……イソシギの言動は、本気にするな、リアラ」
喋れるのか。と彼はつい思ってしまったほど、黒髪の騎士が口を開くことは少ない。
「アイツは魔女を利用しようと企んでいる。魔女もそれをわかってるんだろう」
昔馴染らしい金髪の騎士に対し、だからこそ知る内情に注意するよう、伝えておきたかったらしい。
「でもファー、ナナハを利用とはどういうことです? イソシギは求愛しかしていませんよ?」
「……」
「王家の顧問をしてくれるナナハには、確かに様々な権限があります。それでもナナハは私や父上の意志に反することを、独自で画策するヒトではありません。イソシギがたとえ出世欲の塊でも、甘い顔をするナナハではないと思います」
……わかってるんじゃないか。と言いたげな表情だと、溜め息で答えた黒髪の騎士に彼は思わずにいられなかった。
それに、と王女は、今度は申し訳なさそうに彼らを見つめる。
「結婚式を挙げるためということなら、お二人にもう少し、長く滞在していただける口実もできるのですが……」
この客間を借りられるのは、そう長い期間でないのは彼らも聞いていた。
「本当にごめんなさい。でも、王城で働きたいと言って下さる千族の方は多くて、現在は皆さんをお断りしている状態なので……」
ディアルス国民となった今では、確かに国賓待遇はおかしな話だった。
「大丈夫だよ、リアラ。ごめんね、仕事も家も決められないって我が侭言って」
いつまた彼らは、幼馴染みや他の同郷者の手掛かりを得て旅に出るかもわからない。そのため当面は定住の気はない。
事情をわかっている王女が、いいえ、と強く声を張り上げた。
「行方不明の方は私にも大切な我が国の恩人です。どうか早く見つけて差し上げて下さい」
王女の言葉は主に、彼も巻き込まれた事変に関わった幼馴染みを指していた。
「そんな旅する皆さんにも融通が利かせられるよう、国境警備隊の配備体制を考えているところなんです。騎士団は国内に活動が限定されますが、国境警備隊は国外活動も王家の意志ならできるようにしたいと思っています」
軍事系の仕事を求める千族は多いらしく、それで王城には戸籍をもらった千族の来訪が絶えないという。
王女としては、拮抗勢力と言える審議院の手足になる騎士団の増員をなるべく避けたい面もあり、そうした千族の行き場として「国境警備隊」の着想を進めているのが現在ということだった。
「非常に残念なことなのですが、審議院の中には、皆さんを戦いの道具と考える不届き者もいなくはありません。それだから他地域の方に怖がられて、ディアルスは千族狩りなんて言われてしまうんです」
王女は痛切そうにしているが、それは人間だけの咎ではないように彼には思えた。
「……実際、戦う方が好きな奴も多いだろ、千族は」
それぞれが何らかの「力」を持って、生まれてくるものの宿命であるのか。
人間のように環境を整えずとも、不自由なく生きられる千族は、快適さや便利さよりも自らの研鑽を追求し、好戦的なのは確かだった。
この王女のように色々なことを考え、物事が上手くいくよう気を配る人間という生き物は、彼はわりと好きな方だった。
――……親父は半分、人間だったしな。
頑固な正直者が多い千族と複雑な者が多い人間は、どちらが良いとは彼には思えなかった。
結局何の話をしにきたのやら、王女は最終的に、皆さんに天のご加護がありますように! と言って部屋を出ていった。
「リアラって元気だね。まだ若いのに、国のこともわたし達のことも一杯考えてくれて」
感心しきりの連れ合いと彼も同感だ。千族と人間の関係や、ディアルスに魔物襲来という大事件を起こしたシャル都市長も含めて、王女にも悩み事は沢山あるはずなのに、と。
「まさに『炎』の珠玉の適合者だな。頭のいい人間が『力』も持つと、理想的なのかもしれないな」
当たり前のように言った彼に、連れ合いが不思議そうにする。
「そうなの? 『力』ってそんなに性格に関係するの?」
「……むしろ、『力』は『心』だけど」
妖精の女には「心眼」と言われた眼。「力」に固有の色を視て、また介入もできる彼は、それは当然の認識だと思っていたのだが……。
「そうなんだぁ。じゃあレイアスが視てる色は、性格みたいなものなんだ?」
「性格というか……同じような『力』や『心』なら、家族や種族は大体わかるけど」
古い時代とは違って「神」が隠れ、神威を使役する者が少なくなった現在には、召喚士はほとんどなり手がいない。そうした特殊な立ち位置であるせいか、この「宝暦」で主流な魔道の常識が、連れ合いには通用しない。
彼も里で多少習った知識があるだけで、あまりヒトのことは言えないのだが……。
――俺達の霊獣も、外面と本性を体現したものっていうしな……。
空のような青に玄い影を伴う連れ合いは、青は母から、玄は父に近いものに視えたが、同質とは言えないのが彼の軽い気掛かりだった。
その暗色は、誰かに似ている。そこに何故気付かなかったのかが不思議なくらいに。
そうして暗い色を持つ者同士の、呪われし邂逅が「炎と風の国」に近付くことを、今は誰も知る由もない。
下4:黒い悪夢
ディアルス王城のベッドに、ようやく慣れてきた頃に。
久しぶりに見た悪夢は、何かの前兆だったのだろうか。
――ごめんなさい……――あたし……。
今は誰も傍にいない、大切な者達を映す青い夢。そこに何か、黒い異物が混ざり込む。
――……だって誰も、あたしに気付くことなんてない。
誰にも知られず、消えてしまった誰か。残された物は確かに、誰かがそこいたと示しているのに……まるで初めからいなかったかのように、空ろな存在。
本当はみんな、わかっているのだ。誰かもその家族や仲間と、一緒に消えたのだろうと。
確かに誰かは臆病だった。荒事を避ける目敏さは大したもので、残った同郷者の目に触れていないのも、向き合うには辛過ぎると身を隠したのかもしれない。
それでも誰かはその場所にいた。そして消えることになった。
その時は逃げなかった――一人だけなら、きっと助かったのに。
間違いだらけの拙い選択。誰も危機を脱せず、誰かは空しく消えていく。
けれど正しい選択も無かった。そんなものがあれば、誰だってそれを選ぶ。
――アシュリン、お願い――……そのヒトの言うことをきいて……!
……見捨てることも、選ぶこともできなかった。
そのツケを支払うために、誰かの空ろな呪いが目を覚ます――
夢だけでは説明できないその視界が、どうして突然届くようになったのか。
激しい吐き気を堪えながら、あまりに強い悪寒に彼は飛び起きた。
「――……!?」
ディアルス王城一階の四隅に付属する小堡にいるはずが、見回す周囲が、冷たい大気に囲まれていた。
――ここは――どこなんだ……!?
気付けば足場すらなく、夜明けの薄暗い空へと叩き落とされた。
それではこれから――心新たに、茶番を始めよう、と。
わけのわからない彼を連れて、天から落ち往くものへと、慈悲なる声が微かに響く。
その憂色はさながら、天使の初仕事を見守る神のように。
――全く……すっかり予定が、遅れてしまいましたね……。
彼を何故か内包しているそれは、ただひたすらに落ちていく。
羽を持たないそれの背には、大きな落下傘が開く。地に降りゆくそれの目から見えているのは、丈の短い服で半ば以上露わな足が、落下傘の重しとして袋で包まれ、まるで大きな花の短い茎だ。
使命を果たさんと降りていくのは、それ一つではなかった。地上を背景に、同じ丸い花がいくつも眼下の暗がりに咲く。
その先に見える聖なる白城へ、黒い御使いとして顕れるために。
「……って……ディアルス、王城!?」
脳裏を占拠したそんな光景から、彼自身の強い驚きと、必死に彼を揺さぶる連れ合いの声が彼を引き戻した。
「レイアス!? どうしたの、レイアス!?」
生まれつきの一房の黒い前髪を除き、一瞬にして頭と髪が真っ白になった彼は、掴んだ掛け物を握り締めて体を起こした自身にやっと気が付く。
空色の長い髪を下ろし、隣のベッドにいた連れ合いは彼のベッドに座り、彼を覗き込んでいた。
「……ア、フィ?」
「そう、私! 眼を醒まして、レイアス……!」
蒼白な顔で色の落ちた髪の彼は、胸も早まり呼吸も荒く、全身に冷や汗をかいている。暗く青い目の連れ合いは、悪夢から逃げるように彼に訴えかける。
どうしてそれが彼に視えているのか、現状の答はわからなかったが。
「――侵入、者……!?」
「……!?」
今も続く謎の映像は、彼らの滞在する場所の危機なのだ。
自身の胸を抉らんばかりに掴んでいた彼は、ようやくその意味に思い至った。
「アフィ……誰か乗り込んできたぞ、この城に――……!!」
「え……!?」
彼の声でようやく連れ合いは、千族特有の気配の知覚を外界に向ける。そして程無く、強い違和感を探知していた。
「何これ……城の外には兵士さん達、中には知らない変な気配が沢山……!」
「力」は視えるが、気配探知は鈍い彼は、そのまま連れ合いに探索を任せる。
ディアルス王城の守りや、王都の警備を担当する騎士団は下級者が多い。主力は国境に配備され、王の周囲では数を恃んだ兵士が、王城の中庭の兵舎で訓練生活をしているのだ。
「みんな城に入れないみたい……! どうなってるの!?」
多少なりと力を持った大勢の兵士が、近場でざわめく気配。その実情を確認せんと、連れ合いが中庭に出る扉を開けようとした。
「――!? レイアス、ドアが開かないよ……!」
「え!?」
未だにおかしなものが同時に視えている彼は、よろめきながら客間の出口に向かうが、扉を一目視るだけで異状に気が付いていた。
「まさか……『内』と『外』が断絶されてる……!?」
扉を含めて、外気に触れる壁面全てが妙な「力」に覆われている。それがこの客間だけでなく、城全体を包んでいるとすれば、現状は納得できた。
「城に誰かが結界を張ってる――俺達は逆に、外に出られないぞ」
それで中庭にいる兵士達が城内に入れず、右往左往しているのだろう。
「そんな結界、いったい誰が!?」
「わからない……ディアルスの人間でないことは確かだろうが――」
そこで彼はまた、彼でない方の視界が再び強まり、激しい頭痛に襲われて膝をついた。
「っ……!!」
「レイアス!」
まるで視界の主に成り代わるような錯覚の中、そのまま彼は意識を失い……。
連れ合いの声は聞こえているのに、今も彼には、視野を奪う白昼夢が届き続けていた。
その悪夢の使いは、頭上を不自然に占める雲から、黒い花びらを振りまくように放たれていた。
石造りの城の天守に続く郭に、黒い影が降り立つ。それは先に着いていた仲間を見回し、空ろとしか言えない微笑みをたたえる。
――……へぇー……ここが、ディアルスなんだぁ……。
光も彩もない目に映っていたのは、間違うことなく、彼と連れ合いが休む人間の国の城。
その頂点を見上げた女らしき者の冷徹な声色に、彼は何故か、最悪と言える吐き気を催した。
それが彼の意識を強制的に、その女の視界へと向ける。
そうしてわけもわからず、視覚を共有する者がいるとは、その女も知らないだろう。
天空からディアルス王城の楼上に降り立った彼女は、降下に使った黒い落下傘の上下をちぎり、外套と腰巻のように纏う。同様にすっぽりと、落下傘を纏って姿を隠した仲間達の中心に立つと、天守の中間階にあるバルコニーを、単純な高揚と共に見上げ続けた。
「さてさて……あたしの相手をしてくれるのは、誰?」
彼女の姿は彼には視えない。彼はあくまで彼女の目から――まるで霊獣の目を通すように、その感覚全てから、彼女が感じる現状の情報を理不尽に受け取る。
「ほら、出て来て……ディアルス王家の誰かさん……」
楽しげな声色とは裏腹に、その心中は針の蓆だった。
彼女はこの場の責任者に近く、仲間は彼女の指示に従うように命を受けている。しかし新参の彼女が、そんな重役を任されたことへの反発を機敏に感じ……また、それだけ難しい任務を与えられた重圧を孤高に踏みしめている。
「……早く出て来ないと、誰か殺しちゃうぞ?」
呟く声は、驚くほどに空虚な音色。ところが彼女には不自然な確信……彼女が待つ事柄は間もなく成就するはずという、おかしな落ち着きがあった。
そして確かに彼女の思う通り、正確には感じた通りに、見上げるバルコニーには求めた相手の姿が現れていた。
階下を突然占拠した大量の不審な気配に、赤毛の王女がバルコニーに出てきた。そこで王女を見上げる人影の姿に、蒼白な顔付きで悲鳴に近い声を呑み込む。
「……あなた、は……!?」
出て来た王女の役目を、一瞬でも見失うほどに、それは有り得ない相手だった。
こんにちは、と。陽も昇り切らない朝方、相応しい挨拶などどうでもいいように、彼女は頭上の王女に気安く微笑みかけた。
「貴女がこの国……ディアルスの王女?」
「……!?」
「あはは、何で驚いてるの? って当たり前か、でも何か違うことでもビックリしてる?」
王女の動揺を彼女は強く感じ取っていた。彼女にはそうして、周囲の出来事を大まかに把握できる奇妙な感覚があるようで、それが彼女の冷静さの基盤らしい。
その情報量が多過ぎるため、彼女自身が考えていることは逆に、空ろと言っていい拙さだ。彼は何がどうなっていくのか、状況を見守ることしかできなかった。
王女は厳しい顔色で彼女を見つめ、柵を強く握り締めて、身を乗り出す勢いで尋ねた。
「あなたは何故――このような所に!?」
自国の王城に突然、謎の集団に侵入されたら当然のことだが、それ以外にも王女が言葉を失う何かが彼女の存在にはあるようだった。
王女の問いに、彼女はまたも無邪気に笑い返す。
そして、彼女がそこに使いに出された理由……彼女の主が望む展開を、一息に伝えた。
「『千族狩り』のディアルス王女。各地の千族を集めて国力を強化するのみならず、集めた千族を闘技賭博の対象にして、その戦いで発生した力を集めて『悪魔召喚』の動力源として利用した疑いを……我が主、千族秩序の裁定者『四天王』は、とても嘆いているよ」
「――な……!?」
王女が驚愕する。彼女から伝えられる内容――本来は半年前にディアルスで起こされた事変、それも行方不明のシャル都市長が招いた、許し難い禍に対する冤罪もあるが。
何よりこの彼女が、それを王女に告げること……そして口に出された脅威の関係者名に、言葉を失う。
ディアルス王城のいつもの朝は、夜勤の兵士が集まって跳ね橋を下ろす。日勤の兵士とその後交代し、開けられた城門から給仕係などが朝市に向かうことが日課となっている。
そのため城内の警備が手薄となる時間――夜勤者が外に出た直後に、閉ざされた王城に残るのは、王族と重鎮、そして使用人だけだった。
――誰も……『力』を使っていない……?
二階の屋根にあたる郭に降り立った侵入者は、飛び道具や爆発物を使っていた。
その場にいる兵士が戦闘不能にされていくことを、王女と話す彼女の視界の端から、辛うじて彼は読み取っていく。
統率者として、全体の状況も、気を向けるだけで彼女は把握できていた。
「抵抗すれば人死にが出るよ? 既に重傷者も出てるみたいだしね」
傍目には冷淡に王女を見上げながら、そう笑いかける。
その内には、彼もまた吐き気を催すほどの血の匂いと、それに対する彼女自身の感情が何かよぎる。しかしすぐ、多くの違う情報に隠されていく。
王女は華やかな顔をきつく歪め、一瞬背後を振り返る。次に見せたのは若いながらに、威厳と覚悟に満ちた、王族としての表情だった。
「あなたの目的は何なのですか? 我が国にあらぬ言いがかりをつけ、問答無用で不躾な侵入を行い、相応の報いは覚悟されているのでしょうね?」
「へぇ。戦う気あるんだね、王女様」
天守を包囲されて、孤立に近い状況の相手の強気に、彼女が歪んだ笑みをたたえる。
「あらぬ言いがかりか……こちとら、人間の国の商業都市長に泣きつかれてのことだけど。言いがかりと言うなら抵抗せずにこの城を調べさせて、そしてあの人間と同様、四天王様に直接申し立ててくれないとね?」
「――!?」
彼女の言葉が意味するところを悟った王女は、衝撃を確認するよう話を切り返した。
「シャル都市長が四天王に助けを求めたというのですか!? 我が国で不届きな賭け事を行い、悪魔を召喚せんと企んだのはあちらの方ですよ!?」
「そうかな? でもあの人間は、ディアルス国王の命令でそうしたって言ってるけど?」
「四天王」とはそもそも、世界の東西南北に位置する四つの監獄の古城の主――人間には対応できない千族の咎人を引き受ける、魔性の家系のことを言う。
自然界の「力」の四大要素たる地水火風を司るが、その身は悪魔の血をひき、毒を以て毒を制すと言われる最上級の化け物で……特に千族の間では、最も目をつけられたくない相手と言えた。
王女は再び、悲鳴を上げるような声で彼女に叫びかけていた。
「あなたもそれはご存知でしょう!? なのにどうして、あなたがそこにいるのです!?」
「……?」
にやり、と不敵に微笑んだまま、王女を見上げる彼女の思考に、ふっと空白が割り込んでくる。
彼に届く彼女の知覚もぶつぶつ途切れ始め、王女が続けた言葉も聴こえなかった。
彼女は不思議そうに、内心に空っぽな思念を巡らせていく。
「……貴女……あたしのこと、知らないよね?」
言いながら、王女の姿が何処か神経に引っかかるように、声の端には苛立ちを混じらせ始める。
「何でもいいけど、城は調べさせてもらうよ。それと誰か一人、王族を引き渡してね」
そうして彼女が仲間を振り返ると、落下傘で全身を隠す侵入者は全員、姿が消え失せていった。
「――!?」
驚く王女に、自らも纏っていた落下傘を、彼女は頭を隠すように被り直す。
「抵抗しない方がいいよ。妙なことをする奴がいたらあいつら、殺しちゃうから」
そうして、何を求めているかわからない敵が、見えない監視者となった状況が彼に届く。
王女の前から彼女の姿も消えた所で、彼は完全に、自らの視界のみに戻されていった。
扉の開かない客間に閉じ込められて、彼も倒れた状況で、連れ合いがとても心配そうに彼を介抱していた。
意識が戻ると、彼は真っ先に大丈夫だ、と口にした。座り込む連れ合いの手を握り、体を起こして互いに立ち上がると、とにかくまず冷静に呼吸を整えて呑み込む。
「……あれ? レイアス、髪の色――……」
先程までは白かった髪が、普段の灰色に戻った。彼自身にはその変化はわからなかったが、連れ合いは彼の頭を触りながら首を傾げる。
そのまま連れ合いが彼の肩にしがみつくように――安堵と共に、ぎゅううと抱き着いてきた。
「――何があったの? どんどん体が冷たくなって、呼吸まで止まっちゃいそうだったよ……いったい何を視ていたの、レイアス?」
暗く青い目の連れ合いが尋ねることは、ある意味、不自然だった。
彼が彼以外の何かを視ていた状態を、既に悟っている問い方。それは彼の特性――もう一つの体、感覚を共有する霊獣を持ち、使い魔のようにして情報を探れる内情を知るからだろう。
しかし彼がその現状を知ったのは、連れ合いが思うように霊獣で偵察をしたのとは違う不可解な状態だ。
「……ディアルスの城内に、何処かの『四天王』の手先が侵入したみたいだ、アフィ」
彼の異状を説明しても心配をかけるだけだろう。またゆっくり話す余裕のある状況でもなかった。
「『四天王』……? それって、『守護者』と敵対するっていう、あの魔族の『四天王』?」
ポカンとする連れ合いの顔は無理もない。その名は有名ではあるが、滅多に人間世界に関わることはない、強大で偏屈な存在なのだ。
世界で最強と言われる、自然界の「力」――四大要素である地水火風を司る勢力は、現代では魔の者「四天王」と、天上の鳥「守護者」の二系統がある。両者は力の拮抗した対立勢力で、精霊魔法と同等の強さを持つと言われる。
しかし「守護者」の拠点たる「地」が滅ぼされ、天上の鳥が姿を消した昨今、「四天王」が勢力を伸ばしてきている。それが千族間では懸念事項でもあった。
「『四天王』がディアルスに、何の用なの?」
「わからない。ただ、シャル都市長が関わってるのは確かみたいだ――アイツのしたことをディアルス国王の罪だと言って、城を調べさせろ、王族を引き渡せ、と使者が言っていた」
そこまで言うと彼は立ち上がる。荷物置きから小さな短刀と牙型のキーホルダーを掴み、外に出る扉でなく、城内に続く連絡通路の入り口に足を向けた。
「何処に行くの? 部屋からは出られないって、さっき――」
「外には出れないけど、中を動き回ることはできる」
通路側の扉のノブを握ると、簡単にがちゃりと回った。城を包んだ結界はそうして、内と外だけを隔てるのだと、彼の眼にはとっくに視えていた。
連れ合いは慌てて、外出用の鉛色の外套を手に取って彼を追いかける。
「待って、わたしも行く! 着替えるからちょっとだけ待って!」
「いや、アフィはここで待っててくれ。侵入した奴らは姿も気配も消してる……抵抗する奴は殺すと言うから、下手したら即戦闘になる」
でも! と不服を浮かべる連れ合いに、彼は無表情のまま、務めて穏やかに言った。
「俺はラストに相談しにいくだけだよ。アイツなら対抗する道具も造れそうだし、俺なら姿を消した奴らも、『力』の持ち主であれば視える」
「……!」
彼一人なら、見えない敵を判別しながら動くことができる。まずもって楼上で何が起きていたか、階下で把握しているのも彼だけのはずだった。
「アフィは何があってもここを開けるな。俺が帰るまで、自分の身だけ守ってくれ」
「……レイアス……」
連れ合いは召喚士としては強い力を持つが、身を守る術は拙い。それを長く一人にする気はない彼は、そっと客間を出ていった。
廊下に出ると、何が起きているか全くわからない使用人や客人が、不安そうに一階の共用玄関付近に集まっていた。
輪の中心では、若くて身軽な黒衣の千族らしき男が、閉ざされた玄関と格闘している。
「どうして開かないんですかねー? 外のヒトもこれじゃ、入れなくて困りますよねぇ」
その男の存在が、何故か妙に意識にひっかかる。彼は思わず、少し立ち止まった。
「…………」
男は確か、北東の客間に最近滞在を始めた客人だ。肩で括る赤い髪と、縞状に黒く染めた前髪。後は左頬に涙の雫のような化粧があり、道化を思わせる印象が強く、更には纏う色が多様で混沌としている。だから姿を覚えていた。
城の異変に困っているようだが、今はそれどころではない、と彼は踵を返して対側の客間へ向かう。
一階の四隅の小塔に続く客間で、彼は南東に、紫苑の少年は南西に居室を貸されている。そうして南の玄関を素通りしていく彼を、その道化じみた男がちらりと振り返って見ていたことには、彼は気付かなかった。
姿を消した敵にいくつか気付きながら、素知らぬ振りで彼は、紫苑の少年の部屋に辿り着いた。
「おそーい、兄ちゃん! 変なの起きてから何分経ってると思ってんのさ!」
「……さすがだな。もう何か準備中なのか、ラスト」
鋭い気配探知の才を持った少年も、彼とは違う方向で城の異状を感じたのだろう。床には多種多様の、特殊な粉末が広げられていた。
それは少年が、身を隠す結界除けを調合する際に使う材料だと、彼はこれまでの付き合いで大体知っている。
「ところで何が起きてんのさ、ここ。兄ちゃんなら探ってこれた?」
少年もそうして、彼が情報を持っているだろうと尋ねるのは、霊獣族の彼の特性を知っているからだった。
連れ合いと同様に、大元の疑問点は省いて、彼が現状を少年に伝える。
「『四天王』の手先!? そんな奴らが何しにここへ!?」
声は潜めながらも、少年も大いに驚き、その有名な脅威に焦るようにのけぞった。
事情をあらかた聴くと少年は、早く部屋に帰るように彼に促した。
「オレは元々気配ずっと隠してるから、ここに千族がいるとは気付かれてないはずだけど……兄ちゃんがいると、下手したら怪しまれるな」
「……そうだな。オマエの結界除けが完成するまで、誰も下手に動かない方がいい」
彼は本当は、二階の楼上に行きたかった。
つい先刻までは、彼と感覚の繋がっていた謎の視界の主。それが酷く気になっていたが、一番優先すべきは連れ合いを守ることだろう。
「時間かかるよ。張られた結界の中で造る結界除け、無効なことが多いからさ」
とにかく今は、用心すべきなのだ。それは彼も重々、理性ではわかっていた。
あれから王女達はどうなったのか。まだ城に敵がいる以上、何も解決してはいないはずだ。
「ナナハやあの騎士達がついてるし、早々、陥落はしないだろうけど……」
結界除けが完成したら、彼らを訪ねると言う少年の部屋を出る。
帰路についた彼は、先程と違い玄関の人影が消えたことに気が付いた。
「……通気口くらいは生き返るかな?」
ある思惑で彼は、周囲に誰もいないことを確認してから、きらりと短刀を抜いた。
玄関に近付き、上方の格子部分に隙間を縫うよう黒い刃を突き刺し、僅かに安堵の息をつく。
「必要にならなきゃいいけど……念のため、な」
そうして通路に戻ってきた彼の間近に――ふっと。
分岐路から無遠慮に現れた見えない敵に、彼は全ての警戒を忘れて、思わず声を上げてしまった。
「なっ……!?」
それは彼と少年の相談を叩き壊す想定外さ。どうしても見逃しはできない「力」だったからで。
「――きゃっ……!!」
やがて彼は、この悲鳴の主との遭遇が、此度の黒い悪夢の始まりと知ることになる――
下5:黒 -幼馴染み-
ディアルス王城が謎の結界により、城内と城外を分断された。内部には身を隠す多数の侵入者が暗躍し、気付いて抵抗する者は殺す、と使者は宣言を残した……。
そんな状況下で城の一階の廊下を歩いていた彼を、敵の誰かが様子を見に来たこと自体は、おかしな状態ではなかったが。
「何で、お前……!?」
「きゃああっ……!!」
しかし彼の前に突如現れた見えない敵は、視知った色の「力」を持つ者。
思わず彼は、相手の肩辺りのはずの位置を壁に押し付け、手探りですぐ腕を捕まえる。相手が纏った姿隠しの大きな黒布――侵入に使われた落下傘を、勢いのままに剥ぎ取っていた。
「何でここにいるんだ――……セレン!!」
「――!? ……!!」
落下傘を取り払われたことで露わになった姿は、彼と同年代で、胸までの長い茶髪の女。
鳥の嘴のような黒いマスクと黒い腕輪をしていることが、彼の故郷で知る姿とは異様に違ったが――
前髪を長く伸ばし、薄い上着を重ねるつなぎ服を愛用する同郷の女が、腕を掴む彼を必死な目付きで見つめ返した。
「セレン!? いったいどうし……――!!」
くりっと丸い涙目で、彼を見ながら何も喋らない知り合いは、それもそのはず。黒いマスクと腕輪で恐るべき窮状にあるのだと、彼はその特殊な眼で気が付く。
同時に、半年前に滅された故郷で行方不明となっていた同郷者がそこにいる現実に、この事変が彼らと無関係でないことを改めて悟る。
紫苑の少年の部屋を出る前に、少年は彼に、重要なことを問いかけていた。
「何の情報もなかった都市長の手掛かりが、まさか向こうからやってくるとはだけどさ。兄ちゃんはどう思う? 『四天王』は本当に、シャル都市長の言い分を信じてんのかな?」
それは彼も、「四天王」の名を聞いてから、疑惑を巡らせていた部分だった。
「……いや。あくまでまだ推測に過ぎないが……もしも『四天王』がディアルスに最寄の、北の四天王なら……四天王と都市長は、初めからグルなのかもしれない」
「……――」
ある理由で強く言う彼に、少年が息を呑む。黙って数瞬後に、強く頷きを返した。
「兄ちゃんもやっぱり、そう思うか……それなら、オレ達が探す相手も、この異状に関わってる可能性があるってことだよね」
「…………」
シャル都市長の屋敷に結界を提供して、ディアルスでも悪魔召喚の騒ぎを起こした者。そうした道具造りに長け、都市長と共に姿を消した猫風の娘は、少年の双子の妹なのだ。
悪魔召喚の騒ぎの際に、ディアルスを守った行方不明の幼馴染みも、彼らが追う敵と関わっている、という占い師の言葉を彼は思い出した。
だから彼は、その同郷者の「力」を眼にした時には、動揺と共に大きな高揚も抑えることができなかった。
「無事だったのか!? お前と一緒に消えたテルルや他の奴も生きてるのか、セレン!」
「……!」
同郷の女は涙混じりに彼を見返し、黒いマスクに覆われた口からは、悲鳴以外の声も上げられない様相だった。
身振りの相槌すらも打てないのか、と日頃は温厚な彼が、珍しく苛立ちかけた。
同じ瞬間、その黒い悪夢がそこに訪れた。
悪夢は冷然と、希みを貫く虚無の穂先を、彼に背後から突き立ててきて――
「――セイレーネから離れな。不粋な化け物男」
「……!?」
鋭利な殺気は、あまりに速やかだった。同郷の女への動揺が彼を惑わせ、知らない気配が近付いていたことに、彼は直前まで気が付けなかった。
「アンタの血でセイレーネを汚したくない。早くそこをどきな、殺すよ」
冷涼で空ろな声の主は、彼の首筋に冷やりとした長い槍を突き付けている。その相手はいつでも彼の首を突き破れるが、あえてそうしなかった、とそれだけを告げる。
その声が尚更彼を、現在の非常事態を忘れさせるほど茫然とさせた。
「っ――!?」
振り返ると同時に、同郷の女の腕を離した。
横に飛び退った彼の眼に、映った槍使いの姿は……それこそがここで、最も視てはいけない黒い夢の中核だった。
「……な……?」
自身の武器を取ることすらできずに、彼はただ、硬直する。
朝陽が入り始めた古い城の、明りを遮る壁に囲まれた一階の玄関口で。
まるでそこだけが暗闇に包まれたと思えるほどの、黒の坩堝。虚ろに過ぎる、光無き「力」の塊……――
「何、で――……そん、な……――」
真っ黒としか言えない、混沌とした暗い空気の中で。対照的に目立つ大身の槍の白い穂先を、中段に掲げる者の背に長い三つ編みが揺れる。
黒まみれの空気で見えない相手の頭が、おそらく白灰の髪であることを示すように、三つ編みの毛先だけが白く浮かび上がる。
……消え残る理性で、辛うじてわかったこと。それは、この声の主が彼と先程、視界を共有していた不思議な敏さを持つ彼女であること。
それなら彼女の姿に王女が驚いていたのも、納得のいく話だった。
激しい動揺に支配された彼の前で、殺意だけを彼に向ける槍使いの彼女が、同郷の女と彼の間にすぐに入っていた。
「……あれ……アナタ、ひょっとして……」
彼女の背にしがみつく同郷の女を見ずに、彼をまっすぐ見つめる灰色の目。
目敏過ぎる彼女はそこで、ある現実に気が付いたようだった。
彼女はずっと冷たい声色のまま――しかし初めて、小さな愉悦を口端へ載せる。
「アハっ……アナタ、あたしの知り合い?」
「……!?」
彼女の変化を示すように、黒まみれの場が徐々に薄まる。長い槍を持つ彼女の全像が、彼に見せつけられるように明らかとなる。
そこにいたのは、紛れもなく……耳を隠す白灰の硬質な髪を、今までになく長く伸ばして、三つ編みにした同年代の娘。下衣の短い黒と蒼の旗袍を着て、白い大腿を半ば以上露わにした――年齢以上の妖艶さを漂わせる、見慣れない姿の幼馴染みだった。
「お前……アシュー、なのか……!?」
面差しと髪の色は、探し求めていた大切な仲間と全く同じ。しかしあまりに出で立ちが異なり、「力」の色や気配も違う相手に、彼はそれだけ何とか口にする。
「へぇぇ。あたし、アナタの幼馴染みなんだ?」
彼女は更に一足とびに、その結論を呟く。同郷の女をちらりと振り返り、確信したように笑って頷く。
「ホントだ――……それなら、遊んでよ?」
高い天井を上目で見ると、下腿を庇う金属製の臑当てと尖り靴をカツン、と硬く踏み鳴らす。
その瞬間、人間ならぬ速さで彼女が華麗に跳躍して彼の視界から消える。
そうして動けない彼を嘲笑うように、壁を蹴って槍の頭を突き下ろしてきたのだった。
咄嗟に掲げた短刀だけで、彼が弾丸の如き一閃を受け流せたのは、棍使いだった彼女が戦う時には、まず頭を狙う癖を知っていたからだった。
――ええええっっ!? あたしなんか絶対足手まといで嫌がられるってぇぇ!
半年と少し前には、そうして荒事から逃げ回っていた幼馴染み。
棍なら力加減次第で、意識を奪うに留められる。殺生を避け、臆病と言われる彼女は常にそうしていた。
背後に着地した彼女が、すぐさま石突周りに楯状に「気」を張り、突き出された柄の衝撃に彼は弾き飛ばされた。
「がっ……!!」
槍を振り上げるよう立ち上がった彼女は、咳き込む彼にさらに追い打ちをかける。
「無理無理無理! そんな短刀じゃ今度は防げないし!」
それが突きより払いに向いた大身槍でなければ、彼には応戦の術はなかった。
片膝をついた彼に対し、穂先を一度引いて脇で槍を構えた彼女が、踏み込もうとした僅かな隙間。そこで何とか彼は持ってきた牙型のキーホルダーを取り出せていた。
「――!?」
「っ――!」
キーホルダーが光り、現れた長剣を床に突き立てる。下段から襲い来る槍を辛うじて受け止め、彼女との間合いが間近に迫る。
剣と槍では、距離が遠い方が槍に有利だ。彼女はすぐさま飛びのき、改めて彼の様子を窺い始めた。
「武器を携帯型で隠し持ってたか……それ以上はさすがに持ってなさそうだけど、剣以外にも切札はありそうだね?」
呟く事柄は全て的確だ。彼が同じ視界を共有していた時のように、彼女は現状をすらすらとそうして解析していく。
――あいつ……アシュー以上の目敏さと、武技を持ってるっていうのか……!?
とにかく武器を構えながら、幼馴染みの実力を知る彼の背筋に悪寒と戦慄が走る。
長剣と長槍という、相対武器の不利さもさることながら。防戦が精一杯の彼に飛びかかる彼女は、以前より踏み込みが強く動きの素早さも段違いだった。
それでなくとも里一番の武技を持っていた身に、何かで磨きがかかったとしか言えない。
そもそも幼馴染みが長棍を武器としていたのは、殺生という最大の荒事を避けるためだ。
ところが彼に躍りかかるこの彼女は、殺傷力の高い大身の槍を、棍や薙刀でも扱うように無遠慮に振り回す。槍術というより打ち合いを好む立ち回りを見せる。
「あははははは! もっと遊んで!! もっとあたしのこと、ちゃんと教えてよ!!」
「っ、アシュー……!?」
一撃一撃、強力な「気」を載せてくるわりには疲れ知らずだ。彼と刃を交わすことが心から楽しいのだと、その歪んだ黒い笑顔は語り……――
彼が何とか防戦できているのは、彼女のそんな戯れぶりと、新たな義手のおかげだった。
「――ふぅん。何か知らないけど、あたしの攻撃無効化してる? それ」
「……!!」
本来右利きの彼は、義手を傷めないため左手で剣を使っていた。けれど今、利き手で使える剣は予想以上に、彼の戦力を底上げしていた。
思う存分剣を振るってもびくともせずに、段違いに動かし易い義手での攻防は勿論のこと、「力」を視る眼を持つ彼の右手には、「力」に直接介入できる特技がある。
そうした彼の「気」を受けて彼女の斬撃を受け止める剣は、破壊力をその都度削って受け流しているようだった。
「アナタ、面白いね。いったい何者なんだろうね?」
そんな彼をにやりと見つめる黒い彼女に、彼は思わず即座に叫んだ。
「何者って、仲間だろ!? お前こそどうしたっていうんだ、アシュー!?」
それは彼らしからず、隅で彼らを見やる同郷の女をびくりとさせるほど大きく荒い声色だった。
ふーん、と彼女は、何度目かの頷くような溜め息を軽くつく。自分をまっすぐ見つめる彼から目を逸らすように、黒い長槍を後ろ手に持ち直した。
「アナタが知ってるあたしは、いい奴ぽいね」
僅かに俯く灰色の目には、おずおずと、彼女を見守る同郷の女が片隅に映る。
次に彼女が上げた顔には、憎悪混じりの引き攣った微笑が、その全面に載せられていた。
「それじゃあさぁ。そう思うなら、あたし達のために死んでよ?」
「……!!」
いつも困ったように軟らかく笑う幼馴染みには、考えられないあくどさの笑顔。
衝撃が大きく思考がついていかなくなった彼に、彼女が足を屈めて、また跳びかかろうとしたが。
「さすがにその言動は不作法に過ぎる、『キニス』」
彼女と同郷の女が最初に出て来た分岐路、一階の中央の管理棟に繋がる廊下から、新手の声が響いた。それに彼女は舌打ちして、その場所に踏み止まった。
場に出て来た二つの人影に、彼は言葉を呑み込む。そんな彼を横目に見つつ、彼女が不機嫌そうに声をかける。
「何でアンタが出てくんのさ? 弱っちいんだから大人しくしてなよ」
「わたくしは彼に訊きたいことがあるのだ。『桔梗』も付いているし、わたくしに何かあれば、あの方が見過ごされるわけがない」
「……!?」
名指しされた彼は、その礼服姿で褐色の髪の人間の男――彼らを半年前にディアルスの事変に巻き込み、故郷の存亡にも関わっているらしいシャル都市長と、従者らしき朱い忍装束の少女の出現に顔を歪ませる。
「貴様ら――……どうしてここに……――!!」
彼の内に渦巻き始めた激しい感情。それは全身を沸騰させて熱くしていく。
シャル都市長は坦々と、彼のことなど意に介さず、呑気な内容を問いかけてきた。
「貴男が生きているのが、実に不可解なのだがね。邪魔者は葬ったとあの方からは聞いていたが……貴男の連れは、今はおられないのですか?」
都市長が言う連れは、里に残る彼の悪友を指す。都市長は以前、攫った悪友のことを妙に気に入っていた。女嫌いだという都市長のそれは、悪友が恐れおののくほどの好意だった。
「うはー、ディーズ、諦め悪過ぎだし! いくら東の方に口調が似てるからって、まじであの程度の相手にしつこ過ぎだっつー」
そのように従者である者――都市長が屋敷に住まわせていた四人の娘の内、薄柿色の髪の少女にも笑われるほど、周知である偏執らしい。
都市長に答える余裕などない彼をさておき、槍使いの彼女が割って入った。
「いいけどさ、客間のお迎えはもう終わったわけ? それがアンタ達の仕事でしょうが」
侮蔑するように言う彼女に、当たり前だ、と軽く答えたシャル都市長。彼の背中を、それまでの心を無に帰すほどの冷汗が瞬時に走った。
「――何をしたんだ貴様達!?」
客間には作業中の紫苑の少年、そして連れ合いが息を潜めて待っているはずだ。
彼がここで彼女とやり合っている間に、もしも連れ合いに、何かがあったとしたら――
度重なる焦燥と憤怒で、脳裏は最早、焼き切れかけた彼だったのだが……。
都市長達を呆れ目で見る彼女の横顔に、白い誰かの苦笑いが、ふっと重なって映った。
――アフィちゃん、何だか危なげな子だよ――……誰かが見ててあげないと。
だから自分のことは心配するな、とかつて彼に応えていた、白灰の髪の幼馴染み。その残影はひたすらに、この場に固執するな、と彼の取るべき行動を訴えてくる。
そんな過日のやり取りが無ければ、彼は何も納得できないままで、場に留まり続けたことだろう。
「――あれ? 逃げる気なの、アナタ?」
「――っっ……!」
目敏過ぎる彼女が、彼の退却体勢にいち早く気が付く。彼女と都市長の従者をどう切り抜けてこの場を離脱するか、彼は神経に怒気じみた緊張を走らせる。
しかし彼女は意外なことに、彼にあっさりと背を向けていた。
「ま、いっか。どうせ城からは逃げられないし」
そうして最早、興味を失くしたとばかり都市長達を見て、つい今感じたらしい新たな情報を報告する。
「ねー桔梗、何か上が手こずってるし。応援いかないと、多分まずいよ?」
「って、あんたねぇトネリコ! 違ったキニス、アタシに指図すんじゃないよ!」
彼女より年下に見える薄柿色の髪の少女だが、自身は先輩と言いたげな口ぶりだ。何故か二人は、心なしか口調が似通った女達でもあった。
「……!?」
上が手こずっている。それは彼女達が初めに降り立った郭のことだろうが、そこでさらなる戦闘が起きているのか、と彼は身を引き締める。
戦況を伝えた彼女の言う通り、二階へ増援に向かうためだろう。ずっと縮こまっていた同郷の女を彼女が引っ張り、都市長も彼を一瞥してから、従者と共に場を離れていく。
彼女は一度だけ彼を振り返ると、彼が見たくないような歪んだ笑みを再び浮かべた。
「余計な加勢はしないことだよ。後でちゃんと、アナタも殺しに行くから」
「……!!」
やがてまた、黒まみれの空気に包まれていく。そのまま、彼が追い求めた彼女達は、姿を消していったのだった。
客間に戻る方向へ全力で走りながら、嫌な想像だけが彼の総身を駆け巡る。
もしも既に連れ合いが、敵の手中に落ちていた場合――彼はどう戦えると言うのだろうか。
「……余計な加勢、どころの話じゃない」
彼女は当然、自陣の有利さをわかっているのだろう。城に張られた結界は内と外を分けるだけでなく、中にいる者が「力」を使えないよう、制御系統を狂わす妙な念波が流されていた。
「霊獣も使えないと――俺に何ができるって……?」
先刻も生身で、黒い彼女と戦うしかなかった。使い始めたばかりのはずの槍で、体慣らしのようだった彼女に対し、彼は長年愛用している剣の全力であの体たらくだった。
玄関口が無人の時に、唯一の一手は「力」に介入できる特技で行っているが、それが実を結ぶまでは時間がかかる。
それまでディアルスがどうなるか全く予想できない状態で、陸の孤島と化した王城に、大切な連れ合いと閉じ込められている――
連絡通路から焦慮のままに全力で、自室の扉を叩き開ける。
その向こうには、想定外の光景が広がっていた。
「あ、レイアス! 良かった、無事だったんだ!」
「遅いし、兄ちゃん! てっきり捕まったと思ったじゃんか!」
「うわあ~、ビックリしますから静かに開けて下さいよ~」
……はい? と。
彼の元に駆け寄る、二人の声への安堵と共に、続いた若い男の緊張感の無い声。何故か揃って、この客間に隠れていたらしい者達に、彼は茫然と大きく目を開いていた。
「……アンタ、誰だ?」
一応その道化じみた化粧の男が、先程玄関口にいた北東の間の客人とわかっていたが、何故ここにいるのかは、不覚にも彼はさっぱりわからなかった。
「オレの所から順に、客間を調べにきやがった奴がいたんだよ、兄ちゃん」
テキパキと事態を説明する少年は、首を傾げる連れ合いを思わず抱き寄せた彼と違って、冷静そのものだった。
「オレはまだ中途半端だけど結界除けを使ったから、見つからずにそいつらは北の客間を次に調べに行って、オレは先回りしてアフィねーちゃんを隠してたってわけ」
南の玄関口付近で、彼と何者かの戦闘が起こった気配を少年は気付いていたらしい。そこで連れ合いの保護を優先し、敵が二番目に北西の客間を調べている隙に北回りにここまで来たのだ。
その途中で、三番目に調べられるはずの北東の客間の男も拾い、全員を匿ったこの部屋に改めて、結界除けを使ったのだという。
彼はつくづく、その有能な少年を拝むように、感謝することしかできなかった。
「有り難うございます、君は命の恩人ですね~。その優しい心遣いに、私はハートがどきゅんですよ」
北東の客人も少年に手を合わせ、そして意味のわからないことを喋る、道化じみた赤い髪の男だった。
さすがにそれの相手をする余裕は、少年にも今はないように見えた。
「アンタはここで隠れてろよ、誰か逃げてきたら一緒に匿ってやってよ。オレ達は初めの予定通り、天守に加勢に行こう、兄ちゃん」
もう隠れても意味なさそうだし、と少年はその後に続ける。
既に戦闘を起こしていた彼も異論はないのだが、彼としては連れ合いと少年には、このまま隠れていてほしかった。
それはおそらく――
――後でちゃんと、アナタも殺しに行くから。
紫苑の少年に答えられずに黙り込んだ彼を、少年と連れ合い、ついでに客人の男が不思議そうに見る。全員で天守に向かえば、あの彼女との邂逅は避けられないことに彼は俯く。
悩む時間も、事態を説明できる余裕も、天守のことを思うと一刻の猶予もなかった。
「……天守には俺だけで行く。悪いがオマエは、ここでアフィを守っててくれないか」
「――へ?」
「事情は後で説明する。もしも上にオマエの双子がいたら、オマエの代わりに可能な限り保護すると約束する――今すぐに全て、こちらの手札を見せるわけにはいかないんだ」
真剣そのものの彼の眼差しに、少年と連れ合いが顔を見合わせていた。
「オマエはまだ見られてないし、この城の中じゃ精霊も使えないだろ?」
少年の急拵えの結界除けでは、「力」を封じる作用の解除までは難しいだろう、と彼もわかってのことだった。
紫苑の少年は本来、竜の次に強力と言われる精霊使いだ。
自ら造った武器で戦う職人像が普段の姿だが、それも外見に見合わず相当の実力派だ。
もしも今後、先程の黒い彼女が襲ってきた場合、「力」抜きで対抗できる一番手は少年だろう。敏さや扱う武器の特性からも、武技が最も優れているのはこの少年だ、と彼は見定めていた。
それだけの実力を持ちながら居残りを指示された少年は、とても不服気に彼を見上げた。
「そんなこと言って、それで勝算あんのかよ? 兄ちゃんだって霊獣使えないんじゃねー?」
「外向きの『力』を使えないのは多分敵も同じだ。だからあいつらは、爆弾や銃みたいな人間の武器を上では使っていた」
彼女の視界を見ていた時に、それは彼も気が付いていた。
結界の一部である「力」の妨害効果は、敵味方問わずなのだろう。
「……これは多分、俺達の里を滅ぼした結界だと思う。だから自力で、落とし前をつけたい」
「……――」
霊獣という強い「力」を持った者達の隠れ里が、あまりに呆気なく陥落した理由。
生き残った者達からの話で、まずまともに応戦もできなかった無念を、彼らは聞いていたのだ。
可能かはわからないが、結界を壊すことが打開策だろう、と彼は目算を告げる。
ずっと黙っていた連れ合い――竜の娘も、召喚の「力」を封じられて、足手まといを自覚している。だから力無く頷いたことにも胸を痛める。
そうしてそのまま、彼は一人で、その拠点を後にしていった。
下6:色なき戦い
ディアルス王城の内と外を隔て、「力」の使用を妨害する入り組んだ結界。
シャル都市長の屋敷でも同様に、千族の「力」を封じていたそれを感じながら、単身で彼は人気のない階段から楼上へ向かっていた。
「今回のは……『水』だけでなく、『土』なんて稀少属性できたか………」
この結界に力を与えている術者は、おそらく以前と同じで結界内にはいないだろう。
「力」を受け取り、結界を紡ぐ管理者がいれば良い。それが紫苑の少年の家族のはずだ。
だから少年に言った通り、その相手を目標に、彼は起点に近いはずの天守へ向かう。
――余計な加勢はしないことだよ。
「――っつ――……」
やっと見つけた幼馴染み……しかし「力」の色も挙動も別人の、黒にまみれた槍使いの彼女。
どうやら都市長と同じ黒幕に従い動いているが、それが都市長も口にしていた、あの方――おそらくは「四天王」なのだ。
彼の眼が確かならば、ディアルス事変の直前に「炎と風の塔」で、幼馴染みに声をかけていた魔性の男としか考えられなかった。
――……やはり可愛い方ですね、貴女は。
その男はシャル都市長の屋敷に張られた結界に助力し、とても純度の高い「水」の色を纏った魔性の者だった。何かの理由で、幼馴染みをとても気に入った風でもあった。
今から思えば都市長はその後の事変で、己は四天王を目指す、と口にしていた。そして今、四天王の使いを名乗る彼女と働きを共にしている……それらが意味する現実は一つだけだった。
――もしも『四天王』が北の四天王なら……都市長は最初からグルなのかもしれない。
東西南北に居を構える四天王の内、北の四天王は「水」を司る家系として知られる。あの男が四天王であるなら、「水」の色にも納得がいく。
都市長の屋敷に結界を張り、ディアルスに関わり、その途上で目を付けた幼馴染みに何をしたのかはわからない。そうして幼馴染みが彼らと戦うように仕向けた者が、北の四天王だとしたら。
紫苑の少年は奇しくも、同じく都市長の元にいる双子――少年を認識できなかった相手に、ある推測を彼にぼやいていた。
――ミティがオレをわからないのは、何かの精神干渉を受けさせられたのかもしれない……だってあいつ、元々あんな変な口調じゃないんだ。
彼も紫苑の少年も、つまりは同じ局面に立たされていた。
探し求めていた者が彼らを忘れ……そして刃を向ける現実に。
そして少年は気付いていただろう。
少年の身内は最早、彼らにとっては、故郷を滅ぼした仇となってしまったことに。
――……こんな仕掛けを造るミティが、何を考えてるのかわからないんだ。
「可能な限り、保護する……か……」
近付いてきた階段の出口――戦場に向かう扉を見上げながら、彼は半ば自嘲する。
「アシューを見てなきゃ……言えなかったな、そんなこと……」
――このままじゃ何をする気かわからない。どんな理由があってもオレは止めたい。
どんな経緯で、どれだけいたいけな娘であっても、一つの村落を皆殺しにするような結界の構成。その助力は許せることではなかった。
けれど今は他ならぬ彼らの幼馴染みが、平和な人間の国を脅かす暴挙を平然と行っている。
「何で――……こんなことに……?」
彼も少年もずっと呑み込んでいた言葉を、彼は呪うように呟く。
郭の北側から中央までそびえる天守は、昇るための外階段が東西にあり、狭間付きの城壁が縁取る楼上全体は早朝の冷気に包まれている。それでも一部に強い「力」の熱気が飛び交っていた。
郭の南東にある内階段の扉から顔を出した彼に、最初に気付いたのはやはり目敏い彼女だった。
「あれれ? 惜しいな、もう少しで殺せたところだったのに」
彼女の前では王女付きの黒髪の騎士が、赤眼を苦々しげに歪めて満身創痍で、外階段の一つを黙々と死守していた。
「――……!!」
彼女の周囲には数人の見えない敵が弱り、その「力」の色にも彼は驚きを隠せなかった。
彼女が来るまで、その場の他の敵は黒髪の騎士の手で止められたのだろう。
残り一つの外階段がある郭の西、天守を挟む反対の楼上では、金髪の騎士と妖精の女が違う敵達の相手をしているようだった。
「……ナナハ?」
彼が驚いたことには、妖精の女はこの結界の中でも、魔女たる己の魔法を駆使していた。
「あんなの反則だよねぇ。妖精が魔女ってだけで微妙なのに、持続的な結界返しを使って尽きない魔力とか、どんだけなのやら?」
くくく、と嗤う彼女の解説は、彼も少し覚えがある内容だった。
妖精の女は金髪の騎士と背中を合わせ、猫耳を着けた幼い娘と、顔をベールの帽子で隠す魔道士然とした女を相手にしている。この結界に関わる紫苑の少年の双子、猫娘とその従者を前に、ぶち切れ寸前といった鬼面で紅い光を纏って佇む。
物言わぬ従者の横で、自分達を阻む妖精の女に憤慨する猫娘の声が、反対側にいる彼の元にも届いた。
「もー、ですのニ! ミィとれんれんの結界が効かないなんて、おかしいですのニ!」
そして猫娘は、娘なりに真剣らしい声色で、何とも空疎な内容を続ける。
「さすが、悪の総本山攻略は、一筋縄ではいかないですのニ!」
本気でそう思っているとすれば――この侵入者の集団の大義に、彼は改めて顔を歪める。
対する妖精の女は、遊び心の欠片もない声色で厳しく答えていた。
「世の中甘く見るんじゃないわよ。何度も同じ手が通じるわけないでしょ」
「うほー。ナナハちゃん怖ぇ、さすがだねぇ」
その背を守る金髪の騎士や、妖精の女と少し前に交わしていた会話を、彼は思わず頭に浮かべる。
彼の里が何故、呆気なく滅んだか――
おそらく「力」で応戦できなかったのだ、と話した彼に、妖精の女は金髪の騎士を横に、酷く怪訝な顔をしていた。
――そんな高度な結界、一朝一夕で展開できるのはおかしいわ。そもそもからして、結界だらけの隠れ里だったはずでしょ?
――わかんないぜぇ? ナナハちゃんも『力』封じられたらタダの妖精の女の子なんだし、気を付けた方がいーけどなぁ。
ま、おれはその方が守り甲斐あるけど、と笑う騎士を、妖精の女は一見無視していたが。
――そんなのに対抗しようと思えば、日頃から自分に、結界返しをかけておくしかないわね。
その時そう口にした予防策を、どうやら本気で実践していたらしい。何と勤勉なことか、と彼も少し気が遠くなる。
そうした妖精の女のおかげで、ディアルス側の負傷兵達は回復魔法を施されていた。
――ラスティルほどじゃないけど、私だって回復魔法くらい嗜んでいるわ。
精霊魔法の使い手である紫苑の少年を、密かにライバル視しているらしい。不機嫌そうに言っていた姿を思い出しつつ、彼は自身の出方をしばらく悩むことになる。
「貴様は手を出すな。この女はこの手で葬る」
黒い彼女におされながらも、血走った眼で言う黒髪の騎士には、二重の意図があるのだ。
王女は必ず、自分が守る……そして彼の仲間であろうと、彼女に容赦することはない、と。
当初の目的通りであれば、黒髪の騎士と戦う彼女は置いて、結界の猫娘の確保に西側に行くべきだろう。
しかし彼女の先の言葉、もう少しで殺せる、という戦況は嘘ではなかった。
今は彼女も、彼の動向を窺って攻撃を止めているが、ここで見捨てればおそらく黒髪の騎士は死ぬ……黒い彼女に殺されてしまう。
「っ――……くそ……!」
彼らをこの国に迎えた王女の、柔らかな笑顔が脳裏に浮かぶ。
王女がどれだけ黒髪の騎士を信頼し、そして慕っているか。王女の近臣で知らない者はなかった。
――ファーは騎士団だから、一応審議院側でしょ? 審議院の意向に大きく反しないなら、二人は将来一緒になれるんだって。
連れ合いは彼に、妖精の女から聞いた裏情報を嬉々と話した。そのように王家と審議院の選んだ者が婚儀を交わすのが、ディアルスでは伝統であると言う。
黒髪の騎士が国王の器であるかどうかはともかく、王女と騎士は互いを慕い、その仲は国家レベルで公認……祝福されている。
そんな者達の一人を、四天王の裁定であれ彼女が手にかけてしまえば、王女の薄青の目はどれだけ悲しみに染まることか。そして彼女が容赦される余地も無くなるだろう。
「――どうしたの? 二人がかりで来れば、あたしのことも殺せるんじゃない?」
場に留まる彼と、階段の前から離れない騎士に、彼女は意地悪く笑いかける。
「一対一ならどっちも負ける気しないな。『力』無しだとダサいね、アナタ達」
騎士が階段を離れれば、手負いであっても彼女の仲間が天守に侵入できてしまう。それを考えると彼がここで戦うしかない……彼女の言う通り、彼では力不足だとしても。
むしろここまで、階段を守り切った黒髪の騎士は相当のものだ。改めて剣を構えながら彼は嘆息せずにいられなかった。
彼が向かえなかった西側の方では、黒い彼女と共に上がってきた薄柿色の髪で忍装束の少女が、同じような恰好で妹分らしき翡翠の髪の少女に交代を指示していた。
「緋桐はアタシの任務を代わりにやってきな。ぴんぴんしてるの、あんただけでしょ」
「ええ? でも姉様、今、その必要はありますか?」
赤い目を丸くする翡翠の髪の少女は、金髪の騎士と戦っていたが、優勢なのは少女だった。
金髪の騎士はたはは、と、黒髪の騎士ほどではないが傷を負いながら、ひたすら妖精の女の背中を守る。
「やだなぁ、あっちの嬢ちゃんの方がさらにドSそうだなぁ。おれも交代反対~」
「イソシギ! ふざけてないで真面目に戦いなさい!」
猫娘と従者の女相手に、魔法戦を繰り広げる妖精の女が、苛立ち混じりに苦く叫ぶ。
魔法戦も苦闘だった。桜色のショールの中からいくつも飛び道具を取り出し、猫娘は絶え間なく攻撃を仕掛けていた。
「ミィの鉄槌はそう簡単に尽きませんのニ! 悪い奴は許さないですのニ!」
妖精の女はその弾を全て魔法で相殺し、さらには得意の魔弾、魔力の塊で反撃をかけるのだが、それらは全て猫娘の前、従者の女の直前で立ち消えていくのだ。
「何なの……? あの理不尽な防御壁……!」
従者の女の胸元には、ベールに半分隠されながらきらりと光る、黒い珠玉を嵌める赤い胸当て。それが妖精の女の攻撃を弾く力源とはわかったが、その屈強さはどうやら理解を越えたレベルであるらしい。
金髪の騎士が妖精の女の背を守らなければ、近接戦には弱い魔女は隙だらけになる。それを覆すほど全方位への攻撃を続ければ、さすがに魔力が持たないだろう。
黒髪の騎士も同じだろうが、何かを守りながら戦うというのは、なかなか難儀なことなのだった。
「何て言うかね~。敵さんの武器、色々便利過ぎだよなぁ」
金髪の騎士に攻撃を仕掛けていた翡翠の髪の少女は、赤い小手を着けた両手で、小柄な見た目に合わない大きな棍棒を二刀流で振り回していた。
「伸び縮みする棍棒とかさ、しかもそれを軽々扱う腕力とか無しっしょ。いくら化け物娘でも、元の筋力も込められる力も、この結界の中じゃ限界があるだろーになぁ」
棍棒に対して、騎士は鞘に収めたままの剣で対抗していた。妖精の女の背後から大きく動けない以上、間合いだけでも圧倒的に不利だった。
「折れる、折れるー。心じゃなくて、剣が折れるぅー」
不真面目に言いつつも、切実らしい棍棒対剣の攻勢。しかし相手が変わったことで、少し風向きが良くなったようだった。
使用者の元に戻る投擲武器を扱う薄柿色の髪の少女が、投げた凶器を鞘付き剣で打ち返してくる柔軟な金髪の騎士に、腹立たしさを満面に浮かべた。
「――ったく。あいつらからあんまり目ぇ離せないし、面倒くさいったら!」
不利になるのを承知で、この少女はここにいた方が良い事情がある。その時果たして、誰が気付けていただろうか。
西側がそうして、何とか持ちこたえていることだけはわかった。一階の城内よりさらに動き易い場所で、楽しげに長槍での攻撃を繰り出す黒い彼女に、彼も果てしなく苦戦していた。
「あははははは! 何で何で!? 負けるってわかって何でそこまで頑張ってるの!?」
「っ――……!!」
階段を守る黒髪の騎士に、背中を向けられない制約が彼女にもある。それでようやく、彼は応戦できている状態でもある。
それでも彼の目論見に対し、半ば気付いているかのような彼女にも、彼は冷や汗が流れる。
「どうやら時間稼ぎしたいみたいだけどさ。いったい何のアテがあることやらねぇ?」
たまらず彼は、一度大きく後退し、彼女と同じ問いを返さずにはいられなかった。
「何で俺達と戦うんだ!? 四天王に弱みでも握られたのか!?」
彼女はあれ、と。面白そうな歪んだ笑みをたたえ、そこで一旦攻撃の手を止めた。
「あたしだけに訊いてるわけじゃないね? それ」
喋る余裕がほとんどないこともあるが、あえて主語を言わなかった彼の意図を悟るように……くるりとその周囲、負傷して膝をつく見えない仲間達を見回して微笑んでいた。
「なーんだ、知ってたんだね。ここにいるコイツら、セイレーネもだけど、霊獣の里から来た奴らだって」
彼が最初にこの場に来た時、驚愕した大きな理由。そこにいる見えない敵の多くは、知った「力」の色を持つ同郷者だと彼には視えていた。
霊獣の里から来た者だと、仲間を他人事のように語る彼女に、彼はいっそう険しい視線を送る。
「……そいつらのことも、覚えてないのか、アシュー」
「――ううん? あたしの関係者らしいなってことは、ちゃんと知ってるし?」
にやりと彼女は、いったい何処まで現在の己に自覚があるのか、全く掴めない顔付きで口の端を歪める。
「あ、ちなみにあたし、キニスって呼ばれてるから。そんでコイツら、今は口きけないから、何をきいても無駄だし寝返りもできないからね」
「……――」
わざわざそれらの事情を明かす彼女の、真意がわからず彼は黙り込む。
喋れないながら動揺したような、見えない仲間達の中心で、彼女は一人楽しげに笑った。
「代わりに教えてあげちゃおうか。彼らは四天王様に忠誠を誓って、その証として自分の『霊骨』を差し出したわけ……命だけは助けてもらうためにさ」
それはまるで、彼女を良く思っていなかった同郷者への復讐のように――
その闇をあっさりと暴く彼女に、彼は両手を握り締める。
「霊骨」とは、霊獣というもう一つの体を持つ化け物である彼らが、その分身の依代として持つ先天的な器官だ。体内の骨のどれかがそれに成り代わっているが、部位は個体によって違い、霊獣を使う際には熱と光を発することで見分けが付けられている。
「霊骨が無いからこいつら、結界が無くてもどうせ霊獣呼べないし。『実体化』できた奴も全然いないし、あってもどうせ役立たずだろうけどね?」
「……アシュー……!」
「実体化」。普段は霊体として影を投げている霊獣の本体は、本来は異界に坐する。その本体は、霊骨を媒介にしてここにいるヒトの身と存在を入れ替える。そうしてこの世に「力」を体現する霊獣族の奥義が、「実体化」と呼ばれている。
異界と現世を行き来する化け物であるのが彼らの本質と言えた。空気の繋がる視界の内なら、霊体の霊獣は何処でも具現できる。「実体化」ができる成熟した者は異界を経由することで、霊獣を行かせた場所なら本体も一瞬で行ける。
だから幼馴染みは、先に里に向かわせていた自身の霊獣の元まで、彼らより早く故郷に帰ることができたのだ。
「実体化」に到達せず、外界に出ることが許可されていなかった仲間達をにこやかに罵倒する彼女に、彼は吐き気を抑えて叫ぶように問い返していた。
「お前はどうなんだ……! バステトは使えるのか、アシュー!?」
それを尋ねた彼の眼には、彼女が纏う「力」の色は、以前と違って黒まみれに変わり、とても同じ「力」を扱えるようには視えなかった。
荒野の里に、首輪を落としていた彼女の霊獣。彼女と入れ替わらずとも、何故か常に「実体化」していた白猫は、異界に戻すことの方が手間だったという異端の霊獣だ。しかしそれが消えてしまった現実を、彼はここで厳と問いかける。
彼女はふっと、浮かべていた嘲りを消し、恐ろしく空ろな表情を浮かべた。
そして、その存在に対する、彼が最も聞きたくない答を告げていた。
「……あたしは何も使えないよ。バステトもフェンリルも、あたしの中にはいないよ」
「――……!!」
息を呑む彼に対して、これまでの在り方が全て、まるで偽物だったかのように……そこにいたのは、黒いだけの空虚な誰かだった。
「あたしは多分――……誰かの真似をしてるだけだから……」
彼の彩の無い眼を見つめる彼女は、ただ救いを求めるように訴えかける。
「だからあたしに……もっとあたしを教えてもらわないと……――」
その彼女の拙い声に、いつか見た夢の黒い異物が、不意にそこで重なって視えた。
――だって誰も、あたしに気付くことなんてない。
それは彼が、空色の連れ合いに出会って間もない頃に、一度だけ彼の夢に顕れた不思議な黒い少女――
その時は確か、連れ合いと幼馴染みの霊獣の白黒猫が彼の近くで眠っていた。
「お前……まさ、か……」
――わたしは私を奪って、あたしを一人で残していった。
言葉にはできないが、彼は彼女の正体を漠然と感じ取る。
そんな彼だからこそ彼女を視ることができる、と黒い少女は告げていたことも思い出す。
昔からずっと、幼馴染みは白っぽい雰囲気でありつつ、黒い影を常に伴っていた。
――この者も二つの顔を持ってはいなかったか?
――アシュリンのねーちゃんって、キレると別人にならない?
基本的に弱腰な彼女は、倒さなければいけない敵に出会った時は、怯える己を忘れるように真っ白となった。そのように戦うところを、彼も幾度か見かけていた。
「力」は「心」。少し前に自ら口にした言葉が、彼にある真実を囁きかける。
白黒の猫と黒い狼、幼馴染みは二種類の霊獣を「実体化」することができた。それは一人一つの霊獣しか持たない彼らと、最初から違ったもののはずだ、と。
彼は飛び犬、悪友は鳥。かつては暴走する赤い獣だった白い飛び犬は、彼の右腕と共に赤い光を失った。
おそらく目前の黒い彼女も、幼馴染みの命と共にその「力」――心を失った状態なのだ、と己の眼は残酷に告げる。
――でもじゃあ……あの黒は何の黒なんだ……?
今の彼女が纏い続ける、重苦しい雨雲のような暗影。命尽きた彼女を動かす力は、その黒としか思えなかった。
――フェンリルじゃない……? フェンリルもいない、さっきそう言ったよな……?
二つの霊獣を持っていたから、一つを失っても生き延び、「心」の模様も変わってしまった。それが一番頷けるのだが、そうとも言い切れない彼女の姿に、彼は増々混乱に陥る。
何故ならもしも、いずれの霊獣も消えたのならば……それは幼馴染みの姿をしただけの、全くの別人なのだろうから。
どちらも黙り込み、互いを深く見据えるように立ち尽くしていた彼と彼女の元に――
「ちょっとキニス。しっかりしなよ、あんたの仕事は全然終わってないよ」
ぽん、と彼女の頭を背後から叩き、はっと正気付かせていた者。近付いてきたのは彼女とよく似た口調の、薄柿色の髪の少女だった。
「…………」
彼女は相手を軽く振り返り、少女の黒い目をじっと探るように真剣に見つめる。
「……そうだった。あたしはあいつら、殺さないとだった」
まるで薄柿色の髪の少女を写すような、ここに現れた時通りの彼女に立ち戻っていく。
「……!!」
一連の流れに彼は、ある違和感を見逃しはしなかったものの……。
――西はどうなったんだ……!?
彼と彼女が戦い始めてから結構な時間が経っている。西側で戦っていたはずの敵の少女がこちらに来るのは、向こうが制圧されたのか、と一瞬思いかけた。
しかし薄柿色の髪の少女は忌々しげに、その場に来た理由を吐き捨てる。
「全く世話の焼ける奴。緋桐が戻ってきたから良かったもののさ」
下階に送っていた別の仲間が、今は戻って戦っている。つまり敵の勢力が増えて、不利になった事態であるのは変わりがなかった。
黒い彼女はふう、と、不敵に微笑みながら応えるように息をついた。
「城の調査は終了ってとこか。それなら後は、王女か王様を捕まえるだけかな」
視界の端に、彼と黒髪の騎士を捉えながら、見上げた天守にいる王族へ伝えるように呟く。彼はいよいよの時の到来に、全身を緊迫させる。
薄柿色の髪の少女は、黒い彼女ほど戦闘力はないが、手にする投擲武器は剣士の彼や黒髪の騎士には厄介なものだ。それも騎士は、階段前から大きく動けないために尚更になる。
見えない敵が天守に行くのを食い止めるには、あくまで階段前にいなければならない。彼が黒い彼女、騎士が少女の相手をするとして、戦いが長引けばまだ余裕のある彼女達に軍配が上がるだろう。
「チェックメイトって……そろそろ宣言してもいいかな……?」
ずっと天守を見ていた彼女が、戦況にそう言いかけたところで――しかし、次の瞬間。
「――え?」
空模様を映す彼女の灰色の目に、ディアルス王城に大きく影を落とした暗い雲だけでなく、悠然とした異物が割り込む。
それは、朝陽よりも眩く、黄金に輝く赤羽の巨鳥だった。
下7:黒 「小龍」
霊獣族の隠れ里で、今代は誰が一番強かったか、と言われれば。
幼い頃は、赤い獣を頻繁に暴走させていた彼だが……現在最も強力な霊獣を持つのは、長の息子であり、炎の化身たる黄金鳥を本性とする悪友であると彼は断言できた。
「な――……何あれ、どっから湧いて出たのさ、アンチクショウ!?」
薄柿色の髪の少女が驚愕して見上げる空には、体躯全てが炎の羽でできた、巨大な黄金鳥。滞空するだけでは持て余す力を吐き出すように、耳を突き刺す甲高い啼き声を上げる。
少女の傍らで黒い彼女が、興味深そうな目線で彼と黄金鳥を交互に見やる。
「へぇぇ……そっか、待ってたのはコレか」
黄金鳥の近くで、コウモリのような翼で羽ばたく飛び犬にも気が付いたようだ。彼がここに来る前に唯一打っていた布石を、感心げに眺めていた。
黄金鳥が宙に留まる理由が、攻撃先を悩んでのことだと彼はすぐに悟った。
「――大元を叩いてくれ!! タツク!!」
彼の叫びと共に、隣の飛び犬が彗星のように黄金鳥の目前を突っ切り、さらに上空へと飛び上がっていく。
黄金鳥はそれを追うように、ディアルス王城を太陽から隠す雲海へと突っ込んでいく。
薄柿色の髪の少女は、やっと気付いた危機を声高に叫んだ。
「ってアイツ――『小龍』を襲う気ぃ!?」
その獣達の狙いは、まずこの城に黒い使いを振りまいた母船の襲撃。それに気が付いたのだろう。
「何でわかったの!? 『小龍』は完全に雲に擬態できるはずでしょ!?」
焦る薄柿色の髪の少女に対して、黒い彼女が冷静そのものの様子で答える。
「そりゃ、あたし達が天から侵入してくりゃ、それくらいは考えるでしょ」
どうやら彼が、彼女の感覚を一時共有していたことは知らないらしい。頭上の雲を払い飛ばす攻防が始まった様子を、地上から遊びの無い顔付きで見つめた。
「身振り手振りで、あの鳥を連れてきたのは大したものだけど。腐れ縁の勝利?」
彼女が言う通りにそれは、里に残る悪友を自身の霊獣で呼び出した彼の――自らの戦闘も続けながらのSOSという、とにかく苦労談だった。
結界の城内では、霊獣を具現できなかったものの。
――……通気口くらいは生き返るかな?
城の中では霊獣を使えないが、「力」に介入できる彼の些細な特技で、共用玄関口も覆う結界に、気付かれないよう一瞬だけ格子の間から小さな穴を開けたのだ。
空気が繋がる視界の範囲内であれば、霊獣は何処でも呼び出すことができる。結界の影響の無い城の外側……格子から見えた中庭に飛び犬を具現し、助けを呼ぶため、彼らの里へ向かわせたわけだった。
霊獣だけで高速で帰り着いた飛び犬に、悪友は面喰らっていた。
「ちょ、オマ、レイアス!? オマエ、アシューを探して旅しとるんやんな!?」
彼も決して忘れなかった、彼と連れ合いが里を後にした目的。それをすぐ口にする悪友に、ディアルスに戸籍をとった身とはいえ、彼は心からコクコク頷く。
霊獣は喋れず、霊体ではヒトを引っ張ることもできないために、飛び犬の彼は小さな前足を外に誘う方向へとひたすら振り続けた。
「オマエが説明にも来れんほどのピンチにおうとるんか!? おれに来いってことやんな!?」
何とか意志の通じた悪友は霊体の鳥を具現し、飛び犬についてディアルスに向かった。悪友本体は里の者に事情を説明した後、「実体化」を応用し、霊獣に合流した顛末だった。
鳥が先に辿り着いたディアルスへ、「実体化」したことで黄金鳥となって生身で駆けつけた悪友は、何が起きているかはさっぱりわからなかっただろう。
「――大元を叩いてくれ!! タツク!!」
地上の声が届いたかはわからない。飛び犬についていくしかない黄金鳥は、追いかけて飛び出した先で、驚くべき光景を目にしたはずだった。
そこに母船があるだろう、と目星をつけていた彼にも、それは信じられない実態だった。
――何だこれ……こんな船が空を飛ぶのか!?
世間知らずな彼の拙い経験では、空をぽこぽこと、のどかな気球が飛んでいく姿くらいは目にしたことがある。
しかし飛び犬の目で見た、その雲間に融け込む銀色の船を、空に引き上げる風船などない。
海を行く船舶より細長い、蛇のような船体。船首、船橋、船尾の三カ所に楼を構え、いくつも立った柱に舵をとるため、翼の形をした帆がその船には広げられていた。
――飛ばしてるのは、四天王なのか……!?
空を行くための動力は、船底全面に鱗のように描かれた、何百もの魔法陣から発されている。それら全てに魔力を送る源を、飛び犬を通した彼の彩無き眼で力を追っていくと――
船首の船楼に立って地上を見下ろし、長い薄茶の髪をふわふわと優雅に風になびかせる、貴賓のような男。彼は酷く、見覚えがあった。
――……!!
その男が纏う無色の玄は、結界を構成する力の「水」と同じであると彼の眼は捉えた。
それは彼に更なる悪夢……彼が半年前に負った重傷、強靭な水槍で心臓を貫かれた記憶もそこで呼び起こした。
――他の役者は、色々ありそうなので、また次の機会に。
そう言い残していった男を、何故今まで忘れていたのか、彼の全身を憤激が駆け抜ける。
ほぼ単身で船に残るらしい男が、魔性の紅い光を切れ長で整った碧眼にたたえる。
船を隠すために張られた厚い雲を突き抜け、突然現れた黄金鳥に、溢れる熱気を冷たい空で受け止めながら穏やかに微笑みかけた。
「これはこれは――……半年前にも、お目にかかりましたね?」
黄金鳥の方は全く、あずかり知らぬことではあったが。
ディアルスの事変で戦った時に具現されていた黄金鳥を、高見の見物を決め込んでいた男が見知っているのは、何も不思議なことではなかった。
黄金鳥はこれが敵だと、飛び犬ほど認識できているわけではない。
それがわかる彼は、自らの内を走る憤怒も相まって、霊体のまま「気」を大幅に纏い、船首へ激しい特攻をかけた。
「――!」
魔性の男は僅かに顔を歪めたものの、大量の魔法陣を刻んで空を駆ける船は常に「力」を発し、それらに守られているとも言えた。
「無理でしょうね。その程度で私の力は破れませんよ、霊獣族のどなたか」
そのため、男に届く前に、見えない壁に飛び犬が弾き飛ばされる。その姿を嗤うように、余裕を崩さない男は船楼から全く動かなかった。
しかし飛び犬の行動を見た黄金鳥は、迷うこと無くその船を標的と見定めた。
次の瞬間には全身から激しい炎を発し、大蛇の口から尾までを貫き通す勢いでもって――その「小龍」の銀鱗を金赤に染めんと、激しい勢いで飛び込んでいく。
これだけ全力で立ち向かえる相手はそういない、と強大な力が無遠慮に解放される。
もしもそれが、余程強い「水」の力を持った男が動かす船でなければ、大きな衝撃波を巻き起こしつつも黄金鳥を弾き返すことはなかっただろう。
その信じ難い現状も、男が四天王という、最上の魔の者であることを示して余りあった。
そうして飛び犬が視る上空の光景を受け取りながら、彼の本体は今もディアルス王城で、薄柿色の髪の少女と黒い彼女に対峙を続ける。
――アイツを消耗させてくれれば、この結界は弱るはずだ。
母船に襲い掛かる黄金鳥と飛び犬を防ぐ力は、「水」の男には想定外の支出のはずだ。結界に回せる力の余裕が無くなれば、彼らにも勝機が出てくるだろう。
それにはおそらく、もう少し時間がかかると思われたのだが――
手にする槍の穂先を地面に向けて佇み、彼を無愛想に見つめる黒い彼女は、思ったより早く次の行動に移っていた。
「ディシーヴ以下の一般兵は全員撤収! 結界の消失と共に予定通りに動きな!」
無機質ながら大きく張り上げられた声は、現在戦っている者以外の、見えない仲間達の離脱をあっさり指示した。
「緋桐と桔梗はディーズを連れて撤退! 蓮華とミスティルは此方に合流を!」
本来は上の立場な薄柿色の髪の少女も、黒い彼女が真剣に口にすることには従うように言われているのか、不服そうに黙ってその場から消えていく。
「……――!」
シャル都市長を連れて撤退するよう、忍装束の少女達に指示した黒い彼女の声に、彼は少し前に力を借りた都市長の父親を思い出して顔を歪めた。
――息子のことは、命だけはとらないと約束してくれないか……そうでなければ君達に情報を渡すことは、たとえ殺されても私にはできない。
正直なところを言えば、逃げていく侵入者達には彼の同郷者も混じる状況で、恨みの対象である都市長を探して捕えるような余裕は彼にはない。
しかしそうした願いを伝えられ、捕縛さえできれば後はディアルスに引き渡す気である彼らから逃げるより、四天王などと行動を共にする方が余程危険だ。何の力も無い人間の都市長に、それが何故わからないのか……それだけは叫びたい思いにかられる。
黒い彼女の指示通りに、場に残った者は彼女と、東側の階段前にやってきた猫娘と顔の見えない従者だけになった。
「キーたん、どーしたんですのニ? もう悪い奴らのお城討伐は終わりですのニ?」
ずっと物言わぬ従者の横で、両手に銃らしき容赦ない武器を構えながら、呑気な声色で猫娘が黒い彼女をあどけなく見上げる。
彼女はわしゃわしゃと猫娘の頭を撫でながら、掴み所のない微笑みをくすり、と返した。
「ううん? 捕まえるのは諦めだけど、退治する奴はここで終わらせていこう?」
妖精の女と金髪の騎士は、見えない敵の残存の可能性を考えて西側の階段から動けないだろう。
それをあえて放置し、東に戦力を集めた彼女の意図は――
「このお兄ちゃんは悪い奴だよ。階段の騎士は放っておいて、こっちを一緒に倒そうか」
「――!!」
言葉通りに全てを受け取れば、王女や国王の拉致をやめてまでも、彼に殺意を向けている黒い彼女。
黒髪の騎士は自身もボロボロの状態で、階段の前を空けるリスクを冒しても彼を助けるべきかを悩む様子だ。彼は事実上の無援……結界がいつまで続くかわからなくなった今、彼女の判断はあまりに早く、この状況で攻略できる相手を的確に見切っていた。
彼女からは槍、猫娘からは銃を向けられ、従者の女も懐から以前に使った細長い鎖を取り出していた。
「そんなに俺を殺したいのか……!? アシュー……!」
「キニスだよ。言い残したいのはそんな一言だけでいいの?」
この機を逃せば、彼を仕留められないだろう、と彼女は至って冷静に笑い返す。
城内にいた僅かな兵士は負傷者が多く、回復魔法を施されても命の危機を脱しただけだ。それでも集まって来れば邪魔になる、と彼女達が迅速に手を下そうとした瞬間に――
……どうしてそこで、丁度それらは、この場に現れたのだろうか。
「――アシュリン!? アシュリンなの!?」
「やめろよミティ! 銃なんて下ろせ、バカ!」
彼に彼女達の裁きが下される直前、あまりに絶妙のタイミングで階下から現れた者達の声。彼は殺されかけていることも忘れて、内階段の扉を振り返った。
「アフィ、ラスト……!?」
あらら、と彼女は紫苑の少年を警戒するように槍を構え直す。猫娘も彼女に倣うように、標的を彼から少年へ切り替えていた。
「これまた残念。もう少しで殺せたのに、一番難儀な増援が来ちゃったか」
確か彼がここに着いた時にも、同じように言っていた姿が、ふっと彼の脳裏をよぎる。
楼上に駆け込んできた連れ合いは、探していた大切な仲間と同じ姿の黒い彼女が、悪魔のように笑う様子に絶句してしまった。
隣にいた紫苑の少年が、連れ合いをかばってくれながら、少年の武器――両端に大鎌のついた長物を構えて前に出る。
そして少年が猫娘に対して口を開こうとした時に……意外なことに、猫娘から少年へと、初めて声をかける展開が待ち受けていた。
「またアナタですのニ? 相変わらず死神みたいな、悪そうな武器を持ってるですのニ」
「……!!」
少年の驚く顔は無理もない、と連れ合いに駆け寄りながら彼も強く顔をしかめる。
これまで少年は、何度か猫娘に会ったはずだが、その時には目もくれられなかった状態だ。今の猫娘は確かに、少なくとも少年が見かけた顔であることを認識していた。
「どうしてミィに付き纏うんですのニ? ひょっとしてミィのストーカーですの二?」
どんな内容であれ、話ができること自体が、少年にとっては大きな進展だっただろう。
「ミティ――……」
衝撃を受けたのか、少年が言葉に詰まる。何か答える前に、猫娘の従者が大きな袖の中に隠すように、猫娘を己の懐へ引き入れた。
それは少々強引でもあり、うニ!? と猫娘が、半ば抗議するよう小さな声を上げた。
「あーあー。過保護だねぇ、『蓮華』は本当に」
「…………」
ベールに隠されて顔の見えない従者の女は、女の名を強調するよう口にした彼女に、重い溜め息をついたように彼には見えた。
紫苑の少年は猫娘から従者へ、きっと強く表情を引き締めて視線を移す。
「あんたは何者なんだ? ミティを守るってことは、うちの里の生き残りなのか?」
「…………」
「それならオレが、ミティの家族って知ってるだろ? ミティに危害を加えたりしないし……里の奴らのことだって、オレは恨んだりしてない」
かつて故郷で殺されかけた少年。その厳しい顔付きに、声を出さず、何者かもわからない従者は沈黙だけを返す。
そこで少年の声に応えたのは――するりと従者の腕から抜け出して、とても不快そうな表情を浮かべた猫娘だった。
「……ミィには家族なんていないですの二。大切なのは友達だけですの二」
まだ年端もいかない娘なのに、急にひどく濁った幼い声。
吐き捨てるように言った言葉は、少年を思わず黙らせるほどの酷薄さを内に秘めていた。
「……!」
彼が自身の眼を疑うほどに、そこに在るのは「心」ではなく――その声の音は、呪怨の類に視えた。
――あの子は……何、なんだ……?
少年の前で口に出すことはできなかった、率直な印象……手遅れ、という単語が脳裏を掠める。
家族などない、と断言した猫娘の、重い紫の睥睨に紫苑の少年が気圧されていた。
「――母さんはどうしたんだよ、ミティ!? ずっと傍にいてくれただろ!?」
それだけは聞き捨てならない、と何とか返した叫び。彼は何故か、咄嗟にまずい、と感じた。
緊迫する睨み合いの中、連れ合いだけがちらちら黒い彼女を、泣き出しそうな目で窺っていた。
すっかり幼げな笑顔が消え、猫娘が光彩を失った重い目を歪める。不愉快さを組んだ両腕で表しながら、冷め切った声色で淡々と答えた。
「……母さんなんているわけないですのニ? だって、ミィは――」
後から思えば、これはあまりに短い間で、少年がその双子に深く踏み込んだ一時だった。
少年が誰かわからないまま、それでも無意識に、全てを答えようとしてしまった猫娘は――
「ミスティルちゃん。言いたくないことは応えなくていいよ」
やんわり言葉を遮った黒い彼女を、猫娘がキョトンと見上げる。それに淡く笑いかけて、再び従者の女の懐に猫娘を押しやっていた。
猫娘を背中から抱えるように受け取った従者が、彼女に軽く頷いてから、手にした鎖をじゃらりと広げる。
彼女達と相対する彼と紫苑の少年を、ベールに隠された目からふっと見つめてきたことに、彼はその場で気が付いた。
「――……え?」
薄いベールの奥の双眸が、どうしてなのか視えた気がした。それで視線に気が付いた彼は、直後に思ってもみない情景の噴出――ある有り得ない記憶を視ることになった。
「……何……言って――……」
何かがおかしい。
ディアルス王城から突然投げ出された昏い泉に、彼は溺れて呼吸を止める。
「……レイアス?」
何も言えずに後ろにいた連れ合いが、彼の腕を強く握って現実に引き戻させた。
それはごく一瞬のことだったが。彼の全身には、何故か酷く、冷たくなった血が回り始めた。
幼い頃に死にかけて、赤い獣を失った時の悪寒が、唐突に目を覚ましたのだ。
「あんた、いったい……――?」
「……――……」
まだ彼を見つめていた従者の女は、誰にも見えない口元を震わせ、声にできることはない心を――それと知らず、「力」という「心」を視る彼だけに届ける。
……ごめんなさい、と。
彼以外には、視えも聴こえもしない想いは、異様な目敏さを持つ黒い彼女も気付かない、あまりに遠い嘆きだった。
謝って済むことではない、とそれはわかっていたのだろう。
唯一の守るべきもの、小さな猫娘を大切に抱える従者の女に、黒い彼女は横目で合図するように言う。
「それじゃ、そろそろ頃合いかな。もう力は貯まったでしょ? 蓮華」
かなり消耗した彼や騎士達とは違い、紫苑の少年が彼女に対抗し得る相手とわかってか、先に逃がした仲間のように退却の心積もりをけろりと示す。
少年はハッと気付いたように前に出たが、時既に遅く、彼女達はとっくにその逃げ道を確保していた。
「待て、また逃げる気かよ――!」
従者の女が広げていた細長い鎖。それが作る環の中に顕れた闇は、半年前のディアルスでの事変の時も、猫娘と従者、そしてシャル都市長を呑み込んで連れ去った、転位の業を持つ特殊道具だった。
「何で母さんのゲートリングを持ってるんだ、お前……!」
これまでの話はその鎖に、ヒト三人を転位させられるほど大きな力を込めるための時間稼ぎだったのだ。黒い彼女の抜け目のなさに、彼もつくづく頭痛を噛み締める。
従者の女が鎖を翻し、自身と猫娘、黒い彼女に闇を被せるように環の内に引き入れる。黒い球体に覆われたような彼女達の姿が、あっという間に薄まっていく。
「アシュリン……!! 待って――!!」
紫苑の少年に続くように、連れ合いは彼の前に、制止する間もなく駆け出していた。
「そっちに行っちゃ駄目!! お願い――……!!」
その手は届かない、とわかっているのに――
消えゆく黒い彼女に、必死に拙い手を伸ばす空色の連れ合い。いつの間にか彼女は、全ての表情を消して振り返っていた。
未だに体を流れ止まない冷たい血気に、人知れず動けなかった彼の前で、黒い彼女はただ一言だけ、彼と連れ合いに向けた何かを口にしていた。
「……あたしは――……――……」
彼には全ては、聴こえてくれなかった。
つつがなく消えた結界の下、遂げられた転位と共に、儚い声音の余韻だけが残る。
代わりにすぐに気が付いたのは、彼女達の転位先はそう遠くないことだった。
「――!!」
今も遥か頭上の母船に、黄金鳥と飛び犬は特攻を続けている。そちらの視界の方に、船上の「力」の偏りと空間の歪みが即時に映った。
程無く、大気を裂くようにしてそこに現れたのは、猫娘と従者、そして黒い彼女に他ならなかった。
「母船に帰ったのか、あいつら……!」
「レイアス!? まさか――」
唸るように叫んだ彼に、黒い彼女が消えた位置に立ち尽くしていた連れ合いが、焦り顔ですぐさま振り向いた。
「まだ戦う気なの!? 無理だよ、もうボロボロじゃない!」
少しずつ晴れてきた雲と、それを蹴散らす黄金鳥達の姿は、連れ合いも気付いているようだった。
しかし彼は全く迷わず、冷え込む躯体に激を入れるように険しい声を上げる。
「ここは頼んだぞ、ラスト! 俺はタツクと母船を叩く!!」
「え!? まだやんの兄ちゃん!?」
少年は何より彼の剣幕が意外なようで、ちょっと冷静に!? とその後に続けていた。
「ここまでされて黙ってられるか!! 二度と手出しできないくらいに叩き潰してやる!!」
彼自らが、抑えるべきと思いもできない激情が、急激にあふれ出した。
その源はおそらく、この半年の長い暗鬱に加え、探し求めていた大切な者の変貌。そして同郷者達の離反など、いくつも衝撃が重なったことは大きかったが。
今瞠目する両眼を占めるのは、天空の小さな龍に降り立った、黒い彼女の小さな姿で――
その空ろな御使いを出迎えるように、魔性の男が上甲板に降りると、彼女は無表情に、穏やかな笑顔の男の元まで近付いていく。
「……お帰りなさい、キニス」
黙って男を見上げる彼女を、男は愛しげに――彼女の首筋にそっと口付けをして、そのまま間近で見つめる。
「厳しい初陣を任せましたが、ご苦労でしたね――」
その新たな名を呼び、労いを囁く甘ったるい魔性の声。強過ぎる怒りで極限まで感覚を高めた飛び犬は、そんな些細なものまで聴き取り、それを彼に届ける。
襲撃している船に突然現れた、彼らの幼馴染みとそっくりの彼女。その頬を撫でて上を向かせる男を、黄金鳥も目にしていただろう。
己が呼び出された理由を理解し、これまでの倍以上の力を注いだ炎を、黄金鳥が全身に巡らせる。そのように保身を度外視した悪友の姿に、彼も最早何の躊躇いもなく、全力で戦うための「実体化」をその場で行った。
彼の体が消えた次の瞬間、猛獣ほどの大きさの白い飛び犬も消える。
そうしてそれがいたはずの、果てない地平の一角には――
突如として、黄金鳥並みの存在容積を占める灰色の巨獣が、真昼の空へ冷寒に顕れていたのだった。
下8:灰 -飛竜-
抑えられないほどの激しい憎悪と、それとは真逆の冷え切った体で、久々の「実体化」を行使した彼は――
平和だった里にいた頃、最後に実体化した時の獣と今の自身がかなり違う、と、迂闊にもこの空で初めて気付くことになった。
「おやおや……まさかこの平和なご時世、『純血』の家系でもないのに、『飛竜』を担えるような化け物がいたとはねぇ」
上甲板で感心気に呟く男の言う通りに、それはまさに、伝説で語られるような瑞獣。悪魔じみた大きな一対の硬い翼を広くはためかせる、巨大な灰色蜥蜴だった。
彼の「実体化」は元々、犬のような体にコウモリの羽と尖った尻尾が生える珍妙な獣が、馬車ほど大きく生身になる状態だったのだが――
地上から彼の本性を見上げる連れ合いは、遠目でもわかる獣の全像に茫然と呟く。
「ウソ……ホントに兄さんに似てる、レイアス……」
竜宮で彼が遭遇していた幻の兄の白い獣に、その灰色の霊獣は近い姿であるらしい。それは彼にも、驚きの一つではある。
「赤い獣のあの時も、似てると思ったけど……今はもう、姿は違うって言ってたのに……」
以前に妖精の魔法道具の力で、彼が昔に暴走させた赤い獣を連れ合いは見たことがある。今見ている灰色の獣は、赤い獣とは色違いなだけだ、と不思議そうに暗い青の目を丸く見開いていた。
飛び犬という苦し紛れの呼び方ではなく、まさに飛竜と言える獣。しかし二つ、飛び犬の頃にはない大きな欠損があった。
――……!!
一つはまさに、こちらが彼の本性の証かもしれない。
灰色の飛竜は、右前足だけが忽然と消失しており、本体も右手が義手である彼を忠実に再現している。
飛ぶ分には問題はないが、地上を駆ける必要がある時は飛び犬の姿の方が便利だろう。
黒い彼女や猫娘達を下がらせ、飛竜と黄金鳥を魔性の男が冷静に観察する。防ぎ続けた襲来にさすがに疲労がきたのか、難しい顔で再び船楼に立っていた。
「どちらも根本属性は『火』のようですね。しかし奇異な……」
炎を纏い、「水」に守られた船に突撃を続ける黄金鳥と、一見は「力」を纏わないが衝突の度に消耗している飛竜。「力」の相性や、飛竜という獣に多い属性を考えれば、「火」で間違いないと男も思ったようだが……。
「飛竜の方は、『火』であるのに炎を失った状態とでも? それはさぞ、お寒い化け物のことでしょうね」
もう一つの欠損。飛び犬は本来、火というより、流星のように熱を纏うことはできた。
しかし、実体化を行う直前、全身の冷化を感じていた彼の変調を示すように、灰色の巨獣はことごとく「力」の熱を失った状態であり――
身の内に確かに力はあるが、その原料を赤い獣のように、「火」と換える熱を起こす右腕が無い。彼の実感としては、それが一番ぴんとくる話だった。
上甲板の方では、猫娘と従者の女、そして黒い彼女が、船に襲い来る怪物達を思い思いの表情で見上げているようだった。
「…………」
猫娘のように単純な敵意を浮かべるのでなく、かすかな嘆息を漏らしていた従者の女に、目敏い黒い彼女が意味ありげな視線を送る。
いくら「力」の相性上は有利といっても、巨大な獣の激突を受け続けていた空飛ぶ船は、さすがに限界を迎えつつあった。
「おやまあ。私も歳ですねぇ、そろそろ腰が痛くなってきました」
男の力を効率良く利用して、船を飛ばしていた魔法陣の多数が輝きを失っていた。男から魔力を供給されなくなったことを示しているのだろう。
「それで君達は……果たしてこの船を、沈められるんでしょうか?」
あくまで魔性の男は余裕の笑みをたたえる。降下を始めた自船に対して、襲撃の手を止めた巨獣達を怜悧な碧の両眼で真っ向から見据える。
「私は別に、彼女達と心中しても本望ですけどね。君達はそれじゃ困りますよね?」
これ以上攻撃を続ければ、その船は墜ちる――そこに乗る者もただでは済まない。彼らが躊躇うだろうことをわかる悪魔が、そこで楽しげに嗤っていた。
この状況で彼らにできることは、後は一つだけだった。
「元の姿に戻って乗り込んで来ても構いませんよ。キニスが本気でお相手をしますからね」
それも予想している魔性の男は甲板の方を振り返り、黒い彼女を船楼へと手招きしていた。
船に帰ってからぴくりとも笑わなくなった彼女は、猫娘と従者に目配せしてから一足で船楼に跳び上がり、片手で長槍を水平に把持しながら男の横に並び立った。
今までより一段とよく見える所に現れた幼馴染みに、彼も悪友も滞空しながら、動揺で周囲の大気を揺らめかせる。無表情な彼女の薄い灰色の目も、強風に揺れる長い三つ編みも、彼らには見知らぬ姿だった。
特に四肢の露出が多い服装と、生身の下腿を守る銀色の鋭利な臑当ては目立っていた。
「このままでもやれますか? キニス」
「…………」
彼女の艶めかしい両足に目をやりながら、魔性の男が微笑んで尋ねる。黒い彼女は、宙の巨獣達をまっすぐに眺めた数瞬の後――……はい、と感情の皆無な声色で答えた。
次に彼女がとった行動は、彼らがヒトの姿であれば、心配の叫びをあげたほど有り得ない展開だった。
いくら「気」の豊富な化け物である霊獣の徒と言えど、それはヒトの身の限界を越えていた。どれだけ己の足に力を込めても、その跳躍力は翼なき化け物には異常としか言えない。
船首から空に跳び立った無謀過ぎる彼女が、何と彼の灰色の背に降り立っていた。
「――落ちな、飛びトカゲ」
そうして彼女は容赦なく、両手で下向きに構えた槍の穂先を、飛竜の片翼に一瞬で突き立てる。
その稲妻のような無情の一刺しで、彼は完全に戦う力を奪い取られてしまった。
炎に包まれる黄金鳥でなく、王城の戦いの時点でかなり消耗していた彼を、黒い彼女が標的としたのは不思議なことではなかったのだが……。
――それじゃあさぁ。あたし達のために死んでよ?
墜落する彼の背から船体に跳び戻り、落ちていく彼を見下ろす彼女の顔は、ただ真っ黒な虚無に染まる。そこに彼らの幼馴染みはもういない、と最後まで認めたくなかった希み無き夢……視界の暗転する彼を黒塗りにするように、ある光景がさらに襲い来ていた。
その痛みが届いたわけではないだろうが、悪友である黄金鳥は迷わず彼を追いかけ、船に残る黒い彼女より彼の救助を優先していた。
そうしてディアルスの雲上で繰り広げられた空の戦は、降下していく敵船と激しく消耗したディアルス側の化け物達という形で、その日は幕を下ろすことになった。
しかしそれもまだ、これから訪れる様々な戦い――飽く無き呪いの始まりに過ぎないことを、この時点で誰が知っていただろう。
落下していく途中で実体化が途切れ、ヒトに戻った彼を受け止めた黄金鳥が、揃ってディアルス王城に降り立つ。
すぐに実体化を解いた悪友が、空色の連れ合いに引き渡した彼の血まみれの姿に、紫苑の少年が駆けつけてきた。
「あーもー! だから深追いし過ぎだっつーの、兄ちゃんは!」
精霊の力による回復の儀を得意とする少年は、何故か髪がまた真っ白になった彼の傷を、すぐさま癒し始めた……が。
「オレだって堪えてんだから我慢しろよ! 標的さえわかりゃ後は体勢整えて出直すのが最善ってくらい、オレより大人なんだからわかれっつーのこのぉぉ!」
激情に呑まれて上空に向かった彼を、かける文句の尽きない少年は余程心配していたらしい。連れ合いの膝の上の彼を、治療しながらバシバシと叩きまくる激怒ぶりだった。
「とにかく毎度毎度瀕死まで戦うな、退き時を考えろってんだ、何でもいいからさっさと目ぇ覚ませよバカやろー!」
そうして怒る少年の勢いがあまりに強いために、連れ合いや悪友は呆気にとられていた。
ひとまず、久しぶりやな、元気しとったか? うん、助けに来てくれて有り難う、などと、傍らの心休まるやり取りが、ある終わりの夢に迷い込んだ白い彼を何とか引っ張り上げる。
紫苑の少年にすっかり回復された体の重い眼を、彼はようやく、ゆっくりと開き――
「皆さん……! ご無事ですか――……!!」
泣きそうな顔の連れ合いが彼に声をかける前に、城内の負傷兵を労い回っていた王女が、飛び込むように割り込んできた。喋るタイミングを失った連れ合いは、膝に乗せた彼に覆い被さるように、とにかく強く抱き着いてきた。
それにただ彼は……ああ、温かいな……と、一言目に呟く。
「……アフィは温かくて……良かった――……」
身も心も凍えかけた黒夢から、そこで彼が連れ出されたことを誰も知らない。
再び灰色の髪に戻りながら、温もりを確かめるように、連れ合いを両腕で抱き返していた。
その拙い安らぎは、同日中に緊急の会合が持たれるまでの、短いものではあったが。
夕刻からの集まりが始まるまで、とにかく休息を、と。
客間に戻った彼をベッドに寝かせて、連れ合いはずっと暗い面持ちで、真横に置いた椅子に座って彼の様子を見守っていた。
「……タツクは、何処に行ったんだ?」
結局誰にも、ろくに事情を説明できていない彼は、変わり果てた幼馴染みを目にした者全員の動向が気になっていた。
「大丈夫だよ。しばらくラストと一緒の部屋で、タツクもディアルスにいてくれるって」
心細げな彼に無理に笑顔を作る連れ合いは、気になっているはずの黒い彼女のことについて、何一つ尋ねなかった。ひたすら彼の休養を望むように、柔らかく掛け物の上の手を握る。
「…………」
連れ合いのその心遣いが、とても有難い彼ではあった。
「――……一つだけ、訊いておいていいか、アフィ」
誤魔化す気のない現状を認めるために、その小さな空白を、彼は連れ合いに問いかけていた。
「あの時アシューは……消える前に、何て言ったんだ?」
母船に戻る転位の直前に、駆け寄る連れ合いに振り返っていた黒い彼女。その拙い一言は、彼には聞き取れなかった。
「…………」
連れ合いは暗く青い目を伏せて俯きながら、静かでも確かな口調で彼に答える。
「アシュリンは……あたしは何も選ばない、って……そう、言ってたよ」
「…………」
敵陣へ戻る彼女を引き止めた連れ合いへ、それが、彼女の答だった。
そうか、と頷いた彼は、この連れ合いには一言以外、説明は不要だと何故かわかっていた。
「……アシューは……俺達も自分も――全員を捨てたんだ」
それは彼が、何処までも堕ちていく黒い迷夢の内で視た、幼馴染みの最後の選択。
動乱の地に一人帰り着いてしまった彼女を、待ち受けていた虐殺者の罠で――
何も詳しいことは話していないのに、彼が知った現実を感じているかのような連れ合いが、潤んだ暗い青の目で横たわる彼を見つめ続けていた。
「……大丈夫か、アフィ」
厳しい顔色で尋ねた彼に、連れ合いは困ったような苦笑いを浮かべて明るく答えた。
「心配なのはレイアスの方だよ。無理ばっかりしてるんだから」
その連れ合いの笑顔は、彼の気兼ねを退けた時の幼馴染みにあまりに似過ぎていた。
――そんな余裕ないでしょ、レイアス。
最初にあの魔性の男に会った時の、あの悪寒。それを手放してしまった結果が、結局現在なのだ。
思えばずっと連れ合いも、自分のことは心配するなと言い続けている状態だった。
「何でアフィは……これ以上近寄らせてくれないんだ?」
彼自身驚くほどに険しい顔で、強い語調でそう返した後に、連れ合いが大きく目を丸くする。
彼の右手を覆うように重ねられていた手に、彼は逆に手を重ね返し、連れ合いのか細い手を捕まえるように強く握った。
「話してくれない悩み事、沢山あるだろ。魔竜のこととか――自分はいつか消えるとか……前にそう言ってただろ?」
日頃は透き通るような青の目をして、笑顔を絶やさない連れ合いは、何かで強い思いを抱いた時に、その目が暗い青に染まる。彼にはそう視える。
その感情を消化できる時は良いが、それが自らの許容量を超える時には、連れ合いはその心をそっくり忘れてしまうことを、彼はこれまで何度か眼にしていた。
――昔のこと、何も思い出せないもの。
透明な青の連れ合いは、そうしてまた笑う。何かを思いつめていた自身などいなかった――消してしまうしかないのだと、自らを見限ったように。
けれどそれは、ひどく歪んだやり方であるのは明らかだった。
――そなたは自身で思っておるより、根の深い重い感情を抱えておる。
そうまでして連れ合いは、いったい何を閉じ込めているのか……封じられ続けるそれは、何処まで重くなるのだろうか。
「俺のことは一緒に悩んでくれるのに……アフィ自身のことは、俺に背負わせてはくれないのか?」
この半年の暗澹とした日々も、日中に会った黒い彼女も――それも辛かっただろうに、連れ合いは忘れていない。
暗い青の目でいる時間はとても増えた。それは闘っている証であるだろうに。
ずっと気になりながら訊けていなかったことを、やっと尋ねた彼に、連れ合いからは完全に、透明な微笑みが消えていった。
「……ごめんね……」
悲しげとしか言えない暗い青の目には、とても遠い何かを見つめる澱みが浮かぶ。
「わたしもどう話していいか、わからなくって……がっかりさせないか、怖くって……」
それは、彼らが出会ってからの時間の短さを考えれば、当然の躊躇でもあった。
「それでも……色々考えてから、ちゃんと言うね、いつか……」
その拙い声に、彼は竜宮で会った連れ合いの実母との話を、ふっと思い起こす。
彼はその時、連れ合いの実母に単刀直入に、最も気になっていたことを尋ねていた。
「『魔竜』って――何なんですか?」
質問してもいい、と言った連れ合いの実母、青い髪と目の女性は、難しい面持ちで両腕を組む。
「何なのかわからない。それが『魔竜』だけど」
「……?」
「ティアリスの『力』、固定してないでしょ? 後押しがあれば『水』や『風』、さらに他の『力』にも適性があるはず」
それは本来、明確な自然の脅威がヒトの形を取った化け物の竜人にとって、大元のあやふやさがおかしなことなのだと彼も悟る。
「あの子はまず、『竜の眼』を持ってない。『逆鱗』だけがある巫女で、だから竜の召喚ができるんだけど」
竜たる「力」を、ヒトの形にするものが「竜の眼」という。それを持たないものは竜人とは言えないらしい。しかし竜の「力」を極限まで制御できる「逆鱗」だけを持つ者が稀にいて、それが巫女と呼ばれるのだという。
「巫女が喚べる竜も限られてるのに――あの子は私の竜珠を使うことができる」
連れ合いが召喚の際に使う杖にある青い珠玉は、この竜人女性のものであるようだった。
「『力』は似て視えますが、使えるとおかしいんですか」
「似せられるのが問題。あの子、本当は、生粋の『水』を持った子なのに」
この両親も「水」に近い属性に彼には視えたが、それ以上の色を持つ存在であることは彼もわかっていた。
おそらく青い竜の女性が言いたいことは、連れ合いはそうして竜の血を持つ化け物としては曖昧で、他者の「力」を奪ってしまえる「魔」であり――
自らは無色、光無き玄のあやふやな「水」の化身。まだ形の定まらぬ幼い「魔」だと、使い方のわからない「逆鱗」からも彼は当たりを付けていた。
それがどういう危険を招くものであるか、そこまではわからなかったが。
「君の眼、あの子からも聴いたけど本当便利ね。あの子の危ない時もわかりそう」
「……アフィ本来の『力』は、危ないってことですか」
「多分ね。小さい頃はあの子、暴走ばかりしてたし」
だから使いこなせない「逆鱗」を分離したのだ、と女性はあっさりと語る。
「それが記憶に影響するのはわかってたけど……それくらいしか方法が無くてね」
「…………」
自称記憶喪失の連れ合いの理由はそれだと、詳細はわからないが、彼は心するように頷いていた。
「あの子も君みたく、ヒトと違う何かが見えるみたい。うちの血の呪いかな」
それを言える女性の青い目も、普通はわからない何かを視ているのだろう。
妙に目敏かった幼馴染みもそうだが、彼はそんな特殊な感覚を持つ者と縁が強いらしい。
「……寝起きのアフィは、特にそんな感じですね」
夢現な時の連れ合いという、一番の心当たりを口にした彼に、女性も黙って深く頷く。
青い女性は改めて僅かに微笑むと、幾分穏やかな顔付きとなった。
「有難うね。ティアリスのこと、よく視ててくれて」
そうして和んだ場とは裏腹に、厳しい現実を彼に伝える。
「私達は全員、『魔』の因子を持った家族。今日は味方でも、明日は敵になることもある――いつそうなるかわからないから、今日話せて良かったかな」
「……『魔』は、敵ということですか?」
「魔」とは、一般的にはヒトの血や精気を喰らい、奪い続ける果て無き化生だ。何らかの形で他者を糧とするため疎まれる存在について、彼はふっと尋ね返していた。
本来疑問に思われないような問い……彼がそれを尋ねたこと自体に焦点を当てるように、女性は何処か遠い目付きで応える。
「そうだね……君はどう思う?」
「……――」
彼も女性も、それ以上の答は出せないものだと、妙に納得したその一時。
――……がっかりさせないか、怖くて……。
連れ合い自身はきっと、「魔」らしい己を良く思っていないのかもしれない。
それをふと彼が思った時に、奇しくも連れ合いは自分から口を開いていた。
「わたし……『竜の墓場』の、魔物だったみたいなの」
「――へ?」
唐突な単語に目を丸くする彼に、バツが悪そうに顔を伏せる連れ合いだった。
「兄さんは、『竜の墓場』でわたしに会ったって言うの。だから私は、『魔竜』なんだって」
それ以上のことはわからない、と申し訳なさそうにその後に続ける。
「竜の墓場」などというと、連れ合いの実母との話が改めて思い出された。
「もう一つくらい答えられそうだけど、何かある?」
大切な話は終わったとばかり、少し砕けた雰囲気で、青い女性は体を伸ばして尋ねていた。
彼はそこで、前日にこの城をさまよっていた時の、不思議な出来事を思い出した。
「この城は、何も無い中庭とかはありますか?」
全く脈絡もないことを尋ねた彼に、女性はキョトン、と言える勢いで目を大きく丸くする。
少しバツが悪くなりつつも、彼は正直に顛末を伝える。
「ご両親に会えるのを待つ間にふらつかせてもらったら、不思議な部屋があったんです。青白い扉の中は真っ白で、城の中なのに外に出そうな気がして、入らなかったんですが」
開けただけの扉をバタンと締めたら、その少し後に「ごめんなさい」という声が薄暗い廊下に響いた。そんな怪談のようなオチがつく体験だった。
青い髪と目の女性は、それまでになく露骨な感情表現――心から呆れたような目線で、彼を見つめ返してきた。
「まさか……うちに初訪問であれに辿り着くとは……」
「……スミマセン。勝手に出歩いたのは悪いと思ってます」
そういうことじゃない、と、彼を客間に置いていった義理の母は、彼が城を放浪していたことは構わないらしい。
「そこ、今度見つけても絶対入っちゃ駄目。『竜の墓場』だから」
「――え?」
「うちのバカ息子も迷い込んだ神域。まいったな、やっぱり随分境界薄くなったな」
それきり女性は黙り込んでしまい、結局どの話もよくわからないまま、現在に至る。
そんな一見は呑気な会話を思い出すと、彼の気分は少しだけ和らいでいた。
始終、不思議そうな連れ合いは、要は口下手親子かもしれない。ふとそう思って、彼は苦く笑った。
「……上手く言わなくていいから。アフィのこと、もっと教えてくれ」
それに連れ合いは、空のように澄んだ青の目で、うん、と答えて微笑んだのだった。
普通に考えれば――墓場などにいるのは、死者であるはずだろう。
言葉通りに受け取れば、連れ合いはそこにいた時期がある。しかし今はこうして生きて動いている……それには確かに、魔的な気配が限りなく漂う。
「アフィの兄さんはいつ頃、『竜の墓場』でアフィに会ったんだ?」
「……兄さんは二回迷い込んだみたいで、わたしが生まれるよりは前のはずだよ」
連れ合いが生まれた直後に兄は竜宮を出たから、と、迷いなき答も色々と不可解だった。
今話している連れ合いは、透明な青の方であることも、彼は気になるところだった。
そちらの連れ合いが言えることは、客観的な情報がほとんどで――彼が望んだから話してくれているのだろうが、本当に知りたいこととはずれている気もする。
だからであるのか。次の問いの方が連れ合いの心を感じ、彼はすぐに反応していた。
「わたしが魔物でも……レイアスはいいの?」
「――それで辛いのは、俺じゃなくてアフィの方だろ?」
仰向けの彼を覗き込むように尋ねた連れ合いを、思わず抱き寄せて彼は答えた。
「奪わなきゃ生きられない魔物なんて――……ヒトの一番残酷な業じゃないか」
「魔」が疎まれる最大の理由。「死」が無い、つまり既に「死」の内にある「魔」は、己や周囲に容易く「死」を具現してしまう。それを救えるのは「神」だけだ、と古来より言われ……。
「魔物でいいから……ここにいてくれ」
腕の中で黙り込んだ連れ合いは、日没までずっと、彼の胸にしがみついていたのだった。
下9:白昼の黒い夢
魔物と悪魔は、似て非なる存在だというのは、意外にあまり知られていない。
ディアルスの重鎮も四天王のような人型の魔を悪魔、多種多様な形態の変異生物を魔物と区別していた。しかし悪魔にも怪物が、魔物にも人型の者は存在し、幼い頃の彼は魔物扱いされていた時期もあった。
「我が国は悪魔の怒りを買ったのでしょうか? いったいどうしてそんなことに?」
王城に侵入した四天王という悪魔の一派に対し、緊急会合で人間のお偉方――審議院の上院達は、そんな風に怖々と口走る。
悪魔と神の区別すら無い状態で、まともな議論ができるのか、と彼は眉をひそめる。
怒りを下すとすれば神だ。悪魔は人間に付け入るもので、魔物からも、魔物以外からも成る可能性がある。
対して魔物は、多くが地中に棲むことからも言えるが、大体死した生き物が大元であり、自身以外の命を糧とする魔性に強く依存する。
魔性自体は魔族全体の性で、悪魔も魔物も、鬼も妖も持つ。その中でも「魔」と認定されるほどに魔性を発揮する機会が多いのが、魔物と言えた。
「四天王は何が望みなのでしょうか? 王家の血を生贄に差し出せと言うことでは……?」
そんなことは余程、ディアルス王家に怨恨を持つ魔物でもない限りないだろう。「悪魔」はもっと統制された行動原理を持つはずであり、そうしたことを一から説明したものかどうか、彼だけでなく王家の魔女たる妖精の女も悩み始めた様子だった。
不毛な会議にその後、驚きの方向性を持たせたのは、自分も混ぜろ、と無理に列席していた紫苑の少年だった。
「四天王の目的は『炎』と『風』の珠玉だよ。差し出しても余計劣勢になるだけだから、戦うことを考えるしかないんじゃない?」
「――何ですって?」
大きな縦長の古めかしい卓を囲み、怪訝な顔を上座の王女が浮かべる。
「貴方はどうして、何処からそのような情報を得たのです?」
今朝の戦闘に少年は直接参加していなかった。最下階で彼の連れ合いを守り待機していた相手を、彼も不思議に思って見やる。
「オレがぼーっと待ってただけとでも? ひとまず言えるのは、敵は上で戦う奴と、下で何かを探す奴に分かれてたってこと。王家の者を差し出せって言うなら、王家に深く関わる何かが欲しいってことだろ。答は一つしかないじゃん?」
そのように全体を観察し、推論を掲げる少年に彼も頷く。
「……そうだな。四天王がその二つの珠玉の、存在を知っているのは確かだ」
驚く人間達に、半年前の事変で彼が出会っていた四天王の言葉――幼馴染みに言っていた内容の一端を伝える。
「この国の王家はその珠玉の適合者で、他にもそんな珠玉が存在する……そう言っていたアイツは、少なくとも違う一つを多分持ってる」
「でも……それでは四天王は、どうやって我が国の重大機密を知ったのです?」
伝説としては在り、温暖な気候の秘密としても噂の珠玉ではあったが。四天王ほどの悪魔が確信無しに動くとは考え難い、と、王女の疑問も無理はなかった。
紫苑の少年がそこで、幼いながらとても厳しい顔付きとなった。
「オレの部屋に来た奴ら、姿は見えなかったけど、あのガキ、ここにいるって聞いたのに。なんて言ったんだよ。城に張られた結界も相当手が込んでるし、誰かが基盤を仕込んでたはずだ……内通者がいると思った方がいいよ」
そうでなけれはここまでの危機は有り得ない、と彼や少年の故郷を滅ぼした同じ手口に、不快さを全面にして言う。
そして少年は、さらに敵側の事情に踏み込んだ内容を提示する。
「レイアスの兄ちゃんが言うみたいに、四天王は自分が持ってる珠玉の力を、いくつかに分散して部下に使わせてるみたいだ」
「――何だって?」
「魔法を弾く魔道士の女、重装武器を両手に、疲れ知らずで振り回す女の子の化け物……ざっとナナハのねーちゃんに聞いただけでも、その二人は何かがおかしいよ」
いったい何処までこの少年は敏いのか、さすがに彼も耳を疑う。
「共通してるのは赤い防具。魔道士の胸当てと女の子の小手と……胸当ての中央には黒い珠が填まってるみたいだし、そこから力を借りてるんじゃないかって、何でも道具屋としては見立てるけどね」
そこで彼の脳裏には、高い空で飛竜にトドメをさした黒い彼女の有り得ない跳躍……それを助けた下腿の銀色の装具に、少年が言った防具と同じ色が纏わりついていたことが鮮明に浮かび上がった。
その珠玉はかつて、傍に近付いた幼馴染みに、黒の触手を伸ばしたように彼には視えた。
そして今彼女が纏う黒い空気は、それに近い、とようやく気付く。
――アシューはまさか……あの珠玉の適合者だったのか?
それなら四天王が、幼馴染みに近付いた理由もわかる。他の部下達のように、珠玉の力を使える化け物を欲していたのならば。
――でも何であんな……『水』の珠玉に、アシューが……?
黒は確かに、彼女が持っていた色だ。「水」の家系でもないのに、他の適合者よりも珠玉に近いのは確かだった。
「それでは四天王は、我が国の宝を、己が力としようとしていると?」
「その可能性は高いと思う。色んな秘宝の力を道具に使える、お抱え武器屋がいるからね」
四天王に助力する、少年の双子の利用価値。吐き捨てるように少年が言い、後は黙っていた。
その日の会合は、紫苑の少年が城に結界を張って備える、ということで終わった。
本日のような奇襲は、城の防備を上げればそうそうないだろう。それでも四天王に狙われることがどれほど大きな危機であるかは、突然帰るべき里を失った彼らには、恐れおののく人間達より実感があった。
「世界の化け物を牽制するのがアイツらだから……アイツらの暴挙は、誰も止められない」
本来はそれと拮抗する勢力が「守護者」で、天の王と銘打つ四人の魔については、悪魔を牽制する役目を持つ天使も管轄外なのだ。
「神」や「天使」、「悪魔」の四天王などは、古の概念に縛られる神威だ。それから独立したのが「守護者」を含む天威「天界人」で、特に「守護者」は大きな「力」を持つと言われる。天威とはそうして、神威に対抗するために独立した神威崩れとも言えた。
「それまではもっと、神も悪魔も好き勝手してたらしいしな……」
けれど十六年前、「守護者」の本拠、祭壇である天空の「地」が攻撃されて以後天界人は姿を消した。それから四天王は、町や村を滅するほどの裁定を躊躇わなくなった。おそらく彼らの里も猫娘が言ったように、悪の拠点として大義を掲げられたのだろう。
だから王女は最後に、ある意味冷酷なことを、彼に面と向かって尋ねていた。
「次に四天王一派と戦闘になった時は――貴男方には、戦っていただけますか?」
それは今朝、彼らの幼馴染みである彼女が敵として現れた以上、避けられる問題ではない。さらには他にも生き残った同郷者が、敵陣にはいたはずだった。
「……戦うのは当たり前だ。でも、助けられる時には捕虜にする。それはどの戦いでも共通の原理だろ?」
「……はい。……無論、そうして下さい」
複雑な表情でそう認めた王女は、仲間だった者達と戦わせる彼への申し訳なさと、本気で戦ってくれるかの不安……自国を守りたい思いの板挟みであるようだった。
千族に理解のある王女すらそうなのだから、他の人間は彼らを信頼はしないだろう、と自嘲しながら彼は会議部屋を後にする。
会議の場にはいたが、何も喋らなかった悪友が、自室に帰ろうとする彼を呼び止めた。
「待てやコラ。何やねん、さっきの最後の釈明は」
王女の問いに答えた時に、悪友は納得しないだろう、と思っていた彼は、黙って俯く。
「何でもっとちゃんと、色々説明せーへんねん? あれじゃ人間かて、わけがわからんで誰も納得いかんやろ」
「……話しても一緒だ。仲間と戦いたくない、と言った時点で、きっと人間も敵に回る」
「おれはそうは思わへんし、そうならこの国のことも後にするだけや。てかまずな、おれにわかるように説明してくれ。アシューやセレンには何が起こっとんねん?」
「……」
悪友には一言、彼女達は敵側にいる、とだけ言って彼は休んでいたので、その話をきちんとしなければいけないのはわかっていた。
「アフィの前でアシューのシビアな話をしたなかったら、おれんとこに来いや。ラっ君が共用の部屋、今夜は好きに使ってええ言うとんねん」
「――へ?」
図星をつかれた彼に、少し前は色が落ちていた髪を悪友がかきあげる。その苦笑は、彼が酷く消沈していることなどお見通しと言うようだった。
「アイツやばいで、同室やとよーわかるけど気利き過ぎやで。あれは将来モテモテやろな、末恐ろしい奴っちゃ」
「……」
「アフィんとこには自分がおるから、おれはオマエとじっくり話せ、っつーとった。おれでないと言えんことも、オマエには多分あるやろうってな」
そうして悪友は、何処に持っていたのか、何やら大きな酒瓶を片手に取り出した。
「今夜は飲むで! 付き合わんかったら縁切るからな!」
後は空いた手で彼の首根っこを掴み、引きずるように自室に連れ込んだのだった。
ほとんど飲んだことのない、突然の酒の場。何からどう話せばいいか、彼はしばらく考え込んでしまったのだが……。
「……信じられるかどうかは、オマエの自由だけど」
紫苑の少年の客間で、久々の悪友と床に座って少しずつ杯を空けていくと、自然と彼の口も軽くなってくれていた。
「アシューの見ていたものが……何でかわからないが少しの間、俺にも視えたんだ」
「――ほぉう?」
「それでディアルスへの侵入もわかった。……あのアシューが、俺達を覚えていないことも」
「…………」
躊躇いなく飛竜を撃墜し、四天王の船に戻った幼馴染み。それを目の当たりにしていた悪友は、口を引き結んだままじっと彼を見つめる。
「……アシューは昔から、妙に勘が良かっただろ?」
「せやな。目敏いっつーか、オマエと同じで、ヒトと少し違うもんを見とるとこはあったな」
さすがに付き合いの長い悪友は話が早く、彼は少しほっとしながら結論だけを告げる。
「今のあいつは、その直感だけで、周囲があいつに望む通りに動こうとしてる。自分が誰かすら……本当は覚えていないんだ」
――だから……もっとあたしを教えてもらわないと……。
そんな状態でも、一見は大きな違和感なく動けてしまう黒い御使い。その姿は最早――
「……北方四天王の手で、都合良く造り変えられた人形だ。昔のあいつは……もういない」
それすら生易しい表現だとわかりながら、絞り出すように彼がそこまでを口にする。
悪友はしばらく、彼の言ったことを消化するように、真面目な顔付きで黙っていた。
「……あのな、レイアス。お前らが旅に出た後、里の奴らが話してくれたことなんやけどな」
当初は緊急時に不在だった彼らを、生き残った者達はひたすら罵るだけだった。
しかしそれらと向き合い、悪友なりに得たらしい答を、そこから神妙に話し始める。
「アシューは……里を守ろうとしたんやって、おれはちゃんとわかっとるで」
「…………」
「そもそもは急に、里の結界がおかしなって、誰も力を使えへんくなった所に謎の敵襲があった。それはオマエも聞いとったと思うけどな」
「力」の使えない結界の内では、襲撃者も主に重火器を使った殺戮を行ったという。それも酷く強力な武器ばかりで、同郷者は成す術がなく、土地勘を頼りに隠れるしかなかったというが……。
「逃げることすら出けんように里に閉じ込められて、それでも生き残った奴がおるんは……一度だけ、その結界が緩まった時間があったらしいねん」
そうやって息を潜めている時に、その短い異変は訪れたのだ。
「最初は空が一瞬真っ暗んなって、物凄い激震が里中に走ったらしい。その時から結界が急に弱なって、しばらくそれは続いて、わけわからんけど勇気を出してその時逃げた奴が生き残ったみたいや。後はもう、結界が戻ってからは皆殺しやってな」
「…………」
「おれは多分それ……アシューが結界の主と、その時戦っとったんちゃうか、と思うんや」
今回の王城侵入を見ても、結界の「力」の主は外側に在る。邪魔が入らない限り、結界の弱体化は有り得ないことと言えた。
「地面を揺らせるほどの力、あの辺で出せるとしたらアシューの『フェンリル』くらいやろ。そんなんで外から結界壊そうとしたら、当然四天王も見過ごさんかったやろうし」
荒事から逃げるのは上手い幼馴染みが、見つかった理由はそれくらいだろう、と。悪友は痛ましい目で、苦々しさを噛み締めながら口にする。
「……あいつは、里を守ろうとして四天王の手に落ちた。それで何か、おれの理解に不足はあるか?」
「…………」
まっすぐに尋ねる悪友の、深い灰色の目が、今の彼には辛かった。
「今やってセレンとか、他にも仲間が捕まっとるんやろ? そいつらんこと盾にされたら、アシューは四天王に逆らえへんやろ」
つまり彼女が敵側で戦うのは、仲間のためだ、と悪友は言いたいのだろう。
彼の内には、黒い彼女が仲間について口にした事実がよぎる。
――代わりに教えてあげちゃおうか。彼らは四天王様に忠誠を誓って、その証として自分の『霊骨』を差し出したわけ。
それをわざわざ、口に出した真意……悪友のように彼女を信じるのなら、仲間が陥った窮状を伝えたかった可能性もなくはないのか。
黒い彼女は確かに最初、同郷の女を守るために彼の前に現れてきた。そして彼自らが言ったように、周囲の望むように動く人形……助かりたいと願う仲間のために、四天王の期待を一身に背負っているとしたら――
しかし空から落ちる時に視た夢と、彼女が残した言葉はそれとは矛盾する。
――……あたしは何も……選ばない……。
「あいつは多分……そこまで仲間には縛られてない」
一人でそれを思い、嘆くように否定した彼に、悪友は首を傾げる。
「オマエがアシューのことを信じへんなんて、らしくないな、レイアス」
「…………」
「おれは信じへん、あいつがもういないなんて。現にああやって、生きて動いとったしな」
「……そうだな。……オマエはそれでいいと思う、タツク」
信じるかどうかは悪友の自由だ、と、最初に口にした自身の思いはそこにあったらしい。
何故かほっとした彼は、重々しくも苦い顔で悪友と笑い合う。
「また何かアシューのこと視たら、ちゃんと教えろや?」
それに対しては既に秘め事を抱えながら、ああ、と答えてさらに杯を含んでいった。
完全に酔い潰れるように、紫苑の少年の客間でソファにぐったりと彼は横たわった。
治まらない吐き気は最初からあり、慣れない酒のせいではないだろう。
――……仲間に縛られるくらい、アシューの心が生きてたら……。
悪友の言を否定したのは、信頼とは違う理由だった。
彼女が健在であれば、あれが彼女ならそうしただろう。何であれ四天王に従わないと、自身も周囲も危なくなってしまう。
――……はっきり言った方が、いいのか……?
彼の歯切れを悪くさせる、白昼の黒い夢。それは誰かの終わりでしかなく。
悪友が話した里の結界のことも、彼は黒い夢で既に知っていた。
悪友の推測は当たっており、その結界に打撃を与えたのは幼馴染みだ。そこに結界の「力」の主が、捕らえていた里の者を連れ、焦燥まみれの彼女を出迎えた卑劣な経緯を。
どちらを選んでも、自分は結局一人になるのだろう、と。
彼女がそれに気付いたのは、その故郷で友達と呼ぶ相手の悲鳴を聴いた時だった。
「アシュリン、どうしたの!? お願い無茶しないで、そのヒトの言うことをきいて!」
彼女が見ていた結末は、無力に過ぎた友人とは大分違ったのだ。
友人が必死なことは彼女もわかっていた。できることなら助けたい、と強く思った。
そして同時に、最早助けることはできない確信が、痛いほどに浮かぶ。
友人を羽交い絞めにする魔性の男は、端整に笑いながら彼女を見つめていた。
「簡単なことですよ? 君が私の配下になるなら、君達のことは助けます。それだけです」
彼女の仲間である彼に重傷を負わせた男。それに従え、と言われた彼女は総身を強張らせた。
「二人で私に仕えてくれれば良いんです。君達は――友達なんでしょう?」
仲間も家族も殺された中で、友人は男に命乞いをし、辛うじてこの状況を得た。
それは懸命で、身を切る辛さだっただろう。きっと友人は彼女の身も全力で案じている。
ああ……やっぱりあの子は、そうすれば二人共助かると思ってるんだ。
すぐに気付いていたその空気を、彼女は必死に納得しようとするが――
――アイツについても……レイアス達が助けてくれるって、そう思ってるんだ……。
しかしその結果は、彼女と友人達が人質になれば、彼らは勝てないだろう。
それも男は、おそらく彼女に彼らを襲わせる。そうしなければ友人を殺す、と彼女を追い立てる。
男が自陣に求めているのは彼女だけだった。
用済みになれば、友人も殺される。それがわかる彼女は、彼らと友人……どちらなら助けられるか、思わざるを得なかったのだ。
――レイアス達なら……今はとにかく、セイレーネを助けろ、って絶対に言う。
バカな話だ、と彼女は嗤う。彼らと友人、どちらに尋ねても答は同じだろう。
――セイレーネだって裏切るつもりじゃない。今はそれしか方法がないだけ。
その結末は、彼らの敗北と用済みの友人。それに気付かないフリをすることはできたのに、どうしても納得できない自分を、彼女はいつまでも好きになれそうになかった。
――あたしだけなら逃げられるけど……そうすれば今すぐ、セイレーネは殺される。
それは彼女にとっては、彼らと友人、どちらも裏切る末路でしかない。
――行けばレイアス達と殺し合わされる……このヒトはきっと……あたしの全てを奪う。
既に彼女の家族を殺しただろう男に、決して、頷きはできなかった彼女だった。
立ち尽くして俯いたまま、不意にク――……と。
口元を歪めた彼女の姿に、魔性の男は眉をひそめて不思議そうにした。
「……アシュリン……?」
黙ったままの彼女に不安げにする友人の目を、もう二度と見れない、と彼女は自嘲する。
その気配に気付いてのことか、不意に男は、友人を打ち捨てるように突き放した。
「どうやら君は……私と戦うつもりのようですね?」
「……当たり前、じゃない」
決意を固めてしまった彼女を前に、男は自身の「力」を纏い始める。
彼女も武器を取り出すと、逃げ道だった白黒猫の霊獣を、戦うために呼び戻して退路を断った。
「あたしはそもそも――アナタの提案なんて、どれも選ぶ気はないもの」
彼女にできることは、たった一つだった。それが友人に理解できることではなくても。
「アナタがみんなを選ばせてくれないなら……誰も選ばず、全員捨てるだけよ」
男の思惑を崩し、自身が納得できる唯一の道筋。全てを見殺す、と彼女は決めたのだ。
本気の応戦を必要とした男の、容赦できない水槍に貫かれ、自らを失った己を含めて。
酔いのせいか反芻してしまった黒い夢に、胸の悪さを堪えながら馬鹿ヤロウ、と呟く。
誰にも伝えず、悪友も信じないだろう話。そんな光景がどうして彼に届くのだろう。
四天王の男が、彼らの里を滅ぼした理由すらわからないのに。
一番の間違いは、誰もが思う以上に、彼女が強い化け物だったことだろう。
里を囲む結界に対して黒狼を実体化し、彼女は大半の力を既に使い切っていた。それでも別に具現された白黒猫と、四天王たる相手を追い詰めてしまったのだ。
――……向こうだって……殺す気じゃなかっただろうからな……。
どうせ捕まるなら、生きて囚われれば良かったのに。
その時確実に、彼女の心臓は止まり、本性たる「力」――「心」の連続は途切れた。
それからどうして、あの黒い彼女に至ったかはわからないが……半年という時は、黒い彼女が成立するのに必要だったのだろう、と彼には何となくわかった。
「……――待て、よ」
ふっと。暗いまどろみに落ちていた彼の全神経に、電撃が走った。
「何で北方四天王は……アシューの――……」
とても考えたくない疑問が浮上する。衝撃は大きく、易しい酔いは一気に醒めてしまった。
「大体どうして……里の結界は……」
それは夕方の会合でも呈されていた話題なのに、今まで思い至らなかった自身の回転の悪さ。嘆いている場合ではない、と彼は己を鞭打って体を起こす。
どうしても落ち着いておられず、眠っていた悪友を置いて客間を出ると、ちょうど、南の回廊を連れ合いが歩いてくる姿が見えた。
「……あ」
連れ合いも彼に気付き、僅かに赤い顔をして立ち止まる。
「どうしたんだ? こんな遅い時間に」
内心の焦りを隠すように穏やかに尋ねた彼は、連れ合いがいる理由はわかっていた。
「怖い夢……また見たのか?」
「…………」
後ろ髪をくしゃりと、緩く掴むように抱き寄せた彼に、連れ合いは黙って頷く。
暗い青の目の連れ合いがうなされ、目を覚ましては無意識に彼の傍らに来て、そのまま朝まで彼にくっついて眠るのは最近珍しくないことだった。
「……ゴメンなさい。私……子供みたい」
今日は彼が違う場所にいたので、部屋を出てきたのだろう。そんな姿は、愛しいとしか言えなかった。
「俺は歓迎だけど――悪夢さまさまだな、むしろ」
珍しく微笑んだ彼に、腕の中で俯いた連れ合いは――
「うん……妖精の森を出たあの日も……夢を見て、アナタのこと、見つけたの……」
心細げで胡乱な声は、やはり夢現の世界をさまよっているようで。
悲しげな暗い青の目に映る切望の意味を、彼は今も知ることはない。
下10:黒 -竜-
凍え続ける冷えた血を感じ、寒気で目が覚めた彼は、すぐにそれを思い出した。
王城の郭で、猫娘の従者の視線に気が付いた時、彼の眼が最初に映し出したものは覚えているはずのない記憶。それでも確かに彼に関わる、過去の光景であり……。
――ごめんなさい……これはきっと、お節介なことでしょうけど……。
生死の狭間をさまよい、眠り続ける幼い彼。その失った右手に、義手を合わせんとしてくれている者が静かに語りかけた。
――アナタの『力』は、アナタの身には余りそう……まだ小さいのに、とても心配……。
幼い頃に右腕を失い、暗い水底で命を落としかけた彼は、その泉を祀る隠れ里の巫女に助けられていた。
そこは何でも屋である紫苑の少年の故郷で、何かを造ることに特化した千族の長の巫女が、彼の最初の義手を造ってくれた者だった。
――この手を付けている間だけでも……少しは楽になったらいいんだけど……。
義手が造られている間、意識の無かった彼にかけられていた言葉を、彼が自ら思い出せるはずはなかった。
そこで彼に与えられた義手は、魂に反応して動く高度なものだ、と伝えられる。
彼の命から生じる力を受け取り、彼に都合の良いように流用して動かしてくれる――……それなら、その義手を付ける前後に姿を変えた赤い獣は、本当は失われたのではなく……。
「……封印が解けた、ってことじゃないかな。母さんの義手から、オレの義手に替えたことでさ」
ここ一週間、自室にこもって道具造りに勤しんでいた紫苑の少年は、何度目かの相談に訪れた彼の質問にあっさり解答を出してくれた。
「兄ちゃんの昔の『力』の暴走、前の義手を付けた時から止まったんだろ? 母さんならそれくらい、補助効果のある義手を造れたと思うな」
「なるほど……じゃあずっと、知らずに助けられっ放しだったんだな、俺は」
今までの飛び犬は、飛竜が小さく纏められたことで、腕も補填されて熱も分散されなかったイメージだという話は、実に納得がいくものだった。
それなら残る疑問は、彼がそれを自覚したタイミングは何故、猫娘の従者を視た時か、ということに尽きた。
「あの従者……オマエの母さんってこと、やっぱり有り得ないのか?」
「もー、何度も言ってんじゃん? 『炎と風の塔』にあいつらがいた時、素顔を見たけど別人だったし、気配も母さんとは全然違うし」
彼の眼には猫娘とその従者は、少年と同じ紫を纏うように視える。
しかし少年が言う通り、その素顔は「炎と風の塔」で、同じ化け物ギャンブルに参加した彼も偵察の時に視ていたものだった。
「参加登録名は『蓮華』、素性は不明だけど多分鬼の系統。母さんとは似ても似つかねーし」
猫娘がれんれんと呼ぶ、顔を隠した従者は、旧い魔道士風の服装を脱ぐと忍装束が現れる鼠色の短髪の女だ。桔梗や緋桐と呼ばれる少女達の姉貴分と見えた。
「……でも忍の姿の時は、オマエ達と同じ色じゃなかったぞ?」
「オレに言われてもなぁ。顔隠してる時は確かに、気配とかよくわからなくなるし、あのベールに正体隠しの効果はあるんだろーけど」
ほぼでき上がった太い鋏のような道具を磨きながら、少年は複雑そうに続ける。
「……里がなくなって、母さんがどうなったのかは、気になるけどさ」
その道具とセットでハイ、と渡された、風呂敷のような依頼品。同郷者達を助けるために少年を頼っていた彼は、感謝と共にそれらを受け取る。
「実際にソレで、兄ちゃん達の助けになんの? 大まかな情報しかないから、オレも自信ないんだけどさ」
「……わからないが、少なくともセレンには使えるはずだ。それだけでもアシュー……キニスは何か出方を変えるかもしれない」
霊獣族の証である「霊骨」を差し出しさせられ、そして口がきけないように、黒い鋼のマスクをさせられていた同郷の女。相手の窮状がわかった彼は、悪友と少年と作戦会議をしながら今日に至っていた。
「ミティもアシュリンのねーちゃんも、どうすればあんな別人になんだろ……オレ、正直どうしていいかわかんないよ、兄ちゃん」
大体のことは彼らよりしっかりした紫苑の少年だが、その変わり切ってしまった者達には、素直な弱音を隠さずに言う。
「兄ちゃんの『心眼』、そういう精神干渉系の解除とかって無理?」
「俺はわからないが……何をされたか、にもよるんじゃないか」
何か違う色がある場合なら、取り除くのは彼にもできるかもしれない。しかし色を消された――殺されたような時にはどうにもできない。
そういう意味では、元の白黒から白を失った幼馴染みは、別の所にその白があるなら、再び混ぜることはできるかもしれない。
「オマエの双子は、色は変わってなさそうだから……受けたとしたら純粋な洗脳じゃないか?」
――ちょっとキニス。しっかりしなよ。
黒い彼女が空ろな己を曝した時に、薄柿色の髪の少女――彼女と似た口調の者が近付き、彼女に自らの「気」を直接施したことを彼は視ていた。
どうやらそれは、他者の脳に浸透できる特殊な気で、精神干渉という少年の言が全く妥当だ。そのため彼女の口調が干渉者に似たという、人格変化も有り得る話だった。
「オレが里を出て三年以上だけど、それくらいやられるとそうなるってこと?」
「ヒトによると思うが、子供相手なら十分だろう。あんな『気』がなくても、普通に教育するだけでも歪められる期間じゃないか」
幼馴染みと紫苑の少年の双子には、多分どちらも、薄柿色の髪の少女が精神干渉を行っている。
その少女を排除しても、猫娘の方は手遅れな段階に彼には思えた。
「……誰が、何の目的で、オマエの双子にそんな奴を近付けたのかだけど」
じわじわと、それは進められたはずで、そこから誕生した悪魔のお抱え武器屋。殺戮に使われる結界や、その内で使われた兵器製造の責を誰に問うべきであるのか。少年の双子を糾弾するのはやはり憐れだと、彼は思うようになっていた。
紫苑の少年はそうした雰囲気を感じてか、以前よりは張りつめた空気が和らいでいた。
「ところで本当に、今日実行すんの? 例の殴り込み」
「ああ。タツクも今、最後の偵察と警告に行ってるはずだ」
代わりにディアルスそのものを緊迫させていた案件に、共に難しい顔となる。
「あの船、ずっと沖合に停泊してるらしいが……何が目的なのやら……」
先日に彼らが襲撃した母船は、今もディアルス近海にいる。北方四天王の拠点たる北の小島に帰る様子を見せなかったのだ。
「オマエの双子の気配はないみたいだけど、それでも一緒に来るのか?」
「残っててもすることないし。守りは騎士のにーちゃん達と、ナナハのねーちゃんで十分だろ」
「力」を封じられる結界さえ無ければ、相当強い千族達を信頼して少年は言う。
「気配を隠して、本当はいる可能性もあるし……それに船にいるアシュリンのねーちゃん、相手できる奴が必要って言ってたじゃん?」
そこでは少年らしからぬ険しい表情で、彼を鋭く横目で見つめる。
「すまない――オマエが力を貸してくれるなら、物凄く助かる」
幼いながら、ヒトの身では最も高い戦闘能力を持つ仲間に、彼も深く頷いたのだった。
港に向かう馬車の刻限となり、客間を後にした彼らに、楼門近くで同じ客人がばったりすれ違った。
「あれ、皆さんもお出かけですか? 最近は何だか、ディアルスも物騒ですね」
王女や護衛達は、先日の襲撃時から戦時体制で港に布陣を張っている。
商談に来た、という赤い髪の道化じみた化粧の男は、今はそれどころではない、と憂き目にあってしまったようだった。
「先日は本当にお世話になりました、有り難うございます。残念ですが私も今日でお別れなんです、おうちに帰るんです~」
「……そっか、良かった。もう二度と、オレを見かけても近付いてくんなよ」
「いやーん、つれなぁい。ラスト君好みですのに、恩人ですのに~」
敵が客間を探索した際、紫苑の少年が保護していた赤い髪の男は、それから何かと、暇な時には少年にちょっかいをかけていたらしい。
悪友は紫苑の少年を末恐ろしいと言っていたが、既に同性にもモテている少年に、彼は緊張の腰を折られて溜め息をつく。
どの大陸でも、港は普通賑やかなことが多いが、ディアルスでは東端の海岸のごく一部に寂しげな石の岸壁が広がっている。
人気の少ないその地に王女は兵営を敷き、沖に留まる敵船を、この一週間警戒していた。
「……もう何度か来たけど……ここはいつも、何か懐かしいな……」
彼の視線の先では、灰色の岸から海を眺めていた連れ合いが、潮騒の中でほのかに笑って手を振っていた。
一足先に港に行っていた連れ合いが、ずっと偵察を請け負っていた悪友と共に駆け寄ってきた。
「いよいよやな。今日で何としても、決着つけたるで!」
やる気満々の悪友に彼は黙って頷き、紫苑の少年が悪友を見上げるように尋ねる。
「船にいるのは結局、四天王と蓮華とアシュリンのねーちゃんだけ?」
「ああ、ずっと見張っとったけど、見かけて気配もしとるんはそいつらだけや……それに、城から陸路で逃げた奴らも母船には合流しとらん。それぞれ最初から用意しとった小船で、北の島に帰ったみたいや」
やはり猫娘はいないという情報に、少年が少し残念そうにする。
「城の時みたいに、透明になって潜んでることはなさげ?」
「絶対無いとは言えんけど、昼夜問わずやし。船自体傷んどるから、何で留まっとるか知らんが、おれがボスやったら、あの船に部下を乗せて本気で戦う気はせんな」
悪友達が現状を確認している横で、彼と連れ合いは並んで正午の水平線を見つめていた。
「キニス、連れ戻せるかな……ねぇ、レイアス」
あえて新たな名の方を口にする連れ合いに、彼も苦い顔で両腕を組んで答えた。
「……俺もタツクもそれだけが目的だ。四天王の動向はこの際、どうだっていい」
以前の幼馴染みが戻る可能性は少ない、と彼は知っている。それでもせめて望む結論を、無自覚に理解しているような連れ合いが悲しげに笑う。
「うん。無理に戦わないで、キニスと一緒に、無事に戻って来てね」
故郷を滅ぼされた復讐も、ディアルスへの脅威としての対処も。それよりも大切なものが、彼らにはある――
悪友も彼も、今残る仲間を守りながら、可能な限り同郷者を助け出したい方針で固まっている。手始めは当然、現在手の届く位置に在る幼馴染みだった。
しかしそれは、初手にして中核が控える敵陣に挑む、とても困難な課題だったが。
岸壁からすぐ山に続く古い港で、中腹にある展望台に本陣を構えた赤毛の王女は、そんな彼らを朗らかな顔付きで後押ししてくれた。
「目的は戦争ではありません。降りかかる火の粉を払うことへのご協力、感謝致します」
四天王を追い払えれば一番で、激化は本末転倒だ、と人間達との利害も一致している。
それだけ王女が周囲を納得させられたのも、彼らの助力を受けることで跳ね上がる勝算に基づいての、この海上戦の決行だった。
その最たる根拠となったのが連れ合いの存在だ。沖合に漂う敵船に向かって飛び立つ彼らを、青い珠玉を囲む木杖を両手で持って、決意を秘めた笑顔で見送ってくれる。
「……先に行って。わたしもすぐ追いかけるから」
「……――」
この状況なら自分も思う存分戦える。王女と妖精の魔女に対して自ら言い出し、作戦の要となる連れ合いが光らせる、透明な青の目――
しかし彼は、不意に襲われた強い悪寒で、もう一度振り返って黙って見つめる。
――水のそばなら、わたしも戦えるのになぁ。
ディアルス王都に初めて来た日に、そんなことを軽く呟いていた連れ合いが、最も得意とする戦い方は「水」の竜の召喚。海流を操り、渦潮や水柱を自在に制御する自然界の脅威の使役は、海上に陣取る相手には致命的な一手となるだろう。
竜と銘打つ「力」は、「水」の四天王をも上回る最強のはずのものだった。
――俺は、一番危ないのは竜や精霊だと思う。
それでなくとも強大な自然界の「力」を司る化け物で、現在最上である四天王や守護者は、純粋な精霊のレベルと言われている。
守護者は別の力源も持つが、ヒトの身の制御力自体の限界がそこで、それに比べて竜が最強とされるのは「逆鱗」という、制御力を底上げする秘宝の存在にあった。
彼の前の義手にその宝は埋め込まれた。「水」の制御のために義手ごと預かった連れ合いは、立ち止まる彼を安心させるように柔らかく笑いかけた。
「大丈夫だよ。こんなに大切な戦いの時に、わたしはわたしに負けたりしないから」
その召喚はしくじらない、と、確信に満ちた空色の目は本当とわかりながら……彼は絶えない嫌な予感を振り切るように、二度目の飛竜を実体化して宙に消えた。
黄金鳥の悪友を先頭に、紫苑の少年を彼が背に乗せ、目標たる敵船にはあっという間に辿り着いた。
船上には彼らの襲来を探知してか、四天王と隣に立った黒い彼女、猫娘は不在で従者だけの三人が待ち構えるように、一番広い上甲板に立っていた。
「待ちくたびれましたよ、君達。障壁も機能してませんから、降りてきたらいかがです?」
連れ合いの「力」で段々と黒くなってきた海上で、嵐の到来に気付きながら誘いをかける相手の言葉は、どう考えても罠でしかない。
「キニスと話したいんでしょう? 来ないならこのまま、連れて帰りますよ」
その存在が彼らの楔であると、とっくに知っている悪魔の男が微笑む。敵を見下ろせる船楼の屋根に、真っ先に降り立った紫苑の少年の後に、彼と悪友もヒトに戻って続く。
目下の四天王はとても感心したように、まず彼の姿をその眼に捉えて言った。
「ディーズからも聞いていましたが、本当に君は生きていたんですね。気配すら覚えてはいませんでしたが、何としぶとい生命力でしょうか」
半年前に彼の心臓を貫いた魔性の男を、何も答えずに彼は睨み返す。
隣の悪友が代わりに、呪うような低い声で口を開いた。
「……あの胸糞悪い都市長と結託して、何が目的なんだ、お前達は」
まるで彼が喋ったような、訛りのない憎悪の口調で問いかけた悪友。四天王の隣で無表情にしている黒い彼女がふっと見上げる。
その視線に悪友は一瞬息を呑みながら、険しい表情は崩さずに対峙を続ける。
四天王は彼ら全員を見回し、端整な顔にふわり、と雅やかな笑みをたたえた。
そうして、男が様々な千族に関わり、化け物ギャンブル等も手掛けてきた真意。それをあっさり、彼らに明かし始めていた。
「簡単な話ですよ? ……君達全員、私の城に来る気はありませんか?」
「――何、だって?」
中心で話し役を務める悪友の衝撃顔に、背後に従者の女を控えさせた四天王は、身長差のある黒い彼女の肩をわざわざ抱いて、彼らを挑発しながら先を続ける。
「私はキニスやミスティルのように、優秀な部下が欲しいんです。それというのも私は現在、一番弱い四天王でしてね――」
空には暗雲がかかり、海面は黒く染まる。「水」の竜が近付きつつある船は、大きく高波に揺られ出した。
そんな中、自然な気品で話す魔性の男は、この場の緊迫にあまりに不釣り合いだった。
「西の拷問親父には負けたくありませんが、そこには優秀な後継がいますし。ディーズが慕う東の方や、あの方が見守る南も今代は相当の際物ですし……共通していることが、私を除いた四天王は、人間と交わった邪道さなんです」
「……?」
「不安定でも大きな力を得るために、他の四天王は禁を侵した。守護者も消えて、勢力拡大が必要な時世で仕方のないことですが、私はどうしても人間の女が好きになれなくてね……ディーズともそれで気が合ったんですよ」
そこでさらに、彼女を抱え込むよう密着させた四天王に、踏み出しかけた悪友を彼が眼で制止する。
頭上から睨みつける彼らに、一見は脈絡の無い話を四天王が持ち出していた。
「君達は、『オセロット・アーク』という少女の伝説を知っていますか?」
彼と悪友はわけがわからなかったが、紫苑の少年がぴくり、と顔をしかめる。
「人間と化け物の共生などやめろ、という絵本です。化け物に扮して戦った人間の少女を、人間の国を守る化け物が殺してしまった歴史上の逸話で……その国は神暦におけるディアルスだと言われています」
まるでそれが、ディアルスに刃を向けた理由と言わんばかりに、四天王が顔を歪めて笑った。
「ミスティルが姿を模し、蓮華や緋桐が着ける防具は『オセロット・アーク』に由来する秘宝でね。私はそれで化け物に扮したアークが憐れで、化け物にならんと願ったアークを、罰した人間達が好きになれません。それもよりによって、化け物の力を借りて、アークを処刑した人間の国の王女が」
そこで彼も、猫娘が「アークちゃん」と、灰色の猫のぬいぐるみに対して独り言で会話をしていた、という話を思い出した。
四天王が少なくとも、本心で彼らに話をしていることだけはわかり……無意識に呻くほどに、人間と化け物の話は真に迫るものが感じられた。
「キニス、もとい君達の仲間であった彼女は、おそらく残存する全ての防具を身にしても動けるほど、『アーク』の遺産の適合者でした。残念ながら今は他の者達と同じ程度の、一部の防具が使えるだけですがね」
そうやって幼馴染みを自陣に迎えた理由も説明するが、その適合性が落ちた理由――彼女の変容については、四天王も詳細を語りたくないらしい。
「化け物の少女はとても一途です。ミスティルやキニスは、私のためなら何でもするよう躾けられている」
くすり、と笑うように口にした言葉に、彼らの表情に一瞬で霜が降りた。
「彼女達を真に想うなら、なりふり構わず人間への加担などおやめなさい。でなければ君達は、『アーク』を殺した化け物と同じ裏切り者です」
唯一認められるとすれば、四天王は彼女達を、人質にしたわけではないことだろう。
むしろお気に入りである意思を露わにし、彼らを誘うのは彼女達のためも大きいようで、何を最も優先すべきか訴えかける姿勢は、四天王なりの筋道とも言える。
それでも彼同様に、納得できるわけはない悪友が、訛り抜きの口調のままで口を開いた。
「……そんな理由でお前は、アシュリンやラストの妹を攫ったのか」
溢れる怒気で声も震えている悪友に、四天王は全く悪びれずに言葉を被せる。
「救ったと言って下さい。君達こそいったい、彼女達に何をしてあげられましたか?」
「!?」
「己が精霊を奪われ、不自由な体で閉じ込められていたミスティルには自由を。己を嫌う同郷者を守った彼女には居場所を――……君達には到底、払ってやれなかった闇です」
思わぬ話に動揺しつつも、甲板に飛び込みそうな勢いの悪友が、彼に片手で制されながら最大の遺恨をそこで叫んだ。
「まさかそれで、おれ達の里を滅ぼしたっていうのか!?」
「おやおや……私はそこまで、彼女達に重荷を背負わせる気はありませんよ。君達の集落は単純に、以前から危険視されていた、それだけのことです」
最早完全に、夕方のように暗くなった空の下で。
四天王はまさに悪魔の顔で黒い彼女に目配せし、自身の「力」を強く纏い始めた。
「恨むならディアルスに加担した自分達を呪いなさい。あれだけの『力』を見せた君達を、守護者と同様、放っておける道理はありませんから」
世界の脅威は最早、自分達だけで充分だ、と言うかのように。
魔性の男は臨戦態勢に入り、その大きな理由である先程からの異変を、船楼の彼ら越しに見上げた。
「……この『力』も、非常に気になるところですね」
今や激しく揺れ出した船の正面には、海面から立ち上がって四天王一派を見下ろす、自然界の驚異で最強の「力」――
「水」で創り上げられた竜と、それを中心に渦巻いて船を引き寄せる海気が、言葉も無く絶対の警告を卑小な龍の船へと告げていた。
一番最初に動いたのは、ずっと黙っていた紫苑の少年だった。
「!」
両端に鎌のつく武器を振り上げて甲板に飛び込んだ少年を、予期していたのか黒い彼女が長槍で弾き返した。
「あたしの相手はラスティル君? 面白そうだね」
昏い顔付きで笑う彼女に少年も顔を歪め、長物を振り回すために甲板の対側に飛び退る。彼女も遠慮なく四天王から間を取り、少年についていった。
「……いいのかよ。守るべき相手から離れて」
「別に? 一番の邪魔者、多分君だし」
拙い言葉を交わした直後に、少年と彼女の、目を奪われそうな激戦が幕を開ける。
少年が動いた理由、最早一刻の猶予もないことを悟り、彼らもそれぞれの行動に移る。
自船を喰らわんとする「水」の竜――巨大な渦を、四天王は「力」で押し止めている。その間近に少年と同じく彼らも飛び込み、男に正面から剣を突き付け、悪友が従者の女を羽交い絞めにした。
従者を封じた悪友に加えて、黒い彼女が助けに入れないことを確認すると、彼はようやく重い口を開けて要求を伝える。
「今日は逃がさない。アシューを置いて行くなら解放するが、このまま抵抗すれば船ごと沈める――たとえ四天王でも、ここで始末する」
あの「水」の竜に対抗するだけで、四天王は精一杯のはずだ。転位の鎖を持つ従者も動けなければ、実体化の力をも残した彼らは圧倒的に有利だった。
「それは困りましたね。これは確かに想定外な『力』でした」
船上には彼らがいるので、これでも手加減された強力過ぎる海の増援に、完全に余裕を消した四天王だったが。
「……キニスが嫌だ、と言ったら、どうするんです?」
彼女を黒く染め上げる真の呪い。すれ違い続けた彼らに、それが歴然と告げられる――
下11:白黒 -答-
両極の大鎌と大身の長槍。二つの長物が上甲板に留まらず、小さな龍にいくつも張られた翼を越えて、空中でぶつかり合う様は見事としか言えなかった。
「……ふーん。君が知ってるあたしも、何だかいい奴っぽいね」
「……!」
己以外の力を受けて、身体能力を上げる臑当てを装着した彼女に、まだ小柄な体付きの紫苑の少年が僅かにおされ、悔しげにぎりっと見返している。
――アナタが知ってるあたしは、いい奴ぽいね。
彼女の主たる魔性の男を止める彼に、かつて言ったのと同じ言葉。彼らに声が届く帆けたにあえて降り立ち、それを口にしたようだった。
暗雲の中で彼女の姿はほとんど見えず、誰もその表情はわからなかった。
「変な話だね。あたしは凄く、里の奴らに嫌われてるみたいなんだけど――何でこうも、ヒトによってあたしの情報が違うの?」
それはまるで、これではどれを模せばいいのかわからない、と。相手が抱く自身への思いを直接感じているらしい彼女の、嘆きに思えてならなかった。
次に彼女が、まさに呪うような声色で続けた仄暗い訴えこそが――
幼い頃から互いに信頼していたはずの、彼と悪友への告発だった。
「……ねぇ。あたしとアナタ達で、いったい何が違ったの?」
彼らに牽制された四天王や従者が動かない中、黒い彼女が一人、紫苑の少年を警戒しながら全てを見下ろして言う。
幼少時は同じ場所で育ち、彼女の霊獣と同等以上の力を持ったはずの彼と悪友に向けて。
「強かったのは、あたしだけじゃないよね? なのにどうして弱い奴らは、アナタ達には憧れて、あたしのことは嫌っていたの?」
彼らの故郷で良く思われず、孤立しがちだった幼馴染み。
彼らと仲良くしていると尚更反感を買う、と距離を置いていた時期も長い。そのまっすぐな呪詛に、彼も悪友も、思わず洩らした呻き声を呑み込む。
後は空ろに、そうして槍を構える理由を彼女は伝えた。
「……アナタ達と一緒に行くべき理由、あたしには何かあるの?」
つい先程に、四天王たる主が口にした通り、居場所はそこにしかないと。彼らにまるで嗤うように言う。
「あたしは何処にも、行き場なんてない。あたしは何にも――選ぶ気は無い」
だから彼女がそこにいるのは、彼女以外が強く願い、選択された現実なのだと。
「っ――言ってる場合かよ……!!」
彼らの里の事情を知らない上に、自身の双子のことで精一杯の紫苑の少年に、黒い彼女を物理的に圧し止める以上の余裕は皆無だろう。
再び空から襲いかかった彼女に、何も言えず応戦する少年を目に、声を張り上げたのは従者の女を押え続ける悪友だった。
「それでもお前は――里を守りたかったんやろ、アシュー!?」
悲痛な悪友に振り返りもせず、彼女は少年と刃を交え続ける。
「大事なんは、お前がみんなをどう思っとるかやろ!! おれは知っとるで、お前がずっと、セレンやみんなを守ろうとしとるって!!」
戦いをやめない彼女が、単独では決して、彼らと行動を共にしようとしない真情――
それは今も四天王の手中にあるはずの、他の同郷者を見捨てられないからだ、と彼女を信じ切って悪友が叫ぶ。
そのやり取りすらも結局は、四天王の時間稼ぎであると、この後に突き付けられることになっても。
――もういいですよ、と。黒い彼女の無機質な立ち回りを制したのは、まだ彼に動きを止められ続けている四天王だった。
「彼女の遺言はそれで十分でしょう、キニス」
その声と同時に、紫苑の少年から距離をとった黒い彼女は、途端ににこり、と微笑んでいた。追撃をかけようとする少年をそのまま目線だけで制す。
「お遊びはここまでだって。残念だけど生き残れるかな? ラスティル君も」
「――!?」
「ミスティルちゃんと蓮華の力作レプリカ、『小龍』の華々しい最後、それではご覧あれ」
彼女はとても楽しげに、手元に小さな硝子石を取り出した。そしてそれを躊躇いなく握り潰していた。
「残念ですが私は囮ですよ。色々な意味でね?」
彼女が彼らに害されることはないだろう、とわかり切ってその石を預けた悪魔がそこで微笑む。
この船を保つ核石。船に与えられる力を纏め、持ち主の意図を汲み、舵取りの役割も果たす操作道具が壊されたのだと、彼が気が付いた時には遅かった。
「海流に呑まれるまでは予想外でしたが、どちらにしても、末路は同じです」
黒い彼女がそれを破壊したと同時に、真っ黒な闇が飛び散るように船全体を包む。
まるで海上の一角に穴が開いたような黒い球体が、陸にいる者からは見えていただろう。
声だけがわかる異質な黒い場の内で、四天王がわざわざそれを彼らに説明する。
「ブラックホールと言ってもわからないでしょうが、この空間はこれから、縮んで潰れます」
「――な!?」
「うぉあ!? 何すんねんアシュー!?」
暗闇の中で悪友は背後をとられたらしく、従者の女を解放させるよう寝技をかけられ、見えない船床に叩き付けられていた。
彼にも悪友達の発する色だけが視える状態で、気配や場所はわかるが、細かな動きが追えずに対抗手段がなかった。
「蓮華に感謝しなよ、捕まえてなければ一刺しにしてやったのに」
対して黒い彼女はこの暗中でも、相手の状態が的確にわかるようだった。
彼女が従者の女を連れて、四天王の元に戻ったと同時に、じゃらり、と鎖の音がした。
「こらぁ、待て――……!」
それがまた敵達の逃亡の前兆であると、気付いた少年が敏い探知能力を頼りに駆け付ける。
「――駄目だ、ひけ!」
彼が叫んだと同時に、彼女が手にした槍を少年のいる方向に繰り出した。その警告が無ければ、咄嗟に退いた少年も手傷を負っていただろう。
「私達の勝ちです、ディアルスの人間かぶれの諸君」
「――!?」
段々と薄まっていく男の声。闇の何処かの転位口に、四天王達が入ってしまったことをそれは示していた。
「でも後一つ、欲しいものが増えましたので……寄り道をしていきますね――」
最後にそう言い捨て、敵側の三人の色も気配も、真っ暗な場から消え去っていく。
「あーもぉぉー! ミティの奴、無駄に仕掛け凝り過ぎだろー!」
残ったのは、心から悔しげに叫ぶ少年の声だけだ。これから潰れるという漆黒の船上に立つ彼らに少年は、予想以上の現状を伝えてきた。
「オレ達下手したら、永遠にここで暗闇生活だよ、兄ちゃん!」
これから縮んで潰れるという船全体は、一見、何の変化もないように見えた。
しかしそれこそ、彼らごと空間を圧縮し始め、零に至らない限り縮小を続ける無限地獄だった。
「どーいうこっちゃねん!? わけがわからへん、ここは何やねん!?」
とにかく集まった彼らに、紫苑の少年は緊迫したまま説明を続ける。
「魔道的には、永遠に半分にされ続ける効果がある場所と思って! 二分の一の次は四分の一、その次は八分の一、更に次は、みたいに!」
何やてー! と悪友が叫び、彼もようやく事態を飲み込む。
「外から見たら凝縮されまくって潰されてくけど、ゼロになることはないから、中のオレ達はずっとこのまま! 誰か次元移動でも使えない限り、こっからは出られないよ!」
次元移動とは空間転位の別名だ。世界の各地にあるようなワープゲートと同じ奇跡を、ヒトの身で起こす「力」と言える。
その業は四天王以上のレベルの化け物でようやく可能な魔道の儀で、従者の女が使う鎖も四天王から力を受けて、おそらく三人までの転位を何とか行えている状態だった。
彼もひたすら頭が痛かったが、冷静さを失いつつある少年に、務めて落ち着いて声を出す。
「……この空間自体を壊すしかない。あいつらが出て行けた以上、少なくとも一つ、何処かに穴があるはずだろう?」
「言う通りだけど、穴以外を壊したらその時点でアウトだよ? オレ達本当は凄い縮められてんだから、下手に出たらそれが半端に再現されると思う」
「ラっ君……それまさか、ミンチ肉ってことか?」
多分ね。とぼやく少年に、うあああー! と悪友が煩く頭を抱える。
それもそのはず、もしも外界の者がこの空間に気付いても、力ずくで壊されてしまえば同じ状況が彼らには起こる。助けが来てしまうまでが時間制限とも言える。
先程の転位で、何処かにはあるはずの、歪められた空間の穴。
しかしそれは彼の眼を以てしても、黒の中に黒を探す難儀さであり……。
そして四天王が残していった言葉も、妙に彼の焦燥を掻き立てていた。
――後一つ、欲しいものが増えました。
「アイツは何が目的だったんだ……? 俺達の始末なのか――?」
ディアルス沖に一週間も少数で留まり、彼らを誘い出したような魔性の男。
あの三人だけでまともに戦う気があったとは思えず、この稀少な空飛ぶ船も使い捨てるほどの目的。四天王にとっては取るに足りない、彼らの抹殺のためとは思えなかった。
――私は囮ですよ。色々な意味でね?
彼らをここに引き付けておきたかった。本当にもし、この船こそが囮だったとしたら。
――この『力』も気になるところですね。
荒ぶる海に対する四天王の言葉を思い出した瞬間、彼の全身に衝撃の冷感が走った。
信じたくない推測に、まさか、と彼は焦る心を振り切る。ただ必死に、空間の穴を探して、暗闇の船上を歩き回る。
「この船全部探して、船の外も探してって……オレの気配探知でも無理あるし!」
その困難さを一番実感しているためか、最初に泣き言を上げた少年の声に、そもそも何も探す術を持たない悪友もうぉぉ、と頭を抱えて座り込んでしまった。
そうしてじわりと、彼らを追い詰める暗黒。気付きつつある絶望という闇の中で。
一人歩みを止めなかった彼が、大きな音を立てるほどに、突然脱力して両膝をついた。
「――え……?」
驚く少年や悪友が、彼を呼ぶ声も遠い。
少し前と似た彼女の白昼夢が、唐突に彼を襲う。
彼はただ……限りなく哀しい安堵と共に、その答の全てを受け止めていた。
――ああ――……疲れてたんだな、お前……。
痛々しい、としか言えなかった。けれど確かに、そこに幼馴染みの救いはあった。
それは彼女を誰より知っていたものが、何度も彼の眼に送った、彼女の「心」そのもので……――
「……――こっちだ! タツク、ラスト!」
「え、ってわ!?」
「ってレイアス、大丈夫なんか!?」
両手と膝をついて蹲っていた彼を、悪友と少年が心配げに囲んでいた。突然顔を上げた彼は、懐から短刀を取り出して素早く立ち上がった。
「出口がわかった! ここを出るぞ、早く!」
そうして足早に歩き始めた彼を、気がふれたのかと少年と悪友は思いかけたようだが、どの道活路などない、と早々に吹っ切って追いかけてきた。
「帰るんだ、ディアルスに――……アフィの所に……!」
幾度も黒い彼女の「心」を視せてきたものが、つい今届けたある光景。握る短刀に力を込めて、彼の憔悴が倍加していく。
彼がその眼で捉えた出口。それは黒い闇の中でやっと視えた、消えかけている誰かの淡い姿だった。
もうここに来てはいけない、と。その白い影は、彼より研ぎ澄まされた彩の無い眼を以て、閉ざされた虚無の世界の穴を「心」づてに彼に視せる。
「……お前だったんだな――……『バステト』………」
半年前に一度だけ、彼はそれと、薄明るい不思議な所で話をしたことがあった。
彼らの霊獣は坐した異界から影を投げ、本体と同じ「心」を持つ存在で……その相手は彼と同じ「心」を視る眼を持つから、互いの「心」がわかった――話ができたのだろう。
彼の髪を白く染めて、黒い彼女のことを届けていたのも、異界に僅かに消え残ったそれだ。心配そうな白黒猫、幼馴染みの霊獣がかけてくれた、拙い助けの声だった。
消えそうな白黒猫が教えてくれた空間の穴に、「力」に介入する短刀を突き立てて、暗闇が消えた後に現れた場所。そこは石造りの建物が特徴的な、ディアルスの路地裏だった。
「バステト……!?」
明るい場所ではもうその姿はわからず、きょろきょろとする彼を、紫苑の少年と悪友が当惑げに背後から見守っていた。
「ここって……アイツらが転位した先っちゅーことか?」
「多分ね……でも何でわざわざ、ディアルスに戻ったんだろ?」
表通りに出ると、そこは王女が陣取る山海地域に近く、段々と賑やかになってくる港町の郊外であることがすぐにわかった。
とにかく本陣に合流しようと、森に向かった彼らを、すぐに見咎めた一団があった。
「――!? 貴方達、いつ帰ってきてたの!?」
「ナナハにファー!? どうしてここにいるんだ!?」
王女を守り、森にいたはずの妖精の女と黒髪の騎士が、兵士達を引き連れて逆に港町の中心部に向かっていた。互いの気配を見つけて鉢合わせする。
妖精の女はとても険しい顔付きで、驚くべき窮状をすぐに叫んだ。
「王女が裏切り者に攫われたのよ! その後で貴方達が向かった船が消えて、それからアースフィーユまで姿が見えなくて……!」
「何――だって!?」
思わず耳を疑ってしまうほどに、次々と伝えられる悪報。
それは彼らが不在の隙を襲った、猫娘を連れる忍装束の少女達が起こしたことだった。
「――!? 何処行くのさ、兄ちゃん!?」
それなら彼に先刻伝えられた、信じられない最後の光景も真であるのだと――
最初の路地裏に戻る方向に駆け出した彼を、追う余裕がある者もそこにはなかった。
空間の穴を視ることに必死で、重大な情報であると知りながら直視できなかった。その現実が今更、彼を強く責め立て始める。
視えている場所を闇雲に探し、ディアルス港町を走る彼が辿り着いたのは、人気の無い入り江の切り込みの内部。地上からは死角になる、小さな船着き場だった。
そこに落ちていた、ある大切なもの。白黒猫に届けられた警告の中で、視えていたものと同じ残骸。
彼は全身の血が凍ってしまったように、呆然と立ち尽くした。
「そん……な――……」
真っ白になった頭は、またあの白黒猫が、彼に乗り移るよう何かを伝えているのか。それとも純粋に、恐れと絶望によるものか、最早区別はつかなかった。
――先に行って。わたしもすぐ追いかけるから。
彼らの助けに「水」の竜を喚んだ竜の娘。その制御力の要たる「逆鱗」。彼の古い義手に宿る「力」を、この付近で連れ合いは使っていたはずだ。
しかしそこには彼の義手だけが、灰色の入り江にぽつんと取り残されていた。
ずっと、白黒猫は、ディアルス王城が閉鎖された時など、一番重要な情報だけを彼に送り届けてきていた。
それも死にもの狂いなのだろう。占い師の言葉を借りれば、もう十中の一しか残らない存在で、拙い命を削って彼に敵陣の様子を伝えている。
そうまでして伝えようとしたのは、彼の最も大切なもの。白黒猫も気に入っていた空色の連れ合いの、確実な危機に他ならず……。
「アフィが……アシューに、攫われた……――」
平らな石の上に落ちている自らの義手を見つめ、静かな潮騒の中、膝をついてしまう。彼の眼には、改めてその光景が映し出される。
彼らを置いてディアルスに転位し、黒い彼女は、「水」の竜の制御者を探しにきていた。四天王に召喚者を捕えるように言われたのだろう。
そうして、友達だった空色の相手を標的として見つめる者の、昏い視界が再生される。
黒い彼女を無表情に見返し、竜の「力」――青い珠玉の杖を抱える連れ合いは、彼女の訪れを感じた時点で諦め、誰も巻き込まないため一人でいたようだった。
「……どうしてここに来たの? ……キニス」
おそらく彼らの中では初めて、新しい名で彼女のことを呼ぶ。
落ち着き払った連れ合いに、黒い彼女は形容し難い感情を浮かべた。
「あははは。アフィちゃんはあたしのこと、全然怖くないんだね」
「……」
黒い彼女はずっと気が付いていた。彼女が何者かわからず、不安の眼差しを向ける彼や悪友の無自覚な怖れに。
「……うん。だってわたし、あなたがアシュリンでもキニスでも、どっちでもいいもの」
以前の彼女に戻ってほしい。それは彼らの当然の想いで、だから黒い彼女にとっては絶対の断絶……決して越えられない彼らとの壁だったのだ。
居場所などない、と船上で口にしていた彼女。
そうした中で、連れ合いだけは変わらず、彼女を大切な友として暗い青の目で見つめる。
「本当……怖い子だね、アフィちゃんって」
「…………」
「知ってたんだね。あたしとあなたが、こうやって出会う日のこと」
そして彼女達の黒い呪いは――そこで真なる邂逅を果たす。
「それであたしから……居場所を奪ったの?」
絶え間ない潮騒の中、飛び去る水鳥の羽音と共に、視界は黒に塗りたくられる。
義手を拾い、彼は為す術も無く、仲間達の元へ戻るしかなかった。
彼らが不在の間に、本陣で何が起こったのかは、実に簡素に伝えられた。
「イソシギの奴が寝返ったのよ。と言うより……初めから同郷のファーのツテを利用して、ディアルスに潜り込んだネズミだったみたい」
妖精の女曰く、ディアルス王城を改修した時の業者も、裏切った金髪の騎士の手配だと言う。その時に例の結界を仕込んだはずのことや、ディアルス側の情報も敵側に筒抜けで、王女を攫う機会を窺っていただろうことを憎々しげに口にする。
「彼はファーと同じ高潔な血統……『地』の天界人の系譜だから、と油断していた。考えてみれば敵にも同じような、赤目の娘がいたし」
黒髪の騎士と共に、かなり色味の強い赤の目。天上の聖火の眼光を持った者。
しかし幼馴染みは、初対面から胡散臭いと言っていたことを、彼はぽつりと思い起こした。
森の中のテントで円陣を組んで座る王女の側近。妖精の女に黒髪の騎士、彼と悪友の元に、ちょうど入ってきた紫苑の少年がすっと言葉を挟んだ。
「その赤目の娘……『緋桐』は、逆にオレ達の方に来たがってるよ」
――!? と全員の視線を受けた少年は、疲れ混じりの顔に厳しさを載せながら彼の隣に腰を下ろす。少年が今まで伏せ続けていたある真実について、神妙に話し出していた。
「元々オレが、初めてシャル都市長の屋敷に兄ちゃんと乗り込んだ時……ミティの結界で、一度は捕まったんだよね」
シャル都市長の屋敷で、彼らが逃げられたのは、囮の役をした幼馴染みの功績だと少年は言っていた。一人残った少年自身は、そこでは逃げられなかったようだった。
「その時にオレをこっそり逃がしてくれた緋桐が、ディアルス王城の時も姿を隠さずに、一階でうろうろしてたから。捕まえて話を聴いたら、狙いは炎と風の珠玉だって、教えてくれたのもあいつ」
その翡翠の髪の少女は、金髪の騎士と王城の事変の際に戦っていたが、一時薄柿色の髪の少女と交代していた期間がある。その間に少年と再会し、話をしたのだという。
オレが待ってただけとでも? 事変後の会議の少年の言が、やっと彼も納得がいく。
「でもあいつ、ディアルスで受け入れてくれるなら、もっと協力するって言ってたから。王女を助けるのには役に立つんじゃないかな」
そこまで話し終えた少年に、妖精の女が怒り心頭の面持ちで向き直った。
「そんなの信じられると思う!? 大体どうしてもっと早く、そんな大事なことを言わないわけ!?」
「オレ達の中に、自分の仲間――内通者がいるって言うから、話せなかったんだ。話したら下手するとあいつが危ないし、それに……」
内通者がいる警告自体はしていた少年は、怯まずに妖精の女を見返していた。
「誰か教えろって言ったら、それはあいつ、断った。仲間を売れない、自分は裏切りたいわけじゃなくて、良い職場に行きたいだけだって」
「……なるほどなぁ。そら確かに、根は悪い子とはちゃうな」
四天王って人使い荒らそうやしな、と、少年への助け舟のように悪友が加える。
何でもいい、と、重々しく黒髪の騎士が口を開いた。
「……使える者は、全て使って王女を助ける。それでいいだろう、魔女」
「でも、ファー!」
「イソシギとは必ず落とし前をつける。アイツを引き入れた責任はとる」
その相手の裏切りに、おそらくは妖精の女以上に憤怒を抑える声色。珍しく激昂を抑えるような黒髪の騎士でもあった。
「もうこら、四天王を城ごと吹っ飛ばす勢いで、アシューもアフィもセレンらも助け出すしかあらへんな。なぁ、レイアス?」
喋る力もなく項垂れていた彼に、何処か達観してしまった悪友が、あっさり声をかける。
「それ、オレも賛成。もうミティの首輪に鎖付けて引きずって帰るしかねー」
軽々と頷く紫苑の少年にも、彼はひたすら、俯き続ける。
この事変は何処まで大きくなって、そして続くのだろう。目を伏せる彼に、少年はぽんぽんと物怖じもせず、彼の灰色の頭を撫で叩いていたのだった。
下12:白猫と黒い魔物
ディアルス王位継承者、唯一にして第一の王女が攫われた。そんな緊急事態であるにも関わらず、審議院が許可を出した騎士団の動員数は、恐ろしく少なかった。
「いくら本国を守らなければと言ったって、船すら出し渋るのはどーいう了見よ!?」
妖精の女は調整に走り回り、既に五日がたった中で、黒髪の騎士や彼の我慢が切れる直前に出陣準備が整ったと伝えに来ていた。
「アースフィーユは必ず貴方が助け出してよね。リアラ様のことに動揺して、あの子に手が回らなかったのは謝るわ」
「……わかってる。ナナハこそ、船の死守をよろしく頼む」
北の小島に向かうための軍艦は、小さいが防御に優れた物だった。結局少数精鋭で北方四天王の元に行くことになった今は、目立たず隠れることを最重視されていた。
「ところで緋桐とやらに、連絡はとれたの?」
「ああ、ラストが通信道具を渡していたらしい。四天王城の大まかな図面は、後の会議の時に出せる」
翡翠の髪の少女はそれはそれは、にこやかに紫苑の少年の通信に応じたものだった。
「嬉しいです、ラスティルさんから連絡を貰えるなんて。私、ディアルスでは受け入れてもらえそうですか?」
こういうの、とてもスリリングですね! と、通信機の向こうで喜ぶ声。そもそも少年を助けたのも「好みだったから」という理由らしく、彼らは言葉を失うしかない。
それでも翡翠の髪の少女から伝えられた現況に、彼は安堵を隠せなかった。
「王女も青い髪の方も、ついてすぐ研究棟に幽閉されましたが、大切な研究材料だからと平時の扱いは丁重ですよ。キニスがずっと見張りにつけられています」
どうしてなのだろうか。黒い彼女が連れ合いについているということが、彼には逆に胸を撫で下ろさせる一番の情報だった。
「ミスティル様はここの所、不安定ですね。管理者の桔梗姉様が困っています」
「……不安定?」
やはり猫娘は、薄柿色の髪の少女に精神操作を受けているという。少年が厳しい声で詳細を問い返すと、通信相手はけろりと重い内容を答える。
「蓮華姉様が、王女達の精査の手伝いに呼ばれる時間が増えたからだと思います。淋しがられてキニスのそばを離れないんです。それでも引き離すと、一人の時は始終涙されている状態で」
どうやら黒い彼女に余計なことを吹き込まれているのでは、と薄柿色の髪の少女は痛く不機嫌らしい。
そして黒髪の騎士が金髪の騎士のことについて尋ねた時には、翡翠の髪の少女の面持ちも暗くなっていた。
「枝木には、一緒に寝返らないか相談したんですが……どの面下げて帰れっての。の一言でした、すみません」
「……そうか」
滅多に喋らない騎士が問いかけたこと。騎士は翡翠の髪の少女を知らないようだが、金髪の騎士は少女にとって、裏切りのことも相談できる相手なのだ。少女も騎士達もその血統は近く、全員親が「地」という天空島の出自ということだった。
「私は両親が地上に降りてから生まれて、その後孤児になって……守護者もですが、天界人の血は、世界の何処かで息づいているはずなんです」
本来は神威の暴挙から世界を守る、抑止力たる「守護者」の離散。
近年はどの四天王も、大きな力をつけていると翡翠の髪の少女が語る。最後に彼の同郷者達の現状を伝えながら、通信を終えていた。
それに改めて彼と悪友、紫苑の少年は、霊獣の里の者のために用意した道具の妥当さを確認する。
王女も連れ合いも、「竜珠」――竜の遺産と思われる珠玉の適合者だ。他属性の似た珠玉を手に入れた四天王は、そこに興味を持ったのだ、と翡翠の髪の少女は言った。
何処までが史実かわからないが、「オセロット・アーク」の遺品という防具に填まる黒い珠玉。ディアルス歴史学者である王女の従弟に、伝説のことを尋ねてみたところ、確かにそうした言い伝えはある、と迅速な回答があった。
「ディレス初代王は、竜の血をひくと言いましたよね? 初代王こそが『オセロット・アーク』を倒し、『神』にアークの秘宝を差し出した、と古い文献では残っています。でもアークも竜の秘宝を使っていたとすると、『オセロット・アーク』の伝説は、人間と竜の確執を伝える他の文献の考察にも影響が出そうですね……」
そこで考え込みかけて、はっと気付いたように従姉の王女の窮状を思い出したらしい。バツが悪そうに言葉を続ける。
「四天王はそれが、『竜珠』と確信してないと思います。だから調べたいんだと思いますし、竜の遺産がまだ残るなんて、ほとんどの文献には書いてありませんよ」
「……そもそも、竜に遺産があるなんてことも、ほとんどの奴は知らないよな」
「ええ。それは本来、持ち主の竜人の自然回帰と共に消えるもので、ディアルスのように適合者を残さない限り、竜珠は受け継がれないはずなんです」
竜の末裔とも言える国の学者が、そうして大切な疑問を告げる。
「『オセロット・アーク』の防具の黒い珠が、本当に竜珠であれば、適合者なしに残り続けるはずがありません。でも今は中途半端に適合する者達が、分散してその防具の『力』を使っているんですよね?」
「……本来の適合者が、本当は他にいるってことか?」
「もしもそれが真にアークの遺産で、かつ竜珠であるなら、ですけどね」
しかしそれだと、いったいその適合者は何千年生きているのか。数千年前の伝説たる「オセロット・アーク」について、最後に言葉を濁した学者だった。
炎と風の珠玉の王女。水や風を操る連れ合いの「力」となる青い珠玉。一揃いの様々な防具に「力」を与える黒い珠玉。それらに興味を持った四天王の目的は、結局は勢力の維持……。
馬鹿馬鹿しい、と毒づきながら、秘密裏に出航する夜を待つ。誰もいない自室で彼は呆然と、仰向けにソファに横たわっていた。
連れ合いが攫われてから、まともな睡眠はほとんどとれていなかった。
こうしているといつも脳裏を掠めていくのは、先に行って、と最後に笑った連れ合い。その青く光る透き通った目ばかりだ。
「……すぐに追いかける……か……――」
その時から既に、理由もなく嫌な予感はしていたのだ。
何か大切なものを失くす気がする。いつかにも同じように、その思いを振り切ったことで永く後悔した心の悲鳴。それを彼は必死に聞くまいとする。
――わたしが魔物でも……レイアスはいいの?
鬼子と呼ばれていた幼少の時。彼自身は、己が魔物とならないように堪え続けた。
今でもその思いは変わっていない。それは純粋に、魔物とは救われないものであると、本能的に感じているからだろう。
何かを望み、自分以外から奪ってでも、「死」を制して在り続けるものが魔物だ。流れる永い時の中で、たとえ元の形を失っていても。
「アフィがもしも、本当に魔物なら……何を望んでいるんだ……?」
まだ彼は何もしてやれていない。走り続けただけのこの半年を思う。
「お前なら、知っているのか? バステト……」
かつて彼に、その連れ合いとの縁を告げた相手につい尋ねる。
その後まもなく、彼は浅い微睡みの中に落ちていった。
そうして、彼の切なる問いに、それは最後の力で答を届ける……――
潮騒が響く。いつかに彼が迷い込んだ、あの薄明るい場所のように。
その唄が聴こえる限り、姿は見えずとも傍にいる。潮騒に棲むものを待つ魔物は、そうして己を納得させていた。
魔物の生まれた所はとても昏く――魔物となるもの以外、何もない場所だった。
魔物の大切なものはそこに留まらず、その本質である空と海の境に還った。
置き去りにされても、それで良かった。元々、約束を守れなかったのは魔物の方だったから。
――……約束って、何だったっけ?
悲しげな魔物は、薄明るい場所で見つけた不思議な白い猫に尋ねる。
白い猫は何も知らなかったが、魔物のそばにいてくれるようになった。
そしていつしか、大切なものによく似た、大きな白い獣を連れてきてくれた。
――ホンモノにも印をつけておくね。私にしか視えないけど、ちゃんといるからね。
白く大きい獣の頭にあった黒い印を、白い猫は大切なものにもつけてくれると言った。
いつかそれを探して一緒に外に出よう。もう約束は、思い出せなくてもいい。
……そう思ったはずだったのに。ある日魔物は、怖い夢を見てしまったのだ。
そして約束を知ってしまった。知った魔物は、知らない魔物には戻れなかった。
だから白い猫と無理に離れ、約束を果たすために、ヒトのものを奪うと魔物は決める。
白い猫は残念がっていたけれど――それでもそれは、魔物に笑いかけた。
――……大丈夫だよ。そうすればあたしも私も、みんながまた会えるんだから。
変わってしまう魔物が残した心を拾い、白い猫も一部が黒く染まってしまい……。
そんな魔物の呪いを掬った、それの末路。暗黒の船上で視た夢を、彼はふと想う。
その帰り道は、今までになく清々しいものだったことを、それは知っていた。
「あーもー。つくづく、外の世界は怖い……久々に本当、ヤになったなぁ」
化け物ギャンブルへの無理な参加や、大規模な魔物の襲来など。ディアルスで様々な事変に巻き込まれた幼馴染みは、心からそうぼやき、故郷へ帰る準備をしていた。
「里にいた方が確実に平和だった。間違いない、うん」
王都の商店街をさまよいながら、呟く声は自然な響きで。居たたまれずに後にしていた故郷の良さを、一人歩きで笑う彼女は実感できていたのだ。
元来、病に臥す父の薬の材料を買うため頻繁に外に出ていた彼女は、同年代者とは少々悩みの違う世界に生きていた。そのため自身が、周囲に解け込めないことを諦めていた。
正直なところ、強くなることしか考えていない周りが好きになれなかった。
だから自分も受け入れはされない。先に心を閉ざしたのは己だ、ともわかっており――
「ていうか早く、みんなに教えに帰らないと。人間の町も国も、何か危ない所だらけだし」
昔馴染が何やら危ない相手に殺されかけて、自身も死ぬ気で戦ったような事変の後に、それは凄く素直に浮かんだ思いだった。
そこにはいたくない、誰のことも好きじゃない。そう思っていたはずの場所にそんな風に思えたことが、彼女はとても嬉しかったのだ。
「あははは。帰りたいなんて思えたの、ホント何年ぶりだろうなぁ?」
薬の材料さえ揃えば、里に先に向かわせた霊獣の元まで一瞬で跳べる。
いつもはそんなに急がずゆっくり帰路につくのに、今は薬屋も足早に回っている。
どうしてそんな風に思えるようになったのか。それも実は、自覚している彼女だった。
今までこの買い物のための旅は、彼女にとってはただの仕事だった。一人で外界に出ることが、同郷者達の反感を買うことも知っていた。
実際は父のためでもなかった。色んな問題の、その場しのぎの対処法でしかなかった。
いつもそう思いながら、彼女は外に出ていた。大して楽しくもない旅は、里にいて気を使うよりマシなだけの毎日だった。
――でもそれは……ヒトのためだったんじゃないのか?
けれどそれを、彼女に届く形で……拙い奮闘に、ある真心を分けてくれた相手の言葉が、彼女本来の願いを取り戻させてくれた。
――お前、そういう奴だから。放っておけないよ。
その一言だけで、どれほど肩の荷が軽くなっただろう。そうしたかったのは自分だ、と思い出すことができただけで、彼女は救われていたと言って良い。
別の友人にも、同じように言われたことはあった。
――アシュリンは偉いわ。お父様の薬を買いに出るために頑張ったなんて。
その時は齟齬を感じるしかなかった。この友人とは解り合えないだろう、と。
友人は彼女の旅の意義を褒めていたから、彼女はその眼差しに堪えられなかった。
この旅はただの逃げだ。彼女が抱える様々な問題を、決して根本的には解決はしない。そうするしかないだけで、やめられる良い方法があればやめたい。
賞賛の目とは裏を返せば、彼女がその責務を果たさなくなれば失墜するものだ。偉い、と見上げる彼女に妥協を望まない期待が、友人の差し出す好意だった。
……彼はやっと、彼女が何に苦しんでいたのか、その真情の一端を悟る。
「ああ――……疲れてたんだな、お前……」
あの時はそこまで気付いてやれなかった。けれど無意識に口にしたのは、放っておけないという心の声で……それが同じことを言ったはずの彼と友人の、大きな違いなのだろう。
彼は彼女の行動を、偉いと思ったわけでなく、ただ心配だった。
一人で周囲のことを背負う彼女。必要なことだから頑張っているのだろう――そうした姿、彼女自体を良しとし、それ故に気になったただけだ。
「……やめろとも言えないし……無理してるのは、見ればわかるし……」
行動そのものの良し悪し。例えば旅の是非は、彼が計り知れるものではない。
だから彼女は再び意味を見出だせたことを、それは知っていた。
何より彼女自身が馬鹿にしていた、彼女の孤高な闘いの価値を。
「あたしも捨てたもんじゃないかな……頑張ってるよね、あははは」
彼は彼女が旅をやめたところで、悪く思わないだろう。むしろ彼女のために、そこまで背負うことはない、と安心するかもしれない。
そのように思ってくれる相手が一人いるだけで。誰かのためだ、と認めてくれただけで。
これは頑張り甲斐があることなのだ、と、やっと思えた彼女は、色々なことを吹っ切れていた。
「今度セイレーネが、お帰り、お疲れって言ってくれた時は、ちょっとは嬉しい……かも?」
そうなると不思議と、里に帰っても、少しは違う自分でいられる気がしていたのだ。
「色々めんどくさいけど……今からでも、遅くなかったのかな」
すぐに気を許すのは無理でも、今は里の者を心配する自分がいる。外の世界は危ない、と伝えたがっているこの自分なら、いつか周りを好きになれるかもしれない。その予感だけで彼女の足取りが弾む。
「レイアス達も大概ヒドイし。勝手にヒトを別チームに入れたりするし……一緒にいると、何かとハラハラさせられるし」
彼ら以外にも、心を開けるものを見つけなければ。そんな風に彼女は笑う。
「それにレイアスは……アフィちゃんと本当、お似合いだしね」
何より大きかったのは、その思い。だから彼女が、直視する気になれた故郷は――
しかし既に、手遅れだったと知ったのは、帰り着いたその時だった。
痛々しい、としか言えなかった。
彼女の心を、誰より間近で知っていたそれが、彼に届けた彼女の大切な夢。
「お前……だから先に、一人で帰ったのか、アシュー……」
里の危機を知っていたわけではない。しかし何か、予感はあったのかもしれない。
彼女にとっては面倒でもある場所に、居ても立ってもいられなかったのだろう。
「やっと……帰りたいって、思えたんだろ……?」
その思いも、長続きしたとは限らない。故郷が健在で、その内で逆風が吹けば、再びへし折れてしまった彼女かもしれない。
でもその方がまだ良かっただろう……突然何もかもを、奪い去られることに比べれば。
彼女の衝撃までは、届けまいとしたのか。それともそれが、限界に近付いているのか。そこで彼への応えと、拙い望郷の夢が途切れる。
彼が自らの世界へ戻る前に、涼しげな愛らしい声が僅かに闇を揺らした。そうして夢現の中で、一度だけ話した誰かが語りかけてきた。
――……ごめんね……。
誰かの声と共に、彼はごぼり、と……まるで溺れるような息苦しさを、突然自覚する。
送られてきた光景。その水槽にいる黒い彼女は、呼吸をすることは有り得ない、ただの壊れた人形だった。
欠損部を無理に培養された体は髪が伸びて、魔物なら黄泉還ることもあるだろう。けれどゼンマイを失くした普通の人形は、本体を直したところで動きはしない。
しかしそれには呪いという名の、もう一つのスイッチが存在していた。
人形として活用を考えた修理者も驚愕したほど、それは突然、空ろな両の目を開ける。
そして伝えられた、彼の大切なものの危機。
――……私がわかることは……これだけ……。
彼はそれの名前を呼びながら、彼の現実へと還る……。
そろそろ自分は消える、と。目覚め際に伝えられた、とても不吉な言葉。彼は飛び起きて必死に辺りを見回していた。
「バステト……!?」
彼の問いかけに応え、知る限りの「心」を視せてくれた相手。
その猶予も最早無くなってしまったのだ。真っ白な頭の彼に、これから向かう場所の直近の状況を視せて、それは消え去ろうとしていた。
白い壁で縦長の窓が多く、開きはしない息苦しい応接間で。
向かい合うソファに座らされた彼の連れ合いと、赤毛の王女の後ろ姿がまず眼に映った。
「……ですから、もう四天王に従うのはやめて下さい。貴女の仲間のお二人は、貴女達を助けようと必死に頑張っていますよ」
毅然と言う気丈な王女は、城では黒いマスクをさせられず、喋ることができる同郷の女に語りかけていた。
「無理よ! アシュリンだって私を見捨てた、レイアスやタツクも四天王様には勝てない!」
「見捨てたって……どうして?」
不思議そうに見上げる連れ合いに、憔悴している同郷の女は、両手で顔を覆いながら悲痛に続ける。
「四天王様に黙って従えば、こんな待遇になることもなかったのに! アシュリンは勝手に一人で死んで、私はキニスの見張り役なんかにさせられて……!」
これは白黒猫を通した黒い彼女の視界だ。同郷の女は王女の背後に立つ彼女も構わず、無遠慮なことを口にしており、相当追い詰められている様子だった。
「こんな子、私の知ってるアシュリンじゃない! もう嫌、何がどうなってるの!?」
四天王から女は、黒い彼女に変な行動を起こさせれば、女が殺される、と脅されていた。
それは黒い彼女を縛る最大の鎖で、彼女が様々な局面で女を庇っていることも知らずに。
黒い彼女にとっては、薄柿色の髪の少女の操作に加え、目覚めた時から彼女の傍らに置かれた同郷の女の視線が、彼女の形を定める一番の基準だった。助けてほしい、という切なる願いが、空ろな彼女のひとまずの行動をいつも決定させた。
それを知るわけではないだろうが、背後で黙る黒い彼女を、王女が痛ましげに見上げていた。
「この方はどんな形であれ、貴女を守っています。そんな風に仰るのはあんまりではありませんか」
何故それがわからないのか、と、王女は同郷の女をまっすぐ見つめる。
そこに切り込んだのは他でもなく、黒い彼女の辛辣な声だった。
「さすが、守られるのに慣れてる王女様は、言うことが違うね」
あくどく微笑む彼女に、同郷の女が口元を抑える。王女と連れ合いは無表情に彼女を見つめる。
「ヒトにばかり戦わせて、何とかなってきた身は気楽でいいよね。信じているのが王女の役目? 今回ばかりは、どうなるかわからないけどね」
その皮肉の返答すらも、同郷の女の反感を映し、代弁しただけの黒い彼女だった。
「今回って、何? キニス」
淡々と尋ねた連れ合いに、黒い彼女は綺麗な笑顔で答える。
「今夜、アフィちゃんから順に『力』の起動実験をするらしいよ? 特にアフィちゃんは不思議な石を持ってるから、それが何なのか刺激してみるんだって」
そこで黒い彼女がじっと見つめたのは、連れ合いの首元に光る青い菱形の宝石だった。
――それを起こしてはいけない、と、咄嗟に思ったのは誰だったのだろう。
この光景を伝えてくるものが、吐き気を催すほどに強く感じた事柄だった。
連れ合い自身はきょとんとしたまま、囚われの身にしては落ち着いている。彼は僅かに安らいだものの、黒い彼女が言った内容への危機感が強く募る。
やがて視界は途切れ、また映そうとしては暗転するという、あがきの様相を呈し始めた。
――ごめんね……。
もういい、と言おうとした彼に、全く視えないほどにその存在は弱っている。声無き答を、自らが途切れる最後の瞬間に返してきていた。
――私……守ってあげられなかった……。
だからせめて、これくらいは、と嘆く。彼は思わず片眼を掻き毟り、頭を強く掴んで絞り出す声で叫んだ。
「お前のせいじゃない……! キニスは、お前がいたからアシューでいられたのに……!」
……今なら彼には、痛いほどわかった。
黒い彼女の酷薄な姿は、彼女を取り巻く昏い思いの反映であることを。
「もう間に合わないのか? アシューの元に還れないのか、バステト……!」
それのそばに在れた内が、彼女は一番良かったのだろう。常に共に在る、優しくお節介な白黒猫。「心」を視る眼を持つ誰かを、映せていた日々。
今の彼女に残ったものは、過酷な運命に巻き込まれた者達の、望まぬ黒い影だけで……。
消えゆくものを呼ぶ声は、空しく反響して途絶える。
「……バステト……」
応えるものがいなくなった事実を、灰色に戻った彼の髪が静かに証明していた。
不意に、連れ合いの穏やかな声が、彼の心に静寂を取り戻させた。
――キニスと一緒に、無事に戻って来てね。
もしかしたら連れ合いは最初から、彼女がそういう性質とわかっていたのかもしれない。
「……そうだな。……アフィの言う通りだったんだ」
だから必ず、彼女達を無事連れ戻すのだ。
今は連れ合いが無事である情報だけが、崩れ落ちそうな彼の暗礁を照らす、小さな灯台だった。
下13:黒の真実
北の小島は、世界地図に描かれない数多の無人島と、大きくは変わらない閑静ぶりだ。ただし四天王の城と、古の聖地という遺物を除いて。
平坦な大地に森林が広がり、聖地には小丘に四角錐の石の遺跡が建つ。四天王の城は森から空に突き出るように白く建った、外壁の無い高層な洋館なのだが、宝屋根で縦長の本邸に平らな陸屋根で横長の東館が付設した、唯一の有人領域だった。
妖精の魔女の魔法で隠された船を、半月の夜に紛れて城と離れた西海岸に着ける。彼らは最後の作戦会議を船中の食卓で行う。
「要するに、おれが正面でめっちゃ騒いでなるべく敵を引き付ける。その間にファーは本邸裏手に、レイアスとラストが研究棟の東館の屋根から侵入するってことやろ?」
「物凄く簡単に言えばそーだけど。城内は何処も『力』封じの結界が張られてるはずだし、タツクのにーちゃんは絶対入ってくんなよ」
城に侵入するのは上級千族の彼らだけで、後の兵士は船の守りにつく形だった。
「それぞれ目的は自分で頑張って、自分の身は自分で守る。何かあれば自分だけ逃げる!」
身も蓋もない紫苑の少年だが、個々で助けたい者も違い、互いの補助に入る余裕が皆無というのは異論は出なかった。
「おれの方に里の奴が出てくるとえーけどな。それは緋桐ちゃん、確約できんて話やろ?」
「タツクにはすぐ俺も合流する。こっちに里の奴が来たら呼ぶからついて来てくれ」
悪友につくのは彼の霊獣の話だ。城内では「力」が使えない可能性が高い以上、城には本体のみが侵入し、霊獣は悪友と共に外で戦わせることにしていた。
「里の奴を助けへん限り、おれは実体化が使えへんのが痛いけどな。頑張るわ」
そしてこの相談の通り、使役できる限りの鳥を供に、悪友は生身で正面玄関に降り立つ。
「すげー鳥の数……これ全部とタツクのにーちゃんが戦えば、囮は何とかなるかな?」
気配を弱めた飛竜――小さめに実体化させた霊獣の背に少年を乗せて、彼は黙々と東館の屋根に着陸した。
平らな屋根の端でヒト型に戻り、悪友の方に霊獣を送った彼の横で、少年も武器を取り出す。屋根の中央を見て心から嫌そうなしかめ顔を見せた。
「うわ、奈落の底って聞いてたけど本当だ、趣味わりー」
「……ゴミ捨て場の次元の穴って話か。どれくらい深いかはわからないらしいな」
横長の東館は、空から見れば屋根は郵便受けのように黒い差し込み口を持つ回廊型だ。底の見えない真っ暗な中空部分は、東館を貫く大きな芯のようだった。
紫苑の少年が改めて、両極の大鎌――双鎌と銘打つ愛用の自作武器を、体慣らしとして軽く振り回す。
「さてさて、絶対侵入気付かれてるけど、こっちは誰が応対に来るやら?」
笑顔は少なくなったといえ、相変わらず軽いノリの少年は、基本的に彼のように悩みを外に出さない。不敵さも健在の少年に彼は少し安堵しつつ、何かが心配だった。
「……精霊は使えるとはいえ、油断するなよ」
少年は妖精の魔女と同様、単身なら可能な結界返しを自らに施している。持久力の問題がなければ、北方四天王とも渡り合ってやるという意気込みを彼に見せていた。
「ま、オレ達もある意味囮だしなー。今までの恨み分、派手にやろーぜ、兄ちゃん」
さらには、単純な飛び道具や力技なら通じないという魔除けを、この何でも屋は出陣までの期間に、戦う者全員にディアルス王家の出資で製作していた。
造れなかったのは現物を確認できなかった結界除けだけで、情報があり準備ができればまさに百人力の少年は、つくづく彼らの中で最強だった。
自身の霊獣――今では霊体も飛びトカゲの方に感覚をずらすと、霊獣のいる悪友側では、ずらりと正面玄関に並ぶ敵と対面したところだった。
「おいおいおい。おれ一人にその人数はあんまりじゃないか、オマエら」
動き易い淡褐色の武闘服で、玄関前の広場に一人仁王立ちした悪友。暗い空に蔓延る鳥の大群を背後に、霊獣族の里長の息子口調で力強く笑う。
「言っとくけどあいつら、鳥目でよく見えてないから、元仲間だろうと容赦なくつつくぞ。オマエらもだから、遠慮なくかかってこい!」
敵には忍装束の一団と、黒い腕輪に尖ったマスクをさせられた霊獣の里の者が、同郷の女を含めて入り混じっている。泣き出しそうな目の同郷の女と、その背後にいる女の従兄に、爽やかに悪友が笑いかけた。
「無事で良かった、セレン、テルル。他の奴らも、悪いことは言わないから早く帰るぞ!」
侵入者が霊獣族の里の化け物と知っていて、同郷の者を目に見える姿で応戦に出した相手側の意地の悪さに彼は溜め息をつく。
しかしそれは、悪友の方にある道具を持たせた彼らの目論見通りでもあった。
忍装束の者だけを片付けんと、魔除けをつけた悪友が敵の群れに飛び込む。
「おれはそもそも、一対一より乱戦向きなんだよ!」
そう言えば里にいた頃の悪友は、多人数には敵の体ごと振り回して戦うような無茶さが持ち味だった。忍装束の者の「力」での攻撃を妨害する飛びトカゲは思い起こす。
この間に黒髪の騎士が、翡翠の髪の少女の手引きで裏手から侵入し、彼と紫苑の少年が屋根で東館の警備を引き付ける間に研究棟に入る手筈だった。
本邸の正面には下っ端が多く動員された中で、東館の屋根に現れたのはまさに本命……彼と少年の前に、やがて黒い彼女と猫娘、その従者と薄柿色の髪の少女が姿を見せていた。
本当にあまり部下がいないんだな、と、彼は妙に納得してしまった。
ここは四天王の本拠のはずだが、他の場所でも見かけた顔しか出て来ないことが、人手がほしいという四天王の言を裏付ける。
それだけ彼らが上級の千族で、相手をできる部下がいないという意味ではあるが。
初めに口を開いたのは、とても楽しげな黒い彼女だった。
「あははは。このタイミングで来るって、やるねぇアナタ。いいね、ピンチに駆けつけてもらえるアフィちゃん」
「…………」
「城に入らないのも賢い賢い。城内は完全に四天王様の縄張りだから、何処にいようと、その気になればあっさり串刺しだし?」
「――ちょっとキニス。いらん情報喋ってんじゃないよ」
黒い彼女の後ろに立つ薄柿色の髪の少女が、苛立ち混じりの声で両腕を組み、彼女の足の防具を爪先でつついた。
「あんた本当、目離せば何するかわかんないし。北の方の寵愛を受けてるからって、その気ままぶり、まじでむかつくし」
翡翠の髪の少女の情報では、薄柿色の髪の少女はヒト喰い鬼の血筋であるという。
黒い彼女と猫娘の精神干渉を担当するが、少女達はそもそも北方四天王直属ではなく、別の強大な悪魔の傘下で派遣部下であるらしい。
「あんたがディシーヴのトネリコになれば、盛大にいびってやったのに。精々コイツら、今日こそぐちゃぐちゃに始末してよね」
派遣元の集団名を口にしながら唸る薄柿色の髪の少女に、黒い彼女が余裕の体で嗤う。
「…………」
黒い彼女の隣にいる猫娘は、物言わぬ従者の女の陰に隠れて、厳しい面持ちで紫苑の少年を窺っている。その様子に少年も余裕を消し、猫娘を同じ紫の目で見つめる。
中空の建物の屋根は広いようで狭く、黒い彼女が大きく跳躍する。彼と少年の頭上を越えて東端に降り立ち、彼らを挟み撃ちにする態勢をとった。
「桔梗の言う通り、決着をつけよーか。これ以上はさすがに、アナタも疲れたでしょ?」
「……そうだな。……キニス」
彼女の方に向いた彼と、本館側を向く紫苑の少年は距離を置いた背中合わせで、屋根の中空の南側で互いの相手と一直線に対峙する。
右手に水平に長槍を下げる黒い彼女は、長剣を左に、短刀を右に持った彼に、すぐには踏み込まずに適当な話を続けた。
「まだしも冷静なのは、緋桐から情報を聞いたのかな。色々内情、知ってるぽいね」
「……気付いてたのか。それならどうして、仲間に言わない?」
目敏い彼女が翡翠の髪の少女の離反に、勘づいていないかは彼も気になっていた。
「誰もあたしを仲間と思ってないよ。それなら裏切ったもくそもないでしょ」
そうか、と答える彼の静かな痛ましさに、彼女は何処か大人びた顔付きでふっと微笑む。
少年の方では、薄柿色の髪の少女が投擲武器を、猫娘が飛び道具を使って威嚇を始める。流れ弾も猫娘に当てたくない少年は、あえて近接武器の双鎌のみを使うようだった。
あまりに目敏過ぎて、ヒトの闇を映してしまう黒い彼女。それがその紫苑の娘の、閉ざされた感情を掘り起こしていたことを――娘の自我を封じ続けようとした、薄柿色の髪の管理者も手に負えない状態になっていると、双子である少年はすぐさま実感することになる。
「やめろよミティ……! そんなもんここで暴発させたら、この小島ごと吹っ飛ぶぞ!」
「……っ――!!」
飛び道具では、魔除けをつけた彼らには通じない。焦った紫苑の娘は、洒落にならない高度な次元爆弾を、次々投げつけてくる混乱ぶりだった。
「何をそんなに怯えてんだよ!? オレがお前のこと、傷付けるわけがないだろ!」
戦闘には邪魔、の一言の奈落が、まさかここまで役に立つとは。敵弾を全て異次元の入り口であるゴミ捨て場に叩き落とさんと、少年は非常な神経を使っていた。
紫苑の娘は、少女を捕まえようとする少年を防ぐ従者の女の陰に隠れながら、言葉も話せなくなったような焦燥だけを浮かべる。
娘の使う道具が発動すればまずい破壊力と見え、管理者の方は屋根の西端、本邸の壁際に下がって様子を見ていた。
「あーもー! まじ有り得ない! ミスティル様、ミスティル様は何も悪くない、そんな悪者のことなんてミスティル様は知らない!」
そうして娘を後押ししていた管理者だったが――それも思わぬ所で途切れることになった。
「……って、へ!? 緋桐が妙な侵入者と一緒にいる!?」
何かの連絡を受けた管理者が、唯一可愛がった者。妹分の想定外の行動に慌てて館内に戻っていく。
従者の女と二人だけになった紫苑の娘は、ついにぺたんと座り込んでしまった。
「……イヤ……怖いよキーたん、ごめんなさい、ごめんなさい……!」
「ミティ……!?」
従者の女に抱きかかえられて泣きじゃくる娘に、少年も動けなくなっていた。
少年を怖がる娘に、それ以上どうしろというのだろう。
「知らない、あんなコなんて知らない、でもキーたんの言う通りなの、凄く怖いの……!」
妙な口調もほとんど消えた娘が、桜色のショールを両手でぐしゃりと掴んで蹲る。
「どうして、だって私は人形だもん!? 家族なんていない造り物だもん……! だからキーたん、れんれんがいればいいの、友達がいればいいの……!」
だから、と……この半年、お手製の殺戮道具を実戦で使い続けることになった娘は……。
「悪い奴は吹っ飛んじゃえばいいの! 言うこと聞かなかったから悪いの……!」
それで積み上がっていく屍の山。その時点で崩れ落ちていた幼い精神の均衡を、身近な管理者の弛まぬ努力も空しく、黒い誰かは重い蓋を開ける。
「キーたん、怒ってないよね……!? キーたんの友達だって、私……知らなかったの……!」
その娘が造った道具には、様々な物があった。
結界やヒト喰い魔法陣、多機能な落下傘。爆弾や銃に、太古の遺産を模した飛空艇。
そして現在、彼らを最も脅かすのは、同郷者の口を封じる黒いマスクとセットの黒い腕輪。それも娘が造った、裏切り防止のための鎖だった。
「捕まえたぞ、セレン! 助けてやるから大人しくしてろ!」
「……!」
ついに忍装束の者をいなした悪友は、まず同郷の女を捕まえた。突然地面に大きな布を広げると、女を連れて布に描かれた魔法陣の上に飛び込む。
「動くな、手がずれる! そんな爆弾、今切り落としてやる!」
そこで極太の鋏のような物を取り出すと、腕輪とマスクを断ち切り、一人目の救出を果たしたのだった。
「うそ……どうして爆発しないの……!?」
涙ながらに、黒い腕輪をしていた腕を見つめる同郷の女に、悪友が安堵して微笑む。
「お前達が脅されて仕方なく従ってたなんて、おれとレイアスはお見通しだ! この魔法陣は全ての『火』の気を防ぐから、ここならお前達を助けられるんだ!」
正確には、その腕輪に強い「火」の色を視たのは彼だ。それが黒いマスクと繋がり、悲鳴以外の言葉を発せば爆発する仕掛けだと看破した上で、この道具を造ってくれるよう紫苑の少年に頼んだのだ。
窮状を説明できない仕掛けを施され、「力」たる霊骨も取り上げられた同郷者達は、助けるという長の息子に動揺を見せていた。
「この中ではおれも『火』だから『力』は使えないぞ! お前達がやばい時にいなかったおれに文句があれば殴りに来ていい! 里に帰る気がある奴はこっちに来い!」
叫ぶ悪友に、同郷の女が突然しがみついた。
「ごめんなさい! お願い、一緒に逃げて、タツク!」
「って、へ!?」
「脅されたのは本当だけど、でも――……!」
自身の火の黄金鳥も封じられる魔法陣から、悪友は女に引っ張り出された。他の者を助けなければ、と慌てて振り返ったところに――
同郷の女の涙の理由。彼らの故郷に根付いていた闇が、そこで明かされることになる。
平らな屋根の東端で、長槍を棍の如く振り下ろしてきた彼女は、何処となく動きが悪かった。
何度も打ち下ろされる黒い槍は、どうしようもなく、諦めだけの攻撃に思えた。
「俺を……殺したいんじゃなかったのか?」
「アナタこそ。あたしを倒さないと、アフィちゃんは助けられないとわかってるくせに」
つまりそれは、どう戦えばいいかわからない彼を、そのまま映しているのだろう。
じりじりと、槍と剣の鍔迫り合いで、彼女の灰色の目が最大に近付く。そこには嘆息を噛み殺す彼の、悲愴な無表情だけが映る。
そこで力を強め、退く気配を見せない彼女は、この時を望んでいたかのようで――
「……仲間の解放を待ってるんだね。……でも、それは無駄だよ」
長剣を割りそうなほどぎりりと圧してくる、槍身の頑なさとは裏腹に。
肩から胸に白い三つ編みを揺らし、長い横髪の陰になる顔に浮かぶ表情は、これまでの彼女からは考えられない柔らかさだった。
彼と同じ悲しげな無表情が、青白い破月の光を受けて、微笑んだようにすら見えた。
飛びトカゲの彼が見届けた現実を、彼の眼を見て、黒い彼女も感じていたのかもしれない。
「……こっちに帰ってこい、セイレーネ」
故郷ではあまり、話したことのない知り合いの低い声が、悪友の後ろに隠れる同郷の女に突然重々しくかけられていた。
「っ……テルル……!」
声を詰まらせる女と同じ茶色の短い髪で、従兄である者。故郷に結界を張り、隠れ里とすることが役目だった女達の村の主要な担い手が、中心へ出て来ていた。
悪友は同郷の女を庇いながら、信じられないという顔で相手を見つめた。
「テルル……お前……」
「俺達は四天王様に仕える。あんな焼野原に帰ってお前の下につく気は、俺達にはない」
黒いマスクを着けながらも、口を開いても爆発の起こらない相手に、誰もが動揺を見せる。
その相手の存在こそ、黒い彼女が警戒していた、同郷の女が抱える窮状だった。
「まさかお前……里の結界に四天王の手を入れさせたのは、お前なのか……!?」
そして悪友も、前に出て滞空する彼から、裏切り者がいる可能性は聞かされていた。
「お前達は進んで……四天王に仕えるって決めたのか!?」
彼が気付いた一番の疑問は――四天王側のあまりの手際の良さだった。
――何で北方四天王は……アシューの友達がセレンだって知ってたんだ?
視えてしまった幼馴染みの最後の光景で、同郷の女を人質に連れてきた四天王の姿。
そもそもからして、ディアルスの事変に関わり四天王に目を付けられた彼らが、霊獣の里の者だと誰が伝えることができたのか。そしてそれからすぐに起こった隠れ里への襲撃。
――大体どうして……里の結界は、そんなに急に造りかえられたんだ。
そんなことは元々、誰かがじわじわと結界に手を入れていなければ起こり得ない。
きっと以前から霊獣の里を知っていた四天王は、裏切り者と何処かで関わりを持ち、自陣に誘いをかけていた矢先としか思えなかった。
「違うの、タツク……! みんなはそんなつもりなかったの、本当よ!」
同郷の女が叫ぶ通り、他の者達は誰につけば助かるのかと葛藤する。だから黒い彼女は、何も言わずに女だけを保護すると決めていたことを、女は知らなかった。
――もう四天王に従うのはやめて下さい。仲間は貴女達を助けようと頑張ってますよ。
王女がそう告げたのは、迷いにある霊獣族の者達を知ったからだろう。
同郷の女も、従兄が裏切り者だと気が付いたのは、城に連れてこられてからであるようだった。黒い枷をはめられた同郷者達は、中心の男が離反を禁ずる限り、解放の手段を持つ悪友の元に来られそうになかった。
「くそ、お前ら……馬鹿野郎――……!」
城の正面で、囮と同時に同郷者の救出役を引き受けた悪友――長の息子は、同郷者達と敵対はできない。同郷者を巻き込みかねない黄金鳥での攻撃も諦めるしかない。
そして悪友は、裏切り者が失笑する台詞を残して、撤退を決める。
「気が変わったら言ってこい! もう一度助けに来てやるからな!」
「タツク……!」
そのまま女を抱えて、同郷者達に背を向けて走り出す。その背を打とうとした裏切り者を、飛びトカゲが間に入って牽制する。
一緒に逃げて、と唯一こちらに来た女を守る以外、できることはなかったのだった。
そんな無様な顛末を、激しく顔を歪めて霊獣の眼で視ていた彼を知るように。
黒い彼女は彼との圧し合いを続けながら、必要なことだけを確認していた。
「セイレーネ……解放された?」
「…………」
黙って頷く彼に、そっか、と。長剣と槍の刃の向こう、彼女は場違いに安らかに笑った。
「テルルも可哀想だね。これで大物になれると思ってるけど、ここまで大事になるなんて、最初はわかってなかっただろうし」
ただ、結界を通して実力を示したかっただけだ、と。悪魔に誑かされて引き返せなくなった者を、巻き込まれた者を含めて彼女は憐れむ。
「……所詮使い捨てだろう。この城にいても、結局のところは」
「うん。でも、あたしが言っても信じないしね」
「信じたら立ち行かないだけだ。お前はそれを直視させるから、怖がられるんだろ」
「…………」
不意に、間近にあったはずの彼女の長槍……迫り合っていた力があっさり途切れた。
「――……!」
黙って後退した彼女は、離れる直前、彼を見つめる目に狂おしいほどのある想いを映す。
管理者である薄柿色の髪の少女がおらず、同郷の女が助けられたからなのか。安堵したように鳩尾を撫でて息をつく黒い彼女は、戦闘意欲を失くしたようだった。
それでも武器を下ろしはできない。気を許していると示すことはできない彼女が、彼と共に来ることはない、とはっきり口にする。
「あたしは帰れないよ。みんながどうであれ、あたしの居場所はここに作られたから」
もう一度屋根の東端に立った彼女が、彼の肩越しに紫苑の少年達を見つめる。斜め向きに黒い槍を片手で把持したまま、今まで決して見せることのなかった困ったような笑顔は、まるで幼馴染みが戻ってきたような儚い表情。
「ミスティルちゃんも、帰してあげたかったけど――……多分もう、ダメだったなぁ」
この所、彼女に纏わりついていたという猫娘。紫苑の少年を拒絶するように、今も武器を振るう姿が、その目の先にはあるようだった。
「悪魔に魅入られちゃったんだよ。あたしも、そしてミスティルちゃんもね」
「……キニス」
「どうしてそうなったのかな。あたしが嫌われ者だったから、なのかな?」
「っ――……!!」
再び声を呑んだ彼は、歯を食い縛って耐えるしかなかった。
悪友がずっと呆れていたこと……無自覚な彼が、あまりに唐突に知った自身の「心」に。
彼が今、言葉にできることは、本当に拙いとしか言えない応えだけだった。
「お前を嫌ってたのは……里の奴らじゃない、アシュー」
それは幼馴染み自身が、既に知っていた……そして答を得ていた問いかけ。
「アシューもキニスも……嫌ってるのは、お前なんじゃないのか、ずっと」
――あたしも捨てたもんじゃないかな……あははは。
そう感じた時に、やっと心から、故郷に帰りたいと思えていた彼女は――
「……うん。知ってたよ」
周囲との違いを感じ過ぎたために。一番先に自らを否定したのは、おそらく彼女自身だった。
「あたしはみんな、大嫌いだったから」
たとえ違っても、彼や悪友のように気にしなければ良かった。それだけのことだったのに。
「嫌いじゃないのは……アナタだけだった」
全てを他人事に語る、彼女の淡い微笑みに、こんな所で彼はわかってしまった。
「だから……アナタの隣にいたかった」
その目が映す彼の求めていたもの。それは愛しげに彼を見つめる、この彼女だったと。
……その心はきっと、有り得ない魔物が現れなければ、互いに募っていた想いだった。
――それであたしから……居場所を奪ったの?
そのために彼も彼女も、空ろな呪いを背負って生まれ出でたことを。
今はもう、誰も知らずに。
下14:赤の番狂わせ
悪友が同郷の女を預けるために、一度自船に撤退した後に、飛びトカゲの彼は他の同郷者達が城に戻るのを見届けていた。
そのまま姿を消して場から離れた飛びトカゲが、黒髪の騎士の担当の裏手に行くと、おかしな状態に気付くことになった。
――……結界が、無い?
裏手は何故か扉が開いていた。何より不自然なことには、結界に強引に穴を開けて、かつ違う力で補填したような、黒髪の騎士にはできない芸当が施された跡があった。
その欠損部を通れば、「力」を封じる結界の中でも、霊体の彼も動くことができそうだった。
その結界の欠損と置換部位は、「力」を視る眼の彼だからこそ追うことができる。
そのまま透明な飛びトカゲは城に侵入し、それを行った謎の誰かの後をついていく。そうして侵入した敵地、本邸と東館の境目となる、暗く長い階段の先に待っていたのは――
「貴様――……何者だ!?」
呻くように尋ねた黒髪の騎士も、その踊り場まで追いついた彼も、思ってもみなかった惨状。赤眼を大きく見開いた黒髪の騎士と翡翠の髪の少女の目前に、その番狂わせが在った。
「……何か不服か? この男の望みを叶えただけだろう」
そこにいたのは、引き裂かれた笑みをたたえる、悪魔としか言いようのない赤い人影――
「枝木……! そんな、主様、どうして――!」
叫んだ翡翠の髪の少女に対して、赤い人影は首を掴み上げていた金髪の騎士……だった忍装束の男の、胸を貫く剣を引き抜く。まるでゴミでも捨てるように、その体を黒髪の騎士と翡翠の髪の少女の方に放り投げていた。
それを受け止めた黒髪の騎士が、赤い人影を追えずに蒼白な顔付きで止血を始める。
その騎士の横にいる翡翠の髪の少女に、赤い人影の隣の薄柿色の髪の少女が、こちらも蒼い顔付きで妹分に呼びかけていた。
「緋桐! あんたこそ早く、こっちに戻って来な! 裏切り者は枝木ってことでいいだろ、主様が許して下さってる内に早く!」
「桔梗姉様……」
赤い人影は、そんな少女達に興味はないかのように、さっさと上階に行ってしまった。
その人影が、結界を弄り回している謎の誰かだ。それだけは彼もわかった。
翡翠の髪の少女は震えを抑えている。しかし毅然と、姉と慕った者に言い放っていた。
「……私はディシーヴを抜けます、桔梗姉様」
翡翠の髪の少女は、無機質に落ち着いた声で続けた。
「私は姉様の精神制御や、蓮華姉様の憑依のように、特別な才能を持っていません。アークの防具が多少使えるだけで、それもキニスがいればお役御免になります」
「緋桐……!! 何で――何で……!?」
「さようならです、姉様。姉様達は思う存分、その特技を主様の元で振るって下さい」
動揺して人影と妹分を交互に見る薄柿色の髪の少女。その方が余程、自然な反応に彼には見えた。
泣き出しそうな顔の姉貴分が、納得のいかないまま主らしき赤い人影を追っていく。その姿を見送る翡翠の髪の少女の無情さは、あまりに何処か理性的だった。
「……お互いその方が、きっとこの先、面白いですしね」
翡翠の髪の少女の方がおそらく、化け物らしいのだろう。そして精神干渉などを行える才能を持った薄柿色の髪の少女は、人間のような振れ幅があるのかもしれない。
いつも寡黙で、感情を見せなかった黒髪の騎士は、苦々しげに横たわる金髪の男を見下ろしていた。
王女が最優先なのは間違いなかったが、金髪の男のことも助けようとしていたのだと、彼には痛く伝わってきていた。
金髪の男が受けた傷は、千族と言えど確実に命を奪う深さだ。しかしそう簡単に事切れられない化け物は、黒髪の騎士の悲痛な視線に応えるように、うっすらと赤い目を開けていた。
「あー……何て顔してんだよ、ファー」
「……!」
「枝木!」
同じ赤い目の者達に覗き込まれ、たはは、と金髪の男は、血を吐きながら変わらない余裕の笑顔を浮かべていた。
「だから一緒にって、あれほど言ったのに……ファーさんと本気で戦ってまで、どうして……」
「……ばぁか。おれはこの業界で、のし上がるために、マブダチまで利用してやったのに……情が移って更に寝返るとか、完全に小物だろ……?」
赤い人影がここに来るまで、金髪の男は黒髪の騎士の拙い説得に全く応じなかったという。その堅固さは、離反を決めた翡翠の髪の少女と同質のものと言えそうだった。
「いいじゃん、こーいうのも……名も無き下っ端が、超上級の悪魔様に、お手にかけられるとかさ?」
それも出世の証だぜ、と皮肉な笑みをたたえる顔は、赤い人影の残した言葉。望みを叶えたという言を、一見否定できなかった。
離反した翡翠の髪の少女を見る目の内に、男のどんな決意があったか、悟られないことだけを願う――裏切り者となるための望みを。
「……魔女が悲しむぞ、イソシギ」
ぽつり、と重い声で本名を呼ぶ黒髪の騎士に、ふっと金髪の男の笑顔が儚く曇った。
「ナナハちゃん……本当、ナナハちゃんには、悪いことしたなぁ……」
とても勤勉で努力家な妖精の女。その背を守っていた男は、それだけは心残りと――初めて素直な顔付きで、最後の言葉を呟いていた。
「ああ見えて結構、脆いとこあんだぜ……? 可愛かったなぁ……あーあ……」
男には届かなかった夢と言うように、静かに目を閉じる。その真意の全てを呑み込んだ、哀しげな死に顔……一度だけ涙をぬぐった翡翠の髪の少女と、僅かな呻きを洩らした黒髪の騎士だった。
その後は予定通り、気丈な赤い目の者達は、研究棟への侵入を再開する。
――城内は四天王様の縄張りだから、その気になればあっさり串刺しだし?
翡翠の髪の少女は見つかり難い経路を選んでいるはずだが、皮肉にも赤い人影が作った結界の歪みから、少女も黒髪の騎士も更に気付かれ難くなっていた。
少女が主様と呼んだ、悪魔らしき赤い人影。その色に彼は覚えがある気がしたのだが、「力」の封印を重ねているのか、あやふやな色をどうしても思い出せなかった。
そんな予想外の勢力の介入がある中で、彼の置かれた状況も突然激しい悪化を見せた。
「――!?」
泣き叫んで座り込む紫苑の娘を、覆うように従者の女が抱えていた中で。少年が己の武器を携帯型に戻し、娘をこれ以上怯えさせずに近付こうとした間際のことだった。
「アイツ……!」
彼が黒い彼女に、目を奪われてしまった刹那に。東館より高い本邸の尖った屋根に佇み、半月の下で彼らを見下ろす城の主が、その「力」を紫苑の少年に容赦なく打ち出していた。
「やばっ……!」
精霊を使える時間も無く、武器を手放していた少年は転がり避けるしかない。
「やめろ、貴様――!」
さらに放たれた追撃は四方から少年を目がけ、その体勢で避けられる先は奈落以外なかった。
何処に続くかもわからない闇に、飛び込むかどうかの決断を少年が迫られた瞬間。
最初に少年が狙われた時点で、駆け出した者が、少年の動きを封じて覆い被さり――
少年に向けられた全ての水の矢を、その一身に、無言でそれが引き受けていた。
「え……!?」
「――!?」
それを見た四天王は顔を歪め、取り残された紫苑の娘に、すっと碧眼を向ける。
猫娘を守っていたはずの従者の女に突然庇われた少年が、わけがわからず両目を見開いていた。
力無く少年の上に倒れ込んだ女の姿に、紫苑の娘は――
「……いやああああああ! れんれん、れんれん、れんれん……!」
自身がどうしてそこまで狂乱しているかもわからず、娘は女の元に駆け寄ろうとした。
「城に戻りなさい、ミスト」
「!?」
間近に降り立った四天王の冷たい声に、立ち上がった娘がびくり、と全身を硬直させる。
その魔性の男の眼にあるのは、紫苑の少年を初めに狙った理由。娘に対する歪んだ執着でしかなかった。
「その体を失いたくはないでしょう? 城に戻り、桔梗の手当てを受けてきなさい」
「あ――……や……」
有無を言わせぬ冷酷な口調に、独りきりの娘は、ひたすら怯えてじりっと後ずさる。
同じ時間に、それとは真逆の温かな眼差しと声を、紫苑の少年は受けることになっていた。
「何で――……オレを、かばって……」
「…………」
恐る恐る少年が、胸の上に倒れる女の、顔を隠すベール付きの帽子に手をかける。
以前にその中身は目にしたはずだった。しかしこの破れた月の光の下では、違う何かが現れる、と無意識にわかっていたのか――
少年だけに見えた女の顔に、放心したような少年は……ただ、母さん、とだけ呟く。
……良かった、と。女が少年に囁いた言葉を、彼は直接聴いたわけではなかった。
「……蓮華。いや――……蓮華に憑依した、ラスティル君のお母さん」
彼はその彩の無い眼で。黒い彼女は感じ過ぎる才能で、女の真実に触れて立ち尽くす。
「鬼になったお母さん……蓮華の体を借りて、ミスティルちゃんのために……自分の体を差し出したお母さん……」
そこにいた女は、おそらくは三年前に。実の子を同じ里の者達に殺されかけた時に、気がふれたとしか思えなかった。
女が纏う、ごめんなさいという嘆き――ディアルス王城の時と同じ「心」を彼は視る。
幼い彼に、義手を造ってくれたその女の嘆きは、とても根の深い彼との因縁だった。
「俺達の里のことを、最初に四天王に教えたのは……あんただったんだな……」
送り届けた強い千族の子供――霊獣の隠れ里。
情報を直接四天王に与えたわけではないが、女が知ることは全て、憑依した体の本来の主も把握できてしまう状態だったのだ。
そしてさらに、女の里をも滅ぼした悪魔との取引が、女の嘆きの全てだった。
「……そうか。あの子の今の体は……あんたの体を材料に造った、人形なのか」
自分は家族などない、人形だ、と口にしていた紫苑の娘。
少年から聞いた話では、生まれつき酷く体が弱かったという。それを救うために女は、悪魔の力を借りて別の者に憑依し、娘の魂を人形に造り変えた我が身に遷したのだ。
紫苑の娘が少年のことだけでなく、女のことも母とわからないのは、精神干渉以上の心身の負荷――魂の遷移という、最大の蹂躙の結果でもあった。
そして女は娘を守り続けるために悪魔の言いなりとなり、反対した里の者は全て排除した。
その後は悪魔の元で、娘と共に数多の道具や兵器を造り、どんな惨劇が起きても娘さえ守れれば良い鬼となった。そんな女が、滅ぼした里の彼や、再会した少年――まっすぐな我が子を見た時に何を思ったのかは、彼には計り知れない領域だった。
そんな「心」も、一瞬の間に消え……他者に憑依していた女が、終わりを迎える。
その直後に、場の誰もが思ってもみない悪夢を――かの赤い道化師が、戯れに持ち込む。
あーあー、と。突然響いた呑気な声色は、場の惨状にあまりに不釣合だった。
「もう、私のパペットが壊れちゃったじゃないですか~? どうしてくれるんですかー、北の方ー」
「――!?」
陽気な声とは真逆に、場が突然暗転し、その強圧な介入に四天王の呻き声までが洩れる。
声の主はひたすら明るく、まるで商談でもするような軽さで、四天王へ話を続けた。
「炎と風の宝も実質使え無さそうですし、取引はここで終わりにしましょう? そっちのオモチャも返して下さいねー。それはもう、近年稀に見る良い出来なんですからねぇ~」
「――」
黙り込んだ四天王――最上の魔の者すら、その相手の言は反駁できないのか、と声だけが聴こえる彼にも衝撃の戦慄が走った。
「私も残念ですよ~。うちの主や親戚に、そんな宝を是非献上したかったんですがねぇ」
どうやらディアルスの「炎」と「風」の珠玉に、興味を持っていたのは声の主らしい。でなければ「水」の四天王が動く理由は本来ないはずだった。
「ま、そんなの無くても、貴男よりはどちらもお強いですからねぇ、南も西も。貴男もせいぜい、古き良き四天王として頑張って下さいね~」
それだけ言い切ると、異色な声は一旦途切れる。次にその闖入者の目が向いた先は……。
「ラスト、キニス……!」
黒い彼女は真っ暗な中に熔け込み、少年の紫もどんどん彼から離れつつあった。
少年は少し違う所に、闖入者の意図で送られていた。そこを見つけた彼の彩無き眼に、ある呪いの始まりが届く。
「やああああ! 助けてれんれん、れんれん……!」
帰りましょうか? そう尋ねた相手に、紫苑の娘は、闇をも揺らす悲鳴を上げた――
紫苑の少年が娘を呼ぶ声が、娘の「心」が視えてしまった彼に伝わってきた。
暗闇を逃げ惑う娘に、少年は必死に呼びかけている。実の母の死も振り返らずに、ひたすら追いかけ続ける。
しかしそれこそ、一人きりの娘を責め立てる呪いだったとは知らずに。
「オレがいるから、ミティ……! ずっと傍にいるから……!」
娘は尚も、悲痛な叫びを上げる。嘘吐き――と、泣きながら繰り返す。
血路を往く娘を、悪魔の夢に迷い込ませた、本当の闇に追いかけられて。
「知らない、知らない……! 私は知らない、ラティちゃんなんて知らない……!」
娘が決して、思い出してはいけないこと。それはただ、失った家族のことだった。
「……私のこと……置いて出ていっちゃったラティちゃんにはわからないよ!」
その時から娘は全てを失った。家族だけではなく、それを大切と想う自らさえも。
双子の少年は出ていった、と娘に突然伝えた母は、違う人になったような綺麗な笑顔で。それから度々、怖い悪魔達を娘に見舞わせるようになった。
――いいことを思い付いたの、ミスティル……あなたを自由にしてあげるから。
少年のことは何も語らず、戸惑う娘をよそに、母はそんな話しかしなくなった。
何一つ真実を知らされなかった娘は、いつしか少年も母も、心の何処かで恨み始める。
――そんなこと、思っちゃダメ……誰も悪くなんて、ない……。
その双子とずっと一緒にはいられないことは――姉を自負する娘はわかっていた。
――お母様は、ラティちゃんに後を継いでもらいたいと思ってるよ?
少年はいつか、一人立ちする。邪魔をしてはいけない、少年には幸せになってほしい。
だからこれで良かったのだと……そう願い切れない自身を、娘は呪う。少年と母を恨んでしまう自分を責め続けていく。
それが当然の感情と、娘は知らなかった。あまりに娘は、狭い世界にいたのだから。
一人ぼっちだった娘は、母の願いを聴いた悪魔にその後、魂を奪われる。
娘自身も願ってしまった。その呪いから逃げられるなら、たとえそれが――
「……それが、お母さんとのお別れが条件でも、構いませんか?」
娘を見舞い続けていた、赤い道化師がそう言って笑う。
他の悪魔と協力し、色んな千族を滅ぼしている悪魔。母はそれを知っていたはずだが、最後まで娘には何も言わなかった。
「それでは貴女を、可愛いオモチャに生まれ変わらせてあげますよ。大丈夫、今の記憶は全て無くなり、人形として楽しく生きられるようになりますからね」
そうして娘の本来の体も、実の母の手で短い役目を終えさせられる。
暗闇を逃げ惑う娘。ずっと追いかけながら、少年は何も言うことができない。
娘の闇を少年は知らない。まっすぐな少年には理解できないことかもしれない。
だから赤い道化師は改めて――それらの望みを、両方に尋ねる。
「君達は……ずっと一緒にいたいんですか?」
その問いに、答えてはいけない――……しかし彼の声はそこまで届かず、少年と娘は、それぞれの思いを悪魔に曝け出してしまう。
「……ラスト君は可愛いですから、叶えてあげちゃいましょう」
そこで微笑んだ道化師の顔は……その色は紛れもなく、金髪の男を殺した赤い人影で。
そして涙の雫のような化粧を左頬に施す、彼も見知った誰かであり……。
「その不出来な命――大事にするがいい」
何処からともなく剣を抜いたそれは、一瞬で悪魔の顔へと変貌していく。
次の瞬間再び舞台は暗転し、赤い点滅を繰り返した後、ようやく暗闇が徐々に解け出していく。彼が通常の視界を取り戻した時には、そこには、血まみれの少年が横たわっていた。
左肩を止めどない赤色で染め、こみ上げる血が絡んで溺れそうな喉で。
畜生――とだけ呟いた少年を、抱き起こした彼は、必死の形相で呼びかけるしかなかった。
「ラスト……!?」
激しく紫苑の目を歪める少年の視線の先で、四天王が、壊れた人形を両手で抱えている。
血も出ない首を分断され、胸の上に乗せられた紫苑の娘。それを悔しげに見下ろす四天王に、ただ、憎しみの呻きを漏らした少年だった。
「ちく、しょぉぉ……ミ、ティ……――!」
仇を凝視し、少年の左肩から全身が赤く染まる。止められないその侵蝕に彼はすぐに気が付いていた。
少年を染めるのは、一度呑まれてしまえば取り返しのつかない、真っ赤な憎悪の鼓動だった。
まるで彼が、赤い獣と共に持って生まれたあの呪いのように。
「駄目だ、眠るな! 薬草くらい持ってるだろ、出せ、ラスト!」
その肩をとにかく止血する彼に、少年は最後に何とか、彼を案じる声を口にしていた。
「るせー……兄ちゃんは、にげ……――……」
そうして少年の意識が落ちた直後に。この島に来た時に少年が言ったことが彼の脳裏をよぎる。
――自分の身は自分で守る。何かあれば自分だけ逃げる!
以前も少年は同じことを言い、彼らを逃して一人で捕まった。
この少年のその言葉は、少年に何かあっても逃げろ、という前言なのだ。
「……!!」
気を失った少年の言が妥当と示すように、少年を抱えて座り込む彼に、四天王の水矢が八方から襲いかかる。
場には、人形を抱える四天王、彼と少年。そして黒い彼女が中間にいて、何故か従者の女の亡骸は消え、赤い人影も何処にも見当たらない。
「力」を消す短刀で断つにも、あの水矢は硬過ぎる。彼らを守れるものは何も存在しない。
顔を顰めた黒い彼女もどうにもできずに、彼と少年は貫かれるしかないのだろう。
もしもそこが、元々結界の半開放部で――赤い人影に蹂躙された跡地でなければ。
「……おや……?」
四天王がとても不思議そうな顔付きで、目前に展開された異様な光景を、黒い彼女越しにまじまじと眺めていた。
「あれは、先日の飛竜……? しかし随分、姿が薄いですが……」
彼と紫苑の少年を庇うように覆い、四天王の水の矢を全て防ぐ――吸収したかのような灰色の獣。四天王も黒い彼女も、あまりの想定外に息を呑んでいた。
彼にはそれは、「力」の「無意味」化を諦めた、ただの悪あがきだった。
「……これなら……防げる……!」
力を「力」にするための熱。赤い右腕を失い、冷え切ってしまった自らの飛竜。
どんな「力」にも熱は存在する。「力」の原料となる力は、その熱で「力」となるのだ。だから熱を奪えば、完全な無効化は無理でも、勢いは霊獣という「力」で弾き得る威力に落ちる。
「飛竜でも使える――色を抜いたら、熱も奪える……!」
その熱も「力」の一部のため、彼の特技は違う形で功を奏したわけだった。
それも右足の無い飛竜は、右手だけで介入する彼と違い、全身で介入を可能としていた。
詳細はわからずとも、「力」による攻撃は無駄と四天王も悟ったらしい。
「まいりましたね。私は『力』しか攻撃手段がありませんからね」
紫苑の娘だった人形を、奈落に捨ててまで追撃を行うが、堅固な飛竜を貫きはできなかった。
少年を守り続ける彼を、四天王はあくまで始末したがっていた。
「仕方ありません。キニス、彼らにとどめを刺しなさい」
場の暗転の時から動かなかった黒い彼女に、当然のように命じる。
彼女なら簡単に彼らを殺せるだろう。その空ろさを知るだろう四天王に……その前に彼女は、そっと歩み寄った。
「できません。というより、その必要はありません」
四天王を見つめた彼女はおかしなことを、爽涼に即答したのだった。
四天王は酷く、失望した顔で問いかけていた。
「……私を裏切るんですか? キニス」
「いいえ。そんなことは無理って、貴方は知っています」
ふわりと微笑んだ彼女に、改めて四天王が眉をひそめる。
「……貴女が私に、笑いかけたのは初めてですね」
そう言えば四天王と黒い彼女が、まともに話をしている所を彼は初めて見た。その二人の間には虚ろな空気しか無かったことを思い出した。
その青白い微笑みはあまりに遠く……そして月光のように、淡く綺麗だった。
「貴方があたしを信じたことなんてない。この先も、信じることはない」
だから自分が裏切るのは不可能なのだ、と、彼女が軟らかな微笑と声色で告げる。
「それでもあたしはここにいます……何処にも行きません」
そうしてがらんと槍を落とし、空いた手は旗袍の下の方に当てて、戦う気はないと体で示す。
四天王の、次の声はただ、哀惜に満ちたものだった。
「貴女はやはり……とても可愛いヒトですね、キニス」
だから彼は、そこで何が起こったのか、咄嗟に理解できなかった。
そもそもそんなことが起こり得ると、失念していたとしか言えなかった。
魔性の男は彼女に強い執着を視せていたから……その抜け殻すらも、無理に動かすほどに。
……四天王の足元に、すっと膝を折った彼女が、静かに崩れ落ちていった。
「……――え?」
「力」の発動はほとんど無かった。警戒もできないほどの微量な力。
しかし彼が飛竜越しに見た先には、真っ赤に染まる肉塊を掴んだ四天王の左手と――
流れ出す血で自らをひたす彼女という、有ってはいけない光景が広がっていた。
下15:玄 -魔竜-

その悲しげな玄い魔物には、忘れることのできない、怖い夢があった。
何度もそれは、脆弱な己の記憶と共に、怖れを全て取り除けられながら――
取り除けるのも自身だから、忘れているはずなど本当はなかったのだ。
――アフィちゃんは不思議な石を持ってるから、刺激してみるんだって。
囚われた悪魔の城の研究棟で、最上階の一室に横たえられて、眠り続けていたもの。
青く長い髪と目の魔物は、首元に光る青い宝石――「逆鱗」という「力」の制御装置を活性化され、それに封じられた怖い夢を、繰り返し見せられながら静かに横たわる。
――怖い夢――……また見たのか?
いくら見せられたところで、「逆鱗」は優しい記憶も、そうして映し出してくれる。
長く住んでいた妖精の森でも、そんな日が来た時は、と何度も仮想体験をさせられたから、魔物は己を失わないで眠っていられる。
もしもその怖い夢が――それが今宵、本当に起きてしまう惨劇でなかったのなら。
「――あ……――」
ざわり、と背中の下で逆立つ、下ろされた長い髪は空色……夜空のように光無き玄へ。
唐突に見開かれた目の青も同様に暗まり、そこに紅い光を乗せて青白へと変わる。
その目が映していたもの。それは魔物の命が終わる怖い夢が、実現された片割月の夜。
魔物と共に、一つの体に生まれようとした黒い彼女は、たった今、死出の旅路についた。
私はね、と。魔物になるはずだった黒い彼女を、ごっそりお腹を削り取って退治した魔性の男が、最後に愛しい相手に餞別の言葉をかける。
「私はね、キニス……私のものにならない貴女は、目障りなんです」
声の甘さとは裏腹に、足元に転がる彼女を、ごろんと魔性の男が蹴りつける。
それを遠くで見ていた灰色の獣……その「力」に守られる灰色の髪と眼の彼は、瞬時に理性を忘れたようだった。
「けれど貴女を、違う所へやるのも嫌ですから……それならこうするしかありませんね」
転がした彼女を、血まみれとは逆の手で魔性の男が担ぎ上げる。
灰色の彼は、それまで守っていた少年を灰色の獣に委ね、必死に駆け出していた。
「貴様――……!!」
魔性の男が向かった先は、ぽっかり口を開ける地獄のゴミ捨て場だ。だから灰色の彼がとても、鬼のような顔をするのは当たり前だった。
彼は彼女が大切なのだと、彼の連れ合いである魔物は知っていた。
そもそも魔物は、彼女になるはずだった。彼女は黒かった魔物を連れて、彼の近くに共に生まれよう、と言ってくれたのだから。
ずっと一人で、何かを待っていた竜の墓場の魔物。
守りたかった約束があった。だから魔物になってまで、一人でそこで待ち続けていた。
――……先に行って。わたしもすぐ追いかけるから。
大切な何かを探して、魔物は待っていた。それさえ見つかれば、潮騒に消えた彼の元に行ける。
追いかけると約束したのに、彼を一人にしたのは魔物の方だった。彼の絶望――赤い鼓動を知る魔物は、必ず彼に会いに行くと決めていた。
だから魔物は、黒い彼女になることをやめた。
黒い彼女はこの夜……彼を置いていってしまうから。
「……ゴメン、なさい……」
嘆く魔物は、あまりに身勝手だった。その夢を怖れなければ、魔物は黒い己を置き去りにしてまで、青い雷雲の元に玄く生まれることはなかった。
――大丈夫だよ。そうすればみんながまた会えるんだから。
そうして黒く染まった白い彼女に、玄い魔物は自身が受けるべき災厄を押し付けたのだ。
異端者としての孤立も、全てを奪われる運命も、再び出会うための苦境までも。
時は満ち、外の世界に出た魔物は焦がれた彼の隣を、そこに在るべき黒い己から奪う。
――あの日……夢を見て、アナタのこと、見つけたの……。
彼も待っていたはずだった。玄い魔物と白黒の彼女、いったいどちらが彼の失くしたもので、本当に必要とされているのか、今ではわからなくなってしまったが。
僅かな時間、黒煙に侵された髪は、魔物の流涙を受けてすぐ空の青に戻る。
髪の代わりに魔物の周囲を悲しげに染め上げ、玄く震わせる悲痛な泣き声が上がる。
その有り得ない空間の揺らぎを、魑魅魍魎である研究者達は驚愕と共に探知し、慌てて避難所でもある奈落へ逃げ込み――
階下の部屋で研究材料とされていた連れ合い。竜の巫女と言われる空色の娘に、何が起こっているかを彼は知らない。
彼の背中を硬く踏みつけ、半身の欠けた月の下で、魔性の男が歪んだ微笑みを醜悪にたたえていた。
「無様ですね。君はあの、謎の召喚士を助けに来たんじゃなかったんですか?」
男の生来の雅さは消え、彼を見下げる澱んだ碧の眼には、憎悪の感情だけが宿る。
「っ――……!!」
抵抗できない彼は、男の手で暗黒の内へ捨てられた彼女を何とか掴んだ右手を、決して離すまい、と強く握り締めた。
奈落に身を乗り出す形で、意識の無い彼女の手を取った彼を、四天王が強く足蹴にする。空いた右手に持った彼女の槍で、彼の背を何度も何度も――急所を外して貫いてきた。
「今は殺してあげませんよ。キニスの後を追わせたくないですからね」
「力」だけ防御できる密度の飛竜は、意識の無い少年を守らせるしかない。ここで抵抗のため実体化を行えば少年が手薄になり、彼女の手も離してしまう。それをわかっているだろう相手のいたぶりに、彼は耐えることしかできない。
彼女をそうした形でまでも利用し、四天王が彼に激しい感情を向ける理由が、もしも言葉通りであるとすれば、何と滑稽な事態なのだろう。
「ここまで思い通りにならない相手は初めてですよ。せめて彼女が君を望めば、君だけを殺してこんな苛立ちも治まったでしょうに」
……彼女はあくまで、四天王のそばにいると言った。
その目はずっと余所を見ながら、自身を最も望むものを映す答は空ろでしかなく。
「君の大切なものも奪ってやりましょうか。どうせあの珠玉は使えなさそうですしね――」
このまま耐え続ければ、連れ合いを助けにいく力が残ってくれない。
眼下で目を閉じる黒い彼女は、血を流し過ぎて、既にほとんど色が消え去っている。死んだも同然だとわかっているが、それでも彼は手を離すことができなかった。
そんな彼の諦めの悪さを、叶わぬ望みなら自ら断ち切る魔性の男は、憮然と嘲笑する。
「それでは、そろそろお別れです……キニス」
そうして実りなき激情をぶつけることに飽きたのか、男が以前の優雅さに戻って微笑む。
やがてゆっくりと、忍び続けた彼の最後の願いを閉ざすように――
振り上げた黒い槍で、彼女の手を掴む彼の右手を貫き、その義手をぐるりと抉った。
「っあああああ――……!!」
本物の腕が斬り落とされる以上の、彼の全存在を否定する痛み。それが、無力にされた腕を連れる彼女を闇へ堕とし、希みを消してしまったのだった。
その結果は、わかりきっていた。
この状況で抗う余地はないことも――
そもそも彼の故郷が無くなった時から、彼女はとっくにいなくなっていたことも。
鋭敏な痛みを感じる義手を断たれ、這い蹲った彼は、黒い彼女が消えてすぐに一蹴りで仰向かされた。左腕を踏んで胸上をとった魔性の男に、片手だけで首をきつく絞められる。
この暗夜から逃れる術のない彼の苦悶。魔物は真下の昏い空間で、それを全て感じ取っていく。
揺らめく玄い大気の中心で、哀鳴を絞る魔物が胸を激しく掻き毟る。
その直上の青い宝石はあまりに熱く、それが取り除けていた悪夢が一息に曝され、魔物が存在する空間が慟哭で満たされる。
四天王の空いた右手だけで、呼吸を全て閉ざされた彼は、意識を保つことだけに全力を傾けていた。
「君ももれなく、私の部下として再利用してあげます。早く楽になったらいかがですか?」
「――……!!」
そうして彼の魂をも蹂躙しようとする悪魔は、守りの無い彼をいつでも殺すことができる。
飛竜に守られる少年を置いて、「力」で抵抗するしかない。でないと連れ合いどころか、ここで彼が落ちれば少年も助けられない。
しかし現実はいつもこうして、ろくでもない選択肢ばかりを彼らに提示する。
「抵抗すれば当然、ミストの片割れはすぐに殺します。二人で私の軍門に下りなさい」
「っ――……!」
彼も魔物も、形は違えど、その闇路が見えていた。彼は常に現世の色を追い、魔物は悪い夢を負っていた。
それが視えることこそ彼の呪いで、また、さまよい続ける魔物の迷いだった。
――おれは信じへん。あいつがもういないなんて。
悪友のように、心からそう思えたら、彼もどれだけ良かっただろう。
運命の分かれ道を、眼前に突き付けられるまで、彼も魔物も認めなかった。何故ならそれが、夢でない証も無かったからだ。
「力」が視える彼。それを扱う「心」がわかり、だから現実がわかってしまう彼。
運命を識る魔物。それを教える悪い夢の、実際の到来に怯える魔物。
そんな与太話を、誰より信じたくないのは当人だった。彼と魔物を縛り続けた敵は彼ら自身なのだ。
夢なら良かった。どれだけ小さな希望でも、否定する権利が誰にあるだろうか。
暗闇なんて何処にも、いくらでも転がっている。わざわざそれを見ようとしなくても。
だから時に――暗闇そのものがヒトを救うこともあると、彼は知ることになる。
「……――!?」
真下からの異常な「力」の到来を、誰より先に感じた彼は、ある蜘蛛の糸を思い出した。
咄嗟に、その命綱をしまった腰の道具袋に寸断された手をやる。直後に魔性の男の背中に、病魔の如き「力」の介入を彼は叩き込んだ。
「な――!? が、ぁあああっっ!?」
「水」の男に無理やり混ぜた、彼の「火」の気。それを可能にさせたのは、連れ合いが残していった古い方の義手――装着だけなら自動で腕の断端に合わせてくっついてくれる、彼の成長に対応できるように造られた以前の右手だ。
――確かに、予備があるのは心強いな。
奈落に失った義手――強度を重視した方は、そうした迅速な接合は不可能だった。
しかしこちらの、男の不意をつける速さで再起した右手は、更にありったけの「気」をぶつけて男を弾き飛ばした。
何とか自由になった身で、咳込みながら立ち上がった彼は、足元から膨れ上がるような強大な「力」を改めて感じ取った。
慌てて少年の元に戻り、その「力」の主の名を叫ぶ。
「アフィ……!?」
少年を抱え、彼らを守らせる飛竜の懐に入ったのは本当にぎりぎりのタイミングで。
やっと異変に気付いた四天王も、本邸の扉に飛び込むように結界の内に逃げた瞬間――
初めの産声は、自らを束縛する密室の破壊を。
次の気息で、その棟に張り巡る強固な結界の消失。
続く啼泣が上層の大半を噴き飛ばし……辛うじて残る、屋根の端にいた彼と少年の前に。
その魔物……悲しげな玄い「力」に包まれた魔竜の巫女が、ゆらりと顕現していた。
息を呑む彼の眼の先、玄い魔物が、渦巻く夜をさらに虚無へと染め上げていく。
強過ぎる「力」の余波で、魔力耐性付きの服が所々引き裂かれた玄い魔物。昏い半月の下で、長い髪を数多の蛇のように、ふわりとざわめかせている。
天上より上が消失し、設備もことごとく破損した最上階で、罅だらけで崩れ落ちそうな床の上に無表情に立つ連れ合い。胡乱な青白の目は、何処を見つめているのかもわからなかった。
彼の横に、所狭しと悪友が降り立っていた。
「――うぉあぁ!? 何やこれ、どうなっとるんやいったい!?」
眼下の魔物の凄まじい姿に、言葉の無かった彼より先に驚愕の声を上げる。
「さっきファーが王女さん確保したから、後はオマエらだけやで! アフィとアシューはどーなってん、レイアス!?」
同郷の女を船に預けた悪友は、緊急退避警報で警備が手薄になった隙に王女を連れ出した黒髪の騎士と、城の外で会ったらしい。
騎士と王女、翡翠の髪の少女を船に向かわせ、東館の結界が消えたので彼の元に来れたようだが……。
「――今すぐラストを連れて逃げろ、タツク!」
「はぁ!? ってラスト、これクソやばいな!?」
重傷の少年を突然押し付けられた悪友は大慌てで、少年に負荷の少ない体勢で横抱きする。
しかし状況をきく猶予はなく、ゆるりと空を見た魔物の号泣――大気をも切り裂く黒い衝撃の第二波が、逃げる暇も無い彼らを襲った。
「おあああ!?」
黒刃が届かない場所が視える彼は、少年を抱えた悪友を城の外側に突き落とした。
「先にディアルスに戻れ、ラストを助けろ! 俺は後でアフィと戻るから……!」
彼自身は飛竜に守られて難を逃れながら、完全に吹き飛んだ屋根の足場を失い、連れ合いだった魔物のいる階下に瓦礫と共に落とされていく。
何処まで悪友に言葉が届いたかわからないが、紫苑の少年の傷の深さや、この島に仲間が留まる危険を考えると、彼と連れ合いを待てとは言えなかった。
奈落すら消し飛び、鋭利に切り裂かれた鉄骨と石壁に彼は埋もれる。
起き上がっただけでも、全身を尖鋭に分断されるだろう玄い空気が満ち溢れていた。
圧倒的な力から身を守るため、人体ほどの大きさで透明にした飛竜を背に、翼で前を守る急拵えの防壁を纏う。そうして危険な大気中で、彼は何とか立ち上がった。
「アフィ……! アフィなんだろ――!?」
壁も天井も無く、夜空に曝された最上階の玄い場の中心で、両手で顔を覆った魔物。
首元には青い宝石を玄く光らせる連れ合いに、彼はとにかく必死に叫びかけた。
「……――」
彼の声に、連れ合いがびくっと体を震わせる。
それと同時に玄い衝撃の第三波を、全方向に無言で無遠慮に放っていた。
「っ――!?」
「力」の中心の魔物、連れ合いに近付こうとすればするほど、玄い空気が濃くなっていく。
これ以上近付けば飛竜でも防げないと、彼は声を張り上げるしかできなかった。
「聞こえないのかアフィ! 『力』を止めろ、こっちを見てくれ!」
「――…………!」
彼がそうして、呼びかければ呼びかけるほどに。
連れ合いを包む空気はますます玄まり、その色柄は悲哀としか言えなかった。
涙に暮れるように顔を覆ったままの魔物が、全身から玄い瘴気を立ち昇らせ続ける。
「……ちがう――……」
ようやく発した声と同時に、ついにこの場の床も崩壊し、彼らはさらに下の階に落ちる。
四天王すらおそらく、手出しできないほどの「力」の中で、魔物は泣訴の刃を発し続ける。
「私……そんな名前じゃ、ない……」
今も魔物を呼び続ける灰色の彼に。その彼こそが、魔物の悲しみの因と言うように……。
「アナタを追いかけてきたのに……アナタは何も、私を知らない……――」
かつて魔物が、果たせなかった約束。封じられた渇望と共に、魔物はその白眼を開ける。
顔を覆う両手を胸元まで下ろした魔物は、落ちた床に膝をつく傷だらけの彼を見ずに、自らに深く爪を突き立てている。青白い両目からは、止めどない紅涙がこぼれ続けていた。
「私、わかってた……でもどうしても会いたかった、守りたかった……――!」
「……ア、フィ……?」
飛竜による「力」の消熱も、さすがにもう限界だった。
これまでの負傷で意識が朦朧とする彼は、連れ合いの声を聴くだけで精一杯だった。
「こんなに奪って、なのに守れない……!! 大切はどれ――……誰がわたし……!?」
それでも間近に迫った危機に、再装着したばかりのぎこちない右腕を、彼は厳と握り締める。
彼に痛いほど伝わったのは、初めて会った時に、そうして泣いた彼女の涙の意味だった。
――やっと会えたよ、兄さん……!
彼に似ているという、蒼い目の兄。魔物だけでなく、白黒猫にも出会っていたという悪魔のあの伝言。
――俺に似せられた奴を探す、それの何処が悪いんだよ?
「見つからないの――わからないの、私、どうすればいいの……!」
連れ合いはいったい、これ以上何を探しているというのか。
それがわからない彼をこそ、責めるような嘆きが止まらない。混乱する自らを、連れ合いも止めることができないのだろう。
「誰もいない、私のせいで……! アナタもいない、もういないから……!」
魔物となってまで守ろうとしたものが、そこにはあったはずだ。それを何一つ、本当の形では得られずに、他者から奪うことだけが続いていく。
彼の眼には、連れ合いの混沌の涙はそう映った。
魔物ではなく、今を生きる連れ合いの方は、大切な仲間の黒い彼女を犠牲にする……居場所を奪いたいわけではなかったのだ。
そんな身勝手な齟齬の痛みを、誰に向ければいいのだろう、と――
最早空間ごと、ひたすら崩れゆく場に、彼の焦燥もここで頂点を極めつつあった。
無論、四天王の城が崩壊していく様など、彼には全く知ったことではない。
しかしこの強固な結界もろとも、城を吹き飛ばす「力」の爆走が続けば、連れ合いの身がもたないことはすぐにわかった。
この玄い魔竜――大気ごと操る自然の脅威が、何の「力」かまでかはわからない。
けれども連れ合い自身は、「竜の眼」を持たない化け物。彼と大きく変わらない身上の千族なのだ。
――いつか消えるって――そりゃ、これじゃいつでも『力』に食い尽くされるぞ……!
そうして喚び降ろした竜。「力」を誰かに残して消える生贄が、巫女と呼ばれることも。
確かに彼は何も知らない。連れ合いが今、激しく彼女自身を呪うこと以外は。
だからその決断は……何一つ確信など無い彼の、無謀な賭けに過ぎなかった。
玄い光を発し続ける、連れ合いの首元の青い宝石。その石と同じ「力」を持つはずの、彼の古い義手に刻み込まれたもう一つの「逆鱗」。
「アフィ――……!!」
大切な誰かを新たな義手ごと失わなければ、この腕を再び付けることはなかった。
しかしそれも、消えゆく誰かが受け入れた暗闇の贈り物だったとすれば……――
……ばしん、と。飛竜でも消し切れない玄の中で、その音は瀕死の彼にも届いていた。
「……――、え……?」
青い髪と目の彼女が、放心するのも無理は無かった。
怒声一つ彼女に向けたことのない優しい彼が、全身を切り裂かれながら近付いてまで、彼女の白い頬を張ったのだから。
驚きの余りに見開かれた目が、彼の灰色の眼を映して、暗い青に戻る。
「あ……わた、し……――……」
彼の右手の平に、かつて焼き付けられた「逆鱗」の刻印。それを何とか彼女の頬に、「力」をいじる彼の特技で、彼女に命――「心」を奪われゆくからこそ、遷せた彼だった。
「わたし――……レイアスに、なんて、こと――……」
そうして連れ合いに植え込んだ、別の「逆鱗」の効果だろう。玄い光を発する胸元の「逆鱗」を、頬の刻印がどうにか抑え込んでくれた。
「……俺こそごめん。大事なヒトに手を上げるなんて――最低だ」
首の宝石を押えて立ち尽くす彼女を、やっと彼は、愛しく抱きしめる。そのまま拙く、心から笑った。
「怖い夢を見たんだろ。もう大丈夫だから……一緒に帰ろう」
それがたとえ――彼を追いかけてきた魔物が、求めた答ではなかったとしても。
この現世で出会った彼と彼女が、確かに結んだ大切な絆を、もう一度口にする。
「魔物でいいから……ここに、いてくれ」
その答を出してくれたのは、いつかの幼馴染みだった。
――誰かが、見ててあげないと。
彼のことを想いながら、幼馴染みは彼女をも想い、全員のためにそう答えた。
あの時彼は、幼馴染みを放っておけない……そばにいたい、と伝えていたのに。
既にずっと、暗闇にいた幼馴染み。彼の隣を、魔物が奪ったのではない……自ら譲ったのだ。
それはおそらく、ある痛みを知るが故に。
――あたしも、捨てたもんじゃないかな……。
そして彼も、自身の意思でその運命に応えた。そのことを魔物に伝えてやりたかった。
己の業を呪うあまり、自滅せんとする魔物の青白い目を、きっと彼らは知っていた。
「……ゴメンなさい……」
……わたし、子供みたい。ここに生まれた者の声で、空色の彼女が涙混じりに微笑む。
彼もそれに、赤まみれの醜い体で微笑み返す。微笑むことしかできない透明な青の目に、精一杯の心を渡す。
その日彼らが、やっと真に出会ったことを――
昏い片割月の夜光だけが、儚く映し出していたのだった。
下:終幕

北の四天王が替わった、と、噂が流れ始めた頃に――
不思議な桜色の娘に、彼は出会った。
その娘は彼が三年前に、空色の連れ合いと大きく破壊した城で生まれた者で。
「……ひょっとして、アナタ……みえてるの……?」
「――ん? どうしたんだ、サキ?」
彼を見て呟いた後、あどけない娘が、長い桜色の髪を揺らして悪友の後ろに隠れる。
それは悪友が、再び殴り込んだらしい北の四天王城で保護した娘だという。
悪友がディアルスに構えた家の、ゆったりとした応接間で。
びっくりだね、と、彼の隣に座る連れ合いが微笑んでいた。
「北の四天王の噂は聞いてたけど……タツクも関わってたんだね」
「……それ、本当なのか? 人間とハーフの吸血鬼が、新しい四天王って話も」
四天王は本来、魔王という最上の悪魔の下僕と言われる。その魔王が直々に認めた、謎の銀髪の吸血鬼……世襲とは関係の無い魔物が、北の四天王を打ち破ったと、ある活動を続ける彼らは情報を得ていた。
「おれは凄い美女さんの討ち入りに、便乗しただけやけどな。里の仲間も保護できたし、たまたま見つけたサキも連れてくの許してくれて、太っ腹やで、あの吸血鬼さん」
「……それでも、今後は敵になるだろ?」
「せやなぁー。何たってここの王女さん直属の、『反魔王派』やもんな、おれ達はなぁ」
不穏な動きを続ける四天王や魔王といった神威に、本来対抗すべきは「守護者」という天の者だ。
しかしたった四人のその手が届かない地は多く、ディアルスでは彼らを軸に、反魔王活動を推進している。守護者を探し、後押しするための情報集めや、関係者の保護が主な内容だ。
その契機となった、四天王によるディアルス王女誘拐。彼と連れ合いも巻き込まれた事変は、それを乗り越えてからは驚くほどに平穏が戻ってきていた。
その時四天王の城に残っていた彼が、先に逃げろと言ったにも関わらずに、この王女はとんでもない判断を下していた。
「待ってるどころか、総攻撃に入るような王女だもんな……おかげで助かったけど」
そうして王女は、人間である己の唯一の魔法の「力」――竜の遺産という「炎」の珠玉で起こした流星火を、憤怒の発散とばかり何十も四天王の城に叩き込んだ。
妖精の魔女も敵わない威力という火弾のドサクサで、彼と連れ合いも何とか逃げおおせることができたわけだった。
「サキはセイレーネに預けなかったの? タツク」
つい先日、四天王の城に残った霊獣族の者を、悪友は助けに戻ったという。仲間を世話する同郷の女に、桜色の娘以外は引き渡したとのことだった。
「それがな。サキは確かに霊獣族なんやけど、仲間の子供でもないみたいやねん」
その娘は猫型の霊獣を連れ、今では悪友をお父さんと呼んで慕っていた。
「ま、あの顔見ればわかる思うけどな……色々複雑やけど、可愛がったってくれ」
「……」
黙り込む彼らの理由は、その娘が、ある仲間によく似た面差しなことにあった。
まずもって不思議なのは、三年前は存在していなかった娘が、現在既に九歳ほどの年齢であることだ。彼にはその不自然な存在の真実も、悪友が説明せずとも、彩の無い眼であらかた視えていた。
だからおそらく、彼と似た薄い色の眼の娘は、初対面では彼を怖がったのだろう。この少し後に彼は知ることになる。
「ところでラストはどないしとんねん? 晴れ時々虚弱人のくせ、相変わらず旅三昧か?」
悪友が言う青年は、今年で十六歳になる。三年前の事変で左肩に受けた赤い傷が度々痛み、その浸蝕は命を削る呪いだと、青年を既の所で助けた妖精の女は苦く言ったものだった。
「ああ。守護者も全員見つけて、それぞれ何とか戦ってるのを観察中だそうだ」
そんな状態でも世界各地を渡り歩き、戦う職人像も健在な何でも屋に、彼らは揃って苦笑う。
「アイツ、緋桐とは結局どーやねん? てーかナナハとも良い仲やって噂聞いたで?」
「タツク……まだラスト、十六歳だよ?」
「甘いな、アフィ! たらしは何歳からでも関係ないねんで!」
「……確かに軽く見えるけど、アイツ一途だぞ、実際」
彼はその紫苑の青年が今も、失った双子の妹を引きずっていると知っている。
明らかにそのために生き急いでいて、それは反魔王活動以外の大きな心配事の一つだったが……彼自身の生活は現在、すっかり落ち着いたと言って良かった。
故郷の生き残りや、悪友までがディアルスに家を持っていたが。彼と連れ合いは相変わらず、紫苑の青年と同様、特定の住居と仕事を持っていない。
ディアルスにいる時は王城の兵舎で兵士達の教官をして、用事や王女の要請があれば、見知らぬ地でも旅に出る放浪ぶりだった。
その行く先で面倒な事件に巻き込まれる場合も、少なくはなかったが――
「三年前に比べたら、大したことないな」
黙々とそうして仕事をこなす彼は、滅多なことでは動じなくなっていた。
そして連れ合いも、普段は見えない「逆鱗」を頬に刻んだことで、自然の「力」を召喚の大技だけでなく魔法レベルで使えるようになり、己の身は守れる千族になっていた。
そんな彼らも、その桜色の娘の出現には久々の動揺を感じてしまった。
「旧北方四天王の奴……本当、ろくでもないな……」
今日は悪友の家に、連れ合い共々泊めてもらうことにした彼だった。
連れ合いは何故か、悪友が保護した桜色の娘と一緒の部屋がいい、と強く希望し、彼は一人、応接間のソファに陣取っていた。
ゆっくりと羽を伸ばしながら、思い出したくもない相手のことを、苦々しげに呟く。
「それなら殺すなっていうんだ……そこまでアシューを、気に入ってたなら……」
彼が失くした白灰の髪の幼馴染みに、顔立ちが似た桜色の娘。
鎖骨までのまっすぐな桜色の髪は、前開きの白い武闘服に慎ましく映えている。何かと筋が良いと言う娘に、悪友は現在、得意の武術を仕込んでいる最中らしい。
しかし何の因果か、滅んだはずの霊獣族の血をひいた、謎の娘のその「力」は……。
初対面での第一印象は、とても眼が信じられない。の一言だった。
――……バステト……?
その娘が連れているのは、「ヴァシュカ」と名付けた、灰色の霊体の猫だ。
山猫サイズのそれは、彼が視知った猫の白黒を混ぜて、影を投げたような灰色で……。
ちょうどそうして、彼が娘のことを強く考え始めたその時だった。
「……――え?」
「…………」
夜中に一人、明かりもつけずに仰向けでぼやいていた彼。それを廊下から、光が漏れる扉の陰で窺うように、桜色の娘が薄い色の眼で見つめていた。
「……どうしたんだ? サキ」
怯えさせてしまったことを知っている彼は、それでも姿を見せてくれた娘へ、意識して微かな笑顔を作る。
連れ合いはもう眠ったのだろうが、娘とどんな話をしたのだろう。それも少し気になっていた。
「…………」
彼を窺う娘が、纏っている「力」。それが彼には視えると娘はわかって、彼を気にしているのだろう。
何故なら娘も彼と同じ彩、灰に近い桜色の眼を持つがために。
彼がその気になって、「力」の色に介入する特技を使えば、娘の灰色猫を白黒猫に戻すことはできる気がした。
だから娘は、彼を警戒するのかもしれない。
娘自身は何一つ記憶がなく、この邂逅の意味は明かさなくていい。彼はおそらく、最後の未練を一人で静かに断ち切っていく。
……あのね、と。桜色の娘が、伝えずにいられなかったらしいことをそっと口にした。
「……あのね。初めの家の、ぬいぐるみの珠の中に、小さな女の子がいるの」
「――え?」
「アナタとアフィと……凄く似てたよ。だから……いつか会ったら、助けてあげて」
それは娘が生を受けた城で視つけ、手を差し伸べた――今も救いを待ち続けている、黒い珠玉に封じられた殺戮の天使で。
彼がその縁を知る日は、これから十五年も後のことになるが……。
白黒猫によく似たお節介な娘に、彼はすっかり毒気を抜かれて、改めて拙く微笑む。
有り難う、と言った彼にはにかんだ娘は、よく視れば幼馴染みとはそんなに似ておらず。
暗がりの中、彼は穏やかに笑い、その桜色の娘にお休みを告げると――
やっと、旧い想いと決別できた彼に。
薄明るい廊下から、ごめんね、と聴こえた気がした。
+++++
了

空色の髪のキレイなヒトが、わたしを一目見て嬉しそうに笑った。
「……やっと会えたね。あなたは私のこと、覚えてた?」
それでわたしもすぐにわかった。このヒトは、「私」を呼び起こそうとしてるって。
いつかみんなで会える。そう言ったのはどうやら私みたい。
わたしは何も思い出せない。でもこの青白い目のヒトが言うことはわかる気がする。
「私は知ってるよ。わたしには教えないけど、あなたはわたしの大切なヒト」
このヒトもきっとすぐに忘れる。夢を見る時だけが、このヒトが私でいる時間だと思う。
あたしにもいつか、「私」の言う通り出会うのかもしれない。
わたし達はみんな、同じ空の獣と結ばれたもの……このヒトも「私」もそうやって言う。
そして私は、いつかどちらも消えるんだ、と何となくわかった。
「……それは嘘だよ……だって、わたしは――……」
私は魔物になっていく。運命を捻じ曲げるためにここに顕れた、反則の造花だから――
キレイに咲いた私達を、わたしが視つけ出す日は、その内訪れるんだろう。
+++++
Cry per A. -arrestare-
千族化け物譚 C1下篇 『魔竜の巫女』
初稿:2016.4.21
改稿:2018.4.1~5.13
❖閑話:赤い道化と城の鼠❖

忍:
1.忍ぶこと。
2.そっと敵中に入り込む術。忍術。
3.忍びの者;敵陣・他家に忍び入って様子を探る者。忍者。スパイ。
4.忍び込みの窃盗。
C1 Cry/A. -arrestere- 雑話
+++++
write:2020.10.5-
+++++
磯鴫というのは、「海岸に住む渡り鳥」の名だ。「海」というものは天上を指す「空」と対を成し、魔の住処として語られることが多い。言葉通り本当に空が天で海が魔ではないのだが、天上の「地」の民だった両親は何故、彼にそんな名前をつけたのだろう。
空に在る五つの宝、「宝珠」にこの「宝界」は守られている。その宝を狙い続ける魔族の王のいる世界が「魔界」、魔海とも言い変えられる。
「……あれ。ディアルス王家に潜り込んだネズミ、イソシギ君じゃん」
「失礼だなぁ。せめてもちっと、大物っぽい喩えをしてくんない?」
一市民とはいえ、「地」に棲む天の鳥に生まれた彼は、人間の国「ディアルス」に難無く騎士として雇い入れられた。「地」が十年以上前に魔王の襲来で滅ぼされた時、魔王のお抱え忍軍団に捕らわれ、「枝木」の名でずっと魔王に仕えてきた鼠であるのに。
今日は彼が、現在潜入する「ディアルス」の海上に居る船にこっそりと来た。身を隠す魔道具の外套がばさばさと風を孕む。蛇のような形の船はディアルス王城を先日襲来した「小龍」といい、魔王の配下でこの世界の監視者、「北方四天王」が部下に造らせた物だ。彼の外套も同じ部下が造った高度な姿消しになる。
そこで彼を出迎えた白灰の髪で三つ編みの女は、最近突然北方四天王の寵姫となった千族だ。人の姿で人ならぬ力を持つ地上の化け物千族は、「魔の海を泳ぐ魚」と天の者には古来から蔑視されている。
船尾の柵に危うげに座る三つ編みの魚が、仮にも天の者だった鼠を嗤う。
「ここに来た時点でイソシギ君も小物でしょ。最近は音沙汰がなかったくせに」
違いねぇや。と、鼠になってしまった海の鳥は肩を竦める。
「もうとっくにディアルスに情が移ってるくせに。何しにきたの? 裏切者君」
この船が先日ディアルスを襲撃した際には、鼠は結局最後まで正体を明かさず、ディアルス側で戦った。
その闇をいともあっさり、目敏過ぎる白灰の魚は掘り起こす。
今も空に浮かぶ小さな島、「地」にいた天上の民は、様々な文化を狭い天空島に詰め込みひっそり生活していた。世界を巡る自然の「力」を、純粋な元素に戻す濾過機である「宝珠」。その「守護者」を番人と据えた、宝珠の祭壇が「地」だ。
けれど天上の鳥として、大きな「力」を持っているのは守護者の血筋だけだ。彼のような一般市民は、天上の鳥の証である赤い目以外めぼしい「力」をほとんど持っていない。
強いて言えば地上の化け物の千族より、天上の使いの天使のように、太陽という強大で便利な素材を力にできる丈夫さが取り柄だろう。
しかしそんな程度の有利さは、彼の仕える魔王勢力下では大して役に立たなかった。
彼と同じく「地」から捕らわれた両親を持ち、忍軍団で共に育った翡翠の色の髪と赤い目を持つ少女は、彼らが東の大陸で同じ隠れ里にいた修行時代に、常々それを嘆いていた。
「忍はどうして、闇に生きると相場が決まってるのかな、枝木。私達、ここにいても正直未来はないよね?」
「いやぁ、わかんないぜえ? おれも緋桐も確かに何の特技もないけど、この赤い目は最大限に生かすべきなんじゃねーの」
天上の聖火と言われる生粋の赤。できそこないのくすんだ赤なら沢山いるが、彼と少女はそれとは一線を画している。目の色だけなら「火」を司る南の四天王にも負けないほどの純度だ。
ふわふわ髪で小兎のような少女は彼より随分年下のくせに、昔から非情で理知的だった。
「天から見れば私達は裏切者だし、魔王様から見れば用途の限定された駒でしょ。使い捨てられるのは時間の問題なのに、枝木はいつも呑気だよね」
少女は決して、悪い待遇を受けた方ではない。諜報活動を優先する忍軍団は、化け物としてのレベルはそう高くなく、彼や少女程度の化け物でも上澄みにいられた。彼などいつか、この忍軍団の頭領になることを目指していたくらいなのだ。
彼は自分の分を弁えていた。「守護者」達のような強大さは望むべくもない渡り鳥だから、こうして捕らわれた以上は、魔王の鼠として活路を見出すしかない。それで言えば、まだしも上位でいられる忍軍団は最適の地に思えた。
でも同じ赤い目の少女は、やはり天上の鳥なのだろう。機会さえ訪れれば、とずっと離反のタイミングを窺っている。忍同士で大切な身内もいるというのに、「その方が面白いから」と、己の正統な居場所を探している。それは呪いのような冷静さだった。
魔は敵、そうインプットでもされてるんかねぇ、あれ。彼はそう思わずにいられなかったが、忍の者として仕事に出だしてからは、唯一の身内のような少女に会うことはほとんどなかった。
彼は化け物では早い方の成人認定で、十五の歳には人間だらけの西の大陸に遠征に出された。そこで「地」にいた幼い頃の隣人に会うとは思いもよらなかった。
「ええええ、まさか、ファー? お前、生きてたの? え、騎士団? 何それ、ツテがあるならおれも入れて?」
「……」
魔王勢力が襲来した際、「地」にいた者はほとんどそこで殺されたはずだ。生き残ったのは守護者の血筋か、捕らわれた者だけだと彼は思っていた。
「地」では北よりに住んでいた隣人は、それでなくても守護者不在の領域だったので絶対に死んでいる。それを生き残ったしぶとさなら、人間の国では必ず重宝される。
目論見通り、その隣人――赤眼の黒髪の騎士は、高潔な実力者として人間の王女に見初められた。
独断で騎士に化けた彼が報告に戻った際に、その判断も評価されて潜入継続を命じられる。
「いいなぁ、枝木は。私も潜入でここから自由になりたいな」
「まー待て、おれが頭領んなったら、緋桐もディアルスに配属してやっから。だから義兄弟でも蓮華を推してんじゃねぇよ、緋桐?」
忍軍団の次期頭領候補は、彼か少女の姉貴分だった。まだ里にいる少女が言う通り、人間の国で暮らせる身分は非常に貴重だ。
人間の国への潜入は役に立つか。世界中の情報を魔王は持っておきたい、その程度だろう。彼は「地」にいた幼い頃から雑学が好きで、世界情勢を見るのに向いた博識家だ。
ディアルスは残り少ない千族を集めている。監視の必要が増えることこそあれ、放置してよい国ではない。だから鼠の存在意義は不動だ。
ディアルスでの騎士生活は楽しい。彼を引き入れた黒髪の騎士が王女付きになったおかげで、彼まで王女の魔女付きになれた。
王女と相思相愛の黒髪の騎士とは違い、魔女は古い友達の兄が好きらしく、彼がアプローチをかけても拙く突っぱねる。しかし望みの少ない恋と見えて、仕事に生きる怜悧な魔女は、才女の見かけによらず隙だらけなことを彼は程無く悟る。
ある時突然、ディアルスに商談に来たと言って現れた忍軍団の支配人にも、鼠としての彼は己の有用性を報告する。
「でねー、主様? おれがディアルスの魔女さんを落とせたらば、おれをディシーヴの頭領に今度こそ推してくれます?」
「やだなー、私が主なんてぇー。それはそれとしてあの妖精殿は、使いどころが豊富そうなので、是非唾をつけておいて下さいねぇ?」
肩で括る真っ赤な髪に縞状の黒メッシュを入れ、頬に涙の滴のような化粧を施す、道化姿の黒衣の男。ディアルスではただの商人、ディシーヴ内では「南の四天王の部下」で通っている赤い髪の支配人だが、頭領候補で情報通の彼は赤い道化の正体を悟っていた。
「まーたまた、魔王様の息子さん並みに強い力のくせしてー。魔女さんに目をつけたのだって、アレが魔の女神の系統って気付いてるからっしょ?」
「あはははー、君もそんな与太話を信じる口ですか? 魔王様の息子さんとやらに殺されても知らないですからね~」
それは魔王の息子を知る者への警告。忍軍団など沢山ある手駒の一つに過ぎず、何故魔王の息子が南の四天王に仕え、また人間の国に来たのかはわからないが、その時が確実に彼の運命の分岐点だった。
「……まいったな、ありゃあ」
赤い道化。ディアルスを北の四天王の「小龍」が襲撃する少し前から、商人として城に滞在を始めた忍軍団の支配人。「小龍」の襲撃時、鼠がディアルス側で戦ったことは潜入者として当然だと咎められていないが、「小龍」の襲撃にはおそらく必ず支配人も関わっている。
「緋桐がまさか、北に派遣されてるとはねぇ……あいつ、主様に見られてねーだろうな、さすがにな……」
襲撃した「小龍」の兵には翡翠の髪の少女もいた。少女は途中で城の調査を任され、見られてはまずい行動に出ている。その間に城にいた千族の少年に裏切りの相談を持ちかけた、と後の通信で彼に明かしていた。
「主様、少年の近くにいたんだよなあ……見られてればとっくに、殺されてるはずだよな……」
忍というものは大体、同じような戒めの元にある集団だ。仕える組織には絶対服従、裏切者には死あるのみ。だから彼のように、潜入者です。という顔をして軍団に籍は置いたまま、のんびり遠くで暮らすのが一番マシな逃避法なのだ。
だから今、裏切りの予兆を見せ始めた翡翠の少女は、とても危うい位置にいる。少女も道化風のあの男がディシーヴ支配人であると知っているが、魔王の息子というほど危険な存在とは気付いておらず、道化の仮面にまんまと騙されている。
それでは彼も、道化の腹を探るには道化になるしかない。
「ねー、主様あ? おれキニスちゃん凄い好みなんだけど、おれも北に配属し直してもらっちゃダメ? ここにいても魔女さん鉄壁で落とせそうにないよー」
「はい? やだなあ、あれは北方さんの完全な趣味で寵姫ですよ~。ディシーヴ配下にするはずだったんですけど、残念でしたね?」
「小龍」の襲撃で統括を任されていた三つ編みの女。その挙動を彼が見たのは短い間だったが、彼はそこに同類の匂いを感じた。
魔の海に囚われた魚と、魔の手先になった鳥。だから彼は魔道具で身を隠してでも、危険を冒して女を訪ねる。
北方四天王の寵姫と言われながら、三つ編みの女の心は何処にもなかった。女は既に一度命を奪われ、魔物に近い空ろの化け物だったからだ。
求められた役割を果たしているだけの人形。その女が唯一持った願いは、かつて仲間だった者達を敵側で守る――北方四天王から辛くも遠ざける身中の虫になること。渡り鳥の名を持つ鼠にはよく理解できた。
身を隠して船にやってきた鼠に、女は警告する。
「それ、ここでも油断して脱がないようにね。この船ずっと、煩い鳥が監視してるから」
「ありゃりゃぁ。霊獣の奴らって本当、便利な『力』持ちなんねぇ、全く」
彼が本質的に、女が守りたい者達の敵ではないと、不思議に目敏い人形は見切っている。だから鼠に、人間の国でこのまま正体を隠し通せと言っている。
たった一言の警告で、その複雑な立ち位置を彼に解らせる女に、鼠はやはり同族嫌悪を禁じえなかった。
「それな。霊獣君達の大事な仲間のくせして、北方四天王の寵姫になった君が言えること?」
「……」
「この船ずっと見張ってる鳥も、君をひたすら心配してんじゃん? キニスちゃん」
何も選ばない。そう決めて自らを失った女を彼は知らない。知れば思ったことは一つだろう――それは子供騙しの欺瞞であると。
「それでも天秤にかけたんだろ。誰がより強く、キニスちゃんを求めてるかをさ」
別に彼は人形の女を責めに来たわけではない。それでも女の仲間達の嘆きを見ていると、四天王の船で敵として在るのが何故この女なのか、女の色無き瞳に改めて嫌気がさした。
「君でなくても良かったっしょ。と言ってもとっくに、手遅れなんだろうけどさ」
女が北方四天王の下でどんな扱いを受けているか、彼にはおおよそ見当がついている。だから翡翠の少女が北に派遣されているのも頭が痛い。
この船に来た目的は、人間の国の情報を流すのもさることながら、彼も襲撃側の情勢を把握するためだ。でなければとてもあの道化とは話ができないだろう。
だから女は、何故人形になったと問う彼に、素直に口を開いていた。
「多分、アナタと同じだよ。これだけ色々災いがあると、身代わりのし甲斐もあるよね」
「……」
けらけらと唄うように言う女に、今度は彼の方がふっと押し黙る。
「アナタも緋桐ちゃんのために死にたいんでしょ? それは多分、いずれ叶うよ」
彼の背筋が、ぞくりと冷えた。
この白い髪の女が、特別目敏い者な前提を知っていなければ、今の台詞は翡翠の少女の怪しい動きを身内に悟られている徴だ。
しかし女は彼の懸念も感じたように、不思議な白い笑顔で彼を見つめる。
「配置転換、いいんじゃないの。アナタは北に、緋桐ちゃんはディアルスに。アナタや緋桐ちゃんに誰も大きな関心は持ってないし、緋桐ちゃんの周囲は身内に甘い。できると思うよ」
「……キニスちゃんが言うと、まじっぽく聞こえるよねえ、それ」
「だってアナタくらいでしょ。あたしの言葉に耳を傾けよう、なんて奴は」
話の内容はともかく、穏やかに笑っている白い顔は、初めて会った頃の無害さに見えた。それは今の彼を映す姿でもある。
何かとこうして、身も蓋もない言葉を口にする女は、ディアルスで女を待つ仲間達以外には疎まれている。天の鳥でありながら魔の海を渡って生きてきた鼠には、この上なく誠実な人形に見えるというのに。
「緋桐ちゃんはさっぱり、あの道化様の中身を知らない。だから君さえ黙れば道化は納得するよ。あたしの立場で見立てられるのはそれくらいかな」
「……怖いくらいに、必要十分量の情報ですよ、っと。恩に着るぜ、キニスちゃん」
ただ彼は、誰かに背中を押してほしかったのかもしれない。
これから鼠は、長年潜んだ国を裏切る。彼を引き立ててくれた隣人の騎士にも泥を塗る。
そして彼にとっくに落ちていた魔女にも刃を向ける。魔女自身は認めないだろうが、頑張り過ぎて疲れた時や迷いを持った時に、背中を守る彼にだけは寄りかかった孤高な才女を彼は切り捨てる。
北方四天王が望んだので、人間の国の王女と一人の化け物女を、内から手を回して彼が引き渡した。当然の結果、彼は敵側だと悟られ、王女の魔女の付き人まで昇り遂せた幸運は台無しとなった。
北方四天王の配下ではなく、魔王直属の忍軍団である彼は、四天王の城に赴く前に支配人に釘を刺される。
「馬鹿なことをしたもんですねえ、君。北方さんにそこまでしてあげる義理、何かありましたっけ?」
忍軍団支配人の赤い道化は、北方四天王に部下の忍を数人増援として派遣しているだけだ。ディアルスで高い地位にいた彼が、今回独断で北方四天王についたことに、微笑みながらも黒い目は冷たかった。
「やだなー、主様ってば。おれがどうしたいかなんて、とっくにわかってるくせに?」
次に誰がディアルスに潜り込むか。それは「上手くやれた者」が後任になるだけ。その意味で翡翠の少女は、既に攫った王女の周囲に取り入れており、このままいけば自然に彼と入れ替わりになるだろう。推薦などすれば逆に怪しまれてしまう。
それで良かった。誰も彼の理由など知らずに、愚か者だと罵ればいい。人形の女と赤い道化、注意するべきはその二者だけだ。
魔王の息子などという者を、まず騙せると彼は思っていない。だから鼠がディアルスを離れて本当にいいか、悩んだのはその一点だ。
三つ編みの女の言った通り、道化は誰が潜入の後釜でも構わないように見える。意外だったのは一つで、北の四天王の城に向かう鼠に、わざわざ声をかけてきた気まぐれだった。
「私は、君みたいな風見鶏は嫌いじゃなかったんですよ。イソシギ君」
「……――」
「だから残念ですね。でも君の望みは、ちゃんと叶えてあげますからね?」
彼を忍軍団の名でなく、本来の名で呼んだ口元が裂けたように見えた。
魂の芯が凍り付いた。彼のような弱小の化け物の、最大の意地で笑顔を張りつけて硬直していると、最早興味をなくしたような赤い道化が薄ら笑顔ですれ違っていった。
その後、王女達を取り戻しに、ディアルスの一派は北方四天王の城に乗り込んで来た。彼は王女を探す黒髪の騎士と本気で戦ったものの、命令もないのにわざわざ黒髪の騎士の元に向かった時点で、その侵入は彼の手引きと四天王側は迅速に曲解していた。
「そりゃまあ、おれが疑われますわな……王女の居場所を教えるタイミングにも見せられるし、我ながら完璧?」
隣人の情を断ち切るために、容赦はせずに斬り合った。鼠の目的を遂げるためだけに、大きく巻き込んだ騎士と王女に心中で詫びる。
三つ編みの女は何も言わずに退場していった。誰が真に四天王と、忍の軍団を裏切ったのかを。
鼠はそうして、ディアルスからも四天王からも、裏切者として処断を受ける道を辿る。
「……何か不服か? この男の望みを叶えただけだろう」
彼にとどめを刺してくれた赤い道化の、無情な最後の声に彼はしびれた。
やはり彼などの理解が及ばないレベルで、魔王の息子はこの茶番にあっさり幕を下ろした。昏い海で、魔のもの達を一手に束ねる毒蛇の王――最上の悪魔の血筋はそういうものか。卑小な鼠には最大に、派手な舞台が見られただろう。
「いいじゃん、こーいうのも……名も無き下っ端が、超上級の悪魔様に、お手にかけられるとかさ?」
騎士達と通じた翡翠の少女は、道化に見逃された。それがあの悪魔の答だろう。これで彼には何一つ、思い残すことはないはずだった。
「……魔女が悲しむぞ、イソシギ」
最後にまさか、その顔を思い出すとは予想外だった。寡黙な黒髪の赤眼を彼は甘く見ていた。
誰から見ても、あれは彼の一方的な求愛で、魔女が彼に心を許していたなどと思う者はいない。魔女自身ですらそうだ、と彼はわかっていたのに。
あーあ……と。それが鼠の断末摩になった。
それから十九年後、守りを失い孤高に立ち続けた魔女は、僅かな隙を道化の関係者に利用されることになる。
その時魔女も鼠を思い哭くことを、誰も知ることはない。
-了-
❖閑話:氷る夜雨 -黄雀雨-❖

夜雨:夜に降る雨
黄雀雨:陰暦五月か九月の雨。この頃に海の魚が地上の黄雀になると言われる
side A -Atlas'- 裏話
本編:https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=20913600
※Atlas'13話以後は表紙がない内は公開投稿しております
+++++
write:2020.10.9
+++++
貴女、四天王になりませんか?
道化のような化粧で赤い髪の強力な悪魔に、直にそう誘われてしまった時、その吸血鬼は地上で生きる己の失点を悟った。
「貴女の『ストラグル』でのご活躍、聞き及んでおりますよ。上級千族を相手にされても、呼吸一つ乱さずに渡り合われるとか?」
長い銀色の髪を人間の女風に束ね、孔雀緑の眼を持つ吸血鬼。そんな端女は、様々な街の化け物ギャンブルに出たことがあった。
――ここ……本当の魔物がいるぜ。
元は魔界――魔の海で殺伐と生きていた端女だが、地上に移り住んだのは四年ほど前になる。しかし地上に出た途端、魔界時代から協力して暮らす二人、双子の吸血鬼が南の四天王に殺されかけたのが三年前。その後に助けを出してくれた金欠学者、彼女達を館に住まわせている博士吸血鬼に金品を渡すため、化け物ギャンブルで荒稼ぎするのが現在だった。
どうやらそんな世の片隅の戯れを、魔王の関係者などに見られてしまっていた。
「まず地上に出られるだけでも、四天王レベルの次元移動を使える魔の証ですからね。貴女のように正規のルートを使わず魔界から出た方は、見つけ次第スカウトすることにしてるんですよ」
赤い道化の言う通り、己をただの端女とみなす彼女に、そんな高度な「力」が扱えるようになったのは最近のことだ。人間の血をひく端女は大器晩成型だったようで、「使えない」と彼女を魔界に捨てた地上の吸血鬼の長――父の目は節穴だったらしい。
「……それで、つまりは。貴方の誘いを蹴れば、私は排除されるわけね?」
「やだなぁ、お話が早過ぎますけど、端的に言えばそうでしょうね? うちの忍軍団、貴女より弱そうな双子の方にすら全然敵いませんでしたしねぇ」
困ったことに、端女は己が、この世界でそこまで上位だとは知らなかった。わかっていればもう少し人目を忍んだだろうに、と思う。
商業都市に探し物に出て、夜の広場で休んでいた端女を、赤い道化は次の北方四天王に、と誘った。
現在、西の四天王が若い跡継ぎに変わったばかりで、南は彼女達が殺されかけた三年前に世代交代し、東も大分前に代替わりしているという。誰もが人間と魔族の混血という不安定な化け物で、「力」の振れ幅が大きく、どの家系もこれまでで最強の四天王を立てているのだ。
「北だけですよ、頑なに人間との交配を拒んで、弱小化していったのはね。私は嫌いじゃないんですけどねぇ、そういう風流」
「それで、人間と吸血鬼の混血である私に目を付けたと。案外安直なのね、魔王サマとやらは」
「仰る通り、実に効率の悪い博打でしてね。新しい四天王は皆さんメンタル不安定で、愛とかわけのわからないことを言い出しそうなんですよね」
中でも道化は南の四天王を警戒し、自ら部下となって監視しているようだった。西の者は魔王の甥であり、東は道化の抱える忍軍団の本拠で監視しやすく、北は古き良き血筋として、道化とはかなり親交が深かったと言う。
「今の北方さんも、あの少女趣味さえなければ、もう少し聞く耳持ってくれたんでしょーけどねぇ」
「で、私にそのロリコン野郎をぶち殺して、新しい北方四天王になれと」
「あー、めちゃくちゃ嫌そうですねぇ? 貴女、魔王様が怖くないんです?」
「興味が無い、と言っても見逃してはくれないんでしょうけど。私みたいな馬の骨を召したところで、魔王サマにもリスクが増えるだけじゃないの?」
北と言えば、純粋な「水」を司る家系で有名だ。端女は確かに、吸血種という魔でありながら、雨氷の精霊と幼い頃から契約していた異端者で、その自然界の「冰」が四天王向きの「力」であるのは間違いがない。
しかし端女単体で言えば、少しばかり気配探知の力が広くて鋭く、吸血種として身体能力が高いだけだ。夜の世界でひっそり生きていくだけの鬼に、魔王という世界規模の隸など完全に柄ではない。
それでも「ストラグル」に出たのを見られてのことであれば、その誘いに抗える余地はなかった。
「貴女と共に出場されていた双子さん達ね? 既に死線をさまよった身のようですね。貴女の力で生かされている二方でしょう」
「……」
「己の力を分けても生かす相手。美しい仲間の絆ですね。四天王には良い部下も必要ですし、皆さんでぱぁっと、冷たい北の島に花を咲かせません?」
要するに道化は、あの双子の吸血鬼を人質に取っている。部下にしろ、というのは、そうしなければ殺すという意味だ。力を分けられた二人はつまり、その力の分端女を弱くしている、本来邪魔な存在だと言える。
美しい絆。道化がおどけて口にした言葉に、思わず端女は失笑する。
「吸血鬼ごときに、美しい絆があるなんて思っているの。貴方も十分情緒不安定じゃないかしら、魔王サマの関係者さん」
「まぁ、あの二方が貴女をどう思っているかはともかく、人間の血をひく貴女は違うでしょう? 貴女は彼らに利用されても、自分の命が好きに使われても興味ないんでしょう」
道化の言う通り、端女には特に生への執着がない。命を分ける禁術は本来、近い血縁か余程の同調者相手にしかできないにも関わらず、己の心が希薄な端女には、相手を大切とさえ思えばできた。だから腐れ縁の双子達が少しでも生きのびやすくなるよう力を強め、ようやく地上の世界に出てくることができた。
その地上で双子達が、死に体となったのは皮肉な話だ。災いはこの世界に出た端女が、彼女と同等以上の「力」を持つ赤い髪の青年に出会ってしまったこと。それで青年の母である南の四天王の目に障り、双子達とまとめて殺されかけることになった。
青年は何も知らない。急に姿を見せなくなった彼女を心配しているだろう。その後に長く不和だった母を殺し、実弟を傀儡の四天王として暗躍し始めた気配だけは、彼女も異大陸で感じ取っていた。
だからもし、彼女が四天王になることを受け入れれば――
端女の力を分けられた双子達は、四天王の部下としてなら存在を許される。既に百年以上生きた彼女は、己が滅びることはどうでもいいが、二人はまだ生きたがるだろう。
そしてあの南の青年に、また会うことができるだろうか。気配を探る度に荒さが増し、どんどん壊れていく炎の「力」。
南に仕えるという赤い道化に、それだけは聞いてみたかった。
しかし尋ねること自体が、端女と青年の縁を示してしまう。それでなくとも南の前四天王に殺されかけた以上、更に弱みを掴ませることはない。
「……いいわ。黒の『守護者』には私も、私怨があるから」
「――え?」
必ず守る秘密を持つなら、他に撒き餌をした方がいい。
運命とは奇妙だ、と己を嘲笑う。ふざけたことに端女は北方四天王の適性だけでなく、同じ「水」で対立勢力となる「黒の守護者」とも縁があった。
彼女の父たる吸血鬼は、現在彼女を保護している学者の同類で、父も魔界の科学に通じた狂人だった。父が前代の「黒の守護者」と共に、守護者の力を継げる異端の吸血鬼を百年越しで造ったことを彼女は知っていた。
「私は、守護者には――天上の鳥には到底及ばないスズメだ、と父に捨てられたのよ。今でもあのコは、自分が守護者の器とは知らないでしょうけど」
十九年前に消えた他の守護者と違い、黒の守護者は百年以上行方不明だ。その情報を彼女が持つとは、あの時ほど道化が面白い顔を見せたことはない。
その後彼女は、成り行きで同道した霊獣族の男を連れて北方四天王を打倒し、文句なく新たな四天王となる。
彼女を父が黄雀と呼んだこと。彼女が何故雨氷の精霊を司る素質を生まれ持てたか、その意味を知ることはない。
「黒の守護者」となった少年が後に、再会した南の彼と彼女の間に、勝手に人造の娘を造ることも知らない。
ただ彼らが生きていれば、彼女は良かった。昏い魔の海から這い上がり、冷たい夜に降る雨の端女はとっくに冰り付き、他に心は持たなかった。
-了-
❖終夜閑話:残心❖

その無邪気な白い微笑を浮かべる少女に、心眼の彼はただ、厳しい顔で尋ねた。
「……あんた、誰なんだ?」
目前で黒いヘアバンドをつける、白灰の短い髪の少女。その年の頃は、十代に入ったばかりと見える幼さで……。
「ヒドイなぁ。それが懐かしい幼馴染みへの、第一声なの?」
「……あいつはいなくなった。もう、十年以上も前に」
「あはは、そうだね。だからレイアスはあたしのこと、忘れたいんだよね」
ここのところ、こうしてよくこの白い少女が彼の前に現れてくる。
キッカケは彼もわかっていた。しかしそれが何を「意味」しているのか、その彩の無い眼を以てしても、どうしても見極めることができない。
「……俺にその幻を見せて……どうしたいんだ? ……『ラピス』」
彼は酷く悲しげな声色で――白い少女のその向こうに、大切な新しい家族の名を呼んだ。
+++++
Cry per A. -arrestare-
千族化け物譚 C1終夜 『赤まみれの少年』
~The innate killer~
+++++
彼がその空色の連れ合いと出会ってから、早くも十一年が経過していた。
彼を出迎えた旧い悪友が、驚きの声を上げるのも無理はなかった。
「……へぇぇぇー。ひっさびさにディアルスに帰った思えば……まさかオマエらがこんな、可愛い娘を連れてきよるとはなぁー」
「えへへ、可愛いでしょ? ほら、ラピス――タツクおじさんに挨拶して、ね?」
連れ合いが悪友に、彼らの娘となった幼女を紹介する傍ら、彼はふっと辺りを見回す。
家主は不在がちの、ディアルスに構えられた悪友の家で。
彼と連れ合いに挟まれて座る、瑠璃色の髪を二つ括りにする八歳の幼い養女が、全身を固くしている。どうにも緊張を隠せない顔付きは無理もなかった。
「やっぱ女の子って可愛えーなぁ、サキも初めて見つけた時はこんくらいやったなぁー」
思い切り破顔して、武闘服の悪友が養女の頭を撫でる。似たような服を着せた養女は、連れ合いの服の裾を掴む。心細そうに悪友を見上げながらも、拙く口を開いていた。
「……はじめまして……ラピス・シルファリー、です……」
「そっかぁ、ラピスちゃんかぁ。ようディアルスまで来たなぁ、歓迎するでー」
そこで悪友は、養女が首に下げる猫の頭のような形の不思議な笛に気付いていた。
「おー。これがウワサの、代々伝わる『奇跡の幻を呼ぶ笛』か?」
「……」
笛を軽く手にとった悪友に、養女は遠慮がちにおずおずと頷いていた。
「そっかそっかー。大事にするんやで? 何せレイアス達と違うて、ラピスちゃんは人間なんやし……何があっても、まずは自分の身を守るのを優先するんやで」
悪友の言うことを、常々彼らから同じように言い付けられていた養女――彼らが最近引き取った特殊な家系の人間の幼女は、物分り良くまたこくんと頷く。
「……サキは最近、全然帰ってないのか? タツク」
悪友も少し前までは、ある事件で出会った桜色の娘を養子にしていた。
そちらは千族である娘の素性は、一言で語れるものではなく、そして更に――
「ああ。ラストもまた行方不明になってもーたし、まぁ二人共大丈夫やろうとは思うけど……ラストが頑固やから、あいつら結局まとまりそーにないわ」
色々あったのだ、と、簡単に言う悪友だが、父親経験値はどうやら向こうの方が上らしかった。
「ラスト、また行方不明なの? タツク」
左肩に消えない呪いを受け、それからずっと、辛うじて命を繋ぐ旧い仲間。連れ合いが養女を膝に乗せながら、心配そうに尋ねる。
それでも心配ない、とだけ笑う悪友は、この数年で随分大人びたな、と彼はしみじみ思うのだった。
他の者にも顔見せするため、連れ合いと養女が客間を出ていった後で、彼はようやく悪友にその相談を切り出すことができた。
「――はぁ? ラピスちゃんのあの笛で、何でか子供アシュリンの幻が呼ばれるやって?」
「ああ。ラピスが意識してるわけじゃないが、あの子が心細い時に笛を吹くと、かなりの確率で俺の前にだけ現れるんだ」
「ほんま……アシューに関しては何やスッキリせんこと、よーさん残っとるなぁ……」
沈痛な面持ちで悪友が両腕を組む。長椅子で足を組み直して、彼をしっかりと見返してきた。
「アフィの前には現れんとしたら、それはやっぱり――オマエに問題があるんと違うか?」
「……」
「ラピスちゃん、心細い時に笛を吹くんやろ? 寂しい思いしてるてことやんけ。それならもっと、オマエもちゃんと構ったらないかんで」
黙って俯く彼に、悪友は苦笑しながら身を乗り出して、ぽんぽんと彼の肩を叩いた。
「おれも随分、サキには寂しい思いさせてもーたしなぁ。何ちゅーか、どう接してえーかわからんよな、女の子って」
「……全くもって、オマエの言う通りなのが悔しいな」
そもそもどうして、彼らがそれぞれ養女を持つことになったか。
悪友の事情については彼も納得している。その養女と彼には多少の共通項もあり、今もたまに連絡をとる気安い間柄だった。
「サキはもう、最近はアシューに似て見えへんわ。有り得へんのはわかっとるけど、まるでオマエとアシューの子供みたいにも見えんねん」
「本当に有り得ないけどな。あの北方四天王が、わざわざそんなの造るわけない」
幼馴染みを殺した仇敵が、歪んだ情愛の結果として造り出した存在……幼馴染みの模造品という養女は、彼と似た特殊な眼の持ち主だ。そして十七歳になった現在は、幼馴染みと同じ大きな白黒猫の実体化霊獣を連れて、一人で旅をしているらしい。
元は悪友が四天王城から攫い、助け出していた娘に、彼はまた複雑な面持ちで深く息をつく。
「俺はそんなに――アシューの影を、まだ何処かに追ってるのかな?」
「どうやろうな。おれもそれは、まじに訊かれたら自信があらへんわ」
その幼馴染みを知るはずのない養女が、何故彼女の幻を創れるのかも全くわからないが。
「……アフィは何で、ラピスを養女にしたいと言い出したんだろうな」
出会いは偶然、山奥の隠れ里を通りすがった時、幸薄い人間の孤児を見かけただけなのだ。
しかし連れ合いは強くその幼女に感情移入し、不思議がる彼を説得してまで、半ば強引にその幼子を連れ出していた。
「そら、ラピスちゃんのあの笛、竜族の末裔やから持っとるって話やろ? 縁はあるやろ」
「そうだけど、でもラピスは完全に人間だ。俺もあの子は可愛いけど、俺達みたいな化け物と一緒にいさせていいのか……それが心配で」
彼と連れ合いは、連れ合いの両親から、おそらく彼らの間に子供はできないとはっきり予言されていた。
なので養子を持つことに不服はなかったが、よりによって何故連れ合いは、か弱い人間の娘を選んだのだろう。
連れ合いの心がさっぱりわからず、色んな意味で彼は悩んでいた。
「……おれがさっき、正直に思ったこと、言ってえーか?」
悪友はそこで、実にあっさり、単純な答を投げかけたのだった。
「ラピスちゃんは、何やアシューによう似とるわ、雰囲気。しょわんでええ苦労を、子供の内から受け入れてしもうたみたいに」
「……――」
「要するにアフィも、おれらと似たりよったりなんとちゃうか? 誰かの影を、無意識に追っとるんかもしらへん」
……彼はそこでまた、一抹の不安を思い浮かべる。
それは果たして、その影を受ける養女にとって、幸せなことであるのかどうかと。
父としてどう在ればいいか、全くわからなかった彼の戸惑いをよそに。
謎の幻の出現は少しずつ落ち着き、彼らの旅の中で養女が大きな危険に合うこともなく、時間は流れ――おそらく、普通よりも仲の良い親子として、彼らは和やかに過ごせていた。
それは何より、いつからか笑顔を絶やさなくなった養女と、元からほぼ常に笑顔である連れ合いの明るさが大きかった。
「ラピス、今度ジパングのお家に帰ったら、いつくーちゃん達に会いに行こう?」
「ええ? おかーさん、ひょっとしてそれ、全部みんなへのお土産?」
連れ合いの実家へ行き易いジパングという島国に、彼らは家を持った。
その家の近くの街「京都」で、養女には親しい三人の友達ができ、その友達に出会ってから養女はどんどんと明るくなっていった。
「くーちゃん達、異国のお話が好きだから、きっと喜ぶねぇ」
「そうそう。生ものも買っちゃったから、早く帰らないと悪くなっちゃうね」
連れ合いは養女の友達の存在が余程嬉しいのか、彼は会ったことのない友と遊ぶ養女に同伴する機会も多く、こうして自らそれを促すことが度々あった。
「……あんまり子供の集まりに、邪魔しない方が良くないか? アフィ」
今回の旅の用事が昨夜に終わり、今日も朝一番から買い物に出た連れ合いは、帰路に彼らを引っ張る張り切りぶりだ。その相変わらずの童顔に、彼は苦笑った。
「でもわたしもくーちゃん達、大好きなんだもの。本当に可愛いんだよ、あの子達」
「大丈夫だよー、おとーさん。くーちゃんも鶫ちゃんも蒼潤君も、もう慣れっこだよー」
そうしてわいわいと、母子というよりは姉妹のように、道の先を行く連れ合いと養女。彼がお手上げとばかりに軽く片手を上げた――……その、直後のことだった。
「……――……え?」
連れ合いと養女が、不意に硬直したように立ち止まる姿が見えた。
彼もほぼ同時に、彼女らが見ていたある凄惨な光景を、そこで捉えることになる。
「……――子供……!?」
焦り顔ですぐに駆け寄った彼の前で、連れ合いと養女が地面に膝をついて体を屈める。
そこに倒れていた、全身が血まみれの、意識の無い少年。十四歳の養女と年の近そうな、金色の髪で尖った耳の相手を、二人は慌てて介抱していた。
「ねぇ、大丈夫、生きてる……!? どうしたの……!?」
「ラピス、あまり動かしちゃダメ……! ――あ、レイアス――……!」
駆け付けた彼を見上げる連れ合いの青い目は、強い切迫の暗色に澱んで染まっていた。
まだ年端もいかない少年が、血まみれで倒れている衝撃は勿論だったが。
それ以上に、彼もその場で絶句し、連れ合いと養女も大きく動揺していた理由。
それはその、硬く目を閉じた旅人風の外套と黒衣の少年の、あどけない面差しにあった。
「この子どうして――……おとーさんに、そっくり……?」
養女が呆然と呟く通り、大人と子供の違いはあるが、少年の顔立ちは彼と瓜二つだったのだ。
「――……」
そして彼の彩の無い眼にそこで映った、見知らぬ少年のもう一つの現実。
「……アフィと……同じ、色……?」
金色の髪に尖った耳と、見た目は妖精に近い少年が纏った「力」の色。それは何故か限りなく彼の連れ合いに近く、妖精とは違う系統の化け物だと彼にはわかった。
だからこれも、運命としか言えない出会いだったと、この後に彼は知ることになっていく。
全身を負傷していた金色の髪の少年は、目覚めた時には自らの記憶を全く失った状態だった。
妖精の特徴を持つ少年を、まずディアルスで妖精の魔女に見せに行ったのだが、素性の手がかりは掴めなかった。
「とりあえずディアルスに戸籍はないわ。私も正直、このコが妖精だとは断言できない」
連れ合いに手を引かれ、頭を撫でられる少年は、常に所在無さげにしていた。
「……オレ、早く宿に帰りたい」
唯一の持ち物である古い剣を少年は手放さなかった。目深い外套で姿を隠し、外に出るのを嫌がる少年は、自身の名前一つも覚えていない。
そのため養女が適当につけたあだ名で、彼らはしばらく少年を呼ぶことになる。
「大丈夫だよー、金色さん。そんなに怖がらなくても、おとーさん達といれば安全だよ」
少年はそんな養女にまず気を許し、彼と連れ合いのことは遠目に様子を窺っていた。
「ラピスは……レイアス達のこと、ほんとに好きなんだな……」
しかしそれは何故か、警戒というよりは、不可解という台詞がよく似合う表情だった。
「きらきら君、ちょっとは元気になってきたかな? ねぇ、レイアス」
連れ合いは、養女と少年の前にいる時は、いつも通りにしているのだが……。
「ほんとに不思議だね。レイアスとそっくりで――……あれ、あれれれ?」
彼と二人になると、こうして突然涙することが、少年と出会ってから一ヶ月は続いていた。
「――大丈夫なのか? アフィ」
「ごめんね、何でもないの……何だかあのコを見てると、いつも急に胸が詰まるの」
人間の養女と出会った時のように、連れ合いは少年を養子にしたいと彼に強く訴えた。
「そうだな。ラピスと気が合ってるのは……二人共、痛々しいからに見えるよ」
今回は何故か二つ返事で、彼もそのつもりの不思議な出会いだった。
彼らの現住所であるジパングへ向かう途中、少年は剣を教えてほしい、と言い出していた。
「それは別に構わないが……大丈夫なのか? その状態で」
「体は全然、思うように動かないけど。でもオレ、強くならないと、妹……ラピスのこと、守れないから」
剣を持ちながらろくに使えず、化け物としての「力」もわからず、ひたすら少年は弱小だった。しかし彼らと共に過ごす中で、自然にその人間の娘を妹として大切に思うようになっていた。
「……剣を使えば、人殺しになるかもしれない。それでもいいのか?」
「それはわかってる。化け物なんだから当たり前だ」
苦い忠告に、そこであっさり頷いた少年。彼もその時、悪い予感はしていたのだが――
金色の髪で紫の目をした少年は、普段は弱小で大した「力」を持っていなかった。
ところがその本来の姿は、銀色の髪で青い目の苛烈な死神であると、彼らはやがて知ることになる。
「……――『銀色』さん?」
ある何でもない、旅の道中のこと。
何が起きたかわからず、ポカンとする養女の前で、その少年は突然変貌していた。
「――待て……!」
養女が縄を解き、解放しようとした敵。彼ら一行を襲い返り討ちにあった化け物を、少年は相手が自由になったと同時に、無言で自らの剣で貫こうとした。
その髪は金から銀色と変わり、暗い青となった目はただ冷たく……異変に気付いた彼が、既のところで少年の手を打ち、剣を取り落とさせた。
烈しさを呑み込む少年が青く冷え切った目線で、苦顔の彼を斜めに見上げる。
「――何で……殺さないの?」
何一つ表情を浮かべず、それだけを銀色の髪の少年は無機質に尋ねていた。
「……オマエは、誰なんだ?」
ただ厳しい顔で尋ね返した彼は、少年に付き纏う赤い運命を、その眼に映すしかなかった。
「俺にそんなことをきいて……どうしたいんだ? ……キラ」
痛々しく呼んだその名の、大切な「意味」。それを知る新たな旅が、ここから始まる。
千族化け物譚 C1 -了-
千族化け物譚❖Cry/A. 完結篇
ここまで読んで下さりありがとうございました。
何かと暗い下篇でしたが、未来の物語につながるための布石が多く、Cry/シリーズの続編は勿論、直観探偵シリーズで復帰するキャラクターなどもあります。
下記に一端を掲載していますので、良ければご覧ください。
星空文庫限定後日談『空夢』→https://slib.net/119266
ノベラボでの後日談『ELIXIR』→https://www.novelabo.com/books/6716/chapters ※11/25掲載予定
初稿:2016.3.1 C1 Cry/A.


