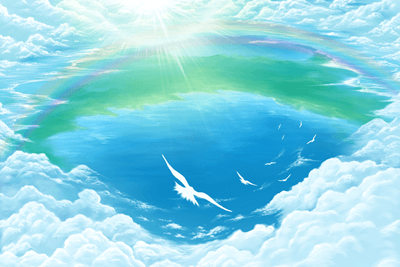
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第二部 第十章 蒼穹への黎明と
こちらは、
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第十章 蒼穹への黎明と
――――です。
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第九章 潮騒の鎮魂歌を https://slib.net/113909
――――の続きとなっております。
長い作品であるため、分割して投稿しています。
プロフィール内に、作品全体の目次があります。
https://slib.net/a/4695/
こちらから「見開き・縦書き」表示の『えあ草紙』で読むこともできます。
(星空文庫に戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください)
※使わせていただいているサービス『QRouton』の仕様により、クッションページが表示されます。
https://qrtn.jp/jy7dtb5
『えあ草紙』の使い方は、ごちらをご参考ください。
https://www.satokazzz.com/doc/%e3%81%88%e3%81%82%e8%8d%89%e7%b4%99%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab
「メニューを表示」→「設定」から、フォント等の変更ができます。PCなら、"UD Digi Kyokasho NP-R"等のフォントが綺麗です。
〈第九章あらすじ&登場人物紹介〉

===第九章 あらすじ===
ルイフォンたちと和解したリュイセンは、タオロンと共に〈蝿〉の捕獲に向かった。いざ突入というとき、〈蝿〉が毒香で彼らを待ち受けていることにタオロンが気づく。
一時撤退し、策を練り直したとき、リュイセンは、自分の取るべき道を悟る。そして、〈蝿〉に対して、『鷹刀一族の血族としての最期をを与える』と、正面から宣言する。
初めは相手にしなかった〈蝿〉だが、リュイセンが大怪我を負っているにも関わらず、毒香をタオロンに任せ、『後継者』の自分が〈蝿〉を裁くことで〈蝿〉を一族に戻す、と手を差し伸べてくれたことを知り、リュイセンの愚かなまでの高潔さと優しさに心を打たれ、降伏した。
一方、ルイフォンたちは、『リュイセンが〈蝿〉を捕らえたあと、オリジナルの死の理由を教えることを条件に、〈蝿〉におとなしく鷹刀一族の屋敷まで来るようにと交渉する』つもりでいたため、すっかり従順になった〈蝿〉に困惑した。
しかし、話の途中で〈蝿〉の様子がおかしくなった。『最高の終幕』を思いついてしまったと言ってリュイセンを昏倒させ、『客としてこの館に入れるようにしたから、展望塔にいるメイシアを連れて、自分のところに来るように』とルイフォンに告げる。
他に誰が来ても構わない、と言われたため、ルイフォン、ミンウェイ、エルファン、シュアンが〈蝿〉の館へと向かった。
そして、ルイフォンはついにメイシアとの再会を果たした。
案内として待っていたリュイセンとも再会し、一行は〈蝿〉と対面する。〈蝿〉の口調は相変わらずであったが、訝しんでいたルイフォンも敵意はないことを認めた。
〈蝿〉との『初対面の再会』を果たしたミンウェイは、想像以上に穏やかな〈蝿〉に動揺していた。〈蝿〉の知りたがっている『オリジナルの死の理由』すなわち、ミンウェイの自殺未遂の件を伝えるべきではないのではと悩む。
そのときエルファンが進み出て、ミンウェイの気持ちを思えば、オリジナルに死を望む理由を聞いておくべきだったと懺悔する。そして、ミンウェイはオリジナルが死んだときの状況を知っていても、オリジナルの心は分からない。だから、オリジナルが何を考えたのか、同じ記憶を持つ〈蝿〉に答えてほしいと求める。
「君に生きていてほしいから」「私がいるから、君が『死』を望んだ。だから、君が生きていけるように、私は自分が消えることにしたんだ」という〈蝿〉の言葉に、ミンウェイは泣き崩れた。
〈蝿〉は満たされた思いで、頭を切り替え、『最高の終幕』についての口火を切る。それはすなわち、『メイシアを〈悪魔〉の契約から解放するため、〈蝿〉が命と引き換えに、ルイフォンたちに王族の『秘密』を教える』というものであった。
ルイフォンは、〈蝿〉の心の内にある、さまざまな思いを噛みしめ、敬意と称賛を込めて「最高の終幕だ」と認めた。
〈蝿〉は、話の途中で事切れたときの保険にと、まずルイフォンに、王族の『秘密』のすべてを記した記憶媒体を渡した。そして、語り始める。『白金の髪、青灰色の瞳という、王の異色は、先天性白皮症に依るものだ』と。
今の王朝ができる以前の、古の王の時代。この国の片隅に先天性白皮症の者が多く生まれる里があった。この里の者が今の王族の先祖である。黒髪黒目の人間しか見たことのなかった古の王は、美しい姿をした異色の者は、神への『供物』だと信じて捕らえ、神に捧げると言って殺していった。
先天性白皮症の症状のひとつに視力障害があるが、その里の出身の男子は必ず盲目だった。あるとき、供物になるのを待つばかりだった少年が、一矢報いたいと、そのためには周りの様子を知りたいと願った。そして、脳を進化させ、『他者から視覚情報を奪う』能力を手に入れた。その能力は『視覚』にとどまらず、『他者の脳から、情報を奪う』能力――創世神話に謳われる『地上のあらゆることを見通す瞳』となった。
この話を聞いたルイフォンは、王の能力――王の『秘密』が、〈天使〉に酷似していることに気づく。案の定、〈蝿〉は『〈天使〉は王の脳細胞をもとに人工的に作られたもの』だと答えた。
時代は流れ、『他者の脳から、情報を奪う』能力は、盲目である異色の男子すべてに表れるようになった。王族の先祖は、その能力をちらつかせることで警護役だった鷹刀一族の先祖を味方に引き込み、古の王を斃して自らが王となった。
王は、異色を神聖なものとするために〈神の御子〉を自称し、神の代理人として国を治めた。また、盲目は弱点であり、情報を奪う能力は切り札となるため、王族の『秘密』として隠されるようになった。
初めは『傍らにいる他者』から情報を奪う程度だった能力は、やがて複数の〈神の御子〉の能力が絡み合い、国中の情報を無制限に収集する巨大な情報回路がとなった。しかし、〈神の御子〉たちの脳に過剰な負荷が掛かり、命を落とす者が出てきた。
この事態を憂いた時の王は、自分の死後、自分の脳細胞を使って無限の容量を持った『人工の脳』を作り、〈神の御子〉たちの負荷を分散させる連携構成を構築するように命じた。こうして誕生したのが『死んだ王の脳細胞から作られた巨大な有機コンピュータ〈冥王〉』である。
〈冥王〉は、王の死出の旅路の供として、近くに生き埋めにされていた鷹刀の護衛の血肉を喰らい、動力源としたため、その後、長く、鷹刀の者たちが〈贄〉として捧げられるようになった。
〈冥王〉が『光の珠』の姿をしていると聞いたルイフォンは、母キリファの作った〈ケル〉や〈ベロ〉と酷似していることに気づく。つまり、〈冥王〉を破壊するために作られた〈ケルベロス〉は、〈冥王〉と同じく有機コンピュータであり、母は自分の脳を使って〈スー〉を作るために死んだのだと悟った。
最後に〈蝿〉は、ルイフォンとメイシアに、処分も視野に入れた上で、『ライシェン』を託した。また、オリジナルは盲目であったが、〈蝿〉の作った『ライシェン』は、セレイエの――正確には〈影〉のホンシュアの依頼で、目が見えるように作ったと告げる。
唖然とするルイフォンに、セレイエの記憶を持つメイシアが、『オリジナルのライシェンは、〈神の御子〉の男子が持つ『情報を読み取る』能力に加え、〈天使〉のセレイエから受け継いだ『情報を書き込む』能力も持っていた』と語る。そして、ライシェンは自分に向けられた殺意を読み取り、自衛のために人を殺したため、危険だと判断した先王に殺されたのだ、と。
セレイエは、蘇生した『ライシェン』には、他人の感情を読み取ってほしくないと願った。故に、目の見える肉体を求めて、『死んだ天才医師〈蝿〉』を蘇らせたのだった。
いよいよ〈蝿〉の命が尽きようとしたとき、彼の看取りには、彼の対として作られたらしい硝子ケースの中の『彼女』も同席すべきだと、リュイセンが彼女を迎えに行く。すると眠ったまま目覚めないはずの彼女が苦しんでいた。慌てて外に出すと、彼女は〈蝿〉とひとつの命を共有する存在で、オリジナルのヘイシャオが望んだ『比翼連理の夢』だと言う。
自分のせいで彼女まで死んでしまうと〈蝿〉は悔やむが、彼女は『眠ったままでは生きていると言えない。今、こうして触れ合える刹那こそ生きていると言える。願いが叶った』と告げる。
そして、ふたりは満ち足りた顔で、幸せそうに息を引き取った。
〈蝿〉の死後、ルイフォンは『ライシェン』を連れて行くと即断し、一同は出発の準備に掛かる。その途中で、展望塔から合流したタオロンが、〈蝿〉が娘のために用意した部屋を見てほしいと、ミンウェイに申し出る。
〈蝿〉の用意した部屋は、幼いころのミンウェイの部屋そのものだった。タオロンは、「〈蝿〉は『娘のミンウェイ』を深く愛していた」と熱弁して去っていった。それとすれ違うように、シュアンが現れる。シュアンは「ミンウェイを追ってくれ」とリュイセンに頼まれたのだ。
「タオロンは、あんたの傷をえぐりまくった」と言うシュアンに、ミンウェイは噛みつくが、「あんたの欲しかった愛は、『娘』としてじゃねぇんだ」「なのに、『娘として愛されていた』と繰り返し言われて、辛くないわけがないだろう!?」という言葉に、泣き崩れた。
『失恋』したのだと、シュアンに言われ、納得しつつあったミンウェイ。しかし、会話の途中で、幼いころに求婚してくれた男の子を、父の命令で殺したことを思い出す。その子への贖罪として自分は幸せになってはいけない、『失恋』なんてもってのほか、そもそも自分には誰かを愛し、幸せになる資格などなかったのだと叫ぶ。
そのとき、いつもミンウェイのそばに座るくせに、決して彼女に触れることのなかったシュアンが、彼女を抱きすくめた。そして、「あんたが幸せになってもならなくても、罪は罪。ならば、あんたの為すべきことは、本当に『あんたが幸せにならないこと』なのか?」と厳しくも正しいことを言う。
その言葉を胸に、ミンウェイはようやく〈蝿〉に――『父親』に別れを告げることができたのだった。
===登場人物===
鷹刀ルイフォン
凶賊鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオの末子。十六歳。
――ということになっているが、本当は次期総帥エルファンの息子なので、イーレオの孫にあたる。
母親のキリファから、〈猫〉というクラッカーの通称を継いでいる。
端正な顔立ちであるのだが、表情のせいでそうは見えない。
長髪を後ろで一本に編み、毛先を母の形見である金の鈴と、青い飾り紐で留めている。
凶賊の一員ではなく、何にも属さない「対等な協力者〈猫〉」であることを主張し、認められている。
※「ハッカー」という用語は、本来「コンピュータ技術に精通した人」の意味であり、悪い意味を持たない。むしろ、尊称として使われている。
対して、「クラッカー」は、悪意を持って他人のコンピュータを攻撃する者を指す。
よって、本作品では、〈猫〉を「クラッカー」と表記する。
メイシア
もと貴族で、藤咲家の娘。十八歳。
ルイフォンと共に居るために、表向き死亡したことになっている。
箱入り娘らしい無知さと明晰な頭脳を持つ。
すなわち、育ちの良さから人を疑うことはできないが、状況の矛盾から嘘を見抜く。
白磁の肌、黒絹の髪の美少女。
王族の血を色濃く引くため、『最強の〈天使〉の器』としてセレイエに選ばれ、ルイフォンとの出逢いを仕組まれた。
セレイエの〈影〉であったホンシュアを通して、セレイエの『記憶』を受け取った。
[鷹刀一族]
凶賊と呼ばれる、大華王国マフィアの一族。
秘密組織〈七つの大罪〉の介入により、近親婚によって作られた「強く美しい」一族。
――と、説明されていたが、実は、有機コンピュータ〈冥王〉を維持するための〈贄〉を強いられてきた一族であった。
鷹刀イーレオ
凶賊鷹刀一族の総帥。六十五歳。
若作りで洒落者。
かつては〈七つの大罪〉の研究者、〈悪魔〉の〈獅子〉であった。
鷹刀エルファン
イーレオの長子。次期総帥。
ルイフォンとは親子ほど歳の離れた異母兄弟ということになっているが、実は父親。
感情を表に出すことが少ない。冷静、冷酷。
鷹刀リュイセン
エルファンの次男。イーレオの孫。十九歳。本人は知らないが、ルイフォンの異母兄にあたる。
文句も多いが、やるときはやる男。
『神速の双刀使い』と呼ばれている。
長男の兄が一族を抜けたため、エルファンの次の総帥になる予定であり、最後の総帥となる決意をした。
鷹刀ミンウェイ
母親がイーレオの娘であり、イーレオの孫娘にあたる。
――ということになっていたが、実は『父親』と思っていたヘイシャオが、不治の病の妻を『蘇生』するために作った、妻から病気の因子を取り除いたクローン。
妻が『蘇生』を拒絶し、クローンを『娘』として育てるように遺言したため、心を病んだヘイシャオに、溺愛という名の虐待を受ける羽目になってしまった。
緩やかに波打つ長い髪と、豊満な肉体を持つ絶世の美女。ただし、本来は直毛。二十代半ばに見える。
薬草と毒草のエキスパート。医師免状も持っている。
かつて〈ベラドンナ〉という名の毒使いの暗殺者として暗躍していた。
現在は、鷹刀一族の屋敷を切り盛りしている。
草薙チャオラウ
イーレオの護衛にして、ルイフォンの武術師範。
無精髭を弄ぶ癖がある。
料理長
鷹刀一族の屋敷の料理長。
恰幅の良い初老の男。人柄が体格に出ている。
キリファ
ルイフォンの母。四年前に当時の国王シルフェンに首を落とされて死亡。
天才クラッカー〈猫〉。
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蠍〉に〈天使〉にされた。
また〈蠍〉に右足首から下を斬られたため、歩行は困難だった。
もとエルファンの愛人で、セレイエとルイフォンを産んだ。
ただし、イーレオ、ユイランと結託して、ルイフォンがエルファンの息子であることを隠していた。
ルイフォンに『手紙』と称し、人工知能〈スー〉のプログラムを託した。
〈ケル〉〈ベロ〉〈スー〉
キリファが、〈冥王〉を破壊するために作った三台の兄弟コンピュータ。
表向きは普通のスーパーコンピュータだが、それは張りぼてである。
本体は、人間の脳から作られた有機コンピュータ。光の珠の姿をしている。
〈ベロ〉の人格は、シャオリエのオリジナル『パイシュエ』である。
〈ケル〉は、キリファの親友といってもよい間柄である。
〈スー〉は、ルイフォンがキリファの『手紙』を正確に打ち込まないと出てこないのだが、所在は、もと〈蠍〉の研究所にあることが分かっている。また、キリファの人格を持っていると推測されている。
セレイエ
エルファンとキリファの娘。
表向きは、ルイフォンの異父姉となっているが、同父母姉である。
リュイセンにとっては、異母姉になる。
生まれながらの〈天使〉。
王族のヤンイェンと恋仲になり、ライシェンという〈神の御子〉を産んだ。
先王シルフェンにライシェンを殺されたため、「ルイフォンの中に封じた、ライシェンの『記憶』」と「〈蝿〉に作らせた『肉体』」を使って、ライシェンを生き返らせる計画――『デヴァイン・シンフォニア計画』を企てた。
ただし、セレイエ本人は、ライシェンの記憶を手に入れるために〈天使〉の力を使い尽くし、あとのことは〈影〉のホンシュアに託して死亡した。
『最強の〈天使〉』となり得るメイシアを選び、ルイフォンと引き合わせた。
メイシアのペンダントの元の持ち主で、『目印』としてメイシアに渡した。
パイシュエ
イーレオ曰く、『俺を育ててくれた女』。
故人。鷹刀一族を〈七つの大罪〉の支配から解放するために〈悪魔〉となり、その身を犠牲にして未来永劫、一族を〈贄〉にせずに済む細工を施した。
自分の死後、一族を率いていくことになるイーレオを助けるために、シャオリエという〈影〉を遺した。
また、どこかに残されていた彼女の何かを使い、キリファは〈ベロ〉を作った。
すなわち、パイシュエというひとりの人間から、『シャオリエ』と〈ベロ〉が作られている。
[〈七つの大罪〉・他]
〈七つの大罪〉
現代の『七つの大罪』=『新・七つの大罪』を犯す『闇の研究組織』。
実は、王の私設研究機関。
王家に、王になる資格を持つ〈神の御子〉が生まれないとき、『過去の王のクローンを作り、王家の断絶を防ぐ』という役割を担っている。
〈冥王〉
他人の脳から情報を読み取ることによって生じる、王族の脳への負荷を分散させるために誕生した連携構成。
太古の昔に死んだ王の脳細胞から生まれた巨大な有機コンピュータで、鷹刀一族の血肉を動力源とする。
『光の珠』の姿をしており、神殿に収められている。
〈悪魔〉
知的好奇心に魂を売り渡した研究者を〈悪魔〉と呼ぶ。
〈悪魔〉は〈神〉から名前を貰い、潤沢な資金と絶対の加護、蓄積された門外不出の技術を元に、更なる高みを目指す。
代償は体に刻み込まれた『契約』。――王族の『秘密』を口にすると死ぬという、〈天使〉による脳内介入を受けている。
『契約』
〈悪魔〉が、王族の『秘密』を口外しないように施される脳内介入。
記憶の中に刻まれるため、〈七つの大罪〉とは縁を切ったイーレオも、『契約』に縛られている。
また、〈悪魔〉であったセレイエの記憶を受け継いだメイシアや、パイシュエの記憶を使って作られた〈ベロ〉も、『契約』に縛られている。
〈天使〉
『記憶の書き込み』ができる人体実験体。
脳内介入を行う際に、背中から光の羽を出し、まるで天使のような姿になる。
〈天使〉とは、脳という記憶装置に、記憶や命令を書き込むオペレーター。いわば、人間に侵入して相手を乗っ取るクラッカー。
羽は、〈天使〉と侵入対象の人間との接続装置であり、限度を超えて酷使すれば熱暴走を起こす。
〈影〉
〈天使〉によって、脳を他人の記憶に書き換えられた人間。
体は元の人物だが、精神が別人となる。
『呪い』・便宜上、そう呼ばれているもの
〈天使〉の脳内介入によって受ける影響、被害といったもの。悪魔の『契約』も『呪い』の一種である。
服従が快楽と錯覚するような他人を支配する命令や、「パパがチョコを食べていいと言った」という他愛のない嘘の記憶まで、いろいろである。
『di;vine+sin;fonia デヴァイン・シンフォニア計画』
セレイエによる、殺された息子ライシェンを生き返らせるための計画。
『di』は、『ふたつ』を意味する接頭辞。『vine』は、『蔓』。
つまり、『ふたつの蔓』――転じて、『二重螺旋』『DNAの立体構造』――『命』の暗喩。
『sin』は『罪』。『fonia』は、ただの語呂合わせ。
これらの意味を繋ぎ合わせて『命に対する冒涜』と、ホンシュアは言った。
ヘイシャオ
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蝿〉。ミンウェイの『父親』。故人。
医者で暗殺者。
病弱な妻のために〈悪魔〉となった。
妻の遺言により、妻の蘇生のために作ったクローン体を『娘』として育てていくうちに心を病んでいった。
十数年前に、娘のミンウェイを連れて現れ、自殺のようなかたちでエルファンに殺された。
現在の〈蝿〉
セレイエが『ライシェン』を作らせるために、蘇らせたヘイシャオ。
セレイエに吹き込まれた嘘のせいでイーレオの命を狙い、鷹刀一族と敵対していたが、リュイセンによって心を入れ替えた。
メイシアを〈悪魔〉の『契約』から解放するため、自ら王族の『秘密』を口にして死亡した。
ホンシュア
殺されたライシェンの侍女であり、自害するくらいならとセレイエの〈影〉となって『デヴァイン・シンフォニア計画』に協力した。体は〈天使〉化してあった。
〈影〉にされたメイシアの父親に、死ぬ前だけでも本人に戻れるような細工をしたため、体が限界を超え、熱暴走を起こして死亡。
メイシアにセレイエの記憶を潜ませ、鷹刀に行くように仕向けた、いわば発端を作った人物である。
〈蛇〉
セレイエの〈悪魔〉としての名前。
〈蝿〉が、セレイエの〈影〉であるホンシュアを〈蛇〉と呼んでいたため、ホンシュアを指すこともある。
ライシェン
ヤンイェンとセレイエの息子で、〈神の御子〉。
〈神の御子〉の男子が持つ『情報を読み取る』能力に加え、〈天使〉のセレイエから受け継いだ『情報を書き込む』能力を持っていた。
彼の力は、〈天使〉の羽のように自分と相手を繋ぐことなく、〈神の御子〉のように手も触れずに扱えたため、先王シルフェンは彼を『神』と呼ぶしかないと言い、『来神』と名付けた。
周りの『殺意』を感じ取り、相手を殺してしまったために、先王に殺された。
『ライシェン』
〈蝿〉が、セレイエに頼まれて作った、ライシェンのクローン体。
オリジナルのライシェンは盲目だったが、周りの『殺意』を感じ取らずにすむようにと、目が見えるように作られた。
凍結処理が施され、ルイフォンとメイシアに託された。
斑目タオロン
よく陽に焼けた浅黒い肌に、意思の強そうな目をした斑目一族の若い衆。
堂々たる体躯に猪突猛進の性格。
二十四歳だが、童顔ゆえに、二十歳そこそこに見られる。
〈蝿〉の部下となっていたが、娘のファンルゥに着けられていた毒針の腕輪が嘘だと分かり、ルイフォンたちの味方になった。
斑目ファンルゥ
タオロンの娘。四、五歳くらい。
くりっとした丸い目に、ぴょんぴょんとはねた癖っ毛が愛らしい。
[藤咲家・他]
藤咲ハオリュウ
メイシアの異母弟。十二歳。
父親を亡くしたため、若年ながら藤咲家の当主を継いだ。
十人並みの容姿に、子供とは思えない言動。いずれは一角の人物になると目される。
異母姉メイシアを自由にするために、表向き死亡したことにしたのは彼である。
女王陛下の婚礼衣装制作に関して、草薙レイウェンと提携を決めた。
藤咲コウレン
メイシア、ハオリュウの父親。厳月家・斑目一族・〈蝿〉の陰謀により死亡。
藤咲コウレンの妻
メイシアの継母。ハオリュウの実母。
心労で正気を失ってしまい、別荘で暮らしていたが、メイシアがお見舞いに行ったあとから徐々に快方に向かっている。
緋扇シュアン
『狂犬』と呼ばれるイカレ警察隊員。三十路手前程度。イーレオには『野犬』と呼ばれた。
ぼさぼさに乱れまくった頭髪、隈のできた血走った目、不健康そうな青白い肌をしている。
凶賊の抗争に巻き込まれて家族を失っており、凶賊を恨んでいる。
凶賊を殲滅すべく、情報を求めて鷹刀一族と手を結んだ。
敬愛する先輩が〈蝿〉の手に堕ちてしまい、自らの手で射殺した。
似た境遇に遭ったハオリュウに庇護欲を感じ、彼に協力することにした。
[王家・他]
白金の髪、青灰色の瞳の先天性白皮症の者が多く生まれる里を起源とした一族。
王家に生まれた先天性白皮症の男子は必ず盲目であり、代わりに他人の脳から『情報を読み取る』能力を持つ。
この特殊な力を持つ者を王としてきたため、先天性白皮症の外見を持つ者だけが〈神の御子〉と呼ばれ、王位継承権を有する。かつては男子のみが王となれたが、現在では〈神の御子〉が生まれにくくなったために女王も認めている。ただし、あくまでも仮初めの王である。
アイリー
大華王国の現女王。十五歳。
彼女の婚約を開始条件に、すべてが――『デヴァイン・シンフォニア計画』が始まった。
メイシアの再従姉妹にあたるが、メイシア曰く『私は数多の貴族のひとりに過ぎなかった』。
シルフェン
先王。四年前、腹心だった甥のヤンイェンに殺害された。
〈神の御子〉に恵まれなかった先々王が〈七つの大罪〉に作らせた『過去の王のクローン』である。
ヤンイェン
先王の甥。女王の婚約者。
実は先王が〈神の御子〉を求めて姉に産ませた隠し子で、女王アイリーや摂政カイウォルの異母兄弟に当たる。
セレイエとの間に生まれたライシェンを殺されたため、その復讐として先王を殺害した。
メイシアの再従兄妹にあたる。
カイウォル
摂政。女王の兄に当たる人物。
摂政を含む、女王以外の兄弟は〈神の御子〉の外見を持たないために、王位継承権はない。
異母兄にあたるヤンイェンとの結婚を嫌がる妹、女王アイリーのため、ハオリュウに『君が女王の婚約者になれば、女王の結婚が延期される』と陰謀を持ちかけた。
[草薙家]
草薙レイウェン
エルファンの長男。リュイセンの兄。
エルファンの後継者であったが、幼馴染で妻のシャンリーを外の世界で活躍させるために
鷹刀一族を出た。
――ということになっているが、リュイセンに後継者を譲ろうと、シャンリーと画策したというのが真相。
服飾会社、警備会社など、複数の会社を興す。
草薙シャンリー
レイウェンの妻。チャオラウの姪だが、赤子のころに両親を亡くしたためチャオラウの養女になっている。
王宮に召されるほどの剣舞の名手。
遠目には男性にしかみえない。本人は男装をしているつもりはないが、男装の麗人と呼ばれる。
タオロンの人柄と腕っぷしを評価し、彼をレイウェンの会社にと推薦した。
草薙クーティエ
レイウェンとシャンリーの娘。リュイセンの姪に当たる。十歳。
可愛らしく、活発。
鷹刀ユイラン
エルファンの正妻。レイウェン、リュイセンの母。
レイウェンの会社の専属デザイナーとして、鷹刀一族の屋敷を出た。
ルイフォンが、エルファンの子であることを隠したいキリファに協力して、愛人をいじめる正妻のふりをしてくれた。
メイシアの異母弟ハオリュウに、メイシアの花嫁衣装を依頼された。
[繁華街]
シャオリエ
高級娼館の女主人。年齢不詳。
外見は嫋やかな美女だが、中身は『姐さん』。
実は〈影〉であり、イーレオを育てた、パイシュエという人物の記憶を持つ。
スーリン
シャオリエの店の娼婦。
くるくる巻き毛のポニーテールが似合う、小柄で可愛らしい少女。ということになっているが妖艶な美女という説もある。
本人曰く、もと女優の卵である。実年齢は不明。
===大華王国について===
黒髪黒目の国民の中で、白金の髪、青灰色の瞳を持つ王が治める王国である。
身分制度は、王族、貴族、平民、自由民に分かれている。
また、暴力的な手段によって団結している集団のことを凶賊と呼ぶ。彼らは平民や自由民であるが、貴族並みの勢力を誇っている。
1.真白き夜更け-1

夏の虫たちの囁きが、夜闇を彩る。落ち着いた澄んだ音色が、鮮やかに広がっていく。
夜半特有の涼やかな南風が、レースのカーテンをふわりと揺らした。清冽な月明かりが窓から入り込み、ルイフォンの眠るベッドへと、まっすぐに降りてくる。
真白き光に誘われて、彼は薄目を開けた。
覚醒と同時に、腕の中のぬくもりを確認する。彼の肩口に、彼女の柔らかな頬。規則正しい寝息が胸元をくすぐり、彼は安堵する。
やっと取り戻した、最愛のメイシア。
彼女は、彼の服の端を固く握りしめたまま、甘えるように彼に体を預けていた。凛と輝く黒曜石の瞳は今は閉ざされ、緩やかな弧を描く睫毛の下に隠されている。その寝顔は無邪気で、無防備だ。
さらさらと流れる黒絹の髪を指先に絡め、くしゃりと撫でたい。ルイフォンは、その衝動を必死に抑える。
長かった軟禁生活から、ようやく解放されたのだ。安らかな眠りの邪魔をしたら、可哀想だろう。それより今は、その身を委ねてくれる愛しい彼女の寝姿を、心ゆくまで堪能しよう……。
約半日前となる昨日の昼、〈蝿〉の死によって、彼との諍いの日々に幕が下りた。
一行は、帰路の途中で草薙家に寄り、タオロンとファンルゥを送り出した。これからタオロンは、レイウェンの警備会社に住み込みで働くことになる。
待ち構えていたシャンリーやクーティエに熱烈な歓迎を受けていたから、小さなファンルゥも、きっとすぐに馴染むことだろう。闇に捕らわれ続けていたこの父娘も、これでようやく光の中を歩ける。本当によかったと思う。
屋敷に到着すると、料理長がご馳走の用意をして待っていた。イーレオやチャオラウも揃い、久しぶりに――本当に久しぶりに、皆で食卓を囲んだ。
料理の出来映えについて伺いに来た料理長に、リュイセンがいきなり席を立って土下座するという一幕もあった。彼が裏切り、メイシアを連れ去ったあの日、料理長の心づくしの晩餐を台無しにしたからだという。そんな彼を、料理長は笑って許してくれた。
食事を楽しんだあとは、『各人ゆっくりと休むように』とイーレオが言い渡し、解散となった。先にエルファンが電話連絡を入れていたこともあり、詳しい報告の会議は明日の午後とされたのだ。
リュイセンは、屋敷のあちこちへと挨拶に行った。彼の裏切り行為についての真相を明かすことはできないが、ケジメは必要だということだ。
ミンウェイは、〈蝿〉――『彼』と『彼女』の遺体が埋葬するまでの間に傷まないよう、処置を施すと言っていた。大掛かりな葬儀を行うことはないが、日を改めて弔う手はずになっている。
ちゃっかりというか、当然の権利というか、共に食卓についていたシュアンは、その足でメイシアの異母弟ハオリュウのもとへ向かった。ことの顛末について、説明してきてくれるそうだ。
そして――。
ルイフォンとメイシアは、『ライシェン』を屋敷の地下にいる〈ベロ〉に預けた。
〈神の御子〉の姿をした硝子ケースの赤子など、万が一にも屋敷の者たちに見られるわけにはいかない。また、よく分からないものであるからには、常に監視しておいたほうがよいだろうと考えたためだ。
「〈ベロ〉なら、不眠不休で『ライシェン』を見守れるだろ?」
〔ちょっとぉ、なんで私が、子守りしなきゃいけないのよ? だいたい私は、人の世には関わらない決まりよ!〕
気安く頼んだルイフォンに、〈ベロ〉は渋面を作るように光の糸を震わせた。
「お前が適任なんだから、そこをなんとか頼むよ。それに〈七つの大罪〉の技術でできた『ライシェン』は、人の世のものではないだろ?」
そう押し切って、〈ベロ〉のいる小部屋に、強引に『ライシェン』を置いてきたのだ。
そのあと……。
ちょっと仮眠を取ろうと、メイシアと共に横になった途端、ふたりとも泥のように眠ってしまったのだ。昨日は、ほぼ徹夜であったので、それも当然だったのかもしれない。
もうすっかり夜中だな。
高く上った、真円に近い月を見上げ、ルイフォンは思う。
晩御飯の時間はとっくに過ぎているだろう。いつもの通りなら、気を利かせた料理長が、部屋の外に夜食を置いてくれたはずだ。手間を掛けて申し訳ないが、あとで、ありがたくメイシアといただこう。
そんなことを考えていると、不意にメイシアの視線を感じた。
「ごめん。起こしちゃったか」
口では謝りながらも、彼女と言葉を交わせるのが嬉しくて、ルイフォンの顔は自然とほころぶ。しかし、ぱっちりと開かれた黒曜石の瞳が潤んでいることに気づき、彼は「どうした?」と顔色を変えた。
「ルイフォン……」
彼の名を呼びながら、彼女は彼の胸板に頬を寄せる。細い指先が彼の脇腹に回され、全身で彼の存在を確かめるかのように抱きついてきた。
「夢を見ていたの」
ぴたりと触れ合った体から、彼女の鼓動の速さが伝わってきた。
囚われの生活による心労から、悪夢を見たのだろう。それ自体はよいことではないが、夢でよかったと、ルイフォンは安堵する。
気にすることはないと笑いかけ、黒絹の髪をくしゃりとしようとしたとき、メイシアが再び口を開いた。
「でも、それは夢じゃなくて、セレイエさんの記憶なんだと思う。いろんなことを、とりとめもなく、たくさん……、セレイエさんの目で、セレイエさんの心で、見ていたの」
「!」
ルイフォンの心臓が跳ねた。
今まで、メイシアの身柄を取り戻すことが最優先で、彼女に刻まれたセレイエの記憶について考える余裕がなかった。『私が知りたいと思わなければ、セレイエさんの記憶は私の邪魔をしないから大丈夫』と、メイシアが言っていたために安心していたということもある。
しかし、やはり悪影響はあったのだ。ふとしたとき、おそらくは眠っているときのように、メイシアの自我が弱まっているとき、彼女はセレイエの辛酸を我がことのように受け止めてしまうようだ。
「糞っ……」
どうしたらよいのか分からず、ルイフォンは悪態をつく。
「ルイフォン」
硬い声で呟き、メイシアは顔を上げた。長い黒髪の先が、名残惜しげに彼の体を撫でていき、途中で、窓から入り込んだ風に舞い上げられる。
カーテンがなびき、白い月光が部屋に入り込んだ。照らし出された花の顔に、ルイフォンは息を呑む。
メイシアのまとう雰囲気が変わっていた。
その瞳が光るのは、辛い感情から生まれた涙の反射のはずなのに、まるで彼女の芯の強さが灯ったかのような凛と鋭い眼差しだった。
「セレイエさんの記憶から知った『デヴァイン・シンフォニア計画』のこと。――私……、まだ、ちゃんと話せていなかったの」
「あ、ああ。今まで、それどころじゃなかったし、迂闊なことを言えば、お前が〈悪魔〉の『契約』に抵触する羽目になったからな」
だから、先延ばしにしていた。
けれど、もはや阻むものは何もないのだ。
メイシアは、こうしてルイフォンの傍に居るし、〈悪魔〉の『契約』は、〈蝿〉の死と引き換えに、事実上、無効となった。
ルイフォンは、彼女と向き合うように、体を起こす。
「話してくれ。『デヴァイン・シンフォニア計画』は、お前が、ひとりで抱えるべき問題じゃない」
ルイフォンとメイシアは『ふたり』で居るのだから、メイシアが『ひとり』で苦しむのはおかしなことだ。
メイシアの喉がこくりと動き、薄紅の唇がゆっくりと動き出す。
「私、まだ言っていなかったの。セレイエさんの心からの願い。『デヴァイン・シンフォニア計画』の――セレイエさんの真の目的を……」
「なっ!?」
ルイフォンは、メイシアの言葉の途中で、思わず驚愕の叫びを上げた。
「セレイエの目的って、息子の『ライシェン』を生き返らせることじゃないのか!?」
メイシアが、すべて言い終えるまで待つのが礼儀だ。しかし、口を挟まずにいられなかったのだ。
「――と、すまん」
話を遮った彼にメイシアは気を悪くしたふうもなく、むしろ、自分の話の進め方がよくなかったことを恥じらうように「ううん」と首を振る。
「その通りなんだけど、それだと半分なの」
「半分?」
「うん。『ライシェン』を生き返らせることは、大前提。でも、セレイエさんには技術で解決する『蘇生』よりも、もっと重要視していたことがあったの」
セレイエの気持ちに同調しているのだろうか。メイシアは切なげに顔を歪めた。
彼女は祈るように瞳を閉じ、澄んだ声で告げる。
「『生き返った『ライシェン』が、今度こそ幸せな人生を送れるようにすること』――これがセレイエさんの願いで、『デヴァイン・シンフォニア計画』の真の目的」
その瞬間、ルイフォンは軽い困惑と、不思議な感覚に陥った。
あの我儘で、自己中心的な異父姉も、『母親』になったのだなと、初めて心に響いた。『ライシェン』が、セレイエの息子だという話は既に聞いていたが、今まで実感がなかったのだ。
そして。
それはつまり、あの硝子ケースの中の赤子は、ルイフォンとは血の繋がった甥ということでもある。
「セレイエさんは『ライシェン』のために、ふたつの道を用意したの」
メイシアの声が、静かに続けられる。
「ひとつ目は、オリジナルのライシェンが本来、送るはずだった未来。王家に生まれた〈神の御子〉として、王となる道」
ルイフォンは、ただ黙って、相槌を打つように頷く。
ライシェンが誕生した当時、男の〈神の御子〉は先王シルフェン、ただひとりだった。だから、ライシェンは生まれた瞬間に、次代の王を約束されたはずだった。
「『ライシェン』が、スムーズに王位を継承するためには、女王陛下の御子として生まれるのが順当。だから、セレイエさんは、過去の王の遺伝子をすべて廃棄して、『ライシェン』を唯一の〈神の御子〉の男子にしたの。そして、更に……」
まだ、何かあるのか? と、また余計な口出しをしそうなところを、ルイフォンはぐっと押さえ、無言で耳をそばだてる。
「セレイエさんは……――正確には〈影〉のホンシュアが、『唯一の〈神の御子〉の男子である『ライシェン』を渡してほしければ、女王陛下の夫をヤンイェン殿下にするように』と、カイウォル摂政殿下に迫ったの。そうすれば、『ライシェン』は、実の父であるヤンイェン殿下の子供として生まれることができるから……」
「……」
――そう。
セレイエが子供を産んでいたことにも驚いたが、その子供の父親が、王族のヤンイェンであったことも、ルイフォンには衝撃だった。
母のキリファは『セレイエは、貴族と駆け落ちした』と言っていたが、それは『セレイエは、身分違いの相手の子供を身ごもった』ということを示唆していたのだ。
ヤンイェンは、表向きは神殿に属する神官である。しかし、彼の実質の役割は、先王から〈七つの大罪〉の運営を一手に任された、事実上の〈七つの大罪〉の最高責任者だった。
『自分のことを知りたい』と言って〈七つの大罪〉に飛び込んでいったセレイエと出逢ったのは、自然の流れだったのだろう。
「ん? ヤンイェンって、もともと女王の婚約者に内定していたんだろ? なら、そんな脅迫まがいのことをしなくても、夫に決まったんじゃないのか?」
「ルイフォン、思い出して。ヤンイェン殿下は、公的には病気静養だったけど、本当は先王陛下を弑逆した罪で幽閉されていたの。そんな大罪人が女王陛下の夫になるなんて、あり得ないでしょう?」
「!」
ヤンイェンは、息子のライシェンを殺された恨みで、先王を殺害した。その思いは正当であったとしても、許される罪ではない。
「ましてや、女王陛下の夫を誰にするかの決定権があるのは、この国の現在の最高権力者、カイウォル摂政殿下なんだもの。彼にしてみれば、仲の悪いヤンイェン殿下なんて選びたくないはず」
「そうだよな……」
「摂政殿下は、ヤンイェン殿下を生涯、幽閉の館に閉じ込めておくつもりだった。摂政であれば、それができるだけの権力があった」
淡々と告げるメイシアの顔が、切なげに揺れる。それは、おそらく、メイシア自身の感情ではなく、セレイエのものだろう。
セレイエは、愛しいヤンイェンが一生、囚われの身であることを憂い、彼を解放するためにも、彼を『女王の夫』にする必要があったのだ。
「ヤンイェン殿下は、その血統から、内々に女王陛下の婚約者とされていただけで、正式に発表されていたわけじゃない。だから、摂政殿下が『療養が必要なヤンイェン殿下よりも、他の健康な者を陛下の婚約者に選んだ』と言えば、誰もが納得する状況だった」
「そこに、セレイエが横槍を入れた、というわけか」
「うん……」
『国王殺しの反逆者が、どうして女王の婚約者になれる?』――リュイセンが散々、疑問を投げつけ、だから、ヤンイェンが黒幕ではないかと訝しんだこともあった。その謎の答えが、セレイエだった……。
――セレイエは、一国の摂政を相手に喧嘩を売ったのだ。
ルイフォンは頭を抱えたくなった。ハオリュウとのやり取りを盗み見た限り、摂政に良い印象はまったくないが、だからといって敵に回すべき相手ではないだろう。
「あの摂政、絶対に厄介だぞ……」
ルイフォンの無意識のぼやきに、メイシアが「うん」と深々と頷く。
「セレイエさんも、カイウォル摂政殿下のいる王宮で『ライシェン』が王となることは、必ずしも幸せな道だとは思わなかった。だから、もうひとつの未来を用意したの。それが、ふたつ目の道」
そう告げたメイシアの顔には、惑うような、泣き笑いの表情が浮かんでいた。
「……?」
ルイフォンは首をかしげ、けれど彼の両腕は、惹き寄せられるようにメイシアへと動いた。彼女を抱きしめなければ、と思ったのだ。
指先に黒絹の髪を絡め、くしゃりと撫でる。
メイシアは、驚いたように瞳を瞬かせたが、すぐに彼の背に手を回してきた。
「セレイエさんは『ライシェン』に、愛情あふれる家庭の、平凡な子供として生きる道を用意したの。優しい養父母に愛されて、のびのびと育ってほしい、って」
「優しい養父母……」
かすれた声で、ルイフォンは唱える。
現実味などない。けれど、セレイエの意図が今、はっきりと見えた。
「セレイエさんは、ルイフォンと私に、『ライシェン』を育ててほしいと願ったの。……だから、私たちを出逢わせた」
セレイエの声が、記憶の中のどこかで響く。
『デヴァイン・シンフォニア』は、『di;vine+sin;fonia』――『神』として生まれたライシェンに捧げる交響曲であり、『命に対する冒涜』。
それでも、私は願わずにはいられなかった。
人を恐れたライシェンが世界を愛することを。
人を殺めたライシェンが世界に愛されることを――。
私が選んだ、ふたりに託す。
貴族の娘と凶賊の息子。
天と地が手を繋ぎ合うような奇跡の出逢いを私は紡ぐ。
この光の糸は、運命の糸。
人の運命は、天球儀を巡る輪環。
そして私は、本来なら交わることのなかった、ふたりの軌道を重ね合わせる。
1.真白き夜更け-2

「セレイエさんは『ライシェン』に、愛し、愛される、幸せな世界を贈りたかったの」
メイシアの声を借り、セレイエの願いが唱えられた。
窓からの涼風が薄いカーテンを揺らし、差し込んできた白い月明かりが、セレイエの祈りを包み込む。我が子の幸せを望む愛情が、淡い光に溶けていく。
「セレイエさんは、本物の愛、真実の愛で『ライシェン』を迎えてあげたかった。だから、養父母にと選んだ私たちのことは、ただ出逢いを仕組んだだけで、心を操るようなことはしなかったの」
「そう……か」
ルイフォンは、忘れかけていた出来ごとを思い出す。
以前〈蝿〉に、『メイシアの恋心は、操られてのものだ』と言われ、激しく動揺したことがあった。そう考えたほうが、セレイエと『デヴァイン・シンフォニア計画』にとって都合がよいと思われ、〈蝿〉の言葉は理に適っていると惑わされてしまったのだ。
「――なるほどな」
もはや気にも留めていなかったことだが、やはり、どこかすっきりした。
「異父弟のルイフォンと、ヤンイェン殿下の再従兄妹の私。このふたりなら必ず惹かれ合うって、セレイエさんは信じていた。――だって、自分とヤンイェン殿下の血縁なんだから、って」
「滅茶苦茶な理屈だな」
思わずそう口走り、だが結局はセレイエの思惑通りになったわけで……、ルイフォンは憮然として押し黙る。
「でもね、期待通りに私たちが恋仲にならなくても、私たちなら『ライシェン』に愛のある環境を与えてくれるって、セレイエさんは疑っていなかった。『ライシェン』が幸せなら、細かいことは気にしないって。……セレイエさん、ちょっとルイフォンに似ている」
メイシアが、くすりと笑いながら言う。けれど、その語尾は不自然に崩れ、涙声となって消えた。
「どうした?」
「ルイフォン……」
メイシアの声が、彼女のものとは思えぬほどに低く響いた。
ルイフォンは黒絹の髪に指を絡め、何を打ち明けても大丈夫だと示す。
「昼間、〈蝿〉も言ったけど……、セレイエさんは亡くなったの。――私たちにライシェンを託して」
「……ああ」
ずっと、そんな気がしていた。
あの異父姉が生きているのなら、自分の作った『デヴァイン・シンフォニア計画』を人任せなんかにしない。中心となって動き回り、とっくにルイフォンの前に現れているはずだ。現に、〈影〉のホンシュアは、高熱を押して彼に会いに来たのだから。
「早く言わなきゃ、って思っていたけど、彼女が亡くなった原因が〈冥王〉と関係があるから言えなかった。『〈冥王〉』と口にしただけで、〈悪魔〉の『契約』に抵触してしまったから……」
「〈冥王〉?」
意外な名前に、ルイフォンは顔色を変えた。
セレイエは、てっきり王宮の関係者に殺されたとばかり思っていたのだ。
「〈蝿〉から聞いたでしょう? 〈冥王〉は、〈神の御子〉の負荷を肩代わりして、ありとあらゆる情報を無限に収集する有機コンピュータだ、って。つまり、〈冥王〉は『人間の記憶を集約する、巨大なデータベース』といえるの」
「あ、ああ……?」
だが、それがセレイエとどう関係するのだ? と、ルイフォンは眉を寄せる。
「セレイエさんは、〈冥王〉に侵入して、膨大な記憶の中から『オリジナルのライシェン』の記憶を掻き集めたの。『ライシェンが亡くなったばかりで、まだあちこちに記憶が飛び散っていなかったこと』、『セレイエさんが王族の血を引いた、力の強い〈天使〉だったこと』から、ぎりぎり可能だった」
ルイフォンは、はっと息を呑んだ。
「そうか……。『ライシェン』を生き返らせるためには、新しい『肉体』と、オリジナルの『記憶』が必要――赤ん坊にだって、ちゃんと記憶はあるはずだからな」
『肉体』だけだったら、それはクローンであって、『ライシェンを生き返らせた』ことにはならない。少なくとも、セレイエなら、そう考えるはずだ。
「セレイエさんは、広大な砂漠の中から一粒の砂を見つけ出すような無茶をした――〈冥王〉への侵入の中で〈天使〉の力の限界を超えてしまって、熱暴走を起こしたの」
「そういうことか……」
ルイフォンの呟きに、メイシアの声が「うん」と沈む。
「熱暴走が止まらなくなることは、初めから計算できていたの。ライシェンの記憶を手に入れれば自分は死ぬって、セレイエさんは知っていた。それで構わない。むしろ、死者の蘇生なんて、そのくらいの代償がなければ、やってはいけない『罪』だって」
メイシアは、ルイフォンの服をぎゅっと握りしめた。「あのね……」という呼びかけの声が、弱々しく揺らぐ。だから彼は、黙って彼女を抱きしめる。
「〈冥王〉への侵入で命を落としても、新しい『セレイエさんの肉体』があれば、生き返ることができる。『ライシェン』の肉体と一緒に作ればいい。――そのことに、セレイエさんは気づいていた」
「……え?」
「だって、セレイエさんの『記憶』なら、ホンシュアが持っているんだもの、『肉体』と『記憶』が揃えば、蘇生できるわけでしょう?」
「!」
その通りだ。
しかし、セレイエは……?
目を見開いたルイフォンに、メイシアが頷く。
「でも、セレイエさんは、自分が生き返ることを望まなかった。だって、それは『罪』だと、彼女はちゃんと分かっていたから。――それでもっ」
メイシアが、ぐっと顔を上げた。
潤んだ瞳で、けれど、毅然とした眼差しで、彼女は告げる。
「自分の命をひとつ捧げるから、『ライシェン』の命をひとつ与えてほしい。……ううん、手に入れてみせる――って、彼女は笑って〈冥王〉に侵入したの……!」
メイシアの瞳から、涙がこぼれ落ちた。
「セレイエの奴……!」
ルイフォンは奥歯を噛みしめる。
母親そっくりの、とんでもない異父姉だが、血を分けた異父姉弟だ。彼だって、彼女の死を悼んでいる。
なのに……。
――否、だからこそ……。
「子供のために、笑って命を捧げた――だと……!」
押し殺した声で、うなるようにルイフォンは漏らす。それは徐々に大きくなり、やがて悲痛の叫びとなった。
「そっくり同じことを、俺たちの母さんもしたんだぞ……! お前のために! セレイエ!」
ルイフォンの咆哮が、白い月夜に木霊する。
詳しい事情は分からない。
けれど、間違いない。
母のキリファは、セレイエのために、自分の脳を使って有機コンピュータ〈スー〉を完成させた。
「ふざけんなよ……!」
母の最期を、ルイフォンは覚えている。〈天使〉の母に消されるはずだった記憶を、彼は強い意志の力で手放さなかった。
――母は、誇らしげに笑っていた。
ルイフォンの瞳に焼きついているその顔と、〈冥王〉へと向かったセレイエのそれは……。
そっくり同じ表情なのだろう……。
「ルイフォン……」
メイシアの手が彼を掻き抱くように伸ばされ、後ろから髪に触れた。彼は、その手に誘われるように彼女の肩に頭を預ける。
彼の背で一本に編まれた髪が揺れ、毛先を飾る金の鈴が月光を弾いた。
白い月が傾きを変え、夏の虫たちが歌い手を交代していく。
ルイフォンとメイシアは、どちらからともなく顔を上げ、互いを見つめ合った。
「ごめんなさい。話が、ぐちゃぐちゃになっちゃった」
明らかに無理やりであったが、メイシアが、ふわりと柔らかに笑う。
「ちゃんと、筋道を立てて話さなきゃね。『デヴァイン・シンフォニア計画』のこと。セレイエさんがしてきたこと。セレイエさんがしようとしていたこと……」
「ああ。頼む。教えてくれ」
メイシアの心遣いに感謝し、笑顔のぎこちなさには気づかないふりだ。
どんなことが語られても泰然と受け止めよう、そう思った矢先、彼女の顔がにわかに改まり、緊張と……困惑のようなものが入り混じった。
「メイシア?」
「セレイエさんは、〈冥王〉から掻き集めたライシェンの『記憶』を、亡くなる前にルイフォンに預けたの」
「……は?」
理解できない。
「ええと、ね。『ライシェン』が生まれるまでの間、セレイエさんが手に入れたオリジナルのライシェンの『記憶』は、どこかに保管しておく必要がある、というのは……分かるかしら?」
「それならば分かる。『肉体』がなければ『記憶』の入れようがない、ってことだろ?」
「うん。そんな感じ」
ルイフォンらしい解釈の仕方に、メイシアは苦笑しながらも同意する。
「『記憶』とは脳に刻まれるものだから、『記憶』を保管できる場所とは、すなわち『人間の脳』。――ほら、〈冥王〉だって、王の『脳』細胞からできているわけでしょう?」
「あ、ああ……、そう……だよな?」
ゆっくりと咀嚼するように、けれど、すぐには呑み込めずに、ルイフォンは曖昧に相槌を打つ。
「でも、『誰かの脳』に、ライシェンの記憶を書き込んだら、その人はライシェンの〈影〉になってしまう」
メイシアの声が硬さを帯びた。
「そもそも、セレイエさんが、どうやってライシェンの記憶を集めたかというと……」
彼女は説明に悩むように口ごもり、それから、細い声を響かせる。
「〈冥王〉に侵入した彼女は、ライシェンの記憶を見つけては、『自分の脳』に複製を書き込んでいったの」
「そんなことをすれば、セレイエが、ライシェンの〈影〉になるんじゃ……?」
訝しげに問うたルイフォンに、メイシアは、すかさず「ええとね」と受けた。
「セレイエさんはキリファさんの子供で、わずかながらだけど王族の血を引いているから、一般人よりも脳の容量が大きいの。だから、普段、使ってない領域にライシェンの記憶を書き込むことで、〈影〉になることを回避できたの」
メイシアは、上手く伝わっているかを確認するように、不安げな目でルイフォンを見上げた。彼は納得したと、深く頷く。
「お前がセレイエの記憶を持っていても、お前のままでいるのと同じ理屈だな?」
「うん、そう」
メイシアの顔が少しだけ、ほころぶ。
「――そして」
黒曜石の瞳が、まっすぐにルイフォンを捉えた。
反射的に、彼の猫背が伸びる。
「セレイエさんと同じく、キリファさんの子供であるルイフォンも、普通の人よりも脳の容量が大きいの。――だから、セレイエさんは、異父弟にライシェンの記憶を預けた。彼女が持ったままでは、彼女の肉体の死と共に、ライシェンの記憶も失われてしまうから……」
「――!」
理解した……理屈は。
だからといって、感情がついていかない。
「嘘……だろ? 俺の脳に、ライシェンの記憶……?」
いくらメイシアの弁でも、にわかには信じがたい。しかし、メイシアが、遠慮がちに水を向ける。
「キリファさんが亡くなったあと、ひとりになってしまったルイフォンは、しばらくの間、シャオリエさんのところにご厄介になっていたでしょう? そこに、セレイエさんが訪ねてきたことがあった……」
「!」
猫の目が見開かれた。
そうだ。
ルイフォンの記憶にはないが、世話をしてくれていた少女娼婦スーリンが、セレイエの来訪を証言している。しかもスーリンは、セレイエの〈天使〉姿を目撃しているのだ。
「あのとき……、セレイエは、俺の脳にライシェンの記憶を書き込みに来たのか……」
解けていく謎に愕然としていると、メイシアの言葉が更に続いた。
「しかも、ルイフォンの中に書き込まれた記憶は、ただの記憶じゃなくて、ルイフォンが見聞きし、考えたことから『善悪』を学び、成長していく心なの」
「俺から『善悪』を学ぶだって……? 俺の価値基準に何を期待……」
軽口を叩きかけ、はっと気づく。
「――オリジナルは、人を殺したんだったな」
如何にルイフォンといえど、さすがに口調が重くなった。メイシアも沈鬱な面持ちで「うん」と頷く。
「新しく作られる『ライシェン』の肉体の目が見えたとしても、〈神の御子〉の力が消える保証はない。だから、その場合でも同じ悲劇を繰り返さないように、セレイエさんはルイフォンを教育係にしたの」
「セレイエの奴……、やりたい放題だな」
ルイフォンは渋面になる。――わずかな懐かしさを含ませながら。
緻密で巧妙なプログラムは、セレイエの特徴。抜け目がなくて、ちゃっかりしているところが如何にも彼女らしい。
「それからね」
感傷めいたものに浸っていると、メイシアが彼の顔を窺いながら、そっと口を開いた。
「私が『お守り』だと信じていたペンダント――セレイエさんが、スーリンさんに『目印』だと言ったあれは、『ルイフォンの中にいる、ライシェン』に、迎えにきたことを教えるための『目印』だったの。姿は変わっていても、『目印』を持った人の中にセレイエさんがいるから安心して、って」
その瞬間。
ルイフォンの脳裏に、さらさらとした鎖の感触が浮かび上がった。それから流れるような、金属の響き合う音。
「メイシアのペンダント……、俺は『見たことがある』と感じた」
ぽつりと呟き、「違うな」と首を振る。
「――『見て』はいないんだ。盲目のライシェンが触って、金属のこすれる音を聞いて『知っていた』。その『記憶』を、俺は持っていたんだ……」
ホンシュアに会ったとき、ルイフォンは彼女を『母さん』と呼んだ。あれは、彼の中にいるライシェンの言葉だったのだ。
「あのペンダントは、ヤンイェン殿下がセレイエさんに贈ったものなの。彼女はいつも身につけていて、ライシェンは抱っこのときに、よく触っていたの」
メイシアが自分の胸元に手をやる。ペンダントに触れるときの仕草だ。
彼女は『ペンダントを握りしめると、安心する』と言っていた。セレイエの〈影〉であったホンシュアに、そう思い込まされたのだ。
そんな癖があれば、凶賊である鷹刀一族の屋敷を訪れた、貴族の箱入り娘のメイシアは、自分を奮い立たそうと、必ずルイフォンの前でペンダントを握ることになる。
やたらと触っていれば、ルイフォンは嫌でもペンダントに注目する。すなわち、『ルイフォンの中にいる、ライシェン』が『目印』に気づく――という構図だったのだ。
持っていると狙われる、危険な『目印』だと思い、預かってしまったのだが、彼こそが――正確には『彼の中のライシェン』こそが、『目印』に気づくべき対象者であったとは、なんとも滑稽な話である。
「ルイフォン」
ペンダントに関する考察に意識を飛ばしていたルイフォンは、メイシアの声に我に返った。
彼女は、悲壮にも見える深刻な顔をしていた。
「今まで話したことが、セレイエさんがしてきたこと――過去のこと。今から、セレイエさんがしようとしていたことを――未来の話をしようと思うのだけれど、その前に、ちゃんと……正確な情報で、伝えておかなければいけないことがあるの」
彼女は逡巡に言葉を詰まらせ、けれど、思い切ったように顔を上げると、澄んだ声を響かせた。
「セレイエさんの……本当の最期の情報を――」
1.真白き夜更け-3

「はっ!? セレイエの最期って、熱暴走なんだろ?」
メイシアは先ほど、そう言ったはずだ。
何故、またその話を? との疑問を含ませてルイフォンが問いかけると、彼女は曖昧に頷き、静かに口を開く。
「〈冥王〉への侵入から戻ってきて、ルイフォンにライシェンの記憶を預けたら、セレイエさんの熱暴走は、もう冷却剤をいくら飲んでも止まらなかった。もはや死は免れない。それが、はっきりと分かる状態だった。だから……」
メイシアの花の顔が、切なげに歪んだ。
「『ひと目でいいから、ヤンイェンに逢いたい』と言って、セレイエさんは、殿下が幽閉されている館に向かったの。彼女は最後の力を振り絞り、〈天使〉の羽を広げて、警備の者の目を――記憶を掻いくぐった……」
メイシアの背後で、レースのカーテンが、ふわりと風に舞った。
その瞬間、白い月光を浴びた彼女の背から羽が生えたように見え、ルイフォンは狼狽した。
「!?」
――無論、錯覚だった。
安堵すると同時に、どうかしていると、ルイフォンは自分を叱咤する。セレイエの最期を想像して〈天使〉の幻影を見たのだろうが、それをメイシアに重ねてしまうなんて縁起でもない。
動揺をメイシアに気取られぬよう、ルイフォンは先を促すような相槌を打ち、そっと表情を誤魔化した。
「今にも崩れ落ちそうなセレイエさんの背中を、ホンシュアは見送ったの。――ほら、私にセレイエさんの記憶を書き込んだのは、『セレイエさん本人』ではなくて『〈影〉のホンシュア』なわけでしょう? だから、私の知っている最期の光景は『ホンシュアの目線』になるの」
「ああ、そうか。……そうなるのか」
――ということは、セレイエは死んだとは限らない……?
ルイフォンの胸中に疑念がもたげる。
彼が顔色を変えたことに、メイシアは当然、気づいただろう。しかし、彼女はそのまま話を続けた。
「ホンシュアは、最後までセレイエさんと一緒にいたわけじゃないから、セレイエさんが無事に殿下と会えたかどうかは分からない。途中で力尽きてしまったかもしれないし、弱りきったところを警備の者に捕まり、酷い目に遭わされたかもしれない。――セレイエさんの最期の様子は、正確には分からないの……」
そこでメイシアは、うつむき加減になって薄紅の唇を噛み締める。
「どうした?」
「ルイフォン……」
「セレイエが生きている可能性を考えているんだな? ――お前も」
ルイフォンの問いに、メイシアの頭が一度こくりと動きかけ、しかし首は左右に振られた。
「メイシア?」
「ホンシュアは、セレイエさんが息を引き取るところを見ていない。だから、私は、セレイエさんが一命をとりとめた可能性を否定できない。――けど!」
メイシアが勢いよく顔を上げた。硬い表情で、まっすぐにルイフォンを見つめる。
「それは、希望的観測でしかないの……。――だって、私の中のセレイエさんの記憶が告げている。あの状態になった〈天使〉に助かる術などないって」
震える声で言い切ると、堪えきれなくなったように「ごめんなさい」と、黒曜石の瞳が伏せられた。
「セレイエさんの最期をありのまま伝えれば、ルイフォンが希望を持ってしまうのは分かりきっていた。私だって、セレイエさんが無事であってほしいと思う。私自身は、生きていると信じたい……」
鈴を転がすようなメイシアの声が徐々に薄れていき、そこから急に弾ける。
「――でも、あり得ないの……! ごめんなさい。黙っていたほうがよかったのかもしれないけど、ルイフォンには、ちゃんと言いたかったし、言うべきだと思ったから……」
細い首がうなだれ、黒絹の髪が顔を隠すように流れた。その姿は、消え入りそうなほどに儚げで、ルイフォンは思わず彼女を抱き寄せる。
「なんで、お前が謝るんだよ? 俺は、教えてくれて嬉しい。気を遣ってくれてありがとな」
心優しいメイシアにとって、もしかしたらという希望を、絶望に塗り替えて伝えねばならなかったのは、どんなに酷であったことだろう。
彼は彼女の髪をくしゃりと撫でる。
「セレイエは死んだんだろう。無事でいるのなら、俺たちに接触してくるはずだ」
「……うん」
細くかすれてはいたが、メイシアの声は、どこか胸のつかえが取れたような響きをしていた。
ルイフォンは気持ちを切り替えるように、「それよりさ」と、努めて明るい声を作る。
「俺たちが『ライシェン』を連れてきたことを、父親のヤンイェンに教えないとな。セレイエの計画にはなかった展開だろ? 心配するはずだ。――けど、平民から王族には近づけないし……、ヤンイェンが異変に気づいて、俺たちに連絡してくるのを待つ感じかな」
あの異父姉と恋に落ち、子供までもうけたという王族、ヤンイェン。
いったい、どんな人物なのか。
まだ見ぬ、事実上の義兄というべき相手への想像を膨らませていると、メイシアが申し訳なさそうに眉を寄せ、口ごもりながら「あのね」と切り出した。
「ヤンイェン殿下は、『デヴァイン・シンフォニア計画』のことをご存知ないの。だから、ルイフォンや私が『ライシェン』と関わりがあるなんて、まったく知らないの」
「なっ!?」
「確かにね、オリジナルのライシェンが殺された直後から、ヤンイェン殿下とセレイエさんは〈七つの大罪〉の技術で息子を生き返らせることを考えていた。でもそれは、王宮を離れ、三人で静かに暮らしたいという思いからで、『デヴァイン・シンフォニア計画』のように『ライシェン』を女王陛下の御子として誕生させる気なんてなかったの」
「なん……だって……?」
困惑に目を瞬かせるルイフォンに、メイシアが言葉を重ねる。
「殿下とセレイエさんは、息子を殺した先王陛下への憎しみはあったけれど、それはオリジナルのライシェンが人を殺してしまったからだと、理性で乗り越えようとしていた」
「え……?」
ルイフォンにとって、ヤンイェンは名前しか知らない相手だ。だから、先王を殺したという事実から血の気の多い男だと考えていた。しかし、どうやら違うらしい。
「じゃあ、ヤンイェンは、どうして先王を殺したんだ?」
「ライシェンを蘇生させようとしていることに気づいた先王陛下が、ヤンイェン殿下を呼び出して厳しくお叱りになったから。先王陛下は〈七つの大罪〉の『技術は禁忌だ』とおっしゃり、ヤンイェン殿下は『『ライシェン』には人を殺させないから認めてほしい』と主張した。ふたりは口論になって、殿下には堪えていた恨みもあって押さえきれずに――それで……」
ルイフォンは「なるほど」と納得しかけ、途中で、はっと矛盾に気づく。
「待った! 〈七つの大罪〉は、王を頂点とした秘密研究機関だろ? 先王にしてみれば、いわば『自分のところの組織』だ。そこで開発された技術を所有者自らが、なんで禁忌だなんて言うんだよ?」
「それは、先王陛下が〈七つの大罪〉の技術を憎んでらしたから。……ルイフォン、覚えている? 先王陛下は、王位を継ぐためだけに作られた『過去の王のクローン』だった、ってこと」
「あー……」
そういえば、ハオリュウと摂政の密談を盗み見たときに、そんな話が出た気がする。
愛情を与えてもらえなかった先王は〈七つの大罪〉の技術を拒み、クローンに頼らない王位継承者を求めて、公的には姉である女性を手籠めにした、と。
そして、生まれたのがヤンイェン。だから、先王とヤンイェンは実の父子だ。
「ヤンイェンは、実の父親を殺したことになるのか……」
「うん……」
メイシアは「いろいろ、あったの」と呟き、遠い日を思い出すような目で、遠くの白い月を見やる。
「あのね、ライシェンが生まれたとき、先王陛下が一番、喜んでくださったの。ご自身が作られた存在だったから、自然に生まれたライシェンを心から祝福してくださった。母親が平民だって構わない、って」
「はぁ? 嘘だろ?」
ルイフォンは反射的に不審の声を上げたが、この場でメイシアが嘘を言うはずもない。彼が気まずげに首をすくめると、月に照らされた彼女の横顔は、ただ悲しげに微笑んでいた。
「それが、どうして、こうなっちゃったんだろう……。誰も、悪くなかったはずなのに……」
「……!?」
今のは、セレイエの言葉だ。
メイシアが、セレイエの感情に流された。
戦慄する彼の前で、レースのカーテンが風に舞い、途方に暮れたように落とされたメイシアの肩をかすめた。差し込んできた白い光がふわりと広がり、彼女の背に再び幻影の羽を作り出す。
刹那。
ルイフォンの耳に、エルファンの言葉が蘇った。
『セレイエは、メイシアを『最強の〈天使〉』にして、その体を乗っ取ろうとしている』
メイシアが〈蝿〉のもとへさらわれる直前、エルファンは断片的な情報から、そう推測した。
だが、先ほどメイシアから明かされた『デヴァイン・シンフォニア計画』の『真の目的』からすれば、セレイエが願ってやまない『本物の愛』、『真実の愛』のためには、メイシアが乗っ取られる心配はないと信じてよいはずだ。
ただし。
メイシアが『最強の〈天使〉』になり得るのは真実。
娼館生まれの母キリファは、わずかに王族の血が混じっていたというだけで、力の強い〈天使〉となった。では、王族の血を色濃く引くメイシアならば――。
「!」
その瞬間、彼は理解した。
セレイエは、メイシアを『最強の〈天使〉』にして、『ライシェン』の庇護を託すつもりだ。
風がそよぎ、月光が差し込む。
黒絹の髪がなびき、白金の羽が背中に広がる。
「メイシア!」
ルイフォンは、思わず彼女の名を叫んだ。
急激に鼓動が跳ね上がり、全身に嫌な汗が噴き上がる。
……幻だ。
光の具合いで、そう見えただけだ……。
「ルイフォン!? どうしたの?」
「あ、いや……。……つまり、ヤンイェンが先王を殺して幽閉されたあとで、セレイエは『デヴァイン・シンフォニア計画』をひとりで組み上げた、ってわけだな。……ああ、そうか。ヤンイェンの解放を求めて、摂政を脅迫したとか言っていたしな……。ヤンイェンが身動きを取れないから、俺やメイシアに託したというわけか……」
ルイフォンはしどろもどろになりながら、無理やりに話を繋ぐ。
……気づいてしまったのだ。
否。無意識のうちに、気づいていたのだ。だから、メイシアに〈天使〉の幻影を見た。
メイシアは、ホンシュアと接触したときに、気づかぬうちに『セレイエの記憶』を受け取った。
ならば、そのとき、知らぬうちに『〈天使〉の羽』も受け取っていたとしてもおかしくない。
つまり――。
メイシアは、既に〈天使〉となっている可能性がある。
1.真白き夜更け-4

セレイエは、メイシアを『最強の〈天使〉』にして、『ライシェン』の庇護を託すつもりだ。
そして。
メイシアは既に、〈天使〉となっている可能性がある。
それも、本人の知らないうちに……。
ルイフォンは、荒くなる呼吸を必死に抑えた。
電灯はつけておらず、白い月明かりの下だ。メイシアは、彼の顔色の悪さに気づいていないはずだと、平静を装う。
彼の努力が功を奏したのだろう。メイシアは少しだけ不思議そうな顔をしていたが、やがて、柔らかに微笑んだ。
「いつまでも、セレイエさんの辛い過去を悲しんでいるだけじゃ駄目よね。私たちは未来のことを考えなきゃ」
黒曜石の瞳に、凛とした知性の光が灯る。けれど、口元に手を当てて考え込む仕草は、どこか可愛らしい。
メイシアらしい姿だ。
愛しさがこみ上げ、早鐘を打っていた心臓が落ち着きを取り戻す。
彼女が〈天使〉になっていようが、いまいが、そんなことは関係ない。彼はただ、彼女を守っていくだけだ――。
メイシアがルイフォンを見上げ、口を開いた。
「ともかく、どうにかして、ヤンイェン殿下に『ライシェン』が鷹刀にいることをお知らせしなきゃ」
「そうだな」
ルイフォンは頷いて同意を示し、そして尋ねる。
「なぁ、メイシア。そもそも、セレイエは何をどうするつもりだったんだ?」
「え? ええとね……」
メイシアは、わずかに首を傾け、指先を軽く頭に添えた。文字通り、セレイエの記憶をたどっているのだろう。
「セレイエさんの計画では、もう少ししたら私の中のセレイエさんが自然に目覚めて、ホンシュアと連絡を取る予定だった。それをきっかけに、ルイフォンも中にいるライシェンから王族の『秘密』をそれとなく感じ取れるようになって、私たちの間では〈悪魔〉の『契約』は無効になるはずだったの」
「……随分と都合のいい話だな」
ルイフォンの茶々に、メイシアはなんともいえない苦笑をする。
「ホンシュアの手引きで、私とルイフォンが『ライシェン』に会いにいく。そして、ルイフォンに預けた記憶を、ホンシュアが『ライシェン』に写す。――それから、『ライシェン』は王宮に引き渡され、女王陛下の御子として誕生することになっていた……」
メイシアの肩口で、カーテンがはためいた。
月明かりが広がり、彼女の背に幻の羽を描き出す。
ルイフォンはカーテンの端をむんずと掴むと、邪魔だとばかりに薙ぎ払った。全開となった窓が白く輝き、幻影の羽は光の中に解けていく。
彼は満足げに口元を緩めると、メイシアに向き直った。
「セレイエはさ、生まれたあとの『ライシェン』に、ふたつの未来を用意したんだよな? 実父のヤンイェンのもとで王として生きる道と、俺たちに引き取られて平凡な子供として生きる道」
「うん、そう」
「じゃあ、どちらにするかを選ぶのは『いつ』だ? そして『誰』だ?」
「え?」
メイシアの瞳が、戸惑いに揺れた。問い詰めるような言い方になってしまったことを悔いつつ、ルイフォンは続ける。
「セレイエは、緻密で巧妙な計画を書く奴だ。でも、『ライシェン』の未来に起こり得る、無限にある状態の組み合わせの中から、あらかじめ『幸せ』の最適解を求めておくことは不可能だ。――だから、ふたつの未来を用意した」
ルイフォンは、癖の強い前髪を乱暴に掻き上げた。そして、確認の形を取りながらも、断言する。
「セレイエは、お前に全部、丸投げしたんだろ?」
「……っ!」
メイシアの目が驚愕に見開かれ、彼の顔を凝視した。
「セレイエは、死んでいく自分の代わりに、臨機応変に『ライシェン』を『幸せ』に導いてほしいと、お前に託した。『ライシェン』は、とりあえずは王として誕生する予定だけれど、それが不幸な道だと思ったら、いつでも王宮から掻っさらってきてほしい。そんな無茶苦茶ができるだけの力を――『最強の〈天使〉』の力を、お前に授けるから、と」
〈天使〉とは、人の脳に記憶や命令を書き込むクラッカー。
他人の目を――記憶を掻いくぐる無敵の存在。
『死』を招く命令を刻めば、人の死すらも操れる……。
強力な力の代償に、たいていの〈天使〉は、ほんの数回の脳内介入を行うだけで、限界を迎えて死に至る。
しかし、王族の血を色濃く引き、〈天使〉の力の使い方を熟知したセレイエの記憶を持つメイシアなら、熱暴走とは無縁だ――。
「ルイフォン……」
細い指先が伸びてきて、彼の服の端を握りしめた。その手は、小刻みに震えていた。
「セレイエさんは『ライシェン』を守り抜くことができる強い力を欲していた。……だから、私を選んだ。私にすべてを賭けて、私にすべてを託した。――『ライシェン』をお願い、って」
「セレイエの奴! 勝手なことを……! 〈天使〉って、要するに人体実験体だろうが!」
ルイフォンが吐き捨てる。その怒声に、メイシアが「あ、あのね」と、握っていた彼の服の端を強く引いた。
「生粋の〈天使〉であるセレイエさんにとって、〈天使〉の羽は、ちっとも特別なものじゃなかったの。お異母兄さんのレイウェンさんや、お義姉さんのシャンリーさんが持つ刀と同じ――誰かを傷つけるものではあるけれど、誰かを守るものでもあるという認識。怖いものでも、悪いものでもない……って」
「……」
セレイエが、初めてその背から羽を出したのは、敵対する凶賊に襲われ、小さな妹を守るために瀕死となった、異母兄と義姉を守るためだったという。あの事件がなければと、今でもレイウェンが悔やんでいることを、それとなく周りから聞いた……。
ルイフォンは唇を噛み締め、やるせない思いを無理矢理に溜め息にして吐き出す。
そして、メイシアをきつく抱きしめた。
腕の中にすっぽりと収まる華奢な体。ほのかに上気した肌の香り。それらを全身で愛くしみながら、彼はできるだけ穏やかで、柔らかなテノールで告げる。
「お前が鷹刀の屋敷に来る直前、お前の家に仕立て屋に化けたホンシュアが現れたとき――、お前はあのとき、気づかないうちに〈天使〉にされたと……思う」
セレイエが〈天使〉を忌避していないというのなら、間違いないだろう。
『デヴァイン・シンフォニア計画』を推し進めていくためには、メイシアが『最強の〈天使〉』になることは必須条件なのだから。
……別に構わない。
メイシアは、メイシアだ。
一緒に暮らしていた母のキリファと、異父姉のセレイエが〈天使〉であったことに、ルイフォンは今まで気づかなかったくらいなのだ。日常生活に支障はないだろう。
どんなことがあっても、彼女と共に在るだけだ。
ルイフォンが、改めて心に誓ったとき――。
「ルイフォン――!?」
絹を裂くような悲鳴――に、近い声が響き渡った。
「メイシア?」
「ち、違う! ルイフォン、勘違いしている!」
メイシアは慌てふためき、激しく首を振っていた。
「〈天使〉化って、そんな簡単にできることじゃないの! いつの間にか〈天使〉になっているなんてことはあり得ないの!」
「え……? なんだ……、そうなのか……?」
覚悟を決めて告げたのだが、拍子抜けだった。
「……そうだったのか」
不意に、喉が、目頭が、熱くなった。
あ、まずい……と思い、彼は堪えるべく、彼女の髪に顔を埋めた。彼女の存在を胸いっぱいに吸い込み、心を鎮める。
――俺、……弱いな。……情けねぇ。
今更のように、体が震えてきた。
「ルイ……フォン……?」
メイシアは戸惑いに声を揺らしたが、すぐに「心配してくれて、ありがとう」と、彼の背に手を回し、ぎゅっと抱きついてきた。
触れ合った部分から、温かな心音が伝わってくる。安らかなのに、彼を奮い立たせる旋律が刻まれていく。
「あのね、〈天使〉化するためには、〈冥王〉が収められている神殿まで行かないと駄目なの。〈天使〉の羽は、〈冥王〉の一部を移植することで作られるから。だから、私は〈天使〉になってない、って断言できる。――安心して」
「そうか。……よかった」
ルイフォンは、安堵の息を深く吐き出す。
『光の糸』を絡めて作ったような〈天使〉の羽が、『光の珠』の姿をしているという〈冥王〉から移植されたもの、というのは、納得できる話だ。
「……ああ、なるほど。〈天使〉の羽は、〈冥王〉の端末みたいなものなのか。だから母さんは、〈冥王〉を破壊すれば『〈天使〉の力の源』を絶てると言ったんだな」
思わぬところで、謎がひとつ解けた。母の遺した難題の一端を解析できたようで、ルイフォンは無意識に、にやりと笑みをこぼす。
すっかりいつもの調子を取り戻した彼に、ためらいがちなメイシアの声が響いた。
「ルイフォン、聞いて……」
消え入りそうな儚さに、どきりとした。
彼を見上げる黒曜石の瞳が、昏く沈んでいた。
「セレイエさんの計画では、私はホンシュアの手引きで神殿に潜入して、〈天使〉化することになっていたの。ホンシュアが〈天使〉の力で警備の目を誤魔化して、ね……」
「でも、ホンシュアは死んじまったから、お前は〈天使〉になれないし、そもそも、なる必要もない」
だから心配することはないだろ? と、ルイフォンは力強く言う。
「……でも、ホンシュアが亡くなって、私も〈天使〉にならなければ、ライシェンの記憶を『ライシェン』に書き込む〈天使〉がいないの」
思いつめたような声色だった。
「……メイシア?」
「セレイエさんは、命を擲ってライシェンの記憶を手に入れたのに……。セレイエさんの死が、無駄になってしまうの……!」
「それは……仕方ねぇだろ。少なくとも、お前が気に病むことじゃ……」
ルイフォンがそう言いかけたとき、メイシアが遮るように首を振った。
「私には、セレイエさんの記憶がある。だから、人間を〈天使〉にする方法を知っている。そして、神殿への潜入は、ホンシュアの力に頼らなくても、武力で突破することだってできるはずなの……」
メイシアの目元が歪んだ。うつむき、すがるように彼の胸に顔を埋める。
「私が、まだ〈天使〉になっていなくても、『デヴァイン・シンフォニア計画』は……、『ライシェン』の運命は……、既に、私の手に……委ねられているの……!」
「――!」
見えない毒刃を心臓に突き立てられたような衝撃を感じた。
菖蒲の館で聞いた、死を目前にした〈蝿〉の声が、猛毒のように全身を駆け巡る。
『ルイフォン、メイシア。――鷹刀セレイエが『デヴァイン・シンフォニア計画』のために選んだ、あなたたち』
『『ライシェン』をどうするか――』
『処分するのか……』
『すべては、あなたたちの思うがままに……。『ライシェン』の命運、その全権をあなたたちに委ねます』
ルイフォンは〈蝿〉の言葉を嚥下し、重く噛みしめる。
「……ルイフォン。私……、どうすれば……」
目の前で、華奢な肩が震えていた。
それは、寒さからなどではない。けれど、彼女の心が凍えないようにと、ルイフォンは全身で彼女を包み込む。
「メイシア、間違えるな。『お前』がどうする、じゃない。『俺たち』がどうするか、だ。『ライシェン』のことは『俺たち』に託されたんだ」
メイシアの耳元に囁きながら、ルイフォンは自分自身に告げていた。
『ライシェン』の運命を――ひとつの命の未来を決める。
それが『ライシェン』を菖蒲の館から連れてきた責任だ。
黒絹の髪に指を滑らせ、ルイフォンはメイシアをしっかりと抱く。すると、彼の背に回されていた彼女の両手に力が込められた。
「……ルイフォン。あのね、私……、セレイエさんが可哀想だと思う。『ライシェン』に何かしてあげたいと思う。――でも!」
細い声を跳ね上げ、メイシアは、しゃくりあげた。
「私は、『デヴァイン・シンフォニア計画』を受け入れられない……!」
彼女は訴えるように顔を上げた。
「私が『〈天使〉になりたくない』って気持ちは、勿論ある。でも、それだけじゃないの。だって、何かが、違う! 間違っている! そう……思うの……。理屈じゃなくて、心で……。……でも、セレイエさんは命を賭けて……! …………っ!」
上目遣いに見つめてくるメイシアの瞳は潤み、白い月光をたたえていた。
彼女の中にある、相容れない、ふたつの思い。
セレイエの記憶と、メイシアの魂が慟哭を上げる。
月の雫が、彼女の頬を滑り落ちた。
「メイシア!」
優しい彼女は、セレイエの願いを、祈りを――『デヴァイン・シンフォニア計画』を叶えてあげたいと思っているのだろう。
けれど、その代償は……。
「メイシア、お前が〈天使〉になる必要なんてないだろ? 勿論、お前以外の奴が〈天使〉になる必要もない。誰かを犠牲にして叶える願いなんて、あってはならないはずだからな」
「でも、王族の血を濃く引く私は、熱暴走とは無縁のはずで……、『犠牲』には……」
「それでも、だ! メイシア!」
繰り返し、彼女の名を口にする。
メイシアの心が、セレイエの気持ちに押し流されたりなどしないように。
彼女は『メイシア』なのだから、セレイエに気を遣う必要はないのだと。
「『死んだ人間は生き返らない』――それが、人の世の理だ」
決して感情的にならず、だからこその力強さでもって、彼は告げる。
「だから、俺たちは『デヴァイン・シンフォニア計画』を受け入れられない。――な? 単純な話だろ?」
「……うん。――ルイフォンらしい……」
かすれた声で、けれど確かに、メイシアの口元がほころんだ。
「メイシア、お前が、罪悪感を覚える必要はないんだ。『デヴァイン・シンフォニア計画』は、セレイエの我儘だ。俺たちに叶えてやる義理はない」
覇気にあふれたテノールが、朗々と響き渡る。
「『ライシェン』は、オリジナルの記憶を入れないまま、オリジナルとは別人として、幸せになればいい。――どうしてやったらいいのか。どんなことならしてやれるのか……。これから、ゆっくり、考えていこう」
そして、ルイフォンは、ふっと雰囲気を和らげた。メイシアの黒髪を梳き、愛しげに、くしゃりと撫でる。
「ごめんな。今まで、セレイエの思いをひとりで抱えていて、辛かったよな」
「う、ううん……、…………うん」
メイシアは一度、首を振り、けれど、小さな声で甘えるように言い直した。
彼女の顔を見やれば、憂い顔に涙が浮かんでいる。ルイフォンは彼女の目尻に唇を寄せ、ためらうことなく舐め取った。
「ル、ルイフォン!?」
狼狽の声に構わず、彼女を抱きしめる。
舌の上に、しょっぱさが残る。こんなものでは全然、足りないが、欠片くらいは彼女の辛さを分けてもらえただろうか、などと思う。
「未来をどうするか。肚を据えて考えていこうぜ? ――ふたりで、な」
「うん」
真白き月が、固く抱き合うふたりを照らす。
絨毯に落ちた影は、ふたりだけれども、ひとつ。
2.心魂を捧ぐ盟約-1

時刻は遡り、ルイフォンたち一行が、菖蒲の館で〈蝿〉との決着をつけた日の午後。
鷹刀一族の屋敷にて、料理長の心づくしのご相伴にあずかった緋扇シュアンは、その足で、メイシアの実家の藤咲家に向かうと告げた。彼女の異母弟である貴族の藤咲家当主、藤咲ハオリュウに、ことの顛末を報告するためである。
他の面々と同じく、シュアンもまた前日の夜から、ほぼ不眠不休だった。故にメイシアは、異母弟のところへ行くのは後日でよいのではないかと勧めたのだが、彼は軽く聞き流した。
「鉄砲玉の性分、というやつでしてね」
口の端を上げ、シュアンは胡散臭い笑みを浮かべる。まったく取り合わない彼に、メイシアは遠慮がちに言葉を重ねた。
「緋扇さん、顔色が良くないです」
彼女の言う通り、シュアンの不健康そのものの肌には艶がなく、三白眼の眼窩は落ち窪み、濃い隈に覆われていた。中肉中背の体躯は姿勢が悪く、気だるげである。メイシアの最愛のルイフォンも見事な猫背であるが、好戦的な好奇心にあふれた彼とは、まるで異なる雰囲気だった。
「俺の顔が悪いのは生まれつきなんで、諦めるしかないんですよ」
「緋扇さん! ふざけないでください。『顔色』が! 悪いんです」
からかい混じりに返してくるシュアンに、メイシアは握りしめた拳をふるふると震わせて真剣に怒った。その仕草は、どことなく小動物的で、実に可愛らしい。
そのためルイフォンは、『メイシアにそんな態度を取っていいのは俺だけだぞ』と割って入るべきか否かと悩んだのだが、シュアンが先に口を開いてしまった。
「面白いことを言いますねぇ? じゃあ、普段の俺と、いったいどこが違うと言うんです?」
「えっ……?」
真面目なメイシアは、とっさに答えられない。何しろ、シュアンの悪相は、本人の言う通り地顔なのだ。
シュアンは微苦笑を漏らした。以前、似たようなやり取りを、彼女の異母弟と交わしたことを思い出したのだ。あれは、車椅子のハオリュウの介助者として、摂政の会食へと赴く直前のこと。最終確認だと言って、ハオリュウとふたりで話したときのことだ。
姉弟で反応はそれぞれが、あのときは口が回るハオリュウも押し黙った。一見、まったく血の繋がりを感じられない異母姉弟だが、案外、似ているのかもしれない、などとシュアンは思う。
「メイシア嬢。俺は、ハオリュウのために行くわけじゃねぇんですよ」
「え?」
心底、驚いたような素振りを見せたメイシアに、シュアンは、それまでとは少し違う口調で続ける。
「あんたが元気なことは、ハオリュウの奴にきっちり話してくる。それから、王族の『秘密』も伝えて、あんたとハオリュウの間でも、〈悪魔〉の『契約』が無効になるようにしてやる」
シュアンは、そこで言葉を切り、ふっと遠くを見やった。
「――けどな、俺とハオリュウにとって、〈蝿〉との決着がついたってことは、特別な意味を持つんだよ」
その瞬間、シュアンの三白眼が、虚空を射抜くように細められた。
すぐそばにいたメイシアは勿論、一歩離れたところにいたルイフォンも息を呑む。
「俺は、ケジメをつけに行くのさ」
ぼさぼさ頭をふわりと揺らしながら、シュアンは視線を戻す。その口元は、確かにほころんでいるにも関わらず、どこか張り詰めたような顔だった。
――喩えていうのならば、引き金を引く直前の、狙撃手の表情。
「それじゃ、俺はこれで」
飄々と立ち去るシュアンの後ろ姿に、ルイフォンもメイシアも、声を掛けることはできなかった。
鷹刀一族の屋敷と同じく、ハオリュウの藤咲家も、シュアンにとっては、もはや勝手知ったる他人の家であった。
貴族の邸宅に似つかわしくない風体のシュアンが、豪奢な廊下を堂々と歩く様は、実に不遜といえた。しかし、彼の役回りが、事実上のハオリュウの使い走りであることを考えれば、それは当然の権利なのであった。
シュアンが警察隊員であることは、この家の使用人たちに、きちんと説明されている……はずである。しかし、何故か、レイウェンの警備会社から派遣された、もと凶賊の凄腕の護衛で通っている。別に、それで支障はなく、むしろ皆が納得しているようなので、ハオリュウも特に訂正していない。
「シュアン! お疲れのところ、ありがとうございます」
ハオリュウの書斎に入ると、十二歳の少年には不釣り合いな当主の椅子から、深みのある声が掛けられた。この数ヶ月で、急に大人びたハオリュウである。
自宅であるためにか、スーツこそ着ていないものの、上質なシャツのボタンは、首元の一番上までかっちりと留めていた。
「どうぞ、奥まで入ってきてください」
昨日までの鬼気迫る威圧が払拭され、柔和な笑顔である。もし、彼の足が悪くなければ、身分的には下であるシュアンのもとまで自ら出迎え、丁寧に労いの言葉を述べたことだろう。
――その椅子も、不釣り合いではなくなってきたか。
勧めに従い、奥へと歩きながら、そんなことをシュアンは思う。
成り行きではあるが、シュアンは、ハオリュウが当主として立ってから今まで、ずっと彼を見守ってきた。かねてから、領地の運営などについては勉強をしていた様子であるが、段々と、当主が板についてきた気がする。以前とは、顔つきが違う。
……この書斎も、すっかり馴染みになったな。
シュアンは、いつもの通り、ハオリュウの執務机と向き合うように置かれた椅子に、どっかりと座った。ふかふかの心地良さは、如何にも貴族の調度だ。
おそらくは、代々の当主が使ってきた執務室なのであろう。部屋の中を見渡せば、年代物の逸品で整えられている。しかし、その中でひとつだけ、異彩を放っているものがあった。――最近、飾られたばかりの絵である。
自然と、壁に目が行ってしまったシュアンは、三白眼を和らげ、苦笑した。
他ならぬシュアンが預かり、ハオリュウに渡したもので、一面に水色のクレヨンで塗られた上に、紫の丸が無数に描かれた抽象画――ではなくて、ただの子供の落書きである。
人質として、菖蒲の館の一室に閉じ込められていた小さなファンルゥが、『病気のあの子』に贈った『空に浮かぶ、紫の風船』――もとい、『菖蒲の花』の絵。
立派な額縁に収められたそれは、切り取られた画用紙に描かれたものであり、丁寧に皺が伸ばされてはいたが、曲がった折り目を完全に隠し切ることはできていない。
そんなものが、つい先日までそこにあった名画と思しき絵と箝げ替えられ、物々しく飾られているのを目にした日には、さすがのシュアンも度肝を抜かれた。
『あんた、何を考えて……?』
『ファンルゥさんは、姉様の命の恩人ですよ?』
澄まして答えたハオリュウ曰く、展望塔に囚われたメイシアを、ファンルゥが助けようとしてくれたからこそ、事態が好転したと。
感謝と敬意なのだろう。――貴族のハオリュウから見れば、取るに足らない平民の、それも幼児といって差し支えないほどの子供に対して。
実に馬鹿馬鹿しいようでいて、なかなかできることではないと……腐った権力者を見続けてきたシュアンは知っている。
シュアンは壁から視線を移し、ハオリュウに向き直った。
「ハオリュウ、あんたの姉さんは、無事にルイフォンのもとに戻ったぞ」
先に連絡は送っていたが、一番初めに言うべきことは、やはりこれだろう。
「ありがとうございます。――ええ、確かに、あなたから頂いたメッセージに『ルイフォンのもとに戻った姉様』の写真が添付されていましたね」
「あ……」
冷気を帯びた、含みのあるハオリュウの物言いに、シュアンは気まずげに目を泳がせた。
そういえば、感動の再会の瞬間――『朝陽を受けて抱き合うふたり』という、見方によっては、かなり濃厚な抱擁といえなくもない写真を送っていた。
「あ、あれはミンウェイにけしかけられて、だな」
まだ刺激が強すぎたかと焦るシュアンに、ハオリュウは神妙な顔で告げる。
「いい写真でしたね」
「おいっ!」
どうやら、からかわれたらしい。
牙をむいたシュアンに、ハオリュウは貴族らしく、くすくすと上品に口元に手を当てた。
「あなたにしては粋な計らいだと思っていたのですが……、なるほど、ミンウェイさんの入れ知恵でしたか」
「――ったく」
笑い方にすら育ちが出ているような上流階級のお坊っちゃんと、こんな軽口を叩けるような間柄になるとは思ってもいなかった。
シュアンは、じっと、ハオリュウを見つめる。
背丈だけは伸びたものの、まだあどけなさの残る、少年らしい風貌。本来なら、素朴な無邪気さを振りまいていただけであろう面差しは、人畜無害の善人面ゆえに、古狸の大人たちと渡り合うための武器となった。
――ハオリュウが、一国の行く末に関与できるだけの権力を持っているからだ。
「シュアン? どうしました?」
「……いや、なんでもねぇさ」
身だしなみのきちんとしたハオリュウとは異なり、まったく手入れのなっていない、ぼさぼさ頭を揺らし、シュアンは首を振る。
「では、早速ですが、報告をお願いいたします。〈蝿〉の態度が急変したことは、先の連絡で伺っていますが、僕にはまるで話が見えておりませんので」
「そりゃそうだろうな」
複雑すぎて、どこから話したらよいものか、シュアンとしては頭が痛い。
「それと、ミンウェイさんから、彼女の出生も含めて、すべてをあなたから聞くようにとメッセージを頂いております」
「ああ……」
それも、シュアンを悩ませている一因だ。
ハオリュウのもとに向かう際、シュアンはミンウェイに呼び止められた。
『ルイフォンとメイシアは、私を気遣って、私がクローンであることをハオリュウには言っていません。でも、それも含めて、彼には、すべてを話してきてほしいんです』
そう頼み込んだミンウェイは、とても穏やかな表情をしていた。
しかし、だからと言って、何もかも包み隠さず伝えるばかりがよいとは限らないだろう。
『せっかく、あいつらが気を遣ってくれたんなら、そのまま黙ってりゃいいだろう?』
『ハオリュウにとって、〈蝿〉は『父親の仇』です。八つ裂きにして殺しても飽き足りない相手です』
『それは、そうだが……』
人の良さそうな外見からは想像しにくいが、ハオリュウの気性は激しい。表には出さないが、腹黒い残忍さを持ち合わせているのは事実だ。彼は、ライバルであった貴族、厳月家の当主を、〈蝿〉と共に父を死に追いやった仇として、シュアンの手を借りて暗殺している。
『〈蝿〉がしてきたことを考えれば、彼の死は、許されないほどに安らかなものであったと思います。すべてを包み隠さずに伝えなければ、ハオリュウは到底、受け入れることができないでしょう』
『……』
『何よりも、私自身が知っていてほしいんです。私の『父』、鷹刀ヘイシャオの記憶を持ち、非道に堕ちながらも、もがき苦しんだ『〈蝿〉』という人間のことを……』
ミンウェイは、切れ長の瞳をそっと伏せた。けれど、彼女は涙をこぼすことなく、ただ胸に手を当てる。それから顔を上げ、シュアンを見つめた。
『本当なら、私の口から話すべきだと思います。私のことも、〈蝿〉のことも。……でも、まだ、そこまではできそうにないから。――あなたに、甘えさせてください』
彼女は柳眉を下げながらも、紅の取れかけた唇を無理やりに上げる。だからシュアンは、このとんでもなく面倒くさい頼みごとを満面の笑顔で引き受けた。――もっとも彼女には、不快げに凶相を歪めたようにしか見えなかったであろうけれど。
シュアンはハオリュウを見やり、深く息を吐き出した。
それは決して溜め息などではない。気合いを入れるための予備動作だ。
「長い、長い話になるぞ」
「ええ、構いません」
打てば響くように、ハオリュウが返してきた。
そして、シュアンは語り始める。
彼とハオリュウの仇だった〈蝿〉という男が、なんのために生きて、なんのために死んでいったのかを――。
それが、シュアンとハオリュウの間で交わされた黙約の終焉となる。
2.心魂を捧ぐ盟約-2

すべてを話し終えたときには、もともと濁声だったシュアンの声が、明らかに普段と違うと分かるほどに、かすれていた。聞き手だったハオリュウも、目に見えてぐったりとしている。
「ハオリュウ」
ひび割れた声で、シュアンは呼びかけた。
「俺は、先輩が死んだのに〈蝿〉の野郎が、のうのうと生きていることが許せなかった」
「僕も、同じでしたよ」
ぽつりと呟くように、ハオリュウが同意した。
「俺は初め、奴の腸が飛び散るのを見なければ、気がすまないと思っていた」
「僕は、ひと思いにとどめを刺すよりも、……いえ、そういうことは、口にすべきではありませんね」
ハオリュウは薄い笑みを残して、上品に口をつぐむ。その作り笑顔からは、彼の肚の内は窺い知れないが、会話は過去形で成立していた。
シュアンは三白眼を和らげ、静かに告げる。
「俺には、〈蝿〉の野郎を許すことはできない。この恨みは、先輩を撃った弾丸の重さと共に、俺は一生、抱えていく」
グリップだこで変形した手を、シュアンは固く握りしめる。
先輩を思うと、胸が苦しい。口の中に広がる苦さを、唇を噛むことで、どうにか堪える。
「ハオリュウ……、俺は……、〈蝿〉への発砲の許可を受けていた。……けど、俺は結局、奴を撃たなかった」
それまでと打って変わり、シュアンは途切れがちに言葉を紡ぐ。その落差に、ハオリュウは戸惑うように瞳を揺らしたが、やがて黙って頷いた。
シュアンに発表許可を、と言い出したイーレオは、あのとき既に、〈蝿〉が王族の『秘密』を口にして死ぬつもりであることを察していたのだ。だから、許可を求めながらも、保険だと言った。
あのやりとりは、〈蝿〉が自ら死に向かうことをシュアンにほのめかし、シュアンの憎悪は承知しているが〈蝿〉の思うようにやらせてほしいと――義父としてのイーレオからの懇願だったのだ。
「奴を撃たないことも、俺の不可逆の選択だった。――そして俺は、この結末に納得している。奴の言う通り、『最高の終幕』だったと……俺は思う。あんな奴を認めるのは癪だけどな」
自分の心の内を明らかにし、シュアンはハオリュウへと視線を送る。執務机の上で組まれた少年の指には、当主の指輪が落ち着いた金の光を放っていた。
数ヶ月前。
ハオリュウが父を失い、自身も足に一生、残る傷を負った日。涙ひとつ見せずに復讐を語った糞餓鬼の彼と、シュアンは黙約を結んだ。
「ハオリュウ。俺の手は、俺の手であるけれども、あんたの手でもある。――あんたは、この手が選んだ結末を……、その……」
「認めますよ」
言いよどんだシュアンに手を差し伸べるように、ハオリュウは澄んだ声を響かせた。
「僕がその場にいたとしても、引き金に指を掛けることはなかったでしょう。〈蝿〉の『最高の終幕』には、隙がありませんでしたから。……たいした策士です」
皮肉交じりでありながら、ハオリュウは清々しい顔で言う。
「〈蝿〉の死に様に、異論はありませんよ。何より、姉様を〈悪魔〉の『契約』とやらから解放するために死んだというのなら、不本意ながらも彼を評価しないわけにはいきません」
だから、これが、ふたりの交わした黙約の結末。
終わったのだ。
貴族の少年当主と、権力者嫌いのチンピラ警察隊員。立場も年齢も違う、ふたり。
本来なら、関わり合うことなどあり得なかった間柄が、同じ相手に復讐を誓ったがために手を取り合った、数奇な巡り合わせ……。
シュアンは腹に力を込め、心に決めてきた話を切り出そうとした。
だが、気合いを入れている間に、「シュアン」と、彼を呼ぶハオリュウの声に出鼻をくじかれた。
「今まで、ありがとうございました」
晴れやかに笑うハオリュウの顔に、シュアンは眉をひそめる。先を越されれば、ハオリュウが口にする内容など分かりきっていたからだ。
「あなたには、本当にお世話になりました。〈蝿〉を討つための同志という関係だけのはずが、当主として立ったばかりの未熟な私に、何かと力を貸してくださいました。あなたがいてくださって、私は心強かった」
純真な少年の顔に、為政者の風格を混ぜ、ハオリュウは告げる。
「若輩の身ではありますが、私は腐っても貴族の当主です。困ったことがあれば、いつでも頼ってください」
「――ハオリュウ」
シュアンは低く、どすの利いた声を上げた。
別れを口にしているにも関わらず、寂しそうな顔ひとつ見せずに、綺麗な外面で微笑むハオリュウが腹立たしかった。
「俺は、これから職場に行って、辞表を出してくる」
「シュアン!?」
「だから、あんたは俺を雇うんだ」
刹那――。
ハオリュウの善人面が崩れた。
むき出しになった本心は、紛うことなく子供の泣き顔だった。
次の瞬間には、いつもの顔に戻っていたが、ハオリュウが今までに一度も見せたことのなかった表情を引き出せたことに、シュアンは溜飲を下げる。
「護衛から運転手、足の悪い主人の介助まで、俺は、なんでもこなすことができる。この有能な人材を見逃す手はないだろう?」
にやりと口角を上げ、自分を売り込むシュアンに、ハオリュウは生真面目な顔で首を振る。
「せっかくのお話ですが、丁重にお断り申し上げます」
思った通りの返事だった。
あまりにも想像と違わない反応に、シュアンの口からは失笑が漏れる。
ハオリュウは、自分を取り巻く環境が平穏ではないことを理解している。だから、多少なりともシュアンに恩やら情やらを感じていれば、巻き込みたくないと考えるだろうと――分かっていた。
古狸どもを煙に巻く、厚顔の持ち主のくせに、とんだ甘ちゃんなのだ。
……そうでなければ、赤く染まったシュアンの手を、自身の手とみなすことなど、できやしないのだ。
ともあれ。
今までは、シュアンも復讐の当事者だった。だから、対等といえた。
だが、黙約が果たされた今、状況は変わった。
「あんた、俺がいると心強いんだろう?」
「それは、社交辞令です」
ハオリュウは、すげなく言い放つ。
彼は咳払いをひとつすると、腹黒さの漂う、彼本来の昏い瞳でシュアンを見つめた。
「あなたの申し出はありがたい。それは確かです。そして、『デヴァイン・シンフォニア計画』とやらは、まだ中途半端な状態――〈蝿〉が死んだからといって、まだ終わった気がしないという気持ちも分かります」
「……」
「ですが、この先は『ライシェン』を巡る、政治的な問題となります。あなたの大嫌いな権力者の駆け引きです」
ハオリュウは淡々と告げ、そこで不意に瞳を伏せた。
「僕は、友人である、あなたに、僕の汚い部分を見せたくはありません」
まだ線の細い少年の肩が儚げに落とされるのを、冷ややかな三白眼が捉えた。シュアンは座っていた椅子から、すっと立ち上がる。
そして、つかつかと執務机を回り込み、きょとんとしているハオリュウの頭に、拳骨を落とした。
「阿呆か」
シュアンは、侮蔑の眼差しで吐き捨てる。
「!?」
ハオリュウが頭を押さえながら、批難を込めて――ただし、誤魔化しようもないほどの涙目で、シュアンを見上げた。痛みによる反射は、いくら強情な彼でも堪えきれなかったらしい。いい気味である。
シュアンは高級そうな執務机に無遠慮に尻を乗せ、高い位置からハオリュウの鼻先へと、ぐっと人差し指を突きつけた。
「何が『僕の汚い部分を見せたくない』だ? 今更だろうが」
「シュアン……」
ハオリュウは、しばらく呆然とシュアンを見つめていたが、やがてふっと口元をほころばせた。
「貴族の当主に手を上げるのは、立派な犯罪ですよ?」
「ふざけんな。俺は、あんたの『友人』なんだろう? だったら、おトモダチ同士の『拳での語らい』だろうが」
ふん、と鼻を鳴らし、シュアンは言い切る。
だいたい、シュアンはちゃんと手加減をしたのだ。どうやら坊ちゃん育ちには、思っていた以上に効いていたようであるが、それは、ひ弱なハオリュウに問題があるのであって、シュアンは悪くない。
「……『汚い部分を見せたくない』というのは、嘘偽りない本心なんですけどね」
ハオリュウは苦笑いをし、それから、揺るぎなき眼差しをシュアンに向けた。
「僕は、あなたに軽蔑されたくない。けど、近くにいれば、あなたはこの先、必ず僕の醜い部分を見ることになるはずだ」
矜持に懸けて譲らないという、強い信念。
「構わねぇよ」
シュアンは口の端を上げ、悪相を歪める。
「醜いものなんざ、俺は山ほど見てきている。だいたい俺自身が、狂犬と呼ばれた汚らしいクズだ」
「ですが……!」
「それに、あんたは勘違いしている」
反論しようとするハオリュウを遮り、シュアンは続けた。
「あんたは『デヴァイン・シンフォニア計画』が中途半端なのがどうの、と言っていたが、俺にとっては、〈蝿〉が死ねば、あんな計画はどうでもいい。俺が、あんたにつきまとおうとするのは、もっと別の理由からだ」
「じゃあ、なんだと言うんです?」
ハオリュウは苛立ちを隠しもしない。思慮深いはずの彼が、自分で推測もせずに尋ねるとは、余裕のなさの表れだ。シュアンとしては、愉快でたまらない。
「あんただよ」
「は?」
「俺は、あんたが欲しい」
シュアンが撃ち込んだのは、真正面からの言葉の弾丸。
「は…………?」
着弾の衝撃に、ハオリュウの眼差しが大きく揺れた。どう受け止めたらよいのか、分からないのだろう。
シュアンとて、この大物を一発で仕留められるとは思っていない。
にやりと、ほくそ笑みながら、彼は語りかける。
「ハオリュウ。俺が警察隊員になった理由は、話したことがあったよな?」
「え、ええ……。ただ街を歩いていただけなのに、突然、凶賊の抗争に巻き込まれ、ご家族をすべて失った。だから、凶賊を取り締まる警察隊員になった、と」
「ああ、そうだ。世を正すために、俺は警察隊に入った。だが、そこには、俺が信じていた正義はなく、腐った社会というものを見せつけられただけだった」
警察隊には失望した。
それは真実。
けれども、ローヤン先輩との出会いもあった。
彼と肩を組みながら、『いつか、世を正す』と絵空事を本気で謳った日があった。
ただ、それは永遠ではなかった。シュアンの心が、ぽっきりと折れてしまった。
先輩だって、散々、辛酸を嘗めていたのに、シュアンには耐えられなかった。殴り合って袂を分かち、それきりになってしまった……。
「俺は荒れた。ならば権力を持った奴らに媚びて、そいつらを利用して力をつけ、いずれ足元をすくってやろうと考えた」
「あなたと初めて会ったときの、あの上官もそのひとり、というわけですね」
「ああ。でも、思えば、俺は迷走していただけだった。糞上官に、おべっかを使ったところで、底が浅い奴のおこぼれの権力なんて、たかが知れている。……だからよ」
三白眼が、意味ありげにハオリュウを見やる。
「だから、僕に乗り換えると?」
「そういうことだ」
シュアンの答えに、ハオリュウは首を振った。
「残念ですが、僕は、あなたの期待に応えられそうもありません。僕はまだ、当主の座を守るだけで精いっぱいなんですよ?」
気弱な言葉は、謙遜ではなくて事実だろう。
殊勝な態度に、可愛いところもあるものだと、シュアンは口元を緩める。
「あんたが餓鬼だってことは、俺もちゃんと把握しているさ。これでも俺は、れっきとした大人なんだからよ」
シュアンは腰掛けている執務机に手をつき、上体を傾けた。ハオリュウに目線を合わせ、胡散臭げな笑みを浮かべる。
「『世を正す』なんて、俺なんかには、できるはずもない夢物語だと思っていた。だが、案外、簡単なことだと気づいたのさ」
「え?」
ハオリュウは、困惑気味に首をかしげた。
「あんたを、俺好みの権力者に育てればいい。俺の正義のためには、それが一番の近道だ」
軽口を装いながらも、むき出しの思いをさらけ出す。
これが、シュアンのたどり着いた、彼が為すべきことを為すための道筋だ。
「俺は、あんたに賭けてみたい」
シュアンは、ぎろりと三白眼を巡らせ、ハオリュウに狙いをつける。
「俺は、あんたが欲しい。――国の中枢に喰い込める貴族の当主」
無音の銃声が、鳴り響いた。
ハオリュウが息を呑んだまま、動きを止める。
一発目の弾丸は、相手を驚かせただけだった。
しかし、二発目の弾丸は…………相手の心臓を撃ち抜いた。
どのくらい、時が凍りついていただろうか。
やがて、ハオリュウは弱々しく視線を動かし、シュアンを見上げた。知れず、呼吸が乱れ、絞り出すように声を紡ぐ。
「僕と一緒にいるということは……、平穏な人生を歩めなくなる――ということですよ?」
「ああ――……」
シュアンは、無意識に瞳を閉じた。
脳裏にちらりと、『穏やかな日常』を求めてやまない、お人好しの顔がかすめる。……しかし、すぐに打ち消した。
「……――望むところだ」
「シュアン……! ……ありがとう、ございます……」
ハオリュウが頭を垂れる。伏せられた顔の口元を、そして目元を――当主の指輪の光る手が覆い隠した。
小刻みに震える、少年の華奢な肩に、シュアンは声を落とす。
「俺に『穏やかな日常』は、似合わねぇからよ」
その言葉は、内容とは裏腹に、優しい響きをしていた。
そして――。
「すみませんが、警察隊は辞めずに、今までのようにはいきませんか?」
遠慮がちにハオリュウが尋ねた。
あんな腐った組織には、早々におさらばする気で満々だったシュアンは、不快げに「何故だ?」と眉を上げる。
「あなたには、僕の対等な友人であってほしいからです。雇ったら、僕の使用人になってしまうでしょう?」
「それはそうだが……」
実のところ、シュアンの勤務態度には、たびたび注意が入っている。右から左へと聞き流してはいるが、それなりに面倒臭いのだ。だから、きっぱり縁を切ろうと思っていた。
だが、ハオリュウの気持ちも分かる。貴族の当主にここまで言わせたのならば、可愛い我儘くらい聞いてやってもよいだろうと、シュアンは結論づけた。
「どうせ、俺はそのうち免職になるぞ?」
おどけて言えば、ハオリュウが上品に、くすりと笑う。
「それまでの間で構いません」
ハオリュウが右手を差し出し、シュアンもそれに倣う。
繋ぎ合わされた手の重さを、シュアンはがっしりと受け止める。
ふと、壁に飾られた謎の抽象画――もとい、小さなファンルゥの落書きが目に入った。
シュアンには理解できないが、のびのびとした筆致のそれは、彼女の夢や思いが、いっぱいに詰まっているのだろう。
だから、きっと。
この絵と名画を箝げ替える、奇天烈な少年当主なら、シュアンの描く絵も趣深いと言ってくれるに違いない。
――先輩。
俺は、誰もが笑い飛ばすような絵空事を、本気で描いてみようと思いますよ。
3.崇き狼の宣誓-1

〈蝿〉の死から、一夜明けた早朝。
鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオは、執務室の窓辺に立ち、外の景色を見るともなしに眺めていた。
濃い緑をまとった桜の大樹が、眩しい朝陽に透かされて金色に輝き、夏の暑さに染まる前の涼やかな風が、ざわざわと枝葉を奏でていく。
「……結局、会えずじまいだったな」
開け放たれた窓から空を仰ぎ、イーレオは、ぽつりと漏らした。
最後まで、〈蝿〉と――ヘイシャオの記憶と、相まみえることはなかった。それでよかったのだと思うし、やはり、会いたかったようにも思う。
〈蝿〉にしろ、ヘイシャオにしろ、イーレオと意見を異にすることはあっても、敵であったことは一度もなかった。ずっと変わらず、イーレオの大切な一族であり、娘婿だった。勿論、総帥という立場上、それを口にすることは許されなかったのだけれども。
蒼天から降り注ぐ光と風とを受け、イーレオの黒髪が艷やかに流れる。それはまるで、彼の哀悼の思いが流れていく様子を、可視化したかのようでもあった。
「ありがとう」
イーレオは、天に向かって謝意を述べる。
〈蝿〉は、メイシアを〈悪魔〉の『契約』から解き放った。
それは同時に、〈悪魔〉の〈獅子〉であったイーレオの『契約』をも無効にした。
この余波は、決して偶然などではない。聡明なヘイシャオの〈影〉であれば、当然、気づいていたはず。意図してのことだったはずだ。
約三十年前、イーレオは〈七つの大罪〉から――王族から、一族を解放した。
しかし彼は、彼を信じ、慕い、ついてきてくれた者たちに、何も説明することができなかった。〈悪魔〉の『契約』に縛られていたためである。
何がどうなって、自由の身になれたのか。そもそも一族は、なんのために〈贄〉にされ続けてきたのか。――エルファンやチャオラウといった、イーレオのすぐそばで、彼を支えてきてくれた者たちは、気になって仕方がなかったであろう。
だが、彼らも『契約』のことは承知していたから、イーレオに真実を求めなかった。済んだ過去のことであると割り切ってくれた。
そうして、長い年月、忘れたふりをしてくれていた。
「ヘイシャオ……、俺も解放されたよ」
〈悪魔〉の『契約』から、そして、鷹刀の者たちに一族の過去を黙し続けるという、孤独から。
勿論、リュイセンやルイフォンといった、若い世代には興味のない話だったろう。――それでいい。これは、年寄りの感傷に過ぎない。
「――リュイセンには……、憶えていてもらうべきか」
魅惑の低音をゆるりと響かせ、イーレオは口元をほころばせた。
〈蝿〉との最後の勝負のとき、リュイセンは、高潔なる断罪者として君臨した。イーレオの想像を超えた、絶対の王者の振る舞いだった。だからこそ、〈蝿〉も屈した。
見事だった。
リュイセンは紛うことなく、鷹刀の未来を統べる王だ。
優しさを求心力に、歴代で最高の……。
そして――。
「お前が、最後の総帥だ」
自室で眠っているであろうリュイセンに、イーレオは呼びかける。
リュイセンは、自分が一族の幕を下ろすのだと決意した。
自分の未熟さを痛感しているためにか、まだ正式に宣誓したわけではないけれど、彼がそのつもりであることをイーレオは知っている。
鷹刀の終焉を飾るリュイセンには、一族がそれまで紡いできた過去を憶えていてほしいと願う。未来はいきなり生まれるものではなく、先人の流してきた血と、受け継いできた血を重ね合わせることで作られていくのだから。
かつて盲目の王は、護衛の鷹刀一族が、ほんの一時でもそばから離れることを許さなかった。それを信頼と呼べば聞こえはよいが、単に隷属を強いただけだった。
勿論、初代の王には、確かに信頼があっただろう。しかし、時代を経るごとに、鷹刀一族が〈贄〉、すなわち〈冥王〉に喰わせるための『餌』であることから、家畜の如く軽視されていったのだ。
王の先祖が、神の『供物』として捧げられた歴史と似ているのは、あるいは偶然ではないのかもしれない。他の者を虐げることで、恨みを晴らしていたのだ。
その関係を変えたのが、イーレオも歴史の上でしか知らない、大昔の鷹刀の総帥だ。
彼によって、鷹刀一族は『護衛』という名の奴隷から独立した。そして、〈贄〉の提供の代償として、鷹刀一族にあらゆる便宜を図ることを王に約束させた。
『凶賊』という『地位』は、そのときに、もぎ取った。鷹刀一族にのみ、与えられた『王国の闇を統べる一族』という称号である。――いつの間にか『ならず者の集まり』の意味を持つ蔑称になってしまっていたが。
『表』の王家と対になる、『裏』の鷹刀。――鷹刀一族は、王国の闇を支配する、もうひとつの王家だった。
イーレオは、それを〈贄〉の廃止と引き換えに返上した。
今度はリュイセンが『凶賊』の肩書きを捨て、鷹の一族は名実ともに、もとの自由な市井の一市民に戻る。
幾千もの時を経て、やっと……。
ふと、イーレオは廊下に気配を感じた。おそらく次期総帥たる長子エルファンだろう。
昨日の夕刻、『リュイセンの処遇について話がある』と持ちかけられた。その時点で、エルファンの弁は聞いたのであるが、イーレオは『互いに一晩、考えよう』と切り上げた。
「エルファンの奴、疲れていただろうに、随分と朝が早いな」
あいつも年寄りの仲間入りか、とイーレオは苦笑し、開け放たれていた窓をぴたりと閉めた。
そして、執務室は完全防音となった。
午後になった。
まもなく執務室にて、報告の会議が始まる。
リュイセンは緊張の面持ちで廊下を歩いていた。黄金比の美貌は彫像のように硬く、しなやかなはずの肉体も機械人形のようにぎこちない。
だが、それも仕方のないことといえよう。
報告とは、詳しい状況を知らない相手に、経緯と結末を子細に説明する行為であり、今回の場合、単独行動を続けてきたリュイセンが何をしてきたかを釈明することを示す。
……要するに、リュイセンの吊し上げの会に他ならない。
生真面目な彼は、午前中いっぱい掛けて原稿を用意した。それでも、口が達者ではないために、皆に迷惑を掛けるであろうことは目に見えている。
気が重い。
なし崩しに皆と共にあの庭園を脱出し、そのまま鷹刀一族の屋敷の門をくぐってしまったが、リュイセンは裏切り者だ。責任を取る必要がある。
ルイフォンによれば、リュイセンがメイシアをさらった直後、追放が言い渡されたらしい。だが、〈蝿〉を下したことで追放は解かれたという。――リュイセンのいない場所での出来ごとなので、彼としては実感が沸かないし、どう捉えたらよいものかも分からない。
ともかく、この会議で、何かしらの処分が言い渡されるはずだ。それが道理というものだ。
どんな処分を言い渡されたとしても、たとえ、死をもってケジメをつけろと命じられたとしても、従う覚悟はある。
可能性として一番高いのは、後継者の地位の剥奪だと思われるが、そうであったとしても甘んじて受け入れよう。〈蝿〉に『未来の総帥』として一族を託されたのだが――。
「……いや」
リュイセンは立ち止まり、首を振った。
どんなに時間が掛かってもいい。イーレオと一族に、総帥にふさわしい人間であると認めてもらえるまで努力をしよう。
何故なら、〈蝿〉に誓ったのだから。――『私にお任せください』と。
「おい。いきなり立ち止まって、どうした?」
突然、背後から耳障りな甲高い声が響き、リュイセンは心臓が止まりそうになった。
「緋扇!?」
リュイセンが振り返ると、胡散臭そうな三白眼が「よお」と歪められる。
気配に敏いリュイセンが、こんな至近距離にまで接近を許すとは。しかも、相手があの緋扇シュアンであるとは……。気の重い会議を前に、相当、落ち着きを失っていたようである。
「なんで、お前がここにいるんだ?」
「あれ、聞いていないのか? 俺は、ハオリュウの代理だ」
「?」
シュアンとハオリュウは、復讐のために手を結んだのだ。だから、〈蝿〉との決着がついた今、シュアンが使い走りをする義理はないはずである。……いや、そういう問題ではなく、今回の会議はリュイセンの弁明と処分のための、身内だけの会議ではなかったのか――?
リュイセンが首をかしげていると、シュアンも察したらしい。理由を教えてくれた。
「〈蝿〉の件は決着がついたが、今後も変わらず、俺がハオリュウの子守りをすることになってな。それで、イーレオさんに挨拶の電話を入れたら、今日の会議に出るようにと言われたのさ。なんでも、メイシア嬢から『デヴァイン・シンフォニア計画』についての説明があるんだと」
「そうなのか……?」
リュイセンが自室に籠もって原稿を作っていた間に、他の者たちには連絡が行っていたのだろうか? あるいは、上の空だった彼が、単に聞き逃していただけかもしれないが……。
確かに、『デヴァイン・シンフォニア計画』の話が出るとなれば、ハオリュウは無関係ではないだろう。異母姉のメイシアが巻き込まえている上に、彼自身、摂政に女王の婚約者に――すなわち、『ライシェン』の『父親』になるように持ちかけられている。
『ライシェン』が、こちらの手に移った現在、摂政がハオリュウに対して、どんな態度を取ってくるのかは分からない。だが、ハオリュウとしては、やはり『デヴァイン・シンフォニア計画』の情報は欲しいだろう。
「それじゃ、俺は先に行くぜ」
シュアンが手を振りながら去っていく。
姿勢の悪い、どうにも冴えない背中を見送りながら、リュイセンは礼を言うのを忘れていたことに気づいた。
信じられないことだが、一族とルイフォンを裏切ったリュイセンに対し、シュアンが誰よりも先に、手を差し伸べてくれたのだという。『難攻不落の敵地に、先だって潜入成功している、頼もしい仲間』だと。
「緋扇……!」
しかし、呼び止めようとしたときには、もう彼の姿は消えていた。
仕方ない。会議のあとにでも、また声を掛けよう。ともかく、まずはこの会議を乗り切ることが先決だ。
リュイセンは気持ちを引き締め、歩き出した。
……案の定、会議は長時間に及んだ。
その原因の大半が、リュイセンの説明能力の稚拙さに依るものであった。
後日、ルイフォンには『メイシアに出した飯の内容なんてものは、わざわざ報告しなくていいんだ』と、溜め息混じりに、たしなめられた。
一方で、メイシアによる『デヴァイン・シンフォニア計画』の詳説は分かりやすく、彼女の聡明さが際立った。リュイセンとしては穴があったら入りたいくらいである。
ただ、最後にルイフォンが付け加えたひとこと――「要するに、セレイエは俺たちに『ライシェン』のことを丸投げしたというわけだ」には唖然とした。
「すまない。『ライシェン』がこの屋敷にいるだけで、鷹刀は潜在的な危険に晒されている。――近いうちに必ず、方針を打ち出す。少し待ってほしい」
メイシアの手を取り、そう言って頭を下げた弟分の姿は、悔しいけれども格好よかった。負けるものかと思う。
だから、報告とそれに対する質疑応答が落ち着いたとき、リュイセンは自ら切り出した。
「総帥。よろしいでしょうか」
その呼びかけに、ひとり掛けのソファーで優雅に足を組んでいたイーレオは、姿勢を変えず、目線だけを動かした。何もかもを見透かしたような瞳に、リュイセンは、ごくりと唾を呑む。
「なんだ? 言ってみろ」
イーレオの許可が出ると、リュイセンはソファーから立ち上がった。膝を屈し、床に手を付く。
「私は、許されざる裏切り行為を働きました。誠に申し訳ございません。――如何ような処罰も覚悟しております。どうか、御沙汰をお願いいたします」
すらりとした背を腰から綺麗に折り曲げ、額が絨毯をこする直前でぴたりと止める。そのまま時が凍ったように、リュイセンは微動だにしない。
「――なるほど。お前は、今回の件の責任を取るというわけだな」
「はい」
凪いだように静かなイーレオの低い声に、リュイセンは、はっきりと答えた。
「一族の者たちは、お前の裏切り行為に激しく動揺している。俺も、このまま放置するわけにはいかぬと考えていた」
リュイセンは頭を下げたまま、「申し訳ございません」と声を絞り出す。
「俺だけじゃない。エルファンもだ。『リュイセンの処遇について、提案がある』と、昨日の夕方、わざわざ俺のところに来た」
「父上が……!?」
意外だった。なんとなく――であるが、この手のことに、父は口出ししないような気がしていたのだ。
「エルファン」
イーレオが、共犯者の目でエルファンを見やる。
それを受け、エルファンが口の端を上げた。軽く声もたてて笑っていたのだが、不可聴音が如き低音はたいして響かず、平伏のため顔を見ていないリュイセンは、エルファンが笑んだことに、まるで気づかない。
「リュイセン」
イーレオと同じ声質。けれど、感情の消え失せた氷のような音質。
父エルファンの声に、リュイセンは身を引き締める。
「私は、次期総帥の座を退く」
「……?」
「今後は、お前が次期総帥となり、一族をまとめていけ」
「!?」
冷たく耳朶を打つ声に、リュイセンは思わず面を上げた。黄金比の美貌を崩し、ぽかんと口を開けたまま固まる。
驚愕のリュイセンをまるで意に介さず、エルファンは淡々と続けた。
「これは、総帥と私が、よくよく話し合った上での決定だ。異論は許さぬ」
3.崇き狼の宣誓-2

『今後は、お前が次期総帥となり、一族をまとめていけ』
何を言われたのか、理解できなかった。
リュイセンは、ただただ呆然とエルファンを――次期総帥であるはずの父の顔を見つめる。
しかし、無表情の美貌からは、何も読み取ることができない。
「ど……う、して……」
どうしてですか、と問おうとして、『異論は許さぬ』と言われたことを思い出し、唇を噛んだ。
わけが分からない。
何故、次期総帥などという重要な役目を任ぜようとするのか。しかも、次期総帥の座は現在、空席ではない。父が退いて、リュイセンが収まるのだという。
あり得ない。あってはならない。
リュイセンは裏切り者だ。彼に与えられるべきものは、地位ではなく、然るべき罰のはずだ。
がたがたと体が震えてきた。たとえ百人の敵を前にしても、臆することのないリュイセンが、情けないことに、父のひとことに恐れを感じていた。
「リュイセン」
静かな低音が響く。
父――ではない。祖父、総帥イーレオだ。
「理由を知りたいか?」
「は……い」
リュイセンは、かすれた声で答える。
「お前が、総帥の器だからだ」
呼吸が止まった。
今にも眼球が飛び出さんばかりに大きく目を見開き、イーレオを凝視する。
「何、故……!」
青ざめた顔で、やっと、それだけ吐き出した。
『異論は許さぬ』と言われた……しかし、これは異論でも反論でもなく、ただの疑問だ。
「俺には……、俺が総帥の器だなんて思えません。納得のいく説明を願います!」
床に手を付いたままの姿勢でありながらも、牙をむいた狼が如く。リュイセンは噛み付くように訴えかけた。
それは予測通りの反応だったのだろう。イーレオは、ソファーの肘掛けで優雅に頬杖を付きながら、眼鏡の奥の目をにやりと細めた。
「この俺がそう思い、俺が信を置くエルファンもそう思った。――ならば、それは正しいことだろう?」
王国一の凶賊の総帥は、実に楽しげな様子で、とんでもない屁理屈を傲然と言ってのけた。
「俺は、納得のできる説明を、と申し上げました! 失礼ですが、それでは俺は納得できません!」
「ほぅ……。では、お前は、この俺がここまで自信を持って言っていることが、間違いだとでも?」
イーレオならではの伝家の宝刀とでもいうべき発言に、しかし、今回ばかりは、リュイセンも引き下がれない。
「この件に関してだけは、そう言わせていただきます!」
若き狼が吼え、老獪な獅子王を睨みつける。
執務室は奇妙な緊迫に包まれ、当事者以外の者たちは、呆気混じりの、なんとも言えない顔で眉根を寄せた。
リュイセン本人は処罰を求めたが、他の者たちからすれば、敵対していた〈蝿〉を下し、『最高の終幕』へと導いたリュイセンは、称賛されることこそあれ、罰せられるべきではない。否、褒美を与えられて然るべき、と思っている。
しかし、エルファンが次期総帥の座を退いてまで、リュイセンを抜擢するほどかといえば、さすがに首をかしげざるを得なくなる。
ただ、イーレオが本気であることは、誰の目にも明らかであった。
リュイセンを本気でからかいつつ、本気で讃えている。
だから、これはもう決定項なのだ。
ルイフォンなどは、詳しい説明を求めるべく、兄貴分の援護をしたかったのであるが、一族を抜けた以上、彼は部外者である。そもそも、こんな重大な話を一族以外の者の前でするな、と言いたいところではあったが、ぐっと拳を握りしめて押し黙った。
もっとも、一族であるミンウェイやチャオラウにしたところで、総帥の決定に口を挟むことなどできようはずもない。固唾を呑んで、ただ状況を見守るのみである。
めでたい話であるはずなのに、どうして、こんな険悪な雰囲気になっているのか。傍観者たちが、ほとほと困り果てようとしたとき……。
イーレオの口元が、ふっとほころんだ。
「そうやって、何者にも屈しないところも、総帥に向いていると思わんか?」
「祖父上……? いえ、これは当然の……」
反論しかけたリュイセンの言葉を、イーレオは慈愛の眼差しで押さえ込む。
「いささか挑発に乗せられやすく、思慮の足りないところは玉に瑕だが、『未来の鷹刀』をまとめていくには、どこまでもまっすぐで高潔な人間こそが、ふさわしいだろう?」
魅惑の低音が、リュイセンを包み込む。
ひとり掛けのソファーにもたれ、緩やかに腕を組む姿は、尊大とも取れる態度であるはずなのに、王者の風格を漂わせたイーレオであれば、実に自然な絵となる。
――総帥にふさわしい人間とは、祖父イーレオのような者をいうのだ。
解せぬと顔をしかめたリュイセンに、イーレオは苦笑を漏らした。感情をあからさまに出しすぎだ、ということらしい。
それからイーレオは、エルファンに視線を送る。
現時点での次期総帥は了承の意を返し、未だ床にひざまずいたままのリュイセンに席に戻るよう言い渡すと、玲瓏とした声を響かせた。
「リュイセン。この件は、私から総帥に進言した。お前になら任せられるであろう、とな」
「父上!?」
父はいつも、できの悪い次男を不甲斐なく思っていたのではなかったのか? 優秀な長男が一族を抜けていなければ――と。
リュイセンの頭を、ぐるぐると疑問が駆け巡る。その思いは、すべて顔に出ていたのだが、エルファンは構わずに続けた。
「もとより私は、次の総帥にふさわしい後継者が育つまでの中継ぎだ。『次期総帥』の肩書きは、一時的に預かっていただけにすぎん」
「なっ……!?」
衝撃の告白だった。
「俺のせい――俺のためだ」
絶句したリュイセンの耳に、イーレオの声が静かに、けれども強い振動で轟く。それは、エルファンの発言の補足であり、イーレオの悔恨の思い。
イーレオの秀でた額に皺が寄り、それを隠すように、はらりと落ちた黒髪が寂寥を帯びた。
「三十年前、俺は――俺たちは簒奪者だった。俺の父親である前総帥を弑し、武力で鷹刀を掌中に収めた」
底知れぬ深い海の色合いの瞳に、リュイセンは促されるように頷く。
それは知っている、と。
「一族をまとめ、規律正しい組織に作り変えていくためには、飴と鞭が必要だった。だから、総帥となった俺に悪感情が向かないよう、俺は『飴』に。そして、エルファンが自ら『鞭』を買って出てくれた」
イーレオが告げる。
そして、エルファンが「続きは、私が――」と、言を継ぐ。
「『鞭』は、不満や反感を集めるのが仕事だ。そして人間は、一度、抱いた感情を塗り替えることは、あまり得意ではない。私が総帥になれば、必ず波乱を招くだろう。だから、私は頃合いを見て、位を退くべきなのだ。――ましてや、『未来の鷹刀』は『鞭』で従わせるような組織であってはならないのだからな」
リュイセンは、はっと息を呑んだ。
イーレオも、エルファンも、『未来の鷹刀』と口にした。
それは額面通りに受け取れば、単に『将来』を意味する。しかし、リュイセンは、イーレオがいずれ一族を解散させようとしていることを知っている。
つまり、『未来の鷹刀』とは、解散へと舵を切る鷹刀一族のことだ。
ならば、ふたりが望む『次の総帥』とは――。
『最後の総帥』だ。
リュイセンの心臓が、激しく脈打つ。
祖父と父は、一族の終焉をリュイセンに託そうとしているのだ……。
「私は総帥となって、人の上に立ちたいとは思わない」
淡々とした声が響いた。人の恨みに慣れるために、感情を殺してきた父の声だ。
「それよりも、私にしかできない役割をこなすほうが、よほど有意義だと考える。――本望だ」
――だから、お前も、自分にしかできない、やるべきことをやれ。
無言の声が聞こえた。
「今回のお前の裏切り行為は、決して許されるものではない。だが同時に、お前は、補って余りある功績を上げた。――私は『時が来た』と思った」
リュイセンは、膝の上に置いた両手を硬く握りしめた。それでも、高鳴る鼓動は鎮まることを知らない。
「とはいえ、先ほど総帥がおっしゃったように、お前の裏切りには一族の者たちが激しく動揺している。この状況で、お前を引き立てるわけにはいかないだろう」
「その通りです。俺……私は、償うべき立場です」
硬い声で、リュイセンが告げると、エルファンは黙って頷いた。
「皆を納得させるためには、今回の出来ごとを包み隠さず、すべて詳らかにするのが一番であるが、あまりにもことが大きすぎる。そこで私は一計を案じた」
「計略、ですか……?」
「お前は『敵を欺くにはまず味方から、ということで、やむを得ず、独断で行動した』ということにする」
「え……」
そんな詭弁程度では、一族は納得しないだろう。それに償いは、責任はどうなるのだ?
思考が表情に出まくっているリュイセンに、エルファンは目元だけで苦笑した。そして、静かに続ける。
「無論、お前は『見事、鷹刀に刃を向けた敵を討ち倒した』と発表する。そして、『重大な機密情報に触れるため、詳細を広く皆に教えることはできないが、私が次期総帥の位を譲ることで、お前の功績の大きさを示す』――とする」
「そ、それでは、俺は責任を取ったことになりません!」
思わず口走った言葉は、いつもの『俺』に戻っていた。声に出してから気づき、リュイセンは恥辱に震える。
彼の失態に気づいたからか、それとも別の理由からか。エルファンが口の端を上げた。
「何を言っている? お前はこれから『次期総帥』――ひいては『総帥』という重責を担うことになる。お前の一生を捧げることになるのだ。これ以上の罰もなかろう」
無情の策略家と謳われる次期総帥エルファンが、氷の瞳を細めて嗤う。
「!」
リュイセンの美貌が、彫像のように凍りついた。
耳を疑った。
それは『罰』などではなく、『信頼』に他ならない――!
「どうだ、リュイセン。私の策に異論はあるか?」
未熟な自分が、祖父と父の期待に応えられるだろうか。
そんな疑問を抱いたのは刹那のこと。
リュイセンを行動を決めるものは、理屈ではなく直感。故に、次の瞬間には、リュイセンは立ち上がり、再び床にひざまずいていた。
「ございません!」
両手を付き、深く頭を垂れる。
「謹んで、お受けいたします」
次期総帥を。
最後の総帥という役割を――。
そして、執務室は祝福の拍手喝采で沸き立った。
「緋扇! 待ってくれ」
本業があると、さっと退室していったシュアンを追いかけ、リュイセンは広い庭を走った。
会議がお開きになってすぐに声を掛けられればよかったのだが、『次期総帥任命の儀の段取りについて、話がある』とイーレオに引き止められたのだ。
勿論、すぐに『世話になった緋扇に、きちんと礼を言っておきたい』と断りを入れて執務室を飛び出したのだが、随分と出遅れてしまった。
「はぁ? どうした?」
耳障りな甲高い声を上げながらシュアンが振り返ると、制帽に押さえつけられていない、自由気ままなぼさぼさ頭が、ふわりと揺れた。凶賊の屋敷に行くのに警察隊の制服は不適切だとして、今は私服姿なのだ。これからどこかで着替えるのだろう。彼も大変である。
「珍しいな。あんたが俺に用があるなんて……ああ、なるほど」
シュアンは、胡散臭気な笑みを浮かべた。それから、特徴的な三白眼を細め、周囲を警戒するように鋭く視線を走らせる。
「……?」
リュイセンは、つられるように、あたりを見渡した。
ふたりが立っている場所は、ミンウェイお気に入りの温室のそばだった。彼女がひとりになりたいときに籠もる、あの温室である。
そして、そこは奇しくも、以前、今と同じように、リュイセンがシュアンを呼び止めた場所でもあった。『今後いっさい、ミンウェイには関わるな』と警告したときだ。
あれは、情けない嫉妬から出た言葉だった。今のリュイセンなら、非礼であったと素直に認められる。
そんなことを思い出し、リュイセンが気まずげに表情を曇らせていると、シュアンが唐突に、かつ無遠慮に間合いに入り込んできた。そして、草むしりの庭師や、鍛錬中の凶賊、洗濯物を運ぶメイドたちに聞こえないような低い声で語りかけてくる。
「昨日、あれから、ミンウェイがどうなったかを知りたいんだな?」
「へっ!? 昨日……?」
不意の問いかけに、リュイセンは呆けた。
何やら勘違いしている様子のシュアンを前に、慌てて状況の把握に努める。
昨日――。
長かった〈蝿〉との対立に、終止符が打たれた。
そして、〈蝿〉が『対』として作られた『彼女』と共に息を引き取ったあと、タオロンがミンウェイに会いに来た。なんでも、娘のファンルゥの部屋を見てほしいのだという。
リュイセンは、ファンルゥの部屋に入ったことがある。彼に、女児の部屋の良し悪しなど分かるはずもないが、それでも、たくさんの玩具に囲まれたあの部屋からは、深い愛情が感じられた。
だから、リュイセンには直感的に分かってしまった。
あのタイミングで、タオロンが『ミンウェイに部屋を見せたい』と言ったからには、あの部屋は〈蝿〉が用意したものなのだ。
〈蝿〉が、小さな女の子のために――娘の喜ぶ顔を思い出して――揃えたものなのだ。
あの部屋を見て、ミンウェイが何を思うのか。
それは、正の感情なのか、負の感情なのか。……それとも両方なのか。
いずれにせよ、ミンウェイは激しく感情を揺さぶられる。〈蝿〉の『死』を強く実感することになるからだ。
――そのときに、彼女の心に救いをあげたい。
だから。
『緋扇……、お前が、ミンウェイのあとを追ってくれ』
『今のミンウェイには、お前の言葉が必要だ』
そう言って、シュアンに頭を下げた。
本当は、リュイセン自身が彼女のそばに行きたかった。彼女を支えたかった。
けれど、彼女は、彼の言葉には作り笑顔で応えようとするから。
だからあのとき、リュイセンのすべきことは、自分がミンウェイを追いかけることではなく、シュアンを送り出すことだった。
後悔などしていないし、正しかったと思っている。
何故なら、戻ってきた彼女は、涙の乾いた顔で、けれども、心から――笑っていたから。
ミンウェイの笑顔を思い出し、リュイセンの口元がほころんだ。
「リュイセン?」
シュアンが訝しげに眉を寄せた。
リュイセンは、なんでもないと首を振る。
「ミンウェイのことは心配していない。彼女は、もう大丈夫だろう」
ミンウェイがどんな顔をして、シュアンはなんて声を掛けたのか。気にならないと言えば嘘になる。そのときに、ミンウェイの心がシュアンに傾いたとしても不思議がないことも、承知している。
それでも――。
大切なのは、ミンウェイが今、前を向いているということだけだ。
シュアンは、しばらく狐につままれたような顔でぽかんとしていたが、やがて「ああ、そうさ」と頷いた。その声は、濁声のシュアンとは思えないような、優しい響きをしていた。
「彼女は受け入れた。『どうにもならねぇ』ってことを、ありのままな」
そう言って、シュアンも微笑む。笑んだところで相変わらずの強面の凶相だったが、何も言わないわけでもなく、かといって詳しく語るわけでもない――そんな答え方をしてくれたことに、彼の誠実さが感じられた。
「緋扇、ありがとう」
ミンウェイの心を救ってくれて。
リュイセンは、彼女の心を守ろうとして一族を裏切った。けれど、それは、ただの空回りだった。
だから――ありがとう。
感謝の言葉は、とても自然に口からこぼれた。
ふと気づけば、シュアンが三白眼を見開き、リュイセンを凝視していた。
「あんた、変わったな……」
「え?」
「なんでもねぇよ。――それじゃ、俺は行くぞ」
シュアンが、くるりと踵を返す。
「あ、待て。俺の用件はまだ終わってねぇ」
「は? じゃあ、なんの用だよ?」
問われて気づく。
たった今、謝意を伝えたばかりであるが、本来の目的も礼だった。――なんとなく、きまりが悪い。
「…………礼を言いに来た」
「はぁ? 礼なら、今――」
案の定の反応に、リュイセンは神速で「別件だ」と遮る。
「俺が鷹刀を裏切ったとき、お前が誰よりも先に、俺のことを『味方』だと言ってくれたと聞いた。『先だって潜入成功している、頼もしい仲間』だと」
「ああ……」
シュアンは、どことなく気まずげに視線をそらした。らしくないことをしたと、照れているらしい。悪人面なので、はっきりとは分からないが。
「だってよ? どう考えても、あんたは〈蝿〉の野郎に脅されているに決まっているのに、鷹刀の連中は、凶賊の仁義だか流儀だかのために、ちっとも動かねぇんだよ……」
空を仰ぎながら、シュアンは、ぼやくように言う。
「俺は、しびれを切らして口出ししただけだ。〈蝿〉への復讐は、俺にとっても大事なことだったんでな。俺は俺で、必要に迫られただけさ」
「けど、お前のおかげで、今がある。――緋扇、ありがとう。感謝している」
ひねくれ者のシュアンには、直球の謝辞は、むず痒かったらしい。彼は、ぼさぼさ頭をがりがりと掻いた。そして、ほんの少しの逡巡ののち、ぼそりと呟く。
「……俺が、あんたの立場だったら、あんな馬鹿なことはしなかった」
「――っ」
自分でも未熟だとは思うが、リュイセンは反射的に眉を吊り上げた。しかし、彼が何かを口走るよりも先に、シュアンが続けた。
「でもそれは『しなかった』じゃなくて、『できなかった』なんだろう。――だから、あんたは『尊敬に値する馬鹿』だ」
「なっ――!」
喧嘩を売っているとしか思えない言葉だった。
……けれど、シュアンの三白眼がいつになく切なげで、リュイセンは戸惑う。
「あんたなら、あの危なっかしいお人好しが無茶をしても、体を張って止めてやれるだろう」
「――え?」
シュアンは今、なんと言った?
それは、どういう意味だ?
疑問が渦巻く。
しかし、彼はリュイセンの心を見透かしたかのように――質問は許さぬと言うかのように、すっと一歩、後ろに下がった。
「頑張れよ、次期総帥。……――ま、俺は、お前たちを取り締まる立場だけどな」
どことなく揶揄が混じったような、いつもの軽薄な口調。警察隊員でありながら、まるきり悪党の顔で、シュアンは、にやりと口角を上げる。
「緋扇?」
「おっと、いい加減、職場に戻らねぇと」
鷹刀一族で一、二を争う猛者であるリュイセンを前に、シュアンの背中に隙はなく――。
不意に、風が吹き抜けた。
爽やかさの中に、徐々に熱気をはらんできた夏の風だ。
「ミンウェイに、――――――を……頼む」
シュアンのいる風上から流れてきた空気の中に、リュイセンは彼の呟きを聞いた。
風が巡り、時が廻る。
始まりの桜吹雪の舞は、薄紅から色を移し、濃緑の葉擦れが、蒼天に捧ぐ旋律を奏でる。
新しい季節が始まろうとしていた。
4.風凪の眠りに灯る光-1

菖蒲の館の〈蝿〉の地下研究室は、予定通り時間を置いてから、ルイフォンが遠隔操作で爆破した。〈蝿〉と『彼女』の遺体は、ミンウェイが略式の葬儀を挙げ、彼らのオリジナルたちが眠る、海を臨む丘に埋葬した。
リュイセンの次期総帥昇格については一族を大いに驚かせたが、彼の顔つきが変わったのは誰もが認めるところで、概ね、好感をもって受け入れられた。任命の儀は、つつがなく執り行われ、彼は晴れて次期総帥となった。
〈蝿〉との決着から、そんな慌ただしい日々が続いていたが、ようやくひと区切りがついた。
「――なぁ、メイシア」
彼女が差し入れてくれたお茶を飲み干し、ルイフォンは呼びかけた。
ここ数日、彼は仕事部屋に籠もりきりで作業を続けていた。ずっと、ほったらかしにしていた〈スー〉のプログラムの解析に本腰を入れ始めたのだ。
〈スー〉のことは、今までは漠然と、『母の遺産』として価値があるものだと思っていた。言い換えれば、とんでもない技術の結晶という『もの』としての興味しかなかった。
しかし、〈蝿〉から〈冥王〉のことを聞き、〈スー〉は、母の脳を素にした有機コンピュータなのだと気づいた。
母のキリファの『命そのもの』なのだと。
『本体』とでもいうべき光の珠は、〈蠍〉の研究室跡に建てられた家にある。ルイフォンは実物を見てこなかったが、エルファンによれば、眠るように静かに、ほのかな光を灯していたという。
そして、『本体』に、〈スー〉のプログラムを解析した『中身』を合わせれば、母から作られた〈スー〉が目覚める――。
ルイフォンの意識は変わった。
しかし、進捗は芳しくない。悪筆の母の手書き文字で書かれたプログラムは暗号に等しく、正しくは『解析』ではなく、困難を極める『解読』作業なのだ。ルイフォンが今まで先延ばしにしていた所以でもある……。
手を止めて、OAグラスを外した彼を見て、メイシアは機械類の載った机の下から丸椅子を出して座った。その際、流れてきた長い黒髪をすっと指先で耳に掛ける。何気ない仕草だが、半袖のメイド服から伸びた華奢な腕が、白く艶めく。
だから、ルイフォンは、彼女に言おうとしていた用件は脇に置き、まずは素直な感想を口にした。
「お前、また綺麗になったな」
「ル、ルイフォン!? い、いきなり何を……」
メイシアは、彼が見惚れた白磁の肌をさぁっと紅に染め、恥ずかしそうにうつむいた。照れも遠慮もない彼の言動は、いつものことであろうに、いまだに慣れないものらしい。
「俺は、思ったことを言ったまでだ。離れ離れになっている間に、色気が増したというか……。見た目だけじゃないんだよな。『堂々たる気品』とでも言えばいいのか? ともかく、惚れ直した」
ルイフォンは、愛しげに目を細める。彼女がそばに居ることが、どれだけ大切なことなのか。離れていた一週間ばかりで思い知らされた。
そんなご機嫌な彼を前に、メイシアは困ったように身を縮こめる。けれど、すぐに、まだ赤みの残る顔で彼を見上げ、笑顔の花を咲かせてくれた。
「ありがとう、……嬉しい。――うん。私も、逢えなかった間に、ルイフォンが少し変わった気がしていた」
「え?」
意外な発言に、彼は軽く目を見張る。
「あのね、落ち着いた雰囲気になったの。だからといって、覇気がないわけじゃない。むしろ、覇気であふれている」
それから彼女は、ほんの少し、ためらうように視線を落とした。無意識に顎を引いたせいか、再び顔を上げたときに、はにかむような上目遣いの、どこか甘えた可愛らしい表情になっている。
「私……、そんなルイフォンに、どきどきする。今までも、ルイフォンのことが好きだったのに、前よりももっと――好きなの」
その瞬間、ルイフォンは得も言われぬ幸せで満たされた。
座っている回転椅子をすっと滑らせ、ふわりと彼女の肩を抱き寄せる。
「メイシア、俺もだ。――けど、たぶん、明日にはもっと、お前を好きになっているだろう」
ルイフォンが変わっていくのは、メイシアのため。彼女が安心して、彼のそばに居られるように、強く在りたいと願っているから。
それは彼女も同じなのだと――自惚れかもしれないが、自信を持って言える。
ふと、彼は、彼女の体が冷えていることに気づいた。この仕事部屋は、機械類のために室温を低く設定してある。夏服のメイド服では寒かろう。
「続きは、隣で話そう」
ルイフォンは、問答無用でメイシアを抱き上げた。「きゃっ」という小さな悲鳴は、ただのお約束だ。彼女が遠慮がちに嬉しそうな顔をしていることに、彼はちゃんと気づいている。
腕の中の重みと柔らかさに、心地の良い安らぎを感じながら、彼は続き部屋の私室の扉を開いた。
メイシアと向かい合ってテーブルに着くと、今度は話が横道にそれないよう、ルイフォンは早速、切り出した。
「前にさ、俺が『〈蝿〉との決着がついたら、お前を連れて鷹刀を出る』って、言っていたこと――覚えているか?」
それは、ルイフォンがリュイセンを置いて、〈蝿〉のもとから逃げてきたときのことだ。
静かなテノールに、メイシアの表情がすっと引き締まる。
「うん。覚えている」
随分と前のことなのに、さすがはメイシアである。彼は「ありがとな」と、口元を緩めた。
「俺は鷹刀を出て、セレイエを探すつもりだった。あいつに洗いざらい吐かせて、『デヴァイン・シンフォニア計画』を終わらせるために……な」
囁くように落とされた語尾に、メイシアが硬い顔で頷く。
目線を交わす。ふたりの間に無言の声が響く。
――けれど、セレイエは、ふたりに『ライシェン』の幸せを託して死んでいた。
その一方で、『デヴァイン・シンフォニア計画』の全貌はメイシアの脳に刻まれており、すべてが明らかになっている……。
「セレイエを探す必要はなくなった」
ルイフォンの言葉に、メイシアは沈んだ声で「うん」と同意する。
「でも、俺が鷹刀を出ようと思った理由は、もうひとつあって、『デヴァイン・シンフォニア計画』と関係ないはずの鷹刀を巻き込まないためでもあった」
計画に組み込まれていたのは、『ルイフォンとメイシア』であり、『鷹刀』は、ふたりが出逢う場所として利用されただけだった。
ならば、〈猫〉として独立したからには、自分に掛かる火の粉くらい、自分で払う。抜けたはずの一族に守られているようでは、『対等』な協力者とは言えないのだから。――そう思った。
「だから、とりあえず、俺が昔、住んでいた〈ケル〉の家に、お前と移ろうかと考えていた。『ライシェン』も連れてさ。――けど……」
ルイフォンの声が一段、低くなる。
「摂政が鷹刀に目をつけている、という情報が入った」
その瞬間、メイシアが鋭く息を呑んだ。
「セレイエさんも……予期……、心配……していた。鷹刀のこと……」
彼女は両手を頭に添え、綺麗な眉を苦しげに寄せる。セレイエの記憶をたどっているのだ。
「鷹刀はセレイエさんの実家だし、もともと鷹刀と王家には因縁の歴史があるから……。カイウォル摂政殿下は、鷹刀が一枚噛んでいると疑うに違いない――って」
『デヴァイン・シンフォニア計画』は、セレイエにとっては『息子を生き返らせたい』という切なる願いだ。
しかし、摂政にしてみれば、『ライシェン』の後見人の座を巡る政権闘争である。セレイエの死を知らない彼は、なんとしてでも彼女を見つけ出し、排除したいであろう。故に、彼女の実家であり、匿っている可能性の高い王国一の凶賊、鷹刀一族の存在は無視できない。
ルイフォンは唇を噛んだ。
「俺たちが今、鷹刀を離れても、どうやら手遅れらしい。しかも摂政は、お前が生きていることを知っている。何かを仕掛けてくるかもしれない。そのとき、俺ひとりで、お前の身を守り抜くことは難しい。――情けねぇけど」
ルイフォンが、リュイセンのように一騎当千の猛者だったらよかったのだろうかと、考えもした。しかし、すぐに、それは否定した。
そもそも、メイシアが狙われるような隙を見せること自体が間違い――否、愚かなのだ。『守る』ということは、『彼女を危険な状況に陥らせない』ということだ。魔術師である彼には、騎士のような華々しい活躍なんか必要ない。
「『お前を連れて出る』なんて宣言していたのに格好つかねぇけどさ、現状を考えると、俺たちは、この屋敷に留まるべきだと思う。勿論、世話になるだけじゃなくて、俺は〈猫〉として貢献するし、お前だって鷹刀のために働く。メイドとしてだけじゃなくて、ミンウェイがお前を助手として欲しがっていた」
「え……?」
最後のひとことに、だろう。メイシアが、きょとんと目を丸くした。彼女は、自分の価値が分かっていないのだ。ルイフォンは苦笑を漏らし、ミンウェイに言われたことを思い出しながら、誇らしげな気持ちで補足する。
「前に、お前がミンウェイを手伝ったことがあっただろ? そのとき、手際の良さに感動した、ってさ。――で、今はリュイセンが次期総帥を継いだばかりで、なんか雑務が多いらしい。助けてほしいそうだ」
「嬉しい……。私でも、お役に立てたんだ……」
頬を染めながら言う台詞もまた自己評価が低く、如何にもメイシアである。しかし、彼女は瞳を輝かせながら、大きく頷いた。
「――うん。今は、もうしばらく鷹刀にご厄介になりましょう。私たちは『ふたりきり』じゃなくて、『皆に囲まれた、ふたり』なんだもの」
嬉しそうなメイシアに、ルイフォンは少しだけ憮然とする。
「俺としては、お前と『ふたりきり』にも憧れるけどな」
ぼそりと漏らすと、彼女は照れたような笑みを返してくれた。
だから、彼も口元をほころばせる。
「ともかくさ。俺たちの目標は『デヴァイン・シンフォニア計画』を終焉へと導くことだ。『ライシェン』に何をしてやれるのか――どんな着地点を目指すのかは、まだ決まっていないけど……。でも、この計画を終わらせる。できるだけ早く――な」
「うん」
打てば響くような、澄んだ声。
彼の戦乙女がそばに居れば、彼は無敵だ。
「『ライシェン』の未来は、摂政カイウォルと父親のヤンイェン――このふたりの王族の肚に依るところが大きいだろう。そんなすぐに白黒がつく問題じゃない、しばらく様子見になる。だから、俺は、まずはできることから――というわけで、〈スー〉を目覚めさせる」
ルイフォンは、今まで作業をしていた仕事部屋をちらりと見やる。
「母さんが命を賭けた意味を知りたいし、〈冥王〉のことも訊きたい。もし、母さんの願い通りに〈冥王〉を破壊したら、〈神の御子〉の『ライシェン』を始め、誰に――何に、どんな影響があるのか、理解しておきたい」
ルイフォンが未来を見据え、そう告げたとき、唐突にメイシアの瞳から涙がこぼれた。白い頬をなぞるように、緩やかな曲線を描きながら、音もなく光の筋が流れていく。
「メイシア!?」
何故、彼女が泣くのか? わけが分からず、ルイフォンは狼狽する。
しかし、当のメイシアのほうが、彼以上に困惑したような顔をしていた。自分の頬に触れ、濡れた指先を呆然と見つめている。
「あ……、セレイエさんが……セレイエさんの記憶が泣いている……」
細い声が、涙を含んで震えた。
「ああ……、セレイエさんも、キリファさんが命を賭けた意味を知りたがっていたんだ……。なんとなく、自分のせいだと察していたけど、理由が分からなかったから。だから、この涙は、罪の意識……」
メイシアは、さっとハンカチを取り出して涙を拭う。そして、「驚かせてごめんなさい」と、少し無理のある顔で笑った。
「おい、大丈夫か?」
「うん。……ええとね」
彼女は指先を自分の頭に当てる。また、セレイエの記憶をたどっているのだ。
「セレイエさんが『デヴァイン・シンフォニア計画』を作ったのは、キリファさんが亡くなって……、ヤンイェン殿下が先王陛下を殺害し、幽閉されたあと。――セレイエさんが、ひとりきりになってしまってからなんだけど……。でも、それよりもずっと前、ライシェンが殺されてすぐに、セレイエさんはキリファさんに会いに行っていたの」
「え? セレイエが母さんに会いに来た? ――って、俺は、同じ家に住んでいたはずなんだけど、その時期にセレイエが来たなんて知らねぇぞ」
「ううんと……。あ、ルイフォンが出掛けている間に行ったみたい」
思い出すような素振りで、メイシアが言う。まさに『記憶を掘り起こしている』というべきか。
脳に刻まれたセレイエの記憶は、メイシアが知りたいと思わなければ、気づかないものらしい。しかし、いきなり泣き出したりもするので、どうにも仕組みが曖昧だ。
……ルイフォンとしては、セレイエにメイシアを奪われたような気がして、正直なところ不快――腹が立つ。
「セレイエさんは、キリファさんに〈冥王〉について聞きに行ったの。セレイエさんの力で、ライシェンの記憶を集められるかどうか……。でも、キリファさんは、ライシェンの蘇生に猛反対で、喧嘩別れみたいになっちゃったの」
「そりゃまぁ、そうだろ。母さんは〈七つの大罪〉の技術を否定する側だ。蘇生なんて認められないだろ」
「うん……。だけど、そのあと、キリファさんは亡くなって……、セレイエさんは、自分のために違いないと……、それで……」
そう呟いた彼女の顔には血の気がなく、白蝋のようで……。
「おい! 顔色が悪いぞ」
メイシアが、セレイエに同調している――。
本能的な恐怖を覚え、ルイフォンは血相を変えた。椅子を倒しながら席を立ち、彼女へと駆け寄る。
「ルイフォン?」
「もう、セレイエの記憶を見るな!」
『デヴァイン・シンフォニア計画』の詳細を聞いたときに、そう言っておくべきだった。あのときも、メイシアは、セレイエの記憶に心を流されそうになった。
ルイフォンは、彼女を背中から包み込む。黒絹の髪に指を滑らせ、くしゃりと撫でる。
メイシアはセレイエの記憶は悪さをしないと言ったが、他人の記憶、他人の感情が精神に良い影響を与えるわけがない。心に負担が掛かる。何故なら、心優しいメイシアは、どうしたってセレイエを思いやる。それではメイシアの心がもたないのだ。
急に叫んだルイフォンに、メイシアは、びくりと体を震わせた。
けれど、ゆっくりと彼を振り返り……、ふわりと笑う。
「心配してくれて、ありがとう」
「え……、あ……、大声を出して……すまん」
落ち着き払った様子のメイシアに、ルイフォンは面目なく尻つぼみに謝る。
「ううん。でも、セレイエさんの記憶は、重要な『情報』なの。彼女の気持ちを思うと辛くなることもあるけれど、こうしてルイフォンが抱きしめてくれるから、大丈夫」
凛とした黒曜石の瞳が、まっすぐに彼を映す。
「メイシア……」
彼女は強くなった。――ルイフォンのために。
……それでも。
「俺が嫌だから、セレイエの記憶を見るのは禁止だ」
「えっ!?」
ルイフォンの堂々たる我儘に、メイシアは声を失った。
しかし一瞬、彼女を黙らせたところで意味はない。彼女は、嫋やかなようでいて芯が強く、しかも聡明だ。きちんと説き伏せなければ、納得しないだろう。
癖の強い前髪を乱暴に掻き上げ、ルイフォンは思案する。
そして、はっと閃いた。
「お前に、セレイエの記憶を見ることを禁止する、大義名分があった」
彼は猫の目を得意げに細め、にやりと口角を上げる。
「お前がセレイエの記憶を持っているのは、ホンシュアが〈天使〉の力を使って、お前に記憶を書き込んだから――つまり、〈七つの大罪〉の技術に依るものだ」
「え? ええ、うん……」
メイシアは、戸惑いながらも相槌を打つ。
「〈七つの大罪〉の技術は確かに凄い。けど、頼ったらいけない、禁忌のものだ。――だから、封じるべきだ。勝手に見えちまう分はどうしようもないけど、わざわざ自分から、セレイエの記憶を見ようとしないでくれ」
鋭いテノールに、メイシアの表情が揺れた。ルイフォンの弁は正論と思いつつ、全面的に肯定できないでいるのだ。
ルイフォンは畳み掛けるように続ける。
「セレイエの記憶が、有益な情報であることは承知している。でも、俺たちなら、別の方法で必ず、なんとかできるはずだ」
彼は笑う。
彼女が好きだと言ってくれる、覇気のあふれる顔で。
「俺たちが一番知りたくて、セレイエが一番伝えたかった『デヴァイン・シンフォニア計画』の情報は、既に入手している。それでもう、充分だろ?」
「……っ」
メイシアの顔が曇った。
セレイエが一番伝えたかったのは、メイシアが『最強の〈天使〉』になるために必要な、『〈天使〉の力を使いこなすための知識』ではないのか? ――そんな反論が、彼女の心をよぎったのが見て取れた。
しかし、メイシアは〈天使〉にはならない。
メイシア本人も望んでいなければ、ルイフォンだって猛反対だからだ。故に、セレイエの知識は不要なものだ。メイシアも、それが分かっているから口に出さない。
ならば、もうひと押し。
ルイフォンは、おそらく決定打となるであろう、ひとことを加える。
「それにセレイエだって、他人に根掘り葉掘り、記憶を探られたくはないはずだ。誰しも、秘密にしておきたいことくらいあるはずだからな。――暴いたら駄目だろ?」
「!」
黒曜石の瞳が、いっぱいに見開かれた。
「そ、そうよね……、私、セレイエさんに凄く失礼なことをしていた……。恥ずかしい」
「だろ?」
完璧な論理だと、ルイフォンは鼻高々である。
だからつい、口を滑らせた。
「セレイエの記憶の中には、餓鬼のころの俺の姿もあるはずだ。そんなもの、俺も知られたくはな……」
「あぁっ!」
突然、メイシアが華やかな声を上げる。
慎み深い彼女のこと、すぐにうつむいて口元を隠したが、黒曜石の瞳はきらきらと輝き、まろみ帯びた頬はわずかに上気している。遠慮がちでありながら、しかし明白に、うずうずという好奇心の音が聞こえていた。
ルイフォンは、おそるおそる尋ねる。
「ひょっとして、お前、餓鬼のころの俺に興味がある?」
「うん」
控えめに頷きつつも、彼女の頬は薔薇色に染まっている。
「だからと言って、セレイエの記憶を見るのは――」
「ち、違うの! そんな、セレイエさんにも、ルイフォンにも失礼なことはしない! ……ただ純粋に、小さいころのルイフォンを想像して、その……、可愛かっただろうなぁ、って。…………見たいな、って。あ、勿論、見ないの! 私の中に、そんな記憶が刻まれているんだな、ってだけで……」
彼女らしくもなく、支離滅裂である。
ルイフォンは唖然としつつ、こんなメイシアも可愛らしいなと目を細める。すると、何を勘違いしたのか、彼女は、ぼそぼそと弁解するように呟いた。
「だって、私の知らないルイフォンなんだもの……」
ほんの少し拗ねたような、甘えたような上目遣い。彼の最愛のメイシアは、それと分かりにくいが、意外と独占欲が強いのだ。
そして、そんなところも愛おしい。
出逢ったばかりのころの彼女からは想像もできない、彼しか知らない蠱惑の顔に、ルイフォンは魅入られる。
だから、彼女の喜ぶ顔を見たくて、彼は尋ねる。
「餓鬼のころの俺の写真、見るか?」
恥ずかしい過去の逸話は封印だが、写真くらいなら構わない。
「見たい!」
期待通り、彼女は嬉しそうに即答してくれた。
そういえば、メイシアは、ルイフォンの女装姿『ルイリン』の写真をとても大切にしているのだった。時々、携帯端末を眺めては、口元をほころばせていることを彼は知っている。
彼女はきっと、『子供のころのルイフォンの写真も欲しい』と言い出すに違いない。……どうせなら、まともな写真も持っていてほしい。
「ああ、そうか」
「え?」
不意に呟いたルイフォンに、メイシアが不思議そうな顔をする。
「俺たち『ふたり』の写真を撮ろう」
よく考えたら、『ふたり』一緒の写真は、菖蒲の庭園での再会のとき、シュアンがハオリュウに送るために撮ったものしかない。
本当に、まだまだ、これからの『ふたり』なのだ。
思い立ったが吉日とばかりに、ルイフォンが携帯端末を取り出すと、メイシアが極上の笑顔を煌めかせた。
これからずっと、何度でも。
寄り添う、ふたりの姿を残していこう。
そうして、共に時を重ねていくのだ――。
4.風凪の眠りに灯る光-2

深緑の街路樹の間を一台のバイクが駆け抜ける。
郊外に位置する、貴族の別荘地。綺麗に舗装された道路は滑らかで、車輪は摩擦を忘れたかのよう。家はまばらで人影もなく、木漏れ日の差す音すら聞こえてきそうな閑静さである。
ルイフォンは、タンデムシートのメイシアの体温を背中に感じながら、風を切っていた。
目指すは〈蠍〉の研究所跡。〈スー〉の家だ。
〈スー〉のプログラムの解析が終わるのは、まだまだ先の話なのであるが、埃だらけだという家の様子を聞いたメイシアが、〈スー〉の目覚めの日のために掃除をしておきたいと言ってくれたのだ。
「もし、ルイフォンが〈スー〉の解析作業で忙しいなら、私ひとりでも大丈夫だから……」
メイシアは、如何にも彼女らしく遠慮がちに申し出た。
「何を言ってんだよ? 勿論、俺も一緒に行く。それに、俺も掃除くらい手伝うよ」
「ありがとう! 嬉しい」
顔をほころばせる彼女を可愛らしく思いながら、ルイフォンは、あの家の状態を思い出す。
電気だけは通っていたものの、何年も放置されていた家だ。しかも、〈ケル〉の家の設計図をそのまま流用しただけあって、それなりに広い。掃除『くらい』というレベルの作業では済まないはずだ。専門の業者に頼まなければ無理だろう。
どう考えても、ふたりが一日掛けて掃除をしたところで、使えるような家にはならない。それは、分かりきっていた。だが、まずは、ふたりきりで行きたいと思ったのだ。
――そう。誰かに護衛を頼んだりせずに、『ふたりきり』だ。
ここ最近、ルイフォンは、一族を抜けて以来、怠けていた鍛錬を再開した。〈スー〉の解析作業で忙しくはあるのだが、やはり体を鍛えることも大切だと心を入れ替えたのだ。――勿論、万一のときに、メイシアを守り抜くためである。いくら、普段は鷹刀一族の厄介になることにしたとはいえ、たまには、メイシアと『ふたりきり』で出掛けたいからだ。
出発準備として、〈蠍〉の研究所跡の住所をエルファンに教えてもらった。前回は車で連れて行ってもらっただけなので、正確な位置を知らなかったのだ。そして、地図で確認したとき、ルイフォンは思わず感嘆の声を漏らした。
「母さん、やる気満々だな」
「え? どういうこと?」
首をかしげたメイシアに、ルイフォンは、にやりと口角を上げる。
「ほら、ここが、俺が昔、住んでいた〈ケル〉の家だろ? で、ここが〈ベロ〉のいる鷹刀の屋敷」
彼は、メイシアに地図を示す。
「そして、ここが〈蠍〉の研究所跡――〈スー〉の家」
ルイフォンが、〈ケル〉〈ベロ〉〈スー〉のいる三箇所を順に指でなぞると、地図上に、ほぼ正三角形の図形が描かれた。
「あ!」
敏いメイシアは、それだけで分かってくれたようだ。驚きの声を上げつつも、興奮を隠しきれない様子で、指先をそっと正三角形の中心に載せる。
桜色の爪の先が示したのは『神殿』――〈冥王〉が収められている場所である。
〈ケルベロス〉は、〈冥王〉を取り囲むように配置されていたのだ。
「まさに『包囲網』って、感じだな」
「キリファさん……。なんか、凄い……」
ふたりは顔を見合わせ、改めて、キリファの『〈冥王〉を破壊したい』という思いを受け止めた。――それを叶えるのか否かは、まだ未知数であるけれども。
閑散とした別荘地の中でも、更に周りからぽつんと取り残されたように、一軒だけ離れたところに〈スー〉の家はあった。その門扉の前で、ルイフォンはバイクを停める。
タンデムシートから降りたメイシアは、生け垣の隙間から雑草のはびこる庭を覗き見て、放心していた。思っていた以上に、荒れ放題だったのだろう。
しかし、目つきが徐々に真剣になっていく。この庭の手入れをする算段を組み立てているのだ。
「あのさ、先に言わなかったのは悪いんだけど、たぶん、俺たちが手作業で、この家を綺麗にするのは無理だと思う。あとで業者を頼むつもりだ」
「え……」
ルイフォンが少し申し訳ない気分で白状すると、案の定、メイシアは愕然とした面持ちで絶句した。どうやら、張り切っていたらしい。
そういえば、今日の彼女は、いつもは長くおろしている黒絹の髪を高い位置でひとつにまとめていた。てっきり暑いからだと思っていたのだが、作業の邪魔にならないようにとの意気込みだったのかもしれない。彼女が、がっくりと肩を落とすと、あらわになった白いうなじが、彼の目に眩しく映った。
「今日はさ、この家の状況を確認しようと思う。造りは〈ケル〉の家と同じなんだけど、置いてあるものとか、壊れてしまっているものとか、いろいろ把握しておきたいからさ」
「うん、分かった。――あ、桜……!」
ルイフォンに返事をしつつ、メイシアは庭の桜の木に気づいたらしい。嬉しそうに言葉尻を跳ねかせた。掃除の件では拍子抜けしたものの、気が遠くなるような作業がなくなって、心に余裕ができたのだろう。
濃い緑に覆われた木が、夏風にざわざわと枝葉を揺らす。
根本に置かれたベンチを見つけ、彼女は「わぁ」と声を漏らした。細部までもが〈ケル〉の家と、そっくりなことに気づいたのだ。
「ルイフォン」
「ん?」
「キリファさん、本当にこの家が好きだったのね。――エルファン様が設計してくださった、この家が」
葉擦れの音に、メイシアの微笑が溶ける。笑っているはずなのに、薄紅の唇はどこか儚げで、黒曜石の瞳は切なげに細められていた。
「メイシア?」
不思議な表情を見せる彼女に、ルイフォンは戸惑う。
「ルイフォンのお父様は、本当はイーレオ様じゃなくて、エルファン様なんじゃないか――って、レイウェンさんがおっしゃっていたのよね?」
「え? ああ。レイウェンの奴、どうしても俺を異母弟にしたがっていた。よく分かんねぇけど」
それは、菖蒲の館からの屈辱の敗走の末、レイウェンの家に寄らせてもらったときのことだ。レイウェンが強引に、異母兄を名乗ったのだ。
「その話、本当だと思うの。――だって、キリファさんは、こんなにもエルファン様を想っている……」
「はぁ? 母さんは、単に設計図を使いまわしただけだろ?」
「それだけだったら、庭まで同じにしなくてもいいと思うの」
「うーん……?」
メイシアの理屈はよく分からない。
ただ、母がずっとエルファンを想っていたことは、どうやら本当らしい。〈ケル〉がそんなことを匂わせていた。だから、ひょっとしたら……とは思うものの、実のところ、ルイフォンとしては父親が誰でも構わないのだ。
何故なら、彼はもう独立しているのだから。
そして何より、メイシアという伴侶が居るのだから。
イーレオのことも、エルファンのことも、血族だと思っているし、敬愛もしている。それで充分ではないかと思う。
「――けど。〈スー〉は、エルファンに逢いたいだろうな……」
「え?」
小さな呟きは風に紛れ、メイシアにはよく聞こえなかったようだ。彼女は、きょとんと彼を見上げる。
「早く、〈スー〉のプログラムの解析を終えなきゃな、ってことだ」
そう言って、ルイフォンはメイシアの手を引き、門扉を抜けた。
〈スー〉は、キリファではない。
たとえ〈スー〉が、母から作られた有機コンピュータであったとしても、母本人ではない。
死んだ人間は生き返らないのが、自然の理だからだ。
そして、おそらく『〈冥王〉の破壊』という目的が達成されたら、〈ケルベロス〉は消える。〈七つの大罪〉の技術を否定する母が設計したものであるのなら、それが道理だ。
だから、〈スー〉を目覚めさせても、いずれ別れを経験することになる。
それでも――。
家の中に足を踏み入れると、ふわりと埃が舞い上がった。かび臭さが、むわっと広がる。
庭の荒れ具合いから、メイシアは屋内の様子を覚悟していたらしく、驚くことはなかった。だが、如何にも廃屋然とした暗がりの廊下は、やはり怖かったようだ。ルイフォンの服の端をぎゅっと握りしめてきた。
だから彼は、華奢な肩をそっと抱き寄せる。
「メイシア、まずは地下だ」
前回、この家に来たときには、〈スー〉のいる地下へは行かなかった。〈スー〉のプログラムの解析が終わらないうちは、行くべきではないと思ったのだ。
けれど、今日は事情が違う。
業者に掃除を頼むつもりでありながら、わざわざメイシアと『ふたりきり』で来たのには、ちゃんと理由がある。
「お前を〈スー〉に――母さんに紹介したい」
「えっ」
薄明かりの中でも、はっきりと分かるほどに、黒曜石の瞳が大きく見開かれた。
「お前だって、俺のことをお継母さんに紹介してくれただろ? だから俺も、お前を母さんに紹介したいんだ」
〈スー〉は母ではないし、そもそも、まだ眠りの中だ。メイシアが彼を継母に紹介してくれたのとは、同じ意味にはならないだろう。
けれど、意義はあるはずだ。
「俺にとって母さんは、『乗り越えるべき壁』みたいな存在だった。母さんに認められれば『一人前』なんだと、ずっと思っていた」
昔を懐かしむように苦笑しながら、ルイフォンは語る。
「母さんが死んだとき、俺はまだまだ餓鬼だった。自分が『一人前』には、ほど遠いのは分かっていて、俺のことを認めさせる前に、母さんが死んじまったのが悔しかった」
メイシアの眉が曇った。
そんな顔はしなくてよいのだ。もうとっくに過ぎた過去の話だ。ルイフォンは柔らかな表情で、彼女の髪をくしゃりと撫でる。
「今だって、どうなれば『一人前』といえるのか、分かっているわけじゃない。でも俺は、お前と出逢って確実に変わったと思う。『一人前』に近づけたんじゃないかと思う。――だから、お前を母さんに見せたいんだ」
ルイフォンはメイシアを見つめ、覇気に満ちたテノールを響かせる。
「まぁ、結局のところ、お前のことを自慢したいだけかもな」
そう言って、得意げに口の端を上げた。
地下の造りも、当然のことながら〈ケル〉の家とそっくりで、迷うことはなかった。
奥の小部屋の手前には、ルイフォンが『張りぼて』と呼ぶ巨大なコンピュータが設置されており、体を芯から揺り動かすような騒音が鳴り響いていることも、また同じである。
この張りぼてに関しては、〈ベロ〉から新しい情報を得ていた。
曰く、光の珠の姿をした真の〈ケルベロス〉のために、張りぼての〈ケルベロス〉が、電気エネルギーを有機コンピュータが消費できる形の動力源に変換しているのだという。
このことは、ルイフォンがこんな質問をしたことから判明した。
『まさか、〈ケルベロス〉も、〈冥王〉みたいに人の血肉を喰らって動いている、ってことはねぇよな?』
なかば恐喝の口調で尋ねたら、人の世には関わらないと公言している〈ベロ〉も、さすがにかちんと来たのか、声を張り上げて教えてくれたのだ。
『キリファが、そんなものを作るわけないでしょ! お前が『張りぼて』呼ばわりしている、あのデカブツ。あれが、〈ケルベロス〉の『動力変換器』になっているのよ!』――と。
だから、眠っているとはいえ、密やかに息づいている真の〈スー〉に動力源を供給するために、張りぼての〈スー〉は無人の家で動き続けている。そう思うと、不快な振動も、どことなく頼もしかった。
それに――。
「メイシア」
轟音に声を掻き消されても、彼女はちゃんと分かってくれる。
彼が手を伸ばせば、彼女は手を重ね合わせてくれる。
そして、ふたりで〈スー〉の部屋の扉を開いた。
小部屋に入り、分厚い防音扉を閉じる。密封された空間に、今までの騒音が嘘のような静寂が訪れる。
照明のスイッチの在り処は知っていたが、あえて点けない。余計な光は、今は野暮だ。
部屋の奥を見やり、ルイフォンとメイシアは、同時に息を呑む。
漆黒の中に、神秘的な白金の光が、淡く浮かび上がっていた。
幻想的な輝きを放つ光の珠は、まるで寝息を立てるようにゆっくりと明るさを変えていく……。
ルイフォンは、メイシアの手を取った。
彼女の指先は、緊張で震えていた。そして、彼は、はっと気づく。
「よく考えたら、母さんに向かって堅苦しい挨拶なんて、可笑しいな」
「えっ!?」
「だって、俺は、最高のお前を母さんに見せたい。――だから、お前が笑っていなきゃ、意味がない!」
彼は、にやりと猫の目を細めた。そして、実に洗練された動作で、滑らかに彼女の膝裏をすくい上げる。
「え……? ――きゃっ!」
最近、鍛えていたのは伊達ではなく、メイシアの体は、あっという間に、軽々とルイフォンに抱き上げられた。
……とはいえ、不意打ちだった彼女は本気で驚き、必死に彼にしがみついてくる。
「ル、ルイフォン!」
遠慮がちな抗議の声は可愛らしく、その表情はいつもの自然なメイシアだ。
ルイフォンは満足気に微笑むと、光の珠へと近づき、晴れやかな声を響かせた。
「母さん、紹介するよ。俺のメイシアだ」
背筋を伸ばし、誇らしげに胸を張る。
「俺を幸せにしてくれる女。そして、俺が幸せにする女だ」
抜けるような青空の笑顔で宣告する。
腕の中のメイシアが、ぱっとルイフォンを見上げた。その瞳はうっすらと涙で潤み……、けれど、それはすぐに極上の笑みへと移り変わった。
そして、彼に床に下ろしてほしいと頼み、彼女もまた光の珠と正面から向き合う。
優雅に一礼し、祈りを捧げるように胸元で両手を組んだ。
「キリファさん。ルイフォンは、私がいつも笑っていられるように、と言ってくれるんです。だから私も、ルイフォンがいつも笑っていられるように尽くすと――誓います」
微笑みながらも、凛と響く声。
感極まったルイフォンは大きく腕を広げ、包み込むように彼女を抱きしめた。その動きに、彼の背で一本に編まれた髪も、彼女を守るように流れていく――。
光の珠が、ほのかに煌めく。
凪いだような静けさの中、ルイフォンの髪先を飾る金の鈴に、祝福の光を灯した。
~ 第十章 了 ~
~ 第二部 完 ~
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第二部 第十章 蒼穹への黎明と
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第三部 海誓山盟 第一章 夏嵐の襲来から https://slib.net/115847
――――に、続きます。


