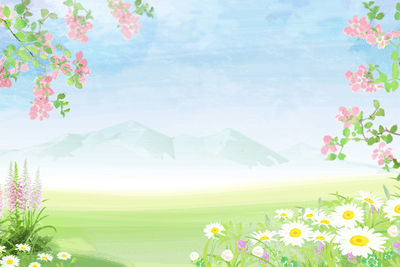
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第二部 第八章 夢幻の根幹から
こちらは、
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第八章 夢幻の根幹から
――――です。
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第七章 五里霧の囚獄で https://slib.net/113419
――――の続きとなっております。
長い作品であるため、分割して投稿しています。
プロフィール内に、作品全体の目次があります。
https://slib.net/a/4695/
こちらから「見開き・縦書き」表示の『えあ草紙』で読むこともできます。
(星空文庫に戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください)
※使わせていただいているサービス『QRouton』の仕様により、クッションページが表示されます。
https://qrtn.jp/22wz8m8
『えあ草紙』の使い方は、ごちらをご参考ください。
https://www.satokazzz.com/doc/%e3%81%88%e3%81%82%e8%8d%89%e7%b4%99%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab
「メニューを表示」→「設定」から、フォント等の変更ができます。PCなら、"UD Digi Kyokasho NP-R"等のフォントが綺麗です。
〈第七章あらすじ&登場人物紹介〉

===第七章 あらすじ===
メイシアを連れ去ろうとするリュイセンを目撃したものの、ルイフォンは阻止することができなかった。その結果、メイシアは〈蝿〉に囚われ、裏切り行為を働いたリュイセンは本人不在のまま、鷹刀一族からの追放処分となった。
リュイセンに斬られた腹の傷のため、ルイフォンは絶対安静を言い渡された。しかし、エルファンが現れ、地下にいる〈ベロ〉と話をしたいと、彼を強引に連れて行く。
エルファンは、〈ケルベロス〉はセレイエのために作られたシステムで、〈天使〉の力を無効化できる。だから、メイシアが『セレイエの〈影〉』にされるのを阻止して欲しい、と〈ベロ〉に頼んだ。しかし、不可能だと言われてしまう。
何故なら、〈ケルベロス〉は『〈天使〉の力の源』を破壊する手段であり、個々の〈天使〉の力を消すものではないからだ、と。
〈ベロ〉が、『〈天使〉の力の源』とは『〈冥王〉』である、と言ったとき、〈ベロ〉に〈悪魔〉の『契約』が発動した。
どうやら『〈冥王〉』という言葉は、王族の『秘密』と関係があるらしい。また、『人』だったときの記憶を持っているために『契約』が発動した、と〈ベロ〉に説明されたことで、〈ケルベロス〉は『人』の記憶を利用して作られていることが判明した。
〈ベロ〉は別れ際、『契約』に抵触するから詳しいことは言えないが、メイシアがセレイエの〈影〉にされることはないから安心するように、と告げた。
リュイセンを憂い、温室に籠もったミンウェイに、シュアンは、リュイセンは愛するミンウェイのために裏切ったのだ、と断言する。シュアンの推測によれば、リュイセンは〈蝿〉に『この薬を投与しなければ、ミンウェイは母親と同じ病で死ぬ』などと言われて従っているのだろう、と。
ミンウェイは、自分の体は母親と違って健康体だと反論するが、シュアンは、リュイセンが信じさえすれば、嘘でもいいんだと言い張る。だが、どちらにせよ、閉じ籠もっていないで、ルイフォンと協力して現状を抜け出すべきだと、ミンウェイは心を入れ替えた。
〈蝿〉の地下研究室で目を覚ましたメイシアは、〈蝿〉に、鷹刀セレイエを見つけるのが目的だ、と言われる。メイシアの中に刻まれた『セレイエの記憶』が居場所を知っているはずだ、と。
また、王族の血を引くメイシアは、『メイシア本人』と『セレイエ』の両方の記憶を同時に持つことが可能であるため、『セレイエの記憶』を思い出しても〈影〉にはならない。リュイセンに教えたことは半分嘘だったと告げられる。
セレイエを探す理由を問うたメイシアに、〈蝿〉は『生を享けた以上、生をまっとうする』という妻との約束を守るために、セレイエと手を組むか、あるいはセレイエを摂政に売って身の安全を確保するためだと答えた。
〈蝿〉はメイシアに、『デヴァイン・シンフォニア計画』は、セレイエが殺された息子を生き返らせるための計画であると教えた。つまり、〈神の御子〉の『ライシェン』は、セレイエの子供のクローンであると。そして、〈蝿〉が『ライシェン』を見せたとき、メイシアの世界は暗転した。
気を失ったメイシアの頭に「『最強の〈天使〉』の力で、ルイフォンと共に『ライシェン』を守って」というセレイエの願いが響き、メイシアはセレイエの記憶を得る。その中で、ライシェンの父親は、先王の甥であり、現女王の婚約者ヤンイェンだと分かる。また、ヤンイェンが先王を殺したのは、息子ライシェンを殺されたためであったと知った。
一方、鷹刀一族の屋敷では、ルイフォンとミンウェイが手を取り合った直後に、口論を始めた。『リュイセンはミンウェイのために裏切った』ことは共通の認識でありながら、リュイセンを弁護するミンウェイに対し、ルイフォンはなんの相談もせずにメイシアを連れ去った兄貴分を許せないと言い張ったためだ。
そこにシュアンが現れ、ハオリュウからの伝言により、ルイフォンは、『メイシアはリュイセンと共に逃げようとしているはずだ』と気づく。そして、リュイセンが〈蝿〉に追い込まれているのなら、弟分の自分こそが助けるべきだと考え直す。
シュアンは、リュイセンは嘘の薬を求めて〈蝿〉に踊らされているのではないか、と持論を主張した。それを聞いたルイフォンは、『天性の勘を持ったリュイセンは嘘には騙されない。つまり〈蝿〉は、ミンウェイに関する抗いようもない事実でリュイセンを従わせたのだ』と気づく。
そして、『ミンウェイが健康であること』こそが、脅しの事実だと悟る。
展望塔に囚われたメイシアは、『セレイエの記憶』の首尾を聞きにきた〈蝿〉に「楽しい記憶しか思い出せない」と嘘を言った。それは、どんな些細な情報も教えたくなかったためと、これからどうすればいいのか考える時間が欲しかったためである。危うい交渉の末、彼女は一週間の猶予をもぎ取った。
リュイセンがメイシアの世話係となり、彼と話す機会を得たが、顔向けできないと、口を閉ざされてしまった。
黄昏どきに紛れ、ファンルゥが、メイシアを助けるために現れた。ファンルゥの考えた方法での脱出は無理だったが、メイシアはファンルゥの『毒針が出る腕輪』が嘘であると気づく。そして、ファンルゥとタオロンに協力してもらう作戦を思いついた。
タオロンはメイシアからの『密書』に従って、〈蝿〉から外出許可を得て、見張りの男に『いい思い』の約束で協力させ、娼館に行く。そこで待っていたのは女装姿のルイフォンだった。密会の場として店を貸す代償として、シャオリエとスーリンに悪ふざけの餌食にされたのだった。
タオロンは正式に味方になり、なんでもするとルイフォンに約束した。同時に、ルイフォンは『何故メイシアは、タオロンの武力で〈蝿〉を捕まえて逃げてくるのではなく、タオロンに苦手な嘘と演技を頼んで、携帯端末を持ってくることを願ったのか』と疑問に思う。
ルイフォンとメイシアは電話での再会を果たした。感極まったメイシアが落ち着いたあと、ルイフォンは彼女に、どうしてタオロンに『〈蝿〉を捕まえて欲しい』と頼まなかったのかを尋ねた。
するとメイシアは、セレイエの記憶を受け取った自分は『デヴァイン・シンフォニア計画』のすべてを知っている。だから、〈蝿〉には情報源としての価値はなくなってしまった。〈蝿〉のことは『捕まえる』ではなくて『殺す』べき。けれど、自分には『殺して』とは言えなかった、と泣き出した。
ルイフォンは、メイシアの気持ちは当然のことだと言い、タオロンには鷹刀一族や〈猫〉からの正式な依頼として、〈蝿〉殺害を頼もうと決める。しかしそのとき、〈蝿〉に引導を渡す役は、リュイセンであるべきだと思い立った。
リュイセンは〈蝿〉に逆らえないのでは? と尋ねるメイシアに、ルイフォンは「俺がリュイセンの束縛を解いてやる」と答える。ルイフォンには、リュイセンが〈蝿〉に従っている理由が分かったのだ。ただし、まだ推測に過ぎない。だから、「これから証拠を手に入れて、リュイセンを解放する」と彼は宣言した。
===登場人物===
鷹刀ルイフォン
凶賊鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオの末子。十六歳。
――ということになっているが、本当は次期総帥エルファンの息子なので、イーレオの孫にあたる。
母親のキリファから、〈猫〉というクラッカーの通称を継いでいる。
端正な顔立ちであるのだが、表情のせいでそうは見えない。
長髪を後ろで一本に編み、毛先を母の形見である金の鈴と、青い飾り紐で留めている。
凶賊の一員ではなく、何にも属さない「対等な協力者〈猫〉」であることを主張し、認められている。
※「ハッカー」という用語は、本来「コンピュータ技術に精通した人」の意味であり、悪い意味を持たない。むしろ、尊称として使われている。
対して、「クラッカー」は、悪意を持って他人のコンピュータを攻撃する者を指す。
よって、本作品では、〈猫〉を「クラッカー」と表記する。
メイシア
もと貴族で、藤咲家の娘。十八歳。
ルイフォンと共に居るために、表向き死亡したことになっている。
箱入り娘らしい無知さと明晰な頭脳を持つ。
すなわち、育ちの良さから人を疑うことはできないが、状況の矛盾から嘘を見抜く。
白磁の肌、黒絹の髪の美少女。
王族の血を色濃く引くため、『最強の〈天使〉の器』としてセレイエに選ばれ、ルイフォンとの出逢いを仕組まれた。
セレイエの〈影〉であったホンシュアを通して、セレイエの『記憶』を受け取った。
[鷹刀一族]
凶賊と呼ばれる、大華王国マフィアの一族。
秘密組織〈七つの大罪〉の介入により、近親婚によって作られた「強く美しい」一族。
――と、説明されていたが、実は〈七つの大罪〉が〈贄〉として作った一族であった。
鷹刀イーレオ
凶賊鷹刀一族の総帥。六十五歳。
若作りで洒落者。
かつては〈七つの大罪〉の研究者、〈悪魔〉の〈獅子〉であった。
鷹刀エルファン
イーレオの長子。次期総帥。
ルイフォンとは親子ほど歳の離れた異母兄弟ということになっているが、実は父親。
感情を表に出すことが少ない。冷静、冷酷。
鷹刀リュイセン
エルファンの次男。イーレオの孫。十九歳。本人は知らないが、ルイフォンの異母兄にあたる。
文句も多いが、やるときはやる男。
『神速の双刀使い』と呼ばれている。
長男の兄が一族を抜けたため、エルファンの次の総帥になる予定であり、最後の総帥となる決意をした。
〈蝿〉に脅迫され、不本意ながら彼の部下となっている。
鷹刀ミンウェイ
母親がイーレオの娘であり、イーレオの孫娘にあたる。二十代半ばに見える。
鷹刀一族の屋敷を切り盛りしている。
緩やかに波打つ長い髪と、豊満な肉体を持つ絶世の美女。ただし、本来は直毛。
薬草と毒草のエキスパート。医師免状も持っている。
かつて〈ベラドンナ〉という名の毒使いの暗殺者として暗躍していた。
父親ヘイシャオに、溺愛という名の虐待を受けていた。
草薙チャオラウ
イーレオの護衛にして、ルイフォンの武術師範。
無精髭を弄ぶ癖がある。
料理長
鷹刀一族の屋敷の料理長。
恰幅の良い初老の男。人柄が体格に出ている。
キリファ
ルイフォンの母。四年前に当時の国王シルフェンに首を落とされて死亡。
天才クラッカー〈猫〉。
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蠍〉に〈天使〉にされた。
また〈蠍〉に右足首から下を斬られたため、歩行は困難だった。
もとエルファンの愛人で、セレイエとルイフォンを産んだ。
ただし、イーレオ、ユイランと結託して、ルイフォンがエルファンの息子であることを隠していた。
ルイフォンに『手紙』と称し、人工知能〈スー〉のプログラムを託した。
〈ケル〉〈ベロ〉〈スー〉
キリファが作った三台の兄弟コンピュータ。
表向きは普通のスーパーコンピュータだが、それは張りぼて。本体は〈七つの大罪〉の技術により、人間の記憶を利用して作られた光の珠である。
『〈天使〉の力の源である〈冥王〉を破壊するためのもの』であるらしい。
〈ベロ〉の人格は、シャオリエのオリジナル『パイシュエ』である。
〈ケル〉は、キリファの親友といってもよい間柄である。
また〈スー〉は、ルイフォンがキリファの『手紙』を正確に打ち込まないと出てこない。
セレイエ
エルファンとキリファの娘。
表向きは、ルイフォンの異父姉となっているが、同父母姉である。
リュイセンにとっては、異母姉になる。
生まれながらの〈天使〉。
貴族と駆け落ちして消息不明と思われていたが……、王族のヤンイェンと恋仲になり、ライシェンという〈神の御子〉を産んだ。
ライシェンを先王シルフェンに殺されたため、ライシェンを生き返らせるための計画『デヴァイン・シンフォニア計画』を作り、身を隠した――というのが真相。
『最強の〈天使〉』となり得るメイシアを選び、ルイフォンと引き合わせた。
メイシアのペンダントの元の持ち主で、『目印』としてメイシアに渡した。
四年前にルイフォンに会いに来て、〈天使〉の能力で何かをした。
パイシュエ
イーレオ曰く、『俺を育ててくれた女』。
故人。鷹刀一族を〈七つの大罪〉の支配から解放するために〈悪魔〉となり、その身を犠牲にして未来永劫、一族を〈贄〉にせずに済む細工を施した。
自分の死後、一族を率いていくことになるイーレオを助けるために、シャオリエという〈影〉を遺した。
また、どこかに残されていた彼女の『記憶』を使い、キリファは〈ベロ〉を作った。
すなわち、パイシュエというひとりの人間から、『シャオリエ』と〈ベロ〉が作られている。
[〈七つの大罪〉・他]
〈七つの大罪〉
現代の『七つの大罪』=『新・七つの大罪』を犯す『闇の研究組織』。
実は、王の私設研究機関。
王家に、王になる資格を持つ〈神の御子〉が生まれないとき、『過去の王のクローンを作り、王家の断絶を防ぐ』という役割を担っている。
〈悪魔〉
知的好奇心に魂を売り渡した研究者を〈悪魔〉と呼ぶ。
〈悪魔〉は〈神〉から名前を貰い、潤沢な資金と絶対の加護、蓄積された門外不出の技術を元に、更なる高みを目指す。
代償は体に刻み込まれた『契約』。――王族の『秘密』を口にすると死ぬという、〈天使〉による脳内介入を受けている。
『契約』
〈悪魔〉が、王族の『秘密』を口外しないように施される脳内介入。
記憶の中に刻まれるため、〈七つの大罪〉とは縁を切ったイーレオも、『契約』に縛られている。
〈天使〉
「記憶の書き込み」ができる人体実験体。
脳内介入を行う際に、背中から光の羽を出し、まるで天使のような姿になる。
〈天使〉とは、脳という記憶装置に、記憶や命令を書き込むオペレーター。いわば、人間に侵入して相手を乗っ取るクラッカー。
羽は、〈天使〉と侵入対象の人間との接続装置であり、限度を超えて酷使すれば熱暴走を起こす。
〈影〉
〈天使〉によって、脳を他人の記憶に書き換えられた人間。
体は元の人物だが、精神が別人となる。
『呪い』・便宜上、そう呼ばれているもの
〈天使〉の脳内介入によって受ける影響、被害といったもの。悪魔の『契約』も『呪い』の一種である。
服従が快楽と錯覚するような他人を支配する命令や、「パパがチョコを食べていいと言った」という他愛のない嘘の記憶まで、いろいろである。
『di;vine+sin;fonia デヴァイン・シンフォニア計画』
セレイエによる、殺された息子ライシェンを生き返らせるための計画。
『di』は、『ふたつ』を意味する接頭辞。『vine』は、『蔓』。
つまり、『ふたつの蔓』――転じて、『二重螺旋』『DNAの立体構造』――『命』の暗喩。
『sin』は『罪』。『fonia』は、ただの語呂合わせ。
これらの意味を繋ぎ合わせて『命に対する冒涜』と、ホンシュアは言った。
ヘイシャオ
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蝿〉。ミンウェイの父。故人。
医者で暗殺者。
病弱な妻のために〈悪魔〉となった。
〈七つの大罪〉の技術を否定したイーレオを恨んでいるらしい。
娘を、亡くした妻の代わりにするという、異常な愛情で溺愛していた。
そのため、娘に、妻と同じ名前『ミンウェイ』と名付けている。
十数年前に、娘のミンウェイを連れて現れ、自殺のようなかたちでエルファンに殺された。
現在の〈蝿〉
セレイエが『ライシェン』を作らせるために、蘇らせたヘイシャオ。
セレイエに吹き込まれた嘘のせいで、イーレオの命を狙ってきた。
死の間際のホンシュアから、メイシアに『セレイエの記憶』が刻まれていると教えられ、セレイエの居場所を知るために、リュイセンを脅迫をして、メイシアを囚えた。
ヘイシャオそのものだが、記憶と肉体の年齢が合っていない。
ホンシュア
殺されたライシェンの侍女であり、自害するくらいならとセレイエの〈影〉となって『デヴァイン・シンフォニア計画』に協力した。体は〈天使〉化してあった。
〈影〉にされたメイシアの父親に、死ぬ前だけでも本人に戻れるような細工をしたため、体が限界を超え、熱暴走を起こして死亡。
メイシアにセレイエの記憶を潜ませ、鷹刀に行くように仕向けた、いわば発端を作った人物である。
〈蛇〉
セレイエの〈悪魔〉としての名前。
〈蝿〉が、セレイエの〈影〉であるホンシュアを〈蛇〉と呼んでいたため、ホンシュアを指すこともある。
ライシェン
殺されたセレイエの息子の名前。
〈神の御子〉だった。
斑目タオロン
よく陽に焼けた浅黒い肌に、意思の強そうな目をした斑目一族の若い衆。
堂々たる体躯に猪突猛進の性格。
二十四歳だが、童顔ゆえに、二十歳そこそこに見られる。
〈蝿〉の部下となっていたが、娘のファンルゥに着けられていた毒針の腕輪が嘘だと分かり、ルイフォンたちの味方になった。
斑目ファンルゥ
タオロンの娘。四、五歳くらい。
くりっとした丸い目に、ぴょんぴょんとはねた癖っ毛が愛らしい。
彼女の優しさのおかげで、状況が一転し、解決へと向かい始めた。
[藤咲家・他]
藤咲ハオリュウ
メイシアの異母弟。十二歳。
父親を亡くしたため、若年ながら藤咲家の当主を継いだ。
十人並みの容姿に、子供とは思えない言動。いずれは一角の人物になると目される。
異母姉メイシアを自由にするために、表向き死亡したことにしたのは彼である。
女王陛下の婚礼衣装制作に関して、草薙レイウェンと提携を決めた。
緋扇シュアン
『狂犬』と呼ばれるイカレ警察隊員。三十路手前程度。イーレオには『野犬』と呼ばれた。
ぼさぼさに乱れまくった頭髪、隈のできた血走った目、不健康そうな青白い肌をしている。
凶賊の抗争に巻き込まれて家族を失っており、凶賊を恨んでいる。
凶賊を殲滅すべく、情報を求めて鷹刀一族と手を結んだ。
敬愛する先輩が〈蝿〉の手に堕ちてしまい、自らの手で射殺した。
似た境遇に遭ったハオリュウに庇護欲を感じ、彼に協力することにした。
[王家・他]
アイリー
大華王国の現女王。十五歳。
彼女の婚約を開始条件に、すべてが――『デヴァイン・シンフォニア計画』が始まったと思われる。
メイシアの再従姉妹にあたるが、メイシア曰く『私は数多の貴族のひとりに過ぎなかった』。
シルフェン
先王。四年前、腹心だった甥のヤンイェンに殺害された。
〈神の御子〉に恵まれなかった先々王が〈七つの大罪〉に作らせた『過去の王のクローン』である。
ヤンイェン
先王の甥。女王の婚約者。
実は先王が〈神の御子〉を求めて姉に産ませた隠し子で、女王アイリーや摂政カイウォルの異母兄弟に当たる。
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉だったセレイエと恋仲になり、ライシェンが生まれた。
しかし、〈神の御子〉であったライシェンは殺され、その復讐として先王を殺害した。
メイシアの再従兄妹にあたる。
カイウォル
摂政。女王の兄に当たる人物。
摂政を含む、女王以外の兄弟は〈神の御子〉の外見を持たないために、王位継承権はない。
異母兄にあたるヤンイェンとの結婚を嫌がる妹、女王アイリーのため、ハオリュウに『君が女王の婚約者になれば、女王の結婚が延期される』と陰謀を持ちかけた。
[草薙家]
草薙レイウェン
エルファンの長男。リュイセンの兄。
エルファンの後継者であったが、幼馴染で妻のシャンリーを外の世界で活躍させるために
鷹刀一族を出た。
――ということになっているが、リュイセンに後継者を譲ろうと、シャンリーと画策したというのが真相。
服飾会社、警備会社など、複数の会社を興す。
草薙シャンリー
レイウェンの妻。チャオラウの姪だが、赤子のころに両親を亡くしたためチャオラウの養女になっている。
王宮に召されるほどの剣舞の名手。
遠目には男性にしかみえない。本人は男装をしているつもりはないが、男装の麗人と呼ばれる。
草薙クーティエ
レイウェンとシャンリーの娘。リュイセンの姪に当たる。十歳。
可愛らしく、活発。
鷹刀ユイラン
エルファンの正妻。レイウェン、リュイセンの母。
レイウェンの会社の専属デザイナーとして、鷹刀一族の屋敷を出た。
ルイフォンが、エルファンの子であることを隠したいキリファに協力して、愛人をいじめる正妻のふりをしてくれた。
メイシアの異母弟ハオリュウに、メイシアの花嫁衣装を依頼された。
また、ヘイシャオの実の姉でもある。
[繁華街]
シャオリエ
高級娼館の女主人。年齢不詳。
外見は嫋やかな美女だが、中身は『姐さん』。
実は〈影〉であり、イーレオを育てた、パイシュエという人物の記憶を持つ。
スーリン
シャオリエの店の娼婦。
くるくる巻き毛のポニーテールが似合う、小柄で可愛らしい少女。ということになっているが妖艶な美女という説もある。
本人曰く、もと女優の卵である。実年齢は不明。
ルイリン
ルイフォンの女装姿につけられた名前。
タオロンと好い仲の少女娼婦。癖の強い、長い黒髪の美少女。
少女にしては長身で、そのことを気するかのように猫背である。
――という設定になっている。
===大華王国について===
黒髪黒目の国民の中で、白金の髪、青灰色の瞳を持つ王が治める王国である。
身分制度は、王族、貴族、平民、自由民に分かれている。
また、暴力的な手段によって団結している集団のことを凶賊と呼ぶ。彼らは平民や自由民であるが、貴族並みの勢力を誇っている。
1.咲き誇りし華の根源-1

夜闇に黒く沈んだ窓硝子が、執務室の風景を映し出す――。
メイシアとの電話のあとすぐ、ルイフォンは緊急の会議を開くために皆を集めた。
鷹刀一族総帥イーレオと、護衛のチャオラウ。次期総帥エルファンに、総帥の補佐たるミンウェイ。
そして、鷹刀一族の『対等な協力者』〈猫〉こと、ルイフォン――の五人。
すっかり寂しくなってしまった光景に、ルイフォンの胸が痛む。
しかし、それは今だけだ。すぐにメイシアとリュイセンを取り戻してみせる。
ルイフォンは心の中で誓い、猫の目を鋭く光らせる。拳をぐっと握りしめ、決意も新たに口火を切った。
「こんな夜遅い時間にすまない。先ほど予定通り、無事にメイシアと連絡を取ることができた。それで俺から――〈猫〉から、今後について提案がある」
端的なテノールが響き渡る。
場の空気が研ぎ澄まされ、一気に緊張を帯びていくのが分かる。おそらく誰もが、この言葉を待っていたのだ。
「ルイフォン。お前のことだ、その策に自信があるんだろう?」
美麗な口元をほころばせながら、イーレオが問う。眼鏡の奥の目は、いたずらを思いついた子供のように楽しげに細められていた。
「ああ、勿論だ」
「そうだろうと思って、ハオリュウとシュアンにも連絡を入れておいた。急なことだから、さすがにハオリュウは無理だったが、シュアンはあとから来るそうだ。待たせるのは悪いから、先に話を始めていてほしいと言われている」
「!」
ルイフォンは目を見開いた。
内容も聞かずに彼らに声を掛けるということは、全面的にルイフォンを信頼し、その案を採用するつもりでいるということだ。
握りしめた掌が、うっすらと汗を帯びる。
「ハオリュウには、メイシアが電話すると言っていたから、彼にも話がいくはずだ」
平静を保ち、ルイフォンは言う。
「ああ、そうか。そうだな。それがいい」
魅惑の低音が、安堵に溶けた。
愛する異母姉をリュイセンにさらわれたハオリュウは、一時は鷹刀一族に絶縁状を叩きつけんばかりに怒り狂った。その非難の言葉の数々を、凶賊の総帥たるイーレオが、ひとことの弁解もなく黙って受け入れたという。
イーレオは、その一幕を思い出していたに違いない。それで、ハオリュウは今ごろ、メイシアの声を聞いて一安心だと、胸を撫で下ろしたのだろう。
ルイフォンは、ぐるりと皆の顔に瞳を巡らせ、最後にミンウェイの美貌の上で目を止めた。
生粋の鷹刀一族の顔立ちであるが、その艷やかな黒髪は本来の直毛ではなく、豪奢に波を打っている。『母親の身代わり、という心の檻から出てらっしゃい』と、ミンウェイがこの屋敷に来たとき、世話を焼いたユイランが掛けた変身の魔法だ。
〈蝿〉に――ヘイシャオに、溺愛という支配を受けていたミンウェイ。彼女が――彼女の『秘密』が、この先の鍵となる……。
ルイフォンは、ごくりと唾を呑み込んだ。
「まず、メイシアとの電話の内容を報告する」
そう言って、彼は話を始めた。
「……――つまり現状でも、タオロンに依頼をすれば、鷹刀が一族の意志と決めた『死』を〈蝿〉に与え、メイシアを救出することができる。だが、ほぼ部外者のタオロンにすべてを託すのは、道理に合わないと俺は考える」
ルイフォンは、そこで言葉を切った。
ここからが本題だ。
「〈蝿〉は、もと一族であるヘイシャオを生き返らせた『もの』だ。そして奴を作ったのは、鷹刀の血を引く俺の異父姉、セレイエ。――ならば〈蝿〉に関する責任は、鷹刀にあるといえる。故に、奴に『死』を与える者は、一族の人間であるべきだ」
ルイフォンは語気を強めて言い放ち、大きく息を吸う。自然と胸を張る姿勢になり、反らされた背中の上で金の鈴が煌めいた。
そして彼は、その名を挙げる。
「すなわち、リュイセン!」
告げた瞬間、皆が色めきだった。
誰もが、何かを内に抱えた顔になる。しかし構わずに、ルイフォンは続けた。
「現状において〈蝿〉の最も近くにいる一族の者。難攻不落のあの庭園に、既に侵入を果たしている人物だ。彼をおいて、他に適任者はいない」
挑発的ともいえる眼差しで、ルイフォンはイーレオを見やる。
「よって〈猫〉は、『鷹刀の後継者』たる、鷹刀リュイセンに〈蝿〉を討ち取らせることを提案する!」
力強いテノールが、執務室の窓硝子を震わせた。
湧き上がる高揚に、知れず全身が上気する。
リュイセンの追放処分を承知していて、あえて『鷹刀の後継者』と口にした。それに対し、イーレオがどんな反応を示すか――。
「〈猫〉」
感情という揺らぎを消し去った、凪いだ海のような声が響いた。ルイフォンの思惑を探るべく、無風を保つ――イーレオの低音は、そんな色合いをしていた。
「リュイセンは、一族から除籍されている。故に、鷹刀とは無関係だ」
「分かっている。だから、リュイセンがことを為したあとで構わない、遡って、追放を取り消せばいい」
当然、来るであろうと思っていた言葉を、用意しておいた台詞で返す。
間髪を容れずのルイフォンに、イーレオは「ふむ……」と呟いた。神妙な顔をしつつも、片頬杖で潰されていないほうの頬が、ぴくりと動く。いい手応えだと、ルイフォンは内心でほくそ笑んだ。
崩した姿勢のままのイーレオは、視線を上げることでルイフォンの顔をじっと見つめ、そして問う。
「つまりお前は、リュイセンが〈蝿〉を討つことを条件に、リュイセンの追放を解いてほしい、と言っているわけか」
「そういうことだ」
「ほう? リュイセンは、お前のメイシアをさらった張本人だぞ。どうして、肩入れをする?」
ルイフォンの思惑を知ったからだろう。イーレオは態度を一変させ、興味津々といった表情を隠しもせずに揶揄混じりの口角を上げた。
「俺だって、初めはリュイセンを絶対に許せねぇと思ったさ。……でも、違うだろ? あいつが好きで俺を裏切るわけがない。そんなことは分かりきっている。何か事情があるんだ。――だったら、俺のほうから手を差し伸べてやるべきだろ?」
猫の目を光らせ、きっぱりと言い切る。そう思えるようになるまでには、それなりの葛藤があったが、もう過去の話だ。
さも当然、といった体のルイフォンに、イーレオが低く嗤う。
「だが、今のリュイセンは『敵』だ。〈蝿〉の部下になっている。そのリュイセンに、どうやって〈蝿〉を討たせるつもりだ?」
「リュイセンは〈蝿〉に脅されて従っているだけだ。だから俺が――〈猫〉が、その原因を取り除いて、あいつを〈蝿〉の束縛から解放すればいい」
鋭く斬り込むような返答。そして、それを皆のざわめきが包み込む。
イーレオにとっても、予想外の宣言だったらしい。総帥たる彼が、驚きに声を揺らす。
「お前は、リュイセンが〈蝿〉に従っている理由を解き明かした――ということか?」
「理由を読み解いた――だ。だから、まだ憶測に過ぎないけどな……」
ルイフォンの口の中に、苦いものが混じる。それまで威勢のよかった口調が急速に力を失い、ぽつりとした呟きに変わる。
「……でも、あいつが俺にすら隠して、すべてを裏切るしかなかった理由なんて、他にあり得ない……」
「ルイフォン! それは、いったい何!?」
弱々しく消えていくテノールの語尾と、弾かれたような草の香りが空中でぶつかり合った。
見れば、ミンウェイがソファーから立ち上がり、波打つ髪をなびかせている。
「ミンウェイ……」
「教えて! リュイセンは、私のために裏切ったんでしょう?」
「あ、ああ……」
ルイフォンは迫力に圧されて思わず頷き、慌てて「でも、お前が悪いわけじゃない!」と、付け加えた。
「俺は――〈猫〉は、リュイセンが〈蝿〉に従った理由をこう考えている。根拠は、メイシアからの情報だ」
聡明なメイシアは、〈蝿〉から重要な情報を聞き出してくれていた。
彼女は、〈蝿〉にこう言われたという。
『リュイセンと私は、〈ベラドンナ〉の『秘密』を共有する同志となったのですよ』
その『秘密』とは、ミンウェイ本人が知らない――ミンウェイが『知りたくもない』ようなものらしい。
つまり、ミンウェイが知れば深く傷つくであろう、重大で、そして非道な『秘密』ということだ。
「リュイセンは、ミンウェイの『秘密』を無理やり聞かされたんだ。そして、『秘密』を知ったことで、あいつは〈蝿〉に従うようになった。――ならば、〈蝿〉が使った脅し文句は、これしかない」
ルイフォンは言葉を切り、〈蝿〉の声色を真似るかのように、一段、低い声を作る。
「『この『秘密』を『ミンウェイ本人』にバラされたくなければ、私に従え』」
――一瞬の沈黙。
それから、誰からともなく、ざわめきの吐息が漏れた。
「なるほど」
皆を代表するかのように、イーレオが相槌を打つ。
「ミンウェイを傷つけるような『秘密』から彼女を守るために、リュイセンは裏切った――ということか。あり得る……いや、それが真実なのだろう。ルイフォンの――〈猫〉の言う通りに」
「――じゃ、じゃあ、リュイセンが〈蝿〉の言いなりになってまで、私から隠したいほどの重大な『秘密』って、なんなの……?」
紅の取れかけた唇を震わせ、ミンウェイが割り込むようにして尋ねた。勢いに反して、その声はか細くかすれており、漠然とした不安に駆られたのか、彼女の顔はみるみるうちに蒼白になる。
それは、当然の質問――予期していた質問だった。
ルイフォンは唇を噛み、しかし「すまん」と、はっきりと告げた。
「その答えは少し待ってほしい。勿論、『秘密』に心当たりはある。けど、そこがさっき『憶測に過ぎない』と言っていた部分で、俺の頭の中では理屈は成立しているけど、証拠がない。まだ空論でしかないんだ。だから、証拠を掴むまで――」
「小難しいことを言ってないで、心当たりがあるなら、さっさと教えなさいよ!」
絹を裂くような声が、ルイフォンを遮った。青白い顔で精いっぱいの虚勢を張りながら、ミンウェイは唇を尖らせる。
けれど、ルイフォンも引くわけにはいかなかった。
これは、リュイセンがすべてと引き換えにしてでも、ミンウェイから隠そうとした『秘密』なのだ。憶測の段階で、おいそれと口にしてよいものではないはずだ。
「ミンウェイ、本当にすまない。でも、俺の憶測は、お前を傷つけるものなんだ。俺は自分の考えが正しいと思っているけど、万が一、見当違いだったら申し訳が立たない。――だから、まずは調べたい。そして、証拠を手に入れてから、きちんと説明したい」
「そこまで言っておいて、重要なところで黙るなんて、おかしいわ!」
ミンウェイはルイフォンを睨みつけるように柳眉を逆立て、更に言葉を重ねる。
「だって、ルイフォンは自分の理屈に自信があるんでしょ!? ならば言うべきだわ! 私も、あなたの頭の良さは認めているし、憶測が外れている可能性があることも承知したわ!」
「……っ」
言葉を詰まらせたルイフォンに、「〈猫〉」と低い声が掛かった。
「お前はさっき、『リュイセンが〈蝿〉に脅されている原因を取り除いて、あいつを〈蝿〉の束縛から解放する』と言ったな」
「あ、ああ」
「それはつまり、ミンウェイが『秘密』を知ることで、『秘密』を『秘密』でなくする。そして、リュイセンが〈蝿〉に従う理由を失わせる。――ということだな?」
「……そうだ」
「だったら、ミンウェイに教えなければ意味がないだろう?」
押さえつけるようなイーレオの物言いに、ルイフォンは猫の目を尖らせる。
「だから! きちんと証拠を手に入れてから、だ! 〈猫〉は、いい加減な情報でミンウェイを翻弄させるような真似はしたくない」
ルイフォンが正面から対峙すると、イーレオは表情の読めない美貌で畳み掛けた。
「では、その証拠はどこにあると踏んでいる?」
「生前のヘイシャオが〈七つの大罪〉に提出した研究報告書に載っていると思う。ヘイシャオの研究室を家探しするか、〈七つの大罪〉に侵入をかけるかで手に入れる」
答えながら、説得力に欠けるな、とルイフォンは奥歯を噛んだ。案の定、イーレオが鼻で笑った。
「だったら、なおのこと、ミンウェイに憶測とやらを話して協力を願うべきだろう。ヘイシャオの研究室は、ミンウェイが昔、住んでいた家にあるんだからな」
「…………」
ルイフォンの溜め息が、虚空に溶けた。
ミンウェイに『秘密』を隠したまま、この作戦を認めてもらうのは無理だろうと、初めから分かっていた。だが、言いたくなかったのだ。……せめて、証拠を掴むまでは。
それは、ケジメのようなもので、リュイセンへの義理立てのような感情だ。
何故なら、ミンウェイに『秘密』を教えることは、リュイセンがすべてを裏切り、失うことを対価に守ろうとした、ミンウェイの心の安寧を奪い去ることになるからだ。すなわち、リュイセンの愛を踏みにじる行為なのだから……。
うなだれたルイフォンに、イーレオの低音が落とされる。
「鷹刀の総帥として、『対等な協力者』である〈猫〉に要請する。お前の憶測を詳しく話せ」
「……『要請』じゃなくて『命令』――だろ」
王者の傲然たる美貌を見上げ、ルイフォンは、うそぶく。だが彼自身、自分のほうが道理が通っていないのは分かりきっていた。
彼は観念したように力なく姿勢を正し、ゆっくりと口を開く。
「ミンウェイの『秘密』――それは、ミンウェイが『健康であること』だ」
「……なっ!? 私の健康が、どうして『秘密』なのよ!?」
詰め寄るミンウェイに、しかしルイフォンは、彼女から逃げるように顔をそむけた。そして、『彼女以外の三人』に向かって問いかける。
「親父、エルファン、チャオラウ……。古い時代の鷹刀を知っている者なら、不思議に思っていたんじゃないのか……? 病弱な母親から生まれたミンウェイが、何故、健康なのだろう――って」
彼らは皆、一様にびくりと体を震わせた。
予想通りの反応など、まるで嬉しくなかった。ルイフォンは小さく息を吐き、無表情の〈猫〉の顔となって、イーレオを捕らえる。
「親父……、生前のヘイシャオとの最後の電話――あれは、ミンウェイが生まれるよりも前だよな? 内容……ちゃんと覚えているか?」
刹那――。
イーレオは頬杖の手から顔を浮かせ、凶賊の総帥らしからぬ動揺をあらわにした。
「そういう……ことか…………!」
「……ああ。ずっと言っている通り、憶測に過ぎないけどな。……でも、それしか考えられないだろ?」
ミンウェイが『健康であること』に秘密があるのではないかと疑ったのは、ルイフォンがシュアンと話したときのことだった。
シュアンは、〈蝿〉は『ミンウェイの命』を盾にリュイセンを脅したに違いない、と主張していた。『〈蝿〉の持っている薬を投与しなければ、ミンウェイが死ぬ』といった類の嘘に乗せられ、リュイセンはありもしない薬を得るために裏切ったのだと。
だが、リュイセンに嘘は通用しないのだ。
大局的に本質を見抜く、天性の勘を持った兄貴分は、それが嘘なら絶対に騙されない。彼が信じたのなら、それは真実なのだ。『抗いようもない事実』を提示され、リュイセンは身動きを取れなくなったのだ。
では、『抗いようもない事実』とは何か――?
そう考えたとき、リュイセンの兄、レイウェンの憂い顔が蘇った。古い時代の鷹刀を知る、最後の直系である彼は、育たなかった兄弟たちのことを今でも悼み続けていた。
鷹刀一族にとって『健康であること』は尊く、そして『稀有』。
「この『秘密』は、ミンウェイ本人は知らないだろう。そして、ヘイシャオの記憶を持つ〈蝿〉なら知っている。――メイシアが聞き出した〈蝿〉の言葉とも、辻褄が合う」
「……なるほどな」
深い溜め息と共に、イーレオがソファーに身を投げ出した。頭を抱えるように髪を掻き上げると、はらはらと落ちる黒髪が美貌に影を落とす。
「ルイフォン? ど……、どういうことよ!? ――お祖父様……! どういう意味でしょうか!」
ミンウェイが声を張り上げた。
だが、打ちひしがれたようなイーレオの姿は変わらず、ならばと、彼女はエルファンとチャオラウに救いを求めて視線を送るが、彼らもイーレオと同様の顔で押し黙ったままだった。
「ちょっ、ちょっと……ルイフォン! 私だけが置いてきぼりだわ!」
彼女は声を尖らせ、ぎろりと彼を睨みつける。――が、その唇は心細げに、わなないていた。
「き、きちんと説明しなさい!」
「あ、ああ……。すまん……、……っ」
ルイフォンは、ミンウェイの一族そのものの美貌と向き合い、しかし、言いよどむ。
「ルイフォン!」
ミンウェイは高い鼻梁をつんと上に向け、歯切れの悪い彼に畳み掛けるように続けようとして……そこで一度、息を止める。陶器のような白い喉が、こくりと動いた。
それから、意を決したように――問う。
「つまり……、私の健康は作られたものだった、ってこと……? リュイセンは、それを秘密にしておくために〈蝿〉に従ったというの!?」
鮮やかな緋色の衣服が、炎のように見えた。
烈火をまとうミンウェイは、絶対に引かぬと艶やかに咲き誇った。
1.咲き誇りし華の根源-2

ミンウェイが柳眉を逆立てる。
リュイセンの裏切りは彼女のためと言われ続け、今まさに核心に迫ろうとしているにも関わらず、ひとりだけ蚊帳の外であれば当然といえよう。
『私の健康は作られたものだった、ってこと……? リュイセンは、それを秘密にしておくために〈蝿〉に従ったというの!?』
しかし、ルイフォンは、その問いに即答できなかった。
喉に声が貼りつき、言葉が出ない。
中途半端な情報に、彼女が脅えているのは理解できる。けれど……。
「――まだ、ただの憶測なんだ。だから、これから……。分かってくれよ……」
それは口の中で転がされた小さな呟きだったが、全身を苛立ちに染めていたミンウェイは耳ざとく拾い、「ルイフォン!」と彼の名を叫ぶ。
「私は憶測で構わないって、言っているでしょ!」
声を荒立てるミンウェイに、ルイフォンは張り合うように言葉を叩きつけた。
「俺が、構うんだよ……!」
胸が、喉が――熱かった。
慟哭のようなテノールに、ミンウェイが目を丸くする。
「ルイフォン……?」
「いいか? リュイセンは、ミンウェイが『秘密』によって傷ついてほしくないから、俺を裏切った。二度と戻れないのを承知の上で、一族を捨てた。それが、どれほどの覚悟なのか、考えてみろよ!」
「……っ」
鋭く斬りつけるような猫の目に、ミンウェイが息を呑んだ。
「リュイセンが、そこまでの想いで守ろうとしたミンウェイの心を、俺が憶測で傷つけていいはずがない!」
ルイフォンは、視線をミンウェイからイーレオへと移す。
そして声を張り上げ、きっぱりと宣告した。
「俺は――情報屋〈猫〉は、証拠によって『憶測』が『事実』になるまで、ミンウェイに『秘密』を説明することを断固、拒否する!」
イーレオは――鷹刀一族の総帥は、〈猫〉の憶測を理解したはずだ。それでなお、ミンウェイに話すべきだと思うのなら、仕方ない。鷹刀一族の判断として、総帥イーレオが話せばよい。
だが、〈猫〉は口を閉ざすと決めた。
イーレオの視線が、ルイフォンのそれと交差する。深い海のような総帥の瞳は、揺らぎのない凪で満たされていた。
「ミンウェイ、席を外せ」
「お祖父様!?」
「お前は、しばらく会議に出てはならない」
「そんな! 横暴です!」
立ち上がったミンウェイの髪が、華やかに舞う。
「先ほど、お祖父様――総帥は、おっしゃったではありませんか! 『対等な協力者』である〈猫〉に、憶測を詳しく話すことを要請する――と」
彼女は自分の主張の正しさを訴え、咲き誇るように胸を張る。しかし、イーレオは静かに首を振った。
「〈猫〉は、鷹刀一族の総帥である俺と『対等』なのだ。そして、俺は〈猫〉の憶測を理解した。だから、〈猫〉はきちんと要請に応えたことになる」
「そんな……!」
美貌を蒼白に染めるミンウェイに、イーレオはそれまでとは打って変わった慈愛の眼差しを向けた。
「すまんな、ミンウェイ。〈猫〉の憶測は突拍子もなくて、荒唐無稽なものだ。だが、言われてみれば、それしかないと思える」
「お祖父様! わけが分かりません!」
牙をむくミンウェイに、しかし、イーレオは構わずに続ける。
「……正直なところ、俺自身、納得したのに、信じられなくもある。〈猫〉がきちんと証拠を添えて説明したいというのも、もっともな話だ。それが、お前に対する礼儀だというのも、理に適っている」
切れ長の目を大きく見開き、ミンウェイは唇をわななかせた。
「皆、勝手だわ! 私の気持ちはどうなるのよ!?」
心からの叫び。
蒼白だった顔は、上気して炎をまとったかのようだった。
――そのときだった。
執務室の扉が、小さな機械音を立てて開いた。
人の気配。
近づいてくる足音。
そして、場の緊張に気圧されたような一瞬の狼狽のあとに、苦笑が続く。
「おいおい、ミンウェイ。あんたの怒った顔も、そりゃあ美人だが、そんなに目を吊り上げたら魅力は半減だぜ?」
挨拶もなく部屋に入り込んできたのは、乱れ放題のぼさぼさ頭に、血走った三白眼。顔についての講釈を垂れるつもりなら、まずは自分の姿を鏡に映してこい、と言いたくなるような、外見には無頓着な男。
今は私服に着替えているが、本業は警察隊員。しかし最近は、毎日のように凶賊である鷹刀一族の屋敷に顔を出している、緋扇シュアンであった。
「緋扇さん!」
ミンウェイの声が喜色を帯びた。
からかわれているのは承知していても、シュアンは何かと親身になってくれる人物だ。現在、孤立無援の彼女にしてみれば、味方を得た気分だっただろう。
「イーレオさん、遅れてすみません」
皆の注目を充分に集めてから、取ってつけたようにシュアンは会釈した。とはいえ、制帽を身に着けているときの癖なのか、自分のぼさぼさ頭に軽く手を触れただけの、非常に彼らしいぞんざいな仕草である。
「ああ、いや。忙しいところ呼び立てしてすまなかった」
「いえいえ。囚われのメイシア嬢と連絡が取れて、ルイフォンから提案があると聞かされれば、そりゃあ飛んできますよ」
シュアンは軽い口調で話しながら、当然のようにミンウェイの隣に腰掛ける。
「――で、詳しい話はあとでミンウェイに聞いておきますから、かいつまんで方針だけ教えて下さいよ。ああ、そもそも、その案、鷹刀としては採用ですか?」
無遠慮な三白眼が、ぎょろりとイーレオを捕らえた。
対してイーレオは、シュアンを一蹴するかのような傲然とした笑みを浮かべ、力強い王者の声で決定を下す。
「採用だ。〈猫〉がリュイセンを解放し、リュイセンに〈蝿〉を討ち取らせる」
「親父……」
ルイフォンは、ごくりと唾を呑んだ。
不協和音が聞こえてきそうな、妙に緊迫したこの状況。どのような態度を取るのが吉なのか、彼は惑う。そのため、提案を受け入れてくれた感謝を述べるべきところで、彼は押し黙ってしまった。
「ほぉ……」
ルイフォンとは対象的に、シュアンが甲高い声を上げる。彼独特の響きは、感嘆にも揶揄にも聞こえた。
「〈猫〉がリュイセンを解放――ということは、リュイセンが脅されたネタを〈猫〉は割り出したのか。ふむ、さすがは噂に名高い〈猫〉だ。実に見事、実に素晴らしい!」
にたにたと品のない嗤いを浮かべながら、シュアンは両手を打ち鳴らした。その意図が読めず、ルイフォンは不審げに……不快げに眉をひそめる。
そこで急に、シュアンの拍手がぴたりと止まった。
「――はて? 無事に作戦が決まって、実にめでたい状況だと思うんですが、なんでミンウェイは美女を台無しにして怒っているんですかね?」
ぐっと顎を上げ、シュアンはルイフォンを見やる。本職の凶賊よりも、よほど凶賊らしい凶相が凄みを増した。
そして、決して低い声質ではないくせに、怖気が走るような、どすの利いた声で迫る。
「今回の作戦の立案者にして、立役者の〈猫〉。――どうして、あんたが、捨て猫のような惨めったらしい顔をしているんだ?」
「――!」
侮辱された、と。反射的に思った。
作戦は認められたものの、ミンウェイとの言い争いの最中であったため、確かに、ルイフォンは嬉しそうな顔をしていなかっただろう。しかし、だからといって、情けない顔もしていないはずだ。
「シュアン……!」
「ま、ミンウェイの顔と、あんたの顔と、それから『リュイセンの解放』と来れば、訊かなくたって状況は理解できるけどよ」
拳を握りしめ、言葉を返そうとしたルイフォンを遮り、シュアンが鼻で笑う。
「この期に及んでなお、あんたは『リュイセンが脅されたネタ』をミンウェイに言えないでいるんだろう? ――そいつを言えば、ミンウェイが傷つくからな」
「……っ」
ずばりと言い当てられ、ルイフォンは思わず顔色を変える。――と同時に、ミンウェイが驚きの声を上げた。
「緋扇さん!? どうして分かるんですか!?」
「そりゃ、見たまんまだからだ」
「説明になっていません!」
噛み付いてきたミンウェイに、シュアンは、おどけた顔で苦笑し、大げさな仕草で肩をすくめる。
「つまり、だ。――〈蝿〉の使った脅しのネタは、あのリュイセンを言いなりにしちまうくらい、とんでもなく碌でもないもんである、と。それなら、ルイフォンが口にするのをビビっちまうのも仕方ねぇなぁ、と俺は納得したわけだ」
「――っ!」
清々しいまでに軽薄な口調に、ルイフォンは猫の目を釣り上げた。
シュアンなんかに、好き勝手、言われる筋合いはない――!
ルイフォンは膨らみかけた憎悪を努めて押さえ、冷静な〈猫〉の顔で告げる。
「シュアン。お前の言う『脅しのネタ』は、裏付けとなる証拠を手に入れた上でミンウェイに説明すると、先ほど鷹刀の総帥と決定したところだ」
その瞬間、耳障りなシュアンの声が鼓膜を突き抜けた。
「はぁ? 当事者であるミンウェイには、こそこそ隠すだと? あんたら、ミンウェイを馬鹿にしてんのか?」
「なんだと!?」
挑発するシュアンを、ルイフォンは睨みつける。だが、シュアンは、まるで気にすることなくルイフォンから目線を外し、ぐるりと部屋を見渡した。
「どうせ、ミンウェイを傷つけないように――なんて考えているんだろ? まったく、鷹刀の連中は、どいつもこいつもミンウェイに対して過保護だ。端から見ている俺としては、気持ち悪いくらいさ」
シュアンは、イーレオの美貌の上で目を止め、ここぞとばかりに吐き出した。
「皆でミンウェイを守ってやろうってのは、血族の愛とやらなのかもしれませんが、過保護も過ぎれば、立派な虐待ですよ。――ま、ミンウェイのほうも遠慮ばかりだから、仕方ないですかね?」
薄笑いと共に、シュアンは、わざとらしい溜め息をついた。
「緋扇さん……」
シュアンの隣で、ミンウェイが困惑したように草の香を揺らす。そんな彼女に、しかし、彼は一瞬ぎょろりと眼球を寄せただけで、すぐに無視した。
それからシュアンは、ぼさぼさ頭を傾け、ルイフォンの顔を覗き込む。
狂犬と呼ばれた彼の血走った三白眼が、猫の目を捕らえる。
赤く濁った瞳は、それまでの彼の人生を物語るように汚れきっており、醜かった。
「守ってやろうなんて感情は、傲慢じゃねぇのか?」
皮肉げな響きを含んだ声が、挑発的に語尾を上げる。
見下すような目線が、癪に障った。
けれど、シュアンの言葉は――……。
「ルイフォン、あんたの情報ってやつは、俺の弾丸とは違う。俺は一発、ズドンと当てちまえば、それは不可逆だ。けど、あんたが傷つけたところで、ミンウェイならそのうち立ち直るはずだ。――信じてやれ」
「――――」
シュアン――と、声に出したつもりだった。けれど、唇から出たのは短い息だけだった。
……だが、それで正しかったのだ。
ルイフォンが呼びかけるべき名前は、シュアンではない。
「親父……いや、鷹刀の総帥」
澄んだテノールが、執務室をすっと流れた。
「すまない。前言撤回だ。〈猫〉は、ミンウェイに『秘密』について説明する」
鋭く息を呑む音が聴こえた。
それはミンウェイのものであり、イーレオのものであり、その場にいた皆のものであった。
「リュイセンのことを思えば、本心では言いたくない。でもそれは、〈猫〉ではなく、俺の個人の感情だ。……ミンウェイは、ちゃんと憶測だと承知している。なのに応えないのは、彼女に対する侮辱だ。――シュアンの言う通り、信じるべきだ」
穏やかでありながら、決然とした意志が静かに告げられた。
「そうか……。そうだな、頼む」
感情の読めない、けれど魅惑の低音で、イーレオが首肯する。
そして、ルイフォンが口を開こうとした刹那。
「イーレオさん」
――と。割り込むように、シュアンが呼びかけた。
「は?」
何故、ここで邪魔をする?
出鼻をくじかれたルイフォンは、そのため一瞬、文句が遅れた。その隙に、シュアンが今までの軽薄な口調を返上し、朗々とした深い声を上げる。
「〈蝿〉は先輩の仇です。だから、俺の手で討ち取りたい。しかし残念ですが、俺に手持ちのカードはありません。俺自身も〈蝿〉に対するカードとしては心もとない。ならば、適材適所と割り切るべき、というのが俺の見解です」
唐突に話題をねじ曲げ、シュアンは告げる。不可解な彼の言動に、皆が戸惑う。
協調性を欠いた彼は、周りのことなど気にしない。ただ、言いたいことを言うだけだ。
「俺は、この先のことを、ルイフォンの策に――リュイセンの手に託します」
「……!」
シュアンの態度に不快感を覚えながらも、耳朶を打つ強い声に、ルイフォンの心臓は跳ねた。自分の肩に、見えないシュアンの掌を感じる。ずしりと重く、けれど温かい。
「今回の作戦、俺は鷹刀を支持します。よろしくお願いいたします」
ふわりとした残像を描きながら、シュアンのぼさぼさ頭が下げられた。
「シュアン……?」
理解不能なシュアンの行動に、イーレオの語調が揺らぐ。だが、彼はすぐに泰然と構え直し、シュアンの思いを受け取った。
「お前の無念、預かった。――鷹刀への信頼、感謝する」
シュアンは下を向いたまま、安堵の息を吐いた。その表情は誰からも見えない。――彼の心の中にいる、失われた先輩を覗いては……。
そして、ぼさぼさ頭が先ほどと同じ軌跡をたどって戻ると、シュアンは再びルイフォンと向き合った。
「〈猫〉、あとは任せた。――俺は席を外す」
シュアンらしからぬ、柔らかな角度に口の端を上げ、彼は席を立つ。
「え!?」
「俺は、鷹刀の者じゃない。部外者だ。ミンウェイの『秘密』の話は遠慮するさ」
「ま、待て!」
翻る背中に、ルイフォンは無意識に口走った。
シュアンは構わず、一歩、踏み出し――。
「……おい」
低く、うなるような声を上げる。
シュアンの上着の肩がずるりと落ち、半ば脱げかけていた。それは、彼が着こなしに無頓着だからではなく、ミンウェイが裾を握りしめていたからであった。
「あ……」
振り返ったシュアンと目が合い、ミンウェイは慌てて手を離す。
黙って着崩れを直すシュアンに、イーレオの低音が誘った。
「どうだ、シュアン。乗りかかった船だと思って、この先の話に付き合わないか?」
その声に同意するように、ミンウェイが頭を下げる。
「――」
シュアンの目が見開かれた。
……わずかな空白のあとに、いつもの皮肉げに細められた三白眼に戻る。
「鷹刀の側がよいというのなら、俺には美女との同席を断る理由はありませんね」
そんな軽口を叩き、シュアンは元の位置に腰を下ろした。
そして、ルイフォンは静かに口を開く――。
「ミンウェイの父親ヘイシャオは、妻を生かすために『死者の蘇生』技術を作り上げた。彼が言うには『臓器移植と同じ。新しい肉体に記憶を移すだけ』の技術だ」
ミンウェイが頷き、かすかな草の香が流れる。
「彼は、『記憶』の保存を嫌がる妻を説得してほしいと、親父に電話してきた。そのとき、『肉体』に関してはこう言った」
『救うことのできない肉体の代わりに、妻の遺伝子をもとに、病の因子を排除した健康な新しい肉体を作る』
「結局、記憶の保存はなされないまま、妻は亡くなった。……けれど、ヘイシャオの口ぶりからすれば、『健康な新しい肉体』は既に出来上がっていたはずなんだ」
切れ長の目を瞬かせ、ミンウェイが黙ってルイフォンを見つめた。
その視線を正面から受け、ルイフォンは続ける。
「記憶の年齢まで『急速成長』させるはずだった肉体は、赤ん坊のまま遺されてしまった。……ヘイシャオは、その肉体を――その子を、自然に成長させることで育てた。それが、ミンウェイ。お前だと思う」
ミンウェイが息を呑む。紅の取れかけた唇がわななく。
「つまり、私は……お母様のクローン……。お母様から病の因子を取り除いた、健康な……クローン。――この体は……本当なら、『お母様』になるはずだった……『肉体』」
ミンウェイは自らを掻き抱き、体を丸める。
「私は、身代わりにされていたのではなくて、……存在そのものが、初めから、『お母様』そのもの……だった。そのために、作られた……。……お父様の態度は……だから……だったの、ね……」
彼女が顔を隠すようにうつむくと、『母親』とは違う、緩やかに波打つ黒髪が華やかに広がった。
ヘイシャオは、彼女に名前をつけなかったわけではない。
彼女を『ミンウェイ』以外の名前で呼ぶことを思いつかなかっただけなのだ……。
「ミンウェイ。これは、あくまでも俺の憶測だ。証拠もなく、事実として捉えるのは早急だと思う。――ただ、こう考えると、すべての辻褄が合う。……という、ことだ」
ルイフォンは猫背を伸ばし、脆く崩れるミンウェイの姿を脳裏に焼きつける。――それが、この作戦を提案した彼の義務だと思った。
「リュイセンには『憶測』で話をしても、『馬鹿なことをいうな』と突っぱねられるだけだと思う。ミンウェイのために、認めるわけにはいかないからだ」
下を向いたままのミンウェイが、こくりと頷く。
「それに〈猫〉ならば、情報屋として、きちんと証拠を挙げるべきだ。だから俺は、生前のヘイシャオの研究報告書を手に入れて、今の話を『事実』にしてリュイセンに提示する。リュイセンを追い詰めるような真似をすることになるけど、それが俺のやるべきことだ」
ルイフォンは胸を張る。
虚勢かもしれないが、この行動は正しいのだと、自分に、皆に示す。
伸ばした彼の背中で、金の鈴が煌めいた。
「ミンウェイ本人も知っている『事実』など、もはや『秘密』でも、なんでもない。リュイセンが〈蝿〉に従う理由は消え失せた。――あいつにそう言って、〈蝿〉の支配から……、ミンウェイの『秘密』を独りきりで背負い、苦しんでいる状態から……、解放してやる」
〈蝿〉の脅迫は、狡猾だ。
ミンウェイが知りたくもない、ミンウェイが知ったら深く傷つくような『秘密』を聞かされたら、リュイセンは、何がなんでもミンウェイから隠し通すことを考える。それどころか、誰にも知られたくないと思うだろう。――その気持ちを利用して、〈蝿〉は、リュイセンから『誰かに相談する』という選択肢を奪ったのだ。
生真面目なリュイセンのこと、更には自分の態度から、ミンウェイに何かを感づかれることをも恐れたはずだ。だから、ミンウェイの前から姿を消す決意をした。――だから、二度と戻れないことを承知で、メイシアをさらうという凶行を実行できたのだ。
すべてを黙し、一族を、ルイフォンを裏切ることしかできなかった兄貴分は、どんなに辛かったことだろう――。
「ミンウェイ、すまない。やらせてくれ。――お前の『秘密』を暴く行為を許してほしい。俺は、リュイセンを救いたい」
ルイフォンはミンウェイに頭を下げる。うつむいているミンウェイには見えないかもしれないが、そうせずにはいられなかった。
「……っ、う、ううん……。ルイフォン……、私のほうから、お願いしたことよ……! 私は、リュイセンを取り戻したいんだから!」
ミンウェイは小刻みに肩を揺らしながら、けれど、はっきりと答えた。
儚くも強い、柔らかな草の香りが漂う。
不意にシュアンが立ち上がり、上着を脱いでミンウェイの頭からかぶせた。彼女は驚いたようにびくりと体を震わせたが、弱い自分を隠してくれる上着を振り払うことはしなかった。
「イーレオさん、すみません。そろそろ失礼します」
「シュアン……? もう、帰るのか? ……いや、お前は明日も仕事か」
くぐもった嗚咽の漏れるシュアンの上着を見やりながら、イーレオは低く「ご苦労だった」と付け加える。
シュアンは三白眼を揺らし、それから自分のぼさぼさ頭を掻き上げた。
「…………、俺はちょいと、『座りたい椅子』があるんでね」
それは少しだけ反応の遅い返答だったが、うまいことを言ったとばかりにシュアンは満足げに口の端を上げた。そして彼は軽やかに一礼し、踵を返した。
ルイフォンは、シュアンの背中を見送りながら、『座りたい椅子』などと口にするとは、彼にも昇進への興味があったのかと、意外に思いつつ首をかしげた。
その夜。
庭の片隅にある温室の明かりは、一晩中、消えることがなかった。
硝子の壁が、夜闇に白く浮かび上がる。その中に溶け込むように、密やかな人影がふたつ、ガーデンチェアーに座って寄り添っていた。
同時刻。菖蒲の館にて――。
リュイセンが部屋に戻ると、窓際に小さな侵入者の姿があった。
ぴょんぴょんと元気に跳ねまくった癖っ毛。ふわふわとした毛玉のような頭が、こくりこくりと船を漕いでいる。
「ファンルゥ……」
また来ていたのかと、彼は目を尖らせる。
脱走が見つかったら、どんな目に遭うのか。小さな彼女はちっとも分かっていないのだ。
「おい、ファンルゥ。起きろ」
もう来るな、と言った。
『リュイセン、〈蝿〉のおじさんの手下なんか、やめよう! メイシアをさらってくるなんて、おかしいもん!』
そう詰め寄ってきた彼女を厳しく叱りつけた。
「ふにゃあ……」
ファンルゥが目をこする。
寝ぼけ眼でリュイセンを見つけると、彼女は実に嬉しそうに、にっこりと笑った。
「リュイセン……、メイシアがね、皆でこの庭園を出よう、って言っているの……。ファンルゥやパパも一緒。勿論、リュイセンもだよぅ……」
寝言のように呟かれた言葉は、幸せな夢を見ているかのようだった……。
2.幕引きへの萌芽-1

『メイシア、俺の策が通った。俺が――〈猫〉がリュイセンを解放し、リュイセンに〈蝿〉を討ち取らせる』
メイシアのもとに、待ちかねていた報告が来たのは、夜も更けてからのことだった。
ルイフォンとふたりで『リュイセンを解放する』と誓い合ったあと、ひとまず通話を切った。ルイフォンが、『対等な協力者』〈猫〉からの提案として、鷹刀一族に話を持っていくためである。
その間に、メイシアは異母弟ハオリュウに電話をした。昼間のうちに、鷹刀一族からメイシアの無事を知らせる連絡がいっていたため、ハオリュウが盛大に驚くことはなかったが、やはり電話口の声は震えていた。
異母弟は、ルイフォンの案を支持してくれた。
父の仇である〈蝿〉の処断を、全面的に鷹刀一族に委ねることになるが、それでよいと言ってくれた。ミンウェイが『母親』のクローンだという話は伏せたので、ハオリュウにしてみれば曖昧なところのある策であったろうに、ルイフォンを信用してくれたのだ。
しかし、ルイフォンの側は、そうもいかなかった。彼は『証拠を手にするまでは、ミンウェイの『秘密』を伏せておきたい』と言っていたが、『結局、明かした』――と、硬い声で告げた。
『早速、明日から行動を開始する!』
「うん……!」
ミンウェイの『秘密』を口にしてしまった苦さを振り払い、覇気に満ちたテノールを発するルイフォンに、メイシアの心も奮い立った。
『ただ、タイムリミットを言い渡されたんだ』
「タイムリミット?」
『ああ。〈蝿〉がお前に自白剤を使うと言った日の『前日までに』なんとかしろと言われた。間に合わなければ、タオロンに〈蝿〉暗殺を依頼する、ってな』
「自白剤……」
メイシアは怖気を覚え、無意識に自分の体を抱きしめる。
『自白剤によって、お前が本当はセレイエの記憶を持っているとばれたら、〈蝿〉が何をするか分からないから、って。俺も、そう思う。――だから、明日から三日で決着をつける』
「……」
三日。――たった三日。
それは、あまりにも短いのではないだろうか。
メイシアが眉を曇らせると、あたかも、その顔が見えているかのように、ルイフォンの柔らかな声が彼女を撫でた。
『俺を信じろ』
「!」
彼の言葉は、魔法の言葉だ。
耳にした瞬間に、メイシアの心配は霧散した。気づけば、彼女の口は自然に動いていた。
「うん、信じる。ルイフォンなら、できる」
『ありがとな』
猫の目が細まり、得意げに頬が緩んだのを感じる。目には見えないけれど、心で見える。
『万が一のときにはタオロンを頼れるのは心強いな。何があっても、数日中にお前を取り戻せる保証があるってのは嬉しい。――ミンウェイが『母親』のクローンだという証拠を手に入れても、リュイセンが『それ』をネタに脅された、ということもまた、俺の憶測でしかないんだからな……』
ほんの少しだけ、ルイフォンが弱音を吐く。自信過剰の彼が、気負いもなく素直に吐露するのはメイシアにだけ、ということに最近、気づいた。――おそらく、彼に自覚はないであろうことも。
「大丈夫。ルイフォンだから。リュイセンのことで間違えることはないの」
メイシアは、彼の髪をくしゃりと撫でる。癖の強い猫毛が、自己主張しながら指の間を流れていく。――勿論、錯覚だ。現実ではない。けれど、彼にはちゃんと伝わっているはずだ。
『……そうだな。ここで俺が弱気になったら、ミンウェイに申し訳が立たないよな』
「うん……。……あの、ミンウェイさん……その……、どう……している?」
初めにルイフォンからクローンだという話を聞いたときには、メイシアは耳を疑った。辻褄が合うと納得をしても、それでもまだ信じられない気持ちが残っている。
メイシアがこんな状態ならば、ミンウェイ本人は、さぞ受け入れがたい思いをしていることだろう……。
『たぶん、シュアンといると思う。シュアンの奴、さっさと帰ると言いながら、温室の前でうろついていたのを見回りに目撃されている』
「緋扇さん……?」
どういうことだろうか?
しかし、ルイフォンは、それ以上のことを言うつもりはないようだった。
兄貴分のリュイセンがいない間に、他の男がミンウェイに近づくのを快く思っていないのは確かだろう。ただ、シュアンには世話になっているから強く出られない。そんな雰囲気を感じた。
『明日、生前のヘイシャオの研究報告書を探しに、ミンウェイの昔の家に――ヘイシャオの研究室のあった家に行ってくる。ミンウェイが案内してくれるそうだ』
話をそらすように、あるいは話を進めるように、ルイフォンが告げる。
だからメイシアも、シュアンについてはもう訊かない。それよりも、積極的に動こうとするミンウェイに安堵した。そして、同時に尊敬する。
『ヘイシャオは、妻の病を研究するために〈七つの大罪〉から資金を受け取っていた。だから、成果の報告は義務だ。報告書は必ず存在する。……彼の研究室に残っているはずなんだ。妻の体をもとに健康な肉体を作り出し、その後、その子を育てた――と』
「うん……」
メイシアの声が沈んでしまったからだろう。ルイフォンが、軽口を叩くように言う。
『〈猫〉としては、報告書が電子的に保管されているとありがたいんだけどな。圧倒的に検索が楽になる』
彼らしい言葉に、彼女はくすりと笑う。それからヘイシャオの研究室を思い浮かべ、なんの気もなしに口を開いた。
「〈七つの大罪〉への報告書は、ヘイシャオさんの時代には電子データで提出することになっていたはずだから大丈夫。ただ、彼が生前、使っていたコンピュータが今も動くかどうかは分からない。古いし、埃まみれだったから――」
『――!?』
「けど、紙の書類ならあると思う。几帳面な彼は、報告書にまとめる前の記録ノートを大切にしていたみたいで、そういった資料が棚いっぱいに……」
そこまで言ったとき、メイシアは、はっと自分の口元を押さえた。
「――私、なんで、知って……?」
『メイシア?』
「今のは――セレイエさんの記憶……!」
声が震えた。
半音ずれたような、歪んだ彼女の声を聞いて、ルイフォンが血相を変えた。
『どうした!?』
メイシアの顔から血の気が引いていく。滑らかな白磁の肌が、青く黒ずんでいく。手足の感覚が鈍くなり、自分の体が自分でなくなっていくように思えてくる。
『メイシア! 大丈夫か!?』
ルイフォンが叫ぶ。彼女に駆け寄ろうと、腰を浮かせる彼の気配を感じる。けれど、それは文字通り遠くの場所での出来ごとで、その手が彼女に触れることは叶わない。
メイシアの脳裏に、ヘイシャオの研究室の風景が鮮明に浮かび上がった。
大きな硝子ケースの中で、一組の男女が眠っていた。『ヘイシャオ』と『ミンウェイ』――生前のヘイシャオが遺したものだ。
「セレイエさんの……ああ、違う、これはセレイエさんの〈影〉となったホンシュアの記憶。彼女は、ヘイシャオさんの研究室に行ったの。そこで現在の『〈蝿〉』を目覚めさせた……」
『おい! メイシア! どうしたんだよ!?』
メイシアは、記憶を受け取った。
だから、知っている。知らないはずのことを知っている。
『ライシェン』を見た瞬間、メイシアはセレイエに同調した。彼女の経験がメイシアの中に蘇り、感情すらも同化した。
けれど落ち着いてきたら、自分とセレイエの記憶をはっきりと区別できるようになった。〈蝿〉の指示による『ライシェン』との対面のときも、最初のときのように心を揺さぶられるようなことはない。
だから、安心していたのだが、どうやら彼女の記憶に触れようとすると、自分と彼女との境界が曖昧になるらしい。
普段は『そちら』を見ないようにしているだけで、メイシアが知ろうと思えば、いつだってセレイエの――ホンシュアの記憶を覗くことができる。メイシアの中には、確かに、自分のものではない記憶が存在するのだ。
ルイフォンの焦燥の息遣いが、荒く耳元に掛かる。彼女の顔が見えないことが、余計に不安を煽っているのだろう。
「ルイフォン、ごめんなさい。心配させて」
『説明してくれ。――お前の中で何が起きたんだ? セレイエの記憶が、お前に何かしたのか!?』
「……何かされた――とかじゃないの。でも……、私の中に、私の知らない記憶がある。……だから、私は行ったこともないヘイシャオさんの研究室の様子を知っているの。それで少し混乱して……」
『……っ! セレイエの奴! 俺のメイシアに……! 糞っ!』
拳をどこかに叩きつける音。
言葉にならない、ルイフォンのうめき……。
「心配しないで! 私に危険はないの」
憎悪と呼べそうなほどの彼の怒りに、メイシアは焦る。
「落ち着いて。私が知りたいと思わなければ、彼女の記憶は私の邪魔をしないから大丈夫」
『本当なのか……?』
いつも強気な猫の目が、不安げに彼女を見つめる。見えないけれど、その視線を感じる。
「安心して。変な感じはするけれど、記憶を受け取ったことで、私は多くの情報を手に入れたの。――望ましいことだと思う。だって、『情報を制する者が勝つ』でしょう?」
彼の口癖を、彼女は唇に載せる。
『それは……そうだけど……』
「いずれは、なんとかしないといけないかもしれない。でも、ともかく今は、この庭園を皆で出ることを考えないと」
『そうだ、な……』
ルイフォンの相槌を受けて、メイシアは記憶を探る。
彼に前へと進んでほしいから。
彼の役に立ちたいと思う。できる限りのことをしたいと望む。
だから、彼女は記憶を読み上げる。
無意識に。呼吸をするように、ごく自然に。
……それが、何を引き起こすかなど、微塵にも考えることなく。
「〈悪魔〉は年に一度、報告書と『記憶』を提出する義務があるの。報告書の内容は〈七つの大罪〉のデータベースに収められるから、もしヘイシャオさんの研究室が空振りだったら、そちらへの侵入を考えて。〈天使〉なら、『記憶』を書き込んだ〈冥王〉に接触もできるけ……、……! …………ぅ、…………っ」
刹那。
メイシアは、声にならない悲鳴を上げた。
心臓を鷲掴みにされるような感覚がして、息が止まる。
全身から脂汗が吹き出した。
そして、本能的に悟る。
――これ以上、言ってはいけない。
『メイシア!? メイシア、どうし……、……!』
ルイフォンが鋭く息を呑んだ。
気を失いそうな状況下でも、メイシアの手は携帯端末を固く握りしめたままだったので、その音がはっきりと聞こえた。
『お前、セレイエの記憶があるんだよな!?』
うん、と答えたつもりだった。しかし、それは吐息にすらならない。
『〈悪魔〉の『契約』だ! お前は、セレイエが〈蛇〉として交わした『契約』に縛られたんだ! 糞っ……! セレイエ! ふざけんな!』
ルイフォンが憤怒に吠える。猫の目が、ぎらりと光り、攻撃性を帯びる。
『メイシア、『〈冥王〉』は〈悪魔〉にとって禁句だ! 親父も、〈悪魔〉の記憶を受け継いだ〈ベロ〉も、『〈冥王〉』と口にしたら『契約』の警告を受けた』
「〈ベロ〉……?」
『あとで言おうと思っていたんだけど、俺は〈ベロ〉と会った。――それより、お前の体だ! とにかく、横になれ! 苦しいだろ!? 畜生……!』
いつになく取り乱すルイフォンに、メイシアは――。
……彼には申し訳ないのだけれど、嬉しかった。
幸せだと思ってしまった。
知らないうちに〈悪魔〉の〈蛇〉として『契約』に囚われてしまったことは不安であり、恐ろしいのに。……なのに、ルイフォンの声を聞いていると怖くない。
そうか。――と、彼女は気づいた。
「ルイフォン」
大切な名前を、心を込めて口に載せる。『契約』の警告は収まってきたようで、今度は素直に声が出た。
『メイシア、どうした? 具合いは!?』
「愛している」
彼が居るから、平気なのだ。
……。
…………。
………………。
ルイフォンは、しばらく固まっていた。
勿論、メイシアにその姿が見えるわけではないのだが、携帯端末は無反応でも通話時間の表示だけは加算されていくので間違いない。
「ルイフォン?」
様子を窺うように、そっと彼を呼ぶ。彼はまだ呆けているようで、心ここにあらずの『ああ』という返事が返ってきた。
「セレイエさんの記憶のこと、『デヴァイン・シンフォニア計画』のこと、いろいろ気になることはあるけれど、今はこの庭園を出ることを一番に考えましょう? ――だって、私……ルイフォンに逢いたい」
逢いたい。
彼に逢いたい。
『……ああ、そうだな。……俺も、早くメイシアに逢いたい。お前を抱きしめたい』
いつもの調子に戻ったルイフォンが、力強い声で告げる。
だからメイシアも、想いを伝える。
「うん、私も。ルイフォンに抱きしめてもらいたい」
顔の見えない電話だからだろうか。それとも、離れている時間が長いからだろうか。普段なら、とても言えない言葉がすっと出た。
それから互いに、離れ離れになってからの出来ごとを報告し合った。
そして――。
『『デヴァイン・シンフォニア計画』は、殺された子供を生き返らせるために、セレイエが組み上げたもの……か』
かすれたテノールが、メイシアの耳に響く。
『………………なるほどな』
そのひとことが返ってくるまでの間の長さに、彼の衝撃が現れていた。
「……うん」
『分かった。ありがとな。……お前、ひとりで辛かったな』
「…………うん。ルイフォン、ありがとう」
メイシアの心が、ふわりと温かくなる。
しかし。
彼女は、『すべて』をルイフォンに伝えることはできない。
メイシアの心に、〈蛇〉の交わした『契約』が、重くのしかかっていた――。
2.幕引きへの萌芽-2

石造りの展望塔が、朝陽に包まれる。
初夏とはいえ、月の支配下にある間はひやりと冷たい外壁が、ゆっくりと熱を蓄えていく。
するすると滑らかな音を立てるようにして闇の緞帳が引き払われ、菖蒲の庭園は光に満ちた夜明けを迎えた。
「朝……」
展望塔の最上階、展望室にいる囚われのメイシアもまた、目を覚ます。
長い睫毛を瞬かせ、枕元にある愛用の携帯端末を瞳に映した。
昨日の出来ごとは夢ではなかったのだと実感し、彼女はほっと息を吐く。和らいだ顔は徐々にほころび、微笑みに変わった。
この端末は、小さなファンルゥの温かな手から受け取った。タオロンや情報屋のトンツァイ、娼館のシャオリエとスーリン……たくさんの人々の助けによって、メイシアのもとに届けられた。皆への感謝の気持ちで胸がいっぱいになる。
まだ離れ離れだけれど、電波という見えない糸でルイフォンと繋がった。
そして、この庭園から抜け出すための道が決まった――。
メイシアはベッドから半身を起こし、ぐっと気を引き締める。
凛と輝く黒曜石の瞳で、遥かなルイフォンを見つめる。
それから彼女は携帯端末を手に取り、今日の日付けを確認した。
日時を示すものが手元にはそれしかないからであるが、ルイフォンみたいだな、と思う。カレンダーや時計があっても、携帯端末を頼みとするのが彼の習慣なのだ。
まるでルイフォンと一心同体。そう思ってから、乙女心あふれる発想に赤面しつつも、やはり嬉しく、なんとなく誇らしい。
「今日から、三日の間に……」
携帯端末に表示された日付けを見つめ、メイシアは呟く。
ルイフォンが、ミンウェイは『母親』のクローンであるという証拠を手に入れ、リュイセンを解放するために行動できる時間は、三日間。それが、タイムリミットだ。
彼は今日、生前のヘイシャオが使っていた研究室に、証拠を探しに行く。うまくすれば、三日も必要とせずに、そこですぐに決着がつくかもしれない。
自然に頬が緩んできて、メイシアは慌てて表情を引き締めた。
油断は禁物。明るい顔を見せれば、〈蝿〉が不審に思うことだろう。それはいけない。〈蝿〉には何も気取られてはならないのだ。
気持ちを切り替えるべく、彼女はベッドを出て、顔を洗いに行った。
朝食を終えると、メイシアは『ライシェン』との対面のため、リュイセンに連れられ、展望塔から館の地下研究室へと移動する。
それが、定められた日課となっていた。
世話係となったリュイセンは、日に何度か――主に食事のときに、メイシアのいる展望室を訪れた。彼は常にうつむき加減で、彼女から目をそらした。合わせる顔がない、ということなのだろう。
メイシアとしては、本当はリュイセンにいろいろと打ち明けたかった。
タオロンが味方になったことや、ルイフォンと連絡が取れるようになったこと。何より、この庭園を出るために、リュイセンには重要な役割を担ってほしいことを……。
しかし、現状では『敵』であるリュイセンには何も知らせないでおこう、とルイフォンと決めていた。すぐに『味方』に戻すから、それまでは――と。
何故なら、リュイセンは気配を消すのは得意であるのに、感情を隠すのは下手なのだ。彼の挙動から、〈蝿〉が疑念を抱く可能性がある。不測の事態は、いつどこで何が原因で起こるか分からない。慎重であるべきなのだ。
メイシアは、リュイセンのあとについて館に入り、闇に呑み込まれるような地下への階段を降りた。そして研究室の扉の前で、そっぽを向いたままの彼に声を掛ける。ほんの少しでいいから、こちらを向いてほしいと願いながら。
「リュイセン、ありがとう。また、あとで」
「……また、あとで」
独り言のような低い呟きが、かろうじてメイシアの耳に届いた。
リュイセンは、くるりと踵を返し、去っていく。大柄な彼の背中はどこか丸く、弱りきっているように見えた。
「お待ちしていましたよ」
薄暗い地下通路から一転し、明るく清潔な研究室に入れば、白衣の裾を翻し、〈蝿〉がメイシアを迎える。
メイシアは黙って奥に進んだ。衝立で仕切られた向こう側に『ライシェン』がいるのだ。
逆らうことは無駄とばかりの、従順な様子の彼女に〈蝿〉は薄笑いを浮かべる。
「『ライシェン』は、いつ『誕生』しても構わないくらいに成長しました。そろそろ凍結保存の時期です。――あなたから『鷹刀セレイエ』のことを聞けたら、処置を施そうと思っているのですよ」
『セレイエ』に揺さぶりをかけるなら、凍結された仮死状態よりも、時々、寝返りを打ちながら愛らしく眠っている姿のほうが効果的であろう。
だから、わざわざ待ってやっているのだ。早く、すべての『セレイエ』の記憶を手に入れろ。――暗にそう言っている。
言葉の端々から、高慢な態度が見え隠れしていた。
「……」
静かな黒曜石の瞳で、メイシアは〈蝿〉を見つめた。いつもなら、恐怖と憎悪を感じる〈蝿〉の顔が、今日は哀れな亡者に映った。
彼にはもう、未来はない。
他ならぬメイシアが、彼を屠るための死神を呼び寄せた。
〈蝿〉のしたことを思えば、それは決して間違いではない。そう言い切れるだけの怨嗟が、メイシアの中には確かにある。
それでも、見えない死神の鎌が彼の首筋に狙いを定めているのを感じると、彼女の胸は締め付けられるように痛んだ。
何故なら、彼女の中には、セレイエの記憶が――正確には『セレイエの記憶』と、セレイエの〈影〉となり、『デヴァイン・シンフォニア計画』の水先案内人として奔走していた『ホンシュアの記憶』がある。
『ホンシュアの記憶』に依れば、ホンシュアは、打ち捨てられたような古い研究室で、大型の硝子ケースを見つけた。
その中には、『ヘイシャオ』と『ミンウェイ』の二体の肉体が仲睦まじく眠っていた。ひと目見て、彼らは『対』であるのだとホンシュアは理解した。
それが分かっていても、ホンシュアは二体を――ふたりを引き離し、『ヘイシャオ』だけを目覚めさせた。『ライシェン』の目を見えるようにするためには、どうしても天才医師〈蝿〉の技術が必要だったから……。
〈蝿〉が『生き返った』のは、ホンシュアの――セレイエの身勝手な都合のためだ。
そうして『生』を享けた彼は、ホンシュアの嘘に翻弄されてイーレオの命を狙い、その過程でさまざまな人々の恨みを買い、その結果、メイシアの手引きする死神に『死』を与えられようとしている。
彼自身は、強く『生』を望んでいるのに。
『私は――いえ、オリジナルの『鷹刀ヘイシャオ』は、ミンウェイと約束を交わしました。『生を享けた以上、生をまっとうする』――これは、『私』にとって絶対の誓約です』
メイシアの脳裏に、矜持にあふれた〈蝿〉の昏い美貌が蘇る。
「……」
〈蝿〉は父の仇だ。
絶対に許すことはできない。
――けれど。
『尊厳は守ってやりたい』と言ったイーレオの気持ちが、今なら分かる気がする。
〈蝿〉もまた、『デヴァイン・シンフォニア計画』の犠牲者なのだから……。
「どうかしました?」
思考の海に沈んでいたメイシアを、〈蝿〉の声が呼び戻す。
「いえ、なんでもありません」
培養液に身を委ね、白金の髪を踊らせる美しい赤子に目を向けながら、メイシアはふと思う。
〈蝿〉がセレイエを探しているのは、セレイエを利用して自分が『生き残る』ためだ。なのに、オリジナルのヘイシャオは、自ら『生』を手放したという。
『鷹刀ヘイシャオが、自殺などするはずがないのです。彼が自ら『死』を望むなど、あり得ない!』
『ええ、私も馬鹿ではありません。分かっていますよ。――私の持つ記憶が保存された時点から、オリジナルの鷹刀ヘイシャオが死ぬまでの間に、彼が心変わりするような事件があった、ということでしょう』
耳の中で、〈蝿〉の叫びが木霊する。
『生』を望む〈蝿〉と、『死』を求めたオリジナルのヘイシャオ。
このふたりの違いは、持っている記憶の時差だ。
では、『生』から『死』へと心変わりするような事件とは、いったい――?
「…………」
〈蝿〉は憎き仇だ。
これ以上、彼について考える必要はない。
彼に『死』が与えられれば、すべては無となる。この疑問を解くことに意味はない。
メイシアはそう思い……、しかし、心の中に小さなしこりを感じていた。
そして。
一方、リュイセンは――。
メイシアを〈蝿〉の地下研究室に送り届けたのち、割り当てられた部屋へと足早に戻っていた。
別に、急ぐ理由があるわけではない。ただ、途中ですれ違う〈蝿〉の私兵たちの視線が、好奇と畏怖の入り混じった不快なものであるからだ。
リュイセンの顔立ちが〈蝿〉そっくりであるのだから当然といえよう。叔父と甥の関係であると言ったかどうかは忘れたが、〈蝿〉が彼を特別扱いをしていることは自明である。
最近では、メイシアの世話係となったことが、やっかみの対象であるらしい。
何故そんなことが? と、初めは疑問に思ったのだが、展望塔と地下研究室を往復する彼女を遠巻きに見る、私兵たちの卑猥な目を見て得心がいった。リュイセンはメイシアの世話係――実は、逃亡を防ぐための見張りも兼ねていると〈蝿〉に言われているのだが、どちらかというと護衛の意味合いのほうが大きいようだった。
部屋にたどり着き、リュイセンは乱暴に扉を閉める。
このあとは、昼前にメイシアを迎えに行くまで特にやることがない。
世話係としては、彼女がいない間に掃除でもしておくべきなのかもしれないが、女性の部屋に勝手に出入りをするのは非常識な気がした。そもそも、メイド見習いで鍛えた彼女は、彼よりも、よほど身の回りのことを器用にこなすのだ。その手際は、とても、もと貴族の箱入り娘とは思えない。
「……違うか」
努力して、できるようになったのだ。――ルイフォンのために。
部屋の隅にうずくまるようにして座り込んだリュイセンは、力なく顔を伏せる。肩で揃えられた髪が鋭利な刃物のように首筋をかすめると、いっそ、この首と引き替えに現状を打破できるならば、殺ってくれ……などと、彼らしくもないことを考えてしまう。
「畜生……!」
どうにかして、メイシアを無事にルイフォンのもとへ帰すのだ。
しかし、彼女が逃げたら、〈蝿〉はミンウェイの『秘密』をミンウェイに暴露するという。
つまりリュイセンは、自身が手引きすることもできなければ、外部からルイフォンが助けに来たとしても、それを阻止しなければならないのだ。
……故に。
リュイセンが採るべき道は決まっている。
――〈蝿〉を殺す。
〈蝿〉から情報を得ようとしているルイフォンには悪いが、仕方ない。
ミンウェイの『秘密』もろともに、〈蝿〉を葬り去るのだ。
そして同時に、リュイセンも姿を消す。
そうすれば、ミンウェイの『秘密』を知る者は誰もいなくなる。ミンウェイは何も知らぬままに、幸せに暮らすことができるだろう。
メイシアの脱出はタオロンに頼む。同じ館にいながら、互いに気まずくて顔を合わせていないが、彼になら任せられる。
〈蝿〉が死ねば、奴の脳波がスイッチだというファンルゥの腕輪の毒針は無効になる。
だから、メイシアを鷹刀一族の屋敷に送ったら、タオロンは父娘で草薙家に向かえばいい。予定とはだいぶ変わってしまったが、リュイセンの兄の一家は、きっと快く彼らを迎えてくれることだろう。
リュイセンは、昨晩、勝手に彼の部屋に入り込み、眠りこけていたファンルゥを思い出す。
どうやら彼女は、メイシアを元気づけようと展望塔に行っているらしい。思い切り叱りつけてしまったが、本当に優しい子だと思う。自由な生活を与えてやりたいと、切に願う。
そんなことをつらつらと考え、リュイセンは溜め息と共に肩を落とす。
彼が、〈蝿〉殺害に踏み切れない理由が、頭の中を駆け巡った。
『この手の話の定石だとは思いますが、もしも私が死ぬようなことがあれば、〈ベラドンナ〉のもとに彼女の『秘密』がもたらされるよう、仕掛けをしてあります』
『何をしたんだ?』
『私がそれを言うはずがないでしょう? 言う義理もありません』
リュイセンの野生の勘では、〈蝿〉の言葉がハッタリである確率は、半分。だが、残りの半分であった場合のために、身動きを取れない。
「――どうすればいいんだ、俺は……」
振り上げた拳が、力なく床を打つ。
ハッタリか、否か。――どちらなのか見極めようと、彼はミンウェイの『秘密』を告げられた日のことを思い返した……。
3.昏迷のささやき

それは、リュイセンが〈蝿〉との勝負に敗れて大怪我を負い、不本意にも〈蝿〉に輸血されて一命をとりとめた日から数日後のことだった。
リュイセンの部屋を訪れた〈蝿〉は、傷の診察をしたのちに、こう言った。
「そろそろ、約束の〈ベラドンナ〉の話をして差し上げましょう」
〈蝿〉は、ミンウェイのことを〈ベラドンナ〉と呼ぶ。毒使いの暗殺者としてのミンウェイの名前である。
娘を〈ベラドンナ〉と呼ぶことで、妻のミンウェイと呼び分けているのであるが、『ミンウェイ』という名前は、妻だけのものだと言わんばかりの態度に、リュイセンは不快げに眉を寄せる。あとになってから、毒花などという呼び名をつけるくらいなら、生まれたときに、きちんと彼女だけの名前を贈ればよかったのだ。
嫌悪感もあらわなリュイセンには構わず、〈蝿〉は話を続けた。
「あなたが目を覚ましたときに言ったでしょう? あなたも私も回復したら、改めて〈ベラドンナ〉のことを話しましょう、と」
そんなことを言っていたような気もするが、それは〈蝿〉の一方的な言い分だ。リュイセンの側には聞く義務はない。それどころか、ミンウェイを虐待していた悪魔が彼女を語るなど、考えただけでも反吐が出る。
「断る。俺は、お前の話などに興味はない」
武器を取り上げられ、傷も癒えていない。そんな状況で〈蝿〉に反抗するのは愚かしいかもしれない。しかし、リュイセンの矜持が断固とした姿勢を取らせた。
剣呑な目つきの彼を前に、〈蝿〉は、ふっと嗤った。彼がそう返してくることは、とっくにお見通しだとばかりに。
「聞かなくていいのですか? 〈ベラドンナ〉の健康に関することですよ?」
「ミンウェイの健康?」
罠だ――と、本能では悟った。
けれど、リュイセンは心の隙を突かれた。――彼が抗えるような話題ではなかった。
「ミンウェイは――私の妻は、二十歳にもならずに亡くなりました。病弱に生まれついた鷹刀の血族は、皆そうです。……ですが、〈ベラドンナ〉は見たところ、既に二十歳を超えていますね」
「だから、なんだというんだ?」
「どうやら、私の施した処置が功を奏したようです。あの子は間違いなく健康体です」
思わせぶりに、〈蝿〉がにやりと嗤う。
「……!?」
リュイセンは、何を言われたのか分からなかった。そんな彼の耳元に、そっと囁くように〈蝿〉が告げる。
「病弱な私の妻から生まれた〈ベラドンナ〉が、自然のままで健康であるわけがないでしょう?」
「!」
息を呑んだリュイセンに、〈蝿〉は畳み掛ける。低く美声を放つ唇が、笑みの形を描く。
「ああ、『私の妻から生まれた』という言い方は正しくないですね。……いえ、ある意味、実に的確な表現かもしれませんが」
「どういう意味だ……?」
リュイセンの胸に警鐘が鳴り響く。しかし、彼は問い返さずにはいられない。まるで悪魔に魅入られたかのように。
「あなたは〈ベラドンナ〉のことを、本当に私の妻が産んだ娘だと信じているのですか?」
「!?」
「冷静に考えてご覧なさい。妊娠は母体に多大な負荷をかけます。病弱な彼女の寿命を縮めるような真似を、この私が――オリジナルのヘイシャオが、許すはずないでしょう?」
〈蝿〉が溜め息を落とす。だがそれは、多分に演技じみた仕草だった。
「……つまり、ミンウェイは……、お前――ヘイシャオ叔父と、……叔母上から人工的に作られた子供だと……?」
信じたくはないが、あり得る話だ。
病弱な叔母の遺伝子から病気の因子を取り除いたあと、健康な受精卵を作る。そして、研究室で見た『ライシェン』のように硝子ケースの中で育て、誕生させる。技術的なことはよく分からないが、〈蝿〉ならきっとできるだろう。
――叔母のことを『ミンウェイ叔母上』とは呼べなかった。リュイセンが『ミンウェイ』と呼ぶ相手は、ただひとりだからだ。
リュイセンは、複雑な思いで〈蝿〉を見やる。
遺伝子操作などという、得体の知れないものによってミンウェイの体ができているというのは、正直なところ嫌である。しかし、そうでもしなければ、ミンウェイもまた母親のように二十歳を迎えることなく亡くなったのかと思うと受け入れざるを得ない。
そんなリュイセンの視線の先で、〈蝿〉は……。
――悲しげに……微笑んでいた。
白髪混じりの髪が、はらりと頬に掛かり、すぅっと流れた銀色の光が一瞬だけ……涙に見えた。
「ミンウェイが、ただ病弱なだけだったら……、……そんなことも考えたかも知れませんね」
「〈蝿〉……!?」
「ですが、そんなことを考える余裕など、なかったのですよ。死相を浮かべたミンウェイは、明日を生きるどころか、今日を生き抜くことで精いっぱいだった。私たちの子供など……夢でしかなかった」
「!?」
「もしもミンウェイが子供を望んだら、それは彼女が生きて育てたいからではなく、死んでいく自分の代わりを遺すために過ぎません。……それが分かっていたから、私たちはあえて子供の話を口にしなかった。――私たちは、ミンウェイが生き抜くことを決して諦めなかったのですから……!」
〈蝿〉は拳を握りしめ、血を吐くように低い声を震わせる。
リュイセンは、瞬きひとつできなかった。
……目の前の状況に呑まれていた。先ほどまでの〈蝿〉は確かに演技めいていたのに、今の言葉は本心なのだと本能的に察してしまった。
「……じゃあ、ミンウェイは……?」
訊くべきではない。
なのに、気づけば、リュイセンは尋ねていた。
〈蝿〉が嗤う。それは彼が誘導した質問であり、彼としては思惑通りの展開であるにも関わらず、どこか自嘲めいた笑みだった。
「鷹刀イーレオから、聞いているのでしょう? 私がミンウェイの記憶を保存し、新しい肉体に移すことで、彼女を生き存えさせようとしていたことを」
「……ああ」
「結局、最期まで、ミンウェイは記憶の保存に同意してくれませんでした」
「……」
「ですが、肉体のほうはできていたのですよ。ミンウェイの遺伝子をもとに、病の因子を排除した健康な新しい肉体が――」
「――!?」
〈蝿〉の声はちゃんと聞こえている。それが、どういう意味なのか、本当は分かっている。
しかし、謎解きが得意でないリュイセンの心は、理解を拒否した。ただ頭が割れるように痛む。
「死を目前にしたミンウェイは、私に言いました」
〈蝿〉が静かに口を開く。
『あなたは、私のあとを追うつもりなのでしょう? 駄目。許さない』
『生きて』
『それが、どんなに尊いことか。私たちは知っているのだから』
「彼女は、自分のために作られた健康な肉体があることを知っていました。そして、その肉体もまた、ひとつの『命』だと言いました」
『……あなたを独りにしない。私の……私たちの『娘』がいる』
『だから、お願い……。ヘイシャオ、生きて……』
「そうして『誕生』し、育てた『娘』が、〈ベラドンナ〉――あなたのいう『ミンウェイ』です」
疲れ果てたようでありながら、〈蝿〉は幸せそうに微笑む。
「〈ベラドンナ〉は、ミンウェイなのですよ。健康に生まれた、ミンウェイ。私とミンウェイの『願い』の結晶……」
「……」
「あなたの頭で理解しやすいように言えば、『私の妻から、病気の因子を取り除いたクローン』――かもしれませんがね」
そこで急に、〈蝿〉の顔が禍々しい闇に染まった。
亡き妻を想う愛妻家の慟哭は吸い込まれ、残酷な微笑を浮かべた悪魔の美貌だけが残る。
「〈ベラドンナ〉は知りませんよ。彼女は、自分が生まれるのと引き換えに、母親は亡くなったのだと信じています。だから『父親』は、自分に母を重ねるのだ、と」
――その通りだ。
ミンウェイを両親の墓参に連れて行ったとき、彼女はこう言った。
『私はお母様から名前を貰ったのだと知ったわ。いいえ、お母様がくれたのは名前だけじゃない。この命も――。お母様は、私を産んだことで亡くなったのだと理解した。だから、私はお母様の代わりをすべきだと思った』
『私、頑張ってお母様になろうとした……。でもね、やっぱり辛かった……』
「……っ」
リュイセンは、奥歯を噛みしめる。
「『ヘイシャオ』にとって、〈ベラドンナ〉は『娘』などではありません。健康を手に入れ、長く共に生きるはずだった『妻』です。――なのに妻の心は亡くなり、肉体だけが生き残っている。その事実は、時に『ヘイシャオ』を狂わせ、〈ベラドンナ〉に対して苛立ちと、そして、憎悪を抱かせました」
「――?」
「『妻であるはずの肉体に、別の精神が宿っている』『そいつが妻を奪ったのだ』という、錯覚を起こしていたんですよ」
まるで他人ごとのように語る〈蝿〉の口ぶりに、リュイセンの目の前が、かっと赤くなった。それまで言葉を失っていたのが嘘のように、弾かれたように彼は叫ぶ。
「ふざけるな! お前自身のことだろう!?」
「『私』ではありませんよ。オリジナルの『ヘイシャオ』のことです」
素知らぬ顔で言ってのける〈蝿〉は、まさに冷酷な悪魔そのもの。黒く艶めく瞳が捕食者の眼光を放ち、リュイセンを捕らえる。
「前にも申し上げたでしょう? 『私』自身は〈ベラドンナ〉に会ったこともないのですよ?」
「――けどよ!」
「まぁ、落ち着きなさい。私のことはどうでもよいのです。――問題は〈ベラドンナ〉がどう思うか、ですよ」
「……何を言いたい?」
リュイセンの背に、嫌な緊張が走った。気持ちの悪い汗が体中から吹き出る。
「もしも〈ベラドンナ〉が、この事実を知ったら、彼女はどんな気持ちになるのでしょうね?」
「……え?」
「自分は『娘』ではなく『母親のクローン』。『作り物』で『紛い物』。『母親』の記憶を持たない『偽物』。……『憎しみの対象』。――そう教えて差し上げたら、今まで信じていたものが足元から崩されることでしょう」
『私……。昔……、まだ父が生きていたころ、……自殺しようとしたんです』
リュイセンの耳に、ミンウェイの声が蘇る。
ミンウェイに会いに行った緋扇シュアンを監視するため、彼のあとを追って温室に入ったときのことだ。結果として、ミンウェイの告白を盗み聞きしてしまった。
『本当は……、父の、関心を引きたかっただけなのかもしれない……! 母ではなくて、私自身を見てもらうために……!』
『暗殺者になったのも、病弱だった母にはできなかったことをして、父に認めてもらいたかったからなのかも……。だって、暗殺者として〈ベラドンナ〉という名を与えられたとき、私は嬉しかった。それは、私だけの名前だから……!』
ミンウェイの努力は、すべて無駄だったというのか? それではミンウェイは、なんのために生きてきたのだろう……?
リュイセンは怒りを覚え、ぎらつく双眸で〈蝿〉を睨みつけた。
しかし、〈蝿〉は少しもひるむことなく、薄笑いを浮かべる。その思わせぶりな表情に、リュイセンは、はっと顔色を変えた。
〈蝿〉は、『もしも〈ベラドンナ〉が、この事実を知ったら』と口にした。
つまり、これは脅迫なのだ。
そう……、〈蝿〉はリュイセンに『協力してほしい』と言っていた。――その話の続きだ……!
リュイセンは自分の頭の回転の遅さに歯噛みして、それから改めて考える。
――もしも、ミンウェイが知ったら……?
リュイセンの全身から血の気が失せた。まるで、奈落の底に引きずり込まれていくような感覚だった。
ミンウェイの心は、いまだ、死んだ父親に囚われている。
十数年もの時を経るうちに、少しずつ気持ちが薄れていったのは間違いないが、〈蝿〉の登場によって、彼女は今、再び揺れている。
彼女はまだ、父親を忘れていない。――心の底で愛している。
彼女が不安定であることが、何よりの証拠だ。
そんな彼女が、真実を知ったら……。
今度こそ、本当に自ら命を絶ってしまうかも知れない……。
「リュイセン」
〈蝿〉が珍しく、彼を名前で呼んだ。
「取り引きをしましょう」
やめろ、と。リュイセンは叫んだ……叫んだつもりだった。しかし、喉からは、ひゅうひゅうとした息が漏れただけだった。
「リュイセン、私の駒になりなさい。さもなくば、〈ベラドンナ〉に、この『秘密』を伝えます」
とろけるような甘い響きでもって、悪魔は低く囁いた――。
4.錯綜にざわめく葉擦れの音-1

メイシアは、ミンウェイの『秘密』の証拠を探しに行ったルイフォンの首尾を気にしつつ、落ち着かない気持ちが顔に出ないように注意して、今日の『ライシェン』との対面を無事に終えた。
昼になり、地下研究室を出る際に、〈蝿〉がいつものように「今日も、なんの成果も得られなかったのですか?」と、凄みを帯びた目で睨んできても、今は逆らうべきときではないので、恐縮したように頭を下げて切り抜けた。
そして、決められた通りに迎えに来たリュイセンに連れられ、展望塔に戻り、昼食を摂る。
ルイフォンからの連絡を確認するのは、今はまだ『敵』であるリュイセンが部屋を出たあとだ。気がはやるが、もう少しの辛抱である。
リュイセンは相変わらず目を合わせてはくれず、食事のテーブルから少し離れたところで彫像のように立ち尽くしていた。
うつむき加減のその姿勢から、暗鬱な表情をしているものと思い込んでいたメイシアは、だから、彼が声を掛けてきたとき、初めは空耳だと聞き流してしまった。
「――メイシア」
「えっ?」
おそらく、既に何度か呼びかけたあとなのだろう。はっきりと聞こえてきた声には、わずかにだが苛立ちが含まれていた。
驚いて食事のテーブルから顔を上げると、リュイセンの黄金比の美貌はまっすぐにメイシアに向けられていた。久しぶりにまともに見ることのできた彼の顔には、研ぎ澄まされたような鋭さがある。
「メイシア……。俺は、なんとしてでも、お前をルイフォンのもとに帰す」
「リュイセン?」
「ハッタリか否か、見極めがついたらすぐに行動に移す。……だから、少しだけ待っていてほしい」
そう言ってリュイセンは視線を下げ、再びメイシアから顔をそらす。全面の硝子窓から入ってきた陽光が、彼の片頬の端だけを明るく照らし、顔色全体を暗く沈ませた。
言葉は少なかったが、彼の内部に渦巻く、ぎらついた焦燥を強く感じた。
彼は自分の犯した裏切りに絶望し、闇の中でたたずんでいたわけではなかったのだ。――メイシアの心が大きく震える。
「……すまんな。――ルイフォンに逢いたいだろう……?」
静かに吐き出された低音が、メイシアの胸に染み込み、溶けていく。
あっ、と思ったときには、ひと筋の涙が頬を伝っていた。下を向いてしまった彼には見られていないと思うが、彼女は慌ててナプキンで拭う。
――そう。
リュイセンは、メイシアが展望塔に囚われた初日に『何があっても、お前をルイフォンのもとに帰す』と宣言した。
彼の言葉は、ただの口約束ではない。口にしたからには、必ず実行する男だ。
彼の様子から察するに、何かの事情があって今すぐには思うように行動できないのだろう。だから、待ってほしいと言ってきたのだ。
現状を打破しようと、彼は孤軍奮闘で戦っている。息を潜めながら、牙をむくべきときを虎視眈々と狙っている……。
リュイセンは強い。
囚われたばかりのころ、ひとりきりであることに打ちひしがれていたメイシアとは雲泥の差だ。自身も辛い状態の彼に、彼女を気遣う心の余裕などないはずなのに……。
「リュイセン、ありがとう」
心を込めて、感謝を告げる。自然に口元がほころび、柔らかな笑顔となる。
その顔は、うつむいている彼には見えないだろうけれど、言葉に込めた気持ちは、きっと伝わるはずだ。
もし、ルイフォンから良い知らせが来ていれば、すぐにも彼を孤独から救える――。
一刻も早く携帯端末を確認したい、という衝動に駆られ、メイシアは不自然ではない程度に急いで食事を口に運んだ。
昼食が終わり、リュイセンがワゴンを押しながら部屋を出ていく。
エレベーターの表示が、彼が地上階まで降りたことを教えてくれるのを待ってから、メイシアは割り当てられたふたつの部屋のうちの、もうひとつへと移った。ベッドのマットの隙間に、電源を切った携帯端末が隠してあるのだ。
証拠は無事に見つかっただろうか。
早鐘を打つ心臓を押さえながら、メイシアは、ルイフォンとの会話を思い出す。
今朝早く、いつものルイフォンならぐっすりと寝ている時間に、『朝食を終えたらすぐに、ヘイシャオの研究室に向かうから、その前に』と、彼が電話をくれたのだ。
『リュイセンにさ、証拠もなく、ただ口先だけで、『ミンウェイはクローンだ』『本人だって知っている』って言ったところで、あいつは『でたらめを言うな』と否定すると思う。――いや、絶対に、そう言うんだ』
ルイフォンは、メイシアにそう告げた。
『確たる証拠がなければ、リュイセンは『憶測に過ぎない』と突っぱねる。あいつは、ミンウェイに向かって『馬鹿げたことを信じるな』と笑い飛ばすだろう。ミンウェイの心を守るために、さ……。『憶測』と『事実』の間には、大きな隔たりがあるんだ』
「うん……」
『だから俺は、ミンウェイがクローンだという決定的な証拠を手に入れて、それをリュイセンに示す。その上で、ミンウェイ自身に『事実』を受け入れたと、電話で宣言してもらう。あいつが〈蝿〉に従う理由をなくすんだ。――それが、『リュイセンを解放する』ことになる』
リュイセンはルイフォンや一族を裏切り、自分を犠牲にしてまで、ミンウェイから彼女の『秘密』を隠そうとした。
ならば、頑なまでに、その信念を貫こうとするだろう。
それを――打ち砕く。
ルイフォンの武器である『情報』でもって。
『あいつの想いを踏みにじっているのは分かっている。――けど、俺はやる』
「――ルイフォン……」
メイシアは、遠慮がちに口を開いた。
彼の言うことは正しいと思う。メイシアも、彼の策に賛同している。
……けれど。
人の心は、そんな簡単に割り切れるものではないと思うのだ。
すべてを打ち明けられたとき、リュイセンはどう感じるだろうか?
リュイセンなら、ルイフォンが彼のために奔走したということは理解してくれるだろう。
――それでも。
リュイセンの視点からすれば『余計なこと』だ。
ルイフォンがこれから手に入れようとしている証拠は、悪い言い方をすれば、『リュイセンが言い逃れをできないようにするためのもの』だ。
彼を追い詰めるもの。彼を屈服させるもの……。
そして、リュイセンが己のすべてを懸けて隠そうとしたミンウェイの『秘密』は、彼の知らないうちにミンウェイに伝えられている。――そのことに、憤りを覚えるのではないだろうか……?
「ルイフォン、私もルイフォンの作戦に賛成。それは絶対なの」
ためらいつつ、それでもメイシアは懸命に口を開く。世話係として彼女の部屋を訪れる、リュイセンの罪悪感に満ちた顔を思い出しながら。
「けど、想いを踏みにじられたリュイセンが……、その……怒ってしまう、という可能性はないの?」
これから証拠を手に入れに行くのだと、意気揚々としているルイフォンに水を差すようなことを言いたくはない。けれど、無視できない懸案事項だと思うのだ。
「あるいは……、一度、裏切ってしまったルイフォンの手を、再び取ることはできないと、拒まれてしまう可能性も……」
不安を告げただけなのだが、ルイフォンに申し訳ないことを言っている気持ちでいっぱいだった。携帯端末を握る手が緊張で強張り、心臓が激しく高鳴る。
ルイフォンは……――ふっと、笑った。
『メイシア。今、物凄く、脅えた顔をしているだろ? 俺に『悪いこと言っちゃった』って』
「え? な、なんで分かるの?」
先ほどとは別の意味で、心臓が跳ねる。
『そりゃ、お前のことだから。――そんな顔するなよ。大丈夫だ。俺だって、うまくいかない可能性は考えている。それどころか、リュイセンがへそを曲げずに、俺のシナリオ通りに動いてくれたら、それは奇跡なんじゃねぇか?』
「え? ええっ!?」
今までと言っていることが違うような気がするのだが、どういうつもりだろう?
『いいか? 俺の最大の目的は、お前を取り戻すこと。これが絶対。何があっても譲らない』
「う、うん……」
『だから、タオロンが味方になってくれた時点で、タオロンに頼んでお前を取り戻してもよかった。リュイセンのことは見捨ててさ』
「……」
『でも、俺は欲張りだから。リュイセンのことも取り戻したい。――今、足掻いているのは、そのためだ』
ふわりと優しい声がメイシアを包み込んだ。
『確かにやり方は荒っぽいかもしれない。あいつの神経を逆なでしたとしても無理はない。――けどな!』
そこで急に、ルイフォンの口調が変わる。
『先に手を出してきたのはあいつのほうだ! あいつは、俺のメイシアを奪った!』
「ル、ルイフォン……」
『お前の命が危険に晒された! 分かるか!? 俺が、どんなに苦しんだか!』
「ルイフォン……、ごめんなさい、心配かけて……」
『なんで、お前が謝るんだよ!?』
「あ……、ええと、ありがとう……」
『……あ。……すまん』
熱くなりすぎたことに気づき、ばつの悪そうにルイフォンが謝る。けれど、それはメイシアへの想いゆえだ。心が、ほわりと温かくなる。
落ち着きを取り戻したルイフォンが、再び口を開いた。
『あいつは、俺の逆鱗に触れた。それでも、俺はあいつを取り戻したいと思った。――あいつと決別するよりも、あいつと共にいたいと思ったからだ』
そこで、ほんのわずかに声が弱まる。
『――けど、あいつのほうに俺の手を取る気がないなら、それは構わない。今度こそ、本当に袂を分かつだけだ』
「……」
『俺は、お前を確実に取り戻すために、タオロンという保険を残している。抜かりはない。――冷たいかもしれないが、俺にとっては、お前が一番、大切なんだ』
彼は一度、言葉を止め、それから苦しげに吐き出す。
『リュイセンのことは、できたら取り戻したい……そういう思い――願いだ……』
わずかな沈黙。
そして、彼らしくもない弱気な呟きが漏れた。
『エゴだな……。俺の我儘で、独りよがりな空回りかもしれない。――俺は『お前が一番』と言いながら、お前を待たせて、リュイセンを救おうとしているんだよな。……悪い』
うなだれた猫背を感じた瞬間、メイシアは思わず叫んでいた。
「何を言っているの!? 私も、ルイフォンが示した道が『進むべき道』だと思った。――だから、もし我儘だというのなら、それはルイフォンだけの我儘じゃない。『私たち、ふたり』の我儘なの」
『メイシア……』
「私がこの庭園を出るときは、リュイセンも一緒なの……!」
『ありがとう』
ルイフォンの声が、穏やかに、柔らかに解けた。彼は今、澄み渡った青空のような顔をしている。その微笑みが、メイシアには見えた。
そして、彼は続ける。
『――あいつは必ず、俺の手を取る』
その言葉の裏に、不安が隠されているのは分かった。けれども力強いテノールは、メイシアの耳を――心を打った。
彼女は「うん」と頷いた。その声が涙ぐんでしまったことは、きっとルイフォンには、ばれている。けれど彼は、優しい吐息を漏らしただけだった。
そのとき、電話口の向こうから、ルイフォンを呼ぶ声がかすかに聞こえた。
ミンウェイの声だろう。艶のある美声はよく響き、元気そうだ。――本当は、辛い気持ちを無理に抑え込んでいるのだろう。それでも、彼女は前を向いている。
「ルイフォン。私も信じる。リュイセンは手を取ってくれる、って」
『ありがとう』
「……そろそろ、電話を切らないとね?」
『ああ』
ルイフォンの声を耳に、メイシアは大きく息を吸い込んだ。
そして、精いっぱいの想いで彼を送り出すために、極上の笑顔で告げた。
「いってらっしゃい」
隠してある携帯端末を取り出す前に、メイシアは、まずは全面の硝子窓にブラインドを下ろした。眺めのよい展望室は、逆にいえば外から丸見えなのだ。ファンルゥだって、泣いているメイシアを部屋から見たと証言していた。
そうでなくても、日当たりのよすぎる部屋だ。ブラインドに加えて、適度な空調をつけなければ、この初夏の陽射しでは干上がってしまうだろう。
部屋を整え、心を落ち着けて、メイシアは携帯端末の電源を入れる。
……ルイフォンからの連絡は、まだ来ていなかった。
落胆の息が漏れたが、しかし、代わりにスーリンからのメッセージが入っていた。
――メイシアへ
このメッセージを読んでいる、ってことは、携帯端末は無事にあなたの手に渡った、ってことかしら?
私も一応は関わったんだから、連絡くらい寄越しなさいよ。心配するでしょ?
「スーリンさん……!」
メイシアは一気に青ざめた。
協力してもらっておきながら、お礼を言うのをすっかり忘れていた。いくら急に事態が動き、慌ただしくなったとはいえ、昨日の晩に端末を受け取ってから今までに、時間がなかったわけではない。
なんて失礼なことをしてしまったのだろう。
メイシアは、震える手でメッセージの続きを繰る。
――どうせ、昨日の晩はルイフォンと話し込んでいて、私のことなんかすっかり忘れていたんでしょ? 怒っていないから、ちゃんと白状しなさい。
まぁ、女の友情より、男を優先するのは正しいことよ。いい傾向だわ。
それに私のほうも、夜は仕事で忙しいからね。
くるくるのポニーテールを揺らしながら、にっこりと笑う、スーリンの可憐な姿が見えた。彼女らしい優しさが、小さな端末の画面からあふれてくる。
――事情はルイフォンから、だいたい聞いたわ。本当に、驚いたわよ!
でも、まさかメイシアが私を頼ってくれるなんて思わなかった。だから、嬉しかったわ。
「え……」
こちらから、無茶なお願いをした。なのに『嬉しい』と、スーリンは言っている。
メイシアは、読み間違いではないかと瞬きを繰り返した。けれど、文面は変わらない。
「……スーリンさん、ありがとう……!」
彼女の娼婦という職業を利用した、とても失礼な作戦だった。シャオリエの店と鷹刀一族の関係から、嫌々ながらでも協力してくれると信じていたが、不快な思いをさせてしまうと覚悟していた。なのに……。
――そうそう。あなたのお使いできたタオロンさんに、『素敵なプレゼントをありがとう』と、お礼を言っておいて。
それから、『今度は是非、お客さんとしてお店に来てね』って、お願いするわ。
タオロンさん、こういうお店に慣れていないでしょ? 朴訥とした感じが新鮮だったわ。逞しくて魅力的だし、私じゃなくても、皆、彼にならサービスしたい、って思うんじゃないかしら?
「……」
いくら『仲良しの女友達』のスーリンからの伝言でも、お礼はともかく、お願いのほうを伝えるのは……。
メイシアの顔が真っ赤に染まる。
――メイシアとは、また女の子同士の秘密の話をしたいから、早く、その変な庭園から出てらっしゃい。待っているわ。
それと、あなたに是非、見せたい写真があるから添付するわね。
それじゃ、またね。
4.錯綜にざわめく葉擦れの音-2

時は、少し遡る――。
まだ陽射しが本領を発揮する前の、爽やかな朝の時刻。今日ばかりはと早起きをしたルイフォンは、ミンウェイに案内され、ヘイシャオの研究室に向かっていた。
ふたりの乗る車を運転しているのは――エルファン。
勿論、ルイフォンは一度、断った。何も、次期総帥自らが調査に出向かなくてもよいだろう、と。
しかしエルファンは、まだ傷の癒えていないルイフォンが途中で倒れたら、彼を担ぐための男手が必要であること。そもそも見知らぬ場所に赴くにあたり、充分な戦力を有した者を伴わないのは不用心であることを挙げてきた。
その説明の中に、同行者が次期総帥である必要性はまったく入っていない。けれど、ルイフォンは「助かる」と言って、素直に頭を下げた。
エルファンは、ヘイシャオの住んでいた場所を見たいのだろう。
双子のように育った従弟であり、親友でもあるヘイシャオが、一族を抜けたあと、どのように暮らしていたのか。
そして、叶うことなら知りたいのだろう。
ヘイシャオは何故、妻の死後、十数年も経ってから、今更のように『死』を求めてエルファンの前に現れたのか……。
「ここです」
緊張を帯びたミンウェイの声で、車は止まった。
周りに他の建物のない、郊外の一軒家だった。錆びついた鉄格子の門を押し開けると、ぎぎいと大きな音が鳴る。
アプローチの先には、古びた家。
邸宅と呼んでも支障なさそうな立派な家構えであるが、壁という壁を蔦が這い、見るからに廃屋だった。しかし、大掛かりな研究装置を収める建物だけに、頑丈な造りであるのだろう。十数年も手入れをしていないにも関わらず、崩れ落ちるような気配はない。
ミンウェイは、音もなくアプローチに踏み出した。
すらりと背筋を伸ばした足運びには一片の迷いもなく、颯爽と滑るように進んでいく。やがて、玄関扉にたどり着くと、彼女は凪いだ瞳で家全体を見渡した。
――しばらく、ミンウェイをひとりにしておくべきなのだろうか?
ルイフォンは戸惑う。
ここは、彼女の過去が詰まった場所だ。彼女の古い思い出も、これから暴こうとしている、彼女の生まれる前の真実も……。
ちらりと、隣を見やれば、エルファンが無表情にミンウェイの背中を見つめていた。彼の顔から感情を読み解くのは難しいが、おそらく彼も、思い惑っているのだろう。
そのとき。
「早く、行きましょう?」
波打つ黒髪を豪奢になびかせ、ミンウェイが振り返った。光沢のある緋色の衣服が朝日を跳ね返し、きらりと輝く。
彼女は、足を止めたままのルイフォンたちのもとへ、軽やかに戻ってきた。その歩みと共に、ふわりとした優しい草の香りが漂う。
「私なら、心配要らないわよ?」
ルイフォンはきっと、呆けた顔をしていたのだろう。くすくすとした笑いながら、ミンウェイの拳が彼の額を小突いた。
「痛っ!」
見た目よりもずっと骨に響いた一撃に、ルイフォンは思わず声を上げる。
「……本当はね、ここに来るまでは不安だったわ」
恨みがましい目で額を押さえるルイフォンを横目に、ミンウェイは綺麗に紅の引かれた唇をすっと上げる。
「でも、実際に来てみると、ああ、もう、こんなに何もかもが古ぼけちゃうくらい、昔のことだったんだなぁって……思った」
絶世の美貌が、緩やかに大輪の華を咲かせた。
その身にすべてを受け止め、あらゆるものを吸い込んで養分としたかのように、彼女は深みのある色彩で笑う。
「勿論、忘れたわけじゃないわ。いろんなことを、ちゃんと覚えている。私の中には相変わらず、卑屈でいじけた女の子がいるのも分かっている」
「……」
「でも、そんな意気地なしには、リュイセンを救えないでしょ? だったら私は、全部、抱えたままで前に進むわ。――別に気にすることも、今更、傷つく必要もないでしょ? だって、この家にあるのは、とっくの昔の過去だもの」
蔦に覆われた、かつての我が家を再び振り返り、彼女は小さく微笑む。
「――そう……思えてきたわ……」
「ミンウェイ……」
ルイフォンは、なんと言ったらよいか分からず、ただ彼女の名を呼んだ。
「……少し前にね、リュイセンが、お父様とお母様のお墓参りに連れて行ってくれたの。――あのときは、まだ気持ちがぐちゃぐちゃで、リュイセンに悪いことしちゃった。彼は、お父様を過去のものにしようとしてくれていたのにね。今、やっと分かったわ……」
そしてミンウェイは、ルイフォンに一歩、近づく。
「ルイフォン、私はリュイセンに会いたい。――だから、お願い。リュイセンを助けて」
切れ長の瞳がルイフォンを捕らえる。
ルイフォンは猫の目をにやりと歪め、好戦的に口角を上げた。
「当たり前だろ。俺だって、あいつに会いたい。あいつに会って、メイシアをさらった落とし前として、きっちり殴り倒してやる」
彼の返答に、ミンウェイもまた口元をほころばせた。
そんなふたりの様子を見守っていたエルファンが、おもむろに口を開く。
「ミンウェイ、家の鍵は持っているのか?」
「え? ああ! すみません! 持っていません! ……あの日は、お父様が鍵を掛けましたし、……まさか、もう二度と戻ってこないとは思いませんでしたから、私は何も持たずにそのままで……」
ここに来て生じた大問題に、ミンウェイは口ごもる。しかしエルファンは、さも当然とばかりに「だろうな」と呟いただけだった。
「庭に回っていいか?」
そう尋ねながらも、既にエルファンは歩き出している。
小走りになって追いかけながら、ルイフォンは思う。
セレイエは――正確には、セレイエの〈影〉であったホンシュアは、この家の中に入ったはずだ。メイシアが受け取った記憶が、それを証明している。
きっと彼女は、そつなく鍵を入手していたのだろう。そんな気がする。……なんか悔しい。
裏手に回ると、家と同じく、庭も荒れ放題だった。
鬱蒼とした木々が、ざわざわと葉擦れの音を鳴らす。広く張った太い根に、時折、足を取られそうになるのに気をつけながら、ルイフォンは奥へと進んだ。
高く伸びた雑草に埋もれるようにたたずむ、枯れ果てた温室を見つけると、やはりここはミンウェイの育った家なのだと、なんともいえない感慨を覚える。
「ここがいいか」
唐突に、エルファンが立ち止まった。彼は庭に背を向け、家と向き合う。
呼吸をするような、ごく自然な鞘走りの音――。
エルファンの両手から、銀光が流れ出す。
その軌跡を、ルイフォンは目で追うことはできなかった。気づいたときには、家を覆っていた蔓の一部がばらばらになって地面に落ちていた。そして、今まで蔦の這っていた場所には、大きな窓が現れる。
『神速の双刀使い』
その二つ名は次男リュイセンに譲って久しいが、いまだエルファンの両腕には神技が宿っていた。
彼は両手に持った双刀を一度、鞘に戻し、それから改めて今度は鞘ごと腰から外す。手の中で転がすようにして感触を確かめたかと思うと、神速の御業でもって窓硝子を貫いた。
――!
ルイフォンもミンウェイも、声ひとつ発せぬうちに、硝子の飛沫が奏でる旋律を聞いた。
勢いよく穿たれた穴は、さして大きくはなかったが、エルファンが手を入れる程度には充分で、彼はこともなげにクレセント錠を外し、窓を開けた。
「私が同行してよかっただろう?」
口の端だけをわずかに上げ、エルファンが告げる。
得意げに笑っている……のだろうか?
「……いや、まぁ、それくらいしか方法がないのは分かるけどさ……」
警報でも鳴ったら面倒だと、つい考えてしまうのは、ルイフォンの性質だ。
勿論、こんな古びた家にセキュリティも何もないだろう。場合によれば、電気すら通っていない可能性もある。
そう考え、ルイフォンは眉を寄せた。
通電してない場合は、少々、厄介だ。埃まみれのコンピュータが果たして使えるのか否か試せない。――いや。ここは医者でもあったヘイシャオの研究施設だ。自家発電の設備がどこかにあるはず……。
そんなことを考えながら窓から家に侵入し、ミンウェイに先導されてしばらく歩いていると、不意にエルファンが呟いた。
「……嫌な予感がする」
「え?」
「足元を見ろ。埃の上に、何かを運んだ跡が残っている」
「!」
エルファンの予感は当たっていた。
ヘイシャオの研究室には、コンピュータの類を始め、棚にいっぱいあったという研究資料が綺麗になくなっていた。古びた薬瓶だけはそのまま残されていたが、なんの役にも立たない。
「〈蝿〉だ……! 〈蝿〉が、あの菖蒲の館に運んだんだ……」
埃に残された台車のような形跡から、まず間違いない。ホンシュアに目覚めさせられ、『ライシェン』を作るように依頼された彼は、昔の資料を持って新しく用意された研究室に引っ越したのだ。
「糞っ……!」
今回ばかりは、〈蝿〉が意図してルイフォンの邪魔をしたわけではないのは分かっている。だが、腹立たしくてならない。足を踏み鳴らすと、床の埃がぶわりと舞い上がった。エルファンとミンウェイは顔をしかめたが……、何も言わなかった。
ここなら、求めている証拠があると信じていた。実際、あったはずなのだ。セレイエの――ホンシュアの記憶を持つメイシアが、そう証言していたのだから。
『報告書の内容は〈七つの大罪〉のデータベースに収められるから、もしヘイシャオさんの研究室が空振りだったら、そちらへの侵入を考えて』
メイシアのことを考えた瞬間、ルイフォンの耳の中に鈴を振るような声が蘇った。
「――!」
確か、そう言っていた。
その直後に、彼女が『契約』に触れて苦しみだしたため、それどころでなくなり、忘れかけていた。
「屋敷に戻る!」
「ルイフォン?」
急に叫んだルイフォンに、ミンウェイが不思議そうな顔をする。
「今すぐ屋敷に戻って、〈七つの大罪〉のデータベースに侵入をかける!」
〈七つの大罪〉は、もはや瓦解した組織。だが、セレイエの記憶を持つメイシアが『ある』と言った以上、データベースはまだ存在する。
しかし同時に、セキュリティもまた健在のはずだ。
「……っ!」
それはつまり、あの母キリファや、あの異父姉セレイエと同等――あるいは、まさに本人たちが組み上げたセキュリティを相手にするということだ。
「――やるしかねぇだろ……!」
緊張からくる震えを、武者震いと言い換え、ルイフォンは自分を奮い立てる。
彼は大股に一歩、足を踏み出し……、困惑したように彼を見守っていたミンウェイと目が合った。
「……ぁ」
自分のことで頭がいっぱいになっていたが、ここはミンウェイの思い出の詰まった場所だ。ある日、突然、何も持たずに出ていったままならば、きっと何か持ち帰りたいものがあるだろう。
「ミンウェイ、すまん。まずは、お前は自分の部屋で……」
「ううん」
ルイフォンの言葉を途中で遮り、ミンウェイは艶めく美声できっぱりと告げる。
「私がこの家で為すべきことは『お別れ』よ。それは、もう済ませたわ。だから、帰りましょう!」
「……すまん。……ありがとうな」
この先の困難を考えると、決して晴れやかな気分とは言い難い。しかし、華やかなミンウェイの笑顔に、この家に来たことは無駄ではなかったとルイフォンは思う。
「ミンウェイ」
それまで、ひとりでごそごそと戸棚を漁っていたエルファンが、どこからともなく古びた刀を出してきた。そして、きょとんとするミンウェイに、その鍔飾りを示す。
そこには優美に舞う蝶の姿が描かれていた。
「お前は、この鍔飾りを知っているか?」
「いいえ。――その刀は……?」
「ヘイシャオの刀だ。見覚えがある。病弱な私の妹が、蝶のように自由に羽ばたけるように、との願を掛けていた」
エルファンの妹――すなわち、ヘイシャオの妻で、ミンウェイの『母親』だ。
「え……? でも、お父様はいつも、小さな花の鍔飾りを使っていて……」
可憐な小花は、きっと母をイメージしたものなのだろうと、ミンウェイは思っていた。父は幾振りかの刀を持っていたが、それらはどれも花の鍔飾りだった。
どういうことかと彼女が首を傾げると、ルイフォンが口を挟む。
「俺も、〈蝿〉の鍔飾りを見たことがある。メイシアが鷹刀に来た翌日に、〈蝿〉に襲われたときだ。――奴には似合わないような、可愛らしい花の意匠だったから、よく覚えている」
ルイフォンが、初めて本気で死を覚悟した瞬間に見たものが、それだった。
エルファンは、ふたりの様子を交互に見やり、そしてふっと微笑んだ。……彼にしては珍しく、切なげな優しさを漂わせていた。
「ヘイシャオが『大切なもの』を仕舞い込むときの癖を思い出してな。何かあるかと探してみたら、この刀が出てきた。――『大切なもの』といっても、壊れてしまったけれど捨てられない記念の品のような、そういう使えない、使うつもりのないもの、だ」
「エルファン? どういう意味だ」
謎掛けのような言葉に、ルイフォンは尖った声で尋ねる。
しかしエルファンの低音は、それを柔らかに受け止めた。
「ヘイシャオが、ミンウェイを連れて私のもとにやってきたとき、あいつが使っていた刀の鍔飾りは花だった。小さすぎて見た目では花の種類は判別できないが、あいつの考えることなら分かる。――あれは『ベラドンナの花』だ」
ルイフォンの隣で、ミンウェイが大きく息を呑む。
「あいつは妹の死後、蝶を封じて、花と共に在ろうとしたんだな……」
そして、ルイフォンは仕事部屋に籠もる――。
4.錯綜にざわめく葉擦れの音-3

昼夜を知らぬ、ルイフォンの仕事部屋。
窓はなく、機械類にとって常に最適な温度に保たれた密室は、外界とは切り離された異空間である。その中で、ルイフォンは車座に配置された機器の間を飛び回るようにして、あちらこちらでキーボードを打ち鳴らし、あるいはモニタ画面に目を走らせていた。
リュイセンを解放するために、ミンウェイが『母親』のクローンである確たる証拠を手に入れる。――そのために、〈七つの大罪〉のデータベースへの侵入を試みているのだった。
「……っ!」
ルイフォンは舌打ちをした。
癖の強い前髪を掻き上げ、頭皮にがりがりと爪を立てる。
作業は難航していた。そもそも、取っ掛かりすら分からない状態だった。
そして――。
「……あ」
はたと思い出し、彼は携帯端末を取り出した。
案の定、メイシアからのメッセージが届いていた。
ヘイシャオの研究室での証拠探しはどうなったのか。こちらは、夕食までは誰も部屋に来ないから連絡してほしい、という内容が、彼女らしい遠慮がちな文章で綴られていた。
「あー……」
端末の隅に表示されている時刻を目にして、ルイフォンはしまった、と思う。
既に、夕方だった。
ヘイシャオの研究室が空振りに終わり、取って返して屋敷に戻ったあと、彼は仕事部屋に引き籠もった。
そのときは、すぐにもメイシアに連絡をしたいと思っていた。だが、まだ午前中の早い時間で、彼女は〈蝿〉の地下研究室にいると知っていたために後回しにしたのだ。
メッセージを入れておく、という発想はない。面倒臭い。
それよりも、彼女がいる時間に、直接、電話をかけたほうが、声も聞けて一石二鳥だと考えた。敵が情報機器に詳しくない〈蝿〉だと分かっている以上、音声通話の傍受を警戒する必要はないのだ。また、『彼女がひとりのとき以外は、端末の電源は切っておく』と取り決めてあるから、不用意に呼び出し音を鳴らしてしまう心配もない。
そんなわけで、彼女が昼食を終えたころに電話をしようと思っていた……のだが、気づいたらこの時間だ。メイシアは、さぞ気をもんでいることだろう。
周りを見渡せば、車座に並べられた机のひとつに、サンドイッチが載っていたと思しき皿が置いてあった。……そういえば、昼にミンウェイが持ってきてくれたような気がする。
頭が異次元に行っていた彼は、無意識のうちに食事を摂りながら作業をしていたらしい。完全に記憶が飛んでいるが、よくあることだ。
幸い、メイシアの夕食の時間までには、余裕があった。今なら、まだ大丈夫だろう。
ルイフォンは、携帯端末に指を走らせる。
今朝、出発前に電話をしたときは、随分と大見得を切った。……しかし、空振りに終わってしまった。
勿論、〈蝿〉が先に資料を持ち出していたのはルイフォンのせいではない。だが、そのあと何時間も掛けているのに〈七つの大罪〉のデータベースの糸口すら掴めていないのは、クラッカーとしてあまりにも面目が立たないだろう。
「……」
滅多にないことだが……、メイシアと話すのが気が重かった。
「ル、ルイフォン!?」
電話に出た瞬間のメイシアは、焦ったような様子だった。
かといって、まずいことが起きているふうでもない。どちらかというと嬉しそうな、弾んだ声だ。
……囚われの身の彼女に、どんな良いことがあったというのだ?
気になる。
しかし今は、先に重要な報告をすべきだろう。状況は、極めて芳しくないのだ。
彼女の話はあとで教えてもらうことにして、ルイフォンは、まずは連絡が遅れたことを詫び、現状について説明をした。相槌を打つ彼女の声は、すぐにいつも通りに戻り――否、真剣な、ややもすれば『沈んだ』響きになり、ルイフォンの胸が傷む。
「……――というわけで、今、全力で〈七つの大罪〉のデータベースに侵入をかけようとしている」
『ごめんなさい。私が、ヘイシャオさんの研究室には資料がたくさんあった、なんて言ったから……』
「なんで、お前が謝るんだよ?」
なんでもかんでも自分に非があるように捉えるのは、彼女のよくない癖だ。
『私が太鼓判を押したから、ルイフォンも期待していたと思うの……』
「何、言ってんだよ。お前の持つホンシュアの記憶よりもあとに〈蝿〉が資料を持って行っちまったんだから、仕方ないだろ?」
『うん……、でも……』
「それよりさ……」
ルイフォンは、変に責任を感じて落ち込んでいる彼女に、明るく声を掛ける。気の重い報告はもう終えたことだし、先ほど気になった件を訊く、ちょうどよいタイミングだと思った。
「お前のほうは何があったんだ? ――いいことが、あったんだろ?」
『えっ!? あ、あああ……、あのっ!』
メイシアの声が急に上ずった。
「?」
随分とおかしな反応だな、と首をかしげながら、ルイフォンは促す。
「教えてほしい。お前にいいことがあったなら、俺も嬉しいからさ」
『ええと……、ええと、ね。……ちゃんと、ルイフォンに言おうと思っていたんだけどね……』
あからさまに不審である。
そして、妙な態度ではあるが、彼女は機嫌がいいように思えた。
ルイフォンは、面白くないと感じた。
理由は単純だ。
――俺以外の奴がメイシアを喜ばせるなんて、許せん!
心の中で叫んでから、さすがにそれは狭量だと思い直す。
しかし……、釈然としなかった。侵入がうまくいかなくて、気が立っていたというのもあるだろう。
「何があったんだ?」
棘のあるテノールが、口をついて出た。
言ってから、感じが悪かったなと反省する。もっとも、ルイフォンにとっては幸運なことに、電話口の向こうで密かに百面相をしていたメイシアは、彼の口調の変化に気づいていなかった。
『……あ、あのね。スーリンさんから、メッセージをいただいたの』
「……は? スーリン?」
メイシアの携帯端末の受け渡し場所として、シャオリエの娼館の世話になった都合上、スーリンもメイシアが囚われていることを知っている。だから、心配してくれたのだろう。
『ご迷惑をおかけしたのに、私のことを励ましてくれたの。凄く嬉しかった』
「あ……、ああ……」
メイシアとスーリンの仲が良いという、不可思議な現実に対しては複雑な思いがあるため、ルイフォンとしてはどうしても歯切れが悪くなる。
だが、メイシアがスーリンのメッセージに喜んでいるというのなら、納得のいく話だ。
素直に、良かったなと思う。ささくれだっていた感情が、すっと落ち着いていく。
その間にも、メイシアの言葉は続いていた。
『それで、スーリンさんがね。是非、私に見せたいという写真を添付してくれたの』
「写真? なんの写真だ?」
普段の彼だったら、ここですぐにピンときたはずだった。しかし彼の頭は、難航する侵入作業のおかげで疲れ切っていた。
『ええと……、あの、ね』
メイシアが口ごもる。
だが、ルイフォンに隠しごとをしないと誓いを立てている彼女は、素直に告白する。
少し、遠慮がちに。
けれど、とても嬉しそうに。薔薇色に頬を染めた声で――。
『『ルイリン』さんの写真……』
「――――――!」
刹那。
ルイフォンの全身の血の気が引いた。
「消せ! 今すぐ消去しろ!」
鋭いテノールが発せられる。
だが、そこには迫力の欠片もなく、代わりに、彼がとうの昔に無くしたはずの羞恥心らしきものが、ちょこんと可愛らしく載っていた。
「……ったく、スーリンの奴!」
くしゃくしゃと前髪を掻き上げると、頭の中に昨日の悪夢が蘇る。
『ルイリン』とは、ルイフォンの女装姿につけられた名前である。
携帯端末を受け取りに来たタオロンが『馴染みの女』に逢いにきたという設定だったので、調子に乗ったシャオリエとスーリンが、ルイフォンを『ルイリン』にしたのだ。
そしてそのとき、ルイフォンは不覚にもスーリンに写真を撮られてしまったのである。
――『あれ』をメイシアに見られた……。
先ほど引いた血の気が、にわかに戻ってきて、今度は彼の顔を真っ赤に染める。
もしも、今の通話が画像付きのものであったら、メイシアは『ルイリン』以上に貴重なものを見ることができたのかもしれない。しかし、画像は通信負荷を増やし、音質を著しく落としてしまうため、残念ながら音声のみの通話であった。
『……やっぱり……、消さなきゃ駄目、よね……?』
今まで弾んでいたメイシアの声が、急にしぼんだ。
『……ごめんなさい。ルイフォンは嫌だったのよね。私の作戦のせいで無理矢理に、だもの……。ごめんなさい。……写真に浮かれていて……ごめんなさい』
「え……?」
スーリンからとんでもないものが送られてきて、メイシアは困惑しているのだとルイフォンは考えていた。彼女は、彼に隠しごとをするのはいけないことだと思っている。だから、きちんと報告をしているだけだと――。
「メイシア……、お前……。……もしかして、その写真――」
考えたくない。実に、考えたくない。
だが、しかし――。
彼女が申し訳なさそうに我儘を言うときの、少し恥ずかしそうな上目遣いの顔が脳裏に浮かぶ。それは、つまり、彼女はその写真を……。
「――ひょっとして、気に入っている……?」
『うん! 凄く、素敵』
しおれていた花が生気を取り戻し、柔らかにほころんでいくかのように、彼女の声が華やいだ。
思わず聞き惚れてしまいそうな心地の良い声。しかし、ルイフォンは反論せずにはいられない。
「どこがだよ!?」
『ルイフォンは格好いいだけじゃなくて、綺麗でもあったんだなぁ、って』
「はぁ?」
不気味なだけだろ! と、続けて叫ぼうとした彼を遮り、彼女はうっとりと呟く。
『そんな人が私のそばにいてくれるなんて、嬉しいというか、誇らしいというか……、凄く幸せだと思ったの。――あ、あのっ、ごめんなさい。勿論、外見だけじゃなくて、中身が好きだからこそで……』
メイシアは慌てふためくが、どこか的外れだった。
しかも、いつもなら絶対に口にしないような言葉をぽろぽろと漏らしている。電話だけのやり取りになってから、彼女は少し大胆だ。
ルイフォンの心がじわりと温かくなり、先ほどとは別の、薄く淡い色合いで頬が染まった。
「……っ」
自分が照れているのだと気づき、彼は驚く。
自信過剰な彼は、得意げに胸を張ることはあっても、胸を高鳴らせながら赤面するなどという経験は今までなかった。
信じられないが、新鮮で……悪い気分ではない。
メイシアが上機嫌なのは『ルイリン』――ルイフォンが原因。
それはどう考えても、彼女が彼にべた惚れであるが故の、恋は盲目というやつだ。
――嬉しいじゃねぇか。
自分でも単純な気がするが、喜びに打ち震える。――心の片隅にだけは、どこか釈然としない思いを残しながらも……。
「……消さなくていい」
『ええっ!?』
「お前が、俺の写真を気に入ったというのなら、それは持っていていい」
メイシアが喜んでいるのなら、それはよいことなのだ。
「――けど! 他の奴には、絶対に見せるなよ!」
『いいの!? 嬉しい! ありがとう!』
鈴を振るような声が高らかに響き渡ると、ルイフォンの耳が幸せに包まれた。
何か間違っているような気がしないでもないが、侵入がうまくいかずに苛立っていたルイフォンは、満たされた気持ちになって通話を終えたのだった。
無情なる時は、瞬く間に流れていき、やがて夜が訪れる。
鷹刀一族がルイフォンに言い渡した時間は、三日間。
三日のうちに、リュイセンを解放するための、確たる証拠を手に入れなければならない。
そのうちの一日が、終わろうとしていた。
ルイフォンは、〈七つの大罪〉のデータベースへの侵入に効果的な方策を見いだせないまま、仕事部屋で崩れ落ちるように眠りに落ちた。
メイシアは、ルイフォンの作業の邪魔にならないよう、彼への直接の連絡を避け、ミンウェイに電話で夜食と毛布を頼んだ。
そして、リュイセンは……。
夜になり、〈蝿〉は自室と決めた、王の部屋で睡眠を取るために研究室を出た。
扉を開けた瞬間、地下通路の闇が迫る。
光に慣れていた目は暗がりの負荷に圧されるが、彼の鋭敏な感覚は闇に溶け込む人の気配を見逃したりなどしなかった。
「どうしましたか? ――リュイセン」
唇に薄笑いを載せて、低く問う。
その声に応えるように気配はゆっくりと近づいてきて、研究室内から漏れ出す光がかろうじて届くという位置で止まった。
高い鼻梁と頬が白く照らし出され、他の部分は黒く沈む。黄金比の美貌は、若いころのエルファンにそっくりだ。初めて出会ったころのリュイセンは、図体ばかりが大きな、甘っちょろい若造といった体であったが、今は抜き身の刀のような凄みをまとっている。
あからさまな敵意を向けられても、どこか愛しく感じるのは、遥か昔に捨てた一族そのものの姿を彼が有しているからだろう。どうやら〈蝿〉は、思っていた以上に、かの血を持つ者に郷愁の念を抱いているらしい。無論、還ることなどできはしないが。
「……そういえば、お前に文句を言い忘れていたな、と思ってな」
威嚇するように、リュイセンが顎を上げると、肩で揃えた髪が後ろに流れ、背後の闇と同化する。
「文句ですか」
〈蝿〉は、ほんの少し口の端を上げた。
心当たりがありすぎて、苦笑するしかない。
「何が可笑しい?」
「いえ。なんでもありませんよ」
瞳に険を載せたリュイセンの苛立ちを、〈蝿〉は軽い吐息と共にさっと払う。
リュイセンは、むっと眉を吊り上げ、しかし、追求はしなかった。不毛な言い争いになれば、口が達者ではない彼が不利になることが明白だったからだ。
故に、話が横道にそれないうちにと、リュイセンは単刀直入に口火を切った。
「お前――、『メイシアは、いずれセレイエに乗っ取られて消えてしまう』と言っていたが、嘘だってな」
「あの小娘から聞いたのですか」
「ああ」
「ふむ……」
別に、どうということはない。
リュイセンを世話係にすれば、そのくらいの話はするだろう。あのおめでたい小娘は、リュイセンが裏切ったとは考えていないのだから。
彼女は、一緒に逃げようと持ちかけたはずだ。
しかし、リュイセンは決して応じない。〈ベラドンナ〉のために〈蝿〉に従う。
初めは希望を持っていた彼女も、やがて絶望に染まっていく。それは、さぞ愉快なことだろうと思ったからこそ、リュイセンをそばに置いたのだが、あの貴族の娘は存外しぶとく、いまだに諦めていないようだった。
王族の血を濃く引く、小娘――。
神話の時代から、鷹刀一族を支配してきた王家に連なる者。
まったく忌々しい……。
「俺を騙したな」
リュイセンの低いうなり声に、〈蝿〉は思考を呼び戻された。
「さて? 〈天使〉やら記憶やらについては私は門外漢ですので、あなたを誤解させるような言い方をしてしまったのかもしれませんね」
「はん! わざとだろ? お前は『生を享けた以上、生をまっとうする』と言っていた。そのためにメイシアを利用してやるんだと。――だから、俺を騙してメイシアをさらわせた」
噛み付くような口ぶりも、〈蝿〉から見れば負け犬の遠吠え。憐れみの眼差しを向けるだけで、特に言い返す気にもならない。
「お前は、自分が生き残るためには手段を選ばない。――卑劣だ」
「ええ。否定しませんよ」
柔らかな声色で、〈蝿〉は口角を上げる。過ぎたことに固執するリュイセンが滑稽でならなかった。
世話係として、常にあの小娘と顔を合わせなければならないのが相当こたえているのだろう。リュイセンは、〈蝿〉をなじらなければ気がすまないのだ。
「そんなに『死』が怖いのかよ? 死んだら何もかもなくなると、恐れているのか?」
リュイセンは嘲るように言う。
けれど、その声には引きつったような響きが含まれており、逆らうべきではない相手を揶揄することへの恐怖を必死に隠そうと、虚勢を張っているように聞こえた。
「死んだあとのことなど、どうでもよいことですよ。考える価値もありません。大切なのは、生きていることなのですから」
〈蝿〉は、できの悪い子供を嘆くように溜め息をつく。
そのとき、演技じみた仕草で肩をすくめ、視線を下げた〈蝿〉は気づかなかった。
ほんの一瞬。
瞬きをするよりも、ごくわずかな刹那、リュイセンの美貌が凍りつき、その瞳が大きく見開かれたことに――。
「無駄話は、このくらいでよろしいですか? もう、夜も更けています。私は休みたいのですよ」
〈蝿〉は、論ずるに足りぬ戯言を好まない。
だから、この中身のない会話を打ち切りたかった。
そして、『目的を果たした』リュイセンもまた、不快感しか感じられない〈蝿〉と顔を突き合わせている意味を終えた。
「邪魔をしたな」
リュイセンは愛想なくそう言い、足早に立ち去る。
高鳴る鼓動を〈蝿〉に悟られないよう、一刻も早く、ひとりになる必要があった。
5.幽明の狭間に落つる慟哭-1

またひとつ、夜が明けた――。
夢を見た。
眠りから覚めた〈蝿〉は、ゆっくりとベッドから身を起こし、周りを――現実を確認する。
肌を滑り落ちた毛布は、極上の手触りをしていた。
マットのスプリングは、彼の体重を心地よく受け止めてくれている。
それらの夜具は、それなりに裕福な生活を送っていた彼の過去の記憶においても、まずお目にかかったことのないような上等な品だった。
部屋の中に目を向ければ、贅を尽くした最高級の調度。一般市民が手を触れるのは畏れ多いほどの――。
当然だ。ここは、かつての王の居室なのだから。
……けれど、〈蝿〉の心が踊ることはない。
何故なら、ここには最愛のミンウェイがいない。
双子も同然だったエルファンもいない。
夢の中で共に笑い合っていた彼らが……いない。
ふと視線を落とせば、青黒い血管の浮き出た、自分の手の甲が見えた。
老けたな――と、思う。
老人と呼ばれる年齢にはまだまだ早いが、三十代の記憶を五十路手前のこの肉体に入れられたのは……。
そう思いかけて、〈蝿〉は首を振る。
そうではない。
夢で見た『あのころ』と比べて――老いたのだ。
「……」
昔の夢などを見たのは、おそらく昨晩のリュイセンのせいだろう。記憶の中のエルファンと瓜二つだった。
〈蝿〉は溜め息を落とし、のろのろと身支度を始める……。
部屋を出るとき、扉を飾り立てる天空神フェイレンの彫刻が目に入り、彼は鼻に皺を寄せた。
天空神が大きく翼を広げて下界を見下ろしている。この一見、優美な意匠には、神の罪が隠されていると〈蝿〉は思う。
天空神が広げている翼は、鷹の羽根。鷹刀一族から奪い取ったものだ。
神は、鷹の一族に翼を差し出させ、代わりに刀を授けて守護の任を命じた。故に、鷹刀一族の紋章は、翼が刀と化した鷹なのである。
無論、これは伝承だ。
しかし、この国の王が、鷹刀の血族を〈贄〉に生き存えてきたことを象徴的に示している。
すなわち、天空神の姿は、鷹刀一族への搾取の証そのもの。
――病弱に生まれたミンウェイも、王の犠牲者のひとりだ……。
〈蝿〉は口の中に血の味を覚え、自分が唇を噛んでいたことに気づく。
彼は、何ごともなかったかのように扉に背を向け、歩き出した。
緋毛氈の廊下に朝日が差し込み、〈蝿〉の後ろに長い影を描く。黒い翼を伸ばしたかのようなその姿は、孤独を引きずっているようにも見えた。
定められた日課として、メイシアは今日も『ライシェン』と対面していた。
白金の髪の赤子はいつもと変わらず、硝子ケースの揺り籠で夢見るようにまどろんでいる。ゆらりゆらりと培養液の中をたゆたい、ごくまれに瞬きをしては、美しい青灰色の瞳を彼女に見せてくれた。
しかし、メイシアの心は『ライシェン』にはない。
〈七つの大罪〉のデータベースへの侵入に難航しているルイフォンを想い、彼女は憂いに眉を曇らせる。
彼は今、どうしているだろうか?
邪魔をしてはいけないと、電話は控えた。メッセージは入れておいたが、おそらく読んでいないだろう。集中しているときの彼は、頭が異次元に飛んでいる。寂しくはあるが、別に構わない。そんな懸命なところも、彼の魅力のひとつだと思うからだ。
しかし、〈七つの大罪〉のデータベースは、簡単には侵入を許してくれないだろう。
メイシアの中には、セレイエの記憶がある。だから、そのセキュリティがどんなに強固な障壁であるのかを知っている。そのくせ、メイシアが『セレイエとして』、ルイフォンにその壁の打ち破り方を教えることはできそうにないのだ。
初めて『ライシェン』を見たあの瞬間だけは、メイシアは感覚や感情すらも引きずられ、完全にセレイエと同化した。けれど、それは特別なことだったらしい。
メイシアの中にあるセレイエの記憶は、言うなれば分厚い事典のようなものだ。
さまざまなことが記されているが、それを『持っている』だけでは、内容のすべてを『知っている』ことにはならない。中身を読んで、理解して、初めて身につく――そんな感じなのだ。
だから、セレイエ――あるいは〈影〉となったあとのホンシュアが見聞きした『経験』は、比較的すっと頭に入ってくるのだが、専門的な『知識』となると、にわかではお手上げだった。
「何を考えているのですか?」
苛立ちを含んだ低い声が響き、メイシアの思考は中断された。
椅子に座ったまま、体をひねって振り返ると、いつの間にか背後に立っていた〈蝿〉が、不機嫌な顔つきで彼女を睨んでいた。なかなかセレイエの情報を得られないためか、このところずっと機嫌が悪かったのだが、今日はいつもにも増して眉間に深い皺が寄せられていた。
メイシアは知る由もないことだったが、今朝の〈蝿〉は夢見が『良すぎた』。それで、夢と現実とのあまりの落差に、どす黒い感情が揺らめいていたのである。
「どうにも、あなたは真面目に『ライシェン』と向き合っているように思えませんね」
「……すみません」
逆らっても仕方ないので、メイシアは素直に頭を下げた。そして、そのまま身を固くして、じっとしている。
しかし――。
今日の〈蝿〉は、極めて虫の居所が悪かった。
彼女が殊勝な態度をとっても、彼は満足できなかった。
「――そうですね。あなたが協力的でないのなら仕方ありません。今から、自白剤を使ってみましょう」
「……え?」
メイシアは耳を疑った。
〈蝿〉は今、なんと言ったのか?
「自白剤……です、か……?」
顔面が蒼白になる。
紫がかった薄紅の唇から漏れたのは、確認というよりも、ただの呟きだ。
「ええ」
椅子に座ったメイシアの耳に届くよう、〈蝿〉がわずかにかがんだ。その拍子に白衣の裾が揺れ、床に落ちた影が黒い翼のようにはためく。
「自白剤で駄目なら、あなたの脳に電極を刺し、刺激を与えてみます。ありとあらゆる手段を講じてみましょう」
『悪魔』が発する囁きに、メイシアは目の前が真っ暗になった。
――甘かったのだ。
そもそも〈蝿〉は、一週間くらい『ライシェン』と対面してみようと、気まぐれに言っただけだ。いつしびれを切らしてもおかしくなかった。一週間の猶予が確実である保証など、どこにもなかったのだ。
メイシアのすべては、〈蝿〉の掌にある。
歯の根が合わず、メイシアの口が、かちかちと小さな音を立てる。
全身が震え始め、それを押さえようと彼女は自分の体を掻き抱く。しかし、小刻みに揺れる長い黒絹の髪が、彼女の激しい脅えをあらわにするだけだった。
まるで命乞いをするかの様子に、〈蝿〉は美麗な顔を醜く歪めて破顔した。そして、白衣を翻し、薬棚のある部屋の奥へと向かっていく……。
その瞬間、メイシアの心臓が跳ねた。
自白剤について、彼女はミンウェイに聞いたことがあった。
それは、泥酔した人間に秘密を吐き出させるようなものだという。
だから、知りたい情報を得られるとは限らない。逆に、思いもよらなかったことを勝手に喋り始めることもある。
つまり。
もしも、今のメイシアに自白剤が投与されたら……、口にしてしまうのはセレイエに関する情報だけではないかもしれない。
ルイフォンのことを――彼と連絡を取れたことを、告白してしまうかもしれない。
タオロンやファンルゥが協力してくれたことを、打ち明けてしまうかもしれない。
そうなれば、今まで苦労してきたすべては水泡に帰す。そして、タオロン父娘は、危険に晒される……!
「ま、待ってください!」
メイシアは、弾かれたように立ち上がった。
「私は、あなたを騙していました……!」
閉ざされた研究室に響き渡る、凛と澄んだ声――。
迷いはなかった。
今、為すべきことは、〈蝿〉の後ろ姿を引き止めることだ。
「私は――本当は、セレイエさんの記憶をすべて受け取っています」
〈蝿〉の足が、ぴたりと止まった。
白衣の裾と、その影だけが慣性に流されていく。
「……」
沈黙の中で、〈蝿〉の広い肩が、わなわなと恐ろしげに震えた。
メイシアは縮み上がりそうな心を奮い立たせ、あらん限りの力を振り絞って叫ぶ。
「だけど! あなたになんか何も教えたくなかった! ……だから、嘘をつきました!」
「小娘――!」
振り返った〈蝿〉の顔は、驚愕と憤怒に彩られていた。
彼は、にわかには言葉が続かず、半端に口を開けたまま。その隙に、メイシアは畳み掛ける。
「でも、自白剤を使えば、私の嘘はばれてしまうのでしょう? だったら、先に私から――……きゃあぁっ!」
最後まで言うことはできなかった。
大股に近づいてきた〈蝿〉が、メイシアの襟首を掴み上げたのだ。
「この私を――騙していた、だと……!?」
「は……、い……」
咳き込みながらも、メイシアは毅然と答える。
苦しい呼吸の中で、懸命に打開策を組み立てる。
これは戦いなのだ。
喰うか喰われるかの、戦い。
物理的な、肉体的な勝負では、メイシアの身柄を自由にできる〈蝿〉が圧倒的に優位。これを覆すことはできない。
だから彼女は、別の方向から〈蝿〉に立ち向かう。
それは『情報』――ルイフォンが使う武器。
『情報を制する者が勝つ』
ルイフォンの持論だ。
セレイエの記憶を受け取ったメイシアは、多くの情報を手に入れた。
だから、きっと手段はある……。
「ほぅ、それで? 嘘がばれる前に白状すれば、私が許すとでも?」
メイシアの思考に割り込むように、〈蝿〉の低い声が耳朶を打つ。
ばらけそうになる意識を必死にかき集め、メイシアは首を振る。
――ルイフォン……!
脳裏に、彼の顔を思い浮かべる。
刹那、彼女は閃いた。
最強の切り札を――。
「あなた……は、許してくれるような……人、じゃない……。でも、先に……言えば、まだ……話を聞いて……くれ、る……」
「はっ! 一度、嘘をついた人間の話など、誰が聞くというのですか?」
嘘まみれの〈蝿〉が口にするには、あまりにも滑稽な台詞だった。けれど、厚顔な彼はそのことに気づいていない。
「ほら……、こうし、て、……今、だって……、話を、している……」
〈蝿〉を見上げ、メイシアは嗤う。
彼を挑発するように、婉然と。花の顔を、美しく妖しく歪めながら。
「馬鹿馬鹿しい」
〈蝿〉は言い捨て、メイシアの襟を離す。
その途端、メイシアは床に崩れ落ち、激しく咳き込んだ。
「あなたが『鷹刀セレイエの記憶を受け取った』と白状したなら、今こそ、私は自白剤を使えばよいだけでしょう?」
床にうずくまるメイシアを打ち捨て、〈蝿〉は再び、薬棚へと向かう。
その背中に向かって、床に座り込んだままのメイシアが上半身を起こして叫んだ。
「〈蝿〉!」
けれど、彼が立ち止まることはなかった。
それでも構わない。
こちらには、最強の切り札がある。
「私は『亡くなった、あなたの奥様』を生き返らせることができます」
その声にも、〈蝿〉は歩み続ける――。
しかし……、彼の肩はわずかに揺れていた。
「奥様の『肉体』は、すぐそこにあります。そして私なら――私が〈天使〉になれば――既に亡くなった方の『記憶』を手に入れることができます」
メイシアは言葉を重ねる。
〈蝿〉の心を揺さぶるために。
「『肉体』と『記憶』。このふたつがあれば、奥様の『蘇生』は可能でしょう?」
見えない刃で、〈蝿〉を斬りつける――!
『既に死んだ人間の『記憶』を手に入れられる』
嘘ではない。……おそらくは。
セレイエから受け取った記憶――情報からすると、理屈の上では可能なはずだ。
ただし、〈蝿〉が信じるかどうかは――。
「……小娘」
ゆらり、と。
幽鬼のように、〈蝿〉が振り返った。
「よりによって、詭弁にミンウェイを持ち出すとは……」
愛する妻を駆け引きに利用された。その屈辱に〈蝿〉は激憤していた。
彼はゆっくりと、ゆっくりとメイシアに近づいてくる。
「その減らず口、どうしてやりましょうか……?」
地の底から湧き上がってくるような、低い声。
彼の深い憤りが――否、妻を想う慟哭が、床を通じて伝わってくるような気がして、メイシアは戦慄した。
逆鱗――だ。
分かっていて、口にした。
メイシアは罪悪感を振り払い、正面から〈蝿〉と向き合う。
黒曜石の瞳をいっぱいに見開き、静かに口を開く。
「一度、嘘をついた私の言い分を信じないのは、賢明な判断だと思います」
彼女は、すっと自分の胸に手を当てた。
それは、はちきれそうな心臓を押さえるためであったが、結果として、ぴんと姿勢が正され、毅然とした構えとなった。
「ですが、〈蝿〉――。技術的にそれが可能か否かを検討しないとは、あなたは〈七つの大罪〉の〈悪魔〉として、随分と浅慮ではありませんか?」
メイシアは、凛と対峙する。
美しい戦乙女の顔をして。
「――っ!」
メイシアの言葉は、あまりにも正鵠を射ていて、知を誇る〈蝿〉には我慢のならないものだった。憎々しげに顔を歪め、彼は吐き捨てる。
「はっ! それもこれも、自白剤を使って、あなたに喋らせればよいだけのことです」
「お断りします」
メイシアは即答した。
そのあまりの素早さに、〈蝿〉は呆気にとられた。彼が二の句を継げずにいるうちに、彼女は続ける。
「大嫌いなあなたに屈するなんて、私の矜持が許さない」
それは、ただの我儘に聞こえたのだろう。ようやく口をきけるようになった〈蝿〉は、さも可笑しそうに鼻で笑った。
「囚われのあなたに、そんなことを言う資格はないでしょう?」
「いいえ。取り引きが成立する間柄だと思います」
「取り引き? あなたと私が? 何をそんな世迷い言を」
〈蝿〉の哄笑の中で、メイシアは冷静に告げる。
「私は、あなたの奥様を蘇らせます。その代わり……」
「ほう!」
彼はメイシアを遮り、揶揄するような奇声を上げた。それは、失ったはずの妻を取り戻すという、あまりにも魅力的な誘惑に囚われないようにするための、無意識の防御だった。
そんな夢物語を信じられるほど、〈蝿〉の心は希望に満ちていない。それでも、絶望の中から見げれば、思わず手を伸ばしたくなるような光が、彼は怖かった。
メイシアを見下ろし、〈蝿〉は言い放つ。
「『その代わり』、――見事、ミンウェイを生き返らせてみせるから、自白剤を使わずとも自分の言うことを信用しろ、とでも?」
彼の喉の奥から、虚勢にまみれた低い嗤いが漏れた。
メイシアは、ごくりと唾を呑み込んだ。
ここで、自白剤にこだわるような発言をしてはならない。
彼女の真の目的が、単にこの場を切り抜けることであったとしても。
展望室に戻って、ルイフォンに事態の急変の連絡を入れることであったとしても。
その結果、タオロンに頼んで〈蝿〉を討ち取ってもらうことだったとしても……。
間違えてはいけない。
彼女が提示すべき要求は、これだ――!
「私を、ルイフォンのもとに帰してください!」
メイシアは立ち上がり、〈蝿〉にぐっと迫る。
その勢いに、黒絹の髪がふわりと舞う。
つぶらに見開かれた黒曜石の瞳が、ぎろりと〈蝿〉を睨み……、ひとしずくの涙が、堪えきれなくなったように、きらきらとした軌跡を描きながらこぼれ落ちた。
「あ……」
泣くつもりなど、なかった。
これは、〈蝿〉を喰らうための演技なのだから。
けれど、今、口にした思いは本当で、心からの切望で――。
「なるほど、そうですね。あなたの望むことなど、それしかありませんね。私としたことが愚かなことを訊きました」
ほんのわずかな狼狽を混ぜながら、〈蝿〉が口の端を上げる。
「しかし、それなら何故もっと早く、その要求を出さなかったのですか? あなたは帰りたいのでしょう? あの子猫のもとへ」
〈蝿〉の弁はもっともだ。
だが、彼の疑念をかわすための答えなら、メイシアはあらかじめ用意してあった。
「……何を言っているのですか、あなたは……! 分かって……いないのですか!?」
彼女は声を震わせる。
「亡くなった方の記憶を集められるようになるために、私は……、私はっ……、……〈天使〉にならないといけないんです!」
本当に〈天使〉になるつもりなどない。けれど、想像しただけでも恐ろしく、彼女の脅えは本物だった。
「そんなこと、簡単に決意できない! ――でも、このままここにいたら、私はあなたのいいようにされるだけです。それなら、私は自分の誇りを守るため、〈天使〉になることを選びます!」
彼女は〈蝿〉に詰め寄る。
言葉の罠で、彼を絡め取る。
「ふむ。理屈は通っているようですね。……しかし、死んだ人間の記憶を手に入れることができるなど、信じられませんよ。どうせつくなら、もう少しましな嘘を……」
「できます!」
凛とした声が、〈蝿〉の言葉を打ち消した。
「『デヴァイン・シンフォニア計画』が、その証拠です!」
「『デヴァイン・シンフォニア計画』?」
唐突に出された、諸悪の根源たる名称に〈蝿〉は眉をひそめる。
「『デヴァイン・シンフォニア計画』は、亡くなったライシェンの『肉体』をあなたに作らせ、『記憶』を〈天使〉であるセレイエさんが用意して、ライシェンを生き返らせるという計画です」
メイシアはそこで一度、言葉を切り、ゆっくりと解き明かすように言う。
「ライシェンの暗殺は、まさかの出来ごとでした。当然のことながら『生前のうちに、保存しておいた記憶』などありません。だから、ライシェンが亡くなったあとで、セレイエさんが掻き集めたんです」
――これは、事実だ。
記憶の集め方を詳しく説明すれば、王族の『秘密』に触れるため、ルイフォンには言っていない。しかし、〈悪魔〉である〈蝿〉になら言える……。
「!」
〈蝿〉が息を呑んだ。
しかし、それでも抗うように、彼は言葉を漏らす。
「赤ん坊の記憶など、なくても構わないでしょう? 私が『ライシェン』の肉体を作れば、それで生き返ったことに……」
「それで、セレイエさんが満足すると思いますか!?」
畳み掛けたメイシアに、〈蝿〉は押し黙った。
彼女の話に破綻はないと、彼の頭脳は悟ってしまったのだ。それを屁理屈で否定していくほど、彼は愚者ではなかった。
「詳しい話を……聞いて差し上げてもよろしいですよ」
地下研究室に、乾いた低音が響いた。
5.幽明の狭間に落つる慟哭-2

〈蝿〉は、メイシアに椅子に座るよう、目線で促した。それから、彼自身も作業机から椅子を運んできて、彼女と向き合うようにして腰を下ろす。
「それで、いったいどこから、とうの昔に死んだミンウェイの記憶を掻き集めるというのですか?」
嘲るような口調だった。
けれど、いつものような高飛車な威圧感はない。
メイシアを論破して、あり得ない夢物語を騙った彼女に鉄槌を下してやろうと意気込んでいるような、そうでなければならないのだと強迫観念に駆り立てられているような、そんな心の揺らぎが垣間見えた。
『『亡くなった、あなたの奥様』を生き返らせることができます』
それは、どんなに胡散臭くとも、〈蝿〉にとっては甘美な誘惑以外、何ものでもないだろう。だから、深い猜疑の眼差しの中に、すがるような惑いが混ざる。
彼の反応は、まさにメイシアの思惑通り。
しかし、だからこそ罪悪感が彼女を襲う。
この場を乗り切るためだけに、〈蝿〉の心のもっとも弱く、純粋なところを衝くのだ。得体のしれない恐怖が胸を占め、声が詰まる。
「小娘。私は訊いているのですよ? それとも、やはり嘘だったということですか?」
〈蝿〉が先を急かすのは、彼の気持ちに余裕がないから。めったにないことだ。ひるんでいる場合ではない。
彼女は意を決し、掌を握りしめながら恐る恐る口を開いた。
「〈冥王〉……です」
「――!」
刹那、〈蝿〉の顔つきが明らかに変わった。突き刺すような視線で、メイシアの顔を凝視する。
彼女は早鐘を打つ心臓を押さえ、すかさず言を継いだ。
「〈蝿〉……、あなたも〈悪魔〉なら、創世神話の真実を知っているのでしょう?」
「創世神話の……真実」
繰り返された〈蝿〉の声は、あまりにも低くて感情の色が見えない。
恐ろしいほどに張り詰めた空気を肌で感じながら、メイシアは努めて平然を保ち、畳み掛ける。
「すべての人の記憶は〈冥王〉に集約されます。ならば、亡くなった奥様の記憶は、今も〈冥王〉の中に残っているはずです」
〈蝿〉の喉仏が、こくりと動いた。
「……あなたの中には、本当に『鷹刀セレイエ』がいるのですね」
その呟きは、メイシアとの受け答えからは少しずれていた。だから、おそらくは独白だったのだろう。
もしかしたら彼は、メイシアがセレイエの記憶を得たことすら半信半疑だったのかもしれない。そこに、一部の王族か、〈悪魔〉しか知り得ないことを口にしたことで、彼女の中のセレイエを――〈悪魔〉の〈蛇〉を確信したのだ。
〈蝿〉は、おもむろに腕を組み、椅子の背にもたれて思案を始めた。
肘に回された長い指先が、苛々と小刻みに白衣を叩く。眉間には深い皺が刻まれ、美麗な顔は不機嫌にしかめられていた。
ふたりの間に、重い沈黙が訪れる。
メイシアは、固唾を呑んで〈蝿〉の様子を見守る。
彼女が話した情報は、すべて真実だ。だが、彼がそれを信じ、乗ってくるか否か――。
別に取り引きが成立しなくてもいいのだ。ただ、ひとこと『少し、検討させてください』と言わせることができればいい。
そうなれば、メイシアは自白剤を投与されることなく展望室に戻される。昼食のあとのひとりきりの時間に、ルイフォンと連絡を取れる。タオロンに〈蝿〉の暗殺を依頼できる……。
メイシアの心臓が、激しく脈打った。
額にはうっすらと汗が浮かび、目眩がしそうになる。
今ここで、〈蝿〉をその気にさせなければならない。
……けれど、それがうまくいったところで、リュイセンを解放し、彼を味方に迎えて〈蝿〉を討つというルイフォンが目指した道は、もはや、たどることができないのだ。
口の中に、苦い味が広がる……。
「――なるほど」
不意に、〈蝿〉の声が響いた。忙しなく動いていた指先が、ぴたりと動きを止める。
彼が口角を上げ、次の瞬間、弾かれたような哄笑が沸き起こった。
「〈蝿〉!?」
メイシアは狼狽する。
「私としたことが、あなたに惑わされるところでした」
ひとしきり嗤ったあと、彼は落ち着き払った低音で告げた。
「……ど、どういうことですか……!」
メイシアの問いかけに、しかし〈蝿〉は直接的には答えずに、薄ら笑いを浮かべる。
「そうですね。確かに〈冥王〉ならば、ミンウェイの記憶が残されているでしょう。可能性を示してくださったあなたには感謝いたします」
〈蝿〉は大仰に頷いてみせてから、演技じみた仕草で肩をすくめる。
「しかし、膨大な記憶を保持する〈冥王〉の中から、ミンウェイの記憶だけを選んで取り出すのは、砂漠の中から一粒の砂を拾い上げるようなものです。現実的ではありませんね」
「ですが! 事実として、セレイエさんは〈冥王〉の中からライシェンの記憶を手に入れたんです!」
「ほぅ?」
揶揄するように〈蝿〉が相槌を打つ。
「本当です! 並の〈天使〉では到底、不可能ですが、王族の血を引くセレイエさんには可能でした。そして、それなら、より濃い王族の血を引く私が〈天使〉になれば……」
そう言いかけたところで、〈蝿〉は『掛かったな』とばかりに、にやりと目を細め、メイシアの言葉を遮った。
「ええ、そうですね。つまり、『鷹刀セレイエ』と『〈天使〉になった、あなた』――どちらでも、ミンウェイの記憶を手に入れることができる、というわけですね」
「え?」
「ならば私は、あなたからは鷹刀セレイエの居場所を聞き出すにとどめ、ミンウェイの記憶に関しては鷹刀セレイエと取り引きしますよ。彼女には、ライシェンの記憶を手に入れた実績があるそうですしね」
「――っ、そんな……」
メイシアの顔が凍りつく。
〈蝿〉は満足げに口の端を上げ、喉の奥で冷たく嗤った。
「お忘れですか? そもそも私は、自分の身の安全を確保するために、鷹刀セレイエを探しているのです。もしもミンウェイが生き返るのだとしても、私の命が狙われているような状況では、傍にいる彼女も危険に晒されます。それは望ましくありません」
彼は、できの悪い弟子を諭すかのように雄弁に語る。
「まずは鷹刀セレイエを見つけ出し、私の安全を保証させる。それから、ミンウェイを蘇らせる。この順番を間違えてはいけませんよ」
「……!」
〈蝿〉の言う通りだった。
〈悪魔〉としての知識のある彼は、〈冥王〉に記憶が残されているというメイシアの弁を真っ向から否定しているわけではない。
むしろ、信じている。
その証拠に、幽鬼のようだった頬には赤みが差し、冷酷な瞳の奥は、ぎらつく生気で満たされている。
だが、話は信じても、話に乗ってこなかった……。
メイシアの背中を冷たい汗が滑り落ちる。
「勿論、あなたにも役に立ってもらいますよ。あなたは鷹刀セレイエに対する大事な切り札なのですから」
ねとつくような目線で、〈蝿〉はメイシアを舐める。
「それよりも素朴な疑問なのですが、あなたは本当に〈天使〉になる覚悟ができていたのですか?」
「……え?」
「どうせ口先だけなのでしょう?」
見透かされていた。
メイシアは無意識に自分の体を掻き抱く。
「別に答えなくて構いませんよ。口でなら、どうとでも言えますからね。――それに、前にも言ったと思いますが、私はあなたを〈天使〉にする気はありません。そんな危険なこと、できるわけがないでしょう?」
「危険……?」
メイシアが目を瞬かせると、〈蝿〉はやれやれとばかりに、わざとらしい溜め息をつく。
「〈天使〉とは、人を操る化け物です。しかも、濃い王族の血と、鷹刀セレイエの知識を持つあなたなら、およそ熱暴走とは無縁の『最強の〈天使〉』になるのでしょう? 〈天使〉となったあなたの前には、私などひとたまりもありません」
そこで〈蝿〉は何を思ったのか、ふっと遠い目をした。
「現に、私の同僚だった〈蠍〉という〈悪魔〉は、研究対象だった実験体の〈天使〉に反抗され、殺されています。――そう、鷹刀セレイエとあの子猫の母親ですよ。その後、エルファンが彼女を鷹刀に連れて行き……、巡り巡って、今があるというわけです」
言葉の途中で、〈蝿〉の顔が寂寥を帯びた。言い終えてから、彼は余計なことを言ったと首を振り、「話を戻しましょう」と告げる。
「あなたの要求は、あの子猫のもとに帰りたい――ですね?」
メイシアは呆然としながらも、こくりと頷く。駆け引きなどとは関係なく、それは間違いなく真実だった。
「ならば、私に協力してください」
「……協力?」
「ええ。私の要求は、初めからずっと同じです。――私を鷹刀セレイエに会わせてください」
「……」
「鷹刀セレイエとの交渉の中で、私は勿論、あなたを切り札として使います。けれど心配しなくとも、最終的には、あなたの身柄は子猫のもとに引き渡されることになるはずですよ」
「……どうして、そう言い切れるのですか?」
か細い声で尋ねるメイシアを〈蝿〉は鼻で笑う。
「私は鷹刀セレイエ本人には会ったことはありませんが、〈影〉であったホンシュアのことならば知っています」
彼は、ほんの少し前に詰め寄り、言い含めるようにメイシアの顔を見やる。
「いろいろと謀略を巡らせながらも、結局のところ、ホンシュアは甘さが抜けきりませんでした。ならば、『同一人物』である鷹刀セレイエも、同じく甘い性格であるはず。異父弟と恋仲になったあなたを見捨てるわけがありません」
確かに、メイシアの中の『セレイエ』も、情の深い人間だ。
濃い王族の血を引く者たちの中から、異父弟ルイフォンと共に『ライシェン』を守ってくれそうな娘として選んだメイシアを、大切に思ってくれているのを感じる。
けれど……。
「……セレイエさんは……既に、亡くなっています……」
ぽつりと、メイシアは漏らした。
この情報を明かすのは、吉か、凶か――。
賭けになるが、〈蝿〉が、交渉の相手はあくまでもセレイエだと言い張り、メイシアに取り合ってくれないのなら、セレイエへの道を閉ざすしかない。
「な……!」
〈蝿〉は目を見開いた。
「何をふざけたことを……!」
わなわなと唇を震わせる〈蝿〉に、メイシアは静かに告げる。
「ライシェンの記憶を集めたことによって、セレイエさんは限界を超え、熱暴走を起こしました。――あなたがさっきおっしゃっていた通り、私なら熱暴走とは無縁だったでしょう。けれどセレイエさんの中の王族の血は、そこまで濃くなかったんです」
「……!」
「セレイエさんは分かっていました。死者の記憶を集めるなんて無茶をすれば、命を落とす、って。――だからこそ、『デヴァイン・シンフォニア計画』の水先案内人として、『〈影〉のホンシュア』が必要だったんです」
「――っ!? 摂政に命を狙われているから、鷹刀セレイエは〈影〉にすべてを任せて、姿を消しているのでは……」
そう言ってから、「そんなことは、どうでもいい」と呟き、〈蝿〉は頭を振った。そして、メイシアの話に破綻を見出そうと、白髪頭を掻きむしる。
しばらくの間、うなるような声を上げていた〈蝿〉だが、急に、はっと思いついたように「小娘」と口を開いた。
「鷹刀セレイエが命を懸けて手に入れたという、ライシェンの記憶はどこにあるのですか?」
にたり、と。
笑んだ口元が、余裕を取り戻す。
「王族の血を引いた鷹刀セレイエの容量なら、自分の記憶以外に、ライシェンの記憶も保持できるでしょう。しかし、鷹刀セレイエの代わりとなった、水先案内人のホンシュアの肉体は一般人です。鷹刀セレイエとライシェン――ふたり分の記憶を持つことはできません。鷹刀セレイエが死ねば、ライシェンの記憶は失われることになります」
ほら、ほころびを見つけたと、〈蝿〉の顔が愉悦に歪む。
彼は、意気揚々として続ける。
「せっかく、ライシェンの記憶を手に入れても、肉体ができる前に失われてしまったら意味がありません。だいたい死んでしまったら、鷹刀セレイエは蘇ったライシェンと再会できないのですよ? ……本当は、どこかで生きているのでしょう?」
セレイエが死んだことにしたほうが、〈蝿〉と取り引きをしたいメイシアにとって都合がよい。だから、嘘をついているのだろうと、〈蝿〉は言っているのだ。
しかし、メイシアはゆっくりと頭を振った。
そして、自分の中にある、セレイエの切ない思いを噛み締め、吐き出すように告げる。
「セレイエさんは、亡くした息子に再び会いたいから生き返らせたいのではありません。理不尽に奪われた小さな命に、本来、与えられるはずだった幸せを届けたい。正しい未来を取り戻したい、そう願っているんです」
セレイエの望みは、妻との幸せな生活の続きを夢見た〈蝿〉とは異なる。
どちらがどう、ということはない。
どちらも、亡くした幸せを求めているだけだ……。
メイシアは、こみ上げてくる思いを飲み込み、〈蝿〉と対峙する。
情に流されてはいけない。
これは、〈蝿〉とメイシアの戦いなのだから――。
「あなたがおっしゃる通り、ホンシュアではライシェンの記憶を保持できません。だから、セレイエさんは亡くなる前に、別の人に預けたんです」
「ほう、別の人物に――ですか」
からかいを含んだ低音で語尾を跳ね上げ、〈蝿〉は尋ねる。
「確かに、〈七つの大罪〉の〈悪魔〉なら、大手を振るって王宮に出入りできます。王族の血を引く者との接触も可能でしょう。――しかし、ライシェンが殺されたあとの鷹刀セレイエは、王宮のお尋ね者だったのではないですか? いったい誰に、ライシェンの記憶を預けるというのです?」
当然の質問に、メイシアの心臓が高鳴った。
胸の奥が熱くなる。
その名前は、とてもとても大切なもの――。
「ルイフォン」
「!」
〈蝿〉の眉がぴくりと上がった。
「セレイエさんは、ルイフォンに――彼女と同じく、わずかながらですが王族の血を引く異父弟に……、ライシェンの記憶を預けたんです。王宮とは無関係な異父弟のところなら安全だろう、と」
これこそが、ルイフォンが『デヴァイン・シンフォニア計画』に深く関わることになった理由。
ルイフォンは気づいていないけれど、彼の中に『ライシェン』が眠っている。
少女娼婦スーリンが目撃した、あのとき。セレイエは、異父弟にライシェンの記憶を預けたのだ。
「セレイエさんは、もういないんです。……ルイフォンに会ったあと、彼女は亡くなりました」
〈蝿〉の顔色が変わった。メイシアの弁を信じたのだ。
脅える自分を奮い立たせ、彼女は毅然と告げる。
「〈蝿〉、セレイエさんが亡くなっている以上、あなたは私と取り引きするしかありません」
彼は沈黙したまま、瞳だけをぎろりとメイシアに向けた。
メイシアは悲鳴をこらえ、懸命に訴える。
「おっしゃる通り、私は〈天使〉になるのは怖いですし、あなたも私が〈天使〉になることを望まない。ならば、どうしたら互いの利益になるのか、少し落ち着いて考えましょう」
答えは出なくていいのだ。
とにかく、この場を乗り切り、展望室に戻ることができれば……。
「小娘……」
地を轟かせるような〈蝿〉の声が研究室を揺らした。
「つまり、あなたは、鷹刀セレイエの行方を必死に求める私を、ずっと影で嘲笑っていた――ということですね!」
「――!?」
閃光の速さで、白衣の腕が、長い指先が伸ばされた。
身構える間もなく、メイシアは白い小首を〈蝿〉に絞め上げられた。
5.幽明の狭間に落つる慟哭-3

メイシアが〈蝿〉の地下研究室で『ライシェン』と対面している、その時刻。
リュイセンは割り当てられた自室でひとり、思索にふけっていた。
『この手の話の定石だとは思いますが、もしも私が死ぬようなことがあれば、〈ベラドンナ〉のもとに彼女の『秘密』がもたらされるよう、仕掛けをしてあります』
だから私を害そうなどと、ゆめゆめ考えることのなきよう……。
耳に蘇る、聞き慣れた低音は、あからさまな牽制。
一族特有の声質でありながら誰のものとも違う、ねっとりとした響きがリュイセンに絡みつき、彼の自由を奪った。
リュイセンとて、〈蝿〉の脅迫を頭から信じたわけではない。彼の持つ野生の勘は、五分の確率だと告げた。
〈蝿〉の弁が本当である確率が半分。ハッタリである確率が半分。
しかし、半々では身動きを取れない。
だから昨晩、リュイセンは〈蝿〉に問うたのだ。
『そんなに『死』が怖いのかよ? 死んだら何もかもなくなると、恐れているのか?』
対して、〈蝿〉はこう答えた。
『死んだあとのことなど、どうでもよいことですよ。考える価値もありません。大切なのは、生きていることなのですから』
聞いた瞬間、リュイセンは天啓を得た。
『死んだあとのことなど、どうでもよい』――すなわち〈蝿〉は、自分の死後の現世に、興味がない。
リュイセンの脳裏で、確率の天秤が、ぐらりと音を立てて傾いた。
――ハッタリだ……。
無論、常人であれば、この程度の台詞から確信に至るのは早急であろう。しかしリュイセンには天性の直感がある。細かな理屈などは一足飛びに捨て置き、彼は本質を見抜き、真理へとたどり着く。
〈蝿〉を殺す。
決意を胸に虚空を仰げば、黄金比の美貌から表情が消えた。無慈悲な機械人形が如き瞳には、冷徹な光が浮かぶ。
〈蝿〉がこの世から失せれば、ミンウェイを脅かすものはなくなる。彼女は安心して、穏やかな日常を過ごすことができる。
ミンウェイの幸せを守るために。
〈蝿〉を亡き者にするのだ。
それからタオロンに頼んで、メイシアをルイフォンのもとに帰す。
そして――。
ミンウェイの『秘密』をなかったことにするために、それを知るリュイセンは姿を消す……。
リュイセンは壁にもたれ、思考を巡らせる。
「ミンウェイ……」
その名を呟いた途端、無機質な氷と化していたはずのリュイセンの面差しが、ふわりと解けた。口元に柔らかな微笑が浮かび、双眸に切なげな光が灯る。
心の一部をどこかに置き去りにしてきてしまったミンウェイ。
無防備で、不安定で、危うい、大切な女。
彼女の欠けた心を埋めてあげるのだと、幼き日に誓った。
守ってあげるのだ――と。
「俺は、ミンウェイを守る」
どんなことをしてでも。
たとえ、二度と逢うことは叶わなくとも……。
「…………」
雑念を振り払うように首を振ると、肩の上で揃えられた黒髪がさらさらと哀しげな音を立てながら流れた。
昼が近づき、リュイセンは地下へと向かう。朝、〈蝿〉のもとに送ったメイシアを迎えに行き、彼女が起居する展望室に連れて帰るという、日課のためである。
地下研究室で何が行われているのか、詳しいことをリュイセンは知らない。初めは、メイシアの身に何か危険があるのではないかと、ひやひやしていたのだが、一週間は問題ないのだと彼女から聞いた。
――だから、その間に〈蝿〉を殺す。
今日か、明日か……。
刀は取り上げられてしまっているが、管理しているのは〈蝿〉ではなく部下の私兵だ。奪い返すことなど、造作もない。私兵ごときなら素手で黙らせる自信はある。
そんなことをつらつらと考えながら、リュイセンは廊下を歩く。
生真面目な性格上、彼は時間に余裕を持って行動する。だからいつも、かなり早くに到着して、扉の前で待っているのだ。
研究室と廊下は丈夫な扉で隔てられており、中の様子は、ほとんど読み取れない。ただ、メイシアが出てくる少し前になると、決まって〈蝿〉が嫌味を言うような気配を感じる。
しかし、今日は違った。
リュイセンが地下に降り立った瞬間、肌を刺すような予感がした。気のせいであってほしいと願いながら、彼は足早に通路を駆け抜ける。
そして、扉の前に着いたとき、それは現実に変わった。
漏れ聞こえる、〈蝿〉とメイシアの言い争うような声。飛びつくように扉に耳を付ければ、『小娘……』という〈蝿〉の轟くような怒号が、振動となって伝わってくる。
『つまり、あなたは……、……私を、ずっと影で嘲笑っていた――ということですね!』
言葉の端々までは、正確には聞き取れない。しかし、ただならぬ様子は明らか――。
刹那、椅子が倒れるような音が響き、間髪を容れず、メイシアの苦しげなうめきがリュイセンの耳朶を打った。
「――!」
メイシアが危ない――!
止めなければ――と、リュイセンの体は瞬時に動いた。
扉には鍵が掛かっている。秘密の地下研究室なのだから、当然だ。
だから彼は、蹴破ろうと身を翻した。
助走をつけ……、そこではっと、我に返る。
彼が如何な武の達人でも、この頑丈な扉を壊せるわけがない。頭を使うのだ。――ルイフォンのように。
そのとき、リュイセンの脳裏にルイフォンの言葉が蘇った。
それは、ハオリュウの車に隠れ、初めてこの館に侵入したときのもの。
ルイフォンは、敵地に乗り込むハオリュウを案じ、万一のときには小火騒ぎを起こすと言った。それからリュイセンへの指示として、こう付け加えたのだ。
『お前は非常ベルを押してくれ。混乱に乗じて助けに行く』
――非常ベルだ!
確か、地下に降りる階段の脇にあった。
リュイセンは、全力で通路を戻る。小火まで起こせなくとも警報が鳴れば、さすがの〈蝿〉も研究室から出てくるはずだ――!
けたたましい警報音が響き渡った。
私兵たちが次々に廊下に飛び出し、何ごとかと右往左往する。その気配を尻目に、リュイセンは再び地下通路を走り抜け、研究室の前に戻ってきた。
「〈蝿〉! 火事だ!」
どんどんどんどん……。
リュイセンは力いっぱい、扉を叩く。
非常ベルの音は、研究室の中にまで届いていたのだろう。リュイセンが叫ぶまでもなく、〈蝿〉は外に出ようとしていたらしい。――そんなタイミングで、扉が開かれた。
暗い地下通路に、部屋の明かりが差し込んだ。
逆光に沈んだ〈蝿〉の姿が幽鬼のように浮かび上がる。しかし、リュイセンは構わずに室内に目を走らせた。
「メイシア!」
硬質な白い床に、長い黒絹の髪が広がっていた。瞼を閉じ、仰向けに倒れた顔は蒼白で、喉元には締められたような指の跡がくっきりと赤く残っている。
リュイセンは、取っ手を掴んだままの〈蝿〉を突き飛ばし、メイシアのもとへ駆け寄った。
「メイシア! 大丈夫か!」
膝を付き、そっと体を起こす。彼女は小さく咳き込んで、やがて薄目を開けた。
「リュイセン……?」
「メイシア! よかった……」
苦しげではあるが、ちゃんと意識がある。リュイセンは、ほっと胸を撫で下ろす。
と同時に、ゆっくりと近づいてくる白衣の影が、彼らのそばまで伸びてきた。黒い陰りに呑まれるよりも先に、リュイセンはメイシアを庇うように立ち上がる。
〈蝿〉とメイシアの間で、何があったのかは分からない。けれど、〈蝿〉が非道を働いた。そのことに間違いはない。
――この男は『悪』だ。滅ぼすべき相手だ。
ミンウェイを不幸に陥れ、メイシアにも危害を及ぼす。
艷やかな黒髪を逆立たせ、若き狼が牙をむく。
愛刀を取り戻してから〈蝿〉と対峙するつもりだった。
敵の本拠地ともいえる、この研究室では、どんな不測の事態が起こるか分からない。得体のしれない薬物でも持ち出されたら、一瞬にして不利になるだろう。
しかし、ここで見過ごすなどあり得ない。
素手でいい。〈蝿〉を縊り殺す。
リュイセンの殺気が膨れ上がった。
重心を移し、まさに飛びかかろうとした――その瞬間だった。
「ほう……」
よく通る〈蝿〉の低音が機先を制した。
揶揄するような、尻上がりの軽い響き。――しかし、研ぎ澄まされすぎたリュイセンの神経には、充分すぎるほどの妨害だった。
「――っ!」
リュイセンは、たたらを踏む。
「なるほど。非常ベルを鳴らしたのは、あなたというわけですね」
リュイセンから発せられる、魂が凍りつきそうなほどの殺気を浴びながらも、〈蝿〉はいつもと変わらぬ調子で嗤った。そして、あろうことか、リュイセンの脇を平然とすり抜け、床にうずくまるメイシアのそばにしゃがみ込んだのだ。
「〈蝿〉!?」
リュイセンが慌てて振り返ると、〈蝿〉は後ずさるメイシアの手首を強引に取り、彼女の脈をとっていた。どうやら医者として容態を診ているらしい。
白衣の背中が、無防備に晒されている。
しかし、リュイセンは拳を握りしめ、その手を力なく下ろした。
今ここでやりあえば、確実にメイシアを巻き込む。〈蝿〉はそれを示唆したのだ。
「特に異常はありません。――私としたことが、つい話に夢中になってしまいましたね」
〈蝿〉は悪びれもせずにメイシアにそう言うと、すっと立ち上がり、リュイセンを睥睨した。
反射的に身構えたリュイセンに、〈蝿〉は不気味な嗤いを漏らす。
……だがそれは、実のところ、〈蝿〉の虚勢だった。
扉を開けた瞬間に、〈蝿〉はリュイセンが何をしたのかを理解した。だから、リュイセンが次に取る行動を容易に想像できた。
すなわち。
倒れているメイシアを見れば、リュイセンは激昂する。そして、〈蝿〉に敵意を――否、殺意を抱く。
メイシアに危害が加えられただけなら、殺意に至るまでの憎悪にはならないだろう。しかし、〈ベラドンナ〉に愛を注いでいるリュイセンは、もともと〈蝿〉が憎くてたまらない。〈蝿〉に脅迫されていることを忘れ、一時的に箍が外れても不思議ではない。
リュイセンが本気で歯向かえば、〈蝿〉にまず勝ち目はない。
だから〈蝿〉は、リュイセンの殺意を削ぐべく、動じない態度という先手を打ったのだ。リュイセンの熱い血も、機を逃せば冷めるだろう。何しろ〈蝿〉には、〈ベラドンナ〉の『秘密』という盾があるのだから――と。
――しかし。
リュイセンに対しては冷静に対処できる〈蝿〉も、自分自身の感情に関しては違っていた。
内心では、必死に動揺を隠していた。
正直なところ、彼は非常ベルの音に救われたと思っていたのだ。
『鷹刀セレイエ』の記憶を持つメイシアは、絶対に手放してはならない切り札。もしも怒りに身を任せ、衝動で殺していたら、彼は大事な手札を失うところだった。自分の落ち度で取り返しのつかない事態となれば、悔やんでも悔やみきれない。
リュイセンの邪魔が、結果として役に立ったからだろう。いつもなら楯突くような真似をした相手を決して許さない〈蝿〉が、リュイセンを軽くいなしただけで、報復を忘れていた。――そのくらい動転していたのである。
「もう昼ですか」
まるで世間話のような調子で発した言葉の裏に、〈蝿〉は『命拾いしましたね』という、メイシアへの嫌味を含ませる。
勿論、そんなことはリュイセンには分からない。
ただ、ともかくメイシアを安全なところに連れて行くべきだと、彼は思った。〈蝿〉の首級は、おあずけだ。
「小娘。あなたが話したことについて、私は冷静に考える必要がありそうです。……続きは明日にしましょう」
視線を下げ、まだ床に座り込んだままのメイシアへと〈蝿〉が声を掛ける。
その際、向き合って立っていたリュイセンには、〈蝿〉の眉間に刻まれた皺が妙にくっきりと見えた。色あせた白髪頭も精彩を欠き、随分と弱気な〈蝿〉に彼は首をかしげる。
しかし、そんな疑問は、〈蝿〉の次の台詞を聞いた瞬間に、どうでもよくなった。
「……ミンウェイの記憶を手に入れたとしても、それは彼女が亡くなったときの年齢のもの――また二十歳にもならない少女のものなのですよ。その記憶を、そこの硝子ケースの『ミンウェイ』に入れるなど、酷いことです」
「……っ!」
メイシアが鋭く息を呑んだ。細い指が口元を押さえるが、体は小刻みに震え、黒曜石の瞳が罪悪感に染まる。
「――だからといって、その記憶のために新しく若い肉体を作ったとして……、二十歳にもならない娘に、この老いた肉体の私のそばにいてくれ、と言うのですか……?」
静かに吐き出された言葉は、慟哭の裏返し……。
「続きは明日です。――出ていってください」
念を押すように繰り返し、〈蝿〉は白衣を翻しながら研究室の奥へと歩いていく。その先の衝立の向こうに『ミンウェイ』がいる。リュイセンは、そう察した。
そして、そのとき。
リュイセンは……苛立ちを――怒りを覚えていた。
〈蝿〉が、この研究室でメイシアに何をさせようとしているのかは分からない。
しかし、今の〈蝿〉の言動は、亡くした妻への深い想いだ。
『娘』のミンウェイを、さんざん妻の代わりにしておきながら、それでも〈蝿〉は永遠に妻を想い続けるのだ。
――許せねぇ……。
「リュイセン……?」
ぎこちなく立ち上がったメイシアが、心配そうに彼の顔を覗き込んだ。
「あ、ああ……、いや……」
リュイセンは奥歯を噛み、ぐっとこらえる。
今はまだ、動くべきときではない。夜だ。
今宵――。
就寝のために、この研究室を出たときが奴の最期だ。
「メイシア、行こう」
ここに長居をする理由はない。彼はメイシアを伴い、部屋を出た。
5.幽明の狭間に落つる慟哭-4

研究室の扉を開くと、真っ暗な地下通路が広がった。
闇に沈むような空間に向かって、メイシアは、ふらつく足で転げるように身を躍らせる。
背後で、重い音を立てながら扉が閉まった。その音が石造りの壁に反響し、振動が空気を伝って彼女の肌を撫でた。
「……っ」
かくっ、と。足の力が抜けた。
メイシアは、へなへなとその場に崩れ落ちる。
部屋からの光は完全に遮断され、一面の漆黒の世界。だがそれは〈蝿〉と隔てられた証拠であり、彼女は恐怖どころか、安らぎを覚えた。まるで『悪魔』が封印されたかのように安堵したのだ。
「大丈夫か?」
頭上から、リュイセンの声が降りてきた。夜目が効く彼には、彼女がへたり込んでいる姿が見えているのだろう。
人の動く気配がして、やがて、あたりが明るくなる。リュイセンが電灯を点けてくれたのだ。
メイシアは立ち上がろうとして、しかし、動けなかった。今ごろになって、全身が激しく震えていた。
「メイシア?」
「リュイセン……、ありがとう……」
もう少しで、〈蝿〉に絞め殺されるところだった。リュイセンが助けてくれなければ、命はなかった。
二度と再び、ルイフォンに逢えないところだった……。
「――っ」
ルイフォンを心に想い描いた瞬間、黒曜石の瞳から、はらりとひと筋、涙がこぼれた。
彼がここに居たら、きっと強く抱きしめてくれたに違いない。彼女の髪をくしゃりと撫で、優しいテノールで『怖かったな』と包み込んでくれたことだろう。――そう、思ってしまった。
胸が苦しい。喉が熱い。
涙は、堰を切ったように次から次へとあふれてきた。止めたいのに止まらない。メイシアは、嗚咽を殺して泣きじゃくる。
「お、おい……、メイシア……」
リュイセンがうろたえ、彼の影が戸惑いに揺れ動いた。
「ご、ごめんなさい」
メイシアは慌てて顔を拭う。
そうだ、泣いている場合ではない。
危機は去ったのだ。経緯は最悪だったかもしれないが、狙い通りに、〈蝿〉に『考えさせてほしい』と言わせることができた。明日までという期限が守られる保証はなくとも、少なくとも、ルイフォンと連絡を取るくらいの時間は稼げたはずだ。
だから、まずは立ち上がり、携帯端末のある展望室に戻る――。
気持ちを入れ替えると、意外なほどに滑らかに体が動いた。リュイセンがほっと息をつき、「行くぞ」と歩き始める。
リュイセンの広い背中を追いながら、メイシアは徐々に冷静になってきた。
今までは、一週間が過ぎるまで、メイシアの身に危険はないと考えていた。だから、その間に、リュイセンを〈蝿〉の支配から解放する予定だった。そして、〈蝿〉の首級を手柄に、リュイセンが一族に戻れるように、と――言い方は悪いが、お膳立ての準備をしていた。
しかし、状況が変わった以上、今は一刻も早く〈蝿〉の息の根を止めるべきだ。したがって、次に〈蝿〉が研究室から出てきたときに、タオロンに仕留めてもらうことになるだろう。
おそらくは、今夜――。
「……っ」
リュイセンの後ろ姿を見つめるメイシアの目が、悲痛に歪んだ。
タオロンに暗殺を依頼すれば、リュイセンが再び鷹刀一族を名乗る道は閉ざされる。
〈蝿〉がいなくなり、リュイセンがこの庭園に留まる理由がなくなったとき、彼は速やかに誰も知らない何処かに去っていくことだろう。高潔であるがゆえ、裏切ってしまった一族のもとへは決して姿を現すまい。事実上の永久の別れだ。
――嫌だ。
メイシアは奥歯を噛み、潤みそうになった黒曜石の瞳に力を込めた。
目の前には、リュイセンのすらりと伸びた背と、迷わずに前へと突き進む手足。あたかも、彼の性格を表しているかのような――。
そう。
彼はただ、ミンウェイのためを想ってまっすぐに行動しただけだ。
彼の気持ちを利用する〈蝿〉に、抗えなかっただけだ。
リュイセンを見捨てるような真似はしたくない……。
ふと。
メイシアは思った。
リュイセンに、すべてを打ち明けては駄目だろうか。
ルイフォンは、ミンウェイが母親のクローンだという確たる証拠を示した上で、リュイセンに〈蝿〉暗殺を持ちかけると言っている。そうでもしなければ、リュイセンは頑なにミンウェイの『秘密』を認めないであろうから、と。
だが寸刻を争う事態なら、何はともあれ、リュイセンと腹を割って話すべきではないだろうか。もしかしたら証拠などなくとも、リュイセンは、こちらの手を取ってくれるかもしれない。その可能性に賭けたい。
今までのルイフォンの苦労を無にするようで申し訳ないが、リュイセンを失いたくないのだ。
それに、ルイフォンだって、現状を知れば同意してくれるのではないかと思う。何故なら、彼は『リュイセンを取り戻したい』と明言しているのだから。
ルイフォンに提案してみよう。
メイシアは、前を歩くリュイセンの背中をじっと見つめる。まるで、視線で彼を取り戻そうとでもするかのように。
ともかく、まずは展望室に戻り、昼食を終える。そして、ひとりきりになったら、ルイフォンと連絡を取る。リュイセンと話すのは夕食のときだ。
諦めるのはまだ早い。
メイシアは頭の中で段取りを決め、気を引き締めるべく体の芯にぐっと力を入れた。
展望室に着くと、リュイセンの後ろ姿がひらりと翻った。勢いよく黒髪がなびき、メイシアと正面から向き合う。
双刀の煌めきを宿したかのような双眸が、しかとメイシアを捕らえた。今までずっと、彼女の目を避けるようにしていたのが嘘のようだった。
「リュイセン……?」
急激な変化に彼女は戸惑う。
黄金比の美貌は相変わらずだが、そこには温かみの欠片もなかった。眼差しは冷たく冴え渡る氷のようで、睫毛の先までもが凍りついたかのように張り詰めている。
凄みのある美の根底にあるのは――深い憤り。
「メイシア」
「は、はい」
彼女は思わず、びくりと肩を上げた。
「お前が危険な目に遭ったのは、お前をさらってきた俺のせいだ。すまなかった」
「リュイセン!?」
頭を下げる彼に、メイシアは驚き、声を跳ね上げる。
どうやら、彼女が殺されかけたことに責任を感じ、〈蝿〉と自分自身に対して怒っているのだろう。――メイシアは、そう解釈した。
だが、それは正解ではなかった。
確かに、リュイセンの内部にはメイシアへの罪悪感が存在する。けれど彼の激情は、死んだ妻のことしか頭にない〈蝿〉に向けられていた。
詳しいことを知らないリュイセンでも、先ほどの研究室では〈蝿〉の妻の話がなされていたのだと察しがついた。そして、あのときの〈蝿〉の口ぶりは、リュイセンにしてみれば、妻を亡くした不幸な自分の運命を呪い、憐れんだ自己陶酔としか思えなかった。
『娘』のミンウェイを不幸に陥れておきながら、よくもぬけぬけと……と、リュイセンの心には嵐が吹き荒れていた。
『娘』を無理やりに妻の代わりにしておきながら、結局のところ、彼は死んだ妻を求め続ける。
『娘』には、自分だけを望むよう、支配して育てたくせに。
歪んだ世界に閉じ込められた『娘』は、服毒自殺を試みるまでに追い詰められたというのに……。
リュイセンは〈蝿〉の殺害をとうに決意していたが、研究室からこの展望室に着くまでの間、〈蝿〉の言動を反芻し続け、昏い憎悪を更に腹に溜め込んでいた。
――故に。彼は抜き身の刀と化していたのだ。
勿論、メイシアは、そんなリュイセンの心情など知る由もない。だから、彼女はただ恐ろしげな雰囲気に圧倒され、困惑するばかりだった。
「リュイセン……、あのっ、ごめんなさい」
「なんで、お前が謝るんだ?」
「私が不用意に〈蝿〉を怒らせたから、あんなことになったんです」
リュイセンは自分のために怒っているのだと勘違いしているメイシアは、恐縮に身を縮こめる。
「〈蝿〉のことは許せない。けど、だからといって、私が礼儀知らずになるのは違ったんです」
〈蝿〉の妻を駆け引きに利用したのは、やはり卑劣だったと思う。メイシアにも非があるのだから、ともかくリュイセンには怒りを鎮めてほしい。――そういう思いだった。
しかし、リュイセンは、眦を吊り上げた。
「礼儀だと? 本気で言っているのか? あいつは、ミンウェイを追い詰め、死に追いやろうとした奴だぞ!」
「……え?」
突然、叫びだしたリュイセンに、メイシアは混乱した。
にわかには彼の言葉の意味を理解できず、声を失う。その間にリュイセンは、はっと我に返り、余計なことを言ったと気まずげな顔になった。
だが――。
メイシアの聡明な頭脳は、聞き流してはいけないと警告を発した。
「ミンウェイさんが殺されそうになった……? ……それはあり得ないはずです……。〈蝿〉にとって、『生』は尊いものなんですから……」
「忘れてくれ」
リュイセンは吐き捨てたが、メイシアは思考を巡らせる。
激しい違和感があった。
『生を享けた以上、生をまっとうする』――そう言って『生』に執着する〈蝿〉が、ミンウェイに『死』を与えようとすることはないはずなのだ。
「『追い詰められて』の『死』ということは……、ミンウェイさんは過去に自殺しようとした――ということですか……?」
「昼食を運んでくる!」
唐突にリュイセンが言い放ち、神速で踵を返した。
彼の荒い声が、苦しげな響きが、そして何よりも彼の態度が――メイシアの言葉は正しいと、雄弁に語っていた。それと同時に、もうこの話題に触れるなという、強い拒絶もまた。
「ご、ごめんなさい……」
リュイセンが消えたあとの扉に向かって、メイシアは謝る。
しかし――。
胸騒ぎがした。
『看過してはならない』という、奇妙な――焦燥のような、ざわついた気持ちが拭えない。
かつて、ミンウェイが自殺――自殺未遂をした。
よく考えれば、それはちっとも不思議なことではない。
少女時代のミンウェイは、『父親』に溺愛という名の虐待を受けていた。そのころの彼女なら、『死』を望んでもおかしくないだろう。
「あ……、『〈蝿〉』じゃなくて、『ヘイシャオさん』だ……」
先ほどの会話では、メイシアもリュイセンも混同していたが、『〈蝿〉』と『ヘイシャオ』は、共通の記憶を持ちつつも『別人』だ。
現在の『〈蝿〉』とミンウェイは、一度も会ったことはない。
ミンウェイは、生前の『ヘイシャオ』との生活で追い詰められ、自ら『死』を求めたのだ。
「――っ!」
メイシアの心臓が激しく跳ね上がった。
鋭く息を呑み、無意識に体を掻き抱く。
『ミンウェイ』と呼ばれる存在が、ヘイシャオの前で、『死』を望んだ……。
たとえクローンであっても、『娘』のミンウェイは、妻のミンウェイとは違う人間だ。
しかし、頭では分かっていても、ヘイシャオの心は、ふたりを区別できていなかった節がある。
妻に先立たれたヘイシャオを生かしていたのは、『生を享けた以上、生をまっとうする』という妻との約束。そんなヘイシャオのそばで、妻と見分けがつかなくなった『娘』が自殺しようとしたら……?
ヘイシャオの世界は、壊れる――……。
「――だから、なの……?」
誰もいない部屋で、メイシアは虚空に向かって尋ねる。
「『ミンウェイ』さんが『死』を求めたから、ヘイシャオさんを『生』に繋ぎ留めていた約束が消えてしまった――ということなの……?」
メイシアの耳に、〈蝿〉の深い憤りが、怨嗟に満ちた自嘲が、狂おしいほどの慟哭が蘇る。
『鷹刀ヘイシャオが、自殺などするはずがないのです。彼が自ら『死』を望むなど、あり得ない!』
『ええ、私も馬鹿ではありません。分かっていますよ』
『私の持つ記憶が保存された時点から、オリジナルの鷹刀ヘイシャオが死ぬまでの間に、彼が心変わりするような事件があった、ということでしょう』
『生』を望む〈蝿〉と、『死』を求めたヘイシャオ。
ふたりの狭間に横たわる、記憶の時差。
『生』から『死』へと心変わりした理由は――。
ミンウェイの自殺未遂だ……。
ぴたりと合った符丁に、メイシアの顔から血の気が引いていく。知らず、握りしめていた掌は、うっすらと汗で湿っていた。
〈蝿〉は『『死』はミンウェイへの裏切り行為』だと吐き捨て、オリジナルのヘイシャオを許さないと言っていた。
しかし本当は、『自分』が自殺した理由を知りたがっていたように思える。
それを知ったところで何にもならないが、純粋に知りたいのだろう。――最愛の妻を裏切るほどの理由とは、なんであったのかを。
メイシアは、ごくりと唾を呑んだ。
これは『情報』だ。
相手の知りたい情報は、武器になる。
だから、これは〈蝿〉に対する、強い武器だ。
彼女はそう思い、しかし、首を振った。
〈蝿〉はもう、メイシアの話には、まともに耳を貸さないだろう。なんの戯言だと言って、一笑に付すに違いない。
……それに。
憎き仇ではあるけれども、〈蝿〉は『デヴァイン・シンフォニア計画』に利用されるために作られた被害者でもある。セレイエの記憶に引きずられて罪悪感を覚えているだけかもしれないが、これ以上、彼の心をえぐるような真似はしたくない……。
メイシアは高ぶる感情を落ち着けようと、ゆっくりと深呼吸をした。
そして、気づいた。
「……違う。逆かもしれない……」
駒として作り出され、何も知らされず、嘘に翻弄されるがままであった〈蝿〉にとって、真実の情報を得ることは――。
「救いに――なるのかもしれない……?」
小さく呟き、彼女は慌てて口元を押さえた。
〈蝿〉は敵なのだ。
情のような気持ちを抱くべきではない。
彼の『生』は、できるならリュイセンに――それが無理な場合にはタオロンに、幕を下ろしてもらう。
それで、終わり。今晩、決着をつける。
だからメイシアは、二度と彼に会うことはない……。
彼女はそう結論づけ、この情報を心の奥に封印した。
けれど、口の中には、なんともいえない苦さが残り続けた。
リュイセンが運んできてくれた昼食は、腕の良い料理人の作であるにも関わらず、砂を噛むような味しかしなかった。
会話のない、事務的な食事は短時間で終わり、再び、リュイセンが部屋を出ていく。
メイシアは、エレベーターが地上まで降りたのを確認すると、部屋を移動し、ベッドの隙間から携帯端末を取り出した。滑らかに動かぬ指先をもどかしく思いながら、ルイフォンへと電話を掛ける。
一刻も早く、彼の声を聞きたかった。
あの優しいテノールに、身を委ねたかった……。
6.障壁に穿たれた穴-1

時は少し遡り、メイシアが〈蝿〉に首を絞められたのと同日の朝――。
ルイフォンは、仕事部屋の机の上で目を覚ました。
〈七つの大罪〉のデータベースへの侵入がうまくいかぬまま、作業の途中で倒れるように眠りに落ちてしまったらしい。
貴重な時間を無駄にしてしまった――!
どっと冷や汗が出て、自分の顔が青ざめていくのをはっきりと感じる。
荒々しく携帯端末を取り出し、現在時刻を確認すると、朝食の時間が終わってから二時間が経過――というところだった。
ルイフォンは、癖の強い前髪をがりがりと掻き上げる。
よく見れば、彼が突っ伏していた机の上には『料理長に温かいものを用意してもらうから、起きたら連絡するように』とのミンウェイの書き置きが残されていた。
「……っ」
ミンウェイの奴、ここに来たのなら起こしてくれればいいのに――そんな言葉を呑み込む。
分かっている。昨日の昼間からずっと根を詰め続けている彼を、彼女は心配しただけ。力尽きて眠ったのなら、そっとしておくべきだと思っただけだろう。
むしろ、彼女には感謝すべきだ。
まだ腹の傷も癒えていない彼に『医者としては失格なんだけど』と言いつつ、協力してくれている。
それどころか……。
「……」
ルイフォンは唇を噛んだ。
今、彼がしている作業は、ミンウェイが『母親』のための肉体として用意されたクローンであるという『憶測』を、『事実』にするための証拠探しだ。いわば、ミンウェイが『作り物』であることを確定するための行為。
ミンウェイにとって、嬉しいことではないはずだ。
けれど彼女は、決して暗い顔を見せない。あろうことか、ルイフォンに『ありがとう』とすら言ってきた。――『父親』の取ってきた態度に納得できたから、と。
まるで憑き物が落ちたかのように、彼女は自然に笑うようになった。
すべてをあるがままに受け入れた。だから、もう何も怖くない。そんな、しなやかな強さを身にまとう。
そして。
『リュイセンを取り戻したい』
切れ長の瞳が、熱く訴えかける。
「……リュイセン」
兄貴分の名を、ルイフォンはぽつりと呟く。
「お前は今、何をしている……?」
リュイセンは『やるべきだと思ったことを、やるだけだ』と言って、メイシアをさらっていった。そうしなければ、ミンウェイに『秘密』を教えると、〈蝿〉に脅されたのだろう。
あのときのリュイセンは、メイシアはセレイエに乗っ取られ、いずれ消えてしまうと〈蝿〉に思い込まされていた。だから、凶行に踏み切れた。
だが、今のリュイセンは、それは嘘だったと知っている――そう、メイシアから聞いた。
「お前は、どう動く……?」
生真面目で、責任感が強く、そして気高い兄貴分。彼が〈蝿〉の部下として、おとなしく収まっているとは考えられない。
まず間違いなく、メイシアを逃がそうと画策しているはずだ。
何より、ミンウェイを脅かす存在である〈蝿〉をリュイセンは許さない。
――お前も、〈蝿〉を殺そうとしているんだろ?
ルイフォンの豊かな表情が消え、端正で無機質な〈猫〉の顔になる。
立場を異にしながらも、目指すところは同じはずだ。
だが、リュイセンが単独でことを為した場合、彼はそのまま姿を消すだろう。そして二度と、一族の前にも、ミンウェイの前にも戻ってこない……。
「俺は、お前に選ばせてやる」
『鷹刀の後継者』と『ひとりの男』、どちらの立場で〈蝿〉を滅するのか。――一族に戻ってくるのか、否か。
兄貴分に選択肢を与えるために、ルイフォンは『憶測』を『事実』にする証拠を掴む。
行動すべきときには迷わない兄貴分が、まだ〈蝿〉殺害に及んでない以上、現在の彼には身動きの取れない事情があるのだと思う。
だから今のうちに。できるだけ早く――!
「待っていろ、リュイセン……」
あの菖蒲の庭園を思い描き、ルイフォンは、ぐっと虚空を見上げる。一本に編まれた髪が背中で踊り、毛先を飾る金の鈴が鋭い光を放った。
そして、それから――。
気持ちも新たに、モニタ画面に向き合い……、彼は作業再開の前に腹ごしらえをしようと思い直した。
昨日の晩は、ミンウェイが差し入れてくれたものを口にしたはずだが、意識が異次元に飛んでいたため、何を食べたのか記憶にない。そんな調子なので、彼の胃袋は激しく空腹を訴えていたのである。
ミンウェイに連絡するべく携帯端末を手に取り、ルイフォンは、はっと気づく。
メイシアからメッセージが届いていた。――それも、二通。
ルイフォンの邪魔にならないようにと電話は控え、昨日の晩と、今日の朝にそっと送ってくれたらしい。その気遣いを申し訳なく思うと同時に、彼の心は彼女への愛であふれかえった。
浮かれた指先がメッセージを開いていくと、どちらもルイフォンのことを心配した内容だった。彼女も心細いであろうに、そんなことは微塵にも感じさせない。むしろ、凛とした戦乙女の顔が垣間見える。
――私は、セレイエさんの――〈悪魔〉の〈蛇〉の記憶を持っているのに、専門的な『知識』は、私自身がちゃんと理解できていないと、うまく使いこなせないみたいなの。
侵入の役に立てなくてごめんなさい。
メッセージの中には、そんな文面が混じっていた。
謝るメイシアの言葉に、ルイフォンの心がずきりと痛む。
彼女は知らぬうちに『〈悪魔〉の〈蛇〉』にされてしまった。気丈に振る舞っているが、不安なはずだ。
そう――。
『〈冥王〉』と口にしたとき、メイシアの体を〈悪魔〉の『契約』が襲った……。
容態が落ち着いたあと、メイシアは、セレイエの記憶を得たことで判明した『デヴァイン・シンフォニア計画』についての情報を語ってくれたが、あのときの彼女は明らかに言葉を選んでいた。迂闊なことを言えば、命に関わると気づいたのだ。
『ルイフォンに隠しごとをしたくない』――そう言って、むき出しの心のまま、彼の胸に飛び込んできてくれるメイシア。なのに、秘密にしなければならないことができてしまった。どれほど辛いことだろう。
ルイフォンにとっても、それは同じだ。
直接、彼女に触れることのできないような、もどかしさ。まさに、今のこの現状とそっくりだ。
「…………っ」
悔しい。
踊らされている。
『デヴァイン・シンフォニア計画』は、異父姉セレイエが、殺された息子ライシェンを蘇らせるために組み上げたもの。
セレイエが、自分の子供のために必死であることは分かった。けれど、だからといって、メイシアを苦しめていいわけではない――!
――ルイフォン。
あなたは今、凄く焦っていると思う。
私のために、リュイセンのために、皆のために、どうもありがとう。大好き。愛している。
「メイシア……」
――侵入に関して、ひょっとしたら、〈悪魔〉だったイーレオ様を頼れるかもしれない。
王族の『秘密』に関することは『契約』に触れてしまうけれど、データベースについてなら問題ないはずだから。
ひとりで思い詰めすぎないで……。
イーレオには、既に相談していた。
しかし、イーレオが〈悪魔〉であった時代は、まだ研究報告書が電子データに移行する途中の段階で、門外漢の彼はデータベースについては何も知らなかった。
更に、実は〈ベロ〉を頼ろうともした。
『人の世に関わってはいけない』と断られるのを覚悟で会いに行ったのだが、そもそも〈ベロ〉は〈七つの大罪〉とは関係なくキリファが作ったものなので、データベースへのアクセス権はないと言われてしまった。
「国中に散ったという〈悪魔〉の残党なら、アクセスできるんだろうな……」
昨日から何度も侵入を試みて、思い知った。
〈七つの大罪〉とは無縁の、まったくの外部からの侵入は不可能とみて間違いない。あの強固な壁を崩すなら、なんらかの方法で内部の者と誤認させる必要がある。
「他の〈悪魔〉――か……」
ルイフォンは呟き、はっと息を呑んだ。
勢いよく立ち上がると、今まで座っていた回転椅子が後ろへと滑っていき、機械類の載った机にぶつかって派手な音を立てながら倒れた。
からからと空回りする車輪の音をあとに残し、ルイフォンは金の鈴を煌めかせ、仕事部屋を飛び出した。
「〈蠍〉の研究所跡に連れて行ってほしい――だと?」
沈着冷静な次期総帥エルファンも、唐突なルイフォンの発言には少なからず驚いたようだった。氷の美貌に大きな変化は見られないが、わずかに眉がひそめられる。
「ああ。〈七つの大罪〉のデータベースは、外部から闇雲に攻撃しても、まったく歯が立たない。内部の者と認識される必要があるんだ」
ルイフォンがエルファンの部屋に入ったのは、おそらく初めてだと思う。必要最低限のものしか置かれていない、えらく殺風景な空間だった。
ただ、ふたりの間に横たわるテーブルの上には、何故かインテリアよろしく、果実酒の空き瓶が置かれていた。繊細な、可愛らしいフォルムのそれは、鑑賞物だと思えば決して見栄えは悪くないのだが、どう考えてもエルファンのイメージではない。
そもそも酒豪の次期総帥が、どうして甘いだけの果実酒などを空けたのだろう……?
そんな疑問がルイフォンの頭をよぎったが、それも一瞬のこと。すぐに〈猫〉の表情に戻り、彼は畳み掛けた。
「だから、〈蠍〉の使っていたコンピュータからなら、そんなに苦労せずに〈七つの大罪〉のデータベースにアクセスできるはずなんだ」
〈蠍〉――ルイフォンの母キリファを身請けして、〈天使〉という人体実験体にした〈悪魔〉。
キリファの強すぎる〈天使〉の力を危惧した〈蠍〉は、研究と称して彼女を殺そうとした。それを事前に察知した彼女は、〈七つの大罪〉に否定的な態度を取る鷹刀一族に助けを求めた。これが、キリファと鷹刀一族との馴れ初めである。
「エルファンが、母さんを迎えに行ったんだろ?」
だから、〈蠍〉の研究所の場所を知っているだろ? そういう意味合いだった。
しかし、ルイフォンの言葉を聞いた瞬間、エルファンの氷の仮面に亀裂が入った。痛みをこらえるかのように顔が歪み、切なげに瞳が細められる。
「エルファン……?」
尻上がりに名前を呼んでから、ルイフォンは、しまったと思った。最近のエルファンにとって、母キリファの話題は地雷だった。
どうもエルファンとキリファは互いにずっと想い合いながら、すれ違っていただけのようなのだ。キリファの親友ともいえる人工知能〈ケル〉が、そんなことを匂わせて以降、エルファンはキリファの名に過剰な反応を示すようになった……気がする。
ルイフォンの内心の焦りを知ってか知らでか、当のエルファンは、ひと呼吸と置かずに、いつもの無表情に戻った。そして、揺らぎのない低音で応える。
「〈蠍〉の研究所は、キリファの羽が発した熱波で崩れ落ちた。今は廃墟だろう」
取るに足らぬ些細なことを告げるときの、つまらなそうな面倒臭そうなエルファンの口調。話は終わりだ、出ていけ、と目線をそらした横顔が無言で命じている。その必要以上の素っ気なさからは、キリファに関することには触れてほしくないとの本心が見え隠れしていた。
彼女と出逢った日のことを思い出しているのだろう。ルイフォンは、なんとなくそう察する。
しかし、ここで引くわけにはいかなかった。〈蠍〉の研究所は、時間の差し迫る中、やっと思いついた有力な手段なのだ。捨て置けるわけがない。
「待てよ、エルファン。それは短絡的だ」
「……」
ルイフォンの挑発的な物言いに、エルファンは横を向いたまま、鋭く睨めつける。
凍てつく怒気が『どういう意味だ?』と問いかけていた。無論、ルイフォンの計算通りだ。
「現場にいたエルファンがそう言うのなら、建物はなくなっているんだろう。けど、〈蠍〉の研究テーマは〈天使〉。熱暴走への備えをしていたはずだ。――おそらく、地下がある」
自信ありげに、ルイフォンが口角を上げる。しかし、エルファンは相手にせずに受け流す。
「当て推量を言うな」
「いや、根拠はある」
予想通りの反論。故に、ルイフォンは即座に跳ねのけた。そして、猫の目をすぅっと得意げに細める。
「〈蠍〉は母さんの『師匠』だ。〈天使〉を研究する〈悪魔〉であると同時に、奴はクラッカーとしても一流だった。当然、それなりの計算能力のあるマシンを所有していたはずだ」
「……」
「〈ベロ〉や〈ケル〉のような、馬鹿でかくて重たい――つまり、地下に置かなければならないようなものを、だ」
〈ベロ〉や〈ケル〉といっても、今の場合は、光の珠の姿をした真の〈ベロ〉や〈ケル〉のことではない。ルイフォンが『張りぼて』と呼ぶ巨大なコンピュータのほうだ。
エルファンの眉が、ぴくりと動いた。
頭の切れる彼は、ルイフォンの言葉の正しさを認めざるを得なかったのだろう。けれど、吐き捨てた。
「……二十年以上も前のものが、動くわけないだろう?」
「まぁ、そうなんだけどさ」
実のところ、放置された機体がどうなっているかを考えると、過度な期待は禁物だった。それに動いたところで、スーパーコンピュータも二十年前のものともなれば、今の小さな携帯端末ひとつぶんの計算能力もない。どのくらいの作業ができるのやら。
それでも、〈蠍〉の研究所は、行き詰まっている現状を打破できるかもしれない、ひと筋の光明だった。こんなところで無駄な議論をしているくらいなら、行動すべきなのだ。
「ま、いいか。親父に訊いてみる」
〈蠍〉はキリファに通ずるため、エルファンに話を訊くのが筋だと思ったのだが、それで機嫌を損ねたのなら余計な気遣いだったようだ。
ルイフォンとしては、研究所の場所さえ分かればよいのだ。イーレオでも、チャオラウでも、他を当たればいい。このところ、エルファンが親身になってくれていたので物寂しくはあるが、仕方ない。
――母さんと出逢った、思い出の場所だから行きたくないんだろ?
それは、声に出して尋ねるべきことではない。
ルイフォンがソファーから立ち上がり、踵を返そうとしたときだった。
〔エルファン、行ってあげて! ……お願い〕
唐突に、澄んだ少女の声が聞こえてきた。
清らかな川のように透明で、けれど、水しぶきを上げる急流が如き勢いで……。どこからともなく流れ込んできた叫びは、祈るような響きをしていた。
「誰だ!?」
エルファンの一声が、空を薙ぐ。
鋭い眼光が部屋を巡った。武人たる彼が、まるで気配を感じられずに至近距離で声を掛けられたのだから、当然だろう。
一方ルイフォンは、どこかで聞いた声だと必死に記憶を探っていた。そこに、新たなる声が更に割り込む。
〔あらぁ、ちょっと〈ケル〉、それは少し、干渉しすぎじゃなぁい? それに鷹刀の屋敷は、お前の管轄じゃないでしょう?〕
〔〈ベロ〉様! す、すみません……!〕
「っ!」
ルイフォンは短く息を吸い、弾かれたように自分の携帯端末を取り出した。……が、何も異常はない。
「……え?」
てっきり、人工知能の――真の〈ケル〉と〈ベロ〉に端末を乗っ取られたかと思ったのだが……、彼は狐につままれたような顔で首をひねる。
〔で、ですが、〈ベロ〉様。ルイフォンは、こうと決めたら引かない子です。――彼はもう、イーレオに場所を訊いて出掛けるつもりでしたから、『人の世に関わった』ことにはならないかと……〕
〔ルイフォンが『あれ』を見つけることは、確定した未来でいいわぁ。けど、そうじゃなくて、せっかくルイフォンが誘ってくれているのに、意地になって引き籠もるエルファンは放っておかなくちゃ駄目でしょう?〕
不意に、エルファンが立ち上がった。
彼も、この声の主が誰だか気づいたのだろう。奥にある書き物机まで大股に行くと、自分の携帯端末を持って戻ってきた。
案の定だった。
エルファンの端末から、意地悪く微笑むような声が流れてくる。
〔帰ってきたルイフォンから『あれ』の話を聞いて、夜中ひとりでこそこそ出掛ける、見栄っ張りのエルファンを盗撮する楽しみがなくなるじゃない?〕
〔〈ベロ〉様……〕
眉間に皺を寄せ、エルファンは渋面で押し黙る。
ルイフォンからすると、冷酷と恐れられる次期総帥が、言われっぱなしでおとなしくしているのは不可思議なのだが、エルファンは〈ベロ〉に絶対服従である。どうやら〈ベロ〉のもととなった、生前の『パイシュエ』との力関係が原因らしい。
「〈ベロ〉様、〈蠍〉の研究所跡に何かがあるんですね?」
〔さぁ? 私からは、なんとも言えないわぁ〕
笑いを含んだ声で、〈ベロ〉がしらばっくれる。
だが、答えは明白だった。
そもそも、〈ケル〉と〈ベロ〉が会話をしようと思ったら、音声で喋る必要はない。『彼女』たちなら、瞬時に情報交換ができる。
つまり、ふたりは、ルイフォンとエルファンにわざと聞かせているのだ。
そして、暗に告げている。
『〈蠍〉の研究所跡に行け』――と。
「……?」
ほんの少しだけ、ルイフォンは違和感を覚えた。
彼は、エルファンが同行してくれなくても、ひとりで出掛けるつもりだった。そこに、〈ケル〉と〈ベロ〉が乱入してきた。
――つまり、『エルファンが』そこに行くことに意味がある……?
「ルイフォン」
思索の海に潜りそうになっていたルイフォンを、感情の読めない低い声が引き戻す。
「〈蠍〉の研究所跡に行くぞ」
「エルファン!?」
ふと気づけば、双刀を腰に佩き、武装を整えたエルファンの背中が部屋を出るところであった。
6.障壁に穿たれた穴-2

出掛けると決まってから十数分後には、車で屋敷を発っていた。
そこに至るまでの間、エルファンは、いち早く運転席で待機しながら、無表情に腕時計の針の動きを目で追っていた。
寝起きだったルイフォンは今更のように顔を洗い、これから行く〈蠍〉の研究所で必要になりそうな荷物をまとめた。その途中で、ミンウェイがいい匂いのする包みを持って現れた。料理長特製の朝食だという。
「話は、エルファン伯父様から聞いたわ」
彼女もまた、一緒に行く気で満々らしい。小脇に医療用鞄を抱えている。まだ本調子でないルイフォンに、万一のことがあったらとの備えだろう。
「……」
ミンウェイの出で立ちに、ルイフォンは言葉を詰まらせた。
昨日行ったヘイシャオの研究室は、そこが昔、彼女の住んでいた家なのだから、案内として同行するのは当然といえた。しかし、今回は違う。
「私も行くわよ?」
「あ、ああ……」
ルイフォンの表情に何かを察したのだろう。ミンウェイのほうから強気に言われてしまい、彼は歯切れ悪く相槌を打つ。
……目の前で、『秘密』が解き明かされるのは、ミンウェイにとって残酷なことではないのだろうか?
そんなことを考えてしまう。
勿論、彼女の立ち会いの有無に関わらず、事実は変わらない。
けれど……。
「ほら、伯父様が待っているわよ」
素っ気ない言葉の中に含まれた、迷いのない意志。
彼女はルイフォンの頭をこつんと小突き、外に向かうべく身を翻した。緋色の衣服が光沢を放ち、波打つ黒髪から漂う優しい草の香りが彼を包む。
背中を押してくれる力強い手を感じた。
ミンウェイは微笑みながら、未来へと進んでいる……。
ルイフォンは、ぐっと拳を握りしめた。
「行くぞ……!」
彼は誰に言うともなく呟き、覇気に満ちた足取りで彼女のあとに続いた。
車の後部座席で、ルイフォンは朝食として渡された料理長特製の小籠包を口に入れた。猫舌の彼でも火傷しないよう程よく冷ました肉汁が口の中で広がり、全身にしみ渡る。一晩中、空調のよく効いた仕事部屋にいたためか、知らぬうちに体が冷え切っていたようだった。
「ミンウェイ」
不意に、運転席のエルファンが声を上げた。
ルイフォンの隣に座っていたミンウェイが、引き締まった表情で「はい」と応じる。どうやら重要な指示だと思ったらしい。
たまたまバックミラーが目に入っていたルイフォンは、エルファンがほんの少し困惑に眉を寄せたのに気づいた。
「……そんなに、かしこまるな」
氷の面を前に向けたまま、エルファンが低い声を落とす。どことなく危うげな、ためらうような響きだったが、ハンドルを握る手は安全運転を心がけているようで、その点だけは心配なさそうだった。
ミンウェイは、きょとんと首をかしげた。ルイフォンもまた、不審げに目を眇める。
「お前も知っての通り、二十数年前、私はキリファを迎えるために〈蠍〉の研究所に赴いた」
ほんの少し、エルファンが下を向く。バックミラーに写る角度がわずかにずれ、彼の顔はルイフォンからは死角になる。
「〈蠍〉は、ヘイシャオと面識があったらしい。私を見て『〈蝿〉とそっくりだ』と言った」
単調なようでいて、どこか深く沈んだエルファンの声。
ミンウェイは、切れ長の目をぱちぱちと瞬かせた。エルファンの意図を読みかねてるらしい。それは、ルイフォンも同じだった。
そんなふたりの様子は、後ろを振り向かなくとも、エルファンなら気配で察していただろう。けれど、彼はそのままの調子で続けた。
「もしも、あのとき、『ヘイシャオは、どうしているのか』と〈蠍〉に問うていれば、ヘイシャオが道を誤り、お前に身代わりの人生を強いるよりも前に、私は『お前たち、ふたり』を鷹刀に連れてこられたのかもしれない。……すまなかった」
「伯父様……」
ミンウェイの声が、かすれた。
彼女の年齢から推測すると、エルファンが〈蠍〉の研究所を訪れたのは、ヘイシャオが妻を亡くし、『娘』を育て始めてから少し経ったころになる。エルファンが悔やむのも無理はなかった。
「妹は病で死に、ヘイシャオはあとを追ったものと私は考えていた。だから、そんな話は聞きたくなかった。……臆病だったのだな」
「伯父様!? そんな、臆病だなんて……!」
ミンウェイが慌てて否定を口走る。その声を掻き消すように、エルファンは言葉をかぶせた。
「いや。私はどうしようもなく、愚かな人間だよ」
静かな低音が、吐き出されるように漏れてくる。
「あいつとは袂を分かったのだ。別の道を選んだあいつの意志を尊重してやろう。――そんな考えは、驕った思い違いだった。……そうだろう? ルイフォン」
「!?」
唐突に名を呼ばれ、それまで、ふたりの会話――主にエルファンの謝罪の邪魔をしてはならぬと聞き流しつつ、食事に専念していたルイフォンは、思わず小籠包を喉に詰まらせそうになった。
気づけば、エルファンの氷の瞳が、バックミラー越しにルイフォンの猫の目を捕らえている。
「エルファン……?」
口の中のものをなんとか飲み込み、ルイフォンは呟く。
「ルイフォン。私は、お前に余計なことを言った。すまない」
「『余計なこと』って、なんだよ?」
ルイフォンは、探るように尋ねる。
「メイシアをさらっていったリュイセンに対して、私は『あいつは『裏切った』のではない。『袂を分かった』のだ』と言った」
「え……? それが何か……?」
その言葉によって、ルイフォンは、リュイセンがミンウェイのために凶行に及んだのだと気づかされた。大事なひとことだったように思う。
「どんなに言い方を飾ろうと、私の言葉は『リュイセンを見捨てろ』という意味にしかならんだろう? ――私が、ヘイシャオを見捨てたのと同じように」
ミラーに映るエルファンの顔は、彼らしくあるのなら、相変わらずの無表情であるべきだった。しかし、斜め上からの角度のせいか、ルイフォンには切なげに自嘲しているように見えた。
ルイフォンが戸惑いに声を失っている間にも、抑揚に欠けた声が重ねられる。
「お前は今、リュイセンに手を差し伸べようとしている。私にはできなかったことを為そうとしている。……だから、私の言葉は余計だった」
「エルファン、それは違う!」
ルイフォンは、ぐっと身を乗り出した。その勢いに、彼の背中で金の鈴が跳ねる。
「俺は、エルファンにああ言われたから、リュイセンにはリュイセンの想いがあると納得できた。あのときの俺は、メイシアを奪われた怒りで頭がいっぱいで、だから、エルファンと話すことで冷静になれた。あのひとことは必要だった」
彼は一気に言い抜け、そして、ひと呼吸だけ置いて……吐き出す。
「――それに、俺だって、一度はリュイセンを切り捨てた……!」
ルイフォンは、そんなに褒められた人間ではない。
ここまで、ひとりで来たわけではないのだ。
「リュイセンを救いたいと言い出したのは、ミンウェイだ。それから、メイシアやハオリュウ、ファンルゥも……」
皆がリュイセンを求めた。
リュイセンと共に在りたいと願った。
声を震わせるルイフォンに、ミンウェイも口を挟む。
「最初に働きかけてくれたのは、緋扇さんです」
「――緋扇シュアンも、なのか……」
仲が悪いはずの相手の名前まで出てきて、さすがのエルファンも驚きを隠せなかったようだ。
シュアンが動いたのには、多分にミンウェイの存在が大きいと思われるが、それでも心底、嫌っていたのなら放っておいただろう。エルファンは言葉の途中で絶句し……やがて、普段の彼からは信じられないような柔和な笑みをふわりと浮かべた。
「リュイセンは『人』に恵まれたな。……いや、あいつが『人』に篤いからか」
誰に語るわけでもなく、エルファンは独り言ちる。
「エルファン?」
ひとりで納得したようなエルファンに、ルイフォンは遠慮がちに説明を促す。
「いや、なんでもない。ただ……」
「ただ?」
「リュイセンは案外、いい総帥になるかもしれんと思っただけだ」
そう言うと、エルファンは話を打ち切った。あとは黙々と、正確無比に運転を続ける。
だから、彼の心の内の呟きにルイフォンが気づくことはなかった。
それは、決して届かない懺悔であり、睦言であり――。
『私が、もう少しだけ他人に優しくできたなら……。…………なぁ、キリファ?』
「この近くだ」
エルファンがそう言ってから、数分後のことだった。
それまで安全運転だった彼が、突然、急ブレーキを掛けた。
「なっ!?」
道路との摩擦にタイヤが軋み、甲高い悲鳴を上げた。
強烈な負の加速度が押し寄せ、慣性に乗っていたルイフォンの体が浮き立つ。
「お、おい! エルファン!?」
車の停止と同時にルイフォンは叫んだが、エルファンは何も言わずにシートベルトを外し、神速の勢いで車外へと飛び出した。
ただならぬ様子に、ルイフォンも慌てて、あとを追う。
荷物の中の機械類の破損が気になるが、確認している場合ではないだろう。小籠包を食べ終えていたことは幸いだった。
エルファンは、来た道を一心不乱に戻っていた。腰に佩いた双刀は、それなりの重量があるだろうに、まったく重さを感じさせない走りである。
このあたりは貴族の別荘地になっているらしく、家はまばらで、人の気配もなかった。そんな閑静な地の真ん中に、ぽつんと取り残されたような一軒の家の前で彼は立ち止まった。そして、生け垣の外から庭を覗く。
その瞬間、エルファンは呆けたように口を開き、氷の瞳もまた見開いた。
いつもは無表情な美貌を驚愕で染め上げ、その家を見つめたまま、彼は彫像のように微動だにしない。南風に舞い上げられた髪だけが自由気ままで、漆黒の中に紛れた白いものが陽光を浴びてきらりと光った。
「キリファ……?」
唇の動きが、その名をかたどる。
音未満のそれは、誰の耳にも届かず、だから、やっとのことでエルファンに追いついたルイフォンは、ただ家を指して「ここなのか?」と尋ねた。
「ああ……」
肯定の返事に、ルイフォンも並んで、その場所を見る。
廃墟となった研究所跡のはずだった。熱波で崩れ落ちたとの話なので、瓦礫の中から地下への階段を探すことになると思っていた。
しかし、目の前にあるのは、広い庭を持つ、こぢんまりとした屋敷。長いこと手入れをされていないようで、荒れ放題ではあるのだが、それでも二十年以上、放置されたものとは思えない。せいぜい数年といったところである。
「建て替えたのか……。……知らなかった。だから、通り過ぎてしまった」
エルファンが呟く。そして彼は、迷うことなく門扉があるであろう表側に回ろうとした。
「待てよ、エルファン! 建て替えられているのなら、〈蠍〉が死んだあと、〈七つの大罪〉の関係者がここを管理――監視している可能性がある。迂闊な行動は危険だ」
道をふさぐように、ルイフォンは立ちふさがる。
だが、エルファンが足を止めたのは、ルイフォンに行く手を阻まれたからではなく、彼の発言を論破するためだった。
「この家はキリファが建てたものだ」
そんなことも分からないのかと、氷の微笑が冷酷に見下す。しかし、わずかに緩んだ頬が、どこか得意げでもあった。
「俺も、その可能性は高いと考えている。だが、確証がないうちは……」
「庭の桜。――彼女が好きだった花だ。そして、その根本にあるベンチに杖を立て掛ける用のフックが付いている。義足と杖と、彼女は両方、使っていたからな」
「……あ」
言われて見てみれば、エルファンの言う通りだった。
「そもそも、この家は〈ケル〉のある家に酷似している。お前が生まれ育った、あの家だ」
「!」
ベンチもフックも、あの家にあるものとそっくりだった。荒れていたために、すぐには気づかなかった。――なんとも情けない。
「〈ケル〉の家は、私がキリファの好みに合わせて設計した家だ。私が間違えるはずないだろう?」
エルファンがそう言い残して門に向かおうとしたとき、背後から車のクラクションが響いた。振り返ると運転席の窓がすっと開き、中からミンウェイが声を張り上げる。
「ちょっと、ふたりとも! そのまま行くなら、行くと言ってよ! 私はひとりで待ちぼうけだったのよ!」
そして、改めて三人で門へと向かう。
門扉には、ルイフォンにとってお馴染みの認証システムが仕掛けられていたが、難なく通り抜けることができた。
それは当然のことといえた。
何故なら、〈ケル〉と〈ベロ〉が、〈蠍〉の研究所跡に行くようにと勧めていたのだから――。
6.障壁に穿たれた穴-3

〈蠍〉の研究所跡に密かに建てられていたその家は、間違いなくキリファが用意したものであった。
門扉に仕掛けられていた認証システムをすんなり通過できたことが何よりの証拠であるが、中に入ったルイフォンは、一瞬、呆気にとられたのちに微苦笑を浮かべた。屋内の造りが、ルイフォンの生まれ育った、〈ケル〉のある家とそっくりだったのだ。
閉鎖されていた空間はかび臭く、床は黒ずみ、壁は日に焼け、電灯からは蜘蛛の巣が垂れ下がっている。しかし、見慣れたこの間取りは、見間違えようもない。
「あの家の図面をそのまま使ったな」
ルイフォンが思ったのと同じことを、エルファンが口にした。
「だよな? まったく、母さんのこだわりなんだか、手抜きなんだか……」
そう軽口を叩き、ルイフォンは、はっと顔色を変える。
――母は、〈ケル〉のある家と同じ構造の家を建てた。
なんのために?
「……地下だ」
ルイフォンの口から、かすれたテノールがこぼれた。
全身が緊張で満たされ、冷や汗が落ちる。
激しく脈打つ心臓を押さえ、ルイフォンは地下に向かって……。
「待ちなさい!」
ひらりと舞った緋色の影に、行く手を阻まれた。
「ルイフォン! 今、走ろうとしたでしょ! あなたはまだ怪我人なのよ! 自覚しなさい! さっきも、車からいきなり飛び出しちゃうし、傷が開いたら……!」
「それどころじゃないんだ!」
眉を吊り上げるミンウェイに、ルイフォンは噛み付くように言い返す。
そのとき、ふたりの脇を神速の風が走り抜けた。
ルイフォンから一瞬遅れ、エルファンもまた気づいたのだ。
「ちょっ!? ちょっと、エルファン伯父様まで!?」
すれ違いざまにちらりと見えた横顔は、氷の美貌をかなぐり捨て、動揺に掻き乱された必死の形相。床に足を付けるたびに勢いよく埃が跳ね、点々と残されていく痕跡は尋常でない歩幅を示す。
広い背中は、あっという間に小さくなり、地下への階段へと吸い込まれていった。
「エルファン、待てよ!」
ルイフォンも、すぐさま追いかけようとして……。
「――っ。すまん、ミンウェイ」
ひとり、状況から取り残され、呆然としている彼女の姿に彼は思いとどまった。
よく見れば、彼女の顔は、うっすらと青ざめていた。いよいよ自分の『秘密』が事実として暴かれるかもしれないという場所に来て、冷静沈着なエルファンがあれだけ取り乱せば不安にもなるだろう。
まずは、きちんと彼女に説明をしておくべきだ、とルイフォンは反省する。
それに、先に行ったエルファンが落ち着くまで、少し待ってやったほうがいいかもしれない。――そんなことを考えていると、ミンウェイのほうからぽつりと尋ねてきた。
「ルイフォン、この家は、いったいなんなの……?」
「すまない。何も言わずに振り回して」
ルイフォンは、彼女を安心させるように柔らかに答え、そして、どこかで絶対に聞いているはずの〈ケル〉と〈ベロ〉を意識して言う。
「〈スー〉だよ。……ここは〈スー〉の家なんだ」
「〈スー〉? 〈スー〉って、〈ケル〉や〈ベロ〉と合わせて、何か凄いことができるようになるっていう――あなたのお母様が作っていたコンピュータのこと?」
ミンウェイの、実に分かりやすく簡略化された解釈に、ルイフォンは苦笑する。
彼としては、〈七つの大罪〉の技術の粋を尽くした〈ケルベロス〉には、もう少し大仰な表現を使ってほしい気がするのだが、ともかく、彼女の理解が早いのは助かった。
「そうだ。母さんが〈ケル〉の家とそっくりな家を建てたなら、まだ開発中だと言っていた〈スー〉がこの家にある、と考えるのが自然だろう?」
「なるほど。そういうことね」
ミンウェイは頷き、表情を和らげた。だが、すぐに違和感に気づく。
「でも、じゃあ、どうして『エルファン伯父様が』あんなに慌ててらっしゃったの?」
母が遺した〈スー〉が見つかれば、ルイフォンが興奮するのは当然といえよう。だが、『エルファンも』血相を変えた。――ミンウェイが不思議に思うのは、もっともだ。
「……ああ。それは……な」
ルイフォンは、ほんの少しだけためらった。
しかし、体の芯に力を込め、はっきりとしたテノールを響かせる。
「〈スー〉は……、母さん――なんだ」
ミンウェイは「え?」と声を漏らしたまま絶句し、切れ長の目を何度も瞬かせた。
そんな彼女に伝わるように、そして〈ケル〉と〈ベロ〉に語りかけるように、ルイフォンは静かに続ける。
「メイシアがさらわれた日、俺はエルファンと共に〈ベロ〉に会いにいった。そのとき、『〈ケルベロス〉は、人間の記憶を使って作られている』――と、〈ベロ〉に教えてもらった」
鋭く息を呑む音と同時に、ミンウェイの肩がびくりと上がった。閉塞感で満たされた室内に、彼女のまとう優しい草の香が広がる。
「母さんは、セレイエの〈天使〉の力を無効化するために〈ケルベロス〉を作り始めたそうだ。それがどんなに大変なことか、〈スー〉のプログラムをかじった程度の俺でもよく分かる。……母さんにとって、〈ケルベロス〉は絶対に完成させるべきものだった」
ルイフォンは目線を下げ、唇を噛んだ。無意識に握られた拳が、血の気を失うまで固く閉ざされる。
母の最期の瞬間。
彼女は挑発するような目で嗤い、自分の勝利を宣言していたように思う。
あの日の記憶は、多くは母によって改竄されてしまったけれど、形見となった金の鈴が『あの瞬間』の記憶を守ってくれた。――だから、間違いない。
「〈ケル〉の口ぶりからすると、母さんは自ら、先王に首を落とさせた。でも、〈ケルベロス〉が完成しないうちに、母さんが死ぬはずがないんだ。そもそも、あの自信過剰で、けど、口先だけじゃなくて実力も伴っていた母さんが、いつまでも〈スー〉を完成させなかったこと自体がおかしかった」
そう考えたら、答えはひとつしかない。
「つまり〈スー〉は、母さんの命と引き替えに完成するもの。――母さん自身が〈スー〉になるように設計されていた、ってことだ」
生粋の〈天使〉として生まれてしまった娘のために。
母は命を懸けて、娘を〈天使〉の呪縛から解き放とうとしていた。
そのことを〈ケル〉は知っていた。だから、『いずれその日が来ることは分かっていた。でも、それは『今』でなくてもいいはずだ』と、ルイフォンに語ったのだ。
そして、おそらく――否、間違いなく。
四年前、〈ケル〉が覚悟していたよりも早く、母が〈スー〉を完成させたのは、セレイエのためだ。ちょうどそのころ、セレイエの息子ライシェンが殺されたのだから。
母は、なんらかの方法でセレイエの力になろうとしたのだ。
……なんとも、母親らしい最期ではないか。
「エルファンも、俺と同じように考えたと思う」
今ごろ、彼は地下の小部屋で光の珠を見つけていることだろう。
けれど、その珠は何も応えない。
何故なら、ルイフォンがまだ母の『手紙』の解析を終えておらず、〈スー〉のプログラムを入力していないからだ。
「……っ」
ルイフォンは虚空を見上げ、猫の目を見開いた。
それから、ふっと息を吐く。肩が丸まり、いつもの猫背が強調され、母親譲りの癖の強い前髪が瞳に掛かった。
「……地下に行くのはやめだ」
「えっ!?」
話に聞き入っていたミンウェイの、艶のある美声が裏返る。彼女は当然、ルイフォンは地下に行くものと思っていた。
「俺は、〈七つの大罪〉のデータベースに侵入するために、ここに来たんだ。目的を間違えたら駄目だろ?」
「え、でも……」
「それに、俺はまだ、母さんから渡された『手紙』の解析を終えていない。そんな状態で、母さんの――〈スー〉の前には出られねぇよ」
彼はそう言って、猫の目を細める。
本心を言えば、何も反応がないのが分かっても〈スー〉に会いたいと思う。だが、口に出して言った通り、面目ないというのがひとつ。
そして、もうひとつ。
――エルファンと、ふたりきりの再会のほうがいいだろ?
「というわけで、俺たちは、上の部屋の端末から〈七つの大罪〉のデータベースに侵入だ」
好戦的に口角を上げ、ルイフォンは上階を示す。
「ミンウェイ。悪いけど、俺が作業を始めたら、待っている間に電話でもメッセージでもいいから、携帯端末でエルファンに連絡を入れてくれ。『地下はエルファンに任せた。俺は、上の部屋にいる』ってな」
勝手知ったる間取りであるため、端末のある部屋の見当はついている。
しかし、廊下を歩きながら、ルイフォンは一抹の不安を抱えていた。
ここには〈悪魔〉であった〈蠍〉のコンピュータが残されていると思っていた。だから、それを使って〈七つの大罪〉のセキュリティの壁を打ち破れると期待していた。
だが、実際にあったのは〈スー〉。――この目で確認はしていないが、地下に行ったエルファンが戻ってこないので、そう言い切ってよいだろう。
まだ目覚めていない、光の珠の真の〈スー〉と、ルイフォンが張りぼてと呼ぶ、巨大なコンピュータの〈スー〉が、ここにはある。
今回、ルイフォンが必要としているのは、侵入に利用できるコンピュータだ。
だから、張りぼてのほうの〈スー〉ということになるのだが、〈スー〉は〈七つの大罪〉とは関係なく、母のキリファが作ったものだ。兄弟機の〈ベロ〉からは侵入できなかったことを考えると、望みは薄くなるのではないか……。
〔あらぁ、ルイフォン。どうしたの? 浮かない顔ねぇ〕
出し抜けに、ルイフォンの携帯端末が高飛車な声を響かせた。まるで彼を挑発するように、ブルブルという不快な振動まで加わる。
「〈ベロ〉!?」
〔せっかく、〈スー〉を見つけたっていうのに、やせ我慢するしぃ〕
「な……っ!?」
思わず反応を返したのは失態だった。〈ベロ〉が、実に嬉しそうに哄笑を上げる。
もしも相手に実体があったなら、ルイフォンは詰め寄り、襟首を掴んで『黙れ!』と睨みをきかせただろう。
しかし、〈ベロ〉だ。
無視するしかない。そもそも、シャオリエと同じ人格なのだから、関わってはいけないのだ。
ルイフォンは黙って、携帯端末の電源を切った。
――が、無駄なことだった。
〔あああああ! いきなり切るなんて酷いわぁ! せっかく、いいことを教えてあげようと思ったのにぃ!〕
耳をつんざくような金切り声に、ミンウェイの携帯端末のスピーカーが音割れを起こす。驚いたミンウェイが慌てて音量を調整しようとしたが、乗っ取られてしまった端末は制御が効かなかった。
「な、何これ!?」
ミンウェイがおろおろしているうちに、今度は清らかな声が滑り込んだ。
〔〈ベロ〉様。今のは〈ベロ〉様が悪いです。あんなふうにからかえば、ルイフォンだって怒ります〕
〔あら、〈ケル〉。お前、ルイフォンの味方なの?〕
〔いえ。私は公平な意見として……〕
「――ミンウェイ。端末の電源を切れ」
ルイフォンは、冷ややかな眼差しで言い捨てた。
「え、でも、何か教えてくれるって……」
〔ルイフォンも、短気を起こさないでください!〕
ミンウェイの戸惑いに、〈ケル〉の叫びが重なり、それが更に続く。
〔あなたは基本的にはいい子なのに、どうして斜に構えた、無意味な格好つけばかりするんですか! 子供のころから、ちっとも成長していません!〕
「…………ミンウェイ、切れ」
〈ケル〉は、ルイフォンが生まれ育った家に『憑いている』ような『もの』だ。考えようによっては、〈ベロ〉以上に面倒臭い相手であった。
〔待ってください! ルイフォン、聞いてください。――大丈夫です、うまくいきます〕
早口に告げられた〈ケル〉の言葉に、ルイフォンは「え?」と呟く。
そして〈ベロ〉もまた、意地の悪い、思わせぶりなを台詞を吐いた。
〔〈スー〉は特別なのよぅ〕
くすくすと笑う音声の裏側に『要求』が見えた。ルイフォンは舌打ちをしてから、自棄になって叫ぶ。
「……俺が悪かった! だから、教えてくれ」
〔初めから、そう言えばいいのに。素直じゃないんだからぁ〕
いい加減にしろ! ――という言葉を呑み込み、ルイフォンはじっと耐える。その甲斐あってか、〈ベロ〉はすぐに話を進めてくれた。
〔キリファが〈ケルベロス〉を作った目的は覚えているわね〕
「『〈冥王〉』の破壊――だろ?」
ルイフォンはそう答え、探るように付け足す。
「『〈冥王〉』なんて言われても、俺にはなんだかさっぱりだ。……けど、王とか〈七つの大罪〉にとっては重要な『何か』――だったな?」
〔ええ、そう。私が口にすれば『契約』に抵触する『それ』は、〈七つの大罪〉と密接な関係がある。――言い換えれば、〈ケルベロス〉が目的を達成するためには、〈七つの大罪〉にまったく接触できないような状態では、お話にならない、ってことよ〕
「――!」
ルイフォンの目が大きく見開かれ、希望に輝く。そこに〈ケル〉がそっと補足してくれた。
〔キリファは〈蠍〉の遺産をもとに〈スー〉を作ったんです〕
「――なるほど。ありがとな!」
先ほどまでの不機嫌をすっかり忘れ、ルイフォンは抜けるような青空の笑顔を浮かべた。
よく考えれば、〈ケル〉と〈ベロ〉が出てこなくても、実際に侵入を試してみれば分かったことかもしれない。けれど、ふたりはわざわざ、ルイフォンの背中を押しに来てくれたのだ。
〔あとは、お前の技倆次第よ。せいぜい頑張りなさいね〕
「ああ、任せろ!」
〈ベロ〉の声に、ルイフォンは胸を張る。反らせた背中の上で、金の鈴が踊る。
〔ルイフォン。……エルファンをここに連れてきてくれて、ありがとう〕
〈ケル〉は、エルファンに対して罪悪感を抱いていた。仕方がなかったとはいえ、キリファの死の瞬間を見せたことで、ずっと苦しんでいた。
「こっちこそ、ありがとな」
――きっと、母さんも喜んでいるから……。
そして――。
〈七つの大罪〉のデータベースに侵入するにあたり、何も障害がなかったわけではない。
だが、今までの苦労からすれば些細なもので、あれだけ強固に思えたセキュリティの壁は、ルイフォンの手によってあっけなく穴が穿たれた。
興奮を帯びたテノールが、鋭く響き渡る。
「ミンウェイ! ヘイシャオの報告書を手に入れた。――一緒に見る……で、いいよな?」
力強く放たれた叫びは、しかし途中で勢いを失い、語尾は消え入るようにかすれていた。
6.障壁に穿たれた穴-4

『ミンウェイ! ヘイシャオの報告書を手に入れた。――一緒に見る……で、いいよな?』
――そう言って回転椅子を半回転させ、後ろを向いたルイフォンが目にしたのは、ぎこちない動きで唾を嚥下した、ミンウェイの白い喉だった。
ルイフォンの仕事部屋と同じく窓のないこの部屋は、自然光は入ってこないものの、電灯によって充分な明るさが確保されている。だから、彼女の頬が青白く見えるのは、決して彼の気のせいではないだろう。
そしてまた、ルイフォン自身も同じ顔色をしていた。――彼のすぐ前にある、モニタ画面の反射のせいではなく。
彼らの間を占めるのは、空調からの送風音と、機械類の低いうなり。
ミンウェイの唇が動いたが、声にはならない。
それでも彼女はゆっくりと、しかし間違いなく頷いた。その証拠に、柔らかな草の香りが漂う。
ルイフォンは、モニタの近くに椅子を寄せるよう彼女を促し、緊張に震える指先でヘイシャオの報告書のファイルを開いた。
――――…………。
「ルイフォン、この部屋か?」
扉の開く音と共に、廊下からの自然の風と、エルファンの低い声が流れ込んできた。
「やはり、ここだったか」
探していた背中を認めたエルファンが、独り言つように呟く。彼は、そのまま歩を進めようとして……、途中で足を止めた。
ルイフォンの後ろ姿に、崩れ落ちそうな危うさを感じたのだ。丸い猫背はいつものことだが、あの過剰なまでに自信に満ちた覇気が消えていた。
「ルイフォン……?」
エルファンの呼びかけに、ルイフォンは回転椅子をきしませ、ゆっくりと振り返った。
そして、母親譲りの癖の強い前髪の隙間から、これまた母親そっくりの猫の目でエルファンを見上げる。
「――エルファン。……地下は、もういいのか?」
ルイフォンの硬質な声には、感情が載っていなかった。その表情は、無機質な〈猫〉の顔つきとは微妙に異なり、言うなれば、放心したような顔だった。
エルファンは、とりあえず「ああ」と応じたものの、胸中で困惑が渦を巻く。
しかし彼は、まずはルイフォンが気になっているであろう、地下の様子を報告することにした。てっきり後ろから追いかけてくるものと思っていたふたりが、上階で侵入作業をすると連絡を寄越してきて、ばつの悪さと同時に、彼らの気遣いを感じていたのだ。
「ルイフォン、地下には巨大なコンピュータがあり、奥の小部屋には光の珠があった。珠は〈ベロ〉様のような強い光は発せず、眠るように静かに、ほのかな光を灯していた」
「そうか。……ありがとう」
素っ気ないまでに簡潔なエルファンの物言いに、かえって彼の深い想いを感じ、ルイフォンは口元をほころばせた。それを契機に、彼の顔にいつもの鮮やかな表情が戻ってくる。
「ま、俺が『手紙』の解析を終えていないんだから、そうなるよな。……けど、〈スー〉はここにいる。母さんが――な」
「……ああ」
氷が溶けたような温んだ面差しで、エルファンが頷く。
ルイフォンは、そんなエルファンに微笑を向け、それから、心を落ち着けるようにすぅっと息を吐きだした。
彼のまとう雰囲気が〈猫〉のものへと変わっていく――。
「俺のほうの報告をする」
近くの椅子に座るようエルファンに目線を送り、ルイフォンはモニタと向き合うべく、回転椅子を回す。背中で一本に編まれた髪が、それまでの空気を掻き消すかのように薙ぎ払われ、毛先を留めた飾り紐の中央で金の鈴が煌めいた。
そして彼は、報告書のファイルで埋め尽くされた、モニタ画面をエルファンに示す。
「こちらは〈七つの大罪〉のデータベースへの侵入に成功した」
「――!?」
はっきりと告げられた声に、エルファンが彼らしくもなく驚きもあらわに瞳を瞬かせた。
ルイフォンと――それから、先ほどから身じろぎひとつしないミンウェイの様子から、良くない知らせが来ると思っていたのだろう。
ならば何故、ふたりの様子が浮かないのか。
無表情なはずのエルファンの顔に、ありありと疑問が描かれる。
それはルイフォンの予想通りの反応で、だから彼は間髪を容れず、「結論から言う」と鋭く続けた。
「俺が求めていたような証拠は、存在しない」
「――存在しない……?」
訝しげに眉を上げながら、エルファンが言葉を繰り返す。
「ああ。ヘイシャオが、妻のために『病の因子を排除した、健康なクローン体』を完成させたのは真実だ。その報告書は見つかった。――けど、『育てている娘が、妻のクローン体であること』を示すものは、どこにもない。ヘイシャオが書面に残さなかったんだ」
そのとき、ルイフォンの隣でミンウェイがしゃくりあげた。
彼女は耐えるように口元を押さえ、肩を震わせる。けれど、話を続けようとしたルイフォンを制し、「私に言わせて」と潤んだ瞳で訴えた。
ルイフォンは黙って頷き、場を譲るように体を引くと、ミンウェイの細くかすれた声が言を継いだ。
「お父様は、私を研究対象にしたくなかったんです」
伏せられた切れ長の瞳の端から、透明な光がすっと流れた。
「普通の娘として……、私を育てようとしてくれたんです」
そこまで言うと彼女は草の香を漂わせながらうつむき、堪えきれずに嗚咽を漏らし始めた。
ヘイシャオの『死者の蘇生』の研究は、彼の妻の死をもって終了となった。――少なくとも、ヘイシャオ本人はそのつもりであったし、報告書の提出によって義務も果たしたはずだった。
けれど〈七つの大罪〉は、この技術は有用だと判断し、続けるようにと命じた。
何故なら、ヘイシャオの研究とは、言い換えれば、こういうことだからだ。
『不治の病を抱えた人間に、健康な新しい肉体を提供できる』
移植用の臓器から不老不死まで、利用価値は無限にある。この技術が、魅力的でないわけがない。
〈七つの大罪〉は、妻での成功をもとに、他の病の人間にも適応できるよう更に研鑽を積むようにと、ヘイシャオに申し渡した。
そしてまた、彼が育てている『病の因子を排除した、健康なクローン体』について、成長しても本当になんの不具合も起きないのか、経過を観察し、報告するようにとも命じた。
「ヘイシャオは、〈七つの大罪〉に対し、『クローン体など育てていない』と返事をしたんだ」
泣き崩れたミンウェイに代わり、ルイフォンが続ける。
「勿論、嘘のはずだ。何しろ〈七つの大罪〉は、報告書と共に、ヘイシャオの記憶も提出させているんだから事実を知っている。けれど、ヘイシャオは『言いがかりです。どうしてもと言うのなら、私の記憶にそう書いてあったという証拠を、私に示してごらんなさい』と啖呵を切った」
提出された記憶が、どんな形状をしているのかは分からない。だが、少なくとも〈天使〉ではない、ただの人間であるヘイシャオに『示す』ことは不可能なのだろう。
真実を知っている〈七つの大罪〉に対して、たいした言い草だが、これは有効だったらしい。――というよりも、〈七つの大罪〉は、天才的な頭脳を持つヘイシャオの機嫌を損ねることは、不利益だと判断したのだろう。
「結論としては、〈七つの大罪〉が折れて、その件はうやむやになった。だから……」
ルイフォンの言葉に、エルファンが得心したと深々と頷く。
「だから、『育てている娘が、妻のクローン体であること』を証明するものは存在しない。――そう言い切れる、というわけだな」
「そういうことだ」
ルイフォンは、ちらりとミンウェイを見やり、奥歯を噛みしめた。
彼は、ミンウェイが『母親』のクローンであるという『憶測』を『事実』にする証拠を求め、ここまで来た。
けれど、証拠は存在しない。
ヘイシャオが、頑として残さなかった。〈七つの大罪〉に逆ってまでも……。
だから、リュイセンに証拠を示し、彼を解放するという、ルイフォンの目的を達成することはできない。
――けれど。
この結末は、決して悪くはないはずだ。
『ヘイシャオは、『娘』のミンウェイを〈七つの大罪〉の好奇の目から守った』という事実の証明なのだから……。
「お父様は、初めは、私を本当の娘として大切に育ててくれていたんです……!」
嗚咽の中から、ミンウェイが、か細くも強い声を張り上げた。
「私が『〈七つの大罪〉に加わって、お父様のお手伝いをしたい』と言ったときに猛反対したのも、私がクローンであることに感づいたりしないようにと……、私の心を守って……」
「そうだな。そうでなければ、あいつは蝶の鍔飾りのついた刀を封印したりしなかっただろう」
エルファンの低音が、彼女の言葉を受け止める。広く優しく、『父親』そっくりの声で。
「……でも、私が成長するにつれ、お父様は、お母様とそっくりな姿をしながらも中身の違う私に、戸惑い、耐えられなくなってしまったんです」
誰に言うともなく、ミンウェイが告げる。
彼女の『父親』の気持ちを代弁するかのように。
それは彼女の勝手な想像に過ぎないのだが、きっと正しいだろう。――そう信じたいと、ルイフォンは思う。
「私がクローンだと知っているお父様は、中身までお母様そっくりになってほしいと願ってしまったんです。『お前はミンウェイなのに』『ミンウェイのくせに』――よく、そうおっしゃっていました。……その言葉の意味、今ならよく分かります」
ヘイシャオと〈七つの大罪〉の関係は、結局、険悪なままだった。
データベースの記録からすると、どちらかというと、ヘイシャオのほうが〈七つの大罪〉を避けるような状態であったらしい。そもそも、妻のために〈悪魔〉となった彼には、妻を亡くしたら、〈七つの大罪〉に留まる理由がないのだ。
ほとんど研究を行わず、名ばかりの〈悪魔〉となった彼は、〈七つの大罪〉からたいした資金を得られなくなり、暗殺者として生計を立てた。
暗殺の対象が主に貴族だったのは、依頼主の多くが同じく貴族で金払いが良かったのと、〈七つの大罪〉が王に属する私設研究機関であることから、王族に連なる貴族で憂さ晴らしをしたかったためと思われる。
大切な『娘』に、自分の仕事を手伝わせたヘイシャオの心理は不明だ。
ひょっとしたら、妻にはできなかったことをさせることによって、妻と『娘』は違う人間だと認識したかったのかもしれない……。
「ルイフォン……! ありがとう……」
涙に濡れたミンウェイが、彼に頭を下げる。波打つ長い髪が揺れ、彼女の『母親』にはなかったであろう草の香がふわりと漂う。
「ごめん……、こんな顔で。……でも、先に進まなきゃ」
彼女は目元をハンカチで押さえ、鮮やかな紅の唇を上げて……笑う。――無理やりにでも力強く、華やかに。
「ねぇ、ルイフォン。結局、リュイセンに示せるような証拠って……、やっぱり、『ない』ってことなの? ……――本当に?」
「…………っ」
射抜くような切れ長の瞳に見つめられ、ルイフォンは声を奪われた。
『証拠は存在しない』
先ほどから何度も、そう言ってきた。
なのに彼は、答えることができなかった。
「あなたが求めていたような、証拠になる書類がなければ、それは『ない』なの?」
畳み掛けるようにミンウェイが尋ね、ぐいと詰め寄る。
ルイフォンは気圧され、思わず回転椅子ごと後ろに下がる。
「そんなの、可笑しいわ。お父様と〈七つの大罪〉のやり取りの記録を見れば、一目瞭然。どう考えたって、私はお母様のクローンでしょ? 病気なんてまったくない、完全に健康な――ね」
そして彼女は、自分の体を愛しげに掻き抱く。
「だから私は、心身ともに、こんなに丈夫でいられるの。嫌なことや辛いことがあっても、めげずに逞しく、しぶとく立ち直れる」
「ミンウェイ……」
「普通の人とは違う形だったかもしれないけれど、この命は、お父様とお母様からいただいた大切なものよ。恥じることも、気に病むこともないでしょ?」
艶やかな微笑みで、彼女は告げる。
「『私は、自分を誇りに思っている』――リュイセンに、そう伝えるのでは駄目なの?」
「……?」
「リュイセンは、私が傷つくのを恐れて〈蝿〉に従ったんでしょう? ならば、『私は大丈夫』って、彼に電話で言えばいいだけじゃない!」
「――!」
虚を衝かれた。
彼女の言う通りだった。
証拠にこだわっていた自分が、愚かしく思えてくる。
ルイフォンは、大きく見開いた猫の目を隠すように、癖のある前髪をがりがりと掻いた。そんな彼に見せつけるように、ミンウェイが胸を張り、鮮やかに咲き誇る。
「ね? そうでしょ!」
それは、まるで緋色に輝く、大輪の華。
彼は破顔して「ああ」と答えるしかない。
「なんか、俺……、空回りしていたな……」
清々しい気分で、溜め息混じりの苦笑を漏らす。
すると突然、ミンウェイが眦を吊り上げた。「何を言っているの!」と叫びながら、あっという間に彼の懐に入り、彼の鼻先を人差し指で押しつぶす。
「ふはぁっ!?」
「ルイフォンがここまで情報を引き出してくれたから、私が自分を誇れるようになったんじゃない! あなたのおかげよ。あなたがいなきゃ、こんなふうには思えなかったわ」
椅子から立ち上がり、片手を腰に当ててルイフォンを見下ろすその姿は、気高い女神のようであり――。
「……いつものミンウェイだ」
少し乱暴で、お節介で、お人好しの――大切な家族。
強気な切れ長の瞳を有する、優しげな美貌。ふわりと波打つ黒髪は、柔らかな草の香で、あらゆるものを穏やかに包み込む。
不意に、ルイフォンの胸の中から笑いがこみ上げてきた。
「な、何よ? 何が可笑しいのよ?」
急に大声で笑い出したルイフォンに、ミンウェイは一瞬ひるみ、それから噛み付いてくる。
けれど、彼は笑い続けた。
純粋に嬉しかったのだ。
今まで張り詰めていたものが、ふっと解け、心が軽くなった気がした。
「帰ろうぜ」
存分に笑ったあと、ルイフォンは憮然としているミンウェイに明るく言う。
「車の中で親父に報告を入れて、屋敷に戻ったらすぐに作戦会議だ。――リュイセンと話をつけるための、な」
唐突に頭を切り替えたルイフォンに、ミンウェイは勿論、今まで黙って見守っていたエルファンも唖然とし、やがて口元をほころばせた。
ヘイシャオの研究報告書を引き出した端末に終了処理を施すべく、ルイフォンは回転椅子を滑らせる。ミンウェイに圧され、モニタの正面から随分と離れてしまっていたのだ。
熟練のピアニストを思わせる手付きでキーボードを鳴らしながら、彼は言う。
「この会議には、メイシアにもリモートで参加してもらう。リュイセンを解放する役目は勿論、ミンウェイだけど、まずはメイシアに、リュイセンを電話口まで連れてきてもらわなきゃ始まらない。それに、やはりこういうときは、『皆で』だろ?」
彼が方針を述べている間にも、ミンウェイは素早く自分の携帯端末を取り出し、屋敷へと連絡を入れていた。
漏れ聞こえる声は、詳細はあとで報告するが、ともかく今から屋敷に戻ると。それから、三人分の昼食を用意しておいてほしいと伝えるあたり、抜け目がない。とはいえ、行きの車で朝食をとったルイフォンはともかく、あとのふたりはさぞかし空腹だったのだろう。
「エルファン」
モニタ上を流れていく終了メッセージを瞳に映しながら、ルイフォンは背後で同じものを見ているエルファンに声を掛ける。門外漢の彼には、このメッセージの意味は分からないであろうが、ルイフォンが帰り支度をしていることは理解しているはずだった。
「〈スー〉のプログラムの解析が後回しですまない。――母さんに……」
逢いたかったよな……?
そう言ったものか否か。迷っている間に、エルファンが先に口を開いた。
「〈ベロ〉様は、〈スー〉のことは後回しでよいと言っていただろう? ――それに、〈スー〉はキリファではない。〈ベロ〉様がパイシュエ様ではないのと同じだ」
先ほどは、〈スー〉をキリファだと認めたはずのエルファンが顔をしかめる。
「……ああ。そうだったな」
〈七つの大罪〉の技術は禁忌であり、人の世とは関わってはいけない。
少なくとも母はそう思っていたし、ルイフォンもそう思う。そして、エルファンもまた……。
だから、死んだ人間は生き返らない。
「――まぁ、でも。なるべく早く、解析を済ませるよ」
軽く言ったつもりのテノールは、無意識のうちに沈んでいた。
そのためだろうか。
エルファンが、彼らしくない穏やかな低音をそっと落とした。
「私は、〈スー〉に逢ったら訊いてみたいことがある。……頼んだぞ」
そして――。
屋敷に戻る途中の車の中で、ルイフォンの携帯端末の呼び出し音が鳴った。
表示された相手の名に、ルイフォンの心が浮き立つ。
「メイシアだ!」
〈蠍〉の研究所跡での大発見と、今後の方針について伝えようと思いながら、彼はうきうきと電話に出る。その直後、メイシアの悲壮な声が彼の鼓膜を打った。
『ルイフォン。緊急事態なの……!』
「!?」
『〈蝿〉が一週間を待たずに、私に自白剤を打つと言い出して、それで……』
「な、なんだと……! メイシア、大丈夫か!?」
『うん。あのね……』
震える声で告げられた〈蝿〉の研究室での出来ごとに、ルイフォンは拳を握りしめ、唇を噛んだ。口の中に鉄の味が広がる。
安心しきっていた自分に反吐が出そうだった。
メイシアはずっと、敵地にいたというのに……。
話を聞き終えたとき、ルイフォンの腹の底は〈蝿〉への怒りで煮えくり返っていた。しかし彼はぐっとこらえ、優しいテノールで告げる。
「メイシア、怖かっただろ? よく頑張ったな」
この声は、彼女の耳へと直接、届く。
だから、この口から出すのは〈蝿〉への罵倒ではなく、彼女への想いであるべきだ。
本当は、ひとりで耐え抜いた彼女を抱きしめたい。けれど、今はそれができないから、せめて言葉でだけでも、彼女を包み込みたい――。
刹那、電話口の向こうで、メイシアが堪えきれなくなったように泣き出した。
「メイシア!? どうした? 不安か? ――当たり前だよな、ごめんな」
『あ、ううん。ごめんなさい……! 違うの、大丈夫。――そうじゃなくて。ルイフォンが私の欲しい言葉をくれるから……、嬉しくて』
「え……?」
『泣いている場合じゃないのに……』
そんな呟きと共に、彼女が顔を拭う気配がした。
そして、そのあとに続いた声は、凛とした戦乙女のものだった。
『ルイフォン。状況が変わった場合には、すぐにタオロンさんに〈蝿〉の暗殺を依頼することになっていたと思う』
「あ、ああ」
確かにそう決めていたが、これからリュイセンと話をつけるための会議を――と、彼が続けるよりも前に、思い詰めたような彼女の声が畳み掛けた。
『それ、待ってほしいの! まず先に、リュイセンにすべてを打ち明けたい。――彼を諦めたくないの!』
「――!」
誰も彼もが、リュイセンを求めていた。
彼に帰ってきてほしいと。
ルイフォンは青空の笑顔を浮かべ、メイシアに告げる。
「大丈夫だ。心配は要らない。リュイセンのこと、そう言ってくれてありがとな」
『え?』
「リュイセンは戻ってくる。――絶対に」
そしてルイフォンは、〈蠍〉の研究所跡での出来ごとをメイシアに語り始めた――。
7.岐路で選り抜く道しるべ-1

〈蠍〉の研究所跡に行っていたルイフォン、ミンウェイ、エルファンの三人が、鷹刀一族の屋敷に戻ったのは、彼らを出迎えてくれた料理長の食事が『早めの夕食』ではなく、かろうじて『遅い昼食』と呼べるくらいの時間帯であった。
駐車場から食堂に直行し、蟹炒飯と雲呑スープで手早く腹を満たす。
このあとは、いよいよリュイセンと話をつけるための作戦会議である。
ルイフォンの胸は、否が応でも高鳴った。イーレオへの報告は、あらかじめ帰りの車の中で済ませておいたため、会議の内容は、ほぼ段取りの確認となる。
心地の良い緊張をまとい、わずかに大股で廊下をゆく。そして、執務室の扉を開けた瞬間、ルイフォンは「え?」と、戸惑いに足を止めた。
予想外の人物が、さも当然とばかりにソファーでふんぞり返っていたのだ。
「よう、〈猫〉。――話は聞いた。お手柄だったそうだな」
「シュアン!? どうして、ここに!?」
警察隊の緋扇シュアン――。
今の時間は、勤務中なのではないだろうか?
疑問を浮かべるルイフォンに、しかしシュアンは、こともなげに「イーレオさんから連絡を貰ったのさ」と言って凶相を歪めた。どうやら、本人としては笑いかけたつもりらしい。
「いくら親父が連絡したからって……」
凶賊とは犬猿の仲であるはずの警察隊の彼が、鷹刀一族の屋敷に出入りしていること自体は、もはや日常と化しているのでどうでもいい。けれど、今回の会議は単なる確認だ。本業を投げ打つまでして来る必要はないはずだ。
今日はたまたま非番だった、ということはないだろう。何故なら、いつもなら私服に着替えてくるところが、制服のままだ。職場から駆けつけたとしか思えない。
「お前たちの到着を待っていたぜ?」
早く来いよ、とばかりにシュアンが顎をしゃくると、ぼさぼさ頭を押し込めていた制帽が、こらえきれずにずるりと落ちた。
メイシアも交えてのリモート会議とするため、彼女の携帯端末に連絡を入れて回線を繋いだ。
画質は今ひとつで、動きも滑らかではないが、テーブルに据え置かれたモニタに彼女の花の顔が映し出されると、ルイフォンの心が華やいだ。
彼女のほうの画面は、残念ながらルイフォンの顔の大写しではなく、天井カメラからの映像だ。会議なので、執務室全体の様子が分かるようにしたのだ。だから彼は、上を向いて口角を上げる。
モニタ画面のメイシアが喜色を浮かべたのを確認すると、ルイフォンは「準備できたぜ」とイーレオに合図をした。
ひとり掛けのソファーで、優雅に頬杖を付いていたイーレオが、組んでいた足を解く。長身を正すと、艷やかな黒髪がさらりと背中を流れた。
一族の総帥たる威厳を示すかのように一同を睥睨し、それから魅惑の低音を朗々と響かせる。
「それでは、会議を始める」
そのひとことで空気の色が変わった。
ちょうどよいはずの室温も、ひやりと引き締まる。
「〈猫〉」
イーレオの王者の瞳が、ルイフォンを捕らえた。
「この場は、お前に任せるべきだろう。――鷹刀は、お前の指揮に従う」
「親父……っ、いや、鷹刀の総帥……、感謝する」
ルイフォンは深く一礼する。
そして、再び頭を上げたとき、彼の顔は端正で無機質な〈猫〉のものとなった。
「――皆、聞いていると思うが、俺は、先ほど〈七つの大罪〉のデータベースに侵入して、『俺が求めていたような証拠はない』ということをはっきり知った。だが、ミンウェイが呼びかけることによって、リュイセンを〈蝿〉の束縛から解放することが可能だと判断した。――よって、ミンウェイの電話による、リュイセンとの接触を試みる」
ちらりとミンウェイを見やると、彼女は冴え渡った切れ長の目をルイフォンに向けた。
「任せてください」
綺麗に紅の引かれた唇を弓形に上げ、彼女は高らかに答える。
「頼んだ」
ぴんと背筋を伸ばして前を向くミンウェイの姿に、ルイフォンの胸が熱くなる。辛い思いをさせたはずなのに、彼女の瞳は彼への感謝でいっぱいだった。
「それで、いつリュイセンと接触を図るか――だが、リュイセンはメイシアの世話係として、食事を運んでくるのが日課になっている。だから、次にリュイセンが部屋に来る夕食のときに、メイシアは携帯端末をこの執務室に繋いで、強引にでもリュイセンを出してほしい」
『分かりました』
ルイフォンが天井に向かって告げると、鈴を振るように美しい、しかし凛とした声が、間髪を容れずに返ってきた。
「……ごめんな、メイシア」
『え?』
唐突に、〈猫〉ではなく、いつものルイフォンの顔になった彼に、メイシアが目を丸くする。
「〈蝿〉は、『また明日、お前と話をする』と言ったそうだが、奴はいつ何をしでかすか、予測もつかない。明日を待たずに、今この瞬間にも、お前のところに押しかけてくる可能性だってある。……不安だろ?」
『ルイフォン、そんな……』
メイシアの表情が、くるくると変わる。
心配をしてくれるのは嬉しいけれど、今は会議中なのにと、思っているのが手にとるように分かった。実際、この場にふさわしい台詞ではないだろう。だが、彼のメイシアが危険に晒されているのだ。このくらい言わせてもらっても、罰は当たるまい。
「本当は、リュイセンがお前の部屋に来る夕食時なんか待っていないで、今すぐタオロンに頼んで、リュイセンに会いに行ってもらおうかと考えた。タオロンの携帯端末で、リュイセンと執務室を繋ぐんだ。――けど、リュイセンとの接触は、確実に邪魔の入らない、落ち着いた場所で行いたい。そう思うと、お前のいる展望室が一番、適している。それに、お前にも立ち会ってほしいから……」
『ルイフォン。……ありがとう。私なら大丈夫』
力強く微笑むメイシアに、ルイフォンは「ごめんな」と繰り返し、それから「ありがとう」と言い直す。
「万一を考えて、タオロンとは既に連絡を取ってある」
『え、ええと……?』
「こちらの状況を説明して、〈蝿〉の監視を頼んだ。〈蝿〉が予想外の行動をとったら、すぐに知らせがくる」
『いつの間に……?』
「さっき。車の中で、だ」
ルイフォンは簡潔に答えたが、タオロンは常に見張られているということだったので、実のところ、連絡がつくまでは気が気でなかった。
とはいえ、タオロンに関しては幸運が続いた。
メイシアの策で〈蝿〉から外出許可を取った際、タオロンがやたら と『手柄』を主張したため、〈蝿〉の態度が変わったのだ。タオロンのことは、締めつけるよりも適度に緩めたほうが扱いやすいと判断されたらしく、今では、まるで凶賊でいうところの幹部待遇だそうだ。
それに加え、タオロンの主たる仕事がメイシアを手に入れることであったため、彼女が囚われて以降、彼は待機状態であり、現在、〈蝿〉に言いつけられている用事はなかった。すなわち、自由に行動できると、なんでも任せろと言ってくれた。
だからタオロンは、ふたつ返事で〈蝿〉の監視を引き受けてくれた。
「〈蝿〉が、普段通りに夜まで研究室に籠もっているようなら、それでいい。……だが、もしも、俺たちがリュイセンと話をつけるよりも先に、〈蝿〉がお前に危害を加えるようなことがあれば……」
ルイフォンは、そこで一度、言葉を切り、ごくりと唾を呑み込んだ。
そして、一気に言い放つ。
「そのときは、リュイセンには構わず、タオロンに〈蝿〉を討ってもらう!」
『ルイフォン――!?』
メイシアの困惑の叫び。
彼女の顔が、見る間に蒼白に染まっていく。
執務室の空気も一転し、緊張を帯びた。……だが、誰しもが、ルイフォンの言葉を認めていた。
「最も優先すべきことは、メイシアを無事に救出することだ。――これは、絶対だ。譲らない」
猫の目を煌めかせ、ルイフォンが宣言する。
『……っ』
不鮮明なモニタ画面でも、メイシアの顔が悲痛に歪んだのがはっきりと分かった。
「メイシア。これは確率の低い『もしも』の話だ。単に、はっきりさせておく必要があるから言ったまでだ。……大丈夫だ」
ルイフォンは、掌を握りしめる。
この手は、画面の向こうの遥かな彼女に触れることはできない。あの黒絹の髪を、くしゃりと指で梳くことは叶わない。――けれど、それは今だけだ。
「あと数時間。それで、すべてを終わらせる」
『分かった。……信じる』
黒曜石の瞳が真っ直ぐにルイフォンを見つめ、桜色の唇が凛と告げた。
「ああ。俺も、信じている」
覇気に満ちたテノールで、ルイフォンはメイシアに言葉を重ね、言葉で彼女を包み込む。
信じる。――すべてがうまくいくと。
「リュイセンが『鷹刀の後継者』として、今晩、〈蝿〉に引導を渡す!」
あらゆる障壁を打ち砕く、ルイフォンの鋭い声が、この先の取るべき道を指し示す……。
――そのとき。
「ごほん」
胡散臭いほどにわざとらしい咳払いが、高揚した雰囲気を間抜けに崩した。
「――!?」
皆が驚き、音の発生源へと視線を送る。
場の注目を集めた先にあったのは、咳払いと同じくらいに如何わしい、悪人面の凶相――。
「シュアン?」
ルイフォンが名を呟くと、シュアンは、くいっと口の端を上げた。
「〈猫〉さんよ。ちょいと確認したいんだが、『引導を渡す』ってのは、要するに『殺す』だな?」
「ああ。――それがどうした?」
突っかかるような言い方に反感を覚えながら、ルイフォンは尋ね返す。しかし、シュアンは彼の問いかけには答えずに、耳障りな甲高い声で、歌うように唱えた。
「あの庭園で、リュイセンが〈蝿〉を殺す。――先輩と、先輩の家族を不幸に陥れた〈蝿〉が死ぬ。ハオリュウと、メイシア嬢の家族の仇でもある、〈蝿〉が死ぬ……」
シュアンは、血走った三白眼をうっとりと細め、低く嗤う。そして彼は、隣に座るミンウェイの耳元に、そっと囁いた。
「俺の悲願が、ようやく叶うな」
ミンウェイが、びくりと肩を上げ、草の香りを撒き散らした。
けれど、シュアンは構わずに――否、彼女を逃すまいとでもするかのように、血色の悪い唇を彼女の耳朶に寄せる。
「俺は職業柄、死体を見飽きている。だから、〈蝿〉の糞野郎の屍なんざ、特に見たいとも思わねぇ。それに、リュイセンが殺したと言えば、疑う余地もないだろう。――だから俺は、死体の確認は不要と思うが……、ミンウェイはどう思う? やはり運んできてほしいか?」
「……っ!?」
「それとも何か? 〈蝿〉が命乞いをする様を見てみたいか?」
悪相を歪め、シュアンはへらへらと体を揺らした。しかし、胡乱な三白眼は、凍りつくように冷たい。
「――だったら、リュイセンに頼んで、〈蝿〉を生かしたまま連れてきてもらわないといけねぇなぁ。――面倒臭そうだが……」
そう言いながら、シュアンは思案をアピールするかのように腕を組み、「ふむ」と眉を寄せた。
「こちらのカードは、鷹刀リュイセンと斑目タオロンか……」
「緋扇さん……! ――あなたは、いったい何を……」
不気味な笑みを浮かべたシュアンに、ミンウェイは得体の知れない恐怖を覚える。
「鷹刀リュイセンに斑目タオロンといえば、凶賊の次世代を担う若い衆として、警察隊のブラックリストにも載っている超大物だ。極悪な凶賊の双璧、鷹刀と斑目それぞれ随一の猛者が手を組んで、中年男ひとり捕まえられないなんてお粗末なことはないだろう」
「…………!」
「まぁ、俺は〈蝿〉の野郎が確実に死ねば、他はどうでもいい。あの野郎の顔も見たくなければ、言葉を交わしたいとも思わない。――『俺は』な」
鼻で笑うような、軽薄なシュアンの声。
最後のひとことが、あまりに大きく聞こえたため、ミンウェイは狂犬の牙に噛み付かれたのかと錯覚した。弾かれたように耳を押さえ、絹を裂くような悲鳴を上げる。
「やめてください!」
しかし、シュアンが言葉を止めることはなかった。
「俺の記憶違いでなければ、あんたは『〈蝿〉と決着をつける』と言っていた。『何が決着になるのか分からないが、とりあえず〈蝿〉と話をしたい』ってな」
「やめて!」
脅えたように、ミンウェイが身を縮こめる。そんな彼女をいたぶるように「いいのか?」と、シュアンの揶揄が襲う。
嗜虐心に酔ったようなシュアンに、ルイフォンは制止の声を上げようと鋭く息を吸った。――だが、堪えた。
途中から、シュアンの意図に気づいてしまったのだ……。
甲高いくせに、妙に静かなシュアンの声が降りてくる。
「オリジナルの父親は何も言わずに、あんたを置いて勝手に死んだ。臆病だったあんたも、何も言えないまま――永久の別れを迎えた」
ミンウェイが激しく頭を振る。
シュアンの言葉を振り払おうとでもするかのように。
まるで、子供が駄々をこねるような仕草を、ルイフォンは黙って見つめる。
「本来なら、それで終わりだった。何故なら、世界は不可逆だからだ。……なのに、なんの因果か、あんたには機会が訪れた。――奇跡だ」
「……」
「あんた、何も言えないままでいいのか? 〈蝿〉の顔も見ないまま……。本当に、それでいいのか?」
「……、……なんで……っ」
艶めく美声が裏返り、引きつれて惨めにかすれた。
「……なんで、そんなことを言うのよ……! もう、作戦は決まったじゃない! リュイセンが、すべてを終わらせる……。それで……いいでしょう!」
ミンウェイはシュアンに詰め寄り、彼の制服を掴もうとして……ためらった。だから、持て余した指先を折り曲げ、握りこぶしの形にして震わせる。
「……それに、〈蝿〉は、お父様じゃない! ただの『作りもの』……よ!」
「ま、それもそうだな」
シュアンは肯定した。
同意して、――それだけだった。
ミンウェイの反論に納得したから、引き下がる。
もはや、〈蝿〉への興味は完全に消え失せたと言わんばかりに、「話の腰を折って悪かったな」などと、ルイフォンに詫びまで入れる。
刹那。
ミンウェイの肩が、しゃくりあげるように跳ねた。シュアンの弁を言い返そうと、待ち構えていた唇が、たたらを踏んだようにわなないた。
もしもシュアンが、あとひとこと何かを言い続けていれば、ミンウェイは強い口調で『〈蝿〉になんて、会いたくない』と口にできただろう。はっきりと声に出して言うことで、心の奥底に眠る、名前の分からない感情を断ち切れたはずだった。
けれど、シュアンは引いてしまった。
ミンウェイの中で渦巻く、矛盾した、不可思議な思いを暴いておきながら。
封じられた、支離滅裂な思いの存在を、彼女に自覚させておきながら……。
ルイフォンは、奥歯を噛み締めた。
シュアンは、ミンウェイに言葉を掛けつつ、この場にいる皆に問いかけたのだ。
――このままリュイセンに〈蝿〉を討たせれば、ミンウェイは一度も〈蝿〉と会うことなく終わりを迎える。
それでいいのか……?
すっかり過去と決別し、まっすぐに未来を見つめるようになったミンウェイに、ルイフォンは安心しきっていた。けれど、今まで知らなかった『父親』の行動を知ったミンウェイが、『父親』の記憶を持つ〈蝿〉に対して、何も感じないはずがないのだ。
だが、『〈蝿〉に会ってみたい』『〈蝿〉を屋敷まで連れてきてほしい』とは、ミンウェイには言えない。
それは和を乱す我儘だと、彼女なら考える。他人に対してはお節介なほどに強引なくせに、自分のことは遠慮ばかりする彼女なら。
だからシュアンは、職場から駆けつけたのだ――。
「……作戦変更だ」
一音、一音に力を込め、ルイフォンは告げた。
「リュイセンには、〈蝿〉を捕獲――この屋敷まで連行してもらうことにする」
「ルイフォン!? 何を言っているの!」
シュアンによって気づかされてしまった感情を押し込め、ミンウェイは叫んだ。
反射的に睨みつけた相手の顔が、無機質な〈猫〉のそれであることに気づき、彼女は言い換える。
「それは、無駄に危険を増やす行為です! 私は反対です!」
しかし、ルイフォンは泰然と胸を張り、威圧的に足を組んだ。
「この場は〈猫〉の指揮下にあると、鷹刀の総帥に委ねられている。だから、俺の独断に従ってもらう。無論、何かあったときには俺の責任だ」
そしてルイフォンは、ぐっと顎を上げ、イーレオを見やる。
――文句はないよな?
目線だけで問いかけると、イーレオは麗しの美貌を頬杖で支え、優雅に姿勢を崩した。
――お前に任せたんだから、お前の好きなようにやれ。
そんな声が聞こえたかと思ったら、イーレオの背後に控える護衛のチャオラウが、小刻みに無精髭を揺らしていた。……笑いをこらえているのだ。どうせ、『本当に、そっくりですね』とでも思っているのだろう。
ルイフォンは鼻に皺を寄せ、しかし次の瞬間、はっと閃いた。
ひょっとして、この展開は、親父の計算通りだったということか――?
今回の作戦について、シュアンは先日、『鷹刀を支持する』と明言した。だから、勤務中と分かっている彼に、わざわざ会議を知らせる必要はなかったはずだ。なのに、イーレオは彼に連絡を入れた……。
そこまで考え、ルイフォンは思考を止めた。
いくらなんでも、うがち過ぎだろう。
それに、たとえ掌の上で踊っていたのだとしても、その振りつけはシュアンなり、ルイフォンなりが好き勝手に決めたものだ。指図されてのことではない。
ルイフォンは、いまだ柳眉を逆立て反対を訴えているミンウェイを見やり、それから、彼女の隣のシュアンへと視線を移す。ルイフォンの口から、狙い通りに『作戦変更』の文言を引き出したシュアンは、得意げな笑みを浮かべて……いなかった。
ルイフォンと目が合うと、シュアンはそっと三白眼を伏せ、深々と頭を垂れた。ぼさぼさ頭を押さえる制帽は、とうの昔にそのへんに放置してあり、ふわふわとした髪が、まるで彼自身を象徴するかのように自由気ままに跳ねる。
「ちょ、ちょっと……、皆、どうして……!」
ミンウェイは、切れ長の瞳をあちらこちらに巡らせ、恐慌に陥った。
「そ、それに、いったい、どうやって〈蝿〉を連れてくるつもりなのよ!? 確かに、リュイセンたちなら〈蝿〉を捕まえることはできると思うわ。でも、あの館には私兵がたくさんいて、門は近衛隊で固められているのよ!?」
「そんなの、俺とリュイセンがあの庭園に潜入したときの、初めの方法でいいだろ?」
結局、実行されなかった、あの作戦だ。
〈蝿〉は自分だけ、離れたところにある上等な部屋で寝る。だから、夜中を待って、ひとりになったところを襲う。――それだけだ。
「まぁ、以前の作戦では、用意していった薬で意識を奪って、シーツにくるんで車で運ぶ予定だったけど、今回は薬なんてないから、殴る蹴るで気絶させるしかないけどな」
あまりスマートな方法ではないが、そこは仕方ないだろう。
肩をすくめたルイフォンに、ミンウェイは眉を吊り上げた。
「あの庭園には、メイシアとタオロン氏のお嬢さんもいるのよ! 万が一、彼女たちを人質に取られたら、リュイセンたちは身動きを取れなくなるの! ――だから、お願い。無茶なことはやめて!」
「……っ」
メイシアの名に、ルイフォンの顔が陰った。
ミンウェイの言うことは、一理あった。
リュイセンとタオロンが揃っていれば、戦力的には容易に〈蝿〉を捕らえられる。
そして、ふたりのうちのどちらかが運転する車で、もう片方が〈蝿〉を監視しながら、近衛隊が守る門を通過するという流れになる。
だが、脱出のときは、メイシアとファンルゥも一緒なのだ。いつ気絶から目覚めるか分からない〈蝿〉と、彼女たちが近い距離にいることになる……。
考えたくもない想像が、ルイフォンの頭をよぎった。
彼はそれを否定し、しかし、否定しきれない可能性にたじろぐ。
そのときだった。
『〈猫〉、私に発言許可をください』
凛と響く、細く澄んだ声。
「メイシア!?」
執務室にいる皆の目が、一斉にテーブルに集まった。
モニタ画面の中で、彼女は緊張に顔を強張らせつつも、白い頬を薔薇色に上気させていた。
『私に提案があります。〈蝿〉をおとなしく連行するための方法です』
芯の強さを秘めた、聡明な黒曜石の瞳が、ルイフォンを導こうと懸命に輝く。
――彼の大切な戦乙女だ。
「ああ……」
ルイフォンの口元が自然にほころぶ。
「発言を許可する。――頼むぞ」
満面の笑みを浮かべた彼に、メイシアは表情を引き締めつつも、誇らしげに『ありがとうございます』と答えた。
7.岐路で選り抜く道しるべ-2

発言許可を得たメイシアの目線が、落ち着きなく揺れた。
それは初め、彼女の遠慮がちな性格のためだと、ルイフォンは思った。だが、すぐに、それだけではないと気づく。
「メイシア、すまん。お前の画面には『俺たちの頭』が映っているんだよな?」
執務室のモニタ画面には、メイシアの顔が正面からの角度で映っている。しかし、彼女のほうは、天井カメラの映像だ。これでは話しにくかろう。
「ちょっと待ってな。モニタに付いているカメラに切り替える。俺と向き合う形にしよう」
ルイフォンが素早く腰を浮かすと、メイシアは「あっ」と声を漏らした。
「メイシア?」
『あ、あのね、ルイフォンの顔は見たいの。けど、今はミンウェイさんをお願いしても……いい?』
彼女は心底、申し訳なさそうに、大真面目に眉を曇らせた。彼に頭を下げようとしているために首をすくめており、しかし、目線はカメラに向けなければと思っているらしく、結果として、ねだるような上目遣いになっている。
言っていることも、仕草も可愛すぎた。
ルイフォンは一瞬、目を丸くして、それから、この会議の場にそぐわないくらいに破顔した。
「ああ、勿論だ」
浮かれた声で気楽に答え、「いいよな?」とミンウェイに声を掛け……はっとする。
いつもなら『相変わらず、仲がいいわね』と、冷やかしながらも、くすりと笑うミンウェイが、凍りついた表情をしていた。
当然だった。
メイシアは、これから〈蝿〉に関する発言をする。それを『ミンウェイに向かって』話したいと願い出たのだから……。
ルイフォンは気まずげに咳払いをひとつして、緩んだ顔をもとに戻す。それから、カメラを切り替え、ミンウェイの目の前へとモニタを移動させた。
執務室のミンウェイと、遥かな庭園に囚われたメイシアとが空間を超えて向き合った。
メイシアは一礼し、緊張の面持ちで口を開く。
『この庭園から鷹刀のお屋敷まで、〈蝿〉をおとなしく連行する方法を提案いたします』
モニタの正面にいるミンウェイが、硬い顔で相槌を打った。それを確認したかのようなタイミングで、メイシアが告げる。
『〈蝿〉に向かって、『ミンウェイさんに会えば、あなたが知りたがっていた情報を教えてもらえる』と言えば、彼は暴れたりはしないはずです』
「どういうこと? 私は何も知らないわ。……〈蝿〉を騙すの?」
困惑のためか、やや強い口調でミンウェイは尋ねた。言ってしまってから、彼女は「ごめんなさい」と、草の香を散らす。
『騙すのではありません。〈蝿〉が心から欲している情報を、ミンウェイさんは知っているんです』
「ええっ!? 何よ……? それ……」
ミンウェイは、動揺もあらわに声を上げた。
対してメイシアは、本人は平静を保っているつもりのようであったが、目線がわずかに下がる。その証拠に、黒絹の髪がさらりと胸元に流れた。
『〈蝿〉は『自分』が――オリジナルのヘイシャオさんが、自ら『死』を望んだ理由を知りたがっています』
「お父様が亡くなった理由……?」
『はい。彼は、亡くなった奥様と『生を享けた以上、生をまっとうする』と固く約束を交わしていたそうです。だから、どうして自分が『死』を求めたのか。〈蝿〉の言葉を借りれば、どうして妻への『裏切り行為』を働いたのか。知りたがっているんです』
メイシアは黒曜石の瞳を陰らせ、唇を噛む。
『〈蝿〉の持っている記憶は保存されていたものなので、〈蝿〉は亡くなる直前のヘイシャオさんのことを知りません。――けど、一緒に暮らしていたミンウェイさんなら、知っているんです……』
「し、知らないわ……!」
ミンウェイの声が裏返った。
絶世の美貌は悲壮に彩られ、血の気がすっと引いていく。
「そんなことを言われても、どうしてお父様が亡くなったのかなんて、私にはさっぱり分からないわ。だって、ある日突然、お父様は私を連れて、エルファン伯父様のところに行ったのよ……」
ミンウェイには、本当に心当たりがなかった。
彼女はずっと、『父親』の顔色を窺いながら暮らしてきた。けれど、彼のことは何ひとつ、分からなかったのだ。
どうしたら彼が怒らないのか、どうしたら彼が喜ぶのか。……どうしたら、彼女のことを見てくれるのか。
探りながら、悩みながら、生きてきた。
それが、『父親』が亡くなって十数年も経った今――この数日の間に、彼がずっと隠し続けていた『秘密』が、急に明らかになった。
『父親』は、妻のクローンである彼女を『娘』として育てようとして、心が受け入れきれずに病んでいったのだと……理解した。
でも、それはきっと、まだ彼という人間のごく一部。
謎だった彼の心に、指先をかすめた程度のこと。
だから――。
「知りたいのは私のほう……。私は、お父様のことを、まったく分かってなかったんだから。――お父様とは、一緒に暮らしていながらも、一緒に生きてはいなかったの……」
吐き出された言葉は、切ない思い。
「私は、お父様が何を考えて生きていたのか知りたい。……だから、……〈蝿〉に会ってみたいと思っ……」
心の奥底に封じたはずの願いが、自然に口からこぼれた。
声にしてしまってから、ミンウェイは慌てて口元を押さえる。顔色を変え、脅えたように視線をさまよわせると、隣にいたシュアンが凶相に似合わぬ笑みを浮かべた。
「遠慮することないだろ? メイシア嬢の策に乗ればいい」
「でも!」
ミンウェイは弾かれたように腰を浮かせ、喰らいつくようにシュアンの着崩した制服を掴んだ。
「私は『お父様が亡くなった理由』を知りません! メイシアの策は、私がそれを言えないと駄目なんです!」
どことなく、すがるような必死さで、ミンウェイはシュアンの服をぐいと引く。
結果、シュアンは絞め上げられたような格好になったのだが、彼は揶揄するように口の端を上げた。
「あんたの『父親』が死んだ理由なら、俺が知っている」
「え……?」
ミンウェイの手から力が抜けた。シュアンを絞める拘束が緩んだ。
だが、ミンウェイの指先はシュアンの上着に掛けられたまま――そんな彼女の手を無理に払うことなく、彼は三白眼の眼球だけをテーブルの上のモニタ画面に移した。故に、ガラの悪い面構えが、いつもにもまして悪相になる。
「あんたも知っているんだろう、メイシア嬢? ――リュイセンから聞いたな?」
『緋扇さん!? ……どうして?』
シュアンの視線と、メイシアの叫びにつられるように、執務室にいる皆がテーブルに注目すれば、不鮮明なモニタ画面の中でメイシアが愕然としていた。
「賢いメイシア嬢が、詰めの甘いまま、策を披露するはずがないだろう?」
『……』
「そのくせ、聡明なメイシア嬢らしくもなく、重要なところが後回しだったな」
『……っ』
「言いにくいんだろう? 『ミンウェイの自殺未遂が原因だ』とは」
『緋扇さん!』
悲鳴のようなメイシアの高い声が、音割れを起こした。
初耳だったルイフォンは驚愕に目を見開き、ミンウェイを見やる。彼女は蒼白な顔で拳を握りしめていた。――シュアンの制服の端を皺にしながら。
騒然とした場の空気に、しかし、シュアンは構わずに続ける。
「そんなことを言ったら、なんでも自分の責任にしたがるミンウェイが、気に病むからな。――逆なのによ」
シュアンは笑い飛ばすように、軽薄に言い放つ。
「メイシア嬢がさっき言った『生を享けた以上、生をまっとうする』という約束というやつで、はっきり分かった。――あの『父親』の心は、妻が死んだときに死んでいた。なのに、その言葉で、無理やり生かされていたのさ」
「どういうこと!?」
噛み付くように、ミンウェイが尋ねる。
「あの『父親』は、本当は妻のあとを追いたかった。だが、妻との約束がそれを阻む。俺には、同情する気はこれっぽっちもねぇが、まぁ、苦しかったんだろうよ。――それが、妻になるはずだった『娘』が『死』を望んだ。『父親』にしてみれば、それは『死の許しを得た』ように感じられたんだろう。……推測だけどな」
『私も、そう思います。……いえ、少しだけ違うでしょうか』
すかさずメイシアが口を挟むと、シュアンは気を悪くしたふうでもなく、ただ興味深げに悪人面をにたりと歪めた。
「ほう。では、メイシア嬢の見解は如何に?」
水を向けられたメイシアは、軽く会釈をして口を開く。
『必死に『生』を望んだ奥様とそっくりでありながら、『死』を求めたミンウェイさんを見て、ヘイシャオさんは、やっとふたりの区別ができるようになったんだと思います。だから、悪い夢から覚めたような気持ちで、奥様に逢いにいったのではないかと。そんな気がします』
そこまで言ってから、メイシアは考えるような素振りを示した。
『……やっぱり、緋扇さんがおっしゃったことと同じことなのかもしれません』
申し訳なさそうにシュアンに言い、メイシアは、ほのかな笑みを混じえた眼差しをミンウェイに向けた。
そして、はっきりと告げる。
『ヘイシャオさんは、ミンウェイさんに救われたんです』
遥かな庭園から回線を介し、澄んだ声が届けられた。穏やかなはずのその響きは、ミンウェイの心の奥を激しく揺らした。
「お父……様……!」
シュアンの制服を握りしめたままの拳が、ふるふると震える。
そんなミンウェイを刺激しないよう、シュアンは足元に落ちていた制帽を爪先を使って器用に拾い、彼女の頭に目深にかぶせた。潤んだ切れ長の瞳が、広いつばの下に隠れた。
しっとりと濡れたような沈黙が訪れる。
モニタの発する電子的な雑音だけが、妙に大きく聞こえる……。
やがて、メイシアが『ミンウェイさん』と、遠慮がちに呼びかけた。
『私にとって〈蝿〉は、父の仇です。リュイセンを苦しめ、私を囚えた憎い敵です。許すことはできません』
揺らぎのない黒曜石の瞳がきっぱり告げ、けれど、すぐに『でも――』と続ける。
『〈蝿〉は『デヴァイン・シンフォニア計画』のために作られた存在です。何も知らされずに、それどころか騙され、利用されただけの被害者でもあるんです』
メイシアは声を落とし、わずかに目を伏せた。
『セレイエさんの――ホンシュアの記憶を受け取ったせいなのかもしれませんが、私は〈蝿〉を憎むと同時に、憐れだとも感じています。彼は不幸だと思っています。……おかしいかもしれませんが、本当です』
嫋やかでありながらも芯の強い戦乙女が、慈悲と無慈悲を両手に携え、悲しげに微笑んだ。
『〈蝿〉に与えるべきものは『死』です。それを譲るつもりはありません。――けれど、彼に救いがほしいんです』
「メイシア……?」
シュアンの制帽の影から、ミンウェイが首をかしげる。
『ヘイシャオさんと〈蝿〉は、別人です。だから、ヘイシャオさんにとって救いだったことが、〈蝿〉にとっても救いになるかどうかは分かりません。けど、ヘイシャオさんの『死』の理由を知ることは、〈蝿〉にとって絶対に意味があるはずです。……だから、この策を採ってください』
メイシアの策を反対する者など、誰もいなかった。
「メイシアの安全が最優先よ! 不測の事態のときは、とっとと決着をつけるのよ!」と、ミンウェイが強く主張した以外は、満場一致で決定し、会議はお開きとなった。
ルイフォンの「解散」の声を聞くやいなや、シュアンが「あとは任せた」と足早に執務室を出ていく。なんでも、適当に誤魔化して職場を抜けてきたのだという。
メイシアの夕食とき、すなわち、リュイセンとの接触のときには顔を出せないが、夜には首尾を聞きに来ると言い残していった。よほど慌てていたらしく、ミンウェイの頭に制帽を忘れたままだ。――免職になる日も近そうである。
ルイフォンも、そそくさと自室に戻り、メイシアとふたりきりの時間を過ごす。
勿論、電話での逢瀬だが、ひとりきりで頑張り抜いたメイシアを労い、あとひと息だと激励する。
「メイシア、今夜、決着をつける」
『うん。――ルイフォン。今まで、お疲れ様』
「メイシアこそ、ありがとう」
そして、緊張と興奮に彩られた時が流れ、メイシアの夕食の時間となった。
部屋の扉に、ぴたりと張りつき、メイシアは耳をそばだてていた。
――これでやっと、リュイセンと手を取り合うことができる。
祈るように組み合わされた両手が、小刻みに震えていた。
今までのリュイセンの言動を考えると、すんなり話を聞いてくれるとは思わない。けれど、頭から突っぱねるようなことはないだろう。だから、最後にはきっと、彼は味方になる……。
待ち望んでいたエレベーターの駆動音が聞こえてきた。滑らかな上昇の気配に続く、停止のチャイム。
「……っ!」
メイシアの心臓が跳ねる。食事のワゴンがエレベーターを降りるときの、ドアの溝を超える、がたんという音が響く。
メイシアは、扉に飛びつくようにして施錠を解いた。
そのときだった。
「ま、待て! 開けるな!」
野太い男の叫びが聞こえた。
リュイセンではない。知らない男の声だ。
「あんたの姿を見たら、俺は死ぬ!」
「え……」
「〈蝿〉がそう言った! あいつの言うとおりにしないと、俺は殺されるんだ!」
「……?」
何が起きた?
リュイセンは、どうした? 〈蝿〉は、いったい……?
メイシアの頭の中を疑問が渦巻き、駆け巡る。
「食事は、ここに置いていく。あんたは、俺がいなくなってから取るんだ。食べ終わったら、ワゴンを廊下に置いておけ!」
外にいる男は、そう言ってすぐに立ち去ろうとした。
「待ってください! リュイセンはどうしたんですか!」
男を引き留めようと、メイシアの体は無意識に動いた。ドアノブをひねり、扉を開こうと……。
「やめろ!」
男は絶叫し、体当たりで勢いよく扉を押さえた。
「きゃっ」
メイシアは危うく指を挟まれそうになったが、ぎりぎり難を逃れる。
「開けるな……、開けないでくれ……、俺はまだ死にたくない……」
よく聞けば、男の声はがたがたと震えていた。
そういえば、私兵たちは〈蝿〉の偽薬と虚言で、いいように操られているのだということをメイシアは思い出す。
「あんたの質問に答える! だから、出てこないでくれ、……頼む」
脅えきっている男には申し訳ないのだが、メイシアにとって好都合な展開だった。
ここで男から情報を得なければ、すべては水泡に帰すかもしれない。彼女は黒曜石の瞳を閃かせ、毅然と尋ねる。
「私の食事は、世話係のリュイセンが持ってきてくれることになっています。それが、どうしてリュイセンではなく、あなたなのですか?」
「リュイセンは、あんたの昼食を下げてきたあと、〈蝿〉に反省房に入れられた。そのとき、今後、あんたの食事は俺が代わりに持っていけと、〈蝿〉に命令された」
「反省房!?」
思ってもみなかった単語に、メイシアは困惑――否、愕然とする。
「あ、あんたが原因だろう!」
「え?」
「昼間の火事騒動。あれは、あんたが〈蝿〉の実験体にされるのを防ごうと、リュイセンが非常ベルを鳴らしたんだってな!」
それは、おおむね間違ってはいない。
実験体ではなく、激昂した〈蝿〉に殺されかけたところをリュイセンが助けてくれた、というのが正しいのであるが。
「反省房は、リュイセンが〈蝿〉に逆らった罰だ!」
「――!」
「そもそも、あんたは〈蝿〉の研究のために連れてこられたんだろう? それが、世話係になったリュイセンを誘惑し、自分の身を守らせようとした。――俺が、あんたを見たら殺されるってのも、リュイセンに続いて、俺まで惑わされたらたまらないからだと〈蝿〉は言っていたぞ!」
「…………」
男の弁は、ところどころ〈蝿〉による脚色が入っているようだが、だいたいのところは事実だろう。
要するに、リュイセンの身柄は〈蝿〉に拘束された。
それは、従順な駒であるはずの彼が、メイシアを助けようと〈蝿〉に逆らった罰。
同時に、〈蝿〉がメイシアに『続きは明日』と言った件を話すときに、再び彼に邪魔されないよう隔離した、という意味もあるのだろう。
メイシアの白磁の肌が赤みを失い、透き通るような青白さを帯びた。
急転直下の非常事態だった。
ここにきて、まさか、そんな……と、体が震え始める。
「もういいだろう!」
男が金切り声を上げた。早くこの場を去りたいという気持ちが、扉越しでも、びしばしと伝わってきた。
よほど〈蝿〉に脅されたらしい。――そう思ったとき、メイシアは、はっと気づく。
彼女が初めてこの展望室に囚われた日、私兵たちが悪さを働く可能性があると、〈蝿〉は彼女に警告し、鍵を閉めるようにと忠告した。
つまり、彼女にとって、私兵たちは危険な存在だ。
〈蝿〉は、そんな私兵のひとりである扉の向こうの男を執拗に脅し、メイシアと顔を合わせないように計らった。それは、明日の交渉相手である彼女を丁重に扱っている、という意思表示だ。
「〈蝿〉……」
彼もまた、必死なのだ。
「おい、聞いているのか! 俺はもう、行っていいだろう!」
扉の外で男が叫ぶ。
「は、はい! どうもありがとうございました」
メイシアも叫ぶようにして言葉を返し、携帯端末へと走る。
ともかく、ルイフォンに報告するのだ。
そして、この事態を打開すべく、新たなる方策を一刻も早く講じなければならない……。
8.重ね結びの光と影-1

リュイセンはメイシアの世話係として、彼女の部屋に夕食を運んでくる。
そのときこそ、待ちに待った兄貴分との接触の瞬間だ――。
ルイフォンは興奮に顔を上気させ、執務室のソファーで待機していた。心地の良い緊張が程よく体内を巡り、覇気で満たされていく。
奥の執務机では、一族の総帥たるイーレオの美貌が頬杖によって支えられており、その背後には護衛のチャオラウが控えていた。ルイフォンの向かいのソファーでは、次期総帥エルファンが、相変わらずの無表情で腕を組んでいる。
そして……。
ルイフォンの隣には、ミンウェイ。
メイシアから電話が来たら、まずはルイフォンが受ける。けれど、それから、すぐにミンウェイに替わることになるため、この配置となった。
とはいえ、話し手はミンウェイでも、会話の内容は皆で聞けるよう、電話の音声出力は外部スピーカーにしてある。画像付きの会議システムだと音質が落ちてしまい、複雑な話には不向きであるため、音声のみの状態だが、ミンウェイの顔を見せたほうが効果的だと判断した場合には、すぐに切り替えるつもりだ。
ミンウェイは、シュアンが忘れていった制帽を膝に載せ、身じろぎひとつせずにテーブルの上の電話を見つめていた。切れ長の瞳が伏せられているのは、視線が低い位置にあるからか、それとも彼女の気持ちの問題か。
ルイフォンは、ミンウェイに発破を掛けようとして……やめた。
彼女の内部では、いろいろな思いが巡っているはずだ。そっとしておくべきだろう。もし、彼女がリュイセンとの会話の途中で言葉を詰まらせたなら、ルイフォンが代わればよいだけだ。
兄貴分は、必ず取り戻す。
ルイフォンは、リュイセンのいる庭園へと、挑むように猫の目を光らせる。
そちらの方角にある窓は、まだ明るさを残した藍色をしていた。夏の陽射しが長いのと、メイシアの食事の時間がやや早めに設定されているためだ。
ほどなくして――。
待ち望んでいた呼び出し音が、執務室の空気を震わせた。
『ルイフォン』
彼の名を呼ぶ、メイシアの第一声。
その硬い声色だけで、不測の事態が起きたのだと、ルイフォンは理解できた。
「何があった?」
返した声は自分でも驚くほどに鋭く、慌てて彼は、弁解するように「教えてくれ」と、柔らかに付け加える。
『リュイセンが、反省房に入れられてしまったの』
メイシアの語尾は震えていた。
それは、非常事態に直面した彼女の不安の表れだと、ルイフォンは思った。だが本当は、良くない知らせをすぐに察してくれた彼への、軽い驚きと深い安堵に、彼女が涙ぐんでいたためであった。
彼の言葉に力を得た彼女は、即座に頭を切り替える。今すべきことは、正確な報告だと。
『リュイセンは、〈蝿〉に逆らって私を助けた罰で、昼食のあと拘束されてしまったらしいの。だから、私の夕食は別の人が持ってきて、リュイセンはこの部屋に来なかった――会えなかったの』
「!」
ルイフォンは愕然として、受話器を取り落しそうになった。
何故、この事態を予測できなかったのだろう。
メイシアのために動いたリュイセンは、〈蝿〉にとって、もはや部下ではなく、警戒すべき相手と変わったのだ。〈蝿〉が、メイシアからリュイセンを遠ざけることは、視野に入れておくべき懸案事項だったはずだ。
ぎりりと奥歯を鳴らし、拳を震わせる。自分の甘さに腹が立つ……。
そのとき。
『ルイフォン!』
凛とした呼びかけが、彼の耳朶を打った。
『何か予想外のことが起きた場合には、リュイセンとの接触を諦めて、タオロンさんに〈蝿〉暗殺を依頼する取り決めだったと思う。でも、今現在、私の身に危険が迫っているわけではないの。だから――!』
高く澄んだ響きに、ルイフォンは、はっとした。
メイシアの――彼の戦乙女の示す道が、目の前に広がって見えた。
その瞬間、彼は瞳を煌めかせ、迷わずに言い放つ。
「だから、まだ諦めない!」
『うん!』
重ねた思いに、彼女は嬉しそうに応える。
遥かな庭園にいながらも、彼女は彼と共にある――。
ルイフォンは、次に取るべき行動を即座に閃かせた。
「タオロンだ! タオロンに頼んで、リュイセンを反省房から助け出す。そして、メイシアの部屋まで連れてきてもらう」
『展望塔の扉の鍵も、私の部屋と同じで内鍵なの。だから、鍵が掛かっていても、私が開けられる! 見張りは……』
「見張りなんか、あのふたりの前には、いないも同然だ。――問題ないな!」
『うん!』
小気味よいやり取りを繰り広げ、ルイフォンは好戦的な笑みを浮かべた。
そして、ぐいと顔を上げ、執務机のイーレオを見やる。彼の背で、金の鈴が誇るように跳ねた。
「親父! それでいいよな!」
「今回の件はお前に一任してある。好きにやれ」
頬杖を崩すことなく返された、豪然とした響き。イーレオは眼鏡の奥の目を細め、すっと口角を上げる。
ルイフォンは一瞬だけ、頬に緊張を走らせ、しかし、すぐに感謝を込めて頭を下げた。そして、タオロンに連絡を取るべく、尻ポケットから携帯端末を取り出す。
現在、タオロンには、地下研究室に籠もっている〈蝿〉の見張りを頼んでいる。
三十分ほど前に『〈蝿〉の行動に異常なし』の報告を受けていたので、すっかり安心していたが、時間的にいって、タオロンが見張りにつくよりも前に、〈蝿〉はリュイセンを反省房に入れていたのだ。
同じ館内でのできごとなのに気づかなかったと、タオロンは気に病みそうだが、おそらく、リュイセンが囚われたことは意図的に隠された。
〈蝿〉は、タオロンは裏切れないと信じているが、同時に、心情的にはリュイセンの味方であることも承知している。ならば、面倒ごとの火種になりかねない情報は、用心のために遮断するだろう。
タオロンに責任はない。それどころか、後手に回ったルイフォンの落ち度だ。
現状を考察しながら、タオロンの連絡先を繰り出したとき、「ルイフォン」と低い声が響いた。
「?」
イーレオ……ではなかった。
同じ声質を持った、次期総帥エルファンの氷の眼差しが、こちらを向いていた。一族そのものの美貌には懸念が浮かんでおり、わずかに眉がひそめられている。
「リュイセンは、たとえ素手でも、私兵たちやヘイシャオの〈影〉よりも、よほど強い。あいつが、おとなしく反省房とやらに捕まっているのなら、自分の意思で入っているということだ」
威圧を含んだ口調は、ルイフォンに同意を求めており、彼は促されるままに「あ、ああ」と首肯する。
「ならば、斑目タオロンが『助けに来た』と言ったところで、素直についていくことはないだろう」
「そこは、タオロンに引きずってでも連れてきてもら……」
そこまで言いかけて、ルイフォンは気づく。
リュイセンとタオロンは、どちらも甲乙をつけがたい武人である。もしも、本当にタオロンがリュイセンを引きずる事態になった場合には、ふたりとも満身創痍の大騒ぎになっているはずだ。
ルイフォンが言葉を詰まらせていると、彼の隣で草の香が動いた。
「斑目タオロン氏に、伝言を頼んでください」
鮮やかな緋色の衣服の胸を張り、ミンウェイが毅然と告げる。
「『鷹刀ミンウェイという人物が、リュイセンと話をしたいと電話を待っている。だから、メイシアの部屋に行ってほしい。メイシアと鷹刀は、とっくに連携している』――私の名前を知らないはずのタオロン氏にこう言われれば、リュイセンはタオロン氏の言葉を信じ、来てくれます」
彼女は断言し、それから、はっと顔色を変えて「……と、思います」と付け加えた。
「ミンウェイ! 名案だ!」
自信なさげなミンウェイの雰囲気を吹き飛ばすように、ルイフォンは叫び、破顔する。
「それでいこう! いいよな!?」
彼は立ち上がり、ぐるりと皆を見渡す。一本に編まれた髪が、道を切り拓くように空を薙ぎ、その先で金の鈴が煌めく。
彼の言葉に、否やを言う者は誰もなかった。
タオロンは、地下研究室にいる〈蝿〉を見張っていた。
正確には、〈蝿〉が就寝時間よりも前に研究室から出てきたら、すぐにもルイフォンに連絡できるよう、地下への階段が見える位置で身を潜めていた。
不意に、彼の胸元で携帯端末が振動する。
発信元の相手は、ルイフォン。
電話ではなく、メッセージの着信通知だった。周りを警戒しての配慮だろう。
ちょうどそのとき、〈蝿〉の夕食を載せたワゴンが、こちらに向かってやってくるのが見えたので、タオロンは、メイシアもまた食事の時間を迎え、リュイセンとの接触がうまくいったという、朗報が来たのだと思った。
彼は、ほっと相好を崩した。
タオロンの夕食は、娘のファンルゥと共に摂ることになっている。〈蝿〉の見張りをリュイセンと交代し、自分は部屋に戻ってよいか訊いてみよう、そんなことを思いながらメッセージを開き、彼は息を呑んだ。
――リュイセンは反省房に入れられたため、メイシアの部屋に来なかった。
ルイフォンからのメッセージは、そんな文面から始まり、こと細かに状況が綴られていた。
「嘘、だろ……? 俺は、何も知らね……」
タオロンは愕然とし、慌てて携帯端末に指を走らせる。
外見の印象通りに、あまり機械類の操作が得意でない彼が、懸命に誤字混じりの謝罪文を打ち込むと、次の瞬間には、情報機器の専門家であるルイフォンから『タオロンの責任ではない』と速攻で返ってきた。
「本当に、すまん」
太い指がもどかしく、タオロンは思わず口に出して謝る。
勿論、その声はルイフォンには聞こえない。けれど、彼を仲間として信頼するメッセージが届けられた。
――頼む、協力してくれ。お前にかかっている。
続けて送られてきた指示に、ごくりと唾を呑み込み、タオロンは足早にファンルゥの部屋へと向かった。
夕食は、いつも通りにファンルゥと摂った。
〈蝿〉も、自分の食事を中断してまで、何かの行動を起こすことはないだろうから、少しでもファンルゥのそばにいて、安心させてあげてくれ。――ルイフォンが、メッセージでそう言ってくれたのだ。
だが、このあとまた、〈蝿〉の見張りに戻る。
そして夜が更け、夜番以外の私兵が室外への出歩き禁止の時間になったら、リュイセンを反省房から助け出し、メイシアのもとに連れて行ってほしい。そのあとは、もとの作戦通り、リュイセンを味方に戻し、塒に戻る〈蝿〉を待ち伏せて捕獲するから、援護を頼む。――これが、ルイフォンからの要請だった。
食事のあとのテーブルを拭き終え、タオロンは、そのままなんとなく椅子に座った。
否、なんとなくではない。
片付いたテーブルの上にスケッチブックを広げはじめた愛娘の顔を、よく見たかったのだ。
ファンルゥは黒いクレヨンで大きな丸を描き、その中にありったけの色を詰め込んでいた。
最近は『空に浮かぶ、紫の風船』ばかりを描いているようだが、食後に描く絵だけは、この庭園に来てからずっと変わらずに『これ』である。いつだったか、何を描いているのかと尋ねたタオロンに、彼女はこう答えた。
『今、食べたご飯』
丸は、皿であるらしい。
『ここのご飯は、斑目のお家のご飯よりも、ずっと美味しいね』
不満の多い窮屈な生活の中でも、食事だけは特別な楽しみのようだった。
ファンルゥの身を守り、そして、飢えさせない。――たったそれだけのことかもしれないが、タオロンにとっては何よりも大切なことだ。
「……」
彼は、刈り上げた短髪と額の間にきつく巻かれた赤いバンダナを、そっと解いた。だいぶ色あせてしまったそれは、彼の愛した女が、彼に巻いてくれたものだ。
『猪突猛進に走り出しそうになったら、バンダナを結び直しながら、もう一度だけ考えてみて』
『それでも、走るべきだと思ったら、走ったらいいわ』
彼女の言葉が、耳に蘇る。
それと同時に、先ほど、ルイフォンから送られてきたメッセージを反芻する。
――リュイセンを反省房から助け出せば、タオロンは『明確に、〈蝿〉を裏切った』ということになる。見張りの私兵たちを、その場で全員、身動きの取れない状態にできなければ、〈蝿〉に報告されるだろう。
そうなったとき、ファンルゥの身に危険が及ぶかもしれない。……すまない。
でも、どうか、お願いできないだろうか。
頼む。お前にしかできないんだ。
「……猪突猛進なんかじゃないさ」
両手で持ったバンダナを、タオロンは再び額に巻き直す。――いつもよりも、ぎゅっと、きつく。
「パパ?」
ご機嫌な様子で絵を描いていたファンルゥが、くりっとした丸い目を大きく見開いた。
彼女は握っていたクレヨンを放り出し、自分の椅子から、ぴょこんと飛び降りる。ぱたぱたとテーブルを回って、タオロンの胸へと飛び込んできた。
「ファンルゥ!?」
彼の膝によじ登り、甘えるように抱きついてきたファンルゥに、タオロンは困惑する。
「パパ。バンダナ、きゅっきゅっ、ね?」
「?」
愛娘の言葉の意味が分からずに、タオロンは太い眉を寄せる。
「ファンルゥ、知っているもん! パパのバンダナは、ママのおまじないでしょ! 『パパ、頑張って!』って、ママが言っているの!」
ファンルゥは、あちこちに元気に跳ねたくせっ毛をタオロンの頬に擦り寄せ、小さな手を伸ばして赤いバンダナの結び目に触れる。
「パパはね、これから、ちょっと大変になるとき、バンダナをきゅっきゅっ、って結び直すの。そうすると、力がもりもり出てきて、パパは無敵になるの」
「ファンルゥ……」
バンダナについて、『昔、ママから貰った』くらいは言ったことがあると思うが、特に詳しく説明した覚えはない。
だから、ファンルゥは『お話』を作ったのだ。
大好きなパパとママが、今も赤いバンダナで繋がっているという、素敵なお話を――。
「そうだよ、ファンルゥ」
タオロンは愛娘を抱きしめた。
太い腕で、優しく包み込みながら、本当は包まれているのは自分のほうだと思う。
小さくて軽くて柔らかくて……。こんなに、か弱い存在なのに、ファンルゥは幸せという名の温かさで彼を包んでくれる。
「パパが、正しいことを頑張れるようになる、魔法のバンダナだ」
『魔法』などという、およそ自分らしくない言葉に照れながら、それでもタオロンは朗らかに笑った。
だが、その笑みは、耳元で囁かれた、ファンルゥの次のひとことで凍りついた。
「パパ、リュイセンを助けに行くんでしょ?」
「――!?」
「ファンルゥ、見張りのおじさんたちのおしゃべりを聞いていたから、知っているもん。リュイセンはメイシアを守ろうとして、〈蝿〉のおじさんに逆らったの。それで、罰として閉じ込められちゃった、って」
タオロンの首に、ぎゅっとしがみつき、できるだけ小さな声でファンルゥが言う。内緒にするべき話だと、ちゃんと分かっているのだ。
「ねぇ、リュイセンを助けて、今晩、皆で逃げるんでしょ? もう、〈蝿〉のおじさんの言うことなんか、きくもんか! って」
「ファンルゥ……、お前……」
タオロンは、太い眉の下の目をいっぱいに見開く。
小さな子供だから、何も分かっていないと思っていた。
好奇心旺盛なだけの、おてんば娘だと思っていた。
「ファンルゥ……!」
無骨なタオロンは、こんなときにぴったりな、うまい言葉など知らない。だから、守り抜くという意思表示として、大切な娘を抱きしめる。
そして、彼女の耳元で、これからのことを説明する。
「ルイフォンから連絡があったんだ。お前の言う通り、リュイセンを助けてほしい、って。――でも、俺が助けたのが〈蝿〉にばれたら、この部屋の外にいる見張りが入ってきて、ファンルゥ……お前が殺されるかもしれない」
「……っ! ファ、ファンルゥは、上手に隠れている……ね!」
脅えた声を上げながらも、彼女なりの策を練る娘の頭を、タオロンは大きな手で包み込んだ。
「安心しろ。ルイフォンは、ちゃんとお前のことを考えていて、先に逃げるようにと言っている。――お前は、寝る時間になったら、電気を消したあと、ベッドじゃなくてメイシアの部屋に行くんだ。メイシアとふたりで待っていてくれ」
それが、ルイフォンからの指示だった。
本当はファンルゥが眠くなる前に移動させたいのだが、夕食の時間帯は、私兵たちが交代で食堂を利用するために、あちこちに人の目がある。それで、ファンルゥが寝る前ということになったのだ。
「分かった。赤いピエロさんが出てきたら、ファンルゥはメイシアのところに行く」
ファンルゥは、壁に掛けられた絡繰り時計を示す。
文字盤が読めなくても、時報で出てくる絡繰り仕掛けのピエロの色が、時間を教えてくれるのだ。これもまた〈蝿〉が用意した子供のための品のひとつで、ファンルゥのお気に入りである。タオロンとしては複雑な気持ちだが、役に立ってくれるのはありがたかった。
ファンルゥは、父親そっくりの太い眉に強い意思の力を載せ、満面の笑顔を浮かべる。
「パパ、行ってらっしゃい! 頑張って!」
「ああ、頑張ってくる」
タオロンも、笑いながら部屋を出た。
夜が更けてきた。
荒くれ者の私兵たちでも、得体の知れぬ〈蝿〉は怖いらしく、夜番以外は決められた時間になれば部屋に籠もる。
館内の気配が鎮まってきたのを感じたタオロンは、時計を確認し、バンダナの結び目に手を触れた。武器は武器庫で管理されているため、愛用の大刀は手元にはないが、〈蝿〉の雇った私兵ごとき、『魔法のバンダナ』さえあれば素手で充分だ。
ファンルゥは、もう部屋を出たことだろう。
彼もまた、行動を開始すべきときだ。
タオロンは『〈蝿〉の見張りから、リュイセンの救出に移る』と、ルイフォンにメッセージを送り、現場に向かいはじめた。
『反省房』とはいっても、館内に牢があるわけではない。
何故なら、この庭園は何代か前の王の療養施設であり、不始末をしでかした使用人は、即刻、処分を言い渡される。反省を促すための場所など必要ないのだ。
だから、〈蝿〉が『反省房』と呼んでいるのは、館の隅のほうにある、日当たりの悪い部屋のことだ。地下研究室からは距離があるため、タオロンは自然と急ぎ足になっていた。
墨を溶かし込んだかのような暗い廊下に、月明かりが差し込む。普段、使っていない区域であるため、電灯は点けられていないものの、夜目の効くタオロンには充分な明るさだ。
しかし、反省房に近づくにつれ、彼の心臓は妙に落ち着きを失っていった。
豪胆を誇りとする彼である。恐怖ではないと断言できる。けれど、それに近いような胸騒ぎがした。
極力、足音を立てぬよう、気配を殺して先へと進む。
やがて、この先の角を曲がれば、反省房まで一直線の廊下となる――そんな位置までたどり着いたとき……。
「!」
鼻を突く、馴染みの感覚。
血の臭いだ……。
タオロンは太い眉をひそめた。喉仏が、こくりと動く。
「いったい、何が起こっていやがる……?」
悪態をつくように呟き、彼は警戒に身を引き締める。
どこからともなく吹いてきた初夏の風が、彼の背中を撫でた。この季節らしい、生ぬるさを運ぶはずの風が、しかし彼には、ひやりと冷たく感じられた。
そして、そのころ――。
ファンルゥの部屋で、絡繰り仕掛けの赤いピエロが踊る。
『さあ、窓からこっそり抜け出して、メイシアのいる展望塔を目指そう』
軽快な音楽に乗って、ピエロはファンルゥを誘う。
――しかし、ファンルゥは、すっかり夢の中だった。
これから起こる『わくわく』に興奮しすぎた彼女は、赤いピエロを待てずに、疲れ切って眠ってしまったのである……。
8.重ね結びの光と影-2

遥かなる庭園を案じ、執務室のルイフォンは、そちらの方角の窓を見やる。
リュイセンが反省房に囚われたという知らせを受けたときには、まだ藍色を残していた空は、すっかり夜闇の漆黒に染め上げられていた。
『夜には首尾を聞きに来る』と言っていたシュアンは、宣言通りに到着した。現状を説明された彼は「そうか」と呟き、そのあとは黙ってミンウェイの隣に陣取っている。
タオロンからは、先ほど『私兵たちの出歩き禁止の時間になった。〈蝿〉の見張りから、リュイセンの救出に移る』と連絡があった。反省房までは距離があるそうだから、今は移動中だろうか。
――タオロン、頼むぞ……。
ルイフォンが強い思いを託したとき、テーブルの上の電話が呼び出し音を響かせた。
『ファンルゥちゃんが、まだ来ないの』
メイシアの弱りきった声がスピーカーから流れ、執務室は緊張に包まれた。ルイフォンの受話器を握る手に力がこもり、イーレオをはじめとする皆が息を呑む。
『たぶん、眠っちゃったんだと思う。私、約束の時間の少し前から、ファンルゥちゃんの部屋の窓を見ていたんだけど、出てくる気配がなくて……』
メイシアの囚われている展望室からは、ファンルゥの部屋が見える。心配で、ずっと見守っていたのだろう。
「――っ」
ルイフォンは、うなるような声を上げて頭を抱えた。
タオロンは、ファンルゥが寝てしまうことを危惧していた。だが、ルイフォンは、好奇心旺盛なファンルゥなら、こんなときこそ張り切って起きているだろうと、安易に押し切ってしまったのだ。人目の多い時間帯に部屋を出て、私兵たちに見つかることのほうが怖いから、と。
「俺のミスだ……」
父親であるタオロンの言うことを、もっと真剣に聞くべきだった。
後悔しても、あとの祭りである。
部屋に残されたファンルゥが、必ずしも危険な目に遭うとは限らない。
けれど、少しでも身がおびやかされる可能性があるのなら保護すべきだ。それはタオロンに対する礼儀ではなくて、ファンルゥが大切だからだ。
勿論、メイシアと一緒にいれば絶対に安全、というわけではない。メイシアだって、どちらかといえば弱い存在だ。けれど彼女なら、機転を利かせることでファンルゥを守り抜ける。
「タオロンに状況を説明して、ファンルゥを起こしに、一度、部屋に戻ってもらおう」
即断しつつも、ルイフォンの猫の目は眇められ、渋面を作っていた。
その顔は、音声通話のメイシアの瞳には映らない。なのに、彼女は問うてきた。
『ルイフォン……? 何か、気になるの?』
「あ、いや……」
否定しかけて、彼は首を振る。
どうやら、見えなくても彼女には伝わってしまうらしい。ならば、素直に話すべきだろう。
ルイフォンはまず、「些細なことなんだ」と前置きをする。言っても仕方のないぼやきを聞いてもらうことに、ほんの少しだけ、彼女への甘えを自覚しながら。
「タオロンに部屋に戻ってもらうと、リュイセンの救出が遅くなるだろ? そうすると、『リュイセンと話をして、あいつを味方に戻して、そして〈蝿〉を捕まえる』という作戦の開始も遅くなる。けど、『〈蝿〉の捕獲が可能な時間』は限られているんだ。――間に合わなくなると困るな、と思った」
『『〈蝿〉の捕獲が可能な時間』……? ……あっ!』
聡明なメイシアは、すぐに気づいたようだ。
反面、執務室の面々のうち、半分ほどは、きょとんとしている。ルイフォンは彼らに説明すべく、補足する。
「用心深い〈蝿〉は、部屋にいるときは鍵を掛ける。だから、奴を捕まえられるのは『廊下を歩いているとき』のみ。つまり『〈蝿〉が地下研究室から出てきて、寝床にしている王の部屋に入るまで』だけなんだ」
扉を破壊することは絶対に不可能、とまでは言わないが、現実的ではないだろう。
ハオリュウの車に隠れ、ルイフォンとリュイセンであの館に侵入したときは、偽造カードキーを用意していった。しかし、あれはルイフォンが持ち帰ってしまった。
「でも、ファンルゥの安全が優先だ。――タオロンに戻るよう、連絡を取る」
懸念を口に出したことで、かえって不安がなくなった。
晴れやかに宣言したルイフォンに、メイシアが遠慮がちに言う。
『『〈蝿〉が部屋にいる間』は手を出せないなら、『朝になって、〈蝿〉が寝室から出てくるとき』を待つのでは駄目なの? 焦らなくても、大丈夫だと思うの』
「あ……」
盲点だった。
勿論、〈蝿〉の捕獲は、密やかに実行されるべき作戦だ。夜のうちに片をつけるほうが望ましいだろう。しかし、朝になってからでは駄目だという理由はない。
「その通りだ! さすが、俺のメイシアだ!」
ルイフォンがそう叫んだとき、彼の携帯端末が振動した。
「タオロンから電話だ」
少し早い気がするが、もうリュイセンを反省房から助け出したのだろうか。そうなると、部屋に残ったままのファンルゥは……?
ともかく、ルイフォンは電話を受ける。
その連絡が、メッセージではなくて音声電話であるのは、文字の打ち込みが苦手なタオロンが、複雑な内容を告げるためであることに気づかぬまま……。
時は少し、遡る――。
タオロンは曲がり角に身を隠し、反省房まで一直線となる廊下の様子をそっと窺った。
刹那、彼の顔に生ぬるい風が吹きつける。
血臭が鼻を突き、月光が瞳を刺した。
反省房として使っている部屋を一番奥に、どん詰まりとなっている廊下の窓が大きく開け放たれていた。それ自体は、どうということはない。単に夏だからだろう。
だが、遮るものが何もない、まっすぐな廊下には、月の光に照らし出されるはずの見張りたちの姿がなかった。
「……」
人間の存在なら、先ほどから濃厚に感じている。血の臭いという、実に分かりやすい形で。
タオロンの太い眉の下の小さな目が、剣呑な光を放つ。
――リュイセンが動いたのか?
タオロンは警戒しつつ、月明かりの織りなす、光と影の入り混じった廊下を進む。
反省房の扉の前に立つと、部屋の内側から明確な人の気配を感じた。
それも結構な数。十人はいる。
呼吸の具合いから、意識があるかどうかは微妙だ。
足元には不快な感触――血を吸った絨毯がぬめりを伝えてくる。あとで靴を拭わなければ、血痕の足跡をつけて回ることになるだろう。
――おそらく、リュイセンは脱走した。
廊下にいた見張りたちを倒し、目立たぬよう部屋の中に移動させて……。
推測の正しさを確認すべく、タオロンは、そろりと薄く扉を開く。鍵の掛かっていない扉は素直に動き、室内を照らす煌々とした電灯の光が、長い筋となって漏れ出してきた。
夜目に慣れたタオロンが目を細めながら覗き見ると、思った通り、室内には見張りと思しき男たちが転がされていた。誰も彼もが、着ていた服を裂いて作ったらしき紐で両手両足を縛られ、猿ぐつわを噛まされている。一見したところ、皆、気を失っているようであった。
そのとき。
「――、――っ!」
男のひとりが、声を上げた。扉が動いたことに気づき、助けを求めてきたのだ。
タオロンは、とっさに『まずい』と思った。
気づいたのはその男だけ。あとの者たちの反応はない。だが、ひとりが騒ぎ立てれば、やがて他の者も目覚めるだろう。面倒なことになる。
タオロンは扉を開け放った。
ぬちゃりと血濡れた絨毯を蹴り、重力から解き放たれたかのように巨躯を踊らせる。
そして、着地と共に再び重力をまとい、勢いのままに男の首を締め上げた。
「――!?」
男は、信じられないものを見たかのように目を見開き、その眼差しで『裏切り者』と罵る。……しかし、すぐに泡を吹いて意識を手放した。
このときになって初めて、タオロンは自分の失態に気づいた。
リュイセンが自力で脱走したのなら、タオロンは〈蝿〉の忠実な部下のふりをし続けるべきだったのだ。何故なら、彼の裏切りは、ファンルゥの生命の危機に直結するのだから。
だのに、今の行為によって、タオロンは自ら、自分の立ち位置を明らかにしてしまった。この男は、目を覚ましたらすぐに〈蝿〉に報告するだろう。
タオロンは己の短慮を後悔する。
だが、時すでに遅し……。
彼は広い肩を落とし、冷静な――冷酷な瞳で、部屋を見渡した。
拘束された男たちから、最も遠い位置に刀が積み上げられていた。
武器は武器庫に集められているのだが、チンピラ程度の彼らが、武の達人であるリュイセンの見張りの任に就くにあたり、〈蝿〉から支給されたのだろう。――それをリュイセンに奪われているようでは、なんのための武器だか分からぬが。
タオロンは無造作に、ひと振りの刀を手に取った。愛用の大刀と比べ、借り物の刀はまるで玩具のように心もとないが仕方あるまい。
これで、先ほどの男の口を封じる。
ファンルゥに害を及ぼしかねない、危険の芽を摘むのだ。
タオロンは、巨躯を感じさせない静けさで動く。
浅黒い顔には、いつもの気のいい大男の面影はなかった。太い眉に、不動の意志をたたえた殺戮者。――これも、彼の一面だった。
そもそも、彼がリュイセンの立場に置かれたなら、初めから全員を確実に屠っていた。拘束するにとどめたリュイセンは、甘いのだ。
タオロンの影が、男のすぐそばまで近づく。
そして、彼は息を呑んだ。
――リュイセンの奴……。
吸い込んだ息が、鉛のような重さを伴って吐き出される。
拘束された男たちは皆、お手本のような太刀筋で綺麗に急所を外されていた。出血は派手だが、命に別条はない。
リュイセンは、多勢に無勢の不利を補うために、脅しの効果を狙って流血沙汰にしただけなのだ。彼らが気を失っているのは、峰打ちなり、当て身なりのためで、失血が原因ではない。
タオロンは、刀を持っていないほうの手で、バンダナに触れた。
『ファンルゥ、知っているもん! パパのバンダナは、ママのおまじないでしょ! 『パパ、頑張って!』って、ママが言っているの!』
小さな彼の娘は、頬を擦り寄せ、バンダナの結び目に手を伸ばした。
それに対し、彼は彼女を抱きしめ、こう答えた。
『パパが、正しいことを頑張れるようになる、魔法のバンダナだ』
「――……!」
タオロンの手から、刀が滑り落ちる。
銀色の刀身が、ぎらりと光を放ちながら床に突き刺さり、タオロンの黒い影を貫く。
『俺の手を取ってくれるか?』
藤咲メイシアに指定された娼館で、ルイフォンが右手を差し出してくれた。
以前、彼らが――ルイフォンとリュイセンが――この館に侵入したとき、〈蝿〉の前で『俺たちの手を取れ』と言ったときのやり直しだった。
「……俺は、『あいつら』と手を結んだんだ」
ルイフォンと。
そして、リュイセンと。
タオロンはバンダナの結び目に手を触れ、柔らかに微笑む。そして、後ろを振り返ることなく反省房を出た。
一刻も早く、ルイフォンに現状を伝える必要があった。
――リュイセンが、自力で反省房から脱走した。
タオロンからの報告を受け、ルイフォンは愕然とした。
「何が起きたの?」
ただならぬ様子の彼に、向かいに座っていたミンウェイが尋ねる。
彼女に限らず、携帯端末での通話の声は、他の者には聞こえない。皆、緊張の面持ちでルイフォンに注目している。
ルイフォンは、ごくりと唾を呑み込んだ。そして、耳にしたばかりのタオロンの野太い声を繰り返す。
「リュイセンが、自力で反省房から脱走した」
豊かな表情を持つ彼の顔が、彫刻のように作り物めいていく。冷静に状況を分析する、無機質な〈猫〉の顔となる。
「リュイセンは〈蝿〉を殺すつもりだ」
硬質なテノールが、執務室の空気に圧をかけた。
「えっ……!? どうして、そうなるの?」
弾かれたように問うてくるミンウェイに、ルイフォンは声色を変えぬままに答える。
「不本意ながらも〈蝿〉に従っていたリュイセンが、ここで反旗を翻したなら、それは、あいつが〈蝿〉を殺す決意をしたということに他ならない。――素直に反省房に入ったのは、単に夜になるのを待っていただけだ。あいつも今夜、動くつもりだったんだ」
ルイフォンは奥歯を噛みしめる。無表情になっていた顔が、苦しげに、悔しげに歪められる。
――どうして、リュイセンの心情を読み解けなかったのだろう?
兄貴分もまた〈蝿〉を殺す機会を狙っていると、分かっていたのに。
そして、気づいていたのに。
ことを為したあと。
高潔な彼は、一族を裏切った罪を背負い、姿を消すつもりだと……。
思考を闇へと傾けた刹那、ルイフォンは戦慄に襲われた。
リュイセンを永遠に失う。――その可能性に、感情が凍りつく。
『ルイフォン? 何があったの?』
困惑したメイシアの声が、執務室のスピーカーから流れた。
携帯端末にタオロンからの連絡が入ったとき、ルイフォンは、メイシアと繋がっていた電話の受話器をテーブルに置いた。だから、一応は音を拾っているはずだが、小さな送話口の集音能力では、執務室のやり取りを満足には伝えられまい。彼女には、何がなんだかさっぱりだろう。
メイシアにも状況が伝わるよう、会議システムに切り替えなければ……。
のろのろと立ち上がるルイフォンに、ミンウェイが不審に眉を寄せる。しかし、すぐに草の香を散らして動き出した。彼女には彼の気持ちは分からなかったが、自分がやるべきことに気づいたのだ。
ミンウェイはテーブルの上にさっと手を伸ばし、メイシアと繋がっている電話を取った。そして、執務室の現状を手短に説明する。
直後、メイシアの驚愕の息遣いがスピーカーを震わせた。
『リュイセンを止めないと……!』
悲鳴のような声が細く響く。
『〈蝿〉に与えるものが、最終的には『死』であることは変わらなくても、それは、こんな形じゃない! 〈蝿〉は捕まえて、ミンウェイさんと会って、ミンウェイさんと話をして……!』
「ああ、分かっている!」
猫背を丸めながら会議システムの準備をしていたルイフォンは、吐き捨てるように叫んだ。険のある声は八つ当たりだと思いつつ、押さえられなかった。
「リュイセンを止められるのは、タオロンしかいない。だから今すぐ、タオロンにリュイセンを探しに行ってほしい。――けど!」
ルイフォンは唇を噛む。鉄の味が口の中に広がる。
「ファンルゥが部屋で寝ている。タオロンに起こしに行ってもらわないと駄目だ!」
タオロンは、裏切りを知られた私兵を殺さなかった。
それは、リュイセンの行動を認め、ルイフォンなら対処できると信じてくれたからだ。
悪手だなんて思わない。仲間として、最高の判断だ。
その私兵が目覚め、拘束を解いて〈蝿〉に連絡するまで、それなりの時間は掛かるだろう。だから、ファンルゥは危険に直面しているわけではない。
……だが、彼女の安全の確保は最優先であるべきだ。
ならば、タオロンには、まずファンルゥを起こしに行ってもらって、それからリュイセンを探すのでよいのではないか。ルイフォンが先ほど懸念したように、〈蝿〉に手を出すことができるのは奴が廊下を歩いているときだけ。いつもの行動パターンなら、奴の就寝時間には、まだ余裕がある。
「……っ」
今日は、『いつも』ではない。
〈蝿〉はリュイセンを捕らえ、明日になったらメイシアと話をすると宣言している。早めに床に就く可能性は充分にあり得る。
――どうすべきか。
迷っている暇などない。決断せねば。
早鐘を打つ鼓動が、ルイフォンを急き立てた。ただ指先だけが、慣性に従うかのように機械的に動き続け、会議システムを構築する。
モニタ画面の不安定な波の向こうに、メイシアの花の顔が映し出された。
その映像が凪いだ瞬間、毅然と向けられた黒曜石の瞳に、ルイフォンはどきりとする。
『ルイフォン!』
険しさをたたえながらも、高く澄んだ透明な声。
『私が、ファンルゥちゃんを迎えに行きます。だから、タオロンさんにはリュイセンを探してもらって』
「!?」
一瞬、何を言われたのか理解できなかった。
猫の目を見開いたまま、ルイフォンは表情を止める。そんな彼に、メイシアは必死に言を継ぐ。
『私は、ここに閉じ込められているわけじゃないもの』
「メイシア……?」
『この展望室の鍵は内鍵で、私は自由に開けられる。そして、この展望塔からは、階段の明かり取りの小窓から出られる。――ファンルゥちゃんが初めてここに来たとき、教えてくれたの』
「あ、ああ……」
『だから、ファンルゥちゃんが来てくれるときと逆のルートで、私がファンルゥちゃんの部屋に行く。そして、彼女を起こして、一緒にこの展望室に戻ってくる』
「なっ……!」
ルイフォンは絶句した。
彼だけではない。執務室にいる誰もが唖然としている。
「危険だ! ファンルゥの部屋へは、雨どいを伝って窓から入るんだぞ! そんなこと、お前にさせられない」
あれは身が軽くて、普段から飛び回っているようなファンルゥだからこそ、可能な技なのだ。メイシアだって決して重くはないが、どう考えたって無謀だ。
『でも、リュイセンを止めるのも、ファンルゥちゃんを起こすのも、この庭園にいる人間しかできないの。なら、私とタオロンさんで分担するべきでしょう』
「だからって、無茶を言うな!」
『そして、リュイセンを探すのは、この庭園内を動き回っても不審に思われないタオロンさんのほうが向いているし、ファンルゥちゃんは私のところに来るのだから、私が迎えに行くのが適当』
「駄目だ!」
ルイフォンが吠える。
こんな議論をしているくらいなら、余計なことは考えずに、さっさとタオロンにファンルゥを起こしに行ってもらうべきだろう。メイシアの言う通り、あの庭園のことは、あの庭園にいる人間にしか手を下しようもないのだから……。
「糞っ!」
ルイフォンは、やり場のない思いを床に向かって吐き捨てた。
反動で、後ろで一本に編まれた髪が、胸元に飛び込む。毛先を留める金の鈴が、鈍い光を放ちながら視界に映り込んだ。
――本当に、そうか……?
遠く離れているから、何もできない?
「違う……」
『ルイフォン?』
「俺は、〈猫〉だ。――遠隔攻撃が得意な、魔術師だ……」
口の中で言葉を転がし、虚空をじっと見据える。
そして、はっと閃いた。
「俺に任せろ! ファンルゥのことは、俺が守る!」
ルイフォンは勢いよく立ち上がる。
煌めきを取り戻した金の鈴が、彼の背で挑むように跳ねた。
「鍵だ! 仕事部屋に行ってくる!」
『鍵?』
メイシアは勿論、彼の叫びを聞いた皆が首をかしげる。
当然だろう。これは、〈猫〉ならではの発想であり、手段だ。
ルイフォンは執務室を飛び出そうとしていた足を止め、猫背を正して胸を張る。
「メイシアの展望室が内鍵であるように、ファンルゥの部屋だって内鍵だ。だから、ファンルゥの身が危険に晒されるのは、『鍵を持った私兵が、外から鍵を開けて入ってくる』とき。ならば、俺が――〈猫〉が、私兵の持っている鍵を無効化すればいい」
「どういうこと?」
皆を代表するように、近くにいたミンウェイが、すかさず問う。
ルイフォンは猫の目を光らせ、不敵に嗤った。
「あの館の鍵は『電子錠』だ。電子的に管理されているものは、〈猫〉の支配下にあると言っていい。しかも、あの館の鍵なら、偽造カードキーを作ったときに仕組みを調べ上げているから、すぐにも俺は動ける」
「ええと? つまり、何をするつもりなの?」
回りくどいと思ったのだろう。ミンウェイが、焦れるように柳眉を寄せる。
ルイフォンは、自分中心の説明だったなと、ほんの少しばつが悪そうに前髪を掻き上げ、しかし、得意げに答えた。
「仕事部屋からの遠隔操作で、ファンルゥの部屋の鍵を、今とは別の番号に変えて施錠する。これで、私兵は入ってこられない。ファンルゥは、安心して寝ていて大丈夫だ」
執務室が沸き立った。
遥かな庭園にいるメイシアとタオロンも、それぞれの回線を通してルイフォンの弁を聞き、胸を撫で下ろす。
「タオロン。すまないが、リュイセンを探してくれ。あいつは〈蝿〉を狙って現れるはずだ」
『分かった』
ルイフォンは身を翻し、仕事部屋へと向かう。
皆が讃える声を背中に、段々と冷静になってきて、彼は思う。
……実は、俺がもっと早く、鍵に注目すればよかっただけじゃないのか?
鍵を自在に扱えるのなら、〈蝿〉の寝室だって、奴が寝入った真夜中に開けることができる。時間を気にして焦る必要もない。
誰も見ていない廊下で彼は赤面し、面目なさそうに髪を掻き上げた。
――どすん。
何かが打ちつけられるような物音で、ファンルゥは目を覚ました。
彼女は目をこすり、自分がベッドではなく、テーブルに突っ伏して眠っていたことに首をかしげる。
――どすん。
再び、音がした。
部屋が揺れているような気がした。
「なんの音?」
ファンルゥは、椅子を飛び降り、気になる音を確かめに行く。
ルイフォンが守りを固めた扉からではなく、『窓の外』から響く音の、謎を解きに――。
9.猛き狼の啼哭-1

反省房を脱走したリュイセンは、武器庫を制圧し、愛用の双刀を取り戻した。腰に掛かる愛刀の重みは心地よく、まるで本来の自分へと返ったかのような気分になる。
彼はそのまま、紺碧の夜が支配する館の外へと身を躍らせた。この季節らしい生ぬるい風が、ふわりと髪を巻き上げる。
空を見上げれば、燦然と輝く、真円にほど近い月。
目線より、やや高い位置から注がれる白い光が、彼に時を告げていた。〈蝿〉が研究室から出てくる頃合いまで、あと少し。それまでに、速やかに準備を整えろ――と。
今宵、〈蝿〉を殺す。
昼間に決意した。
そのあとで、〈蝿〉に捕らえられた。
メイシアの昼食のワゴンを下げに行った厨房で、私兵を率いた〈蝿〉が待ち構えていた。非常ベルを鳴らして騒ぎを起こした罰だと言われ、反省房に入れられた。
抵抗はしなかった。する意味がなかった。行動を起こすのは夜だと決めていたから、それまでの数時間を過ごす場所が充てがわれた自室ではなく、反省房に変わっただけだ。
何も問題はない。
何故なら『反省房』などと呼ばれているが、そこはただの部屋なのだ。内鍵だから、いつでも外に出られる。見張りはつくであろうが、そんなものは倒せばよい。〈蝿〉の雇った私兵ごときが束でかかってきたところで、リュイセンに敵う由もない。
それよりも下手に〈蝿〉を怒らせて、薬物を投与されることが怖かった。いくら鍛え上げた肉体でも、思うように動かなければ価値を失うのだから。
――そう考え、おとなしくしていた甲斐があってか、リュイセンは難なく反省房を脱し、こうして愛刀を佩いている。
あとは〈蝿〉を討つだけ……だがその前に、斑目タオロンに会って、あとを託す必要があった。
〈蝿〉が死ねば、脳波でスイッチが入るというファンルゥの腕輪の毒針は無効になる。だから、メイシアを連れてこの庭園を脱出し、彼女を鷹刀一族の屋敷に送り届けてほしい。タオロンとファンルゥの今後なら、警備会社を経営しているリュイセンの兄夫婦のところに行けば、必ず受け入れてもらえるから。どうか頼む――と。
リュイセンは、館の影に隠れながら移動する。非常階段の近くで立ち止まり、タオロンの部屋の窓を探した。
脱走中の身としては、館内をうろついて夜回りに見つかるのは厄介であるため、館の内部からではなく、外からの訪問を目指すのだ。そもそもタオロンの部屋は、常に監視のついているファンルゥの部屋の隣だ。中から行けば、必ず私兵に見つかってしまうだろう。
「俺の見張りの中に、タオロンがいればよかったんだがな」
夜闇に溶けるような声で、低くぼやく。
タオロンは、この館で唯一、リュイセンに匹敵する猛者だ。見張りには、うってつけのはずなのだが、リュイセンにタオロンを近づけるのは危険だと、〈蝿〉は警戒したのだろう。
事実、リュイセンの手には、双刀と共に武器庫から持ち出したタオロンの大刀が握られており、これから彼は、それを持ち主に返して頼みごとをしようとしている。〈蝿〉の読みは正しかったといえよう。
月光を浴びて朧に浮かび上がる館を仰ぎ、端から窓の数を数えていたリュイセンは、ふと首をかしげた。
角部屋がファンルゥで、その隣がタオロンの部屋のはずだった。
けれど、ファンルゥの部屋にだけ明かりが灯っていて、タオロンの部屋が暗い。小さな子供はとっくに寝ている時間だと思うのだが、元気なファンルゥが遊び足りないと、タオロンを困らせているのだろうか。
できればファンルゥのいないところで『〈蝿〉暗殺』を口にしたかったのだが……。
リュイセンは眉を寄せ、美麗な顔をしかめる。
「仕方ねぇよな」
彼は溜め息をつきつつ、非常階段を登る。
ファンルゥは雨どいを伝って非常階段と窓を行き来していたようだが、体重の重いリュイセンに同じことはできない。だから、武器庫から失敬してきたナイフを壁に刺し、それを手掛かりにして、窓まで移動する肚だ。さすがにタオロンの大刀を持ったままでは動きが制限されるので、それは草むらに隠していった。
ファンルゥの部屋がある階に上がり、窓までの目算を立てる。たいした距離はない。リュイセンは懐からナイフを取り出し、壁の目地を狙って思い切り突き刺した。
――どすん。
思うようには深く刺さらない。
だから再び、更に力を込めて打ち込み直す。
――どすん。
ファンルゥの部屋の窓硝子が、共鳴するように揺れた。
そして……。
「なんの音?」
舌足らずな高い声。ファンルゥだ。
ガタガタと椅子を引きずる音が響き、がらりと窓が開けられる。続いて、ふわふわとした毛玉のような影がひょっこりと現れた。
「リュイ……!」
叫び声の途中で、ファンルゥは自分の口を小さな両手でしっかりと押さえ込んだ。くりっとした目を見開いて、ぶるぶると激しく首を振る。
『ファンルゥ、大きな声なんか出してないもん。うるさくしたら駄目だって、ちゃんと知っているもん』と訴えているのだが、リュイセンには伝わらない。だが窓が開いたことで、ナイフに頼らずとも手を伸ばせば窓枠に指を掛けられると判断した彼は、「ファンルゥ、ちょっと下がってくれ」と小声で叫んだ。
ファンルゥは大きく頷き、部屋の中に姿を消す。それを見届けると、リュイセンは、あたかも月夜を駆ける若き狼が如く、非常階段から軽やかに跳び立った。
ほとんど物音を立てず、危なげなく窓から飛来したリュイセンを迎えたのは、全身で喜びを示す、小さな抱擁だった。
「リュイセン、無事だったぁ!」
声は潜めているものの、細い腕が力いっぱい、しがみついてきた。すりすりと嬉しそうに頬を寄せてくるファンルゥに、リュイセンは面食らう。
部屋を見渡せば、そこにいると思っていたタオロンの姿がない。
どういうことだ?
リュイセンは眉を寄せる。
タオロンは、こんな時間に幼い娘を放置するような輩ではないはずだ。なのに、ベッドは綺麗なままで、ファンルゥは寝間着にすらなっていない。
明かりの消えていた隣のタオロンの部屋は、やはり無人だ。非常階段からではさすがに判別できなかったが、こうして壁一枚の距離まで近づけば、気配に敏いリュイセンには断言できる。
では、タオロンは、どこに行ったのだろう。
そう考えて、リュイセンはある可能性を思いつく。
何かのきっかけで、早くもリュイセンの脱走がばれてしまったのだ。そして彼を捕獲するため、タオロンは〈蝿〉に呼び出された……。
「リュイセン? パパは一緒じゃないの?」
深刻な顔で押し黙ったままの彼を、ファンルゥが不思議そうに見上げる。
「え?」
「パパは、〈蝿〉のおじさんに捕まっちゃったリュイセンを助けに行ったの……」
言いながら、ファンルゥも何かがおかしいと感じたのだろう。言葉尻が、ごにょごにょと崩れていく。
「なるほど。タオロンが俺を助けに、か」
だから、部屋を空けていたのだ。
「俺は、自力で反省房を脱してきた。どうやら、タオロンとはすれ違ったようだな」
リュイセンの言葉に、ファンルゥはしばらく考えるような仕草を見せ、それから、やっと、こくんと頷く。少し言い方が難しかったらしい。理解するのに時間が掛かったようだ。
ともかく、タオロンの不在には納得した。しかし、今まで〈蝿〉の従順な部下であった彼が、どうして急に裏切るような真似をするのだろう。
彼にとって、リュイセンを助けることは、たいして重要なことではないはずだ。それに、ファンルゥの腕輪の毒針がある以上、彼は決して〈蝿〉に逆らうことはできないはず……。
リュイセンは、ちらりとファンルゥの手首に目をやり、はっと息を呑む。
「ファンルゥ! 腕輪は!?」
細い手首を飾る、模造石の煌めきが消えていた。子供の持ち物としては優美すぎて、それ故に、ファンルゥのお気に入りだった品だ。
「かゆいから、外しちゃった」
「なっ!? タオロンは何も言わなかったのか!?」
「初めはパパには内緒だったけど、かゆいならいいって。……〈蝿〉のおじさんにばれるのは駄目だけど」
ファンルゥは、いたずらな子供そのものの顔で、可愛らしく答える。見れば、彼女の手首は確かに赤い。ずっと付けっぱなしにしていれば当然だった。
しかし、かぶれ以外には、ファンルゥの皮膚に異常はない。つまり、無理に腕輪を外したら毒針が出るというのは、真っ赤な嘘。
またしても、〈蝿〉の虚言に踊らされていただけだったのだ。
リュイセンは歯噛みする。だが、父親であるタオロンの憤りは、彼の比ではなかったことであろう。
――そのとき。
「リュイセン!」
ファンルゥが大真面目な顔で彼の名を呼び、そばにあった椅子にぴょんと飛び乗った。先ほど、彼女が窓を開けるのに使った椅子で、今度は長身の彼の耳元で囁くために使うらしい。口元に手で筒を作りながら、彼に寄ってくる。
「えっとね、今日は、凄く大事な日なの!」
扉の外にいる見張りを警戒しての内緒話のつもりなのだろう。そのわりには弾んだ声が大きい。
リュイセンは美麗な顔をしかめた。だがそれは、ファンルゥの声量のせいではなく、リュイセンの都合のためだ。彼は迅速にタオロンと話をつけ、寝床に戻る〈蝿〉を待ち構え、討たねばならぬのだ。可哀想だが、ファンルゥの話に付き合っている場合ではない。
このまま、ファンルゥの部屋で待っていれば、タオロンはいずれ戻ってくる。だが、それより置き手紙をして、さっさとこの場を立ち去るほうが賢明だろう。
そんなことを考えていると、ファンルゥの細い指がリュイセンの頭を捕まえた。椅子を使っても身長の足りない彼女が、彼にしがみつくようにして背伸びをしたのだ。
そして、今度は正しく小さな囁きが、耳の中に吹き込まれる。
「これから皆で、ここを出るの!」
「!?」
衝撃に、リュイセンは言葉を発せなかった。
それは、これから彼がタオロンに持ちかける予定の計画で、間違っても、小さなファンルゥから聞く話ではないはずだ。
「リュイセン、パパに会ってないから、知らないの。でも、今日なの!」
無理な背伸びをやめたファンルゥが、嬉しそうに告げる。
「リュイセンは〈蝿〉のおじさんから逃げてきたあと、パパのところに隠れようと思って来たんでしょ! リュイセンと『すれ違い』しないで、本当によかった!」
ひとりで、こくこく頷きながら納得し、ご機嫌な様子で癖っ毛を跳ねかせるファンルゥに、リュイセンは焦る。彼の知らないところで、物ごとが激しく動いていた。
「おい、そんなことを言われても、俺は知らな……」
「だから、リュイセンは知らないから、今、ファンルゥが教えてあげたの! メイシアがずっと言っていたでしょ! 皆で、ここを出よう、って!」
「――!」
ファンルゥの言葉で思い出した。
そういえば、メイシアが囚われてすぐのとき、ファンルゥは彼女に会いに行ったと報告してきた。体の小さなファンルゥなら、展望塔の小窓から忍び込めるのだと言っていた。
『リュイセン……、メイシアがね、皆でこの庭園を出よう、って言っているの……。ファンルゥやパパも一緒。勿論、リュイセンもだよぅ……』
リュイセンの部屋に侵入し、寝ぼけ眼で待っていたファンルゥは、寝言のように呟いた。
あのとき既に、メイシアは、ファンルゥの腕輪が無害なものだと見抜いていたのだろう。脱出するだけなら、すぐにも可能だったのだ。
けれど、メイシアは、リュイセンが彼女の手を取るのを待っていた。
そして、彼の協力で、『デヴァイン・シンフォニア計画』の詳細を知る〈蝿〉を捕らえた上で、皆で庭園を出たいと考えていた。
だが、今日の昼、メイシアは〈蝿〉に生命を脅かされ、リュイセンは反省房に囚われた。これ以上、この庭園にいるのは危険だと判断した彼女は、急遽、脱出へと舵を切ったのだろう。そう考えれば、タオロンの行動も納得できる。
「……なるほど」
メイシアの判断は正しい。
だがリュイセンは、彼女の手を取るわけにはいかない。
ミンウェイを脅かす〈蝿〉を滅することなく、この庭園を離れることはできない。
そして奴の息の根を止めたのちは、ミンウェイの『秘密』を知る彼もまた姿を消し、彼女の心の安寧を永遠に守るのだ。
彼は祈るように胸に手を当てる。
純粋な想いと引き換えに、彼はその身を昏い闇に堕とす。
「リュイセン?」
遠い目をした彼に、不安を感じたのだろうか。緊張を帯びた丸い目が、じっと彼を見上げていた。
「ファンルゥ」
彼女を安心させるよう、リュイセンは優しく呼びかける。
波長の長い低音は、特に声量を抑えなくとも聞こえにくく、けれど緩やかに広がり、回析してファンルゥを包み込んだ。
「反省房に俺がいないのを知れば、タオロンはファンルゥのところに戻ってくるだろう。そしたら、この部屋の真下の草むらに大刀を隠してあると、彼に伝えてくれないか」
「?」
「そして、メイシアとファンルゥを連れて、この庭園を脱出してほしい。メイシアを鷹刀の屋敷に送り届ければ、タオロンは俺の兄の会社で雇ってもらえるはずだ」
「……」
元気に跳ねた癖っ毛を揺らし、ファンルゥの頭がきょとんと傾く。
子供に不慣れな彼は、また難しい言い方をしてしまったらしい。いったい、どうしたら伝わるのだろう。
リュイセンは戸惑い、必死に言葉を探す。
そのときだった。
「――リュイセンは?」
細く高い声だった。
なのに、リュイセンは、そのひとことに恐ろしいほどの威圧を感じた。
「リュイセンは、どうするの?」
「俺は……」
「皆で、ここを出るの。ファンルゥは、そう言ったの」
リュイセンの喉が、ひくりと動いた。けれど、声が出ない。
……嘘をつけばいいのだ。
やらなければならないことがあるから、別行動を取るのだと。
あとで追いつくから、庭園の外で会おう――。
頭では分かっていたのに、とっさに言うことができなかった。
「リュイセン!」
椅子に乗っていても、リュイセンよりもずっと低い位置に頭のあるファンルゥは、だから、顎をぐっと上げることで彼に詰め寄った。
「〈蝿〉のおじさんの手下になって、メイシアをさらってきたことを気にしているんでしょ!? 大丈夫! メイシア、怒ってないもん!」
彼が言葉を濁す理由を、彼女なりに考えてくれたらしい。
思い込みの激しい、けれど優しい気遣いに、リュイセンは、ほんの少しだけ口元を緩めながら首を振る。
「合わせる顔がない。――俺は一族も、ルイフォンも裏切った。だから、帰ることはできないんだ」
素直な気持ちが、思わずこぼれた。
それは、口にする必要のない言葉だった。――否、口にしてはならない言葉だった。
「それで?」
「え?」
ファンルゥのまとう気配が変わった。
強い意思を持つ太い眉と、その下のくりっとした大きな瞳が、リュイセンに鋭く攻め入る。
「『さよなら』なの?」
「……っ」
「そういうことでしょ? だって、リュイセン、『ごめんなさい』できなくて、どっか行っちゃうって、言ってるんだもん」
「……なっ!?」
言われた瞬間、リュイセンの顔が憤怒に歪んだ。
そんな子供の喧嘩のような問題ではない。
リュイセンは激昂しそうになり……その寸前で思いとどまる。
子供が、子供なりの解釈で口をきいただけだ。それに対して、目くじらを立てて声を荒らげるのは、あまりにも大人げないだろう。
「そういうことになる……かな」
不本意だが、曖昧な言葉でファンルゥを肯定した。逆らわないほうが、こじれなくていいだろうと思った、それだけのことだった。そして今度こそ、嘘の口約束で……。
「駄目!」
「……っ」
舌打ちのような息が、リュイセンの口から漏れる。ファンルゥから解放されたいとの思いからか、無意識に体が一歩、下がる。
すると、小さな手が伸びてきて、彼の服を掴んで引き寄せた。
まるで睨みつけるような双眸にリュイセンは捕らえられ、動きを封じられる。
「『さよなら』には、ふたつあるの」
「『また会える、さよなら』と、『二度と会えない、さよなら』」
「ファンルゥは、『二度と会えない、さよなら』をたくさん知っている」
畳み掛けるようにそこまで言ったとき、不意にファンルゥの体が大きく震えた。
リュイセンは息を呑んだ。
彼女が次に口にするであろう言葉に気づいてしまったのだ。
耳をふさぎたかった。けれど、そこまで言わせてしまった彼に、その資格はなかった。
そして――。
「ファンルゥは、ママには会えない! どんなに会いたくても、絶対に会うことはできない!」
可愛らしい、舌足らずな声が、氷を弾いたように冷たく響き渡る。
ファンルゥは知っている。
画用紙に描いた世界では母親に会えても、現実の世界では決して会うことはできないと。
「ママは死んじゃったから、会えない。でも、生きていても会えない『さよなら』だって、ファンルゥは知っているよ」
くりっとした瞳が、ひときわ大きく見開かれた。
「お世話係のキツネのおばちゃんも! 『天使の国』に帰っちゃったホンシュアも! もう会うことはできない。ファンルゥの力じゃ、どうにもならない、って、ファンルゥは知っている! どんなに、ファンルゥが会いたいと思っていても――!」
どんっ、と。
小さな体が、まるごとリュイセンに飛び込んできた。突然のぬくもりに、彼は戸惑い、呆然と立ち尽くす。
「リュイセン! どっか行っちゃ、嫌ぁ!」
薄手のシャツを通して、熱い涙がリュイセンの胸に掛かった。
錯覚だと分かっていても、皮膚を灼かれている気がした。
焦がれるようなファンルゥの思いに、呑み込まれそうになる。
『二度と会えない、さよなら』
――果たしてリュイセンは、その『さよなら』を知っているだろうか……。
「ファンルゥ、すまん!」
リュイセンは、手荒にならないように注意しながらも、ファンルゥの体を勢いよく引きはがした。
「リュイセン!?」
「俺には、やるべきことがあるんだ」
そう言い放ち、リュイセンは床を蹴る。開け放したままであった窓へと、ひらりと身を翻す。
下は草原だ。このくらいの高さなら、怪我などしない。
――ミンウェイを守るのだ……。
彫像めいた美貌が、月を仰ぐ。
その仕草は、まるで月に吠える狼のよう。
肩で揃えられた髪が流れ、無音の哭き声が響いていた。
9.猛き狼の啼哭-2

「リュイセン!」
ファンルゥは、リュイセンが身を躍らせた窓へと駆け寄った。
しかし、彼女の背丈では、爪先立ちになっても外は見えない。慌てて取って返し、椅子を引きずってくる。
ぴょんと飛び乗り、眼下を見やれば、そこは一面の草の海だ。ただし、見慣れた緑の野原ではない。昼とは違う、黒い波がざわざわと揺れている。
「……」
たとえ夜でも、月明かりに照らされて、リュイセンが駆けていく姿が見えるものと思っていた。しかし、月はファンルゥが考えているほどには明るくなく、部屋の電灯に慣れた目には世界は真っ黒に映った。
まるで黒い波濤に呑まれてしまったかのように、リュイセンは消えてしまった……。
想像していなかった風景に、ファンルゥは焦る。
「リュイセン……」
大声を出すのは駄目だ。ファンルゥの部屋の前には見張りがいる。
「どうしよう……」
そのとき、絡繰り時計が、ぎぃと音を立てた。
文字盤の数字が裏返り、後ろに控えていたピエロが現れる。
赤いピエロではない。メイシアのところに行く約束の時間を教えてくれる彼なら、とっくに帰ってしまった。だから、別のピエロ。青いピエロだ。
「青いピエロさん……?」
軽快な音楽に乗って登場するはずのピエロが、演奏なしで静かに踊っていた。
ファンルゥの就寝時間を過ぎているので、音が鳴らないように設定されている。それだけのことなのだが、ファンルゥには特別なことに思えた。
『ファンルゥ、見張りに気づかれないように、こっそり聞いて』
無言で踊るピエロが、ファンルゥに呼びかける。
『これから皆で、ここを出るんでしょ?』
ファンルゥは、こくりと頷く。
『じゃあ、どうするの? ファンルゥはどうすればいいの?』
無論、青いピエロは、ただ踊っているだけだ。ファンルゥに話しかけたりなどしない。
けれど、ファンルゥが自分の中に持っている答えを引き出すのに、充分なきっかけを与えてくれた。
『俺には、やるべきことがあるんだ』
ファンルゥの耳の中に、リュイセンの声が蘇る。
「リュイセンには、リュイセンのやることがある……」
『やること』のために、彼は出ていったのだ。ならば、ファンルゥはリュイセンを追いかけてはならない。彼の邪魔をしたら駄目だ。
それに、リュイセンなら自分から戻ってきてくれる。――そう思う。リュイセンなら、絶対……。
「じゃあ、ファンルゥは?」
ファンルゥにも、ファンルゥのやるべきことがある……?
「ああ!」
小さな肩が跳ね、くりっとした目がまん丸になった。
「メイシアのところに行かなきゃ!」
きっと、メイシアは心配している。
ファンルゥは、急いで出発の準備を始めた。
この部屋には素敵なものがたくさんあるけれど、本当に大切な宝物は、ひとつだけ。父親のタオロンがこの前、買ってきてくれた『ご褒美』だけだ。ファンルゥは、それをポケットにしまった。間違っても落としたりしないように、ぐいぐいっと奥深くに。
それから、ほんの少し顔をしかめてから〈蝿〉に渡された模造石の腕輪を手首にはめる。
かゆくなるから嫌なのだが、これから外に出るので、〈蝿〉の言いつけを守っているふりをしなければいけないと考えたのだ。
「ピエロさん、ありがとう! ファンルゥ、行くね!」
声に出して告げたら、急に寂しくなって、ちょっぴり涙がこぼれそうになった。
さっきは『ご褒美』以外は、置いていって構わないと思ったけれど、いざお別れとなると胸が苦しい。窮屈で退屈な日々だったけれど、この部屋も、ここにある玩具たちも、ファンルゥにとても優しくしてくれた。
「……でも! ファンルゥには、やるべきことがあるの!」
自分を奮い立たせるように言い放ち、スイッチに背伸びして電灯を消す。
そして、ファンルゥは夜の海原へと旅立った。
夜の暗さもなんのその、ファンルゥは軽やかに雨どいを伝い、草原に降りた。
窓からの印象通り、地上は黒い海が広がっているようだった。ざわめく草の音は、まるで潮騒だ。
見渡す限り、外灯はひとつもない。
この庭園は、王の療養のために作られた施設であり、安らぎの静かな夜を主に捧げるべく、無粋な光を抑えているのだ。
とはいえ、目が慣れてきたのか、先ほどよりも月が明るい。移動に支障はない。
ファンルゥは、目指す展望塔を視界に捕らえた。
「綺麗……」
深い闇の向こうでは、壮麗な石造りの塔が白く浮き立っていた。外壁に取り付けられた淡い明かりによるもので、外灯の代わりにと、庭園の設計者が趣向を凝らしたものらしい。
そして、最上階の展望室は、温かな光であふれている。まるで、黒い海を渡るファンルゥのための灯台のように。
メイシアだ。
メイシアが『こっちよ』と、ファンルゥを呼んでいる。
ファンルゥは、草の原を一目散に駆け出した。
時々、足を滑らせ、転びそうになりながらも、ぐっと踏ん張って前へと進む。
息が弾む。頬に受ける生ぬるい風を振り払い、先へと切り拓く。
走って、走って、展望塔はすぐそこだ。
近くまで来ると、外壁の明かりによって、入り口にいる見張りの男たちの顔がはっきり分かるようになった。だから、見つからないように。いつもの通り、こっそり裏側に回って……。
そのときだった。
ファンルゥの手首が、きらりと光った。
明かりが腕輪に当たり、模造石に反射して煌めいたのだ。
「ん?」
見張りのひとりが、不審の声を上げる。
「どうした?」
「今、何か光らなかったか?」
「ああ、俺も見た」
見張りの男たちが騒ぎ始める。
ファンルゥの心臓が、どきりと飛び跳ねた。
動いてはいけない。見つからないように、じっとしているのだ。
彼女は、強く自分に言い聞かせる。
「もしかして、塔の姫君に骨抜きにされたリュイセンが、反省房から脱走して姫のところに戻ってきたのか……?」
ひとりの男がそう言った。刹那、見張りたちの間に緊張が走る。
たいした技倆はないとはいえ、ここにいる者たちは皆、武に頼る生き方をしている。夜闇に光るものといえば、刃物の煌めきに決まっているのだ。
男たちは、見張りの特権で許された刀を次々に抜き放つ。
「待て」
血気はやる仲間たちに、ひとりが制止をかけた。
「迂闊に近づいたら危険だ。まずは俺がやる」
そう言いながら、男は懐から菱形の刃を取り出す。ルイフォンが使うのと同じ、投擲用の武器だ。
「リュイセンが飛び出してきたら、一斉に襲いかかるんだ。いくら奴でも、多勢に無勢じゃ敵わんだろう」
狙いをつけるため、男は素早く場所を移る。塔から少し離れた暗がりで、刃を構える。
月を背にしたシルエットが、ファンルゥの瞳に大きく映り込んだ。恐怖が焼きつけられる。足がすくんで逃げられない。
月が襲ってくる――!
男の腕が振り下ろされた。
指先から放たれた刃が、空を斬り裂く。
魂を凍りつかせるような、鋭利な輝き。それも一刀ではない。二刀、三刀と、続けざまに銀光が煌めく。
月光を宿した凶刃が、真正面から飛来する。
それを目にした瞬間、ファンルゥは短く息を吸い込み――……。
「ファンルゥ!」
艶めく低音が響き渡った。
大地を駆ける狼が如く、長身の影が神速で現れ、しなやかに跳躍する。そして、あたかも月光を奪い返すかのように、刃の軌道を遮った。
「――!?」
自分をきつく抱きしめる、逞しい両腕の強さ。ぴたりと密着した硬い筋肉と、そこから振動として伝わってくる、彼の背中に突き刺さる刃の衝撃。
胸板で視界をふさがれ、何も見ることはできないが、ファンルゥは全身で感じ取る。
「……リュイセン?」
「つっ……」
ファンルゥの髪に、苦痛の吐息が掛かった。
「リュイセン!」
血の臭いが鼻を突く。
時々、父親のタオロンから感じる臭い。
父が隠そうとしていることを知っているから、ファンルゥも知らんぷりしている臭い。
「どうして! どうして!」
どうして、リュイセンがここにいるのだ?
どうして、リュイセンから血臭がするのだ?
「嫌! 嫌ぁ――!」
叫びだしたファンルゥに、リュイセンが慌てて「静かにしろ」と短く命じる。
「安心しろ。かすり傷だ」
「え……?」
「後ろに下がっていろ。見張りを倒す」
彼はそう言って、ファンルゥを解放すると、腰に佩いた双刀を抜き放った。
リュイセンは双刀を高く掲げ、鋭い銀の煌めきを見張りたちに誇示した。
逃げも隠れもしない。相手をしてやる。
無言で宣告し、威圧の眼光を放つ。
「……っ、リュイセン……」
「やるしかねぇ……」
見張りたちにしてみれば、何が起きたのか、半分も理解できていなかっただろう。しかし、闘気を放つリュイセンを前に、戦う以外の選択肢はない。格の違いに、すっかり腰が引けていたが、それぞれに構えをとった。
実のところ、リュイセンの怪我は、かすり傷などではなかった。
筋肉の鎧をまとった彼の体は、多少のことではびくともしないが、先ほどの刃のうちの一本だけは運悪く深手となっていた。迂闊に引き抜けば、ひどい出血となるため、筋肉を締めて背中に刺さったままにしてある。
幸い毒は塗ってなかったようだが、できるだけ早く処置をしたほうがよいだろう。耐えることはできるが、ずきずきと強い痛みを感じる。自分としたことが情けないと、リュイセンは唇を噛む。
ファンルゥが狙われたとき、もっと彼女との距離が近ければ、愛刀で刃を弾き返すことができた。しかし、彼女に気づかれぬよう、遠くからそっと見守っていたために、駆け寄るだけで精いっぱいだったのだ。
……ファンルゥの部屋の窓から飛び出した瞬間、彼を呼び止める声が聞こえた。あの別れ方なら当然だろう。
大声はまずいと、ひやりとしたのだが、すぐに止んだ。うるさくしたらいけないのだと、ファンルゥはちゃんと知っているのだ。そして、感情を律することができる。恵まれない環境を生き抜くために、無邪気なその心を、切ないほどに押し込める術を知っている……。
『ファンルゥは、『二度と会えない、さよなら』をたくさん知っている』
舌足らずな声が耳に残っている。
リュイセンはそれを振り払うように頭を振ると、館の影に身を潜めつつ、〈蝿〉の部屋へと急いだ。寝床に戻ってきた奴を仕留めるのだ。チャンスは一度きり。逃してはならない。
そう思っていたのに、生ぬるい風の中に混じる、人の呼吸に気づいてしまった。
弾んだ息遣いは早く、間違いなく子供のもの。振り返れば、案の定、草原を走るファンルゥの姿が見えた。夜目の効くリュイセンには、月明かりで充分だった。
彼を探して駆け回っているのだと思い、舌打ちをした。脱走に慣れているのは知っているが、無鉄砲すぎる。特に、今は夜だ。どんな危険があるかも分からない。
困ったことになったと眉を寄せていると、彼女の走りに迷いがないことに気づいた。彼を求めて、さまよっているのではない。目的に向かって、まっすぐに突き進んでいる。
彼女の行く手を見やれば、幻想的に浮かび上がる展望塔があった。
リュイセンは得心した。ファンルゥはメイシアのところに行こうとしているのだ。皆でこの庭園を出ると言っていたから、合流する手はずになっていたのだろう。
彼は安堵の息を漏らすと同時に、ほんの少しだけ寂寥を覚える。迷惑だと思いつつ、彼女は自分を追いかけているものと信じて疑わなかったのだ。
――ともかく、彼女が無事に展望塔にたどり着くまで見守っていよう。
〈蝿〉の部屋へと急いでいたはずだが、放っておくことは考えられなかった。
そして、現在――。
リュイセンは、見張りの男たちと対峙する。
相手は五人。いつものリュイセンなら、しかも愛刀を取り戻した彼ならば、容易に瞬殺できる。けれど今は、背中に受けた傷のために無理が効かない。動きが制限される。向かってくる敵を斬り捨てるのはよいが、こちらから仕掛けにいくのは避けるべきだった。
「どうした? 多勢に無勢で、俺に襲いかかるのではなかったか? ――来いよ」
くいと顎を上げ、リュイセンは挑発する。黄金比の美貌が冷酷に歪み、月光を浴びて魔性をはらむ。
ごくりと唾を呑む音が聞こえた。男たちの緊張の息遣いからは、額から流れ落ちる冷や汗が見えた。リュイセンの目論見とは逆に、怖気づいた彼らは、向かってくるどころか身じろぎひとつできなかったのだ。
仕方ない……。
長引けば、最悪、痛みで気を失う可能性があった。
「そうか。ならば俺のほうから行こう」
口の端を上げた。
背中の負傷を微塵にも感じさせない、余裕の嗤笑……。
双子の刀が左右に広げられ、月光を弾いた軌跡がまるで白銀の翼に見えた。
天翔ける狼が、神速で男たちに迫る。男たちは、まるで喰らいつかれるのを待っているかのように、ただ呆然と立ち尽くし、あっけなく餌食となった。
――否。
ひとりだけ。先ほど刃を投げた男だけが、腰を抜かしかけながらも逃げ出した。
「応援……っ、呼んでくらぁ……」
長刀よりも投擲武器を主とする、前線よりも少し下がったところからの攻撃が得意な輩なのだろう。彼だけが、リュイセンとの正面衝突を避けたのだ。
「待てっ!」
リュイセンが叫ぶ。
あとを追うべく、足元に転がる男たちを飛び越える。
背中の傷をおして全力で走るのは望ましくない。しかし、逃げる男が、懐から携帯端末を取り出すのが見えたのだ。
そのとき。
男の前に、黒い巨体が立ちふさがった。
「ぐほっ!」
蛙が潰れるような声を上げ、男の体が沈み込む。
「……!?」
状況が掴めず、リュイセンは目を瞬かせる。そこに、ファンルゥの歓喜の声が響いた。
「パパ!」
彼女の言う通り、夜闇の中に斑目タオロンの巨躯があった。彼は、腹への一撃で倒した男を担ぎ上げ、急ぎ足でリュイセンのもとへとやってくる。そして、男を米俵のように放り投げ、空いた両手をばっと地に付け……土下座した。
「鷹刀リュイセン!」
タオロンは、勢いよく額を地面にこすりつける。
「ファンルゥのために……すまん! ありがとう、本当にありがとうよぅ……。お前は、ファンルゥの命の恩人だ」
最後のほうは涙声だ。
ファンルゥが「パパ」と駆け寄ると、彼は一度、愛娘を強く抱きしめてから、彼女を隣に座らせ、ぐいと頭を下げさせる。
「ファンルゥ。お前も、ちゃんとお礼を言うんだ!」
普段、さほど声を荒らげたりしない父の叱責に彼女はびくりと体を震わせ、けれど、リュイセンへの感謝の気持ちは彼女も同じだったので、彼女も父に倣う。ふわふわの頭が、ぴょこんと地面にくっついた。
「リュイセン! えっと……、大好き!」
タオロンの顔が凍りついた。
リュイセンは、どう反応したらよいのか分からず、目の前の父娘に交互に目をやり、視線をさまよわせる。
ともかく、タオロンが来ればファンルゥのことは心配ないだろう。
こちらから話を持ちかけなくとも、彼らはメイシアの主導で庭園を脱出する予定だ。引き止められる前に、この場を去るのが賢明だ。
そして、〈蝿〉を殺す――!
「リュイセン!」
気配を察したのだろう。タオロンの肉厚の手が、素早くリュイセンの肩を掴んだ。衝撃に背中の傷が、ずきりと痛み、思わず顔をしかめる。
「だいたいのことはルイフォンから聞いている。……皆が、お前を待っているぞ」
「!?」
リュイセンは耳を疑った。何故、タオロンがルイフォンと……?
「お前が今、〈蝿〉を狙っていることも知っている。俺はルイフォンから、お前を止めるように頼まれていて、お前を探していた」
「どういう……ことだよ……?」
自分の声が、自分のものではないように聞こえた。
「ファンルゥの部屋を出入りするお前をメイシアが見つけて、知らせを受けて飛んできた。――あとは、鷹刀の連中に聞いてほしい。俺じゃあ、詳しいことは分からねぇし、うまく説明できる自信もねぇ」
タオロンはそう言って、上空に向かって手を降る。
つられて見やれば、展望塔の最上階、展望室の窓に張りつくようにたたずむ、メイシアの影が見えた。彼女も手を振り返し、部屋の奥へと姿を消す。ほどなくして、塔の中からエレベーターの動く低い音が聞こえてきた。上階で彼女が呼んだのだろう。降りてくるつもりなのだ。
――駄目だ。
ミンウェイを苦しめる悪魔を放置することはできない。
リュイセンがタオロンの手を振り払おうとし、タオロンがそれに抗おうとしたとき、ファンルゥが「パパ!」と叫んだ。
「リュイセンには『やること』があるの。だから、邪魔しちゃ駄目なの」
ファンルゥはタオロンの足にしがみつき、駄々をこねるように体を揺らす。
「ファンルゥ、だが、ルイフォンが……」
「大丈夫だよ、パパ! リュイセンは 『やること』が終わったら、絶対、帰ってくる。ファンルゥは知っているもん!」
彼女はリュイセンに向かって、にこりと笑う。『二度と会えない、さよなら』じゃないよね? だから、行ってきて。――まっすぐな瞳が、彼を送り出す。
「ファンルゥ……」
寄せられた全幅の信頼が、タオロンの豪腕よりも強い力でリュイセンの足を縫い止めた。彼女自身は進めと言ってくれているのに。彼の心は行かなければと思っているのに……。
愛娘の妨害に、タオロンは太い眉をしかめていたが、はっと何かを思いつき、顔を輝かせた。
「ファンルゥ、リュイセンは大怪我をしている! 怪我には治療が必要だ!」
「あー……!」
これには、ファンルゥも押し黙るしかない。
無骨なタオロンにしては、珍しく気の利いた正論を言えた。そのことにタオロン本人が、ほっとする。そして、彼はリュイセンに向かって続けた。
「リュイセン、その背に刺さった刃は、自分で手当てするのは難しいだろう。俺にやらせてくれ」
「……」
タオロンの弁は紛うことなく正しく、ひとつも間違っていない。
背中の刃を引き抜けば、大量出血は免れない。止血の準備を万全にした上で、治療にかかる必要がある。ひとりでは不可能とは言わないが、困難を極めるだろう。
――しかし、〈蝿〉は今宵、仕留めなければならない。
リュイセンが拳を握りしめたとき、展望塔の中からエレベーターの到着するチャイムが聞こえた。メイシアが地上に降りてきたのだ。重たい音が響き、塔の入り口の扉が開く。
「リュイセン! ミンウェイさんが!」
携帯端末を片手に、メイシアが転がるように飛び出してきた。
そのとき、タオロンが息を呑んだ。
「そうだ、その名前だ! ルイフォンからの伝言があったんだ。すまん、忘れていた!」
タオロンは焦り、同時に、思い出せてよかったと胸を撫で下ろす。何故なら、それは先ほどの正論などよりも、よほどリュイセンを思う言葉だから……。
「『鷹刀ミンウェイという人物が、リュイセンと話をしたいと電話を待っている。だから、メイシアの部屋に行ってほしい。メイシアと鷹刀は、とっくに連携している』――だそうだ」
「――!?」
リュイセンは目を見開いた。
いったい、何がどうなっている――?
理解できない事態の連続に、頭の中が飽和する。耳鳴りがして、気が狂いそうだ。
黄金比の美貌が表情を失う。彫像のように立ち尽くすリュイセンに、メイシアが携帯端末を差し出す。
『リュイセン!』
無機質な端末から、生気に満ちた声が流れた。
忘れもしない、愛しい女の……。
緩やかに波打つ黒髪と、優しい草の香り。まっすぐに彼を見つめる切れ長の瞳が脳裏に浮かび、魂を揺さぶられる。
『お願い、話を聞いて! あなたの力が必要なの!』
別れすら告げずに彼女のそばを離れてから、いったいどのくらいの時が過ぎたのだろう。
餓えていた響きを耳にしたリュイセンは、糸が切れた人形のようにその場に崩れ落ちた。
9.猛き狼の啼哭-3

淡い明かりによって、白く浮かび上がる展望塔。その入り口の草地に、リュイセンは膝から崩れ落ちた。
かくりと頭が傾ぎ、揃えられた髪が肩を撫でる。しかし、他はどこも動かない。すべての力が抜け落ちてしまったかのように。
『リュイセン?』
携帯端末から、ミンウェイの声が響く。
端末を握っている己の手の感覚はあやふやなのに、聴覚だけは鋭敏で、流れてくる彼女の声を、言葉を、吐息を、リュイセンは必死に求める。
『リュイセン、どうしたの? お願い、返事をして!』
彼女に応えなければ。
彼女が心配している。彼女が不安がっている。
柳眉を下げ、綺麗な紅の唇が震えている。――見えなくても分かる。どうか、そんな顔をしないでほしい。
「ミンウェイ……」
やっとのことで、一番、大切な言葉を口にした。
だが、それ以上の声は出ず、頭も働かない。
『リュイセン!』
彼女が、彼の名前を呼ぶ。
それだけで、幸せだと思った。
その瞬間、彼は意識を手放した。
リュイセンが再び目を開けたとき、そこはメイシアに割り当てられている、ふたつの半円形の展望室のうち、食事に使うほうの部屋だった。
すべすべとした革の感触が頬を撫でた。どうやら負傷した背中に負担が掛からないよう、ソファーの背もたれを支えにして、横向きに寝かされているらしい。
「リュイセン! よかったぁ!」
すぐそばにいたファンルゥが彼に飛びつこうとして、すんでのところで留まった。
彼女はぶんぶんと首を振り、太い眉をぎゅっと寄せる。『リュイセンは怪我人なの。そっとしておかなきゃ駄目だって、ファンルゥ、知っているもん』という意味なのだが、残念ながら、リュイセンの目には謎の行動としか映らなかった。
そんな娘の背後から、父親のタオロンがぬっと顔を出した。
「刃は抜いたぞ。幸い、後遺症が残るような部位ではなかったから、安心してくれ」
タオロンは目を細め、安堵の息を吐く。
リュイセンはゆっくりと体を起こし、自分の状況を確認した。
上半身は裸で、シーツを裂いて作ったと思しき包帯がきつく巻かれていた。体は綺麗に拭かれているものの、周りの絨毯は血の吹き出したような跡で真っ赤に染まっている。気の弱い者なら卒倒しかねない惨状だ。あの刃を引き抜けば当然だろう。
そして、血臭もさることながら、酒の匂いが鼻につき、見るからに高級そうな酒瓶が転がっている。この部屋にあった、王の秘蔵の逸品を傷の消毒に使ったのだ。置き去りにされていたのだから構わないだろうが、世界一高価な消毒薬だったに違いない。
「お前が気を失っていたのは、せいぜい三十分ほどだ。それから、塔の見張りは、縛り上げて階段に転がしておいた」
「タオロン。いろいろ、すまない。ありがとう」
「感謝するのは俺のほうだ。……よかった、本当によかった」
何かに耐えるように歯を食いしばり、タオロンは肩を震わせる。愛娘のために負傷した恩人が昏倒したのだ。さぞや責任を感じていたのだろう。
リュイセンは申し訳ない気持ちになった。
倒れたのは、どちらかというと怪我のせいではなく、心労のためだ。ミンウェイの声を聞き、張り詰めていた精神の均衡が崩れた。
リュイセンの口から、細く長い息が漏れる。
黄金比の美貌が冴え渡り、澄み切った双眸が静かに凪ぐ。
これから彼のやるべきことが、理屈ではなく、直感で浮かび上がる……。
〈蝿〉との決着は、今夜中につける。
だが、その前に、鷹刀に――ルイフォンとメイシアに、義を尽くす。
先ほど、タオロンは『メイシアと鷹刀は、とっくに連携している』と言っていた。
そして、囚われのはずのメイシアが、何故か携帯端末を持っていて、その端末がミンウェイと繋がっていた。聡明なメイシアは、水面下で着々と脱出の準備を進めていたのだ。
その計画の中には、リュイセンも含まれているのだろう。しかし、それは丁重に断らねばならない。リュイセンは道を違えたのだから。
彼は、ぐるりと瞳を巡らせ、姿の見当たらない彼女の所在をタオロンに尋ねる。
「メイシアはどこにいる?」
「向こうの部屋で、お前の着替えになりそうなものを見繕っている」
「ありがとう」
立ち上がろうとしたリュイセンを、タオロンが慌てて押し止めた。
「お前は、できるだけ体力を温存しろ! あとで動けなくなるぞ」
怒鳴りつけるような言い方にリュイセンは軽く目を見張り、それからタオロンの気遣いに相好を崩す。
「……ああ。そうだな」
ふたりとも、分かっていた。リュイセンの怪我の具合いからすれば、無理は禁物。平時であれば、しばらく安静にすべき重傷だ。
けれど、今宵は行動のとき。怪我を押してでも動かねばならぬ。
長い夜は、まだこれからなのだと、交わされた視線が暗黙の了解を成立させる。
「メイシアは俺が呼んでくる」
「すまない。……一刻も早く、鷹刀と連絡を取りたい」
「そうか」
リュイセンの言葉に、タオロンの口元が緩む。
「俺は、向こうの部屋でファンルゥを寝かしつける。メイシアがベッドを貸してくれると言っていたんでな」
だから、鷹刀の連中と腹を割って話せ。――太い眉がぐっと寄り、無言で告げる。
リュイセンは、苦い思いを呑み込んだ。
タオロンは、リュイセンが一族と和解するものだと信じている。だが、申し訳ないが、その期待には応えられないのだ……。
「タオロン、……感謝する」
「感謝ならメイシアにしてくれ。俺は彼女の指示で動いただけだ。――さっきだって、お前の傷の治療は、貴族のお嬢さんには刺激が強すぎるからと手伝いを断ったんだが、頑として譲らなくてな。蒼白になりながらも、必死に働いてくれた」
「メイシアが……。そうか、……ありがとな」
「だから、礼はメイシアに言えって」
浅黒い肌の厳つい大男は、笑うと人懐っこい童顔が際立った。
リュイセンの看病をするのだと、口を尖らせるファンルゥを抱え上げ、広い背中が去っていく。そういえば、タオロンとはいつの間に、こんなふうに口をきける間柄になったのだろうか。ずっと敵だったはずなのだが――。
「……ずっと、仲間だったのかもしれないな」
ただ、すれ違っていただけで、心は響き合っていた。
そして――。
心は深く求めながらも裏切り、二度と相まみえることはあるまいと決別した血族。
これから、彼らと対峙する。
彼らとの、最後の言葉を交わす……。
『今、タオロンさんが来て、リュイセンが目を覚ましたと知らせてくれたの。傷は浅くはないけれど、とりあえず大丈夫だって。それで、リュイセンが『鷹刀と話をしたい』と言っていると――』
メイシアからの連絡に、執務室が沸き立った。
「そうか、分かった」
ルイフォンは短く返し、受話器をぐっと握りしめる。
事態は二転三転し、予断を許さない状況が続いていたが、ようやくここまでたどり着いた。しかも、リュイセンのほうから対話を求めてきた。
あと、もうひと息だ。
リュイセンはまだ、ルイフォンがミンウェイの『秘密』を暴いたことを知らない。彼女が『母親』のクローンであったという事実を受け入れたことを知らない。
それを知ったとき、リュイセンはどう思うのか。
鼓動が高鳴る。緊張に体が強張る。次の指示を出さなければと思っているのに、喉が詰まって声にならない。
そんなルイフォンの様子は、最愛のメイシアにはお見通しなのだろう。彼女の声が、そっと寄り添い、彼に覇気を吹き込んだ。
『ルイフォン。リュイセンは大丈夫』
「……ああ。――あいつなら、大丈夫だな」
彼女に導かれ、重ねるように唱えた。すると、昂る鼓動に変わりはないのに、不思議と思考が明瞭になる。
ルイフォンは穏やかに微笑み、メイシアに告げた。
「互いに顔が見えたほうがいいよな? 会議システムに切り替えるから、メイシアも準備してくれ」
『はい』
そして、一度、メイシアとの通話を切る。
そのとき、シュアンが唐突に「便所に行ってくる」と立ち上がった。
「晩に食った弁当が、どうも古かったみたいでな。さっきから腹が痛くてたまらないのさ」
当分、帰ってくるつもりはないと暗に言う。
無論、腹痛は席を外すための方便だろう。リュイセンに蛇蝎の如く嫌われている彼の姿が見えれば、まとまる話もまとまらなくなると、気を遣ってくれたのだ。
「緋扇さん……」
ミンウェイが申し訳なさそうな顔で見上げると、シュアンは口元を緩めた。笑い掛けたつもりなのだろうが、歪んだ口の端と細められた三白眼は、どこまでも悪人面でしかない。
彼は、ひょいとかがんで、ミンウェイの膝に置き去りにされていた、警察隊の制帽を取り上げた。その際に彼女の肩に手を載せて、ルイフォンが準備しているモニタ画面のほうへと、そっと押し出す。――まるで送り出すかのように。
「あとは頼んだぞ」
わざとらしく腹をさすりながら身を翻し、制帽を載せたぼさぼさ頭は執務室から消えていった。
そして――。
切れかけた絆を結ぶように、回線が繋がる……。
その瞬間、スピーカーを低く震わせたのは、内に静かな高温を秘めた、熱した鋼のようなリュイセンの謝罪だった。
『ルイフォン、メイシア。お前たちに深く詫びる。ルイフォンに刃を向け、メイシアを〈蝿〉のもとへさらっていき、すまなかった』
罪を口にして、頭が下げられた。肩を薙いだ黒髪が綺麗に揃ったまま、モニタ画面の中で静止する。本当は、床に手を付こうとしていたのだが、動いては傷に障ると血相を変えたメイシアに止められたのだ。
まっすぐな姿勢に、ルイフォンは面食らった。
彼としては、いつの間にか、メイシアと鷹刀一族の連携が取れていることに関して、まずは詰問されると思っていた。しかし、よく考えれば、あらゆる情報を手に入れていたルイフォンとは違い、閉ざされた空間にいたリュイセンは、いまだ決別したあの時点に取り残されたままだったのだ。
「……」
ルイフォンは、リュイセンの想いを踏みにじるようにミンウェイの『秘密』を暴いたが、リュイセンも、ルイフォンの想いを引き裂くようにメイシアを奪っていった。
あのときの絶望は、忘れたわけではない。
リュイセンを取り戻すと決めたあとも、自分を裏切った相手と、いざ再び顔を突き合わせたとき、どんな感情を抱くのか不安に思ったこともある。
本当に、彼を許せるのだろうか――と。
「リュイセン」
長いこと、呼びかけていなかった名前を口にする。
どこまでも律儀で、頑なで、筋を通さねばすまない、頼もしい兄貴分。
本当は、今すぐにでも〈蝿〉にとどめを刺しに行きたいのだろうに、ルイフォンと連絡がついたからには、きっちりと頭を下げずにはいられなかったのだ。
――こいつを失うなんて、考えられないだろ……。
ルイフォンは前髪を掻き上げ、猫の目を好戦的に光らせる。その動きに合わせて、背中で金の鈴が跳ねる。
「俺は〈猫〉。天才クラッカーにして、情報屋だ」
テノールを響かせ、ルイフォンは――〈猫〉は、不敵な笑みを浮かべる。
「〈猫〉は、すべてを知っている。お前の身に起きたことの『すべて』を、だ」
『――!?』
リュイセンは反射的に顔を上げ、ルイフォンを凝視した。
驚愕と疑念の混じる兄貴分の双眸に、ルイフォンは不遜なまでの自信過剰を見せつける。それが〈猫〉だと知らしめる。
「鷹刀の後継者」
『!?』
「情報を共有しよう。――そして、俺の手を取れ!」
時々、雑音の混ざる音質と、揺れて途切れる映像。
不安定な通信を補うように。
千切れそうな絆を撚り合わせるように。
情報を送り出す――…………――受け止める。
もたらされた情報に、リュイセンは愕然とした。
彼が必死に守ろうとしていたミンウェイの『秘密』は、とっくに彼女に伝わっていた。
「俺はいったい、なんのために……」
ぽつりと呟く。乾いた笑いすらも出てこない。
余計なことをしたルイフォンに憤りを覚える。
だが、それ以上に惨めだった。
自分のすべてと引き換えにしてでも守りたかったものを、守ることができなかった。
わなわなと震える両手で、リュイセンは自分の頭を掻きむしる。いつの間にか荒くなっていた呼吸が、まるで他人のものに感じられる。
……無論、理解はしている。
ルイフォンは、リュイセンのためを思って行動したのだと。それが、リュイセンにとって如何に腹立たしいことであるかも含めて、すべて承知の上で。
「……」
リュイセンは唇を噛みしめた。口の中に血の味が広がる。
そのとき。
『リュイセン』――と。
艷やかな美声が、耳朶を打った。
はっと顔を上げると、小さな携帯端末の画面の中から、彼女が見つめている。
波打つ黒髪の絶世の美女。二度と目にすることは叶わないと思っていた愛しい女。
「ミンウェイ……」
『私の『過去』を守るために、ありがとう。……私がいつまでも、お父様に囚われていたから、あなたが苦しむことになってしまったの。――ごめんなさい』
「ミンウェイが謝る必要はない!」
彼女は何も悪くない。
すべては、あの悪魔のせいだ。
『ううん。私のせいよ』
ミンウェイが緩やかに首を振る。離れていても、草の香が漂うのが分かる。
リュイセンが重ねて『違う!』と叫ぼうとしたとき、それより早く、語勢を強めた彼女の声が響いた。
『でも、私! 結果として、自分が何者なのかを知ることができて良かったと思っているわ。だって、『過去』があやふやだったから、『現在』に引きずってしまったんだもの!』
綺麗に紅の引かれた唇が、きゅっと上がった。強気の笑顔が、輝く。
「――!?」
ミンウェイが笑っている。とても、生き生きと。
リュイセンは己の目を疑った。
あの『秘密』を知れば、彼女は傷つくものと思っていた。どうすることもできない事実に打ちひしがれ、永遠に抜け出すことのできない闇に囚われてしまうのだと信じていた。
思考が凍りついた彼に、彼女が穏やかに語りかける。
『ねぇ、リュイセン。いつだったか、あなたがお祖父様に『『過去』より『未来』のほうが大切だ』と啖呵を切ったのを覚えている?』
「あ、ああ……」
覚えている。忘れるわけがない。
一族の総帥たる祖父に、あれほど真っ向から意見を叩きつけたのは初めてだった。
あれも、ミンウェイのためだった。煮え切らない態度を取る祖父に対し、彼女を苦しめる〈蝿〉は一刻も早く捕らえるべきだと主張し、彼女の憂いを取り除こうと……。
『あなたの言う通りだと思うの。――私、ちゃんと『未来』を生きたいわ』
夢見る少女のように微笑みながら、切れ長の瞳は、あくまでも冷静に前を見据えていた。その視線に、揺らぎのない強さを感じる。
今までの彼女は、一族からの信頼の篤い、姉御肌のしっかり者だった。けれど、どこかに無理があった。誰かのために尽くさなければという、気負いがあった。
それが、目の前の彼女は、極めて自然で、そして自由だ。
『お父様とお母様の思いを知った上で、私は、『私』として、未来を生きたい』
そこでミンウェイは、言葉を一度、切る。
白い喉がこくりと動いた。唾を呑んだのだ。
『……そのために、あなたの力を貸してほしいの』
「俺の力?」
リュイセンは訝しみながら言葉を転がし、ふと思い出した。
彼が展望塔の入り口で倒れる直前にも、ミンウェイは『あなたの力が必要』と言っていた。あのときは、メイシアの脱出に協力してほしいという意味だと思ったのだが、違うのだろうか。
疑問を抱く彼に、彼女が『リュイセン』と呼びかける。
『ここから先の話は、私の我儘よ。聞いてくれるかしら?』
強気の口調は崩さず、けれど、語尾が震えている。
緊張しているのだ。
その証拠に、彼女の美貌は強張っている。不穏を感じ、リュイセンは胸騒ぎを覚える。
「俺に……、何を求める?」
彼の声もまた、緊張にかすれていた。
ミンウェイの瞳が惑うように揺れる。けれど、意を決したように紅の唇が動く。
『〈蝿〉を捕獲して、鷹刀の屋敷まで連れてきてほしいの』
「なっ……!?」
一瞬にして、リュイセンの眦が大きく吊り上がった。
「さっきのルイフォンの話では、メイシアが、セレイエの記憶を得た以上、〈蝿〉は用済みだと……!」
『間違えないで! 〈蝿〉の助命を乞うているのではないわ。最終的に〈蝿〉に与えるべきものは『死』。それは絶対の一族の意志。私も同意しているわ』
「ならば、何故……?」
『でも、その前に、私は〈蝿〉と――『お父様の記憶を持つ者』と話をしたい。きちんと向き合うことのできなかったお父様と、最後に向き合いたい。――そして、きちんと『過去』に別れを告げたい』
鮮やかな緋色の衣服を誇張するように、ミンウェイが胸を張る。
「ミンウェイ……」
『あなたが納得できないなら、今の話は取り消し! ……だって、お父様は『過去』だもの』
高い鼻梁をつんと上げ、ミンウェイがきっぱりと言い切る。
その切れ長の瞳の奥に、小さな女の子が見え隠れする。
置き去りにされたままの、過去のミンウェイ。
いつも脅えていたあの子が、はにかむように笑っていた……ような気がした。
「――――!」
『俺は、やるべきことをやるだけだ』
それが、リュイセンの口癖だ。
そして、理屈ではなく直感で、一足飛びに真理までたどり着くリュイセンには、自分のやるべきことがなんであるか理解してしまった。
「畜生……」
ミンウェイの願いは、真実の気持ちだろう。
だが、分かっている。シナリオを書いているのはルイフォンだ。あの賢い弟分は、はっきりと『俺の手を取れ!』と言ったのだから。
ルイフォンは、リュイセンの想いを踏みにじった。リュイセンの覚悟を無にした。――そのほうが、誰もが幸せになれる、正しい道だと信じたから。
すべてがお膳立てされた中で、ルイフォンの手を取るのは屈辱だ。不愉快だ。
けれど――。
リュイセンは携帯端末を覗き込み、ミンウェイの後ろに小さく映っているルイフォンの目を見た。
「〈猫〉」
どんなに悔しかろうが、どんなに情けなかろうが、ここで〈猫〉の手を取らないのは、醜悪な愚か者でしかない。
「お前の策に乗ってやる」
『リュイセン!?』
音質の悪い回線の中でも、弾かれたようなテノールがしっかりと聞こえた。
「お前が策を立て、俺が実行するのが、俺たちのやり方だ。やってやる。――俺が〈蝿〉を捕獲する」
『本当か!』
「ああ」
『お前、怪我は大丈夫なのか?』
「正直なところ、万全とは言い難い。だが、俺がやらなきゃ、筋が通らねぇだろう?」
単に〈蝿〉を捕獲するだけなら、タオロンに頼むことだってできる。だが、これはリュイセンがやるべきことだ。
ルイフォンが瞳を瞬かせ、『感謝する』と頭を下げる。
普段はいい加減なくせに、こんなときだけ礼儀正しい台詞を吐くのが、この弟分だ。
「馬鹿野郎! 感謝すべきは、俺のほうだろう!」
『ま、それもそうか』
ルイフォンが、にやりと笑う。そうだ、それでいい。
不意に、ルイフォンが真顔になった。
『けど、さすがにお前ひとりじゃ危険だから、鷹刀の総帥と〈猫〉の名において、タオロンに補佐を頼む。それは、いいよな?』
「上等だ」
リュイセンとルイフォンの、目と目が合った。
そして、どちらからともなく、笑みを浮かべる。
『リュイセン』
「なんだ?」
首をかしげたリュイセンに向かい、ルイフォンが右手の『掌』を差し出した。
リュイセンは息を呑んだ。
それは、ふたりの間で通じる、特別な儀式。
握手ではなく、『掌』と『拳』を打ち合わせ……。
――共に行こうと、相手を迎える――。
『おかえり』
抜けるような青空の笑顔で、ルイフォンがテノールを響かせる。
だからリュイセンは『拳』にした右手を、滲んだ画面に向かって突き出した。
「……ただいま」
~ 第八章 了 ~
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第二部 第八章 夢幻の根幹から
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第九章 潮騒の鎮魂歌を https://slib.net/113909
――――に、続きます。


