
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第二部 第七章 五里霧の囚獄で
こちらは、
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第七章 五里霧の囚獄で
――――です。
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第六章 天球儀の輪環よ https://slib.net/113237
――――の続きとなっております。
長い作品であるため、分割して投稿しています。
プロフィール内に、作品全体の目次があります。
https://slib.net/a/4695/
こちらから「見開き・縦書き」表示の『えあ草紙』で読むこともできます。
(星空文庫に戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください)
※使わせていただいているサービス『QRouton』の仕様により、クッションページが表示されます。
https://qrtn.jp/jw8k4vs
『えあ草紙』の使い方は、ごちらをご参考ください。
https://www.satokazzz.com/doc/%e3%81%88%e3%81%82%e8%8d%89%e7%b4%99%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab
「メニューを表示」→「設定」から、フォント等の変更ができます。PCなら、"UD Digi Kyokasho NP-R"等のフォントが綺麗です。
〈第六章あらすじ&登場人物紹介〉

===第六章 あらすじ===
〈蝿〉との対決に破れ、リュイセンによって逃されたルイフォンは、草薙家に身を寄せた。シャンリーとレイウェンによって、敗走の屈辱から立ち直り始めた彼は、リュイセンの生死も分からずに、鷹刀一族の屋敷に戻ることはできないと考える。そして、監視カメラの過去の映像を手に入れることで、リュイセンが即死ではなかったことを明らかにした。
メイシアに関して、〈蝿〉は「ホンシュアに操られて、ルイフォンに恋心を抱いた」と言った。その真偽は分からないものの、否定できないルイフォンは、メイシアに「ゼロからやり直したい」と告げた。しかし、見事、メイシアが論破し、ルイフォンの迷いは晴れた。
リュイセン救出のための会議の席で、メイシアは『〈蝿〉に偽りの和解を申し出る』という案を出した。イーレオは反対したものの、最終的には折れる。
一方、囚われのリュイセンは、〈蝿〉の地下研究室で目覚めた。そばにあった硝子ケースの中にいる、ミンウェイの母親としか思えないような『彼女』が気になり、〈蝿〉に尋ねると、「オリジナルの鷹刀ヘイシャオが、〈蝿〉の肉体と『彼女』を作ったと思われる」という答えが返ってきた。推測の言い方であるのは、〈蝿〉の持つ記憶が採取されたあとで、オリジナルがふたりを作ったと考えられ、〈蝿〉の『記憶にない』からだと言う。
〈蝿〉は、自分は鷹刀セレイエに利用されただけだと主張し、リュイセンに復讐に協力してほしいと迫る。リュイセンは当然、断るが、〈蝿〉は勝手に話を続ける。
そして、『メイシアは、セレイエの〈影〉』で、『最強の〈天使〉の器』だと告げる。更に詳しく説明しようとしたとき、〈悪魔〉の『契約』に抵触して苦しみ始め、『だからこそ、真実でしょう』と言わんばかりの顔をした。
ルイフォンとメイシアが、〈蝿〉に偽りの和解を申し入れに旅立つ日の早朝、なんと囚われていたリュイセンが自力で戻ってきた。しかし、それは〈蝿〉によって、わざと逃されたのだとルイフォンは推測する。
リュイセンの様子はおかしかった。それは、どうやら〈蝿〉に、強引に『メイシアの正体』を聞かされたためであると、ルイフォンは感づく。
会議の場にて、リュイセンは『メイシアは、セレイエの〈影〉であり、今はメイシア本人であるが、いずれメイシアでなくなる』と〈蝿〉に聞かされたと白状する。また、『最強の〈天使〉の器』でもあるのだと。
消化不良のまま会議はお開きになった。ルイフォンは、リュイセンともっと話そうと彼の部屋を訪れるが、部屋には鍵が掛かっていた。話をしたくないのだという意思を感じ、ルイフォンは落ち込む。
そこにエルファンが現れ「リュイセンはまだ隠し事をしている」と言う。そして、ひとつの推測と前置きをした上で、「セレイエは、メイシアを『最強の〈天使〉』にして、その体を乗っ取ろうとしている」と告げた。
夕食のために自室を出たルイフォンは、『ぐったりとしたメイシアを連れ去ろうとしている、リュイセン』を目撃する。「どういうことだ!?」と詰め寄ると、リュイセンは無言でルイフォンを斬り捨てた。そして、重要な極秘任務だと偽り、シーツで包み隠したメイシアを車に乗せて屋敷を出ていった。
===登場人物===
鷹刀ルイフォン
凶賊鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオの末子。十六歳。
――ということになっているが、本当は次期総帥エルファンの息子なので、イーレオの孫にあたる。
母親のキリファから、〈猫〉というクラッカーの通称を継いでいる。
端正な顔立ちであるのだが、表情のせいでそうは見えない。
長髪を後ろで一本に編み、毛先を母の形見である金の鈴と、青い飾り紐で留めている。
凶賊の一員ではなく、何にも属さない「対等な協力者〈猫〉」であることを主張し、認められている。
※「ハッカー」という用語は、本来「コンピュータ技術に精通した人」の意味であり、悪い意味を持たない。むしろ、尊称として使われている。
対して、「クラッカー」は、悪意を持って他人のコンピュータを攻撃する者を指す。
よって、本作品では、〈猫〉を「クラッカー」と表記する。
メイシア
もと貴族で、藤咲家の娘。十八歳。
ルイフォンと共に居るために、表向き死亡したことになっている。
箱入り娘らしい無知さと明晰な頭脳を持つ。
すなわち、育ちの良さから人を疑うことはできないが、状況の矛盾から嘘を見抜く。
白磁の肌、黒絹の髪の美少女。
王族の血を色濃く引くため、『最強の〈天使〉の器』としてルイフォンとの出逢いを仕組まれた……?
[鷹刀一族]
凶賊と呼ばれる、大華王国マフィアの一族。
秘密組織〈七つの大罪〉の介入により、近親婚によって作られた「強く美しい」一族。
――と、説明されていたが、実は〈七つの大罪〉が〈贄〉として作った一族であった。
鷹刀イーレオ
凶賊鷹刀一族の総帥。六十五歳。
若作りで洒落者。
かつては〈七つの大罪〉の研究者、〈悪魔〉の〈獅子〉であった。
鷹刀エルファン
イーレオの長子。次期総帥。
ルイフォンとは親子ほど歳の離れた異母兄弟ということになっているが、実は父親。
感情を表に出すことが少ない。冷静、冷酷。
鷹刀リュイセン
エルファンの次男。イーレオの孫。十九歳。本人は知らないが、ルイフォンの異母兄にあたる。
文句も多いが、やるときはやる男。
『神速の双刀使い』と呼ばれている。
長男の兄が一族を抜けたため、エルファンの次の総帥になる予定であり、最後の総帥となる決意をした。
〈蝿〉から解放されたあと、メイシアを連れ去るという不可解な行動を取った。
鷹刀ミンウェイ
母親がイーレオの娘であり、イーレオの孫娘にあたる。二十代半ばに見える。
鷹刀一族の屋敷を切り盛りしている。
緩やかに波打つ長い髪と、豊満な肉体を持つ絶世の美女。ただし、本来は直毛。
薬草と毒草のエキスパート。医師免状も持っている。
かつて〈ベラドンナ〉という名の毒使いの暗殺者として暗躍していた。
父親ヘイシャオに、溺愛という名の虐待を受けていた。
草薙チャオラウ
イーレオの護衛にして、ルイフォンの武術師範。
無精髭を弄ぶ癖がある。
料理長
鷹刀一族の屋敷の料理長。
恰幅の良い初老の男。人柄が体格に出ている。
キリファ
ルイフォンの母。四年前に当時の国王シルフェンに首を落とされて死亡。
天才クラッカー〈猫〉。
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蠍〉に〈天使〉にされた。
また〈蠍〉に右足首から下を斬られたため、歩行は困難だった。
もとエルファンの愛人で、セレイエとルイフォンを産んだ。
ただし、イーレオ、ユイランと結託して、ルイフォンがエルファンの息子であることを隠していた。
ルイフォンに『手紙』と称し、人工知能〈スー〉のプログラムを託した。
〈ケル〉〈ベロ〉〈スー〉
キリファが作った三台の兄弟コンピュータ。
表向きは普通のスーパーコンピュータだが、それは張りぼてで、真の姿は〈七つの大罪〉の技術を使った、人間と同じ思考の出来る光の糸、あるいは光の珠である。
〈ベロ〉に載せられた人格は、シャオリエを元に作られているらしい。
〈ケル〉は、キリファの親友といってもよい間柄である。
また〈スー〉は、ルイフォンがキリファの『手紙』を正確に打ち込まないと出てこない。
セレイエ
エルファンとキリファの娘。
表向きは、ルイフォンの異父姉となっているが、同父母姉である。
リュイセンにとっては、異母姉になる。
生まれながらの〈天使〉。
貴族と駆け落ちして消息不明。
メイシアを選び、ルイフォンと引き合わせた、らしい。
メイシアのペンダントの元の持ち主で、『目印』としてメイシアに渡した、らしい。
四年前にルイフォンに会いに来て、〈天使〉の能力で何かをした、らしい。
王族の血が濃いほど強い〈天使〉となるために、メイシアを〈影〉にして、体を乗っ取ろうとしている、のかもしれない。
[〈七つの大罪〉・他]
〈七つの大罪〉
現代の『七つの大罪』=『新・七つの大罪』を犯す『闇の研究組織』。
実は、王の私設研究機関。
王家に、王になる資格を持つ〈神の御子〉が生まれないとき、『過去の王のクローンを作り、王家の断絶を防ぐ』という役割を担っている。
〈悪魔〉
知的好奇心に魂を売り渡した研究者を〈悪魔〉と呼ぶ。
〈悪魔〉は〈神〉から名前を貰い、潤沢な資金と絶対の加護、蓄積された門外不出の技術を元に、更なる高みを目指す。
代償は体に刻み込まれた『契約』。――王族の『秘密』を口にすると死ぬという、〈天使〉による脳内介入を受けている。
『契約』
〈悪魔〉が、王族の『秘密』を口外しないように施される脳内介入。
記憶の中に刻まれるため、〈七つの大罪〉とは縁を切ったイーレオも、『契約』に縛られている。
〈天使〉
「記憶の書き込み」ができる人体実験体。
脳内介入を行う際に、背中から光の羽を出し、まるで天使のような姿になる。
〈天使〉とは、脳という記憶装置に、記憶や命令を書き込むオペレーター。いわば、人間に侵入して相手を乗っ取るクラッカー。
羽は、〈天使〉と侵入対象の人間との接続装置であり、限度を超えて酷使すれば熱暴走を起こす。
〈影〉
〈天使〉によって、脳を他人の記憶に書き換えられた人間。
体は元の人物だが、精神が別人となる。
『呪い』・便宜上、そう呼ばれているもの
〈天使〉の脳内介入によって受ける影響、被害といったもの。悪魔の『契約』も『呪い』の一種である。
服従が快楽と錯覚するような他人を支配する命令や、「パパがチョコを食べていいと言った」という他愛のない嘘の記憶まで、いろいろである。
『di;vine+sin;fonia デヴァイン・シンフォニア計画』
セレイエが企んでいる計画。
『ライシェン』という名前の『特別な王』が必要であり、〈蝿〉に作らせた。
詳細は、まだ謎に包まれている。
『di』は、『ふたつ』を意味する接頭辞。『vine』は、『蔓』。
つまり、『ふたつの蔓』――転じて、『二重螺旋』『DNAの立体構造』――『命』の暗喩。
『sin』は『罪』。『fonia』は、ただの語呂合わせ。
これらの意味を繋ぎ合わせて『命に対する冒涜』と、ホンシュアは言った。
ヘイシャオ
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蝿〉。ミンウェイの父。故人。
医者で暗殺者。
病弱な妻のために〈悪魔〉となった。
〈七つの大罪〉の技術を否定したイーレオを恨んでいるらしい。
娘を、亡くした妻の代わりにするという、異常な愛情で溺愛していた。
そのため、娘に、妻と同じ名前『ミンウェイ』と名付けている。
十数年前に、娘のミンウェイを連れて現れ、自殺のようなかたちでエルファンに殺された。
現在の〈蝿〉
セレイエが『特別な王』を作らせるために、蘇らせたヘイシャオ。
セレイエに吹き込まれた嘘のせいで、イーレオの命を狙ってきた。
死の間際のホンシュアから、メイシアに関する重大な秘密を教えられたため、タオロンに命じ、メイシアをさらおうとした。
ヘイシャオそのものだが、記憶と肉体の年齢が合っていない。
ホンシュア
セレイエの〈影〉となって『デヴァイン・シンフォニア計画』に協力した、セレイエの知己。
体は〈天使〉化してあった。
〈影〉にされたメイシアの父親に、死ぬ前だけでも本人に戻れるような細工をしたため、体が限界を超え、熱暴走を起こして死亡。
メイシアにセレイエの記憶を潜ませ、鷹刀に行くように仕向けた、いわば発端を作った人物である。
〈蛇〉
セレイエの〈悪魔〉としての名前。
〈蝿〉が、セレイエの〈影〉であるホンシュアを〈蛇〉と呼んでいたため、ホンシュアを指すこともある。
ライシェン
ホンシュアがルイフォンに向かって呼びかけた名前。
そして、ホンシュアが、蘇らせた〈蝿〉に作らせた『特別な王』の名前も『ライシェン』である。
斑目タオロン
よく陽に焼けた浅黒い肌に、意思の強そうな目をした斑目一族の若い衆。
堂々たる体躯に猪突猛進の性格。
二十四歳だが、童顔ゆえに、二十歳そこそこに見られる。
娘のファンルゥを盾にされ、〈蝿〉に逆らうことができないため、気持ちの上ではルイフォンたちとは仲間だが、敵対している。
斑目ファンルゥ
タオロンの娘。四、五歳くらい。
くりっとした丸い目に、ぴょんぴょんとはねた癖っ毛が愛らしい。
人質であるため、〈蝿〉に毒針の出る腕輪をはめられている。
ただし、本人には「部屋から出ようとしたら音の鳴る腕輪」と説明されている。
[藤咲家・他]
藤咲ハオリュウ
メイシアの異母弟。十二歳。
父親を亡くしたため、若年ながら藤咲家の当主を継いだ。
十人並みの容姿に、子供とは思えない言動。いずれは一角の人物になると目される。
異母姉メイシアを自由にするために、表向き死亡したことにしたのは彼である。
女王陛下の婚礼衣装制作に関して、草薙レイウェンと提携を決めた。
緋扇シュアン
『狂犬』と呼ばれるイカレ警察隊員。三十路手前程度。イーレオには『野犬』と呼ばれた。
ぼさぼさに乱れまくった頭髪、隈のできた血走った目、不健康そうな青白い肌をしている。
凶賊の抗争に巻き込まれて家族を失っており、凶賊を恨んでいる。
凶賊を殲滅すべく、情報を求めて鷹刀一族と手を結んだ。
敬愛する先輩が〈蝿〉の手に堕ちてしまい、自らの手で射殺した。
似た境遇に遭ったハオリュウに庇護欲を感じ、彼に協力することにした。
[王家・他]
アイリー
大華王国の現女王。十五歳。
彼女の婚約を開始条件に、すべてが――『デヴァイン・シンフォニア計画』が始まったと思われる。
メイシアの再従姉妹にあたるが、メイシア曰く『私は数多の貴族のひとりに過ぎなかった』。
シルフェン
先王。四年前、腹心だった甥のヤンイェンに殺害されたらしい。
〈神の御子〉に恵まれなかった先々王が〈七つの大罪〉に作らせた『過去の王のクローン』である。
ヤンイェン
先王を殺害し、幽閉されていたが、女王の婚約者として表舞台に戻ってきた謎の人物。
メイシアの再従兄妹にあたる。
平民を後妻に迎えたメイシアの父、コウレンに好意的だったらしい。
実は、先王シルフェンが〈神の御子〉を求めて姉に産ませた、隠し子。
そのため、女王アイリーや摂政カイウォルの異母兄弟に当たる。
カイウォル
摂政。女王の兄に当たる人物。
摂政を含む、女王以外の兄弟は〈神の御子〉の外見を持たないために、王位継承権はない。
異母兄にあたるヤンイェンとの結婚を嫌がる妹、女王アイリーのため、ハオリュウに『君が女王の婚約者になれば、女王の結婚が延期される』と陰謀を持ちかけた。
[草薙家]
草薙レイウェン
エルファンの長男。リュイセンの兄。
エルファンの後継者であったが、幼馴染で妻のシャンリーを外の世界で活躍させるために
鷹刀一族を出た。
――ということになっているが、リュイセンに後継者を譲ろうと、シャンリーと画策したというのが真相。
服飾会社、警備会社など、複数の会社を興す。
草薙シャンリー
レイウェンの妻。チャオラウの姪だが、赤子のころに両親を亡くしたためチャオラウの養女になっている。
王宮に召されるほどの剣舞の名手。
遠目には男性にしかみえない。本人は男装をしているつもりはないが、男装の麗人と呼ばれる。
草薙クーティエ
レイウェンとシャンリーの娘。リュイセンの姪に当たる。十歳。
可愛らしく、活発。
鷹刀ユイラン
エルファンの正妻。レイウェン、リュイセンの母。
レイウェンの会社の専属デザイナーとして、鷹刀一族の屋敷を出た。
ルイフォンが、エルファンの子であることを隠したいキリファに協力して、愛人をいじめる正妻のふりをしてくれた。
メイシアの異母弟ハオリュウに、メイシアの花嫁衣装を依頼された。
また、ヘイシャオの実の姉でもある。
[繁華街]
シャオリエ
高級娼館の女主人。年齢不詳。
外見は嫋やかな美女だが、中身は『姐さん』。
元鷹刀一族であり、イーレオを育てた人物であるらしい。
実は〈影〉であり、体は別人。そのことをイーレオが気にしないようにと、一族を離れた。
イーレオと同じく、〈七つの大罪〉の〈悪魔〉であった。
スーリン
シャオリエの店の娼婦。
くるくる巻き毛のポニーテールが似合う、小柄で可愛らしい少女。ということになっているが妖艶な美女という説もある。
本人曰く、もと女優の卵である。実年齢は不明。
トンツァイ
繁華街の情報屋。
痩せぎすの男。
キンタン
トンツァイの息子。ルイフォンと同い年。
カードゲームが好き。
===大華王国について===
黒髪黒目の国民の中で、白金の髪、青灰色の瞳を持つ王が治める王国である。
身分制度は、王族、貴族、平民、自由民に分かれている。
また、暴力的な手段によって団結している集団のことを凶賊と呼ぶ。彼らは平民や自由民であるが、貴族並みの勢力を誇っている。
1.失跡の顛末-1
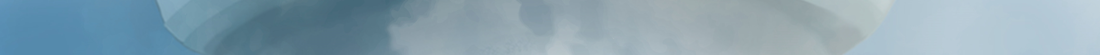
不吉な雷光が、暗い天空を紫に染めた。
悪鬼の形相をした、リュイセンの美貌が浮かび上がる。
神速の――無言の一刀。
容赦ない太刀筋が、ルイフォンの腹を裂く。けれど、それよりも……。
「メイシア――!」
右手を虚空に伸ばした状態で、ルイフォンは、はっと目を覚ました。
「ルイフォン!」
草の香が揺れる。波打つ髪をひとつにまとめた白衣姿のミンウェイが、青ざめた表情で彼の顔を覗き込んでいた。
「ミンウェイ……?」
ルイフォンは力なく右手を下ろす。その手の中には、当然のことながら何もない。
状況が掴めない。
今、自分が自室のベッドに寝かされていることは分かる。だが、さっきまで、彼は廊下にいた。気を失ったメイシアをリュイセンが抱きかかえていて、駆け寄ろうとしたらリュイセンが……。
「あなたは、自分の部屋の前で血まみれになって倒れていたのよ」
眉を曇らせたミンウェイが、静かに告げる。
「メイシアは!? メイシアはどこにいる!?」
あの状況――。
なんらかの理由で意識を失ったメイシアをリュイセンが運んでいた……などではない。あれは間違いなくリュイセンがメイシアを襲ったのだ。
ルイフォンの腹の底から憤怒が湧き上がる。
「リュイセン……! あの野郎!」
叫ぶと同時に、彼はベッドから飛び起きた。
刹那、腹に激痛が走る。反射的に腹部を押さえれば、半裸の体に包帯を巻かれていた。
「ルイフォン、落ち着いて。あなたは重傷なの。何針も縫ったのよ!」
「落ち着いていられるか! メイシアがさらわれたんだぞ!」
「分かっているわ! どうして、リュイセンは……!」
ミンウェイが唇を噛んだ。落ちかけの紅が苦しげに歪む。
「ともかく、あなたには安静が必要なの。――今、お祖父さまがこの部屋にいらっしゃるわ。現状を説明してくださるから……」
「ふざけんな! そんな悠長なことを言っている場合じゃねぇだろ! リュイセンはどこだ!? 屋敷を出たのか!? すぐにでも追わねぇと! 地の果てまで追いかけてやる!」
ミンウェイの言葉が終わるより前に、ルイフォンがいきり立つ。
「だから、ルイフォン。落ち着いて! もう真夜中なの。リュイセンが出ていってから、だいぶ時間が経ってしまっている。私たちは遅れを取ってしまった。リュイセンは――」
ミンウェイは一瞬、声を詰まらせ、ごくりと唾を呑み込んだ。
「リュイセンは……、おそらく〈蝿〉の庭園にいる。メイシアを連れて……」
「!」
考えたくはない。
けれど、それしかあり得ないということは、ルイフォンにも理解できた。
数時間前――。
夕食の時間になっても、ルイフォン、メイシア、リュイセンの三人は食堂に現れなかった。いつもなら、調理の手伝いをしているメイシアが頃合いを見てルイフォンを迎えに行き、律儀なリュイセンは呼ばれなくとも時間通りに来て着席しているはずだった。
だが今日は、〈蝿〉に囚われていたリュイセンが帰ってきたばかりであり、しかも彼の様子はおかしかった。そのことから察するに、リュイセンを心配したルイフォンとメイシアが声を掛けに行き、話し込んでいるに違いない。あるいは、口論になっているのかもしれない。
ともかく、三人は一緒だろう。ここは若い連中同士に任せて、しばらく待つのがよかろう。――イーレオは、そう考えた。
しかし、三十分が過ぎても、三人は来なかった。料理長の心づくしも、すっかり冷めてしまっている。いくらなんでも遅すぎる。
さすがにイーレオもしびれを切らし、ルイフォンとリュイセンの部屋へと、それぞれメイドを向かわせた。
「リュイセンの部屋には鍵が掛かっており、中には入れなかった。そして、お前の部屋の前で、血まみれのお前が見つかった。そのときになって初めて、ただならぬ事態になっていることに気づいた。……すまない。俺は、判断を誤った」
ルイフォンの部屋を訪れたイーレオは、深々と頭を下げた。艷やかな黒髪がさらさらと流れ、大華王国一の凶賊、鷹刀一族の総帥が惜しげもなく首筋を晒す。
「親父……」
喉まで出かかっていた罵倒をルイフォンは飲み込んだ。イーレオにまったく非がないとはいえないかもしれない。だが、ここで声を荒らげたら八つ当たりだ。
何より、ルイフォンはあの現場にいた。彼がリュイセンよりも強ければ、メイシアがさらわれることはなかったのだ。
「……俺が寝ていた間のことを話してくれ」
まずは情報である。ルイフォンは努めて冷静を保つ。
ゆっくりと顔を上げたイーレオの額には、深い皺が寄っていた。
「すぐに屋敷中を探させたが、そのとき既に、リュイセンは車で屋敷を発っていた。極秘任務だと偽り、布で包んだ大きな荷物を持っていたそうだ」
「……っ!」
ルイフォンの握りしめた拳の中で、爪が皮膚に食い込んだ。
「リュイセンの車は、人気のない場所に乗り捨てられていた。GPSがついていたから簡単に見つかった。――すぐに足がつくのが分かっていたから、別の車に乗り換えたのだろう」
イーレオは小さく溜め息をつき、続ける。
「〈蝿〉の潜伏場所である、あの庭園を見張っている部下と連絡を取って、確証を得た。リュイセンが屋敷を発ったのと同じころに車が出ていき、しばらくして戻ってきたそうだ。夜である上に、スモークガラスで中は分からなかったということだが……」
「〈蝿〉の私兵が、リュイセンとメイシアを迎えに行き、乗せて帰ってきたんだろ」
吐き捨てるようにルイフォンが言うと、「そういうことだろう」とイーレオが頷く。
「ルイフォン、本当にすまない。俺は、リュイセンが〈蝿〉の手に落ちていたことを見抜けなかった」
「それは俺も同じだ」
ルイフォンは、ぎりりと奥歯を噛みしめる。
まさか……であった。
もしも、これが他の奴だったら――例えば、タオロンが〈蝿〉の庭園から逃げ出してきて、保護を求めたなどであったなら、多少なりとも疑いの眼差しを向けただろう。
しかし、リュイセンだった。長い時間を共に過ごしてきた、大切な兄貴分だった。
様子がおかしいことを承知していても、それでも疑うことなどあり得なかった。
はらわたが煮えくり返る。全身が憎悪に震える。かっと見開いた瞳に、すべてを斬り裂くような鋭い光を宿す。
リュイセンは敵だ。
何故、〈蝿〉に与したのかは分からない。何かしらの理由はあるのだろう。
しかし、メイシアに害をなしたからには、敵以外の何者でもない――!
ルイフォンの思いを読み取ったかのように、イーレオが宣告する。
「リュイセンは追放処分だ」
冷淡に放たれた美声。しかし、そこには、いつものような魅惑の響きはなかった。
「あいつは、一族の総帥である俺に何も告げずに、鷹刀と敵対する〈蝿〉の指示に従った。事情があったのなら、幾らでも説明する機会はあったはずだ」
静かな低音が、光の差さぬ、深い海の底へと沈んでいく。
イーレオは、何よりも『人』に価値を見出し、誰よりも『人』を愛してやまない。そんな慈愛の王者の美貌からは、リュイセンの裏切りに対する悲哀がにじみ出ていた。
そのとき、ルイフォンは、イーレオの背後に控えていた次期総帥、エルファンの視線を感じた。相変わらずの氷のように無色透明な表情。しかし、その瞳が無言でルイフォンを包み込む。
『お前は決して、最愛の者を理不尽に奪われたりするなよ』
夕方、珍しくエルファンとふたりで話をした。あのときと同じ色合いの眼差しだった。
「!」
リュイセンへの怒りを昂らせている場合ではない。優先すべきことを間違えるな。――エルファンは、無言でそう告げていた。
「親父……、確かにリュイセンには頭にきているが、今はそこじゃねぇ」
ルイフォンは大きく息を吸い込んだ。
「俺は、メイシアを取り戻す――!」
あの庭園に向け、ルイフォンは鋭い猫の目を光らせた。
『まずは、怪我の回復に努めるように』と言い残し、イーレオを始めとする皆は、ルイフォンの部屋をあとにした。
時刻は深夜。怪我人でなくとも、体を休める時間である。部屋の照明はミンウェイによって落とされ、足元の常夜灯がぼんやりと淡い光を放つのみだった。
ルイフォンは傷を庇うようにして手を伸ばし、ベッドのそばにある窓のカーテンを開け放つ。
あの酷い雷雨は止んでいた。しかし、月明かりは途切れ途切れ――黒い雲が、上空を矢のように走り抜けている。天上は目まぐるしく明暗を変え、不気味にのたうち回る不吉な影を地上に落としていた。
ルイフォンは、ベッドに体を横たえた。けれど、眠れるわけがない。ぎしぎしとスプリングをきしませて寝返りを打つと、腹の傷が引きつれ、声にならない悲鳴を上げた。
「メイシア……」
あと少しで、指先が触れるところだった。
ルイフォンは寝転がったまま掌をかざし、虚しく空を掴む。
メイシアは、あの庭園にいる。近衛隊に守られた、あの門の内側に。
庭園を出入りする〈蝿〉の私兵の車を奪えないだろうか。いや、近衛隊のチェックがあるから、奪うのではなく、私兵の買収か脅迫だ。問題は、そのあと。彼女がどこにいて、どうしたら無事に助け出せるのか。監視カメラは電源が落とされたままだ……。
ルイフォンは虚空を見つめ、思考を巡らせる。
ふとそのとき、部屋の扉が叩かれた。
「誰だ?」
「私だ」
低く魅惑的な声と共に、長身の影がするりと忍び込む。ルイフォンの部屋は、いつだって鍵が掛かっていないのだ。
「エルファン!?」
「眠れないのだろう?」
エルファンは窓辺のベッドにたどり着く途中で、テーブルから椅子を拝借してきた。どう見ても話し込む姿勢である。医者のミンウェイが、去り際に口を酸っぱくして『たとえ眠れなくても、目を閉じて安静にしているのよ』と言っており、その場にエルファンもいたのだが、聞こえなかったことにするらしい。
とはいえ、部屋の照明を点けないのは、明かりが外に漏れるのを恐れてのことだろう。
「エルファン……。お前に忠告されたばかりだったのにな……」
なのに、この手からメイシアを奪われた――。
目を覚ましてから初めての、弱気な発言だった。
声に出してしまうと、心がぐらりと不安に傾く。慌てて腹に力を入れ、気を引き締めようとすると、今度は傷口が言いようもないほどに痛んだ。
「仕方ない。ヘイシャオの〈影〉のほうが一枚、上手だっただけだ。――だが、まだ失ったわけではない」
素っ気ない言葉が、そっとルイフォンを支える。
「ああ、そうだな……」
――メイシアを取り戻す。
猫の目が、夜闇に光る。この強い想いだけは、揺らぐことはない。
「ルイフォン」
まだら模様の月明かりがエルファンを照らし、氷の美貌をさまざまな角度から浮き立たせた。薄い闇に身を溶かしながら、じっと光を見守る。一族の影の部分を司る彼らしい姿が、視覚的に映し出された。
「リュイセンの裏切りと、お前の怪我と――。父上は、すべての責任は自分にあると思ってらっしゃる。……その思いから、お前がおとなしく安静にしていられるよう、お前に余計なことを言うなと皆に通告した」
「……なっ!」
ルイフォンは、思わず唾を飛ばす。
「ふざけんな、親父の奴! メイシアがさらわれたんだぞ!」
「だから、私が来た」
「え?」
悪役然としたエルファンの微笑が、闇に浮かぶ。
「お前は、じっとしているような奴ではないだろう?」
1.失跡の顛末-2

「まず、父上がまるで触れなかった鷹刀の外での動きだが……、メイシアがさらわれたということで、彼女の身内に――異母弟であるハオリュウに、父上自らが電話で報告した」
「……っ」
ルイフォンの顔が凍りついた。その表情は、暗がりでもはっきりと分かったのだろう。エルファンが眉間に皺を寄せる。
「黙っているわけにはいかないだろう? 連絡が遅くなるほどに、信頼関係は失われていくのだからな」
「……ああ」
ルイフォンを信じて、大切な異母姉を託してくれたハオリュウ……。
心臓が、ずきりと痛む。
「そんな顔をするな。お前はメイシアを守ろうとして重傷を負い、生死の境をさまよっていると父上が説明した。お前に対しては、感謝の言葉まで貰っている」
「……!?」
ハオリュウの怒りの矛先がルイフォンに向かわないよう、イーレオは怪我の具合いを大げさに伝えたのだ。
しかし――。
「『俺に対しては』?」
それはつまり……と、おそるおそる目線で尋ねると、エルファンが溜め息混じりに肩を落とした。
「鷹刀に対しては、怒り狂っている」
「……」
無理もない。ハオリュウは、メイシアのためになら命すら厭わないほどに、彼女を溺愛している。彼女を『死者』にしてまで送り出してくれたのだって、政争で不穏な貴族の世界よりも、大華王国一の凶賊のもとで生きたほうが安全だろう、という目論見もあったはずだ。
「父上と、だいぶ険悪な状態だ。いや、ハオリュウのほうが一方的に、だな」
先ほどのイーレオの精彩のなさは、ここにも原因があったようだ。
押し黙ったルイフォンを見やり、エルファンが続ける。
「ハオリュウは『夜であるから人目につかないはずだ』と言い張って、鷹刀に乗り込んでこようとしたのだが、今、彼が来てもどうにもならない。『それでも』と問答しているところに、先に手を回しておいた緋扇が藤咲家に到着した」
「え? シュアン?」
「ああ。奴が間に入って、とりあえずハオリュウには引いてもらった。明日、ハオリュウの代理として、緋扇が鷹刀に詳細を聞きに来ることを条件にな」
「……そんなことになっていたのか」
使い走りのようにされているシュアンには悪いが、彼がいてくれて助かったようだ。しかし、本業の警察隊の仕事は大丈夫なのだろうか。少しだけ心配になる。
「それから、リュイセンについてだが……」
エルファンは間を置かず、顔色も変えずに、その名を挙げた。まるで不意打ちのような所業に、ルイフォンの胸が波打つ。
「あいつがメイシアをさらったのは、〈蝿〉の指示と考えられる。それは先ほど、父上がおっしゃった通りなのだが、あいつ自身の判断で凶行に及んだとみて間違いない。つまり、何かの手段によって『操られていた』ということは『ない』」
「……ああ。〈蝿〉のところから戻ってきたリュイセンは様子がおかしかったけど、操られているという感じはしなかった」
ルイフォンの言葉に、エルファンは頷く。
「実は、鍵の掛かっていたリュイセンの部屋をマスターキーで開けさせたのだ。そしたら、机の上に……」
「書き置きがあったのか!?」
飛びつくように叫ぶと、腹の傷が引きつるように傷んだ。悶絶するルイフォンを横目に、エルファンは淡々と告げる。
「『子供の描いた絵』が残されていた」
「はぁ?」
予想外の答えに、ルイフォンは、ぽかんと口を開けた。
「スケッチブックを切り離したと思しき画用紙が、不格好に折りたたまれていた。広げてみると、一面、水色のクレヨンで塗りつぶした上に、無数の紫の円が描かれていた」
『ファンルゥ。……絵を、預かってやる』
ルイフォンの脳裏に、リュイセンの低音が蘇る。
〈蝿〉を捕らえるべく、リュイセンと共にあの菖蒲の館に潜入したとき、部屋から脱走して廊下をうろついていたタオロンの娘、ファンルゥを保護した。彼女は、車椅子のハオリュウが館に入るところを目撃し、『病気のあの子』を励ますために絵を贈ろうとしていたのだ。
それはファンルゥの思い込みに過ぎなかったのだが、彼女の優しさに応えてやりたいと、リュイセンは『あの子に届ける』と言って、絵を預かったのである。あのあと激しい戦闘となったが、絵は先に脱いだ上着のポケットに入れていたから無事だったのだろう。
「確かに、書き置きもあった。『身勝手なお願いだと思いますが、この絵をハオリュウに届けてください』――という、な」
「……」
「お前の報告書に、その絵についての記載があったから事情は理解できた。――あいつは律儀だからな。その子供との約束を、きちんと果たしておきたかったのだろう」
もう二度と、戻るつもりはないから――。
この機会を逃したら、次はないから。だから、ここに託す――。
ふっと雲が途切れ、エルファンの顔を明るく照らした。月を映した瞳は、穏やかにルイフォンを見つめていた。
「〈蝿〉に囚われていたときに、リュイセンの身に何が起きたのかは分からない。だが、あいつは自分の意思で考え、行動した」
エルファンの低い声が、リュイセンの呟きと重なる。
『……俺は、凄くも、正しくもなくて……。ただ、やるべきだと思ったことを、やるだけだ……』
リュイセンが帰ってきてすぐ、半ば強引に押しかけていって話をしたときに、兄貴分はそう言った。あのとき既に、今の事態を決意していたのだ。
「だからな、ルイフォン……。あいつは『裏切った』のではない。『袂を分かった』のだ」
リュイセンの決断を認めてやれ。――エルファンの氷の瞳が、無言でそう告げる。
すべてと引き替えにしてでもそうすべきだと、リュイセンは覚悟を決めて行動したのだから、と。
ルイフォンは、拳を握りしめた。
「リュイセン……!」
ぐっと歯を食いしばり、喉元の熱さをこらえる。
胸の中を渦巻く感情を、どう表現したらいいのか分からない。――ただ、苦しい……。
黒い雲が、月を隠しては流れ……、また流れては隠していく。瞬きをするような月明かりがルイフォンを包み込む。そして、闇の中にあらゆる音を吸い込み、静かな夜が更けていく――。
どのくらい、時が過ぎただろうか。
再び、雲が途切れた。
月を宿したエルファンの瞳は、変わらずにルイフォンを見守っていた。そのときになってやっと、ルイフォンは気づいた。
エルファンは、ルイフォンを慰めに来たのだ――おそらく。
不器用な温かさが心にしみる。
「エルファン……」
名を呼びかけ、けれど、そこで言葉に詰まった。
だが、心配は杞憂だった。エルファンのほうから口を開いたのだ。
「ルイフォン。どうせ、お前は眠れないことだし、できることをしてみるか」
「!?」
唐突な言葉に、ルイフォンはきょとんとする。
「私を〈ベロ〉に会わせろ」
「は? 〈ベロ〉!?」
あまりにも意外すぎる発言に、今までの湿った気持ちが一気に吹き飛んだ。
「〈ベロ〉って、張りぼてのほうじゃなくて、人工知能のほうの〈ベロ〉のことだよな?」
シャオリエをモデルにしたという、高飛車な『真の〈ベロ〉』。警察隊が執務室に押し寄せたときに一度だけ現れ、それ以来、だんまりを決め込んでいる自分勝手な人工知能。
『彼女』に会いたいとは、いったいどういうことだと、ルイフォンは盛大に目を見開く。
「あの人工知能は、この屋敷を守っているはずだろう? なのに、メイシアの危機に警報のひとつも鳴らさなかった。是非とも、その理由を釈明してもらいたい」
エルファンの瞳がすっと細まり、冷徹な光を放つ。
「〈ベロ〉への強制アクセス。ルイフォン、お前ならば可能だな?」
凍てつくような低い声に気圧され、ルイフォンは、ごくりと唾を呑み込んだ。
「ああ。――できる」
母キリファと住んでいた家にある、〈ケル〉への強制アクセスは成功した。ならば、同じシステムである〈ベロ〉へのアクセスも同様に可能なはずだ。
「――けど、『強制アクセス』といっても、『呼び出すことができる』だけで、俺の支配下に入るわけじゃない。おとなしい〈ケル〉ですら、言いたくないことは言わなかったんだ。シャオリエの性格をした〈ベロ〉が素直に話すとは思えない」
「会ってみなければ分からないだろう?」
「だって、目的が『理由を釈明しろ』だろ? それで、あいつが答えるわけがない」
「お前は、この私に〈ベロ〉の口を割らせることはできない――と言うのか?」
くっ、と好戦的に口角を上げる様は、美麗でありながらも禍々しく、さながら人知を超えた魔性のよう。そして、更に畳み掛ける。
「それに……、〈ベロ〉は、あのキリファが遺したものだ。それでも、邂逅は無意味だと、お前は思うのか?」
「――!?」
心の隙を衝くかのような、思わせぶりな口調。まるで魅入られたかのように、ルイフォンの胸は高鳴った。得体のしれない高度な技術から成る、あの〈ベロ〉なら、あるいは何か……と、根拠のない期待が膨らむ。
「そうだな、〈ベロ〉に会いに……」
そう言いかけたところで、彼は、はたと気づいた。
「無理だ。強制アクセスをするには、〈ベロ〉のそばの操作卓まで行く必要があるんだ」
張りぼての〈ベロ〉は地下にある。〈ケル〉と同じ作りであるなら、真の〈ベロ〉は、その隣の小部屋にあるはずだ。
「? 行けばいいだろう?」
何を言っているのだと、エルファンが首をかしげる。
「そりゃ、いつもの俺なら行っているさ。けど、今の俺は、絶対安静の怪我人だ」
「夜のうちなら、誰かに見つかることもないだろう。人の気配を感じたら、私が教えるから大丈夫だ」
「そうじゃなくて……。少し動いただけでも、物凄く腹が痛むんだよ」
おとなしく寝ていたいとは思わない。だが、この傷で地下まで行くことを考えると、気が遠くなりそうだった。ミンウェイが、口を酸っぱくして安静を命じただけのことはある。
しかし、エルファンは眉ひとつ動かすことなく、平然とした口調で言ってのけた。
「お前も鷹刀の男なら、そのくらいの傷、どうということはないだろう」
「おいっ、ちょっと待て!」
無茶苦茶だ。
ルイフォンは頭脳派なのだ。日々、鍛錬に精進しているような、勤勉な武闘派ではないのだ。いや、そもそも、これだけの傷を負えば、どんな剛の者だって動けないのではないだろうか。
「仕方ない」
エルファンが大きく溜め息をついた。日を改めることにしたのだろう。
その様子に、ルイフォンは、ほっと胸を撫で下ろす。〈ベロ〉との対面を先延ばしにするのは残念だが、さすがに今は体が言うことを聞かないのだから勘弁だ。
「すまない。一日でいいから休ませてくれ」
ともかく、体を回復させるべきだ。このままでは、メイシアを助けるために庭園に乗り込むどころか、ベッドから出ることすらできない。
今晩は、お開きということだろう。エルファンが椅子から立ち上がった。
そして――。
「なっ……!」
いきなり毛布を跳ねのけられ、ルイフォンは仰天した。反射的に声を上げるも、問答無用でエルファンの手が伸びてきて、ルイフォンの体をすくい上げる。
「な、何するんだよ!?」
「このまま、お前を運んでいく。地下でいいんだな?」
「うわっ、やめろ!」
いい歳をした男が、男に抱き上げられるなど、言語道断。自分はあくまでも、抱き上げる側であって、その相手はメイシアに限る!
ルイフォンは全力で抵抗しようとするが、下手に動けば傷口に激痛が走る。
「ちょっと、待てよ! エルファン、落ち着け!」
「静かにしろ。周りに気づかれる」
「だから、あり得ねぇだろ! 子供じゃねぇんだからよ!」
そのとき、エルファンの動きが一瞬だけ止まった。
明滅する月明かりの中で、かろうじてルイフォンが目にしたのは、氷が溶けたように目を細めたエルファンの微笑だった。
「ああ、そうだな。お前を抱えてやったことはなかったから、ちょうどいい」
「は?」
「いや、なんでもない」
エルファンはそう言って、ベッドの上の枕から、片手で器用に枕カバーをはぎ取った。そして素早くルイフォンに猿ぐつわを噛ませ、彼を抱き上げたまま、悠然と部屋を出ていったのであった。
2.守護者との邂逅-1

〈ベロ〉と話をしたいというエルファンに運ばれ、ルイフォンは屋敷の地下にやってきた。
物凄い唸りと振動を撒き散らす、巨大なコンピュータ――ルイフォンが『張りぼて』と呼んでいるほうの〈ベロ〉の脇を通り抜け、続き部屋となっている小部屋の扉を開く。
その瞬間。
部屋の中から、まばゆい光があふれ出した。
「――っ!?」
瞳を灼くような、無数の光の糸。
清冽な白金の流れが、勢いよく小部屋を巡る。
神々しさすら感じる輝きの渦。
やがてそれは、個々に意思を持ったかのように乱舞を始め、互いに絡み合い、繋がり合い、光のヴェールを作り出していく……。
幻想的な光景に、目を奪われた。
〈天使〉の羽に酷似したその光は、神聖で犯しがたく、禁忌的。
同じ『もの』である〈ケル〉を知っているルイフォンですら息を呑むのだから、いわんや初めて見たエルファンは、目を見開いたまま凍りついたように動かない。
しかし――。
その神秘的な様相もそこまでだった。
〔ああ、もうっ、可笑しいわぁ、最高!〕
豊かに艶めく女の声が響き渡り、それに高笑いが続く。
部屋の中の、ありとあらゆる白金の糸が震えた。光と音の振動は、まるで巨大な竪琴のすべての弦を弾いたかのよう。その響きは、開け放した扉のこちら側にある、張りぼての〈ベロ〉に勝るとも劣らぬ――騒音……だった。
〔ちょっと、そっちの部屋、うるさいわ。さっさと扉を閉めて中に入ってきなさいよ〕
この声色、この口調。紛れもなく〈ベロ〉である。
「お前のほうが、よっぽどうるさいだろ!」
ルイフォンは、エルファンに噛まされていた猿ぐつわを引きはがし、思い切り叫んだ。だがそれも、あっけなく周りの音に掻き消される。
そんなルイフォンを抱きかかえたまま、冷静さを取り戻したエルファンが小部屋に入り、扉を閉めた。
「何がそんなに可笑しいのだ?」
無表情に尋ねるも、エルファンの目線は、さまよっていた。どこに向かって話しかければよいのか、迷っているだけなのかもしれないが、やはり狼狽しているように感じられる。
〔そりゃ、可笑しいわよ。というよりも、滑稽ね。珍しい組み合わせで仲良くやっているわぁ。あら、微笑ましい、なんて思っていたら、猿ぐつわで拉致だもの! まったく、お前って相変わらずだわぁ〕
涙を浮かべて笑い転げる、人工知能――。
姿のない『もの』であるのだから想像でしかないのだが、ルイフォンの目には、その姿が、はっきりと見えた気がした。
「〈ベロ〉、お前は、ルイフォンが強制アクセスしなければ、出てこないのではなかったか?」
エルファンは、〈ベロ〉の笑いをきっぱり無視することに決めたらしい。その態度に、〔つまらない男ね〕という感想に舌打ちまで聞こえ、更に部屋の光がゆらりと不満げに揺れる。
〔私には、お前たちが来るのが分かっているんだから、強制的に引っ張り出されるよりも、あらかじめ待機しておいたほうがスマートでしょう?〕
そんなことも分からないの? と言わんばかりの高飛車な声である。
〈ベロ〉の言うことは、もっともだ。そのほうが効率が良い。この点は、ルイフォンも同意する。だが、どうして、いちいち人の神経を逆なでするような言い方をするのだろう。
――というよりも、これは〈ベロ〉のモデルとなったシャオリエの性格の問題だ。
母は人選を間違えたのだ。ルイフォンは、そう思わずにはいられない。
「なるほど」
一方、エルファンは静かに相槌を打つと、口の端を上げた。
「お前は、この屋敷の出来ごとをすべて知っているというわけか。それなら話は早い。では、説明は不要だな?」
〔エルファン、そのへんにキリファの仮眠用のベッドがあるから、ルイフォンを寝かせるといいわ〕
「あ? ああ」
質問への返答としては微妙に噛み合っていないのだが、相手は、思うままに、気ままに好き勝手のシャオリエ――をモデルにした『もの』である。
一応は気遣いだと解釈したエルファンは「すまない」と述べて、ルイフォンを下ろす。しかし、次の〈ベロ〉のひとことが、彼の謝意を無下にした。
〔これが十年前ならば、嬉しいくせに無愛想にルイフォンを抱っこしているお前なんて、さぞかし見ものだったんでしょうけれど、さすがにその図体になってからだと、むさ苦しいだけだわぁ。――それと、エルファン。お前、いつまでも若いつもりでいると、ぎっくり腰になるわよ?〕
「……」
エルファンは黙って虚空を見つめた。彼の双眸には、凍てつく殺気がみなぎっている。
その状況をベッドから眺めやり、ルイフォンは心の中で呟いた。
――ああ、面倒臭ぇ……。
やはり、というか。なんというか。〈ベロ〉とは会話が成立しない。シャオリエそのものなのだから、当然だろう。
まったく、こんな奴と話をしたいとは、エルファンも物好きだ。
ルイフォンは傍観を決め込むことにした。横になったことだし、少しでも体を休めて早く傷を治すのだ。それがメイシアを助けることに繋がる。
彼は半眼になりながらそう思い、同時にふと疑問を抱く。
機械類、とりわけ母の遺した〈ケルベロス〉に興味津々のルイフォンからすれば、〈ベロ〉との対面は、鬱陶しいながらも、好奇心を刺激する。けれど、門外漢のエルファンにとっては、そうではないだろう。
なのにエルファンは、唐突に〈ベロ〉に会いたいと言い出した。
しかも、その目的が『メイシアの危機に、〈ベロ〉が警報のひとつも鳴らさなかった理由を釈明させるため』だ。
これは、無意味だ。
リュイセンは既に、メイシアをさらって屋敷を発っている。起きてしまったことを今更、責め立てたところでどうにもならない。
相手が部下の凶賊なら、責任の追求は必要だろう。だが、〈ベロ〉は得体の知れない人工知能。非を認めさせたところで罰の与えようもないのだ。
何故だ?
エルファンが無意味なことをするとは考えられない。
ルイフォンの思考は一転し、その体は、にわかに緊張に包まれる。
「〈ベロ〉、そろそろ本題に移ろう」
気を取り直したのか、はたまた、眉間に浮かんだ苛立ちを、氷の仮面の下に綺麗に収め終えたのか。エルファンを取り巻く空気が一段、重くなった。
〔そうね。私も充分に笑わせてもらったし、そろそろ、お前に付き合ってあげてもいいわ〕
受けて立つ、とでもいうように部屋中の糸が挑戦的にうねりを上げ、からかうような声が響く。
〔お前は、私が警報を鳴らさなかった理由を知りたいんだっけ?〕
「ああ、それならば知っている」
即答だった。
わずかに顎を上げたエルファンは、無表情ながらもどこか得意げで、緩やかに腕を組むその仕草は、今までのお返しだと言わんばかりに見えた。
「〈ケルベロス〉は〈七つの大罪〉の技術の結晶。その性能をフルに使えば、不可能も可能になる、そんな禁忌の代物だ。だから、キリファが『原則として、〈ケルベロス〉は人の世に関わってはいけない』と決めた。――それを守っているためだろう?」
〔何よ! ちゃんと分かっているじゃないの!〕
唇を尖らせたような声と共に、周り中の光が振動する。まるで、不平不満を視覚化したようだ。
「は……?」
ルイフォンは呆けたように呟いた。
母は、〈ケルベロス〉に『人の世に関わってはいけない』と命じたという。それは、つまり『何もするな』ということだ。
ならば、いったいなんのために、母は〈ケルベロス〉を作ったのだ?
ルイフォンは思索の海に沈みかけ、はたと現状に気づく。
「おい、エルファン。じゃあ、警報がどうのって話はなんだよ?」
さっきまで、それを真剣に考えていた彼は、思わずベッドから体を浮かせた。その途端、腹の傷が引きつれて、「痛ぇ……」と悶絶する羽目になる。
ルイフォンの抗議など、エルファンはとっくに予測済みだったのだろう。こちらを振り返り、ふっと鼻で笑った。
「ああ。それは面倒な説明を抜きにして、とりあえずお前を〈ベロ〉のところに連れてくるための方便だ。あんな適当な理由に、お前もよく納得したな」
「納得してねぇよ! お前が、俺を勝手に運んだだけだろ!」
傷を庇いながらも、ルイフォンは言い返す。
わけが分からない。いったい、エルファンは何を考えているのだ。
猫の目を吊り上げ、文句たらたらのルイフォンに、エルファンは口の端を上げた。
「まぁ、聞いていろ。これから、お前とメイシアにとって重要な話になる」
「メイシア!?」
愛しい名前に胸が震えた。
そして次の瞬間には、ルイフォンの目つきは鋭くなり、顔つきが変わり、神経が研ぎ澄まされる。
「ルイフォン、お前はメイシアを取り戻す。それがどんなに困難だったとしても。――そうだな?」
重く、冷ややかな口調であったが、白金の光を映すエルファンの瞳には慈愛の色が見えた。質問の意図は分からぬが、ルイフォンの答えはひとつに決まっている。
「当然だ!」
「それでこそ、だ」
エルファンは満足げな笑みをこぼすと、身を翻す。広い背中が『ついて来い』と告げているように見えた。
「〈ベロ〉」
玲瓏たる響きが、虚空に向けて放たれた。
エルファンは光の波打つ天井を仰ぎ、そのうねりを追うように瞳を巡らせる。ちらりと見えた横顔は、神秘の白金に照らされて、まるで祈りを捧げるかのように静謐だった。
「メイシアの身柄は、必ずルイフォンが取り戻す。人の世のことは、人の手でなんとかする。そこに、お前の協力は求めない。それは約束する」
〔いきなり、どうしたの?〕
目的の読めぬ言動への不快と、興味。光の糸が弾かれ、ざわりと蠢く。
「だが、〈七つの大罪〉の領域にあるものは、私たちにはどうすることもできない。だから、お前に助けてほしい。――頼む」
〔どういうこと?〕
白金の光が、戸惑うように明暗を変えた。
「メイシアがさらわれた経緯は知っているのだろう? では、メイシアを手に入れた〈蝿〉が、次に何をするか。――今までの情報と照らし合わせれば、彼女を『セレイエの〈影〉』にする可能性が高い」
「――!」
ルイフォンの心臓に衝撃が走った。
そうだ。
〈蝿〉のもとから帰ってきたリュイセンは、こう言っていた。
『メイシアは、『セレイエの〈影〉』だそうだ……』
『『今はメイシア本人だけど、いずれメイシアでなくなる』と……』
脳裏に蘇ったリュイセンの言葉に、息が止まりそうになる。
メイシアが、初めて鷹刀一族の屋敷を訪れた日。その直前に、彼女は仕立て屋に化けたセレイエの〈影〉、ホンシュアに会っている。そのときに何かをされたのは、もう疑いようもない。
そして――。
『セレイエは、メイシアを『最強の〈天使〉』にして、その体を乗っ取ろうとしている』
エルファンは、そう読んだ。
今まさに、その話をしているのだ。
「――メイシア……!」
ルイフォンは叫びたくなるのを押さえ、唇を噛んだ。口の中に広がる血の味も、ぐっとこらえる。
「〈ベロ〉、〈影〉は人の世の存在ではない。〈七つの大罪〉の領域だ。――ルイフォンはメイシアの身柄を取り戻すことはできても、彼女が〈影〉にされるのを止めることはできない」
「!」
エルファンの言葉に、ルイフォンの体は情けないくらいに震えた。
後ろを振り返らなくとも、エルファンには、その様子が手に取るように分かっていただろう。しかし、彼はそのまま白金の光を浴びながら、祈るように告げた。
「だから、〈ベロ〉。手を貸してくれ。メイシアが〈影〉にされるのを阻止してほしい」
「!?」
ルイフォンは息を呑んだ。
「……できるのか?」
〈天使〉の力には抗えない。〈天使〉である母に記憶を改竄されたルイフォンは、それを身をもって知っている。
けれど――。
「〈ベロ〉、お前なら、メイシアを助けられるのか!?」
ルイフォンは痛む腹も気にせずに、ベッドから飛び下りた。引きつるような激痛が走ったが、そんなことは構わない。這うようにして移動して、エルファンの隣にひざまずく。
「〈ベロ〉、頼む! メイシアを助けてくれ!」
体を折り曲げ、頭を下げると、腹が裂けたような感触があった。だらだらと冷や汗をたらすルイフォンに、エルファンが顔色を変え、〈ベロ〉の光が慌てふためく。
「ルイフォン!」
〔ルイフォン、やめなさい!〕
ぱたりと倒れそうになったルイフォンを、エルファンは抱え上げた。そして、天の光に向かって叫ぶ。
「〈ベロ〉! 頼む! ルイフォンに手を貸してやってくれ!」
すがるような眼差しだった。そこに、冷徹なる次期総帥の面影はない。
強く弾かれた弦のように、光の糸が大きくたわんだ。白金の輝きが、震えるように明暗を揺らす。
そして。
〔……お前たちの望みには、応えられないわ〕
艶を欠いた、乾いた〈ベロ〉の声が響いた。
2.守護者との邂逅-2

「何故だ?」
エルファンのまとう気配が、一瞬にして氷点下となった。
刺すような冷気があたりを漂う。凍てつく魔性の瞳が天井を見つめ、冷ややかに責め立てる。
「これは〈七つの大罪〉の領域だ。しかも、セレイエの仕業だ。あの子が……、私の娘がしでかしたことだ」
エルファンは、決して声を荒らげたわけではなかった。けれど、彼に抱えられていたルイフォンには、地底から轟くような憤怒が腕から直接、伝わってきた。
「キリファが、お前たち〈ケルベロス〉を作った意味を忘れたわけじゃないだろう!?」
〔キリファのことを、何も分かってあげられなかったお前に言われたくないわ〕
「なんだと!」
〔だって、お前はキリファの気持ちに気づかなかったでしょう?〕
「お前に何が分かる!?」
ぐっと詰め寄るように光に挑むと、エルファンは目を細めた。それは、白金の輝きが眩しいためと見せかけていたが、眉間の皺が彼の後悔を暴いている。
にわかに混乱めいてきた。――というよりも、明らかに話が横道にそれている。
「おい、お前ら! 脱線しているぞ!」
ルイフォンは猫の目を尖らせた。
「今は、母さんとエルファンの話じゃねぇだろ! メイシアだ! あいつを〈影〉にされないためにはどうすればいいのか。〈ベロ〉、お前は何か知っているんじゃないのか!?」
昔話が気にならないわけではないが、今は、そんなことを揉めている場合ではない。ルイフォンは、エルファンの胸を叩き、「下ろせ」と不快げに命じる。
はっと我に返ったエルファンは、すみやかにルイフォンをベッドに戻した。〈ベロ〉もまた、余計なことを言ったと、ばつが悪そうに光を揺らす。
「話をもとに戻せ。そして、俺に分かるように説明しろ」
ルイフォンの冷静な怒りのテノールが両者に告げる。
彼の頭上で、どちらが説明するのか、無言の押し付け合いの気配が繰り広げられ……やがて、エルファンが静かに口を開いた。つまり、彼のほうが、いろいろと分が悪いらしい。
「〈ケルベロス〉は、セレイエのために作られたシステムだ」
氷の美声が、ひやりと耳を撫でた。
とんでもない性能を持った〈ケルベロス〉。母は何故、こんなものを三台も作ろうとしていたのか、ルイフォンはずっと疑問だった。
その答えが――。
「セレイエのため……?」
「ああ。セレイエが生まれながらの〈天使〉だと分かったあとに、キリファが作り始めた。――『〈天使〉の力を無効化するもの』だと聞いている」
「――!」
母は、〈ケルベロス〉に『人の世に関わってはいけない』と命じた。
それは『何もするな』という意味ではなく、〈七つの大罪〉の技術の結晶である〈ケルベロス〉には、同じく〈七つの大罪〉の領域に属する〈天使〉の力を封じることだけを望み、他の活動を禁じた――という意味だったのだ。
そして、悪用されることのないよう、張りぼての〈ケルベロス〉の後ろに隠した。
納得した様子のルイフォンに頷き、エルファンは再び天井を仰ぐ。
「〈ベロ〉、お前は〈天使〉の力を無効化できる。ならば、メイシアが〈影〉にされるのを阻止することもできるはずだ」
〔だから、その望みには『応えられない』の! ……『無理』なのよ〕
それまでの〈ベロ〉とは打って変わって、気弱な声だった。光の糸もまた弱々しく震え、部屋全体に淡い色合いが広がる。
〔意地悪を言っているわけじゃなくて、私には『不可能』なの〕
そこでルイフォンは、はっとした。
「もしかして、俺がまだ〈スー〉の解析を終えていないからか? 〈ケルベロス〉は三台が揃わないと、本来の性能を発揮できないのか!?」
もし、そうであるのなら、全力で解析を進める。今までも少しずつやってはいたのだが、何しろ効率の悪い作業だ。その上、最近は〈蝿〉の庭園への潜入作戦の準備もあった。
……とはいえ、忙しさにかまけて、面倒な作業を後回しにしていた感は否めない。ルイフォンは猛省する。
〔ルイフォン……。確かに〈ケルベロス〉は、すべてが揃わなければ、真の能力が発揮できないのは本当よ。でも、そうじゃなくて、エルファンは根本的に勘違いをしているの〕
「勘違い……?」
エルファンが低い声で呟き、眉を上げる。
〔〈ケルベロス〉は、セレイエの母親であるキリファが、娘の幸せを願って作ったものよ。自分の血を受け継いでしまったばかりに〈天使〉の宿命を背負ってしまった娘を、解放するためのもの……〕
穏やかに波打つ糸の中を、淋しげな陰りを帯びた光が駆け抜ける。
〔だから、〈ケルベロス〉の能力は、エルファンが考えているような、〈天使〉個人に働きかけて羽を使えなくしたり、〈天使〉に介入された人間の状態をもとに戻したりするようなものではないの〕
白金の糸が揺れる。どう説明したものか迷うように、光の流れが惑う。
〔そんな、個々を相手に『無効化』するような、みみっちいものじゃないの。もっと、根本的に解決する方法。『〈天使〉という存在を、無効化させる』、最終手段――〕
〈ベロ〉は、そこで大きく息を吸うように、光をたわませた。
それは、〈ベロ〉らしからぬ逡巡に感じられ、ルイフォンの背中に不吉な予感が走る。
〔〈天使〉の力の源である、〈冥王〉を破壊するためのシステム……――っ、…………〕
その瞬間、部屋中の光が激しい明滅を繰り返した。
瞳を刺すような閃光と、漆黒の暗闇。
そのふたつが交互に、そして瞬時に切り替えられる。視覚が混乱に陥れられ、激しい目眩に襲われる。
そんな中、細く、苦しげな〈ベロ〉の声が聞こえた。
〔ああ、……やっぱり……来たわ、ねぇ……、〈悪魔〉の『契約』……〕
「『契約』!?」
吐き気がするような状況であったが、ルイフォンは聞き返さずにはいられなかった。
〈悪魔〉には、王族の秘密を口外すれば死が訪れる、という『契約』が刻まれている。今の場合は、おそらく、いや間違いなく『〈冥王〉』という名称が引き金だったのだろう。
聞き覚えがあった。
以前、会議中にイーレオが『〈冥王〉』と口走った瞬間に苦しみだした。
――だが、『契約』が発動したからには、〈ベロ〉は〈悪魔〉だということになる……?
困惑するルイフォンに、〈ベロ〉がくすりと笑う。
〔私は〈悪魔〉では……ない、わ……。ただ……、『人』だったときの記憶を……持っているだけ〕
そのとき、エルファンが血相を変えて叫んだ。
「パイシュエ様!? 『あなた』は、パイシュエ様なのですか!?」
光の明滅が徐々に収まってきた。あたりが見えるようになってきて、ルイフォンは、エルファンが蒼白な顔をしていることに気づく。
「エルファン、『パイシュエ』って。もしかして……?」
「シャオリエ様が〈影〉だというのは、お前も知っているだろう? あの方の本来のお名前だ」
想像通りの答えだった。
彼女はかつて、イーレオと共に〈悪魔〉として〈七つの大罪〉の内部に深く入り込み、一族を解放するために奔走した人だ。詳しいことは知らないが、彼女の犠牲によって、悲願が叶ったのだという。イーレオが『俺を育ててくれた女』と愛しげに呼ぶ人物だ。
「そうか……」
〈ケルベロス〉が、これほどまでに『人』に近いのは、なんらかの方法で『人』の記憶を利用して作られているからだ。そして、記憶を受け継いでいるために、記憶に刻まれていた『契約』も引き継いでしまっている――。
〔エルファン、私を『パイシュエ』と呼んだら駄目よ。私は『〈ベロ〉』でなくちゃ。私が『パイシュエ』だったら、死んだはずの人間が生き返ったことになるわ。――そんなのは許されない。『パイシュエ』は〈七つの大罪〉の技術を否定する側の人間だったんだから〕
「!」
エルファンは短く息を吸った。だが、すぐに平静を取り戻す。
「はい。その通りですね、〈ベロ〉様」
彼は〈ベロ〉の名に敬称をつけ、頭を垂れた。
優しく見守るような、柔らかな光が揺れる。その様子を見ながら、ルイフォンは、ふと疑問に思う。
「でも、だったらなんで、お前は母さんに利用されて〈ベロ〉になることを許したんだ? 〈ケルベロス〉はお前が否定する〈七つの大罪〉の技術の結晶だろ? 無理やりだったのか?」
シャオリエ――『パイシュエ』なら、〈七つの大罪〉について詳しく、また鷹刀一族の屋敷の守護を任せるにふさわしい。母が、『パイシュエ』を〈ベロ〉に選ぶのも分かる。けれど、『パイシュエ』の気持ちは……。
〔……ぷっ〕
いきなり〈ベロ〉が吹き出した。
「なっ!? 何が可笑しい?」
〔お前が、大真面目な顔をして心配してくれちゃうから、可愛くて。生まれたときは赤ん坊だったのに、本当に大きくなったわねぇ」
「生まれたときが赤ん坊なのは、当たり前だろ!」
迂闊だった。〈ベロ〉は、あのシャオリエと同じ性格をしているのだ。それとなく訊かなければ、茶化されるに決まっていた。――正面から真剣に気遣ったことをルイフォンは後悔する。
〔あらぁ、褒めてあげたのに。拗ねないでよ〕
ルイフォンの気持ちなどお構いなしに、〈ベロ〉は、くすくすと笑う。
〔大丈夫よ。無理やりなんかじゃないわ。私は今の状態を楽しんでいる。私は望んで、キリファに一口、乗ったのよ〕
「どういう意味だ?」
〔キリファが〈ケルベロス〉にやらせようとしていることは、〈七つの大罪〉の技術の破壊よ。最高の魔術師による、今まで誰も思いつきもしなかった、この国を根底から覆すような大掛かりな『魔法』。そんな面白いもの、この私が見逃すはずないじゃない〕
「『魔法』?」
〔ものの例えよ。けど、とんでもないことをやらかそうとしている、というのは分かるでしょう? ――何しろ、キリファの呼び出しには、先王シルフェンが応じたくらいなんだから〕
「――!」
刹那、ルイフォンの全身を貫くような衝撃が走った。
〈ベロ〉は、母が先王に殺されたときのことを言っている――!
「〈ベロ〉、それは……、つまり……どういう……?」
声が、心が、体が、震えた。
しかし、ぴしゃりと跳ねのけるように、光の糸が弾かれる。
〔言わないわ。だって、〈ケル〉も言わなかったでしょう?〕
「……っ!」
ルイフォンは奥歯を噛んだ。
何かを掴めそうになった瞬間の、喪失感。これまでに何度も味わってきたものだ。ベッドに横になったまま、彼は無意識に前髪を掻き上げる。
自分とそっくりな猫の目を持った母が、どこかで嗤っている。
『あんたなんて、まだまだね』――そう言って、彼を待っている……。
〔ルイフォン〕
〈ベロ〉の声に、どこかへ迷い込みそうになっていた意識が引き戻された。
〔いい? 私は、自ら望んでキリファに協力している。――誇りを持って、ね〕
竪琴の弦を爪弾くように、白金の糸が細やかに揺れる。光の音楽を奏でる〈ベロ〉は、実に『生き生きと』していた。
「……ああ、そうだな」
詳しいことはお預けだが、ともかく〈ベロ〉は、自分の意志で今の状況にある。
彼は「よかった」と口走りそうになり、すんでのところで堪えた。気遣いをそのまま口に出したら、また〈ベロ〉にからかわれる。だから、今度は混ぜっ返されないように、心の中だけで安堵した。
そして、代わりに別のことを呟く。
「早く、〈スー〉の解析を終えなきゃな……」
すると、光の糸が、すっとルイフォンの頭を撫でるようにかすめていった。
「?」
首をかしげた彼に、〈ベロ〉が言う。
〔ルイフォン。とりあえず、〈スー〉のことは放置でいいわ〕
「え? だって、〈スー〉が揃わないと〈ケルベロス〉は真の能力が発揮できないんだろ? それじゃ、お前は……」
〔別に、『ずっと、ほったらかしでいい』とは言ってないでしょ〕
戸惑うルイフォンを、〈ベロ〉の声がすかさず遮った。
〔でも、今までの話で分かったでしょう? 〈ケルベロス〉では、メイシアが〈影〉にされるのを阻止することはできない。お前が直面している問題に対して〈ケルベロス〉は役に立たない〕
「……」
白金を見つめるルイフォンの顔が、陰りを帯びる。
〔だから、〈スー〉の解析は後回し。まずは、メイシアの身柄を取り戻しなさい。それが、お前が今、為すべきことよ〕
「それは勿論だが……」
身柄を取り戻しても、〈影〉にされてしまったら、彼女を失ったと同じことなのだ。
〔安心しなさい。私の見解では『メイシアの体が、セレイエに乗っ取られる』ことはないわ〕
「何故、そう思うんだ?」
〔セレイエが、そこまで非道に堕ちたとは思わないからよ〕
「はぁっ!?」
まったくもって論理的でない答えに、思わず語尾が上がった。
〔だって、あの子、ルイフォンとメイシアをくっつけるために、いろいろ画策していたわけでしょう。なのに、メイシアを自分が乗っ取って終わりって、それは酷いんじゃない?〕
「……」
押し黙ったルイフォンの代わりに、エルファンが口を挟む。
「〈ベロ〉様、それはあまりにも楽観的ではありませんか?」
〔お前ってば相変わらず、悲観的ねぇ。ルイフォンも、そばにいると辛気臭いのが移るわよ。気をつけてね〕
「〈ベロ〉様!〕
〔あら、怖い。いい男が台無しよ?〕
からからとした明るい笑い声と共に、部屋を巡る光が、からかうようにさっと流れ、それから、ぴたりと止まる。
〔メイシアは王族の血を引いているから、大丈夫よ〕
「どういうことだ!?」
ルイフォンは息を呑んだ。
かっと見開かれた猫の目に、鋭い光が宿る。しかし、白金の糸が淡く首を振るように揺らめいた。
〔『契約』に抵触するから言えないわ〕
「――っ! すまない……」
〔まぁ、すべてはセレイエの心次第ね。メイシアの身柄を囚えているのがヘイシャオの〈影〉であっても、結局はセレイエの〈影〉が、メイシアの中にどんな命令を刻み込んだかの問題だから〕
「……分かった」
すべてはセレイエ次第……。
そんなあやふやなものに、メイシアを委ねるのは恐ろしい。
身を震わせたルイフォンのそばを、ひときわ強い光が駆け抜けた。それは、まるで彼を挑発するようであり、また鼓舞するようでもあった。
〔ともかく、お前のやるべきことはひとつだけ〕
「ああ。メイシアを取り戻す――!」
〔そう。それでいいわ〕
正確なことは不明だ。けれど進めと、〈ベロ〉がルイフォンの背中を押す。
「〈ベロ〉、ありがとな」
ルイフォンは、ベッドから光を見上げた。
礼くらい、きちんと立って頭を下げるべきだと思ったが、それは無理だと腹の傷が告げていた。この怪我を治さなければ何も始まらない。まずは、そこからだ。
〔いえいえ。それじゃあ、私はそろそろ消えるわ。……あまり長く『人』と接していると、自分が『人』だと錯覚してしまいそうだから〕
軽やかに弾かれた糸が、愛しげな光を放つ。
それは、叶えてはいけない願い。禁じられた望みだ。
何故なら〈ベロ〉は、人の世の存在ではないのだから……。
部屋中に広がっていた光の糸は、くるくると回転しながらひとつに集まり、白金に輝く光の珠へと姿を変えていく。
〔あとは人の手で頑張りなさいね。ひよっ子に何ができるか。楽しみにしているわ〕
3.硝子の華の希求

屋敷の温室にて、ミンウェイはひとり、ガーデンチェアーに腰掛けていた。
硝子張りの空間は、初夏の陽射しを集めて離さず、決して快適とはいえない密室だった。波打つ長い黒髪をひとつにまとめ、首筋を外気に晒していても、額にはうっすらと汗が浮かんでくる。
風が、そよとも吹かぬのだから当然だろう。外界の音はここには届かず、緑が放つ、かすかな息吹だけが聞こえている。
「……」
彼女はテーブルに頬杖を付いた。鋳物の天板に広がる蔦の装飾模様を眺めながら、大きな溜め息を吐く。切れ長の目には深い隈ができており、絶世の美貌には濃い影が落ちていた。
――昨晩は大変だった。
リュイセンがメイシアを襲い、〈蝿〉のもとへ連れ去るという、まさかの裏切り。その際に、弟分であるルイフォンを斬りつけるという凶行にまで及んだ。そしてルイフォンは、何針も縫う大怪我を負った。
それだけでも大事件なのに、安静を言い渡しておいたルイフォンが、夜中に動き回ったのだ。しかも、その片棒を担いだのが、常に冷静なはずの次期総帥エルファン。ふたりで、地下にある『真の〈ベロ〉』に会いにいったという。
にわかには信じられなかったが、ルイフォンの容態の悪化は現実のもので、彼女は寝ていたところを叩き起こされた。
『忘れないうちに、親父に報告書を書いておきたい』などと、ふざけたことを言うルイフォンを叱り飛ばし、彼女は処置にあたった。報告書はエルファンが引き受けることで落ち着かせたが、あれから半日ほど経った今も、ルイフォンは熱を出して寝込んでいる。
無茶をしたのだから、自業自得だ。
けれど――。
ルイフォンは、メイシアのために必死だったのだ。
そして、彼に無茶をさせたエルファンもまた、メイシアが手遅れに――〈影〉にされてしまうことを恐れ、焦っていたのだと報告書から知った。
「……っ」
ミンウェイは唇を噛んだ。申し訳程度に塗った紅が、ぐにゃりと歪む。
リュイセンは何故、一族を、ルイフォンとメイシアを裏切ったのだろう?
失敗してしまった〈蝿〉捕獲作戦の報告の中に『斑目タオロンの娘のファンルゥは、ルイフォンやリュイセンにとっても人質として有効だと、〈蝿〉に看破されてしまった』とあった。しかし、ファンルゥの命をちらつかされて脅されたなら、リュイセンは皆に相談したはずだ。黙ってメイシアを差し出すなんてあり得ない。
それに、もと一族である父の記憶を受け継いだ〈蝿〉なら、鷹刀の人間が、顔見知り程度の縁故のために一族を裏切るとは考えないだろう。
囚われてしまったリュイセンは、てっきり人質として使われるものと考えられていた。けれど〈蝿〉は、リュイセンを手駒にして、『一度、解放した』。『リュイセンは、絶対にメイシアを連れて戻ってくる』という自信がなければできないことだ。
――〈蝿〉に囚われていた間に、リュイセンに何があったのだろう……?
ミンウェイは、頭を抱えるようにして目を伏せる。
リュイセンが戻ってきてすぐの、昨日の午前中、彼とふたりきりになったときがあった。
言葉は、ほとんど交わさなかった。『健康状態を確認する』という名目で部屋を訪れたのがよくなかったのかもしれない。
はらりと落とされた上着と、むき出しの上半身に声を出せなくなった。
死線をさまよったのが、はっきりと分かる傷痕と、それを診たのが父だと分かる丁寧な縫合――。
心が痛くて、自分がどんな診察をしたのかさえ、よく覚えていない。リュイセンもまた無口で、そして、切なげにこちらを見つめていたのは……知っている。
あのとき既に、リュイセンは裏切りを決意していたのだ。だから言葉少なだったのだろう。
けれど、彼女が部屋を去るときだけは、優しい低音を鮮やかに響かせた。
『ミンウェイ、ありがとう』
力強い腕が彼女を包み、一瞬だけ唇が触れた。
何が起きたのか。彼女が理解するよりも先に、軽く肩を押された。彼女の体が廊下へと、よろめいた。その隙に素早く扉が閉められ、鍵の掛かる音が聞こえた。
「……リュイセン」
あれは、どういう意味だったのだろう。
彼女の思考はそこで止まっている。
分からない。……たぶん、考えたくない。
自分だけが取り残されているのを感じる。周りにいる誰もが、どんどんと前に進む。けれども、彼女は動けない。動きたくない。
置き去りのミンウェイは、こうしてひとり、無音の世界に留まっている……。
どのくらいの時が過ぎたのだろうか。
ほぼ真上にあった太陽が、斜めに角度を変えてきた。
不意に、背後で緑の揺れる気配がした。この空間にはないはずの風がそよぎ、ミンウェイは振り返る。
「……緋扇さん!?」
そこに、警察隊の緋扇シュアンの姿があった。
いつ櫛を入れたのか分からないような、ぼさぼさ頭に、特徴的な三白眼。そして、血色の悪い凶相。ただし、顔色の悪さに限っては、今日はお互い様だろう。
彼は、左右から張り出した枝を邪魔そうに掻き分けながら、こちらにやってきた。
「やっぱり、あんたはここだったな」
溜め息と共に呟き、シュアンは当然のように向かいのガーデンチェアーに腰を下ろす。
どうして彼がここに? と、疑問が浮かんだが、すぐに思い出した。メイシアの異母弟ハオリュウの代理として、今回の件の詳細を聞きに来る約束をしていた。その帰りなのだろう。
前にも、シュアンは屋敷への用事のついでに、温室に立ち寄ったことがある。だから、この場所を知っている。けれど同時に、ミンウェイがひとりになりたくて、ここにいることもまた彼なら分かるはずだ。
勝手に入り込んでくるのは無神経だ。彼女の気持ちなど、お構いなし。図々しくて、ふてぶてしい。
それが、シュアンだ。
……彼の、無愛想な優しさだ。
けれど、今は、本気で放っておいてほしい。
ミンウェイは顔には出さず、内心で眉を寄せる。
……自分は、どうにも彼に余計なことを漏らしてしまうきらいがある。
前にこの温室で話したときには、かつて自殺しようとしたことを告白してしまったし、別のときには、リュイセンに『死んだ父を男として愛していた』などと言われたことを伝えてしまった。
どちらも、言う必要のない話だった。むしろ、言うべきではなかった。
なのに、ぽろりとこぼしてしまうのは、彼が以前、『負い目に思うことは何もない』と言ってくれたからだろう。
だから、つい気を許してしまう。口を滑らせてしまう。そうすれば、少しだけ楽になれるから……。
――でも今は、本当に、誰にも会いたくない。何も話したくないのだ。
なんとかして、追い返したい。
ミンウェイは当たり障りのない言葉を探し求めるが、それを待ってくれるようなシュアンではなかった。
「あんた、また引き籠もっているんだな」
開口一番、容赦ないひとことだった。できるだけ穏便に、と思っていたミンウェイも、さすがに声を荒らげる。
「そんな、私は……!」
「ほう? 違うのか? リュイセンの裏切りは自分のせいだと、うじうじ悩んでいたんじゃねぇのか?」
「えっ!?」
シュアンの口調は軽かった。決して責めるような様子はなく、むしろ、からかうような、笑い飛ばすような、そんな声色だった。
しかし、彼の言葉は、まるで斬りつけるかのようにミンウェイの耳朶を打った。痛みを感じる。耳にも、心にも。それなのに、まったく意味を理解できなかった。
「どうして、リュイセンの裏切りが……私のせいになるんですか……?」
ミンウェイは、シュアンの顔を穴があくほど凝視する。
「は?」
シュアンの目が点になった。彼の代名詞ともいえる三白眼を放棄して、ミンウェイを見つめ返す。
「おい、嘘だろ!? あんた、まさか気づいていなかったのか!?」
愕然とした顔で、素っ頓狂な声を上げた。
やがて彼は、がくりと肩を落とし、テーブルに肘を付いた。ぼさぼさ頭をがりがりと掻きむしる。私服のため、制帽のない頭は乱れ放題だ。
「鷹刀の連中も、あんたに何も言わなかったのかよ。過保護にも程があるだろ……」
「緋扇さん? いったい、なんですか?」
言っていることが分からない。だが、失礼な態度であることは明白だ。ミンウェイは切れ長の目に険を載せ、テーブルに突っ伏したシュアンを睨む。
殺気にも近い気配に、シュアンは顔を上げた。そして、ふっと口元を緩める。
「……怒った顔も美人だな」
「緋扇さん!」
ミンウェイは柳眉を逆立てた。シュアンの掴みどころのなさは、いつものことだが、今日はまた格別だ。
「悪い。あまりの事態に、つい現実逃避しかけた」
シュアンは大きく息を吐く。それから、すっと目を細めると、普段通りの三白眼に戻った。
「ミンウェイ」
彼女の名を呼び、真剣に考えるような素振りをした。彼にしては珍しい。状況の不可解さと併せ、彼女の心に不安がよぎる。
「……なんでしょうか」
「いいか? リュイセンのしたことは、ルイフォンの逆鱗に触れるものだ。あのふたりの仲が元通りになることは、二度とないだろう」
「……っ!」
背筋が、ぞくりとした。
シュアンの言う通りだ。
「どうして、リュイセンは……」
子供が駄々をこねるように身をよじると、ひとつにまとめた髪が揺れ、草の香が漂う。
『どうして』は、昨晩から何度も、心の中で繰り返してきた問いだった。しかし、投げかけても投げかけても、自分の中からは何も返ってこなかった。
そんな疑問をシュアンはこともなげに受け止め、明確な答えを彼女に示す。
「決まっている。『弟分のルイフォンよりも、大切な人間のため』だ」
「え……?」
「それ以外の理由で、あの堅物がルイフォンを裏切るわけがないだろう? ――つまり、ミンウェイ。『あんたのため』だ」
凶相から紡がれた響きは、あくまでも柔らかかった。けれど、突きつけられた言葉がミンウェイの心を鋭くえぐる。
「あいつが、あんたに惚れているのは、さすがに分かっているんだろう?」
ミンウェイは……小さく頷いた。
分かっている。
結局、撤回されたが、リュイセンにはプロポーズまでされたのだから。
「……でも、緋扇さん。裏切りが、どうして私のためになるんですか? 私は、こんな事態なんか望んでいません! なんで、なんで、こんな……っ!」
喉が詰まった。嗚咽のような声が漏れ、ミンウェイは慌てて口元を押さえる。しかし、先を読んでいたのか、シュアンは表情を変えることもなく、諭すように答えた。
「別に、裏切ることが直接、あんたのためになるわけじゃないさ。それどころか、あんたを深く傷つけることくらい、リュイセンには分かりきっていたはずだ。それでも、あいつは裏切らざるを得なかったんだろう」
「どういう……ことですか?」
ミンウェイは、ごくりと唾を呑んだ。身を乗り出してきた彼女に、シュアンは「状況を整理するぞ」と静かに告げる。
「〈蝿〉は、メイシア嬢の身柄を欲しがっていた。だが、鷹刀のガードが固く、手を出せないでいた。そんなとき、リュイセンを囚えた。彼なら、誰にも疑われることなくメイシア嬢に近づき、さらうことができる。――〈蝿〉はそう考え、リュイセンを手駒にしたんだ」
淡々とした説明に、ミンウェイは、ひとつひとつ頷いていく。
「〈蝿〉は、斑目タオロンに対しては、娘を人質に取った。それと同じことで、リュイセンに対しては、あんたを使ったのさ。おそらく、あんたをネタに脅したんだろう」
「私をネタに脅す……?」
ミンウェイは首をかしげ、問い返す。
「ああ。例えば、そうだな。『〈蝿〉が持っている薬を投与しなければ、ミンウェイは母親と同じ病で死ぬ』と脅されたら、リュイセンは薬を手に入れるためになんでもするだろう」
「え? 私は、お母様とは違って健康体だと、お父様は……」
「だから、『例えば』と言っただろう? ネタはなんだっていい、嘘でもいいのさ。リュイセンの馬鹿が信じさえすればな」
「そんな……!」
「『〈蝿〉に従わなければ、あんたに良くないことが起きる』――そう臭わせるだけで、リュイセンには充分なのさ。あいつなら、簡単に〈蝿〉の手に堕ちるだろう」
息を呑んだミンウェイに、シュアンは畳み掛ける。
「〈蝿〉は、あんたの父親の記憶を持っている。それをちらつかせ、『自分だけが知っている、重大な事実だ』とでも言われれば、あの単細胞には逆らうことはできないさ」
「――!」
シュアンの言っていることは、あくまでも彼の推測だ。けれど、もし真実なら、リュイセンの言動に説明がつく……。
ミンウェイの目線が力なく落ちていった。長い睫毛が綺麗に下を向き、テーブルの装飾模様をなぞっているかのように揺れ動く。
「ミンウェイ。――リュイセンの裏切りには、必ず納得できる理由がある」
シュアンの声が、そっと肩を抱くように優しく彼女を包んだ。けれど、その声色はそこまでだった。
「まぁ、俺は奴には毛嫌いされていたから、いなくなって清々しているけどな」
不意に、がらりと、シュアンの雰囲気が変わった。
ミンウェイが驚いて顔を上げれば、にやりと口角を上げた凶相が、立派な悪人面を作っていた。
「――けど、あんたはそうじゃねぇな?」
三白眼が意味ありげに歪み、彼女に問いかける。
シュアンは、ふんぞり返るように足を組んだ。ガーデンチェアーの背にのけぞれば、ミンウェイとの距離が少し離れる。
『俺は、あんたとは違って、リュイセンなんてどうでもいいのさ』――そう主張するかのような距離感。そして彼は、世間話のような口調で言う。
「イーレオさんは、リュイセンを追放処分にしたそうだな。奴がしたことを考えれば、抹殺命令が出されてもおかしくなさそうなのにさ。思わず、理由を訊いちまったよ」
何が可笑しいのか、シュアンは低く喉を鳴らした。
「『もし、リュイセンが一族の者を傷つけたなら、問答無用で抹殺命令を出した』だそうだ。けど、ルイフォンとメイシア嬢は『対等な協力者』であって、『一族』ではないから、追放処分にとどめたんだとよ。――あんた、この屁理屈を信じるか?」
おどけたように肩をすくめ、軽薄な口調で彼女に尋ねる。
「え……? 屁理屈……なんですか?」
「屁理屈さ。イーレオさんの甘さが透けて見える。この様子なら、メイシア嬢を無事に取り戻した上で、リュイセンに納得のいく説明をさせる。そんでもって、あんたやルイフォンとメイシアが口添えをすれば、リュイセンの追放処分の取り消しも可能じゃねぇか?」
「でも、ルイフォンは……!」
ルイフォンは、メイシアに危害を加えたリュイセンを決して許すことはないだろう。それは先ほど、シュアンも口にしていたはずだ。
悲壮な顔をするミンウェイに、シュアンが告げる。
「あんた、さっき言ったよな。『こんな事態なんか望んでいない』って。それは、誰もが同じはずだ。――ルイフォンだって、イーレオさんだってな」
「……」
「望んでいない事態なら、変えればいい。――ルイフォンはメイシア嬢のために、早速、無茶な行動を起こして寝込んでいるんだろう? 今回は、エルファンさんまで一枚、噛んだんだってな?」
テーブルの向こうのシュアンは、面白そうに三白眼を細め、癖のある笑みを作った。腕まで組んで、対岸を楽しげに眺めるかのような態度だ。
けれど、突き放したようでありながら、そっとミンウェイの背中を押している。
『それで? あんたは?』
『いつまで引き籠もっているつもりだ?』
無言の声が聞こえる。
刹那、ミンウェイは立ち上がった。
彼女の背で、波打つ黒髪が宙を舞う。
無風の温室に、草の香りの風が広がっていく。
「……ぁ」
いきなり席を立ったりして、どうするというのだろう。シュアンも変に思ったに違いない。
羞恥と狼狽で彼を見やれば、ぼさぼさ頭がゆっくりと動き出した。
「さて、俺はこれから、ハオリュウのところに状況説明に行かなきゃな」
がたがたと、ガーデンチェアーの脚を地面にこすらせながら、シュアンが腰を上げる。
「ミンウェイ。ハオリュウが、ルイフォンの怪我をだいぶ心配していた。まずは、あいつを頼む。メイシア嬢を取り戻すのも、あいつが中心になるだろうからな」
できるところから進めていけ。
シュアンが、そう道を示す。
「はい!」
ミンウェイは、艶やかに微笑んだ。顔色の悪さが即時に払拭されることはないが、彼女の象徴ともいえる緋色の衣服が華やぎを添える。
「緋扇さん、門までお送りします」
「ほお。美女に別れを惜しまれるとは、光栄なことで」
シュアンの眉がわざとらしく驚きを表し、三白眼が嬉しげに細まる。
「いえ。私はこれからルイフォンのところに行くので、そのついでです」
「……相変わらず、あんたはつれないねぇ」
予想通りの台詞で苦笑するシュアンに、ミンウェイはくすりと笑みをこぼした。
「緋扇さんは、また来てくださるのでしょう? だったら、別れなど惜しくありません」
「!?」
思わぬ反撃に面食らったのか、シュアンが声を詰まらせた。それから、これは一本とられたと破顔する。
「……ああ、そうだな。当分の間、慌ただしくなるからな」
ふたりは肩を並べ、緑の中を抜けていく……。
温室の出口の手前で、ミンウェイはシュアンに向き合った。扉の隙間から漏れてくる風が、彼女の髪をなびかせ、彼のぼさぼさ頭を揺らしていく。
「緋扇さん。ありがとうございました」
晴れやかな声に、シュアンは口元をほころばせ、彼女に応える。
「はて? なんのことやら」
そして、ミンウェイはシュアンと共に温室を出た。
4.囚われの姫君-1

夕食の用意ができたと、ルイフォンを迎えに行くところだった。
リュイセンが無事に戻ってきたお祝いだと、料理長が盛大に腕をふるったご馳走の数々は本当に美味しそうで、メイシアは晩餐がとても楽しみだった。
不安は山ほどある。けれど、皆がいれば大丈夫。――そう思いながら、ルイフォンの部屋のある階まで登ってきた。
すると、長い廊下の先に、すらりとした人影が見えた。
「リュイセン?」
疑問の形で呼んだのは、自信がなかったからだ。
初夏とはいえ、夜。しかも、空は雨雲に覆われていて暗かった。ぼんやりと電灯に照らされた顔は、確かにリュイセンのものに見えるのだが、彼が持っているはずの輝きは消え失せており、存在感が薄い。まるで幽鬼だ。
彼は、ゆっくりとメイシアに近づいてきた。
窓の外で、紫の雷光が閃く。
黄金比の美貌が、妖しく浮かび上がる。
「え?」
そう呟いたときには、首筋に手刀を落とされていた。メイシアの体は崩れ落ち、彼に抱きとめられる。
腕に、ちくりとした痛みを感じた。
そして、彼女は完全に意識を失った。
人の気配を感じ、メイシアは身をよじらせた。
「やっと、目が覚めましたか」
閉じた瞼の向こう側から、低く美麗な声が彼女を迎えた。
鷹刀一族の屋敷でよく聞く声質だが、彼女の知っている、どの声とも雰囲気が違う。響きの中に、神経質な音が混ざっている。
まどろみから、覚醒へと。
彼女は五感を取り戻す。
「――!」
目の前に、次期総帥エルファンとそっくりな顔があった。
――〈蝿〉だ。
メイシアは即座に理解した。
――ここは、〈蝿〉の研究室だ。
見た目は、白く清潔でありながら、黒い陰謀と禁忌にまみれた密室。
異母弟ハオリュウは、摂政カイウォルと共にこの部屋を訪れ、次代の王『ライシェン』を見た。そして、王家に〈神の御子〉が生まれぬ場合には、〈七つの大罪〉の〈悪魔〉が過去の王のクローンを作るのだと知らされた……。
白衣姿の〈蝿〉が、ベッドの上のメイシアを舐めるように見つめていた。彼女は怖気を感じ、思わず自分の体を掻き抱く。
「!?」
その瞬間、メイシアは、自分の手首に硬い感触が食い込むのを感じ、青ざめた。
両手が枷で繋がれていた。
右手と左手が鎖で結ばれ、手と手を離すことができない。
今までに経験したことのない事態に、彼女の恐怖が一気に膨れ上がった。歯の根が合わない口は悲鳴すらも上げられず、ただ脅えきった瞳を、この仕打ちをしたであろう〈蝿〉に向ける。
「安心してください。別に私は、あなたに危害を加えるつもりはありませんよ」
〈蝿〉は微笑みさえ浮かべ、優しげな低音を落とした。
「その枷は、単に、あなたの置かれた立場を分かりやすく伝えるための措置です。あなたが囚われていることに納得したら、すぐに外して差し上げますよ」
囚われている――。
その言葉が、メイシアの心臓を握り潰す。
自分は、敵地であるこの研究室で、独りきり。皆はいない。――ルイフォンがいない。
自分は、どうなるのか分からない。きっと、皆が心配している。――ルイフォンが心配している……。
「……」
ルイフォン、と、心の中で叫ぶと、涙が浮かんできた。
そんなメイシアの様子を〈蝿〉が、ふっと嗤う。彼女は、羞恥と屈辱で、慌てて指先で目元を拭った。枷で繋がれた、もう片方の手が引きずられ、嫌でも『置かれた立場』を認識させられる。
両手の間で、鎖がじゃらりと鳴った。
ざらついた重い音と、硬く冷たい感触。それが、彼女に突きつけられた現実だ。
恐ろしくて、不安で、惨めで、苦しい。けれど同時に、腹の底から怒りが湧いてきた。
――屈しない。
必ず、ルイフォンが助けに来てくれる。だから、それまで独りで耐え抜く。
メイシアの中で、覚悟が生まれた。
まずは、ベッドに転がされている状況から、脱するのだ。
「ああ、いきなり起き上がらないほうがいいですよ。まだ、麻酔の余韻が残っているでしょうからね」
〈蝿〉が口の端を上げた。そのときには動き出していた彼女は、身をもって彼の言葉の正しさを知る羽目になる。頭を上げようとしただけで、くらりと目眩がした。
「なかなか目を覚まさないので心配しました。もう、翌日の昼ですよ。途中であなたが暴れたら厄介かと思って、リュイセンに薬を使わせたのですが、やりすぎだったかと後悔し始めたところでした」
「!」
リュイセン――!
決定的な言葉が、メイシアの心を刺した。
何かの間違いであって欲しいと、願っていた。
しかし、やはり――。
「リュイセンが……私を、あなたのもとに連れてきたんですね」
メイシアの声はかすれていた。けれど、凛と澄んだ黒曜石の瞳は、まっすぐに〈蝿〉を捕らえている。
取り乱すことなく問うたメイシアに、〈蝿〉はわずかに目を見開いた。それから、顔をほころばせ「ええ、そうですよ」と答える。
「飲み込みが早くて助かります」
「……リュイセンに、何をしたんですか!」
彼が、ルイフォンやメイシアを裏切るとは思えない。
メイシアの拉致は、もはや、どうしようもない事実であるのだが、本意ではなかったはずだ。きっと何か事情がある。
睨みつけてくる彼女を、〈蝿〉が低く嗤った。
「リュイセンは、彼の意思で、私に協力してくれたんですよ」
「嘘です!」
鎖を掛けられ、憐れに横たわり、長い黒絹の髪は乱れ放題……。
今のメイシアは、力なき者の象徴のような姿であった。それにも関わらず、高く澄んだ声は、勢いよく〈蝿〉の言葉を跳ね返した。青ざめていたはずの白磁の肌は紅潮し、怒気をまとう。
「随分と、はっきりおっしゃいますね」
半ば呆れたような、感心したような調子で〈蝿〉が微笑んだ。歯向かったメイシアに腹を立てる様子もないのは、優位に立つ者の余裕だろう。
「ですが、事実なのですよ。……ああ、では、こうしましょう。あとで、リュイセンに会わせて差し上げます。直接、本人に訊くとよいでしょう」
我ながら名案だとばかりに、美麗な顔が柔らかに緩んだ。
魅惑の微笑の中に、狡猾さが見え隠れする。少しでも気を抜くと、醜く歪んだ事態に呑み込まれてしまいそうだ。
メイシアは必死に自分を奮い立たせる。
今の言葉は、現状を把握するための、重要なヒントだ。
『あとで』と言った以上、メイシアがこの場で殺されることはないだろう。おそらく、どこかに監禁されるのだ。
彼女を囚えた目的を果たすまでは、身の安全は保証されるとみてよさそうだ。長期戦になるだろうが、その分、〈蝿〉を出し抜く機会はあるはずだ。
そして、〈蝿〉のほうから、リュイセンに会わせてくれると言い出した。
これは重大な情報だ。
もしも、リュイセンが薬などで自我を奪われているのであれば、〈蝿〉は彼を隠すだろう。つまり、リュイセンの意識は、はっきりとしており、しかし卑劣な手段によって〈蝿〉に逆らうことができないのだ。
しかも、メイシアとリュイセンが力を合わせたところで、現状を覆すことはできない。少なくとも、〈蝿〉はそう考えている。そうでなければ、ふたりを近づけない。
この自信の根拠は、なんであろう?
そもそも、どうしてリュイセンは、〈蝿〉に従う羽目になった……?
「何か、問題でも?」
メイシアの思考を遮るように、薄ら笑いの声が割り込んだ。裏を読もうとしても無駄ですよ、と言っているように聞こえた。
確かに、今ここで考えても答えは出まい。〈蝿〉の言いなりも癪だが、リュイセンに会えば、もう少し何かが分かるだろう。
「いえ。あなたのおっしゃる通り、リュイセンに訊くことにします」
「ええ、それがよいでしょう。……では、そろそろ、私の話を始めてもよろしいですか?」
刹那、メイシアの背筋に緊張が走った。
〈蝿〉が彼女を囚えた理由――その話だと、直感的に悟る。
「すみません。体勢を変えさせてください」
メイシアは大きく息を吐き、体の芯に力を入れた。
いつまでも、こんな情けない格好では心が弱くなってしまう。せめて、きちんと体を起こすのだ。
彼女は、枷で繋がれた不自由な両手を支えにしながら、ゆっくりと上体を持ち上げた。ベッドから足を下ろし、膝を揃えてきちんと座る。背筋を伸ばし、椅子に腰掛けた〈蝿〉と目線を合わせるべく顔を上向かせると、彼女の気迫を後押しするかのように黒絹の髪がさらさらと背中を流れた。
「私は、鷹刀セレイエを見つけ出したいのです」
閉ざされた地下に、秘密を打ち明けるかのような〈蝿〉の低い声が響いた。
「セレイエさん……ですか」
「ええ。彼女は、自分の〈影〉であるホンシュアに命じて、私を作り、騙し、『駒』として利用しました」
〈蝿〉から、昏い憎悪が放たれた。
それは、ここにはいないセレイエに向けられたものであったが、余波を浴びたメイシアは身を震わせる。
「鷹刀セレイエは、『デヴァイン・シンフォニア計画』を企てておきながら、自分自身では手を下さず、すべて〈影〉に任せていました。そして、〈影〉が死んでなお、いまだ隠れ続けている。――その彼女を表に引きずり出したいのですよ」
そこまで言って、〈蝿〉はじっとメイシアを見つめた。口元はわずかにほころび、不気味な笑みが浮かんでいる。
獲物を狙う捕食者の、ぞくりとする視線だった。吸い付いてくるような瞳は、まるで舌舐めずりをしているかのよう。
メイシアは奥歯を噛み締め、ひるみそうになる心をぐっと抑える。
ふたりの間で、無音が広がった。
実際には、研究室内にある機械類が鈍く振動していたのだが、それはもはや音として認識されない。
握りしめた手が、しっとりと汗ばむ。
――〈蝿〉はセレイエに復讐したい、ということだろうか……?
メイシアもまた、〈蝿〉の顔を凝視した。
鷹刀一族そのものの、美麗な顔貌。生え際に混じる白い毛が、神経質な印象を与える。武の家系の直系でありながら医学を極めた彼は、知的であり、冷徹にも見え、そのくせ所作はどこか柔らかい……。
不意に、〈蝿〉が吐息を漏らした。
「この程度では、なんの反応もありませんか」
「え……?」
メイシアは瞳を瞬かせた。
「あなたの中の『鷹刀セレイエ』に語りかけたつもりだったのですが、どうやら届かなかったようです」
「私の中の、セレイエさん……? どういうこと……ですか?」
メイシアの心臓が警鐘を鳴らし始めた。
問い返しながらも彼女の中に予感が芽生え、恐怖が体を凍らせていく。
「おや、賢しいあなたが、私の言葉の意味を理解できないとは意外ですね」
〈蝿〉は小馬鹿にしたように肩をすくめた。
「リュイセンが言ったはずですよ。あなたは『鷹刀セレイエの〈影〉』だと」
「……っ!」
メイシアは鋭く息を呑む。悲鳴のような音が喉からこぼれた。
「鷹刀の面々に漏らしてしまったと、リュイセンから報告を受けているのですが……聞いていませんか?」
「私……、私は……私、です……! 〈影〉なんかじゃ……!」
途切れ途切れの反論は弱々しく、語尾は擦り切れ、消えていく……。
リュイセンが戻ってきたあとの、会議のとき。
ルイフォンに問い詰められたリュイセンは、苦しげに告げた。
『メイシアは、『セレイエの〈影〉』だそうだ……』
『なんだよ、それ? あり得ねぇだろ!』
ルイフォンは笑い飛ばしてくれた。
『俺だって、〈蝿〉にそう言った! そしたら、『今はメイシア本人だけど、いずれメイシアでなくなる』と……』
リュイセンは噛み付くように言い返した。
『〈蝿〉に『契約』が発動した。『王族の血を濃く引いた、あの娘なら』――そう言いかけたところで苦しみ始めた』
「ああ……、ああぁ……!」
メイシアの脳裏に、あのときのやり取りが蘇る。
思わず耳をふさごうとして、鎖にじゃらりと邪魔された。離すことのできない両手では、両耳をふさげない。
そもそも、記憶に残る声は、耳をふさいだところで消えはしない……。
『私は何者でもなく、ただの『メイシア』で――ルイフォンのそばに居る者なの』
『怖いと思う。何が起きているのかすら分からないのが、凄く不安……。でも、ルイフォンが居る。だから、大丈夫』
ルイフォンと、ふたりきりになったとき、メイシアはそう言った。
『ルイフォンがいるから、大丈夫』
けれど、今ここに、彼はいない。
愛しくて、切なくて、苦しい。
自分が、自分以外になったら、この気持ちを忘れてしまうのだろうか……?
……嫌だ。許せない。
――この魂を奪われてなるものか……!
「〈蝿〉!」
黒曜石の瞳を真っ赤に充血させ、メイシアは叫んだ。
「私は、私です! 何故、私を『セレイエさんの〈影〉』などと言うのですか!」
黒絹の髪を振り乱し、牙をむいたメイシアに、しかし〈蝿〉は苦笑した。
「迂闊なことを言えば、私は『契約』に抵触してしまうのですよ。……それも、リュイセンから聞いているでしょう?」
「答える気がないのなら、別に構いません。私は〈影〉になるつもりなどありませんから、この話は終わりにしましょう!」
すると〈蝿〉は、何が可笑しいのか喉の奥で静かに嗤った。すっと立ち上がり、メイシアの両手を繋ぐ鎖を掴む。そして、それをぐいと引き上げた。
「あなたは、自分が囚われの身だということをお忘れではないですか?」
「!?」
次の瞬間、彼女の体はふわりと宙を舞った。
〈蝿〉は、たいして力を加えたようには見えなかった。しかし、彼女は軽々と投げ飛ばされ、冷たい床に打ち付けられる。
「…………っ!」
全身に痛みが広がった。枷に繋がれた手では受け身を取ることもできず――そもそも、彼女の身体能力では、たとえ両手が自由だったとしても、されるがままに転がされるしかなかっただろう。
「あなたの中の『鷹刀セレイエ』が目覚めてくださらないと、私が困るのですよ。その記憶が、雲隠れした鷹刀セレイエの居場所を知る、唯一の手掛かりなのですから」
高い位置から見下ろし、〈蝿〉は冷酷な声で告げる。
「鷹刀セレイエ本人だって、きっと困っていることでしょう。『デヴァイン・シンフォニア計画』の水先案内人として、あらゆる雑事をこなしていたホンシュアが死んだ今、代わりの〈影〉が必要なはずです」
メイシアは悟る。
自分の置かれた立場を忘れ、感情のままに叫んだのは、確かに失態だった。囚われの身だからこそ、冷静になる必要があった。
ここは敵地で、メイシアは今、戦っているのだ。
非力な彼女は、賢く立ち回らなければならない。
そのために、敵である〈蝿〉を知る。どんな些細なことでもいい、〈蝿〉を理解する。だから、今は彼との会話を繋げるのだ……。
威圧的な〈蝿〉に、メイシアは震えながら、それでも毅然と上を向いた。
彼女は、よろよろと立ち上がり、ベッドに座る。〈蝿〉は、その様子を興味深げに見るだけで、止めることはなかった。
そして、時間が少し前に巻き戻ったかのように、ふたりは再び向き合った――。
4.囚われの姫君-2

「取り乱したりして、失礼いたしました」
メイシアは、〈蝿〉に頭を下げた。
黒絹の髪の先が、自分の膝をさらりと撫でる。体を動かすと、投げ飛ばされたときに打った背中が悲鳴を上げたが、その痛みは矜持でもって表には出さなかった。
「おやおや、急に従順になりましたね」
揶揄するような〈蝿〉の言葉を、彼女はじっと聞き流す。彼を怒らせるのは得策ではない。たった今、文字通りに『痛いほど』理解した。
そんな彼女の屈辱など、お見通しなのだろう。〈蝿〉が愉悦の笑みを浮かべる。
「心を入れ替えたあなたに、敬意を表して良いことを教えて差し上げましょう」
〈蝿〉の言うことなど碌なことではない。
身構えると、自然と肩に力が入る。その様子に、〈蝿〉がまた嬉しそうに目を細めた。
「『契約』に抵触するため、詳しい理屈は説明できませんが、リュイセンに教えたことの半分は嘘ですよ」
「え……?」
「あなたは『鷹刀セレイエの〈影〉』であり、『今はあなた本人だけど、いずれあなたでなくなる』という話――本当は、少し違うのです」
「!?」
メイシアは不審と不安、それから、ほんの少しの期待で体を震わせた。無意識に自分の体を抱きしめれば、手枷の鎖が油断は禁物だとばかりに、じゃらりと音を立てる。
「あなたにとっては朗報ですよ」
優しげにすら見える眼差しで、彼女を囚えている〈悪魔〉は告げる。
「あなたは、あなたのまま、別人になることはありません。あなたは、ただ『鷹刀セレイエ』の記憶『も』、持っているだけ――……っ!」
突然、〈蝿〉は、白衣の胸をぐしゃりと握りしめた。ぱりっとした布地を皺だらけにして、彼は苦痛に顔を歪める。
「〈蝿〉!?」
「な、に……!? ……この……程度で……、駄目、なのか……! 糞……っ」
「大丈夫ですか!?」
メイシアは血相を変えた。たとえ彼が敵であっても、いきなり目の前で苦しみ出したら、さすがに落ち着いてなどいられない。思わず、ベッドから飛び降りる。
「だから……『契約』……言った……しょう……!」
脂汗を浮かべながら、憤怒の顔で〈蝿〉は言い放った。駆け寄ろうとしたメイシアをぎろりと睨みつけ、追い返すように鋭く手を払う。
「しばらく……、収まり……す」
〈蝿〉の荒い呼吸が、空間を占めた。
辛そうに肩を上下させる〈蝿〉を瞳に映し、メイシアは茫然と、倒れ込むようにしてベッドに戻る。
「『契約』……、王族の『秘密』に抵触したから……」
今、起きたことを確認するかのように、彼女は、ぽつりと言葉を落とした。
「私は、私のままでありながら、セレイエさんの記憶も持つことができる。それは、私が王族の血を引いているから……?」
〈蝿〉は憎々しげに眉を寄せたものの、ふいと目をそらした。聞こえなかったふりをしたのだ。
当然だろう。迂闊に肯定などしようものなら、死が訪れる。
しかし、その彼の態度が、彼女の言葉の正しさを示していた。
それは、すなわち。
メイシアの魂は、奪われることはない――。
「あぁ……」
心の底から、安堵が広がる。
歓喜がこみ上げてきた。こんな状況にも関わらず、薄紅の唇に微笑みが浮かぶ。
ルイフォン、と心の中で呼びかけた。
必ず、あなたのもとに帰るから……。
「安心しましたか?」
憮然とした声が、彼女を現実に引き戻した。
〈蝿〉を見やれば、彼は乱れた髪を整え、白衣の襟元を正していた。具合いが良くなったのか、声にはまだ、かすれたところがあるものの、言葉はしっかりとしている。
「あなたが、あなたの中の『鷹刀セレイエ』をあれほど激しく拒絶してしまっては、『彼女』が目覚めるのは難しいかと思いましてね。あなたを落ち着けて差し上げようとしたのですよ。……無茶をしました」
「……」
随分と恩着せがましい物言いだった。〈蝿〉が無茶をしたのは自分の利益のためであり、メイシアを喜ばせるためではない。
だから、当然のことながら、〈蝿〉に対して感謝の気持ちなど、微塵にも抱く気にならない。
ただ――。
いまだ〈蝿〉の額に張り付いている、白髪混じりの前髪を見つめながら、メイシアは思う。
彼は決して、狂人などではなく、『セレイエを見つける』という目的のためになら、手段を問わないほどに必死なだけだ。
だからこそ、手強い。
そして、リュイセンも……。
〈蝿〉が、リュイセンに『今はメイシア本人だけど、いずれメイシアでなくなる』と嘘をついたのは、『契約』への抵触を避けると同時に、彼の裏切りを後押しするためだ。
リュイセンが裏切らなくても、やがてメイシアは消えてしまう。そう説明されれば、リュイセンも決断しやすくなる。
何故、リュイセンが〈蝿〉の言いなりになってしまったのかは、まったくの謎だけれど、彼もまた、『何か』に必死なのは確かだ……。
「計画では、時が来れば、あなたの中の『鷹刀セレイエ』は自然に目覚めるはずだったそうですよ」
『契約』の警告が収まったからか、前より少し軽い口調で、〈蝿〉が世間話のように告げる。
メイシアは、問わずにはいられなかった。
「……あなたがセレイエさんを探しているのは、彼女に復讐するため、ですか?」
〈蝿〉がメイシアの中の『セレイエ』を目覚めさせようと躍起になっているのは、行方不明のセレイエの居場所を訊くためだ。
では、セレイエに会ったなら――?
メイシアの黒曜石の瞳が陰りを帯びる。
「〈蝿〉……、あなたは『デヴァイン・シンフォニア計画』のために、セレイエさんに作られたと聞きました。『駒』にされるために生を享けたなら、セレイエさんに対するあなたの恨みは、もっともなことだと思います」
けど――と、続けようとしたところで、〈蝿〉が口を挟んだ。
「ほう? いったい何を言い出すかと思えば……」
彼は、わざとらしく驚いたように眉を上げ、鼻で笑う。
「同情を装った、ご機嫌取りですか」
「い、いえ!」
メイシアは、反射的に否定した。
しかし、否定してから気づく。
囚われの身の彼女にとって、〈蝿〉の機嫌を取ることは必要なことだ。彼に寄り添うような姿勢を見せることで、彼の口を滑らかにし、少しでも役に立ちそうな情報を引き出す。
良いことではない。けれど、やるべきことだ。これは、彼女の戦いなのだから。
メイシアは、手枷の鎖を鳴らし、胸に手を当てた。
それは、高鳴る鼓動を鎮めるためでもあり、同時に、自分の行為は、決して卑屈な腰巾着のそれではないと、胸を張るためでもあった。
「私……、あなたのお姉様に――ユイラン様にお会いしました」
「姉さん……!?」
〈蝿〉はあからさまに顔色を変えた。
メイシアは、やはり、と内心で思う。
目的のためには手段を選ばないような〈蝿〉であるが、彼の心にも弱い部分がある。
――『鷹刀一族への思い』だ。
もはや関係の修復は不可能と諦めながらも、彼は今でも一族を大切に思っている。それは、これまでのやり取りから明らかで、だからメイシアは、卑劣と思いながらも『偽りの『和解』で彼を騙す』という策まで考えた。
ユイランの名前を出したのは、生前のヘイシャオにとって身近であろう人物で、かつ現在、正面から敵対しているイーレオやエルファンを避けた結果だ。
「ユイラン様は、『弟の死は、事実上の自殺だった。だから、彼が自分の意思で生き返ることはあり得ない。〈蝿〉は、弟の最期の思いを無視して、第三者に利用されてしまった悲しい存在だ』と、やるせなさそうで……。だから、あなたがセレイエさんを恨む気持ちは当然のものだと、私は――」
「はっ!」
突然、〈蝿〉が不快感もあらわに吐き捨てた。言葉の途中で遮られ、メイシアはびくりと肩を上げる。
「それはつまり、私は『不本意に『生』を享けたから』、鷹刀セレイエを恨んでいる。――そういうことですか!?」
その通りだ。
意に反しての蘇りを強いられた上に、『駒』にされたのだ。さぞや恨み骨髄だろうと、メイシアは話を持っていくつもりだった。
しかし、〈蝿〉の放つ殺気が、彼女から声を奪う。触れてはいけない話題だったのだろうか。彼の態度の理由がまるで分からない。
「あなたも――姉さんも、『私』は自殺したと言うのですね!」
〈蝿〉の剣幕に、メイシアはたじろいだ。
「ええ、分かっていますとも! それが真実なのでしょう! 死の間際のホンシュアも、同じことを言っていましたから!」
彼は、悪鬼の形相で吠えた。
わなわなと曲げられた指で、白髪混じりの自分の頭を掻きむしる。まるで、その中にある記憶をほじくり返し、暴こうとでもするかのように。
「けれど、『私』は知りません……! 『私』は、『鷹刀ヘイシャオ』が死んだことすら知りません!」
「え……? ……あっ!」
メイシアは一瞬、混乱し、しかし聡明な彼女は、すぐに〈蝿〉の悲痛な叫びの意味を察する。息を呑んだ彼女に、畳み掛けるようにして吐き出された彼の次の台詞が、彼女の推測の正しさを証明した。
「当然でしょう! 『私』が持つ記憶は、『ヘイシャオが生きている間』に保存されたもの。『私』が、彼の死を知るはずがありません!」
「……っ」
叩きつけられた鋭い声に、メイシアは肩を縮こませる。
「私は――いえ、オリジナルの『鷹刀ヘイシャオ』は、ミンウェイと約束を交わしました。『生を享けた以上、生をまっとうする』――これは、『私』にとって絶対の誓約です」
昏い美貌に、矜持に似た何かが浮かぶ。
「鷹刀ヘイシャオが、自殺などするはずがないのです。彼が自ら『死』を望むなど、あり得ない!」
「きゃっ」
だんっ、と強く足を踏み鳴らした〈蝿〉に、メイシアは思わず悲鳴を上げた。
激しい憤りの表情を見せながら、しかし、彼の心は明らかに追い詰められていた。それは、彼が鷹刀ヘイシャオ本人ではなく、作られた『もの』であるが故の苦しみであり、憐れであり、不幸だった。
「ええ、私も馬鹿ではありません。分かっていますよ。――私の持つ記憶が保存された時点から、オリジナルの鷹刀ヘイシャオが死ぬまでの間に、『彼が心変わりするような事件があった』ということでしょう」
ぞっとするほどに深く、怨嗟に満ちた笑みで、〈蝿〉は自嘲する。
「しかし、たとえ何があったとしても、『死』はミンウェイへの裏切り行為です。私はヘイシャオを許しません」
『ミンウェイ』と口にしたときだけ、〈蝿〉の声色が変わる。
切なげで愛しげで、辛そうでもあるのに、そのときだけ険が和らぐ……。
彼の言う『ミンウェイ』は、メイシアのよく知るミンウェイではなく、彼女の母であり、〈蝿〉の妻であった女を指すことは一目瞭然だった。
「小娘。あなたは、私が鷹刀セレイエを探す理由を訊きましたね。――お答えしましょう。『私が、生き残るため』ですよ」
「……!?」
唐突な発言だった。
メイシアは理解が追いつかず、黒曜石の瞳をただただ大きく見開く。そんな彼女に、〈蝿〉が口の端を上げた。
「まず初めに確認ですが、鷹刀の子猫や、あなたの異母弟がこの館で見聞きしたことは、あなたにも伝わっていると考えて問題ありませんね?」
「――はい」
恐る恐る、答えた。
何か、とんでもない話が始まる予感がして、メイシアの体は、否が応でも緊張で固まっていく。
「ならば、私が〈神の御子〉を――『ライシェン』を作ったことはご存知でしょう?」
「はい……」
「『ライシェン』は、王家のトップシークレットです。摂政カイウォルは、完成した『ライシェン』を受け取ったあかつきには、秘密を知る私を殺そうとするでしょう」
メイシアは、そのまま頷こうとして、はたと疑問に思った。戸惑いの呼吸に、気配にさとい〈蝿〉が、ぎろりと目玉を動かす。
この状況で何も言わないのは得策ではないだろう。彼女は遠慮がちに「すみません」と断り、慎重に言葉を選びながら、おずおずと尋ねる。
「王家に〈神の御子〉が必要になったとき、〈悪魔〉たちが〈神の御子〉を作ることは、慣例となっているはずです。なのに、役目を果たした〈悪魔〉が殺されるなんて、おかしいと思います」
彼女の弁に、〈蝿〉は面倒臭そうに鼻を鳴らした。
「『ライシェン』には、特別な事情があるのですよ」
気になる答えだった。
しかし、〈蝿〉は、それ以上のことを言うつもりはないらしく、「さておき」と続ける。これでは、メイシアは押し黙るしかない。
「そして、鷹刀セレイエもまた、摂政に命を狙われています。摂政にとって、彼女は私以上に目障りな人間なのですよ。彼女がすべてを〈影〉に任せて雲隠れしているのも、おそらく摂政から身を守るためでしょう」
メイシアは瞳を瞬かせた。
セレイエもまた、〈蝿〉と同じく、王族にとって大事な〈悪魔〉であるはずだ。なのに、この扱いはどういうことだろう。
首をかしげたメイシアの耳に、驚くべき〈蝿〉の発言が流れてくる。
「ですから、私は、摂政に対抗するために、鷹刀セレイエと手を組みたいのです」
「……!?」
思わず、目を見開いた。
〈蝿〉は、セレイエを恨んでいるのではなかったか……?
その疑問は、そのまま顔に出ていたのだろう。彼は忌々しげに口元を歪め、神経質な眉間に皺を寄せた。
「あなたの言いたいことは分かります。私は、自分を『駒』にしたセレイエを憎んでいるはずだ、手を組むなど、あり得ない。――そうでしょう?」
声高な〈蝿〉に圧倒され、メイシアの喉が張り付いた。故に、彼女はただ、ゆっくりと首肯する。
「……憎んでいますよ。こうしている今だって、はらわたが煮えくり返っています。――しかし、『生きて』と言った、ミンウェイとの最後の約束を守るためには、そうするしかないのです」
〈蝿〉にとって、死んだ妻の言葉は何よりも重いらしい。
彼女と交わした約束は、絶対の誓約。
純粋すぎる思いが、痛々しいほどの哀愁を漂わせる。
けれど同時に、そんな彼を冷ややかな目で見つめる自分がいることに、メイシアは気づいた。
彼の言葉を、ほんの少し離れて聞いてみれば、それはただの生への執着だ。
この男は、他人の犠牲をいとわない。メイシアの父は、彼に殺されたも同然だ。そんな人間の語る生など、耳を傾ける価値はない。――そう思う。
「鷹刀セレイエへの復讐は、私の身の安全が保証されてからです。場合によっては、表に引きずり出した彼女を摂政に売って、保身を図ってもよいわけです。交渉次第ですよ」
そう言って〈蝿〉は、ねとつく視線をメイシアに向ける。
「何しろ私の手元には、鷹刀セレイエが最大の頼みにしている『最強の〈天使〉の器』がありますからね。彼女は私を無碍にはできないはずです」
「!?」
捕食者の目だった。
本能的に身の危険を感じ、メイシアの背筋が凍る。
『最強の〈天使〉の器』――あの会議のときに、リュイセンが、メイシアに対して口にした言葉だ。そして、イーレオが『契約』に苦しみ、エルファンがこう叫んだのだ――。
「――王族の血を引く者が〈天使〉になれば、強い力を持つ……」
知らず、声に出した彼女に、〈蝿〉が驚きの表情を見せる。
「どうしてそれを?」
失言だったのか――?
焦るメイシアに〈蝿〉が無言の圧力を掛ける。故に、彼女は選択の余地もなく答えた。
「……エルファン様が、ルイフォンのお母様から――〈天使〉だったキリファさんから聞いたそうです」
「なるほど。『契約』に触れかねない話でしたから、あなたがご存知で助かりました」
〈蝿〉は、ほっとしたように息を吐いた。
「そうです。あなたこそ、『最強の〈天使〉の器』です。……ひとつ付け加えるならば、あなたが最強といえる理由は、王族の血を引くことに加えて、あなたの中に『鷹刀セレイエ』の記憶があるからですよ」
「え?」
「〈天使〉の力の使い方を熟知した『鷹刀セレイエ』の知識があるからこそ、最強たり得るのです。ただ王族の血を引いているだけでは、力は強くとも、制御しきれずに熱暴走を起こすだろうと、ホンシュアが言っていました」
メイシアは、無意識に自分の体を抱きしめた。
血の気の引いた白蝋のような顔で、じっと〈蝿〉の言葉を噛みしめる。室温は変わっていないはずなのに、寒くてたまらない。
「あなたは切り札です。あなたの身柄が、私を優位に立たせてくれる。――あなたは、『デヴァイン・シンフォニア計画』を生き抜くための、最大の鍵なのです」
「『デヴァイン・シンフォニア計画』……」
結局は、これなのだ。
がたがたと、体が震える。
その動きに合わせ、手首から伸びた鎖が、囚われの音色を響かせる。
「……『デヴァイン・シンフォニア計画』とは、いったい、なんなのですか?」
仕組まれた運命からの解放を祈るように、メイシアの口から細い声が漏れた。
「私も全貌を把握しているわけではありません。それより、あなたの中の『鷹刀セレイエ』が目覚めれば、あなたは自然にすべてを知ることができるはずなのですが……」
〈蝿〉は、ほんの少し思案の顔を見せ、そして続けた。
「わざわざ説明するのは面倒臭いと思っておりましたが、まぁ、よいでしょう。あなたの中の『鷹刀セレイエ』への刺激になるかもしれませんし、あなたが驚く顔を見るのも面白い余興でしょう」
閉ざされた地下の研究室に、魅惑の薄笑いが広がる。
白衣の〈悪魔〉は、まるで呪文を描くかのように、虚空に向かって指を滑らせた。
「『デヴァイン・シンフォニア』は、『di;vine+sin;fonia』と綴るのだそうですよ」
『di』は、『ふたつ』を意味する接頭辞。『vine』は、『蔓』。
つまり、『ふたつの蔓』。
――転じて、『二重螺旋』『DNAの立体構造』――『命』の暗喩。
『sin』は『罪』。『fonia』は語呂合わせ。
これらの意味を繋ぎ合わせて、『命に対する冒涜』。
「鷹刀セレイエは、自分の『願い』が冒涜であると理解していながら、それでもなお、望まずにはいられなかったんですよ」
「セレイエさんの『願い』……?」
メイシアが問うと、〈蝿〉の喉の奥から低い嗤いが返ってきた。
「彼女は私と同類です。――死んだ人間を諦めきれず、それが『命に対する冒涜』と知りながらも、蘇らせようと希う……」
「セレイエさんは、どなたか大切な方を亡くした。……そういうことですか?」
顔色を変えたメイシアに、〈蝿〉は大仰なほどに深々と頷いた。
「ええ。鷹刀セレイエは子供を亡くしました。……殺されたんですよ」
「!?」
メイシアは息を呑んだ。
ルイフォンが言っていた。――異父姉のセレイエは貴族と駆け落ちをしたと。
そして、子供が生まれていたのだ。
「どうして……、殺されるなんて……」
メイシアのその言葉を待っていたのだろう。〈蝿〉がにやりと嗤う。
「生まれた子供が、『白金の髪、青灰色の瞳の男子』――すなわち、〈神の御子〉の男子だったからですよ」
「――!」
それがもし本当ならば、その子供は現女王を退け、王位に就く資格を持つ。
しかし、王族にしてみれば、どこの馬の骨とも知れぬ女が産んだ子供を王と認めるだろうか。
――否だ。
だから、殺されたのだ。
「もう、お分かりでしょう? 〈神の御子〉の『ライシェン』。――彼は、鷹刀セレイエの子供のクローンです」
「……!」
悲鳴が、漏れそうになった。
声を押さえようと口元に手を当てると、それに連なる手枷の鎖が、代わりの音を高く響かせる。
〈悪魔〉は蕩けるような微笑を浮かべ、甘やかさすら漂う優しい低音で、そっと囁いた。
「鷹刀セレイエは、殺された息子を『次代の王』として誕生させようとしているのですよ」
それが――。
『デヴァイン・シンフォニア計画』。
4.囚われの姫君-3

『〈神の御子〉の『ライシェン』。――彼は、鷹刀セレイエの子供のクローンです』
『彼女は、殺された息子を『次代の王』として誕生させようとしているのですよ』
それが――。
『デヴァイン・シンフォニア計画』。
研究室の空気が、冷たく沈み込んだ。
メイシアも、〈蝿〉も押し黙り、地下の空間は重たい静寂に包まれる。ふたりとも、時が止まったかのように動かず、機械類の鈍い振動だけが、現実との繋がりを示していた。
どのくらい、そうしていただろうか。
不意に、〈蝿〉が勝ち誇ったかのように口角を上げた。期待通りのメイシアの反応に、愉悦の笑みをこらえきれなくなったのだ。
〈蝿〉の低い嗤いが広がる。
それでもメイシアは、凍りついたように瞬きひとつできない。
ひとしきり冷笑を響かせると、彼は満足したのだろう。彼女の驚愕は充分に堪能したとばかりの上機嫌な様子で、付け足すように言う。
「鷹刀セレイエは、大切に保管されていたはずの『過去の王の遺伝子』をすべて廃棄しました。つまり、〈神の御子〉のクローンが欲しければ『ライシェン』を作るしかない、という状況を作り上げたわけですよ」
「――!」
メイシアが掌で口元を押さえると、手枷の鎖が音を立てた。
〈蝿〉は嬉しそうに、喉の奥を鳴らす。
「彼女は、女王と婚約者が『異母兄妹』だということも知っていたのでしょう。だから、まず間違いなく、女王は自分で〈神の御子〉を産もうなどとは考えない。結婚が決まれば、すぐにクローンに頼る。――そう踏んだわけです。まったく、たいした策士ですね」
〈蝿〉は、肩をすくめて称賛した。
けれど――。
彼は、セレイエを自分の『同類』と言っていた。憎みながら、恨みながら、それだけではない感情を抱いている。
軽く目を伏せた美貌は、意地の悪い微笑。自分の子を蘇らせようと必死にあがくセレイエに対し、嘲っているようであり――、憐れんでいるようにも……見えてしまった。
メイシアは、目線を落とし、〈蝿〉を視界から外す。間違っても、彼に同情などしたくなかった。
綺麗に磨かれた床を見ながら、彼女は、ふと思い出す。
『女王の婚約を開始条件に、『デヴァイン・シンフォニア計画』は動き出す』
ルイフォンは、ずっとそう言っていた。
本当に、その通りだったのだ。
ぴたりと合った符丁に、震えが止まらない……。
「さて。余興は、このくらいでよいでしょう」
不意を衝くような低音に、メイシアは、はっとした。
そうであった。
〈蝿〉にとっては、『デヴァイン・シンフォニア計画』の目的を語ることは、余興に過ぎない。この男はただ、彼女が驚く様を見たかっただけだ。
彼は、おもむろに立ち上がった。くるりと白衣の背を見せ、そのまま部屋の奥へと歩き出す。
行く手に衝立が見えた。
明らかに不自然に置かれたそれは、その向こう側にあるものを隠すためだろう。
「!」
メイシアは悟り、顔色を変える。
――『ライシェン』と『ミンウェイ』だ。
衝立の向こうには、硝子ケースに入った『彼ら』がいる。
そうとしか考えられない。
さらわれ、囚われてしまったという、自分の状況にばかり目が行ってしまい、周りを探ることを忘れていた。
何故もっと早く、『彼ら』の姿が見えないことに気づかなかったのであろう。この研究室は『彼ら』のための場所といっても過言ではないのに。
そう思った瞬間、ぞくりと悪寒が走った。
本能的な恐怖だった。
〈蝿〉は、メイシアと『ライシェン』を対面させる気なのだ。そして、彼女の中の『セレイエ』に揺さぶりをかけ、目覚めさせようとしている。
『ライシェン』を目にすれば、『セレイエ』は必ず出てくる。理屈は分からないが、確信めいた予感がした。
「待ってください!」
鋭い声に、〈蝿〉が何ごとかと立ち止まる。彼の足元で、長い白衣の裾が慣性に舞い上がった。
「『セレイエさん』が出てきたら、私は〈天使〉になるのですか?」
刹那、〈蝿〉の哄笑が響き渡る。
「なるほど。そういうことですか。それを恐れて、頑なに『鷹刀セレイエ』を拒んでいたのですね」
「いえ、そういうわけでは……」
「安心なさい。〈天使〉化には、外科的手術のような手続きが必要だと聞いています。――いつの間にか背中に羽が生えているなんてことはありませんし、専門外の私では、あなたを〈天使〉にすることはできませんよ」
メイシアは、あからさまに安堵する。その表情が〈蝿〉の失笑を買ったが、気づきもしなかった。
「第一、あなたが〈天使〉になったら、あなたは私のことを殺すでしょう? 〈天使〉化すれば、あなたは無敵の化け物になるのですからね」
粘性を帯びた、不快な視線が彼女を舐めた。
「――!」
〈天使〉とは、人の脳に記憶や命令を書き込むクラッカー。
『死』を招く命令を刻めば、人の死すらも操れる――。
メイシアは総毛立った。
人知を超えた力は、〈蝿〉の言う通り『化け物』といえるだろう。
自分が、自分でなくなる。別のものになってしまう。
それが今ではないとしても、セレイエが『最強の〈天使〉』を望んでいるのなら、いずれは……。
「大丈夫ですよ。私にとっては、あなたは、あくまでも鷹刀セレイエとの取り引き材料であり、情報源ですよ」
薄く嗤って、彼は再び身を翻す。
「待っ……」
引き止めようと伸ばした手から、じゃらりという冷たい鎖の音が響いた。
「……!」
囚われの彼女には、自由な意思はない。〈蝿〉が『ライシェン』を見せたいと思えば、それは実行されるのだ。
がたがたと震える体をメイシアは掻き抱いた。
わめき散らしたい心を抑え、涙を堪えるために、黒曜石の瞳を必死に見開く。薄紅の唇を噛み締め、血の赤が混じっても嗚咽ひとつ漏らさない。
それが、せめてもの矜持だ。
そして――。
〈蝿〉は、黒い布で上からすっぽりと覆われたワゴンを押してきた。
メイシアは、びくりと身をすくませ、慌てて、睨みつけるような強い眼差しを彼に向ける。その滑稽な不調和に、〈蝿〉は抑えた嗤いで肩を揺らした。
「これがなんだか、分かってらっしゃるようですね。さすが、察しの良いことで」
「……っ」
「しかし、何故そんなに脅えているのか、私にはちっとも理解できません。あなたは、何ひとつ失うことなく、『鷹刀セレイエ』という天才的な策士の頭脳を手に入れられるのですよ?」
〈蝿〉の言いたいことは分かる。
労せずして、セレイエの持つあらゆる知識と情報を手に入れられるのだ。メイシアを翻弄し続けた『デヴァイン・シンフォニア計画』の全貌だって知ることもできる。
損得でいえば、『得』だ。
それでも、本能的な拒絶が湧き上がる。
「私は、私自身しか必要としていません……!」
細い声が、メイシアの口から絞り出された。
〈七つの大罪〉の技術は、禁忌に触れる。人の世の理から外れたもの。
「私は、『悪魔』ではないから……! 私は、無力なただの『人』だから……!」
〈蝿〉は、やれやれとばかりに首を振った。お互い、相容れないことだけは分かち合いましたね、とでも言いたいのだろう、大儀そうに溜め息をついた。
それから彼は、まるで単純な作業でもするかように、無表情な美貌でメイシアに右手を伸ばした。手枷の鎖を無造作に掴み、彼女が逃げられないように引き寄せる。
「――!」
メイシアは、声にならない悲鳴を上げた。
次の瞬間、〈蝿〉の左手が、ワゴンに掛けられた黒い布を取り払った。
培養液に満たされた硝子ケースの中。
ゆらりゆらりと、揺り籠でまどろむように漂い、瞬きをする、ひとりの赤子。
陽光を溶かし込んだような、白金の髪。
蒼天を写し取ったような、澄んだ青灰色の瞳……。
『ライシェン』を目にした瞬間、メイシアの世界は暗転した――。
メイシア……。
お願い。『ライシェン』を守って……。
〈蝿〉の言ったことは、『デヴァイン・シンフォニア計画』の真実の半分だけ。
『デヴァイン・シンフォニア計画』は、『ライシェン』に幸せを贈るための計画。
ライシェンに。
叶えられなかった幸せを――。
与えられなかった未来を――。
『最強の〈天使〉』の力は、そのためだけのものだから……。
『デヴァイン・シンフォニア』は、『di;vine+sin;fonia』――『神』として生まれたライシェンに捧げる交響曲であり、『命に対する冒涜』。
ルイフォンとふたりで、『ライシェン』を守って……。
メイシアは、腕の中に温かな重みを感じた。
不思議に思って目線を下げれば、白金の産毛が浅い呼吸と共に踊っていた。甘いミルクの香りを漂わせ、小さな赤子が彼女に抱かれて眠っている。
――ライシェン!?
驚きに心臓が跳ね、彼を取り落しそうになった――と思って、焦る。
しかし、彼女の腕は、変わらずにライシェンを優しく包んでいた。
安心しきった様子の彼は、彼女の胸に、ことんと頭を預ける。彼の体温を感じた箇所から、幸せが広がっていく。
……メイシアは理解した。これは、セレイエの記憶だ。
生まれて間もないライシェンの、柔らかな感触。彼を見つめるセレイエから、狂おしいほどの愛情が伝わってくる。
ふと、ライシェンが目を開けた。
ぱっちりと開かれた瞳は、透き通るような青灰色。彼もまた、嬉しそうに、セレイエを見つめ返しているように感じる。
小さな手が伸びてきて、セレイエの胸元を飾っていたものを握った。
それが何かに気づき、メイシアは息を呑む。
――『お守り』のペンダントだ……。
セレイエによって、メイシアが『お守り』だと思い込まされたそれを見つけ、ライシェンはご機嫌のようだった。
「口に入れたりしないかな?」
少し心配そうな男性の声が聞こえた。
「気をつけてあげないとね」
セレイエは指先でそっとライシェンをあやし、ペンダントを返してもらった。
それから彼女は顔を上げ、先ほどの男性を瞳に映す。その顔を見た瞬間、メイシアは驚愕に震えた。
――ヤンイェン殿下……!
先王の甥であり、現女王の婚約者、ヤンイェン。
セレイエとライシェンを優しく見守る彼は、どう考えても彼らの『家族』だった。
――つまり、ライシェンの父親は、ヤンイェン殿下だ。
セレイエが貴族と駆け落ちしたと伝えられていたのは、王族と言うのがはばかられたからだろう。
しかし、どうしてセレイエとヤンイェンが……?
メイシアがそう思った瞬間、セレイエの中にあるヤンイェンに関する記憶が、あふれ出てきた。
「君が新しく加わった〈悪魔〉? 私はヤンイェン。〈七つの大罪〉の運営を一任されている。よろしく」
「〈神の御子〉……? 私の血のせいだ……」
「殺された――! ライシェンが! 王に――!」
「セレイエ!」
勢いよく開かれた扉の音が、セレイエの耳朶を打った。いつもとは違う悲痛な声に、彼女の心臓が警鐘を鳴らす。
流れ込んできた風の中に、鉄の匂いが混じっていた。
不吉な予感に振り向くと、胸元を紅に染めたヤンイェンが、よろよろと部屋に倒れ込んでくる。
「ヤンイェン!?」
「心配は要らない」
血相を変えて駆け寄るセレイエを、押し止めるようにヤンイェンは言った。
「これは、返り血だ」
彼は低く呟き、真っ赤な飛沫を浴びた両手を見せる。
皮膚にこびりついた罪の色は、まだ新しく鮮やかで――しかし、既に起きてしまったことを示すように、彼の指先は震えていた。
「許せなかった……。王を――父を……」
「ごめん、セレイエ……」
「私は王を殺した。じきに捕まるだろう。――だから、君は逃げるんだ」
セレイエが血の穢れに染まらぬようにと、ヤンイェンは彼女の腕を拒んだ。
けれど構わず、彼女は無我夢中で彼を抱きしめた。
血を吸い上げた彼の上着は、上質な布地であることを忘れ、重くごわついていた。
体を離そうとする彼に、むしろ体を擦り寄せ、分かち合う。
彼と熱を合わせ、罪を共にする。
そして――。
『デヴァイン・シンフォニア計画』が始まる……。
5.創痍からの策動-1

初夏の風を頬に感じた。
爽やかな気配に撫でられ、ルイフォンは、自分の意識がふっと浮上していくのを感じた。
どうやら、また、うとうとしていたらしい。薄目を開けると、真上に、ふわりと揺れるカーテンが見える。窓際に置かれたベッドからの、いつもの風景だ。
ゆらりゆらりと、白いレース地が風に乗る。その穏やかな動きを見ていると、朦朧とした心地よさが襲ってきて、ルイフォンの瞼は再び重くなる。
まどろみに身を委ねたい。そんな誘惑が、彼を眠りの世界へと誘う……。
「――じゃねぇよ!」
ルイフォンは、鋭いテノールで自分に突っ込んだ。
のんびりと寝ている場合ではない。メイシアだ。メイシアがさらわれた。一刻も早く、取り戻すのだ。
猫の目をかっと見開き、彼は勢いよく毛布を跳ね上げる。
「――っ!」
飛び起きはしたものの、今度は腹を押さえてうずくまる羽目になった。
リュイセンに斬られた傷が痛む。全身が熱を持っているのを感じる。すぐに眠くなるのも、体が休息を必要としているためだ。――そんなことは分かっている。
枕元に置いていた携帯端末を手に取り、彼は唇を噛んだ。
メイシアがさらわれてから、二日後の日付けだった。〈ベロ〉との対面のあと、熱を出して寝込んだ。それからの記憶は、ほとんどない。
「糞……っ!」
癖の強い前髪をぐしゃぐしゃと掻き上げ、彼は布団に拳を打ち付ける。
〈ベロ〉が言うには、メイシアがセレイエに乗っ取られる心配はないという。しかし、〈蝿〉が彼女にどんな危害を加えるのかと思うと、気が狂いそうだった。
「メイシア……!」
落ち着くのだ。――ルイフォンは、自分に言い聞かせる。
焦ったところで、何も解決しない。それよりも考えるのだ。この窮地を脱するための方策を――!
そうしてしばらく、己の中の感情と理性とを戦わせているうちに、ルイフォンはふと、サイドテーブルの上の書き置きに気づいた。『診察をしたいから、目が覚めたら連絡して』との、ミンウェイからの伝言だった。
ルイフォンは溜め息をひとつ落とし、携帯端末に指を滑らせた。
「まだ熱があるわね。傷のほうは順調だけど、当分は安静よ」
白衣姿のミンウェイは、てきぱきと包帯を取り替えたあと、柳眉をひそめてそう言った。
『安静』の部分が、心なしか強調されていたのは、きっと気のせいではないだろう。彼女が口を酸っぱくして、おとなしくしているように言っていたのに、人目を忍んで〈ベロ〉のところに行ったことを咎めているのだ。
あれは、エルファンに無理やり連れて行かれただけだ。
ルイフォンは顔をしかめたが、口答えはしなかった。結果として、〈ベロ〉から有益な情報を得られたのだから、エルファンに対して文句はないし、ミンウェイの小言も甘んじて受け入れる。
もとより、ミンウェイが療養生活を言い渡すことは分かりきっていた。だから彼は、彼女が来るまでの間ずっと、身構えて待っていた。
「……ミンウェイが、医者として必要なことを言っているのは分かる。でも、俺はメイシアを助けに行かないといけない。だから、寝ているわけにはいかない」
声を荒らげるわけではなく、静かな声で告げた。
これは、ただの事実の羅列だ。
ルイフォンが為すべきことは、安静ではなく、行動を起こすことだという――。
端正で無機質な〈猫〉の顔で、彼はミンウェイと向き合った。
「ミンウェイには、迷惑をかけて悪いと思っている。心配してくれて、感謝もしている。ありがとう、そして、すまない。……あ、いや、……っと、……申し訳ございません」
慣れない言葉遣いに、尻がむずがゆくなる。
「ルイフォン……?」
ミンウェイにしてみれば、寝耳に水だろう。ぎこちなくも、かしこまった面持ちの彼を、彼女はまじまじと見つめ返す。
その視線をまっすぐに受け止め、ルイフォンは意を決して切り出した。
「ミンウェイ……、お願いがあるんだ」
「え……?」
「まだ、メイシアを助ける算段は立っていない。けど、すぐに考える。――そしたら、解熱剤でも鎮痛薬でも、なんでも使って、俺の体を動けるようにしてほしい。頼む」
ミンウェイの切れ長の瞳が、弾かれたように瞬いた。
しかし、ルイフォンは構わずに、畳み掛けるように言う。
「今後はミンウェイの目を盗んで、こそこそ動き回ったりしない。約束する。だから、お願いします。――俺は、一刻も早く、メイシアを取り戻したいんだ……!」
ルイフォンは頭を下げた。寝ている間も編まれたままだった髪が背中を転がり、毛先を飾る金の鈴が彼の脇からちょこんと顔を覗かせる。まるで、持ち主と一緒に頼み込むかのようだった。
「ちょっ、ちょっと待って……」
頭上に感じる、ミンウェイの戸惑いの息遣い。これから、『何を馬鹿なことを言っているのよ!?』と、ぴしゃりとくるのだと、ルイフォンは首をすくめる。
怒られるのは覚悟の上だ。
それでも、どうしても譲れない。
「無茶なことを……、勝手なことを言っているのは分かっている。でも、メイシアを取り戻すために――! ……頼む、ミンウェイ!」
メイシアのことを考えると、心が騒ぐ。暴走しそうになる気持ちを必死に抑え、ルイフォンは訴える。
きつく奥歯を噛み締め、じっとしていると、やがて音もなく草の香が近づいてきた。
ミンウェイの気配だ。――と思った、瞬間。
「痛ぇっ!」
うつむいた彼の眉間に、痛烈な一撃が見舞われた。ミンウェイの人差し指が、彼の額を弾いたのだ。
「お腹を圧迫して――こんな、体に負担がかかる格好をしちゃ駄目でしょ! 傷口に悪いわ」
彼女の指の威力に、ルイフォンは、のけ反るように強制的に上を向かされた。
額がひりひりする。
安静は嫌だと突っぱね、更に動けるようにしてくれだなんて、虫のいいことを言っているのは分かっている。しかし、いきなり手を出してくるのは酷くないだろうか。
鼻に皺を寄せてミンウェイを見やり……、ルイフォンは狼狽した。彼女の眼差しは柔らかで、優しく彼を包み込むかのようだった。
「いくら鎮痛剤を使っても、無茶なことばかりしていたら、途中で動けなくなっちゃうわよ」
綺麗に紅の引かれた唇をきゅっと上げ、彼女は、いたずらめいた笑みを浮かべる。
「だから、あなた自身も、ちゃんと治す努力をするのよ。その上でなら、私にできる限りの協力をするわ」
「……えっ!?」
「私のほうこそ、ルイフォンに言おうと思っていたの。……さすがに、もう少し回復してからのつもりだったけどね」
困惑するルイフォンの目の前で、ミンウェイの雰囲気が、にわかに変わっていく。
彼女は、診察の邪魔にならないよう、背中でまとめていた髪を解いた。波打つ黒髪が豪奢に広がり、爽やかな草の香が流れてくる。
「これを言ったら、医者としては失格。でも私は、鷹刀の人間だから……」
ミンウェイは、ぱっと白衣を脱ぎ捨てた。
中から現れたのは、彼女を象徴する、鮮やかな緋色の衣服。彼女が誇らしげな顔で胸を張ると、艶やかな華やぎが広がっていく。
「多少の無茶など、構わない。それより今は、動き出すべきとき――だわ」
「ミンウェイ……?」
予想外の彼女の言動に、ルイフォンは絶句する。あまりの驚きに、喜ぶよりも、ただただ彼女を凝視した。
「ルイフォン、現状は間違っているわ」
切れ長の瞳に挑むような光を載せ、ミンウェイは静かに告げる。
「メイシアは、あなたのそばに居るべきだし、リュイセンは、あなたを裏切るべきじゃない」
「――っ!」
刹那、ルイフォンの眦が吊り上がった。
浮き立ち始めていた心が一転して、深い地の底に落とされる。
「――リュイセン、あいつは……!」
押し殺した声を漏らし、ぐっと拳を握りしめた。自然と腹にも力が入り、激痛が走る。
痛みの表情は、とっさに隠した。――そのつもりだったが、当然の如くミンウェイには見抜かれており、絶世の美貌による無言の迫力よって、ルイフォンはベッドに沈められる。
横になった彼は、彼女にどう言ったらよいのか迷いながら、ぽつりと呟いた。
「……あいつは――リュイセンは、俺とは袂を分かったんだ」
苦しげなテノールが虚空に溶けた。
自分で発した言葉が、自分に重くのしかかった。
「ルイフォン、聞いて」
ミンウェイは、彼を追いかけるようにかがみ込み、ベッドの上の彼と目線を合わせる。
「緋扇さんが教えてくれたの。リュイセンは、私に関する『何か』を材料に、〈蝿〉に脅迫されているだけだろう、って」
「――!」
「リュイセンは、〈蝿〉に脅されているだけ。やむを得ず、メイシアをさらっただけ。――あなたを裏切ってなんかいないの」
ミンウェイの言葉を聞いた瞬間、ルイフォンの全身の血が湧いた。
「ふざけんな!」
片手を支えに体を起こし、ぐいと顎を上げた。そのまま、ミンウェイに喰らいつかんばかりに、牙をむく。
「リュイセンは、ミンウェイ絡みで〈蝿〉に脅された。――そんなことくらい、『俺も気づいていた』さ! だって、あいつが俺を裏切るなんて、それしかないだろ?」
「ルイフォン……、知っていた……?」
うろたえるミンウェイを、ルイフォンは一瞥した。彼女には黙っていようと思っていたのに、シュアンのせいで台無しだった。ハオリュウの代理で屋敷に来ることは聞いていたが、余計なことをしてくれたものだ。
「ああ。エルファンが、それとなく教えてくれた」
この二日間、夢うつつをさまよっているうちに、エルファンの真意に気づいた。
リュイセンは〈七つの大罪〉の怪しい技術で操られていたわけではない。意識は、はっきりしていたと、エルファンはまず初めに告げた。
その言葉の裏には『それにも関わらず、あの生真面目なリュイセンが彼らしくないことをしたのなら、それは彼が一番大切にしている、ミンウェイのためでしかあり得ない』――そういう意味が隠されていた。
リュイセンの苦渋の思いを理解したエルファンは、リュイセンの選択を認めたのだ。だから、ルイフォンに対して『袂を分かった』という聞こえのよい言葉で押し切った。
そして、ルイフォンの中でくすぶっていた『メイシアへの焦燥』と『リュイセンへの憤怒』という、ふたつの感情を昇華させ、『メイシアの救出』に向かって邁進すべく、ルイフォンを〈ベロ〉のもとへと連れて行ったのだ。
「けどな! リュイセンは、俺に相談すべきだった! メイシアや、ミンウェイには黙っていてもいい。でも、俺だけには言うべきだった! 違うか!?」
ミンウェイが、びくりと肩を上げるが、ルイフォンは構わず続ける。
「リュイセンが、どんなネタで脅されたのかは分からない。でも、俺に相談することを選ばずに、俺のメイシアを奪った! ならば、あいつは俺の敵だ!」
癖のある前髪の隙間から、鋭い猫の目が光る。逆毛を立て、今にも飛びかかりそうな形相で、ミンウェイを睨みつける。
ミンウェイは短く息を呑み、ひるんだように、わずかに身を引いた。
だが、それは一瞬のことだった。すぐに鮮やかな緋色を翻し、ルイフォンにずいと迫る。
「ルイフォン! あなたが、そうやってリュイセンを憎んでいるのも、間違っているわ! こんな事態、誰も望んでいないはずよ!」
「間違ってなんかねぇよ!」
「いいえ! 間違いよ!」
ルイフォンの反論を、ミンウェイが高い声をかぶせて打ち消す。泥沼の水掛け論になりつつあるのが分かっていても、どちらも引くことはできない。
「メイシアも、リュイセンも取り戻す。それから、お父様と――〈蝿〉と決着をつける。これが、私たちが今すべきことではないの?」
「そんな、おめでたい綺麗ごとなんか、あり得ねぇよ!」
ルイフォンがそう言い返したときだった。
不意に、がちゃりと。
ドアノブをひねる音が響いた。
「――!?」
常に鍵のかかっていない、ルイフォンの自室。いつでも、誰でも、拒むことのない部屋。――しかし、廊下まで聞こえているであろう口論のさなか、わざわざ乗り込んでくる物好きとは、いったい……。
ルイフォンは勿論、普段は気配に敏感なはずのミンウェイさえも、驚きの顔で音の発生源に注目する。彼らの視線の先で、その扉は、ためらいの欠片も感じぬ滑らかさで、すっと開いた。
最初にひょこりと覗いたのは、手入れを知らぬ、ぼさぼさ頭だった。
「おいおい。死にそうな怪我人だと聞いていたんだが、随分と元気そうじゃねぇか」
見るからに凶悪な三白眼が、にやりと歪む。その姿を見た瞬間、ミンウェイが叫んだ。
「緋扇さん!?」
「ミンウェイ、そいつのどこが重傷なんだ? あんた、藪医者なのか?」
へらへらと笑いながら、警察隊の緋扇シュアンが部屋に入ってきた。
ルイフォンは、むっと眉根を寄せた。
確かにシュアンなら、話の途中に断りもなく、それどころか、さも当然と平気で割り込むだろう。何故なら彼は、ミンウェイの加勢に来たのだろうから。
見た目に反して、シュアンが案外いい奴だということは知っている。
だが、はっきりいって、今は単なる邪魔者。
――否、迷惑な妨害者だ!
「よう、ルイフォン。ハオリュウの代わりに見舞いに来てやったのに、なかなか手厚い歓迎だな」
ルイフォンの渋面を楽しげに皮肉りながら、シュアンはテーブルから椅子を引きずり、ベッドサイドにやってきた。
ルイフォンとしては、すぐにも追い出したい。しかし、何かと世話になっていることもあり、とりあえず『帰れ』のひとことだけは、かろうじて呑み込んだ。
「まぁ、有り体に言えば、俺は立ち聞きしていたわけだけどさ」
「……」
堂々とした態度に、ルイフォンは、もはや何も言う気になれなかった。故に、片腕で起こしていた体を倒し、要望通りの怪我人らしさを演出する。――無言の『帰れ』だ。
だがそれは、シュアンを見くびる行為だったと、すぐに気づくことになる。
沈黙のルイフォンに、シュアンは調子に乗ったように続けた。
「ルイフォン。あんた、さっき、『リュイセンが、どんなネタで脅されたのかは分からない』って言っていたよな? それって、『〈猫〉』としてどうなのさ? 凄腕の情報屋だと聞いているんだけどよ。さすがの〈猫〉も分からねぇ、ってか?」
妙に甲高い、挑発的な声が耳朶を打った。
情報屋〈猫〉をなじられ、ルイフォンは反射的にベッドを飛び起きる。
「てめぇっ」
「メイシア嬢を奪われて、あんたが気が立っているのは分かるさ。だがそれで、視野が狭くなったら阿呆だぜ?」
反応を見せたルイフォンを、シュアンがせせら笑う。
こちらを見つめる眼光が、有無を言わせぬ凄みをまとった。口角を上げた悪相に、ルイフォンは不覚にも一瞬、たじろぐ。
「脅されたネタさえ暴いちまえば、リュイセンは味方に戻る。――そしたら奴は、『難攻不落の敵地に、先だって潜入成功している、頼もしい仲間』になるんだぜ?」
血色の悪い凶相が、からかうように、にたりと緩んだ。
軽口を叩いているようでいて、しかし、シュアンの抜け目のない三白眼は笑ってなどいなかった。
5.創痍からの策動-2
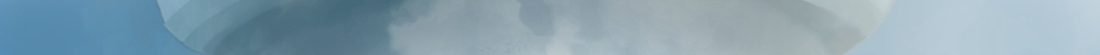
挑発的なシュアンの声が、ルイフォンの心を揺さぶる。
『脅されたネタさえ暴いちまえば、リュイセンは味方に戻る』
『そしたら奴は、『難攻不落の敵地に、先だって潜入成功している、頼もしい仲間』になるんだぜ?』
――リュイセンの裏切りは、ミンウェイのため。
夢うつつに気づいたとき、胸が苦しくなった。
如何にも、兄貴分らしいと思った。
ミンウェイに伝わらないよう、誰にも言わなかったのだ。
ミンウェイに悟られないよう、何も残さなかったのだ。
リュイセンも、ミンウェイは悪くない。ただ、〈蝿〉が狡猾だっただけだ。
けれど、ミンウェイが知れば、彼女は気に病む。――だから、リュイセンは黙した。
如何にも兄貴分らしいと、ルイフォンは納得した。
その一方で、どうして自分に相談してくれなかったのかと、怒りを感じた。そんなに自分は頼りないのかと、憤りを覚えた。
……違う。そうではない。分かっている。
弟分のルイフォン以上に、ミンウェイのことが大切だっただけだ。
だから、『袂を分かった』という言葉を受け入れた。
リュイセンは敵だと、決別したのだ――。
シュアンは、ふんと鼻息を漏らすと、ぼさぼさ頭を弾ませ、ルイフォンの顔を覗き込んだ。
「おい」
思いがけず近くから聞こえた声に、ルイフォンは、はっと我に返る。
すっかりシュアンに呑まれていた。――それだけ彼の弁は的を射ていたと、認めざるを得ない。
「ハオリュウからの伝言だ。『摂政殿下を通して、〈蝿〉に圧力を掛ける準備をしています。他に、僕にできることがあれば、なんでもおっしゃってください』だそうだ」
急に現実的な話になり、ルイフォンは戸惑いながらも頭を切り替える。
「ハオリュウが、そんなことを……」
異母姉メイシアを屋敷内でさらわれ、彼は鷹刀に激怒していると聞いた。随分と買っていたリュイセンが裏切ったのだから、当然だろう。
育ちの良さからくる上品な振舞いと、人畜無害そうな平凡な容姿からは想像しにくいが、ハオリュウはかなり気性が激しい。もし、貴族の当主という立場ではなく、足が不自由でもなかったなら、とっくに〈蝿〉の庭園に乗り込んでいたに違いない。
「駄目だ。――シュアン、ハオリュウを止めてくれ」
ルイフォンは、押し殺したような声を吐き出した。
「気持ちはありがたいが、あいつが摂政に掛け合うってことは、あいつが摂政の手駒になることを約束する、って意味だ。ハオリュウの手は借りられない。メイシアだって、望んでいないはずだ……」
「そうだな。俺も『やめておけ』と言っておいた。――ハオリュウに頼まれたから、伝えただけだ。だから、これは忘れろ」
シュアンは椅子の背もたれに片腕を掛けるようにして、ふんぞり返り、大きく足を組んだ。見るからに偉そうな態度は、実は普段のルイフォンと大差ないのだが、他人がやると妙にむかつく。
「そもそもハオリュウだって、お前は断るだろう、と言っていた」
つまらない茶番のやり取りだったと言わんばかりの調子で、シュアンは吐き捨てる。
だったら、このどっかりと座り込んだ、長居する気で満々の姿勢はなんだ?
ルイフォンが憮然とした顔でシュアンを見やると、彼は意味ありげな嗤いを漏らした。人を喰ったような仕草が気に障る。
「そういうわけで、ハオリュウからの伝言が、もうひとつある」
シュアンは、三白眼をすっと眇めた。血色の悪い凶相が凄みを増し、まるきりの悪人面となる。
「『僕の手を取れないなら、リュイセンさんと協力してください』――だそうだ」
「は……?」
ルイフォンは呆けた。思いもよらぬ言葉だった。
……理解できない。
「おい! なんで、そうなるんだよ!?」
思わず、毛布に拳を打ちつけた。怪我さえなければ、ベッドから飛び降りて、シュアンの襟首を掴み上げていただろう。
そばで聞いていたミンウェイもまた、口元に手を当てて絶句する。しかし彼女は、ルイフォンの猫の目が、すぅっと細くなっていくのに気づくと、その先の彼の昂りを予測して、こわごわと身をすくめた。
「おい、シュアン! ハオリュウは、リュイセンに怒り狂っているんじゃなかったのか!? どういうことだよ!?」
「ああ。荒れ狂っていて、手がつけられない状態だったさ。まぁ、あいつの場合、ものに八つ当たりするわけじゃないけどな。――禍々しい顔で嗤いながら、自分の権力の限りを尽くした鷹刀への報復措置を、ひたすら紙に書き連ねていた」
「……」
だが、そのハオリュウが、どうして態度を一変させたのか。
ルイフォンの目が、ベッドからぎろりと上を向き、シュアンに尋ねる。
「思い込みの激しい、元気な嬢ちゃんが描いたという、あの絵を渡したのさ」
「――絵? ……なんだ、それ? ……あ」
ルイフォンは、はたと思い出した。
〈蝿〉の館に潜入したとき、ルイフォンたちは、部屋を抜け出していたタオロンの娘、ファンルゥを保護した。彼女は、窓から見かけた車椅子のハオリュウを〈蝿〉の患者だと思い込み、自分の描いた絵を持って見舞いに行こうとしていたのだ。
万一、脱走がばれたら、ファンルゥは、ただではすまないだろう。だから、リュイセンが『絵は代わりに届けるから』と言って、彼女を部屋に返した。
そして、リュイセンは預かったままになっていたその絵を、メイシアを連れ去る前に、自室の机に残した。『身勝手なお願いだと思いますが、この絵をハオリュウに届けてください』という書き置きを添えて――。
「ハオリュウは初め、面食らっていたが、事情を話すと拍子抜けするくらいにあっさりと絵を受け取った。てっきり俺は、突っ返されるとばかり思っていたんだけどさ」
ルイフォンにとっても、意外だった。
そもそも、リュイセンに対して激怒しているハオリュウに、リュイセンの頼み通りにあの絵を届けるとは思ってもいなかった。シュアンに絵を託したであろうイーレオも大概だが、言われるままに渡したシュアンも存外、人がいい。
当惑顔のルイフォンに、シュアンはゆっくりと口を開く。
「ハオリュウは、溜め息混じりに、こう言った」
――まったく、リュイセンさんは律儀な人です。
他にいくらでも、書き残しておくべきことはあるでしょうに、なんでまた……。
これが、リュイセンさんのお人柄ということですか。
……いいでしょう、シュアン。矛を収めましょう。
あなたの言うように、リュイセンさんがミンウェイさんのために動いたという話はなんとも判断いたしかねますが、少なくとも姉様をさらったことは、彼の本意ではなかったと認めます。
それに、リュイセンさんを『敵』として扱うよりは、『味方になり得る相手』として捉えておいたほうが、この先の策の幅が広がるのは確かです。
期待はしません。けれど、リュイセンさんの存在を、まるきり除外もしません。
これで手打ちにします。
「……っ」
ルイフォンは、唇を噛んだ。
リュイセンは、何も残さなかったわけではなかった。
もっとも彼らしい、『誠実さ』を残していったのだ。
「それからハオリュウは、こんなふうに続けた」
シュアンは組んだ足を解き、ずいとルイフォンに身を寄せる。
――ただ、ルイフォンは、僕よりも、もっと複雑だと思いますよ。リュイセンさんと、より深い絆があるからこそ、彼を許すことはできないでしょう。
だから……、そうですね。
『僕の手を取れないなら、リュイセンさんと協力してください』
こう、伝えてください。
これでルイフォンは、逆らえなくなります。
僕としては、ここまでリュイセンさんのためにする義理はないのですが、姉様のためです。
彼女はきっと、初めからリュイセンさんを悪く思っていません。それどころか、〈蝿〉に従わざるを得ない状況に追い詰められたリュイセンさんに、心を痛めているはずです。おそらく、彼とふたりで、あの庭園から逃げ出す方法を考えているはずです。
……それが、僕の姉様です。
「……」
ぐっと息を吸い込み、ルイフォンは押し黙った。
メイシアが何を思い、どう行動しようとしているかなんて考えてもいなかった。ただ、彼女を助けることだけで頭がいっぱいだった。
けれど、彼女は違う――。
ハオリュウの言葉を聞いた今、ルイフォンにも、メイシアの心が、はっきりと見えた。
嫋やかでありながらも、芯の強いメイシア。
彼女はきっと、自分自身だけでなく、リュイセンのことも助けようと、必死に〈蝿〉と戦っている。
彼女を想い、彼女を感じ……、ルイフォンは、彼女の心に共鳴する……。
リュイセンに、どんな事情があるのかは分からない。けれど、彼は何も言わずに――否、何も言えずに、裏切るしかなかったのだ。
そんな事態に兄貴分が追い込まれたのなら、弟分たる自分が手を差し伸べてやるべきだ。それでこそ、弟分というものではなかろうか――。
シュアンは、しばらくルイフォンの顔を見つめていたが、ふっと三白眼を閉じて視線を外した。
そして、静かに口を開く。
「ハオリュウは、こんなことも言っていた」
胸を押さえるルイフォンの頭上から、シュアンの声が落ちる。
――もしリュイセンさんが、シュアンの言うように『ミンウェイさんのための薬』などを得るために〈蝿〉に従っていたのなら、その『報酬』を持ってミンウェイさんに接触してくる可能性があります。
そのときのリュイセンさんへの対応が、重要な鍵となるでしょう。心に留めおいてください。
もっとも、あくまでも仮定に仮定を重ねただけで、あまり確率が高いとは思いませんけどね。
ルイフォンは目を瞬かせた。
「『ミンウェイのための薬』? なんだ、それ?」
「それは、俺の推測だ。リュイセンが〈蝿〉の言いなりになっている理由として、『〈蝿〉が持っている薬を投与しなければ、ミンウェイは母親と同じ病で死ぬ』と脅されたんじゃないか、と言ったのさ。割といい線だと思うぜ?」
シュアンの返答に、ミンウェイが眉を寄せる。
「でも、緋扇さん。前にも言いましたが、私は、お母様と違って健康体だと、お父様に言われています」
「だから、リュイセンを脅すためのネタは嘘でもいいのさ。リュイセンが信じさえすれば、なんだっていい。――って、俺も前に言ったじゃねぇか」
ミンウェイの反論に、シュアンが顔をしかめる。よほど自信のある推察なのだろう。
ルイフォンは、はっと息を呑んだ。
「待て――」
鋭いテノールが、ふたりの会話を切り裂く。
「リュイセンに、嘘は通用しねぇぞ」
唐突な発言に、シュアンがきょとんとし、ミンウェイが顔色を変える。
ルイフォンは、ミンウェイに向かって深く頷いた。
「あいつは、恐ろしく勘がいい。どんなに理屈で固めても、それが嘘なら絶対に騙されない」
リュイセンは、腹の探り合いのような駆け引きは得意ではない。本人は、それを負い目に思っているようだが、ルイフォンに言わせれば、彼にそんなものは必要ないのだ。
何故ならリュイセンは、大局的に本質を見抜くことのできる、天性の勘を持っているからだ。
ルイフォンが苦労して理論で検証するところを、彼は一足飛びに追い越して、真理へとたどり着く。さすがに、細かな部分では惑わされることもあるが、これほどの重大事において、リュイセンが読み誤るはずがないのだ。
「あいつが信じたなら、それは真実だ。〈蝿〉は、抗いようもない事実をリュイセンに提示したんだ……」
自分で言っていて、ルイフォンはぞくりとした。
今まで、リュイセンに対して怒りを覚えていたから深く考えていなかったが、あの兄貴分を従わせるだけの事実など、そうそうあるものではない。
「おいおい、何をそんなに怖い顔をしてんだよ? ミンウェイの命に関わると言われれば、たとえ半信半疑だったとしても、リュイセンなら従うだろう?」
殺気すらも垣間見えそうなルイフォンに、シュアンが、やや困惑しながらも軽口を叩く。しかし、ルイフォンは首を振り、きっぱりと言い放った。
「いや、リュイセンは、そんな曖昧なことでは俺を裏切らない」
「……」
シュアンが呆れたように肩をすくめた。つい先ほどまで、『袂を分かった』などと抜かしていたくせに、たいした変わりようだ、と言いたいのだろう。
ルイフォンは唇を尖らせ、口早に言う。
「それに、お前の推測は、如何にも嘘臭いだろ。どう見ても、ミンウェイは健康だ。病気で死ぬとか言われても、俺だって信じねぇぞ」
きっぱり言い切った、そのとき。
不意に、リュイセンの兄、レイウェンの声が、ルイフォンの脳裏をよぎった。
『私は、ほら、鷹刀の直系だろう? 血を濃く煮詰めすぎた『鷹刀』だ』
『私は運良く健康に生まれたけれど、私の上には育たなかった兄弟が何人もいるし、私とシャンリーは、生まれたばかりの弟が、ほんの数時間で息を引き取ったのをこの目で見ている』
リュイセンを〈蝿〉の館に残して逃げた、あの屈辱の敗走の末に、レイウェンの家に立ち寄ったときのことだ。
濃い血族の死を目の当たりにしたことのないルイフォンは、レイウェンの言葉に強い衝撃を受けた。
鷹刀一族にとって、『健康であること』は、奇跡のような幸運であるのだ。
「…………!」
頭の隅で、情報が閃いた。
そこから、幾つもの情報の欠片が繋がっていき、ルイフォンは、ひとつの可能性に気づく。
心臓が、どきりと跳ねた。
ミンウェイに、病に冒されている様子はない。
すなわち。
ミンウェイが、『健康であること』こそが、〈蝿〉が提示した『抗いようもない事実』だ。
「――――!」
確証はない。
しかし…………。
――おそらく、そういうことだ……。
ルイフォンは、自分の血の気が引いていくのを感じた。
「どうしたの? 顔色が悪いわ」
ミンウェイに声を掛けられ、ルイフォンは動転する。これは、彼女に言うべきことではない。――絶対に。
窮地に陥りかけた彼を救ったのは、彼自身だった。なんと、実に都合よく、腹の虫がぐぐうと盛大に鳴ったのだ。
「ああ、そういえば、ずっと寝ていたから何も食べていなかったわね。きっと空腹による、軽い貧血よ。料理長に頼んで消化の良いものを用意してもらうわ」
彼女はくすりと笑い、「お開きにしましょう」と告げた。
「まずは、ルイフォンの回復が最優先だわ。――それと……」
そこで急にミンウェイの歯切れが悪くなり、彼女は申し訳なさそうにルイフォンを見つめる。
「あの……ね。実はルイフォンが寝ている間に、エルファン伯父様が〈蝿〉の私兵を捕らえたの。……言いそびれていてごめんなさい」
「え……?」
「けど、たいした情報は得られなくて、メイシアについては、展望塔に閉じ込められている、とだけ。しばらく監禁を続けるみたいで、彼女の身の回りに必要なものが運び込まれたそうよ」
「――!?」
メイシアに関することは、最重要事項だろ!
一番先に、言うべきことだろ!
そんな言葉が頭をよぎるが、ルイフォンは声を出せなかった。
とても無事とはいえない状況だが、それでも、メイシアがさらわれてから初めての、彼女の消息だった。
「メイシア……」
全身の力が抜けていく。
胸が苦しい。喉が熱くなる。
「それから、もうひとつ。――二日後に、食料を積んだ車があの庭園に来るそうなの。それをうまく利用できないか、ルイフォンと相談したいって、エルファン伯父様が……」
更なる情報が告げられた。
その重大さに、ルイフォンは一転して猫の目を光らせる。
「ちょっと待て、ミンウェイ! どうして、そんな重要なことを早く言わなかった!?」
噛みつくルイフォンに、ミンウェイがばつが悪そうに言い返す。
「あなたが、いきなり頭を下げてきて『動けるようにしてくれ』なんて言い出すから、タイミングを逃しちゃったのよ!」
携帯端末を使い、その場でルイフォンの食事の手配をすると、ミンウェイは、シュアンと共にルイフォンの部屋を出た。
「緋扇さん、ありがとうございました」
「はぁ? なんのことだ?」
シュアンの三白眼が、わざとらしいほどに明後日を向く。
「あなたのおかげで、ルイフォンが、メイシアだけでなく、リュイセンのことも取り戻そうという気になってくれました」
綺麗に紅の引かれた唇をほころばせ、ミンウェイは笑う。最後のほうは、だいぶ脱線した気もするが、それはご愛嬌だろう。
シュアンは「ふん」とだけ答えた。
「私……、お父様と――〈蝿〉と決着をつけます。何が決着になるのかは分かりませんが、とりあえず話をしたいと思っています」
「そうか。――あんた……」
彼は、何かを言い掛け、途中でやめた。
「緋扇さん?」
「いや、今日もあんたは美人だな、ってだけだ」
聞き返そうとしたミンウェイをはぐらかし、彼は口元を緩める。
「たまには本業に行ってくる」
そう言って、シュアンは、ぼさぼさ頭を揺らして身を翻した。
片手を振って去っていく後ろ姿に、ミンウェイは草の香を漂わせながら深々と頭を下げた。
6.塔の上の姫君-1

培養液に満たされた硝子ケースで、赤子がまどろむ。
陽の光を溶かし込んだような白金の産毛が、ふわりとたゆたう。
空の色を写し取ったような青灰色の瞳が、ぴくりと瞬く。
『ライシェン』を目にした瞬間、メイシアの中に、セレイエの記憶が押し寄せてきた。
腕の中に感じる、温かな重み。
胸の中にあふれる、狂おしいほどの愛情。
思いの渦に呑み込まれ、翻弄される……。
『デヴァイン・シンフォニア計画』は、『ライシェン』に幸せを贈るための計画。
ライシェンに。
叶えられなかった幸せを――。
与えられなかった未来を――。
ルイフォンとふたりで、『ライシェン』を守って……。
はっと目を覚ますと、メイシアは、豪奢な天蓋付きのベッドの上に寝かされていた。
全身を包み込む寝具は、極上の柔らかさを誇り、天蓋から垂れ下がるカーテンは、しっとりとした光沢を放ちながら、優美なドレープを揺らす。
体を起こせば、そこは見知らぬ部屋であった。
〈蝿〉の姿はなく、代わりに手の込んだ織りの絨毯が視界に入った。
中央にはベッドに合わせたようなアンティーク調のソファーが据えられており、少し離れたところには品の良いローチェストがひっそりとたたずんでいる。窓は一面の硝子張りで、明るい光が注がれていた。
ひと目見て、貴人がくつろぐための部屋だと分かった。
と、同時に、メイシアは青ざめる。
ここは、〈蝿〉が潜伏している庭園内のどこかであるはずだ。すなわち、何代か前の王が療養のために作らせた施設の一角である。そんな場所で『貴人』といえば王、もしくは王妃だ。
――陛下のベッドで休むとは、なんとも畏れ多いことをしてしまった!
もと貴族のメイシアは、『死者』となって上流階級を去った今でも、体に染み付いた臣下の意識が抜けていなかった……。
彼女は、まるで逃げ出すかのように、そろりとベッドを降りた。
部屋全体から、長い間、使われていなかった空間特有の湿った臭いがした。うっすらと埃も感じ、窓を開けようと思い立つ。
そのとき、彼女はこの部屋の異質さに気づいた。
窓硝子が、平面ではなく、曲面を描いていた。よくよく床を見てみれば、ベッドのある壁側を直径とした半円形になっている。
「パノラマ展望台……?」
こんな形状をした部屋といえば、そのくらいしか思いつかない。そういった展望室であれば、床は完全な円形で、全方向三百六十度が見渡せるはずだが、ここは、ちょうど半分にしたかのようだった。
窓際に寄り、メイシアは自分の推測が正しいことを知る。
彼女は、塔の上にいた。
王都にある電波塔と比べれば、おもちゃのようなものであるが、それでも常とは違う高さにひやりとする。
眼下に広がる緑の大地は、遙か彼方まで続いているかのように見えた。
一方、足元となる真下には、この塔の入り口らしき部分が見え、数人の見張りが立っている。隣には、〈蝿〉が起居していると思しき館があり、その周りには、鮮やかな紫を綺麗に箱詰めしたような、四角い区画が散らばっていた。菖蒲園であろう。
そういえば、ルイフォンが庭園の地図を手に入れたとき、館の隣には、古い時代の建築を模した、石造りの展望塔があると言っていた。
〈蝿〉捕獲作戦には関係がなかったので、それきりの話になってしまったが、おそらく療養中の王の気晴らしにと建てられたものなのだろう。展望室にベッドがあるのは、いつでも王が休めるようにとの配慮というところか。
換気をしようと思ったのだが、残念ながら窓は開けられないようになっていた。高い塔の上なのだから、安全のため当然の造りかもしれない。
仕方ない。空調はついていたので、それだけでも、ありがたいと思わなければ……と溜め息をついたとき、メイシアはふと気づいた。先ほどまで彼女を拘束していた手枷が外されている。
『その枷は、あなたの置かれた立場を分かりやすく伝えるための措置です』
〈蝿〉はそう言った。
つまり、今度は高い塔に監禁することで、囚われの身分を表しているつもりなのだろう。実に分かりやすく、如何にも〈蝿〉の好きそうな演出だった。
「ルイフォン……」
メイシアは、ぽつりと呟いた。
――ルイフォンに逢いたい。
〈蝿〉に囚われてしまった。
この先どうなるのか、不安でたまらない。
〈蝿〉は、『生を享けた以上、生をまっとうする』という妻との約束を守るため、メイシアを駆け引きに利用して、生き残るのだと言った。
彼に『ライシェン』を見せられた瞬間、自分の意識がセレイエの記憶と繋がったのを感じた。
切なさで、胸が押しつぶされそうになった。
セレイエが託した思いを――『デヴァイン・シンフォニア計画』の真の目的を知った。
――けれど。
メイシアは、心の痛みを押さえるように、胸に手を当てた。
――ルイフォンに逢いたい……!
〈蝿〉にも、セレイエにも、それぞれに、切なる思いがある。
けれど。
それらは決して、メイシアとは相容れない。
――ルイフォン、助けて……!
ひとりで抱えるには、あまりにも重すぎる……。
メイシアは滲んできた涙を拳で拭い、嗚咽をぐっとこらえた。
声に出して叫んでしまったら、きっと泣きじゃくって、心が弱くなる。だから今は、歯を食いしばって、平気な顔をする。
なんとしてでも、この庭園から抜け出し、ルイフォンのもとに帰るのだ――!
メイシアは現実と向き合うように、黒曜石の瞳を凛と大きく見開いた。
「これから〈蝿〉が、セレイエさんの行方を聞きに来る……」
彼女は口元に手を当てて、眉を寄せた。
セレイエの記憶から得た情報を、正直に〈蝿〉に伝えるべきだろうか。
――否だ。
情報には、価値がある。いつも、ルイフォンがそう言っているし、メイシアもそう思う。
どんな些細な情報だって〈蝿〉に渡してはならない。
メイシアは、受け取った記憶を反芻する。
彼女に刻まれた記憶は、正確には『セレイエ』ではなくて、『セレイエの〈影〉のホンシュア』のものだ。
すなわち、セレイエが生まれてから、ホンシュアを〈影〉にした瞬間までの『セレイエ本人』の記憶。そして、その先、〈影〉として行動し、仕立て屋と偽ってメイシアに会ったときまでの『〈影〉のホンシュア』の記憶である。
ホンシュアは、ライシェンの侍女だった。
彼女は『主人の死は、そばにいながら守りきれなかった自分に責任がある』と言って、自害しようとしていた。そんなとき『デヴァイン・シンフォニア計画』のことを知り、自ら望んで水先案内人に――セレイエの〈影〉となった……。
「…………」
メイシアは思案する。
自分は、あまりにも非力だ。
望みがあるとしたら……リュイセンだ。
〈蝿〉は、あとでリュイセンに会わせてくれると言っていた。リュイセンの裏切りを本人の口から告白させることで、メイシアに絶望を与えるつもりなのだろう。――しかし、それは違う。
リュイセンは希望だ。
彼は、なんらかの理由で〈蝿〉に従っているだけだ。彼もまた、メイシアと同じく〈蝿〉に囚われているのだ。
身柄を拘束されたメイシアと、おそらく、心理的に束縛状態にあるリュイセン。
ふたりで協力して、この窮地を脱する。
「ルイフォン……」
メイシアは、硝子張りの世界の向こうへと瞳を巡らせる。
「必ず、あなたのもとに帰る」
高く澄んだ声を響かせ、誓いを立てた。
〈蝿〉が部屋に現れたのは、それから少し経ってからのことだった。
初めに、壁の向こうから、かすかな機械音が聞こえた。メイシアは、凶賊たちのように気配に敏感ではないのだが、無音の展望室に鈍い振動が伝わってきて気づいた。
エレベーターがあるのだろう。外観こそは古い様式を真似ていても、療養中の王のための建物だ。階段のみということはあるまい。
固唾を呑んで身構えていると、案の定、〈蝿〉が現れた。開かれた扉から、彼の斜め後ろでエレベーターの戸が閉まるのが見えた。
「お目覚めでしたか」
どことなく嬉しそうに〈蝿〉が言った。
「『ライシェン』を見た瞬間、あなたは気を失ったのですよ。さすがに刺激が強すぎたのでしょうかね」
「……」
どう答えるのが吉なのかを測りかね、メイシアは曖昧な視線を返す。〈蝿〉に媚びへつらうのは論外だが、逆らうよりは、彼の機嫌をとって饒舌になってもらうべきなのは、地下の研究室で学んだ通りだ。
「立ち話もなんですから、向かいの部屋に移りましょう」
「向かいの部屋……?」
「ええ。賢いあなたのことですから、ここが展望塔の上であることには気づいてらっしゃるのでしょう? ならばこの半円形状の部屋が、円形の展望室を二つに分けたうちの片方であることも、お分かりでしょう?」
確かに、それは予想通りであったので、メイシアは素直に「はい」と頷く。
「展望室は、この庭園を作らせた王のお気に入りの場所だったそうですよ。こちらで休息を取り、あちらの部屋で食事を摂る。――そのように使い分けていたようです」
そう言いながら、〈蝿〉は、メイシアについてくるようにと促す。
「今は、どちらもあなたの部屋ですよ」
何気なく付け足されたひとことに、メイシアは驚いて足を止めた。
「どうして、陛下がお使いになっていたような良いお部屋を、私に二部屋も与えるのですか?」
警戒心もあらわな彼女に、〈蝿〉は、わざとらしく苦笑する。
「あなたは、私の大事な切り札ですよ。それに見合った待遇ということです。――それより、私がこの部屋に鍵を掛けていなかったことに、気づかなかったようですね」
「え……?」
囚われのメイシアは、部屋からは出られないものと思い込んでいた。だから、鍵を確認するなんて、考えつきもしなかった。しかし、言われてみれば〈蝿〉が入ってきたときに鍵を開けた様子はなかった。
「どうして……?」
「この部屋の鍵が『内鍵』だからですよ。鍵を掛けても、あなたを閉じ込めることはできないのです。――もとは、王の娯楽のために造られた場所なのですから、内鍵は当然でしょう?」
「あ……」
ここは本来、『王の個室』なのだ。外から鍵を掛ける仕様では、『王を閉じ込める』ことができてしまう。それは不敬にあたるだろう。
顔を赤らめたメイシアに、〈蝿〉はくすりと嗤う。
「勿論、塔の入り口には見張りがいます。けれど、この塔の中ならば、あなたは自由に動き回れるわけです。ならば、二部屋とも、あなたに自由に使っていただこうと思っただけですよ」
〈蝿〉に続いて部屋を出ると、そこは廊下というよりも通路といったほうがふさわしいような場所だった。すぐ正面に扉があり、左右はエレベーターと階段になっている。
それを見て、メイシアは、なるほどと思った。
展望室をふたつに分けた造りには、やや疑問があったのだが、大きな円形の部屋であったなら、王がくつろぐための空間にエレベーターと階段が直結してしまう。それは無粋だと設計者が考えたのだろう。
もうひとつの部屋に入ると、そちらも全面が硝子張りの明るい部屋であった。
先に〈蝿〉が言った通り、食事などの、より活動的な物ごとをするための場所であることは見て取れた。中央にあるテーブルと椅子以外にも、何か書きものでもするような机や、置いてある本は少ないものの本棚もある。
「今は鍵を掛けませんが、あなたがひとりになったら施錠しておくことをお勧めしますよ」
「何故ですか?」
メイシアが首をかしげると、〈蝿〉が涼しげに答える。
「私の雇った私兵たちが、あなたに悪事を働かないという保証はありませんからね」
静かに落とされた低い声に、メイシアはぞくりと身を震わせた。その反応は、〈蝿〉の予想通りだったのだろう。彼は、満足そうに喉の奥を鳴らす。
「私にはマスターキーがありますから、あなたに用があるときは、いつでも部屋に入れます。遠慮せずに鍵を掛けて構いませんよ」
賓客をもてなすように扱いながら、その実、自由などひとつもない……。
メイシアは、改めて囚われの身であることを思い知らされた。
脅えた顔の彼女を置き去りにして、〈蝿〉は、部屋の奥へと入っていく。彼はテーブルにつくと、彼女にも向かいに座るよう顎で示した。彼女に拒否権はない。ただ従うだけだ。
「それで、『鷹刀セレイエ』の記憶は、どうなりましたか?」
メイシアが席に着くか着かないかのうちに、〈蝿〉は単刀直入に尋ねた。興奮の入り混じった、期待の眼差しで彼女を見つめている。
〈蝿〉が、苦労してメイシアを手に入れたのは、セレイエの居場所を突き止めるため。ひいては自分の身の安全を確保するため。そのための第一歩が、メイシアの中の『セレイエ』だ。
ねっとりとした視線が絡みつく。メイシアは自分の手札だと、彼は暗に告げていた。
6.塔の上の姫君-2

「……『ライシェン』を見た瞬間、胸が苦しくなりました」
メイシアは、ぽつりと漏らすように答えた。
「懐かしくて、愛しくて、切なくて……。私が『ライシェン』を見たのは、初めてであるはずなのに、私は彼を知っていました。――セレイエさんの記憶だと思います」
「ほう……。それから?」
〈蝿〉が肘を付き、ずいと身を乗り出した。捕食者の瞳が爛々と輝く。
メイシアは、思わず小さな悲鳴を上げそうになった。けれど、掌を固く握りしめることで、かろうじてこらえる。
「生まれて間もないライシェンを、腕に抱いたことを思い出しました。驚くほど小さくて、柔らかくて……。誰かから話を聞くのとは違う、自分の体験としての感触が蘇りました」
「なるほど。あなた自身の経験のように、記憶が処理されるわけですか」
〈蝿〉の目つきが、研究者のそれになった。
しかし、今の彼にとって、メイシアは研究の対象ではない。情報源であり、生き残るための切り札だ。
平時であれば、彼女の脳に電極を刺し、情報伝達の仕組みでも解明しようとしたことだろう。けれども現在、彼に必要なのは、知的好奇心を満たすことではなく、セレイエの居場所を知ることだった。
「では、教えて下さい。鷹刀セレイエ本人は今、どうしていますか? 彼女は『ライシェン』に会いたいはずです。どのようにして、彼女は現れるつもりですか?」
「それは……」
メイシアは、ごくりと唾を呑み込んだ。テーブルの下の拳が、うっすらと汗ばむ。
「……私の中に蘇るのは、ライシェンとの思い出ばかりなんです。――セレイエさんが幸せだったころの記憶だけ……なんです」
「……!?」
〈蝿〉の眉が跳ね上がった。メイシアが言わんとしていることに気づいたのだ。
顔色を変えた彼を恐れるように、けれど、言うしかないと覚悟を決めたかのように、彼女は細い声を震わせる。
「ライシェンの命が狙われている、という記憶に触れそうになると、怖い、悲しいといった気持ちがあふれてきます。そして、それ以降のことは思い出したくない、と……」
「つまり、あなたの中の『鷹刀セレイエ』は、楽しい思い出に浸りきっている、というわけですか!」
苛立ちのままに、〈蝿〉はテーブルに拳を打ち付けた。メイシアは、びくりと肩を上げ、身を縮こませる。
「……すみません」
萎縮したようにうつむく。――嘘をついていることがばれないよう、顔を隠すために……。
今までの人生において、およそ人を騙したことなどない彼女の、一世一代の演技だった。
〈蝿〉には、どんな些細な情報だって渡す気はない。けれど、それをそのまま言ったら、〈蝿〉の機嫌を損ねるだけだろう。
だから、できるだけ多くの真実を混ぜた嘘を伝える。
そして、時間を稼ぐのだ。
メイシアに『ライシェン』を見せれば、すべて上手くいくと思っていた〈蝿〉は、これから次の手を考えなければならなくなった。そこに掛かる『時間』が、メイシアの勝機に繋がる。
現在のメイシアの目的は、この庭園からリュイセンと共に逃げることだ。そのための情報を集め、策を練る時間が欲しかった。
「あなたの中で、『鷹刀セレイエ』が目覚めていることは確かなわけですね」
〈蝿〉が、低い声を落とした。冷静さを取り戻したように、緩やかに口角を上げる。
不穏な気配に、判断を誤ったかとメイシアの心臓が跳ねた。しかし、話の流れから、もはや肯定以外の返答は許されない。
「――はい」
「分かりました。あなたに自白剤を投与しましょう」
「!」
「そもそも、初めからそのつもりでした。――あなたが『鷹刀セレイエ』の記憶を得たところで、素直に話してくれるとは思っていませんでしたからね」
絶世の美貌が『悪魔』の残忍さをまとう。
メイシアが情報を隠そうとすることなど、〈蝿〉にはお見通しだった。
背中を冷や汗が流れた。顔から一気に血の気が引き、歯の根が合わなくなる。
「どうしました?」
涼しげな声で、〈蝿〉は尋ねる。
「……怖い……です」
メイシアは、状況と矛盾しない返答を必死に紡ぎ出した。言ったあとも、疑念を抱かれない台詞だったろうかと、不安に鼓動を早める。
「あなたは大事な切り札ですから、廃人にしたりなどしませんよ」
白衣の〈悪魔〉は、脅える患者を諭すように、優しげな笑みを浮かべる。医者として、研究者として、薬物の副作用はないと、そう言いたいのだろう。勿論、本心からメイシアを案じているわけではない。ただの演出だ。
しかし、彼が口にした『廃人』のひとことは、メイシアにとっさの詭弁をひらめかせた。
「ル、ルイフォンが言っていました……!」
彼女は、叫ぶように切り出す。
「〈天使〉の脳内介入は、一歩、間違えれば廃人になるような繊細なものだそうです。ですから、私に刻まれた『セレイエさん』の記憶を、薬を使って無理に引き出すことは危険です」
がたがたと震えながら、メイシアは必死に訴えた。けれど、〈蝿〉は一笑に付す。
「まったく論理的ではありませんね。適当な理由をつけて、自白剤を忌避しようとしているようにしか聞こえません」
「……」
事実、その通りなのだから、そう言われても仕方ない。
「――ですが、よく考えれば、あなた自身が認識できていないような記憶を、薬で強制的に引きずり出そうとすることは、『危険』というよりも『見当違い』かもしれませんね。『知らない』ことは、自白のしようもありませんから」
〈蝿〉は緩く腕を組み、「それでは、こうしましょう」と、優位にある者の顔でメイシアを睥睨する。
「これから毎日、あなたには『ライシェン』と対面してもらい、あなたの中の『鷹刀セレイエ』に揺さぶりをかけ続けます。そうですね、一週間くらいでいいでしょうか。そのあとで、自白剤を投与してみましょう」
「!?」
一週間の猶予――!?
メイシアの詭弁は失敗したのに、〈蝿〉のほうから時間を与えてくれるとは!?
……信じられないほどの幸運だった。
「分かりました」
メイシアの口元が、自然にほころぶ。
思わず表情を緩めてしまってから、不審な態度ではなかったかとメイシアは焦るが、彼女の一喜一憂は自分の言葉に翻弄されているからこそと、〈蝿〉は捉えているようだった。満足げな様子で彼女を見つめている。どうやら、大丈夫そうだ。
かなり危ういやり取りではあったが、こうしてメイシアは、ひとまずの時間を手に入れた。
話が、ひと段落したからだろう。「食事を用意させます」と言って、〈蝿〉は携帯端末に向かって指示を出した。
ずっと眠っていたとはいえ、メイシアは鷹刀一族の屋敷からさらわれて以来、丸一日、何も口にしていない。敵からの施しとはいえ、ありがたかった。
ほどなくして、エレベーターの気配を感じ、扉がノックされた。
部屋に入ってきた人物を見て、メイシアは目を見開く。
「リュイセン……」
輝くような黄金比の美貌はすっかり陰りを帯び、すらりとした長身は、弟分のルイフォンもかくやというほどに猫背になっている。
彼は、メイシアと目を合わせることができず、押してきたワゴンの手元にずっと視線を落としていた。
「彼に会わせて差し上げると、約束をしたでしょう?」
うつむいたままのリュイセンを一瞥し、〈蝿〉がくすりと嗤う。
「あなたの身の回りの世話はリュイセンに任せます。見知らぬ男に部屋をうろつかれるよりも安心でしょう」
まるで善行を自慢するかのように〈蝿〉は言った。そして彼は、自分は研究室に戻らなければならないと、部屋を出ていった。
あとには、メイシアとリュイセンのふたりきりが残された……。
リュイセンの押すワゴンが、車輪の音をからからと響かせて近づいてくる。場違いなほどに軽快な音は、メイシアの鼓動と歩調を合わせるように高鳴り、彼女の座るテーブルの横で止まった。
「リュイセン……、……っ」
何を言えばいいのか、分からなかった。けれど、彼の姿を正面から見た瞬間、メイシアの瞳から涙がこぼれた。
……安堵したのだ。
彼女をさらったのは間違いなく彼なのに、見知った顔が近くにあることが、とてつもなく心強かった。
「メイシア……。……すまん」
暗く沈んだ声が、光のあふれる展望室に掻き消される。
「リュイセン、あのっ……!」
「まずは、食べてくれ。ずっと何も食べていないはずだ。……体に悪い」
話しかけようとしたメイシアから逃げるように、リュイセンはぎこちない手つきで、ワゴンからテーブルへと皿を移す。
「リュイセン……」
用意された食事は、ライ麦の入ったパンと、香辛料で軽く調味した肉のソテー。野菜もきちんと添えられていて、思っていたよりもずっと豪華であった。どうやら〈蝿〉は、専任の料理人も雇っているらしい。レトルト食品を温めただけのものが出てきても美味しくいただこうと、身構えていたメイシアは拍子抜けした。
ルイフォンと生活していくうちに、貴族の世界では口にすることもなかったようなものも食べるようになった彼女ではあるが、基本的には屋敷の料理長の絶品料理をいただいている。……目の前の食事に、ほっとしたのも事実だった。
「いただきます」
リュイセンの様子を窺いながら、メイシアはナイフとフォークを手に取った。
食器の奏でる音だけが、ふたりの間を埋める。
ふたりとも無言だった。メイシアは、何度か口を開こうとしたのだが、リュイセンの視線がそれを許さなかった。
息苦しい空気が部屋を占める。
料理長の手伝いをするようになってから、メイシアは食べ物に対する感謝の気持ちがいっそう深くなっている。このままでは料理に失礼だ。きちんといただこうと、彼女は食事に専念することにした。
……やがて、綺麗に食べ終わり、メイシアはナプキンで口元を押さえた。
「ご馳走様でした」
一礼し、改めてリュイセンと向き合う。
「リュイセン、一緒にこの庭園を逃げましょう」
黒曜石の瞳が、じっと彼を捕らえた。凛とした強さに、無言で食器を下げようとしていたリュイセンの肩がびくりと揺れ、思わずメイシアを振り返る。
「あなたは、好きで〈蝿〉に従っているわけではないでしょう?」
「……っ」
リュイセンは押し黙り、目線をそらした。
思わしくない反応は承知していた。何故なら、リュイセンとふたりきりにしても、メイシアが逃げることにならないと踏んでいるからこそ、〈蝿〉は安心して研究室に戻っていったのだから。
「リュイセン、私がセレイエさんの〈影〉だという話。あれは正確ではなかったんです」
「――え?」
リュイセンの頬が、ぴくりと動いた。初めて、彼の表情が変化した。
「王族の血を引く私は特別で、私の中には、私自身と『セレイエさん』が同時に存在できるんです。だから、〈蝿〉が言った『いずれ私は、私でなくなる』というのは嘘だったんです」
「……!」
「リュイセンは、私が〈影〉となって消えてしまうと思ったからこそ、私をさらうことに納得したんじゃありませんか?」
メイシアの問いに、リュイセンの喉仏が、こくりと下がるのが分かった。口に出しては何も言わないが、それは正直すぎる彼の不器用な首肯だった。
「〈蝿〉は、リュイセンの背中を後押しするために、嘘を言ったんです」
畳み掛けられた言葉に、リュイセンは鋭く息を呑んだ。
彼の視界は、後悔と憎悪で黒く塗りつぶされた。目の前が見えなくなった彼は、片付けようとしていた皿を思わず取り落とす。
高い音が響いた。
粉々になった陶器の破片が飛び散り、床の上に広がる。
「――!」
崩れ落ちるようにリュイセンがしゃがみこんだのは、割れた皿を拾うためか。
それとも、今まで彼を支えてきた、拠りどころとなる免罪符を失ったためか……。
「――つっ……」
リュイセンの指先に赤い筋が走った。まともに手元を見ずに、破片を掴んだからだ。
「リュイセン、待って! 箒を持ってきます!」
この部屋に入るとき、階段の脇にロッカーのようなものが見えた。おそらく、掃除用具入れだ。
メイシアは、ぱっと席を立ち、小走りに取りに行く……。
思った通りに箒を手に入れて戻ると、リュイセンが大きめの破片を黙々と拾っていた。
「あとは私がやります」
メイド見習いとして修行を積み、ひと通りのことはできるようになったのだ。腕の見せどころだろう。
「――いや。自分のしたことは、自分で決着をつける。――当然だ」
「えっ!?」
先ほどまでの肩を落としたリュイセンとは、別人のように艶めいた低い声だった。
顔を上げた彼の瞳は、触れれば斬れるような抜き身の刀の様相をしていた。血の気の失せた美貌は透けるように白かったが、それが強い意志を得た黒目をより印象的に際立たせている。
「リュイセン……?」
彼の中で、何かが変わったのだ。
彼は、やるべきことをやる男。常に前を、未来を向いて歩いていく――。
「……それは、お皿のことではなく、今の状況のことですよね。ならば、ひとりではなく、私と一緒に……」
そう言いかけたメイシアの声を、リュイセンが遮った。
「すまん、メイシア。それはできない。俺は――……」
言い掛けて、途中で奥歯を噛みしめるようにして、彼は口をつぐむ。
「〈蝿〉に、脅されているんですね」
「……」
「教えて下さい。リュイセンは何故、〈蝿〉に従っているんですか? いったい、何があったんですか!?」
「……答えられない。――けど、お前のことは必ず、ルイフォンのもとに帰す。必ず、絶対だ」
噛みしめるように告げられた言葉は、メイシアに誓いを立てるようでいて、自分に言い聞かせるようでもあった。
メイシアは、ごくりと唾を呑み、喰らいつくようにリュイセンに迫る。
「私は〈蝿〉から一週間の猶予を得ました。その間に、あなたが〈蝿〉に従う原因を取り除きます――!」
「……無理だ」
はっきりと言い切ったリュイセンを無視し、メイシアは続ける。
「純粋な武力の勝負なら、あなたは〈蝿〉を遥かに上回ると、ルイフォンから聞いています。――つまり、あなたが〈蝿〉から解放されれば、『〈蝿〉を捕らえる』という私たちの本来の目的は簡単に達成できます」
――そうだ。
ただ逃げることばかり考えていたが、反撃に出ることもできるのだ。
メイシアの頬が紅潮し、黒曜石の瞳が煌めく。
「捕らえた〈蝿〉を車に乗せて、鷹刀に戻りましょう。――〈蝿〉の部下となっているあなたなら、門を守る近衛隊の方々に呼び止められることなく、この庭園を出られるはずです」
やはり、リュイセンは希望だと、メイシアは思う。
リュイセンは今、苦しんでいる。けれど、この窮地さえ乗り越えれば、すべて解決するのだ。
「――だから、教えてください」
凛とした眼差しが訴える。
「リュイセンは、いったい何に縛られているのですか……?」
「……すまん」
リュイセンは、皿の破片を拾い終えていた。ごみとなったそれをワゴンに載せ、踵を返す。
「メイシア。俺は、お前の敵なんだ。……仇なんだ」
「リュイセン!」
「お前を連れ去ろうとしたとき、ルイフォンに見つかった。俺は、退路を断つつもりで……、ルイフォンを斬ってきた」
「――!?」
まさかの告白だった。
メイシアは口元に手を当て、血相を変える。
心臓が激しく脈打った。目眩がして、周りの景色が歪んでいく……。
「命に別条はない。……けど、決して軽い怪我じゃない。峰打ちだけで充分だったのに……。――すまん。お前の大事な奴を……」
弱々しくこぼされた言葉に、メイシアは反射的に叫んだ。
「ルイフォンは、リュイセンの大切な弟分です!」
これだけでは、何を言いたいのか、リュイセンに伝わらないだろう。
ルイフォンは、メイシアの大事な人であると同時に、リュイセンにとっても、かけがいのない相棒だ。――そう言いたかったのだ。
リュイセンの口ぶりは、まるで彼とルイフォンの間には、関係を示す言葉が何もないのだと言っているかのようで……。胸が苦しくて声が出ない。
たとえ傷つけたのが彼自身だとしても、深手を負ったルイフォンのことを、リュイセンは心から案じている。
ルイフォンとリュイセンは、長い間ふたりで築きあげてきた、太い絆で繋がっている。
だからこそ、リュイセンは、裏切りを決意したからには、絆もろともルイフォンに刀を振るい、断ち斬らずにはいられなかったのだろう。
どうして、こんなことになったのか。
……自分がさらわれたこと以上に、心が痛い。
「俺は、お前にも、……あいつにも、もう顔向けできないんだ……」
ワゴンの音が、からからと遠ざかっていく。
「待ってください!」
メイシアが椅子から立ち上がった瞬間、リュイセンがくるりと振り返った。
肩で綺麗に切り揃えられた髪が、空を薙ぐ。
地底の闇を秘めた双眸が、メイシアを映す。
その顔は……拒絶――だった。
「――けど、何があっても、お前をルイフォンのもとに帰す。――それは、絶対だ」
そして、リュイセンは扉の向こうに消えた。
メイシアはただ、見送ることしかできなかった。
重い体を引きずるようにして、メイシアは窓際に立った。少しでも、ルイフォンのいる場所に近づきたかった。
怪我の具合いは、どんなだろうか。
彼はきっと、ミンウェイの制止も聞かずに、動き回ろうとしているに違いない。
……メイシアを取り戻すために。
「ルイフォン……」
彼に逢いたい。そして、つきっきりで看病をするのだ。
彼はきっと、嬉しそうに猫の目を細め、『ありがとう』と彼女を抱きしめてくれるだろう……。
「――……っ」
メイシアの頬をひと筋の涙が流れた。
光あふれる展望室からの風景は、遥か遠く、どこまでも冴え渡っていた。
けれど、メイシアの周りだけは深い霧に覆われている。
どこに向かって手を伸ばせばいいのか分からず、彼女は祈るように両手を組み合わせた……。
7.黄昏どきの来訪者-1
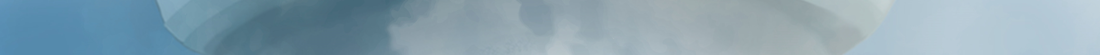
リュイセンが部屋を出ていったあと、メイシアは寒さに凍える小鳥のように、窓際でうずくまっていた。
膝に顔を埋めた姿勢でしゃくりあげれば、長い黒髪が床の埃を払っていく。この塔で目覚めた直後には、換気のために窓を開けようとした彼女だが、今は封じられていた空間特有の汚れなど、何も気にならなくなっていた。
どのくらい、そうしていただろうか。
透き通った輝きを放っていた陽光が、ほんのりと闇を秘めた橙色に染まってきた。窓から望む草原もまた、瑞々しい緑色から茫とした黄金色へと塗り重ねられていく。
黄昏どきだ。
そこにないはずのものが紛れ込んでも分からない、そんな狭間の時刻――。
「……ルイフォン」
落ち込んでいても何も始まらない。彼に逢いたいのなら行動するのだ。
メイシアは、のろのろと立ち上がる。
気づけば、室内もだいぶ暗くなっていた。
まずは電灯のスイッチを探すことから始めよう。しばらくここで暮らすのなら、部屋の設備を確認しておくことは必要だ。
そんなふうに些細な目標を決めて、気持ちを無理やり奮い立たせていく。
スイッチは、扉のすぐ横にあった。ぱちりと押すと、ぱぁっと部屋が明るむ。少しだけ、心が和らいだ。
そう思ったときだった。
部屋の外に何かの気配を感じた。扉に耳を付けると、階段を駆け上がってくるような足音と、ぜえぜえという荒い息遣いが響いてくる。
誰かが、この塔を登ってきている――?
メイシアは、はっと思い出した。
部屋の鍵を閉めるようにと、〈蝿〉に忠告されていた。――私兵たちが悪事を働くかもしれないから、と。
彼女の顔は一瞬にして蒼白になり、がたがたと震える手で鍵を掛けた。それから部屋を見渡し、テーブルや椅子をバリケードとして運んでくるべきかと考え、首を振る。メイシアが運べる程度の重さでは役に立たないだろう。
そうこうしているうちに、気配はすぐそこまでやってきた。息は多少、乱れているが、足音は随分と軽快で――。
がちゃり、と。ドアノブがひねられた。
メイシアは反射的に目をつぶる。鍵が掛かっているのは分かったはずだ。だから諦めて帰ってほしいと、天に祈る。
しかし、鍵に気づいた相手は、今度は扉を叩き始めた。恐怖に駆られたメイシアは、無意味と分かりつつも耳をふさぐ。
そのときだった。
「ああぁ……!」
扉の向こうから聞こえたのは、細く、高い声。
予想していたような、野太い男の声ではない。無邪気で可愛らしい、小さな女の子の悲壮な叫びだ。
「――!?」
メイシアは扉に張り付き、外の人物の様子を探る。
「鍵……、掛かっている……。ファンルゥ、メイシアに会わないといけないのに……」
涙声のあとには、ぐすんと鼻をすする音が続いた。
ファンルゥ――!?
心臓が跳ねる。メイシアは、その名前を知っていた。人質として〈蝿〉の監視下にある、斑目タオロンの娘だ。
年齢は四、五歳くらい。行動力抜群で、よく部屋から抜け出しているらしい。
以前の〈蝿〉捕獲作戦のときも脱走していて、ルイフォンたちに保護された。しかし、それは単なる好奇心からではなく、重い病気だと勘違いしたハオリュウに、お見舞いの絵を贈るためだった。とても優しい子なのだ。
「ぁ……」
メイシアの口から、小さな息が漏れた。ファンルゥが訪ねてきた理由に気づいたのだ。
彼女は、誰かから囚われのメイシアの話を聞き、慰めたい一心で、いてもたってもいられずに駆けつけてくれたのだ。
自分の境遇にばかりに頭が行ってしまって、同じ庭園内にファンルゥやタオロンがいることをすっかり忘れていた。心優しいファンルゥが、さらわれてきたメイシアを見逃すはずがないのだ。
心が、ほわりと温かくなる。
しかし、どうやってこの塔に入ってきたのだろう? 入り口には見張りがいるはずだ。
メイシアが首をかしげていると、ファンルゥの声が再び聞こえてきた。
「窓……、窓は……? どうやって行けばいいんだろう……?」
心底、困ったような呟き――。
迷う必要はなかった。メイシアは素早く内鍵を外し、扉を開ける。
薄暗い通路に、部屋の光が差し込んだ。
その明るさに引かれるように、小さな頭が上を向く。涙をたたえた大きな目が、電灯の光を反射して、きらきらと輝いた。
「……ほんとに、お姫様だぁ……」
可愛らしい口をぽかんと開けて、ファンルゥはメイシアを凝視した。
開口一番の台詞にメイシアは戸惑う。しかし、ともかく、ファンルゥを部屋に入れたほうがよいだろう。見張りは塔の外に立っているはずだが、階段を伝って声が響くかもしれない。
メイシアが手招きしようとしたとき、はっと我に返ったファンルゥが叫んだ。
「リュイセンは、悪くないの! ファンルゥとパパが、ごめんなさいなの!」
「え!?」
「だから、ファンルゥ、メイシアを助けるの!」
甲高い声が、通路に反響する。
メイシアは、慌ててファンルゥの手を引き、彼女を部屋に入れて、扉と鍵を閉めた。
部屋に入った瞬間、ファンルゥは「うわぁ……」と声を漏らしたあと、しばし絶句した。
展望室を半分に区切ったこの部屋は、彼女の想像を超えていたらしい。広い空間と、一面の硝子張りの窓に目を奪われている。
「ファンルゥちゃん、来てくれてありがとう。そこに座ってね」
メイシアは柔らかにそう言って、食事に使ったテーブルを指した。
内心では、いきなり現れたファンルゥに動揺していた。けれど、メイシアがそれを表に出してしまったら、もともと興奮状態にあったファンルゥは、更に落ち着きを失ってしまう。だから、努めて自然な感じに振舞った。
ファンルゥは、弾かれたようにメイシアを見上げると、素直に「うん」と頷いた。
メイシアのことは、父親のタオロンから聞いているのだろう。初対面であるが、以前からの顔見知りのように、人懐っこい表情を見せてくれる。今までの生活の中で、小さな女の子とは縁がなかったメイシアとしては、こそばゆいような嬉しさがあった。
あちこちに跳ねた癖っ毛を揺らしながら、ファンルゥは元気よく駆けていき、ちょこんと椅子に腰掛けた。足は床に届かないため、宙でぶらぶらとさせていたが、メイシアが向かいに座ると、ぴたりと動きを止める。
「メイシア……」
ファンルゥは、くりっとした丸い目を見開き、まっすぐにメイシアを見つめた。
それから、すぅっと大きく息を吸い込み、一気に吐き出す。
「ごめんなさい!」
勢いよく頭を下げ、テーブルに、ごちんと額をぶつけた。
「ファンルゥちゃん!?」
「――いっ……、痛くないもん……っ。ファンルゥ、平気だもん!」
涙目になりながらも、ファンルゥは、ぶんぶんと首を横に振る。強がりを言う彼女にメイシアは駆け寄り、赤くなってしまった額を覗き込んだ。
「大丈夫?」
「ファンルゥは大丈夫! でも、メイシアが大丈夫じゃないの! メイシア、泣いていた! ファンルゥ、知っている! お部屋の窓から見ていた!」
「えっ!?」
メイシアは狼狽し、さぁっと顔を赤らめた。
まさか見られていたなんて、思ってもいなかった。
無意識に身を引きかけたメイシアの袖を、ファンルゥは、ぐいと掴む。
「ファンルゥ、すぐにメイシアのところに行きたかった。でも、見つからないように暗くなるまで待っていたの!」
「心配してくれたの……? ありがとう」
優しさが、じわりと胸に染み込む。誰かのために、一生懸命。本当に、聞いていた通りの子だった。
ファンルゥは、子供らしく拙いながらも、懸命に、ここまでの『冒険』について説明してくれた。
それによると、彼女はまず、館にある自分の部屋を窓から脱出して、外に出た。
私兵たちに見つからないように、気をつけながら草原を走り抜け、この展望塔に到着。塔の見張りは入り口側にしかいないので、身を隠しながら裏側に回る。そして、明かり取りの小窓まで石の壁をよじ登り、階段から入ってきたのだという。
とても小さな女の子とは思えないほどの行動力だった。
「でも、どうして『ごめんなさい』なの?」
問いかけたメイシアに、ファンルゥは、父親譲りの太い眉をぎゅっと内側に寄せた。使命感に燃えているようでもであり、泣き出したいのをこらえているようでもある。
「メイシアをさらってきたのはリュイセンだけど、リュイセンが〈蝿〉のおじさんの手下になっちゃったのは、『パパがリュイセンを捕まえたから』だもん……」
初めは力いっぱいだった声が、だんだんと尻つぼみになっていく。
考えてもいなかった理由に、メイシアは戸惑った。
タオロンと、メイシアの拉致の間に、関連はあるだろうか? ――否、ないだろう。少なくとも、ファンルゥが責任を感じる問題ではない。
「ううん、違う。ファンルゥちゃんが謝ることなんか何もない」
しかし、ファンルゥは聞いていなかった。彼女はぶんぶんと頭を振り、心の膿を吐き出すように叫んだ。
「ファンルゥとパパは、〈蝿〉のおじさんが大嫌い! ……でも、斑目のお家の追手から守ってもらっているから、命令に逆らえないの……」
叫びの後半で声に勢いがなくなっても、ファンルゥの口元は皺が寄るほどにきつく結ばれており、強い反発の意思が表れている。
ファンルゥは椅子からぴょこんと飛び降り、険しい顔でメイシアに迫った。
「メイシアも、知っているんだよね!?」
「え!?」
「ルイフォンとリュイセンが、パパに会いにきてくれたこと!」
「あ……、うん」
失敗してしまった〈蝿〉捕獲作戦のときのことだろう。
「ルイフォンたちは、パパに『〈蝿〉の手下なんかやめて、一緒に行こう』って誘いに来てくれたんだよね? ――でも、パパは断っちゃったんだよね……?」
食い入るようなファンルゥの眼差しに、メイシアは困惑したが、すぐに気づいた。
タオロンは、子供のファンルゥには詳しいことを伝えていないのだ。だから、ファンルゥは知りたいのだ。
――タオロンが口を濁すのは当然だ。
あのとき彼は、心情的にはルイフォンたちの味方だった。けれど、他でもないファンルゥを人質に取られているがために、身動きが取れなくなってしまったのだ。
メイシアは、ちらりとファンルゥの左手首を見やる。そこには、きらきらと輝く綺麗な腕輪がはめられていた。〈蝿〉がファンルゥに渡した、人質の証だった。
「タオロンさんは、『〈蝿〉にはお世話になっているから、ルイフォンたちとは一緒に行けない』って言ったの」
メイシアも、嘘をついた。
ファンルゥが、タオロンの枷になっているだなんて言えるわけがなかった。
「うん。やっぱり。ファンルゥの思っていた通り! ファンルゥ、パパだけじゃなくて、リュイセンにも聞きに行ったから、気づいていたもん!」
「リュイセンにも会ったの!?」
口ぶりからして、リュイセンとの面会は、間違いなく〈蝿〉の許可を得たものではなく、お得意の脱走に依るものだ。この塔に来たこともそうであるが、ファンルゥの無鉄砲さにメイシアは青ざめる。
「うん。ファンルゥが会いにいったら、リュイセンはむーっとして、ぎろりだった。――でも、すっごく悲しそうだった……」
そのときのことを思い出したのか、ファンルゥの顔が陰る。
「けどね、ファンルゥ、パパやリュイセンのお顔を見て分かったよ! ――〈蝿〉のおじさんは、パパを連れて行こうとしたルイフォンとリュイセンに、ぷんぷんなの。だから、『ふたりを捕まえて手下にしてやる』って言ったの」
「えっと……、そう、かしら……?」
メイシアがなんと答えるべきか迷っていると、ファンルゥは「そうなの!」と重ねて言う。
「だから、パパに命令して、リュイセンを捕まえて、手下にしたの」
それから身振り手振りが加わり、ファンルゥの講釈に熱が入る。
「〈蝿〉のおじさんは、逃げたルイフォンには、もっとぷんぷんで、『逆らったことを後悔させてやるぞ』で、いっひっひーなの」
「……」
「『ルイフォンの一番、嫌なことをしてやる』って、わっはっはー。――だから、手下にしたリュイセンに命令して、ルイフォンの恋人のメイシアをさらわせたの」
だんだんと〈蝿〉がおとぎ話の悪い魔王のようになってきた。それでも、現実の状況に則しており、かつ、とりあえず辻褄の合った物語になっている。その発想力が凄い。
「ファンルゥの見張りのおじさんたちが『リュイセンがお姫様をさらってきて、〈蝿〉が塔の上に閉じ込めた』って噂していたから、すぐにピンときたよ!」
自慢するように胸を張り、それからファンルゥは、はっと表情を変えた。
メイシアが囚われていることは、ちっとも良いことではないと気づいたのだ。得意げだった顔が、急速にしぼんでいき、「ごめんなさい」と沈んだ声で呟く。
「えっと、つまりね。ファンルゥとパパが、〈蝿〉のおじさんの『お世話』になっているから、メイシアがさらわれちゃった、ってことなの。――だから、ファンルゥとパパが、ごめんなさいなの」
合っているでしょ? と、くりっとした目が訴えていた。
「ううん、やっぱり違う。ファンルゥちゃんは、とってもいい子なんだから、謝る必要はないの」
メイシアは、ゆっくりと頭を振る。すると、ファンルゥは、まるで張り合うかのように、ぶんぶんと激しく首を左右に振った。
「ファンルゥちゃん?」
「メイシアはルイフォンのところに帰りたい、って泣いている! だから、ファンルゥは、メイシアを逃してあげなきゃいけないの!」
「え……。私を、逃がす……?」
唐突な言葉に、メイシアは瞳を瞬かせた。
「うん! ファンルゥ、初めに言った! メイシアを助ける、って!」
ファンルゥは、父親そっくりの太い眉に意志の力を載せ、毅然と言い放つ。
「だから、暗くなるまで、メイシアに会いに行くのを我慢したの。――ほら!」
彼女は、ぱたぱたと可愛らしい足音を立てながら窓際に向かって駆けていき、闇に染められつつある外の世界を示す。
メイシアもあとを追えば、眼前に深い色合いの草の海が広がっていた。
「もうちょっとしたら、もっと暗くなるの。そしたら、お星様しか見えなくなるよ!」
言われて見渡せば、庭園内は極端に電灯が少なかった。王の療養施設として作られたためか、無粋な明かりは排除して、星空を楽しめるようにとの配慮かもしれない。
「ファンルゥが入ってきたところから出られるよ。パパみたいに大きい人だと駄目だけど、メイシアなら大丈夫! メイシア、お外に逃げられるよ!」
ファンルゥは、にっこりと誇らしげに笑った。
「…………」
メイシアは……。
ほんの一瞬――ごくわずかな時間、心が浮き立った。
けれど、それだけの刹那で、ファンルゥの計画の欠点に気づいてしまった。
「ファンルゥちゃん、ごめんね。ファンルゥちゃんが通ってきた小窓から塔の外には出られるけれど、この庭園の周りには近衛隊が――凄い見張りがいるの」
ファンルゥにとって、『外』とは建物の外なのだ。ずっと閉じ込められていたファンルゥは、この広い草原の向こうにも見張りがいることを知らないのだ。
メイシアの胸が、ずきりと痛む。
物心ついたころから、父親のタオロンを縛る道具として利用されてきた彼女は、おそらく箱庭の世界しか見たことがない……。
「凄い見張り……? メイシア、逃げられないの……?」
愕然とした顔でファンルゥが尋ねる。
メイシアが力なくうなずくと、ファンルゥの目から、ぽろりと涙がこぼれ落ちた。彼女はしゃくりあげながら、それを乱暴に腕で拭う。
「う……っ」
嗚咽を漏らし、ファンルゥはメイシアに体当りするように抱きついてきた。
「……ごめんなさい。ファンルゥのせいで、ごめんなさい!」
ファンルゥは、ふわふわの毛玉のような頭を揺らし、小さな体をすり寄せる。
「ううん。ファンルゥちゃんはちっとも悪くない。私のために、いっぱい考えてくれてありがとう」
メイシアもまた、ファンルゥをぎゅっと強く抱きしめた。
「うっ……、うう……、メイシア――!」
小さな肩を震わせ、ファンルゥの頬を幾筋もの涙が流れていく。
誰かのために、無我夢中で突っ込んでいく――黄昏どきの来訪者の涙は、とてもとても優しい色をしていた。
7.黄昏どきの来訪者-2
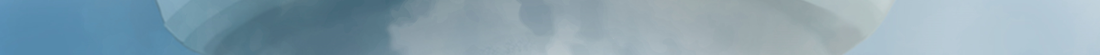
ファンルゥが全体重を預けてきても、華奢なメイシアの両腕で簡単に受け止められた。そんなに小さなファンルゥが、メイシアを助けようと懸命に飛び込んできてくれた……。
メイシアの服に顔を埋めたファンルゥが、不規則にしゃくりあげる。抱きついてくる掌を温かいと感じるのは、子供の体温が高いからだけではないだろう。
――ファンルゥを外の世界に連れて行ってあげたい。
心の奥から、強い思いが湧き上がってくる。
もしも、〈蝿〉捕獲作戦が成功していれば、ファンルゥは今ごろ、鷹刀一族の親戚である草薙レイウェンの家で暮らしているはずだった。彼の妻のシャンリーが、是非にと望んでくれていた。
タオロンとファンルゥの父娘の境遇を知ったシャンリーは、こう言った。
『坊やの娘だって、いつまでも親に守られているだけじゃ駄目だろう?』
『私が鍛えてやる。あの坊やの娘なら素質があるだろう。自分で身を守れるようになれば、坊やも、その子も、自由になれる』
小さな子供に対するにしては、少し厳しい言葉かもしれない。けれど、ファンルゥの将来を真に思いやった、シャンリーらしい深い優しさだった。
メイシアは、ファンルゥの頭に手を載せて、指先にじゃれてくる癖っ毛をくしゃりと撫でた。ルイフォンが『大丈夫だ。安心しろ』と言ってくれるときのことを思い出しながら、凛と告げる。
「皆でここを出ましょう」
包み込むような柔らかな声で、しかし、誓うように。
決して無謀な話ではない。ここにはリュイセンがいる。
彼は、〈蝿〉の気まぐれで、メイシアの世話係となった。おそらく、食事のたびに会えるだろう。先ほどは、けんもほろろだったが、まだまだ機会はある。
リュイセンが脅されている内容を聞き出して、解決する。彼の場合、どう考えてもタオロンのように人質がいるわけではない。ならば、〈蝿〉のお得意の妄言に踊らされているだけだろう。それを暴けば、リュイセンは解放されるのだ。
「ルイフォンが来てくれるの!?」
「え?」
弾んだ声に驚けば、ファンルゥが期待の眼差しでこちらを見ていた。
「〈蝿〉のおじさんは『恋人は預かった。悔しければ、取り返しに来い』で、はっはっはー、なんだね! だから、もうすぐルイフォンが来るんだ!」
高い塔にさらわれたお姫様のメイシアを、恋人のルイフォンが助けにくる――おとぎ話さながらの名場面を思い描いたのだろう。ファンルゥは目を輝かせながら喜色を上げた。
「えっと……、ルイフォンは……」
メイシアは、反射的に真面目に考えてしまった。
小さなファンルゥが相手なのだ。彼女の安心のために、『そうなの!』と即答してもよかっただろう。しかし、メイシアは真正直な性格だった。故に、ルイフォンの現状を正確に答えようと思考を巡らせた。
――ルイフォンも、動き出しているはずだ。大怪我を負ったと聞いているが、彼がじっとしているわけがない。
けれど、具体的なことは分からない。
さらわれたとき、メイシアは携帯端末を厨房に置いてきてしまった。いや、持っていたとしても、この庭園に着いたときに〈蝿〉に取り上げられてしまっただろう。
ルイフォンと連絡が取れれば……。
そんな思いが、メイシアの心をよぎる。
リュイセンが何に囚われているのか、ルイフォンに相談できる。弟分の彼なら、何か気づくかもしれない。
あるいは庭園の中と外で連携すれば、リュイセンを味方にできないままでも、〈蝿〉を捕らえられるかもしれない。〈蝿〉さえ捕らえてしまえば、メイシアやリュイセンは勿論、ファンルゥとタオロンも解放される。
メイシアは理性でそう思い、同時に、胸の奥からあふれてきた、切ない感情で苦しくなる。
――ルイフォンの声を聞きたい……!
自分は無事だと、ルイフォンに伝えたい。それから、ルイフォンの傷の具合いを知りたい。
ルイフォンと連絡を取る――その方法は……。
メイシアの頭に、『ある考え』が、ふっと浮かんだ。ファンルゥを抱きしめる手が、じわりと汗ばむ。
……駄目。
彼女は心の中で否定した。
ファンルゥを危険に晒すことはできない……。
「……ルイフォンって、弱いの?」
「えっ?」
ふと気づけば、ファンルゥが首をかしげていた。『助けに来てくれるの?』に対する答えがいつまでも返ってこないからだと、メイシアはひと呼吸、遅れてから気づいた。
「パパは凄く強いの。大きな刀も、軽くふんふんって、できるの」
でも、ルイフォンは細身で、そんなことはできそうもない。だから弱くて、助けに来られないのではないか。――そういうことらしい。
確かに、剛の者のタオロンと比べれば、ルイフォンの武力は弱いだろう。
けれど――。
「ルイフォンは、頭がいいの」
メイシアは、そう答えた。なんとなく負け惜しみのようだが、本当のことだ。
それに対して、ファンルゥが言う。
「パパはね、強くて、凄くて、格好いいの!」
息荒く、胸を張る。可愛らしい顔は誇らしげで、父への愛情で満ちていた。
ファンルゥにつられるように、メイシアもまた、ルイフォンへの想いを口に載せる。
「ルイフォンも、格好いいの。――優しくて、おおらかで、頼もしいの……」
「うー! パパだって、優しいもん! ファンルゥ、パパ大好き!」
少し、すねたようにファンルゥが叫んだ。大好きなパパが一番だと言いたかったらしい。そして、どうやら、それをメイシアにも認めてほしかったようだ。
無邪気な可愛らしさに、メイシアは、くすりとした。――それは、この庭園に囚われてから初めての微笑みだった。
「うん。ファンルゥちゃんのパパは素敵ね。でも、『大好き』はファンルゥちゃんに任せる。私は、ルイフォンが一番、大好きだから」
「あぁぁ、そっかぁ……。ううぅ! そうだよねぇ。メイシア、ルイフォンの恋人だもん」
ファンルゥは納得し、「うーん」とうなりながら太い眉を寄せる。
「パパにはママがいるから……。じゃあ、ファンルゥはリュイセンにする!」
「……えっ!?」
「リュイセン、初めて会ったときは、こーんな顔で怖かったけど、本当は優しいんだって、ファンルゥ、知っているもん」
何やら、おかしな方向に話が転がってしまったようだ……。
窓の外は、夜の帳が下り始めていた。薄い闇をまとった天空に、一番星が輝く。
ファンルゥのおかげで、メイシアの心はすっかり落ち着きを取り戻した。彼女は黒曜石の瞳を細め、穏やかな面持ちでファンルゥを見やる。
ファンルゥが来てくれて本当に嬉しかった。もっといてほしいけれど、あまり引き止めていては脱走がばれてしまうかもしれない。早く帰したほうがよいだろう。
「――……」
メイシアは、ファンルゥに気づかれないように拳を握りしめ、奥歯を噛んだ。そして、先ほど浮かんだ考えを、捨てきれないでいる自分を叱りつける。
――それは、駄目だ。
メイシアは、ファンルゥの手首に視線を落とした。そこには模造石で飾られた、綺麗な腕輪がはめられている。人質の証だ。
部屋から出ようとすると、音が鳴る。ファンルゥには、そう説明されている。
だが、本当は違う。
〈蝿〉の脳波によって毒針が飛び出すという、恐ろしい仕掛けが施された代物だ。また、勝手に外そうとしても同様。
この腕輪のために、タオロンは〈蝿〉の言いなりになっている……。
メイシアは深い息を吐き、それと共に未練を捨てようと試みる。
ルイフォンは、〈蝿〉捕獲作戦の失敗は自分の調査が足りなかったせいだと、酷く後悔していた。その理由のひとつが、ファンルゥの腕輪だった。
遠隔操作で毒針が出ると聞いた瞬間、リュイセンが〈蝿〉の両腕の腱を切ろうとしたらしい。手が使えなければ、リモコンのボタンを押せないだろうと考えたそうだ。しかし、脳波がスイッチになっているのだと、嘲るように〈蝿〉に告げられたという。
腕輪の存在に、あらかじめ気づくべきだったと、ルイフォンは悔いていた。
曰く。脳波についてはよく分からない。けれど、遠隔操作をするなら、どこかに受信機や中継機といった類のものがあったに違いない。不審な機器を見落としたのは、自分の落ち度だ――と。
「……!?」
そのとき、メイシアは違和感を覚えた。
ルイフォンの話では、遠隔操作の有効範囲は『館内』だったはずだ。〈蝿〉本人から聞いたというのだから間違いない。
だが、現在ファンルゥは、館の『外』にある展望塔にいる。
――彼女は今、毒針の呪縛から逃れているのだろうか……?
そんな馬鹿な、とメイシアは自分の疑問を打ち消した。
これで無効だなんて、〈蝿〉のやることにしてはお粗末すぎる。これでは、ちっとも腕輪は人質を繋ぎ止める枷にならない……。
「メイシア?」
どうしたの、と。くりっとした丸い瞳が尋ねていた。メイシアの視線が腕輪にあるのは気づいているようで、ファンルゥは、ちらりと自分の手首を見たあと、どことなく得意げな顔をした。
そういえば、ルイフォンが言っていた。〈蝿〉に渡されたことや、音が鳴ることは嫌だけれども、腕輪自体はファンルゥのお気に入りらしい。だから、おとなしく身に着けているのだろう、と。
「その腕輪、素敵だなって、見とれていたの」
ファンルゥは腕輪を褒めてほしいのだ。そう理解したメイシアは期待に応える。
実際、メイシアの目から見ても、とても良いセンスだと思った。模造石であるので、貴族の宴席では使えないが、繁華街の店先に並べてあれば、大人の女性でも思わず手に取ってみたくなるような品だ。
「うん、綺麗でしょ! ……でも、これ、ビービーなの。それがなければ、いいんだけどなぁ」
そう言いながら、ファンルゥは――。
腕輪を外した。
「――!」
メイシアは、『ファンルゥちゃん!』と、名前を叫んだはずだった。けれど、戦慄のあまり声にならなかった。
この腕輪は、『勝手に外そうとしたら、毒針が飛び出す』のだ……。
愕然とするメイシアに、可愛らしい声が掛かる。
「メイシアに、ちょっとだけ貸してあげる!」
ファンルゥが腕輪を差し出し、にこにことしていた。
「え……?」
何も起きていなかった。
女の子同士でおしゃれの話題を楽しむ、小さな淑女がいるだけだった。
「メイシア、お姫様だから似合うと思うの!」
ファンルゥに押し切られるようにして腕輪を受け取り、メイシアはその内側をそっと確認する。
表面はつるんとしており、針穴のようなものはなかった。どう見ても、ただの腕輪だった。
恐る恐る手首にはめると、ファンルゥが歓声を上げる。きらきらとした輝きが、メイシアの白磁の肌によく映えて、楚々とした気品を際立たせた。
しばらくファンルゥの賛辞を受けたあと、メイシアは尋ねる。
「ファンルゥちゃん、タオロンさんは腕輪を外してはいけない、って言わなかった……?」
「言っていた! でも、かゆくなったときに、時々、こっそり外していた!」
見れば、ファンルゥの手首は少し赤くかぶれていた。毎日の手洗いで濡れたあとや、自身の汗などをそのままにして、ずっと身につけていれば当然であろう。そして、子供のファンルゥが、かゆみを我慢できるわけがないのだ。
――つまり、毒針は『嘘』だ。
〈蝿〉は、もっともらしい嘘でタオロンを騙しただけだ。
「――!」
メイシアの耳に、先ほどのファンルゥの言葉が蘇る。
『ファンルゥとパパは、〈蝿〉のおじさんが大嫌い! ……でも、斑目のお家の追手から守ってもらっているから、命令に逆らえないの……』
タオロンが〈蝿〉の配下となったのは、斑目一族からファンルゥを守るためだ。〈蝿〉に強要されてのことではない。
かつて、ファンルゥの母親と共に一族から逃げたとき、タオロンは不在中に最愛の彼女を殺された。その後悔から、気に食わない相手と思いながらも〈蝿〉を頼ったのだ。
他に行き場のないタオロンは、ファンルゥを庭園内に匿ってもらうだけで、〈蝿〉に恩義を感じる。〈蝿〉は、タオロンが裏切ったり、勝手に出ていったりすることを心配する必要はない。
〈蝿〉にとってのファンルゥの腕輪は、気の進まない仕事を命じるときの強制力くらいの意味しかなかったのだ。実際、タオロンは、嫌々ながらもメイシアをさらいに来た。
娘の命は〈蝿〉の掌中にある。
タオロンが、そう信じて従順であればよい。
毒針は、嘘でよいのだ。もし本物だったとしても、どうせ〈蝿〉には使えない。
何故なら、ファンルゥを殺せば、その瞬間にタオロンは牙をむく。そのとき、武の達人のタオロンに、医者の〈蝿〉は敵うべくもないのだから……。
「……」
だんだん読めてきた〈蝿〉の真意に、メイシアは、ごくりと唾を呑む。
だから――。
ルイフォンたちが『草薙家』という受け入れ先まで用意して、『俺たちのところに来い』と手を差し伸べてきたのは、〈蝿〉にとって想定外。――否、恐怖だっただろう。
そのため、〈蝿〉は、とっさに虚言を吐いたのだ。
『脳波がスイッチになっています』
『誰にも、リモコンを奪うことはできません』
『文字通り、娘を瞬殺できるのですよ』
こうでも言わなければ、タオロンは裏切った。
タオロンが寝返れば、〈蝿〉に勝ち目はない。
敗北は、死を意味する――。
リモコンの有効範囲がお粗末だったのは、慌てて適当に口走ったからだ。
つまり……。
タオロンとファンルゥは、自由だ――。
「お願い、ファンルゥちゃん! 力を貸して!」
「どうしたの、メイシア?」
突然、叫んだメイシアに、ファンルゥは目を丸くする。
「タオロンさんに、手紙を届けてほしいの」
そう言いながら、メイシアは書き物用の机に小走りに向かう。
期待通り、引き出しの中には、赤茶けた便箋と万年筆が残されていた。幸運にも、インクは固まっていない。
何やら新しい『どきどき』と『わくわく』が始まったらしいと察知したファンルゥは、メイシアに負けず劣らず、目を輝かせながら飛んできた。
「ファンルゥ、郵便屋さんだね!」
楽しげな返事に、メイシアは、はっと顔色を変えた。
――自分のことばかり考えていた。
腕輪の仕掛けは嘘だと分かったが、それだけでファンルゥの安全が保証されたわけではないのだ。彼女が人質として軟禁されていることは変わらないし、脱走が見つかれば害されるだろう。
単に、重くのしかかっていた『毒針』という枷が外れただけだ。
それだけで、タオロンやファンルゥを頼ってもよいのだろうか。彼らには、密かにこの庭園から逃げるように勧めたほうがよいのではないだろうか……? 草薙家なら受け入れてくれるはずだ。
「メイシア?」
「ファンルゥちゃん、ごめんね。危険なことなの……」
タオロンとのやり取りは一度だけではすまない。連絡係となるファンルゥは、そのたびに危険に晒される。
急に口ごもったメイシアに、ファンルゥは意思の強そうな太い眉にぐっと力を入れた。
「ファンルゥは、『危険は、しょーち!』で、メイシアを助けに来たの!」
唇を尖らせるようにして、言い放つ。
「パパも、メイシアのことを心配していた。――何も言わなかったけど、たぶん、リュイセンも」
ファンルゥは、元気な癖っ毛を踊らせ、メイシアに迫る。そして、得意げな顔で告げた。
「メイシア、さっき言っていた! 『皆でここを出ましょう』って。パパへのお手紙は、その作戦の『密書』でしょ!? ファンルゥ、分かっちゃったもん!」
「…………」
ためらうメイシアに、ファンルゥが畳み掛ける。
「ファンルゥ、メイシアに意地悪する〈蝿〉のおじさんなんか、大嫌い! 斑目のお家が追っかけてきても、〈蝿〉のおじさんの『お世話』なんて、もう要らない!」
「ファンルゥちゃん……」
「『皆で』出ていく! メイシアも、ファンルゥも、パパも、リュイセンも……! 皆、一緒!」
ファンルゥの笑顔が、メイシアの背中を押す。
くりっとした瞳が、燦然とした輝きを放つ。それは模造石などとは比べようもないほどに強く眩しい、本物の煌めきだった。
「ね! メイシア!」
早く早くと急かすように、机の周りでふわふわの頭がぴょこぴょこ跳ねる。
「ファンルゥちゃん、ありがとう……」
メイシアは、頼もしい協力者に心からの感謝を述べた。
そして、挑むように便箋に向かった。
8.姫君からの使者-1

庭園の夜が更けてきた。
〈蝿〉は時計を確認すると、のろのろと椅子から立ち上がった。
いろいろとあった一日だったが、ひとまず、藤咲メイシアは用意しておいた展望室でおとなしくしているらしい。彼女の夕食を下げてきたリュイセンから、そう報告を受けた。
そろそろ寝る時間だと、彼は地下の研究室から、自室と定めた王の居室へと移動する。
本心で言えば、硝子ケースの中の『ミンウェイ』と、片時も離れたくはない。しかし、いまだ完全には慣れぬ、この老いを迎え始めた体をしっかりと休ませるためには、上質な睡眠が必要だった。
廊下の窓から外を見やれば、外灯のない草の地上は深い闇に沈み、紺碧の天空と、そこに撒き散らされた星々の輝きに主役の座を譲っている。
庭園の主であった王に捧げるための、静かな夜だ。
けれど、この星空は、ミンウェイにこそふさわしいと、〈蝿〉は思う。
何故なら、彼女が喜んだ、あの海辺の夜を彷彿させる。今は彼女の墓のある、あの丘からの風景だ。暗い草原を渡る風の音は、まるで潮騒……。
『ミンウェイ』にも、見せてやろうか。
ふと、そんな考えが浮かんだが、〈蝿〉は首を振った。――『ミンウェイ』は、ただの容れ物だ。煌めく笑顔を期待してはいけない。
そして『自分』もまた、彼女の隣に置かれていた容れ物のはずだった。なのに『中身』を入れられてしまったら。
――独りで生きるしかないではないか……。
〈蝿〉は奥歯を噛み締め、歩を速める。
やがて、天空神フェイレンの彫刻が施された、豪奢な王の部屋の扉が見えてきた。
そこに、待ち構えていたかのようにたたずむ、斑目タオロンの姿があった。
「休暇ですか?」
常から愛想のない男であったが、今宵のタオロンは、いつもにも増しての仏頂面であった。
太い眉がぐっと内側に寄るのを隠しもしない。それでいて、健康的な浅黒い肌の大男のそこかしこから、脅えのようなものが感じられる。内に不満を抱えつつも、〈蝿〉に対する服従心に支配されている。それが手に取るように分かり、実に滑稽だった。
「休暇を取って、どうするのですか?」
タオロンが、自分から現れるのは珍しい。これはひとつ、腰を据えて話を聞いてやらねばならぬと、立ち話ではなく部屋に入れた。その判断は正しかったようで、向き合って座った瞬間に飛び出した言葉は、随分と想定外のものであった。
「ファンルゥを外に――遊びに連れて行ってやりたい。あいつはもう、二ヶ月以上も、あの部屋に閉じ込められたままだ」
口調も目線も、明らかに〈蝿〉を責め立てていた。だが、本人としては、平静さを保っているつもりであるところが、なんとも可笑しかった。
「御冗談を。今、あなた方、父娘を外に出したら、藤咲メイシアを取り戻そうとしている、鷹刀ルイフォンに加担するでしょう?」
〈蝿〉としては、至極、当然のことを言ったまでだった。しかし、タオロンは唇をわななかせ、テーブルに拳を叩きつけた。
「ふざけるな!」
鈍い音が響く。厚みのある、贅沢な一枚板でなければ、天板が真っ二つに割れていたことだろう。
「何故、そんなに怒ってらっしゃるのですか?」
どうにもこの若造は、猪突猛進が過ぎる。だからこそ、扱いやすいといえるのだが。
そんなことを思いながら、〈蝿〉は口の端を上げた。タオロンの心の内を探るため、神経を逆撫でするよう、わざと高圧的に。
「俺は……、俺は……! お前の命令で……鷹刀リュイセンを捕らえた!」
「ええ、そうでしたね」
「お前の捕虜になったせいで、リュイセンの奴は、頭がおかしくなっちまった。大事な弟分の女を、藤咲メイシアをさらってきた。――やばい薬を使ったんだろ……?」
タオロンは、憎悪とも恐怖ともつかぬ顔で〈蝿〉を睨みつけ、声を震わせる。娘が人質になっているくせに、随分と軽々しく反抗的な態度を取るものだと思うが、それがこの男の性分だ。仕方なかろう。
〈蝿〉は薬を使ったわけではない。ただ『交渉』しただけだ。だが、いちいち訂正する必要はないので、薄い嗤いを返した。タオロンが、どう解釈しようと〈蝿〉に興味はない。
「それが、あなたに、なんの関係があるのですか?」
「なっ……!」
変わらずの涼しい顔の〈蝿〉に、タオロンは激昂する。
「あいつらは、敵のはずの俺に手を差し伸べてくれた! ファンルゥの将来まで、考えてくれていた……! なのに俺は、あいつらの好意を一番、酷いやり方で踏みにじっちまったんだよ!」
タオロンは、血の気が失せるほどに強く握りしめた拳をテーブルに落とす。
「俺のしたことは許されることじゃねぇ! ルイフォンにしてみりゃ、俺は、兄貴分を薬漬けにして、女を奪った憎い敵でしかねぇんだよ! ――それが、『鷹刀ルイフォンに加担』だと? ふざけるな! どの面下げて、あいつに会えるっていうんだよ!」
腹の奥に澱んでいた思いを吐き出すように、タオロンが吠える。斑目一族の総帥の血筋に生まれながら、彼の魂はどこまでも義理堅く、高潔だった。
ぎりりと歯を食いしばるようにして、タオロンは怨恨の視線を〈蝿〉に送る。しかし、微動だにしない相手に、やがて力なく肩を落とした。
「――仕方ねぇよ……。俺は先に、お前の手を取っちまったんだからよぉ……」
全身を震わせ、血の涙を流す。
「運がなかっただけだ、諦めるしかねぇ……。今までも、そうしてきたし、これからも、そうするだけだ。いつものことだ。……俺の娘に生まれてきちまったばっかりに、ファンルゥは……。……糞っ!」
タオロンは、再びテーブルに拳を打ち付けると、大きな体を丸めた。
「……せっかく、ファンルゥが表の世界に行けるチャンスだったのによぉ……。――畜生……!」
ぶつぶつと悲嘆に暮れる様は、惨めな敗残者そのものだ。これだから、この男はいつまで経っても『非捕食者』なのだと〈蝿〉は思わずにはいられない。
――ともかく、タオロンの思考は読み解けた。
要するに、自分の娘に罪悪感を抱いているのだ。
日頃から息苦しい生活を強いている上に、娘の知らないところで、おそらく彼女にとって最高の好機をふいにした。せめてもの償いとして、『外に遊びに連れて行ってやりたい』というわけだろう。
心情は分かったが、それを叶えてやるほど〈蝿〉は甘くない。タオロンにその気がなくとも、鷹刀ルイフォンの側にしてみれば、喉から手が出るほど内通者を欲しがっているはずだ。外に出すのは危険だ。
「話は終わりですか? 私はそろそろ眠りたいのですが」
タオロンの弁は、ただの愚痴だ。
〈蝿〉は知的な会話を好むのだ。愚痴なら聞いてやる価値はない。ましてや、睡眠時間を割いてやる義理もない。
すると、タオロンは慌てたように「待て!」と食い下がった。
「俺がリュイセンを捕まえたから、お前は、前々からの望み通りに、藤咲メイシアを手に入れられたんだ。だったら、俺の手柄だ! 少しくらいは、俺に褒美があってもいいだろう!? お前ばかりが、いい思いをするのはおかしいじゃねぇか!」
「……ふむ」
一理ある。
従順なこの男が、珍しく自分から何かを言い出したのは、そんなところにも不満があったからなのかと、〈蝿〉は妙に納得した。
〈蝿〉としては、藤咲メイシアから思うように情報を得られず、決して喜ばしい状態ではないのだが、だからといってタオロンに当たり散らしたりはしない。〈蝿〉は、理知的な思考の持ち主なのだから。
「褒美ですか。しかし、あなたは金品を欲しがるような方ではありませんしね」
だからこそ休暇なのかと理解したが、それは却下だ。
だがタオロンは、分かっているじゃねぇか、といわんばかりに大きく頷き、何を勘違いしたのか、心なしか嬉しそうな顔になった。
「ああ、俺は、ものは要らねぇ。俺の望みは、ファンルゥを喜ばせることだ」
「ならば、あなたの娘に、何か贈り物をしましょう。何がいいでしょうかね?」
刹那、弾かれたようにタオロンが身を乗り出し、唾を飛ばした。
「お前が贈るんじゃねぇ!」
タオロンの野太い声に、容赦なく鼓膜を打ち付けられ、〈蝿〉は渋面を作る。しかし、タオロンは構わず続けた。
「ファンルゥは、お前から貰っても嬉しくなんかねぇんだよ!」
鼻息荒く、タオロンが言い放つ。
が、次の瞬間、彼は、ぱっと閃いたように顔を明るませた。
「お前はどうせ、俺とファンルゥがふたりで出かけるのは駄目だと言うんだろう? なら、俺に外出許可をくれ。あいつに何か買ってきてやる。いつも、おとなしくしている、ご褒美だ。ペンダントとか、ブローチとか、あいつに似合う、綺麗なやつを探してきてやる」
「……」
嬉しそうに声を弾ませるタオロンに、〈蝿〉は絶句した。
そして、次第に笑いがこみ上げてくる。
タオロンの口から、ペンダントだのブローチだのといった、きらきらとした言葉が出てきたのは、間違いなく、娘に渡した腕輪に対抗してのことだ。
あの子供は、送り主の〈蝿〉を毛嫌いしているくせに、腕輪そのものは殊のほか気に入っている。それをタオロンが面白くないと思っていることは、自明の理である。
「いいでしょう」
無骨な大男が、どんな顔をして娘への贈り物を選ぶのかを想像すると、そのくらいは許してやってもよいと思えてきた。
タオロンは従順な駒であるからよいのだ。不満を溜め込ませるのは得策ではない。ガス抜きは必要だ。
「いつも通り、あなたに見張りをつけますが、よいですね?」
「ああ、構わねぇ」
「それでは、明後日の午後でどうでしょう」
「上出来だ」
こうして交渉は成立し、希望していた休暇を得られなかったにも関わらず、タオロンは上機嫌で部屋を出ていったのであった。
翌日。
メイシアが展望塔で迎える、初めての夜明け――。
朝陽を美しいと感じた。
昨晩はよく眠れなかったものの、明るい光を浴びると不思議と力がみなぎってきた。不安な囚われの身であるが、くよくよしていたら何も始まらない。前を向こう。――そう思えてくる。
何より、ファンルゥという力強い味方ができた。彼女に預けた手紙がどうなったかは、まだ分からない。だから、メイシアは今、自分にできることから進めていく……。
「ルイフォン……、私、頑張るから……」
愛しい名前に誓いを立てる。
気になるのは、リュイセンのことだ。彼について、一晩、落ち着いて考えた。
そして、ふっと気づいた。
リュイセンが大切な一族を、ルイフォンを裏切る理由なんて、ひとつしかない。
――ミンウェイのためだ。
遥か遠く離れた場所にいるルイフォンたちと同じように、メイシアもまた、リュイセンが〈蝿〉に従う原因は、ミンウェイにあるのではないかという考えに至った。
そして、彼女がルイフォンたちと違うのは、すぐそこに当人たち――リュイセンと〈蝿〉がいることだった。
昨日のリュイセンの様子だと、彼は固く口を閉ざしたまま、何も語ってくれないだろう。
だから、〈蝿〉に探りを入れる。
メイシアは気持ちを引き締め、心の中で密やかなる反撃の狼煙を上げた。
朝食が済むと、メイシアは世話係となったリュイセンに連れられ、〈蝿〉の研究室を訪れた。これから毎日、午前中を『ライシェン』と過ごすようにと、〈蝿〉が定めたためである。
午後は、展望塔で休んでいいらしい。〈蝿〉が『自分の研究室に他人がいるのは落ち着かない』と言って、『ライシェン』との対面の時間は半日でよいと決めたからだ。
リュイセンは終始無言のまま、扉のところで彼女と別れた。うなだれた大きな背中は、怪我をしているわけでもないのに痛々しく見えた。
それから数時間。
メイシアはただ黙って、まどろみに身を委ねる『ライシェン』を見つめ続ける……。
そろそろ昼どきというあたりで〈蝿〉が話しかけてきた。
「『ライシェン』を見ても、何も感じませんか?」
〈蝿〉の眉間には、神経質な皺が寄っていた。メイシアは彼を不用意に刺激しないよう、神妙な顔で胸に手を当てる。
「切なくて、心がざわつきます。そして、苦しくて逃げたいのに、ずっとそばに居たい――そう思います」
勿論、口から出任せだ。実際には、何も感じていない。
だが〈蝿〉は、それなりの手応えがあったと思ったらしい。満足げに微笑んだ。
「そうですか。では、今日はこのくらいにしましょう」
機嫌よく言った彼に、メイシアはすかさず切り出す。
「昨日、あなたがおっしゃった通りに、リュイセンに直接、何故あなたに従うのかを尋ねました」
「ほう。――それで?」
『ライシェン』とは関係ない話をするな、と怒鳴られるのではないかと、内心びくびくしていたのだが、意外なことに〈蝿〉は興味深げに口角を上げた。
リュイセンは決して口を割らないという自信があるのだろう。そして、そのことに絶望するメイシアを期待しているらしい。
彼女は、ごくりと唾を呑み込んだ。
ここで明らかな嘘を言ってはならない。ごく自然に――多くの事実の中に、ほんのひと筆の『鎌かけ』を混ぜた絵を描くのだ。
「リュイセンは、私と目を合わせることすらしてくれませんでした。何を話しかけても、ぼそぼそと『すまない』と言うだけで……」
「ほほう」
〈蝿〉の顔をが愉悦に歪む。
「――でも。『〈蝿〉に従うなんて、ミンウェイさんを裏切る行為だと思わなかったんですか!?』と、……少し、責めるように言ってしまったとき、『違う! 俺はミンウェイのために……』と言い掛けて、慌てて口を押さえたんです」
その瞬間、〈蝿〉は顔をしかめた。それから、半ば呆れたように溜め息を漏らす。
望ましくないことだが、リュイセンなら、そのくらいの失言はしかねない。――そう思っているのが読み取れた。
「リュイセンは、彼の意思であなたに従っているわけではなく、ミンウェイさんのために裏切り行為を働いたんですね」
「そうですよ」
〈蝿〉は肩をすくめ――『肯定した』。
――推測が当たった……!
メイシアの心臓が激しく高鳴る。
このまま、もう少し詳しく何かを聞き出せないか――〈蝿〉に従うことがミンウェイのためになるとは、どういうことなのか……と、彼女は必死に頭を巡らせる。
「随分と嬉しそうですね」
「えっ!? あっ……」
揶揄するような〈蝿〉の声に、メイシアは焦った。
「素直に喜んで構いませんよ? あなたにとっては嬉しいことでしょうから。よかったですね。リュイセンが、心から私に心服しているわけではなくて。すべては〈ベラドンナ〉のため――ああ、あなたには、ミンウェイ、と呼んだほうが分かりやすいでしょうか?」
どことなく小馬鹿にした口調で、呼び名まで訂正し、〈蝿〉は口の端を弓なりに上げた。そして、彼は低く喉を鳴らす。
「別に隠すほどのことでもありませんから、教えて差し上げますよ。――どうして、リュイセンが私に従っているのかを」
「――!?」
唐突な〈蝿〉の弁に、メイシアは黒曜石の瞳を瞬かせた。そんな彼女をねぶるように、彼は告げる。
「リュイセンと私が、〈ベラドンナ〉の『秘密』を共有する同志となったからですよ」
「ミンウェイさんの『秘密』を……共有……?」
答えを与えられたはずなのに、メイシアの頭はかえって混乱した。その顔は〈蝿〉の期待通りだったらしい。彼は上機嫌で嗤いかける。
「私には『鷹刀ヘイシャオ』の記憶があります。〈ベラドンナ〉を育てた人物の記憶です。――つまり、〈ベラドンナ〉本人以上に、彼女のことを知っているのですよ」
「……え?」
「彼女の知らない――彼女が『知りたくもない』ようなことをも――ね」
「あなたは、いったい何を……?」
メイシアの問いに、しかし、当然のことながら〈蝿〉は答えたりなどしなかった。その代わりに、『悪魔』の言葉を朗々と響かせる。
「〈ベラドンナ〉を愛するリュイセンは、あの『秘密』を知る私には、決して逆らえないのですよ」
そして、地下研究室は〈蝿〉の哄笑で満たされた――。
8.姫君からの使者-2

『斑目タオロンの見張りとして、奴の買い物に付き合うように』と命じられたとき、〈蝿〉の私兵のひとりであるその男は、自分の運の良さを喜んだ。
報酬に釣られて『国宝級の科学者』に雇われたら、怪しげな薬物を投与されて『逆らえば、死に至る』と脅された。生きた心地のしない生活の中で、たとえ一時でも、買い物などという至極、平穏な目的で、この閉ざされた庭園の外に出られるのは、実に僥倖といえた。
男は今まで、タオロンとは、ほとんど接触がなかった。馴れ合いを危惧した〈蝿〉が、わざわざそういう人選をしたのだ。だから、ほぼ初対面の相手とふたりきりで半日を過ごすわけだが、緊張するかといえば、そうでもなかった。
同僚から聞いた噂では、タオロンは、ひとことで言って要領の悪い馬鹿だ。見上げるような立派な体躯も、恐るるに足らず。故に、男は安心して、思い切り羽を伸ばそうと胸を弾ませていた。
「午後から繁華街だから、たまには外で飯を食って、それから買い物でいいか? 勿論、俺の奢りだ」
そう言うタオロンに、二つ返事で了承した。
庭園での食事は専属の料理人によるもので、〈蝿〉が美食家であるためなのか、私兵に提供するものとは思えないほどに豪勢である。しかし、味は良くとも、味気ないのだ。
「……おい、タオロン。外の飯屋といったら、普通、可愛い姉ちゃんが給仕するもんだろうが!」
ウェイトレスの尻のひとつも撫でてやろうと、楽しみにしていた男は、肩透かしを食らい、思わず悪態をついた。
「すまねぇ」
タオロンは申し訳なさそうに、バンダナで押さえた頭を掻く。
知り合いに紹介された店だと、散々迷った挙げ句に連れて行かれたその食堂では、賭けカードに興じていた小僧が、母親らしき女将に尻を叩かれて注文を取りに来たのだった。
その女将が、美人ならばまだ許せた。しかし、この女を娶ったのはどんな男だろう、顔を拝んでやりたい、と思わずにはいられないような貫禄の持ち主だった。
――と思ったら、小僧と瓜二つの、痩せぎすの男が厨房で鍋を振るっていた。なるほど、尻に敷かれているのかと、合点がいった。
ただし味は極上で、庭園での食事とはまた違う、下町の素朴な旨さに舌鼓を打った。それだけは満足だった。
大男と、やたらとあちこちに視線を走らせる、ギョロ目の小男のふたり組の客が店を出ていったあと、厨房にいた食堂の主人ことトンツァイは、そっと鍋を置き、カウンターの女房に「ちょっと、いいか」と声を掛けた。
あの大男は、斑目タオロンだ。
昼は食堂、夜は酒場となるこの店の主人――というのは、トンツァイの表の顔に過ぎない。彼の本業は、情報屋である。鷹刀一族や、情報屋〈猫〉とも懇意にしている彼は、当然の如くタオロンの顔を知っていた。
トンツァイは、タオロンがどのような状況にあるのかも、おおよそ把握していた。だから、ふたり組の客が入ってきたときから、それとなく観察していたのだ。
とんだ大物の登場だ。今すぐ部下を手配して、タオロンのあとを追わせよう。――トンツァイはそう考え、店を任せるために女房を呼んだのだ。
ただならぬ事件の予感に、情報屋の血がたぎる。しかし彼の興奮は、厨房に入ってきた女房の台詞によって、仰天に取って代わられた。
「あんた、大変だよ! さっきの客、勘定のときに、こっそり、あたしにこれを渡したんだよ」
「何!?」
奪い取るようにして受け取ったのは、小さく折りたたまれた紙。――手紙だった。
赤茶けた便箋に書かれた、流麗な文字を目で追い、トンツァイはごくりと唾を呑んだ。
昼食を済ませると、いよいよタオロンの買い物だった。
その品目が、娘にプレゼントするためのアクセサリーだと聞いて、見張りの男は目が点になった。しかも、玩具ではなくて、本物が欲しいというのだ。
妻を亡くし、父娘ふたりきりのタオロンが、幼い娘を溺愛しているのは知っていた。彼女が〈蝿〉の人質になっているのは、他人ごとなりに可哀想だなぁ、くらいには思っている。しかし何故、餓鬼へのご褒美が、光り物なのだ?
ともかく、今日の仕事は、タオロンの見張りであるので、男はあとについていくしかない。
タオロンは、このあたりの店には詳しくないようだった。困ったように、うろうろしたのちに、やっと天然石を加工してアクセサリーに仕立てている店を見つけた。
無愛想な大男が、明らかに女性用の商品を扱う店に入れば、当然のように店員がすり寄ってくる。顔を赤らめ狼狽するタオロンに、心の中で手を叩いて笑っていたら、男にも店員が声を掛けてきた。よく考えれば、傍目には、男も客に見えるのだった。
こりゃ敵わんと「俺は、店の外で待っているぜ」と言い残して退散した。
しばらくして店から出てきたタオロンは、贈り物用に包装された包みを『ふたつ』、手にしていた。
「ひとつに決められなくて、両方、買わされたのかよ?」
店員もやり手だな。いや、口下手なタオロンなら、案外、簡単に押し切れるかもしれねぇか。――などと思いながら、男は軽口を叩く。
しかし、そのあとのタオロンの返答に、男は腰を抜かしかけた。
「違う。ひとつはファンルゥに渡すものだが、もうひとつは馴染みの女に贈るためのものだ。――これから彼女に逢いに行く。長いこと通ってやれなかったから、機嫌を損ねているはずだ」
「はぁ!?」
驚愕のあまり、男の思考が停止した。
呆然と立ち尽くす男を置いたまま、タオロンは大股に歩を進める。今まで道に迷っていたのが嘘のように、一直線だ。
「ちょ、ちょっと待てよ、お前! じゃあ、何か? 娘へのプレゼントを買うというのは建て前で、女のところへ行くための口実だったのかよ!?」
「そうだ」
タオロンは足を止めることなく、端的に言ってのけた。気が逸っているのか、脇目も振らず。顔をにやけさせるどころか、一心不乱の猪突猛進である。
「お、おい……! それは、まずいだろ」
「お前が〈蝿〉に報告しなければいいだけだ」
「ふざけんな! なんで俺が、お前の逢い引きの片棒を担いでやらなきゃならねぇんだよ! 今すぐ、〈蝿〉の旦那にばらしてやる!」
タオロンがあの庭園に閉じ込められていたのと同じように、男だって、ご無沙汰なのだ。しかも外に出たところで、決まった女などいない。
そのとき、タオロンが急に立ち止まり、くるりと振り返った。
「な、なんだよ! 文句あんのか!」
タオロンの巨体で迫られれば、誰だって腰が引ける。思わずたじろいだものの、そんな羨ましい身勝手、許すまじ、と男は噛み付いた。
だがタオロンは、唐突に「頼む!」と頭を下げてきた。
「お前にも、いい思いをさせてやる。今の時間はまだ店は開いていないはずだが、俺の連れなら入れてくれるはずだ」
「え……、『いい思い』ってことは……」
ピンときた。タオロンの情婦は、娼婦なのだ。子持ちやもめのタオロンは、遊びに行った先の店の女と懇意になったのだ。
「支払いは当然、俺持ちだ。――悪い話じゃねぇだろう?」
普通なら、にやりと共犯者の笑みを浮かべるところを、タオロンは大真面目に持ちかける。間抜けな馬鹿っぽさが、如何にもタオロンだった。よほど、その女に逢いたいのだろう。
無論、男に否やはなかった。むしろ、大歓迎である。
「そういえば、俺は〈蝿〉の旦那に、お前の『買い物』に付き合うように頼まれていたんだった。その買い物が『女』だというなら、俺は当然、付き合うべきだってことだな」
鼻の下を伸ばしながら、男はうきうきと答える。
「恩に着る!」
満面の笑顔を見せたタオロンに、俺はなんていい奴なんだと、男は自分を称賛した。
そして、タオロンに案内され、蔦を這わせた瀟洒なアーチの前にたどり着いた。アンティーク調の館へと誘うように、煉瓦の敷石が足元から続いている。
高級娼館だ……。
男は、呆けたように口をぽかんと開けていた。
途中で貧民街に入ったときには肝を冷やした。ガラの悪い連中の値踏みするような視線は、タオロンのひと睨みで霧散したのだが、これは早まったかと後悔すらした。どんな店に連れて行かれるのかと、戦々恐々だった。
それが……である。
そういえば、噂に聞いたことがあった。貴族がお忍びで来るための遊興施設が、貧民街の近くに隠れるように立ち並んでいる、と。
「ここ……なのか?」
「ああ」
タオロンが深々と頷く。
よく考えれば、タオロンは斑目一族の総帥の血統だ。失脚して一族から追われているようだが、もとはそれなりの地位にあったのだろう。
今日の仕事は、斑目タオロンの買い物の付き合いだ。
男は、自分は最高に運が良いと思った。
目的の娼館を目の前にして、タオロンは深く息を吐いた。
すべて、藤咲メイシアの指示通りにやった。時々、ひやりとすることもあったが、大きな失敗はしていないはずだ……。
ファンルゥから、メイシアの手紙を受け取ったとき、タオロンは驚愕と歓喜に打ち震えた。そして、必ずや成し遂げてみせると誓いを立てた。
メイシアは、決して難しい演技を要求しなかった。それどころか、いつもの彼らしく朴訥であってほしいと綴っていた。
まさか、外出許可が下りるとは思わなかった。しかし、彼女の言う通りに話を進めたら、〈蝿〉は驚くほどあっさりと許してくれた。
指定された食堂に行くのには、だいぶ迷ってしまった。おかげで、昼食時の混雑は避けられたが、遅くなってしまった。
買い物は、急いで済ませた。それでも、ファンルゥへのご褒美には時間を掛けた。反面、架空の『馴染みの女』への贈り物は、店員に言われるままに、やたらと高価なものを買ってしまった気がするが、それは仕方ないだろう。
しかし、娼館への道は迷わなかった。何故なら、前に一度、来たからである。
とはいっても、中に入ったことがあるわけではない。藤咲メイシアを捕らえるよう、〈蝿〉に命じられたとき、彼女がここを訪れたのをつけていたのだ。その帰りにルイフォンたちと接触し、タオロンが発信機を預かったことによって、〈蝿〉の居場所が鷹刀一族の側に伝わったのだ。
娼館まで迷わずに来たことで、見張りの男は『馴染みの女』の存在をすっかり信じてくれたようだ。
この男が、メイシアを一緒につけていた面子でなくて本当に助かった。ここの娼館を知っていたら何か勘ぐられる心配があった。勿論、抜かりのないメイシアは、その場合の言い訳も用意してくれていたが、口達者でないタオロンには、うまく切り抜ける自信がなかった。
さて――。
もう、ひと息だ。
食堂の女将に渡した手紙によって、この娼館と鷹刀一族の屋敷に連絡がいったはずだ。あとは見張りの男を娼婦に任せ、タオロンは別の個室で、鷹刀から娼館に届けるように頼んだメイシアの携帯端末を『馴染みの女』から受け取ればよい。
――初めて入る店に、さも常連といった態度を取れるだろうか。
そんな不安を振り切り、タオロンは前を向く。
「行くぞ」
見張りの男に声を掛け、タオロンは煉瓦の敷石に足を踏み出した。
8.姫君からの使者-3

小洒落た木製の扉を開けると、そこは落ち着いたバーのようであった。
蔦の這う窓格子の隙間からは柔らかな陽射しが差し込み、穏やかな光が優しく店内を満たしている。奥のカウンターの棚には、繊細なフォルムを誇る、色とりどりの瓶が並べられ、磨き上げられたグラスが客の来訪を待ちわびていた。
そして、ゆったりとしたソファーの狭間で、箒を手にした少女がひとり――。
「タオロン様……!?」
ぱっちりとした愛らしい目をいっぱいに見開き、彼女はタオロンを凝視していた。内なる驚愕の度合いを示すかのように、高くポニーテールにしたくるくるの巻き毛が、大きく揺れている。
いきなり名前を呼んできた少女に、タオロンは戸惑った。
何か言葉を返さなければ、後ろにいる見張りの男に不審に思われる。――そう焦るのだが、喉が張り付いて声が出ない。
そんな調子のタオロンには構わず、少女は柔らかに微笑んだ。
「お久しぶりです」
さっと近くのソファーに箒を立て掛け、優雅に一礼する。可愛らしさの中に気品が加わり、ただの町娘とは違う空気を匂わせた。
軽やかに近づいてくる彼女に、タオロンは、ようやく、しどろもどろに「ああ」と答える。
この少女が『馴染みの女』役なのだろうか?
タオロンがぎこちなく笑いかけると、彼女は、彼の懐にぐぐっと遠慮なく入ってきた。か弱い女性を相手に拳を振るうことなどあり得ないが、武人の彼としては、この間合いは落ち着かない。
「タオロン様、ばつの悪そうなお顔ですよ?」
小柄な彼女が、背伸びをするようにしてタオロンの顔を覗き込むと、反射的に体が引けた。
しまった――!
『馴染みの女』なのだから、抱きしめなければいけなかったのでは!?
――だが、可憐な見た目に反し、少女には妙な迫力があった。武の者なら『闘気』とでも呼ぶべきそれを撒き散らす彼女を相手に、抱きしめるどころか、指一本、触れてはならない気がする……。
「ルイリンが泣いていました」
「……!?」
「他人の恋路に余計な口出しはいけませんが、さすがに親友としては、おとなしいあの子の代わりに、ひとことくらい申し上げたいわ。――今回はまた、随分とご無沙汰でしたね?」
少女が上目遣いに睨んでくる。可愛らしいのに、恐ろしい。
「……あ、ああ……、……すまん」
気づけば、勝手に口が謝っていた。
――と、同時に、これまでのタオロンのギクシャクとした態度は、このやりとりですっかり自然なものとなっていた。
つまり、この少女は『馴染みの女』ではなくて、その親友、という役回りなのだ。そして、『馴染みの女』の名前は『ルイリン』。
――『ルイリン』……?
タオロンの眉がぴくりと動く。そのとき、すかさず少女が口を開き、彼が言葉を発するのを封じた。
「ごめんなさい。言い過ぎました」
恥じらうように視線を下げ、頬を染める。先ほどまでの威圧感は、嘘のように消え去り、そうなると、親友思いの優しい少女にしか見えない。
背後から、見張りの男の狼狽を感じた。
タオロンの豪腕ならひとひねり、といったふうな華奢な少女に対し、巨躯を丸めてたじたじなのだから当然だろう。約束していた『いい思い』が取り消しになることを恐れているだけかもしれないが、少なくとも、目の前の少女が一芝居打っているとは、夢にも思うまい。
ともかく、何か会話を続けたほうがよいのだろう。
そんな思いが頭をよぎるが、無骨なタオロンの口から、気の利いた台詞が出てくるわけもない。表情の読みにくい浅黒い肌の下で困り顔になるタオロンに、少女はふわりと包み込むような笑顔を浮かべた。
「安心してください。ルイリンは、タオロン様が面倒なお仕事をなさっているのだと、ちゃんと理解していますよ。――勿論、私も」
少女のぱっちりとした大きな瞳が、かすかに細められた。
「!?」
刹那に発せられた肉食獣の煌めきは、決して気のせいではないだろう。武人の彼が、見逃すはずがない。
困惑するタオロンをよそに、少女は、彼の脇をすっとすり抜けた。その瞬間、タオロンと少女のふたりに当たっていたはずの見えないスポットライトは、タオロンを置き去りにして、少女を追いかけ始める。
堂々たる主演女優が如く、少女は、まっすぐに舞台を歩く。
舞台袖に追いやられたタオロンは、どういうことだ? と。巻毛のポニーテールを求めて、後ろを振り返った。
すると――。
そこには、丁寧にお辞儀をする少女と、いきなり傍観者から舞台に引き上げられて面食らっている、見張りの男の姿があった。
「はじめまして。スーリンと申します」
少女――スーリンが、男に向かって可愛らしく微笑む。
小柄な彼女が、わずかに首を傾けて男を見上げると、くるくるの髪が踊るように流れ、細い首筋が男の目を惹き寄せた。両手の指を軽く絡み合わせた仕草が、なで肩の嫋やかさをそれとなく強調する。
庇護欲を掻き立てるような愛らしさに、男の喉仏がごくりと動いた。『いい思い』の約束が頭を巡ったのだろう。男の視線が、あからさまな欲望の色でスーリンを舐める。
思わず身を乗り出しかけた男に、スーリンは申し訳なさそうに眉を曇らせた。
「タオロン様が、夜ではなく、昼間にいらした意味。おひとりではなく、お連れの方がいらっしゃる意味。――察しております」
「……あ?」
持って回った言い方に、勢い込んでいた男は戸惑う。要するに『娼館が時間外なのもお構いなしに来たのは今しか機会がないからで、同僚を連れて来たってことは、ふたりで結託して仕事中に抜けてきたってことでしょ?』と言っているのだが、あいにく男は、機知という言葉とは無縁だった。
それは、スーリンも承知の上。単に、本来なら場違いである男に対し、聡明な高級娼婦という『格』を印象づけるためだ。彼女は、誰にでも媚を売り、気安くしなだれかかるような安い店の女ではないのだと。
とはいえ、これでは埒が明かないので、彼女は噛み砕いて言を継ぐ。
「上役の方に知られたら、あなたもお叱りを受けてしまうお立場なのでしょう?」
「……は? あ、ああ……、……?」
スーリンの意図が読めず、男は曖昧な相槌を返す。
やがて男は、お高い女は自分などを相手にしたくないのだと思いあたり、不快げに鼻に皺を寄せた。やはり、〈蝿〉に報告してやろう、と。
そのとき――。
スーリンが、とろけるような笑みをこぼした。
「――なのに、黙って、タオロン様を見守ってくださるあなた様に、ルイリンの親友として感謝申し上げます」
「……!?」
まるで見惚れているかのような、うっとりとした眼差しでスーリンが男を見つめてきた。
そのへんの娼婦とは違う、器量も頭脳も上等な女が、自分に好意を持っている。そんな錯覚を起こすのに充分な熱量。男は一転して、胸と鼻の穴を期待に膨らませた。
スーリンは男に一歩、近寄った。
手を伸ばせば、すぐに届くような距離。
けれど、吐息を感じるには、あと一歩が必要な距離。
男の心を浮き立たせ、しかし、もどかしく物足りない。絶妙な位置だ。
「まぁ、なんだな。タオロンの奴が可哀想になってよ」
『いい思い』に釣られて、ほいほい乗ってきただけなのだが、男は、いつの間にかタオロンのためにひと肌脱いだ気になっていた。
「お優しいんですね」
花がほころぶように、スーリンが微笑む。
そして、顔を赤らめながら、彼女はもじもじと告げた。
「あの、タオロン様がルイリンと逢っている間、あなたは私と一緒に、別のお部屋で待っているのでは駄目ですか? ルイリンをタオロン様とふたりきりにしてあげたいの……」
今までと比べて、少しだけ砕けた口調になって、スーリンがねだる。もとより、そのつもりの男に否やはない。
「当たり前じゃねぇか。野暮なこと言うなよ」
猪突猛進の馬鹿の同僚のために、危険を犯して手助けをしたら、その男気に極上の女が惚れ込んできた。――スーリンが見せた幻に、男はいとも簡単に囚われた。
スーリンは、ごく自然に最後の一歩を詰める。
けれど、彼女からは男に触れない。恥ずかしげに男を見つめ、男が抱き寄せてくれるのを待ち望んでいるのだという、大いなる幻想の夢を紡ぐ。
迷わず、肩に手を回してきた男に、スーリンは内心でほくそ笑んだ。この男は完全に落とした。タオロンが外で『ルイリン』と逢っていたことは、口が裂けても言わないであろう――と。
一方、このスーリンの独壇場を固唾を呑んで見守っていたタオロンは、だらだらと脂汗を流していた。
……怖い。
剛の者の彼が、手足を震わせていた。
世の中には、決して逆らってはいけない相手がいるのだと、思わずにはいられなかった……。
「ルイリンを呼んでくるわね」
すっかり親しげな調子になったスーリンが、奥の階段を登っていく。
その後ろ姿を見送り、タオロンがちらりと横を見やれば、スーリンの恐ろしさに気づいていない見張りの男が、だらしのない顔で鼻の下を伸ばしていた。
ほどなくして、階上から人の動く気配を感じる。
「内緒、内緒! とにかく、来て!」
スーリンの弾んだ声が響く。タオロンが来ていることは秘密にしている、という設定なのだろう。
タオロンは、はっと顔色を変えた。
『馴染みの女』は、どこかの部屋で待っていて、タオロンがそこに行くのではないのか?
見張りの男に『馴染みの女』の姿を見せることで、より信用を得ようとしているのは分かる。しかし、『馴染みの女』は――。
そのとき、階段にふたつの影が現れた。
先に立つのは、スーリン。うきうきと軽やかな足取りで、段を踏み鳴らす。
そして、もうひとりは――。
長いスカートの裾を気にしながら、しずしずと降りてきた人物を目にしたとき、タオロンは息を呑んだ。
はっと目を引くような、端正な顔の美少女。
目元がややきつく感じられるが、それも彼女の魅力のうちだ。緩やかに波打つ長い黒髪は後ろに垂らし、そのうちのひと房を青い飾り紐で結わえている。
ただ、小柄なスーリンと比べて、すらりと背が高く、それを気にしているかのような自信なさげな猫背で……。
「ル、ルイフォ……」
言い掛けて、タオロンは慌てて口を閉ざした。そして、もぞもぞと「ルイリン……」と言い直す。
隣では、見張りの男がぴゅうと尻上がりの口笛を吹いた。タオロンの相手が、想像以上の美少女だったからだろう。
「ルイリン! タオロン様が来てくださったのよ!」
あくまでも、親友思いの少女を演じるスーリン。その満面の笑顔は、タオロンには悪魔の微笑にしか見えない。
ルイリン――こと、ルイフォンは、タオロンと目があった瞬間にばっと顔を赤く染め、くるりと背中を向けた。飾り紐が勢いになびき、その中心に留められていた金の鈴がきらりと光る。
そのまま彼女――彼は、スカートを翻し、今、降りてきた階段を再び駆け上がった。
「あっ、ルイリン! ちょ、ちょっと、何、照れているのよ!」
焦ったようにスーリンが叫ぶ。
「タオロン様、追いかけて!」
あっけにとられていたタオロンは、スーリンのひとことに我に返った。追い立てられるように促され、慌ててルイリン――ルイフォンを追いかける。
「しっかり可愛がってやれよ!」
背後から、見張りの男がとんでもない激励の言葉をくれた……。
8.姫君からの使者-4

時は、ほんの少しだけ遡る――。
「タオロンが、シャオリエの店に!?」
その報告を聞いたとき、ルイフォンは耳を疑った。
いつもは細く眇められている猫の目が、ぱっと見開かれる。研ぎ澄まされたようなテノールが、部屋の空気を鋭く斬り裂いた。
鷹刀一族の屋敷に、繁華街の情報屋トンツァイからの連絡が入ったのは、メイシアがさらわれてから三日目。〈蝿〉のいる庭園に、食料を積んだ車が来るという日を翌日に控えたものの、それをどう有効活用するか、いまだ名案が浮かばぬままでいるときのことであった。
腹の傷の養生のため、ルイフォンは自室のベッドに横になり、そこにエルファンが足を運び、ふたりで額を突き合わせている。そんなところへの、まさかの朗報だった。
「そうなのよ! メイシアの指示ですって!」
報を受け、ルイフォンの部屋に駆け込んできたミンウェイが息を弾ませる。
「それで、彼女の携帯端末をシャオリエ様の店まで持ってきてほしいそうよ。――けど何よりも、できるだけ早く、ルイフォンに『私は無事です』と伝えてくださいって、メイシアが……」
「メイシアが……!」
ルイフォンは、大きく息を呑んだ。
胸にあふれてくるのは、間違いなく歓喜だ。
なのに呼吸が乱れ、息苦しい。熱は下がったはずなのに、全身の感覚が鈍く、現実味がない。
「メイシア……」
目頭が――熱い……。
「……無事……だったんだな……! ――――、――――っ!」
ルイフォンは雄叫びを上げる。
彼女の無事を信じていた。
だが、それでも――……一抹の不安と戦っていた。
「メイシア……、お前って奴は……!」
それが、どんな魔法を使ったのか、彼女はタオロンという使者を立ててきた。
自分は無事だと、伝えてきた。
「最高じゃねぇか……!」
彼の最愛の姫は、黙って騎士の助けを待っているような、凡庸な姫君ではなかった。
自ら動くことのできる、聡明な戦乙女だ。
情報屋トンツァイの食堂に手紙を託すのは、多少、頭の回る者なら思いつく手段だろう。しかし、シャオリエの娼館を頼るという、盲点をついた奇策。
貴族の箱入り娘だった彼女らしからぬ作戦であるが、おそらく、仲良くなった少女娼婦スーリンから聞いていたのだろう。娼館というのは、その秘匿性から陰謀の隠れ蓑として使われることがあるのだと。ルイフォンが『あり得ない』と言い切ったスーリンとの絆を、しっかりと結んだからこその策だ。
ルイフォンの喉の奥から、好戦的な笑いがこみ上げてくる。――だがそれは、本人は気づいていないだけの、くしゃくしゃの泣き笑いの顔だった。
「それでこそ、俺のメイシアだ!」
彼は叫ぶ。
誇らしかった。自慢のパートナーだと思った。
「行ってくる!」
ルイフォンは、勢いよくベッドから起き上がる。その瞬間、ぴりっと走る痛みに顔をしかめた。
「ルイフォン! まだ、動き回るのは早いわ」
ミンウェイが血相を変えた。しかし、ルイフォンは口角を上げ、猫の目を光らせる。
「ミンウェイ、約束だったろ? 今は動くべきときで、だから協力してくれるって。――俺を動けるようにしてくれ。頼んだ」
しかし、ミンウェイは首を振った。
「そりゃ私も、多少の無茶は構わない、と言ったわよ。でも今回は、その時じゃないわ」
「違う! 今が、その時だ!」
「ルイフォン、落ち着いて。どうやらメイシアは、あなたが怪我をしたことをリュイセンから聞いたみたい。それで、『端末を届けるのは、ルイフォンでなくて構いません。ルイフォンは、くれぐれも無理しないでください。どうか、お大事に』と、トンツァイが受け取った手紙に書かれていたそうよ」
「……!」
メイシアはルイフォンの性格を理解していて、だから、先回りして気遣ってくれていた。
――だが。
「いや、俺が行くべきだ」
「ルイフォン!?」
「タオロンは、メイシアが送り出してくれた使者だ。俺が迎えなくてどうする?」
ルイフォンはベッドを飛び降り、戸棚に向かう。そして、大切に保管していたメイシアの携帯端末を取り出し、握りしめた。あの日、厨房に残されていたものだ。
怪我をした初日に〈ベロ〉に会いに行って以来、ルイフォンは、ほとんど部屋から出ていない。腹の傷は痛いし、足腰が弱っているのも感じる。
それでも、行くべきだった。
「ミンウェイ、ルイフォンに鎮痛剤を処方してやってくれ」
不意に、それまで沈黙を保っていたエルファンが低い声で命じる。
「エルファン!」
「エルファン伯父様!?」
ルイフォンとミンウェイは、意味合いの異なる驚きによって、不協和音の二重奏を響かせた。
「急がないと、斑目タオロンがシャオリエ様の店に着いてしまうぞ」
エルファンは氷の微笑を浮かべる。その眼差しは、温かくルイフォンを後押ししていた。
シャオリエの店に急行すると、女主人のシャオリエは勿論、スーリンと、それからトンツァイまでもが待ち構えていた。
トンツァイは、彼の食堂に来たタオロンと見張りの男の様子をざっと話し、それから預かっていたメイシアからの手紙をルイフォンに渡す。それには、庭園での出来ごとが書かれていた。
「そうか……、ファンルゥが手を貸してくれたのか……」
くりっとした丸い目いっぱいに好奇心を載せた、行動力のある小さな女の子。父親のタオロンにそっくりな、まっすぐな心の持ち主。彼女の原動力は優しさだ。
ファンルゥが意図したことではないのだが、彼女の描いた絵が巡り巡って、ハオリュウの怒りを鎮め、リュイセンの弁護をするまでに至った。
『姉様は、リュイセンさんとふたりで、あの庭園から逃げ出す方法を考えているはずです』
『……それが、僕の姉様です』
その言葉に、ルイフォンの心は揺さぶられた。リュイセンを切り捨てる決意をしていた彼の目に、皆で笑い合う未来を見せてくれた。
「凄えな。味方だらけじゃねぇか」
ルイフォンの胸が熱くなる。
――と、そのとき。
背筋に、ぞくりと悪寒が走った。
身の危険を感じながら、恐る恐る振り向くと、そこには女物の服と化粧道具を持って、にやりと嗤うシャオリエとスーリンの姿があった。
「斑目タオロンは、『馴染みの女』に逢いに来るのよねぇ」
アーモンド型の瞳をすうっと細めながら、シャオリエがにじり寄る。
「お、おい……、待て……!」
意味するところを理解して、ルイフォンの顔がさぁっと青ざめた。
「俺は部屋で待っていて、スーリンがタオロンを連れてくればいいだけだろ!」
「あらぁ、それじゃあ、私が面白くないでしょう? 私は、この店を密談の場として提供してあげるのよ? お前は、誠意を見せるべきだと思うわぁ」
シャオリエは、さも当然とばかりに、ふふんと笑う。
「ばれたらどうするんだよ!?」
「ルイフォンなら、大丈夫よ!」
すかさずスーリンが言い放ち、隙を衝いて、ルイフォンの髪を留めている青い飾り紐の先を引いた。一本に編まれていた髪は解き放たれ、もとの癖毛と相まって、優雅に波打つ黒髪が広がる。
「や、やめろ……! トンツァイ、助けてくれ!」
ルイフォンは、憐れみの目で彼を見守っていた情報屋に救いを求めたが、トンツァイは神妙な顔で告げた。
「ルイフォン、この界隈でシャオリエさんに逆らったら、生きていけねぇんだよ」
そう言って、……腹を抱えて笑い出した。
数分後――。
出来上がった『ルイリン』を目にした瞬間、トンツァイは腰を抜かした。
「ルイフォン、お前……。やっぱり、鷹刀の血統だったんだなぁ……」
やっとそれだけ呟き、ただただ呆然とルイフォンを見つめる。
シャオリエもまた、自分の『作品』に大変、満足したようで、片手を頬に当て、わざとらしいくらいに体をくねらせて「あらぁ」と、わけの分からない感嘆の声を上げた。
「やっぱり、私の若いころにそっくりだわぁ」
「そんなわけあるか!」
反射的にルイフォンが叫ぶと、彼女は不気味な嗤いを見せたのちに、徐々に不思議な笑みを浮かべる。
「……?」
ルイフォンは疑問に思い……、それから、はっと気づく。
シャオリエの若いころは、『パイシュエ』なのだ。すなわち、もと鷹刀一族であり、父イーレオを『育ててくれた女』だ。
〈ベロ〉のところで『パイシュエ』の名前を知ったあと、ルイフォンは彼女の素性を調べた。
――ルイフォンが、若いころの『パイシュエ』と似ているのは当然といえた。立派に血が繋がっているのだから……。
なんともいえない感情を抱いていると、不意にスーリンに呼ばれた。
「ルイフォン! こっち向いて!」
ルイフォンの思考は、完全に他所に行っていた。だから、スーリンの黄色い声に、つい無警戒に従ってしまった。
しまった、と思ったときには、スーリンの携帯端末が電子的なシャッター音を鳴らしていた。
――そして……。
「しっかり可愛がってやれよ!」
背後から、タオロンの見張りの男が囃し立てる声が聞こえた。
――ふざけんなっ!
振り返って、ど突き倒したい気持ちを必死に抑え、ルイフォンは階段を駆け上る。
さすがのシャオリエも、女装姿での長居は危険だと認めてくれた。『ルイリン』は内気な少女という設定にするから、タオロンの姿を見たらすぐに走り去っていい、ということになった。
当然だ! 声でも出したら、一発で男だとばれる。
残念ながら、ルイフォンの声質は、生粋の鷹刀一族の男たちのような低く渋いものではないが、間違っても女の声には聞こえないはずだ。
タオロンは『ルイフォン』と言い掛けて、慌てて『ルイリン』と言い直した。本当は、さぞかし度肝を抜かれているのであろうに、律儀な奴である。そこは尊敬に値する。
だがしかし!
――わざわざ、訂正しなくていい! もう、勘弁してくれ!
ルイフォンは心で叫びながら、懸命に段を上がった。
足にまとわりついてくるスカートをたくし上げるわけにもいかず、それどころか、高級娼館にいる娘にふさわしく、足音も立てずに小股で上品に逃げなければならないというのは、大変な苦行であった。
背中にタオロンの気配を感じながら、なんとか階段を上りきり、ルイフォンは、あらかじめ決めてあった部屋の扉を開ける。そして、ちらりと後ろを振り返り、目配せでタオロンに『入れ』と合図した。
ふたり揃って部屋に入り、すかさず鍵を掛ける。防音は完備されているので、これでひとまず安心だ。全速力で走ったわけでもないのに、どっと疲れが出た。
「ルイフォン……、だよな?」
タオロンが遠慮がちに尋ねてきた。
「ああ。変なもんを見せて悪かったな。――この店を利用させてもらうのと交換条件に、ちょっと、な……」
手の甲で口紅を拭いながら、できるだけ平静を保ってルイフォンは答える。実は……、あまりにも違和感のない自分の女装姿に、それなりにショックを受けていたのだ。
「あ、いや、ちっとも変じゃねぇ。見張りの奴も、まったく気づいていなかった。大丈夫だ、お前は綺麗だ」
「…………タオロン」
ルイフォンの猫の目がすぅっと細くなり、彼の喉から発することのできる最も低い音程で、羨ましいほどに男らしい体躯の巨漢の名を呼ぶ。
「女装を褒められても、俺はちっとも嬉しくねぇんだよ!」
八つ当たりだと思いながら、ルイフォンは吠えた。
「す、すまん! ……ほら、もしも俺が女の格好をしたら、恐ろしいことになるはずだ。それに比べて、お前は凄い、と……」
「フォローになってねぇよ……」
溜め息混じりにぼやくルイフォンに、タオロンが再び「すまん」を重ねる。
まるで、数年来の友人と話してるかのような軽口が、互いに自然に出てきていた。
――タオロンとは敵同士だった。
今でも、表向きは敵であるはずだ。
だが、ずっと仲間だった。初めて会ったときから、いずれそうなる予感がしていた。
「タオロン」
いつもの声色に戻り、改めて無骨な大男の顔を見る。
よく日に焼けた浅黒い肌に、太い眉。意外に可愛らしい小さな目が、彼の人の良さをよく示している。だが、娘のファンルゥのためになら、心を傷だらけにしながらも、どんな冷酷な命令もこなす男だ。
――でも、もう、こいつに意に沿わぬ行為はさせない……。
「俺の手を取ってくれるか?」
ルイフォンは、右手を差し出す。
メイシアの使者として来てくれた彼に対し、今更かもしれない。けれど、最後に会ったときの――〈蝿〉の前で『俺たちの手を取れ』と言ったときのやり直しだ。
「……いいのか?」
タオロンの声は、かすれていた。図体に見合わぬ気弱な仕草で、上げかけた手をためらいに揺らす。
「当たり前だろ」
「――ありがとな……。本当に、ありがとなぁ……!」
固く分厚い手が、ルイフォンの手に喰らいつくかのように握りしめてきた。見た目通りの怪力に一瞬、顔をしかめるが、そこは耐える。
何しろ、ようやく――なのだ。
やっと、タオロンと手を取り合うことができたのだ……。
「こっちこそ、ありがとな。メイシアが無事だと分かって、本当にほっとした」
「ああ、いや、それはファンルゥが……」
そこまで言い掛けて、タオロンは急に顔を引き締めた。そして、正面からルイフォンを見据える。
「藤咲メイシアは、まだ助かったわけじゃねぇ。お前のところに帰って初めて、無事と言えるんだ」
思わぬ強い口調にルイフォンは戸惑う。確かにタオロンの言う通りなのだが、何か含みがありそうだった。
「タオロン、とりあえず座って話そうぜ」
ルイフォンはタオロンを椅子へと促し、自らも向かいに座る。
その際、スカートの足を大きく開いて腰掛けたら、タオロンが残念なものを見る目を向けてきた。――が、ルイフォンの知ったことではない。
きっぱり無視したつもりだったが、どうやら目つきが剣呑になっていたらしい。タオロンが「すまん」と体を小さくして謝ってきた。
「ルイフォン。藤咲メイシアは、俺に遠慮している」
意思の強そうな眉をぐっと寄せ、タオロンは、そう切り出してきた。
「彼女が、俺に頼んだことは、この店で携帯端末を受け取り、ファンルゥに届けさせることだけだ。それすらも、ファンルゥに危険なことを頼んで申し訳ないと謝っていた」
ファンルゥの腕輪の仕掛けが真っ赤な嘘だったことは、トンツァイを介して受け取った手紙から、ルイフォンも知った。してやられたと思った。
だが、メイシアが心配している通り、いくら毒針が嘘でも、脱走が見つかれば、ファンルゥはただではすまないだろう。メイシアの性格からして、遠慮がちになるのは当然だ。
「俺だって、ファンルゥに無茶させて悪いなと思うよ」
「違う。そういう意味じゃねぇ。――頭のいい藤咲メイシアなら、気づいていたはずなんだ」
「え?」
猪突猛進のタオロンらしくない、婉曲な言い回しだった。ルイフォンは、困惑に瞳を瞬かせる。
「藤咲メイシアは、すぐにも、お前のもとに帰りたいはずだ。だったら、手っ取り早く、俺にこう頼めばよかったんだ」
タオロンはそこで言葉を切り、今までの親しみやすい、気の優しい大男の顔を捨てた。そして、斑目一族総帥の血を受け継ぐ、ぞくりとする凶賊の凄みをまとい、告げる。
「〈蝿〉を殺せ――って、な」
ルイフォンは息を呑んだ。
「――そうか……」
ファンルゥの腕輪が、ただの腕輪であるのなら、タオロンには〈蝿〉に従う義理はない。堂々と、裏切って構わないのだ。しかも、部下である彼ならば、〈蝿〉に疑われることなく、簡単に懐に入ることができる――。
押し黙ったルイフォンに、タオロンは何か勘違いをしたらしい。「あっ」と叫び、焦ったように続けた。
「すまん。お前らは〈蝿〉を捕まえて、情報を吐かせたいんだったな。殺しちまったら困るわけだ。……ああ、でもそれなら、『殺せ』じゃなくて、『捕まえろ』と言ってくれれば、俺はそうするし……」
やはり、どうにも腑に落ちないらしく、タオロンは、しきりに首をかしげる。
ルイフォンもまた、メイシアの真意を測りかねていた。
勇猛な武人であるタオロンが味方になってくれたのだ。ならば、彼には武力を頼るのが自然だろう。
だが、メイシアは、タオロンを携帯端末を手に入れるための使者とした。無骨で不器用なタオロンに、〈蝿〉や見張りの男に対して、嘘と演技を願った。
果たして、それは最善手だっただろうか……?
「……メイシアは、何を差し置いても、まずは俺との連絡手段が欲しかったんだ……」
ぽつりと。独り言のように、ルイフォンは呟いた。ひとこと漏らせば、朧気ながら彼女の意図が読めてくる。
「手紙じゃ駄目なんだ……。あいつは、俺に何か相談したがっている……」
「そうなのか」
恋人であるルイフォンの弁ならと、タオロンは納得したらしい。身を乗り出して、言を継ぐ。
「じゃあ、とりあえず今日は、指示通りに携帯端末を預かっていくだけにするが、必要なときには、いつでも言ってくれ。俺は、なんだってやってやる」
「すまない。ありがとう」
感謝を述べると、タオロンは言いにくそうにバンダナの頭を掻いた。
「いや、俺には下心がある。……お前らに顔向けできねぇことをしたくせに厚かましいと思うが、俺とファンルゥが身を寄せる先への口利きを、どうか頼む!」
「ああ、レイウェンのところか。――何、言ってんだよ。向こうは待ちかねているくらいだ。シャンリーが、お前のことを随分、心配していたぞ」
ルイフォンが笑い飛ばすように言うと、タオロンは心底、ほっとしたかのように大きく息をついた。
それから、ルイフォンは真顔になって切り出す。
「タオロン――、今後のために、こちらの事情を知っていてほしい。かなり複雑な話になるが、聞いてほしい……」
ルイフォンは、〈蝿〉のこと、『デヴァイン・シンフォニア計画』のこと……これまでのことをタオロンに語った。
タオロンは、時々、眉をひそめながら、それでも懸命に聞いてくれた――。
「ルイフォン。お前は、メイシアとリュイセンを〈蝿〉に囚われて、心が休まらないと思う。だが、俺が必ず、あいつらを守る。遠慮なんて要らない。俺に任せろ」
太い腕を胸に当て、タオロンが誓う。
「ありがとう、タオロン。感謝する」
「よせよ、そんな堅苦しく……」
照れくさそうなタオロンに、ルイフォンは言葉を重ねる。
「言わせてくれよ。俺は、お前に直接、礼を言うためにこの店に来たんだからさ。――本当にありがとな。それから、頼んだ……!」
――時間も尽きてきた。
ルイフォンはメイシアの携帯端末をタオロンに託し、また彼ら同士も連絡先の交換をする。
最後にタオロンは、思い出したように綺麗に包装された包みを出してきた。『馴染みの女』のために買った、高価なアクセサリーである。
「これを、あのスーリンという女性に渡してくれ」
タオロンが持っていても仕方がない。だから、世話になったスーリンに贈るのが適当だろうというわけだ。
それは、もっともなことであったので、ルイフォンは、なんの気なしに「分かった」と預かった。タオロンが内心で、やたら値の張るものを買う羽目になったのは、天の配剤というやつが『あの』スーリンに似合うものを用意させたからに違いないと、妙に納得していたことなど、ルイフォンには知る由もなかった。
9.遥かな傍らで響く声

待ちかねていた着信音が鳴り響いたのは、蒼天が薄闇のヴェールをまとい、密やかな時間にふさわしい装いを整え始めたころのことだった。
『ルイフォン……?』
透き通った響きが、彼の鼓膜を震わせる。
その振動は、彼の心に、体に、全身に伝わっていく。
鈴を振るような、心地の良い音色。わずかな不安と緊張が語尾をかすらせ、それが逆に、彼女の温かな吐息をじかに受けているような錯覚を起こさせる。
「メイシア……」
携帯端末を持っていないほうの手が、無意識に彼女を抱き寄せようとした。しかし、遥かな展望塔に囚われている彼女に、彼の手は届かない。
切なさに心臓が痛みを訴えたとき、彼の耳が彼女のかすかな嗚咽を捕らえた。
彼を心配させまいと、押し殺したような息遣いだが、それでも彼には彼女の泣き顔が見えた。心細さと安堵とが、ない混ぜになって、涙という形で感情があふれ出したのだろう。
――昨日までは感じることのできなかった彼女の気配が、すぐ耳元にある。
ルイフォンの心臓の痛みが、ふっと和らいだ。
いまだ、彼女に触れることは叶わない。けれど、間違いなく、彼女に一歩、近づいたのだ。何故なら、彼女に言葉を伝えることができるのだから。
彼は、もう彼女が泣かなくてすむように『大丈夫だ。安心しろ』と言い掛け……、飲み込んだ。
「メイシア、ありがとう」
『……え?』
「お前の行動で、こうして連絡を取れるようになった。お前の声を聞くことができるようになった。――ありがとう。嬉しい。……お前は凄い奴だ。俺は、お前に惚れ直した!」
遥かな彼女に笑いかける。きっと彼女の瞳には、彼の抜けるような青空の笑顔が映っている。
『ルイフォン……!』
想いの詰まった、ひとことが、彼の耳に飛び込んできた。そして、メイシアは声を押さえることを忘れ、堰を切ったように泣き出した。
泣いていい。――彼女は今まで、ひとりで戦っていたのだから。
思う存分、泣かせてやりたい。
遠く離れた彼女には、胸を貸すこともできなければ、黒絹の髪をくしゃりと撫でることもできない。けれど、心で包み込むことならできるから……。
初めの電話は、ほとんど会話のないままに終わった。
無事な姿をこの目で確認したくて、途中で映像付きのビデオ通話に切り替えたら、音質が著しく落ちて満足に声が通らなくなった――という事情もある。だが、そうでなくても、黙って互いの顔を見つめ合っていたことだろう。
それで充分だった。
一度、電話を切ったのは、メイシアの食事の時間になったからだ。世話係となったリュイセンが部屋に来るらしい。
メイシアが、携帯端末という連絡手段を手に入れたことは、リュイセンには、まだ秘密だ。〈蝿〉の束縛を解くまでは、兄貴分は『敵』だからだ。
そして、無数の星々によって、紺碧の空が埋め尽くされたころ、再び、ルイフォンの端末が鳴った。
『ルイフォン、さっきは泣いてばかりで、ごめんなさい』
気恥ずかしそうな口調で、ほんの少しだけ、おどおどと。会話を優先するために、今度は音声のみの通話にしたのだが、彼女が顔を真っ赤にしている様子が目に見えるようだった。
「謝ることはないだろ。今まで辛かったよな。本当に、お前はよく頑張ったと思う」
『ありがとう。ルイフォンの声を聞いたから、もう、大丈夫。――それより、これからのことを考えないと』
先ほどまでとは違う、凛とした声がルイフォンの耳に響いた。
彼女自身の言う通り、もう大丈夫だろう。ならばと、ルイフォンも気を引き締める。
「メイシア……、どうしてタオロンに武力を頼らなかったんだ?」
『え?』
「タオロンは嘘が下手だ。けど、強い。ならば、危険を冒して携帯端末を取りに行ってもらうよりも、『〈蝿〉を捕まえて欲しい』と頼むほうが向いていたはずだ。――なのにそうしなかったのには理由があるんだろ?」
メイシアの吐息が揺れた。ルイフォンは、彼女が顔色を変えたのを感じる。
「〈蝿〉は、タオロンが俺たちの側に付いたことに気づいていない。完全に油断しているはずだ。だから、奴に頼めば簡単に片がつくだろう」
『……』
「『遠慮なんて要らない。俺に任せろ』と、タオロンは言ってくれた。奴とは連絡先を交わしたから、今すぐにでも俺から頼むことができる」
『――っ』
鋭く息を呑む気配――。
やはり、何かがあるのだ。彼女が携帯端末を求めた意味が――すなわち、ルイフォンに相談したいことが。
しかし、何があるというのだろう?
単刀直入に尋ねようとした瞬間、『ルイフォン……』と、か細く頼りなげな声が響いた。
「どうした?」
『〈蝿〉を『捕まえる』のと、……『殺す』のでは、違う……よ、ね……?」
「え?」
唐突すぎる発言に、わけが分からずルイフォンは戸惑う。
「えっと……? とりあえず〈蝿〉は『捕まえる』けど、奴の知っている情報を洗いざらい吐かせたあとは、『殺す』だ。何故なら、奴のしたことは許されないし、死者を生き返らせた存在であることも認められな……」
『ルイフォン!』
彼の言葉の途中で、メイシアが遮った。彼女らしくない行為に困惑している間にも、彼女は続ける。
『タオロンさんにとって、不意を衝いて〈蝿〉を『殺す』のは難しくないと思う。――でも、『捕まえた』あと、ルイフォンが使うような動きを封じる薬物もない状態で、狡猾な〈蝿〉を鷹刀の屋敷にまで連れて行くのは、『殺す』よりもずっと危険なことだと思う……』
「あ、ああ、そうかもしれないけど……。でも、〈蝿〉からは情報を……」
口を挟んだルイフォンに、またもやメイシアが言葉をかぶせた。
『もし――! 『捕まえる』必要がなくて、『殺す』のでよいのなら……、そのほうが安全で確実……よ、ね……?』
「……メイシア?」
彼女の様子がおかしい。
いったい、どうしたというのだろう。
胸騒ぎに、ルイフォンの鼓動が早まる。
『ルイフォン……、答えて……。お願い……』
すがるような涙声だった。
質問をしておきながら、メイシアは正解を知っている。ただ、ルイフォンの肯定がほしいだけだ。
当惑しつつも、ともかく彼は正直に答えた。
「ああ。『捕まえる』よりも『殺す』ほうが確実だ。――特に、〈蝿〉ならな」
〈蝿〉は、決して武力的に強いわけではない。なのに、あと少しのところまで追い詰めながらも失敗した。
言葉巧みに人を惑わし、気を抜けば、あっという間に翻弄されてしまう。たとえ捕まえても、すぐに足元をすくわれ、逃げられてしまうような、そういう敵だ。
『……っ』
メイシアの吐息が聞こえた。
それから突然、ぴんと張り詰めたような彼女の声が、ルイフォンの耳朶を打つ。
『ならば、タオロンさんにお願いすべきことは『殺す』なの。――確実のために。タオロンさんの安全のために。万が一にも、ファンルゥちゃんを悲しませないために……』
「どういうことだ……?」
ルイフォンは、猫の目を大きく見開く。
『……気づいちゃったの。〈蝿〉はもう、情報源としての価値がなくなってしまったんだ、ってことに……』
「情報源として、価値が……ない?」
不可思議な彼女の言葉を、彼は、おうむ返しに唱える。
『危険を冒してまで〈蝿〉を『捕まえる』意味がないのなら、鷹刀が一族の意志として決定した『死』を、彼に与えるべきなの……』
「待てよ。奴からは『デヴァイン・シンフォニア計画』のことを……」
『ルイフォン……、『デヴァイン・シンフォニア計画』のことなら、私がすべて知っている。……〈蝿〉の知らない、細部までも――』
それは透明すぎて、色を失ったことに気づかぬような声だった。
「……どういう意味だ?」
『私は……セレイエさんの記憶を持っているの。――『デヴァイン・シンフォニア計画』を作った、セレイエさんの記憶を……』
ルイフォンの耳に、厳かな響きが木霊した。
心臓が跳ね上がった。不吉な感触が彼を襲う。
携帯端末を握る手の感覚が薄れていき、自分が今、どこにいるのかを見失いそうになる。
……メイシアからの手紙を、シャオリエの店で受け取った。
そこに、ちゃんと書いてあった。
『セレイエさんの記憶を受け取りました』――と。
セレイエは記憶を書き込んだだけで、メイシアが乗っ取られることはないのだと知り、ルイフォンは安堵した。〈ベロ〉の言った通りだったと思った。
安心して、それでセレイエの記憶について考察するのは後回しと決めた。それよりもメイシアと、そしてリュイセンを取り戻す算段を詰めていくべきだと頭を切り替えた。
セレイエの記憶が、何をもたらすのかを深く考えもせずに……。
『ルイフォン……』
かすれたメイシアの声が、彼を現実に引き戻す。
『〈蝿〉はもう……必要……ないの……』
儚く、脆い。今にも消え入りそうな呟き。ぽつりと涙がこぼれるように、残酷なひとことが落とされる。
あっけないほどに、あっさりと言い渡された、〈蝿〉への『死』の宣告――。
『でも、私……! タオロンさんに『〈蝿〉を殺して』なんて、頼めなかった! そうするべきなのに、できなかった! 取り返しのつかない、戻ることのできない決断が怖かった……!』
急に声を荒らげ、しゃくりあげるようにメイシアが叫ぶ。
『ルイフォンが言った通り、〈蝿〉は、タオロンさんのことを忠実な部下だと信じている。――用心深い〈蝿〉の、こんな懐深くにまで入り込める好機なんて、もう二度と訪れないと思う。だから今! ここで! 決着をつけるべきなの……! 一刻も早くお願いするべき。それができるのは私しかいない。なのに……、なのに、私はっ……!』
「メイシア!」
脅える彼女の姿が見えた。
華奢な体を包み込んでやりたくて、ルイフォンは思わず虚空を掻き抱く。しかし、彼女の慟哭は止まらない。
『初めは本当に、ただルイフォンの声を聞きたい、って気持ちだけで、携帯端末があればと思ったの。ルイフォンと連絡を取れれば、リュイセンのことを相談できるし、庭園の中と外で連携が取れれば、道が開けるかも、って』
メイシアは、そこまで一気にまくし立て、『――でも!』と、絹を裂くような声を上げる。
『タオロンさんに手紙を書いている途中で、……気づいたの! ファンルゥちゃんの腕輪の毒針が嘘で、タオロンさんが〈蝿〉に歯向かえるのなら、携帯端末じゃなくて、〈蝿〉をっ……殺、して……って、お願いすべき……っ。……けど、そう考えたら、体が震えてきて、……ルイフォン、助けて、って――そればかりが心を占めて……!』
悲鳴のような咽びが、ルイフォンの耳で反響する。
『……だから! 初めに思いついた通り、まずは携帯端末を手に入れて――、それから、ルイフォンに相談して一緒に決めよう、って……。でも、そんなのは表向きで……本当はルイフォンに甘えて、決断を委ねて……責任を押し付けて……私……卑怯なの。……ごめんなさい。けど、ひとりで背負うなんてできなかった……! 私……、私は……!』
彼女は、ひときわ声をわななかせ、そして、告げる。
『……ルイフォンがいなきゃ、駄目なの……!』
メイシアの声は嗚咽に流され、消えていく。
知らずのうちに息を止めていたルイフォンは、肺の中に溜まっていた空気をゆっくりと吐き出した。
自然と肩の力が抜ける。追い詰められているメイシアには申し訳ないが、彼女への愛しさがこみ上げてきてたまらなかった。
「嬉しいことを言ってくれるじゃねぇか」
『え?』
その声だけで、黒曜石の瞳をいっぱいに見開き、きょとんと首をかしげるメイシアの姿が見えた。長い黒髪がさらりと流れる音まで、ルイフォンには感じ取ることができる。
彼女はただ、思ったままのことを言っただけだろう。それが、熱烈な愛の告白であることには気づかずに。――実に、メイシアらしい。
普段なら、ややきつめに上がっている、ルイフォンの猫の目が垂れた。口元には締まりがなく、にやにやと緩んでいる。電話口の向こうの彼女に、だらしない顔が見えないのは幸いだった。
「そりゃ、お前に頼られたら、俺は嬉しいに決まっているだろ? お前を支えるのは、俺の役目なんだからさ」
『ルイフォン……。ごめんなさ……』
言い掛けて、言い直す。
『……ううん。ありがとう……』
ふわりと花がほころぶように、メイシアの声が和らいだ。
出逢ったばかりのころのように、むやみに謝ったりしない。それよりも『ありがとう』で返す。――極上の笑顔と共に。
それが、ふたりで築き上げてきたものだ。
「だいたい、〈蝿〉を『捕まえる』ならともかく『殺す』である場合、お前がひとりで背負う必要はないだろ。それは、あまりにも重すぎる。怖くて当たり前だ。いくら敵でも、命は命なんだからな」
『……うん』
「ならば、〈蝿〉の『死』を決定した親父に――鷹刀の総帥に指示を仰ぐのが筋だ。つまり、お前の取った行動は正しい。タオロンだって、そんなすぐに寝返ったのがばれるようなミスはしないだろう」
『なら……、これで良かった、の……?』
メイシアの声が震えた。きっと今、彼女の頬で涙がきらりと光っている。
「ああ。お前は最善の選択をした。最高だ! さすが、俺の惚れ込んだ女だ」
『――っ!』
涙の通り過ぎたあとの頬が、薔薇色に染まる。彼女は泣きながら、笑っている。
『えっと……、ルイフォンは最高に頼もしくて……、その……さすが、私が好きになった人だ、と……』
真っ赤になりながらも、懸命に言葉を返してくれる。そんな彼女の姿がありありと目に浮かんできて、ルイフォンは穏やかに微笑んだ。
「ひとりで心細かったよな。もう大丈夫だ」
メイシアは、本当によくやったと思う。
だから、ここから先はルイフォンの番だ。
「俺はこれから親父のところに行って、『鷹刀の総帥と〈猫〉の連名で、タオロンに〈蝿〉暗殺を依頼しよう』と提案してくる。タオロンに対しても、凶賊の総帥からの正式な依頼としたほうが礼儀に適っているだろう」
そう言ってから「俺たちだけじゃ駄目か」と呟く。
「多少なりとも〈蝿〉に一族の情を感じている親父より、ハオリュウやシュアンのほうが、よっぽど〈蝿〉を憎んでいる。だから、あいつらにも名を連ねてもらって、タオロンに……」
ルイフォンは、そこで言葉を止めた。
――本当に、それでいいのだろうか。
『デヴァイン・シンフォニア計画』を作り、さまざまな人々を不幸に陥れた元凶は、異父姉のセレイエだ。だが、もしも〈蝿〉が暴走しなければ、これほどまでの不幸は訪れなかったはずだ。
〈蝿〉は紛れもなく、皆の怨嗟の象徴。
その幕引きを務めるのが、タオロンでよいのだろうか――?
「違う……。タオロンじゃねぇ……」
タオロンだって、まったくの部外者ではないだろう。だが彼は、腕輪の件で騙されていたとはいえ、〈蝿〉の世話になっていた一面もある。
だから、彼ではない。もっと別の配役であるべきだ。
ならば、誰だ?
〈蝿〉の終幕を担うにふさわしい人物とは……。
「――!」
ルイフォンは息を呑んだ。
「なんだ、ちゃんと庭園に配置されているじゃねぇかよ……」
『ルイフォン? どうしたの?』
急に笑い出した彼に、メイシアが不思議そうに尋ねる。
「タオロンに依頼するのは保留だ。それは最後の手段、保険だ」
『え?』
「今まで散々な目に遭わされてきた〈蝿〉に引導を渡す役が、ちょいと部外者のタオロンじゃ、皆が納得できない。もっと深く関わりのあった者。俺たちの内部の者であるべきだ」
『え、うん……、それは、そうかもしれないけど……、でも……?』
困惑した様子のメイシアに、ルイフォンはにやりと口角を上げる。
「庭園にいるだろ? 俺たちの仲間が――鷹刀の後継者が」
『リュイセンのこと……!?』
戸惑いと動揺。そして同時に、喜色の混じった声が返ってくる。その声色だけで、メイシアは、まったくリュイセンを恨んでおらず、それどころか、ずっと彼を心配していたことが伝わってきた。
事実、彼女は手紙で、リュイセンの裏切りはやむを得ないものであったのだと、必死に弁護していた。その証拠として、『リュイセンは、ミンウェイの『秘密』に関することで脅されている』という重大な情報を〈蝿〉から聞き出していた。
そして、『ミンウェイさんが関係するのなら、リュイセンは決して事情を話してくれないと思う。でも、〈蝿〉の支配がなくなれば、もとに戻れるはず。私はリュイセンを信じる』と、懸命に訴えていた。
その便箋だけ別の封筒に入っていたことから察するに、じっとしていられないファンルゥが、初めの手紙を預かったあと、時間を置いて再びメイシアを訪れたに違いない。その間に、メイシアは新しい情報を聞き出していて、だから、新しい手紙を書いたのだ。
――皆が、前へ前へと突き進もうとしている。
ならば。
『皆』で、大団円を目指すのだ。
「ああ。俺たちの仲間――『鷹刀の後継者』リュイセンだ。今は、追放処分になっているけどな」
『えっ!?』
「つまり、リュイセンは、〈蝿〉が死んで、〈蝿〉から自由になっても、このままでは鷹刀に戻ることはできない。けど、リュイセンが〈蝿〉の首級を挙げれば、それを手柄に追放を解いてもらうことが可能だろう。一石二鳥だ」
『でもリュイセンは、〈蝿〉に逆らえなくて……』
メイシアがそう言うのは当然だろう。現在のリュイセンは〈蝿〉の言いなりであり、ルイフォンたちの敵なのだから。
「俺がリュイセンの束縛を解いてやる」
その瞬間、メイシアが短く息を吸い、叫んだ。
『ルイフォンには分かるの!? リュイセンが囚われてしまった理由が……』
驚愕でありながらも、歓喜にあふれた弾んだ響き。
ルイフォンは「まだ、確証はないけどな」と答えながらも、そのテノールは自信に満ち満ちている。
「現時点では、俺の勘に過ぎない。でも、間違いないと思う。――リュイセンが俺にすら隠して、すべてを裏切るしかなかった理由……その情報を、俺はこれから手に入れる」
深い霧に閉ざされていたような視界が、さぁっと晴れていく。そこに現れたのは、大地にしっかりと打ち立てられた一本の道しるべだった。
「そして、リュイセンを解放する――!」
それが、あるべき正しい道だ。
好戦的な光を帯びた猫の目で、ルイフォンが遥かな庭園を睨みつける。その強い意思に呼応するかのように、彼の背では金の鈴が輝いた。
~ 第七章 了 ~
幕間 永遠の連理

『連理の枝』などというものは、ただの夢物語だ。
ミンウェイの体は、限界に近づいていた。
俺がどんなに気休めを言ったところで、ミンウェイ自身が一番よく分かっているだろう。
だから俺は、ついに禁断の領域に手を出した。
「……ミンウェイ。君の細胞から、新しい君の体を作った。先天的な病の因子をすべて取り除いた、健康な肉体だよ」
自分の声であるはずなのに、まるで他人が喋っているかのようだった。
俺は、〈悪魔〉だ。
『研究のために、魂を捧げた者』だ。
目には見えない真っ黒な翼を白衣に押し込め、血まみれの両手を洗い流して、そ知らぬふりをする。そうでもしていないと気が狂いそうだった。
「〈蠍〉という同僚の〈悪魔〉が、〈天使〉の研究をしている。奴に頼んで、君の記憶を新しい肉体に移してもらう」
「ヘイシャオ! ――それって……」
ベッドの上のミンウェイは、ただでさえ青白い顔を更に蒼白にした。血色の悪い唇が小さく開かれたまま、言葉を失っている。
「そうだね。驚くよね」
俺は、彼女には決して見せられない〈悪魔〉の顔を隠して、優しく微笑む。
毛布の上に出ていた彼女の手を取り、握りしめた。寝間着の袖がめくれると、透き通るような白い肌が露出する。かさついた皮膚には、無残な点滴のあとが無数に残されていた。
健康な肉体を得れば、彼女はこんなに苦しまなくて済むのだ……。
「君が脅えるのも無理はない。何しろ、俺が世界で初めて確立した手法だ。――けど、安心してほしい。実験は成功している。協力してもらった被験者は、新しい肉体で、新しい人生を送っている」
俺の言葉は、すべてが嘘ではないが、すべてが真実でもない。
成功例もあれば、失敗例もある。成功したところで、存在しないはずの人間だ。どんな新しい人生があるというのだろう。
俺は、『悪魔』だ。
ミンウェイのためになら、魂など要らない。
「怖いことはないよ。臓器移植と同じだ。具合の悪いところを取り替えるだけだ」
「違う! 違うわ、ヘイシャオ!」
この弱ってしまった体の、いったい、どこにそんな力が残っていたのか。彼女は、俺の手がきしむほどに握り返し、全身で声を震わせた。
「絶対に、嫌……!」
そう叫んだ途端、彼女は胸を押さえて苦しみだす。
まずい。興奮させすぎてしまった。
俺は慌てて彼女に鎮静剤を打ち、眠りにつかせる。
このぬくもりを失ってなるものかと、すがるように抱きしめながら――。
「ヘイシャオ」
数日後、容態の落ち着いたミンウェイが、例の話を切り出してきた。
「『それ』は、私じゃないわ。私のふりをした、私じゃないものが、私の代わりにあなたのそばに居るだけ」
床に臥している間、ずっと考えていたのだろう。
彼女の言葉は、少しの揺れも澱みもなく、まっすぐに俺に流れてきた。
「このぼろぼろの体を引きずりながら、必死にあなたと生きたいと願っているのが『私』なの」
ベッドから伸ばされた手が、俺を呼んだ。彼女の調子が良いときは、体を起こしてやるようにしている。それをねだるように、彼女の瞳が俺を見上げていた。
促されるままに、俺はゆっくりと電動ベッドを上げる。途中で彼女がよろけたりしないよう、すっかり細くなった体にそっと手を添えて。
やがて彼女の目線が、かがんだ俺の襟元に来たとき、彼女の両手が俺の白衣を掴んで引き寄せた。
「ヘイシャオ。私は、あなたのおかげで、ここまで生きてきたわ」
澄んだ眼差しが、俺を捕らえる。
「この体は、あなたが大切に守ってくれたもの。出来損ないかもしれないけど、凄く愛しい」
「ミンウェイ……」
「記憶にも、肉体にも、私はあなたを刻み込んできた。――それが『私』。幼いころからずっと、この『私』が、あなたと時を過ごしてきたのよ」
ふわり、と。
重さを感じないような両腕が俺の首に回され、甘えるように頬をすり寄せてくる。病人特有の匂いの中に、子供のころ一緒に駆けた、懐かしい野原の草の香を感じた。
「……っ」
胸が苦しくてたまらない。
彼女の言っていることは理解できる。
俺だって、彼女の体を生き存えさせることができるのなら、そうしたかった。
けれど、残酷な現実は、許してくれない。
彼女の体は、二十歳までは生きられない。
分かっていたことだ。
俺も、彼女も――。
「――駄目だ……」
俺は、子供が駄々をこねるように身をよじった。
「駄目だ! 駄目だ、ミンウェイ。それじゃ、俺のしてきたことが全部、無駄になる! ――今まで俺は、なんのために生きてきた! ……俺は……なんのために……!」
〈悪魔〉の行為の告白を、俺はかろうじて飲み込む。
けれどミンウェイは、俺の言葉の先を、俺の代わりに続けた。
「『なんのために、殺してきた』」
俺と生きてきたミンウェイが、知らないわけがない――。
なんのために生きてきた。
なんのために殺してきた。
「私が、あなたと生きたいと願ったから、あなたは私を生かすために生きて、私を生かすために殺してきたの」
「ミンウェイ!」
「あなたがしてきたことは、無意味なんかじゃない。刹那の時かもしれないけれど、私の願いは叶ったわ。だから、私は幸せよ」
彼女が、泣きながら笑う。
幸せの裏に何があったのかを知りつつも、それでも幸せを感じていた人でなしだと、自分を責めながら……。
「まだだ! これからだ! これから、もっと……!」
「ヘイシャオ、落ち着いて。これから先のあなたのことを考えるの。ふたりで、一緒に……!」
「嫌だ! ミンウェイ、俺が君と生きたいんだ! 俺が、辛いんだ。俺が、耐えられないんだ。俺が、君を失いたくないんだ!」
愚かしいほどに取り乱し、彼女の細い肩を抱きしめる。
血も涙もないはずの俺の目から、涙があふれた。
「あなたは苦しみながら、〈悪魔〉の罪を重ねてきた。でも、それは私のための罪よ。だから、私の罪であるべきなの。あなたが背負うことはないわ」
言葉が空回りをしているのを感じた。
「あなたの〈悪魔〉としての罪は、私がすべて持って逝く。だから、あなたは〈悪魔〉をやめて鷹刀に戻るの。それが私の、今の願いよ」
彼女は、俺の技術を受け入れない。
「あなたは、私のあとを追うつもりなのでしょう? 駄目。許さない」
ずっと連絡を絶っていたお義父さんに、数年ぶりに電話を掛けた。
「ヘイシャオ。私は生きたい。本当は生きたい。あなたと生きたい。『死にたくない』じゃないの、『生きたい』なの」
……お義父さんには失望した。
「生きて」
「それが、どんなに尊いことか。私たちは知っているのだから」
「……あなたを独りにしない」
「だから、お願い……」
「――ヘイシャオ、生きて……」
「ヘイシャオ、大好き。愛している」
そして――。
ミンウェイは俺を置いて逝ってしまった。
あの子を遺して……。
――再び君に逢うために――。
記憶の君は少女のままで、私は君を置き去りにして歳を取った。
君と離れた長い年月の中で、私は罪を犯していった。
どんなに面影を残していても、あの子は君ではなかった……。
別れを告げてから、十数年が経つというのにも関わらず、エルファンは身勝手な私の呼び出しに応えてくれた。
指定した場所に現れた彼は、昔の面差しを残しつつ、以前のような明朗さを失っていた。どことなく陰りがあるように感じるのは、眉間に深く刻まれた皺のせいだろうか。
〈七つの大罪〉――すなわち国王の庇護を失った鷹刀は、想定通りではあるが、一時期、かなり弱体化した。しかし、総帥イーレオのおおらかな人望と、次期総帥エルファンの規律に対する厳格さによって、再び盛り返した。
結果だけ見れば、新しい鷹刀は、うまく舵取りをしてきたように感じる。しかし、おそらく、そうではないだろう。
私が鷹刀に残っていれば、少しはエルファンの負担を軽くできたのだろうか。
一瞬だけ、そんな考えがよぎる。
けれど、すぐに打ち消した。
たとえ時が戻ったとしても、私にはミンウェイと生きる道しか選べない。何度、選択を迫られたところで、どんなにわずかだったとしても、彼女との刹那の時間を伸ばすことを願うだろう。
「お父様……?」
私の後ろで、〈ベラドンナ〉の気配が揺れた。私とそっくりなエルファンに動揺していた。
血族に囲まれて育った私にとっては、同じ顔など珍しくもない。だが、〈ベラドンナ〉にとっては初めて見る、私以外の血族だ。驚いて当然だろう。
「ヘイシャオ。その子は……」
私と同じ声が呟く。とはいえ、エルファンのほうは生粋の鷹刀の容姿を持つ〈ベラドンナ〉に、疑問を持つことはなかった。
「エルファン。ミンウェイが亡くなった。……もう、十数年も前のことだ」
「……ああ」
「墓は、彼女が一度だけ行くことができた、あの海の近くにある。君や姉さんたちと泊まった、丘の上の別荘を買い取った」
「……そうか」
エルファンの視線が、遠くの海を見つめる。
「ヘイシャオ、感謝している。……あいつは幸せだったと思う」
私は『勿論、幸せにしたさ』と、言い掛けてためらった。
幸せにした。それは間違いない。
けれど、最期の瞬間に、彼女が幸せだったのか。安心して逝くことができたのか、私には分からない。
そして今の私は、許されざる罪人だ。
「病弱に生まれた血族は、何ひとつ為すこともできずに儚く死んでいくのが習いだったのに、あいつときたら、我儘で、お前を振り回してばかりで。案外しっかり者で、お前を尻に敷いて……」
エルファンの眉間の皺は相変わらずだったが、新たに目元にできた皺が、彼の表情を穏やかなものにしていた。そこには、懐かしい少年のころの輝きが垣間見えた。
「ヘイシャオ、すまなかった。お前ひとりに背負わせた」
「そんなことはない。……私は、幸せだった」
幸せだった。
彼女と生きることができて。
けれど、この世界には、彼女はもういないのだ。
「それで、ヘイシャオ。今日はどうしたんだ?」
それは、当然の疑問だろう。
「――帰って……来るのか?」
エルファンの声は、期待に震えていた。冷酷な次期総帥を演じてきた月日のせいか、彼の感情の起伏は昔のように明確ではない。けれども、私には分かった。
私は、ゆっくりと首を振った。
そして彼に背を向け、数歩、離れる。
それから再び、くるりと振り返り、腰の刀の柄を握った。
「エルファン。私は、鷹刀の前総帥の後継者の息子だ。だから、私こそが、正当な鷹刀の主だ」
「ヘイ……シャオ……?」
「私は、鷹刀イーレオを倒して総帥になる。まず手始めに、次期総帥の君を討つ」
エルファンの美貌が彫像のように固まり、それから深い溜め息が落とされた。
「――そういうことに、したいんだな……」
彼の口元が、ぐっと歪んだ。奥歯を噛み締めたのだろう。
双子のように育った、私の従兄――私の親友。
音信不通の日々を飛び越え、何も言わなくても彼は理解してくれた。固く握りしめた、彼の拳が震えている。
「……ああ。すまない」
俺の肯定に、エルファンは軽く頭を振った。
「あいつは我儘だったから、お前に誓わせたんだろう? ――決して、自ら命は絶たない、と」
「……」
「お前が逆らえるわけがない。まったく、酷い妹だ。おかげで、兄の私が尻拭いというわけか」
投げやりにも聞こえる口調は、しかし見せかけだ。
「理由を訊かないのか?」
「お前から言わない以上、言いたくないんだろう?」
「……っ」
「だったら訊かないでいてやるさ。――あいつの死を、ひとりで背負ったお前の頼みだ。後悔しようが構わない――」
エルファンの理知的な眼差しが、優しく私を包み込む。胸の中に、懐かしい温かさが広がっていく。
「引き受けてやるよ」
「ありがとう……」
エルファンが双刀の柄に手をやるのにあわせ、私も銀の刀身をすらりと抜き払った。
手元の鍔飾りには、可愛らしい小さな花があしらわれている。
ベラドンナの花だ。
ミンウェイを亡くしたあと、〈悪魔〉として研究を続ける意味を失った私は、名ばかりの研究員となった。〈七つの大罪〉からは、たいした資金を与えられなくなり、私は暗殺者として生計を立てることにした。
これからは、〈ベラドンナ〉のために生きる。その決意を込めて、仕事道具となった刀の鍔飾りをベラドンナの花にした。
なのに私は、すっかり忘れてしまった。
そして、罪を犯したのだ……。
「お父様……! 嫌ぁ……!」
〈ベラドンナ〉は、ミンウェイではない。
だから、解放してやらねばならない。
いつまでも、こんな狂った私に縛られていたらいけない。
「お前の父は、私が殺した」
「――あ、ああ……、いや……」
「お前は私を恨め。誰かを恨んでなければ、やっていられないだろう」
「――――! ――――……!」
エルファンと〈ベラドンナ〉の声が聞こえる。
これでもう、〈ベラドンナ〉は大丈夫だろう。
幸せにおなり、私の娘……。
――再び君に逢えたなら――。
俺は、夢物語の願いを叶える。
君と共に、歳を取りたい。
君のそばで、永遠に在りたい。
君と刹那を積み上げ、刹那を繋ぎ合わせ、刹那を連ね続け……。
刹那を重ねていけば、それは、いつかきっと、永遠になる。
君が憧れた、あの海を見ながら、俺たちの墓標は寄り添うだろう。
連理の枝のように――。
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第二部 第七章 五里霧の囚獄で
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第八章 夢幻の根幹から https://slib.net/113650
――――に、続きます。


