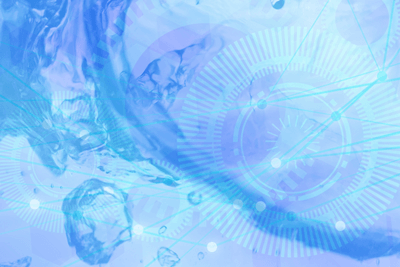
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第二部 第二章 約束の残響音に
こちらは、
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第二章 約束の残響音に
――――です。
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第一章 遥か過ぎし日の https://slib.net/112161
――――の続きとなっております。
長い作品であるため、分割して投稿しています。
プロフィール内に、作品全体の目次があります。
https://slib.net/a/4695/
こちらから「見開き・縦書き」表示の『えあ草紙』で読むこともできます。
(星空文庫に戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください)
※使わせていただいているサービス『QRouton』の仕様により、クッションページが表示されます。
https://qrtn.jp/b2hjtcx
『えあ草紙』の使い方は、ごちらをご参考ください。
https://www.satokazzz.com/doc/%e3%81%88%e3%81%82%e8%8d%89%e7%b4%99%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab
「メニューを表示」→「設定」から、フォント等の変更ができます。PCなら、"UD Digi Kyokasho NP-R"等のフォントが綺麗です。
〈第一章あらすじ&登場人物紹介〉

===第一章 あらすじ===
メイシアが鷹刀一族の屋敷で暮らすようになってから、ひと月が過ぎた。〈蝿〉の行方は掴めず、一族の総帥イーレオは保留という方針を宣言する。
ルイフォンは、母キリファが〈七つの大罪〉の実験体、〈天使〉ではないかという疑問をイーレオに投げかけ、「そうだ」との答えを得る。そして、『〈天使〉とは、脳という記憶装置に、記憶や命令を書き込むオペレーター。いわば、人間に侵入して相手を乗っ取るクラッカー』だと教えられた。
かつて、キリファは強大な力を恐れられ、殺されそうになっていたところを、次期総帥エルファンによって助け出され、鷹刀一族のもとへやってきたのだった。
ある夜。リュイセンは『イーレオは、一族の解体を目指している』と知らされたことを思い出し、悩んでいた。そこにルイフォンが来て励まされる。
同時刻。メイシアは密かにイーレオを訪ね、『ルイフォンは、母キリファの〈天使〉の力によって、母の死の記憶を改竄されているのではないか』という疑問を投げかけていた。
メイシアは、更に踏み込んで、イーレオはキリファの死の真相を知っているのではないかと問い詰める。イーレオは『触れてはいけないものに触れてしまう』と明確な答えはくれなかったが、『キリファを殺した者は既に死んでいる』と教え、『自分は〈七つの大罪〉の研究者、〈悪魔〉である』ことを暗に匂わせた。
ある休日。リュイセンは、イーレオによって半ば強制的に、一族を抜けた兄レイウェンの家を訪ねていた。しかしそれは、『リュイセンが忘れた、よもぎあんパンを届ける』という口実をでっちあげ、メイシアをレイウェンの家に行かせ、そこに住んでいるユイランと引き合わせるための策略だった。
ユイランとは、リュイセンとレイウェンの母であり、エルファンの正妻である。ルイフォンの母キリファが、エルファンの愛人であったため、ルイフォンやメイシアにとっては『敵対関係』にあるといえる。幼いころから『母は愛人へのあてつけで自分を生んだのだ』と思っているリュイセンは、母とは仲が悪く、そんな母と引き合わせると聞いて、メイシアのことを心配する。
そんな中、リュイセンは、母は憎き〈蝿〉の実姉であると教えられ驚愕する。更に、〈蝿〉が娘のミンウェイへの異常な愛情を向けた理由は、娘を死んだ妻の身代わりにしていたからであり、『ミンウェイ』という名前自体、妻の名前をそのままつけただけだと知らされる。
一方、ユイランと対面したメイシアは、三つの用件があると言われる。
1.さる方からメイシアの服の仕立てを頼まれたので、採寸したい。
2.過去の鷹刀のことを話すようにと、イーレオに頼まれている。
3.死ぬ前のキリファから預かった、ルイフォンへの手紙を届けてほしい。
話の流れから、まず初めに過去の鷹刀のことをユイランは話し始めた。
闇の研究組織〈七つの大罪〉の支配下にあった時代の鷹刀一族は、〈贄〉と呼ばれる実験体にされるために、異常な血族婚を強いられており、そのために子供も育ちにくいという状況だった。ユイランとエルファンもまた、そうして定められた夫婦であり、尊敬はあるが愛情はない関係だった。
そんな一族を解放するために、イーレオは総帥となった。その後、エルファンとキリファが出逢う。立場上、ユイランとキリファは正妻と愛人という間柄となったが、ユイランとしてはキリファを大歓迎しており、いずれは正妻の座を譲るつもりだった。
しかし、敵対する凶賊に、レイウェンとセレイエの幼い異母兄妹が襲われてしまう。そして、もともと凶賊ではなかったキリファと、その娘セレイエは、安全のために鷹刀の外に出されることになった。また一族の後継者となるレイウェンを助け、万一のときにはレイウェンの代わりの後継者となるべく、リュイセンの誕生が望まれた。――という。
話を盗み聞きしていたリュイセンは「納得した」と言い、和解とは違うが、不仲であった母ユイランとの距離を少しだけ縮めた。
ユイランは、メイシアとリュイセンに、〈蝿〉について語る。
現在の〈蝿〉と、ユイランの実弟であり、ミンウェイの父であるヘイシャオは『別人』であると、ユイランは言う。ヘイシャオは病弱な妻のためだけに生きたような男であり、娘のミンウェイを託し、妻のあとを追って事実上の自殺をしたのだから、この世に未練はない。〈蝿〉は、何者かが、ヘイシャオを悪用するために用意した『駒』だと断言した。
一方、鷹刀一族の屋敷にいるルイフォンは、メイシアが『敵対関係』のユイランのところにいると聞き、駆けつける。そこで待っていたものは、ウェディングドレス姿のメイシアだった。メイシアの異母弟ハオリュウが花嫁衣装を注文しており、その採寸が、ユイランのひとつ目の用件だったのだ。状況を察し、ルイフォンは『敵対者』と思っていたユイランに頭を下げた。
そしてユイランは、三つ目の用件、キリファから預かった『手紙』とい名目の分厚い茶封筒をルイフォンに手渡す。中身は人工知能〈スー〉のプログラムであり、悪筆のキリファの手書き文字を、一文字も間違わずに解読して〈ベロ〉に打ち込めば、〈スー〉が出てくるというものだった。
キリファが住んでいた家と、鷹刀一族の屋敷にあるコンピュータ、〈ケル〉〈ベロ〉は、一見、普通の高性能マシンであるが、実は『張りぼて』だった。それとは別に、〈七つの大罪〉の技術で作った機体に、キリファの作った人工知能を載せた、とんでもない性能を持った真の〈ケル〉〈ベロ〉がいるという。
真の〈ケル〉〈ベロ〉は、『張りぼて』の〈ケル〉〈ベロ〉の目や耳を使って、どこかから鷹刀を見守っているらしい。そして、〈スー〉を起動させれば、何かしらの情報を喋ってくれるのではないかと推測できた。
屋敷に戻り、メイシアはルイフォンに、ルイフォンの記憶が改竄されている可能性があると、イーレオに相談したことを打ち明ける。そのとき、イーレオが、自分は〈悪魔〉であると示唆したことを告げる。
話をしていくうちに、ふたりは、『昔の鷹刀』を知ることで、イーレオが理解を得ようとしていたこと、そのためにメイシアとユイランを引き合わせたのだということに気づいた。そしてルイフォンは、『隠しごとばかりする糞親父を吊るし上げる』と宣言したのだった。
また、ルイフォンは、ユイランが別れ際に『〈天使〉のホンシュアは、ルイフォンの異父姉セレイエの〈影〉だ』と暗に伝えてきたことを言う。
今までの出来ごとを重ね合わせると、『女王の婚約を開始条件に、『デヴァイン・シンフォニア計画』は動き出す』。
つまり、〈七つの大罪〉の正体とは――。
そして、『デヴァイン・シンフォニア計画』とは、いったいなんなのか……。
何が起きているのか分からない。それでも、〈天使〉のホンシュアが――セレイエが引き合わせたメイシアを、必ずこの手で幸せにすると、ルイフォンは決意を新たにしたのだった。
===登場人物===
鷹刀ルイフォン
凶賊鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオの末子。十六歳。
母親のキリファから、〈猫〉というクラッカーの通称を継いでいる。
端正な顔立ちであるのだが、表情のせいでそうは見えない。
長髪を後ろで一本に編み、毛先を金の鈴と青い飾り紐で留めている。
凶賊の一員ではなく、何にも属さない「対等な協力者〈猫〉」であることを主張し、認められている。
※「ハッカー」という用語は、「コンピュータ技術に精通した人」の意味であり、悪い意味を持たない。むしろ、尊称として使われていた。
「クラッカー」には悪意を持って他人のコンピュータを攻撃する者を指す。
よって、本作品では、〈猫〉を「クラッカー」と表記する。
メイシア
元・貴族の藤咲家の娘。十八歳。
ルイフォンと共に居るために、表向き死亡したことになっている。
箱入り娘らしい無知さと明晰な頭脳を持つ。
すなわち、育ちの良さから人を疑うことはできないが、状況の矛盾から嘘を見抜く。
白磁の肌、黒絹の髪の美少女。
[鷹刀一族]
凶賊と呼ばれる、大華王国マフィアの一族。
秘密組織〈七つの大罪〉の介入により、近親婚によって作られた「強く美しい」一族。
――と、説明されていたが、実は〈七つの大罪〉が〈贄〉として作った一族であった。
鷹刀イーレオ
凶賊鷹刀一族の総帥。六十五歳。
若作りで洒落者。
実は〈七つの大罪〉の研究者、〈悪魔〉であったらしい。
鷹刀エルファン
イーレオの長子。次期総帥。ルイフォンとは親子ほど歳の離れた異母兄弟。
感情を表に出すことが少ない。冷静、冷酷。
鷹刀リュイセン
エルファンの次男。イーレオの孫。ルイフォンの年上の『甥』。十九歳。
文句も多いが、やるときはやる男。
『神速の双刀使い』と呼ばれている。
長兄レイウェンが一族を抜けたため、エルファンの次の総帥になる予定である。
鷹刀ミンウェイ
イーレオの孫娘にして、ルイフォンの年上の『姪』。二十代半ばに見える。
鷹刀一族の屋敷を切り盛りしている。
緩やかに波打つ長い髪と、豊満な肉体を持つ絶世の美女。ただし、本来は直毛。
薬草と毒草のエキスパート。医師免状も持っている。
かつて〈ベラドンナ〉という名の毒使いの暗殺者として暗躍していた。
父親ヘイシャオに、溺愛という名の虐待を受けていた。
草薙チャオラウ
イーレオの護衛にして、ルイフォンの武術師範。
無精髭を弄ぶ癖がある。
料理長
鷹刀一族の屋敷の料理長。
恰幅の良い初老の男。人柄が体格に出ている。
キリファ
ルイフォンの母。四年前に謎の集団に首を落とされて死亡。
ただし、これは「ルイフォンの記憶」であり、偽りである可能性が濃厚である。
天才クラッカー〈猫〉。
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蠍〉に〈天使〉にされた。
また〈蠍〉に右足首から下を斬られたため、歩行は困難だった。
もとエルファンの愛人。エルファンとの間に生まれた娘がセレイエである。
ルイフォンに『手紙』と称し、人工知能〈スー〉のプログラムを託した。
〈ケル〉〈ベロ〉〈スー〉
キリファが作った三台の兄弟コンピュータ。
表向きは普通のコンピュータだが、それは張りぼてで、本当は〈七つの大罪〉の技術を使った、人間と同じ思考の出来る人工知能を搭載できる機体である。
〈ベロ〉に載せられた人工知能の人格は、シャオリエを元に作られているらしい。
また〈スー〉は、ルイフォンがキリファの『手紙』を正確に打ち込まないと出てこない。
セレイエ
エルファンとキリファの娘。
ルイフォンの異父姉、かつ『姪』。リュイセンの異母姉。
貴族と駆け落ちして消息不明。
〈影〉と思われるホンシュアの『中身』だと推測されている。
メイシアを選び、ルイフォンと引き合わせた、らしい。
[〈七つの大罪〉・他]
〈七つの大罪〉
現代の『七つの大罪』=『新・七つの大罪』を犯す『闇の研究組織』。
〈悪魔〉
知的好奇心に魂を売り渡した研究者を〈悪魔〉と呼ぶ。
〈悪魔〉は〈神〉から名前を貰い、潤沢な資金と絶対の加護、蓄積された門外不出の技術を元に、更なる高みを目指す。
代償は体に刻み込まれた『契約』。――といわれているが、おそらくは組織のトップである〈神〉に逆らえないように、〈悪魔〉となるときに〈天使〉による脳内介入を受けている、という意味だと思われる。
〈天使〉
「記憶の書き込み」ができる人体実験体。
脳内介入を行う際に、背中から光の羽を出し、まるで天使のような姿になる。
〈天使〉とは、脳という記憶装置に、記憶や命令を書き込むオペレーター。いわば、人間に侵入して相手を乗っ取るクラッカー。
羽は、〈天使〉と侵入対象の人間との接続装置であり、限度を超えて酷使すれば熱暴走を起こす。
〈影〉
〈天使〉によって、脳を他人の記憶に書き換えられた人間。
体は元の人物だが、精神が別人となる。
『呪い』・便宜上、そう呼ばれているもの
〈天使〉の脳内介入によって受ける影響、被害といったもの。
服従が快楽と錯覚するような他人を支配する命令や、「パパがチョコを食べていいと言った」という他愛のない嘘の記憶まで、いろいろである。
『di;vine+sin;fonia デヴァイン・シンフォニア計画』
〈蛇〉が企んでいる計画。
〈蝿〉の協力が必要であるらしいのだが、謎に包まれている。
『di』は、『ふたつ』を意味する接頭辞。『vine』は、『蔓』。
つまり、『ふたつの蔓』――転じて、『二重螺旋』『DNAの立体構造』――『命』の暗喩。
『sin』は『罪』。『fonia』は、ただの語呂合わせ。
これらの意味を繋ぎ合わせて『命に対する冒涜』と、ホンシュアは言った。
ヘイシャオ
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蝿〉。ミンウェイの父。故人。
医者で暗殺者。
病弱な妻のために〈悪魔〉となった。
〈七つの大罪〉の技術を否定したイーレオを恨んでいるらしい。
娘を、亡くした妻の代わりにするという、異常な愛情で溺愛していた。
そのため、娘に、妻と同じ名前『ミンウェイ』と名付けている。
十数年前に、娘のミンウェイを連れて現れ、自殺のような状態でエルファンに殺された。
現在の〈蝿〉
〈七つの大罪〉の技術によって蘇ったと思われるヘイシャオ。
イーレオに恨みを抱き、命を狙ってくる。
記憶も姿も、ヘイシャオそのものであるが、実姉のユイランに言わせれば『第三者が自分の目的を果たすために作った、ただの駒』であり、ヘイシャオとは『別人』。
ホンシュア
セレイエの〈影〉と思われる人物で、〈天使〉の体にさせられていた。
〈影〉にされたメイシアの父親に、死ぬ前だけでも本人に戻れるような細工をしたため、体が限界を超え、熱暴走を起こして死亡。
〈蛇〉
〈蝿〉が、ホンシュアのことを〈蛇〉と呼んでいた。
ホンシュアの中身はセレイエだと思われるため、セレイエが〈蛇〉である……かは不明。
[草薙家]
草薙レイウェン
エルファンの長男。リュイセンの兄。
エルファンの後継者であったが、幼馴染で妻のシャンリーを外の世界で活躍させるために
鷹刀一族を出た。
――ということになっているが、リュイセンに後継者を譲ろうと、シャンリーと画策したというのが真相。
服飾会社、警備会社など、複数の会社を興す。
草薙シャンリー
レイウェンの妻。チャオラウの姪だが、赤子のころに両親を亡くしたためチャオラウの養女になっている。
王宮に召されるほどの剣舞の名手。
遠目には男性にしかみえない。本人は男装をしているつもりはないが、男装の麗人と呼ばれる。
草薙クーティエ
レイウェンとシャンリーの娘。リュイセンの姪に当たる。十歳。
可愛らしく、活発。
鷹刀ユイラン
エルファンの正妻。レイウェン、リュイセンの母。
レイウェンの会社の専属デザイナーとして、鷹刀一族の屋敷を出た。
エルファンの愛人キリファとは敵対関係、と周りに思わせていたが、実はキリファが信頼をおいていた人物のひとり。
メイシアの異母弟ハオリュウに、メイシアの花嫁衣装を依頼された。
[藤咲家・他]
藤咲ハオリュウ
メイシアの異母弟。十二歳。
父親を亡くしたため、若年ながら藤咲家の当主を継いだ。
十人並みの容姿に、子供とは思えない言動。いずれは一角の人物になると目される。
異母姉メイシアを自由にするために、表向き死亡したことにしたのは彼である。
女王陛下の婚礼衣装制作に関して、草薙レイウェンと提携を決めた。
緋扇シュアン
『狂犬』と呼ばれるイカレ警察隊員。三十路手前程度。イーレオには『野犬』と呼ばれた。
ぼさぼさに乱れまくった頭髪、隈のできた血走った目、不健康そうな青白い肌をしている。
凶賊の抗争に巻き込まれて家族を失っており、凶賊を恨んでいる。
凶賊を殲滅すべく、情報を求めて鷹刀一族と手を結んだ。
敬愛する先輩が〈蝿〉の手に堕ちてしまい、自らの手で射殺した。
似た境遇に遭ったハオリュウに庇護欲を感じ、彼に協力することにした。
[繁華街]
シャオリエ
高級娼館の女主人。年齢不詳。
外見は嫋やかな美女だが、中身は『姐さん』。
元鷹刀一族であり、イーレオを育てた、と言っている。
実は〈影〉であり、体は別人。そのことをイーレオが気にしないようにと、一族を離れた。
トンツァイ
繁華街の情報屋。
痩せぎすの男。
===大華王国について===
黒髪黒目の国民の中で、白金の髪、青灰色の瞳を持つ王が治める王国である。
身分制度は、王族、貴族、平民、自由民に分かれている。
また、暴力的な手段によって団結している集団のことを凶賊と呼ぶ。彼らは平民や自由民であるが、貴族並みの勢力を誇っている。
1.吊し上げの獅子-1

ひやりとした空気が、部屋中に満ちていた。
比喩的な意味ではなく、現実として室温が低いのである。初夏と呼ぶにはやや早い陽気にも関わらず、空調がひっきりなしに冷気を送り込んでいるためだ。
昼間ではあったが、電灯が室内を照らしている。もとより窓はない。
ぴっちりと閉ざされた異次元――通称『仕事部屋』。
ルイフォンは普段、多種多様な機械類の載った、車座に配置された机の内側で作業をする。メイシアが魔方陣と呼ぶ場所である。
だが今日は、彼は魔方陣の外にいた。
専門書の詰まった壁一面の棚と、魔方陣の間の広々とした空間で、ルイフォンは集めた一同の顔を見渡していた。
向かい合うように座する彼の父、鷹刀一族総帥イーレオをはじめ、異母兄にして次期総帥エルファン、武術の師匠であり総帥の護衛であるチャオラウ。それから、年上の姪のミンウェイと、同じく年上の甥のリュイセン――鷹刀一族の中枢たる顔ぶれが並んでいる。
一方、ルイフォンの側には、彼の最愛のメイシアが寄り添うように控えていた。
「忙しいところ、すまなかった。ありがとう」
ルイフォンは、皆に向かってテノールを響かせた。
口調だけは感謝に似ていた。しかし、肘掛け付きの回転椅子にどっかりと座り、足を組んだ姿勢の彼から、謝意を感じとれる者はいない。
眉間に皺を寄せたリュイセンが、皆を代表するように苛々と口を開く。
「何を偉そうに言ってんだ? 話があるって言うから来てやったけど、せめて執務室か食堂に集めろよ」
適当に並べられた丸椅子に不平を鳴らしたイーレオのため、リュイセンは続き部屋となっているルイフォンの私室からソファーを運ばされたのである。
「まぁ、そう言うな。今回は、俺の領域であることに意味があるんだから」
リュイセンと共にソファーを運んだルイフォンが苦笑する。
文句たらたらの兄貴分に言われるがまま、快く労働力を提供したあたり、ルイフォンだって一応は年長者への敬意はあるのだ。――ただ、謙虚さが抜け落ちているがために、尊大さが目立っているだけで。
「ともかく、始めるぞ。この部屋は完全防音だ。如何な声も漏れることはないから、安心してくれ」
話が横道にそれる前にと、ルイフォンは舵を切る。ひとりひとりの表情を確かめ、彼は口を開いた。
「話というのは〈七つの大罪〉と〈悪魔〉についてだ。本当は、シャオリエとユイランにも来てもらいたかったんだが――」
もと一族の娼館の女主人、シャオリエ。エルファンの正妻にして、かつては総帥の補佐を努めていたユイラン。共に、〈七つの大罪〉に関して詳しいはずだ。
「――屋敷の外にいる彼女らを呼ぶのは気が引けた。それに、鷹刀イーレオさえ協力的ならば、俺の目的は果たせるからな」
父であり、総帥たるイーレオの名を呼び捨てたことに、場が色めきだつ。しかしルイフォンは、猫のような目をすっと細め、好戦的に嗤った。
「分かってんだろ? ――鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオ」
「そりゃ、俺自身がメイシアに教えたようなものだからな。お前に伝わるのも、お前が怒るのも時間の問題だと思っていたさ」
ルイフォンの挑発に、イーレオが魅惑の笑みで応じる。
少ない言葉のやり取りで、すべてが通じてしまうのは、良くも悪くも互いを理解し合っているからだろう。単に、似た者同士というだけかもしれないが。
けれど、皆が以心伝心であるわけもない。故に、ルイフォンの期待通り、リュイセンが割り込んできた。
「おい、ルイフォン。感じ悪いぞ。俺たちが置いてけぼりだ。お前が招集をかけた以上、集まってくれた人間に対して、きちんと説明するのが礼儀ってもんだろう?」
リュイセンのもっともな発言に、ルイフォンは「すまんな」と確信犯の笑みを浮かべる。それから組んでいた足を解き、背を起こした。
「まず始めに。この座席の配置が、俺の立ち位置だ」
そう言って、すっと右手を横に滑らせ、自分の前に境界線を描く。
「どういう意味だ?」
「分からないか、リュイセン」
ルイフォンは口の端を上げる。
「お前たちは『鷹刀』だが、俺とメイシアは違う。俺たちは、〈猫〉とそのパートナー。鷹刀の『対等な協力者』に過ぎない」
彼はそう言って、ぎろりとイーレオを睨みつけた。
「しかも『協力者』と言ったって、ただの口約束だ。なんの契約もない。だから、この俺が、鷹刀は協力するに値しないと判断したとき、いつでも解消できる関係だ。それを履き違えてもらっては困る」
宣戦布告にも等しいルイフォンの口上を、イーレオはのんびりとソファーに寄り掛かりながら聞いていた。涼し気な美貌をわずかにほころばせ、やんちゃな息子を愛しげに見つめている――そんな顔だ。
ルイフォンの視線が、異論はあるか? と問いかける。するとイーレオは少しだけ姿勢を正し、穏やかに尋ねた。
「つまりお前は、俺の返答次第では、鷹刀と縁を切ると言っているわけだな」
言葉の内容とは裏腹に、口元は楽しげだ。
ルイフォンが強気の姿勢を崩さずに「そうだ」と鋭く明快に答えると、イーレオは喉の奥で笑いを漏らした。そして、ぱっと両手を上げる。――降伏の仕草だった。
「今回は、俺が悪い。全面的に〈猫〉に従おう」
「祖父上!?」
一族を背負って立つ総帥のまさかの行動に、リュイセンが目をむく。その他の者たちも、声には出さずとも狼狽を隠しきれない。
そんな皆を諭すように、イーレオはゆっくりと頭を振った。
「俺はルイフォンのことも、メイシアのことも気に入っている。彼らは、俺を魅了してやまない。――だから俺は、契約を交わさずとも、彼らの協力を得られるような人間でありたいと願うだけだ」
「親父……」
予想外の返答に、ルイフォンは困惑した。
追い詰める台詞なら、幾らも考えておいた。だが、こうもあっさりと白旗を掲げられたら、調子が狂ってしまう。
――こんな大海のように構えられたら、こちらが主導権を握ったはずなのに、なんとなく負けた気がするではないか……。
ルイフォンの内心をよそに、イーレオが面白そうに問うてきた。
「お前の要求はなんだ、〈猫〉? 自分の領域に連れ込んで、力関係を主張して。――俺に何をさせたい?」
「あ、ああ……」
イーレオの軽い物言いが、話を円滑に進めようと誘っている。戸惑っていたルイフォンも、それに応え、いつもの不敵な笑みを取り戻した。
「分かっているだろ? 自分から言えよ。隠されているのも不快だが、暴露するのはもっと胸糞悪い」
ほんの一瞬、イーレオは虚を衝かれたように言葉を詰まらせた。
そして、目を細める。
「お前は……。本当に、俺の『協力者』だな」
一族の和を乱さぬよう、暴くのではなく、自ら語るように仕向ける。――ルイフォンの意図にイーレオは感謝を込めて頷くと、にわかに剣呑な雰囲気を身にまとった。
「では〈猫〉の要求に従い、告白しよう。――俺は〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈獅子〉だった」
がたん……。
リノリウムの床に、椅子の倒れる音が響いた。丸椅子に腰掛けていたリュイセンが、勢いよく立ち上がったのだ。
「ど、どういうことですか!?」
ふらつく足でイーレオへと一歩寄るが、立場をわきまえてか、身動きが取れなくなる。
動揺する兄貴分を横目に、ルイフォンは冷静に皆の表情を観察していた。そして、注目を集めるように、「やはりな」と声高に発する。
「知らなかったのは、リュイセンとミンウェイだけか」
ルイフォンはそう言い、イーレオの様子を窺った。それから、猫の目をすっと細め、ゆっくりと問いかける。
「それじゃ、エルファンやチャオラウも〈悪魔〉なのか? シャオリエとユイランはどうなんだ?」
イーレオは、ただ小さく息を吐いた。
「いや。〈悪魔〉は、俺と――昔のシャオリエだけだ」
常に余裕綽々のイーレオの美貌が、シャオリエの名を口にした途端に陰る。
「昔の……?」
「今のシャオリエは〈影〉だ。彼女の本来の体は、とっくに死んでいる」
「!」
常々、シャオリエには何かあると感じていた。けれど、さすがに想定外だ。目の前に危険が迫っているわけでもないのに、ルイフォンは怖気を覚えた。
「彼女は、俺を育ててくれた女だ。〈七つの大罪〉から、鷹刀を解き放つためにやむを得ず、本来の体を捨てた。……もっと詳しく知りたいか?」
いつもとは別人のような顔で、イーレオが冷たく嗤う。
蔑みの響きをまとった、ぞくりとする低音。嘲りの対象は、シャオリエを犠牲にした過去のイーレオ自身だろう。
「……いや。今は、それはいい」
ルイフォンは、首を振った。
――本当は気になる。凄く、気になる。……だが、イーレオの古傷をえぐったところで、ルイフォンの好奇心が満たされる以外のなんの効果もない。
今回の目的は、あくまでも現状の整理。シャオリエの件は、もしも必要なときが来たら、改めて訊けばよいのだ。
「ただ、これだけは確認させてくれ。親父は今も、〈七つの大罪〉と裏で繋がっているのか?」
勿論、ルイフォンは、現在のイーレオは〈七つの大罪〉とは無関係だと思っている。
いまだに何かあるのなら、〈蝿〉に対して、ここまで遅れを取ることはないのだ。だから、これは皆を安心させるためのやり取りだった。
「完全に切れている。俺が総帥になって鷹刀が新しく生まれ変わり、〈七つの大罪〉と絶縁したときに、俺とシャオリエの〈悪魔〉としての活動も終わった」
「そうか。では、現在についての話をしよう」
そう言って進めようとしたとき、ルイフォンは中途半端にイーレオに近寄ったままのリュイセンに気づいた。兄貴分の気持ちは、手に取るように分かる。生真面目な彼からすれば、天地がひっくり返るような思いだろう。
ルイフォンは小さく咳払いをして、立ち尽くしたままのリュイセンに着席するよう、目で促した。それから「言っておくが」と続ける。
「親父が〈悪魔〉となった理由なら察しがついている。過去の鷹刀では、〈七つの大罪〉の内部にいたほうが、情報が手に入りやすかったんだろ?」
「そんなところだ」
イーレオは首肯して、ちらりとリュイセンとミンウェイを盗み見る。そして、彼らに言い聞かせるように、つけ加えた。
「俺は血族の者が〈七つの大罪〉の〈贄〉に捧げられるのを止めたかった。そのために、〈七つの大罪〉が何をしているのか。何故〈贄〉を必要としているのかを知りたかった」
それは遠い、若き日のイーレオの決意。
慈愛に満ちた思いは、昔も今も変わらない。如何にもイーレオらしい言葉だった。
「親父、信じていいんだな?」
「ああ、勿論だ」
イーレオが深く頷くと、安堵の息がふたつ聞こえた。――リュイセンとミンウェイの顔が明るんでいた。
皆が納得した様子に、ルイフォンはひとまず安心した。
場が落ち着いたのを確認すると、彼は口火を切る。いよいよ、ここからだ。
「では、改めて――。鷹刀イーレオ、答えろ。お前が〈悪魔〉だったということを、何故、俺に黙っていた?」
冴え冴えとしたテノールが、部屋の冷気を斬り裂く。静かな怒りをはらみながら、ルイフォンは更に語調を強めた。
「俺は情報屋〈猫〉。情報というものの価値を重んじる者だ」
彼は、ゆっくりと視線を巡らせ、イーレオを睥睨する。
「この俺を『対等な協力者』として迎えたのなら、お前が知っているあらゆる情報は、俺に開示すべきものだ。つまり俺は、軽んじられたと解釈する」
畳み掛けるルイフォンに、イーレオは「弁解の余地もない」と呟く。そして、気負いのない、少しだけ頼りなさげにすら見える顔で苦笑した。
「過去のしがらみに、若いお前たちを巻き込むべきではない。〈蝿〉に対しては年寄り連中だけで対処しよう、そう考えて口を閉ざした。――だから、ずっと黙っているつもりだったんだが、ユイランがキリファの遺した『手紙』があると言い出し、それから、メイシアに……まぁ、諭されてだな」
「えっ!?」
急に名を出され、メイシアが驚きの声を上げた。そして、イーレオが何を指して言っているのかに気づき、はっと顔色を変える。
ルイフォンの記憶が改竄されているのではないかと、イーレオと二人きりで話をしたときのことだ。そのとき彼女は『イーレオ様の役に立つ権利がある』などと、出過ぎた口をきいてしまったのである。
「イーレオ様。あのっ、その節は……」
慌てて頭を下げようとするメイシアを、ルイフォンは彼女の髪をくしゃりとして遮った。
ここは恐縮する場面ではない。逆だ。誇るべきところなのだ。
ルイフォンとしては、さすがは俺のメイシアだと、抱きしめたいくらいだったのだが、さすがに場をわきまえた。
そんな息子の胸中を見透かしたように、イーレオがにやりと笑う。だが、すぐに表情を引き締め、秀でた額に皺を寄せた。
「――……俺が〈悪魔〉であることを黙っていたのには、もうひとつ理由がある」
「もうひとつ……?」
微妙な雰囲気を感じとり、ルイフォンは不審げに眉をひそめる。
「〈七つの大罪〉は、もはや存在しないはずの組織だからだ」
「存在しないはず……だと?」
耳を疑った。
あり得ないことだった。
「お前が、現在の状況を『鷹刀と、〈七つの大罪〉との争い』だと考えているのだとしたら、それは違う」
「どういうことだよ?」
「俺が所属していた〈七つの大罪〉と、現在〈七つの大罪〉を名乗っている輩は、別の組織だ。なのに、『俺は〈悪魔〉だった』などと言えば、混乱を招くと思ったのだ」
「そんな、馬鹿な!」
ルイフォンは眉を吊り上げ、不可解な言葉を発したイーレオを視線で刺す。ぐっと身を乗り出すと、背中で金の鈴が転がった。
「〈七つの大罪〉は、なくなるはずがない……。何故なら……っ!」
次の句を、彼は一瞬ためらった。
今日ここに皆を集め、イーレオを問いただそうとした最大の理由を、こんな勢いのままに吐き出してよいものかと迷った。
けれど……問わずにはいられなかった。
「〈七つの大罪〉の正体は、王族の研究機関だろ!? なくなるはずがない!」
1.吊し上げの獅子-2

かつてルイフォンは、母親のキリファに尋ねた。
「結局のところ、〈七つの大罪〉って、なんなのさ? 語源は『キリスト教の教え』ってやつだろ?」
この大華王国において『神』といえば、天空の神フェイレンを指す。
輝く白金の髪と、澄んだ青灰色の瞳を有する神。この地上の、ありとあらゆる事象を見通す万能神だ。
創世神話によれば、フェイレン神は、この地を治めるために王族を創り出したらしい。だから、国民は黒髪黒目であるにも関わらず、『神の代理人』たる王は、神と同じ異色の姿をしているのだという。
つまり大華王国は、統治者が信仰の対象になっている宗教国家だ。
そんな国で『異教の教え』を組織名に使うのはナンセンス。否、不敬罪でしょっぴかれてもおかしくないのだから、これは大胆不敵と称賛すべきではないか、とルイフォンは思った。
勿論ルイフォンは、フェイレン神など信じていない。彼が信じるものは、自分自身だけだ。
問われたキリファは、キーボードを叩いた。〈七つの大罪〉に身請けされるまで文盲だった彼女は、大人になっても自らの手で文字を書くことが苦手だった。
1.Genetic modification 遺伝子を改造すること
2.Carrying out experiments on humans 人体実験を行うこと
3.Polluting the environment 環境を汚染すること
4.Causing social injustice 社会的な不公正を行うこと
5.Causing poverty 他人を貧困にすること
6.Becoming obscenely wealthy 悪辣に金を得ること
7.Taking drugs 薬物を濫用すること
「これが現代の『七つの大罪』。『新・七つの大罪』と、いわれるものよ。つまり、これらを犯す組織が、この国で〈七つの大罪〉と呼ばれている『闇の研究組織』」
知らなかったでしょう? と言わんばかりに、彼女は得意げに猫のような目を細めた。ルイフォンは少しむっとして、けれど素直に疑問をぶつけた。
「なんで、わざわざ異教の宗教用語を組織名に使うわけ?」
「うちの神様は自虐的な偽善者ってことでしょうね」
「わけが分かんないよ」
ルイフォンが不満げな顔をしても、キリファはただ曖昧に笑うだけだった。
――〈七つの大罪〉の正体は、王族の研究機関だろ!?
弾劾にも似た、ルイフォンの叫びが突き抜けた。
鋭いテノールが場の空気と摩擦を起こし、火花を散らす。冷気で満たされた部屋に、熱が生み出されていく。
その熱気は、何も知らされずにくすぶっていたリュイセンを焚き付けた。軽々と発火点を迎えた彼は、絶妙な比率から成る美貌を崩し、ぐっと眉をせり上げる。
「どういうことだよ!?」
罵るような声が発せられ、さらさらとした黒髪が肩の上で暴れる。
「ルイフォンは〈七つの大罪〉が王族の研究機関だと言い、祖父上は〈七つの大罪〉は存在しないと言う。滅茶苦茶だ。……それとも、俺だけが知らないのか?」
リュイセンがちらりと見やった先には、ミンウェイがいた。彼女は戸惑うように身じろぎ、首を振る。
「私は、父――〈蝿〉からは何も聞いていないわ。どちらかというと父は、私を〈七つの大罪〉から遠ざけたかったみたいだから……」
それから彼女は、ためらいがちにイーレオに顔を向けた。
「私は、父の役に立ちたくて、〈悪魔〉に名を連ねたいと言ったことがあります。猛反対されて、それきりなのですが――。けれど、少なくとも父が生きていたころは、〈七つの大罪〉は存在していたと思われます」
「親父、説明しろよ!」
ミンウェイの声にかぶさるように、ルイフォンが詰め寄る。
しかし――。
責め立てる若い世代の者たちに動じることなく、イーレオは穏やかな目をしていた。
彼は、静かに波が寄せるように一同を見渡す。そして最後に、長子たる次期総帥エルファンに目を留めた。視線を解したエルファンは、小さくそっと頷く。
「親父!」
「ああ、すまん。俺は〈猫〉に全面降伏だったな。だが、その前に訊いてもいいか?」
「なんだよ?」
主導権はこちらにあるはずだぞ、とルイフォンは睨みを利かせる。
「お前は何故、〈七つの大罪〉の正体が王族だと思ったんだ?」
「母さんは『女王の婚約が決まったら』、俺に『手紙』を渡すようにと、ユイランに託して死んだ。王族が無関係なはずがないだろ。それに、〈七つの大罪〉という、この組織名……」
「組織名?」
意外なことを聞いた、というように、イーレオはおうむ返しに呟く。
「ああ。唯一神フェイレンを崇めるはずのこの国に、異教を持ち込むことは『フェイレン神の否定』、つまり『王政に対する反逆』だ」
ルイフォンは、そこで一度、呼吸を整え、ゆっくりと続ける。
「けど、母さんは『うちの神様は自虐的な偽善者』と言った。『反逆』じゃなくて、『自虐』だ。――『フェイレン神の否定』が自虐になる者といったら、王族しかないだろう?」
「……ああ。そうだな」
「おそらく歴代の王たちは、〈七つの大罪〉の技術を使って、『神の奇跡』でも起こしてきたんだろう。つまり〈七つの大罪〉は、この国の王が、王として君臨するために作った『闇の研究組織』だ」
権力者の裏の顔など、いつの時代の、何処の国でもそんなものだ。別段、珍しくもない。
「あえて自虐的な名称をつけたから、母さんはそれを揶揄して『偽善者』と言ったんだろう」
「なるほど……」
「もういいだろ? 親父、真実を教えろ。〈七つの大罪〉は王族のための組織なんだろ?」
イーレオは――〈七つの大罪〉の〈悪魔〉である〈獅子〉は、ゆったりと腕を組んだまま、眼鏡の奥の瞳を閉じた。
「親父?」
無言の父を訝しみ、ルイフォンは顔を覗き込む。
「――!?」
次の瞬間、ルイフォンは目を疑った。
父が――、いつも超然と構えている父が、魅惑の美貌を苦痛に歪めていた。
呼吸は荒く、胸に手を押し当てている。びくりと肩が上がり、まるで心臓を握りしめるかのように指先を曲げた。こめかみの血管が浮き上がり、耐えるように背を丸める。
「な? なんだよ!?」
ルイフォンは顔色を変え、立ち上がった。一本に編まれた髪が、彼の背で勢いよくうねり、しかし、それ以上は進むことはできず、行き場をなくしたように垂れ下がる。
空調の冷気が、無言で頬を撫でていった。
彼はその風を冷たいとは思わなかったが、気化熱を奪われたことで自分が嫌な汗をかいていることに気づかされた。
部屋が、緊迫の色で満たされる。
それはまるで、薄氷で覆われた湖面。少しでも動いたら調和が乱れる。そんな本能的な恐れが、ルイフォンを襲う……。
「お前の言う通りだ」
無限かと思われた時が唐突に途切れ、沈黙の氷がぱりんと割り砕かれた。
「〈七つの大罪〉は、王の私設研究機関だ」
耳慣れた、低く魅惑的な声が抜けていく。しかし、玲瓏たる音色を響かせたのは……イーレオではなかった。
「エルファン……?」
父とそっくりな声質を持つ、異母兄エルファン。感情を伺いしれない凍てついた瞳がルイフォンを一瞥すると、医者であるミンウェイに、イーレオを診るよう指示を出す。
苦しげに肩で息をしながらも、イーレオは「大丈夫だ」と口の端を上げた。そこに、脈を取るミンウェイの「横になってください」との声が重なる。
「いったい、何が……?」
「これが……〈悪魔〉を支配する、『契約』、だ……。〈七つの大罪〉の……『秘密』を漏らそうと考えれば、こうなる……」
ルイフォンの呟きに、イーレオの荒い呼吸が答える。にやりと皮肉げに嗤う〈悪魔〉の〈獅子〉を、エルファンがひと睨みした。
「父上、余計なおしゃべりは無用です。あとは私に任せて、休んでいてください」
冷たく言い放つような口調だが、エルファンの険しい顔は確かにイーレオを心配していた。
「親父に、何が起きたんだ?」
「お前も知っているだろう? 〈悪魔〉となる代償に、〈神〉に逆らえないような『契約』をするという話を。〈七つの大罪〉と縁を切っても、『契約』は体の内部に――『記憶』に刻まれるから、永遠に消えることはないのだ」
「……!」
エルファンの言葉に、キリファの声が蘇る。
それは、おとぎ話の絵本などを読み聞かせてくれたことのない母が、彼に語った神話のような物語――。
〈悪魔〉は〈神〉から名前を貰い、潤沢な資金と絶対の加護、蓄積された門外不出の技術を元に、更なる高みを目指す。
その代償として、その体には『契約』が刻み込まれる。
ひとたび交わされれば、決して逃れることのできない『呪い』。犯せば、滅びは必ず訪れる……。
「親父は『話すことができない』のか。すまん……」
呆然としながら、ルイフォンは倒れ込むようにして椅子に腰を下ろした。
エルファンが大きく溜め息をつき、ルイフォンを見やる。
「お前とのやり取り次第では、父上はここにいる者を皆殺しにして、ご自身も自害なさる――なんて可能性もあり得た」
「……おい。そんな物騒なことだったのか!?」
「そうだ。お前は愚かにも、よく知りもせずに暴挙に出た」
氷の瞳が、冷たくルイフォンを突き刺す。つくづく、他人の神経を逆なでする言動が似合う異母兄である。
「そんなの、分かるわけないだろ!」
「確かにな。――だからこそ父上は、私に暗黙の指示を出していた。お前たちが『契約』に納得したら、私の口から話すように、とな」
「え?」
「私が語る分には無害であるし、既に漏れてしまった『秘密』についてなら、その後、父上が話題にしても問題ない。要は〈悪魔〉本人がバラさなければいいだけだ」
「ちょっと待て。どうして〈悪魔〉ではないエルファンが、〈七つの大罪〉の正体は、王の私設研究機関だ、って知っているんだよ?」
ルイフォンの当然の疑問に、エルファンは軽く腕を組み、くっと口角を上げた。怜悧な容貌がひときわ光彩を放ち、悪役然とした仕草が映える。
「私は〈七つの大罪〉に支配されていた時代の鷹刀を知っている。少しでも頭が回れば、自然に気づくさ」
「言いすぎですよ、エルファン様。行動力のあるエルファン様だからこそ、お分かりになっただけです」
後ろに控えていたチャオラウが、すかさず口を挟んだ。
それが決して褒め言葉などではないことは、含みのある物言いと、溜め息混じりに揺れる無精髭が物語っている。おそらく若かりしころのエルファンは、チャオラウをも巻き込み、危険を犯して調べ上げたのだろう。
「王族には、この濃すぎる鷹刀の血が必要であったらしい。我々は、奴らの家畜に過ぎなかった。私が知ることができたのは、そこまでだった」
エルファンはそこで言葉を切り、溜め息をつきながら視線を落とす。
「それ以上は、〈悪魔〉のみが知る王族の『秘密』だ。私も〈悪魔〉になると言ったのだが、父上に反対されてな」
「エルファンまで、この『契約』に犯される必要はないだろう?」
そう言いながら、イーレオが体を起こす。乱れた髪を、すっと手で撫でつけ、「久しぶりに、この感覚を味わったな」と自嘲気味に漏らす様子は、すっかりいつもどおりの彼であった。
ゆるりとソファーに背を預け、イーレオは優雅に足を組んだ。
「王族が何故、鷹刀からの〈贄〉を必要としていたかは、王族の『秘密』に抵触するから、俺は言うことはできない。……それより、お前たち。鷹刀の総帥となった者が〈贄〉を捧げる見返りとして、王族は――〈七つの大罪〉は、鷹刀に庇護を与えてきた、という話は、ユイランから聞いたよな?」
イーレオの言葉に、若い者たちが頷く。
「俺は自分が総帥になって、その関係を終わりにした。シャオリエを犠牲に、〈贄〉に代わるものを未来永劫提供することで、当時の〈神〉と――先王シルフェンと話をつけ、今後は互いに不干渉だと約束をした。だから、〈七つの大罪〉が鷹刀に手を出すことはないんだ」
「ですが、祖父上。現に〈七つの大罪〉が――〈七つの大罪〉が蘇らせた〈蝿〉が、鷹刀の前に現れ、我々に歯向かいました。これは、どう説明するんですか?」
リュイセンが遠慮がちに、しかし、決然と問う。だがそれは、イーレオによって誘導された質問だった。
イーレオは魅惑の微笑をこぼす。
「そこで、さっき俺が『〈七つの大罪〉は、もはや存在しない』と言った話に戻るわけだ」
「待て、親父。その話、『契約』は問題ないのか?」
下手なことを喋ったら、『死』ではないのか? と、ルイフォンは慎重になる。
そんな息子にわずかに目を細め、イーレオは泰然と首を振った。
「王族の『秘密』に触れなければ大丈夫だ。――それに、これは凶賊の総帥としての調査結果だ」
そう言ってイーレオは胸を張り、国中を見渡すかのように、遥か遠くを睥睨する。
「〈七つの大罪〉は、王の私設研究機関。そして、組織の頂点に立つ〈神〉は、この国の王だ。それは理解したな?」
底知れぬ深い色合いの瞳が一巡すると、皆が思い思いに頷く。
「その決まりでいえば、現在の〈神〉は、現女王であるはずだ。だが、女王の即位は、先王の急死によるものだ。当時、十一歳だった子供に、あの〈七つの大罪〉の存在が知らされていたとは考えられない。――〈神〉が不在になり、〈七つの大罪〉は消滅したはずだ」
「おい、そんな単純にはいかないだろ? そういうときは他の政務と同じように、摂政が〈神〉の代理を務めるんじゃないのか?」
ルイフォンが、慌てたように尋ねる。イーレオも言う通り、『あの』〈七つの大罪〉なのだ。簡単になくなるとは信じられない。
「〈七つの大罪〉は政務とは違って、神殿の管轄だ。摂政も、王が『闇の研究組織』を持っていることは知っていても、〈七つの大罪〉の実態は把握できてないはずだ」
「だったら、神殿のお偉いさんが〈神〉の代理をすればいいだろ?」
なかなか道筋の読めない話に、ルイフォンは苛立つ。目をすがめながら問うと、その言葉を待っていたとばかりに、イーレオの口の端がすっと上がった。
「それができなかったのさ」
秘密を打ち明けるような、囁くような低い声――。
「そのころの〈七つの大罪〉の運営は、先王が最も可愛がっていた腹心に一任されていた。――そして先王は、そいつに殺された」
「王が、殺された……!?」
衝撃的な言葉に、頭がついていかない。
しんと静まり返る中、イーレオの声だけが響いていく。
「そいつは捕らえられ、密かに幽閉された」
「幽閉……!? ――何故、処刑されない……?」
「『そいつ』が、先王の甥だったからだ。つまり王族だ。処刑どころか、ことを公にすることすらできなかったんだよ」
そういえば……と、ルイフォンは思い出す――。
あまりにも急な王の死に、当時は暗殺の噂が流れた。けれど、王族の圧力によってもみ消され、いつの間にか忘れ去られていったのだ。
「その状況で、〈七つの大罪〉が現女王に引き継がれたとは考えられんだろう? 瓦解したはずだ」
「……なるほど。親父が言うのも、もっともだ。……だが、何故そいつは先王を殺したんだ? 腹心って、ことは信頼されていたんだろ?」
「そこまでは俺も知らん。ともかく、現在の〈七つの大罪〉は、〈悪魔〉の残党が勝手にそう名乗っているか、先王の甥が組織を私物化したものか……。いずれにせよ、もはや俺の知らない組織だ」
「……っ!」
のんびりとしたイーレオの口調。――しかし、ルイフォンは、はっと顔色を変える。その反応に、イーレオが満足そうに目を細めた。
そこへ、ルイフォンほど情報通ではないリュイセンが、当然の疑問を投げる。
「甥が組織を私物化? そいつは、幽閉されているんですよね? どうやって……」
「いや。つい最近、奴は幽閉を解かれたんだ。――親父、そういうことだよな? 『先王の甥』って、そいつだな?」
鋭く質問してきたルイフォンに、イーレオは「ああ」と答える。
「幽閉を解かれた? 何故だ?」
リュイセンの問いに、ルイフォンはぐっと拳を握りしめた。
「……よく聞け。先王の甥――先王を殺し、今まで幽閉されていたそいつは……『女王の婚約者』だ」
「えっ?」
「公的には病気静養だったそいつは、婚約を機に表舞台に戻ってきたんだ……!」
「そんな!? 国王殺しの反逆者だろ!? なんで、そんな奴が女王の婚約者になれるんだ?」
激しい驚愕に包まれたリュイセンの声が、部屋の冷気を震わせる。しかし、答えられる者のいない問いかけは、閉ざされた空間の中で虚しく木霊するだけだった。
ルイフォンは唇を噛む。
自分の知らないところで、高度に計算され尽くした計画が走り出している。まるで彼をあざ笑うかのように、実に巧妙に……。
彼はまだ、それを読み解くことができないでいる――。
――女王の婚約を開始条件に、『デヴァイン・シンフォニア計画』は動き出す……。
2.謎めきのふたつの死-1

仕事部屋でのイーレオ吊し上げの会議から、数日後。
ルイフォンとメイシアは、〈ケル〉の家を訪れていた――。
閑静なたたずまいの郊外の一軒家。
ルイフォンが生まれ育ったその場所は、屋敷というほどには大きくはなく、しかし、ただの家と呼ぶには立派すぎる、そんな塩梅の住居であった。
門扉に仕掛けられた認証は相変わらずで、この家を管理するコンピュータ〈ケル〉が、いつも通りに無言で迎え入れてくれる。
そのまま、すぐにも屋内へと向かおうとするメイシアを誘い、ルイフォンは庭へと回った。鷹刀一族の屋敷にあるものほどの大樹ではないが、こちらにも見事な桜の木があるのだ。
花は終わってしまったが、代わって濃い若葉の香りが、全身を包み込む。
目に鮮やかな新緑と、そこからこぼれ落ちる木漏れ日。彼女と肩を並べて芝を歩けば、陽の光がまるで万華鏡のように、きらきらと形を変えながら輝きを放つ。
「すっかり、季節が変わったな」
ごくごく自然に、彼は自分の指先を彼女の掌の中に滑り込ませ、指を絡めて握りしめた。
「う、うん……」
彼女は、いまだに慌てたように顔を赤らめる。
けれどそのあとに続くのは、芽吹きを思わせるような、伸びやかな笑顔だ。黒曜石の瞳が愛しげに彼を見つめ、彼女の指先もぎゅっと彼を握り返す。
そして、ほんの少し。彼の肩に触れるか触れないかという、とてもわずかな距離であるが、彼に身を任せるように体を寄せた。
「メイシア」
名を呼ぶと、彼女は、ぱっと彼を見上げた。黒絹の髪がさらりと揺れ、艷やかな感触が彼の首筋をかすめる。
彼女が無意識に放つ色香に、彼はどきりとした。
匂い立つような稀有なる佳人。そんな言葉がぴったりくる。
彼は自信家だが、彼女に釣り合っていると思うほど、うぬぼれてはいない。けれど彼女は、彼を信じてついてきてくれる。
――だからこそ、彼女のことは大切にせねばと、改めて思う。
「思わず、お前を連れてきちまったけどさ……。よく考えれば、今回のことは俺がひとりで行けばいい案件だった」
彼女の覚悟を確かめず、ただひとこと『一緒に来てくれ』だけで、タンデムシートに乗せた。彼女の緊張を背中に感じながら、彼はバイクを走らせた。
「ごめんな。……お前は上の部屋で待っていてくれ。俺ひとりで、地下に降りるよ」
メイシアが気にしないように、ルイフォンは努めて柔らかく言う。しかし、彼女は驚いたように目を丸くした。
「どうして? 私が一緒じゃ駄目なの?」
「駄目ってわけじゃないけどさ……」
悲しげな眼差しのメイシアに、ルイフォンは口ごもる。
危険――ではない。
だが、今更かもしれないが、穢れなき彼女を、これ以上、血なまぐさい世界に引きずり込みたくないのだ。
「俺はこれから、母さんが殺されたときの『もうひとりの目撃者』と話をする。――母さんは、首を落とされて死んだ。その映像を……見ることになるかもしれない」
彼の言葉に、彼女は首を振る。
「それでもいい。私も行く。私自身が『ルイフォンのそばに居たい』と思っているから」
彼女は笑顔で答える。彼の心に負担をかけないようにしながら、応えてくれる。
「ルイフォンが居るから、平気なの」
そう言って照れたように、額をこつんと彼の胸に載せた。
ルイフォンの心が、ほわりと温かくなり、彼は彼女を抱きしめる。
「メイシア……。ありがとう」
桜花は流れ、青葉が茂る。
メイシアは、まさに桜の化身だと、ルイフォンは思う。
春風に巻かれ、舞い踊らされていた彼女が、今は薫風を浴びながら、鮮やかに瑞々しく華やいでいる。
「……お母様は〈ケル〉のそばで、その……亡くなられたのよね?」
彼の胸から聞こえる彼女の言葉は、遠慮がちに語尾が揺れていた。
それはルイフォンへの気遣いと――、おそらくは王族への畏敬。もと貴族の彼女は、信仰心とは別に王族への服従めいた感情があるらしい。
彼女自身、自分の中にあるその気持ちに気づいたのだろう。首を振って、言い直す。
「キリファさんは……シルフェン先王陛下に『殺された』のよね……」
ルイフォンは、硬い顔をしているメイシアの髪をくしゃりと撫でた。
「それを……確かめに行こう」
彼女の緊張がわずかに緩み、「はい」という声が凛と響く。
そして、ふたりは歩き始める。
キリファの死の真相を知る『目撃者』――地下にいる〈ケル〉に会いに……。
先日ルイフォンは、〈七つの大罪〉や王族について、いろいろと隠しごとをしていたイーレオを問い詰めた。
その流れの中で、先王は腹心だった甥に殺されたとこと、反逆者である甥は一度は幽閉されたものの、『女王の婚約者』として表舞台に戻ってきたことが語られた。
――如何にもきな臭い、この甥こそが、現在の〈七つの大罪〉を牛耳っている人物に違いない……。
それでお開きになる――と思われた。
そのときだった。
唐突にメイシアが「待ってください」と、慌てたように手を挙げたのだ。おとなしい彼女にしては、珍しいことだった。
皆が驚く中、彼女はおずおずと口を開く。
「殺された先王陛下には、殺されるだけの『罪』があった、ということはございませんか?」
出過ぎた真似をと恥じ入るように、そして先王に対して恐れ多いことをと身を固くしながらも、彼女はきっぱりと言い切った。
一同の注目の視線が、困惑を帯びる。彼女の言わんとしていることを理解できなかったためだ。
メイシアは自分の言葉の足りなさに気づき、顔を赤らめた。恐縮に肩を縮こませ、ペンダントをぎゅっと握りしめる。
「鷹刀から見れば、先王陛下はイーレオ様との話し合いにきちんと応じ、一族を〈七つの大罪〉から解放することを認めた人物です。悪い印象の方ではありません。殺されたとなれば『被害者』と感じるでしょう。けれど……」
そこでメイシアは、曇りなき黒曜石の瞳で、まっすぐにイーレオを捕らえた。
「先王陛下は、甥に対して、殺意を抱かれても仕方ないほどの『罪』を犯していた、というふうには考えられませんか? ――先王陛下は、決して善人ではないのですから。……それは、イーレオ様もご存知でしょう?」
「メイシア?」
常とは違う彼女に、ルイフォンは戸惑う。
メイシアの声は、緊張を帯びながらも澄み渡り、揺らぐことはなかった。
「先に、ルイフォンと相談してから、お尋ねしようと思っていました。……けれど、先王陛下のお話が出たので、今、お訊きしてしまいます。――イーレオ様。なにとぞ、お答えください」
メイシアは一度、言葉を切り、イーレオに喰らいつくような視線を向けた。
「ルイフォンのお母様――キリファさんを死に追いやったのは……シルフェン先王陛下ではありませんか?」
ルイフォンは一瞬、呼吸を忘れた。
頭の中が真っ白になる。
「……イーレオ様のお話からすると、そうとしか考えられないんです」
隣りにいるはずのメイシアの声が、遠くに聞こえた。
ルイフォンは、はっと思い出す。
彼女は、イーレオは〈悪魔〉なのではないかと彼に告げたとき、こうも言っていた。
『イーレオ様のお話を繋ぎ合わせると、キリファさんは〈七つの大罪〉の頂点に立つ〈神〉という人に殺された――そういうことになるの』
〈七つの大罪〉は、王の私設研究機関で、その頂点に立つ〈神〉は、この国の王である。
そして、母が殺された当時の国王は、先王シルフェン――。
普段の彼ならば、すぐに気づいたはずだ。それなのに、記憶の改竄のせいなのか、母の死に関する情報への感覚が、まるで目隠しをされているかのように鈍い。
「親父、本当なのか……!?」
ルイフォンは血相を変えて立ち上がり、イーレオの表情を読み解く。
イーレオは凪いだ目をしていた。その意味を考え、ルイフォンの心臓は早鐘を打つ。
母は〈天使〉だった。しかも〈堕天使〉として〈猫〉の名まで与えられていた。〈七つの大罪〉の〈神〉であった先王とは面識があったはずだ。
「母さんは、王に殺された……」
どんな事情があったのかは分からない。けれど、充分にあり得る……。
「ルイフォンが陛下のお姿を見たのなら、キリファさんが記憶を改竄したのも納得できます。仇を討てるような相手ではありませんし、それよりもユイランさんに預けた『手紙』にあとを託していたのだと思います。……イーレオ様、どうか教えてください」
遠慮がちでありながらも強い意志を感じるメイシアの細い声が、そう締めくくる。
――そして次の瞬間、ルイフォンは左手にぬくもりを感じた。
「!?」
立ち上がっていた彼の手を、メイシアの両手がそっと包み込んでいた。優しい手つきに、彼は今、自分がどんな顔をしているのかを察する。
「あぁ……」
我を忘れるところだった――。
こんな重要な局面で、冷静さを失っては、自慢の頭の回転も台無しだ。
ルイフォンは目元を和らげ、右手でメイシアの頭を撫でた。それから、何ごともなかったかのように、すとんと着席する。
それを見届けると、イーレオはゆっくりと告げた。
「メイシアの言う通りだ。――キリファは、先王シルフェンに殺された」
深く響く、魅惑の低音。
はっきりとした断定に、ルイフォンの全身が粟立つ。だが彼は、努めて平静を保ち、軽い口調で言い放った。
「さすがメイシアだ。お前は、本当に賢いな」
「ルイフォン……」
彼女の目は、涙目になっていた。こんな大事なことを相談なしに言い出して、申し訳ないと思っているのだろう。
そんなことはないのだ。
まったく、彼女らしくて――愛おしい。
メイシアの髪をくしゃくしゃと撫で回すと、いつもの自分が返ってくる。心が研ぎ澄まされ、思考が鋭く巡り始める。
「つまり、殺されたからといって、先王が『善』で、被害者とは限らない。きな臭いのは甥のほうじゃなくて、先王かもしれない――」
メイシアが、小さく頷いた。
「しかも、母さんが殺されたのは四年前。先王が殺されたのも四年前――母さんが殺された少しあとだ。このふたつの死には、何か関係がありそうだ……」
ふたつの死には、なんの意味があるのか。
必ず真実を突き止め、すべてを明らかにしてやる……!
ルイフォンは好戦的に嗤う。そこへリュイセンが、不機嫌極まりないという顔で口を挟んだ。
「けど、先王の甥が、先王を殺したのなら、やはり奴が現在の〈七つの大罪〉を牛耳っている可能性が高いわけだろう? つまり、〈蝿〉を蘇らせて、鷹刀を襲った『黒幕』ってことだ。甥が胡散臭いことに変わりはない」
兄貴分の強い憤慨に、ルイフォンはややも鼻白む。しかし彼が口を開くよりも前に、メイシアがさっと答えた。
「ええ。そうなります」
そして彼女は、再び遠慮がちにイーレオに尋ねる。
「だからイーレオ様、教えてください。キリファさんは何故、先王陛下に殺されなければならなかったのでしょうか。その理由が分かれば、先王陛下のことが少しは理解できるかと思います」
メイシアの真剣な眼差しが、イーレオを刺す。
それを受けたイーレオは、肩で深い息をついた。
「すまんな」
低く呟く。はらりと顔に掛かった黒髪が、妙にやつれた様相を醸し出し、彼の実年齢を垣間見せる。
「俺は無力で……いまだに何も知らんのだよ」
「なんだって?」
ルイフォンの声が跳ね上がった。続いてメイシアも、焦ったように問う。
「イーレオ様は、詳しい経緯をご存知だったのではないのですか? それなら何故、キリファさんを殺害した相手を知っているのですか? 現場にいたのは、ルイフォンだけだったはずです……!」
「それは……」
ためらうような顔で、イーレオはエルファンに視線を移す。
エルファンは、ぴくりと眉を動かした。だが、感情のようなものを見せたのはそれきりで、麗しの美貌から表情を消し去る。
彼は姿勢を正し、落ち着き払った素振りで長い指を優雅に組み合わせた。そして、美しくも冷たい、氷のような声を落とす。
「あの場にいたのは、ルイフォンだけではない」
「えっ?」
ルイフォンが驚きの声を上げる。
「――〈ケル〉だ。あの家の警護を任されたコンピュータ、あの家のすべてを知る『もの』が、駆けつけた私に教えたのだ……」
2.謎めきのふたつの死-2

四年前の、その夜――。
ルイフォンは、けたたましい警報音に叩き起こされた。
部屋を出て階下に降りると、警護の男たちが殺されていた。――強盗の類だと、彼は思った。
物音をたどって地下に行くと、母親のキリファがいた。
顔を隠した男と、何かを言い争っているようだった。
そして、刀が振り上げられる。
白刃が、ぎらりと煌めく。
母の首元を飾っていた革のチョーカーが斬れ、金の鈴が飛んだ……。
目が覚めたら、繁華街にあるシャオリエの娼館にいた。誰かが、彼を家から運んだらしい。
頭が重く、靄がかかったように記憶が曖昧だった。
ふと彼は、自分の拳が固く握られたままであることに違和感を覚えた。一本一本、指を引きはがすように開いていく。
開かれた掌の上に、金色の光が広がった。
母が、肌身離さず身につけていた――鈴、だった。
「キリファの家の異変は、〈ケル〉が、鷹刀の屋敷にある〈ベロ〉の警報器を鳴らしたことによって伝わり、私が駆けつけた」
「エルファンが……?」
静かな異母兄の言葉に、ルイフォンは思わず目を見開いた。
確かに母は、かつてはエルファンの愛人だった。しかし、仲がこじれてそれきりと聞いている。だから、てっきりイーレオが駆けつけたものと思っていたのだ。
「そこに残されていたのは、意識を失ったルイフォン――お前と、大量の血痕。そして、ふと気づくと、近くにあったモニタに、防犯カメラが撮っていたと思われる『犯行現場』が映し出されていた」
「――そんな、都合のいい……?」
そう口走り、ルイフォンは「あっ」と叫ぶ。
「〈ケル〉か! 〈ベロ〉の兄弟なら、状況判断ができるはずだ。それで、何が起きたのかをエルファンに伝えようと……」
「そういうことだろう。あのときの私は、偶然にしては都合が良すぎると気づけなかったがな」
「その映像によって、先王が母さんを殺したと分かった、ということか……」
知らずに噛んでいた唇が切れ、口の中にざらりと血の味が広がった。ふつふつと、怒りが湧いてくる。
ルイフォンは、見たはずなのだ。
エルファンが記録された録画で見たものを、この目で見たはずなのだ。
なのに、いくら懸命に記憶をたどっても、刀を振り上げたあの男の顔は朧気で、紗が掛かったように判然としない。
「これが、〈天使〉の力……か」
拳を握りしめる。
王を相手に無謀な仇討ちを仕掛けないよう、息子を守ろうとした母の愛は、復讐心にすら蓋をした。人づてに聞いて、やっと正しく湧き出た憎悪が、不甲斐なくてたまらない。
「あの夜。〈ケル〉の警報器がけたたましく鳴り響いて、俺は起こされた。部屋を出たら警護の者が殺されていて……」
「ルイフォン?」
エルファンが咎めるような声を発した。見れば、怪訝な顔でこちらを見ている。
「なんだよ?」
「お前の記憶では、警報器が鳴って、警護の者が殺されているのか?」
異母兄の不可解な質問に、ルイフォンはぽかんと口を開け、続けて息を呑む。
「現実は、違うのか……!?」
「ああ。あの日キリファは、警護の者たちに暇を出していた」
「……!?」
心臓が、大きく脈打った。
信じられない証言だった。
「〈ケル〉も、先王を客として迎え入れていて、警報を鳴らしていない。〈ケル〉が〈ベロ〉の警報器を鳴らしたのは、タイミングからして、キリファが殺される直前だ」
「……それじゃあ母さんは、……先王と約束をしていた……」
「そうなるな」
「そんな……、先王は強盗を装って、母さんを殺しに来たんじゃ……」
ルイフォンは、母親譲りの癖の強い前髪を掻き上げた。
母は、なんのために先王を招いたのだろう?
先王は、どうして母に会いに来た?
……それは、王の地位にある者が王宮を抜け出て、自ら出向くほどの用件なのだ――。
「そうだ、会話の記録は!? 俺の記憶では、母さんと侵入者が何かを言い争っていた。あれが偽の記憶でなければ、カメラの録画記録にはそのときの会話が残されていたはずだ」
期待を込めて、ルイフォンはエルファンを見つめ……恐怖を覚えた。
映すものすべてを凍りつかせるような、冷たい瞳――。
「先王とキリファは、確かに何かを話していた。……その話し合いの末に、王が抜刀した」
「エルファン?」
ルイフォンの不審の声に、エルファンは何かを払うように首を振った。だが、膝の上で組んだ彼の指先は、強く握りしめすぎて白くなっている。
「私が見た――〈ケル〉に見せられたのは、音声の入っていない、映像のみの記録だった。だから、会話内容は分からん。キリファの死の真相は、いまだに謎に包まれたままだ」
「……そうか」
ルイフォンは肩を落とす。
そこに追い打ちをかけるかのように、エルファンが「しかも――」と、続ける。
「父上にご確認願おうと、記録を持ち帰ろうとしたのだが、そのときには既に上書きされて消されていた」
「なっ!? 〈ケル〉が故意に消した……? 何故だ……?」
「あのコンピュータについては、お前のほうが専門だろう?」
吐き捨てるように言って、エルファンは溜め息をつく。話はそれだけだ、ということらしい。大事なところが分からずじまいとなったルイフォンは、ぎりっと奥歯を噛む。
ルイフォンの隣から「あのっ……」と、申し訳なさそうなメイシアの声が上がった。
「エルファン様……、その……すみませんでした。……ルイフォンも……」
「ん? どうして、お前が謝るんだ?」
「だって、ルイフォン。もとはといえば、『先王陛下の甥』についてのお話をしていたはずなのに、私がキリファさんと先王陛下の件を持ち出したりして……」
そう言いながらも、彼女の視線は迷うように揺れている。
ルイフォンは、ピンと来た。メイシアが理由もなく、混乱を招くような発言をするわけがないのだ。こういうときの彼女には後押しが必要だ。
「何か、あるんだろ? 言ってみろよ」
できるだけ、さりげなく促す。
メイシアはわずかに逡巡し、けれど頷いた。
「実は……、先王陛下の甥、ヤンイェン殿下は、私の再従兄妹にあたる方です。――私の父方の祖母が、ご降嫁された王女殿下なんです」
「っ……?」
ルイフォンは虚を衝かれた。
メイシアが王族の血を引いているなんて、初耳だった。貴族であることは分かりきっていたが、王族との繋がりなど、まったく考えたこともなかった。
「お前……ひょっとして、女王とも血縁なのか……?」
ルイフォンの驚きに、メイシアは気後れした様子で「はい」と小さく答え、皆に向かって改めて告げる。
「私は、女王陛下とも再従姉妹の関係にあります。ですが、数多の貴族のひとりに過ぎず、陛下と血縁を名乗れるような者ではありません。けれど、ヤンイェン殿下は……」
「何か、あるのか?」
ルイフォンの言葉に、メイシアが遠慮がちに頷く。
「立場としては雲の上のような方ですが、少しだけ親しくお声を掛けていただいておりました」
「親しく……?」
メイシアに妙な下心を抱いていたのかと、険悪な顔になる。それに気づいた彼女は、ふるふると首を振った。
「あの方は、浮世離れした不思議な方で、……父に、興味がおありだったんです」
「親父さん……?」
「平民と再婚した父に対して、『藤咲の当主はロマンチストだ。憧れるね』――と。貴族の社会で異端視されていた、平民の血を引くハオリュウにも好意的でらっしゃいました」
まるで知らない、別世界のメイシアを見せつけられ、ルイフォンは衝撃を受けた。現在の彼女とはもはや関係ないはずだが、やはり何も思わずにはいられない。
「すみません。だから私、ヤンイェン殿下を悪く思いたくなくて……余計なことを言いました。申し訳ございません」
深々と頭を下げ、メイシアは言葉を終えた。
――なんとも言えぬ、微妙な空気が流れる。
その居心地の悪さに耐えかねたように、どことなく、ばつの悪そうなリュイセンが「すまんな」とメイシアに声を掛けた。
「だが、メイシア。先王の甥――ヤンイェンというのか? ……そいつは、どう考えても疑わしい。奴は国王殺しのくせに、幽閉を解かれて女王の婚約者に収まった。権力を狙う野心家にしか見えない」
「――ええ。現状を考えると、リュイセンの言う通りだと思います。けど……」
メイシアは困ったように口ごもり、けれど続けた。
「ヤンイェン殿下は、女王陛下がお生まれになられたときから、第一の夫候補でした。十歳以上もお歳が離れてらっしゃいますが、血統的にあの方以上の方はいらっしゃらないからです」
「なんだって!? それじゃ、もともと女王に次ぐ権力が約束されていた、ってことか!?」
リュイセンの驚愕の叫びに、メイシアは首肯する。
「なんだよ、それ!? わけが分からん! 先王に腹心として気に入られていて、未来の女王の夫の座も内定していて――それなのに何故、ヤンイェンは先王を殺したんだ?」
リュイセンが首をかしげる。けれど、それにはメイシアも答えられなかった。
空調の冷気が、すっと部屋を横切る。わずかな風音がやけに大きく聞こえた。
イーレオがぶるりと身を震わせ、「この部屋は寒すぎるぞ」と、ぼやいた。
「〈猫〉、そろそろ、お開きでいいか?」
イーレオは、ルイフォンに尋ねる。
既に、どうでもよさそうなことだが、ルイフォンが『鷹刀の対等な協力者』〈猫〉として皆を集めていたので、イーレオは礼儀を通して『〈猫〉』と呼んだのだ。
しかし、ルイフォンからの返事はなかった。彼は椅子の肘掛けに頬杖をつき、頭の中を異次元に飛ばしていた。
「母さんの死と、先王の死――。ふたつの死には、どんな意味があったのか……」
誰に言うわけでもなく、うつむき加減にルイフォンは独りごちる。
「おい、〈猫〉!」
やや高圧的にイーレオが呼びかけると、ルイフォンは顔を上げ、にやりと不敵に嗤った。
「確かに、これ以上、ここで考えていても仕方がない。お開きだ。――だがひとつ、俺がやるべきことを思いついた」
ルイフォンは鋭い視線を巡らせ、一同を見やる。
「〈ケル〉に話を聞きに行く」
「〈ケル〉に!?」
そう叫んだのはリュイセンだったが、皆、同じ思いだった。
「あいつは、母さんと先王のやり取りをすべて見ていた。――あいつはこの屋敷の〈ベロ〉の兄弟機だ。人間並みの判断力を持った人工知能が隠されているはずだ。あいつに、教えてもらう」
「そんなことできるのか? だって〈ベロ〉はあのあと、お前がいくら呼んでも出てこなかったんだろう?」
なかなか嫌なことを言ってくる兄貴分に、ルイフォンは顔をしかめる。
「ユイランから受け取った、母さんの『手紙』。あれは同じシステムである〈スー〉のプログラムと、〈ケルベロス〉の解説書だ。あれを読んで、〈ケルベロス〉の扱いが少しだけ分かったんだよ」
まだほんの触りしか理解できていないが、それでもやれるはずだ。ルイフォンは口角を上げる。
「簡単には出てきてくれやしないだろうが、この俺が相手だ。必ず〈ケル〉を引きずり出してやる。――ということで、解散!」
ルイフォンは勢いよく立ち上がる。それに応えるように、彼の背で金色の鈴が大きく跳ねた。
そして今――。
ルイフォンはメイシアを伴い、かつて母と住んでいた家に来ている。
彼はメイシアの手を握り、地下に向かう。
ゆっくりと階段を降りる足音が、閉ざされた空間に響いた。
3.冥府の警護者-1

かつん、と靴音を鳴らし、ルイフォンとメイシアは地下通路に降り立った。
照明は点けられているものの、どこか薄暗い感は否めない。緊張するメイシアを引き寄せ、ルイフォンは肩を抱くようにして奥に進む。
ほどなく、〈ケル〉の収められた部屋の前にたどり着いた。
挑みかかるように瞳を光らせ、彼は分厚い扉を力強く開け放つ。
「……っ」
封じられていた冷気が解放され、波濤のように押し寄せる。
と同時に、〈ケル〉本体と冷却装置が生み出す、激しい振動の二重奏が襲いかかってきた。
「……いつものことだけど、ここは人間の来るところじゃねぇな」
軽口を叩くルイフォンの声も、騒音とも言うべき機械音に、半ば掻き消される。
彼には馴染みの場所であるが、メイシアにとってはまだまだ物珍しいらしい。今日、初めて見たというわけではないのに、部屋を埋め尽くす〈ケル〉の巨大な筐体に圧倒され、溜め息をついていた。
鷹刀一族の屋敷にある兄弟機〈ベロ〉と同じく、〈ケル〉もまた小さな家一軒分くらいの床面積を持つ。そして、それに見合った放熱量を誇るため、専用の冷却装置を備えていた。そんな重量と騒音の問題から、『彼ら』は地下に設置されているのだ。
普段は〈ベロ〉は仕事部屋から、〈ケル〉はこの家の別の部屋から遠隔操作している。しかし、今回は特別だった。
母キリファの『手紙』によれば、〈ケル〉のすぐそばにある操作卓からのみ、人工知能の〈ケル〉――真の〈ケル〉に強制アクセスできるというのだ……。
「メイシア」
ルイフォンは彼女の名を呼び、操作卓を示した。
おそらく、騒音に負けて声は届いていなかったろう。けれど彼女は気配に頷き、彼についてくる。
回転椅子にどっかりと座ったルイフォンがモニタと向き合うと、メイシアが隣の椅子にちょこんと品よく腰掛けた。
「それじゃ、〈ケル〉を呼び出すか」
ルイフォンは、にやりと笑い、おもむろにOAグラスを鼻に載せる。
「ねぇっ……」
メイシアが遠慮がちに彼の袖を引いた。声は聞こえていなかったが、彼女の口の動きから、たぶんそう言ったのだろうと思う。
「なんだ?」
叫ぶようにして言葉を返すと、メイシアは彼に寄り、耳元で尋ねた。
「先王陛下とキリファさんは、本当にこの部屋で話をしていたの?」
「……!」
ルイフォンは息を呑んだ。
この騒音の中では、まともな会話が成立するはずがない。
はっきりと顔色を変えた彼を捕らえ、メイシアの黒曜石の瞳が不安げに揺れた。
OAグラスに反射した青白いモニタの光が、ルイフォンの肌の色の彩度を落とす。いつもの豊かな表情は鳴りを潜め、端正だが無機質な容貌が浮かび上がる。
――彼のもう一つの顔、〈猫〉。
座っているだけのメイシアは面白くもないだろうに悪いな、などと最初は気にしていたルイフォンだが、いつの間にか彼女のことも騒音のこともすっかり忘れていた。実に彼らしいことである。
メイシアも、ちゃんと心得ていて、邪魔にならないようにおとなしくしていた。それでいて、たまに、持参したお茶を絶妙なタイミングで差し入れるのだった。
ルイフォンが操作卓に向かってから、小一時間。
状況は芳しくなかった。
あの『手紙』の通りなら、とっくに〈ケル〉が応えているはずだった。
彼は癖のある前髪を、くしゃくしゃと掻き上げる。
まだまだこれからだと思いつつも、疲れを隠しきれなくなってきたころ――すなわち、集中力が途切れかけて初めて、ルイフォンはメイシアが何か言いたげな顔をしていることに気づいた。
作業中の彼には、彼女は決して声を掛けない。
ルイフォンはOAグラスを外し、小休止を示した。
「どうした?」
「ルイフォン」
騒音の中に落とされた小さな呟きは、実際には聞き取れなかったのだが、彼女の顔を見ていれば分かる。彼の名を呼ぶときは、いつだって彼女は嬉しそうなのだ。――と、彼は自負している。
「何かあるんだろ? 言ってみろ」
「この部屋で、先王陛下とキリファさんが話をしたというのは、やはり無理があると思って。それで……」
先ほどの疑問を、彼女はずっと考えていたらしい。
言いにくいことがあるのだろう。萎縮したような上目遣いになる。
そうしないと声が通らないからだが、彼女はおずおずと彼の耳元に唇を寄せた。空調で冷やされた耳朶に、温かな、彼にとっての癒やしの息が掛かる。
けれどそれは、彼女のためらいの吐息でもあった。
「エルファン様は……、先王陛下とキリファさんが〈ケル〉のそばで話をしていた、とはおっしゃっていない。――そう言っているのは、ルイフォンだけなの……」
「……!」
「私、気になって……それで、さっきエルファン様に確認したの。……勝手に、ごめんなさい」
メイシアが差し出した彼女の携帯端末を、ルイフォンは半ば奪うようにして受け取った。食い入るように履歴を見つめる彼の耳に、同じ内容がメイシアの声で囁かれる。
「この部屋の隣に、お母様が休憩をとられるときに使ってらしたお部屋があるのでしょう? ――エルファン様は、そこだと……」
「俺の記憶が、偽りだと……?」
母の最期の瞬間は、〈ケル〉のそばのはずだ。
改竄の疑いがある記憶を拠り所にしても、説得力などまるでないのだが、ルイフォンの中の何かが、頑なにそう告げる。
けれど、メイシアの言う通り、この場所では会話などできない。
体中に響く振動は、慣れているルイフォンですら神経を逆なでされる。メイシアが初めてここに来たときには、耳鳴りがするとさえ言っていた。この家の主であった母ならともかく、先王が落ち着けるわけもない。
だから、エルファンの証言は正しい。そう、認めざるを得ない……。
「また、母さんかよ……! なんだよ! いったい、なんなんだよ!?」
ルイフォンは乱暴に操作卓に手をつき、勢いよく立ち上がった。彼が座っていた回転椅子が後ろに突き飛ばされ、からからと音を立てて回る。
母の遺した『手紙』が、彼を翻弄する。〈ケル〉は、魔術師だった母の使い魔でしかなく、彼の言うことを聞かない。
母は、彼のものであるはずの記憶を勝手に奪う。情報を改竄されるおぞましさは、クラッカーである彼にとって何よりも許しがたい。
何を信じたらいいのか、分からない。
何をしても、結局、母に踊らされる。……母に、敵わないような気がしてならない。
「畜生……!」
「ルイフォン!」
操作卓を叩こうとした拳を、白い手が止めた。彼を操作卓から引き剥がすかのように、華奢な体が胸に飛び込んでくる。
「お母様は、ルイフォンを悪いようにしない!」
彼をきつく抱きしめ、彼女が叫んだ。触れ合った体を通じて、〈ケル〉の騒音よりも確かな振動で言葉を響かせる。
「必ず、意味があるはずなの! お母様を信じて……」
シャツ越しにも分かる肌の熱と共に、早鐘のような鼓動が伝わってくる。
彼女の存在を、全身で感じる。
「メイシア……」
うつむいた彼女の首筋で、長い髪が左右に分かれた。小刻みに震える肩にあわせ、うなじの白さがちらちらと見え隠れしていた。
「差し出がましいことを……ごめんなさいっ」
美しい歌だけを歌うように育てられた鳥籠の小鳥は、大空を羽ばたくようになった今も、警告のさえずりは得意でない。
慌てて離れようとする腕を捕まえ、ルイフォンはメイシアを抱き寄せた。
「すまん」
視野が狭くなっていた自分を恥じる。
彼は、艷やかな黒髪の中に指先を滑り込ませ、彼女の頭をくしゃりと撫でた。
「〈ケル〉へのアクセスに難航していて、苛立っていた」
ルイフォンは、胸元にメイシアを掻き抱く。強い力に驚いたメイシアが小さく悲鳴を上げる。けれど構わず、黒絹の髪に頬を寄せた。
「俺にとって母さんは、乗り越えるべき壁みたいなもので……。だから、つい感情的になった。すまない。……ありがとな」
いつの間にかメイシアとエルファンがやり取りしていたことも、心穏やかでない原因だったのだが、それは見苦しい嫉妬なので口には出さない。
「私こそ、ごめんなさい。……お母様の最期を見届けたルイフォンの記憶を――気持ちを踏みにじってしまったと思うの……」
「いや……。お前の言う通り、母さんが俺の記憶をいじることに、なんか意味があるんだろ」
そう呟いたとき、ルイフォンは、はっと思い出した。
『記憶の改竄』について、メイシアが初めて彼に話したときの言葉を――。
『亡くなる直前のキリファさんがルイフォンの記憶を改竄したのなら、それはつまり、ルイフォンは見てはいけないものを見たんだと思う』
獲物を捉えた猫のように、ルイフォンの目が鋭く光った。
徐々に口角が上がり、不敵に笑う。先ほどまでとは打って変わった、覇気あふれる顔つきだった。
「ルイフォン?」
急に気配の変わった彼に、メイシアが首をかしげる。
「……解けたよ、メイシア」
「え?」
「俺が〈ケル〉のそばにこだわった理由と、母さんが部屋の記憶を改竄した理由。そして俺が今、〈ケル〉の強制アクセスに失敗している理由も、すべて分かった」
立て板に水を流すように、ルイフォンは言った。
隣の部屋に行って確認しないことには断定できないが、おそらく間違いない。気がつけば、実に単純なことだった。
「俺は、隣の部屋で母さんと先王が言い争っていたとき、先王の顔以外にも『見てはいけないもの』を見たんだ」
「何か、思い出したの?」
メイシアが気遣わしげに尋ねてくる。思い出したくない記憶だろうと、心配しているのだろう。ルイフォンは彼女の髪をくしゃりとした。
「思い出したわけじゃない。けど、前にお前が言ったろ? 母さんは俺が『見てはいけないもの』を見たから記憶を改竄したんだ、と」
「あ、うん……」
けれど、ではいったい何を見たのかと、メイシアの瞳が問うている。
「〈ケル〉だ。――俺は、隣の部屋で〈ケル〉を見たはずだ。それしか考えられない」
「〈ケル〉? 〈ケル〉なら……」
ここにあるでしょう? と言い掛けて、彼女の瞳が見開かれた。聡明な彼女もまた、気づいたのだ。
「そう……〈ケル〉と呼ばれる『もの』は二台ある。張りぼての〈ケル〉と、真の〈ケル〉が。――ここにあるのは、張りぼての〈ケル〉。そして隣の部屋に、真の〈ケル〉がいる……」
メイシアの喉が、こくりと動いた。緊張に彩られた顔貌が、じっとルイフォンを見つめる。
「母さんは〈ケル〉のそばで死んだ。俺の記憶は正しいんだ。――ただし、ここにある張りぼての〈ケル〉ではなく、隣の部屋の真の〈ケル〉のそばで、だ」
〈七つの大罪〉の技術で作られた真の〈ケル〉が、どんな姿をしたものか、ルイフォンは知らない。それでも、母の最期は『〈ケル〉のそば』と、正しく心に刻まれていたのだ。
「そして、〈ケル〉のそばの操作卓からなら強制アクセスできる、って話のからくりも、それだ。隣の部屋の操作卓を指していたんだ」
母は、ルイフォンが勘違いすることを期待していたに違いない。彼そっくりの猫のような目を細め、ふふんと笑う顔が浮かんでくる。
からかいを含んだ眼差しで、『あんたなんて、まだまだね』と。
――けれど同時に、彼が読み解くことを信じていたはずだ。そうでなければ、わざわざ『手紙』に書き残したりしないのだ。
「お前のおかげだ」
ルイフォンは腕の中のメイシアをぎゅっと抱きしめ、口づける。相変わらず、白磁の肌をさぁっと染める彼女に苦笑しながら、彼は瞳を巡らせる――隣の部屋へと。
「行くぞ!」
ルイフォンはメイシアと手を取り合い、歩き出した。
3.冥府の警護者-2

部屋の外にある照明のスイッチを入れ、ルイフォンは分厚く頑丈な扉を、体重をかけるようにして押し開けた。
メイシアの手を引き中に入り、また閉じる。
すると、今まで感じていた振動がぴたりと収まった。すぐ隣で――続き部屋であるので、本当に壁一枚を隔てた向こうがわで、〈ケル〉がうなりを上げているにも関わらず、まったく音も揺れも感じない。
「凄い防音壁だな……」
母のキリファが、休息を取るのに使っていた小部屋――。
仮眠をとるのが主な目的の部屋であるから、壁が厚いのは当然、といえば当然かもしれない。
実はルイフォンは子供のころ、ここは入ってはいけない場所だと思っていた。理由は簡単で、扉が重すぎた。入りたくても入れなかったのである。
大きくなってからは、そんなことはなかったのだが、無意識の遠慮があった。それは、ただのすり込みで、けれどそのために、この部屋は盲点だった。まさに、真の〈ケル〉の隠し場所にふさわしい。
「……母さん、狙っていたな」
厳重に隠すのではなく、見える状態にしておきながら、気づかないルイフォンを鼻で笑う。なんとも、あの母らしい気がする。
そんな感慨にふけっていると、メイシアの視線を感じた。
「ああ、すまん。ちょっと思い出してな」
「ルイフォン、嬉しそう。……よかった」
何を思い出していたのか説明しなくても、彼女は分かっている。そして、先ほど母への苛立ちを爆発させた彼に『よかった』と言ってくれる。
「俺、嬉しそうか?」
「うん」
「そうか……」
彼女の小さなひとことが、心を落ち着かせる。
だから、大丈夫だと思える。だから、真の〈ケル〉が何を告げても構わない。
ルイフォンは、ゆっくりと部屋を見渡した。
飾り気のない殺風景な部屋に、仮眠用のベッド。軽食でも摂るのに使っていたであろうテーブルと椅子。
奥に据えられた操作卓。
「……!?」
ルイフォンは顔色を変えた。
モニタのそばに、白金の光を放つ珠が飾られていた。
大きさは握りこぶし大、といったところか。ゆらりゆらりと緩やかに明るさを変えながら、彼を誘っている。
「……」
一見したところ洒落た置物のようであるが、母にそんなものを飾る趣味があったとは思えない。引き寄せられるように近づいて見れば、珠だと思ったそれは、複雑に絡み合った光る糸の塊だった。
一本一本の糸が、細くなったり太くなったりを繰り返し、時折り糸の内部をひときわ強い光が駆け抜ける。そのさまは、生命が脈打っているかのよう。
――そう。これは、まるで……。
「……間違いない。これが、真の〈ケル〉だ」
「これが……?」
メイシアが、驚きに瞳を瞬かせた。
彼女は当然、無機質な筐体を思い描いていただろう。ルイフォンだって、この珠を見るまではそうだった。
「ああ。これは、〈天使〉の羽にそっくりなんだ」
「!」
メイシアが息を呑んだ。
侵入した斑目一族の別荘で、ルイフォンは〈天使〉のホンシュアと出会った。
薄暗い月明かりの中、彼女の背から、まばゆい白金の光の糸が噴き出した。無数の糸は互いに繋がり合い、網の目のように広がり、羽となった。
――この珠は、羽の一部を取り分け、丸めて球状にしたような感じだ……。
珠の光は淡く、手をかざせばほんのり温かい程度だった。冷却剤で落ち着いたあとのホンシュアの羽と似ている。幻想的に揺らめくさまからは、神性すら感じられた。
ルイフォンは静かに操作卓の椅子に座り、キーボードに指を滑らせた。
キーボードが奏でる、カタカタという調べ。
ルイフォンの指先がキーの上で軽やかに踊り、モニタ上の表示が目まぐるしく変わる。
リズミカルな音を打ち鳴らし、チカチカと光るバックライトを浴びながら、〈猫〉が己の技を魅せる。機械的でありながら、不思議と優美な滑らかさを感じる音と光の共演に、メイシアは目を奪われていた。
壁の向こうにある巨大な〈ケル〉と対峙していた、先ほどのルイフォンとは違った。
彼は今、とても穏やかな顔をしている。〈猫〉であるときの彼は、ほとんど無表情なのだが、それでも順調なのか否か、メイシアにも、なんとなく分かるようになってきた。
不意に、〈猫〉の動きが止まった。
どうしたのだろうと、メイシアがルイフォンの横顔を見やれば、彼の呼吸が荒くなっている。忙しなく明滅するモニタの光と、息を合わせているかのように速い。
画面の中で、カーソルが点滅していた。
初め、メイシアは入力を促されているのかと思った。しかし、それは既に終わっているらしい。彼女には分からない、難しい文字の羅列が打ち込まれている。
――けれど彼の指先は、ひとつのキーの上に載せられたまま、ぴくりとも動かない。
「ルイフォン」
メイシアは、すっと彼に寄り添った。止まったままの彼の手に、そっと自分の掌を載せる。
「一緒に……押していい?」
機械類に詳しくない彼女にも分かった。このキーを押せば、〈ケル〉への強制アクセスが可能になるのだ。
「……メイシア」
ふっ、と。
彼が破顔した。嬉しそうに、愛しそうに目を細める。
「ああ、頼む」
力強く、彼は頷く。
その声を合図に、ふたりはキーの上に力を加えた。――刹那、部屋の照明が消えた。
「……!」
ルイフォンは、即座に椅子から立ち上がった。メイシアを抱き寄せ、守るように後ずさる。
ふつり、と。照明に続き、モニタがブラックアウトした。
そして……。
唯一の光源となった珠から、まばゆい光が噴き上がった――!
「っ!」
鋭い息を発したのは自分なのか。それとも、そばにいる最愛の相手なのか。
ルイフォンにも、メイシアにも分からなかった。ぴたりと触れ合った体では、早鐘のような心音が共鳴し合っている。
珠は、くるくると回転しながら巻き上げられた糸がほどけるように広がっていき、互いに絡まり合っては網目状に結びついていく。
「〈天使〉の羽、だ……」
ルイフォンが呟いた。
それは、光の波紋。急流のような勢いで駆け巡り、部屋を覆っていく。
あるいは、光の渦。壁にぶつかっては跳ね返り、すれ違う光を巻き込みながら、部屋を包んでいく。
瞬く間に、光の繭が出来上がった。そして、ルイフォンとメイシアは今、その内側にいる。
闇に浮かぶ幻想的な光は、妖しくも神々しく、人の目には禁忌なのか、あるいは畏敬なのか……。
張りぼての〈ケル〉の後ろに、真の〈ケル〉が封じられていた理由を――封じられなくてはならなかった理由を、言葉ではなく本能で感じ取れた。
ルイフォンは、ごくりと唾を呑んだ。
考えようによっては得体の知れないものに『閉じ込められた』。だが、それを口にしても、メイシアを不安がらせるだけだ。
彼は口角を上げ、余裕の笑みを作る。ハッタリは得意だ。
「よぅ、〈ケル〉。やっと会えたな」
何に話し掛ければよいのか分からなかったので、とりあえず珠があったあたりに彼は顔を向けた。すると、そこら中の光がさらさらと動き、部屋全体が揺れた。
〔ルイフォン……〕
何処からともなく、声が響く。
〔ごめんなさい〕
高くもなく、低くもない、落ち着いた少女の声。清らかな川の流れのように澄んでいるのに、物悲しい愁いを帯びている。
ルイフォンは拍子抜けした。
なんとなく、女の声で出てくるであろうとは予測していたが、『ごめんなさい』は予想外だった。〈ベロ〉があの通りなので、もっと高圧的にくると思っていたのだ。
「何故、謝るんだ?」
彼の質問に、近くを流れていた光が、さぁっと陰りをはらむ。人でいうのなら、あたかも顔を曇らせたかのようだ。
〔あなたが来ることは〈ベロ〉様から聞いておりました。けれど私は、あなたがここまでたどり着けないことを祈っていました〕
丁寧ではあるものの、きっぱりとした拒絶の姿勢。
母キリファに作られた『もの』であるはずの〈ケル〉にも、しっかりとした人格が感じられる。〈ベロ〉にシャオリエというモデルがいるように、〈ケル〉にもおそらくモデルがいるのだろう。
それは誰なのか。心当たりはないが、キリファが〈ケル〉を作ったのは、ルイフォンが生まれる前だ。そもそも彼の知らない人物である可能性のほうが高い。
そんなふうに〈ケル〉について推測しつつ、ルイフォンは尋ねる。
「なんで、俺に会いたくなかったんだ?」
〔あなたが知りたがっていることを、私はお答えできないからです。――申し訳ございません〕
声だけなのに、きちんと正座をした『彼女』が、三つ指をついて頭を下げる姿が目に浮かぶ。しとやかな淑女。けれど、ややもすると素っ気ない印象も受ける。
「母さんと先王が、何を話していたのか――『教えるわけにはいかない』と、いうことだな?」
ルイフォンは、慎重に言葉を言い換えた。
『知らないから、答えられない』のではなくて、『知っているけれども、答えられない』のだということの確認だ。
〔はい〕
「理由は?」
ルイフォンはぐっと顎を上げ、姿なき〈ケル〉を威圧的に睨んだ。
そこら中を漂うこの光の糸が、もし本当に〈天使〉の羽と同じものなら、〈ケル〉と人間を繋ぐ接続装置だ。触れれば、脳内に侵入される。機嫌を損ねたら、何をされるか分からない。
けれど〈ケル〉は、彼がたどり着けないことを祈りながらも、彼の呼びかけに応えた。直感に過ぎないが、〈ケル〉は敵ではない。非現実的な光景には気圧されたが、恐れることはないのだ。
〔理由は……。言えば、あなたは怒ります〕
「とりあえず、言ってみてくれ。どう感じるかは、俺が決めることだ」
〔そうですね。あなたは昔から、そういう子でした〕
「……?」
ルイフォンは眉を寄せ、それから気づく。少女の声に惑わされてしまいそうだが、〈ケル〉は彼が生まれる前からこの家にいる。彼のことは、なんでも知っているのだ。
〈ケル〉の糸の一部が、淡く光った。その光は揺らぎを見せながら、緩やかに伝搬していく。
それは、水面に投じられた一石が波紋を広げる様と似ていて、苦笑いと共に落とされた〈ケル〉の溜め息のように見えた。
〔……私は、キリファの支配下にあるのです。だから、キリファの望まないことは、私にはできません〕
「なっ!? また、母さんかよ! おい、今の俺には『強制アクセス権』があるんじゃないのか? それでも、俺より母さんに従うのか?」
〔ごめんなさい。『強制アクセス』とは、『隠れている私を強制的に引っ張り出し、接触する』という意味です。私があなたの支配下に入ったわけではありません〕
〈ケル〉の言葉の裏に、ルイフォンは、自分とそっくりな猫の目で、にやりと笑う母を見た。
癖のある前髪を、彼は乱暴に掻き上げる。その髪もまた、癪なことに母親譲りであった。
――ふと、ルイフォンの腕の中で、メイシアが動いた。黒曜石の瞳が、頼むように彼を見上げている。〈ケル〉に何か言いたいことがあるらしい。
どうやら危険はなさそうだ。彼はそっと力を緩めると、彼女は「ありがとう」と囁き、隣に立った。
「はじめまして〈ケル〉、私はメイシアと申します。誰よりも、ルイフォンを愛する者です」
高く透明な声が、凛と告げた。
少し前には考えられなかったような強い言葉に、ルイフォンはどきりとする。
〔ええ。知っています。いつも、ルイフォンをありがとう〕
ふわりと微笑むように光が流れた。と、同時にメイシアが、はっと顔色を変える。
「あっ……、そうでしたね。この家で起きたことは全部、ご存知なのですよね……」
尻つぼみになる声と共に、頬がさぁっと熱を持ち、彼女はうつむく。
メイシアが何を考えたかを察し、ルイフォンは苦笑した。〈ケル〉は『なんでも』知っているのだ。些細な失敗から、ふたりの睦言まで。
第一声で、彼をどきりとさせたくせに、こんなことで耳まで赤く染めるとは、相変わらずだ。
「メイシア」
ルイフォンは、彼女の髪をくしゃりとした。
「〈ケル〉が何を見ていようと、俺は気にならない。俺はいつだって、俺として恥ずかしくないように、俺らしく正々堂々と生きているからだ。――お前だって、そうだろ?」
「え……!? あ……、う……」
ルイフォンが腰に手を当て、胸を張る。過剰なまでに、自信に満ちあふれた彼の顔に、メイシアは視線をさまよわせて狼狽する。
しかし有無を言わせぬ彼の笑顔に、やがて彼女も「はい」と微笑んだ。――顔は赤いままだが、それは仕方ない。
メイシアは改めて、姿なき〈ケル〉と向き合った。
照明の消えた室内。太く細く、ゆっくりと明暗を繰り返す〈ケル〉の光がメイシアを照らす。薄闇に浮かび上がる横顔は……緊張に彩られていた。
「〈ケル〉……。四年前、キリファさんがお亡くなりになったときの『ルイフォンについて』、お話をさせてください」
「俺について……?」
唐突な、思いもよらぬ発言だった。
メイシアがいったい何を言うつもりなのか、ルイフォンには見当もつかない。けれど聡明な彼女は、何かに気づいたのだ。それだけは理解した。
だから彼は、そっと彼女の手を取った。冷静な口調とは裏腹に、固く握りしめられた彼女の拳が、小刻みに震えていたからだ。
〔……何のお話ですか?〕
光が揺らいだ。〈ケル〉の声もまた、不安定に揺らいでいた。メイシアは返事があったことに少しだけ安堵して、口を開く。
「あの日。この場所にルイフォンが来たのは、キリファさんにとっては予定外のことだったと思います。だから記憶を改竄して、ルイフォンを守ろうとしたのだと思います」
〔そうですね……〕
抑揚を失った〈ケル〉の声が、静かに相槌を打つ。
「なら、何故、ルイフォンはこの場に来たのですか? ……偶然ですか?」
本人を目の前にしながら、メイシアは〈ケル〉に尋ねた。ルイフォンは首をかしげつつ、口を挟む。
「メイシア、俺は警報音で起きたんだ。部屋を飛び出すと警護の者が殺されていて、胸騒ぎがして地下に……」
「待って、ルイフォン。あなたの記憶ではそうかもしれないけれど、本当は警護の者たちは休みを出されていたのでしょう?」
「……!」
キリファは警護の者たちに暇を出していた。それは、キリファと先王の密会が、秘密裏に行われるべきものだったからだ。
誰にも知られずに、密やかに……。息子のルイフォンにも、悟られないように……。彼が眠っているうちに……。
――なら、あの警報音は……?
「おかしいと思うのです。何故、夜中にルイフォンが目を覚ましたのか。……都合よく目覚めるなんてあり得ないと思うのです」
そしてメイシアは、まっすぐに前を見つめた。
「〈ケル〉、あなたがルイフォンを起こしたのではないですか?」
3.冥府の警護者-3

母が殺された、あの日。
いつも夜中は熟睡しているルイフォンが、ふと目を覚ました。
そして、心理的な盲点にある、この母の休息部屋にやってきた――。
「あり得ない! ……俺が自分から、この部屋に来ることは『ない』」
ルイフォンは、きっぱりと言い切った。
また、記憶のほころびを見つけた。知らぬうちに、駒のように動かされていたという現実に、憤りを覚える。
姿なき〈ケル〉に向かい、彼は睨みつけるような険しい視線をぶつけた。
「メイシアの言う通り、〈ケル〉、お前が俺を起こした。そして、この部屋に呼んだんだな!」
〔……はい〕
観念したように、けれど、はっきりと〈ケル〉は肯定した。
〔警報音を鳴らし、あなたの携帯端末を乗っ取って、この部屋に来るように言いました〕
「母さんは、先王が来たことを俺には隠したかったはずだ。なのに、お前は俺を呼んだ――俺を『呼ぶことができた』」
この事実から導かれる答え――メイシアが指摘したかった点が、今はっきりと見える。
「それは、つまり、お前は『母さんの支配下にない』ってことだ!」
ルイフォンの体が、自然に一歩前に出て、見えない〈ケル〉に喰らいついた。
〔……!〕
〈ケル〉の気配が一瞬、大きく震えた。
しかしそのあとは、さらさらと流れていた光がぴたりと止まる。まるで、息するのを忘れてしまったかのように。
「〈ケル〉!」
押し黙る〈ケル〉に、なおも詰め寄ろうとしたとき、遠慮がちなメイシアの手が彼の袖を引いた。
気遣うような黒曜石の瞳が、優しく彼を映していた。その穏やかな黒に、ルイフォンは感情に押し流されそうになっていた自分に気づく。もとはといえば、メイシアと〈ケル〉との会話の途中であった。
ルイフォンは、いつの間にかに怒らせていた肩を下ろす。「すまん」と面目なく呟くと、メイシアは小さく首を振って笑んだ。
「〈ケル〉、ルイフォンの言う通り、あなたはキリファさんの支配下にない――自由なはずです」
〔……〕
「あなたは、あなたの意思で、キリファさんの死の真相をルイフォンに教えたくないのです」
その言葉は批難であり、弾劾であるはずなのに、決して激しくはなかった。何故なら、彼女の目的は〈ケル〉の嘘を暴くことではなかったから――。
メイシアは、見えない〈ケル〉を見つめた。その視線には、切実な思いが込められていた。
「どうか、そんな意地悪をしないでください。ルイフォンの心は、分からないことだらけの不安の中で、とても疲れてしまっています。……お願いです。彼のために教えてください」
メイシアは深々と頭を垂れた。
あたりが、しんと静まり返る。
動きを止めた光が、惑うように明るさだけを変えていく。不規則な方向に伸びたルイフォンとメイシアの影が床で踊る。
〔メイシア……〕
〈ケル〉が呟いた。そして、溜め息のような光の波紋が広がった。
〔……ええ。私がキリファに支配されているというのは、嘘です。……でも、本当でもあります〕
謎掛けみたいな答えに、ルイフォンの瞳がすっと細まり、剣呑に光る。
しかし、ここはメイシアに任せるべきだと、彼は理性でとどめた。そんな彼に気づいたのか、彼女は頷き、「どういうことですか?」と柔らかに問う。
〔私にとって、キリファはとても大切な友人です。だから、彼女の願いは叶えてあげたいのです。――彼女は、自分の死の真相を、ルイフォンに知られることを望んでいません〕
〈ケル〉は決然と言い切った。けれど、メイシアは緩やかに返す。
「でもあなたは、ルイフォンを起こしました。それは、キリファさんが『望まなかったこと』です」
〔……っ、それは……〕
小さく息を呑み、〈ケル〉が言いよどむ。その反応を予期していたメイシアは、鋭くも優しい言葉をすっと滑り込ませた。
「それは、あなたが、キリファさんが亡くなることを知っていたから。あなたは、キリファさんを助けたくて、ルイフォンを起こした――違いますか?」
〔……!〕
光が、大きくたわんだ。
刹那、部屋全体がまばゆい光で満たされる。
目を灼くような強い光。ルイフォンは「メイシア!」と彼女の名を叫び、華奢な体を抱きしめた。きつく瞑った瞳の裏にまで輝きが入り込み、なんとしてでも彼女を守らねばと、心臓が跳ね上がる――!
と、そのとき。
唐突に光が霧散した。瞼越しに、そう感じた。
「……?」
恐る恐る薄目を開ければ、淡く細かな光が、波打つように揺れている。まるで肩をむせばせ、震えるように……。
〔ええ、そう……。メイシア、あなたの言う通りです……〕
かすれた〈ケル〉の声が、呟くように落とされた。
〔命と引き換えに、キリファがしようとしていたこと――彼女の気持ちを、私は理解しました。だから、彼女に従いました――従おうと思いました……。けれどっ……! 私には、耐えられませんでした……!〕
吐き出すように〈ケル〉が叫んだ瞬間、せき止められていた堤が決壊したかのように、清水の如き光がさらさらと流れる。
澄んだ光が煌めく様は、まるで〈ケル〉の涙――。
〔キリファは王に、自分の体を持っていくよう仕向けました。……そして、王が去ったら、この部屋を――キリファのベッドを中心に炎で灼き尽くすよう、私に頼みました。〈天使〉の熱暴走によってキリファは死んだのだと、皆に思わせるように……〕
ルイフォンの眉が、ぴくりと上がった。
「体を持っていかせた……? どういうことだ?」
〔これ以上は、教えられません。キリファが命を懸けて為したことを――あなたには秘密にしてほしいと頼まれたことを、私は言えません〕
ひと筋の光が、ひときわ強く輝いた。雫のように流れ落ちたそれは床で跳ね返り、細かな粒子となって散ってゆく。
「〈ケル〉……」
メイシアが小さく呟いた。そして「ごめんなさい」と続ける。〈ケル〉の気持ちも知らず、こちらの思いばかりを押し付けてごめんなさい、ということだろう。
ルイフォンは、そっとメイシアの肩に手を回し、彼女の体を自分の胸に預けさせる。その手で彼女の頬を撫で、耳元から髪を梳くようにして、柔らかな黒絹をくしゃりとした。
「――それなら、仕方ないよな」
〈ケル〉は母の支配下にない。〈ケル〉は自由だ。
自由だからこそ、〈ケル〉は、〈ケル〉の意思で口を閉ざすのだ。強制アクセス権なんかよりも、ずっとずっと強固な絆で、母と繋がっているから。
「母さんの、たっての願い、だったんだろ?」
〔え……?〕
「お前から、先王と母さんのことを訊くのは諦めた。少なくとも母さんは、一方的に先王に殺されたわけじゃないらしい。むしろ先王を利用して、自分の目論見通りにことを運んだ、ってわけだろ? それが分かっただけでも収穫だ」
〔ルイフォン……〕
声を沈ませる〈ケル〉に、ルイフォンは口の端を上げる。
「自分の命を懸けて、国王すらも顎で使ってやるって――如何にも、母さんらしいじゃねぇか」
〈ケル〉に訊かなくとも、母はちゃんと道を示してくれている。『手紙』に記された〈スー〉のプログラムの解析を進めれば、何かが分かるのだろう。
言われた通りにするのは、母の掌の上にいるようで気に喰わないが、そんな子供の意地で、できることをしないのも愚かなことだ。
知りたかったことは、分からずじまい。けれど、気分は晴れやかだった。
「それじゃ、行こうか」
胸の中のメイシアを見やると、彼女は大きく頷いた。
メイシアのおかげで、〈ケル〉の気持ちを聞けた。彼女には、本当にいつも助けられている。聡明な瞳は真実を見抜き、澄んだ心が優しさを紡ぐ。そんな彼女が愛しくてたまらない。
ルイフォンは正面を向き、姿なき〈ケル〉を見つめた。
「〈ケル〉、ありがとう」
抜けるような青空の笑顔で、彼は笑った。
『彼女』は、母が作った『もの』かもしれないが、母の大切な友人で、ルイフォンのことを生まれたときから見守ってくれている。
「それから、ごめんな」
〔え?〕
「お前は、ずっと自分を責めていただろ? 母さんが自分勝手しただけなのに、お前は母さんの死に責任を感じていた。だから、俺に会うのも怖かった――だろ?」
〈ケル〉が一番初めに言った『ごめんなさい』には、そんな思いも込められていたに違いない。
「お前に会えてよかった。……母さんのせいで辛い思いをさせて、すまなかった」
ルイフォンは彼の特徴ともいえる猫背を伸ばし、それからきっちり腰を直角に折った。
〔ルイフォン……?〕
〈ケル〉は驚いたように呟き、それから一段低い声になる。
〔……私は、あなたに謝罪されるような者ではありません〕
「そんなことないさ」
ルイフォンは顔を上げ、頑なな〈ケル〉に苦笑する。けれど〈ケル〉は陰りのある声を返してきた。
〔私はあの日、幾つもの罪を犯しました〕
「罪? 何が罪だというんだよ?」
〔キリファの死が変わらないのであれば、私はあなたを起こすべきではありませんでした〕
ルイフォンの強い口調を、脈打つ光が静かに跳ねのける。繰り返される明暗の中には、〈ケル〉の後悔が見え隠れしていた。
〔私が何もしなければ、あなたはキリファの最期を目にすることもなく、記憶の改竄もありませんでした。私がしたことは、あなたを苦しめただけです〕
「そんなこと……」
〔いいえ!〕
ルイフォンの言葉を遮り、〈ケル〉は鋭く畳み掛ける。
〔それどころか、私はエルファンに――!〕
「エルファン?」
いきなり出てきた異母兄の名前に、ルイフォンを瞳を瞬かせ……そして思い出す。あの日、彼が気を失ったあと、この家に駆けつけたのはエルファンだった。
〔ええ……。私は彼にとって一番、酷い仕打ちをしました……〕
「酷い仕打ち……?」
〔私の罪の告白を、聞いてくれますか? ――エルファンの代わりに……〕
それは問いかけの形をとっていたが、断れるはずもない願いだった。
ルイフォンは「ああ」と頷き、ちらりとメイシアを見やる。彼女もまた同じように頷いていたのを知ると、少しだけ心が軽くなった。
〔ありがとう〕
さらさらと、微笑むように光が流れた。
それから、溜め息のような波紋が広がると、〈ケル〉の声が厳かに響き始めた。
3.冥府の警護者-4

時を巻き戻そうとでもするかのように、切なげな光がすぅっと反時計回りに流れた。
そして清らかな〈ケル〉の声が、四年前のできごとを紡いでいく――。
王が部屋に到着すると、〈ケル〉は小さな珠から本来の姿へと形を変えた。
それはキリファの要望であったが、〈ケル〉にとっては、最大の処理能力を発揮できるようになった瞬間でもあった。
〈ケル〉は、ずっと迷っていた。
大切な友人であるキリファが、命を懸けて為そうとしていることは正しいのだろうか?
――否。
〈ケル〉が作られたときから、いずれその日が来ることは分かっていた。だから、受け入れようと思った。でも、それは『今』でなくてもいいはずだ――!
決意した〈ケル〉は、即座に〈ベロ〉に連絡をとった。
キリファは、『口うるさいから』と言って〈ベロ〉には何も話していなかったが、一瞬にも満たない時間で、すべての事情は伝わった。最大の処理能力を活かせば、造作もないことだった。
〔〈ベロ〉様、どうか、エルファンに――!〕
キリファはまだ、エルファンに言っていないことがある。
そのままにして、よいわけがない。
〔〈ケル〉、落ち着いて。今、エルファンをそちらに向かわせたけど、どうしても移動に時間が掛かるわ〕
〈ベロ〉にそう言われた瞬間、〈ケル〉はルイフォンを起こすことを思いついた。
息子が乱入してくれば、キリファはためらうかもしれない。ルイフォンを呼んで時間を稼いでもらう。――今から考えれば、他にも手段はあったのかもしれない。けれど、そのときの〈ケル〉は、これしかないと思ったのだ。
「それで、俺が呼ばれたわけだな」
ルイフォンが相槌を打つと、〈ケル〉が頷くように光を揺らした。
〔あの日、あなたはこの姿の私と会っています。おそらく、あなたには理解できなかったと思いますが、私が〈ケル〉であることも告げています。……けれど、あなたは覚えていませんよね?〕
「すまないが、母さんに消されているらしい」
彼がそう言うと、〈ケル〉は頷くように光の波紋を広げた。
現れたルイフォンを見て、キリファはくすりと笑った。
「〈ケル〉、あんたはきっと、最後で耐えられなくなると思っていたわ。だって、あんたは優しいもの」
怒っている様子はなかった。それどころか、「今まで協力してくれてありがとう」とすら、彼女は言った。
「でも、ごめんね。あたしは、あたしのやりたいようにやるわ――」
刹那、キリファの背中が白金に輝き、光の糸が噴き出した。強く弱く、あるいは太く細く、白金の光が紡ぎ出され、瞬く間に〈天使〉の羽を構成していく。
網の目のように広がった羽が、優美に伸ばされ、ルイフォンを包み込んだ。
光の糸の中を、さまざまな情報が複雑に絡み合いながら流れ、行き交うのが〈ケル〉には見えた。王や〈ケル〉に関する記憶の改竄と、この夜のことを深く考えてはいけないという命令が、ルイフォンに刻み込まれていくのが分かった。
「行きなさい、ルイフォン。そして、忘れなさい。あんたは、ずっと眠っていたの。何も見ていない、何も知らないの」
子守唄のようにキリファの声は優しく、その瞳は愛しげにルイフォンを見つめていた。
ルイフォンの体は、言葉に誘われるように、ふらふらと歩き出し、しかし途中でその場に崩れ落ちた。キリファとしては、自室に戻ってから眠ってほしかったのだろうが、仕方ないわね、とばかりに微苦笑する。
それから彼女は、今まで黙って成り行きを見ていた王と向き合った。
輝く白金の髪と、澄んだ青灰色の瞳を有する、この国の王――シルフェン。
「待たせたわね」
キリファは、王に嗤いかけた。
〔そして、キリファは斬られ、王は彼女の体を持ち去りました……〕
ぽつりと。
涙の雫が落とされたかのように、〈ケル〉は告げた。ルイフォンは口を開きかけ、しかし何を言ったらよいのか分からず、再び口を閉ざす。
そんなふうに彼が戸惑っているうちに、〈ケル〉はまた、光の波紋を広げて溜め息をつき、悲しげに続けた。
〔そこに、血相を変えたエルファンが飛び込んできました。私は、キリファに部屋を灼くようにと頼まれていたのに、呆然としていて何もしていませんでした〕
「ああ。エルファンから聞いている。意識を失った俺と、大量の血痕を見た、ってな」
母の予定通りなら、そこにはルイフォンはおらず、部屋は灼かれて血痕は消されていたはずだった。
〈天使〉のキリファは熱暴走によって、ひとり静かに命を落とした。――そういうシナリオだった。〈天使〉を知らない当時のルイフォンに対しては、大人たちが何かしらの説明をつけるだろうと、母は踏んでいたに違いない。
「お前はエルファンに、母さんが殺されたときの映像を見せたんだろ? 何故、そんなことをしたんだ?」
母の望みに従うつもりなら、先王のことは隠しておくべきだ。なのに〈ケル〉は、わざわざ教えるような真似をした。不可解な行動だ。
〔エルファンの暴走を止めるためです〕
「エルファンの『暴走』?」
おうむ返しの語尾が、思わず跳ね上がる。
ルイフォンは大きく目を見開いたまま、絶句した。
異母兄は常に冷静で、氷のような男だ。基本的に無表情で、たまに感情を見せたかと思えば、高圧的で皮肉げなものばかり。そういう人間のはずだ――。
エルファンは半狂乱になっていた。
それはそうだろう。キリファの危機と聞いて駆けつけてみれば、大量の血痕が残されているだけで彼女の姿はない。
そして、ルイフォンが倒れている。うつ伏せの状態で右手を伸ばし、固く拳を握っている。何かを掴み、そこで力尽きた、そんなふうに――。
エルファンは、ルイフォンに駆け寄った。
抱き起こすと、ルイフォンの握りしめられたままの右手が、だらんと垂れた。人形のような動きにエルファンは青ざめ、慌てて呼吸を確かめる。
それから、ほっと安堵の息をついた。
体は温かく、脈もあった。外傷を調べても何もない。ただ気を失っているだけだ。
けれど、まだ幼さの残る顔立ちには血の気がなかった。キリファにそっくりな癖のある前髪が額に掛かり、髪の黒さが肌の白さを引き立てている。
エルファンは、じっとルイフォンを見つめ、小さく「キリファ……」と呟き、その声を呑み込んだ。
「ルイフォン」
彼は、ルイフォンの頬を軽く叩いた。
「起きろ。何が起きた?」
音のない部屋に、低い声が響く。
「おい、ルイフォン! キリファはどうした!?」
ルイフォンは目覚めない。〈ケル〉には、それが脳内介入の余波だと分かった。
だが、エルファンは知る由もない。不安に駆り立てられた彼は、ルイフォンの頬を思い切り叩く。
「起きろ。キリファは何処にいる?」
叩かれたルイフォンの頬は、うっすらと腫れ上がっていた。しかし、エルファンは構わない。
彼は、意識のないルイフォンの体を激しく揺さぶる。それは、床に叩きつけんばかりの勢いで、狂人めいた行為だった。
「いつまで寝ているつもりだ? とっとと起きて、キリファを襲った奴のことを言え!」
地の底から噴き出すような、湧き立つ炎の怒り。なのに、限りなく冷たく、凍れる声が木霊した――。
「エルファンが、そんな……?」
ルイフォンの口から出た声はかすれ、別人のようだった。
〔いつまでも目覚めぬあなたに、エルファンは業を煮やし、ついに刀まで抜こうとしました〕
光が陰る。〈ケル〉の心を映すように。
〔血痕が残っていて、キリファの姿が見当たらないとなれば、彼女は襲われ、連れ去られたと考えるのが自然です。――エルファンもそう考えていました。毒づき、罵りの言葉を吐きながら……キリファの身を案じていました〕
「……!」
ルイフォンの心臓が、大きな音を立てた。
不可解に思えた〈ケル〉の行動が、その理由が分かった。
つまり――。
〔エルファンは、キリファが既にこの世の者ではない可能性を、微塵にも考えていませんでした。――だから……、だからっ、私はっ……!〕
〈ケル〉の悲痛な声が響く。
くらりと目眩がしそうなほどに、たわむように光が揺らぐ。
〔私は――エルファンに、真実の映像を見せました。……彼の希望を打ち砕くために――!〕
ひと筋の光がきらりと輝き、長い尾を引きながら流星のように流れ落ちる。
〔だって、そうしなければ、エルファンは永遠に……、地の果てまでも……、キリファを探しに行こうとするから……!〕
血を吐くような〈ケル〉の慟哭。
滂沱の涙の如き光が、部屋を巡る。あとから、あとから、とめどなく光が流れ続ける。
「〈ケル〉!」
ルイフォンは叫んだ。
「自分を責めるな!」
〔私は、エルファンにとって、何よりも残酷なことをしたのです……!〕
「でも、エルファンのためだ」
〔いいえ! そもそも、私が余計なことをしたのが間違いでした!〕
強く叩きつけるような〈ケル〉の声。
〔私は、キリファが望んでいた通りに、彼女と王との会見を静かに見届け、誰にも知らせずにこの部屋を灼いていればよかったのです。そうすればエルファンに、キリファの最期を見せる必要はありませんでした……!〕
〈ケル〉の後悔が、痛いほど伝わってくる。
けれど、〈ケル〉のどこが悪かったというのだろう。〈ケル〉は母の、エルファンのためを思い、心を砕いただけだ。
「……っ」
噛み締めた唇が切れ、口の中に鉄の味が広がる。
隣から、メイシアの嗚咽が聞こえてきた。邪魔をしないよう、ずっとこらえていたらしい。口元をハンカチで抑えている。瞳を見れば、案の定、真っ赤だった。
メイシアの泣き顔を見て、ルイフォンはすっと冷静になった。
彼女の肩を抱き寄せ、くしゃりと髪を撫でる。彼女は縮こまって「ごめんなさい」と涙混じりの声を漏らした。いったい何に謝っているのやら、相変わらずの彼女に、彼の心が温かくなる。
この涙は、彼女の優しさだ。
そして〈ケル〉の『涙』も、優しさからできている。
「〈ケル〉」
ルイフォンは、呼びかけた。ずっと気になっていたことを、今こそ問おうと思った。
「お前は、エルファンを呼んだんだよな?」
〔はい、そうですが……?〕
「何故、親父じゃなくて、エルファンだったんだ?」
はっと〈ケル〉が息を呑んだのが分かった。それで充分だった。――その答えが欲しかった。
〔あ、あのっ、そのっ……、イーレオではなかったのは……〕
しどろもどろの〈ケル〉に、ルイフォンはくすりとする。
意地悪のようなことをして〈ケル〉を困らせても可哀想だ。彼は、自分のほうから言葉を重ねた。
「お前は知っていたんだろ? たとえ、すれ違っていたとしても、今でも母さんとエルファンは互いに想い合っている、ってこと」
〔……!〕
「お前は本当に、エルファンには嘘を信じ込ませるべきだったと思うか? それより、真実を伝えられてよかったと思えないか?」
〔ルイフォン……〕
「俺なら、真実を知りたい」
きっぱりと言い切り、ルイフォンは挑戦的に笑う。
「エルファンは、俺と似ているはずだ。だから、俺と同意見だと思う。――俺たちに、優しい嘘は必要ない」
〔――ああ……〕
周り中の光が、きらきらと輝いた。それは涙のようでありながら、〈ケル〉の微笑みのようでもあった。
四年もの間ずっと、〈ケル〉はこの封じられた小部屋の中で、孤独な涙を流し続けていたに違いない。
悔いて、悔いて、悔いて……。
友情と感情の板挟みになった運命を呪い、巻き戻すことのできない時の流れを恨み、そして、何もできなかった自分を責め続けた。
「〈ケル〉。俺は、お前が起こしてくれてよかったと思っている。母さんの最期に立ち会わせてくれて感謝している。礼を言うよ。――ありがとう」
ルイフォンがそう言った瞬間、〈ケル〉は戸惑うように、しかし、きっぱりと〔いいえ〕と言った。
予想外の反応に彼は戸惑い、瞳を瞬かせる。
〔私に感謝する必要はありません。あなたがキリファの最期を覚えているのは、あなた自身の強い意志によるものです〕
「俺自身の意志?」
ルイフォンは訝しげに眉を寄せた。
〔確かに私は、あなたを呼びました。けれどあなたは、この部屋に来た途端に、キリファの『忘れなさい』という命令を受けたのです。あなたはそこで寝てしまい、キリファの最期を見ることもなく、『朝までぐっすり眠っていた』という記憶しか残らないはずでした〕
「え……?」
自然と足が一歩、後ずさった。
「でも、俺は覚えているし、母さんの最期も見た……!」
覚えている。忘れるはずがない。ぎらりと煌めく白刃が、母の首を……。
悲惨な記憶だ。
残酷な記憶だ。
けれど、敬愛する母の最期の姿なのだ。どんなに辛くとも、刻み込んでおくべき記憶だ。
〔ええ。だから、『あなたの強い意志』で覚えているのです〕
「どういうことだよ?」
苛立ちにとがる声を努めて抑え、ルイフォンは問う。
〔まず、キリファの脳内介入を受けて、あなたが眠ってしまったと思ったのは、私やキリファの勘違いでした。あなたは命令に対抗しようとしたために、あの場に崩れ落ちただけで、意識はありました。――あなたは確かに、キリファの最期を見届けたのです〕
「じゃあ、俺は母さんの命令とやらを跳ねのけたから、最期の記憶を覚えている、ってことか?」
そう考えれば納得できる。
しかし〈ケル〉は即答しなかった。しばし考え込むように光が揺れ、やがて〔推測ですが……〕と前置きをする。
〔それは、半分正しくて、半分違うと思います。――あなたは、王や私のことは忘れました。当然、抱いたであろう復讐心すらも忘れました〕
「……っ!」
腹立たしいことに、その通りだった。
憮然とするルイフォンに、〈ケル〉がそっと尋ねる。
〔王が去ったあとの、あなたの行動を、あなた自身は覚えていますか?〕
「え? いや、全然」
〔そうですか……。あなたは、床を這うようにして、体を引きずりながら動き出しました〕
眠ってしまったとばかり思っていたルイフォンの肩が、ぴくりと動いた。
よく見れば、彼の両目は、かっと見開かれていた。
いつからそうだったのか、〈ケル〉には分からない。けれど、彼の表情から、彼がずっと意識を保っていたことを悟った。
何も映していないような、虚ろな瞳からは次から次へと涙があふれていた。けれど、それを拭うための両手は動かず、代わりに固く歯を食いしばっている。
――ルイフォンは、声を殺して泣いていた。
どのくらい、そうしていただろうか。
ふと、彼は動き出した。
まだ体の自由が効かないのか、立ち上がろうとして、よろける。だから彼は体を引きずり、床を這うようにして歩み始めた。
〈ケル〉には、彼が何をしようとしているのか、分からなかった。
「……、……」
ルイフォンは何かを呟き、右手を遠くに伸ばす。
きらりと。彼の指の間で、金色の光が散った。
彼は小さな光を大切そうに握りしめ、そこで今度こそ意識を失った――。
〔あなたが〈天使〉の脳内介入にあらがい、記憶を残すことができたのは、おそらくキリファの鈴が存在したからです〕
「鈴!?」
ルイフォンは叫ぶと同時に、自分の後ろ髪を乱暴に胸元に手繰り寄せた。
一本に編まれた髪の先は青い飾り紐で留められ、その中央で金色の鈴が光る。彼が常に身につけているお守りのようなものであり、かつては母のチョーカーとして彼女の首元を飾っていた鈴だった。
「……そうか」
シャオリエの娼館で目覚めたとき、ルイフォンは自分の拳が固く握られていることに気づいた。こわばる指を一本一本、開いてみれば、鈴が現れた。
それを見た瞬間、彼は母の革のチョーカーが斬れたことを思い出した。鈴は、電灯の光を金色に反射させながら、放物線を描いて飛んだのだ。
「鈴が……、母さんの首にあるはずの鈴が、俺の手にあるということが――母さんは首を落とされ、俺が現場で拾ったという証拠になった……」
〔はい。その証拠によって、キリファが書き込んだ『ぐっすり眠っていた』という記憶に矛盾が生じたため、『忘れなさい』という命令が破棄されたのだと考えられます〕
「……なるほどな」
〔家が強盗に襲われたという記憶も、辻褄を合わせるために、あなた自身が作り上げたものです。キリファは関与していません〕
「鈴のおかげ、か……」
ルイフォンは、自分の毛先で光る金色の鈴を、指先でそっと撫でる。
『それ、首輪じゃん』
幼いルイフォンは、からかい混じりにそう言った。すると母は、胸を張った。
『そうよ。あたしは鷹刀の飼い猫なのよ』
とてもとても自慢げに――幸せそうに笑っていた。
彼女は、肌身離さずチョーカーを身につけていた。それは、『鷹刀の飼い猫』という言葉の裏に隠した、贈り主への想いを示していた。
「……まったく。……母さんも、あと、ちょっと待ってりゃよかったのに……」
それでも母は、自分のやりたいようにやっただろうか。ルイフォンにしたのと同じく、エルファンにも〈天使〉の羽を見せただろうか。
たぶん、そうしただろう。
何故なら、彼女は我儘で自分勝手だからだ。一国の王すらも利用した謎の企みの成功を疑わず、自信過剰の笑みを見せたはずだ。
「……」
わけの分からない感情が胸に押し寄せ、苦しくなる。
ルイフォンは無意識に手を伸ばし、隣にいるメイシアを強引に抱き寄せた。驚いた彼女は小さく声を漏らすが、彼の胸に収まると、華奢な手をそっと背に回してくれた。
「メイシア」
名を呼びながら、彼女の長い髪に顔をうずめる。
「母さんは、物凄くとんでもない奴で、救いようもないくらい身勝手な奴だった」
返答に困ったよう息遣いが、彼の耳朶をくすぐる。
「母さんが何を考え、何をしようとしていたのか……。俺は、暴いてやる!」
思いを声に出すと、心臓が締め付けられるように痛んだ。
いくら真相にたどり着いたとしても、過去には戻らない。それが分かっているから、切なく空虚だ。
ルイフォンが重い息を吐き出したとき、ふわりと、メイシアの手が彼の髪に触れた。細い指先が、すっと猫毛を滑る。
「うん。私も知りたい。ルイフォンと一緒に」
透き通るような声が、心に響いた。純粋に知りたいから、だから真実を求めようと、彼の背中を押している。
温かい。
胸の中が、ゆっくりと満たされていく。
「ああ。……ありがとな」
彼は顔を上げ、彼女の額に自分の額をこつんと合わせた。
そして、彼は天井を仰ぎ、姿なき〈ケル〉に告げる。
「〈ケル〉、いろいろ、ありがとう」
〔いえ、だから私は、そんな……〕
慌てる〈ケル〉を遮り、ルイフォンは朗らかに言う。
「これからも、よろしく。――母さんの親友」
〔……!〕
その途端、煌めくように光が弾け、柔らかな優しい風となって流れていった。
4.若き狼の咆哮-1

照明の落とされた夜の食堂は、幻想的な雰囲気を醸し出していた。
一面、硝子張りの南側からは、清冽な月明かりが差し込み、純白のテーブルクロスを青白く浮かび上がらせる。そして、それを取り囲む椅子の背は、長い長い影を床に落としていた。
鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオは、足音もなくテーブルの脇を通り過ぎた。夜闇に溶けるような黒髪をなびかせ、橙色の明かりの灯る奥の厨房へと向かう。
今の時間なら、まだ料理長が明日の仕込みをしているはずだった。
「これはこれは、イーレオ様。如何なさいました?」
戸口で声を掛ければ、思った通りに返事があった。
立派な太鼓腹を揺らし、前掛けで手を拭きながら料理長が現れる。肉に埋もれそうな小さな目を丸くして、意外な人物の登場を歓迎していた。
「何かご入用ですか? お申し付けくだされば、お持ちいたしましたのに」
「いや、それには及ばない。忙しいお前の手を煩わせたら、明日の料理に支障が出るからな」
イーレオの軽い冗談に、しかし料理長は、ほんの少しだけ眉を寄せる。
「イーレオ様。気の利いたことをおっしゃったおつもりでしょうが、あいにく、それしきのことで私の料理の味が変わったりはしませんよ」
ともすれば憤慨とも取れる台詞だが、料理長の福相から発せられると、ただの事実にしか聞こえない。実際、そうであろう。
「すまん。失言だった」
イーレオは、面目なさげに髪を掻き上げた。凶賊の総帥であれど、あっさり非を詫びるところが、なんともこの男らしい。
料理長は敬愛する総帥に頬を緩め、「それで、どんなご用件で?」と、このどうでもいい話題を打ち切った。
「酒を一本、見繕ってくれ」
イーレオがそう言うと、料理長はぽんと手を打つ。
「リュイセン様とお飲みになるんですね」
「いや、違うが?」
どうしてそんなことを言うのかと、イーレオは首をかしげた。
「おや、違いましたか。それなら、エルファン様とですか。ですが、エルファン様なら、先ほどご所望でしたので、メイドに部屋まで運ばせましたよ」
何故、エルファンとだと分かったのだろう? イーレオは、ぽかんと口を開ける。
その間にも、料理長は「ああ、つまみの追加はあったほうがいいですね」と、そそくさと厨房に戻って用意を始めた。
「おい、料理長。お前は人の心が読めるのか?」
「そんなこと、あるわけないじゃないですか」
肉付きのよい腹を揺らしながら、料理長が全身で笑う。
「お夕食のときの皆様のご様子ですよ」
「あ、ああ……」
なるほど、と納得しつつ、いやいや食事中に会議の話はしなかったはずだぞ、とイーレオは思い返した――。
その日の夕方、いつもの中枢たる面々が執務室に集まった。キリファが作った人工知能〈ケル〉の件で、ルイフォンとメイシアから報告があったのだ。
彼らは、キリファの死の真相を知るために〈ケル〉を訪ねていた。しかし、結果は芳しくなかった。〈ケル〉はキリファに義理立てして、その件に関しては口を閉ざしたらしい。
「人に作られた『もの』のくせに」と、リュイセンが毒づいたが、あれは『人』なのだとイーレオは知っている。この屋敷にいる〈ベロ〉が、彼を育ててくれたあの女であるように、〈ケル〉もまた『誰か』なのだ。
メイシア誘拐の冤罪事件のとき、警察隊が執務室に押し入るまでは、人工知能の〈ベロ〉は完全に傍観者に徹していた。だから、キリファに教えられていたことをすっかり忘れていた。というよりも、半信半疑だった、のほうが正しいかもしれない。
ともあれ、目的は空振りに終わったが、ルイフォンの顔が妙に晴れ晴れとしていたので、〈ケル〉との接触は無駄足ではなかった。
――と、話が締めくくられるところだった。
「祖父上! 何を悠長なことをおっしゃっているのですか!」
リュイセンが眦を吊り上げた。
「我々は一刻も早く、敵の正体を見極め、排除しなければなりません。さもなくば、また〈蝿〉の襲撃を受けることになります!」
固く握った拳が、どん、とローテーブルに打ちつけられる。
「我々の敵とは、すなわち、現在の〈七つの大罪〉です」
リュイセンは『現在の』に、力を込めて言い放った。
先日のイーレオの弁によれば、王族の私設研究機関としての〈七つの大罪〉は瓦解したという。組織の支配者であった先王が急死し、次代に引き継がれなかったためである。
それにも関わらず、〈七つの大罪〉の〈悪魔〉を名乗る者が現れた。それはつまり、何者かが〈七つの大罪〉を手中に収めたということである。――そういう話だった。
次から次へと突きつけられた新しい話に、リュイセンの頭は破裂しそうだった。しかし、苦労してなんとか理解した。
彼は決して鋭くはない。けれど大局的には、目標を見誤ることはない。
確かな証拠がない以上、もっともらしく語られた話も、推測の域を出ないことは承知していた。その上で、彼は全部、信じることにした。
だからこそ、祖父の生ぬるい態度を許すことはできなかったのだ。
「現在の〈七つの大罪〉の支配者、つまり『黒幕』は誰か。そいつは何故、鷹刀を狙うのか。これを調べることが、我々が今、為すべきことです!」
肩までの髪をさらりと揺らし、リュイセンはぐっと顎を上げる。
目線の先はイーレオ。ひとり掛けの肘掛けソファーで、優雅に足を組んでいる祖父の姿を睨みつける。
「先王の急死によって、〈七つの大罪〉が何者かに乗っ取られたというのなら、俺は、先王を殺害した人間が『黒幕』であると考えます。つまり、先王の甥ヤンイェンです」
殺害が露見して幽閉されたものの、〈七つの大罪〉を支配することに成功し、女王の婚約者として返り咲いた男。権力を欲する野心家。リュイセンの目に、ヤンイェンはそう映った。
「けど、もと貴族のメイシアの証言によると、ヤンイェンは初めから婚約者に内定していました。となると、冤罪の可能性もあります。あるいは先王との間に、なんらかのトラブルがあったのか……」
イーレオは小さく、ほう、と息をついた。
感情のままに訴えているのかと思ったら、どうやら少し違うらしい。なかなか、考えるようになってきた。そう思い、口の端が緩やかに上がる。
「誰が、なんのために、先王を殺したのか。――『黒幕』の正体を知るためには、当時の先王を取り巻く、人間関係を洗う必要があります」
リュイセンはそこで一度、ためらった。
言い方を間違えれば、無用な論争になるのは目に見えていた。そして口達者ではない彼が、誤解される可能性は大いにある。
しかし無駄に言葉を飾っても、混乱するだけだ。だから彼は、結局、思ったままのことを口にした。
「ルイフォンの母親は、まさにこの時期の先王に殺されています。彼女が何かを知っていた可能性は、極めて高い。だから俺は、〈ケル〉からの情報に期待を寄せていました」
リュイセンは、隣に座るルイフォンをちらりと見やる。今の発言は、ルイフォンの手ぶらの帰還を責めているようにも聞こえたはずだ。
ルイフォンは腕を組んだまま、じっとしていた。いつもの好奇心旺盛な猫の目は鳴りをひそめ、無表情な〈猫〉の顔である。むしろ、反対側の隣にいるメイシアのほうが、気遣わしげに視線をさまよわせていて落ち着かない。
「すまんな」
リュイセンが気まずい思いをするよりも先に、涼し気なテノールが応えた。
意に介するふうもない、穏やかな響きに、リュイセンは戸惑う。少し前までのルイフォンなら、声色にもっと苛立ちが含まれていたはずだ。
「大手を振って出掛けたくせに、収穫なしだ」
ルイフォンは癖のある前髪を掻き上げ、肩をすくめて晴れやかに笑う。
「リュイセンの言い分はもっともだ。俺個人としては、母さんの過去も垣間見れたし、知らなかったとはいえ、さんざん世話になっていた〈ケル〉にも挨拶ができて、まずまずだった。――だが、鷹刀に対しての利益はゼロだ。悪いな」
「違う、ルイフォン!」
リュイセンは、とっさに叫んだ。
「俺は、お前を責めるつもりは、まったくない。むしろ、逆だ」
そう言って、リュイセンはこの場にいる者たちを見渡す。――主にイーレオを。
「おかしいと思いませんか? 俺は――鷹刀は、どうしてルイフォンからの情報に期待するのです?」
「どういう意味だよ?」
即座にそう返したのは、リュイセンの視線の先にいるイーレオではなく、ルイフォンだった。それまでの和やかさを返上し、すがめた猫目に険が混じる。
リュイセンは、自分の話術の不甲斐なさに溜め息をつきながら、ひとまずルイフォンを無視してイーレオに畳み掛けた。
「ルイフォンは、〈猫〉です」
「はぁ?」
「『鷹刀の対等な協力者』であって、一族ではありません」
「それがどうした?」
いちいち口を挟むルイフォンに、リュイセンのこめかみの血管が、ぴくりと浮き立った。
これは八つ当たりのような感情だ。苛立っても仕方のないものだ。だが、ずっと感じている焦燥感が――〈猫〉として独り立ちした、ルイフォンに対する劣等感が――リュイセンを刺激した。
彼は肩を怒らせ、ぐいっと体ごとルイフォンに向き直る。
「どうしたも、こうしたもないだろ!?」
「は?」
ルイフォンとて、細身ではあっても決して小柄なわけではない。だが、長身を誇る鷹刀一族の直系のリュイセンに迫られれば、自然と腰が引ける。
「どうしたんだよ、お前……?」
「〈猫〉にばかり調べさせて、鷹刀は何もしてない! ……期待していたお前の情報源が空振ったなら、今度は鷹刀の番のはずだ。なのに、お前の報告が終わって『はい、解散』じゃ、ちっとも『対等』じゃねぇ! 俺たちだって……、……俺だって動くべきだ!」
リュイセンの剣幕に面食らいながらも、ルイフォンが言い返す。
「そんなこと言ったって、諜報活動は俺の担当だし?」
「違う……!」
叫んでからリュイセンは、強く首を振り「ああ、いや。お前は必要なんだ」と、うまく言葉を操れないもどかしさに舌打ちをする。
「今回だって、〈猫〉は収穫なしじゃない。お前の母親は、哀れな被害者などではないことがはっきりした。彼女の足跡を追っていけば、いずれ先王に関わる重要な情報にたどり着くはずだ」
「そうだな」
ルイフォンは、リュイセンの態度に納得したわけではなかった。だが、言っていることは実にもっともだったので、首肯して「ともかく『手紙』の解析を急がないとな」などと呟く。
そんなルイフォンを見て、リュイセンはぐっと拳を握りしめた。〈猫〉には、やるべきことが幾らもあるのだ。そして、着実に前へと進んでいる。
だから、自分も――と、彼は思う。
リュイセンは、すぅっと大きく息を吸い込んだ。それから、ゆっくりと吐き出し、祖父を――総帥イーレオを見据える。
ぐっと胸を張り、「総帥」と鋭く呼びかけた。
「現在の〈七つの大罪〉の実態を知るために、我々ができるアプローチは、ふたつあると思います」
若々しく張りのある低音が、執務室に鳴り響く。
リュイセンは策を練るのは得意ではない。それでも、彼なりにずっと考えていたのだ。
「聞こう」
楽しげにも聞こえる、魅惑の音色が受けて立つ。リュイセンと同じ声質だが、より深く、まろみがあった。
リュイセンは、ごくりと唾を呑み、「至極、単純なことです」と口火を切った。
「組織の『頂点』から調べるか、『末端』から調べるか、のふたつです」
彼は右手でひらりと、ルイフォンとメイシアを示す。
「ルイフォンたちは――〈猫〉は、『頂点』から探っています。先王と彼の母親は何かしらの因縁があるはずですし、もと貴族のメイシアは貴重な情報源です」
そこでリュイセンは身を乗り出した。さらさらとした黒髪が肩をかすめ、イーレオに詰め寄る。
「ならば鷹刀は、『末端』から切り崩していくべきです」
「具体的には?」
「〈蝿〉を捕らえます。そして多少、荒っぽいことをしてでも、〈七つの大罪〉の現状を奴に吐かせます」
「……」
イーレオの無言の視線が、鋭く突き刺さった。ひるみそうになる心を叱りつけ、リュイセンは語気を強める。
「俺は今までに二度、奴に会っています。奴の口ぶりからすると、奴は〈七つの大罪〉に不満を抱えているようでした。身の危険を感じれば、簡単に組織を裏切り、口を割るでしょう」
ひとことひとことを丁寧に、焦ることなく言い切り、リュイセンはじっとイーレオを見つめた。
イーレオは答えるべく、口を開こうとして……それよりも早く、ローテーブルを叩く、とんっ、という小さな音に遮られる。
発生源は、エルファンだった。
「机上の空論だ。姿を消した奴を、どうやって捕まえるつもりだ?」
「父上……」
次期総帥の声が、氷の刃のようにリュイセンを斬りつける。嘲笑に頭が揺れれば、黒髪の中にまばらに混じった、白い髪までもが冷たく光った。
「リュイセン。お前は、前にも同じことを言っている。愚か者めが」
「……っ」
その通りだった。
以前、〈蝿〉のことは保留、要するに放置という方針を出されたとき、リュイセンはイーレオに強く反発した。だが彼の弁は感情論と切り捨てられ、それに対し、彼は何も言い返すことができなかった。
リュイセンは腹にくすぶる思いを抑え、唇を噛む。
そのとき、ふわりと草の香が広がった。ミンウェイの手がすっと挙がり、「よろしいでしょうか」と艷やかな声が掛かる。
「私が、囮になります」
「ミンウェイ!?」
リュイセンは驚き、彼女の美麗な顔を凝視した。
「父は私に固執しています。おそらく、隠れて私のことを監視しているでしょう。そこで私が、不用心に見える単独行動をとれば……」
「駄目だ! ミンウェイを危険に晒すわけにはいかない!」
予想外の発言にリュイセンが慌てて叫ぶと、ミンウェイは「心配ありがとう」と柔らかに笑む。その目は鏡のように凪いでいて、冷静であるのは明らかなのに、何処か危うく感じられた。
「でも……、私は……」
「違う!」
そう口走ってから、彼は思う。何故、自分は先ほどから『違う』を連発しているのだろう。――どうして皆、分からないのだろう。
リュイセンから、ゆらりと陽炎が立つような怒気が広がった。
「祖父上、ずっと疑問に思っていたことがあります!」
どんっ、とローテーブルに手をつき、彼は立ち上がる。
「何故、『鷹刀』が動かない! どうして、一族の者に〈蝿〉の名を隠そうとするのです!」
祖父は、『古い連中を不安がらせたくない』と言った。
だから一族の者たちには、今までの一連の事件は、ルイフォンが斑目一族を経済的に壊滅状態に追い込んだことで、すべて解決したと説明されている。
あとは残党狩りとして、『斑目の食客だった男』の行方を追わせているという状態だ。そいつが〈七つの大罪〉の〈悪魔〉であることを知っている者はごくわずかであり、更に〈蝿〉と名乗っていたことを知る者は果たしているのか、いないのか。
古い者を大切にしたいという、イーレオの気持ちは尊重すべきだと思う。だが、一族がすっかり安心しきっている現状は、間違っている……!
「何故、本気になって〈蝿〉を探さないのですか! 〈蝿〉は、鷹刀にとっての直接的な脅威です。奴のしたことを考えれば、一族を総動員して、草の根を分けてでも探し出すべき相手です。――どうして、そうなさらないのですか!」
一族の総帥を相手に、リュイセンは喰らいつくような眼光を向けた。
「トンツァイをはじめとする、腕利きの情報屋に手を回し、あのいけ好かない警察隊員、緋扇シュアンの人脈まで頼っているのも知っています。……けれど、あくまでも外部の人間が中心です」
ずっと不思議だった。
古い人間なら、〈蝿〉本人を知っている。捜索には有利だ。それは、不安がらせたくない、などという甘い感情よりも、優先順位が高いはずだ。
リュイセンは、大きく息を吸い込んだ。ぐっと腹に力を込め、意を決したように告げる。
「祖父上は、あの〈蝿〉を『血族』だと思ってらっしゃるのです! 一族には秘密裏に捕らえ、見せしめの類はせずに処断したいと考えてらっしゃる!」
母のユイランが、『弟のヘイシャオ』と『〈蝿〉』は『別人』だと言い切ったのを聞いて、気がついた。
イーレオは、母とは逆の見解なのだ。
ユイランにしろ、イーレオにしろ、ヘイシャオ本人が死んでいるのは承知している。その上で、現在の〈七つの大罪〉によって生き返らされた〈蝿〉を、『別人』として見るか、『血族』として見るか――。
「いい加減、はっきりさせましょう! 俺たちの前に現れた、あの『〈蝿〉』という男は、我々にとって『何者』なのか――!」
風もないのに、リュイセンの黒髪が、ぞわりと逆立つ。その姿は、目の前に立ちふさがる、すべてのものを噛み砕き、排斥しようと牙をむく若き狼だった。
4.若き狼の咆哮-2

リュイセンの叫びは、まるで若き狼の咆哮だった。
『祖父上は、あの〈蝿〉を『血族』だと思ってらっしゃるのです!』
『いい加減、はっきりさせましょう! 俺たちの前に現れた、あの『〈蝿〉』という男は、我々にとって『何者』なのか――!』
イーレオは眼鏡の奥の目をわずかに細めた。秀でた額に皺が寄り、思索の表情を作る。だがそれは、どことなく迷いの印象をも抱かせる顔だった。
「リュイセン! 言葉が過ぎる」
エルファンの厳しい叱声が飛んだ。
だが、氷原を吹きすさぶ雪嵐の一喝にも、烈火をたたえた今のリュイセンは動じない。そもそも、次期総帥たる父の叱責など、承知の上だったのだろう。ただ静かに一礼をし、リュイセンは着席した。
なおも言葉を重ねようとするエルファンを、イーレオは「構わん」と遮った。そして一族の総帥は、わずかに背を起こし、皆を睥睨する。
深い海の色合いの瞳は、ひとりひとりの心を覗き込むかのようでもあった。果てなき淵に似た双眸からは、感情を読み取ることができない。
「では、リュイセンに尋ねよう。お前は、あの〈蝿〉を『何者』だと捉えている?」
リュイセンはごくりと唾を呑んだ。思いがけぬ質問であったが、これは特別に与えられた提言の機会だった。
「奴は、現在の〈七つの大罪〉が作り出した、ただの『駒』です。大華王国一の凶賊である鷹刀、および総帥である祖父上を害するための刺客で、我々に揺さぶりをかけるために、わざわざ因縁のある人物を選んで作り出した、卑劣な罠です」
「そうか」
イーレオは、ふっと口元を緩めた。
「つまり、お前の見解では、『黒幕』の目的は、あくまでも『俺や鷹刀に危害を与える』こと。その手段として〈蝿〉を使っただけであり、奴を血族とみなしたり、ましてや血族の情に流されるようでは、思う壺だと」
海底から響くような、低い低い声。暗い渦に呑み込まれそうな気配に、リュイセンの肩がびくりと動く。
「祖父上……」
「そう言って、お前は俺を愚弄したわけだな?」
リュイセンは、ぐっと奥歯を噛んだ。息が止まり、冷や汗が背を伝う。
しかし、彼の視界の端にはミンウェイがいた。狂った父親が紡ぐ世界に囚われていた娘。彼女に、再び悪夢を見せる必要はない。あれはただの『駒』で、彼女の父親とは関係ない――!
「おっしゃるとおりです」
リュイセンは一同を見渡し、ひときわ声を張り上げた。
「あれは『駒』です。なのに、祖父上も、父上も、……ミンウェイも! 生前の奴を知る者は皆、惑わされる……!」
彼は唾を飛ばし、熱弁をふるう。
「――それは、愚かなことです!」
その一声は、まるで神速の閃光。
一族の長の威圧を、リュイセンは愛刀を振るうが如く斬り捨てた。抜き身の双刀を宿したかのように、双つの瞳がぎらりと煌めく。
「リュイセン!」
エルファンの声が、轟いた。
それを、イーレオの視線が制する。
真空のような無音が広がった。吐息で場を乱すことさえも許されぬ、張り詰めた静寂の支配下となる……。
どのくらいの時が、過ぎただろうか。
ルイフォンは、ふと、奇妙な気配を感じた。
ゆるりと柔らかな息遣い。まるで微笑みが漏れ出したかのような、穏やかな呼吸――。
場違いな違和感の発生源をおっかなびっくり、たどってみれば、リュイセンに慈愛の眼差しを向けるイーレオがいた。
「親父……?」
ルイフォンの呟きに応えるかのように、イーレオの目元に笑い皺ができる。その茶目っ気たっぷりの様子に、ルイフォンは理解した。
イーレオは、わざと怒らせたのだ。リュイセンは誰の目にも明らかなくらいに、不満を抱えていた。だから、それを吐き出させた。
そして同時に、リュイセンを試したのではないかと、ルイフォンは邪推する。
――鷹刀イーレオという人間は、何よりも人を魅了する『人』が好きである。そして今、イーレオは、とても満足げな顔をしている。つまり、リュイセンは期待に応えたのだ。
「リュイセン」
イーレオが名を呼んだ。
ルイフォンとは違い、状況を飲み込めずにいるリュイセンは、イーレオの柔らかな声に戸惑い、瞳を瞬かせた。
「俺は、あの〈蝿〉の正体を、おそらく正確に言い当てられる」
ざわりと場が色めき立つ中で、リュイセンが「祖父上!?」と、一段大きな声で叫んだ。その反応を予測していたイーレオは、すかさず言を継ぐ。
「推測が当たっている自信はある。だが、確たる証拠を掴むまではと、伝えるのを先延ばしにしていた。そのせいで――リュイセン、お前の気を揉ませた。……悪かったな」
寄せて返す波のように、低い声がすっと消え入った。
「そ、祖父上、そんな……! 顔を上げてください」
わずかに、ではあるものの、確かに下げられたイーレオの頭に、リュイセンは狼狽する。
イーレオの静かな語り口調は、どこか遠くに向けられていた。なんとなく儚げに見える眼差しに、ルイフォンは一抹の不安を覚える。
「親父……、親父は〈蝿〉を……、その……見逃したいのか?」
「逆だ」
イーレオの答えは端的で、そして即答だった。
予想外に険しい口調にルイフォンが面喰らっていると、付け足すような低い声が続く。
「奴は、葬り去らねばならない存在だ」
無慈悲なほどに凪いだ目で、イーレオは、はっきりと告げた。
「……だが、尊厳は守ってやりたい。甘いかもしれないがな」
溜め息と共に、わずかに首を傾ければ、長髪のひと房が頬に落ちた。イーレオは、それを指先ですっと払う。綺麗に染められた黒髪は艷やかに光を跳ね返しはするが、所詮、若作り。まがい物だ。
「どういう、こと……ですか!? 祖父上は、何を……ご存知なのですか?」
気持ちの上では一直線に問いただしたいリュイセンであったが、イーレオの雰囲気に呑まれ、ためらいながら言葉を選ぶ。
イーレオには、それが手に取るように分った。わずかに苦笑して、けれど、どこから話したものかと悩み、眉を寄せる。
「……あの〈蝿〉は、ヘイシャオに似た年格好の人間の変装などではなく、生き返ったヘイシャオである。つまり、『〈七つの大罪〉には、死者を生き返らせる技術がある』――このことには皆、納得しているな?」
イーレオの問いかけに、一同は思い思いに頷いた。
ルイフォンとリュイセンが見た〈蝿〉の顔は、明らかに鷹刀一族のものであったし、ミンウェイが会話した〈影〉は、間違いなく父だと彼女は感じた。
一方で、十数年前には、エルファンが確かにヘイシャオの息の根を止めており、その亡骸を埋葬している。実は生きていた、なんてことはあり得ない。
「だが、俺が〈悪魔〉の〈獅子〉として、〈七つの大罪〉に関わっていたころには、そんな技術は存在しなかった」
「え?」
誰からともなく、疑問を漏らす。それを受けるように、イーレオは深々と頷いた。
「俺が抜けたあとに、研究されたんだ。――〈七つの大罪〉に残ったヘイシャオによって、……『死者を生き返らせる技術』が」
「……!」
ミンウェイが息を呑んだ。華やかな美貌から、色味が消えていく。
イーレオが総帥になり、鷹刀一族は〈七つの大罪〉と手を切った。だが、ミンウェイの父ヘイシャオは、妻の病の研究を続けるために一族を捨て、〈七つの大罪〉を選んだ。
――『病を治す研究』のため……のはず、だった……。
「袂を分かって、数年後。ミンウェイが生まれるよりも前のことだ。音信不通になっていたヘイシャオから電話があった」
「お父様から……!?」
「ああ。『助けてください』と、彼は電話口で声を震わせた」
今までの〈蝿〉――ヘイシャオの印象からは、信じられないような発言に、場の空気が揺れる。
「『もう、妻の体は長くは保たない』と。『どんなに手を尽くしても、変えられない運命だ』と。ヘイシャオは嘆いた。そのときの俺は――」
イーレオは目線を下げ、自嘲の笑みを浮かべた。
「来るべきときが来たなと、ただ冷静に聞いていた。それどころか、わざわざ連絡を寄越すとは律儀だな、とすら思った。……薄情だろう? 彼の妻は、俺の娘なのに。――俺の中では、あの子はとっくに死んでいたんだ……」
鷹刀一族の濃い血を持った人間が、無事に育つ確率は極めて低い。それを目の当たりにしてきたイーレオの諦観は、仕方のないことといえた。
イーレオは、ヘイシャオに心からの感謝を述べた。
「今まで、ありがとう。お前のおかげで、あの子も幸せだったろう。残りの時間を有意義に……」
『何をおっしゃるんですか! 彼女はまだ生きている! そして、彼女が生きられる方法があるんです!』
電話回線を通したヘイシャオの声は、興奮でひび割れていた。
頭に血が上った彼の話は、しばらく要領を得なかったが、彼は本来、理詰めでものを言う医師であり研究者である。やがて落ち着きを取り戻し、これまでのことを語り始めた。
彼の研究は、初めは『病の治癒』だった。
それが、いつの間にか『延命』になった。
そして――。
「ヘイシャオ、それは『死者の蘇生』と同じじゃないか? いくらなんでも、自然の理に反している」
『違います。臓器移植と同じです。新しい体に記憶を移すだけです!』
救うことのできない肉体の代わりに、彼女の遺伝子をもとに、病の因子を排除した健康な新しい肉体を作る。そして〈天使〉を使って、記憶を移す。――ヘイシャオはそう言った。
〈影〉と同じように聞こえるかもしれないが、彼女本人の体を新しく作るのだから、〈影〉とは違う、と。
『クローン技術に、私が研究を重ねて完成させた『肉体の急速成長』技術を組み合わせて、現在の年齢の彼女の体を作ります』
「な……!? そんなことができるのか?」
『既に、実験は成功しています。安全です。何も問題はありません』
畳み掛けるヘイシャオに、イーレオは言葉を失った。
理論上は可能だろう。既に成功しているという話も、ヘイシャオが言うのなら、そうなのだろう。多くの犠牲を伴ったであろうけれど。
――しかし。これは、禁忌の領域だ。
イーレオは、本能的な嫌悪を抱いた。
同時に、ヘイシャオを一族に引き止めなかったことを悔いた。
生まれつき病弱なイーレオの娘が、天寿を全うできるわけがない。その日が近づけば、ヘイシャオが暴走するのは火を見るより明らかだったはずだ。何故ならヘイシャオは、彼女のために〈悪魔〉となったのだから……。
『お義父さん』
電話口から、決然とした声が響いた。
そう呼ばれたのは初めてではないのに、イーレオの心臓はどきりと音を立てた。
『この方法を使うためには、彼女の体が生きているうちに、記憶を保存しておく必要があります。けれど、彼女が同意してくれないのです!』
イーレオは、ほっと安堵の息をついた。ヘイシャオはすっかり動転しているようだが、娘は冷静だった。
『これは『死者の蘇生』ではなく、『もうひとりの自分を作る』技術です。悪用されることもあるでしょう。お義父さんが、よい顔をしないであろうことも承知しています。けれど、悪いのは技術ではなく、使う人間です』
話の筋道が見えない。イーレオは困惑した。
「お前は、何を言いたいんだ?」
『彼女の説得に、協力してください!』
ヘイシャオの声が、イーレオの耳に鋭く突き刺さった。
『無茶なお願いをしていると、分かっています。けれど、〈七つの大罪〉を否定したお義父さんが勧めてくれたなら、彼女も納得してくれると思うのです!』
「…………断る」
イーレオとて、まったく迷いがなかったわけではない。とうの昔に諦めていた娘の命を、これほどまで愛おしんでくれる男に、酷いことを言っていると分かっている。
しかし……。
ここに来るまでに、どれほどの努力と――どれほどの犠牲が払われたのか。そしてまた、これから〈天使〉を使えば、その〈天使〉は遠からず熱暴走で命を落とす。
命を弄ぶ行為だ。
許されるはずがない……!
「それは『悪魔』のすることだ。俺はもう、〈悪魔〉をやめた」
『精神はそのままに、具合の悪い肉体を交換するだけ。それの、どこがいけないんですか!』
どす黒い、執念の叫びだった。けれど、魂が裂けるような想いは、悲しいほどに美しかった。
『お義父さん、どうかお願いします。私は、彼女を失いたくないんです!』
「娘も嫌がっているのだろう?」
『ええ。だから、彼女の意思を無視して、勝手に記憶を保存するようなことはしたくありません』
破綻しているような理屈だった。
けれど、ヘイシャオの中では正しく成立していた。何をおいても彼女が一番という、彼の絶対の不文律に対して矛盾しないのだった。
「ヘイシャオ、現実を見据えろ。娘の言っていることを、ちゃんと聞いてやってくれ……」
『どうして分かってくれないんですか! ――彼女が死んだら、あなたのせいだ!』
イーレオがヘイシャオと言葉を交わしたのは、それが最後だった。
その後、ミンウェイが生まれ、娘は死んだ。
そして十数年も経ってから、ヘイシャオは、イーレオではなくエルファンの前に現れた。自分を殺してもらうために――。
「ミンウェイ。この話をお前に聞かせてよいものか。俺は、ずっと迷っていたよ」
独りごつように、イーレオが呟いた。
禁忌に手を染め、祖父を罵った、父親の話だ。
狂おしいまでに深く妻を愛した、父親の話だ。
「いいえ、お祖父様。お聞かせくださり、ありがとうございます」
ミンウェイは落ち着いた声で、穏やかに笑った。
「お父様は、お母様を亡くすことが恐ろしくてたまらなかったのでしょう。そして、たぶん……お母様は、お父様を残して逝くことが不安だったのだと思います」
彼女は、緩やかに目を伏せる。
母には、禁忌の技術を受け入れることができなかった。けれど最愛の人を、ひとりぽっちにしたくなかった。だから……。
「お母様は、ご自分の記憶の代わりに、私を――お父様に遺したんですね。そんな両親を知ることができて……よかったと思います」
ぽつりと、ミンウェイが漏らした。
その直後に、慌てたような草の香が広がる。波打つ髪の影に隠し、目頭を押さえる彼女の顔を、誰もが見ないふりをした。
4.若き狼の咆哮-3

しめやかな空間に、ミンウェイのむせび声だけが、静かに響いていた。
イーレオは、やるせない顔つきで見守っていたが、やがて深く息を吐き、「話を戻そう」と切り出す。彼らしくもない、抑揚に欠けた乾いた声も、二、三の咳払いののちに調子を変えた。
「俺たちの前に現れた〈蝿〉の正体の話だ」
ソファーに体を預け、胸を張る。内心はさておき『現在』に気持ちを移せと、イーレオは一同を諭す。
いち早く反応を返したのは、リュイセンだった。〈蝿〉についての話を初めに切り出した、張本人である。
「あの〈蝿〉は、今、祖父上が話してくださった、ヘイシャオ叔父の研究、『死者の蘇生』技術によって作れらた――ということですね」
「そう考えるのが妥当だろう」
イーレオの肯定を聞くと、リュイセンは、なんとも言えぬ持ちで眉をひそめた。
ヘイシャオは、最愛の妻を失いたくないがために、血を吐く思いで禁忌の技術を編み出した。それを死後、自分自身に使われた、ということになる。
彼の死因は、事実上の自殺だと聞いている。蘇生は不本意だったはずだ。
リュイセンは、ミンウェイを苦しめたヘイシャオを憎んでいる。だが、ヘイシャオの皮肉な運命を嗤う気にはなれなかった。同情はしないが、憐れだと思う――。
不意に、ルイフォンが「待てよ、親父」と、声を発した。
「ヘイシャオの技術には、肉体と記憶が必要だ。肉体は髪の毛でも残っていれば、なんとかなりそうだが、記憶はどうやって用意した? 記憶がネックで、ミンウェイの母親を蘇生できなかったんだろ?」
「もっともな質問だが、ヘイシャオの記憶なら簡単なことだ」
予測していたらしく、イーレオは軽く応じる。
「〈悪魔〉には、記憶の定期的な提出義務がある」
「記憶の提出義務?」
ルイフォンは、おうむ返しに語尾を上げた。
「ああ。〈悪魔〉とは、〈七つの大罪〉から出資を受ける研究者だ。当然、成果を報告する義務がある。その方法は、書面と――『記憶』だ」
イーレオは、自分の頭を指先で叩く。
「頭の中身を全部、差し出すんだよ。研究以外にも何を考えたか、すべて晒される。それが〈七つの大罪〉への服従の証にもなる。だから〈七つの大罪〉は、当然のようにヘイシャオの記憶を持っているはずだ」
「なるほどな。それなら、異論はない。が――」
ルイフォンは、ぎろりと猫の目を光らせた。
「今までの説明からでは、どうして親父が『〈蝿〉の尊厳を守ってやりたい』なんて言い出すのかが、さっぱり分からない!」
不機嫌なテノールが、無遠慮にぶつけられた。その語勢は、すぐ隣で思考の海に潜っていた兄貴分をも呼び戻す。はっと気づいたようなリュイセンが、ルイフォンに続いた。
「そうです! 祖父上が、ヘイシャオ叔父を気に掛ける理由は分かりましたが、それはあくまでも亡くなった叔父本人に対してのみ、であるべきです。あの〈蝿〉は、鷹刀を害するために作られた、単なる『駒』に過ぎません!」
「……そうだな。年寄りの感傷だ。お前たちの理解を得られなくて当然か」
その通りだ、と言わんばかりのふたりに、イーレオは額に皺を寄せ、溜め息をつく。
「だが、誤解するな。さっきも言ったが、俺の考える最終的な着地点は、お前たちと同じだ」
「着地点?」
リュイセンの声に、イーレオは深く頷いた。
「どんな理由であれ、鷹刀に刃を向けた相手を許すわけにはいかない。そして、自然の理に反した〈蝿〉の存在を、俺は認めない」
「祖父上……」
「だから、俺が奴に与えるべきものは『死』のみだと考える。尊厳を守ってやりたい、という思いは、奴の死が約束された上でのことだ。――この言い方ならば、お前たちは納得できるか?」
明確な言葉に、リュイセンの顔がぱっと明るんだ。ルイフォンも強い同意を見せながら、深々と頷く。
そんなふたりの様子に、イーレオは安堵の表情を見せ、「では――」と皆に向かって告げる。
「『〈蝿〉は葬り去る』。これを、皆の一致した意見とする。一族の方針として……異議はないな?」
力強い声に、場が一瞬、しんと静まり返った。
だが、次の瞬間には、リュイセンとルイフォンが鋭い承諾の声を上げ、メイシアも顔を強張らせながらも頷く。〈蝿〉は父親の仇なのだ。当然だろう。
イーレオは黒目だけをそろりと動かし、ミンウェイの様子を盗み見た。彼女は作り物のような無表情をしていた。やがて、周りが同意しているのに気づき、慌てたように首肯する。
「皆、ありがとう」
イーレオは低く、そっと言う。ミンウェイが気掛かりだが、どうしようもない。イーレオ自身だって、消化できていないのだ。
「では、リュイセンやルイフォンの理解を得られるかは分からないが、俺があの〈蝿〉をどう捉えているのかを話そう」
彼は咳払いをひとつして、一同を見渡す。
「リュイセンは、『〈七つの大罪〉は、俺や鷹刀を害するために〈蝿〉を作った』と言った。因縁ある人物に襲わせることによって、動揺を誘うのが目的だ、と。――だが、俺は違うと思う」
イーレオは、リュイセンに向かって、ぐっと身を乗り出す。
「冷静に考えてみろ。生き返ったヘイシャオごときに、俺を殺せると思うか?」
冷ややかな眼差しで、口角を上げる。笑んでいるはずの顔だが、リュイセンの背筋を冷たいものが突き抜けた。
「死んだ人間が出てくれば驚くさ。けど、それだけだ。〈七つの大罪〉に関わりのあった俺が、『生き返った』なんて非科学を信じるわけがない。すぐに、ただの技術と気づく」
ゆるりと腕を組み、イーレオは嗤う。
「化けの皮が剥がれたヘイシャオの偽者など、俺の敵ではない。――ヘイシャオは鷹刀の血族だけあって、並の人間よりは腕が立つ。頭だっていい。だがな、相手が悪いだろう? 『この俺』には、敵うべくもない」
ぞくりとする低い声が、鳴り響いた。世界を支配下においたような尊大さでありながら、決して大言壮語とは切り捨てられぬ、不可侵の王者の風格が漂う。
「俺への刺客とするには、〈蝿〉では勝負にならん。〈七つの大罪〉は、次は別の人材を用意すべきだろう。けどな……」
ぐるりと、イーレオが瞳を巡らせた。その動きにつられるように、皆が目線が追いかける。
「俺は――」
イーレオは、急に声を潜めた。生真面目な声色に、一同はごくりと唾を呑む。
「清廉潔白な人間なんだ」
「……は?」
ルイフォンの目が点になった。
今まで黙って聞いていた――それどころか、彼にしては珍しく、途中で口を挟むことなく緊張感を持って聞き入っていた――のだが、それが一瞬にして崩れ去った。
「俺には、命を狙われる覚えはない!」
「はぁっ!? 何言ってんだよ、親父! 凶賊の総帥やってて、そんなわけないだろうが!」
拳を握りしめ、ルイフォンが噛み付く。
しかし、いち早く叫んだのが彼だった、というだけで、誰もが同じ思いだったに違いない。
「そこで俺は、疑問に思ったわけだ。『そもそも俺は、本当に、『現在の〈七つの大罪〉』に狙われているのか』――?」
「俺の突っ込みは無視かよ!」
そのまま話を続けるイーレオに、ルイフォンの言葉は虚しく流される。
「で、思った。正体も分からない『現在の〈七つの大罪〉』に狙われているかどうかなんて、考えるだけ無駄だ」
「おいっ!」
「だが、ヘイシャオの記憶を引き継いだ〈蝿〉になら、俺は恨まれているだろう。だから、今回のことは〈七つの大罪〉とは関係ない、死んだヘイシャオの私怨――……」
「待てよ、親父!」
勝手に喋り続けるイーレオの台詞の隙間に、ルイフォンは強引に割り込んだ。
「〈蝿〉は、〈七つの大罪〉から〈天使〉を与えられていた。思いっきり、〈七つの大罪〉が関与しているじゃねぇか!」
〈蝿〉が〈天使〉を使ったせいで、メイシアの父は〈影〉にされ、亡くなったのだ。ルイフォンは決してそれを忘れない。
だから、これは理にかなった意見だ。少なくとも、ルイフォンはそう思った。
だが、あろうことか、イーレオは掛かったな、と言わんばかりに嬉しそうに、にやりと笑った。
「な、なんだよ!?」
「ルイフォン、『〈天使〉』が俺の考えの根拠だ」
「どういうことだよ!」
ルイフォンは、思わず腰を浮かせかける。
その瞬間イーレオが、ぱしん、と手を合わせた。まるで、ルイフォンの苛立ちを御するかのように、小気味よい音が鳴り響く。
「――いいか」
視線が、黙って聞けと命じる。抗える者は、ひとりもいない。
「〈蝿〉は、〈天使〉を使って〈影〉を作り、俺たちを翻弄した。――奴がやったことは、〈蝿〉でなくとも、〈天使〉を利用できる者なら誰でも、可能な手段だった」
「!」
ルイフォンは、はっと顔色を変えた。
「『死んだヘイシャオを生き返らせる』なんて面倒な真似をしなくとも、他の人間で事足りたんだよ」
イーレオの言う通りだった。
「俺の至らなさが原因で、不意打ちを喰らったことは認める。だが、相手がヘイシャオだったから油断した、ということはない。……何しろ、俺自身は〈蝿〉の姿を見ていないんだからな」
「……っ!」
とても簡単なことを見落としていた。
まったくもって、反論できない。ルイフォンは、自分の愚かさに舌打ちをする。
「奴を見たのは、俺とリュイセンだけ……。動揺を誘うつもりなら、生前のヘイシャオを知っている人間の前に現れるべきだった。そうでなければ、意味がない……」
「そういうことだ。――だから、『〈七つの大罪〉は、俺を害するために〈蝿〉を作ったわけではない』と、俺は考える」
イーレオは肘掛けに手を置き、ぐっと背を起こす。
そして、あたかも重大事を宣告するかのように、魅惑の美声を張り上げた。
「〈七つの大罪〉は、俺の命など狙っていない。――〈蝿〉が俺を狙ったのは、完全に私怨。死んだヘイシャオの怨念が、俺を殺したいんだろう」
「ですが!」
間髪おかず、リュイセンが口を挟んだ。
「それなら何故、〈七つの大罪〉は〈蝿〉を作ったのですか!?」
「その答えなら簡単だ。――『ヘイシャオが、天才だったから』だ」
「へ?」
「ことの善悪はさておき、彼は『死者の蘇生』技術すら生み出した、俺の知る限り最高の天才医師だ。――俺の娘のために、血の滲むような努力を続けた男なんだからな……」
はっ、と。息を呑むような気配とともに、草の香が漂った。潤んだ瞳のミンウェイを視界の端に捕らえ、イーレオは続ける。
「現在の〈七つの大罪〉には、死者であるヘイシャオを蘇らせてでも、彼にやらせたい『何か』があるのだろう。唯一無二の天才医師ならばと、望みをかけてな。――〈蝿〉が〈天使〉を与えられたのは、報酬みたいなものだろう」
イーレオがそう言った瞬間、ルイフォンの頭の中を、閃光のような衝撃が駆け抜けた。点在していた情報のかけらが結びついていき、ひとつの情報網を組み上げていく。
「繋がった……」
震えるように、ルイフォンは小さく呟いた。
「『デヴァイン・シンフォニア計画』だ……!」
猫の目が、虚空を見据えた。
〈猫〉の目には、不可視の情報の網が、大きく伸びていくのが見えていた。
「リュイセン、覚えてないか? 潜入した斑目の別荘での、〈蝿〉とホンシュアのやり取り――」
熱暴走に苦しむ〈天使〉のホンシュアを見下ろし、わざとらしい溜め息をついて〈蝿〉は言った。
『『デヴァイン・シンフォニア計画』とやらが頓挫しても構わないのですか? 私の技術が必要なのでしょう?』――と。
リュイセンの瞳が、大きく見開かれた。
ルイフォンは身を翻し、挑むような視線をイーレオに向けた。その勢いに、背中で金の鈴が跳ねる。
「〈七つの大罪〉は、『デヴァイン・シンフォニア計画』のために、〈蝿〉を作った。――親父、そういうことだな?」
「ああ。俺は、そう考えている。そしてな――」
血気はやるルイフォンに、しかしイーレオは、さざなみひとつ立てぬ、まっさらな表情を返す。
「……俺はあの〈蝿〉を、歪んだ憎しみに囚われた、憐れな『過去のヘイシャオ』だと思っている」
「なんだよ、それ」
目の前がぱっと開けたような、気持ちのよい高揚感に水を差され、ルイフォンは口を尖らせた。
「奴が〈七つの大罪〉に命じられて俺を襲ったのなら、俺は問答無用で斬り捨てる。だが――」
憮然とするルイフォンを承知の上で、イーレオは言を継ぐ。やはり、これは若い彼らとは相容れぬ感情なのだと、納得をするために。
「ヘイシャオの無念が俺を狙ったのなら、俺は〈蝿〉の思いを受け止めてやりたいと思うよ。……行き着く先が『奴の死』でしかなくてもな」
「……っ」
感情をこらえるような、小さな声がミンウェイの口からこぼれた。けれど、その息遣いは、あまりにもかすかで、聞き逃したリュイセンは自分の思いのままに、イーレオに食って掛かる。
「祖父上! ヘイシャオ叔父は、逆恨みの極悪人です。手を差し伸べる価値などありません! ましてや〈蝿〉は、単なる作り物です!」
イーレオは、誰にも気付かれないように、ミンウェイを見やる。そっと口元を押さえていたハンカチを、人目を盗むようにして目尻に当てる彼女に、心をこめて告げる。
「あのとき――ヘイシャオからの、最後の電話を貰ったときに、もう少し何か言ってやれればよかったと、俺は今でも後悔しているよ」
もしも、あのとき。ヘイシャオの目を覚ますことができたなら――。
彼の心が、壊れてしまわなければ――。
孫娘は別の名前を与えられ、別の人生を歩んでいたのではないだろうか……。
そして、今ここに。ヘイシャオもまた、共に並んで座っていたかもしれない……。
そんな思いを、イーレオは呑み込む。
「俺を狙う敵としてではなく、俺の娘を最後まで愛してくれたひとりの人間として、俺は奴と対峙したい。奴の心に救いを与えたい。――甘いな。……すまん」
「親父……」
ルイフォンは、声を詰まらせた。
『甘い。認められない』――口元まで出かかった言葉を、吐き出せない。もどかしさに拳を握りしめた、そのときだった。
「――それでも」
すぐ隣で、リュイセンが動いた。肩で揃えられた髪が勢いよく広がり、場を斬り裂く。
「〈蝿〉は、祖父上がご自身でおっしゃった通り、『過去』の存在です。〈蝿〉の心が救われたところで、『現在』が変わるわけではありません。だから、鷹刀の『未来』のために、祖父上に害をなそうとする〈蝿〉は、草の根を分けてでも、即刻、見つけ出すべきです」
張りのある声が、朗々と告げた。
若き狼は礼節をもって、老いた獅子王に頭を垂れる。
「リュイセン……」
今までだって、リュイセンがイーレオに意見することは幾らもあった。けれど、それは文句に近い形での訴えだった。たいていは軽くあしらわれ、そして、どこか堅苦しいところのある兄貴分が、立場をわきまえ引き下がる。そんなことの繰り返しだった。
――そのはずだった。
ルイフォンは握りしめていた拳を開き、その手を挙手へと移す。
「親父……。俺は、リュイセンを支持する。親父の気持ちは、間違っていないかもしれない。でも、リュイセンの言う通り、親父が見ているのは『過去』だ」
〈七つの大罪〉の存在が、ちらつくようになってから感じていた、世代間の差異。古い時代を知る者と、知らない者との温度差。
イーレオは、とうの昔に気づいていたに違いない。だから、ことあるごとに『年寄り連中で対処するつもりだった』と言ったのだ。
けれど、それでは『一族』ではないから――。
ばらばらになってしまうから――。
ルイフォンは、ぐっと唇を噛んだ。
「一族を抜けた俺が、鷹刀の方針に口出しするのは越権行為だと思う。けど、『対等な協力者』としての意見を許してほしい」
猫背を正し、鋭い目でイーレオを捕らえる。
「〈猫〉は、鷹刀の全力での〈蝿〉捜索を要請する。狙いが親父だけだったとしても、奴は他の人間を巻き込むことを躊躇しない。危険な相手だ。それに――俺は、奴から『デヴァイン・シンフォニア計画』の情報を得たい」
「『デヴァイン・シンフォニア計画』の情報……?」
唐突なルイフォンの発言に対し、リュイセンが問い返す。
「ああ。たとえ、親父と〈蝿〉の因縁が解決したとしても、『デヴァイン・シンフォニア計画』には、母さんが関わっている。俺は、これを解き明かさなければならない」
関わっているのは、母だけではない。貴族と駆け落ちしたはずの異父姉、消息不明のセレイエも……。
熱暴走で死んでしまった〈天使〉ホンシュアの正体は、セレイエだった。――ホンシュアは、セレイエの〈影〉だった。
そのことは皆に報告済みであったが、あえて、セレイエの名前を出すのは控えた。彼女は、〈七つの大罪〉の〈悪魔〉、〈蛇〉として、一族に害を及ぼす存在になっているのかもしれないから……。
「……分かった」
水底に沈んでいくような、深く静かな声が響いた。
「全力での〈蝿〉の捜索を約束しよう」
――イーレオが、折れた。
ルイフォンとリュイセンは、互いに顔を見合わせた。驚きと喜びで一瞬、顔が緩む。しかし、すぐに表情を引き締め、敬意と謝意を込めてイーレオに頭を下げた。
イーレオは、ゆるやかに首を振る。
「鷹刀の『未来』のためだ……」
――一族の流れを、いずれ舵を取るリュイセンに向けていくために……。
低い声が響いたあとには、慈愛で満たされた、無風の水面が広がっていった。
そうして、この場がお開きとなる――その間際に。
ルイフォンは、ただ自分の知的好奇心を満たすためだけに、イーレオに尋ねた。
「そういえば、親父。〈悪魔〉の記憶って、定期的に提出されるって言っていたけど、『どこに』保管するんだ?」
記憶を上書きすることで作られる〈影〉なら、〈天使〉の羽を中継して、人から人へ記憶を書き写すイメージだと解釈できる。けれど、保管しておくのなら、どこかに『保存場所』が必要と思われた。
「それは……――っ、――〈冥王〉……!」
言葉の途中で、突然、イーレオが胸を押さえてソファーから転げ落ちた。
「!?」
皆の悲鳴が飛び交う中、イーレオは苦しげな呼吸を繰り返す。ごくわずかな時間に、玉のような汗がびっしりと浮かんでいた。
駆け寄ったミンウェイが脈を取り、エルファンを振り返る。痙攣するようなイーレオの動きに、ルイフォンは、はっとした。
そのあたりで、誰もが気づいた。
これは、〈悪魔〉を支配する、死の『契約』――!
「親父!」
ルイフォンが慌てて叫ぶ。
「すまん。考えるな! 俺は何も聞かなかった! 親父は何も言わなくていい!」
まさか、だった。
『契約』は、〈悪魔〉となったことで知り得た〈七つの大罪〉の『秘密』――すなわち、王族の『秘密』を口外しようとしたときに発動する……。
――つまり、記憶の『保存場所』は、王族の『秘密』に抵触する……。
「皆……心配、するな。……そのうち、収まる……」
額に張り付く髪を払い、イーレオは穏やかに微笑む。陰りのある美貌に、ルイフォンはやり場のない憤りを覚えた。
〈七つの大罪〉、王族――。
そして、『デヴァイン・シンフォニア計画』……。
自分を取り巻く、不可解な現状。言いようもない焦燥感に駆られ、ルイフォンは癖のある前髪を乱暴に掻き上げた。
5.封じられた甘き香に-1

「イーレオ様、つまみのご用意ができましたよ」
夜の食堂に料理長の朗らかな声が響いた。見た目通りの、大振りな彼の気配に、イーレオは現実に引き戻される。
そうであった。エルファンと飲むために、厨房まで酒を貰いに来ていたのだった。だが、既にエルファンが酒を所望したと聞き、つまみのみを頼んだのである。
エルファンが気がかりであったため、夕方の会議は、早々に終わらせるつもりだった。それが、リュイセンの思わぬ追求に遭い、流れが変わってしまった。今ひとつ、後継者として不甲斐のなかった彼が、意外な成長を遂げていたのは喜ばしい。しかし、〈ケル〉に関する報告のあとは、すぐに解散としたかった。
イーレオは眉間に皺を寄せる。知らずのうちに、再び思考の海に沈み込みそうになっていた。だから、何気ない料理長のひとことに不意を衝かれた。
「キリファ様の思い出を肴に、エルファン様と語られるのですか?」
「!?」
心臓が、どきりと跳ね上がった。
「何故、それを……?」
「私には、皆様のお心が読めますから」
料理長が、にこやかに答える。嬉しそうな様子からして、確証はなかったのだろう。それでも言い当てる彼の観察眼には、本当に舌を巻く。
一瞬とはいえ、凶賊の総帥ともあろう者が本気で驚かされてしまった。だが、邪気のない料理長の福相にイーレオは相好を崩す。
「お前、さっきは『人の心など読めるわけがない』と、言っただろう? この二枚舌め」
「ええ、私は料理人ですから。会話用と味見用の、二枚の舌を持っているんですよ」
「な……」
予想外の返しに、イーレオは絶句する。
「冗談ですよ。――エルファン様が、果実酒をご所望されたんです」
「そんなの、ジュースだろう。エルファンが、なんでまた? ――ああ……。キリファが、好きだったな」
「ええ、そういうことです」
キリファはめっぽう酒に強く、いくらでも飲めた。しかし、好んで飲むのはアルコール濃度の低い果実酒ばかりだった。
もと貧民街の娼婦だった彼女は、酒といえば不味い安酒しか知らなかった。だから、鷹刀一族の屋敷に来て初めて飲んだ甘い酒に、すっかり魅了されたのだ。当時の彼女は、まだ十代の少女だったから当然というべきか、飲酒にはまだ、やや歳が足りなかったはずと言うべきか……。
「イーレオ様には、別のお酒をご用意いたしましょうか?」
「いや、よい。キリファを偲んで飲む酒だからな」
そしてイーレオは、つまみの礼を言い、厨房をあとにした。
軽いノックで、すぐに扉は開かれた。
そもそも、戸を叩く必要はなかったのかもしれない。反応の速さから考えて、エルファンはイーレオが近づいてくる気配を察していたと思われる。
迎え入れられた室内は、照明がかなり絞られていた。ほのかな明るさは、淡い橙色というよりも、セピアに近い。
良くいえば整然とした、悪くいえば殺風景なだけの部屋の中央に、ローテーブル。上に載せられた果実酒の瓶だけが、わずかに赤みを帯びた影を落とす。
寄り添うように置かれたグラスは空だった。酔えるはずもない弱い酒を、幾杯も重ねたのだろう。部屋の主には不似合いな、甘い香りが漂っている。
「父上が私を訪ねてくるとは、珍しいですね」
ごく自然に笑みながらエルファンはそう言い、イーレオにソファーを勧めた。
エルファン自身が戸棚に向かったのは、グラスを追加するためだ。硝子戸の前でわずかな逡巡を見せた彼は、やがてグラスと共に酒瓶をひとつ取り出す。果実酒以外なら、部屋に在庫があるのだ。
「ああ、エルファン。俺も、ここにあるのでいい」
イーレオは果実酒を指し、「つまみも貰ってきたから、気遣い無用だ」と、付け足す。
エルファンは穏やかに「そうですか」と応じた。だが内心では、かなりの苛立ちを覚えているはずだ。ひとり、静かに飲みたかったところを邪魔しにきたのだ。機嫌を損ねて当然だろう。
「先ほどは、リュイセンが失礼いたしました」
イーレオの訪問を、夕方の会議の件だと解釈したのか。酒をつぐなり、エルファンは頭を下げた。
「何をお前が謝る? 奴が言ったことは至極まっとうだった。頼もしい限りじゃないか」
「ですが、父上をあまりにも蔑ろにした物言いは、看過できるものではありません。それに泥臭い方法で〈蝿〉を探す手を増やしても、さして効果はないでしょう」
「いや、この先の鷹刀は、あれでいい。リュイセンに任せておけば、緩やかな解散も実現できるだろう」
からん、と。
グラスの中で、氷が崩れた。
「リュイセンは……まだ未熟です」
「そこがいいんじゃないか? それに、ルイフォンもいる」
ルイフォンの名前に、エルファンの表情がかすかに揺れた。しかし、イーレオは気づかなかったふりをした。
「ルイフォンの奴、一族を抜けたことに、えらいこだわりがあるみたいだな。『越権行為』だの、『意見を許してほしい』だの……。あそこまで畏まらくてもなぁ」
イーレオは可愛くて仕方ない、というように、目を細める。
「そこはやはり、けじめです。線引きは必要でしょう」
「まぁ、その通りなんだが。でも俺たちとルイフォンは、いい加減な口約束のもとに、馴れ合っている。それでなんとかなるくらいが、ちょどいい。――それが、『絆』ってもんだろう? 契約で縛れるような関係に、価値はないと、俺は思うよ」
エルファンは、じっとイーレオを見つめていたが、ふと視線をそらした。
「なんとも、父上らしいお言葉ですね」
口調だけは柔らかに、けれど無表情な瞳で、エルファンは言う。そして、飲み干したグラスの空虚さを埋めるかのように、こぽこぽと注ぎ足す。
酒と瓶とが奏でる音に、イーレオは眉を曇らせた。
「俗に、さ――」
イーレオが吐き出した言葉は、半分以上、溜め息に覆われていた。我ながら、ずいぶんと精彩を欠いた声が出てきたものだと、彼は自嘲する。
「『飲む・打つ・買う』と言うだろう?」
酒瓶を持つエルファンの手が、一瞬止まった。この父はまた、なんと突拍子もないことを言い出すのだ――そう思っているのが、ありありと伝わってくる。それを承知しながら、イーレオは続ける。
「お前は、博打も女遊びもしないが、酒だけはやるんだな」
「……父上の意図は分かりかねますが、おっしゃる通りですね」
平静を装いながらも、不快感が見え隠れしていた。
エルファンにしてみれば、父の来訪自体が予定外の番狂わせだ。その上、一方的にわけの分からないことを言われれば、声が尖るのも仕方ないだろう。
「博打と女遊びは、同じなんだよ」
エルファンの苛立ちもお構いなしに、イーレオはマイペースに口の端を上げる。どういう意味だか分かるか? と、暗に問うていた。
それに対し、エルファンの横顔が、くだらない話題に付き合うつもりはないと返事する。あまりに予想通りの態度に思わず苦笑して、イーレオは正解を告げた。
「賭けごとにしても、女にしても、どちらも『相手』が必要。ひとりじゃ無理だ。だが――」
言いながらイーレオは、手にしていたグラスをあおる。
「酒は、ひとりでも飲めるな」
空になったグラスが、テーブルにことん、と載せられた。
決して乱暴にぶつけたわけではないのに、その音は妙に響いた。そうなるように、イーレオが狙ったのだ。
「……」
エルファンは、わずかに眉を寄せた。
しかし、テーブルに置いたグラスを握ったままの、低い姿勢から見上げてくる父の視線に気づいたとき、はっと息を呑む。
凪いだ海のように静かでありながら、圧倒的な力強さを感じる眼光――。
「父、上……?」
「俺が、お前を――、そういう人間にしてしまったんだな」
溜め息と共に、うつむき加減に顔が動かされると、眼鏡のレンズがイーレオの美貌にセピアの影を落とした。
「……また、その話ですか?」
エルファンは、もはや、うんざりした様子を隠さなかった。
「父上が総帥になったき、鷹刀は規律を重んじる組織に生まれ変わった。厳しくすれば、どうしても不満が生じる。その矛先が総帥である父上に向かないよう、私が憎まれ役になる。そう決めた。――ただの役割分担だ」
今まで静かにたたえられてきた苛立ちの湧き水が、ついに堰を切ったかのように、エルファンは一気に言い返す。
「それで私が多少、孤立したところで、全体の利益に比べれば些細な問題だ。いまだに何故、そんなことを言う?」
鋭い口調は、常とは違っていた。けれど三十年前には、いつもそばで聞いていた、耳に馴染んだ響きだった。
ああ、やはり似ている、とイーレオは思う。
「俺は、そんな古い話を持ち出したいわけじゃない。……お前だって、分かっていて、わざと――……」
そう言ってしまってから、イーレオは強く首を振った。
「すまん。逃げているのは俺のほうだ。……どう切り出せばいいのか、分からないんだよ。悩んでいて、横道にそれた」
イーレオは弱りきった顔で、力なく笑う。
彼は目線をテーブルに落とし、果実酒の瓶を見つめた。華奢で可愛らしいフォルムは、彼女を彷彿させる――。
「俺が、お前からキリファを奪ったから、お前は孤独を好むようになった……だろう?」
「……っ!」
エルファンは、鋭く息を吸い込んだ。
表情は凍りついたように変化のないまま。しかし、浅い呼吸が繰り返される。
「父上が、奪ったわけではありません……」
激しく高鳴る鼓動を隠して、エルファンは冷静を装った声を出す。
「些細な行き違いから、私はキリファに愛想を尽かされました。そして、鷹刀を出ていこうとした彼女を、父上が『総帥の愛人』の地位を提示して引き止めた――それだけのことです」
鷹刀一族は、キリファのクラッカー〈猫〉の能力を高く買っていた。
一方、キリファは、クラッカーとしての能力を発揮できる環境が整っていなければ、もと娼婦で〈七つの大罪〉の実験体の、搾取される生活しか知らない、か弱い女でしかなかった。
外の世界で暮らすには、彼女は非力な存在だった。経歴があやふやである上に、右足首から下が義足の彼女は、奇異な目で見られただろう。しかも、娘のセレイエはまだ小さく、将来を考えれば不安しかない。
〈天使〉の能力を使えば、あるいは人並み以上の生活を送れたのかもしれない。しかし、道理に合わない力は、いずれどこかで碌でもない災厄を招く。
イーレオの申し出は、事実上、キリファのためを思った、婉曲的な庇護であった。それが分かっているから、彼女は応じた。
そして、エルファンもまた、父の温情を理解していた。だからこそ、最愛の女を取られても一族を離反したりせず、むしろ感謝をもって受け入れたのだ。
「そうだな。そういうことになっているな」
「父上?」
言葉の上では肯定かもしれないが、イーレオの返事は決して肯定などではなかった。エルファンは訝しげにイーレオを見つめ、その真意を問う。
「今日のルイフォンの報告にあった〈ケル〉の話……。キリファの最期に呼ばれたのは、俺ではなくて、エルファン――お前だった。このことを、お前はどう解釈する?」
それはまさに、エルファンがひとりで杯を重ねていた理由だった。彼は、不快げに鼻に皺を寄せる。
「〈ケル〉は、私とキリファの和解を求めていたのでしょう。……それとも父上は、キリファが私のことをずっと想っていた、とでもおっしゃりたいのですか?」
軽薄な嗤いと、低い声で抑え込んでいても、エルファンの言葉尻からは激昂が漏れ出ていた。
それは、本心の裏返しだ。
そうであればよいのに、と強く願う気持ちが反発し、荒ぶっている。
イーレオは、やり切れない思いで、エルファンを見つめた。
キリファの死後も、彼女との約束を守って口を閉ざしてきた。しかし、〈ケル〉がキリファの気持ちを代弁したも同然の状況で、黙し続けていることが正しいとは思えなかった。
「……エルファン。キリファはずっと、お前を愛していたよ」
その瞬間、エルファンの氷の眼差しが、イーレオを鋭く貫いた。
「気休めは無用。彼女は私と別れ、父上を選んだ。彼女は名目上の愛人ではなく、あなたとの間にルイフォンまでもうけた。そのあなたに慰められるなど、さすがに私が惨めです。……すみません。出ていってください」
冷酷なまでに無に徹した表情は、完全なる拒絶だった。
「――そうだったな。お前にとって、ルイフォンの存在が決定打になったんだったな……」
明らかに一触即発のエルファンを前に、イーレオが溜め息混じりにそう言う。
エルファンは、怒りに体を震わせた。自らの矜持を捨ててでも、実力行使に移るべきかと、にわかに検討を始める。
その気配を感じ取り、イーレオは冷静に先手を打った。
「――けどな。俺は、キリファには手を出していない」
「!?」
エルファンは、自分の耳を疑った。イーレオの言葉は、確かに聞こえているのに、理解が追いつかない。
「ルイフォンは、俺の子じゃない――」
イーレオの呼気に混じり、果実酒の香がふわりと漂う。
「――お前の子だ」
キリファを思い起こす甘さを撒き散らしながら、低い声がエルファンの胸に届いた。
5.封じられた甘き香に-2

イーレオの告白は、甘い果実酒の柔らかな香りに包まれていたが、エルファンの氷の仮面を叩き割るのに充分な威力を持っていた。
「どう……いう…………?」
やっと口からこぼれ出た疑問も、途中で霞みながら沈んでいく。
「だから、言っただろう? キリファはずっと、お前を愛していた、と」
「っ! ふざけるな!」
エルファンは、両手を思い切りテーブルに叩きつけた。振動で、グラスの中の果実酒がさざ波を立てる。
「父上の子を身籠ったと言うから、私は彼女をすっぱり諦めたんだ……!」
エルファンはぐっと手を伸ばし、テーブル越しにイーレオの襟元を掴み上げた。
「説明しろ!」
血走った目で憎々しげに迫るエルファンに、しかし、イーレオは泰然とした構えを解くことはなかった。
「キリファは、な。ルイフォンを――お前の子を宿したから、お前のそばを離れたんだ」
「わけの分からぬことを!」
この期に及んでなお、謎掛けのようなことを言うイーレオに、エルファンの怒りが膨れ上がる。襟元を掴む手に更に力が加わると、イーレオは「ああ、そうだよ」と、くっと口元を歪めた。
「俺だって、わけが分からなかったよ」
殺意すら感じられる低い声が、エルファンの耳朶を打った。
本能的な恐怖に目の前を凝視すれば、イーレオの表情は穏やかなようでありながら、その瞳の奥に深い憤りと苛立ちをくすぶらせている。
「父、上……?」
「子供ができれば、めでたいじゃないか。喜んでお前に報告すればいい。なのにキリファは、お前に知られることを極度に恐れた。鷹刀を出て、ひとりで育てると言う。『あたしはもう、子供は産まない、って、エルファンに宣言したんだから』ってな」
「! ……セレイエの……事件……。あのとき……言った……?」
エルファンは、瞠目した。
途切れ途切れの言葉は不明瞭な発音から成っており、それらは明確な台詞にならぬままに消える。イーレオの襟を握りしめていた手の力が、するりと抜け落ちた。
「ああ」
楽になった襟元を直し、イーレオは頷いた。
――ルイフォンの姉、セレイエ。
彼女は幼いころ、異母兄のレイウェン、幼馴染のシャンリーの子供たち三人だけで遊びに出掛け、敵対する凶賊に襲われた。
そのとき、レイウェンは重症を負い、生死の境をさまよった。
しかし、セレイエはもっと深刻だった。通常の医療では手の施しようがなかったのだ。
襲撃をきっかけに、彼女の持って生まれた運命が明らかになった。限界を超えて酷使された体は高熱にうなされ、意識を失ったままの状態が幾日も続いた。
再び目を覚ますことができたのは、奇跡としかいいようがなかった。
事件のあと、セレイエは、母親のキリファと共に屋敷の外で暮らすことになった。彼女が凶賊として再び襲われることのないように、一族ではないと分かりやすく示すためだった。
だが、凶賊と縁を切ったところで、今後も何かのはずみで同じことが起こり得る。彼女は常に、死と隣り合わせで生きていかなければならない――。
そしてキリファは、もう子供は作らないと宣言した。
次の子供もまた、セレイエと同じに違いないから、と。更には、子供を産むのは正妻のユイランに任せる、とまで言い切った。
「だからと言って、そんな……」
「俺だって、キリファの言い分は、まったく理解できない。だが彼女にとって、あの宣言は絶対に守るべき誓いだったらしい」
「…………」
エルファンは、自分の中に湧き上がってくる気持ちをどう捉えればよいのか分からず、ただ拳を握りしめた。全身に強く力を入れていないと、気が狂いそうだった。
イーレオは、陰鬱な面持ちで視線を落とし、「出ていこうとしていたキリファに気づいたのは、ユイランだった」と語り始める。
「様子のおかしいキリファを根気強くなだめすかして、白状させたそうだ。嫌がるキリファを俺の前に連れてきて、相談に乗ってほしいと言ってきた」
ユイランの思考もまたイーレオには理解しがたいのだが、彼女はキリファを非常に可愛がっていた。キリファに何を言われても、野良猫に引っかかれた程度にしか感じていなかったように思える。
「キリファは戸惑いながらも、子供ができたこと自体は喜んでいたよ。だが、お前を心配して……というのか――。お前に対して、罪悪感にすら似た気持ちを抱いていた」
『エルファンが喜んでくれるのは分かっているわ。でも、またセレイエみたいになったら……! エルファンはね、いつも仏頂面だけど、本当は凄く繊細なの。――あたし、エルファンを悲しませたくない……!』
「どうして、罪悪感を抱く?」
「分からん。ユイランが言うには、かなり異常性に満ちてはいるが、これも『女心』だそうだ。つまり、元気な子供を産める、完璧で理想的な『お前の女』でありたいのに、そうなれないのは罪深いのだと。そう思い込むような精神状態だったらしい」
そう言ってから、イーレオは「やはり、俺には分からんよ」と、お手上げだとばかりに首を振る。
「馬鹿なことを言ってないで、とっととエルファンに報告しろ、と言ったんだが、手のつけられないような興奮状態でな。『勝手にエルファンに伝えたら、〈天使〉の力を使って記憶をぐちゃぐちゃにしてやる』とまで言ってきた」
そのときのことを思い出し、イーレオは重い息をつく。
「相手は妊婦だから気が立っているのだろう、刺激してはいけないと、俺は無理やり自分を納得させたよ。――ともかくキリファの決意は固くて、今にも鷹刀を飛び出していきそうな勢いだった。だから、なんとか思いとどまらせようと、俺は必死に考えた」
イーレオは、自分とそっくりなエルファンの顔を、まっすぐに見つめた。
「キリファの憂慮は、『お前を』悲しませたくない、ということだけだった。それで、『だったら、エルファンではなくて、俺の子供ということにしておけばいい』と提案した。外見からは絶対に分からないから、とな」
「つまり、『総帥の愛人』という地位を提示したのは――キリファを庇護するのと同時に、子供の父親をあやふやにするため……」
「そういうことだ」
結局、キリファはイーレオの申し出に応じた。
初めは、『あたしは、ひとりで生きていけるわ。馬鹿にしないで』と強気に言っていたが、思うようにならぬ身重の体に、やがて折れた。自分だけならまだしも、腹の子と幼いセレイエのことを考えたら、やはり不安だったのだろう。我儘放題に見えても、キリファは母親だった。
そして、言いがかりのような喧嘩をふっかけて、キリファはエルファンに別れを告げた。ユイランもまた、キリファの行動が自然に見えるよう『愛人を追い出した、怖い正妻』を演じた。
「落ち着いたら、真実を話せばいい。それで大丈夫だろうと考えた俺が――傲慢だったよ」
最後のひとことは、深い後悔。それは、やり場のない怨嗟の響きを帯びていた。
イーレオの思惑や、キリファの憂慮など、エルファンは知る由もなかった。だから彼は自分を抑え、彼女の幸せだけを願った。
すぐそばにいながらも、その瞳に永遠の決別の色を浮かべた。どす黒い感情と葛藤し、割り切り、彼女への想いを粉々に砕き、諦めた。
『人』を避ける傾向にあったエルファンにとって、キリファは、気負いのない心を見せることのできる、ただひとりの相手だった。彼女を失った空虚さに、彼は『人』との関わり合いを拒み、孤独を好み、心を閉ざすようになった。
「浅はかな俺の考えが……お前の心を殺した。――すまなかった」
イーレオの頭が深々と下げられた。背で緩くまとめられた長髪がほどけ、あとを追うようにさらさらと流れる。
エルファンは、それを呆然と見つめていた。心が凍りついたように何も感じることができなかった。
すべてが、ぴくりとも動かぬ、無音の世界が訪れる。
グラスの中の果実酒さえ、その水面をゆらりともさせない。時の流れから切り離されたような空間は、セピアに彩られて現実味を失っていた。
そのまま、どのくらいが過ぎただろうか。やがて、ゆっくりとイーレオが顔を上げた。
「ルイフォンが生まれて、成長して……、セレイエのような兆候は見られなかった。だから、真実を伝えてはどうかと、俺はキリファに勧めた」
「……」
「だが、『エルファンの心はもう、あたしにはないから、言えない』と――」
「……!」
刹那――。
音を立てて崩れる流氷のように、エルファンの心に亀裂が走った。
「ちがぅ……キリファは……、何度も言おうとしていた…………!」
華奢な体躯が、そっと近づいてきた。小柄な彼女がエルファンを見上げれば、ちょっときつめの猫目が上目遣いになる。
何か言いたげな顔だと、すぐに分かった。けれど、素直に言えぬ性格だと、よく知っていた。だから、水を向けてやれば喜ぶのだと、その笑顔の幻影が見えていた。
なのに、気づかないふりをした。もう想うことの許されない相手なのだから、と。
「――言えなかったんじゃない。私がキリファに、何も言わせなかったんだ……!」
エルファンは虚空を掻き抱いた。
あのときの彼女を引き寄せるように腕を滑らせ、胸の中に包み込んだ。うつむいた彼の鼻腔を、果実酒の香りがくすぐる。甘いはずのそれは、心につん、と鋭くしみた。
イーレオは、空になっていた自分のグラスに酒を注いだ。そして、置かれたままだったエルファンのグラスに、強引に触れ合わせる。
可愛らしい音色が、ちん、と鳴り響いた。
「酒は、ひとりで飲むよりも、誰かと飲んだほうが……美味いぞ」
「……っ」
エルファンの息が乱れた。
イーレオは、手にしたグラスを一気に飲み干し、甘く笑う。
「『あたしの嘘も見抜けないほど馬鹿な男だなんて、思ってもいなかったわ』と、キリファは愛しげにうそぶいていたよ」
低い声が、優しく落ちた。
「……ああ」
エルファンの瞼に、キリファの姿が鮮明に浮かび上がる。
強気な口調で言ってのけ、柔らかな猫毛を揺らして、ぷいと横を向く。それは、誰にも見られたくない顔を、隠すため――。
「彼女は泣きながら、そう言ったんですね……?」
「泣き笑いの顔でな」
「強がりで、不器用なんですよ」
警戒心が強いくせに、寂しがり。生まれたときから、ごみ溜めのようなところで暮らしてきたくせに、まっすぐすぎる魂は、どこまでも純粋無垢。
とても一途で……可愛い女なのだ。
次から次へと、尽きることなき泉のように、彼女への想いがあふれ出す。
「――別れたあとも、私が贈ったチョーカーを外さなかった……」
あれは、いわば所有の証だ。それを身に着け続けている意味を、エルファンはずっと理解できなかった。
「チョーカー?」
イーレオが、からかい混じりの、尻上がりの声を出す。
「ルイフォンの持っている鈴がついていた、あの首輪か? お前、いくら自分の女だからって、首輪は悪趣味だぞ」
批判的な意見に、エルファンはむっと眉を寄せる。
「似合っていたからいいんです。それに彼女も喜んでいました」
『あたしはエルファンの飼い猫になったの』――そう言って、彼女は無邪気に笑った。
裏切りという言葉を知っているくせに、彼女は恐れることなく彼だけを見てくれた。あの小さな体のどこから、そんな強さが生まれてくるのだろうと思うほどに、彼を愛してくれた。
あのチョーカーの鈴の存在が、キリファの最期のときの記憶を、ルイフォンに残したという。それは、どこか運命的に感じられた。
――そう。エルファンの『息子』、ルイフォンの……。
「父上」
声を掛けたエルファンは、冷涼としていながらも穏やかな目をしていた。
「リュイセンではありませんが、『過去』ばかりを見ているわけにはいきません。『未来』の話をしましょう」
「そうだな」
イーレオが、ふっと口元を緩める。
その表情を見て、エルファンは気づいた。父は、もともとそのつもりだったのだ。
「まず、ルイフォンの件ですが、今まで通り、父上の子ということにしておいてください」
「なんだ、親子の名乗りを上げないのか?」
「親が何者であるか、などということは、どうでもよいことです。自分自身が何者になるかが、問題なのです。――それにルイフォンは、既に事実上の伴侶まで得て、独立しました。そんな男に親など無用です」
正論と言えなくもないエルファンの弁だが、イーレオには『今更、どの面下げて名乗れるか』と、顔に書いてあるようにしか見えなかった。
「ユイランが、がっかりするな」
「何故ですか?」
残念そうなイーレオに、エルファンは訝しげに目を尖らせる。
「この前、ユイランは久々にルイフォンに会って、成長した姿を見たわけだろう? 昔のお前にそっくりだと、嬉しそうだった。あれは明らかに、言いふらしたくてうずうずしていたぞ」
エルファンは、眉間に皺を寄せた。イーレオの言ったことが、不可解だったのだ。
「ルイフォンはキリファ似ですから、私にはあまり似ていません」
「似ているのは顔じゃないさ」
にやにやとするイーレオに、エルファンは憮然とする。
「だいたい何故、私とルイフォンが似ていると、ユイランが喜ぶんですか? 論理的でありませんね」
「さて? ユイランが喜ぶ理由は知らん。だが、昔のお前を知っていれば、懐かしくもなるのは分からんでもないさ」
イーレオは楽しげに笑いながら、グラスをあおった。エルファンは合点がゆかぬ顔で見つめていたが、やがて、つられるようにグラスを傾ける。
そして――。
「それから……、セレイエですね」
「ああ」
それこそが、『未来』の話――。
キリファが、ふたり目の子供の妊娠を隠したがった心情は理解できないと、先ほどイーレオは言った。しかし実は、ほんの少しだけ分かる気もするのだ。セレイエの運命を知ったときのエルファンの嘆きようは、尋常ではなかった。だから、同じことを繰り返したくないと、キリファは思ったのだろう。
そしてイーレオも、エルファンの前で、セレイエの名を口にするのを避けてきたきらいがある。
……けれど、もはや、そうも言っていられない。この部屋を訪れたのは、『過去』と向き合って、『未来』を掴むためなのだから――。
「まだ、見つかっていないのですよね」
「手を尽くして探してはいるが……正直、見つかる気がしない」
エルファンの問いに、イーレオは渋面を作る。
『自分のことを知りたいの』
そのひとことで、セレイエは〈七つの大罪〉へと飛び込んでいった。
母親のキリファとは、たまに連絡を取っていたようだが、キリファが死んでからは、まるで消息を掴めない。
「ユイランとシャンリーは、メイシアに『過去』を話したときも、セレイエについてはほとんど触れなかったそうだ。本人のいないところで、勝手に話すべきではないと判断した、と」
ユイランは、そもそも過去の話にセレイエを出そうとしなかったし、シャンリーは『黙するべきことは、わきまえます』と言って巧みに避けた。
「だが、若い連中に言わないわけにはいかんだろう?」
イーレオは、冷徹な視線をエルファンに向けた。
それを受けたエルファンは、一瞬だけ苦しげに表情を崩したが、すぐに「ええ――」と頷く。
「おそらく、セレイエが鷹刀を『デヴァイン・シンフォニア計画』に巻き込んだ張本人でしょうから……」
「――ああ」
イーレオは目線を落とし、指先で摘んだグラスを見つめる。期待した通りの言葉が返ってきたところで、出てくるものは溜め息しかないのだ。
「セレイエは、鷹刀の『敵』となった可能性が高い」
硬い表情で、エルファンは呟いた。
「まだ、断定するのは早い。……助けを求めているのかもしれないぞ。作られた〈蝿〉は俺を狙っているが、現在の〈七つの大罪〉と鷹刀の関係は、必ずしも『敵対』とは限らない。……まだ、なんとも言えないんだ」
イーレオは、エルファンの空のグラスに酒を注ぐ。エルファンはそれを受けると、今度は彼が酌を返した。
「セレイエに関しては、私から、若い奴らに言います」
そう言って、エルファンは一気に飲み干す。
「そうか。では、次の会議のときに頼む。――お前から言ってくれるのなら、助かる。俺もいい加減、『昔のことを隠してばかりの爺』の汚名を返上したいんでな」
台詞の最後は冗談で流したが、最初の部分はイーレオの気遣いだった。ルイフォンなどであれば、明日にも皆を集めて情報共有すべきと言うであろうが、少しとはいえ時間の猶予を与え、気持ちの整理を促したのだ――。
酒を注ぎつ、注がれつ。エルファンの部屋に、甘き香が漂う。
セピアの苦味に包まれながらも、こんな酒も悪くはない。果実酒の瓶が落とす柔らかな影を瞳に映し、エルファンはそう思った。
~ 第二章 了 ~
幕間 孤独の〈猫〉

その瞬間、世界が白金に包まれた。
目のくらむような、まばゆい光。反射的に、私は腕で顔をかばう。
透かし見た先には、爆風に短髪を逆立てた、少女の姿があった。その背からは、閃光のような光の糸が、あとからあとから噴き出ている。
「迎えが来ただけよ」
そばにあった机に手を付き、彼女はそれを伝うようにして進む。話に聞いていた通り、彼女は片足首を失っていた。身請けの際の条件だったという。
彼女が、よろけながらも目指す先は、私ではない。
腰を抜かし、床に這いつくばりながら後ずさる、憐れな男。顔の造作としては、なかなかの優男ではあるが、今は恐怖に引きつり台無しになっている。
彼女から放出された光の糸は、生き物のようにうねりながら互いに絡み合い、やがて波打つように明暗を繰り返す、輝く羽となった。
――〈天使〉。
〈七つの大罪〉が作り出した、人体実験体。
人間の脳に侵入し、相手を乗っ取るクラッカー。
しかし脳内介入は、〈天使〉の体に過剰な負荷をかける。限度を超えれば、羽が熱暴走を起こし、死に至る……。
熱気があたりを包み込み、機械類を繋いでいたコードが溶け出した。唸りを上げ、作動中を示すライトを明滅させていた筐体が突然、火を噴く。幾つもあるモニタはブラックアウトし、ことごとくひびが入っていった……。
研究室の様相は一変した。
男にとって、寝耳に水の事態だろう。彼女は、妄信的に彼に従う存在のはずだったのだから。
けれど、彼女が羽を現した理由を誤って解釈するほど、彼は愚かではなかった。彼女が自分を害そうとしていることを、彼は正確に理解していた。
彼女から逃げるため、男はなんとか立ち上がるも、床に飛び散った資料に足を滑らせ、再び転倒する。
所詮、無駄な悪あがきだった。
何しろ、ひとつしかない出口の前には私がいるのだ。彼女と私の間で挟み打ちになった男に、いったい何ができるというのだろう。
「〈猫〉! 何故、羽を出す!? 俺をどうする気だ!? ……こいつは、いったい何者だ!?」
私を指差し、男は金切り声を上げる。
「だから、言ったでしょ、〈蠍〉。迎えが来ただけだ、って」
猫のような目を細め、彼女が笑う。
小柄な少女だ。
歳は十五か、十六だと言っていたが、正確なところは本人も知らないらしい。もしも、十三歳だと言われれば、私は驚くことなく、そのまま信じただろう。そのくらい細く、華奢な体つきをしていた。
「迎え……? どういう……? お前は、何を……!?」
〈蠍〉と呼ばれた男は、私と彼女を交互に見ながら、単語を並べただけの未熟な疑問を口にする。だが、途中で、はっと顔色を変えた。
私の顔を凝視しながら、震えるように呟く。
「こいつは、鷹刀の直系の大物だ。〈猫〉、お前、〈七つの大罪〉を捨てた鷹刀と組んで、何をする気だ……!?」
「へぇ、その人、大物なんだ? 知り合いなの?」
〈猫〉は、折れそうなほど細い小首をかしげる。
小動物的なその仕草と、幻想的な美しさを放つ羽のおかげで、可愛らしくも神々しくも見える姿だが、その瞳は、獲物を狩る野生の獣のそれだ。
そんな〈猫〉に気圧されてか、〈蠍〉は律儀に答えた。
「面識はないが、鷹刀は〈贄〉の一族。煮詰めた血のせいで、皆、同じ顔だから、ひと目、見りゃ分かる。それに、こいつは〈蝿〉にそっくりだ」
〈蝿〉の名に、私は自分の眉が、ぴくりと動いたのを自覚した。だが、それ以上の表情の変化は許さない。
まさか、こんなところで〈蝿〉――ヘイシャオを知る者に出くわすとは思わなかった。〈悪魔〉同士の交流は皆無に等しいと、同じく〈悪魔〉であった父上がおっしゃっていたから、想定外だった。
そういえば、ヘイシャオはミンウェイの記憶を保存するのだと言っていた。それで〈天使〉の専門である〈蠍〉と面識があるのかもしれない。
ヘイシャオは、どうしているだろうか。
ミンウェイは――妹は、まだ生きているのだろうか……。
ほんの一瞬だけ、ふたりの消息を尋ねたいという誘惑が、私の頭をよぎった。しかし、私はそれを切り捨てる。
聞いても仕方のないことだ。ミンウェイは助からない。それが天命だ。
そして、ミンウェイを亡くしたあと、おそらくヘイシャオは自ら命を断つだろう。そういう男だ。
彼らは、私には理解できない感情で繋がっていた。
――故に。
遅かれ早かれ、彼らの行き着く先に変わりはない――。
「〈猫〉、約束通り、迎えに来た。私は、その男を斬って、お前を連れていけばよいのか?」
意識を現実に戻すべく、私が自分から口を開くと、〈蠍〉が、ぎょっとしたように、私を振り返った。
一方、〈猫〉はといえば、緩やかに口角を上げ、少女とは思えないような妖艶な笑みを浮かべる。
「ええ、連れていってほしいの。――でも、〈蠍〉に関しては、それには及ばないわ」
「ほう?」
では、どうするつもりなのか。
私の疑問は、すぐに彼女の行動によって解消された。すなわち、彼女の羽がぐっと伸び、〈蠍〉に襲いかかったのだ。
「〈猫〉!?」
光の糸に巻きつかれ、〈蠍〉が悲鳴を上げる。
「お、おのれ、〈猫〉! ごみ溜めから拾ってやった恩も忘れて、この俺に!」
高圧的にわめきたてるも、糸に縛り上げられ、床を転がる男が何を言ったところで、滑稽なだけだった。
羽から発せられる熱気に、彼女の短い髪が、ふわりと舞い上がる。まるで、彼女の感情の高ぶりを示すかのように。
「あんたは……、研究という名目で、あたしを解剖して……殺すんでしょう?」
〈猫〉は冷静なようでいて、実は、まったくの逆だった。
彼女の声が揺れた。
勝ち気な瞳が潤み、それもまた揺れる。
〈蠍〉は息を呑んだ。
「どうして、それを……」
「馬鹿ね。あんた、言っていたでしょう? 『この世に完璧なプログラムなんて存在しない』って。あたしが、あんたのセキュリティを破って、あんたの落書きを見つけた。それだけのことよ」
「……くっ!」
〈蠍〉の顔に浮かんだのは、屈辱と憎悪。
それに対して、〈猫〉は、微笑んだ。この場にふさわしくない、とても澄んだ笑顔だった。
「あたし、あんたに感謝しているわ」
歌うように、さえずるように、彼女が笑う。
「あんたの言う通り、あんたはあたしを、ごみ溜めから拾い上げてくれた。あんたのおかげで、あたしは人間の生き方を知ることができた。……ありがとう」
あどけなさの残る少女の言葉が、彼女の残酷な半生を物語る。
その声には一片の偽りもなく、彼女は真に〈蠍〉に感謝していた。それが、部外者の私にも、はっきりと伝わってくる。
やがて彼女は、ゆっくりと天を仰いだ。
切なげにつむった瞳から、涙がこぼれ落ちた。
苦しげに食いしばった歯の隙間から、嗚咽が漏れた。
そして、彼女の背が、羽の根元が、強く輝く――!
その輝きは複雑に明暗を繰り返しながら、〈蠍〉に巻き付いた糸へと伝搬していく……。
「〈猫〉! やめろ! やめてくれ!」
「ねぇ、〈蠍〉。あんたが、あたしを愛していると言ったのは、本当だった?」
か弱き、無邪気な少女の顔で、〈猫〉が問う。
「本当だ! 本当だとも! お前は、俺の最高のパートナーだ! 俺とお前が組めば、無敵だったろう!? だから、これからも……!」
「……嘘つき」
ぞくりと艶めく、女の呟き。
「嘘じゃない! 俺はお前を愛している!」
〈蠍〉が叫ぶ。だが、〈猫〉は悲しげな顔で首を振った。そして、彼に巻き付いていた糸がほどけ、彼女の羽に戻る。
「今、あんたに書き込んだ命令。あんたには読めないわよね」
「え?」
読めずとも、不穏な雰囲気は充分に伝わっていた。〈蠍〉は許しを請うように、〈猫〉にすがる。
「助けてくれ! お前は、俺に何を……!?」
〈猫〉が嗤った。
その言葉を待っていた、とでもいうように、彼女は口元をほころばせた。
「教えてあげるわ。あたしが書き込んだ命令の意味――『嘘つきは、死になさい』」
「!」
次の瞬間、〈蠍〉が血しぶきを上げた。
体中の血管という血管が破裂し、血染めの体が床に落ちる。救いを求めるように、片手を〈猫〉へと伸ばしたまま、彼はこと切れた。
羽が生き物のように脈打ち、激しく瞬きながら、〈猫〉の背の中に戻っていく。輝く渦の中心で、彼女が泣いているのか、笑っているのか、私には判別できない。
「……あたしは。あんたなんか……、愛していなかったわ……!」
消え入りそうなほどに小さな慟哭。〈猫〉の静かな孤独。
彼女もまた嘘つきだと、私は思った。
無垢な想いに魂を震わせながら、彼女は全身で、愛していると告げていた。
それは、私には理解できない、曖昧で不明瞭な感情だった。
羽が吸い込まれ、光が消えたあとも、彼女は〈蠍〉だったものの亡骸を見つめていた。癖の強い前髪が目元を隠していても、私にはそれが分かった。
彼女の生い立ちは、前情報として聞いている。喰うか、喰われるかの、屍で埋もれた世界にいた。
私と、大差ない。
なのに、どうして――。
彼女は、こんなにも、純粋でいられるのだろう……。
私は、惹き寄せられるように彼女に近づいた。
血まみれの〈蠍〉の死体を無造作にまたぐと、彼女の視線が私に移った。
間近で見た彼女は、とても小さかった。片足を失っているため、体を机に預けた姿勢しかとれず、私の胸の高さほどしかない。
私は手を伸ばし、彼女の髪をくしゃりと撫でた。
「!?」
彼女は驚いたように目を見開き、警戒に身を強張らせた。まるで毛を逆立てた野良猫のようだ。足が不自由でなければ逃げ出していたかもしれない。
だが、驚いたのは、私も同じだった。
それは無意識の行動だった。幼い息子のレイウェンにすらしたことのない、不可解な行為だった。
癖の強い髪は、思ったよりも繊細で滑らかで。その感触が心地よくて、私は彼女が顔をしかめるのも構わずに何度も撫でる。
「なっ、何よ……!?」
「迎えに来た。行くぞ」
私は、彼女をひょいと抱き上げた。見た目通りに、とても軽い。決して肉付きはよくないのに、彼女の体はおそろしく柔らかかった。
「な、何をするの!?」
「お前は、足が不自由だろう?」
そう言うと、彼女は腕の中でおとなしくなる。だが、不満はあったようだ。
「あんた、顔が怖い。怒っている?」
「いや。私はいつも、この顔だ」
確かに愛想はないかもしれない。しかし、鷹刀の規律のため、あえて風当たりの強い役割を果たすのが、私の務めだから仕方ない。
「……あんた、優しいのに。なんか、もったいない……」
〈猫〉が呟き、ことんと私の胸に頭を預けた。
彼女のぬくもりが伝わってきた。私はそれを、微塵にもこぼさずに得ようと、腕に力を入れる。
「……あたしね、こんなことされたの、初めて」
「私も、初めてだな」
自分から手を伸ばし、誰かに触れるなどということは……。
「あんたの名前は?」
〈猫〉が、私を見上げた。
どこまでも澄んだ、綺麗な猫の目が、私を魅了した。
「エルファン。鷹刀エルファンだ、〈猫〉」
「違うわ。あたしは、キリファ。それが、あたしの名前」
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第二部 第二章 約束の残響音に
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第二部 比翼連理 第三章 綾模様の流れへ https://slib.net/112775
――――に、続きます。


