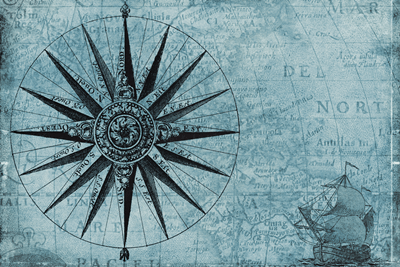
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第一部 第六章 飛翔の羅針図を
こちらは、
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第一部 落花流水 第六章 飛翔の羅針図を
――――です。
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第一部 落花流水 第五章 騒乱の居城から https://slib.net/111097
――――の続きとなっております。
長い作品であるため、分割して投稿しています。
プロフィール内に、作品全体の目次があります。
https://slib.net/a/4695/
こちらから「見開き・縦書き」表示の『えあ草紙』で読むこともできます。
(星空文庫に戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください)
※使わせていただいているサービス『QRouton』の仕様により、クッションページが表示されます。
https://qrtn.jp/yxmg5un
『えあ草紙』の使い方は、ごちらをご参考ください。
https://www.satokazzz.com/doc/%e3%81%88%e3%81%82%e8%8d%89%e7%b4%99%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab
「メニューを表示」→「設定」から、フォント等の変更ができます。PCなら、"UD Digi Kyokasho NP-R"等のフォントが綺麗です。
〈第五章あらすじ&登場人物紹介〉

===第五章 あらすじ===
鷹刀一族の屋敷は、警察隊の家宅捜索を受けていた。総帥イーレオに対し、『貴族の藤咲メイシア嬢を誘拐した』として逮捕状が出たためである。
「私がなんとかします」と言ったメイシアがやっと到着し、スピーカーを使って、屋敷中の人間を桜の大木のある庭に集めた。
メイシアが皆に向かって話を始めようとしたとき、ひとりの警察隊員が「あなたはメイシア嬢の替え玉ですね」と、彼女に向かって発砲する。危ういところで、リュイセンがその警察隊員を倒し、事なきを得た。
改めて、メイシアが話を始めるという段になったとき、彼女はいきなりルイフォンにキスをしてきた。そして、「自分とルイフォンは恋仲であり、反対する父親から逃げ出してきた。だから誘拐されたのではなく、自分の意志でここにいるのだ」と宣言する。
勿論、警察隊を退けるための演技である。「騙されるな」と叫ぶ、警察隊の指揮官。しかし、そこにメイシアの異母弟ハオリュウが現れた。
ハオリュウは、異母姉メイシアに「どうしても鷹刀一族を助けたいのか」と尋ね、異母姉の決意が堅いのを知ると、しぶしぶながら協力してくれる。囚えられた父親が、家を出る前に残していった「当主の指輪」を示し、当主代理として警察隊を黙らせたのだ。
一般の警察隊員はそれで収まったのであるが、執務室でイーレオと対峙していた指揮官は、それで引き下がるわけにはいかなかった。彼は、斑目一族や厳月家と共謀しており、イーレオを必ず逮捕するようにと、警察隊に化けた屈強な男たちを補佐につけてもらっていたのだ。
指揮官は、「イーレオを逮捕できないなら殺せ」と男たちに命じる。しかし男たちの代表の巨漢が、なんと指揮官を刺し、イーレオに対して『指揮官傷害事件』の現行犯で逮捕するといい出したのだ。指揮官が「イーレオがやった」と言い張れば、その通りになると言い張って。
絶体絶命のピンチ。だが、イーレオは平然と、護衛のチャオラウに向かって「巨漢を捕まえろ」と命じ、チャオラウも主人の期待に応え、巨漢を捕縛したのだった。
執務室に、ルイフォン、メイシア、ハオリュウらが到着した。彼らの目的は、ハオリュウの権力で指揮官を従わせることである。
しかし、執務室に入ったハオリュウが見たものは、血溜まりの中に倒れている指揮官と、捕縛された警察隊姿の巨漢だった。
敵対している者たちが倒されているのを見て、ハオリュウはイーレオがやったと思い込み、「やはり凶賊は信用ならない」と落胆する。しかし、メイシアの説得と、鷹刀一族と手を組んだ警察隊員、緋扇シュアンの機転により、誤解は解ける。
これで一件落着と思ったところで、捕まっている巨漢が「自分はどうなってもいいから、邪魔者をすべて殺せ」と部下である屈強な男たちに命じる。そのとき、イーレオが「〈ベロ〉、殺れ!」と叫んだ。
〈ベロ〉とは、屋敷を守るコンピュータの名前である。〈ベロ〉には、イーレオの命令で、執務室にいる「登録されていない人間すべて」を銃殺するよう、ルイフォンの仕掛けが施されていた。
これによって、敵をすべて抹殺。情報を聞き出そうと、チャオラウに命じて捕縛した巨漢までが殺された――と思ったら、〈ベロ〉が『自分の意志で』巨漢への攻撃を手加減していた。〈ベロ〉はただのコンピュータではなく、亡くなったルイフォンの母親が、密かに人工知能を仕込んでいたのだ。
めでたく警察隊を撃退したにも関わらず、得意分野であるコンピュータで、亡き母親に叩きのめされたルイフォンはショックを受け、部屋に引きこもってしまった。
また、生かされた巨漢と、メイシアに発砲してリュイセンに倒された警察隊員は、情報を聞き出すための捕虜となった。
ルイフォンを心配して、メイシアは彼の部屋に行く。だが、自棄になったルイフォンは、メイシアに冷たい言葉を浴びせた。
それでもメイシアは「無事だったことを、『今、あなたと一緒に』喜びたい」と、ルイフォンを包み込む。気休めの慰めを言うわけでなく、もっと大切なことを教えてくれたメイシアに、ルイフォンは心を打たれ、立ち直る。
そして、彼は「ある決意」をしたのだった。
===登場人物===
[鷹刀一族]
鷹刀ルイフォン
凶賊鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオの末子。十六歳。
母から、〈猫〉というクラッカーの通称を継いでいる。
端正な顔立ちであるのだが、表情のせいでそうは見えない。
長髪を後ろで一本に編み、毛先を金の鈴と青い飾り紐で留めている。
※「ハッカー」という用語は、「コンピュータ技術に精通した人」の意味であり、悪い意味を持たない。むしろ、尊称として使われていた。
「クラッカー」には悪意を持って他人のコンピュータを攻撃する者を指す。
よって、本作品では、〈猫〉を「クラッカー」と表記する。
鷹刀イーレオ
凶賊鷹刀一族の総帥。六十五歳。
若作りで洒落者。
鷹刀ミンウェイ
イーレオの孫娘にして、ルイフォンの年上の『姪』。二十代半ばに見える。
鷹刀一族の屋敷を切り盛りしている。
緩やかに波打つ長い髪と、豊満な肉体を持つ絶世の美女。
薬草と毒草のエキスパート。
かつて〈ベラドンナ〉という名の毒使いの暗殺者として暗躍していた。
鷹刀エルファン
イーレオの長子。次期総帥。ルイフォンとは親子ほど歳の離れた異母兄弟。
感情を表に出すことが少ない。冷静、冷酷。
倭国に出掛けていた。
鷹刀リュイセン
エルファンの次男。イーレオの孫。ルイフォンの年上の『甥』。十九歳。
文句も多いが、やるときはやる男。
『神速の双刀使い』と呼ばれている。
父、エルファンと共に倭国に出掛けていた。
長男の兄が一族を抜けたため、エルファンの次の総帥になる予定である。
草薙チャオラウ
イーレオの護衛にして、ルイフォンの武術師範。
無精髭を弄ぶ癖がある。
料理長
鷹刀一族の屋敷の料理長。
恰幅の良い初老の男。人柄が体格に出ている。
キリファ
ルイフォンの母。四年前に謎の集団に首を落とされて死亡。
天才クラッカー〈猫〉。
右足首から下を失っており、歩行は困難だった。
かつて〈七つの大罪〉に属していたらしい。
鷹刀一族の屋敷に謎の人工知能〈ベロ〉を遺していた。
もとエルファンの愛人。エルファンとの間に一女あり。
〈ケル〉〈ベロ〉〈スー〉
ルイフォンの母が作った三台の兄弟コンピュータ。
ただし、〈スー〉は、まだできていないらしい。
〈ベロ〉は、独自の判断で、「敵を全滅する」というルイフォンの指示を無視した。
[藤咲家]
藤咲メイシア
貴族の娘。十八歳。
箱入り娘らしい無知さと明晰な頭脳を持つ。
すなわち、育ちの良さから人を疑うことはできないが、状況の矛盾から嘘を見抜く。
白磁の肌、黒絹の髪の美少女。
藤咲ハオリュウ
メイシアの異母弟。十二歳。
十人並みの容姿に、子供とは思えない言動。いずれは一角の人物になると目される。
斑目一族に誘拐されていたが、解放された。
藤咲家当主
メイシア・ハオリュウの父。
斑目一族の別荘に囚われている。
[繁華街]
シャオリエ
高級娼館の女主人。年齢不詳。
外見は嫋やかな美女だが、中身は『姐さん』。
元鷹刀一族であったが、イーレオの負担にならないように一族を離れた。
スーリン
シャオリエの店の娼婦。
くるくる巻き毛のポニーテールが似合う、小柄で可愛らしい少女。
本人曰く、もと女優の卵。
トンツァイ
繁華街の情報屋。
痩せぎすの男。
キンタン
トンツァイの息子。ルイフォンと同い年。
カードゲームが好き。
[斑目一族]
斑目タオロン
よく陽に焼けた浅黒い肌に、意思の強そうな目をした斑目一族の若い衆。
堂々たる体躯に猪突猛進の性格。二十歳過ぎに見える。
斑目一族の非道に反感を抱いているらしいが、逆らうことはできないらしい。
[〈七つの大罪〉]
〈七つの大罪〉
現代の『七つの大罪』《『新・七つの大罪』》を犯す『闇の研究組織』。
知的好奇心に魂を売り渡した研究者を〈悪魔〉と呼ぶ。
〈悪魔〉は〈神〉から名前を貰い、潤沢な資金と絶対の加護、蓄積された門外不出の技術を元に、更なる高みを目指す。代償は体に刻み込まれた『契約』。
〈蝿〉
〈七つの大罪〉の〈悪魔〉。
ルイフォンの母のことを知っているらしい。
鷹刀一族、特にイーレオに恨みがある。
ミンウェイが、かつて〈ベラドンナ〉と呼ばれていたことを知っていた。
医者で暗殺者。
ホンシュア = 〈蛇〉?
鷹刀一族に助けを求めるよう、メイシアを唆した女。
仕立て屋と名乗っていた。
[警察隊]
緋扇シュアン
『狂犬』と呼ばれるイカレ警察隊員。三十路手前程度。
ぼさぼさに乱れまくった頭髪、隈のできた血走った目、不健康そうな青白い肌をしている。
凶賊の抗争に巻き込まれて家族を失っており、凶賊を恨んでいる。
凶賊を殲滅すべく、情報を求めて鷹刀一族と手を結んだ。
シュアンの『先輩』
警察隊が鷹刀一族の屋敷に来たとき、メイシアに銃を向けた男。
何かを知っているのではないかとのことで、ハオリュウの権力で身柄を預かった。
斑目一族の?『巨漢』
警察隊に紛れてイーレオの執務室にまで乗り込んできた巨漢。
斑目一族の者?
何かを知っているらしいので拘束した。
===大華王国について===
黒髪黒目の国民の中で、白金の髪、青灰色の瞳を持つ王が治める王国である。
身分制度は、王族、貴族、平民、自由民に分かれている。
また、暴力的な手段によって団結している集団のことを凶賊と呼ぶ。彼らは平民や自由民であるが、貴族並みの勢力を誇っている。
1.花咲く藤の昼下がり-1

明るく柔らかな陽の光が、午後の食堂へと注ぎ込む。
一面の硝子張りの向こう側は、目に鮮やかな萌える緑で溢れていた。
祝福の桜は広い庭の奥にあり、残念ながらここからは愛でることはできない。だが、その花びらが、時折こちらの庭まで遊びにやってきていた。
一同を待ちかねていた料理長の指示のもと、次々と料理が運ばれてくる。
この一週間ほどは、次期総帥エルファンと、その次男リュイセン父子が倭国に行っており、料理長としては今ひとつ、腕の振るい甲斐がなかった。
そこへ、そのふたりが帰国した上に、メイシアとハオリュウという貴族姉弟が加わったのだ。倭国は料理が美味しいと評判であるし、貴族たちはさぞ舌が肥えているであろう。料理長は否が応でも張り切りざるを得ない。
時期よりやや早い藤が、瑞々しい房を優美に垂らし、テーブルに華やぎを添えていた。ミンウェイによって活けられたその花には、『藤咲』という貴族姉弟の家名に、花言葉の『歓迎』の思いが込められていた。
時刻は少し遡る。
「祖父上! 藤咲ハオリュウに『協力する』とは、どういうことですか!」
リュイセンの食って掛かる声が、執務室に響き渡った。本当は、祖父がそう言ったその場で割って入りたかったところなのだが、さすがに分をわきまえ今まで我慢していたのだ。
負傷しているルイフォンは医務室に、メイシアもそれを追うように付き添った。
緋扇シュアンは後処理のため、既に警察隊に戻っている。
ハオリュウを客間に案内するよう命じられたミンウェイは、ひと足先にハオリュウと共に執務室を辞した。
そして、屍と捕らえた巨漢は運び出された。
――だから今は、イーレオ、エルファン、リュイセンの父子三代に、護衛のチャオラウだけしか、執務室にはいなかった。
「ふむ? リュイセンには情報が行ってなかったのか? メイシアとハオリュウの父親が斑目に……」
イーレオが、執務机の定位置にて椅子を揺らす。
「ああ、聞いていますよ! つまり! 『協力する』ってのは、囚えられている、あいつらの父親を救出するということですよね! 我々、鷹刀が! 危険を承知で!」
リュイセンは、こめかみに青筋を立てた。
帰国してからずっと、怒鳴り続けている気がする、と彼は思った。
いい加減、疲れが溜まっているので風呂でのんびりしたい。だが、ここで放置すれば、この祖父はまた喜んで厄介ごとを背負い込むのだ。
「俺が言いたいのは! なんで我々が、貴族を助けるような真似をしなければならないのか、という点です! 確かに我々は斑目と敵対しています。今回、屋敷にまで乗り込んできたことに対する報復は必要でしょう」
リュイセンは唾を飛ばし、熱弁を振るう。
「けれど! 斑目からあいつらの父親を助け出すのは、全然、別の問題です! なんのメリットもない! 『救出』は『攻撃』よりも、ずっと大変です。それは、祖父上もご存知でしょう!」
「落ち着け、リュイセン」
低い声でそう制したのは、彼の父エルファンである。
エルファンは息子に下がるようにと目で命じ、執務机の前に立った。座っているイーレオの顔に、怜悧な眼差しを落とす。
「私も、今回のことは随分と軽率なことをなさったと思っています。――我々が手を貸してやるだけの価値が、あの姉弟にはあるのですか?」
「ある」
イーレオは即答し、にやりと口の端を上げた。椅子に背を預け、両腕を組みながら鷹揚にエルファンを見上げる。その過剰なまでに好戦的な楽天ぶりに、エルファンは氷の微笑を溶かした。
「そうですか。なら、従いましょう」
「父上! なんでそれで納得するんですか!?」
孤立無援となったリュイセンが、不満を全面に出して抗議する。
イーレオ、エルファン、リュイセンの三世代の血族は、年齢だけが違う、同じ人物を見ているかのようにそっくりだった。特に、声だけを聞いたなら、三人のうちの誰が喋っているのか、判別は難しい。しかし、声色と発言内容から意外に聞き分けられるものだと、一歩下がった位置で控えていたチャオラウは苦笑した。
彼がわずかに無精髭を揺らしたとき、廊下に気配を感じた。
彫刻の鷹――〈ベロ〉という名の守護者との問答がかすかに聞こえるが、聞き耳をたてなくても外にいる者が誰だか、チャオラウには分かった。
「俺だって、あの姉弟が可哀想だとは思っていますよ!? 運悪く利用されただけ、とね。しかし、世の中に不幸な奴はごまんといます。いちいち付き合っていたらたまりません。別に危害を加えようと言っているわけじゃない。ただ追い出せばいいだけです!」
リュイセンが、そう吠えたとき、執務室の扉が開いた。
「お昼食についてお伺いを立てに来たところだったのですが、お取り込み中でしたか」
白い調理服に身を包んだ、恰幅の良い初老の男。一族の胃袋を預かる厨房の主、料理長である。
彼は腹を揺らしながら歩み出て、室内の面々を順に見やった。ぐるりと一巡したあと、拳を握りしめたリュイセンに目を留める。声にこそ出さないものの、明らかに「ははぁ」と得心のいった顔になった。
「いや、この話はこれで終わりだ」
冷たく言い放ったイーレオの言葉に、リュイセンは唇を噛んだ。
「失礼します!」
「待て、リュイセン」
「何か?」
怒りを、申し訳程度に押さえ込んだだけの声は、総帥であり祖父である男に対して、限りなく刺々しいものであった。
「お前、貧民街で〈蝿〉と名乗る男に会ったか?」
「は……?」
能天気な祖父のこと。てっきりふざけた言葉のひとつでも出して、この場を茶化して終わらせるつもりなのだろうと、リュイセンは思っていた。だから、その問いかけは、まったく予期せぬものであった。
彼は、はて、なんのことかと一瞬、悩んだ。
貧民街での記憶を手繰り寄せ、やたらと尊大な、不愉快な男のことを思い出す。父のエルファンと比べられ、散々、馬鹿にされた不快感までもが蘇り、リュイセンは鼻に皺を寄せた。
彼にとって、〈蝿〉とは、そんな人物であった。
だが、扉に向かっていたリュイセンには見えない位置で、エルファンの頬に緊張が走った。
「ええ、会いましたよ。父上のことをよく知っているようでした」
「どんな男だった?」
畳み掛けるように、イーレオが問う。
「サングラスで顔を隠していましたが、歳は……そうですね、体つきからして父上と同じか、少し上くらいでしょうか。細身の刀を使い、動きが素早い。決して『強い』とは言い切れないのですが、奴は『負けない』。ああ、本業は医者だと言っていました」
「分かった。――行っていいぞ」
こんなふうに聞かれれば、気に掛かるものである。
しかし、イーレオの言葉は、退室の『許可』ではなく『命令』だった。そして、リュイセンは気が立っており、自分から尋ねる気になれなかった。
彼は「失礼します」と低く言うと、振り返ることなく執務室を出ていった。
ともかく、風呂と飯。そして寝るに限る――。
リュイセンは肩を怒らせながら、自室に向かっていた。
執務室に来た料理長の口ぶりから、飯はじきに用意されるはずだ。だから、まずは熱い湯に浸かりたい。そして、すべてを流すのだ。
彼とて、総帥が決定したことに逆らうつもりはない。一度は異議を申し立てるが、聞き入れられなければ、すっぱりと諦める。――とはいえ、現在において、苛立ちが胸の中を吹き荒れているのはどうしようもなかった。
「リュイセン様!」
背後から、重量感ある足音が聞こえてきた。本人は小走りのつもりなのだろうが、地響きのせいで、そうは感じられない。
「料理長?」
「お呼び止めいたしまして申し訳ございません」
料理長はリュイセンのそばまで来て姿勢を正すと、足を揃えて優雅に一礼した。
「大変、ご立腹なご様子でしたので、僭越ながらひとこと申し上げようと参りました」
「いや、いい。済んだことだ」
リュイセンは首を振る。肩までの艶やかな黒髪がさらさらと流れた。諦観とも自棄とも取れる彼の仕草に、料理長は微苦笑する。
「あの姉弟を、『貴族』という一括りの中に閉じ込めてしまうのは、早計かと思いますよ?」
「何を言いたい?」
「そうですねぇ。例えば、気位の高い貴族の当主代理殿が、リュイセン様に頭を下げて、『凶賊でなければ、雇いたい』と言ったこととか」
「なんで、そのことを……?」
遠巻きに見ていたであろう料理長には、声は聞こえていないはずだ。
「私は料理人です。食べ物を味わう口元の動きには敏感です」
肉付きのよい顔に満面の笑顔をたたえて、料理長はリュイセンのささやかな疑問を煙に巻く。
「まぁ、それよりも、気になるのはお嬢さんのほうですけどね」
料理長の言葉に、リュイセンは儚げな容貌の貴族の少女を思い浮かべ……そこに年下の叔父の姿を重ねる。
「……いったいルイフォンは、どうなっちまったんだ?」
リュイセンは吐き出すように、ぼやく。
帰国してからずっと、彼は、弟分のらしくない言動に驚かされ続けていた。彼の知るルイフォンは、もっと飄々としていて掴みどころがなく、損得勘定が上手で要領が良い。そして、誰かに固執することはない人間だったはずだ。
「さて? ……私は昨日の晩、彼女がルイフォン様と食堂で話しているのを、聞くともなしに聞いてしまったのですが――そのときの彼女は、繊細で綺麗すぎて、いざとなれば舌でも噛み切りかねないような危うさがありました」
「あの女、そんな玉じゃねぇよ。見た目こそ大人しいが、無計画で、無鉄砲だ」
メイシアを買いかぶる料理長に、リュイセンは反感を抱く。
「ええ。今の彼女は違いますね。出かけている間に何があったのやら……?」
「知るかよ」
投げやりに言い放ったリュイセンに、料理長は目を細めた。ふっくらとした顔の中に目が埋もれ、それがまた、実に穏やかな福相を作る。
「あの子は、世間ずれしていない貴族の箱入り娘です。……だからこそ、何もできないくせに、なんでもできるでしょう――ルイフォン様のためになら」
「え……?」
リュイセンは、一瞬だけ料理長から不穏な空気を感じ取り、ひやりとした。だが、どう見ても人の好さそうな料理長の丸顔に、気のせいだと思い直す。
「リュイセン様、気になるのなら、ご自分の目でお確かめになられたらよいかと思いますよ」
厨房へと戻る料理長と途中で別れ、リュイセンは医務室に向かった。ルイフォンが怪我の手当てを受けに行ったはずだからである。
しかし、医務室に行ってみると、ルイフォンは来ていないと言われた。
では、ルイフォンはどこに行ったのか――リュイセンはすぐに思い当たった。
ルイフォンの自室、『仕事部屋』だろう。
執務室に突如現れた〈ベロ〉――ルイフォンの母親が遺した、人工知能らしきもの。ルイフォンは、あれについて調べているに違いない。
〈ベロ〉は、ルイフォンご自慢の虹彩認証システムを鼻で笑っていた。リュイセンとしても、正直なところ、執務室に入るたびに認証処理をするのは面倒だったので、〈ベロ〉というのが勝手に敵を判別してくれるなら楽でよいと思う。――つまり、ルイフォンと、その母親との技倆の差は歴然、というわけだ。
「――相当、荒れているだろうな……」
執務室を出ていったときのルイフォンの後ろ姿は、憐れなものだった。
リュイセンは弟分の心情を思い、溜め息をつく。自信家だけに、プライドはズタズタだろう。
貴族の娘は、あの状態のルイフォンに付き添うと言って出ていった。おそらくは邪魔だと追い返されたか、よくて完全無視――。
彼がそう思ったとき、少し先の扉が急に開いた。
「す、すすすみません! 失礼します!」
鈴を振るような、可愛らしい声――ただし、悲鳴に聞こえなくもない――が響いた。
リュイセンは、はっと身構える。ルイフォンの部屋から飛び出してきたのは、リュイセンの頭を悩ませている諸悪の根源、あの貴族の娘だったのだ。
彼が咄嗟に思ったことは、何やら面倒臭そうだ、であった。
すっと端に寄り、気配を殺して壁と同化する。
顔を真っ赤にして、必死に廊下を駆け抜ける少女には、それで充分だった。リュイセンに気づかずに走り去っていった。
「なんだったんだ?」
階段へと消えていく彼女の背中を唖然として見送ったあと、リュイセンはルイフォンの部屋の扉を開ける。
その瞬間、冷気が彼を迎え入れ、思わずくしゃみが出た。
相変わらず、寒い部屋だった。機械に合わせて空調を設定しているとかで、通年この温度だ。だからその点については驚かない。
「お前…………」
リュイセンはルイフォンの姿を認めて、絶句した。
それまでの経緯から、彼の弟分は荒れているか、落ち込んでいるか。そのどちらかの状態だと想定していた。
しかしルイフォンは、半裸の肉体を冷風に晒しながら――。
――――。
「お、リュイセン、どうした?」
ルイフォンの表情に呑まれていたリュイセンは、はっとした。気づいたときには、彼の弟分は、いつものひと癖ありそうな猫の顔で笑っていた。
そのあまりにもあっけらかんとした様子に毒気を抜かれながら、リュイセンは、かろうじて可能性のありそうな解の正否について尋ねる。
「……襲ったのか?」
「喜びを分かち合っていたんだよ」
からかうように、ルイフォンは目を細めた。……どう受け止めればいいのか、よく分からない。
けれど、リュイセンは確かに見たのだ――扉を開けた瞬間の、ルイフォンの表情を。
鋭くも柔らかく、遠ざかるものを名残惜しげに慈しむ、愛しさにあふれた男の顔を――。
「……落ち込んでいると思っていたぞ」
まるで、ふてくされた子供のようにリュイセンは言った。
結構、心配していたのだ。頭が異次元に行ったまま、数日は帰ってこないだろうと思っていた。
「ああ。落ち込んでいるさ。たぶん、かつてないほどにな」
「そうは見えないぞ」
「今やるべきことを、あいつが教えてくれたからな」
ルイフォンはそこで言葉を切り、猫背を伸ばして佇まいを正した。長身のリュイセンと比べれば小柄と言わざるを得ないルイフォンは、やや顔を上げた姿勢で、強い視線をまっすぐに送ってくる。
「リュイセン、礼を言う――ありがとな」
リュイセンの眼下に癖の強い黒髪が広がった。唯我独尊のルイフォンが、きっちりと頭を下げていた。
「ルイフォン……?」
自分の目が信じられず、リュイセンは瞬きを繰り返す。
「お前のお陰で、俺もメイシアも無事だった。感謝している」
リュイセンは、あんぐりと口を開けたまま、穴が開きそうなほどルイフォンの後頭部を見つめる。
やがて顔を上げたルイフォンが、そんな彼を見て苦笑した。
「何、驚いているんだよ?」
「ああ、いや……。らしくないな、と……」
「そうだな。――俺もそう思う」
澄んだテノールだった。ルイフォンが、明るい青空の顔で爽やかに笑う。
貴族の娘は、ルイフォンに、いったいどんな魔法をかけたのだろう。――この部屋に戻ってきたときのルイフォンは、プライドを粉々にされ、手のつけられない状態だったはずなのに……。
ルイフォンに聞けば、素直に答えてくれるだろう。弟分は、そういう奴だ。
だが、きっとこれは、自分の目で確かめなければ意味がない。
「……仕方ねぇな。関わっちまった以上、最後まできっちり面倒を見てやるべきだな」
リュイセンは口の中で、小さく呟いた……。
料理長がリュイセンを追うように執務室を出ていき、扉が閉まる音を確認してから、エルファンは口を開いた。
「――父上。〈蝿〉とは、どういうことでしょうか?」
からんと、グラスの中で氷が響くような涼やかな声色で、彼は尋ねる。
エルファンは感情をあまり表に出さない。特に、焦りを見せることは敗北を招くと考える。だから事態が深刻さを増すほどに、彼の言葉は穏やかに、纏う気配は冷気を帯びる。
「分からん。ただ、貧民街でルイフォンたちを襲った者の中に〈蝿〉を名乗る者がいた、との報告を受けていただけだ。〈蝿〉を名乗る別人だと思っていたが……」
「ヘイシャオ……」
エルファンが口に出した名前に、イーレオが黙って頷く。長い黒髪がさらさらと流れ、秀でた額を覆った。
「……奴は死んだはずです。私がこの手で殺しました」
エルファンの声が、乾いた音を立てながら凍りついた空気を裂いた。
1.花咲く藤の昼下がり-2

料理長の心づくしに舌鼓を打ったあと、食堂はそのまま会議場となった。給仕の者たちが手際よくテーブルを片付けていき、メイドが茶を振る舞う。
香り立つ茶器を差し出してきた相手が、自分とたいして歳の変わらぬ少女であることに気づいて、ハオリュウは目を丸くした。貴族の世界ではあり得ぬことだからだ。
彼女が一礼をして、ふわりとしたスカートをなびかせながら下がっていく。なんとなく、その後ろ姿を見送ってしまったハオリュウだったが、彼女が厨房へ消えていくと同時に、気持ちを入れ替えた。握りしめた拳に、当主の指輪が食い込んだ。
隣に座っていたイーレオが目配せをしてきた。ハオリュウは、それに頷きで返した。
「鷹刀一族の方々、藤咲の無理なお願いを快諾いただき、ありがとうございます」
ハオリュウは立ち上がり、頭を下げた。堂々たる様子に、誰もが彼を藤咲家の名代と認める。イーレオが第一声をハオリュウに譲ったことも、彼の立場を後押ししていた。
「改めて、僕……私からのお願いを申し上げます。父の身柄を斑目一族から取り戻していただきたい。――まずは、これまでの経緯をご説明いたします」
そう言って、ハオリュウは一同を見渡した。
彼から左回りに、鷹刀一族総帥イーレオ、無表情で底の読めない次期総帥エルファン。何かと世話になっているミンウェイに、妙技で危機を救ってくれたリュイセン、むかつくばかりのルイフォンと続く。
そして、ぐるりと回って戻ってきた左隣には、最愛の異母姉メイシアがいて、テーブルから少し離れたところに護衛のチャオラウが控えていた。
「ことの始まりは、私が斑目一族に誘拐されたことですが……そもそも根底に、我が藤咲家と同じく貴族である厳月家との不仲があり、そちらの鷹刀一族と斑目一族の敵対があります。今回のことは厳月・斑目が手を組んで、藤咲・鷹刀を陥れようとした、とも言えます」
少年のハスキーボイスに似合わぬ、冷静な物言い。母親が平民出身という理由だけでハオリュウを蔑む親族は、愚かとしか言いようがない。あるいは有能であるが故に彼が疎ましいのか――。
「きっかけとなったのは、我が藤咲家と厳月家が、とある案件についての役職を争い……」
「ハオリュウ」
――と、ルイフォンが言葉を遮った。ハオリュウが、むっと眉を寄せる。
「回りくどい言い方をしなくても、その件は知っている。女王の婚礼衣装担当家の話だろ?」
「何故、それを! 箝口令だぞ! 僕だって、問い詰めるまで知らなかったのに!」
「情報網の差だ」
目を細め、ルイフォンがにやり、と笑う。
風呂でさっぱりとしてきた体に、いつも通りの一本に編んだ髪。その先は真新しい青い飾り紐で留められており、中央を金の鈴が飾っていた。
「俺たちは手を組んだんだ。一方的な話じゃなくて、情報のすり合わせで行こうぜ。その鬱陶しい喋り方もやめろよな」
「貴様……!」
ルイフォンの横柄な態度に、ハオリュウが歯噛みする。それを見て、リュイセンが呆れたようにルイフォンを肘でつついた。
「喧嘩売るなよ」
「別に、売ってねぇよ」
「ええ、私も気にしていませんよ」
ルイフォンの反論に、ハオリュウも感情を押し殺した声で続ける。
彼は、ルイフォンに冷ややかな視線を送った。
「そうですね。私はずっと囚えられていましたから、知らないことも多いでしょう。――ではルイフォン、あなたに話を進めてもらいます」
ルイフォンが「了解」と軽く手を上げて応えると、ハオリュウは会釈して席についた。
歳は下でも立場は上なのだ、との意味合いをこめて、『ルイフォン』と呼び捨てにしたのだが、気づいていないどころか友好の証と捉えられたような気がする――ハオリュウは不快げに顔をしかめた。
ルイフォンは着席のまま、とん、と人差し指の先でテーブルを叩いた。皆の注目が集まり、ルイフォンがテノールを響かせた。
「発端は、女王の結婚話。そして、婚礼衣装担当家が藤咲家に決まったこと。それが面白くないライバルの厳月家が、斑目を雇って藤咲家の息子――つまり、ハオリュウを誘拐して、担当家を辞退するよう脅迫した。ここまでは、よくある話だ」
「よくある話じゃないぞ!」
ルイフォンの口ぶりに、声を震わせてハオリュウが激昂する。進行役を譲った途端だが、聞き流すことなどできなかった。
「この脅迫は『究極の二択』なんだ! 跡継ぎの僕の死か、家の没落か、だ」
「おい、待ってくれ」とリュイセンが手を上げた。
「なんで、『家の没落』?」
純粋な疑問として首をかしげるリュイセンに、ハオリュウは、はっとした。
彼らは凶賊なのだ。貴族の感覚なら当たり前であることも、彼らにとっては違う。
協力を願うのなら狭い視野ではいけないのだ。――同じ台詞を言ったのがルイフォンだったなら反発したであろう彼も、異母姉を助けてくれたとの思いが強いリュイセンには素直だった。
「凶賊の皆様には、ご理解いただけないかもしれませんが、名誉ある役を辞退するということは、王族を侮辱したにも等しいんです。貴族の地位の剥奪は必須でしょう」
言いながら、ハオリュウはその事実を知ったときのことを思い出し、身を震わせた。
囚えられていたときは、ただの身代金目的の誘拐だと思っていた。貴族の子女なら、よくある、とまでは言わないものの、あり得ることだ。不安ではあったが待遇が悪いということはなかったから、いずれ解放されると高をくくってもいた。
それが、解放されて家に戻ったときには、父も異母姉もいなかった。まさか、家名を賭けた壮大な陰謀だったなんて、想像だにしなかった。
事実を知ったときの、あの、臓腑が煮えくり返るような思い――。
「けれど、どっちも選択できなかった父は、多額の身代金を持って斑目一族を訪れた。厳月よりも高い値をつけて、斑目一族を買収しようとした。しかし交渉決裂して、父もまた囚えられた……」
「ちょっと待て、ハオリュウ。もう一段階、話は複雑だ」
ルイフォンの鋭い声に、ハオリュウは「え?」と目を見開く。
「お前の父が斑目に行く前に、厳月家が動いている。それと、お前の父は呼び出された可能性が高い」
「なんだって!?」
ルイフォンが考え込むように眉間にしわを寄せ、癖のある前髪をくしゃりと掻き上げた。
「お前が解放されたのって、今日の午前中だっけ?」
「そうだ。それより厳月が動いたとか、父が呼び出されたとか、僕は知らないぞ! 説明しろよ!」
悔しいが、情報網の差というのは確かなようだった。
ハオリュウは、ルイフォンのひと癖ありそうな顔立ちを、苛立たしげに睨みつける。端正と言えなくもないが、ひと目で直系と分かるリュイセンなどとは比べるべくもない。
裏を返せば、直系ではないのにルイフォンは一族の中心にいるということで――ハオリュウは実家での自分との違いに、奥歯を噛みしめた。
「あとでちゃんと順を追って説明する。――で、お前は、メイシアが鷹刀にいる、って聞いて、すぐに家を出たんだな?」
「当たり前だろ! 姉様が凶賊のところにいるんだ! しかも、警察隊が救出に向かっているけど、その警察隊内部に別の凶賊と通じている者がいるんだぞ! そんな危険な状況で、異母弟の僕が現場に駆けつけなくてどうする!?」
ルイフォンは半ば呆れ顔で溜め息をついた。
「あぁあ……了解。お前が母親から聞いた話は、だいぶ端折られている。というか、詳しく聞く前に、お前が飛び出していったんじゃないか……?」
「……母は…………」
ハオリュウは言いかけて、隣に座るメイシアを見た。綺麗で優しくて、儚げな異母姉――。
母が正気を失ってしまったなどということは、彼女の耳には入れたくなかった。いずれ知られてしまうとしても、今は、まだ。だから、話は伯父から聞いたのだということを、あえて言う必要もない。
「……そうかもしれない。だから、詳しい情報を頼む」
急におとなしくなったハオリュウに、ルイフォンは不審な目を向けたが、倭国に行っていたエルファンやリュイセンにも説明しておく必要があったので、話を戻すことにした。
1.花咲く藤の昼下がり-3

「それじゃあ、厳月家の動きから説明する――」
茶で喉を湿らせたルイフォンは、再び話を始めた。
「厳月家は、藤咲家に対し『娘を厳月家の嫁にくれるなら、姻戚のよしみで息子を誘拐犯から助けるための私兵を貸す』と言ってきたんだ」
「は……? 『私兵を貸す』だって? 誘拐犯は斑目で、斑目は厳月家が雇っているんだから、私兵なんか使わなくても、厳月家ならハオリュウを解放できるだろ?」
直接的に受け止めたリュイセンが、率直な疑問を投げ返す。いかにも彼らしい反応だと、ルイフォンは軽く笑んだ。
「私兵は口実だよ。厳月家の申し入れは、ずばり『娘をくれれば、息子を返す』だ。――厳月家は貴族だ。誘拐とは無関係、という態度をとりたいわけだよ。だから、面倒くさい言い方をするんだ」
「姉様を嫁に? そんな馬鹿な……?」
ハオリュウが呟いた。
厳月家は藤咲家とは不仲である。それは互いに絹織物の産地を領土に持つ以上、仕方のないことのはず。なのに、婚姻を結びたいとは……?
「初めから、それが厳月家の狙いだったのだろう」
権謀術数に長けたエルファンが、低く声を漏らした。相手の腹を読み解いた充足感よりも、その策の低俗さに呆れた彼は、氷の嘲笑を浮かべる。
「どういうことですか!?」
食らいつくように、ハオリュウが叫んだ。
「厳月家にとって一番旨味があるのは、藤咲家が役職を辞退して没落した上に、宙に浮いたその役職の座が転がり込むことだ。一方、そのとき藤咲家は、誘拐されたお前が助かっても、その後は衰退の一途をたどるだけだ。つまりはお前ともども、一族の婉曲なる死にしかならない――」
たった十二歳の子供に語るにしては、エルファンの言葉は厳しく、声色に体温を欠いていた。だが、諭すような眼差しは、決して凍りついたものではない。
「――ならば藤咲家が採るべき選択肢は明らかだ」
「僕を見捨てること、ですか……」
「そうだ。だが、厳月家としても、お前の首を取ったところで得るものなど何もない。だから自家の利益になる第三の選択肢を用意した。――婚姻は一見、平和的だ。平時ならともかく、お前の言う『究極の二択』のあとに出されたら、藤咲家は飛びつくだろう」
「でも、姉様を迎えても……?」
「嫁に出された娘は人質になりうるだろう? いずれ、外から藤咲家を操るつもりか、ほとぼりが冷めたころにお前を暗殺して、厳月家の血を引く異母姉の子を当主に据えるか。ともかく藤咲家は乗っ取られるだろう」
エルファンの言葉にハオリュウは顔色を変えた。
「厳月め……!」
卑劣な手口に毒づく。
進行を務めていたはずのルイフォンは途中から口を閉ざし、エルファンの解説に聞き入っていた。昨日、ルイフォンがメイシアに言った解釈とほぼ同じであるが、海千山千の異母兄のほうが、より悪意に満ちていた。
「……すまんが、いいか?」
話の区切りを待っていたリュイセンが、肩までの髪をさらりと揺らし、やや遠慮がちに切り出す。
「厳月家の目論見って、とっくに失敗してないか? 藤咲家の当主が斑目に囚えられたら、結婚話なんて進められないぞ。厳月家って、もう関係ないんじゃねぇか?」
父親のエルファンとは違い、リュイセンは、あまり腹の探り合いは得意でない。だが、一足飛びに本質を見抜く能力があった。
「ああ、その通りだ。つまり、どういうことだと思う――?」
ルイフォンが猫のような目をすっと細め、問いかける。
「斑目が厳月家の意向に逆らった。――裏切りだろ」
ほぼ即答で、リュイセンが応じる。
「厳月の高慢さは有名だ。雇っている者が勝手な行動をして許すわけがない。仲は決裂したはずだ」
遅れてハオリュウが続いた。そんなふたりに、ルイフォンは頷く。
「さすがに俺の情報網でも、斑目の裏切りの事情までは掴めてない。だから憶測しかできないんだが――斑目は、貴族の厳月家の言いなりになることよりも、凶賊として、敵対している俺たち鷹刀を陥れることを選んだんじゃないか?」
リュイセンとハオリュウの目が、ルイフォンを捕らえた。どういう意味だ、と問うている。
ルイフォンは目線を返し、言葉を続けた。
「おそらく斑目は、厳月家を通して警察隊の指揮官と知り合ったんだろう。そして、そのパイプを利用して、親父を――鷹刀イーレオを罠にはめる策を思いついた。――それが雇い主の厳月家に逆らう行為だとしても、奴らは構わず実行に移した……。そんなところじゃないだろうか? 他の皆はどう思う?」
ルイフォンは視線でテーブルの円周をなぞる。
「同意するわ」
綺麗に紅の引かれた唇をきゅっと引き上げ、ミンウェイが短く答えた。
彼女は、この場は帰国したばかりのエルファンとリュイセン、そして渦中にありながら囚われていて情報不足のハオリュウのためのもの、と思っていたので今まで発言を控えていたのだ。
「待ってください。……父を囚えることが、裏切り行為になるのは分かります。けど、斑目は、なんのために父を囚えたのですか? 父を手に入れることに意味などあるのでしょうか?」
うつむいて考え込んでいたメイシアが、顔を上げた。
そのとき――。
「あるだろう」
魅惑の低音が響いた。
決して大きな声ではないのに、そのひとことで、すべての視線を一身に集める。
テーブルに肘をつき、掌で顎を支えていた男。分厚い報告書をなぞる会議など眠たくてたまらぬと、半ば瞼を閉じて、うつらうつらとしていた人物。
総帥、鷹刀イーレオ。
皆が固唾を呑んで、彼の次のひとことを待つ――。
「『お前』だ。メイシア」
イーレオが、にやりと笑った。
眼鏡の奥の眼光は鋭く、先ほどまで欠伸を噛み殺していた人間とは思えない。
「奴らが何をしたか。それを考えれば、簡単なことだ」
「え?」と、疑問形の口のまま、メイシアの聡明な頭脳は混乱に陥った。
「奴らの目的がなんだったか――。チャオラウ」
イーレオが背後を振り返った。そこには、護衛の大男チャオラウが控えている。彼は主人の意図を汲んで「僭越ながら」と無精髭を揺らした。
「斑目の狙いは、イーレオ様に罪を着せ、身柄を確保することです。執務室に押しかけてきた連中が、そう言っていたのを、私はこの耳で聞いております」
エルファンが、「なるほど」ゆっくりと腕を組んだ。
「斑目は、警察隊にパイプができている。だから、父上に適当な罪を被せて逮捕させ、あとで密かに身柄を引き渡させよう、という腹か。厳月家はいい面の皮だ」
「その『罪』が、私の『誘拐』……」
メイシアが呟き、イーレオが頷く。
「そうだ。斑目は、俺の『罪』を作るために、お前がこの屋敷に行かざるを得ない状況を作り出した。――お前の父を囚えて、お前を追い詰めたんだ」
「……そんな……」
メイシアが、胸元でぎゅっと手を握りしめた。自分のせいで父が囚えられたのだと思うと、心が苦しくてたまらない。
エルファンが眉を寄せ、不快げに鼻を鳴らした。
「『貴族令嬢の誘拐』なら大々的に警察隊を動かすのにうってつけだ。しかも、彼女が屋敷にいるという事実だけで『誘拐犯』に仕立てられる。――生死は別にしてな」
そのとき、ルイフォンは、はっと思い出した。
貧民街で〈蝿〉と対峙したとき、奴は、はっきりと言っていた。
『あの駒は、鷹刀の屋敷に置いておく必要がありました。けれど、そこから動かされてしまったのなら、無理にでも運ぶしかないでしょう?』
『他ならぬ、あなたが計画を崩してくれたんですよ』
「……だから、メイシアを屋敷の外に連れ出したら、斑目の野郎が襲ってきたのか……」
癖のある前髪を掻きむしるようにして、ルイフォンが頭を抱えた。彼の安易な行動が、メイシアを危険に晒してしまったというわけだ。
ルイフォンが呻き声を上げる中、ハオリュウがためらいがちに手を上げた。
「……すみませんが、やはり僕には分かりません。イーレオさんを誘拐犯に仕立て上げたいのなら、異母姉を言葉巧みに操るよりも、芝居のできる人間を雇って、この屋敷に押しかけさせるほうが、確実ではないですか?」
「馬鹿だな、ハオリュウ」
イーレオが鼻で笑った。そして、顎をぐっと上げて、尊大に胸を張る。
「この俺が、そのへんの女に引っ掛かるわけないだろう?」
「……は?」
「どう見ても騙されている薄幸の美少女。か弱いくせに、やたら根性があって引き下がらない芯の強さ――メイシアでなければ、俺は屋敷に入れようとは思わなかった」
流し目を送られたメイシアが、顔を真っ赤にしてうつむいた。
「俺を罠に掛けるためにメイシアを見つけ出してきた、その慧眼。敵ながら、あっぱれだな」
そう言ってイーレオは、人を惹き込む眼差しで、魅力的に笑う。
……最愛の異母姉が値踏みされたようで、ハオリュウの胸に不快感が沸き起こる。
――と、同時に、彼の最高の異母姉が絶賛されているのも分かるので、彼はもやもやとした、なんとも複雑な心境になった。
ふと、エルファンが顔を曇らせた。
「父上、その『慧眼』の持ち主は……」
「ああ、おそらくは……」
わずかに瞳を陰らせ、イーレオがゆっくりと首肯する。
そのやりとりに凶賊たちは顔色を変えた。各人、思うところは微妙に異なるが、皆、同じ人物を頭に描いた。――〈蝿〉と名乗った男を。
あたりが澱んだ空気に包まれ、心当たりのないハオリュウは、不安を掻き立てられる。
「何かあるのですか?」
どう説明したものかと、イーレオは額に皺を寄せた。その隙に、ルイフォンがするりと口を挟む。
「こっちの情報網で引っかかった話だ。斑目は、厳月家とは別の、厄介な相手と手を組んだらしい。けど、お前が心配することじゃない」
「なんだよ。僕を部外者扱いする気か?」
「ああ。これから前線に出る俺が、気にしておけばいいだけだ」
鋭く目を光らせるルイフォンに、メイシアは、はっとした。
ルイフォンは、ハオリュウに負担をかけまいとしている。――そして、傷だらけの体で、再び危険を冒そうとしている。
「それよりハオリュウ、お前、自分がやばいことをしたって、気づいているか?」
「え?」
「斑目の目的だった『鷹刀イーレオの逮捕』を阻止したのは、主に、お前だということに気づいているか? ――俺たちとしては助かったわけだけど、斑目からすれば『当主を人質にしているのに、藤咲家が逆らった』ということになるんだが?」
ハオリュウの顔から血の気が引いていく。
「後先考えないで、行動したろ?」
「――! でも、姉様が、この屋敷に……」
「分かっている。お前は、メイシアとそっくりだからな」
「……!?」
浅はかさを指摘されたハオリュウは、てっきり嫌味が来ると思っていた。ルイフォンの真意を読み取れず、穴が空くほどに相手の顔を見つめる。
「メイシアも、お前や父親を助けたい一心で鷹刀の屋敷に飛び込んできた。お前たちの父親だって、同じ気持ちで斑目に行ったんだろうよ。いい血筋じゃねぇか。俺はそういうの、いいと思うぜ?」
ルイフォンが邪気のない顔で笑う。
――いつ、足元をすくわれるか分からない。だからミスは許されない。
ハオリュウは、平民の血を引く跡継ぎとして、常に張り詰めて生きてきた。結果を伴わない行動など、認められない。ましてや身内を窮地に陥れる行動など、もってのほかだ。
なのに――……。
「そういうわけだから、こいつらの父親の命は、風前の灯だろう――」
そう言いながら、音を立ててテーブルに両手を付き、ルイフォンは立ち上がった。
身を乗り出し、全員の顔との距離を近づける。好戦的な眼差しで睨めつけ、皆の注目を強引に支配下に置く。
これから俺の言うことに、有無は言わせない。――そういう、気迫。
「――だから、俺は今晩、救出に向かう」
鋭い声が食堂に響き渡った。
1.花咲く藤の昼下がり-4

「やっと姉様と、ふたりきりになれた」
温かな湯気の向こうでハオリュウが言った。
ティーカップから立ち上る香りは芳醇で、先ほど退室したメイドが『屋敷で一番、美味しいお茶を淹れてくれる子』だという、ミンウェイのお墨付きを証明している。
険しい顔をしていた異母弟も、鼻腔をくすぐる癒やしの香に一瞬、顔をほころばせた。だが、すぐにまた元の表情に戻る――。
「ハオリュウ……、心配かけてごめんなさい」
メイシアは目を伏せた。申し訳なさでいっぱいで、まともに異母弟の顔を見ることができなかった。
ハオリュウの不機嫌の理由は、メイシアに対して怒っているからではない。彼は、すべての責任は、初めに誘拐された自分にあると思っている。失態を悔いているのだ。
誘拐は暴力による不可抗力であり、彼の落ち度ではないのに。
メイシアは、いたたまれない気持ちになる。
「姉様。……本当に姉様は……、その……何もされなかった?」
「え?」
「父様の救出を頼んでいる身で疑うのはよくないけど、彼らは凶賊だ。もし、姉様に何かあったのなら、僕は絶対に許さ……」
「そんなこと、ないわ!」
ぱっ、と顔を上げ、メイシアは叫んだ。ティーカップの表面に、琥珀色の波が立つ。
「姉様?」
「鷹刀の人たちは本当に、よくしてくれたの!」
彼らがしてくれたことを、ひとつ残らずハオリュウに教えたい。自分の感じた思いを、分かち合いたい。
けれど、それはあまりにも複雑すぎて、どんな言葉を使っても伝えきることはできないだろう。それがとても、もどかしい。――そう、メイシアは思った。
けれど、ハオリュウは目元を和らげた。顔に険を作っていた憤りの影が消えていく。言葉に表さなくとも、彼には異母姉の心の色が見えていた。
「姉様がそう言うのなら、もういいや。……あいつ……ルイフォン……、姉様のことを…………だし、悪いようにはしてないってのは……分かるよ」
独り言のように呟き、ハオリュウはそれ以上の思いを吐き出さないように、ティーカップで自分の口を塞いだ。彼はそのまま一気に中身をあおろうとしたのだが、あまりの香りの良さに思い留まり、上品に一口だけ飲む。
ハオリュウの顔に、ほっ、と安らぎが生まれた。それを見てメイシアも微笑み、ティーカップを手に取った。
芳醇な香りに包まれた、温かな琥珀色の時間が流れる。
しばしの安らぎと幸福。
――けれどそれは、ティーカップがソーサーに戻されるまで。かたん、と小さな音と共に終わりを告げる。
夢見心地の世界は終わる……。
メイシアは、ごくりと唾を呑み込み、切り出した。
「ハオリュウ。……家は……どんな状況なの……?」
彼女が飛び出してきたときには、実家は大混乱に陥っていた。深窓の令嬢の彼女が、ひとりで外出しても誰も見咎めないくらいに。
ハオリュウが解放されて、少しは落ち着いたのだろうか。
――継母は……。
継母に売られたことを思い出し、ちくり、と胸が痛んだ。だから彼女は、いつもならすぐに返ってくるはずの異母弟の返事が遅れたことに気づかなかった。
「……家は大丈夫だよ。うるさい親戚連中にも帰ってもらった」
「え……。でも、親族の皆様は……」
藤咲家最大の危機に駆けつけた親族は、必ずしも有り難いものではなかった。今後の方針を議論する合間に、頼りない当主の父や、平民の継母の悪口を挟む――そういう人たちだ。
そんな彼らが素直に帰ったりするだろうか――?
「当主の父様がいない今、当主代理の僕が、藤咲家の法だ。この僕に逆らえる者なんていないんだよ」
ハオリュウは、口元から白い歯をちらりと覗かせ、はにかむようにして首を傾けた。
笑みを浮かべているのに、かすれたハスキーボイスが泣いているように聞こえる。――勿論、それは気のせいだ。この異母弟は決して人前で涙を見せない。
けれど、ハオリュウの心は、血の涙を流しているはずなのだ。
権力を振りかざした彼には、親族の容赦ない敵意と悪意が襲いかかったことだろう。たった十二歳の少年が、それで平気なわけがない。
メイシアは、心臓を握りつぶされたような痛みを感じた。
「ハオリュウ……」
泣かない異母弟の代わりに、異母姉の瞳が涙をにじませる。
「姉様、そんな顔をしないで。全部、僕に任せて。大丈夫だから」
ハオリュウがぐっと胸を張る。そして、やや高くなった目線の先に窓辺を映し、彼は「あっ!」と、わざと明るい声を出した。――曇ってしまった異母姉の顔を晴らすために。
「あの庭の桜……! この部屋から見えるんだ。凄い……、絶景だね……」
ハオリュウは桜に惹き寄せられるように歩み寄り、外に出られる大きなテラス窓を開けた。途端、柔らかな春風が室内に舞い込み、桜の花びらが送り込まれる。
「うわぁ……」
風にふわりと前髪を持ち上げられ、ハオリュウは軽く目を閉じた。花びらを浴びようとでもするかのように、少し顎を上げる。その仕草は日差しと無邪気に戯れているようでもあった。
桜吹雪を抱こうとするかのように、ハオリュウは両手を伸ばす。
――その手には、当主の証である金色の指輪が光っている……。
「姉様の部屋が、一番いい客間みたいだね」
「ミンウェイさんが、この部屋に案内してくれたの」
「ああ、やっぱり。――姉様は、賓客扱いだ」
ハオリュウが、くすりと笑う。
「鷹刀一族の人は不思議だね。極悪非道のならず者かと思ったら、こんな景色を愛でる心を持っている。……どう考えても利益にならない、父様の救出なんてことを、笑いながら引き受けてくれる」
彼の掌に、薄紅のひとひらが舞い降りた。だが、それはすぐに悪戯な春風に吹かれ、再び力強く飛び立っていく。
「――凶賊というのは嘘なんじゃないかと、錯覚しそうになるよ」
後ろ姿のハオリュウは、穏やかで……どこか物悲しげで――儚く消えてしまいそう。
気づいたら、メイシアはハオリュウに駆け寄り、後ろから抱きしめていた。
「!? 姉様!?」
「どうしてハオリュウは、全部ひとりで背負い込もうとするの!? 嫌よ、なんか知らない人みたい」
メイシアの腕に包まれたハオリュウの体が、びくりと震えた。
「……姉様、はしたないよ。いくら異母弟でも僕は男だ。むやみに触っちゃ駄目」
「ハオリュウ?」
「分かってくれるかな? 僕はもう子供じゃない。『男』なんだ。自分が守りたいもののために戦いたい。――認めてよ、姉様」
少しだけ甘えたような、ハスキーボイス。
「守りたいもの……?」
「僕の家族――姉様と……父様と母様」
柔らかな声が、メイシアを包む。
彼女が守ってあげなければと思った小さな赤子は、いつの間にか彼女よりも大きくなっていた。切なさで胸がいっぱいになる。
でも、認めてしまったら、異母弟が遠い人になってしまいそうで――彼女の口を衝いたのは意地っ張りの強がりだった。
「……私も同じよ。家族を守りたいと思ったから、家を飛び出して鷹刀に来……」
言葉の途中で、メイシアが止まった。
「……姉様?」
体の触れ合った箇所から、異母姉が小刻みに震えているを感じ、ハオリュウは疑問の声を上げる。
「……違ったわ……。私は、踊らされただけだった……」
メイシアは、自分の台詞が、道化者のそれであることに気づいたのだ。彼女が家族を思う感情こそが、利用されたものだったのだから。
「ね、姉様、ごめん! そうだよね、姉様だって同じだった……」
「ううん、ハオリュウは立派だわ! 家族のために動いている。……でも、私は……、私は……! ……それに……お継母様は私のことを……」
「姉様? 何を言って……? ――あ! ……姉様、ひょっとして……?」
ハオリュウは、緩んできたメイシアの腕をそっと外し、振り向いて異母姉と向き合った。真剣な眼差しで、問い詰めるように尋ねる。
「姉様は自分が鷹刀一族の屋敷に行くことになった経緯、どこまで詳しく知っているの?」
「どこまで、って……?」
メイシアは、質問の意図が読み取れず、首をかしげる。
「姉様は、母様の採寸に来た仕立て屋に『鷹刀一族なら助けてくれる』と言われたんでしょう?」
ハオリュウの言葉に、仕立て屋の絡みつくような蛇の目が思い起こされた。ねっとりとした女の声と、毒々しい紅い唇の動きが蘇ってきて、メイシアは身を震わせる。
「その仕立て屋は偽者で、斑目一族の息の掛かった者だった、って――姉様も、それは知っているよね?」
「ええ。あの仕立て屋に『凶賊には凶賊を』と言われなければ、凶賊を頼るだなんて、私では思いつかなかったもの……」
鷹刀イーレオを『誘拐犯』にするためには、誰かがメイシアを鷹刀一族の屋敷に誘導しなければならない。その役目を請け負ったのが、偽の仕立て屋ホンシュアだった。
「姉様は、その仕立て屋が、どうやって藤咲の屋敷内に入ったか――知っているの?」
「……聞いているわ。お継母様が斑目に脅されて、藤咲家に出入りできる『許可証』を発行して呼び込んだ、って……」
「違う!」
ハオリュウが叫んだ。
「母様じゃない! 伯父様が勝手にやったことだ。母様は半狂乱になって断ったって聞いた!」
「え……!?」
娼館の女主人シャオリエには、継母に売られたのだと教えられた――と、そう言いそうになり、メイシアは、はたと気づく。
シャオリエは、そうは言っていなかった。藤咲家、ホンシュア、斑目一族の三者の動きを教えてくれただけで、結論づけたのメイシア自身だった。
「じゃ、じゃあ、テンカオ伯父様が……」
そんなことをする伯父といえば、テンカオしかあり得ない。
「そう。伯父様は…………僕のことが大事だから……」
――伯父は、貴族の前妻の娘であるメイシアのことが嫌いだから……。
テンカオは、ハオリュウの母の兄である。平民だが、父の右腕として藤咲家のために尽力してくれている。
当主の父がおっとりしているにも関わらず、藤咲家が他家に喰われずにいる――それどころか先代のとき以上に繁栄しているのは、彼のお陰だといわれている。そのため、口うるさい親族も、平民である彼を正面から攻撃しあぐねているくらいだ。
「……お継母様じゃ、なかった…………」
するり、とメイシアの頬を透明な涙が滑り落ちた。毛足の長い絨毯の先にこぼれ落ち、弾けて消える。
夫と息子が人質になっていたら、従うのが当然のはずだ。しかも、凶賊の屋敷に送りまれる義理の娘は、翌日には誘拐事件として警察隊が救い出すという手はずなのだ。
たった一晩。
餓えた獣の巣に放り込まれた娘の身に、何が起こるかに目をつぶりさえすれば、丸く収まる。
それなのに――。
「お継母様は、断ってくださったのね……」
「何言っているんだよ! 母様は姉様のことが大事だよ! 僕のことなんかより、ずっと……!」
「ハオリュウ!?」
「姉様は全然、分かってない! 確かに母様からすれば僕は実の子で、姉様は義理の子供だ。でも、母様が可愛いと思っているのは姉様なんだ! 母様にとって、僕は『跡継ぎの男子』――腫れ物扱いだ」
血を吐くような叫びだった。
肩で息をしながら言い切り、そのあとでハオリュウは、はっと顔色を変えた。
「ごめん、姉様。……言い過ぎた」
「ううん……」
「……姉様が藤咲の家を飛び出したあと、それに気づいた母様が伯父様に掴みかかって暴れた、って聞いた。――僕は、そんな母様を知らない」
実の母が藤咲家を出ていって間もなく、メイシアは継母と出会った。事務見習いとして、父の秘書――今となっては伯父となったテンカオ――の口利きで屋敷に来たのだ。
とても風の強い日だった。
庭の片隅で泣いていたメイシアに、手作りのクッキーをくれた。そそっかしい継母が途中で転んだせいで、それはだいぶ崩れていたのだけれど。
そのときの驚いた表情、赤面した顔、メイシアが「美味しい」と言ったときのあけすけの笑顔。継母は感情豊かな、素朴な町娘だった。メイシアは優しい彼女をすぐに大好きになったし、父も同じ気持ちだったのだと思う。
それが、『貴族の奥方』になった瞬間に、崩れ落ちた。彼女がくれた『砂』というクッキーの名前の通りに、さらさらと。
貴族の奥方として、あるべき姿を強要された彼女は、笑わなくなった。萎縮して、遠慮して、周りの様子をおどおどと窺うばかりになった。
だから、ハオリュウは知らない。本当の継母を知らない。
「お継母様は、そういう方なのよ……」
貴族の奥方だったら、義理の娘の犠牲など厭わなかっただろう。継母は、どこまでも普通の平民だったのだ。
――お継母様、疑って、ごめんなさい……。
メイシアの視界の中で、吹き飛ばされてしまったはずの砂粒が、きらきらと輝き始めた。眩しくて眩しくて涙が止まらない。
「姉様……」
スーツの内ポケットから、ハオリュウが金刺繍の施されたハンカチを出した。
「もう大丈夫だよ。こんなのは今晩で終わりだ。父様を連れて、皆で家に帰ろう。……母様が待っている」
力強く語りかけるハオリュウの脳裏に、正気を失った母の姿がかすめたことを――勿論、メイシアは知らない……。
2.猫の征く道-1

リノリウム張りの床に、流れるような打鍵の音色が木霊する。
高名なピアニストのごとく、高らかにキーボードを鳴り響かせているのは、言わずもがな、この部屋の主、ルイフォンである。天才クラッカー〈猫〉の名を母から引き継いだ彼は、今まさに『仕事中』であった。
「ふぅ……」
記憶媒体にデータを移し、ルイフォンはひと息ついた。
中身は斑目一族の息の掛かった店の実態、偽装事故の証拠、麻薬取引の予定日時、密輸品の売買記録……などなど。表に出れば斑目一族にとって痛手となる情報が、十ばかり入っている。
斑目一族に繋がるコンピュータは、いつでも自由に乗っ取れるようにしてあった。斑目一族だけでなく、あらゆる凶賊、ひと通りの公共機関、主要な企業のコンピュータが、彼の支配下にあると言っても過言ではない。
ルイフォンはOAグラスを外し、目元を軽くマッサージした。
この前、寝たのはいつだったか。――昨日は、ほぼ徹夜だったはずだ。
「うっわ。俺、凄ぇ働き者?」
思わず声に出して驚いてしまう。そして、メイシアの膝枕で昼寝したことと、情報屋トンツァイが『ハオリュウ解放』の報を持ってきたことで叩き起こされたことを同時に思い出し、頬をたるませつつ鼻に皺を寄せるという、複雑な表情を作った。
ルイフォンは大きく伸びをして、首を回した。自分でも、こりゃ酷いな、と思うほどの音を立てて骨が鳴る。
あと、もうひと踏ん張りと、携帯端末を取り出した。これに必要な情報を入れたら終わりだ。
そのとき、部屋の扉がノックされた。
「誰だぁ? 入れよ」
鍵は掛けていない。迎えに出るのも面倒臭いので、おざなりに返事をする。
すぐに扉の開く音がして、低温に保たれた室内と常温の廊下との間で、空気のやり取りが行われた。
「ミンウェイか」
足音はしないが、干した草の香りを感じ、ルイフォンは声を掛けた。ちょうどよかった、と彼は思った。彼女には言っておかねばならぬことがあった。
「ルイフォン、例のものはできた? ほどほどでいいから、少しは休まないと……」
波打つ髪を豪奢に揺らし、ミンウェイが近づいてきた。手にはティーポットとカップがふたつ載ったトレイ。彼女はそれを机の空いている場所に置いた。
「ああ、終わったよ」
言いながら、ルイフォンは先ほどの記憶媒体をミンウェイに手渡す。
「これを、警察隊の……なんていったっけ、あいつ」
「緋扇シュアン、よ」
「そう、そいつ。緋扇シュアンに渡してほしい」
「ご苦労様。さっき話をつけたから、手ぐすね引いて待っているわ」
「あ、おい、お前が緋扇のところに行くのか?」
リュイセンが切れるぞ、という台詞は口には出さない。これは一族の暗黙の了解である。
「まさか。私は屋敷でやることがあるし、誰かを使いにやらせるわ」
ミンウェイは綺麗に紅の引かれた口元を、くすりとほころばせた。
それはそれで、シュアンの期待を裏切るのかもしれないな、とルイフォンは思う。自分がミンウェイに心を動かされることは、髪の毛ひと筋ほどの可能性もないが、我が『姪』ながら彼女は無意味に色気があるのだ。――たとえ歳が十以上、上であっても、彼女は彼の『姪』であった。
「……ルイフォン、あなたこそ、本当に自分で行くつもり? あなたは本来、後衛部隊よ。今の仕事で充分、働いているわ」
ミンウェイが記憶媒体を示して言う。
――それは数時間ほど前の、鷹刀一族と藤咲家が手を組んでの会議の場でのこと。
互いの情報をすり合わせ、共有したところで、ルイフォンがこう宣言したのだ。
『こいつら父親の命は風前の灯だろう。だから、俺は今晩、救出に向かう』
鋭く、好戦的な眼差し。
過剰なほどの自信に満ち溢れた表情。
ルイフォンのテノールの響きが消えたのち、完全に無音の時間が訪れた――。
「ばっ……!」
口火を切ったのはリュイセンだった。
「ば、馬鹿言うなよ!? 斑目のところへ戦争をしかけるのに、お前みたいな弱っちい奴を連れていけるか!」
彼もまた立ち上がり、起立した状態であったルイフォンの襟元を掴み上げた。
もし、その手に双刀があれば、軽く峰打ちにしてルイフォンを黙らせていたことだろう。――さすがの彼も、屋敷内では帯刀していなかったので、それは未遂に終わったのだが。
感情が先走ったようなリュイセンと、自分を締め上げてくる相手を平然と見返すルイフォン。どちらが優勢であるかは傍目には明らかで、リュイセンの父であるエルファンは、大きく溜め息をついた。
「リュイセン、とりあえず拳を収めろ。――まずは、ふたりとも席につけ」
低く冷徹な声が命ずる。
ばつが悪そうにリュイセンが着席すると、ルイフォンもそれに続いた。ふたりが落ち着いたのを確認すると、エルファンは斬りつけるような冷たい視線をルイフォンに向けた。
「これは、藤咲の当主の人命に関わると同時に、我々鷹刀の体面に関わる問題だ。無様な戦い方はできない。――ルイフォン、子供の感傷も大概にしろ。お前は足手まといだ」
エルファンの弁は道理である。
ルイフォンは当然、誰かがそう言ってくると構えていた。むしろ、それを待っていたといってもいい。
「俺は、ひとりの死傷者も出すつもりはないぜ?」
にやりと、含みのある笑いを漏らす。
エルファンが、ぴくりと眉を上げた。裏があることに、いち早く気づいたのだ。わずかに体を引き、静観の姿勢を取る。
と、なると、声を上げるのは――。
「はぁ?」
すぐ隣から、素っ頓狂な声がルイフォンの耳朶を打った。
「斑目の本拠地を総攻撃して、無傷ですむわけないだろ!?」
唾を飛ばし、リュイセンが噛み付く。
期待通りの反応に満足し、ルイフォンは涼しげな顔で、とぼけた答えを返した。
「メイシアの親父さんを助けるために、他の誰かが犠牲になったら、メイシアが悔やむだろ?」
そして、柔らかな微笑みをメイシアに向ける。
彼女は、険悪な雰囲気のふたりを交互に見ていたのだが、ルイフォンの顔の上でぴたりと視線を止めた。そして、鋭く息を呑み込む。……しかし、彼女は吐き出す言葉を思いつけなかった。ただ、どきりとした心臓を抑えたまま、目を見開いている。
「何、ふざけたことを言っているんだよ!」
リュイセンの尖った声がテーブルに突き刺さった。――描いていたシナリオそのものの展開に、ルイフォンは内心でほくそ笑む。
「まぁ、聞けよ。――一族の中には貴族を快く思っていない者も多い。そいつらの感情を考えたって、犠牲は絶対に許されないんだ」
「そんなこと言ったって無理なものは無理だ! 割り切る他ない。祖父上の決めたことに逆らう奴は、一族にはいない」
「今後も、鷹刀と藤咲家が友好な関係でいてくれないと、俺が困るんだよ」
リュイセンの剣幕をもろともせず、ルイフォンが意味ありげな微笑みを浮かべる。
「だから、一族をあげての総攻撃はしない。今回のことは、俺がひとりで全部やる。斑目のことは親父の――総帥の希望通りのレベルにまで、俺が責任持って叩き潰してやる。その代わり、メイシアの親父さんに関しては、救出だけが目的の隠密行動として、俺に行かせてくれ」
「いい加減にしろ! お前ひとりで、叩き潰せるわけないだ……」
「経済制裁――!」
鋭いテノールがリュイセンの言葉を遮り、食堂の空気を斬り裂いた。
ルイフォンが、すぅっと目を細め、酷薄な笑みを浮かべる。
彼の言葉の意味を一瞬で理解した者は――――ひとりだけ、いた。黙って頬杖をついて聞いていたイーレオが、人知れず眼鏡の奥の目を楽しげに細めた。
疑問と緊迫とが渦巻き、皆の視線がルイフォンに集中する。
「人間は食わなければ死ぬ。そして、食うためには金が要る。だから俺は、斑目の資金源を断つ。――こちらの被害はゼロという条件で、斑目に打撃を与える方法はこれしかないと思う」
そう言ってルイフォンは、鼻息を荒くしているリュイセンをちらりと見やった。
「勿論、うちの連中の中には、斑目の血を見ないと納得しない奴もいるのは分かっている。けど、今日の襲撃では、こちらに死傷者はいないんだ。警察隊に立ち入られたという不名誉も、藤咲家のふたりの機転によって雪がれている。だから、今回の報復は、経済的に斑目を追い詰めることで良しとしてくれないか?」
エルファンが「ほほぅ」と、感心した声を上げた。
「それは面白いな。あの狂犬に、ちょうどよい餌を与えることもできる」
「ああ。あの警察隊員が使えるというのも、この案を考えた一因だ」
ここで、話の流れが読めずに様子を窺っていたハオリュウが、むっとした声で口を挟んだ。
「すみませんが、鷹刀一族の方々だけで話されては困りますね。『経済制裁』とは、どういうことですか? 何をする気なのか、具体的に示してください」
片方の眉を上げ、慇懃無礼にルイフォンを睨みつける。そんなハオリュウに、ルイフォンは「ああ」と相づちを打ち、猫背をぐっと伸ばして胸を張った。
「斑目が資金源にしているものは、ほとんどが非合法のものだ。その不正の証拠を警察隊に渡して、潰してもらう。――言ったろ、情報網の差だって。俺は、いざとなれば斑目の息の根を止められる証拠を揃えられる」
彼が天才クラッカー〈猫〉であることは、一族ではないハオリュウに明かすことはできない。だから、こんな言い方しかできないが、彼がその気になれば、すべての凶賊を滅ぼすことも不可能ではないのだ。
「どうだろう――『総帥』」
挑戦的な目を向け、ルイフォンが父イーレオに問う。
ずっと頬杖をつきながら楽しげに成り行きを見守っていたイーレオは、そのままの姿勢で、にやりと笑った。
「いいだろう。斑目の総帥の逮捕状が、五通くらい書けるネタを用意しろ」
「へ? それだけかよ? もっと、壊滅的なネタを用意できるぜ?」
拍子抜けしたルイフォンに、イーレオが珍しく渋い顔で諭した。
「斑目を頼って生活せざるを得ない、末端の者たちも存在する。完全に潰す必要はない。『必要悪』程度に生かしておけ」
ルイフォンは腑に落ちない様子であったが、長年、父の片腕として働いている次期総帥エルファンは、「父上らしいな」と独りごちた。
一方、いつもならルイフォン以上に、イーレオの生ぬるい指示に不平を鳴らすリュイセンが、じっと押し黙っていた。不審に思ったルイフォンが「どうした?」と水を向けると、思案顔で口を開いた。。
「総攻撃をしなくても、結局、こいつらの父親を助けるためには、斑目の屋敷に忍び込む必要があるわけだろ? それをお前ひとりでやるのは不可能じゃないか?」
ルイフォンは、にんまりと笑った。
「ああ、お前には言ってなかったな。メイシアの親父さんは斑目の本拠地じゃなくて、別荘に囚われている。既に情報屋トンツァイから見取り図を貰っている」
「な、なんだよ! それじゃ、全然、難易度が下がるじゃん!?」
「そ。だから俺が、こっそり救出してくるって。セキュリティを騙せば、なんとかなるだろ」
「いや、お前じゃ無理だろ。お前、貧民街で俺に助けてもらったこと、もう忘れたのか?」
言いながら、リュイセンがルイフォンを小突く。
「祖父上。そういうわけで、俺がルイフォンに同行します」
肩までの黒髪をさらりと流し、よく通る低音を響かせる――『神速の双刀使い』。
その発言に、ハオリュウを除く誰もが目を見開いた。
ここにいる凶賊たちの中で、もっとも貴族に否定的なのが、リュイセンだったはず……。――ちなみに、ハオリュウは素直に感激している。
「お前……。どうした風の吹き回しだ?」
「茶化すな、ルイフォン。絶対に成功させるべき案件を、みすみす失敗させることは、愚かとしか言いようがないだろ? それとも、俺と一緒は嫌なのか?」
「そんなことあるわけないだろ! お前がいれば百人力だ!」
ルイフォンが満面の笑みを浮かべ、リュイセンの首に腕を回して、ぐっと彼を引き寄せた。
予想外の頼もしい発言をした息子に微笑しながら、彼の父親であるエルファンが問う。
「ルイフォン、斑目は『鷹刀が人質の正確な居場所を知っていること』を、知らないのだよな?」
「ああ。そのはずだ」
「だったら、私が陽動に出よう。現状なら斑目は『鷹刀の総攻撃が本拠地に来る』と考えているはずだ。それに乗ってやる。大部隊を用意して斑目の屋敷に向かう素振りを見せれば、そっちの別荘の守りは薄くなるだろう」
「えっ!?」
リュイセンに続いての援軍に、ルイフォンの全身が興奮する。思ってもみない僥倖だった。
「助かる!」
「よし、それじゃ、決まったな」
イーレオが頬杖から身を起こした。
「決行は今晩。ルイフォンはそれまでに、経済制裁となる証拠を揃えておくこと。エルファンは陽動。好きなだけうちの奴らを使っていい。ルイフォンとリュイセンは救出だ。それから――」
イーレオは、言葉少なに座っていたミンウェイのほうを向いた。
「――ミンウェイは自白剤を調合して、捕虜を吐かせろ」
忘れかけていた捕虜の存在に、一同が軽くざわめく。
捕虜――執務室で傍若無人に振る舞った巨漢と、庭でメイシアに銃を向けた警察隊員。
「分かりました」
ミンウェイが答える。
「本来なら、奴らから充分に情報を引き出した上で、救出作戦に移りたいところだが、藤咲家の当主の命が掛かっているから仕方ない。――以上だ、解散!」
イーレオの低く魅力的な声が、食堂を震わせた――。
2.猫の征く道-2

「あなたは本来、後衛部隊よ」
ため息混じりに、ミンウェイはルイフォンを見やった。
まったくもって戦闘向きではないルイフォンが、救出のみが目的とはいえ、斑目一族の別荘に潜入するというのだ。ミンウェイの心配は当然だった。
「今の仕事で充分、働いているわ」
そう言いながら、彼女は彼から渡された記憶媒体を示す。その中身は、斑目一族の不法行為の証拠である。これを警察隊の緋扇シュアンに渡すことで、斑目一族に経済的な打撃を与えられるのだ。
「俺が行かなきゃ、格好つかないだろ?」
どこ吹く風といった体で、ルイフォンがにやりと笑う。
「……あなたには言っても無駄よね」
ミンウェイは諦めきった顔で、渡された記憶媒体をポケットにしまった。
藤咲家当主――メイシアとハオリュウの父親救出作戦の準備は、着々と進められている。
陽動として大部隊を率いて斑目一族の屋敷に向かうエルファンは、目立つように庭に部下たちを集めていた。付近に隠れているであろう、斑目一族の偵察部隊の目を誘うためである。
その息子のリュイセンは、倭国からの帰路で切望していた風呂、飯を済ませたので、最後の寝るの欲求を満たすべく、自室で仮眠を取っている。
会話が少し途切れたところで、ルイフォンとミンウェイは、ふたりとも表情を改めた。
「ミンウェイ」
「ルイフォン」
ふたりが同時に相手の名を呼んだ。
「先にどうぞ」
片手をルイフォンに向け、ミンウェイが譲る。彼女が少し体を引いた瞬間に、ふわりと草の香が漂った。
「たぶん、お前と俺の話は同じことだと思う」
「……そうね」
長くなりそうだと察したのか、ミンウェイは向かいの机の下に入れてあった丸椅子を、勝手知ったるとばかりに取りに行った。そのときの彼女に、足音はない。
貧民街で会った斑目一族の食客〈蝿〉は、ミンウェイのかつての通り名を知っていた。〈ベラドンナ〉という毒使いの暗殺者の名前を――。
彼女が足音を立てないのは、暗殺者としての訓練の賜物だ。リュイセンなども、ある程度、足音や気配を殺せるが、彼女ほど完璧ではない。ちなみに、戦闘員ではないルイフォンは問題外である。
そして彼女が、凶賊にしては言葉遣いが妙に丁寧なのは、主に貴族を相手に依頼を引き受けていたため。――裕福な商人の娘を演じることが多かったため。
暗殺者にとっては禁忌とも言える『匂い』を消さずに身に纏っているのは、二度と暗殺者に戻らないため――。
ミンウェイが、持ってきたティーカップに茶を注いだ。色と甘い香りから、濃いめに淹れたチャイだと分かる。疲労回復にと、砂糖多めのやつを用意してくれたようだ。
猫舌のルイフォンに合わせて、ほどよく冷ましてあるそれを受け取り、彼はありがたく一気にあおる。やけに美味しく感じるということは、思っていた以上に疲れていたということか。気遣いに感謝して、ルイフォンは大きく息をついた。
「……さっきの作戦会議のあと、親父に貧民街での出来ごとを詳しく報告してきた」
ゆっくりとルイフォンが切り出すと、ミンウェイの、ごくりと唾を呑む音が聞こえた。華のある顔立ちが、青ざめて精彩を欠いていた。
「メイシアが屋敷に連絡してくれたとき、お前も聞いていたんだってな……」
ルイフォンはミンウェイの顔を正面から見据えた。
貧民街にいるときから、彼女に知らせなければ、と思っていた。だが、どう切り出したものかと悩んでいた。
しかし、既に話は伝わっていた。
それならば、ためらっても仕方ない。単刀直入に言うべきだ。
「俺は、貧民街で〈七つの大罪〉の〈蝿〉と名乗る男に会った」
ルイフォンは端然としたテノールで、はっきりと告げた。
ミンウェイの頬がぴくりと動く。
「……ええ。その連絡を受けたのは私だもの。知っているわ」
彼女は目を逸らすことなく、双眸にルイフォンの姿を映す。しかし、艶のあるはずの声が、かすれて色あせていた。
正直なところ、そんな彼女など見たくはなかった。だが、ルイフォンは感情を取り払った〈猫〉の顔で言う。
「〈蝿〉っていったら、お前の親父のことだろう――?」
ルイフォンの言葉が、温度を低く保たれた、この部屋の冷気のように吹きつける。ミンウェイの顔が人形のように表情を失った。
「でも、お父様は……!」
ミンウェイは少女時代の半ばまでを、父親とふたりで暮らしていた。〈ベラドンナ〉という名前で生きてきた。
彼女は、言葉を途切らせたまま押し黙る。
言いたくないのだ。それが分かるから、ルイフォンが言を継ぐ。
「……ああ。死んだはずだ」
冷酷なルイフォンの声が、空調の風に乗る。豪奢に波打つミンウェイの髪から、草の香を奪っていく。
「ルイフォン、教えて! その人は本当に、私のお父様だった!?」
がたん、と小さな椅子の足がリノリウムの床を強く踏み鳴らした。バランスの悪い丸椅子から滑り落ちるように、ミンウェイは全身で詰め寄った。
「そんなこと言われたって、分からねぇよ。俺はお前の親父に会ったことねぇし」
「ごめんなさい……」
ミンウェイは目線を落とす。女丈夫の彼女の肩が、ずいぶんと小さく見えた。
「……親父と話したんだけど、〈蝿〉の身体的特徴や発言内容は、お前の親父、ヘイシャオと似ているらしい。けど、本人ではあり得ないとエルファンが断言している――死んだ、ってな」
ミンウェイは何も言わず、ただ頷いた。
「だから、ヘイシャオの偽者を俺たちの前に出して、鷹刀の動揺を誘っているんじゃないか、という見解だ」
「そう……よね。死んだ人間が生き返るはずないわ……。それにお父様は、お祖父様やエルファン伯父様に害をなす者だもの。生き返ったらいけない……」
ミンウェイの声が震えていた。
――彼女の父親のことは一族の誰もが知っている。だが、できるだけ話題から避けられていた。
彼女の両親は従兄妹同士だった。母親がイーレオの娘、父親がイーレオの長兄の息子である。
ふたりが結婚したのは、イーレオが総帥に立つ少し前。イーレオの父親であり、彼らふたりの祖父である男が、悪逆非道の限りを尽くしていた時代である。鷹刀という一族は、強く美しい血筋を保つために、代々異常な近親婚を繰り返しており、彼らの婚姻もそんな縁のひとつだった。
数年後、イーレオの悲願だった総帥位略奪計画が成功した。そしてイーレオの父親と、次期総帥であった長兄が殺された。そのとき、長兄の息子であったヘイシャオは、ミンウェイの母親を連れて姿をくらました。
イーレオがミンウェイの誕生と、娘であるミンウェイの母親の死を知ったのは、それから十数年を経てからのことである。
つまり、ミンウェイの父ヘイシャオは、鷹刀一族の正当な後継者の息子――。
本来なら、今、この屋敷を我が物顔で歩いているはずの人物。
現在の鷹刀一族に恨みがあって当然の人間……。
「親父が総帥になる前の鷹刀は、〈七つの大罪〉と組んでいた。だから今、斑目が〈七つの大罪〉と組んでいるのなら、鷹刀の情報が斑目に流れていたとしても不思議じゃない。偽者の〈蝿〉を仕立てることも、わけないはずだ」
何故なら、医学、薬学に深い造詣のあったヘイシャオは、鷹刀一族と蜜月関係にあった闇の研究組織〈七つの大罪〉に、研究者を意味する〈悪魔〉の〈蝿〉として所属していたから――。
「……貧民街に現れた〈蝿〉は、お父様じゃないのね」
「当たり前だ。死んだ人間は生き返らない。ただ気をつけてほしいのが……」
「何?」
「ミンウェイが自白を任された捕虜たちは、俺の会った〈蝿〉と口調がそっくりなんだ。わざと奴の真似をして、揺さぶりを掛けようとしているとしか思えない。あいつらは斑目の手の者というよりは、〈七つの大罪〉の関係者だろう」
「お父様のことを知っている……?」
「ああ。だからこそ、奴らが持っている情報は気になるが……」
言葉の途中で、ルイフォンは、はっと顔色を変えた。
ミンウェイの上半身が、背もたれのない丸椅子から倒れ落ちようとしていたのだ。
「おい!」
ルイフォンは慌てて抱きとめる。
ふわりと草の香が鼻をかすめ、温かな体の重さが腕に掛かった。
「大丈夫か!?」
「あ……、ごめんなさい……」
「お前、真っ青だぞ!」
波打つ髪が顔の半分以上を隠していたが――否。だからこそ、黒髪の狭間で白い頬が浮き立ち、光って見えた。
全身を鍛えられた筋肉で覆われている彼女なのに、女性的に柔らかい。そこに色気など感じないが、それが彼女の脆さの象徴のようで、ルイフォンは怖くなった。
「平気よ……」
「平気じゃねぇだろ! お前にとって、父親のことは鬼門だ」
「そうね、そうかもしれない」
「お前は一旦、この件から外れたほうがいい。親父に進言する」
そう、ルイフォンが言った瞬間、弾かれたようにミンウェイが叫んだ。
「駄目よ! これは、私が避けてはいけないことだわ!」
「ミンウェイ……」
不意に、彼女が彼の背中に腕を回してきた。そして、ぎゅっと体を密着させる。草の香りが彼の鼻腔をくすぐった。
「それ以上、何か言うと、可愛い叔父様を誘惑するわよ?」
いつもの調子に戻ったようなミンウェイは、単に無理をしているだけだ。けれど、いつも通りに振る舞ってほしい、という気持ちが伝わってくる。
だから、この話は打ち切る。心配はあるけれど、誰にも引けない時はある。
ルイフォンはミンウェイの体を引き剥がした。もともと冗談で貼り付いているだけなので、回された腕はあっさりと外れた。彼は癖のある前髪をくしゃりと掻き上げた――いつものように。
「あのなぁ……。俺、お前に何か感じるほど飢えてないから」
「メイシアが、いるものね?」
「そうなる予定だ」
「白状したわね?」
「別に隠してねぇし?」
そう言って目を細め、にやりと笑う。そんなルイフォンに一瞬、あっけにとられたミンウェイだが、徐々に穏やかな笑みを浮かべた。
「いつの間にか、いい男に成長したわね。これもメイシアのお陰かしら?」
「何、言ってんだよ? 俺はもともといい男だぜ?」
そして、どちらからともなく、声を上げて笑い出した。
2.猫の征く道-3

少しだけ濃くなってきた蒼天の空に、薄紅色の桜が咲き誇る。ひらりひらりと舞い落ちる花びらが、斜めからの陽光を受けて、輝きを撒き散らしていた。
メイシアは窓辺にたたずみ、見るともなしに桜を見ていた。
テラス窓を開けると、春風に運ばれたひとひらが、彼女のもとへと訪れた。枝から離れたばかりの花弁は瑞々しく、しっとりと濡れている。
あらゆるものが美しく見えた。世界が優しく彼女を包み込んでいるのを感じた。
彼女と彼女の家族のために、皆が動き出している――。
ハオリュウは、先ほど自分の案内された客間に戻った。
父が救出されるの待つため、異母弟は今晩、メイシアと共に鷹刀一族の屋敷に泊まることになった。そんな連絡や状況の報告を藤咲家にしておく、と彼は言っていた。
明日になれば家族揃って継母の待つ藤咲家に帰るのだと、ハオリュウは思っている。だが、メイシアはイーレオの愛人で、いずれは娼婦になる約束なのだ。そのことはどうなるのだろう?
心臓がちくりと痛むのを感じた。
メイシアは胸を抑えた。そして桜を見つめる……。
「おい」
ルイフォンは、メイシアの部屋のドアノブをノックなしで捻った。扉はそのまま抵抗なく、すっと滑らかに開く。彼女は相変わらず、鍵を掛けられることに気づいていないようだ。聡明なのに世間知らずな彼女らしい。
「きゃっ」
唐突な呼びかけに、窓辺で外を見ていたメイシアは驚きの声を上げた。彼女が長い髪を舞わせて振り向くと、開け放された窓から桜色の花びらが髪飾りのようについてくる。
彼女はルイフォンの姿を認めると、口元を両手で覆い、目を丸くした。
「邪魔するぜ」
ルイフォンは、ずかずかと室内に入り、当然のように椅子に座る。そして、落ち着きのない様子のメイシアに、目線で椅子を勧めた。
「ルイフォンは今、忙しいのではないですか?」
促されるままに向かいに座りつつ、メイシアが問うた。斑目一族を経済的に追い詰める、不法行為の証拠集めのことを言っているのだろう。
「俺を誰だと思っている? そんな仕事、とっくに終わった」
やや不機嫌な顔を作り、ルイフォンは口元を歪めた。するとメイシアは申し訳なさそうに肩を縮こめ、けれどしっかりと反論してくる。
「なら、休んでください! ルイフォンは怪我人なんです。それに目が真っ赤で、隈が出ていて……。お疲れなんです! 昨日からずっと、無茶しすぎです!」
メイシアの心配は当然といえば当然で、ルイフォンとしても気遣いが嬉しくないはずがない。だが、彼女のあまりに悲愴な顔つきに、思わず口から笑いが漏れた。
「ルイフォン!」
「ごめん、ごめん。……ありがとな。このあと仮眠をとるから大丈夫だ」
そう言って、ルイフォンは、ごそごそと懐をまさぐった。そして、きらりと光るものをを取り出す。小さな金属の流れる音が、机の上に載せられた。
「え? それ……?」
それは、メイシアがずっと身につけていたペンダントだった。繁華街に行く際に、貴金属は物騒だからと言われ、と置いていったのだ。
「すまない。こいつに何か仕掛けられている可能性があったから、ミンウェイに頼んで勝手に調べさせてもらった。結果、シロだった。疑って悪かった」
「え、いえ」
「お詫びに今度、俺が何か贈ってやる。アクセサリーなんてよく知らんが、こんな感じのは見覚えがあるから大丈夫だ」
「い、いえ。そんな!」
何故、贈り物をされるのか、何故、見覚えがあると大丈夫なのか、メイシアには分からない。だが彼女の顔は、ふっと陰った。
「お忙しいのに私を訪ねて来るなんて、どうしたのかと思ったら、これを届けに来てくれたんですね。……ありがとうございます」
メイシアは机の上のペンダントを受け取ると、首をかがめて身につけた。白いうなじが一瞬だけ、ちらりと覗き、また黒髪の中に埋もれる。
「ルイフォンは早くお部屋に戻って、少しでも休んでくださいね」
ごくわずかに――音階にして半音程度、彼女の声が沈んでいる。
そんな彼女に、ルイフォンは一瞬、あっけにとられ、癖のある前髪をくしゃくしゃと掻き上げた。
「……ペンダントはついでだ。俺は、お前に会いに来た」
「え……!?」
ルイフォンは、すっと猫背を伸ばした。彼は、決してリュイセンのように長身ではないが、それだけで随分と印象が変わる。ぐっと表情を引き締め、彼本来の精悍な顔立ちをあらわにした。
「お前の親父を救出して、この件の片が付いたら――俺は、鷹刀を出ようと思う」
「えっ!? ……ど、どういうことですか!?」
「俺は、もともと一族であって一族ではない。――俺は〈猫〉。〈猫〉は情報屋で、鷹刀とは対等な協力者のはずだ。俺が鷹刀の屋敷にいるのは、母さんが死んだとき、俺がまだ餓鬼だったから。放っておけないから親父が引きとった。それだけだ」
「でも、どうして? ルイフォンが鷹刀を出ることに、どんな意味があるんですか?」
ルイフォンは――。
――挑戦的な目をして、笑った。
「俺が、お前の居場所になる」
テノールの響きが、魔法のようにメイシアの動きを止めた。
鈴を張ったような瞳が、大きくルイフォンを映していた。この呪文の意味を、必死に読み取ろうとしているのだろう。
そんなに難しい話ではない。けれど、彼女の生きてきた価値観からすると、難しいかもしれない。ルイフォンは彼女の表情を確認しながら、ゆっくりと口を開く。
「今、鷹刀と藤咲家は協力体制を取っている。けど、お前の親父を救出したら、お前の所在を巡って対立するかもしれない」
彼女が息を呑んだ。硬い顔をして彼を凝視する。
「ハオリュウは当然、お前を家に連れて帰るつもりだろうし、親父はお前を気に入っているから手放したくないだろう。それにお前自身も、親父のものになるっていう『取り引き』を忘れちゃいないはず――自縄自縛だ」
「……そう、ですね」
細い声が揺れた。メイシアは視線を落とした。――か弱く儚げに見える存在。でも、それは彼女の本質ではない。
彼女は、鳥籠で愛でる鳥ではないのだ。決して力強くはないけど、大空に向かって高く羽ばたく。蒼天の下でこそ輝く、優美な鳥――。
自由に翼を広げてほしい――ルイフォンは、そう願う。
「振り切っちまえよ」
「え?」
「しがらみも『取り引き』も、全部、無視だ。……別に喧嘩しろというわけじゃない。できるだけ良好な関係は保つ。だから――」
ルイフォンは、まっすぐにメイシアを見つめた。
「――俺のところに来い」
テラス窓から、風が舞い込む。
薄紅色の花びらを載せて、ふたりを包む。
「ルイフォン……、私……」
彼を見上げたメイシアの顔が、不意に、さぁっと赤く染まった。彼女は、あっという間に耳まで赤くして、耐えきれなくなったようにうつむく。だから彼は、一瞬だけしか見ることができなかったのであるが、それは純粋で無防備な、むき出しの笑顔だった。
「深く考えるな。直感でいいんだ。今、お前は喜んだだろ? ――俺は、お前の顔を確かに見たからな」
「えっ!? やだ!」
変な顔だったに決まっていると、メイシアは両手で顔を覆った。
「そ、そんなこと言って! ルイフォンは、私に『直感的に生きたほうがいい』って言ったこと、忘れていたじゃないですか!」
「忘れてたけど、今もう一度言ったから、それでいいんだ」
「そんな……!」
「何も問題はないだろう?」
ルイフォンの言葉に、メイシアの鋭い呼気の音。
そのまま彼女は息を止め、小さく首を振ったように見えた。
「メイシア……?」
ルイフォンは不審の声を上げる。
やがて彼女は、音もなく息を吐いた。その吐息は、細く長く――。
ゆっくりと黒絹の髪が後ろに流れ、花の顔が現れた。
「……私は一度、直感ではなくて、計算尽くで我儘を通したんです」
「我儘、って、なんのことだ? 俺の部屋で『今、あなたと一緒に喜びたい』って言ったやつか?」
「あ、ああああれも、恥ずかしい我儘でした。…………けど、そうじゃなくて。それよりも、もっと前。庭で警察隊に囲まれたとき。私……ルイフォンに……」
「庭? 警察隊?」
「なんのお断りもなく、あ、あの……」
なんのことを言っているのか、ルイフォンは初め、さっぱり分からなかった。
だが、しどろもどろのメイシアを見ているうちに、だんだんと察しがついた。彼女がこんな態度をとるときは決まっていた。
彼なりに気を張っていたのだが、慌てふためく彼女の可愛らしさに緊張が解ける。いつもの猫背に戻ると同時に、むくむくと嗜虐心が沸き起こった。
「何を言いたいのか、まったく分からないんだが?」
「ですから!」
反射的に顔を上げたメイシアの目には、涙が浮かんでいた。
「あ、あなたの意志を無視して、私が強引に……!」
勢い込んで、そこまでは言えるのだが、ここで口の動きが止まってしまう。
瞳を潤ませ、真っ赤な顔で彼を見つめる口元が、やや拗ねていた。からかわれているのは分かっているらしい。聡明で落ち着いた彼女からは想像できない、喜怒哀楽のはっきりした自然な表情――。
メイシアは類稀なる美少女であり、そこに立っているだけで誰もが見惚れる。優しく微笑まれたりでもしたら、天にも昇る心地になるだろう。
けれどルイフォンは、彼女が必死に訴えたり、泣きながらも凛と前を向くような、そんな感情豊かな顔に惹かれる。透き通った魂が、ありのままに強く存在を示そうとする姿に魅了される。
――とはいえ、あまり苛めすぎるのも可哀想なので、助け舟を出した。
「お前が俺にキスしたこと?」
「そうです!」
叫ぶように答え、彼女は大きく息をつく。目尻から薄く涙がはみ出ていた。
「絶対に避けられないところで、お断りなしに……すみませんでした」
「謝ることはない。俺はいい思いをしたし、策としても悪くなかった。けど、驚いた。いったい、どうしたんだ?」
メイシアはルイフォンから隠れるかのように、再び、うつむいた。視線が落とされるのを追いかけるように、さらさらとした黒髪が流れ落ちる。
まただ。――ルイフォンの肌が粟立つ。
楽しく会話していたと思えば、唐突に彼女が沈む。どこかでボタンを掛け違えたかのような、この不自然さは……なんだ?
やがて、透明で繊細な、硝子細工のような声が響いた。
「スーリンさんが…………綺麗だったんです」
「は? スーリン?」
ここでどうして、シャオリエの店の少女娼婦、スーリンの名が出るのだろう。ルイフォンは訝しげに眉を上げた。
「シャオリエさんの店に入ったとき、スーリンさんはルイフォンに、その……抱きつきましたよね」
「……ああ」
ルイフォンは、そのときのことを思い出して顔をしかめた。
元一族のシャオリエは、自分の好奇心を満たすために、ルイフォンたちを呼びつけた――口では一族のためと言っても、本心はただの野次馬だと、ルイフォンは思っている。
そして、ルイフォンがメイシアを連れているのを知っていて、スーリンはメイシアの前でキスしたのだ。
「彼女は、本当にルイフォンを想っていて。それが、そばにいた私にも伝わってきて。いやらしさなんて欠片もなくて……」
「…………」
美化されている。
あの状況をどう見たら、そう解釈できるのか……。
ルイフォンが判然としない思いでメイシアを見やると、いつの間にか顔を上げていた彼女は、穏やかな優しい顔をしていた。
「私は、家が決めた相手に嫁ぐ身として育てられました。だから、ああいったことは、はしたないことだと思っていました。けど、あのときのスーリンさんは、本当に綺麗だったんです。『恋』というのは、あんなに素敵なものなんだ、って感動して…………憧れたんです」
彼女は白い頬を桜色に染め、何処か遠くを見つめていた。
「――だから、あんなことをしてしまいました。すみません。……夢みたいでした。……でも、これ以上は駄目です。ルイフォンのご厚意には甘えられません」
ルイフォンの口から「え……?」とひび割れた声が漏れた。
「あれはスーリンの真似っこだったのか」
「……はい。…………私、スーリンさんに憧れたんです」
その答えを聞いた瞬間、ルイフォンは、強い力で胸が押しつぶされるのを感じた。呼吸が止まり、息苦しさに脂汗が垂れる。
目の前にいるのは、恋に恋する少女――。
彼女は、貴族として生まれ、貴族として育った。
どんなに美しく羽ばたける翼を持っていたとしても、籠から出たばかりの彼女の心は、まだ雛鳥のまま――。
「……って、ことは、あの状況なら、相手はリュイセンでもよかったわけだ」
心にもない言葉が、思わず口から漏れていた。
悔しいような切ないような、やり切れない思いが、胸を掻きむしった。
「『恋人ごっこ』なら、誰でも同じだからな」
――決意と覚悟を踏みにじられた気がした。自分が傷つくだけの台詞を、それでも言わずにはいられなかった。
「ち、違います!」
「どこが違うんだ!? 反論できねぇだろ!」
「……っ!」
刹那、メイシアの表情が一転した。
すっと上げられたその眼差しは――まるで憎しみ。
「…………どうして……『憧れ』ということにしてくれないの……?」
押し殺したような、声が揺らめく。
「憧れだって、憧れに過ぎないって、思い込もうとしているのに……!」
美しいはずの顔は奇妙に歪み、怒りに飲み込まれていた。しかし、指先ひとつ触れれば泣き出しそうな――そんな危うい均衡を保っていた。
「なんで、他の人じゃなくて、『ルイフォン』なのかって!? そんなの!」
彼女は、肩を使って大きく息を吸い込んだ。
一度、息を止め、……そして、一気に吐き出す――!
「『ルイフォンの恋人』になりたかったからに決まっているじゃない!」
魂の叫びが舞い上がった。
ざぁぁっと、勢いよく叩きつけられた想い――それはまるで、桜吹雪のよう……。
「だから、これが、私の『計算尽くの我儘』……! お芝居でいい、一瞬だけでいい、私、『ルイフォンの恋人』になりたかった!」
「……お前、言っていることが……」
そんな彼の呟きは、彼女の強い声に遮られる。
「――だって……」
メイシアの瞳が盛り上がる。
そして――。
「望んじゃ駄目なことだから……!」
均衡が崩れた。
透明な涙があふれ出し、メイシアの頬に光の軌跡を描きながら流れ落ちる。
はっとして、ルイフォンは慌てて口を開いた。
「……な、なんで、駄目なんだよ!?」
望んでいるのなら、何故、差し伸べた手を素直に取らないのだ? 混乱する。訳が分からない。
「私は藤咲の家で、家柄の合った殿方に嫁ぐか……、鷹刀のイーレオ様のもので、いずれ、そ、その、多くのお客さんのお相手をするって、お約束をしている身で……!」
「だから、それを振り切れって!」
メイシアが唇を噛んだ。
目をそらし、肩を震わせながら、苦しげな声を絞り出す。
「……だって、…………だって! 振り切ったとしても、ルイフォンにはスーリンさんがいるじゃない!」
「……は?」
「私が欲しいのは『自由』じゃない! ……『ルイフォン』なの!」
籠の外を知った雛鳥の、精一杯の告白。飾らない無垢な言葉。
「だから、……私は、これ以上を望んじゃ駄目……、もう充分に幸せな思い出を貰った……。私、ルイフォンとスーリンさんが仲良くしているところ、見たくない……。――独り占めしたい。……でも……私だけのルイフォンにならないのなら…………要らないの」
また、ひと筋、メイシアの頬を涙が伝った。
ルイフォンは、どきりとした。
彼女の泣き顔は何度も見ているけれど、これほど重い涙は初めてだった。
「……俺は馬鹿だ」
彼は癖のある前髪を掻き上げた。そして、その手で自らの頭を叩く。
鳥籠の小鳥は、すべてを与えられてきた。与えられないものは、存在しないものと信じてきた。
そんな小鳥が初めて欲したもの――。
「『俺のところに来い』じゃねぇや……」
くだらない格好つけだった。雛鳥の彼女に言うべき言葉は、そんな言葉ではなかった。
「俺は、お前が好きなんだ。――俺が好きなのは、お前だけだ」
メイシアの瞳が大きく見開かれ、更に、ひと筋の涙がこぼれる。
「スーリンさんは……?」
「スーリンは恩人だけど、恋人じゃない」
「え……?」
「母さんが死んだあと、俺がシャオリエのところに預けられたことは言ったよな。スーリンにはそのときに世話になった。記憶があやふやなんだが、あのころの俺は放っておけない状態だったらしい」
ルイフォンは姿勢を正した。
自分を見る、濡れた黒曜石の瞳に惹きつけられる。いつだって彼女は懸命で、魂の輝きが彼を魅了した。
「そばに居てほしい。お前を藤咲家に帰したくない。親父のものにもしたくない。だから、これは俺の我儘だ。全部振り切って――俺のそばに居てほしい」
まっすぐにメイシアだけを見つめて、ルイフォンは、はっきりと告げた。
曇りない、透き通った言葉が、ふたりだけの空間を切り取った。それは、まるで時が止まったかのような世界――。
不意に、メイシアの瞳から朝露のような涙が輝いた。
「はい……!」
固く閉じられていた蕾がほころび、ふわりと広がるような笑顔だった。
ルイフォンは立ち上がり、彼女の元へ寄る。赤らんだ彼女の顔を見つめながら顎に指を掛け、桜色の唇に口づけた。
「芝居じゃない、本物のキス。一瞬じゃなくて、一生の恋人だ」
テノールの息が掛かり、メイシアの心臓が高鳴る。夢見心地に上気する体が、現実として、ふわりと浮いた。
「え?」
ルイフォンが、メイシアを抱き上げていた。
「ルイフォン?」
彼は愛しそうに彼女の黒髪に頬を寄せると、彼女をしっかりと胸の中に抱きかかえ、ゆっくりと歩き出す。細身だが、しっかりとした筋肉が大切に大切に彼女を守り、危なげなく運んでいく。
そして、その先は――。
「どこに行くの?」
「寝室」
「え!? あの、あのっ!?」
彼女は真っ赤になって慌てふためき、手を振り上げようとして……果たしてそれは正しい行為なのか、大真面目に悩んで動きを止める。
密着した体から、彼は彼女の鼓動が早まるのを感じた。
続き部屋の扉を開き、ベッドを目前にすると、彼は彼女の全身が強張るのが感じた。それでも彼女は無言で、身じろぎせずに彼の腕の中に収まっている。
そんな彼女を、彼は柔らかな毛布の上に、そっと下ろした。彼女の体重を捉えたスプリングが、小さな呻きを漏らす。
長い黒髪が、洗いたての真っ白なシーツに広がり、艶めいた。白磁の肌が、ほんのりと桜色を帯び、ほのかに香る。
彼女は、ただ真上を見ていた。
緊張した目で、けれど、まっすぐに彼を見ていた。
ルイフォンは……笑いを堪えることができなかった。
「ルイフォン!?」
腹を抱えて笑い転げる彼に、狼狽した彼女の声が裏返る。
「『俺はこのあと仮眠をとる』って言っただろ? 膝枕を所望する」
「え、あ! ああ、そうですよね!」
……あからさまに、ほっとされると、それはそれで傷つく。
残念そうに苦笑するルイフォンに、メイシアは、ささっと上半身を起こし、「どうぞ」と膝を差し出した。
彼は、衣服に包まれた柔らかそうな太腿をじっと見て、しばし考え込んだ。
「やっぱ、こっちのほうがいいや」
ルイフォンがベッドに上がり、ぎしり、とマットが沈む。そのはずみでメイシアの体が少し傾くのを、彼の両腕がしっかりと包み込んだ。彼はそのまま、彼女を抱きかかえるように体を転がし、ベッドに倒れ込んだ。
「きゃっ!?」
「添い寝」
そう言ってルイフォンは、メイシアをしっかりと胸に収めた。彼女の体が、かぁっと熱を持つ。柔らかな肉体が、早めの呼吸に合わせて蠢いていた。湿った息が胸元に掛かり、ぞくぞくする。
鼻先をかすめる温かさ。芳しいだけでない、生きている香り。
彼女に気づかれないように、こっそり唇でこめかみに触れると、血液の流れる音が響いてきた。羊水に揺蕩うような心地とは、これに違いないと肌で思う。
彼女に居場所を与えようと思った。
けれど、彼もまた居場所を貰ったのだと、全身で感じていた。
そうしてルイフォンは、幸せな夢路についた――。
~ 第六章 了 ~
幕間 黄昏の言霊

一生に一度の、恋をした――。
そのとき私は、たった五つの子供だった。
そんな子供に、父は真剣に恋を語った。
「一生に一度のお願いなんだ」
父は、祈るように両手を組んでいた。
貴族の当主としては、ぱっとしない男だった。庭の木陰で、ぼんやりと居眠りしているのが似合う人だった。
傍目には寝ているようにしか見えないけれど、彼はいつも、頭の中で冒険譚を描いているのだという。いつだったか、こっそり教えてくれた。
そんな、夢見がちな人だった。
「彼女を妻として迎えたい。君のお継母様になる。祝福してくれないだろうか」
緊張しているのか、大人相手のような言葉遣いで、父は頭を下げた。
私は彼女のことが大好きだったけれど、貴族の奥方に平民がふさわしくないことは、教育係から教えられていた。そして、口さがない親族たちが入れ替わり立ち替わり現れては、歯に衣着せぬ言葉を落としていった。
それに何より、彼女自身が私に言っていた。
――私は、だいそれたことなんて望まないわ。今のままがいいの……。
真面目で、義理堅いことだけが取り柄の父。年端もいかぬ娘にすら、筋を通そうと頭を垂れる。庭師にでも生まれ落ちていれば、きっと幸せな人生を送れたことだろう。
そんな父の、一生に一度の恋。
家の望むまま、愛も知らずに妻を娶り、破局した男の初めての想い。
「どうして、今のままじゃ駄目なの?」
彼女は我が家で事務の仕事をしていたから、毎日のように逢うことができた。私は花冠が完成したら、すぐに彼女に見せに行ったし、おやつは父の書斎で一緒に食べていた。
「夜の闇から目覚めた瞬間に、彼女の姿を瞳に映したいんだ。そして……」
「そして?」
口ごもる父に、私は小首をかしげる。
「暁の光の中で、彼女に『おはよう』って言ってもらいたい――」
そう言って父は、照れたように笑った。
聞きようによっては、愛の睦言にも取れる詩人めいた言葉。勿論、子供だった当時の私は、素直に、いつも共に在りたいということなのだと解釈した。
――今の私なら……。いえ、今の私でも、やはり父は、純粋な気持ちで言ったのではないかと思う。
ただ彼女に、いつもそばにいてほしいと願った。
運命の姫に出会った少年は恋に落ち、周囲の反対を押し切って結ばれる。きっと父は、そんな物語を頭に描いたのだろう。そして、それを現実のものにした。
それは私の憧れであり、叶わぬ夢と思っていた――。
肩に回った彼の腕が、ぐっと私を抱き寄せた。思わず声を出しそうになるのを、私は必死にこらえる。
これは腕枕というのだろうか。
腕というよりも、私の頭が彼の肩口に載っかってしまっている。頬に彼の鎖骨を感じて、私の鼓動は爆発しそうに高鳴った。
素肌に触れているわけではない。けれど薄地のシャツなど、なんの意味もない。私とはまったく違う肌の香りを阻んだりはしないし、脈打つ体のわずかな動きさえ、損なうことなく滑らかに伝わってくる。
彼の吐息が私の前髪を揺らした。額がかっと熱を持ち、心臓がびくんと跳ね上がる。
彼の吐息が、再び私に掛かる。私は再び……。
――彼は規則的な寝息を立てている。そう、彼は寝ているのだ。熟睡している。信じられないことに! 私が、どんな思いをしているかなんて、お構いなしだ。
強引で、マイペースで、私の言うことなんて、ちっとも聞かない。
ただひたすらに、自分の決めた道に向かって突っ走っていく……。
――そんな強さに惹かれた。
彼の腕が、私の体を更に引き寄せた。私の上半身が彼の胸に載り、心臓と心臓が重なり合う。あまりの距離の近さに、私は思わず体を離そうとするが、細身なのに筋肉質な腕は振りほどけない。
私の心音がうるさくて、彼を起こしてしまいそう。なのに、鎮まれ、鎮まれと念じるたびに、私の心臓は勢いを増す。
これは夢じゃない。
目眩がしそう。
甘くて柔らかな、綿菓子のようなものだと思っていた。
優しい言葉と、温かい微笑みだけの世界だと思っていた。
けれど現実は、傷つけ合ったり、すれ違ったり、伝わらなかったり。泣いたり、怒ったり、笑ったり……。
自分の中の汚いものを全部さらけ出して、相手の強さも弱さも、まるごと受け入れて……。
――全身に、彼のぬくもりを感じる。
このぬくもりを、ずっとそばに感じていたい……。
寝室の小窓が、黄昏どきを告げていた。
彼の体が、ぴくりと動いた。
続けて、小さな呻き声。――目覚めたのだろう。
彼は、私の存在を確かめるかのように、両腕で強く抱きしめてきた。苦しさに、私が小さな声を漏らすと、腕の力がふっと緩む。そこで私は、初めて体を動かすことができた。抱きすくめられたまま、今まで彼の寝顔を見ることも叶わなかったのだ。
寝起きの彼は、まだ目がとろんとしていて、子猫のようだった。癖のある前髪が、更にぼさぼさになっている。
無防備な彼に、愛しさがこみ上げてきた。
そして、私は、にこやかに笑う。
「おはよう、ルイフォン」
黄昏の光が、きっと私の顔の赤さを隠してくれていると信じて――。
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第一部 第六章 飛翔の羅針図を
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第一部 落花流水 第七章 星影の境界線で https://slib.net/111469
――――に、続きます。


