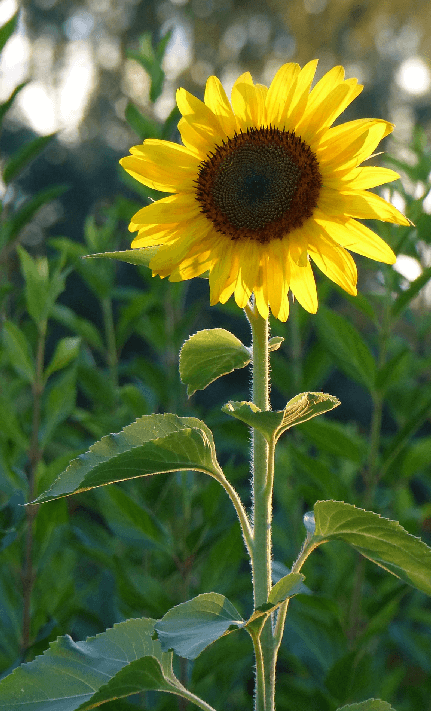
この夏風が、あの子のもとに届いたら。
第1話 夏色に染まった公園で。
焼け付くような夏の陽射しが、駅前公園に降り注いでいた。
園内のあちこちの木々から、アブラゼミの声がうるさいくらいに響いてくる。
アスファルトの敷かれた地面からは熱気がゆらゆらと立ち上り、精気いっぱいの枝葉の隙間から見える蒼い空には、子どもが作ったでっかいわたあめみたいな入道雲がふんわりと浮かんでいた。
何気なく駅の方に目を移すと、構内から出てきたサラリーマン風の人がハンカチで汗を拭いながらタクシーに足早に乗り込んでいく姿が目に入る。
広場中央にある遊泳禁止のはずの噴水では、兄弟らしい小学生ふたりが暑さに耐えられなくなったのか、中に飛び込んでバシャバシャと水遊びを始めてしまっていた。
吹き抜ける風は生ぬるく、鼻の奥で感じる香りは紛れもなく夏の匂いで。
時期的としてはまだ初夏のはずなのに、今年は早くもこの街に盛夏が訪れていた。
そんな光景を、木漏れ日の下にひとり座ってぼーっと眺めていた。
ふと我に返り、そういえばここに来てからどれくらい経ったっけ、と時間を確認しようと鞄からスマホを取りだす。
ずいぶんと早く来すぎたせいもあって、表示されたデジタル時計はようやく待ち合わせの時間になっていた。
そこでふと気づき、天気予報アプリを起動してみる。
本日は一日中晴天。
最高気温、36度。
「あっついわけだよ……」
思わずそう口にしてしまい、慌てて今のひとりごとを聞かれてないかと辺りを見回す。
とは言っても、広場の片隅にちょこんと配置されたベンチには私ひとりだけ。
噴水の向こうに見える東屋では、大学生らしいお兄さん達がわいわい騒いでたけどその他には私と同じようにベンチに座ったり、横になったりしてる人が数える程度しかいない。
さすがにこの猛暑だと、日陰とはいえわざわざ屋外に出ようという人は少ないみたいだった。
とりあえず、ほっと一息。
そこで突然携帯が大音量で着信音を流し始めた。
「わ、わわっ!?」
マナーモードにするのを忘れてたのに気づき、慌てて電話に出る。
『おまたせ、今駅についたよー』
「あ、彩ちゃん。おはよう」
待ち合わせ相手の彩花ちゃんからだった。
『葉月は今どこにいるの?』
「えっと、駅前公園の噴水の近く」
『げ、この暑いのに外にいるの? 駅の中で涼んでればいいのに』
「んー、なんとなく」
『わかった。じゃあ今からそっち行くから待ってて』
そう言って電話は切れる。
「……言われてみれば、確かにわざわざ外で待ってる必要もなかったかも」
どうして涼しい駅構内ではなく、夏の熱気漂う公園で待っていたのか、自分でもよくわからない。
でもあえて理由をつけるとしたら、せっかくの夏なのに暑さを堪能しないのはもったいないだとか、そんなことを思ったからなのかもしれなかった。
着信の切れた携帯から目を離すと、なにやら女性の怒鳴り声が鼓膜に飛び込んでくる。
見ると噴水で遊んでいた兄弟の親御さんらしい人が、服を着たまま噴水に飛び込んで全身びしょ濡れになった子達を叱りつけているところだった。
「……でも、気持ちはちょっとわかるなぁ」
炎天下の中、子どもを叱りつけているお母さんは早くも汗だくになっていた。
やがて暑さからか怒るのをやめると、げんなりした様子でやんちゃっ子ふたりを連れて広場から去っていく。
こう暑いんじゃ、噴水にも飛び込みたくなるよね。
そんなことを思いながら、かぶってきた帽子でぱたぱたと自分をあおぐ。
いくら日陰とは言っても、気温そのものがすごく高い。一歩間違えれば熱中症になりかねない暑さだった。
「いたいた。ごめん葉月、お待たせー!」
自販機にジュースでも買いに行こうかな、と思ったところで耳慣れた彩ちゃんの声が聞こえた。
「あ、ううん。私の方が早く来過ぎちゃったから……」
そう言いながら声のした方を振り向くと、何やら知らないお姉さんが親しげに手を振っていた。
ツインテールにした髪に、タータンチェックのプリーツスカート。
それにこの暑いのに、熱をよく溜め込みそうな真っ黒なニーソックス。
少なくとも、私の知ってる『彩ちゃん』のイメージとは大きく異なる人だった。
「……どちらさまで?」
「なにそれ、ひどくない?」
「えっと……アイドルのコスプレかなにか?」
「んー、どうせならそこは『ラブパニ』のコスって言ってほしかったかなぁ」
彩ちゃんが最近はまってるアニメの名前だった。
「なんでコスプレ?」
「違う違う。ほら、ひふみって結構なお嬢様だって話じゃない」
「あー。そういえば、前にそんなこと言ってたような……?」
「そんなひふみの家って言ったらすっごい豪邸だとしても不思議じゃないでしょ。だからちゃんと《《正装》》してきたのよ」
「……正装?」
「正装」
何か問題でも? と言いたげな彩ちゃんに、何も言えなくなってしまった。
第2話 インドア姫の憂鬱。
話をさかのぼると昨日、つまり一学期最終日のこと。
体育館で校長先生の長い話を聞いて。
終業式のあと教室に戻って。
担任の先生から通知票と夏休み中の注意事項と、「先生にはなー、夏休みとかないんだぞー?」というありがたーいお言葉をいただいて。
最後に「それじゃ、みんな二学期に」という締めの言葉を受けて、教室中が一気に夏休みモードになった。
またたく間にごった返す教室内。
あちこちから「一緒に海に行かない?」とか「山でキャンプしようぜ!」とか「夏祭り楽しみだねー!」なんて会話が飛び交う、浮ついた雰囲気で満たされていた。
「ねー、葉月ぃ」
そんな中、眼鏡をかけたふたつ結びの子が、きちんと校則を守ったひざ下丈のスカートを揺らしながら私の席までやってきた。
「なぁに、彩ちゃん?」
……私の記憶が確かなら、学校での彩ちゃんは確かにそういう地味めな子だった。
「葉月は夏休み、なんか予定ある?」
「ううん、今年はお父さんもお母さんも仕事で忙しくてどこにも行けなさそう」
「じゃあさじゃあさ、夏休み中ヒマだったら一緒にどっか遊びに行かない?」
「おっけー、いいよ」
今思うとずいぶんと安請け合いしたかもしれない。
でも今年はお父さんもお母さんも仕事で忙しくて旅行の計画なんてなかったし、長い休みをどう過ごそうか考えあぐねてたのも事実だった。
「それじゃ、ひふみも誘ってみよっか」
そう言って彩ちゃん(地味モード)が後ろの席へと振り返る。
けれどそこには誰もおらず、机には鞄すらかかっていなかった。
「って、もういないし」
「あれ? さっきまでそこにいたのに……?」
そう言いながら、何気なく教室の後ろのドアに目を向ける。
すると黒曜石みたいにつややかなストレートヘアーをなびかせながら、見覚えのあるボストンバッグが廊下に出て行くのが見えた。
「ナナちゃん、もう帰ってるよ!?」
「ちょっ……待ちなさい、ひふみっ!」
彩ちゃんが怒気の混じった声で振り向くと、そのままの勢いで廊下へと走って行った。
私も負けじとそれについていく。
廊下の向こう。昇降口に通じる階段。
さっきの黒髪ロングの後ろ姿は、早くもそこまで辿り着いていた。
「ひふみっ、そこでストーップ!!」
彩ちゃんが周りからの注目も考えず、大声をあげる。
さすがにその声で気がついたのか、下り階段に足をかけようとしていたその子は、くるりとあたし達の方を振り向いた。
片手に持ったスマホに、両耳につけられたイヤホン。
肩からは紺色のスクールバッグがかけられていて、もう片方の手でパンパンになったボストンバッグを持っていた。
墨で染めたみたいに真っ黒な髪はどこか重苦しく、ツンとした吊り目はどこか近寄りがたい雰囲気を漂わせている。
「なに?」
少しキツさと拒絶を感じさせる、人を寄せ付けないような突き放した声色。
そして知らない人からしたら、関わりづらそうな子だって印象を受けそうな、ほとんど動きのない表情。
七嶋ひふみ。通称ナナちゃんは、そんなどこか孤高な空気を纏った子だった。
「ね、ひふみも一緒に夏休みどこか行かない?」
そんなナナちゃんの態度に少しも気後れしない彩ちゃんが、両腕でがっつりと両肩を掴んだままそう提案する。
きっと逃げられないように確保してるんだろう。
「行かない」
それに対するナナちゃんの反応は見た目の印象通り、すごく冷たく感じられる。
でもナナちゃんの言葉足らずなところは私もすっかり慣れたから、ちっとも怖くはなかった。
「そんなこと言わないで、一緒に海とかお祭りとか行こうよ」
だから私も彩ちゃんに続いて説得に当たることにする。
ナナちゃんはこっちをちらりと向いたけど、私と視線が合うと困ったようにさっと目を逸らしてしまった。
「……はーちゃんとあやちゃんの、ふたりで行けばいい」
そっぽを向いたまま、私たちをちゃんづけで呼んでくれた。
ナナちゃんって見た目はちょっと怖いけど、実は中身はこういう子だったりする。
「でもせっかくだし、どうせなら三人で遊びたいな」
「そうそう、なにげに高校入ってから初めての長休みじゃん。いっそあたし達だけで旅行とか行ってみるのもアリじゃない?」
私の加勢に勢いづいたのか、彩ちゃんがまくし立てるように続けた。
「そうだ、それならお盆ごろに有明あたりとかいいんじゃない? そうね、さすがにもうメジャーどころのホテルは埋まっちゃってるだろうから、今からなら飛び込みで民宿とか探してみるのもいいかもしれないわね。そういうのも面白そうじゃない?」
「なんでそんなに乗り気なの?」
「ん? 別に他意はないよ?」
妙に具体的な旅行プランを提示する彩ちゃんに、思わず聞き返してしまった。
すると自分の意見抜きで勝手に話が進められてると思ったのか、ナナちゃんが慌ててそれに口を挟んでくる。
「ちょ、ちょっと待って? わたし、まだ行くって言ってない」
「あ、いや、有明は冗談としてもね……」
「彩ちゃん、冗談だったんだ?」
「いや、半分ぐらいは願望混じってたけど。まぁそれはそれとしてさ、旅行じゃなくてもいいからひふみも一緒にどっか遊びに行こうよ」
「…………」
そう言って再び遊びに誘おうとする彩ちゃんだったけど、ナナちゃんの反応はどうにも芳しくはなかった。
「なにか用事でもあるの?」
その様子から察して、なんとなく聞いてみる。
「あ、あのね……っ!」
私の言葉を受けて、ようやく助け船が出たとばかりに食いついてくるナナちゃん。
が、口をぱくぱくさせて何かを伝えようとするも、上手く言葉が出てこないようで。
やがて力なくうつむくと、どうにか聞こえるくらいのちいさな声で「ごめんね」と呟いてから、私たちに向けて高らかに宣言した。
「わたしはね」
その目には一切の迷いもなく、はっきりとした意志が込められていて。
なにか重大な告知が行われる気配に、思わず背筋をピンと伸ばす。
「夏休み中、おうちから一歩も出たくないの」
が、その内容はひざから崩れ落ちるほどのインドア宣言だったのでした。
第3話 炎天下のバスに揺られて。
駅前からのバスに乗り、約十分ほど。
私たちは目的地すぐ近くのバス停で降りた。
結局昨日、ナナちゃんを説得することはできなかった。
とはいえしつこく誘い続けた私たちを見かねたのか、最後には少しの妥協点を見せてくれて。
『じゃあ明日、わたしのうちに来て。今日はもう帰りたいの』
ようやく引き出せたその言葉を残して、引き留める彩ちゃんの声をそのままに、ナナちゃんはそそくさと帰ってしまった。
その結果、私たちはこうして冷房の効いた車内から、夏の日差しの襲いかかる炎天下に身を投じることになっている。
排気ガスをまき散らしながら去って行くバスを見送って、ぐるりと辺りを見回してみる。
バス停の看板はすっかりサビついていて、文字を読むのがやっとの状態。
焼けたアスファルトの上には、暑さでひからびたらしいミミズが点々と。
道路際のガードレールには謎の三角形の金属片がいくつも張り付いていて、白く塗られていたはずのそれは陽に焼けて少しくすんだ色をしていた。
その向こうに広がるのは、一面の田んぼ。
収穫の秋を前にすくすくと実りをつけつつある稲穂たちが、太陽の光を浴びてまぶしく輝いている。
その反対側に目を向けると鬱蒼とした山林が広がっていて、セミやカエルや名前も知らないたくさんの虫の声がBGMとして流れていた。
「ド田舎ね……」
歯に衣着せず、彩ちゃんがぼそりと呟いた。
「ねぇ葉月、本当にここであってるの?」
「昨日教えてもらった住所によると、あってるはずなんだけど……」
言いながら停留所の古びたベンチに座り、鞄からスマホを取りだす。
彩ちゃんも私の隣に勢いよく腰掛けたけど、べきっという嫌な音がして慌ててベンチから立ち上がっていた。
「なーんかイメージと違うわね……。ひふみの家だから、もっと高級住宅街にあるようなのを想像してたんだけどなー?」
ごまかすようにヒビの入ったベンチから話を逸らそうとする。
とはいえ、確かに学校では一緒にいることが多いけど、ナナちゃんの家には行ったことがないからどういう場所なのか全然想像が付かなかった。
とりあえず彩ちゃんは置いといて、スマホの音声案内アプリを立ち上げた。
ご用件はなんですか? という機械音声に次いで、そのままスマホに話しかける。
「七嶋ひふみさんの家に行きたいです」
受け取ったナナちゃんちの住所は既にアドレス帳に登録済みだから、この言い方なら正確に認識してくれる。
少しの検索のあと、画面に私たちがいる場所とナナちゃんちへのルートが表示された。
「よかった……ここからそんなに歩かないみたいだよ」
「毎度思うけど、葉月はよくそんな簡単に位置情報を提供できるわよね……」
「彩ちゃんが気にしすぎだと思うけどなぁ」
言いながら、表示された地図を少し指で動かしてみる。
すると、画面に水色の部分が多く表示されるようになった。
「あ」
「ん、どした?」
「なんか地図によると、ここから海がすぐ近くみたい」
画面から目を離し、再び辺りを見回してみるも海の気配は感じられない。
漂う空気はどこまでも夏の匂いで、青々とした草木や稲穂のむせるような精気しか私にはかぎ取ることはできなかった。
「そう言われてみると、ちょっと潮の香りがするかもしれないわね」
「え、潮の香りする?」
「あー、うん。なんとなくね」
彩ちゃんは鼻がきくのか、私には感じ取れない海辺の存在を感じ取ったみたいだった。
もっとも彩ちゃんはたまに思い込みが激しいところがあるから、私が海が近いと言ったのを受けてそう思い込んだだけなのかも知れないけど。
「ま、ひふみんちが近いならそれに越したことはないわ。こんなあっついところにいたら蒸し焼きになりそうだし、早く行きましょ」
そう言って彩ちゃんは、停留所のひさしから一歩踏み出す。
日なたに出るとすぐに直射日光にさらされて、彩ちゃんは夏の日差しにそのまま貫かれることになった。
「あっつっ!!」
慌ててひさしの下に戻ってきた。
「この炎天下なのに、帽子も日傘も持ってきてないからだよ……」
「えー。だってまさか、こんなところだなんて想像もしてなかったもん」
「とりあえず折りたたみの日傘あるけど、使う?」
「うー、使う……」
げんなりした様子でそう答える彩ちゃん。
鞄から傘を取りだしながら、そういえばこの傘を買ってから一度も使ってないことに気づく。
「あ……えと、なんだったら私の帽子を貸してもいいけど」
そう思ったらなんだか初めてを取られるのが惜しい気がして、思わずそんなことを言ってしまう。
口にしてから「私も心が狭いな」と少し苦い気持ちが広がった。
「んー……」
そんな私の胸中を知ってか知らずか、差し出された傘を見ながら彩ちゃんは何かを熟考する。
内心を見透かされてるような気がして、少しどきどきした。
「やっぱり日傘貸してもらっていい? 葉月のその帽子はあんたによく似合ってるし、そのままかぶってなさいな」
「そ、そう……」
内心のモヤモヤを悟られないように、そのまま折りたたみ傘を手渡した。
「なんだか買ったばっかりみたいなのに、ごめんね葉月」
「え……!? な、なんでそんなことわかったの?」
「いや、だってここに値段付いたままだもの」
彩ちゃんの指さしたところには、『大特価、1,980円!!』という値札がぶら下がったままだった。
第4話 真夏の昼のメイドさん。
バス停から歩くことしばし。
私たちはナビに従って、灼熱の道路を歩く。
照りつける陽射しがアスファルトを熱して、遠くに陽炎が立っていた。
道路の真ん中を歩いていてもなんの問題もなさそうなほど、車や人の気配がない。
頭上を見上げれば、抜けるような青空。
そして元気の良すぎる太陽。
さっき見た入道雲はいつの間にか消えていて、雨の降る気配も感じられない。
夏の日差しで影の濃淡がくっきりとした雲が、青いキャンバスに子どもが適当に白い絵の具を塗りたくったみたいにいくつも浮かんでいた。
「あつい~! しぬ~! ジュースのみたーい、アイスたべたーいっ!!」
隣を歩く彩ちゃんは貸した日傘を差して、さっきから暑い暑いと文句ばかり繰り返している。
例の値札については恥ずかしいから取ってと頼んだけど、「名前代わりになってていいじゃん」と言って外してくれなかった。
ある意味これは、彩ちゃんなりの意地悪なのかもしれない。
「もうすぐだから、我慢してね」
そんな子どもみたいにだだをこねる彩ちゃんをなだめながら、私たちは先を急ぐ。
彩ちゃんみたいに騒ぐ気にはなれないけど、一刻も早くこの熱さから解放されたいのは事実だった。
やがて、目的の場所へとたどり着く。
「ここなの?」
「住所だと、確かにここなんだけど……」
木漏れ日が差す、なだらかなスロープ。
石畳の道は坂の上へと通じていて、両端には背の高い木立が並んでいる。
そしてその入り口には高級ホテルみたいに大きな看板が立っていて、シックな字体で『NANASHIMA』と彫られていた。
「……観光ホテルか何かと間違えたんじゃない?」
「でも、住所はここになってるよ?」
ナビははっきりと坂の上が目的地だと示していた。
私たちは思わず顔を見合わせる。
「ひふみってホテル住まいなの?」
「そういえば、両親とは離れて暮らしてるとか言ってた……かも?」
ずっと前、今の学校に通うために実家を離れて一人暮らしをしてる、とか言ってたのを思い出した。
「なるほど……さすがはお嬢様ね。賃貸なんかじゃなくて、ホテルの一室を借り切ってるわけか」
「この看板からすると、ナナちゃんの親戚の人がやってるところだったりするのかな?」
「きっとそういうことね。一人暮らしをするからって親戚の経営してるホテルの一室を借りてるのよ、たぶん」
どうにか納得できる答えが見つかって、私たちは頷いて坂を登り始める。
緩やかな坂ではあったけど車で来ることを前提にしてるのか、歩きだとちょっと大変な勾配だった。
やがて坂の上に、立派な建造物が見えてくる。
ぶわっと視界が開け、まず目に入るのは紅色。
入口の柱は神社の鳥居のような赤で染められていて、その上には瓦屋根。
坂の下から続いていた石畳は、そのまま玄関へと続いていて、その両端には石灯篭がどっしりと身を据えている。
どちらかというとホテルというよりも、旅館といった方がしっくりと来る和風な佇まいだった。
「……あれ?」
「ん、どした?」
「なんか、少し海の匂いがしたような……」
「え、そう?」
建物に目を向けていたけれど、鼻腔にわずかに潮の香りが感じられた。
改めて地図に目をやると、この旅館の裏側には海が広がっているようだった。
「あら?」
そこに、知らない人の声がかかる。
「人違いでしたら申し訳ありません。小波さまと一条さまでしょうか?」
近づいてきたのはナナちゃんじゃなかった。
見た目だけじゃよくわからないけど、たぶん二十歳は越えているだろう、大人の雰囲気を漂わせた女性。
外見からはナナちゃんと似てるようには見えず、親戚の方なのかお手伝いさんなのか、今ひとつ判断が付かなかった。
でも、それ以上に気になって仕方ないところがあって。
「……こすぷれ、ですか?」
「いえ、本物ですよ?」
もっと他に聞くことはあったはずなのに、真っ先にそれを聞いてしまった私はバカなのかもしれない。
というのも、お姉さんの身につけているのは黒いロングスカートにフリルの付いたエプロン、さらに頭にホワイトブリム。
どこからどう見ても、秋葉原によくいるというメイドさんにしか見えなかった。
「えっと、もしかしてメイド喫茶とまちがえた……?」
「いえ、こちらであってますよ。繰り返しになりますが、小波葉月さまと一条彩花さまでしょうか?」
「は、はい……」
そう答えると、お姉さんはにっこりと笑顔を浮かべて深々と頭を下げる。
ポニーテールに結んだ髪が、その動きにあわせてさらりと揺れた。
「遠いところ、ようこそおいでくださいました。ひふみさまがお待ちです。どうぞ中へ」
そう言って、旅館の入口へと案内される。
さすがにこの状況に戸惑いを隠せずに、彩ちゃんと顔を見合わせた。
「すごいわね……」
「うん……ナナちゃんが普段どういう生活してるのか、よくわからなくなってきたよ」
「本当、なんなのかしら……。あの人この暑いのに、長袖メイド服で汗ひとつかいてなかったわよ?」
「そこなの?」
とりあえずメイドのお姉さんの導きに従い、館内に入る。
中はひんやりとした冷房が効いていて、ここに来るまでの暑さをぬぐい去ってくれた。
「土足のままでいいんですか?」
「ええ、そのままどうぞ」
靴を脱ぐ場所が見当たらなかったから、一応訊いてみる。
エントランスホールは靴のまま立ち入るのも拒まれるような、立派なカーペットが敷き詰められていた。
フロントには人の姿はなく、営業してるのかどうかはわからない。
けれど辺りはゴミひとつ落ちておらず、丁寧に掃除されているのが一目でわかった。
見上げると天井は高く、上階まで吹き抜けになっていた。
ちょうど二階部分に当たるところに、落下防止の手すりと分厚いガラスが付いているのが目に入る。
サマーシーズンの今なら宿泊客でいっぱいになっていてもおかしくない、お洒落な内装をしていた。
「それでは、ご案内しますね」
物珍しくてきょろきょろしていた私は、お姉さんのその言葉でハッと我に返った。
そのまま奥の間へと案内される。
途中の廊下に飾られている調度品の数々も、価値のわからない私から見ても高級そうなものばかり。
なんとなく、居心地の悪さを覚えた。
「こちらです」
「え、ここ?」
そうして案内された部屋は、入口からするとちょうど建物の端にあたる部分。
思わず彩ちゃんが疑問の声を出すのもわかるくらい、それまで通って来た部屋の数々からするとずいぶんと小さめな部屋だった。
「はい。こちらがひふみさまのお部屋になります」
「こんなに部屋数があるんだから、わざわざこんな部屋で暮らさなくてもいいのに」
「でも、ナナちゃんらしいね」
けれどどういうわけか、そこがナナちゃんの部屋だと聞いて安心している私がいた。
私の知ってるナナちゃんが選ぶとしたら、きっと大広間やスイートルームじゃなくて、こういうこぢんまりとした部屋だろうなという想いがあったから。
メイドのお姉さんがコンコン、とドアをノックする。
「ひふみさま、ご友人のお二方をお連れしました」
そう呼びかけるも、中から返事はない。
「もしかすると、お昼寝なさってるのかもしれませんね」
しばらくの無言の後、お姉さんは苦笑い気味にそう告げた。
「よろしければ、中でお待ちいただけますか?」
「え、いいんですか?」
「ひふみさまから、ご友人がいらっしゃった際は部屋で待っていてほしいと言付けられておりますので」
そう言って、ドアをがちゃりと開く。
中は壁から床から一面の木製で、ほんのかすかに生木の香りがした。
「三和土がありますので、履き物を脱いでお上がりくださいね」
たたきとか言われてもよくわからなかったけど、とりあえず言われたとおりに靴を脱ぐ。
ちいさめな客室とはいえ、中はいくつかの部屋に分かれているようだった。
「あら」
案内された部屋はどうやらリビングみたいだった。
窓からは外の景色が見えて、そこから遠くに少しだけ青い水平線が広がっているのが目に入る。
そして床には高級そうなソファが置かれていて、その一角でナナちゃんが座ったまま居眠りをしていた。
学校での制服姿しか見たことのないナナちゃんは、白いTシャツにふんわりとしたキュロットというリラックスした格好をしていた。
靴下も穿いておらず、両足とも裸足のまま。
学校では目を惹くキリッとした黒髪も、寝癖がついててちょっとだらしなく感じてしまう。
ただそれ以上に、Tシャツに達筆な文字で書かれた『ネコと和解せよ』という文句にどうしても目が行ってしまった。
「ひふみさま、ご友人がいらっしゃいましたよ」
「……ふぇ?」
お姉さんがナナちゃんに声をかけると、ナナちゃんは寝ぼけ眼で目を覚ました。
「なーん」
そのひざの上では、ちいさな茶トラ柄の猫が一匹丸くなっていて。
「あ、きた」
そして学校ではクールビューティーな雰囲気を漂わせているナナちゃんの頭に、なぜか猫耳のついたカチューシャが付けられていた。
第5話 にゃんこさんとねこみみの事情。
「ひふみ、なにそれ?」
「ねこ」
「いやそっちじゃなくて、頭につけてる方」
「ねこみみ」
私より先に彩ちゃんが突っ込んでいた。
でもナナちゃんはこれっぽっちも気にしてないようで、淡々と事実を告げるだけでまともな会話は成立していなかった。
「とりあえず、座る?」
促されて、私たちはナナちゃんの向かい側のソファに座る。
座ったとたん、全体重がふっくらとしたクッションに飲み込まれて、危うく意識が飛びそうになるくらい気持ちがよかった。
このソファ、いい仕事してる。
「それで、ナナちゃん。その子は?」
「ねこみみ」
「いやそっちじゃなくて、ひざの上のにゃんこさんの方」
「にゃんこさんって、葉月あんたいくつよ……」
とりあえず色々と聞きたいことはあったけど、目の前の可愛い生き物が気になってしょうがなくて、まずはそこから切り出してみた。
「ナナちゃんのにゃんこさん?」
「うん。とっても可愛いよ」
「すごく綺麗な毛並みしてるね。なんて名前なの?」
「ポチ」
一瞬、言葉につまった。
「にゃんこさんだよね?」
「うん」
「にゃんこさんなのに、ポチ?」
「正確に言うと、ぽち」
いや、ひらがなとカタカナの違いとか口頭じゃわかんないから。
「この前、拾ったの」
急にナナちゃんの声のトーンが下がった。
「まだ子猫なのにすごく弱ってて。どうしようかと思ったけど、とりあえず家に連れて帰ってきたの。獣医師の人が来てくれて一命は取り留めたけど、ミルクもごはんも何も食べてくれなくて。このままじゃ、衰弱死するのも時間の問題だって言われて……」
俯きながら紡がれる言葉からは、その時のナナちゃんの焦りと困惑、そして哀しみが痛いほど伝わってきた。
「それで、これを試してみたの」
そう言いながら、頭の猫耳カチューシャをさわさわする。
「これをつけてれば、同じ猫だと勘違いしてくれるかなって思って。同じ猫からだったら、ごはんもちゃんと食べてくれるかな、って」
「…………」
彩ちゃんがすっごく何か言いたげな顔でナナちゃんを見てたけど、あえて気づかないふりをしておいた。
「そしたら、食べてくれたの」
「食べたの!?」
「ミルクも飲んでくれて、その後どんどん体力をつけて元気になっていったんだよ」
彩ちゃんの叫びも聞こえないほどに、ナナちゃんの語りは静かに熱く続いた。
「そしたらすっかり懐かれちゃって。お母さんだと思ってくれたのかな? わたしの側から離れようとしなくなっちゃった」
そう言いながら、ひざの上のぽちちゃんをなでなでする。
その手つきはどこまでも優しく、母猫が子猫のグルーミングをする姿を思わせた。
「でもわたしは学校があったし、いつもぽちと一緒に居られるわけじゃなかったから」
「そういえば、一学期の終わりごろから急に早々と帰るようになってたよね」
「うん。ぽちが心配だったから」
言ってくれれば良かったのにとふと思ったけど、そういうことをあまり口にしないのもナナちゃんという子の特徴だった。
「学校に行ってる間は雅さんにお世話してもらってたけど、わたしがいないと落ち着かない様子でみゃーみゃー鳴いてるんだって。だからわたし、夏休みの間だけでもこの子と一緒にいてあげたいの」
「みやびさん?」
「大変失礼しました。そういえば、自己紹介がまだでした」
振り向くと、さっきのメイドのお姉さんがトレイにグラスを三つ乗せてやってきていた。
それをソファの間のテーブルにコースター付きで乗せてから、深々と頭を下げる。
「話の途中に申し訳ありません。私、四谷雅と申します。ひふみさまの生活の補助や当館の管理等、全般を任されております。小波さまと一条さま、今後ともよろしくお願いいたします」
「は、はい……」
ずっと年上の人にここまでかしこまられると、かえってこっちが恐縮してしまう。
「雅さん、しっつもーん」
「はい、一条さまなんでしょうか?」
そんな私と違い、彩ちゃんは興味津々で雅さんに質問を投げかけていた。
「雅さんって、メイド喫茶とかで働いてたことあるんですか?」
「ありますよ。ずっと若い頃に少しだけですが」
「じゃあ、そのクラシカルメイド服はそのころのお下がりなんですか? コスプレ用のスカート丈の短いものじゃないですし、布の素材もすごく上質なものを使われてるように見えるんですけど」
「こちらは七嶋家にお仕えする際に支給されたもので、お下がりではありません」
「ってことは、ひふみの実家は雅さんみたいな人がいっぱいのメイド天国になってるってこと……?」
「いえ、他の使用人の方々はごく普通の服装をなされてます。私は特注で作っていただいたものを着ているだけです」
「特注……? なんで特注?」
「おそらく私の経歴を見た採用者の方が、思うところあって気を利かせていただいたのではないかと」
ガンガン攻める彩ちゃんに対し、気後れすることなく答えていく雅さんのその姿は大人の余裕を感じさせるものがあった。
「で、そんなわけだから夏休み中はぽちとおうちにいるつもり」
彩ちゃんと雅さんのやり取りをよそに、ナナちゃんは私に例のインドア宣言の真相を伝えてくれていた。
事情を聞いた私は、どうしようかと少し頭を悩ませてしまう。
「ええと……。とりあえず気になったんだけど、つまり家に居る間はずっとその猫耳をつけたままなの?」
こくん、と頷かれた。
「夏休み中はぽちのためにもずっとつけてるつもり」
「……恥ずかしくない?」
「恥ずかしいよ。だからお外に出たくないの」
……理由付けがここまでしっかりしてると、ますます口を挟みにくくなってしまった。
「それにしても……」
改めて室内を見回して、思う。
アニメのコスプレみたいな格好の彩ちゃんに、猫耳をつけたナナちゃん。さらにメイドの雅さん。
なんだか私だけ普通の服装で来たような気がして、なんとなく場違い感を覚えた。
「みんなコスプレみたいな格好してて、私だけすっごく浮いてる気がするよ……」
「葉月、なに言ってるの?」
思ったことをそのまま口にしてみると、彩ちゃんから驚いたような返答が返ってきた。
「ある意味あんたが一番この中でコスプレっぽい格好してるじゃないの」
「え?」
「そうですね……そのようなお洋服がお似合いになるのは、素直にうらやましく思います」
「は、はい?」
「はーちゃん、もしかして気づいてない?」
三人に一気にまくし立てられ、私は軽く混乱する。
「ど、どこかおかしかった? 今日の私の服装……」
「いや、っていうかさぁ」
彩ちゃんが私をじいっと見つめながら、深いため息をついた。
「夏だからって白ワンピースに麦わら帽子なんてベタベタな格好、いくらあたしでもできそうにないわよ」
彩ちゃんの指摘にうんうん、とナナちゃんにまで頷かれた。
思ってもみなかった言葉に、ノースリーブの白ワンピースを着た自分をまじまじと見つめてしまう。
私は手に持った麦わら帽子を胸に抱きながら、少し戸惑いつつ答えた。
「一応これでも、正装のつもりだったんだけど……」
「正装?」
「正装……」
なんだか前にもどこかで見たようなやり取りを、再び繰り返すことになった。
第6話 七嶋家の一族。
「話を戻すと、ひふみは夏休み中外出するつもりはないってこと?」
雅さんの持ってきてくれた麦茶をいただきながら、また話を戻した。
彩ちゃんは喉が渇いていたのか一気に飲み干すと、せっかく用意してくれたコースターも使わずにテーブルの上にそのまま冷えたグラスを置いている。
私はこういうのは見てて気になって仕方なくて、結露してテーブルが濡れる前に空になったグラスをこっそりとコースターの上に戻しておいた。
「一条さま、おかわりお持ちしましょうか?」
「あ、いただきます」
そんな彩ちゃんの様子を見て、雅さんが気を利かせて麦茶のおかわりを持ってきてくれていた。
複雑な細工の彫られたガラス製のピッチャーから薄茶色の液体がグラスに注がれ、ステンレス製の容器からトングで氷をつまみ、その中にゆっくりと落とし込む。
氷とグラスがぶつかってカラン、と涼しげな音を奏でた。
「ぽちと一緒にいたいのもあるけど」
ひざの上のぽちちゃんのアゴの下をこしょこしょしながら、ナナちゃんが言葉を紡ぐ。
「やっぱりわたし、おうちが好きだから」
「ま、これだけの旅館なら外出しなくても不便はなさそうよね。雅さんもいるし」
雅さんから受け取った麦茶を一気にあおり、早くも次のおかわりを要求しながら彩ちゃんが同意した。
「それに、窓から海も見えるもんね……。いいなぁ」
窓の外に目を移しながら、思っていたことをぼんやりと口にする。
ガラス越しに見える景色は夏の日差しと青々とした木々、そしてわずかな蒼を写していた。
そして外の世界の暑さや喧噪は、部屋の中からは微塵も感じられない。
こんな景色が冷房の効いた自室から見られるんだったら、わざわざ外出しようなんて思わないのもわかるような気がする。
「ひふみさまは昨日からずっと、このお部屋から出てませんものね?」
そんな私の言葉を受けて、雅さんが眉を八の字にしながらナナちゃんに問いかける。
ナナちゃんは雅さんの気持ちを知ってか知らずか、黙ってこくんと頷いた。
「え、部屋そのものから?」
「ここトイレもお風呂も冷蔵庫もあるし、雅さんが洗濯したお洋服やご飯を持ってきてくれるから、部屋から出る必要がないの」
「なにその、うらやましい……」
彩ちゃんはどこか妬ましさすら感じさせる声色でそう言うも、私は逆にちょっと心配になってしまう。
「雅さん、さすがにこれはナナちゃんをダメにしちゃうような気がするんですけど……」
「そう思うのですが……私はあくまでひふみさまの生活補助の権限しか与えられておりませんし、ひふみさまのご意思を尊重するしかできないんです」
権限とかいう言葉が出てきて、なんだか難しい話になりそうな気がした。
「雅さんはナナちゃんの教育係じゃないんですか?」
「いえ、そんな大層なものではありません。私はひふみさまがこちらで暮らされることが決まった際に、お世話係としてご一緒させていただいただけの身ですので」
「そういえば気になってたんだけど、ここってひふみの親戚の旅館かなにかなの?」
私も気になっていたことを、彩ちゃんがナナちゃんに尋ねた。
フロントには誰も居なかったし、館内は私たち以外に人の居る気配がない。
まさかとは思うけど、ナナちゃんがこの旅館ごと借りきってるってことはない……よね?
「ここは七嶋系列会社の保養所だったんですよ」
その疑問に答えたのは雅さんだった。
「保養所ってなんですか?」
「簡単に言いますと、七嶋グループの社員の方々がレジャーや研修等で使われる宿泊施設です。交通の便の悪さから数年前に閉館になってしまいましたが、この度ひふみさまがこちらの学校に通われるとのことで補修を行い、現在はひふみさまのお住まいとして利用されているんです」
「ななしまぐるーぷ……」
ナナちゃんから少しは話を聞いていたものの、どうもナナちゃんは筋金入りのお嬢様と見て間違いないみたいだった。
「とはいえひふみさまがお一人で暮らされると聞いて、私は心配で仕方なくなってしまって……。かなりの無理を言って、同行する許可を出していただいたんです」
言いながら、雅さんはナナちゃんを慈しむような目でじっと見つめる。
その視線を受けてもナナちゃんはいつもの無表情だったけど、雅さんを見つめ返す表情はとても和らいでいるように思えて。
そのふたりの間に漂う優しい空気から、主従関係以上の繋がりが感じられた気がした。
「雅さんは、ナナちゃんと長いお付き合いなんですか?」
「ええ。ひふみさまがうーんとちいさなころからご一緒でしたから。失礼に当たるのを承知で言いますと、ひふみさまは私にとって、むす……」
と、そこで突然言葉を切ると、雅さんは軽くこほんと咳払いをした。
「妹みたいなものですからね」
……今、絶対「娘みたいなもの」って言おうとしてたよね?
ちょっとだけ雅さんの年齢が気になったけど、明らかに地雷っぽかったから触れないことにした。
「うん。わたしも雅さんのことはお姉ちゃんみたいに思ってる。幼稚園のころからずっとお世話になってるし」
「えーと、今ひふみが高一でしょ。幼稚園からのつきあいで、本物のメイドになる前にメイド喫茶で働ける年齢だったってことは……?」
「彩ちゃん、ストップ!!」
指折り数えながら、積極的に地雷を踏みに行こうとする彩ちゃんを慌てて止める。
雅さんの顔色をうかがってみたけど、にっこり笑顔が崩れることはなく、それが逆に怖かった。
「そ、そうだ、海っ! 海がみたいな、私っ」
話を逸らすために、半ば強引に提案してみた。
「ここに来るまでの間ずっと思ってたの。海が近くにあるなら見ておきたいなって」
「それでしたら、当館上階に全面ガラス張りのラウンジがありますよ」
私の内心を知ってか知らずか、雅さんが穏やかな声で告げる。
「海側に向けたバルコニーがありますので、そこからでしたら海を望む景色をお楽しみいただけるかと思います」
「わぁ、素敵です……!」
「んー、そうね。せっかくだし海くらい見ておいてもいいかな」
苦し紛れに言ってみたことだったけど、雅さんの助言で実にあっさりと海を見ることができそうだった。
「それでは、よろしければご案内します。エレベーターは停止中なので、電源が入るまで少しお待ちいただくことになりますが……」
「ええ、待ってます」
私の言葉ににこりと頷いて、雅さんは部屋から出て行った。
その背中を見送りながら、この場の最大権力者から何の承諾も得ていないことに気づく。
「えと……ナナちゃんも行く、よね?」
さすがに館内だし、外に出たくないとは言い出さないとは思いつつも、一応訊いてみる。
すると少しうーんと考え込むようにして、「バルコニーに出なければセーフかな」とだけ告げた。
「……なんでバルコニーはアウトなの?」
「一応これでも、すっごく妥協したんだよ?」
ナナちゃんはひざの上からぽちちゃんを降ろし、ソファからすっくと立ち上がる。
ぽちちゃんは自由の身になったものの、ナナちゃんの足下にすりすりしたまま離れようとしなかった。
「ぽちも一緒に連れて行きたいし、ぽちが怖がるところには連れて行きたくない。それに……」
「それに?」
そのまま窓の外に視線を移して、ぼそりと呟いた。
「言っちゃうと、この部屋の外は廊下も含めて全部お外になるわけだから」
ナナちゃんの生活圏内は、想像以上に狭いみたいだった。
第7話 その海は手が届きそうなほどに遠くて。
体が少し浮くような感覚の後、軽快な音を立てて扉が開いた。
まず感じたのは鼻先をくすぐる、今まで嗅いだことのない大人な香水の匂い。
次に目に飛び込んできたのは、窓越しに広がる濃淡様々なたくさんの蒼。
雅さんの言っていたとおり、高い天井ぎりぎりにまではめ込まれたガラス張りの向こうに、空と海の青が水平線で交わっているのが見えた。
「海だー!!」
それを見て、思わず私ひとりだけ先にエレベーターから飛び出してしまった。
革張りソファや漫画でしか見たことのないような背の低いテーブル、それに間接照明の森をくぐり抜ける。
そして無人のカウンターを素通りし、そのまま窓に張り付いた。
窓はぴかぴかに磨かれていて、思わずさわってしまった私の指紋がべったりくっつくほど透明度が高い。
水平線の向こうからやってきた大小様々な波が、無人の砂浜に打ち寄せる様子がはっきりと見えた。
海からの使者が地上を覆いつくそうとするかのように、ゆっくりと浜辺に広がっていく白波は沿岸を越えることも出来ないまま、名残惜しそうに引き返していく。
けれど諦めることなく波は浜辺に広がり続け、燦々とした陽光に照らされる砂浜を決して乾かせまいと、潮の浸食は止むことなくひたすら続いていた。
その光景はきっと何万年も前から変わることはなく、まるでいつか地上に上がることを望んでいるかのようで。
波音こそ聞こえなかったけど、私は紛れもなく海を見ていた。
「子どもか!」
そんなはしゃぐ私の様子を見て、彩ちゃんが呆れたように叫んだ。
「はーちゃん、そんなに海が好きだったんだ……」
ぽちちゃんを胸に抱いたままのナナちゃんにまで、そんなことを言われてしまう。
その隣で雅さんにまで苦笑されているのに気づいて、今さら顔が熱くなった。
「だ、だって、海なんて見るの久々だったから……」
言いながら、最後に海を見たのはいつだったっけと考えた。
確かまだお父さんが生きてたころ、家族旅行で行ったのが最後に見た海だったような気がする。
つまり、私が小学生のころ以来。
そりゃあはしゃぎたくなるのも無理はないよね、と自分で自分を納得させた。
「にしても、こんなところがあるなんて驚きね」
彩ちゃんが辺りを見回しながら、感心したように言う。
「外観からすると和風旅館っぽかったから、こういう大人な空間があるなんて思わなかったわ」
「元保養所ですので、こういった場も必要だったんです。もっとも今では使われておりませんが」
改めて室内を見てみると、そこは私みたいな一般庶民が立ち入っていいような空間じゃなかった。
何もかもが高級感に溢れていて、天井から吊されたシャンデリアは明かりも付いていないのに宝石のように輝いている。
きっと会社の社長さん達がお酒を飲んだり女の人に囲まれたりと、テレビでしか観たことがないようなことが行われていたんだろう。
「使われてないにしては、ずいぶんと綺麗になってますよね?」
「もちろん、毎日のお掃除は欠かしてませんから」
「あれ、でもエレベーターは止まってたはずじゃ……?」
「ええ。しかし階段がありますから。歩くのは健康にいいんですよ?」
階数表示をしっかり見てたわけじゃないけど、結構長い間エレベーターに乗っていたような気がする。
それだけの階数を毎日上り下りしてる雅さんの体力を想像したら、軽くぞっとしてしまった。
「それよりもみなさま、何かお飲みになりますか? カウンターの冷蔵庫にあるものでよろしければ、お飲み物をご用意します」
「え、いいんですか?」
「もちろんです。しかし私も冷蔵庫の中まではしっかり覚えておりませんし、確認してからになってしまいますが……。ちょっと席を外させていただきますね」
そう言って、雅さんは「前に在庫の補充をしたのはいつでしたっけ……」とか呟きながらバーカウンターの奥へと消える。
その姿を見送ってから、彩ちゃんは近くにあったソファにどっかりと腰をおろした。
「はぁ~。いい……いいわ。なんか一気にお金持ちになった気分ね」
ソファの背もたれに両腕を乗せて、足を組みながら悦に浸る彩ちゃんはなかなか様になっていた。
性格こそあんなだけどスタイルもいいし、足がすらっとしてるから見栄えだけなら確かにいいところのお嬢様に見えなくもない。
「ぽち、いい? ここのソファで爪研ぎとかしちゃダメだからね」
「にゃうん」
そして本物のお嬢様と言えば、彩ちゃんの向かい側に座って子猫相手に注意事項を説明していた。
ふたりを見比べると、どちらかといえば彩ちゃんの方がお嬢様っぽく見える。
ナナちゃんもそれなりに背丈があるし、それっぽくすれば十分お嬢様に見えそうなんだけどね。
「ほら、葉月もこっちに来てリッチな気分になりなさい」
「本当にリッチな人は、自分でリッチとか言わないと思うなぁ……」
そう言いつつ、ふんぞり返っている彩ちゃんの隣にちょこんと腰掛ける。
私はふたりと比べるとずっと背が低いから、彩ちゃんのまねをしても大人ぶってる子どもにしか見えなさそうな気がして、あえて何もしなかった。
「お嬢様方、お待たせしました」
そこに雅さんが戻ってくる。
私たちの様子を見て察したところがあるのか、少し茶目っ気を込めてお嬢様と呼んでくれたのが少し嬉しい。
「アイスティーしかありませんでしたが、よろしいでしょうか?」
「え……アイスティー?」
「はい」
嬉々として真っ先にドリンクを受け取ろうとした彩ちゃんが、それを聞いてぴたりと手を止めた。
私とナナちゃんは気にせずに、雅さんからストローの刺さったグラスを受け取る。
「うまー!」
「ん、おいしい」
一口すすっただけで口の中に広がる香りに思わず叫んだ。
アイスティーと言っても市販のものとは違い、レモン果汁とミントの葉を入れた一手間加えたものだった。
すっぱいレモンとドライミントの爽やかな香りが一層清涼感を強く感じさせてくれる気がする。
彩ちゃんも一応受け取ったものの、何か思うところがあるのかストローに口をつけようとはしなかった。
「そうだ、バルコニー!」
急に思い出して、雅さんに叫ぶように訴えてしまう。
そんな私の突然の大声にもかかわらず、雅さんはにっこりと頷いてくれた。
「はい。よろしければご案内いたします」
私はそのままアイスティーを持ったまま立ち上がる。
そんな私を見てグラスをテーブルの上に置いたまま、彩ちゃんも立ち上がった。
「写真撮りたいし、あたしも行くわ。SNSにアップしときたいし」
「あ、私もそうしよう。記念に一枚撮っておきたいかも」
言いながら、鞄からスマホを撮りだして撮影モードにする。
しかしナナちゃんは口にストローをくわえて、そんな私たちをじっと見つめたまま動こうとはしなかった。
「わたしはここで、ぽちと待ってる」
その言葉を聞いて、胸にじんわりとした罪悪感が生まれた。
ここでナナちゃんを誘うのは、とっても簡単なことだ。
でもそれは、ナナちゃんのルールを踏みにじることを意味している。
「……バルコニーは、やっぱりアウト?」
「ん。お日さまの当たるところはアウト」
「ひふみ、一度決めた自分ルールは何があっても譲らないもんね」
このままナナちゃんを置いたまま、バルコニーに出ることもできる。
でもそれは、私たちの繋がりを否定することにもなるような気がした。
「じゃ、ナナちゃんが行かないなら私も行かないっ」
そう言って、再びソファに座り直す。
「ま、仕方ないわね」
同じく彩ちゃんも、そのまま腰をおろした。
「え……わたしのことは気にしないで、行ってきていいのに」
「いいの。なんか急に行きたくなくなっただけだから」
「そうそう。それに写真だったら、窓越しでも撮れるもの」
言いながら、彩ちゃんは窓際に近づいてパシャリと一枚撮影する。
見せてもらうとやはり窓越しの撮影のせいか、光が反射してそれほどくっきりとは海が写ってはいなかった。
「ん、上出来。これを少し加工してアップすれば、みんなに海に行ったって自慢できるわね」
「え、私がフォローしてるやつにアップするんじゃないの?」
「あれはあくまで連絡用よ。そんなの用途によって使い分けてるに決まってるじゃない、あたしがいくつアカウントを持ってると思ってるわけ?」
「……彩ちゃん、愚痴用アカウントとかで私たちのこと呟いたりしてないよね?」
「さぁ?」
冗談っぽく言う彩ちゃんに、ナナちゃんがほんの少しだけ表情を和らげる。
そんな私たちを、雅さんは何も言わずににこにこと見守ってくれていた。
第8話 たまには、こんな夏休み。
ずいぶんと長いこと話し込んでいたのか、空の彼方があかね色に染まりつつあった。
窓越しにすっかり傾いた黄昏色の斜陽が差し込んでくる。
水平線の向こうにゆっくりとオレンジ色の太陽が姿を消していく。
空の彼方が、だんだんと夕闇に染まっていった。
夏の夕暮れ。
そんな風景を、私たちは特等席から眺めていた。
「綺麗ね」
シャッター音がして振り向くと、彩ちゃんがスマホのカメラを遠い水平線に向けていた。
テーブルの上には、空になったグラスがいくつも置いてある。
結局あの後、彩ちゃんも喉の渇きに耐えられずに雅さんお手製のアイスティーを口にしていた。
そして一口飲んだだけですっかりお気に召したらしく、何度もおかわりを頼んだ結果がこの有様。
なんというか、彩ちゃんは少し遠慮ってものを覚えた方がいいような気がする。
「この光景をそのまま形にできないのが惜しいわ」
「そのままって?」
「いくら画質が良くても、写るのは風景だけだしね。あたしはこの景色そのものを切り抜いて、撮影してみたいのよ」
「……なんか変なものでも食べたの?」
「はーちゃん、さすがにそれはあやちゃんに失礼」
いつになく詩的なことを口にする彩ちゃんに思わず口を挟んだら、ナナちゃんからストップをかけられてしまった。
それで彩ちゃんも自分の発言がどういったニュアンスのものだったかに気づき、こほんとひとつ咳払いをする。
「それで」
どっかりと座り直して、足を組みながら彩ちゃんは尋ねる。
「結局ひふみは、夏休み中ずっと外出する気はないってことでいいの?」
「うん」
散々脱線していた話がようやく元に戻った。
「わたしとしては部屋からも出るつもりはなかったんだけど。今日ははーちゃんとあやちゃんが来たから、ちょっとだけ特別」
「ひふみ、今回のマイルール厳しすぎない? っていうか何と戦ってるの、あんた」
「自分自身との戦い」
「いや、戦わなくていいよ。ナナちゃん」
ナナちゃんはたまに、こうやって自分で勝手にルールを決めて、それを遵守した一人遊びをすることがある。
わかりやすく言うと横断歩道の白線だけを踏んで渡るとか、階段を一段飛ばしでのぼるとか、そういう感じの子どもっぽい遊び。
そりゃあ私も小学校のころは似たようなことをやってたけど、さすがに中学に入る前にはやめた。
けれどナナちゃんの中では、その遊びはまだまだ現役で。
しかも子どもがやるような単純なものではない、より複雑なルールを自分に強いるような遊び方をしていた。
「でも、遊びにはルールが必要だよ? ルールのない遊びほどつまんないものはないもの」
「いや、ナナちゃん。そうじゃなくってね?」
「そりゃ、誰にも迷惑かけずに一人でこっそりやる分には何も言わないけどさ。今回は雅さんに迷惑かけちゃってるじゃないのよ」
「いえ、私はひふみさまが楽しんでらっしゃるのなら、迷惑でも何でもありませんよ?」
急に飛び火したにもかかわらず、空になったグラスを片付けに来た雅さんが殊勝にもそんなことを口にする。
「それに私よりも、ひふみさまとご一緒の方が『ぽちさま』も落ち着いてらっしゃいますし。おふたりが幸せなら、私に口を挟む権限はありません」
「……猫にまで『さま』付けなんですか?」
「もちろんです。ひふみさまの愛猫ともなれば、私よりも立場が上ですから」
そうきっぱりと言い切る雅さんに、なんとなくプロ意識を感じた。
「それにわたし、今年の夏休みはビッグプロジェクトを計画中なの」
「なにそれ?」
少しドヤ顔で言い放つナナちゃんに思わず問い返す。
「いかに外に出ずに夏休みを満喫できるか、それを試してみようと思うの」
そのあまりにも突拍子もない計画内容に、思わず軽く眩暈を覚えた。
「ナナちゃん、なんでそんな発想に至ったの……?」
「だから、ぽちと一緒に居たいから」
「うん、根っこの部分はそれなのはわかるよ。でもそれなら、ぽちちゃんと一緒に外に出てもいいんじゃない?」
「ぽち、お外に出たがらないんだよ。拾った時あちこち怪我してたから、カラスかなにかに襲われたのかもしれない」
言いながら、ひざの上ですっかり安らいでいるぽちちゃんを優しく撫でる。
その姿からは、ぽちちゃんがかつて捨て猫だったというのを想像することはできなかった。
「それできっとお外が怖くなっちゃったんだと思う。わたしが学校に行こうとすると玄関まではついてくるけど、絶対に外に出ようとはしないんだよ」
「…………」
「だからわたしと居たいって思ってくれてるぽちのためにも、できるだけ一緒に居られる方法を考えたの」
その言葉の端々から、不器用な優しさが垣間見える。
少しズレてるけど、こういう子だからこそどこかほっとけないところがナナちゃんにはあった。
「……案外悪くないかもしれないわね」
「え?」
「ひふみの提案する、外出しない夏休みってやつもさ」
私が言葉に困っていると、彩ちゃんが呆れたように口を開いた。
「ひふみの気持ちはよーくわかった。全部納得できたわけじゃないけど、ちゃんとした理由もあるわけだし、あたし達が口を挟むようなことじゃないわよね?」
「え、うん……」
同意を求められたから、とりあえず頷いておく。
「でもね、ひふみと一緒に居たいのはぼっちだけじゃないのよ?」
「あやちゃん。ぼっちじゃなくて、ぽち」
「そ。ぽちだけじゃなくて、あたし達もひふみと一緒に夏休みを過ごしたいのよ」
そう言われて、少しナナちゃんは少し戸惑ったようだった。
「だから、あたしもひふみプロデュースのインドアな夏休みに参加してみてもいいかなって」
「あ、私も」
彩ちゃんが何を言いたいのか思い至り、私も追従して同意しておく。
ナナちゃんもそこで彩ちゃんの意図を理解したのか、困惑気味に尋ねた。
「……いいの?」
「いいも何も、あたし夏休み中ずっと暇だし」
「私も予定ないし、ナナちゃんさえよければ一緒したいな」
私たちは、ナナちゃんと「どこにも出かけない夏休み」を過ごすことを選んだ。
「電車は定期があるからお金かからないし、バスも乗り継ぎはなかったから、駅前から直で来られそうだしね」
「次に来る時は、ちゃんと日射病対策しないとだね、彩ちゃん」
「そうね。いつまでも葉月の名札つきの日傘使ってるわけにも行かないし」
「待って、あれ名札じゃないからっ!」
私たちの会話を、ナナちゃんはどこかぼんやりとした表情で聞いていて。
それに気づいた私は、最大限の信頼を込めて微笑みながら伝える。
「ナナちゃん流の夏休みの過ごし方、楽しみにしてるね」
「ひふみのことだから、色々プランは考えてあるんでしょ? 期待してるからね」
できるだけプレッシャーにならないように、重荷にならないように。
でもナナちゃんが変な責任を感じないように、私たちは参加表明を示す。
「……うん」
私たちの気持ちをどこまで汲み取ってくれたのかはわからないけど、ナナちゃんはゆっくりと頷いた。
「わたし、ふたりに外に出なくても夏は思いっきり楽しめるってこと、ちゃんと証明してみせるから」
そう言って、軽くガッツポーズを決めるナナちゃんはどこか頼もしく見えた。
「みなさま、口を挟んで申し訳ありません。よろしければ、私におふたりの送迎を任せていただけないでしょうか?」
それを聞いていた雅さんが、おずおずと会話に参加してくる。
「こちらのすぐ側の停留所には、バスは一日数本しか通らないんです。もともと交通の便が悪く、閉館となった場所ですから」
「……ってことは、もしかして帰りのバスも出てなかったりするんですか?」
「そうですね。今の時間だと、今日の分のバスは全て出てしまったかと思われます」
帰りの足があると思い込んでいた私は、雅さんの言葉で思わずぞっとしてしまった。
「雅さん、いいの? ただでさえ毎日、お仕事大変そうなのに……」
「お気になさらずに。ひふみさまのお友達ためでしたら、このくらいなんてことはないです」
心配そうに聞くナナちゃんに、雅さんは笑顔で答える。
「それに、私がそうしたいんです。だからこれは、ただのわがままなんですよ」
そのわがままはあまりにも優しくて、思わず「いいなぁ」なんて思ってしまった。
「こんなにいい場所なのに、もったいないですね」
穏やかな空気に、ぼんやりと思ったことをそのまま口にした。
「ずっと見てたけど、あの砂浜なんて誰も来なかったですし。地元の人しか知らないような穴場なのかな、ここって」
「一応言うと、あの浜辺はうちのだよ?」
「へ?」
ナナちゃんの言葉に、裏返った声を出してしまう。
「ここから見える砂浜は、七嶋家のプライベートビーチとなっております」
「はいぃ!?」
そして雅さんの追加説明に、思わず我を忘れて叫んでしまった。
「じゃあ行こうよ!? もったいないよ! 海が泣いてるよ!?」
「葉月、あんたいきなり言ってること破綻してるって自覚してる?」
「はーちゃん、言ったでしょ?」
思わず海への想いから「外出しない夏休みルール」を逸脱したことを口走った私に、ナナちゃんは穏やかに言葉を返す。
「わたしはおうちを出たくないの」
にっこりと笑った。
第9話 この夏風が……
「本日はご足労をおかけしました。誠にありがとうございます」
帰宅ラッシュで人通りの多い駅前。
遠い山に日は落ちて、街灯が煌々と辺りを照らす中、道行く人達から視線を浴びながらメイドさんに深々と頭を下げされる不審者がふたり。
他でもない、私と彩ちゃんだった。
あの後、雅さんの車でわざわざ駅前まで送ってもらい、私たちは無事に駅まで戻ってきていた。
乗るバスがなく帰る方法を持たない私たちには、雅さんが女神にも思えた。
予想外だったのは、雅さんが《《メイド姿のまま》》車に乗り込んだこと。
猫耳をつけたまま外に出るのは恥ずかしいとか言ってたナナちゃんとは違い、雅さんはそのままの格好で外出することに何の躊躇いもないみたいだった。
ホームに電車が到着したらしく、駅構内から乗車していた人達がどっと溢れてくる。
そして駅前にいるメイドさんの姿を見て、ほとんどの人達はぎょっとした表情を浮かべながらも足早に去って行く。
しかし雅さんは慣れているのか、これっぽっちも気にしている素振りはなかった。
彩ちゃんや私までコスプレっぽい格好をしてるせいか、「なんかのイベントかな?」なんて囁きながらOLさんらしい人達が横を通りぬけていった。
おまけにカメラを持った人に「写真いいですか?」なんて尋ねられるなんてハプニングも起きた。
そこは彩ちゃんが機転を利かせて、「イベントじゃないので撮影禁止です」とか断ってくれてたけど。
……はっきり言って、この状況は無茶苦茶恥ずかしい。
下手をすれば、知らない間にSNSに写真がアップされててもおかしくなかった。
「雅さん雅さん、このままだと葉月が恥ずか死しそうなんで、この辺でもう解散しません?」
居たたまれなくてうつむいたままの私を見てか、彩ちゃんがフォローしてくれた。
それを受けて、雅さんは少し戸惑ったように答える。
「その……小波さまは、注目を浴びるのはお嫌いなのですか?」
「えーと、基本的にこの子って日陰の民なんで、あんまり見られることに慣れてないんです」
「注目されるということはそれだけ魅力的ということですし、誇ってもいいと思うのですが……」
……ここまで人種の違いを感じたのは生まれて初めてかもしれない。
「しかしわかりました。小波さまにご迷惑をかけるわけにもいきませんし、私はこれで失礼いたしますね」
「あ、あの……ごめんなさい……」
「いえ、こちらこそお気遣い申し訳ありません。それでは、また後日に」
そう言って雅さんは愛車に乗り込むと、にっこり笑顔で会釈をした。
その直後、いきなりアクセル全開にして車を発進させて去って行く。
送ってもらっておいてなんだけど、雅さんはハンドルを握ると性格が変わるタイプだと思う。
正直なところ、道中すっごい怖かった。
「とりあえず、ここから離れましょ」
雅さんが去ってもギャラリーの注目はまだ途切れておらず、残された私たちをじろじろ見つめる視線が残ったまま。
ひとまず彩ちゃんの言うとおり、その場から離れることにした。
とりあえず、駅前公園の方まで歩いてきた。
昼間とは違い、人影はほとんどない。
噴水はライトアップされていて子どものはしゃぎ声はどこにもなく、園内では夏の夜の虫のオーケストラが開かれている。
ただ昼間は大学生がたむろしていた例の東屋に、一組の恋人同士が静かに寄り添い合っているシルエットだけが見えた。
「リア充、おっつー」
そんなことを言いながら、彩ちゃんが公園の片隅の自販機に硬貨を投下する。
ガコンという音がふたつして、「あたしのおごりよ」と一本ジュースの缶を私の方に放り投げた。
が、私は彩ちゃんのそんな行動を全然予測してなくて、見事に受け取り失敗して地面に落としてしまう。
「あー、それ炭酸だから少し時間を置いてから開けた方がいいわよ」
「……ありがと」
少しへこんだ缶を拾いながら、とりあえずお礼を口にしておいた。
東屋の恋人達と距離を置いて、空いていたベンチに彩ちゃんと腰をおろす。
彩ちゃんはカシュッとプルトップを開けて一口飲むと、はぁと深いため息をついた。
「しっかし、今日は色々あったわねー」
「そだねー」
雅さんは「事前に連絡をいただければ駅までお迎えに参ります」と言ってくれていた。
私は駅前まで徒歩で来られるし、彩ちゃんは定期があるから電車で駅まで来るのは問題ないとのことだった。
「葉月は明日も行くつもり?」
「うん。雅さんがせっかくああ言ってくれてたし、ナナちゃんとも約束しちゃったから」
別れ際、旅館の入口を境に私たちと雅さん、それとナナちゃんぽちちゃんのふた組が向かい合わせになっていた。
ナナちゃんにとっては、そこが最大限譲歩した「外と内の境目」。
玄関口につけてくれた雅さんの車に乗り込む私たちを、どこか寂しそうに見送るナナちゃんの姿がどうにも気になって。
つい、「また明日ね」と口にしてしまったのだった。
「じゃ、あたしも行こうかなー。どうせやることなくて暇だし」
「彩ちゃんは電車だから大変じゃない?」
「別に学校じゃないんだから、いつ行ったっていいわけでしょ? 適当に空いてる時間の電車に乗ってのんびり来ることにするわ」
そこまで口にして、突然何かを思い出したように自分のバッグをごそごそする彩ちゃん。
「忘れるところだったわ。はいこれ、例の葉月の名札付きの傘」
「……いい加減、もうそのネタ引っぱるのやめてくれないかなぁ」
差し出された値札付きの折り畳み日傘を受け取りながら、少しげんなりしてそう返す。
彩ちゃんは私の批難を全く意に介した様子もなく、ぐいっと手にしたジュースを一口あおった。
「…………」
ふいに会話が途切れた。
虫の声と、噴水からの水音だけが辺りに響く。
「ねぇ、葉月」
彩ちゃんが声のトーンを落として、ぼそりと呟いた。
「あたし、迷惑じゃなかったかな」
「え?」
「ひふみの家に行って、好き放題騒いでさ。雅さんにもずいぶん失礼なことをしちゃって、嫌な子だって思われなかったかな」
「…………」
……たまに。
ほんのたまにだけど、彩ちゃんは普段の姿からは想像も付かないような気弱な言葉を、私にだけこぼすことがある。
まるで、迷子になった女の子が泣くのを我慢しているかのように。
手を差し伸べてくれる誰かを、待っているかのように。
「そんなことないよ」
でも、彩ちゃんの明るさに救われてるのは事実だったから。
今日だって、きっと私とナナちゃんだけじゃ上手く夏休みの計画なんて立てられそうになかったから。
「私は今日も、彩ちゃんにはすごく救われてたんだよ」
だから、思ったままのことを言った。
私にないものを彩ちゃんは持ってて、たまにそれがものすごくうらやましく思うことがあるけど。
でもきっと、それは彩ちゃんが持ってるからこそ意味があるもので、私が手に入れても上手く使いこなせるはずがないのもちゃんとわかっていた。
「……ありがと」
そう言って、どこか儚げに微笑んだ。
「やっぱり、葉月は葉月よね」
「え?」
「あたしにはない、とっても素敵なものを持ってるってことよ」
言ってから恥ずかしくなったのか、彩ちゃんはそっぽを向くとまた一口ジュースをあおる。
私といえば、彩ちゃんも同じようなことを思ってたことが、ただ嬉しかった。
「さて、それじゃあたしはそろそろ帰るわ。次の電車の時間まであと少しだしね」
「うん。またね、彩ちゃん」
「もう暗いから、寄り道しないで帰りなさいよ? 変な人について行っちゃダメだからね」
「そうやって子ども扱いするのはやめてほしいかなぁ……」
そんな軽口を交わして、彩ちゃんは駅の方へと戻っていった。
その背中が見えなくなるまで見送って、私もゆっくりとベンチから立ち上がる。
私の家はこの公園を抜けて、明るい商店街を通ったその先にある。
だから彩ちゃんが心配するほど危険な場所を通る必要はなかった。
夏の夜の音が辺りに響いていた。
園内のあちこちの草むらから、たくさんの虫の声が聞こえてくる。
そういえば『夏は夜』とか習ったなぁ、なんて思いながら頭上を見上げると、半分の月が静かに佇んでいた。
途中、園内のひまわり畑の前を通る。
月明かりの下に広がる太陽の花は、昼間に見るのとは違った印象を受けた。
ゆっくりと歩道を歩きながらそんな光景を眺めていると、「麦わら帽子に白ワンピ、それにひまわりなんてさすがにベタ過ぎじゃないの?」なんて彩ちゃんの空耳が聞こえた気がして、ひとり苦笑いを浮かべた。
その時、一陣の風が吹いた。
ふんわりとした夜風が、肩まで伸びた私の髪を揺らす。
その風に揺られて、ひまわり畑がざざぁんとさざ波のような音を奏でた。
夏の匂いを孕んだ空気が、私の体の中をすぅっと通りぬけていった。
日中に溜め込まれた熱が、夜の帳にゆっくりと放出されていく。
宵闇を溶かして熟成させたような香りが、体中に染み込んでいくような気がした。
全身に浸透していく、夏の気配。
ああ、これから夏なんだと、体そのもので実感できたような気がした。
ふいに猫耳をつけた不器用な女の子のことを思い出す。
彼女の元にもこの風はちゃんと届いてるのかな、なんてことをふと思った。
――もしもこの夏風が、あの子のもとに届いたら。
そうしたら、きっと夏が好きになってくれるはずだから。
あの海にみんなで一緒に行くことを、了承してくれたりしないかな。
……なんて。
誠に勝手なことながら、ふとそんなことを思ってしまう私なのでした。
『この夏風が、あの子の元に届いたら』 休止のお知らせ
最終更新からかなりの時間が開いてしまったため、今さらかも知れませんが『この夏風が、あの子のもとに届いたら』の休止をお知らせします。
理由としては、この作品が生まれた背景として「夏休みは外で遊ばないと損だよね、という共通認識があるけどそんなことないんじゃいかな」という思いがありました。
自分もどちらかというとインドア派だったので。
しかしその後、コロナ禍が始まり、アウトドア派の方も含めて世界中がインドアにならざるを得ない世界になってしまいました。
始めのころこそ「ステイホームでインドアネタが増えるかも」なんて都合良く考えていましたが、あまりにもコロナ禍が長く続き、インドア派の自分ですら家にこもりっきりの生活に嫌気がさしてしまいました。
また、本作は「家で楽しい夏休みを過ごす」という主旨で描かれているため、そのテーマに真新しさがなくなってしまったのも理由の一つです。
シナリオ的には終わりまで組んでありましたし、登場キャラクターの掘り下げ等行っていました。
しかし諸々の理由もあり、それらのシナリオはコロナ禍前の常識をベースにしているため、あまりにも時代遅れになっていると判断しました。
その未公開部分に関しては後に書くだろう小説のネタとして転用する予定です。
また、この作品のキャラクター達、3人とねことメイドさんの組み合わせは個人的にも気に入っているので、どこか別のお話でスターシステム的に登場するかも知れません。
長々と更新しなかったのもあり、待っていた方がおりましたら申し訳ありませんでした。
最近また創作熱がうずきつつあるので、近々執筆再開予定です。
よろしければ他の作品もよろしくお願いします。
最後に。ごめんね、ひふみ、葉月、彩花。
2022/6/18 霧野リノ
この夏風が、あの子のもとに届いたら。


