ふつう
そして俺は死んだ。
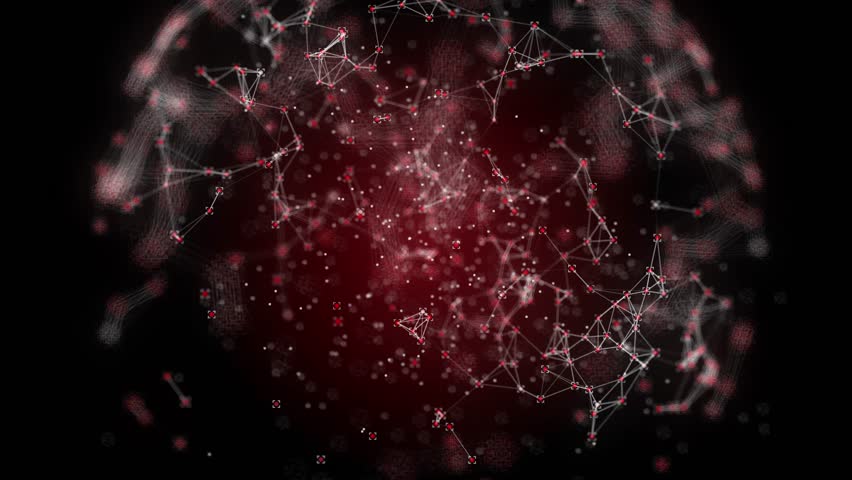
そして俺は死んだ。ごく普通な家庭生まれ、ごく普通な学校に入り、ごく普通な青春をし、ごく普通な会社に入社、ごく普通な過程を持ち、ごく普通な余生を送った。中にはいくつものドラマがあったが、それもごくごく普通であっただろう。
なぜなら俺は小さい時からこの「普通」という言葉について小さな疑問を持っていた。
「普通ってなに?」
子供の頃、俺はたくさんの人に聞いた。
「身長、体重、コレステロールの平均値なんじゃない?」
普遍的な回答ばかりだった。俺は一番合理的なもの、辞書に聞いた。
「ありふれていること。一般。」
どこか納得できなかった。いくら聞いても、みんな答えは同じ。そこで俺は余生を利用して本を書いた。「普通ってなに」だ。
おおまかな内容はこうだった。「いくら探しても答えの見つからない『普通』。私は思った。それらの全てが普通なのではないかと。そしてそれらは、自分では気づくことのできないものなのだ。『あなたは普通だ』と指をさされれば、『あなたも普通だ』と言わんばかりであるのだ。普通とは、自分自身なのだ。」。一節を抜粋するとこういった内容だ。
だから俺は普通という言葉でいかんせん、儲けることができたし、唯一自分が「普通」の日常からちょっとズレることのできた特別なものとなった。しかし、その要素を覗くとやはり他人から見れば普通だ。
つまり、人生において事故なく終わった私の生涯は、ここに終わる。いま目の前に広がるのは、まるで光が目の中にずっとたまっていくような、強い、目に痛い、白色が増していく情景である。ああ、どこへ行くのだろう。
カレの体が動いた。いや、カレの体が動いたというよりは、大きい板の上に乗せられていたところ、その板が動いたのだ。「シュー」という音と、白いたくさんの煙を出しながら。
大方、カレの体は足のつまさきまで(頭から)出た。とかと、カレはまだ目を閉じ眠っていた。白い煙がどこかへ消えて行き、機械の音がしなくなった頃、カレは目をパチリと目を覚ました。
「ん、んん…」
やけに眩しい光が強さを増して、それがずっと続くかと思ったら、今度はえらく蒸気の響くところへ来た。とカレは思った。仰向けになっていたカレの体から天井のようなものを確認することができた。
あれは天井か?たしかに病院の天井は白色だったが。その黒っぽい青色の天井を見ながら思う。
そうか、ここは天国か。いや、この異様な雰囲気、もしかして地獄か。どっちにしろ、死後の世界なのであろう。俺はさっき、意識がもうろうとするなか、死んだんだ。たしか最後にそう、あの強さが増す光の中で、「おとうさん!」とか「おじいちゃん!」という声が聞こえた。冥土の土産といったところか。
などと、カレがそんなことを考えていると、「ツカツカ」と足音がした。ん!?なんだ、人か、番人か、獄卒か、天使か、それとも形容しがたい何かだろうか。
その音は少しずつ大きくなり、近くに誰かの気配を感じたところで止まった。彼は胸が張り裂けそうなほどの緊張を覚えた。そして思わず首を右へ向けた。誰もいなかった。今度は左へ向けた。いた。というより、左へ向けたところへその「誰か」が入ってきた。
このスカートを履いたスーツ姿、女であろうか。体は細く、スラっとし、スタイルがよい。カレはじっとその美しい体を見つめた。まるで吸い込まれてしまいそうだった。すると、
「長い人生お疲れ様でした。しばらく体を動かしてなかったので、動かしにくいと思いますが、もうしばらく待っていると、ちゃんと動くようになります。」
という今まで聞いたこともないような透き通った声がした。言っていることはまるでわからなかったが、女の声で、それがいま目の前にいる人からだとは思えた。
反応をしなかったせいか、その女は前かがみになり、彼が向けている頭へ顔を近づけた。そこで初めて顔を見ることができたし、初めて目が合った。顔もまた美しく、まさに声通りであった。眼鏡をかけていて、ブロンドの長髪がきれいに動いている。そしてもう一度先ほどと同じようなことを繰り返した。カレの緊張はどこかへ消えていた。
これが天国にいると言われている天使か。なんだ、もっと小さなものを想像していたが、とても人間的で普通ではないか。いや、これは普通なのだろうか、死んだ人が誰でも通り道で、たまたま自分が初めてで新しく、新鮮だから普通と思えないのか、おそらくそれだ。女は何かを考えている彼を見て、悟ったのかまた口を開いた。
「ここは天国でも地獄でもありません。あなたが死んで、死後の世界に来たわけでもありません。ただ、疑似体験から目が覚めただけ。ここが真の世界です。」
どうやら今までの「普通」は作られた「普通」だったのか。ここが普通なところではないのが、その証拠だ。どうやら「普通ってなに?」の原稿を書き直さなくてはならない。いま初めて文末をかざる言葉ができた。「普通とは、死して初めて理解できる。」
しかし、何かがおかしい。なぜ目が覚めたのに、以前ここにいた記憶がないのだ。夢から覚めた少年は「ああ、夢だっのか。ここは普通の世界か」と現実と非現実を理解できるはずなのに。
彼は初めてその女に口を開いた。
「君の話はどうもおかしい。疑似体験の装置だか何だか知らないが、私は夢から覚めたのだろう。どうしてここにいた事の記憶がないのだ。」
初めて口を開いたのか、自分が20代の声、体に若返っていることに気がついた。そして女はそれを聞いてね慣れた口調でこう答えた。
「疑うのことは無理もありません。話すと他のことも混ざって、話が長くなりますが、かまいませんか?」
「頼む」
「では、すこし歩きながら説明致します。」
そう言われ、カレはさっきまで感覚の無かった手や足が動くことに気がついた。どうやら自分はMRIのような装置の上にいたらしい。
彼は起き上がり、そして久しぶりに、本当に久しぶりに立ち上がった。そしてそれは目に飛び込んできた。同じような装置、それも自分が入っていたものと同じような装置がズラっと地平線まで並べられている。そしてここは大きな屋外施設だったということに。
なんだここは…、果てがないようだ…。後ろを振り返っても、左右両方を見ても、すべて同じように地平線へ装置が広がっている。
「こんな景色は初めて見るかと思います。そしてここが何なのか、どうやら言わなくてもわかるようですね。」
改めて肩を並べてみたその女はやはり美しく、天使と呼ぶにふさわしかった。どうやらここには、死ぬ前の、普通の世界で生きている生物全てがいるのだろう。ついさっきまで、俺が入っていたのだから。
「全部か。」
ついこんな言葉が出る。
「全部です。いまここ、私たちは「中央」と呼んでいます。この中央で疑似体験ができるということです。ある人は人間、ある人は動物や虫、ある人は植物や穀物、微生物にだってなりたがります。もっとも、人間になるのが一番難しいので、大半は諦めています。」
話は壮大だった。恐らく、すべて説明されたら終わりがないのであろう。
「では、歩きましょう」
そう女が言ったときにまた気がついた。いつの間にかあの中央から別の場所、エレベーターのような狭い空間の中に移動していた。透明ガラスで出来たエレベーターだったため、外をよく見ることができた。とにかく、広大な景色が広がっていた。その中に、山や海のようなものもいくつかある。どうやら随分と高いところへ来た。
「さて、何から話しましょうか」
その景色を隣で見ていた女が、こちらを振り向き言った。自分も振り向いた。
「この世界について説明してくれ」
エレベーターが下がり始めた。
「ここは全てです。というしか形容ができません。ある日突然、私を含めこの世界はこうなっていました。だから、全てなのです。あなたのいた地球もそうですし、ここで「石」と呼ばれるこれ
を真空の中へ放り込み、さらに世界の居場所を増やすことで、そこで暮らしたり、ここで暮らしたりできます。もちろん、石の中で死ぬと先ほどあなたがいた中央から出てくる仕組みです。そして私たちが適切な処置を致します。」
一度区切って、また続けた。
「もちろん、あなたがいた装置は出るときはそれまでの記憶のままです。地球にい時の記憶のことです。」
「なるほど、目が覚めたときにから、ここがどこだかわからないのは、そのせいか。」
「はい。そして私たちは目が覚めたあなた達のお手伝いをする者です。」
こんな美しい女性がしばらく付き添いをすることに、カレは驚いた。
「そうだな、地球には場所によって様々な文明や種がある。顔の作りや信じているものも違うんだ。君はその中でも特にある人種に近い。そうだな……」カレは名前を決めた。
「……いい名前ですね。気に入りました。」
ふとエレベーターの外を見てみると、山と山の間や、海に面したところにいくつか街があるのは確認できた。彼女の体がほんのり光に照らされていた。
「1つ聞いていいか、適切な処置を施すというのは、どういうことなんだ。」
「簡単に言うと、この世界へ適用するための調整です。例えば「犬」になっていた人は疑似体験が終わったあと、言葉は理解できても、人間としての体の動きを忘れています。だからそれを回復するために、調整を加えます。」
「なるほど、では、私にはどんな調整を施したのだ。」
そう聞くと彼女は俺の目をじっと見つめ、髪をさっと耳にかけて「美人が派遣されました。あなたのタイプに合わせて。
この世界にも、性別の理解があるらしい。納得がいった。しばらくの沈黙が続いた。カレは何か悪い夢でも見ているのか、非現実的ないまの状況に困惑した。本当に夢を見ているだけなのかもしれないとまで思えた。あまりにも急で非現実なこの世界は、受け入れられない。しかし、いままでが夢で、これが現実ということに変わりはない。
ただ一つ言えることは、カレの隣にいる女はたしかに存在しているということだ。少なくとも、カレの周りにある人物であるというは間違いない。たとえ嘘であってもそう願いたい。
「まだまだたくさん、言いたいことや聞きたいことがあるみたいですね。無理もありません。あなたは新しい世界へ来たも同然なのですから。」
ふと、また窓の外を見ると、エレベーターは止まり、外には地平線までぎっしりと家なもが広がっている景色が見えた。おそらく住居であろう。その形は四角く均一で、白い。
「ようこそ全てへ。」
その見ていたガラスの窓が「プシュー」と音を立てて開いた。風は入ってこなかった。天気がないのであろうか。
カレはまるで世界のどこよりも美しい絶景を見たような感動をおぼえた。胸が高鳴り、その鼓動が口から溢れ出そうだった。彼は故郷へ帰ってきたのでだ。体が、本能が、大きく震えた。それは感動であり、恐怖であり、興奮でもあった。隣でその景色ではなく、カレの方を見ていた彼女は、その感動をしているのを見て、羨ましそうな顔をしていた。もちろん、いまのカレには絶景を見ること以外、出来なくなっていたが。
「一体ここは、この美しい光景はいつからなのだ!」
「説明が難しいのですが、ここが全てであり、初めからここにあったのです。たしかに一番説明が難しいのですが、そうですね、あなたが地球で生を受けた時のことを話しましょう。」
「俺が生まれた時の話?母親の中で生命が誕生したときのことか。」
「そう、あなはたしかにあなたの父親と母親の間に生まれた地球人です。命はそうして受け継がれていくのですが、全てではそれがありません。」
いつの間にか足を動かしていた2人は、その家並みが広がる逆を光が射していく方へ歩いていた。
「無いって…」
「地球では遺伝子によって石と同じようなことが起こります。でも、想像できますか、それも石が作り出しているもので、細かい機械のようなものだと。ほとんどそれも、生を持って動いています。」
カレはその時頭の中で、一人の人間に数億あると言われているDNAを思い出した。
「ではどうして顔や形が人それぞれ違うのでしょう?簡単です。」
「交わるからか。」
「そうです。そうして何年も同じものを受け継いでいくので、人々は「時間」を用いて石に変化をもたらしてきた。整理をしただけなのです。本当は意味がないのてすが。」
カレはさっき、瞬間的に移動していた時のことを思い出した。なるほど「時間」が存在するというのは、そういうことか。
そんなこの本当の世界の説明を話しながらしばらく歩いていると、「ここです。」と言い、いくら歩いても同じ形でしかなかった家並みの一軒を彼女が指さした。
「今日からここで暮らすのか。」
「暮らすというよりは、ここで「待つ」や「居る」と言っほうが正しいです。」
中は殺風景だった。ただ、外見同様に四角く囲むように壁があるだけ。カレは無性に地球にいた頃が懐かしくなったが、今おかれている状況、普通ではない状況への興奮の方が大きかった。異国の民家に住むことになった錯覚のようなものを感じた。
彼女との不思議な暮らしが始まった。しかしそれはすぐ終わることとなった。
初めに気がついたことは、食べなくてもよいということだ。どうやら全てで、常に人間は健康らしい。そして何より、服が選んでもいないのに自分の理想ぴったりなのだ。いつの間にか服が変わっているらしかった。自分の心境や状況に合わせて、イメージ通りになる。ここには衣・食・住と人間に必要なもの全てが揃ってある。初めはなんとも不気味であったが、これが普通なのだと思うと、今までの地球の暮らしが馬鹿らしく思えてきた。
欲しいものは何でも手に入った。ただなんとなく、頭の中で欲求が芽生えると、いつの間にか目の前の情景がその欲求で満たされている。景色、音、物、感動、悲観、全てが思いままとなった。本当の健康状態である。なんと快適で、安らかな世界。まさしく全てであった。
それはすぐに最悪な環境になった。ここには楽しいや悲しいがいくらでもある。でもここにはウレシイや苦しいが一つもない。ふと生きているときにこんなことを思った事がある。「ああ、こんな仕事は早く終わらせて楽になりたい。何でも自分の金を使って好き勝手やりたい。」と何度も思った。その思いが通じたのが、ここである全てだ。
しかしそれは人間としての終わりを告げていた。とにかくここにはそんな嬉しいや苦しいが一つもなく、退屈なのだ。自分で嬉しくなるようなシナリや苦しくなるようなシナリオを思い描いてみたが、それもどこか駄目であった。予想外なこと、生きるために必要だった人類の知恵や、思考では考えもつかないような事がないと駄目なのだ。欲求によって生まれるさらに大きい欲求や達成感が欲しいので。しかし、この世界にはそれがない。
まるで、無のようだった。
地球ではどうだろう、人付き合いはどこか上手くいかず、人の考えていることに不安を抱き、喜びを感じる。そして死をみて悲しみ、泣く。働いても幸福は訪れず、こんな世界は嫌だと嘆く。何をやっても全ては満たされないのだ。全てが満たされてはいけないのだ。
まるで地獄のようだった。
「無」という地獄。「地獄」という苦しみ。カレは苦しみの中でさらに苦しんだ。そしてあるとき、彼女にこういった。
「こんな世界にいて、怖く、恐ろしくならないのか。俺にはとても、こんな生活ができそうもない。」
「どうしてでしょう。私はこれが普通であるなら、これが全てと思います。私は中央に入ったことがないので、そういうことがわからないのかもしれません。」
彼女の顔が真剣になる。
「どうしてだ。ここにはなんでもあるようで、実は何もない。まるで「無」だ。植物になったようだ。」
すると彼女は俯いてこう言った。「わからない。会う人みんな、あなたのような事を口にします。そしてまた中央へ戻っていく。」
「俺も、入りたい。ここでは、生きている希望や目標が何もないのだから。まるで自分が存在していないようだ。一緒に、行こう!」
と言うと、彼女は俯いていた顔を上げ、悲しそうにこう返した。
「私にはそれが怖いのです!いまある存在が消えてしまうのが怖いのです。」
そこで彼は、中央に入るとき、自身の記憶が消えてしまうことを思い出した。つまり、本当の意味での死を思い描いたのだ。カレは首筋に悪感が走った。
「…そうか。」
この言葉しか出なかった。そう言われると、確かにそうだった。しかも尚さら、それを知らない彼女にとっては恐怖でしかない。それでもカレは、この環境にいることは出来ないと考えた。
「俺はまた中央に入る。」
カレは中央の脇で隣に立っている彼女を見つめながら話した。周りに人はいない。それはねこの装置の置かれている場所の広さを示していた。ただ、人間規模での話であったが。
彼女はただカレの方を見つめているだけであった。カレの体はゆっくりと装置の中へ入っていく。だんだん暗くなってくる頭の中で、カレは思った。意識の行方はどこなのだろ。ひょっとして、どこかで俺を思い出すのだろうか、それとも、今度は本当に俺は暗闇の中をさまようのだろうか。わからない。ただ、いまわかっていることは、俺は子供の時のことを思い出している。父親と母親の手のぬくもりさえ感じることができる。死んでも生まれ変わることの繰り返しなのだろうか。それは特別なことなのだろうか。ただ、普通に見えるだけなのだろう。日々の中で刺激や苦渋を味わえるはずである。味わっていたはずである。ただ、気付けなかっただけ。
意識がもうろうとする中で、カレは微かに、囁きのような、呟きのような、叫びともとれる声を聞いた。彼女の声だった。
「こうして人間は同じことを繰り返すのです。」
とある異郷の地。人が溢れ返り、バイクのエンジン音が街の音楽を作る。笑う人、泣く人、騙す人、騙される人、なにかを信じ、なにげなく。
そんな中、2人の若者は沈みかけた夕日を背に飯を食べていた。
「なあ、今日はよく稼げたか。」
「ビントゥオン。」
ふつう
(2011年 / 大鳥 著)

