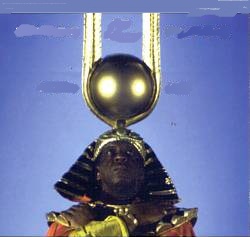不安神経 - 芥川龍之介へ
わたくしはこれからおいでになる時々不特定な人たちに面会するのが、とてもつらい。
てのひらに汗を充満させ、呼吸をあらくし、心臓がドクドクと鳴る。これはいつの歳になっても変わらない。
彼らは白い服を着て、宛もわたくしを脅すように、こちらをじろり、血管の浮き出た眼玉で視るのだから、私は全くおびえてしまう。
彼らは私の出生からこれまでの経緯、家族のこと、病気のこと、なぞをくわしく知っているように話す。じっさい知る由もない。
諭しきれば彼らの仕事は成功に終わるのである。そんなれんちゅうにわたくしの繊細なこころは殺させない。
云い忘れたけれど、わたくしは今、病院で、自邸でガス自殺をやってしまった。四回目の未遂だ。
そして、おいでになるかたをまっているのです。部屋はむしむししていて冷房の温度調節が拙い。
わたくしは白むくれがきたらすぐ眠剤をうってもらうつもりだ。
しかしながら、わたくしの本意としても、只、その白むくれのにんげん、その手にかかって死にたいのである。
自尊死はわたくしが二十七年間生きて、思春期のころからずっと考えてきたことだ。
わたくしは全く何にも殺されたくないが、家族に殺されて生涯を終えるものだと思っていた。
家族ならわたくしを殺してもいいが、家族がそんなマネをするはずもない。
わたくしは自分に殺されるのも、病気に殺されるのもまっぴらだ。できればあの白むくれのれんちゅうに殺されたい。
癌など考えるだけでも嘔吐(は)いてしまう。
ベッドの脇に置いてある芥川の『歯車』の「レエンコオト」という言葉を何故か私はとても好いた。
そして、『或る阿呆の一生』の傾いた部屋に共感しながら面白く読んだ。
わたくしは愈愈狂いかけてきてございますので、もう注射で死ぬのがいちばんではないかと考え始めた。
---自殺の動機は?
変なことを訊くな。俺には俺の人生があるのだぞ。
わたくしはこんな設問にさえ苛々して答えなかった。病院も毎回同じで、あきれているのだろう。
その晩。奥のベッドの癌患者が
「死にきれなかった亡霊が。」とわたくしに言い放った。
この一言にわたくしは衝撃を受け、この世界に生きる意味など、じっさい存在しないのではないかと考え始めた。
恥ずかしながら、こんなことを考えたのは始めてであった。
生きる意味が、大体として、子どもであり、親であり、兄弟であり、妻であり、そのほか色んなものであることはたしかだが、いまのわたくしにはさりとて大した生きる用がなかった。
だから、「死にきれなかった亡霊」は正解である。
小学生のころをおもいだす。階段から突き落とされた。裸にされ、殴るける。悔しさで舌を噛んで病院に行った。
それはイジメた児童にはなんの意味もないことだが、わたくしはそんな苦痛にたえる力を身につけた。わたくしはイジメに勝利したに等しかった。
わたくしには重大な意味をもっていた。わたくしは自殺しながらどこかで生きていればいいのにと思いながら、畢竟生きてしまったのである。
わたくしはこれからどう生きようか。
もう二十七になるというのに、定職に就かず、なんと冷たい世の中だろうと歎き、五回目の自殺へと、破滅へと、向かうのだろうか。
この世は不安に充ち、芥川のいう「只、ぼんやりとした不安」におおわれている。
芥川は心理劇の作家だが、その鋭利な小説はわたくしの生きる糧の一つになっていた。彼が生きていたならば---。
わたくしは奇妙な空気に思わず笑ってしまった。白むくれはハテナの顔をしている。
「もう二度とこんな危ういことはせんといてくれ。」と白むくれが云った。
「命の保証はない。」とも云った。そんなもんいるか、こころで絶叫した。
わたくしを不安にさせるのは、この白むくれたちのせいだけではない。
通りで交尾する猫や犬、軒先の人間もわたくしのこころをただならぬものとした。猫のあの喘ぎ声は煩わしくてしかたない。
人間のおんなの声も虚無感にかられたわたくしには只の絶叫にしか聞えなかった。
わたくしの中にある病苦への不安が、わたしくをだんだん殺し始めた。わたくしが死んで悲しむ家族はもうない。
私は死ぬために生まれてきたのだ。不安神経の暴走はわたくし自身を止められないのである。今度は曖昧な死に方はしないつもりだ。
投身して生き残ったら、ナイフを首に突きつけて殺してほしい。
不安神経 - 芥川龍之介へ