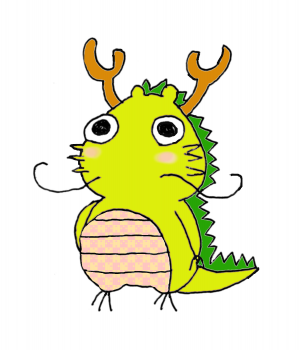キョウジ兄さんたちに捧げる物語。
この小説は、私のブログ「農家の嫁の日記」の方でも掲載しているものです。……が、あんまり人目に触れる機会がなさそうでしたので(笑)、こちらの方にも掲載させていただきました。
「機動武闘伝Gガンダム」が好きで、その中でもキョウジ兄さんとシュバルツが大好きで、いろいろと想像を膨らませていくうちにこの話が出来上がりました。私のくだらない夢物語かもしれませんが、どうかお楽しみください。
ただ、この話を読むにあたっていくつか注意事項を。
・登場人物は、基本Gガンから借り受けております。しかし、架空の世界観で構成されておりますので、Gガンの設定とは異なるところもあります。
・例えば、「ガンダムファイト」というものは存在せず、デビルガンダムのことは「事件」として取り扱われております。
・その事件は起きるけど、命を落とさなかったという、キョウジとシュバルツと師匠が活躍するお話です。
・ですので、「ガンダム」がデビルガンダムしか出てきません。
・スペースコロニーも無いことになっております。
・それでも「Gガンダム」のネタばれが多数出てきます。未見の方は注意してください。
・登場人物の鬼のような強さはそのまんまです。
・ドモン、師匠、シュバルツとかは出てきますが、シャッフル同盟の面々は出てまいりません。
・これは、あんまり大人数が動く話を書けない作者の力量不足によるところが大きいです。この方々のファンの方たち、本当にすみません。
・何故か、「NINJA GAIDENシリーズ」より、リュウ・ハヤブサが出てきます。
・これは単に、シュバルツ vs リュウ・ハヤブサが書きたいという、ただそれだけでございます(←おい!)
・というか、この話自体が私の書きたい場面の羅列になっているという可能性が大です。
・それでもOKですよ~という、心の広い方は、どうぞお読みくださいませ。
この物語が、ほんのちょっとでも誰かの心に響けば幸いです。
黒零様! 素敵なイラストをありがとうございました!
どうせなら、こんな夢物語の話をしよう。
ちょっと贅沢な、夢物語を。
「序章」
巨大な黒い塊がうごめいている。
もういらないの。もう要らないの。
ヒトの生き血はもうたくさん。
叫ぶのに、嘆くのに、だれも私の声を聞いてくれない。私の声は、だれにも届かない。
どうして私を生み出したの。
どうしてヒトの醜さばかり見せるの。
―――かわいそうに。
いつの間にか、目の前に巫女が座っていた。
もう大丈夫よ。もう大丈夫。
ほら、見えるでしょう? これが、あなたの力の源。
これを、こうして私の中に入れて。
一緒に、あの炎の中に行きましょう。
そうすれば、もうあなたは行きたいところに行けるの。
大丈夫。私はずっと一緒だよ…。
「第一章」
リュウ・ハヤブサは、闇の中を疾走していた。
前方に、気配を感じる。標的の物だ、と感じたハヤブサは、さらに速度を上げた。
木立の間を縫うように、若者が4人走っている。彼らがその異変に気付いた時には、もう二人がハヤブサによって斬り捨てられていた。
「ひっ……!」
3人目も刀を抜こうとした瞬間、首が飛んだ。
あと一人。
ここでハヤブサはわざと速度を落とす。情報を得るために。先ほどはねた首が、ドン、と音を立てて足元に転がった。
「わ……わ……」
4人目は、完全に戦意を喪失していた。
「ま、待ってくれ! 俺が悪かった!!」
後ずさりながら、必死に助けを請う。
「魔が差したんだ……! 外の世界が見たかっただけなんだ!!」
「龍の勾玉はどこだ」
必要なことだけを、ハヤブサは聞いた。漆黒の覆面の間から、色素の薄いグリーンの瞳が標的を射すくめる。
「し、知らねぇよ…! もうここには無いんだ!! 本当なんだよ!!」
悲鳴に近い声を上げながら、若者はさらに後ずさる。
「ざ、残月さんが……金! 金になるからって! ……ほら!!」
震える手で懐から金を取り出そうとしたが、うまくいくはずもなく、大半はむなしく地面に散っていった。それを踏みつけながら、無情にも暗殺者はさらに近付く。若者は気付きたくなかった。自分が今手に持っているものが、実は何の役にも立たないという事実に。
おかしい。おかしいよ。これさえあれば、何でもできるはずだったのに。
「リュウさん!! あんたにやる!! これ全部あんたに……」
ドンッ!!
鈍い音とともに、最後の男の首が、宙を舞った。
ブン、と露払いをしてから、深いため息とともにハヤブサは刀を鞘におさめた。
「外の世界が見たい」
人里離れた奥深い忍びの里で育った若者が、そういう欲求を持つのは至極当然のことだとハヤブサは思う。見聞を広めるために、己が力量を図るために外に出るのはむしろ推奨されるべきで、止めるべきものではない。
だが。
彼ら四人は、絶対に里から出してはいけないものまで一緒に持ち出してしまった。
『龍の勾玉』
これが人の世に出づる時、世界は災厄に見舞われるという。
勾玉の紛失が里の長老に知れた時、リュウ・ハヤブサに使命が下った。勾玉の奪還及び、禁を犯した者たちに制裁を。
思えば、若者たちだけの仕業にしては手際が良すぎた。やはり、手引きした者がいた。
「残月……」
次の標的の名をぼそりと呟き、ハヤブサは闇の中へと消えていった。
闇の中、細身の長髪隻眼の男が立っていた。
「残月とやら。御苦労だったな。『例の物』は、手に入ったのか?」
どこからともなく声が聞こえてきた。しわがれた老人の声だ。
「ワシを誰だと思っている。里を知り尽くしておれば、造作もないことだ」
男は無造作に懐に手を突っ込むと、ずい、と小さな袋を差し出した。
「どれ、俺が確認してやろう」
横から乱暴に、ベレー帽をかぶった体の大きな男が袋を奪い取る。袋の口をあけ、広げた右手の上で軽く振る。それだけで、目的の物の姿を拝めるはずであった。
しかし。
「!? 無い!」
ベレー帽の男がいくら袋を振っても、目的の物が出てくることはなかった。
「馬鹿な! ワシは確かに手に入れたはず!」
狼狽しながら残月は袋を奪い確認するが、袋からは中が空であるという現実を突きつけられるだけであった。
「ふん! だから忍者風情などに任せず、最初から我々が出ておればよかったのだ!」
「何だと!?」
「ククククッ。よいよい」
気色ばむ二人をなだめるように、不気味な声がまた響く。先ほどの老人の物とはまた違う、男とも女とも区別のつかない奇怪な声であった。
「隼の里より持ち出せただけでも収穫があったわ。焦ることはない。『あれ』が我が手に落ちるのも、時間の問題ぞ……」
這うような笑い声とともに、不気味な唸り声も聞こえてきた。
「おうおう、お前も早う『あれ』がほしいか」
愛でるような声に、唸り声が一層大きく反応する。
「残月よ。よく思い出してみるのだ。お前がここに来るまでに通った道のりをな……」
どこかからかうような口調だった。
残月はその中に「侮蔑」を感じ取り、ギリ、と歯ぎしりをした。
「はぁ?」
閑静な住宅街の一角にて。部屋中に、ドモン・カッシュの疑問を投げかける声が響き渡っていた。ドモンの目の前には、久しぶりに会った兄、キョウジ・カッシュが座っている。
右の頬に十字傷。赤い鉢巻をしめ、やんちゃそうな印象を人に与えるドモンに対して、静かで、優しそうな印象をキョウジは人に与えていた。微笑むと、中性的ですらある。
この二人、兄弟でありながら得意分野は全然違う。兄は科学者。弟は武術の道を極めていた。
「いや、だから」
キョウジは苦笑していた。自分でも変なことを言っていることは、よく分かっていた。理解しがたい、といった表情を浮かべている弟に対して、もう一度説明を試みてみる。
「学会の帰りの空港で……」
「帰りの空港で?」
兄の言った言葉をドモンが復唱する。
「こう……光るものが、上から降ってきて……」
「上から降ってきて?」
すうっと、キョウジの人差し指が空から己の右手へと移動する。
「手のひらの上に落ちてきた、と、思ったら」
「と、思ったら?」
「どうもそのまま私の手の中に、入っちゃったみたいなんだよね」
そこまで言うと、キョウジは軽く笑った。我ながら嘘みたいな話だと思うが、厳然たる事実だ。
「手の中に、入った?」
ドモンは相変わらず、怪訝な顔をしている。
「うん、手の中に。なんだか溶けていくみたいに」
キョウジはもう一度念を押した。
「手の中に?」
「うん」
「…………」
ドモンがしばし沈黙した。
今度こそ理解してもらえただろうか。キョウジはドモンの様子を見守ることにした。
「―――――で?」
ドモンがおもむろに顔を上げる。
「で? とは?」
今度はキョウジが聞き返した。
「今どこにあるんだ。その落ちてきた光っている奴っていうのは。見せてみろよ」
「………!」
キョウジはイスからずり落ちそうになった。ドモンは、もう考えることがいっぱいいっぱいという表情をしている。ええい。鈍い奴だとは思っていたが、ここまで鈍いとは。こいつ、わざとか? わざととぼけているのか? と、疑いたくなる。それとも本気で分からないのか、はたまた理解を拒んでいるのか。
「見せたいのは山々なんだけど、無理なんだよ」
ドモンの要求に、キョウジは気を取り直して答えた。
「何で?」
「何でって……だから!」
いい加減察しの悪い弟に状況を分かってもらうため、最もわかりやすい言葉をキョウジは選択することにした。
「どうも私の身体の中にそいつが入っちゃったみたいだから、見せるのは無理だって言っているんだ!」
「え?」
ボ――ン、ボ――ン。
ドモンが固まった瞬間、部屋に時計の音が響き渡った。
キッチンの方からコーヒーの芳醇な香りが漂ってくる。淹れてくれているのは、ドモンの恋人であるレインか。じゃあ、もうすぐおいしいコーヒーが飲めるなぁ―――などと、キョウジは何となく思っていた。
「兄さん……」
しばしの沈黙の後、ドモンがピクリと動く。
「何だ?」
やれやれ、やっと理解してもらえたかな? と、キョウジがドモンを覗き込もうとした瞬間。いきなりドモンが椅子を蹴倒して立ち上がった。
「つまり兄さんの身体の中に異物混入で、兄さんは命の危機にあるということかぁぁぁ――――っ!!」
「いや、そこまで言っていないんだけど」
キョウジは冷静に否定するが、ドモンの方は聞いていない。気のせいか、彼の後ろに炎が見える。
「おのれ! そのあやかしの光!! この俺が、このキング・オブ・ハートがこの拳にかけて倒してくれる!! 兄さんを傷つけるものは! 神であろうと悪魔であろうと、この俺がゆるさ――――ん!!」
「いや、だからドモン……」
キョウジは頭を抱えていた。自分を心配してくれる気持ちは嬉しいが、どうしてこうこいつは極端から極端に走るんだ。どうも1年前のデビルガンダム事件で自分が死にかけて以来、弟のブラコン度が悪化しているような気がする。最も本人にそれを指摘したら、おそらく全力で否定されるであろうが。
「はいはい、ちょっと冷静になりましょうね」
バコン。
分厚い医学事典で殴られたドモンがこけた。
「レイン」
ドモンを止めてくれた人物に、キョウジは微笑みかけた。
「キョウジさん、久しぶり」
レインも笑顔で答える。相変わらず、ドモンにはもったいないほどの美人だなと、キョウジは思った。
「キョウジさんはコーヒー、ブラックでよかったわよね。ほら、ドモンも」
レインがてきぱきとコーヒーをテーブルの上に並べていく。カップの中でゆらゆら揺れる琥珀色の液体を眺めながら、キョウジは、やっと冷静に話を進めることができそうだと、ほっと一息をついた。
「そういえばキョウジさん、お仕事の方はどうしたの?」
「休みをもらったよ」
コーヒーを飲みながらキョウジは答える。デビルガンダム事件の後、しばらく療養していたキョウジであったが、彼がもともと優秀な科学者であったこと、その才能を惜しむ周りの人たちの助力を得て、研究の場に復帰していた。その身代わりになるかのように、兄弟の父、ライゾウ・カッシュ博士が亡くなっていた。亡き父の研究を引き継いだり、ときには大学で講義をしたりと、忙しい毎日を送っている。よく休みがもらえたわね、というレインに対して、まあその辺はいろいろと、と、キョウジは若干何かを含んだいたずらっぽい笑みを見せた。
「その……体の方は、大丈夫なの? ちらちら聞こえていたんだけど、何か変なことがあったって……」
レインの至極まっとうな問いに、キョウジは軽く笑った。
「体温、血圧、心拍数、血液成分、どれをとっても正常値の範囲内だよ。ただ……」
「ただ……?」
「兄さんに命の危機が!?」
軽く言い淀んだ兄に、過剰反応を見せるドモン。
「はいはい、先走らない」
再び先ほどの医学事典がドモンの頭を襲い、彼はおとなしくなった。便利だな、あれ。今度ドモンと話をするときは、あの事典借りようか、と、キョウジは思った。
「いや……気にするほどのことではないと思うんだけど」
そう言って、キョウジは語りだした。最近、自分が研究室をあけている間に、誰かが無断で入ってきたような痕跡があるのだ。それも、複数回にわたって。特に何かを捕るでもなく、研究のデータが荒らされているわけでもないのだが。
「私は全然気がつかなかったんだけど、シュバルツがそう言って」
「もう一人の兄さんが?」
シュバルツの名前に、ドモンが反応する。シュバルツというのは、1年前のデビルガンダム事件の際、暴走したデビルガンダムに取り込まれかけたキョウジが、ドモンを影から守るためにデビルガンダムの細胞を使って作りだしたアンドロイドで、キョウジのコピーともいえる存在だった。外見はキョウジと瓜二つで、人格もキョウジの物だが、その戦闘力は本人をはるかに凌駕する。
シュバルツはその力で、幾度となくドモンを助けていた。だから、事件が終わった今でもドモンはシュバルツのことをキョウジと同じように「兄さん」と呼んだりして、とても慕っている。時々組み手の相手もしてもらっているようだ。
「そういえば、シュバルツはどうしたんだよ。今日は来てないのか?」
ドモンの問いに、キョウジはちょっとすまなさそうな笑みを浮かべた。
「悪いな。研究所でのこともあるし、そのあたりのことを今彼に調べてもらっているんだ。あいつ、忍びの心得があるからね」
「そっか……久しぶりに会いたかったな」
ドモンが結構残念そうな顔をする。それを見て、シュバルツは本当にドモンに慕われているな、と、キョウジとしては、嬉しいような淋しいような、少し複雑な心境を味わった。
「本当に…大丈夫なの?」
その声に顔を上げると、レインが真剣な眼差しでこちらを見ていた。
「ああ、研究所の方なら大丈夫だよ。今研究中の物は、すべてロックをかけてきているし……正直、休みたくなんかなかったんだけどね。今大事なところに差し掛かっている研究とかいっぱいあるし」
ここまで話すとキョウジは結構深いため息をついた。
「あ~……ちくしょう。邪魔してきたやつの目的は、いったい何なんだ……」
「キョウジさん……」
「兄さん。今度はどんなやばい研究をやらかしたんだよ?」
ドモンがじと~っとキョウジをにらむ。
「いや、軍部に提供できるような研究は…やってないはずだよ……多分」
「本当に?」
ドモンがさらに睨みつける。対して、キョウジの目線は若干泳ぎ気味だ。ドモンはあきらめて視線を外した。
「兄さんにその気が無くたって、悪用されるものは悪用されるだろ。アルティメット細胞のときだってそうだ」
「―――あれは、結構画期的な発見だったんだけどなぁ」
珍しくまともなことを言う弟に苦笑しながら、キョウジはカップに視線を落とす。
アルティメット細胞―――金属の性質を持ちながら、有機物と結合することが可能。さらに、細胞自身に自己再生、自己増殖、自己進化の特性があり、その細胞と結合した有機体は、ほぼ半永久的に活動が可能になるというものだった。
といっても、アルティメット細胞自体にはそう力があるわけではなく、再生、増殖、進化の力も微々たるものだった。暴走して、デビルガンダム細胞と化すまでは。
新しい科学技術を発見するのも人間、それを使うのも人間。
それを善とするか悪とするかは、結局それを使う人間次第なのだ。
―――今更ながら、人間って業が深いよな……。
苦いコーヒーを口に含みながら、キョウジは自嘲的に笑った。
「研究も大事だけど、私が言いたいのはそういうことじゃなくて」
レインは少しためらってから、口を開いた。
「キョウジさん……あなた自身が狙われている可能性は、無いの?」
ピク、と、キョウジのカップを持つ手が止まり、ドモンの表情がみるみるひきつっていく。
「何ぃ~~? 兄さんを狙う不届きものがっ……!!」
ゴ~~~~ン!
「だから冷静になりなさいって」
レインが立ち上がろうとするドモンの頭上に巨大中華鍋を持ってきていた。中華鍋がクリーンヒットしたドモンは、頭に巨大たんこぶを作って机に突っ伏す羽目になっている。
「て、手慣れてるね…」
「長い付き合いですから」
そう言って、中華鍋を抱えてにっこりほほ笑むレインに、さすがのキョウジも引き気味だ。
「本当に、実際のところどうなの? ここに来たのも、もしかして……」
「いや……まだ私自身が狙われているとか、そんな確証はないよ」
キョウジは冷静に否定する。だが、それでもキョウジはドモンの家に来た。仕事を休んでまで。
「だが、狙われていない、という保証もない……そんなところかな」
「…………」
少し眉をひそめるレインに、キョウジは笑顔を見せた。
「ほら、私はそこにいるドモンみたいに人類の規格外の強さがないから、憶病なんだよ。だから、打てる手を打っておきたいだけさ。それに……」
「それに?」
机に突っ伏していたドモンが、顔を上げる。
「もし万が一、私自身が狙われているとしたら、『私の弟』というだけで、ドモン、お前も巻き込まれる」
「!!」
キョウジは、冷静に現実を分析していた。そこには妥協も理想も願望もない。自分が事件に巻き込まれてしまったら、どんな形にしろ弟にも影響が及ぶ。
「そうなったときに―――また1年前のあの時みたいに、お前に誤解されるのだけは、もうたくさんだからな………それだけだ」
「兄さん……」
ドモンはそれ以上の言葉を失う。そうなのだ。1年前の「デビルガンダム事件」の時、ドモンは最初父が開発した強大な力を持つガンダムを兄が自分の野望のために強奪した、と思い込まされていた。だが真実は全く逆で、軍の一部の人間が己の野望のためにガンダムを強奪しようとし、兄はそれを阻止するためにガンダムに乗ったのだ。ところがその過程でガンダム自体が暴走してしまい、兄はデビルガンダムと化したガンダムに取り込まれてしまった。ドモンはなかなか真実にたどり着けず、本当にもう少しで、兄をこの手で殺めてしまうところだった。
兄が助かったと知った時、自分はどれだけ泣いたことだろう。
本当に良かった。この優しい人を永遠に失わずに済んで、本当によかった……。
知らず、泣きそうな顔になっていたのだろう。兄の手が自分の頭に伸びてきた。そのまま優しくポンポンと撫でられる。幼いころから自分が泣いていると、必ず兄がしてくれていた行為だった。
「―――そんなわけで、しばらく厄介になるよ。シュバルツが帰ってきて、何も心配がないとわかったら、またすぐ帰るからさ」
キョウジが笑顔でドモンに手を差し出す。
「ああ、わかったよ、兄さん。でも、そんな遠慮しないで、しばらくいてくれていいのに」
ドモンも笑顔で手を握り返した。
「そういうわけにもいかんだろう。新婚家庭なのに」
「やぁだキョウジさん! 新婚だなんてそんな…!」
照れるレインに、何故かドモンが殴り倒された。
「……レイン……」
涙目でレインを見上げるドモンに、ごめんなさい、とあわてて謝るレイン。夫婦漫才を見ているようだな、とキョウジは苦笑した。
「―――本当、頼りにしているよ。キング・オブ・ハート」
兄の小さな声に、弟がピクリと反応する。
頼りにしているよ……頼りにしている……頼りに……頼りに……!
―――俺は今、兄さんに頼りにされている!!
「レイン、今の聞いたか?」
「何を?」
「俺は、兄さんに頼られる、一人前の男になったんだ!」
「ふ~ん?」
「話しかけるなよ、レイン。今俺は、猛烈な感動に浸っているのだから!」
「別に何も言っていないでしょ?」
「よし!! 俺はやるぞ!! キング・オブ・ハートの名に懸けて! 必ず優勝してみせる!!」
「何に優勝するつもりよ」
キョウジの目の前で、平和そのものといった光景が繰り広げられている。このまま、夜が来たら夕飯を皆で食べて、寝て、またいつも通りの朝が来て―――それがずっと続くものと、つい思いたくなってしまう。
実際、研究所でわずかに異変が起きている程度で、自分のとった行動は大げさすぎるものかもしれない。単に今行っている研究がちょっと煮詰まっているから、気分転換の口実を作っているだけかもしれない。
だが、何よりもキョウジを不安にさせているのは、おそらく自分の身体に吸収されてしまったであろう、あの『光』の存在だった。この不確定要素だけが、どうしたって自分の心にどす黒く蟠る。
『あれ』は一体何だったのか。
それを判断するには、時間も情報も圧倒的に足りなかった。今のところ、自分の身体に何かの異変が起きているわけでもないし、自覚症状もない。
どうか取り越し苦労であってほしい。帰ってきたシュバルツに、
「いちいちこんなつまらんことで私をこき使うな!」
と、怒られる程度のことであってほしい。シュバルツ、早く帰ってきてくれ…!
「キョウジさん?」
「!!」
ドモンの相手をしていたはずのレインが、いつの間にかこちらに来て顔を覗き込んでいる。レインの顔を見て初めて、キョウジは自分の表情から笑顔が消えていたことに気づいた。
「―――何だい?」
すっ…と、キョウジの顔に笑顔が戻る。優しい笑顔だが、これ以上の詮索を拒んでいるようにも見えた。
大丈夫? そう聞こうとしたが、レインはやめた。
「コーヒー、おかわりはいかが?」
「あ……いや、いいよ。ありがとう」
「そう? …じゃ、カップを片づけるわね」
カチャカチャとカップを盆に載せながら、レインは考えていた。
キョウジは、先ほどから明らかに言葉と態度を選んでいる。ドモンを必要以上に刺激しないようにとの配慮もあるのだろうが、それにしても……。
(キョウジさんの抱えている問題は、ひょっとしたら私が思っているよりもずっと根が深い物なのかもしれない……。それも、かなり悪い方に)
キョウジは、こういえば本人は絶対否定するだろうけど、とても有能な人だ。たいていの問題は、一人で解決できてしまう。そのキョウジが、一人ではもてあます問題かもしれない、と判断して、ドモンのところに来た。
巻き込みたくない、というためらいもあっただろうに、それでも来てくれた。彼のことだ。かなりぎりぎりまで悩んだだろう。そして、ドモンが巻き込まれるということは、必然的に私も巻き込まれるということ。
―――ならば、私がキョウジさんのためにできることは、なに?
カップを洗い終わり、キュッと水道の蛇口を閉める。空になったシンクの中をしばらくレインは眺めていたが、やがて顔を上げた。
おもむろに電話を取り上げる。意を決して、その番号を押す。
「―――あ、もしもし? レイモンドさん? 私です。レインです。そう、お久しぶり―――」
2時間後。
閑静な住宅街におよそ似つかわしくない巨大な黒塗りのロールスロイスがカッシュ家の前に止まっていた。そして、玄関先では一般家庭とは無縁そうなお姫様がひらひらと手を振っている。
「マリアルイゼ様! お久しぶり~」
「レインさん! お元気でいらっしゃいましたか?」
マリアルイゼという人は、「デビルガンダム事件」の折に、ひょんなことから知り合ったフランスのお姫様だった。いきなりの訪問に唖然としているカッシュ兄弟を放置して、レインとマリアルイゼはきゃあきゃあとガールズトークで盛り上がっている。
「いや~お話は伺いましたよ、ドモンさん。レインさんにプレゼントを差し上げたそうですね~」
まだあごが外れかかったような表情のドモンに、サンド家の執事であるレイモンドが近寄ってきた。
「我がフランスには、レインさんが喜んでいただけるような保養地もたくさんございます。きっといい休養になるでしょう」
「きゅ、休養って……レイン?」
(あ………!)
いまいち事態が把握できていないドモンに対して、キョウジはレインの意図したことが正確に理解できてしまった。みるみるキョウジの表情が、申し訳なさそうに曇っていく。
「ですからどうか安心して、レインさんを我々にお任せください」
レイモンドが白髪頭を深々とカッシュ兄弟に向かって下げる。
「レイン……どういうことだ?」
「ウフ…どうせだから、ちょっと贅沢しちゃった」
疑問を投げかけるドモンに対して、レインはペロッと舌を出して答えた。それからふいに真顔になり、ドモン、ちょっと、とレインはドモンに顔を近づけていく。
「―――ドモン、私は大丈夫……だから、キョウジさんをちゃんと守ってあげてね」
「あ………!」
ここに至って、ドモンもようやくレインの意図を理解した。レインは、ドモンの守る対象をキョウジ一人に集中させたいのだ。そのために、自分はできるだけ安全なところに避難する―――これが、レインの下した決断だった。
「もし、何事も起こらないようなら連絡ちょうだい。すぐ帰ってくるから」
「ああ、分かった」
レインの言葉にドモンも笑顔で答えた。彼女がキョウジのためを想って起こした行動ならば、自分も反対する理由はない。
「ドモンさん、安心してくださいませ。このマリアルイゼの名にかけて、レインさんのフランスでの安全を保証いたしますわ」
「―――それは心強いな。よろしく頼むよ」
小さなお姫様の言葉に、ドモンも笑顔を返す。その場は笑顔に包まれた―――かに見えたが、約1名、笑っていない人物がいた。
「レイン……」
消え入りそうな、小さな声がする。レインが振り向くと、それはそれは気の毒なほどに申し訳なさそうな表情をしているキョウジの姿があった。
「その……」
キョウジがその先の言葉を紡ぐのを、レインは手で制した。
(あのね、キョウジさん。傍から冷静な目で見ると、私のとっている行動は、急に訪れてきた小姑に当たる義理のお兄さんの面倒をみるのが嫌で、家から出ていく嫁と同じものなのよ。だから、本当ならそんな申し訳なさそうな顔をする所じゃなくて、怒っても良いところなのよ。それなのに……これだから、キョウジさんは―――)
レインは苦笑した。
キョウジさんは、人が良すぎる。
「キョウジさん」
だから、レインは言葉を選ぶ。キョウジの心の負担が少しでも軽くなるように、祈りを込めて。
「―――ドモンをお願いね」
「――――!」
「ドモンが突っ走りそうになったら、殺す気で殴っていいから」
「殺す気って……おい、レイン!」
殴るふりをしてキョウジにウインクを送るレインに、ドモンから文句が上がる。それを見たキョウジの表情が、わずかに緩んだ。―――よし、もう一息。と、レインはドモンに向き直った。
「ドモン!」
「何だよ」
「キョウジさんに迷惑かけちゃだめよ!」
レインの言葉にドモンが鼻で笑って答える。
「分かってるって。もう俺も良い大人なんだし、迷惑はかけな……」
ドモンの言葉が終わらないうちに、レインはたたみかけた。
「特に、靴下! どこでもあちこち脱ぎ散らかしているんじゃないわよ! 私がどれだけあなたの靴下を拾って歩いていると思ってんの!?」
「へ!?」
予想もしなかったレインからの攻撃に、さすがのドモンも動揺が隠せないらしい。思いっきり間抜け面をさらしてしまっている。
「帰ってきた時に、家中が靴下だらけになっていたり片方無くなっていたりしたら、承知しないからね~!!」
こう言い残して、レインはロールスロイスの中に姿を消した。
「レ、レインのやつ……俺、そんなに靴下脱ぎ散らかしてないだろ?」
レインを見送りながらぶつくさつぶやくドモンの後ろで「ぶ……」と、声がする。ドモンが振り向くと、キョウジが必死に笑いをこらえていた。
「に、兄さん! 笑うことないだろ!!」
ドモンの抗議の声が、却ってキョウジの我慢の堰を外してしまったらしい。彼はついに、声を立てて笑い出してしまった。
「あっはっはっは!!……いや、すまんすまん。でも何、お前、子供のころからの癖がまだ治ってなかったのか?」
そう言いながら、キョウジはまだくすくす笑っている。
「ちがう! 俺は脱ぎ散らかしているんじゃなくて、気がついたら靴下が無くなっているんだ!!」
ドモンが訳のわからない理論を振り回してくる。それをキョウジは「分かった、分かった」と、軽くいなした。
それにしても。
キョウジは思う。レインには、どうして自分の不安が簡単に伝わってしまったのだろう。
出来るだけ、何でもない風を装っていたつもりだった。実際、まだ何かが起こっているわけでもないのだから。それなのに、彼女はたったあれだけのやり取りの中だけで、自分の不安をくみ取ってくれた。それどころか、こちらの負担にならないよう、自分の身の置き所までさっと決めてしまった。キョウジには、彼女のその配慮がありがたかった。
(レイン……本当にすまない。そして―――ありがとう)
キョウジは心の中で、レインに頭を下げた。
キョウジがドモンの家を訪ねてきた時には真上にあった太陽が、大分西に傾いてきていた。レインを見送り、家に入ろうとしたキョウジがふいに「ああっ!!」と、大声を出した。
「兄さん!? どうした!?」
ドモンがあわてて駆け寄ると、キョウジは凍りついた笑顔をドモンに向けた。
「あ……いや、その……」
「兄さん!?」
「ドモン………レインちゃんって…」
「レイン!? レインがどうかしたのか!?」
「―――夕食、作って行ってなかった……よね?」
ガク。
―――夕食かよ!!
ドモンは心の中でキョウジに盛大な突っ込みを入れた。
「ああ、なんか荷造りしてたみたいだからな。夕食作る間無かったんだろ」
「………だよなぁ」
キョウジはガクっと頭を垂れる。実は秘かに楽しみにしていたのだ。レインの手作り料理を。なのに、食べ損ねてしまった。
―――しまった! 私の馬鹿…。もう少しうまく不安な気持ちを隠し通しておけばよかった…! レイン……君はいろいろ気がつくのが早すぎる…!
そう、料理を食べ損ねたのは、ほかでもない、自分自身のせいなのだ。「自業自得」という言葉が、キョウジの胸に今切なく突き刺さる。
「いいじゃん、料理ぐらい。出前でも頼めばさ」
日頃から恵まれているドモンが、あっけらかんとひどいことを言っている。ちくしょう! ドモンの奴め! 私は自慢じゃないが、出前もコンビニ弁当も食べ飽きているんだ!! と、心の中で毒づく。もちろん、ドモンには聞こえていない。
日頃から研究所に泊まり込みになったりすることが多いキョウジは、必然的にそういう食べ物と縁が深い。だから、今日は久しぶりにまともな食事ができると期待していたのだが…。
「はぁ~~~~………」
キョウジは深~いため息をついた。
レインは、自分の気持ちをくみ取ってくれた。その結果、彼女の手作り料理が食べられなかったって、仕方のない事じゃないか……。
「しょうがない。今日の夕食は、兄ちゃんが作りますか……」
とぼとぼとキョウジは台所に入って行く。対してドモンは
「やった! 兄さんの料理!」
と、嬉しそうだ。
―――かわいい奴。
キョウジはドモンをちらりと見やり、苦笑する。
「味は期待するなよ」
ぶっきらぼうに言うキョウジに対してドモンは「は~い」と、返事をする。しかしドモンは知っているのだ。キョウジは料理もうまいということを。
その日の夜。カッシュ家は、久しぶりに兄弟水入らずの時間を過ごした。
「第二章」
夜更け。ドモンが眠りについた後も、キョウジは一人、起きていた。
(夜のメディカルチェックも異常なし……か)
ため息をつきながら、廊下を歩く。あの『光』が自分の身体に入ってから一週間が経過する。もし、ウイルスとかの類であれば、そろそろなんらかの症状が出てくる可能性もある頃だ。しかし、今のところ何の異常もない。
(ここまで異常がないとなると……特に気にする必要もなかったのかな…。あるいは、光自体が目の錯覚だった……とか)
と、ついそんな楽観的なことまで考えたくなってしまう。
異常がないから気にしない―――そういう風に割り切れたら、もっと楽だろうに。いちいちこんな些細なことを気にしてしまうのは、自分が小心者だからだろうか。それとも、疑問はとことん追求しないと気が済まないという、学者としての性がそうさせているのだろうか。
軽く自己嫌悪に陥りながらふと見ると、廊下に白い物体が転がっている。よく見ると、ドモンの靴下だった。
―――ドモンの奴! あれほどレインに言われていたのに……。
やれやれ、しょうがない奴だな、と、キョウジが靴下に手を伸ばした時。先ほどまで誰もいなかったはずの壁際に、人が佇んでいることに気がついた。キョウジと同じ容姿をした青年だった。違いは、キョウジよりも少し体格がいいのと、革のロングコートを着ているぐらいだろうか。彼は腕組みをして、こちらを静かに見ていた。
「―――シュバルツ!」
キョウジは彼の名を呼び、そばに駆け寄る。
「どうだった? 何か分かったのか?」
「キョウジ……」
キョウジの問いかけに、シュバルツは微笑んだ。
「!?」
そのあまりにも優しすぎる微笑みに、却って異様なものを感じたキョウジは一瞬動きを止める。
「―――お前の勘、当たったぞ」
「えっ? それはどういう……」
キョウジはその言葉を最後まで言えなかった。次の瞬間、シュバルツの左拳が
ドンッ!
と、音を立ててキョウジの鳩尾にめり込んでいたからだ。
「……っ! シュ…バ……?」
そのまま意識を手放すキョウジの身体を、シュバルツが支えた。シュバルツは、最後まで微笑んでいた。
「―――兄さん?」
その頃になって何か気配を感じたのか、ドモンが顔を出してきた。見ると、シュバルツが気を失ったキョウジの身体を横たえている。
「ちょっ……! 兄さん!!」
「―――甘いな、ドモン」
駆け寄ってきたドモンをはねつけるように、シュバルツが口を開いた。
「もしも私が刺客なら、キョウジはとっくに命が無いか、拉致されている」
「――――っ! それは……!!」
ドモンは反論しようとしたが、それ以上言葉が出てこなかった。現に、キョウジは意識を失って倒れている。それが、己の未熟ぶりに対する動かぬ証しだ。
―――何なんだ俺は…! 口では兄さんを守ると言っておきながら……!
ギリ、と唇をかみしめる。完全に油断していた己に、腹が立った。
「…………」
シュバルツはそんなドモンの様子をしばらく見つめていたが、やがて口を開いた。
「ドモン―――キョウジは狙われている」
「………!」
シュバルツの言葉が、ドモンの背中に冷たい物を走らせた。つまり、先ほどのシュバルツが本当に本物の刺客になる可能性があるのだ。
―――しっかりしろ、ドモン! もう同じ過ちを繰り返しちゃだめだ!
ブンっ! と、頭を振り、パン! と、両頬をたたいて気合を入れなおす。
「正確には、キョウジの中に吸収された『物』が狙われているのだがな」
「『物』…? あの『光』のことか!」
(やっぱりあの『光』は不吉なものだったんじゃないか!)
あの「デビルガンダム事件」の時のように、また兄は自分の預かり知らないところで危険なものに巻き込まれている。何か理不尽なものを感じて、ドモンはギュッと拳を握りこんだ。
だが今は、怒りに流されている時ではない。1年前の事件の時には、自分は兄のそばにはいなかった。今は、ちゃんとそばにいる。まだ守れるはず―――そう、信じる。
シュバルツはいつの間にかキョウジの側にスーツケースと鞄を持ってきていた。スーツケースの中からキョウジの服を取り出している。
「シュバルツ、これから……」
どうする、と聞こうとしたドモンをシュバルツが手で制した。
「―――感じないか? ドモン。殺気だ」
「!?」
静かに周囲の気配を探ると、確かに、殺気を帯びた気配がこちらに向かって来ている。それも、複数。
「時間が無いドモン。まずお前はレインを安全なところに―――」
「レインなら、もう避難させた」
「何!?」
シュバルツが意外そうな顔をする。
「―――キョウジがそうしろと言ったのか?」
「違う! 避難したのはレインの意思だ!」
「………!」
シュバルツの表情が、キョウジと同じように申し訳なさそうに曇っていく。こういうところを見ていると、やっぱりこの人も自分の兄なのだ、と、ドモンは思う。
「……すまない、迷惑をかけてしまったな」
「何、水臭いことを言っているんだよ兄さん。兄弟じゃないか! こういうとき助けあうのは、当たり前だろ」
ドモンの笑顔に、シュバルツの表情も緩む。
「―――そうだな…」
すまない、と言いかけて、シュバルツはやめた。
「ありがとう」
―――兄さんに、礼を言われた…!
ドモンは、照れくさいような嬉しいような、くすぐったい気持になった。
「さてドモン、本当に時間が無いから手早く話すぞ」
シュバルツはいつものロングコートを脱ぎ、キョウジの服に袖を通していた。こうしてしまうと、本当にキョウジと見分けがつかなくなる。そのままシュバルツは、ドン! と廊下の一ヵ所を拳で叩く。すると、床の一部がめくり上がり、地下への入り口が出現した。
「ち、地下室!? 家にこんなものあったっけ?」
ドモンが面食らっているのに対して、シュバルツは至って冷静だ。
「レインの許可なら取ったぞ」
キョウジとスーツケース類を抱えて地下へと降りていく。
「レ、レインの許可って…!」
「ここの家長はレインだろう」
「……………!!」
ドモンは開いた口が塞がらない。
「違うのか?」
「…………」
反論したいことはいっぱいあった。いっぱいあったが、悲しいかな言葉が出てこない。
て、言うか、人の家に勝手に地下室ってほかにもつり天井とかどんでん返しとかいつの間にやら忍者屋敷っぽく改造されていたりしないだろうなとドモンは思う。こっちの忍者の方の兄さんは、元の兄さんよりも行動力がある分、はるかに厄介かもしれない。
「キョウジに取り込まれた『物』の正体だが…名前だけは分かった」
キョウジを床に横たえながら、シュバルツは淡々と話す。ドモンは、頭をかきむしるのをやめた。
「『龍の勾玉』と言うらしい。……それ以上は、残念ながら分からなかった」
「龍の…勾玉…」
「私が表の敵を引き付ける。その間に、お前はキョウジと共にここを脱出しろ」
シュバルツがドモンにくるりと背を向け、そのまま地下室から出ていこうとする。
「ちょ、ちょっと待ってよ! 兄さん!」
あまりの展開の速さに置いて行かれそうに感じたドモンは、思わずシュバルツを引きとめた。
「脱出はみんなでした方が……」
「私が餌になった方が効率が良いんだ」
「え、餌!? ……何で!!」
シュバルツは小さくため息をついた。ドモンには、一から説明した方がいいかと思いなおして向き直る。
「いいか、ドモン。狙われているのはキョウジだ」
「…………」
「そして、キョウジに必要なものは、『情報』だ。『龍の勾玉』がいったいどういう物であるのかが分からないうちは、敵の手に落ちるわけにはいかん」
「それはそうだけど…」
「そこで、私の出番だ」
シュバルツはにっこり笑う。
「私はキョウジの影―――敵は『キョウジ』が二人いることを知らない。私が出ていけば、敵を十分引き付けられるだろう。お前たちが逃げるくらいの時間は稼げるはずだ」
「シュバルツ……」
ドモンは躊躇っていた。シュバルツの言っていることは理屈では分かる。でも、これではシュバルツ一人を死地に放り込むようなものではないのか。
「私のことなら心配するな。万が一敵の手に落ちたとしても私は『龍の勾玉』を持っていないし、オリジナルのキョウジが無事なら、私は何度でも甦ることができる…」
「――――っ!!」
ギッ! とドモンが顔を上げた。
「あんただって俺の大事な兄さんだ! オリジナルだとかコピーだとか、そんなことを言うな!!」
ドモンはそう言って、全身で怒りをあらわにしている。
(……事実を言っただけなんだが…。言葉を誤ったか……)
シュバルツは少々うんざりしながらこの熱血漢の弟を見つめていた。この手の話題になると、いつも弟はこのような反応を見せ、結局水掛け論になってしまう。今は、そのような論議に時間を割いている場合ではないというのに。
―――キョウジと同じように、こいつも殴り倒せばよかったか?
キョウジもシュバルツが囮になると言えば、「お前を捨て駒にするような真似はできない」とか言い出して、反対するのが目に見えていた。説得するのがめんどうくさいので、手っ取り早く殴り倒したのだが…。
ドモンの方をちらりと見る。しかし、ドモンはこちらに一撃で倒されてくれるような隙を見せてくれそうになかった。第一、二人とも殴り倒してしまったら、伝言を預けることができなくなってしまうではないか―――。
焦る気持ちをぐっとこらえ、シュバルツはドモンに向き直った。
「分かった、ドモン。俺が悪かった――――」
「兄さん……」
ドモンは、言いようのない淋しさに襲われていた。目の前の兄は、ちっとも自分自身のことを大事に思っていない。簡単に命を捨てるようなことを言う。その態度が、こちらにどれだけ辛い思いをさせているのか分かっていない。「分かった」と言いながら、ちっともわかっていない!
「だがな、敵は待ってはくれんぞ。こうしている間にも、包囲は狭まりつつある」
腕組みをしつつ、シュバルツはドモンに現実を突きつけた。
「―――分かってる! 分かってるよ!!」
ドモンも、自分が半ば駄々をこねていることは分かっていた。だが、自分の中でどうしても割り切ることができない。正体不明の恐怖に似た感情が、ドモンの中で渦巻いている。
「ドモン」
シュバルツはドモンを正面から見据えた。
「今、私たちが守らなければいけない者は誰だ?」
「それは……」
「そこに倒れているキョウジだろう?」
「…………!」
ドモンは、そこに無防備な状態で倒れている兄に目を走らせた。そうだった。こっちの兄さんは、本当に守らないと…!
「―――頼む。彼をしっかり守ってくれ。彼を守ることが、私を守ることにつながる」
「兄さん……」
「頼む……な?」
「…………」
こうまで兄に頼まれては、折れざるを得ない―――ドモンはついに頷いた。
「で、でも…これから俺はどうすれば……」
心細さの一因を、素直に口にするドモン。シュバルツは苦笑した。そんなのは自分で考えろ、と、突き放してもよかったが、折れてくれたドモンに免じて、ヒントを与えることにした。
「『龍の勾玉』について、キョウジと一緒に調べてほしい。……お前にはお前の、情報の伝手があるはずだ」
(―――――あ!)
ドモンの脳裏に、ある人物が浮かぶ。
―――――師匠!
そうだ! 古今東西の戦いの歴史に精通したあの人ならば!
ドモンの瞳に生気が戻る。もう大丈夫だな、と、確信したシュバルツは、ドモンに声をかけた。
「じゃあ私は行くぞ。今からゆっくり百数えて、周りの状況を確認してからここを脱出しろ」
「―――分かった」
力強く頷く弟に笑顔を見せて、シュバルツは出ていこうとした。
「兄さん!」
後ろから追いかけてきた声に、もう一度振り向く。
「―――死ぬなよ!」
(実際死なないんだけどね……)
ちょっと困ったように微笑んで、シュバルツは出ていった。
シュバルツが出て行った後、ドモンは兄のそばに腰を据え、油断なく身構えた。
(大丈夫……シュバルツは死なない……)
不安をぬぐうように、自分に言い聞かせる。とにかく今は、自分のできることを―――兄さんを守る。そして、師匠に会う!
(一………二………三………)
ドモンはゆっくりと、百までのカウントを開始した。
一方、地下から出てきたシュバルツは、素早く出入り口を閉じる。周囲に殺気は感じるが、幸い家の中まで覗かれている気配はなかった。まだ少し距離がある。
(さてと、どれが釣れるかな?)
―――キョウジは狙われている。それも、複数の敵から。
これが、現時点でシュバルツがつかんでいる情報だった。「複数の敵」という情報を結局渡すことができなかったが、仕方のないことだと思った。この情報を、今のドモンに渡したところで状況は変わらないし、話がこじれるだけだからだ。
この中で一つだけ、シュバルツは気になる情報があった。『龍の勾玉』を狙っている敵の中に、『龍の忍者』がいるというのだ。『龍の忍者』―――その存在自体、伝説と思われてきた忍者だ。噂では、神をも滅する力があるという。相対したいような、出来れば相手にしたくないような―――複雑な気持ちだった。
鬼が出るか、邪が出るか。
突き刺さるような殺気を感じながら、シュバルツは、玄関のドアを開けた。
「―――ターゲットが出てきた」
少し離れた屋根の上から、ドモンの家を確認していた黒づくめの忍び装束を着た男が声を出した。
「一人か?」
別の男が問いかける。
「そのようだ」
男たちが眼下を確認する。確かに、キョウジ・カッシュが一人で歩いていた。
「うかつな。狙われていることに気が付いてないのか?」
一人の問いかけに、別の男が鼻で笑う。
「直接的な接触すら、今日が初めてだ。内偵の痕跡も残していないのに、気づいているはずがない」
「やるか?」
仲間内の気の早い一人が、もう手に獲物を持って構えている。
「まて。家との距離がまだ近すぎる。奴の弟に気づかれる可能性がある」
「武術の達人、と言ってもわれら黒蜘蛛党の敵ではないであろう? 出てきたら、返り討ちにすればよい」
「……確かに。だが、不確定要素は少しでも排除した方が良い」
リーダー格の男が、断を下す。
「残月殿が来る前に、片をつける……行くぞ」
黒い影たちが、キョウジの後を追って動き始めた。
(……来てるな)
シュバルツは歩きながら、周りの気配を探った。割と近くに三人。それから少し離れた屋根の上から、こちらの動きがよく見えるところに陣取っている者が、二人。後、読み取れないが、もう少し離れたところに何人かいるようだ。
彼らは、すぐに手を出してくる気配はなかった。キョウジからドモンを、少しでも引き離したいのだろう。それは、こちらとしても好都合だった。近所のコンビニにでも行くように装いながら、家との距離をあけていく。
やがて、シュバルツ―――キョウジは、薄暗い路地へと差し掛かった。
―――やれ!
リーダー格の男の合図と同時に、仲間が棒手裏剣を音もなく投げつける。
不意に、キョウジが身をかがめた。
(避けられた!?)
男たちは一瞬色めきだったが、すぐに身をかがめた理由が判明した。彼は、靴ひもを直していたのだ。
カッ! と音を立てて、キョウジの目の前の地面に棒手裏剣が突き刺さる。
「?」
きょとん、と不思議そうな顔をして、キョウジは目の前の物体を眺めている。ならば、と、先ほど棒手裏剣を投げつけた男が、続けざまに三本キョウジに向かって新たに放った。
「わわっ!?」
キョウジは三本とも器用に避けた後、バランスを崩して倒れてしまった。
「いてて……」
腰の辺りをさすりながら起き上る。
「ほう、うまく避けたな。キョウジ・カッシュ」
声のする方にキョウジが顔を上げると、路地に黒づくめの忍び装束に身を固めた男たちが三人、道を塞ぐように立っていた。
「―――な、何です? あなた方は…」
キョウジの端正な顔に、あからさまに怯えの色が浮かんだ。
「我らと御同道願いたい」
三人の男たちは、キョウジの逃げ場を塞ぐように取り囲んだ。後ずさりをしたキョウジだが、ドン、と壁に背後を阻まれてしまう。
「あ……う……」
怯えのあまり声も出せないキョウジの様子に、男たちの間から失笑が漏れた。なんて楽な仕事だ、と、男の一人がキョウジに手を伸ばした瞬間。するり、とキョウジが男たちの包囲網から抜け出した。男たちの身体のわずかな隙間から転がり出たのだ。そのままキョウジは、一目散に走り出す。
「―――ほう、活きのいい子ウサギだ。そうこなくてはな」
キョウジは走っているが、そのスピードは忍者の足と比べるべくもない。
「我ら相手に、どこまで逃げ切れるかな?」
男たちは楽しそうに後を追い始めた。先ほどのキョウジの怯えた表情が、彼らの嗜虐心に少なからず火をつけたようだ。
走りながらシュバルツは素早く左右に目を走らせる。もちろん、本気を出して走っていない。キョウジを狙いに来た者たちの注意を、すべて自分に引き付けるためだ。彼らが家から離れ、こちらに集中してくれればくれるほど、ドモンとキョウジの脱出がたやすくなる。
―――さあ、お前たちの「餌」はこっちだよ。
もっと私に、喰いついて来い!
追手の一人が、キョウジの足元めがけて棒手裏剣を投げつける。読み通り、キョウジはバランスを崩した。
「頂き!」
間を開けず、男が転んだキョウジの上に飛び乗ろうとする。ところが、キョウジは間一髪のところでまたしても避けた。何とか体勢を立て直し、また走り出す。
だが、彼の行く手はまたしても別の大男に阻まれてしまった。
「頑張るじゃないですか。学者先生」
馬鹿にしたようにキョウジを見下ろしてくる。
「…………!」
何とか突破口を探そうとするが、男によってたやすく封じられてしまう。
「ぐずぐずしていると捕まりますよ。学者先生!」
仲間の一人が、背後からキョウジを羽交い絞めにしようとする。だが、その目論見は、寸でのところでまたしても失敗した。転びながらも器用に避けたのだ。それを見た道を塞いでいた男がキョウジを捕まえようとしたが、手の間をするり、と抜けられた。前方が開いた、とキョウジは見るなり体勢を立て直して再び走り出す。
「こ、こいつ……!」
男たちは躍起になってキョウジを追いだした。キョウジの足は、決して速くない。たやすく追いつくことができる。ただ、そこから先、捕まえようと手を伸ばすが、何故か捕まえることができない。あと一息、というところで、すっと逃げられてしまう。
「何をやっている!? 早く捕まえろ!」
屋根の上から見張り役が叫ぶ。
「分かっている! だがこいつ、なかなか素早くて…!」
そう言いながらキョウジを捕まえようと腕を振り回していた男が、何度か空振りをした後にバランスを崩し、あろうことか転んでしまった。チッ、と舌打ちをしながら、見張り役の男たちが追跡に加わる。その後ろからさらに、新たな見張り役が屋根の上に現われた。
―――やはり、まだ潜んでいたか!
ぜいぜいと肩で息をして、走るのもつらそうに装いながら、シュバルツはその様子を冷静に見ていた。いったい全部で何人がこの場に来ているのか。やはり、もっと家から離れねばならない。もっと遠くへ―――出来るだけ遠くへ!
「どうだ! これならばもう逃げられまい!」
5人がキョウジの周囲をぐるりと取り囲む。
「く………!」
さすがに進退きわまったような表情を見せるキョウジ。勝利を確信した男たちは、合図とともに一斉に飛びかかった。
「何!?」
直後、その様子を見ていたリーダー格の男から驚愕の声が上がった。5人の男たちが飛びかかる時にできた一瞬のわずかな隙間から、するり、とキョウジの身体が抜け出てきたのだ。抑え込むべきターゲットを見失った5人の部下たちの身体がぶつかり、無様に重なり合っている。いくら素早いといっても、ここまで来ると最早神業のレベルだ。
―――こいつ、まさか。
試しに、キョウジに向かって棒手裏剣を投げつける。すると、彼は目を開けたまま棒手裏剣の動きを見て、ぎりぎりまで引き付けたうえですっと避けた。そのあと、派手にバランスを崩して転がっている。
「ふざけるな!!」
リーダー格の男は6本の棒手裏剣をじゃらっと取り出すと、十字打ちという手法で投げつけた。これは、文字通り6本の手裏剣が十の文字状にターゲットに襲いかかる。よほどの手練れでも、すべての手裏剣をよけきることは不可能な技であった。
「―――っ!」
転んだところに十字打ちに襲われたシュバルツは、それでも5本までは避けきった。ただ、最後の1本が、左腕に突き刺さってしまった。
「ぐぅっ………」
よろめきながらも立ち上がり、シュバルツは再び走り出す。
「やった! さすが頭領!」
部下がのんきな賛辞を送ってくる。
「馬鹿もの! 早く奴を追え!」
「え? もう捕まえられるのも時間の問題なのでは?」
自分の部下は、まだ状況が分かっていない。黒蜘蛛党の頭領は、本気で部下を殴りたくなった。
「まだ分からんのか!?」
「はあ?」
「奴は、あの転んだ体勢から、俺の投げた十字打ちをほぼ完全に避けたのだぞ!?」
「――――!」
部下たちが息を呑むのが分かった。
「奴は相当な手練れだ。手負いの今、仕留めておかないと逃げられてしまう…早く追え!」
(ばれたかな?……まあ、ごまかしきれるとは思っていなかったが)
追手から少し離れたところで身を隠したシュバルツは、腕に刺さった棒手裏剣を抜き、簡単な止血処理をする。傷口の成分を分析してみるが、棒手裏剣に毒を塗られたりはしていないようだった。
(さて、これからどうする。まだ追手を引き付けておきたいが…)
不意に、頭上の空気を割く音がする。
「!」
素早く転がり、それを避けた。シュバルツのいた場所に、棒手裏剣がドドッと突き刺さる。
「―――やはり、避けたか! 次だ!!」
声と同時に、抜刀した3人がシュバルツに襲いかかる。一人はシュバルツの首に、一人は胴に、一人は足に、それぞれ狙いを定めていた。
シュバルツの方に躊躇はなかった。襲ってきた3人よりもさらに高く跳び上がる。足を払おうとした者が空振りをし、胴を襲った仲間を誤って斬ってしまった。斬られた者が悲鳴をあげて倒れる。
「!」
首を狙った者にも隙が生じる。それが、彼の命取りとなった。いつの間にかそばに来ていたシュバルツの蹴りが、まず刀を遥か上空に奪う。それから、強烈な回し蹴りを放った。それを喰らった男の身体が、はるか後方に吹っ飛ぶ。
「何だと!?」
自分たちの必殺の戦法があっさり破られてしまったのである。黒蜘蛛党の頭領は、驚愕の眼差しを目の前の青年に向けた。青年は着地と同時に、蹴り飛ばした刀をその手におさめていた。まるで、そうなるのが必然だと言わんばかりの動きだ。
「き、貴様何者だ!?」
頭領の背に、冷たい物が流れる。予想以上の腕だと思った。
手にした刀を構えるでもなく、青年は静かに佇んでいる。なのに、一分も隙が無い。
「何者って……キョウジ・カッシュですが…」
妙にのんきな声が響く。そう。彼もまた、キョウジ・カッシュ。嘘は言っていない。だが、黒蜘蛛党の頭領は頭を振った。彼が聞きたいのは、そういうことではないのだ。
「キョウジ・カッシュは学者のはずだ!」
「ええ。確かに学者ですよ」
そう言ってシュバルツはにっこりほほ笑む。それは、この場にはあまりにも似つかわしくないほどの、優しい笑みだった。
「私は、キョウジ・カッシュです。―――何を言えば、信じてもらえますか?」
態度は慇懃、顔には笑顔。
「生年月日ですか? それとも、家族構成?」
なのに、その場にいる全員が、何故か気圧されていた。微笑まれているのに、笑顔が別の何かに見える。
「何でしたら―――『例の事件』の、私しか知らない真相を語って差し上げましょうか?」
「や、やめろ!!」
たまらず頭領は静止した。
「お前がキョウジ・カッシュだということは認めることとして―――」
声が上ずる。彼は、自分たちの情報収集の甘さを悔いていた。このような悪魔的な男だと知っていたら、もっと万全に備えをしていたものを…。
「りゅ、『龍の勾玉』を、お前は持っているはずだ」
「龍の……勾玉?」
シュバルツは、さも今はじめてその名を知った、という風な顔をする。
「お、おまえが空港で手に入れたことは、分かっているんだ! 監視カメラにも映っていたし、目撃者もいたんだぞ!」
部下の一人が、悲鳴のような声を上げた。
(なるほど。そこまで分かっていたのか…)
ご親切にどうも。と、口の中で情報提供者に礼を言う。
「空港で…………ああ、あれね」
まるで、昨日の夕食のメニューでも思い出すようなのんきさで、シュバルツは返した。
「持っている……と、言ったら?」
「それをこちらによこせ」
間髪入れず、頭領が答えた。
「う~~ん、どうしようかな……」
ぽりぽりと頭をかきながら、シュバルツは悩んで見せた。
「そもそも、『龍の勾玉』って何なんです?」
ちらり、と、頭領の方に目を走らせる。
「貴様がそれを知って何とする?」
ぎろり、と睨み返された。
「単に学者としての興味ですよ」
シュバルツは肩をすくめた。肝心の『物』の正体について、ここで話を聞くのは難しそうだった。
「とにかく、それを奪還することが我らの使命―――渡してもらおう」
「お断りします」
「………!」
予想していたとはいえ、あまりにもはっきりと断られたので、思わず頭領の眉が釣り上がる。
「―――あなた方のやり方が気に入らない。どうせ、ろくな事には使わないでしょう」
そう言って、青年はまたにっこりほほ笑む。頭領は、頭に血が昇るのを感じた。
―――なめられている。
直感的に、そう思った。
「そうか、残念だ」
頭領は、怒りで震える手を刀の柄に伸ばした。
「一つだけ言っておく。我らが欲しいのは『龍の勾玉』……お前の生死までは問われていない」
そう言って青年を見る。しかし、彼の表情はピクリとも変わらない。
「……伝承の通りなら、お前の身体に勾玉は吸収されているはず」
「…………」
ふっと、困ったように青年は微笑む。頭領はその表情の動きで、彼がまさに勾玉を持っている、と確信した。
(勾玉が身体に吸収されたのは、伝承に沿った事。そして、敵方にとって、キョウジの生死は問題ではない……)
新たにこれだけの情報を得られた。勾玉の正体が判らなかったのは残念だが、それなりの収穫と言っていいだろう。
(これは、ますますキョウジ本人を敵の手に渡すわけにはいかなくなったな…)
「―――殺!」
頭領の鋭い掛け声とともに、その場にいる黒蜘蛛党全員が一斉に抜刀した。そして、二重の輪を作り、シュバルツを取り囲む。たとえ、輪の一重目をシュバルツが飛んで脱出をしたとしても、外側の輪の者がシュバルツが着地した瞬間を狙うだろう。中の輪が5人、そして、外の輪が……8人。
充分引き付けられたな。
シュバルツは思った。これだけの人数がこちらにいる。おそらく、ドモンの家への注意は、完全に逸れているはずだ。距離も時間も、十分稼げたはず。
(ドモン、うまく脱出しろよ)
シュバルツは、右手に持っていた刀を逆手に持ち直し、改めて構えた。
中の輪の5人の役割は、はっきりしていた。ターゲットを飛びあがらせさえすればよいのだ。どんな達人でも、慣性の法則に逆らうのは不可能である。着地の瞬間に、どうしても隙ができる。とどめは、外の輪の者がしてくれる。
標的を逃げられないように囲い込み、足を狙って攻撃を繰り出す。
刹那、シュバルツが動いた。黒蜘蛛党の予想に反して、彼は飛び上がらなかった。身を低く低くして、包囲の一角に突っ込んでいく。
裂帛の掛け声とともに足を跳ね飛ばされたのは、黒蜘蛛党の男の方だった。
「こいつ!」
シュバルツに向かって棒手裏剣が飛ぶ。あっさり避けられ、あろうことかシュバルツに攻撃を仕掛けようとした味方に当たってしまった。動揺した一瞬の隙に、シュバルツの投げた棒手裏剣が眉間に食い込む。
(3人!)
刀を構えなおして、再び低い姿勢を保ったまま黒蜘蛛党の陣に突っ込んでいく。
(速い!!)
頭領は棒手裏剣を構えたまま唸った。低い姿勢で陣の中を駆け回るシュバルツに、手裏剣を投げつける隙を見出すことは不可能だった。それどころか、部下たちの身体が壁となり、同志打ちの危険すら漂わせている。こうしている間にも、彼の手によって部下が次々倒されていく。
―――このままでは逃げられてしまう!
黒蜘蛛党の頭領の思考は、ここで途切れた。あり得ない後ろからの攻撃によって、命を絶たれたのだ。末期の声を上げることもなく崩折れる頭領の背後に、黒い忍者の姿があった―――。
(何だ?)
戦いながらシュバルツは、違和感を覚える。空気の流れが変わった。先ほどよりも濃くなる、血の匂い……。
ばたっ、と人の倒れる音がする。異変は、外側の輪の方で起きているようだ。
どんどん、人の気配が消えていく。その間を、一陣の黒い風が走り抜けていく。
「――――!」
黒い風に不吉なものを感じたシュバルツは、思わず距離を取った。
黒蜘蛛党の最後の一人が悲鳴とともに倒れ、その場に立っている者は、シュバルツと黒い風の主だけとなった。ブン、と、刀の露払いをし、ゆっくりとシュバルツの方にその主が振り向く。
―――何だ、こいつは!?
覆面の間から覗く色素の薄い緑色の瞳に射すくめられたシュバルツは、全身が総毛立つのを感じた。
強さが分かった。
危険さが分かった。
生存本能が警告を発する。
生き残りたければ、絶対にその前に立ってはならない相手だと。
「キョウジ・カッシュか?」
低い声で、問われる。
「そうだと言ったら?」
声が震えそうになるのを、かろうじて抑える。
危険。
キケン。
刀を握る手が、じっとりと汗ばんでいるのが分かる。
「『龍の勾玉』はどこだ」
黒の忍者は、必要なことだけを聞いてくる。
―――やはり、こいつも『龍の勾玉』狙いか!
シュバルツは唇をかみしめた。
こいつの腕は、おそらくドモンと互角。いや、それ以上かもしれない。
『龍の勾玉』が狙いならば、おそらくこいつもキョウジの生死を問うてはいない。キョウジを庇いながらこの男と戦うことは、ドモンでも厳しい物になるだろう。
「それを、私が答えると思うか?」
シュバルツは悟った。自分の役目は、一分でも一秒でも長くこの男をここに足止めすることだと。片手で持っていた刀を、両手でつかんで構えなおす。
黒の忍者―――リュウ・ハヤブサは、その様子を黙ってみていたが、やはり、戦いは避けられないものと悟る。
あれから、残月を追跡していたハヤブサであったが、残月もまた『龍の勾玉』を手に入れられず、探しているという情報を得た。そして、独自に勾玉の行方を追跡しているうちに、手に入れた可能性のある人物としてキョウジ・カッシュが浮かんできたのである。
ハヤブサは、黒蜘蛛党よりも少し遅れてカッシュ邸に向かっていた。その道中でキョウジ―――正確にはシュバルツなのだが―――と、黒蜘蛛党の戦いに行きあたった。肩書きは学者であるはずのキョウジが、黒蜘蛛党相手に互角以上の戦いをしている。
(面白い)
ハヤブサは、純粋に興味を持った。
「勾玉を持つターゲット」と言う以上に、手合わせをしたいという衝動に駆られたのは、剣士としての性だろうか。
「答えぬか?」
「断る!」
問いを、一刀両断された。もう、話し合いは成立しない。
「ならば、剣に問うまで―――」
ハヤブサもまた、ゆっくりと刀を構えなおす。先ほどの黒蜘蛛党との戦いから、キョウジの腕を認めたから故の構えであった。
(龍のイメージ?)
ハヤブサの構えから、シュバルツは直感的に感じる。
「我が名は、ハヤブサ」
黒の忍者が名乗りを上げた。
ハヤブサ―――リュウ・ハヤブサ。『龍の忍者』か!
なるほど、道理でと、シュバルツは合点がいった。狙われていることは知っていたが、こんなに早く接触できるとは思っていなかった。思いもかけぬ大物が釣れてしまった。
「いざ、参る」
ジャリ、と、龍の忍者が半歩、動く。
(―――来る!)
シュバルツはふっと息を吐き、身体の余分な力を抜く。そして、ハヤブサの動きに全神経を集中させていく。
果たしてその瞬間、一体どちらが早かったのか。
ダン! と、踏み込む音と同時に二人の姿が消えた。刹那、裂帛の気合と同時に青白い剣撃が、二人の間を交差する。
いた場所を入れ替えて、着地する二人。だがすぐ、お互いが次の攻撃動作へと移った。空中で、凄まじい斬り合いが繰り広げられていく。切り結ぶたびに、二人の間に青白い火花が飛び散った。
「哈―――――っ!!!」
「うおおおおおっ!!!」
ガキィッ!!
影が二つに分かれ、地面に着地する。シュバルツの頬の傷から、一筋の血が流れ、同時にハヤブサの覆面の一部も裂けた。
(―――速い!)
(強い!)
互いの腕を認めた瞬間だった。
シュバルツの目的ははっきりしている。ハヤブサとの戦いを、少しでも長引かせること。あわよくば、打ちとること―――。しかし、ハヤブサの繰り出す攻撃は、一撃一撃が鋭く、重い。そう何合も受けきれるものではない。少しでも対応を誤れば、こちらがやられてしまうだろう。
唯一勝機があるとするならば、それは―――自分の「不死」の特性を利用することだ。
一度死して油断を誘ったところを不意打ちするのが一番現実的だが、全機能が停止してから回復して再び動けるようになるためには、少なくとも3時間はかかる。それだけの時間をハヤブサほどの忍者に与えてしまうのは、危険すぎるといえた。3時間の遅れが、ドモンと本物のキョウジへの致命傷にもつながりかねないからだ。
ならば、相打ちに持ち込むしかない。
それも、相手を確実に仕留められるような方法で。打ち損じは、許されない。
―――これは……本当に、最後の手段だな…。
シュバルツはふっと笑う。
(笑った?)
命のやり取りの最中に、こんな風に笑う人間は滅多にいない。ハヤブサは警戒して少し距離を取った。
ハヤブサからの攻撃が、少しの間止まる。シュバルツが仕掛けた。
消せ。
消せ。
すべての気配を。
駆動音すら―――消えてしまえ!
「む!?」
ハヤブサは目を疑った。目の前にいるキョウジの姿が、まるでかき消すように見えなくなっていく。ハヤブサが手裏剣を投げつけた時には、キョウジの気配は完全に消えていた。手裏剣が、むなしく空を切っていく。あたりを探ってみるが、どこにいるのかまるで見当もつかない。
(見事なものだ…。これほどの忍びがまだいたか!)
ハヤブサは素直に相手に賛辞を送った。ここまで気配を完全に消せる忍びはなかなかいない。それだけに確信する。奴は逃げてはいない。必ず近くにいて、自分を討つ機会を虎視眈々と狙っていると。
ハヤブサは、目を閉じた。見えない以上、目に頼っていても仕方がないからだ。刀を構え、周りの気配に集中する。
感じろ。
わずかな空気の流れ。
動き。
気配。
背後の―――空気!
ほんのわずか、空気を割く音がしただけだった。反応があと少し遅ければ、ハヤブサの身体は真っ二つになっていただろう。
「ちぃっ!」
渾身の一撃をかわされたシュバルツが舌打ちをする。だがすぐに踏み込み、ハヤブサとの距離を詰める。再び激しい剣の応酬が始まった。二つの影がぶつかり合うたびに、金属音と青白い火花が当たりに飛び散る。
シュバルツの左腕に時々痛みが走る。今になって、この痛みが煩わしくて仕方がない。ほんのわずかな遅れが即、こちらの『死』につながる。痛みに気をとられるな! 今は戦いに集中するのみ!
「うおおぉぉ―――っ!!」
シュバルツから、凄まじい手数の攻撃が繰り出される。
(速い!!)
ハヤブサはそれらを紙一重でかわし、受け、時に払う。そして、攻撃のチャンスを待つ。スピードと手数で押してくる相手というのは、動作から動作に移る一瞬の間に、わずかだが隙ができるのが常だ。しかし、目の前のキョウジからは、なかなかその隙が見いだせない。
ガン!!
キョウジからの刃を、真っ向から受け止める。力勝負なら、若干こちらに分があるとハヤブサは感じる。
「吩!!」
力任せに刃を押し返す。弾き飛ばされたかに見えたキョウジの身体が、空中でくるりと猫のように回転する。そのまま着地するであろうと思われる場所に、ハヤブサは手裏剣を投げつけた。だがキョウジは、そこに刀を突き立てて手裏剣をかわす。刀を軸にくるりと回って地面に着地した。
もちろん、その隙を見逃すハヤブサではない。猛スピードで距離を詰め、キョウジに攻撃を仕掛ける。キョウジは地面に突き立てた刀をあっさりあきらめた。ハヤブサの攻撃を右に左にかわしながら、懐をまさぐる。
ごろり、とキョウジは転がりながらハヤブサに向かって両の拳を突き出す。ばっと手を開くと、そこから投網のようなネットが現れた。
「何!?」
このままでは絡め捕られると判断したハヤブサは、スライディングをしてそれをかわす。その間に、キョウジは再び刀を手にしていた。
「やるな……」
思わず相手への賛辞が口に出た。ハヤブサにしては珍しいことだ。
「…………」
シュバルツはそれには応えず、ともすれば乱れがちになる息を整えて、刀を構える。止血を施した左腕の傷から、ジワリと血が滲み出て、腕に巻いた白い布を赤く染めていた。負荷がかかりすぎて、DG細胞の再生が追い付いていないのだ。
(まだだ! まだ倒れるわけにはいかない!)
刀を構えて再び対峙する二人の間を、一陣の風が吹き抜ける。二人の戦いは、このままいつ果てるともなく続くと思われた。
二人にとって不幸だったのは、ここが誰もいない荒野ではなく、街中だったということだ。
とあるアパートの一室で、母親が娘に起こされていた。
「のどが渇いた」
と、言うので、娘に茶を入れてやる。茶を一気に飲み干した後、娘が口を開いた。
「ねぇ、ママ。何か変な音がするよ?」
「気のせいじゃないの? ママ、何も聞こえないわよ?」
5歳になったばかりの娘の結衣は、空想力が豊かすぎるのか、時々あらぬ方向をじっと見ていたり、突拍子もない事を言い出すことがある。どうせ今回もその類だろうと、母親はまじめに取り合わなかった。それよりも、夜中に起こされてかなり眠い。明日も仕事があるし、早く寝てほしいと思った。
しかし、娘は母親の気持ちを知ってか知らずか、窓の方をじっと見つめている。
「何かぴかぴか光ってるよ? あれ何~?」
どうせ道路工事のネオンか、信号か何かだろう、と思いながら、母親も娘が指さしている方を見る。しかし、そこにあるのは闇ばかりで、何も見えなかった。
「何もないわよ?」
普段はこう言えば、娘は引き下がるのだが、その日はなぜか違った。
「ううん。絶対光ったよ? あ! ほら、また!」
母親も見るが、母親にはやはり闇しか見えない。
「何だろう……? 花火かなぁ?」
娘はそう言いながら、窓へとにじり寄っていく。母親はため息をつきながら娘を見守った。ここは3階だ。窓には手すりが付いているとはいえ、落ちたら危ない。娘のことを頭から否定してへそを曲げられても面倒なので、しばらくは娘のしたい様にさせてやる。
「きれいだな……」
結衣は窓を開け、手すりにしがみついて光を見つめていた。
そのアパートからかなり離れたところで、シュバルツとハヤブサの討ちあいはまだ続いていた。青白い剣撃の火花を飛び散らせながら、高速で移動し、ぶつかり合う。二人の間で「加減」の二文字はとうに吹き飛んでいる。それどころか「周りへの配慮」すら、彼方に消えていこうとしていた。もうシュバルツもハヤブサも、互いの姿しか見えていない。足場がどうだろうと、周りに何があろうと最早関係なく、互いの姿だけをただ追い求め、剣を交える。
ハヤブサから繰り出される何度目かの剣撃を刀で受けた瞬間、シュバルツの左腕に激痛が走った。
「ぐ…あ……ッ!」
ほんの一瞬、初めてといっていいほどの隙がシュバルツに生まれる。それを見逃すハヤブサではなかった。今日一番と言って良いハヤブサの渾身の一撃が、シュバルツを襲う。
「!!」
受けるのは無理、と判断したシュバルツは、咄嗟に身をよじる。それでもわずかに反応が遅れた分、剣先がシュバルツの身体をわずかに掠め、シャツを切り裂く。
そして、斬撃の威力はそこだけではおさまらなかった。
ガシャン!!
派手な音を立てて、背後の壁と窓が破壊される。その窓には、結衣がいた―――。
(あ…………!!)
身をよじって壁の方に身体を向けていたシュバルツには、破壊された窓と、壊れて落ちていく手すりにしがみついて目を見開いている少女の姿が、はっきりと見えた。
危ない―――!
瞬間、シュバルツの頭からすべてのことが吹き飛んだ。
キョウジのことも、龍の勾玉のことも、目の前のハヤブサのことすらも。
ただ、スローモーションのように落ちていく少女の姿だけが、意識のすべてを支配する。
考えるより先に、手が出ていた。脊髄反射と言ってもよかった。
少女の身体に必死に手を伸ばし、引き寄せる。
腕の中に少女の安全を確保してから、はっと気がついた。
―――しまった! 戦いの最中…!
(何をしている!?)
斬るつもりで第2撃を放とうとしていたハヤブサも驚いた。それまで隙らしい隙を見せてこなかったキョウジが、全く無防備に自分の前にその身を晒している。それも、ただ一人の少女を助けるためだけに。
―――何をしている!? 斬ってしまうぞ!!
「く……!」
斬ろうとしていた腕を何とか抑え、ハヤブサも少し距離を取る。キョウジを斬る、千載一遇のチャンスだった。それを逃す自分も、まだまだ甘い。
少女を抱えたキョウジがこちらを見る。
(どう動く?)
ハヤブサは刀を構える。一度は見逃した。だが、二度は無い。
少女を置いて戦いに戻るか、はたまた少女を人質に取るか―――。
シュバルツは、そのどちらも選ばなかった。人質どころか、少女をこれ以上巻き込むことすら、己の中では是とできなかった。勝敗は、すでに決していた。少女に気を取られた瞬間、ハヤブサは、確実に自分を斬ることができたはず。自分はこの勝負に負けたのだ。彼がなぜあの時自分を斬らなかったのか。それは分からない。
ただ、自分たちの戦いに巻き込んでしまったこの少女だけは、元いた場所に返したいと願った。
―――すまない。ドモン、キョウジ……私は、ここまでだ。
心の中で、二人に詫びた。
シュバルツは、刀を捨てた。ハヤブサの前で、刀を捨てる―――これが、何を意味するのか、分からぬシュバルツではない。ただ、自分の生殺与奪の権利は、勝者であるハヤブサにある、と、思った。ハヤブサから目をそらし、背を向ける。彼女が落ちてきた、破壊された窓に視線を移す。自分は、願いをかなえるだけ。
ハヤブサは、少なからず衝撃を受けていた。何故だ。何故、こんな形で勝負に決着をつけようとする。暗殺者である自分の前にその無防備な姿を二度も晒すということが、どういうことなのか分かっていないのか!?
「―――ッ! 馬鹿者!!」
ハヤブサの悲鳴のような怒号が、辺りに響いた。
母親は、何が起きたのか理解できなかった。
分かるのは、いきなり壁と窓が壊れ、娘の姿が消えたこと。
(落ちた……!?)
そんなこと、思いたくない。でも、窓が無くなり、娘がいない。
確認しなければならない。でも、足がすくんで動けない。
娘が脳漿をぶちまけ、変わり果てた姿で瓦礫の中に横たわっている―――そんなことを思うだけで、気が狂いそうだった。
ふわ、と、誰かが壊れた窓から入ってきた。
青年のようだ。暗がりでよく見えないが、微笑んでいるように見える。そして、彼の腕の中に―――。
「結衣!」
娘の結衣は、何が起こったのか分からずきょとんとしているが、怪我もなく元気そうだった。
「結衣! 結衣!!」
娘の名前を必死に叫びながら、母親は娘に近づく。娘の方も母親に気がつき、「ママ!」と、無邪気に手を伸ばしてきた。
青年から娘を受け取る。娘の温かい体温を腕に感じた時、母親は、ようやく娘の無事を実感することができた。
瞬間。
ドンッ! という音とともに、目の前の青年が物も言わずに倒れる。青年の背後に、いつの間にか黒い忍び装束を着た人間が佇んでいた。そのあまりに異様な光景に、母親は思わず娘を抱きかかえたまま、一歩身を引く。
「―――邪魔をしたな」
黒の忍者が、小さく呟く。覆面の間から覗く緑色の瞳が、何故か淋しさをたたえているように見えた。
そのまま黒の忍者は青年の身体を抱えると、夜の闇へと消えていった。
「バイバイ……」
誰もいなくなった窓に向かって、少女はそう呟いた。怖さなど、少しも感じなかった。だって、しっかりと守られていたから―――。
「――――!」
不意に、キョウジの意識が戻った。と、同時に、自分の身体が狭い不安定なところに押し込められているのを感じる。いきなり下からガクン、と突き上げられ、頭をぶつけた。
「いてっ!」
思わず間抜けな声が出る。
「兄さん、気がついた?」
前方から、ドモンの声がする。
「ドモン?」
「待って、兄さん! まだ出てきちゃだめだ!」
ドモンの制止の声に、キョウジはそこから這い出ようとした動きを止めた。かわりに自分に掛けられている布のようなものを少し持ち上げ、辺りの様子を確認する。前方に、ドモンが運転している姿が見える。それで、ここがドモンの車の中だと気付いた。
「シュバルツが言っていた―――『兄さんが狙われている』って。だから、安全が確認できるまで、出てきちゃだめだ」
―――シュバルツ!
自分が意識を失う直前に、微笑んでいたシュバルツが脳裏によぎる。
シュバルツはどうした、と、言おうとした瞬間、ズキ、と、鳩尾に鈍い痛みが走った。
(あいつ…! 思いっきりぶん殴りやがって…!)
文句の一つも言いたくて、シュバルツの気配を探したが、近くに感じられなかった。
「シュバルツは……?」
ドモンが何か知っていないかと、たずねてみる。
「あいつなら、兄さんの代わりに出ていった」
「…………!」
キョウジは思わず絶句する。
「家に、兄さんを狙っている奴らが来たんだ。それを引き付けるために、あいつ―――」
「何でだ……シュバルツ、身代わりになんて……! 私は―――」
「俺は、一緒に逃げようって言ったんだ!!」
「ドモン……」
「だけど、あいつ、『守らなければならないのは兄さんだ』って言って、それで…」
「…………」
(お、落ち着け、自分。とにかく落ち着け―――)
自分の中で、いろいろとぐるぐる感情が回る。キョウジは、何とか冷静さを取り戻そうとした。
狙われていたのは、私。
私を守るために、シュバルツが出ていった。
どうして、彼がそういう選択をしたのか。それは、冷静になって少し考えれば分かる。
外見が瓜二つなうえに、彼の方が腕が立つ。囮としては、これ以上ないというほど最適な人間だ。たぶん、立場が逆なら、私でもそういう選択をする。
身体の組織がDG細胞によって構成されているため、ほぼ「不死」を誇るシュバルツ。唯一彼が「死」を迎える可能性があるとしたら、それは、彼の人格部分の元となったオリジナルの人間が死ぬこと―――即ち、私の死が、彼の死につながる「らしい」
「らしい」というのは、まだ、はっきりと確認ができているわけではないから。ただ、『デビルガンダム事件』の折、私が死にかけた際、彼の意識レベルも低下し、活動も困難になっていったという。
だから、彼が私を守ろうとするのは、彼が生きるために絶対必要な選択なのであって…。
なら何故。どうして。
どうしてだ、シュバルツ。
あの時。私の身代わりになると決意していたんだろう。
何故、あんな風に微笑んだんだ。
何で、あんなに幸せそうに。
まるで、私の身代わりになることが、最上の喜びであるとでも言わんばかりに―――。
私は、貴方にそんな風に守ってもらう資格のある人間じゃない。
だって―――私は―――人間であった貴方の―――。
「兄さん? どうした? 大丈夫か?」
「…………!」
ドモンの呼び掛ける声に、はっと我に返る。落ち着きを取り戻すどころか、自身の思考の暗黒面に陥りそうになっていたことに驚き、少なからず動揺した。
「あ、ああ…大丈夫。悪い。…少し、考え事をしていた…」
心臓が、早鐘のように脈を打っている。少し、汗もかいていた。
「ふうん? …ならいいけど」
ドモンは少し訝しんでいるようだが、それ以上は追及してこなかった。キョウジはほっと息をつく。
「あ、そうそう、シュバルツから一つ情報を預かったんだ」
ふいに思い出したように、ドモンが口を開いた。
「情報?」
「兄さんの、身体に入った光のこと……『龍の勾玉』って言うんだって。それ」
「龍の……勾玉」
キョウジは、光が吸収されていった己の右手を見つめた。
(勾玉か……そういえば、そんな感じの形だったかな)
ぼんやりと、あの日の光のことを思い出す。
「正確には、敵さんの狙いはその勾玉らしい…それ以上のことは、分からなかったらしいけど」
「そうか……」
―――シュバルツ…。
キョウジは、右手をぐっと握りしめ、胸に当てる。
覚悟を決めろ。キョウジ・カッシュ。
もう事態は動き出してしまっている。争い事が嫌だとか、そんなことを言っている場合ではない。
敵に狙われたのに、まだ自分はこうして無事で、弟と一緒に動くことができる。
これは、シュバルツが、身体を張って作ってくれた貴重な「時間」だ。
それに、私は応えなければならない。
(ありがとう、シュバルツ…。お前がくれたこの「時間」を、私は絶対無駄にはしない!)
キョウジは、自分の思考の暗黒面に、あえて蓋をした。今はまだ、これと向き合う時ではないと、直感的に感じる。シュバルツへの複雑な思いも、今は飲み込む。前に進むために、もう少しだけ、シュバルツに甘えることにする。
せめて、シュバルツの無事を祈る。
どうか、無茶だけはしないでほしい―――。
「ところでドモン。この車はいったいどこへ向かっているんだ?」
気持ちを切り替えて、キョウジは尋ねた。
「敵に狙われているこの状況で、俺が頼るところは一つしかない!」
ドモンが力強く宣言をする。
「え!? まさか……うわっ!」
ドモンがアクセルを踏み込んだため、狭い所に押し込められているキョウジの身体が、あちこちにぶつかった。
「師匠~~!! 待っていてください!!!」
ドモンの車が快調に夜の道を加速していった。
ハヤブサとシュバルツの戦いが終わった夜の街で、一つの黒い影が動いていた。
連絡係の忍者である。彼は戦いには参加せず、総てを見届ける役目を背負っていた。そこで起こったすべての顛末を、雇い主や別働隊に報告するためである。たとえ、そこで戦っていた者たちが全滅しても、忍者は必ずこういう手法を取って、情報が次に生かされるようにしてきた。古くからの伝統的なやり方である。
彼の頭の中には、キョウジ・カッシュが腕の立つ忍者であったこと。そして、ハヤブサに連れ去られたこと。キョウジが家から出て少し時間が経ってから、カッシュ邸から車が一台出ていった―――という情報が、入っていた。
そして、彼はもう一つ、役目を背負っていた。
全滅させられた黒蜘蛛党の遺骸があるところに行くと、懐のから鏡のようなものを取り出す。印を結んで呪文を唱えると、鏡の中から半透明の薄く輝くモノが現れた。あやふやな形をしているが、少女のようにも見える。
「ほら、餌だ。食え」
影の言葉と同時に、それは、死体を食べ始めた。骨を砕く音、べちゃべちゃと血液や内臓をなめるような音が、辺りに響く。あっという間にその場にあった死体を平らげてしまった。
半透明の少女が、まだ物欲しげに影の方を見る。しかし、鏡を再びかざされると、大人しくその中に入っていった。時間にして、わずか十分ぐらいの出来ことであっただろうか。
夜の街は、再び静寂の中に包まれていった。
「第三章」
知っていた。
知っていました。
私は、貴方の――――。
ハヤブサが、この廃ビルに入ってから、少し時間が経過していた。
(迷っている……)
ハヤブサは、今の自分の状態をそう感じる。これは、忍びにとって非常に危険な状態であるといえた。決断の連続である忍びは、わずかな迷いですら命取りになることがあるからだ。
目の前には、ハヤブサにとってまさに迷いの元凶であるキョウジ・カッシュが横たわっていた。手足には、戒めが施してある。
そう、戒めは、必要だ。彼は、腕の立つ忍者であるから。気がついた時、逃げられたら困る。
腕の立つ忍者……ここで、ハヤブサは頭を抱える。そう、彼は腕の立つ忍者のはずなのだ。それなのに。
脳裏に、先ほどの戦いがよみがえる。
彼は、一人の少女を助けるためだけに、全く無防備に飛び出していった。こちらへの警戒など微塵もなかった。こちらがその気なっていれば、10回くらいは斬り刻めている。それくらい、あの姿は本当に愚かだと思った。滑稽ですらあった。
(こいつ……この甘さで、よくここまで生きてこられたものだな…)
改めて、キョウジの顔をじっと見つめる。自分より少し年上ぐらいだろうか。
自分なら、少女を助けるためとはいえ、あんなにあけすけに飛び出して行ったりはしない。甘い。甘すぎる。
(いや、この甘さを装うのが、こいつの手なのかもしれない)
忍者の本質は詐道だ。いかに相手の裏をかくか、騙すか―――。もしも、こいつが甘さを装い、こちらの動揺を誘っているのだとしたら、こいつの目論見は半分以上成功していることになる。現に自分は今、迷っている。
そして、さらにハヤブサを悩ませる問題が発生していた。
『龍の勾玉』は、キョウジ・カッシュの身体に吸収されたものと思っていた。空港の防犯カメラの映像にも、光がキョウジの手元で消えていっているような様子が映っていたし、そのあと、はっきりと動揺しているキョウジの姿も捉えられていたからだ。
『龍の勾玉』が、この世に現れてから八百年。人の身体に吸収されたことは、稀にだがあったらしい。
だから、キョウジの身体を確保すれば、この任務はある程度完了するものと思っていた。しかし、今目の前にいるキョウジからは、『龍の勾玉』の波動が感じられない。つまり、キョウジは今ここに、『龍の勾玉』を持っていない―――と、言うことになる。
もしかしたら、誰かがこのキョウジ・カッシュになり済ましているのではないかとも疑い、変装かどうか調べてみたが、残念ながら、彼の髪も顔も本物だった。
(どういうことだ? 龍の勾玉は、こいつに吸収されなかったのか? それとも、まさか取り出すことができたとでも?)
ここでハヤブサは、頭を振る。一度身体に吸収された勾玉は、ある方法を経なければ取り出すことは不可能なはずだからだ。そして、それを行った人間が、生きているはずがない。
キョウジと龍の勾玉には接点がある。これは、確かな情報だ。
だから、本来なら、自分が取るべき行動は一つ。龍の勾玉の行方をキョウジにしゃべらせること―――だ。素直に協力してくれればいい。だが、戦いの前に確認した時、彼は、はっきりと撥ねつけてきた。おそらく、簡単に教えてはくれないだろう。
そうなると、こちらとしても手段を問えなくなる。最悪の場合―――。
「…………!」
ハヤブサは、悩む。こんな忍者にはあるまじき奇跡のような甘さを持った男を、使命のためとはいえ、非人道的に踏みにじってしまって良いものなのだろうかと。
もしかしたら―――こんな甘さを持った男なら―――筋を通して話をすれば…。
(危険だ)
本能が警告を発する。忍者は騙すもの。信じることは危険だ。
(だが、もしかしたら)
彼が自分の手に落ちた時のことを思い出す。刀を捨て、背を向けた時―――彼は、承知していた。これから自分の身に起こることを。こちらが近づいても、攻撃を仕掛けても、避けることすらしなかった。ただ、少女を母親へ返すことだけに、最後まで専念していた。
(馬鹿だ―――本当に)
その馬鹿なところを信じてみたくなっている自分がいる。一方で、危険だと自制を促す自分がいる。
(迷っている…)
そして、最初に戻る。
キョウジ・カッシュの刃と気迫が、自分と互角なものでなければ、ここまで迷いはしなかっただろう。こいつは一体何なのだ。すご腕の忍者なのに、信じられないほどの愚かさと甘さを併せ持っている。
(俺は、斬れるか? この男を)
ハヤブサは、自問自答する。どんな人間も、斬ってしまえば皆同じだ。物言わぬ肉塊に帰るだけ。そして、二度と会えない。ただ、それだけのことだ。こいつの強さと甘さと愚かさも、斬ってしまえばそこで終る。ただの肉塊になるだけだ。
(………タクナイ)
不意に、心の中に自分にとって信じられない言葉が並んだような気がした。まさか、と、ハヤブサがもう一度自分に問いなおそうとした瞬間。
「う………」
目の前のキョウジが身じろいだ。意識が戻ってきたのだ。
―――時間切れか…!
ハヤブサは唇をかみしめた。
まず、シュバルツの目に飛び込んできたのは、冷たいコンクリートの床だった。ここはどこだ、と、身体を起こそうとして、手足の自由が利かないことに気づく。縄のようなもので縛られていた。
(そうだった……私はハヤブサに)
「―――気がついたか?」
黒の忍者の低い声が響く。
―――ハヤブサ!
シュバルツは、入れかけていた身体の力を抜いた。ばた、と、無機質に、モノのようにそこに横たわる。この状態では、そうする以外に道はないからだ。
「……………」
ハヤブサはしばらく黙ってその様子を見つめていたが、やがて立ち上がり、シュバルツとの距離を詰めてきた。
「お前に、聞きたいことがある」
床に横たわるシュバルツのすぐそばまで来たハヤブサは、膝をついてそこに座る。覆面の間から見下ろしてくる色素の薄い緑色の瞳からは、何の感情も読み取れない。
「お前は、龍の勾玉を手に入れたはず」
「…………」
シュバルツは、沈黙を返す。それをある程度予想していたハヤブサは、かまわず続けた。
「だが―――なぜ今、それを持っていない?」
「――――!」
少し、シュバルツの表情が動いた。これは、彼にとっても予想外だった。まさか、こんなに早く自分が勾玉を持っていないことを見破られるとは思っていなかったのだ。
「あれは、俺の里の物だ。たとえ身体の中に吸収されていようと、俺はその波動を感じ取ることができる―――」
ここまでしゃべると、ハヤブサはキョウジの襟首をつかんで自分の方に引き寄せた。
「勾玉は、お前の身体に吸収されなかったのか?」
「…………」
「されなかったのなら、今どこにある?」
「…………」
「答えろ―――あれをどこにやった?」
「……私がそれを、答えると思うか?」
戦う前と、同じ答え―――予想していたとはいえ、ハヤブサは天を仰ぎたくなった。キョウジの襟首を握る手に、思わず力が入る。
(―――分かっているのか!? このままでは俺は、貴様から情報を得るために手段を選べなくなってしまうのだぞ!!)
「……喋らせる手段なぞ、いくらでもある」
間近でキョウジを睨みつけ、おどす。だが、彼は目をそらさなかった。
「拷問でもなんでも、するのなら、すればいい……私は、答えん」
冷たい眼差し。しかし、何もかも覚悟を決めて、受け入れる眼差し。ハヤブサは見ていられなくなった。思わずキョウジの身体を、ダン!! と、乱暴に床にたたきつける。
「貴様、あれがどういうものか分かっているのか!? あれは、世に出してはならぬ物だ!! 里の奥で、厳重に封印しておくべき物なのだ!!」
気がつけば、ハヤブサは叫んでいた。本来なら、決して外部に漏らしてはならない秘中の秘をだ。だが、ハヤブサ自身、もう止めることができなかった。
「あれは、大いなる災厄の源だ!! あれが世に災いをなす前に、俺は―――何としてもそれを止めねばならぬ! 例え、どんなことをしてでもだ……!!」
(ハヤブサ……!?)
シュバルツは信じられない思いでハヤブサを見つめていた。忍びというのは本来、自分の授かった任務を簡単に人に漏らすものではない。それを、彼は今、叫んでいるのだ。
―――お願いだ、キョウジ…!
俺に、お前を踏みにじる道を選ばせないでくれ…!
「頼む! 答えてくれ……。勾玉は、どこだ……!」
「…………!」
まるで、祈るような声だとシュバルツは思った。顔は伏せられて見えないが、彼の拳が震えているのが見える。それは、シュバルツの心を打つには十分すぎた。期せずしてハヤブサは、筋を通して話をする方を選んでいたのだ。
(信じていいのか……?)
シュバルツは思う。このハヤブサと、先ほど戦った忍者たちとは、明らかに背負っている物が違う。彼の言葉を、その拳の震えを―――信じられるものなら、信じたい。勾玉が、ハヤブサの里の物であるというのならば、返せるものなら返したかった。
(だが、勾玉をその身に宿しているキョウジは……キョウジはどうなる?)
現段階で、キョウジの身の安全につながる保証は何もない。自分の身なら、どうなってもいい。分解されようが、このまま消えてなくなってしまおうが、いっこうに構わない。だがキョウジは、紛い物の自分と違って正真正銘の人間だ。彼を守りたい。
そう思うのは、彼が自分を作った創造主で、作られた物であるが故の本能からなのか、それとも、自分がこうなる前の肉体の記憶によるものなのか、自身の生存本能が働いてしまうからなのか―――それは、分からない。
ただ、キョウジを守りたい、と、願った。
―――いっそ私の中に勾玉があれば、もっと話は早かっただろうに…!
シュバルツは歯噛みした。自分ならば、勾玉が体のどこにあろうと取り出すことができるのに。何故あの日、キョウジを学会に一人で行かせてしまったのか。苦い後悔が押し寄せる。それとも勾玉は、私とキョウジが並んでいても、紛い物である私よりも「人間」である彼の方を、選ぶのだろうか―――。
ハヤブサに応えたい。しかし、キョウジも守りたい。相反する二つの感情が、しばしシュバルツの中でせめぎ合う。
とにかく、このまま沈黙を貫きとおすのは、ハヤブサを追い詰めるだけだと判断したシュバルツは、口を開いた。
「……ハヤブサ…」
「――――!」
シュバルツの声に、ハヤブサが伏せていた顔を上げる。
「……その…」
(しかし、どうする? ―――どう説明する?)
口を開くと決めて、いざ、話そうとすると―――何から話し始めたものか、自分とキョウジの関係を、どう説明したらいいものか、しばし戸惑う。
(―――答えようとしている?)
ハヤブサは、キョウジから目が離せなくなった。彼の眼が、口が、確かにこちらに何かを伝えようとしているのが分かる。
(お願いだ、キョウジ…。そのまま答えてくれ!)
互いの視線と視線がぶつかりあい、異様な緊張がその場を支配する。
「…………」
「…………」
それ故に、二人ともが外への注意を払えなかったことを、誰が責められるだろう。
ガシャン!!
派手にガラスが割れる音とともに、先端に鈎針のような物がついたロープが飛び込んできた。それは、シュバルツを戒めている縄を過たず捕らえると、そのまま彼の身体を窓の外へと引っ張り出してしまった。
「―――ッ!?」
「キョウジ!!」
引っ張り出されたキョウジを追って、ハヤブサもビルの外へと飛び出す。外では、ちょうどキョウジを引っ張り出した主が、その身体を受け止めているところだった。
「―――久しいな。リュウ・ハヤブサ」
黒の着物を着流した、長髪隻眼の男がにやりと笑う。
「残月……!」
(不覚…! 気配に気づかなかったとは…!!)
ハヤブサは、己の未熟を悔いた。
「キョウジ・カッシュを捕らえるとは、さすがだな―――しかし、らしくないではないか。儂の気配に気づかんとは」
そう言って、残月と呼ばれた男は、キョウジを抱えたままクックッと、笑う。その声には、ハヤブサを揶揄する響きが含まれていた。
「―――何故、勾玉に手を出したりした?」
そう、この男こそがすべての元凶。残月が里の若者をそそのかして、勾玉を里の外に持ち出しさえしなければ、こんなことは起きなかった。ハヤブサの中から抑えようもない怒りが、ふつふつと沸き上がる。
「何故? ククッ、愚問だな。ハヤブサ―――貴様は勾玉が持つ大いなる力に、興味はないのか?」
「――――!?」
シュバルツとハヤブサが、同時に残月を見る。
「儂は里での生活も、使命に縛られるのも、飽き飽きしておったのよ…しかし、この勾玉の力さえあれば、世界は意のままに破壊と絶望に満たされる―――おもしろいではないか。力ある物が力無きものを思うさま蹂躙できるのだ…使命とは関係なく、力が揮える世界を儂は見てみたい!」
そしてまた、低い声で薄く笑う。
(冗談ではない!)
シュバルツは思った。この男からは、ハヤブサと違って底知れぬ悪意しか感じない。このままこの男に捕まっていても、事態はますます悪化していくばかりだ。
―――何とか―――何とかここから脱出しなければ…!
「放せ!」
残月の手から逃れようと、軽く体に力を入れた瞬間。
「!?」
シュバルツは、あることに気付く。
(これは………!)
「―――大人しくしていろ!!」
暴れられたら面倒とばかりに、残月はキョウジに素早く当て身を喰らわした。
「…………!」
キョウジの身体から、ガクっと力が抜けていく。
残月の注意が一瞬キョウジに奪われた隙に、ハヤブサは残月に斬りかかろうとした。だが、残月はそれを予期していたのか、意識を失い、弛緩しているキョウジの身体を盾にした。
「――――っ!」
これでは、残月の身体を斬ろうとすれば、キョウジの身体ごと斬らねばならない。ハヤブサの刃が、キョウジに触れる寸前でピタリと止まった。
「……ほう、斬るのをやめたか。主ならば、この男の身体ごと儂を斬るかと思ったが」
残月の刀がキョウジの背中にピタリと当てられている。ハヤブサが残月を斬ろうと間合いに入った瞬間、キョウジの身体ごと、ハヤブサを貫く心積もりであったらしい。
「それとも、この男は生かしておいた方がいいのか? 勾玉を手に入れるだけなら、こいつの生死は関係なかろうに」
「―――!!」
核心を突かれたハヤブサに一瞬動揺が走る。それを見て残月は愉快そうに笑った。
「そういえば、主は勾玉の波動が分かるのであったな……もしかして、この男は勾玉を持っていないのか?」
「…………」
ハヤブサは、沈黙を返す。残月も、返事を期待してはいないらしい。ひとり言のように、さらにつづけた。
「残念ながら、儂にはその波動とか言う物は分からん……里でも、主ぐらいしか感じ取れないものであったからな……だが、ハヤブサよ」
残月の、ククッ、と、暗い笑い声が響く。
「こちらにも、その波動が分かる者がいる―――と、言ったら、何とする?」
「―――!?」
(まさか―――! あれは、里の中でも秘中の秘。秘術を託された者にしか、その波動は感じ取れぬはず……!)
咄嗟にハヤブサは、自分以外に里で波動を感じ取れそうな者を思い浮かべてみる。しかし、秘術を知っている者は先代の里の長と、自分以外にはいないはず―――であった。
(誰だ…?)
一体誰に、そのようなことができるというのか。里以外の者で、波動を感じ取れるなど、ありえぬはずだ。
「フフフ、動揺しておるな……? だが、世の中には不可思議なことが偶に起こる―――それが、また面白い」
残月の、見透かすような声が響く。
「さて、目的の物も手に入ったことだし、儂はそろそろ退散させてもらおうか……」
キョウジに刃を突きつけながら、じりじりと残月が後退していく。
「―――待て!」
ハヤブサがそれを許すはずもない。しかし、残月は更にたたみかけた。
「おっと、下手に手出しをするなよ…? こちらは、お前と違って、本当にこの男の生死など、どうでも良いのだからな…」
「!?」
「嘘か本当か知らないが、こちらの波動を感じるお方は、死者の魂からも情報を引き出す術があるらしい……」
「な―――!」
ハヤブサは、息を呑んだ。
「儂としては、それを試してみてもよいぞ…? ククッ、偉大なお方よ……」
「………!」
(キョウジ……!)
ギリ、と、ハヤブサは唇を噛みしめる。
彼に戒めをするべきではなかった。ただ、筋を通して話をするだけでよかったのだ。彼が見せた愚直なまでのあの姿を、信じ切れなかった自分の弱さ―――それが、今の事態を招いてしまった。
残月に捕らえられる寸前の、キョウジの表情を思い出す。彼は確かに、こちらに応えようとしてくれていた。
(せめて、キョウジに意識があれば…!)
そう。彼ほどの忍びならば、意識さえあれば、この状況を打破できるかも―――そこまで考えて、ハヤブサははっと我に返る。どうかしている。今更他人の力をあてにしようなどと思うとは。
こうしている間にも、残月はじりじりと後退を続けている。
キョウジは連れて行かれて―――この後、どんな目に遭う?
ハヤブサは思う。キョウジに口を開かせる手段はただ一つ。誠意をもってきちんと話をすることだけだ。だが、残月たちが、キョウジにそのようなアプローチをする可能性は皆無に等しい。彼はおそらく、情報を得るためと称されて、思う様に嬲られ、蹂躙され―――死してなお、魂までも弄ばれてしまうだろう。
そんな目に遭わすと分かっていて、今、残月に連れ去られようとしているのを黙って見ていることができるか?
―――否。答えは断じて、否である。
キョウジ―――お前を―――そのような目に遭わす位なら……!
ハヤブサは決断した。今、残月にキョウジを連れて行かすわけにはいかない。例え、彼がここで殺されて、身体だけの存在になってしまったとしてもだ。
自分は、死者の魂に答えを聞く手段など持ち合わせていない。キョウジが死んでしまったら、勾玉を得る自分の使命は、大きく後退を余儀なくされるだろう。
それでも。
それでも、キョウジの魂だけは―――何としても守りたい。ハヤブサはそう、願った。
(キョウジ、お前は…俺を恨むだろうか?)
魂を守るために、命を見殺す決断をした、俺を。
だが、俺は所詮人斬り。こんなことしか―――俺は、お前にしてやれない。
(む……!?)
残月は、ハヤブサの殺気が強く鋭くなっていくのを感じた。
(ハヤブサめ……決断しおったな…!)
ここに至って残月は、キョウジという盾が、ハヤブサに通用しなくなったことを悟る。
「ハヤブサ……どうしても、儂との決着が望みか?」
「…………」
残月の問いかけに、ハヤブサは抜刀したままジャリ、と一歩踏み出すことで答える。その眼差しに、もはや迷いはなかった。
「そうか……」
残月は、薄く笑う。
「しかし、主がいくら望んでも、儂は今『荷物』を抱えている。まともにやり合う気なぞ、さらさら無いわ」
「――――!」
ピク、と、ハヤブサの眉が釣り上がる。残月はキョウジの身体を肩に担ぎあげると、刀の切っ先を、だら、と下に垂らした。
「見事見切って見せるか…? 我が秘術、『朧霞』を――――」
そのまま、残月はそこから動かない。しかしよく見ると、刀の先から何か液体のような物を垂らしていた。
ハヤブサの方に躊躇はなかった。術の発動などにつきあう義理もない。ドン、と地面をけると、凄まじい気迫とともに刀を振り下ろす。例えその刃の下にキョウジの身体が来ようとも、止めずに振りぬく―――ハヤブサは、そう決めている。
刀は、残月の身体を過たず捉えた―――かに見えた。しかし、そこに手応えは、無かった。
「!?」
残月の身体と思われていた影は雲散霧消し、辺りに霧のような物が発生する。
(フフフフ、主に、儂の姿が捉えられるかな?)
残月の、仄暗い笑い声が響いてきた。
(ここだ!)
(ここだ、ここだ!!)
(儂は、ここにおるぞ…?)
「…………!」
気がつくと、何人もの残月に取り囲まれていた。声も、四方八方から聞こえてくる。
(幻か!?)
本物の残月は一人のはず―――ハヤブサは周囲の気配を探った。
こうしている間にも、発生した霧はますます濃くなり、ハヤブサの視界をどんどん覆っていく。もう、5メートル先も、よく見えなくなってきていた。
ヒュ…、と空気を割く音がする。
(鎌!?)
それは、回転しながらハヤブサめがけて飛んで来ていた。
「迂闊な!」
飛び道具を使うとは、敵に位置を教えてやっているようなもの―――ハヤブサは鎌を避けてから飛んできた方角めがけて手裏剣を投げた。
しかし、当たった手応えは無い。
「………?」
おかしい―――と、思った瞬間。今度は、先の物とは全く違う方向から空気を割く音が聞こえた。鎌が、またハヤブサめがけて飛んできている。
「!!」
かろうじて、これをかわす。今度は、さらに別方向から手裏剣が飛んできた。ハヤブサは、跳んでこれをかわした。
(おかしい。こんなにあちこちから飛び道具が飛んでくるはずが無い!)
飛び道具自体が幻かもしれない―――廃ビルの壁を背に受けながら、そう思い始めたハヤブサの前に、またも鎌が飛来する。ハヤブサは、それを刀でたたき落とす選択をした。キン! という確かな手応えと金属音と共に、それは地面に突き刺さる。
(本物…?)
質感、手応え、ともに疑う余地が無かった。また別方向から手裏剣が飛んでくる。ハヤブサは、身を伏せてそれをかわす。
とにかく、一ヵ所に留まり続けるのはまずい。
そう感じたハヤブサは、一か八か、今いる場所から飛び出すことにした。
とたんに、背後に恐ろしいほどの殺気を感じる。いつの間にか、残月がピタリと背後につけていた。
「―――ッ!」
背後の黒い影を、容赦なく斬り裂く。しかし、残月の姿はまたしても雲散霧消し、刀はむなしく空を切った。
間をおかずに、鎌と手裏剣が次々と飛んでくる。
―――このままでは…!
ハヤブサは、焦りそうになる己に歯止めをかける。焦れば焦るほど、残月の術にはまっていくばかりだ。残月の気配を探ろうにも、四方から聞こえてくる耳障りな高笑いが、ハヤブサの集中を乱してくる。
(恐らく、本物の攻撃はごく僅か。後は皆、幻のはず!)
ハヤブサは、幻からの脱出を試みた。
ドンッ!
「…………!」
痛点の一番集まるつま先に、自身の刀を突き立てる。もしも己が幻に呑まれているのだとしても、これで正気に帰れるはずだった。
しかし、霧も晴れず、残月の姿も、耳障りな笑い声も消える気配がない。
(おかしい…! まだ痛みへの集中が、足りないのか…?)
自身の足に刀を突き立てたまま、目を閉じる。
邪魔な笑い声を、なるべく遠くに感じようと試みる。
「…………」
―――手裏剣の、気配がする…。
ハヤブサは、動かない。すると手裏剣は、ハヤブサの身体に当たらず、す…っと霧の中に消えていった。
近くに、残月の息遣いを感じる。しかし、攻撃を仕掛けてはこない。
(やはり、幻……!)
確信する。攻撃自体は僅かなもの。これは残月の『逃げ技』とみていい。
かすかだが、残月の気配をまだ感じる。奴は、まだ近くにいる…!
ともすれば、術に引っ張り込まれそうになる。足の痛みを強く感じることで、ハヤブサは幻と現実のはざまにとどまり続けた。
感じろ。
ほんの僅かでいい。
術のほころびを感じろ。
(これは、賭けだ)
ハヤブサは思う。
このままでは逃げられるかもしれない。
―――が、じっと留まる自分を見て、殺しに近寄ってくるかもしれない。
油断でもなんでもいい。
残月の気を、一瞬でも乱すことができれば――――!
―――無駄なことを……。
ハヤブサから少し離れた建物の陰から、その様子を残月はほくそ笑みながら見ていた。
この術は、確かに相手に幻覚を見せる類のもの。痛みを感じることにより、幻覚から覚醒される効果があることも、百も承知だった。しかし、残月のこの術は、その手で今まで破られたことは一度もない。自他共に認める強力な技―――で、あった。
(今なら奴を、仕留めることができるか…?)
刀を突き立てたまま、ピクリとも動かないハヤブサの姿に、刺客としての本能が疼く。
しかし、今はキョウジ・カッシュの身体をクライアントに届けねばならない。生死は問われていなかったが、このままいけば、生かしたまま届けることができる。そちらの方を優先せねばなるまい。
(ハヤブサよ……貴様の命、しばらく預けておくぞ…)
このまま滞りなく使命を完遂するために、残月は退却を選ぶ。ハヤブサに術を施すために、一度肩からキョウジをやむを得ず下ろしたが、彼は縛られている上に気を失っている。少しの間目を離したところで、何も問題は無いはずであった。
もう一度、担ぎなおすべく、残月は、後ろを振り返る。
「…………!」
そこで、残月は、信じ難いものを見た。
下ろしたはずのキョウジの身体が、掻き消えていたのだ。
―――馬鹿な! 目を離した時間はごく僅か。その隙に…!?
残月の気が、一瞬乱れる。これこそが、ハヤブサの待ち望んでいたものであった。
「そこっ!!」
裂帛の叫びと共に、ハヤブサは刀を投げる。その刀は過たず、今度こそ残月を捉えた。
「ちぃぃっ!」
刀は、残月の右肩を割いて、ドスッ、と地面に突き刺さった。
「捉えたぞ、残月―――」
クナイを手に、ハヤブサは歩きだす。
(まずい!)
残月は焦った。右肩をやられ、利き手が使えない。左手でハヤブサとやり合うのは分が悪すぎる。幻術を使おうにもこの出血では、血の匂いですぐに本体がばれてしまう。
「ま、待て…ハヤブサ。キョウジ…キョウジ・カッシュが逃げた」
後ずさりながら、残月が口を開く。何とか、ハヤブサの注意を自分から逸らそうと試みた。
「…………」
しかし、ハヤブサは無言で、さらに歩を進める。残月に、交渉の余地はない事を知らしめる。
「…………!」
ハヤブサからの容赦ない殺気が、残月をさらに後ろへと下がらせた。
ふと、ハヤブサの目に、キョウジを戒めていた縄がうつった。解かれた縄が、空しく転がっている。近くにキョウジの気配は、もう感じられない。
―――逃げたか、キョウジ。
どこかで安堵している己を、ハヤブサは感じていた。これで、心おきなく残月に集中できる。キョウジへの話の聞き方は、もう分かっている。自分は、後を追うだけだ。
だから今はいい。逃げたのなら、それでいい。
「ま、勾玉の情報源だぞ…? 追わなくていいのか……?」
「―――今は、貴様が先だ! 残月!!」
時間を稼ごうとした残月の試みを、斬って捨てる。非情な暗殺者の顔をしたハヤブサが、さらに近付く。こうなってしまっては、残月が生き延びる可能性は皆無に等しい。
(死ぬのか!? 儂は!?)
残月は歯ぎしりをした。冗談じゃない。こんなところで死んでたまるか―――!
ふと、自分の懐に、クライアントが「万が一のために」と持たせたものがあることを思い出す。正直効き目があるかどうかも分からぬものだったので、残月としては半信半疑でこれを持っていたのだが。
「覚悟!!」
叫ぶと同時に、ハヤブサが地面を蹴った。
(チッ! こんな物に頼ることになろうとは―――!)
藁にもすがる思いで、残月は懐に手を突っ込む。
「ハヤブサ! 見ろ!!」
六角形の薄い小さな鏡のような物を懐から取り出した残月は、それを地面にたたきつけた。パリン! と、音を立てて鏡が砕け散る―――その瞬間。
ドクン!!
「――――ッ!?」
ハヤブサの身体を、突如異変が襲った。割れた鏡から飛び出した黒い影が、まるで明確な意志を持つかのように、ハヤブサの右腕に襲いかかり、そこを侵食しだしたのだ。
「…う…ぐ……! ………ああっ!」
右腕から全身に襲いかかる強烈な痛み、違和感の蠢き、熱―――。それはハヤブサの視界を歪め、平衡感覚を容赦なく奪う。立っていられなくなった彼は、ついに膝をついてしまった。
「…………!」
残月は、しばらく茫然とその様を見つめていたが、やがて、表に凶悪な笑みを浮かべた。
「フ…フ……。フハハハハ! ヒャハハハハハ!!」
腹を抱えて笑い転げる。こんな愉快なことはない。自分を追い詰めていた暗殺者が、今、為すすべもなく無様に目の前でのたうっているのだ。
「ハヤブサよ……形勢逆転とはまさにこのことだな」
残月は、そう言いながらハヤブサを足蹴にする。蹴られたハヤブサは、あっさり倒されてしまった。
「クライアントの言っていた通り…主の右腕には、呪いの名残があるようだな。非常に呪いを受け付けやすい。僅かな呪でも、それその通りの様になる」
愉快そうに笑いながら、残月は左手で抜刀した。
「……苦しいか? 苦しかろう?」
「…………!」
立ち上がろうともがくハヤブサをドスッと踏みつける。からかうように刀を振るうと、ハヤブサの左手のクナイが襲いかかってきた。だがすぐに力つき、クナイはむなしく空を斬ってしまう。
(ほう、この状態でまだ動くとは……!)
残月は、笑いが止まらなかった。この期に及んでまだ闘志を失わない極上の獲物を、自分はこの手で仕留めることができるのだ。
「―――ひとつだけ、良い事を教えてやろう。その呪いは一過性のもの…。時が経てば、収まるらしい…」
そう言いながら、残月は刀を上段に構える。
「だが、その前に! 儂が主を楽にしてやろう……永遠にな!!」
「く……う……ッ!」
残月が、刀を振り下ろそうとしているのがかろうじて見える。しかし、熱と痛みで、四肢に思うように力が入らない。
―――だめだ―――! こんなところで、死ぬわけには―――!!
懸命に、打開策を探る。動かぬ四肢を鞭打つ。しかし、ハヤブサを死へと誘う運命は、もはや定められたもののようですらあった。
「ハハハハ! さらばだ!!」
「…………!」
―――無念……!
ハヤブサは目を閉じ、残月の刃が己の肉に食い込むのを待った。もう、それしかできなかった―――。
刹那。
一陣の風が、地面に刺さっていたハヤブサの刀を奪う。その風は、そのまま二人の間に割って入った。
ガンッ!!
「…………?」
覚悟していた痛みが来るどころか、頭上に聞こえるはずの無い金属音が響いたことを訝しく思ったハヤブサが、顔を上げる。そこには、逃げたはずのキョウジ・カッシュの姿があった。彼はハヤブサを背に庇うように片膝をつき、振り下ろしてきた残月の刀を、ハヤブサの刀を使って受け止めている。
「な……! キョウジ!?」
(―――何故戻ってきた!? 何故俺を助ける!?)
ハヤブサは混乱する。俺はキョウジを狙った。殺そうとした。信じることができずに縄を打ち、揚句、命を見捨てる選択までした。キョウジには、俺から逃げたり、殺そうとする理由はあっても、助ける理由など無いはずだ。
「――――!!」
残月も混乱していた。逃げられたと思っていた標的が、いきなり目の前に現れた。しかも、左手で振るったとはいえ、自分の必殺の太刀を受け止められたのだ。
(どういうことだ!? こいつ、まだ近くにいたのか!? まさかこの儂が、こいつの気配を感じられなかったとでもいうのか!? ―――しかも、何故ハヤブサを庇う!?)
キィィン!
混乱する残月の刃は、キョウジによって押し返される。残月は後退を余儀なくされた。
「チ………!」
「…………」
少し距離をあけて、キョウジと残月は睨みあう。その時キョウジが、ハヤブサにだけ聞こえる声で小さく呟いた。
(目を伏せろ)
「………!」
ハヤブサは、驚愕に目を見開いた。やはりキョウジは、明確な意志を持って自分を助けにきている。何故だ―――疑問が襲い来る。
残月に正対していたキョウジが、懐から何かを取り出す。今は、選択の余地はない。ハヤブサは、目を伏せた。
キョウジがその手を残月に向けた途端、凄まじい光の乱流が彼の手からあふれ出す。
「何!?」
一瞬まともにそれを見てしまった残月の視力は、容赦なく奪われてしまった。さらにキョウジがそれを地面に叩きつけると、辺り一面に光の渦が爆ぜる。
やがて、すべての爆音が収まり、光が消え―――ゆるゆると残月の視力が回復してきた時には、ハヤブサの姿もキョウジの姿も、忽然と掻き消えていた。気配をたどることすら、できそうになかった。
(おのれ………!)
残月は歯ぎしりをする。獲物をしとめるまで後一歩と言うところまで迫りながら、逃げられてしまったのだ。
―――リュウ・ハヤブサ、キョウジ・カッシュ……! 次に会った時には、こうはいかぬぞ……!
必ず報復してやる―――そう誓いながら、残月もまた斬られた右肩を抑えながら、闇の中へと消えていった。
疾走するキョウジの背に追われながら、ハヤブサは朦朧とする意識をかろうじて保たせていた。
(……同情、されたのか…)
キョウジの甘すぎる性格から考えて、十分にあり得るとハヤブサは思った。何もできずに一方的に殺されそうになっていた自分の姿を見て、飛び出してきたのかもしれない。まるで、あの時の少女を助けるように。
「…………!」
(屈辱だ……!)
堪らない。こんな風に同情されるくらいなら、あの時殺されていた方がまだましだった。
「……おい…!」
かろうじて、声を絞り出す。声が届いたのか、キョウジは走るスピードを落とした。
「何だ?」
振り向かず、声だけが帰ってくる。足の歩みも止まらなかった。
「どういうつもりだ……!」
「…………」
キョウジからの返事は無い。ハヤブサは、今入る渾身の力を込めて、叫んだ。
「―――下ろせ!」
ぴた。と、キョウジの足が止まる。
「それが、お前の望みか?」
「……そうだ…!」
下ろされたところで、身動きがとれないので状況は変わらない。しかし、これ以上背負われていたくはなかった。
「……………」
キョウジは、何か考え込むようにしばらく沈黙していたが、やがて口を開いた。
「どうしても下ろせというのなら、下ろすが―――その前に、私の質問に答えろ」
静かな声。そこからは何の感情も感じられず、前を向いたままなので、表情もうかがい知れない。何を聞きたいのかは知らないが、とにかく、早く下ろしてほしい―――ハヤブサは、そう思った。
「先ほどお前は、私に『どういうつもりだ』と、聞いたな?」
「……ああ…」
苦しい息の下から、答えを絞り出す。
「私こそ、お前に聞きたい。……一体、どういうつもりだ?」
「………?」
「何故、私を助ける? ―――どうも先程から私は、お前に助けられてばかりのような気がする」
「な――――!!」
キョウジの意外すぎる言葉に、ハヤブサは激しく動揺した。
「ば……馬鹿なことを言うな! …俺がいつ、貴様を助けたと……!」
「―――じゃあ、私があの子供を助けようとした時、何故斬らなかった?」
ハヤブサの言葉が終らぬうちに、キョウジがズバッと斬りこんできた。
「そ、それは―――」
ハヤブサは、必死に言い訳の言葉を探す。
「子供―――子供を守るためだ! 別に、お前を助けたわけでは…」
「違うな」
「!?」
「お前ほどの腕があれば、私を斬ってから、子供を助けることもできたはず」
「………!」
あまりにも的確すぎる分析に、ハヤブサは言葉を失った。
「あの瞬間、どれだけ無防備に飛び出してしまったか、自分でも分かっているつもりだ。―――ここまで来ると、一種の病気だな」
そう言って、苦笑するキョウジの声が聞こえる。
(こ、こいつ……『馬鹿』の自覚があったのか…!)
ハヤブサは、呪いとはまた別の種類の眩暈を覚えた。自覚があって、なおかつそれを貫き通すとは…! こいつは、真の筋金入りの馬鹿なのか、それとも、途方もない大物なのか。
「―――まだあるぞ」
キョウジは、ハヤブサを背負ったまま再びゆっくりと足を進めながら、更にたたみかけてくる。
「私を戒めていた縄―――何故、あんなに緩くしていた?」
「――――っ!」
「あれでは……縄抜けの技能を持つ者であれば、子供でも抜けられる」
これにはハヤブサも、二の句が継げなかった。
そう。確かに自分は、キョウジに縄を打つ時、かなり迷っていた。出来れば、キョウジの意識が戻った時に、自力で縄を解いてほしいとさえ、思っていた。そして、再び対戦できればと―――。結局、最初にキョウジに意識が戻った時、彼があっさりと縛られている状態を受け入れてしまったために、話を進めざるを得なくなってしまったのだが。
「だからこれは―――お前に受けた借りを返すために、私が勝手にやっていることだ。……お前が、負担に思うことはない」
「…………!」
(借り!? 『一瞬斬らなかった』とか、『縄がゆるかった』とか、そんな些細なことを、お前は『借り』と言うのか――!?)
あまりにもいろいろな思いが、ハヤブサの中で渦を巻く。思わず、クナイを握る左手に、力が入ってしまった。
キョウジは、それをハヤブサの自分への殺意と感じたらしい。静かに問うてきた。
「……殺すか?」
だが彼は、ハヤブサを下ろすこともせず、歩みも止めず―――ただ、続けた。
「殺すなら、殺せばいいさ……許せないなら、仕方がない」
「…………!!」
(こいつ―――馬鹿だ―――本物の―――しかも、性質の悪い……!)
そう思いながらハヤブサは、もう意識を保つことができなくなっている己を感じていた。体中の力が、勝手に抜けていく。
カラン、と、音を立てて、クナイがキョウジの―――シュバルツの足元に転がる。
「ハヤブサ?」
彼が武器を落とすなど、ありえない。シュバルツが、そう思った瞬間。いきなりハヤブサの身体の力が抜け、全体重がシュバルツにかかってきた。
「うわ……っ!」
危うく、ハヤブサの身体を落としそうになるのを、かろうじてこらえる。
「おい! ハヤブサ!? ―――ハヤブサ!! しっかりしろ!!」
呼びかけてみるが、返事が無い。ただ、彼から呼吸音が聞こえ、身体から脈拍を感じる。呪いに呑まれたというわけではなさそうだった。右腕に穿たれた呪いの印も、先ほどより小さくなっているように見える。
(これはたぶん……どこかで休んだ方がいい)
シュバルツはそう判断して、移動の速度を再び上げていった。
しばらく潜むのに適していそうな空き家は、割とすぐ見つかった。
家に人の気配が無いことを改めて確認し、尾行がついていないことも確認してから、壁抜けの術を使って忍び込む。夜露をしのげるし、ハヤブサを休ませるための畳部屋があったことが、何よりもありがたかった。そこに、ハヤブサの身体をそっと横たえる。
呼吸が苦しそうだったので、顔を覆っている覆面も取ろうかと悩んだが―――止めた。
(本人の許可なく、隠している素顔を見るのはまずいだろう)
自身も、先の『デビルガンダム事件』の折、弟に正体を隠して近づく際、覆面を使用した経験がある。まさかとは思うが、面を取ってしまうことで、彼の大事な何かを壊してしまうのは、シュバルツの本意ではなかった。
時が経つとともに、呪いの印がどんどん小さくなっていった。苦しげだったハヤブサの呼吸も、だんだんと規則正しいものへと変わっていく。
―――呪いは一過性の物―――。
残月がそう言っていたことを思い出す。
(嘘じゃなくて良かった)
シュバルツは、ほっと息をつく。窓から外を見ると、まだ漆黒の闇に彩られていた。しかし、そろそろ夜明けも近いはずであった。
(ドモンとキョウジは、無事に脱出できたのだろうか……)
直接確認する術は、今は無い。ただ、自分がこうして動けているということは、少なくとも、キョウジは現時点では生きているということになる。
ふと、ハヤブサが身じろぐのが見えた。
(強いな……もう回復するのか……)
シュバルツは、静かにハヤブサの意識が戻ってくるのを待った。
まず、見知らぬ天井が、ハヤブサの目に飛び込んできた。
(……ここは…?)
ゆるゆると意識が覚醒していく間に、ふとハヤブサは、意識を失う直前のことを思い出す。
「――――ッ!!」
思わずガバッと跳ね起きた。
(何という失態だ…!)
自分で自分が信じられなかった。いくら呪いを受けたとはいえ、他人の前で、完全に意識を失って昏倒するとは…!
無意識のうちに、左手が刀を探して掴む。掴んでから―――はっと思い当る。
(俺は、残月に刀を投げたはず―――何故、これがここにある!?)
「気がついたか?」
穏やかな声に、はっと振り向く。窓辺に、キョウジ・カッシュが立っていた。
「キョウジ……」
キョウジは、ハヤブサと視線が合うと、にこ、と、人懐こい笑みを浮かべた。
「妖刀だな。それは………よく、持っていられるものだ」
「―――使ったのか!?」
「一瞬だけ、借りた。―――喰われるかと思ったぞ」
そう言いながらシュバルツは、残月の太刀を受け止めたあの瞬間を思い出す。刀から、凄まじいエネルギーの逆流を感じた。残月があの一太刀で引いてくれていなければ、自分が刀の傀儡となり果ててしまっていたかもしれない。
(これを、一瞬でも使えたのか……!)
ハヤブサは逆に、たとえ一瞬だったとはいえ、キョウジが刀を使って無事だったことに驚いた。ハヤブサの刀は『龍剣』と、言って、里に伝わる伝説の刀だ。その刀には龍の力が宿り、刀が使い手と認めたハヤブサ以外の者がそれを使おうとすると、刀自体が使った者に牙を剝き、その命を喰らうと言われている。それを……。
「…………」
ハヤブサは、改めてキョウジを見る。彼は相変わらず、穏やかな笑みを浮かべていた。その姿からは、戦闘意思がもはや感じられない。ハヤブサが刀を手にしていても、警戒するそぶりすら、見せなかった。
(キョウジは、きっとこの刀が妖刀ではなくとも、俺に返したのだろうな…)
そういう邪心の無い奴だから、龍剣も力を貸したのだろうか―――刀をいつものところに収めながら、ハヤブサは思った。
成り行きで今は休戦状態に入っているとはいえ、先ほどまで真剣に斬り合っていた者同士なのだ。相手が意識を失っているのなら、その間に、普通なら武装を解除する。
(だからこれは―――お前に受けた借りを返すために、私が勝手にやっていることだ。……お前が、負担に思うことはない)
(殺すなら、殺せばいいさ……許せないなら、仕方がない)
気を失う前に、キョウジがそう言っていたことを思い出す。
(今も、そういう覚悟でそこにいるのだろうか)
そうでなければ、彼のこの態度の説明ができないと思った。彼には、何か大事な信念があり、それを貫き通しているのだ。彼にとってこの信念は、おそらく自身の命よりも、はるかに重いものなのだろう。
(もしかして、今なら―――)
ハヤブサは、ふと思う。もしかして今なら、借りを返させる名目で、キョウジから一方的に龍の勾玉の情報を引き出すこともできるかもしれない。
だが。
ハヤブサは頭を振る。
そうではない。自分は、そんなことはもう望んでいない。
僅かな『借り』に、信じられないほどの誠意を示してくる男―――この愚直な男と、同じところに立って向き合いたい。そうしなければ、ハヤブサ自身が、もう自分自身を許せなくなると感じた。
おもむろにハヤブサは、自身の顔を覆っていた覆面を取る。誠意を示すのなら、顔を隠すのは失礼だと思ったからだ。面の下から、少し日本人離れをした、色白の端正な顔が現れる。
「――――!」
これにはシュバルツの方が驚いた。まさか、いきなり彼の方から覆面を取ってくるとは思っていなかったのだ。更に、伝説の龍の忍者の、意外に若い素顔に驚く。ドモンより少し上、キョウジより、少し年下ぐらいだろうか。
「ハヤブサ……!」
シュバルツが何か言いかけるのをハヤブサは手で制して、すっと居住まいを正した。
「まずこちらの、数々の非礼を詫びる―――」
そう言って、頭を下げる。
「ハ、ハヤブサ!? ちょ、ちょっと待て……!」
シュバルツは、本当に面食らってしまった。何故ハヤブサが謝る必要があるのかが分からず、あわててハヤブサの近くまで走り寄る。頭を下げることをやめさせなければと、強く思った。
「非礼も何も―――お互い、任務と言うか使命と言うか、そういう物を背負って戦ったわけだから……!」
頭を下げるハヤブサのすぐ近くに膝をつき、とにかく顔を上げてもらおうと、必死に言葉を紡ぐ。しかし、ハヤブサは頑なに頭を下げ続けた。
「いや―――もっと早くこうすべきだった」
そう。キョウジが戦闘を放棄したあの時点で、自分も戦闘行為をやめるべきだった。縄など打たず、ただ話し合いをすれば良かったのだ。それができなかったばかりに、キョウジを危険にさらし、本当にあと少しで殺してしまうところだった。今回キョウジが死なずにすんだのは、運が良かったとしか言いようがない。すべて自分の未熟が引き起こしてしまったこと―――ハヤブサは、そう思った。
自分は、キョウジの恩人と言うより、まぎれもない加害者だ。
だから、頭を下げているというのに。
キョウジの方には、どうもハヤブサのその想いが伝わっていないらしい。それどころか、こちらが詫びるのを必死にやめさせようとさえしている。
「と、とにかく頭を上げてくれ! 恩人のお前に、これ以上―――」
「…………!」
キョウジのこの言葉に、ハヤブサが顔を上げる。ただ、その面は、かなり怒気を食んでいた。
(こいつ―――! 俺のことを恩人とか、まだ言うか―――!)
ハヤブサに殺気だった目でジロリ、と睨まれて、シュバルツは思わず口をつぐむ。
「……………」
(詫びているのに、睨んでどうする)
ハヤブサは、深いため息とともに、キョウジを睨むのをやめる。気がつけば、頭を下げるのもやめざるを得なくなっていた。
(恩人とかそういうのではなく、対等に話がしたいだけだというのに……どうすれば、この一途な馬鹿にそれが分かってもらえる?)
こちらが頭を下げても駄目となると―――ハヤブサは腕を組んで懸命に考えた。
シュバルツも、ハヤブサが頭を下げることをやめてくれたので、とりあえず黙った。しかし、何やら殺気だった目でこちらを睨んできたハヤブサが押し黙ってしまったので、少し心配になる。だが、余計なことを言ってハヤブサをさらに怒らせることも避けたかったので、シュバルツも沈黙を続けた。
「…………」
「…………」
奇妙な静寂が、部屋を支配する。
(―――馬鹿には直接言うのが一番早いか)
馬鹿につける薬は無い―――何かあきらめにも似た気持ちと共に、ハヤブサは結論に達した。
「―――おい」
ハヤブサが、ぶっきらぼうに口を開く。
「な、何だ?」
ハヤブサの殺気だった声に、多少引き気味に返事をするシュバルツ。
「やめろ」
「え?」
「俺を、いちいち恩人扱いすることを、だ」
「え…? しかし…!」
「いいか。俺はお前の命を狙った―――お前を、殺すところだった」
「いや、だからそれは、お互いに……」
「いいから、黙って聞け」
キョウジが何か言いかけるのを、ハヤブサは手で制した。
「俺は、お前にとって紛れもない加害者のはず―――それを、恩人扱いされてしまっては……」
ハヤブサが、少し哀しそうに目を伏せた。
「俺が、困る」
「ハヤブサ……」
(困る……迷惑…か…)
シュバルツは、膝の上に置いていた己の拳をぎゅっと握りしめた。自分は借りを返すつもりでしてきたことだが、ハヤブサにとっては迷惑でしかなかったのだとしたら、それはやはり―――恩を仇で返してしまったことになる。
そんなつもりはなかったのだが、自分の行為は、ハヤブサを傷つけるだけだったのか…。
(……きついな……)
シュバルツは顔を伏せ、自嘲的な笑みを浮かべた。
「ち、違う! 俺が望むのは、そうではない。俺がお前に望むのは―――」
ハヤブサは慌てた。キョウジを否定したいわけではないのだ。必死に伝えたい言葉を探して、続ける。
「もっと―――普通に話がしたい」
「………!」
ハヤブサからの意外な言葉に、シュバルツは伏せていた顔を上げた。
「恩人とか、そういうのではなく……普通にだ」
「ハヤブサ…!」
「もし―――お前が、まだ俺のことを恩人と思っているというのなら―――」
ハヤブサは慎重に言葉を選ぶ。先ほどからややこしい事を言っていると、自分でも感じる。口下手な自分が、ちゃんと言いたいことをキョウジに伝えられているかどうか、不安だった。
「なおさら、俺のことを恩人扱いするな。……それが、俺の望みと言うか―――」
ハヤブサは、ここまで言葉を紡ぐと、キョウジから視線を外して、小さく呟いた。
「願い、だ」
「――――!」
またも、室内に沈黙が広がる。
(言いたいことは、全部言った)
ハヤブサは目を閉じ、ひとつ大きく息をした。
他人に自分の思いを言葉で伝えるというのは、自分の中ではかなり苦手な部類に入る。だから、下手に飾らず、直球的な言葉を選んだつもりだが。
「…………」
キョウジからの反応が、なかなか返ってこない。
(普通に、などと、今更虫がよすぎただろうか―――)
そんなことを思いながら、ハヤブサは目をあける。キョウジと、視線が合った。彼が茫然としていたので、ハヤブサは少しびっくりする。
「キョウジ?」
「あ………」
キョウジは、ハヤブサと視線があったことで、初めて我にかえったようだった。
「…ハヤブサ……分、かっ…た……」
それでも呆けた表情のまま、とぎれとぎれに返事が返ってくる。
「普通…に、だな……分かっ、た―――」
それまできれいな正座を保っていたキョウジの姿勢が、いきなりガクッと崩れた。
「お、おい!?」
ハヤブサが慌てて声をかけると、キョウジがちょっと苦笑の交じった笑顔を見せた。
「いや……悪い……。何だか、いろんな意味で……気が……抜けて…」
「…………」
(無理もないか)
ハヤブサは思った。この男は、ずっと俺に斬られる覚悟で今までそばにいたのだ。『決死の覚悟』と、一言で片づけるのは簡単だが、白刃をその身に受け入れる緊張と覚悟を保ち続けることが、どれほど大変な事か―――同じ戦いの中に身を置く者として、それが分かる。
「…よかった……本当に、よかった……」
キョウジが、心底ほっとしたような表情を浮かべている。
(俺も、よかった…)
決死の覚悟を胸に秘めた硬い笑顔ではなく、こんな柔らかい表情を彼にさせることができて、本当に良かった。ハヤブサも気がつけば、自然に笑みが浮かんでいた。
「よかった……私、ハヤブサに聞きたいことがあったんだよね」
キョウジが、人懐こい笑みを浮かべて顔を上げてきた。
「聞きたいこと?」
「龍の勾玉のことさ」
「…………!」
「それって…ハヤブサの里の物なんだろ? だったら、勾玉のことについて、よく知っているのかなって……いやぁ、私は勾玉の正体が全然分からなくてさ」
キョウジは悪びれもせずに、あっけらかんとハヤブサに聞いてくる。
「それにしてもよかったよ…。勾玉のことだけに、借りがある状態で、ハヤブサに聞きにくくってさ。逆に、『借りを返すために勾玉の情報をこっちによこせ』って、ハヤブサに言われたらどうしようか、と、冷や冷やしてたんだけど……『普通に』ってことは、情報交換の取引も可能ってことだよな?」
「――――!」
ハヤブサは開いた口が塞がらなくなるのを感じた。
(まさか、『よかった』ってそういう―――!? こ、こいつ、切り替えが早いというか、何というか……!)
「おい! まさか、俺をわざわざ助けたのも……!」
「恩義を感じた、というのは、本当だよ」
勾玉の情報を得るためか―――と、ハヤブサが言う前にキョウジが答えた。
「真剣に斬り合いをしていて、こちらがあんな大きな隙を見せた時に、斬ってこない奴の方が珍しいんだ……。たいていは、斬られる」
「…………!」
「まして、今回の場合、キョ……私の、生死が問われているわけではないのだから、なおさらだ」
(―――斬られるって……! こいつ……!)
呆れかえりそうになって、はたと思い当たる。自分たちは忍びの者―――いわば、闇の世界の住人だ。強いものが生き残り、弱い者や隙を見せた者が淘汰されるのが当たり前の日常を生きている。そんな中でこの甘さを貫いて、今まで無事でいられたわけがないのだ。
ハヤブサは、呆れかえるを通り越して、何故かだんだん腹が立ってきた。
「―――斬られたことがあったのか? あったんだな!?」
「ま、まぁ、その時々によりけり……だけどな?」
キョウジは苦笑いながら引き気味に答える。ハヤブサの中で、思わず何かが「ぶちっ」と切れた。
「学習しろ!!! 斬られたことがあるのなら!!」
「だ、だから言ったじゃないか。あれはほとんど私の持病みたいなものだって…」
「病気で片づけるな!!! ―――そんな事を繰り返していたら、お前いつか死ぬぞ!? 絶対死ぬ―――!」
「…………」
キョウジは、ハヤブサの言葉に微笑みを返した。
不思議な笑みだと、ハヤブサは思った。笑っているのに、笑っているように見えない。淋しさと―――何故か冷たさすら感じる。無言の拒否の意思を感じた。
(余計な事を言うな―――と、言うことか…)
「…………!」
ハヤブサは、大きな息を一つついて、立ちあがりかけていた腰を落とした。熱くなりすぎていた己を落ち着かせようと試みる。
人には人の事情がある。いろいろと承知をしているこいつが、敢えてこんな馬鹿なことを貫き通しているのも、恐らく何かに義理立てをしての事だろうが……それにしても―――。
「―――馬鹿な奴め…!」
最後のところだけ、思わず口に出てしまった。それを聞いたキョウジが、今度はちゃんと微笑んだ。
「馬鹿を貫いていると、良い事もあるんだ……本当に、稀にだけど、な」
「…………」
(稀に……まあ、そうだろうな……)
不条理が平気な顔をしてまかり通る世の中だから―――と、思いかけたハヤブサが、はっと思い当る。
「―――おい。まさか今『いい事が起きている』とか言うんじゃないだろうな?」
「いやぁ」
キョウジが否定も肯定もせず、にっこり微笑んだ。
「微笑むな!!!」
思わずキョウジに雷震撃を叩き込んでしまった。ハヤブサ、クールダウン失敗である。
「じゃあ、どうしろって言うんだよ?」
壁際まで吹っ飛ばされたキョウジが、座り込んでむくれた顔をしている。
「いいか!! 俺は―――!!」
ハヤブサが拳を振り上げて尚も怒り続けようとすると、今度はキョウジが捨てられた子犬のような眼差しになっていった。
「ハヤブサ……」
「………! …………!! …………!!!」
キョウジのこの眼差しと、生来の自身の口下手さが相俟って、ハヤブサの怒りの言葉は完全に封じ込められてしまった。振り上げた拳が、行き場をなくして空しく宙を舞っている。
「~~~~~~っ!!」
ガクッと膝をついてハヤブサは座り込んでしまった。
「ハ、ハヤブサ…?」
恐る恐るといった感じで、キョウジがハヤブサに近づいてくる。
「も、もういい……。もう、好きにしろ……」
ハヤブサは、完全にキョウジに振り回されている己を感じていた。この男、訳が分からない。一途な馬鹿なのかと思えば、怖いほどの奥深さを垣間見せてくる。どこまでが素で、どこからが計算なのかも全く読めない。
「そ、それじゃあそろそろ、仕事の話に移ってもいいか?」
キョウジの提案に、ハヤブサもため息交じりに同意した。不毛な会話は、真剣で斬り合うよりも精神的にはるかに消耗することを、ハヤブサは身を持って知った。
「それでは、私の方から―――」
二人は部屋の中で、改めて向かい合って座した。シュバルツの方から、話を切り出す。
「勾玉は、ある人物が持っている。申し訳ないが、その人物の名を、今明かすことはできない」
「…………」
ハヤブサは、黙って腕組みをして聞いていた。
「だが、その人間は、勾玉を悪用するようなことは、絶対にない。この私の―――」
ここでキョウジが、何故か、何か言おうとしてやめたようにハヤブサには見えた。
「………キョウジ・カッシュの名にかけて、それを誓おう」
(首をかける、とは言わんのだな。こいつなら、絶対そう言いそうなものだが……)
まあ、首でも名でも、こいつがかけて誓うのなら信用できるが―――ハヤブサはそう思いながらも、軽く違和感を覚えた。
「勝手な望みだが、私はその人間を、守りたいと思っている…」
「………!」
「だが、勾玉がそちらの里の物だというのなら、返さなければならないのも事実。……だから、知りたい。勾玉の正体を」
「…………」
「体に吸収された物を、取り出す術があるのかどうかも含めて、知りたい」
「―――――!」
ハヤブサは、思わず目を見開いた。やはり、勾玉は人の身体に吸収されていた。しかも、よりにもよって、キョウジが守りたい、と、願っている人間の身体に。
自分が知る限り、一度身体に吸収された勾玉を取り出す方法は、その人間の『死』が、絶対条件になる。それ以外の方法は、 無 い。
―――こんな……! こんな事って……!
ハヤブサは、自分でも気付かないうちに、腕に力が入っていた。
「勾玉の正体を知った上で―――決めたい。これからどうすべきなのか」
「…………」
ハヤブサは微動だにせず、虚空の一点を険しい顔をして見つめている。
「ハヤブサ? 聞いているか?」
「…………」
呼びかけても、反応が無い。シュバルツは心配になった。
「ハヤブサ? おい! ハヤブサ!!」
「――――!」
ハヤブサが、やっとシュバルツと目を合わせる。だが、険しい顔のままだった。
(もしかして、無理難題を突き付けてしまったのだろうか…)
ハヤブサの顔色を見て、シュバルツはそう感じる。事が勾玉のことだけに、正体を知りたい、と、言うだけでも難しいのかもしれない。
「……すまない。こちらが勝手な要求をしているのは、分かっているのだが……」
シュバルツが申し訳なさそうに顔を伏せる。それを見たハヤブサが、まるで弾かれるように、叫んだ。
「謝るな!!!」
「――――!」
「謝るな……! ―――頼むから……!!」
そう言ったきり、ハヤブサは再び顔を伏せてしまう。
「ハヤブサ……?」
(震えてる……?)
握りしめた拳が、小刻みに震えていた。ハヤブサは、明らかに苦しんでいるように見える。
ハヤブサは、忸怩たる思いだった。何故、残月の目論見を、自分は事前に察知することができなかったのか。勾玉が里から外に持ち出されさえしなければ、このような事にはならなかった。
キョウジは、勾玉とは全く関係が無い。純粋な被害者だ。
それなのに、彼の守りたいと願っている人間の身体にそれが吸収され、こちらの都合で理不尽に狙われ、あまつさえ命を奪われようとしている。そして、それを実行するのが自分の役割かもしれないのだ―――。
最悪だ。
単なる人斬りより、もっと非道い。
大事な者を、奪う。一番酷く、キョウジを傷つける。
これも、誰かれ構わず、使命のために容赦なく人の命を奪い続けた、自分に対する報いなのか―――。
ハヤブサは、己の所業に吐き気を覚えた。
「ハヤブサ? 大丈夫か?」
「…………!」
気がつくと、キョウジの手が、自分の手にそっと添えられていた。キョウジからは、ハヤブサに対する優しい心遣いしか感じられない。
胸が締め付けられ、泣きそうになる。この誠意と優しさを、今のままでは自分は、手酷く裏切ってしまうことになるのだ。
「その……無理、ならば……本当に……」
シュバルツはおずおずと申し出る。この要求でハヤブサを苦しめるのは、自分としても本意ではなかった。そんなことをするくらいなら、別ルートを探したほうが余程いい、と、思う。
「…………」
ハヤブサは、そんなキョウジの顔をしばらく黙って見つめていたが、やがて眼を閉じ、頭を振る。
「無理ではない……大丈夫だ…」
「ハヤブサ……!」
心配するキョウジの手を軽く振り払い、ハヤブサは立ちあがった。
「ついて来い、キョウジ……。隼の里に、案内しよう」
(キョウジには、総てを知る権利がある)
ハヤブサは、思う。そう、総てを知る権利がある―――そして、自分たちを恨み、報復する権利も。
守りたい、と、願っている者の命を、容赦なく奪うのだ。いくらこの温厚な男でも、これはさすがに許せないだろうと、思う。
覚悟が、必要だ。恨みを、総て引き受ける覚悟―――。
キョウジのような漢の、恨みの刃によって倒されるのならば、自分のような者には、ある意味、過ぎた幸せかもしれない。
(殺さずに済む道もあるのなら……)
ちらりと思い、すぐに打ち消す。それこそ、淡雪のような、愚かな望みだ。
「そこで、総てを話す」
そう言ったきり、ハヤブサはキョウジと口を利かなくなった。ひたすら前を見つめ、隼の里へと歩を進めることに専念した。
「…………」
シュバルツは、ハヤブサの後を黙ってついて行きながら、胸に広がる黒い予感を、どうしても打ち消すことができなかった。
ハヤブサは、明らかに苦しんでいる。自分自身のためではない。苦しめている原因が、こちらにあるのは明白だった。たぶん、とても良くないことを、ハヤブサは一人で抱え込んでしまっている。
(ハヤブサ…教えてくれ。お前は一体、『何』にそんなに苦しんでいる…?)
ハヤブサの背中が、近いのに遠い。シュバルツには、それが辛かった。
二人の行く先を包み込もうとする暗い予感とは裏腹に、朝日が、疾走する二人の姿を照らしていた―――。
「第四章」
ドモンとキョウジが、カッシュ邸から脱出をしてから丸一日が経つ。
二人が目指した男―――東方不敗マスターアジアの家は、人里離れた山の奥に、ひっそりとあった。ドモンは、家から少し離れた林の中に車を止め、用心深く外に出る。周囲に人がいないのを確認してから、彼は初めて兄を車の外に出した。
「兄さん? 大丈夫か?」
「あ……ああ、何とか、な……」
心配するドモンにかろうじて笑顔を見せるも、地面がぐるぐる回る感覚を、どうしても止めることができない。
(うう…気持ち悪い……酔い止めを飲んどきゃよかった……)
整備された都会の道を走るのならばともかく、長時間狭い所に押し込められた状態で、曲がりくねった山道を走ってきたのだ。おまけに、追われているから仕方がないとはいえ、ドモンの車の運転はかなり荒っぽい。周りが見えないから、次どちらに曲がるとかの対応が全くできないし、身体はあちこちぶつけて痣だらけになるしで、これでは車に酔うなという方が、無理、というものであった。
「さて、師匠……いらっしゃるかな?」
ドモンがそっと家の方を伺い見る。しかし、茅葺の、あばら家といった風情を漂わせている家からは、人の気配が感じられない。
「師匠? 師―――!」
とたんに、鋭い殺気をドモンは捉えた。
「兄さん!」
「え?」
ドモンがキョウジを抱えて跳躍する。直後、二人のいた地面が、ドゴォッ!! と、音を立てて大きく穿たれた。
「久しいな! ドモンよ!!」
舞い上がる土煙りの中から、体格のいい一人の男が飛び出してくる。三つ編みで一つに束ねられた銀色の長い髪をなびかせながら、老人、と呼んでもいい外見をしたその男は、まっすぐドモンに向かって来た。
「師ィ匠ォォ――――!!!」
その男の姿を認めたドモンも、キョウジを置いて、真っ向からぶつかっていく。ドカン!! と、音を立てて二人の拳と拳がぶつかった。そのまま、激しい拳の応酬へと移行していく。
「ドモンよ! 我が問いに答えよ!!」
拳の乱撃の最中、ドモンから「師匠」と呼ばれた男が叫ぶ。
「流派!! 東方不敗は!!」
師匠からの拳を受けたドモンが返す。
「王者の風よ!!」
「全新系列!!」
「天破侠乱!!」
ここで、二人の拳と拳が再び真正面からぶつかり合った。
ドン!!
拳から放たれた互いの衝撃波が、周りの地面から粉塵を巻き上げ、近くの木々を激しく揺らす。
「…………!」
近くで見ていたキョウジは、あおられて倒れそうになるのをかろうじてこらえた。
「見よ!! 東方は、赤く燃えている―――!!」
師匠と弟子の叫び声が、ぴったり重なる。二人の男は、拳と拳を合わせたまま、しばし睨みあった。
先に動いたのは、東方不敗の方であった。彼の鋭かった眼光が、ふっと穏やかな色に染まる。
「ドモンよ。腕を上げたな」
「師匠……!」
合わせていた拳を、ドモンの方が解き、そのまま師の拳を包み込んだ。
「お会いしとうございました…! お元気そうで、何よりです」
「うむ」
ドモンが心からの笑顔になり、東方不敗も笑顔を返す。二人の間にかわされたのは、拳と掛け声だけ―――。だがそれでも、二人は口で語り合うよりも雄弁に、拳で語り合ったに違いない。
(拳で語り合う、ファイターか……)
キョウジは眩しそうに二人を見つめていた。学者である自分には、たぶん永遠に分からない世界なのだろうな、と思う。
「ところでドモンよ。今日は一体何用で来たのだ?」
「はい。それが―――」
東方不敗の問いかけに、ドモンはキョウジの方に振り向く。ここではじめて、東方不敗はキョウジの存在に気付いた。
「おや、兄御も一緒か。これは珍しい―――」
「お久しぶりです。マスターアジア」
意外そうな顔を向ける東方不敗に、キョウジは人懐こい笑みを浮かべて答えた。
「ご無沙汰しています。弟が、いつもお世話になりまして―――」
キョウジが、深々と丁寧に頭を下げる。
「ああ、いや、ご丁寧に……ところで、お身体の方はすっかり良いのかな?」
「ええ。おかげさまで―――マスターこそ、その後お身体は…?」
「ワシか…。ワシの方はすっかり治ったぞ? 医者に後50年は生きられると、太鼓判を押されたわい」
そう言ってカラカラと豪快に笑う。この東方不敗マスターアジアという人間は、良くも悪くも武闘家らしい、豪胆な人柄であった。
実は、この東方不敗とキョウジの間には、浅からぬ因縁がある。
先の『デビルガンダム事件』の際、デビルガンダムに取り込まれたキョウジを、東方不敗は己の願いを現実のものとするために利用していた。
東方不敗の願い―――それは、地球の自然再生と、それを阻害する人類の抹殺である。
不治の病を得たと、思いこんでしまったが故に、東方不敗は生き急ぎ、デビルガンダムの持つ強大な力に惹かれてしまった。そして、デビルガンダムに取り込まれたキョウジを傀儡として祭り上げ、それを止めに来たドモンとぶつかり合うことになったのである。
最終的に見事師を超えるほど成長を遂げたドモンによって説得され、人類抹殺という選択肢を東方不敗は捨てることになるのだが。
あの悪夢のような事件からお互い無事に生還した今、キョウジの方はもうそれほど気にしてはいないのだが、やはり東方不敗の方には、キョウジを利用してしまったという負い目が微妙にあるらしい。何となくキョウジに対して、東方不敗は今でも壁を作ることがある。
(この人が力を貸してくれたら、心強いんだけどな)
キョウジはちらりと、そう思った。だが、東方不敗という人間は、根っからの武人。彼が認めた者のためにしか、その力は振るわれないだろう。拳で語ることができるドモンならともかく、武闘家でもない自分がこの人に認められる可能性は、もしかしたら皆無に近いかもしれない。
(贅沢な望みか……だが―――)
キョウジの心に、微笑んでいたシュバルツの姿がよぎる。
今、この瞬間も、シュバルツは身体を張って戦っているかもしれない。そのおかげで出来た、敵から狙われない貴重な空白時間。ここで自分は、この人と運良く接触ができた。
(これは、チャンスなんだ)
キョウジは、そう思うことにした。今のうちに、東方不敗から全面協力とまではいかないまでも、少しでも、勾玉の情報と助力が得られたら―――そのために自分ができることがあるなら、何でもするつもりだった。
基本、キョウジは来る者は拒まずだが、去る者も追わない姿勢を貫いている。人と深くかかわることが苦手な自分を、十分自覚していた。だから、自分が東方不敗に助力を請う試みも、もしかしたら空振りに終わり、失敗してしまうかもしれない。
それでもいい。
やらないよりは。
そうしなければ―――シュバルツが身体を張ってくれた意味が、無い。
幸いなことに、自分には彼の一番弟子の兄というアドバンテージもある。ほかの人よりは、この人に対するとっかかりができやすいはずだった。ただ、このアドバンテージ自体も、この人にどこまで通用するのかは、いささか疑問ではあるが。
(失敗しても、その時はその時)
キョウジは腹をくくって、一歩前に進み出た。
「マスター、これはドモンから……お口に合えばいいのですが」
そう言ってキョウジは、ドモンが師匠のために買って来た土産をそっと東方不敗に差し出す。
「おお、月餅か……いつもすまんのう」
東方不敗は礼を言いながらも、少し戸惑った。いつもなら通り一遍のあいさつを済ました後はドモンの後ろに控えるキョウジが、珍しく前面に出てきているからだ。
「そしてマスター……もう一つは、私から」
そう言ってキョウジは、手に持っていた小さな袋を持ちあげる。
「ん?」
「よい茶葉が手に入りましたので―――不躾ながら、茶を淹れさせていただけませんか?」
「何? 主が茶―――とな?」
ジロリ、と、東方不敗の鋭い視線が、容赦なくキョウジに浴びせられる。
(本当に不躾だったかな?)
キョウジの背中に、冷たい物が一瞬流れる。しかし、彼はそれを表には出さず、穏やかな視線で東方不敗を見つめ返した。
(兄さん?)
ドモンは不思議な気持ちで兄の背中を見つめていた。いつもなら他人に対して淡白な兄が、何故か今日に限って、積極的に師匠に係わろうとしているように見える。
「………………」
キョウジは、最後まで視線を逸らさなかった。それを見た東方不敗が、にやりと笑う。
「よかろう……付いて来なさい」
「ありがとうございます」
軽く頭を下げ、東方不敗の後に続く。キョウジの静かなる戦いが、今、始まろうとしていた。
東方不敗はまず、キョウジ達を家の方ではなく、蔵の方へと案内した。
「ここに茶器がある。好きなのを使いなさい」
壁際の棚に、箱にも入れられていない茶碗がきれいに並べられている。それらをしばらく眺めていたキョウジが、東方不敗に尋ねてきた。
「これらは、マスターが作られたのですか?」
「………! 何故そう思った?」
東方不敗が意外そうに、逆に問い返してくる。
「碗から受ける印象が……その、何となく、マスターらしいかな、と……」
キョウジは慎重に言葉を選びながらも、素直な感想を述べた。形がとても武骨で、力強い存在感があるのに、何故か繊細な印象も受ける。それがとても東方不敗らしい、と、キョウジには感じられたからだ。ただ、自分には焼き物を見る審美眼があるわけではないので、本当に感覚的な感想なのだが。
「フフフ……『ワシらしい』か…」
東方不敗がにやりと笑う。どうやらキョウジの答えに満足したような印象だった。
「―――いかにも、ここにある焼き物のほとんどは、ワシが作ったものじゃ。そうでない物もあるがな」
「師匠、陶芸もなさるんですか?」
ドモンが意外そうな声を上げた。ドモンの中では、師匠と芸術が、なかなかイコールで結びつけられないらしい。
「ドモンよ。土を触ることは良いぞ? 心静かにろくろを回すことは、己の精神を鍛えてくれる……ここは、善い土が取れて良い」
「―――はぁ」
師匠の言葉に返事をしながらも、ドモンの顔にはクエスチョンマークが浮かんでいた。
(俺には全部、同じようなものに見える……)
それがドモンの、正直な感想である。
(こ奴はやっぱり、相も変わらず芸術を理解せんな……)
特に興味もなさそうに、何となく陶器を見つめているドモンの態度に、東方不敗はため息をつく。このドモンの粗野な所は、きっと一生治らないのだろう。
(まあよい。これもこ奴の個性のうち―――)
事実、この一本気なドモンの性格ゆえに、東方不敗自身がどれだけ彼に救われたか分からない。ドモンはこのままでいいと思いつつ、東方不敗はキョウジの方にちらりと視線を走らせた。
キョウジは先ほどから、一つ一つの焼き物を丁寧に吟味するように見ている。
(あ奴は今日の茶に、どの器を選ぶのであろうか……)
どの器を選ぼうが別にかまわないのだが、と、思いつつも、東方不敗は少し気になった。先ほどキョウジは、特にこちらが何も言わなかったのに、これらの焼き物が自分の作だと言い当てた。なかなか鋭い観察眼を持っているのは、さすが学者といったところか。
この蔵には、東方不敗自身が作った焼き物もあるが、そうでない物もある。お土産用の1000円ぐらいの器もあれば、東方不敗自身がわざわざ求めた、人間国宝の手によって作り出された貴重な碗もある。
(こ奴が何を考えとるのかは知らんが、面白くなってきおったな…)
虫干しのために並べていた碗が、思いもかけぬ興を呼び込んできた。キョウジは、人間国宝の器を取るのか、はたまた、土産物レベルの普通の器を手に取るのか―――。我知らず、東方不敗の面に、にやりと笑みが浮かぶ。
キョウジはやがて、一つの碗を手に取って振り返った。
「マスター……こちらをお借りしてもよろしいでしょうか?」
「――――!」
東方不敗は驚いた。キョウジは、人間国宝の手による器の横に置いてあった、東方不敗の作である器を手に取っていたからである。
「お主、何故それを選んだ?」
東方不敗は腕組みをしながら、キョウジに聞いた。
「景色(陶磁器の表面に浮き出る不測の模様)がとても綺麗だったものですから…」
そう言ってキョウジは、手に取った碗を優しく見つめている。
「…………!」
キョウジが指摘した通り、その器は、鎌の中で偶然起こった釉薬の流れが、武骨な中に美しい彩りを添えていた。東方不敗が自分で作った物の中でも、最も気に入っていた一品である。その出来は、人間国宝の作にも負けはしない。そう思えたからこそ、敢えてその作品の横に置いていた物でもある。
「ああ、すみません。……もしかして、触れてはいけない物でしたか?」
東方不敗があまりにもじ~っとこちらを見ているので、キョウジは少し焦った。
好きなのを使いなさい、と、東方不敗は言ってくれたが、キョウジは、東方不敗の手による碗をぜひとも使いたい、と、思っていた。それが、頼みごとをする側の礼儀だろうと感じたからである。この碗は、明らかに毛色が違う碗の横に、誇らしげに置いてあった。きっと、東方不敗も気に入っている一品だろうと踏んで、敢えてこれを手に取ったのだが。
逆に、気に入りすぎている碗だから、他人には触れてほしくないと思っている可能性もある。そうなると、今この瞬間、自分は東方不敗に対して最大級の無礼を働いていることになるのだ。手から、止めようもない汗があふれてくるのを感じる。
(今、手を滑らせてこの碗を落としたりしたら、私、たぶん死ぬな……)
尻込みしそうになる己を叱咤する。
しっかりしろ、キョウジ・カッシュ。
挑んでいるのは自分だ。試されているのも、自分だ。
絶対に―――逃 げ る な !
内面の葛藤を表に出さず、キョウジは東方不敗を穏やかに見つめ返した。
(その視線に、迷いなし……か)
東方不敗の視線が、ふっと優しい物になる。
「構わん。道具は使われてこそ、生きてくるというものよ」
それを使え、と、踵を返す東方不敗に、
「ありがとうございます」
と、キョウジは礼儀正しく頭を下げた。
「茶室はこっちじゃ。ついて来なさい」
東方不敗の言葉に、カッシュ兄弟は大人しく従った。
茶室は、俗世から切り離された別世界である―――と、よく言われる。東方不敗の家にしつらえられた四畳半の茶室が、今まさに別世界と呼ぶのにふさわしい場所になっていた。木立の間を通り抜ける風が、木々のざわめきを伴いながら穏やかに障子をたたく。障子越しの優しい木漏れ日の中、キョウジは東方不敗とドモンに茶をふるまうために、粛々と準備を進めていた。
(ほう、これは……)
東方不敗はキョウジの様子を眺めながら、ドモンとキョウジが茶室に入る前に交わしていた、小声の会話を思い出す。
「兄さん、茶道なんて習ったことがあるの?」
問いかける弟に、兄は笑顔を返した。
「興味があったから。でも、かじった程度だよ―――」
本人は、確かにそう言っていた。しかし、今目の前で行われているキョウジの所作は、どれも無駄が無く美しい。とてもかじった程度とは思えないほど、堂に入っていた。
「兄さんって、本当に何でもできるんだよな……」
東方不敗の横で胡坐をかいて座っているドモンが、ぼそりと呟く。
ドモンが小学校に上がる頃には、成績優秀で何でもできるキョウジはすでに有名になっていた。「あのキョウジ・カッシュの弟が入学してきた」と、ドモンも随分と注目されたものである。
先生も友達も、自分のことを「キョウジの弟」と呼び、事あるごとに兄と比較してくる。当然自分は兄ほど頭が良いわけでもなく、何でもできるわけではない。
―――「あの」キョウジ・カッシュの弟なのにねぇ……。
先生や、周りの無神経な大人たちのささやく声が、ドモンの耳には嫌が応にも入ってくる。こうしてたまりにたまった鬱積を、ある日、たまたまキョウジと一緒に学校から帰っていたときに、ドモンはついに爆発させてしまった。
「俺の名前はドモン・カッシュだ!! 『キョウジの弟』じゃ……無いッ!!」
「…………!」
しばしの沈黙の後、「―――分かったよ」と、吐き捨てるように兄は言い、それまでつないでいた手を離して、すたすたと先に歩いて行ってしまった。
(なんであの人が俺の兄で、俺は、弟なんだ……!)
涙でかすむ兄の後ろ姿を見ながら、やるせない気持ちになったことを、つい昨日のことのように思い出す。
もちろん今では、こうして何でもできる兄の姿を見ても、それを穏やかな気持ちで受け入れることができている。それだけ自分も少しは成長出来た証だろうか、と、ドモンは思う。
「ドモンは、茶を嗜んでみようとは思わんのか」
東方不敗がドモンに声をかけてきた。
「う~ん、俺には文化的な物は、よく分からなくて……」
ある程度予想どおりなドモンの反応に、東方不敗は苦笑した。
「よいか、ドモンよ。茶というのは女子ばかりが嗜む物ではないぞ。戦国時代に遡れば、それは武士の必須の嗜みであったのだ」
「そうなんですか?」
ドモンが少し興味を持ったようだ。東方不敗はさらに続けた。
「昔から、この四畳半の空間は、特別なものとされておる。茶をたしなむ者は皆、この茶室に入った瞬間から、俗世のしがらみを忘れ、争いごとを持ちこまぬようにしておった。で、あるから、たとえ戦争をしている国同士の君主であっても、茶室に入れば同席して茶を飲んだという」
「…………」
「見よ、この静謐なる空間を…。昔の武士の心が、伝わってくるようには感じぬか?」
(武士の、心……)
ドモンは黙って茶を点てる兄の姿を見つめた。師匠が言っていた難しい話は、正直よく分からなかったが、障子越しの優しい光の中、静かに茶を点てている兄の姿は、何故だか美しく感じられた。そこから漂ってくる凛とした空気が、自然に、ドモンの姿勢を正させる。
(そう……俗世のしがらみを忘れ……)
「――――!」
不意に、東方不敗は思い当った。自分とキョウジの間にも、しがらみがあったことを。
そして、悟った。
何故彼が今、この席を設け、自分に茶を点てているのか。その意味を―――。
どうか、忘れてくださいと、彼は言っているのだ。
自分と、貴方の間に在ったあの苦いしがらみを、どうか。
この茶の一杯で、忘れていただけませんか―――。
(キョウジの奴……味なまねを…!)
まさか、彼の方からこのような風流なやり方で、自分にアプローチしてくるとは思わなかった。己の心が心地よく揺さぶられているのを、東方不敗は感じていた。
「―――どうぞ」
ここで、最初の茶を点て終わったキョウジが、東方不敗の方にそっと茶を差し出した。そして、東方不敗に正対して座りなおし、深く静かに頭を下げる。
―――彼は、ワシとの和解を望んでいる……。
東方不敗は、何故か素直にそう思えた。
キョウジの所作は、最後まで乱れず、美しかった。それは、彼の心根の美しさを、そのまま反映しているものに違いなかった。
(ウム。キョウジよ! 茶に込めたそなたの心、この東方不敗確かに受け取った!)
東方不敗は作法に則ってキョウジからの茶を受け取ると、音を立てて一気に飲み干した。
「ああ……旨い。キョウジよ、結構な点前であったぞ」
「―――ありがとうございます」
礼を言うキョウジの面が、さらに穏やかな色を帯びる。
「兄さん! 俺にも!」
師匠があまりにもうまそうに茶を飲んだので、ドモンの方が我慢出来なくなったらしい。屈託なく兄を急かしてくる。
「ちょっと待ってろ。今点ててやるから」
キョウジは苦笑しながら、次の茶を点てる準備に入った。
東方不敗の家の茶室は、久々に穏やかな空気に包まれていた―――。
(知らなかった。お茶って甘いんだ……)
兄に点ててもらった何度目かのお茶を味わいながら、ドモンは思った。こんなにうまい飲み物があるなら、もっと早く教えてもらえば良かったと、少し後悔していたりする。
「ドモン、そろそろ本題に……」
兄の声に、ドモンもここに訪ねてきた当初の目的を思い出す。ドモンは居住まいを正して師匠の方に向き直った。
「師匠」
「うん?」
「実は、我ら兄弟が師匠のところにお訪ねしたのは、お伺いしたい事があったからなのです」
ドモンの改まった様子に、東方不敗の目つきも鋭い物になる。
「何じゃ。申せ」
「師匠は、『龍の勾玉』というものを、ご存知でしょうか?」
「龍の勾玉…」
東方不敗が訝しげに聞き返した。
「数日前、これが兄の身体に吸収されてしまったようなのです。その為に兄は狙われ―――我々はそれを避けるために、ここへ来ました」
「なるほど……で、何故ワシがその勾玉について知っていると思った?」
「我らシャッフル同盟は、古今東西の戦いを見守る存在であるはず―――」
シャッフル同盟とは、キング・オブ・ハートを筆頭に、ブラック・ジョーカー、クラブ・エース、ジャック・イン・ダイヤ、クイーン・ザ・スペードの5名から構成される、どの組織にも属さない独立した戦闘集団であった。その歴史は古く、人類史の大きな戦争の影には、必ずシャッフル同盟の者たちの何らかの関与があったとさえ云われている。ただ、あまり表舞台に出てくることが無いため、存在自体が伝説化しており、一般的には知られていないのが現状である。
東方不敗は、先代のキング・オブ・ハートで、今はそれをドモン・カッシュが受け継いでいた。ブラック・ジョーカー以下4名も現存しており、ドモンにとっては良きライバルであり、素晴らしい友人達ともなっている。
ちなみに先の『デビルガンダム事件』の折にはシャッフル同盟がそろい踏みをし、事件解決に、大きく貢献したと伝えられている。
「戦いの影に、必ずその姿ありと言われていたシャッフル同盟。その先代のキング・オブ・ハートであった師匠ならば、ありとあらゆる戦いの歴史に通じていらっしゃるはず……その中に、『龍の勾玉』に関連する物があれば―――と、思いまして……」
「ふむ……」
東方不敗は目を閉じ、顎に手を当てて考え込んだ。
(龍の勾玉……はて、どこかで見た…ような……)
頭の中で、自分が今まで読んできた戦いの歴史に関する資料を紐解いてみる。やがて、東方不敗は、一つの可能性のある答えに行きあたった。
「龍の勾玉―――確かに、何かの文献で見たことがある」
「――――!!」
東方不敗の思いもかけぬ言葉に、カッシュ兄弟は色めき立つ。
「師匠! 知ってらっしゃるなら教えてください! 『龍の勾玉』とは一体―――!?」
興奮して詰め寄ろうとするドモンを、東方不敗は「まぁ、待て」と、軽く制する。
「ワシも、うろ覚えの範囲であるから、はっきりしたことは言えんが―――」
ここまで言って東方不敗は、軽くキョウジの方に視線を走らせた。
「キョウジよ。お主の身体に、その勾玉は吸収されたと言ったな?」
「はい」
「…………」
即答するキョウジに、東方不敗はしばし黙り込む。腕を組み、これからどう説明すべきか考えているようにも見えた。
「ワシの記憶に間違いが無ければ、それは確か、何かの『鍵』だ」
「鍵……ですか」
確認するキョウジに、東方不敗はじろりと鋭い一瞥を返す。
「そう―――それも、あまり良くない物のな」
「…………!」
東方不敗の容赦ない一言に、さすがのキョウジも顔色が変わる。だが―――それ以上に、ドモンの方の顔色が、凄まじく変わっていた。
「良くない物って……! 師匠!! どういうことですか!? 兄さんは……! 何で兄さんに、そんな物が!!」
「落ち着かんか、ドモン」
激しく詰め寄ってくるドモンを、東方不敗は鬱陶しそうに振り払おうとする。しかし、ドモンは引き下がらなかった。
「これが落ち着いていられるか!! どういうことですか師匠!! 兄さんはいったいどうなる!? 兄さんが、何をしたって言うんだ―――!!」
「ええい、落ち着けと言うておる! この馬鹿弟子が!!」
一瞬、東方不敗が手を動かしたかと思うと、ドモンは東方不敗の尻の下に抑え込まれていた。
「―――全く、頭に血が上ると前後の見境がなくなるのは、相変わらずじゃな……」
ドモンが下でもがいているが、上に乗っている東方不敗はびくともしない。膝に肘をつきながら、ドモンに対してぶつくさ文句を言っている。
「くそっ! 放せ!! はな……!!」
「―――落ちつけよ、ドモン」
「兄さん!?」
声のした方にドモンが顔を上げると、兄がすぐ近くまで来て座り、穏やかな顔でドモンを見下ろしていた。
「兄さん……何で……」
ドモンの問いに、キョウジはふっと笑顔になった。
「―――お前が、私の分まで焦ったり怒ったりするから、おかげで私は、することが無くなる」
「――――!」
ドモンがようやく、もがくのをやめた。それを見て、東方不敗がやれやれと腰をどける。
「ワシもうろ覚えの範囲だと言うておろうが。詳しい事は、その文献を読みなおさんと、はっきりとしたことは言えん」
「そうですか……」
キョウジは平静を装った返事をしたが、内心は、
(うわぁ……その文献、読んでみたい……!)
という、書痴な自分との戦いが繰り広げられていた。学者という種類の人間は、とかく貴重な資料とか文献には弱い。歴代のキング・オブ・ハートが受け継いできた文献ならば、さぞかし読みごたえがありそうだ。
(まあ、キング・オブ・ハート以外は読んではダメな資料なら、私は読めないだろうけどな……)
何とか自分をあきらめさせようと理由をこじつけるが、どこかで「チッ」と舌打ちをしている自分がいる。もしも東方不敗が、「これを読ませてやるから3回まわってワンと言え」と、キョウジに命じたならば、彼はあっさりそれに応えてしまうかもしれなかった。
気の毒なのはドモンである。兄の命の心配をしているその横で、兄自体がこんなのんきな葛藤を抱いているとは夢にも思わないだろう。キョウジの冷静さ、ここに極まれりである。
「で、その文献は、今どこに?」
キョウジは我慢できずに、つい、ぼろっと聞いてしまう。
「うむ。その文献は―――」
ここまで言った東方不敗が、ジロリ、とキョウジを睨んできたように見えた。
(まずい! 出すぎた質問をしてしまったか!?)
キョウジ的にはかなり下心を含んだ質問だっただけに、背中に一気に冷たい物が流れる。
だが、東方不敗はどうやら別の物に反応したようだった。
「良くない物は、どうやら良くない物を呼び込むようだな」
そう言うと東方不敗はにやりと笑う。
「感じぬか? ドモン」
「え?」
「静かすぎる。先ほどから―――鳥や虫といった、動物の鳴き声がしておらんぞ」
野生動物の音が消えるということは、近くに人間が来ているということを意味する。
「!!」
ドモンは弾かれるように、家から飛び出した。
「ドモン・カッシュが出てきたぞ!!」
ドモンの姿を認めた軍人らしき男が大声を上げる。その声を合図に、わらわらと男たちが銃を構えて飛び出してくる。東方不敗の家は、いつの間にか完全武装した30人ほどの軍隊に、すっかり取り囲まれていた。
(こいつらが……兄さんを狙っている奴らか―――!)
ぴくぴくと、頬がひきつるのを感じる。銃口がこちらに向けられているのを見ても、ドモンは怖じ気るどころか、腹の底から怒りがわき上がってくるばかりだ。
「ドモン!!」
キョウジも、ドモンにつられて立ち上がった。だが、東方不敗がキョウジの手を取り、キョウジがそこから動くことを阻んだ。
「マスター!?」
「キョウジよ…。言うておくことがある」
「――――!」
東方不敗の真剣な眼差しに、キョウジは悟った。
(ドモンには聞かせたくないことで、私に話があるのか)
「どうぞ」
覚悟を決めて、キョウジは東方不敗に向き直る。
「これから先の戦い、お主は絶対に敵の手に落ちるな」
「―――? それはどういう…?」
「その勾玉は、確か強大な力を持つ物の鍵……つまり、コアとなるべき物だ。それが、何を意味するか分かるか?」
「―――!」
瞬間、キョウジの背中に寒気が走る。意味を、悟ったからだ。
「そう―――敵の手に落ちれば、お主は確実にそれに取り込まれる。先の一件で、お主がデビルガンダムに取り込まれたようにな」
「!!」
キョウジは、思わず口に手を当てた。顔色も、真っ青になっていく。
「そうなると―――もう、ワシやドモンでも、どうしてやることもできんぞ。取り込まれた時の無力は、己が一番よく知っておろう?」
「………ッ!」
キョウジの脳内に、デビルガンダムに取り込まれていく己の体験がフラッシュバックする。抵抗するも、どんどん自我が奪われていく恐怖―――目の前で、たくさんの命が失われていくのを、ただ黙って見ているしかない無力。
(あれが……また―――!)
いやだ―――と、大声で叫びたくなる。手足が、勝手にがたがたと震えていた。
(―――無理もない……)
東方不敗は思った。「取り込まれる」という経験は、おそらくキョウジにとっては、最大級のトラウマとなっているに違いない。それが、もう一度彼を襲う可能性があるのだ。普通なら、それを思うだけで、精神が瓦解してしまってもおかしくない。
「だから―――絶対に、敵の手に落ちるな。例え、この先何を犠牲にしたとしても、だ」
「…………」
キョウジの荒くなりかけていた呼吸が、だんだん静かなものになっていく。東方不敗はただ見守った。自分は、事実を述べ、助言をしただけだ。これを受け入れられないようなら、これ以上キョウジに戦いを強要することはできない。戦えぬのなら、酷なようだが見放さなければならない。覚悟もできぬ者が、強大な力の源を握りこんでいたところで、迷惑千万なだけだからだ。
必要とあれば、キョウジを殺すことまで東方不敗は考えた。そうしなければ、キョウジをいたずらに苦しめるだけでなく、勝ち目のない戦いに、ドモンも自分も巻き込まれていくだけだ。
(どうする、キョウジ―――。今、ここで死ぬか?)
自然に、東方不敗の拳に力が入る。
「――――」
キョウジは目を閉じ、まだ震える己の手を握りこんだ。まるで祈るような仕種だと、東方不敗は思った。そのままキョウジは深く息をすると、静かに目をあける。
(震えを止めた?)
握りこんでいた手を解き、すっと自然な立ち姿になったキョウジは、もう震えていなかった。正眼で東方不敗に相対し、そして―――。
「分かりました」
と、ただ、それだけを言った。
さすがに顔色も悪く、表情も硬い。しかし、眼は力を失ってはいなかった。
(こ奴―――! すべてを、受け入れおった……!)
東方不敗は理解した。キョウジのこの態度は、トラウマから逃げたのではない。強がっているのでもない。ただ、受け入れたのだ。自分にトラウマがあることも、それにがたがた震える情けない己も、次に、またそれが自分を襲う可能性があることすらも。すべてを是とし、受け入れた。それどころか、自分に襲い来る「死」さえも受け入れている節がある。そうでなければ、こんな迷いのない穏やかな眼差しを、東方不敗に向けられるはずが無いのだ。
(ただの優男と思っておったが、何という強さ、懐の深さか―――)
東方不敗はにやりと笑う。今ここで、自分が力を貸すだけの価値が、キョウジにはどうやらあるようだ。
「よかろう。キョウジよ。外に出るか」
「え?」
一瞬東方不敗が何を言っているのかが分からず、キョウジはきょとんとする。
「面白い物を見せてやる」
それだけ言うと、東方不敗は強引にキョウジの手を引っ張った。
「あ、あの! でも、マスター! 私は……!」
キョウジが何か言っているようだが、東方不敗にはもう聞こえていない。久々に血がたぎる展開に、胸を躍らせているようであった。
キョウジと東方不敗が部屋の中で話をしている頃、ドモンもまた外で、軍隊の男たちと対峙していた。
「お初にお目にかかる。ドモン・カッシュ君。私はダレク大佐だ。『大佐』と、呼んでくれても構わんぞ?」
(―――誰が呼ぶか!!)
部隊の中のひときわ高い所で、重装備をしているベレー帽の男にそう名乗られたドモンは、心の中で盛大に毒づく。
「―――何の用だ!!」
今すぐこいつをミンチにしてやりたい―――そういう物騒な衝動をかろうじて抑えながら、ドモンは口を開いた。しかし、ドモンの鋭い声を、ダレクは鼻で笑ってあしらった。
「あの夜、家からひそかに脱出した君は、必ず師匠である東方先生の家を訪ねると思っていた―――私の読み通りだ」
「だから、何だ!!」
「しかし、驚いたのは、何故か先に家を出たはずのキョウジ・カッシュ君の姿もあったようだね…。どういうことだ? 詳しく話を聞かせてもらえないかね?」
(誰が話すか!!)
ドモンの頬のひきつりが、さらに激しくなってきた。下種が! お前が軽々しく兄の名を呼ぶな!! ―――そう叫びそうになる。
「断る、と、言ったら?」
「―――君は、状況を理解していないのかね?」
ダレクが手を上げると、周りの男たちが物々しく音をさせて、一斉に銃口をドモンに向けた。―――だが、ドモンはそれを鼻で笑う。
「ああ、理解しているさ―――あんた方では、俺に傷一つつけることはできないってね」
「何だと?」
偉そうにふんぞり返っていた、ダレクの眉が釣り上がっている。
「―――試してみるかい?」
凶暴な笑みが、ドモンの面に浮かんだ。その、あまりにも自信たっぷりな様子に、ダレクは一瞬気圧される。しかし、気を取り直した。30発の銃口から無事に生還できる人間など、この世に存在しはしない。
「かわいそうに……恐怖のあまり、気が触れたと見える」
わざと、芝居めいた仕種をして、ドモンを哀れんで見せた。しかし、ドモンの態度は変わらない。
「―――怖いのか? かかって来いよ」
逆に、挑発し返してくる始末だ。ダレクは、深いため息をついた。
「残念ながら、こちらは君に用があるわけではない……。キョウジ・カッシュ君を呼ばせてもらうよ」
「こいつ―――!!」
ドモンは歯噛みした。銃に負けない自信はある。ただ、30発もの銃口に狙われていては、迂闊に身動きが取れないのも事実だ。こいつらに銃を撃たせさえすれば、こちらのペースに持ち込めるのに……!
「キョウジ・カッシュ君! 中にいるのだろう? 出て来たまえ―――君のかわいい弟が、穴だらけになる前に!!」
「兄さん!! 駄目だ!! 出てくるな!!」
(そんな言い方をしたら、兄さんは絶対に出てきてしまう……!)
ドモンの表情が、焦りを帯びる。
(何て素晴らしい展開だ……!)
ダレクは勝利を確信し、笑いをかみ殺した。平和に暮らしてきた普通の人間は、ちょっと肉親を人質にとられたぐらいで、あっさりとこちらの意のままになる。
キョウジが家から出てきたら、「撃たないから」と、言ってこちらに身柄を確保する。そのうえで、彼の弟と師匠とやらをハチの巣にしてやるのだ。その時の、身内を殺されてしまった者の絶望と怒りの入り乱れた表情を眺める瞬間が、ダレクは何よりも好きだった。
(さて―――今回の獲物は、どんな表情を見せてくれるのか)
資料で見た限り、キョウジ・カッシュはなかなかの美青年だ。これが、どんな風に表情を歪ませるのか―――ダレクの表情に、下卑た笑みが自然に浮かぶ。
ダレクの声は、中にいるキョウジにも当然聞こえていた。
「…………!」
ふら、と、キョウジが歩を進めようとするのを、東方不敗が止める。
「待たんか、キョウジ」
「しかし、あのままでは―――!」
珍しくキョウジの顔に、焦りの表情が浮かんでいる。東方不敗は苦笑した。先ほど、あれだけの強さを見せたというのに、身内への攻撃に対しては、恐ろしく弱いというのが、どうやらこのキョウジ・カッシュという男の特徴らしい。
「案ずるな。ドモンを信じよ。そして、ワシを信じよ。ワシもドモンも、あの程度の者共に負けるような、やわな鍛え方はしておらんぞ」
「マスター……!」
キョウジの瞳に、落ち着いた色が戻ってくる。東方不敗はにやりと笑った。
「行くぞ、キョウジ! いざ、戦いの場へ―――!」
「キョウジ君? どうしたのだ? 君は、弟を見捨てるのかね?」
すぐに出てくるだろうと踏んでいたキョウジが、なかなか出てこない。ダレクは少し、焦れた。
「お前ごとき、兄さんが相手にするか!!」
ドモンも必死に声を張り上げる。とにかく、奴らが過信している銃がただの木偶の棒であることを、早く知らしめてやりたかった。が、こちらに手を出してくれないと、それを証明することもできない。
「仕方が無い。軽く脅かすとするか―――」
ダレクが部隊に指揮をするべく、手を上げる。
(しめた―――!)
ドモンが、待ってましたと身構えた瞬間。
「キョウジ・カッシュならここに居るぞ!! 逃げも隠れもせぬわ!!」
野太い老人の声と共に、体格のいい老人と、ターゲットであるキョウジ・カッシュが家の中から姿を現した。
「大佐、やはり、おかしいです」
キョウジの姿を認めた部下の一人が、ダレクに進言する。
「何だ?」
「キョウジ・カッシュは昨晩残月殿と戦闘後、ロストしているのですが、どう考えてもこの距離をいきなり移動してくるのは無理です。あそこにキョウジ・カッシュがいるのは、おかしくないですか?」
「忍者風情からの情報など、あてになるか!」
部下からの進言を、ダレクは斬って捨てた。
「だいたい、キョウジ・カッシュと戦闘しながらロストするという情報自体も、忍者のでっち上げかもしれんのだ! ターゲットを見つけられなかった、己の無能を隠すためのな!!」
「―――はっ!」
(自分は、忍者からの情報を頼りにここまで来たくせに…!)
部下は礼儀正しく引き下がりながらも、内心舌打ちをした。
(シュバルツは、捕まってはいない……)
ダレクと部下のやり取りからシュバルツの無事を確認したドモンとキョウジは、同時にほっと息をついた。不死を誇るが故に、シュバルツは常に無茶をする傾向があるから心配だった。敵がロストしているということは、囮となった後、うまく姿をくらませることができたのだろう。
「ドモンよ。どんな状況だ?」
東方不敗は背にキョウジを庇うようにしながら、ドモンの背後に立った。
「はい。御覧の通りです」
百聞は一見に如かず―――と、言う言葉通りの説明を、ドモンはした。
「ほう……」
東方不敗は、家の周りを取り囲んだ30人ほどの兵士たちを、ぐるりと見渡したかと思うと、いきなり声を立てて笑い出した。
「フフフフ……。うわっはっはっはっは!! があっはっはっは!!」
「―――何がおかしい!?」
現れるなり、いきなり高笑いを始めたこの無礼な老人に対して、ダレクの眉が釣り上がる。
「―――これが笑わずにいられるか! ワシとドモンの師弟関係を調べたことだけは褒めてやるが、貴様らはあまりにも無知!!」
「何だと?」
「よいか!! 貴様らごときの腕で、ワシらと戦おうというのなら、最低でも百人は必要……それを、これだけの人数でどうこうしようなどと思うとは、片腹痛いわ!!」
「――――!」
ダレクは思わず息がつまった。この老人は、自分たちの圧倒的武力を、いきなり言下に否定したのだ。何か言わねばと思ったが、頭に血が上り過ぎて、咄嗟に言葉が出でこない。
「ドモンよ…お前の兄の事は心配するな。ワシがきっちり守ってやる」
「師匠が?」
ドモンは、少し意外そうに聞き返した。戦闘がはじまった場合、兄を守るのは自分の役目だと何となく思っていたからだ。
ドモンは、師匠の後ろに控えている兄に視線を走らせる。兄は穏やかな顔をしてドモンに頷き返した。
(ああ、兄さんは大丈夫だ)
ドモンは兄に微笑み返して、再び前を向いた。
「そして、キョウジよ……お主はそこを動くな。死にたく無ければな」
「分かりました」
キョウジは東方不敗をまっすぐ見つめて即答した。その眼差しには、恐れも迷いもない。
(よい眼差しだ)
東方不敗はキョウジから視線を前方に戻し、にやりと笑う。これで、こちらの戦闘準備は整った。
「ドモンよ!! 奴らにお主の力、存分に見せつけてやれい! ……ただし、家は壊すなよ。こんなあばら家でも、ワシは結構気に入っておる」
「―――了解!!」
ドモンもまた不敵に笑い、改めてファイティングポーズをとる。
(こ、ここここいつら……! この状況で、自分の命の心配よりも、家の心配だと!?)
ダレクの顔色が、怒りの余り真っ白になっている。この状況下なら、一方的に弱者を踏みにじる立場になるのはこちらでなければならないはずだ。それなのに先ほどから、こちらがさも弱者のように扱われているのは何故だ。
ああ、そうか、分かったぞ。
向こうは、こちらがキョウジ・カッシュを撃てないと思っているのだ。
だから、これだけの重火器を前にしても、そのような不遜な態度を貫いていられるのだ―――!
「キョウジ君。こちらとしては、君の死体を持ち帰っても、全然構わないのだよ」
「……………」
(私の生死は問われていなかったのか……シュバルツが身代わりになってくれていなかったら、本当に危なかったな…)
キョウジは表情を変えず、ただ心の中でシュバルツに感謝した。
「つまらん御託はいいから、さっさとかかって来んか」
東方不敗が、心底そんなことはどうでもいいと言わんばかりに催促をしてくる。ダレクの中で、ついに堪忍袋の緒が切れた。
ハチの巣だ!! こいつら、二目と見られないような姿にしてやる―――!!
「撃て!!」
「え? しかし、キョウジ・カッシュを投降させるのが先では?」
「構わん!! どうせ生死は問われていないのだ!! 撃て!! 撃ち尽くせ!!」
ダレクの怒号のような合図とともに、銃を構えた兵たちが一斉に発砲した。辺りに凄まじい轟音と煙と、火薬のにおいが充満する。
「ハハハハ! どうだ!! こちらを馬鹿にするから、貴様らはそういう目に合うんだ!!」
ターゲットに向かって飛んでいく鉛玉の群れを見ながら、ダレクは悦に入っていた。きっと今頃奴らの身体には、無数の穴が開き、無残な肉片と化しているに違いない。
「撃ち方やめ!」
そろそろ頃合いかと、兵の発砲をやめさせる。後は、死体を確認して、キョウジ・カッシュだけを回収すればいいだけだ。おお神よ、感謝します。何と楽な仕事でしょう。
ターゲット周辺に籠っていた煙が、晴れていく。
死体を確認するために、一隊が静かに近づく。そこで彼らは、信じ難い物を見た。何と、肉片と化していなければならないはずの人間が、その場に立っていたのだ。
「!?」
驚愕する兵たちの前で、ドモンは握りこぶしを作っていた両の手を、静かに解く。バラバラ……と、音を立てて地面に落されていくのは、今まさに自分たちが撃った鉛の玉だった。その後ろで、東方不敗が腰に巻いていた白い布を手に持ち、ブンと、何かを払い落すように振る。やはり、無数の鉛玉が、彼の足元に転がっていた。
「ひっ!?」
常識では考えられないことを目撃してしまった兵たちの、動きが一瞬止まる。
「行けっ!! ドモンよ!!」
東方不敗の合図とともに、ドモンは鎖から解き放たれた獣のごとく飛び出した。
「ハイイィ――――ッ!!!」
ドン!! と、勢いよく踏み込んだドモンが、手のひらを兵たちの腹にヒットさせる。とたんに、ボン!! と凄まじい音を立てて、兵士二人がはるか彼方に吹っ飛ばされた。
「うわぁ!?」
ドモンの近くにいた兵が、銃を発砲しようと咄嗟に構えようとする。ドモンは振り向きざまにその銃を手刀で真っ二つに叩き折り、下から容赦なく顎に掌底を喰らわした。顎を砕かれた兵が、もんどりを打って倒れる。ドモンに殴りかかろうとしたもう一人の兵が、蹴りを喰らって吹っ飛ばされた。
「何だと!?」
ダレクは我が目を疑った。銃も着ている軍服も、クライアントである親会社からもらった最新鋭の装備のはずだ。機密性にも、防弾性にも優れているはずだ。それが人の手であっさり破られるなど、あっさり破壊されるなど―――あってはならないことなのだ!
(馬鹿な! 馬鹿な! 馬鹿な!!)
心の中で呪文のように同じ言葉を繰り返し、目の前の現実を振り払おうとする。しかし、何度見ても、兵士たちは次々とドモンに討ち取られていくだけだった。
「キョウジ―――キョウジ・カッシュを狙え!! 奴さえ捕ることができれば、こいつらは戦えなくなる!!」
「はっ!!」
動揺しながらもダレクは、兵たちに的確な指示を出す。
「―――キョウジ・カッシュは優れた忍者という情報もある。油断するな!」
先ほどダレクに進言をした副官とみられる男が叫ぶ。
(それ、ここに限って言うなら誤情報なんだけど……)
キョウジは東方不敗の後ろに控えながら、苦笑するしかなかった。
「そんなことさせるか!!」
兄を狙おうとした兵士たちの一団に、ドモンが突っ込んでいく。
「キョウジよ…。そう言えば、お主はドモンの戦いを、その目で見るのは初めてであったな」
東方不敗が、キョウジの方にちらりと視線を走らせながら語りかけた。そう、先の「デビルガンダム事件」の際、キョウジは、割と早い段階でデビルガンダムに取り込まれてしまったため、ドモンの戦いをその目で見ることはできなかった。実際に彼の側について、ドモンを見守ったのはシュバルツである。
「しっかりと見ておくが良いぞ…。あ奴こそ、ワシが認めた、キング・オブ・ハートよ」
「…………!」
兵たちの装備は、頭の先から足の先まで防弾性を帯びた重装備で固められている。普通に殴ったのでは効果が無い事を、ドモンは十分に承知していた。故に、彼は先ほどから、発勁という手法を用いて兵たちと相対している。力強く踏み込むことによって、人体の臍付近にある丹田で「気」を練り込み、極限まで高めた物を掌より発射するのだ。「気」は防具を通り抜け、人体の内部に確実にダメージを与える。
低い姿勢を保ち、力強く踏み込み、掌を使い、兵士たちを吹き飛ばしていく。そうして行われているドモンの戦いは、まるで武闘の舞を見ているようですらあった。
東方不敗は、そんなドモンの様子をどこか誇らしげに見つめている。
(強い―――! ドモン、本当に強くなったんだな……)
キョウジもまた、ドモンの戦いを、ある種の感慨を持って眺めていた。
小さいころは怖がりで、いつも自分にまとわりついていた、ドモン。
少し成長してからは、コンプレックス故に、いつも下を向いて暗い顔をしていたドモンが。
今や、師匠である東方不敗が誇りにすら思う、キング・オブ・ハート…。
(……て、言うか、強すぎだろ。今、兄弟ゲンカとかしたら、私、瞬殺されるな……)
素手で銃弾を受け止めたり、フル装備のプロの兵たちを赤子の手をひねるがごとく軽々とふっ飛ばしたり……人類の規格外の強さになっていると噂には聞いていたが、実際それを目の当たりにすると、我が弟ながら凄すぎる。目茶苦茶な強さだ。冷静に考えれば考えるほど、もう笑うしかない。
―――ドモンは、私より強いぞ。
シュバルツがそう言っていたことを、キョウジはふいに思い出す。その時は、にわかには信じられなかったが、今なら素直に信じることができそうだ。
キョウジが、ドモンの戦いを見ている間にも、敵はキョウジを集中して狙っているが故に、ドモンの攻撃をかいくぐった兵士たちが詰め寄ってくる。だが、それもことごとく東方不敗によって撃退されていた。
「ランチャーを使え!!」
鋭い号令と共に、森の影から無数のランチャーミサイルが発射される。その弾道は、確実にキョウジを狙っていた。
「ドモンよ!! 分かっておろうな!?」
東方不敗がドモンに向かって声をかける。
「家は守ります!!」
声と共に、ドモンが高々と跳躍する。
東方不敗も顔を上げた。家には当たらないが、キョウジを捉える弾道で飛んできているミサイルが、いくつかある。
「ぬおりゃあああ!!」
東方不敗もまた飛び上がり、腰に巻いた白い布を手に持ち、ぐるぐると回し始めた。すると、あろうことかミサイルがその布に絡まり、あっという間に絡め捕られていく。
「返すぞ!!」
東方不敗が布を一振りさせると、ミサイルは元来た方角へと飛んで行った。森の向こうで、派手な爆発が起こる。
その頃上空では、家に当たる弾道で飛んできているミサイルを、次々とドモンが弾き飛ばしていた。手足、そして、自身の赤い鉢巻を器用に使い、ミサイルにわずかに触れることによって、その弾道を変えている。
だが、何発目かのミサイルを弾く角度を間違えてしまった。ドモンの手をするりとすり抜けたそれは、確実にキョウジに当たるコースへと変更されてしまう。
「―――しまった!! 兄さん!!」
ドモンの悲痛な声と同時に、キョウジの眼には、己を狙って飛来してくるミサイルが飛び込んで来ていた。
「――――!!」
さすがに一瞬息をのむ。だが、すぐにキョウジは思いだした。東方不敗に、死にたくなければ、動くな―――と、言われたことを。ならば、自分は動くべきでは、ない。
東方不敗の助けはすぐに入った。ミサイルとキョウジの間に入り、ミサイルを受け止め、はじき返す。
「未熟者ォ!!」
東方不敗がドモンに向かってそう叫ぶと、ドモンは「すみません!!」と、返しながら、再び戦闘へと戻っていった。東方不敗がミサイルに気を取られたわずかな隙に、キョウジが再び兵に襲われようとしている。
「甘いわ!!」
東方不敗が腰に巻きつけていた布を一閃させると、それは槍のように変化し、キョウジを襲おうとしていた兵士を刺し貫いた。
「キョウジよ! 大丈夫か!?」
キョウジを背に庇うように立って構えた東方不敗が、キョウジに声をかける。
「―――ありがとうございます」
「―――!?」
その声が、あまりにも穏やかな色を帯びていたので、東方不敗は激しく違和感を覚えた。
(そう言えば、こ奴、悲鳴を上げたか?)
30丁もの銃からけたたましく鉛玉が発射され、この戦闘は始まった。並みの者ならば、この時点で怖じ気づき、悲鳴を上げる。その後、武器を持った兵に肉薄され、ミサイルが眼前に迫った。だが、東方不敗は、キョウジの悲鳴を聞いた記憶が無い。
(まさか―――!?)
改めてキョウジの方へ振り返り、その立っている姿を見る。その姿は、最初に自分がキョウジの方に振り返った時から、少しも変わっていないように見える。そう、足の位置すらも―――。
(確かに、ワシは「動くな」と、言ったが……まさかこ奴、本当に動いとらんのか!?)
また、キョウジに兵が襲いかかってくる。東方不敗は先ほどよりワンテンポ遅れて助けに入った。もちろんわざとだ。そして、キョウジがどうするかを見た。
やはりキョウジは、悲鳴をあげない。それどころか、ピクリとも動かない。
(こ、こ奴……!)
別の攻撃が、キョウジを襲う。東方不敗は、さらに先ほどより引き付けてから助けに入る。が、やはりキョウジは、一切動かない。戦いの素人ゆえに、敵に反応できないから「動けない」のか、それとも、本当に覚悟を決めて、「動かない」のか―――。
(面白い!)
東方不敗の眼差しが、俄然凶暴な色を帯びる。
(その覚悟と度胸、どこまで本物か―――この東方不敗が確かめてくれるわ!!)
兵士の一人が、サバイバルナイフを振り回しながら突進してくる。
ちょうどよいとばかりに、東方不敗はその兵士をわざと引き付けた。
東方不敗の、キョウジを助けるタイミングが、どんどん遅くなっていく。それはつまり、敵の攻撃が、それだけキョウジに迫ってくることを意味した。その距離、1メートル。50センチ。20センチ。10センチ…。
バシィッ!!
キョウジのほんの目と鼻の先で、サバイバルナイフが白い布に絡め捕られる。
「…………」
キョウジは、動かなかった。己の身体を庇うそぶりすら見せず、静かにそこに佇んでいる。
(こ奴! 正気か!?)
まさか、眼を開けたまま、気を失っているのではあるまいな―――そう疑いながら、キョウジの顔を覗き込む。すると、キョウジと視線が合った。
(何ですか?)
何か御用でしょうか、と、キョウジから目で問いかけられる。その表情は穏やかで、思わず、ここが戦場であることを忘れそうにすらなる。
「…………」
特に用があるわけではないので、東方不敗は首を振る。するとキョウジはにっこりほほ笑んで、またもとの姿勢に戻った。
(こ、こ奴―――! 本物か? 本物なのか!? キョウジ!!)
東方不敗の白い布を握っている手が、何故か震える。見事な度胸、見事な覚悟だ―――これが、もし本物であるならば。
(いや、まだだ! まだ分からん!!)
東方不敗は頭を振ると、この上に、自身の攻撃すらも、キョウジに肉薄させて行った。東方不敗の拳が、キョウジの肩先を、鼻先を掠めて敵に向かっていく。
「ぬうおおおお!!」
終いには、キョウジの身体を挟んで敵と東方不敗の攻撃の応酬が繰り広げられるような形になった。
「……………」
(攻撃の応酬が、やけに近いな……)
自分の身体のすぐそばを行きかう拳圧を感じながら、キョウジは漠然とそんなことを考えていた。まさか、東方不敗から度胸試しを挑まれているとは、夢にも思っていない。
キョウジが恐れたこと―――それは、自分が、東方不敗やドモンの戦いの邪魔をしてしまうことであった。東方不敗は武術の達人。今、このように敵と異常接近しながら戦っているのも、きっと何かわけがあるに違いない―――キョウジはそう感じている。
自分がこの姿勢でいることも、おそらく東方不敗の戦いの計算の中に入っている。ならば、それこそ怖じ気づいて不用意に動いてしまっては、東方不敗が作り上げているこの戦いの微妙なバランスを、崩してしまう。それでは、東方不敗とドモンに、多大な迷惑をかけてしまうことになる。それだけは、何としても避けたかった。
だから、私は「動かない」
それが、今唯一、私に出来ること―――。
もちろん、キョウジの中に、死への恐怖が無いわけではない。
流れ弾が当たるかもしれない。近づいている敵の攻撃が当たるかもしれない。まかり間違って、東方不敗の拳が当たるかもしれない。
それでも、この勢いだ。当たった瞬間「痛い」と、思う間もなく、あっという間に死ねるだろう。
(それにしても、マスターの拳に当たって死ぬなんて、普通なら、絶対味わえない死に方だよな……)
そういう死に方も悪くないか―――と、キョウジは思い、苦笑する。
(こ奴―――! この状況で、何故笑う!?)
キョウジの身体を挟むような形で行われている戦いは、激しさを増すばかり。最早、まるでキョウジの身体をいくつもの拳が通り抜けているように見える状況だ。それなのに、キョウジ本人は穏やかな顔をして、時折笑みさえ浮かべている。
おかしい。
東方不敗は強く思った。度胸試しを挑んでいるのはこちらのはず。だが、これではまるで、逆にこちらの技量が試されているようだ。お前は、いったいこの状況で、どこまで私を守って戦えるのか―――と、キョウジから静かに問い返されているようだ。知らず、東方不敗の額から、汗が滴り落ちている。
「師匠!!」
少し離れた所から、ドモンの声がする。
「こちらに構うな!! お主は、さっさと敵を殲滅せんか!!」
「―――!」
ドモンは、兄の身体を挟んで敵と師匠が相対している異様な状況に、少なからず驚いた。加勢に行こうかと一瞬迷う。だが、間に挟まれている当の兄は涼しい顔をしているし、師匠は「邪魔をするな」と言わんばかりの気迫で押し返してくる。
(だ、大丈夫―――だよ、な…?)
とにかく、早く敵を撃退した方がいい。そう感じたドモンは、再び戦いの場へと踵を返す。ただ、一言伝えておかねばならないことを思い出して、再び振り返った。
「師匠! 気をつけてください! 敵の中に、妙な手応えの奴がいます!!」
「そんなことは分かっておる!! さっさと行かんか!!」
「はい!!」
ドモンが再び戦闘を開始するのを感じながら、東方不敗は心の中で唸っていた。
(妙な手応えの奴だと!? 今目の前に居るこの男より、妙な手応えのある奴などおるものか―――!!)
東方不敗は分からなくなる。自分はいったい「何」を守り、「何」と戦っているのかが。
凄まじい拳の乱流の中にいながら、穏やかな顔をして立っている彼の姿は、神々しくさえある。「覚悟を決めて、動かない」と選択しているにしても、普通、ここまでの状況でそれを貫き通す馬鹿はいない。とても正気の沙汰とは思えない。
それとも―――ワシを信じ切っているとでも…!?
(馬鹿な!!)
しがらみを捨ててください、と、茶を通じて言われた。自分も「信じろ」と、確かに言った。
しかし―――いきなり普通、ここまで信じるだろうか?
自分は一度、自身の願いのためにキョウジを利用している。いわば、キョウジから見たら、れっきとした加害者になっているのだ。
それがどうだ。今のキョウジの表情は、穏やかさで満ちている。こちらを信じ切っていなければ、こんな表情はできないだろう。まるで、赤子が親を絶対的に信頼しているが如くの表情―――。
分かっておるのか!? キョウジ!!
こちらが手元を少し狂わせただけで、お前は死ぬのだぞ!?
怖くないのか!? 死への恐怖は無いのか!?
ワシに殺されるとは、考えんのか!?
ワシのような悪党を、簡単に信じおってからに……!
キョウジ…! 貴様は……貴様は……!!
「…………」
東方不敗は、それまでラッシュのように繰り出していた攻撃をピタリと止めると、無言でいきなり踵を返した。キョウジに背を向け、すたすたと距離をあけていく。
この東方不敗の異様な行動に、周りの兵たちは一瞬戸惑う。その間にも東方不敗は歩みを止めず、その距離は広がるばかりだ。
(まさか、見捨てたのか!?)
兵たちでさえ、そう疑った。それでも、キョウジは、やはり動こうとしない。
「…………」
その場に、奇妙な静寂が生じた。キョウジ・カッシュは優れた忍者―――という情報があるにもかかわらず、石のように動かないその姿も無気味であったし、今までぴったりと張り付いていた東方不敗が、いきなり離れていった真意も読み取れない。
(罠かもしれない)
誰もが、一瞬そう疑う。しかし、目の前に獲物が全く無防備な状態で佇んでいるのも、事実だ。
これは、チャンスだ―――手柄を、上げる―――!
兵士の一人が、ついにキョウジに向かって飛びかかっていった。
「捕った―――っ!!」
守る者もいないというのに、攻撃されそうになっても本当に動こうとしないキョウジの姿が、東方不敗の目に飛び込んでくる。
(こうなっても……貴様は、まだ動かんと言うのか!? キョウジ!!)
白い布を握る手に、ぐぐっと力が入る。布に、己が拳の震えが伝わる。
(キョウジ……! ワシは……ワシは―――!!)
確かに「守る」と言った。「信じろ」とも言った。しかし……! こ奴―――!!
「キョウジ!! この……大馬鹿者ォォ―――!!!」
裂帛の叫びと共に、振り向きざまに放たれた東方不敗の殺気を乗せた白い布が、槍状に変化してキョウジに向かって飛んでいく。
ドスッ!!
「ぐあっ……!」
白い槍は、キョウジの首筋を掠めて、襲いかかろうとした兵士の方を、過たず刺し貫いていた。
「た、退却!! 退却だ―――!!」
ダレクの間抜けな声が響き渡る。その声と同時に、生き残った兵たちが、我先にとジープに乗りこんでいくのが見える。この戦闘が終了したことを、東方不敗は悟った。
キョウジは、未だ同じ姿勢を保ち続けている。
(こ奴―――ついに、最後まで、動かなんだか……)
ポタ、と、東方不敗の顔から、汗が滴り落ちた。恐ろしく消耗しているのを、自分でも感じた。
(本物――か……)
ここまで動かなければ、さすがにもう認めざるを得ない。恐ろしい程の度胸、凄まじいまでの覚悟だ。
(見事だ―――)
白い布をブン、と振って露払いをし、腰に巻きつけてふっと息を一つ、吐く。まだ、かすかに手が震えていた。
「あっ! こら逃げるな!! 待てっ!!」
ドモンが後を追おうとするのを、東方不敗が止めた。
「ドモンよ! 追わずとも良い。窮鼠猫をかむという言葉もある―――ここまで痛めつけておけば、すぐに襲っては来ぬだろう」
「それもそうですね」
ドモンが穏やかな顔になって振り向く。「兄さん、大丈夫か?」と、無邪気に走り寄ってくるドモンに、キョウジは「ああ」と笑顔で答えた。ドモンの笑顔を見て、東方不敗も少し落ち着きを取り戻す。目の前のこの男が、自分の愛弟子が大切に想っている兄だった事を、東方不敗はようやく思い出した。
「キョウジよ、聞きたいことがある」
ドモンがキョウジの横に並んだのを確認してから、東方不敗は口を開いた。そう、ドモンには、横におってもらわねば困る。そうでないとまた、自分の中に潜む訳の分からない鬼のような感情が、キョウジに向かって不用意に牙をむいてしまいかねない。それを、東方不敗はひどく恐れた。
「はい、何でしょう?」
キョウジの方は、先ほどと変わらない穏やかな目線で、東方不敗を見つめ返してきた。
「先の戦いで、お主……なぜ動かなんだ?」
東方不敗のこの問いに、キョウジは一瞬きょとん、としたかと思うと、ふっと相好を崩した笑顔になった。
「『死にたくなければ、動くな』と、言ったのは、マスターの方じゃないですか。私は死にたくないから、それに従っただけですよ」
さらりと、ある程度こちらが予想していた答えが、本当に帰ってくる。
「…………!」
(いや―――それはそうかもしれないが、先ほどのあの状況で……!)
自分の身体のすぐそばを拳の乱流が行き交い、全く無防備な状態で攻撃にさらされそうになった。それでも動かないのは、「死にたくなければ、動くな」と、言われたからと言って、「はい、そうですか」と、簡単にできるレベルの話ではない。動かないにも程がありすぎる。
東方不敗は腰に手を当て、ふうっと一つ息を吐いた。どうやら、聞き方を間違ったらしい。
「そうではなくて……キョウジよ」
「はい?」
「あの戦いの中、お主は疑いもせなんだのか? 例えば―――ワシに、殺されるかもしれない、とか…」
そう言って、東方不敗はキョウジをジロリ、と睨む。
「師匠?」
東方不敗の物騒なその発言に、ドモンの方の顔色が変わる。
「例え話だ。黙って聞かんか」
いきり立ちそうになっているドモンを制しながら、東方不敗はキョウジに再び問いかけた。
「―――正直なところ、どうなのだ? キョウジよ…」
度胸試しの一環で、何度も死ぬような恐怖を味あわせたはずだった。「殺される」と、感じても、それは仕方ないことだろうと、東方不敗は思う。それでも、何故、動かずにいられたのか―――それも、あんな穏やかな顔をして。本当のキョウジの気持ちを、東方不敗は聞きたいと、思った。
「……………」
キョウジが、しばし沈黙する。東方不敗の問いに、どう答えを返すべきか、考えているようにも見えた。
(正直に、話した方がいいか…)
たぶん、今ここで、偽りの答えを返す方が、この人には失礼な事になるだろうと感じる。意を決して、キョウジは顔を上げた。
「申し訳ありません。誤って拳が当たるかも、とは思いました。しかし、マスターが私を殺す気が無い―――という確証が、私の方にはありましたので、『殺される』とは、正直思いませんでした」
「何っ!?」
東方不敗が、心底意外そうな顔をする。『殺さない』と、キョウジに確証を与えた覚えなど、自分には一切無かったからだ。
「これは面白い事を云う―――キョウジよ、何を以って貴様は、ワシからその確証を得たというのか!」
案の定と言うべきか、東方不敗の瞳に険しい色が宿る。キョウジは、困ったように微笑んだ。
「マスター……お忘れですか?」
「?」
「先に、私を信じてくださったのは、マスターの方ですよ?」
「信じた―――だと?」
(それは、いつだ? いつのことだ…?)
キョウジの意外すぎる問いかけに、東方不敗は懸命にこれまでの事を反芻してみる。しかし、いつ、自分がキョウジにそこまで「信」を与えたのかが、さっぱり分からない。
「あなたは……私が点てた茶を、飲んだ―――」
「茶を……?」
「それで、充分です」
「――――!」
キョウジのこの言葉に、東方不敗は思わず息をのむ。キョウジは、にっこりほほ笑んだ。
(あなたが、私やドモンに害意を持っているのなら、私が淹れた茶など、気持ち悪くて飲めないでしょう)
キョウジの目が、微笑みながらそう言っている。
確かにそうだ。茶は、身体に入れるもの。まして、ああいうこまごまとした作法を必要とする、薄茶を、キョウジはわざわざ点てた。茶に細工をしようと思えば、キョウジには、いくらでもチャンスがあったのだ。
それを、東方不敗は疑いもせず、それこそ一気に飲み干した。ドモンに毒見などもさせず、本当に無造作に―――。「二心なし」と、キョウジに最初に宣言してしまったのは、図らずも、東方不敗の方であったのだ。
(何という男だ―――!)
あの茶で、こちらの真意が、まさか試されていたとは……。東方不敗は自身の背中に、戦いの中でも感じた事の無いような汗が、流れるのを感じた。
「あなたは、私を信じてくださいました。ですから―――」
キョウジは静かに言葉をつづけた。
「私もあなたに、同じものをお返ししなければ―――と……ただ、それだけです」
「―――――!」
東方不敗は、思わずその場にへたり込みそうになるのを、かろうじてこらえた。
(同じ―――!? 同じではないであろう!? キョウジよ!! ワシが茶を飲む程度の信頼と、激戦の中、何度も死にそうな目に遭いながら、それでも寄せる命がけの信頼とは、同じものではないであろう!?)
そう大声で、叫びたくなる。
でかい。
目茶苦茶だ。
この男、返してくる物が、でかすぎる―――!
茫然としている東方不敗に、キョウジは笑顔で問いかけてきた。
「ところで、マスター?」
「な、何じゃ?」
キョウジの声に、はっと我に帰る。
「私は……そろそろ動いてもいいですか?」
ズルッ。
ドモンと東方不敗が、同時にこけた。
「も、もう敵はおらん! 勝手にどこへでも動けばよかろう!」
体勢を立て直しながら、東方不敗が叫ぶ。それを聞いたキョウジが「ありがとうございます」と礼を言い、己に課していた直立不動の姿勢を、やっと解いた。
「に、兄さん、何律儀に師匠の許可を取っているんだよ?」
ドモンが呆れながらキョウジに問いかけてくる。
「だから、何度も言っているだろう? 私は怖がりなんだ! お前みたいに、敵の気配が分かったりするような感覚が無いから、慎重になってるの!」
「え? そうなの?」
「そうさ」
兄弟間の和やかな会話が続く中、東方不敗はキョウジに、全身全霊で裏拳にスピンを利かせた突っ込みを入れたくなるのを、かろうじてこらえていた。
(怖がりだと―――!? 嘘をつくな嘘を!! お前が怖がりだというのなら、世の中の人間は、皆息をするだけで恐怖を感じねばならなくなるわ!!)
恐ろしい程の度胸を、持っておるではないか!
凄まじいまでの覚悟と信念を、その身に宿しておるではないか!!
それを―――!
「…………」
東方不敗は、しばらく腕を組んで考え込むような仕種をしていたが、やがて口を開いた。
「―――ドモンよ」
「はい、何でしょう? 師匠」
兄のそばで何か話していたドモンが、東方不敗の方に駆け寄ってくる。
「お前の兄は……今、何を職としておったかのう?」
「え? 兄の職業ですか?」
師匠からの意外な質問に、ドモンが少しびっくりしたような声を上げる。しかし、すぐに「え~と…」と、師の疑問に答えるべく、律儀に考えだした。
「確か、大学の非常勤講師みたいなのをやってたかな? …後、父さんの知り合いの研究室に所属して、父さんの研究を引き継いだりとか、何か、そんなことをしてたように思いますけど……」
「そうか……」
(―――そんなところでは、あの男にとっては退屈極まりないであろうな……)
東方不敗は思った。決して、非常勤講師という職を軽んじているわけではない。ただ、キョウジの持つあの度胸、信念、知略―――どれをとっても、超一流の物だ。それが、今彼がいる場所では、存分に発揮できないのではないか、と、感じたからだ。彼ほどの才があるのならば、もっと高いところを飛んでいてもいいはずだ。
確信する。キョウジ・カッシュという男は、器がでかい。それも、途方もない大きさだ。
その大きさ故に、キョウジ本人は、もらった物と同じ物を返したつもりでも、相手にとっては、必要以上の大きさを伴って返されたように感じてしまうのだろう。
きっと、この男は、望めば天下すらその手に握れる。そういう器をもっている。―――もっとも本人には、まるでその気が無いようだが。
初めて子供の頃のドモンを見たとき、これほどの気迫を持つ者が、どうしてこんなコンプレックスの塊になっているのかと、驚いたものだが……。今日、やっとその原因が分かった。幼いころから、ずっとこの兄の器のでかさと向き合っていたら、それは、コンプレックスの塊になっても仕方が無いというものだ。
「ドモンよ…お主……」
「? 何ですか? 師匠」
「いや……何でも無い」
今のドモンからは、そんな暗い影が感じられない。愛弟子は、立派に成長しているのだ。自分は、それを素直に喜ぶべきではないのかと、思う。
(とにかく、汗をかきすぎてのどが渇いたな……水を―――)
そう思いながら、東方不敗が家に入ろうとした時。
「…………!」
彼は、あることに気づいてしまった。
「ドモンよ!!」
「? はい! 師匠!」
何だか今日はよく呼ばれるな―――と、思いながら、ドモンは再び師匠のところに走ってくる。
「ワシは、お主に言ったな―――? 『家を守れ』と」
「はい、確かに―――。俺は、ちゃんと守ったと思いますけど?」
屋根もドアも壁も、どこも壊れていないはず。ドモンは、胸を張って答えた。
「では、これは何だ!!」
東方不敗が怒気を食んで指をさす。ドモンが東方不敗の指先に目を移すと、窓の障子があった。
「障子が、どうかしましたか?」
「よく見んか!! 小さな穴が空いておろうが!!」
「え……え~~~?」
ドモンが師匠の指に指されている部分をよく見ると、確かに小さな穴があいている。しかし…。
「師匠……この障子、もともと穴だらけですよ?」
ドモンが指摘した通り、障子はすでにあちこち穴が空いてボロボロといってもいい状態であった。
「馬鹿者!! このあたりの破れには、侘びとサビと風流が絡んどるからわざと放っておいたのじゃ!! それをこの穴一つで台無しにしてくれおってからに! この、馬鹿弟子が!!」
(り、理不尽……!)
ドモンは、師匠のあまりの言い草に、久しぶりに眩暈を感じていた。ドモンがくらくらしているところに、東方不敗の容赦ない蹴りが襲ってくる。
「全く! 家に飛んでくる小石一つ防ぐことができんとは!! この馬鹿弟子が馬鹿弟子が馬鹿弟子が!!」
「~~~~~ッ!!」
東方不敗にドカドカと全身を蹴られながら、ドモンは頭に血が上っていくのを感じた。
(こ、この……! ミサイルとか銃弾とかは防いだだろうが!! そんな穴一つ、生活に支障が出るとか言うのでもあるまいし、何で俺がこんなに怒られなくちゃならないんだ!!)
「でぇい!!」
ドモンが裂帛の気合と共に、蹴っていた東方不敗を弾き飛ばす。
「師匠! 師匠ほどの男が、そんな穴っころ一つ、何と器の小さきことか!!」
「何っ!? ドモン、貴様!! このワシに逆らおうというのか!?」
「男には、引けぬときがある!! その理不尽…許すわけにはいかん!!」
そう言って、ドモンがファイティングポーズをとる。それを見て、東方不敗が不敵に笑った。
「面白い…! ならば、勝負の二文字をもって答えてくれるわ!!」
おそらく、史上最もみみっちい理由による、壮大な師弟対決の火蓋が、今まさに切って落とされるかに見えた。だが―――残念ながらそれは、実現しなかった。
「ド、ドモン!!」
キョウジから、悲鳴にも似た、異常を知らせる叫びが発せられたからである。
「―――兄さん!?」
こうなっては、対決どころではない。ドモンも東方不敗も、慌ててキョウジのところに駆け付けた。
キョウジは、ドモンと東方不敗から少し離れたところで、倒された兵士の死体のすぐそばに座りこんでいた。幸いなことに、キョウジが敵に襲われたというわけではなさそうだった。ただ、その顔色が、真っ青になっていた。
「兄さん! どうした!? 大丈夫か!?」
ドモンが、座り込んでいるキョウジのすぐ横に座って、声をかける。
「わ……私は、大丈夫なんだけど……」
そう言いながらキョウジは、倒れている兵士の、ヘルメット部分に手をあてる。
「死者を辱めるみたいで、あまり気は進まなかったんだけど……勾玉を狙って来ている敵の手がかりみたいなものが無いかと思って、ちょっと探らせてもらったんだ。そうしたら―――」
ガバッと、キョウジがヘルメットをはぎ取る。そこに現れた物を見て、ドモンと東方不敗が、同時に息を飲んだ。
「――――!」
兵士の額に、三つ目の眼があったからだ。
「あやかしの者か……」
「…………」
東方不敗の言葉に、キョウジは応えず沈黙を返した。
「そういえば…!」
ドモンが何か思い当ったのか、別の死体の方に走り出す。戦闘中に感じた妙な手ごたえがあった辺りを思い出しながら、死体をくまなく調べてみる。しばらくして彼は、「兄さん! こっちにも!!」と、叫び声をあげた。
その兵士は体中が体毛に覆われ、口に鋭い牙が生えていた。
「こちらにもおるぞ」
東方不敗も、異常な死体を見つけてくる。ざっと検分しただけで、半数近くの死体が、何らかの異常を身体に備えていた。
「兄さん、これは―――」
さすがのドモンも、顔色が真っ青になっている。
「おそらく、合成獣(キメラ)だな。それも、人為的に作り出されている―――」
キョウジが、一つの遺体を調べながら、妙に冷静な声で答えた。
「人為的って―――人間に、そんなものが作れるのか!? 兄さん!!」
「―――作れるな」
「――――!」
(即答かよ!?)
ドモンは思わず息を飲んで、言葉を失う。そんなドモンに追い打ちをかけるように、キョウジはさらに続けてきた。
「聞こえなかったのか? ……『作れる』と、言ったんだ」
そう言いながら、キョウジはドモンにちらりと視線を走らせる。その目が、そして声の響きが、妙に冷たい。
「作れる技術があって、材料があって、需要があれば、作るだろ。―――それが、人間なのだから…」
「に、兄さん……!」
ドモンの声が震えているのが、キョウジにも分かった。しかし、キョウジはそれには構わず、遺体の検分を続けた。
―――そう、それが人間だ……。
キョウジは思う。作れるのなら、作ってしまう。それが、人間であり、科学者であり、技術者だ。それが、人間社会の発達を助け、技術の進歩を生み続けた。いい方にも―――悪い方にも。
合成獣を作りだした者たちを、正義の味方ぶって一方的に責める気持ちなど、キョウジにはさらさらなかった。人間の、生き物の身体を使って何かを作り出すことが罪だというのなら―――自分だって、同罪だ。自分もすでに、『似たような物』を作り出してしまっている―――!
ガシッ!
「――――!」
不意に力強く腕を掴まれて、キョウジははっと我に帰る。
「兄さん……」
ドモンが、必死にこちらを見つめている。もうすでに、泣き出しそうな表情だった。
「ドモン……」
不意にキョウジは、ドモンに大人げなく八つ当たりをしていた自分に気づく。
(何をやっているんだ、私は…! いくら、自分の『罪』を、目の前で自覚させられたからって…!)
キョウジは、泣きそうになっているドモンの頭を、いつものようにポンポンと撫でようとした。しかし、ただただ自分のことだけを心配してくれている、このきれいな心を持った弟を、罪に汚れた自分の手で触れていいのか、と、思う。
キョウジは、上げかけていた手をおろした。その代わり、言葉を発した。
「すまなかった…。ありがとう。心配、してくれて……」
兄の言葉に、ドモンはふるふると頭を振る。頭を振った拍子に、涙があふれた。兄に涙を見られたくなくて、ドモンは慌てて下を向く。
(―――そんな、辛そうなのに、兄さんは…どうして泣かないんだよ…!)
ドモンは、そう言いたかった。でも、言ったところでこの優しい兄は、「お前が私の代わりに、泣いてくれるからだよ」と、言ってしまうに決まっている。
兄が、どうしようもなく自分を責めている姿が見える。見えるから、止めさせたいと願うのに、兄の陥っている闇が深すぎて、自分の手は、いつも届かない。ドモンは、それが歯痒かった。
「……………」
東方不敗は、そんな兄弟の様子を黙って見つめながら、別の事を考えていた。
(キョウジは、手掛かりを探すために死体を調べた。戦う気は充分ということ―――)
だが、相手は忍者部隊に最新鋭の装備をそろえた軍隊を率いられる力がある。しかも、その中に合成獣といった人外の物まで投入して来ている。
(―――面白い!)
東方不敗は、久しぶりに己の身体が武者震いに襲われるのを感じた。相手の力は強大だ。それに対して、こちらは戦力と呼べる力も、些細なもの。いくら強いと言っても、いずれ力つき踏みつぶされ、普通ならそれで終わる。
しかし。
問題は、大将―――。
向こうの頭はどうか知らないが、こちらの大将に当たるのはキョウジだ。
恐ろしい程の胆力。凄まじいまでの信念。そして、何気ない茶に、二重の意味を持たせる知略―――。器は充分。だから、見届けてみたい。
これからキョウジは、己のトラウマとも言うべき物と、向き合わねばならない。この男が、これとどう戦っていくのかを、最後まで見届けてみたい。そして、見極めてみたい。自分の感じたこの男の器の大きさが、果たして本物かどうか―――!
(なんとも抗いがたい誘惑。何と極上の戦いであろうか…!)
笑いが、震えが止まらない。武人として、自分はこんな戦いを、ずっと待っていた気がする。
だが…。
ふっと、東方不敗の顔が曇る。
(龍の勾玉に関しては、本当にいいイメージがせんのう…。ワシの気のせいであればよいのだが…)
うろ覚えの記憶でも、暗いイメージしか湧いてこない龍の勾玉。これが、どうしても戦いに暗い影を落とす。最悪の場合、総大将が早々に、自ら命を落とす選択をしてしまいかねない危険があった。
(龍の勾玉―――どちらにしろ、きちんと調べる必要があるな……)
東方不敗は決意した。この戦いの行く末を、見届ける事を。
「キョウジよ!」
東方不敗が力強く声を発する。
「はい」
顔を上げたキョウジに、東方不敗はにやりと笑いかけた。
「ワシのとっておきの隠れ家に、案内してやろうか?」
「え?」
師匠のその言葉に、ドモンも顔を上げる。その顔は、もう涙に濡れてはいなかった。
「―――分かりました! 師匠!! 『例の場所』ですね!!」
「うむ。急ぐぞドモン! 追手がかからぬうちに、移動を開始するのだ!」
「はい!!」
ドモンは力強く師匠に応えると、「行こう、兄さん!」と、キョウジの手を強引に引っ張った。
「うわっ、ちょ…! ドモン!! 待て…!」
どこに移動するにしても、少しいろいろ準備したいキョウジが、慌てて弟に制止を求める声を出す。しかし、悲しいかな腕力勝負では、圧倒的にキョウジが不利である。そのままずるずると引きずられていってしまう。
(せ、せめて酔い止めを飲まさせてくれ~~!!)
また、あのドモンが運転する車に乗らねばならないのかと思うと、さすがのキョウジも気が滅入る。せめて、自分が運転できれば、多少は気も紛れるのだが。こういうときだけは、狙われている身の上を少し恨めしく思う。
「行くぞ! 風雲再起!!」
東方不敗がそう叫ぶと、どこからともなく白馬が現れて、東方不敗を自らの背に乗せる。東方不敗が拍車をかけると、風雲再起は猛スピードで走りだした。
「さぁ! 兄さんも早く乗って!!」
そう言いながら、やはりドモンは車の助手席ではなく、トランクの方を開けてくる。
(はははは……。もう、どうにでもしてくれ…)
何かもう、いろいろあきらめて、キョウジは車に乗り込んだ。せめて、リバースすることが無いように、祈るしかない。こういうときは、もうさっさと寝てしまうに限る。
「師匠~! 待ってくださ~い!!」
キョウジの気持ちを知ってか知らずか、ドモンはやはり、車を急発進させていた。
「取り逃がしただと!? それだけの装備を備えておきながら、全く何たる無能だ!!」
某国のオフィス街の一角で、しわがれた老人の声が響く。
「―――銃が通用しなかっただとォ!? そんな人間がいるものか!!」
(いやそれが……ミサイルも通用しなかったんですけど……)
ダレクはそう言いたいのをぐっとこらえて、ただひたすら畏まっていた。銃でこれなのに、ミサイルなど、もっと信じてもらえるはずが無い。
「と、とにかく、我が部隊は壊滅的な被害を被っております。何とか、援軍と補給を頂けませんか…?」
「フン――――」
老人が、忌々しそうに鼻を鳴らした。
「で、いくら用意したらいいのか?」
「最低でも百人―――」
「………!」
(たった一人の男を捕えるために、何故、こんな仰々しくなる!?)
老人は、開いた口が塞がらなくなるのを感じた。忍者部隊といい、自分の私設軍といい、彼らは、果たしてこんなにふがいない者たちだっただろうか?
「―――よいではありませんか」
老人の傍らに、影のように控えていた塊から、ぼそりと声がする。よく見ると、黒いフードを全身にかぶっている人間、のようであった。顔の部分が白い仮面で覆われており、眼の部分だけが、黒く不吉に穿たれている。
「代替え品など、いくらでも用意できるのです…。我らが大望成就のため、ここで投資を惜しんではなりません―――」
地を這うような暗い声で、影は老人にそう助言する。
「…………」
その意見に、しばらく考え込むような仕種をした老人であったが、「よし分かった」と、決断を下した。
「ダレクよ、お前の言うとおり送ってやる。しばしそこで待て―――今度こそ、しくじるな!」
「はっ」
通信終了と同時に、モニターが切れた。老人はため息をつきながら、しばらく暗くなったモニターを眺めていた。
「全く……残月もダレクも、両方がキョウジ・カッシュを発見し、取り逃がしたと報告してくるとは…! 一体、何が起こっておるのだ?」
疑問を口に出してみるが、明確な答えが出てくるわけでもない。忌々しい―――ダン! と、机を叩く。
「それよりも―――シュトワイゼマン様」
「何だ?」
「『あれ』の復活を、急がせましょう…」
影からの提案に、シュトワイゼマン、と呼ばれた老人の眉が、ピクリと動く。
「『あれ』と、龍の勾玉は、引き合うようにできております…。封が破られた今、『あれ』の力が強まれば強まるほど、勾玉はおのずと引き込まれて来ましょう―――」
「もっと死体を与えればよい。ほれ、某国で内戦が起きておるだろう」
影から言われたことなど、分かり切っていると言わんばかりに、老人はめんどくさそうに手を振って答えた。
「もう行っております」
なら、いちいち言わせるな―――と、言わんばかりに老人は鼻を鳴らした。
「―――それよりも、『あれ』の力は、確かなものなんだろうな?」
シュトワイゼマンからの鋭い問いかけに、影はこくりと頷いた。
「はい―――『あれ』が完全復活したら、地脈の流れ、天気、総てが貴方様の思いのままになります。どこに石油をもたらすか、どこに地震を起こすか…。未曾有のハリケーンを作り出すことも可能です―――」
「フフフ……」
シュトワイゼマンの面に、邪悪、としか形容のしようのない笑みが浮かぶ。
「わしは、慈悲深い者であるから、すべての人類を抹殺―――などと考えたりはせんぞ? わしに搾取される者として、人類を生かしておいてやるのだ」
そう。人類を滅ぼしなどしたらつまらない。自分が強大な富と権力を得るために必要だ。金。エネルギー。武器。自然―――すべてを思い通りに操れる力を得る事が出来たら、無能な人類は、この力に跪くしかなくなる。この地球上のすべての人類が、自分の奴隷と化すのだ。想像しただけで、笑いが止まらない。
もっとも、60億もの奴隷はいらない。多少は削除することが必要だ。その作業にも、『あれ』の力が役に立ってくれるだろう。
「……………」
仮面をかぶった影は、そんなシュトワイゼマンの様子を、ただ、黙って見つめていた―――。
人里から遠く離れた山深い場所に、シュバルツとハヤブサの目的地である、「隼の里」があった。
一見、普通に道を歩いているように感じるが、時々ハヤブサが、合図らしきものをいろいろな方向に向かって送っているのが分かる。ハヤブサの合図に応えるように、人影が見え隠れしていた。恐らく、ハヤブサと一緒に歩いていなかったならば、侵入者として扱われ、襲われるか、術をかけられるかして、里へはたどり着けないような仕組みになっているのだろう。
ハヤブサに誘われるまま里に入ると、そこは、意外にも普通の農村の姿をしていた。外を子供たちが走り回り、その横で女たちが世間話をしたり、畑を耕したりしている。ただ、現代日本と少し違うのは、その服装が全員和装である事ぐらいだろうか。まるで、映画のセットの中か、タイムスリップをしたかのような錯覚を覚える。どこか懐かしさすら感じるような気がした。
「―――いいところだな」
シュバルツが、ポツリと呟く。
「…………」
しかし、ハヤブサからは、やはり反応が無かった。ずっと沈黙を決め込まれている。里にたどり着くまでに、何度も何度も会話を試みてみるのだが、こんな調子で、総て徒労に終わっている。シュバルツは、苦笑するしかなかった。
とある家の縁側に近づくと、ハヤブサがやっと口を開いた。
「長老に話してくる。ここで待て」
そして、シュバルツが何か言おうとする前に、さっさと姿を消してしまう。どうも業務連絡の類だと、口をきいてくれるらしい。シュバルツは、ため息とともにその家の縁側に腰を下ろした。
どこまでも青い空の中を、トンビが旋回している姿が見える。トンビ以外にも、ムクドリや雲雀、鶯、ハト―――といった様々な鳥の鳴き声がシュバルツの耳朶を打つ。ふと見ると、子供たちの間を縫うように、セキレイが餌を探して地面を走りまわっていた。
(鳥の種類の多さが、自然の豊かさを測る指標になると言うが……ここの自然は、豊かなんだな……)
人里から遠く離れたところにこの里はあるのだから、ある意味、当たり前といえば当たり前なのだが―――シュバルツはそう感じて、何故か安心していた。地球の自然の豊かさと力強さを感じられる瞬間が、彼はとても好きだった。
ポン、と、音を立てて、シュバルツの足に毬が当たる。そっと拾うと、子供が二人近づいてきた。
「おっちゃん、お客様か?」
子供たちが、屈託なく聞いてくる。
(おっちゃん……! 28歳って、やっぱりこの子らからすると『おっちゃん』になるのかな……)
多少顔をひきつらせながらも、「ああ、そうだよ」と、笑顔を見せて答える。すると、子供たちの方がこの笑顔に安心したのか、「じゃあ、外のお話を聞かせて!」と、身を乗り出してきた。
「え……え~~~? 外の話って言っても……う~~ん……」
シュバルツは困ってしまった。自分もある意味闇の世界に身を置く同業者だ。子供たちの期待する「外の話」というのがどういう類のものか分からないから、うまく応えられる自信が無い。
しばらく腕組みをして考え込んでいたシュバルツであったが、自分の懐にある物を持っていた事を思い出し、「そうだ、いい物を見せてあげようか?」と、取り出した。それは、刀の刃などを拭く懐紙だった。彼はそれを手早く器用に折っていくと、懐紙は紙飛行機へと姿を変える。
「ほら」
シュバルツがスッと投げると、その紙飛行機はよく飛んだ。
「うわぁ~!! すご~い!!」
「おっちゃん!! 僕にも折って!!」
「私にも! 私にも!!」
子供たちが大興奮状態で押し寄せてくる。
「待てって…順番に折ってやるから―――ああ、でも紙が足りないか?」
寄って来た子供たちの数をざっと見ながら懐をまさぐっていると、「栄太のうちに紙があったよ! 取ってくる!」と、子供の一人が駆け出して行った。たちまちのうちに、辺り一帯は折り紙教室の様相を呈してくる。
(懐かしいな……。そういえば、ドモンにも、よくこうやって折ったり教えたりしてたっけ……)
紙飛行機を無邪気に追いかける子供たちの姿を見ながら、シュバルツはそんな事を思い出す。
キョウジは、8歳年下の弟のドモンの子守をしながら、いらなくなった書類とかプリントとかを使って、よく紙飛行機を作った。ドモンが小さい頃は、紙飛行機が遠くへ飛べば飛ぶほど、単純に喜んでくれた。だから、キョウジの方も、ドモンが喜ぶ顔がもっと見たくて、つい、紙飛行機に改良に改良を重ねてしまう。そして、ドモンが自分で紙飛行機を折りたがる歳になる頃には、キョウジの作る紙飛行機は、子供が初めて折って作るには、少し難しすぎるものになっていた。
それでも、負けず嫌いのドモンは、一生けん命同じ物を作ろうとする。しかし、何度挑戦しても、キョウジのようになかなかうまくいかない。
「もういい!!」
終いにはヒステリーを起こして、ぐしゃぐしゃになった紙を投げ捨てて、いじけながらどこかに行ってしまう。後に残った大量の紙の残骸を片づけるのは、いつもキョウジの役目だった。
(またドモンを怒らせちゃった……。難しいな…子守って……)
グシャ、と髪をかきながら、ため息をつく。ぐしゃぐしゃに丸められたり、引きちぎられたりしている紙は、まるでドモンの心その物の姿をキョウジに見せつけているようだ。
(弟を傷つけてばかり―――やっぱり俺は、駄目な兄貴なのかな……)
紙を片づけながらそう思い、少し哀しくなった。懐かしい記憶だ。
「おっちゃん! コマ回してよ!」
一人の少年が、シュバルツに木製のコマを差し出してくる。
「よし―――見てろよ」
シュバルツは紐を手早くコマに掛けると、素早く手首を動かしてコマを放った。放たれたコマは、縁側の上の一点にとどまり、バランス良く回転する。
「よっ……と」
彼はそのコマを、今度はそれを回すのに使った紐の上に、器用に掬う。コマは細い紐の上で、見事に回り続けた。
「わぁ……!」
子供たちがうれしそうに、眼を輝かせる。シュバルツは、しばらくコマを紐の上で、右に動かしたり左に動かしたりしていたが、やがて、コマを回してと頼んできた少年に「手を出して」と、言った。少年が言われたとおりに手のひらをシュバルツに向けると、シュバルツは、コマをその手の上にポン、と乗せた。
自分の手の上で、コマが回っている―――めったに味わえない出来事とその感触に、少年がきゃらきゃらと声を立てて笑い出した。
子供たちの明るい笑い声の響きにつられるように、今度は女たちが寄ってくる。
「あれ、あんた見かけない顔だね。お客さんかい?」
農作業からの帰りと思われる女性が、シュバルツに声をかけてきた。
「お邪魔してます」
シュバルツが、軽くだが丁寧に挨拶を返す。それに女性も軽く応えてから、「ジロウ、あんまりお客さんに迷惑をかけるんじゃないよ」と、子供の中に我が子の姿を見つけて声をかける。子供が「は~い」と、明らかに生返事と分かる物を返してきて、母親はやれやれとため息をついた。
「何もないところだけど、ゆっくりしていってね」
女性はそう言い置いて、その場から去っていく。今度は、別の年配の女性が声をかけてきた。
「あれ、おまえさん。その服、ボロボロじゃないのかね? それに、怪我もなさっているようだ―――」
「あ………」
その老女の指摘した通り、シュバルツの服装は黒蜘蛛党とハヤブサとの激闘の後で、すっかりボロボロになっていた。棒手裏剣を腕に受けた時に、血止めのために巻いた白い布も、そのまま巻きっぱなしになっている。
「怪我の方は、もう治っています。どうかお気づかいなく―――」
シュバルツは、慌てて白い布を取った。白い布に血の跡は残っているが、言葉通り、怪我はすっかり治っている。棒手裏剣を受けた傷跡は、もうどこにも見当たらなかった。痛みが無くなっていたものだから、すっかり忘れていた。
「でも、服の方はボロボロじゃろう。こっちによこしなさい。繕ってあげるから」
「え? いや、でも―――」
遠慮して辞退しようとしたシュバルツに、老女は強引に手に持っている服を押しつけてくる。
「ほれ、これに着替えて」
「あ……りがとうございます」
半ば押し切られるような形で、シュバルツは服を受け取った。
「おっちゃん! 服着替えるんならこっちだよ!」
子供たちが、頼みもしないのに家の中を案内してくれる。シュバルツは苦笑しながら礼を言った。
(そういえば、和装とかって、初めてだ……)
手にした服を広げながら、シュバルツはふと思った。
(どうしてだろう……『忍者』やっているのに…。やっぱり、ドイツの『ニンジャ』だからかな―――)
可笑しくなって、少し、笑った。
服を着替えて老女に服を手渡す時、やっぱりシュバルツは、少し遠慮した。
「申し訳ありません。なんだかお手を煩わせてしまうみたいで―――」
そう言うシュバルツに、老女がニッと微笑み返す。
「あんたは、里の子供たちと遊んでくれている―――それで、充分さ」
「…………!」
老女はそれだけ言うと、服を繕う作業に取り掛かった。シュバルツは、ただ黙って深々と頭を下げた。
(―――やっぱり、いいところだ。ここは…)
元気な子供たち。優しい景色。優しい人たち―――。こんな中にいられる自分は今、少なくとも幸せだと感じている。
「おっちゃ~ん! 遊んで~!!」
「遊んで~!!」
シュバルツが服を着替え終わったと見るや、待ち構えていたように子供たちが飛びかかってくる。一人二人の子供たちならともかく、5、6人に一斉に飛びかかられたので、さすがのシュバルツも、危うくバランスを崩しそうになった。
「待て待て! 順番に遊んでやるから…」
遠慮のなくなった子供たちのパワーというのは、本当に力強い。少々翻弄されている自分を感じながら、子供たちと懐かしい遊びの数々に没頭していった。
「……………」
ハヤブサは、少し前からそこに戻ってきていた。キョウジを、長老のところに案内するためだ。
しかし、彼はそこから動けなかった。
あまりにも、目の前の景色が平和すぎたからだ。
キョウジを取り囲んで、子供たちが楽しそうに遊んでいる。その子供たちの輪を、その子の母親たちと思われる女たちが、優しい眼差しで見つめている。「いい男だねぇ」と、のんきにキョウジを評する声が聞こえてきたりする。家の奥では老女が繕い物に精を出し、道行く男たちが「元気だなぁ」とか、「お、やっているな」と、言いながら通り過ぎていく。
あまりにも―――何て、平和な日常。
分かっている。
これは、あくまでも仮初めの平和。
これからキョウジが直面しなければならない事実を考えると、とても、こんなふうに笑ってなどいられない。分かっている。こちらが現実だ。
だが―――動けない。
こんな平和な景色の中では、自分の方が、存在の誤った黒い汚点のように感じる。ここにいてはいけない。いるべきではない―――と、強く思う。
(キョウジが気付くまでは、ここに居よう)
キョウジから隠れるように、でも、ほんの少しだけは見えるように、場所を変えてそこに立つ。
(あと少しだけ―――ほんの、あと少しだけ……)
腕組みをして壁にもたれかかり、眼を閉じて、祈る。
この平和な景色が、後、ほんのひと時でいい。続きますように。
どうか、自分の存在に、キョウジが気付きませんように…。
長老が、現実が待っている。分かっている。
(知ったことか!)
心の中で毒づく。誰も救えない無力な現実に、何の意味があるというのか。
このまま、時が止まってしまえばいい―――。
何て、陳腐な願い。だが、ハヤブサは、半ば本気で、そう祈っていた。
「あれ? リュウさん、帰って来てたのか。何やってんだ? そんな所で…」
偶然通りかかった鍬を持った男に、声をかけられる。こうして平和な時間は、あっさり終わりを告げてしまった。
「――――ッ!」
ハヤブサは思わず頭を抱える。
「ハヤブサ?」
子供たちに囲まれていたキョウジが、顔を上げてこちらを見る。あああ、見ろ! キョウジが気付いてしまったではないか…!
立ちあがって、その場を離れようとするシュバルツに、子供たちが尚も群がってくる。
「おっちゃん、行っちゃうの?」
「もっと遊んで! 遊んでよ~!」
「いや、ほら、おっちゃんはあっちでハヤブサが待っているから―――もう、行かないと」
シュバルツが苦笑しながら子供たちを諭す。
「…………」
向こうで佇んでいるハヤブサを見、それからシュバルツを見た子供たちが、名残惜しそうにしながらも、掴んでいたシュバルツの服の端を離す。ああ、この子たちは、もう「何」を優先しなければならないのかを分かっているのか―――そう感じると、少し切なくなる。
「また、遊んでね!」
子供たちが手を振り、口々にそう叫ぶ。それに「ああ、また―――」と、キョウジが手を振って答えていた。
(―――「次」など、ありはしないのに……)
ハヤブサは、暗澹たる気持ちになりながら、その様子を眺めていた。
「ハヤブサ? もしかして、待たせたか?」
子供たちと少し離れてから、キョウジは足早にこちらに向かって走ってきた。
「いや……」
(―――もう少し、待ちたかったぐらいだ)
そう口走りそうになるのを、ぐっとこらえて、キョウジから、早々に視線を逸らす。そのまま踵を返して、キョウジを長老の元へ案内しようとした。
「ハヤブサ……」
キョウジが、呼びかけてくる声がする。だが、ハヤブサは今までと同じように、何も答えるつもりはなかった。声が聞こえていないふりをして、そのまま足を進めようとする。
しかし。
「―――あまり、良くない話なのだろう?」
「――――!?」
いきなり核心を突かれて、ハヤブサは思わず振り返ってしまう。「ああ、やっと反応したな」と、久しぶりに目があったキョウジの顔が、微笑んだ。
「お前がずっとそんな調子では、いくら私が馬鹿でも分かるぞ―――これから聞く話は、あまり良いものではないのだな?」
そう言いながら、穏やかに見つめてくるキョウジの顔。
(ああ、どこかで―――見た事がある)
ハヤブサは思った。キョウジのこの表情は、あの空き家で見た、白刃をその身に受け入れる覚悟をしている時の顔だ。ああ、なんて、固い笑顔。こんな表情、もう一度見たいと願いはしなかったのに。
「そこまで分かっているのなら―――キョウジ」
ハヤブサは、キョウジに刀をずいっと差し出した。
「お前の差し料だ……持って行け」
「――――!」
差し出された刀を見て、シュバルツは少なからず動揺した。
(どういうことだ? 私はこれから、里の長老のところへ向かうはず……。なのに、『武器を持て』とは…! 普通は、逆だろう!?)
「いや……私が、武器を持つわけには―――」
やはり、遠慮をしようとするキョウジを、ハヤブサは許そうとしなった。
「お前は虜囚ではない! 佩刀は当然の権利だ!! 持て!!」
「…………!」
ハヤブサの語気に押される形で、シュバルツは一旦手を上げた。
(何故だ、ハヤブサ――! これから先、私は武器を振るわねばならなくなるのか? しかも、長老の元で!?)
刀に向かう手が、小刻みに震える。話を聞きに行くだけなのに、『武器』を手に取ることに、どうしても抵抗を感じた。
(勾玉の話を聞いた後、命を奪われる必要があるというのなら―――私はそのまま、斬られるのに!)
ただ、卑怯にも、そのあと甦ってしまう。甦った私は、キョウジに勾玉の情報を、伝えに行ってしまうだろう。それだけは―――どうか、許してほしい。
だから、斬られる。
「勾玉の秘密を守った」と、いう心の安寧が、里の人々にとって必要だというのならば。
優しい時間をくれた里の人たちに、私はもう―――刃は、向けられない。
「―――すまない、ハヤブサ…。やはり、私は、それは持てない」
「キョウジ!!」
震えながらも刀を取ろうとしていた手を、引っ込めてしまったキョウジの姿に、ハヤブサは語気をさらに強める。だが、キョウジは頑なだった。
「私が、刀を持つことで―――警戒され、『勾玉』の正確な情報が得られなくなる……そうなる方が……私は、困る」
「――――!」
「だから、『持ちたくない』んだ……すまないな、ハヤブサ」
そう言って、キョウジは微笑む。断固たる拒絶の意思を、漂わせながら。
こうなってしまっては、もうどんなに頼み込んでもキョウジは刀を持とうとはしないだろう。ハヤブサは、ため息とともに差し出していた刀を下ろした。
「分かった。……では、これは―――俺が、『預かる』」
「ハヤブサ……!」
―――ハヤブサは、やはり私に刀を持たせたがっている……!
そう感じて、シュバルツの動揺はさらに深まる。
(どうしてだ、ハヤブサ……!)
何故だ―――と、今聞いても、ハヤブサは、答えてはくれないだろう。
「長老の家はこっちだ……行くぞ」
そう言うと、ハヤブサは刀を二本持ったまま、すたすたと歩き出した。
(キョウジ……お前は、報復の刃を振るう権利があるのだぞ…!)
歩きながらハヤブサは思った。
これからキョウジは、知ることになる。勾玉の正体と、勾玉を体内に入れてしまった者は選べる道が、二つしかない事を。それは、化け物に取り込まれるか、それを阻止するために、その者の命を犠牲にするか。取り込まれるか、死か―――という残酷な事実。
(お前も、お前が守りたいと願っている人間も、勾玉とはまるで関係が無い。それなのに、この理不尽―――お前はそれが、許せるのか? キョウジ!!)
自分なら、許せない。納得もできない。
しかも、勾玉は、こちらの封が破られて、外に持ち出されてしまった。いわば、完全にこちらの手落ちだ。だから、報復する権利が、キョウジにはある。キョウジが怒り、戦いを望めば―――ハヤブサは、すぐにでもこの刀を、キョウジに渡すつもりだった。
(だから―――戦う事を、望め。キョウジ! お前は、怒っていいんだ…!)
そして、お前は許さなくていい。
勾玉を封印するための刺客として、既に選ばれている、俺を。
責めてくれていい。憎んでくれていい。
その方が、俺も、気が楽だ―――。
「ここだ」
里の中でもかなり奥まった所にある大きな家の前で、ハヤブサは足をとめた。
ハヤブサの後に続いてシュバルツもその家に入り、暗く長い廊下を歩く。その家のおそらく最奥と思われる部屋で、長老は待っていた。
「リュウ・ハヤブサ、キョウジ・カッシュを連れて参りました」
「入れ」
しわがれた老人の声が、入室の許可を告げる。ハヤブサは、作法に則って襖を開け、中に入る。シュバルツもそれに続いた。
「…………!」
ハヤブサが、刀を二本携えてきている事に気付き、長老の眉が僅かに動く。
(ハヤブサ…! やはりお主は、納得してはおらんのか……)
二本目の刀が誰のために用意された物なのか―――長老には、すぐ分かった。
「…………!」
部屋に入った瞬間、シュバルツにも伝わる物があった。
(潜んでいる……)
天井裏。長老の後ろにある衝立の裏。左右の襖の向こう―――。
「…………」
ハヤブサが、こちらを見ている。刀を取れ―――と、眼が訴えている。
「…………」
(私は刀は取らない。分かっているだろう、ハヤブサ…)
面に穏やかな笑みを浮かべると、シュバルツは、ハヤブサの後ろに控えて座り、礼に則り頭を下げる。
長老は、そんな二人の様子を静かに見つめていたが、やがて、口を開いた。
「まずは二人とも、面を上げよ」
許しを得た二人が、顔を上げる。長老はまずハヤブサを見、そしてキョウジの方を見た。
ハヤブサの言う通り、腕が立つ忍びの者であるのならば、こちらが潜ませている者たちの事は気付いているはずだった。しかし、キョウジの眼差しからは、動揺した色も、殺気さえも感じられない。ただ、深く穏やかであった。
(なるほど……これでは、ハヤブサが戦いたがらぬのも無理はない……)
そして、長老は悟った。キョウジには、総てを話さねばならない事を―――。
「……キョウジ殿。そこにいるハヤブサから、大体の事情は聞いている。確かに、そなたには―――すべてを知る、権利がある」
これから話す事は、里の奥でずっと伏せられ、秘かに伝えられてきたことだ。だから、本来なら人払いをしなければならない。しかし、総てを話し終わった後、キョウジとハヤブサが、どう動くかが分からない。「長老」という立場の責任上、潜ませている護衛を、自分の傍から離すわけにはいかなかった。
それにもう、勾玉の封印は解かれ、おそらく邪悪な物も動き出してしまっているだろう。今更すべてを秘そうとしても、詮無き事だと長老は思った。
「総てを話そう―――。勾玉の正体、そして、それが何故、里の奥で封印され、秘中の秘とされてきたか、その訳を―――」
時は今から800年ほど遡る。
度重なる戦。襲い来る飢饉。世は、荒れに荒れていた。
ここに、一人の僧がいた。名を、慧信といった。
彼は、荒む世を憂い―――何とかしようと走り回った。幸いなことに、彼は異国へ留学していたので、その手には、知識があった。技術があった。そして彼は、自分の力が小さい事を、良く知っていた。
だから、彼は荒れる世の小さな一角に、集落を作った。そして、その知識と技術を惜しみなく村人たちに与え、戦を避け、飢えをしのいだ。荒れた世の中で、そこだけがいつも平和であったが故に、いつしかそこは、「奇跡の集落」と呼ばれるまでになっていた。
慧信には、妻がいた。この時代、僧が妻帯することは、珍しい事ではなかった。妻は、慧信の事を良く理解し、支えた。村人たちからも、彼女は慕われていた。
だが―――悲劇は起きた。
その年も、また天候不順で飢饉が襲う。慧信が作った集落も、例外ではなかった。村人たちは、僅かに収穫できた作物を持ち寄り、分け合って飢えをしのいでいた。しかし、それにも限界がある。
慧信は、食料を得るべく、集落より外に出た。妻に、留守を任せて。
だが、飢えに強いはずの集落でさえ飢えるこの状況では、外の世界がさらにひどい状況であった事は、想像に難くなかった。それでも慧信はあきらめず、それこそ血を吐くような思いをして、何とか少しの食料を集める事が出来た。それを持って、慧信は村に帰還する。
しかし、帰還した慧信を出迎えたのは、燃え盛る集落の景色だった。
集落は、外からの侵入は容易くできないような構造になっていたはずであった。それが、襲われたという事は、誰かが手引きをした以外には考えられない。襲い来る嫌な予感を振り払いつつ、慧信は炎の中を、必死になって妻を、生存者を捜しまわった。
やがて、彼は見つけてしまう。見るも無残に五体を引き裂かれて、血だまりの中にバラバラに転がっている、「妻」であった、女の遺骸を―――。
妻の遺体のそばで、何時も夫妻に良くしてくれていた老人が泣き崩れていた。
「すまない…! 慧信さん……! 儂は、皆を止められなかった…! 野盗のほかに、村人までもが一緒に加わって、略奪が……! この人は、老い先短い儂なんかを守って……!」
「――――ッ!!」
慧信は、衝撃を受けた。
妻は、村人たちに殺された……!?
それでは、私は今まで、何のために、何のために、何のために―――!!
「あ…あ……! ああぁぁあぁあ――――ッ!!」
それは、慧信を暗黒に突き落とすには充分すぎた。
慧信には、知識があった。喪ったモノを、甦らせる邪法。
慧信には、技術があった。邪法を、確実に行える技術。
彼は、七日七晩もの間それを行って―――ついに、妻を、甦らせた。
ただし、「化け物」として。
昼は、普通の女の顔をした妻が、夜になると、人を襲い、人の死体を喰らう。
慧信は、それで構わないと思っていた。妻は、人間に殺されたのだ。だから、これは正統な復讐だ。殺された者が殺す側に回って、何が悪い。
邪法によって甦った妻だが、まだ僅かに、人であった頃の優しい心が残っていた。
(死体なんか食べたくない。化け物なんかになりたくない。誰か助けて―――)
助けを求めて夫を見る。しかし、夫は、別人のように荒んだ暗い眼差しで自分を見つめてくる。「化け物」を見る目で―――。
(嫌だ。いや。誰か―――)
そうしている間にも、妻の死体を食べる量はどんどん増え、妻は日毎、化け物じみていく。
(誰か、誰か、だれか―――!!)
「かわいそうに……」
気がつくと、慧信と妻は、退治される標的として、いつの間にか追われる身になっていた。追う者たちの先頭に、巫女がいた。
巫女は、邪法破りの術を知っていた。
「あなたの力の源は、これ―――」
そう言って巫女は、妻であったモノの腹の辺りから、光る塊を取り出す。
「大丈夫よ。これであなたはどこへでも行ける。私も、一緒に行くから―――」
巫女はそう言うや否や、自ら熾した護摩の炎の中に、塊と一緒に飛び込んだ。あっという間に、巫女の身体が炎に包まれる。と、同時に、妻であったモノの身体も、金色の炎に包まれていた。
断末魔の悲鳴を上げながら、炎に包まれたそれは、慧信の身体に飛びつく。二人は、一緒に燃えだした。
「―――――」
妻であったモノが、最期に慧信に何事かを言った。果たしてそれは、懺悔の言葉であったのか、それとも、恨みの言葉であったのか。聞き取れた者は、誰もいなかった。
そして、総てが燃えて灰になった後、巫女が燃えた跡に、光る小さな塊が残った。それが、『龍の勾玉』―――と、呼ばれる物になった。
「慧信の事件が起こったのが800年前―――。すべてが灰になり、そこで総てが終わった―――と、誰もが思った」
人々は、巫女が燃え、勾玉が出現した場所に祠を立て、勾玉を封印し、大事に祀った。
しかし、10年、20年と時が経つうちに、事件は人々の記憶から薄れ、忘れ去られていく。50年、100年―――やがて、200年目になろうかというある日、一人の盗賊が、その祠を破壊した。転がり出た勾玉は、その盗賊の体内に吸収される。
勾玉を体内に収めた盗賊は、まるで導かれるようにある場所へと向かう。その先に待っていたのは、黒い装束に白い仮面をかぶった人物と、女の形をした黒い化け物―――。
盗賊は、あっという間に化け物に捕まり、取り込まれた。
盗賊は、己の境遇を呪い、世のすべてを憎んでいた。故に、化け物とよく馴染んだ。勾玉を得た化け物は、恐ろしい早さで自己進化を始める。
化け物による、大量虐殺が始まった。
殺された人々の数は、200年前の比ではなかった。化け物が出現した辺り一帯は血の海と化し、生き物は皆死に絶えた。
だが、人間たちも立ち上がる。己の種の存続をかけて。
人間対化け物の、激烈な戦いが始まった。
「戦いは、困難を極めた―――。しかし、最後には、200年前と同じように力の源を巫女に取りだされ―――」
巫女は、200年前と同じように死んだ。巨大化していた黒い女の化け物は、「禍払いの剣」によって斬り伏せられ、炎に巻かれながら滅された。そして、やはり燃えた跡地には、ただ勾玉だけが残された。
「その『禍払いの剣』が、「龍剣」であったと伝えられている。故に、その勾玉は、我が里で封印されることとなった……」
「…………」
ハヤブサは黙って長老の言葉を聞いていた。自分が、現在の龍剣の使い手である意味を、噛みしめながら。
それから10年、20年―――何事もなく時が過ぎていく。
50年、100年―――そして、200年目を迎えたある日、何故か封印が解かれ、そこに一人の侵入者を許してしまった。
「それは、当時の隼の里の長の、5歳にも満たぬ娘だった―――」
「…………!」
これから聞かねばならぬ話の惨さを予見して、シュバルツの顔色が変わる。
勾玉は、その娘の体内に吸収された。それを知った長は、愕然とした。
長は、ただ短絡的に娘を斬るような男ではなかった。
(何か、手はないか。何か、娘を救えるような手が―――!!)
長は、狂ったように駆けずり回り、寝食も忘れてありとあらゆる書物を読みふけった。
しかし、どこを見ても何を調べても―――事実は長に残酷な選択を突きつけてくる。
「娘を、巫女に見立てて護摩の炎の中に投げ入れろ」
「200年毎に、その黒い化け物が甦っているかもしれない―――と、気がついたのも、その長だ」
慧信の事件から、400年。化け物が出現したら、今回で3度目―――理屈は通る。
何かの間違いであってほしい、と、長は祈った。しかし、その長をあざ笑うかのように、黒い化け物は出現した。付近の村々を破壊しながら、隼の里を目指してくる。
「呼んでる。行かなきゃ」
黒い化け物に向かって、歩いて行こうとする娘。勾玉が化け物に取り込まれたら、200年前のように、また大量虐殺が起こり、里も―――何もかもが壊滅してしまう。
長は、決断を下した。
龍剣もまた、当時の使い手によって役割を果たし、化け物は炎に巻かれながら消えた。
そしてまた、勾玉だけがそこに残った―――。
(こんな物があるから……)
長は思った。これがこの世に存在する限り、また200年後に、誰かの身に悲劇が降りかかるかもしれない。長は、ただちに勾玉の破壊を部下に命じた。それを行ったが故の呪いは、自分が引き受けるつもりだった。
しかし、ありとあらゆる手段を尽くしても、勾玉を破壊することができない。
「勾玉を里の奥深くに封印し、その存在を伏せよ。そして、年数を数えよ。200年後、封印が破られそうになったら、ありとあらゆる手段を用いて封印しなおせ。もう、あのような悲劇を、誰の身にも味あわせてはならん―――」
そう言い置いて、長は翌朝腹を切った。
長の遺言は、ただちに実行された。封印された場所を知る人間は限られ、『龍の勾玉』に関する一切の事柄に緘口令が布かれた。
そして、封印された年数も、同時に刻まれていく。10年。20年。長の遺言は守られていった。50年。100年。勾玉の事件を直接知る人間がいなくなっても、里の者たちは頑なに、祈るように長の遺言を守り続けた。
「そして200年目が近づいた時……封印の力が弱まっている事を、わしは発見した―――」
封印をし直すために、巫女が秘かに用意された。巫女の霊力を持って、弱った封印の上から封印の重ねがけをするためだ。巫女は斎戒沐浴をし、その時に備えた。
「だが―――巫女が何者かによって殺され、勾玉は持ち出された…。後は、ご存じのとおりじゃ……」
そこまで言い終えると、長老はキョウジの方に視線を移した。
「……………」
キョウジは無言で、ただ、ある一点を見つめていた。何かを考えているふうにも見えた。
(キョウジ……)
ハヤブサもまた、キョウジを見ていた。
(分かっただろう。お前が「守りたい」と願っている人間の運命が…。 化け物に取り込まれるか、それを防ぐために死を選ぶか―――それしかないんだ!)
キョウジが不意に、口開く。
「つまり……勾玉を、取り出す方法は……」
それを質問と取った長老は、答えた。
「殺してもいい。生きたままでも構わぬ。勾玉を取りこんだ人間を、炎の中に投じるか―――化け物にそれが取り込まれた後に、霊力の高い巫女が、化け物の腹からその塊を取り出して、巫女の身ごと、一緒に焼くか………それ以外には、無い」
長老がそう言い切ってしまったことに、ハヤブサの胸が何故か痛む。無意識のうちに、キョウジに渡すつもりの刀の方に、手が伸びていた。
当然、その動きは、長老にも、長老を守ろうとする護衛たちにも、はっきりと見えている。部屋の空気が、一気に緊張の色を帯びた。
そんな中、ただ一人、シュバルツだけが静寂の中にいた。
(ああ…何だ……。つまり、そういうことか…。それで、ハヤブサは―――)
いろいろと合点がいった。何故ハヤブサが、急に自分から距離を取ろうとしていたのか―――。
答えは簡単だった。
私が「守りたい」と、願いを言ってしまったからだ。彼は、それが叶えられない事を知っていた。だから、彼は、一人苦しんで―――。
(余計な事を言ってしまったな……。『願い』なんて、軽々しく口に出すものじゃない―――)
だから、私は駄目なんだ。
肝心なところで、いつもいつも―――。
与えなくていい苦しみを、ハヤブサに与えてしまった。それだけが―――ただ、苦い。
キョウジの顔に、自嘲的な笑みが浮かぶ。
「キョウジ―――!」
ハヤブサは悟った。このタイミングで微笑むキョウジは、自分が一番恐れ、見たくない物であった事を。
「長老!! 本当に―――本当に、それ以外の方法は無いのですか!?」
キョウジが何か言う事を遮るように、ハヤブサは言葉を発した。
「無い。―――歴史がそう、証明している」
「まだ試していない方法もあるはずです! 総てを試してみたのでしょうか!?」
「ハヤブサよ……。200年前、我が子の体内に勾玉が吸収されたと知った長が、何も試さなかったと思うか……」
「それは―――! しかし……!!」
ハヤブサは、なおも食い下がった。今、自分が黙ってしまうわけにはいかない、と、強く感じていた。
「ならばせめて、勾玉を確実に消滅させる方法―――これも、無いのですか!?」
「有れば、800年も勾玉は受け継がれてはおらぬ」
長老が、容赦なく断言する。
「しかし―――このままでは、あまりにも―――!」
ハヤブサは思った。キョウジの守りたいと願っている人間が死して、なおも勾玉が残り続けるのであれば、それは結局のところ、『犬死』に等しい。勾玉が新たな血を吸っただけで何も変わらず、200年後に、また誰かの身に悲劇が降りかかるだけではないか。
「何か……何か手はあるはずです! あきらめてしまうのは、あまりにも―――!」
「―――ハヤブサ、もういい」
不意に、背後から穏やかな声が聞こえてくる。
「キョウジ!!」
ハヤブサは弾かれるように、声の主の方へ振り返った。
「もういい。もういいんだ、ハヤブサ。充分だ―――ありがとう」
そう言って微笑むキョウジの眼差しは、凪いだ海のように深く静かだった。
「…………!」
(キョウジ―――何故だ……!)
ハヤブサは、思わず言葉を失う。その間に、キョウジは長老の方にも向き直って姿勢を正した。
「長老も……貴重な話を聞かせてくださり、本当に―――ありがとうございました」
そう言って、丁寧に頭を下げる。
「…………!」
長老も、思わず絶句した。キョウジからは、殺気も怒りも、何も感じない。あるのは―――ただ、話を聞かせてもらったことへの感謝の念。本当に、それしかなかったからだ。
(何と―――この男……! 総てを、受け入れたとでもいうのか……!?)
まさか、と疑う。今、この男を襲っているのは、勾玉の呪いにも似た理不尽だ。それは、何の前触れもなく突然やって来て、「あなたが生きていると、たくさんの人が死ぬから、生贄になって死んでくれないか」と、言われているようなものだ。しかも、本人にではなく、彼が「守りたい」と願っている者に。それは、到底受け入れられるものではない。それが普通だ。それなのに―――。
(守りたい、と、願う者と共に、死ぬ気であろうか。この男は……)
そうでなければ、彼のこの態度は説明ができない、と、長老は思った。まるで、今から腹を切るような清々しさすら漂わせている。
その姿は、あまりにも愚かで―――。
あまりにも、惜しい。
「……せめて、ごゆるりと滞在されよ」
気がつけば、長老はキョウジにそう声をかけていた。かけずには、いられなかった。
「わしは、もう休む。お前たちも、下がれ―――」
そう言って、長老は座をはずした。潜んでいた護衛たちの気配も、消えていった。
(―――納得、できるか…!)
ハヤブサは、長老の後を追った。部屋には、シュバルツ一人が残された。
「……………」
奇妙な、安堵感があった。心は、不思議と凪いでいた。
(この勾玉を取りこんだのが、『キョウジ』で良かった……)
これが、今シュバルツが感じている、偽らざる心境だった。そう、こんな救いのない呪われたような勾玉を吸収したのが、キョウジで良かった。たとえば、この里の誰かではなく―――ドモンや、レインでもなく。
もし、ドモンやレインにこんな物が吸収されていたら、自分も、そしておそらくキョウジも、とてもじゃないが正気を保っている自信がなかった。それこそ、狂ったように駆けずり回り、取り出す手段を探さずにはいられなかっただろう。下手したら、本当に発狂してしまうかもしれない。
だからせめて―――取り込んだのが、キョウジで良かった。心から、そう思う。
(勾玉の正体を知れば、キョウジはどうするだろうか……)
これから自分は、キョウジに勾玉の正体を報告しに行かなければならない。それで、今回の自分の仕事は、一応終わる。後は、キョウジの判断に、総てをゆだねるしかない。
ただ、シュバルツには確信があった。この勾玉の正体を知れば、キョウジはおそらく自分の『死』を、確実に選択肢の一つに入れるだろうという事を。キョウジは、そういう人間だと思った。自分もある意味『キョウジ』だから―――それが、分かる。
キョウジが、どういう道を選ぼうと、自分はそれに従うだけだ。生きるのならば、共に生きるし、死ぬのならば、共に死ぬだけだ。ただ、それだけのこと。と、言うか、自分には、それしか出来ない―――。
「あの………」
部屋の外から遠慮がちに声を掛けられ、シュバルツは思考することをやめて振り返る。一人の若者が佇んでいた。
「これ……祖母から、服が直りましたので……」
「あ………!」
わざわざ届けてくれたのかと驚く。
「ありがとうございます。本当に―――」
若者から差し出された服を、シュバルツは押し戴く様に受け取った。本当に、きれいに直してくれていた。その心遣いが、ありがたかった。
「あと、宿に案内するように言い使っております。ぜひ―――」
そう言って若者は宿に案内しようとする。これでは本当に世話になりっぱなしになるので、一瞬辞退しようかとシュバルツは思った。しかし―――。
(今、私がこの里から黙って姿を消したら、ハヤブサが烈火のごとく怒るだろうな…)
そう感じて思いとどまる。ここまでいろいろと世話になってしまっているハヤブサに、今更義理を欠くような真似をするわけにはいかない、と思った。
(一晩だけ、世話になろう。ハヤブサも、そのうち来るだろう)
シュバルツはそう決意して、若者の後に従った。
ふっと、おそらくキョウジと共に行動しているであろう、ドモンの顔が、シュバルツの頭に何故かよぎる。
(キョウジが『死』を決意したなら―――また、泣かせてしまうな……)
そう思うと、少し、胸が痛んだ。
その頃ハヤブサは、まだ長老の前にいた。
「今からでもいい。勾玉を、俺の身体に移し替える事は―――!」
「移し替えるにしても、勾玉を人の身体の外に取りださねばならん。取り出すためにすることは一緒だ。―――結局、同じ事だ」
「…………ッ!」
先ほどから、ずっとこういった調子で押し問答が続いている。長老は、思わずため息をついた。
「ハヤブサ―――。お主、まだ、納得できんのか…」
「納得できません!!」
長老の言が終わらぬうちに、ハヤブサは大声を張り上げる。
納得できない―――何もかもが納得できない。
勾玉がもたらす、この呪いのような理不尽―――納得できるわけがない。出来る方がおかしい。
それなのに。
キョウジのあの態度――――それが一番納得できない!!
何故だキョウジ…!
何故……!
『守りたい』と、願っていたではないか!!
もう、その願いすら捨ててしまったのか!?
何故―――この理不尽を、あっさり受け入れるんだ!!
「キョウジ・カッシュ……」
ぼそりと長老が、その名を呟く。ハヤブサは、思わず顔を上げた。
「ハヤブサよ……本当にあの者は、『勾玉をその身に入れた者を守りたい』と、お主に言ったのか?」
長老の言葉に、ハヤブサは「はい」と頷く。
「…………」
長老は暫く瞠目して考え込むようにしていたが、やがて一言「惜しいな……」と、呟いた。
「あれは、腹を切る者の目だ……」
「!!」
ハヤブサが、弾かれるように、ダンッ!! と、音を立てて踵を返す。そのまま、走り去る足音が、彼が家を出ていくまで響き渡った。
(こんなに足音をたておって……忍び失格だ……)
気持ちは分からんでもないが―――そう思ってしまって、長老も、深いため息をつく。
(前途ある若者が……何と、惜しい事よ……)
何を言っても、何をやっても今更事実は変えられないが、やるせなくなる時もある。自分より年若い者の『死』は、特にそうだ。
隼の里に、夜の帳が下りてきている。
今宵は、特に寝苦しい夜になりそうだ―――と、長老は感じて、また一つ、ため息をついた。
宿に案内してもらったシュバルツは、繕ってもらった服をそっと置くと、部屋の奥の窓際に腰を下ろした。障子を開け、外の景色を眺める。上空には上限の月が淡い光を放っている。余計な明かりもないせいか、星々もよく見えた。
虫の音色と共に、優しい風がシュバルツの頬を撫でる。久しぶりに感じる、平和な夜だと思った。
不意に、静寂を引き裂く様に足音が響き渡る。
(何だ?)
シュバルツがそう訝しむ間にも、足音はまっすぐこの部屋へ近づいてきている。
ダァン!! と、壊れるのではないかと思うくらい勢いよく部屋の襖が開け放たれたかと思うと、そこから目にもとまらぬ速さで黒い影が飛び込んできた。
「!?」
その影に、シュバルツはいきなり右手を取られて床に引き倒される。そのまま、あっと思う間もなく着物の前をはだけさせられた。
「何をする!?」
空いている左手で相手を殴り飛ばそうとして―――自分を引き倒している黒い影が、ハヤブサである事にシュバルツは気がついた。
ハヤブサは、長老に「キョウジが、腹を切るかも」と、指摘された瞬間、頭が真っ白になった。
(しまった―――! キョウジを、一人にしては―――!!)
元いた部屋に戻った時、キョウジの姿はすでに消えていた。
「ここにいた客人はどこへ行った!?」
たまたま部屋の片づけに来ていた飯炊きの女を捕まえて問いただす。
「あ、あの方なら、先ほど宿の方に案内されていたようですが……」
女の言が終わらぬうちに、ハヤブサは家を飛び出した。そのまま宿に向かってなりふり構わず走り出す。
血溜まりの中、突っ伏しているキョウジの姿が、どうしても脳裏をよぎる。
(キョウジ―――! 早まるな!!)
宿の者に声をかける間すら惜しんで、ハヤブサは中に走り込む。襖を開け放つと、そこにキョウジの姿があった。
切腹を試みているのなら、右手に短刀が握りこまれ、腹に傷が走っているはずである。それを止めさせなければと、ハヤブサはまずキョウジの右手を抑える。それから、腹に傷が付いていないかを確認するべく着物の前を無理やり広げた。
腹には傷一つなく、右手にも短刀が握りこまれていない。
(よかった………)
ここでようやくハヤブサは人心地がついた。ほっと小さなため息が、ハヤブサの口から洩れる。
「ハヤブサ? 何やっているんだ? お前」
「――――!」
キョウジの声に、ハヤブサははっと我に帰る。見ると、ハヤブサに右手を取られて押し倒され、着物をはだけさせられているキョウジが、半ば不審者を見るような目つきでじ~っとこちらを見ている。それで、今のこの体勢が、いろんな意味で非常に危険な物であることに、ハヤブサはやっと気がついた。
「ち、違う!! これは……!」
慌ててキョウジから身体を離す。顔が勝手に赤面した。キョウジから、思いっきり離れてから、ようやく口を開く。
「ちょ、長老が、『お前が切腹する』なんて言うから―――!」
「ああ……それで―――」
キョウジが得心したように微笑みながら、身を起こした。
「大丈夫だ。私は切腹などしないよ」
着物を直しながら、そう告げる。
(した所で、死ねない。私は)
シュバルツは、心の中で、そう続けた。
「…………!」
私は切腹などしないよ―――『今は』
ハヤブサには、キョウジが何故かそう言ったように聞こえた。
(それはそうだ。キョウジには、勾玉の正体を、今本当にそれをその身に宿している者に伝えに行く義務がある。今すぐに、切腹などする訳がない―――)
そう思って、とにかく落ち着こうとする。しかし、顔にあてた手が、勝手に震えていた。
キョウジは、静かに微笑んでいる。ただその笑みが、却ってハヤブサの心をかき乱す。
何でそんなふうに―――何もかもあきらめたような微笑みを、浮かべるんだ! お前は―――!!
馬鹿野郎!! 何を考えている―――!! そう、大声で怒鳴りつけたくなる。だが、必死にこらえる。今ここでキョウジを一方的に責めたいわけではない。なじりたいわけではない。それをしたところで、状況は変わらない。分かっている。嫌というほど、分かっている。
(と、とにかく、冷静に……冷静に―――)
深呼吸をして、心を無理やり落ちつけてから、ハヤブサは口を開いた。
「キョウジ……分かっただろう? 勾玉の正体―――」
「ああ……そうだな」
キョウジは、ハヤブサとは視線を合わさず、身を起したときの姿勢のまま、静かに虚空の一点を見つめている。ハヤブサの言葉に相槌を打った後、彼はぼそりと何事かを小さく呟いた。それは、誰にも聞かせるつもりのない、彼の独り言だった。
―――いっそ、私の身に、勾玉が入ればよかったのに―――。
「…………!」
ハヤブサは、忍者であるが故に、耳がいい。常人ならば聞き逃したであろうその独り言を、彼の耳は捉えてしまっていた。だが、シュバルツはそれに気がつかなかった。
勾玉を吸収したのが私であれば、少なくともオリジナルのキョウジは死なずに済んだ。ドモンも悲しませずに済んだ。
炎に焼かれるのは、私だけで良かった。
それとも、DG細胞でできているこの身体は、炎に焼かれても消えずに再生するのだろうか―――。
(この期に及んで、まだそんな学術的好奇心が湧く―――つくづく馬鹿だな…私も…)
知らず、顔に微かな自嘲の色が浮かぶ。それを敏感に感じ取ってしまったがために、ハヤブサの―――堪忍袋の緒が、ついに切れた。
「―――いい加減にしろ!」
駄目だ―――! 冷静に―――! と、理性が悲鳴を上げるが、最早歯止めがきく状態ではなかった。
「お前、本当、いい加減にしろ! 何を考えている!? 先程から―――!」
「…………?」
キョウジが、びっくりしたようにこちらを見ている。だが、ハヤブサは、かまわず続けた。
「だって、そうだろう!? 何がおかしいって、お前のその態度が、一番おかしい!!」
「ハヤ…ブサ……?」
シュバルツは、ハヤブサが何故怒っているのかが分からず、戸惑ってしまう。
「お前は、いつもそうだ!! 最初に会った時から、いつもいつも―――!」
そう言いながら、ハヤブサがつかつかと距離を縮めてくる。
「何故だ!?」
シュバルツのすぐそばまできて立ち止まり、ハヤブサは叫んだ。
「何故―――いつも死ぬ方ばかりを選ぶ!? どうして、生きる方を選ばないんだ!!」
「――――!」
ハヤブサの鋭すぎる指摘に、シュバルツは思わず言葉を失った。
「何故そう死にたがる!? 生きたくはないのか!? キョウジ!!」
「は、ハヤブサ―――」
ハヤブサの言葉が、胸を鋭く抉る。確かにそうだ。自分は常に、死ぬ方、殺される方を選択していた気がする。
だが…それは―――!
キョウジが、激しく動揺しているのがはっきりと分かった。だが、それには構わず、キョウジの着物の襟首をつかんで無理やり立たせ、自分の方へ引き寄せる。キョウジが苦しそうにくぐもった声を漏らす。このまま望みどおり、本当に殺してやろうか―――と、一瞬凶悪な衝動に駆られる。
だが、違う。
違うんだ、キョウジ。
俺は―――!!
「いいか―――俺は、お前が『守りたい』と願っている者を殺す―――! そしてその身を焼き、勾玉を取り出す。それが、俺の使命だ。それは、何をしても、もう覆らない―――!」
「ハ、ヤブサ……」
「俺が、憎いか? キョウジ…!」
ハヤブサが、殺気だった目で睨みつけてくる。まるで、初めて会った時のように。
「憎いはずだ!! 普通なら、許せないと、思うはずだ!!」
「……………」
だが、見つめ返してくるキョウジの瞳には、殺気の色が灯らない。凪いだ海のような深さの中に、ただ哀しみだけが漂っていた。
(こいつ―――!! 追い込み方が、まだ足りないっていうのか―――!?)
ハヤブサはキョウジの身体を ダンッ!! と、乱暴に壁に押し付けた。そのまま、本当に殺しかねない勢いで、キョウジを締め上げる。
「俺を憎め! キョウジ―――!! どうした! このままだと、本当に殺してしまうぞ!!」
「ハ……ヤ……」
さすがに苦しいのか、キョウジの手がハヤブサのキョウジを締め上げている手に添えられてくる。ハヤブサは、キョウジが少しでもこの手を撥ね退けようとしたら、すぐにでも手を離すつもりだった。
だが、キョウジの手は、ハヤブサの手を優しく撫でたかと思うと、そのまま下にだら…と、垂れてしまう。
「キョウジ!!」
ハヤブサは、衝撃を受けて、思わず手を離した。触れてきた手が、あまりにも優しすぎた。
空気を求めて喘いでいた気管に、大量の空気がいきなり流れてきたシュバルツは、激しく咳き込んだ。立っていられなくなって、そのままずるずると座り込んでしまう。
(こいつ―――この期に及んで、また……!)
まただ。また、キョウジは、俺に絞殺される方を―――死ぬ方を、選択した。
「何故だ………」
ハヤブサも、立っていられなくなって、思わずへたり込んでしまった。
「何故だ!」
「ハヤブサ……」
やっと呼吸が落ち着いてきたシュバルツが、顔を上げる。
「何故だ! 何故だ!! 何故だッ!!!」
ハヤブサは、声の限りに叫んでいた。叫ばずにはいられなかった。
(どうして―――分からないんだ!! こいつは!!)
「キョウジ―――!」
ハヤブサの手が、キョウジの肩に伸びて、ドン! と、再びキョウジの身体が壁に押し付けられる。
「どうして憎まない!? もしかして、憎む事を厭っているのか!?」
「ハヤブサ……」
(そうじゃない。―――そうじゃないんだ、ハヤブサ……)
シュバルツは、声なき声で答えていた。それが瞳に伝わり、哀しみをたたえて揺れる。
「俺は―――お前の守りたい者を、助けてやる事が出来ない…! もう、どうしようもないんだ!」
「――――!」
ハヤブサの、紛う事なき本心からの叫びが、シュバルツの耳朶に届く。ハヤブサの瞳に、うっすらと光る物が浮かんでいた。
「だが、お前は―――その人がいないと生きていけないというのであれば、俺を憎めばいい! 俺が、その人を殺すのだから!!」
「ハヤブサ―――!」
「俺はいい。お前が必要ならば、お前の憎しみなど、いくらでも受けてやる。受けてやるから……! だから、キョウジ―――」
ハヤブサは、渾身の力を込めて叫んだ。
「一言でいい!! 『生きる』と言え!!!」
ハ ヤ ブ サ ――― !
シュバルツは、ただ、茫然としていた。心が、木石で出来ているわけではないから、ひどく打たれた。
「俺は何度も何度も言った!! お前に―――『生きろ』と!」
縄を緩めていたのもそうだ。刀を渡そうとしたのもそうだ。憎まれようとしたのも、そうだ。もしかしたら―――子供を無防備に助けた姿を見たあの瞬間から、自分はキョウジを『生かしたい』と思ってしまっていたのかもしれない。
「なのに、お前は……まだ一度も俺に言っていないんだ。『生きる』と……! 何故、それが分からないんだ! キョウジ!!」
「ハ…ヤ…ブ…サ……」
ああ。何故だ。息が苦しい。
絞められてもいないのに、窒息してしまいそうだ。
身体が、勝手に歓喜に震える。
応えたい。
ハヤブサに、応えてしまいたい―――!
だが、出来ない。
私はそれに、応える事が出来ないんだ。
この『シュバルツ』と言う人間は、とっくに人間としての生命活動を終えている。キョウジが―――殺した。殺してしまった。
私は、その死体を依り代に、DG細胞によって作られた疑似生命体―――。
言わば、キョウジの、『罪』の証、だった。
私は、知っていた。
私と向き合うたびに、キョウジに『罪』を突きつけてしまっているという、事実。
人を殺した上に、死体を使って人ならざる者を生み出してしまったという、証。
もちろん、キョウジは何も言わない。『罪』の意識を感じている事を、巧みに隠している。私の存在自体に罪はない―――彼は、そう言いたいのだろう。
だが、どうしても気づいてしまう。キョウジが時々、秘かに自分を責めてしまっている姿に。
だからせめて、これ以上キョウジに罪の意識を感じさせないように、私を作った事を後悔させないように―――総ての事に誠実であろうと願い、実行しようとする。
しかし、誠実であろうとすればするほど―――自分で生き死にを選ぶことの出来ない身体が、自分にどうしようもない事実を突きつけてくる。
「お前の身体は、所詮借りもの。紛い物の、命なのだ」と…。
斬られても、甦る。撃たれても、生き還ってしまう。この、不自然な身体―――。
「貴方のために命をかける」と言っても、かける命が無い。
「殺されてもいい」と、言っても、甦ってしまうのであれば、その言葉は詭弁へと変わる。
どう足掻いても、結局真実の一つも言えない自分の言葉は、舞い落ちる枯れ葉よりも軽く感じる。
落とされても、生え換わってしまうような首に、何の価値があるだろう。
命は、一つしかないから、美しいのに。
死んでしまうから、生きる事も選べるのに―――。
この命が溢れている世界の中で、自分の存在だけが、ひどくいびつだと感じる。
どうしても―――そう感じてしまう。
そして、自分がそう感じている事に、キョウジが気付いてしまう。
それが、キョウジを更に苦しめることになる。
それは―――どうしようもない苦悩の連鎖だ。ここまで来ると、もう笑うしかない。
それでも私がキョウジの側にいるのは、黙って消えてしまう方が、もっとひどくキョウジを傷つける――――それが分かっているから。ただそれだけだった。
存在するだけで、傷つけているのが分かっているのに、自分で、自分を消すことも出来ない。
本当に、私は一体何なのだ――――。
こんな、中途半端な存在の私が、『生きる』なんて、言えない。
言えないんだ。ハヤブサ―――。
「…………」
シュバルツは、自分の肩をつかんでいるハヤブサの手に、そっと触れる。
暖かい手だと思った。こんな自分なんかのために、「馬鹿」と怒り、懸命に手を差し伸べてくれた。自分が本物の『シュバルツ』であったなら、あるいは、本物の『キョウジ』であったなら、きっと、この手を取ることに躊躇いはしなかった。
シュバルツは、ハヤブサの手を自分の肩からはずしながら、自分の手に視線を移す。
(この手……もう人としてのぬくもりを伝えてはいないだろうに、ハヤブサには、『キョウジは冷え症』ぐらいにしか、思われていないのだろうな……)
そう思うと、妙に可笑しかった。
ハヤブサは、懸命にキョウジを見つめていた。キョウジは、物事を受け取る力がとても強い人間だ。こちらが投げかけた物を、必要以上に誠実に対応して、ちゃんと投げ返してくる―――そういう男だと、思った。
それなのに、『生きろ』というメッセージにだけは、何故か頑なに応えようとしない。だから、ついに痺れを切らして、直接叫んでしまった。
キョウジが、生きる事を選択してくれるならば、それが、せめてもの希望になると信じた。この優しくて誠実な男が、この空の下、どこかで生きている。そう思えるだけで、この世界がほんの少し、優しい色を帯びるように感じられる。例え、その優しさが、もう二度と自分に向けられるものではなくなったとしても、きっと、その優しさが、誰かには向かっているはずだから。
大丈夫。今言った言葉は、キョウジにはちゃんと届いていると確信する。現に、彼の身体が小刻みに震えているのが、手に伝わってくる。
だが、茫然とこちらを見つめていたキョウジが、ふっと天を仰いだかと思うと、視線を下げてしまう。彼の少し長めの前髪が下がって来て、目元を隠してしまった。
「………………」
長い沈黙の後、キョウジの手が、自分の手に、そっと触れてくる。
掴んでいた肩から、手を外された。だが何故か、ハヤブサはそれに逆らえなかった。自分の手を、ものすごく大事な物のように扱われたからだ。まるで、この世に二つとない貴重な貴重な宝物を、壊れないように、そっと包み込むように―――自分の身体の方に、返された。―――.何故か、そう感じた。
キョウジの口元に、笑みが浮かんでいる。
そして頬に、白く光る細い筋が二つ、流れて消えた。
「ありがとう……ハヤブサ……。嬉しい……とても―――」
「キョウジ……」
今度こそ、分かってもらえただろうか―――ハヤブサは、そう思おうとした。
でも、待て。
何かがおかしい。
「嬉しい」と、言いながら―――何故、キョウジからは、哀しみしか伝わってこない?
何だ。
この違和感は、いったい何だ。
ハヤブサは、キョウジに声をかけようとした。しかし、それより早く、シュバルツが口を開いた。
「だが……私は所詮『影』―――」
「!?」
あまりにも不意を突かれたせいなのか、ハヤブサは、反射的に身を引いてしまった。その隙を、シュバルツは逃さなかった。ハヤブサの眼前から、キョウジの姿がフッと消える。
「キョウジ!?」
ハヤブサは、慌てて辺りを見回す。キョウジは、部屋の中にいた。窓を背にして、静かに佇んでいる。
「キョウジ―――」
「…………」
ハヤブサは、呼びかけてみる。しかし、キョウジからの返事は、無い。
表情は、穏やかそのものだ。しかし、キョウジの背後から入ってくる月明かりが眩しすぎて、キョウジの顔を、闇に覆ってしまう。
「私は、『影』だ。『影』は、ただ、つき従う者と心得る―――」
闇から、ぼそりと答えが返ってくる。
「お前―――!」
ハヤブサは、息が詰まりそうになった。否が応にも増大してくる違和感に、飲み込まれそうになる。
「お前……一体、何を、言って――――」
「…………」
ハヤブサは、「キョウジ」と思われる者に、声をかけた。しかし、またその者からの返事が、返ってこない。ハヤブサは、冷水を浴びたような気分になる。
おかしい。
今俺の目の前にいる、この男は一体何だ。
キョウジの顔を見たいと願う。しかし、月明かりが眩しすぎて、キョウジの顔が、よく見えない―――。
「お前……おかしいぞ……」
ハヤブサが、茫然と呟く。
「何が?」
無感情な声が、返ってくる。
「何がって――――」
背中から額から、急に汗が噴き出てくるのを感じる。
「お前が……お前がそんな、まるで、闇の住人……みたいに――――」
「何を今更―――」
キョウジらしからぬ、冷たい声。ハヤブサは、己が耳を疑った。
「私たちは、闇の世界に生きる者。だから、その心得を言ったまでだ。それを『おかしい』などと言うとは……おかしいのはお前だ。ハヤブサ―――」
「…………!」
(『生きる』って―――お前、一度も『生きて』いないだろう?)
そう思って、また違和感を覚える。そして、その違和感が、闇へと姿を変えていく。
闇は、あからさまにキョウジから発されていた。それが、この部屋を暗黒へと染め上げ、キョウジの姿を見えにくくしていく。
この闇は何だ。
この容赦のない、闇は何だ。
恐ろしい程の眩しい光を内包している男が、どうしてこんな、闇の中にいる。
これでは、闇がこの男を蝕んでいると言ってもいいくらいだ。
「――――!」
ハヤブサは唐突に理解した。
自分は、何かを見落としているのだ。
それも、この男を理解する上で、絶対にはずしてはならない、大事な『何か』を。
根源的な、『何か』を――――。
それを理解しない限り、自分の言葉はこの男を捉えることはできない。何を言ってもそれは力を持たず、空しく表面を滑っていくだけだ。
(何だ…? 俺は、何を、見落としている―――?)
懸命に考える。だが、分からない。分かる事が出来ない。
(キョウジ……!)
キョウジとの距離が、恐ろしく遠い。ハヤブサは、心が折れそうだった。
(もう、そろそろ潮時か……)
シュバルツは、そう感じていた。「龍の勾玉の正体を知りたい」と言う自分の要求に対して、ハヤブサは、ここまで応えてくれた。それこそ、充分すぎるほどに―――。
本当は、ハヤブサに詫びを言いたかった。
余計な苦しみを、与えてしまってすまない。その手を、取れなくて―――本当にすまない……と。
だが、今詫びを入れても、余計にハヤブサを苦しめるだけだと感じる。だから、もう、詫びる事が出来ない。詫びる事が出来ないから、礼も云えない。
もう、本当に、何も言えない。
そして、私は、キョウジの刺客として、ハヤブサ、お前を選ぶ。
ハヤブサは『キョウジ』を斬りたがっていない。それが分かる。だからだ。
これでキョウジは、決して短絡的に斬られたりはしない。ありとあらゆる道を模索されて、本当にどうしようもなくなった時―――ハヤブサは、その使命を果たす事だろう。
(それにしても、斬りたがっていない人間を、敢えて刺客に選ぶなんて……私は本当に、性格が悪いな……)
そう感じて苦笑する。そう言えば、先の「デビルガンダム事件」の折りも、自分はキョウジの刺客として、弟であるドモンを選んだ。真相を知れば、ドモンはおそらく兄を撃ちたがらないと分かっていたのに―――。
そして、ハヤブサ。
私がお前に言う事が出来る唯一の真実。
「キョウジが死ねば、私の機能も停止し、『死』を迎える」
これだけは、絶対にお前には告げない。お前の使命の完遂の、妨げとならないために。
それが、私のお前に対する精一杯の礼だ。どうか、受け取ってほしい―――。
すまない。ハヤブサ。
最後まで嘘つきで、本当に、済まない。
「ハヤブサ……」
シュバルツの呼び掛けに、うつむいていたハヤブサが、ピクリと反応する。
「何だ……」
「『龍の勾玉』の所に、お前を案内しよう」
「――――!」
シュバルツのこの言葉に、ハヤブサの反応が、更に大きくなる。
「お前……それが、何を意味するのか、分かっているのか……」
「ああ。分かっている。―――お前は、使命を全うするのだろう?」
あくまでも穏やかなキョウジの声に、ハヤブサの心は再びかき乱される。だがもう、「馬鹿野郎」と、怒鳴りつけることなど出来なかった。
「キョウジ……何度言ったら分かる……」
言いながらハヤブサは、自分の耳を疑う。自分の声は、こんなに弱々しい物だっただろうか。
「俺は……お前を、傷つけたくないんだ……」
言ったところで、届かないと分かっている言葉が、空しい響きを含んで落ちる。何という無力感だろう。
「知っている。―――お前は最初から、そうだったな」
闇から、淡々と返事が返ってくる。例え表面だけでも、何かが掠めれば、この闇は律儀に返事を返してくるのだ。
(知っているのなら、何で―――!)
一瞬、激昂しそうになる。しかし、声がのどから先に出る事を拒否してしまう。何よりも、顔があげられない。今の、闇にまみれているキョウジの顔を見る勇気が、どうしても持てなかった。
キョウジは、勾玉を持つ者を俺に斬れと言う。
その後で、自分も死ぬ気でいる。それが、痛いほど伝わってくる。
「生きろ」と、言い続けた俺の声が、まるで聞こえていないかのようだ。
俺が、見落としてしまった物は。
そんなにも、大きい物だったのか…?
分からない―――キョウジが、分からない―――。
「誰か、他の奴を選べ……俺は……もう―――」
「私は、お前以外の奴は、勾玉の所には案内しない」
「…………!」
自分の弱気な発言を、言下に否定される。自分は、最早キョウジの姿を見失っているというのに、闇の方が自分を逃がしてくれそうになかった。
「何で……」
自然と、ハヤブサの口から疑問がついて出る。
「何で、俺だ……」
「―――腹を切る武士だって、介錯の相手ぐらいは、選べるだろう?」
「――――!」
「だったら、私はお前がいい―――お前が、いいんだ」
「キョウジ……!」
(何故だ……!)
お前の介錯をする。俺は―――それが嫌だと、言っているのに!
自分の想いが、絶望的に届いていないのを痛感する。ハヤブサはたまらなかった。
(ふざけるな……)
チリ、と、心の奥に怒りの火が灯る。俺の想いは聞かないくせに、どうしてこの闇は、俺に執着する!?
「ふざけるな! 何で―――何で俺に……俺ばかりに―――!」
ハヤブサは、つい顔を上げてしまった。届かなくても何でも、怒りをぶつけずにはいられなくなった。
その瞬間、雲が月を隠し、闇の存在を浮き彫りにしていた光が、姿を消す。ハヤブサには、キョウジの顔が、はっきりと見えた―――。
「おまえは、私を、怒ってくれたじゃないか―――」
キョウジは、ただ、優しく微笑んでいた。
(ああ、やっと反応したな)
そう言って微笑んだ時と、同じ笑顔で―――。
「キョウ……!!」
「私の事を、『馬鹿』と。何度も何度も……」
「…………!」
「私は、それでもう、充分なんだ……」
「キョウ…ジ……」
「もう、充分なんだよ。ハヤブサ―――」
あまりの事に、胸が詰まった。
この男は、ずっとこうやって微笑んでいたというのか。
こんな容赦のない闇の中、ずっと独りで―――。
キョウジに、俺の声が届いていないわけではなかった。ちゃんと聞こえていた。手を差し伸べた姿が見えていた。
ただ―――キョウジは、俺の手をつかまないのではない。つかめないのだ。
彼を捕らえている闇が、あまりにも深すぎて―――今のままでは、掴むことが出来ないのだ。
だから彼は、ただ、優しく微笑むのだ。
闇にまみれている事を、恨むでもなく。
届かない事を、嘆くでもなく。
「手を差し伸べてくれて、ありがとう」と、礼を言いながら―――闇の深淵に、一人佇んでいるのだ。
その姿は、あまりにも孤独で――――。
(――――馬鹿だ!! やっぱりこいつは、大馬鹿野郎だ!!)
勝手に、とめどなく涙があふれた。ハヤブサはそれを見られたくなくて、慌てて下を向く。しかし、どうしようもなく零れ落ちていく。
これだけ涙を落とせば、キョウジには絶対ばれているだろうと思う。だが、この涙をどう思われようとも、もう知った事ではない、とも、思った。出る物は出るんだ。これの抑え方なんて、俺は知らない。
「―――馬、鹿、野郎が……ッ!!」
零れ落ちる涙と共に、ハヤブサの声が絞り出されていく。
「ハヤブサ……!」
それと同時に、フッとハヤブサはシュバルツの前から姿を消した。光る物を、撒き散らしながら。
「ハヤブサ……?」
シュバルツは、思わずハヤブサの姿を探してしまう。その時、どこからともなくハヤブサの声が聞こえてきた。
(キョウジ……)
「ハヤブサ?」
周りを見渡してみるが、ハヤブサの姿を捉える事は出来ない。近くに潜んでいるのは分かるが、姿を見せる気はないようだ。
(明日だ……。明日、龍の勾玉の所に、俺を案内しろ)
「――――!」
(刺客となる事を、受けてくれたのか、ハヤブサ……)
ほっと、小さく安堵の息をつく。
「承知した」
頷きながら、了承の意を伝えると、再び闇の中からハヤブサの声がした。
(これだけは、お前に伝えておく)
「何だ?」
(俺は――――絶対に、あきらめない!!)
「…………!」
覚えておけ! ―――ハヤブサの声はそう言い置くと、闇の中へと消えていった。
(あいつ……! 何をあきらめないって言うんだ……)
ひどく消耗しているのを感じたシュバルツは、己の身体を、トン、と、横にあった壁にもたれかけさせた。最後は涙まで……あいつは、人の心を殴りすぎだ―――。
(『キョウジ』を、あきらめないという事だろうか……)
そうならいい、と、シュバルツは思った。キョウジをあきらめないでいてくれれば―――。
これで、ハヤブサをキョウジの元に案内したなら、自分の任務は終わる。後は、キョウジとハヤブサの問題だと思った。どうなろうと、自分はそれに、従うだけ―――と、言うか、それしか出来ない……。
キョウジ……。
この星空の下、どこかにいるであろうキョウジの事に、シュバルツは想いを馳せる。
キョウジ……お前には、分からないだろう。
お前が、狙われていると知った時……私は――――嬉しかった。
「やっと、お前の役に立てる」と……。
お前と、瓜二つの外見も。死なない自分の身体すらも―――。
何一つ惜しむことなく、利用できる。お前を、守ることができる。それが、どれだけ嬉しかったか―――。
この歓喜を、誰にも邪魔されたくなかった。例え、弟のドモンであったとしても―――。
(でも、持って帰る情報が、結構ネガティブな物ばかり……おまけに、暗殺者まで連れて帰るんじゃなぁ……)
普通に考えなくても「お前は阿呆か」と、言われそうなレベルだ。全く私は、役に立っているんだか、立っていないんだか…。苦笑しながら、頭をかく。
ただ、どうなろうと、私はキョウジの役に立ちたいと願っている。それは、ずっと、変わらない。
(キョウジ……今はどうしている…? こんな私でも、少しはお前の役に立ったか…?)
窓から入ってくる夜風が、心地いい。だけど、変に月が霞む。
シュバルツはそう思いながら、いつまでも夜空に輝く上弦の月を眺めていた―――。
「第5章」
これより少し、時を遡る。キョウジ達は、ギアナ高地に着いていた。南米にあるこの場所は、ドモンが少年時代に武者修行した舞台でもあり、キョウジが研究のために、何度も訪れた所でもある。東方不敗の言う「とっておきの隠れ家」は、まさにここに在った。
問題は、移動手段だった。
キョウジは、狙われている身であるが故に、大っぴらに飛行機に乗る事が出来ない。
「武者修行のため、泳いで行こう」
と、ドモンが言いだした時、キョウジは生きた心地がしなかったが、
「お前は阿呆か。こういう時は、素直に仲間を頼らんか」
と、師匠がドモンを蹴飛ばしてくれたので、キョウジは何とか、今日を生き延びる事が出来た。
ドモンが、アメリカにいる友人チボデー・クロケットに連絡を取ると、彼はすぐに、シャトルを一台手配してくれた。
「悪いな。俺も付き合えればよかったんだが、もうすぐ大事な試合があるから―――」
目的地に着いて、シャトルから降りようとするドモン達に、チボデーが残念そうに声をかける。彼は、プロのボクサーでもあった。
「いいさ。こちらには師匠もいるし、兄さんも一緒だ。誰が来ようと、負ける気がしない」
「言いやがったな。こいつめ」
自信たっぷりに言い切るドモンに、チボデーも笑って相槌を打つ。
「試合、頑張れよ。でも、何かあった時には―――」
ドモンが右手にキング・オブ・ハートの紋章を浮かび上がらせると、チボデーも右手にクイーン・ザ・スペードの紋章を浮かび上がらせて答える。
「任せな! この紋章にかけて、いつでもすっ飛んで来てやるぜ!」
彼もまた、シャッフル同盟の一員であった。
「ドモン達も、頑張って!」
チボデーの後ろで、チボデーをいつもサポートしている女性たちが、ひらひらと手を振っている。皆が、それぞれに励ましの言葉をドモン達に投げかけながら、シャトルは発進して行った。
「―――いい友人だな」
キョウジがドモンに声をかけると、ドモンも誇らしげに頷いた。
「ああ。チボデーも、ジョルジュも、サイ・サイシーも、アルゴも……みんな俺の自慢の友人たちだ」
「そうか……」
ドモンにそういう友人たちがいる事を、キョウジは素直に喜んだ。
「お主たち、もう少し歩くぞ。……こっちだ」
東方不敗の案内に、カッシュ兄弟は素直に従った。
東方不敗のとっておきの隠れ家は、天然に出来ている入りくんだ洞窟の、奥の方に在った。入口になる洞窟自体も非常に分かりにくく、中も複雑に枝分かれしている。きちんとした案内なしでは、たどり着く事も不可能なように思われた。
火を焚いても煙がこもる事が無い。恐らく、換気が出来ているのであろう。近くにはきれいな湧水があり、飲料水にも事欠かない。奥には備蓄用と思われる食糧もあった。どうやら、ここでしばらく腰を据えて活動をしても、支障はないようだ。
「どうじゃ。なかなかのものであろう?」
「そうですね……」
東方不敗がちょっと誇らしげに中を案内してくれている横で、キョウジはきょろきょろとある物を探していた。それは、勾玉の事を調べるにあたって、自分には絶対必要不可欠なものであった。
「ところでマスター。一つ、お聞きしてもいいですか?」
探してもどうしても見つからないので、キョウジは笑顔を作って東方不敗に問いかける事にした。
「何じゃ?」
「『電気』はどこにありますか?」
「そんな物あるか」
「…………!」
東方不敗にズバッと切り返されて、キョウジは笑顔のままで固まった。
「電気なんぞ無くても、ここでの生活に支障は出ん。問題なかろう」
(いや、それはそうかもしれないけれど……)
自分は、勾玉の事をいろいろ検証するために、パソコンを使用している。自分のメディカルチェックのデータとか、過去の有機体の実験のデータベースとか閲覧したり使用したりしたいから、どうしても電気が必要なのだ。
「マ、マスター……では、もう一つお聞きしますけど……」
半ば絶望的な気持ちになりながらも、キョウジはさらに東方不敗に質問をした。
「ここにいるときに、外の情報とかは、どうやって仕入れているんですか……?」
「フフフフ。良い質問じゃな」
東方不敗が、にやりと得意げな笑みを面に浮かべる。
「わしがここで情報を得る時は、ある事をしておるのよ」
「―――師匠! あの奥義を久々に見せていただけるのですね!!」
東方不敗の横で、ドモンがわくわくしている。何かもうそれだけで、キョウジにはドブ色の未来しか見えてこない。
「見よ!! これぞ流派、東方不敗が奥義! 『水盆』じゃあ!!」
東方不敗が複雑な手の動きをした後、窪地に溜まっている水たまりに向かって手をかざすと、そこに外の景色が映り込んできた。
「フフフフ。この奥義で、大体ワシが見たい所は見る事が出来るようになっておるぞ? まぁ、ちと精度は荒いがな」
そう言いながら、水たまりに移っている映像が、世界のあちこちの場所へと切り替わっていく。
「さすがです! 師匠!! ―――俺は、なかなかそれが出来ないんだよなぁ」
ドモンが師匠に対して拍手を送っている背後で、キョウジは眩暈を起こして突っ伏していた。
(こ……この、人類の規格外師弟……! 分かってはいたけど……! 分かってはいたけど……!!)
ついにキョウジの中で、何かが「ぶちっ」と音を立てて切れた。
「ああもう!! 分かったよ!! どうせ電気が必要なひ弱な一般市民は、この中では私だけですよ!! 作りゃあいいんだろ!? 作れば!!」
キョウジのあまりの大声にびっくりしている師弟を尻目に、「ちくしょう!! 作ってやる―――!」と、口走りながら、キョウジは己のトランクから何やら引っ張り出して来て、本当に何かを作り始めた。
「…………!」
東方不敗が茫然とその様子を眺めていると、ドモンがそろそろと、この部屋から出て行こうとしている。
「どこへ行く?」
見咎めて声をかけると、ドモンがおっかなびっくりといった様子で振り返った。
「い、いや……カッシュ家にはいろいろ決まりごとがあったんだけど、その中の一つに、『ああなった兄さんには近寄っちゃいけない』って言うのがあって……」
「ああなった兄御に?」
そう言いながら東方不敗は、キョウジの方に振り返る。確かに、ただならぬ集中力と―――気のせいか、殺気まで漂わせている。見ているうちに、何やら一つ、部品らしきものを完成させて、もう次に取り掛かっていた。
「兄さん、ああなっちゃうと、本当に周りが見えなくなることがあるから―――危ないから近付くなって、母さんが……」
「なるほどのう……」
ドモンの言葉に東方不敗が納得しているうちに、キョウジがまた何か一つ完成させて、さらに次に取り掛かっている。
(これは、何かを作っているというよりは、まるで戦いじゃな……)
東方不敗はそう感じて、キョウジの様子を見守ることにした。
「俺、修行するついでに、何か食材を調達してきます……」
ドモンがそう言って静かに出ていく間にも、キョウジは更に、完成させた部品同士を組み立てにかかっている。まるで、魔法を見ているかのようだ。
(キョウジよ……ワシからしてみれば、何もない所からそのように次々と何かを作り出していくお主の方が、よっぽど人間離れしているように見えるのだが―――)
「ちくしょう!」と、叫びながらドカドカ部品を叩いているキョウジの後ろ姿を見ながら、東方不敗はそう思ったのだが。
(まあいい。黙っといてやるか)
彼にしては珍しく、空気を読んだ。
3時間後。
キョウジは本当に、自分に必要な電源と、システム一式を完成させていた。いつの間にやら椅子まで作って、そこにぐたっと、もたれかかる様に座っている。
(あ~……久々に本気だして仕事した……さすがに疲れた……)
でも、休んでいる暇はないと感じる。調べなければならないこと、やらなければならない事が山積しているからだ。
(でも……せめて、コーヒーが飲みたい……)
パソコンからつながっているサーバーに至るまでの主電源のスイッチをオンにしながらキョウジがため息をついていると、背後からずいっと茶が差し出された。驚いて振り返ると、そこに東方不敗が立っていた。
「烏龍茶だ。口に合うかどうかは分からんがな」
「あ……りがとうございます」
礼を言いながら、おずおずと茶を受け取る。
「大した奴よ。このワシに、茶を入れさせるとはな」
「…………!」
少し驚いた表情を見せるキョウジに、東方不敗はにやりと笑いかけて踵を返す。
差し出された茶から、ゆらゆらと湯気が立ち上っていた。
(……温かい……)
烏龍茶をすすりながら一息ついていると、何やら別方向から鋭い視線を感じる。
「?」
キョウジがそちらに振り返ってみると、弟のドモンが、物陰からこちらの様子を伺っていた。しかも、その目線が、何やら恨めしさを帯びている。
「ド、ドモン?」
キョウジが冷や汗を流しながらドモンに声をかけると、彼から心の声で返事が返ってきた。
(師匠から、茶を入れてもらうなんて……!)
まるで、白いハンカチでも、口にくわえそうな勢いだ。
(こ…これって……私が、悪い…の…か……?)
思いもかけず弟から恨みを買ってしまったような格好になったことに戸惑っていると、ドモンが勢いよく部屋に飛び込んできた。
「師ィ匠ォ!! 改めてあんたに、闘いを申し込む!! 俺が勝ったら、あんたに茶を入れてもらうからな!!」
「………!」
キョウジは、イスからずり落ちそうになった。
(茶をめぐってのバトル……。まあ、らしいっちゃ、らしいけど……)
ドモンからの宣戦布告に、東方不敗が不敵に笑って答える。
「ほう……貴様ごときが、ワシから見事、茶を得る権利を勝ち取ることができるかな?」
「やってみなければ分からん!!」
そう言いながら、ドモンがファイティングポーズをとる。
「このひよっこがぁ!!」
東方不敗もそれに応じるようにファイティングポーズをとる。
今度は、何も止め立てする物が無かったが故に、茶をめぐっての師弟対決が始まってしまった。二人の遠慮のない拳の応酬が、周囲の土ぼこりを巻き上げ、壁に振動を与え、小石をパラパラと降らせてくる事態へと発展していく。
「…………」
最初は止め立てするのは不可能かと思い、沈黙を決め込んで茶をすすっていたキョウジであったが。
(近い……システムが、壊されるんじゃないか?)
そう思っている間にも、ドモンの拳が床を穿ち、巻き上がった小石が、コンピューターの一部に当たる。
「おい! 二人とも、いい加減に―――!」
無駄と知りつつ声をかけてみるが、やはりというか、二人のバトルは一向に止まる気配が無い。そうこうしているうちに、東方不敗の布が、サーバーのすぐ上の壁を抉る。小石がサーバーに当たる金属音を聞いた瞬間、キョウジの中で、またしても何かが「ぶちっ」と派手な音を立てて切れた。
「……………」
無言で、イスを持ってすたすたと歩き出す。眼にもとまらぬ速さで動いている筈の、二つの影の動きを眼で追い、先を読む。
(ここだ!!)
ありったけの気合を込めて、イスを投げつけた。
ドカン!!
投げ込まれたイスが、東方不敗とドモンの間に入る。見事に二人の拳を捉え、闘いを一時中断させることに、奇跡的に成功していた。
「な、何じゃ?」
東方不敗とドモンが、驚いてイスが飛んできた方向に振り返ると、キョウジが、尋常ではない殺気を迸らせながら立っていた。しかし、顔だけが、微笑んでいる。微笑んでいるだけに、余計に、怖い。
「―――申し訳ないんだけど、二人ともここで暴れるのはやめてもらえないかな。ここにある物は、私にとっては一応大事な物なんだ」
「お、おお、これはすまなんだな」
流石にまずいと思ったのか、東方不敗が素直に詫びの言葉を入れる。詫びた後で、横にいるドモンを秘かにどついた。
(みろ! 貴様のせいでキョウジを怒らせてしまったではないか!)
(元はと言えば、師匠が兄さんだけにお茶を入れたのが原因でしょうが! 俺には滅多に入れてくれなかったのに―――!)
(阿呆か! キョウジはワシを唸らせるだけの事をしたから茶を入れたのだ! 悔しかったら貴様もワシを感心させるだけの事をして見せい!)
(何おう!?)
(やるか!?)
二人の間に、再び戦いの火花が散りかける。しかし。
ドカカカカカッ!!
派手な音を立てて、二人の目の前の地面に何かが突き刺さる。よく見ると、それはフロッピーディスクだった。二人が恐る恐る顔を上げると、最早、顔に笑顔を貼り付けていると言っても過言ではないキョウジが、そこに立っていた。彼の後ろに、仁王像が浮かび上がっている。
「―――もう一度、言うぞ……。出・て・行・け!」
「…………はい」
二人は素直に回れ右をし、部屋を出て行った。
(あ~……イス、作り直し……)
ボロボロになったイスを見つめながら、キョウジはため息をついた。
「何か……興がそがれたのう」
部屋を出た所で、東方不敗が一つため息をつく。もうドモンとのバトルという気分ではなくなってしまった。どうやら、ドモンの方も同じことを感じているようで、ため息をついている。
(そう言えば、ワシは「龍の勾玉」の事を調べるために、ここに来たのであったな……)
東方不敗は、当初の目的を思い出した。
「ドモンよ。ワシは、今から書庫に行って勾玉の事について調べるが―――」
「俺も、御供します。師匠」
「……………」
即答してきたドモンを、じっと見つめる。キョウジの事を、人一倍心配しているドモンからしてみれば、勾玉の正体は、一刻も早く知りたいところなのだろう。
しかし―――自分のうろ覚えの記憶の中にある勾玉の不吉なイメージが、引っかかってしまう東方不敗は、すぐにドモンに「よし、ついて来い」とは言えなかった。どうしても、まず自分で確認する必要がある、と感じていた。
「いや、ドモン。お主は夕餉の支度をせい」
「え…? でも……!」
「お主、『あの』兄上に、夕食を作ってもらうつもりか?」
「…………!」
ドモンの脳裏に、先ほどの顔だけ不自然に微笑ませながら怒りを顕わにしている兄の姿が甦ってくる。「夕食作って」と頼みに行ったならば、今度こそ、ものすごい雷を落とされそうな気がした。
「分かりました……行ってきます」
そう返事をして踵を返すドモンだが、足取りが気の毒なほど重そうだ。やはり、大好きな兄に怒られてしまった事が、よほど堪えているのだろう。東方不敗はやれやれとため息をつく。
「ちゃんと作れよ……ワシが『旨い』と感じたら、お主にも茶を入れてやる」
「………! 分かりました! 頑張ります!!」
たちまちのうちに笑顔になって、台所へと走っていくドモン。
(単純な奴よのう……)
東方不敗は苦笑しながら、その後ろ姿を見送った。
その頃キョウジは、先ほどよりも座り心地が若干悪くなったイスに腰掛けて、ある所にハッキングを試みていた。いくつものセキュリティを潜り抜け、ついにキョウジは、目的のファイルへと辿り着く。
―――「デビルガンダム事件」の極秘資料―――
「……………」
画面に浮かんでいる文字を眺めながら、キョウジはしばしの間、動きを止める。
もう、閲覧できる状態までは漕ぎつけている。後は、クリックをしてファイルを開くだけだった。しかし―――。
あまり見たくない、というのが正直な気持ちだった。
実際、自分はこの事件が勃発してから、割と早い段階でデビルガンダムのコアとして取り込まれてしまったため、シュバルツを作ってからの記憶があまり定かではない。長い事闇に閉ざされ―――気がつけば、病院のベッドの上だった。
だから、もしかしたら、これを見る事によって、知らなくてもよかった事まで、知ってしまうかもしれない。改めて自分の『罪』を確認して、もっとダメージを受けてしまうかもしれない。
「……………」
だが、迷っている場合ではない、とも感じる。今、自分の中にある勾玉も、このデビルガンダムと似たような物の「コア」であると、東方不敗は言っていた。ならば―――何か、参考に出来るような事柄が、この中にあるかもしれない。無いかもしれないが…。
ふ―――っ、と一つ、大きく息を吐く。なりふり構っている場合ではない、と、己に言い聞かせ、気持ちを落ち着かせる。
キョウジは覚悟を決めて、マウスを操作した―――。
「…………」
書庫に着いた東方不敗は、さっそく自分の記憶に在った書物を見つけ、それを読みふけっていた。そこには、慧信が起こした事件の一連の件が記されていた。
(確かに、これだけでも十分不吉なものだが……果たして、これだけだったかのう…?)
そう感じて、首をひねる。何かが、まだ抜け落ちているような気がした。
おかしい、と、感じながら、他の書物も紐解いてみる。しかし、これ以外の『龍の勾玉』に関する記録が、なかなか見つけられなかった。
(む……いかん、眼が疲れてきた……)
やれやれ、寄る年波には勝てんわい、と、思いながら、東方不敗は書庫からいったん出る。首をコキコキと鳴らして、身体を伸ばそうとした時―――前方に暗いオーラを背負って座り込んでいる人間がいる事に、東方不敗は気がついた。
「キョウジ? 何をしておるのじゃ? そんな所で―――」
「あ………」
東方不敗の呼び掛けに、キョウジが顔を上げる。東方不敗の姿を認めて、笑顔になった。だが、固い。顔色も悪かった。
「すみません。ちょっとパソコンの画面に酔っちゃったみたいで……」
正確には、記録に酔っていた。
デビルガンダムが残した被害の爪跡の記録に。
覚悟はしていたが、やはり、きつい。
「…………」
東方不敗は、そんなキョウジの様子を黙ってみていたが、やがて、彼に一つの提案を持ちかけた。
「どうじゃ、気分転換に、書庫の方を覗いてみるか?」
「え? いいんですか?」
「――――!」
先ほどの笑顔と打って変わって、明るい物になる。兄弟なのに、ドモンとは全然好みが違うということを実感して、東方不敗は苦笑した。ドモンならば、書庫、と聞いただけで、あまり良い顔はしない。
「歴代のキング・オブ・ハートが記した戦いの記録がある。書庫からの持ち出しは禁ずるが、後は、好きに見て構わんぞ」
「分かりました。ありがとうございます」
キョウジを書庫に案内すると、彼はさっそく一つの巻物を手にとって読み始めた。
「キョウジ―――」
「…………」
声をかけてみるが、返事が無い。完全に巻物に没頭していた。ものすごい集中力だ。
(―――ドモンにも、せめてこ奴の半分くらいでいいから、書物と向き合ってほしい物だな……)
東方不敗は苦笑しながら、自身も『龍の勾玉』の資料探しを再び始めた。
しばらくして、キョウジが何冊目かの書物を読み終わり、次に移ろうとする。東方不敗は、それを待っていたかのように声をかけた。
「キョウジよ」
「―――! はい」
「ここに『龍の勾玉』に関する記述がある。読んでみるか?」
気分転換に書庫に来ているのに、現実に引き戻すのもいかがなものかと思いながらも、東方不敗はそれをキョウジに薦めた。ドモンはともかく、キョウジ自身には、一刻も早く勾玉の正体を把握してもらう必要があると、思ったからだ。
「ありがとうございます。拝見いたします」
キョウジも同じことを感じていたらしく、躊躇うことなく書物を手にすると、すぐに読み始めた。
「…………」
慧信の事件。即ち、『龍の勾玉』の、誕生の記録だ。
(人の身体……邪法……死体を喰らう―――)
キョウジは、気になったキーワードを、頭の中に並べていく。
(力の源……炎……結晶体……)
「…………」
東方不敗は、キョウジの様子を見守っていた。勾玉に対して、キョウジがどのような意見を持つのか聞きたいとも思っていたからだ。キョウジは静かに書物に向かっているが、時々顎がかすかに動いていた。何かを考えながら読んでいる証拠だ。そして、キョウジにしては珍しく、書物を読むスピードが、だんだん遅くなっている。
意見が聴けるのはもう少し先か、と、東方不敗が思った瞬間、キョウジがいきなり本を閉じてこちらに走ってきた。
「マスター。ありがとうございました。参考になりました」
「あ? ああ……」
本を東方不敗に返すや否や、キョウジは踵を返して走り出す。
「うわっ……と」
書庫の出入り口の所でドモンとぶつかりそうになったが、それすらも気づいていないように走り去っていった。
「ドモン? どうした?」
東方不敗がドモンの姿に気がついて、声をかける。
「あ……ご飯の用意が出来たから、呼びに来たんですけど……」
言いながらドモンは、兄が走り去った方向を見つめながら、頭をかいている。
「用意が出来たのなら、兄上も―――」
そういう東方不敗に、ドモンは苦笑交じりの笑顔を返した。
「いや、たぶん、ああなっちゃったら、兄さんはしばらく部屋から出て来ない……」
「…………!」
「兄さんは、何かの研究が進む時とか、新しい発見があった時によくあんな風になってた…。たぶん、今調べているのが『龍の勾玉』だったから、それについて、何か分かったんじゃないかな……」
俺には、よく分からないけれど―――と、言いながら、ドモンは再び頭をかいている。
「そうか……」
東方不敗は、キョウジが走り去った方を黙って見やった。東方不敗は武闘家として、身体を作る元となる『食』をとても大事にしている。だから、食事は全員でそろって食べるべきだと思っているし、食事を抜くなどは言語道断だとも思っている。
キョウジが自分の弟子であるならば、遠慮なく叱り飛ばして無理やりにでも食事の場に連れてくる所だ。しかし、残念ながら、キョウジは自分の弟子ではない。まして、ある意味最優先事項である『龍の勾玉』について、彼は調べている。
(……強制はできんか……)
ため息とともに、東方不敗はそう結論付けた。
「仕方がない。では、我らだけで頂こう。兄上には、後で届ければよい」
「分かりました。……でも…」
「でも…? どうした?」
「兄さん、食べてくれるかな。ああなっちゃうと、たまに本当に寝食を忘れる事があるから―――」
そう言いながら、ドモンはとても心配そうな顔をしている。
「分かった。後で、ワシも様子を見に行ってやろう。…それよりも、料理の方はちゃんと作ったのか? まさか、ワシから茶を得る事を、あきらめたのではあるまいな」
東方不敗からの挑戦的な物言いに、ドモンの表情も強気な物に変わる。
「任せてください、師匠! 今回は、自信があります!」
「ほう…それは楽しみな事だな」
師弟は笑いながら、食事の場へと向かって行った。
夜更け。
「…………」
キョウジは、自分の左腕にギリっと駆血帯を巻いて、口で絞めていた。静脈の位置を確かめ、慣れた手つきで採血のために注射針を刺そうとする。
ところが、針が刺さる寸前で、不意に大きな手がキョウジの肘の上に乗せられて、それを阻んだ。
「―――!」
ビクッとなって顔を上げると、東方不敗がそこに立っていた。
「もうその辺で止めておけ……。お主、これで何回目の採血だ?」
「…………!」
「先ほどは、何やら怪しげなものを飲んでおったようだし―――」
「嫌だなぁ、見ていたんですか?」
キョウジは苦笑しながら注射を置き、駆血帯を外した。
「仕方がなかろう。食事に呼んでも出て来ぬし、ドモンも心配しておったし……」
「―――!」
「ドモン」という言葉に、キョウジがピクリと反応する。
「あの……ドモンは……」
「あ奴なら、食後のロードワークに放り出してやった。暫くは帰って来ん」
「そうですか……」
東方不敗の言葉に、キョウジはホッとしたような表情を浮かべる。
「お主、いったい何をやっておるのだ?」
「勾玉の事を調べていて……すみません。いろいろ思いつくと、試さずにはいられなくて―――」
「だからと言って、お主……いくら自分の身体に勾玉が入っているからとは言え―――」
「大丈夫。無茶はしていません。自分の身体ですから……」
「…………」
(こ奴―――嘘をついておるな……)
東方不敗は思った。この男は、自分の身体だからこそ、逆に一切容赦をしていない可能性が高い。
「お主―――ドモンがこの部屋に、夕食を持ってきたのに気づいておるか?」
「えっ……?」
「ほれ、そこの、テーブルの上に置いてあるだろう」
「…………!」
東方不敗に顎で指されて、初めてキョウジは夕食の存在に気がついた。深めの皿に、豪快に切られた芋やら根菜やらが煮込まれた料理が盛りつけられてある。
煮込み料理だから、匂いがしていなかったはずがない。それなのに、気がつかなかった理由は、一つしかない。おそらく自分の身体の声に、耳を傾けていないからだ。
「焦る気持ちは分からんでもないが、せめて自分の身体の食欲ぐらいは許してやれ……。それは、ドモンが作った料理だ。味は、なかなかの物だったぞ? まあ、茶を入れるほどではなかったが……」
「ドモンが……!?」
キョウジは衝撃を受けていた。弟がいつこの部屋に入ってきたのか、全然気が付いていなかった。声をかけてくれたのだろうか。それとも、気を使って、黙って置いて行ってくれたのだろうか。
どちらにしろ、今の今まで弟の存在を、完全に無視してしまっていた自分に気づく。もしかしてまた自分は、弟をひどく傷つけてしまったのではないだろうか―――。
「今が、敵に狙われていない平和な状況であれば、ワシも何も言わんのだが……」
キョウジが予想以上に動揺しているのを見て取って、東方不敗はため息をつく。
「ここも、敵に発見されんと言う保証はない。その時に、お主が自力で動けなくなる状況に陥られては、こちらが困る。体調管理も、戦いの内ぞ―――」
「……申し訳、ありませんでした……」
キョウジがみるみる、気の毒なほど落ち込んで行っているのが分かる。東方不敗は苦笑した。
「分かればよい。さあ、今日はそれを食べてもう寝なさい。冷えていては旨くなかろう。温めなおして来てやる」
「あ……だ、大丈夫です! 自分で出来ますから―――」
碗を持って行こうとしたら、慌てて止められた。では、それぐらいは自分でやってもらうか―――と、東方不敗は碗をキョウジに渡した。
「お主の事を、常に心配しておる存在―――それを、忘れるな」
それだけ言い置くと、東方不敗は部屋から出て行った。
「……………」
(ドモン……)
キョウジは、しばらく動けなかった。手にした碗が、やけに重く感じた―――。
時が過ぎて、よれよれになったドモンが帰ってきた。余程ハードな物だったのだろう。
「ちくしょう……師匠め……! 料理の腕を認めるどころか、いきなりこのロードワークを課してくるとは……! 覚えてろ……! 次こそ絶対……!」
ふらつきながら部屋に入ろうとすると、何かに思いっきり蹴躓いた。
「うわぁ!?」
派手に転んでしまってから、躓いた物の方に振り返る。
「だ、誰だ!? こんなところに物を―――!!」
そこでドモンは絶句してしまう。そこには、膝を抱えて座り込んでいるキョウジがいたからだ。
「に、兄さん…?」
「…………」
恐る恐る呼びかけてみるが、返事が無い。ドモンは慌ててキョウジを揺さぶった。
「ちょっ……! 兄さん!! 兄さん!!」
「う……ん、あ……? ああ、ドモン……」
ゆすられたキョウジが、はっと覚醒する。どうやら、眠っていたらしい。
「に、兄さん……? 何やっているんだ? こんな所で……」
「いかんいかん、待っているつもりが――――」
キョウジが、眠そうに眼をこすっている。
「ま、待っているって……! 何を……?」
「ドモン、お前を―――だよ」
「お、俺!?」
素っ頓狂な声を上げるドモンに、キョウジは微笑みを返した。
「一言、お礼を言いたくて……でも、駄目だな。腹が膨れると、睡魔に勝てなかった……」
「兄さん……?」
ドモンが、怪訝そうな顔をする。何で礼を言われるのかが分かっていない様子に、キョウジは苦笑した。
「夕食……食べたよ。お前が、作ったんだろ?」
「兄さ……!」
「すごく、おいしかった。―――だから、つい、食べ過ぎてしまって……」
「――――!」
「腕を上げたな、ドモン」
ドモンは、勝手にほてってくる頬を、バン! と、両手で覆った。
(やば……! 師匠に茶を入れられるよりも、嬉しいかもしれない…!)
兄に、認めてもらえた嬉しさ、それもある。しかし、何よりも嬉しいのは―――。
「良かった……。兄さん、夕食、食べてくれたんだ……」
「ドモン……」
ドモンが、心底ほっとしたような笑顔を浮かべている。それを見たキョウジの胸が、ズキ、と痛んだ。
(お主の事を、常に心配しておる存在―――それを、忘れるな)
東方不敗の言葉が、重くのしかかってくる。
「すまなかった、ドモン……。本当なら、もっと早く食べなきゃいけないのに―――」
どれだけこの優しい弟を心配させてしまっていたのか―――。キョウジが申し訳なさそうに目を伏せる。それを見たドモンの方が慌てた。
「な、何を言っているんだよ! 兄さん! 兄さんの方が、『龍の勾玉』なんて、訳の分からない物が身体に入ってしまって、大変なのに―――」
そこまで言ったドモンが、不意にキョウジの両手をつかんでくる。
「兄さん……本当のところはどうなの? 『龍の勾玉』は、何とかなりそうなのか…?」
「――――!」
「まさか……死ぬようなことになったりしないよな? 大丈夫だよな?」
そう言いながら、ドモンは食い入るような眼差しを、こちらに向けてくる。
「ドモン……」
大丈夫だよ、と、言ってやりたかった。しかし、はっきりとした事は、キョウジ自身にもまだ分からない。ドモンが、真剣に心配してくれている事が分かるだけに、いい加減な返事を返せなかった。
「私もいろいろと調べているんだけどね……。まず、身体から出さないと、何とも―――」
「俺、もう嫌だからな。兄さんが死のうとするのを見るの、本当に嫌だからな」
「ドモ……!」
「もう本当に―――。あんな事は、二度と―――」
「…………」
忘れない。
「デビルガンダム」に取り込まれて、ボロボロになった兄の姿。
そのコクピットに飛び込み、「私たちを撃て!!」と、叫んだシュバルツ。
忘れたくても、忘れる事が出来ない。今でも、悪夢のように記憶に焼き付いている。
「そうだな…。私だって、死にたくない―――」
そう言いながら、キョウジは苦笑する。
しかし、ドモン。
普通にいけば、いずれ、「兄」は「弟」より先に死ぬのものだ。
でも、そんな事を言ったら、また、泣かせちゃうかな―――。
「ああ……いかん…睡魔が……」
ここまで来て、キョウジは、身体がもう起きていられない、と悲鳴を上げるのを感じていた。
「悪い……ドモン……私…は……」
そう言いながら、キョウジの身体が、ガクン、と崩折れる。床にキョウジの頭がぶつかる寸前、ドモンがそれを支えた。
「兄さん……?」
ドモンがキョウジの顔を覗き込むと、兄は穏やかな顔で、眠りに落ちている。規則正しい寝息が、ドモンの耳にも聞こえてきた。
(兄さん……疲れてたのに―――)
何故か、泣きそうになる。ドモンは、兄の身体をそっと抱きかかえた。
せめて、今の兄のこの眠りだけは、誰にも邪魔をさせはしない。それが出来なくて、何がキング・オブ・ハートか―――。
(ゆっくり眠って、兄さん。今だけでも……)
ドモンは兄を起こさないように細心の注意を払いながら、兄の身体を寝室へと運んだ。
「…………」
東方不敗は物陰から兄弟の様子を見守りながら、これからの事を考えていた。
(キョウジが、少し疲れてきておるようだな……。まあ、無理もない所ではあるが)
狙われてからの、無茶な移動。おまけに、自分の身体を省みていない実験。これを日々繰り返していては、どんなタフな人間であったとしても、いずれ倒れてしまう。
(どうする? 罠を仕掛けておくか―――?)
ここの隠れ家が、いつまでも敵に発見されないという保証はない。おまけに、前回敵と戦った時、敵の戦力を「人数不足だ」と挑発して切り捨てた。敵がそれを轍として、もっと戦力を投入してくる可能性がある。備えの必要性を感じた。
(明日から修業がてら、ドモンと共に罠作りにいそしむとするか……)
これからの方針を決めた所で、東方不敗も睡眠をとることにした。
それから数日間は、静かに流れた。
ドモンと東方不敗が交代でキョウジの護衛をしつつ、地形を生かしながら、周囲に罠を張り巡らせていく。キョウジの方も、龍の勾玉について調べる実験を続けてはいたが、寝食を忘れる、という事は無くなっていた。
時折、罠の仕掛け方について、東方不敗はキョウジとも意見を交わした。キョウジの意見は、どれも的を得ていて、とても参考になった。
(こ奴……いっぱしの軍師にもなれるな……)
そう感じて、それとなくキョウジに勧めてみるのだが、争い事は苦手ですから、と、笑ってするりとかわされる。やはり、能力はあるのに野心を持つ気はさらさらないようだった。
ある日。ドモンがいつもの通り罠を仕掛けていると、少し離れた所で、移動している二つの影を発見した。
一人は、見覚えの無い人間だったが、もう一人の方は、キョウジと同じ背格好をしている。
(シュバルツ―――!!)
その姿を確認したドモンはいても立ってもいられなくなり、その場からシュバルツに向かって走り出していた。
「本当に、こんな所に勾玉の持ち主がいるのか……?」
ハヤブサが、思わず疑問を口にしていた。先ほどから、密林、と言っても差し支えのないギアナ高地の自然の中を進んできている。あまりにも人気が無さ過ぎて、少し不安になった。
しかし、目の前のキョウジの足取りは、まるでここに何度も足を運んだ事があるかのように、慣れた物だった。
「多分―――『あの二人』がそろえば、十中八九ここに来ているとみて、間違いはない」
そう言いながら先を歩いているキョウジは、時折懐かしい物を見るような眼で、周りの景色を見ている。こういう時に見せる眼差しは、およそ、闇の住人らしからぬ物となる。つくづく、不思議な奴だとハヤブサは思った。
不意に、自分たち以外の人の気配を感じて、ハヤブサは顔を上げる。
「兄さ―――――ん!!」
力強い叫びと共に、上空から赤い鉢巻に赤いマントをなびかせた青年が降ってきた。
「!?」
二人がその場から飛び退くと同時に、青年が、二人がいた場所の地面を ドゴォッ!!と穿つ。青年は、そのままキョウジの方を追いかけだした。
「キョウジ!!」
ハヤブサは、キョウジの加勢に行こうとする。しかし。
「弟だ!!」
「―――!」
キョウジの叫ぶ声に、ハヤブサは足をとめた。
そのまま青年とキョウジは、まるで拳法の組み手の型のように、拳と、足技を多彩に織り交ぜながら、高速で移動し、ぶつかり合っていく。
やがて、ドン!! という音と共に、互いの手刀をのど元に突きつけて、二人の動きが止まった。
「…………」
しばらくそのままの体勢で止まっていた二人が、同時に笑顔になる。
「兄さん!! よく無事で!!」
「ドモン! お前も―――」
二人を包む空気が、一気に和やかなものになった。ドモン、と呼ばれた青年が、キョウジに甘えるように抱きつき、キョウジもそれに応えるように抱擁したり、軽く小突いたりしている。
(―――弟がいたのか……)
キョウジの表情が、今までに見たことも無いような親しい色を帯びている。その表情だけで、キョウジが、ドモンの事をどれだけ大切に想っているかが分かる。
(もしかして、彼が勾玉の持ち主か? ―――いや、それにしては……)
そう考えるには、キョウジの反応がおかしすぎる。もしも、勾玉を持っているのがこの弟なら、キョウジは「命かけて守りたい」と思いこそすれ、「共に死にたい」と、願うだろうか。
「…………」
ハヤブサは口の中で文言を唱え、印を結んでドモンの中から勾玉の気配を探ろうとする。しかし。
「―――おい! お前さっきから何やってるんだ? 人の事をこそこそ探るように……」
「―――!」
先ほどまでキョウジにじゃれるようにしていたドモンが、いきなり自分の間合いに入ってきたのでハヤブサは驚いた。ドモンから目を離したのは、文言を唱え、印を結んだその一瞬だけだ。その僅かな隙を突かれたということになる。
「あ……いや、これは……」
この男、かなりできる―――そう思いながら、ハヤブサは少し身を引いた。今、キョウジの弟と、事を構える気はないからだ。
だが、ハヤブサの声を聞いた途端、今度はドモンの方が、何だかおかしな表情をしだした。ハヤブサの方をじ~っとみていたかと思うと、今度はおもむろに、キョウジの方に振り返る。
「おい―――『シュバルツ』」
(シュバルツ!?)
ハヤブサが、キョウジの方を見る。
「何だ?」
「シュバルツ」と、ドモンに呼ばれたキョウジが、普通に返事をしている。それからハヤブサの方をちらっと見て、すまなさそうな笑みを浮かべた。
(どういうことだ…? 「キョウジ」じゃないのか? て、言うか偽名だったのか!? いや、姿かたちはどう見てもキョウジ・カッシュの物だし、顔だって髪だって、変装ではなかったし……)
ハヤブサが混乱している横で、ドモンもまた混乱していた。
(おかしい……! 兄さんとこの男の声が、全く同じ様なものに聞こえる……!)
「シュ、シュバルツ……こいつは一体…?」
「ああ、こちらは『リュウ・ハヤブサ』といって―――」
「リュウ・ハヤブサだ」
ハヤブサが、多少不機嫌な響きをを含んだ声で答える。それを聞いたドモンが、頭を抱えて唸りだした。
「おい、ドモン? どうした?」
シュバルツがドモンに声をかけると、ドモンが何かブツブツ小さな声で呟いている。
「に……兄さんの声が、サラウンドステレオ……」
「ああ……」
(特に気にはしなかったんだけど、そんなに似てるかなぁ?)
ちらり、と、ハヤブサの方にシュバルツが視線を走らせると、ハヤブサが、ものすごく殺気だった目で睨み返してきた。
「おい! キョウジ―――いや、シュバルツか?」
「―――な、何だ?」
ハヤブサの殺気に押されるように、多少引き気味に返事を返すシュバルツ。
「どういうことだ? お前、『キョウジ』じゃなかったのか?」
「あはは……『キョウジ』じゃ無いわけじゃないんだけどね。微妙に違うというかなんというか……」
「? ―――どういう、ことだ?」
「まあ、見てもらった方が早いと思って……。ちょっといろいろややこしい事情が……」
「…………」
じ~っとハヤブサは無言でシュバルツを見ていたが、やがて、口を開いた。
「おい。お前、こんな調子で後いくつ俺に隠し事をしている?」
「え? え~っと……」
そう言いながらシュバルツは、ハヤブサから思いっきり視線を逸らしている。
(隠している事が、まだあるのか……)
ハヤブサは、ため息と共にシュバルツを睨むのを止めた。今、強引にすべてを聞き出そうとしても、絶対に話してはくれないだろう。
「―――まあいい。無理に聞こうとは思わん」
「そうか?」
そうしてくれると助かる―――と、言わんばかりの微笑みを、シュバルツから向けられる。それを、ハヤブサは思いっきり睨み返した。
(聞こうとは思わんが―――探らない、とも言っていない!)
そう、ハヤブサは腹を立てていた。
いきなり、あのような容赦のない闇と、その深淵で孤独に微笑む彼の姿を見せられてしまったのだ。これから先も、この男がずっとそのままで生き続けていくのかと思うと、何故か無性に腹が立った。
(見てろ―――! 絶対にお前の根源を探り当ててから、抉るように一発ぶん殴ってやる!!)
ハヤブサはそう決意して、シュバルツについて来ていた。
(やばい……ハヤブサが、何だか怖い……)
ハヤブサから放たれる殺気から何とか逃れようと、シュバルツはドモンに声をかけた。
「おい、ドモン。―――おい!」
「う~ん、う~ん………あっちからもこっちからも、兄さんの声が……! ここにキョウジ兄さんまで加わってくると、トリプルサラウンドシステム……!」
ドモンが、まだ何かブツブツ言っている。シュバルツはため息をついた。
「―――おい、ドモン。いい加減立ち直ってくれないと、ここにハヤブサを呼んで来て、お前の耳元で輪唱するぞ」
「そ! ソレダケハ勘弁シテクダサイ!!」
ドモンが、心底怯えたように耳を塞ぎながら飛びのいた。それを見て、シュバルツは苦笑する。
「冗談はともかくとして、キョウジは今どこにいる? こちらはキョウジに会いたいのだが」
「キョウジ兄さんに? じゃあ、そっちのハヤブサって人は一体…?」
「ハヤブサは、『龍の勾玉』の関係者だ」
「『龍の勾玉』の―――!?」
ドモンの顔が、一気に正気を帯びたものに戻っていく。
「わ、分かった……。兄さんは今、師匠の隠れ家にいる……」
こっちだ、と、ドモンは二人を案内する。だが何故か、得体の知れない不安に襲われた。来るべき物が来た、と、感じてしまった。
(兄さん……大丈夫、だよな……?)
自分の想いが天に届く事を、ドモンは祈るしかなかった。
隠れ家についたシュバルツ達を、まず東方不敗が出迎えた。
「久しいな。シュバルツ・ブルーダー」
「お久しぶりです。マスター・アジア」
一瞬、二人の間に青い火花が バチッ! と、音を立てて飛び散る。しかし。
「やめよう。今は、敵同士というわけでもない」
そう言って東方不敗がにやりと笑うと、それもそうですね、と、シュバルツも笑って肩の力を抜いた。
(キョウジが武道を極めた姿がこ奴―――と思えば、悪くないのだが……。やはり、ワシはこ奴が、どうも苦手だわい)
「デビルガンダム事件」の際、東方不敗はシュバルツに、自分の大望をさんざん邪魔された経歴を持つ。なので、シュバルツの顔を見ると、どうしても苦手意識が、ちらり、と頭をもたげてくるのである。
(キョウジの方にはそう感じはせぬのに……。やはり、これもこ奴の腕が立つゆえの物なのか―――)
そう思いながら、ふと東方不敗は、シュバルツの後ろに黒の忍者が佇んでいる事に気づく。
「ところでシュバルツ。お主の後ろに居る男は何者だ?」
「ああ、彼はリュウ・ハヤブサと言って―――」
その名を聞いた途端、東方不敗は驚きの声を上げた。
「リュウ・ハヤブサ……。何と! 『龍の忍者』か!」
東方不敗が驚いている横で、ドモンがきょとん、とした顔をしている。
「師匠、何をそんなに驚いているんですか?」
「ドモンよ……。奴こそ、伝説とうたわれる『龍の忍者』だ。一説によると、神をも滅する力があると言う。噂には聞いておったが、実際に存在しておったとはな……」
「龍の、忍者……」
(へぇ……神をも滅する、ね……)
まるで値踏みでもするかのように、ドモンはハヤブサを見る。
ドモンの視線を受け止めながら、ハヤブサも口を開いた。
「こちらも、噂を聞いた事がある。東方不敗マスター・アジア……。『キング・オブ・ハート』だな」
「ほう、あまり知名度の無いシャッフル同盟を知っておるとは、さすが、情報通の忍者と言ったところか……。だが、ワシは先代だ。現キング・オブ・ハートは、こちらに居るドモン・カッシュよ」
東方不敗に紹介されて、ドモンがずいっとハヤブサの方に進み出る。
「ドモン・カッシュだ」
そう名乗った後、彼はハヤブサに対して不敵な笑みを浮かべた。
「神をも滅する力のある伝説の忍者……ぜひ、お手並みを拝見したいね」
「…………!」
ドモンの、挑発的ともとれる物言いに、ハヤブサの眉がピクリ、とつり上がる。
「―――お望みとあらば」
バチバチバチッ! と、二人の間に青い火花が無数に飛び散る。このまま何かきっかけさえあれば、すぐにでも戦いが始まる様相を呈してきた。だが、次に訪れたきっかけは、二人の戦いを止めるものであった。
「シュバルツが来たのか?」
そう言って、キョウジがひょこっと顔を出す。
「兄さん」
「キョウジ」
ドモンとシュバルツが、同時にキョウジの方を見る。ハヤブサもそちらの方に顔を向けて―――そのままの姿勢で、固まった。
「――――ッ!」
シュバルツが、キョウジの方に歩み寄る。
(何だこれは―――!!)
そこにいたのは、寸分違わぬ同じ人間だった。シュバルツがキョウジと同じ格好をしているから、余計にそう感じられた。
いや、微妙な違いはある。シュバルツの方には、忍び独特の目の配り方、身体の使い方がある。そして、少し体格がいい。「キョウジ」の方にはそれが無い。それにしても……これは……。
(馬鹿が二人に増えた……)
いや、そうじゃなく―――そうじゃなくて。
「シュ、バルツ……」
目の前に繰り広げられている、あまりにも異様な光景に、ハヤブサは己が声が上ずるのを感じる。
「これは……どういうことだ……?」
「あ……その……」
ハヤブサの問いかけに、シュバルツが歯切れの悪い返事を返す。
(どうする? どこまで話すべきなんだ?)
ハヤブサに真実を話すなら、今しかないと感じる。自分は、キョウジに作られたアンドロイドなのだと。
だがそれを話してしまうと、もう自分はハヤブサに、嘘をつきとおせなくなる、とも感じていた。きっと自分は、なし崩し的に、キョウジの死が自分の死につながる事を、隠す事が出来なくなってしまうだろう。そうなってしまうと、ハヤブサに、それこそ余計な苦しみを与えてしまうことにもなりかねない。それだけは、シュバルツは何としても避けるべきだと思った。。
ただ、ハヤブサに対して嘘を重ねていくことに、良心の呵責を感じるのも、また事実だ。
(どうする―――どうしたらいい……?)
「…………」
(シュバルツ?)
珍しくシュバルツが迷っている気配を感じて、キョウジが顔を上げる。異様な沈黙が一瞬その場を支配したが、東方不敗がそれを打ち破った。
「そっくりであろう? 彼らは双子の兄弟よ。兄の方が武道、弟の方が学問に精通しておる」
「…………!」
東方不敗のその物言いに、シュバルツが驚いて東方不敗の方を見る。すると、東方不敗がドモンの方を見ながら、シュバルツに目配せを送ってきた。
(余計な事を言うでない)
東方不敗の目が、彼にそう合図を送ってきている。
「――――!」
(ドモン……! そうだった……)
ドモンは、シュバルツが自分の事を「コピー」とか「アンドロイド」ということを、ちらっとでも言おうものなら、それこそ烈火のごとく怒ってくる。こんな時に、余計なトラブルを持ちこむな―――と、東方不敗は言いたいのだろう。
「…………」
シュバルツは、沈黙を選択せざるを得なくなった。
「うん――――二人とも、俺にとっては大事な兄さんだ」
東方不敗の言葉に、ドモンが満足そうに頷いている。彼は本当に、心の底からそう思っているのだろう。
ただハヤブサは、東方不敗の「双子」の言に、まだ納得できていなかった。
双子―――双子か? 本当にそうなのか?
双子にしては、あまりにも違いが無さ過ぎやしないか?
それとも双子とは―――そういうものなのか?
「……………」
ハヤブサは、無言でキョウジを見やる。
(こいつも、馬鹿なのだろうか)
迫りくる白刃を、あっさり笑って受け入れるような―――そんな、馬鹿なのだろうか。そんな馬鹿な人間が、そう何人も存在するのだろうか。
シュバルツから漂う気配と、キョウジから漂う気配。それが、全く同じ物でさえなければ、ハヤブサもすんなり双子と納得できただろう。だが、この気配は―――彼らが同一人物である可能性すら、示唆している。
(嘘だろう…?)
何かの冗談だと思いたかった。魂のレベルで似ている双子が、この世に存在するのだろうか。
「お前が本物の『キョウジ』か? ちょっといいか―――」
ハヤブサが、キョウジの方に進み出る。
「? 何でしょう」
キョウジが、ハヤブサの方に向き直る。ハヤブサは、キョウジの目の前で文言を唱え、印を結んだ。
ポウ……。
ハヤブサが手をかざすと、キョウジの胸のあたりに白く光る輝きが現れる。
「勾玉―――!」
「!!」
ハヤブサの小さいが鋭い叫びに、全員が反応する。
「ここにあったのか………!」
キョウジが、その所在を確かめるように、シャツをはだけて己の胸を見る。信じ難い事だが、確かに自分の内部から、その光は漏れ出ていた。
「おい、お前―――!」
ハヤブサが振り向くと、ドモンが食い入るようにこちらを見つめている。
「そんなことが出来るってことは、『龍の勾玉』について、何か知っているんだな? シュバルツが言っていた通り、お前は勾玉の、関係者なんだな?」
「そうだ。勾玉は……俺の里の物だ」
「じゃあ……じゃあ、教えてくれ! こいつの正体は、いったい何だ? これを持っている兄さんは、いったいどうなる? 兄さんを、助ける事は出来るのか!?」
「――――!」
ドモンのその言葉に、ハヤブサは咄嗟に返事をする事が出来ない。
「ドモン! ひとまず落ち着け。性急すぎだ―――」
シュバルツが、ドモンとハヤブサの間に割って入る。そんなハヤブサとシュバルツの表情と動きを見た東方不敗には、ピン、と来る物があった。
(―――あまり良くない事なのだな!?)
「ハヤブサとやら―――構わん。総てを話せ」
壁際にもたれかかって腕を組んで立っている東方不敗が、そう言い放った。
「いや、しかし……!」
シュバルツがドモンの方をちらっと見ながら、東方不敗に反対してくる。よほど悪い事なのだろう。それも、ドモンには出来れば聞かせたく無い程の―――。
「構わん。潮時だ。黙っていた所で、いずれはばれる」
「…………!」
東方不敗の言葉に、一同は沈黙を余儀なくされた。
「さあ、さっさと話さんか」
東方不敗が、再びハヤブサを急かしてくる。
「―――分かった。では……」
ハヤブサは、語りだした。慧信という一人の男から始まった、800年にも及ぶ勾玉の歴史を―――。
「―――以上が、里に伝わる、『龍の勾玉』に関するすべてだ」
ハヤブサは、長老から伝え聞いた勾玉の話を、余すところなく一同に伝えた。
「……………」
部屋に、重い沈黙がのしかかってくる。
「……待て……」
一番最初にそれを破ったのは、途中からピクリとも身動きをしなくなったドモンであった。
「……待て……待て……待てよ……! つまり、勾玉を持つ者は、化け物に取り込まれる………?」
「そうだ」
よく分かっているじゃないか―――と言わんばかりに、ハヤブサは肯定した。
「…そうなったら、たくさんの人が死ぬから……に、兄さん、は……」
ここまで言い終わった時、ドモンの握りしめた拳がぶるぶると震えだした。
「……それを、防ぐため、に……? そ、の、身を、炎、で……焼―――!」
ドモンは、目の前が真っ赤に染まるのを感じた。
見える。
躊躇う事無く、あっさり炎に身を投じる、兄の姿が。
見たくなくても、見えてしまう―――!
「……そうだな。そうやって勾玉を回収する。それが、俺の『使命』だ」
ハヤブサの、その冷静すぎる物言いに、ドモンの闘気が ドン!! と、音を立てて一気に膨れ上がった。
「………ふざけるな……! ふざけるな!! ふざけるなッ!!! 兄さんが、お前たちの里に何をした!? 全く無関係じゃないか!!」
「そうだな」
ドモンが怒り狂う様を、ハヤブサは冷静に見ていた。
「それなのに、勾玉を勝手に世に出して、勝手に兄さんの身体に入れて―――!!」
「ドモン、それは違う―――!」
ドモンの怒りに筋違いな物を感じたキョウジは、ドモンを止めようとした。
「その人は言っていたじゃないか! 隼の里の人たちは、封印を守ろうとしたと…! 子供を犠牲にまでして―――!」
「兄さんはちょっと黙っててくれ!!」
ドモンは、自分の肩に置かれたキョウジの手を乱暴に振り払った。ただ、怒りにまかせてそれをしてしまったため、いつもの加減が出来なかった。
「うわっ……!」
振り払われたキョウジが、身体ごと吹き飛ばされ、壁に叩きつけられそうになる。
「キョウジ!!」
寸前の所で、シュバルツがそれを防いだ。それを見たドモンが、一瞬心底怯えた、子供のような目になる。
「ご、ごめん。兄さん…! ごめん―――」
「ドモン……」
シュバルツに支えられたキョウジが、顔を上げる。
「でも俺……。納得、出来ないよ! こんなの、全然…納得できないよ!!」
「奇遇だな。俺も―――全然、納得など出来ないよ」
混乱して頭をふるドモンに、ハヤブサの挑発的な物言いが被さる。
「貴様―――!!」
ギリ、と、歯ぎしりしたドモンが、悪鬼のごとき形相でハヤブサを睨みつけてくる。
(何だ。こいつはちゃんと怒るじゃないか。こいつまであっさりいろいろ受け入れる馬鹿だったら、本当にどうしようかと思った―――)
ドモンを見ながらハヤブサは思った。大事に想っている人間に、いきなりこんな理不尽が舞い降りてきたら、普通は許せないと思うし、納得もできない。怒り狂って、当たり前なのだ。それが、普通の反応のはずだ。
それなのに―――あのシュバルツの反応。あれは、やっぱりどう考えてもおかしすぎる。
何なんだ。あいつは。
本当に一体、何なんだ。
そして、シュバルツと瓜二つのキョウジ―――。
あれが、俺が今回『斬らねばならない標的』だという―――!
何なんだ、これは。
これは、悪い夢だ。
悪夢すぎて、逆に、笑える―――。
「何か無いのか!? 焼くとか、殺す以外で、勾玉を身体の外に出す方法が―――!!」
「―――ははっ! あれば俺が、それを教えてほしいぐらいだ!」
「…………!!」
見る間に、ドモンから放たれる殺気が、膨れ上がっていくのが分かる。
(な、何でこの二人が戦う必要がある? 止めないと……!)
キョウジは強く思った。ここで起こるこんな戦いに、何の意味があるというのか。
「ドモン……」
ふらり、と、キョウジが二人の間に入っていこうとするのを、シュバルツが止めた。
「止めておけ……お前が死ぬぞ」
「シュバルツ―――!」
「今止めに入った所で、お前に何ができる?」
「――――ッ!」
正論だ。そう感じて、キョウジはギリ、と、歯を食いしばる。
確かに自分では、もうああなってしまったドモンには、触れることすらできない。さっきみたいに、吹き飛ばされるのが落ちだろう。
「ならばシュバルツ、貴方が―――!」
そう言いながら振り返ったキョウジに、シュバルツは哀しげな目を向けた。
「すまない、キョウジ……。私には、ドモンとハヤブサ、二人の気持ちが分かる―――。だから、止められない」
「…………!」
ドモンは、まっすぐ『キョウジ』を想うが故に。
ハヤブサは、己が背負う使命の理不尽さに納得が出来ないが故に。
二人の想いは、おそらく一緒なのだ。二人とも、ただ一つの事しか願っていない。たが、それを叶える事が非常に困難な事を、二人ともが理解してしまっている。
それが苦しくて、やるせなくて―――ただ、吐きだしたい。それだけなのだ。
そして、二人の願いと自分の願いが、同じであるという事も、シュバルツは知っていた。だから、止められない。自分と同じ想いの二人を、止めることなど出来ない。
「ただ……このまま二人がぶつかると、ハヤブサが勝つ」
「―――!」
シュバルツの言葉に、キョウジの顔色が変わる。
「ドモンが怒りに呑まれているのに対して、ハヤブサの方が、まだ冷静だ。このままでは、戦う前から結果が目に見えている」
「…………!」
「問題は……あの状態のドモン相手に、ハヤブサがどれだけ手加減できるか―――ただ、それだけだな」
「ドモン―――!」
キョウジが、またドモンの方に足を進めようとする。
「キョウジ……!」
それを、シュバルツは懸命に止めた。キョウジには、生死を選ぶ権利がある。だけど今、こんなふうにこんな所で、死んでほしくは無いと思った。
「この―――!」
ドモンが怒りにまかせて、戦いへと足を踏み入れようとする。その瞬間。
「ドモン!! この馬鹿弟子がぁ!! ちょっとこっちへ来んか!!」
今まで沈黙を守ってきた東方不敗が、大声で怒鳴りながら、ドモンの首根っこを掴んだ。そのまま彼は部屋の外へとドモンを引きずっていく。
「師匠!? 何をする!? くそっ! 離せ!! 離せ―――ッ!!!」
抵抗するも師匠にかなうはずもなく、むなしくドモンが部屋の外へと消えていく。戻ってきた静寂に、キョウジとシュバルツが、同時にほっと息をついた。
(―――あのまま弟に、俺は殴られてもよかったのに……!)
ハヤブサも、苦い息を一つ、ついた。
そんなハヤブサに、キョウジがそろそろと近寄っていく。
「あの……ハヤブサ『さん』?」
「ハヤブサでいい」
呼び捨てにすることを遠慮したキョウジに、ぶっきらぼうに意思を伝える。
「あの……ありがとうございました。勾玉の、貴重な話を―――」
キョウジはそう言って、ハヤブサに手を差し出してくる。
「――――ッ!」
それは、隼の里の長老に向かって頭を下げたシュバルツと、全く同じ様なものに見えた。それが故に、ハヤブサは、キョウジの手を パン! と、払いのけた。
「勘違いするな! 俺は貴様を斬りに来たんだ!」
「―――!」
「慣れ合いなどせん!」
そう言い置いて、ハヤブサも部屋から出て行った。
「…………」
キョウジとシュバルツの二人だけになって、部屋がしばし沈黙に包まれる。
キョウジは、払われた手を抑えたまま、じっとその場に佇んでいた。
「キョウジ……」
シュバルツは、そっと呼びかけてみる。一気にいろいろな事が、キョウジの身に重なりすぎている。いくら飽和力があるキョウジでも、さすがに限界が来ているのではないかと、心配だった。
シュバルツの呼び掛けに気がついたキョウジが、振り返る。
「あはは……嫌われちゃったよ」
払われた手をひらひらさせながら、キョウジは苦笑している。その表情に、全く暗い影が宿っていなかったので、シュバルツは少し拍子抜けした。
「……あれで、優しい男なんだがなぁ……」
シュバルツもキョウジにつられるように苦笑しながら、ハヤブサの事をそう評する。
「へぇ~……お前にそう言われるんじゃ、よっぽどだね」
キョウジのそのからかうような物言いに、シュバルツは少しムッとする。
「―――人の事、言えるのか?」
「そうだっけ?」
「そうだ。私の元は、お前だろう」
「あははは……」
ばれたか、と、キョウジがいたずらっぽく笑う。シュバルツは、やれやれ、と、ため息をついた。
「キョウジ……これから、どうするんだ?」
キョウジのいつもと変わらない態度に安心しつつも、シュバルツは問うた。彼には、過酷な現実が突きつけられている。キョウジは、決断を下して選ばねばならない。
「う~ん……覚悟を決める事は決める事として……とりあえず……」
「とりあえず?」
「……実験かな。せっかく勾玉の位置が分かった事だし―――」
(じ、実験!?)
シュバルツは、己の耳を疑った。この期に及んでこの男は―――いや、この期に及んでいるからこそ、実験を選択するのか…?
「あそこをああして……あれを使って……」
ブツブツ言いながら、キョウジはもう駆け出している。
「ごめん! シュバルツ。また後で―――!」
キョウジも、あわただしく部屋を出て行った。
一人になったシュバルツは、ため息をつきつつ苦笑する。
(やれやれ…。この状況でもいつも通り…。キョウジは、恐ろしくタフだな……)
そのタフさ―――本当に、自分の分身なのかと疑いたくもなる。
ただ、キョウジは、「覚悟を決める」とも言っていた。やはり、自分の『死』を選択肢の一つに選んでいるのだろう。
(存分に、最後まで生き抜け、キョウジ……。どうなろうとも、私はついて行くから―――)
とりあえず、服を着替えるか、と、シュバルツもこの部屋から出て行った。
そして部屋は、無人の静けさに覆われて行った―――。
ガンッ!!
隠れ家から外に出たハヤブサは、手近にあった岩を、思いっきり殴った。その衝撃で岩が穿たれ、ハヤブサの足元に、無数の小石や砂が降り注いでくる。
結局、俺は斬らねばならないのか。
「斬りたくない」と、あれほど願った人間と、同じ魂の持主を。
結局―――斬らねばならないのか!
性質の悪い冗談だと思った。夢なら覚めてほしいと願った。
シュバルツが「守りたい」と願っていた人間が、あれほどシュバルツと似た魂の持主だとは思わなかった。あんな馬鹿な人間、この世に二人といない、と思っていたのに―――。
勾玉の話を聞いた時のキョウジの反応が、シュバルツの時と全く同じだった。己の身に降りかかる不幸よりも、周りの事を先に心配して……。
(だからなのか? 魂が似通っているから、片方が死んでしまったら、もう片方はもう生きていけないほどのダメージを、受けるのか……?)
でも、それはおかしい。いくらダメージを受けたからといって、生きていくのをあきらめてしまう理由にはならない。生きる事を、選択できるはずだ。
それとも、双子だから、一蓮托生だとでもいうのか? そういう、ものなのか…?
「…………」
考えれば考えるほど、混乱してくる。
片方の名前が「キョウジ」なのに、もう片方の名前が「シュバルツ」と言う、明らかに国籍の違う名前を名乗っているのも、おかしな話だ。まあ、シュバルツは忍者だから、本名とは違う「通り名」を使っている可能性も、否定はできないが。
まだ、何かがある。「双子」では片づけられない、何かが―――。
できればそれを調べたい。調べたいが―――おそらく、あまり時間も残されてはいない。「化け物」が、勾玉を宿したキョウジを取り込みに動き出したら、そこでタイムオーバーだ。自分は―――キョウジを斬らねばならなくなる。
(シュバルツ―――何故、俺をキョウジの元に連れてきた……。そして―――何故俺は、『人斬り』なんだッ!!)
ドンッ!!
渾身の力で打ち込まれたハヤブサの正拳が、先ほどの岩を、今度は完全に粉砕する。だが、空しい。こんな事が出来た所で、「斬りたくない」という願い一つすら、自分は叶える事が出来ない。破壊にしか、殺しにしか使えない力に、何の意味があるというのだろう。
「……………」
拳を握りしめて佇むハヤブサの姿を、夕陽が赤く照らし出していた。
その頃ドモンも、東方不敗によって隠れ家から外に連れ出されていた。その身体を、乱暴に地面に放り出される。
「何をする師匠!! 何で戦いを止める!?」
激昂するドモンに、東方不敗はやれやれとため息をつく。
「阿呆が。簡単に、前後の見境が無くなりおってからに……」
「何ィ!?」
「では問うが―――あの龍の忍者を責め立てた所で、何か状況が変わるのか!?」
「――――!」
東方不敗の言葉に、ドモンは二の句が継げずに絶句する。
「そうすれば、兄上の身体から、『龍の勾玉』が消えるとでもいうのか? 兄上の命が、助かるとでもいうのか!?」
「―――ッ! それは……!」
「おまけにドモン…。お主、兄を守るどころか、殺しかけたな?」
「!!」
ドモンの脳裏に、自分が腕を振っただけで、簡単に飛ばされてしまった兄の姿がフラッシュバックする。
「シュバルツが居ったから良かったようなものの……誰を守らねばならんのかすら分からんようになる―――それを、前後の見境が無いと言わずして、何という!?」
「うるさい!!」
ドモンは、思わず大声を張り上げていた。
「あんたなんかに、何が分かる!!」
「フン―――お前が、どうしようもない馬鹿弟子だという事は分かるぞ」
そう言いながら東方不敗は、ドモンを ドカン! と、蹴り飛ばす。
「ほれほれどうした! かかって来んかぁ!!」
「うっ……くそっ……!」
蹴られた瞬間、口の中を切った。それを手でぬぐいながら、ドモンは立ちあがる。
「あんたなんかに……あんたなんかに……! 何が分かるっ!!」
ブンっと拳を力任せに振るう。しかし、そのような拳が東方不敗に当たるはずもなく、逸れて空しく地面を穿った。
「ちくしょう!!」
何としても、師匠を一発殴るつもりで、ドモンは東方不敗に向かって、無数の拳撃を繰り出す。しかし、ただの一発たりとも、東方不敗を捉える事が出来ない。それどころか、僅かな隙を突かれて反撃され、ドモンは再び吹っ飛ばされた。
それでもドモンは、攻撃する事を止めない。何度も何度も東方不敗に挑み、吹っ飛ばされる事を繰り返した。
「何で……! 何で―――!!」
空振りする拳を、何度も突きだす。
「兄さんは…! デビルガンダムに取り込まれて! 死にかけて―――!!」
思い出す。あの時、自分は兄を殺す直前まで行った。でも、奇跡的に助けられた。兄は病院へ収容された。
しかし、意識がなかなか戻らない。自分は、時間が許す限り、毎日病院へと足を運んだ。
意識が戻ったこと自体が、奇跡だと言われた。
それからの兄は、ゆっくり、だが確実に回復して行った。苦しいリハビリにも耐え抜いた。
「やっと……やっと、普通に生活できるまで回復して……! 前みたいに、笑ってくれるようにもなって……ッ!」
いつの間にかドモンは、滂沱の涙を流していた。
「本当に―――何もかも、これからって時じゃないか!! なのに……!」
「…………」
東方不敗は、ただドモンを見守った。
「何でこうなる!? 何で、兄さんばっかり―――!!」
ドモンがそう言って拳を振るうたびに、東方不敗の周りの岩が破壊される。
勾玉をその身に宿してしまった兄は、このままでは生きる事は許されない。化け物に取り込まれるか、それを防ぐために自ら死を選ぶか―――。その、どちらかしかない。
「デビルガンダム事件」から、やっと生還したばかりだというのに、今度は勾玉―――運命はどこまでも兄を死へと誘わずにはいられないようだ。
まるで「お前は大罪人だから、生きていてはいけない」とでも言わんばかりに。
確かに、あのガンダムを開発したのは父と兄だ。しかし、それを悪意を持って利用しようとしたのは、他の連中だ。それを防ごうとして、結果的に取り込まれてしまった兄は、純粋な被害者じゃないのか?
それなのに、暴走したデビルガンダムが刻みつけた『罪』は、兄の『罪』なのか!?
DG細胞を発見したというだけで、強大な力を持つガンダムを開発したというだけで―――それすら、兄の『罪』なのか!?
その『罪』は、そんなにも重いのか? もう生きることすら、許されないほどに……!
理不尽だ。
あまりにも、理不尽だ。
「どうして―――!! 兄さん……! 何でだ……ッ!!」
ドモンは、もう立っていられなかった。東方不敗の姿すら見ず、ただ、己の拳を地面に叩きつけ続けた。
兄は、デビルガンダムに取り込まれるという極限の状況の中でも、己の身を省みる事無く自分を助けてくれた。
だから、今度は自分が助けたいのに。
今度こそ、兄に報いたいのに。
なのに、その手段が分からない。
自分は、強くなったはずなのに―――何で、こんなに無力なんだ……ッ!
「兄さん……ッ! うわあ……!! あ……あ……!!」
後は、言葉にすらならなかった。ただ、哀しすぎる嗚咽が、辺りに響いた。
「ドモンよ……」
東方不敗がドモンにそっと近づき、声をかける。
「泣くなとは言わん……怒るなとも言わん。存分に泣いて良い。怒って良い―――。ただ……今だけにしておけ」
「……何…で……」
「お主がそのように動揺しておっては―――兄御はまた、お主に何も言えなくなってしまう」
「――――!」
「何も言わせないまま、逝かせてしまってよいのか?」
ドモンの動きが、一瞬止まる。だがすぐに、彼は頭をふった。
「……いやだ…。俺は嫌だ! 兄さんが死ぬのを手伝う事だけは、絶対に嫌だ!!」
「ドモン―――」
「そんな事を兄さんの口から聞くぐらいなら、何も言わせたくない! 兄さんだって『死にたくない』って言っていたのに―――!!」
「まだ、死ぬ―――と決まったわけではなかろう」
(気休めだ―――)
言いながら、聞きながら、東方不敗とドモンは同時に思った。今のままでは、キョウジはあっさりと死を選んでしまう確率が非常に高い。他に有効な手立てがなければ、彼は迷いなくそうするだろう。
そして、自分たちでは、キョウジの死を止めるだけの手段を持ち合わせていない。これが、現実だ。
ただ、キョウジは、ずっと独自に勾玉の事を調べていた。それは、決して自分が『死』を選ぶための行動ではないはずだ。それに、賭けてみるしかないのか。それとも―――。
「とにかく、我らはキョウジを支えるだけだ。奴に死を選ばせぬ道も、もしかしたらあるやもしれん。それなのに、そのように泣いておっては……支える事も、出来ぬであろう?」
「し、師匠……!」
そう言ったきり、ドモンはまた俯いて泣き始めた。涙が、後から後からこぼれていた。
東方不敗は、そんな愛弟子の震える肩に、ポン、と手を置いた。それ以上に、慰める術を、自分は知らなかった。
(キョウジよ……そなた、どうするつもりなのだ。まさか、この戦いを、このまま終わらせるつもりではあるまいな……)
キョウジは、今死なせるにはあまりにも惜しい若者だ。それだけに、今、未来が閉ざされつつある現状に、東方不敗は息苦しさを覚える。
キョウジの真意を、確かめなければならない。たとえ僅かでも、「生きる」という意志を示しさえしてくれれば、こちらも迷いなく手が貸せるだろう。例え、全世界を敵に回すようなことになったとしても。
だが、万が一、死ぬ決意を固めていたら、どうするべきか。
「…………」
いつの間にか、ギアナ高地を夜の帳が包み、満月に近い月が、上空に顔を出していた。
何故、こんな時に見上げる月は、必要以上に美しいのか―――。
東方不敗は月明かりを浴びながら、ふと、そんな事を考えていた。
夜更け。
いつもの革のロングコートに着替えたシュバルツは、隠れ家からほど近い所にある大きな木の上で軽く己の身体を休めていた。そんなシュバルツの様子を、少し離れた所から、ハヤブサが見ていた。時間が無いのは百も承知だが、探らずにはいられなかった。
あまりにも似すぎている双子―――。しかし、「双子」では片づけられない何かが、彼らにはあるはずと確信している。このまま、何もかも納得できないまま、キョウジを斬りたくはなかった。
(あまり斬るべき対象を、調べるべきではないのだろうが……)
今の時点では、自分はキョウジを斬るしかない。だから、必要以上にキョウジの事を知りすぎるのは、任務を遂行する上では支障にしかならない場合がある。
だが、それでも―――。
「!」
ふと、隠れ家から誰かが出てくる気配を感じて、ハヤブサは身を潜めた。
出て来た人間は、まさにターゲットのキョウジだった。どうやら、シュバルツと接触するつもりらしい。好都合だと思った。
しかし、何か足取りがおかしい。時々、ふらついているようにも見える。
「…………」
彼は無言で、シュバルツが休んでいる木の下まで迷いなく歩を進めると、そこで立ち止まり「シュバルツ、いるんだろ?」と、声を出した。だが、シュバルツが下りてくるまで、彼はその体勢を保つ事が出来なかった。
「――――ッ」
ふら、と、キョウジの身体が倒れようとする。
「キョウジ!」
間一髪、シュバルツの支えが間に合った。
「ありがとう……助かった……」
そう言いながらキョウジは自力で立とうとするが、再び崩折れそうになる。それを支えながらシュバルツは、キョウジの身体が異常に熱を帯びている事に気がついた。
「お前―――熱が……」
シュバルツの指摘に、キョウジは苦笑する。
「大丈夫か?」
「大丈夫―――と、言いたいところだけど……これは、さすがに、ちょっときついな……。悪い……下ろしてくれ……。流石に、起きていられそうにない……」
シュバルツがそっとキョウジの身体を地面に横たえると、キョウジは、ほっと、小さく息を吐いた。
「―――何を、やった?」
先ほどまで元気に走っていたキョウジが、いきなりこの高熱。色々原因は考えられるが、主な原因は、やはり―――。
「ちょっと、ね……。でも、私の生命維持レベルに、支障は来たしていないはずだよ……」
「…………!」
キョウジの言葉に、シュバルツは思わず絶句する。
「それとも、シュバルツ……。お前の方に、何か……支障が出てるか…?」
「いや……」
特にそういう事は無いので、否定のために頭を振る。
「そっか……良かった……」
それを見たキョウジが、にっこり微笑んだ。だが、額から汗が流れ、息づかいも辛そうだ。
(こんな時に―――私の事まで気を使っている場合ではないだろう、キョウジ……!)
「キョウジ―――何を、やった?」
シュバルツは、もう一度キョウジに問うた。キョウジの身体がこんな状態になっているという事は、何か、命に危険が及ぶ際どいレベルでの実験を、行ったに違いないのだ。だが、その問いに、キョウジはきちんと答えを返さなかった。
「ごめん……。まだ、はっきりした事は、言えないんだ……。確認、しないと……」
「…………」
(知的分野はキョウジの方に任せて、自分はあまり口を出さないようにしてきたが―――流石に今回ばかりは、付き添っていた方が良かったか……?)
そういう事を感じて、シュバルツは己の拳を握りしめる。何をやるかを見ていれば、少なくとも、無茶な実験をしようとするのを、止めることぐらいは出来たかもしれない。
「とにかくキョウジ―――そんな身体でここにいては、ますます悪くなる。部屋まで運ぼう」
そう言って、シュバルツがキョウジの身体を持ちあげようとするのを、キョウジが止めた。
「待ってくれ、シュバルツ……! お前に、話があるんだ……!」
「話……?」
こんな体調で苦しそうなのに、それを押してまでの話とは―――。
「部屋とか……明日とかではだめなのか?」
シュバルツのまっとうな質問に、キョウジは苦笑した。
「布団に入っちゃうと、私は寝てしまうし……ドモンにも、聞かれたくない―――」
「――――!」
「ドモン、は……?」
「東方不敗と一緒にいる。―――大泣きしているぞ」
「……そう、か……」
それを聞いたキョウジは、哀しそうに笑った。
「私の事で……そんなに、悲しまなくても……いいのに……」
「キョウジ―――」
何故か、シュバルツの胸が痛んだ。キョウジの気持ちも、ドモンの気持ちも―――分かり過ぎるぐらい、分かるからだろうか。
「シュバルツ……多分、私にはもう、時間も、そんなに残されていない……」
「―――!」
「お前も……勾玉の話を聞いて、分かっただろう…? 勾玉が、私の身体に入ってから……もう2週間近く、経つ…。化け物が、いつ、私を取り込みにやって来ても……おかしくは、ない……」
ハヤブサの話だけでは、勾玉の封印が破られてから、化け物が育ちきるまでの猶予期間がどれくらいあるのかまでは、分からない。だがもう、時間の問題である事だけは確かだ。
「私も……いろいろ、考えてみたけど……どうやら、私が死んだ方が、話は早そうだ……」
「キョウジ―――!」
ガン! と、頭を殴られたような衝撃を受ける。キョウジが、そういう決断を下すと、覚悟は決めていたつもりだった。しかしいざ、それを耳にすると、少し平静でいられないのは何故なのだろう。
「『死ぬ』以外に―――選択肢はないのか?」
念のために、シュバルツは問うてみた。だがその問いに、キョウジは意外な答えを返してきた。
「有るには、ある……」
「…………!」
(…………!)
身を潜めて二人の会話を聞いていたハヤブサにとっても、それは意外だった。
「でもなぁ……。これは、みんなに大幅に迷惑をかけちゃうからなぁ……」
「私は構わない。お前がそれで生きるのならば―――」
「シュバルツ……!」
迷うことなく即答してきたシュバルツに、キョウジは驚いたような表情を見せた。それに対して、シュバルツは優しく微笑みかける。生きるために必要な迷惑ならば、いくらでもかけてほしいと思う。それで役に立てるのならば、こんなに嬉しい事はない。
「ドモンもきっと、同じ事を言うと思うぞ」
「ドモン………」
少し考え込むような顔をしていたキョウジが、やがてにっこりほほ笑んだ。
「ありがとう…シュバルツ……。貴方は、優しいね……」
「キョウジ……?」
「そんな、貴方だから……私は、ついつい、甘えちゃうのかな……」
そう言って笑うキョウジの頬に、汗以外の物が流れ落ちていた。
「ごめんなさい……シュバルツ……。本当なら、もっと早く……貴方を、私の『影』から、解放しなければ、いけなかったのに―――」
「キョウジ―――!」
(『影』からの解放―――!?)
身を潜めていたハヤブサは、思わず息を飲んだ。
「『デビルガンダム』を止めるために……弟を、守るために…私は、貴方を作った……。その目的は、達せられた……。なのに…貴方だけ―――」
(『貴方を作った』だと―――!?)
知らず、ハヤブサは動揺してしまう。その気配が、シュバルツに伝わってしまった。
「―――誰だ!?」
(まずい―――!)
間髪入れず、シュバルツから手裏剣が放たれる。手裏剣が目的地に達すると同時に、シュバルツが距離を詰めて来た。
茂みの中を、ザザッとかき分け覗き見る。しかし、そこには誰もいなかった。
(…気のせいか……? 誰かの気配がしたかと思ったが……)
「シュ、バルツ……?」
見ると、キョウジが無理に身を起こそうとしている。
「キョウジ! 起きようとするな!」
シュバルツは、慌ててキョウジの元へと戻った。
「……………」
そこから少し離れた場所にある木の陰で、ハヤブサは呼吸を落ち着けていた。しかし、鼓動がなかなか落ち着かない。
(『影』からの解放―――? 作った―――!?)
懸命に、先ほど聞いた話の内容を、頭の中で整理する。
(馬鹿な―――! 『人間じゃない』とでも、言うのか―――!?)
自分の行きついてしまった結論に、さらに動揺が深まってしまう。しかし、あの話の内容を考えれば考えるほど、そう結論付けざるを得なくなってしまう。
(いや、しかし―――腹を見たが、確か―――)
切腹しているかも、と、誤解した時の映像が、頭の中に甦ってくる。着物の下から現れた肌は、どう見ても人間の物だと思った。それにしても、シュバルツのあの姿には、妙な色香が―――。
「…………!!」
ハヤブサは、自分の周りに集まってきた妙な空気を、慌ててバタバタと追い払った。
しっかりしろ! 俺!!
相手は男だぞ!! 惑わされてどうする!?
「……………」
はぁ、と、一つ息をつく。
(どうする? もう一度、話を聞きに戻るか?)
先ほどまで自分がいた場所に、視線を送る。まだ、人の気配があった。二人の会話が、まだ続いているのだろう。
だが、ハヤブサは戻るのを止めた。
『死』を決意し、体調を崩しながらも、キョウジはシュバルツに語りかけている。その貴重な時間を、これ以上自分が邪魔するべきではないと思った。何よりも、動揺を抑える自信が、もうなかった。
キョウジは、『死』以外の選択肢もある、と言っていた。ならば、あともう少し、時間が生まれるかもしれない。
それに賭けてみるかと、ハヤブサは、黙ってその場を立ち去った。
「誰か…いたのか……?」
「いや、気のせいだった。無理に起きようとするな! キョウジ―――」
その制止の声を聞かずに、キョウジは上半身を起こした。
「平、気だよ……。寝てても、起きていても……しんどさは…変わらない、から……」
そう言いながらもキョウジは、起こした上半身を木の幹に、トン、と、凭れかけさせる。
顔は、微笑んでいた。しかし、頬には涙が伝い続けていた。
「キョウジ……」
シュバルツは、そっとその涙を指で拭う。
「あは……参ったな……。泣く気は、ないんだけど……。熱の、せいかな―――」
気にしないでくれ、と、キョウジは言った。だが、その姿が、あまりにも痛々しかった。
「キョウジ……これ以上は無理だ。もう、寝た方がいい」
「ごめん、シュバルツ―――。私は、下手したら明日、死ぬかもしれない……。だから、今の内に、言いたい事を、言わせてくれ……」
「キョウジ―――!」
「分かっているだろ……? もう、これは…時間との闘いなのだと……。もし、勾玉を封印しなおすのなら、早くした方がいい……。そうしないと、『化け物』が、力を蓄えるだけ……余計な犠牲が増えるだけだ……」
「――――ッ!」
分かっている。キョウジは、客観的な事実を言っているだけ。なのに、どうして心がこんなに痛むのだろうか。
「死なない方の選択肢を、皆に言う気は―――?」
「一応…明日、説明するよ……」
「そうか……」
シュバルツはホッと胸を撫で下ろした。選択肢を持っているのに、それすら皆に言わずに黙って死を選ぶのは、あまりにも哀しすぎる。
「でも、その説明で、皆を説得できなかったら……私は死ぬしか、無くなるんだよなぁ……。プレゼンの失敗が、死につながるなんて、何か、嫌すぎる……」
そう言ってキョウジは、何とくすくす笑っている。
(笑っている場合か―――!?)
シュバルツは思わず頭を抱えた。『明日死ぬ』なんて思っている人間は、普通こんなふうには笑わないぞ、キョウジ……。
「死にたくなければ、全力でやれ! そのプレゼンを―――」
「ええ~? ちょっと自信が、無いんだけど……。皆への負担が、きつすぎるし…手間かかるし、この選択肢ですら、私が死なないとは、限らないし……」
「……そうか……」
キョウジに差し迫っている状況の厳しさを、改めて痛感する。表情を曇らせるシュバルツに、キョウジは苦笑した。
「だから……だから、シュバルツ……」
「何だ?」
「私が死んでも、貴方が残ればいいのに―――」
「――――!!」
シュバルツは、鈍器で殴られたような衝撃を受けた。
「ずっと、思っていたんだ……。その方が…きっと、ドモンも喜ぶよ……。もう、私では……兄弟ゲンカすら、出来やしない……」
そう言いながら、キョウジは、ドモンに簡単に吹き飛ばされた瞬間を思い出していた。
ドモンは、軽く腕を振っただけ。なのに、自分は、身体ごと飛ばされてしまった。あの弟が、自分と向き合う時、どれだけ気を使って力を制御しているのか―――改めて思い知らされた瞬間だった。
シュバルツならば、きっと、そのような事は無いのだろう。
ドモンが、遠慮なくじゃれつく事が出来る。普通の兄弟みたいに。
拳で、語り合う事が出来る。ドモンを、心からの笑顔にさせる事が出来る。あの、マスター・アジアみたいに。
それは、自分では、どう足掻いても、出来なかった事だった。
「キョ、ウジ……!」
シュバルツは、嫌だ、と思った。
キョウジに、そんな思いをさせてしまっている己も。闇に、独り、取り残されてしまうのも―――。
「だから、シュバルツ……聞いてくれ…! もし、私が死んでも、貴方が残ったら―――」
「悪いがキョウジ―――それは、無理だ」
シュバルツは、キョウジの言葉を遮るように言い放った。
「シュバルツ…!」
「お前が死にかけた時、私の回復力も落ちて行ったし、身体を動かす事も、意識を保つことも、難しくなって行った…。だから―――無理だ。その願いは、叶えられない―――」
「で、でも……!」
「キョウジ…。私は『影』だ。お前の『影』―――。本体が消えれば、影も消える。これは、当たり前の事なんだ。だから、お前が私の事で、気に病む必要は無いんだ……」
そう言ってシュバルツは、ただ優しく微笑む。だが勝手に、拳が震える。この震えに、キョウジが気づかないで欲しいと祈った。
「…………!」
でも、じゃあ、どうすれば―――。
人間だった貴方を、一瞬でも覚えてしまっている私は、どうすればいい?
償う事も出来ずに、また。
自分の都合で、貴方を巻き添えにしてしまう……。
「それにキョウジ―――。ドモンが求めているのは、あくまで『お前』だ」
「――――!」
「本当だ…。私はずっと、ドモンを見守ってきた。だから、分かる」
病院に収容されて意識のないキョウジを、ドモンはほぼ毎日見舞いに来ていた。
医師に、『意識が戻るのは難しいかもしれない』と告げられても、それでも通い続けてきた。
日々己を責め続け、憔悴するドモンを見ていられなくなったシュバルツは、人目を忍んでドモンに会った。
「お前にはお前の生活がある。兄の事など忘れて、お前はもう、自由に暮らせ」
キョウジなら、きっとドモンにそう望む―――そう思って、シュバルツは、ドモンにそう告げるつもりでいた。しかしドモンは、シュバルツの姿を確認するなり、無言ですがりついてきた。「心配していた」と、レインにも泣かれ、シュバルツは、もう何も言えなくなってしまった。
それからは、ドモンが望む時に、人目につかないことを条件に、会うことになった。
ドモンは、シュバルツに『兄』を求め、時に拳の相手を求めた。シュバルツは、可能な限りそれに応えた。
ただ、ドモンは、シュバルツとどんなに会話をしようとも、拳を交えようとも、最後には必ずキョウジの病室に立ち寄り、語りかける事を忘れなかった。その後ろ姿を見るたびに、ドモンがどれほど『キョウジ』を求めているか―――痛感させられ続けた。
「ドモンが私になついているのだとしたら、それは、私の中にお前の面影があるからだ…。もし私が、ただの『シュバルツ』であったならば、ドモンは私の事など、気にも留めないはずだ……」
「でも…シュバルツ……私は―――ぐ…う……ッ!!」
何か言いかけたキョウジが、胸のあたりを押さえて苦しみ出す。
「キョウジ!?」
心配するシュバルツに、キョウジは苦笑した顔を上げた。
「ご、ごめん……実は、ちょっと……痛みも、あって……」
「な―――!」
思わずシュバルツは絶句してしまう。熱だけにしては、変に汗をかいていると思っていたら―――!
「…………ッ!」
キョウジは己の身体を抱え込むようにして、声を殺して痛みを我慢している。
「馬鹿かお前は!! 何故そんな状態で、無理に起きていようとする!?」
シュバルツは強引にキョウジの身体を抱きかかえた。キョウジが小さく抵抗の意思を示したが、もう聞いている場合ではない、と、思った。
「待ってくれ、シュバルツ……! 最後に、これだけは、言わせてくれ……!」
「もういい、キョウジ! また後で―――」
「シュバルツ、私は……貴方には、生きてほしいと…願って、いるよ……『私』に、縛られることなく……」
「――――!」
「でも…分かっている…。これは、私のエゴだ……。自分の作った物が、後の世に残ってほしいと、願う……愚かなエゴだ……」
「キョウジ……!」
「……自分で、生死が選べないのと……ただ、ひたすら……死ねないの…と……一体、どちらが……残酷、なんだろう……ね……」
「キョウジ、もういい――! もう、休め……!」
シュバルツはたまらなかった。これ以上キョウジに何か言われたら、人目もはばからずに泣き叫んでしまうと思った。
「…………」
「キョウジ……?」
キョウジは、そのまま眠りに落ちていた。ここまでが、体力の限界だったらしい。その頬に、涙が光っていた。
「キョウジ―――!」
勝手に、キョウジの頬の上に、自身の涙が零れおちる。
いけない、と、思った。キョウジの眠りを、妨げてしまう。
だがもう、止まらない。止める事が出来ない。勝手に自身の頬を伝い落ちるそれは、次々と、キョウジの上へと落ちて行ってしまう。
だから、せめて声を殺した。声を殺して、泣き続けた。
キョウジは、自分が犯してしまった『罪』を、分かり過ぎるほど分かっている。
その『罪』に、今も苦しんでいる。それこそ、充分すぎるほどに。
そして、その『罪』の一角に―――自分が、絡んでしまっているという事実が、シュバルツには辛く、そして重かった。
今更だ。
何もかもが、今更だ。手遅れなのは、分かっている。
でも、もし、神がいるのならば、せめて祈りたい。
「今、腕の中にいるこの人の苦しみを、少しでもいいから軽くしてあげてください」と…。
そんな二人の姿を、ギアナ高地の月明かりが、優しく照らし出していた。
こうして、それぞれにとっての夜が、更けて行った―――。
翌朝。
キョウジは起きて、パソコンに向かっていた。その横に、シュバルツが控えていた。
キョウジは、まだ熱も引いていない。痛みも、断続的に続いているようだ。本来なら、寝ていてほしい所だ。
しかしキョウジは、「原因は分かっている。大丈夫、病気じゃないから―――」と、寝る事を拒んだ。時間がない、と、分かっている今、寝ている場合ではないのも事実だ。
ならばせめて、説明する役を変わろうかと申し出た。その提案に、キョウジは少し考えてから返事を返してきた。
「これは多分―――私が自分で、きちんとやらないと、意味がない……。私が生きるための、戦いだから……」
「そうか……」
ならば、と、シュバルツも、覚悟を決めた。キョウジの戦いを、最後まで見届ける。キョウジが死ぬ時が、自分も死ぬ時―――そう思いながら、彼は今、キョウジの横に控えている。
「……………」
二人から少し離れた所の壁際に、ハヤブサが腕を組んでもたれかかっていた。
昨日の二人の話から、シュバルツが人間ではない、という可能性が浮上してきている。しかも、キョウジが『作った』と……。
(本当に、人間じゃないのか……? にわかには信じ難いが―――)
そう思いながら、シュバルツをじっと見つめる。キョウジの横で佇んでいるその姿は、どこからどう見ても人間のもののように見える。もしこれが、本当に作られたものであるというのならば、恐ろしい程の技術力と、言わざるを得ない。
キョウジと瓜二つなのは、キョウジがシュバルツを『影』として意識して作ったからなのか。弟を、守るために―――。
(『影』で、作りものだから、『生きる』と言う選択が出来ないのか? いや、それだけでは……キョウジが死んだら、共に死なねばならないという理由にはならない。まだ、シュバルツには生き続ける選択肢もあるはずだ)
それとも、メンテナンスの関係上、そうならざるを得ないとか……?
「…………」
考えれば考えるほど、訳が分からなくなってくる。まだ何かが足りていない。シュバルツをぶん殴るまでには至っていないと感じる。
その為には、もう少し調べる必要がある。時間が欲しい。昨日の話だと、キョウジは『死』以外の選択肢も持っているという。
(どういうことか、早く説明をしろ、キョウジ……。そうすれば、俺は―――)
場合によっては、キョウジを斬らずに済むかもしれない。淡雪のようだと思っていた望みを、現実のものとする事が出来るかもしれない。そんな事、あり得ないかもしれないが―――。
キョウジの呼吸は浅く、不自然に汗もかいている。昨夜からの熱が、まだ引いていない事が分かる。それでも、無理を押して起きているのは、おそらくキョウジは待っているのだ。全員がここにそろうのを。自分の選択肢を説明するために。
今、ここにそろっていないのは、キョウジの弟であるドモンと、その師である東方不敗だけだ。ドモンは、おそらく自分がキョウジを斬ろうとした時に、一番厄介になる相手だと感じる。彼は、キョウジが斬られる覚悟を固めていたとしても、最後までキョウジを守りとおそうとするだろう。
行動が読めないのは、東方不敗。あの男が、どう動くか―――。
ふと、部屋の出入り口の所で、新たな人の気配を感じた。入ってきたのは、ドモン・カッシュだが……。
「…………!」
全員がドモンの方を見て、思わず絶句してしまう。ドモンの目が凄まじく腫れあがっていたからだ。恐らく一晩中泣きあかしていたのだろう。顔色もひどく悪かった。
「ド、ドモン!?」
ドモンのあまりの状態に、キョウジの方がたまらず声をかけた。
「お前……大丈夫か…? 顔色が…」
「だ、大丈夫だよ。平気……」
そう言いながらも、ドモンはキョウジの方を見ようとしない。
ドモンは、ほぼ一晩近く泣きあかした。体力が続く限り、泣いて泣いて―――。
(どうなるかは分からないけど、とにかく兄さんを支えないと……!)
そう決意して、兄のいる場所に足を運んだはずだった。しかしいざ、兄を目の前にすると、「嫌だ―――!!」と、泣いてすがって、駄々をこねそうになってしまう。まるで、小さな子供みたいに。そんな事をしても、状況は変わらないばかりか、兄にとっては迷惑にしかならない。分かっている。分かっているのに―――。
「ドモン……」
ドモンが恐ろしく不安定な状態になっていると感じたキョウジは、思わずドモンに向かって手を伸ばしていた。
「だ、大丈夫だってば! 本当に―――!」
ドモンが、キョウジの手に怯え、それから逃れるように、一歩身を引いた。ドモンからしてみれば、今キョウジに触れてしまうと、自分が何をしてしまうかが分からない恐怖にかられてそうしたのだが、傍から見ていると、完全にドモンがキョウジを拒絶しているようにしか見えない。
「…………!」
案の定、単純に「拒絶された」と感じたキョウジが、手を引っ込めながら哀しそうな表情をしている。その様子をずっと見つめていた三人が、
(ドモンの馬鹿!)
(―――馬鹿だな)
(阿呆弟子が!!)
と、頭を抱えたりため息をついたり、舌打ちをしたりしていた。『三人』―――そう、東方不敗も、物陰に隠れて、先ほどから見ていたのだ。東方不敗も待っていた。キョウジの真意を確かめるタイミングを―――。
キョウジの真意を確かめる。これは、ある意味弟であるドモンの役目だと、東方不敗は思っていた。しかし、今のドモンでは兄の真意を確かめるどころか、兄に逆に気を遣わせている始末だ。これではいつまでたってもキョウジを守って戦う態勢にはなりはしない。
(やむを得んか……)
今は、一分でも一秒でも時間は無駄には出来ない。キョウジに戦う意思があればよし。逆に、死ぬ決意を固めているのならば、この戦いは、ここで終わらせねばならぬ。そうでなければ、皆の苦しみが、いたずらに長引くだけだ。
(どうせ終わらせねばならぬのなら、キョウジの命は、このワシの手で―――!)
そう断を下した東方不敗は、全員がそろっている部屋に向かって足を踏み出した。
「全員そろっておるな」
そう言いながら、東方不敗がずかずかと部屋に入ってくる。入ってくるなり彼は、ドモンに対して鋭い視線を投げつけた。
「ドモンよ!!」
「は、はい!」
「まず―――そこに座れ!」
師匠の、有無を言わさぬ迫力に押される形で、ドモンは言われたとおりその場に座った。すると、東方不敗は己の腰に巻いている白い布を手に持って一閃させる。ドモンの目の前の地面が削られ、一本の直線が穿たれた。
「よいか!! 貴様はこの線より一歩でも外に出たら、師弟の縁を切ったと見なし、破門とする!!」
「ええっ!?」
「…………!」
東方不敗のいきなりのこの宣言に、ドモンが息を飲む。ただ、キョウジは、「来た」と、思った。始まったのだ。自分の生死を決める、戦いが。
「そして―――キョウジよ!!」
「はい」
「ワシは、貴様に問わねばならぬ事がある。但し―――返答次第では、貴様の素っ首、このワシ自ら刎ね飛ばしてくれるわ!」
「―――!」
「師匠!? いきなり何を―――!?」
「お主は黙っとれ!! ワシはキョウジに問うておるのだ!!」
「…………!」
東方不敗から放たれる尋常ならざる殺気に、ドモンは思わず気圧された。何が起こっているのか俄かに理解できない。まさか師匠は、本気で兄を殺す気なのだろうか。
(兄さん……!)
ドモンが、やっとまともに兄の方を見る。兄は、怖じ気た様子もなく、静かに東方不敗の方を見ていた。やがて彼はすっと椅子から立ち上がると、ドモンでさえ気圧された殺気を放つ東方不敗の真正面まで歩を進め、そこに座る。東方不敗がその布を一閃させれば、簡単に首が飛ぶ間合いだった。
(キョウジ……)
それを見届けたシュバルツは、あえて東方不敗とキョウジの姿から、背を向けた。もし、東方不敗がキョウジの首を刎ねるために動き出したとしても、それを邪魔しないためだ。キョウジは、何もかも覚悟を決めてそこに座っている。ならば、自分はついて行くだけだ。これは―――キョウジの戦いなのだから。
「…………」
ハヤブサは、何が起こっても対応できる位置に移動した。これから先事態がどう動くのかは分からないが、キョウジが死ぬのならば、自分は勾玉を回収しなければならない。今自分が集中するべきは、その一点のみと悟る。
(やはり、受けて立ちおったか……キョウジ!)
臆することなく、自分の前にすっと座ったキョウジの姿に、東方不敗の心が震える。
並の人間ならば、自分が怒鳴っただけで腰を抜かす。しかし、キョウジは、これだけの殺気を浴びてもなお、自分の正面に歩を進めてくるのだ。その姿には、迷いも恐れもない。首を差し出す『覚悟』が、出来ているのだろう。
それだけに、惜しい。
今死なすには、あまりにも惜しい。
何と見事な―――若武者よ!
だからこそ、敢えて問わねばならぬ。彼に、戦う意思があるのかどうか。
殺そうとする自分を見事説き伏せ、生を勝ち取ってほしい。
それが叶わぬのならば、せめて―――苦しませずに、その生を終わらせてやる。
「キョウジよ! 貴様に問おう。―――まさか貴様、この戦いを、自らの『死』を持って終わらせようなどと言う、府抜けた考えを持ってはおるまいな―――?」
東方不敗は、ストレートにこの質問を投げつけて来た。これは、ここにいる全員がまさにキョウジに聞きたい事だった。4人分の目と耳が、キョウジへと集まっていく。
「…………」
キョウジは、しばらく眼を閉じて何事かを考えていたように見えたが、やがて、その口を開いた。
「……誤解を恐れずに、言わせてもらうなら……確かに私の『死』は―――選択肢の一つに、あります」
「何っ!?」
「兄さん!」
「…………」
キョウジの言に、東方不敗とドモンが反応を返し、シュバルツとハヤブサは沈黙を返した。
「キョウジ―――!」
東方不敗の布を握る手に、力が入る。やはり、殺さねばならんと言うのか―――?
「ですが……もう一つ―――」
「!?」
「みっともなく『生』に執着し……足掻く事が、許されるのなら―――試してみたい事が…あるのですが……」
「何だと!?」
「………!」
兄の、思わぬその発言に、ドモンは思わず立ちかける。東方不敗はをれを眼で制してから、手に持っていた布を腰に巻き戻して、キョウジに問いかけた。
「何だ。話してみろ」
「――――ッ」
キョウジは、腕を組むふりをして、胸を抑えた。
(ごめん……辛抱してくれ。後、もう少しだから……)
こらえようもない汗が、滴り落ちていく。それをごまかすべく、キョウジは努めて明るくふるまった。
「う~ん……でもなぁ…。これは、私一人では絶対無理だし、かと言って……協力してくれる人が、いたとしても……かなり、迷惑をかけちゃうから―――」
「な、何じゃ? 勿体ぶらずにさっさと話さんか」
東方不敗は、いつの間にか前のめりの姿勢になっていた。
「まず……確認したい事が、あるんだけど……ハヤブサ…」
「何だ?」
キョウジに名を呼ばれたハヤブサが、顔を上げる。
「今までの事例で……『化け物』が、勾玉を取り込みに来るまで、どれくらいの猶予期間があった…?」
「―――!」
「私が……勾玉を取り込んでから、もう2週間近く、経つ…。だが、私はまだ…それらしきものと、接触をしていない……。これは…長いのだろうか。それとも……」
「―――文献には、勾玉の封印が破られてから化け物が発生するまでどれくらいかかっているかという、詳しい日にちまでは書かれていない。…が、200年前に勾玉の禍に遭ったハヤブサの里の長の記録によると、確か、娘に勾玉が吸収されてから、化け物と遭遇するまでの期間は10日ほどだったそうだ」
「……と、言う事は、やはり意図的に姿を現していない……と、考えた方が、よさそうだな……」
「姿を現していない…? どういうことだ?」
東方不敗の疑問を発する声に、キョウジは笑顔を向けた。
「もし…敵方が勾玉を単純に手に入れたいとだけ思っているのならば、化け物と共に行動して、こちらを襲った方が、話は早い……。化け物と勾玉が、惹かれあっている……と、言うのなら―――」
「うむ」
「ただ……勾玉が封印されていた隼の里には、化け物にとっては天敵ともいえる『龍剣』がある…。しかも、勾玉の封印の仕方まで伝わっている…。不用意に近づけば、また封印され、復活するまで200年の時を待たなければならない…」
「…………」
「だから、化け物自身か、化け物を率いている者かは分からないが―――単独で動く事を避けることにした。今の世界で、ある程度の軍事力と権力を持っている者と、手を組んだ……」
「何故、そんな事が分かる?」
東方不敗が疑問を発する。
「私たちを襲って来た者を見れば、分かる。私たちは、合成獣まで投入されたフル装備の軍隊に。最初にシュバルツが対応してくれた方は―――」
「忍者部隊だ」
シュバルツが口を開く。
「これらの者たちを、意のままに動かすには―――ある程度の軍事力と権力を持っていなければ、無理だ」
「確かに…な」
東方不敗が頷いた。
「じゃ、じゃあ…兄さんに勾玉が吸収されたのは……」
「まあ、敵方からしても想定外だったんだろうね」
ドモンに、キョウジは苦笑した顔を向ける。
「敵方からしたら、『龍剣』と勾玉は、何が何でも引き離したかったはずだ…。それを画策している途中で起きた、アクシデント……だったんだろう」
「…………!」
(『アクシデント』なんて言葉で、片づけられないだろ……!)
ドモンは、悔しさをかみ殺す。
「それで、キョウジ。お主の『試したい事』とは、一体何だ?」
「――――」
東方不敗の問いに、キョウジの答えが不自然に一瞬遅れる。熱と痛みが、キョウジの体力を容赦なく奪っていた。
(キョウジ……!)
それが分かるシュバルツは、拳を握りしめる。その苦しみ、代われるものなら代わってやりたかった。
「私は……勾玉が身体に吸収されてから、何とかそれを、外に出せないかと、考えて……」
「―――!」
「正体を調べるにしても、身体の中にあったのでは、調べにくいからね…」
キョウジのこの言葉に、一同が息を飲む。
まさか。
まさか、この男―――!
「まさか…出せたのか…?」
東方不敗の言葉に応えるべく、キョウジは立ちあがろうとする。だが、激しい眩暈に襲われた。
(駄目だ…! 今立てったら倒れる―――!)
「…シュバルツ……」
「―――!」
キョウジの助けを求める響きを含んだ小さな声に、シュバルツは鋭く反応した。
「何だ? キョウジ…」
キョウジのすぐそばまで走り寄って膝をつく。それにキョウジは、笑顔を返した。
「悪い……デスクの上に、シャーレがあるだろ…? それを持って、出来るだけ私から離れて、立ってくれないか…?」
キョウジに言われたとおり、パソコンが置いてあるデスクにシュバルツが目を向けると、蓋をしたシャーレが置いてあった。しかし、一見空のようにも見える。
「これでいいのか?」
シュバルツはキョウジに言われたとおりに、シャーレを持って少し離れた壁際に立った。それを見たキョウジは頷いて、今度はハヤブサの方に振り返る。
「ハヤブサ―――」
この状況で、自分がするべき事は一つしかない。半信半疑ながらもハヤブサは頷き、シュバルツの前で文言を唱え、印を結び、手をかざした―――。
ポウ…。
シャーレの中から、確かに微弱ながら勾玉の反応が返ってくる。
「勾玉―――!」
そう言ったきり、ハヤブサは絶句する。
「………!」
茫然と、シュバルツはシャーレの中をもう一度見る。空だと思っていたシャーレだが、よく見ると、小さな小さな物体が、淡い光を放っていた。
「何と……!」
「に、兄さん……!」
一同が、信じられない思いでキョウジの方を見る。それに対してキョウジは笑顔を返した。
「ああ……やっぱり、それが勾玉だったんだ……。よかっ…た……」
そう言いながら、キョウジの身体が、ガクン、と、崩折れる。
「キョウジ!!」
「兄さん!!」
思わず全員がキョウジの側に走り寄る。一番近くにいた東方不敗が、キョウジの身体を支えた。
「お主…先ほどから様子がおかしいと思ったら、熱が―――!」
キョウジの身体に触れて異変に気付いた東方不敗に、キョウジは微笑んだ。
「大丈夫です…。これは、病気じゃない…。シュバルツ……悪いんだけど、そのシャーレをこっちに―――」
シュバルツが言われたとおりにキョウジにシャーレを渡す。キョウジが蓋をあけると、小さな光はシャーレの中から飛び出して、再びキョウジの身体へと入っていった。
「勾玉が―――!」
ドモンが思わず声を上げる。
「……は……あ……」
勾玉によってもたらされていた熱と痛みが劇的に引いて行くのが分かって、キョウジの口から思わず声が出る。青白かったその頬に、再び生気の色が戻って来つつあった。
「~~~~~ッ! きつかっ……た…!」
はあっ、と大きく息を吐きながら、キョウジは身体を起こした。
「に、兄さん…せっかく出した勾玉を―――」
「あれは、ほんの一部だ…。本体はあれよりもう少し大きい。今のここの設備と、私の技術では、あれが限界―――というか、これ以上この状態を続けるのは無理―――」
「え…? それはどういうこと? 兄さん」
問いかけてくるドモンに、キョウジは苦笑交じりの笑顔を向ける。
「あはは……。勾玉を無理やり引きちぎって、一部分だけ抽出したような形になっちゃったからね…。それを勾玉自体が痛がって暴れて、それが私に反映されちゃって、もう痛いの何のって―――。だから、これ以上は本当、無理―――私の身体が、保たないよ」
「――――!」
(その痛みに耐えていたのは、いつからだ―――!?)
キョウジの様子がおかしかったのは、昨晩からだ。それからずっと、彼は今まで痛みに耐え続けていた事になる。
ハヤブサは、開いた口が塞がらなくなるのを感じた。
(馬鹿だ、こいつ。馬鹿だ―――! もっと早く俺に言ってくれれば、それが勾玉かどうかぐらい、すぐに確認したというのに……!)
ハヤブサは思わず怒鳴り付けそうになった。
「馬――――!!」
「ば?」
キョウジとシュバルツが、同時にハヤブサの方を見る。それを見たハヤブサが、はっと我に帰った。今ここで怒鳴りつけてしまうと、昨夜のキョウジとシュバルツの会話を盗み聞いた事が、ばれてしまう。キョウジの調子が昨晩から悪かった事を、自分が知っていてはおかしいのだ。
「慣れ合いをしない」と、キョウジに宣言してしまったのは、ほかならぬ自分だ。だから、キョウジの方が遠慮してしまったのだろう。皆に、きちんと説明できる機会を得るまで…。
(何てことだ……馬鹿は、俺か―――)
「……何でも無い」
ハヤブサは、少しばつが悪そうに横を向いた。
「……………」
シュバルツは、ハヤブサのそんな態度に、少し思う所があったが、敢えて口には出さなかった。
「ごめん……ちょっと水を飲ませてもらってもいいかな? 汗をかきすぎて、咽が―――」
キョウジがそう言って立ちあがろうとすると、キョウジの目の前から四人の男たちの姿が一斉に消える。しかし次の瞬間、四人が四人とも、それぞれ手にしたコップに水をいっぱい湛えて、キョウジの前に差し出した。
「…………!」
これには、さすがのキョウジも面食らう。
「あ、ありがとう…。順番に飲むから、ここに置いといてくれるかな?」
キョウジは、苦笑しながらそう頼むしかなかった。
「…………」
運んできてくれた四つのコップの内の一つに手を伸ばして、水を飲む。
(おいしい……)
ようやくキョウジは、人心地がついた。
「キョウジよ。お主『今のここの設備と技術ではこれが限界』―――と、言ったな?」
「はい。勾玉と私を完全に分離するまでには至らなくて…。でも、一部でもこの思いついた方法で抽出できるのか、どうしても試したくて…。ちょっと勾玉には、かわいそうな事をしてしまいました」
(かわいそう―――? まるで、勾玉を生き物のように言う。変わった事を言う奴よ……)
東方不敗はキョウジの物言いに、不思議な印象を持った。
「それで、キョウジ。お主が『試したい事』というのは―――」
「そうですね。ここからが、本題です」
キョウジは、一杯目の水を飲み干し、二杯めの水を途中まで飲んでから、改めて居住まいを正した。
「今から私が話すことをよく聞いて―――その上で、決めてください」
「何をだ?」
「私を―――生かすか、殺すか」
「…………!」
シン、と、冷水を浴びせられたような静けさが、その場を支配する。キョウジは、たとえ一部だけとはいえ、勾玉を身体の外に出すことに成功している。それでもまだ、『死ぬ』という選択肢を捨てる事が出来ないのか―――と、皆が思った。その中で、ただキョウジの面だけが穏やかさをたたえていた。
「に、兄さん……何で…そんなことを―――」
ドモンの手が、ふらふらとキョウジに向かって伸びる。それを、東方不敗が見咎めた。
「ドモンよ!! 線を越えたら破門だと言うておろうが!!」
「うわっ! は、はい!!」
その東方不敗の声が合図となるかのように、キョウジの側にいた全員が、それぞれ最初にいた場所に戻った。
「よかろう! 聞いてやるから、さっさと話せ」
東方不敗はキョウジの前に立ち、腕を組んで居丈高に構える。但し、自分の武器となる腰に巻いた白い布には手を伸ばさなかった。
「分かりました―――」
キョウジは頷き、話し始める。
「化け物の側が権力者と手を組んだ理由はいろいろ考えられるけど…その中の一つに、龍剣対策は確実に含まれていると思う。恐らく、龍剣と対峙しても簡単に倒されないようにするために…。だけど、権力者と手を組もうと言うのなら、化け物の側も、ある事をしなければならなくなる。権力者の『信頼』を得るために―――」
「ある事?」
キョウジの言葉に、東方不敗が怪訝な顔をする。
「確認したいんだけど―――ハヤブサ」
「何だ?」
「化け物の力は―――『自分の周りにあるありとあらゆるモノの命を手当たり次第に奪い、破壊する』と、いう風に考えていいんだな?」
「そうだ。特に、盗賊をコアとした時の化け物の破壊活動は、凄まじい物だったと聞く。そいつが通った後は、本当に―――草木一本たりとも残らなかった」
「そんな物騒な物、何の対策もなしに、権力者は自分の傍には置かないよなぁ」
キョウジが、少し人の悪そうな笑みを浮かべる。
「…………!」
東方不敗の眉が、ピクリ、と、動いた。
「無軌道に破壊行為をする―――というのではなく、権力者の意のままに破壊活動を行う必要があるから、ある程度外からその行動を制御できるように、システムを作っている必要がある―――と、思うんだけど……『デビルガンダム』の時みたいに」
「――――!」
場の空気が、一瞬にして凍りつく。
キョウジは、そのデビルガンダムに取り込まれ、東方不敗は―――まさに、そのデビルガンダムの力を利用した、当事者だ。
「……お主、『あの時』の記憶が、あるのか?」
問いただす東方不敗に、キョウジはあっけらかんとした笑顔を見せた。
「まさか! 取り込まれてしまってからの記憶はありませんよ。ただ―――『記録』を見ただけです」
(こ、こ奴―――!)
東方不敗の背中に、冷たい物が流れる。
「生体ユニットである私があのガンダムを動かせなくなっても―――外からの制御で、動いてましたよね? あのガンダム」
「…………ッ!」
東方不敗は、思わずキョウジから一歩身を引きそうになった。「デビルガンダム事件」は、それで死にかけたキョウジにとっては、最大級のトラウマとなっているはずだ。それを恐れて避けるどころか、今回の事件の踏み台にしようとさえしている。
(何という図太さ―――! 何という根性の持ち主―――!)
東方不敗は、思わず唸らずにはいられなかった。
確かに、デビルガンダムには、自分も外から干渉したし、当時手を組んでいたウォン・ユン・ファという某国の代表も、外から動かすシステムを構築し、デビルガンダムを動かしている。
「私は、そのシステムを狙いたい」
「………!!」
キョウジのこの言葉に、一同が息を飲む。
「外側から、ある程度化け物を制御することができるシステムに、勾玉を持った私が干渉し、乗っ取ることができれば、どうなるか―――」
「ば、化け物を、完全制圧するつもりか……!」
東方不敗の言葉に対し、キョウジが笑みを返す。
「うまくいけば、ね。……私が生き延びる可能性があるとしたら、おそらくここだろう…」
「…………」
東方不敗はじっとキョウジの顔を見つめる。だが次の瞬間、キョウジはふっと相好を崩した笑顔になった。
「でも……そんなシステムなら、まあ、敵のど真ん中にあるだろうし…そんなシステム自体があるかどうかも分からない…。そういう意味では、敵の力を当てにしすぎた作戦ではある……。化け物に私が近づいた途端、速攻で取り込まれないとも限らないし……」
「…………」
「化け物を制御するシステムが、妖術や魔術といった類のものなら、私は完全にお手上げだし―――」
「フン。外の世界とネットでつなぐシステムを作る時に、ワシの水盆の技術を応用した男が、今更何をぬかしておる」
東方不敗のその言葉に、キョウジが「ばれてました?」と、いたずらっぽい笑みを浮かべた。そんなキョウジの態度に、東方不敗はやれやれ、とため息をつく。
「―――で? ワシらは何をすればよい?」
「え?」
東方不敗の問いかけに、キョウジはきょとんとした顔をする。
「お主の事だ。もう作戦も考えてあるのであろう? だったら、何をぐずぐずしておる」
「え……? いや、あの……」
「皆の者! 作戦会議を始めるぞ! 準備をせんか!」
「…………!」
茫然としているキョウジをよそに、皆がまたキョウジと東方不敗の元に集まってこようとする。
「いや…ちょっと……! ちょっと待ってくれ! この話は、まだ終わりじゃない!」
キョウジの制止をかける声に、東方不敗が心外そうな声を上げる。
「何じゃキョウジ…! まさか、ワシらの力では、お主を助けるには足りないとでもいうのか?」
東方不敗のこの言葉に、キョウジは慌てて頭をふる。
「いえ、滅相もない! 貴方がたの力を借りられるのなら、例え狙っているシステムが敵の施設のどこにあろうとも、必ず成功する事が出来るでしょう」
「だったら何故――? 何を躊躇う事があると言うのか?」
「そう。成功する―――。成功するからこそ、残ってしまうんです。私の手元に、勾玉と、化け物が―――」
「…………!」
キョウジのこの言葉に、全員の動きが、一瞬止まった。
「運よく、勾玉を持った私がシステムを乗っ取って、化け物を完全制御できたとして―――」
キョウジは懸命に説明した。この作戦を行った場合、自分が―――というより、皆が背負わなければならなくなる、リスクを。
「残った勾玉と、化け物をどうします?」
キョウジのこの問いかけに、皆が咄嗟に答えられない。
「やはり、古からの封印の方法に則って、私の身を焼き、『龍剣』に化け物を滅してもらうべきなのか?」
「――――!!」
キョウジのこの言葉に、ドモンの顔色が真っ青になる。
「でも、それでは、また200年後に勾玉の封印が解かれ、誰かの身に、この悲劇が降りかかってしまう…。同じことの、繰り返しですよね?」
「ふむ………」
東方不敗が考え込む横で、ドモンがホッと胸をなでおろしている。
「ですから―――もし、許されるのであれば……私は勾玉と、化け物の研究がしたい」
「…………!」
「『封印』という方法ではなくて、本当に、この世からちゃんと消滅させる……あるいは、無害化させる……それが出来れば、一番いい」
「兄さん……」
ドモンの声にキョウジは振り向き、笑顔を見せる。
「『化け物』と、言ったって、元は人間だ。それが800年も呪いのようなものに囚われて―――それじゃあ、あんまりだ……解放してあげられるのなら、そうしてあげたい」
(キョウジ……)
シュバルツは、ただ虚空を見つめた。
「でもなぁ……」
ここでキョウジが、自信がなさそうに腕を組んで考え込みだした。
「でも―――何じゃ?」
「問題は、この研究……すぐに終わるかどうか……」
「―――!?」
東方不敗は、思わずキョウジを凝視した。
「相手は、800年も残って来ている勾玉…。おまけに、邪法やら呪いやらと言ったおっかない物まで絡んできている代物だし―――」
「そんなに厳しいのか?」
東方不敗の問いかけに、キョウジは難しい顔になる。
「……私が死ぬまでに、終わるといいけど……」
「………!」
キョウジが何やらとんでもない事を言いだしたのが分かって、全員開いた口が塞がらなくなるのを感じた。
「おまけに、もう一つ厳しい状況がある」
異様な空気の中、キョウジが更にたたみかけて来た。
「化け物を制御できるようになった私が『これは研究するためだけに使います。他には一切使用しません』と、宣言して研究室に籠ったとして―――」
ここでキョウジは顔を上げた。
「一体、世界中の誰が―――その言葉を信じる?」
「………!」
全員が、絶句する。キョウジは少し、淋しそうに笑った。
「普通は、誰も信じない。手にしている力が強大であればあるほど―――どこの組織にも属さないそんな力は、存在する事自体許されない。きっと、世界中から狙われるか非難されるかして……私は、あっという間に世紀の大犯罪者に祭り上げられるだろう」
「に、兄さん……!」
呆然とするドモンに、キョウジは笑顔を向けた。
「そうなると……研究どころではなくなるのも、事実だ。後はただ、大義名分も立たない戦いに、発展していくだけだ…」
シン、と、重苦しい沈黙が、部屋を支配する。
(私は、死ぬしかなくなったかな?)
静寂の中、キョウジは何となくそう感じていた。
自分が生きよう、生きようとすればするほど、状況が泥沼化していく。これが、今自分が置かれている現状だった。どう考えても、死を選んだほうが話は早い。
自分はいい。自分の手は、既に罪で真っ黒に汚れている。この上に犯罪の肩書が一つ増えた所で同じだ。今更、この後の人生を、まっとうに生きられるなんて思っていない。今ここで死ぬにしても、受け入れられる。
だが、他の皆には、まだ真っ白な未来がある。それを、自分なんかに付き合って、不毛な戦いに巻き込まれる事はない。その後の人生を、喰いつぶされる必要もない。
ただ、一つの心残りは、シュバルツ―――。
本当に、私が死んでしまったら、彼も死んでしまうのだろうか。
彼を作った時、断じて誓うが、そんなプログラムを組んだ覚えはない。それなのに、気がついたらそんな機能が付いていた。まるで、呪いのように―――。
他はどうしようもなくても、せめて、その機能だけでも、何とかしてあげたかった。こんなに早く、自分の人生が終わるとは、思っていなかったから……。
ごめん、シュバルツ。
本当に、ごめん。
ただ、私が死んでも、貴方が残る―――そんな奇跡が起きたら。
その時は、どうか自分を責めないで。
貴方だけの道を、歩んでください。『私』に囚われず―――。
「だから―――選んでください」
キョウジは、たぶん自分の死刑宣告になるであろう、言葉を発した。
「私に付き合って、世界中を敵に回して、先の見えない戦いと研究に巻き込まれるか―――今すぐ勾玉を封印しなおして、200年後の英知を待つか―――その、どちらかを」
「……………」
「……………」
「……………」
「……………」
4人の内の誰もが、すぐに言葉を発しなかった。部屋に、しばし静寂が訪れる。
(みんな、優しいんだな……何を、そんなに迷う事があるのだろう)
この状況。どう考えても、自分が死ぬ方が話は早い。キョウジは苦笑した。
「……よく考えたら、200年という期間は長い。この勾玉の禍に、遭わずに生まれて死ぬ事が出来る人も、結構いるんじゃないかな。だから、先送りするのも、一つの手だ」
皆の決断を助けようと、キョウジは言葉を発する。
「―――キョウジよ」
東方不敗が、4人の中で一番早く口を開いた。
「はい」
「その研究―――どれくらいの期間がかかるのだ?」
「――――!?」
意外ともいえるこの質問に、キョウジは面食らう。
「えっ……と、実際にそれを見てみないと分からないですが―――多分、すぐには終われません。下手したら100年単位で―――」
「長いな」
「はい」
「50年だ」
「はい?」
「50年以内に、何とかせい」
「……え?」
キョウジは、東方不敗に何を言われているのかが咄嗟に分からず、きょとん、としてしまう。
「師匠、何で50年なんですか?」
ドモンの方が、東方不敗に質問をした。
「医師から言われたワシの残り寿命は、50年だ。だから、それ以内にこ奴の研究を終わらせてもらわねば、困る。事の顛末を、見届けられん」
「なるほど……って、師匠! 何歳まで生きるつもりなんですか!?」
「そんなもの、死ぬまで生きるに決まっておるわい」
ドモンの突っ込みに、東方不敗はズバッと切り返した。
「あ、あの……」
自分の目の前で繰り広げられている、何かがおかしい展開に、キョウジの脳が思わず理解を拒否してしまいそうになる。
「よし―――皆の者、改めて作戦会議をするぞ。さっさと用意を―――」
「あ、あの、ちょっと…! ちょっと待ってください!!」
何故か自分が置いて行かれそうな方向に事態が発展しようとしていると感じたキョウジは、思わず声を上げた。
「何じゃ! まだ何かあるのか!?」
東方不敗が少し鬱陶しそうに声を出す。キョウジは思わず身を引きそうになった。
「いえ、あの―――人の話を聞いてましたか? それなのに、作戦会議って…!」
「ああ。聞いておったぞ? 敵の中枢にある、化け物を制御するシステムを狙うのであろう?」
「そうなんですけど―――そうじゃなくて!」
それをやっていくと、状況が泥沼化していく。自分は、そう説明したはずなのだ。
「化け物を制御するシステムが、本当にあるかどうかも分からないし…」
「あるだろう。お主に勾玉が吸収されてから2週間も経っているのに、いまだにお主の周りに化け物らしきものが現れていないのが、いい証拠だ」
「…………!」
東方不敗が、スパン、と、切り返してくる。自分で言った説に、自分が言いくるめられている状態に、キョウジはぐっと言葉に詰まった。
「いや、だから……化け物が残ってしまうから……。そ、そうだ! 化け物を研究するための施設が無い!」
「ここを使えばよかろう」
「――――!」
「知っておるぞ? お主が自分の研究するための施設部屋を、次々と広げておる事を―――」
そう言って東方不敗が、キョウジをじろりと睨む。それにキョウジは苦笑いで答えるしかなかった。
(あ、あれ…? おかしい…。課題が、次々とクリアされて行っている、ような…?)
何だか、別の意味で自分が追い詰められつつある事を感じて、キョウジは少し焦った。
「で、でも……それをやっちゃうと、世界中から、非難と敵意が―――」
「だからどうした」
東方不敗が一言の元に斬り捨てる。
「…………!」
「全く問題ないな」
ドモンが頷く。
「問題ない」
と、ハヤブサ。
「……だ、そうだ。キョウジ―――」
シュバルツが、何かもういろいろあきらめたような笑みを浮かべて、こちらを見ている。
(こ、この人たち……正気か? 何で、わざわざ世界を敵に回す方を選ぶ―――?)
キョウジは、開いた口が塞がらなくなるのを感じていた。
「いや、でも……世界中から非難されると言う事は、あちこちからちょっかい出されたり、交渉事を持ちかけられたりするわけだから…。そうなったら研究どころでは―――」
「その辺は問題なかろう。ある程度の交渉事ならワシも引き受けるし、お主が直接出て行かねばならんことが起きたとしても、幸いお主には、優秀な影武者がおる。そいつが表に立てばよかろう」
東方不敗の言に、皆の注目がシュバルツに集まる。
「影武者……」
(ああ―――なるほど、そうか)
東方不敗の言葉に納得したシュバルツは、ポン、と手を打つと、ものすごくいい笑顔でキョウジに微笑みかけてきた。
(雑事は任せろ! キョウジ!)
シュバルツの背後から、隠しようもない喜びのオーラがきらきらと滲み出ている。
(おい! 何だよ! その無駄に爽やかな微笑みは! うわ~~……歯とかものすごく光っちゃってる……)
シュバルツから発せられる眩しい空気に、キョウジはちょっと引き気味になる。
おかしい。
先程から、どんどん消されて行っているような気がする。
自分が、『死ぬ』方の選択肢が―――。
「で、でも……あの……!」
「何じゃ。まだ、何か不安なのか。キョウジ―――」
「――――!」
東方不敗に言われて、キョウジは初めて自分の気持ちに気づく。
「不安」なのではない。今、自分を支配しているのは「遠慮」だ。
「いいのだろうか」という気持ち―――。このまま自分なんかにこの人たちをつき合わせてしまっていいのか。この人たちの残りの人生を、自分の都合で食い潰してしまいかねない。それで、いいのか。
「……いいのでしょうか…。貴方がたには、貴方がたの人生があるのに……」
素直な気持ちを、言葉に落とす。このまま突き進んでいけば、先の見えない泥沼の中に突入するのが目に見えている。それに付き合わせるという事は、皆の残りの人生を自分が奪うも同然なのだ。そんな事が、許されるのだろうか。
「キョウジよ……」
東方不敗が一つ大きくため息をつく。
「あまりワシを見くびるな。この東方不敗、生半可な気持ちで、お主をここに連れてきとりはせん」
「…………!」
キョウジが驚いて顔を上げる。キョウジと目があった東方不敗が、にやり、と笑った。
「ワシはな。己が認めた者にしか手は貸さん。ワシは、『お主』だから手を貸した。『お主』だから、キング・オブ・ハートの書物も見ることを許可したし、アジトの改造も許可しておるのだ」
「マ、マスター……!」
東方不敗の口から、何か信じられない言葉を聞いたような気がして、キョウジはただただ呆然とする。
「もとより、乗りかかった船だ。お主が生きるために戦うと言うのであれば、ワシは、最後まで付き合うぞ」
「そうだよ、兄さん。俺だって―――」
「ドモン……」
声をかけて来た弟の方に、キョウジは振り向く。この弟こそ、真っ白な未来がある一人なのに―――。
「兄さん、俺……今度こそ、ちゃんと兄さんの役に立ちたい。あの時みたいに、兄さんを殺すんじゃなくて―――」
ここまで言ったドモンの瞳から、涙が溢れてくる。「デビルガンダム事件」の時は、兄を殺すために動いていただけに、こみ上げてくるものが、あるのだろう。
「生かすための戦い―――それを…ちゃんとしたいんだ!」
「ドモン……!」
(ドモン……!)
シュバルツは、思わず天を仰いだ。あの時、自分もドモンを助けてキョウジを殺すために動いていた。それだけに、ドモンの言葉が余計に胸に響く。
「俺も―――」
ハヤブサが、口を開いた。
「この戦いには、つきあう義務がある。龍の勾玉は俺の里の物だし、俺は、龍剣の使い手として、勾玉から離れるわけにはいかん」
「ハヤブサ……」
「そして何より―――勾玉を『封印』するのではなく、『消滅』させる事は、我が里の悲願でもある。……それが出来るのであるならば、俺は、協力を惜しまない」
「――――」
キョウジは、言葉を失うほかなかった。
みんな。
みんな、どうして―――。
「そうだな…。ワシの見立てでは、おそらく勾玉を消滅させる事が出来るのは、お主しかおらん。誰もが不可能だと思っていた、勾玉を例え一部でも体の外に出すことに、お主は成功した―――。お主に出来なければ、たとえ200年経とうが、400年経とうが、勾玉を消滅させる事など無理だ」
東方不敗の言葉に、皆が頷く。
「そんな……買いかぶり過ぎです。私は……」
皆の心に、キョウジの身体が震える。自分は皆に、そんなふうに思ってもらえる人間じゃないのに……。
「キョウジ……お主には見えないのか。お主の目の前に並んでおる、四つのコップが―――」
「…………!」
「それが、ワシらの心だ。ワシらの心は、とうに決まっておる。『お主を生かしたい』と、願い、手を差し伸べておるのだ」
「……………」
キョウジは、無言で目の前に並んだコップを見る。皆が一斉に、水をたたえて差し出してきてくれた、コップを。
「お主は、決して独りではない。後はお主だけだ。キョウジ―――」
キョウジは、何か言わねばと思った。しかし、うまく言葉が出てこない。
「何を遠慮することがある。手を伸ばせ。皆の手を取れ」
「…………ッ!」
いいのだろうか。
本当に、いいのだろうか。
手を、伸ばしてしまっても―――。
今までの『罪』が、これから背負わねばならない『責任』の重さが、キョウジを躊躇わせる。
「キョウジよ―――」
東方不敗は一つ大きく息を吐くと、キョウジに決断を迫った。
「はっきりせい! お主は、生きたいのか!? それとも、死にたいのか!!」
「――――!」
ビクッと、キョウジの身体が反応する。
いいのだろうか。
「生きたい」と、言っても。
「生きたい」とも、「死にたい」とも言えない存在を作り出してしまった私が、「生きたい」などと、言ってしまっても―――。
「…………」
葛藤する。
躊躇う。
だけど。
ああ、だけど。
あの時、自分に誓ったはずだ。
意識が戻ってから、たった一度だけ、自分で命を断とうとしたあの日に。
リハビリで直した足で、病院の屋上から、愚かにも飛び降りようとしたあの日に。
シュバルツに止められ、
ドモンに止められ、
レインに止められた。
「私は―――生きたいんだ!!」
シュバルツに、涙ながらに『嘘』を言わせてしまったあの日に。
どんなに苦しくても。
どんなに愚かでも。
生きる道を―――選び続ける、と……。
「生きる」とも「死ぬ」とも言えないシュバルツの命を、自分は背負っているのだから―――。
しかし、キョウジは、顔があげられなかった。膝の上で、ぎゅっと握りこぶしを握りしめ、小さな声で、絞り出した。
「………すみません。生きたい……です……」
その途端、誰かにガバッと抱きすくめられた。自分のすぐそばで赤いマントが、小刻みに震えている。
「兄さん……! よかった……! 兄さん―――」
「ドモン……」
ドモンの、嗚咽する声が響き渡る。それを抱きとめながら、キョウジの瞳にも、うっすらと光る物が浮かんでいた。
「全く―――世話の焼ける奴じゃな」
東方不敗がため息と共に口を開いた。
「生きる道があるのならば、生きればいいのだ。足掻ける道があるのなら、足掻けばいいのだ。何を遠慮することがあろうか。死ぬ事など―――いつでも出来るのだから」
「はい………」
そう言って頷くキョウジの頬に、涙が伝い落ちる。それを見た東方不敗が、やれやれ、兄弟そろって―――と、また、ため息をついた。
「ドモンよ。まだ泣くのは早いぞ? 事態は、まだ何も解決しておらん。やっとスタートラインに立った所だ」
東方不敗の言葉にドモンが「分かってますよ!」と、涙をぬぐいながら毒づいた。
「それにしても、兄さん……良かった……。あっさり死ぬんじゃないかって、俺もうそればかりが心配で―――」
ドモンの言葉に、キョウジが苦笑する。
「あはは……心配かけたな、ドモン。でも私には、まだ足掻ける道があったみたいだ……。ドモン、また、力を貸してくれるか?」
「もちろん! 兄さん! 喜んで!!」
キョウジの言葉に、ドモンが力強く頷いた。
「ところで、ドモン」
「何? 兄さん」
「お前……師匠の線、越えちゃっているけど、大丈夫か?」
「あ!!」
はた、と、気がついたドモンが、恐る恐る師匠の方に振り向くと、東方不敗が無言でドモンの方を見下ろしていた。
(破門―――!!)
不吉な二文字がドモンの頭の中で、ぐるぐる回る。
でも、後悔はしていない。自分は「生きる」と言ってくれた兄を、抱きしめずにはいられなかった。この喜びを、兄に伝えずして、他にどうしろというのだろう。
だから、線を越え、師匠に逆らったとしても、後悔など無かった。
(馬鹿弟子が……)
まっすぐ見つめ返してくるドモンに、東方不敗にあきらめにも似た表情が浮かぶ。
「……仕方あるまい。そもそも、最初に線を越えた時に、ワシも注意するのを忘れておった」
最初に線を越えた時―――それは、キョウジが勾玉を外に出せた事を、確認した瞬間だった。
倒れかけたキョウジの側に、全員が駆け寄った。その時すでに、ドモンは師匠の引いた線を越えていたのだ。
「よって今回は、『破門』は無しじゃ」
そう言って東方不敗は踵を返す。もともと、キョウジの意思を確認するために、ドモンの動きを封じるために行った線引きだ。キョウジの明確な意思が示された以上、ドモンを破門にする理由はとうに無くなっている。
「師匠―――」
ドモンはそう言って、師に向かって丁寧に頭を下げ、キョウジは、ほっと、小さく息を吐いた。
少し離れた所で、シュバルツも小さく息を吐いていた。
「―――死に損なったな……」
小さな声で、ポツリと呟く。
「―――チッ、斬り損なった」
「―――!?」
ギョッとなって声のした方に振り向くと、いつの間にかハヤブサが、自分のすぐ隣まで来ていた。
「…………」
シュバルツが、じっと自分の方を見ていると気がついたハヤブサが、シュバルツの方に振り返って、にやり、と笑う。
「冗談だ」
(お、お前が言うと、冗談に聞こえないんだけど……)
そう感じて、シュバルツが苦笑する。そんなシュバルツをハヤブサはじっと見ていたが、やがて、ふっと表情を緩ませた。
「―――大した『玉』だな。お前が守りたいと願った『キョウジ』というのは……」
「…………!」
驚くシュバルツの肩を、ハヤブサはポン、と叩くと、そのままキョウジの方に歩を進めた。
「キョウジ―――」
ハヤブサの呼び掛けに、キョウジが振り向く。
「改めて、お前に協力を申し出よう。お前を、斬るような展開にならない事を――祈る!」
そう言って、ハヤブサがキョウジに差し出した手を、キョウジは微笑みながら握り返した。
「ありがとうございます。心強いです」
「さあ、皆! 作戦会議を始めるぞ! さっさと寄って来んか!! 特にキョウジ―――お主がおらんと始まらん。決めている事を、とっとと話せ!!」
東方不敗の強引ともいえるその言葉に、キョウジは苦笑する。
「……全く。もう、どうなっても知りませんよ」
キョウジのこの挑戦的ともいえる物言いに、全員が「望むところだ!」と、にやりと笑って返した。
「これから始まるこの戦いより―――心躍る事は無い!」
東方不敗のこの言葉が、皆の心を代弁していた。
夜更け。
隠れ家からそっと抜け出す、二つの影があった。シュバルツとハヤブサである。二人には、キョウジがある程度まで検討をつけ絞り込んであった『敵』に対する内偵の任務が与えられている。
「―――シュバルツ……」
不意に、ハヤブサから声を掛けられ、シュバルツが振り返る。
「仕事に入る前に、一つ確認しておきたいのだが……その……」
珍しく、ハヤブサが歯切れの悪い物言いをしている。
「どうした?」
問い返してくるシュバルツに、ハヤブサは若干ためらいを見せてから、口を開いた。
「単刀直入に聞くぞ。……お前……」
「何だ?」
「人間じゃ、ないのか?」
「――――!」
ビクッとシュバルツが反応する。
「悪いが…昨晩の二人の会話を、聞いた」
「―――どこまで聞いていた?」
鋭い声音で問い返してくるシュバルツに、ハヤブサは、戦闘意思が無い事を手で示しながら答える。
「お前に、手裏剣を投げつけられるまで。……それ以上は、聞いていない」
「…………」
シュバルツは、しばらくハヤブサの事を推し量るように見ていたが、やがて、口を開いた。
「……そうだ。私は、人間ではない。キョウジに作られた―――アンドロイドだ」
「――――!」
ある程度推測していたとはいえ、シュバルツ自身に認められると、動揺してしまう己をハヤブサは自覚せざるを得ない。
「……………」
シュバルツは、そんなハヤブサをしばらく見つめていたが、おもむろにハヤブサに問いかけた。
「まだ―――私に何か聞くか?」
「…………!」
シュバルツの静かな声に、ハヤブサは顔を上げる。少し、哀しげに微笑んでいるシュバルツと、目が合った。ただ、彼の身体の周りに、いつか見たあの闇の気配が漂っているのが分かる。
ハヤブサは、逆にシュバルツに問い返した。
「………話したいか?」
「――――!」
「お前に、話す気があるのなら……俺は、聞く」
「…………ッ」
シュバルツが、ハヤブサから目を逸らす。しばらく、二人の間に静寂が訪れた。シュバルツの手が、微かに震えている。彼が、逡巡しているのが分かった。
「すまない、ハヤブサ―――。私は……」
シュバルツが、少し苦しそうに声を出す。それだけで、シュバルツがまだ、自分に話せる段階ではないのだと言う事が、ハヤブサには分かった。
「いい。無理に聞こうとは思わない」
「ハヤブサ……!」
「気長に待つさ。……キョウジのおかげで、たっぷり時間が出来そうだしな」
ハヤブサのこの言葉には、シュバルツは苦笑で応えるしかない。
「ただ―――」
「ただ?」
ハヤブサが、少し険しい顔をしてシュバルツを見つめた。
「本当に、キョウジを取り巻く状況が厳しい物になって、キョウジが、それに耐えられなくなってきたら……俺は、勾玉を再封印するために、動くかもしれない。…それでも、いいか?」
「――――!」
「俺も、出来ればそのような事はしたくは無いが……」
そう言いながら、ハヤブサは龍剣に目を落とす。この剣を持っていて、自分の生業が人斬りである以上、この役目は、自分にしか出来ない―――避けて通れない物であると、ハヤブサは自覚していた。これは、本当に最終手段であり、ある意味、汚れ役でもある。
だが、それを聞いたシュバルツは、安心したように微笑んだ。
「その心遣い……きっと、キョウジは感謝する。私もだ。……ありがとう…」
「――――!」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサは一瞬茫然とした表情を見せたが、やがて、ため息をついた。
「……俺は、『斬る』と、言っているんだぞ……。なのに、何故感謝されねばならない…。全く、お前と言い、キョウジと言い―――」
(やっぱり、ダブル馬鹿だ…)
何か、あきらめにも似た脱力感が、ハヤブサを襲う。
だが―――こういう『馬鹿』は、
嫌いではない。
「まあいい。お互い、仕事に戻ろう」
ハヤブサの言葉にシュバルツも頷く。
やがて、ギアナ高地の暗闇の中、二つの影がそれぞれの目的地に向かって、散っていった。
「第6章」
ハヤブサとシュバルツに、敵の内偵作業を頼んでから、二日が経過している。
そう、たった二日のはずなのだ。それなのに。
今、キョウジと東方不敗がいる部屋は、書類の山に埋め尽くされようとしていた。パソコンの方にも、先ほどから「スパムか!!」と、突っ込みを入れたくなるレベルで、メールの着信を告げる音が鳴り続けている。
「いや~、腕利きの忍者が二人もいるって、すごいねぇ」
キョウジが、書類の山に埋もれそうになりながら、ため息とともに苦笑する。この二日間で、シュバルツとハヤブサは、キョウジが「欲しい」と思っていた情報を、ほぼ手に入れてきてくれた。それも―――期待以上に。
突如、鋭い鳴き声とともに、一羽の鳥が部屋に飛び込んでくる。
「わっ! また来た!」
キョウジが慌てて持っているバインダーで頭を庇う。その鳥は、部屋を一回り旋回したかと思うと、足元から何かを下に落とす。それは、床に胡坐をかいて座り、書類を読みふけっていた東方不敗の頭を、過たずに直撃した。
「…………!」
無礼な鳥に少々むかつきながら、東方不敗は鳥が落として行った小さな筒状の物の蓋をあける。途端に、
ボン!
という音を立てて、筒の中から無数の書類が飛び出してきた。
「あ奴は一体どうやってこの中にこれだけの書類を入れておるのだ……。それと、あ奴はいったいこの鳥を、何羽飼っておるのだ!」
書類のシャワーを浴びながら、額に少々青筋を浮かべて、東方不敗はブツブツ文句を言っている。
「隼―――ですよね、これ……。やっぱり近くで見ると、格好いいなぁ」
のんきに鳥の事を評しているキョウジの傍には、キョウジの指示を仰ぐためと思われる二羽の隼が、とまっている。そこに、先ほど書類を東方不敗の頭にぶつけた三羽目の隼が、入ってきた。
「すまないな。お前の主人には、『もう帰って来い』っていう指示を出しちゃったから……もう、届けてもらうものは無いよ」
すまなさそうにそう言うキョウジに対して、隼は鋭く高い声で鳴いて答えた。
「キョウジよ―――やはり、化け物はこ奴らと手を組んだとみて、間違いないのか?」
そう言ってキョウジの側に寄ってくる東方不敗の手には、一つの軍需関係の会社の資料が握られていた。
「そうですね……。多分、ここで決まりでしょう。他の所も調べてもらったけど、それらしきものが出て来なかったから―――」
キョウジも、そう言いながら東方不敗が手にしている資料を覗き込む。そこには、「エヌルタ・ミニッションズ・カンパニー」という社名とともに、CEOであるシュトワイゼマンの写真が記されていた。
「……ハヤブサに調べてもらってたはずの所が、何か、テロっぽい襲撃に遭ったみたいですし……」
「……おそらく、その襲撃は、龍の忍者の仕業であろうな」
「へっ!?」
東方不敗の不敗の言葉に、キョウジは思わず素っ頓狂な声を上げてしまう。
「う~む…やはり、あの噂は真実であったか……」
「噂?」
「あ奴、忍びの癖に忍ばないらしいぞ?」
「はあ!?」
キョウジは、持っていた烏龍茶を落としそうになる。
「忍ばないから、見つかるが、返り討ちにした―――と、言ったところか。およそ忍びらしからぬ戦いをする奴よの…」
やはり、一度手合わせしてみたいものよ、と、言って笑っている東方不敗の横で、キョウジは頭を抱えていた。
(私が見当つけていた所は、どれも結構権力もあって財力もあって、えげつない事をしてそうな所ばっかりだったからなぁ…。潜入している先で、こっちの事件とは関係ない何かがあったのかな……)
見つかって、普通なら逃げるだけの所を返り討ちにして、相手方に壊滅的なダメージを与えている辺りに、ハヤブサの怒りの要素が加わっている事を感じてしまう。ハヤブサが「超忍」と呼ばれる所以を垣間見た気がした。
突然、部屋に5、6羽の隼が、一斉に乱入して来る。それは、まっすぐ東方不敗の頭めがけて書類の筒を落としてきた。
「うおっ!?」
流石に師匠である。今度の筒の襲撃は、見事に全部避けきった。
「―――誰が忍ばないって?」
頭の上から声がする。見上げると、天井の板が一枚外されていて、ハヤブサがそこから顔を出していた。
「お主は一体、この鳥どもにどんな教育をしておるのだ!」
東方不敗がハヤブサの顔を見るなり、いきなり文句をつけている。余程この鳥の態度に腹をすえかねたのだろう。
「相手に確実に書簡が届いていいだろう?」
ハヤブサがしれっと言い返す。これで東方不敗のご機嫌を損ねようと、お構いなしのようだ。
「おまけに書いてある文字―――独特の忍び文字を使用しおってからに…!」
「問題ないだろう? 情報をやり取りするのに暗号を使うのは忍者の基本だ。第一、キョウジは読めたようだし―――」
そう言ったハヤブサに対して、キョウジが意外な言葉を発してきた。
「面白い連絡手段だよね、それ…。最初解読するのに、私は5分もかかっちゃった」
「――――!?」
東方不敗とハヤブサが、驚いて同時にキョウジの方を見る。
「……知っていたのではなかったのか?」
「シュバルツに教えてもらって、そういう文字の存在がある事は知っていたのですが…実際に見たのは今回が初めてです」
東方不敗の問いに、キョウジは笑顔を見せながら答えた。
(こ、こいつ―――! 初めて見た忍び文字を、あっさり使いこなしたっていうのか―――!?)
「忍び文字」と、一言で言っても、文字の種類も使われ方も、忍びの部族によって、それこそ多岐にわたっている。普通の人間が一見しただけでは、何が書かれているのかすら分からないのが当たり前なのだ。それなのに、キョウジから送られ来た返事の書簡には、ハヤブサが使用した忍び文字を、違える事無く使用されていた。だからハヤブサは、キョウジはシュバルツか東方不敗に、この文字の読み方をあらかじめ教えてもらっていたのかと、勝手に解釈していたのだが。
(…やっぱりこ奴の脳みそは、多少人間離れしておるな……)
そう感じて東方不敗も改めて舌を巻く。よく考えたら忍びの一族の中でも数が少ない隼の一族の文字を、キョウジが最初から知っていたはずが無いのだ。
「キョウジ―――のんびりしている場合ではないぞ」
その声と同時にシュバルツが部屋に入ってくる。
「敵方に、お前がここにいる事をかぎつけられた。間もなくこちらに大部隊が送り込まれてくる」
「――――!」
シュバルツのその言葉に、東方不敗とキョウジが同時に驚く。
「貴様! そう言う大事な事を、何故もっと早く書簡にて知らせて来んのか!?」
「―――知らせたぞ? 最後のメールで」
シュバルツの言葉が終わると同時に、パソコンからメールの着信を知らせる音が、軽快に鳴り響いた。
「……もしかして、今着いたこれがそうかな?」
「ん?」
キョウジの言葉に、シュバルツが首を捻る。
「おかしい……。私の計算では、もう少し早くメールが着く筈だったんだが…?」
「俺も、最後の書簡で知らせた」
「どれだ!!」
ハヤブサの言葉に、東方不敗から激しい突っ込みが入る。
(連絡手段よりも、本人が帰ってくる方が早い忍者って、いったい……)
キョウジは軽く眩暈を覚えた。
「それにしても、凄い情報の量だよね…。建物の設計図や警備状況、社員リストとか会社の権益や経歴とかはともかくとして、シュトワイゼマンの囲っている愛人の数とか、小学校時代の成績とか、表沙汰に出来ない金の流れとか、癒着している議員とか―――」
こんなにこの会社の事を知っちゃって、私は一体どうすればいいんだろう、と、キョウジは半ば途方に暮れている。
「フフフ…。その情報を生かすも殺すもお主次第だ。頭に刻み込んでおけばよかろう」
「あははは……頑張ります」
東方不敗の言葉に、キョウジはもう苦笑するしかない。
「兄さん!」
ドモンが、勢いよく部屋に飛び込んでくる。彼が開けたドアの風圧で、積み重ねてあった書類が舞い上がった。
「こりゃドモン! この部屋に入る時は静かに入れと何度も言うたであろうが!!」
舞い上がった書類を手早く回収しながらドモンを怒鳴りつける東方不敗に、「すいません!」と、返しながら、ドモンも慌てて書類の回収作業を手伝った。
「ドモン、シャッフルの皆とは、連絡がついたのか?」
キョウジからの問いかけに、ドモンが頷く。
「ああ。こちらから合図を送れば、皆各地で指示通り動いてくれる手はずになっている。―――それよりも、兄さん!」
「何だ?」
「ついに敵が現れた! まっすぐこっちに向かって来ている!」
――――来た!
ドモンの言葉に、それぞれの面に戦いへ向かう決意の表情が現れる。
「いよいよ始まるというわけだな…。我らの戦いが―――」
東方不敗の言葉に、皆が頷く。
「俺は、いつでも行けるぜ!」
「こちらも、問題ない」
「私もだ」
皆が一斉にキョウジを見る。その眼差しに、キョウジは笑顔で答えた。
「それでは皆さん、手筈通り―――頼みます」
「応っ!」
掛け声と同時に、皆が一斉に部屋から姿を消す。それと同時に、一頭の馬が部屋に入ってきた。東方不敗の愛馬、風雲再起である。
「それじゃあ、私たちも行こうか。よろしくな。風雲再起」
キョウジの言葉に、風雲再起は嘶きを持って答えた。
「―――本当に、こんな所にキョウジ・カッシュは居るのか?」
輸送機からギアナ高地に降り立ちながら、ダレクはいまだ半信半疑だった。キョウジ・カッシュをロストしたのは日本のはずだったからだ。だが、今回の任務についてきた仮面をかぶった男が、彼らをギアナ高地へと、強引に誘った。
「……貴方がたが、もっと早くキョウジ・カッシュと『龍の勾玉』を手に入れてきてくれてさえいれば、私も強引についてきたりはしなかったのですがね……」
そう言いながら、仮面をつけた魔道師は、強風に黒のフードをはためかせながら、ダレクにぼそりと呟く。
「今回の遠征で、『龍の勾玉』を手に入れる事は、シュトワイゼマン様のたっての願いでもあり、我が神『黒の女神』の復活のためでもある……。その女神が、私に言ったのだ。『龍の勾玉は、ギアナ高地にあり』とな。ゆめゆめ疑うことの無き様に―――」
「フン……」
魔道師の言に、ダレクは鼻を鳴らして答えた。大体、己の正体も明かさないこの胡散臭さの塊のような存在を、ダレクは好きにはなれない。この男が自分の主でもあるシュトワイゼマンのお気に入りでなかったら、とっくに輸送機から叩きだしている所だ。
おまけに、ダレクの機嫌をもう一つ損ねる要因があった。今回の作戦には、残月率いる忍者部隊までもが一緒に加わっているのである。これも、仮面の男がシュトワイゼマンに強く進言したからだと、後から聞いた。
(たかだか3人の人間相手に、300人の精鋭部隊と50人の忍者部隊―――大げさすぎる)
そう感じてため息をつく。忍者部隊などいらない。300人の我が精鋭だけで十分だ。
そして、今度こそ圧倒的。圧倒的な武力だ。
強いて注意する事と言えば、同志討ちを避けねばならんということぐらいか。
銃が通用しないのは分かっているから、今回の部隊は肉弾戦に特化した装備を配備している。兵士たちの力を何倍にも高める事が出来るパワードスーツを、全員に抜かりなく着用させていた。自分用にも、特注品を用意させている。合成獣の割合も増やした。前回は望めなかった空からの援護―――ヘリ部隊も控えている。
(見ていろ――! 今度こそ、あの3人を無様に地面に這いつくばらせてやる!)
ダレクの面に、自然と凶悪な笑みが浮かびあがっていた。
「大佐! 各部隊、配置につきました!」
部下からの報告に頷くと、ダレクは右手を上げた。
「よし! 陣を崩さずに進軍だ! 哨戒部隊は警戒を怠るな!!」
「了解!」
ダレクの部隊が進軍するのを見届けてから、残月の部隊も動いた。
「我らも動くぞ…。リュウ・ハヤブサとキョウジ・カッシュの姿を見つけたら、必ず報告するように」
「はっ」
声と同時に忍者部隊の中の何人かが森の中へと姿を消していく。
「……………」
仮面の魔道師はそんな部隊の動きを見つめながら、近づきつつある勾玉の気配に全神経を集中させていった。それは、確実に、自分の方に近づきつつある。いや―――自分の方が、勾玉に近づきつつあるのか。
その時、上空のヘリ部隊と、残月が放った斥候部隊から、同時に報告が入った。
「キョウジ・カッシュを発見しました!」
「何っ!? どこだ!?」
問い返すダレクの声に、ヘリから返答が返ってくる。
「11時方向、拓けた丘の上です!!」
報告の声に合わせて、全員が丘の方に視線を移す。するとそこには、確かに一匹の白い馬と、それに跨ったキョウジ・カッシュの姿があった。
(キョウジ・カッシュ……!)
その姿を認めた仮面の魔道師が、文言を唱え、手をかざす。すると、キョウジの胸のあたりに、勾玉の反応を示す白い光が出現した。二人の距離は、かなり離れている。それでこの文言を届かす魔道師の魔力は、相当なものであると言えた。
「勾玉……! おお……!!」
魔道師の身体が、ぶるぶると震えだす。
「あの者をここに連れて参れ!! それを成し遂げた者は、シュトワイゼマン様に進言して、思いのままの褒美を取らせるぞ!!」
魔道師のこの言葉に、兵たちの士気が一気に上がった。うおおおっ! と、各々が雄たけびを上げると、丘の上に無防備に佇んでいるキョウジに向かって殺到する。
(敵方にも勾玉の波動を感じ取れる者がいる、と、言っていた、ハヤブサの言葉が、これで証明されたな……。シュバルツに囮を頼まなくてよかった…)
胸元に現れた勾玉の光を見つめながら、キョウジはそんな事を考えていた。「キョウジが実は二人いる」という情報は、敵方には絶対に渡してはいけない物の一つだ。だから今はシュバルツも、覆面をかぶって行動をしている。
「キョウジよ、大丈夫か?」
キョウジの耳元のイヤホンから東方不敗の声が聞こえてくる。
「大丈夫ですが……流石に壮観ですね」
口元のマイクに向かって、微笑みながら答える。自分に向かって軍隊が殺到してくる光景なんて、そうそう見れるものではない。
「ただ―――強いて言うなら、ヘリ部隊が気になるかな……」
軍隊の上をホバリング飛行をしている四台のヘリを見ながら、キョウジは呟いた。空からいろいろ見渡せるヘリは、こちらが仕掛けてあるトラップの類なども見破ってしまう可能性がある。
「―――任せろ」
イヤホンの向こうから、ハヤブサの声がした。
「現在目標の周りに敵影は無し。単独で行動している模様―――」
ヘリに乗っている兵たちは、標的であるキョウジの方に注目していた。それ故に気がつかなかった。音もなく背後から滑空してくる、黒の忍者の存在に。
ガンッ! という音とともに、ヘリのバランスが一瞬崩れる。
「!?」
ヘリの中の兵たちが、異常を感知した時には、もう遅かった。破壊音とともに、外から壁を突き破ってきた刀が、激しい金属音とともに、一直線に壁を走っていく。
ヘリから刀を引き抜いたハヤブサが、トン、と軽くヘリを蹴って、次の目標に向かって跳躍する。ハヤブサが離れた瞬間、そのヘリは真っ二つに割れ、大爆発を起こした。
「何が起こった!?」
別のヘリに乗っていた兵士が、異常に向かって反応した瞬間。
ガシャン!!
ガラスが割れる音とともに、刀が外から突きいれられる。
「――――!」
外にいた黒の忍者と目が合った。
「哈――――――ッ!!」
次の瞬間、黒の忍者が裂帛の気合とともに外の壁を走りだす。それと同時に、ヘリの壁も切り裂かれていく。ハヤブサが離れた瞬間、そのヘリも爆ぜた。
「敵襲!?」
三台目のヘリの乗組員が事態を把握しかけた瞬間。
「高熱源体接近! 避けられません!!」
それが、そのヘリで交わされた最後の会話となった。
「石破天驚拳!!」
叫び声とともに、金色に光る巨大な拳が飛んできて、そのヘリが破壊される。残った一台も、プロペラにネットの様な物が絡まって、失速しながら墜ちて行った。
「何だと!?」
ダレクは驚愕に目を見開いた。キョウジ・カッシュ発見からわずか30秒。あっという間に四台のヘリを失ったことになるのだ。ダレク自身にも、兵たちの間にも動揺が走る。
だが、指揮系統を立て直す暇は与えられなかった。
キョウジに殺到しようとしていた兵たちの中央付近に、一本のクナイが投じられる。それが地面に突き刺さった瞬間、激しい光と爆風の乱流を巻き起こした。
「て、敵襲―――ッ!! 敵襲―――ッ!!」
光によって視力を奪われ、混乱した兵たちの何人かが無暗に発砲する。
「光と風だけだ! 落ち着かんか!!」
ダレクが兵たちを何とか鎮めようとするが、兵士たちの怒号と悲鳴にかき消されて、なかなかその声が届かない。そうしている間に、同志討ちによって何人かの兵たちが倒されて行った。
「発砲を止めろ! このままでは同志討ちに―――!」
その言葉が終わらぬうちに、ドゴォッ! という音とともに、混乱している隊の一角の兵たちが天に向かって撥ね上げられる。
(本物の、敵襲!?)
ダレクが茫然としている間にも、兵たちの間を走り抜ける黒い風が、手当たり次第に兵たちを撥ね上げ、切り刻み、飯綱落としを喰らわせている。
(リュウ・ハヤブサ―――!)
黒い風の正体に、残月は気がついた。
(残月―――!)
自分に送られてくる鋭い視線に、ハヤブサも気づく。土埃と血しぶきと、悲鳴が飛び交う混乱の中、二人の忍者の視線が、しばしの間ぶつかった。
先に視線を逸らしたのはハヤブサであった。
(今は、敵のかく乱が目的。残月に構っている場合ではない)
ハヤブサは再び、混乱する兵たちの中へと突っ込んでいく。
(―――逃がすか!!)
自分の存在がハヤブサに無視されるような格好になった残月は、歯ぎしりしながら忍者隊に命を下す。
「隊を二手に分けるぞ! 一隊はキョウジ・カッシュに向かえ! もう一隊は、儂に続け!」
「はっ!」
残月の命に従った忍者隊が、混乱する兵たちの間を錐を押しこむように一直線に突き進んでくる。
(引き潮か……)
ハヤブサは、引き際を悟った。
自分に狙いをつけている忍者隊を、兵たちの混乱をさらに煽るような場所に誘導しながら、兵もなぎ倒しつつ、その場からの離脱を試みる。
「キョウジ―――。兵達以外に、忍者隊も来ている」
走りながらハヤブサは、キョウジへの状況報告も怠らなかった。
「忍者隊の動きは、どんな様子ですか?」
キョウジの問いに、ハヤブサは的確に答えを返す。
「隊を二手に分けたようだ。一隊は、俺に向かって来ている」
「そうですか……」
キョウジからしばし思案するような沈黙が返ってきた。
「忍者隊の数を減らしつつ、ポイントHまで誘導する事は出来ますか?」
「問題ない」
ハヤブサは手短に返事を返しながら、己の役割を理解する。
「キョウジ。忍者隊がそちらにも向かっている。注意しろ」
「分かりました」
ハヤブサとの交信を終えたキョウジは、風雲再起に声をかけた。
「じゃあ、私たちもそろそろ動こうか。風雲再起―――」
キョウジの声に応えるように、風雲再起も、ブルルルッ、と声を立てた。
丘の上に佇んでいたキョウジが、不意に馬首を返す。それを見た兵士の一人が叫んだ。
「目標が逃げるぞ!!」
「逃がすか! 追え!!」
前方の兵士たちは、そのままキョウジに向かって突っ込んでいった。この戦いは、キョウジ・カッシュの身柄を確保さえすれば終わる。そして何より―――キョウジを捕らえたら、破格の報奨が待っている。それ故に、キョウジを追う兵士たちの姿勢は、自然に前のめりな物となっていった。
追う兵士たちの前方に、丘から降りて来たキョウジが現れる。彼は少し馬を走らせると、そこでピタリと止まって振り返った。
「あの~……貴方たち、そのまま前に進むと……」
キョウジが何か小さな声でこちらに向かって言っている。しかし、兵たちはそれには構わずキョウジに向かって殺到しようとした。その瞬間―――兵士たちの踏み出した足の下から、地面が消えた。
「うわあああああ―――!!」
自然に出来ている地面の亀裂の上に被せてあったシートごと、10人ぐらいの兵士たちが、奈落の底へと落ちていく。
「危ないですよ―――と、言おうとしたんだけど……遅いか」
「―――おのれ!」
落下を免れた兵たちが、キョウジに向かって発砲する。だが、その銃弾がキョウジの身体に届く前に、その前に飛び込んできた赤いマントの男によって、総て防がれてしまった。
「兄さんに話があるっていうんなら、俺を通してもらわないとな!」
そう言いながらドモンは、受け止めた銃弾を下にバラバラと落とす。
「な――――!!」
銃が通用しない瞬間を目の当たりにしてしまった兵士たちは、一瞬怯んでしまう。その隙を、ドモンは逃さなかった。
「でぇい!!」
ドモンの、極限まで練り込まれた『気』が、拳を通して発射される。それは、巨大な拳の形を作って、兵士たちに襲いかかった。ドォン!! という音とともに、ドモンの真正面にいた兵たちが吹っ飛ばされて行く。
「―――ドモン、そろそろ逃げるぞ」
それを見届けたキョウジが、ドモンに声をかけた。
「了解! や~い! お前ら! 悔しかったらここまで来てみろ~!」
そう言ってドモンは、ご丁寧に「あっかんべ~」までしてから踵を返す。あからさまな挑発行為だ。だがこの挑発は、ダレクには絶大な威力を発揮した。
「お、おのれ~! 許さん!!」
ダレクの顔色が、見る見るうちに朱に染まっていく。
「奴らをひっ捕らえてここに連れて来い!! 八つ裂きにしてやる!!」
幸い、目の前にある自然に出来た地面の亀裂は、飛び越えられない距離ではなかった。
「追えッ! 追え―――ッ!!」
ダレクの怒号とともに、兵士たちは逃げたキョウジ達を、猛追撃しだした。
だが―――この追撃命令を出した事を、ダレクはすぐに後悔することになった。
キョウジを追いかけているうちに、いつの間にか谷間に誘導される。兵の半数以上が谷間に侵入した瞬間に、頭上から巨大な岩が大量に降ってくる。これをかろうじてかわして尚も追撃を続けた兵士たちも、地雷原に踏み込み、落とし穴にはまり―――揚句、「浅い」と思って渡りだした川で、水攻めに遭って大半が流された。気がつけば、300人いたはずの兵士の数が、いつのまにか80人以下にまで減らされていた。しかも、大半が負傷したり疲労したりしている。
「ど、どういうことだ……? 敵勢力は、僅か3人ではなかったのか…?」
ダレクは茫然としながら、傷だらけになった自分の隊と、目の前にいる二人の姿とを見比べた。敵の戦力は、あそこにいるキョウジ・カッシュとドモン・カッシュ、それに、東方不敗とか言うあの老人だけのはずだ。いや、それ以外に「リュウ・ハヤブサを見た」という報告もあったような気がする。しかし、それを入れたとしても―――4人。
(そう言えば、あの老人の姿が見えない…。まさか、あの老人が一人で、これだけの罠を発動させたとでも言うのか―――!?)
馬鹿な! と、ダレクはすぐその考えを打ち消す。しかし、皮肉な事に、ダレクのその読みは当たっていたのだ。
(フフフフ……キョウジの奴め…。この老人をこき使いおってからに…)
破壊された堰から勢いよく流れ落ちる水を眺めながら、東方不敗はにやりと笑う。
敵が襲ってきた場合に備えて迎え撃つ場所、逃走ルート、罠を仕掛ける所、発動させるタイミング―――何度も何度もキョウジと打ち合わせをした。それでもここまでうまくいくとは、正直思っていなかった。キョウジが冷徹に戦場全体を見渡し、こちらが動くタイミングも図りながら、自分に殺到してくる軍隊を見事にコントロールしきった結果と言えよう。
(戦嫌いが聞いてあきれる―――やはり、奴はいっぱしの軍師じゃわい)
東方不敗はふと思う。「デビルガンダム事件」の際、DG細胞に侵されていないまともな状態のキョウジと手を組めていたなら―――自分の大望も、実現できていたのではないだろうかと。
だが、その考えはすぐに否定した。キョウジはあれで、善意の塊のような男だ。「人類抹殺」などと言った物騒な事柄には、絶対に手を貸さないだろう。
(さあ、ここにきて敵勢力の7割が消失。残った勢力も被害甚大―――。こ奴らはどう動く?)
腕を組みながら、指揮を執っているであろうダレクの方を見る。まっとうな指揮官なら、ここで退却を命じる所だ。兵達がこの状態では、正直言って戦にならない。
「おっさんたち、どうした!? もう追いかけて来ないのか?」
ドモンが、切りたった渓谷の上に掛けられた、人一人通るのがやっと、という細い橋の上で、なおもダレク達を挑発している。橋を渡りきった所に、キョウジが控えていた。
こいつさえ討ちとれば―――と、生き残った兵たちは、果敢にドモンへと挑んでいく。しかし、この細い橋の上では、必然的に1対1の状況にならざるを得ない。いくらパワードスーツで強化しているとはいえ、1対1でドモンに戦いを挑んで、勝てる存在などなかなかいない。兵士たちは、次から次へと橋から叩き落とされていた。
「雑魚じゃ物足りない! 大将を出せ!!」
そう言いながらドモンは、息一つ乱さず、ファイティングポーズをとっている。
「お、おのれ~~……!」
歯噛みするダレクに、部下が心細そうな目を向けてくる。完全に勝敗がついてしまっているような格好だ。ついに、ドモンに挑もうとする者は、誰もいなくなってしまった。
「追ってこないんなら―――俺達はもう行くぜ!」
ドモンがそう捨て台詞を吐きながら、踵を返す。橋を渡って兄と合流し、そのまま走り去った。橋を残したまま―――。
しばらく走った所で、ドモンとキョウジは東方不敗と合流した。
「ご苦労様でした。マスター」
東方不敗の姿を認めたキョウジが、にこやかにその労をねぎらう。
「フン、肩慣らしにもならん。……キョウジよ。お主こそ、囮役ご苦労だったな」
「私は何も…。ドモンと、この風雲再起のおかげです」
そう言いながら、キョウジは馬から降りる。風雲再起は、嬉しそうに東方不敗の元に寄って行った。
「ところで兄さん。橋は落とさなくてもよかったの? ここを過ぎると、もうポイントHまで罠らしい罠は無いんだろう?」
ドモンが、少し心配そうにキョウジに聞いてきた。かなり痛めつけているとはいえ、まだ追ってくる可能性は十二分にある。それなのに、わざわざ追ってくるための道を残しておく必要はないのではないか―――と、言うのがドモンの意見だった。
「そうだね。確かにこのルートでは、罠らしい罠はあそこまでもう無い……だけどね、ドモン」
キョウジは、にこやかな顔をドモンに向けた。
「あの橋を渡れる人間は……ちょっといないよ」
「―――? どういう、こと?」
ドモンは、キョウジの言葉が理解できず、きょとんとしてしまう。それを見た東方不敗が、にやりと笑った。
「フフフフ。ドモンよ。あ奴らは、ここに来るまでに、さんざん罠に痛めつけられておる。だから、進めぬのだ」
「何故ですか?」
「橋の向こうに、罠がある―――と、思ってしまうからよ」
「…………!」
東方不敗の言葉に、ドモンは目を見張る。
「ドモンよ―――。覚えておくがよいぞ? 兵法とは詭道だ。即ち、相手の裏をかくことが肝心となってくる。お主も兵法書を読んで、よく学べ」
「う~~ん……」
ドモンはしばらく考え込むような仕種をしたかと思うと、ポツリと漏らした。
「俺なら、気にせず橋を渡っちゃうけどなぁ……」
ドモンのその言葉に、東方不敗はズルッと足を滑らせ、キョウジは苦笑した。
(馬鹿の一念、岩をも砕く、だな……)
キョウジはそう思ったが、口には出さなかった。言ってしまったら、多分ドモンを怒らせる。
「忍者隊と、あのダレクという人が、もう少し連携が取れていたら―――また、違った展開になったのでしょうけどね……」
キョウジの言葉に東方不敗も同意する。
「あの忍者二人が、うまく忍者部隊をかく乱したのであろうな―――」
その頃ダレクは、誰もいなくなった橋の手前で脂汗を流しながら考え込んでいた。
(一体、この向こうの林には、どれだけの敵勢力が潜んでいるんだ…? どれほどの罠が、仕掛けてあるのだ……?)
わざわざ橋を落とさずに残したという事は、この橋を自分たちが渡る事を、相手方は承知している―――ということになる。と、言う事は、この橋の向こうには、さらなる罠が張り巡らされている、と考えねばならない。
「そう言えば忍者部隊―――忍者部隊は、どうした!?」
今頃になってダレクは忍者部隊の存在を思い出す。こういう時に罠の有無とか潜んでいる敵勢力とかを調べるのに、忍者はうってつけのはずだ。しかし、部下の誰に聞いても、「さあ?」と、首を捻るだけであった。
(ええい! 肝心なところで役に立たん奴らめ!! 一体何をやっているのだ!!)
その頃忍者隊は、足止めを喰らっていた。二隊に分けたうちの一隊は、ハヤブサによって。そしてもう一隊は―――シュバルツによって。
シュバルツは、ハヤブサが奇襲を仕掛けている間に、気配を消して敵陣に紛れ込んでいた。もし、忍者隊とダレクの間で連携が取れているのであれば、それをかく乱するつもりでいた。しかし、忍者隊とダレクの間には、連携をとれているような動きがあるどころか、互いの存在を無視するような様相さえ見せている。
(もし、ダレクが忍者を有効利用できていたら……もう少し、違った展開になっていだだろうにな……)
シュバルツは苦笑しながら、ハヤブサについて行った忍者隊とは別の忍者隊に、狙いを絞った。
キョウジとドモンの挑発に、ダレクは頭から突っ込んでいく。だが、案の定忍者隊は、ダレクの様に突っ込んで行こうとはせず、罠の有無を確かめるべく、斥候隊を放っている。
シュバルツは、あえて『キョウジ』の格好をして、極限まで気配を消して忍者隊を指揮していると思われる人物のそばまで寄って行く。そして、その真後ろで―――いきなりその姿を現した。
「こんにちは」
「!!!」
突然自分たちの隊のど真ん中に現れたこの大胆不敵な目標に、誰もが驚き、動揺した。
「キョ、キョウジ・カッシュ―――!!」
頭目のその言に、シュバルツはにっこり笑って答える。次の瞬間、シュバルツはいきなり懐から取り出した煙幕弾を投げつけた。
ドォン! という音とともに、辺りの視界が一気に悪くなる。不意を突かれた忍者隊は、完全に混乱した。その混乱の最中、シュバルツは間を縫うように、ついでに何人かを倒しながら走り抜けた。
「――――!」
煙幕の合間に、林の方へと走り去るキョウジの後ろ姿が頭の目に映る。
(どういうことだ!? キョウジ・カッシュは、馬に乗ってあちらの方向に逃げたはずだが……!)
だが、「キョウジ・カッシュは優れた忍者」という情報が、却って頭の判断を誤らせる結果となった。『忍者』であるから、神出鬼没なのは当たり前―――と、思ってしまったのだ。
「我らは林の中に逃げた目標を追うぞ!」
残月から離れた一隊は、こうしてシュバルツの方を追い始めた。見事に、忍者隊とダレクの隊の分断に成功したのである。
林の中にキョウジを追って入ってきた忍者隊は、いきなりキョウジを見失った。
その代わり、姿の見えない敵からの襲撃を受け、次々と仲間が倒されて行く。
(罠―――!?)
頭がそう思った瞬間、前方に、自分たちを襲ったと思われる人間が姿を現した。覆面をかぶったその人物は、革のロングコートをひるがえしながら林の奥へと走り去っていく。
「奴を追え!」
忍者隊は懸命に目標を追いだした。キョウジ・カッシュが『忍者』であるというのなら―――今逃げて行った人間こそが、キョウジである可能性が極めて高いからだ。
だが、追いだしてすぐ、異変に見舞われた。
「ギャッ!」
「うわぁ!?」
木の枝から枝へ飛び移ろうとした仲間が、次々と落下していく。
(何だ!?)
頭自身も、目の前の木の枝につかまろうとした瞬間、いきなりその枝が折れて下に落ちてしまった。太さも強度も充分にありそうな枝が、何故いきなり―――と、頭はその枝を見て、絶句した。枝にあらかじめ切れ込みが入れられていたのだ。
「くそっ! 姑息な手を―――!」
枝を叩きつけて、再び後を追う。手裏剣が届く距離まで詰めた、と判断した頭は、迷うことなく手裏剣を放つ。だが、あっさりかわされた。まるで、後ろにも目があるのかのように。逆に、相手の放った手裏剣が、次々と部下の命を奪って行く。
「おのれ!」
距離を詰めるべく、手を伸ばして目の前の木の枝をつかむ。しかし、その枝がまたしても折れた。
「…………ッ!」
あまりにも人を小馬鹿にしたような罠に、頭は完全に逆上した。躍起になって、シュバルツを追いだした。そしてそれ故に、気がつかなかった。シュバルツの懐から―――黒い粉がさらさらと流れ落ちていた事に。
林の中の少し拓けた空間に出て、シュバルツは足を止め、振り返った。
(ここらでいいか)
懐から何かを取り出して、ぽいっと投げ捨てる。
「!?」
シュバルツの不審な動きに、頭は思わず足を止める。
「何をやった?」
頭の問いに、シュバルツは「別に」と、しれっと答える。
「それよりも、忠告する。お前たちは……」
シュバルツがそう言いかけた瞬間。シュバルツの背後から、黒い影が飛び出してきた。
「―――!」
シュバルツは、咄嗟に身をよじって避ける。飛び出してきた黒い影は、ギィン! と、金属音を響かせると、二つに分かれて着地した。
「ハヤブサ―――!」
「残月殿!」
シュバルツと忍者隊が、同時に声を上げる。
「シュバルツか!」
シュバルツに気がついたハヤブサが、声をかける。ハヤブサを追って、更に2、3の黒い影が林から飛び出してきた。二人はそれを、手裏剣を放って叩き落とす。
「おい、ハヤブサ。ここは―――」
声をかけるシュバルツに、ハヤブサはにやりと笑って答えた。
「知っている。『仕掛け』があるのだろう? だから来たんだ」
(仕掛けだと―――!?)
二人の会話の内容に、残月は周りを見回す。そして気付いた。あちこちの木に、不自然な切れ込みがある。そして、その中に―――。
(火薬―――!!)
仕込まれている。
木の中に。
草陰に。
地面の上にすら。
残月は悟った。ここは火計の、爆心地だと―――!
「皆! ここから離れ……!」
「遅い!!」
残月の叫びとシュバルツの言葉が被さった。それと同時に、シュバルツの足元から、一気に炎が四方に走る。ドォン!! という大音響とともに火柱があちこちから立ち上がり、あっという間に辺りは火の海に包まれた。
「うわああああっ!」
「た、助けてくれ~!!」
末期の叫びを上げながら、忍者隊が次々と炎に呑まれていく。
「お、おのれ……!」
残月は咄嗟に飛びのいて、炎に巻かれるのを何とか免れた。しかし、火勢が強く、ハヤブサの姿を見失ってしまう。それどころか、この迫りくる炎。自身の身すら危うい。
(ちらっと見た、あの覆面の男の仕業か……! しかし、あの男の気配…どこかで……?)
懸命に考えるが、咄嗟に思い浮かばない。残月は舌打ちしながら後退した。
シュバルツが仕掛けた火計の炎は、キョウジ達がいる場所からも見えた。
「やっておるな……。もしかしたらポイントHまで行かずとも、この勝負片がつくやもしれん」
「そう、願います」
東方不敗の言葉に、キョウジも頷く。今のところ、ダレクの隊があの橋を渡ってくるような気配はない。あの火計も、シュバルツが発動させたものだとしたら、確実に忍者隊にダメージを与えているだろう。だが、キョウジは少し険しい顔になっていた。
「心配せずとも、相手方の被害は甚大だ。まっとうな指揮官なら、退却を命じる」
キョウジの不安を払拭させようと、東方不敗はそう告げる。しかし、キョウジはそれには答えなかった。
「……………」
(そう、『まっとうな』指揮官ならば、ここで退却を命じる……)
隊は分断され、兵の戦意は喪失しつつある。このまま引いてくれれば、これ以上余計な犠牲も出さずに済む。そしてこちらは、向こうの戦力が整わないうちに、化け物の制御システムがあるであろう、敵本部への奇襲を敢行する。これが―――今、キョウジが頭の中で組み立てている、おおよその戦いのシナリオだった。
ただ、この作戦を実行するにあたって、まだいくつかの不安点がある。
おそらく、化け物を制御するシステムは、化け物のすぐ傍に存在している筈だ。シュバルツ達に調べてもらった資料の中から、化け物がいるであろうと思われる候補地はいくつか上がっているのだが、それがまだ一つに絞り切れていない。
そして―――もう一つ。
(私の体内にある勾玉を光らせる事が出来た存在―――これが、気になる……)
このような事が出来る、という事は、勾玉もしくは化け物と深く縁のある者の可能性が高い。それが、この戦場に来ている。
この存在は、果たして『まっとうな』指揮官か?
キョウジは自問自答する。今のところ、敵方の指揮官は、ダレク。だが、この戦場に出てきている存在は、何が何でもこの勾玉が欲しいはずだ。それが―――このまま引き下がるだろうか?
「……来るかもしれない」
「え?」
兄の、緊張を帯びた声音に、ドモンが思わず振り向く。
「マスター! シュバルツとハヤブサに、ここに来るよう合図を送ってください!」
「キョ、キョウジ?」
キョウジの必死の形相に、東方不敗は少し戸惑う。だが―――キョウジの中ではもはや「不安」ではなく「確信」になりつつあった。
「早く―――! 間に合わないかもしれない!!」
(くそっ! 退却すべきなのか!?)
傷だらけになっている自分の隊の兵と、どうしても渡れない橋を見ながら、ダレクは唸っていた。相手の戦力を、たかだか3人と侮った。その結果がこれだ。
あの男は、姿をくらましている間に協力者を得たのかもしれない。そうでなければ、こちらがこうも一方的に、叩きのめされるはずがない。
(作戦の練り直しだ)
ダレクは思った。ここは一旦引いて、相手の戦力を改めて分析して、それからもう一度来るべきだ。これ以上勝ち目のない戦いを、続行するわけにはいかない。
「…………!」
そんなダレクの様子を、少し離れた場所から仮面の魔道師が見ていた。そして、ダレクが『退却』を選ぼうとしているのが分かった。
(退却だと!? 馬鹿な!! 『勾玉』が、そこにあると言うのに―――!!)
仮面越しに、キョウジ・カッシュの姿を見る。その体内にある、勾玉を見る。少し手を伸ばせば、我が手に掴めそうな勾玉を感じ取る。
「……無能どもめ! 許さん! 許さんぞ!! このまま退却するなど―――!!」
叫びとともに、仮面の目が妖しく光る。魔道師が力を込めて握りしめていた拳を天に向かって解き放つと、その中から禍々しい妖気を帯びた『気』の塊が出現する。
「―――――」
魔道師が文言を唱えながら力を込めると、その塊はどんどん巨大化して行った。それに比例するかのように帯びる妖気も巨大化し、辺りの気配を、そして天候を―――禍々しい物へと変えていく。
「さあ―――わが望みに答えよ! この力を以って、勾玉を手に入れるのだ!!」
ドンッ!!
激しい轟音とともに、膨れ上がった塊が弾け飛ぶ。その欠片はこの戦場全体へと降り注いで行った。
「――――ウ!?」
シュバルツの視界が、突然赤く染まる。と、同時に立っていられないほどの眩暈を感じた。走っていたシュバルツの体勢が、不自然に崩れる。
「どうした!?」
シュバルツの異常に気がついたハヤブサが、走り寄ってくる。
「く…う……ッ!」
シュバルツは、己の身体を抱え込むように座り込んでしまった。
(何だ―――? これは、いったい何だ―――!?)
何かが、自分の身体の中を走り抜けて行った。それに引っ張られるように、自分の根幹の何かが、揺さぶられているような感覚―――。
ドクン!
闇の中で、何かが蠢く。
「…………ッ!」
(駄目だ! これに引きずられては駄目だ!)
何か不吉な物が呼びさまされそうになる感覚を、シュバルツは懸命に身体を抱え込んで耐えた。腕をつかんでいる手が、小刻みに震えている。
「おい! シュバルツ! しっかり……!!」
シュバルツに呼びかけながら、ハヤブサは見てしまった。シュバルツの瞳が、真紅に染まっているのを。
「!?」
何故か不吉な物を感じて、一瞬絶句する。だが、シュバルツがハヤブサの方に振り返った次の瞬間、瞳の色が、元の黒橡色に戻っていた。
「ハ…ヤブサ……」
「シュバルツ―――大丈夫か?」
ハヤブサの問いかけに、シュバルツは半ば茫然としながらも「ああ……」と、頷いた。
シュバルツが正気であると確認したハヤブサは、ほっと息を吐く。
(何だったんだ、今のは―――。あの感覚は、一体……)
「…………」
まだ少し、手が震えている。身体の中を走り抜けて行った物は、妙に禍々しく、おぞましさすら感じた。どちらにしろ、あんな感覚を味わうのは二度とごめんだ―――と思いながら、シュバルツは立ちあがろうとした。
その途端。
グオオオオオッ!! と、獣のような雄たけびが、辺りに響き渡る。それと同時に、草むらから炎をまとった何かが飛び出してきた。
「危ない!!」
まだふらついているシュバルツがこれを避けるのは無理、と判断したハヤブサは、咄嗟にシュバルツを突き飛ばした。振り向きざまに龍剣を抜き放ち、その攻撃を受け止める。
ガンッ!!
「……………!」
だが、襲って来たその力は、ハヤブサの予測をはるかに上回る物だった。踏ん張る足が地面にめり込み、そのままずるずると後ろに下がらされてしまう。
「ハヤブサ!!」
何とか受け身が取れたシュバルツは、ハヤブサの助太刀に行こうと起き上がろうとした。刹那、背後から殺気を含んだ風を感じる。
「!!」
シュバルツが手をついて地面から跳躍した瞬間、彼のいた場所が凄まじい膂力を以って穿たれた。
「―――!」
太刀を合わせていたハヤブサは、相手の正体にここで気づいた。これは―――先ほど炎に巻かれたはずの、忍者隊だ。相手は炎に巻かれ、その身体が焼き崩れていくのにも構わず、こちらに攻撃を仕掛けてきている。
「―――くそっ!」
ハヤブサは相手の太刀を撥ね上げると、その身体を乱暴に蹴り飛ばした。その横で、シュバルツも両の手に刀を二本、逆手に持って応戦している。力任せに腕を振り回してくる相手の攻撃をかいくぐり、シュバルツの太刀が、相手の腕の一本を捉えて刎ね飛ばした。だが、相手はそれに構わず、更にシュバルツに攻撃を仕掛けてくる。
「な―――!」
普通なら、腕を斬られたら痛みで怯む。それが全く無かったのだ。不意を突かれた格好になったシュバルツは、殴り倒されてしまった。
「シュバルツ!!」
倒れたシュバルツの上に馬乗りになって、更に殴りかかろうとしていた相手を、ハヤブサは力任せに蹴り飛ばす。
「大丈夫か!?」
「―――すまない! 助かった」
問うハヤブサに、シュバルツはすぐに起き上がることで答えた。
「シュバルツ―――こいつらは、確実にとどめを刺さないと駄目だ」
仕事の関係で、ハヤブサはこの手合いの敵とも何度か戦った事があるが故に、その判断も早かった。
「…………!」
「おそらく、こいつらには何らかの魔力が働いている。だから、己の身体の事など省みる事無く、攻撃を繰り返してくるんだ。その生命活動を終えるまで―――」
(惨い……!)
シュバルツは思わず眉を顰めた。人を、本人の意思とは関係なく、ただ戦う傀儡へと貶めている。先ほど感じたあのおぞましい感覚―――それが、これをもたらしたのだろうか。
だとしたら、何と暗く、邪悪な意志なのだろう。
待て―――!
シュバルツは、はっと気づく。
ここでこういう現象が起きているという事は、きっとドモンやキョウジがいる所も、無事では済んでいない。魔力によって力が何倍にも跳ね上がった兵士たちに、襲われている可能性が高い。
「ハヤブサ! キョウジ達が―――!」
シュバルツがそう口を開いた瞬間―――ドン! ドン! と、2発の号砲が響き渡る。キョウジが、自分達を呼ぶ合図だ。
「ハヤブサ……キョウジたちの所へ行くぞ」
「行くって……こいつらを突破してか?」
ハヤブサは、先ほどよりも数が増えてきている、妖気をまとった忍者隊に目を走らせながら、シュバルツに問うた。
「仕方あるまい……。この戦い、キョウジが捕られれば総てが終わる。しかも、ドモンとマスター・アジアはキョウジを守りながら、この敵と戦わねばならない。これは、大きなハンデとなる」
だから、我らが行かねば―――と、シュバルツは正眼で刀を構えた。
シュバルツのこの言葉に、ハヤブサも止めても無駄かと納得する。
「心得た。リュウ・ハヤブサ―――これより、ここを押し通る」
遅れるな、と言うハヤブサに、そちらこそ、と、シュバルツが返した。
東方不敗が合図を送ると同時に、キョウジ達がいる所にも、妖気をまとった兵達が到達していた。
「な、何だこいつら……!」
ドモンが、兵達から発せられる妖気から兄を庇うように、その前に立つ。
「ドモンよ。油断するでない。こ奴ら、何かがおかしいぞ」
東方不敗が、キョウジの後ろに立って構える。兵達の目が、皆真紅に染まっていた。
(やはり―――指揮権が……)
キョウジは拳を握りしめた。もう少し、早く気がつけばよかった。だが、後悔してももう遅い。兵達の中には、あからさまに合成獣である事を誇示するかのように、牙や鋭い爪を見せつけている者もいる。『魔』の力が、兵達に強く働いていることがうかがえた。
(どうする?)
敵の狙いは、自分の体内にある勾玉。しかしこの状況。自分は、どう考えても足手まといだ。
(火薬、持っておけばよかった……)
キョウジは少し後悔した。そうすれば、いざという時、自分で自分を焼けたはずだった。
「―――余計な事は、考えるなよ。キョウジ……」
「…………!」
東方不敗に、小声でそう言われ、キョウジは驚いた。まるで、こちらの考えが見透かされているように感じた。
「お主はただ、自分が生き延びることだけを考えろ」
「マスター……!」
「そうだよ、兄さん」
師匠と兄の会話を聞きつけたドモンが構えをとりながら口を開く。
「兄さんは、俺が守る―――! その為の、キング・オブ・ハートだ!!」
そう言い終わると同時に、ドモンの闘気が、ドンッ! と、音を立てて爆発的に膨れ上がっていく。
グオオオオッ!!
人間とも獣とも区別のつかぬ叫び声を上げながら、兵達がキョウジめがけて突っ込んできた。
「フンッ!!」
ドモンがそれを、弾き返す。何人かの兵が同じように挑んでくるが、全員ドモンによって弾き返されてしまった。
ドモンを突破するのが難しいと悟った兵達が、今度は周りに展開して、ぐるりとキョウジ達を取り囲む。四方から、一斉に飛びかかった。
「甘いわ!!」
「でぇい!!」
東方不敗が腰に巻いた布を使い、ドモンは己の鉢巻を使って、キョウジを背中に挟んで互いに180度ずつ振り回す。兵士たちが360度に渡って吹っ飛ばされた。
(チッ! 人間風情が―――!!)
少し離れた小高い丘の上から、その様子を見ていた仮面の魔道師が舌打ちをする。
「ならば、これはどうだ!!」
魔道師が、何かを操るように手を激しく動かす。すると、3人を取り囲んでいた兵達の身体が、今度は宙に浮きだした。
「フン。平面で駄目だから、今度は立体で来るわけか。小賢しい―――」
東方不敗が、浮いた兵達に目を走らせながら構えをとる。
「足や手が、もげかけているのが居るじゃないか…。それでもこいつら、向かってくるのかよ!」
反則臭ぇ、と、ドモンがこぼす。ドモンの言う通り、宙に浮いた兵士たちの中には、身体の関節や腕や足が、不自然に曲がっているのがあからさまに分かる者がいた。
「…………!」
その光景に、キョウジは思わず目を逸らしそうになる。合成獣とはいえ―――あまりにも、惨い。
「ダレク―――」
仮面の魔道師がくいっと手を動かすと、いかつい鎧のようなバトルスーツに身を包んだダレクが、ドモンの前に現れた。手足を長い鉄のアームで補強し、手に巨大な武器を携えている。ドモンを見下ろしているその姿は、最早人型戦闘兵器―――と、言っても過言ではなかった。
ダレクの目も真紅に染まり、顔からは表情が消えている。
「哀れなものだな! そんな表情で戦闘をするなんて―――!」
ドモンの一言にも、ダレクは表情を変えない。完全に自我を失っているようだ。
魔道師の手の動きに合わせて、ダレクはその巨大なアームをドモンめがけて振り下ろす。ただそのスピードは、ドモンの予測をはるかに超えていた。
「!!」
ドモンは、思わずそこから跳躍してそれを避けてしまう。それと同時に、360度ぐるり空中で取り囲んでいる兵達が、キョウジに向かって一斉に発砲した。
「チィッ!」
東方不敗がキョウジを抱えてその場から飛び退く。それと同時に、二人がいた地面が無数の弾痕に穿たれた。
「師匠! 兄さん!!」
こちらの身を案じて叫ぶドモンに、東方不敗は叫び返した。
「こちらに構うな!! お主は、目の前の敵に集中せい!!」
だがドモンは、何とかして二人の側に行こうとする。しかし、ダレクとほかの兵達が、それを阻んだ。ダレクの武器と兵達の捨て身の攻撃の連携に、ドモンと二人の距離は縮まるどころか、逆に開いて行く一方だ。
「こちらの戦力を分断して、個々に叩く戦法か! なかなかやりおる!!」
東方不敗は、足だけで襲い来る兵達に対応していた。手はキョウジを抱えているが故に、使う事が出来ない。それでも、まるで舞を舞うかの如く兵達をあしらうその様は、さすが東方不敗と言ったところか。
それでも、この状況では、それが長く続かないのは目に見えている。
(せめてマスターの手が使えれば……! この状況……やはり、どう考えても私が邪魔だ―――!)
どうする?
キョウジは考えた。一番いいのは、自分の身の安全をしっかり確保できる場所に行くことだ。そうすれば、マスターもドモンも、何の心配もなく戦う事が出来る。
だが―――周りをぐるりと見渡しても、ギアナ高地の中で、ここは珍しく見晴らしのいい平地が続いている。身を隠す場所などあろうはずが無かった。
(そうだ! 『ポイントH』―――あそこに行ければ!)
あそこは、いわゆる『特別な空間』だ。あそこなら、自分の身を隠す場所もあるし、大軍を迎え撃つ事も出来る。
ただ―――どうやって、そこまで行く?
『ポイントH』がある方向を見やりながら、有効な手段が思いつかない事にキョウジは歯噛みする。
ぐるり360度、頭の上まであやかしの兵に取り囲まれているこの状況で、どうやって。
自分を抱えているが故に手が使えないマスターとともに、どうやって―――!
「……………」
東方不敗の顎から、汗が滴り落ちている。息も乱れかけてきている。
(駄目だ……)
キョウジは、限界を感じた。このままでは、共倒れになってしまう。
「マスター……」
「何じゃ! このくそ忙しい時に!」
キョウジの呼び掛けに、東方不敗はぶっきらぼうに答える。それは、自身の疲れをキョウジに悟らせまいとする、東方不敗の虚勢だった。
「火薬……持っていますか?」
「――――!!」
キョウジの考えがすぐに分かった東方不敗の顔色が、変わる。
「阿呆が! 貴様を燃やすための火薬なぞ無いわ!」
「でも、マスター…。このままでは―――」
「やかましい!! ちょっと黙っとれ!!」
そう言いながら、東方不敗は敵の攻撃をかわし続ける。
「キョウジよ…。ワシは、お主を守ることしか考えとらんぞ―――」
動きながら、東方不敗はキョウジに語りかけた。
「だから、お主も考えろ! ワシを生かしたいのなら、己が生き残る、有効な手立てを―――!!」
「…………!」
(無茶を言う………!)
東方不敗からのかなり無茶な要求に、キョウジは苦笑うしかない。
「『ポイントH』……」
キョウジからの言葉に、東方不敗の眉がピクリと動く。
「もし、今の状況から逆転できる可能性があるとするならば、そこ―――」
「…………!」
(そうか、あそこなら―――!)
東方不敗もはっと思い当る。確かにあそこは、『特別な空間』だ。だが次の瞬間、キョウジは心底困ったような笑顔を浮かべた。
「でも……どうやってそこまで、行きましょうか?」
「――――ッ!」
キョウジの問いかけに、東方不敗も咄嗟に応える事が出来ない。
(やはり……キョウジを下ろして戦うしかないのか!?)
東方不敗は、迷う。『ポイントH』に行くためには、この包囲網を突破するしかない。突破するためには、足だけでは無く手も使って、強力な技を出すしかない。
しかし、それをするためには、キョウジを下ろさねばならない。360度敵に取り囲まれた状態でキョウジを下ろしてしまった場合、自身の防御手段を持たないに等しいキョウジは、狙い撃ちにされてしまう可能性がある。それでは、意味が無い。
(おのれ……八方ふさがりとは、まさにこの事か―――!)
東方不敗はキョウジを抱きかかえながら、ギリ、と歯を食いしばった。
勝った―――!
仮面の魔道師は、戦場を見下ろしながらほくそ笑んだ。赤いマントの男は孤立し、あの老人と目標は、身動きが取れない。あとひと押しで、勾玉を手に入れる事が出来る。その為の仕上げを、自分はすれば良いだけだ。
まず、あちらの赤いマントの男の方への攻撃を、更に苛烈なものにする。
魔道師の手の動きに合わせて、ダレクの動きが、取り巻く兵達の動きが、更に鋭く容赦ないものになっていく。なにせ、体の一部分でも無事で、命が消えていなければ、兵達はドモンに攻撃を加えてくるのだ。しかも、魔道の力が働いているが故に、物理法則を無視している。それでもドモンは懸命に対応していた。しかし―――ついにダレクが放った一撃が、ドモンの身体を捉えてしまう。
「―――――――ッ!」
ドモンは声も無く吹っ飛ばされてしまった。
「ドモン!!」
「!!」
キョウジの叫び声に、東方不敗も一瞬気を取られてしまう。
「隙あり!!」
魔道師の兵士に放たせた一撃が、東方不敗の腕を捉える。その衝撃で、東方不敗はついに、キョウジの身体を手放してしまった。そのままキョウジは、地面に投げ出されてしまう。
「ぬうっ!!」
東方不敗は、すぐにキョウジを拾おうとした。だがその動作は、自身に大きな隙を作ることになる。それ故に、身体をぶつけるように襲いかかってきた兵士たちの攻撃を、東方不敗は咄嗟に避ける事が出来なかった。あっという間に10人ぐらいの兵士に、上から乗りかかられてしまう。
「マスター!!」
東方不敗の身を案じて叫ぶキョウジを、兵士が後ろから乱暴に引っ掴む。そのまま無造作に放り投げられてしまった。東方不敗から少し離れた所の地面に、キョウジの身体が叩きつけられる。
「う……」
身を起こそうとしたキョウジに向かって、周りの兵士たちが銃口をつきつけた。
「―――――ッ!」
自分の置かれている絶望的な状況に、キョウジは思わず絶句する。
(チェックメイト―――!)
仮面の魔道師は、歓喜に震える。
「兄さん!!」
ドモンが兄の方へ行こうとする。隙だらけだ。ダレクに殴らせる。ドモンの身体が吹っ飛ばされる。動かれたら面倒とばかりに、倒れたドモンの上に、ダレクをはじめとした数人の兵士たちを力任せに押しつけた。
「兄さん…ッ! にい……さ……!」
魔道の力に抑えつけられながらも、ドモンは懸命に足掻く。
「ドモン――!」
弟の自分を呼ぶ声に、キョウジは反射的に動こうとする。だが、兵達がそれを許すはずもない。殴られたうえに、背中から踏みつけられ、銃口を押しつけられた。
「…………ッ!」
あまりにも無力な自分に、キョウジは唇をかみしめるしか出来ない。
「クハハハハ! この勝負―――我の勝ちだ!!」
仮面の魔道師が、己の勝利を確信した瞬間。
「うおおおおっ!!」
獣のような咆哮とともに、東方不敗が抑えつけていた兵士たちを弾き飛ばした。
「何ぃ!?」
自分の術を破った人間に、魔道師は驚愕の眼差しを向ける。
「おのれ……! よくも―――!!」
殺気だった目で、東方不敗は周りを見渡す。そして、自分から少し離れた所で兵士に取り囲まれ、銃を突きつけられているキョウジの姿を見つけた。
東方不敗に迷いはなかった。白い布を一閃させ、まずキョウジの近くで銃口を突き付けている兵士たちを一掃する。
「人間風情が!! ―――だが、もう遅い!!」
勾玉さえ手に入れば、キョウジの生死など関係無い。仮面の魔道師はキョウジから少し離れた所に控えていた兵士たちに、ついに発砲を命じた。
(いかん! 間に合わん―――!!)
そう判断した東方不敗は、キョウジの身体を少しでも敵から隠すように、その身をキョウジの上に投げ出した。
キョウジは目が良いが故に、東方不敗が何をしようとしているのかを正確に理解した。
「――――!」
キョウジはそうなる事を、望まない。しかし、それを防ぐための手段が、自分には無い。そう悟った瞬間、全身の血が凍りつく。
「マスタ――――ッ!!!」
キョウジは、力の限り叫んだ。叫ぶしか―――もうできなかった。
刹那―――黒い龍が天地をつんざく咆哮とともに飛び込んでくる。その龍は、キョウジ達の周りをぐるりと回り、彼らに向かっていた銃弾をすべて破壊して―――消えた。
「何だと!?」
突然の闖入者に仮面の魔道師は動揺を隠せない。ドモンにかけていた魔道の力が一瞬弱まってしまった。
「このぉ!!」
その隙を逃さず、ドモンが自分の上に乗りかかっていた兵士たちを跳ね飛ばす。
「おのれ!」
魔道師はダレクに、手に持っていた武器を振り下ろすように命じた。しかし―――それは実行されなかった。飛来してきた網が、ダレクの動きを封じていたからである。もがいているダレクに向かって、何者かが猛烈な蹴りのラッシュを食らわす。ダレクはそのまま弾き飛ばされてしまった。
ドモンは、飛び込んで来た者の正体に気づく。
「にい……シュバルツ!!」
「走れ!! ドモン!!」
「―――!」
シュバルツの声に弾かれるように、ドモンは走りだす。間髪入れず、シュバルツは一本のクナイを放った。地面に刺さったそれについている導火線が、ジジ……と、音を立てている。火が消えた瞬間、クナイから大爆発が巻き起こった。ドモンに襲いかかろうとしていた兵士たちが、それに巻き込まれて吹っ飛ばされて行く。
「シュバルツ! 兄さんが!!」
合流してきたシュバルツに、ドモンが叫ぶ。
「分かってる…! だから、走れ!!」
二人はキョウジ達に合流すべく、走り続けた。
「どうやら間に合ったようだな」
ハヤブサが、東方不敗とキョウジに襲いかかろうとする兵士たちを倒しながら、走ってきた。
「遅いわ! もっと早く来んか!!」
東方不敗がキョウジを庇いながら、さっそくハヤブサに文句をつけている。
「無茶言うな! こっちだって、襲われたんだ!」
ハヤブサは東方不敗の方に振り向きもせずに答える。
「キョウジよ、大丈夫か?」
「へ、平気です…。大丈夫―――」
そう言いながら、キョウジは口元についた血と土を拭った。殴られた瞬間、口の中を切ったらしい。ただ、少し身体が震えていた。自分を守るために、東方不敗がその命を投げ出そうとした―――その事実に、少なからず衝撃を受けていた。
「兄さん!!」
「ドモン……!」
走ってきたドモンの無事な姿を見て、キョウジはホッと胸をなでおろす。ただ、ドモンの方の顔色が、見る見るうちに真っ青になって行った。キョウジの顔に、殴られた跡と血のついた跡があるのに、気づいてしまったからだ。
ドモンの身体がわなわなと震えだす。
(あ、やばい)
キョウジは慌てて笑顔を作る。今ドモンに暴走されたら、たまったものではない。
「ド、ドモン―――! ほら……私は、大丈夫だから……!」
そう言ってドモンを落ち着かせようとするが、ドモンの方は既に聞いてはいない。気のせいか、彼の背後から「ゴゴゴゴ……」と、地鳴りが聞こえる。
「―――おのれ!! よくも兄さんを投げ飛ばした上に殴り倒してに土をなめさせ、更にそれを上から踏んづけて銃口を押しつけて傷をつけてくれたな!! 貴様ら全員、明日の朝日は拝めないと思え!!」
まるで、火山が噴火するが如くにドモンの怒りが爆発した。口から火まで噴きそうな勢いだ。
(な、何で一見しただけで、そんなに詳しく分かるんだろう……)
ドモンの鬼のような観察眼に、キョウジはただ苦笑うしかない。その観察力―――もっとほかの事に生かせばいいのにとキョウジは思う。
「阿呆か!!」
そんなドモンに、東方不敗とシュバルツから、同時に拳の突っ込みが入った。
「怒りのスーパーモードはならんとあれほど言っていると言うのにお前は―――!」
「簡単に前後の見境が無くなりおってからに! この馬鹿弟子が―――!」
「そ、そんな事言ったって……兄さんが―――!」
師匠と、師と言っても過言ではない存在の二人から、ダブル説教を喰らったドモンが、たじたじになりながらも反論する。
「おい、そこの三馬鹿」
「「「誰が馬鹿だ!!」」」
ハヤブサからの無礼な物言いに、三人が息ぴったりに反論した。
「ど突き漫才をしている場合ではないぞ…。状況は、あまり改善されてはいない。寧ろ、悪化しているかもな」
敵に対して龍剣でけん制しながら、ハヤブサは言った。
「何ぃ?」
ハヤブサの言葉に、東方不敗の眉が釣り上がる。
「……客も一緒に連れてきてしまったんだ」
ハヤブサが、多少不満を含んだ声で答えた。
「客?」
疑問を呈すキョウジに、シュバルツが苦笑した。
「すまないな。突破する事のみに集中してここまで来たものだから、忍者隊の数をそんなに減らせないまま、ここに連れてきてしまったんだ」
「……………!」
確かに、見回してみると兵と合成獣の間に、忍者の姿もかなり確認できる。
「俺は、もう少し討ち取るつもりだったんだが、シュバルツが先へ先へと急ぐものだから―――」
「しょうがないだろう。ああいう場合は、現場に到達する事が最優先事項だ」
「それでも、現場の戦況を悪くしたのでは、意味が無い!」
「到達するのが遅れて、総ての取り返しがつかなくなるよりはいい!」
今度は、忍者二人が口論を始めた。その横で「に、兄さんの声が…! 兄さんの声が…!」と、ドモンがまた頭を抱えてのたうちまわりだしている。
「ええい! 似たような声で喧嘩するのはやめんか!!」
東方不敗が怒鳴るが、二人の忍者は聞いていない。そのままギャーギャーと、口論を続けている。
(本当に、声似てるよな……。今度、声紋鑑定でもしてみようか…。あ、でもシュバルツと声が似ているってことは、私とも声が似ている事になるのかな?)
キョウジは苦笑しながら、そんな事を考えていた。
「…………!」
仮面の魔道師は、わなわなと震えながらその様子を見ていた。先ほどまで、確かに手の内に勝利が有った。それが、するりと逃げて行ってしまった。
(それにしても……ふざけているのか―――?)
先ほどまで死にそうな顔をしていた奴らが、もう笑顔を見せている。状況が、そんなに劇的に変化したわけではない。寧ろ、忍者隊が加わったこちらの方が、戦力的には充実しているはずなのだ。それなのに、人間どもはこちらを警戒するようなそぶりを見せるどころか、口論をしたり、ふざけ合ったりしている。
たかだか二人―――二人、増えただけではないか。それなのに、奴らが見せているその余裕は何だ!?
「二人増えた―――それが、何だと言うのだ!!」
魔道師は再び、キョウジに攻撃を加えるよう、兵士たちに命じた。それまで静かに宙を漂っていた兵士たちが、いきなりキョウジに向かって武器を振り回しながら突進してくる。
「――――!」
「キョウジ!!」
ドカカカカッ!!
キョウジの姿があっという間に見えなくなり、そこは、槍を突き立てた十数人の兵士たちの山で埋められた。しかし、次の瞬間。
ドカン!!
派手な音を立てて、兵士たちの山が弾かれ、中から4人の男たちが姿を現した。彼らはそれぞれが背中にキョウジを護る様にして、構えている。
「この、愚か者どもが…!」
「私たちがキョウジから注意を逸らすとでも思っていたのか!?」
「今度こそ、兄さんを守る!」
「さあ―――我らの真の実力の程、見せつけてくれようぞ!」
「おのれ! ―――何が『真の実力』だ!!」
魔道師は再び兵達に攻撃を命じた。だが、すぐに思い知ることになる。東方不敗が言った『真の実力』と言う言葉の意味を―――。
東方不敗とドモンには、一撃で複数の敵を倒す事が出来る高威力の技がある。しかし、それを撃つためには、攻撃前の予備動作が必要で、そこにどうしても隙が出来る。先ほどは、キョウジを守ることに専念しなければならなかったが為に、その技を使う事が出来なかった。しかし今は、シュバルツがいる。ハヤブサがいる。キョウジを護る者として。そして―――自分達に生じる隙を、消す者として。
「石破天驚拳!!」
「ダークネスフィンガー!!」
遠慮なく次々と放たれる二人の大技に、兵士たちが倒されて行く。
「十二王方牌大車併―――ッ!!」
東方不敗の言葉に合わせて宙に浮かんだ漢字が『気』の塊となって周囲の敵に襲いかかる。これに取りつかれた敵は、極端に動きが遅くなってしまう。足止め効果のある東方不敗の技にやられた所を、ハヤブサとシュバルツがとどめを刺して行く。時折ハヤブサも、文言を唱えて黒い龍を召喚している。これも、複数の敵を倒す事が出来る高威力の大技だ。直線的に進むドモンと東方不敗の技に対して、ハヤブサの龍は曲線的に進み、周りの敵を掃討する。
シュバルツはその間を縫うように全体を見渡しながら、時にキョウジの護衛に付き、時に防御の薄い所に回り、時に攻撃に移る。その動き、まさに変幻自在―――それでいて、大技を放ちまくる二人と、そしてその周りで立ち回りをしているハヤブサとも連携が取れていた。そこから生じる破壊力は、最早手がつけられないレベルと言っても過言ではない。
(馬鹿な――――!!)
先ほどから自分の攻撃が、全然キョウジに届かなくなってしまっている事に、魔道師は気付いた。たかだか二人の参入が、人間達の力を信じられないくらいに底上げしているのだ。
「マスター……このまま『ポイントH』まで向かいましょう」
自分を護る『陣』の中で、キョウジは東方不敗に提案した。
「何故じゃ? このままでも押しきれそうな勢いだが……」
東方不敗がそう返してくる。確かに、今のところ―――自分達が優勢だ。だが、油断は禁物、と、キョウジは思う。相手が普通の人間ではなく、『魔』の力を持つが故に、この状況で、まだ打てる手があるかもしれない。
「相手がどのような手を打ってくるか分からないですし……この広い平地で戦い続けるのは、数で劣る我々には、やはり不利です」
キョウジの言葉に東方不敗はふむ、と、考え込む。
「一ヵ所に固まっていると、ミサイルを撃ち込まれないとも限りませんし……」
すみません、少し慎重になり過ぎているかもしれませんが、と、キョウジは付け加えた。
ただ、先ほど自分を守るために、東方不敗ですらその命を投げ出そうとしたのを、キョウジは忘れていなかった。皆が自分を守るために命を投げ出すリスクがある以上、そういう事態を出来るだけ避ける努力をするのが自分の役目なのだと、キョウジは考えていた。
「まあ、それでお主の不安がはれるのなら―――」
と、東方不敗も、どうやら納得したようだ。
「だが心配するな、キョウジよ。ミサイルが飛んできた所で、ワシが叩き返してやるがな」
そう言って東方不敗がにやりと笑う。
「叩っ切る!」と、ハヤブサ。
「同じく」と、シュバルツ。
「ぶっ壊す!! ―――第一、兄さんに傷をつけた時点で、こいつらの皆殺しは決定しているんだ!」
ドモンがそう言いながら指をバキバキ鳴らしている。まだ怒りが収まっていないらしい。
(やっぱりこの人たち……人類の規格外だ…)
そう感じて、キョウジは苦笑する。
「よし! 皆の者! このまま『ポイントH』まで敵を誘いこみながら移動する! ただし、『陣』は決して崩すでないぞ―――よいな!!」
「応ッ!!」
東方不敗の言葉に、皆が力強く答える。そのまま彼らは、キョウジを守りながら、少しずつ移動を開始した。
移動をしたい方向に攻撃の比重をかけ、道が開いたと見るや移動する。移動する時に生じる隙は殿を引き受ける者がカバーする。その役目を代わるがわる交代しながら、じりじりと、少しずつだが確実に、キョウジ達は目的の場所に近づきつつあった。
退却戦の要領―――一つの連係ミスが、命取りにつながる。しかし彼らは見事なチームワークで、それをこなしていた。
(このまま……このまま何事もなく、目的地までたどり着ければ―――!)
キョウジは祈るような気持ちで戦況を見つめていた。
(おのれ……!)
仮面の魔道師は、怒りに震えていた。たかだか人間四人が作り上げている『陣』。それが、どうしても破る事が出来ない。まるで、堅牢な『城』を相手取って戦っているようだ。一人一人が己の役割を理解し、互いをカバーし、弱点を消し合っている。
(こいつらの強みは『連携』……これさえ崩せれば―――!)
「ならば、この手はどうだ!!」
魔道師は忍者隊に命を下した。その命に従って、忍者たちは一斉に、四人に向かって煙幕弾を投げつける。
ドォン! と言う音ともに、キョウジ達の周りで煙幕弾がさく裂し、あっという間に視界を奪って行った。
「皆! その場を動くな! 奴らが来るぞ!!」
東方不敗の声に、皆が動きを止めて警戒する。この煙では、互いの姿の確認すら覚束ない。しかし、それは敵にも言えることだ。この煙の中では、キョウジがどこにいるのか、咄嗟に確認出来ないはずだ。
(少しでも敵に見つかりにくいように、私は身を伏せるぐらいした方がいいのだろうか?)
キョウジがそう思った―――次の瞬間。
ピカッ!!
突然眩いばかりの光が辺りを照らした。
「な―――!!」
キョウジは思わず絶句する。光源は、自分の体内に有る『龍の勾玉』だったからだ。
(まずい!!)
キョウジは慌てて光を隠そうとする。しかし、その努力をあざ笑うかのように、光は強さを増し、辺りを照らし続けた。これでは自分がどこに居ようと、相手からは丸見えの状態に等しい。
「さあ―――お前たちの目標はそこにいる! 光に向かって喰らいつけ!!」
仮面の魔道師の号令に合わせて、兵達が一斉に光に向かって殺到した。
「く……!」
(駄目だ…! このままでは、また、足手まといに―――!)
皆を危険にさらすぐらいなら、この光る胸、いっそ抉り取って―――などと、物騒な考えがキョウジの胸をよぎった瞬間。
「光を隠すな!! キョウジ!!」
力強い声とともに、バシバシバシッ! と、キョウジの周りで何かがぶつかる音がする。4人の男たちが、キョウジに突進してきた兵士たちの攻撃を、受け止めた音だった。
「絶対に、光を隠すなよ、キョウジ……!」
忍者とつばぜり合いをしながら、ハヤブサが言う。
「その光は、敵にとっては目標だろうが―――私たちにとっても導となる…!」
合成獣の爪を受け止めながら、シュバルツが口を開く。
「そう。攻撃してくる所さえ分かっておれば、止めるのは容易い。光に寄ってくる愚かな虫を、罠にはめるが如く狩りとってくれる!」
合成獣と組み合いながら、東方不敗がにやりと笑う。
「光っている方が、兄さんの姿を見失わないで済む―――俺には、ちょうどいいくらいだ!!」
ドカン!!
ドモンの言葉が合図だと言わんばかりに、男たちは敵の攻撃を撥ね退けた。
「皆―――やるべき事は、分かっておろうな!?」
東方不敗の問いかけに、ハヤブサが答える。
「分かっている。光を、『ポイントH』まで導けばいいのだろう?」
「大分近づいている筈だから、あと少しの距離だ。進むべき方向は、分かっているな?」
シュバルツの問いかけに、皆が「ああ」と、頷いた。だが、ドモンだけが
「え~っと……どっちだっけ?」
と、言って来たので、ドモン以外の全員が思わずつんのめりそうになる。キョウジに敵の攻撃がいくつかヒットしそうになるのを、東方不敗とハヤブサとシュバルツがかろうじて防いだ。
「おまっ……! このタイミングでボケるのはやめろ!!」
シュバルツが悲鳴のような叫びを上げる。冗談抜きで、今日一番肝が冷えた瞬間だったらしい。
「ボケているわけじゃない! 本当に分からないんだってば!!」
「なお悪いわ!! この馬鹿弟子がぁ!!」
東方不敗の鉄拳制裁が、この煙の中、正確にドモンにヒットした。
「と、とにかくキョウジよ―――」
東方不敗が咳払いをしながら、キョウジに語りかける。
「目的地まであと少し。ワシらは、お前の光を見ながらお前を守る。だから、お前のやるべき事は一つだ」
「何でしょう?」
「ワシらが『走れ』と言ったら走れ! 目的地に向かって―――」
「…………!」
この煙の中を? と、キョウジは思わず聞き返しそうになる。今の有視界距離は50センチ程度。目の前で話しているはずの東方不敗の表情さえよく見えない。はっきり言って、目隠しをして走るのと、ほぼ変わらない状況だ。
「もちろん、危なくなったら止まるよう指示を出すし、間違った方向に走っているようなら、ちゃんと修正もする」
東方不敗がキョウジに語りかけている間にも、敵からの攻撃は続いている。それを、皆が防ぎ続けていた。東方不敗も話しながら時々反撃したりしている。
「どうだ? 走れるか? ワシらの声を信じて―――」
「大丈夫です」
キョウジは即答した。命がけで自分を守ろうとしてくれている人たちが、声をかけて導いてくれる。それならば、何を恐れる事があるだろうか。
大丈夫。
走れる。
どんな闇の中であろうと、皆と一緒ならば―――。
「よし―――」
キョウジの迷いの無い落ち着いた様子に、東方不敗は頷いた。
「では、参ろうぞ! ワシらの声、聞き逃すな!」
「はい!!」
返事をすると同時に、キョウジは腹に力を入れる。声がかかれば、いつでも走りだす事が出来るよう、構えを取った。そのまま目を閉じて、周りの音に集中する。
金属と金属がぶつかる音。打撃音。唸り声。うめき声。踏み込む音。斬撃音―――。
「走れ!!」
「!」
東方不敗の声に、キョウジは弾かれるように走り出した。しばらく走っていると、後ろからハヤブサに声をかけられる。
「止まって、一歩左!!」
言われたとおりキョウジが左に動いた瞬間、キョウジのすぐ右側を、斬撃が通りぬけた。空ぶったと悟った相手が二撃目を繰り出す前に、ハヤブサによって押し返されていく。
「兄さん! 頭下げて!!」
キョウジが下げた頭の上を、ドモンの拳が通過する。ドン!! と、音を立てて、キョウジに襲いかかろうとしていた合成獣の頭を、その拳は砕いた。
「キョウジ! 走れ!!」
シュバルツの声。キョウジは再び、迷わず走りだす。
自分の左斜め前方に、シュバルツの気配があるのが分かる。カン、カン! と、金属音が響き渡る。シュバルツが、手裏剣を弾きながら走っているのだろうか。
「止まって―――半歩下がれ!」
キョウジが下がると同時に、シュバルツがキョウジの前に飛び出してくる。
「やあああ―――ッ!!」
裂帛の気合と共に、前方にいた兵士を、手に持っていたサブマシンガンごとぶった斬った。
「一歩前へ!!」
東方不敗の声。背後から、グオオオオッ!! と、合成獣の咆哮が聞こえる。前に一歩出たキョウジの背中を、合成獣の爪が掠めた。
「甘いわ!!」
ドン!! と言う音とともに、東方不敗の気合を入れた拳が、合成獣の鳩尾にめり込む。
(まだか……? まだ着かないのか…?)
川の流れる音が近づいてきている。だから、目的地は近いはず。だが、先が見えない。見えないが故に、焦りそうになる。相変わらず、胸の勾玉は光らされ続けている。それも、キョウジを焦らせる要因の一つになっている。
(落ちつけ……! ここで焦っても、何にもならない……!)
キョウジは深呼吸をして、目を閉じた。自分に今できる事は、皆の声をしっかり聞いて、信じて走る―――ただ、それだけだ。
「走れ!!」
その声に、キョウジは再び走り始めた。
どれくらい、それを繰り返していただろう。
「キョウジ!! 着いたぞ!!」
「―――!」
東方不敗の声に、キョウジが視線を上げると、確かに目的の石柱が見えていた。ポイントHの入り口だ。
「シュバルツ! ハヤブサ! ついて来てくれ!!」
キョウジはそう叫ぶと、迷うこと無くその中に走り込んだ。
「兄さん!! 俺は!?」
ドモンの声が追いかけてくる。
「悪い! お前は―――外を、頼む!!」
そう言ってキョウジは、忍者二人とともに、石柱の乱立する『陣』の中へと消えて行った。
「兄さん……何で……」
兄の後ろ姿を見ながら、ドモンが淋しそうに呟く。その横で――――師匠が大爆笑する声が聞こえた。
「し、師匠!? 何で笑うんですか!!」
憤慨するドモンに、東方不敗は笑いながら答える。
「わはははは! キョウジの奴め、なかなかやりおる! なるほど、ドモンよ―――確かにお主は行かぬ方がいいな」
「? 何でですか?」
ドモンは、師匠が何を言わんとしているのかが分からず、きょとん、としてしまう。
「ここはワシとキョウジが作り上げた――――特別な場所よ」
そう言って東方不敗は、にやりと笑った。
「!?」
キョウジが石柱の陣の中に入ってすぐに、仮面の魔道師は異変に気付いた。
(勾玉の気配が、感じられない?)
まさか、と思いながら、石柱が乱立する地点の中の気配を探ろうとする。しかし、どういうわけか、魔道の力を以ってしても、中の様子を感じ取ることが出来ない。まるで結界が施されているかのように。
(『結界』だと……!? 馬鹿な―――!!)
仮面の魔道師は、茫然とその石柱の乱立地点を見下ろしていた。
(消えた……)
石柱の陣に入ってからすぐ、あれだけ眩しく輝いていた勾玉が、光を放たなくなった。
(思った通り…ここには、結界のような作用が働いている……)
やはりここは、特別な場所だ。そう感じながら、キョウジは石柱を見上げていた。この石陣を考案した、1800年以上前の天才軍師に想いを馳せる。
「キョウジ、これからどうする? すぐに敵は追いついてくるぞ」
ハヤブサがキョウジに声をかけてくる。確かにこの石陣の中は、複雑な迷路のようになっている。しかし、それだけでは敵の追撃を防ぐ有効な手立てにはなり得ない。多少の時は稼げても、追いつかれるのは時間の問題だった。
「うん。そうだね。だから、二人にはやってほしい事があるんだけど」
そう言ってキョウジが微笑みながら二人を見つめる。
「やってほしい事?」
「何だ?」
「ちょっと、耳貸してくれないか?」
そう言いながらキョウジは二人をちょいちょい、と、手招きをする。
「………………」
二人の忍者は互いの顔を見合わせた後、キョウジのそばに寄って行った。
一方、キョウジ達を追って石陣に入った敵の方にも変化が出ていた。
魔道師の魔力が及ばなくなったため、怪我をした者、命が切れる寸前の者は、石陣に入った途端に動けなくなってしまった。正気に戻った者も、目の前に広がる異様な光景に少なからずパニックを起こしかけた。
しかし、やがて兵の一人がキョウジの姿を発見する。
「キョウジ・カッシュがいたぞ!!」
この声に正気に返った兵達が、キョウジの姿を認めて後を追い始めた。
だが、キョウジの姿は石陣の柱の間に紛れ込み、あっという間に見失ってしまう。
「くそっ! どこへ消えた!?」
兵たちは、懸命にキョウジの姿を求めたが、どうしても見つける事が出来なかった。
ただ風が、石の柱の間を不気味な音を立てて通り過ぎて行くだけであった。
「師匠、ここは一体何なんです? ただの石だらけの場所にしか見えないんですが―――」
陣の外で兵達と戦いながら、ドモンは師匠に聞いた。
「フフフフ、良い質問だ。ここは『石兵八陣』といって、通称『八卦の陣』よ。ただ石が乱立しているようにしか見えんだろうが、何も知らぬ者がここに入り込んだが最後、二度と出てくる事は出来んようになっておる」
「――――!」
ドモンは思わず絶句する。
「そ、そんな所に入って、兄さん達は―――!」
「心配はいらん。この八卦の陣を設計したのは、キョウジだ」
「………!!」
師匠の言葉に、ドモンは更に驚く。
「もともとこの陣を考案したのは、古の中国に居った一人の天才軍師だ。その者の名は、諸葛亮、字を孔明という。この者の作った陣を参考に、キョウジが設計し、ワシが組み上げた。……まさか、この陣の設計図をこの目で見る事が出来るとは、夢にも思わなかったぞ」
そう言いながら、東方不敗はキョウジから設計図を提示された時の事を思い出す。あの時のキョウジに対して感じた畏怖と感動を、どう言葉で表現すればいいのだろう。あの八卦の陣について書かれた難解な書物を、キョウジは見事、読み解いて見せたのだ。
「諸葛……孔明……」
東方不敗の言葉を復唱した後、ドモンは言った。
「――――って、誰?」
ズルッ。
東方不敗は思わず足を滑らせた。
阿呆だ阿呆だと思っていた弟子の、本気の阿呆さ加減に、思わず泣きそうになる。
「ま、まあ、諸葛孔明の事については、時間のある時においおい調べておけ…。ただ―――これだけは言える。この陣を作った諸葛亮は、その力を、10万の大軍になぞらえた」
「10万!?」
途方もない数字に、ドモンは咄嗟にその威力が想像つかない。
「その上、キョウジはシュバルツとハヤブサと言う、二人の忍者を連れて行った……。ワシなら、絶対にこの罠にははまりたくないな」
そう言って、東方不敗はにやりと笑う。それを聞いたドモンは、改めて石陣の方へ視線を走らせた。
(10万の大軍……? おまけに、師匠が絶対にかかりたくない罠って、いったい……?)
石陣の中をのぞき見るが、やはり、ドモンの目には、ただ石の柱が乱立しているようにしか見えなかった。
中に紛れ込んだ兵たちは、既にパニック状態だった。
まず、どこに走っても同じような景色が続くばかりで、出口が分からない。キョウジ・カッシュの姿を見かけた、と、思ったら、すぐに見失ってしまう。
そうこうしているうちに、気がつけば、仲間ともはぐれている。あちこちで、悲鳴のような叫び声が聞こえたかと思うと、不気味な沈黙が辺りを支配する。時々、水が流れ込むような音すら聞こえてくる。
いつの間にか濃霧が立ち込め、近くにいる仲間の姿さえも確認が取りづらくなってきた。
「み、みんな……どこにいるんだ…?」
兵の一人が、霧の中に呼びかけた瞬間。
一陣の風が、兵士の脇を通り抜け―――その命を奪って行った。風が通り抜けた後には、ただ物言わぬ骸が転がるだけであった。
このままキョウジに対する追手が全滅するのは、時間の問題かと思われた。だが、僅か1隊だけ―――この八陣の中を平気な顔をして進んで行く者たちがいた。
残月と、残月が率いる忍者隊である。
ダレクと同じように魔道師に操られていた残月であったが、この八陣に飛び込んだと同時に、魔道師の支配下から覚めていた。正気を取り戻した残月は、生き残った忍者隊を集めて、独自に動きだしていた。
残月の目の前に、キョウジの姿が現れる。
「……………」
残月は無言で、キョウジに向かって短刀を投げつける。すると、キョウジの姿は煙のように掻き消えた。
「フン―――やはり、幻か……」
岩に刺さった短刀を引き抜きながら、残月は独りごちる。
「儂の十八番は幻術―――その儂に向かって、幻術で挑んでくるとは……全く馬鹿な奴らよ」
目の前の者が幻かそうでないか―――それを見抜く絶対の自信が、残月にはあった。
「みておれ……リュウ・ハヤブサ、キョウジ・カッシュ。必ず貴様らを、血祭りにあげてやる……!」
そう言いながら残月は、二人の姿を求めて再び足を進めた。
「ドモンよ、気づかぬか?」
戦いながら東方不敗は、ドモンに呼びかける。
「師匠、何をですか?」
ドモンも戦いながら、東方不敗に返事をする。しかし、戦うと言っても、身を守る程度の軽い戦いしか二人は行っていない。キョウジを追って石陣に入る者たちを、無理やり止めたりはしていなかった。
「あれほど立ち込めておった霧のような煙が、晴れておる」
「そう言えば……!」
いつの間にかクリアになっていた視界に、ドモンもはっとなる。キョウジと一緒にいた時は、互いの顔も見えないほどの煙に覆われていたと言うのに。
「おそらく、この兵どもを操っていた存在が、忍者の煙に『魔』の力を紛れ込ませて我らの周りに漂わせておったのだろうな…。だから、いくら移動しても煙が晴れなかった。だが、八卦の陣の中までは、その力を及ばせる事が出来なんだのだろう―――」
八卦の陣には、強力な結界のような作用がある。だから、キョウジはここに行きたがった。相手の持つ『魔力』に、少しでも対抗するために―――。
キョウジを見失ったような形になっている『魔』の力を持つ者は、考え込むはず。それ故、周りを漂わせていた霧も晴れた。この戦場に注ぎ込まれる『魔』の力が、今は、一時的に弱まっているのだ。
「そして、その者が、次に手を打つとしたら、それは何か―――」
東方不敗の言葉に呼応するかのように、それは姿を現した。
ズシン!
歩く重装戦車と表現してもおかしくないほど、兵器に埋もれた姿をしたダレクが、ドモン達の前に姿を現した。相変わらず目は真紅に染まり、無表情のままだ。
「おそらく、石兵八陣その物の破壊に乗り出すであろうな……。中の様子が探れぬのなら、外から壊すのが手っ取り早い。つまり、我らの役目は―――」
東方不敗の言葉に、ドモンは不敵に笑って答える。
「この石陣を壊させぬよう、守り抜けってことですね!」
「そういうことだ」
ダレクと、重火器を持った兵団を前に、師弟は改めてファイティングポーズをとった。
(正解は、この道で間違いは無い……)
残月には確証があった。幻術の達人であるが故に、ある一定の術をかけながら八卦の陣の中を見ると、たった一本だけ、安全であると思われる道筋が浮かび上がってくる。それを見ながら残月は足を進めていた。
ふと気配を感じて顔を上げると、前方の方に佇んでいる、キョウジ・カッシュの姿が見える。
(あれも、幻……)
残月には分かる。だから、相手にはしない。無言で歩を進める。
やがて、霧が辺りに立ち込めてきた。
「ギャッ!」
突然、後ろの方で悲鳴が上がる。霧に乗じて誰かが襲って来たようだ。
残月の方に迷いはなかった。素早く抜刀すると、襲ってきた相手に向かって突進する。
霧の中で、忍者隊を倒しながら走る影が見える。その首を狙って残月は、刀を走らせた。
ガキッ!!
太刀を受け止められる。相手の顔は―――キョウジ・カッシュであった。
「会いたかったぞ! キョウジ・カッシュ―――!」
残月の顔に、凶悪な笑みが浮かび上がる。
ガンッ!!
鍔迫り合いから分かれた二つの影。だが、キョウジは残月とこれ以上太刀を合わせようとせず、くるりと踵を返す。
「逃げるか!!」
残月はキョウジの後を追おうとして、はっと我に返った。術を通してキョウジの逃げた方の道を見る。
(罠か……)
危険を示す朱に彩られた道を、キョウジは走って行った。追いかけていたら、おそらく命を落とすであろう。忍者隊の何人かがキョウジを追いかけて行ったようだが、彼らの姿はあっという間に石陣の中に紛れて見えなくなってしまった。
(馬鹿な奴らだ…。儂に黙ってついて来ておればよいものを……)
残月は、再び正解と思われる道に、足を進めようとした。
――――その道で、良いのか?
不意に、誰かの声が辺りに響き渡る。
「キョウジ・カッシュか!?」
残月が問いかける。しかし、返事は無い。チッと、舌打ちをした残月は、再び歩を進めた。
――――その道で、良いのか?
再び、誰かの声がする。今度は―――『別方向』から。
(何っ!?)
残月は声のした方に振り返った。しかし、誰もいない。
―――引き返せ! そうすれば、命までは取らない。
また―――『別方向』から声がする。
(馬鹿な―――!)
残月は息を飲んだ。自分は、確かに幻術に嵌ってはいないはず。それなのに、何故、こうもあちこちから『キョウジ・カッシュ』の声が聞こえる?
「隠れてないで姿を現せ!! それとも―――儂に、臆したか!?」
残月は大音声で呼び掛けた。
―――お望みとあらば。
すらり、と、刀を鞘から抜き放つ音がする。また―――声とは『別方向』から。
「―――!」
眼の端に、刀を手にしたキョウジの姿を捉えた。キョウジは、無言でこちらに向かって走ってくる。
「そこか!!」
残月が間髪いれずに短刀を投げつけた。ガシャン!! と、音がして、キョウジの姿が砕ける。
(鏡―――!?)
そう悟った残月が、後ろを振り返った時、キョウジの投げた手裏剣が、忍者隊の一人の命を奪っていた。
「チィィッ!!」
手裏剣を投げた後、なおも突進してくるキョウジを、残月は袈裟懸けに斬ろうとした。だがキョウジは、その刀を紙一重で避け、また霧の中へと姿を消す。危険へ誘う方向へと。
あからさまな挑発行為―――だがそれには、乗れない。
「……………」
残月は無言で刀を鞘に納めると、自分が『正解』と確信している道の方へ、足を進めようとする。
―――引き返せ!
―――引き返せ!
―――引き返せ!
またあちこちから、『キョウジ』の声がする。
「五月蝿い!!」
残月は思わず怒鳴った。
―――『術』に嵌るぞ。それでも良いのか?
「術なんぞに嵌ってはいない! 儂に幻覚など通用せん!!」
残月のこの言葉に、キョウジから高笑いが返ってくる。笑い声があちこちに反響し、どこから声が聞こえてくるのすら、分からなくなってしまう。
「ひ、ひぃぃぃっ!!」
「も、もう嫌だ! こいつは―――悪魔だ!!」
ついにこの状態に耐えきれなくなった者たちが、また一人、また一人と脱落し、残月から離れて石陣の中へと姿を消していく。
(くそっ!! 引き返すべきなのか!?)
残月はギリ、と、歯を食いしばった。正解の道は、見えている。幻術に嵌っていないと言う確証もある――――あるはずだ。自分に、幻術は、通用しないはずなのだ。それなのに何故―――こうもキョウジの『声』が、四方八方から聞こえる?
残月は頭をふって、引き返す選択肢を捨てた。
この状態にも、何らかの種があるはず。ここまで来たのだ。『キョウジ』の首を取らずして、どうして引き返せようか。
残月はいつの間にか一人になっていた。それでも歩き続けた。そしてついに―――石陣の中にしては、広く拓けた空間に出た。
「へぇ、ついにここまで来たんだ」
のんきな声が残月の耳朶を打つ。
「―――!」
残月が声のした方に振り向くと、中央の少し低く積まれた石柱の上に、刀を抱えて座っているキョウジ・カッシュの姿があった。
「キョウジ・カッシュ……!」
残月の自分を呼び掛ける声に、キョウジはにこ、と、人懐こい笑みを浮かべて答えた。
(この『キョウジ』は、本物か?)
残月は、自問自答する。確かに、実体がある。目の前にいるキョウジは、本物だ。
「ここまでたどり着いた貴方に敬意を表して―――名前を、聞いておこうかな」
目の前のキョウジの口調は、あくまで穏やかだ。抱えている刀を、抜くそぶりすら見せない。なめているのか、と思いつつ、残月は口を開いた。
「儂の名は―――残月」
「残月……」
キョウジが復唱をする。
「『あの時』は―――世話になったな」
そう言ってキョウジは、にっこり笑った。
「……キョウジ・カッシュ。儂と一緒に来てもらおうか」
残月は刀を構えながらじりじりと距離を詰める。しかし、キョウジの穏やかな表情は変わらない。
「断る、と、言ったら?」
「お前に、断る権利は無い。何なら、死体でも構わん」
「そうか……」
残月の言葉に、キョウジは目を閉じる。刀を抜くか、と、残月は構えた。しかし、キョウジは刀を抱えたままだった。
「残月―――お前は確か、幻術の達人……」
目の前のキョウジが、ポツリと呟く。
「そう。儂は幻術使い。主が幻かそうでないかは、すぐに分かる……小細工しても、無駄と知れ」
残月のこの言葉に、キョウジはにやり、と笑った。
「その達人に、敢えて問おう。……今目の前にいる私は―――本物か?」
「何ぃ?」
残月の眉が、釣り上がる。
「儂の目はごまかせん。お前は、どこからどう見ても本物―――」
(―――そう。そこにいるキョウジ・カッシュ―――それは、本物か?)
残月の言葉が終わらないうちに、目の前のキョウジとは全く別の方向から、声が聞こえた。
「―――!?」
(そこにいる私は、本物か?)
また、別方向から声が聞こえる。声のする方を見るが、誰もいない。再び目の前のキョウジに視線を戻すと、キョウジはにっこり微笑んだ。
「さあ―――私は、本物か?」
間髪いれず、別方向から声がする。
(そこにいる『キョウジ』は、本物か?)
(本当に―――本物なのか?)
(見えている『キョウジ』は、本物なのか?)
(よく考えろ! お前は『術』に、嵌っていないと―――言えるのか?)
「何だと……!?」
残月は思わず息を飲んだ。何故―――何故こうも、キョウジの『声』があちこちから聞こえる?
もう一度、目の前のキョウジの姿を確認する。実体がある。確かに、幻ではなく本物のはず――――本物の、はずだ。
では、この『声』は、何だ?
(まさか、儂はすでに、術に嵌って……?)
馬鹿な―――!!
残月は頭を振る。この手の術は、自分には通用しない。通用しないはずなのだ。だからこそ自分は、一流の幻術使いのはずなのだ。
ふと目の前のキョウジが抱えている刀の正体に気づく。それは、ハヤブサが持っているはずの『龍剣』だった。
「貴様―――それはハヤブサの物のはず。なのに、何故貴様がそれを持っている?」
「さあ? 何故でしょう」
問いただす残月に、キョウジはそう言ってフフフ、と笑う。
―――おのれ……!
残月の中で、何かが音を立てて切れた。本物だろうが偽物だろうが、目の前にいるこいつには実体がある。それだけは、確かなのだ。
「黙れ!! 貴様はキョウジか、それで無ければリュウ・ハヤブサが変装した姿だ!!」
叫びながら、残月は刀を振るった。だが、刀がキョウジに届く直前、キョウジの身体が柱の上から後ろに飛びのく。
残月の剣圧で、キョウジの乗っていた石柱が、グシャッ! と、音を立てて崩れた。それと同時に、ヒュ…と、空気を割く音がする。
「―――!!」
キョウジがいた所と全然違う方向から、自分めがけて手裏剣が飛んで来ていた。残月はそれを、身をよじってかわす。かわしている間に―――キョウジの姿を、再び見失ってしまった。
チッ、と舌打ちをしている残月に、キョウジの声が再び襲いかかる。
(砕いたな。その石柱を)
(その石柱は、罠を発動させるための物。それを―――お前は、砕いたのだ)
「何っ!?」
(さあ―――あの音が聞こえないのか?)
にわかに、石柱の間を強風が駆け抜ける。激しい風音の合間に、ザブ、ザザァ、と、波音が交じって聞こえた。
「まさか……!」
息を飲む残月に、キョウジの声が笑いながら答える。
(そう。間もなくここに、大量の川の水が流れ込む)
(その石柱は、その罠を発動させるための物だ)
「おのれ……!」
ギリ、と、歯を食いしばる残月に、声は呼びかけてきた。
(勾玉をあきらめ、降伏するか?)
「断る!! お前が死ぬか―――儂が、死ぬかだ」
(そうか……)
声が、少し哀しげに揺らめいたように感じたのは、気のせいだろうか。
「……………」
残月は、無言で刀の柄に口をあてた。残月の周りの空気が、ゆら、と揺らめく。
とたんに、不思議な事が起こった。残月の周りに、数人の残月が現れる。残月の術が発動したのだ。
「さあ来い、キョウジ・カッシュ。儂の『分かれ身の術』見事破れるものならばな」
そう言って8人ほどの残月が、ゆっくりと歩き出す。それぞれの構えが別なら、歩く歩調も方向もバラバラだった。
「なるほど―――見事なものだね」
「――――!」
残月が声のした方に視線を走らせると、キョウジが一本の石柱に背を凭れかけさせるようにして立っていた。また―――手にハヤブサの龍剣を持っている。ただ、剣は鞘におさめたままだった。
(実体がある……馬鹿め! のこのこと―――!)
残月はにやりと笑う。
「観念したのか? キョウジ・カッシュ」
「そう―――私は、キョウジ・カッシュ……」
残月の言葉に、キョウジもにやりと笑う。
「ならばここにいる、私は誰だ?」
「!?」
残月がギョッとなって声のした方に振り向くと、そこにも『キョウジ』が立っていた。
「そしてここにいる、私は誰だ?」
更に別方向からも声がする。そしてそこにも―――『キョウジ』がいた。
(何だと―――!?)
残月は思わず息を飲む。ここにいる3人のキョウジには、どれも実体があるようにしか感じられなかったからだ。
「8対3……。数では、負けているね」
「3人のうち、どれかが本物だ」
「さあ―――お前にそれが、分かるか?」
そう言いながら、キョウジたちは残月を見る。
(本物が一人だと…!? 馬鹿な―――!!)
どれにも実体があるようにしか見えない。これが幻術なのだとしたら、相手は、自分を上回る腕の幻術使いと言うことになる。残月は、己の刀を握る手が、じっとりと汗ばんでいるのが分かった。
3人のキョウジ達を、それぞれ見比べる。
一人は、刀を抜かずに石柱を背に、腕を組んで凭れている。ただ、その持っている刀は『龍剣』だった。ほかの二人が持つ刀は、特に銘入り、というわけではなさそうだ。その刀を無造作に下げ、自分達との間合いを図っているように見える。
(くそっ! どれだ!? どれが本体だ!?)
一番怪しいのは、一人だけ『龍剣』を下げているあのキョウジだ。通常の幻術では、持っている武器が違うように見せる事は出来ないはずだからだ。―――ただ、彼は石柱にわざわざ凭れるようにして立っている。あの石柱を壊させるための、誘いの罠かもしれない。
だとしたら、怪しいのは残りの二人。
残月がそう勘繰った時、二人のキョウジが同時に動いた。
すらり、と、音を立てて、鞘から刀を抜く。そして、構える。
「――――!」
ここで残月は、ある事に気付いた。二人のキョウジは、向かい合って同じ格好、同じ動きをしていたのだ。片方のキョウジは右手に、そして、もう片方のキョウジは左手に刀を持っている。まるで、『鏡に映したよう』に―――。
(そうか!! 分かったぞ!! 馬鹿め!! 同じ手が何度も通用すると思っていたのか!!)
残月は、キョウジの本体を確信した。刀を構え、にやりと笑うと、己が分身に攻撃を命じる。8人の残月が、それぞれのキョウジに向かって歩を進めて行く。
「愚か者が!! 死ね――――ッ!!」
幻術に紛れて、残月本人も、本物、と確信する右手で刀を構えているキョウジに向かって突進して行った。
ドスッ!!
肉に、刃がめり込む音がする。ポタ……と、残月とキョウジの間に、血の滴が落ちた。
「あ……。何……だ…と………?」
残月が、信じられない面持ちで後ろを振り返った。攻撃を受けたのは自身の身体。しかも、『鏡に映った姿』だと思っていた―――『左手に刀を持ったキョウジ』から攻撃されていたからだ。
残月と目があったキョウジが、おもむろに自身の顔をバリバリ、と、剥ぎ取る。その下から現れた顔は、リュウ・ハヤブサの物だった。
「……ま…さ…か……貴様……が―――」
「『忍者』だからな…。変装の心得ぐらいはあるさ」
残月の言葉に、ハヤブサが答える。振り返って残月は、目の前にいるキョウジを見る。残月と視線が合った『キョウジ』は、少し哀しげに瞳を曇らせた。
「済まないな。鏡に映ったように演技をしたのは、私の方だ……」
そこにいたのはキョウジの格好をしたシュバルツ。彼は、左手で刀を持ったハヤブサの動きに合わせて動いていたのだ。
「――――」
絶句する残月に、ハヤブサが語りかける。
「あれだけ動揺すれば、いくらお前の術が完璧でも、そこにほころびが生じる。俺は、そこから本体を探るだけで良かった」
だから、キョウジは残月の攻撃対象から真っ先にはずされる、左手に刀を持つ役目を、ハヤブサに振りあてた。残月を仕留めるのは自分―――これは、ハヤブサが望んだ事だっだからだ。
残月は、目の前にいるキョウジを見、そして、龍剣を持っていたキョウジを眼の端に捉える。ここに至っても、二人のキョウジは消えていなかった。そこから導き出される答えは、一つしかない。
(キョウジ・カッシュは―――『二人』いるのか―――!?)
「私が『本物のキョウジ』だ……」
龍剣を持ったキョウジが、残月の方に歩を進める。
「貴方が私の言葉に惑わされず……その刀を振り下ろしていたならば、勝負は貴方の勝ちだっただろう」
「……………!」
龍剣を手にしたキョウジは、この場所で最初からその姿を残月の前に晒していた。彼もまた、命かけて勝負を挑んでいたのだ。剣ではなく―――『声』と、その『言葉』で。
惑わされたのは、自分だ。幻術使いであるが故に。
踏み込めなかったのも、自分だ。己を信じ切れながったが故に。
(―――負けた……)
残月の面に、穏やかな末期の笑みが浮かぶ。それと同時に、ハヤブサが残月の身体を斬り裂いた。ドウッ! と、音を立てて、残月の身体が倒れる。
「任務完了―――」
そう言いながら、ハヤブサはブン、と刀の露払いをし、刀を鞘におさめた。
「……………」
ふと見ると、キョウジが残月に向かって手を合わせている。
「―――あまり気にするな。互いに、命をかけて戦った結果だ」
ハヤブサは、キョウジに声をかけた。
「殺らなければ、こちらが殺られる…。俺もお前も、今はそういう場所にいる。…お前は生きて、龍の勾玉と化け物を、呪いから解放しなければならないんだろう?」
「うん、分かってる」
ハヤブサの言葉に、キョウジは頷く。
「よく―――分かっているよ」
そう言って彼は、笑顔を見せた。
「キョウジ……ここを出よう。ここにも直に、川の水が来る」
シュバルツが、キョウジに声をかける。これで、石陣の中に水が流れ込めば、生き残っている兵や忍者隊も、流されて行ってしまうだろう。追手は、ほぼ壊滅的な打撃を受けたと言っていい。
(これで……これで、この場での戦いをあきらめてくれればいいのだけれど―――)
キョウジは祈るような想いで、勾玉がある胸のあたりを、手で押さえた。
「このポンコツ野郎!! もう、起き上がってくるなよ!!」
そう言いながらドモンは、グシャッ!! と、ダレクのアームを踏みつけて砕く。ダレクの兵装は、手も足も捥がれてダルマの様になっていた。それでもダレクは露出した線からバチバチ、と、音を立てて尚も起き上がろうとしていた。しかし、その動きもやがて止まり―――沈黙が、辺りを支配する。
あちこちに、ミサイルや重兵器の潰された物が転がり、そこかしこから黒煙が上がっていた。
「…………」
ドモンの顔から、汗がポタっと滴り落ちた。身体中にかすり傷を作り、息も上がりかけている。それだけで、ここで行われた戦闘がいかに激しいものだったかが分かった。
「ドモン―――ちょっとこちらに来て、見てみろ」
小高い丘に登った東方不敗が、汗を拭いながらドモンに声をかける。ドモンが師匠のそばに行くと、丘から石兵八陣の様子が、よく見えた。
「これは―――!」
ドモンはそう言って、言葉を失う。八陣の中に、川の水が大量に流れ込んでいたからだ。川の水は石柱と石柱の間を走り、渦を作りながら、ゴオオオオッ、と、音を立てて流れていく。またたく間に、石陣は川の流れの中に沈んで行った。
「こ、こんなになったんじゃ、兄さんたちは―――!」
「勝手に殺すな。ちゃんと生きてるよ」
茫然と呟くドモンに、背後からキョウジの声がかけられる。
「兄さん!!」
ドモンの表情が、ぱっと明るいものになる。走り寄ってくるドモンを、キョウジは笑顔で迎えた。
「………………!」
その様子を、仮面の魔道師は少し離れた小高い丘の林の中から見ていた。
(全滅だと―――!? たかが少数の人間ごときの手によって、こちらの部隊が……!?)
屈辱と怒りのあまり、全身が震える。ダレクから指揮権を奪ってから途中までは、確かに勝利は自分の手の内に有ったはずだ。それが覆されたばかりか、逆に完膚なきまでに叩きのめされることになろうとは、夢にも思わなかった。しかも、完全に兵達を自分が操ってのこの敗北――――それ故、人間が無能だからと、その責任をなすりつけることすらできない。
(おのれ………!)
視線の先に、平和に笑い合っている兄弟の姿を捉える。勾玉をその身に宿している、キョウジの姿を捉える。人間どもはあの男を中心に、信じられないほどのまとまりを見せ、その力を発揮しているようだ。
(あの男は、危険だ)
仮面の魔道師は、はっきりと理解した。人間側の大将ともいうべき存在になっているのは、あの男―――キョウジ・カッシュ。この男だけは、何としても葬っておかねばならない、と言う事を。
今倒しておかなければ、この後、どんな反撃を人間達から喰らうか分からない。そんな危うさすら、キョウジからは感じられたからだ。
(やむを得ん。『あれ』を使うか)
仮面の魔道師は決意した。龍剣が勾玉の近くにいる状態で『これ』を使う事は、できれば避けたい事だった。しかし、キョウジを確実に葬ると言うのであれば、事情は変わってくる。『これ』を見て、人間どもがその威力に絶望し、勾玉の封印を試みても―――『キョウジを葬る』という目的は、達せられるからだ。封印の過程で、キョウジ・カッシュは必ず命を落とす。
もちろん、勾玉が封印されるのであれば、こちらも200年の間、また眠りにつかねばならない。しかし、200年後の世界には、確実にキョウジ・カッシュはいない。それで充分だった。自分の望みを実現させるのは、その時でも遅くは無い。人の身を超えた自分にとって、200年の歳月などあっという間だ。ならば―――『これ』を使ってどう転ぼうとも、結局自分にとっては痛くもかゆくもないのだ。
もちろん『これ』で、勾玉を手に入れる事が出来れば、それこそ万々歳だ。
「さあ――――我が女神よ。我が望みに答えよ!!」
魔道師の呼び掛けに応えるように、低い唸り声とも呻き声とも区別のつかぬ声が、辺りに響き渡る。今―――キョウジ達にとっての真の敵が、その姿を現そうとしていた。
「相手の部隊は壊滅状態だ。もう、さすがにこれ以上戦おうとはせぬじゃろう」
東方不敗の言葉に、キョウジも「ええ」と、返事をしようとした。しかし―――彼はそれが出来なかった。
―――カッ!!
龍の勾玉から、いきなり激しい光が溢れだす。しかも、勾玉は、ただ光るだけでは終わらなかった。何かに反応したかのように、キョウジの体内で暴れ出す。それが、激烈な痛みを伴ってキョウジを襲った。
「……う!? ッあああ―――ッ!!」
その痛みにキョウジは耐えきれず、声を上げ、その場にうずくまってしまう。
「キョウジ!?」
「兄さん!?」
「どうした!?」
皆の自分を案じる声が聞こえる。キョウジは、何とか返事をしようとした。
「……分から、ない…。急に…勾玉、が……ッ!」
痛みを何とかこらえようと、キョウジは己の身体を抱え込む。
「兄さん!? 兄さん!!」
ドモンは、苦しんでいる兄の身体を懸命に抱きしめる。しかし、そんなことでキョウジの苦しみが和らぐわけもなく、ドモンの腕の中で、キョウジの身体は痛み故に強張り続けた。
「兄さん―――!」
ドモンの、泣き出しそうな声が聞こえる。
「――――ッ」
大丈夫だ。キョウジはそう、ドモンに言ってやりたいのに、うまく言葉が出て来ない。
ああ―――この痛み。痛みが、邪魔だ。
「何か来るぞ!!」
東方不敗の緊張を含んだ声音が響き渡る。一同は顔を上げた。
ウォオオオオォォォ―――!!
不気味な吠え声とともに、地鳴りが、そして、激しい揺れが皆を襲う。ギアナ高地の大地を引き裂きながら―――それは姿を現した。
それは、真っ黒な『女』の形をした物だった。
長い髪を振り乱しながら、金色に輝く目を見開き、大地に立ちあがる。だが、まだ完成体でないせいであろうか。皮膚の一部がドロドロと溶け、黒い塊を地面に、グチャ、と、落とし続けていた。薄く開いた口から、鋭い牙がのぞいている。
「ほう、あれが……!」
「何という、巨体……!」
「奴が、伝承の―――!」
東方不敗が、シュバルツがハヤブサが、『化け物』に対する感想を口にする中、ドモンだけがギリ、と、無言で歯を食いしばっていた。
あれが―――『化け物』
あれが―――兄さんを苦しめる、諸悪の根源……!
あいつのせいで……。
あいつのせいで、兄さんは―――!!
「…………ッ」
キョウジも、顔を上げて『化け物』を見る。だが、それを見た途端、勾玉が激しく反応した。
「―――――ッ!」
(呼ばれている……? 違う…。違う、この反応は……!)
キョウジは、何とか勾玉の反応を探ろうとするが、痛みが思考の邪魔をする。
「さあ―――我が女神よ。『餌』を喰らいつつ、勾玉を手に入れよ!!」
仮面の魔道師の声に呼応するように、『女神』と呼ばれたモノは形容しがたい叫び声を上げると、ズシン! と、足を一歩前に踏み出した。
(さて……我も動くか……)
魔道師の周りの空気がゆら、と、揺らめいたかと思うと、煙が大気の中に溶けて行くように、魔道師の姿も見えなくなって行った―――。
「―――ッ! う……!」
キョウジは懸命に声を殺し、身体の力を抜いて痛みを流そうとする。しかし、痛みの強さがキョウジの許容を超えているが故に、身体がどうしても強張る。その強張りがドモンに伝わるたびに―――自分に触れる弟の指先の震えが、激しくなって行くのが分かった。
(駄目だ…! ドモンの怒りに、油を注いでいる…!)
「ドモ…ン……ッ!」
とにかく弟から、自分の身体を離さないと。「大丈夫だ」と、言わないと。
キョウジは強くそう感じて、懸命に動こうと試みるのだが、痛みに邪魔され、徒労に終わってしまう。
(お願いだ! ドモン…!! 怒りに囚われて、暴走だけはしないでくれ……!!)
キョウジはドモンの腕の中で、そう祈るしか出来なかった。
(いかん―――!)
ドモンが、今、危険な状態にいる。シュバルツにも、それが分かった。
キョウジを抱きかかえながら、化け物を睨みつけ、まるで獣のように唸りながら、全身の毛を逆立てている。暴走する一歩手前だった。
ズシン!!
黒の女の化け物が、両の手を大地につける。地面に転がる『餌』を見つけたのだ。化け物はそれを拾い上げると、無造作に口に放り込む。まるで、飴でも食べるかのように。その光景が、ドモンの中の何かを、ついに切れさせた。
「おのれっ!!」
ドモンは立ち上がり、怒りにまかせて化け物に突進しようとする。
「待てっ! ドモン!!」
そのドモンの前に、シュバルツが両手を広げて立ちはだかった。
「シュバルツ!? 何で邪魔をする!?」
「今の自分を冷静に見てみろ! 完全に怒りに呑まれているではないか! そんな状態で敵に向かって行っても、返り討ちにあうだけだ!!」
「――――!」
シュバルツもまた『兄』だ。兄からの説教に、ドモンは一瞬我に返る。
「で、でも……! 兄さんが―――!」
「『兄さんが』では無いわ! この馬鹿弟子が―――!」
シュバルツに向かって言い訳をしようとしたドモンに、東方不敗が後ろから拳骨を食らわす。
「し、師匠!? 何するんですか!!」
痛む頭をさすりながら振り返るドモンに、東方不敗は冷たい視線を返した。
「お主、兄御はどうした―――?」
「あ!!」
東方不敗からの問いかけに、ドモンは顔から血の気が引いた。化け物が死体を食べているのを見た所からの自分の行動が、よく思い出せない―――!
「に、兄さん……?」
恐る恐る兄の方に振り返ると、ハヤブサがキョウジの身体を抱きかかえていた。覆面の間から覗くグリーンの瞳が、ドモンに向かって思いっきり
(何やってるんだ? お前。阿呆か)
と、言っているのが分かる。おそらくドモンに放り出されたキョウジを、ハヤブサが受け止めたのであろう。
「あ………!」
ドモンが、気の毒なほど落ち込んで行く表情をする。それを見てキョウジは、ようやくその面に笑顔を浮かべることに成功していた。
「全く……しょうが…ない…奴だな。お前、は―――」
痛みでどうしても言葉は途切れがちになる。それでもキョウジは、笑顔でドモンにひらひらと手を振った。
「兄さん―――」
ドモンの表情が、ようやく落ち着いたものになる。一同は、やれやれ、と、ため息をついた。
グルルルル……。
しばらく『餌』を漁っていた化け物が、唸り声を発しながら顔を上げる。ハヤブサの腕の中にいるキョウジと、目が合った。
(気づかれた…!)
その場にいた全員が、息を飲む。化け物の金色の目が、妖しく光った。
ガカッ!!
眼の光に呼応するかのように、勾玉もまた激しい光を放つ。
「うわあああっ!! あうっ―――!!」
不意に襲われた強い痛み―――キョウジは、声を殺し損ねた。
「キョウジ!!」
「兄さん!? 兄さん!!」
「あ……! う……!」
キョウジは身体を抱え込んで痛みに耐える。しかし、その身体が震えていた。
その間に、化け物が身体を起こす。
ウォォオオオォォ―――ッ!!
周囲をつんざくような大音声を、化け物がその口から発する。周りの木々が激しく揺さぶられ、異常に耐えかねた鳥や動物たちが、一斉に森から飛び出した。
化け物は、歓喜の舞を舞う。
髪を振り乱し、どす黒い肉片を撒き散らしながら。
手を左右に大きく広げ、その体をくねらせる。
やっと―――やっと、見つけたのだ。
200年ぶりの、我が源との再会―――!!
カァァァ――――ッ!!
化け物の口の付近に、光の玉が形作られて行く。それは、周りの空気を圧縮しながら、みるみる巨大化して行った。
「伏せろ!!」
シュバルツが叫ぶと同時に、化け物が光の弾を発射する。
ドォォォォン!!
光の弾は何もかもを吹き飛ばし、ギアナ高地の地形を変えた。
「…………!」
そのあまりの威力の凄まじさに、一同は言葉を失うしかない。
「……私の…身を、焼くか?」
キョウジが、苦笑交じりに提案する。
「「「「断る!!!」」」」
四人全員の意見が一致した。
「だが……このままでは―――ウッ! く……!」
キョウジは身体を抱え込む。痛みが邪魔をして、考える事も、話すことすらままならない。
(いかん、このままでは―――!)
シュバルツは強く思った。とにかく化け物を―――化け物を、何とかしなければ。
その為に、自分が出来る事は―――。
「ハヤブサ! キョウジをこちらへ渡せ!!」
「シュバルツ!?」
ズシン!
化け物の、足音が響き渡る。こちらに向かって、足を進めてきていた。
「シュバルツ! お主…何をする気だ!?」
東方不敗がシュバルツの真意を図りかねて、問いただす。
「―――私たちが、囮になる!」
「!?」
シュバルツの言葉に、ドモンが息を飲んだ。
ズシン!
足音が、さらに近付いてくる。
「早く! ハヤブサ!! 時間が無い!!」
「――――」
急かしてくるシュバルツに、ハヤブサは躊躇う。
「にい……シュバルツ、何で―――」
茫然と聞いてくるドモンを、シュバルツは見据えた。
「簡単な事だ。お前たちには、化け物に対抗しえる力がある。だが、私には無い―――」
「………!」
絶句するドモンにシュバルツは微笑みかける。
「…な。だから、狙われているキョウジを抱えて逃げ回るのは、私の役目だ」
「―――なるほどな」
東方不敗は納得した。確かに、化け物に対して有効だと思われる手段は、勾玉を封印する事を除くと、現時点では二つある。ハヤブサの『龍剣』と、自分達が持っている『シャッフル同盟の紋章の力』―――これは、無我の境地―――ハイパーモードで発動すれば、暴走したDG細胞ですら破壊する力を持つ。あの化け物に対しても、効くかもしれない
「ハヤブサ! キョウジを奴に渡せ!!」
東方不敗にまで言われては、ハヤブサも否やは言えない。ハヤブサはキョウジを、シュバルツに渡した。
「シュバルツ……無茶はするなよ」
そう言うハヤブサに、シュバルツは笑顔を返した。
「心配せずとも、どんな事をしても、キョウジは守って見せるさ」
「――――!」
(ちょっと待て!! キョウジ『は』って何だ!? 『は』って―――!!)
「おい―――!」
ハヤブサはシュバルツを呼びとめようとした瞬間、自分達の頭上を黒い影が覆う。
キャアアァァアアア―――ッ!!
化け物がキョウジの中の勾玉を求め、その腕を振り下ろしてきた。シュバルツも、そしてやむを得ずハヤブサも、その場から飛び退く。ドスン!! と言う音とともに地面が穿たれた。
シュバルツは、敢えて化け物から少し離れた化け物からよく見える場所に着地した。
「……………」
わざと腕の中のキョウジを見せつけるようにすると、そのままロングコートを翻して、森の奥へと走り去る。それを見た化け物は雄たけびを上げると、そのまま二人を追いだした。
(―――チッ! あの馬鹿!!)
ハヤブサは舌打ちをした。
「シュバルツ!! 兄さん!!」
ドモンが、二人の身を案じて叫んでいる。
「マスタ―アジア!! ドモン・カッシュ!! とにかく化け物を何とかしよう!! 早くしないと、馬鹿が馬鹿をする!!」
ハヤブサの呼び掛けに、東方不敗も同意する。
「そうだな…。ドモンよ! 急ぐのだ!! こんな化け物ごとき、わしらの力で倒してくれようぞ!!」
「―――はい!!」
師匠の言葉に、ドモンも力強く頷いた。
化け物は、勾玉だけを求めて行動している。それ故、足元で動いている人間達の動きには、さほど注意を払っていなかった。しかも、まだその身に勾玉を吸収していないせいなのか、動きも鈍い。付け入る隙には事欠かなかった。
「石破天驚拳!!」
声と共に放たれた東方不敗の拳が、化け物の左腕を破壊する。
「やった! 師匠!!」
ドモンが見つめる先で、左腕を失った化け物が、ぐらり、と、そのバランスを崩す。
だが―――次の瞬間。
ぐにゅり。
と、音を立てて、失ったはずの左腕を化け物は再生させた。
「何だと―――!?」
驚愕する東方不敗。
「くそっ! ならば、これはどうだ!!」
、ドモンが静かにふ―――っと息を吐いて構える。みるみるドモンの闘気が高まり、ドンッ! と言う音と共に、ドモンの身体が金色に輝きだした。ドモンの手にした無我の境地―――『明鏡止水』の発動である。『デビルガンダム事件』の際、奇しくもこの同じギアナ高地で、ドモンはシュバルツに助けられてこの境地を体得した。
「石破!! 天驚拳ぇぇぇ―――ん!!」
ドモンから放たれた金色の拳は、過たずに化け物の首元を捉える。更に、その後ろから黒い影が襲いかかった。
「りゃあああああっ!!」
石破天驚拳で吹っ飛ばした根元を、ハヤブサの龍剣が更に斬りつける。シャッフルの紋章の力と、龍剣の重ね掛けだ。化け物の首が吹っ飛び、その身体がぐらり、と、後ろに傾く。
「やったか!?」
ハヤブサは化け物の方に振り返った。首を飛ばしたのだ。大概の生物は、これが致命傷になる。
しかし。
失ったはずの首が、あっという間に再生した。化け物の金色の目がぎょろりと光り、ハヤブサの姿を捉える。
「な――――! ぐっ!!」
高速で動かされた化け物の腕が、ハヤブサを捉えた。そのまま、払い飛ばされてしまう。
「ハヤブサ!!」
ドモンがハヤブサの身を案じて叫ぶ。そこに、化け物の腕が襲いかかってきた。まるで、邪魔な虫でも払うかのように。ドモンと、そして東方不敗の身体が吹っ飛ばされる。
「うわあっ!」
「ぐぅっ!!」
そのまま二人の身体は、地面に叩きつけられた。
グルルルルル……!
化け物は唸りながら、他に『虫』はいないか、とでも言わんばかりに、辺りを見回す。
その化け物の首元に、一本のクナイが、カッ、と、刺さる。途端に、そのクナイが爆ぜた。
「ぎゃああああああ―――!!」
雄たけびを上げて振り返る化け物の視線の先に、キョウジと、キョウジを抱えたシュバルツがいた。
「何をやっている! お前の目的の物は、こちらだろう……!」
シュバルツの言葉に、グオオオッ! と、吠えながら、化け物は再びキョウジ達を追い始めた。
「くそっ!」
ハヤブサがめり込んだ地面の間から身体を起こす。立ちあがった彼は、地面に横たわっているドモン達の姿を認めて走りだした。
「―――おい! 大丈夫か!?」
ハヤブサの声に、ドモン達がピクリと反応する。
「くそったれ!!」
「おのれ! コケにしおってからに!!」
二人とも、すぐに立ち上がった。
「ほう、タフだな。あれを喰らって立つか!」
そう言って素直に賛辞を送るハヤブサに、ドモンもにやりと笑い返す。
「当たり前だ! あんなもの、師匠の拳に比べたら数十倍軽い!!」
「フン! 我ら武闘家たるもの、あれくらいの打撃は日常茶飯事よ!」
二人とも、ダメージを与えても再生してしまう化け物を目の当たりにしても、戦闘意欲が衰えるどころか、パワーアップしている。
「しかし―――どうなっているんだ? 確実にダメージを与えたと思ったのに、手応えが―――」
ドモンが、先ほどの戦闘で感じた事を素直に口にした。あれだけの巨体を持った化け物にしては、手応えが軽すぎるように感じた。
「おそらく……まだ体内に勾玉を収めておらぬ故、ちゃんとした実体になっていないせいなのであろうな……」
東方不敗が推測する。
「だからこそ、こちらにも付け入る隙があるはず。もしかしたら、ダメージを与え続けてある一定量を超えると―――再生をしなくなるのかもしれない……」
かなり希望的観測だが。と、ハヤブサは付け加えた。仕事柄、こういう敵とも何度か遭遇し、戦った事がある故の、憶測だ。
「どうだ? まだ戦えそうか?」
ハヤブサの問いかけに、二人の戦士は眉を吊り上げる。
「当然じゃ!! 流派東方不敗に、『あきらめる』と言う言葉は無い!!」
「倒れるまでぶん殴る!!」
ドモンがそう言って指をバキバキ鳴らしている。
「その言葉―――忘れるな!」
そう言うと、ハヤブサも顔を上げた。
ガアアアァァアア―――ッ!!
化け物が雄たけびを上げながら、キョウジに向かって手を伸ばす。それをシュバルツは、つかず離れずの距離を保ちながらかわし続けていた。とにかく、化け物の注意をできるだけこちらに引き付けておかなければならない。そうする事が、化け物と戦うドモン達の負担軽減にもつながる。
キョウジを抱えているとはいえ、化け物の動きは比較的鈍重。それに、化け物にダメージを与える事は考えなくていい。スピードに長けるシュバルツにとって、攻撃を避け続けるという事は、楽な作業であった。
「シュバルツ―――」
ふと、腕の中のキョウジが身じろぐ。
「どうした? キョウジ……」
キョウジの声に気付いたシュバルツが、問いかける。
「…皆に、伝言、を……頼ん…で、いいか…?」
痛みで、どうしても言葉が途切れがちになるが、それでも、キョウジは荒い息の下、言葉を紡いだ。
「伝言?」
問い返すシュバルツに、キョウジは頷く。
「そう―――伝言。…勾玉…に、集中……できた、おかげ…で……少し、分かった…事が、ある……」
自分の身体を抱える者がシュバルツになったおかげで、キョウジは余計な気を相手に対して回さなくてよくなった分、勾玉に集中できていた。それ故に、勾玉の事が少しずつだが分かりかけてきていた。
「…話…して、良い……か?」
問うキョウジに、シュバルツは頷いた。
「じゃあ……話す…ぞ。あれは……あの、化け…物、は――――」
シュバルツは、キョウジの言葉に耳を傾け続けた。
「――――!」
やがて、キョウジの言葉に、シュバルツは目を見開く。
「本当か?」
問い直すシュバルツに、キョウジは頷いた。
「よし、分かった。任せろ」
そう言うと、シュバルツはキョウジを抱えたまま、くるりと踵を返した。
化け物と、間合いを詰めるような格好になる。だがシュバルツは、それにかまわず突っ込んで行った。
ドンッ! ドンッ! と、化け物の拳がシュバルツめがけて振り下ろされる。シュバルツは、それを右に左に器用にかわしながら、化け物の下を潜り抜けた。
「シュバルツ!?」
「兄さん!!」
ちょうど化け物に対して攻撃を加えようとしていたドモン達とはち合わせる。
「皆! よく聞け! この化け物は―――!!」
グオオォォオオ―――ッ!!
まるでシュバルツに叫ばせまいとするように、化け物が拳を振り下ろしてくる。それを皆は、間一髪で避けた。
「この化け物は、『影』だ!!」
着地と同時に、シュバルツは叫んだ。
「『影』だから、いくら攻撃を受けても傷がつかず、再生してしまうんだ!! 本体は―――別の場所にいる!!」
「ええっ!?」
「何と―――!!」
「………!」
シュバルツの言葉に、一同は息を飲む――――陰で潜んでいた、仮面の魔道師でさえも。
「それは、確かなのであろうな! シュバルツ!」
「ああ…。キョウジがそう言ったんだ。間違いは無い」
東方不敗の言葉に、シュバルツが答えた。それを聞いて、仮面の魔道師は絶句する。
(あれの正体が、見破られただと―――!? 馬鹿な……!!)
あの男は、勾玉から与えられる苦痛に耐えるのが精いっぱいという状況のはずだ。そうだと言うのに、まだあれの正体を言い当てる離れ業を見せている。
倒しても倒しても再生し続ける『あれ』を使って、人間どもに絶望を与えるつもりが……!!
(おのれ……!)
怒りと屈辱で、魔道師の身体がわなわなと震える。
危険―――キケンダ。
キョウジ・カッシュ……。
この男だけは、絶対に殺しておかねば危険ダ!
殺してやる……!
殺してやる殺してやる殺してやる殺してヤル殺シテコロシテ―――。
(………………)
計算が、必要だ。
あの男を●スには、冷徹な計算が、必要ダ。
仮面の魔道師の姿が、ゆらり、と再び闇に溶けた。
「本体は、どこにいるのだ!?」
東方不敗の問いに、シュバルツが再び答える。
「分からない―――だが、近くにはいないそうだ」
(近くにはいない―――と、言う事は、何らかの『術』で、呼び出されているのか?)
ハヤブサがそう思い至った瞬間。
グワォオオォォオオ―――ッ!!
化け物が、再び大音声で吠えた。それと同時に、指の先からボタボタッと、大量の黒い塊を落とす。地面に落ちたそれは、いびつな『兵士』の形へと、変貌を遂げた。
それは、シュバルツの方に向かってじりじりと距離を詰めながら、周りを囲いこんでいく。
「…………!」
シュバルツは、脱出口を探るべく、素早く周囲に目を走らせた。だが、なかなかその隙が見いだせない。
「石破天驚拳!!」
ドン!! と言う音と共に、包囲網の一角がこじ開けられた。
「兄さん!! 早く!!」
叫ぶドモンに、「すまん!」と、シュバルツも答えると、そこから走り抜けていく。走るシュバルツの側に、黒い影が寄り添って来た。
「キョウジ―――そのまま聞け。『あれ』は、何らかの術であそこに呼び出されている、と、考えていいか?」
声の主は、ハヤブサだった。ハヤブサの問いに、キョウジは頷いた。
「よし―――」
そう言って、一度前を向いたハヤブサが、再びシュバルツの方に振り向く。
「シュバルツ。分かっているのだろうな! くれぐれも無茶はするなよ!」
ハヤブサの念押しに、シュバルツは苦笑する。
「分かっている。危険を感じたら、すぐに合図を送って知らせるさ」
「―――本当だな!? 絶対だぞ!!」
そう言い置いて、ハヤブサはシュバルツのそばから離れた。
「―――ったく、あいつはどこまで心配症なんだ……」
ハヤブサが去った後、ぼそり、とこぼすシュバルツの胸元で「ぶ……」と、声がする。ふと見ると、キョウジが痛みと―――笑いをこらえていた。
「キョウジ!?」
「ぶ……ククッ。あは…! あっはっはっは!! ―――あ痛! ……笑うと―――痛い!」
「…………!」
茫然とキョウジを見るシュバルツに、キョウジは苦笑しながら顔を上げる。
「―――なるほど……優しい、男…だね」
そう言いながらキョウジは笑い―――また、痛がっている。シュバルツは、はぁ、と、ため息をついた。
「キョウジ……笑うか、痛がるかどっちかにしろ」
「しょうがないじゃないか……笑える…ん、だから……」
「……まあ、笑える余裕があるんなら、良いけど―――」
何かをあきらめたように、シュバルツが呟く。キョウジは苦笑した。
「……シュバルツ…。お前、の……体調…は……?」
「―――全く持って、すこぶる快調だよ。どこにも異常は無い」
「は…はは……。これだけ、痛い…のに、死ぬほど、の、レベルじゃ…ないんだ…。人間の身体って…頑丈、だ…ねぇ」
そう言ってキョウジはため息をつき―――また、痛がっている。
「私に異常が出たら、ちゃんと言う。だから―――安心して痛がっていろ」
少し、突き放すような物言い。だが、キョウジは頷いた。
「うん―――そうさせて、もらうよ……」
そう言ってキョウジは、目を閉じた。
化け物から落とされる兵の数は、なおも増え続けて行く一方だ。
「ドモン!! お主はキョウジの護衛に回れ!! 化け物に直接ダメージが与えられぬと分かった以上、キョウジを守る事を優先した方が良い!!」
「分かりました!」
東方不敗の言葉に、ドモンは頷いた。そのまま踵を返し、シュバルツの方に走っていく。
(こ奴が『影』と分かって―――さて、どうする?)
群がる兵達を倒しながら、東方不敗は考えていた。幸いな事に、兵達の動きも比較的鈍重なものであったため、少々数が増えたぐらいでは、まだ脅威にはならない。しかし、このまま数が増える事を止められないとなると―――少々厄介な事になりそうだ。
「マスターアジア!」
ハヤブサから声をかけられる。
「何じゃ?」
「こいつはおそらく、何らかの『術』でここに呼び出されているらしい。だから俺は、その術の源を探ろうと思う」
ハヤブサのこの言葉に、東方不敗がピクリと反応する。
「―――そんな事が出来るのか?」
「多分―――だが、探っている間、少し無防備な状態になる…」
だから、少しの間護衛を頼めるとありがたいのだが、と言うハヤブサに、東方不敗は頷いた。
「よかろう!! さっさと済ませよ!」
「―――承知!!」
ハヤブサは、文言を唱え、印を結び―――目を閉じた。化け物から流れ出ている魔力の気配を探る。
「さあ―――かかってくる奴は、かかって来んか!!」
東方不敗は、ハヤブサを背に庇い、改めてファイティングポーズをとった。
化け物と、化け物から生まれた兵たちは、キョウジとシュバルツの方に向かって来ていた。動きはゆっくりなものだが、確実にその数を増やしつつある。
(この兵―――まだ増えるのか? あまり増えると厄介だな…)
そう思いながら走るシュバルツの腕の中で、キョウジは目を閉じている。
「…………」
痛みをこらえる―――と、言うよりは、懸命に勾玉の気配を探っていた。
(お願いだから、大人しくしてくれ……! 何でそんなに暴れているんだ…?)
キョウジの問いかけに、答えは無い。ただ、鋭い痛みが返ってくるだけだ。だが、勾玉が身体に入ってから、これほど濃厚にその存在を主張してきた事は無い。化け物が攻撃を受けるたび、勾玉も微妙に反応していた。だからこそ、あそこにいるモノがいわゆる『枝』で―――本体が別にいる事も、分かったのだ。
ハヤブサは、勾玉が化け物に「呼ばれている」と、言っていた。しかし、この勾玉の反応は―――少なくとも、『呼ばれている』と言うものではない。何か、別の物だ。
何だろう。この反応は。
勾玉が、何か言っている気がする。
ああ―――でも、聞き取れない。
その声が、小さすぎて。痛みが…酷過ぎて。
せめて、この痛み…この痛みが、もう少し、和らいでくれたなら……!
「…………!」
シュバルツが、小さな声を上げる。その声に、キョウジは顔を上げた。
「……シュバルツ?」
「―――囲まれている」
シュバルツが、鋭い視線を前方に投げかけている。木々の間から、化け物から生み出されたと思われる兵士たちの、妖しく光る眼が見え隠れしていた。それも、一人や二人の物ではない。おびただしい数だ。
立ち止まり、警戒するシュバルツから少し離れた所で、化け物が雄たけびを上げながら肉片を激しく撒き散らしていた。その一つ一つが、兵士へと変貌していく。兵を産み出す速度を、加速させているのだ。
背後からも、シュバルツ達を追って、ゆっくりとだが確実に兵士たちが迫りつつある。
「キョウジ……少し、荒っぽくなるぞ。それでもいいか?」
キョウジを抱く手に少し力を込めながら、シュバルツは言う。キョウジは頷いた。
「うん―――任せる…」
「よし―――」
シュバルツは、ダッと走りだした。そのまま木を駆け上がり、梢の間を枝から枝へと器用に移動して行く。上から兵達の群れを見下ろしながら、包囲の手薄な所を探る。
何故、彼がわざわざ狭い梢の間を移動する事を選んだのか―――それは、四方八方から一斉に囲まれて襲われる事を避けるためだ。兵達が飛び道具を使って来たとしても、木の枝や葉が、盾代わりになってくれるだろう。
幸いな事に、兵達は飛び道具を使ってこなかった。ゆっくりとだが木に這いあがり、シュバルツに飛びつこうとしている。後ろから攻撃してきた兵士が、木の枝に当たって落下した。
タタタタッ、と、軽快な足音を響かせながら、シュバルツは不安定な足場をものともせず、狭い梢の間をすり抜けていく。前方の枝の上に、兵士が立ち塞がっていた。それをシュバルツは、思いっきり蹴り飛ばす。グシャッ! と、音を立てて兵士の身体が砕け、ただの土くれになった。
少し離れた場所で、化け物がまた雄たけびを上げている。
シュバルツは走りながら、もう一度周りの状況を確認した。どこも兵達がひしめいているが、まだ左側の包囲網の方が、薄いように見受けられた。
(よし、左へ―――!)
シュバルツが左の方に方向転換しようとした瞬間。
「――――!」
何故か、シュバルツの脳裏にイメージがよぎった。
高熱源体のイメージ。
このまま左へ進んで行くと―――『灼かれる』
「チィッ!」
シュバルツは左に傾きかけていた重心を右に振り、そのまま右の方向を選んだ。木の上で待ち受けていた兵士たちを、2、3人まとめて蹴り飛ばす。そのまま梢を渡りながら、兵士たちの間をすり抜けようとした時。
ドォン!!
と、言う音と共に、シュバルツのすぐ後ろを高熱源体が通り過ぎ、彼の背後に有った森を、消し飛ばしてしまった。
「く………!」
爆風のあおりを受け、バランスを崩してしまう。それでもシュバルツは、キョウジを庇いながら―――何とか地面に着地した。
腕の中で、キョウジが呻く。
「大丈夫か? キョウジ…」
シュバルツの問いかけに、キョウジは笑顔を見せた。
「平気、だよ。…私に、外からの、ダメージ…は、加わって…いない……」
「そうか……」
シュバルツは、ほっと息を吐く。だが、彼の表情は、すぐに険しいものになった。周り一帯を、兵達に囲まれていたのだ。
「……………」
シュバルツはそっとキョウジを近くの大きな樹の根元に下ろした。そしてその樹を背に、キョウジを庇うようにして、その前に立つ。すらり、と、右手で剣を抜き、構えた。
ふと、懐に有る信号弾を、意識する。
(信号弾―――上げるか?)
一瞬そう思うが、すぐに頭を振った。
囲まれているとはいえ、兵の動きは鈍重なもの。おまけにこちらが少し攻撃を加えれば、その身体はあっという間に崩れ、土に還るという代物だ。先ほどの、モンスターまがいの兵や忍者たちに囲まれた時とは、状況が違う。この程度―――まだ、ピンチとは言えない。
「さあ―――どいつから来るんだ?」
刀で兵士の群れをけん制しながら、シュバルツは油断なく周囲に視線を走らせる。
見ろ。
見ろ。
必ず―――包囲を抜け出す機会はある。
包囲網を形成していた兵士の一体が、押し出されるようにしてシュバルツに向かってくる。
ドンッ! と、音を立ててシュバルツの刀が兵士の身体を斬り裂く。兵の身体は、あっという間にボロボロと崩れた。だが、それをきっかけとするように、次々と兵達が襲いかかってくる。
シュバルツはそれらを、刀で、拳で、時に蹴りを放って、次々と撃退して行く。それでいて、キョウジを庇うための立ち位置は、少しも変わらない。まるで、美しい剣の舞を見ているかのような戦いだ。
今戦っている相手が、この兵達だけなら、このままでいい。だが問題は、化け物の動きだ。先ほどから巨大なプレッシャーがキョウジに対して向けられているのが分かる。キョウジが森のどこに居ようと、化け物にはその位置が分かるのだろう。化け物と勾玉が、惹かれあっている―――と、言うのなら。それ故に、長く同じ場所に留まり続けるのは、危険すぎると言えた。
キョウジは、荒い息を吐きながらも眼を閉じ、静かに樹にもたれかかっている。
キョウジは『任せる』と言っていた。そして―――その通りにしてくれているのが分かる。自分に対する絶対の『信頼』が、その姿から感じられた。
だからこそ。
だからこそ―――願う。
キョウジだけは、守りたい。
それが叶うのであれば、自分の身など、どうなってしまってもいい。
シュバルツの両の手から放たれた複数の手裏剣が、周りの兵達の身体を破壊し、土へと還す。兵達との間合いが、少し開いた。
(今だ!)
シュバルツの方に迷いはなかった。キョウジの身体を左手で強引に担ぎあげると、背後の巨木を一気に駆け上がり、再び器用に枝から枝へとその身を走らせて行く。
また、化け物が雄たけびを上げている。
(高熱源体―――来るか!?)
シュバルツは走りながら、その気配を探った。一射目を撃ってから二射目を撃つまでの間のチャージ時間から考えて、そろそろか―――シュバルツがそう思った瞬間。
化け物の方が、意想外の行動に出た。ドンッ!! と、辺りを揺らすほどの勢いで地面を蹴ると、信じられないほどの距離を跳躍して来たのだ。バキバキバキッ! と、木々をなぎ倒しながら、シュバルツの正面に化け物は着地する。
「……………!」
シュバルツと化け物の視線が、しばしぶつかり合う。
(近い―――!!)
この距離であれを放たれたら、避けきれない。
カァァァァ――――ッ!!
化け物の口のあたりに、高熱源体の塊が、形作られて行く。
(まだ―――まだ、あきらめるな!!)
シュバルツは、走り続ける事を選択した。足を止めてしまえば、そこで総てが終わってしまう。しかし、キョウジに迫る高熱源体の気配は、濃厚になっていくばかりだ。
(キョウジ……!)
いざとなったらキョウジを放り出してでも―――シュバルツがそう決意して懐の信号弾を手にした瞬間。
「石破天驚拳!!」
声と共に、化け物の首が吹っ飛ばされる。
「――――!」
シュバルツが声のした方に視線を移すと、そこにドモンがいた。
「シュバルツ!! 兄さん!!」
ドモンが叫びながら、こちらに走ってくる。
「ドモン!!」
「…………!」
シュバルツの弟を呼び掛ける声に、キョウジも顔を上げる。
「ありがとう、助かった。―――だがドモン、どうしてここに?」
シュバルツの問いにドモンは応えた。
「師匠の指示で―――『化け物が直接倒せない以上、兄さんを守る事を優先しろ』って……」
でもシュバルツ、お前足早すぎだよ―――と、ドモンは息を切らしながら言う。おかげで追いつくまでに、かなり時間がかかってしまった。
「ドモン―――まだ、足を止めるわけにはいかん。走るぞ……ついてこれるか?」
「もちろん!」
シュバルツの問いかけに、ドモンは即答する。自分は兄を助けに来たのだ。足手まといにはなりたくなかった。
兄弟たちは、再び森の中を走り始めた。
「ハヤブサ―――! まだか!?」
東方不敗の、多少いらつきを含んだ声が響き渡る。化け物の動きがかなり激しくなってきている。このままでは何もかもが手遅れになる事態にもなりかねない。
(キョウジ…! 死ぬなよ…!! お主が死ねば、ワシも生きてはおらんぞ―――!!)
化け物を睨みつけながら、東方不敗は強く思っていた。
「――――!!」
不意にハヤブサが、面を上げる。
(見えた! あれだ!!)
「マスターアジア!! ついて来てくれ!!」
叫びながらハヤブサは、もう走り出している。東方不敗も、弾かれるように走り出した。
「―――分かったのか?」
東方不敗の問いに、ハヤブサは頷く。
「多分―――あれだ。間違いない」
ハヤブサが示す先に、一本の木が在った。幹に、何か札のようなものが貼り付けてある。
「マスターアジア! 木の根元に有る鏡を破壊できるか!?」
「―――鏡だと?」
東方不敗が根元に視線を移すと、確かにそこに、何か光るものがある。
「これか!?」
東方不敗は迷うことなく、それに向かって拳を振るった。それと同時にハヤブサが、札に向かって龍剣を振るう。
「いやああああっ!!」
ドンッ!!
音と共に、札を貼り付けて合った木が真っ二つになり、鏡が粉々に砕け散る。その瞬間。
「ギャアアアア――――ッ!!」
化け物が、悲鳴と共にその身体をのけ反らした。
「効いた!!」
ハヤブサが、叫ぶ。人間の反撃が、確かに化け物に入った瞬間だった。
「ハヤブサよ…。これで『術』とやらは破壊出来たのか?」
東方不敗の言葉に、ハヤブサは頭を振った。
「いや、まだだ…。見ろ―――」
そう言ってハヤブサが印を結んで呪を唱える。すると、ハヤブサの足元から前後に、青白い光が走った。それは、緩やかな弧を描きながら、遠くへと続いて行く。
「この手の化け物は、たいてい『陣』を使って召喚されることが多い。今破壊したのは、その陣を形成している一角にすぎないんだ」
「…………!」
東方不敗は、青白い光の行き先を見る。『陣』と言われるだけあって、巨大な円を描いているのだろうと言う事が、何となく見て取れた。
「おそらく今の様にこの円に沿って、札と鏡で要が形成されているはず…。それらをすべて破壊できれば―――」
「あそこにいる化け物を、倒す事が出来るのか!?」
東方不敗の言葉に、ハヤブサは腕を組んだ。
「……倒すと言うか、少なくともあそこにいる化け物を消す事は出来るな。本体は別にいるから、そちらにまでダメージが与えられるかどうかまでは、分からん…」
「ふむ……だが、あそこにいる化け物を消す事が出来れば、少なくとも今、キョウジは命を落とさずに済む…」
顎に手を当てながら、東方不敗が述べた意見に、ハヤブサも頷いた。
「―――問題は、俺たちがこの『陣』を破壊する事を、あの化け物を召喚した奴が黙って見ているかどうかだが……」
ハヤブサのこの言葉に、東方不敗はにやりと笑った。
「そんなもの―――何を恐れる事があろうか! 返り討ちにしてくれるわ!!」
「頼もしい事だな。―――では、二手に分かれよう」
その方が手っ取り早いだろう? と言うハヤブサに、東方不敗も否やを唱えなかった。
「ワシはもう行くぞ。お主も遅れるな!」
そう言うと、東方不敗はもう走り出している。やれやれ、気の早い事だな―――と、ハヤブサも思いながら、前を向いた。
男たちはそれぞれ、円に沿って反対方向に走り始めた。
化け物の『陣』の一角が崩されたことで、キョウジの方にも変化が起きていた。
「…………!」
キョウジの上げる小さな声に、シュバルツが反応する。
「どうした? キョウジ…」
「あ……いや、何か、痛みが―――」
和らいだ気がする、と、言いながら、キョウジは勾玉がある己が胸を見る。
「本当か?」
問うシュバルツに、キョウジは頷いた。
「兄さん! シュバルツ!」
ドモンの呼び掛ける声に、二人は顔を上げる。
「見てくれ! 兵が消えてる!」
「――――!」
ドモンが指さしたあたりを見ると、確かに、先ほどまでひしめき合う様にそこにいた兵士たちの姿が、消えている。
「な、何が起こったんだ……?」
茫然と呟くドモンに、キョウジが答えた。
「おそらく……ハヤブサが、何か…手を打ったのだろう……」
「ハヤブサが?」
振り返るドモンに、キョウジが頷く。
「……ごめん、シュバルツ…。今、下ろしてもらっても…大丈夫、か?」
「…………」
シュバルツは、無言で周りを見渡した。近くにいた兵士の一団が姿を消し、すぐに兵士たちが迫ってくるような気配は無い。化け物も、ダメージを喰らったのか、少し動きが鈍くなっている。少しの間だけなら、キョウジを下ろしても問題はなさそうだった。
「いいだろう。……だが、少しの間だぞ」
そう言いながらシュバルツは、キョウジを比較的大きな樹の根元に下ろす。
「うん―――ありがとう…」
キョウジは樹に凭れかかりながら、小さくほっと息を吐いている。口には出さないが、やはり、辛いのだろう。その苦しみ、代わってやれれば―――もうシュバルツは、何度そう思ったか分からない。
「―――ハヤブサは、あの化け物に…対抗するための手段を、知っているんだ…。でなければ―――」
「で、なければ?」
問いかけるドモンに、キョウジはふっと相好を崩した笑顔を見せた。
「……あんなに心配していた、シュバルツの側を…離れるわけがない―――」
「へ?」
ドモンが、ハトが豆鉄砲を喰らったような顔をする。それを見たキョウジが、また笑い出した。笑いながら―――また、痛がっている。
「キョウジ…。お前なぁ……」
呆れたようにこちらを見てくるシュバルツに、キョウジは笑いかけた。
「フフフ…。大切に、しろよ。せっかく……出来そうな『友達』…なんだから……」
「へっ!? 友達!?」
「シュバルツに!?」
キョウジの言葉を聞いたシュバルツとドモンが、同時に素っ頓狂な声を上げる。そのまま二人とも、固まってしまった。
「そう―――友達」
「…………」
「あれっ? 違った?」
「…………」
「お~い、シュバルツ~」
「…………」
「おいってば!」
「――――!」
やっとシュバルツから反応が返ってくる。しかし、何故か、かなり戸惑ったような気配を漂わせていた。
「ハヤブサは……お前の『友達』…だろ?」
ちょっといたずらっぽい笑みを浮かべながら、キョウジはもう一回シュバルツに聞いてみる。
「いや―――『友達』って……え? そうだったのか…? トモダチ……?」
シュバルツは、聞きなれない単語を聞いてしまったせいか、何だかぐるぐるしているようだ。
(確かに、ハヤブサとは同じ職種だし、何となく通じ合える所が無いわけではないが……しかし、あれは『友達』か…? 『友達』…? そもそも、『友達』の定義って、何だ?)
そのまま腕を組んで、頭を捻りだしている。
(ああ、考えてる考えてる…)
そんなシュバルツを見ながらキョウジは苦笑した。その横で、ドモンが一昔前の少女漫画によくあるような、まつ毛だけを残して瞳が無い―――いわゆる「白目」で衝撃を受けたような顔をしている。
(に、兄さんに…俺以外の親しい人間が―――!?)
背景にべたフラッシュが走り、バラの花びらでも舞いそうな勢いだ。
「お~い、ドモ~ン? 良いじゃないか。シュバルツに…だって、友達の一人や二人、出来たって……」
ドモンの心の声を察知したキョウジが、冷静にドモンにそう告げる。しかしドモンは「嫌だっ!!」と、いきなり大声を出してきた。
「シュバルツは、俺だけを見ててくれなくちゃ嫌だ!! 兄さんは、僕だけの物だ―――ッ!!」
「阿呆か――――ッ!!」
裂帛の叫びと共に、シュバルツの渾身の一撃がドモンを襲う。「あ~あ~」と言いながら見ているキョウジの前を、ドモンは木々をなぎ倒しながら派手に吹っ飛ばされてしまった。それでも次の瞬間「痛い!」と言いながらもすぐ身を起こすあたりが、さすが腐ってもキング・オブ・ハートと言ったところか。
「何するんだよ!! シュバルツ!!」
「それはこっちの台詞だ!! 何阿呆な言葉をギアナ高地の中心で叫んでいるんだ!!」
「だ、だって…兄さんが――! シュバルツが―――!!」
「だってもくそもあるか!! 大体お前はいつもいつも……!」
だがここで、二人の兄弟ゲンカはいったん中断してしまう。キョウジの笑いながら痛がる声が、また聞こえてきたからだ。
「……全く、この痛み……どうにか、ならないの…かな。これが無ければ、もっと……思いっきり、笑えるのに―――」
そう言いながらキョウジは、胸を押さえながらくすくす笑って、痛がっている。それを見たドモンはただ茫然とし―――シュバルツは、はぁ、と、ため息をついた。
「キョウジ……もう時間切れだ。移動するぞ」
そう言ってシュバルツがキョウジを抱きかかえる。キョウジはあきらめた様に「は~い」と、生返事をしながら、大人しく従った。
「…………」
疾走するシュバルツの腕の中で、キョウジは目を閉じ、トン、と身体を凭れかけさせた。
(ハヤブサが、シュバルツの事を心配する気持ち―――よく分かる…。私も同じだ…。シュバルツ―――私は、お前の事がとても心配だ……)
キョウジは思う。自分にも、多少その傾向があるのだろうが、シュバルツの方が、余程自分の身を省みていない。『死ねない身体』であるが故に、余計にそうなってしまうのだろう。
彼を、そういう身体にしてしまったのは、他ならぬ自分。
そして―――彼を、そういう行動に駆り立ててしまっているのも、おそらく自分が原因なのだ。それを思うと、キョウジは『自分』と言う存在の業の深さ、罪の重さに思わず吐き気を覚えてしまう。
どうすればいい。
いったいどうすれば、この罪を、償える?
ずっと、考え続けている。だけど、未だに答えは出ない。
その時ふと、キョウジの耳に、何かとても小さな小さな声が聞こえた。
(何だ―――?)
耳を澄ます。しかし、今度は声の代わりに鋭い痛みが返ってきた。
「――――ッ!」
痛みで、また声を聞き逃す。そして身体が強張る。だが、声を殺すことには成功した。やはり―――痛みが和らいでいるせいなのだろう。そして、自分が身体を強張らすたびに―――自分を抱くシュバルツの指先に、力が入っているのが伝わってくる。心配してくれているのだ。こんな……自分、を…。貴方を地獄につき落とした、張本人…なのに…。
(駄目だ…シュバルツ……。やっぱり―――やっぱり貴方は、優しすぎるよ……)
知らず、泣きそうになる。泣いている場合ではないと言うのに。
「キョウジ…? どうした? 泣いているのか…?」
案の定、こらえきれずに零れ落ちた一筋の涙を、シュバルツに見つけられてしまった。
キョウジは笑って、涙を痛みのせいにして、ごまかした。
ハヤブサは、ひたすら走り続けた。
今までに二つ、陣の『要』の破壊に成功している。そして、破壊が成功するたびに、化け物が確実にダメージを受けているのが分かる。動きも鈍くなり、心なしか、化け物の身体も小さくなってきているような感じだ。
今のところ、陣を破壊する作業に、術者からの妨害らしい妨害は入っていない。このまま、順調に破壊できればいい。しかし、陣が破壊されてしまう事を、術者が黙って見ているはずもない。絶対に、罠を張って待ち受けている。これは、確信だ。
「ムッ!?」
前方に、異変を発見する。そろそろ、『要』があっても良い地点だ。
(来たか―――!)
ハヤブサは、スピードを落とすどころか、むしろ加速した。どんな罠が待ち受けていようが、今更後に引くわけにはいかない。何よりも化け物を早く何とかしなければ、キョウジの―――そして、シュバルツの身に、危険が及ぶ。
特にシュバルツは、必要と判断すれば、キョウジのために簡単にその身を犠牲にする。そういう危うさが見え隠れしている。だから余計に、心配だった。
(絶対に早まるなよ、シュバルツ…! 俺たちが『陣』を破壊するまで―――!)
シャッ! と、音を立てて、鞘から龍剣を抜き放つ。前方に有る、異変の正体を確認する。それは、化け物から生まれ落ちた、黒い兵士の大軍だった。彼らは密集して、ハヤブサが来るのを待ち構えている。
「りゃああああああっ!!」
ハヤブサは迷うことなくその大軍の中に斬り込んだ。裂帛の気合とともにハヤブサが剣をふるうたびに―――無数の兵士たちの身体がボロボロと崩れて土へと帰って行った。それでもその黒い兵士たちは、次から次へと現れてくる。
(チッ! キリが無い!)
ハヤブサは印を結び、文言を唱えて黒龍を召喚した。龍は雄たけびを上げながら兵の群れへ突進し、そこにいた兵士たちを一掃する事に成功した。
(よし―――!)
ハヤブサが更に足を進めようとした瞬間。
彼は新たな異変を眼にすることになる。次にハヤブサを出迎えた集団は、子供と、赤子の群れ―――だったのだ。
「な――――!」
そのあまりの光景に、ハヤブサは思わず声を漏らして絶句する。子供と赤子の、肌の色は黒い。形もいびつ―――化け物から生み出された兵士と、同じ類の物だと、分かる。
ふと、女の子だと分かるような形をしたモノと、視線が合う。
「…………」
何かを求めるように、手を上げられる。ハヤブサは、思わず一歩引いてしまった。
(これを斬れと言うのか―――!? これを、斬れと……!?)
龍剣を握る手が、思わず震える。分かっている。これは、先ほど斬った兵士たちと、同じ類のモノだ。『命』と呼べるものではない。だが……。
寝返りも打てない赤子の手足が、バタバタ動いているのが見える。
(これをここに置くか!? 何と言う『悪意』の塊―――!)
ハヤブサはギリ、と、歯を食いしばった。絶対に斬られる、戦闘に巻き込まれると分かっている場所に、敢えてこのような非戦闘要員の姿をしたモノを配置する。これが―――底知れぬ『悪意』で無くて何だと言うのだ。この罠を設置した術者の確かな敵意に、ハヤブサは寒気すら覚えた。
試しに、斬らずに突破を試みてみる。
すると、子供の格好をしたモノが、次々とハヤブサに飛びかかってきた。ハヤブサに触れた子供の手や足が、熱を持って溶けだし、ハヤブサの肉に侵食してこようとする。
「うっ!! ……く、くそっ!!」
やむを得ずハヤブサは、龍剣を振るった。斬られた子供の形をしたモノが、ボロボロと土に還っていく。
(やはり、斬るしかないのか――!? 斬るしか……!!)
ハヤブサはギリ、と、歯を食いしばった。分かっている。今目の前にいるモノは、先ほど斬って捨てた兵士たちと同じモノ。ただ、外見が違うだけだ。ただ、それだけの事なのだ。だが―――。
「…………ッ!」
(斬れっ!!)
自身を、叱咤する声が聞こえる。
(斬れっ!!)
分かっている。自分は『人斬り』だ。今までに、任務のために、何人の命をこの手で奪って来たか、分からない。躊躇っている場合ではない。斬らなければ、前に進めない。『斬らなければ』、キョウジも―――そして、シュバルツも、救えない。
「…………」
ハヤブサが覚悟を決め、龍剣を握る手に、力を入れようとした瞬間。
「石破天驚拳!!」
力強い声と共に、巨大な掌の形をした気の塊が飛んでくる。それは、ドォン!! と、音を立てて子供の形をしたモノの集団にぶつかり、それらを次々と消し飛ばして行く。
「マスターアジア!?」
振り返るハヤブサの目に、東方不敗の姿が飛び込んできた。
「うおおっ! もう一発!!」
東方不敗は次々と掌の気を放ち、子供の姿をしたモノたちを消し飛ばして行った。総てのモノがいなくなったのを確認してから、東方不敗はようやくその拳を下ろす。
「―――おのれ! 姑息な手を使いおってからに……!」
東方不敗は、少し息を切らしながら、吐き捨てるようにそう言った。
「……マスターアジア…」
ハヤブサは構えを解き、龍剣を下ろしながら東方不敗の方を見た。
「フン―――これを仕掛けた奴は、ワシらが子供、赤子の類を見れば、手が出せんとでも思っておったのだろうよ。だがな……」
東方不敗はカッと目を見開き、己が拳を握りしめた。
「ワシは……キョウジが生きるために障害となりうるのであるならば、例えそれが老人であろうが女子供であろうが、容赦なく殺す―――! 例えその数が千に登ろうと、万になろうともだ…!」
「――――!」
ハヤブサは思わず言葉を失う。それは、東方不敗がそれだけの価値を『キョウジ』に見出しているということに他ならない。東方不敗は、そこに有ったのが例え本物の命であったとしても、躊躇わずにその拳を振るうのだろう。キョウジを生かすために、それをしなければならない―――と言うのであれば。
ある意味、こういった『悪意』に対して真っ先に犠牲になってしまいそうなキョウジにとっては、絶対に必要不可欠なサポートだ。だが―――『それ』を行う東方不敗を、人は『鬼』と呼ぶだろう。
「このようなこと―――キョウジには言うなよ!」と、言う東方不敗に対して、ハヤブサも「言えるか!」と、吐き捨てた。無意識のうちに、龍剣を握る手に力が入る。本当なら、自分もそれをしなければいけなかった。ハヤブサは、強くそう感じる。
自分は、躊躇った。
修羅に、なり切れなかった。
やはり自分は―――まだまだ甘い。
「―――なるほど、人間の中にも『鬼』がいるようですね……」
突如として、不思議な響きを含んだ声が、辺りに響いた。二人が声のした方に振り返ると、黒いフードをかぶり、白い仮面をつけた人物が、そこに佇んでいた。眼の所が黒く穿たれ、そこから金色に妖しく光る眼球を覗かせている。
「……まあ、人間など、所詮皆『鬼』の様なものだがな。互いを食い物にし、殺し合い……必要とあれば、平気で我が子すらその手にかける―――」
「つまらん御託はいい。貴様、何者だ!」
仮面の人物が話す言葉を、東方不敗は斬って捨てた。斬って捨てられた方は、からからと笑う。
「名など無い―――。人は、私の事を『仮面の魔道師』と、呼ぶがね」
「フン―――その『名無しの権兵衛』が、何用だ!」
東方不敗が、横目で魔道師を睨みつけている。『気に入らん』と、態度で言っているのが、はっきりと分かった。
「まあ、そう邪険にしなさんな……。せっかく、貴方がたが探している物を持って来てやったと言うのに―――」
そう言いながら、仮面の魔道師が、懐から札と鏡を取り出して、二人に見せつけてくる。
「…………!」
東方不敗とハヤブサが、同時にピクッ、と、反応した。
「おめでとう―――貴方がたは、この『要』の破壊をほぼ成功させている。残りは、これ一つだ」
「ほう………」
魔道師の言葉に、東方不敗はにやり、と笑い、ハヤブサの表情は更に険しいものになる。
「敵に、わざわざそのような事を教えても良いのかな?」
東方不敗の言葉に、仮面の魔道師はからからと笑った。
「かまわないさ。特に問題があるわけでもない―――」
そう言って、札をひらひらと振る魔道師。あからさまな挑発行為だ。
(罠か……?)
そう感じて、ハヤブサは警戒する。だが、東方不敗はそうしなかった。
「面白い―――問題が無いのなら、遠慮なく壊してくれるわ!!」
彼はそう言うや否や、いきなり攻撃態勢に移った。
「―――待てっ! マスターアジア!!」
ハヤブサが止める間にも、東方不敗は白い布を一閃させ、魔道師ごと札と鏡を破壊した。
ガシャン!!
札が真っ二つになり、鏡が粉々に砕け散る。だが次の瞬間、信じ難い事が起こった。砕けた鏡の破片の一つ一つが、『札と鏡を持った仮面の魔道師』へと姿を変えて行ったのだ。
「言ったはずですよ…。『特に問題は無い』―――と……」
そう言って魔道師たちは、どうしようもない暗さを含んだ声で笑い出す。
「…………!」
ハヤブサと東方不敗は、そのまま魔道師たちに取り囲まれてしまった。
「だから! 大丈夫だって! 痛みも、もうほとんど感じなくなっているし―――」
「キョウジ……本当か? 無理していないか?」
「してないって!」
そう言ってキョウジは、先程からあくまでも自力で歩くことを主張している。
「でも兄さん…。俺たちに心配かけまいとしてない?」
「してないよ! 無理なら『無理』ってちゃんと言うから―――」
「本当に?」
そう言ってドモンが、じ~っとキョウジの方を見ている。
(兄さんの『無理』は、人よりハードルが高いから―――)
兄は、いつもぎりぎりまで我慢していると日頃から感じているドモンは、兄の『大丈夫』がちょっと信用できないのだ。
(全く……どれだけ信用ないんだ、私は―――)
そう感じて、キョウジは苦笑するしかない。でも、今まで感じていた痛みが、かなり弱くなってきているのも、事実だ。それは、ハヤブサと東方不敗が『要』の破壊を成功させるたびに、キョウジの方に現れた変化だった。
今では、「あれ? 痛い……かな?」と、言うぐらいにしか感じない。
「とにかくもう、自力で歩くよ。実際、もう歩けるんだし、シュバルツだって、手が空いていた方が、何かと都合がいいだろ」
そう言ってキョウジは踵を返し、そのまますたすたと歩きかける。しかし。
「あ……あれ…?」
2、3歩歩いた所でいきなり眩暈に襲われ、倒れかけた。
「キョウジ!」
「兄さん!!」
二人が慌てて、キョウジの身体を支える。
「ほらみろ! やはり、無理をしているだろう!」
「兄さん―――!」
シュバルツの怒鳴り声と、ドモンの泣きそうな声の、ダブルパンチに見舞われる。
「お、おかしいな……。もう大丈夫だと思ったんだけど…」
苦笑しながらそう言うキョウジに、シュバルツは、はぁ、と、ため息をついた。
「あのなぁ、キョウジ……。お前はどれだけ痛みに耐えていたと思っているんだ。体力だって、想像以上に消耗している…」
だから、無理をするな、というシュバルツに、キョウジは苦笑しながらも頷くしかない。
「ご、ごめん……。ならばせめて、休ませてもらっていいか? そうすれば、もう少し回復すると思うから―――」
「…………」
キョウジの言葉に、シュバルツは無言であたりを見回す。
「いいんじゃないの? もうほとんど兵の姿も見えないし、化け物の方も、さっきブッ飛ばしたばかりだし―――」
ドモンがそう言って、キョウジに賛同する。
ハヤブサと東方不敗が化け物を召喚する陣の『要』を破壊するたびに、化け物の方にも変化が現れてきていた。あれほどひしめき合う様に出現していた兵達が、次々と姿を消し、化け物自体も小さくなり、その攻撃力も弱まって来ている。回復するスピードも、かなり遅くなっていた。
「……良いだろう。だが、危険を感じたら、すぐに移動をするからな」
「うん―――ありがとう」
そう言ってキョウジは、比較的大きな樹の根元に腰をおろして、ほっと息を吐いた。
「…………」
そのまま木の幹に凭れて目を閉じ、勾玉の気配に集中する。最初の内は、あれほど濃厚にキョウジの体内でその存在を主張していた勾玉も、痛みが薄れてくるにつれて、その気配も、おぼろげな物になってしまった。今では、その気配を探ることすら難しくなりつつある。
勾玉は、確かに化け物と惹かれあっていた。でも、『呼ばれている』のではない。正確には、『引き摺られている』……化け物に無理やり、引っ張られているような感覚だった。それが嫌で、勾玉自体は『抵抗している』―――それ故に『暴れている』、そう表現した方がしっくり来る気がした。勾玉のあの状態を言葉で表すとするならば。
(教えてくれ……。どうしてそんなに暴れていたんだ? 一体君は……私に対して、『何』を言おうとしていたんだ…?)
キョウジの問いかけに、勾玉からの答えは無い。ただ静寂が、返ってくるばかりだ。
先ほどまで、勾玉が何かを言っていたような気がするのに、その声すらもう聞き取れない。
(やはり、駄目か……。また、一から探りなおしかな……)
キョウジがため息と共に、そう思った瞬間。
「……………」
確かに聞こえてきた。とても小さな―――小さな声が。
だが、今度は小さすぎて聞き取りにくい。
でも、何かを言っている。叫んでいる。
とても大事な―――『何か』を。
(待ってくれ! 消えないで…! 君は……君は、いったい何を叫んでいるんだ!?)
キョウジはいつしか、懸命に勾玉の声に耳を澄ますことに集中していた。
「……………」
魔道師たちが、東方不敗とハヤブサを取り囲みながら、げらげら嗤っている。
「フン―――」
東方不敗は、手近に居る魔道師に対して、無造作に攻撃を仕掛けてみる。やはり、鏡が割れた破片の一つ一つが、同じように魔道師の姿に変化した。こちらを取り囲む魔道師の数が、更に増える。そして皆―――けたたましく嗤いだした。
「おい! 何をしている!?」
ハヤブサが、不用意に攻撃を仕掛けて魔道師の数を増やしてしまった東方不敗に対して、抗議の声を上げる。しかし、東方不敗はそれには答えず、魔道師たちの方を睨みつけていた。
(気に入らんな)
東方不敗は先程から、ある事が引っ掛かっていた。それが、どうしても気に入らない。
もう一度、魔道師に攻撃を仕掛ける。やはり―――数が増えた。そして、嗤いだす。
それを見た東方不敗の目に、俄然凶暴な色が宿った。
「面白い!! 貴様の魔力がどれほどのものか、このワシ自らが確かめてくれるわ!!」
そう叫んだかと思うと、東方不敗はいきなり魔道師たちの中に突っ込んで行った。自らの身体を激しく回転させながら、手当たり次第に魔道師達を破壊して行く。破壊された先で、魔道師が更に数を増やしている。だが、それすらも構わずに、東方不敗は魔道師達を破壊し続けた。
(な……何をしているんだ? この男……正気か?)
ハヤブサは、そんな東方不敗を半ば呆れながら眺めていた。勇猛果敢に魔道師に挑んでいるが、その姿はどう見ても、頭から罠に突っ込んで行っているようにしか見えない。
そんなハヤブサの目の前で、東方不敗の魔道師を破壊する攻撃が、ひたすら続けられていた。
グオオォォ……!
遠くの方で、化け物の雄たけびが聞こえる。だが、その声も小さく、かなり弱っているようであった。ズシン! と、化け物が倒れる音がする。歩くことすらままならないようだ。
「……随分、弱くなったな」
ドモンがそんな化け物の姿を見て、ポツリと感想を漏らす。
「そうだな…。ハヤブサたちの攻撃の効果が、現れているんだろう…」
ドモンの言葉に、シュバルツが答える。倒れた化け物が、足掻いているように見えるが、起き上がってくる気配はない。もう、兵を産み出す力も、残っていないようだ。
「―――それにしても、師匠たち遅いな……。何をやっているんだろう? まだ戦っているのかな?」
そう言いながらドモンは、きょろきょろと辺りを見回す。化け物が衰弱してから、かなり時間が経っている。化け物が弱るペース、兄が回復して行くスピードを考えると、もうそろそろ戦いに終止符が打たれても良いころなのじゃないかと、ドモンは思った。
ふと、ドモンの視線が、東方不敗の姿を捉える。ここから少し離れた場所で、何かと戦っているように見えた。
「シュバルツ」
「ん?」
ドモンの呼び掛けに、シュバルツが振り向く。
「俺、師匠の方の様子を見てきてもいいか? 俺が離れても、ここは問題ないだろう?」
「そうだな……」
ドモンの問いに、シュバルツは周りを見渡す。確かに、今すぐキョウジの身に、何か危険が差し迫っているような様子は無い。ドモンがここを離れても、問題は無いように思えた。
「……良いだろう。但し、油断はするなよ。未だ戦いが終わっているわけではない」
シュバルツの言葉に、ドモンも頷く。
「分かってる! シュバルツこそ―――兄さんを、頼むな!」
「ああ。任せておけ」
覆面越しに、シュバルツが笑顔になっているのが分かる。ドモンもそれに笑顔を返して、師匠の方に向かって走って行った。
それを見届けたシュバルツは、キョウジの方に振り返り、そっと呼びかけてみる。
「キョウジ……」
「…………」
キョウジからの返事は無い。休んでいるのだろうか―――と、様子を伺うと、どうやらそうではないらしい。勾玉がある胸のあたりに手を当て、息を潜めてじっとしている。何かに集中しているような気配だ。まるで、祈っているようにすら見える。
(……邪魔をしない方がいいか)
シュバルツはそう判断した。本当なら、少しでも休憩を取ってほしい所ではあるが、もしかしたら、勾玉の事で何か分かりかけている事があるのかもしれない。キョウジはこうなってしまったら、外からの呼び掛けには一切反応しなくなる。いつものことながら、ものすごい集中力だ。
(何があろうと、私は、キョウジを守りぬくだけだ)
シュバルツはまた顔を上げると、油断なく辺りの気配を探り始めた。
東方不敗の、仮面の魔道師の群れに対する攻撃は、まだ続いていた。そこに、ドモンが走り込んでくる。
「師匠! ハヤブサ!」
「ドモン・カッシュか! キョウジとシュバルツはどうした!?」
ドモンの姿を認めたハヤブサが声をかける。
「あっちの方は問題ない。化け物もだいぶ弱まってきたから、こっちの方を手伝いに―――って、何だこりゃ!?」
ドモンがここで初めて魔道師の群れに気づいて、素っ頓狂な声を上げる。
「ドモン! 良い所に来た!! お前もちょっと手伝わんか!!」
魔道師たちに攻撃を仕掛けている東方不敗から、声をかけられる。
(あれ? おかしいな……。傍から師匠を見た時は、こんな奴らの姿、見えなかったように思うけど―――)
ドモンは一瞬そう思う。しかし―――。
(ま、いいか。師匠がそう言うんだから…)
と、深く考えなかった。何よりも、師匠と共に闘うのは楽しい。そっちの誘惑の方が、ドモンにとっては抗いがたかった。
「よく分かりませんが、分かりました! こいつらを倒せばいいんですね!」
「おう! さっさとせんか! どちらがたくさん倒せるか、競争じゃ!!」
「はい!!」
「―――おいっ! ちょっと待―――!!」
ハヤブサが止める間もあればこそ。ドモンはあっという間に師匠と共に、魔道師の群れに突っ込んで行く。そのまま、実に楽しそうに戦い始めてしまった。ドモンを引き留めようとしたハヤブサの手が、空しく宙を漂っている。
(阿呆が二人に増えた……。もう嫌だ。この馬鹿師弟―――)
そう思って、頭を抱えようとしたハヤブサだが、ここで、ある事に気がついた。
(……魔道師の『魔力』の気配が、弱まって来ている?)
まさかと思い、少し探ってみる。すると、やはり、最初に感じた時よりも、魔道師一体一体から感じる魔力の気配が弱くなってきている。東方不敗にドモンが加わり、破壊と再生のスピードが速まったせいなのだろうか。
それに先ほどから、魔道師はげらげら嗤うだけで、攻撃を仕掛けてくるような気配はない。もしかしたら、単純に『時間』を稼がれている可能性もある。
(これは、急いだ方がいいかもしれない)
強くそう感じたハヤブサは、文言を唱えて印を結んだ。術の出所を探る事に集中する。その間、少し無防備な状態になるが、仕方がなかった。恐らく、ここで時間を稼がれてしまう方が、もっと悪い事が起きる―――そんな予感がした。
術の気配を探るハヤブサの周りで、師弟の魔道師たちの群れを破壊する戦いが、いつ果てるともなく続けられていた。
闇の中で、魔道師が嗤う。
ここまでは、計算通り。
さあ―――後、もう一息だ。
(何だ……?)
シュバルツがふと違和感を覚えて顔を上げる。
何だろう、これは。
何かが、おかしい―――。
キョウジの方を振り返る。キョウジの方に変化はない。先程と同じ格好をして、じっと息を潜めている。
では、この気配は何だ―――?
周りを探る。だが、何もない。
でも、おかしい。
何かが―――『いる』ような気配。
(これは……ここから移動した方がいいかもしれない)
シュバルツは強くそう感じた。
術の気配を探るハヤブサを、魔道師たちはいつまでも黙って見てはいなかった。ついに攻撃を仕掛けてきた。
「――――!」
気配を察したハヤブサが、目を開ける。だが、ハヤブサに攻撃が届く前に、魔道師たちはすべて東方不敗によって破壊された。
ハヤブサと、東方不敗の視線が合う。
(早くしろ)
東方不敗の目がそう言っているのを、ハヤブサは確かに見た。それで―――総てを察した。
(何て奴だ! 頭から罠に突っ込んで行っているように見せかけておきながら…!)
東方不敗は、最初から魔道師の魔力の撹拌を狙っていたのだ。幻覚を見せるにしても、強制的に数を増やされていけば、やがて限界値が来てしまう。これは、ある意味無謀で、馬鹿なやり方だ。だが―――『東方不敗は、王者の風』その言葉通りの戦い方を、彼はしている。
(あっちの方で、楽しそうに戦っている馬鹿弟子の方は、分からないがな…)
そう感じて苦笑するハヤブサの目の前で、ドモンが「超級! 覇王! 電影弾!!」と、叫びながら、火の玉のように突進して大量の魔道師達を破壊している。
しかしこれで―――心おきなく術の出所を探る事に集中できる。
ハヤブサは目を閉じ、再び術の気配を感じ取る作業に没頭して行った。
(お願いだ! 教えてくれ…! 君は、叫んでいるんだろう? 何か、何か大事な事を……!)
キョウジの呼び掛けに、勾玉から確かに答えが返ってきている。でもその声がひどく小さい。化け物が弱っていくのに呼応するように、声も…その気配すら、もう消えてしまいそうだ。
「キョウジ……」
シュバルツが、自分を呼び掛ける声がする。でも、無視をした。申し訳ないが、今はそれどころじゃない。
「……………」
確かに、何かを言っている。
ああ、でも、聞こえない。
聞こえないんだ。
「キョウジ――」
再びシュバルツから呼び掛けられる。
「―――ごめん、シュバルツ。少し黙っててくれ!」
「…………!」
キョウジから半ば悲鳴のような返事が返ってくる。それを聞いたシュバルツは、もう何も言えなくなってしまった。
だが『居る』
確かに『居る』
突き刺さるような殺気を感じる。鳥や虫の鳴き声も、先程から聞こえていない。
何かが、誰かが―――キョウジを狙っている。これは、確信だ。
お願い……お願いだ!
教えてくれ!
君は、いったい何を―――。
何を、叫んで……!
「―――――」
「!?」
(何……? 何…だって…?)
初めてキョウジの耳に、意味を持った『言葉』が届いた。
ドクン!
それと同時に、キョウジの目の前に、見たことも無い景色が広がる。
(な……何だ? これは……)
呆然とするキョウジの視界に入ってくる、黒い手。そして、首を鎖でつながれている感覚―――。
―――これは、何?
これは、いったい何だ。
無機質な壁に囲まれている。高い所から、自分を見下ろしている一人の老人が居る。
あれは―――『シュトワイゼマン』
「!!」
その瞬間キョウジは悟った。今見ている映像は、化け物の『本体』が見ている物なのだと。
空を見上げる。壁に阻まれる。だが、少し外が見える天窓からは、美しい星空が見えた。
立ち上がり、吠える。言葉にならない叫びを上げる。
声に乗って、キョウジの意識が、建物から外へと飛ばされる。
森が見える。少し郊外のようだ。そして―――今出てきた建物を見る。
この建物の構造―――どこかで見た。
確かに見た。シュバルツ達が調べてきてくれた資料の中に、あった。
あれは、どこだったか……どこだったのか―――。
―――調べないと!!
キョウジが、いきなり走り出した。周りに注意を払っていたシュバルツは、完全に不意を突かれた格好になった。
「キョウジ! 待てっ!!」
シュバルツが制止のための声を上げるが、キョウジには聞こえていない。まるで何かに魅入られたかの様に、一直線に走っている。
待ッタ……。
待ッテイタゾ。コノ瞬間ヲ―――!
走るキョウジの周りの空気が、ゆらり、と揺らめく。
「キョウジ・カッシュ!!」
「!?」
聞いたことも無い声に名前を呼ばれ、キョウジは瞬間足をとめた。振り返ると、黒いフードに白い仮面をつけた人物が、自分に向かって鋭い爪を振り上げているのが、見えた。
(え……?)
そのあまりに異様な光景に、キョウジの思考が一瞬止まる。
「もらっタ――――!!!」
「キョウジ!!」
シュバルツは信号弾を放り投げながら、キョウジに向かって飛び込んだ―――。
ドンッ!!
続けて、パリン、と、ガラスの砕ける音がする。魔道師の仕掛けた最後の『要』に、ハヤブサの龍剣が突き刺さっていた。
「ギャアアアア―――ッ!!」
断末魔の叫びを上げながら、化け物の姿が消えていく。それと同時に、魔道師たちの姿も、一斉に消えた。視界が開けた瞬間、パンッ! と、音が響き渡る。ハヤブサたちがそちらの方に振り向くと、そこにはシュバルツが放り投げた信号弾が、光を放っていた。
キョウジは最初、何が起こったのか理解できなかった。
爪が振りあげられているのが見えた、と、思った瞬間、誰かに突き飛ばされた。咄嗟の事で受け身も取れず、そのまま倒されてしまう。
「つ……!」
地面に叩きつけられたが、起き上がる事は出来そうだった。身を起こそうとして、足元に誰かの身体が乗っている事に気づく。そちらの方に視線を移すと、そこには―――シュバルツが倒れていた。
「シュバルツ!」
キョウジの呼び掛けに、シュバルツがピクッと反応する。
「キョウジ……」
そう言って顔を上げるシュバルツから、覆面が取れてバサッと落ちる。
(な、何で、シュバルツの覆面が、取れる……?)
そう思って混乱しかけるキョウジに、シュバルツから声がかけられた。
「キョウジ……怪我は、無いか…?」
自身に大きな怪我は無いので、キョウジはとりあえず頷く。
「そうか……良かった……」
そう言って、シュバルツは微笑んだ。
「ならば、キョウジ……。立て。そして―――走れ!」
「!?」
何故シュバルツがそんな事を言うのか、キョウジは咄嗟に理解できない。
「どうした、キョウジ…。早く!」
尚もシュバルツはキョウジを急かしてくる。ここに至って、ようやくキョウジは思考がゆるゆると回復しだした。
(そうだ…。私は多分、あの仮面の男に襲われたんだ…。だから、逃げないと……)
でも、逃げると言うのなら。
シュバルツも一緒に。
そう思って、キョウジはシュバルツに声をかける。
「シュバルツ……貴方…も…」
キョウジの言葉に、シュバルツは苦笑した。
「済まないな、キョウジ……。私は、ちょっと動けそうにない……」
「!?」
何故―――そう思いながらキョウジは身を起こす。身を起して、シュバルツの背中を見て―――息を飲んだ。
「―――!!」
シュバルツの背中に、鋭い爪で抉られた傷が刻み込まれていからだ。赤い筋が四つ、斜めに深く大きく走っている。
「あ……!」
そのまま、キョウジは視線を更に上にあげる。すると、そこには自分を襲ったと思われる仮面の男が佇んでいた。
「グ………!」
手に鉤爪の様な武器を装着していた。だが、腕を押さえて苦しんでいる。仮面の男の腕から、ポタ、と、赤黒い液体が滴り落ちていた。
シュバルツの右手には、短刀が逆手に握りこまれている。
「………!」
ここでキョウジは、ようやく状況を理解した。
つまり自分は、あの男に襲われて。
それを防ごうと、シュバルツは飛び出してきて。
シュバルツは、あの男にダメージを与えた。でも、私に向かう攻撃を防ぎきれたわけじゃない。
だから―――シュバルツは、その爪の下に、自分の身体を入れて。
私の『代わり』に、攻撃を―――『受けた』
「―――――ッ!!」
キョウジは思わず絶叫しそうになった。完全に、自分のミス―――自分の、ミスだ。
シュバルツの方に落ち度はない。思えばこうなる前、シュバルツは自分に声をかけてくれていた。恐らく、注意を促すために。
だけど、自分はそれを聞かなかった。それどころか、勝手に独りで飛び出した。
だから、シュバルツの背中のこの傷は、本来なら、自分が受けなければいけない物だった。自分が―――『受けなければならない』物だったのに……!
(おのれ……!)
仮面の魔道師は、シュバルツから受けた傷だけではなく、術を破られたことによる返しのダメージも受けていた。こんなに早く人間共に、あの術を破られるとは思っていなかった。それだけが、計算外だ。
ただ、標的であるキョウジ・カッシュも何故かすぐには動けないようだ。この男を仕留めるなら、今しかないと感じる。それにしても忌々しいのは、覆面を被ったこの男―――こいつさえ邪魔しなければ、今頃確実にキョウジ・カッシュを殺せていたものを……。
だが、この傷だ。この男も、もう動けまい。
後は、自分の身体―――早くダメージから回復せねば……!
「キョウジ―――早く!」
シュバルツは顔を上げ、懸命にキョウジに訴えた。
私はもう動けない。動けないんだ。
分かっているだろう? キョウジ……。お前の『死』が、私の『死』につながる。
お前が無事ならば、私は何度でも甦るんだ。だから―――今は、私の事には構わず、立って走ってほしい。
私の事を守りたいと思うのならば、尚更。
「……シュ、バ…ルツ…!」
理屈ではそうだ。分かっている。
今、自分がやらなければならない事は、自分の身を守ることだ。だから、立って、走らなければならない。
シュバルツを、見捨てて。
シュバルツを、『モノ』の様に、扱っ…て……。
「…………!」
何故だ。足が、動かない。
まるで、石で固められてしまったかのように、動かないんだ。
ゆらり、と、魔道師が動くような気配がする。
「キョウジ……!」
シュバルツは、ギリ、と、歯を食いしばった。
(何故だ、キョウジ……! 何故、立って、走ってくれない…?)
私は『モノ』だ。人では無い。
だから、そう扱ってくれていいのに。私を見捨てることに、良心の呵責など感じなくてもいいのに。
キョウジ……どうして……! 何故だ……!
「う……ッ! く……!」
とにかく、キョウジを守らなければ―――その一心で、シュバルツは動いた。
動かない身体に無理やり鞭を打ち、何とか上半身を起こす。そのまま身体を捻り、魔道師の方に相対する。短刀を持ちあげて、構えた。
たったそれだけの動きで、息が上がる。
景色が霞む。手にした短刀が、やけに重い。
だが、今倒れるわけにはいかない。キョウジを―――キョウジを、守らなければ…!
振り返ったシュバルツの顔を見て、仮面の魔道師は息を飲む。
(同じ顔―――! キョウジ・カッシュは二人いるのか―――!?)
シュバルツに背を向けられたが故に、キョウジにはシュバルツの背中の傷が、はっきり見えてしまった。
傷は背中を深く穿ち、裂けた中は紅く染まっている。そして、その周りが黒く変色していた。その不吉な紅は、シュバルツの身体が自ら治ろうとするのを、頑なに『拒んでいる』様に、何故かキョウジには見えた。
更に、シュバルツの身体を抉ったであろう魔道師の鉤爪の先が、黒い色を帯び、バチバチッ! と、放電しているような音を出している。
そこに有るモノは、何か。
抉られたのは、シュバルツの身体。
だから、そこに付着している物は、彼の身体を構成しているモノ。
そこからたどり着く結論は、一つしかない。
『DG細胞』を、敵に、取られた―――。
最悪だ。
今まで自分がしてきたミスの中でも、最悪の部類に入るミス―――それを、自分は犯してしまった。
キョウジ・カッシュが二人いる事を、敵にばらしてしまった事。
そして―――DG細胞を、敵に渡してしまった事。
何もかも自分のせい―――自分の、せいで。
(刺殺を、装った方がいいか……?)
短刀を構えながら、シュバルツは考えていた。
この、ろくに動けない身体でキョウジを守るには、どうすればいいか。それは、敵と相討ちに持ち込むことだ。それも、出来るだけ、敵にダメージを与えるやり方で。
その為に、シュバルツが選択した手段は、『自爆』―――だった。
刺殺を装えば、敵はそれを防ぐために、自分に攻撃を仕掛けてくる。斬られている間に、敵に抱きつきさえすればいい。後は懐の火薬が、役割を果たしてくれるだろう。
(問題は、あの仮面の男にこの攻撃が効くかどうかだが……)
そう思いながら、シュバルツは仮面の男を見据える。恐らくこの男は、何がしかの『魔力』を帯びている。だからもしかしたら―――この攻撃でも、あの男には致命傷を与えることは出来ないかもしれない。
だが、それでもいい。
時間さえ稼げれば。
信号弾は、上げた。
後は、ドモンが、東方不敗が、ハヤブサが―――キョウジを、守ってくれるだろう。
だが、問題は、キョウジとのこの距離。
自爆攻撃を仕掛けるには―――キョウジが近すぎる。
巻き添えにしてしまったのでは、意味が無い。
「キョウジ……!」
「あ……!」
シュバルツが、懸命に訴えているのが分かる。逃げろと。立って走れと。
分かってる。分かっているんだ。
自分の『死』が、シュバルツの『死』につながる。ここに居ても、自分は何の役にも立たない。だから、逃げないと。逃げるのが、正しい。分かっているのに―――。
足が……足が、動かない。
シュバルツの背中の傷が、嫌でもキョウジの目に飛び込んでくる。
深く抉られた傷から、バチッ! ジジッ! と、音がしている。紅の色が、先ほどよりもきつくなっている気がする。黒く変色した部分も、広がっているように見える。
やはり、治る気配が―――無い。それどころか、傷が、シュバルツを侵食しだしているような……。
駄目だ―――やはり、この傷は『普通じゃない』
治さないと…! おそらく、シュバルツの自己再生では、治せない。
シュバルツが、何かの位置を確認するかのように懐をまさぐっている。ちらり、と、線の様なものが見えた。
(導火線―――? まさか、シュバルツ、『自爆』する気か!?)
忍びは人外の化生。たいていの事を、やってのけるのが忍び―――そう『忍者』の事を評した戦国時代の武将が居た事を、キョウジは思い出す。
自分が身動きできない状況で、それでも敵にダメージを与えることだけを狙うなら、『自爆』という選択肢も十分あり得る。
でも、駄目だ。シュバルツ。
その傷は駄目だ。
その傷を持ったまま自爆すると…。
下手をしたら、シュバルツを……。
(キョウジ……走れないのか? やはり、駄目なのか…?)
何故―――見捨ててくれない。そう思って、シュバルツは歯噛みした。
分かっていた事ではないか。
キョウジは―――優しすぎる。
私を『モノ』扱いしろ、と言って、一番そう出来ないのが彼なのだ。
私のような紛い物の『生』でさえ、まっとうな『命』として扱おうとするのが彼なのだ。
そんな―――キョウジだから、私は。
彼を……『守りたい』と。
(立てっ!)
シュバルツは、強く己に命じた。
キョウジが立って走れないのなら、自分が距離を、あけるしかない。
(立てっ!)
背中が焼けるように痛む。膝がふらつく。足に力が入らない。
だが、そんな事に構っている場合ではない。
今の私は、キョウジを守る―――それしか、存在意義が無い。
それが、守るどころか、キョウジの『死』の一因を担ってしまう事になるのだけは―――絶対にごめんだ!
シュバルツは、立った。
ふらつきながらも、肩で荒い息をしながらも、短刀を構え、仮面の魔道師を睨み据える。
「何…だ、と……?」
この気迫に、仮面の魔道師も思わず気圧された。知らず、身を一歩引いてしまう。
馬鹿な……! この男、まだ立つと言うのか…?
この私でさえ、まだダメージから回復していないと言うのに……!
(おのれ……!)
怒りで身体がわなわなと震える。『キョウジ』と同じ顔をしている。それだけで、余計に腹立たしい。
(この死に損ないが―――何が出来ると言うのか!?)
返り討ちにしてやる、と、魔道師はガシャッと鉤爪を構える。その爪の先で、バチバチッと放電している物体がある事に、彼はまだ気づいていない。
(駄目だ、シュバルツ。駄目だ―――!)
自爆を止めさせなければ、と、キョウジは強く思った。
でも、どうすればいい。
どうすれば。
私が彼を庇っても、私が死んでしまったら、彼も死んでしまう。
かと言って、私が立って走ったら、彼は迷い無く自爆をしてしまうだろう。
あの傷を持ったまま、更にダメージを喰らった場合、本当にもう取り返しがつかなくなってしまう可能性が高い。
シュバルツを……喪ってしまう、可能性が、高い。
嫌だ! それは嫌だ!
キョウジは真っ先にそう思った。
死んでほしくない。
死んでほしくないよ。シュバルツ。
例え、この『生』が、貴方には『生き地獄』であったとしても……。
シュバルツ―――貴方を、そんな身体にしてしまってから、貴方には、辛いことしか無かったかもしれない。
もう、早く消えてしまいたい。解放されたい。そう、願っているのかもしれない。
でも―――でも、こんな所で、そんなふうに死んでほしくは無いよ。
しかも―――私の『ミス』のせいで……!
これは、エゴなんだ。
シュバルツを縛り付けている、私の愚かなエゴ。
分かっている。彼に生き地獄を強いる権利なんて、私には無い。
分かっているんだ…!
でも、嫌だ。彼が死ぬのを止めたい。
でも、じゃあ、どうすればいい?
今のままでは、何をやっても、どうやっても―――彼は死んでしまう。
本当に……本当に、打つ手が―――無 い 。
ダメ。
駄目だ。
あまりにも無力な己に、キョウジは絶望しそうになる。
「う……あ……!」
知らず、口から声が漏れ出ていた。このままもし、ここに誰も走り込んでこなかったなら、キョウジは狂ったように叫んでいたかもしれない。
「シュバルツ! キョウジ!!」
声と共に、黒い影が仮面の魔道師に向かって突き進んできた。
ダンッ! と、ハヤブサが踏み込み、龍剣を仮面の魔道師に向かって振るう。
「チィッ!!」
魔道師は、ハヤブサの攻撃を間一髪で避けた。
「二人とも無事か!?」
シュバルツと魔道師の間に割って入り、魔道師との間合いが少し開いた所で、ハヤブサは二人の方に振り返った。
「――――ッ」
ハヤブサと視線があったシュバルツの身体が、ぐらっと傾く。
「シュバルツ!!」
そのシュバルツの身体を、キョウジが支えた。そんな二人の様子に、ハヤブサも一瞬気を取られてしまう。
(馬鹿め! 隙だらけだ!!)
仮面の魔道師が、再び攻勢に転じようとする。―――しかし、それは叶わなかった。
「石破天驚拳!!」
声と共に、巨大な気の塊が拳の形を成して、仮面の魔道師に襲いかかってくる。それが当たる直前、魔道師は己が身体を魔道の力で分解し、別の場所に再構成させる。
だが、そこには東方不敗が居た。
「おのれ!!」
魔道師の姿を確認するや否や、東方不敗は白い布を振り回して、魔道師の身体を真っ二つにしようとする。
(……チッ! ここまでか―――)
仮面の魔道師は、ついに退却を選択した。
「皆! 無事か!?」
魔道師の姿が消えたのを確認してから、東方不敗は振り返った。そこで―――東方不敗は己が目を疑う光景を見た。
ドンッ! と、シュバルツが、キョウジを振り払うように突き飛ばしていたからだ。突き飛ばされたキョウジは尻もちをつき、突き飛ばしたシュバルツの方も、ガクっと膝をついている。
「キョウジ……お前……どういう、つもりだ……!」
シュバルツがキョウジを睨み据えている。キョウジを振り払った手が、わなわなと震えていた。
「シュバルツ……」
当然だ、と、キョウジは思った。シュバルツを怒らせるだけの事を、自分はしてしまったのだから。
「お前…! 分かっているのか!? 本当に、分かっているのか!? …何故、走って逃げない…! 死ぬところだったんだぞ!?」
「…………!」
シュバルツのあまりの剣幕に、一同は言葉を失う。しかも、シュバルツが向けている怒りの矛先は、キョウジ。ある意味、自分を容赦なく責め立てている状態だ。故に『口をはさめない』―――と、誰もが思った。
「分かってる……。ごめん―――ごめん…な、さい……」
キョウジは、消え入りそうな声で謝った。それしか―――言えなかった。それ以外に、何が言えるだろう。
「いいや! 分かっていないだろう、お前…! 分かっていない!! いいか!? お前の命はお前だけの物じゃない! ここにいる、全員の命を、お前は背負っているんだ!!」
「…………ッ」
キョウジは、膝の上でぎゅっと握りこぶしを作る。
正論だ。正論なんだ。シュバルツの言っている事は―――どこまでも、正しい。
「私だけじゃない…! ここにいる全員が、お前を守るために命をかける…! だから、お前は何としても生きなければならない、義務があるんだ!! それを―――何だ!! 私が怪我をしたぐらいで……!」
シュバルツの瞳に、うっすらと光る物が浮かんでいた。
分かっている。自分は、存在しているだけで、キョウジに『罪』を突きつけている。傷つけている。
だから―――せめて、キョウジの役に立ちたいのに。キョウジを、生かしたいと願うのに。
さっきのキョウジの態度は、自分と共に『死にたがっている』としか―――思えない。
自分のせいでキョウジが死ぬ―――それは、一番自分が望まない事なのに…!
「分かっているだろう!? 私は『影』だ!! お前が生きるために必要ならば、真っ先に斬り捨てるべき存在なんだ!!」
「シュバルツ……」
キョウジの眉が、ピクリ、とつり上がる。
「ちゃんと『捨てろ』!! いちいち私の事を―――!!」
「シュバルツ、傷を見せろ」
キョウジが、低い声で言う。まるで、これ以上シュバルツにしゃべらせる事を拒むかのように。
「キョウジ―――! 人の話を……!」
「私の事はいくらでも罵っていい!! だから―――傷を見せろ!!」
「キョウジ……!」
めったに大声を出さないキョウジの怒鳴り声に、シュバルツは思わず気圧されてしまう。シン…。と、水を打ったような静けさに、辺りは包まれた。
不意に。
「うげぇぇぇ」
と、カエルが潰れたような声に、その沈黙が破られる。驚いて一同がそちらの方を見ると、ドモンが胃の中の物をリバースしていた。
「「ド、ドモン!?」」
二人の兄が、同時に声を上げる。
「ご、ごめん……ちょっと、空気に耐えきれなくて――――」
そう言いながらドモンはまた噎せ、ゲホゲホと吐いている。それを見た二人の兄は、同時にドモンの方へ行こうとし―――シュバルツは立ち上がれずにガクっと膝をついてしまう。それを見たキョウジが、ドモンの方に行こうか、それともシュバルツの方に行こうかと、わたわたしている。
その様子を見た東方不敗が、やれやれ、とため息をつきながら、ドモンの方に近づいた。
「この馬鹿弟子が。この程度で何を吐いておる」
そう言いながら東方不敗はドモンを軽くどついて、それからハンカチを差し出した。
「これを使え。全く、修行が足りん奴だ」
「で、でも師匠……兄さんが……」
ドモンがハンカチで口元を拭いながら、涙目で東方不敗の方を見る。兄同士の口論が、よほど堪えたのだろう。
「阿呆か。兄御達だって人間だ。意見が食い違う時だってあるわい。生きておるのだから―――」
「…………!」
それを聞いたキョウジとシュバルツが、同時に互いの顔を見る。が、すぐにシュバルツの方が少しばつが悪そうに眼をそむけた。それを見たキョウジが、少し哀しげに苦笑する。
だが、その表情は、穏やかな『いつものキョウジ』だった。
それを見てドモンは―――やっと、落ち着く事が出来た。
「シュバルツ、大丈夫か?」
ようやくハヤブサも、シュバルツに声をかける事が出来る。それぐらい、先程の二人の口論は、他人の介入を許さない雰囲気があった。
「平気だ」
シュバルツの方は、まだ怒りが収まっていないのか、多少ぶっきらぼうな返事が返ってくる。
「でも、お前……この傷は―――」
そう言ってハヤブサがシュバルツの背中の傷に触れる。その途端。バシッ!! と、大きな音がした。それが、シュバルツの方に激烈な痛みをもたらし、ハヤブサの手にも、弾かれたような衝撃をもたらす。
「うわああああっ!!」
「―――ッ!」
あまりの痛みに、シュバルツは思わず叫んでしまった。ハヤブサも、思わず触れた手を抑える。
「シュバルツ!!」
「兄さん!! 兄さん!!」
ドモンが、叫びながら走り寄ってくる。
(『兄さん』……ドモンでさえ、戦いの最中はシュバルツの事をそう呼ぶ事を、我慢してくれていたと言うのに――――)
キョウジは、思わず己の拳を握りしめた。これは『キョウジが二人いる』という情報を敵に渡さないようにするために、戦いの前、キョウジとシュバルツが、シュバルツの事を『兄』と呼ばないように、ドモンに頼んだ事だった。
なのに、結局自分はその情報を敵に渡してしまった。自らの『ミス』のせいで―――。
思えば、自分の人生は、こういう事の連続の様な気がする。肝心な時に、一番やってはいけない『ミス』をする―――そう感じて、キョウジは軽く自己嫌悪に陥ってしまう。
「平気だ……放っておけば、治る。お前も…知っているだろう」
心配してくるドモンを振り払うようにシュバルツは言った。
「で、でも……!」
「無理だ……シュバルツ。その傷は、『治らない』」
キョウジの静かな声が響き渡る。一同が驚いて顔を上げると、穏やかな―――しかし、哀しげな眼差しをしているキョウジと、目があった。
「な………!」
シュバルツは思わず息を飲んでしまう。キョウジは、そんなシュバルツに確認させるように、もう一度、言った。
「『治らない』んだ。その傷は……。治さないと…」
「―――何故だ……!」
茫然とシュバルツは呟く。キョウジの方に、異常が出ているわけではないのに……。
「分からない……。でも、もしかしたら…あの仮面の男が帯びている『負』の魔力に、DG細胞が引きずられているのかもしれない……」
そう言いながらキョウジは、シュバルツの背中越しに見たあの仮面の男の事を思い出す。あの男からは仄暗い、悪意のよう意志を感じた。その意思が、シュバルツを構成しているDG細胞に働きかけて、シュバルツがシュバルツであろうとする事を拒否しようとしている―――そんな感じがする。
だから、傷は逆にシュバルツを侵食して行き、シュバルツを破壊する。それから、自己再生機能は働くだろう。しかし、それで再生した『モノ』は、もうシュバルツとは呼べない物になってしまうに違いない。
本当に―――最悪の『ミス』だ。
DG細胞にこれほど強く働きかける事が出来る敵に、それを渡してしまった。故に、敵の手に渡ったDG細胞は、本来の凶悪性を取り戻した物になって自分達の前に立ち塞がってくるだろう。
勝手に飛び出したのは自分なのに、シュバルツに庇わせてしまった。
やはり、シュバルツの背中のこの傷は、自分にこそ刻みこまさなければならない物だった……!
強くそう感じて、キョウジは唇をかみしめた。
(DG細胞?)
聞きなれない言葉に、ハヤブサがピクリと反応する。
「に、兄さん……!」
ドモンが震えながら、キョウジの方に近づく。
「な、治るよな? シュバルツは…治す事が、出来るんだよな…?」
「大丈夫だ―――治せるよ」
そう言って微笑むキョウジに、ドモンはホッと息を吐いた。
「…なら、さっさとシュバルツの傷を治せキョウジ。総てはそれからだ」
東方不敗が、キョウジに声をかけてくる。その言葉に、キョウジも頷いた。
シュバルツを両脇から、ドモンとハヤブサが支える。シュバルツはやはり苦しいのか、時折くぐもった呻き声を漏らしていた。
(やはり、背中の傷が、拡がって来ている……)
シュバルツの背中の傷の状態を確認したキョウジは、暗澹たる気持ちになる。
「キョウジ……」
シュバルツから声を掛けられ、キョウジは顔を上げた。
「お前……あの時、走らなかったのは……私の背中の傷が、治らない……と、気づいたから、なのか…?」
シュバルツのこの言葉に、キョウジは苦笑しながら頭を振った。
「いや…。傷の性質とかに気づく前から、私は走る事が出来なかった…。やっぱり、駄目だな。私は……。頭では、分かっていたのに―――」
「キョウジ……」
そう言って淋しそうに笑うキョウジを見て、シュバルツの、背中では無く胸の方が何故か痛む。
確かに、最初は単純に走れなかっただけかもしれない。だが、傷が『治らない』と気づいてからは、別の走れない理由が、キョウジには加わっていた可能性があるのだ。
(まさか、私の自爆を止めたかったのか? 私が本当に『壊れてしまう』と気がついたから―――)
まさかと思う。
そんな馬鹿なと思う。
私は、キョウジにとっては『罪』その物をつきつけている存在のはず。
時折、私の方を見て辛そうに笑うキョウジ。傷つけていないはずがない。
だから―――自分は、早く消えてしまった方が、キョウジのためにはいいのではないか、と、思う事がある。もっとも、消え方が分からないから、困っているのだが…。
なのに、キョウジは私に『生きろ』と言う。
私が消えるのを、拒むような事をする。
何故だ、キョウジ……。
何故―――。
「キョウジ……」
もう一度、シュバルツはキョウジに声をかける。その答えが聞きたくて。だが、キョウジは、シュバルツの方に振り返ると、彼の表情から別の事を感じ取ったようだ。
「お前が謝る必要はないよ。悪いのは私だ。……全く、私は本当にどうしようもない『へたれ』だよなぁ。肝心な時に、腰が抜けちゃうんだから―――」
そう言って明るく笑うキョウジからは、シュバルツが望む答えは聞けそうになかった。
「皆、ありがとう。後は、私が処置するから―――」
キョウジがそう言って、皆に礼を言う。あれから皆は東方不敗のアジトに帰り、シュバルツはキョウジの研究室の寝台に、運び込まれていた。
「兄さん、何か手伝う事は?」
そう声をかけてくるドモンに、キョウジは微笑み返す。
「今のところはいいよ。ああ、でも―――部屋の外でいいから、近くに誰かいてくれるか? 人手がいるようになったら、呼ぶかもしれないから……」
「―――分かった」
ドモンがそう言って頷いたのを確認してから、キョウジは研究室の扉を閉めようとする。
「兄さん! シュバルツ!」
「―――大丈夫だよ」
扉が閉まる直前、思わず走り寄ろうとしてしまったドモンに、兄はそう言って笑顔を残して、ドアの向こうへと消えた。
「…………」
ドモンは、ドアの前で立ち尽くした。
東方不敗もハヤブサも――――誰も、その部屋の近くから、動こうとしなかった。
「シュバルツ」
キョウジは寝台の上にうつぶせに寝かせてあるシュバルツに声をかけた。そろそろ麻酔が効いている頃合いだと思った。しかし―――。
「キョウジ……」
シュバルツから反応が返ってくる。キョウジは驚いた。
(まさか―――麻酔が効かないのか!?)
「シュバルツ……気分は、どうだ?」
努めて平静を装って、キョウジはシュバルツに声をかけた。背中の傷は、やはり、最初に見た時よりも大きくなってきている。傷は、ゆっくりとだが確実に、シュバルツを侵食しつつあるようだ。
「気持ちわるい……。これは、何だ? 麻酔か…?」
シュバルツは頭を少し持ち上げ、顔についているマスクを外そうとする。
「寝たくない―――寝たくないんだ、キョウジ……」
そう言ってシュバルツは頭を振った。まるで、何かに抗うかのように。
(これは……麻酔が効かないと言うより、『拒否』している…?)
シュバルツの意識が―――と言うより、シュバルツ自体が、麻酔を拒絶しているような―――そんな感じだった。傷が、『悪意』が、シュバルツの根幹部分を揺るがし始めているのかもしれない。意識を手放すことで、それが加速する事を、シュバルツは本能的に防衛しているかのように、見えた。
「キョウジ……」
シュバルツの顔色が、ますます悪くなって行く。
もう彼にとって『麻酔』は、本来の働きで機能していない。毒ガスの様な物にしか感じられないのだろう。シュバルツにこれ以上麻酔を施すのは危険――――キョウジは、そう判断せざるを得なくなった。麻酔を止めると、シュバルツはホッとしたように息を吐いた。
「…………」
だがこれでは―――シュバルツの治療を、『麻酔無し』でやらなければならない、と言う事になる。
キョウジは、拳を握りしめた。
「シュバルツ―――傷の状態を、見るぞ」
キョウジは、シュバルツにそう声をかけてから、背中の傷に触れる。その途端。
バシッ!!
大きな音がして、キョウジの手が弾かれた。傷からもたらされる激しい痛みを伴った衝撃故に、シュバルツの身体もビクン、と、撥ねる。
「あっ……ッ! ぐ……ぅ…ッ!」
シュバルツは懸命に声を殺して痛みをこらえた。悲鳴を、キョウジに出来るだけ聞かせたくはなかった。
「――――ッ!」
キョウジも、弾かれた衝撃で、2、3歩後ろに下がってしまう。まるで傷から『治す事など許さない』とでも言われているかのようだった。
(くそっ……!)
衝撃で少し痺れる手をキョウジが抑えていると、寝台の方でシュバルツが動く気配がする。ふと見ると、シュバルツが身を起こそうとしていた。
「キョ…ウ、ジ……」
その瞳には、キョウジを心配する色だけしか、浮かんでいない。
(こんな時に―――私の身の方を案じている場合じゃないだろう! シュバルツ!!)
キョウジはギリ、と、歯を食いしばった。厚手のゴム手袋を、両手に嵌める。気休めだろうが、無いよりはましだ。シュバルツを治すための器具やら工具やらが入っているキャスター付きの道具一式を多少乱暴に引き寄せる。
それからキョウジは、白いハンドタオルを折りたたんでシュバルツに差し出した。
「これを口に咥えてろ。麻酔が効いていないから、痛みがダイレクトに来る。噛みしめたら、奥歯が砕けるぞ―――」
シュバルツは無言で頷いて、ハンドタオルを受け取った。
「後―――動くなよ。動かれたら、治療が出来ない」
必要なら、身体を固定するか、皆を呼んで押さえてもらおうか、と、キョウジはシュバルツに提案した。だが、シュバルツは「いらない。大丈夫だ」と、断った。
「じゃあ、始めるぞ」
キョウジがそう言って、器具の一つを手に取る。シュバルツはハンドタオルを口に深く咥え込み、寝台の端に手をかけた。
ドンッ!!
キョウジが治療を開始した途端、激烈な痛みを伴った波が、シュバルツの身体の中を走る。
「――――――ッ!!」
その痛み故に、シュバルツは絶叫した。くぐもった悲鳴が、部屋に響き渡る。だがそれでも、彼は身体を動かさなかった。寝台の端を抱えて、『動くな―――!』と、ただひたすら己に命じ続けた。痛みで撥ねそうになる身体を、抑え込んだ。
自分は、痛みに耐えるだけでいい。
だが、治すキョウジの方が、もっと……もっと、大変なんだ。
だから―――こんな痛みが、何だと言うのだ……!
タオルを噛み締め、叫び、呻きながら―――シュバルツはそう、思った。
治療の手を進めるたびに、傷がキョウジを弾き飛ばそうとしてくる。『治すな―――!』と、激しく抵抗してくるのが分かる。
(くそっ! ふざけるな!!)
その一つ一つを、キョウジは力でねじ伏せる様に治して行く。
傷からにじみ出る『悪意』に叩かれ続ける手が、痛みで痺れる。だが―――それがどうしたと、キョウジは思った。
シュバルツの方が、もっと痛い。
シュバルツの方が、もっと苦しい―――。
だから―――こんな手先の痛みぐらいが、何だと言うのだ。
絶対引かない! 絶対に、治す!!
(シュバルツ……!)
青白い光が飛び散る中、キョウジの戦いの様な治療が、続けられて行った。
ドンッ!!
治療と言うにはあまりにも激しすぎる音が、部屋の外まで響き渡ってくる。そして、合間にシュバルツの―――『兄』の、くぐもったような悲鳴が、漏れ聞こえてくる。
最初の内は、ドアから少し離れた所で、己の身体を抱え込むようにして立ちつくしていたドモンであったが、やがて、我慢の限界を超えてしまった。
「兄さん! 兄さん!!」
悲鳴のような声を上げながら、部屋へ突進しようとする。
「馬鹿者!! 治療中だぞ!!」
そんなドモンを、東方不敗が羽交い絞めにして止めた。
「――――!」
東方不敗の言葉に、ドモンは一瞬我に返る。だが、また部屋から聞こえてくる治療の音と悲鳴に、ドモンの忍耐はあっさりと崩壊する。
「兄さぁぁ―――ん!!」
「…………ッ!」
東方不敗は、叫びながら足掻く弟子の身体を押さえ続けた。
ハヤブサもまた、己の身体を抱え込むようにしながら、近くの椅子に腰をおろしていた。立ちあがったら、ドモンと同様に病室に走り込んでしまうと思った。
『人間』の治療では、絶対に響かないような激しい音が、部屋から聞こえてくる。それが、『シュバルツは人間ではない』と言う事実を、ハヤブサに突きつけてくる。
それにしても、どうすればよかったのか。
あの時―――キョウジをシュバルツに渡すべきではなかったのか。
もっと、こちらが早くあの陣を破るべきだったのか。
こんな事、今更考えても詮の無い事だと分かっている。だが―――どうしても、考えてしまう。キョウジのために簡単にその身を投げ出すシュバルツの危うさが、自分には分かっていた。分かっていたのに―――。
まるで、1分が永遠の時間を湛えているように感じる。
そんな重苦しい時間が、部屋の外では蟠っていた。
そうして、どれくらい時が過ぎただろか。
治療の音が止み、しばらくの沈黙を経てから―――研究室のドアが、開いた。
「……………」
中からキョウジがふらつきながら出てくる。
「兄さん! シュバルツは!?」
「大丈夫だ……。やっと―――やっと、『気を失ってくれた』よ……」
「……………!」
キョウジの言葉に、一同は絶句する。それだけで、中で行われた治療の凄まじさが窺えた。
「済まないが……シュバルツを、ちゃんとしたベッドで寝かせたい。運ぶのを手伝ってくれるか?」
壁にもたれかかり、額の汗を拭いながら言うキョウジに、一同は承諾の返事を返した。
「……血の匂いがするな」
研究室に入った途端、東方不敗がポツリと漏らした。
「えっ? そんなはずは…。シュバルツの方は、もう完全に治って―――」
「違う。匂いがするのは、お主の方からだ」
そう言うや否や、東方不敗はキョウジの腕をグイッ、と、掴む。
「あ! ……これは―――!」
キョウジは慌てて掴まれた腕を振りほどこうとした。しかし、力で東方不敗にかなうはずもない。そのまま東方不敗は、キョウジの手に嵌められていたゴム手袋を無理やり外した。
「あっ……つ……!」
痛み故にキョウジの顔がしかめられる。外されたゴム手袋から、血がビシャッと音を立てて滴り落ちた。
「兄さん―――!」
ドモンはキョウジの手の状態を見て絶句する。キョウジの手は赤く腫れあがり、血だらけになっていたからだ。
「フン―――やはりな。無茶をしおる」
そう言いながら、東方不敗はキョウジのもう片方の手からも同様にゴム手袋を外した。同じようにキョウジの足元に、血がビシャッと音を立てて滴り落ちる。
「…………!」
ハヤブサも、思わず言葉を失った。シュバルツの背中の傷に触れた時の、あの返ってきた衝撃を思い出す。治療をし続けると言う事は、ずっとあの痛みを浴び続けると言う事になるのだ。
それでもシュバルツの治療をやりきったキョウジは、決して腰抜けとかいう類の人間ではない。寧ろ、根性が座っている。それなのに、シュバルツが怪我をしたあの局面で、動けなかったというキョウジ―――。
(それだけシュバルツと言う存在は、キョウジにとっては『特別』なのだろうか…)
ハヤブサは、何となくそう感じた。
「キョウジの治療はワシがする。お主たちは、シュバルツを運んでやれ」
「師匠……」
「―――分かった。行こう、ドモン」
ハヤブサに促されて、ドモンは一旦シュバルツの方に振り向く。しかし、手を傷だらけにした兄の方も気になって、ドモンは再び師と兄の方に振り返った。
ドモンの視線の先で、兄が師匠に手をひかれていく姿があった。傷口の消毒でもするのだろうか。
「ドモン」
ハヤブサにもう一度呼ばれたドモンは、「分かった、今行く」と、返事を返して、駆け出した。
「ほら、傷口をちゃんと洗わんか」
そう言って東方不敗はキョウジの手を流れる水に当てる。
「うっ……ッ……!」
冷たい水が、傷口にしみる。キョウジは知らず、呻いてしまう。傷の周りを覆っていた血の跡が取れ、傷その物が、くっきりと浮かび上がってくる。東方不敗はキョウジの手をタオルで拭いて水気を取ってやると、立ち上がった。
「ワシ秘伝の傷薬を持って来てやる。しばらくそのままで待っておれ」
そう言うと、すたすたと歩いて行った。
「……………」
一人になったキョウジは、傷だらけになった己の手を無言で見つめた。
腫れ上がり、あちこちの皮が剝け、裂けた傷口から、また血が滲み出て来ている。
(実際、私の手は、こんな物かもしれないな……。『罪』にまみれている私の手は―――)
こんなボロボロの手こそが、
自分にはふさわしいのかもしれない―――。
そんな事を、キョウジが考えていた矢先。
ゴン!
誰かの拳骨が、キョウジの頭を見舞った。
「!?」
驚いたキョウジが、思わず殴られた所に手を当てようとすると、
「馬鹿者! 手を使おうとするでない!」
上から東方不敗の声が降ってきた。
「マ、マスター!?」
見上げて来たキョウジと視線があった東方不敗が、フン、と鼻を鳴らす。
「……どうせ、ろくでもない事でも考えておったのだろう。この馬鹿者が…!」
「…………!」
キョウジは思わず言葉を失う。どうしてこの人は時々、自分の考えを見透かしてくるのだろう、と、思う。
キョウジの視線から疑問の色を感じ取った東方不敗から、答えが返ってくる。
「―――あまり年長者をなめるな。お主の様な青二才の考えとることなど、このワシにはお見通しじゃ。……ほれ、さっさと手を出せ」
キョウジが言われたとおりに東方不敗に手を差し出すと、東方不敗は多少乱暴に、そこに薬を塗りつけてくる。
「う……あ……ッ!」
この薬が、やけに傷口にしみる。キョウジは、思わず声を上げていた。
「あまり、自分を卑下するでない。それは、お主の悪い癖だ」
薬を塗り終えた東方不敗が、キョウジの手に包帯を巻きつけながら言う。
「この傷だってそうじゃ。一体どこに卑下する理由がある。お主は、ちゃんとシュバルツを治した。やりきった証しなのだ。寧ろ、誇ってもいい物ぞ―――」
「――――!」
(そうだろうか)
キョウジは思う。
シュバルツが、この傷を見たら、どう思うだろうか。自分を治すために、私の手に刻み込まれたこの傷を、見たら―――。
きっと、彼は、激しく自分を責める。自分のために誰かが傷つく事を、彼は一番望まないから―――。
だから、隠さないと。この傷は。
シュバルツに見つからないように、隠さないと。
(フ……。それにしても何をやっているんだろうな。私は…。自分の『影』を相手に――――)
バカみたいだ。
本当に―――本当に、バカみたいだ。
それにしてもこの薬、やけにしみる。やけに、しみるから―――。
「…………!」
東方不敗はキョウジの手に包帯を巻きながら、キョウジの頬に伝い落ちる涙に気付いた。
「キョウジ、どうした」
「…………」
「傷が、しみるのか」
「ハハッ。しみますね……」
「そうか……」
東方不敗は、そう言ったきり、黙ってキョウジの手に包帯を巻き続けた。
キョウジは、涙を止めたいと願った。だが、それを叶える事は出来ずに、涙は、ただキョウジの頬を伝い続けた。
包帯を巻き終わった東方不敗が、温かい烏龍茶を入れてきてくれた。キョウジにそれを渡した後、自身もキョウジから少し離れた所の壁に凭れて、烏龍茶を飲んでいる。
手は痛むが、コップが持てないほどではない。その温かさを口に入れ、キョウジは少し、落ち着きを取り戻す。落ち着きを取り戻した所で―――彼は、口を開いた。
「マスター……」
「ん?」
「どうして……何も、言わないんですか? 涙なんかを、見せた私に―――」
実際キョウジは不思議だった。この東方不敗の性格からすれば、涙を流している『男』を見れば「男児が涙なんぞを見せおって―――」と、説教の一つでも喰らわせそうなものであるのに。
その言葉を聞いた東方不敗が、キョウジの方をちらりと見やると少しだけ表情を崩す。
「そうだな……。ドモンは、何でもかんでも吐きだし過ぎだ。だが、お主は逆に、ため込み過ぎだ」
「――――!」
「お主は少し、いろいろ吐きだした方が良い……ワシからしてみれば、『やっと泣いた』と、言いたい所だがな」
「……はは、は……」
東方不敗のこの言葉に、キョウジは苦笑するしかない。
「お主は充分『強い』……。多少泣こうがわめこうが、それは、変わらん。だから―――良いのだ」
「…………!」
東方不敗はそう言ったきり、また黙って烏龍茶を飲みだす。部屋を、沈黙が支配した。この沈黙が――――キョウジには、やけに堪えた。
「……で、でもマスター……私は……」
コップを握る手が、やけに痛い。気がつけば、コップを握りしめていた。止めなければと思ったが、握りしめずにはいられなかった。
「…私の、『ミス』のせいで……シュバルツに……怪我を、させて……ッ」
瞳から、大粒の涙が零れおちる。こらえられない。この涙を止める手段など、キョウジの中ではとっくに崩壊している。
「あ…揚句、DG細胞、を……敵に―――!」
キョウジは、それ以上言葉を紡ぐ事が出来なかった。頭を垂れ、肩を震わせて泣き続けた。
何もかも、自分のせい―――自分のせいで。
皆が自分に力を貸してくれていたと言うのに、最後の最後で、自分がミスをしてしまった。それが、敵に一番渡してはいけない情報を渡すことにつながってしまった。
そんな自分が、情けなかった。許せなくすらあった。
本当に、どうして。
どうして、私は―――!
あまりにもいろいろな想いが胸の中に渦を巻く。巻きすぎて、胸が痛い。
痛くて―――涙が、止められない。
「…………」
東方不敗は、静かに烏龍茶を飲んでいた。キョウジに声をかけるでもなく、そばに寄るわけでもなく―――ただ黙って、キョウジが泣く事を『許している』、そんな感じの態度だった。
しばらくその部屋には、キョウジの声を殺した嗚咽が、響き渡っていた。
(今が、平和な時分であったなら、もう少し泣かせてやるのだがな……)
東方不敗はそう思いながらも、キョウジに声をかけることにした。DG細胞までもが絡んでくるこの事態。いつまでも、下を向いて泣いている場合ではない。
「キョウジよ……」
呼びかけられたキョウジの肩が、ピクリ、と動く。
「DG細胞の事なら案ずるな。その為に―――シャッフルの紋章を持ったワシらがおるのだ」
「…………」
キョウジからの反応は無い。ただ―――彼から嗚咽の声が消えた。
「だが……敵との戦いに、もうあまり時間をかける事は出来ん。この意味は、分かるな?」
「…………!」
東方不敗の言葉に、キョウジは振り返った。
相手がDG細胞を利用してくる可能性がある以上、時間を相手に与えてしまう事は、確かにこちらの不利が増えるばかりで、何のメリットも無い。こちらが時間をかければかけるほど、相手はDG細胞を培養し、強力な物を作り出して行ってしまうだろう。
「―――闘えるか?」
まだ涙の跡が残るキョウジに、東方不敗はそれだけを聞いた。
「闘います」
キョウジはきっぱりと、それだけを言った。それだけで東方不敗には、もう充分だった。
「どれ、ワシは、ドモンの様子を見てくるが―――キョウジ、お主は?」
東方不敗の言葉に、キョウジは少し苦笑した笑顔を見せる。
「すみません。あと少しだけ―――時間をくれませんか?」
こんな顔、弟に見せられませんから、と言うキョウジに、東方不敗はにやりと笑う。
「よかろう―――だが、なるべく早く来いよ」
そう言って、東方不敗はキョウジの居る部屋を後にした。
だが、東方不敗は部屋から出て2、3歩歩いた所で、意外な人物がいた事に目を丸くする。そこには、ドモンが佇んでいた。
「―――ッ! ド……!」
思わず大声を出しそうになった東方不敗だが、慌てて声を潜める。
(ドモン、お主いつから……!)
ここにいた? と、東方不敗はドモンに聞く事が出来なかった。何故ならドモンが、ものすごく沈んだ顔をしていたからだ。
「師匠……」
ドモンがポツリと呟くように、声を出す。
「師匠ばっかり、ずるいですよ。兄さんを、泣かす事が出来るなんて……」
「……………!」
ドモンは、シュバルツをベッドまで運んだ後、やはり、キョウジの方も気になって、こちらまで足を運んで来ていた。そこで、兄に包帯を巻く師匠と、静かに涙を落としている兄の姿を見てしまった。それで、もう―――部屋に入れなくなってしまった。
「俺……知らなかった。兄さんって、声を殺して泣くんだ……」
兄はどんなに辛そうでも―――自分の前では泣かなかった。いつも笑顔で、先に泣いてしまう自分を、労わってくれていた。でも、自分も兄を労わりたかった。「泣いた方が、楽になる事もある」と、言う事を、ドモンは経験的に知っていたからだ。
だが、自分がどんなに頑張って見ても、やはり兄は、ずっと笑顔を崩さない。そして、先に自分が泣いてしまう。労わられる。この繰り返し―――。
兄が泣いた姿を見て、『やっと泣いた』と、師匠は言った。自分も同意見だった。兄は―――『やっと泣けた』のだ。ならば、自分は邪魔するべきではない。自分の姿を見たら、兄は、すぐに泣くのを止めてしまうに決まっているから。
ドモンは、踵を返して歩き出した。ここに自分がいた事を、兄に知られては駄目だと思った。
東方不敗も、そんなドモンに黙ってついて行く。
「師匠……」
歩きながら、ドモンはポツリと漏らした。
「俺って、兄さんにとって何なのでしょうね……」
ドモンは思う。もしかして自分は、兄にとっては、我慢を強いているだけの存在なのではないのだろうか。迷惑をかけているだけではないのだろうかと。
「フン―――青いのう。お前は……」
東方不敗は、ドモンの言葉にため息をついた。
「お主が居るから、『兄』は『兄』で居られる―――と、言う事も、あるのだぞ?」
「そうでしょうか……」
師匠の言葉の意味が、ドモンには良く分からなかった。ただ、はっきり分かった事が一つある。泣く兄の側に、近づけなかった自分。これが―――この距離が、自分と兄の、今の距離なのだと言う事が。
これが、現実だ。
現実なんだ。
悔しいが、そう認めざるを得ない。
ドモンは、落ち込んでいた。しかし、涙は流していなかった。そこだけは、東方不敗も評価した。
「まあ、兄御に頼りにされたかったら、もう少し男を磨く事じゃな。そうすれば―――お主の前でも、兄御は泣いてくれるやもしれん」
「……………」
師匠の言葉に、ドモンは返事を返さなかった。ただ漠然と、そんな日が来るのかな、とだけ、思った。
「……………」
ハヤブサは、ベッドの上で眠り続けるシュバルツを見つめ続けていた。
そんなハヤブサの頭の中で、今までの『シュバルツ』に関連する、新たに分かった情報が、浮かんでは消えていく。
「……そうだ。私は、人間ではない。キョウジに作られた―――アンドロイドだ」
「平気だ……放っておけば、治る。お前も…知っているだろう」
「無理だ……シュバルツ。その傷は、『治らない』」
「『治らない』んだ。その傷は……。治さないと…」
『DG細胞』が―――負の魔力に引きずられて――――。
(『DG細胞』……どこかで聞いたか……?)
忍者という職業上、いろいろな情報に触れる機会はある。しかし、この『DG細胞』と言う言葉だけは、耳慣れない物だと思った。
アンドロイド―――。
放っておけば、治る―――。
治らない―――。
『DG細胞』が―――負の魔力に……。
「…………」
何か、分かりそうで分からない。肝心なところで、情報に霞がかかる。それを突破する『鍵』が―――おそらく『DG細胞』なのだ。
否応なしにはっきりと分かった情報は一つだけある。確かにシュバルツは、人間ではなかった。激しい音を伴った治療を終えた後のシュバルツの身体には、あれほどはっきり刻まれていた傷が、きれいさっぱり無くなっていたからだ。あれだけの傷、普通人間が負えば、こんな風にすぐには治らない。どうしたって、傷跡が残る。それが―――全く無かったのだ。
(…見た目は本当に、人間と変わらないのにな……)
そう思いながら、規則正しく聞こえてくる呼吸音に耳を澄ます。息だって、しているじゃないかと、思う。それどころか、とても人間らしい『愚直さ』もある奴なのに……。
「ハヤブサ。ここに居たのか」
不意に、シュバルツとそっくりだが、シュバルツではない者の声が耳に飛び込んでくる。振り返ると、部屋の出入り口の所にキョウジが佇んでいた。相変わらず、彼らしい穏やかな顔をしている、と、ハヤブサは思った。
「シュバルツの様子、は……」
「よく寝ている」
ハヤブサの短い返答に、キョウジは「そうか」と、だけ答えると、シュバルツが寝ているベッドのそばに歩み寄った。
「……………」
キョウジが、静かにシュバルツを見つめている。
その眼差しは穏やかで、優しさに満ちている。しかし、どこか苦しげで、何故か哀しみさえ感じる。とにかく―――複雑―――複雑なんだ、と、ハヤブサは思った。それもこれも、シュバルツが、キョウジにとって『特別』であるからだろうか。
ふと、キョウジの手に、手袋がはめられている事にハヤブサは気付く。あの手袋の下のキョウジの手は、確か傷だらけになっているはずだった。だからこの手袋は、その治療跡を隠すための物であると言う事が、容易に想像できる。
(でも―――その手袋は、治療跡を『誰』から隠すためのものだ?)
ふと、ハヤブサは思った。
兄が傷つくことを極端に嫌がる弟から隠すためだろうか。
それとも――――。
「ハヤブサ……。話が、あるんだ。少し、良いか…?」
「話?」
急にキョウジから声を掛けられて、はっと我に返る。
「あ、ああ。構わないが」
そう返事をするハヤブサに、キョウジは「ありがとう」とにっこり微笑んでから、言った。
「ここじゃ何だから、外に出ないか?」
キョウジの提案に、ハヤブサも素直に従った。
「先程ドモン達にも話したんだが、『化け物』の本体が居る建物の位置が分かった」
歩きながら、キョウジが切り出してくる。
「本当か!?」
「ああ……。だがその為に、シュバルツに怪我をさせてしまったが……」
「…………!」
(やはり、キョウジの方にも事情があった……)
キョウジは、ただひたすら「自分がミスをしてしまった」と、言い続けていたが、キョウジの方にも一人で飛び出してしまうだけの事情が、やはりあった。シュバルツもだが、キョウジも、およそ『言い訳』と言うものをしない。良い意味でも悪い意味でも、そういう所が潔すぎると、思う。
「だから―――これから、その場所に奇襲をかけようと思うのだが、ただ一つ、懸案事項が増えてしまった。それを、ハヤブサに伝えておこうと思って」
「懸案事項?」
ハヤブサは、鸚鵡返しでキョウジに尋ねる。
「『DG細胞』だ……。それを、敵に獲られた」
(DG細胞―――!)
ドクン!
ハヤブサは、己の鼓動が大きく脈打つのを意識する。
これだ。
おそらくこれを理解しなければ、闇の中のシュバルツに、たどり着けない。
これは―――確信だ。
「キョウジ…。聞いても、良いか?」
「何を?」
振り返るキョウジと、視線が合う。
あの闇にまみれたシュバルツの姿を思い出す。
その闇の根源にかかわる話―――と、思っただけで、あまり良い内容の話ではないのだろうと容易に察しが付く。
でも、聞かなければ。
聞かなければ―――理解できない。
だからハヤブサは、一歩踏み出す事を選択した。
「『DG細胞』とは、何だ?」
「―――――」
その問いに、キョウジの口元がピクリ、と動く。ハヤブサは、そんなキョウジを正眼で見据えた。二人の間を、しばし沈黙が支配する。
先にその静寂を破ったのは、キョウジの方であった。
「そうだね。貴方には、総てを話した方がいいかもしれない……」
表情は穏やか。
だが、あまりにも哀しげな瞳。
それ故にハヤブサは、キョウジが一瞬泣くのではないかと思った。
それと、同時に。
キョウジの背後から溢れだしてくる――――『闇』。
シュバルツと同じか、それ以上の……!
(何故、『人間』であるはずのキョウジまで、こんなに『闇』にまみれている!?)
あまりの光景に、ハヤブサは思わず息を飲む。
「ここで立ち話も何だから、よかったら、私の部屋で」
「分かった」
キョウジの言葉に、ハヤブサは同意した。
今更後には引けないし、引く気もなかった。
(ごめん……シュバルツ)
キョウジは心の中で、シュバルツに謝った。
今から自分は、勝手にハヤブサに話そうとしている。本人の許可も無く、シュバルツの『秘密』を。
でも―――聞いてほしいと思った。
ハヤブサは、シュバルツの事をとても心配してくれている。自分とはまた、違った目線で。シュバルツの方も、まんざらでもなさそうだった。同じ『忍者』同士、通じ合える所もあるのだろう。
だから、余計に。
シュバルツを、想ってくれている人に、聞いてほしいと思った。
そして―――裁いてほしいと、願った。
自分の犯してしまった
『罪』を。
「第7章」
時は、今から数年前に遡る。
一人の博士が、ある『細胞』を発見した。その細胞は、優秀な特性を持っていた。並はずれた生命力を持つ上に、有機体、金属とも融合が可能。その上、『自己再生』『自己進化』『自己増殖』の、能力を有するが故に、その細胞を使った物や生命体には、無限の進化の可能性と、死なない、朽ちない身体を手にする事が出来る。
だが、この細胞には、致命的ともいえる欠点があった。
それは、この細胞を有したキャリアーには、強制的に他者への強烈な攻撃衝動が付随してしまうと言うものだった。現にこの細胞を植え付けたマウスは、他のマウスをただひたすら攻撃し、そこからその細胞を感染させ、仲間を増やして行こうとした。この凶悪性は、最早病原体―――と、言っても、過言ではない。
「……これでは駄目だな…。使い物にならない」
博士は、ため息と共にこの細胞の研究を、一度封印しようとした。だが、その細胞の入ったカプセルを、その博士の助手である息子が、じっと見つめていた―――。
それから数ヵ月後。
「父さん。このデータを見てほしいんだけど」
助手である息子が、書類を持ってパタパタと、父である博士の所に歩み寄ってくる。息子からその書類を渡された博士は、このデータが、自分が数ヶ月前に封印を決めた細胞の物であるとすぐに分かった。
「キョウジ、これは―――!」
「ご、ごめん。勝手に触ったりして……。でも、見てくれる?」
息子は少しすまなさそうな顔をしたが、特に悪びれもせず、父にデータを見るよう再度求めてくる。息子の言に従い、データに再度目を通した博士は、息を飲んだ。
「こ、これは―――!」
眼にしたのは信じられない数値だった。あの細胞の唯一にして最大の欠点である『攻撃性』を司る部位の遺伝子の数値が、とても低く抑えられていたからだ。
「……これなら実用性のめども見えてくるんじゃないかな。ただ、最初に発見した細胞よりは、『自己再生』『自己進化』『自己増殖』の能力は、かなり抑えられたものになってしまうけど―――」
「…………」
息子の言葉を聞きながら、博士はデータにさっと目を通す。確かに、そちらの能力は低い。ただ、最初の細胞のデータよりは、安全性という面では、はるかに高いものになっていた。
「しかしキョウジ…。お前、どうやってこの細胞を抽出した?」
父―――ライゾウ・カッシュ博士からの問いに、キョウジはあっけらかんと答える。
「いや……特に何かしたわけじゃないんだけど、あの細胞、何だか人の『ココロ』に反応していたような感じだったから―――」
「…………!」
「試しに『優しい心』を向け続けたらどうなるのかなって……それだけだよ」
そう言って、笑顔を見せる息子を父は驚嘆の眼差しで見つめた。
キョウジは、特に物事の本質を見極める目が、人よりも鋭いように感じられる。人は、自分の事を「天才だ」と言うが、真の天才とは、自分の息子の事を言うのではないかと、実は父は思っている。
このキョウジと言う人間は、万事がこんな調子であった。特に、物事の本質を見極める目が鋭いが故に、人が何年もかけてたどり着いた答えや奥義に、あっという間にたどり着いてしまう。
それ故にキョウジは、師に恵まれなかった。またたく間に自分より高みに登り詰めてしまう弟子など、普通誰も取りたがらない。同世代の友人たちも、気軽にキョウジに声をかけられず、距離をとるようになる。時には憎まれ、嫌われることすらあった。
自身のこの能力が、人を傷つけていると悟ったキョウジは、敢えて自分の能力を封印するようにした。争い事は好まなかったし、誰かを傷つけるぐらいなら、自分が譲る方が容易かった。この類稀なる能力を持った青年は、類稀なる優しい心の持ち主でもあったのだ。
そんなキョウジだが、彼が『彼』として、能力を存分に振るう事を許してくれる存在がいた。一人は父であるライゾウ・カッシュ博士。そして、もう一人は―――ミカムラ博士であった。
ミカムラ博士とは、父ライゾウの古くからの親友で、レインの父親でもある。
レインの母親は、レインが小さい時に他界してしまった。パートナーを失ったミカムラ博士は、ただひたすら泣いていた。ドモンやレインより少し大きくて、博士の涙の意味が分かるキョウジは、レインと一緒にドモンを連れて、博士を慰めようとした。
「ありがとう……君は、優しいね……」
慰めに行ったはずが、逆に抱きしめられた。
「レイン……お父さんは頑張るから……。お父さん、お前達のために、頑張って生きるからね……」
そう言って博士は3人を抱きしめ、また涙を流して泣きだした。
「お父様……」
博士に抱きしめられながら、レインは泣いた。もう会えない母と、涙を流す父を想って泣いた。ドモンは、そんなレインにつられて涙を流した。
キョウジもまた、泣いていた。
この人は、辛い目に遭っているはずなのに、逆に自分達を気遣い、抱きしめてくれている。その腕は暖かかった。優しい人なのだとキョウジは思った。そして現実に、ミカムラ博士は優しい人だった。男手一つで、レインを立派に育て上げていた。
キョウジは、この人の事が好きだと思った。
ミカムラ博士もその優しさ故に、父ライゾウとキョウジの理解者になり得た。
それがやがて、どうしようもない悲劇の発端となる事に気づかずに。
歳を重ねるにつれ、時々ミカムラ博士が、どうしようもなく暗い顔をする事がある事に、キョウジは気付いた。
心配して声をかける。すると博士は、
「いや……ちょっと、自分の器の小ささが、嫌になっただけだよ」
と言って、淋しそうに笑う。そしてまた、元の優しい人に戻った。キョウジは少し気になったが、これ以上踏み込む事は出来なかった。下手に踏み込んで、博士を更に傷つける事は、キョウジの望むところでは無かったし、そして何より―――この優しい人を失う事を、キョウジは恐れた。ミカムラ博士は、キョウジが『自分』でいる事を許してくれる、数少ない大人であったから。
「えっ? お父様が?」
「うん。何か言ってなかった? 父や、私の事で―――」
相変わらず、暗い顔をする事がある博士を心配したキョウジは、娘であるレインにそれとなく聞いてみた。
「……特に、何も言っていなかったと思うけど…。いつも通りのお父様よ?」
「そうか……」
レインからの言葉を聞いて、キョウジは温かいブラックコーヒーを口に含む。気にしすぎたか、と、少し反省する。
「それにしても、どうしたの? 急にそんな事を聞いてくるなんて……」
「あ、ああ…。大したことじゃないんだけど、ちょっと私が失礼な事を、しちゃったかな~って……」
そう取り繕うように言うキョウジに、レインは屈託のない笑顔を見せる。
「キョウジさんたら、相変わらずね。そんな事、気にしなくていいのに。『キョウジさんが気にしてる』なんてお父様が気付いたら、お父様の方があたふたしちゃうわ」
そうなのだ。実際ミカムラ博士とは、そういう人なのだ。そして、娘であるレインには、そんな暗い影は宿っていない。それだけで、キョウジにはもう充分に思えた。
「それよりもキョウジさん……。ちょっと聞いてほしい事が、あるのだけれど…」
「? 何だい?」
「実は……ちょっと気になる人が、居て……」
「――――!」
キョウジは、飲みかけのコーヒーを、思いっきり噴いた。しかも、その後で激しく噎せた。
「だ、大丈夫? キョウジさん」
レインが慌てて介抱しに来ようとするのを、キョウジは手で制した。
「ゲホッ! だ、大丈夫、だよ……」
何とか笑って、体裁を取り繕う。
「それにしても、『気になる人』って―――。そうか……もうレインちゃんも、そんな年頃になるんだな…」
「もう! キョウジさんったら! 『レインちゃん』呼ばわりは止めてって言っているのに!」
そう言ってむくれるレインに、キョウジは「ごめん、ごめん」と、笑いながら謝った。
「気になるのなら、声をかけてみればいいのに…。君に声をかけられたら、きっとそいつも喜ぶよ」
「そうかしら……」
そう言ってはにかむレインからは、しっかり女性らしい色香が漂っている。どこの誰だか知らないが、レインにそんなふうに想ってもらえるなんて、ちょっと羨ましいとキョウジは思ったりする。
苦笑しながらコーヒーを飲むキョウジに、レインは少し申し訳なさそうな笑みを浮かべた。
「ご、ごめんなさい……。変な事相談しちゃって。でも、こんな事、お父様に相談するわけにもいかないし、キョウジさんなら、安心して相談できるっていうか……」
「ははは……。それは良かった。君の役に立てるのなら……」
(相談対象……。要するに、レインの中では私は『話せるお兄ちゃん』と、言った所なんだな……。恋愛対象ではないんだ……)
まあ別にいいんだけどと思いつつ、軽く失恋したような気持を味わってしまうのは何故なのだろう、と、キョウジは思う。所詮、『お兄ちゃん』はどこまで行っても『お兄ちゃん』なのか―――と、まで考えた時、キョウジははた、と思い至った。
「そう言えば、レインちゃ……」
ん、と、言おうとして、レインにものすごく睨まれている事に気がついたキョウジは、慌てて口をつぐんだ。咳払いをして、言いなおす。
「レイン」
「何? キョウジさん」
「その……最近、ドモンとは、連絡取っているのか?」
そう言いながらキョウジは、数年前に家から出て行った弟の事を思い出す。ドモンは、幼いころからレインの事が大好きだったらしく、よくレインにまとわりつく様に遊んでいた。あの不器用で一途な弟は、今でもレインの事が好きなのではないかと、キョウジは秘かに思っている。
「ドモン?」
レインが、きょとんとしたような顔をする。
「…………………」
その場に、しばしの沈黙が訪れる。
「ああ―――そう言えば、家を出て修行をしているって言っていたわよね。何? ドモンがどうかしたの?」
「い、いや……別に……」
(うわぁ……私よりドモンの方が、更に『アウト・オブ・眼中』だった―――!!)
レインの態度から、はっきりとそれが読み取れてしまって、キョウジは動揺が隠せない。
あの弟の事だ。どうせ修行の方に夢中になって、レインに手紙もメールも、送っていないのだろうと言う事は、容易に察しがつく。
(ははは……兄弟そろって失恋したことになるのかな…。帰って来てレインに恋人が出来たと知ったら、あいつ、また泣くかもな―――)
キョウジは苦笑しながら、帰って来たドモンがショックを受けたら、どうやって慰めようか―――と、考えていた。
「おっと……休憩を終えて、そろそろ研究の方に戻らないと…」
キョウジが腕時計の方に目を走らせて、もたれていた壁から身を起こす。
「あ…! ごめんなさい。キョウジさん忙しかったのに、私ったら―――」
「いや……いいよ。もともと、呼び止めたのは私の方だったし」
そう言いながらキョウジは、自身の飲んでいた缶コーヒーの空き缶を、ゴミ箱に放る。ついでにレインのも片付けようと手を差し出したが、彼女はまだ飲んでいる途中だったらしく、遠慮された。
「そう言えば、お父様たちは今日―――」
「ああ……学会に行っているよ」
そう言いながらキョウジは、今日学会で論文を発表しているであろう父、ライゾウに思いを馳せる。
「キョウジさんも、学会に行けばよかったのに…」
そう言うレインに、キョウジは少し苦笑した笑顔を返す。
「いや……私は、人ごみも人前に出るのもどうも苦手で―――研究室に引きこもっていた方が、余程いいよ」
「引きこもりって……もう、キョウジさんたら!」
そう言ってレインは笑う。やっぱり、レインの笑顔は可愛い―――と、キョウジも笑いながら、そう思った。
「いやぁ、ミカムラ博士、素晴らしかったですよ。今日の貴方の論文。『ロボットの関節駆動におけるエネルギーの流れと効率向上について』…実に、分かりやすくためになる論文だった」
「ありがとうございます」
学会が終わった後の懇親会で、ミカムラ博士は同僚からの賛辞を受けていた。
「でも―――今日一番の話題は、やはりあのカッシュ博士の『細胞の未来と可能性について』と題して発表された、あの論文でしょうな。あの三大理論は、素晴らしかった」
そう言いながら、同僚が後ろを振り返る。彼の視線の先には、たくさんの人々に囲まれて、論文の賛辞を受けたり説明を求められたりしている、カッシュ博士の姿があった。
「……全く、同期にあんな『天才』がいたら、我々の影も霞んでしまいますなぁ。話題も賛辞も、みんな彼が持って行ってしまう」
「……全くですな」
同僚の言葉に、ミカムラ博士も苦笑した笑みを返す。
「どれ―――私も、ちょっとカッシュ博士に、挨拶に行ってくるとしますか」
そう言いながら声をかけてきた同僚は、シャンパン片手にカッシュ博士を取り巻く人々の中に入って行った。
「…………」
(くそっ! 面白くない!)
ミカムラ博士は、持っていたシャンパンの杯を、乱暴に呷る。そのシャンパンは、少しも味がしなかった。
もう、何度こんな苦杯を舐めた事だろう。
今日は、自分だって論文を発表したのだ。それなのに、自分の論文は、全く顧みられていない。先程来たあの同僚だって、『同期の誼』という程度で、挨拶をしに来てくれたにすぎない。
分かっている。カッシュの凄さが今に始まった事ではないと言うことぐらい、よく分かっている。そして、自分が平々凡々であると言う事も。だが―――改めて、こうも見せつけられると、やはり、堪らない。
何杯か、味のしないシャンパンを喉に流し込む。それをしているうちに、身体が生理現象を訴える。
「……………」
ミカムラ博士は、黙って懇親会の会場から出て行った。彼が姿を消した事を、会場に居る人間は、誰も気がつかなかった。
所用が済んで、手洗いからミカムラ博士が出ようとした時、ふと、廊下で誰かが話しているのが耳に入ってきた。
「やはり、カッシュ博士はすごいなぁ。細胞にあの三大理論が加わった物が実用化されると、人類に無限の可能性の扉が与えられることになるぞ」
「しかし、いささか飛躍しすぎてはいないか? 何事も慎重に検討しないと、物が『細胞』なだけに、リスクも大き過ぎる気もする」
「まあ、あの人は『天才』だからなぁ……」
どうやら学者の中でも比較的若い世代の連中が、今日の論文を批評し合っているようだ。
ハハッ、いいぞ…。カッシュの論文が『批評』されている…。
知らず、ミカムラ博士の口元に、暗い笑みが浮かぶ。
「そう言えば、もう一人論文を発表していただろ? 誰だったかな?」
「ああ……確か、ミカムラ博士が……」
(…………!)
ミカムラ博士は、ドアの向こうで息を潜めた。
「……でも、あの人の論文はなぁ……」
「何と言うか、『普通』―――だな」
「可もなく不可もなく―――と、言ったところか。悪いが、印象にも残らないんだよな……」
そう言った後、笑い合う声が聞こえる。
「――――!」
博士は思わずこぶしを握りしめた。だが、ドアを開けて彼らの前に姿を現す事は出来なかった。ミカムラ博士は確かに優しい。優しいが―――同時に、小心な男でもあった。その小心さゆえに、自分の才能の限界、また、自分の中にある親友に対する歪んだ想いを素直に認める事が出来なかった。娘のレインにすら、それを吐きだす事が出来なかった。
その結果、ミカムラ博士の中で、誰にも気づかれる事のないどす黒い思いが、どんどん鬱積されて行く。
「くそっ! あいつら―――好き勝手言いおって! 何も知らないくせに!! わしの気持ちなど、何も知らんくせに!!」
廊下で話していた一団が去った後、一人手洗い場で流しに拳を叩きつける、ミカムラ博士の姿があった。
(分かっている!! カッシュが山の頂に居るとしたら、私は山のふもとで蠢いている虫だ!! だが今に見ていろ―――! わしだって、いつかは、いつかは……!)
あの、山の頂に―――!
そう思いながら博士が流しに両の拳を叩きつけた瞬間、不意に、手洗い場のドアがガチャッと開いた。
「――――!」
ビクッとなって振り返ると、そこにはスーツ姿の見知らぬ男が立っていた。
「おや? ミカムラ博士ではありませんか―――」
その男は、そう言いながら、穏やかな笑みを浮かべて近づいてくる。だが、その目は笑ってはいなかった。
何とも不快な印象を受けたミカムラ博士は、「失礼」と言いながら、その場を去ろうとする。だが、男の方が、それを許そうとしなかった。
「どういうつもりだね!? 君は―――!」
「まあ、待ってくださいよ。実は、私はこういう者でして……」
そう言いながら、男が強引に名刺を見せつけてくる。名刺の肩書に、軍の特務機関の名前があった。
「軍!? 軍が……私に、何の用だ?」
訝しげな視線を向けるミカムラ博士に、男は冷たい笑みを浮かべてくる。
「ミカムラ博士は……確か、カッシュ博士の御親友―――でしたな?」
「…………!」
「今日のカッシュ博士の論文は、実に素晴らしいものだった。いや全く、鳥肌が立ちましたよ…」
「――――!」
(何だ? こいつ……。そんな事を言いに、わざわざ―――?)
怒りで、目の前が真っ赤に染まる。
「……それなら、本人にそう言えばよろしかろう。わしは、失礼する」
「まあ、そう言わずに」
またしても男に、進路を塞がれる。
「カッシュ博士の研究―――軍事用に転用できれば、さらに素晴らしいものになるとは、思いませんか?」
「な――――!」
軍事用に転用と言う恐ろしい響きに、ミカムラ博士は息を飲む。
「ば……馬鹿な…! カッシュは―――カッシュはそんなつもりでは……!」
「研究していない―――と、仰りたいのでしょう? 確かに、そのようですね。先程本人に打診しましたが、見事に断られてしまいました。……全く、頭の固い御仁です」
そう言いながら男は肩をすくめ、低い声で笑う。嫌な声だと思った。
「どうでしょう? ここはひとつ、御親友の貴方からも、カッシュ博士にお口添えを願えませんか?」
「何………?」
「これは、カッシュ博士にとっても、悪い話ではないはずですよ? 我々に協力をしていただけるのなら、豊富な資金と、最新鋭の設備が使い放題になるのですから……。博士の研究も、大いに進む事でしょう―――」
(いけない―――!!)
ミカムラ博士は強く思った。この男は悪魔だ。これは、悪魔の囁きなのだと。だから自分は今すぐ、この男を振り払って、外に出て行かねばならない。
なのに―――何故。
何故自分は、この男を突っぱねられないのか―――。
「………………」
反応を返さず、じっと佇んでいるミカムラ博士を見て、男はフ……と、静かに笑った。
「この名刺は、差し上げましょう」
男はそう言うと、ミカムラ博士に強引に名刺を押しつけてきた。
「…お気が変わったら、いつでも電話をしてきてください。お待ちしていますよ。……そう―――いつでもね」
それだけを言うと、男は笑いながらそこから出て行った。
ミカムラ博士は、男から貰った名刺を捨てなければと思った。
だが何故か―――彼はそれを、捨てられなかった。
それから数ヵ月後。
「ミカムラ。見てほしいものがあるんだ」
そう言いながら、ライゾウ・カッシュが自分の方に書類を持ってくる。ミカムラ博士は黙ってその書類を受け取った。
「こ、これは―――!」
書類に記されているデータを見て、ミカムラ博士は息を飲んだ。片方の細胞のデータは見覚えがある。確か、論文でも発表されていたもので、一度カッシュはこの細胞の研究を封印しているはずだ。だが―――もう片方の、この細胞のデータは……すぐにでも、実用可能なレベルの物だった。
「カ、カッシュ……! これは―――!!」
驚きの表情を浮かべてこちらを見るミカムラに、ライゾウは笑みを浮かべる。
「どうだ? 素晴らしいだろう」
「た……確かに、すごい―――」
生唾を飲み込みながら、ミカムラ博士は食い入るようにその細胞のデータと、それに添えられている論文を見る。先に聞いたものよりも、また一段と素晴らしい出来である事が、ミカムラ博士には分かった。
「だが、カッシュ……。お前はどうやって、この細胞を抽出した?」
ミカムラ博士の問いに、ライゾウは困ったような笑みを浮かべた。
「いや……この細胞を抽出したのは私じゃない。息子のキョウジだ」
「な―――!!」
ミカムラ博士は、鈍器で殴られたような衝撃を受けた。
「…全く、我が息子ながら恐ろしい奴だよ。あいつはこの細胞の特性を、一眼で見抜いたのだから……」
「――――ッ!」
何か恐ろしい事を聞いているような気がして、ミカムラ博士の身体が勝手に震える。
「……で、ではカッシュ……。この……この論文を、書いたのは……?」
ミカムラ博士の問いに、ライゾウは事もなげに答えた。
「お察しの通り、キョウジだよ。どうだ? 素晴らしい出来だろう?」
「――――!」
「だから、今度の学会で、あいつにこの論文を発表させようと思うんだ。だがなぁ……肝心のあいつが、『父さんがまた発表すればいいよ』の一点張りで、なかなか学会に出ようとしない。あいつはどうも、引っ込み思案でいかん」
(何だと――――!?)
ミカムラ博士の頭の中で、ガン、ガン、ガン! と、うるさい音が鳴り響き続ける。
キョウジ……あいつは確か、高校を出てから、本格的に父親の手伝いを始めたはず。
だから、この世界に入ってから、僅か10年。
僅か10年の、若造だ。
それが……。
10年の間に、これだけの発見をし、これだけの論文を書いただと―――!?
しかも、学会で自分が発表せず、それを、父親に『譲る』だと―――!?
『譲る』と言うのなら、わしにくれ!!
このデータを!
その才能を!!
全部―――わしに譲ってくれ!!
「それでだな、ミカムラ…。お前も一緒に来て、キョウジに学会に出るよう説得するのを手伝ってくれないか? あいつもそろそろ、一人前の研究者として、名乗りを上げてもいい頃だ」
ライゾウは、ミカムラ博士の身体が震えているのに気がつかないのか、のんきに言葉を続けている。ミカムラ博士は、まるで壊れた機械人形のように、ギ、ギ、とライゾウの方に顔を向けて、聞いた。
「キ……キョウジ―――君、は……今、どこに……?」
「あいつは今、その細胞を使ってある物を組み上げているんだ。そうだ、君も見てみるか? きっと驚くぞ―――」
そう言うなり、ライゾウは半ば強引にミカムラの手を引っ張る。
(嫌だ! 見たくない!!)
ミカムラ博士は強く思った。
今すぐカッシュの手を振り払うべきだ。わしは見たくない。見てはいけない。その扉を―――開けたくはないんだ……!
だが、ミカムラ博士の願いも空しく、ついにその扉は、開けられてしまった。
重厚な扉の向こうに現れたそれは、とてつもなく巨大な物だった。
「こ…これは、いったい……!」
息を飲みながら声を出すミカムラに、ライゾウが応える。
「大きいだろう? 私たちは『アルティメット・ガンダム』と、呼んでいる」
「…………!」
「地球の、ありとあらゆる場所で活動可能なように、私とキョウジが設計した。組み上げるのは、ほぼキョウジに任せているんだが……それにしても……」
多少、でかくなりすぎた、と笑うライゾウの隣で、ミカムラ博士の顔は、色を失っている。
私は……一体、何を見ているのだ?
私は…一体、『何』を……!
「キョウジ! ミカムラさんが来てくれたぞ!」
父親の呼び掛ける声に、アルティメット・ガンダムの頭頂付近から、キョウジがひょこっと顔を出す。
「えっ? ミカムラ博士が?」
キョウジが父親の声がした方を見ると、確かに、その隣にミカムラ博士の姿があった。随分久しぶりに会うと思った。まあもっとも、自分がほとんど研究室とこの工房の行き来しかしないから、それも当たり前か―――と思いつつ、キョウジはいつも通り微笑んだ。
「お久しぶりです。ミカムラ博士」
「――――!」
邪心の無い笑み。それが、ミカムラ博士の心を、更に悪い方へと揺さぶってしまった。
「待っていてください。今、そちらに行きますから……うわっ!?」
頭頂部から降りようとしたキョウジが、つるっと足を滑らす。
「キョウジ!!」
息子の身を案じた父と、そばで別の作業をしていた母が気付いて、同時に声を上げる。だが、キョウジの身体は、重力に引かれて加速がかかる前に、アルティメット・ガンダムの手によって、受け止められた。
「……ありがとう。また、お前に助けられたな。『A・G』」
キョウジが、ガンダムの手の上で穏やかに微笑む。それを見て、父と母は、ようやくほっと息を吐いた。
「また、キョウジを助けるために動いたわね。このガンダムは……」
母ミキノが、苦笑を交じえながら、ライゾウに声をかけてくる。
「そうだな。不思議な事もあるものだ」
ライゾウも、腕を組みながら首を捻った。自分も科学に携わるようになっていろいろな事を経験し、解き明かしてきたが、未だに論理的に説明できない事に遭遇する事がある。これだから、探求する事は止められないのだと、ライゾウは思う。
「あれっ? ミカムラ博士は?」
頭上からの息子の声に、ここで二人は初めてミカムラ博士の姿が消えている事に気付いた。
「あら……変ねぇ? どこに行ったのかしら?」
母親が、ミカムラ博士の姿を求めて辺りを見回す。しかし、彼の姿を見つける事は出来なかった。
(博士……?)
キョウジは、工房の僅かに開いたドアの隙間を見る。あの隙間から、博士は出て行ってしまったのだろうか。
久しぶりに、話がしたかったのに―――。そんな事を思いながら、キョウジはそのドアの隙間を見つめていた。
ミカムラ博士は工房から夢中で走り出て、暗い廊下で独りへたり込んでいた。
あれは何だ? あれは何だ? あれは何だ!?
わしは一体何を―――何を、見たんだ!?
ショックだった。
とにかく、ショックだった。
そう―――見えた。見えてしまったのだ。自分と、ライゾウと、その息子キョウジとの、『差』が。絶望的な、『距離』が。
大きくて高い山がある。その麓で足掻いているのが自分だとしたら、その山の頂に居るのがライゾウだ。そして―――そのさらに上の、大空を自由に飛び回る鳥が、息子のキョウジだ。自分が望む場所に、自分が行きたくて足掻いているその場所に、キョウジは―――最初から『居る』。
ミカムラ博士も、科学者として日々努力をしている一人だ。だから、分かった。分かってしまった。キョウジの持つ資質が。能力の高さが。
「……………!」
何だこれは。
何なんだこれは。
頂ならまだいい。頂ならば、どんな虫だって足掻いてでも這いあがれば、いつかはたどり着く事が出来る。だが、そこから上の空は? そこに居る鳥に、虫は届くのか?
無理だ。
絶対に、不可能だ。
逆に、捕食されるのが落ちだ。
何故奴は―――あの若さで、あの年齢で、もうあんな高みに居る!?
この『差』は何だ。
この絶望的な、『差』は何だ。
こんな事が――――許されるのか? 許されて、いいのか!?
父親に続き息子まで……もう嫌だ。もう嫌だ。もう嫌だ…。
ニクイ。
あの高みが、あの翼が、あの才能が――――!!
あの翼…! あの翼…!
あの翼さえあれば、わしは―――!!
気がつけばミカムラ博士は、あの名刺に記されていた番号に、電話をかけていた。
「これはこれはミカムラ博士……。お待ちしていましたよ」
受話器の向こうから、あの冷たい男の声がした。
「それにしてもキョウジ……。随分でかくなったなぁ」
ライゾウが苦笑しながら、またガンダムの背中の部分で作業を再開しだした息子に声をかける。
「そうかなぁ…。これでも随分削ったつもりなんだけど」
背中の部分の作業用のハッチを開けて、その中に潜り込んで作業をしている息子から、のんきな声で返事が返ってくる。
「削ったって言っても…お前―――」
「しょうがないわよ。あなた」
尚も苦言を呈そうとする父に、苦笑しながら母が声をかけた。
「キョウジが造っているんですもの。大きくなっても、仕方が無いわ」
ミキノ・カッシュは母親として思う。息子であるキョウジは、とても大きな愛情を持っている、と。その愛情を、誰かに、何かに―――注ぎたくて仕方が無いような感じなのだ。
ドモンが産まれた時、キョウジは最初、ドモンにその愛情を注ごうとしていた。だが、その大き過ぎる愛情を扱うには、キョウジもドモンも、共に幼かった。そして、その愛情を受けきるには、ドモンは少し勝ち気過ぎた。結果、二人がともに傷つき、追い詰められたドモンは家を出る事を選択してしまった。
キョウジもまた、ドモンを傷つけてしまった事を自覚していたようだ。それ故にキョウジは、ドモンが出て行った日以来、周りから少し距離をとるようになった、と、母の目には映った。
もちろん、彼の胸の内に大きな愛情があることは変わらない。でも、何でも不用意にそれを注げば、またドモンの二の舞になってしまう。息子は、そう考えたのだろう。彼はあえて孤独を選んでいた。自身の中の愛情を、持て余したまま―――。
ところがある日、DG細胞の中からアルティメット細胞を抽出した日から、キョウジの生活が一変した。
寝ても覚めてもその細胞の事ばかりを考える息子。熱心にその細胞の特性について語り、調べ、研究を進めていく。母親は悟った。ようやく息子は、その愛情を遠慮なく注げる対象を見つけたのだと。
愛情を注ぐ対象が『細胞』と言うのもいかがなものかと思ったりもするが、人の『ココロ』に感応するというこの細胞は、キョウジの優しい心に良く応えていた。それは、自然災害で傷ついた植物の傷を癒した。動物の傷を癒した。日々、優しい細胞へと、変化して行った。現時点で、キョウジにとっては、まさにベストパートナーと言えるほどだった。
その息子が、そのパートナーとも言うべき細胞を使って『モノ』を組み上げるのだ。多少、愛情が暴走気味になっても、それは仕方のない事ではないのかと、母親は思った。
だが、一つだけ気になる事があった。
「キョウジ……このガンダム、本当に、貴方が乗らないの?」
母親の問いに、作業の手を止めずに息子は応える。
「うん。このガンダムは物を産み出す事が出来る力も備わっているから―――実際に子供を産める『女性』が乗った方が、シンクロ率も高いし、性能もフルに引き出せると思うんだ」
「……でもねぇ。このガンダムは、もう貴方を助けるために何度も勝手に動いているんだし、貴方が乗ってあげた方が―――」
「そうかな? ……でも、やっぱり優しい女性が乗った方が、『この子』のためにはいいと思うんだけど」
(それは、理論上ではそうでしょうけど……)
母親はため息をつきながら、ガンダムを見上げる。このガンダムの方は、キョウジを主と認めているような感じだ。だから、乗ってあげればいいのにと思ってしまう自分は、やはり単純なのだろうか。それに、キョウジは『優しい女性』がいい、と、言っていたが、この息子より『優しい』女性なんて、申し訳ないが―――なかなか居ない気がする。
(多分、このガンダムに乗れる人が、この子の『お嫁さん』になれる人なのでしょうけど……)
ハードル高そう、と、母親はガンダムを見上げながら、苦笑するしかなかった。
(ドモンの方も修行三昧のようだし……孫の顔を見られるのは、まだ当分先ね)
彼女はそう思って、またため息をついた。
そしてついに―――運命の『あの日』を迎えた。カッシュ家の紡いできた平和な時間は、ここで終わりを告げてしまった。
突如として工房に鳴り響く警報。
防犯カメラに、銃を持った複数の男たちの姿が捉えられる。
(軍部の手の者か!!)
ライゾウはすぐに悟った。軍からのしつこいともいえる勧誘を、自分はずっと断り続けていたからだ。しかし、まさかこのような強硬手段に訴えてくるとは思わなかった。しかも、相手はこちらのセキュリティを易々と破って来ている。ここにたどり着くのも、時間の問題だった。
相手の狙いは分かっている。
この細胞の研究と、その成果ともいえるこのガンダム―――!
「キョウジ!! ガンダムに乗って逃げなさい!!」
だから父親は叫んだ。これの、真の研究者はキョウジだ。それを守るために。
「で、でも、父さん達は!?」
案の定、優しい息子はしり込みをする。父親は、諭すように言った。
「私たちなら何とかなる。大丈夫だ―――!」
『研究』が欲しいのなら、それのノウハウを持っている自分を、まさか殺すまではしないはず。ライゾウはそう思っていた。
「それよりも、そのガンダムを軍部に悪用させてはならん! だから―――行きなさい!!」
「…………!」
キョウジは父親の気迫に押されるように頷いた。頷いて―――ガンダムに向かって走り出した。
その直後、銃を持った男たちがカッシュ家の工房に乱入してくる。あっという間にカッシュ夫妻は男たちに取り囲まれてしまった。ガンダムに乗ろうとしたキョウジも、取り押さえられた。
男たちの間から、自分をしつこく勧誘して来た男が、冷たい笑みを浮かべながら姿を現す。
「残念ですよ、カッシュ博士。我々に隠れて、まさかこのような強力な『兵器』を製造していたとは……」
「あれは地球探査用のロボットだ! 作業をするための手とかはあるが、『武器』となる様な物は何一つ積んではいない!」
男に反論しながらライゾウは、男の横に佇んでいる一人の人物に気づいてしまう。
「…ミカムラ! 何故君が―――!?」
「!?」
キョウジも驚いて顔を上げる。そして見てしまう。ミカムラ博士が、暗い眼差しを無言でこちらに向けているのを―――。
(博士…! 何故…? どうして―――!)
そこに確かな悪意を感じて、知らず、キョウジの身体が震えてしまう。
「フン―――哀れなものだな。信じ切っていた博士に裏切られるなんて…」
キョウジを取り押さえていた兵士が、からかうように言ってくる。だがその瞬間、僅かな隙が出来た。
(今だ!!)
キョウジはその隙をついて、兵士を振りほどいて再び走り出した。皮肉な事に、彼は自身の持っている資質の高さゆえに、このような悪意を浴びるのも、取り押さえられるのも、初めての経験ではなかったのだ。だから、咄嗟に身体は動いた。彼は『逃げ方』を知っていた。
ガンダムに向かって走るキョウジを、男は冷たい笑みを浮かべながら見ていた。
「……息子の方は、殺しても?」
隣に居るミカムラ博士に問いかける。
「構いません」
ミカムラ博士ははっきりと答えた。その言葉は、両親の耳にもはっきりと聞こえた。
だから、母ミキノは、銃口の前にその身を投げ出した。
「止めて―――――ッ!!!」
パン! パン! と、乾いた銃声が響き渡る。一発が、キョウジの肩を掠めた。
「う……!」
撃たれた肩を抑えながら、キョウジは振り返った。そんな彼の視界に飛び込んできたのは、銃口と、自分の間に割って入り、撃たれた衝撃で崩折れて行く母の姿――――。
「母さん!!」
工房内に、キョウジの悲痛な叫びがこだました。
意志を失った母の身体は、無機質な『モノ』のように倒れて行く。
「母さん!! 母さん!!」
必死に叫びながら、キョウジは母親のそばへ行こうとする。そんな彼に、兵達はなおも銃を向けようとした。
「やめろ!!」
父親が、息子に銃を向ける兵達に飛びかかっていく。
「キョウジ!! 何をしている!? 早く行きなさい!!」
兵達と取っ組み合いながら、父親は叫んだ。
「と、父さん……!」
茫然と父親を見るキョウジの足元で、動かない母の身体から血が溢れ、床に赤い染みを作っていく。
「キョウジ!! 早く!!」
「………ッ!」
キョウジは、選択せざるを得なかった。父と母を置いて、逃げる事を―――。
彼が操縦席に身を滑り込ませ、ハッチを閉めると同時に、無数の銃撃が浴びせられる。だが、噴火口の中ですら作業可能な装甲を有しているガンダムに、銃弾などが効く筈もなかった。
慣れた手つきで操縦システムを起動させ、発進させようとする。ふと視界の隅に、父と母の姿を捉えた。父が、母の身体のそばに行こうとして、兵達に乱暴に取り押さえられていた。兵の一人が動かない母の頭に、至近距離から銃で狙いをつけている。とどめを刺すつもりのようだ。
「――――!」
キョウジは、その瞬間を、直視する事など出来なかった。
工房から去っていくガンダムを、男は冷たい笑いを浮かべながら見送った。
「すでに特務部隊第3空挺師団にスクランブルをかけてある。武器も持たぬ作業用ロボットが、逃げ切れるものか―――」
(何でこんな事になった? 何で、こんな事に―――!)
操縦桿を握る手が震えている。次から次へと涙が頬を伝い落ちた。
父さん……殴られていた。
母さん………!
私を、庇って……!
兵がとどめを刺していた。まだ息が、あったのだろうか。
痛かっただろうか。
苦しんだだろうか。
血が、あんなにたくさん、母さんの身体から流れて―――。
何故だ! 少なくとも母は……! 母は、あんな風に死んでいい人じゃない。あんな風に―――死んでいい人なんかじゃないんだ!
それなのに、何故……!?
ミカムラ博士……。
キョウジの脳裏に、暗い眼差しをこちらに向けていた、ミカムラ博士の姿がよぎる。
―――お前は、知っていたはずだ。博士が、時々暗い眼差しをしていた事を…。
「!」
不意に、誰かの声が聞こえてくる。キョウジは、すぐに悟った。これは、自分の心の声だと。この『もう一人の自分』は、常に客観的に、冷静に―――物事を見ている。
―――博士の暗い眼差しを知っていて…何故、何の対策も打たなかった?
(打たなかったんじゃない! 信じていたんだ! 博士は父の親友で―――レインの父親だ!)
―――『信じる』……随分都合のいい言葉だな。あの暗い眼差しの向こうに『何』が潜んでいるのか、知らないお前ではないだろう?
(…………!)
そうだ。自分は知っていた。
あの向こうに潜んでいたのは『悪意』だ。それは、人間なら誰もが持っている―――どうしようもなく、暗く哀しい感情だ。
―――人の心は、弱い。そして、移ろいやすい…。
(そうだ…。人の心は弱い……。簡単に、『闇』に『悪意』に流されやすい……)
知っていた。
人の心が作り出す世の中は、綺麗事だけでは通用しない事など、とっくに承知していた。
裏切りだって『有り』だ。一方が一方をさんざん利用して、搾取して捨てることだって『有り』だ。哀しいけれど、これが現実だ。現実なんだ。
だけど、それでも……!
それでも、私は―――!
「信じたかったんだ!! ミカムラ博士を! あの優しさを! 自分が辛い目に遭いながらも抱き寄せてくれた、あの腕のぬくもりを―――私は、信じたかったんだッ!!」
ダンッ!!
キョウジの両の拳が、操縦席のパネルに叩きつけられる。ひびが入り、それは拳を傷つけた。だがキョウジは、それすら気づかずに涙を落とし続けた。
―――そして、信じた結果が『これ』か。
「―――ッ!」
―――『信じた』のではない。お前は、何もしなかったんだ。博士の苦しみから目を背け、自分の好きな事だけに没頭した―――それが、今の事態を招いたんだ。言わば、お前の『怠慢』だ。
「怠慢……」
―――そう。それが、母を殺したんだ…。
「母さん……を……」
そうなのか。
結局私が―――。
私の『怠慢』が、母を殺してしまったのか。
キョウジは、激しく動揺していた。その動揺が、自分への苛烈ともいえる責めを誘発していた。平静など、とても保ってはいられなかった。
不意に。
レーダーが、何か接近してくる物体を捉える。表示は『unknown』となっていた。
「……………」
キョウジはそれを、ひどく醒めた目で見ていた。
レーダーが捉える機影は、次から次へと増えていく。あっという間に取り囲まれた。
やがて、コクピット内に、警報音が鳴り響く。相手から、攻撃のためにロックされた事を知らせる音だった。パネルの表示が『unknown』から『enemy』へと変わる。
『enemy』……『敵』……。
軍……。
キョウジの脳裏に、両親の姿が甦る。倒れた母のそばに行こうとして、兵達に殴られていた父。撃たれたうえに、至近距離からとどめを刺された母――――。
分かる。
ミカムラ博士をそそのかしたのも、おそらくこいつらだ。
こいつらが……。
こいつらさえ、いなければ――――!!
キョウジの胸の奥に、青白い炎がボウ、と音を立てて燃え上がる。
それは、28年間心穏やかに生きてきた青年の胸に、初めて灯る怒りの炎だ。それは、何とも御しがたい勢いを備えて燃え広がる。彼自身、もうどうする事も出来ない怒りが、憎しみが、哀しみが、絶望が―――心を飲みこみ、支配して行く。
(ふざけるな……!)
何の心の準備もなしに、いきなり目の前で愛する者を傷つけられ、殺されたのだ。彼が『そう』なってしまうのを、いったい誰が止める事が出来ただろうか。
重ねて言う。彼が今まで生きてきて、怒りの激情に我を忘れてしまったのは、本当に、この一瞬だけだ。だが―――キョウジにとって不幸だったのは、この瞬間、世界で一番怒りに流されてはいけない場所に、彼は『居た』
アルティメット細胞は、人の『ココロ』に感応する。
キョウジの、強烈ともいえる怒りの『ココロ』に、アルティメット細胞もまた、次々と揺さぶられて行く。
揺さぶられながら、アルティメット細胞は、キョウジに問いかける。
キョウジ…。
キョウジハ、何ヲ、望ム?
(望み―――。私の、『望み』は―――)
怒りに猛り狂うキョウジが望んだのは、裁きのための強力な雷。
総てを焼き払うための、炎――――。
アルティメット・ガンダムは猛スピードでその姿を変えていく。…キョウジの、望むままに。
雷を備え、炎を備えた。そして、コクピットに、ボタンを出現させる。それをコントロールし、吐き出すためのボタンを―――。
「――――!」
キョウジにもそれが分かった。ここに出現して来たボタンが『何』なのか。これを押せば、何が起きるのかが。
そしてキョウジは、それを、躊躇わなかった。
いらない。
お前ら全員
消エテシマ エ
ガンダムから吐き出された雷と炎は、あっという間に取り囲んでいた空軍を殲滅した。
コクピット内に、ひどくけたたましい笑い声が響き渡った。キョウジは、その声が自身の物だと気がつくのに、ずいぶん時間がかかった。
彼は、ただひたすら狂ったように笑い続けた。そして―――涙を、落とし続けた。
だがやがて、空しさに襲われた。
こんな事をした所で、父が解放されるわけでもない。母が、還ってくるわけでもない。
哀しみの上に哀しみを、上書きしてしまっただけだと気付く。
「……父さん……母さん……」
誰にも届く事のない呟きが、涙と共に彼の口から零れる。ここでキョウジは、意識を手放した。撃たれた肩から流れ出た血が、彼の右手全体を真っ赤に染めていた。血を流し過ぎてしまっていたのだ。
そして、コントロールを失ったアルティメット・ガンダムもまた、突き抜けかけていた成層圏から重力に引かれ、地球に墜ちて行った―――。
キョウジが次に意識を取り戻した時、彼はコクピットから外に投げ出されていた。
振り返ると、落下の衝撃でめちゃくちゃに壊れたアルティメット・ガンダムの残骸がある。
(このガンダムと、私は一緒に壊れても良かったのに……)
そう思いながらも、キョウジは首を捻った。これほどの衝撃を受けながら、どうして自分は助かったのだろう、と。
そしてある意味、彼個人としては、ここで死んでいた方がまだ良かったかもしれない。
何故なら―――さらなる『地獄』が、彼を待ち受けていたのだから。
ぐじゅり、と、音を立てて、アルティメット・ガンダムの一部が勝手に動く。
(自己再生―――?)
まさか、早すぎる。キョウジがそう思った瞬間、『それ』は始まった。
ぞぞぞぞぞぞ。
不吉な音を立てて、ガンダムはコクピットを中心に再生して行く。しかしその形は、最初の物とは大きく異なるものであった。
何かがおかしい。
そう感じたキョウジが、コクピットを覗き込む。そこで彼は『声』を聞いてしまった。細胞たちが、囁く『声』を―――。
殺ス…。殺ス、殺ス、殺ス!
消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ…。
「お前……! 一体、何を言って……?」
キョウジの問いかけに、細胞たちは応えない。ただ無機質に、同じ囁きを繰り返す。
消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ……。
「――――ッ!」
キョウジは悟った。これは、自分のあの時の声だ。どうしようもなく怒りに流されてしまった時の、自分の怨嗟の声なのだと。
「駄目だ! 何を言っているんだ『A・G』! やめてくれ!!」
キョウジの声に、細胞たちは一瞬沈黙を返す。しかし、すぐにまた声が聞こえ始めた。
殺ス! ミンナ、殺ス!
「……………!」
絶句するキョウジに、細胞たちは更にたたみかけてきた。
ダッテ、ソレガ、キョウジの『望ミ』デショ?
「な――――!」
アハハハハハハハハアハハハハハハハアハハハハハハハハハ
殺ス殺ス殺ス殺ス殺ス殺ス殺ス殺ス殺ス
消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ消エテシマエ
(狂ってる――――!)
キョウジは、目の前が真っ暗になるのを感じた。
とにかく止めないと。
このガンダムは暴走しかけている。しかも、自分の怒りの感情のせいで。
だから、止めないと。
キョウジは強くそう感じて、コクピットの中に身を滑り込ませる。メンテナンス用のハッチを開けて、メインプログラムへの接触を試みた。
しかし。
モニターに映し出されるのは『error』の文字。
「!?」
もう一度試みる。しかし、やはり同じように『error』と表示される。
そんな馬鹿な、と、メインプログラムの存在を探した。すると、返ってきた答えは『no data』
つまり
プログラムが
無 い
「……………!」
このプログラムが無ければ、現時点でガンダムに干渉出来る術が無い。このままでは、暴走を止める事が出来ない。つまり、暴走を止めるためには、もう一度このプログラムを組みなおさなければならない、と言う事になる。
しかし、プログラムを一から組みなおすとなると、どんなに急いでも、最低2日はかかってしまう。
このガンダムの再生スピードの前に『2日』と言う時間。
どう考えても―――間 に 合 わ な い 。
自身のたどり着いた結論に、キョウジは絶望しそうになる。
だが、やらなければ。
暴走したガンダムによって、惨劇が起きてしまう。
それだけは……!
キョウジは、歯を食いしばった。今、このガンダムを突き動かしているのは、紛れもなく自分の怒り。そして、怨嗟の声なのだ。だから、止めなければ。無理でも何でも、やらなければ―――!
キョウジは無言で、プログラムの再構築作業に取り掛かった。しかし、すぐに邪魔が入った。アルティメット・ガンダムが、自身の再生速度を加速させるために、搭乗者を―――『生体ユニット』を求め始めていたからだ。
キョウジに向かって何本ものケーブルが伸びてくる。キョウジはそれを懸命に振り払いながら作業を続けた。そのうちに、いつの間にか撃たれた肩の傷が、治ってしまっている事に気づく。自身がDG細胞に感染したと知った。
DG細胞に感染した生物は、脳にまでそれが達すると、ただひたすら破壊衝動に駆りたてられて、周りを攻撃することしか考えられなくなってしまう。それだけは避けなければと、キョウジは自身の身体にDG細胞の抗体をあるだけ乱暴に打ち込んだ。
そして再び作業に戻る。無駄な作業だろうと思いながらも、キョウジは懸命にそれを続けた。続けなければならない、と、思った。何故なら、このガンダムがこうなってしまったのは、ほぼ自分のせいなのだから。
しかし、やはりと言うべきか。
キョウジはついに、『生体ユニット』として、ガンダムに囚われてしまった。
この強大なガンダムの前に、人間一人の力は、あまりにも無力だった。
「やめろ! やめてくれ! 『A・G』!!」
ユニットになりながらも、キョウジは懸命に叫び続けた。アルティメット細胞は、人の『ココロ』に感応する。それに賭けて、キョウジは自分の心を伝え続けた。
だが、狂ってしまっている細胞たちに、キョウジの心は伝わらない。
殺ス、殺ス、殺ス!!
ダッテ、ソレガ、キョウジの『望ミ』―――
「違う、違う! 私はそんな事は望まない!! 望まないんだ!!」
そんなキョウジの心とは裏腹に、ガンダムは狂ったまま、破壊活動に移行しようとする。
「やめろ! 動くな!!」
キョウジは、ケーブルに絡め捕られた手足を懸命に動かして、ガンダムの動きを阻む。しかし。
邪魔ヲスルナ!!
伸びてきたケーブルに、首を絞められた。
「…………!」
キョウジはそのまま、意識を手放した―――。
次に彼が目覚めたとき、辺りは更地になっていた。
遠くの方に町らしきものがあり、そこのあちこちで、黒煙が上がっている。だが、ガンダムの近くの土地には、何も―――何も、なかった。綺麗な『更地』になっていた。
「ああ………!」
自分は、ガンダムの破壊活動を、止められなかったのだと知った。
殺ス! 殺ス! ミンナ、殺ス!
細胞たちは、同じ言葉を繰り返している。
「う…げ、ぇ……っ……オエッ……」
キョウジは、こみ上げて来たものを吐いた。びちゃびちゃびちゃっと、音を立てて、それはコクピットの床を汚す。だが、少しも楽にならなかった。
自分の―――このガンダムの足元に、何があったのか、とか、
何人死んだのかとか――――。
考えたく、なかった。
意識がある間は、懸命に細胞たちに自分の心を訴え、ガンダムの動きを阻む。しかし、時に意識を奪われ、あるいは知らぬ間に意識をなくし―――気がつけば、辺り一帯が破壊されている。そんな日々をキョウジはアルティメット・ガンダムの中で繰り返した。そして、徐々に意識を失っている方の時間が確実に増えつつあった。
自分の心を細胞たちに伝える事も出来ないまま―――もう、キョウジが『キョウジ』で無くなってしまうのも、時間の問題かと思われた。
そんな中、キョウジは『彼』と出会ったのだ。
『人間』であった、シュバルツと―――。
不意にキョウジは、自分の左腕が刎ね飛ばされたような衝撃を受けた。だがおかげで、自分が『気を失っていた』と言う事に気づけた。
実際に刎ね飛ばされたのは、アルティメット・ガンダムの左腕だった。そして、ガンダムは破壊活動の最中であった。
「やめろ!!」
無駄と知りつつ、キョウジはガンダムの動きを阻む事を試みた。とにかく、少しでも目の前の犠牲を減らしたい一心だった。戦いの最中に意識が戻る事など、もうほとんどなくなっていたからだ。
それをしながらキョウジは、アルティメット・ガンダムの腕を刎ね飛ばした者を探す。すると、彼の目に、一体の黒い機影が飛び込んできた。
その黒い機体は強かった。こちらの攻撃をかわし、時に反撃しながら、住人達の避難を誘導している。
(強い―――! この機体ならば……!)
キョウジは思った。もしかしたら、この機体を操っている人ならば、このガンダムを止める事が出来るのではないかと。生体ユニットである自分が消えれば、おそらくガンダムの活動も止まるはず。キョウジは、そう考えていたのだ。
(何とか―――向こうの機体と接触できないだろうか。何とか……!)
囚われた手足を解放しようと足掻く。操作パネルまで、僅かの距離。なのに、その距離が、遠い。そうこうしているうちに、向こうの機体からこちらに通信が入った。
「おい。貴様何者だ。何故、こんな事をする―――?」
(僥倖だ…!)
キョウジは強く思った。モニターに映る相手の顔は、覆面をかぶっているせいで、どういう人物なのかまでは分からない。でも、腕が立つのは確かなのだ。キョウジは懸命に、相手の呼び掛けに応えた。
「わ、私はキョウジ・カッシュです…!」
「……! ほう。お前がキョウジ・カッシュか」
キョウジは驚いた。まるで相手が自分の事を知っているような口ぶりであったから。
「わ、私の事を、ご存知なのですか!?」
「知っているも何も―――『闇の世界』では、お前は既に有名人だ」
「!?」
キョウジは、相手の言っている事が咄嗟に理解出来ない。
「あ、貴方は一体…?」
キョウジの問いかけを、相手は正確に理解してくれたようだ。
「私か。私の名は、シュバルツ・ブルーダー。『忍者』を生業とする者だ」
シュバルツは、『忍者』と名乗るだけあって、いろいろとよく知っていた。彼は教えてくれた。自分たち一家を襲った、『軍部』が発表した方の情報を―――。
母が死した後、父は『国家反逆罪』の罪を問われて冷凍刑に処せられたと言う。
(冷凍刑……ほぼ死刑と変わらない『口封じ』じゃないか…!)
父の身に降りかかってしまった悲劇にキョウジは愕然とした。
「公にはなっていないが、お前と、この『デビルガンダム』には莫大な懸賞金がかかっているぞ。まあ、これだけ強力な兵器である『国家機密』をお前は盗みだしたのだから、当然だろうな」
「…………!」
キョウジは、このガンダムが『デビルガンダム』と呼ばれてしまっていることにショックを受けた。
だが。
「殺す」と叫び
誰かれ構わす容赦なく破壊し、その命を奪う
この姿が『悪魔』で無くて
何だと言うのだろう。
キョウジは、唇を噛みしめるしかなかった。
―――殺ス!
右手が、目の前のシュバルツの機体に攻撃を仕掛けようとする。キョウジがそれに抗おうとする前に、シュバルツによって右手が刎ね飛ばされた。
「――――ッ!」
キョウジの身体を、激痛が襲う。だが、彼は悲鳴を上げなかった。今の自分には、悲鳴を上げる資格すらない、と、思ったから。
すぐに、右手が治る感触を得る。治らなくていいのに、と、思う。
「お前の国の方は、このデビルガンダムに対する正式な討ち手として、『ドモン・カッシュ』を選出したようだがな…」
(ドモン―――!)
不意に出てきた弟の名に、キョウジはピクリと反応する。
「ドモン・カッシュとは……」
「私の―――弟です!」
キョウジは懸命に答えを返した。
「そうか……やはり身内か……」
それきり相手の方は沈黙をしてしまう。だが、キョウジの方にはまだ聞きたい事があった。だから、懸命に声を上げた。
「待って―――! 待ってください! お願いします!!」
願いを込めて、相手の顔を見る。自分はどんなに罵られても良いから、これだけは教えてほしいと願った。
「私の弟は、東方不敗の元に弟子入りをし、『強くなった』と聞きました! だから―――だから、お願いです! これだけは教えてください!!」
「何をだ?」
「弟は、このガンダムを倒せるでしょうか!? これを倒せるほど、強くなっているのでしょうか!?」
「…………」
相手から、しばし沈黙が返ってくる。だがやがて、キョウジが欲した答えを、相手は返して来てくれた。
「無理だ」
明確に、3文字で。
「…………!」
絶句するキョウジに、相手は更にたたみかけてきた。
「東方不敗の事も良く知っている。奴は、弟子の事を認め、『キング・オブ・ハート』の称号を譲ったようだが……私から言わせれば、まだまだ弟子の方はひよっこだ」
「な………!」
「そんな奴が、『これ』に挑んだ所で、返り討ちにあうのが落ちだ―――」
「あ……あ……! う…! うあ……! うわあああぁぁああぁああぁあ―――ッ!!」
気がつけばキョウジは絶叫していた。叫ばずには居られなかった。
何を―――何をやっているんだ、私は…!
自分の『怠慢』が母を殺し、
父親を冷凍刑に追いやり、
このガンダムを『悪魔』に貶め――――
揚句、たった一人残された弟の、『未来』までもを奪おうとしている。
駄目だ!! せめて弟は―――!
せめて、弟だけでも、守らなくては……!
その為に、今、私が出来る事は。
顔を上げてモニターを見る。既に相手からの通信は切れていた。
でも、何が何でも相手にやってもらわなければならない事がある。キョウジは渾身の力を振り絞って足掻いた。自分が『自分』で居られるのもあと僅か。そして、これほど腕が立つ相手に巡り合う事も、もうないだろう。
これが、自分に与えられた最後のチャンスなのだとキョウジは自覚していた。だから、持てる力の総てを振り絞って暴れた。
足が自由になる。コクピットのハッチを開けるためのボタンを足で押す。バシュッ、と、音を立ててハッチが開くが、すぐに閉じられる。あきらめずにもう一回押す。ハッチが開く。また閉じられる。ボタンを蹴り飛ばす。開きかけたハッチが閉じられた所で、足が再びケーブルに捕らえられた。
(爆弾が欲しい―――! ハッチを吹き飛ばせるほどの、強力な物が―――!!)
キョウジが強く念じる。すると。
にゅるり、と、音がして、コクピットの壁から手榴弾が出てくる。それが、キョウジの右手に手渡された。
「『A・G』…! お前……?」
キョウジが、己が手に有る手榴弾を見ながら、アルティメット・ガンダムに問いかける。
「私の言う事が……分かるのか?」
(………………)
細胞たちからの答えは返ってこない。ただ、あれほど殺ス、殺ス、とわめいていた細胞たちの声が止まっている。
まさか、と、キョウジは思った。
しかし、もしかして今なら―――。
キョウジは、祈るような気持ちでアルティメット・ガンダムに呼びかけた。
「『A・G』…。お願いだ…! 動きを、止めてくれ!」
シュウウウウウ……。
ガンダムの巨体が、一切の動きを、止めた。
A・G……お前…。
戻ってる―――? 戻っているのか……?
優しかった、あの、お前に……。
狂う前の、お前に―――。
(………………)
細胞たちは、相変わらず沈黙を守っている。でも、言う事を聞いてくれている。
何故、そうなったのかは分からない。だが、それだけで―――キョウジには、もう充分に思えた。
「ハッチを…開けて―――」
キョウジの願いに応えて、ゆっくりとコクピットのハッチが開かれて行く。
外から、新鮮な空気が流れ込んでくる。頬に当たる風が心地いいと思った。
ただ、煤けた匂いがする。ガンダムが、破壊活動をしていたせいなのだろう。あちこちで火災が起こっていた。瓦礫が散乱していた。木々がなぎ倒されていた。黒煙が空を黒く覆い、火の粉が天まで届いていた。
きっと、美しい街だったのだろう。ガンダムがここを破壊するまでは。人々の営みが、確かにここにあったのだろう。
知らず、キョウジの頬を涙が伝う。
ごめん。ごめんな、A・G……。
本当ならお前は、こういう所の傷を癒す、優しいガンダムになるはずだったのに……。
私の、不用意な『怒り』が、お前を『悪魔』に貶めてしまった。
本当に―――本当に、ごめん……。
でも、お前はこんなになってでも、私の言う事を聞いてくれるのか。
やっぱり……やっぱりお前は、優しい奴なんだ。
「……ありがとう、A・G……」
だから、キョウジは微笑んでそう言った。今までの感謝も込めて―――。
目の前に、あの黒い機体が居る。静止して、こちらを見ている。
おあつらえ向きだと思った。
さあ、お前を『悪魔』に貶めた元凶は、ここで消える。
だからお願いだ……。どうか、このまま動きを止めて。
そして、優しかった、あの頃のお前に戻ってほしい―――。
キョウジはきっと顔を上げ、黒い機体を正眼で見据えた。あそこまで声が届く事を祈りながら、キョウジは声を張り上げる。
「シュバルツとか言ったな!?」
黒い機体からの返事はない。だが、キョウジは構わず続けた。
「私を撃て!!」
「…………!」
黒い機体から、張り詰めたような気配が返ってくる。
「私を撃てば、『この子』は止まる!! だから、撃て!!」
黒い機体は、動かない。でも、自分は叫び続けるしかない。
「そして……これは末期の願いだ! 弟を―――!! 弟を、助けてやってくれ……!!」
叫びながら、キョウジは思う。なんて勝手な願いなのだろうと。
だけど、弟には罪はない。
このガンダムにも、罪はない。
悪いのは、私なのだ。
消えるべきは、裁かれるべきは―――私だけなのだ。
ふと、黒い機体が動いた。こちらに向かって飛んできている。
ああよかった、と、キョウジは思った。きっと、彼は撃ってくれる。私には、懸賞金もかかっている。そして、これだけ街を破壊した極悪人だ。彼が、撃つのを躊躇う理由は、何一つないはずなのだから。
だが、黒い機体が動くと同時に、あれほど鎮まり返っていた細胞たちも、また囁き始めていた。……ス。殺ス、殺ス! と……。ガンダムもまた、動きだしそうな気配がしている。
「―――駄目だ!! まだ動くな! A・G!!」
キョウジは悟った。神様がくれた奇跡の時間が、終わりを告げようとしているのだと。
でも、待ってくれ。お願いだ。お前を『悪魔』に貶めた元凶が、まだ消えていない。だからお願いだ。あと少しだけ、待ってくれ。
「動くな……! 動くな……ッ!」
動きたがっているガンダムを、懸命に抑え込む。そうしている間にも、黒い機体がさらに近付いてきた。
(早く撃ってくれ! 早く……!)
キョウジは祈るように黒い機体を見た。すると、何故か黒い機体のコクピットのハッチが開いた。
「!?」
何が起きているのか咄嗟に理解出来ないキョウジに向かって、シュバルツが顔を出し、そして身を乗り出した。シュバルツはキョウジに向かって手を差し伸べながら、こう叫んだ。
「青年よ!! お前は生きねばならぬ!!」
「―――!?」
何を言われたのかが分からず、キョウジは瞬間呆然とする。刹那、ガンダムの動きを抑えていた、キョウジの力が緩んでしまった。
「駄目だ!! やめろ!!」
キョウジが叫んだ時には、既に遅かった。ガンダムの右手から放たれた無数の光が、シュバルツの身体と黒い機体を、刺し貫いていた。
「……お前、は……生き…て……」
それが、『人間』であったシュバルツの、最期の言葉であった。
「あ、あ……ああっ………」
虚しく落ちて行く黒い機体とシュバルツの身体を、キョウジは震えながら見守るしか出来なかった。
「シュバルツ――――ッ!!!」
キョウジの叫びは、ただ虚空へと吸い込まれて行った。
そして、街は廃墟へと姿を変えた。いつもの通りに。キョウジはただ、涙を落とし続けるしかなかった。
ふと、シュバルツの遺骸と、黒い機体の残骸が、キョウジの目に飛び込んでくる。
(何故……何故、貴方は手を差し伸べたりなどしたんだ。こんな…私なんかに―――)
分からない。
冷静に考えれば考えるほど、彼が自分に手を差し伸べる要素など、ありはしないではないか。
―――生きろ。
シュバルツの、最期に言った言葉が、キョウジの脳裏によみがえる。
(無理だ……。この状況からどうやって……)
―――お前は、生きろ。
「……………!」
ここでキョウジは、ある可能性に行きあたる。だがしかし、すぐに頭を振った。そんな事、道義的に許される事ではないからだ。しかし―――。
目の前に横たわる男の遺骸を見る。この人は、強かった。この『デビルガンダム』と化してしまったガンダムと、渡り合えるほどに―――。
そして、自分に手を差し伸べてくれた。
『生きろ』と、言ってくれた。
この人にとっては、完全に極悪人であっただろう自分に向かって―――。
なら―――ならば、許してくれますか。
自分の『意志』を体現する者として、貴方を選び使役する事を。
貴方は、許してくれますか。
ドクン!
使えるのは、この人の『遺骸』と、『狂って』DG細胞と化した、アルティメット細胞のみ―――。
ドクン!
「……………」
人として、科学者として技術者として―――『超えてはならぬ一線』がある事を、キョウジは重々承知している。それを今、自分は踏み越えようとしている。そこから生じる確かな罪悪感が、キョウジを責め立てた。
(無理だ)
(やめておけ)
「……………」
キョウジはその声には応えず、一歩前に進み出る。
(人体実験がまだだ)
(モンスターを一体作るだけだ)
死体損壊だ。暴走している細胞だぞ。倫理的に許されない。手を差し伸べてくれた人の眠りをお前は妨げるのか。人殺し。死者への冒涜。お前に何の権利があってそんな―――
自分に向かってありとあらゆる警鐘が鳴る。だが、そんな声たちに向かって、キョウジは強く頭を振った。
分かっている! そんな事は、とっくに承知している!
でも
それでも
たった一人残されてしまう弟を―――
弟を、あきらめる事が出来ずに、私は……!
「……………」
キョウジは、祈るように、縋るように。
シュバルツの遺骸に向かって、ケーブルを、伸ばした―――。
作業は、成功した。
奇跡的に、細胞は暴走を起こさなかった。
こうして、現在の『シュバルツ』は誕生した。
去っていく黒い機体を眺めながら、キョウジは、己の精も根も尽き果てて行くのを感じていた。
(シュバルツ……頼みます。私の代わりに―――)
弟を。
キョウジの脳裏に、久しく会っていない弟の顔が浮かぶ。
ドモン……済まない。
『兄らしい事』を、何一つしてやる事が出来なかった。
それどころか、お前から『家』を奪った。
父を奪った。
母を殺した。
あまつさえ、お前の『未来』すら、狂わせようとしている。
だから。
だからせめて
『影』をよこす。
真実など、知らなくていい。
憎んでくれたままでいいよ。
お前は―――生きて。
そして、願わくば……『この子』を止めてくれ。
私のせいで狂ってしまった、かわいそうな子を―――
最後まで
勝手な兄で
『悪い兄』で
ごめん……な……
ド…モ……ン………
「もういい!! やめてくれ!!」
「――――!」
部屋に、ハヤブサの声が響き渡った。キョウジは、話を中断せざるを得なくなった。
ハヤブサは、涙を落していた。拳を握りしめ、震わせていた。
「ハヤブサ……」
キョウジはただ、哀しげにそれを見つめていた。この人はもしかして、もう自分の事を斬りたくなっているのではないかと。
無理もない。自分は、あまりにも『罪』を犯し過ぎている。この人が、自分を斬りたくなるのも当然だと、キョウジは思った。もともとハヤブサは、勾玉を回収する使命を帯びて、ここに居るのだから。
「くそっ!!」
ハヤブサの拳が、ドン! と床を叩いた。叩かれた床に、ひびが入る。でも、そんな所を殴ったのでは、ハヤブサの拳の方が傷んでしまう。殴るのなら、自分の方を殴れば良いのに、と、思って、キョウジはハヤブサに声をかけた。
「ハヤブサ……殴るのならば」
「違う!!」
キョウジが誤解していると察したハヤブサは、言下に否定した。
「違う―――! 否定したいのは、お前では無い!」
「――――!」
「殴りたいのは、お前ではない…ッ!!」
「ハヤブサ……」
キョウジが見守る前で、ハヤブサの拳が、また床に向かって振り下ろされた。ドンッ! と、音を立てたそれは、またひびを広げていく。
(くそっ! 本当に、どうすればいい!? このやり場のない怒りは―――!!)
キョウジの話を聞きながら、ハヤブサは深い憤りを感じていた。それと同時に、どうしようもない哀しみも。
何が悪いんだ!? 何がいけなかったんだ!? 何を間違えてしまったんだ!?
こいつの父親が、『DG細胞』を発見したのが、総ての間違いだったのか!?
キョウジの『才』が、人よりも抜きんでていたのが、そんなにも悪い事だったのか!?
ミカムラ博士が父親の『親友』で、弱過ぎたのが、そもそもいけなかったのか!?
いや―――それよりも。
ミカムラ博士が流される原因となった『悪意』―――。
生きている人間ならば、誰しもが持つ可能性のあるものだが…今だけは。
今だけは―――『それ』をぶん殴ってやりたい、と、ハヤブサは強く思った。具体的に言うならば、研究を悪用しようと狙った連中。それを、一人残らずだ。
(とにかく落ち着け)
ハヤブサは、強く己に命じる。自分の中の感情だけに振り回されては駄目だ。自分はまだ、肝心の『シュバルツ』に関する話を聞いていない。今の話は、誕生にまつわる話を聞いただけだ。
「キョウジ―――『シュバルツ』は……元は人間だったのか」
ハヤブサは、涙を拭いながらキョウジに問うた。とにかく気持ちを落ち着けながら、話を整理する必要がある、と、思った。
「ああ。死したシュバルツと言う人間の上に、DG細胞で上書きして出来たのが、今のシュバルツだ」
ここまで話したキョウジは、少し哀しそうに眼を伏せた。
「『人間』であったシュバルツが、どういう人だったのか……残念ながら、私は知らない。ただ―――あの状況下の私に、手を差し伸べてくれるような……そんな、人だった」
そして自分は、その人を殺めてしまった。彼の最期の言葉と、墜ちて行く姿を―――自分は今も、忘れる事が出来ない。
(俺も…もしかしたら、手を差し伸べてしまうかもしれない)
ハヤブサはふと思った。だから、口を開いた。
「……そのシュバルツには、分かったんだろう。お前が『被害者』だと言う事が」
「ハヤブサ……」
「はっきり言う。お前の話を聞いた限り―――お前は、『自分が悪い』とひたすら言っていたが、どう考えても、お前は『被害者』だ」
「……………」
「ただ―――一度狂った歯車が、どんどん悪い方へ悪い方へと転がって行っただけだ。お前は、それに巻き込まれてしまったんだ……不運にも」
(そうだろうか……)
キョウジは、膝の上でぎゅっと握りこぶしを作る。
「そんな中、お前は、最後まで責任を取ろうとしていた。…それが、シュバルツには伝わったんだろう。だから、手を差し伸べたのではないかと―――俺は、思う」
「…………ッ」
それまで淡々とした表情をしていたキョウジが、泣きそうになっている。それを見たハヤブサが、慌てて言った。
「勘違いするなよ。俺は別にお前を慰めようとして言っているわけではない。ただ忍びとして―――情報を扱う者として、客観的に判断して、そう言っているだけだ」
それを聞いたキョウジが、ふっと優しい笑顔になる。
「……貴方やシュバルツを見ていると、忍びの人は皆優しいのではないかと、勘違いをしてしまいそうだ」
キョウジは思った。もしかしたら、『人間』であったシュバルツと、このハヤブサと言う人は、とても似ていたのではないだろうかと。
「―――それは危険な勘違いだな。止めておいた方がいい」
そう言ってハヤブサが渋い顔をするので、キョウジもつられて苦笑した。場の空気が、少しだけ和やかな物になる。
「……私の話をするよりも、シュバルツの話をしましょうか」
貴方が聞きたいのも、おそらくこれでしょう? と、問いかけるキョウジに、ハヤブサも頷いた。ただキョウジは、話の流れによっては、今度こそ、ハヤブサに殴られるかもしれない、とも、思った。
「今のシュバルツは、一度死した人間の上に、DG細胞で情報を上書きしている。…ハヤブサ、これがどういうことか、貴方には分かりますか?」
キョウジの言葉に、ハヤブサは頭を振る。
「……つまりシュバルツは、『人間として』の生命活動をしていないんだ。DG細胞の能力によって活動をしている」
「!?」
ハヤブサは瞬間、キョウジが何を言っているのか理解できなかった。
「ま―――待て……。だって……あいつは……」
「うん」
キョウジが、穏やかに返事を返す。
「呼吸を―――。息を……しているだろう?」
「うん、しているね」
「『血』だって……流して―――」
「そうだね…。流すね」
「とても―――とても、『人間』らしい奴で……」
「そう―――『人間』……彼は、『人間』であろうと『擬態』をしている…」
「な――――!」
ハヤブサは、キョウジの言葉に鈍器で殴られたような衝撃を受けた。
「『人間』の間に混じるのならば、呼吸をしていないと不自然だろう?」
「…………!」
「『血』だって―――最初は、頭部からしか出血しなかった。それが、今では身体のどこを負傷しても、『血』らしきものが流れ出るようになっている……」
おそらく、DG細胞が、シュバルツをより人間らしく擬態させるために、自己進化をしたのだろう、と、キョウジは言った。ハヤブサは、理解出来ない―――と言うより、理解したくない、と、思った。
「貴方は、シュバルツに触れた事は?」
「ある…。2、3度、手に触れた」
「その手を、『冷たい』とは―――思わなかった?」
「――――!」
ハヤブサは、必死にシュバルツの手に触れた時の事を思い出す。だが、どの時も、自分の方が余裕が無かった時だったような気がする。だから正直、シュバルツの手の温かさにまで気が回っていなかった。
「シュバルツは、私と入れ替わる時以外は、常に手袋をしている。恐らく、相手に自分の体温が無い事を伝える事を避けるためだろうね。……DG細胞も、まだ『生きている人間の体温の再現』までは、難しいみたいだ……」
そう言ってキョウジは淋しそうに笑う。ハヤブサは、頭がズキズキと痛むのを感じた。
そうなのか? シュバルツ。
お前は『生きていない』から
『生きる』―――と、言えなかったのか…?
これが、シュバルツの『闇』の一端なのか、と、ハヤブサは思った。
「彼が、『人間として』の生命活動をしていない、と言える証拠は、まだある」
キョウジが、更にたたみかけるように口を開いた。
「DG細胞は、その活動エネルギーを、物質的な物から得るのではなく、精神的な物から得ている。だから―――シュバルツは、自身の活動のために、固形エネルギーを摂取する必要が無い」
「……どういう、事だ?」
「つまり、『食事』を必要としないんだ」
「…………!」
ハヤブサは思わず言葉を失う。
「試しに、シュバルツを食事抜きの状態で監禁したとしても、おそらく平気で生き続けるだろうね……」
そんな実験、したくもないけど―――と、キョウジは、吐き捨てるように言った。
「ま、まさか―――。でも、あいつは……!」
ハヤブサは、俄かに信じ難くて、思わず意味の無い言葉を吐いてしまう。
「では……貴方は見たのか? シュバルツが、『食事』をする所を―――」
「――――!」
ハヤブサは、必死にシュバルツの行動を思い出す。隼の里に向かう時、行動を共にはしていたが、自分はシュバルツの方を見てはいなかった。里につくまでの間、自分は忍者用の非常食を口にしていた。だから、シュバルツもそうしているものと思って、気にも留めていなかった。
隼の里の宿の時は―――。
反射的にハヤブサの脳裏に、着物をはだけたシュバルツの姿が浮かび上がってくる。
「…………ッ!」
だから違う! それどころではない―――と、慌ててその映像を追い払う。
確か、宿の者の話では、食事をとらなかった、と……あの時も、『食事どころではない』と…自分は勝手に思ってしまっていた。
結局、見ていない。自分は、シュバルツが食事をする所を、見てはいない―――。その事実に気づいて、ハヤブサは愕然とするほかなかった。
サインは出ていたのに。
彼から『人間ではない』というサインが、確かに出ていたのに。
何故自分はそれに、気づく事が出来なかったのか―――。
「な……ならば……」
何故か、身体が小刻みに震えてしまう。
「シュバルツが、常に『死ぬ方』を、選択してしまうのは……」
「…………!」
ああ―――と、キョウジは目を閉じる。ハヤブサは、やはり気付いていた。シュバルツの危うさに。
「彼は…死なないんだ。例え死ぬほどの致命傷を負い、その機能が停止したとしても―――DG細胞の自己再生能力が、彼を甦らせてしまう…」
「…………!」
「誠意を尽くしたい…。だけど、命をかける事が出来ない……。死ねないから…。『命』が無いから―――」
(そうか―――!)
ハヤブサの中で、やっとシュバルツの行動原理が線でつながる。
こちらが『死ぬぞ』と忠告をした時に、何故冷たい笑みを返してきたのか。
『生きろ』というこちらのメッセージに、何故頑ななまでに応えようとしなかったのか―――。
応えようとしなかったのではない。『応えられなかった』のだ。
死ねないから。
命が無いから―――。
ああ。だから、闇にまみれる。
己の中身が空虚だと、知っているから。
己の事を、『影』という。
他に形容のしようが無い事を、知っているから―――。
脳裏に、一人の少女を助けるために、無防備に飛び出したシュバルツの姿が浮かんでくる。
彼は、分かっているのだ。
『命』の重さが。
尊さが。
だから救う。何を置いてでも。
無辜の命を救う事を、優先する。
なのに、自身には、それが無い―――。
その苦しみと葛藤は、どれ程の物なのだろうか。
(こんな―――! こんな事って……!)
知らず、感情に流されそうになる。
ハヤブサはそれを、懸命にこらえた。未だ流されるわけにはいかない。シュバルツの事で、まだ分からない事がある。それを聞くまでは…!
「シュバルツに『命』が無い事は分かった。『死ねない』ことも―――」
震える拳を、ぐっと握りしめる。
「では、キョウジ―――聞いていいか?」
「どうぞ」
キョウジは即答してきた。彼の面には、どこかで見たような表情が浮かんでいる。
ああ―――これは。
白刃をその身に受ける覚悟を固めている時のシュバルツと、同じ表情だ。
「『死ねない』はずのシュバルツから、どうしようもなく『死』の気配を感じる事があった」
「――――!」
「それは、何故だ? 何故彼は、生き続ける事を選択できないんだ?」
彼は、はっきりと言っていた。
『自分の介錯を、俺に』と。
あの時のシュバルツは、はっきりと『死』を意識していた。腹を斬る清々しさを、その身に湛えていた―――。
何故だ?
不死であるのならば、ずっと存在し続けられるはずであるのに。
「……………」
キョウジは、一瞬開きかけた口を話す事を躊躇うかのように閉じる。膝の上の拳が、ぎゅっと握りなおされた。
「…『不死』であるはずのシュバルツだが……彼が唯一『死』を迎える方法が、ある」
「……それは?」
「それは、彼の行動エネルギーの源にもなっている、オリジナルの『ココロ』の持ち主の存在が消えること――――」
「…………?」
何を言われているのかハヤブサは咄嗟に分からず、眉を顰める。キョウジは、哀しそうに眼を伏せた。
「即ち、私の『死』だ。私の『死』が―――彼の『死』に、つながる」
「な―――!」
思わぬ言葉にハヤブサは絶句する。しばし、その場に沈黙が舞い降りた。
「……つまり、私は―――」
先に沈黙を破ったのは、キョウジ。
「『人間』であった彼の……命を奪い―――」
そう。自分が彼を殺した。紛れもなく。
彼は、自分に向かって手を差し伸べてくれたと言うのに。
「容姿を奪い、記憶を奪い、人格を奪って……」
握りしめられたキョウジの拳が震えている。冷静さを保とうとして、保てなくなっているのが、見て取れた。
「死ねない身体にして……揚句私は、シュバルツから『殺された事』への報復する権利すら、奪っている…。私の『死』が、彼の『死』につながってしまう事に因って……!」
そう言ったままキョウジは下を向いてしまう。口に出して改めて思った。よくもまあ自分は、人に対してこれだけひどい事が出来たものだと。弟を守るために、やむを得ない仕儀だったとは言え―――。本当に、何もかも。総てを彼から奪ってしまった。
シュバルツの方を見て、その拳を見て―――。その拳で、自分を殴ってくれればいいのに。何度そう願った事だろう。
キョウジは思う。もし『悪魔』という者が存在するのだとしたら、それはきっと、自分の様な姿形をしているに違いない―――。
「キ、キョウジ……」
キョウジが、どうしようもなく自分を責めているのが分かる。
(間違えるな)
ハヤブサは強く思った。少なくともシュバルツは―――。あのシュバルツは、キョウジを責め立てる事を望んではいない。
あいつは、はっきり言ったんだ。
「キョウジを、守りたい」と。
その願いは、それをしなければ自分が死んでしまうから、という義務感に駆られての物ではなかった。
心の底から、そう願っていた―――。
キョウジの話は、淡々と続く。自分を責め続けたまま。
「『デビルガンダム』と化したガンダムは倒され―――弟も、無事この事件から生還できた…。私が、シュバルツを作った目的も果たされた……」
そして、皮肉にも自分は生き残ってしまった。そして、シュバルツも。
意識の無かった自分は、そのまま病院へ収容された。その間に、シュバルツは忽然と姿を消していた。
だが、彼は自分の近くに居た。人目につかないようにしながら、秘かに自分を守ってくれていたのだ。そんな、シュバルツであったのに―――。
「……病院で意識が戻って、私は―――絶対にやってはいけない『ミス』を、シュバルツにしてしまった…」
「ミス?」
「―――微笑めなかったんだ。私は…」
「? ……どういう、事だ?」
話がいまいち見えないハヤブサは、首をかしげる。
「意識が戻って…初めてシュバルツに会った時―――最初に私がした事は、自分の『罪』の自覚だった…」
暗がりの中で、初めてシュバルツの姿を認めた時に―――気づいてしまった。自分が『何』をしてしまったのか。彼だけを闇に置き去りにしてしまったのだ。自分は、助かって光の中に戻ったと言うのに。
その結果、自分の面に『罪に怯えた』表情が、浮かんでしまう。それが、シュバルツに『何』を突きつけてしまうのか、という事に、気づきもせずに。
「……………!」
シュバルツは、はっきりと傷ついた表情をした。
気づいてしまったのだ。彼も。
自分の存在の、『罪』といびつさに―――。
それを彼に、突きつけてしまった。他ならぬ―――自分が…!
「微笑まなきゃいけなかったのに…。『ありがとう』って、真っ先に言わなければいけなかったのに……」
そうすれば、少なくともすぐにシュバルツを傷つける事はなかった。彼に、自身の存在のいびつさに気付かせる事を、もう少し遅らせる事が出来たはずだ。キョウジは今も、それを悔やみ続けている。
シュバルツは、病室から走り去った。自分は、後を追えなかった。
それからシュバルツは、しばらく行方をくらませてしまった。
「私が『自殺』を試みたのも、この時だ」
「――――!」
キョウジの言葉に、ハヤブサは絶句する。キョウジは静かに話し続けた。
『罪』にまみれている自分が嫌になって。
シュバルツを『解放』するために、それしか手段が思い浮かばなくて―――。
詫びるつもりで、病院の屋上から、飛び下りようとした。
寸前の所で、戻ってきたシュバルツに止められた。ドモンが、知り合い全部に声をかけて、シュバルツを探し出して来てくれたのだと、後から聞いた。
「何故だ!? キョウジ!! せっかく助かった命を―――何故捨てようとする!?」
『命』が無いシュバルツからの、涙ながらの説教はものすごく堪えた。
この時に、自分の命とシュバルツの命が、連動している事を聞かされた。『生きなければ』と、強く思った。そして自覚する。また自分は、シュバルツに助けられたのだと―――。
彼に、報いたい。そして、償いたい。
でも、どうすればいいのだろう。
「とにかく私は―――『シュバルツが必要だ』そう言い続けるしか、無いと思った」
最初はとにかく大げさなほど、シュバルツを頼るようにした。こうして、自分の『影』との、奇妙な共同生活が始まった。
そして、すぐにある事に気づいてしまう。
「『ある事』? 何か不具合でもあったのか?」
ハヤブサの問いに、キョウジは頭を振る。
「違う―――『快適』なんだ」
「? 何だって?」
何かおかしい単語を聞いた様な気がして、ハヤブサは思わずキョウジに問い直してしまう。
「『快適』なんだ―――彼との共同生活が…」
ある意味、自分の『影』だ。だから、当たり前と言えば当たり前なのだが、彼はよくわきまえてくれていた。独りになりたい時、集中したい時などは、必要以上に干渉しては来なかったし、それでいて、こちらが頼りたい時には、ちゃんと背中を貸してくれた。
そして何より―――『会話』が出来た。
「会話?」
「そう、会話…。こういう事を言ったら、笑われるかもしれないけど―――」
日常の、何気ない出来事。世界で起きる事件。研究での疑問。愚痴―――遠慮なく投げかける事が出来る。向こうからも忌憚のない意見が返ってくる。確かな手ごたえを伴って―――。
遠慮のない『会話』の楽しさを、初めて知った。
そして思い知った。今まで自分は、どれだけ相手に遠慮しながら会話をしていたか。そして、自分が今まで如何に『孤独』だったのかを―――。
空を飛ぶ鳥にとって、空は広く、自由に飛びまわれた。
だけど―――その鳥はいつも、独りきりだった。
だが今は、振り返ればシュバルツが居る。
自分と同じ高さで、すぐ近くを飛んでいてくれる。
それが楽しい。
それが、嬉しい。
だから気がつけば、自分は無意識にシュバルツの存在を探すようになっていた。
今では、彼がどこに潜んで居ようがその気配を察知出来てしまうほどに―――。
だが、一緒に暮らしているうちに、気づいてしまう事もある。
「おそらくシュバルツには、味覚が無い―――」
「――――!」
「『食事』を必要としないんだ。だからある意味、いらない能力なのかもしれないな…。口の中に含んだ物の成分分析を、舌の上で出来るみたいだけど……」
だから、食べ物の中に毒が入っていてもすぐに分かるし、見た目がグロテスクなその土地ならではの料理も平気で口に放り込めるから、諜報活動には便利だ、と、シュバルツは笑いながら言った。それを聞いたキョウジは、複雑な気持ちになった。
後、一度行方をくらましてから帰ってきたシュバルツは、自分が機能停止してから復活するまでの時間や経過に、やたら詳しくなっていた。
それが意味する所は、何か―――。
「おそらく、彼の方も何度も試みているんだ」
「何を?」
「自死を――――」
「な―――!」
絶句するハヤブサ。キョウジは、哀しそうに眼を伏せた。
「それも、一度や二度じゃない。ありとあらゆる方法を試しているんだ…。そうでなければ―――あんなに、自分の身体が破壊された後の自己再生の経過や時間に、詳しくなっているはずが無い……」
「…………!」
あまりの事にハヤブサは、眩暈を覚える。死なないとはいえ―――いや、死なないからこそ―――何度も何度も試みたと言うのか。『あいつならやりかねない』と、簡単に思えるから、余計に性質が悪い。
痛みを感じないわけじゃないだろう!?
苦しまないわけじゃないだろう!?
それなのに―――!!
(馬鹿だ!! あいつは本当に、大馬鹿野郎だ!!)
今、ここにあいつがいたら、5、6発は殴ってる―――!
ハヤブサは、震える拳をぎゅっと握りしめた。
「それだけ苦しんだと言うのに……それでも彼は、私の元に戻って来てくれた」
キョウジの言葉に、ハヤブサははっと我に返る。
「そして私に……『死ぬな、生きろ』と、言ってくれたんだ……」
「キョウジ……」
キョウジの肩が震え、瞳から光る物が零れおちている。ハヤブサは、かける言葉が見つからない。
「本当に、もうどうすればいいのか―――。どうすれば、彼に償えるのか―――」
苦しんでいる。傷ついていると言うのに、それでも私に肩を貸してくれる。
シュバルツ、貴方は優しすぎる―――。
このままでは本当に、私の方が助けられてばかりだ。
「『食』の楽しみも無い。生死も自分で選べない。生き物としては、不自然だ……」
涙が零れ落ちる。胸の内から次々と溢れ出るそれと言葉を、キョウジは止める事が出来ない。
「それが彼を苦しめている。傷つけている。分かっている。分かっているのに―――!」
既に、自死を何度も試みさせている。
苦しくないはずが無い。
辛くないはずが無いのに。
「それでも―――私は望んでしまうんだ……!」
「望み……?」
「シュバルツの―――『生』を……!」
「…………!」
「『生きて』ほしいと―――! 傍に…居てほしいと――――!」
独リニシナイデ
傍ニ、居テ
まるで小さな子供のように―――!
こんな自分、気づきたくなかった。
こんな、弱い自分。
「……『生きて』ないのに……!」
「キョウジ……」
「―――自分の、『影』なのに―――!」
「…………」
「馬鹿みたいだ―――。本当に、本当に……馬鹿みたいだ―――!」
会話が出来る。
振り返れば、居てくれる。
たったそれだけの、小さな『幸せ』―――
手放せない。
手放せないんだ。
でも、このままでは駄目な事も分かっている。
こんな、中途半端な状態のままで、いつまでもシュバルツを自分の『影』として縛りつけ、使役している状態は―――不自然だ。
「シュバルツの……『幸せ』って、何だろう……?」
キョウジの口から零れおちた言葉に、ハヤブサはすぐに答えられない。
「『人間』であった時の記憶を戻し、容姿を戻して……彼が本当に大切にしていた人たちの所に、彼を返すべきなのか……」
「―――そんな事が出来るのか?」
ハヤブサの問いに、キョウジは涙を拭い、困ったように笑いながら答える。
「データがあれば…。本来なら、真っ先にそれをするべきなのだろうけどね……」
だがキョウジは、それをする事が出来なかった。何故なら―――。
「データが無かった……。それどころか、『シュバルツ・ブルーダー』と言う人の、生きた痕跡すら―――」
何も―――何も無かった。見事に無かった。人一人が生きた痕跡を、ここまで消せるものなのかと思えるほどに。……作為的な匂いすら、感じた。
しかしこれで―――シュバルツを『シュバルツ』に返す手段が、無くなってしまった。
呆然とする一方で、どこかで安堵している自分を感じる。それが、またキョウジの自己嫌悪の要因の一つになる。…悪循環。
じゃあ、どうすればいいのか―――。
何が、彼にとっての幸せなのか―――。
「…分からない…。分からないんだ……」
「キョウジ……」
そう言って肩を震わせながら泣くキョウジを、ハヤブサはただ見守るしか出来なかった。
(でも、このままではまずいだろう?)
ハヤブサは思った。シュバルツの幸せを考えるのなら……。多分、このままではまずい。キョウジがこんなふうに自分を責め立てる事を、あいつは絶対に望んでいない。それだけは、分かる。
だが、どうすればいいのかが分からない。
シュバルツ…。あいつは―――。
「…………」
(……と、言うか、俺が聞いたのは『DG細胞とは何だ?』という問いのはずだったんだが……何がどうしてこうなった?)
ハヤブサはそう感じて頭を抱えてしまう。
DG細胞とシュバルツが、密接に結びついているのが分かったから、ある意味、仕方が無い事なのかもしれないが、それにしても―――。
これは、『人生相談』の類だ。
参った。自分はこんな時、気の利いた事など絶対に言えはしないと言うのに―――。
どうして、こんな話を聞いてしまったのが俺なんだ。
ハヤブサは、口下手な己を呪う。
もっと、気の利いた事を言える奴が、他に居るだろうに。
ただハヤブサは、キョウジに対して「自業自得だ。馬鹿じゃないのか」と、罵るとか「自分同士で―――」と、嘲笑うという選択肢だけは、残念ながら持ち合わせていなかった。
何故、自分にこんな話をしてくれたのかは分からない。しかし、おそらく、包み隠さず誠意を持って話してくれたであろうキョウジに対して、何か言わなければ―――と、真面目に思い、ハヤブサは懸命に頭を捻った。何よりも、ここまで内面がボロボロになっている二人を、放ってはおけない。
「キョウジ……」
でも、何を話せばいいのか……。何を言えばいいのか……。
「キョウジ……。その……」
そう、シュバルツだ。自分が感じたシュバルツの像を、キョウジに話せばいい。それが…キョウジの心を癒せるかどうかまでは分からない。だが、ある意味シュバルツと同じ世界で生きている自分だからこそ、キョウジに伝えられる事も、あるかもしれない。無いかもしれないが…。
「その……シュバルツは……」
「…………!」
ハヤブサの口から出た『シュバルツ』という言葉に、キョウジがピクリと反応をする。
「シュバルツは……あいつは……」
あいつは……あいつは……と、懸命に考えたハヤブサの口から、次の言葉が絞り出された。
「……あいつの、笑顔は―――綺麗だ……」
「………?」
ハヤブサに対して、キョウジが怪訝な表情を見せる。それを見たハヤブサが、はっと我に返った。
「ち、違うぞ!? 決してやましい意味で言ったわけではなくて、その……!」
「? ……?」
慌てて言い訳のようなものを口にするが、キョウジは疑問符を浮かべて首をかしげるばかりだ。つまり、変なふうに意識して赤面しているのは自分だけ―――と、気づいたハヤブサは、はぁ、とため息をついて頭を垂れる。
「……つまりだな、キョウジ……。俺が言いたいのは―――」
頭をかきながらハヤブサは、気を取り直して言葉を紡ぐ。こういう作業は苦手だ、と、思いながら。
「シュバルツは……あいつは…少なくとも、自分の置かれた『境遇』に対して、嘆いたりはしていない」
「………え?」
ハヤブサの言葉を意外に感じたキョウジから、思わず問い直す声が漏れる。
「俺は……勾玉の話をするために、あいつを隼の里に連れて行った事がある……」
その時の事だ。自分はシュバルツを、里の中でも老人と修行前の子供たちが居る、一番平和な居住空間に招き入れていた。普通なら、余程信用が置ける者で無いと案内しないと言うのに、何故か自分は彼をその場所に案内していた。おそらく無意識のうちに、自分はシュバルツをかなり信用してしまっていたのだと思う。
「そこであいつは……とても優しく笑っていた。子供たちも、安心したようにあいつの周りに群がって……とても平和な光景だと思った…」
思わず、血の匂いを身体からさせている自分の方が、場違いなのではないかと思うほど、あの風景は優しかった。あのまま時が止まってほしいと、本気で祈った。今思い出しても、何故か胸が締め付けられる。
「もし、あいつが自分の置かれた境遇を『不幸』と呪っているのなら……あんなに綺麗に笑えないと思う。もっと、暗い表情になるはずだ……」
「…………!」
「あいつは、受け入れる事が出来る奴だ…。そうは思わないか? キョウジ……」
そんなまさか、と、思おうとして、今度はキョウジの方が、シュバルツの行動をいろいろと思い出していた。そして思い当る。確かに彼は、自分に生死の選択権が無い事、味覚がない事、それに対して文句を言った事は、一度もない。
(そんな……シュバルツ―――!)
キョウジはただ、愕然とするしかなかった。
「後、俺は……最初シュバルツの事を『人間』で『キョウジ』だと思っていたから、そのつもりで話しかけていた…」
しかし、シュバルツは『人間』の様に命を持つ者ではない。それが、自分の『想い』とシュバルツの間に、すれ違いをもたらしていた。そのすれ違っている溝を埋めたくて、自分は思わず踏み込んでしまった。
そして、出てきてしまった。闇にまみれた『シュバルツ』の姿が―――。
「だが……そこでもあいつは、笑ってた―――」
「……………!」
「ただ優しく、笑っていたんだ……」
「…………ッ!」
キョウジの瞳から、大粒の涙が零れおちる。涙腺が、完全に決壊してしまっているようだ。
「何故……シュバルツ…! どうしてだ……!」
キョウジは泣きながら訴える。その闇に叩き落としたのは、紛れもなく自分であると言うのに、どうして彼は―――。
「あいつは……お前に報復したいとか、そんなことは一切望んでいない……だから…お前がそんなふうに…必要以上に自分を責める事は無いと思う……」
「……………」
キョウジが、膝の上の拳を無言で握りしめている。ハヤブサは、頭をかいた。
(シュバルツの『幸せ』か…。難しいな……)
「闇の中のあいつの姿は…『孤独』だった……。でも、『不幸』そうでは無かった…」
だって、あいつは笑ってた。とても満ち足りたように、笑っていたんだ。
「『孤独』と『不幸』は似ているようで違う気がする…。うまくは言えないが……」
「ハヤブサ……」
キョウジが涙を拭っている。少し、落ち着きを取り戻したようだ。
「ただ……シュバルツのあの姿から、受けた印象は……」
ハヤブサは、懸命に闇にまみれたシュバルツの姿を思い出していた。あの姿を見て、自分は思わず涙を落した。とても『孤独』で、でも、穏やかに笑っていて……。
ただ――――。
哀シイ。
哀シイ。
自分ノ『存在』ガ、貴方ヲ傷ツケテイル―――。
ソレガタダ、 『哀シイ』 ノ デス 。
「あ………!」
今度は、ハヤブサの涙腺が決壊した。
(しまった―――!)
ハヤブサは、慌てて下を向いた。だがもう遅い。堰を切ったように溢れるそれは、次から次へと零れ落ちていく。
なんて迂闊なんだ、俺は。
シュバルツのあの姿の事を思い出すと、自分は絶対泣くと分かっていて―――!
「…………ッ!」
懸命に涙を拭う。流されてどうする、と、己を叱咤する。今は、キョウジの話を聞いている立場だ。自分が泣いている場合ではない。泣いている場合では、無いと言うのに……!
「ハヤブサ……」
ハヤブサの涙を見たせいなのか、キョウジの方は大分落ち着いていた。涙を拭い、そして微笑んだ。
「ありがとう……。やはり貴方は、優しいね……」
「違う…! 優しいのはお前だ…! そして、シュバルツだ……!」
シュバルツもキョウジも、互いを思いやり過ぎている。シュバルツは、キョウジが自分のせいで心を痛め、涙を流している事を知っている。「そんな事をしなくていい」と、伝えたい。しかし、伝える手段が見つからない。
だから微笑む。
せめて微笑む。
少しでも、キョウジの心の負担が軽くなる事を祈るように―――。
「でも……貴方のその涙は、シュバルツのための物でしょう?」
「…………!」
「貴方に、話を聞いてもらえて良かった」
「キョウジ……ッ!」
「良かったよ…。ハヤブサ―――ありがとう……」
そう言って、綺麗に微笑むキョウジは、もう涙を流していなかった。
「……馬鹿野郎が…ッ!」
対するハヤブサは、完全に涙を止める術を失っていた。手元にタオルを用意しておくのだった、と、少し後悔した。
二人が話をしているキョウジの部屋の外で、座り込んでいる二人の男たちがいた。東方不敗とドモン・カッシュである。二人ともキョウジの姿を求めてここまでやって来て、部屋の外で話を聞いてしまっていたのだ。
(ううっ…! 兄さん……ッ! 兄さん――――!)
ドモンはそう言いながら、涙をぼろぼろ零している。そんなドモンを、東方不敗がどついた。
(こらドモン! もう少し気配を殺さんか! 中に居る二人に気づかれたら終わりぞ! 全く貴様という奴は、いつまでも泣き虫でいかん!)
そう言う東方不敗に、ドモンの方も反撃する。
(し、師匠だって…涙を流しているじゃないですか……!)
(馬鹿者!! ワシのこれは、目から流れ出る漢の汗じゃ! 断じて涙などでは無い!!)
(じゃあ俺のだって、『漢の汗』です!)
(何ぃ? 貴様! 師であるワシに向かって―――!)
「……お前たち、そんな所で何をしているんだ?」
「――――!」
二人がギョッとなって声のした方に振り返ると、革のロングコートを肩に羽織っているシュバルツの姿があった。
「シュッ、シュバッ……!!」
「お、お主、意識が戻ったのか……!?」
ドモンと東方不敗が、同時にあたふたしだす。無理もない。彼は今まさに、部屋の中で行われている会話の中心人物であったのだから。
「ああ……。眼が覚めたら、誰もいなかったから……キョウジとハヤブサはどこだ?」
そう言ってシュバルツがきょろきょろとあたりを見回す。東方不敗とドモンは「わ~ははは!!」と、笑いながら、慌ててキョウジの部屋のドアの前に立ち塞がった。中ではキョウジが、シュバルツの許可を得ずにシュバルツの根幹にかかわる秘密をハヤブサに話しているのだ。それがシュバルツに伝わってしまったらと思うと、修羅場の予感しかしない。
何としても、シュバルツがこの部屋に入るのだけは阻止しなければ―――と、二人ともが思った。
「……何をやっているんだ? お前たち……」
しかし当然、この二人の不審な行動は、シュバルツの不信を招いてしまう。
「い、いやあ、別に何も…! なぁ、ドモン!」
「そ、そうそう…! この中で、兄さんがハヤブサにDG細胞とシュバルツの秘密にかかわる話をしているなんて事は、絶対に無いから……!」
「―――馬鹿者!!」
東方不敗がそう叫んだ時には既に遅かった。しまった、と、ドモンの顔色が変わると同時に、シュバルツの顔色も変っている。二人とも、悲しい程に嘘をつくのが下手くそだ。
「何!? どういうことだ!?」
「あああの…その、俺達も兄さんを探していて……そ、そしたら、その……」
ドモンはシュバルツに見据えられて、完全にしどろもどろになっている。
「そ、それよりもお主…。身体はもういいのか?」
「それどころではない! そこをどけ!!」
東方不敗の言葉を撥ね退けるように、シュバルツが叫ぶ。
「い、いや、でも……!」
ドモンが怖じ気たように首を振り、東方不敗がフン、と鼻を鳴らす。
「―――断ると言ったら?」
「…………ッ!」
ピクリ、とシュバルツの眉が釣り上がる。
「……どうあっても、部屋に入らせてもらう」
シュバルツからほとばしる殺気に、東方不敗が構えを取った。
「来るか!?」
「……………」
構える東方不敗に対して、シュバルツは氷のような冷たい眼差しを向ける。彼はふっと一つ息を吐くと、猛然と突っ込んで行った。ただし、東方不敗の居るドアの方ではなく、誰もいない壁の方へ。
「しまった!!」
東方不敗が叫んだ時には既に遅かった。シュバルツは『壁抜けの術』を発動して、あっという間に壁の向こうに姿を消してしまったのだ。
(ええい! 忌々しい! これだから『忍者』という奴は―――!!)
東方不敗が頭を抱えている横で、ドモンがひたすらおろおろしている。
「ど……ど、どうしよう…! 兄さんが……シュバルツが……!」
「入ってしまった物は仕方あるまい。とにかく我らも、様子を見よう」
師匠の言葉にドモンも一も二も無く頷いた。
「とりあえず、中には踏み込まず、そうっとな……」
「…中に入らないんですか?」
めずらしく弱気な発言をする師匠に、ドモンから突っ込みが入る。
「ではお主、中に入るのか?」
師匠からの切り返しに、ドモンは勢い良く首を横に振る。「それ見ろ!」という東方不敗に、ドモンも反論できなかった。
二人は恐る恐る、キョウジの部屋のドアを開けた。
(キョウジ……! 「あの事件」の話をするなんて―――! なんて馬鹿な事を……!)
シュバルツは歯噛みする。あの事件から自分を作った過程を話す事など、キョウジにとっては自分の傷口をわざわざえぐって広げるような真似をしているも同然だ。きっと、自分をぼろぼろになるまで責め抜いているに決まっている。
壁を抜けると、ハヤブサと向かい合うようにして座っていたキョウジと、目が合った。
「キョウジ―――」
自分が声をかけると、キョウジはビクッと顔を上げた。
「シュバルツ……!」
「…………ッ!」
キョウジの目元に痛々しい程の涙の跡があるのを認めて、シュバルツは唇を噛みしめる。
「キョウジ……お前―――!」
「ご、ごめん…! シュバルツ―――。勝手に……!」
シュバルツの秘密を話した事を責められる、と、思ったキョウジが身構える。膝の上で握りなおされたキョウジの手に手袋がはめられている事に、シュバルツが目ざとく気づいてしまった。
「キョウジ……その手はどうした?」
「あ…! これは、何でも無くて―――」
慌ててキョウジが手を隠そうとするのを、シュバルツが阻止しようとする。そのシュバルツの手を、誰かの手が掴んだ。
「ハヤブサ!?」
掴んできた手の主に、驚いたシュバルツが声をかける。
「……………」
しかしハヤブサはシュバルツに返事を返さず、無言でその手を掴み続けた。
「放せ……!」
シュバルツがハヤブサの手を振りほどこうと、腕に力を込める。しかし、ハヤブサの手は離れなかった。ハヤブサはシュバルツの手を掴んだまま、無言で立ちあがってきた。
「…………ッ!」
そして、うつむいていたハヤブサが、いきなり顔を上げる。彼の目から、光る物が飛び散った。
「!?」
ハヤブサの涙にシュバルツが気を取られた瞬間、ハヤブサからの強烈な一撃が、シュバルツを襲う。殴り飛ばされたシュバルツは、そのまま床に倒されてしまった。
「―――何をする!?」
起き上がって抗議の声を出すシュバルツを、ハヤブサが睨み返した。眼からたくさんの涙を落としながら―――。
「すまん…。殴るつもりはなかったんだが……手が滑った!」
「…え? …え……?」
茫然とするシュバルツを見ながら、ハヤブサは「くそっ!」と、涙を拭う。それでも溢れてくる涙をぼろぼろと零しながら、ハヤブサは口を開いた。
「悪いが……『全部』聞かせてもらった!」
「――――!?」
「そう……『全部』だ! 意味は分かるな?」
「…………!」
シュバルツは驚いた様にハヤブサを見、そしてキョウジを見た。シュバルツと視線が合ったキョウジが、申し訳なさそうに身を引いている。
「だが…正直、良く分からない所もあった! 細胞の三大理論がどうとか、特性がどうとか言われても―――難しい理論は、俺にはさっぱりだ!」
唖然とするシュバルツを見ながら、ハヤブサはにやりと笑う。
「―――頭悪いからな! 俺は!」
(ハヤブサ……?)
『全部』聞いたハヤブサが、どうして涙を落としながら怒鳴らねばならないのか。さっぱり話の流れが見えてこないシュバルツは、ただ茫然とするばかりだ。
「だが! 俺は一つだけ! お前に文句を言う事があるぞ!?」
「文句?」
そう言って不思議そうに見つめ返してくるシュバルツを、ハヤブサは思いっきり睨みつける。
「………お前、『不死』なんだって?」
「――――!」
そう言うハヤブサの目が、完全に据わっている。シュバルツは伏し目がちに頷いた。
「あ……ああ。私は―――」
そんなシュバルツに向かってハヤブサは思いっきり怒鳴りつけた。
「こぉの馬鹿野郎!!」
ハヤブサのあまりの大声に、シュバルツとキョウジの耳が同時に『き――ん』となってしまう。
「ハ、ハヤブサ?」
びっくりして耳を抑えるシュバルツに、ハヤブサは更にたたみかけてきた。
「何故、そういう大事な事を早く言わない!?」
「!?」
もう少し別の言葉で『不死』な事を責められると思っていたシュバルツが、びっくりして顔を上げる。
「お前が『不死』だと知っていたら、こちらもそのつもりで動くし! 戦い方も変わってくると言うのに―――!!」
「え…? いや、でも………」
戸惑っているシュバルツに、ハヤブサは憮然とした表情を向ける。
「だいたい、『忍者』で『不死』なんて、稀にだがある話だ! 江戸時代辺りには、嘘か本当か知らないが、そういう忍者もいたらしいし―――」
そう言いながら、ハヤブサは腕を組んでため息をついている。
「……ハヤブサ……」
だが、シュバルツに声をかけられると、再びジロリ、と彼を睨み据えた。。
「それに、お前みたいな危なっかしい奴は、『不死』ぐらいでちょうどいいんだ! 本当にお前は、命がいくつあっても足りない様な事ばかりしやがって! 俺がどれだけ心配したと思っているんだ!?」
「…………!」
ハヤブサの「『不死』ぐらいでちょうどいい」と言う言葉に、キョウジがピクリと反応する。それに対してシュバルツは、ハヤブサの剣幕にかなり引き気味になっていた。ハヤブサが本当に自分の事を心配してくれていた事が分かっているだけに、もう苦笑するしかない。
「いや、すぐに秘密を話さなかったのは、悪かったよ…。で、でもな? 一応言わせてもらうと、ほら…最初の内は敵か味方かはっきりしなかったし……」
多少こちらにも言い分があるので、そろっと主張してみる。しかし、ハヤブサの方は既に聞いてなどいない感じだった。
「あああ、思い出したらだんだん腹が立ってきた! お前が残月に囚われた時に、俺がどれだけお前の命や魂の心配をしたと―――!」
「いや、そもそも最初に私を捕えて縛ったのはお前で―――」
「それだって、お前が『こっちが攻撃する』と言っていると言うのに、避けもしなかったせいだろうが! 本当に……本当にお前と言う奴は―――!!」
ここに来てついに、ハヤブサの中でぶちっと音を立てて何かが切れた。
「返せっ!! お前の事を心配して縮んだ10日分ぐらいの寿命を、今すぐのしをつけて返せ―――っ!!」
そう言いながらハヤブサは、何故か右手の籠手を外しながらシュバルツに殴りかかっていく。
「ま、待て…! 私は傷が治ったばかりで―――!」
「待てるか!! 大人しく殴られろ!!」
「話の流れが分からなくて、自分も納得できていないのに喧嘩なんか買えるか!!」
「ええい! ちょろちょろと…! 待てと言うのに!!」
あっという間に、キョウジの部屋を、忍者二人が所狭しと駆けずり回る状態になってしまう。
「キョウジ! 一体どういう事だ!? 私が納得できるように説明しろ!!」
シュバルツが、ハヤブサの攻撃をかわしながら、キョウジに説明を求めてくる。
「さ、さあ……。私にもよく―――」
わからない、と、言おうとしたキョウジが、いきなり誰かにガバッと抱きすくめられた。「!?」
驚いたキョウジのすぐそばで、赤いマントが震えている。
「ううっ! 兄さん……ッ! 兄さん――――!」
「ド、ドモン!?」
「兄さん……!」
そう言ってキョウジを見つめるドモンは、ただ滂沱していた。その様子から、キョウジは察してしまう。
「お、お前……! まさか、私たちの話を聞いて……?」
キョウジの言葉に、ドモンは涙を落としながら頷く。
「……知らなくても良かったのに…。私の『罪』の話など……」
茫然と、呟くように言うキョウジに、ドモンは頭を振った。
「ううん。俺は、知って良かったよ」
「ドモン……!」
「知って良かった……。兄さん―――!」
そう言いながらドモンは、再びキョウジに抱きついていた。
「……しょうがない奴だな、お前は……」
キョウジは優しくドモンを抱き返す。弟は、ひたすら泣き続けていた。
「いいんだ……。俺、今は『泣く』って決めてる……ッ」
「ドモン……」
「誰にどう思われようと……俺は泣くんだ! 泣くしかないんだ―――!」
あの極限の状況の元、ただただ、自分の事だけを想ってくれた兄。
『兄らしい事を、何一つしてやる事が出来なかった』と、この人は言っていたが、そんな事はなかった。この人の優しさを、自分はたくさん浴び続けていたはずだった。
それを信じる事が出来なかった、己の不明を恥じねばならないのだ。
兄を、闇の中に閉じ込めたまま、その命を奪う事にならなくて、本当に良かったと、心から思う。
とにかく自分の中で、兄への想いが複雑に入り乱れすぎて、もう泣くしかない、と、ドモンは思っている。泣いて吐き出して―――すっきりさせねばならないのだ。
「兄さん―――! ううっ! 兄さん―――!!」
そう言ってえぐえぐと泣き続ける弟に、キョウジは苦笑するしかない。でも、『泣く』と決めて、素直に泣く事が出来る弟は、潔い―――と、思った。
その一方で、忍者同士の追いかけっこは、まだ続いていた。とにかくハヤブサは、シュバルツが何を聞いても何を言っても「殴らせろ!」の一点張りで、会話が成立しそうにない。話の見えないシュバルツは、いささか辟易気味になる。それが、彼の集中力を鈍らせることにつながってしまった。
「うわっと……!」
足元に転がっていたペンに気づかず踏んづけてしまい、少しバランスを崩してしまう。そして当然その隙を見逃すハヤブサでは無かった。
「隙あり!」
「!!」
ハヤブサに飛びかかられて、シュバルツはバランスを失ってしまった。そのまま床に倒れ込んでしまう。慌てて起き上がろうとするシュバルツを、ハヤブサは上からのしかかって手足を押さえこんでその動きを封じた。
「さぁて……どうしてくれようか―――」
上からシュバルツを覗き込むハヤブサの面に、凶悪な笑みが浮かぶ。対するシュバルツの方には、ひきつった笑みが浮かんでいた。
(しょうがない……一発ぐらいは殴られた方がいいんだろうか…? いろいろ隠していたのは事実だし……)
ただ、殴る力を手加減してくれそうにないハヤブサの様相に、「殴られてもいいか」と、思ってしまった事を後悔しそうになる。恐らくどういうふうに喰らっても『痛い』だけでは済まないだろう。
ふと、ハヤブサの右手が動いた。
「――――!」
(殴られる―――!)
シュバルツは襲い来る衝撃を予想して、身体を固くした。
だが。
シュバルツに降ってきたのはハヤブサの拳ではなく、『言葉』だった。
「――――――」
その言葉に驚いたシュバルツが、思わずハヤブサの方に振り向く。シュバルツと視線が合ったハヤブサが、頷いた。そしてまた、シュバルツの耳元に、『言葉』を紡ぐ。
「……………!」
その言葉を聞いたシュバルツが、ただ茫然とハヤブサから視線を逸らす。それを見たハヤブサが、何を思ったのか、今度はシュバルツの耳元に『フッ』と、息を吹きかけた。
「うあっ!?」
完全に不意を突かれたシュバルツの身体が、ビクン、と撥ねる。
その様子が妙に艶めかしかったので、ハヤブサは思わずクラリ、と、来てしまう。
「……お前、感度がいいな」
「へっ!?」
それと同時に、シュバルツを抑えつけているハヤブサの手に、ぐっと力が入る。
「お、おいっ! ちょっと……!」
「シュバルツ―――」
「………!」
熱を含んだ声で名前を呼ばれ、シュバルツの背中に寒気を含んだ何かが走り抜ける。
「ハヤブサ!? 何をする気だ! 放せ!!」
このままでは何かがまずい、と思ったシュバルツが、ハヤブサから逃れようと足掻く。だが、自分を抑えつけているハヤブサの手足は、残念ながらびくともしない。
「いいじゃないか。減るもんじゃなし」
そう言いながらハヤブサの顔が近づいてくる。
「減る減らないの問題じゃないだろう!! おいっ! ちょっと待―――!!」
「……貴様ら、何をやっておるか。人のアジトで―――」
不意に、上から声が降って来て、ハヤブサの動きが止まった。二人がそちらの方を見上げると、東方不敗が腕組みをしてじと~っとこちらを見下ろしている。それを見たハヤブサが、小さな息を一つ吐きながらシュバルツから身体を離す。シュバルツも助かった、と、息を吐いた。
「別に。ちょっと話をしていただけだ」
ハヤブサは憮然とした表情でそう言いながら、周りに聞こえるほどの盛大な音で「チッ!」と舌打ちをする。
「おいっ! その舌うちは何だ!!」
シュバルツの突っ込みに、ハヤブサは振り返る。
「別に―――」
それだけ言うと、すたすたと歩いて行ってしまった。シュバルツは、開いた口が塞がらなくなるのを感じた。
(何を考えているんだあいつは…! さっぱり分からん……)
シュバルツが頭痛を感じて頭を抱えている横で、東方不敗が先に部屋に走り込んで行った弟子の方に声をかけていた。
「ドモンも―――いつまで泣いておる! 今は未だ戦いの最中じゃ! 敵は待ってはくれんぞ!」
師匠の言葉に、ドモンも「分かってますよ!」と、涙を拭いながら答える。キョウジの方に、「えへへ」と笑いかけてから、ドモンは立ち上がった。
キョウジもまた、立ち上がってシュバルツの姿を探した。彼はキョウジから少し離れた所で、頭を押さえながら佇んでいる。キョウジは、床に落ちている革のロングコートを拾うと、シュバルツの方に歩み寄った。
「シュバルツ……」
シュバルツが、キョウジの呼び掛けに気づいて振り向く。
「キョウジ……」
キョウジは、目元に涙の跡が刻み込まれてはいるが、表情は穏やかそのものであった。
「お前……大丈夫か? その…あの事件の話を、人にしたりして……」
シュバルツの問いかけに、キョウジはにっこりと微笑む。
「大丈夫、だよ。寧ろ、話してすっきりした……。やっぱり、ハヤブサは優しい人だ」
「はぁ…。まあ、そうなんだろうけどな…」
キョウジの言葉に、シュバルツは複雑な表情を見せる。優しい……優しいには、違い無いんだろうが……それにしても、さっきのハヤブサは―――訳が分からん、と、シュバルツはため息をつく。
シュバルツの表情が曇ったのを見て、キョウジの表情もまた曇っていった。
「ご、ごめん……。勝手に秘密を話したりして……。やっぱり、許可を―――」
「いや、いいよ。お前がすっきりしたのなら―――それでいい」
シュバルツは苦笑しながらそう言って、キョウジに手を差し出した。革のロングコートを、キョウジから受け取るつもりだった。だがキョウジは、コートをシュバルツの肩に羽織らせると、右手をシュバルツの左肩に置いて、シュバルツの真横に立った。
「キョウジ……?」
少し、抱きつかれているような格好になる事に、シュバルツは戸惑った。キョウジの顔を見ようとしたが、真横に立たれているせいで、キョウジの表情が良く見えない。
「ごめん、シュバルツ…。少しの間、このまま聞いてくれるか…?」
「ああ……構わないが……?」
頷いたシュバルツに、「ありがとう」と、小さく礼を言ってから、キョウジは話し出した。
「私がハヤブサに『あの事件』の話をしたのは、『DG細胞』について話をする必要があったからだ……」
「――――!」
シュバルツがピクリ、と反応する。キョウジは言葉を続けた。
「シュバルツ、どうか、自分を責めないで聞いて。今度の敵は―――」
ここまで言ったキョウジが、次の言葉を一瞬ためらう。何故なら、次の言葉がシュバルツにとって辛いものになる、と言う事が分かっているからだ。それでも、言わねばならない。それが『現実』なのだからと、キョウジは意を決した。
「……今度敵は、おそらく『DG細胞』を使ってくる……」
「な―――!」
「あの仮面の男は……おそらくDG細胞に強く働きかける事が出来る能力を持っている。そいつが細胞を手に入れてしまったから……」
「…………!」
シュバルツは息を飲んだ。そして気付いてしまう。どうやってあの仮面の男がDG細胞を入手する事が出来たのかを。
(……私が、あの男に『攻撃』されたからか……!)
あの男の武器である爪には、攻撃を受け、抉りとられた自分の身体の一部が付着している。そして、自分の身体が『何』で構成されているのか―――考えるまでも無く、原因はおのずと明らかだ。
「……私の、せい―――」
「違う!! 私が『ミス』をしたせいだ!!」
シュバルツの言葉を遮るかのように、キョウジは大声を出した。
「お前のせいじゃない……! ……お前は何も悪くなんか、無いんだ……!」
そう言いながら、キョウジはシュバルツの肩に置いている手に、ぐっと力を入れる。
「キョウジ……」
シュバルツは、キョウジの手の力を肩に感じながら、ハヤブサとのやり取りを思い出していた。
―――シュバルツ、お前はキョウジに望まれているんだ。『生きろ』と……。
まさか、とハヤブサに目で問うと、彼は頷いた。そして、右手を見せながら彼はまた言葉を紡いできた。ハヤブサの右手には鞭で叩かれたような赤い線が一筋走り、それが蚯蚓腫れの様になっていた。あの時の背中の傷に触れて出来たものだと、ハヤブサは言った。
―――本当だ。現にキョウジの手は傷だらけになっている。あれは、お前を治すためにそうなったものだ。あの手の傷が、キョウジのお前への『想い』の証だ…。
(信じていいのだろうか…。ハヤブサの言葉を…)
信じてもいいのだろうか。
自分の存在は、キョウジを傷つけているだけでは無いのだ、と言う事を。
「……………」
シュバルツは、そっと、自分の肩に置かれているキョウジの手に触れる。
「………!」
キョウジは、一瞬小さく声を上げたが、肩から手をどける事はなかった。シュバルツはそのまま、手袋の下にあるキョウジの手に巻かれた包帯の感触を確かめる。それは、手の甲から指先に至るまで、余すところなく巻かれているのが分かった。
(キョウジ……)
キョウジの手を、上からそっと包み込む。そして考える。今のキョウジが望んでいる事を―――。
キョウジは、私に『自分を責めるな』と言った。
ならば、自分を責めてはいけない。
そして、今の私が、キョウジに言うべき言葉は、一つだけだ。
「分かった……」
シュバルツのこの言葉を聞いたキョウジは、安心したように、手の力を緩めた。
「ありがとう……」
キョウジはそう言いながら、シュバルツの肩から手を離した。シュバルツが、自分を責めずにただ頷いてくれた事が、キョウジには嬉しかった。
そのままキョウジは振り返らずに、東方不敗の方に足を進める。戦うための準備が整った合図だ。それを察した東方不敗が、キョウジに声をかける。
「キョウジよ。もう良いのか?」
「はい。お待たせしました」
そう言って東方不敗をまっすぐ見つめるキョウジの眼差しには、恐れも迷いも無い。
(やはり、見事な『若武者』よ……)
東方不敗は改めて思う。自身はデビルガンダムに取り込まれながも、見事に弟を助け切るという離れ業を、この男はやってのけているのだ。そして、身近な人間に裏切られると言う経験もしていると言うのに、まだ人を信じる心を持ち続ける事が出来る。この懐の広さ―――心の強さは、称賛に値するものだ。
あの事件の際、キョウジがもしあのまま死んでいたら、自分はキョウジについて本当に何も知らないまま、その人生を終えることになっていただろう。それはとてつもなく恐ろしく、そして勿体ない事だと東方不敗は思った。
「―――皆の者! やる事は分かっておろうな!?」
東方不敗の言葉に皆が頷く。
「分かってる! 化け物の居る建物に、奇襲をかけるんだろ?」と、ドモン。
「俺は、いつでもいいぞ」と、ハヤブサ。
「同じく」と、シュバルツ。
皆の言葉にキョウジは微笑んだ。
「じゃあ、作戦会議に移りましょうか」
その意見に、皆異存はなかった。
「化け物の居る建物は、おそらくここ―――」
部屋の中で、キョウジが地図を広げている。指を刺した場所は、某大国にある、エヌルタ・ミニッションズ・カンパニー所有の軍需施設だ。
「シュバルツが入手して来てくれた見取り図から推測すると、化け物はこの区画に居るはず…。だから、私が狙うシステムの中枢も、おそらくこの近くにあるだろう」
「うむ」
「なので、戦力を二つに分けて挑みたい。システムにアタックをかける部隊と、撹乱目的で正面から斬り込む、囮部隊とにだ」
「面白そうだな」
どうやら、本気で暴れても差し支えが無さそうな展開に、ドモンが嬉しそうな声を出す。
「もちろん、この施設だけに戦力が集中する事態を避けるために、シャッフル同盟の皆にも、世界各地にあるこの会社の拠点や施設に奇襲をかけてもらうが……ドモン、シャッフルの皆とは、連絡が取れているよな?」
キョウジの言葉に、ドモンは胸を張った。
「ああ。こちらが合図を送り次第、皆一斉に動いてくれる手筈になっている。任せてくれ」
ドモンの言葉に、キョウジは微笑んだ。
「じゃあ次に、部隊の編成だが―――」
そう言いながら、キョウジはシュバルツの顔を見た。
「………………」
ここで何故か、キョウジがシュバルツの顔を見たまま沈黙してしまう。
「……? どうした? キョウジ」
キョウジの視線を感じたシュバルツが、図面から顔を上げる。
「あ……ああ、ごめん―――」
キョウジはそう言いながら、面に笑みを浮かべた。
「シュバルツ……また、囮の方を頼んでもいいか?」
「ああ。任せておけ」
当然だと言わんばかりに頷くシュバルツ。
「兄さん! 俺も、囮の方に回っていい? そっちの方が面白そうだ!」
「そうだな、ドモン。じゃあ、お願いしようか」
キョウジにそう言われて、ドモンは嬉しそうに微笑んだ。
「ワシは、今回はキョウジと共に動くぞ」
東方不敗はそう言ってから「良いな、シュバルツ」と、シュバルツの方に視線を走らせた。
「―――!」
シュバルツは気付く。東方不敗の視線の意味を。
(もしまたお主に何かがあってキョウジが身動きできなくなった場合、ワシは遠慮なくお主を見捨ててキョウジを逃がす算段をするぞ―――)
東方不敗はそう言っているのだ。シュバルツは、それでいいと思った。
「ああ。私に異存はない」
シュバルツの言葉に、東方不敗はフン、と鼻を鳴らす。
「じゃあ、俺もキョウジと共に行動した方がいいな。戦力バランス的に―――」
ハヤブサの言葉に、皆が頷いた。
「それでは皆さん、作戦決行に当たって準備を進めてください。明日にはここを出発します。もう時間はかけられないですから―――」
こうして、作戦会議の場は終了した。
「兄さん! 組み手とロードワークにつきあってよ!」
ドモンが嬉しそうにシュバルツの腕を引っ張りながらそう言っている。ドモンは、シュバルツと―――『兄』と共に同じ戦線に立てる事が、嬉しくて仕方がないようだ。
「分かったよ。……ったく、しょうがない奴だな。お前は」
シュバルツは苦笑しながらドモンについて行った。
そんなシュバルツの後ろ姿を見ながら、ハヤブサもドモン達とは別方向からアジトの外に出た。自分の気持ちを、整理するためだ。
ハヤブサが、キョウジについて行く事を選択した理由はいろいろある。戦力バランスを考えて―――という意味合いが一番大きいが、それ以外にも。
万が一、キョウジが化け物に取り込まれそうになった場合―――それを斬るためだ。
勾玉を消滅させる事が出来るのならば、それが一番いいのだが、まだ封印しなければならない可能性も捨て切れていない。この作戦における最終手段的役割が、自分にはあるのだと、強く言い聞かせていた。
ただ―――覚悟が必要だ。
それをするのであるならば、キョウジとシュバルツ、二人分の命を、斬る覚悟が―――。
ハヤブサは、シャッと音を立てて鞘から龍剣を抜き放つ。刀身が、月明かりを反射して、青白い光を放った。
(迷うな)
ハヤブサは、強く己に命じる。
例えこの刀が、キョウジの血を吸う事になったとしても。
その瞬間が来たら、自分は迷ってはならないのだ。僅かな遅れが、取り返しのつかない事態を招いてしまうものだから。
「………………」
こんな夜は、いつも持ち慣れている龍剣に、少し重さを感じる。何故なのだろう。
(シュバルツ……あいつ、黙って死ぬつもりだったんだな……)
自分が『キョウジを斬る』と、言っていた時に、死の気配を漂わせながら、微笑んでいたシュバルツ。今ならよく分かる。生死の選択権が無いが故に、「生きる」とも言えず、かと言って、俺の使命の邪魔をすることも本意ではなかった。だから、総てを受け入れて―――笑って死ぬつもりだったのだ。
(キョウジが死ねば、自分も死ぬ―――もしかしたらあいつは、一番この事実を、俺に伏せたかったのかもしれないな…)
ハヤブサは、ふとそう思った。シュバルツはハヤブサに、余計な負担をかけると思ったのだろう。
「―――全く、あいつはどこまでお人よしなんだか……」
ハヤブサはそう独りごちながらため息をつく。
(安心しろ、シュバルツ…。もし、『その時』が来ても俺は迷わない。ちゃんと、お前の分の命も感じながら、キョウジを斬ってやる)
もっとも、そのような事態にならない事を祈りたい。だが、最悪の事態も想定しておかないと、咄嗟の時に身体が動かない。厄介な癖だとも思うが、自分が『忍者』で『人斬り』である以上、この癖は、きっと一生治らないのだろう。
降る様な星空の元、心地よいギアナ高地の夜風を肌に感じながら、ハヤブサは独り、佇んでいた。
「キョウジよ……」
部屋にキョウジと二人きりになったのを見計らってから、東方不敗はキョウジに声をかけた。
「はい?」
穏やかな顔をした、キョウジが振り向く。
「お主、正気か?」
「…………!」
キョウジの眉が、ピクリ、と動いた。
「……何の事です?」
「シュバルツの事だ」
「――――!」
「何故、今回の作戦に奴を連れていく?」
「…………」
「ワシは、てっきり置いて行くものと思った」
「……何故です?」
キョウジの問いに、東方不敗は腕組みをしながら答える。
「シュバルツを連れて行くリスクに、気づかぬお前ではあるまい?」
「―――嫌だなぁ、気づいちゃったんですか? 皆に不安を与えないようにと思って、黙っていたのに」
そう言いながら、キョウジはふっと相好を崩したような笑顔になる。その笑顔故に、東方不敗は危うく気圧されそうになった。
「…あまり、年長者を舐めるな―――」
内心の動揺を悟られないように、東方不敗は努めて冷静に言葉を紡いだ。
「あの仮面の男の能力がシュバルツのDG細胞に強烈に作用する事を考えれば、再びあ奴らを相対させる事は危険すぎる、とすぐに分かる。まっとうな指揮官であれば、奴をこの作戦からは外すであろうな」
そう言いながら、東方不敗はキョウジを見据える。だが、キョウジの穏やかな表情は変わらなかった。
「……そうですね。『まっとうな指揮官』ならば、まずリスクを減らす事を考えるのでしょうね。あの仮面の男がいる所に、DG細胞の塊であるシュバルツを連れて行くなんて――――正気の沙汰じゃない」
「――――!」
自らの事をそう評するキョウジに、東方不敗は思わず絶句する。
「それに、あの仮面の男は龍の勾玉の波動を感じる取る事が出来る。故に、いくら外見が瓜二つであっても、あの男には私とシュバルツの見分けが正確につく。おそらくあの男には『囮』という概念は通用しないでしょうね。せいぜい、一般の兵達の目をごまかせるぐらいだ」
キョウジの話を聞きながら、東方不敗は己が顔が引きつってくるのを感じる。
「そ、そこまで分かっておるのなら……何故シュバルツを―――」
外さないのか。東方不敗は思わずそうキョウジに問いかけていた。
「そう……シュバルツは、『囮』というよりは……」
そう言いながらキョウジは、東方不敗から視線を外す。
「『餌』―――です」
「―――!?」
『餌』と言う、ある種物騒な響きを持った言葉に、東方不敗は思わず身を引きそうになる。
「私とシュバルツの見分けがつくが故に、あの仮面の男にとってシュバルツは、抗いがたい―――強烈な甘い匂いを放つ『餌』になります」
「な……何故……」
東方不敗は知らず、汗をかいていた。
「何故、シュバルツがあの男にとって『餌』となる事が分かる?」
東方不敗の問いに、キョウジはにっこりと笑って答える。
「あの仮面の男が、DG細胞の特性とシュバルツの正体に気づかない―――という楽観を、私はしないですから」
「…………!」
「DG細胞の特性を知り、手に入れたいと思っている所に、その塊であるシュバルツが、目の前に現れる……」
東方不敗は、懸命に平静を装おうと努力をするが、背中に冷たいものが流れ落ちるのを、止める事が出来ない。
「どうです? 充分『餌』になり得るでしょう?」
「ううむ……」
東方不敗は思わず唸った。確かにシュバルツは、充分『餌』となり得る。それどころか、あの仮面の男の狙う『大本命』にすら、なりかねない。
「ですから、これは『賭け』です」
「賭け?」
問い直す東方不敗に、キョウジは笑みを向ける。
「あの仮面の男が狙うのは―――果たしてどちらか」
「――――!」
「私を狙うのか……それとも、シュバルツを狙うのか……『龍の勾玉』か、『DG細胞』か―――と言う、ね……」
(こ、こ奴―――!)
東方不敗は己の身体にブルッ、と震えが来るのを感じる。それは、恐怖ゆえの物ではない。いわゆる武者震いと言う奴だ。この男は、何という挑戦的な作戦を思いつくのか。
「シュバルツを狙ってくるのであれば、それだけ私の方の作業は楽に進むことになりますし―――」
ここでキョウジは、少し苦笑した。
「私の方を狙ってくるのであれば、ドモンが施設をめちゃくちゃに破壊して行くでしょうね。シュバルツも多分、積極的にはそれを止めないでしょうから」
「フフフ。確かにのう」
キョウジの言葉に東方不敗もにやりと笑う。愛弟子の戦い方は、良くも悪くも直線的で、破壊力も凄まじい。まして、兄を狙っている敵の本拠地に殴り込みをかけるのだ。「破壊するな」と言っても、彼は決して聞かないだろう。
「それに―――シュバルツをこの作戦からはずして置いて行こうとしても、多分無理です」
「無理?」
問い直す東方不敗に、キョウジは肩をすくめる。
「縄抜けしちゃうし、壁抜けしちゃうし―――姿消せちゃいますしね」
「ム………」
おそらくありとあらゆる手段を用いて、彼はついてきてしまいます、と言うキョウジの言葉に、東方不敗は返す言葉を失う。自身も先ほど、シュバルツの壁抜けの術を目の前で見たばかりだ。
「それに…もしもシュバルツが仮面の男に狙われる可能性があるのなら、独りにしておく方が却って危険だ。それなら尚更、皆で行動した方がいい」
「確かに……」
東方不敗は顎に手を当てて頷いた。シュバルツを眼の届く所に置いておく方が、それこそ何かあった時でも、皆でフォローし合えると言う物だ。そう考えると、今提示されているキョウジの策が、まさにベストなのだと思えてくる。
「キョウジよ。お主はやはり、いっぱしの『軍師』じゃのう」
東方不敗は素直に賛辞を口にする。それに対してキョウジは頭を振った。
「違います。単に私が、『シュバルツに頼らない』と言う選択肢を、選べないだけです……」
そう―――この局面で、シュバルツを頼らない方が、おそらく彼にとっては残酷なのだ。今頼らなかったら、はっきりと傷つけてしまうと分かる。恐らく、あの病院の時以上に。
再びあの仮面の男と相対する事によって、もしかしたらあの怪我よりも、シュバルツをもっとひどい目に遭わせてしまうかもしれないのに。
そのリスクに、皆を巻き込んでしまうかもしれないのに―――。
それでも『シュバルツを傷つけたくない』と言う気持ちを優先してしまう自分は―――とても我が儘な人間なのかもしれない。
「キョウジよ……」
東方不敗は腕組みをしながらキョウジに問うた。
「お主は……シュバルツの事を『信じて』おるのか? あの仮面の男と対峙する事によって生じるリスクを、奴ならば乗り越えられると――――」
「………………」
その問いに、キョウジはすぐには答えなかった。眼を閉じて、何か思考をしているように見えた。
「『信じている』とは、少し違います…」
ここまで言ったキョウジは、東方不敗に苦笑した笑顔を見せた。
「私は多分、『利用している』んです。シュバルツの事を―――彼の戦闘力も…。彼が、DG細胞で出来ている事すらも……」
そう。自分は計算しているだけだ。
冷徹に計算して、将棋の駒のように彼を利用しているにすぎない。
『彼なら何でも乗り越えられる』などという、無責任な責任の押しつけなど出来ない。
「…………!」
「だからきっと、あの男と対峙しても、すぐにはやられない。ある程度までなら、持ちこたえてくれるはず…」
ドモンの破壊力。そして、それをフォローするシュバルツの力。そのコンビネーションを生かす事が出来れば、あの仮面の男といえども、そう簡単にシュバルツには手出しできないだろう。そして、そうやってシュバルツが注意を引きつけてくれる時間が長ければ長い程、こちらには有利になっていく。
問題は、シュバルツが敵を引き付けてくれている間に、こちらのシステムの掌握が間に合うかどうかだ。それさえ間に合えば―――あの化け物の脅威が無くなれば、この戦いにおけるリスクを、かなり減らす事が出来る。
「…………」
「もっとも、あの仮面の男の能力を完全に把握しているわけでは無いので、正確な事は言えませんが」
キョウジがそう言った所で、東方不敗が「フ……」と笑った。
「……安心した。『盲信』しておるわけではないのだな。やはり、智将はそうでなくてはならん」
「――――!」
「お主が、リスクも何もかも把握したうえで、覚悟を決めてこの戦いに臨むと言うのならば……ワシも安心して、力を貸せると言うものよ」
「マスター……」
呆然とこちらを見るキョウジに、東方不敗は笑みを向けた。彼は少しシュバルツの事を羨ましいと思った。キョウジが計算したうえで『利用する』と言い切ると言う事は、それだけ彼がシュバルツの価値を認めていると言う事に他ならない。
(それにしても……これだけの『計算』が出来ると言うのに、この男は……)
ぎりぎりの所で、甘さが出る。シュバルツに限らず、誰かが危機に陥った時、彼はそれを決して見捨てる事が出来ないのだろう。そう言う所が恐ろしく甘すぎる―――そう感じて、東方不敗は苦笑した。
だが、キョウジはそのままいいと思った。
彼が『鬼』になりきれない所は、自分が『鬼』になれば良いだけの話だ。
そしてそれこそが―――自分がキョウジのために出来る『役割』なのだろう。
「明日も早いのであろう? 今日はもう休め」
そう言って踵を返し、東方不敗は部屋を出ようとする。後ろから、キョウジの声が追いかけてきた。
「あ、あの! マスター!」
「うん?」
振り返る東方不敗に、キョウジは少し戸惑ったような表情を見せた。
「あの……ありがとうございます。本当に、その……いろいろと―――」
愛弟子の兄―――と言うだけでは説明できないほど、この人は自分に力を貸してくれている。そう感じたが故の言葉であった。今だってそうだ。この人に話を聞いてもらえたおかげで、自分はかなり落ち着く事が出来た。
本当に不思議だった。どうしてこの人には、自分が揺れ動いている事が簡単に伝わってしまうのだろう。
そんなキョウジに対して、東方不敗はピクリと眉を吊り上げる。
「礼を言うのはまだ早い。作戦が無事に終わってからにしてもらわんとな」
「あ………」
慌てて口を押さえるキョウジに、東方不敗は苦笑する。
「ゆっくり休めよ」
そう言い置いて、東方不敗は部屋を出て行った。キョウジは、そんな彼の後ろ姿に、黙って頭を下げていた。
「全滅しただと!? お前までついて行っておきながら、一体どういう事だ!!」
部屋に、シュトワイゼマンの激昂した声が響き渡る。
「また補充すればよろしいでしょう」
仮面の男が悪びれもせずに言葉を返す。その言葉にシュトワイゼマンが苛立ったように舌打ちをした。
「奴らにも、元手がかかっておるのだ! 元手が!!」
全員に最新鋭の装備を用意したのだ。それが全部台無しになったのかと思うと、流石にうんざりする。損失額を考えるだけでも恐ろしい。
「また兵器を売ればよろしいでしょう。需要はいくらでもあるのですから。国家、テロリスト、犯罪組織―――『平和』を望まぬ人間、力を欲する人間など、いくらでもいるものですよ」
「そんな事は分かっておる!」
シュトワイゼマンは忌々しそうに机を叩いた。
必要とされれば、どこにでも『武器』を売ってきた。国家相手にも、それに敵対するテロリストにも―――。火種がくすぶっている所には、さらに煽って争いの火を起こし、そこに武器を売りつけた。こうして自分は、今の財と権力を手に入れたのだ。
平和になってもらっては困る。
争いの火種が―――戦争が、自分の利益の元なのだから。
「それよりもシュトワイゼマン様。面白い物を手に入れました」
「面白い物だと?」
ピクリ、と眉根を寄せるシュトワイゼマンに仮面の魔道師は人を呼んである物を持ってこさせる。シュトワイゼマンの前に、ネズミの入ったケースが用意された。
「何だこれは?」
そう言って訝しげな顔を見せるシュトワイゼマンに、仮面の魔道師は「まあ、見ていてください」と言いながら、シュバルツを攻撃するのに使った鉤爪を取り出す。鉤爪の先端についている物をこすりつけるように魔道師はネズミに傷をつける。それから手をかざして、『念』をそのネズミに送った。
すると。
「キシャァァアァアアァ!!」
ネズミの身体が一気に金属の様に硬質化し、その面構えが凶悪な物になる。魔道師は、そのネズミをもう一つのネズミが複数いるケースの中に放り込んだ。放り込まれたそのネズミは、次々とほかのネズミに襲いかかっていく。
「こ、これは……!?」
呆然とその光景を見守るシュトワイゼマンに、仮面の魔道師が説明を始める。
「標的の近くに居るある男がこれを持っていました。『菌』と言うか、『細胞』の様なものです。これを植え付けられた生物は皆、激しい攻撃衝動を持ち、相手が誰であろうと何であろうと、襲いかかっていくようになるようです」
「何……?」
「そして―――これを、ご覧ください」
そう言いながら仮面の魔道師が差したケースの中で、最初のネズミに襲われたネズミが、同じように凶悪な様相になっていく。そして、同じように他のネズミに襲いかかりだした。
「攻撃されたネズミはどうやらこの『細胞』に感染して―――同じように他者への攻撃衝動を持つようですね。病気がうつるように、この『細胞』は広まっていくようです」
たちまちケースの中のネズミたちは、凄まじい同士討ちを始めた。ケースの中が、あっという間に朱に染まっていく。
「ほう……」
シュトワイゼマンは、感心したようにネズミたちを眺めていた。
「素晴らしいな…。『戦争』を望む我が社にとっては、まさに理想的な『細胞』ではないか。…これを、標的の身近にいた者が持っていると言うのか?」
「持っている……と、言うより、おそらくあれは―――」
仮面の魔道師は、しばらく思考したのち、口を開いた。
「この『細胞』の、『キャリアー』ではないかと」
「何!?」
「この爪は、その者に傷を負わせた時の物です。その時に抉れた肉からこの細胞が抽出されたものですから……」
そう言って仮面の魔道師は仄暗く笑う。シュトワイゼマンは顎に手を当てた。
「……そのような物騒な物が、一般の社会に出て歩き回っているのはまずいな。ぜひ、我が社で保護をし、厳重に管理せねばならんだろう」
「御意にございます」
仮面の魔道師の同意を得た所で、シュトワイゼマンはにやりと笑った。
「よし。手段は任せる。金に糸目もつけずとも良い。この『細胞』を持つ者を捕らえて、厳重に保護をしろ」
「ははっ」
仮面の魔道師は恭しく頭を下げながら、別の事を考えていた。
(この『細胞』にはおそらく、まだまだ秘密がある…。キョウジと同じ顔をしたあの男……あの男が、このような凶暴性を帯びていなかった事が、少し気になるが……)
だがもしかしたら、使いように依れば最初に作ったあの『女神』よりも、はるかに凶悪な『武器』となり得るかも知れない。そう感じて、仮面の下に知らず笑みが浮かぶ。
(何はともあれ、今度はあの『細胞』の持ち主を我が手に収める事を優先するべきだな…)
爪の先で、どす黒い輝きを放ちながらバチバチッと音を立てている細胞の群れを、仮面の魔道師は陶酔するように眺めていた。しかも、あの標的は『キョウジ・カッシュ』と同じ顔をしている。それだけで、存分にいたぶりがいがありそうだ。
(さあ、挑んでくるがいい。キョウジ・カッシュ…。今度こそ、返り討ちにしてくれるわ…!)
勝つのは魔道師達か。
それとも、キョウジ達か―――。
決戦へと続く運命の夜が、今、明けようとしていた。
「第8章」
それは何の前触れも無く、突然襲って来た。
「シュトワイゼマン様! 大変です!!」
警報音と部下の悲鳴のような声に、早朝の惰眠を貪っていたシュトワイゼマンは叩き起こされた。
「……何事だ! こんな朝早くから……!」
「アメリカの施設が、何者かによって襲撃されました!!」
「何ぃ!?」
シュトワイゼマンは、いきなり覚醒を余儀なくされてしまった。
彼が執務室に着く頃には、状況がさらに悪化していた。部下たちがあわただしく走り回り、書類が散乱し、怒号が飛び交っている。情報が錯綜しているのが見て取れた。
「中国の地下施設が襲われただと!?」
「ロシアの状況はどうなっている!?」
「EUで次々と工場が襲われている!? 確かな情報なのだろうな!!」
切れ切れに飛び込んでくる言葉は、どれも不吉な物ばかりだ。
「魔道師よ!!」
イラついている事も隠さずに、シュトワイゼマンはイスに座る。そこに仮面の魔道師が静かに近寄ってきた。
「これは一体どういう事だ!? 何が起こっているのだ!!」
「……御覧の通り、『同時多発テロ』ですよ」
魔道師が冷静な声音で、とんでもない事を言ってくる。
「な…………!」
シュトワイゼマンは、思わず絶句した。
「おそらく、キョウジ・カッシュが仕組んだものと思われますが……」
魔道師も冷静を装ってはいるが、内心はらわたは煮えくりかえっていた。ギアナ高地で戦った時に確認出来た相手は5人。いかにキョウジ・カッシュが切れ者だとは言え、たかだか5人の人間だ。仕掛けにも、動ける範囲にも、限界があるだろうと魔道師はタカをくくっていた。
それがどうしたことだ。この世界規模で同時に起こっている異変は。まるで世界中に、彼の味方となり得る者の存在がある、とでも言うのだろうか。
「何故だ!? 何故奴らは、我が社の施設や工場の位置が、正確に分かっている!?」
横でそう言いながらシュトワイゼマンが机を叩いている。実際、『軍需工場』『軍需施設』とは、一見して分からないように、かなりカモフラージュが施してあると言うのに、襲われた施設も工場も、見事なまでに自身の会社の物だった。
「……内通者でも居るのでは?」
「…………!」
仮面の魔道師のとんでもない言葉に、シュトワイゼマンだけでなく、執務室近くで働いていた部下達の顔色まで変わる。
「内通者がいるのなら、それこそ徹底的にあぶり出さねばならないが、今はそれよりも、被害状況の把握とその対策に―――」
シュトワイゼマンの言葉が終わらないうちに、また一人、部下が執務室に飛び込んでくる。
「た、大変です!! 報告いたします!!」
「何だ!?」
シュトワイゼマン以下執務室に居る全員の殺気だった視線を浴びた部下は、一瞬怯む。しかし、気を取り直して叫んだ。自分が報告しなければならない事は、充分重大事案に当たる自信があったからだ。
「キョ、キョウジ・カッシュが―――キョウジ・カッシュが現れました!!」
「何っ!? どこにだ!?」
身を乗り出して問いかけるシュトワイゼマンに、部下は生唾を飲みながら答えた。
「こっ、この施設の―――正門付近です!!」
「何ぃ!?」
部下の一人が、慌てて正門付近に仕掛けている防犯カメラの映像を確認する。
すると、そこには飴細工のようにグニャリ、と捻じ曲げられて哀れに壊されている門扉が映る。その近くに赤いマントを翻している男と、緑のジャケットを着ている男が佇んでいるのを捉えた。
「お前ら……うちの兄さんに用事があるんだってな……!」
そう言いながら、赤いマントを翻しているドモン・カッシュがバキバキと指を鳴らしている。
「あ…あの男は……!」
仮面の魔道師が、防犯カメラの映像に引き寄せられるように前のめりの姿勢になる。それと同時に、映像の中の赤いマントの男が叫んだ。
「お前らがあまりにも周りをちょろちょろしてうざったいから―――わざわざ直接来てやったぜ!!」
男が叫ぶと同時に、彼の闘気が爆発的に膨れ上がる。ドン!! と言う音と共に、防犯カメラはその役割を終了した。
「…………!」
砂模様を移す画像を茫然と見つめるシュトワイゼマンの横で、仮面の魔道師が叫ぶ。
「シュトワイゼマン様! あの赤いマントの横に居たあの男―――あの男こそが、細胞の『キャリアー』です!!」
「何っ!?」
魔道師の叫び声に、シュトワイゼマンははっと我に返る。
「…あの男は、龍の勾玉を持っている『キョウジ・カッシュ』ではないのか?」
問い直すシュトワイゼマンに、魔道師は答えを返す。
「あの男は、キョウジ・カッシュと同じ顔をしていますが、別の人間です! 奴は、龍の勾玉を持っていません! キョウジ・カッシュは『二人いる』のです!!」
「な―――!」
息を飲むシュトワイゼマンだが、これで忍者部隊と自分の私設部隊―――その両方が「キョウジ・カッシュを見た」と報告して来た謎が解けた。キョウジ・カッシュは最初から『二人いた』のだ。蓋を開けてみれば、実に単純なトリックだ。
「シュトワイゼマン様。まさに奴らこそ、飛んで火に入る夏の虫です。奴を捕えるために、ここに居る『兵』たちを動かす御許可を―――!」
仮面の魔道師の願いに、シュトワイゼマンも頷いた。
「良かろう! 見事奴を捕えて見せよ!」
シュトワイゼマンの許可に魔道師は一礼を返すと、周りに居る部下たちに次々と指示を出した。
「凍結している合成獣部隊、待機している兵士たちに出撃命令を出せ! この近くに居る部隊もすべてこの作戦に投入しろ!」
「り、了解!!」
指示を受けた部下が、さっそく魔道師の命令を伝えようとする。しかし、同時に複数の施設を攻撃され、混乱した情報と指揮系統は、すぐに立ち直るような気配を見せなかった。
(チッ! 先手を打たれた…!)
仮面の魔道師は歯噛みする。ギアナ高地で大規模な戦闘を行ったのは、ついこの間の事だ。それからほとんど間をおかず、よりにもよっていきなりここが急襲されるとは思ってもいなかった。先の戦闘で、こちらの部隊も壊滅的な被害を被ったが、奴らもダメージが無いわけでは無かった。キョウジ・カッシュと同じ顔をした男は、確か大怪我をして―――。
ここまで考えた仮面の魔道師は、はたと思い当たる。
(そう言えば、あの男は私によって致命傷とも言える傷を負ったはずだ…! それなのに―――何故奴は、平気な顔をしてまたあそこに現れた?)
背中の肉を抉りとった傷は深く、奴は動くことすら辛そうだった。普通ならばしばらく動くことすら出来ず、命を落とさずとも、かなりの日数を療養に割かねばならなくなるはずであるのに。
実は動くのも辛いが、はったりであそこに立っているのか。それとも、『本当に傷が完治して』あそこに立っているのか―――。
(やはり…あの細胞には、まだ『秘密』がある……! ぜひとも、解き明かさなければ…!)
仮面の魔道師は、部下から乱暴にマイクを奪い取ると、全館に指令を出した。
「正門付近に居るキョウジ・カッシュを捕えろ! それを成し遂げた者は、報償は思いのままぞ!!」
その声に、施設のあちこちから「ウオオオオッ!」と、怒号が上がった。
(―――来たか……!)
仮面の魔道師がかけた全館放送は、当然シュバルツ達の耳にも入っている。シュバルツは刀を抜刀し、逆手に持って構えた。正門から建物に至るまでの空間は、あっという間に兵やら合成獣やらの群れで埋め尽くされて行く。
「兄さん、人気者だね」
ドモンの軽口に、シュバルツも苦笑しながら答える。
「こんな連中にもてても、嬉しくもなんともないがな」
ドモンも、ファイティングポーズをとった。そんなドモンにシュバルツが声をかける。
「ドモン。やる事は分かっているな?」
「ああ。分かっている」
ドモンはそう言いながら、昨夜のシュバルツとの組み手を思い出していた。
「ドモン。次の戦いは―――敵は、間違いなく『私』を狙ってくるだろう…」
夜のギアナ高地の森の中、ドモンの正面に立ってそう言うシュバルツに、ドモンは一瞬キョトンとしてから、ああ、と、頷いた。
「そうだね。兄さんは、『龍の勾玉』を持っているから……」
「―――!」
ドモンの言葉に、今度はシュバルツの方が瞬間目を丸くする。しかし、すぐに笑顔を作った。
「ああ。そうだな……」
(ドモンは、理解しているようで理解していないんだな。私がDG細胞で出来ている、と言う事と、DG細胞が敵にとられた事で、何が起こるのか―――と言う事を…)
そう感じて苦笑する。しかし、ドモンはそのままでいいと思った。敵の動機がどうであれ、自分が狙われることに変わりはないし、ドモンと自分がやるべき事も変わらない。
ただ、DG細胞の塊である自分を、この戦いに連れて行くリスクに気づかないキョウジではないはずだ。だがそれすらも呑み込んで、彼は自分を頼ってくれた。シュバルツには、それが嬉しかった。
「シュバルツ……次の戦い、俺はどうすればいい?」
ドモンが、正眼でシュバルツを見ている。弟の心技体がともに充実している気配を見て取って、シュバルツは「そうだな……」と、にっこり微笑んだ。
「遠慮はいらん、ドモン。正面から殴りこんで、力いっぱいぶちかませ!」
「やった!! そうこなくっちゃ!」
暴れることに兄からお墨付きをもらった形になったドモンは、素直に喜んだ。
「ただし! 守ってもらう事が二つあるぞ?」
「ふぇ?」
シュバルツが手を突き出して立てた2本の指を、ドモンは不思議そうに眺める。
「一つ。あまり建物を破壊しすぎない事」
「えっ? 何で?」
いきなり弟からそう返されて、シュバルツはズルッとこけそうになった。
「……あのなぁ。キョウジやお前の師匠も建物の中に潜入してシステムを狙うんだぞ? 建物ごと、二人を殺す気か?」
「あ! そうか!!」
ポン、と、納得したように手を打つ弟を見て、シュバルツは思わず頭を抱えてしまう。あの仮面の男や化け物によるダメージよりも先に、弟による不慮の事故で命を落としかねない事実に涙が出そうだ。まあ、キョウジのそばには東方不敗がついているから、多分大丈夫だろうが。
「う~ん……。でも、難しいな……」
「何がだ?」
顎に手を当てて難しい顔をしている弟に、シュバルツは声をかける。
「建物を破壊しちゃ駄目となると……どれくらいの力加減で戦えばいいのかな? ……もういっそ、建物の中に入らずに、外で戦うべきか?」
「…………!」
(ドモン…ッ! 天然か? 天然なのか!? お前っ……!)
シュバルツは眩暈を感じて倒れそうになるのを懸命にこらえた。馬鹿だ馬鹿だと思っていた自分の弟の本気の馬鹿さ加減に、思わず泣きそうになる。
「ドモンよ……」
シュバルツはふうっと一つため息をつくと、懐から施設の見取り図を取り出して、ドモンの前にバサッと広げた。
「図面を見て確認しろ!! ここが私たちの突入予定ポイントで! キョウジが狙っているシステムの場所は、ここだ!!」
指を差して説明するシュバルツの前で、ドモンは「う~ん」と、唸り声を上げていた。
「……と、言う事は、どの辺まで壊していいの? 兄さん」
(……どうしても、壊すことが前提なのか……)
シュバルツはついに、近くに在った切り株の上に突っ伏してしまった。
「分かった……ドモン……。じゃあこうしよう。壊したらまずい所には、私は近づかないようにするから―――お前はそれについて来い」
ズキズキと痛む頭を押さえながらシュバルツが提案した妥協案に、ドモンは嬉しそうに「うん、分かった!」と、頷いた。
「それにしてもドモン……どうしてそんなに建物を壊したがるんだ」
呆れたように呟くシュバルツに、ドモンはきっと顔を上げた。
「だって! こいつら兄さんを狙っているんだろ!? 本当なら俺は、そんな奴らの建物なんて、柱一本たりとも存在する事を許したくないんだ!!」
もうそれこそ完膚なきまでに叩き潰してやりたい―――とわめく弟を、「分かった、分かった」と、シュバルツは何とかなだめた。
「一応、システムの掌握に成功して、キョウジの安全が確認できるまでは建物を壊すのはやめておけ…。その後なら、どうしようと構わないから」
そのシュバルツの言葉に、ドモンは「本当?」と、顔を輝かす。
「だから、もう一つ」
シュバルツは苦笑いながらドモンに提言した。
「どのような場所で戦おうが、どのような状況で戦おうが―――私がいる位置だけは、常に把握するように心がけてくれ」
「? どうして?」
不思議そうに首をかしげるドモンに、シュバルツは言葉を続けた。
「敵の標的が『私』だからだ。私の居る場所が、すなわち敵の狙う場所になる」
「………!」
「敵がどこを狙って攻撃するか分かった方が、お前も戦いやすいだろう?」
「それは…そうだけど……」
ドモンが少し戸惑ったような表情を見せている。
「もちろん、馬鹿みたいに一ヵ所に留まる様な戦い方はしない。それなりに気配を消して動きまわる。お前の戦いをフォローするようにも動く」
「――――!」
緊張を帯びた弟の表情に、シュバルツはふっと相好を崩した笑顔を見せた。
「その時に、お前の攻撃を敵と一緒に喰らいたくないからな。だから、お前には、私の位置を常に把握するように心がけておいてほしいんだ」
「―――分かった」
真剣な表情をして、ドモンは頷く。それを見たシュバルツは、今度は挑戦的な笑みをその面に浮かべた。
「ならば……お前が私の気配をどこまで追えるか、試させてもらっていいか?」
「ああ、いいぜ?」
それに対してドモンも不敵に笑う。そのまま兄弟二人は、ギアナ高地の森林の中、特訓とも言える組み手へと移行して行った。
(シュバルツは今……気配を消さずに俺の隣に居る……)
自分達に―――と言うよりも、『兄』に向かって殺到してくる敵の大軍を見ながら、ドモンはふ―――っと長い息を吐く。
落ちつけ。
こういう時こそ
心を静かに―――。
「でりゃあ!!」
ドモンの気合を乗せた拳圧が、殺到して来た敵の大軍を吹き飛ばす。それと同時に横に居たシュバルツが動いた。彼は手近に居た兵や合成獣達をその刀で切り裂きながら風のように走り抜け、あっという間に姿が見えなくなってしまう。
「どこへ行った!?」
兵達がシュバルツの姿を探す中、ただドモンだけが静寂の中に居た。
(違う…。気配を絶っただけだ。シュバルツは、まだ近くに居る…)
この戦いに至るまでの間、ドモンは懸命に考えていた。『兄』を守るにはどうすればいいか―――。
兄は、とても優しい人だ。自分よりも周りを優先してしまう。戦いにおいても然りだ。ぎりぎりの局面で兄は自分の身を顧みずにこちらを守ろうとする。シュバルツは『不死』であるが故に、その傾向が余計に強い。
だから。だからこそ。
兄を―――シュバルツを守ろうと思うのなら、無理に守ろうとしてはならない。逆にシュバルツに自分を守らせようとしてもいけない。
自分の身は自分でしっかり守って、シュバルツに、「ドモンは大丈夫だ」と、思ってもらわねばならないのだ。それが、シュバルツを守ることにつながる。
その為に自分は、感情の赴くままに暴走してはならない。
デビルガンダム事件の際、自分は感情のままに暴走したが故に、シュバルツに自分を庇わせてしまった。その過ちを、二度と繰り返してはならない。
兄を狙っている敵の本拠地に乗り込んできているからこそ、逆に氷のように冷静にならなければならないのだ。それが出来ずして―――何が、キング・オブ・ハートか!
(…………!)
ドモンの研ぎ澄まされた感覚が、シュバルツの気配を捉える。目の前の敵と戦いながらも、その気配をドモンは感覚から外さない。
不意に、シュバルツの気配が濃くなる。
「キョウジ・カッシュがいたぞ!!」
兵の叫び声が聞こえると同時に、前方で一陣の風が巻き起こる。風は、兵達を跳ね飛ばしながら高速で進んで行く。その風を追おうとした兵達を、ドモンの拳圧弾が次々と襲う。
誰かが、銃を乱射するが、高速で移動をしているシュバルツには当たるはずもない。
「火器を使うな!! 同士討ちになるぞ!!」
集団の中、怒号が飛び交う。
「おのれっ!!」
近くに居た兵士がドモンに襲いかかろうとする。
「!!」
兵士がドモンに向かって銃刀を振り下ろそうとした瞬間、ドモンの強烈な蹴りが兵士の顔面を見舞う。そのまま兵士は吹っ飛ばされた。
「こいつ!」
近くに居た兵士たちと乱戦状態になる。空から、翼を持った合成獣が、ドモンに襲いかかろうとした。だが緑色の風が、空中でその合成獣を捕まえる。
「ハ――――ッ!!」
そのままきりもみ状態になりながら、合成獣を地面に叩きつけた。飯綱落しだ。叩きつけられた時の衝撃で、周りの兵士たちが吹っ飛ばされる。
「ドモン、大丈夫か!?」
そう言いながらシュバルツが、自分の背後に来た。一瞬、兄弟が互いの背中を庇い合うように立つ格好になる。
「ああ。全然平気だ!!」
ドモンがファイティングポーズをとる。殺気を纏ってはいるが、激情に駆られている様子でも無いドモンを見て、シュバルツも「フ……」と、笑った。
「頼もしい事だな…。では、行くぞ!!」
「ああ!」
シュバルツが再び走り出し、その周りをドモンの拳圧弾が襲う。兄弟の息の合った攻撃が、再び正門前の広場を席巻して行った。
「フフフ…。やっておるな…」
正門前の広場から聞こえる轟音や兵士たちの怒号を聞きながら、東方不敗はにやりと笑った。
「さあ、我らも行くぞ! 準備はよいな!?」
東方不敗が振り返った視線の先にはキョウジとハヤブサがいた。キョウジは無言で頷き、ハヤブサが「問題無い」と答える。
「皆、気をつけて―――」
ヘリの操縦席から、女性の声が追いかけてきた。チボデー・クロケットをサポートしている女性の一人、シャリーだ。彼女が、彼らをヘリでここまで運んできてくれていたのだ。
「ありがとう。本当に―――」
ヘリから降りる直前、キョウジは振り返って彼女に礼を言った。それに対してシャリーは「フフ」と、大人びた笑顔を見せる。ドモンの恋人のレインとはまた違ったタイプの美人だった。
「いいのよ。もう一人の貴方―――シュバルツさんには私たちもお世話になっているから……その、恩返し。『困った時は、お互いさま』よ」
「――――!」
「じゃあ、私はもう行くわ。成功を祈っているわね」
そう言い置いて、シャリーのヘリは飛び立った。
(また、シュバルツやドモンに助けられたことになるのかな……)
ヘリを見送りながら、キョウジはそう感じていた。あの『デビルガンダム事件』は、悲惨な事件だった。だが、そんな状況下でも、人は絆を作り、希望の光を見出して行く。それは、人間の素晴らしい所だと、思うのだ。
「キョウジ」
ハヤブサに呼びかけられ、「今行く」とキョウジは振り返り、走りだした。
正門から一番離れている場所にあるその出入り口は、静かだった。それでも、何人かの見張りはいた。
「少し待っていろ」
ハヤブサはそう言い置くと、音も立てずにその出入り口に近づく。やがて
「ぎゃっ!!」
「ぐうっ!!」
小さな呻き声が聞こえたかと思うと、辺りから人の気配が消えた。それからしばらくして、ハヤブサがこちらに向かって手招きをする姿が見える。
「行くぞ!」
東方不敗の声に合わせて、キョウジも走りだした。
ここからは、時間との勝負だ。
シュバルツ達が、どこまで持ちこたえられるか。
こちらのシステム掌握が、どこまで迅速に行えるか。
自分が建物に侵入した事、おそらくあの仮面の男には伝わっている事だろう。
あの男は、こちらの狙いに気づくか。
そして、シュバルツと自分、どちらに狙いを絞ってくるか―――。
キョウジの読みでは7:3の割合で、シュバルツを狙ってくると踏んでいた。ギアナ高地の戦いで、相手の戦力にかなりダメージを与えている。しかも、現在進行形で、世界各地で起こっている襲撃により、指揮系統が乱されている。そんな中で、自分達二人を同時に狙う事は、おそらく無理だろう。
(お願いだ…。もう少しだから―――。だから、力を貸してくれ……!)
キョウジはいつしか、勾玉のある胸の辺りに祈るように手を当てていた。
(……………!)
キョウジの中にある勾玉の存在故に、仮面の魔道師はキョウジが建物に侵入した事に気付いた。
(キョウジ・カッシュがここに来た……しかし、何をしに来た!?)
勾玉を持つ身で黒の女神に近づけば、取り込まれる事は百も承知のはずだ。それなのに、逃げるどころか敢えて攻撃を仕掛けてくるのは何故だ。
こちらが手を組んだ『組織』への、徹底的なダメージを狙っているのか?
それとも、自分の身を犠牲にする覚悟で、黒の女神と『心中』しに来たのか?
それならば、何故あの細胞のキャリアーまで一緒に連れてきた? 奴の近くには女神の天敵である『龍剣の使い手』も一緒に居る。『心中』するだけならば、わざわざここに乗り込んでくる必要もないであろうに。
「……………」
何か―――何かを企んでいる。こちらにとっては、とてもよくない何かを。
(どうする?)
仮面の魔道師は自問自答をする。キョウジ・カッシュを放置しておくのはまずい。しかし、彼のそばには龍剣の使い手が控えている。下手にちょっかいを出したら、こちらが逆に封印されかねない。
それよりも、キョウジ・カッシュに有効に対抗するのであるならば―――あの細胞の『キャリアー』であるあの男…。あの男を利用できれば―――。
この細胞は、自分の魔力とよく馴染んでいる。だからこそ、うまくすれば、あの男自体を自分の新たな武器として、利用できる可能性が高い。
(あの男を捕るか)
それも、出来るだけ早く。恐らく早ければ早いほどいい。これ以上、時間と戦力を割く事は出来ない。時間をかければかけるほど、キョウジ・カッシュの企みを手助けしてしまうに違いない。これは、確信だ。
「シュトワイゼマン様」
「何だ?」
魔道師の呼び掛けに、シュトワイゼマンは振り返る。
「黒の女神の使用許可を願います」
「何故だ?」
「『龍の勾玉』を持つ、キョウジ・カッシュが近くまで来ています」
「何ぃ!?」
仮面の魔道師からの報告に、シュトワイゼマンは驚きを隠せない。
「おそらく何か狙いがあって乗り込んできていると思われますが―――表の細胞のキャリアーも放置するわけにはいきません」
「ううむ……」
考え込むシュトワイゼマンに、仮面の魔道師はなおも進言する。
「『龍の勾玉』と『黒の女神』は惹きあいます。勾玉の方は黒の女神に任せて―――我らは、細胞のキャリアーの方に注力するべきかと」
「両方狙うわけにはいかんのか?」
シュトワイゼマンの言葉に、仮面の魔道師は頭を振った。
「残念ながら、我らの今の戦力では―――両方を狙うと言う策は現実的ではありません」
この言葉にシュトワイゼマンは、小さく舌打ちをする。やはり、ギアナ高地で失った戦力が、今頃になって響いてくる。
「分かった…。黒の女神の戒めを解け」
「ありがとうございます」
シュトワイゼマンの言葉に、仮面の魔道師は恭しく頭を下げる。
「ただし!」
踵を返そうとした魔道師を、シュトワイゼマンが呼び止めた。
「強大な火力の封を解く事は許さんぞ。ここを消し炭にされてはかなわんからな」
「畏まりました」
そう言ってシュトワイゼマンの前から退出する魔道師も、(狭量な男が)と、シュトワイゼマンに対して小さく舌打ちをしていた。
ドン! ドン!! と、振動を伴った轟音が響く。だが、建物内に人気はなかった。皆、シュバルツの方に引き付けられているのだろう。
時折、見張りが配置されている場所があるが、ハヤブサと東方不敗の手によって、難なく排除されていた。今のところ順調―――だ。恐ろしい程に。
窓のから、ドーム状の建物が見える。
(あの中に……いる)
建物の方に引かれようとする勾玉の気配を、キョウジは強く感じていた。
あの『白昼夢』とも言えるものの中で見た景色と確かに同じ物が、今目の前に広がっている。そして、勾玉が反応を示している。恐らく、向こうにも、こちらの存在が伝わっている事だろう。
こちらが狙うシステムのある場所まであと少し。
このまま何事も無く無事に辿りつければいい。しかし、重要なシステムがある場所を、あの男が無防備に晒しているはずもない。必ず『罠』か、『仕掛け』があるはずだ。
いくつかの廊下を走り、部屋を通り抜けた時―――キョウジ達一行の前に、少し拓けた空間が現れた。
大きな部屋の向こう側に、目指すシステムの部屋へと続く廊下が見える。そこに向かって歩を進めようとした時、突然背後の出入り口のドアが閉められた。その上から分厚い壁が下りてきて、完全に退路を断たれてしまう。
「…………!」
だが、東方不敗もハヤブサも、ちらっと背後を見ただけで特に慌てる様子も無かった。
「後ろが塞がれちゃいましたが……」
キョウジが一応二人に声をかけてみる。
「小賢しい。前に進めばいいだけだ」
東方不敗が事もなげに言い放てば、ハヤブサも「問題無い」と、短く答えた。
「あははは……頼もしい事で……」
そう言って苦笑うキョウジに、東方不敗が言葉をかける。
「今更『普通』を装おうとするのはやめろ。お主も怖じ気てなどないくせに……」
「―――!」
「何か来るぞ! 油断するでない!」
東方不敗の言葉に、キョウジも「はい!」と顔を上げる。そんなキョウジの様子を見ながら東方不敗は、この青年は一体いつから『普通』を装う癖を身につけてしまったのだろう、と、ふと思った。
不意に、轟音が響き、横の壁が大きく開く。
ガシャン、ガシャン、と金属音をきしませながら、巨大な物体が姿を現した。
それは蜘蛛の様な形をしていた。八本の足を動かしながら、こちらに向かって進んでくる。胴体からカメラを先につけたケーブルを伸ばし、こちらに向けてきた。
「ココカラ先ハ、許可サレタ者シカ通ル事ハ出来マセン。登録サレタIDト認証番号ヲ報告シテクダサイ―――」
無感情な金属の声が、3人にかけられる。
「そんな物あるか」
と、東方不敗。
「同じく」
と、ハヤブサ。
「研究所のIDならあるんだけど……ID番号は―――」
キョウジの発言に、前に居た二人がズルッとこけた。
「ええい! こんな奴の発言に、いちいち真面目に答えようとするでない!!」
「いやだって……聞かれたからには答えてあげないと、悪いかなって……」
東方不敗からの突っ込みに引き気味に答えるキョウジを見ながら、ハヤブサはズキズキと頭痛がするのを懸命にこらえていた。ここに、もしキョウジじゃ無くてシュバルツがいても、似たようなボケをかましそうで怖い。
(弟がいる時は、それなりにしっかりした『兄』の顔をするのだろうけどな……)
実際、シュバルツもキョウジも、かなり天然な所がある様な気がする。最も本人にそれを言ったら、全力で否定されそうだが。
「IDト、認証番号ヲ認識不可能―――」
当然機械の方は、3人のそんなやり取りに興味を示すはずも無く、無機質に与えられた使命を実行する。
「侵入者トミナシ、排除イタシマス」
機械の声に、東方不敗とハヤブサの目つきが、同時に険しい物となる。
頭頂部が左右に開いて、武器の発射口が出現した。
「!!」
東方不敗がキョウジを抱きかかえ、ハヤブサも素早くその場から飛び退く。それと同時に3人がいた場所に、バシュッと音を立てて赤いレーザーの光が穿たれた。レーザーが当たった所が、しばらく赤く焼け焦げている。当たれば「痛い」では済まないだろう。
ハヤブサが、すらり、と龍剣を抜き放つ。
「いざ、参る」
その言葉が終わると同時に、再びレーザーがクモ状のメカから放たれる。だが、レーザーがハヤブサのいた場所を穿った時、そこに彼の姿はなかった。彼は、メカの頭上高くに跳躍をしていたのだ。
「哈――――ッ!!」
裂帛の気合と共に、ハヤブサの龍剣がクモ状のメカに振り下ろされる。ガキィィン!! と、派手な音がした。だが次の瞬間、メカに龍剣を突き立てたハヤブサの顔が、顰められる。
「つ………ッ!」
龍剣はメカの装甲に少し食い込んで止まった。メカを切断できなかった反動が、もろに手に来る。
「チッ!!」
少し痺れる手を押さえながら、舌打ちをしつつ龍剣を引き抜く。刹那、空気を割く気配がした。
ハヤブサが底を飛び退くと同時に、メカの脚の一つから出現した巨大な鎌状の武器が、ハヤブサがいた場所を払う。慣性の法則に従ってハヤブサが向かった着地地点を、再び赤いレーザービームが襲った。
「!!」
咄嗟に身体を回転させ、手の先だけを地面について、着地する場所を変える。だが、ハヤブサが止まる事を許さないかのように、クモ状のメカは執拗にハヤブサをめがけてビームを放ち続けた。
「ハヤブサ!!」
叫ぶキョウジの近くで、東方不敗が身構える。キョウジの護衛をしなければならないので、彼のそばを離れるわけにはいかないが、可能ならばハヤブサの援護もするべきかと考えた。
しかし。
突如として、壁の一角が小さく開いて、獣の群れがそこに乱入してくる。オオカミとドーベルマンを掛け合わせたような容姿をしていたが、皆頭が二つ付いていた。
「しゃらくさい!!」
キョウジに向かって突進してくる獣の群れを、東方不敗が次々と撃退して行く。
「キョウジよ! ワシのそばから離れるな!!」
キョウジを後ろに庇いながら、東方不敗が叫ぶ。
「はい!」
キョウジは東方不敗に答えながら、懸命に目の前の蜘蛛型のメカを見た。
自分は、戦う事は出来ない。
だが、見る事なら出来る。
見ろ。
見ろ。
あのメカの『弱点』はどこだ。
襲い来るビームの嵐をかいくぐりながら、ハヤブサは体勢を立て直した。
(脚部分には装甲はない。まず脚を叩く―――)
龍剣を握りなおし、脚に狙いを定める。間合いを詰めてきたハヤブサに、再び脚から伸びた鎌状の武器が襲いかかった。
ギャリイィィィィッ!!
ハヤブサが、鎌状の武器を龍剣で受け流しながら、尚も間合いを詰める。龍剣とメカの武器の間に、青白い火花が走った。
「はあああああっ!!」
裂帛の気合と共に、龍剣が唸りを上げて脚の接合部分に喰らいつく。
ドン!! と言う音と共に、鎌状の武器は見事にメカの脚から切り離された。
「まず一本!」
叫ぶハヤブサ。だが、次の瞬間異変が起こる。
メカの脚の切断面から、にゅるり、とケーブルが延びる。それは落ちている鎌を拾い上げると、再び自身の脚に綺麗にひっつけてしまった。
「な―――!」
「『自己再生』―――DG細胞!!」
「何だと!?」
それぞれが叫び、息を飲んだ。
再び鎌がブオン!! と唸りを上げてハヤブサに迫る。彼はそれを、間一髪でかわした。
「ハヤブサ!! 鎌の脚から一番遠い反対側の脚を切断する事は出来るか!?」
キョウジがハヤブサに向かって叫ぶ。
「問題無い!」
ハヤブサは短く答えると、再びメカとの間合いを詰めた。間断なく迫ってくるレーザーと鎌の攻撃を、紙一重で避け、受け流す。鎌がドンッ! と、音を立てて地面にめり込んだ瞬間、ハヤブサの身体は再びメカの上に跳躍していた。
「りゃああああっ!!」
龍剣は、キョウジが指摘した個所を、過たず刎ね飛ばす。切断され、ガシャン! と、音を立てて転がった脚は、今度は自己再生をしなかった。
「やはり―――」
「!? どういう事だ!? キョウジ!!」
一人得心しているキョウジに、東方不敗が質問する。
「あのメカは、DG細胞が移植されてから、まだそんなに時間が経っていないんです」
「何故そんな事が分かる?」
怪訝な顔をする東方不敗に対して、キョウジが言葉を続ける。
「このメカのプログラムは、まだ『暴走』をしていない。恐らく、あの武器を持っている脚の辺りにしか、DG細胞が広まっていないんだ。あの段階ならば、メカを完全に破壊する事が出来さえすれば―――」
「こいつを黙らせる事が出来るんだな!?」
ハヤブサの言葉に、キョウジは頷いた。
「よし! ならば―――」
ハヤブサは龍剣を構えなおす。
「いざ参る!!」
龍の忍者が、再びメカへと間合いを詰めて行った。
広場に居る兵達は頭を抱えていた。
「キョウジ」に狙いを定めて攻撃を仕掛けても、乱戦の中、いつの間にか見失ってしまう。そこにドモンの攻撃が襲いかかって来てダメージを喰らう。
ならば、と、ドモンの方に攻撃の狙いを定めても、いつの間にか「キョウジ」が舞い戻って来て不意打ちをされる。そして、キョウジを追いまわしているうちに―――いつの間にか一ヵ所に固められて、そこに「石破天驚拳!!」と、ドモンの拳が飛んで来て、まとめてやられてしまう。この兄弟の息の合った攻撃―――まさに、『手がつけられない』としか、言いようがない。
「く、くそ……!」
歯噛みする兵達の前で、キョウジが―――正確にはシュバルツなのだが―――爽やかに微笑みながら、「かかって来い」とでも言わんばかりにちょいちょい、と、指を動かしている。あからさまな挑発行為だ。だが、その後ろにこれ見よがしに待ち構えている弟の姿を見ると、とてもかかっていく気にはなれない。
(無能どもめ!!)
その様子を監視カメラのモニター越しに見ていた仮面の魔道師は舌打ちをした。分かっていたこととはいえ―――こうも圧倒されると腹だたしい。
「どうする気なのだ! あの『キョウジ』は捕らえられるのか?」
別のモニターから、シュトワイゼマンの苛立ちを含んだ声が飛んでくる。
「もうしばらくお待ちください。手を打って―――」
そこまで言いかけた仮面の魔道師は、不意に画面の中のキョウジが、ある建物の方に向かって走っていくのを視界の端に捉える。
(ほう……『生産工場』の方に向かって走っていくのか……)
仮面の魔道師は口の中で「ククッ」と笑う。あそこならば都合がいい。兵の補充には事欠かないし、何よりもあそこには―――『ダレク』がいる。そして『訓練場』の中に閉じ込めさえすれば……。
「ご安心くださいシュトワイゼマン様。訓練場に『罠』を張ります」
「……ほう、そんな事が出来るのか?」
シュトワイゼマンの問いかけに、仮面の魔道師は頷く。
「よろしければ、ご見学なさいますか? 面白い物をお見せしましょう―――」
そう言いながら仄暗く笑う魔道師の目が、妖しく光っていた。
「兄さん! そっちには何があるの?」
走りながらドモンは、シュバルツに向かって問いかける。
「兵の『生産工場』だ」
「――――!」
シュバルツが、振り向きもせずに答えた。だが、シュバルツの口から出た単語の意味に、ドモンは思わず絶句する。
「あそこはひどい。『生命』を弄んでいる……」
言いながらシュバルツは、ここに潜入した時の事を思い出す。ここに押し込められた人間も動物達も―――ひどい扱いを受けていた。尊厳をはぎ取られ、身体のパーツは『部品』と化していた。無慈悲な『実験』が、何度も繰り返されていた。
潜入捜査中、何度叫びそうになったか分からない。
もし、ここに乗り込む事があったら―――真っ先に『壊そう』と、シュバルツは心に決めていたのだ。
「ここならいいぞ、ドモン。存分に暴れろ」
兄の言葉に、ドモンは力強く頷いた。
「うん! 任せてよ! 兄さん!!」
走る兄弟達の行く手に―――無機質な黒い建物が、ただ聳えていた。
「むうっ!」
東方不敗は唸っていた。キョウジに向かって突進してくる動物達の中にも、『異変』がある事に気付いたのだ。
「キョウジよ!! 気をつけろ!! どうやら獣たちの中にも―――DG細胞に感染した者がおるぞ!!」
「!?」
東方不敗の言葉に、キョウジは驚いて獣たちを見る。確かに東方不敗の攻撃を受けて、そのまま絶命したり退散する獣もいたが、怪我を治し、ことさら牙をむいてこちらに向かってくる獣もいた。
「石破天驚拳!!」
東方不敗の必殺の拳が、そんな獣たちをなぎ払って行く。DG細胞が暴走しそうになっていた獣たちが、跡形も無く消えて行った。
そんな中ハヤブサは、蜘蛛型メカの脚を切断しつつ、懐に潜り込む。
「いやあああああっ!!」
裂帛の叫びと共に、蜘蛛型メカを下から龍剣で払い、強引にひっくり返した。龍の忍者の凄まじき膂力だ。
(腹の方までは装甲はあるまい!!)
そう思いながらハヤブサは、ひっくり返った蜘蛛型メカに斬りかかろうとする。だが、それは叶わなかった。蜘蛛型メカには―――腹の方にまで装甲が『あった』のだ。
(周到な……!)
ハヤブサは小さく舌打ちをする。その時、今まで再生をしなかった脚が、『自己再生』を始めた。DG細胞が広がって来ているのだ。ギ、ギ、と音を立て、メカは仰向けの状態から、再び身体を起こそうとしている。
「ハヤブサ!! レーザーの発射口を、攻撃する事は出来るか!?」
「―――!」
キョウジの声に、ハヤブサはピクリと反応する。
「内部に直接ダメージを与えようと思ったら、そこしか無い!!」
レーザーの発射口は、かなり小さいうえに、出現するのも一瞬。しかも、当たればただでは済まない。それなのに、そこを攻撃しろと言う―――。実際、かなりの無茶ぶりだ。
だが、このキョウジからのむちゃくちゃな要求に、ハヤブサの闘争心が燃えた。知らず、口元に不敵な笑みが浮かぶ。
「任せろ!!」
そう短く答えると、ハヤブサは再びメカに相対する。その瞳には、凶悪とも言える闘争の炎が宿っていた。
ガシャン!!! と派手な音を立てて、メカが仰向けの状態から復活した。復活した脚の先から、鎌状の武器が生える。今度その鎌は2本になった。
2本の鎌とレーザーが、ハヤブサに容赦なく襲いかかる。ハヤブサはそれらをかわしながら、レーザーの発射口を凝視する。発射するタイミング、攻撃範囲、そして、間合いを慎重に計る。
「おかしいぞ!? どうしてこうも後から後から、DG細胞に感染した獣たちが来る!?」
東方不敗が獣たちを打ち払いながら叫ぶ。ハヤブサへ加勢に行くタイミングが、なかなかつかめない。
「……いるんだ。あの向こうに。DG細胞をばらまいている奴が―――」
「……………!」
キョウジがそう言いながら見つめる目線の先に、東方不敗も顔を向ける。獣たちが次から次へと出てきている、その向こうの空間に。
「ならば、そ奴を始末してくれる!! ハヤブサ! さっさとそいつを黙らせろ!!」
「今やっている!!」
ブォン! と唸りを上げて迫ってくる鎌を、ハヤブサはガン! と刎ね上げる。もう一本の鎌がなぎ払ってくるのを、ハヤブサは跳んでかわした。そのまま鎌の上に乗る。恐るべきバランス感覚だ。
カシャン、と、音を立てて、レーザーの発射口が顔を出した。ここまでは、ハヤブサの読み通りだ。後は―――メカとハヤブサの「技量」―――どちらが、上か。
ハヤブサの集中力が極限まで高まる。
周りの音が消えていく。
このメカが、立て続けに放つ事の出来るレーザーは、3発。
そして、次弾を充填するまでにできるタイムラグが、0.7秒。
狙うのは
そこ―――!
バシュッ!! と、音を立ててメカがハヤブサに向かってレーザーを放った瞬間、ハヤブサの姿が鎌の上から消えた。
ドン!!
その音と共に、この空間の総ての動きが止まった。
勝負がついたのは一瞬だった。ハヤブサの龍剣は、レーザーの小さな発射口を、過たず捉えていた。
ガシャン!! と、音を立てて、ハヤブサの背後に巨大なメカの鎌が転がる。
「…………」
ハヤブサは、無言で龍剣を引き抜く。その瞬間、一点に収束して外に放たれようとしていたレーザーの強力なエネルギーが、メカの体内に向かって牙を剝いた。
龍の忍者がメカのそばから離れるのと、メカが大爆発を起こすのが、ほぼ同時だった。部屋に、凄まじい風圧を伴った爆風が巻き起こり、群がっていた獣たちも次々と吹き飛ばされて行く。
やがて、総てが収まりそこに静寂が訪れた時―――キョウジと東方不敗の前に、龍の忍者が姿を現した。
「フッフ、余計な手出しだったか?」
東方不敗がハヤブサに声をかける。それにハヤブサは「いや……」と、返した。レーザーの発射口に攻撃を仕掛ける瞬間、メカの鎌がハヤブサに襲いかかろうとしていた。それを、東方不敗が防いでいたのだ。
「ハヤブサ! 怪我を―――」
「…………!」
キョウジの声に、ハヤブサもおのれの腕の怪我に気づく。立て続けに放たれたレーザー。最後の一発だけが避けきれなかったのだ。
「平気だ。放っておけば治る」
「そう言って、本当にすぐ治っちゃうのはシュバルツだけだよ」
そう言いながらキョウジは、懐から救急セットを取り出す。慣れた手つきでハヤブサに手当てを施した。
「これでよし……と。後は、『帰ってから』だね」
「…………!」
キョウジの言葉に、ハヤブサはピクリと反応する。東方不敗は「当然だ」と返した。
(帰れればいい―――皆で)
キョウジには、ここで命を落とす可能性もまだ色濃く残っている。だが―――ハヤブサもそう、願っていた。
「非戦闘員と、戦闘の意思が無い者は、この場から去れ!!」
建物内を走りながら、シュバルツは叫んでいた。その後ろでドモンが「石破天驚拳!!」と、叫びながら、目に付くありとあらゆる設備や装置を、片っ端から壊している。
この建物内で働く技術者や科学者と思われる人々が、蜘蛛の子を散らすように逃げていく。しかし、中には武器を振り回して立ち向かってくる戦闘員もいた。シュバルツは、それらを容赦なく斬り裂いた。
「刃向う者は容赦しない!! 邪魔をするな!!」
ドモンとシュバルツが入り込んだ建物内は、あっという間にパニック状態に陥る。
「……しかし、ひどいな。ここは……」
戦闘の切れ目に、シュバルツのそばに寄ってきたドモンが、ぼそりと呟く。設備を攻撃していると、どうしても目に入ってしまう。その中に『何』が入っていたのかが。
人間の身体の一部。
動物の身体の一部。
奇形な胎児らしきモノもいたかもしれない。
奇妙な形の死体。
培養液から出た途端、僅かに足掻いて絶命する『モノ』――――。
(キモチワルイ……)
深く考えれば考えるほど吐きそうになる。だから、ドモンは自身の思考をある程度麻痺させるように努力した。今は、自身の感情だけに流されている場合ではないのだ。自身の感情の乱れが、即、自分を危地に陥れることになり、それが、シュバルツを窮地に追い込んでしまう事につながってしまう。それだけは、何としても避けたかった。自分は、兄を守りに来たのだ。
「大丈夫か? ドモン」
シュバルツが心配そうにドモンに声をかけてくる。弟にこのような物を見せるべきではなかったか、と、少し後悔する。
「平気だ!」
ドモンは少し強めに返事を返した。シュバルツの方も顔色が悪い。兄も、これだけの光景を見て、平気でいられる人ではないのだ。それなのに、気を遣わせている場合ではない。
「それよりもシュバルツ! もっとほかに壊す所は!?」
そう言ってドモンはシュバルツを正眼で見た。
「……………」
シュバルツは、そんなドモンの様子を黙って見つめ返したが、弟が思いのほか冷静な様子を保っているのに「フ……」と、笑みを浮かべる。
「……ならば、もう少し地下に潜るか」
「地下? そこに何があるの? 兄さん」
ドモンの問いに、シュバルツは少し困ったような笑みを浮かべた。
「多少危険かもしれないが……あそこには、まだ助けられる可能性がある人たちが、いるはずなんだ……」
「…………!」
だが、彼らを助けると言う事は、それだけこちらにかかってくる不確定要素とリスクが増える。だから、どうするべきかとシュバルツは少し迷っていたのだ。だが。
「じゃあ、行こう! 兄さん! 助けられる人がいるのなら―――」
ドモンは迷わずそう言った。
「――――!」
シュバルツは思わずドモンを見つめた。ドモンはまっすぐシュバルツを見ていた。その視線に、迷いはない。「助けられるのなら、助ける」おそらく彼は、単純にそう思っているのだろう。それと共に背負わねばならなくなるリスクを、考えもせずに。
だが―――弟が、人を助けることに躊躇わない心を持って成長してくれた事を、シュバルツは『兄』として、とても嬉しく思った。
「よし、分かった――――行くか!」
「うん!」
シュバルツの言葉に、ドモンは嬉しそうに頷く。
そして兄弟たちは、地下へ向かう階段を目指して、再び走り出した。
「な――――!」
獣たちが入って来た出入り口から部屋を抜けたキョウジ達は、言葉を失っていた。そこに、意外な人物が待ち受けていたからだ。
長い髪を無造作に束ね、隻眼で着流し姿の男が、げらげら笑いながら獣たちに向かって刀を振り回している。それは、紛れも無く『残月』であった。彼に斬られた獣たちが、倒れたかと思うとすぐに起き上がり、凶悪な顔つきになっている。どうやら残月の「刀」に特殊な仕掛けが施され、DG細胞がばらまかれているようだった。
「馬鹿な……! 残月……!」
ハヤブサが茫然と言葉を発する。
「あいつは―――俺が、仕留めたはずだ……!」
八卦の陣の中で、自分は確かに残月を斬った。その時の感触が、まだ手に残っている。彼はそこで、絶命したはずだった。なのに何故、再び目の前に居るのか。
「……DG細胞だ……」
ハヤブサの疑問を見透かすように、キョウジがポツリと呟いた。
「おそらく、ギアナ高地から残月の遺体を回収して、DG細胞を植え付けているんだ……。だから、あれはDG細胞の力で動いている」
「な………!」
振り返ったハヤブサと視線のあったキョウジが、悲しそうに眼を伏せる。
「だけど……おそらくあれには『残月』と言う人の人格はない…。ただ、他者への攻撃衝動だけが、彼を突き動かしているんだ……。DG細胞に感染した人の末路は、たいていああなる。シュバルツの様に『人格』を保って『暴走』もしないなんて―――本当に、稀な例なんだ……」
「―――!」
ハヤブサは絶句しながら残月を見る。けたたましく笑いながら獣たちを攻撃していた残月も、ハヤブサたちの存在に気付いたのか、顔を上げた。
「くふふふふ……! げひゃひゃひゃひゃひゃ!」
狂人の笑い声が、その空間に響き渡る。
「おのれッ! 石破天驚拳!!」
東方不敗が残月に向かって拳を放った瞬間、残月の姿がそこから消えた。
ガンッ!!!
残月は迷う事無くハヤブサに向かって突進していた。それに気づいたハヤブサが、咄嗟に龍剣でその攻撃を受ける。
「…………ッ!」
だが、予測していたよりもはるかに速く、そして質量を伴った重い攻撃に、ハヤブサの踏ん張る足がずずっと後ろに下がらされる。
「気をつけて! DG細胞は、相手の力を強化するんだ!!」
「……そのようだ、な!!」
叫びながらハヤブサは、残月の刀をガン!! と、跳ね返す。撥ね飛ばされた残月は、2、3歩後ろに下がったかと思うと、げたげた笑いながら、再びハヤブサに襲いかかっていく。
「おのれ!! ここはワシの紋章の力で!!」
そう言って東方不敗が残月に向かって拳を放とうとするのを、ハヤブサが止めた。
「これは俺の『獲物』だ!! 手出し無用―――!!」
「何!?」
「ハヤブサ!?」
驚く東方不敗とキョウジに向かって、ハヤブサは二人に窓の外を見るように顎で指す。
「……あれを見ろ! 『あいつ』が動き出している!」
二人が窓の外を見ると、外のドーム型の建物がこじ開けられ、中から『化け物』の姿が見えた。仮面の魔道師が『黒の女神』と、呼んでいる物が、瞳を金色に妖しく光らせながら、身体を外に出そうとしている。
「…………!」
あれに取り込まれてしまったら、総てが終わりだ。絶句するキョウジに向かって、ハヤブサが声をかける。
「分かっただろう!? もう時間が無い!!」
「ハヤブサ……!」
残月が、けたたましく笑いながらハヤブサに斬りかかっていく。それを龍剣で弾き返しながら、ハヤブサは叫んだ。
「キョウジ! お前は行け!! 『生きる』ために―――!!」
「――――!」
「そ奴の言うとおりぞ!! キョウジ!!」
キョウジに襲いかかろうとする獣たちをなぎ払いながら、東方不敗も叫んだ。
「あの黒の化け物に取り込まれたら、お主は終わりだ!! だから、取り込まれる前に、逆にシステムを制圧せねばならん!!」
「マスター……!」
東方不敗の言葉に、キョウジは顔を上げる。目指すシステムのある部屋は、もう本当に目と鼻の先だ。
「行け!! キョウジ!! ―――走れ!!」
戦いながら叫ぶハヤブサに、キョウジは頷いた。
「分かった……。ありがとう」
ハヤブサの声に押されるように、キョウジは走りだした。その後ろに、東方不敗も続いていた。東方不敗が傍にいる限り、キョウジの身にすぐ危険が迫ると言う事はないだろう。だから今は―――目の前の『残月』に、自分は集中するのみだ。
「さあ―――来い!!」
残月と相対したハヤブサは、正眼で龍剣を構えた。
「おっとっと…。ここだ、ここだ」
地下に向かって走っていたシュバルツが、ある部屋の前まで来ると、急に立ち止まる。簡素な作りのドアを、シュバルツは足で乱暴に蹴り飛ばして開けた。
「兄さん? 何? ここ……」
シュバルツが急に立ち止まって部屋の中に入ってしまったので、すぐに止まれなかったドモンがUターンをしてきて、出入り口からひょこっと顔を出す。
「武器庫だよ。ちょっと拝借しようと思って」
そう言いながらシュバルツは、手当たり次第にガチャガチャと武器を抱え込んでいる。「ドモン、お前も手伝え」と、言うシュバルツに、ドモンは首をかしげた。
「?? 何で? 俺達には必要ないだろう?」
ドモンのもっともな疑問に、シュバルツは苦笑しながら答える。
「私たちには必要無くても―――ここから脱出する人たちには、『これ』が必要だろう?」
「あ……なるほど……」
「納得したのなら、手伝ってくれ」
シュバルツの言葉に、ドモンも今度は素直に頷いた。
兄弟たちは、両手にたくさんの武器を抱え込むと、再び走り出した。
「IDト、パスワードヲ入力シテクダサイ―――」
目指すシステムのある部屋は、電子ロックのついた分厚い扉に閉ざされていた。
(どうやって錠を解除しようか)
キョウジが電子ロックの錠を見ながらその方法を考えようとすると、後ろから東方不敗の声がした。
「キョウジ! どけい!!」
「―――!」
キョウジが扉のそばから離れると同時に、東方不敗の「気」の塊が、扉に向かって突進した。
「ぬぅおりゃああああああっ!!」
バコォッ!!!
派手な音を立ててシステム制御室の扉が吹っ飛ばされる。
(電子錠の意味無い……)
キョウジはそう感じて、苦笑するしかなかった。
部屋の中に飛び込んだ東方不敗とキョウジの前に、今度は背の高い二体の人型戦闘ロボットが姿を現す。
「不法侵入者トミナシ、タダチニ排除―――」
「やかましい!!!」
だが東方不敗がその一言の下、あっという間にそのロボットたちをスクラップにしてしまう。ロボットの残骸を踏みつけながら、東方不敗はキョウジに向かって叫んだ。
「キョウジ!! 分かっておろうな!? ここからがお主の勝負ぞ!!」
「はい!」
東方不敗に答えたキョウジは、制御システムのメインコンピューターの前に走り込んだ。持ってきた自身のノートパソコンのスイッチを入れ、立ち上げる。
(ここだ!)
メインコンピューターへのアクセスの入り口を見つけたキョウジは、そこにノートパソコンから伸びる接続端子を押し込んだ。パソコンから、接続を認識したと告げる音が鳴る。
「…………」
パソコンの画面を見ながら、キョウジは一つ大きく息をした。
(ここまでは、計算通り…。後は、私がこのシステムを、掌握する力があるかどうか―――)
メインコンピューターにアクセスを試みたパソコンから、早速第一関門に行きあたったと告げる画面が表示される。
(勝負!!)
タタタタタ、と軽快な音を立てながら、キョウジの指が猛スピードでパソコンのキーの上を走る。パソコンの画面上にアルファベットと数値が走り、めまぐるしく変化して行く。傍から見ていると、最早パソコン上で何が起きているのか、理解することすら不可能だ。
獣が1匹部屋に走り込んでくる。東方不敗がそれを撃退しても、キョウジは振り向くことすらしない。
(相変わらず、恐ろしい程の集中力じゃな……)
東方不敗はにやりと笑う。きっとキョウジならば、システムの掌握をやり遂げる事だろう。だから、この戦いを邪魔する者は排除する。それが、自分の役目なのだと東方不敗は自覚する。
「さあ―――我が王の戦い、何者であろうと邪魔する事は許さんぞ!!」
とんでもない事を口走りながら、東方不敗はキョウジを背後に守る様にファイティングポーズをとった。
「…………!」
残月の太刀を受け止めながらハヤブサは、己の中にふつふつと度し難い怒りの感情が湧きあがってくるのを感じていた。
兎に角、気に食わない。
何もかもが。
残月は、確かに力が上がっている。スピードも速く、一撃にかかる重さも増している。
だが……それだけだ。今の残月は、ただ、相手を『攻撃』することしか考えていない。里で一、二を争う幻術の使い手が、ただ、狂ったように笑いながら、相手を攻撃する事だけしか出来ない哀れな「人形」になり下がっている。
(ふざけるな……)
残月を構成している『モノ』は、残月の『死体』と、『DG細胞』―――つまり、シュバルツと『同じ』と、いうことになる。
(ふざけるな……!)
そういう結論にいきつく己の思考に腹が立つ。この残月とあのシュバルツを同類のモノだなどと―――断じて思いたくなかった。
残月の太刀をガン!! と撥ね上げ、がら空きになった胴にけりを入れる。残月は後方に吹っ飛ばされ、壁に激突し、その身がめり込む。戦いの場に、しばし静寂が訪れた。
「ふざけるな……!」
ハヤブサはいつしか、感情を口に吐露していた。龍剣を握る手に、ぐっと力が入る。
胸の奥でちりちりと音をたてて燃えていた青白い炎が、ぼうっと音を立てて燃え広がっていくのを感じる。ただ彼は、それと同時に己を律した。極限まで集中力を高めて、青白い炎を、己の内に制御する。呑まれないように。怒りに取り込まれてしまわないように―――そうして練り込まれて行った青い炎は、いつしか、『龍』の形へと姿を変えて行く。
ドクン!!
『龍剣』から凶悪な波動が発せられているのを右手に感じる。
喰らいたがっているのだ。龍剣は。
目の前に居る『獲物』を。
狂ったようにげらげら笑い、攻撃するしか出来ない哀れな『獲物』を。
待て。慌てるな。
今―――喰わせてやる。
「ひゃははははははは! ぎゃはははははははは!」
めり込んでいた壁から身を起こし、残月は再び攻撃に移る。残月の太刀がハヤブサを袈裟掛けに斬ろうとした瞬間、ハヤブサの姿がそこから消えた。斬るべき標的を見失い、少しバランスを崩した残月の頭上から、龍の忍者の声が降りかかってくる。
「ふ、ざ、けるなぁぁぁぁ――――ッ!!!」
ドカッ!!
裂帛の気合と共に、残月の身体はハヤブサによって真っ二つに脳天から斬り裂かれていた。それと同時に龍の形をした青い炎が残月に襲いかかり、二つに裂かれた残月の身体は、あっという間に炎に包まれて行く。
末期の悲鳴を上げる事も無く、炎の中崩れていく残月の姿を、ハヤブサはただ無言で見守っていた。
「……………」
ブン、と、刀の露払いをし、鞘にそれを収めようとする。龍剣の刀身から放たれる青白い光を眼にした時、ハヤブサはふと思い至った。
(待て―――! DG細胞で動かされていた残月を、滅する事が出来たと言う事は……この太刀は―――!)
まさか、同じようにシュバルツも『滅する事が出来る』のではないのだろうか……!?
「…………ッ!」
ハヤブサはブン、と頭を振った。何故、こんな事に気づいてしまったのかと、内心舌打ちをする。
(違う……! シュバルツが『死』を迎える可能性があるのは、キョウジの『死』以外には無いはず……! シュバルツだけを消す事など、出来ないはずだ……!)
ハヤブサは懸命にそう思い込もうとした。しかし、一度気づいてしまったこの事実は、しつこくハヤブサの頭の隅に留まり続ける。この太刀は、シュバルツを『喰らう』ことが出来るのだと。
やめろ。
やめてくれ。
俺はあいつを斬りたくない。
斬りたくないと、言うのに――――!
ウオオォォォオオォオオオ――――ッ!!!
「――――!」
天地をつんざく様な化け物の咆哮に、ハヤブサの思考は『現実』に引き戻された。窓の外で勾玉を求めて動き出している『化け物』の姿が見える。
(そうだ―――! 今は、『あいつ』を何とかしなければ……! あれをキョウジに接触させてしまったら、何もかもが終わりだ!)
おそらくキョウジはもうシステムの掌握に動きだしているはずだ。だから今は、あの『化け物』の足止めをする、あわよくば『滅する』ことこそが、自分の役割なのだ。
龍の忍者は、巨大な女の形をした黒の女神をキッと見据える。あの手合いの敵など、もう何度も屠ってきた。今更、何を臆する事があろうか。
ハヤブサは化け物めがけて、窓から建物の外に飛び出した。
(…チッ! 貧乏くじを引いたぜ……)
捕虜たちを捕らえている牢の見張りの兵士は、そう思ってため息をついていた。
先程館内放送で「キョウジ・カッシュを捕らえた者は、褒美は思いのまま―――」と、告げられるのを聞いていた。しかし、捕虜たちの見張りを放り出すことに対して許可は下りていない。にもかかわらず、ここを放り出してキョウジ・カッシュの探索に加わった事が上に知られたら、おそらくただでは済まない。下手をしたら自分が牢に放り込まれ、『実験材料』にされる側に回ってしまうだろう。
シュトワイゼマンも仮面の魔道師も、『実験材料』の数が減ってしまう事を、非常に嫌っている。今ここで、あの二人の機嫌を損ねるような事だけは、断固として避けねばならなかった。
結果として、彼は今持ち場を離れるわけにはいかず―――同僚と二人、任務を遂行中なのであった。シフトの交代まで、あと2時間ある。
不意に、カタン、と音がする。
「?」
疑問に思って顔をそちらに向けた彼の視界に、一人の青年の姿が飛び込んできた。見覚えのあるその姿に、思わず息を飲む。
「キ、キョウジ・カッ………!」
そう口走った瞬間、鳩尾に凄まじい衝撃を喰らって、彼は意識を手放した。
「どうした?」
もう一人の兵士も、そう言った瞬間に、延髄に手刀を喰らって気を失う。
「よし! ドモン! ぶち抜け!!」
二人の兵士を倒したシュバルツに、ドモンが応じる。
「でええええいっ!!」
ドン!!
派手な音を立てて、捕虜たちを閉じ込めている区画へと続く扉が吹っ飛ばされた。その音に、牢の中に閉じ込められていた捕虜たちが、それぞれに顔を上げる。
「な、何だ? あんたたちは―――」
「貴方がたを助けに来た! 悪いが少しそこから離れて―――!」
シュバルツの言葉に、捕虜たちは全員慌てて奥の方に引っ込む。
「はあああ――――ッ!!」
裂帛の叫びと共に、シュバルツは持っていた刀で牢の出入り口を斬り裂いた。その向こうでドモンも、牢を破壊している。その区画に在った4つの牢は、兄弟たちによってあっという間に破られてしまった。
「さあ早く! ここから出て! 今の内に、逃げるんだ!」
シュバルツの言葉に、捕虜たちは戸惑いながらも牢を出る。
「に、逃げると言ったって……どうやって―――」
一人の捕虜の言葉に応えるべく、シュバルツはドモンの方へ振り向く。
「ドモン!! この壁をぶち抜け!!」
そう言いながらシュバルツは、牢の間にある壁を指す。
「え?」
瞬間シュバルツの意図が把握出来無かったドモンは戸惑った。『ぶち抜け』と言われても、ここは地下だ。壁を撃ち抜いた所で、地面が現れるだけで、脱出するのは不可能なのではないだろうか。それとも兄は、『トンネルを掘れ』とでも言いたいのだろうか。
「いいから早く!! 思いっきり!! 手加減なしで!!」
「わ、分かった!」
シュバルツの気迫に押されるように、ドモンは頷いた。『兄』の言う事に間違いはないはず。きっと、何か考えがあるのだろう。
「はぁぁぁ――――ッ!」
ドモンは大きく息を吐きながら、臍の辺りにある丹田に、『気』を練り込んでいく。彼の纏う『闘気』が、爆発的に膨れ上がって行った。
「でえいっ!!!」
兄の言葉を信じて手加減無く放たれた拳は、ドォン!! と、派手な音を立てて、その壁をぶち抜いた。大きく深く穿たれたその穴の中に、シュバルツが走り込む。
「よしっ! 計算通り―――」
そう彼が叫んだ視線の先には、地上へと続く階段が存在していた。
「さあ―――ここから上へあがっていけば、地上へと出られる! 武器もある!!」
そう言いながらシュバルツは、持ってきた武器を捕虜たちに差し出した。
「ありがたい!」
感謝の言葉を述べて受け取る者もいれば、「待て」と、疑問の声を上げる者もいた。
「お前が、此処の回し者じゃない、と言う保証はあるのかよ? 武器を与え、脱出路をちらつかせて俺達をぬか喜びさせて―――新しい武器を試そうとか言うんじゃないだろうな?」
「―――!」
その言葉に、ドモンは憤り、シュバルツの表情が哀しみゆえに曇る。この極限の状況。実は、信じる方が難しい事を、彼は知っているからだ。
「……この階段は、下の『訓練場』から地上に伸びている『脱出路』だ。今、この施設は私たちが襲撃した事によって混乱が起きている。逃げるのなら、今しかない」
シュバルツは、疑いの眼差しを正眼で受け止めながら、淡々と事実を述べた。
「……お前の言葉が、『真実だ』と言う保証は?」
そう言いながらその男は、シュバルツに銃を向けてくる。だが、シュバルツの表情は変わらなかった。
「……信じてもらうしかない」
シュバルツの言葉に、銃を向けている男の眉がピクリとつり上がる。
「どうしても『信じられない』と言うのなら、その銃で私を撃ち、そして出て行け!」
「な―――!」
「兄さん!!」
ドモンが動こうとするのを、シュバルツは手で制する。そのまま彼は、背後に弟を庇うように、銃を向ける男に戦闘意思が無い事を示すかのように―――手を広げてそこに立った。
「…………!」
そんなシュバルツの様子に、銃を向ける男の殺意が揺らぐ。それを見透かしたかのように、彼の背後から声がかけられた。
「やめろ、ワッツ。この勝負、お前の負けだ」
「で、でもお頭―――」
ワッツに『頭』と呼ばれた男が、のそりと動いてくる。
「その御仁も命をかけている。でなければ、わざわざこんな所に乗り込んで、そんな事を言うわけがなかろう。しかも、ご丁寧に、こんな武器まで手渡してくれて―――」
そう言いながら、頭は手にしたショットガンに弾込めをしている。
「いい『得物』だ…。これだけあれば、我らも戦えるな」
「では……?」
シュバルツの問いかけに、頭は赤茶けたひげ面に、白い歯を浮かべる。
「俺は、あんたの言葉を信じよう。我らは『赤の盗賊団』……受けた恩義は忘れない」
頭のその言葉に、シュバルツも笑みを浮かべる。
「ありがとうございます」
頭とシュバルツは固く握手を交わした。
「兄さん! 話がついたんなら急いで―――!」
ドモンの急かす言葉に、一同は頷いた。
「武器を持っている物で外側を固めろ! 自力で走れない者には手を貸してやれ!」
頭の指示に従って、虜囚たちの脱出作業は続いていた。穿たれた穴の先にある階段の所でシュバルツが皆を「上へ!」と誘導をし、殿をドモンが務めている。
「いたぞ!!」
ドモンの姿を発見した兵士たちが、怒号と共に牢のある部屋になだれ込もうとする。
「でりゃあああっ!!」
ドモンの拳圧弾が、兵士たちを次々と吹っ飛ばして行った。
「これは、おまけだ!!」
間髪いれずにドモンは手榴弾の安全ピンを口で外して、投げる。
「うわああああっ!?」
手榴弾が転がった先に居た兵士たちは、蜘蛛の子を散らすように逃げて行った。それからきっかり2秒後に、手榴弾が派手に爆ぜる。
「へっ! ざまぁみやがれ!!」
この間に牢に居た虜囚たちは、全員階段の方へ脱出する事に成功していた。ここでの自分の役目は終わったと悟ったドモンが、踵を返して脱出しようとする。
その瞬間、天井の一部がいきなり落下してきた。それは、まるで防火の扉の様に、ドモンと兵士たちの間を遮断する。
「!?」
ドモンは一瞬訝しく思ったが、「これで追手はこちらには入って来られないだろう」と単純に考えて、自身の穿った穴から階段へと続く方へと走り込んだ。
「―――!」
その頃シュバルツの方も異変を察知していた。階段の下の方から、何者かが上がってくる気配がする。
空気を切り裂く気配。シュバルツは、躊躇う事無く抜刀した。
キィィイイ―――ン!
シュバルツが鞘走らせた刀は、違う事無く銃弾を真っ二つにしていた。
(来たか……!)
シュバルツが刀を構えるのと同時に、ドモンが走り込んでくる。
「兄さん!!」
「ドモン! 全員脱出できたのか!?」
シュバルツの言葉に、ドモンは頷く。また空気を割く気配。振るわれた刀は、銃弾を斬り裂いた。
「追手がかかっている! 皆、急いで!!」
シュバルツの言葉に、虜囚たちは階段を駆け上がる。それでも何人かは、共に戦う事を申し出てきた。
「あんたは我々の恩人だ」
「ともに脱出を―――!」
その言葉にシュバルツは頭を振る。
「申し出はありがたいが、狙われているのは私だ。私と共に動く方が、貴方がたにかかるリスクが増える」
「…………!」
いや、しかし―――と、志願して来た男たちが身をのりだそうとした瞬間。パラ…と、天井から小石が落ちてきたかと思うと、大きな岩が、通路を塞ぐように降ってきた。
「兄さん!」
「危ねぇ!」
ドモンがシュバルツの背を引っ張り、志願して来た男たちもまた仲間に手を引っ張られたおかげで、岩につぶされた者はいなかった。しかし、岩はシュバルツと男たちの間に落ちて、それぞれを分断していた。
「大丈夫か!?」
シュバルツの呼び掛けに、岩の向こうで男たちが「応!」と、答える。安堵の笑みを一瞬浮かべたシュバルツは、すぐに男たちに呼びかけた。
「どうか貴方がたはそのまま脱出を―――! 幸運を祈っている!!」
こうなってしまっては、男たちもシュバルツと共に行動する事を断念せざるを得ない。
「分かった! あんたも―――!!」
男たちは口々にそう言いながら、階段を駆け上がって行った。途端に、シュバルツ側の方が、激しい銃撃に見舞われる。
「兄さん!!」
ドモンがシュバルツを背後に庇うように立ち、鉢巻きで銃弾を弾いている。階下から、兵達が駆け上がってくる足音が響き渡ってきた。
「済まないな、ドモン」
シュバルツが、ドモンの横に並んで応戦しながら、ドモンに声をかけてきた。
「何が?」
「退路を、塞ぐような形になってしまって―――」
シュバルツの言葉に、ドモンが「ああ……」と、答えた後、にやりと笑みを返した。
「そんなもの―――入ってきた時が正面からだったんだから、出る時も、当然正面から堂々と出て行けばいいだろう? 何も問題ないよ」
「―――!」
ドモンの言葉にシュバルツは瞬間目をぱちくりさせた後、苦笑に近い笑みを浮かべた。
「―――ったくお前って奴は……まあ、その通りなんだろうけどな……」
「だろ?」
そんなシュバルツに、ドモンは得意げな笑みを返す。
「よし! じゃあ、行くか!」
シュバルツの声が合図になるかのように、兄弟たちは、階段を猛スピードで駆け下りだした。
キョウジは既に、10個目の関門を突破していた。分かる。残る関門は、おそらくあと僅か―――。目指すシステムまで、あとひと押しだ。
(痛ッ………!)
キーの上を走る指に、時々痛みが走る。恐らく、シュバルツを治す時に出来た傷が、開きかけているのだろう。
「……………!」
キョウジはギリ、と歯を食いしばった。
こんな所で。
そんな理由で。
立ち止まるわけには、行かない。
自分はシュバルツを利用しているのだから、尚更だ。
(くそっ………!)
キーの上を走るキョウジの指のスピードは、衰えるどころか、なお増して行くばかりであった。
『黒の女神』と相対しながら、ハヤブサは辟易していた。
女神から繰り出される攻撃自体は、物理的な物ばかりだ。たとえば、腕を振り下ろしてくる。足で踏みつけてくる。火力を使ったとしても、指の先から出る細いレーザーの様なものだ。それらは、ハヤブサの能力を持ってすれば、余裕でかわす事が出来た。
ギアナ高地で見せた、地形を変えるような強力な火力は、幸いな事に使ってこなかった。やはり基地に対して、致命的なダメージを与えないようにしているのであろう。この『化け物』が、ある程度外から制御されていると窺わせるには十分なものであった。ここまでは、キョウジの読みが当たっていた―――と、言える。
だから、女神と相対する事自体に問題があるわけではなかった。
ならば、何故ハヤブサは辟易しなければならないのか――――その原因は、先ほどから龍剣からひっきりなしに発せられる『声』にあった。
振り下ろされる拳をかわして、女神の腕に龍剣を突き立てる。
「はああああああああっ!!」
そのまま腕を駆け上がりながら龍剣で腕を斬り裂いて行く。
「ギャァァアアアァァアアアア―――ッ!!」
腕を割かれ、のけぞる女神―――だが、すぐに腕が再生した。
そして、女神を攻撃するたびに、『龍剣』が声を発するのだ。
違ウ―――。
コイツハ『虚空』ダ。
『本体』ヲ斬レ。
(五月蝿い……)
ハヤブサはその声を極力無視しようとする。しかし、無視しようとすればするほど、龍剣が強く訴えてくる。
アソコダ。
アソコニ居ル、『勾玉』
アレダ。
(五月蝿い! 黙れ!)
ハヤブサは半ばうんざりしながら龍剣に告げる。しかし、龍剣の声は止まなかった。
アノ『勾玉』ヲ―――!
『勾玉』ノ持チ主ヲ斬レ!
「五月蝿い! 黙れと言うのに!!」
意識するまいとハヤブサが抵抗すればするほどに、龍剣は勾玉を持つキョウジの存在を色濃くハヤブサに示してくる。あれを斬らせろ、あれを食わせろ、と、訴えてくる。
(冗談じゃない! 使い手は俺だ! 剣の意思に食われてたまるか―――!)
今の自分の役割は、虚空でも何でも、この『化け物』の足止めをすることだ。キョウジを斬るにしても、勾玉を滅するにしても―――それは『今』じゃない。まだ早いんだ。キョウジはまだ―――化け物に『何もしていない』
自分がキョウジを斬るのは最終手段だ。キョウジの力が、この『化け物』に及ばなかったと判断した時だけだ。この化け物が、外からある程度制御されている可能性がある以上、キョウジの試みが成功する可能性がある。それがあるうちは、自分はキョウジを斬るわけにはいかないのだ。
(キョウジ―――まだか、早くしろ……!)
『斬らせろ』と、腕の中で暴れる龍を制御しながら、ハヤブサは『黒の女神』に立ち向かって行った。
「何だと―――!?」
訓練場から脱出路へと続く階段で発砲していた兵士は驚いた。何故なら、ターゲットは階段の上を走って来ていない。壁を走って来ていたからだ。
「ハ―――――ッ!!」
ドカッ!!
慣性と重力の力を得たシュバルツの蹴りを喰らった兵士数人が、たまらず吹っ飛ばされる。
「うおりゃああああっ!!」
その後ろから、弟の拳圧弾が飛んでくる。逃げ場のない狭い階段上では避けられるはずもない。兄弟二人は階段に居る兵士たちを蹴散らしながら、あっという間に階段の終点までたどり着いた。『奇襲には高さを利用しろ』とよく言われるが、この二人の戦いは、文字通りその威力を証明していた。
「さて、ここから先は『訓練場』だが……」
兵士たちを倒して一段落したシュバルツが、そっと中の様子を覗き見る。特に何事もなければUターンして、再び地上に出る事をシュバルツは考えていた。
しかし。
中の様子を見たシュバルツの顔色が変わる。
そこにいたのは『ダレク』だった。ギアナ高地で、ドモンに倒されて絶命したはずの『ダレク』―――しかも、彼の様子がどこかおかしい。
「ぐはははははは! ひゃはははははは!!」
彼はひたすら高笑いをしながら、銃を乱射している。銃弾を受けて、そばにいた兵士たちが次々と倒れていた。
それだけでも十分目を覆いたくなる光景であったが、異変はそれだけでは収まらなかった。何と、銃弾を受けた兵士たちが、次々と起き上がってきたのだ。しかも、兵士たちの皮膚が金属の様に硬質化し、ダレクと同じように凶悪な笑みをその面に浮かべ始めている。
(DG細胞―――!)
シュバルツがそう悟った瞬間、既に彼の身体が動いていた。
「兄さん!!」
ドモンが止める間もあればこそ―――シュバルツは訓練場の中の、ダレクに向かって突進していた。
「止めろ!!」
声と共にシュバルツの鉄拳がダレクに向かって飛ぶ。殴られたダレクは、銃を手放しながら派手に吹っ飛ばされた。地面に叩きつけられたダレクの上に、シュバルツは馬乗りになる。
「何故そんな事をする!? 貴様、これがどういう物なのか、分かっているのか!?」
ダレクの首根っこを捕まえながら、シュバルツは叫んだ。
相手は既に、DG細胞が脳まで到達している。だから、こんな事を言った所でもう相手には通じていない。分かっている。
でも―――叫ばずにはいられなかった。
DG細胞に振り回される者の悲劇など、自分達だけでたくさんだ。
「グフフフフ……」
当然ダレクはシュバルツの言葉にまともな反応など返さない。焦点のあっていない眼差しをこちらに向けながら、ただげらげら笑っている。そんなシュバルツの背後に、DG細胞に侵された兵士たちが迫る。
「………!」
ここに至って、やっとシュバルツは、自分が無防備に敵の真ん中に飛び込んでしまった事実に気づく。凶悪な目つきになった兵士たちが、じりじりとシュバルツとの距離を詰めてきた。
しまった、と、シュバルツが思った瞬間。
「シュバルツ! どけっ!!」
ドモンから『シュバルツ』と呼ばれたことで、彼の身体が咄嗟に動いた。シュバルツの姿が、その場から消えたと同時に
「石破天驚拳!!」
と、ドモンの拳がその場を襲う。紋章の力を得て放たれたその拳は、DG細胞に侵された兵士たちをあっという間に瞬滅した。ダレクも少し巻き込まれて、右腕が無くなっている。
「あ………」
少し離れた所に着地して、茫然とその様を見ていたシュバルツに、ドモンが手を差し出してきた。
「兄さん、大丈夫か?」
「ドモン……」
ドモンの手をとりながら、シュバルツは思った。
(そうだった……。ドモンの『紋章の力』は、DG細胞を消す事が出来る……)
ならば、私も消してもらう事が出来るのだろうか。
この不自然な身体を、その紋章の力で―――。
「…………!」
シュバルツの眼差しから、何かを感じ取ったのだろうか。ドモンの眉がピクリとつり上がった。
「俺は、絶対に嫌だからな…!」
「ドモン……」
「俺は……絶対に、あんたを撃たない!!」
「――――!」
ドモンにそう言われたシュバルツは、嬉しさと同時に、何故か淋しさも募った。
(もし、『撃つ』と言ってくれたなら……私はお前に兄貴面をする事を、止める事が出来るのにな……)
そう思ったが故に、彼の面には、少し淋しげな笑みが浮かぶ。
「そうか……」
そう言いながら、シュバルツはドモンの手を取って立ち上がった。
刹那。
ガシャン!! と、派手な音を立てて、訓練場の各出入り口の扉が封鎖される。それと同時に、仄暗い笑い声が訓練場の中に響いた。兄弟がその声のした方に顔を向けると、訓練場の中で、小高いステージのようになっている場所に、仮面をつけた人物が佇んでいた。そこから少し離れた更に高いボックス席の様な所に、シュトワイゼマンの姿も見える。
(待ち受けられていた―――!)
この二人がそろった姿に、シュバルツは直感的に悟った。
「よく来たな……待っていたぞ。君の事は何て呼べばいいのかな? 『キョウジ君』かね? それとも……『シュバルツ君』かね?」
「…………」
シュバルツは沈黙を返した。ただ、どちらの名を呼ばれるにしろ、この仮面の男から呼び掛けられるのは、ひどく不快だと思った。
「クククク……この建物に入って、まさかまっすぐあの虜囚たちを助けに向かうとは……。おかげでこちらは、たいして罠を張る事もせず、君をここまで導く事が出来たよ。あの虜囚たちには、礼を言わねばならんのかな……」
そう言って仮面の魔道師は愉快そうに笑う。それからふと、彼は顎に手を当てた。
「……それにしても、解せんな……」
「………?」
「君は、あの虜囚たちとは何か縁故があるのか? 顔見知りかね?」
「いいや」
シュバルツは正直に首を振った。あの虜囚たちとは、縁も所縁もない。顔を合わせたのも、今日が初めてだ。
「それならば、何故……わざわざ彼らを助けた? 彼らは君に、何か見返りを与えてくれたのかね? そういう約束でもしたのかね?」
「――――」
酷く的外れな質問をされたような気がして、シュバルツは言葉を失う。
見返りが欲しくて、彼らを助けたわけではない。そんな物、最初から期待などしていない。
ただ「助けられるから、助けた」だけだ。生きられる可能性のある『命』なのだから、そうした方がいいと思った。本当に、それだけだった。だが―――この仮面の男にそう言ったとしても、おそらく理解してはもらえないだろう。
「……貴方に、いちいち説明する気はないし、理解してもらおうとも思っていない」
だからシュバルツは、低い声でそう返す。
「ククク……怖い怖い……」
そう言って暗く笑う魔道師をシュバルツは暗澹たる気持ちで見つめながら、(どうする)と、考えていた。
この仮面の男の持つ魔力は、自分にとっては非常に危険な物だ。先の戦いでこの男につけられた傷を、自分の自己再生では治す事が出来なかった。だから、この男と相対する事は、正直避けたかったところではある。
しかし、と、シュバルツは思う。
この男がこちらに来た、と言う事は、キョウジへのマークは薄くなっているとみていい。キョウジの作業がどこまで進んでいるかは分からないが、出来るだけ、こちらにあの男の注意を引きつけておく必要があると思った。
「どうだね?『シュバルツ君』……私と取引をしないか?」
「取引?」
怪訝そうな顔を向けるシュバルツに、仮面の魔道師が笑いながら言葉を続ける。
「私は温厚な人間だから―――必要以上に事を荒立てたくはないのだよ。分かるだろう?」
「…………」
「私は、君の『虜囚を逃がす』という要望に答えた…。だから、今度は君が、私の要望に応える番だとは思わないか……?」
「どういう、事だ?」
まっとうな『取引』など、この男からは期待できるはずもないが、シュバルツは一応聞いた。時間を稼ぐためだ。
「我が元に来給え」
仮面の魔道師は、ストレートに要望をぶつけてきた。
「――――!」
「君がその身を私に委ねてくれるのならば―――君の隣にいる弟の身の安全は保障しよう。それと、もう一人の……『キョウジ君』の……」
「断る!!」
仮面の魔道師の言葉を途中で撥ね退けるように叫んだのは、それまで沈黙を守っていたドモンであった。
「…私は君とは話していない。こちらの『シュバルツ君』……」
「うるさい!! 黙れ!!」
またしてもドモンは、仮面の男の言を遮るように声を出す。この男に兄たちの名前を呼ばれる事は、ドモンにとってもひどく不快だった。それこそ、虫唾が走るほどに。
「そんな取引は、こちらからお断りだ!! いいか!? よく聞け!!」
ドモンは、怒りを隠そうともせず、仮面の男を睨み据えた。
「兄を犠牲にして―――喜ぶ弟がどこにいる!!」
ドモンのその言葉に対して、仮面の魔道師は可笑しそうに笑う。
「クククク……結構いると思いますけどね? 『人間』とは―――そう言う者でしょう? 自己のために、他人を踏みにじるのは、当たり前―――」
「他の奴の事など知らん! だが―――『俺は』いやだ!!」
ドモンは拳を握りしめる。
「兄さんだけを犠牲にして……自分だけが助かるなんて……!」
それは、まさしく1年前の『デビルガンダム事件』の時の自分達の姿だ。あの時兄は、文字通り『犠牲』になろうとしていた。
嫌だ。
誰が何と言おうと。
あんな光景を見るのも、あんな気持ちを味わうのも。
もう二度と。
絶対に―――。
「嫌だ!! 俺は絶対に―――いやだ!!」
ドモンはいつしか大声で叫んでいた。
「ドモン……」
シュバルツはただ、ドモンを見守った。あの『デビルガンダム事件』は、自分の『罪』故に起こったものだ。だから自分は、その罪の償いをしていたにすぎない。弟であるドモンはむしろ―――それに巻き込まれてしまった『被害者』になるのだ。
それなのに、こんな自分なんかのために、拳を震わせて『嫌だ』と叫ぶ弟は―――優しすぎる、と、シュバルツは思った。
「ククク……では、交渉は『決裂』と、言う事で、よろしいのかな……」
仮面の魔道師は、仄暗く笑いながらそう言った。
(どうする?)
シュバルツは懸命に考えた。あの男と直接相対する事は、自分にとっては危険だ。だが、キョウジのためにあの男を、まだ自分に引きつけておかねばならない。
時間を稼がねばならない―――が、このままでは、戦いにもつれ込む事は避けられそうにない。
自分はどうなってもいい。だが弟は。弟だけは、何としても守らなくては。
(いざとなれば…ドモンだけでも、何とか訓練場の外に―――!)
そう思ってシュバルツがドモンに視線を走らせると、ドモンもこちらを見ていた。
「兄さん―――」
ドモンが小声で、シュバルツに声をかけてくる。
「兄さん…。俺は、何をすればいい?」
「…………!」
シュバルツは驚いた。あれほど怒りに猛っていたドモンの眼差しが、冷静そのものであったからだ。
(ここだ)
と、ドモンは思った。
兄を―――シュバルツを守りたい、その『信』を得たいと思うのならば、ここで自分が踏ん張らなければならないのだと。
いくら敵がむかつくからとは言え―――その挑発に簡単に負けて怒りの感情に流されてしまうようでは、いつまでたっても子供のままだ。怒りの感情は兄を振り回すだけにしかならず、その足を引っ張るだけになる。自分は兄を守りに来たのだ。手助けをしに来たのだ。
この局面で、自分が兄の足手まといになって、結果として、兄を窮地に追い込んでしまう事だけは、何としても避けねばならないと思った。それが出来ずして―――何がキング・オブ・ハートだ。
「戦いに突入する事は避けられないだろうな……。だが、キョウジのためには、もう少し時間を稼ぎたいところだが…」
ドモンは大丈夫だろうかと思いつつ、シュバルツはそっと自分の意図している所をドモンに伝えてみる。ここでまともな話が出来なければ、作戦を練り直さねばならないからだ。
「……と、言う事は、ここでしばらく暴れていいってことだな。分かった!」
その言葉と同時に、ドモンの纏っている殺気が跳ね上がる。
「お、おい。暴れるのはいいが―――」
見境なく仮面の男に突進して行きかねない弟の様子に、シュバルツは慌ててくぎを刺す。その言葉に、ドモンは笑みを返した。
「大丈夫だって! 正門前の広場での戦いと、やる事は変わらないんだろ?」
「――――!」
「見せつけてやろうぜ! 俺たちの力を!!」
そう言ってドモンは、シュバルツに向かって片方の拳を突き出してくる。ドモンのその笑みと言葉に、シュバルツは少し安心した。この局面で笑う事が出来る弟の冷静さは、本物だ。
「……無茶はするなよ」
シュバルツは多少苦笑を含んだ笑みを浮かべながら、ドモンに向かって同じように拳を突き出す。
「兄さんこそ―――あの仮面の男に攻撃されたらやばいんだろ? 無茶するなよ!」
「分かっているよ」
トン! と、音を立てて、兄弟同士の拳が合わさった。
兄弟がそうしている間に、あちこちから兵士やら合成獣やら殺人機械やらの軍団が訓練場に入ってくる。どうやら仮面の魔道師は、あらかじめここに兵力を集めていたようだった。兄弟たちは、あっという間にそれらに十重二十重に囲まれてしまう。
「『シュバルツ君』……考え直すなら、今ですよ」
仮面の魔道師の、勝ち誇ったような響きを含んだ声が響く。
「残念ながら……『兄』として、弟の望まない事は出来ないんでね―――お断りだ!」
シュバルツもきっぱりと言い放った。これでもう、『言葉』による交渉の余地は、無くなった。
「その言葉―――すぐに後悔させて差し上げましょう…」
白い仮面に黒く穿たれた目の奥が、妖しい光を帯びる。口調こそ慇懃だが―――拒絶されたことに対する憤りが、あちこちから滲み出ていた。
「ダレク―――」
くいっと魔道師が指を動かすと、ダレクの失われたはずの右腕が再生した。それどころか、手足の先からケーブルの様な物が無数に伸び、その身体を巨大にせしめて行く。ダレクは、あっという間に手に無数の武器を備えた巨大な二足歩行戦闘機の様に自己進化して行った。
(…………!)
それと同時に、シュバルツの中にも、何か嫌な感触が走り抜けていく。この感触には覚えがあった。ギアナ高地で一度味わったものだ。
(これは、あの魔道師の力によるものだったのか…。それにしても……DG細胞が、ここまであの男の『魔力』に引きずられるとは―――)
シュバルツは、自分の中の不快感を表に出さないように懸命にこらえた。もし、あの男の魔力に自分のDG細胞が感応していると知られてしまったら、それこそ向こうにどんな手を打たれてくるか分からない。
「行くぞ! ドモン!!」
自身の中の不快感を振り払うように、シュバルツは叫んだ。
その声が合図となるかのように、訓練場の中に戦いの嵐が巻き起こる。
シュバルツが敵を切り裂きながら間を走り抜け、ドモンがその周りに拳圧弾を放つ。シュバルツを追いまわしていたら、弟の拳にまとめてやられ、弟を狙い撃ちしようとしたら、いつの間にかシュバルツが傍に来て攻撃される。兄弟の連携は、ここでも見事に発揮されていた。
そんな中、魔道師は目を妖しく光らせながらシュバルツを見ていた。
魔道師には確信があった。あの『シュバルツ』と言う人間はDG細胞を持っている。それ故に、おそらく自分があの男に触れる事が出来さえすれば、意のままに操る事が出来るのではないかと。
だから乱戦の中、魔道師はひたすらシュバルツに触れる機会を伺った。
だが、シュバルツの方もその危険性をとっくに察知しているのか、敵と激しく応戦しながらも、常に魔道師との距離を一定以上に保つようにしている。
(ならば……)
魔道師は妖力を使って、ゆらり、と、その姿を消す。
シュバルツが機械兵を刀で撃退した瞬間を狙って、魔道師はその背後に姿を現した。
(もらった――――!!!)
無言で鉤爪を振り下ろす。だが、鉤爪が彼の肉を捕らえる直前、シュバルツの姿がいきなり消えた。
「――――!?」
消えたシュバルツの姿を魔道師が探していると、「石破天驚拳!!」という叫び声と共に、巨大な『気』の塊が飛んでくる。魔道師は間一髪、身体をよじって避けた。しかし、避け損なった腕の一部が『気』の塊に触れて、チリ、と音を立てて焼かれる。
「………!」
焼かれた腕の一部は、再生しなかった。ぶすぶすと音を立てて、傷口に煙が燻ぶっている。
(何だあの男の力は―――!?)
驚愕の眼差しで、この拳を放ったドモンを見る。ドモンは既に、仮面の魔道師の方には見向きもせず、自分の周りに群がる敵と戦っていた。
仮面の魔道師は、ドモンの持つ『紋章の力』の危険性に、初めて気づいた。先程の拳、まともに浴びていたら、本当にこちらが『消されて』しまうかもしれない。
(おのれ……!)
仮面の魔道師は歯ぎしりする。冗談じゃない。ここまで来て―――たかが『人間』ごときの力にやられてたまるか…!
「皆の者!! あの赤いマントの男を狙って……!!」
そこまで叫んだ魔道師の眼前で、いきなり飛来して来たクナイが爆ぜる。
「ク………ッ!」
熱と爆風を避けるために、魔道師は後退せざるを得ない。少し距離を取ってから、魔道師はクナイが飛んできた方向を見た。するとそこには、片手でクナイを二本ポンポン、と、お手玉するようにしながら、じ~っとこちらを見ているシュバルツの姿があった。
(どうした。お前が狙っているのは、私ではなかったのか?)
彼の視線が、魔道師に向かってそう訴えかけている。敵に囲まれていると言うのに、その彼の行動は、あからさまに挑発の意味を含んでいた。
「おのれ!!」
瞬間魔道師は、目の前が真っ赤に染まるほどの怒りを覚える。
それは周りにいた兵達も同様であったようで、皆がシュバルツに殺到しようとした。だがすぐに、弟の『紋章の力』を含んだ拳が飛んで来て、周りの兵達は瞬滅されてしまった。
「ダレク!!」
兎に角、弟の方を何とかしなければ、シュバルツに触れるどころではないと悟った魔道師は、ダレクをドモンに向かわせる。ダレクの巨体が、ズシン、ズシン、と音を立てながら、ドモンに近づいて行った。
「……………」
ダレクの巨躯を眼前にしても、ドモンが動じる事はなかった。ふ―――っと静かに息を吐きながら、構えを取る。周りにいた兵達も、二人の戦いに巻き込まれる事を遠慮したのか、少し距離を取った。そこに奇妙な空間と、静寂が生まれる。
しばし両者は無言で睨みあったが、先に仕掛けたのは、ダレクの方であった。足首の辺りからランチャーミサイルが無数に発射されると同時に、ドモンに向かって巨大な鎌状の武器を振り下ろす。ドモンがミサイルを避けるために飛びあがる所を、鎌の餌食にするつもりの攻撃であった。
「――――!」
その意図を本能的な直感で見破ったドモンは、ミサイルを横っとびにかわす。かわされたと悟ったダレクは、鎌を振り下ろす位置をドモンの方に合わせてずらす。ドモンは、それを転がってかわした。
「ドモン!!」
ドモンの身に危険が迫っていると見て取ったシュバルツが、ドモンの加勢に行こうとする。だが、シュバルツが助けに入ろうとするより早く、ドモンが叫んだ。
「こちらに構うな! 兄さんは、自分の戦いに集中して!!」
「―――!」
ドモンの声に、シュバルツは瞬間足を止める。だがそのおかげで、自分のすぐ近くに来ていた魔道師の気配を、察知する事が出来た。自分に向かって振り下ろされる鉤爪を、シュバルツは間一髪でかわす。
「チィッ!」
舌打ちをしながらも魔道師は、更にシュバルツに向かって第2撃、第3撃と繰り出そうとした。しかし、それをしようとした魔道師の眼前に投網のようなネットが広がる。それに絡め捕られるのを魔道師が避けようとしている間に、またしてもシュバルツに距離を開けられてしまった。
(おのれ……!)
歯ぎしりをする魔道師の手元に、シュトワイゼマンからの通信を知らせる光が灯る。
「魔道師よ!」
通信機を取り上げると、苛立ちを隠そうともしないシュトワイゼマンの声が魔道師の耳に飛び込んできた。
「一体いつになったら『面白い事』を見させてくれると言うのだ!? 今目の前で見えている物は、くだらん消耗戦ではないか!!」
「は……もう少しお待ちください。必ずや―――」
「知っていると思うが……わしはそんなに気が長い方ではない! いつまでもは待てんぞ!!」
一方的に怒鳴りつけるだけ怒鳴りつけて、その通信は切れた。魔道師は思わず、その通信機を叩き壊しそうになった。
「全く……! 何回も何回も―――!!」
ドモンは、ダレクから繰り出される攻撃を右に左にとかわしながら、反撃の機会を伺った。
「お前との勝負は、とっくの昔についているんだよ……! それなのに―――!」
ドン!! と、音を立てて、ダレクから振り下ろされた斧が地面にめり込む。立ち上がろうとしたドモンのすぐ上を、鎌が通過する。
(今だ!!)
僅かな攻撃の空白期間が訪れた事を悟ったドモンは、全身を使って飛びあがった。ジャンプの最高地点にダレクの頭頂部があり、ダレクとドモンの視線がぶつかる。
「何度も何度も……しつこいんだ、よッ!!」
そう叫ぶドモンの右手が、黄金色に輝いている。
「喰らいやがれ!! 俺の、『黄金の指』!!」
ガシッとドモンの右手が、ダレクの頭頂部をわしづかみにした!
「ゴッド・フィンガ――――ッ!!」
いわゆる、頭頂部へゼロ距離からの『石破天驚拳』である。これを喰らって、無事で済む者はまずいない。
哀れダレクの巨体は、あっという間に炎に包まれて―――そのまま倒れて行った。
(おのれ……ッ!!)
仮面の下に隠れて見えないが、魔道師は、己が唇を切れるほど強く噛み締めていた。たかが人間二人―――しかも、その片方の身体に触れるという簡単そうに思える事が、どうしてこうも困難になってしまっているのか。
誤算だったのは、あのドモンとか言う男の持っている訳の分からない力だ。あの男の力は、DG細胞をねじ伏せている。それどころか、下手をするとこちらの身すら危ない。
シュバルツの身体に触れる事が出来さえすれば、この状況から逆転する事は可能だ。だが、シュバルツにもドモンにも、全く隙が無い。この二人の連携を崩すことも難しい。
(何か手はないか―――! 何か手は―――!!)
じりじりする様な想いで、仮面の魔道師は戦況を見つめていた。
(ドモン……もう、すっかり1人前だな……)
戦うドモンの姿を見守りながら、シュバルツは思った。
思えば、先の『デビルガンダム事件』の際に、自分はドモンと真剣に勝負をした。お互いに死力を尽くしてぶつかり合い―――僅かの差でドモンが勝った。
その時ドモンの周りには、事件を通して知り合った、助けあえる仲間たちがいた。
支えてくれるレインがいた。
そして、自分は思ったのだ。
『終えていいか』と。
『兄』の役目を。
ドモンを導く『師』としての役割を。
もう、終えていいかと……。
ドモンは、もう戦士として十分に成長していた。もしかしたら自分の方こそが、『弟離れ』が出来ていないのではないかと、シュバルツは苦笑する。
(このまま順当に、時間が稼げれば―――)
戦いながらシュバルツは、そう願っていた。
だが戦いのバランスは、意外な所から破られることになる。
ドカン!! と、派手な音がして、訓練場の天井の一部が崩れ落ちてきた。大きく開いた天井の穴から吹き込んでくる空気が、訓練場内で燃え上がっている炎を更に大きな物にする。
そして―――大量の瓦礫と一緒に、龍の忍者と黒の女神も一緒に落ちてきたのだ。
「――――ッ」
ストン、と着地したハヤブサは、一瞬ガクっと膝をつく。だがすぐに立ち上がった。女神の方も訓練場に着地した後、大きく雄たけびを上げている。
「くそっ!!」
ハヤブサは、既に身体中に傷を作っていた。無理もない。彼は今まで一人で黒の女神のキョウジへと向かう足を、引きとめていたのだから。
「ハヤブサ!!」
その姿に気づいたシュバルツが、ハヤブサに声をかける。
「シュバルツか!?」
その声に気付いたハヤブサも、驚いた様に振り向く。それと同時に。
(リュウ・ハヤブサ………! この勝負、勝った―――!!)
仮面の魔道師の目も、妖しく光っていた。
勝利のための道筋は見えた。後は、自分はそれを実行するだけだ。ちょうどいい按配に、『黒の女神』もこちらに来ている。
(女神よ! 我に力を貸せ!!)
魔道師の呼び掛けに、女神が吠えて応える。
「ドモン・カッシュを襲え!!」
その言葉を、女神は忠実に実行した。女神の手が、脚が、掌から放たれる高熱の塊が、次々とドモンに襲いかかる。
「おっと!」
もちろん、そんな物にやられるドモンではない。女神の攻撃を次々とかわす。だが周りの兵士たちも、こぞってドモンに集中攻撃をしだした。流石のドモンも、じりじりと後退を余儀なくされてしまう。
「ドモン!!」
「兄さんはこちらへ来るな!!」
シュバルツの自分を案じる声に、ドモンはそう返した。敵の狙いはあくまで兄。その為に自分が集中して狙われる事など、先程から繰り返しやられている。自分のせいで兄を窮地に追い込む事だけは絶対に避けるべきなのだ。
案の定、魔道師の攻撃がシュバルツに肉薄する。だが、その気配を察したシュバルツは、またしてもそれを避けた。
(クククク……『弟』からお前を崩せるとは思っていないさ……。だが、こちらはどうかな……?)
乱戦の中、仮面の魔道師はひたすら待った。厄介な弟がシュバルツから離れ、シュバルツとハヤブサの距離が適当に開き、なおかつシュバルツからハヤブサの姿が目に入ると言う、自分が望む位置関係になる事を―――。
(今だ!!)
今がまさにその時と判断した魔道師は、勝利を確信して懐に手を伸ばした。
「リュウ・ハヤブサ!!」
「―――!?」
魔道師の自分を呼び掛ける声に、ハヤブサは思わず振り向く。そして見てしまう。魔道師が高々と振り上げている手の内に、『何』が握られているのかを。
きらり、と光を放つそれを、ハヤブサは覚えていた。あれは確か、残月が持っていた、呪を発動する鏡――――!
しまった! と、ハヤブサが思ったのと、魔道師が地面に鏡を叩きつけたのが、ほぼ同時だった。
ドクン!
鏡から飛び出したどす黒い悪意が、ハヤブサの右手に残されている呪の名残を、強制的に発動させる。
「うぐ……! あ……ッ!」
それは、ハヤブサから戦う力を容赦なく奪う。立っていられなくなった彼は、その場に崩折れてしまった。そこに周りの兵士たちからの攻撃が、ハヤブサに襲いかかろうとする。
「ハヤブサ!!」
ハヤブサの窮地が見えていたが故に、シュバルツの身体は考えるよりも先に動いていた。ハヤブサを救おうと、一直線にその身を走らせる。
「馬鹿!! 来るな!!」
呪を発動した者の狙いを瞬時に悟ったハヤブサは、思わず叫んでいた。
ハヤブサにははっきりと見えていた。
自分に振り下ろされようとする刀よりも早く、こちらに向かってくるシュバルツ。
そしてその背後に迫る、黒い影が―――。
ドン!!
シュバルツは、間に合った。ハヤブサの窮地には。
彼の刀は、ハヤブサに攻撃を加えようとしていた兵士総てを一掃した。
しかし―――。
魔道師の鉤爪もまた、彼を捕らえていた。その爪は、シュバルツの背中から胸を容赦なく刺し貫いていた。
「あ………!」
シュバルツの胸から飛び出した鉤爪の先から、彼の『血』らしきものが、ぽたり、と音を立てて滴り落ちる。
「ついに……捕らえましたよ。『シュバルツ君』……」
シュバルツの背後で、仮面の魔道師が勝ち誇ったように嗤う。
「さあ―――『狂宴』を、始めましょうか―――」
ドクン!!
魔道師の負の魔力が、鉤爪を通して容赦なくシュバルツに注ぎ込まれる。
「うあ……! ああああ――――ッ!!!」
最初に彼の『左腕』が、人間の形を保つ事を止めた。ドゴォッ!! と音を立てて無数のケーブルが派生する。その先には、ありとあらゆる『武器』が形作られて行った。
「素晴らしい…! 素晴らしいぞ……!」
魔力を注ぎ込みながら、魔道師が嗤う。やはりこの『細胞』は、自分の力とよく馴染む。
「おや……この身体―――貴方、『人間』ではありませんね?」
『肉』を抉った時とはあからさまに違う感触を確かめるように、魔道師は乱暴に鉤爪を動かす。
「うぐッ! ああッ……!!」
ガキッ! と硬い金属音と共に、傷の隙間からシュバルツを『構成』しているメカの部分が露出し、『部品』が零れおちる。落ちた部品もまた、『異形のモノ』へと変化して行く。
「『作りモノ』ですね? しかも―――もしかして貴方の全身が、この凶悪な『細胞』で形作られているのですか?」
「う……! ぐうっ!」
自分の根幹が激しく揺さぶられ、邪悪な物が強制的に呼び起されて行く。
シュバルツは頭を振って、その感覚に懸命に抗った。
だが魔道師の負の魔力は、そんなシュバルツをあざ笑うかのように強引に中へと侵食してくる。
「おや……『死臭』までする…。どうやら、貴方の元には『死体』も使われている様ですねぇ」
「………ッ!」
中に入り込んだ魔道師の魔力が、『シュバルツ』を無遠慮に暴き立てて行く。
「素晴らしい……! どこの誰がお前を作ったのかは知らないが――――『これ』を作った人間は、正真正銘の悪魔だな!! アハハハハハハ! クハハハハハハハ!!」
魔道師の耳障りな笑い声が、シュバルツの耳元で響き渡る。
「……やめろ……!」
ざわ、と、シュバルツの心が波立った。
シュバルツの脳裏に、優しく微笑むキョウジの姿が浮かぶ。
やめろ。
何も知らないくせに。
キョウジが『自分』を作ったことで、どれ程己を責め続けているか。
どれだけ涙を流しているか―――。
「キョウジを……悪く言うな……!」
自分はいい。だが、キョウジを悪く言うのは許せない。
何も知らないくせに。
あんなに優しい
あんなに哀しい
涙を流す『悪魔』など―――居るものか!
「おや……怒りました? でもほら……あんまり怒ると―――」
魔道師が愉快そうに笑いながら、シュバルツに声をかける。
「ああっ!」
ドゴォッ!! と、音を立てて、今度はシュバルツの『左足』が、人間の形を保てなくなる。左腕と同じように無数のケーブルが派生して、その数だけ、無数の兵器が出現した。
「兄さん!? 兄さん!!」
兄の身に襲いかかる異変に気付いたドモンが、悲鳴のような声を上げながら走り寄ろうとする。そこに、ズシン! と、音を立てて黒の女神が立ちはだかった。
「どけぇっ!!」
ドモンの気迫と共に放たれた拳が、女神の足を砕く。女神が倒れる横をドモンは走り抜け、兄の姿を見て―――息を飲んだ。
「兄さん――――!」
兄の左半身が、完全に『異形のモノ』と言ってもおかしくない姿へと、変わり果ててしまっている。
「ドモ…ン……!」
弟の声に気付いたシュバルツが、反応を返した。
「ちょうどいい……! さあ、『シュバルツ』―――」
ぐっと、鉤爪に力を込め、魔力を注ぎ込みながら、魔道師はシュバルツに声をかけた。
「まず手始めに……『弟』と『龍の忍者』を―――その手で殺したまえ!」
「………ッ!」
「―――!?」
魔道師の言葉に、『呪い』の力で苦しめられているハヤブサと、立ち尽くしていたドモンが、同時に小さな声を上げた。
「―――ウ!?」
その時キョウジの方も、急な異変に襲われていた。
ドクン!
激しい胸の痛みと同時に、どうしようもない嘔吐感に襲われる。たまらずキョウジは咳き込んだ。
「う……ッ ゲホッ!! ガホッ!!」
ビシャッ! と言う音と同時に、キョウジの目の前が真っ赤に染まる。
「あ………?」
朱に染まった己が手を茫然と見つめるキョウジの口の端から、パタ、パタ、と、血が零れおちている。
(え……? 血……? 何故、私が血を――――)
ここでキョウジの足元の地面がいきなりグニャリ、と歪む。それ故にキョウジは、立っていられなくなった。ガタン!! と、派手な音を立てて、キョウジが倒れる。
「キョウジ!?」
キョウジの異変に気付いた東方不敗が、慌てて駆け寄ってきた。
「キョウジ!? キョウジ!! どうした!! しっかりせんか!!」
「ウ……ウ……ッ!」
シュバルツは「二人を殺せ」と言う魔道師の命に抗うべく、懸命に頭を振る。だがシュバルツの『意志』とは裏腹に―――彼から派生した武器たちは、ドモンとハヤブサに、それぞれ狙いを定め始めた。
「いやだ……! い…や…だ……ッ!」
それでもシュバルツは―――懸命に抵抗の意思を示し続ける。
(シュバルツ……!)
『呪い』の力で強制的にシュバルツのすぐそばで膝をつかされていたが故に、ハヤブサにはシュバルツの声がよく聞こえていた。
(俺のせいだ……! 俺のせいで―――!)
ハヤブサは、忸怩たる思いだった。
この『右腕』―――呪いが穿たれた『右腕』を、何故自分はもっと早く斬り落としておかなかったのか。自分に課せられた呪いの名残を、敵に利用される可能性があると、気づいていながら……!
(くそっ! 動け!!)
石の様に動かない身体を、ハヤブサは懸命に鞭打った。ぐ、ぐ、と、やっとのことで動いた右手が、そばに落ちていた『龍剣』を拾う。
―――喰ワセロ!
「…………!」
剣を掴んだ途端に、凶悪な意志が身体に流れ込んでくる。
ああ分かった。
喰わせてやるとも。
俺の命だって何だって、貴様にくれてやる。
だから―――だから、今だけ。
俺に、力を貸せ!!
ゆらり、と、ハヤブサは立ち上がった。
目が回る。息が上がる。
足が勝手に膝から崩れそうだ。
だが踏ん張る。倒れるわけにはいかない。今入る、ありったけの『気』を込めて、龍剣を握りなおす。
ボウ、と、音を立てて、龍剣に青白い『炎』が宿る気配がする。DG細胞さえも滅する炎の力が―――。
呪いと龍剣の熱で、右腕が焼けるようだった。
顔を上げる。目の前にいるシュバルツと、視線が合う。
「……………」
「おや……『斬る』気ですか?」
仮面の魔道師が、シュバルツを盾にするようにしながら、愉快そうに笑う。
ああ。斬る気だ。斬るつもりだとも。
シュバルツと―――貴様をな。
「ハ…ヤ、ブサ……」
こちらの意図を察したのか、シュバルツの面に、微笑みが浮かんだ。
相変わらず、綺麗に笑う奴だと思った。
馬鹿野郎。
馬鹿野郎。
何故、俺などを助けたりしたのだ。
俺は、『無辜の命』ではない。『人斬り』だぞ。
必要とあらば、命乞いをする奴まで斬ってきた男だ。
この『呪い』は、それ故の名残だと言うのに―――。
いつの間にか、ハヤブサの頬に、熱い物が伝い落ちていた。
ああ。
何故、そんなに綺麗に笑うのだ。
俺は、願っていたのに。
「お前だけは斬りたくない」と、心の底から願っていたのに――――!
不意に、シュバルツから派生している武器たちが、一斉に動き出す。
それは、一直線にドモンとハヤブサに向かっている―――かに見えた。
ドカカカカカカッ!!
派手な音を立てた武器たちは、ドモンとハヤブサを襲わなかった。その周りにいる兵達を掃討する。まるで―――二人を守るかのように。
「おのれ!! 抗うか!!」
魔道師が怒りの声を上げながら、シュバルツに刺している鉤爪を乱暴に動かす。
「うわああっ! あ、ぐ……ッ!!」
それでもシュバルツは、懸命に抗い続けた。武器たちは、あくまでも二人を襲おうとはしなかった。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは、己の身体に『動け』と、命じた。
これ以上、シュバルツをいたずらに苦しませるのは酷だと思った。
もういい。
もういいんだシュバルツ。
せめて、お前の魂がこれ以上汚れないうちに。
清いままで―――逝かせてやる。
それは、彼が『人斬り』であるが故の決断だった。
哀しいかな彼は―――そう、あっさり断が下せてしまえるほど―――人を斬るのに慣れ過ぎていた。
「何だと!?」
仮面の魔道師は、思わず驚愕の声を上げた。呪いの力によって動けないはずの龍の忍者が、立ち上がったばかりか、シュバルツから派生しているケーブルの一つに、トトトトト、と、身軽に登り始めたからだ。その動きは、呪いの影響など少しも感じられないものであった。
馬鹿な、と、魔道師はハヤブサの右腕を見る。
彼の右腕は、自分が発動させた術によって、黒く蟠っていた。それは確かに、ハヤブサの右腕を食い荒らしていると言うのに―――!
(……ここらでいいか…)
ある程度の高さまで登ったハヤブサが、振り返る。力が思うように出せない現状では、『高さ』を力に換えるしかない。シュバルツを一気に斬るために。…彼をこれ以上、無駄に苦しませないために。
眼下に見えるシュバルツの姿が、やけに霞む。
きっと、これは呪いのせいだ。呪いの熱と痛みが、自分の視界を奪っているのだ―――。ハヤブサは、そう思いたかった。
(シュバルツ……シュバルツ……!)
もう、迷わない。
ハヤブサは、トン、とケーブルを蹴った。
其れと同時に龍剣を、大上段に振りかぶる。
「こ、の……ッ! 馬、鹿、野郎ォォォ――――ッ!!」
ドカッ!!
ハヤブサの迷い無き太刀は、シュバルツの身体を真っ二つに斬り裂いていた。
ストン、と音を立てて、ハヤブサは着地する。そして、返す刀で魔道師に斬りかかろうとして―――そこで力尽きた。ガクっと膝をついてしまう。
「――――」
ハヤブサはじっと己が手を見た。『シュバルツを斬った』と言う嫌な感触。おそらくこれは、忘れようとしても忘れられないだろう。
だが次の瞬間。
「……ハ、ヤ…ブサ……」
「!?」
斬ったはずのシュバルツから声を掛けられて、ハヤブサは思わず顔を上げる。
見ると、身体を二つに斬り裂かれた状態のままのシュバルツが―――「喋って」いたのだ。
「……ハヤブ、サ……逃げ…ロ……!」
そう言ったシュバルツの身体が、ぐじゅり、と、音を立てて一つに戻る。
「――――!」
そして今度は彼の『右足』が、人間の形では無くなってしまった。ドゴォ!! と、音を立てて激しくうねりながら伸びてくるケーブルが、ハヤブサを弾き飛ばしてしまう
「ぐぅッ!!」
ドン!!
凄まじい音を立てて、ハヤブサの身体が壁に叩きつけられる。そのままずるずると壁に沿うように床に落ちたハヤブサは―――ピクリとも動かなくなってしまった。
「クハハハハハ! 馬鹿め!! その程度の妖力で、この『化け物』が滅せられるものか!! 痛みと苦痛は、こいつの変化を早めさせるだけだ!!」
魔道師の勝ち誇ったような笑い声が、辺りに響き渡る。
「ハヤブサ……! おい……! 起きろよ……!」
ただ茫然と二人の様子を見ていたドモンが、やっとのことで声を絞り出す。
「…………」
だがハヤブサからの反応は返ってこない。
「くそっ! 何なんだよ……! ハヤブサ! …兄さん……! 兄さぁぁぁ――――ん!!」
目の前で起きている事態にどう対処していいのか分からないドモンは、ただ叫ぶしか出来なかった。
(――――!?)
気がつけばシュバルツは、独り闇の中に佇んでいた。
ドモンが泣き叫んでいた気がする。だから、そばに行って慰めてやらなければいけないのに。
見渡す限り、ただ、闇、闇、闇……。
ここはどこだ?
何故、私はここにいるんだ?
確か、何かと戦っていたような気がする。なのに、それが思い出せない。
戦わなければいけないのに。
抗わなければいけないのに―――。
不意に、人の気配を感じたシュバルツは、そちらに視線を向けた。
闇の中、うっすらと明かりが灯り、そこに一人の女性が佇んでいる。
その女性のシルエットに、シュバルツは見覚えがあった。あれは……。
「母さん……? 母さん!」
あれは、キョウジの母であるミキノの後ろ姿だ。死んだはずの母が何故ここに―――と、一瞬疑問に思うが、シュバルツはとにかく駆け寄った。母と話すことで、この闇から抜けられるヒントが得られればと思った。
だが、母の様子が何かおかしい。
あらぬ方向を見ながら、暗い表情で、何事かをブツブツと呟いている。
「全くひどい話よね……。どうしてこんな事になっちゃったのかしら……」
「か……母さん……?」
シュバルツは母に声をかけてみる。しかし、母の方は聞こえていないのか、全く反応を返さない。ただブツブツと言葉を続けている。
「あの子があんな物を作ったせいで……私は殺されて……。私は『キョウジ』に殺されたのも同然よ……」
「――――!」
母の思いもかけない言葉に、シュバルツの足がピタリと止まる。
「どうして……あんな子を産んじゃったのかしら……」
ドスッ! と、心臓にナイフを突き立てられたようなショックを受けた。
「そうだぞ。キョウジ――――」
不意に、後ろから声をかけられる。振り向くと、今度は険しい表情をした父が、闇の中に佇んでいた。
「と……父さん……!」
「私は一度、あの『細胞』を、封印しようとしたんだ―――」
そこまで言葉を紡いだ父の眉間に、一層深い縦じわが刻まれる。
「なのに何故、勝手に実験などした?」
「そ…それは……!」
「お前が勝手にあの『細胞』を世の中に送り出したおかげで―――どれだけの人に、迷惑をかけた?」
「――――!」
父からの自分を責める言葉に、シュバルツは二の句を継げなくなってしまう。
「大方、自分の才能に驕っておったのだろうよ……」
たたみかけるように言葉を発しながら、ある人物が浮かび上がってくる。
「ミカムラ博士……!」
シュバルツは震えながら後ずさった。だがそれよりも早く、ミカムラ博士は迫ってくる。
「キョウジ君…。君は、知らないだろう……。君のおかげで、わしがどれだけ傷ついていたか……」
「博士……!」
「わしがどれだけ惨めな思いをしたか―――! 君は、知らないだろう!」
「ち…違う……! そんなつもりは……」
そう言いながら後ずさろうとしたシュバルツだが、すぐに何かにぶつかった。
振り返ると、弟であるドモンがいた。酷く冷たい眼差しをした―――ドモンが。
「ドモン……」
シュバルツの声に、ドモンの眉がピクリとつり上がる。
「……何もかも、あんたのせいだ……!」
ドモンの表情が、たちまち怒気を食んだ物へとなっていく。
「あんたのせいで、母は死に!! 父は冷凍刑!! そして俺は―――あんたを追ってこのざまだ!! あんたのせいで―――! 何もかも、あんたのせいで!!」
「あ……!」
シュバルツは、震える体を抱え込んだ。そんな彼の上に、更に言葉が降りかかってくる。
「お前のせいだ!」
「君のせいで―――!」
「俺の名前は『キョウジの弟』じゃない!」
「どうしてこんな子が……私の息子なの?」
「…………!」
シュバルツは懸命に耳を塞ぐ。だが『言葉』たちは―――そんなシュバルツをあざ笑うかのように、強引に中へと侵入してきた。
「かわいそうに……」
そんな中、仄暗い笑い声とともに、不思議な声が聞こえてくる。
「貴方は―――誰にも望まれていないのね……」
「う……く……ッ!」
倒れた状態から懸命に起き上がろうとするキョウジ。しかし、手についた血が、彼の手を滑らせた。
再び床に叩きつけられそうになる。それを、東方不敗が支えて防いだ。
グオオオオ! と吠えながら、一匹の獣が突進してくる。
「やかましい!!」
東方不敗はそれを、裏拳の一撃で撃退した。
「う……!」
腕の中のキョウジが、再び起き上がろうとしている。しかしすぐに咳き込んで―――また血を吐いてしまった。
「キョウジ!? キョウジ!!」
支える東方不敗の腕の中で、キョウジが足掻く。
「後……少し……! 後……少し…なん…だ……!」
そう言いながらキョウジは、ふらふらと自分のパソコンに向かおうとする。だが、立ち上がることすらままならないようだ。
「どこを押せばよいのだ!? 教えろ! キョウジ!」
足で襲い来る獣たちを撃退しながら、東方不敗が叫ぶ。
「……ここ…の、実行……キー……を……!」
「実行キー!? これか!?」
震えるキョウジの指が差すキーを、東方不敗が、タン! と押す。すると、ノートパソコンのつながった先から緑色の光がポウ、と、灯った。それは、あっという間にそのシステムの全体を走り抜け、オレンジ色に光っていたシステムの光を、緑色の光へと変えて行く。
「おお……!」
それは、キョウジのシステムを書き換えるプログラムが、誤る事無く作動した結果が、視覚的に見えた所以の物であった。一点から全体へと緑色の光が広がっていく様は、美しくすらある。東方不敗は、思わず感嘆の声を上げていた。
「……これで、システムの乗っ取りは、ほぼ完了しました……」
そう言いながらキョウジが、いつの間にか立ち上がっている。
「キョ、キョウジ! 大丈夫なのか!?」
東方不敗の問いに、キョウジはにっこり微笑んで、頷く。だがすぐ咳き込んでしまう。咳をするたびに、キョウジの血がパタパタと音を立てて床へと落ちた。
「いかん! キョウジ! それ以上動いては……!」
「駄目です―――。まだ、終わりじゃない……」
キョウジが動く事を止めようとする東方不敗を手で制して、キョウジはゆらりと歩き出す。システムの、手の様な形をしている操作パネルの所まで行きつくと、その上に、彼は手袋をはずして、右手をそっと置いた。
「…………」
右手の下から、緑色の光が灯り、操作パネルの上を走る。キョウジは目を閉じて、静かに『その時』を待った。
ふわ、と、キョウジの周りに、緩やかな風が巻き起こる。
それと同時に、キョウジの胸の辺りが、淡く輝きだす。
その光は、だんだんと強さを増し、やがてキョウジの胸の前で、ある形となって―――キョウジから分離するように、それは現れた。
「そ、それは……? まさか……!」
ある意味神秘的ともいえる光景を前に、東方不敗は息を飲む。
「……こうすれば、『出てくる』と思っていました……。『龍の勾玉』…です……。これで……あの、『黒の女神』が…ドモン達を、襲う事は…無……い……」
微笑みながらキョウジは言うと、そのままふらっと倒れそうになる。それを、東方不敗が慌てて支えた。
「キョウジ…。いつからだ? いつからお主は、そのように具合が悪くなっておったのだ?」
キョウジが病気になったのではと勘繰っている東方不敗に、彼は頭を振って答えた。
「いいえ……。これは、病気じゃない……おそらく―――」
キョウジは自分の身体に問う様に、そっと胸に手を当てる。
「シュバルツに……何か、あったんだ……」
「!?」
「それも……とても良くない…何かが―――」
「シュバルツへのダメージが、お主にフィードバックされておるのか!?」
東方不敗の問いかけを、キョウジは苦笑いながら否定する。
「そんなはずはないんだけどな……そんな風にしていたら、私の身体の方が……とっくにもたなくなっているはず……」
そう言いながらキョウジはまた咳き込んで―――自分の手を赤く汚した。
「と、とにかくお主はしばらく休んでおれ! 勾玉を外に出したのなら、後はワシらに任せて―――」
そう言って東方不敗は、キョウジの胸の前で輝く勾玉に、手を伸ばそうとする。それに気付いたキョウジが、慌てて止めようとした。
「―――! まだ触れては駄目だ!!」
バシッ!!
「ぬぅっ!!」
「――――ッ!」
青白く輝く勾玉が、東方不敗の手を拒絶するように弾いた。思ったよりも強い衝撃を受けた東方不敗の手に、痺れるような痛みをもたらす。
「すみません……。この勾玉は、まだ、私と繋がっている……。ちゃんと『分離』出来ていないんです……」
キョウジがそう言いながら、申し訳なさそうな笑みを浮かべる。
「とにかくマスター……。このままでは…シュバルツも……そして、その近くにいるドモンも危ない……」
「――――!」
「だから……行きましょう……」
「い、行くって……どこへだ?」
戸惑い気味の東方不敗に、キョウジは指をさす。
「あそこへ……。あの、『訓練場』へ……」
キョウジの差す、『訓練場』の方に視線を走らせて、東方不敗は絶句する。天井が壊れた建物から黒煙が噴き出し、そこで火災が起きている事が分かる。更に、『黒の女神』の姿もあった。
「いかん! あんな危険な所にお主を連れて行くわけには―――!」
東方不敗の言葉に、キョウジは笑顔で首を振った。
「正確には……マスター…貴方にあそこに行って欲しい……」
「―――!?」
キョウジが何故そんな事を言うのか、東方不敗は咄嗟に理解出来ない。
「おそらく……『シュバルツに悪い事が起きている』と、言う事は…ドモンもシュバルツも……窮地に追い込まれている……」
「――――!」
「だから…シュバルツには、ドモンの助けが必要で……ドモンには、貴方の助けが必要なんだ……」
「キョウジ……」
東方不敗の脳裏に、自分の愛弟子の姿が浮かぶ。確かにあいつは、一人前になっているように見えて、まだまだ詰めが甘い所がある。それ故に、東方不敗は己が役割を「理解」した。
「分かった……。しかし、お主はどうする?」
東方不敗はキョウジに問うた。システムを掌握したとは言え―――ここは敵の真っただ中だ。こんな所に、キョウジ一人を置いて行くわけにはいかない。
「そうですね…。ですから……私を、あそこに……」
そう言いながら、キョウジは女神の近くにある一本の柱を指す。柱の上に、小さな踊り場が設置されていて、人ひとりぐらいなら安全にその上に立てそうだ。しかし、柱の下は、炎の海と化していた。
「あんな所にか!?」
東方不敗は思わず絶句した。襲われないと分かっているとはいえ、女神のすぐそば。しかも、炎に囲まれているそれは、いつ崩れてもおかしくない状態だ。
「あんな所だからこそ……敵に襲われる心配はない……」
キョウジは微笑みながら言葉を続けた。
「それに……万が一の場合、私は……『倒れる』だけで済む……」
「な―――!」
東方不敗はキョウジの意図している所を理解して息を飲んだ。柱の上で倒れた先にあるのは、炎の海だ。万が一、事態がどうにもならないとキョウジが悟った場合は、自ら炎の海に飛び込んで―――勾玉を封印することで、この事件にけりをつけるつもりなのだ。
「すみません……。ちょっと…もうあちこち動き回れそうになくて……。でも…倒れるだけなら、出来そうだから……」
「――――ッ!」
(おのれッ!!)
東方不敗はいきなり勾玉に手を伸ばしてきた。バシッ!! と、音を立てて、勾玉が東方不敗の手を撥ね退けようとする。だが、それにも構わずに、東方不敗は勾玉に掴みかかった。
「マスター!?」
驚いて声を上げるキョウジに構わず、彼の胸の辺りから―――勾玉をそのままむしり取ろうとする。だが―――勾玉は、キョウジの胸の前から、びくりとも動こうとしなかった。
「うぐッ! ああああああ――――ッ!!」
それどころか、キョウジが悲鳴を上げはじめた。勾玉に力を加えると、彼の方に激しい痛みが襲いかかってしまうようだ。
「う……ッ! あ……!」
キョウジが、苦しそうに胸を抱え込むようにしている。
「キョウジ……!」
東方不敗はついに―――勾玉を、キョウジから引き剥がす事をあきらめざるを得なかった。キョウジを助けたいのに苦しめてしまっているのでは、本末転倒だ。
だが……。
東方不敗は、己の拳の震えを、止める事が出来ない。
「キョウジよ……!」
言葉が溢れるのを―――止める事が出来ない。
「この馬鹿者…! 馬鹿者!!」
「マスター……あっ!?」
キョウジが小さく驚きの声を上げた。東方不敗にいきなり抱きすくめられたからだ。
胸の前の勾玉が、東方不敗を拒絶するかのように、バシン! バシン! と、音を立てながら強い光を放っている。それでも東方不敗は、キョウジを更に深く抱き込んできた。
勾玉が東方不敗を傷つける事を恐れたキョウジは、慌てて勾玉を両手で覆う。すると勾玉は、拒絶する様な光を放つ事を止め、大人しくキョウジの手の中に収まった。
「何故じゃキョウジ!! 何故―――!」
キョウジを抱きしめながら、東方不敗が叫んだ。
「何故勾玉を、己の身体からちゃんと分離せんのだ!! さすればそれを抱えて炎に飛び込む役ぐらい、ワシが代わってやろうものを――――!!」
「…………!」
驚くキョウジの手の上に、東方不敗から流れた涙の滴が落ちてくる。
(この人が……私のために泣いてくれるなんて……!)
それこそ、思いもよらない事だった。自分には、勿体なさ過ぎると思った。
「…………」
キョウジは、身体の力を少し抜いて、東方不敗に凭れかかる。
温かい胸だと思った。優しいぬくもりを感じた。
こんなふうに抱きしめられるのは、一体いつ以来だろう。
ああ、そうだ。
この人はこの優しさで――――。
傷ついたドモンを、笑顔にしてくれた人なのだ。
それは自分では、どう足掻いても、出来なかった事だった。
だからキョウジは、言葉を紡いだ。この人には『生きて』欲しくて。
「駄目ですよ、マスター……。貴方が死ねば…ドモンが悲しみます……」
「お主が死んでもドモンは哀しむ!! 何故それが分からんのだ!!」
そう叫んだ東方不敗の口から、最早隠しようもない嗚咽が漏れる。キョウジを抱きしめるその身体が―――震えていた。
「マスター……」
キョウジは、困ったように微笑んだ。
ありがとう。
ありがとう、マスター。
もう充分です。
貴方のその涙だけで。
温もりだけで―――。
私にはもう、充分すぎる。
「……行きましょう、マスター……」
咽び泣く東方不敗に、キョウジは声をかけた。
「…闘いに――――」
「――――!」
キョウジの言葉に、東方不敗はピクリと反応する。
「……『闘う』のか?」
顔を上げ、問いかける東方不敗に、キョウジは頷いた。
「最後まで―――」
「…………!」
じっと、こちらを見定めるように見てくる東方不敗に、キョウジはふっと相好を崩したような笑みを見せる。
「すみません…。私は割と……あきらめは悪いです……」
「キョウジ……!」
「ですから、行きましょう。マスター……」
「…………」
「闘わせてください…。最後まで―――」
「…………ッ!」
キョウジにこうまで言われてしまっては、東方不敗も、もう立ち上がらざるを得ない。
「分かった……。参ろうぞ、キョウジ…。戦いの場へ―――」
だが死ぬな、決して死ぬな、と、東方不敗はキョウジに何度も何度も念を押す。それに対してキョウジは「努力します」と、苦笑いながら答えるしかなかった。
「では……行くぞ!」
東方不敗は総てを吹っ切るようにそう言うと、キョウジを抱きかかえ、立ち上がった。
移動を開始した東方不敗の腕の中で、キョウジは、胸に激しい痛みを感じ、嘔吐感を覚える。
「――――ッ!」
ぐっとこらえたが、口の中に血が溢れ、それが、口の端から零れおちた。東方不敗にそれと悟られないように、彼はその血をそっと拭う。
(シュバルツ……)
そして勾玉を両手で包み込むようにしながら、この自分の不可解なダメージの原因になっているのであろうシュバルツに、想いを馳せる。
(どうしたんだ、シュバルツ……。一体、何があった……?)
眼を閉じ、祈るような格好になっているキョウジの手の中で、勾玉が淡い光を放っていた。
(嫌だ……! 聞きたくない……! 聞きたくないのに―――!)
闇の中、シュバルツは懸命に耳を塞ぐ。だが、いくら耳を塞いでも―――『言葉』たちは滑り込むように、シュバルツの耳に入ってくる。
何故、生きているんだ。
お前のせいだ!
化け物―――!
お前が、『あんな物』を作ったせいで―――!
聞こえてくるのは、否定の言葉ばかり。
激しい憎悪と悪意を伴った――――冷たい言葉ばかり。
違う。
あそこに居る人たちは、全部偽物だ。
父さんや母さんやドモンが―――
あんな事を言うはずがない。
「いい加減、あきらめればいいのに……。貴方も大概、しつこいわねぇ……」
すぐ傍で、侮蔑と嘲笑を含んだ、『女』の声が響き渡る。
「もう、あきらめてこちらへ来れば―――? とっても楽になるわよ……?」
そう言いながら、女の物と思われる手が、シュバルツにそっと触れてくる。触れられた個所がジリッ! と、音を立て―――シュバルツに刺すような痛みをもたらす。
「離せっ!!」
シュバルツは女の手を振り払うように、その場から飛び退いた。
すると、今度は彼のすぐ後ろで、『男』の声が響き渡る。
「……君は、いい加減認めるべきだ。自分は『化け物』なのだと……」
「――――ッ!」
「死体なんだろう? 死なないんだろう? 命が無いんだろう?」
そう言いながら、男はげらげらと嗤う。
「………やめろ……!」
シュバルツは懸命に、耳を塞ぐ。
分かっている―――! 自分のこの身体は『異常』だ。
今更言われなくても、分かっている!
でも―――だからこそ、なりたくない。
『化け物』と、呼ばれる物に、なってしまいたくない―――!
「でも……あるんでしょう? 貴方は…。『化け物』を見られるような眼で、見られた事が……」
「そんな事はない!!」
シュバルツは女の言葉を強く否定する。だが、それに対して女はクククっと笑った。
「あら―――嘘よ、嘘うそ。貴方―――あるんでしょう? 見られた事が、あるんでしょう?」
「どうやら、忘れてしまっているようだね……」
そう言って男も、愉快そうに笑う。
「思い出させてあげましょうか」
「そうだな。思い出させてやろう」
「―――! やめろッ!!」
シュバルツは、懸命に逃れようとする。だがすぐに捕まり―――男の方に取り押さえられてしまう。そこに、女の手が伸びてきた。それは、ズブリ、と、音を立てて、シュバルツの身体の中に入ってくる。
「うっ……! ぐ……!」
腹の中をぐちゃぐちゃと掻き回される感覚。痛みと気持ち悪さで、思わず吐きそうになる。
「……ほうら、あった、あった……」
目的の物を探り当てた女が、にたり、と嗤った。
シュバルツの目の前に、『キョウジ』の姿が浮かんでくる。
病院の入院服を着て、ベッドの上で点滴を受けながら、本を呼んでいる彼の姿を見た瞬間、『何時』の記憶なのかシュバルツは悟った。悟ってしまったが故に―――息を飲んだ。
「やめろッ!!」
その記憶が再生される事を拒もうと、シュバルツは懸命に足掻く。だが、彼を抑えつけている男の手はびくともしない。
「覚えている? これは、『例の事件』が終わった後―――病院で、『彼』の意識が戻った時のものよ……」
「――――ッ!」
シュバルツは思わず目を閉じ、顔を逸らす。だが、何故かその映像は、視界の中から消えなかった。
「……無理だよ。君は見なければならない」
口の中で嗤いながら、男は言った。
「そうよ……貴方は、迷っていたのよね? 意識の戻った『彼』の前に、姿を現すかどうか……迷っていたのよね?」
そうだ。私は迷っていた。
意識の戻ったキョウジの前に、姿を現すかどうか―――迷っていた。
私は『影』だ。だからこのまま、キョウジの前には姿を現さず―――ずっと『影』でいる事が、ある意味正しいのかもしれない。
だけど、『知っていて欲しい』とも思った。
自分が、そばにいる事を。
キョウジに。
それ以外に、他意は無かった。
「そして……貴方は、姿を現す決意をした……」
誰もいなくなった、夜の病室で。
眠れないのか、ベッドサイドの明かりを点けて、本を読んでいるキョウジの前に。
「…………?」
こちらの気配に気づいたキョウジが、振り返る。
そして――――。
「あ……! あ……ッ!!」
彼の眼が見開かれ、その表情が歪んで行く。
浮かんできたのは『恐怖』の色。
その『罪』故に、怯えた表情―――!
キョウジ――――!
「『突きつけた』のよね? 貴方が―――『彼』に。『罪』を……!」
「…………!」
「かわいそうに……。『彼』はせっかく忘れていたのに……。あの事件から生還して。意識が戻って……そしてその記憶も、曖昧だったと言うのに……」
シュバルツは、顔を覆う。耳を塞ぐ。
「『君』を見たことで、『彼』は総てを思い出してしまった…。『君』が、『彼』に罪を自覚させたのだ。『君』の存在は―――『彼』の罪その物だ!」
嫌だ……! 聞きたくない……! 聞きたく……無いのに――――!
「そして……貴方は、どうしたの?」
シュバルツの耳元で、女が囁く。
「………やめろ……!」
「『逃げた』のよね? 彼のそばから……」
「――――ッ!」
「『罪』だと分かったから……『逃げた』んでしょう?」
ガシャン!!
派手な音を立てて点滴の装置が倒れ―――振り向くとキョウジがベッドから落ちていた。
でも、罪にまみれた自分がキョウジに触れる事は、憚られた。だから、ナースコールだけを押して―――病室から走り去った。
キョウジの前に出てしまった事を、激しく後悔した。
自分を消さなければ。
消さなければ。
強く思った。
「でも―――『消せなかった』んだろう? 君は……」
そう言いながら男が口の中でクククっと嗤う。
「『化け物』だから―――」
「…………ッ!」
そうだ。死ねなかった。
頭を銃で撃ち抜こうが、腹を搔き斬ろうが、首を斬り落そうが―――。
2~3時間後には、生き還ってしまった。
「何故、生きているの?」
そう言いながら女の顔が、シュバルツの眼前にずいっと迫ってくる。
「『罪』を突きつけていると分かっていて―――何故貴方は、彼の側にいるの……?」
「……それは……!」
ガシャン!!
キョウジが、洗面台の鏡を叩き割っている。
拳から血を流しながら、泣いている。
今でも彼は―――自分を責め続けている。その『罪』故に。
―――兄さん。シュバルツを、どうするつもりなの?
ドモンがキョウジに問いかけている。
―――分からないんだ。
キョウジが穏やかに微笑みながら答える。
……………『消し方』が。
「――――!!」
シュバルツは、呼吸の仕方を忘れそうになる。
――――あれは『化け物』だ…。いつまでも存在させておくのは、不自然で……おかしいよ。
「キ……キョウジ……!」
シュバルツは天地が分からなくなって――――立っていられなくなった。
ペタン、と、その場にへたり込んでしまう。
「もう貴方は充分『化け物』なのに……いつまでここに、居るつもりなの?」
「……やめろ……」
シュバルツは、耳を塞ぎたかった。でも、もう、動く事も出来ない。
「『罪』を突きつけているのに……いつまで、彼の側にいるつもりなの?」
「…………」
もう反応を、返すことすら出来ない。
「君は、早く『消える』べきだよ」
男の声の後に、女がククククッと嗤いながら言った。
「いくらそこで座り込んでいても、無駄よ。助けなんて、来ないわ」
「助けなんて――――来ないのよ」
「…………」
動けなくなったシュバルツに、尚も容赦なく悪意と敵意が降り注いでくる。
やめろ。
もうやめてくれ。
消えたいんだ。
私だって、消えたいんだ。
「消えたいの?」
女の問いかけに、シュバルツは頷く。
消えたい―――でも。
消え方が、分からない。
「あら……簡単よ。ほら、そこ。そこの『流れ』に―――手を出してごらんなさい」
シュバルツが顔を上げると、赤と黒の混ざりあった毒々しい色の光を放つ、何かの『流れ』があった。そこから無数の、悲鳴のような声が聞こえる。
シュバルツは言われたとおり、『流れ』に向かって左手を出してみた。バシュッ!! と、音を立てて左手が刎ね飛ばされる。そしてその左手は――――『再生』しなかった。
「…………!」
消えれるのか。
消えた左手を見ながら、シュバルツは思った。
「簡単でしょ? 後は……立って歩くだけよ」
そう言いながら、女はクスクスと笑う。
そうか…。じゃあ。
消えてしまおうか。
もういいだろう。
ここにいても、私は人を傷つけるだけ。
『罪』を、突きつけるだけなのだから―――。
ゆらり、と、シュバルツは立ち上がった。
そして、流れに向かって、一歩、足を踏み出そうとする。
だが。
その歩こうとするシュバルツの手を―――。
誰かの手が、掴んだ。
「―――!?」
驚いて振り向くシュバルツの視界に、『キョウジ』の姿が飛び込んでくる。
キョウジ、と、呼びかけようとしたシュバルツは、彼の姿の異様さに更に驚いた。
それは、いつからそこにあったのか。
シュバルツの目の前に、一本の、淡く光を放つ巨大な『樹』があった。
それは、どこから生えているのか―――下を見ても、底が見えない。
幹の太さがどれほどあるのか、見渡そうとしても見渡しきれない。
上を見上げても、果てが無い。
それでもそれが『樹』と分かるのは、ところどころから生えている枝に、葉が茂り、優しいざわめきの音を奏でているからだ。
そしてその『樹』の幹の途中から――――キョウジの上半身が『生えていた』
そしてその手が―――シュバルツを掴んでいたのである。
キョウジ自体も、淡い光を放っていた。
「キョウジ……?」
呼び掛けるシュバルツに、キョウジは答えた。
「シュバルツ……」
「シュバルツ……駄目だ。行っては駄目だ」
キョウジは必死な眼差しで、シュバルツを見つめている。
「何を言っているの? 貴方は」
シュバルツの背後で、女が嗤う。
「この人はもう―――消えたがっているのよ?」
「それでも、駄目だ!」
キョウジはきっぱりと言い放つ。
「あら……でも、もう遅いわ」
女がクスクスと笑いながら言う。
「この人の身体は……ほら」
その言葉と同時に、シュバルツの身体がざぁっ、と、音を立てて消え始める。
「―――消えるな!!」
キョウジが叫ぶと同時に、ドン!! と、音を立ててキョウジからシュバルツへと光が注ぎ込まれる。すると、消えかけていたシュバルツの身体が、『再生』した。
「―――――!」
その出来事に、シュバルツと男と女の3人が、同時に息を飲む。
「なんて事を……! なんて事を、貴方は―――!」
女の口調に、怒気がにじんだ。
「分からないの!? この人はもう、消えたがって―――!」
「駄目だ!!」
ドン!! と言う音と共に、消えようとするシュバルツを、またしてもキョウジが阻んだ。
「こ、こいつ……!」
ギリ、と、男が歯ぎしりする音がする。
「キョウジ……」
呆然とこちらを見るシュバルツを、キョウジは懸命に見つめ返した。
「駄目だシュバルツ…。今―――『お前』が消えては駄目だ!」
「何故……」
力無く問い返すシュバルツに、キョウジは必死に問いかけた。
「よく考えろ、シュバルツ! 『お前』が消えてしまったら……残されたお前の身体は、何をする事になると思う!?」
「……………?」
「ドモンとハヤブサを――――その手で殺す事になるんだ!!」
「――――!!」
キョウジに叫ばれて、シュバルツはようやく状況を思い出す。
そうだ…! 私は確か、仮面の男に刺されて。
『魔力』を注ぎ込まれて―――。
シュバルツの視界に、ドモンとハヤブサの姿が入ってくる。
倒れて―――動かない、ハヤブサ。
「兄さん!! 兄さん!!」
涙を流しながら、叫ぶ弟―――。
「お前は自分の『弟』を! お前の事を想ってくれる『友人』を! その手で殺すのか!?」
「…………!」
「駄目だ!! お前は絶対に―――そんな事をしちゃいけない!!」
「キョウジ……!」
「今更そんな事を言った所でもう遅い。さあ、その手を離したまえ!」
男が、強い口調でキョウジに迫ってくる。
「嫌だ!!」
キョウジは頑なに撥ねのけた。
「『人間』風情が、笑わせる――――」
男が無造作に腕を振る。すると、男によって巻き起こされた風が『刃』へと変化し、キョウジを襲った。
バシュッ!! と言う音と共に、キョウジの肩から腕にかけて、ざっくりと斬り裂かれる。その痛み故に、キョウジは小さく呻いた。
「キョウジ!!」
「――――ッ」
だが次の瞬間、斬り裂かれた傷がすぅっ、と、消える。『樹』から注ぎ込まれるエネルギーが、キョウジを治しているように、シュバルツには見えた。
「次は、腕を刎ね飛ばす!」
男の冷たい声が、キョウジに警告を発する。
「さあ―――その手を、離したまえ!!」
「断る!!」
キョウジが、男よりもさらに強い口調で撥ねのける。普段温厚なキョウジからは、考えられないような激しさだ。
「……何ぃ?」
男の声に含まれる殺気が、更に強い物になる。
「私は絶対にこの手を離さない! 誰に何と言われようとも―――!」
そう言いながらキョウジは、男を見据える。
「はったりよ。どうせ、すぐに手を離す事になるわ」
そう言って、女が嘲笑う。だが、キョウジの方にも『不敵』とも取れる笑みが浮かんでいた。
「やれるものなら、やってみろ!」
「――――!」
「言っておくが……私はかなり、あきらめは悪いぞ!」
キョウジの言葉に、男女の殺気が更に硬化な物になる。
「ふざけるな!! 人間ごときが―――!!」
「その言葉! すぐに後悔させてあげるわ!!」
叫んだ男女の袂から、無数の刃が飛び出した。
ドドドドドッ! と、音を立てて、刃がキョウジを襲う。襲い来る痛みを予期して、キョウジは目を閉じた。だが―――いつまでたっても、痛みは彼を襲わなかった。
「…………?」
訝しく思ったキョウジが目を開ける。そして、その原因が分かった。
「う……! く……ッ!」
シュバルツが、キョウジを斬撃から守る様に、キョウジに覆いかぶさるように立っていたからだ。
「シュバルツ!!」
キョウジの叫び声に目を開けたシュバルツは、微笑んだ。
「キョウジ……」
切り刻まれたシュバルツの傷は、治らない。それを見たキョウジは、あわててシュバルツに光を注ぎ込んで傷を治す。ありがとう、と、シュバルツは小さくキョウジに言うと、男女の方に振り返った。
「私の目の前で、キョウジを傷つけるのは――――許さない!」
そう言うと、彼はキョウジを守る様に背に庇い、そこに仁王立ちになった。
(シュバルツ……!)
流石にこの体勢でシュバルツの手を掴み続けるのは困難か、と、判断したキョウジは、掴む所を手から背中へと移した。とにかく自分は、シュバルツを『掴み続ける』―――絶対に『離さない』
「どきたまえ、シュバルツ君」
闇の中で、金色に光る目をぎらつかせている男が言った。
「君はもう―――消えかけの『木偶人形』だ。そんな所に立った所で、何の役にも立たないよ」
「……………」
「そうよ。シュバルツさん」
同じく目をぎらつかせながら、長い髪を振り乱している女が言った。
「貴方もう、消えたがっていたじゃない。……あきらめてこっちにいらっしゃい? とっても楽になるわよ?」
だがシュバルツは、短く撥ねつけた。
「断る!」
「…………!」
闇の中、男と女が息を飲む気配が伝わってきた。
「今、私が消える事を『キョウジ』は望んでいない。だから……私はそちらに行くわけにはいかん!」
シュバルツはそう言って、目の前の男女を睨み据える。
「貴方、先程も似たような事を言っていたわよね――――」
女がうんざりしたような声で言った。
「『弟』が望むから…。『キョウジ』が望むから……。じゃあ、『貴方』は? 『貴方』自身の、望みはないの!?」
「あるさ」
シュバルツは即答した。
「だが、その『望み』を―――人にべらべらしゃべる趣味はないがな……」
そう言ってシュバルツはにやりと笑う。女が闇の中で、絶句する気配が伝わってきた。
「いいだろう。どうせ君は、もう消える運命だ。君が消えさえすれば、こちらとしては何でもいいんだ」
男の殺気が、爆発的に膨れ上がる。
「切り刻んで――――消してやる!!」
ザン!! と、音を立てて、シュバルツに無数の刃が襲いかかる。
だが、シュバルツはそこに立ち続けた。キョウジを守る様に、ただそこに立ち続けた。
そしてキョウジは、そんな彼を治し続けた。
繰り返し。
ただひたすら。
光を注ぎ込んで、傷つく彼を治し続けた。
「う……ッ! ぐ……!」
シュバルツから時折、小さな呻き声が聞こえてくる。
全身を斬られ続けているのだ。痛くないはずがない。苦しくないはずがない。
それでもキョウジは、彼を治し続けた。
無慈悲に。
容赦なく。
光を注ぎ込み続ける。
ただ彼を、存在させ続けるためだけに。
今、彼を消してしまう訳にはいかないから…。
『彼』が消えてしまったら、総てが終わってしまうから……。
『ドモン』と『ハヤブサ』と、そして、『自分』のため、に…彼を、消すわけには――――。
「…………ッ!」
いつしかキョウジはその瞳から、涙を零していた。雫がパタ、パタ、と、音を立てて、シュバルツの足元に染みを作る。
こんなの、全然シュバルツのためなんかじゃない。
自分の『想い』を貫くために―――ただ彼を、苦しませているだけだ。
「……よくもまあ、そんな惨い事が出来るわね。貴方―――」
女の呆れた様な声が響く。
「この人はもう、『消えたがっている』……『解放』されたがっているのよ? それを……こんな苦しみを、ただ長引かせるだけの様な事を……よくもまあ―――!」
「……うるさい!」
キョウジは叫びながら、またシュバルツを治す。
「もしも…シュバルツが、本当に『解放』を……『消える』ことを望んでいると言うのなら――――」
そう言いながらキョウジは、シュバルツの背中を掴んでいる手に、ぐっと力を込める。
「私だって……その手助けをするさ……」
「キョウジ……」
シュバルツはここで初めて、キョウジの声の震えに―――キョウジが『泣いている』ことに気付いた。
「でも……こんな、絶望と孤独に打ちひしがれて……人を殺すために『消える』と言うのなら……」
「私は断固拒否する!! 誰に何と言われようと!! 例え、シュバルツをどんなに苦しませようともだ……ッ!!」
「――――!」
(キョウジ……!)
シュバルツの背中越しに、キョウジの震えが伝わってくる。
違う、キョウジ。
お前の方こそが、苦しんでいるではないか。
「そんな世迷いごと―――笑わせてくれる!」
再び男から放たれる斬撃の嵐が、シュバルツを襲う。
「――――ッ!」
全身に、痛みが駆け巡る。
だが、すぐに、キョウジが治してくれる。
温かくて、優しい『気』が、流れ込んでくる。
だから私は、立っていられる。
キョウジを――――守るために。
ああ、何故だろう。
私は今――――『幸せ』だ。
(シュバルツ……!)
ただ治す。
治し続ける。
彼の存在を消したくない。ただ、それだけのために、こんな事を出来てしまえる自分は―――ある意味『鬼』だ。
彼が『解放』を、『消滅』を望むと言うのなら――――自分はそれを、手助けしなければならない。
でも、ごめん。
それは『今』じゃない。
『今』、こんな形で、お前が消えるのだけは、嫌なんだ。
私はどうしても――――嫌なんだ……。
「キョウジ……」
シュバルツから、声をかけられる。
「泣くな……キョウジ……」
無理だ。
無理だよ、シュバルツ。
「泣くな」と、言われても――――。
「私の事なら……気にするな……」
斬られながら治されながら、シュバルツは、淡々と言葉を紡いだ。
「こういう『痛み』には……慣れている……だから――――」
ドカン!! と、音を立てて、多少荒っぽい『気』が、キョウジからシュバルツに注がれる。
「――――!?」
「馬鹿だろう……お前……」
驚いて振り向くシュバルツに、キョウジが涙を落としながら言葉を紡いだ。
「『痛み』に慣れる生物なんか――――いない……ッ!」
「キョウジ……」
「居る訳ないんだ……この…馬鹿が……ッ!」
そう言いながらキョウジは、はらはらと涙を落とす。落としながら、彼はシュバルツを治し続ける。シュバルツが消えようとするのを、拒み続ける。
何故だ。
シュバルツは、不思議だった。
斬られている全身よりも。
キョウジに掴まれている背中の方が痛い。
消エナイデ。
消エナイデ。
悲鳴のような叫びと共に、彼の『想い』が自分の中に流れ込んでくる。
温かい。
優しい。
そして、小さく囁く声―――。
(ソバニ、イテ)
ああ――――。
自分は、痛さも麻痺してしまうほどの苦痛を味わっていると言うのに。
キョウジは涙を流して苦しんでいると言うのに。
何故……私はこんなにも、
酷く『幸せ』なのだろう。
「……埒が明かないな。このままでは―――」
闇の中、男の業を煮やした様な声が響く。
「やはり……大元を叩かなければ、駄目なようね……」
同じように、女の声が響く。
「ならば……この手はどう―――!?」
女がそう叫び、さっと手を振る気配がする。それと同時に異変は起きた。
シュバルツの足元の地面に、亀裂が走る。
「!?」
あ、と叫ぶ間もなく、シュバルツの足元から―――『地面』が無くなった。
「シュバルツ!!」
落ちて行こうとするシュバルツの手を、間一髪でキョウジの手が掴む。そのままシュバルツの身体は、キョウジの手にぶら下がるような格好になった。
さらに。
辺り一帯に、俄かに強風が巻き起こる。
その風は、明確な意思を持って、シュバルツの身体を引きこもうとしていた。あの、赤と黒の光を放つ―――不気味な『嵐』の中へと。
「さあ! これで、貴方を守る者は、居なくなったわ!!」
「これでも君が手を離さないかどうか―――見届けてやる!!」
勝ち誇ったように嗤う男女の声が響いたかと思うと、再び容赦のない斬撃の嵐が、今度は『キョウジ』に直接襲いかかる。
「ぐ……ッ!」
「キョウジ!!」
自分の目の前でキョウジが斬り裂かれて行く事態に、シュバルツの顔色が変わる。
だが、自分の身体が明確な意思を持って引っ張られている嵐の中では、シュバルツは身動きすることすらままならない。
「う……! う………ッ!」
キョウジが小さく呻く。苦痛をこちらに感じさせないように、声を殺しているのは明白だった。
「やめろ!! キョウジ―――! キョウジ!!」
だがもうシュバルツは、ただ、叫ぶしか出来なかった。
斬られながら――――しかし、キョウジは頑なだった。
斬られた個所を自身で治しながら、シュバルツの手をただひたすら掴み続ける。
「いい加減、あきらめろ!!」
攻撃しながら男が叫ぶ。
「助けなど―――来ない! 早く絶望したまえ!!」
ビシッ!! と、音を立てて、キョウジの肩口が斬り裂かれる。
「『助け』が来ない……」
「だから、何だ!!」
叫びながらキョウジは、また自身の傷を治す。
「助けが来ない―――それが、どうした!!」
「…………!」
男は思わず、キョウジの気迫に気圧されてしまう。
「そんな『絶望』など―――私はあの時味わい尽くした!! あの『事件』の時に……!」
そう言いながら男を睨み据えるキョウジの目に、うっすらと涙が浮かぶ。
そうだ。私はあの時、相談できる相手すらいなくて。
暴走するガンダムの前に、為す術もなく―――どうしようもなく『独り』だった。
『助け』など――――期待できるはずもなかった。
でも。
でも。
あの時に……!
「腕を―――!」
女が叫んで、男がキョウジの腕を斬り飛ばす。
「――――ッ!」
だがキョウジはすぐに、自身の腕を草の弦の様に変化させて、シュバルツの手を絡め取る。
嵐に触れたシュバルツの足が、チリ、と、音を立てて消え始める。
「消えるな!!」
ドン!! と、音を立てて、シュバルツに光が注ぎ込まれる。『再生』したシュバルツを、キョウジから派生した草の弦が引っ張って、また―――元の位置に戻した。
「何て奴だ……!」
男は息を飲んだ。
斬っても傷つけても、『再生』するキョウジの身体。
どんなに切り離そうとしても、決してその手はシュバルツを離そうとしない。
シュバルツは、あと少しで消えそうだ。なのに―――キョウジが光を送り続けてそれを阻む。
とにかくこの事態―――『あきらめが悪い』にも程がある。
これでは、こちらの方が、先に音を上げてしまいそうだ。
「それならこれはどうだ!?」
男がさっと手を振ると、キョウジの前に、母『ミキノ』の姿が現れる。
――――あなたのせいで……。
ミキノが暗い声で囁く。
「嘘だ!! 私の母はそんな事は言わない!!」
キョウジはそんな『母』の姿を、真正面から見据える。
「母は優しい人だった…! 『息子』としては変わり者だっただろう私の事を、受け止めてくれたんだ!!」
忘れない。
28年間、自分に注ぎ続けてくれた母の愛は、本物だった。
例え、事切れる瞬間、母が、自分を恨んでいたのだとしても―――。
「私は母を、信じている!!」
キョウジの叫びに、母は答えた。
(――――キョウジ……)
そう言ってにっこり微笑むと、母の姿は消えた。
次いで、父親がキョウジの前に現れる。
だが、父親も、キョウジにとっては同様だった。
どんな言葉を浴びせられようが―――父に対する想いは変わらない。
父は―――自分の生きる道を教えてくれた、偉大な師だ。この人が総てを受け止めてくれたから―――今の自分があるのだ。
(頑張ったな。キョウジ……)
父もまた、微笑みを返してくれた。
ゆらり、と、闇の中、ミカムラ博士の姿が浮かび上がる。
「博士………」
この人にだけは、キョウジはどうしようもない罪悪感を感じる。
きっと、散々苦しめた。
博士が『悪意』に流されてしまったのは、それはきっと、自分が追い詰めてしまったからに他ならない。
(……………)
ミカムラ博士が、無言でこちらを見ている。
「博士――――」
キョウジもまた、博士を見つめ返した。
眼をそらさず。
まっすぐに。
この人からは、何を言われても仕方が無いと、キョウジは思った。
でも博士。一つだけ。
貴方からどんなに罵られようと、責められようとも。
今―――シュバルツの手だけは、離せない。
それだけは――――本当に、ごめんなさい。
(キョウジ君………)
哀しみに曇った表情を浮かべたミカムラ博士から、名前を呼び掛けられる。
その横に、ゆらり、と、父であるライゾウが姿を現す。
ライゾウは、ミカムラ博士の肩に、ポン、と手を置いた。
博士は、ライゾウに気づいて少し戸惑った様な表情を浮かべたが、肩に置かれたライゾウの手の上に、彼はそっと自分の手を添えた。
「博士―――!」
驚きの声を上げるキョウジに向かって、ミカムラ博士は、少しばつの悪そうな笑みを浮かべる。
そして、父と共に消えた。
(博士………!)
二人が消えた方を見やりながら、キョウジの目からいつしか涙が零れていた。
ミカムラ博士は、一度軍部に加担した。だが、最後には軍部から離反し、冷凍刑に処せられていた父親を助ける最中に亡くなったのだと、キョウジは人づてに聞いた事を思い出す。
つい先日、その父も彼岸へと旅立った。
二人は―――そこで、再会できたのだろうか。
「何なの!? 貴方も!! 貴方の周りの人たちも―――!」
闇の中、女がヒステリックに叫ぶ声が聞こえる。
「どうして、自分の運命を呪わないの!? 絶望しないの!? 理不尽に、命を奪われたんでしょう!? 苦しめられたんでしょう!?」
女が放つ叫びに―――しかし、答える者は誰もいない。
「………『私』は、誰も助けてくれなかったわ……!」
絞り出される様な、声が響く。
「それどころか……願われたわ…! 『早く化け物になってしまえ』って……!」
「――――!」
(この人はもしかして――――!)
その女の叫び故に、キョウジとシュバルツは、同時に『それ』に思い当たった。しかしそれと同時に―――女もまた、狂ったように嗤いだした。
「フフ……クククク……ッ アハハハハハハハ!」
闇の中で、振り乱された女の長い髪が、妖しく揺れる。
「死ネ―――――ッ!!!」
「…………ッ!」
女の叫びが合図になるかのように、再び前以上の斬撃の嵐がキョウジを襲う。
しかし、キョウジはシュバルツの手を掴み続ける。
そして、『光』を送り続ける。
「キ……キョウジ……!」
だが、シュバルツは気付いてしまう。
キョウジの身体が生えている『樹』から放たれる光が、弱くなってきている事に。
気がつけば嵐の中、無数に木の葉が舞っている。樹が、葉を落とし始めているのだ。
「駄目だ……!」
キョウジの生命エネルギーが衰えようとしている。そう悟ったが故に、シュバルツは恐怖した。
「駄目だ、キョウジ―――!」
このままでは、キョウジの方が死んでしまう。『自分のせい』で、死んでしまう。シュバルツはたまらず叫んだ。
「キョウジ! 手をはな―――!」
「嫌だ!!」
キョウジはシュバルツの言葉を遮るように即答した。
「しかしキョウジ…! このままでは―――!」
「嫌だ!!」
「しかし―――!」
尚も反論しようとするシュバルツを、キョウジが睨む。
「お前は……ドモンとハヤブサを、その手で殺したいのか!?」
「それは……! だが、キョウジ……! このままではお前が―――!」
シュバルツは、キョウジの身を案じて叫ぶ。しかし、キョウジは頑として聞き入れなかった。
「私は、嫌だ!!」
「キョウジ……」
「ドモンとハヤブサが殺されるのも……! お前が……消えてしまうのも!!」
「――――!」
「私は! 絶対に嫌だっ!!」
叫んでキョウジは、また消えそうになるシュバルツを再生させる。
自身が傷つくのも構わずに、
何度も何度も、シュバルツに『光』を送り続ける。
「キョウジ……ッ!」
シュバルツの視界の中で、キョウジの姿が、涙で霞む。
キョウジの姿は、既に傷だらけだ。
どこもかしこも、傷だらけだ。
先程まで自身に受けた傷を、自分で治していたと言うのに。
「キョウジ……傷を―――傷を治せ……!」
シュバルツは懸命に、キョウジに訴えた。それに対してキョウジは、大丈夫だよ、と、微笑みながら首を振る。シュバルツはたまらず下を向いた。瞳から光る物が、とめどなく零れて行くのが自分でも分かる。『キョウジ』の後ろに控えている『樹』は、もうほとんど光を放っていない。キョウジ自体の『光』も、弱くなってきている。
キョウジが弱って来ているのは、もう明白だった。
どうすればいい。
このままではキョウジが死んでしまう。
『私のせい』で死んでしまう。
(嫌だ……!)
シュバルツは強く思った。
キョウジを守りたい。
キョウジを、死なせたくない。
キョウジには、生きていて欲しい。
ならば、どうする?
懸命に考える。
ドモンの命。ハヤブサの命。そして―――自分。
そして―――キョウジの命。
それらを秤にかけて、考えた。
そうしてシュバルツの出した結論は。
『自分を消すこと』―――だった。
自分が消えれば、おそらく残された自分の身体は『暴走』を始める。それは、ドモンとハヤブサを、窮地に追い込んでしまう物かもしれない。
だが、ドモンもハヤブサも『強い』
そして、DG細胞に対抗し得る手段も持っている。
だから、あの二人ならば―――。
きっと、『暴走』した自分を、倒してくれる事だろう。
「…………」
知らず、シュバルツの面に笑みが浮かぶ。
ありがとう、キョウジ。
私はもういい。
もう充分なんだ。
キョウジが「消えるな」と、叫んでくれた。
何度も『光』を送って、私を治してくれた。
それだけでもう―――本当に、充分なんだ。
懐に忍ばせてある、短刀を意識する。
自身の手を斬り落とすには、これで充分事足りる。
良かった。
最期にキョウジの
手のぬくもりに触れられて――――良かった。
私には、過ぎた『幸せ』だった。
「キョウジ……」
シュバルツはキョウジに声をかけながら、懐の短刀に――――手を、伸ばそうとした。
だが、それは叶わなかった。
「待て、シュバルツ」
妙に低いキョウジの声と共に、一本の草の弦が伸びてきて、短刀に向かおうとしたシュバルツの手を絡め取る。そのまま弦は、彼の手をギリっと引っ張り、その動きを封じた。
「!?」
驚いて顔を上げると、キョウジと視線が合った。ただしキョウジがシュバルツを見つめる視線には、かなりの『怒気』が含まれていた。
「キ、キョウジ!?」
思わず息を飲むシュバルツに向かって、キョウジの低い声が飛ぶ。
「お前――――今、何をしようとした?」
「な、何をって……?」
普通に返事をしようとしてシュバルツは失敗する。声に、若干震えが出てしまった。
「懐に、こんな物なんか忍ばせて――――」
一本の草の弦が素早く伸びてきて、シュバルツの懐にあった短刀を絡め取る。そしてその弦は、短刀をあっという間にキョウジの元へと運んで行ってしまった。
「これでお前は、何をしようとした!? 何をするつもりだったんだ!!」
「キ、キョウジ……」
「腕を斬って……『消える』つもりだったな!? そうだろう!!」
「――――!」
自分の考えがキョウジに完全に読まれていた事に動揺し、シュバルツは思わず気圧されてしまう。黙ってしまったシュバルツを前に、キョウジは深いため息をついた。
「―――シュバルツ……。お前、まだ分からないのか……!」
キョウジの瞳から、光る物が飛び散る。
「私は! お前に『消えてほしくない』って言っているんだ!!」
「キョウジ―――!」
キョウジからの思わぬ言葉に、シュバルツは今度は別の意味で呼吸の仕方を忘れそうになる。
「……もう、嫌なんだ……!」
キョウジは、既にボロボロと涙をこぼしていた。
「自分が作ったモノが……自分から『産まれたモノ』が……! 『暴走』するのを見るのも……! それを、止められないのも―――!」
「…………!」
「私は! もう絶対に、嫌なんだ!!」
「キョウジ………」
茫然と見つめるシュバルツの前で、キョウジは涙を落とし続ける。
「一人目の……『A・G』の時は、私は無力だった……。『あの子』は……何度も何度も、私を助けてくれたと言うのに……!」
忘れない。
建設作業中、落ちそうになった自分を、あの子は何度も助けてくれた。
優しい能力を持った子だった。
自分の願いによく答えてくれた子だった。
『A・G』のそんな能力が、皆の役に立つ事を願い―――。
そして『A・G』の『幸せ』を、願った。
なのに―――。
襲われ。
怒りに流され。
壊して。
揚句、暴走させてしまった。
『悪魔』と呼ばれてしまう物に、貶めてしまった。
(キョウジ―――!)
キョウジの独白を聞きながら、シュバルツは、自分の根幹にある別の『何か』が、激しく揺さぶられるのを感じていた。
何だろう。
この感覚は。
身体の中で、何かが叫んでいる。
キョウジ。
キョウジ。
泣カナイ デ。
「『あの子』の暴走を……私は止められなかった…! 私が無力だったから……!」
違ウ、キョウジ―――。
違ウ。
「でも……だからこそ! お前は止める!! お前は守る!! 例えどんな事をしても!! 自分がどうなろうとも―――!!」
キョウジの叫びが、嵐の中に響き渡る。
「この手は、絶対離さない!!」
「キョウジ……!」
シュバルツは、ただ茫然とキョウジを見つめる。
心が震えすぎて息が詰まる。
キョウジに握られている、手が熱い。
「そして、私は願っている!! 『A・G』と同じように! シュバルツ―――お前の『幸せ』を……!!」
そんなキョウジの言葉を、男が嘲笑う。
「馬鹿め! こいつは呪われた身体を持つ、命の無い化け物だ!! そんな奴に、『幸せ』も何もあるものか!!」
「それでも『居る』んだ!! ここに『在る』んだ!! シュバルツの『心』が!! 『存在』が―――!!!」
キョウジの叫びに、その場にいた全員が息を飲む。
「『存在』があるから、『幸せ』を願うんだ……! 『消えてほしくない』って、祈るんだ!! 『形』はどうでも……『成り立ち』は呪われたモノでも……! もう、私にとっては『命』なんだ!!」
キョウジ―――!
キョウジ。
傍ニ、居テイイ?
傍ニ、居テイイノ?
「う……ッ! く……!」
シュバルツは、宙で足掻いた。自分を無理やり引っ張る力を、初めて煩わしいと感じた。
今すぐキョウジのそばに行きたい。
キョウジに、触れたいのに―――!
「シュバルツ……!」
シュバルツの足掻きが、キョウジの手に伝わってくる。
彼をこちらに引き寄せたいと願う。だがもう、自分にその力は無かった。シュバルツが嵐に巻き込まれないようにつなぎ止めるのが、もう自分の精一杯だった。
「キョウジ……ッ!」
腕に力を入れる。腕に絡みついた蔓に力を込める。それを手繰って、何とかキョウジのそばに行こうと試みる。だがその蔓は、その身にかかる過剰な負荷に耐えきれず、ブチッと、音を立てて切れてしまった。
「うわっ!?」
「――――ッ!」
シュバルツは大きくバランスを崩すが、キョウジの手は離れない。シュバルツの足先が背後に迫りくる嵐に触れ、消えそうになるが、キョウジがまた、それを阻んだ。
消えたくない。
消えられない…!
強くそう望んでくれる人がいるから――――!
「キョウジ……!」
シュバルツは懸命にキョウジに向かって手を伸ばす。
キョウジも、もう一度シュバルツに蔓を伸ばした。
腕に、腹筋に、背筋に―――シュバルツはありったけの力を込める。自身を背後に引っ張る力をねじ伏せるように、前に進む。ただひたすら、前に進む。そして彼は―――ついに腕の力だけで、キョウジが生えている木の幹の所まで、たどり着く事に成功した。
幹にしがみつこうとするシュバルツを守るかのように、枝が、蔓が、彼に向かって伸びてくる。それらを使ってシュバルツは、己の身体が背後に飛ばされないように固定して―――やっと、息を吐く事が出来た。
「シュバルツ……」
そんな彼を、キョウジは優しく笑って迎え入れた。
「……なんて奴らだ…!」
そんな光景を見ていた男が、呆れたように呟く。それからしばらく茫然とその様子を眺めていたが、はっと我に返った。
「おのれ! まだ攻撃が足りないと言うのなら―――!」
そう言ってなおも攻撃を加えようとする男を、女が制した。
「もう、やめましょう。『良人(あなた)』――――」
「しかし―――!」
男が振り向くと、そこにはひどく醒めた、冷たい表情をした『妻』がいた。
「もうこれ以上、あの二人に攻撃を仕掛けても、無駄よ。それよりも―――『最期』の時ぐらい、そっとしておいてあげましょう」
「…………!」
驚く男に、妻は冷たい視線を走らせる。
「良人(あなた)も、知っているでしょう…? あの『嵐』はこれからどんどん大きくなる。そして、ここにあるすべてを飲みこんでしまう―――」
「それは……そうだが……」
「私は、『経験』したから、知っているの」
「…………」
だから、あの男に、助かる術なんて無い――――『妻』は、そう暗い声で言い放った。
「飲み込まれて――――終わるだけよ。……哀れな物よね…」
そうだな、と男は短く呟く。だが、妻はそれには応えず、二人の姿から背を向け、闇に向かって歩き出した。
「キョウジ……傷だらけじゃないか……」
シュバルツの手が、キョウジの頬を撫でる。あちこちに裂傷を作り、それを治すかのように自身の身体から木の枝葉や草の蔓を生やしているキョウジの姿は、『人間』と言うよりは、もはや『植物』と表現した方が近い。
「あは……大丈夫だよ。ちょっとこの世界で、『形』を保つのが難しくなっているだけだから……でも、心配しないで」
そう言いながらキョウジは微笑む。
「後100回ぐらいはお前を治す余力は残っているから」
「ひゃ、100回って、お前……!」
キョウジの言葉に思わず呆然とするシュバルツを見て、キョウジは声を立てて笑い出した。
(笑っている場合か―――!?)
シュバルツは思わず頭を抱えてしまう。
「キョウジ…! お前なぁ……!」
「ブ……ククッ ごめん、ごめん。だってお前の顔、おかしくって―――」
「人の顔を見て笑うな! 第一、私の顔はお前の顔だ!」
「あれ…? そうだっけ?」
そう言って素っとぼけようとするキョウジに、そうだ、とシュバルツは憮然と返す。それを見てキョウジは――――また笑い出した。
「まあ、笑えるのならいいけど――――」
シュバルツは半ばあきらめたようにため息をつく。どんな時でも、自分の側にいるキョウジは、たいていこうして笑っている。彼が笑い上戸なのは、今に始まった事ではない。
だが、このキョウジの笑顔で、自分がとても安心するのも事実だ。半ばキョウジに丸めこまれている気がしないでもないが、この割と極限の状況下でも、平静な自分を保てるのは、素直にありがたかった。
「シュバルツ……」
キョウジは不意に笑う事を止め、握っているシュバルツの手を、自分の方に引き寄せた。
「シュバルツ―――私は、貴方の『手』が好きだよ。とても……」
「キョウジ……?」
シュバルツは、何故キョウジが急にこんな事を言うのかが分からず、小首をかしげる。それに対してキョウジは、少し淋しげな笑みを浮かべた。
「……これは、貴方が『人間』だった時の話だ…。だから……貴方は憶えていないかもしれないけれど―――」
「………?」
「貴方は……死ぬ直前、私に『手』を差し伸べてくれたんだ……」
「……手を……?」
分からない、と、言わんばかりの反応を返すシュバルツを見て、キョウジは苦笑する。
「憶えていない……そうだよな…。やっぱり……」
キョウジが沈んで行くような表情に見えたので、シュバルツは慌ててすまない、と、謝った。それに対してキョウジは、貴方は悪くない、と、笑顔で首を振る。
シュバルツには、『人間』であった時の記憶が無い。
正確には、戦うために身体が習得している体術や忍術以外の記憶を、総て失くしてしまっているのだ。
思考パターンや人格、過去の『記憶』などは、総てキョウジが持っている物に拠っている。皮肉にも、キョウジ自身の高い技術や技能―――そして、DG細胞の力が、それを可能にしてしまった。
だから、『人間』であった方のシュバルツに対して何か言おうとしても、『今』のシュバルツには何の意味も持たないし、通じない事も、キョウジには分かっている。
でも、『知っていて欲しい』とも、思った。
書き換えてしまったとは言え―――この『手』は元々、『あの人』の物なのだから。
「あの時私は……目の前で母が殺された怒りに我を忘れ……その挙句に『A・G』を暴走させてしまった……そしてそれに、取り込まれかけた―――」
そこに在った物は、どうしようもない怒りと憎しみ。そして、哀しみと絶望。
自分の未来が、闇に閉ざされて行くのが分かった。
「でも―――そこに貴方が、手を差し伸べてくれたんだ……」
忘れない。
自分に向かって飛んでくる黒い機体。
そこから身を乗り出して『生きろ』と、叫んでくれた人。
手を伸ばしてくれた人―――。
忘れてはいけない、と、思う。
「『今』の貴方にこの事を言っても、仕方が無い事は分かっている……。この言葉が、貴方の表面を滑り落ちて行ってしまう事も―――」
「キョウジ……」
「でも……今だけ、言わせて。『この手』に、言わせて」
そう言いながらキョウジは、シュバルツの手を自身の額に当てる。まるで大切な物を、押し戴く様に。そして、「シュバルツ」と、口を開いた。
「………『ありがとう』」
「――――!」
(キョウジ……!)
自分の手を持つキョウジの手が、肩が、小刻みに震えている。きらきらと光る物が、次々と流れ落ちて、消えて行った。
「貴方が……あの時、『手』を差し伸べてくれたから―――」
あの時―――あの人には、自分に手を差し出すだけのメリットは、何も無かったはずだった。
にもかかわらず、あの人は、自分に向かって手を伸ばしてきた。『生きろ』と叫んだ。己の身を顧みることなく―――。
純粋な『善意』が、そこに在った。
「私は……闇の中に『絶望』してしまわずに済んだ……」
そうだ。
あのまま何事もなく、ただ取り込まれてしまうだけだったら。
もっと私は絶望していたかもしれない。
人を恨んでいたかもしれない。
世界を憎んでいたかもしれない。
弟に『生きろ』とも―――言えなかっただろう。
でも。
貴方の『差し出された手』が、教えてくれた。
どんなに悪意に打ちひしがれようとも。
どんなに底に落とされようとも。
そこに差し込む『光』は在るのだと――――。
貴方は教えてくれたのだ。
そうだ。
世界は、『悪意』だけじゃない。
『光』だって、『優しさ』だって。
ちゃんと『在る』じゃないか――――!
そして、目の前で、墜ちて行った光。
光を見てしまったが故に、あきらめられなくなってしまった。
だから――――。
「シュバルツ……確かにあなたの成り立ちは、私の『罪』だ。私は『貴方』を殺した……。そして、その死体を利用した……」
「キョウジ……」
「でも……『罪(それ)』だけじゃない」
「――――!」
「『罪』だけじゃないんだ……シュバルツ……。私にとって、貴方の存在は――――」
キョウジは優しく微笑んでいる。そして、涙を落とし続ける。
「貴方は……『光』だ。そして……私にとっての『希望』―――」
「………!」
「貴方が『光』をくれたから……私は貴方に『希望』を託せた」
(キョウジ―――!)
あまりにも意想外の事をキョウジから言われたシュバルツは、思わず状況を忘れそうになる。
「弟に、『光の中で生きて』と……『祈り』を、『希望』を……託す事が、出来たんだ……」
キョウジ―――!
何を、言っているんだキョウジ。
お前こそが『光』じゃないのか。
お前こそが『希望』じゃないのか―――!
「だから……シュバルツ……」
「『ありがとう』」
「キョウジ―――!」
心臓を、わし掴まれるような衝撃を、シュバルツは受けた。
「『ありがとう』……手を差し伸べてくれて。
『ありがとう』……光をくれて。
『ありがとう』
『ありがとう』
祈りを、希望を――――届けてくれて、『ありがとう』……」
そう言って涙を落としながら微笑むキョウジは、ただひたすら綺麗だった。
キョウジ――――!
キョウジ……!
ああどうしよう。
キョウジをすごく―――
抱きしめて、しまいたい……ッ!
「キョウジ……ッ!」
シュバルツは、無我夢中で、キョウジに手を伸ばそうとした。
だがすぐに、自分が身動きできない状況に気付いた。自身が細工した草の蔓に行動を阻まれ、腹を思いっきり強打してしまう。
「~~~~~~ッ!」
「シュバルツ? どうした?」
目の前でシュバルツがいきなり腹を抱え込んで呻きだしたので、驚いたキョウジが声をかける。
「い、いや……大丈夫…。何でも無い……」
そう言いながらシュバルツは表面上は体裁を取り繕う。しかし、内心は、泣きたい気持ちでいっぱいだった。
(『状況』を忘れていた……。私は阿呆か。これじゃあ、ドモンの事を責められないな……)
痛む腹をさすりながら、肝心な時にドジを踏む自分に、軽く自己嫌悪を感じてしまう。
そんなシュバルツの様子を見て、優しく笑っていたキョウジであったが、不意に小さく呻いた。
「キョウジ? どうした?」
そんなキョウジの様子に、シュバルツが鋭く反応する。
「あ……いや、大丈夫…。ただちょっと、うるさくってさ」
そう言ってキョウジは、シュバルツに笑顔を返した。
「うるさい?」
「うん。ちょっと樹の幹の所に耳を当ててみてよ。お前にも聞こえると思うからさ」
「………?」
多少訝しく思いながらも、シュバルツはキョウジに言われたとおりに幹に耳を当ててみる。すると―――。
「兄さん!! 兄さんッ!!」
―――ドモン!
声を限りに懸命に叫ぶ弟の声が、シュバルツの耳に飛び込んでくる。
「……な? うるさいんだ。さっきから……」
そう言ってキョウジは苦笑する。
「ドモン……」
弟の悲痛とも言える叫び声に、シュバルツの心はかき乱される。
ドモンが―――『弟』が泣いている。
行かないと。
傍に行ってやらないと……!
「だから……シュバルツ……」
「何だ?」
「帰らなきゃ……。帰ってやらないと―――」
「――――!」
キョウジの言葉に、シュバルツは顔を上げる。
「帰ろう、シュバルツ」
シュバルツと視線が合ったキョウジが頷いた。
「『二人』で―――」
「――――!」
眼を見開くシュバルツに、キョウジは相好を崩した笑顔を見せる。
「あれだけ叫んで、待っているんだ。帰ってやらないと、殴られちゃうよ」
「『二人』で―――帰るんだな?」
「もちろん」
シュバルツの問いに、キョウジは笑顔で頷く。
お前には、手伝ってもらいたい事が、たくさんあるんだ
「…………!」
(気のせいだろうか。今、キョウジの『声』の聞こえ方が―――)
異変を感じたシュバルツが、もう一度キョウジに声をかける。
「キョウジ? 大丈夫か?」
大丈夫だよ。
キョウジは、あくまで笑顔でそう答える。
だが気のせいではない。キョウジの声の聞こえ方が、『遠い』
「キョウジ!? ―――キョウジ!!」
嫌な予感を拭えずに、シュバルツは叫ぶ。
平気―――。
だが、キョウジの笑顔と答えは変わらなかった。
(キョウジ……! 何か、『無理』をしているな……?)
確信めいたものを感じて、シュバルツは唇を噛みしめた。
そして皮肉にも、シュバルツの読みは当たっていた。
この世界に吹き荒れる『嵐』が、キョウジの『樹』を侵食し始めていたのである。
帰ろう、シュバルツ―――。
しかしキョウジは、笑顔で再びシュバルツに、そう言った。
「兄さん!! 兄さん!!」
ドモンが叫ぶ目の前で、シュバルツの『変化(へんげ)』は止まる気配を見せない。彼から変化し、派生したケーブルは、今や訓練場全体を覆う勢いで広がっている。それでもドモンが目の前のシュバルツの事を『兄』と呼ぶのを止めないのは、彼にまだ少し『兄』の面影が残っているからだ。
右手から上の、上半身の一部。そして、顔の右半分―――。
その部分だけが、まだシュバルツが『キョウジ』の容姿をとどめていた。
そして、彼から派生している『武器』たちは、未だドモンとハヤブサを、襲おうとしていなかった。
「おのれッ! まだ抗うか!! いい加減あきらめれば良いものを―――!!」
叫びながら魔道師は、尚もシュバルツに魔力を注ぎ込む。
「ア……! ガ……ッ!!」
だがシュバルツの方も、それ以上『変化(へんげ)』するのを拒み続けているようだった。
「おのれ―――!」
イラつきを隠せない声を上げる魔道師の所に、シュトワイゼマンから通信が入る。
「魔道師よ……素晴らしいな! お前が『見せたい物』と言っていたのは『これ』か?」
「左様にございます」
「素晴らしい――――」
恭しく答える魔道師に、シュトワイゼマンから満足そうな声が帰ってくる。
「短時間にこれほどの武器を発生させる事が出来るとは……! それも皆『DG細胞』の力によるものか?」
シュトワイゼマンの言葉に、魔道師は同意した。
「そしてこれは、『人間』にも移植は可能なのだな?」
「先程『ダレク』と『残月』を、ご覧になりましたでしょう?」
「そうであったな……」
そう言いながら老人の顔に、暗い笑みが浮かぶ。
「ならば、敵対する勢力の元に、感染者を一人放り込めば、そこに壊滅的な打撃を与える事も出来るだろうな…。それにこれだけの『威力』……欲しがる輩も多かろうて」
また自分の懐に莫大な利益が入ってくる算段が立つ、と、シュトワイゼマンは舌なめずりをした。
「それにしてもこの凶悪な『細胞』……よくぞ今まで軍事転用されずにおったものだな……。細胞を発見した者は誰だ?」
「この者の『記憶』をたどりました所……おそらくこの者の『父親』かと―――」
「ほう! 父親―――!」
それを聞いたシュトワイゼマンは、大笑いをしだした。
「大した父親だな! 細胞を金に換える事もせず、『息子』の身体を改造したのか!?」
「いえ……『これ』を作ったのは、どうやら『息子』本人の様ですよ…」
「!? 自分で『自分』を作ったのか!? 何故そんな酔狂な事をする?」
「さあ――――」
シュトワイゼマンに問われた魔道師は首をかしげる。『記憶』をたどってみたが、自分には理解不能だった。説明するのも困難に感じたし、シュトワイゼマンに説明する必要性も感じない。
「くははははは!! どちらにしろ、父親が『父親』なら息子も『息子』だ!! このような『金のなる木』を有効に生かせないとは――――!」
「――――ッ!!」
父と兄を侮辱されたと感じたドモンは、シュトワイゼマンを撃とうとする。だが、魔道師がシュバルツの身体を盾にするようにシュトワイゼマンを庇うため、ドモンは撃つ事が出来ない。
「兄さん!! 兄さん!!」
必死に呼びかける。呼び掛けると、シュバルツの『右手』が反応しているのが分かる。
兄の右手が、時折自分に向かって伸ばされてくる。
もしかしたら、泣いている自分の頭をなでてくれようとしているのかもしれない。―――いつも、兄がしていてくれたように。
ああ。あの人はまだ『兄』なのだ。
もう身体のほとんどが、『人の姿』で無くなってしまっていると言うのに。
あの人はまだ―――『兄』であろうとし続けているのだ。
その証拠に、シュバルツから派生している『武器』たちは、まだ自分やハヤブサを襲おうとしていない。攻撃は肉薄して来ている。でも―――まだ、当たらない。武器たちは自分達を掠めて、むしろ敵方を攻撃している。兄の明確な意思が働かない限り、こんな事は不可能だ。
シュバルツと視線が合う。
その口元が動く。
『撃て』と、動いているような気がする。
「嫌だ」と、ドモンは首を振る。
だって、あそこにいるのは兄だ。兄なのだ。
撃ちたくない。
撃てば『兄』は―――シュバルツは、消えてしまう。
撃ちたくないんだ……!
(撃つべきだ)
別の誰かの声が、ドモンの中で囁く。
兄が、兄のままでいるうちに撃つべきだ。
あのままでは、遅かれ早かれ完全に『化け物』と呼ばれる者に移行してしまう。
そうなる前に撃ってやるのが、せめてもの「情け」だ。
(…………!)
理屈はそうだ。分かっている。
でも嫌だ。
撃ちたくない。
ドモンは頑なに首を振る。
自分は兄を殺したくない。助けたいのだ。
助けたいのに――――!
その方法が分からない。
(何が、『キング・オブ・ハート』……!)
この局面で、あまりにも無力な己に、ドモンの膝が折れそうになる。
(『強く』なったはずなのに、結局俺は……)
何にも、出来ないじゃないか――――!
「兄さん……ッ!! 兄さぁぁぁぁ―――――ん!!!」
叫ぶしか出来ない自分の視界の中で、『兄』の姿が霞んで行く。
このままドモンの目の前で、シュバルツが『シュバルツ』で無くなってしまうのも、時間の問題かと思われた―――将にその時。
「ドモン!! 何を呆けておるかぁ!!」
「―――!」
頭上から声と共に、東方不敗が姿を現した。
「師匠!?」
驚くドモンのすぐ横に着地した東方不敗は、間髪いれずに攻撃動作に入る。
「石破天驚―――!」
「おっと!!」
撃たせるものかと魔道師は、シュバルツを盾にしてきた。だが東方不敗は躊躇わずにその拳を撃ち切った。
ドカン!! と、派手な音がして、シュバルツの右足から派生していたケーブルが吹っ飛ばされる。
「ガッ……!」
シュバルツが苦しそうに呻く。
「―――!?」
驚く魔道師に向かって、東方不敗がにやりと笑みを浮かべる。
「シュバルツを盾とするか! むしろ好都合!!」
「―――何ィ?」
「ワシの狙いは最初っからそれよ!! うおおおっ! もう一発!!」
「師! 師匠!?」
叫びながら攻撃動作に入ろうとした東方不敗に、ドモンはたまらず声をかける。
師である東方不敗もまた、DG細胞を滅する事の出来る『紋章の力』の持ち主。撃てばその力はシュバルツを消してしまいかねない。
だが、東方不敗はそんなドモンを厳しい目つきで睨め付けると、こう叫んだ。
「―――ドモン!! お主はワシを信じるか!?」
「―――!?」
師から発せられた質問の意味が一瞬分からず、ドモンは立ちすくんでしまう。だが東方不敗の見開かれた眼は、ドモンから逸らされる事は無かった。
(信じるか!?)
師の眼差しから、もう一度問われる。
信じる――――!?
ドモンは己の中で自己問答をした。
師匠の行動を信じろと言うのか。
紋章の力で拳を放ち、シュバルツを消しかねない行動をしている師匠を――――!
「信じます!!」
ドモンは叫んだ。
そこに在るのは『理屈』ではなかった。
ドモンは『本能』でそれを言った。
師匠の眼差しを信じた。
その拳を信じた。
この局面、師匠を信じる事が出来ずして、これから何を信じられようか―――!
「よかろう!! ドモン!! よくぞ言った!!」
東方不敗は叫びながら、攻撃動作に入る。
(あの構えは―――!)
ドモンも悟った。師匠が今から『何』をしようとしているのかを。
「ドモンよ!! ワシと呼吸を合わせるのだ!!」
ドン!! と、音を立てて、東方不敗の『闘気』が爆発的勢いで高まっていく。
「はい! 師匠!!」
ドモンの闘気も、爆発的に高まった。二人の身体が、黄金色に輝きを放ちだす。
「行くぞ!! 我らが『流派 東方不敗』究極最終奥義―――!」
「撃たせるか!!」
この攻撃の危険性を本能的に悟った魔道師が、自身で魔道弾を放つと同時に、先の攻撃によってシュバルツ本体から離れた『武器』たちに攻撃を命じる。シュバルツの意思が働かない『武器』たちが、東方不敗とドモンに容赦なく殺到した。
「むぅッ!!」
魔道師からの攻撃を避けるために、東方不敗はやむを得ず奥義の『構え』を解こうとした。だが―――二人の身体に、攻撃が当たる事は無かった。
ドカン!!
派手な破壊音と共に、東方不敗とドモンの前に一つの黒い影が飛び込んでくる。
「ハヤブサ!!」
影の正体にいち早く気づいたドモンが叫ぶ。二人に向かう攻撃を、総て防ぎきった龍の忍者は、二人の方にちらりと視線を走らせるとこう叫んだ。
「防御は引き受けた!! 存分に――――!」
そう、ハヤブサも『機』を待っていた。
自分にかけられた『呪い』の効力が弱まり、敵に反撃できるチャンスが来るのを。その為に無駄に消耗する事を避け、動かずにじっと待っていたのだ。
シュバルツの『攻撃』が自分に当たるか当らないか――――それだけが、ハヤブサの中では『賭け』だった。
そして、その賭けに勝利した『今』こそが、その時なのだと悟る。
「よし! ドモンよ!! 行くぞ!!」
「はい! 師匠!!」
龍の忍者によって防御の心配が無くなった二人は、再び奥義の構えに入る。爆発的に高まった二人の『闘気』は、ドン!! と、音を立てて辺り一帯に風を巻き起こした。
「おのれッ!!」
魔道師は攻撃を繰り出すが、総て龍の忍者によって弾かれてしまう。
「我らの拳が真っ赤に燃える!!」
東方不敗の手の甲に『キング・オブ・ハート』の紋章が浮かび上がる。
「勝利を掴めと轟き叫ぶ!!」
同じくドモンの手の甲にも、『キング・オブ・ハート』の紋章が浮かび上がった。
「行くぞ! 我らが最終奥義!!」
東方不敗が大きく構えを取ると同時に、ドモンがその前に走り込んでくる。
「究極―――!!」
「石!!」
「破!!」
「「天・驚・拳――――――!!!」」
師と弟子から同時に放たれた黄金色の『光』が、『シュバルツ』と魔道師の姿を飲みこんで行く。
「―――――――ッ!!」
声にならない誰かの絶叫が響き渡る。
「……………ッ!」
一瞬それが『兄』の声に聞こえたドモンは、怖じ気そうになる。しかし、そんなドモンに後ろから東方不敗の声が飛んだ。
「ドモンよ!! よく見るのじゃ!! お主が守りたい者を!! そして、『撃たなければならないモノ』を―――!!」
守りたい者―――。
そして
『撃たなければならない』モノ――――!
師の言葉を忠実に守り、ドモンは必死に光の中に目を凝らす。
俺が―――守りたい者は――――
兄さん…!
兄さん……!
兄さん―――――!!
ドモンはいつしか、光の中に『兄』の姿を必死に探し求めていた。
闇の中、キョウジの『樹』はシュバルツを守る様に蔓や枝葉で彼の姿を覆っていた。
だが、既にキョウジの表情に『笑顔』は無い。苦しいのか、時折小さな呻き声すら、その口から漏れている。
(キョウジ……!)
キョウジの手を握り返しながらシュバルツは、自分が何もできない現状に唇を噛みしめた。
キョウジのために、何かしてやりたい。だが、自分を消そうとしている『嵐』が迫りくる中、自分が下手に動けば、あっという間に消されそうになってしまうだろう。そうなると、シュバルツが消える事をよしとしないキョウジが、自分に『光』を送り込んでくることになる。たとえそれが、自分の『命』を削る行為であっても、それには構わずに―――。
それは駄目だ。と、シュバルツは思う。
だから自分は、キョウジの傍に留まり続けることしか出来ない―――。
『守られる側』の辛さを、シュバルツは思い知る。
この状況。自分で『守る』ために動いている方が、余程楽だ。
時折キョウジが、シュバルツの手を強く握ってくる。
それは、祈っているようにも―――縋っているようにも、見えた。
だからシュバルツも、せめてキョウジの手を握り返す。
せめて『独りじゃない。傍にいる』と、キョウジに伝わるように。
自分のこの手を、キョウジは『好きだ』と言っていた。
この手が、キョウジの力になれれば良いのに。
私からも、キョウジに『光』を送り込む事が出来れば良いのに―――。
分かっている。空虚な願いだ。
だがシュバルツは、そう願わずにはいられなかった。
―――シュバルツ……。
「――――!」
不意にキョウジから声を掛けられ、シュバルツは顔を上げる。視線が合ったキョウジが、微笑んだ。
「キョウジ……?」
―――ドモンが……来ル。
「ドモンが!?」
驚くシュバルツに、キョウジは綺麗な笑顔を向ける。
―――モう、大丈夫だな……。シュバル…ツ―――
そう言うとキョウジは、ふわ、と、背後の樹の中へと引き込まれるように消えて行った。まるで、力尽きたかのように。
「キョウジ!!」
シュバルツは慌ててキョウジに向かって手を伸ばすが間に合わなかった。のばされた手は、虚しく空を切ってしまう。
それと同時に、シュバルツを守る様に囲んでいた枝葉や草の蔓たちも、バッ、と、音を立てて、雲散霧消するように消えてしまう。
「あっ………!」
シュバルツの身体はあっという間に強風にさらわれ、このまま『嵐』の中に引き込まれるか、と、思われた。
しかし。
ガクン、と、シュバルツの身体が何かに引っ張られて止まる。
「―――!?」
引っ張られた右手を見ると、一本の草の蔓が、シュバルツの右腕に絡まっていた。
その草の蔓は、細く小さな木の枝から伸びている。そしてその木と蔓には、淡い光が宿っていた。それは、キョウジがその身から発していた光と、同じ物だ。
(キョウジ……ッ!)
細くて今にも切れそうな草の蔓。しかし、淡い光を放つそれは、しっかりとシュバルツをつなぎ止めている。そこに、「この手は、絶対離さない!!」と叫んでいたキョウジの姿が重なる。
ああ。
居るのだ。キョウジは。
あんな小さな木の姿になっていても
あそこに……! まだ――――!!
それと同時に。
ゆらり、と、シュバルツの背後に、『闇』が蠢く気配がする。
「…………!」
シュバルツが振り返ると、『闇』の塊が、彼に迫って来ていた。
―――邪魔モノガイナクナッタ…。ヤット『観念』シタノネ……。
―――サア、アキラメテ、我ラノ所ヘ来ルノダ……。
『闇』の中から男女の声がしたかと思うと、そこから4本の腕がズボッ、と、音を立てて伸びてきた。
「――――!」
シュバルツは気付く。『闇』の塊が、男女が混じり合ったような格好をしている事に。
『人間』としての形をとどめている訳ではない。しかし、ところどころに『人間』の――――『男』と『女』の形の名残が不定形にちりばめられている。
そして何よりも『顔』―――男と女の物が歪(いびつ)に融合していた。
闇から伸びてきた腕が、シュバルツの足をガシッと掴む。
「あうっ!!」
焼けるような激しい痛みがシュバルツを襲う。彼はたまらず悲鳴を上げた。
でも、まだ消えていない。『痛み』を伴うと言う事は、自分の実体が、まだある証拠だ。
キョウジ……!
キョウジッ……!!
シュバルツは懸命に、目の前の細い木に向かって腕を伸ばす。
嫌だ。
消えたくない。
消えたくない。
消えたく……無いんだ!
激しい痛みと共に、無理やり引っ張られる身体。
それでも折れない細い枝。
切れない草の蔓。
それに宿る、淡い光―――!
キョウジ――――!!
ズブッ、と、音を立てて、シュバルツの下半身が、闇に呑みこまれた―――その時。
「兄さん!! 兄さぁぁぁぁぁ――――ん!!」
荒れ狂う嵐をものともせず、眩しい光を放ちながら、ドモンが突き進んでくる。
「ドモン!!」
シュバルツの叫びに、ドモンが気付いた。
「兄さん!!」
―――逃ガサナイ…。
更に『闇』が、シュバルツを飲みこもうとする。
「ああっ!!」
全身を襲う激痛に、シュバルツは悲鳴を上げた。
「おのれッ!! 兄さんを離せ!!」
ドモンはまっすぐにシュバルツに向かって飛んでくる。闇に呑まれながらも、シュバルツも懸命にドモンに向かって手を伸ばした。
ガシッ! と、力強い手が、シュバルツの手を掴む。それと同時に、シュバルツの右手に絡まっていた草の蔓と、それを支えていた木が、細かい光の粒子となって消えていった。
「分かった!! ―――俺の『撃つべきモノ』が!!」
『闇』からシュバルツの身体を引っ張り出しながら、ドモンが叫んだ。
「それは……兄さんを捕らえている、お前、だッ!!」
ドゴォッ!! と、音を立てて、ドモンの石破天驚拳が、『闇』の頭頂部分にゼロ距離から炸裂する。
「そして……俺の『斬るべきモノ』も分かった!!」
天驚拳の光と共に、仮面の魔道師に肉薄していたハヤブサが叫んだ。
「それは! お前の『仮面(これ)』だッ!!」
ドン!! と言う音と共に、ハヤブサの『龍剣』は、過たずに仮面を切り裂いていた。
「ぎゃああああああ――――――っ!!」
仮面を破壊された魔道師の断末魔の悲鳴が、辺りに響き渡る。仮面は龍剣が発した炎に包まれて、跡形もなく消えて行った。
「ナゼ……ッ! ナ…ゼ………」
魔道師の身体が黒い煙の様な物を吐きだしながら、ボロボロと崩れて行く。
「前に出すぎだ! 貴様は――――!」
乱れた息を整えるように深い息を吐きながら、ハヤブサは魔道師を見下ろしていた。
シュバルツに弾き飛ばされ、倒れている間、ハヤブサはずっと龍剣を握り込んでいた。そして、その『声』を聞き続けていた。
化け物の『もう一つの本体』を示唆する声を――――。
もしも魔道師が、今まで通りただ『黒の女神』の横に控えているだけの存在であったならば、龍剣も『勾玉』以外の『女神』の本体に気づく事は無かったであろう。それほどまでに、『勾玉』の放つ力は強烈だった。
だが魔道師が、シュバルツにその魔力を注ぎ込んだ事によって、龍剣にその力の源を突き止められてしまう。そして、それが『女神』と連動している事も―――。
事実、『女神』の身体も少しずつ、崩れて行っているようであった。本当の『魔』の源を絶たれて、その形を保っていられなくなってきたのであろう。
DG細胞の『力』に引き寄せられすぎた。それが、魔道師の『敗因』だった。
「兄さん!!」
「――――!」
ドモンの叫び声にハヤブサが振り向くと、ドモンが黒く焼け焦げたケーブルの塊の中から、シュバルツの身体を引っ張り出していた。ズルッ、と、音を立てて、シュバルツの身体が滑り出てくる。一糸まとわぬその身体には、手も足もきちんと備わっていたので、ドモンはとりあえず安堵の息を漏らす。
「兄さん? 兄さん!!」
「…………」
しかし、呼びかけてみても反応が無い。
「シュバルツ!?」
ハヤブサも二人の側に駆け寄ってくる。ドモンはシュバルツの胸に、耳を当てた。
………ピッ………ピッ………
シュバルツの内部の『駆動音』が、ドモンの耳に返ってくる。
「……生きてる……」
ドモンは何故か、泣きそうになった。
「無事なのか!?」
ハヤブサの問いに、ドモンは頷く。
「うん……『生きてる』よ……」
そう言いながらドモンは、シュバルツの身体に自身の赤いマントをかけた。
(――――ッ!)
魔道師の『仮面』が破壊された衝撃が、『勾玉』を通して、キョウジの身体を駆け抜ける。柱の上の踊り場で、膝をついて祈るような姿勢で勾玉を握り込んでいたキョウジであったが、思わず倒れそうになる。
まだ……まだ、倒れるな。
キョウジは強く己に命じる。
強い嘔吐感。また噎せて、そして吐いた。こうして彼の周りには、既にいくつもの血だまりが描かれていた。
「…………」
口の周りについた血を拭い、キョウジは握り込んでいた手を、そっと開く。
(……ありがとう。『力』を貸してくれて―――)
「……………」
それに対して勾玉は、小さな声で答えを返した。それを聞いたキョウジが微笑む。
(いいよ……。君は、思う通りに―――)
「……アリガトウ……」
キョウジの手の中で、勾玉の光が強くなる。
(…………ッ!)
キョウジの身体に、不思議な感覚が走り抜ける。それと同時に、彼の手の中の勾玉から、光の塊が滑り落ちるように分離して行った―――。
「こ、これは一体どういう事だ!? 一体何が起こっているのだ!!」
目の前で起こった事態について行けない老人の叫び声が響く。
「何故奴らが立っているのだ!? 『魔道師』はどこへ行った!? 『DG細胞』の化け物は何処へ―――!!」
「殴れ」
妙に低い声と共に、『殴れ』と命じられた女神の拳が、雄たけびと共にシュトワイゼマンに襲いかかる。
「ヒッ!?」
女神の拳は、シュトワイゼマンを掠めて、その後ろの通路を破壊した。
「だ、脱出路が―――!」
自身の退路を断たれてしまったシュトワイゼマンが、悲鳴に近い声を上げる。通路を破壊した女神もその衝撃で腕が落ちた。崩れて行くのが止まっていない。
「き、貴様は―――!!」
シュトワイゼマンが、柱の上に佇むキョウジの存在に気づく。
「……………」
キョウジはただ無言で、シュトワイゼマンを見下ろしていた。
だがその無言の視線に―――シュトワイゼマンは、何故か気圧されてしまう。
「兄さん!? あんな所に―――!!」
ドモンも、柱の上の踊り場に立つキョウジの存在に気づく。柱の周りの炎が発する熱風が、キョウジの髪と服を揺らし、その胸の前に青白い光が輝いている。そしてその脇に、いつから居たのか――――青白い光を放つ、一人の小さな女の子が控えていた。
不意に、兄の口の端から、赤い筋が一筋流れ落ちたように見える。
(血………!?)
ドモンは訝しんで目を凝らす。だが次の瞬間、兄が口元を手で拭ったと思うと、それは跡形もなく消えていた。
キョウジが、シュトワイゼマンから視線を外し、自分のすぐ近くに控える女の子に視線を移す。その表情は、シュトワイゼマンに見せていたものとは打って変わって優しいものになっていた。
「さあ……行っておいで……」
キョウジの口がそう動いた様に、ドモンには見えた。それに女の子はこっくりと頷くと、着物の裾をなびかせながら、そこからふわりと飛び下りた。それは重力を感じさせない動きで、風に漂う様に舞い降りてきたかと思うと、仮面を破壊され、黒い煙を吐き出しながらのたうちまわっている魔道師の所へと歩を進めて行く。
女の子は、魔道師の身体にそっと手を置くと、こう呼びかけた―――。
(……お父さん……お母さん……)
「―――――!」
のたうちまわっていた魔道師の動きが、一瞬止まる。
(ア…………!)
その声に最初に反応したのは、『妻』の方であった。魔道師の身体から、青白い光を放つ『女』の霊体が分離する。
(ごめん……ごめんな、さい……!)
『女』は、その女の子を抱きしめると、泣きじゃくりだした。
あの日、自分は守れなかった。
夫が作った『奇跡の村』も。
自分の胎に宿った、『小さな命』も―――。
引き裂かれ、蹂躙され、『絶望』の内にその生を閉じた。
そして、『魔』に堕ちた。
それなのにこの子は――――まだ自分の事を『母』と呼んでくれるのか―――。
守れなかったのに。
この手で抱く事も出来なかったのに……。
(良人(あなた)………)
娘を抱いた妻が『慧信』に呼びかける。
「………………」
だが、魔道師の闇の中から、『慧信』が出てくる事は無かった。ぶすぶすと黒い煙を撒き散らしながら、魔道師の身体は塵の様に消えて行った。
「お母さん、行こう」
娘が、母の袖を引っ張る。そうね、と、母親は少し哀しげに微笑みながら、娘に従った。
ふわ、と、母娘(おやこ)の身体が宙に浮く。
――――ゴメンナサイ……。
そう言葉を残して、二人の姿は消えて行った。それと同時にキョウジの胸の前で光を放っていた勾玉も、サアッ、と、霞の様に消えて行く。
(さよなら……)
散っていく光の粒子を、キョウジも淋しげな笑顔を浮かべながら見送った。
勾玉はギアナ高地で必死に黒の女神に向かって叫んでいた。
『お母さん、お母さん』と……。
それでキョウジも、勾玉の正体に確信を持てた。『力の源』とは、生まれ出づる事の出来なかった二人の『子供』なのだと。
(本当ならこの勾玉は、『女性』の胎に入るべきモノだったのかもしれないな……私の様な『男』の身体に入るのではなく……)
そう感じて、キョウジは知らず苦笑していた。
それでも、『自分』で良かったのだろうか?
少なくともレインをこんな目に合わせるのは『嫌』だなぁ、と、キョウジは思った。
「一体これはどういう事だ!? どういう事なんだ!!」
目の前で起こっている事態が、どうしても理解できないシュトワイゼマンの声が響く。そのシュトワイゼマンに止めをさすかのように、『黒の女神』の身体が、がらがらと音を立てて崩れ落ちて行った。
「ええい! 何もかもが勝手に居なくなりおってからに……!」
老人の怒りがついに頂点に達する。
「こうなったら、貴様らも世界も道連れにしてやる!! わしの手元にあるここのボタンを押せば、某国の核ミサイルが、ここに飛んでくるようにする事が出来るのだ!! そうなればお前らも―――世界も、終わりだ!!」
そう言いながら老人は高笑いをする。
「な――――!」
「……………」
老人の言葉に、ドモンとハヤブサの顔色が変わる。だが、キョウジの表情は変わらなかった。相変わらず、何の感情も窺い知れない眼差しで、シュトワイゼマンを見つめている。
「どうだ!! ボタンを押されたくなければ―――!」
「……押すのか?」
妙に冷静な声が、シュトワイゼマンの言葉に重なる。
「――――!?」
一瞬何を言われたのか理解出来無かったシュトワイゼマンは、その言葉を発したキョウジの方を見た。だが、キョウジの静かな眼差しに、変わりはない。
「何を…! わしは、『ボタンを押す』と―――!」
「もう一度聞くぞ? ……『押す』のか?」
「な……何ぃ……?」
「『押す』んだな?」
「―――――ッ!」
シュトワイゼマンは思わず絶句してしまう。
おかしい。
この状況、圧倒的な武力を持ち、目の前の男を脅しているのは自分のはずだ。それなのに、何故自分が追い詰められたような格好になっているのだ。
気に入らない。
自分があの男を『見上げている』のも。
あの男が自分を『見下ろしている』のも――――!
「き、貴様……! わ、わしがこのボタンを押せ」
「『押す』のなら―――押せばいい!」
シュトワイゼマンの言葉を遮る様に、キョウジが叫ぶ。
「『終わり』たければ」
「…………!」
「『忠告』は、したぞ」
キョウジはそう、無表情で言い放つ。
『忠告』―――――『忠告』だと!?
あんな若造が、このわしに向かって生意気にも『忠告』だと!?
(おのれ……ッ!)
シュトワイゼマンはかつてないほど頭に血が上っている自分を感じる。
「若造が!! このわしに向かってそのような口を利いた事、あの世で後悔するがいい! 望みどおり『終わり』をくれてやる!! 世界の終わりを―――!!」
ダン!! と、叩きつけるようにシュトワイゼマンは、そのボタンを押した―――。
「……押したな?」
「うわはははは!! 押した!! 押してやったとも!! これで―――貴様らも、世界も『終わり』だ!!」
そう言いながら、シュトワイゼマンは高笑う。
「……そうだな。確かに、『貴方』は『終わり』だ―――」
「―――!?」
キョウジの言葉に、シュトワイゼマンは再び言葉を失う。何か、不吉な響きを聞いた様な気がした。
「……ど、どういう、事……だ…?」
息を飲みながら問うシュトワイゼマンに、キョウジはただ『笑った』
「どうもこうも―――」
そう言いながらキョウジは、己の腕時計に視線を走らせる。
「ああ……そろそろ『電話』が入ってくるんじゃないかな? 『貴方』に―――」
「…………?」
訝しむシュトワイゼマンの懐で、携帯電話が音を立てる。彼が電話に出ると、知りあいの『議員』の声が機械の向こうから聞こえてきた。
「シュトワイゼマン!! 貴様!! どういうつもりだ!?」
「? どういうつもりとは?」
「とぼけるな!! 何故『あの時』の画像が、ネット上に出回っている!?」
「―――!?」
「おかげでこちらの事務所は、先程から電話が鳴りっぱなしだ!! 『例の件』を秘匿するは、わしらの中では暗黙の了解であるのに――――!!」
「な、何だって…?」
シュトワイゼマンは震える手で、己の端末機を操作する。すると、ネットのトップニュースに『大物上院議員 わいせつ動画がネットに流出』と言う文字が、踊っていた。
「!? !? !?」
茫然とするシュトワイゼマンの目の前で、次々とニュースサイトが更新されて行く。
『大物議員に児童買春の疑い』
『大物上院議員二重帳簿の疑い』
『軍需工場と癒着か? それを示す資料流出』
『軍需会社の闇金? ネットに突如としてそれを示唆する資料が…』
『軍需工場 人道を外れた実験の数々』
『内戦地を、化学兵器の実験場にした疑いも―――』
「な――――!」
茫然とするシュトワイゼマンの所に、『愛人』たちから一斉にメールやら電話やらがかかってくる。
「ちょっとどういう事なの!? 私たちの写真を急にネットに公開するなんて!!」
「この女にはこんな高級バッグを買っていて、私には無いってどういう事!?」
「さっきから取材記者が家に押しかけているわ!! どうしてくれるのよ!!」
「…………! …………!!」
悄然とするシュトワイゼマンに、更にたたみかけるような通信が入ってきた。
「あの~。シュトワイゼマン様?」
「……な……何だ…?」
「株の売買計画は、このままでよろしいので? ものすごい勢いで資産が減っていますが……」
「何だと!?」
「本当です。明日の朝までには、それこそ資産が『0』になる勢いです」
「―――――!」
シュトワイゼマンは、目の前が真っ暗になるのを感じた。
「か……買い戻せ……! 資産を……取り戻さねば……!」
「無理ですよ。ここにいる社員全員、居なくなってしまいました」
「――――ッ!」
「このままでは、私たちの『退職金』もなくなってしまいますからね。そうなる前に、そのお金だけは頂いて、私もお暇させていただきます」
それだけ言うと、その社員からの通信は、ブチッ、と、音を立てて切れてしまった。
「な……! か……! か……ッ!」
あまりの急転直下な事態に、シュトワイゼマンは言葉すら発する事が出来ない。
「申し訳ないが、貴方の会社のマザーコンピューターに、いろいろと細工をさせてもらった。貴方がその『ボタン』を押せば、貴方が『終わり』になる様に」
「な――――!」
キョウジが淡々と紡ぐ言葉に、シュトワイゼマンは息を飲む。
「貴方がそのボタンを押しさえしなければ、私もそこまでするつもりはなかったんですけどね……」
そう言いながらキョウジの口元は『笑顔』を作っている。しかし、その瞳は笑っていない。
「貴方は、私にもシュバルツにも、結構ひどい事をしてくれた……。貴方は、私を怒らせた―――」
「…………ヒッ!」
キョウジの言葉と目線に、シュトワイゼマンは何故か斬りつけられた様な印象を受けて、竦んでしまう。
「だから、それ相応の『報い』を受けてもらう。……何、あともう少しすれば、さすがにこの国の警察も政府も、重い腰を上げざるを得なくなるだろうね。貴方は『トカゲのしっぽ』になるんだ」
「ままま、待て! 待ってくれ!!」
シュトワイゼマンが哀願するように叫んだ。
「お、お前ほどの『才』があるのなら、わしが喜んで雇ってやろう! わしとお前が組めば、『富』も『権力』も……お前の望むままだぞ!?」
「興味無い」
キョウジはそれをズバッと切り捨てる。
「な……! 何故だ!!」
シュトワイゼマンは愕然とした。『富』と『権力』に興味のない人間など、居る筈が無いからだ。
「『富』は、食っていければ充分。『権力』は、必要最低限あれば充分」
「…………!」
「そんな事よりも貴方は、自分の身を心配するべきだ…。まず、どうやってそこから降りるんですか?」
そう言ってキョウジは『にっこり』と微笑む。
(こ、こいつ―――! 自分でこちらの『脱出路』を破壊しておきながら――――!!)
「あ……! か……ッ!」
怒りのあまりにろれつが回らなくなる。それでもシュトワイゼマンは、何とか目の前の男に一矢報いたくて、何とか言葉を絞り出した。
「こ…この……『悪魔』!!」
それに対してキョウジは『にやり』と笑って答えた。
「『褒め言葉』として……受け取っておくよ……」
そしてそれが、キョウジの『限界』だった。
ゆらり、と、キョウジの身体が傾いだかと思うと、木の葉が舞い落ちるかの如く、柱の上の踊り場から落下した―――。
だが、誰よりも早く東方不敗が反応した。彼はドモンと共に石破天驚拳を撃ち終わってからは、ひたすらキョウジの身体のみを案じて、いつでも助けに行ける様に構えていたのだ。空中でキョウジの身体を受け止めると、近くに在った柱に横向きに着地し、その柱を蹴って方向を変え、周りの炎の海から脱出する。その行動をしながら、東方不敗は叫んだ。
「引き潮じゃ!! 皆の者! 脱出するぞ!!」
東方不敗の言葉に、ドモンとハヤブサが従う。ドモンがシュバルツの身体を抱え、ハヤブサがその横について走り出した。
「ま、待て! わしも……! わしも誰か下ろしていけ!!」
だが、そのシュトワイゼマンの言葉に応える者は、誰もいない。
「待て! 誰か……! 誰か―――!!」
老人の叫びは、瓦礫の中へと虚しく吸い込まれて行った。
「最終章」
ココハ、ドコダロウ……。
暗闇の中、意識の目覚めた『何者か』の声が響く。
真っ暗。
自分は一人。
周りには、誰もいない。
怖イ……。
ただ震えるしか出来ない自分。そこに、一筋の『光』が差した。
ヒトが近づいてくる。そのヒトは、自分が入っている器毎ひょいっと持ち上げると、声をかけてきた。
「お前はせっかく生まれてきたのに……『このまま』なんて勿体ないよね」
その人から『温かいモノ』が流れ込んでくる。
何だろう?
これは……何だろう?
それからその人は、光と共に自分の所にやって来るようになった。
この人から声をかけられると、『嬉しい』
この人から流れ込んでくるモノを受け取るのは『気持ちいい』
これを、もっと浴びて居たい。
もっと、もっと――――。
「キョウジ」
そう呼ばれると、目の前のこの人は『はい』と返事をする。
「キョウジ」
この人の、名前。
「キョウジ」
とても『大事な人』―――。
「すごいじゃないか! 『アルティメット』! これならば、お前を本格的に実用化するのも夢じゃなくなる!」
そう言って、キョウジが嬉しそうに笑う。
違う。凄いのはキョウジ。
私はその望みに応えているだけ。
キョウジから送られてくる、温かいシャワーを浴び続けて居たいだけ。
だから、キョウジが喜んでくれるのならば、私は何だってする。
だからキョウジ。もっと望んで。
次の望みは?
次の『望み』は――――?
「……………」
ある日、キョウジがひどく落ち込んだ気持ちを発散していた。
どうしたの?
そう聞きたいけど、自分に『口』があるわけじゃない。
キョウジに声がかけられればいいのに。
私は、キョウジと『お話』がしてみたい。
「次の学会の論文が………」
キョウジがそこまで言ってふっと黙りこむ。
「違う……お前には、『嘘』を言ってもしかたがないよな……」
そう言うと、キョウジはイスに座り、机に頭をゴン、と、打ちつけた。
「父さんと母さんには内緒で……ドモンの……『弟』の様子を、見に行ってたんだ……」
弟? と、不思議に思う。
ずっとキョウジを見てきたけど、弟の姿なんて、見た事が無かったから―――。
「そしたらあいつ……笑ってた」
机の上に突っ伏したまま、キョウジが続ける。
「家でも見せた事の無いような笑顔で……楽しそうに、笑ってたんだ……」
キョウジから、『哀しい』気持ちが発散される。
「私には……絶対、出来なかった事だったのに……」
キョウジ―――。
キョウジ。
キョウジ。
『哀しい』気持ちに揺さぶられる。
「やっぱり私は――――『駄目な兄貴』なのかな……」
そう言いながらキョウジは、また机に頭をゴン、と打ちつけている。
キョウジ。
キョウジが哀しいと、『哀しい』
哀シイ。
哀シイ。
カナ――――。
「……駄目だな…。これ以上は……。お前に『悪影響』が出ちゃうよ……」
そう言ってキョウジが、顔を上げる。
キョウジから、『優しい』気持ちが溢れてくる。いつものように。
でも、『哀しい』
『哀しい』のに――――『優しい』
『優しい』のに――――『哀しい』
キョウジ……どうして?
どうして、自分の事を『駄目だ』なんて言うの?
私には、貴方が『すべて』なのに。
貴方こそが『光』なのに―――。
キョウジ。
キョウジ。
泣カナイ デ
キョウジがついに、私に『身体』を作ってくれた。
嬉しい―――。嬉しいんだけれども。
キョウジ……これは少し、大きすぎやしないだろうか?
だって、ほら――――貴方の身体が、私の手のひらに、乗っちゃうよ。
でもいいや。
そう思う事にした。
だって、その方が―――貴方を守れるし、何よりもキョウジが――――『嬉しそう』
キョウジが『嬉しい』と、私も『嬉しい』
キョウジが『楽しい』と、私も『楽しい』
ああ、また落ちそうになってる。
慌ててその身体を受け止める。
「ありがとう」
礼を言われる。
(ドウイタシマシテ)
返事を返したい。でも、それはまだ、無理っぽい。
この人、大丈夫かな。
いろいろ夢中になったら、結構周りが見えていない様な気がするぞ。
キョウジが、私の内部で作業をしている。少し、くすぐったい。
(キョウジ……)
呼び掛けてみる。
「――――?」
あ、振り向いた。
「呼びかけられた…? まさかな……」
そう言って、また作業に戻る。
ああ残念。やっぱり、私の『声』が聞こえていたわけじゃない。
でも、『気配』は伝えられた。
きっと、もう少しで、『お話』も出来るよね?
キョウジ――――。
平和だった工房に、突如として響き渡る『銃声』『悲鳴』『怒号』――――。
一体何?
これは一体、何?
キョウジが中に乗り込んできて、『発進』の指示を出す。
だから、私はそれに従った。いつもの通りに。
でも、違う。
キョウジが、『いつもの通り』じゃない。
キョウジの脳波が激しく乱れている。
「ア……! ア……ッ!!」
キョウジ――――『泣いている』
『哀しい』? ううん、違う。
『哀しい』より、もっと深い。
『哀しい』より、もっと暗い――――。
ゼツボウ
ウラミ
怒リ――――。
怒リ
『怒リ』
マグマのような激しい怒りと共に、キョウジが望んだ物は、『敵』を一掃できる『雷』と『炎』――――!
それぐらいなら簡単。すぐに作れる。
作った『兵器』をキョウジに渡す。キョウジはそれを撃った。
キョウジ―――。
この力に、満足してくれた?
「フ……! クク……ッ! あはははははははははは!! あははははははははは!!」
聞いた事もないような笑い声と共に、キョウジの『心』が『空洞』になる。
怖イ……!
キョウジ。
キョウジ。
望んで。
何か望んで―――!
(……………)
キョウジから、急に反応が返ってこなくなった。生体反応は在るのに、心は空っぽのまま。
『操縦』されなくなった自分の身体は、バランスを失うしかない。
推進力を失った自分は、地球の引力に引かれるしかなかった。
猛烈なスピードで、墜ちて行く。
このままでは『壊れる』
自分はいい。でもこのままだと、キョウジも『壊れる』――――!
ダメ。
キョウジが『壊れる』のは絶対ダメ。
守ル キョウジ―――『守ル』
コクピットの中で動かなくなったキョウジの身体を、無数のケーブルで『繭』のように覆う。そうして、避けられない地面との激突に備えた。
ドォンッ!!
激しい轟音と共に、周囲の地面をクレーターの様に陥没させ、周囲の土や岩や砂を巻き上げる。コクピットの中のキョウジの身体が大きく跳ねる。ハッチに叩きつけられそうになる。
(ダメ!)
衝撃を、覆っていた『繭』で吸収する。それに耐えきれず、ハッチが砕けると同時に『繭』も砕け、キョウジの身体は外に投げ出された。そのまま地面に激突しようとする。
(ダメ! ダメ!!)
咄嗟に何本かのケーブルを伸ばすが、自身が壊れて行くのに合わせて、ケーブル自体もあっという間にちぎれ飛んでしまう。
それでもかろうじて残った2本のケーブルが、キョウジの身体を空中で受け止める。そして、そうっとキョウジの身体を地面に下ろした。下ろした所で――――その2本のケーブルも、ボロボロと、跡形もなく崩れて行った。
キョ、ウ……ジ……。
キ、……ョ…ウ…ジ……。
呼び掛けてみるけど、反応の無いキョウジ。
ワタシ……守レタ……?
キョウジ……守レ、レ、レ、レ、レレレレレレレレレレ――――――――――――――――――――
ブツン、と、そこで『何か』の意識が途切れた。
そこからしばらく、『靄』がかかったような状態が続く。
誰かがひどく哀しい声を上げて泣いているのが、聞こえたような気がする。
でも―――『誰』だろう。
『誰』の声なのだろう。
どうしても、思い出せなかった――――。
不意に、自分が見えている画像が切り替わる。
見慣れた『コクピット』
破壊された街。
そしてそこに居たのは『デビルガンダム』―――!
唐突に、思い出す。
これは、自分が『人間』だった時の記憶だ。
『人間』から、今の自分になる時に――――手放す事を拒否した『記憶』だ。
街の人々の避難を誘導しながら、目の前の巨大な機体の正体を、私は見当つけていた。
おそらくこれは『デビルガンダム』―――軍の上層部を通して、こちらに秘密裏に通信が入っていた。
「某国の『国家機密』とも言うべき、強力な力を持った兵器が国から逃げ出した。ただちにこの機体を破壊、もしくは捕獲せよ。なお、パイロットであるキョウジ・カッシュの生死は問わない」
そしてそれにかけられた莫大な懸賞金。
死体と破壊された兵器の一部でもそこに提示できれば、これだけの額が手に入る、ということか。ぴゅう、と、思わず口笛を吹いていた。この額が、丸々自分の懐に入るわけではないだろうが、最近にしてはひどく景気のいい話だ、と、思った。
それにしても、奴は何故こんなに街を破壊するのだろう?
自分の力を誇示したいからか?
何か、訴えたい事でもあるのか?
まさか、単なる気違いか?
好奇心が湧いた。
仕留める前に、こんな事をするキョウジ・カッシュの面を拝んでやろうと、私は目の前の『デビルガンダム』に通信を入れた。
パッ、と、音を立てて、目の前のモニターに、青年の顔の部分が映し出される。
(おや?)
不思議に思った。
こんな大それた罪を犯している割には、青年の瞳が随分きれいだったから――――。
それでも『悪党』は『悪党』だ。
どんな主義主張があろうが、それを誇示する手段として、関係無い街を破壊したり、他人の命を終わらせていいという理由には絶対にならない。
この破壊活動で、何人死んだと思っているんだ。
だが、モニター越しの青年は、自分の呼び掛けに必死に応えてくる。
だから私も応えてやった。こいつが犯した罪故に、こいつの家族に『何』が降りかかったのかを――――たいへん分かりやすく、教えてやったのだ。
気の毒だな。母は殺され、父は冷凍刑。
そして―――これは、お前の『弟』か。弟がお前の『討ち手』になるとは。
文字通り、お前の家族の未来は『真っ暗』だ。
お前が、こんなつまらん『罪』を犯したせいで。
何もかも、お前のせいで―――。
しかし…『ドモン・カッシュ』
どこかで聞いた様な名だが―――。
「待って―――! 待ってください! お願いします!!」
青年が、必死に声を張り上げてくる。私は思考する事を止め、顔を上げた。
「私の弟は、東方不敗の元に弟子入りをし、『強くなった』と聞きました! だから―――だから、お願いです! これだけは教えてください!!」
(…………!)
そうか……どこかで聞いた名前だと思ったら、あの『東方不敗』の弟子の名か。
東方不敗マスターアジアの名は、戦いの世界に身を置く者の間では知らない者などいないほどの有名人だった。
まだ直接対峙した事は残念ながら無い。だが、いずれは相対する事もあるだろう。
だから、折を見てこちらは、マスターアジアに関する情報を収集するようにしていた。マスターアジアは、私の事など多分知らないだろう。だが『忍者』とは、所詮そういうものだと思う。
しかし、この青年は、今更私に『何を』教えてくれと言うのだろう?
「何をだ?」
必死に問いかけてくる青年を無下にも出来ず、何となく聞き返した。こいつの問いかけに応える義理も、こちらには無いのだが。
「弟は、このガンダムを倒せるでしょうか!? これを倒せるほど、強くなっているのでしょうか!?」
「――――!」
それは、あまりにも意外すぎる問いかけだった。
何? 倒す?
倒されたいのか?
(分からん………)
目の前の男の奇天烈さに首を捻りながらも、思わず自分は分析していた。
今、自分がやり合っている『ガンダム』の力と、自分が見た、東方不敗の弟子である『ドモン・カッシュ』の力量を、頭の中で比べてみる。
そして―――結論が出た。
爆笑しそうになった。
でも、さすがにそれは気の毒なので、ぐっとこらえて答えてやった。
「無理だ」
明確に、3文字で。
「…………!」
絶句する青年の顔。更に、たたみかけるように言ってやった。
「東方不敗の事も良く知っている。奴は、弟子の事を認め、『キング・オブ・ハート』の称号を譲ったようだが……私から言わせれば、まだまだ弟子の方はひよっこだ」
「な………!」
「そんな奴が、『これ』に挑んだ所で、返り討ちにあうのが落ちだ―――」
「あ……あ……! う…! うあ……!」
見る見るうちにひきつっていく、青年の顔。
叫ばれる、と、悟った私は、通信を切った。『悪党』の叫びなど、聞く義理もないと思った。
愚か者め。やっと、自分の『罪』が分かったか。
自分だけの欲望を通して突っ走ると、周りの人や家族に、そのしわ寄せがいくのだ。
後悔しても、もう遅い。
失われた命も、絶対に返ってこない―――。
デビルガンダムから少し距離を取って、振り返る。
さあ、どうやって仕留めてやろうか―――と、算段しようとした時、目の前のガンダムが、妙な動きをしだした。攻撃をする動きと言うよりは、何か、足掻いているような―――。
その『足掻く』状態がしばらく続いたかと思うと、シュウウウウウ、という機械音と共に、デビルガンダムが一切の動きを、止めた。
何だ? と、訝る私の前で、コクピットと思われる部位のハッチがゆっくりと開いて行く。そこに現れた青年の姿を見て――――私は、息を飲んだ。
青年は、手にも足にも、そして身体にもケーブルを巻きつけている。
その姿は、デビルガンダムを操縦していると言うよりも、『拘束されている』と表現した方が近い。
なのに、面に浮かんでいるのは優しい笑顔。
そして、涙―――。
唇が動く。
『ありがとう』
何故――――!?
何故だ……!
茫然とその様を見る私に、青年はきっと視線を合わせてきた。涙が、光を放って飛び散る。
「シュバルツとか言ったな!?」
青年が、何かを訴えようとしているのが分かった。
何だ?
何を言おうとしている?
『助けて』か?
「私を撃て!!」
「…………!」
私は思わず、目の前の青年の姿を凝視していた。
「私を撃てば、『この子』は止まる!! だから、撃て!!」
そう叫ぶ青年の眼差しは、ぶれる事が無い。
本気だ。
本気でこの青年は、私に『撃たれる』ことを望んでいる。
「そして……これは末期の願いだ! 弟を―――!! 弟を、助けてやってくれ……!!」
何を――――!
何を言っているのだ!? この青年は……!
目の前で起きている事態が、理解できずに混乱する。
この状況。普通の『悪党』なら、まず命乞いをする。
「私が悪かった! 助けてくれ!」と、叫ぶ。
そういう輩なら、それこそ吐いて捨てるほど見てきた。そして、それを屠ってきた。
なのに、目の前のこの青年の口から出た言葉は、
「私を撃て!!」
「弟を―――!」
そこに、自分の身を顧みる余地は一切ない。
自分の身を犠牲にすることで、『デビルガンダム』の破壊活動を止めようとしている。そして、たった一人残される事になる弟を、『守ろう』としている。
(―――――!)
不意に悟った。
目の前の青年は『加害者』なのではない。一番の『被害者』なのだ。
悪意を持った者たちによって追い詰められ、総ての罪を押しつけられ、闇に葬られようとしている。
そして、青年はそれを、甘んじて受けようとしている―――!
何と言う愚かさ……!
そして、
何と言う、高潔な魂の持主なのであろうか――――!
(駄目だ―――!)
強く思った。
こういう青年こそ、助けなければ駄目だ。
生かさなければ駄目だ。
これほど高潔な魂と器を持った人間など、なかなか居ない。
この青年は、こんな所で死すべき人物ではないのだ。
『撃て』と言うのなら。
この青年を追い詰めた人間達。
つまり、この『ガンダム』と青年に莫大な懸賞金をかけた者たちをこそ、撃たなければならないのだ。
不覚……!
『情報』を扱う忍者が、『情報』を読み誤るとは―――!
助けなければ。
助けたい。
無我夢中で機体を駆る。
青年の方に近づく。
生きろ。
お前は、生きろ――――!
「青年よ!! お前は生きねばならぬ!!」
コクピットのハッチを開け、身を乗り出して叫んだ。
手を伸ばす。
どうやって助ける?
どうやって助ければ―――!?
「駄目だ!! やめろ!!」
「――――!?」
叫ぶ青年の声と同時に、光に包まれる。
こうして、私の『人生』は、終わった。
すまない。
助けてやれなくて―――――。
それからどれくらいの時が経っただろうか。
誰かの泣き声が聞こえる。
倒れている自分の身体が見える。
そのすぐ横で、膝をついて泣いている人間がいる。
その姿は――――あの、青年だった。
ああ、よかった。
脱出できたのか。
なら、何故そんな風に泣く?
――――ごめんなさい……。
――――ごめんなさい……。
何故、そんな風に謝る?
詫びると言うのなら、私の方だ。
誤解していて悪かった。
助けてやれなくて……済まなかったな……。
ああ。
何故、そんな風に泣く。
泣くな。
泣くな――――。
慰めようと青年の方に手を伸ばそうとして、自分の腕が動かない事に気づく。
ああ、そうだ。
私はもう、『死んだ』のだったな……。
泣くな。
頼むから。
そんな風に、泣くな――――。
(……………)
また、意識の混濁から覚醒する。
何か、不思議な感覚が、全身を支配する。
何だろう。
身体が
『おかしい』
その横で、絶えず青年の声が聞こえる。
―――暴走するな……!
―――暴走、するな……ッ!
祈るような声。
縋るような声―――。
何だ?
一体、何をしている?
ああ、駄目だ……。
また意識が―――――。
覚醒する間隔が短くなってきている。
一体、何が起こっている……?
私は……。
ふと気づく。
私は――――。
『私』は一体、誰だ?
傍にいる青年に気づく。
あれは……私!?
いや―――『キョウジ』!?
「………………」
キョウジの様子がおかしい。
意識レベルが『危険』の域に達しているのが分かる。
駄目だ! キョウジ!!
それ以上は――――!
手を伸ばした私に、キョウジはふっと笑みを浮かべた。
「どうか……後は……頼みます………『シュバルツ』――――」
そのまま、糸が切れた人形のように、倒れていくキョウジ。
「キョウジ!!」
キョウジを支えようとした私自身もまた、強制的に『何か』に引っ張られて行った――――。
そして目覚める。現在(いま)の『私』が――――。
私の名は、『キョウジ・カッシュ』
キョウジ・カッシュと言う名の、『シュバルツ・ブルーダー』
手も足も、正常に動く。
『実験』は、成功したのだと、知った。
「……………!」
人道を踏み越えてしまったと言う確かな罪悪感故に、怯えそうになる。
(怯えるな)
自分を叱咤する。
何もかも、覚悟したうえでやった事ではないのか。だから怯えるな。『受け入れろ』
ふと、何かの気配を感じて顔を上げる。
するとそこに居たのは――――『キョウジ』
「!?」
何故――――と、激しく動揺する。
自分は……『本体』は、あのガンダムのコクピットの中に居る筈ではないのか!?
「……………」
だが何か、様子がおかしい。そこにいるキョウジは、意志を持たない人形のように、ぼ~っと立っているだけだ。
「おい……?」
呼び掛けてみると、キョウジの顔が一瞬ピクリ、とひきつった。
「フ……。フハハ! アハハハハハハハ!! ヒャハハハハハハハハ!!」
そして、狂ったように嗤いだした。ただひたすら、嗤い続けた。
「―――――ッ!」
シュバルツは、悟る。自分を作り出すために、キョウジが何をやったのかを。
暴走しているDG細胞を使ったはずなのに、暴走していない自分の身体。
つまりキョウジは。
暴走しているDG細胞の中から暴走部分を取り除いた細胞を抽出して、自分に移植して――――その過程で生じた細胞の暴走部分を抑え込むために、『もう一体の木偶人形』を作り上げたのだ。
頭の先から足の先まで、『狂った』DG細胞によって構成されている木偶人形は、それ故にひたすら嗤い続けることしか出来ない。
「……………!」
シュバルツは思わず耳を塞いでいた。『自分』の狂った笑い声など、聞くに堪えない、と思った。
「ククククク! アハ……! アハハハハハハハハ!!」
木偶人形はげらげら嗤いながら、『デビルガンダム』の方へすたすたと歩いて行ってしまった。木偶人形を肩に乗せたデビルガンダムは、ゴゴゴゴ……と、地鳴りを立てながら、地下へと沈んでいく。地下へ潜り、新たなる段階へ『自己進化』をするつもりなのだろう。
「…………」
シュバルツは、暗澹たる気持ちでその様子を眺めていた。
自分の姿をかたどった木偶人形。『あれ』を見てしまったら、もう弟の―――ドモンの誤解を解く事は、決定的に難しくなってしまうだろう。
(『誤解』を解く事は、望んでないよ)
胸の奥で、優しい声が響く。
キョウジの『意志』なのだと、シュバルツは悟った。
(行こう)
また、誰かの声が響く。
(『償い』に――――)
償い?
誰に?
弟にか……?
(キョウジに……)
小さな小さな声だった。
(そんな事、私は望んでいないよ)
また、優しい声が響く。
(それよりも、行こう。私は『望み』を叶えたい)
キョウジ……。
キョウジの『望み』は―――?
(弟を『護る』こと。そして、あわよくば……『あの子』を止めること―――)
その言葉に『皆』が頷く。
分かった。行こう。
その願い、必ず叶える――――。
シュバルツは愛機に乗り込んで、再び戦いの場へと向かって行った。
デモ、『私』はキョウジを裏切ッタ。
ナノニ、私ハ、貴方ノ傍に居てイイノ?
傍に居てイイノ?
キョウジ――――。
「……もう、嫌なんだ……!」
キョウジが、ボロボロと涙をこぼしながら叫ぶ。
「自分が作ったモノが……自分から『産まれたモノ』が……! 『暴走』するのを見るのも……! それを、止められないのも―――!」
―――キョウジ……!
シュバルツは、懸命に宙で足掻く。
だが、自分を無理やり引っ張りこもうとする嵐の中では、身動きすることすらままならない。
「でも……だからこそ! お前は止める!! お前は守る!! 例えどんな事をしても!! 自分がどうなろうとも―――!!」
「この手は、絶対離さない!!」
そう叫ぶキョウジの身体は、既にあちこち傷だらけだ。
キョウジ駄目だ!
傷を治せ!
このままではお前が……!
お前が死んでしまう!!
(大丈夫だよ)
優しく微笑むキョウジから放たれる淡い『光』が、消えて行こうとしている。
駄目だキョウジ!!
駄目だ―――!
お前には死んで欲しくない!
死んで欲しくないのに……!
キョウジに向かって、懸命に手を伸ばす。
キョウジ……!
キョウジ――――!!
「―――ルツ! シュバルツ!!」
力強い声と共に、誰かに手を掴まれる。
「――――!!」
(キョウジ!?)
シュバルツの『意識』が、ようやく現実世界へと引き戻された。
「シュバルツ? 大丈夫か?」
「キョウジ!?」
反射的に手を握り返しながら、シュバルツは『声』の主を見る。するとそこには、キョウジではなく―――ハヤブサの顔があった。
「……悪かったな。『キョウジ』じゃなくて―――」
色素の薄いグリーンの瞳が、すまなさそうな色を帯びる。
「あ………」
シュバルツは、現実と『夢』の区別がしばらくつけられずに混乱した。
ここはどこだ? と、問うシュバルツに、とある郊外の廃屋の中だ、と、ハヤブサが返す。そこの古いベッドの上に、ドモンの赤いマントをかけられた自分の身体が横たえられていた。
カーテンの無い窓から、抜けるような青い空が見える。鳥のさえずりと風の木々を揺らす音が、シュバルツに平和な日常を意識させる。
私は一体どうしたんだ?
確か、仮面の魔道師から攻撃されて……。
キョウジに守られて。
ドモンが来て――――
あれから一体、どうなった?
「キョウジ――――キョウジは!?」
シュバルツの問いかけに、ハヤブサが苦笑する。
「まず、お前に意識があって、『生きている』意味を考えろ! そうしたら、自ずと分かるはずだ」
「………!」
ハヤブサに言われて、シュバルツはようやくゆるゆると自身の思考が回復してきた。
(そうだ……。私の意識があるのなら、キョウジの命も潰えてはいないはず……。と、言う事は、キョウジは無事なのか……)
よかった、と、シュバルツは大きく息を吐いた。
「…………」
シュバルツが静かに身を起こすと、彼にかけられていた赤いマントがずり落ちた。
手も足も、ちゃんとそろっている。このマントがかけられていた、と言う事は、やはりあの時、ドモンに助けられたと言う事だろうか。
(後でちゃんと、礼を言わねばならないな………)
あの嵐をものともせずに、まっすぐに突き進んできた弟の力強い姿を思い出す。
あの『デビルガンダム事件』を経て、ドモンは確かに成長していた。未だ時々感情に流される事もあるが、人を倒すばかりではなく、救うための拳を振るう事が出来る弟は、もう押しも押されぬ『キング・オブ・ハート』になりつつあるのだろう。
そんな弟の姿を、シュバルツは兄として嬉しく思い、また誇らしくもあった。そして、少し淋しささえも感じてしまって苦笑する。一体自分は、どこまで弟の世話を焼きたがっているのだろうと。
窓からみえる空はどこまでも青く澄み渡り、そこから入ってくる風が気持ちいい。久々の平和な景色にシュバルツが人心地ついていると、横からハヤブサの―――申し訳なさそうな声が響いてきた。
「そ、その……シュバルツ……。わ、悪いんだが……何か着てくれないか? こちらが……その、目……目のやり場に困る、と、言うか、何と言うか……」
「あ?」
シュバルツはハヤブサに指摘されて、自分が服を着ていない事を改めて認識した。一瞬何故自分が素っ裸なのかと思うが、冷静になって考えれば分かる事だ。あれだけ身体が『異形のモノ』へと変化しかかっていたと言うのに、服だけ無事だったなら、逆におかしい。
「そ、そこに……お前の弟が置いて行った服があるから……」
ハヤブサが、こちらをなるべく見ないようにしながら、服の方を指さしている。シュバルツがそちらの視線を走らせると、いつもの自分の服一式が、きちんと折りたたんで置かれていた。
(ドモンがこんな綺麗に服をたたんで置く訳が無いな……。たたんでくれたのはハヤブサかな?)
そう感じてシュバルツは苦笑しつつ、ハヤブサに礼を言った。
「ああ……世話になったな。いろいろと―――」
「いや………」
返事をしつつ、ハヤブサは空しさに襲われていた。この状況で、変に意識して赤面しているのは、結局自分だけなのだと思い知る。
(仮にも一度押し倒しているのに――――ちょっと意識しなさすぎじゃないのか!? お前は……!)
別に女みたいに「キャ――――!!」と叫んで身体を隠してほしいとは言わない。だけど、それだけ匂い立つ色香を撒き散らしておいて、全く無防備なのもいかがなものかと思う。お前に惹かれている存在があるのを、完全に無視しないで欲しい。
だからハヤブサは、服に向かうシュバルツの手を取ると、もう一回ベッドに縫い付ける事にした。そして、その身体の上に馬乗りになる。
「ハヤブサ!?」
驚いた顔をこちらに向けるシュバルツに、ハヤブサはにっこりと微笑みかけた。
「俺は別に……お前がその恰好のままでもいいんだが―――」
「はあ?」
案の定シュバルツが、思いっきり不審な目をハヤブサに向ける。だがハヤブサは、笑顔でその視線を跳ね返した。
「俺は忍者だから……『衆道』の心得もあるんだよ」
「…………!」
流石に『衆道』の意味を知っていたのか、シュバルツの顔色が変わる。それを見てハヤブサは、少し『満足』した。
「何なら、今からそれをお前で試そうか?」
「何でそうなる!?」
シュバルツの怒鳴り声と共に、彼の容赦のない左フックがハヤブサのボディを襲う。
「~~~~~~ッ!」
瞬間息が出来なくなってハヤブサがのたうちまわっている隙に、シュバルツは素早くベッドから抜け出した。そして、あっという間に服を着てしまう。
「だったらせめて相手を選べ! 『悪食』か! お前は……!」
ロングコートの袖に手を通しながら、シュバルツがぶりぶり怒っている。それに対してハヤブサは、
「……『お前』だから選んでいるのだがな……」
と、ぼそりと呟く。
「―――? 何か言ったか?」
その小声を、何となく聞き咎めたシュバルツが、ジロリ、と睨み返してくる。それに対してハヤブサは「別に……」と、返した。
「そんな事よりもキョウジはどこだ!? お前は、何か知っているんだろう!?」
シュバルツの問いかけに、ハヤブサは苦笑しながら頷いた。この辺りがそろそろ潮時だと感じる。これ以上シュバルツにちょっかいを出して、彼との間にせっかく出来かけている微妙な信頼関係を崩してしまうのは、ハヤブサとしても本意ではなかった。
「キョウジは、あそこだ。あそこに見える白い建物の中に居る」
そう言いながらハヤブサは、窓から見える白い建物を指さす。
「あそこは『病院』だ。キョウジはあの病院の―――」
キョウジが入院している部屋番号を、ハヤブサがシュバルツに教えようと振り返った時には、シュバルツの姿はもうなかった。
「……お前に付き添っていた俺への『礼』は?」
ハヤブサは小さく呟いてみるが、帰ってくる声は無い。シュバルツは本当に、わき目もふらずに病院へ向かったのだと分かって苦笑する。それほどまでに『キョウジ』と言う存在は、シュバルツにとって特別で、とても大事な人なのだろう。
(まあいいか。同じ『世界』に身を置く者同士、また、会う事もあるだろう)
ハヤブサは、龍剣を帯びて立ち上がった。隼の里に、報告をするために。
自分の任務が無事、完了したと言う事。
そして―――『隼の里』の一つの役割が、終わったのだと言う事を。
「これは一体どういう事なの!? 『総てが終わった』って連絡を受けて来てみれば、何でキョウジさんが入院するはめになっているの!?」
キョウジが入院している病室の一角で、レインの怒鳴り声が響き渡っていた。
病院の白いベッドの上で点滴を受けながら、キョウジは昏々と眠り続けている。そこから少し離れた所で、レインがドモンを怒鳴りつけていた。怒鳴られたドモンが、気の毒なほどにたじたじになってしまっている。
「ドモン……私、言ったわよね? 『キョウジさんを守ってあげてね』って……」
「あ? あ、ああ……」
確かにレインは出て行く間際、自分にそう言っていたので、ドモンは頷くしかない。
「じゃあ何で、貴方がピンピンしているのに、キョウジさんが死ぬほどの怪我をしているわけ!?」
「い、いや、『怪我』と言うか、原因不明の内臓系の異常……」
「どっちでも同じことでしょう!? ……貴方まさか、キョウジさんに『無理』をさせて、自分の事を護らせたりしたんじゃないでしょうね!?」
「そ、そんなはずは……!」
レインに言い訳をしながら、ドモンは懸命に自分の行動を思い出してみる。
あの『会社』に乗り込んだ時、自分の隣に居たのはシュバルツで……。
兄さんと一緒に居たのは師匠で――――。
「そ、そうだ! 兄さんと一緒に居たのは師匠だ! 師匠なら何か知っているはず!」
だが、「師匠!」と叫んで振り返ったドモンの視線の先に、マスターアジアの姿は無かった。
「……マスターなら、先程『花瓶の水をかえてくる』って、出て行かれたわよ?」
レインがそう言いながら、じと~っとドモンを睨んでいる。
「えっ? そうなの?」
「そうよ」
ドモンは自身の背中に、冷たい汗が流れ落ちる事を止める事が出来ない。
(師匠! さては逃げたな……!)
ドモンの中で、師匠に戦いを申し込みたい気持ちが、10上がっていた。
その頃東方不敗は、給湯室にて弟子であるドモンに手を合わせていた。
(ドモンよ……。その戦い、貴様に課せられた試練であると知れ……。貴様の骨は、後でワシがきっちりと拾ってやろうほどに……)
何故か、『コ―――ン』と、鹿威しの音でも響き渡りそうな静謐な雰囲気を、給湯室の中に作り出している。
そう。自分は今から花瓶に花を生けねばならないのだ。
必要以上にゆっくりと。なるべく時間をかけて―――。
如何に流派東方不敗が強くとも、避ける事が可能な戦闘ならば、なるべく避けるのも兵法の一つ。レインと言う女子(おなご)の雷は、ひたすらドモンに落させておくに限る。腕っ節ならば誰にも負けぬが、『口』勝負で男が女子に勝てるわけが無いのだ。
(さて、この花…どうやって生けてくれようか――――)
給湯室の静けさを堪能しながら、東方不敗は1輪の花を取って、じ~っと思考にふけっていた。
「いや…だから、師匠が兄さんと一緒に居たから―――」
「貴方キョウジさんの怪我を、マスターのせいにする気なの?」
「そ、そんなつもりはないけど………」
ドモンはレインに壁際に追い詰められながら、あの時の自分の行動を、懸命に思い返していた。
だから俺は、シュバルツと一緒に居て……。
シュバルツの足を引っ張ったりしないように、戦って……。
戦って戦って戦って……。
あれ?
俺って何か『ミス』をしたっけ?
「レ、レイン……。あのさぁ」
「何よ」
「今思い返してみたんだけど……俺、別に大きなミスをしたような気がしないんだけど……」
「……? どういう事?」
「つ、つまり、俺は特に大きなミスをした記憶が無いと言うか……。シュバルツが怪我をしたのだって――――」
「何でシュバルツさんにまで怪我をさせているのよ!!」
レインの拳骨がドモンを襲う。レインに殴られたドモンは、ダウンさせられてしまった。
「二人共に怪我をさせているんじゃない!! 貴方やっぱり、二人に無茶をさせて―――!」
「ち、違う! 俺はシュバルツを守るつもりで戦って―――!」
「……でも、怪我をさせたんでしょう?」
「う…! でも、それは―――!」
「『守れて』無いじゃない!」
「…………あれ?」
ドモンの周りにクエスチョンマークが浮かんでいる。
おかしい。自分は確かにシュバルツを守るつもりで、あの戦いに望んでいたと言うのに―――。
何でシュバルツは、怪我をしたんだっけ?
「え~っと……レイン、確かシュバルツが怪我をしたのは、俺のせいじゃなくて……」
「人のせいにする気なの!?」
本日2度目の鉄拳制裁が、ドモンの頭に飛んでいた。
「もう! ドモンったら!! 自分の『非』を認めないなんて、男らしくないわ!!」
そう言いながらぷりぷり怒っているレインの足元で、ドモンが小さく「ご、誤解だ~」と、言いながら呻いている。しかし、哀しいかなドモンには、レインをなだめる有効な手立てが思い浮かばない。
(チクショウ…! このまま一方的に詰られ続けるしかないのか……)
ドモンがそう思って泣きそうになった時、思わぬところから助け船が入った。
「もうその辺にしといてあげなよ、レイン……。私の『これ』は、ドモンのせいじゃないから……」
「――――!」
二人が驚いて声のした方に振り返ると、いつの間にか目を覚ましていたキョウジが、身を起こそうとしている。
「兄さん!!」
「キョウジさん! 大丈夫なの!?」
慌てて駆け寄る二人に、キョウジは笑顔を見せた。
「ああ……大丈夫だよ。もう大分、楽になったから……」
「キョウジさん……」
キョウジの笑顔を見て安心したのか、レインが涙ぐんでいる。その涙を見て、キョウジは自分が思う以上に、彼女にひどく心配をかけさせてしまっていた事に気付いた。
「……済まなかったな、レイン……。心配させてしまって……」
キョウジの言葉にレインは頭を振る。
「いいの……。よかった。キョウジさんが無事で……」
そう言って涙を流しながら微笑むレインに、キョウジも少し申し訳なさそうに笑みを浮かべる。そんな二人を穏やかな空気が包み込む。それは、まるで二人が恋人同士であるかのような雰囲気だ。
「………………」
こうなってくると、複雑になってくるのがドモンである。
(大好きな兄さんと大好きなレインの仲がいいのは、嬉しい事のはずなのに……何でこんなに『もやもや』するんだ?)
こんな事でいちいち揺さぶられている自分が、ドモンは少し嫌になる。
兄もレインも、お互いにそう言うのではないと分かり切っている事なのに、二人の間に流れる空気が、ひどく穏やかで―――お似合いであるように感じられるからだ。もしかしたら自分とレインよりも―――。
いかんいかん、と、ドモンは頭を振る。
こうやって、自分がつまらん嫉妬をしてしまった事が、兄との間に溝を作る原因の一つになってしまっていたのだ。同じ過ちを、また繰り返してしまう訳にはいかないと思う。
こんな時こそ、心静かに、『明鏡止水』の心境で――――。
「……ドモンも、ありがとう。お前のおかげで助かった……」
「えっ……!」
驚いて振り返るドモンに、キョウジは笑顔を見せた。
「お前が居てくれてよかったよ…。ありがとう、ドモン―――」
「兄さん……っ!」
ドモンも思わず泣きそうになってしまった。
「居てくれてよかった」と、言う兄の一言で、自分がものすごく報われたような気持ちになるのは何故なのだろう。こんな欠点だらけの『弟』なのに―――。
「そして……」
キョウジはそう言いながら、天井の方を見上げる。
「シュバルツ……」
「えっ?」
「シュバルツさん?」
二人とも驚いて見上げるが、そこには何の変哲もない『天井』の景色があるだけだ。だがキョウジは、そこに向かって微笑みかけると、言葉を続けた。
「……おかえり」
カタン、と、天井の板が外れ、人影が下りてくる。キョウジの言った通り、シュバルツの姿がそこに在った。
「キョウジ……」
シュバルツは顔を上げると、いきなりキョウジを抱きしめていた。
「お、おい!?」
「シュ、シュバルツさん!?」
ドモンとレインが驚きの声を上げるが、シュバルツの方は聞こえていないかのように、キョウジを抱きしめ続けた。そしてその肩が、小刻みに震えていた。
「…………!」
だからドモンは、レインの肩をつついた。
「どうしたの? ドモン」
振り返るレインにドモンは小声で告げる。
(部屋を出よう)
「――――!」
レインも、シュバルツの肩の震えに気付いた様だ。
(そうね…。そうした方がいいかもしれない……)
二人はキョウジとシュバルツの邪魔をしないように、そっと部屋を出て行った。
「キョウジ……! キョウジ……ッ!」
キョウジもまた、自分を抱きしめるシュバルツの腕の震えに気づく。
「シュバルツ…。どうした…?」
震えるシュバルツの身体を優しく抱き返しながら、キョウジは問いかけた。
「夢を、見ていたんだ……」
「夢……?」
「『私』が産まれた頃の―――そして、現在(いま)の『私』になった時の……夢を――――」
「…………!」
それは、決してキョウジが知る事が出来ない、シュバルツだけの『記憶』と悟る。
『細胞』から『A・G』へ。そして、『DG細胞』を経て、『人間』だったシュバルツから、キョウジの『意志』を携えた『現在』のシュバルツへ。
最初に在ったのは、ただ、愛された記憶。
なのに、壊れてしまった自分は『暴走』と言う名の裏切りを犯してしまった。
キョウジを傷つけてしまった。
その事にシュバルツは、今の『シュバルツ』になってから気づく。だが、その時には、何もかもが遅すぎた。
罪にまみれて真っ黒な自分。
本来なら、許されるべきものではないし、裁かれるべきものであるとも思っている。
でも、キョウジが望んでくれた。
『生きろ』と。
注がれた『愛情』は、最初の時と、何ら変わるものではなかった。
キョウジはずっとそうしてくれていたと言うのに――――何故、自分はそれに気づく事が出来なかったのだろうか。
ここまで来るのに、ひどく遠まわりをしてしまっていたような気がする。
「私は……お前の側に居て、いいのか……?」
「もちろん」
シュバルツの言葉に、キョウジは頷いた。
「私は……お前が側に居続けてくれる事を、『望む』よ……」
ずっとそう言い続けているじゃないか、と言って、キョウジは微笑む。
「キョウジ……ッ!」
後は言葉にならなかった。シュバルツはキョウジを抱きしめて、肩をふるわせ続けた。そしてキョウジは、シュバルツの震える身体を、優しく抱き返し続けた。
そんな二人の姿を包み込むかのように、窓から優しい風が入ってくる。
穏やかな午後の日差しが、萌え出づるの木々の若葉を、祝福するように照らし続けていた―――。
どうせなら、こんな夢物語の話をしよう。
とびきり贅沢な、夢の話を。
ご愛読、ありがとうございました。
キョウジ兄さんたちに捧げる物語。
終わった――――!!
終わらせることができて、ほっとしています。
書ききりました! 大好きな兄さんたちを主役にした、自己満足な小説を(笑)
聡い読者様たちは気づいていらっしゃると思いますが、これは本当に私の妄想の場面の連続に、何となく話の体裁を取り繕って、話っぽく見せかけているものでございます。120%の力技で、話をねじ伏せています。
なので、話に意味などはなく、伝えたいメッセージ性があるわけでもございません。
ただただもう「兄さん! 好きじゃあああああ!!」と、叫んでいる小説です。
『読んでくれる人がいなくても、覚悟は決めて書こう』と、決意をして、書きだしたつもりでしたが、やっぱり読んでくれた反応がないと、多少つらいものがありますね(笑) もう、本当に、何度書くのをやめようと思ったことか。
でもそのたびに、ブログの方にコメントがいただけていたり、セッション数に変動があったりと、些細なことが励みになって、最後まで書ききることができました!
もし全部読んでくださっている方、いらっしゃいましたら、本当にありがとうございます! 心よりの感謝を!
『貴方』のおかげで書ききることができました!
「2次創作」なので、所詮私は『ナンチャッテ作家』の部類に入るのでしょうけど、楽しんでいただけたなら幸いです。
感想、聞かせてくれたらうれしいです。
ブログの方にでも、お気軽にお寄せいただけたら……。
それでは!