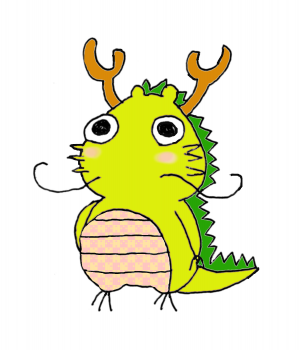マリオネット狂想曲
皆さまこんばんは。空由佳子と申します。
また性懲りもなく、新しい小説が思い浮かんだので、アップしていきたいと思います。
しかし、相変わらずのハヤブサさん×シュバルツさんワールドです。しかも、内容的にかなりけしからん物になる予定です。
このカップリングが好みじゃない。BLって何? 楽しめない、という方は、どうかここでUターンしていただければと思います。読んでも、多分ろくなことにはならないと思いますので。
全然大丈夫! 楽しめるという方は、どうか楽しんでいってください。私も全力で楽しむ所存です。
ただ、シリアスになるかギャグになるかは、書いてみないとわかりません。こんな小説ですが、どうかよろしくお願いいたします。
1
それは、うららかな昼下がりのキョウジの部屋に、突然鳴り響いた。
(シュバルツからのコールだ)
キョウジは手を止めて、コールを鳴らしている携帯を見つめ、その表情を少し硬くした。なぜならその携帯は、シュバルツと直接つながっていて――――彼が緊急事態に陥ったときにしか、鳴らさないものであったからだ。
「………………」
キョウジは静かに、携帯を見つめ続ける。コールが鳴る回数を注視するためだ。
その携帯は、互いに離れていた時に、危地に陥ったときに使おうと、シュバルツとキョウジは話し合って決めていた。アンドロイドであるシュバルツが持つ方は、半ば身体に埋め込まれるように装着されており、普段はその存在が、外からは簡単には知られないような仕様になっていた。
危機に陥ったが、自力で何とか切り抜けられそうならば、10回以内でコールは切れる。しかし、コールは切れず、ひたすら鳴り続けていた。
「……………!」
そして、鳴る回数が20回を超えたところで、携帯が自動的につながり、シュバルツ側の音声を拾い出した。それはつまりシュバルツが『自力で携帯を切ることができない事態に陥った』ということを意味する。
(そんな………! シュバルツ………!)
息を呑みながらもキョウジは、その携帯から流れてくる『音』に耳そばだてた。シュバルツがどういう状態にいるのか、それを掴むために。
その携帯からは、耳慣れぬ男の声が響いてきていた。
「よい獲物が入った………。これで、龍の忍者を罠に嵌めることができるぞ……」
「―――――!」
連れて行け、という男の声に、数人の男たちが答えている。それから、地面を蹴って走るようなノイズ交じりの音を、その携帯は伝えてきた。これは、どう考えてもシュバルツが攫われかけているとしか言いようのない状況。キョウジは思わず、椅子を蹴って立ち上がっていた。
(どうする!?)
自力で助けに行くのは危険すぎるし、不可能に近いので、キョウジは助けを求める先を探す。
(やはり、ハヤブサか………)
男の声は「龍の忍者を罠に嵌めることができる」と言っていた。ならばまず、ハヤブサに連絡を入れるのが筋というものかもしれない。それに、敵の体制が整う前にハヤブサにこの事態を知らせることができれば、敵の機先を制することも可能になるだろう。
(今日、確かハヤブサは、特に予定は入っていなかったはず……!)
シュバルツと付き合うようになってから、ハヤブサは何故か、キョウジの方に自分の行動予定を報告するようになっていた。報告してくる手段は、キョウジの周りに常にいる隼を使って。日時も時間もまちまちに来るが、ハヤブサの行動予定がだいたい把握できるようになっていた。
(ど、どうして彼はそういうことを私にしてくるのだろう……。もしかしなくても、「いざというときは呼べ」と、いうことなのだろうけど………)
ハヤブサの配慮は素直にありがたいが、ここまでされていて頼らなかったり呼ばなかったりしたら、逆にいろいろ怒られたり恨まれたりしてしまいそうだ。キョウジは別の携帯を手にすると、ハヤブサの番号に指を走らせた。
「どうした? キョウジ」
ワンコールと待たずに、ハヤブサはすぐに出た。
「わっ! びっくりした!」
あまりにも早い反応に、キョウジは驚きを隠すことができない。少し戸惑っていると、ハヤブサから更に声をかけられた。
「どうした? キョウジ。何か、緊急の要件か?」
「えっ?」
きょとん、とするキョウジに、ハヤブサからの言葉は続いた。
「お前に教えた携帯の番号は、お前しか知らない。お前専用の直通番号になっているんだ」
「―――――!」
「お前が、特に何の用事もなく俺の携帯を鳴らすような人間ではないことぐらい、百も承知している。何か、火急の用があるのだろう?」
「ハヤブサ………」
ハヤブサの話を聞きながら、キョウジは軽くため息を吐いていた。
(まいったな………。彼には隠し事ができないや……)
だが逆に、そこまで彼が事情を承知してくれているのなら、本題も切り出しやすいとキョウジは思った。キョウジは、一つ深く呼吸をすると、単刀直入に話を始めた。なるべく冷静に話せと、自分に言い聞かせながら。
「分かった……。じゃあ、すぐに本題を話す。シュバルツが、拉致されたらしい」
「何ッ!?」
息を呑むハヤブサに、キョウジはさらに言葉を重ねる。
「シュバルツと直接つながっている携帯から、連絡が入ったんだ。『緊急事態に陥った』と」
「………………!」
「男の人の声で、『連れて行け』と、言っていたのが聞こえたし、そのあと、地面を蹴って走っているような音が聞こえてきた。おそらく、どこかへ連れていかれているのではないかと―――――」
「その男は、他に何か言っていたか?」
ハヤブサの問いかけに、キョウジは一瞬口を開くのを躊躇う。しかし、あえてそれを口にすることを、キョウジは選択していた。これこそが―――――ハヤブサに一番伝えねばならないことだからだ。
「ああ………。男の声は言っていた。『龍の忍者を罠に嵌めることができる』と」
「―――――!」
電話越しに、ハヤブサが息を呑む気配が伝わってくる。キョウジは苦虫を噛み潰したような心持になった。自分はこの件で、ハヤブサを責めたり、なじったりしたいわけではないのだから。
「すまん………俺のせいだな………」
案の定、自分を責めるようなハヤブサの声音が、電話越しに聞こえてくる。キョウジはフルフルと、頭を振らずにはいられなかった。
「違う……! 貴方が悪いんじゃない。私が言いたいのは、あなたが狙われている可能性があるから―――――」
「キョウジ……。シュバルツの居場所は分かるか?」
「えっ?」
言葉が終わらぬうちに問いかけられたハヤブサの言葉に、キョウジは少し目をしばたたかせる。
「お前のことだ。シュバルツの居場所を把握する手段くらい、持ち合わせているのだろう?」
「そ、それはまあ―――――」
「ならば、それを教えろ、キョウジ」
キョウジが曖昧に頷いている間にも、龍の忍者はさらにたたみかけてくる。
「すぐにシュバルツの救出に向かう」
「で、でもハヤブサ……! 危険だよ!」
ハヤブサが少し性急に事を進めようとしていると感じたキョウジは、彼に待ったをかけた。
「敵は、明らかにあなたを狙っているんだ。貴方に対して、何か備えをしているかも―――――」
「そんなものは関係ない。それよりも、シュバルツが危地に陥っている方が問題だ」
「そうかもしれないけど………」
なおも渋るキョウジに、ハヤブサは少し諭すように口を開いた。
「心配するな、キョウジ。シュバルツが人質として利用されたとしても、俺にとって彼が足手まといになる、ということはまずあり得ない」
「ハヤブサ………」
シュバルツは、不死だ。
たとえ喉を刀で掻っ捌かれようとも、銃をその身体に撃ち込まれたとしても、問題なく生き返ることができる。だから、彼の『命』を盾にとっての『脅し』は、自分にとっては全くの無意味だった。
それよりも―――――
「俺を狙うためにシュバルツに手を出すというのなら―――――そんなことを企てたことをたっぷりと後悔させてやる………!」
「――――!」
電話越しに、ハヤブサの殺気がビシビシと伝わってくるから、キョウジは思わず携帯を放り出しそうになっていた。
本気だ。
龍の忍者が本気で怒っている――――――!
「だからキョウジ、シュバルツの居場所を」
「分かったよ」
キョウジは、早々に折れることを選択した。ここで『教えない』などと言おうものなら、ここに殴り込んでこられたりして、自分も無事では済まない気がする。
それに、シュバルツが拉致られていることで、怒りを感じているのは自分も同じだ。だから、自分がハヤブサに対して協力を拒む理由は何もなかった。
「待って、今、シュバルツにつけてあるGPSの信号をキャッチするから」
ハヤブサと話しながら、キョウジは片手でパソコンのキーをカチャカチャと操作する。シュバルツのGPSの受信状態は良好であったことに、キョウジは少し胸を撫で下ろす。
「信号をキャッチした。シュバルツは今、私のアパートから南東に10kmの地点にいる」
「キョウジ、俺の端末のGPSもONにした。俺の場所もわかるか?」
「えっ? ああ、待って、やってみる」
キョウジの指はキーの上を軽快に滑り、ハヤブサの信号をパソコンでキャッチすることに成功する。
(えっ? 割と近くにいた?)
自分のアパートの近くにハヤブサのGPSが点滅したのを見て、キョウジは少し目を丸くする。彼が特に用事もない時、自分のアパートの近くでうろうろしている可能性が浮上してきた。
「ばっちり受信できたよ。割と近くにいるね?」
「まあな」
キョウジの突っつきを、ハヤブサはしれっと受け流す。キョウジは苦笑するしかなかった。
「じゃあ行く。キョウジ、案内を頼めるか?」
「いいよ、任せて」
「よし――――」
ハヤブサは改めてイヤホンとマイクを装着しなおすと、目的地に向かって走り出した。
(やれやれ……気の毒に……)
キョウジはそんなハヤブサのGPSの動きを目で追いながら、軽くため息を吐いていた。
これから怒りに燃えるハヤブサにギタギタに叩きのめされるであろう敵のことを考えると、同情を禁じえなかった。敵は、ハヤブサの最も触れてはいけない逆鱗に、触れてしまったのだから。
これより数刻前。
シュバルツ・ブルーダーは、自身の周りの異変に気付いていた。
(尾(つ)けられている?)
数人の気配が、自分とつかず離れずの距離で、同じ呼吸でついてきているのを感じた。雑踏の中で歩いていて、偶然そうなることもあるかもしれないが、もう10数メートル、同じような呼吸で気配がついてきているこの事態。これは、どう考えても異常だった。
「……………」
だからシュバルツは、わざと人気の無い方を選んで歩を進めた。自分たちの戦いに、巻き込まれる人間が出ないように。
しかし、だれが、何が狙いなのだろう。
歩きながらシュバルツは考えた。
私か?
キョウジか?
それとも―――――
郊外の、雑木林の近くに来た。
殺気が、気配が、一層鋭くなる。
(来る―――――!)
シュバルツが確信すると同時に、「それ」は襲い掛かってきた。
音もなく飛来してくる棒手裏剣。シュバルツはそれを、横っ飛びに躱す。
(棒手裏剣―――――! 相手は『忍者』か!!)
シュバルツが得物を確認すると同時に、さらに襲い来る棒手裏剣。シュバルツはそれを三角飛びの要領で躱した。着地した地点に、一人の忍者が抜刀しながら襲い掛かってくる。身体ごと体当たりしてくるその突きを躱したシュバルツは、相手の刀を強引にもぎ取ってその体を蹴り飛ばしていた。
「近寄るな!! 遠巻きにして、生け捕りにするのだ!!」
どこからか、指示の声が飛んでくる。「応っ!」と、それに応えた忍者たちが、一斉に飛び道具を構え、シュバルツに向かって放ち始めた。
(何者だ!? いったい何人いるんだ!?)
雨あられと降ってくる矢や手裏剣を躱しながら、シュバルツは周りの気配を探る。しかし、巧みに位置を変えながら、間断なく武器を降らせて来る襲撃者たちの攻撃は、位置の特定を容易にさせてはくれなかった。
「―――――!」
投網が飛んできて、シュバルツの身体を絡めとろうとする。しかしシュバルツの刀は、投網が巻き付く直前にそれを粉砕していた。
「うぬっ!!」
投網を投げた忍者が、舌打ちしながらもう一度、懐から投網を出そうとした、刹那。
「お前たちは何者だ? 何故、私をつけ狙う?」
自分の背後から標的の男の声が聞こえてきたから、男は死ぬほどびっくりして、木の上から落ちてしまう。
「ひっ!!」
「問いに答えてくれれば、命まで取りはしない」
シュバルツがそう問いかけながら、男の後を追うように、地面に着地してきた。そのまま、静かに距離を詰めてくる。彼の手に下げた刀が、鋭い光を放っていた。
「さあ――――」
シュバルツはそう言いながら、男との間合いを一足一刀にまで詰める。一歩踏み込めば、一太刀振り下ろせば―――――男を斬り下げることができる。そんな距離であった。
「う………! ぐ………!」
男は低くうめきながらも、なんとか目の前のシュバルツに反撃しようと隙をうかがう。しかし、刀を下げ、無造作に立っているように見えるシュバルツから、なぜかその隙を見出すことができない。
「話してくれないか? 何が狙いだ?」
「……………」
男からは沈黙が返ってくるのみ。そして、周りから再び矢と手裏剣が飛来してくる。
「―――――!」
シュバルツはやむを得ず尋問をあきらめ、男を突き飛ばしてから自身も再び走り出す。その刹那、二人のいた地点に、ドドドッと音を立てて矢や手裏剣が突き刺さった。忍者たちは相変わらず遠巻きに飛び道具を使って攻撃するばかりで、こちらに接近してくる気配を見せない。
(指揮を執っている者はどこだ!? それさえ特定できれば――――!)
シュバルツがそう思いながら周囲を探っているときに――――それは起きた。
「きゃあっ!!」
「―――――!」
甲高い悲鳴にシュバルツがはっと振り返ると、人の女性が忍者によって羽交い絞めにされていた。ジョギングをしていたのだろう。トレーニングウェア姿のその女性は、忍者の手にしている刀を見た途端、血相を変え、さらに叫び声を上げようとしていた。
「きゃ………!」
「黙れ!!」
女性は、口を塞がれ鳩尾に当身をくらわされる。彼女はくぐもった呻き声をあげると、そのまま昏倒してしまっていた。
「な―――――!」
驚くシュバルツに向かって、一本の矢が飛来する。彼はそれをよけずにそのまま肩に受けた。『人質』の存在は、それほどまでに、シュバルツから戦闘意思を奪ってしまっていた。
「自分の『立場』がよく分かっているようだな……。話が早くて良い」
別方向の木の上から、頭領らしき男がゆらりと姿を現す。彼は少し愉快そうに笑うと、シュバルツに改めて命じた。
「そのまま刀を置け。抵抗すると、どうなるか分かっているな?」
「……………」
シュバルツは無言で、昏倒している女性と、その首元に当てられている刀の煌きを見る。自分から女性までの距離が、少しありすぎた。これでは、自分が女性を救うために何らかの動きを起こしたとしても、忍者の刀の方が、一瞬早く女性の命を奪ってしまうだろう。
自分はいい。『命』がない自分は、『殺される』という行為に意味はない。すべての機能が一時的にストップするだけで、何時間か後には、自分の身体を構成している『DG細胞』の『自己再生能力』が、勝手に自分の身体を甦らせてしまうから。
だが――――あそこにいる『人間』の女性には、『命』は一つしかない。
女性の命と自分の身の安全。
どちらが重いか。
そんな物―――――考えるまでもなく、答えは出ている。
シュバルツは、無言で刀を地面に置くと、手を上げた。抵抗する意思がないことを、明確に示すためだ。ただ、その一連の動作の際に、キョウジへの緊急コールをシュバルツは内部で起動させていた。この忍者団は、自分を『殺す』のではなく『生け捕り』にしたがっていた。それがシュバルツは、少し気になっていたからだ。
この忍者団の目的が見えない。
いったい―――――何が狙いなのだろう。
「そのまま、動くなよ」
頭領の言葉に合わせて、数人の忍者たちが、じりじりとシュバルツとの距離を詰めてくる。
そして―――――
ドカッ!!
鈍い音とともに、シュバルツは後頭部を強打される。そのまま彼は、意識を失い昏倒してしまっていた。
「………こうまで人質が有効だとはな。信じられぬほど、甘い奴よ……」
倒れたシュバルツを見下ろしながら、頭領はにやりと笑う。この男は確かに、龍の忍者の『恋人』だという情報を掴んではいた。しかし、人質を取った瞬間、こんなにあっさりと戦闘意思を放棄するとは思ってもいなかった。あの容赦なく人を斬る「龍の忍者」の身内にしては、信じられないほどの甘さだと感じた。
「なんにせよ、よい獲物が入った………。これで、龍の忍者を罠に嵌めることができるぞ……」
連れて行け、と部下たちに命じて、シュバルツの身体を抱えさせる。そのまま、彼らはアジトに向かって走り出していた。
それからしばらくして、シュバルツの意識が戻った時――――彼は、身体の自由が利かないことに気が付いた。手と足が拘束されて、寝台に縫い付けられるように固定されている。上半身の衣服は取り払われ、白い肌が露出していた。
(ここは………?)
目隠しはされていないので、シュバルツは周りの様子を伺いみる。見慣れぬ高い天井に、割れた窓ガラス。ここはどこかの廃ビルの一角なのだと見て取れた。
「気が付いたか?」
「―――――!」
自分を捕えた男の声に、シュバルツははっと身を固くする。シュバルツに睨みつけられた男は、愉快そうに笑いながら顎をしゃくって、そちらの方を見るようにシュバルツに促した。
「おっと………下手な抵抗はするなよ? お主の態度如何で、あの者の生死が決まるのでな」
その男の視線の先には、天井から縛られてぶら下げられている、巻き込まれた女性の姿がある。
「な…………!」
シュバルツは息が詰まる思いがした。
「こうして私を捕え、お前たちの目的は達しただろう!! 彼女を離せ!! もう捕えている必要はないはずだ!!」
シュバルツの叫びに、男は歪んだ笑みを見せる。
「いいやまだだ。まだ――――わしの目的は達成していない」
「…………?」
怪訝な表情を浮かべるシュバルツに、男は勝ち誇ったように答えた。
「お主がわしの『術』にかかり――――わしの忠実な『傀儡人形』となるまではな!!」
「―――――!」
「そのまま、動くなよ? 今――――術をかけてやる」
息を呑み、顔色が蒼白になるシュバルツに向かって、男が墨を浸した筆を持ってにじり寄ってくる。男の持つ墨ツボから、どす黒いまでの禍々しい『気』の気配が渦巻いているの感じた。
「お主は『龍の忍者』と親しいと聞く……。お主をわが傀儡と化せば、龍の忍者を仕留めることなど容易いだろう」
(そうか……! 狙いはハヤブサか………!)
シュバルツはぎり、と、唇をかみしめていた。
「今お主が傀儡となるにふさわしい『印』を授けてやる……。じっとしていろよ……?」
「…………ッ!」
(ハヤブサ………!)
祈るように目を閉じるシュバルツの肌の上に、その『墨』が垂らされ始めた――――
「キョウジ、ここで間違いないのだな?」
郊外の廃ビルの前で、マイクに向かって問いかけるハヤブサのイヤホン越しに、キョウジから答えが返ってくる。
「ああ。間違いない。シュバルツのGPSは、さっきからその中から発信されている」
「そうか」
ハヤブサは己が気持ちを落ち着かせるように一つ呼吸を入れると、キョウジに向かって改めて声をかけた。
「キョウジ、ここで通信を切るぞ」
「えっ? どうして?」
キョウジの疑問に、ハヤブサは答えを返す。
「お前に、要らぬ火の粉がかからぬようにするためだ」
ハヤブサは説明する。自分の通信手段から、『協力者』の存在が割り出されてしまう危険性を。
「そうならないように、この端末のデータも消して、電源も落とす。……心配するな。みすみすやられる気もないし、シュバルツを無事助け出したら、また改めて連絡するから」
「うん。そう言うことなら――――」
幸運を祈る、と、言い残してキョウジは通信を切った。ハヤブサも端末の操作をして、それを懐深くしまった。
(シュバルツが、自分の足手まといになる、ということは絶対にない)
ハヤブサは、改めて自分に強くそう言い聞かせていた。
大丈夫だ。
シュバルツを真の意味で殺せる存在など、そうは居ない。
たとえお前がどうなろうとも、『死体』であろうとも―――――
必ず、お前を連れて帰って見せるから
ハヤブサは改めて覆面をかぶりなおすと、廃ビルの中へと、歩を進めていった。
崩れかかった薄暗い通路を進む。
しばらく行くと階段があり、ハヤブサは、上へ進む道を選択した。音を立てぬよう、静かに階段を昇っていく。何回か上がった先の踊り場に、ドアがあり、その向こうから声らしきものが聞こえてきた。
「……………」
ハヤブサはそっと壁に寄りかかり、耳をそばだてる。
すると、ハヤブサにとってはひどく不吉な声の響きが聞こえてきた。
「ううッ………!」
苦しそうに呻いている声の主は、シュバルツの物だとすぐにわかる。だが、その声の主は、ただ呻いているだけではなかった。
「あ………! あ………! はあっ!」
しどけなく、喘ぐ響きも交じってくるから、ハヤブサは、知らず息を呑んでしまう。その声は―――――自分との情事以外では、できれば聴きたくないものであるのに。
(何をされている!?)
沸騰しそうになる気持ちを抑えながら、ハヤブサはそっとドアを開ける。その先には、少し開けた吹き抜けになっている空間があり、その下の方の寝台に、上半身裸になっているシュバルツが拘束されているのが見えた。
「………………!」
その横で、シュバルツの身体に何かをしている男と、それを嘲笑いながら見ている女の姿が見える。
「どうじゃ? わしの特性の『墨』は……。なかなか、いい按排じゃろう?」
「う………! くぅっ………!」
シュバルツの肌の上を墨を浸した筆が走る。その刺激に耐えられないのか、わずかに動くシュバルツの身体が、びくびくと反応していた。
(な―――――!)
その光景を見た瞬間、ハヤブサは全身の血の逆流を感じるほどに、怒りに燃えあがっていた。
これより少し前、人質となっていた女が、その本性を現していた。
「フフフフ……。本当に、甘い男ねぇ。騙されているとも知らずに、本気で私の身を心配して―――――」
人質となっていた女もまた、この忍者団の一員であった。偽の人質役から解放された女が、勝ち誇ったようにその面に笑みを浮かべている。
シュバルツが騙されていたと気づいた時にはすでに遅く――――男の禍々しい『気』を含んだ『墨』がシュバルツの肌を侵食し始めていて、彼はかなりの自由を奪われていた。
(何だこれは………! 気持ちが悪い……! 熱い………ッ!)
自分の中に強引に入り込んできて、根幹を揺さぶり、すべてを暴き立てようとする感触。シュバルツは懸命にそれを拒絶しようとするのだが、容赦なく肌の上を滑る墨の浸食は、どんどんと深まっていくばかりだ。
「初心(うぶ)な人。本当にあなた忍者なの?」
女の指が、弄ぶようにシュバルツの肌の上を滑る。
「う………! あ………ッ!」
「美弥、あまりこいつで遊ぶでない。術がかかりきらなんだら困る」
男に美弥、と呼ばれた女性は、「分かってるわ」と、肩をすくめながら手を引っ込める。それを見た男は、笑いながらシュバルツのズボンを引き下ろしていた。
「お主が『気』をやるときは、わしと共にイクときじゃ。それまで不用意に『気』を散ぜぬよう、わしが『栓』をしておいてやるからな」
そう言いながら男は、シュバルツの勃ちあがっている牡茎を掴み、亀頭から尿道にかけて、金属製の細い棒のような物を挿し込んでいく。
「あああああああっ!!」
たまらずシュバルツが叫び声をあげると、男はくつくつと笑い出した。
「怏々、愛い奴よ。可愛らしい声で啼きよる」
「ねぇ、そんなにゆっくりと遊んでないで、さっさと術をかけちゃえば?」
私も早くこの男で遊びたいのに、と、焦れたように言う美弥を、まあ待て、と、男は宥めるように口を開いた。
「この男………なかなか面白い『陰脈』の持ち主じゃな。このような細かい紋様を描ける機会など、滅多にない物じゃて……。これほどの器量じゃ。『タチ』であろうと『ネコ』であろうと、両方器用にこなすじゃろう。わしが慰み者にした後で、客を取らせても面白いかもしれぬな………」
そういいながら男は、シュバルツの白い肌の上に、墨で禍々しいがどこか美しい―――――細かい紋様を描きこんでいく。
「まあ、そんなことさせるの? 悪趣味ね」
美弥の、多少揶揄を含んだ言葉に、男はにやりと笑った。
「そういう需要の客もおる、ということじゃ」
「確かにそうね」
男の言葉に、美弥も笑いながら頷いていた。どうやら彼女も『そういう需要の客』のうちの一人であるらしい。
「ううっ! はあっ!!」
(いやだ……! 熱い……ッ! 気持ち悪い……ッ!)
自分の中に入り込んでくる禍々しい『気』が、自分の中に強制的に淫らな熱を呼び起こす。思考を奪う。身体の疼きを解放したくて堪らない。
こんなのは嫌だ。いやなのに―――――
「お………『墨』が自ら走った。『紋様』が完成しおったぞ」
男の言葉通り、『墨』が男の筆の力を借りずとも自ら広がり、シュバルツの肌の上に『術』のもとになる『紋様』を完成させた。その時に『墨』から発せられる妖しい『光』を見ながら、男は満足そうに頷くと、シュバルツの上に覆いかぶさってきた。
「今からわしがお主を抱き、『気』をやることで、この『術』は完成する。お主は総てをわしに奪われ、自我をなくし、わしのための『奴隷』となるのだ」
「……………!」
「すべてを支配してやるぞ……。安心しろ。たっぷりと愛でてやろう程にな………」
「あ…………!」
迫る男の顔面に、シュバルツの中に絶望が広がる。
イヤダ
イヤダ
心の中では懸命に抵抗の叫び声を上げているのに、表に出てくるのはため息のような喘ぎ声ばかりだ。
「あ………! う………!」
あられもない格好で寝台の上に拘束され、わずかばかり動く身体をのたうたせるシュバルツ。
そこから匂い立つ凄絶な色香に、周りを見張っている下忍たちも当てられ気味になっていた。
「おい、お前、さっきから何股間を抑えてるんだよ」
「だ……だってよ………。今度の傀儡の奴すげぇ色っぽいと思って………。最後の最後でいいから、俺にも一度やらせてくれないかな………」
「気持ちは分かるがな……」
同僚の言葉に苦笑しながら答えた下忍もまた、その視線は寝台の上のシュバルツの痴態にくぎ付けになっていた。
それ故に―――――彼らは気が付かなかった。
自分たちのすぐ後ろに、怒りに燃える暗殺者が近づいている、ということに。
「『術』の効果の一端を思い知らせてやろう……。もうお主は、わしの言葉に逆らえなくなってきておるはずじゃ。どれ、まずは足の戒めを外してやろうか」
ガチッと音を立てて足を絡め捕っていた拘束具が外れ、シュバルツの足は自由になる。
「さあ―――――股を開け」
「……………!」
シュバルツ自身は自由になったこの足で、上に覆いかぶさっている男を蹴り飛ばしたいと願う。しかし、その思いとは裏腹に、足は勝手に男の命じるままにゆっくりと開いて行ってしまった。
「あ………! あ………!」
「フフフフ……良い表情、いい反応をしおる。愛い奴じゃ」
絶望に涙し、小さく震えるシュバルツの耳元に、男が勝ち誇ったように唇を近づけていく。
「いいか? 覚えておけよ……。お主は自分から股を開いた。わしに『望んで』抱かれるのだ」
(違う!! 嫌だ………ッ!!)
抱かれたいなどと、自分から望むはずもない。それを自分から望むとすれば、その相手はハヤブサだけだ。それなのに――――
(ああ、馬鹿だな)
シュバルツは、自身の愚かさに臍(ほぞ)を噛む。
人質となった女性の真贋を見抜けなかったばかりに、今の事態になってしまった。「人を見る目がない」などと、弟であるドモンに偉そうに説教できるはずもない。
だけど、一つしかない人間の命と、空虚な器のアンドロイドである自分の身の安全。
自分はどうしても、それを秤にかけられないのだ。
優先すべきは『命』
それは――――どうあっても、変えてはいけない信念だった。
その結果、自分が凌辱されようと、たとえ殺されてしまったとしても――――
それは自己責任で、自業自得なのだとシュバルツは思った。
だから、自分はどうなってもいい。だが、今回の敵は、自分を使ってハヤブサを陥れようとしている。
自分の失態に、ハヤブサを巻き込んでしまう。そして、裏切ってしまう。
それだけは―――――
酷く申し訳ない、と、シュバルツは思った。
ズブ、と、音を立てて、露わになった自分の秘所に、男の指が侵入してくる。
「あっ!!」
「『ここ』はもうわしの魔羅を欲しがっておるようじゃな……何とも淫らな身体よ………」
そう言ってかき回してくる男の指に、シュバルツの身体は素直に反応していた。涙を散らしながらびくびくと震える身体に、男は舌なめずりをする。
「さあ、抱いてやるぞ。存分に―――――」
その刹那。
ドカン!! と、派手な音がして、上から大きな物体が落ちてくる。
あまりにも突然で、男はその塊が、自分の部下の首の無い遺骸なのだと気が付くのに、少し時間がかかった。
「な―――――!」
驚く声を上げる間もなく、今度はいきなり目の前の美弥が切り裂かれる。
ゴロン、と、美弥の首が床に転がると同時に、一つの黒い影が音もなく地面に降り立った。
「………俺に用事があるんだってな。だから、こっちから来てやったぞ」
酷く静かな―――――だが、恐ろしいほどの殺気が込められた声。その影の正体を悟った瞬間、男は天地がひっくり返るほどの衝撃を受けた。
「ひいっ!! 龍の忍者――――!!」
間抜けな叫び声とともに、男はシュバルツのいる寝台から転げ落ちてしまう。男が床の上で体勢を立て直すよりも先に、ハヤブサがその前に距離を詰めてきた。
「10秒待ってやる……。『術』の解き方を教えろ」
しびれるほどの殺気を放ちながら、黒の忍者は必要なことだけを聞いてくる。
「ぶ、部下は? わしの部下はどうした!?」
「全員斬った」
非情な暗殺者が、淡々と告げる。彼の抜身の龍剣からは、まだ、血が滴り落ちていた。
「この『術』は………『術者』であるお前を斬れば、解けるのか?」
「…………!」
男はしばらくハヤブサを呆然と見つめていたが、やがてその面に、ふっと笑みを浮かべた。
「無駄じゃ……。このわしを殺したところで、その術は解けはせん」
男の言葉に、ハヤブサの眉がピクリと吊り上がる。
「それよりも――――」
男の手が懐に伸びた瞬間。
ドカッ!!
ハヤブサの龍剣が一閃し、男を胴切りにしていた。
真っ二つになった男が骸となって転がる。
ハヤブサが改めて懐に伸びた男の手を調べると、焙烙玉が握られていた。どうやら、この辺りを巻き込んで、自爆する算段であったらしい。
「シュバルツ………!」
ハヤブサはシュバルツの方に向き直ると、寝台の拘束具を解く。
そして、シュバルツの身体を腕の中に抱きかかえると、その身体をシーツで包み、その場を後にしていた。
術をかけられそうになっているシュバルツの身体。
ハヤブサはそれを何とかしたくて、キョウジの家へと急いでいた。
キョウジは、シュバルツの製作者にして、優秀な科学者だ。だから、この『術』を解く術も、もしかしたらキョウジなら、探り当てられるかもしれない。
一路、走り続けるハヤブサ。
しかし、それに待ったをかける者がいた。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
腕の中のシュバルツから呼びかけられる。
「どうした? シュバルツ……」
「苦しい……! 助けてくれ、ハヤブサ……!」
「シュバルツ……!」
腕の中で縋りついてくる愛おしいヒトに、ハヤブサは足を止めた。
「しっかりしろ、シュバルツ……! もうすぐキョウジの家に着くからな……!」
なだめるように、優しく抱きしめ返す。しかしシュバルツは、いやいやと頭を振った。
「違うんだ……! ハヤブサ……! 身体が、疼いて………ッ!」
そう言いながら愛おしいヒトが、はあっとしどけなくため息を吐く。こちらを見つめる瞳が熱と涙で潤み、頬が上気していた。
「シュバルツ……」
「抱いてくれ……! ハヤブサ……!」
「な―――――!」
このシュバルツの申し出には、さすがにハヤブサも顔色を変える。
「お願いだ……! 苦しくて………!」
「馬鹿な!! 今の状態で抱かれる、ということがどういうことなのか、お前は分かっていないのか!?」
シュバルツは今、あの男の『術』にかかりかけている状態だった。この状態のシュバルツを抱いてしまうと、あの男の『術』の完成の手助けを、自分がしてしまうことになりかねない。
「あの男の『術』が、お前の身体にまだ残っている! 今誰かに抱かれたら、あの男の『術』によってお前はその相手に支配されてしまう! 文字通り、傀儡となってしまうんだぞ!?」
それでもいいのか――――と、問うハヤブサに、シュバルツは頭を振った。
「良くはない……。よくはない、が………」
ハヤブサに縋りつく手に、ぐぐ、と、力がこもった。
「苦しい……! 身体が熱くて………! 耐えられないんだ……! このままでは私は………誰かれ構わず、この身体を開いてしまいかねない……ッ!」
「な…………!」
「そんなことはしたくない……! この身体は、お前以外には許したくない……!」
「―――――!」
「もし……誰かに支配されるというのなら…………私はその相手に、お前を選ぶ……! ハヤブサ……! 私はお前がいいんだ……!」
「な―――――!」
ある意味、シュバルツの強烈すぎる愛の言葉に、ハヤブサの胸は強くわしづかみにされる。呆然と立ち尽くすハヤブサに、シュバルツはなおも縋りついてきた。
「お願いだ……! 助けてくれ……! 抱いてくれ……!」
「シュバルツ……!」
「こんなこと………キョウジにも、ましてやドモンになど……頼めない……! ハヤブサ……! お前だから……お前だから、頼むんだ………!」
「……………!」
「抱いて、くれ……! ハヤブサ………!」
「―――――ッ!」
(くそっ!)
ハヤブサはぎり、と、歯を食いしばっていた。
普段シュバルツが、こんな風に自分から「抱いて」と頼んでくるような性格ではないことぐらい、ハヤブサは百も承知していた。少々の身体の不調や疼きなら、彼は一人で黙って耐えてしまう。
その彼が、「我慢できない。抱いてほしい」と言う。
これはもう、余程のことなのだろう。
ハヤブサはシュバルツの身体を改めて抱きかかえると、行く先を変えた。二人が、いつも落ち合う郊外の森を目指す。そこならば、滅多なことで邪魔も入らないからだ。
いつもの木の下でハヤブサはシュバルツをそっと地面に横たえさせる。
身体を覆っていたシーツを取り払うと、墨で怪しく紋様を描きこまれた、シュバルツの裸体がそこにあった。
「は………あ…………」
瞳を熱で潤ませながら、しどけないため息を漏らすそのヒトは、どこまでも美しい。
だがやはり、身体に描き込まれた尋常ではない紋様が―――――
その『墨』から立ち上がる、どす黒い『妖気』が―――――
ハヤブサを暗澹たる気持ちにならしめた。
それでも――――
「ハヤブサ……! 早く………!」
焦れたように身をしならせる美しいヒトの媚態を見ると、自分の物は素直に反応してしまう。あまりの単純さに、ハヤブサは少し自己嫌悪に陥りかけた。
この腹の下にいるのは、自分の愛すべき、愛おしむべきヒトだ。
どんな状態になろうとも、自分は彼のヒトを愛し抜くことに変わりはない。
しかし――――
「いいのか……?」
ハヤブサは改めて問いかけていた。
この行為は単純な『愛の行為』ではない。
シュバルツの人格を奪う行為。
彼を傀儡に貶める行為に直結してしまうのだから。
「構わない……」
うるんだ瞳で、まっすぐ見つめてくる愛おしいヒトが、縋るように手を伸ばしてくる。
「抱いて、くれ……。ハヤブサ……」
「シュバルツ……!」
愛おしさが命じるままに、ハヤブサはシュバルツの唇を奪う。そのまま入り口を弄ると、そこはもう蕩けきっていた。ひくひくと妖しく蠢きながら、ハヤブサの指を咥え込んでいく。腰が揺れ、擦りつけられる牡茎。もう―――――そこが刺激を待ち望んでいるのは明白だった。
「……………」
これ以上焦らすのは、もう酷だった。ハヤブサは覚悟を決めると、愛おしいヒトを一気に刺し貫いた。
「あああああああっ!! ああっ!!」
叫び声を上げ、愛おしいヒトの身体がびくびくと震える。今の刺激で達したはずだが、シュバルツの牡茎が『精』を放つことはなかった。
(ああそうか……! 塞がれているから………!)
牡茎の先端から、僅かにのぞく金属製の棒。それが、シュバルツの吐精を妨げていた。腹立たしく思うハヤブサは、それを牡茎から取り除こうと、それをつかみ取る。
しかし、それを抜き取ろうとして、術をかけた男の言葉をハヤブサは思い出していた。
――――お主が『気』をやるときは、わしと共にイクときじゃ。それまで不用意に『気』を散ぜぬよう、わしが『栓』をしておいてやるからな………
「……………!」
『術』というものは、かけるのであれば、きっちりとかけ切った方がいいと、言うことをハヤブサは知っていた。自身も、多少の『術』を繰るものであるが故に。『術』は、中途半端にかけるほうが、却って対象者に要らぬ苦しみを与えてしまうことがある。
(くそっ!)
ハヤブサは歯噛みすると、それを抜き取るのをあきらめた。
しかし、僅かに抜き差しされたその棒の動きは、シュバルツに余計な刺激を与えることになる。
「あああっ!! ああっ!!」
その刺激に悲鳴を上げて、身を捩らせるシュバルツが、可愛らしくてそそられるから―――――ハヤブサはついつい、そこを弄んでしまっていた。その棒を摘み上げ、上下にゆっくりと動かしてやる。
「ああっ!! やあっ!!」
慣れぬ刺激に救いを求めるように、シュバルツが縋りついてくるから、その唇を深く奪っていた。もっと彼を乱れさせたいと願って、さらに彼の弱いところを弄んだ。
何故なのだろう。
この目の前の愛おしいヒトは、すでに術によって犯されているのに。
どうして―――――こんなにも凶悪な衝動を伴って、自分は、彼をさらに犯すことができてしまうのだろう。
深く穿つたびに、悲鳴を上げてのたうつ彼が、愛おしくて愛おしくてたまらない。
分かっているのに。
自分が彼の最奥を突き上げるたびに、術もまた、彼に深く浸食していっているのが、この目にはっきりと映りこんでいるのに――――
それを止めるどころか、さらに術の加速を手助けしてしまっている。
もっと、もっと、と、際限なく暴いて、求めてしまっている。
本当に―――――俺は一体、何なのだろうか。
「ああっ!! ああああっ!!」
二重に犯されているシュバルツから、悲鳴が上がっている。
(ああ、無理もない)
ハヤブサは思った。
シュバルツは今―――――内部から自我が破壊されて行っているも同然なのだから。
「怖い……!! 嫌だ……!! 怖い……ッ!!」
シュバルツが恐怖を叫んでいる。
なのに俺は、それを救う術を持たない。
それどころか、自我を奪っていく元凶になっているのは、紛れもなく自分自身だ。
「シュバルツ……!」
ハヤブサはせめて、シュバルツに呼び掛ける。
今―――――シュバルツを抱いているのは、悪意に塗れていたあの男ではない。
彼を愛してやまない『自分』なのだと。
それに気付いてほしくて。
(だが……それが、何だというのだろう)
ハヤブサはふと、空しさに襲われた。
『術』に犯されているシュバルツをさらに弄んでいる。
その行為自体は、あの男も自分も―――――何ら変わりはない。凡そ、『慈しむ』という行為からは程遠い気がした。
だが。
「ハヤブサ………!」
ハヤブサの呼びかけに気が付いたシュバルツが、ふわりと微笑む。
本当に幸せそうに
安心したように―――――微笑むから。
「シュバルツ……!」
気が付けばハヤブサは、シュバルツの身体を深く抱きしめていた。そうせずにはいられなかった。
「安心しろ、シュバルツ……! 俺は必ず、お前を守る……! お前がどうなろうとも、必ず守って見せるから―――――!」
「ハヤブサ………!」
シュバルツの瞳から、ぽろぽろと大粒の涙がこぼれ落ちる。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……ッ!」
腕の中のシュバルツが、縋りついてくる。「すまない」と、小さな声で、謝られた。
何故謝る?
何故謝るのだ、シュバルツ。
謝らなければならないとしたら、それは俺の方だ。
実際に狙われていたのは俺で―――――
お前はそれに、巻き込まれてしまっただけなのだから
シュバルツの最奥を、深く穿ち続ける。
「あっ!! ああっ!! イキ、た、い………ッ!!」
尿道を塞がれているために吐精が叶わず、何度も何度も空イキをする愛おしいヒトの内側が、甘く震えている。切なく締め付けられる。
ああ――――もう俺も、終わりが近い。
「シュバルツ……!」
唇を奪う。
懸命に応えようとする愛おしいヒト。
だが、彼を内側から破壊し続ける黒い『術』は、彼の総てを奪い去ろうとしていた。彼の舌が、もう思うように動いていないのが分かる。
「愛している……!」
せめて、耳元で囁く。
彼がどうなっても、自分の想いは変わらない。
それを彼に伝えるために。
「……………!」
狂ったように腰をたたきつける。
それをしながらハヤブサは、シュバルツの尿道から金属製の棒をゆっくりと引き抜いて行った。くぷ、くぷ、と音を立てながら金属製の棒がそこから姿を現し、シュバルツ自身が解放されていく。
「ああっ!! も………!」
その刺激に耐えきれず、達しようとする愛おしいヒト。
ハヤブサはその根元をとっさに握りこんだ。まだ自分が達していない。この行為は、二人がともに往かなければ意味がない。
「やあっ!! ああっ!!」
往きたがっているシュバルツが、激しく身を捩り、腰を揺らす。そんなシュバルツを、さらに深く穿つ。そしてついに、ハヤブサもまた限界を迎えてしまって―――――
「―――――ッ!」
自身がシュバルツの内側で爆ぜると同時に、シュバルツの牡茎を握りこんでいた手を、ハヤブサは緩めた。
「あ…………!」
シュバルツもまた、びくびくっ! と、身体を震わせながら、ぴゅくぴゅくと、達した証を吐き出す。
「あ………! あ――――――………」
か細い悲鳴のような声を上げながら、シュバルツはそのまま糸が切れた人形のように、ばたん、と、倒れ込んでしまった。
「シュバルツ………」
「……………」
呼びかけたが、返事がない。シュバルツは完全に気を失ってしまっているようだった。それと同時に、彼の身体に施された『術』が、ガチッと音を立てて、完全に彼の身体を捕えこんでしまった様が見て取れた。術が完成を迎えた瞬間だった。
(これでよかったのだろうか)
ハヤブサは倒れたシュバルツの髪をそっとなでながら、自問自答をせずにはいられなかった。
本当に、これでよかったのだろうか。
乞われたとはいえ
頼まれたとはいえ
彼を傀儡に貶める行為をする必要があったのか。
他に何か方法が、あったのではなかろうか――――
(だが……シュバルツもあんな状態で、キョウジやドモンの前には行けなかっただろうな……。そんなことをするぐらいなら、という苦渋の決断だったのだろう)
術によって強制的に淫らな熱を呼び起こされていたシュバルツ。
頬を上気させ、熱で瞳が潤み――――しどけないため息を吐きながら、何もかもをはち切れんばかりに熟れさせていた。ある意味、絶対他人には知られたくない『醜態』だった。
それを、弟であるドモンや、大切な存在であるキョウジの前に晒してしまうぐらいなら。
俺の『傀儡』になってしまう方がまし―――――シュバルツは、そう考えたのだろう。
それにしても、あの言葉は本当なのだろうか。
「もし……誰かに支配されるというのなら…………私はその相手に、お前を選ぶ……! ハヤブサ……! 私はお前がいいんだ……!」
本当に心の底から、そんなことを考えてくれていたのだろうか。
『俺』になら、すべてを支配されてもいいと
そう思ってくれていたというのなら―――――
ハヤブサの頬が自然に緩む。
愛おしいヒトからの、盤石の信頼が嬉しい。
自分はそれに、全力で応えねばならぬと思う。
(シュバルツ……)
ハヤブサの指の間から、シュバルツの髪がさらりと零れる。
穏やかな寝息を感じる。
だがハヤブサは、ほんの少し寂しかった。
いつものシュバルツであったなら、自分が行為を終えた後、決まって優しく微笑みながら、そっと抱きしめてくれていたのに。
糸が切れたように、眠り続けるシュバルツ。
これが目覚めたとき、彼はもう術にかかっている状態になってしまっている、ということだ。
それがどういう状態なのか、想像するのが困難だから、ハヤブサは少し困惑してしまう。
シュバルツはこれから―――――どのようになってしまうのだろう。
(だが……俺は約束した。シュバルツに、『何があってもお前を守る』と……)
術と俺に犯されながらも、幸せそうに微笑んでくれたシュバルツ。
あの笑顔を忘れない限り、自分はどこまでも頑張れるとハヤブサは思った。
(シュバルツ……)
ハヤブサがそうやってシュバルツの頭を優しく撫で続けていると、やがて、シュバルツが軽く身じろぎをする。どうやら、意識が覚醒してきたようだ。見守るハヤブサの目の前で、シュバルツはぱちりと瞳を開けると、むくり、と起き上がってきた。
「シュバルツ……」
ハヤブサが呼びかけると、シュバルツはくるりと振り返る。
そして、ハヤブサが気分はどうだ、と、聞くより先に、その口を開いていた。
「おはようございます。ご主人様」
2
とにかく、ショックだった。
胸に数千のナイフを突き立てられたような衝撃を受けた。
シュバルツは、俺のことを『ご主人様』と呼ぶ。
そしてこちらを見つめる瞳には―――――何も映っていなかった。彼の無感情な眼差しが、ハヤブサの胸を鋭くえぐる。
「シュバルツ……」
「はい、何でしょう、ご主人様」
「……………ッ!」
覚悟はしていたはずだった。
目が覚めたシュバルツは、もう普通の状態ではないのだと。
だけど―――――寂しい。
恐ろしいほどの孤独を感じるのはなぜなのだろう。
「シュバルツ……」
「はい、何でしょう、ご主人さ―――――」
「その『ご主人様』というのをやめてくれないか?」
言葉を紡ごうとしたシュバルツの唇を、ハヤブサは指で優しく押さえる。
「では………なんとお呼びすれば?」
怪訝そうに小首をかしげるシュバルツに、ハヤブサは苦笑するしかない。
「俺にも名前があるんだ。俺のことは「ハヤブサ」と呼んでくれ」
「分かりました。『ハヤブサ』」
(うう……『ハヤブサ』の響きが、『ご主人様』と同じ響きだ……)
シュバルツには『恋人』でいてほしいのに、これではまるで自分の『付き人』だ。
その残酷な現実の前に、ハヤブサは思わず突っ伏して泣き伏しそうになってしまう。
要らないんだ、付き人は。
もう里にたくさん居るから。
だけど恋人は
恋人は、お前しかいないのに―――――
「……………」
(とにかく、落ち着こう)
ハヤブサは、一つ大きく呼吸をする。
シュバルツがこうなることを覚悟して、それでも彼を抱いたのは自分だ。ならば――――今の状態のシュバルツを受け入れることが、肝要なのではないのか。
「シュバルツ、こちらへおいで」
ハヤブサが呼ぶと、シュバルツは機械的にすっとそばに寄ってくる。一糸纏わぬ姿であるのに、全く恥じらうことも、その身体を隠すこともしない。
まるで無反応なシュバルツ。それでも、ハヤブサにとって愛おしいヒトであることには変わりがない。
(ああ、綺麗だな)
素直にそう思ったハヤブサは、シュバルツの唇に、そっと触れるようなキスをした。
そう―――――触れるようなキス。
それ以上ハヤブサは、シュバルツの身体をどうこうしようと思ったわけではないのだが。
「は………! あ………あ…………!」
キスを終えたシュバルツが、とろんとした眼差しで、頬を上気させながら、扇情的に小さく身を震わせている。
(えええええええええ!?)
まさかと思ってシュバルツの牡茎の方に目を走らせてみれば、そこはもうはち切れんばかりに勃ち上がっていて、愛液を垂らし始めていた。まるで深い深いキスをして、身体のあちこちを弄りまくった後のような様相だ。
(いや……! ちょっ……! あれだけの刺激で――――!?)
戸惑うハヤブサの視界に映りこむのは、シュバルツの身体に刻まれている紋様の、妖しい光。それが、彼の内側深くに入り込んで、彼の中の淫らな『熱』を、強制的に呼び起こしているのが分かった。
(くそっ!)
ハヤブサは小さく舌打ちをすると、シュバルツの身体を抱きかかえた。そのまま二人で川の中に入る。不用意な劣情には、身体の熱を冷ますのが一番だからだ。
しかし。
「あ…………」
術で強制的に熱を体の中から呼び起こされているシュバルツが、水の冷たさぐらいで醒める筈もなく。
それどころか、滴る水は、彼の匂い立つ色香に、さらに拍車をかけてしまっていた。肌を流れ落ちる水滴が妖しく絡みつき、しどけなくため息を吐きながら、甘えるようにハヤブサの身体にその身を擦りつけてくるから―――――
気が付けばハヤブサは、シュバルツの濡れた唇に、噛みつくように吸い付いてしまっていて―――――
「ああ……! んう……! あああ……!」
そのままシュバルツの身体を、滾々と愛し続けて、しまうのだった。
「――――すまん!」
シュバルツをどうにかこうにかキョウジのアパートまで連れてきたハヤブサは、シュバルツをキョウジの前で椅子に座らせて、自分は床に土下座していた。
「え………。えっと………?」
それを見ながらキョウジは、困惑に顔を引きつらせていた。
シュバルツは本当に、人形のような目つきをしているし、ハヤブサは気の毒なほど自分を責めているしで、キョウジ自身も、目の前の事象にどう反応していいのか戸惑っていたからだ。
「えっと………まず、状況を整理させてくれる?」
キョウジが頭をポリポリと掻きながら、ハヤブサに声をかける。とにかく自身の気持ちも含めて、整理する必要がある、と思った。
「シュバルツは、その男の『術』に因って――――今は、操り人形状態になっているってこと?」
「そうだ……。すまん、俺が狙われたばかりにシュバルツは――――」
「ハヤブサが悪いわけじゃないでしょ? 本当に悪いのは、ハヤブサを狙ったその連中なんだから」
「……………!」
「『誰が悪い』とか『誰かのせい』だとか、そんなの今は水掛け論だよ、ハヤブサ。それよりも今は―――――シュバルツの『術』をどうすればいいのか、その話し合いをするべきだと思うんだ」
(そうかもしれないが………)
ハヤブサは忸怩たる思いで歯噛みした。シュバルツもキョウジも優しすぎる。この状況――――どう考えても、俺に咎があるというのに。
「とにかく、シュバルツのその術の紋様を見せてもらってもいいかな?」
「分かった」
キョウジの言葉に頷いて、ハヤブサはシュバルツに余計な刺激を与えないよう、慎重に服を脱がしていく。やがて、シュバルツの上半身が露わになり、キョウジの視界に、シュバルツの肌に施された術の紋様が映りこんだ。
「……何とも不思議な紋様だね……。これは……『墨』?」
キョウジはそう言いながら、その紋様をしげしげと見つめている。
「ああそうだ。あの男は何か特殊な方法で調合した『墨』を使って、シュバルツの身体に術をかけたらしい」
「ふ~ん………」
キョウジはハヤブサの話を聞きながら、シュバルツの肌にそっと触れる。その途端、シュバルツの身体がびくっと跳ねた。
「う………!」
小さく呻く声が漏れ、身体が小刻みに震えだす。
(まずい! この刺激だけでも、感じさせられてしまうのか!?)
ハヤブサは慌ててシュバルツの顔を覗き込む。しかし、彼の様子がおかしいことにすぐに気づいた。その表情には苦悶の色がにじみ、顔色が、見る間に悪くなっていく。
「シュバルツ!? どうした!?」
「えっ?」
驚いたキョウジが顔を上げる。シュバルツに触れていた手を離すと、シュバルツの身体がぐらりと傾ぐ。そのまま椅子から転げ落ちそうになっていた。
「シュバルツ!!」
慌ててハヤブサは、シュバルツの身体を支える。ハヤブサの腕に支えられたシュバルツは、「あ………」と、小さく吐息を漏らした。
「どうした? シュバルツ」
腕の中で小さく震え、まだ顔色の悪いシュバルツに、ハヤブサは問いただした。
「ハヤブサ……」
「俺に隠し事は許さん。素直に言え」
ハヤブサは、あえて強めの口調でシュバルツに言った。シュバルツの状態を正確に把握するために、これは必要な『命令』だと感じていた。あまり気は進まなかったが。
「どうした? 何があった?」
ハヤブサに逆らえないシュバルツは、問われるままに口を開く。
「すみません……。ハヤブサ……。痛くて……」
「痛い?」
怪訝そうに眉を顰めるハヤブサに対して、キョウジはピンと来るものがあった。それを確かめるべく、手を動かす。
「痛いって………まさか、これ?」
そっと、キョウジの手が、シュバルツの肌に触れる。その瞬間。
「うわあああああっ!!」
シュバルツの身体が絶叫とともに跳ねる。
「シュバルツ!」
ハヤブサはとっさにシュバルツの身体を抱きしめ、キョウジは慌てて手を引っ込めた。
「ご、ごめん!」
呆然と謝るキョウジに、ハヤブサはフルフルと首を横に振る。
謝らなければならないのはこちらだ。俺が狙われてしまったばかりに、シュバルツは――――
「でも……ハヤブサに触れていると、痛みが引きます……」
そう言いながらシュバルツが、縋るように身を摺り寄せてくる。
「シュバルツ……!」
呆然とするしかないハヤブサに対して、キョウジは少し困った顔をしながらポリポリと頭を掻いていた。
「参ったな……。と、言うことは、私はシュバルツには触れられないってこと?」
キョウジの言葉に、ハヤブサははっと我に返る。何故かキョウジに対して、深い罪悪感に襲われていた。
「本当にすまん! 俺が――――」
「違うよ。ハヤブサが悪いわけじゃない」
謝ろうとするハヤブサを、キョウジがやんわりと止める。
「悪いのはその『術』であって、その『術』を邪な目的でシュバルツに使おうとした人間であって、ハヤブサが悪いわけじゃないんだ。そこを、はき違えてはいけないよ」
「そうかもしれないが………」
キョウジは優しくそう言ってくれたが、ハヤブサはやはり、納得できなかった。
狙われたのは自分で、シュバルツはそれに純粋に巻き込まれたから、こうなってしまったのに。やはり、すべての元凶は―――――
「うう~~ん………。やっぱり、『術』がどういった類の物なのか、調べる必要はあるよね……。ハヤブサ、この『術』をシュバルツにかけようとしていた人間は――――」
「俺が斬って捨てた」
ハヤブサはぶっきらぼうに言い放つ。
「この俺が、シュバルツをこんな目に合わせた人間を、そのまま放っておくとでも思っているのか?」
「そうでした……」
ハヤブサの言葉に、キョウジはもう苦笑するしかない。龍の忍者にとって、このシュバルツという存在は、間違いなく『逆鱗』に当たる。リュウ・ハヤブサという人間を攻撃しようと意図するとき――――絶対に触ってはいけない存在だった。迂闊に触ったが最後、激怒した龍の忍者によって、攻撃を画策した組織や存在は、壊滅的な返り討ちを受けてしまうだろう。
おまけにシュバルツ自身も不死に近い存在。
故に、彼の『命』を盾にしての恫喝は、まったく無意味なものとなる。
本当にハヤブサは――――ある意味、最強の恋人を手に入れたともいえるのだ。
「しかし参ったなぁ……。『術者』が死んでも、その『術』が解けないとなると――――」
「今………シュバルツに術をかけてしまっているのは俺だ………」
ハヤブサは険しい表情で言葉を紡ぐ。
「俺が死ねば、もしかしたら―――――」
「それは絶対にダメだよ、ハヤブサ」
ハヤブサの言葉に、キョウジがぴしゃりと釘を刺す。
「そんなことをしてシュバルツが正気に戻ったとしても、私もシュバルツも、絶対に喜ばない。特にシュバルツがどれだけ悲しんで泣くか――――貴方は分かっているのか?」
「……………!」
「おそらく、『術』の魔力はその『墨』自体が持っていて、『術者』の生死は関係ないんじゃないかな。詳しく調べてみないとわからないけど……」
(そうかもしれないな)
キョウジの話を聞きながら、ハヤブサもまた男が死ぬ間際の言葉を思い出していた。
「無駄じゃ……。このわしを殺したところで、その術は解けはせん」
あれはつまり、こういうことを示唆していたのではなかったか――――
「とにかく、調べるためにシュバルツから体液のサンプルをとる必要があるね。でも――――」
ここまで話したキョウジが、少し考え込むような仕草をした。
「ハヤブサ、悪いんだけどこの注射器を使って、シュバルツから体液を取ってくれないかな?」
「えっ?」
唐突なキョウジの提案に、ハヤブサはきょとん、としてしまう。
「いや、俺に注射の心得は――――」
「大丈夫だって、ハヤブサ。シュバルツはアンドロイドだから、多少失敗しても問題ないよ」
「そ、それはそうかもしれないが――――」
ハヤブサは少々慌てふためきながらシュバルツの方を見る。しかしシュバルツは、相変わらず表情のない顔で、ぼ~っとどこを見るとでもなく視線を漂わせながら、座り込んでいるだけだ。もし彼の意識があったなら、「キョウジ~~~!」と、怒り出しかねない内容の話をしているというのに。
「忍術とかで針を使う物とかないの? それと同じ要領でやってくれれば問題ないんじゃないかな」
「そ、それは………。しかし、忍術はたいてい『殺し』に使われるもので、医療に使われることがない場合が多いから――――」
「でも、人体の血液の流れとかを見る心得はあるわけでしょう?」
「う……! それはまあ………」
「だったら――――」
「いや待て、キョウジ! やはり、素人の医療行為は危険だ! お前の方が安全に――――!」
「それは………私だってできるならば、自分でやっているけど……」
ここでキョウジは、その面に少し寂しそうな笑みを浮かべる。
「ほら………私は今、シュバルツに触れられないし――――」
「―――――!」
「私が少し触っただけで、シュバルツはこうでしょう?」
キョウジが再び、そっとシュバルツに触れる。
「うあっ!!」
激しい痛みが走るのか、シュバルツが悲鳴を上げた。
「シュバルツ!!」
ハヤブサが慌てて抱きしめると、シュバルツはほっと小さなため息を吐きながら、その身を摺り寄せてきた。やはり、自分が触れると、彼の身体の痛みは消えていくらしい。
「これで私がシュバルツに注射を打つとか、いろんな意味で危険すぎる。ある意味鬼の所業だよ」
苦笑しながら言うキョウジに、ハヤブサも反論の余地を失う。ハヤブサは覚悟を決めた。
「分かった。じゃあ、採血をするから教えてくれ、キョウジ」
ハヤブサの言葉に、キョウジも笑顔で頷いた。
「まず、シュバルツの肘のあたりの『血管』を確認して――――」
シュバルツの二の腕に駆血帯をハヤブサに締めさせてから、キョウジは指示を出した。
「『血管』? シュバルツに『血管』なんかあるのか?」
「身体中に『液』を送るパイプみたいなものだよ。最近シュバルツの人間への擬態化が進んでいて、パイプがまるで人間の血管のように身体中を走っているんだ。だから、人間と同じようなところにそれがあると思う」
キョウジの言葉を聞きながら、ハヤブサがシュバルツの肘のあたりを指で確認すると、確かに、血管らしきものがあった。
「あ………」
シュバルツの身体がぴくっと反応する。
「動くなよ」
ハヤブサはそう命じてから、改めて注射器を構えた。
(これで忍術なら………『毒針』を刺したりするんだがな……)
そっと、シュバルツの腕に注射針を刺す。針は一撃で、シュバルツの『血管』を捉えてくれた。ハヤブサは手際よく、『採血』を済ませていった。
「ありがとう、ハヤブサ。これだけあれば、サンプルとしては十分だよ」
キョウジがハヤブサからいくつかの試験官を受け取り、ニコリと微笑んだ。ハヤブサも、やれやれとほっと溜息を吐く。
しかし――――事はそれで終わらなかった。
「シュバルツ。もう動いても………」
そう言いかけたハヤブサが、シュバルツの様子を見て絶句してしまう。
なぜなら、採血を終えたシュバルツが、トロン、とした眼差しで、恍惚の表情を浮かべていたからだ。
(え………っ? あ、そうか! 『俺』が『針を刺す』なんて行為をしたから――――!)
「は………あ………」
上気した頬に深いため息。もどかしげに揺れる腰は、完全に発情した時のそれだった。
まずい、と、感じたハヤブサは、慌ててシュバルツとキョウジの間に割って入る。それと同時に、キョウジがものすごい勢いでくるりと後ろを振り向いていた。
「キ、キョウジ……! 今の――――」
「み、見てない! 私は何も見てないよ!!」
そう言って狼狽するキョウジは「見てしまった」と言っているも同然だ。ハヤブサは、はあ、と、大きくため息を吐くと、キョウジに声をかけた。
「少し――――シュバルツを借り受けるぞ」
「う……! はい、どうぞ……!」
龍の忍者がシュバルツを抱きかかえて部屋から出ていく。パタン、と、ドアが音を立てて閉まってから、キョウジは「はあ~~~~~」と、大きなため息を吐きながら、その場に頽れてしまった。
(うう……。自分のあんな顔、できれば見たくなかった……!)
自分のコピーとして作られたシュバルツは、ある意味『自分』だ。つまり、シュバルツのあの表情は、自分がああなったときの、表情というわけで――――
「…………!」
ぶんぶん! と、キョウジは大きく首を振る。
気恥ずかしいような、いたたまれないような――――変な心持に襲われた。
(とにかく、『術』の分析をしなきゃ……)
キョウジは懸命にそう考えて、立ち上がろうとする。
しかし、いったん狼狽してしまった心は、なかなか落ち着きを取り戻せそうになかった。
「あ………! あ………!」
いつもの森にやってくると、龍の忍者はシュバルツを暴き立てる。注射の刺激で発情してしまっていたシュバルツは、あられもなく乱れ始めていた。
(くそっ!)
腹の下のシュバルツを愛しながら、ハヤブサはぎり、と、歯を食いしばっていた。
(何なんだこの術は……ッ! これでは『傀儡』というよりも『性奴』ではないか……ッ!)
自分が触れる僅かな刺激で発情してしまうシュバルツ。しかもシュバルツは、自分の言葉に逆らうことができない。
こんなの――――自分が望みさえすればシュバルツに、どのような性的奉仕をさせることも、可能ではないか。
さらに、自分以外の人間が彼に触れると、彼の身体に激痛をもたらしている。
あの術をかけていた男は、「自分が慰み者にした後で、シュバルツに客を取らせる」と言っていた。そのあと女が「悪趣味ね」と、愉快そうに言っていた。その真意を今さらながらに悟ってしまって、ハヤブサは吐き気を覚えずにはいられなかった。
つまり、触れられるだけで激痛にのたうつシュバルツに、性行為を強要させるつもりでいたのだ。痛みに泣き叫ぶシュバルツを、なぶるように凌辱して――――
(よかった……)
そこだけはハヤブサも、胸を撫で下ろしていた。
シュバルツをそういう目に遭わせなくて、本当によかった。間に合ってよかった。術をかけられてしまって、自分がシュバルツに触れられないなど、本当に嫌すぎる。そんなことになってしまったら、自分の方が、気が狂ってしまうかもしれない。
「そういう需要の客もおる、ということじゃ」
男の言動に腹も立てるが、頷かざるを得なかった。
確かにそうだ。
世の中には、そういう物を好む客層も、少なからずいる。
冗談じゃない。
俺の大切なヒトを、そんな輩のおもちゃにさせてたまるか。
「ああ……! イク………! イキ……ます………ッ!」
言葉とともに身を震わせ、ピュク、と、果てるシュバルツ。
傀儡になる前から、イクときには『イク』と言うようにと、ハヤブサはシュバルツに頼み込んでいた。それをシュバルツは傀儡状態になっても律儀に守ってくれている。それに気付いてしまうと、ハヤブサはもう、目の前の彼のヒトが愛おしくてたまらなかった。
居るのだ。シュバルツは。
傀儡状態になっても
その瞳に、俺を写さなくなっても――――
俺の目の前に
ちゃんと『居る』
「シュバルツ……」
愛おしさが命じるままに、その唇を塞ぐ。
シュバルツの口から『イク』という言葉を聞くのは好きだ。
『イク』という言葉の響きが『生きる』と、よく似ているから。
不死の身体を持つアンドロイドであるからだろうか。シュバルツは普段、自分から『生きる』という選択肢をなかなかしないし、『生きたい』と言うこともない。
だけど、こうして身体をつなげている時だけは――――
「ああ……! イク……! イク……ッ!!」
「イキたい……! イキたいからぁ……ッ!」
「ああっ!! イキたい……! もう、イカせて……ッ!!」
『生きたい』『生きたい』と、何度も腕の中で啼いてくれる彼が、たまらなく愛おしい。
そんな彼を見たくて見たくてどうしようもないから、ハヤブサは何度も何度も彼を執拗に追い込んだ。
時に行き過ぎてしまう愛撫―――――それを、彼は優しく笑って許してくれていたのだが。
(今の状態のシュバルツは……自分から抱きついてきたり、『イカせて』と懇願してきたりすることはないだろうな……。何せ『自分』というものがない。要求を相手に伝えるなど、言わずもがなだろう……)
その代わり、こちらが『腰を動かせ』と言えば、素直にずっと腰を動かし続けてくれる。あられもなく乱れてくれる。
何を言っても何をやっても、それに律義に応えてくれるシュバルツの様相に、ハヤブサの中で割と邪な部類の思いがついつい表に出てきてしまう。
「もっと、大きな声で、啼いて」
「は……い……ああっ!!」
「自分の胸を、触って……」
「はい………ああっ! あ………ん………!」
「もっと、指の腹で擦るんだ」
「ああっ! は……! あ………あ……!」
「そのまま、かき回すように腰を動かして――――」
「ああっ!! うぁっ!! あうう……!!」
愛おしいヒトの媚態を目の前に作り上げて、それに酔ってしまう。溺れてしまう。
大切なヒトを、大切にしなければならないと思うのに。
それを軽く凌駕してしまう、この自分の中の凶悪な衝動は一体何なのだろう。
「ああっ!! ハヤブサ……! もう……イキます……ッ!!」
自分で自分の胸を弄りながら腰を淫らに動かし続ける彼のヒトが、今日何度目かの限界を訴える。
「まだだ……! まだ、イクな……!」
ハヤブサはとっさに、はち切れんばかりになっているシュバルツの牡茎の根元を握りこんだ。
「あうううっ!! あうっ!!」
「今度イクときは――――『共に』だ、シュバルツ」
「は………い………」
塞き止められて苦しかろうに、それでも律義にシュバルツは返事を返してくる。胸を弄り、腰を動かす。自分で自分を犯し続けている。
「イキます!! ハヤブサ……! もう、イキます……ッ!!」
『イキたい』と言えないのに、それでも懸命に限界を訴え続けるシュバルツが、愛おしくて可愛らしくて最高に堪らない。
ああ―――――幸せだ。
俺も、もう………!
「―――――!」
互いに身を震わせながら、忍者たちは同時に果てた。
そしてやはり―――――シュバルツは糸が切れたかのように、ばたん、と、倒れ込んでしまう。
(シュバルツ……)
少しの寂しさを感じながらも、ハヤブサはシュバルツの髪を優しく撫でる。
一つだけ、気づいたことがある。
それは、二人で同時に果てた時だけ、シュバルツはこのように意識を失ってしまう状態になる、ということだ。確か、シュバルツに術をかける時も、二人で同時に『気』をやった。やはりこの行為は、術と何らかの深い関係がある、ということなのだろうか。
この術は解けるのか。
解けるとしたら、それはいつなのだろう。
先が見えない今の状態に、ハヤブサはただ、ため息を吐くよりほかはなかった。
3
「うう~~~~~ん………」
シュバルツの二つの体液のデータを見比べながら、キョウジは難しい顔をしている。シュバルツが術にかかってから、かれこれ2週間が経過しようとしていた。
その間、キョウジとハヤブサの消耗は、想像を絶するものがあった。本当に――――いろいろあったのだ。
まず、二人が苦慮したのは、シュバルツの身の置き所だ。
「隼の里にシュバルツを行かせるわけにはいかないかな?」
キョウジの提案に、ハヤブサは渋い顔をした。
「いや、まずいだろうな……。里には、シュバルツを慕っている子供たちがいる」
「えっ?」
「来訪が嬉しい客人に対する子供の突進力は―――――半端なものではないぞ?」
「―――――!」
それは確かにいろいろまずいな、と、キョウジも思った。子供たちに抱きつかれたシュバルツがどうなってしまうのか――――想像するだけでも、気が滅入る。
「じゃあ、あまり気が進まないけど、シュバルツを里の『座敷牢』みたいなところに入れるのは――――」
「座敷牢か……」
キョウジの言葉に、ハヤブサはふむ、と考え込む。
「………………」
しばしの沈黙の後、ハヤブサの面に、『にへら』と、好色そうな笑みが浮かび上がったものだから――――
「や、やっぱりやめておこうか。なんかいろいろ、危険な香りしかしないし……」
顔を引きつらせながら言ったキョウジの言葉に、ハヤブサもはっと我に返った。
「す、すまん!! キョウジ……! 俺としたことが―――――!」
「いや、いいよ……」
「ああっ! 座敷牢の中にいるシュバルツがいろいろと可愛らしすぎて………ッ!」
「そ、そうなんだ………」
座り込んでさめざめと泣いているハヤブサを、キョウジはもう生暖かい眼差しで見つめるしかない。その横で相変わらず表情のないシュバルツが、ぼ~っと椅子に腰かけていた。
(意識があれば、ハヤブサを殴り飛ばしているんだろうけどなぁ……)
ここに身体はあるのに、やはり、シュバルツの不在を感じてしまって、キョウジは少し寂しい心持になる。シュバルツを、早く元に戻さなければと決意を新たにした。
「仕方がないなぁ。定期的にいろんなデータを調べたいから、シュバルツはやはり、私のそばに置いておくとして――――」
キョウジはポリポリと頭を掻きながら、ハヤブサの方に視線を走らせた。
「ハヤブサ、なるべくシュバルツのそばにいて、私の手伝いもしてくれると助かるんだけど――――」
「それはもちろん」
キョウジの言葉に、ハヤブサは力強く頷く。シュバルツを元の状態に戻したいのは自分も同じだし、遠慮なくシュバルツのそばにいられるというのなら、自分としても万々歳だ。
「………と、なると、あと一つの問題は―――――」
キョウジがそう言うと同時に、玄関のドアがバンッ!! と、音を立てて勢いよく開いた。
「兄さん!! ちょっと手合わせに付き合ってくれ!!」
今まさにキョウジが心配していた人物が、笑顔で走りこんでくる。彼の名はドモン・カッシュ。キョウジの弟にして稀代の格闘家である彼は、暇を見つけてはシュバルツに修行をつけてもらいに来ていたのだ。
キョウジのコピーであるシュバルツも、ドモンにとっては『兄』という認識であるため、シュバルツのことも彼は「兄さん」と呼び、とても慕っていた。
「兄さん! ………て、あれ?」
部屋の奥に座るシュバルツの姿を見つけたドモンは、まっすぐに駆け寄ろうとする。だがその前に――――キョウジとハヤブサが立ちはだかっていた。
「ど、どうしたの? 兄さん……」
二人の様子に少し異様なものを感じたドモンは、足を止めて首をかしげる。ドモンが止まったのを確認してから、キョウジはその面に笑みを浮かべた。
「悪いなドモン。シュバルツは今―――――メンテナンス中なんだ」
「メンテナンス?」
かなりびっくりしたように、ドモンはキョウジを見る。シュバルツがカッシュ家の一員に加わってからだいぶ経つが、「メンテナンス」などしているそぶりを、一度たりとも見たことがなかったからだ。
「シュバルツ………どこか悪いのか?」
心配そうに見つめてくる弟に、キョウジは優しい笑顔を向けた。
「そんなんじゃないよ。ちょっと、検査をしたいだけだから」
「検査って…………!」
キョウジの言葉に、ドモンの顔色がますます蒼白になっていく。
(あれ? おかしいな? 私はそんなに心配させるようなことを言っているのかな?)
弟から帰ってくる反応が妙すぎて、キョウジの方もだんだん不安になってくる。
変だな。『心配ない』って、言っているつもりなのに。
対してドモンの方は、『心配ない』と言う兄の言葉を、実はかなり信用していなかった。この目の前にいる優しく笑う兄は、自分がきついときほど『心配ない』『大丈夫だ』と、笑顔で言ってしまえることを知っていたからだ。
「ちょっと……シュバルツの様子を見せてくれ!」
心配が加速する弟は、シュバルツの方に走っていこうとする。「ま、待ってくれドモン!」と、キョウジが制止の声を上げるが、それで止められるはずもなく。しかしドモンがシュバルツの傍に到達する直前―――――龍の忍者が間に割って入った。
「待てと言っている! シュバルツに不用意に触るんじゃない!!」
「――――ッ! 何でだよ!?」
「何ででもだ!!」
口下手な龍の忍者は、ドモンの質問を不愛想に斬って捨てる。それでこの弟が納得するはずもない。
「理由を説明しろ!!」
「言う義理は無いな」
「納得できるか!! 俺は弟だぞ!! 兄を心配する権利ぐらいはある!!」
(それもそうだよな)
ハヤブサとドモンの口論を、キョウジは顔を引きつらせながら見守るしかない。ドモンの言い分はまさに正論だが、理由を説明できないのは自分も同義だった。故に、どちらの肩を持つこともできない。
「とにかく、シュバルツの様子を見せてくれ!!」
「断る!!」
押し通ろうとするドモンを前に、龍の忍者も一歩も引かない。
「そこをどけ!!」
「どいて欲しければ腕ずくで来い!!」
「なにぃ!?」
「尤も―――――返り討ちだがな!」
「おのれ言わせておけば………ッ!」
ぶるぶると震えていたドモンから、「ブチッ!」と、何かが切れた音がしたかと思うと。
「上等だ!! 表へ出ろ!! 叩きのめしてやる!!」
「望むところだ!!」
二人がものすごい勢いで玄関から外へと出ていく。
「行ってらっしゃ~い………」
キョウジはひらひらとハンカチを振りながら見送った後、はあ、と、大きくため息を吐いた。とりあえずのシュバルツの危機は、ハヤブサが身体を張ってくれたおかげで回避できたが、何だか問題を先延ばしにしてしまった感もある。いずれは弟にも事情を説明をしなければならなくなるだろうが――――
だが、早急に、今自分がしておくべきことは。
「………………」
キョウジは手元の携帯をとると、ドモンの恋人であるレインの番号に指を走らせた。スリーコールぐらいで、レインは電話に出てくれた。
「ああ、レイン? いや、今弟とハヤブサが来ててさ……。そのまま修行に行っちゃったんだ」
「あら、また?」
少しあきれたように返事をするレインに、キョウジも苦笑する。
「そうなんだ……。それでまた、『いつものコース』だと思うから、悪いんだけど、夕飯を作るの手伝いに来てくれたら助かるんだけど………」
「ええ、分かったわ。こちらも適当に材料を買って、すぐに行くわね」
そう言って、レインとの通話は切れた。キョウジはやれやれと携帯を机の上に置きながら、今日はどれぐらい食べるんだろう、と、軽くため息を吐いていた。
そして夕飯時。
がつがつとご飯をかきこむ音が、キョウジのアパートのダイニングルームに響き渡っていた。ドモンとハヤブサと―――――そしてなぜか、東方不敗までいる。次から次へと積み上げられていく空の茶碗を、キョウジとレインが半ば呆れながら見つめていた。
「だから何べん言ったら分かるのじゃ! ドモンよ! 貴様は踏み込みが甘い!」
「うるさい!! 俺はまだ認めてないからな!! さっきの勝負、どう見ても俺の勝ちだろう!!」
「どうだかな」
噛みつくように叫ぶドモンを、龍の忍者が味噌汁を飲みながら受け流している。
「何を言うか! ドモンよ! あそこでわしが止めなんだらどうなっていたと思う!?」
「俺がこいつの首を刎ねて終わりだろう!」
「阿呆か!! それよりも先に、貴様の喉仏が砕かれておるわ!! この馬鹿弟子が!!」
「怒るか食べるか説教するかけんかするか……どれか一つにすればいいのに」
呆れながら言うレインに、キョウジも苦笑するしかない。
「まあある意味、器用なんだろうね」
あれだけ口論をしながら、食事が減るペースが変わらないのは、本当にすごいことだと思う。3人ともが10杯目のご飯を綺麗に平らげていた。
「「「ごちそうさまでした」」」
3人が3人とも、茶碗を置いて礼儀正しく箸を置き、胸の前に手を合わせて丁寧に挨拶をする。こういうところがさすがに一流の武闘家だなとキョウジは思う。総じて一つの道を突出して極めている人というのは、こういう礼儀作法も存外きちんとしているものなのだ。
「さて、と………」
食後の一息をついたと思ったら、東方不敗とドモンが、同時に立ち上がった。
「師匠!! いくら師匠でもさっきの暴言は聞き捨てならん!! 表に出ろ!! きっちり白黒をつけてやる!!」
「ぬははははは!! この馬鹿弟子がぁ!! 返り討ちにしてくれるわ!!」
勢いよく飛び出していく子弟に、キョウジは声をかけた。
「夜食、チ●ンラーメンとおにぎり、どっちがいいですか~~~~!?」
その後しばらく耳を澄ませていると、「チ●ンラーメン!」と、微かに返事が返ってきた。今日の夜食のメニューが決定したな、と、キョウジが頷いているところに、ハヤブサが近づいてきた。
「キョウジ……東方不敗が来たから、今宵はもう大丈夫だろう。俺はいったん退くぞ」
「あ……うん、わかった」
「だが何かあったら呼べ。近くにいるから」
そう言って龍の忍者の姿が眼前からフッと消える。
(どこから出て行ったんだろう……)
玄関から普通に出ればいいのに、と、キョウジは思ったりもするのだが、忍者にそれを言うのは野暮、と言う物なのだろうか。
やれやれ、とキョウジがため息を吐いていると、レインがダイニングを片付けている姿が視界に飛び込んでくる。
「置いておいてくれて大丈夫だよ。私が洗うから」
慌てて駆け寄るキョウジに、レインは笑顔を見せる。
「ありがとう。でも、これだけたくさんの食器、一人で洗うの大変でしょう? 私も手伝うわ」
「そうか? ありがとう」
レインの厚意にキョウジも素直に礼を言う。そのまま二人は並んで食器を洗い始めた。
「毎度毎度……よく食べるわね」
「はは………そうだね……」
呆れながら言うレインにキョウジも苦笑する。しばらく、食器を洗う水音が、ダイニングルームに響いた。
「……………」
二人は、しばし黙々と食器を洗い続ける。だがやがて、キョウジの方が意を決したように口を開いた。
「レイン、シュバルツのことなんだけど………」
「そう言えば、シュバルツさん居なかったわね。今日はどうしちゃったの?」
「うん、そのことなんだけど――――」
キョウジは少し迷ったが、やがて、決心を固めた。やはり、レインには素直に事情を話しておいた方がいいと、判断したからだ。シュバルツのためにも、そしてドモンのためにも。
「実は今――――ちょっと普通の状態じゃないんだ。何だか、『術』をかけられているみたいで………」
「ええっ!?」
驚くレインにキョウジは「心配ないよ」と、優しく笑った。
「今ちょっとその『術』のせいで、軽く操り人形状態になっているんだ。その『術』をかけちゃったのはハヤブサで――――それも事故のようなものだったらしい。だけど、その術自体で心配していることは、あまりないんだけどね」
「そうなの?」
きょとんと眼をしばたたかせるレインに、キョウジは優しく微笑みかける。
「あのハヤブサが、いくら自分の意のままに動かせるとは言っても、シュバルツに酷いことをしたりさせたりすることが、あり得ると思う?」
「あ………! 確かに、そうかも………」
キョウジの言葉に、レインも納得したように頷いた。レインもそう納得せざるを得ないほどに、この忍者二人は仲睦まじく映っていたのだ。
「ただ一つ……あの術には難点があってね」
「難点?」
「どうも……『術』をかけたハヤブサ以外がシュバルツの身体に触れると、シュバルツが激痛に襲われるみたいで……」
「……………!」
「そんな状態のシュバルツにドモンを近づければどうなるか………分かるだろう?」
キョウジの言葉に、レインもはっと息を呑む。
確かにそうだ。
そんな状態のシュバルツの傍に、ドモンを近づけるのはあまりにも危険すぎる。
「だからレイン……悪いんだけど、しばらくの間でいいんだ。ドモンにシュバルツに近づかないよう言い含めてくれないかな? さっき私もそのことをドモンに言おうとしたんだけど、うまく伝わらなかったみたいだから――――」
「分かったわ。任せて」
キョウジの言葉に、レインが力強く頷く。それを見て、キョウジも安心したように微笑んだ。こういう時のレインは、とても頼りなる存在だとキョウジは思う。思えばドモンも、いい彼女を手に入れたものだ。
「じゃあ、ドモンが帰ってくるまで、ここで待たせてもらうわね」
夜食も手伝うから、と言うレインに、夜食は簡易ラーメンだから大丈夫だよ、と、キョウジは優しく笑った。
夜更け過ぎ。
ドモンは東方不敗との修行を終えてから、レインとともに自身の家に帰っていた。一人残ったキョウジは、今日測定したシュバルツの体液のデータを、パソコンに打ち込む作業を続けていた。
(………やはり、この塩基配列のデータの、この部分だな………。これだけは、シュバルツのどのデータからも読み取ることができない………)
異常の位置が特定できたとして、問題はそのあとだ。
これは、放置していてもいいものなのか、それとも、何らかの対処をした方がいいのか―――――
(そもそもこれが、どういう性質のものなのか調べるのが先か……)
そう思ったキョウジがパソコンの前でう~ん、と、一つ伸びをした時、カタン、と物音がして、部屋に人が入ってきた。
「……相変わらず研究熱心な奴じゃな……。今度は、何を調べておるのだ?」
「……マスター!」
入ってきた人間の姿を見て、キョウジは少し驚いたような声を上げる。
「シュバルツがおらなんだようだが……」
「えっ?」
「お主………何かあったか?」
そう言いながらキョウジの方をじっと見据えてくる東方不敗に、キョウジはもう苦笑するしかない。
(鋭い……!)
自分は割と、東方不敗に隠し事ができない事実に気付いてしまう。
どうして、すぐに異常に気付かれてしまうのだろう。
自分は普通に振る舞っていたつもりだったのに。
「フン! こちらが突っ込んでいかなければ、お主は絶対に自分からは話そうとはせんからな!」
「あははは………。よくご存じで」
東方不敗の揶揄ともとれる物言いに、キョウジは笑いながら答えると、小さくため息を吐いた。
この状況、下手に隠し立てをするよりも、素直に助力を頼んだ方が、話は早いだろうと、キョウジは判断した。東方不敗は、古来より戦いの舞台の陰に必ず存在していたといわれる『シャッフル同盟』の『キング・オブ・ハート』の紋章を受け継いでいる。それ故に、『戦い』のありとあらゆる『歴史』に精通している人物でもあったのだ。シュバルツにかけられたこの『術』についても、何か教えてもらえることがあるかもしれない。
「では、マスター……。シュバルツの様子を見てもらえますか? 彼は今――――『術』にかかっているみたいで……」
「術じゃと?」
問い返す東方不敗に、キョウジは頷いていた。
キョウジは、東方不敗を地下室へと案内する。キョウジの研究所兼実験室となっているこの場所に、シュバルツがいた。彼は部屋の隅で、椅子に座ってじっとしていた。
「シュバルツ、こちらへおいで」
キョウジが呼びかけると、シュバルツはすっと機械的に立ち上がり、静かにこちらへと歩を進めてきた。シュバルツはハヤブサから、「キョウジの言うことを聞くように」と、言い含められているのだ。
「ここへ座って」
キョウジは、シュバルツを寝台の縁に座るように指示する。彼は、素直にそれに従っていた。
(これは……!)
シュバルツが近づいてきたことで、東方不敗も彼の異常さに気付く。シュバルツの視線には覇気がなく、ガラス玉のような瞳には、何物も映されていないのだと知れた。
「確かに……何かに意志を奪われておるような気配じゃな……。いったい、こ奴が何をされたのか――――それは、分かっておるのか?」
「ええ。身体に特殊な『墨』で呪術的な紋様を描かれています」
「『墨』じゃと?」
問い返す東方不敗に、キョウジは頷く。
「ええ。ある忍者団にその術にかけられそうになっていたのをハヤブサに助けられたんです。ただ、その際に紆余曲折があって―――――ハヤブサがその『術』をシュバルツにかけてしまったような形になっているのですが……」
「ふむ………」
話を聞きながら、東方不敗はしばし考え込む。
「その『紋様』とやらを、見せてもらってもよいか?」
「あ………えっと………」
キョウジは東方不敗の要求に、すぐには答えられなかった。自分が触れるとシュバルツの身体に激痛をもたらしてしまう。シュバルツに『服を脱いで』とお願いしてもいいのだろうが――――
(どうしよう……ハヤブサも呼んだ方がいいのかな……)
万が一、自分か東方不敗がシュバルツの身体に触れてしまえば、シュバルツに激痛がもたらされる。そして、それを収めるにはハヤブサに触れてもらうしか術がない。
少しの間、キョウジが躊躇する。その間、シュバルツを無言で見つめていた東方不敗であるが、やがて、小さくため息を吐いた。
「………もう少し、殺気を隠せ。でないと、すぐに見つかるぞ」
「えっ?」
驚いたキョウジが東方不敗の方に振り返ると同時に、黒い影が音もなく床に降り立ち、その姿を現す。
「……………」
「ハヤブサ……!」
龍の忍者の殺気だった眼差しに、キョウジは少し息を呑んだ。
「……その殺気、まるで抜身の刀身の様じゃな……。だが惜しい。わしの不意を突くつもりならば、もう少しうまく鞘に収めねばならぬ。お主――――わしがシュバルツに手を伸ばせば、斬るつもりでおったな?」
東方不敗の言葉に、龍の忍者はピクリと眉を動かす。それを見た東方不敗はフフフ、と笑った。
「ハヤブサ……。あの………」
キョウジは恐る恐るハヤブサに声をかける。東方不敗にシュバルツの身体に描かれた『紋様』を見せるためには、シュバルツの肌を彼に見せねばならぬ。その許可を得るために。
ただ、好きな人の肌を、必要以上に他人に見せるのは、恋人としては面白くないだろう。キョウジがハヤブサを呼ぶことを躊躇ったのは、その1点の理由故だった。できれば、穏便に隠密裏に、事を運びたかったのだが。
「マスターに………あの『紋様』を見せても、いいかな……?」
「……………」
じっとキョウジを見据えていたハヤブサであるが、やがて、「チッ!」と、小さく舌打ちをした。
「………仕方あるまい。その男の情報には、俺も頼りたいところではあるし――――」
それを聞いた東方不敗がにやりと笑う。どうやら、交渉成立の様だった。
3人は改めて、寝台のふちに腰をかけ続けるシュバルツの前に立つ。
「シュバルツには指一本触れるなよ」
「分かっておる」
ハヤブサの念押しに、東方不敗が答える。それを見てから、キョウジはシュバルツに声をかけた。
「シュバルツ、服を脱いで。上だけでいいから」
「……………」
シュバルツは機械的に、シュルシュルと衣擦れの音を立てながら服を脱ぐ。やがて、3人の前に、シュバルツの白い肌と、その上に描かれた繊細だがどこか妖しく、そして美しい紋様が、その姿を現した。
「ほう…………」
東方不敗が感心したような声を上げる。それほどまでに、この紋様は『見事』の一言に尽きたのだ。しばらくそれをじっと見つめていた東方不敗であったが、やがて一つ頷くと、その顔を上げた。
「これは……間違いない。『腐墨(ふぼく)の術』じゃな」
「『腐墨の術』……ですか?」
問い返すキョウジに、東方不敗が頷く。
「そうじゃ………。室町時代の末期に生きた一人の絵師がその技を得たと伝えられておる。わしも実物を見るまで眉唾物であったがな……。まさか、実在して、それが現在に伝えられておったとは―――」
ここまで話した東方不敗が、ハヤブサの方を見る。
「して、この『術』をこ奴に施した男はどうした?」
「俺が斬って捨てた」
ぶっきらぼうに言い放つ龍の忍者に、東方不敗はからからと笑った。
「仕方がないとはいえ、少し惜しいな……。これだけの技を持つ者――――一目、会いたかったのう」
東方不敗の言葉に、ハヤブサはフン、と、首を背ける。間に挟まれたキョウジは、苦笑するしかなかった。
「シュバルツ、もう服を着ていいよ」
「はい………」
キョウジの言葉に機械的に答えて、シュバルツは服を着始める。とりあえず、東方不敗に危なげなく『紋様』を見せられたことに、キョウジはほっと胸を撫で下ろしていた。
「マスター」
「うん?」
「『腐墨の術』とは――――いったい、どういう物なんですか?」
キョウジの問いかけに、東方不敗は口の端を釣り上げた笑みを見せる。
「読んで字の如く、特殊な製法で『腐らせた墨』を使って、人体に描き込み、その対象を操り人形にする技じゃな。その際に行う、操り人形にするための『催眠』のかけ方はいろいろあると伝え聞いて居るが――――」
「特殊な製法の墨、ですか……。どんな方法で作られたものなんですか?」
「聞きたいか?」
にやりと笑う東方不敗に、ハヤブサは渋い顔をする。
「キョウジ、やめておけ。飯が食えなくなる可能性もある」
「えっ?」
驚くキョウジを、東方不敗は愉快そうに見つめていた。
「そうじゃな……。確かに、3日3晩くらいは、飯が食えなくなる可能性は、あるな……」
「―――――!!」
「それでも、聞きたいか?」
「え、遠慮しておきます……」
キョウジが多少引き気味に首を横に振る。それを見た東方不敗も「それがよい」と、頷いていた。
「『術者』は大概、月に一度、『対象者』に向かって術の上書をするものじゃが……亡くなっておるのならば、その心配もいらぬだろうな」
「月に一度………それは、なぜですか?」
「決まっておる。それが『墨』であるからじゃ」
キョウジの問いに、東方不敗は明確に答える。
「どんなに濃く描き込んでいたとしても、『墨』であるならばいずれ落ちる。故に術者は必要に応じて、何度も紋様を描き込む必要があるのじゃ」
「………と、言うことは、シュバルツに施された『術』は――――」
「まあ、そのうちに消える定めじゃろうな」
ハヤブサの問いに、東方不敗はあっさりと答える。
「良かった……!」
ホッと胸を撫で下ろすキョウジに、東方不敗は少し釘を刺した。
「ただし、いつ消えるかは分からぬぞ? 作られた方法も『邪法』なら、『念』も相当込められておる『墨』じゃ。下手をしたら1年や2年、このままでいる可能性もある」
「え………!」
息を呑むキョウジ。それを聞いたハヤブサは、叫んでいた。
「冗談ではない!!」
「ハヤブサ!?」
「キョウジ! シュバルツを借り受けるぞ!! シュバルツがこのままで良い筈がない!!」
そう叫ぶや否や、ハヤブサはあっという間にシュバルツを抱え上げて、闇夜の中に消えていった。後には、東方不敗とキョウジだけが、残された。
「やれやれ……。あ奴も相当じゃな………」
ため息とともに落とされる東方不敗の言葉に、キョウジも苦笑しながらも同意をするしかなかった。
それから2週間――――ハヤブサとシュバルツは、キョウジの前から姿を消していた。
彼らは何処にいたのか――――答えは簡単だった。
その間彼らは、隼の里の座敷牢の中に居たのだ。
「シュバルツ………」
ハヤブサはシュバルツを、裸にしてそこに拘束した。布団の上に寝かせ、手足をがっちりと固定し、動けないようにする。
「動くなよ」
その上にさらにそう命じてから、ハヤブサはシュバルツの上に覆いかぶさる。そのままそろそろと、その肌に舌を近づけた。
ぺちゃ………と、音を立てて、ハヤブサの舌がシュバルツの肌に描かれた『墨』に触れる。
「は………あ………! あ………!」
ビクッ! と、シュバルツの身体が反応する。舌の動きに合わせて身がしなり始める。
「動くな……」
感じやすい恋人の身体に苦笑しながらも、ハヤブサは重ねて命じる。動かれてはなぞれない。自分の舌で、墨の紋様が。
「は………い………。あ………ッ!」
こちらに律義に返事をして、動かないように必死に努力している愛おしいヒト。
「ん………! く………! はあっ!!」
大きく息を吐きながら、小さく身を震わせ、色々と堪えている様が、たまらなくいじましくて愛おしい。ハヤブサはその媚態を堪能しながら、シュバルツの肌の上の墨を、自らの舌でなぞるように舐めて行っていた。
これは、東方不敗の話を聞いて、『術』の性質を判断したが故の、ハヤブサの行動であった。
強力な『呪術』を以って作られた墨。それは、『普通の水』で洗い落としても取れるものではないだろう。そんな物で簡単に落ちるようでは『術』としては成り立たない。
だが『唾液』なら
唾液ならば、強力な『消化酵素』がある。呪いを『食べる』ことが可能なのではないかと―――――そう思い至ったのだ。
少しずつでいい。
食べた『呪い』を自分の中で『浄化』していく。
それを繰り返していけば――――
シュバルツを早く、この手に取り戻すことが、可能になるのではないだろうか。
「………………!」
だがこの作業、簡単な物ではないと、すぐに思い知ることになる。
シュバルツに描かれた墨の紋様は、とても繊細で複雑怪奇だ。普通になぞるだけでも一苦労なのに。
「あ………! あ………!」
感じやすい彼のヒトが、腹の下で身体をのたうたせるものだから、舐めとる作業を何度も中断せざるを得なくなる。
おまけに。
「イキます……! ハヤブサ……! もう――――」
触れてもないのにはち切れんばかりになり、達しそうになるシュバルツの牡茎。
ハヤブサは、無駄に『気』を散じさせてはならぬと、シュバルツの牡茎をリングや紐で、締め上げなくてはならなくなった。
「ああっ!! あぐぅっ!!」
達することができなくなったシュバルツが、さらにもどかしげに腰を振り、身を捩り始める。
それはひどく悩ましげで―――――
酷く、苦しそうだった。
(すまない、シュバルツ……)
本当は、すぐにでもイカせてやりたい。気持ちよくさせてやりたい。
だけど、だめだ。
この行為は、単純な愛の行為とは違う。半ば、呪術の『儀式』のようなものだから、手順を覆すわけにはいかないのだ。
「シュバルツ………声は殺さなくていい。だが、動かないでくれ……!」
酷な命令を、重ねて下す。だがシュバルツは、それに「はい」と、答える。いじましく、命令を守ろうと努力してくれる。
ああ
やはり、好きだ。
だからこそ、このままで良い筈がない。
シュバルツを元に戻したい。
この手に、取り戻したいのだ。
墨を舐めとる舌先が、徐々に痺れてくる。
――――『墨』が何で出来て居るか知りたいか? 飯が食えなくなるぞ――――
東方不敗の言葉が、頭に隅にちらつく。
自分も、多少は『呪術』に関して知識を持っている端くれの者だ。だから、この墨がかなり『えげつないもの』で出来ているという想像は、容易についた。本来なら、このように舌で触れるなど、断じて憚られる物だろう。
だが、それがどうした、と、ハヤブサは思った。
今、自分が触れているのは愛おしいヒトの肌だ。
そして、これがシュバルツを取り戻すことに繋がっているというのなら―――――
自分は、喜んで毒だって食らう。
「愛してる………」
ようやく一通り紋様を舐め終えたハヤブサが、シュバルツの中に挿入(はい)る。
「ああああああっ!!」
既に何度も空イキをしている愛おしいヒトは、必死に限界を訴えてきた。ハヤブサは優しく笑いながら、シュバルツの牡茎を戒めている紐を解いた。
だが、リングは。
リングは外してやらない。貴方がイクときは、俺も共にイク時だけだ。
「うあっ!! ああっ!! あああっ!!」
行きたがっているシュバルツは、必死に腰を揺らしている。蕩けきった内側は、ハヤブサを甘く締め付けてくる。自分が達するのも、もう――――時間の問題だった。
腰を捕まえて、最奥を深く抉ってやる。
「あ………! あ………! あ………!」
奥の締め付けが
シュバルツの喘ぎ声が切ない。
ハヤブサは頃合いを見計らって、シュバルツ自身をリングから解放した。
「―――――ッ!」
二人は同時に果てて、シュバルツはまた、糸が切れたように気を失ってしまった。
(シュバルツ……)
頬を伝い落ちる涙が
半開きになった唇が―――――
素直に、美しいと、思う。
(キスをしたい……)
そう願うハヤブサの唇が、シュバルツの唇に近づいていく。
しかし、寸前のところで、ハヤブサは思い留まった。
今―――――自分の口腔は、墨の毒を含んでいる。せっかくそれを僅かでもシュバルツから拭い取ったのに、キスをしてしまったら、またそれをシュバルツに還元してしまいそうな気がした。そんなことをしたら、今の行為の意味が完全になくなってしまうだろう。
「……………」
ハヤブサはぐっと堪えてシュバルツとのキスをあきらめると、彼からそっと離れた。自身の中に取り込んだ墨の毒を、浄化しに行くために。
立ち上がり、振り返ると、布団の上に縛られて固定された、シュバルツの裸体がある。
すまない。
今は、その戒めを解いてはやれない。
これは、単純な『愛の行為』ではない。
『墨』の『毒』を浄化するための、術式の一環であるが故に。
待っていろ、シュバルツ。
必ず―――――お前を助け出してやるから。
(だが、正気に戻った後………こんな目に遭わされたとシュバルツが知ったら、俺は、恨まれるかもしれないな………)
だが、仕方がない。
シュバルツがずっと操り人形の状態でいるぐらいなら、自分が恨まれた方がまだましだ。
もとはと言えば、自分が狙われたせいでシュバルツが巻き込まれ、こんなことになってしまったのだから。
恨まれてもいい。シュバルツに『会いたい』
彼を呪いから、取り戻したいのだ。
ハヤブサは小さくため息を吐くと、静かに座敷牢から出て行った。
里の奥深い場所にある『龍の祠』の傍の泉で、斎戒沐浴をする。泉に流れ込む滝に打たれながら、浄化の『誦』を唱え続ける―――――それが、ハヤブサが選んだ毒の浄化の方法だった。『誦』の詠唱を何周かしているうちに、身体の内から『毒素』が抜けていくのが分かった。
一通りの浄化を済ますと、軽めの食事をして、少しの間身を休める。それからまた彼は、間をおかずにシュバルツのいる座敷牢へと向かった。――――シュバルツを清めるために。
「ああ………! ああ………!」
墨を舐めとられるたびに、僅かに動くシュバルツの身体が、小さく震えながらのたうつ。彼を固定している縄が、ぎしぎしと音を立てる。
「動くな」
淫らな熱に犯されている愛おしいヒトに、酷な命令を下し続ける。
「は………い………」
命じられるままに、素直に頷くしかないシュバルツ。トロンとした眼差しで、息も絶え絶えに喘いでいた。上気したその頬には、涙が伝い続けている。
無理もない。
自分に触れられると『術』のせいで淫らに発情してしまうシュバルツ。それが、感じさせられるように身体の上に描かれた紋様の上をぺちゃぺちゃと舐められて、しかも、身動きも射精も許されない状態が続いているのだから。彼のヒトにとっては、これは『快感』と言うよりも、もはや『拷問』に近い状態なのではあるまいか。
(あの男なら、この状態のシュバルツを喜んで弄ぶのだろうな……。『墨』をさらに上書きして、『術』をさらに重ね続けて――――)
そんな状態、想像するだけで胸糞悪くなる。あの男はシュバルツに施した紋様を描き込む力を得るために、いったい、何人の人間をその『墨』の魔力で犠牲にしてきたのだろうか。
腹が立つ。
過ぎたことなのに。
シュバルツに対する愛撫が、ひどく乱暴なものになりかける。
「ああ……! ハヤブサ(ご主人様)………!」
シュバルツのその声に、ハヤブサははっと我に返る。
浄化の途中だったことを、思い出す。
いかん、集中―――――
集中、しなければ
(くそ……ッ!)
墨に触れ続ける舌先が、きつく痺れてきた。
きっと、これは『毒』を舐めとれている証拠――――
ハヤブサはそう信じて、その行為を続けた。
一通り紋様を舐めとって、そして共に果てた。
手順を踏みつつ自分の体内に毒を取り込み、それを浄化し続けた。
それは2週間、ほぼ休みなく続けられた。
そうして、現在に至る。
2週間前と現在のシュバルツの体液のデータを見比べながら、難しい顔で唸り続けるキョウジ。それに向かって、ハヤブサは声をかけた。
「すまないキョウジ……。本当はもう少し『浄化』を続けたかったのだが、断れない『仕事』が入ってな……。俺はそれに行かねばならぬ」
「仕事?」
少し驚いたように顔を上げるキョウジに、ハヤブサは頷いた。
「ああ。それでその間、シュバルツを里に留め置くわけにもいかないから、ここに連れてきた。キョウジ………どうだ? シュバルツのデータに、何か変化は出ているか?」
「そうだね……。確かに………」
2つのデータから目を離さずに、キョウジは口を開いた。
「異常値の値が小さくなってる……。さっき見た墨の紋様も、だいぶ薄くなっているように感じられたしね」
「では―――――?」
問いかけるハヤブサに、キョウジも頷く。
「ああ。このままもう少し行けば、間違いなく『浄化』できるだろう……。シュバルツも、元に戻るんじゃないかな」
(よし……!)
キョウジの言葉に、ハヤブサは小さくガッツポーズを作る。それを、キョウジも微笑みながら見つめていた。
「因みに、ハヤブサ」
「何だ? キョウジ」
「参考までに聞きたいんだけど、この『墨』をどうやって『浄化』したの?」
キョウジの問いに、ハヤブサはあっさりと答える。
「単純に、ただ『舐めた』だけだ」
「『舐めた』!?」
キョウジが、びっくりしたように聞き返してきた。
「『舐めた』って………! あの、『墨』を!?」
その言葉にハヤブサは「ああ」と頷く。すると、キョウジの顔色が、みるみる真っ青になっていった。
「大丈夫か?」
思わず問いかけるハヤブサに、キョウジは「大丈夫」と、言おうとして失敗していた。
「ごめん、ちょっと――――」
そう言い残すと、彼は一目散に手洗いへと走り込んでいった。
「う………ッ! げ………え…………ッ!」
キョウジはトイレに走りこむと、ドアに鍵をかける間もなく、便器に吐き戻していた。
そう。彼は突き止めていたのだ。その『墨』の成り立ちと、その製法を。
東方不敗に、「正体を知れば、飯が食えなくなる可能性がある」と忠告はされていた。だから、ある程度覚悟はしていたのだが。
それでも―――――あそこまで、酷い物とは。
ハヤブサがシュバルツを連れて行ってから2日後に、キョウジはその答えにたどり着いていた。
あまりにも酷い―――――
あまりにもおぞましいその成り立ちに、キョウジは吐き気を堪えきれなかった。
便所に走りこんで、夕飯をすべて戻してしまった。
「う………! げほっ!!」
便器を掴んで噦(えず)いていると、そこに東方不敗がのそりと姿を現してきた。
「お主……『墨』の正体を突き止めたのか?」
問うてくる東方不敗に、キョウジは口元を拭いながら答える。
「はい………」
「愚か者が。わしは忠告したはずだぞ? あれは相当なものだと」
「はい……。すみません……」
東方不敗の言葉に、キョウジはもう苦笑するしかない。
「ですが………シュバルツをあのままにしておけないのも、事実です………。それに、シュバルツを助けたいと願う、ハヤブサの手助けもしたかったから………」
キョウジのその言葉に、東方不敗はやれやれと、ため息を吐く。
「それにしても……あんな物に不用意に触ってはならぬ。あれは、『邪法』の極みぞ」
「そうですね……」
東方不敗に同意しながら、キョウジはまた吐いた。東方不敗はため息を吐きながらも、キョウジの背中をさすり続けてくれていた。
「………落ち着いたか?」
キョウジがこれ以上吐かなくなったのを確認してから、東方不敗はキョウジを寝台へと連れていく。
「はい……。ありがとうございました………」
礼を言うキョウジだが、彼は身を起こすことができなかった。それほどまでに、あの『墨』の製法は、キョウジにダメージを与えていたのだ。
「だから、わしは忠告したはずだぞ、キョウジ」
そんなキョウジに向かって、東方不敗は改めて口を開く。
「あれは相当、酷いものだと……。あんなものに不用意に触れてはならぬ。気長に待てば、いずれは消えるのだ。無理に自ら、突っ込んでいく必要はない」
「それはそうかもしれませんが………」
寝台の上に横になったキョウジは、額の濡れタオルをずらしながら、少し唇を尖らせている。何か、釈然としない思いが自分の中で渦を巻いていた。
「マスター……一つ聞いてもいいですか?」
「何じゃ? キョウジ」
「あの『腐墨の術』は………何度も重ね掛けされた人間は、最終的にはどうなるんですか?」
「そんなもの、答えは単純じゃ。墨の『毒』が全身に回って死ぬ」
「…………!」
一番最悪な答えがあっさりと返ってきて、キョウジは知らず絶句する。
「………じゃが、『術者』がもうこの世には居らん。その点だけは、龍の忍者に感謝せねばならぬな、キョウジ。シュバルツには、術を重ね掛けされる心配はないのであるから……」
「そうですね………」
東方不敗にそう答えながらも、キョウジは布団をぎゅっと握りしめていた。
確かに、放っておけばいいものかもしれないが、自分は、許し難かった。
シュバルツの身に、いつまでもあんな物を留め置いておくなんて。
それに、シュバルツの身を抱えて何処かへ姿を消したハヤブサのことも気にかかる。
何か――――無茶をしていなければいいのだが。
(とにかく、身体を早く治して、あの『墨』を身体から落とす方法がないか、調べてみよう)
そう決意して、キョウジは改めて布団をかぶりなおす。
『呪術』に関しては、非力で無学な自分だが、それでも、何か、できることがあるはずだ――――キョウジは、そう信じることにした。
「すみません……。少し、寝ます………」
東方不敗にそう声をかけると、「うむ、少し休め」と、頷いてくれた。
キョウジはそれに、少しの安心を覚えると、いつしかまどろみの中に、その身を置いていた―――――
何とか、事態を前向きに対処しようと努力したキョウジだが、それでも布団から身を起こすのには3日かかってしまった。東方不敗やドモンやレインの助けがなければ、もっと長引いていたことだろう。
(独りじゃないって、本当にすごいことだな……)
キョウジは、改めて周りの助力に感謝をしていた。
身を起こせるようになってから数日の間、キョウジは呪いを解く方法を調べていた。
しかし、有効な手立てが見つかるわけでもなく、ただ『呪術』に関する知識が、無駄に深まっていくだけだった。
(ううう……。できれば一生知りたくなかった………)
分厚い呪術の本をパタン、と、閉じながら、キョウジは半泣きになってしまう。
結局のところ、呪いを解くには、その『呪詛』を相手に返すか、優秀な『陰陽師』あるいは『巫女』とも呼べる存在に、その『邪気』を払ってもらうしかないらしい。
(でも、『呪詛返し』なんて高等能力、私なんかが扱えるわけないし、『陰陽師』や『巫女』に知り合いなんか居るわけないしな……。不用意に見知らぬ他人に頼むにしても、シュバルツの身体の秘密がばれてしまったら厄介だし……)
そう考えていくと、自力で何とかするしかないのだが、それが出来かねるから、キョウジはもうため息を吐くしかないのである。同じところをぐるぐる回っているなと感じて、一つ大きく伸びをした。もう少し、科学的な方法で、アプローチできないかと思っても見るのだが。
(ハヤブサは……どうしているのだろう)
ギ、と、音を立てて椅子にもたれかかりながら、キョウジは窓から空を見上げる。
ハヤブサのことだから、何らかの手段を思いついたからこそ、シュバルツを連れて行った可能性が高い。彼は心底「シュバルツを取り戻したい」と願っているから、シュバルツの安否に関しては、キョウジはまるで心配していなかった。
心配なのは、むしろハヤブサの方だ。
あれだけの呪い、祓おうとしたら、それをする方もきっとただでは済まない。何らかのダメージを受けるのは必至だった。
ハヤブサは、シュバルツのためならば、平気でその身を捨てようとする。
シュバルツが、周りの人たちのためにその身を簡単に投げ出すのと同じように。
きっと、それは理屈じゃない。
ハヤブサが、それをせずにはいられないのだろう。そういうことをするシュバルツを、愛してしまったが故に。
愛する人と同じ場所に立とうとする。同じ景色を見ようとする。
それが――――リュウ・ハヤブサと言う人の、『愛し方』だった。
ただ、『生命』がなく、何度でも甦ることができるシュバルツと違って、ハヤブサは人の身であるが故に、その生命は一つしかない。それでもなおシュバルツと同じ景色を見ようとするのならば、それはひどく無謀で――――文字通り、命がけの行為だった。
それを貫き通すハヤブサは、本当に強くて―――――
本当に、シュバルツが好きなのだと思う。
そんな風に愛されるシュバルツを、キョウジは少々うらやましいとも思うが、正直、ハヤブサの愛は、自分には重すぎるかなとも思う。あの愛情をこの身に一身に受けたなら、1週間と持たずにこちらが潰されてしまいそうだ。
ハヤブサも、それが分かっているから、私よりもシュバルツを選んでいるのだろう。
自分とシュバルツとハヤブサ――――
本当に、不思議な関係だとキョウジは思った。
(ハヤブサ……せめて、連絡をくれないかな………)
それからキョウジの方は、特に進展があるわけでもなく、ただ時間だけが過ぎて行っていたのだが。
今――――ハヤブサと再会して、ハヤブサが『呪い』を『食べた』と知って、キョウジの中で、処理しきれない様々なものが渦を巻く。堪えきれなくなってしまった彼は、不覚にもまた吐いてしまっていたのである。
「キョウジ……」
トイレの入り口にハヤブサが立ち、心配そうに声をかけてくる。
いけない、と、キョウジは思った。
吐いている場合ではない。
吐くより先に、言わねばならないこと―――――
やらねばならいことが、あるだろう。
吐くのを止めろ、と、キョウジは自分を強く叱咤する。
そうしなければ、ハヤブサに別の要らない誤解を与えかねない。キョウジは、それを恐れた。
しかし、一度沸き上がった吐き気は、キョウジから昼食を取り上げ、まだ出せと要求してくる。
(いやだ……!)
キョウジが必死にそれに抗っていると、ハヤブサが横に座り、そっと声をかけてきた。
「大丈夫か……?」
「ハヤブサ……」
顔面蒼白なキョウジが、目に涙を浮かべながらこちらに振り返る。それを見たハヤブサは、胸につきりと痛みを覚えた。
聡いキョウジのことだ。もしかしたら、あの『墨』の正体を探り当てているのかもしれない。そして、それを自分が『食べた』と知って、この反応をしているというのなら。
「………………」
自分は、確かに穢れている。もしかしたら、そばに寄ってこられるのも「いやだ」と、思われているのかもしれない。
「すまない………」
小さくそう言って、ハヤブサが立ち上がろうとすると、「違う!!」と、キョウジがいきなり腕を掴んできた。
「待って……! ハヤブサ……! 少し、待ってくれ……!」
「キョウジ……!」
「お願いだ……! もう少しだけ―――――うッ!」
キョウジはまた、便器に吐き戻し始めた。しかし、激しく噦(えず)きながらもキョウジは、掴んだハヤブサの手を、決して離そうとはしなかった。それを見てハヤブサは、ようやく自分の方がキョウジの態度を誤解しかかっていたのだと悟った。
「すまない、キョウジ……。大丈夫か?」
そう言いながらハヤブサの手が、キョウジの背に触れ、そこを優しくさすり始める。
「ごめん……! 醜態を――――」
顔色の悪いキョウジが必死に謝ろうとしてくるのを、ハヤブサはやんわりと押しとどめた。
「いい。それよりも、吐くのならば吐ききれ。その方が、楽になる」
「ハヤブサ……」
「俺のことは気にするな。大丈夫だから……」
「………うん……」
ハヤブサのその言葉に、キョウジはようやく笑顔を見せる。しかし、二人がトイレから出るには、もう少しの時が必要であった。
ダイニングで脱力して椅子に座りこんでいるキョウジの前に、トン、と、水が入ったコップが差し出された。
「………落ち着いたか?」
声をかけられて顔を上げると、その先にハヤブサの優しい眼差しがある。
「うん……。ありがとう……」
笑みを見せるキョウジに、ハヤブサも微笑み返す。だが同時に、少しの寂しさも感じた。
愛おしいヒトと同じ笑顔。
自分は、もうずいぶん長いこと、彼のヒトのこんな笑顔を見ていないのだと、否が応でも気づいてしまうから。
「少しずつでも、飲めるようなら飲め。だが、無理はするな」
「うん………」
キョウジは両手でコップを持って、そろりと水分を口に含んだ。口の中の潤いに、キョウジは乾いてしまっている己を自覚する。しかしまだ、水分を一気に飲もうとは、どうしても思えなかった。
「…………………」
ちびりちびりと水を飲みながら、キョウジは己の感情と考えを整理する。
思うところはいろいろある。
だが、最初に自分がハヤブサに伝えねばならぬのは、この言葉だ。
「…………ハヤブサ」
「何だ?」
自身にも茶を入れていたハヤブサが、キョウジの声に振り向く。
「………ありがとう……」
「キョウジ………」
「………シュバルツを、助けてくれて………」
「『助けた』とは少し違う。俺は、責任を取っただけだ」
そう。狙われたのは自分で、シュバルツは何の落ち度もないのに、それに巻き込まれただけだ。その結果、彼が呪われたのだと言うのなら、それを祓うのは自分の当然の責務なのだとハヤブサは思った。
「でも………」
「それに、礼などまだ早いし、不要だ。まだシュバルツを完全に元に戻せたわけでもない」
「……………」
ハヤブサの言葉にキョウジは黙るが、まだ釈然としていない顔をしていた。
「それでもやっぱり、お礼を言わせて、ハヤブサ」
「キョウジ……」
「『呪術』の本で読んだ……。呪いを祓うのに、『食べる』という手段は確かに、有効な手段なのだと……。だけど――――」
キョウジの顔色は、依然として悪く、コップを持つ手もカタカタと小刻みに震えている。
「いくらシュバルツを助けるためとはいえ………あんな……物を………ハヤブサ………!」
「あまり深く考えるな、キョウジ。俺なら平気だ」
キョウジの言葉を断ち切るように、ハヤブサは口を開いた。またキョウジを吐かせるわけにはいかないと思った。
「それに、俺がやったことは、特別なことでもなんでもない。誰だってすることだ」
「そうなのか?」
きょとん、とするキョウジに、ハヤブサは憮然と頷く。
「現に、お前もそうだろう? 誰か親しい者を助けるためならば―――――必要とあれば『毒』でも食らうのではないのか?」
「―――――!」
「それと同じだ。だから、気にするなキョウジ」
(………そうかなぁ……。いや、そうかもしれないけれど……)
ハヤブサの言っていることも分かるが、自分はやはり納得できない。シュバルツも自分も―――――ハヤブサには返しても返しきれない恩義を受けたように思う。
いくら『好き』と言っても、あの『墨』は、生半可の気持ちで口に含める代物ではない。正体を知ってしまっている自分は、なおのこと、それをするのを躊躇してしまうだろう。
(だがハヤブサは……あの『墨』の正体を正確に知っても、躊躇わず同じことをしそうな気がするなぁ。シュバルツを助けるためならば………)
やはり、ハヤブサの愛情は、深く重い。
自分は、そしてシュバルツは
その愛情に、これから先も何らかの形で応えていかねばならないと思う。
「うん……。分かった……。ありがとう、ハヤブサ……」
その決意を胸に秘めて、キョウジは微笑む。その笑みを見たハヤブサは、キョウジが自分の言葉に納得してくれたのだと受け取って、うん、と、頷いた。
「それでだ、キョウジ。俺はこれから『仕事』に向かわねばならぬ」
ハヤブサは本題の話を始めた。シュバルツをここに預けていくために、今日はそのために寄ったのだから。
「詳しくは言えないが、任務には多少の危険が付きまとう。そんなところに今の状態のシュバルツを連れてはいけないんだ。だからキョウジ―――――シュバルツをしばらくここで預かっていてくれないか?」
「それはお安い御用だけれども―――――」
そう言いながら、キョウジは少し難しい顔をする。
「でも、ハヤブサ……。大丈夫なのか? あなたの顔色こそ、少し悪いような――――」
いくら龍の忍者が『強い』と言っても、あの邪法で塗り固められた『墨』は、相当な『毒』を含んだ代物だった。それを体内で『浄化』できていたとしても、ハヤブサに何もダメージがなかったとは、到底思えない。
「案ずるな、キョウジ。問題ない」
キョウジの懸念を断ち切るように、ハヤブサは言い放つ。
確かにこの2週間、ほぼぶっ続けでシュバルツを清め続けたハヤブサに、ダメージが残っていないと言えば、それは嘘になった。
「リュウさん!! 少し、休んでください!!」
最後の方では、里での付き人である与助が悲鳴を上げるほどに、外からもはっきりとわかるほど、ハヤブサはやつれていた。
そんなときに『龍の忍者』に舞い込んできた、仕事の依頼。もちろん、ハヤブサには、断る選択肢もあった。
だが、この――――某国の過激派に捕えられている人質を救出する仕事は、実は数か月前から依頼されていた代物で。沢山の人々の協力や助力が働いて、今、細い一本の線のような救出ルートを作り上げることに成功していた。
これは、奇跡と言ってもよかった。
この機会を逃せば――――人質救出のチャンスなど、もう2度と訪れないと分かる。
だからハヤブサは断れなかった。
依頼してきた機関も、人質となっている人物も、ハヤブサにとっては知らないものではなかったから、余計にだ。
「この仕事は長くはかからない。すぐに戻る」
キョウジを安心させようと、ハヤブサは言葉を続けた。
現にこの仕事は、あまり長い時間をかけてはいけない代物だった。
過激派が横行する現地にとどまり続けるのは危険すぎた。こちらが死ぬ確率も、格段に跳ね上がることを意味するからだ。
「だから、すぐに仕事を終えて帰ってくる。すまないが、キョウジ。シュバルツのことをよろしく頼む」
「ハヤブサ……。私に何かほかに手伝えることは――――」
「案ずるな、キョウジ」
そう言って、優しく笑うハヤブサ。その笑顔の前に、キョウジはもう何も言えなくなってしまった。何を言っても、彼を止められないのだと悟ってしまったから。
「分かった……」
頷いてからキョウジは、縋るようにハヤブサを見た。
「でもハヤブサ、必ず帰ってきてくれ。皆、待っているから――――」
「元より、そのつもりだ」
そう言いおいて、龍の忍者はキョウジの前からフッと姿を消した。後にはキョウジと、人形のように椅子に座り続けるシュバルツだけが、残された。
(さてと……シュバルツをどうしようかな………。とにかく、私はシュバルツに不用意に触らないようにしないと………)
キョウジはそう思って、小さくため息を吐く。
シュバルツが傀儡状態になってから2週間以上―――――実は、結構自分は、シュバルツにもたれかかったり触ったりしていた事実に気付いてしまって、キョウジは地味にストレスを抱えていた。彼が目の前に居るのに、触ったり頼ったりすることができないジレンマ――――果たして自分は、どこまで耐えられるのだろうか。
だが、シュバルツを激痛の中にのたうたせるわけにはいかない。そんなことをさせるぐらいなら、自分が孤独に耐えるほうを選ぶ。キョウジは、うん、と、頷いた。
「シュバルツ……」
キョウジがシュバルツに声をかけたとき、シュバルツの方に変化が起こっていた。それまでぼ~っと人形のように座っていたシュバルツが、ある一点の方向を、食い入るように見つめている。
「シュバルツ? どうした?」
さすがに怪訝に思ったキョウジがもう一度声をかけると、シュバルツの方も口を開いた。
「………ハヤブサ(ご主人様)が………」
「えっ?」
「ハヤブサ(ご主人様)……!」
きょとん、とするキョウジの目の前で、シュバルツの姿がフッと消える。
「えっ? え……ッ!? ちょっと――――!?」
いきなりのシュバルツの行動に、キョウジはただ、呆然とするしか術がなかった。
ドモンと東方不敗が、いつものようにロードワークからキョウジのアパートに向かっていると、その横をシュバルツが走り抜けていく。
「兄さん!?」
それに気づいたドモンが、シュバルツを引き止めようとする。それを、東方不敗に後ろから首根っこを掴まれて阻まれてしまった。
「何をする!? 師匠!!」
振り返って噛みつかんばかりに怒鳴ってくるドモンに、東方不敗はフン、と、鼻を鳴らした。
「この馬鹿弟子が!! お主はまだわしが出した課題を消化しきっておらん!! それを放って、他所事に気を取られておる場合か!?」
「今俺の横を通って行ったのは兄さんだ!! 兄さんが俺にとって『他所事』なわけがあるか!!」
「馬鹿者!! 兄弟であるからこそ、そういうけじめはきっちりとつけねばならんと言うのがまだわからんのか!! だからお前は―――――」
「ドモン!! マスター!!」
こちらに向かって走ってくるキョウジに声をかけられて、このいつもの不毛な言い争いが中断される。
「あ、兄さん!!」
ドモンもまたキョウジの方に向かって足を進める。東方不敗もまた、やれやれ、と、小さくため息を吐きながら、そのあとに続いた。
「どうしたの? 兄さん!」
「ドモン、シュバルツを見なかったか?」
「シュバルツなら、さっきそこを走って行っていたけど………」
「―――――!」
絶句したように息を呑むキョウジ。そこに、東方不敗が声をかけてきた。
「どうしたのじゃ? キョウジ。何があった?」
「あ………えっと………」
キョウジが少し躊躇うように、東方不敗とドモンを見比べる。それに何かを察知した東方不敗が、一つ小さくため息を吐いた。
「遠慮はいらん。何があったか話せキョウジ」
「でも………」
「潮時じゃ。充分じゃろう、もう………」
東方不敗に諭されるように言われて、キョウジもはあ、と、肩を落とす。
「そうですね……」
東方不敗とキョウジのやり取りを、ドモンが怪訝そうに見ている。キョウジは顔を上げると、何かを決意したかのように、うん、と、頷いた。
「マスター……何があったか話しますから、家に来てくれませんか? ドモン、お前も―――」
キョウジの言葉に、二人は素直に従っていた。
「『術』にかかっているだとぉ!? シュバルツが!?」
キョウジの話を聞いたドモンが、素っ頓狂な声を上げる。キョウジは苦笑しながら、「ああ」と頷いていた。
「その『術』のせいで、シュバルツは今――――操り人形みたいな感じになっているんだ。その術をシュバルツにかけようとした男は、ハヤブサにやっつけられたみたいなんだけど、そのあと紆余曲折があって――――その『術』を、ハヤブサがシュバルツにかけたみたいな状態に、なっちゃっていて………」
「………ちょっとその男とハヤブサを、この手で絞めてくる」
表情を硬くしたまま、ドモンが立ち上がる。
「ドモン、ちょっと――――」
キョウジが慌ててドモンを止めようとするのを東方不敗が手で制してから、ドモンに改めて声をかけていた。
「話はまだ終わってはおらん。座れ、ドモンよ」
「でも師匠――――!」
「お前は阿呆か。お前がそんな風だから、兄御がお前にいろいろと話せないということ、まだ悟れんのか?」
「――――!」
「座れ! 兄御の信頼を、その手に得たいと願うのならば」
「……………!」
東方不敗の言葉に、反論の余地を失うドモン。彼は小さく舌打ちをしながらも、再び席についていた。
「……『術』にかかっているって……シュバルツは大丈夫なんだろうな!?」
噛みつかんばかりに聞いてくるドモンに、キョウジは苦笑するしかない。
「『術』をかけているのがハヤブサだったら――――シュバルツの安否はほぼ心配しなくていいと思うよ」
「何でそんなことが言い切れるんだよ!?」
「ハヤブサはシュバルツのことを、『刎頚の友』だと思っているから」
「ふんけ………なんだって??」
「互いに首を刎ねられても、後悔はしない仲、と言うことじゃ」
ドモンのために、横から東方不敗が解説を挟む。
「ドモン、お主にも居るであろう? 相手のためならば、命を取られてもいいと思える友人が………存在が……」
「………確かに……」
東方不敗の言葉に、ドモンの脳裏に数人の友人の顔が浮かぶ。
確かにそうだ。
自分は、あの友人たちのためなら喜んでこの命を差し出すだろうし、友人たちもまた然りだろう。そして、今目の前に居る兄も――――
兄も自分のために命を投げ出してくれる人だ。
だから自分も、兄を助けるためならば、この命を取られても惜しくはないと思った。
(そうか………そういうことか………)
ドモンは少し、シュバルツとハヤブサの関係を理解する。
しかしやはり――――何となく面白くない、と、感じてしまうのはなぜなのだろう。自分だって、同じぐらいシュバルツに命をかけられると思うのに。
「それでさっき、ハヤブサが『仕事に行くから』と言って、シュバルツをこちらに預けに来てくれたんだけど、ハヤブサが出て行ってすぐに、シュバルツも出て行ってしまって―――――」
「出て行った? 後を追っていったってことか?」
問い返すドモンに、キョウジは首をひねる。
「よく分からないけど………多分、やっぱりそうなのかなぁ……」
出ていく直前、シュバルツはハヤブサの名前を口にしていた。だから、その可能性が高いとキョウジは思っている。
「でも……何故なんだろう? ハヤブサは、シュバルツに私の家にいるようにと命を下していた。なのに、どうして自発的に動いたんだろう? シュバルツには今、『自分の意志』がない筈なのに……?」
「『腐墨の術』にかかった者は、その術者と一定以上の距離は離れられないと聞いたことがあるぞ」
「ええっ!?」
「―――――!」
東方不敗の言葉に、ドモンとキョウジが同時に息を呑む。
「………て、事は、やっぱりハヤブサについて行っちゃったのか……! あちゃ~~~……参ったな………」
「兄さん! ハヤブサの野郎は何処に行ったのか聞いているのか!?」
「聞いてないよ」
がっつくようなドモンの問いに、キョウジは心底困ったような顔をする。
「ああ見えてハヤブサはプロだ。自分の『仕事』に関係のない第3者を巻き込むような真似は絶対にしない」
「……………!」
キョウジの言葉を受けたドモンは、立ち上がりかけた椅子に、再びドスン、と、腰を落としていた。「為すすべなし」とはまさに、このことだ。
「………こうなったら、ハヤブサが、シュバルツのことをうまく対処してくれる事を、祈ろう」
落とされたキョウジの言葉に、ドモンは「チッ!」と、舌打ちをした。
「シュバルツ……大丈夫なのか……? ハヤブサめ……! シュバルツに何かあったら、ただじゃおかないからな……!」
「シュバルツの安否に関しては、私は心配してはいないよ。シュバルツを真の意味で殺せるのは、ハヤブサの『龍剣』か、ドモンたちが持っている『紋章の力』だけだから」
そう。
その身体がDG細胞で出来ているシュバルツは、ある意味『不死』の存在だった。
銃で身体を撃たれようが、剣で刺し貫かれようか、DG細胞の『自己再生』の力が働いて、彼は何度でも甦ることができるのだから。
「それはそうかもしれないけどさ……!」
キョウジの話を聞いて尚も、ドモンは不満げだ。
「とりあえずハヤブサの野郎は、帰ってきたら一発殴ってやるからな!! シュバルツをとんでもない目に遭わせやがって!! こっちはえらい迷惑しているんだ!!」
「め、迷惑!? どうして!?」
少し驚くキョウジにドモンは思わず喚いていた。
「本当に―――――どれぐらい俺はシュバルツと手合わせできていないと思っているんだ!!!」
「…………!」
キョウジは知らず、椅子からずるっとずり落ちそうになる。
(あ~~~………でも、気持ちは分かるかも………)
弟の渾身の喚きに、不覚にも少し共感してしまうキョウジ。
自分だってそうだ。
もうずいぶん長いこと――――自分はシュバルツに雑用を押し付けたりご飯を作ってもらったり、代わりに仕事に行ってもらったりをしていないような気がする。
いい加減シュバルツに甘えたい。
ちょっとしたストレスが、割と限界のような気がしたキョウジも、「は~~~~~~………」と、盛大にため息を吐きながら、机の上にごん、と、頭をぶつけて突っ伏してしまう。
(こ、この兄弟は………!)
こうなってくると、少々面白くないのが東方不敗だ。
(確かにあ奴はキョウジのコピーで優秀な部類に入るかもしれんが、手合わせの相手ぐらいわしがいくらでもするし、少々の雑用ぐらいだったらわしもこなせるのに、いったい何が不満なんじゃ!? わしがシュバルツに劣るとでもいうのか!?)
「フン! 貴様の腕では龍の忍者に一発浴びせるどころか、返り討ちに会うのが落ちじゃろうよ!!」
東方不敗の苛立ちは、ドモンへの八つ当たりとなって表に出てくる。案の定、ドモンはすぐにこの挑発に乗ってきた。
「何おう!?」
ガタッと椅子を蹴倒すドモンを、東方不敗はさらに挑発してきた。
「悔しかったらまずは一発、このわしに当ててみろ!!」
ベロベロバーと、いい歳をした老人が、かなり大人げなくドモンをコケにするものだからたまらない。ドモンはそれに頭から突っ込んでいく。
「おのれ!! いくら師匠でもそれは許さん!! まずは貴様の顔面に、俺の拳をめいいっぱい叩き込んでやる!!」
「やれるものならやってみよ!! この馬鹿弟子がぁ!!」
「上等だ!! 表へ出ろ!!」
「フハハハハハ!! 返り討ちにしてくれるわぁ!!」
ものすごい勢いで、師弟が玄関から外へ出ていく。キョウジがやれやれ、と、ため息を吐いていると、開いた玄関のドアからレインが入ってきた。
「レイン」
少し驚くキョウジに、レインが多少苦笑しながら微笑みかける。
「いつものコース………でしょ?」
「あはははは……そうだね」
二人はそのまま、ダイニングで夕飯の準備を始めることにした。
「でも実際、ドモンももう限界なのよね……。シュバルツさん、まだ治らないの?」
ジャガイモの皮むきをしながら、レインがはあ、と、ため息を吐く。
「………う~ん……。もう少しだと、思うんだけどねぇ………?」
玉ねぎを薄切りにしながら、キョウジがつぶやく。どうやら、今夜の晩御飯はカレーに決定しているらしい。もっとも、作る量は半端なものではなく、コンロの上には「炊き出しか!!」と、突っ込みを入れたくなるような巨大な鍋が用意されていた。
「しかし……毎日マスターと手合わせをしているんだろう? それでもだめなのか?」
手を止めずにキョウジが問いかける。
「私にもよくわからないけれど……何か、微妙に違うみたいよ?」
レインも次のジャガイモの皮をむきながら答えた。
「そうなのか?」
「ええ。家に帰ってから唇を尖らせているもの。宥めるのも面倒くさいから、もうほっといているけど」
「ほっといているのか……」
その図が容易く浮かんでしまって、キョウジはもう苦笑するしかない。ためねぎを刻んでいるせいか、涙まで出てきた。
しかし、ドモンの気持ちも分かってしまう。実際自分も、もう限界に近い。
シュバルツとずいぶん長いこと話をしていないような気がする。
「話がしたい」
願いはそれだけだった。
変だな。
一人でいるのは平気だったはずなのに。
「あ~~………。玉ねぎが目に染みる……」
本気で泣きそうになっているのを悟られないように、キョウジは少し、道化を演じる。
こんな時でも、レインや皆がそばにいてくれて良かったと、キョウジは思った。
一人きりだと――――きっと、もっと深刻に落ち込んでしまっていた。
「さあ――――さっさと料理を作り上げてしまおう。ドモンたち、今日は何杯食べるかな?」
(やっぱり、キョウジさんも無理して笑っているわよね………)
レインは、キョウジが多少無理して明るく振る舞っていることに感づいていてしまう。だけど、それ以上キョウジに向かって踏み込めない自分がいることも、同時に感じていた。
キョウジは、私とドモンの仲がうまくいってほしいと願っている。
その願に、自分の存在が妨げになる、と、少しでも感じてしまったら、キョウジは私たちの前から姿を消してしまうだろう。そんなことをさせてはだめだとレインは思った。
だからレインも、キョウジが無理やり笑っていることに、気づかないふりをする。
「そうね……。ごはん、これで足りるかしら?」
一升炊きの炊飯器を見つめながら、レインもまた、シュバルツが早く元に戻ればいいのに、と、祈らずにはいられなかった。
4
「走れ!! アーサー!!」
それから数時間後。
ハヤブサは、某国の戦場の真っただ中にいた。ここが、彼の『任務』の場所だった。
現地のエージェントと軍隊の努力の甲斐あって、捕えられた人質たちの居場所を、奇跡的に突き止めることに成功していた。
逃走ルートを確保できるのはわずかな時間。その間に、速やかに人質たちを救出すること―――――。これが、今回ハヤブサが『龍の忍者』として請け負ったミッションだった。このわずかな時間を確保するために、数か月前から何人もの人間が命懸けで周到な準備をしてきたことをハヤブサは知っていた。だから、絶対にこの依頼は断れなかったし、やり遂げなければならない『仕事』だった。龍の忍者は単身で―――――刀一本で、敵のアジトへと乗り込んでいく。
隠密裏で迅速な彼の行動は、人質たちを一人、また一人と解放していった。
そして、最後の一人を救出しようとした時――――ついに、敵に見つかってしまったのである。
「はあああああっ!!」
だが見つけられたからと言って、怯むハヤブサではなかった。彼は龍剣をふるうと、強引に牢を破壊し、人質の最後の一人となった『アーサー』を引っ張り出す。
「逃げるぞ!!」
ハヤブサはアーサーの手を掴むと、そのまま走り出していた。
「リュウ!! 危険だ!! このまま俺を置いて逃げてくれ!!」
逃げる二人に襲い掛かる、銃弾の嵐。あちこちから、戦車が走ってくるのも見える。
アーサーは某国の軍の将校をしていた。某国は時折、『龍の忍者』としてのハヤブサと接触をし、『仕事』を依頼していた。その際に、アーサーが使いの者として接触をしたり、時に任務に赴くハヤブサのサポートをしたりしていたので、互いに知らぬ仲ではなかったのである。
「何を言うんだ!! アーサー!! 立てッ!! そして、走れ!!」
アーサーは屈強な戦士でもあるが、過酷な人質生活の影響で、かなり衰弱もしていた。しかしハヤブサは、彼を叱咤激励しながら手を伸ばした。
「今お前は死ねないんだろう!? 娘に会うのだろう!?」
「―――――!」
「必ず助ける!! だからお前も、あきらめるな!!」
「しかし………!」
二人のすぐ近くに砲弾が撃ち込まれる。行く手に戦車が立ち塞がっていた。
「りゃあああああ―――――ッ!!」
しかしハヤブサは、戦車に怯むどころか裂帛の気合とともに突っ込んでいく。
鋼鉄の戦車に、刀一本で挑む龍の忍者。一見無謀な勝負だが、その勝敗はあっさりと決まった。
ガキッ!!
派手な金属音が響くとともに、戦車から黒い影が飛びのく。
数秒後、轟音とともに爆発したのは、その戦車の方であったのだ。
「行くぞ!」
龍の忍者はアーサーの手を取ると、再び走り出していた。
龍の忍者の頭の中には、逃走ルートが完全に入っている。
追っ手を撃退しながら、二人は確実に、脱出地点へと向かっていた。
「ありがとう。リュウ……」
道中でぽつりと、アーサーに言われる。
「俺を助けるために、わざわざ………」
「礼を言うのなら、お前を助けるために動いてくれた同僚たちと、エージェントと、俺を雇うために金を出してくれた政府に言うんだな」
「…………!」
「それを言うためにも、お前は生き延びねばならん。俺がこうしてここにいるのも、皆の意志が働いた結果なのだから」
「……………」
黙り込むアーサーの手を引き、ハヤブサは走る。
脱出用の空輸機が待ち構えている地点まで、あと少しと言うところまで迫った。
「いたぞ!!」
怒号とともに、再び降り注ぐ銃弾の嵐。
「ちぃっ!!」
ハヤブサはアーサーを建物の陰にかくまうと、追っ手の方に立ち向かっていく。疾走する黒い影は、屋根の上から銃を乱射していた追っ手の一団を、あっという間に駆逐していた。そのまま跳躍した龍の忍者は、路地からアーサーを狙っていた一団のど真ん中に、上空から突っ込んでいく。
「うわっ!」
「おのれ!!」
不意を突かれた追っ手の兵士の数名が、ハヤブサに向かって銃を向ける。
「馬鹿っ!! 撃つな!!」
隊長格の男がとっさに指示を出すが、間に合わなかった。狭い路地で発射された銃弾は、同志討ちの悲劇をそこに巻き起こす。
「覇――――――ッ!!」
銃弾の嵐の中を、裂帛の気合とともに走り抜ける黒い影。戦いの喧騒が静寂に包まれるまで、そんなに時間はかからなかった。
「さすがだな、リュウ!」
追っ手を駆逐し、こちらに向かって走ってくるハヤブサに向かって、アーサーは素直に賛辞を送る。
「行くぞ!」
ハヤブサはその手を取って、再び走り出していた。
町中から、少し開けた郊外にたどり着く。
目の前には、脱出用の空輸艇が止まっていた。
「アーサー殿! ハヤブサ殿! お早く!!」
中から同じように捕えられ、ハヤブサに助けられたアーサーの部下たちが口々に叫んでいる。
「今行く!!」
アーサーもそれに笑顔で応え、空輸艇に向かって走り出す。だが、次の瞬間、艇の中から叫んでいた部下たちの、顔色が変わった。
「追手が――――!」
「――――!」
それに気づいたハヤブサは、アーサーの背を艇に向かって押した。
「リュウ!?」
驚くアーサーに、ハヤブサは追っ手を見据えながら叫ぶ。
「アーサー!! 走れ!! 俺に構わず艇に乗れ!!」
「な―――――!」
「俺の『任務』は『お前』をここから脱出させることだ!! ここで死なれたら困る!!」
「…………!」
「行け!! 空輸艇が破壊されたら何にもならん!!」
ハヤブサの気迫に、一瞬、気圧されるアーサー。しかし、かろうじて彼は問い返していた。
「リュウ、お前はどうするんだ……!?」
「俺のことなら心配いらん。どうにでもなる」
嘘だ。
本当はここから脱出する安全な経路は、この空輸艇しかない。
だが―――――だからこそ、ハヤブサはアーサーをこの空輸艇に乗せることを優先した。
「行け、アーサー! ここでの躊躇は、あそこにいる部下たちの命を奪う!」
「……………!」
「行け!! 早く!!」
苦い顔をしながらこちらを見ていたアーサーであるが、やがて、ぎり、と、唇をかみしめ、こぶしを握り締めた。
「分かった……! 幸運を祈る!!」
その言葉を残して、アーサーは空輸艇に向かって走り出す。ハヤブサはそれを背に感じながら、追っ手に向かって走り出した。
自分に向かって、乱射される銃。だがハヤブサは、それには特に頓着しなかった。
それよりも今―――――自分が優先的に討たねばならない者は。
龍の忍者の鋭い眼光が戦場を走り、その対象を見つけた。空輸艇に向かってロケットランチャーを構えている者3人。後――――戦車一台。
龍の忍者は無言で大地を蹴る。
凄まじいまでの跳躍力。それは、対象者の一人目の命を、あっという間に屠らせていた。
「ああ!!」
「許さん!! 撃てッ!! 撃て―――――ッ!!」
怒りに燃え、攻撃してくる兵士たちに向かって、ハヤブサは殺した兵の遺骸を投げつける。兵士たちがそれに怯んだ隙にその間を走り抜けていった。
ハヤブサは、二人目を目指す。その間に、アーサーは空輸艇にたどり着いていた。
「艇を出してくれ!!」
アーサーは艇に乗り込みざまに叫ぶ。
「しかし……! まだハヤブサ殿が――――!」
「あいつは、自力で何とかする!!」
驚く部下たちに向かって、アーサーはなおも叫んだ。
「あいつは、伝説の『龍の忍者』だ! この程度の危地など、何度も乗り越えてきた男だ!!」
「…………!」
「それよりも――――今、我らがここに留まり続ける方が、却ってあいつの足を引っ張ってしまう!! あいつは何を置いても、この空輸艇を守り続けようとしてしまうぞ!! 文字通り、『足手まとい』になってしまうんだ!!」
「――――!!」
「それよりも今、我らができることは、できうる限りの安全を確保し、戦力を整えたうえで、改めて龍の忍者の援護に回るべきなのだ!! 違うか!?」
アーサーの問いかけに、皆がはっと息を呑む。それを見て、アーサーは改めて皆に声をかけた。
「艇を出せ!! そして、援護を要請するんだ!!」
「了解(ラジャー)!!」
返事とともに、パイロットは空輸艇を発進させる操作をする。ドアが閉まると同時に、艇が上昇しだした。
艇の発進を目の端でとらえながら、龍の忍者はロケット砲を構える二人目の首を刎ねる。
(次は――――!?)
そこから更に離れたところにロケット砲を構える兵士を発見する。彼は既に、発射体勢に入っていた。
「チィッ!!」
今から跳んでも走っても、もうそこには間に合わない。
ならば、と、龍の忍者は弓矢を取り出し、二本の矢を弓につがえた。
極限まで集中した、龍の忍者が狙ったのは―――――
軽快な弦音を残して、二本の矢が同時に放たれる。それと同時に、兵士も空輸艇に向かってロケット砲を発射していた。
一本は、ロケット砲を放った男に当たる。
そして、もう一本は―――――
空輸艇の近くで、ロケット砲が爆ぜた。爆風で、艇内が振動に襲われる。
「どうした!?」
問うアーサーに、副機長が状況を報告する。
「命中コースに飛来してきたロケット砲が、爆発した模様です!!」
「被害状況は!?」
パイロットの問いかけに、副機長は計器をすばやく確認して、叫んだ。
「異常なし!! 飛べます!!」
その報告に、艇内から安堵の息が一斉に漏れる。
「良かった……!」
「神のご加護だ………!」
皆が口々にそう言う中で、ただ一人アーサーだけが、龍の忍者が守ってくれたのだなと悟っていた。
ハヤブサは矢を放つと同時に、戦車の方に向かって走り出していた。
あれさえ倒せば、ここにいる者たちの空輸艇への攻撃は、無力化できる。そう確信した龍の忍者は、なお一層、足の踏み込みを強くした。
「うおおおおおおおおおお―――――ッ!!」
獣の如き咆哮とともに、龍の忍者の『神速』が戦車に迫る。
「狙われているぞ!!」
「やらせるか!! 撃てッ!! 撃て―――――ッ!!」
兵士たちがハヤブサに向かって発砲する。
しかし、当たらない。当てることができない。
『分かっていても、当てられない』という現実を、兵士たちは認めたくはなかった。
「真正面!! 目標(ターゲット)が来ます!!」
もちろん、狙われていると分かっている戦車部隊も、応戦する体制に入る。ホロスコープの中にハヤブサの姿を捉えた射ち手は、即座に声を上げていた。
「構わん!! 撃てぇい!!」
隊長は、迷わず指示を出した。こういう場合、躊躇ってはいけないことを、彼は既に知っていた。
「はっ!!」
間髪入れず、兵士は引き金(トリガー)を引く。よく整備された戦車は、滞りなく砲弾を発射した。
次の瞬間ホロスコープの中で砲弾が爆ぜ、目標は肉塊になったと、誰もが確信を持った。
しかし。
砲弾がさく裂した次の瞬間、ホロスコープから見える外の世界が暗転する。次いで、戦車内に響き渡る、耳障りな金属音。
「な、何だぁ!?」
「何が起きた!?」
皆が呆然とする中、砲台長は見てしまう。戦車を切り裂く、日本刀の煌きを。
「だ!! 脱出!! 脱出しろ!!」
隊長の指示にしたがって、兵士たちは蜘蛛の子を散らすように戦車から脱出する。その次の瞬間、戦車が轟音とともに大爆発を起こした。
(よし………!)
これで、この場のミッションを達成したと、ハヤブサは確信する。刹那、張り詰めていた『気』が、僅かに緩んだ。
「う………!」
一瞬、ハヤブサを襲う、眩暈。体勢が、僅かに崩れる。その一分の隙に、銃弾がハヤブサの左肩を抉った。
「うぐッ!!」
衝撃でバランスを崩し、もんどりを打って倒れる龍の忍者。左肩に、焼けつくような痛みが走った。
「仕留めだぞ!!」
それを見た兵士たちから、歓声が上がる。
「く…………!」
ハヤブサはすぐに体勢を立て直す。ここで立ち上がらないのは、生きる意志を放棄するのと同義だからだ。
「気をつけろ!! まだ息があるぞ!!」
「おのれ……! 仲間や人質を、駄目にしやがって……!」
「なぶり殺しだ!! 八つ裂きにしてやる!!」
怒りに燃える兵士たちが、銃を構えながらじりじりと距離を詰めてきた。
「……………」
少し、絶望的な状況に、ハヤブサは僅かに苦笑する。そんな彼の耳元の通信機に、クライアントから連絡が入った。
「リュウ・ハヤブサ。今回の『依頼』の『成果』、確かに受け取った」
その声は淡々と、インカム越しに用件を伝えてくる。
「ご苦労だった。報酬はいつもの手段で送る」
幸運を祈る、と、無機質に言われて、その通信は切れた。
(そうか……。アーサーは、無事に脱出できたのだな……。良かった……)
ハヤブサは、少しの安堵を覚える。そして今度は、自分の番だと思った。
「死ぬことなんて許さないよ!! ハヤブサ!! 貴方が死ねばシュバルツがどれだけ悲しんで泣くか―――――貴方は分かっているのか!?」
怒りに燃えるキョウジの言葉が、自分の内側に響く。
(ああ、そうだな)
ハヤブサは刀を構えながら、想った。
帰らないと。
愛おしいヒトのもとへ、俺は帰ってやらないと。
彼のヒトをまた―――――孤独の深淵に、独り、追いやるわけにはいかないのだから。
(シュバルツ……)
不思議だ。
こんな時ですら、大切なヒトのことを想うと、心が凪いだ。
生きる。
生きよう。
あがけ。
足掻くんだ。
あきらめて、生きることを放棄するのは簡単だ。
だが足掻けば―――――
それをして、100%助かるなどと、甘い夢は見ない。
しかし、それをしなければ、生きる道が見えてこないのも、また事実なのだから。
大丈夫だ。
例え、どうなろうとも
『死』の運命が、自分の目の前に押し寄せて来ようとも―――――
彼のヒトを想い続ける限り俺は
死ぬ瞬間まで、たぶん、幸せだと思った。
右手一本で、刀を正眼に構える。
左肩を撃ち抜かれたため、左腕を持ち上げるのは困難だった。ただ、指先は動くから、骨に異常はないのだろうと、悟る。
止血もしたいが今は―――――ここを切り抜けるのが、先だと思った。
「……………」
肩で息をしながらも立ち上がり、刀を構えた龍の忍者の姿に、兵士たちから嘲笑が漏れた。
「見ろよ!! こいつ、まだ戦う気でいるぜ!!」
「この距離で、これだけの銃を構えた俺たちを相手に、逃げ切れるとでも思っているのか!?」
「刃向かって来るのなら丁度いい!! 生まれてきたことを後悔するぐらい―――――なぶり殺しの目に遭わせてやる!!」
残虐性を隠しもしない、下卑た笑いが辺りを包む。ハヤブサはそれには頓着せず、ただ―――――己に『気合』を入れた。
「叭ああああああああっ!!」
「…………!」
瞬間、ハヤブサの気迫に圧される兵士たち。だがそこは歴戦の猛者――――すぐに、己のやるべきことを思い出していた。
「撃てっ!!」
兵士たちは皆、迷わず引き金(トリガー)を引く。その刹那、ハヤブサの姿が視界から、消えた。
「――――!? ギャッ!!」
あっという間に二人の兵士が、龍剣で喉を切り裂かれて倒れる。その間を、黒い影が走り抜けていた。
「おのれ!! 逃がすな!! 追えっ!! 追え―――――ッ!!」
追い始める兵士たちに、更なる声が追いかけてきた。
「あいつの身体の部位には、賞金をつけてやるぞ!! 指一本、目玉一つで報奨は思いのままだ!!」
その言葉に、兵士たちから「うおおおおおっ!!」と、地響きのような歓声が上がる。兵士たちは皆、血相を変えてハヤブサを追いかけ始めた。
「こちらの兵士や戦車を駄目にしてくれた上に、人質まで奪い返されたんだ……。あの男は目の前で八つ裂きにしても、足りんぐらいだがな………」
隊長格の男は、鋭い眼光をぎらつかせながら、舌なめずりをしていた。
「それに、この街は俺たちの『庭』のようなものだ。ここで、俺たちから逃げられるわけもない……。住人達も、俺たちの味方だしな………!」
フフフフ、と、口の中で笑う隊長の目の前で、町の一角から爆発による煙が、立ち上がっていた。
「く………!」
狭い路地を、ハヤブサは走り続ける。
肩から流れ続ける血は、左腕をすでに赤く染め上げていた。そして、身体に取り込んでいた『毒素』も相俟って、ハヤブサの体力は、徐々にだが奪われていきつつあった。
眩暈に襲われる回数が、頻回になってくる。それでもハヤブサは、襲い来る兵士たちを何とか撃退していた。だが欲に眩んだ兵士たちは、あきらめずにハヤブサを猛追してくる。執拗に攻撃を加え、身体の一部でももぎ取ろうと手を伸ばしてきていた。
「う………!」
よろめいたハヤブサの身体が、路地の塀に当たる。そこに、複数の兵士たちが容赦なく殺到してきた。
「報奨金!! もらったああああ!!」
「死ねえええい!!」
喜々とした殺意―――――ハヤブサは一瞬、対応が遅れた。
(しまった―――――!)
せめて急所は、足は庇おうと、ハヤブサは咄嗟に体を捻る。だが、いくつかの攻撃が、自分の身体に当たることは避けられないと悟った。
「――――ッ!」
ハヤブサは歯を食いしばり、来るべき衝撃に備える。
しかし、それらの攻撃がハヤブサの身体に当たることは、無かった。
何故なら―――――
信じられぬことだが、『それ』は自分の『影』から出てきた。
ガキガキガキッ!! と、派手な金属音と火花を散らしながら、『それ』は、自分に向かってきた攻撃をすべて防ぎきる。
「な……………!」
息を呑む自分の目の前で、翻る革のロングコート。
(嘘………だろう……!?)
ハヤブサは、心臓が止まるかというほどに驚いていた。
何故なら、自分を庇うように立つ、その後ろ姿は
自分が死ぬほど愛おしいと、会いたいと願っていた『そのヒト』であったのだから。
「シュバルツ!?」
知らず、素っ頓狂な声を上げるハヤブサに対して、しかしシュバルツは振り向きもしなかった。
「ハヤブサ(ご主人様)を、守る。それが―――――私の役目!!」
彼は一声、そう吠えると、ハヤブサに向かって殺到して来る兵士たちに向かって、立ち向かっていっていた。
(え………!? これは、どういうことだ!? どういうことなのだ!?)
愛おしいヒトの戦う後姿を見ながら、ハヤブサはしばし混乱する。
自分は確か、シュバルツをキョウジに預けてきたはずだ。
それなのになぜ―――――彼のヒトは、今ここにいるのだ? いったい何が――――
「…………!」
ここでハヤブサは、一つの可能性に行き当たる。
(まさか『術』か!? 『術』の力で、シュバルツが引っ張られてきたのか!?)
術の中にはごく稀に、術者とかけられた者が一定以上の距離を離れることができずに、かけられた者が術者についてきてしまうという類のものがある、と、聞いたことがあった。
まさか――――『腐墨の術』が、これに該当する、というのであろうか。
それにしても、シュバルツがそばについてきていることなど、自分は全然気が付かなかった。いつから彼は、自分のそばに潜んでいたのだろう。
常々、気配を消すのがうまいやつだとは思っていたのだが―――――
なんということだ。
自分は、シュバルツにたやすく寝首を掻かれる可能性も、あるのではないだろうか。
(まあ、シュバルツになら、命を取られてもいいがな………)
少し呑気にそんなことを考えかけて、ハヤブサははっと我に返った。
今は、そんなことを考えている場合ではない。
それよりも―――――
「うおおおおおおおッ!!」
獣のような雄たけびを上げながら、また敵を粉砕していくシュバルツ。
それを見ながらハヤブサは、少し眉を顰める。
おかしい。
シュバルツは、こんな戦い方をする奴だっただろうか。
「『腐墨の術』というのは存在自体が伝説めいた物であるゆえ、その術の効き方もいろいろと伝えられておるが、いずれにせよ術をかけられた者は、術者にぴったりと寄り添うようになっておる」
ドモンがレインに連れられて家に帰っていくのを確認してから、東方不敗はキョウジに話し始めていた。キョウジに「術についてもっと詳しく教えてくれ」と、乞われた故だった。
「それは、何故ですか?」
コーヒーカップを片手にキョウジは問い返す。それに対して、東方不敗はにやりと笑みを浮かべた。
「決まっておる。術者を守るためよ」
「…………!」
「術者が命の危険に曝された時――――術をかけられた者は、なりふり構わず術者を守ろうとする。自分の身の危険も顧みずにな………。そうしてその者を盾としながら、術者は己が身の安全を図るのだ」
「そんな…………!」
「それで術をかけられた者が死んでしまえば、術者は、また次の対象者を探す……。文字通り、人を傀儡化して消耗品扱いにする―――――将に、『邪法』じゃな」
「……………ッ!」
キョウジは、コーヒーカップを両手で抱え込むように握りしめ、ぎり、と、歯を食いしばっていた。術をかけられた者は、ただ術者のためにすべてを捧げ、そしてそのまま道具のように消耗され、やがて命をも落としていく。
なんと非道な術なのだろう。
その『術』のせいで犠牲になった人々のことを考えると、キョウジはいたたまれなくなった。
「おそらくシュバルツは、ハヤブサを守るためについていったのであろうが――――」
「シュバルツ………」
キョウジはしばらく無言で、カップの中のコーヒーがゆらゆら揺れるのを見つめていたが、やがて、小さな笑みをその面に浮かべると、ゆっくりとコーヒーを飲み始めた。
「キョウジ、何がおかしい?」
笑みを浮かべるキョウジの真意を測りかねて、東方不敗はキョウジを問いただす。すると、彼は穏やかに答え始めた。
「いえ………『気の毒だな』と、思って……」
「気の毒? 何がじゃ?」
「いま――――ハヤブサに攻撃を仕掛けている、『敵勢力』が」
「…………?」
怪訝さに眉を顰める東方不敗に、キョウジは少しいたずらっぽい笑みを見せる。
「マスターも、覚えておいてください。ハヤブサに勝負を挑もうとするのなら、絶対に、シュバルツに手を出してはダメです」
「何故じゃ?」
「シュバルツが正しく、ハヤブサにとっての『龍の逆鱗』に当たるからですよ」
「――――!」
少し驚く東方不敗に、キョウジは穏やかに答え続ける。
そう。
『逆鱗』とは、龍の鱗で絶対に触れてはならぬもの。それに不用意に触れてしまった者は、激高した龍によって、必ず殺されてしまうという言い伝えがある。
「シュバルツがハヤブサの目の前で、自分を犠牲にするような戦い方をすることを、ハヤブサが許すはずもない。下手をしたら、龍の忍者としての彼が普段眠らせている力を、呼び覚ましてしまうことになりかねないんです」
それは、下手をしたら街を一つ、消してしまうことにつながりかねません、と、笑うキョウジに、東方不敗は「ほう……」と、声を上げた。
「それは逆に、見てみたい気もするがな」
にやりと笑う東方不敗に、「それはやめてください」と、キョウジは肩をすくめていた。
シュバルツは、ハヤブサの手を取って走る。
立ちふさがる者、追ってくる者は容赦なく粉砕する。
「シュバルツ……!」
「……………」
ハヤブサが呼び掛けても、反応しないシュバルツ。時折ぶつぶつと「ハヤブサ(ご主人様)をお守りするために――――」と、抑揚のない声で呟いていた。
「シュバルツ……ッ!」
ハヤブサはぎり、と、唇をかみしめていた。
違う。
ここにいるのはシュバルツであっても『シュバルツ』ではない。
シュバルツの形をした、別の『何か』だった。
「死ねえええい!!」
兵士が、また、発砲しながらこちらに向かってくる。シュバルツは無言で自分の身体の後ろにハヤブサを庇うと、兵士を剣で容赦なく袈裟懸け斬りにしていた。頽れた兵の身体をグシャ、と、踏みつけて、シュバルツはハヤブサの手を引いて走っていく。
(……………!)
ハヤブサは、いたたまれなくなった。
違う――――
シュバルツは
シュバルツは絶対に、こんな戦い方をしないのに。
シュバルツはおよそ、慈悲の塊のような男だった。戦う相手には、必ず敬意を払った。
その刀を振り下ろす瞬間すら、相手を思いやっていた。
こんな風に―――――
「うおおおおおおっ!!」
目の前に来た兵士の首を一瞬にして刎ね飛ばす。
首を失ってよろめく遺骸を、突き飛ばして前に進む。
敵を邪魔な『障害物』程度にしか見ていない―――――そんな戦い方をする男ではなかったのに。
駄目だ。
いくら『術』によって操られているとはいえ
シュバルツにこれ以上、こんな戦い方をさせてはいけない――――!
「ハヤブサ(ご主人様)!!」
シュバルツは自分の身が傷つくのもかまわずに、こちらを庇うことを最優先にする。
彼の身体は、既に傷だらけだった。普通ならば、こんな風に走ったり戦ったりすることすら、もう困難になるほどに。
それなのにシュバルツは、まるでそんなことには頓着もしない風に戦っている。
きっとこれも術のせいだ。
術をかけられた者は、きっと、術者の安全を最優先にしてしまうのだろう。
そして、身も心も消費され切った傀儡が死んでしまえば、術者はまた、次の犠牲者を探して―――――
まるで、道具か何かのように。
(くそ………ッ!)
腹の底からふつふつと、御しがたい怒りが湧き上がってくる。
シュバルツは、消費される『モノ』などではない。
俺の得難い、この世に二人といない、『大切なヒト』だ。
それを―――――
その時、道を走る二人の前方に、何者かが飛び出してくる。シュバルツはまたそれを、無造作に斬って捨てようとした。
だが『それ』が何かということに気が付いた瞬間、ハヤブサは思わず大声で叫んでいた。
「待てっ!! シュバルツ!! 『それ』は斬るな!!」
「―――――!」
自分の声がシュバルツに届いたのか、彼の身体がビクッ! と反応する。
対象に向かって振り下ろされようとしていた刀は軌道を変え、それを掠めて止まった。風圧で対象者の身体を覆っていたブーケが捲れ、まだあどけなさを残した少女の顔が、その姿を現す。
「あ…………?」
「……………」
少女とシュバルツが、しばし無言で見つめあう。奇妙な沈黙が、その場を支配した。
「シュバルツ……! 分かるか……? それは、斬るな……!」
ハヤブサは、シュバルツに余計な刺激を与えぬよう細心の注意を払いながら、そろそろと声をかける。
斬らせては駄目だと思った。
例え『術』に操られた状態であったとしても、シュバルツに女、子供を斬らせては駄目だと、強く思った。
そんなことをさせてしまったら、たとえ正気に戻った後でも、彼のヒトが深く傷つくのがハヤブサには分かってしまうから。
だから、絶対に許してはいけないと思った。
何が何でも、止めねばならないのだ。
「あ…………!」
対してシュバルツは、少女と己が手にしている刀を見比べながら、茫然としている。
「シュバルツ?」
ハヤブサは、軽く違和感を覚えながらもシュバルツに声をかけていた。
シュバルツの様子がおかしい。
まさか―――――
「シュバルツ? 大丈夫か?」
「ハヤブサ……!」
「……………!」
愛おしいヒトが振り返って、自分の名を呼ぶ。
その響きが『ご主人様』と同じではないと気付いて、ハヤブサは息を呑んでいた。
その瞳には、『生気』が宿っている。
ガラス玉ではない、『生気』の光が―――――
「シュバルツ……!」
まさか、と、思いながらも、もう一度、ハヤブサはシュバルツに声をかける。
「シュバルツ……。わかるか……? 『俺』が分かるか……?」
「ハヤブサ……!」
呆然としている、愛おしいヒト。刀を持つその手が、小さく震えていた。
「私は………何を、していた……? 何を、しようと、していた………?」
「シュバルツ! 大丈夫だ!!」
ハヤブサは咄嗟に叫んでいた。
「落ち着け、シュバルツ! お前は『まだ』何もしていない!! 何もしていないんだ!!」
そう。
シュバルツが今まで斬り捨てていたのは、武器を持ってこちらを倒そうとしていた戦闘員だけ。非戦闘員には、断じて害を及ぼしてなどいなかった。
だからこそ、悟らせてはいけない、と、思った。
シュバルツが今―――――目の前の少女を、斬ろうとしていたなどと言うことを。
「しかし………!」
シュバルツはまだ尚も、茫然と自分の手に持つ刀と少女とを見比べている。その時、それまで沈黙を守っていた少女が、ピクリ、と、動いた。
ふらり、と、少女がこちらに向かった歩を進めてくる。しばらく呆然とそれを見守っていたシュバルツであるが、いきなり、その顔色が変わった。
「―――――!」
ダッ! と、少女に向かって飛びかかるように突進する。
「シュバルツ!?」
シュバルツの唐突すぎる行動に、瞬間ハヤブサは面食らう。だがハヤブサは、すぐにシュバルツの行動の意味を『理解』した。シュバルツは少女の身体から『何か』を強引にもぎ取ると、それを空高く放り投げる。それと同時に少女の身体を自分の腹の下に守るように、その上に覆いかぶさった。
「…………!」
ハヤブサもそれが『何』か分かったので、とっさにその身を伏せる。その刹那、放り投げられた『物』が、『ドンッ!!』と、派手な轟音を立てて爆ぜた。少女はこちらに、自爆攻撃を仕掛けていたのだ。
「シュバルツ!!」
爆発が収まるのを待ってから、ハヤブサはシュバルツの身を案じて立ち上がる。シュバルツは、少女の身体を守るように、瓦礫の中にうずくまっていた。
「シュバルツ!! 大丈夫か!?」
ハヤブサは、少女の上からシュバルツを強引にもぎ取るように引き起こす。
「う………! あ………! あ………ッ!」
案の定、シュバルツは少女の身体にその身を触れさせた所為で、凄まじい激痛に襲われていた。それでも彼は、少女を守ろうとしていた。
「馬鹿野郎……! 無茶をする……!」
ハヤブサは思わず、ぎゅっとシュバルツの身体を抱きしめていた。
そしてシュバルツが、あの瞬間確かに『正気』に戻っていたのだとハヤブサは確信した。
どんな状況でも自分がどうなろうとも――――彼は必ず、自分より弱い者を守ろうとする。
ああ、それでこそ、シュバルツだ。
やはり死ぬほど―――――愛おしい。
よくぞ守った。
よくぞ少女を、守り通した。
「ハヤブサ……!」
涙で瞳を潤ませたシュバルツが、腕の中で息を喘がせながらこちらを見上げてくる。
「大丈夫か?」
ハヤブサは、できるだけ己の身をシュバルツに密着させながら問いかけた。こうして彼の身体に触れていれば、彼の身体を襲っている痛みを、和らげることができるのだから。
嬉しい。
愛おしいヒトを、癒すことができる事実が。
ハヤブサの面に、自然と柔らかい笑みが浮かんでいた。
「………………」
しばし、ハヤブサの腕の中で、小さく震えながらその身を摺り寄せるようにしていたシュバルツであるが、唐突に、カッとその目を見開いた。いきなり、ドンッ! と、ハヤブサの身体を突き飛ばす。
「シュバルツ!?」
完全に不意を突かれたハヤブサは、後ろに尻餅をついてしまう。
その目の前でシュバルツは、こちらに近づいてきていたフードを被ったもう一人の女性につかみかかっていた。彼はハヤブサから女性を離しながら、懸命に女性から何かをもぎ取ろうとして―――――
ドゴォッ!!
激しい轟音とともに二人のいた場所が爆ぜた。もう一人の女性が、自爆攻撃を仕掛けてきていたのだ。
「……………!」
爆風の中、シュバルツが自分を守るように立っている背中が見える。ハヤブサはシュバルツを守りたいと願う。だが、どうすることもできぬまま、自身もまた、爆風と轟音の嵐の中に、巻き込まれていった―――――
やがて、爆発が収まり、あたりが静寂に包まれる。
「う……………!」
瓦礫の中からハヤブサが身を起こした時には、周りに生きて動いているのは、最初に自爆攻撃を仕掛けてきた少女と、自分しかいなかった。少女は爆心地を見ながら、茫然としている。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは、瓦礫の中に愛おしいヒトの姿を求める。爆心地には、黒焦げでバラバラになっている『遺骸』らしきものがあった。
「あ………あ…………」
バラバラになって、焼け焦げた『部品』
『肉片』
『千切れ飛んだ腕』―――――
(落ち着け………!)
ハヤブサは、シュバルツの『手』らしきものを己の手の中に握りこみながら、唇を噛みしめていた。
たとえこの状態でも、シュバルツは『死んでなどいない』のだ。彼の身体を構成している『DG細胞』の『自己再生能力』が、彼を必ず、甦らせてくれるのだから。
それでも
それでも―――――
「…………ッ!」
何故こうも、御しがたい『怒り』が、自分の中からふつふつと、湧き上がってきてしまうのだろうか。
「やったか!?」
兵士たちが爆発後にわらわらとやってくる。そして、遺骸の一部を抱えて呆然としているハヤブサと、そのそばでうずくまるように座り込んでいる少女の姿を見つけた。
「生きているじゃねーか!!」
「いや、でもあれだけの爆発だ。無事では済んでいないだろう」
「こいつも……! なんで生きているんだよ!! きっちりと自爆しやがれこの役立たず!!」
兵士の一人が、座り込んでいる少女に向かって、無造作に発砲する。タン!! と、乾いた銃声が響くと同時に、その少女の命はあっさりと奪われていた。
「――――――!!」
その瞬間、ハヤブサの中で、「ブチッ!!」と、何かが切れた音がする。当然そんなことに気付くはずもない兵士たちが、彼の周りを取り囲みだした。
「さあ! 観念しやがれ!!」
「『遺骸』の一部でも、懸賞金が付くんだよな……。本体丸ごとだとどれぐらいだ?」
「おめぇ、独り占めする気か!? そんなことは許さねぇぞ!!」
勝ち誇った嘲笑と殺意がハヤブサを取り囲む。
だが――――本当ならばここで、この兵士たちはなりふり構わず逃げるべきだったのだ。何故なら次の瞬間、彼らは本当に――――『地獄』を見ることになったのだから。
突如として、天地をつんざくような咆哮が、あたりに響き渡る。
「なんだ!? 何が――――」
そう口走った兵士の首が、いきなり宙を舞う。
「!?」
何が起こったのかわからず戸惑う兵士たちに、襲い掛かってくる黒い影。
結局彼らはそのまま自分の身に何が起こったのか『理解』する暇もないまま、自身の生命を終えていったのである。
怒りに燃える龍の忍者の攻撃は、そこで収まらなかった。
実際、ハヤブサの中ではすべてのことが吹き飛んでいた。
積み上げてきた教養も
礼儀作法も
その倫理観も、道徳心も、義侠心すらも―――――
この度し難い怒りの前では、すべてが無意味だった。
火の玉と化した、龍が駆ける。
その巨大な熱は、目に映る全ての物を飲み込み、駆逐していく。
そして―――――
「リュウ……! リュウ………! 聞こえるか!?」
インカムから呼びかける声に、ハヤブサの『理性』が彼に戻ってきた時――――彼の手には、その地区を支配していた組織の幹部の首が、握られていた。
「………………」
ひどく、乱れる呼吸。インカムの声にハヤブサが答えかねていると、声の主はハヤブサの事情を少し察したのか、返答を要求せずに言葉をつづけた。アーサーからの通信だった。
「今から5分後に、我々はY地点に向かう。そこで、5分待機する」
「………………」
「申し訳ないが、それが我々の差し出せる、精一杯の救助の手だ。どうか、時間内にここに来てほしい」
幸運を祈る――――と、言い置いて、その通信は切れた。
(Y地点………あそこか………)
ハヤブサは一つ大きく息を吐くと、ゆっくりと踵を返し、歩き出していた。
あちこちに傷を負っていたが、歩行に支障が出る程度の物はない。特に頓着するでもなく、ハヤブサは歩き続けた。
道中で、シュバルツが『爆死』した地点にたどり着く。
瓦礫だらけの、焼け焦げた場所―――――だが、よく目を凝らしてみると、そこに一人の『人間』が横たわっているのが見える。
その人間は、シュバルツだった。バラバラに砕け散ったはずのシュバルツの身体が今、元の形に形成されつつあった。
「……………」
ハヤブサはその体を仰向けに寝かせて、彼の胸に自身の耳を当てる。しかし、まだ内部の『駆動音』は聞こえてはこなかった。蘇生にまでは至っていないのだと悟る。
(シュバルツ………)
ハヤブサは、近くの崩れた家の中からシーツを引っ張り出し、シュバルツの身体をくるむ。それを抱きかかえて立ち上がると、再び、目的地に向かって歩き出していた。
目的のY地点につくと、そこにはすでに空輸艇が待ち構えていた。ハヤブサが近づいていくとドアが開き、中からアーサーが姿を現す。
「リュウ!! 待ちかねたぞ!!」
叫ぶアーサーにハヤブサは手を挙げて答えると、彼もまた、飛行艇に乗り込んでいった。
「リュウ……! 相変わらず、無茶をする奴だな……! 脱出の手段がこの空輸艇しかないと、どうしてもっと早く教えてくれなかったんだ……!」
艇に乗るなり、アーサーの揶揄ともいえる言葉が飛んでくる。
アーサーは助け出された後でその事実を知り、上層部に掛け合って、再び空輸艇をこの地に来させていたのだ。
「仕方があるまい。今回の任務の最優先事項は、お前の奪還だったのだから」
ハヤブサはそれを振り払うように口を開いた。
そう。頼まれた依頼は『アーサーの奪還』
だから、それ以外の人質たちは無視しても良かったのだが―――――
このアーサーという律義な男は、自分よりも部下の命を優先することを、ハヤブサは知っていた。
だから、アーサーを助けるために、他に人質になっていたアーサーの部下たちも、共に救出したのだ。そうでなければ、「私は絶対に逃げない!」と、駄々をこねられていたことだろう。
「ハヤブサ殿、その手荷物は?」
アーサーとともに空輸艇に乗ってきた武装した兵士が、ハヤブサが持っている物を問うてくる。
「ああ………」
その問いに、ハヤブサはまず、右手に持っている白い布で包まれた、小さな荷物の方を、兵士の方に差し出した。
「まず、これから渡しておこう。あとで改めて首実検をしてもらうが、この地区を実効支配していた過激派組織の幹部の一人の『首』だ」
「………………!」
あまりにも意想外な、物騒なものを渡されて、兵士は思わず息を呑む。持っている『首』を、取り落としそうになって慌てた。
「流石だな! 龍の忍者! また一つ、お前の『伝説』が上書きされたわけだ」
対してアーサーは、心底感心したような眼差しをこちらに向けながら、ヒュウ、と、口笛を吹いている。
(別に好きで、『伝説』を上書きしているわけではない)
そんなアーサーを、ハヤブサは少し醒めた眼差しで見ていた。正直、この幹部を討ち取った時の自分は、凄まじい怒りの乱流に飲まれていただけだ。その間、どうやって戦ったのか、どうやってこの幹部を討ち取ったのかも、よく覚えてはいない。
この為体(ていたらく)で『伝説』などと謳われても、片腹痛いだけだと思うのだが。
「で、では……そのもう一つの大きな荷物は………?」
恐る恐るといった案配で問いかけて来る兵士に、ハヤブサは「ああ……」と、腕に担いでいる方の『荷物』に、視線を走らせた。
「これは、あの戦いの最中、俺を守って死んでしまった人の『遺骸』だ」
「―――――!」
ハヤブサの言葉に、一同ははっと息を呑む。
「あそこではきちんと弔ってやることもできないからな……。できれば、落ち着いた場所に、ちゃんと葬ってやりたいんだ」
シン……、と静まり返ってしまう空輸艇の中。
(やはり、『遺骸』として運び込んだのはまずかったか?)
ハヤブサは少しの気まずさを感じて、目を伏せた。
「すまない……。だが、俺は―――――」
「遠慮するな、リュウ。お前がこの戦いにおいてあげた功績を鑑みるならば、その人に立派な墓を建ててもまだ足りないぐらいだ」
アーサーの言葉に、ハヤブサは少しびっくりして顔を上げる。ハヤブサと視線が合った兵士たちが、うんうん、と、頷いていた。
「なんなら『軍葬』として、隊全体で葬らせてもらってもいいが……」
アーサーの申し出を、ハヤブサは丁重に断った。
「やはり、行くのか? 龍の忍者」
紛争地帯から国境を超え、アーサーの所属する国の軍の基地につく前の広い平野の一角で、ハヤブサは空輸艇から『遺骸』を抱えて降りていた。
「ああ。俺の『任務』はもう果たした。報酬も間違いなく入るようだし、ここでの俺の用事は、もう無いからな」
「リュウ、もう一度言う。うちの国に来る気はないか?」
アーサーは、真剣な面持ちでハヤブサに声をかける。
「お前ならば、破格の待遇でわが軍に迎え入れてやれる。何不自由ない生活と出世が、約束できるだろう」
アーサーの申し出に、しかしハヤブサは、頭を振った。
「何度も言わせるな、アーサー。俺には俺の生きる道がある」
「リュウ………!」
「お前と俺の歩む道に、また接点があれば――――いずれ、会うこともあるだろう」
ハヤブサの言葉に、アーサーは一つ溜息を吐く。
「やはり……お前は『孤高』を選ぶのか、龍の忍者」
その言葉に、龍の忍者からは「ああ」と、短く返事が返ってくる。彼の意志はそう簡単には覆せないのだと、アーサーは悟らざるを得なかった。
「世話になった……。龍の忍者、また、縁があれば会おう」
そういってアーサーは、ハヤブサに向かって最敬礼をする。後ろに控えていた兵士たちも、それに倣った。彼らは空輸艇のドアの向こうにその姿が消えるまで―――――その姿勢を貫いていた。
「さて……俺も行くか………」
空輸艇を空の彼方に見送ってから、ハヤブサもシュバルツを抱きかかえ、独り、歩き出していた。
5
とあるモーテルの一室に、ハヤブサはシュバルツを連れ込んでいた。
バラバラの爆死体になったシュバルツの身体だが、今はきれいに復元されていた。内部の駆動音も甦り、穏やかな呼吸音が、ハヤブサの耳朶をくすぐっている。だがまだ意識は戻らないのか、彼はモーテルのベッドの上で、身動き一つすることなく眠り続けていた。
(シュバルツ……)
ハヤブサは、意識のないシュバルツの服の前をくつろげさせ、その肌を露わにした。
「…………」
そして、少し眉を顰める。まだ『腐墨の術』の『墨』の文様が、その体にうっすらと残っていたからだ。
(これは………目が覚めても、まだ傀儡状態のままかもしれんな……。だがかなり……墨自体は薄まっているようだが………)
この薄さなら、あと一回か二回、『清め』の術を行うだけで、彼を完全に浄化することができそうだ。そういう希望が見えてきて、ハヤブサはほっと、その胸をなでおろしていた。
しかし、恐るべしは『腐墨の術』―――――シュバルツは一度完全に死んでいる。死してなお、その影響から抜け出すことができないとは。
だが、死ぬ前よりも、『墨』の濃さは格段に違う。やはり、人の生死が術に与える影響は、大きなものだと悟らざるを得なかった。
(もしかしたら、シュバルツをもう一度『殺せば』………彼を、完全に『浄化』することができるのだろうが………)
そこまで思い至ったハヤブサは、ブンブン! と、頭を振った。
いやだ。
そんなことはしたくないし、させたくもない。
シュバルツをもう一度死なせるぐらいなら、自分が『毒』を食らう方を選ぶ。
シュバルツを快楽の中に溺れさせ、喘がせる方を選ぶ。
それほどまでに大切な―――――愛おしい、ヒトだった。
(シュバルツ……)
その髪を、そっと撫でる。
すると、シュバルツが軽く身じろぎをした。
「う…………」
どうやら意識が戻ってくるらしい。
ハヤブサは静かに、その時を待った。
やがて。
フ………と、シュバルツの黒縁色の瞳が開く。
「シュバルツ……」
ハヤブサが声をかけると、シュバルツは振り返った。
「ハヤブサ……」
一瞬、その瞳に宿る『生気』
だがすぐに――――――黒緑色の瞳は『ガラス玉』のようになってしまった。
「ハヤブサ(ご主人様)………」
(ああ、やはりだめだったか……)
少しの寂しさを感じて、ハヤブサは苦笑する。
だがそれならそれで、特に問題はなかった。
今からシュバルツを、時間をかけて丹念に『浄化』してやることができるのだから。
「シュバルツ………」
ハヤブサは、シュバルツの唇を深く奪う。口腔深くに舌を侵入させ、弄り、舌を強く吸い上げた。
「ん………!」
そのキスは長く、執拗だった。
『浄化』の儀に入ってしまえば、毒を口の中に含む自分は、シュバルツとキスができなくなってしまう。それ故に尚更―――――ハヤブサは、シュバルツとの口づけに没頭した。愛おしさが命じるままに、唇を求め続けた。
「ん………! んう………!」
呼吸を奪われてしまったシュバルツが、腹の下で小さく震えている。もっともっと乱れてほしいから、彼のはだけた服をさらに乱し、そろそろと乳首に指を這わせた。
「んんっ!! んうっ!!」
ビクビクッ! と、跳ねる身体。しばらくそこを指で弄んでやると、乳首の中にこりっとした芯が芽生え、ぷっくりと熟れてくる。ハヤブサはその変化を、シュバルツの両の乳首に求め――――唇を奪いながら、そこを丹念に指の腹で擦ったり摘み上げたりして、楽しんだ。
「んふ……っ! んく……!」
逃れられない刺激にシュバルツの身体が震え、その腰が揺れている。そろそろ頃合いか、と、その唇を解放してやれば、ひどく蕩けた表情をした、愛おしいヒトの媚態がそこにあった。
「は………あ…………」
ガラス玉のような瞳から涙が零れ、上気した頬を彩っている。半開きになった口からあふれた唾液が、たまらなく艶めかしい。熟れ切った両の乳首に、チュッ、チュッ、と、音を立てて吸い付く。その度に「あ……! あ……!」と、声を上げ、律儀に身体を跳ねさせて応えてくれるシュバルツが、可愛らしくてたまらない。
胸から下半身へと視線を送れば、シュバルツのズボンの前側が、窮屈そうに張りつめているのが見える。カチャカチャと音を立ててベルトを外し、ゆっくりとファスナーを引き下ろす。張り詰めた下着は、すでに外からわかるほど濡れそぼっていた。そっと下着に指をかけて引き下ろしてやれば、待ちかねたように勃ち上がりきったシュバルツの牡茎が、勢いよく飛び出してきた。
(硬いな……。ある意味、当たり前だが………)
腐墨の術に侵された被害者は、術者に触れられると、強制的に淫らに発情させられてしまう。ましてや、明確にシュバルツを乱れさせようと、意志をもってその身体に触れたのだから――――シュバルツは強力な催淫剤を、その身体に塗りたくられているようなものだ。
(せめて一度だけでも……楽にしてやるか)
『浄化の儀』に入ってしまえは、シュバルツは思うように射精もできなくなってしまう。だからハヤブサは、それに入る前に、一度だけでもシュバルツを絶頂に導いてやりたい、と、思った。
ちゅぷっと音を立てて、ハヤブサの口が、シュバルツの牡茎を受け入れていく。
それからしばらくちゅぷちゅぷと淫らな水音が、モーテルの部屋に響き渡った。
「あ………! はあ………っ!!」
シュバルツはハヤブサの愛撫を素直に受け入れ、時折腰を揺らしている。
(普通の状態のシュバルツなら、フェラは嫌がるのだがな……)
自分は、DG細胞の塊だ。だから、自分から出るものは口にするな、飲むな――――と、必死に懇願してくるシュバルツ。それを押さえつけて、無理やりするのも悪くないのだが、こうやって素直にフェラを受け入れてくれるのも、またひどくそそられる。こんな素直なシュバルツが、もうすぐ見られなくなる、と、思うと、少し惜しい気もした。
だが、このままでいいはずがない。
ハヤブサは強く思った。
愛おしいヒトには、自分の明確な『意思』を持っていてほしい。
青空の下、親しい人たちと幸せそうに笑っていてほしい。
自分の『生』を、生ききってほしい―――――
自分が欲しいのは、自分の意のままになる玩具ではない。
自分と『対等』に、共に道を歩んでいける『恋人(パートナー)』なのだ。
そして彼が、自分の『意志』で、俺を選んでくれるなら―――――それでもう、何もいらなかった。
「あ……! ハヤブサ(ご主人様)……! イキます………! もう……!」
「ん…………」
ハヤブサは口でシュバルツ自身を愛しながら、その秘部に指を侵入させる。
「ああっ!! あ………!」
その刺激に耐えられず、シュバルツはついに達してしまった。ぴゅる、と、音を立てて、シュバルツの物が、ハヤブサの口の中に飲み込まれていく。
「あ…………!」
恍惚とした表情を浮かべながら、息を喘がせる愛おしいヒト。達した余韻で、秘部がひくひくと淫らに蠢いていた。
ああ。
たまらなく、綺麗だ。
素直にそう、想う。
ハヤブサは、シュバルツの身体に纏わりついている衣服を取り去り、彼を生まれたままの姿にする。自身も服を脱ぐと、ベッドの上で横たわるシュバルツの上に、そっと近づいた。
「シュバルツ……手を、上にあげて」
ハヤブサに言われるままに、手を上げるシュバルツ。ハヤブサはその手を取ると、その手首に縄を打ち、ベッドの端と端に縫い付けるように固定した。
「あ…………」
キシ……と、縄と、モーテルのベッドが軋む。
その刺激に感じさせられてしまっているのか、シュバルツの頬が、またバラ色に上気しだした。
「足も開いて……」
命ぜられるままに、その足も開いていくシュバルツ。ハヤブサはその足首を捕らえると縄を打ち、手と同じようにベッドに固定した。
「あ………ハヤブサ(ご主人様)………」
身動きも許されず、総てを曝す格好になったシュバルツが、腹の下で小さく震えている。
ハヤブサはそれを見て、ふっと、柔らかい笑みを浮かべると、両の乳首を再び弄び始めた。
「ああっ!! あ………ッ!」
その刺激に耐えられないのか、シュバルツの唯一動くことが許された腰の辺りが跳ね、達して、脱力したばかりの牡茎が、素直に勃ち上がってくる。
「動くなよ」
ハヤブサはシュバルツにそう命じると、シュバルツの牡茎の根元に、カチリと音を立てて、射精を阻害するリングを取り付けた。そこからさらに、細い縄で牡茎をきつく締めあげていく。
「あぐっ! ああっ!!」
急所を締め上げられて、痛むのだろう。シュバルツが涙を散らしながら、悲鳴を上げた。縄できつく締められた牡茎の先端からは、涙のように先走りの汁が垂れ始めている。ハヤブサは、チュッ、と、音を立ててその先端の汁を吸い取ってやると、改めてシュバルツを見た。
「シュバルツ……」
「ハヤブサ(ご主人様)………」
素直で、従順なシュバルツ。
それもまた、たまらなく愛おしい。
だが―――――
やはり彼には、元に戻ってもらいたいと、願う。
「身体の力を抜いて……動くなよ」
「は………い…………」
ふわり、と、四肢を緩めていくシュバルツ。それを確認してからハヤブサは、シュバルツに描かれている『墨』の文様に、ぺちゃ……と、音を立てて、自身の舌を触れさせた。
「はあっ! あ……っ!」
ビクッ! と、跳ねる身体。ベッドと縄が、音を立てて軋む。
だが彼の手は緩く開かれたままだった。「身体の力を抜け」と言った自分の言葉を、律義に守ろうとしてくれているのだ。
(シュバルツ………)
どうしようもない愛おしさを感じながら、鎖骨から胸にかけて、精密に描き込まれている文様を舐める。すると、ハヤブサが舐めた後の文様が、ゆっくりと消えていっているのが分かった。
(やはり……これが、最後の『清めの儀』だな……)
ハヤブサはそう確信すると、ほっと安堵すると同時に、少しの名残惜しさを感じた。
何でも言うことを聞いてくれるシュバルツ。
これが、どうせ最後というのなら―――――
ハヤブサは、ほんの少しの贅沢を、シュバルツに要求した。
「シュバルツ」
「はい………」
息を喘がせながら返事をするシュバルツに、命を下す。
「今からお前に許す言葉は、『愛している』と『ハヤブサ』だけだ」
「え……………」
「言い続けてくれ……。その言葉を……」
「わかりました………」
機械的にうなずくシュバルツに、それでもハヤブサはふわりと微笑む。そしてまた、『清めの儀』へと戻った。
乳首の周りに描かれている、複雑な文様を舐めとる。
「はあっ! ああっ!! 愛して、る………っ!」
次いで、胸の中央から鳩尾付近を。
「あ………! 愛している……! ハヤブサ……!」
さらに、反対側の鎖骨を。
「愛している……! 愛している……!」
(…………!)
ハヤブサは、シュバルツの唇から漏れる言葉の響きに酔う。
分かっている。シュバルツは命じられた言葉を鸚鵡返しにしているだけ。
この言葉に『真実』などないし、意味すらもない。
だが――――
「愛している………!」
彼の唇から漏れる、この言葉の響きが嬉しい。
愛おしいヒトが、そう言ってくれることが嬉しい。
「愛している」
彼はこの言葉を、滅多に言ってはくれないから。
シュバルツは、複雑な出自を持つアンドロイドだ。
だから、自分との恋人関係にあっても、それからいつでも身を引けるようにしている。
――――だって、不自然だろう……?
彼は折に触れ、この言葉を漏らしていた。
――――『アンドロイド』である自分が、いつまでも『人間』であるお前を、自分の横に縛り付ける訳には――――
(構わないのに)
ハヤブサは強く思う。
もっともっと、自分を縛り付けてくれても構わないのに。
もうすでに俺は
お前に深く捕らわれているも、同然なのだから。
生きるのならば、共に生きたい。
ともに死ぬことが叶わないのならば、尚更―――――
俺が生きている間は、傍に居たいと、傍に居て欲しいと、願う。
「ああっ!! ハヤブサ……! 愛している………ッ!」
びくびくと腰の辺りが揺れる。切なそうに、息を喘がせながら、首を振っている。
もうすでに、何度も達しているのだろう。
だが、達した証を吐き出すことが出来ないから、彼はひどく苦しそうだった。
(すまないな、シュバルツ……)
もう片方の、乳首の周りの文様を舐めとる。
「あ………! あ………!」
キシキシと、縄とベッドが軋む。
「愛してる……ッ! ああ……!」
懸命に腰を揺らし、何度も限界を訴えている。
だがまだ達することを許すわけにはいかない。
『清めの儀』は―――――正しく途中なのだから。
脇の下から脇腹、へそ周り、そして、反対側を丹念に舐めとる。
感じて身を捩るシュバルツを、強く押さえつける。
舌先が強く痺れてきたが、ハヤブサは『墨』を舐め続けていた。
もうすぐだ。
きっともうすぐ――――愛おしい人を、墨の呪いから解放できるだろう。
「うぁ……! はぁん……! 愛してる………!」
涙を散らせながら、身体をのたうたせる愛おしいヒト。
「愛している」と言い続けるその媚態に、ハヤブサは幸せを感じると同時に、己の中の突き上げる衝動が、激しくなってくるのが分かった。
早く、シュバルツと一つになりたい。
早く、早く――――
自分の中の嵐のような劣情を、懸命に鞭打って律する。
シュバルツに描かれた『墨』の文様を、正確に舐め続ける。
そして、牡茎の根元まで延びる『墨』を、完全に舐め切った時―――――シュバルツの身体から、黒い『影』のような物が、サアッと、抜けていくのが分かった。
(呪いが解けたか?)
ハヤブサはシュバルツの瞳をのぞき込む。
「ハヤブサ……」
愛おしいヒトの瞳は、涙で潤み、光を放っていた。
(俺の名前の響きが、「ご主人様」と同じではない?)
ハヤブサは確認がしたくて、もう一度、シュバルツに呼び掛けた。
「シュバルツ……。もう一度、俺の名を呼んでくれ」
「ハヤブサ……!」
シュバルツの唇から漏れる自分の名前は、確かに「ご主人様」ではなかった。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは知らず、歓喜に震える。だが次の瞬間、シュバルツの唇から漏れた言葉に、少し衝撃を受けた。
「愛してる……!」
「……………!」
シュバルツが『正気』なら、滅多なことでは口走ってはくれない言葉。まだシュバルツが、『催眠状態』であるということを悟らざるを得なかった。
(無理もないか)
ハヤブサは、わずかばかり苦笑する。
『術』は、ちゃんと手順を踏んで解かねばならぬ。それは、予め分かっていたことではないか。
それならそれで、楽しんでしまおう。
シュバルツが「愛している」と言い続けてくれる、今の状態を――――
「いいぞ、シュバルツ……」
ハヤブサは、熟れ切っているシュバルツの乳首に、チュッと音を立てて吸い付く。
「はんっ!! あ………ッ!」
キシッ! と、大きな音を立てて、縄とベッドが軋んだ。
「言い続けてくれ……。『愛している』と………」
「あ…………」
ハヤブサはシュバルツをベッドに固定している足の縄だけを解いた。彼と、一つになるために。
自由になったシュバルツの足をぐっと持ち上げて大きく開き、その秘部を露わにする。
そこは、射精を許されない牡系から溢れ出た愛液が、涙のように流れ続けてそこに達し、その周辺を艶めかしく濡れさせていた。秘部自体も刺激を求めているのか、ひくひくと淫靡に蠢いているのが見える。
指を二本突き入れてみると、そこはもうそれをたやすく呑み込み、くちゅくちゅと濡れた水音を響かせた。
「ああっ!! 愛してる……ッ!!」
指で秘部を犯されても、「愛している」と言い続けるシュバルツの媚態に、ハヤブサの方もついに我慢の限界を突破する。ろくにほぐすこともせずに、シュバルツのそこを一気に刺し貫いていた。
「ああああああっ!! ハヤブサ……ッ!」
シュバルツは、切羽詰まった表情で自分を抱くハヤブサを見つめる。
ハヤブサが気付いたとおり、シュバルツにかけられていた『墨』の呪いは、確かにあの瞬間に解けていた。だがシュバルツは、あえて、呪いをかけられたふりをし続けていた。
(……………!)
『正気』に戻った瞬間、シュバルツの視界に飛び込んできたのは、懸命にこちらをのぞき込むハヤブサの表情。裸にされ、どうしようもなく熱く火照る身体と、身動き取れないように、ベッドに縫い付けられるように縛り付けられた手足。射精を許すものかと言わんばかりに牡茎を締め上げられているから、そこがもう千切れそうなほどに痛い。
かなり、異様な状況――――
だがシュバルツは、特に怯えることはなかった。だって、自分の目の前には、ハヤブサがいたから――――
「ハヤブサ……」
「……………」
食い入るようにこちらを見つめてくるハヤブサ。それだけで、自分が「正気」を失っている間、ずっと彼がそばにいて、こちらを守ってくれていたのだと分かる。自然と、シュバルツの瞳から涙がさらに溢れていた。
「シュバルツ……。もう一度、俺の名を呼んでくれ」
「ハヤブサ……!」
そう答えた瞬間、シュバルツの中にくすぶる内部の『熱』が、彼に囁きかける。
お前に許されている言葉は『愛している』と『ハヤブサ』だけなのだと。
(ああきっと、呪いの名残だ)
そう感じながらも彼の口は、自然とこの言葉を口走っていた。
「愛してる……!」
ハヤブサは、少し驚いた表情をした後、少し寂しさの混じった―――――だが、優しい笑みをその面に浮かべた。
「いいぞ、シュバルツ……」
チュッと、優しく乳首を吸われるから、身体が勝手に跳ねてしまった。
「言い続けてくれ……。『愛している』と………」
ハヤブサに、そう頼まれる。
(いいのか……?)
シュバルツは、心の奥底で思う。
ハヤブサはきっと、今の自分の状態を『催眠状態』だと思っている。だから、その状態で紡がれる私の言葉など――――『嘘』か『真実』かも、ハヤブサには分からないのではないのかと。
だが―――――
(伝わらないのなら、いいか)
シュバルツは、逆に思った。
彼に「愛している」と、言い続ける自分の言葉に『真実味』がないのなら、逆に、伝えやすいのではないかと。
自分は、ハヤブサを『愛している』
これは、シュバルツの中では揺らぎようのない『真実』だった。
ハヤブサになら、何をされてもいい。
縛られても、殴られても、凌辱されても、例え殺されてしまったとしても―――――
彼がそれを望むのならば、シュバルツは喜んで自身の身を彼の前に投げ出すことができた。
――――ダガ、オ前ハ生キ返ルダロウ?
「……………!」
自分の中に、酷く機械的な声が響く。
――――死ネナイクセニ………
(ああそうだ……。死ねないな……)
シュバルツは少し、自嘲的に笑う。
死ねないから、『殺されてもいい』なんて―――――
まさしく、欺瞞だ。
「愛している……!」
わかっている。
私の言葉には、結局『真実』がない。
「愛している……!」
何を言っても、『嘘』しか言えない私の言葉など――――
ここでハヤブサが、いきなりシュバルツの中に挿入(はい)って来る。
「ああああああっ!! ハヤブサ……ッ!」
圧倒的なハヤブサの存在に、シュバルツの内部は容易く支配されてしまう。それと同時に、奔流のように流れ込んでくる、彼の熱い『想い』が――――
愛シテイル
愛シテイル
愛シテイル
愛シテイル――――!
「ハヤブサ……ッ!! ああっ!!」
シュバルツの身体を構成しているDG細胞は、人間の『ココロ』に感応する能力を持つ。それが、ハヤブサの狂おしいまでの心の声を、シュバルツに聞かせてしまう。
愛シテイル
欲シイ
モット奥まで――――
「ああっ!! ああっ!!」
翻弄される。
流されてしまう。
ダメだ……!
耐えられない。
侵食してくる、甘すぎる『熱』が―――――!
「愛してる……! はあっ!! ハヤブサッ!! 愛している……ッ!」
その熱に引きずられるように、シュバルツは「愛している」と言い続けるしか、もう出来なくなってしまった。
シュバルツの身体を激しく突き上げるごとに、ぎしぎしとベッドが大きな音を立てて軋む。腕を拘束する縄が、ピンと張り詰め、悲鳴を上げている。
「愛している……! ああっ!! うぁ……!」
「シュバルツ……!」
シュバルツの内側を激しく犯しながら、ハヤブサは目の前の景色に酔う。
ああ、なんて綺麗なのだろう。
なんて、愛おしいのだろう。
このヒトは―――――
無防備にさらされているわきにチュッと口づけを落とす。綺麗に熟れて色づいている乳首をつねったり潰したりして弄ぶ。
「はあん!! あううっ!!」
きつく締めあげられている牡茎から溢れ出る愛液は、もう縄をぐしょぐしょに湿らせてしまっている。そこを軽く擦り上げてやると、シュバルツは声にならない悲鳴を上げた。
「解いてほしいか……?」
ハヤブサはそこを揉むように触りながら優しく問いかけてやる。しかしシュバルツから帰ってくる言葉は「愛している……!」の、一点張りだった。
(仕方がないか)
ハヤブサは少しの寂しさとともに苦笑する。
まだ目の前のこのヒトは『正気』には戻っていないのだから。
自らの要求を伝えるなど―――――言わずもがなだろう。
だが―――――今の状態も、また良い。
このヒトから
この唇から
「愛している」と漏れるその言葉が良い。
このヒトは、俺を受け入れてくれている。
「愛している」と、言ってくれる。
それだけで、俺はもう――――
十分すぎるほど、幸せだった。
たとえ刹那的なものであろうが、無理やり言わせているものであろうが、関係ない。
愛するヒトが、自分に向かって愛を囁いてくれる。
この事実が重要なのだ。
これ以上――――何を望むというのだろう。
「ああっ!! ああっ!! ハヤブサ……ッ!」
懸命に身をのたうたせながら、シュバルツは言葉を紡ぐ。
「愛している……!」
そのたびにハヤブサが、幸せそうに微笑むのがわかる、から。
どうして―――――
「愛している……!」
どうして―――――
そんな風に微笑まれてしまったら
もう、言い続けるしかなくなってしまうではないか。
何故
何故だ。
今の私の言葉には『真実』などない。
たとえ『真実』だとしても、「操られている」と思われている今の状態では、この言葉は『真実』にはならない。ハヤブサには、伝わらない、はずなのに。
「シュバルツ……」
ハヤブサにやさしく牡茎を触られる。
「あ………! あ………!」
その刺激に耐えられず、震えながら身を仰け反らせていると、シュル……と、音を立てて、牡茎から縄が外された。
「あ…………」
ギリギリと締め上げられていた牡茎の痛みから解放され、シュバルツの面に、ふわりと恍惚の表情が浮かぶ。それと同時に、絶頂を迎えたいという、どうしようもない焦燥感に強く駆られた。
「ん………!」
(イキたい………!)
ハヤブサの物を咥え込んだまま、シュバルツの腰が牡茎を突き出すように動く。しかし、射精を阻害するリングが嵌め込まれたままであるから、シュバルツの動きは空回りするのみ。それどころか、ハヤブサの物と自身の内側がくちゅくちゅと淫靡な水音を立てて擦れあってしまう。
(イキたい……! イキたい……ッ!)
さらなる快感が、シュバルツを責め苛み、追い込んでいく。ハヤブサの熱を煽ってしまっていることに、シュバルツは気づくことができなかった。
「ん………ッ! くう……ッ! ああ………!」
(イケない……ッ! どうして――――!)
キシ、キシ、と、モーテルのベッドが音を立ててきしむ。
「シュバルツ……!」
ハヤブサはシュバルツの思いもかけない痴態にくぎ付けになる。
今までのシュバルツなら、こちらが何か言わなければ、こんな風に自発的に動くことなどなかった。
やはり、シュバルツの様子が少し違う。
呪いが、解けかかっているのかもしれない。
「いいぞ……。シュバルツ………」
ハヤブサは、己自身でシュバルツの動きを堪能しながら囁きかけた。
「そのまま……動き続けてくれ………」
「あ…………」
――――ハヤブサの言ウコトニ、逆ラッテハイケナイ……!
シュバルツの内に燻る『熱』が、シュバルツに強く囁きかけてくる。
彼はこれでもう、腰を止めることができなくなってしまった。
「あ………! ああ………!」
切なそうに眉を顰め、懸命に腰を動かし続けるシュバルツが、たまらなく淫らで可愛らしい。
「は………あ………!」
「シュバルツ……!」
(キス、したい……)
喘ぐシュバルツの唇に引き寄せられる。素直に、綺麗だと思った。
「あ………」
熱い眼差しでハヤブサがこちらを見つめているのに気づく。
(キス、してほしい……)
シュバルツも、想いを込めてハヤブサを見つめ返す。自分の唇に、触れてほしいと願った。
「……………」
ハヤブサの手が、シュバルツの頬に触れ、そっと唇が近づいてくる。
(ハヤブサ……)
シュバルツも瞳を閉じ、ハヤブサから口付けられるのを待った。
しかし。
(だめだ……! 今、俺の口の中には呪いの毒が―――――!)
せっかく拭い取った『墨』の毒を、シュバルツに還元してはいけない。ハヤブサは唇をかみしめて、顔を逸らした。
「ハヤブサ……!」
しかし、シュバルツにはハヤブサのこの行動の真の理由が伝わらない。「キスを拒否された」と、単純に感じてしまって、少なからずショックを受けてしまう。
「ハヤブサ……ッ!」
知らず、頬を涙が伝う。
キスをしてほしい。
何故だ………?
どうして―――――
寂しい。
寂しくて、たまらなかった。
「愛している……!」
シュバルツは、懸命にハヤブサを見つめながら言葉を紡ぐ。
「愛している……! ハヤブサ……!」
『伝わらない』のは百も承知で、それでも言い続けた。自分は、そうするしか術がないのだ。
ハヤブサを抱きしめたいと、願う。しかし、腕を動かせない。ハヤブサが括り付けた縄なら、自分が勝手に解いてはいけないものだった。ギシッ! と、縄が切ない音を立てて軋んだ。
「シュバルツ……!」
輝きながら頬を伝う涙が
まっすぐにこちらを見つけてくる瞳が
綺麗すぎて、愛おし過ぎて堪らない。
「シュバルツ……!」
そっと、己が唇で頬を伝う涙を掬い取る。しかしその涙は、後から後から溢れてきた。
何故、泣く?
何故――――そんな風に泣くのだ、シュバルツ。
お前を、貪り尽したくなってしまうではないか。
何もかもを忘れて―――――
駄目だ、それは駄目だ。
僅かに残る理性を懸命に奮い立たせる。
これは、彼の呪いを解くための行為なのだから――――
『道』に外れる行動を、してはならないのだ。
「シュバルツ……ッ!」
それでも堪え切れないハヤブサは、彼の身体をぎゅっと、抱きしめていた。
それと同時に、結合も深くなる。
さらに、深く、強く―――――
「あ………!」
奥まで犯される熱に、シュバルツは震える。そこに、ハヤブサの唇が、耳元に寄せられてきた。
「愛している……!」
「ひあっ!!」
耳に直接注ぎ込まれる『熱』と『言葉』に、シュバルツの身体がビクッ! と、跳ねる。
「愛している……! シュバルツ……!」
「や………! あ…………!」
耳に入ってくるそれは、強烈だった。脳にダイレクトに響く愛の言葉は切なすぎて、シュバルツは思わず逃げ出したくなってしまう。必死に、ハヤブサから顔を逸らす。しかしその行為は、ハヤブサに却って己が耳を差し出す結果になっている、ということに、シュバルツは気づくことができない。
ハヤブサはシュバルツの身体を深く抱き込む。差し出された耳に舌を挿し入れたりキスをしたりしながら、言葉を囁き続けた。「愛している、愛している」と――――
「ああっ!! ああっ!!」
もう身体は何度も達しているのに、望む解放が得られない。上と下から侵食してくる甘すぎる熱に、シュバルツはもう、気が狂いそうになってしまう。
「や………! あ……ッ! ハヤブサ……!」
「シュバルツ……! 愛している……!」
「ああっ!! あ……! い―――――!」
自分の身体の中に、蓄積されていくハヤブサの『想い』と『熱』
ついに、それに耐えきれなくなってしまったシュバルツの中で、何かがプツッと、音を立てて切れてしまった。
「イキたい……!」
「……………!」
シュバルツの言葉に、はっと息をのむハヤブサ。その彼の目の前で、シュバルツの訴えはなおも続いた。
「イキたい……! イキたい……ッ!」
「シュバルツ……!」
自分が頼んだ言葉以外を紡ぐシュバルツ。やはり、彼の呪いは、解けかけてきているのだと悟る。
(良かった………!)
愛おしいヒトをこの手に取り戻せそうな予感に、ハヤブサは震えた。もう一度改めて、彼のヒトの身体をギュッと、抱きしめた。
「あ………!」
「分かった……! シュバルツ……!」
ハヤブサは決意を固める。
早くこの『儀式』を終わらせてしまおうと。
「俺も、もうイク……。だから―――――共に行こう」
その言葉に、シュバルツもこくりと頷く。
それを確かめたハヤブサもふわりとほほ笑むと、シュバルツの腰を深く抱き込んだ。彼に自分自身を、強く刻み込むために。
一気に、激しい律動を開始する。
「ああっ!! ああああっ!!」
腕の中で愛おしいヒトが、涙を散らせながら悲鳴を上げる。ベッドが大きな音を立てて軋むのも構わず、ハヤブサはシュバルツに腰を打ち込み続けた。
愛おしい―――――
何て、愛おしいのだろう。
「ハヤブサ……!」
時折、シュバルツがキスを求めてきているのが分かる。だがそのたびに、ハヤブサは顔をそらしてそれを拒否した。自分の口の中には、まだ墨の『毒』が残っている。それを、シュバルツに還元するわけにはいかないのだから。
「ハヤブサ……!」
キスを拒否されたシュバルツが、切なそうな声を上げている。
「愛している……!」
涙ながらに訴えてくるその様が、綺麗で可愛らしくて、胸が締め付けられるから堪らない。
俺だって、お前にキスをしたい。
一刻も早く、キスをしたいのだ。
そのためにも、早くこの『儀式』を終わらせなければ。
早く
早く――――
自然と律動が深く激しくなる。
もう、終わりが近いのだとお互いが悟っていた。
愛シテイル
愛シテイル
愛シテイル―――――
ハヤブサから降り注いでくるのは、紛うことなき愛の言葉のシャワー。
だから、彼の『ココロ』を、シュバルツは疑う余地はなかった。
ならば、何故――――ハヤブサはキスをしてくれないのだろう。
そんなに切なそうな顔をして、顔を逸らすのだろう。
何かハヤブサがキスをためらうような理由が、私の方にあるのだろうか。
(構わないのに)
シュバルツは思った。
多少の不都合ならば、私は飲み込むし、受け入れるのに。
どうして、キスをしてくれない?
どうして
どうして―――――
「シュバルツ……!」
涙を流し続ける愛おしいヒトを、ハヤブサは宥めるように抱きしめる。
ああ もう
終わりが近い。
カチリ、と音を立てて、シュバルツの牡茎から『リング』が外された。
「あ…………っ!」
シュバルツを堰き止めていた、最後の箍が外される。それと同時に、身体の最奥を、激しく、そして容赦なく穿たれた。
「あああっ!! あああっ!! も……う………!」
ビクビクッ! と、忍者二人の身体が同時に震える。ぴゅ、ぴゅる、と、音を立てて、牡茎からシュバルツの達した『証』が放たれた。それと同時に、ハヤブサの物も、シュバルツの中に放たれていた。
「あ………! あ…………!」
じわり、と、中に広がる熱い迸りの感触に、シュバルツの意識が奪われていく。
「愛、している………。ハ……ヤ、ブサ………」
プツン、と、糸が切れたように、シュバルツは意識を手放してしまった。儚いその言葉を残して――――
「…………」
ハヤブサも一つ大きく息を吐くと、シュバルツの身体の中から己自身を引き抜いていた。それと一緒に自分がシュバルツの中に吐き出した熱の名残も、クプ、と、音を立てて彼の中から溢れ出てくる。
ハヤブサは、それを手近にあった紙で一通り拭うと、そっとシュバルツの髪に己が手を触れさせた。そのままそこを、優しく撫でる。
(シュバルツ……)
彼の頬には、涙がキラキラと光っている。それは酷く綺麗で――――ハヤブサの胸を、切なく締め付けていた。
(キスを欲しがっていたのに………。きっと、ひどく傷つけてしまっただろうな……)
呪いが解けかかっていたシュバルツは、正気に戻りつつあった。だから猶更――――自分の先程の一連の行動は、シュバルツからしてみれば単純に「キスを拒絶された」と、感じてしまったことだろう。
だが済まない。
わかってくれ、シュバルツ。
今――――お前とキスをするわけにはいかないのだ。
(これからどうする?)
ハヤブサはシュバルツの髪を撫でながら、自問自答をする。自分が今なすべきことは、体内に取り込んだ『毒』の浄化だ。そのためには、浄化できる『聖なる場所』をこの近辺で探さねばならないが―――――
「……………」
ハヤブサは、気を失っているシュバルツの、泣き濡れた顔を見る。
もし、彼が目を覚ましたとき、独りきりにさせてしまったら、もっとひどく彼を傷つけてしまうかもしれない――――そんな予感がした。
キスを拒絶され、しかも目覚めたときそばにいなければ、「もう自分は、彼に愛想をつかされてしまったのだ」と、シュバルツは思いこんではしまわないだろうか。
駄目だ、と、ハヤブサは強く頭を振った。
そんな哀しい想いを、愛おしいヒトにさせてはいけない。
自分にはシュバルツは愛おしくて必要で――――ずっと傍に居たいと、願っているのだから。
(とにかく、彼が目覚めるまではそばにいよう。きちんと理由を話せば、シュバルツもきっと分かってくれるはずだ)
ハヤブサはそう決意すると、シュバルツの腕を拘束していた縄を解いた。そしてそのまま、気を失っているシュバルツの身体の横に、そっと己が身を横たえる。
(シュバルツ……)
愛おしさを込めて、その身体を抱きしめる。いつものシュバルツのほんのりとした温もりと駆動音に、かなりの安心を感じた。そしてハヤブサは、いつしかまどろみの中に、その身を沈めていくのだった――――
「…………!」
それからしばらくして、シュバルツの方に意識が戻る。見慣れぬ景色と、自分が一糸纏わぬ状態であることに、彼は少し混乱しかけた。
しかし、身を起こそうとして、自分の身体に誰かの手が触れているのに気づく。振り返ってそこにハヤブサの姿を見た時、シュバルツはほっと安堵の吐息を漏らしていた。
(そうだった……。私はハヤブサに……)
先程まで自分は、ハヤブサに激しく抱かれていたことを思い出す。
「もし……誰かに支配されるというのなら…………私はその相手に、お前を選ぶ……! ハヤブサ……! 私はお前がいいんだ……!」
思えば、かなりむちゃくちゃなことをハヤブサに要求してしまったような気がする。それなのに、彼はずっと、正気を失った私のそばにいて、そして、守ってくれていたのだと悟る。
(ハヤブサ……)
本当に、彼には返しても返しきれない『恩』を作ってしまったような気がする。
どうしてだろう。
どうしてハヤブサは、私にこんなに愛情を注いでくれるのだろう。
私は、何も持っていない。
自分の命すら持っていない、いわば『空の器』も同然だ。
私からハヤブサに、返せる『物』など、何もないというのに―――――
(ハヤブサ……)
シュバルツは、想いを込めてハヤブサの髪にそっと触れる。
絹のように細い髪と、意外に長い睫毛が、とても綺麗だと思った。
暫く、ハヤブサの穏やかな寝息と、さらさらとした髪の感触を楽しむ。
彼の寝顔を見るのは好きだ。
彼が自分の傍では「安心してくれている」と、感じることができるから。
何も返せない存在であるなら、せめて、彼の穏やかな眠りを守れる存在でありたい。
せめて、自分の傍にいるひと時だけでも、彼に安らかな時間を感じさせてあげたい。
心の底から、そう―――――願う。
シュバルツがそう思いながらハヤブサの髪をなでていると、ハヤブサがふっと瞳を開けた。
「あ………。起こしてしまったか?」
そう言って、手を引っ込めようとするシュバルツ。その手を、ハヤブサが素早く取った。そのまま、「俺から手を引くことは許さない」と、言わんばかりに自分の方へと引き寄せる。
「シュバルツ……」
「ハヤブサ……」
ハヤブサは、シュバルツの瞳に『生気』が宿っているのを確認してから、口を開いた。
「シュバルツ……。俺が、わかるか……?」
シュバルツはハヤブサの質問の意図が瞬間分からず、少し首をかしげる。しかし、素直に「ああ」と頷いていた。
「私の目の前にいるのは、『リュウ・ハヤブサ』――――『龍の忍者』……だろう?」
「シュバルツ……!」
シュバルツの身体から、完全に呪いが消え去ったのだと悟ったハヤブサは、嬉しさを隠すことができない。そのままシュバルツの身体を自分の方に強引に引き寄せると、彼を強く抱きしめていた。
「あ………!?」
腕の中でシュバルツが小さく身じろぎをする。その反応すら、ハヤブサは嬉しかった。
今まで、人形のようだった愛おしいヒト。こんな反応すら、彼はしてはくれなかったのだから。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
「ハヤブサ……?」
「会いたかった……! シュバルツ……!」
その言葉に、シュバルツははっと息を呑み、ハヤブサはさらに強く、シュバルツの身体を抱きしめていた。
「会いたかったんだ……! シュバルツ……!」
「ハヤブサ……」
シュバルツを抱きしめながら、ハヤブサの身体が小さく震えている。
「……………」
シュバルツはそっとハヤブサを抱きしめ返すと、その背中を優しく撫で始めた。
「すまない……。ハヤブサ……。迷惑をかけてしまったな……」
「迷惑なものか! 元はと言えば、俺が狙われていたんだ! お前はそれに、巻き込まれたに過ぎないのに――――」
「しかし、罠にはまって捕まったのは、私の責任だ。私が――――」
ここまで言葉を紡いでいたシュバルツの唇を、ハヤブサの人差し指が抑える。
「それ以上は言うな、シュバルツ」
「ハヤブサ……! しかし―――――」
「駄目だ。キスをしたくなるから」
「―――――!」
ハヤブサの言葉に、はっとなるシュバルツ。
やはり、ハヤブサの方に、キスをしてこない『理由』があった。
「何故だ? ハヤブサ……」
その答えが知りたくて、シュバルツは思わず問いかけていた。
「シュバルツ?」
「そ、その………お前が、キスをしたいのなら…………」
ここでシュバルツは、瞬間我に返った。自分が、とんでもないことを口走ろうとしているのに気づいてしまって、顔が真っ赤になってしまう。
しかし、もう遅い。
一度踏み出してしまった問いかけならば、最後まで言い切らねばと思った。
それに、この疑問をうやむやなままにしてしまうのは、きっと、よくない。
そんな予感がするから。
「わ………私の方は、そうしてくれても、一向に、構わない………!」
「シュバルツ……!」
「それなのに、何故だ……?」
「えっ?」
「何故………口づけをして、くれないんだ………?」
「……………!」
顔を真っ赤にしながらも疑問を口にして、潤んだ瞳でこちらを見つめてくる愛おしいヒト。この、夢のような状況に、ハヤブサの中で理性がいろいろな方向に飛び散りそうになってしまう。
しかし、懸命に踏みとどまった。
やっと、『腐墨の術』から解放されたシュバルツ。しかし、その『毒』は未だ―――――自分の口の中にある。それを、彼に口づけすることによって、シュバルツに還元してしまうことを、ハヤブサは恐れていた。
「すまない、シュバルツ………」
それにしても、シュバルツが自分と口づけできないのが寂しい、と、感じてくれているのならば、こんなことを思っては不謹慎なのだろうが、嬉しい、と感じてしまう。俺との口づけを、「幸せだ」と感じてくれている証拠にもなるのだから。
ハヤブサは、想いを込めて、指でそっとシュバルツの唇に触れる。
「俺だって、お前とキスをしたい……。だが今は、駄目なんだ……」
「何故だ……?」
問うてくるシュバルツに、ハヤブサは優しく微笑みかける。
「俺の口の中には、お前から拭い去った『呪いの毒』が、あるから」
「―――――!」
シュバルツの瞳が、驚きに見開かれる。ハヤブサはそんなシュバルツの頬を、優しく撫で続けた。
「な………。分かってくれ、シュバルツ。この『毒』を浄化するまでは、お前と口づけをする訳にはいかな―――――」
ここでハヤブサは、これ以上言葉を紡げなくなってしまう。何故ならシュバルツが、本当に一瞬の隙をついてハヤブサの懐に潜り込み、その唇を奪っていたからだ。
「ん………!」
口を閉じる間もなく、シュバルツの舌が口内に侵入してくる。そのまま口腔を弄られ、舌をチュッと吸われた。
「ん………! んく………! …………ッ!」
瞬間何が起こったのか理解できず、混乱するハヤブサ。
うっかり愛おしいヒトからの熱烈な口づけを堪能しそうになってしまう。
「ん…………」
(嬉しい………! 嬉しいが………いや! そうじゃなくて――――!)
「ん………う………」
(この状況……! この状況は、まずい……!)
「ん………ん…………」
(きょ、拒絶――――拒絶、しないと………!)
「………ふ………んぅ………」
ハヤブサは懸命に、理性を奮い起こそうとするのだが、よく考えたら自分の方に、愛おしいヒトからの口づけを拒絶する術など持ち合わせていないことに、割とすぐに気づいてしまう。シュバルツを跳ね除けようと肩に掛けられていた手は、いつしかシュバルツの背中に回り、吸われるままに戸惑っていたハヤブサの舌も、進んでシュバルツの口内に入り、その中を弄ったり舌を吸い上げたりしていた。
しばらく、チュ、チュ、と、濡れた水音が、モーテルの部屋の中に響く。
シュバルツ
シュバルツ
なんて、愛おしい――――
「……………」
しばらくして、シュバルツの方からそっと離れていく。ハヤブサは少し名残惜しそうに、その潤んだ唇を見つめていた。しかし瞬間的に我に返る。こんなことをしている場合ではないと、ハヤブサはシュバルツに慌てて声をかけた。
「シュバルツ!?」
「ん?」
「だ、大丈夫なのか……!? 呪いの毒が………!」
案ずるように声をかけるハヤブサに、シュバルツは「ああ……」と、答える。とりあえずシュバルツが正気を保っていると見て取って、ハヤブサは少し安堵の吐息を漏らした。
「確かに……ハヤブサ、お前は少し、疲れているみたいだな」
対してシュバルツは、口の周りについているハヤブサの唾液をべろりと舐めとると、その唾液の成分分析をしだした。口の中で、いつものように。
「疲れている!? そ、それはまあ………さっきまで戦っていたんだ。疲れていないはずはないが――――」
「それに………ああ、確かに、『毒』はあるな……。いつものお前の唾液からは、出ない成分が中に混じっている。ごくごく微量だが、確かに、これは人体にはあまりよくはなさそうだな……」
「シュバルツ……!」
ハヤブサは、呆然と愛おしいヒトを見つめる。
「お前は、大丈夫、なのか………?」
問いかけるハヤブサに、シュバルツは「ああ」と、あっさり答えた。
「私は平気だ。『毒』といっても、微量な物だし―――――」
「……………!」
「それよりもハヤブサ……。心配なのはお前のほうだ。疲れているみたいだし、ここは休んだ方が―――――んっ!!」
いきなりハヤブサに唇を塞がれ、シュバルツの言葉はここで途切れてしまった。そのままハヤブサに、深く奪われてしまう。唇も、言葉も呼吸も――――
「ん………っ! く……ふ………!」
シュバルツは咄嗟に身を引こうとするが、それも叶わない。ハヤブサが自分を捕まえる力が強すぎて、シュバルツは身動き一つ許されない状態になってしまう。キシッ! と、モーテルのベッドが軋んだ音を立てた。
「………ッ! はあっ………!」
やっと解放されたとき、シュバルツは思考も呼吸も奪われ続けたせいで、身体から力が抜け、倒れそうになる。それをハヤブサに優しく助けられ、そのまま、トサリ、と、ベッドの上に押し倒される結果となった。
「あ…………!」
呆然としているシュバルツの上に、ハヤブサの熱い身体と視線が覆いかぶさってくる。ハヤブサの意図するところを悟ったシュバルツは、少し慌てた。
この状況――――いろいろまずい。
ハヤブサには、休んでほしいと願うのに。
「ま、まて……! ハヤブサ……!」
「待てない」
シュバルツの言葉を、ハヤブサは一刀両断にする。それほどまでに、シュバルツの一連の行動は、ハヤブサの心と身体の熱を、煽ってしまっていたのだ。
「そんな格好で、そんな風にキスをしてきて―――――そのまま俺から逃れられると思っているのか?」
「―――――!」
ハヤブサの指摘に、シュバルツも瞬間的に我に帰る。
裸。
密室。
二人きり。
ベッドの上――――
どう見ても、状況がお膳立てされすぎている。
「あ…………!」
ハヤブサを誘惑する気はなかったのだから、シュバルツは慌てて己が身体のあちこちを隠そうとした。しかし。
「隠すな、シュバルツ……!」
あっという間にその手を搦め取られて、頭上に一括りに抑え込まれてしまった。抵抗する術と、身体を隠す術を失ったところで、ハヤブサのもう片方の手が、シュバルツの乳首にそろそろと伸びてきた。
そのままそこをきゅ、と、優しく摘ままれたり、くりくりと擦られたりしてしまう。
「ん………! あ………! あ………!」
たまらず、甘やかな声を上げてしまうシュバルツ。その反応に気をよくしたハヤブサは、さらに彼を乱れさせようと、もう片方の乳首に自身の唇を寄せた。
チュ、と、優しく口づけをし、吸い上げたり口の中で乳首を舌で転がしたりして、弄ぶ。
「うあっ!! ああっ!! やめ……っ!!」
チュ、チュ、と、熱を持った水音と、キシ、キシ、と、ベッドが軋む音が、暫くモーテルの部屋に響いた。
「ああ………!」
その執拗な愛撫は、シュバルツから抵抗の意思を奪うのには十分すぎて。
彼の乳首がピン、と張り詰め、十分に熟れ切ってしまう頃には、彼の身体から、すっかり力が抜けきっていた。
「シュバルツ……」
トロン、とした眼差しのシュバルツが、たまらなく愛おしい。ハヤブサの呼びかけに、シュバルツは涙で潤んだ瞳をこちらに向けてきた。
「ハヤブサ………」
「抱きたい……! お前を………!」
ストレートに、ハヤブサは要求をぶつける。シュバルツは少し驚いたように瞳を見開いた。
「抱くって………さっき、散々抱いたのではないのか……?」
ある意味もっともなシュバルツの言葉だが、ハヤブサは頭を振った。
「違う。抱きたいのは、『意志を持ったおまえ』だ」
「……………!」
「『人形』のようなお前なら、散々抱いた。これでもかと言う位に」
抵抗もせず、自分の意のままに、どんな淫らな要求にも応えてくれたシュバルツ。それはそれで悪くない。愛おしさは募った。
「だが………俺は、寂しかった」
「ハヤブサ……」
「お前が、目の前にいるのに『居ない』 それを痛感させられ続けて……ひどく、寂しかったんだ……」
「……………!」
ハヤブサは思う。
何でもかんでも自分の意のままになる、意思を持たない相手との性行為というのは、性質の悪い自慰行為と同義なのではないかと。相手を踏みにじって、自分だけが楽しんで――――それでいいはずがない。
自分は、相手と対等でいたいのだ。
自分が性行為を楽しむのなら、相手にも楽しんでほしい。自分の「愛している」という想いを、相手にちゃんと伝えたい。受け止めてほしい。それで、幸せを実感してほしい―――――
愛し、愛されたいと、願う。
この望みは、贅沢な物なのだろうか?
「シュバルツ……! 抱かせてくれ……! 今のお前を……!」
「ハヤブサ……」
「お前がちゃんと俺の目の前に、腕の中にいると……確かめさせてくれ………!」
「あ…………!」
「シュバルツ……!」
こちらを抑え込みながら、必死に訴えかけてくるハヤブサ。シュバルツはしばらくそんなハヤブサを黙って見つめていたが、やがて、あきらめたように小さくため息を吐いた。
「ハヤブサ……。分かった………」
「……………!」
「私は逃げない………。抵抗しないから、そんな風に身体に力を入れて、押さえつけなくていい」
その言葉と同時に、ふっと、身体の力を抜くシュバルツ。
「シュバルツ……!」
ハヤブサはシュバルツを押さえつけていた手をどける。するとシュバルツは、ハヤブサの頬に、自由になった手をそろそろと伸ばしてきた。そのまま彼の頬を、優しく撫でる。
「好きにすればいい……。私の身体は、お前だけの物だから……」
「………『身体だけ』か?」
「えっ?」
「お前が俺にくれるのは『身体』だけなのか?」
ハヤブサが少し、意地悪な笑みを浮かべてこちらを見つめている。
「う…………!」
シュバルツは、自身が耳まで真っ赤になるのを感じていた。
分かっているくせに――――!
私の『ココロ』が誰に向いていて、どこにあるかということぐらい。
それを敢えて口に出させようとしているハヤブサの意図に気づいて、シュバルツはたまらなく恥ずかしくなる。
だがここまで来て、今更逃げ出すわけにもいかない。
シュバルツは、覚悟を決めた。
もう片方の手も、そろそろとハヤブサの方へと伸ばす。
「ハヤブサ……」
想いを込めて、彼を見つめる。真っすぐに見つめてくる薄いグリーンの瞳が、とても綺麗だと思った。
「もちろん、私の『ココロ』も―――――お前のもの、だから………」
「シュバルツ……!」
嬉しい。
心も身体も、俺に捧げると彼は言ってくれた。
それがどんなに俺を幸せにしているか―――――
彼は気づいているのだろうか?
愛おしさが命じるままに、ハヤブサはシュバルツを抱きしめる。もう一度唇を奪い、頬から首筋にかけて、キスの嵐を降らせた。
「は………! あ………! あ………ッ!」
それに、ぴくん、ぴくん、と、反応をしてくれるシュバルツ。胸を弄ると、その反応と嬌声は、いっそう大きくなった。
ああ
なんて、愛おしい。
なんて、愛おしいのだろう。
そのヒトは、いつの間にか、修羅の道を歩む自分の心の一番奥深い場所に、そっと入り込んできていた。
自分にとっては、かなり危険な類の侵入者に当たる。普通なら、躍起になって排斥せねばならない存在になるはずだった。
だが、入ってきたそのヒトは、ただ静かに、自分の心に寄り添ってくれていた。
自分の何を、破壊するでもなく。
自分の何を、否定するでもなく――――
ただ、優しく寄り添ってくれたヒト。
こんな存在は初めてだ。
得難いヒト。
愛おしくてたまらない。
失いたくないと―――――願う。
「あっ!! ああっ!! 深……い……っ!!」
四つん這いにさせられ、腰を高く持ち上げさせられたところに、ハヤブサの物が強引に侵入してくる。そのままぐちゅぐちゅと、その中をかき回されるように動かれた。
「ああっ!! くう……ッ!!」
さらにそれだけで止まらないハヤブサの熱は、さらにシュバルツを求めてくる。手がシュバルツの牡茎に伸びてきて、そこを強く擦り上げ始めた。
「駄目っ!! そんな、事……! 止め……! イク……っ!! イク、からぁ……!」
内側と前を襲ってくる熱い熱と刺激にシュバルツは耐え切れなくなる。ビクビクッ! と、身を震わせながら達してしまう。ただその瞬間、ハヤブサの手がシュバルツの牡茎を包み込み、精をそこで受け止められてしまった。
「あ……………!」
達した余韻の熱に酔うシュバルツ。息を喘がせながらその身を小さく震わせていると、乳首にいきなりぺちゃ………と、生暖かい物が擦り付けられてくる。
(あ………! 私の物が………)
自分の精子を身体に塗られるという異様な状況に、シュバルツは少し戸惑う。
しかし、特に抵抗をする、ということはなかった。
自分は、ハヤブサになら、何をされてもいいと思っているから。
「ん…………!」
ぬるりとした生暖かい感触が、シュバルツの両の乳首を襲う。
シュバルツはそれに耐えながら、背後のハヤブサにその身を委ねた。自分を穢し続けるハヤブサの肩に、そっとその手を回す。「その行為すら許す」という、シュバルツの気持ちの表れだった。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは愛おしいヒトの、その媚態に酔う。
人形のように、無抵抗なのとは違う。確かな『意志』を持って、自分の行為を許してくれる。彼のその愛情が感じられるのが嬉しい。
もっと、それを欲する。
もっと深く、確かめたくなる。
彼のその『愛情』を―――――
もっと、もっと
「フフ…………」
ハヤブサは、精を吐き出したシュバルツの牡茎を改めて手で拭うと、白く汚れたその指を、シュバルツの口の前に差し出した。
「あ……………」
(何だろう……? 清めろ、と、いうことなのだろうか………?)
「……………」
おずおずと、シュバルツの口が開く。そこに、ハヤブサの指がチュプン、と、音を立てて突き入れられてきた。
「ん…………!」
ハヤブサの望むままに、その指を舐めて清めるシュバルツ。チュ、チュプ、と、濡れた水音が、モーテルの部屋に響いた。
「シュバルツ………」
ハヤブサはシュバルツに己が指を舐めさせながら、繋がったままの秘部の律動を再開させる。
「んっ!! んぐっ!!」
くぐもった悲鳴を上げながらも、指を清め続けてくれるシュバルツに、ただ、愛おしさばかりが募った。ハヤブサはシュバルツの口から指を引き抜くと、彼の顎を捉えて、強引にこちらへと振り向かせた。
「あ………? んぅっ!!」
そのままシュバルツの唇を、強引に奪う。舌を侵入させて、その口腔を存分に味わった。
「だ! 駄目だっ!! ハヤブサ……! あっ!!」
しかしシュバルツは、その口づけには抵抗の意を示した。懸命に彼から身を離そうとして、失敗してしまい、またその唇を奪われてしまう。
「ん………! う…………!」
ちゅくちゅくと、唇を吸われながら、下の律動も続けられる。モーテルのベッドが、ぎしぎしと悲鳴に近い音を立てて軋んだ。
「は…………!」
上と下からの刺激に耐えられなくなり、シュバルツの身体が脱力していく。ハヤブサはそれを優しく支えると、彼の身体をトサリ、と、仰向けにベッドの上に押し倒した。
「あ…………?」
呆然とするシュバルツの上に、ハヤブサの身体が覆いかぶさってくる。彼はそのままシュバルツの乳首にそろそろと舌を這わせた。彼に塗り付けた物を、舐めとるために。
「馬鹿ッ!! ハヤブサ!! 止めろっ!!」
ハヤブサが『何』を舐めようとしているのかを悟ったシュバルツは、懸命にハヤブサの下から逃れようとする。しかしいち早くそれを察していたハヤブサによって、抵抗の手段がまたも封じられてしまった。抑え込まれたシュバルツの身体に、ハヤブサの舌が、ぺちゃ……と、音を立てて押し当てられる。そのまま彼は、シュバルツの身体に塗り付けられた彼の精子を、舐め取り始めた。
「いや……あ……ッ! そんな物……舐めるな……! ハヤブサ……!」
シュバルツが首を横に振りながら、懸命にハヤブサに訴えてくる。ハヤブサはわざと「何故だ?」と、問い返した。
「そ、そんなこと……分かっているだろう!? 私の身体から出たものは……!」
「それは杞憂だ。シュバルツ」
ハヤブサはシュバルツの言葉を一刀両断にする。
「いい加減認めろ、シュバルツ。俺とお前はもう何度、身体を繋げたと思っている? それなのに俺は、DG細胞には感染していない。お前から俺に感染することは、おそらく無いのではないのか?」
「し、しかし………!」
なおも躊躇うようにこちらを見つめてくるシュバルツに、ハヤブサは優しく微笑みかけた。
「それにな、シュバルツ。お前が『腐墨の術』で傀儡状態になっている間に、お前に何度もフェラをした」
「な…………!」
「こんな風に―――――」
ちゅぷっと、音を立てて、ハヤブサがシュバルツの牡茎を口に咥える。そのままハヤブサの口が、シュバルツ自身を愛し始めた。
「あ…………! ああ………!」
感じるところを舐められ吸われて、シュバルツはもう身悶えるしかできなくなる。そこに追い打ちをかけるように、ハヤブサが声をかけてきた。
「何度もお前を、口で受け入れた……。それこそ、数えられないくらいにな」
「そ、そんな………!」
「だが俺は………何ともなっていないだろう?」
「……………!」
シュバルツは茫然とハヤブサを見つめる。ハヤブサは『ハヤブサ』のままで、にこりと微笑み返してきた。いつもと同じ、優しい笑顔で――――
「安心しろ、シュバルツ。お前の身体が俺を殺す事はない」
「ハヤブサ……」
勿論ハヤブサは、シュバルツの身体になら、殺されてもいいと思っている。彼の身体からDG細胞を感染させられても、自分は彼を恨むことはないだろう。
だがそれは絶対に口には出さないと、ハヤブサは決意していた。
そんなことを言ったら、彼をひどく哀しませてしまう。それをハヤブサは知っていたから。
「だから怯えるな……。お前のすべてを、俺に赦してくれ」
「…………!」
「愛している……! シュバルツ……! 俺はお前の総てに触れたいんだ。全部が欲しいんだ……!」
「あ…………!」
「拒絶するな……! 心も身体も―――――お前の総てを、俺にくれ……!」
「ハヤブサ……!」
ハヤブサの熱い眼差しの前に、シュバルツは涙を堪えきれなくなる。
「ハヤブサ……ッ!」
自らの心の衝動が命じるままに、シュバルツはハヤブサの胸に、飛び込んで、いた。
「シュバルツ……!」
愛おしいヒトの行動に呆然としながらも、ハヤブサはシュバルツを抱きとめる。するとシュバルツの方も、縋る様にハヤブサの背に手を回してきた。
「ハヤブサ……! 本当に……! お前は――――」
「えっ?」
「本当に、お前は……私からDG細胞が感染(うつ)らないのか? 私の身体が、お前を殺すことはないのか……?」
涙ながらの愛おしいヒトの問いかけに、ハヤブサは「ああ」と、力強く頷いた。
「現に、俺は何ともなっていないだろう? 大丈夫だ」
「本当にそうなのか? 約束できるか……?」
「約束……?」
怪訝そうに小首をかしげるハヤブサを、シュバルツはまっすぐに見つめる。
「私の身体で、お前は死なないと――――」
真剣な眼差し。
懸命な問いかけ。
ハヤブサは、いい加減な気持ちで答えてはいけないと思った。
「ああ、約束しよう。シュバルツ」
愛おしいヒトの背に、そっと、手を回す。
「お前の身体が原因で、俺が死ぬことはない。そう言い切れるぐらい――――俺はお前に触れているから」
「ハヤブサ……!」
「だからシュバルツ……。俺にすべてを―――――」
ここでハヤブサは、これ以上言葉を紡げなくなってしまう。何故ならシュバルツの唇が、ハヤブサの唇を、ふわりと塞いでしまっていたからだ。
「…………!」
呆然と愛おしいヒトを見つめ返すハヤブサに、シュバルツは優しく微笑みかけた。きれいな笑顔だと、ハヤブサは思った。
「ハヤブサ……。ありがとう……」
「シュバルツ……!」
「今度こそ、私の総てをお前に捧げる……。私の心も身体も――――すべて、お前の好きにしていい………」
そう言って微笑むシュバルツが、あまりにも綺麗すぎて
あまりにも愛おしすぎて――――
ハヤブサの中で、何かが音を立てて切れてしまっていた。
「シュバルツ!!」
無我夢中で、愛おしいヒトの身体を押し倒す。そのまま、貪るようにその身体を愛した。
これは、彼のヒトを清めるための『儀式』などではない。
純粋に、このヒトを愛するための行為であるため、ハヤブサは遠慮などもうしなかった。
ただひたすらに、奔放に――――愛おしいヒトを、心のままに愛した。
「あ…………!」
ピュク、と、音を立てて、シュバルツが達するのが見える。
それでいいのだ、と、ハヤブサは思った。
どのようなタイミングで果てようが、どのように愛撫を進めようが、手順を気にする必要など、もうないのだから。
(ハヤブサ……。切れてる………)
嵐のような愛撫と行為に翻弄されながら、シュバルツはそう感じていた。
ハヤブサは自分を抱くとき、理性も何もかもを吹き飛ばして、狂ったように求めてくることが、多々あったからだ。
疑問だ。
常々疑問だった。
男で
アンドロイドで
人間の温もりすら伝えていないこの身体の、いったい何が良いと、ハヤブサは言うのだろう。
絶対に、抱くのならば女性がいい。
それも、『人間』の女性がいい。
きっと、その存在の方が柔らかい。
そして、温かい。
そして何よりも、男の猛り狂う『それ』を、受け止める器官だってちゃんと備わっている。そこから、その『血脈』を受け継ぐ『家族』という尊い宝物を、産み出すことだってできるのに。
なのに、私をこんなにも、求めてくるハヤブサ。
どうして
どうして―――――
「あ………! あ…………!」
ハヤブサの熱を受け止めきれずに、ピュル、と、今日何度目かの達した証を吐き出す。
信じられないほどの醜態を晒しているのに、それを見るたびにハヤブサが幸せそうに微笑む。
優しく唇を求められる。
内部を執拗にかき回される。
乱暴に穿たれているのに、こちらに触れてくる手は必要以上に優しい。
分かる。
きっと、後にも先にも
こんなにも深く、私を愛してくれる人は―――――
もう、いないだろう。
ハヤブサ
愛している
たとえ、この先どうなろうとも
お前と死に別れてしまったとしても―――――
私が愛すのは、お前だけだ。
だから、存分に私の身体を引き裂け。
蹂躙して、刻み付けてくれ。
お前の愛を
その熱を
忘れない。
私はずっと、忘れないから。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
狂ったように腰をたたきつける。
喘ぐ愛おしいヒトの瞳から、涙が飛び散る。
何故だ?
その哀しげな涙が切ない。
その涙を止めたいと、
幸せそうに笑ってほしいと願うのに。
どうして、そんな風に泣く?
何故――――そんな風に泣くのだ、シュバルツ
愛している
愛している、シュバルツ
俺には、お前だけだ。
お前さえ傍に居てくれれば
もう俺は―――――何もいらないのに。
「シュバルツ……!」
「ハヤブサ……!」
呼びかけに、シュバルツは甘やかなキスで応えてくれる。
背中に手を、回してきてくれる。
縋りつくような彼の媚態がたまらなく愛おしい。
ああ―――――
俺は今「死んでもいい」
そう思えるぐらい、幸せだ。
「ん………ッ! んう………ッ!」
呼吸を奪いながら楔を打ち込み続ける。
胸を優しく弄んでやると、自身を包み込む彼のヒトの内側が、甘く切なく痙攣してくる。
ああ、狂おしい―――――
狂おしいほどに、愛おしい。
これほどの想い、他に知らない。
分かる。
きっと、これほどまでに愛しつくせるヒトは
後にも先にも、もう居ないだろう。
「シュバルツ……ッ!」
堪えきれず、熱を放つ。
その瞬間、その名を呼んだ。
「あ…………! ハヤブサ……!」
同時に、シュバルツも達したのだろう。彼の物が、ピュ、と音を立てて、自分の腹と彼自身の身体を白く汚した。
「ハヤブサ………」
愛おしいヒトがふわりと優しく微笑みながら、自分に向かって手を伸ばしてきてくれる。
(彼の身体を拭かなければ)
頭の隅で、ちらりと思う。しかし、シュバルツに優しく抱きしめられた瞬間、感じてしまうどうしようもない幸福感に、彼は抗うことができなかった。
そのまま優しく包み込まれ、そっと背中を撫でられる。
(ああ、身を休めてもいいのだ)
龍の忍者は素直にそう思った。
すまない、シュバルツ
少しの間だけ――――
お前と繋がったまま眠ることを、どうか許してほしい。
「……………」
自分の腹の上で、ハヤブサが穏やかな寝息を立て始める。
(ハヤブサ……)
シュバルツは、ハヤブサの背を優しく撫で続けた。
シュバルツにとっては、至福の瞬間だった。
この刹那のハヤブサだけは、自分だけのもの―――――
素直に、そう思えるから。
今だけ、ゆっくり眠ってくれ。
私は、お前のその眠りを守るから。
傀儡となり、意識を失った私を
ずっと、お前が守ってくれていたように。
(愛している……)
シュバルツは想いを込めて、ハヤブサの身体を抱きしめ続けるのだった。
最終章
シュバルツ・ブルーダーは辟易していた。
どうしたらいいのだろう、と、深いため息を吐くほかなかった。
シュバルツがハヤブサと共に日本に帰国した時、キョウジが感極まったように出迎えてくれた。
「シュバルツ……! 本当に……! 本当に、大丈夫なのか? こうして私が触れても………!」
まったく自分は問題無いので、シュバルツは「ああ」と頷く。すると、キョウジはいきなりシュバルツに縋る様に抱き付いてきた。
「シュバルツ………!」
「お、おい!? キョウジ……!」
「シュバルツ……ッ! よかった………!」
そのままギュッと、強くシュバルツの身体を抱きしめるキョウジ。
「キョウジ………?」
シュバルツが戸惑っていると、横にいたハヤブサから声をかけられた。
「お前が『術』にかかっている間、お前の身体は俺以外が触れられない状態になっていたんだ」
「な…………!」
驚くシュバルツに、ハヤブサは少しバツの悪そうな表情を浮かべる。
「キョウジも、お前を守るために、色々尽力してくれたんだ……。察してやってくれ」
「……………!」
ハヤブサの言葉にシュバルツも、自分を抱きしめるキョウジの身体の小さな震えに気づいてしまう。そうなると、シュバルツももう――――何も言えなくなってしまった。
「キョウジ………」
シュバルツも、そっと、キョウジの身体を抱きしめ返す。
「すまなかったな……。心配を、かけた……」
謝るシュバルツに、キョウジは小さく頭を振った。
「ううん、心配だなんて――――」
「俺からも、謝らせてくれ、キョウジ」
ハヤブサも、改めてキョウジに声をかける。
「俺のせいで、迷惑を――――」
「だから迷惑じゃないって! ハヤブサ!」
キョウジは少し、語気を強めてハヤブサの言葉を否定した。
「こういうのはお互い様で、迷惑をかけたとかかけられたとか―――――そう言うんじゃないんだ。それは、勘違いしないでほしい」
「キョウジ………」
「こうしてシュバルツを無事、返してくれた……。私はそれで、十分だ」
そう言って、シュバルツをまたギュッと、抱きしめるキョウジ。それにシュバルツはキョウジの背中を優しく撫でることで応え、ハヤブサは、小さくため息を吐いた。
「じゃあキョウジ、シュバルツ。俺は、ここで」
そう言ってハヤブサはそこで別れようとする。キョウジはびっくりして顔を上げた。
「もう帰るのか? お茶でも……!」
「いや、それには及ばない。俺は取り急ぎ、里へ任務の報告をせねばならん」
キョウジの誘いを、ハヤブサは苦笑しながらやんわりと断る。
「ハヤブサ………」
「だからキョウジ……。お前は、シュバルツと積もる話があるだろう。二人でゆっくり過ごしてくれ」
「う…………」
キョウジが少し赤面するのを、ハヤブサは微笑ましく見つめていた。
こういう時のキョウジの顔は、本当に、愛おしいヒトとそっくりだ。
だが、ある意味当たり前の話だ。
シュバルツはキョウジの人格を基にした、その分身のようなものなのだから。
それでは、と、踵を返そうとするハヤブサを、シュバルツが呼び止めた。
「ハヤブサ……! また、会えるよな?」
「ああ。近いうちにな」
ハヤブサはそう言いながら、手を上げて答えた。
(だが……しばらく大変なのは、シュバルツの方だろうなぁ。キョウジもドモンも、シュバルツと触れ合えないことに、だいぶ『来て』いたから……)
自分はいいのだ。
ここに来る前に、シュバルツと深く触れ合っているから。
今は、自分は身を引くべきなのだ。
自分まで駄々をこねて、愛おしいヒトに迷惑をかけるわけにはいかないのだから―――――
(しかし、シュバルツは愛されているよなぁ)
そう感じて、ハヤブサは何故か嬉しくなってしまう。
愛おしいヒトが愛されるべき人に愛されて、幸せそうにしている姿を見るのは大好きだ。
こちらも、幸せな気持ちになれるから。
だが、近いうちに、必ずシュバルツの顔を見に来よう。
ハヤブサはそう決意をして、歩き出していた。
そうして、シュバルツは無事に家に帰りついたのだが。
「よかった……! シュバルツ……! 帰ってきてくれて本当に良かった……!」
家に帰るなり、キョウジはそう言って部屋の方へとすたすたと歩いていく。
「ああ、すまなかったな、キョウジ……。心配を―――――」
そう言いかけたシュバルツの前に、キョウジが書類やらファイルやらの束の山を持って、ドンッ! と、勢い良く積み上げる。置いた拍子に、机の上から埃が舞い上がっていた。
「な、なんだぁ!?」
呆然とするシュバルツの前で、キョウジがパンパンと、手をたたきながら埃を払っている。
「じゃあシュバルツ。早速で悪いんだけど、この書類の整理をしてくれる?」
「えっ?」
「それが終わったら、夕飯の買い出しとアカサカ教授の実験の手伝いをして――――」
「へっ?」
「あ、その前にコーヒー淹れて、肩揉んでくれたら嬉しいなぁ」
「お、おい!? キョウジ――――!!」
早速自分をこき使う気満々のキョウジに、シュバルツがたまらず待ったをかける。
「何? シュバルツ」
「確かに私は数日家を空けていた形になってはいたが…………ど、どうしてこんなに仕事が溜まっているんだ?」
「当たり前でしょう? 今まで私とシュバルツ、二人で結構手一杯の仕事量を回してきていたんだ。それが片方の手が止まって、それでも振られてくる仕事量が変わらなければどうなるか―――――それは、自明の理だと思うけど?」
「そ、それはそうかもしれないが―――――」
「おまけに事あるごとにアカサカ教授に呼び出されて雑用は増えるし、ドモンは頻繁に訪ねてくるし―――――私は全部、それらを一人で対処していたんだ!」
「う…………!」
「私だっていい加減ちょっとぐらい休みたい! シュバルツ!! 今すぐコーヒー淹れて!! シュバルツが淹れてくれたコーヒーが飲みたい!! 淹れてくれなきゃ死ぬ―――――ッ!!」
そう言いながらキョウジが床に寝っ転がってじたばたしだしている。
(うわ~~~~………何だ、この駄々っ子………)
久しぶりに見るキョウジの甘えっ子ぶりに、さすがのシュバルツもちょっと引き気味だ。
目の前のキョウジの態度にどう対処しようかとシュバルツが思案していたところに、ドモンが勢いよく部屋に飛び込んできた。
「兄さん!!」
「ド、ドモン!?」
兄二人が自分の方に振り返ったのを見て、ドモン安堵の混じったため息を漏らす。
「よかった………! シュバルツが部屋に入っていくのが見えたから―――――」
「ドモン………」
心配かけたな、と、シュバルツが言うより先に、ドモンがつかつかと歩み寄ってきて、シュバルツの手をギュっ、と握る。
「兄さん……!」
「ドモン? どうした?」
「兄さん頼む! 今すぐ俺と手合わせをしてくれ!!」
「へっ?」
「兄さんと手合わせできなくなって半月―――――俺はもう、限界だ!!」
「ド、ドモン!?」
「兄さん!! 手合わせに行こう!! 今すぐ!!」
そう言いながらドモンが、強引にシュバルツを外に連れ出そうとする。シュバルツは少し慌てた。
「ま!! 待てっ!! ドモン!!」
「どうしたの? 兄さん」
「い……いや、キョウジが―――――」
そう言いながらシュバルツが、キョウジの方にちらりと目線を走らせる。
「キョウジ兄さんが?」
ドモンもシュバルツにつられて、キョウジの方を見る。そしてそこで言葉を失ってしまった。何故ならキョウジが、とても悲しそうな瞳で、こちらを見つめていたからだ。
(ああ……。私がドモンに連れていかれそうになって、ものすごく嫌がっているな)
キョウジの気持ちが手に取るように分かるシュバルツは、キョウジの表情からそんなことを読み取っていた。
(あ、でも、兄として弟を優先してあげなければならない、と、葛藤しているな。「お兄ちゃんでしょ!?」と、自分で自分に言い聞かせている状態だ……)
椅子の背を握りしめながら、唇をかみしめて視線を横にそらしているキョウジ。それがそのままずるずると、床に座り込んでしまった。
(でもこっちにだって仕事があるんだ……! それを、それを……! って、なってる……。だが、ドモンの気持ちもわかるし……。うう~~ん……どうしたものか………)
「な、なあ、シュバルツ……。キョウジ兄さん、どうしちゃったんだ? 様子が変だけど……」
普段、自分の前でなかなか感情を露わにしないキョウジが、床に座り込んだりしているものだから、ドモンも動揺が隠せないらしい。シュバルツはもう、苦笑するしかなかった。
「………いいよ、ドモン………」
ここで、それまで黙っていたキョウジから、絞り出されるような声が発せられる。
「………シュバルツと、手合わせに………行ってくればいい………」
「いや、でも兄さん………」
「キョウジ、そういうことを言うのなら、せめて血涙を流すな」
キョウジの様子に、シュバルツが呆れ返りながら突っ込みを入れる。
「仕方がないだろう!? 私だって……ッ!」
反論するために顔を上げたキョウジだが、その言葉はすぐに途切れることになってしまった。何故なら―――――
「フン! 相変わらず兄御に迷惑をかけておるのか! この馬鹿弟子が――――!」
いきなり東方不敗が床から生えてきたので、その場にいた全員が、ひっくり返るほどに驚いてしまったからだ。
「師、師匠!?」
立ち直ろうとしたドモンの前に、東方不敗は居丈高に立って構える。
「ドモンよ! 今日のロードワークはどうした!? わしのところにまだ終了の報告が入っておらぬようだが―――――」
「そ、それは………! もう少し後でやろうとしていたんだッ!!」
「修行に後も先もあるか!! この馬鹿弟子が!!」
東方不敗はドモンの言葉を一刀両断にする。
「よいか!! 男児たるもの己に課せられた課題というものは、何があっても投げ出してはならぬもの!! それを己の感情に負け、放り出すとは何事かぁ!!」
「放り出したわけじゃない!! 兄さんの無事を確認したくて………!!」
「フン!! その為体―――――次の大会では、優勝どころか一回戦負けじゃろうよ!! この馬鹿弟子が!!」
「何ぃ!?」
ぎりぎりと睨み付けるドモンに対して、東方不敗は右手をバッと目の前に開いて突き出してみせる。
「5秒じゃ!」
「?」
「今の貴様など―――――5秒で瞬殺してくれる!!」
「な―――――!」
傍目にも大変分かりやすい挑発行為。しかしドモンは、東方不敗のこの挑発に、頭から突っ込んでいった。
「上等だ!! 5秒で瞬殺されるのは東方不敗!! 貴様の方だ!!」
「ぬっ!! 師に向かってなんという口の利き方……! その根性、叩き直してくれる!!」
「やれるものならやってみろ!!」
一流の格闘家の、阿呆みたいなやり取りを一通りした後、師弟は勢いよく外へと飛び出していく。呆然とそれを見つめていたキョウジのところには、一枚のメモの切れ端がひらひらと舞い落ちてきて、シュバルツのところには、丸まった紙がぶつけられていた。
「?」
二人は、同時にそれを開く。
キョウジの物にはこう書かれてあった。
(ドモンは引き受けた。後は存分にやるがよい)
対してシュバルツのところには
(貸し一つじゃぞ!!)
と、でかでかと書かれていたので、シュバルツは「うわ……」と、思わず口走ってしまっていた。
東方不敗に『貸し』だなんて、微妙に怖い。後で、3倍返しを要求されたりしないだろうか。
「よかった……! シュバルツ、じゃあ早速、書類の整理をしてくれる?」
だが、キョウジのこの心底嬉しそうな顔を見ると、細かいことは割とどうでもよくなる。こういうところが、自分はかなり単純なのだろうか。
「分かったよ」
シュバルツもため息を吐きながらも立ち上がり、書類の山へと向かっていった。その面にかすかに、優しい笑みを浮かべながら――――
しかし。
小一時間もしないうちに、シュバルツの表情にはしかめっ面が張り付くようになってしまう。何故なら、やはりと言うべきか―――――キョウジの甘えっぷりがひどくなっているからだ。
「キョウジ………」
「なに? シュバルツ」
「いつまで私の背中にくっついているんだ?」
「ああ……私は一向にかまわないから、そのまま作業を続けてくれる?」
そう言いながらキョウジは、シュバルツの背にもたれかかりながら書類を読みつつコーヒーを飲んでいる。これはもちろん、シュバルツの淹れてくれたコーヒーだった。
「いや、お前が構わなくても、私が構うんだ」
「なんで?」
「邪魔だ!!」
シュバルツは知らず、大声で叫んでいた。
「何故私の背中に張り付いて、いちいち書類を読んでいるんだ!? ここじゃなくても他に椅子とかあるだろうが!!」
「だって、ここでいるのがいいんだもん。は~………シュバルツの背中、落ち着く………」
「キョウジ………!」
いつものシュバルツなら、ここで「阿呆か―――――!!」と、怒鳴りつけているところだ。しかし、シュバルツの方にも、しばらく家を何の予告もなく空けてしまったという微妙な負い目がある。それが、彼の反撃の手段を何となく奪う結果となっていたのだ。
そうこうしているうちに、今度はドモンが部屋に入ってくる。
「は~………疲れた……。シュバルツ~~」
彼もまた、そう言いながらキョウジの横に座って、シュバルツの背中にもたれかかってきた。
「おい………」
かなりシュバルツは苛立ちながらドモンに声をかけたのだが、ドモンは逆に身をすりすりと摺り寄せてきた。
「は~~……本当に、こうやって触っても、もう大丈夫なんだな……」
「…………!」
「ずっと、キョウジ兄さんや師匠やレインから、「シュバルツに触っちゃダメ!」って言われ続けていたから……」
「ドモン……」
弟のその言葉に、ハヤブサのみならず、本当に皆に迷惑をかけてしまったんだな、と、シュバルツは少し申し訳ないような気持ちになる。しかし――――
「シュバルツ~……」
「はあ~……落ち着く……」
二人がかりでまったりともたれかかられると、どうにも重いし、結構邪魔になるわけで――――
「ええい! 鬱陶しい!! いい加減離れろ―――――ッ!!」
シュバルツの叫び声が、キョウジのアパートからこだまする。
この兄弟の甘えっ子攻撃は、当分の間続くことになるのであった。
END
マリオネット狂想曲
皆さまこんばんは、空由佳子と申します。
このたびは、私の小説を読んでくださいまして、どうもありがとうございました。
かなり怪しからん内容になってしまいましたが、本人は楽しんで書かせていただきました。
いかがでしたでしょうか?
またブログやツイッターの方に感想をいただけると嬉しいですが……無理だろうなぁ。
でも毎日欠かさず読みに来てくださった方、本当にありがとうございました。
あなた方の存在が、私の創作意欲の原動力になっていますです。はい。
しかし、話を終わらせるのって、本当に難しいですね。それともこんな悩みを持つのは、私だけなのかな。
いつもいつも、盛り上がりが終わって、そのあとの惰性で最後の文章に到達するまでの話が筆が進まなくなります。いったいどうしてなのでしょう。
さて、今回の話はここで終わります。また何か話が思い浮かべば、ここに上げに来るかもしれません。その時まで、私のことを覚えておいていただければ、その時はまたお付き合いいただけると嬉しいです!
それでは皆様、次回作までごきげんよう!