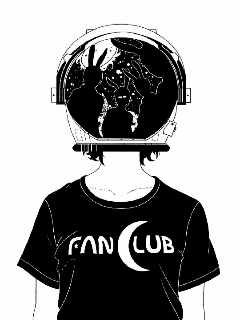秋・眼鏡・7
「どうして秋だけ特別なのかしら。読書も芸術も、スポーツも食欲も、秋に限った話ではないと思うのだけれど」
藤堂乃枝は独り言のように話す。そこには返答を求める気配があまり感じられない。
「それなら、後ろに『秋』を付ければなんだって秋のものにしてしまえるわ。他の三大欲求はどうかしら。人恋しい季節、と言ってみたところでそれは性欲に他ならないし、睡眠の秋、なんて如何にもな響きじゃない。秋眠暁を覚えず、といったところね」
随分とあけすけな物言いをする。桐嶋修介は何と言って良いかわからず、
「はぁ」と間抜けな声を出した。
自分が仕える相手になるかもしれないのだ。呆気に取られたままでは不味い。
「あなたでもう、七人目よ。ロクな人間がいなかったわ。この無意味な問答にそろそろ飽きてきても私に責任はないでしょう?」
「いや、こっちは人生掛かってるんですけど」
修介はたまらず声を挟んだ。これが本当に面接なのかどうか疑い始める頃合だ。彼女に対面して以降、質問らしい質問はまだ一つもなされていない。
緊張をほぐそうと、目だけを部屋の周囲に巡らせる。茶色を基調としていて、両サイドの壁は本棚が占領している。部屋の奥、修介の正面には立派な意匠が施された厳つい机が置かれ、そこに乃枝が悠然と席についている。ここは乃枝の私室なのだろうか。特に説明はされなかったが、だとすれば味気ない。一方こちらに用意された椅子はパイプ椅子だ。
「あなたはどう思う?秋という季節を」
はぁ。反射的に漏れ出そうになる声を修介はなんとか抑えた。どう、だろう。特に思い入れはない。
「えー、と、だから、何をするにも良い機会、なんじゃないですかね。過ごしやすいことに変わりはないわけだし。人間、きっかけがないと案外何もしようとしないんですよ、きっと。そうやって言葉にして季節に頼るのも悪くない、と思います」
適当にでっち上げた。どんどん不安になってくる。この面接において一般的、常識的な質問はまずされないだろう、と修介は覚悟する。
乃枝はただ黙って微笑んで、細めた目で修介を見つめている。そして、徐に机に置いてあった眼鏡を掛けた。
「面接はこれでおしまい、ね。やっとこの苦行から開放されるわ」
乃枝がそう言い放ち、修介は血の気が引いた。これで終わり?冗談じゃない。
「いやいや、もっと、あるでしょう!僕、や、私を掘りさげる質問が!」なりふり構わず修介は叫ぶ。
「いいえ、もう十分。さぁ、早く退室してちょうだい」
これ以上待っても面接再開は見込めない。修介はそう悟って項垂れながら部屋を出た。
その後、修介は別室での待機を命じられた。ガラス張りのテーブルを、長いソファが挟んでいる。そこには六人が既に腰掛けていた。七人目の修介がその端に並ぶ。どうやら面接は修介が最後だったようだ。
眼鏡装着率が異様に高い。如何にも真面目腐った連中が揃っていて、修介は自分だけ場違いであるような気がした。会話なんて、ひとかけらもない。
藤堂家による執事の募集。先程までの面接試験の目的であり、それを目にして現れたのが修介を含む七人だった。
修介は藤堂家について詳しくは知らない。ただ、自宅が近所であるだけだ。そこそこの金持ちではあるようだが、名のある資産家という訳でもなさそうだ。そもそも、ポストに「執事募集!」と手描きで書かれたチラシを入れるという募集方法からして、怪しさはうなぎ上っている。
そんな胡散臭い募集に飛びつく程に修介は職に困っていた。その杜撰な募集方法で、ここまでの執事キャラが揃う世の中の方がどうかしてる。
しばらくして、修介は先程の面接部屋に呼び出された。ドアを二回ノックして入室する。
そこには、カボチャがいた。
目と口がくり抜かれた、あの。
ドアを開けたままの姿勢で固まる修介を促すように、カボチャが喋り出す。
「おめでとう。あなたが、今日からこの藤堂家の執事よ」
こもっていてわかりにくいが、乃枝の声だった。
「なんですか、それ」尚も動けずに修介は言う。
「何って、もうすぐハロウィンでしょう?」
めちゃくちゃ楽しんでるじゃねーか、秋!修介は胸の内で叫んだ。脱力したままパイプ椅子へと腰掛ける。
「私、イベント事はなんでも大好きなの。些細なツッコミは無粋というものだわ。誰かが秋を楽しむために用意した言葉だというのなら、全力で乗っからなきゃ損じゃない」
「さっきと秋に対する態度が違いませんか」
乃枝は頭からカボチャを引き抜いて、脇に置いてから応える。
「女心と秋の空、と言うでしょう」
「それ使い方、絶対間違ってますって」
そう言うと、どちらともなく笑い出した。
乃枝は眼鏡を掛けていた。
後から知ることになるのだが、乃枝の眼鏡は伊達であり、機嫌が良い時にしか掛けないのであった。
秋・眼鏡・7