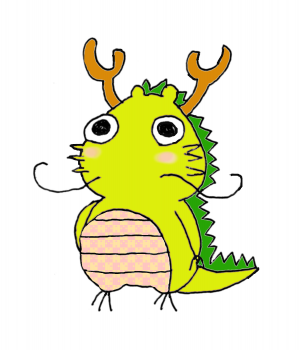龍と剣と、その拳と
皆さまこんばんは。
『ただひたすらに~』の小説の続編とも言える話が浮かんできたので、またちまちまとここにアップして行きたいと思います。
今回の話はあまり色気のある場面は出てきません。しかし、私の書く話の根本には、ハヤブサさん×シュバルツさんの要素が入っている、いわゆる一つのBL小説ですので、それが理解できない方は、どうかご遠慮くださいませ。楽しめる方だけ、どうか読んでいってください。
でも色気のある場面、出てきそうだな……。作者の脳みそが『そう言う』作りだからなのかな……(汗)
一応、登場人物を紹介させていただきます。
・リュウ・ハヤブサ……この物語の主人公、に、なるはず。凄腕の忍者で、その実力は神をも滅すると言われている。現在故あって療養中。
・シュバルツ・ブルーダー……DG細胞でその身体を構成されているアンドロイド。リュウ・ハヤブサの恋人。
・キョウジ・カッシュ……シュバルツの人格の元となった科学者。現在、リュウ・ハヤブサの治療に当たっている。
・ドモン・カッシュ……キョウジの弟でシャッフル同盟の『キング・オブ・ハート』の紋章を背負う者。凄腕の格闘家。
・東方不敗マスターアジア……ドモンの師匠で、先代の『キング・オブ・ハート』 とある事件をきっかけに、キョウジに少し傾倒気味。
・チボデー・クロケット
・ジョルジュ・ド・サンド ……シャッフル同盟の仲間たち。『デビルガンダム事件』以降、ドモン・カッシュと強い絆で結ばれている。
・サイ・サイシー
・アルゴ・ガルスキー
……と、まあ、こんなところでしょうか。
では、よろしくお願いいたします。
序章
闇の中、夢を見ていた。
その夢の正体を悟った瞬間、その夢の主は『いやだ』と足掻いた。
これは、自分を苛む悪夢。
早く覚めなければ。
早く―――――!
だが悪夢は続く。
自分は剣を突き立てていた。
目の前に居るのは愛おしいヒト。
それに向かって、何度も、何度も――――
イヤダ
イヤダ
心は悲鳴を上げ、泣き叫ぶ。
だけど、自分はそれを無視した。そうしなければならなかった。
だって――――自分は、このヒトの手を、振り払ってしまったのだから。
このヒトの事を思い出すと、哀しませてしまう人がいる。
それは駄目だ。
だから
だから―――――
なのに、何度斬りつけても、引き裂いても
目の前の愛おしいヒトの、優しい笑顔は消えない。
その人は手を広げ、無防備に、あけすけに――――自分が何度もこのヒトを傷つける事を赦している。赦し続けている。
ああ
もう、そんな風に俺を許すな、シュバルツ。
俺を憎んでくれ。
恨んでくれ。
いっそ、俺を殺してくれ――――!
ああ
もういっそ、この剣で
一思いに、楽 に
「ハヤブサ!! 駄目だ!!」
目の前の愛おしいヒトが、叫び声を上げる。
それに俺は、首を横に振って応えた。
もういい
もういいんだ、シュバルツ
疲れた
疲 れ た
「ハヤブサ!!」
剣を自分に突き立てようとした刹那、愛おしいヒトに腕を取られる。
「離せ!!」
足掻いた瞬間、もう一度怒鳴られた。
「ハヤブサ!! 起きろ!!」
「―――――!?」
その叫び声でリュウ・ハヤブサはようやく、自分が『悪夢』を見ていた事を、思い出したのだった。
第1章
「ハヤブサ!!」
目が覚めた瞬間、自分の視界いっぱいに広がる、愛おしいヒトの心配そうな顔。
「―――――!」
ハヤブサは瞬間的に身体をひきつらせた後、思わず叫び声を上げていた。
「うわあああああっ!! あああっ!!」
自分が、まだ『悪夢』を見ている、と、思ってしまったからだ。
「ハヤブサ!! 落ちつけ!! 大丈夫だ!!」
方を強く掴んでこちらをまっすぐに見つめながら、懸命に呼びかけてくる、愛おしいヒト。それを見て、ようやく――――ハヤブサも、落ちつく事が出来た。
「あ…………!」
息を荒らげ、小刻みに震えるハヤブサの身体を、シュバルツがそっと、抱きしめる。
「ハヤブサ……」
「シュバルツ……ッ!」
それにハヤブサが、縋りつく様に抱きしめ返してきた。そのままシュバルツの胸に顔をうずめ、身体を振るわせ始める。泣いているのだと、シュバルツは悟った。
(まだ……細いな………)
震えるハヤブサの背中をあやすように撫でながら、シュバルツは少し、眉をひそめた。少し前に起きた『事件』の影響で、死ぬ直前まで衰弱してしまったハヤブサの身体は、なかなか元には戻らなかった。
彼は『龍の忍者』と謳われる程、その腕前は強く、伝説クラスの忍者であったと言うのに。
キョウジとシュバルツの懸命の治療で一命を取り留めてはいたが、相変わらず食も細く、やせ衰えたまま―――――キョウジの処方する点滴で、命を繋いでいる様な状態だった。
「……夢を、見たんだ……。また……お前を、殺す夢を………!」
腕の中でハヤブサが、声を震わせながらそう訴える。
「嫌なのに……! どうして………ッ!」
「ハヤブサ……」
ハヤブサの背中を撫でながら、ハヤブサにどう言葉をかけたら良いものかと、シュバルツは熟考する。自分としては構わない。ハヤブサにならどう引き裂かれようがどう殺されようが、それはむしろ喜んで受け入れられた。だけどきっと、自分のこの心境をハヤブサに告げた所で、彼の救いにはならない。それは確かな予感だった。
ならば、どうすればいいのだろう。
自分は彼に、何をしてあげられるのだろう。
一度、悪夢に苦しんでいる彼に、「起きた時に自分が居ない方がいいのでは?」と、提案した事がある。だがそれは、ハヤブサに猛烈な勢いで却下された。
「止めてくれ!! そんな事をされたら、それこそ俺は気が狂ってしまう!!」
「ハヤブサ……!」
「お前にこうして抱きしめられて……俺はやっと、悪夢から覚めたのだと実感できるのに………!」
そう言いながら、ぎゅっと、シュバルツに縋りついてくるハヤブサ。彼が言うには、夢の中のシュバルツは、決してハヤブサに触れてくることはないのだと言う。
だから
だから、分かる。
こちらが『現実』なのだと。
「お願いだ……! 傍に、いてくれ……!」
その胸に顔をうずめながら、ハヤブサは願う。
「俺の、傍に………!」
「ハヤブサ………」
優しく抱きしめ返しながら、シュバルツは頷く。
「分かった……。傍に、いるよ……」
自分はもとよりハヤブサの物。ハヤブサが望んでいるのに、自分から彼と離れる理由はなかった。それを聞いてハヤブサも、嬉しそうに微笑んでいた。
だから自分はハヤブサの傍に居る。そして、彼を抱きしめ続ける。
彼の望む限り――――。
だけど、それだけでいいのだろうかとシュバルツは思う。
なかなか、回復しないハヤブサの身体。
何か、自分に出来ることはないのかと、つい考えてしまう。
だが、今のところ何一つ有効な手だてが浮かばないから、シュバルツもため息を吐くほかなかった。
「シュバルツ……」
潤んだ眼差しのハヤブサから、じっと見つめられる。
口付けを望まれているのだとシュバルツは悟った。
「ハヤブサ………」
シュバルツがそっと、ハヤブサに顔を近づけた、刹那。
「あの~。ちょっと良い?」
妙にのんきな声が部屋に響き渡る。
「――――――!?」
完全に不意をつかれた忍者二人は動揺しまくった。シュバルツは慌ててハヤブサから距離を取ろうとした、結果。
「シュバルツ……。ハヤブサが落ちてる」
「―――――!?」
部屋に入って来たキョウジに指摘されて、慌ててシュバルツが振り向くと、哀れベットから突き落とされて、潰れた蛙みたいに床に横たわっている龍の忍者の姿があった。どうやらシュバルツがハヤブサから離れる時、彼を強く突き飛ばし過ぎてしまったらしい。
「わ――――ッ!? ハヤブサ!!」
シュバルツが慌ててハヤブサを助け起こすと、彼はしくしくと泣き出してしまった。
「酷い……! 俺一応病人なのに……!」
「わ……悪かったよ。わざとじゃないんだ……一応」
苦笑しつつも謝りながら、シュバルツは少し眉をひそめる。
(不意をつかれたとは言え……まだやはり、受け身も取れないのか……)
健康な時のハヤブサであるならば、自分があれぐらい突き飛ばした所で、問題なく対処できたであろうに。
そっとその身体を抱きかかえると、やはり異様な軽さを感じた。
「大丈夫? ハヤブサ」
キョウジが苦笑しながら部屋に入って来る。「ごめんね。邪魔をするつもりじゃなかったんだけど」と、少し申し訳なさそうに言うキョウジに、ハヤブサは「問題ない」と、憮然と答えていた。
「どうしたんだ? キョウジ。何の用だ?」
その間に少し落ち着きを取り戻したシュバルツが、キョウジに問いかける。すると、キョウジが部屋の外を指さした。
「いや、ハヤブサにお客様が来ていたから……」
「キ、キョウジ殿! 私の事は別に……! 御二人の時間が終わってからで良いと……!」
部屋の外に来ているであろう人物が、慌てふためいた声を上げる。
「いやでも、遠路はるばる来てくれたわけだし、御連れさんたちのためにも――――」
「そ、そんな……! 私たちがリュウさんの邪魔をする訳には――――!」
その声を聞いて、ハヤブサが素っ頓狂な声を上げた。
「与助か!?」
ハヤブサに名前を呼ばれた声の主は、大変申し訳なさそうに部屋に入ってきた。
「お、お久しぶりです……。リュウさん……」
「お前……! どうしてここに……!?」
「ハヤテ殿が教えてくれたんです! リュウさんがここに居ると――――!」
「ハヤテが!?」
驚くハヤブサに、与助は頷いた。
「リュウさん……。天神流の里の者たちのために、かなり危険な任務についていたんですね……。ハヤテ殿が教えてくれました……」
「…………!」
本当は違う。
自分は、そのハヤテに捕らえられて、求愛を受けていた。
自分が愛するのはシュバルツ唯一人。だが、ハヤブサにとって幼馴染であるハヤテを裏切ることもできなかった。
故に、シュバルツと手を切り、ハヤテの愛に応えていこうとしたのだが。
嘘をつけない自分の心が悲鳴を上げる。
シュバルツを、忘れるのはいやだと泣き叫ぶ。
その悲鳴を無視して心を殺し続けた結果、ハヤブサは身体をも病んでしまった。
崩壊して行く心と体を、ハヤブサ自身、もうどうする事も出来なくて。
気がつけば自分は、衰弱の一途をたどっていた。
もう死ぬしかない
そう覚悟を決めた矢先に、ハヤテが自分を解放してくれて―――――現在に至るのだった。
「ハヤテ殿から詫びられました……。酷い目に合わせて済まなかったと……。シュバルツさんにリュウさんが断交宣言したのも、おそらく、危険な任務に巻き込みたくなかったからだろうと……」
「与助……」
「……………」
忍者二人の目の前で、与助はボロボロと涙を流し続ける。与助は、シュバルツが初めて隼の里を訪れた時から、ずっと二人の事を見守り続けていた存在だった。ハヤブサがシュバルツと断交する旨の手紙を受け取った時も、激しく動揺し、人一倍心を砕いていた。
それだけに、今、再び二人の絆が戻った事を知って、胸の内にこみ上げる物があるのだろう。
「もう……! リュウさんは、何でもかんでも一人で背負いすぎです!」
「う………!」
「もう少し、我々の事も頼ってください!! あまり頼りにならないかもしれませんが、これでも皆心配していたのですから……!!」
泣きながらそう言ってくる与助に、ハヤブサも返す言葉を失う。ただ「すまん」と、小さく返すのが、精一杯だった。
それにしても驚いた。まさかハヤテが自分と別れた後、フォローのために走り回ってくれていたとは。
(ハヤテ……!)
ハヤブサは心の中で、ハヤテに手を合わせていた。
「与助さん? ほら……泣いている場合じゃないでしょう? もうひと組のお客さんを、ハヤブサに取り次いでもいい?」
キョウジに優しく言われて、与助もはっと顔を上げる。
「あ……! そうでした……!」
与助は慌てて涙を拭うと、部屋の外に向かって「入っておいで!」と、声をかけた。すると、その声に合わせて、二人の子供が部屋に入ってきた。
「お前たちは……!」
驚いたハヤブサは、思わず身を起こしていた。それもそのはずで、その子たちは、まさに隼の里の子どもたちであったのだから。
「リュウ様!」
「リュウ様!! 大丈夫!?」
子どもたちはハヤブサの姿を認めると、一目散に駆け寄ってきた。
「リュウ様! 僕初めて里の外に出たよ!」
「電車に初めて乗ったの!」
「地下鉄にも!!」
見舞いに来ているはずなのに、初めての体験に大興奮の子どもたち。ハヤブサは「そうか……」と、聞いていたが、その笑顔はとても優しいものになっていた。
「リュウ様、大丈夫!? とてもお辛そう……!」
「ご病気、まだ治らないの?」
「大丈夫だ……。もうすぐ治るから……」
案じる子どもたちに優しく答えるハヤブサを見ながら、キョウジがこそっと与助に問いかける。
「それにしても……この子どもたち、どうやって選んだの? ここに来るの、凄い競争率高そうだけど……」
「ええ……。本当に大変でした。里の外に出る機会など、小さいうちは滅多にありません。だから、里の子の皆が、ここに来たがって――――」
与助が、よくぞ聞いてくれましたと言わんばかりの表情を浮かべて答える。何でも、ここに来る子供を選抜するために、里では、ありとあらゆる試験が、子供たちに課せられたと言う。
手裏剣の技、剣術、裁縫、脚力、料理―――――その『試験』は、多岐にわたった。
「皆、とても真剣にその試験に取り組んでくれました……。しかし、なかなかに甲乙がつけがたかったので――――――最終的には公平に、『くじ引き』で決定しました」
「…………!」
ズルッとこけるキョウジの横で、与助がうんうん、と、頷いている。
「『運』を持っていると言う事も、生き延びていくためにはある意味必須な能力なので――――」
「そ……そうなのか? そうなのかな……? いや、そうとも言えるのか……?」
与助の言葉に真面目に悩みだすキョウジ。それを、シュバルツも苦笑しながら見つめていた。
(……まあ、確かに、『運』は必要だろうけどな……)
何事かを成し遂げるために、確かにある程度の『運』は必要だ。しかし、それだけではない。『運』を手繰り寄せるためにも、相当の努力が必要だとシュバルツは思った。
「リュウ様! これは、里に咲いていた花です!」
「これは皆で作ったの! リュウ様が、早くよくなりますようにって!」
「千羽鶴……! 大変だったんじゃないのか……?」
花と千羽鶴を受け取りながら、少し茫然としているハヤブサに、子どもたちはにこっと笑顔をその面に浮かべた。
「ううん! ちっとも大変じゃなかったよ!」
「言ったじゃん! 『皆で作った』って!」
「おとうもおかあも、じいちゃんもばあちゃんも手伝ってくれたよ!」
「そうか……」
ハヤブサは千羽鶴と花を、そっとベッドに置くと、子どもたちを優しく抱きしめていた。
「ありがとう……。お前たちの気持ち、確かに受け取った。俺は……早くよくなるからな……」
(いい場面だなぁ)
その光景に、キョウジとシュバルツは少し涙ぐむ。そこに、与助がそっと声をかけて来た。
「キョウジ殿……。これは、少ないですが、我等の里からの寸志です。どうぞ、お受け取りください」
「い、いや、ちょっと待って! 私はそんなつもりでハヤブサの看病をしている訳では――――!」
「いえ……! ぜひ、お受け取りください! このままでは我等の気が済みませぬ!」
「や……でも……! こっちも日頃から、ハヤブサには世話になっているから――――!」
『寸志』と言うには、やけに分厚い封筒が、キョウジと与助の間で暫く押し合いをされていたが、与助の『治療の必要経費と思って――――!』と言う言葉と迫力に押されて、ついにキョウジは封筒を受け取ることになってしまった。
「わ、わかった……! じゃあこれは、治療に有効に使わせてもらう事にするよ」
「ありがとうございます……!」
キョウジの言葉に、与助は心底ほっとしたような笑みを浮かべる。それから、改めてキョウジに問いかけて来た。
「それにしてもリュウさんは……どうしてしまったのでしょうか? まさか、あんなに痩せ衰えているとは思ってもいなくて――――」
与助の問いかけに、キョウジも表情を曇らせる。
「うん………。実は、私も迷ったんだ……。あんなに衰弱した状態のハヤブサを、貴方たちに会わせても良いものかどうか―――――」
だが、自分に近しい人たちに会う事、物や気持ちに触れることは、患者にとってマイナスになることはない筈だ。現にハヤブサも、もの凄く柔らかい笑みを浮かべながら、子どもたちと話している。これは、ハヤブサの治ろうとする意志に、強く働きかける筈だと、キョウジは確信していた。
「貴方たちの存在や想いは、ハヤブサにはきっといい方向に働く筈だよ。でも……貴方たちにとっては、もしかしたらショックだった? ハヤブサのあんな姿は――――」
キョウジの言葉に、与助は静かに頭を振っていた。
「いえ……。私は大丈夫です。子どもたちも、問題なさそうです。ですが……やはり、里の者の中には、ショックを受ける者もいるでしょう」
そう、ハヤブサは伝説と称される『龍の忍者』
その強さに、信仰めいた想いを寄せている者たちも、少なからずいる。
「ですから、詳細は伝えず、ここで加療中だと言う事だけ、里の者たちには申し伝えておきます。キョウジ殿とシュバルツ殿の傍に居ると知れば、里の者たちも安心するでしょう」
「あはは……。ご期待に添えるように頑張ります」
与助の言葉に、キョウジは苦笑気味に答える。その目の前には、子どもたちと共に優しく微笑んでいる、ハヤブサとシュバルツの姿があった。
子どもたちと与助が里へと帰り、病室にはまた、静けさが戻って来る。
「さて……私は食事を作って来るかな。ハヤブサ、お粥以外で、何か食べられそう?」
問いかけてくるキョウジに、ハヤブサは首を横に振る。
「済まない、キョウジ……。まだ食欲が戻らなくて……」
「そうか……。いいよ、無理しないで」
キョウジは軽く微笑むと、静かに立ち上がった。
「じゃあシュバルツ。ハヤブサをよろしくね。何かあったら呼んで」
そう言い残すと、キョウジは部屋から出て行った。後には、忍者二人が残された。
「……綺麗な、花だな」
シュバルツはハヤブサのベッドの傍の椅子に腰をおろしながら、ハヤブサにそう声をかける。子どもたちが持ってきたピンクや白の小さくて可憐な花々は、こじんまりとした花瓶に、綺麗に活けられていた。その横に、彩りも鮮やかな千羽鶴が、そっと花を添える様に飾られている。
「里で、よく修業をした滝の傍に咲いていた花々だ……。懐かしいな……」
ハヤブサがその花たちを見つめながら、目を細めている。そこに少し、旅愁の響きを感じたから、シュバルツは思わず問いかけていた。
「………帰りたいか?」
「…………!」
ハヤブサは少し目を見開いた後、花を見つめながらフッと笑った。
「……そうだな……。帰りたくないと言えば、嘘になるな……」
「じゃあ、早く元気にならないと……。里の皆も、きっと待ってるぞ」
そう言って優しく微笑むシュバルツの手を、ハヤブサがぎゅっと握ってきた。
「……その時はシュバルツ……お前も一緒に里に来て、くれるか……?」
「―――――!」
シュバルツは瞬間、驚いた顔をしたが、すぐに優しく微笑んだ。
「……そうだな……。キョウジの許可が下りれば、お前と共に里に行っても良い……」
「――――本当だな!?」
「――――!!」
食い入るようにこちらを見つめてくるハヤブサに、シュバルツは瞬間的に『しまった!』と思う。しかしもう遅い。ハヤブサに『里に同行する』と言う言質を取られてしまった。きっとハヤブサの身体がよくなってきたら、自分は里に、半ば強制的に連行されてしまうことだろう。
「……やった!! よしっ!! 早く治さなければな!」
そう言ってガッツポーズを作っているハヤブサに、シュバルツも苦笑しながら(まあ良いか)と、思ってしまう。
これ以上ないと言う程治す意欲に満ち溢れているハヤブサ。
きっとこれは、彼の身体を治す一助になってくれる事だろう。
「シュバルツ」
呼びかけられ、じっと見つめられる。
キスを求められているのだと悟った。
「……………」
シュバルツは、ハヤブサの顔に、そっと己が顔を近づける。
「ん…………」
そのまま忍者二人は今度こそ――――甘い、甘いキスをした。
「……………」
口付けを終えたハヤブサは、シュバルツの身体をぎゅっと、抱きしめて来た。
「はあ……。早くお前を、抱きたいよ……」
「ハヤブサ……」
シュバルツもハヤブサの身体を、そっと抱きしめ返した。
「私はいつでも、お前の傍に居る。何処にもいかないから―――――」
だから、早くよくなってくれ、と、言うシュバルツに、ハヤブサも頷いた。
「少し、寝る……。シュバルツ、手を握っていてくれるか……?」
そう言いながら、少ししんどそうにベッドに身を横たえるハヤブサ。そっと差し出してきたその手を、シュバルツも優しく握りかえした。
「ゆっくり寝ていろ。傍に居るから……」
「ん…………」
シュバルツの手をぎゅっと握り込みながら、瞳を閉じるハヤブサ。暫くすると穏やかな寝息が聞こえ始めた。
(ハヤブサ……)
少しやつれているが、穏やかな表情をして眠るハヤブサの寝顔を、シュバルツはじっと見つめる。そこに、キョウジが入ってきた。
「……ハヤブサ、寝たの?」
シュバルツが頷くと、キョウジはそうか、と言いながらハヤブサの寝顔をのぞき込みに来た。
「……よく、眠っているね……」
「そうだな……」
暫く二人は、そのままハヤブサの寝顔を見つめていたが、やがて、キョウジがポツリと口を開いた。
「………シュバルツ……。おかしいとは思わないか?」
「? 何が?」
「ハヤブサの容体の事だよ。ここで治療を始めてから、もう半月近く経つ。なのに、一向に――――回復する兆しを見せない……」
「……………!」
「何か、他の病気が隠れているのかと調べても見たけど、そうでもない。単に衰弱しているだけなら、休養と栄養剤の投薬治療で、もうそろそろ回復してきてもおかしくはないはずなんだ……」
「そう言えば……!」
驚くシュバルツに、キョウジは頷く。
「人間の身体にも、自己治癒能力は備わっている。DG細胞ほど強烈な物じゃなくても、その人の生命力が尽きていなければ、身体はゆっくりとだけど回復するようになっているんだ。それなのに、今のハヤブサは……」
食欲も戻らず、体力も無い。
死の危険からとりあえず脱してはいるものの、予断を許さない状態である事に、変わりはなかった。
「……もしかしてキョウジは、ハヤブサが治ろうとしているのを、妨害する『何か』があるかもしれない、と……?」
「まだ、そこまでは分からない……。でも、このデータを見てくれ」
シュバルツの言葉を受けて、キョウジは自分のデスクの方にパタパタと走る。手にハヤブサのカルテを持って、戻ってきた。
「こっちが健康な時のハヤブサの血液の成分。そして、こっちが今の血液の成分。………どう? 見比べてみて、何か気づかない?」
「これは………!」
シュバルツには二つのデータの違いがすぐに分かった。
健康な時のハヤブサの血に在るあるたんぱく質が、今のハヤブサの血液からは全く検出されていないのだ。
「分かっていると思うけど……このたんぱく質は、普通の人間の血液からは検出されない特殊な物だ。このたんぱく質があって初めて、『龍の忍者の血液』と言っていい物になるんじゃないかと、私は思ってる」
キョウジの説明を聞きながら、シュバルツもまた、ハヤブサとキスした時に口の中で分析した唾液の成分を思い出していた。
一見、普通の健康な人間の物とそんなに変わらなかったハヤブサの唾液。
だがシュバルツは何故か、その唾液をハヤブサの物にしては『薄いな』と感じていた。
(……まさか、これが原因なのか……?)
データを見ながら息を飲むシュバルツの横で、キョウジもポリポリと頭を書いていた。
「このたんぱく質が血液の中から出て来て、その数値が上がってくれば―――――ハヤブサも治っていくと思うんだけどね……。でも、どうやったらこれの数値が上がっていくのか、私にもさっぱり分からなくて――――」
「確かに………」
データを見て考え込むシュバルツの横で、キョウジも頭を抱え始めている。
「私の加療、投薬方法に問題があるのか………。それとも……別の、何らかの原因があるのか………」
「別の原因………例えば?」
「………『邪悪な者の呪い』とか」
「―――――!」
キョウジの言葉に、シュバルツは目を2、3回しばたたかせる。2人はしばらく互いの目を見合わせてから―――――「ないな。それは無い」と、同時に苦笑しながら視線を逸らしていた。
「馬鹿な事を言っていないで、現実を見ろ、キョウジ。とりあえずその原因っぽい物まではつき止めているのだから、後はそれをどうにかするだけだろう」
「うう~~~ん………。そうなんだけど………」
シュバルツの言葉に、キョウジは難しい顔をしている。
「いかんせん、ハヤブサの血液が特殊すぎるからなぁ。与助さんに聞いておけばよかった……。里の方に、ハヤブサ専門の主治医がいるかどうか――――」
「そう言う人がいれば、真っ先にここに派遣されていると思うがな……」
シュバルツも、今まで何回か隼の里に逗留した事があるが、そう言う主治医的な存在など聞いた事が無いし、ハヤブサが仕事がらみの怪我以外で薬師にかかっているところを見た事が無かった。
「俺、あんまり病気とかした事が無いんだ」
何時だったか、ハヤブサにそう聞いた事がある。
「それに、実は『病院』とか『医療器具』に、あまり良いイメージは無いな……。ああいう類の連中は何故か皆、俺の身体のデータを執拗に欲しがる。人をモルモットか何かみたいに実験対象にして――――」
「ハヤブサ………」
嫌な事を思い出させてしまったと、瞳を曇らせるシュバルツに、ハヤブサは、優しい笑顔を見せた。
「お前がそんな表情をする事は無い。もう、過ぎた事だ」
「しかし………!」
「なら………忘れさせてくれるか? お前の温もりで――――」
「えっ?」
きょとん、とするシュバルツの顎を、ハヤブサの手が捉える。
「シュバルツ………」
そのまま、ハヤブサの顔が近づいて来て―――――
「シュバルツ? どうしたの?」
「―――――ッ!!」
いきなりキョウジに声を掛けられて、シュバルツははっと現実に返る。「わ―――――ッ!!」と、大声を出しそうになるのを、かろうじて堪えなければならなかった。
「大丈夫? シュバルツ。何か顔色が赤い様な………」
「い……! いや、大丈夫だ、キョウジ……! 何でも、ないから……!」
シュバルツはそう言いながら、火照る頬を懸命に両手で押さえている。
「もしかして、熱が出てたりする? ハヤブサの看病で、疲れているんじゃないの? あれ? でもお前に『熱』って………」
「いや、本当に、何でも無いんだ……! 私の事は気にしないでくれ……! 具合が悪くなったら、ちゃんと言うから……!」
シュバルツはキョウジに必死に言い訳をしながら、内心少し舌打ちをしていた。
(ハヤブサ……! あの馬鹿!! あいつが何かにつけて私を抱く口実を見つけては、抱こうとするから―――――!)
何をしていてもハヤブサとの思い出に繋がり、最終的に身体を奪われる所まで容易く繋がってしまう。この状態は、結構困った物だと思う。
「そうなの?」
キョウジはしばらくシュバルツの方をじっと見つめていたが、やがて小さくため息を吐いた。
「……やっぱり念のために、朝一番で隼の里に使いを出すかな……。もしかしたら、何かヒントになる様な事が分かるかるかもしれないし……」
そう言いながら、ハヤブサの血液のデータを食い入るように見つめているキョウジ。彼にして見れは、もう藁にもすがる思いなのだろう。
「さてと……一応、今までのハヤブサの血液のデータをもう一度整理しておくか……。それが終わったら私は寝るけど、シュバルツはどうする?」
キョウジの問いかけに、シュバルツは少しの笑みを浮かべる。
「私は、ハヤブサの傍に居るよ」
「そっか……。うん、それがいいね」
キョウジはシュバルツの答えに納得すると、顔を上げた。
「じゃあシュバルツ……。ハヤブサの血液のデータをまとめた物をデスクの上に置いておくから、私が仕事に行っている間にでも見て、何か所見があったら聞かせてくれる?」
「わかった」
「じゃあ、お休み」
そう言って、キョウジはパタパタと部屋を出ていく。後にはシュバルツと、寝台の上で眠るハヤブサだけが残された。
「ハヤブサ………」
シュバルツは、眠るハヤブサの髪に、そっと触れる。龍の忍者はただ―――――穏やかな寝息を立てるのみであった。
(ハヤブサ………)
暗闇の中で、愛おしいヒトが微笑んでいる。
そのヒトに向かって、自分は刃を突き立て続けている。
(嫌だ……! 止めてくれ……!)
ハヤブサは、すぐにこれがいつも見ている悪夢だと悟った。
どうして
どうしてこんな夢を、見続けなければならないのだ。
もうシュバルツを愛するのに、躊躇う理由など何もない。
心の中のシュバルツを殺す必要など、もうないのに。
どうして―――――
(どうしても、殺したいのか……? お前は私の事を……)
愛おしいヒトの瞳が、哀しげに曇る。
振り上げたクナイが、またシュバルツの胸に突き刺さった。
「違う……! これは、俺の意思じゃない……ッ!」
必死に否定するが、自分の手を止める事が出来ない。瞬間的に絶命したシュバルツの息が、また吹き返す。そこにめがけて、またクナイが振り下ろされた。
「いやだ……! 嫌だ……! こんなのは……いやだ……ッ!!」
(辛いだろう……)
シュバルツから、不意に声をかけられる。
(死なないから―――――)
「――――――!!」
ガツン、と、心臓をぶん殴られたような衝撃を受けるハヤブサに向かって、その『シュバルツ』はにっこりと微笑みかけて来た。
(死なない私の身体を何度も殺して―――――お前は、私に突きつけ続けたいのか? 『お前は不死の化け物なのだ』と――――)
「ち、違う……!」
弱々しく否定するハヤブサの目の前で、血まみれになっているシュバルツが『ククク』と、笑う。
(そうだな……『化け物』……私は確かに『呪われた化け物』だ……)
「シュバルツ……ッ!」
(哀しむことも、否定する事も無いぞ……これが私の真実。私の、真の姿なのだ………)
「違う!!」
ハヤブサは強く頭をふる。
おかしい。
シュバルツがこんな事を言う筈がない。
分かっている。
これは夢。
このシュバルツは、偽物だ。
覚めろ。
早く。
目覚めろ――――!
(おっと……。足掻いても無駄だぞ、龍の忍者……。この私から、逃れられるとでも、思っているのか……?)
『シュバルツ』の形をした何かが、仄暗く笑う。そのままずいっと、近くに寄ってきた。
「―――――ッ!!」
悪意の塊のような存在に、ハヤブサは全身が総毛立つ。
逃げなければ
立ち向かわなければ
選択肢は二つ。
だがハヤブサは、そのどちらも何故か選ぶ事が出来ず、ピクリとも動かぬ己が足に歯噛みするしか出来なかった。
(ひどいな……ハヤブサ……。服がボロボロだ……)
『シュバルツ』は、その面に、酷く穏やかな笑みを浮かべる。
(お前はいつもそうだ……。何時もいつも……私を傷つけて………)
「…………ッ!」
違うと言いたい。
だが、彼を傷つけたことが無いと、胸を張って言えない自分。
反論の言葉は、喉に詰まって出て来なかった。
(いい加減気づけ……。お前は、存在しているだけで大切な者たちを傷つけて行くんだ。お前の大切な者たちは、お前のせいで………やがて引き裂かれていく事になるぞ……)
「う………! う………!」
(今ならば、まだ間に合う……。お前が自ら、命を断てば―――――)
「……ハヤブサ!! ハヤブサッ!!」
『シュバルツ』の声に被さる様に、別の方から声が聞こえてくる。
「―――――!?」
驚いたハヤブサが振り向いた先に、もう一人の、愛おしいヒトの姿があった。
そのヒトの居る場所には、光が差し込んでいた。
光の中から、そのヒトは、懸命にこちらに手を差し伸べて来ている。
「ハヤブサ――――!」
「シュバルツ……! シュバルツ!!」
ハヤブサは、その優しい『光』に向かって、無我夢中で己が手を伸ばして行った―――――
「――――――!」
はっと覚醒するハヤブサの意識。目の前には心配そうにのぞき込む、シュバルツの顔があった。
「ハヤブサ……! 大丈夫か?」
「シュバルツ……!」
ハヤブサはシュバルツの姿を認めるなり、手を伸ばして、縋るようにその身体に抱きついて来た。
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
「ハヤブサ……?」
戸惑いながらも、そっと抱き返してくれるシュバルツ。
「シュバルツ……!」
その優しい感触にハヤブサはホッとしてしまって――――何時しか涙まで零してしまっていた。
「また……悪夢を見てたのか……?」
問うシュバルツに、ハヤブサは震えながら頷く。
「いやだ……! もう嫌だ……! どうして―――――!」
「ハヤブサ……」
「あんな夢……見たくないのに………!」
「……………」
(妙だ)
シュバルツは、震えるハヤブサを抱きしめ返しながら思う。
どうやらハヤブサは、似たような内容の夢を繰り返し見ているようだが、人は、こんなにも何回も同じような夢を見てしまう物なのだろうか?
(……いや、でもキョウジも、同じような夢を見て、よくうなされている事があるものなぁ……。それと、似た様な物なのかもしれない)
キョウジも、シュバルツを作るきっかけとなった『デビルガンダム事件』の夢を、頻回に見て、うなされていた。そのたびに自分がたたき起こして―――――
悪夢から覚めたキョウジは、『起こしてくれてありがとう』と、必ず言う。
しかし、苦しめられた『夢』その物から、キョウジを守れている訳ではない。
デビルガンダムに取り込まれかけて死にかけた、キョウジが負ってしまった心の傷を、自分が完全に取り除ける訳でもない。
独り苦しむキョウジを、自分はただ見ている事しか出来なかった。
今のハヤブサもそうだ。
親友であるハヤテへの想いと、自分への想いとの間で板挟まれ、苦しんで涙していたお前。自分は、その泣いているハヤブサの手を、取ることができなかった。それは結局、ハヤブサを独り、苦しませる事になる。それを、自分は気付けないままに、彼はそのまま心も身体も消耗して衰弱し切って―――――
(………………!)
シュバルツは、いつしかギリ、と、歯を食いしばっていた。
どうして、こんなにも自分は役に立たないのだろう。
どうして、自分はいつも他人の悲劇の傍観者にしかなり得ないのだろう。
でも、じゃあ、どうすれば良かった?
どうすればよかったのだ。
泣いているハヤブサの手を、強引に取ったところで、ハヤテへの想い故に涙を流していた彼の、真の救いにはなり得なかっただろう。哀しいけれど、それだけは分かる。きっとそれはそれでハヤブサを苦しませてしまって―――――
「ハヤブサ……!」
シュバルツはギュッと、縋りついてくるハヤブサの身体を抱きしめた。
「そばに居る……」
そっと、その耳元に囁きかける。
自分は、それしか出来ないし、言えないから。
独り苦しんだ彼を、守ることも救うことも、出来なかったのだから。
「お前の傍に、居るから……」
「シュバルツ……!」
対してハヤブサは、心底うれしそうな笑みを浮かべていた。
あの時、せっかく差し伸べてくれていたシュバルツの手を、振り払ってしまって、ハヤテの元に留まってから半年。シュバルツが自分に対する『想い』など――――とっくに切れてしまっていても、おかしくは無いと思っていた。自分は、彼を裏切ってしまったも同然なのだから。
だが彼は、変わらぬ態度で自分を受け入れてくれて、こうして抱きしめてくれる。
それに自分がどれだけ救われているか―――――彼は分かっているのだろうか?
「シュバルツ」
呼び掛けて、唇を求めると、彼は優しくそれに応えてくれる。
ああ
幸せだ
自分には、勿体ない程の―――――
「……………」
(……やはり、『薄い』な……)
キスを終えてからシュバルツは、口の中でハヤブサの唾液を分析する。『アンドロイド』である彼は、味覚が無い代わりに、その口の中に含まれた物の成分を、事細かに分析してそれをデータ化する事が出来た。故にシュバルツにとって「キスをする」と言う行為は、愛を確かめ合うと言う以外にも、相手の健康状態を把握すると言う意味も、含まれていたりするのだ。
「………落ち着いたか?」
シュバルツがそっとハヤブサに呼びかけると、ハヤブサは「ん………」と、軽く頷いていた。しばらくシュバルツに甘えるようにその身を擦り寄せていたハヤブサであるが、やがて意を決したのか、そっとシュバルツの腕の中から離れて行った。
「……どうだ? 俺の唾液は、少しは元に戻ってきているか……?」
シュバルツの口の機能を知っているハヤブサも、そう問いかけてくる。それに対してシュバルツは、苦笑しながら答えた。
「まだまだだな……。『健康』と言うには、ほど遠いようだ」
「何でだ……! ここにきて半月も経つのに、どうして俺の身体は治らないんだ……?」
はあ~~~、と、大きなため息を吐くハヤブサに、シュバルツは宥めるように声をかけた。
「焦るな、ハヤブサ。ゆっくりとだが治って来ているんだ。今は、身体をきちんと休めるのが肝要、と言う事なのだろう」
「そうなのだろうが………」
ハヤブサは、納得できない、と、言わんばかりにもう一度、大きなため息を吐いていた。
「夕食、食べていないだろう。何か食べるか?」
シュバルツの提案に、ハヤブサも頷く。
「そうだな……。あまり腹は減ってはいないのだが………」
「それでも少しぐらいは食べないと――――よくはならないぞ?」
やれやれ、と、ため息を吐くシュバルツに、ハヤブサも苦笑する。
「仕方がなかろう……。食べなければならんと分かってはいるのだが―――――」
実際、食欲の戻っていないハヤブサは、食事を無理やり食べてもまだ、吐いてしまう事の方が多かった。だが、彼の内臓の方に何らかの異常がある訳でもないので、この現象にはキョウジも、そしてシュバルツも首を捻るしか無い。何か心理的な事が原因なのかと考えたりもしたのだが―――――
「とにかく、少しでも食べられそうなら食べてみよう、ハヤブサ……。キョウジがお粥を作ってくれているはずだ。それを温めて持ってくるから――――」
「ああ、頼む」
シュバルツが部屋から出て行くのを、ハヤブサは穏やかな表情で見送っていた。
(それにしても、ハヤブサは……今日は、少しでも食べてくれるかな……。本当に、何時になったら、彼の食欲は戻って来るのだろう……)
くつくつと音を立てる小さな土鍋を見つめながら、シュバルツは小さなため息を吐く。
ハヤブサの容体が停滞状態になってから半月―――――少しでも、改善の兆しが見えてくれば、ハヤブサも私も、もう少し希望が持てるのに………。
そう思ってしまってから、シュバルツは頭をブン、と、横に振る。
ハヤブサは、こんな所で終わる奴じゃないんだ。
必ず治る筈なんだ。
それを私が信じずしてどうする――――!
そう強く、シュバルツは自分で自分に言い聞かせる。
ハヤブサだって、生きようと、治ろうとする意志はある。希望は持てる筈だった。
充分温もった土鍋を鍋敷きを置いた盆の上に置き、ハヤブサの部屋へと運ぶ。その道中で、ハヤブサの居る部屋からカタン、と、物音がしたのを、シュバルツの耳が捉えた。
(……何だろう? ハヤブサが起きているのかな……?)
そう思ったシュバルツは部屋を覗き込んで――――――信じ難い光景に、絶句した。
「な…………!」
何故なら、ベッドから起きあがったハヤブサが―――――子供たちが持ってきた花をへし折り、千羽鶴をぐしゃぐしゃにして引きちぎろうとしていたから―――――
「ハヤブサ!? 何をやっているんだ!? お前!!」
思わず大声を出すシュバルツに、ハヤブサがビクッと反応する。
「あ…………?」
そしてハヤブサの方も、手に持っている千切れかかった千羽鶴を見て、茫然としていた。
どうやら彼の方も―――――シュバルツの声で初めて『我に帰った』らしい。
「ち、違う……! 俺は………ッ!」
みるみる顔面蒼白になって、がたがたと震えだすハヤブサ。
「こ、こんな……! どうして………!」
そのままハヤブサの身体がぐらりと傾いで、倒れそうになるから――――
「ハヤブサ!!」
シュバルツは慌ててお粥を置いて、ハヤブサの傍に走り寄る。床に激突しそうになるハヤブサの身体を、寸での所で受け止めた。
「ハヤブサ………!」
シュバルツが呼びかけるが、ハヤブサは腕の中でがたがたと震え続けていた。
「いやだ……! こんな………! 何で……! 何故だ………!」
「ハヤブサ……!」
床に散らばった花々と、ぐしゃぐしゃにされてしまった千羽鶴の姿が目に刺さる。シュバルツは、それらをハヤブサから隠すようにすると、震え続けるハヤブサの身体を、そっと抱きしめた。
「どうしたの!? 一体何があった!?」
シュバルツの大声を聞きつけて、キョウジも部屋に飛び込んでくる。そして、花々と千羽鶴の惨状を見て、彼もまた絶句していた。
「…………!」
キョウジもまた、慌ててハヤブサの傍に駆け寄ろうとする。しかしそれを、シュバルツが合図を送って押しとどめていた。
(私に任せてくれ)
彼の瞳がそう訴えているのを見て、キョウジは足を止めた。
「ち……違う………! 何で……ッ!」
聞き取れないほどの小さな声で呻き、震え続けるハヤブサ。
「分かっている……! 大丈夫だ、ハヤブサ………!」
そんなハヤブサの髪や背を、シュバルツは優しく撫で続けた。
「お前は、こんな事をする奴じゃない。そうだろう?」
「……………!」
ハヤブサは瞬間目を見開いた後、その瞳からポロポロと、涙を零し始めた。
「そ……それでも……! 手に持って、引き裂いていたのは『俺』なんだ……ッ!」
我に帰った瞬間の、手の中に在った千切れかかった千羽鶴の感触が、ハヤブサの手にははっきりと残っている。
「どうして――――! せっかく、子どもたちが……! 里の皆が―――――!」
そう言ったきり、後は言葉にならず、泣き崩れてしまうハヤブサ。
「ハヤブサ……!」
シュバルツはそんな彼の身体を抱きしめ、優しく撫で続ける。
彼がどうなろうと、自分は見捨てる気はない。
ハヤブサにそう伝えるために――――。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは、そんなシュバルツの身体に縋りついてきた。暫く、部屋の中に龍の忍者の慟哭にも似た泣き声が響く。
「………………」
キョウジはただ立ちつくして、そんな二人を見つめていた―――――。
そうして、どれぐらいの時が経っただろう。
涙も枯れて来たのか、それとも無く体力が尽きたのか――――ようやく、落ちついてくるハヤブサ。シュバルツは、そんなハヤブサを優しく抱きあげると、そっとベッドに寝かしつけようとした。しかしハヤブサは、それに弱々しく抗っていた。
「いやだ! 眠りたくないんだ……!」
そう言ってハヤブサは、シュバルツの身体に縋りつく。
「ハヤブサ……!」
「眠りたくない……! 怖いんだ………! またあの夢を見てしまいそうで……!」
夢の中にはいつも、『悪意の塊の様な者』が存在している。
それがいつも、ハヤブサに囁いてくるのだ。
「お前はいつか、お前の大事な物を引き裂く事になるぞ」と………。
「怖いんだ……! 徐々に、夢が夢だけで済まなくなってきているのが分かる……! さっきみたいに意識が無くなってしまった時に、今度は自分が何をしてしまうのか―――――!」
「ハヤブサ……」
「もしかしたら今度は、シュバルツ……お前を傷つけてしまうかもしれない……! いや、それだけじゃない……下手をしたらキョウジも―――――!」
「ハヤブサ!!」
「お願いだ、シュバルツ……! もし今度、俺がそんな事をしそうになったら、俺を―――――んっ!! んう………!」
シュバルツは、半ば強引にハヤブサの唇を奪っていた。舌を深くその口腔に侵入させ、強引に弄る。
馬鹿な事を言い出したハヤブサ。
そこから先の言葉は聞きたくないし、言わせたくないと思った。
だから―――――
「ん………う………」
シュバルツからのキスを受け入れているハヤブサの身体から、力が徐々に抜けていく。
シュバルツはハヤブサの舌を優しく吸い上げると、そっと彼の唇を解放した。
少し放心状態になっているハヤブサを、優しく抱きしめる。
「――――愛している、ハヤブサ……!」
「…………!」
はっと、息を飲むハヤブサの耳元で、シュバルツは尚も囁く。
「お前が、どうなろうとも………この気持ちは変わらない自信があるから………」
「シュバルツ………!」
「だからお願いだ……ハヤブサ……! 『死ぬ』とか、『私の前から消える』とか―――――そんな哀しい事を言わないでくれ………!」
「―――――!」
「そばに、居させてくれ……! そして、守らせてくれ……!」
「シュバルツ………」
「私を、『独り』にしないでくれ……!」
「……………!」
「ハヤブサ……!」
愛おしいヒトからの思いもかけぬ夢の様な言葉に、ハヤブサの瞳からも、いつしか涙が溢れていた。
「シュバルツ……!」
ハヤブサも、縋りつく様に、シュバルツの背に手を回す。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
シュバルツはそのまま、ハヤブサが眠りに落ちるまで、彼の身体を優しく、抱きしめ続けたのだった―――――。
「……………」
眠ったハヤブサの身体を、そっとベッドに横たえる。ふう、と、小さくため息をつきながらシュバルツが身を起こすと、キョウジから声をかけられた。
「ハヤブサ……眠った?」
「あ、ああ……。何とか、な………」
シュバルツは、少しやつれてしまったハヤブサの寝顔を見つめる。『寝たくない』と言われても、寝なければ――――休養しなければ、治る物も治らない。しかし………。
シュバルツは、首を捻ってしまう。
『眠る』ことは本当に―――――今のハヤブサにとっては、いいことなのだろうか?
「………………」
キョウジも同じような事を感じているようで、少し難しい顔をして黙りこくっている。その手元では、ボロボロにされた千羽鶴を、綺麗に修復する作業が続けられていた。ぐしゃぐしゃになってしまった紙を一枚一枚広げて、手早く丁寧に、鶴に折りなおしている。
「手伝おう」
シュバルツがそう言って隣に座ると、「頼む」と、キョウジもシュバルツに紙を渡してきた。暫く二人は無言で鶴を折り続けていたが、やがてキョウジがポツリと口を開いた。
「………ハヤブサが起きるまでには、綺麗にしておいてあげたいよね……」
「そうだな………」
「本当は、花も直してあげたいけど……」
「花は無理だな……」
ため息交じりに返すシュバルツに、キョウジは少し笑顔を浮かべる。
「『禁じ手』を使えば、直せないことも無いけどね……」
「お………おい――――!」
少し驚くシュバルツに、キョウジは苦笑する。
「冗談だよ。冗談」
『禁じ手』とは、『DG細胞』の事だ。この細胞の『自己再生』の能力を使えば、傷ついた花々も、すぐに元に戻す事が出来るだろう。
しかし――――
この細胞には常に『暴走』の危険が付きまとう。下手に扱えば、手に負えない不死の『化け物』を作り出してしまうことすら可能だった。キョウジの取り込まれかけた『デビルガンダム』が、まさにそれに当たった。だから『DG細胞』は『禁じ手』として封印されて居る筈なのだが。
実はキョウジが1人でその細胞について今も秘かに研究を続けている事を、シュバルツも知っている。だが彼は、それに強く反対も出来なかった。キョウジにとってその研究は、学術的な意義もあるだろうが、どちらかと言えば『償い』の気持ちの方が強いと言う事を、シュバルツも承知していたからだ。
(もしも……キョウジが死んでしまったら……この研究は、私が引き継いでいく事になるのかな………。自分の身体の事も含めて……)
千羽鶴を一枚ずつ折りながら、シュバルツが漠然とそんな事を考えていると、キョウジがポツリと口を開いた。
「やはり、ハヤブサは………何か、おかしいよね……」
「キョウジ?」
「だって、おかしいだろう! ハヤブサがこんな事をする筈がないことぐらい、私にだってわかる! これはもう、医学的な範囲を越えておかしい! 何かが………狂ってるように感じる……!」
「キョウジ………!」
「……………」
再び黙りこくって、無言で鶴を折り続けていたキョウジであったが、やがて意を決したように顔を上げた。
「…………ドモンを呼ぼう」
「えっ?」
少し驚いて顔を上げるシュバルツを脇目に、キョウジは立ち上がった。
「やっぱり、ドモンを呼ぼう! 何か、嫌な予感がする……!」
「お、おい、キョウジ――――」
シュバルツも慌てて立ち上がって、携帯電話を掴もうとするキョウジの手を止める。
「性急すぎだ! 何もそんなに焦ってドモンを呼ばなくても―――――」
「でも、もしもこれが、私たちだけでは手に負えない案件に発展して行ったらどうする!? 何かあってからでは遅いんだ!!」
「キョウジ………!」
「口ではうまく説明できないけど、これはもう異常事態なんだ……! なかなか治らないハヤブサの身体と言い、さっきの彼の行動と言い―――――」
「それはそうかもしれないが…………」
キョウジにそう言われると、シュバルツも反論の余地を失う。しかし、それでも少し大袈裟に騒いでいる様な気がしないでもなかった。
「それでもドモンを呼ぶほどの事じゃないだろう? あいつにだって都合や生活がある。もう少し様子を見てからでも――――」
「ああもう! 分かっていないなぁ! シュバルツは!!」
キョウジが、少しイラついた様な声を上げた。
「私は怖いんだ!! もしも何かあった時、私は実質的に自分の身を守る術を持たない!! そんな私と、お前とだけで――――この状態のハヤブサを守れるか!?」
「―――――!」
「怖い……! 訳のわからない恐怖を感じる……! それとも、この感覚は私だけか!? シュバルツ………お前は何も感じないのか!?」
「キョウジ………!」
叫んでこちらをまっすぐ見つめるキョウジの身体が、小刻みに震えている。どうやら彼は本当に―――――洒落にならないレベルで恐怖を感じているようだった。
(キョウジのこういう時の『勘』は、何故か当たることが多いからなぁ……)
シュバルツは小さくため息を吐くと、キョウジに同意する事にした。
「分かった……。お前の気が済むようにすればいい」
「ありがとう、シュバルツ……!」
キョウジはシュバルツに礼を言うと、すぐに携帯を取ってドモンに電話しだした。相変わらず兄からの電話に敏感な弟は、2コール目ぐらいですぐに出た。
「ああドモン? 悪いんだけど、すぐに来てくれないか? ちょっと……話したい事があって………」
「兄さんが危機なのか!? 分かった!! すぐに行くッ!!」
言うや否や、携帯の通話が切れる。これは本当に―――――猛烈に『すぐ』に来そうな予感がした。
「や……まだ、そこまでは言ってないんだけど…………」
通話が切れた携帯電話に向かって、キョウジはそう独りごちる。相変わらず過剰反応してくる弟に苦笑しながらも、彼が来るのならば何か料理でも――――と思ったキョウジが台所に向かおうとして、食料品のストックがあまりなかった事を思い出していた。
「シュバルツ」
「ん?」
ハヤブサの傍で千羽鶴を折っていたシュバルツが、顔を上げる。
「多分、ドモンがすぐ来ると思うから、ちょっと事情を説明していてくれないか? 私はちょっと出かけてくる」
「何処へ行くんだ? キョウジ」
「食料品の買い出し。あいつが来るんなら、買い足しといたほうがいいだろう? よく食べるし、この後、買い物できなくなると困るし――――」
「分かった……。気をつけて行って来い」
「ありがとう。じゃあ、後の事をよろしくね」
そう言って、キョウジは部屋から出て行った。忍者二人になった部屋に、少しの沈黙が訪れる。
「……………」
シュバルツは千羽鶴の修復作業を続けながら、先程のハヤブサとの一連の会話を思い出していた。
(それにしても……ハヤブサの気持ちが、今日少し分かってしまったな……。哀しい言葉を言わせたくなくて、聞きたくなくて―――――その唇を、塞いでしまう事ってあるんだ………)
ハヤブサと会話をしている時、シュバルツも叫ぶ途中でハヤブサによく唇を奪われていた。どうして彼は、いちいちこんな事をしてくるのだろうと思っていたが―――――
確かにそうだ。
黙らせたい時、「愛している」と伝えたい時―――――この手段は、非常に有効だ。
「……………」
シュバルツは、己が唇に、そっと指をあてる。先程のハヤブサとのキスの感触を思い出して、頬が火照るのを感じた。
(そう言えば………一体何時から、私はハヤブサに抱かれていないのだろう………)
ふと、そう思って、身体の最奥が、甘く疼くのを感じた。
こんな事を想うのは禁忌だ。それは充分分かっている。
でも―――――
ココロが勝手に、望んでしまう。
彼に触れたい。
触れて欲しい。
深く繋がりたい。
最奥を掻き回して、私を暴き立てて欲しい―――――
そこまで考えてしまってから、シュバルツははっと我に帰る。
(ば、馬鹿っ!! 無いだろう!? こんな状態のハヤブサに『抱いて欲しい』だなんて―――――!)
だいたい、繋がりを求めるのだって本来なら望んでは駄目なのだ。
ハヤブサは『人間』で、自分は歪な物質『DG細胞』で構成されているアンドロイド。
自分に深く触れると言う事は、少なからずその相手を、『DG細胞』の脅威に曝してしまう事を意味する。そんな事、許される筈もないのに。
(抱きたい……! お前が、欲しいんだ………!)
ハヤブサにそう強く望まれると、拒絶し切れない自分がいる。それどころか、『彼が望むなら、喜んでくれるなら』と、進んで身体を差し出してしまう自分がいる。それで、彼の『愛情』を、自分に繋ぎ止める事が出来るのなら、自分の何と引き換えにしても、惜しくは無いとさえ、思ってしまっていた。
それほどまでに――――ハヤブサから降り注いでくる愛のシャワーは強烈だった。
少しでも傍に居て、長く浴びていたい、と、そう願ってしまうほどに。
(でもきっと……欲しがるだけでは駄目だ……。与えられたのなら、自分はハヤブサに、ちゃんと何かを返して行かないと―――――)
そう。ハヤブサの『愛』を受けても、それを結実させて、彼の命を未来に繋いでいく事の出来ない自分は、ハヤブサにとって、愛し続けていても何もメリットがない存在だった。
だからこそ自分は、ハヤブサの幸せを誰よりも願わなければならないし、彼の幸せを、邪魔する存在であってはならないと思う。
(ハヤブサ……)
愛おしい人。
大切な人。
シュバルツはそっと、眠るハヤブサの前髪に触れる。
すると、眠っていたハヤブサの瞳が、パチッと開いた。
「あ………起こしてしまったか……?」
そう言って、引っ込めようとするシュバルツの手を、ハヤブサがガシッと握ってきた。
「シュ、バルツ……」
「ハヤブサ………?」
じっと見つめられて、シュバルツは少し戸惑う。すると、ムクリと起き上がったハヤブサが、いきなりシュバルツの上にのしかかってきた。
「わっ!? ち、ちょっと……!」
当然ハヤブサの身体はベッドから落ち、シュバルツは床の上に、ハヤブサに押し倒されるような格好になってしまう。ベッドの近くの机の上に在った千羽鶴の紙が、バサバサッと音をたてて床の上に散乱し、点滴台がガシャン! と、派手な音を立ててひっくり返った。
「ハ、ハヤブサ!? 何をやっているんだ! 危ないじゃないか!!」
シュバルツはとにかく、周囲を片づけなければならぬと思って、ハヤブサの下から這い出ようとする。しかしそれを、ハヤブサの手足が阻んだ。ぐっと抑えつけられて、シュバルツの自由を奪ってしまう。
「あっ!」
信じられぬ事に、その力はとても強かった。とても半死半生のハヤブサの力とは思えぬほどに。
「ハ、ハヤブサ……?」
「シュバ……ルツ……」
だが、自分を抑えつけるハヤブサが、酷く苦しそうにしていたから、シュバルツの戸惑いは更に深くなる。何が起こっているのかは分からないが、シュバルツはとにかく抵抗する事を止めた。自分は、ハヤブサと敵対する気はないし、何をされても良いとさえ、思っているからだ。
ふわ……と、身体の力を抜いて行くシュバルツを、ハヤブサがじっと見つめる。
「ハヤブサ……。そんなに、抑えつけなくてもいい……。逃げないから……」
「……………」
「な……。大丈夫だから………」
顔に笑みを浮かべ、ハヤブサを宥めるように話しかけるシュバルツ。それを聞いてくれたのか―――――ハヤブサの方も、ようやく手足の力を緩めた。ハヤブサから解放された手足に、シュバルツはホッと小さく息を吐くと、その手をそっと、ハヤブサの頬に伸ばした。逃げない。抵抗する気はない。その意志を、彼に示すために。
「ハヤブサ……」
頬に触れ、優しく撫でる。すると、ハヤブサの手も、ぐ、ぐ、と動いた。
「……シュ、バ、ル……ツ……!」
酷くぎこちなく、苦しそうなハヤブサの動き。これにはシュバルツも、少し眉をひそめた。
「ハヤブサ?」
おかしい。
ここまで自分が抵抗を止めたら、いつものハヤブサならば、いい加減落ち着いて、それから何らかの意思表示をしてくる筈なのに。
「……………」
ハヤブサの両手がぎこちない動きのままシュバルツの襟元に伸びてくる。彼はそこをぐっと掴んだかと思うと―――――
バリッ!! と、音を立てて一気にシュバルツの服を引き裂いていた。
「――――!」
ハヤブサの前に白い肌が露わになり、流石に息を飲むシュバルツ。
「ば……! 馬鹿っ!! 服は裂くなとあれほど言っているのに――――あっ!!」
顎を万力の様な力で掴まれ、呼吸を奪われそうになる。
「ハ……! ハヤブサ……ッ?」
いつもよりもかなり乱暴な所作のハヤブサに、シュバルツの戸惑いも更に深くなる。どうしたんだ、と、見上げる視線の先に、苦しそうに息をするハヤブサの姿があった。
「違……! ちが、う………!」
聞き取れぬほどの小さな声で、ハヤブサが呻く様に呟く。
「違う……! シュ……バルツ………ッ!」
「ハヤブサ?」
「い……今……! 俺……の、身体、を……動かしている……の、は…………『俺』では、な………い………!」
「―――――!」
はっと、息を飲むシュバルツは、確かに見た。苦しそうに息をするハヤブサの瞳が、真紅に染まっているのを。
「ウ………! ウ………!」
呻き続けるハヤブサの瞳の色が、いつもの色素の薄いグリーンの色と、真紅に染まる色との間を行ったり来たりしている。
「ハヤブサ!!」
シュバルツは悟った。ハヤブサは己が身体を乗っ取ろうとしている物と、懸命に戦っているのだということを。
「逃、げ……ろ……! シュバルツ――――!」
そう言いながらハヤブサの唇は、シュバルツの唇を塞いできた。
「ん………っ!!」
(違う―――――!)
受け入れたのは確かにハヤブサの唇なのに、その感触はハヤブサ以外の別の何かであったから、その感覚のおぞましさに、シュバルツの背に寒気が走る。
「んんっ!! んぐっ!!」
彼は懸命に抵抗を試み始めた。とにかく、このままこの『ハヤブサ』の口付けを、受け入れ続けてはいけない、と思った。
――――大人シクシロ………
「…………!」
シュバルツの『ココロ』に、仄暗い『何か』が囁きかけてくる。
違う。
この声がハヤブサの内側から出ているなど―――――思いたくもなかった。
「んう……! ん……ッ!」
(く、くそ………ッ!)
口腔を悦いように蹂躙してくるその舌は、ハヤブサの物だ。だから噛み千切る訳にもいかない。だけど、このまま好きなようにさせておくわけにもいかないから、シュバルツは懸命に足掻いた。するとシュバルツを抑えつけていたハヤブサの左腕が、ふっと緩む。
「―――――ッ!」
その隙を逃すシュバルツではなかった。彼は自由になったその右拳を、迷いなくハヤブサの鳩尾に叩きこんだ。
「ぐッ……!」
ハヤブサは一声低く呻いて、その意識を手放し昏倒した。それを確認して、シュバルツはようやく安堵の息を吐いた。
(それにしてもどうしてしまったんだ、ハヤブサ……。一体彼に、何が起こっている……?)
明らかに、何者かに操られそうになっていたハヤブサの身体。とりあえず気を失わせたのは良いが、このハヤブサを、このままにしておいていいものかどうか悩んでしまう。
(しかし……危ないからと言って、拘束する訳にもいかないよな……)
重ねて言うが、ハヤブサは半死半生の重病人。本来なら楽な姿勢で、ゆっくり休ませてやりたいところだ。そうしなければ、治る物も治らない。それを『危ないから』と、縛り付けてしまうのは人道に反しているし、言語道断だとシュバルツは思った。
だが、だからといって、このまま放置しておいてもいい訳がない。操られてしまっているハヤブサの身体が、次に何をするか分からない。
これはもう、異常事態。
たしかに、異常事態になってしまっていた。
キョウジの、妙な勘が当たってしまったな、と、シュバルツは軽く苦笑する。
(とにかくキョウジに今あった事を報告しないと……。それと、ハヤブサからも目を離さないようにして行かないといけないな……)
そう考えながら、シュバルツがハヤブサの身体の下から、這い出ようとした、刹那。
「……う………?」
急にシュバルツを襲う、眩暈。身体から、勝手に力が抜けていく。
(何だ……? これは……)
無理やり、眠りに誘われるような感覚。懸命に覚醒しようと努力してみるも、それも叶わず、どんどん意識が薄れていく。
身体に、先程ハヤブサ以外の何者かとキスをした時の様な、おぞましい感覚が這いまわる。
(しまった……! もしかして、捕らえられた………?)
シュバルツがそう悟った時には、既に彼の身体の自由はほとんど利かない状態になっていた。
(駄目だ……! せめて、キョウジに……! 異常があった事だけでも……伝えないと………!)
ハヤブサのベッド脇に、キョウジに直通しているコールボタンがある。緊急時にだけ押すようにと言われているそれを、今こそ使うべきだと思った。
「…………ッ!」
ぐ………ぐ………と、懸命に手を伸ばすが、コールボタンまで、なかなか手が届かない。距離にして僅か数センチ。しかしその距離が、今のシュバルツにとっては恐ろしく遠く感じられた。
(キョウジ……! キョウジ……!)
祈るように伸ばされた手がやっとのことでボタンに触れる。
「―――――――」
そのままシュバルツは昏倒してしまった。
部屋にはただ、沈黙のみが訪れていた。
家から徒歩圏内に在る24時間営業のスーパーで、キョウジがレジの精算を終えた時、それは突然鳴り響いた。
慌てて携帯を確認し、それがシュバルツからの緊急コールと確認して、キョウジの顔色が変わる。買い物を早々に袋に詰め、転がり出るようにスーパーを後にする。家まで猛ダッシュで帰りつき、蹴破るように玄関のドアを開けると、中から弟であるドモンの声が聞こえて来た。
「こいつ!! 兄さんから離れろッ!!」
(ドモン……! シュバルツ――――!)
キョウジは買い物袋を放り出すと、そのまま声のする部屋へと走って行った。
どうか、皆無事で。
そう祈りながら―――――
「大丈夫か!? ドモン!!」
部屋に走り込むと同時にキョウジの視界に飛び込んできたのは、気を失って折り重なる様に倒れている忍者二人と、そのハヤブサからシュバルツを引きはがそうと、悪戦苦闘している弟の姿であった。ドモンが、シュバルツの手を掴むハヤブサの手を引きはがそうとしているのだが、どうした事か―――――彼の手はドモンがどのように力を加えても、少しも離れようとしなかった。
(…………!)
キョウジはそんな3人の様子を見て、ある事に気づく。だから、思わず叫んでいた。
「ドモン!! 止めろ!!」
「えっ?」
振り向いたドモンは、ここでようやくこちらを食い入るように見つめているキョウジの姿に気づく。
「兄さん!?」
「……ドモン、その二人の手を離そうとするのは、止めておいた方がいい」
「えっ? 何で?」
きょとん、と振り返るドモンにキョウジもはっと我に帰る。
(そうか……。ドモンにはあれが見えていないんだな……。あの二人の手を包む白い光が………)
ハヤブサとシュバルツの繋がれた手を、淡い輝きを放つ白い光が包み込んでいる。それがキョウジには、何故か二人を守っているように感じられたからだ。
「……とにかく、二人の手はそのままにして――――二人をベッドに寝かしつけよう。手伝ってくれるか、ドモン」
「えっ? ま、まあ、いいけど……」
ドモンが、まだ少し納得できないと言う表情をしながらも、とりあえず二人の手を引きはがそうとする事は止めた。
「でも兄さん」
「何だ? ドモン」
「何でシュバルツの服、破れているんだ? どうやったら、こんな破れ方をするんだ?」
「……………ッ!」
ドモンの指摘に、流石のキョウジも顔色が変わる。
「やっぱり、ハヤブサの奴が破ったのか? ……でも何で、シュバルツの服を破る必要があるんだ?」
「あ~~~~ははははははは!!」
その辺の事情を、いろいろ深く説明したくないキョウジは、とりあえず、笑ってごまかす事を選択した。
「と……とにかく、二人をベッドに寝かしつけよう。どうして服が破れたかは、シュバルツが起きてから聞けばいい様な気がするから………な?」
「あ、う、うん」
キョウジの言い分にドモンもとりあえず納得してくれたのか、追求する事を止める。キョウジは、ホッと胸を撫で下ろした。
「じゃあドモン、もう一つベッドを出すから、手伝ってくれるか?」
「うん、分かった」
兄弟たちはそのまま、もう一つのベッドをこの部屋に運び込む作業に専念する事になった。
「……それにしても、ハヤブサはともかく、どうしてシュバルツまで起きないんだ? 一体、何があったって言うんだよ?」
「う~~~~ん………」
ベッドを部屋に二つセットして、彼らの身体をそこに寝かしつけても、一向に起きる気配を見せないシュバルツとハヤブサに、ドモンは首を捻る。いつものシュバルツであったなら、どんなに眠っているように見えても、自分が声をかけたら必ず、すぐに起きてくれていたと言うのに。
「どうしたんだろうねぇ……?」
ドモンの問いかけに、明確な答えを返せないキョウジも、首を捻るしかない。
自分が買い物に出る前まで、普通にハヤブサの横で折り鶴を折っていたシュバルツ。最近行ったメンテナンスでも、異常など見つからなかった。
なのに、病気で伏せっているハヤブサも、そしてシュバルツも、共に意識が戻らない。
そして、二人の手は、相変わらずしっかりと握りあわれたままだ。その手の周りには、相変わらず優しく淡い光が、それを守るように包み込んでいた。
(やっぱり、何かあった事は間違いないんだよな………)
キョウジは、折り鶴の紙を何となく弄びながら、独り考え込んでいた。
ドモンの話によると、二人はハヤブサのベッド脇で、折り重なるようにして倒れ込んでいたと言う。自分の手元の緊急コールは確かに鳴った。倒れていたシュバルツの姿勢から考えても、自分に直通の緊急コールボタンを押したのは、彼で間違いない筈だった。
確かに、何か起きている。
看過できない何かが。
恐ろしい何かが―――――
でも、それは何だろう。
分からないから、余計に性質が悪かった。
(寒い……!)
うすら寒さを感じて、キョウジは震える。真面目に身体が震えたので、キョウジは思わずドモンに「寒くないか?」と、問うていた。
「えっ? 別に?」
対してドモンは、きょとん、とした顔をしながら答える。
「…………!」
それによってキョウジは、寒さを感じているのは真面目に自分だけなのだと感じた。
(それはそうだよな……。今は夏で、『寒い』などと普通なら感じる筈もない……)
それでは、先程から感じているこの『寒気』は一体。
風邪でも引いたか―――――と、キョウジが思った時、意外な人物が部屋に入ってきた。
「………心配せずとも良いぞ、キョウジ。その『寒さ』なら、ワシも感じる」
「マスター!!」
キョウジに「マスター」と呼ばれた『老人』は、三つ網に結った銀色の髪を揺らめかせながら、ゆらり、と、姿を現した。口髭をたくわえ、『老人』と言うにはあまりにも体格のいいその人物は、にやりと笑いながら持ってきたズックをドスン、と床におろすと部屋の一角に落ち着く。
「何やら面白き気配を追って来たのだがな……。まさか、ここに行き当たるとは……」
「師匠!!」
ドモンは喜々として、その老人の傍に走り寄る。
この老人こそ、ドモンの『師』にして先代の『キング・オブ・ハート』――――東方不敗マスターアジアその人であった。
「『気配』ですか?」
東方不敗の言葉に反応して、キョウジが問い返す。自分が、訳の分からない寒気を感じているのとマスターが言うこの『気配』――――何か因果関係があるのか、気になった。
「そうよ……『気配』だ。……それも、とびっきり『邪悪』な物のな」
「ええっ!?」
「何ですって!?」
東方不敗の言葉を聞いたドモンが、即座に兄の傍に走り寄って身構える。
「おのれッ!! また何者かが、兄さんを狙って来ているのか!?」
「や……多分、私が狙われているとか、そういう話ではないと思うんだけど」
キョウジはドモンの後ろで冷静に否定するが、ドモンの方が噛みつく様に反論して来た。
「だけど兄さん!! そんなの分からないじゃないか!! 兄さんはよく訳の分からない不幸や理不尽に見舞われたりするから、絶対に油断しちゃ駄目なんだ!!」
鼻息荒くそう云い張る弟に、キョウジはもう苦笑するしかない。そこに東方不敗から助け船が出された。
「まあそうがっつくな、ドモンよ……。『邪悪な気配』と言っても、まだそこまで危険が迫っている訳でもない。だが、看過も出来ぬレベルになって来ているのも確かなのでな……。ちと武闘家の血が、疼いただけの事よ」
「そうなんですか……」
東方不敗の言葉にキョウジは何となく納得する。だがドモンは、まだ頭上に疑問符を飛ばしていた。
「しかし師匠!! 邪悪な物の気配は感じているんですよね!? それは一体どこから―――――!?」
「ドモン、お主は何も感じておらんのか?」
逆に東方不敗から少し驚いたように問い返され、ドモンは一瞬きょとん、となる。
「えっ?」
「寒気とか不快感とか……何かに見られているとか、そう言う気配を、お主は感じぬのか?」
「『みられている』……? 確かに、師匠や兄さんには見られているけど……」
「……………!」
ドモンのその答えに、東方不敗とキョウジは同時にズルッとこけそうになった。
「キョウジよ……。お主の弟は天然記念物か何かなのか?」
呆れたように口走る東方不敗に、キョウジも苦笑で答えるしかない。
「ま、まあ………かなり天然入ってますよね……」
そこがドモンの可愛らしい所でもあるのですが、と、答えるキョウジに、東方不敗も咳払いするしかない。この弟子の天然さは、今に始まった事ではなかった。欠点でもあり強みでもあり、愛すべきそのまっすぐさに、東方不敗もある意味救われたところが多々あるのだから。
「感じておらぬのならまあいい……。いいかお主たち。心して聞けよ」
気を取り直して東方不敗は語り始める。
「邪悪な気配の匂いを辿って来て――――その出所を、ワシはつきとめた」
「ええっ!?」
「どこですか!? それは――――!」
驚く兄弟たちに東方不敗はにやりと笑いかけると、おもむろに指を指した。
「この『邪悪な気配』の『源』は―――――あそこじゃ」
「な―――――!!」
東方不敗の指し示した先を見て、兄弟たちは息を飲む。何故ならそこには、寝台の上で眠り続けるリュウ・ハヤブサの姿があったのだから。
「……感じぬか? ドモンよ……。あの者の身体から発せられている、邪悪な気配を―――――」
「邪悪………」
眉をひそめるドモンの横で、キョウジは息を飲んでいた。
今まで気がつかなかったが、眠るハヤブサの背中から、黒い『邪気』の様な物がジワリ、と、漏れ出て来ているのが見える。
(そうか……。これが私の感じていた『寒気』の原因……!)
ハヤブサの病気が治らないのも行動がおかしくなったのも、この『邪気』が原因なのだとしたら、総ての辻褄が合う。しかし―――――
邪気なんてどうやって治せばいいんだ、と、頭を抱えるキョウジの横で、ドモンが憮然とした表情をしている。
「やっぱりこいつが原因で、シュバルツが気を失っているんじゃないか! あの手を何としても引きはがさないと――――!」
「だからそれは止めておけって、ドモン」
二人の繋がれている手の周りに見える白い光が、どうしても悪いものには見えないキョウジは、殺気立つドモンをやんわりと止める。東方不敗も、それに同意した。
「そうじゃな……。あの手はそのままにしておいた方が良いかもしれぬ。しかし、キョウジよ……」
「はい」
「お主は、あの二人の手を包む『光』が見えておるのか?」
「ええ。どう言う訳か」
東方不敗の問いに、キョウジは苦笑しながら答える。
「分かってはおると思うが、あれは常人には見えぬ物の筈ぞ。それが見えるとは、お主――――」
「止めてくださいよ。私は普通の人間の筈です」
東方不敗の勘繰りを、キョウジは身を引いて否定する。
自分には、そんなに対して霊感は無かった筈だった。
だが最近になって時々、普通には見えざる物が見えてしまう現象が起きている。その事で少し悩んでいた自分に、シュバルツが教えてくれた。自分は一度死して、霊体として彷徨っていた経験があるのだと。一度そうして死んでしまった自分を助けるために、ハヤブサが、時を巻き戻せる巫女『かぐや』の力を借りて、時間を巻き戻し、その運命を否定してくれたのだと言う。
「死んで『霊体』になっていたお前と、私は時々話をしていたのだが……覚えていないか?」
シュバルツのその問いかけに、自分は『覚えていない』と首を振るしか無かった。死んだことすら経験していない事になっているのに、霊体になった時の事など、憶えているはずもない。
「……だよなぁ」
そう言って笑うシュバルツが、少し淋しそうだったから、キョウジもなんだか申し訳ない様な気持ちになる。
「ご、ごめん、シュバルツ……。覚えてなくて……」
「いや……謝ることでもないだろう、キョウジ。それに、『霊体』になった時の記憶など――――憶えていない方がいいのかもしれない」
「そうなのかな?」
疑問を呈するキョウジに、シュバルツは「そうだ」と頷く。
「……じゃあもしかしたら、もう一度死んで『霊体』になれば、その時の記憶を思い出すかもしれなかったりして」
そう言っていたずらっぽく笑うキョウジにシュバルツが「止めてくれ!!」と、怒鳴り声を上げた。
「死なないでくれ、キョウジ……! あんな経験はもうごめんだ!」
そう言いながらシュバルツは、本当に泣きそうな顔をしている。
「ごめん……。悪かったよ……」
キョウジはそう言いながら、思わずシュバルツを抱きしめていた。何故か彼が、幼い子供のように見えてしまったから――――
「約束する……。すぐには死なない……。生きる努力を、ちゃんとするよ……」
「キョウジ……!」
「だからシュバルツ……。泣かないで………ね?」
「泣いてなどいない……ッ!」
涙を流しながらそんな事を言うシュバルツに、「素直じゃないな」とキョウジは苦笑していた。
(でも、こうやって『見えない』はずの物が『見える』様になってしまったから……全く影響がない訳じゃないんだろうな……。一度死んだ経験と言うのは……)
後で念のために別の機会を捉えてハヤブサにも確認してみたが、彼も『霊体』になっていた自分を確かに見たと言っていた。
自分が死んでから暫くは、シュバルツと自分は、全くコンタクトが取れていなかったらしいのだが、とある事件を経てからは、シュバルツと自分の間に意志疎通ができる『パイプ』が出来たらしい。度々霊体である自分と話し込んでいるシュバルツの姿を、ハヤブサは陣屋の中でよく目撃していたのだと言う。
「俺も話がしたかったのだがな……。何せ『霊体』であるお前の姿は俺には見えない、声は聞こえないだから――――」
ハヤブサが言うには、シュバルツ以外には自分の霊体は見えていないようだった。にも拘らず、何故ハヤブサが霊体である自分と話しているシュバルツに気が付いたかと言うと―――――
「……あいつの表情が、酷く穏やかで幸せそうだったからな……。すぐに分かったんだ」
そう言ってハヤブサが、少し憮然としている。どうしてそんなに怒っているのか、と、キョウジが問えば、龍の忍者は「少し悔しいからだ」と答えていた。
「俺の前ではあんな表情、めったに見せてくれないのに……!」
そう言ってむくれているハヤブサに、キョウジは苦笑する。
「そうなの? シュバルツは私の前で貴方の話をする時、結構幸せそうな顔をしているけどなぁ」
「本当か!?」
驚くハヤブサに、キョウジは頷いた。
「本当だよ? シュバルツは本当に、貴方の事が好きなんだな~って思って、ちょっと妬けるなぁって思っていたぐらいなのに」
「…………!」
その話を聞いたハヤブサが、耳まで朱に染めている。面白い、と思いながらキョウジがハヤブサの様子を観察していると、そこに所用で外出していたシュバルツが帰ってきた。
「シュバルツ!! 愛している!!」
部屋に入ってきたシュバルツの姿を確認するなり、ハヤブサはシュバルツに抱きつこうとする。だがそれは、シュバルツの手に持った分厚い本に阻まれていた。
「……キョウジ。頼まれていた本を持って来たぞ……ってハヤブサ、何でお前がここに居る?」
顔をしこたま本に打ち付けて、悶絶しながら座り込んでいるハヤブサに、シュバルツの結構冷たい声と視線が突き刺さる。
「や……ちょっと……」
「『約束の日』にはまだ早いだろう!? 何故ここに居るんだ! ハヤブサ!!」
「た……他意は無いんだ……。ちょっとキョウジに、『愚痴』を聞いてもらいたくて……」
「愚痴?」
怪訝な顔をするシュバルツに、ハヤブサはこくこくと頷く。
「愚痴と言うと……何の愚痴だ?」
問うシュバルツにハヤブサはにっこりと笑いかけた。
「それはお前、夜の」
「出て行け―――――――ッ!!!」
シュバルツの渾身の拳を受けた龍の忍者は、哀れ窓から外に放り出されて、星になって消えたのだった。
「……全く、あいつは本当に、何しに来たんだ!? 訳が分からん……!」
窓から外を眺めながら、ブツブツ言っているシュバルツに、キョウジは苦笑しながら声をかけた。
「ハヤブサが愚痴を言いに来たって言うのは本当だよ。さっきまでそこで床に『の』の字を書いてたし」
「………! そ、そうか………」
シュバルツはキョウジに答えた後、少し複雑な顔をして黙りこんだ。
「どうしたの?」
キョウジは少し怪訝に思ってシュバルツに問う。するとシュバルツは、「な……何でも無い………」と、言って、何でも無くない表情で黙りこむから―――――
「もしかして……何で『愚痴』をハヤブサは自分に言ってくれないんだろうとか………思っていたり、する?」
「う…………!」
図星を指されたのか、顔を真っ赤にしてしまうシュバルツ。キョウジはやれやれと苦笑した。
「ハヤブサが愚痴る原因なんて一つしかないし、貴方に言えなくて私にこぼしてくる愚痴も、一つしか無いよ」
「えっ?」
きょとん、とするシュバルツに、キョウジはにっこりと微笑みかける。
「どうして、貴方にもっと触れさせてもらえないんだろうって、そんな愚痴をこぼしていたけど?」
「―――――!」
「毎日でも、何時間でも触れていたいのにって言ってた」
「ハヤブサ……! あの馬鹿!」
キョウジの言葉に耳まで真っ赤にしながら毒づくシュバルツが、おかしな話だが『可愛らしい』と思ってしまう。
(多分、ハヤブサを飲み込もうとしている何らかの『邪悪な者』にハヤブサともども精神的に飲み込まれて―――――気を失っている感じなのかな。だけど、二人を繋ぐ手と、その周りを囲む光が、二人の精神がその世界で完全に飲み込まれてしまうのを防いでいる様な感じがする……)
だから、とりあえずは大丈夫だろう。
あの手と光が、二人の間に在る間は――――
キョウジは、ベッドを並べて手を握り合って眠る忍者二人の姿を見ながら、そう分析する。シュバルツもハヤブサも、いつも見返りを求めることなく自分を助けてくれていた。だから今度は、自分が助ける番だとキョウジは思った。
(待っていて、シュバルツ……そして、ハヤブサ……! 絶対に助けて見せるから……!)
強く決意して、握りこぶしを作る。そんなキョウジの横で、東方不敗がふむ、と、考え込んでいた。
「それではキョウジよ……。この二人の今の状態を、どう思う?」
「ハヤブサを蝕む何者かに、精神を引きずり込まれた様に見えます」
東方不敗の問いに、キョウジは自分の感じたままを答える。
「何っ!? やっぱりハヤブサの奴が――――!!」
気色ばむドモンを、東方不敗が「まあ待て」と、抑える。キョウジの答えが自分の考えていた事とほぼ一致したと見て取った東方不敗は、少し満足そうな笑みを、その面に浮かべた。
「ドモンよ。確かにこの一件は『龍の忍者』が原因ではあるが、『龍の忍者』そのものが原因ではない」
「………? 師匠、どう言う事ですか? それは……」
東方不敗の言わんとしている事が理解し切れないドモンは、眉をひそめる。東方不敗は顎に手を当てると、言葉を続けた。
「良いか、ドモンよ……。『龍の忍者』と言う者は、ある意味伝説的な存在だ。その腕は凄まじく、一説によれば数多の邪神を滅し、あるいは封印して来たと聞く……。嘘か誠かは分からぬがな……」
東方不敗の言葉に、ドモンはフン、と、鼻を鳴らす。
「こいつが『伝説』なら、俺は『神話』になってやるぜ……!」
さらに訳のわからない対抗心を燃やしながら、ブツブツ口を尖らしている。
(いろんなものを滅殺したり封印したりする事が出来る『キング・オブ・ハート』の紋章を持つ者も、ある意味『伝説』的な存在じゃないのか……?)
キョウジは苦笑しながらそう思ったのだが、敢えて口には出さなかった。相変わらずこの弟は、もの凄く負けず嫌いだと、思う。
「見たところ、今目の前の龍の忍者は、何が原因かは知らぬが――――恐ろしく衰弱しているように見える……。もしもこの『衰弱』が原因で、今までこ奴が封印して来た邪神を封ずる力が――――――弱まってきているとしたら?」
「―――――!」
兄弟たちは同時に息を飲んで、東方不敗の方に振り向く。彼らの眼差しを受け止めて、東方不敗は頷いた。
「ドモンよ。他のシャッフルの紋章を持つ者たちにも、連絡を取れ」
「師匠!!」
「これは……我らシャッフル同盟がそろい踏みをして、当たるべき事柄なのかもしれぬ」
東方不敗はにやりと笑いながら前を見据えていた。久々の大一番のこの戦いに、胸が躍っているように見受けられた。
「それとドモンよ……。首相とのホットラインは、まだ生きておるな?」
「はい! 師匠!!」
先の『デビルガンダム事件』の折りに、ドモンはある意味首相の命を受けて動いていた所もあって、この国の首相と妙な信頼関係が構築されていた。
「では、ただちに首相に連絡を取れ。そうさな……この町内だけで良い。住民をすべて避難させろ」
「避難ですか!?」
素っ頓狂な声を上げるキョウジに、東方不敗はにやりと笑みを見せた。
「そうよ。そうしなければ死人が出るぞ? 間もなくここは―――――戦場になるのだからな」
「……………!」
息を飲むキョウジとは対照的に、ドモンはとても嬉しそうな表情をする。
「分かりました! では早速皆に連絡を取ります! あ……でも師匠!! 避難の理由はどうしましょう?」
「そんなのは向こうに考えさせろ。ただ……避難させねばここに居る者の命の保証は出来ぬと、念を押しておけよ」
「分かりましたっ!!」
東方不敗に応えるや否や、ドモンは嬉しそうに携帯を操作しながら走り出す。その後ろ姿を東方不敗は見送った後、小さなため息を吐きながら、凭れかかっていた壁から身を起こした。
「どれ……。ワシも少し、出かけてくるかな……」
「どちらへ?」
問うキョウジに、東方不敗はにやりと笑みを返す。
「少し、この町に結界を張って来る」
「結界……ですか」
「そうよ。邪悪な者共が、この町から出て行かぬよう――――その結界をな」
「…………!」
息を飲むキョウジにフフフ、と笑いかけると、東方不敗は部屋から出て行った。後にはキョウジ1人が残された。
「………………」
キョウジは無言で椅子に座り直すと、折りかけていた千羽鶴の続きをしだした。手際良く丁寧に――――キョウジの手は、一つ一つの鶴を折りだして行く。
ただ―――――今まで気がつかなかったハヤブサから溢れ出ている黒い邪気が、時折手にまとわりついてくるのが分かる。そしてそれが手に触れるたびに、彼は微かな痛みと寒気を感じなければならなかった。
(やだなぁ……。怖いなぁ……)
ハヤブサから溢れ出ている黒い邪気を感じながら、キョウジは苦笑する。今自分は、邪神に襲われるかもしれないこの状況で、独り、部屋に取り残されている事になるのだから。
(ただ、焦ることは無いんだ)
キョウジは、強く己に言い聞かす。
もしも、本当に危険が差し迫っている状況ならば、東方不敗は決して自分を独りにはしないだろう。あの人がここから場を外したと言う事は、まだここに、そこまで大きな危険は無いと判断したからと言う事に他ならない。
先の『龍の勾玉』の事件の際に、東方不敗は自分を命がけで守ってくれた。だから、あの人は信じていいのだとキョウジは思った。ただ少し、東方不敗は自分の事を買いかぶり過ぎている様な気もする。事あるごとに「天下を取れ」みたいな事を言ってくるから、少し辟易してしまう。それが無ければいいのにとも思うが、それが無ければ自分の事をここまで気にかけてもくれないだろうとも思う。そう考えると、少し複雑だった。
(それにしても……この邪神にとって、折り鶴はやっぱり『邪魔』に感じたんだろうなぁ……)
そう感じて、キョウジは苦笑する。
この折り鶴にも、そして隼の里の花にも、人々の祈りにも似た『想い』が詰まっていた。ハヤブサの治癒が、願われていた筈だ。ただそれらの想いは、邪神にとっては自分の封印の力を助ける物に他ならない。それを目障りに感じた『邪神』は、だからハヤブサの身体を使って―――――
(………酷い事をするなぁ。全く……!)
花と折り鶴を自らの手で引き裂いた事実を目の当たりにした時、ハヤブサがどれだけ傷ついて泣いたか。キョウジは今思い出しても、腹立たしい想いになる。
(……絶対にハヤブサが起きるまでに、この千羽鶴を完璧に綺麗に直してやるからな!)
邪神に当たる存在がこの折り鶴を嫌がっていると言うのなら、尚更、きちんと折りあげてやるべきだと思った。これにどれぐらいの効力があるかは不明だが、嫌がらせぐらいにはなるだろう。
(ハヤブサ……! シュバルツ……!)
眠り続ける忍者二人の身を案じながら、キョウジはひたすら、千羽鶴を折る作業に没頭していったのだった。
第2章
(何だ……? ここは……!)
自分の居る世界に、シュバルツは戸惑い、辟易する。
その場所はひたすら暗く、悪意と瘴気と――――そして、何故か哀しみに満ちていた。
そして、禍々しい化け物の様な物が、数多蠢いていた。
それらが自分を見つけると、奇声を上げながら攻撃を仕掛けてくる。
この世界に在る自分を『異物』と見なして排除しようとしているのか。
それとも―――――取り込もうとしているのか。
「――――――!」
自分に迫る触手状の物の動きを瞬時に見極め、刀で弾き、寸断する。
動かなくなった化け物の死骸を踏みつけ、シュバルツは走る足を加速させた。
捕まる訳にはいかない。
捕まる訳にはいかない。
こんな悪意と哀しみに満ちた世界――――それに取り込まれてしまったら、自分を構成している『DG細胞』がどのような事になってしまうのか。それを想像することすら恐ろしかった。
よくない事が起こる。
よくない事が―――――きっと、起こってしまう。
それは断じて避けなければならぬ。
その様な事態になってしまったら、哀しませてしまう人がいる。苦しませてしまう人がいる。
何よりも大切なその人を、そんな目に遭わす訳にはいかないと、強く思った。
ただ、目の前に広がるのは、広大な、闇、闇、闇………。
屠っても倒しても、尽きず襲いかかって来る化け物たちの群れ。
この戦いに『希望』はあるのか。
『終わり』は来るのか――――
(考えるな)
シュバルツは強く己に命じた。
剣は、上げ続けなければならぬ。
走り続けなければならぬ。
自分は、断じて捕まる訳にはいかないのだから。
「ギシャアアアアアアアッ!!」
赤黒い肌の歪な形をした化け物が鋭い爪を振りかざして襲いかかって来る。
「―――――ッ!」
ガツン!! と、受け止めた刀から、火花が飛び散る。
更にわらわらと集団で、襲いかかって来る異形の者たち。
「叭ッ!!」
シュバルツは最初に襲いかかってきた異形の物を、刀で弾き飛ばして、その集団に突っ込ませる。それによって集団が乱れ、生じた隙にシュバルツも突っ込んで行った。周囲の敵を切り裂きながら、シュバルツはその中を走り抜ける。
まだ走れる。
大丈夫――――
無明の闇の中、シュバルツはそれだけを自分に言い聞かせ続けていた。
絶対に膝はつかぬ。
逃げ切って見せる。
例えこの戦いに、終わりなど来なくとも―――――
永遠に続くかと思われたこの『闇』
それだけに、前方に『光』らしき物が視界に入ってきた瞬間、シュバルツは「まさか」と我が目を疑った。
その白く淡い光は、優しい輝きを放っていた。
どうか、こちらへ
こちらへ――――
何故か、手招きをされているようにすら感じる。
(罠か………?)
シュバルツは、強く疑う。
こんな『闇』と『瘴気』と『哀しみ』の満ちた世界に、『希望』の様な『光』がある筈はない。更に強力な敵があの光を放ち、こちらを誘っていると考えた方が自然だった。
だが、シュバルツの視線は、手は足は―――――どうしても『光』の方に向いてしまう。向かってしまう。
(まるで光に吸い寄せられる、虫の如しだな……)
己の状態をそう分析して、シュバルツは苦笑した。『光』のある方に走ってしまうのは、求めてしまうのは―――――『生命』としての本能なのだろうか。
(私に『生命』という概念も、おかしな話だがな……)
そう。
自分は、キョウジの『影』にして、身体はDG細胞で出来たアンドロイド。殺されても死なない自分に、命としての定義など当てはまる筈もない。
ただそれを言うと、キョウジもドモンも、そしてハヤブサも、烈火のごとく怒り出すから、シュバルツは黙ることを選択する。しかし、自分の基本姿勢は、この先も変えるつもりはなかった。自分は空虚な『影』――――そうあるべきなのだ。
(罠であるなら、それでもいいか)
シュバルツはそう思って、光に向かって足を進めた。どうせ、ここに味方の救助など期待できない。そこに罠があるのなら、敵がいるのなら―――――それを、突き破るまでだ。それをする事によって、事態に何らかの進展が、あるかもしれないのだから。
「りゃああああああっ!!」
裂帛の気合と共に、敵を切り裂く。
敵を屠り、その屍を踏みつけながら、シュバルツはその光を目指して走り続けるのだった。
「……………」
立ちはだかった異形の物を、頭から一刀両断にする。二つに裂けたその身体が、べシャッと音を立てて地面に倒れたのを確認して、シュバルツはふっと一つ息を吐いた。周りに敵の気配もなく、殺気も漂っていないことを確認してから、シュバルツは抜刀していた刀をブン! と、大きく露払いをして、それを鞘へとしまった。
目の前には、あの優しく輝く淡い光がある。
(特に妖しい気配も何も無い……。これは、どう言う事だ……?)
シュバルツは光を見つめながら、却って首を捻っていた。光は穏やかな輝きを辺りに放っているだけで、特に罠らしい物も、殺気も悪意も感じない。
信じられなかった。
こんな暗い世界に、こんな人畜無害な『光』が存在していようとは。
(しかし……これは、どう判断すればいいのだ? この『光』が、この世界を突破するための指針になり得ないのだとなると―――――)
あまり期待はしていなかったが、これからの行動指針を見失いそうになって、シュバルツは少し途方に暮れ気味になる。
「………………」
もうここに、じっと居ても仕方がない。次の行動に移らねばならないと分かっていて、それでも、この光の前から立ち去り難く感じてしまうのは何故なのだろう。
(やっぱり虫と、同レベルなのかな)
光を求める自分の本能に妙なおかしさを感じてシュバルツが苦笑していると、また―――――何処からともなく声が聞こえて来た。
こちらへ
どうぞ―――――こちらへ
(何だ………?)
その不思議な声に、シュバルツが眉をひそめた、刹那。
光から、いきなり伸びてくる白い手。シュバルツはそれを―――――振り払えなかった。
「――――――!?」
彼はそのまま、あっという間に白い光の中に、引きこまれてしまうのだった。
その先の空間には、地面が無かった。
「!? !? !?」
シュバルツは、3度周りと己の体勢を確認して、自分が今空中に放り出されたと確認する。重力に引かれたことで、そちらが『下』と認識したシュバルツは、自分がこれから着地するであろう地面の状態を確認した。
すると、下には円形の地面の様な物があり、そこに一人の人影が動いているように見える。ぶつかると危険と判断したシュバルツは、とりあえずそこの人影に、自分の存在を認識してもらうべく、声を張り上げる事を選択した。
「すまん!! ちょっとそこを、退いてくれええええええっ!!」
「―――――!?」
その人影は上空のシュバルツを認識してくれたのか、俊敏な動きでかわす動きをする。着地できる場所を確保できたシュバルツは、猫の様に着地体勢を整えると、スタッと地面に無事着地をする事に成功していた。
「………………」
周りの物を何も破壊せず、無事に着地出来た事を確認して、シュバルツはほっとため息を吐いていた。やれやれ、と、周囲の状況を彼が確認するべく顔を上げようとするよりも早く、『少年』の怒声が飛んでくる。
「な――――! 貴様ッ!! 何故ここに姿を現した!?」
(子供がいるのか!?)
驚いたシュバルツはその声のした方に顔を上げて、更に驚いてしまう。何故ならそこには、自分の酷く見知った顔があったからだ。
亜麻色の長い髪を無造作に一つに束ねて風になびかせ、黒の忍び装束を身に纏って―――――その少年はそこに立っていた。色素の薄いグリーンの瞳に、日本人離れした、整った顔立ち。勝ち気そうな鋭い視線が、こちらを射抜いてくる。
見間違えようもない、この顔は。この美しい少年は。
「ハヤブサ!?」
シュバルツは思わず、素っ頓狂な声を上げていた。だが、ハヤブサと思われるその少年からは、さらに鋭い怒声が帰ってきた。
「気易く俺の名を呼ぶなッ!!」
「……………!」
真正面からぶつけられる叫び。その少年の面には、殺気と怒りと哀しみが満ち溢れているから、シュバルツは戸惑ってしまう。
分からない。
何故自分は、こんなにもハヤブサから拒絶されるような意志をぶつけられるのだろう?
対して『ハヤブサ』と思われるその少年は、噛みつかんばかりの勢いでシュバルツを睨み続けていた。
「ここは里の中でも絶対的な『聖域』で――――幾重にも施された結界が侵入者を拒んでいる筈だ!! なのに何故―――――貴様の様な者が、こんな所に入り込んでいる!? どうやって入ってきた!?」
「ま、待て! ハヤブサ!」
ハヤブサと思われる少年から受ける殺気や敵意の意味が分からず、シュバルツはただ戸惑うばかりだ。
「俺の名を呼ぶなと言うに!!」
少年が抜刀し、シュバルツに襲いかかって来る。
「くっ!」
やむを得ずシュバルツも抜刀し、それに対応した。
「何故私に戦いを挑む!? 理由を聞かせろ!!」
ハヤブサの鋭い剣撃を受けながら、シュバルツは叫ぶ。すると少年ハヤブサから、意外な答えが返ってきた。
「黙れ!! 里を襲ってきた張本人が――――!!」
「何っ!?」
驚き、息を飲むシュバルツに、ハヤブサは更にたたみかけてくる。
「見間違えも、忘れもしないぞ。貴様のその顔―――――! 女子供、赤子に至るまで容赦なく斬り裂いて―――――!」
「な…………!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツはただ茫然とするしかない。自分は当然隼の里など襲ってなどいない。全くの濡れ衣だった。だが―――――
(―――――!)
ここでシュバルツは、自分の視界に映る自分の服装が、全く別の物になっている事に気づく。いつの間にか自分は、朽葉色の忍び装束を着ていた。手に持っている刀も、全く違う物になっている。
(まさか――――!?)
シュバルツは咄嗟に、自分の姿が確認できる場所を探す。すると少し離れた場所に、小さな滝と、そこから流れ落ちるせせらぎを見つけた。
「……………!」
シュバルツはハヤブサを弾き飛ばすと、無言でそのせせらぎに向かって走り出した。
「お、おい!! 何処へ行く!?」
少年ハヤブサが、後ろから追いかけてくる気配を感じる。それには構わず、シュバルツはひたすらせせらぎを目指した。そして、ガバッとその水面を覗き込んで――――
「あ…………!」
全く見も知らぬ初老の男性の顔がそこにあったから、息を飲んでしまう。白髪混じりの太い眉の下に光る鋭い眼光。尖った鉤鼻、顔中に、深く刻まれた皺――――水面に映る動揺した表情のその男性が、自分と同じ動きをするから、シュバルツは否が応でも突きつけられてしまう。自分は今―――――どう言う理由か分からないが、ハヤブサにとっては『仇』と言っても差し支えも無い人間の姿になってしまっているのだと。
「何をしている!? こっちを向けッ!!」
背後から、少年ハヤブサの怒声が刺さる。
「……………」
シュバルツは無言で振り返る。すると、少年ハヤブサが、刀を構えながら、真っ直ぐこちらを射抜く様な眼差しで見ていた。
「刀を抜けッ!! 構えろ!! 皆の仇――――今ここで俺が討ってやる!!」
(ああ、『本物』だ)
その少年の言動行動に、シュバルツは却って確信を深める。
忍びにはあるまじき、真っ直ぐな勝負を挑んでくる少年。余程自分の腕に自信があるのか、それとも、妙に律儀で義理堅い彼の性格が、そうさせてしまっているのか――――――「忍ばない忍び」になってしまうハヤブサの特徴が、如実に表れていた。
(それにしても、甘い奴だな)
そう感じて、シュバルツは苦笑する。水面を覗き込んでいた時の自分は、確実に隙だらけだった。あの瞬間、背後から討っていたなら、自分を確実に、殺せたであろうに。
(どうする?)
目の前の少年の望みに応じて刀を抜刀し構えながら、シュバルツは考えた。どうやら自分は、あのハヤブサにとっては『仇』に当たる人間になってしまっているようだ。
ハヤブサが望むのならば、討たれることも自分はやぶさかではない。だが――――それで、本当にいいのだろうか? 自分がハヤブサに討たれる事が、今この事態を打開する一助に、なるのだろうか?
「……………」
刀を構えながらハヤブサの様子を見ていたシュバルツは、ここである事に気付いた。
少年ハヤブサの構える刀は、『龍剣』ではない。ごく普通の刀だ。
(妙だな)
シュバルツは軽く違和感を覚える。
ハヤブサと言えば『龍剣の使い手』―――――文字通り、特殊な妖刀『龍剣』に、選ばれた使い手だった。この二つがセットで、彼は『龍の忍者』となり得ていると言っていい。
なのに何故―――――目の前のこの少年ハヤブサは、それを持っていないのだろうか?
(これは少し、様子を見た方がいいのかもしれない)
彼は軽く息を吐きながら、手に持つ刀を構えなおした。
「りゃああああああっ!!」
ガキッ!!
ガツン!!
重々しい太刀の音が、辺りに響き渡る。
シュバルツは少年ハヤブサと手合わせをしながら、さすが、と、内心唸っていた。
ハヤブサの太刀は何処までも鋭く、そして真っ直ぐだ。その戦いぶりには危なげがなく、こちらの繰り出す太刀にも即座に対応してくる。
齢にして12、3歳ごろだろうか。この年齢でこれだけの戦いをするハヤブサの技量は、確かに常軌を逸していた。後に『伝説の龍の忍者』と称されるのも、おおいに頷ける。
ただ、惜しむらくは―――――
ガツン!!
「…………!」
その太刀筋が、哀しみに、怒りに、恨みに―――――濁り過ぎている、と言う事であった。これではいくら鋭く打ち込んだ所で、相手には届かない。それどころかその感情は、自分にそのまま跳ね返って来て、却って諸刃の剣にすらなりかねない。更に何故か「焦り」の感情まで見え隠れしているから、シュバルツは首を捻ってしまう。
「どうした? ハヤブサ」
だからシュバルツは、戦いながら思わずハヤブサに問うてしまう。
「何をそんなに―――――焦っている?」
「うるさい黙れっ!!」
怒りに満ちたハヤブサの剣が、シュバルツに襲いかかる。
「貴様のせいで――――!!」
それを軽くいなしながら、シュバルツは少しずつ後ろに下がる。このまま自分は、彼の『仇』として討たれても良いが、迷ってしまう。
本当に、このままでいいのか?
このまま、討たれてしまっていいのか?
討たれる以外に―――――彼の『助け』となる方法は、ないのだろうか。
不意に、下がり続けたシュバルツの背が、壁の様な物に当たる。
「……………?」
何気なく振り向いて―――――驚いた。氷のような透明な『壁』と言ってもいい物の中に、紛う事なきハヤブサの『龍剣』があったのだから。
「な……! 龍剣……!」
「――――――!!」
思わず漏れ出た、シュバルツの小さな声。それに、ハヤブサが敏感に反応した。
「貴様ッ!! やはり龍剣を狙っていたのか!?」
もう生かしてはおけないと言わんばかりに、ハヤブサの攻撃が一層激しいものになる。
「ハ……ハヤブサ……!」
元よりシュバルツの方にハヤブサと戦う気などない。ハヤブサの猛攻の前に、シュバルツの対応はどうしても後手後手に回ってしまう。シュバルツは次第に、切り立った崖の方へと追い詰められてしまった。下がった足が、崖を踏み外しそうになる。それにシュバルツが一瞬気を取られた、刹那。
「死ねええええええっ!!」
ハヤブサの渾身の一撃が、シュバルツを襲う。それがシュバルツの脇腹を切り裂き、体勢を崩した彼は、そのまま崖から転落するよりほかはなかった。
(ハヤブサ………!)
見上げるシュバルツに、ハヤブサの冷たい視線が突き刺さる。そのまま彼は、崖から奈落の底へと落ちて行った――――――
(何だ………?)
何か妙な胸騒ぎを感じて、キョウジはその顔を上げていた。
目の前には、相変わらず手をつないだまま眠りこけている、忍者二人の姿がある。そして二人の繋がれた手を守る様に、包み込む『光』が優しい輝きを放ち続けていた。
(大丈夫、だよな?)
白い光を見つめながら、キョウジは自分に確認するように言い聞かせる。
いくら邪悪な物にその精神を捕らえられているとはいえ―――――ハヤブサとシュバルツの二人が揃っている。その状態で二人が『邪神』に後れを取るだなどとは、思いたくもなかった。
その横で東方不敗が何かの『香』の様な物を焚きしめている。部屋には、独特の香りが充満していた。
「師匠! 皆を連れて参りました!」
そう言いながらドモンが部屋に入って来る。その後から、ドモンと同じくシャッフルの紋章を持つ者たちが、続けて入ってきた。
「よう! 師匠に兄さん! 久しぶりだな!」
と、チボデー・クロケットがキョウジに向かって手を上げる。ブルーの髪の毛にピンクのメッシュを入れたセミロングの髪形をしている彼は、アメリカ人で、プロのボクサーでもあった。
「うわっ!? 何だ!? この匂い!!」
部屋に入るなり、背の低い子どもと言ってもいい少年が、無造作に一つに束ねた黒髪を揺らしながら鼻を摘まんでいる。彼―――――サイ・サイシーは、実は中国拳法の達人で、亡き父親の後を継いで、道場の再興に勤しんでいる。
「何やら『香』を焚いているようですね……。それにしても、変わった香りだ……」
その後ろから、少しキザで優雅な雰囲気を醸し出している、フランス人の青年が入って来た。彼の名はジョルジュ・ド・サンド。貴族の出身で、フランスの王族の1人であるマリアルイゼ姫に忠誠を誓っている騎士でもある。フェンシングと飛び道具の達人でもあった。
「……………」
一番最後に、2mを越える巨躯を持った筋肉隆々の男が無言で入って来る。
彼の名はアルゴ・ガルスキー。ロシア人で、海賊として暴れまわっていた経歴を持つ。ただ、彼は誰も彼もを襲う賊ではなく、弱気を助け、強きをくじく義賊の様な存在であったらしい。彼を捕らえた女性軍人ナスターシャと気持ちを通わせるようになり、『デビルガンダム事件』以降、彼女と結婚して、幸せな家庭を築いているようである。
「おう、来たな」
東方不敗は、ドモン以下5人の姿を認めると、その面ににやりと笑みを浮かべた。
「師匠、それは何ですか?」
早速ドモンは、東方不敗の手元の『香』を見つけて問いかける。
「これは、『邪気払いの香』よ」
香からくゆる煙を見つめながら、東方不敗は答える。
「今回の戦いには、どうしても必要な物なのでな。所でドモンよ……。この街の住人達は皆、無事に避難を済ませておるのか?」
「はい。師匠。皆言われたとおりに避難してくれました。これで街の中は、人っ子一人おりません」
「うむ」
ドモンの言葉通り、この街の境界線一帯には政府の協力の元、『立ち入り禁止』の黄色い線が張り巡らされ、その外側を警官が警護に当たっていた。それを、輪の外からドモンの恋人であるレインが、心配そうに見守っていた。
(ドモン………)
そんな彼女の肩を、チボデーとともにアメリカからやってきた女性たちが軽く叩く。
「大丈夫よ、レイン」
リーダー格のシャリーが、にっこりと微笑みかけて来た。
「チボデーもドモンも、きっと大丈夫。私たちは彼らを信じましょう」
「ええ、そうね」
レインもにこっと微笑み返す。ただ、彼女の瞳から憂いの影が消えることは無かった。ドモンは多くは語らなかったが、何やらこのトラブルには、彼の兄であるキョウジも巻き込まれているらしい。彼はよく、理不尽な不幸に見舞われる事が多いから、彼女はそれを心配していた。
(ドモン、キョウジさん……。きっと、大丈夫よね………?)
封鎖された街を見つめながら、ただ祈るしか出来ない自分が、レインにはもどかしく感じられた。
「それにしても……何かこう……寒くないか?」
軽く震えているチボデーに、ドモンがきょとん、とした表情で答える。
「えっ? そうか?」
「確かに……何か寒いですね……」
ジョルジュもそう言って眉をひそめる。その横でサイ・サイシーが、「うわあっ!!」と、突然大きな悲鳴を上げた。
「ん? どうした? サイ・サイシー」
サイ・サイシーの声に驚いたドモンが振り向くと、サイ・サイシーの小さな身体が、ドモンの後ろに回り込んできた。
「あ、兄貴……! あそこで寝ている奴の身体から出ているあれ……何だよ!?」
「えっ?」
「ほ、ほら……! あれ……ッ!」
サイ・サイシーは懸命に、ベッドに寝ているハヤブサの方を指す。すると、ハヤブサの身体から、黒い煙の様な物が溢れるように出て来て、床へと流れ落ちている。
(俺が最初見たときより……だいぶ増えたな………)
ドモンはそれを見ながら、漠然とそう思う。だが、周りの皆の言う様に、『寒さ』や『恐怖』は相変わらず感じなかった。
「こ奴は『龍の忍者』と呼ばれる存在で―――――今回、お前たちを招集した原因でもある」
皆の注目がハヤブサに集まったと感じた東方不敗は、改めて口を開いた。
「龍の忍者!?」
「実在していたのですか……!?」
「…………!」
東方不敗の言葉に、チボデーとジョルジュとアルゴはそれぞれ息を飲む。しかし、サイ・サイシーだけが1人、きょとん、としていた。
「なあ、『龍の忍者』って、何だ?」
「伝説の『龍の一族』の血を引く忍者の事ですよ」
サイ・サイシーの問いに、ジョルジュが優しく答えていた。
「何でもその腕は恐ろしく強くて、『龍剣』一本で神をも滅殺すると言われています。いろいろと話は耳にした事があるのですが……如何せんその話の中の『龍の忍者』の腕が凄まじ過ぎて、私は民間伝承か何かだと思っていたのですが……」
「ああ………実在していたとはな………」
話をするジョルジュの横で、チボデーも「信じられない」と言った面持ちでベッドの上のハヤブサを見つめる。その横でドモンは、「やれやれ」とため息を吐いていた。
「みんな驚きすぎだ! 確かにこいつの腕は認めるが、山歩きとかが好きな―――――割と普通の奴だぞ!?」
「ドモンは、こいつを知っているのか!?」
驚くチボデーに、ドモンは「ああ」と頷いた。
「シュバルツとハヤブサが、友人同士なんだよ」
それまで黙っていたキョウジが、そっと口をはさんでくる。
「同じ『忍者』同士だからかな。馬が合うみたいで――――」
「ああ確かに、仲いいみたいだな。手を繋いで寝てやがる」
チボデーが、忍者二人の繋がれた手を見て、少しおどけて見せる。それに対して、ドモンがかなりむくれた顔をした。
「ハヤブサの奴がシュバルツに付き纏いすぎなんだ!! シュバルツは俺の兄さんなのに――――!!」
シュバルツに会いに行ったら、かなりの高確率でハヤブサとも会ってしまう。ドモンは少しそれが面白くなかった。腹が立つから、会うたびにハヤブサに手合わせを挑むのだが、ハヤブサが互角以上に自分と渡り合ってくるから、余計に腹が立つ。
自分も結構口実を設けてシュバルツに会いに行っていることは置いておいて、ドモンはぶつくさと文句を言っていた。
「相変わらずのブラコンだなぁ」
と、チボデーが茶かすと、
「ブラコンじゃない!!」
と、怒鳴りつけるドモンなのであった。
「ですが……この手は、離さない方が良いみたいですね。これによって、何かを『封印』しているようにも見えます」
「お主もそう思うか?」
東方不敗の問いに、ジョルジュは頷いた。
「ええ。二人の手を包むかのように、白い光が見えますので―――――」
「そう。この白い光は問題ではない。危険なのは、こ奴の身体から発せられている、黒い『邪気』の様な物だ」
そう話す東方不敗の手元で、『邪気払いの香』の煙が、ゆらゆらと漂っていた。
「どう言う理由かは知らぬが、このリュウ・ハヤブサの身体は、かなり激しく衰弱しておる。そして、こ奴が衰弱する事によって、今まで龍の忍者が『封印』してきた数多の邪神の類が封を破り、復活しようとしておるのだ………。この『邪気』は、その邪神から漏れ出ている様なものよ」
「げっ!!」
「何ですって!?」
「うわあ、おっかね~~~!!」
「……………!」
東方不敗の言葉に、4人がそれぞれ息を飲む。ドモンはフン、と、鼻息を荒くし、東方不敗はそれを見てにやりと笑った。
「その邪神が完全に地上に解き放たれてしまったら、この世界は大変な事になる……。それを防ぐのが、我等の役目、と言う訳よ」
「なるほど……」と、ジョルジュが頷けば、「よッしゃ、任せな!!」と、チボデーがバキバキと指を鳴らす。「ああ! おいらたちの手で、『邪神』なんかひとひねりだぜ!」サイ・サイシーも拳法の型を構えて格好をつけるが、アルゴに、「なら俺のズボンの裾から手を離せ」と、軽くたしなめられていた。
「だ………だってよ……! おいら、お化けとかの類がどうも苦手で………!」
「おやあ? サイ・サイシーちゃんは、夜中にトイレに独りで行けない口か?」
「失礼な!! トイレぐらい独りで行けるよ!!」
チボデーのからかいに、サイ・サイシーはムキになって突っかかる。しかし、時々自分の世話役である恵雲(けいうん)と瑞山(ずいせん)に、夜中のトイレについて来てもらっていることは、自分だけの秘密だった。
「しかし、師匠!」
「何じゃ? ドモン」
「未だ姿を見せぬ『邪神』と、どうやってわたり合おうとお考えなのですか!? 今のままでは何も出来ぬかと――――」
「………そうじゃな。だから、この『香』を焚きしめておるのよ」
愛弟子の問いに、東方不敗はにやりと笑って返事を返す。
「良いかドモンよ。この『香』は、『邪気払いの香』と言って、邪気を払う効果がある。邪神の目的は、この龍の忍者の身体を乗っ取る事であろうが――――この『香』と、二人の『繋がれた手』によって、それが阻止されておる。みよ。龍の忍者から溢れ出た邪気が――――――この『香』の効力を嫌って、床から外に逃げて行っておるのが分かるであろう?」
「本当だ………」
見守るドモンの目の前で、ハヤブサから漏れ出ている黒い邪気が、床から下に消えているのが見える。大量に邪気が溢れ出ているように見えるのに、今だこの部屋に邪気が充満しない理由がここに在った。
「この『香』で邪神をいぶり出し、殲滅をしたい所ではあるが、相手は何せ『神』と呼ばれる存在。一筋縄ではいかぬであろうな。ドモンよ………この外に漏れ出た『邪気』がこれからどう言う動きをするか、お主は想像がつくか?」
「いえ、全く。どう言う動きをするんですか?」
素直に問い返してくる愛弟子に、東方不敗はフフフ、と、笑みを浮かべた。
「龍の忍者と言う拠り代から追い出された邪気は、もう一度龍の忍者の身体を乗っ取るべく、エネルギーを摂取する道を選ぶであろうな。『邪神』が一番エネルギーを摂取するのに、効率のいい方法は、分かるか? ドモンよ」
「いえ、全く」
ドモンがきょとん、とする横で、キョウジが眉をひそめていた。どうやら彼は、『邪神』がエネルギーを摂取する方法の見当が、いち早くついた様だった。
「………一番手っ取り早いのは―――――人間の『命』をかき集める事よ」
「ええっ!?」
「何ですって!?」
「チィッ! なんてこった!」
Oh my god !! と、小さく毒づくチボデーの横で、サイ・サイシーの顔面は蒼白になり、アルゴは苦い顔をしている。
「人間の『命』自体は勿論のこと―――――『命』を奪われる瞬間の人間の『恐怖』『哀しみ』『絶望』『憎しみ』と言った感情も、邪神にとっては最高のエナジーとなる。だから、外に溢れ出た『邪気』は、今頃外で命を探し始めているころじゃろうな……。それを、屠るために―――――」
「な―――――!」
東方不敗の言葉に息を飲むドモン。彼の脳裏に、ここに来る前に、街の境界線付近で別れたレインの顔が、真っ先に浮かんだ。
「気をつけてね、ドモン」
彼女の憂える瞳に、「心配ない。片を付けたらすぐに戻ってくる」と、ドモンは笑みを浮かべながら答える。ドモンは避難所に行くようにとレインに指示をしたのだが、彼女は自分の姿が見えなくなるまで、兄の家に向かう自分を見送っていてくれた。
もしも彼女が――――未だ境界線付近に留まっていたとしたら。
「レイン!!」
ドモンは叫びながら、脱兎のごとく部屋を飛び出して行った。
「シャリー! キャス! バニー! ジャネット!!」
チボデーも憶えがあるのだろう。ドモンに続いて部屋を飛び出して行く。
「ま……! 待ってくれよ~! 兄貴!!」
サイ・サイシーも、二人の後を追いかけて、部屋を飛び出して行く。
「アルゴ、私たちも行きましょう!」
ジョルジュの呼び掛けにアルゴも無言で頷いて、それぞれ部屋を出て行った。後には、東方不敗とキョウジ、そして、眠り続ける忍者二人が残された。
「キョウジよ」
皆が部屋を出て行ったのを確認してから、東方不敗はキョウジに声をかける。
「はい。何でしょう? マスター」
千羽鶴を折り続けていたキョウジが手を止め、顔を上げる。
「お主は……街の外に出んで良いのか?」
「えっ?」
目をぱちくりさせるキョウジに、東方不敗はさらに続けた。
「言うたであろう? 今から我等は、邪神をいぶり出し、それに戦いを挑む。この街全体が戦場になるのだ。しかも、我らが居る場所には龍の忍者の身体があり、『邪気払いの香』もある。ここに目的の物があるが故に、この場所は最も強力な敵が出てくる事になるぞ?」
「……………!」
東方不敗の言葉に、キョウジが息を飲む。
「ここに居る限り、命の保証は出来ぬ。だが今ならば―――――ワシはお前を街の外まで安全に送ってやることができる。どうする? キョウジよ……。もし、戦いを望まぬのなら―――――」
「私は、ハヤブサの主治医です!!」
東方不敗の言葉が終わらぬうちに、キョウジが叫んでいた。
「医者が、患者を見捨てて逃げ出すなんて―――――あり得ません! 私もここに残ります!」
「……命の保証は出来ぬと、ワシは言うたぞ? それでもか?」
きっぱりと言い放つキョウジに、東方不敗は確認する様に問いかける。それに対してキョウジは、視線を逸らさずに、真っ直ぐに―――――頷いた。
「――――覚悟の上です!」
「………………」
東方不敗はしばらく、キョウジをじっと検分するように見つめていたが、キョウジからその視線が逸らされることはない。彼の決意は固いのだと見て取って、東方不敗はその面に納得したような笑みを浮かべた。
最後まで責任を取ろうとするその一途さ、頑固さ―――――そして、覚悟。
相変わらず、見事なまでの腹の据わり方だと、東方不敗は思った。
それでこそ
それでこそ―――――自分は
この男に手助けし甲斐がある、と、言う物だった。
「よかろう。ならば、好きにしろ」
少し突き放すように東方不敗はキョウジに言った。
勿論、彼を命がけで守ると言う自分の決意は揺るぎないものだ。
しかし、それでもわざと突き放すような物言いをしたのは、見てみたかったからだ。この極限の状況の中で、彼がどう言う戦いをするのか。彼が近頃シュバルツやハヤブサや自分を相手に、戦い方の修業をしているのは知っている。そして彼は自分で『ハヤブサの主治医』と言った。ある意味シュバルツの命を握り込んでいる存在である自覚も、ある筈だ。
絶対に死ぬことが許されない厳しい状況下で、彼がどういうふうに戦うのか。その修業の成果を見てみたいと東方不敗は思っていた。
「分かりました!」
キョウジは東方不敗に返事をすると、ダッシュで奥の部屋に引っ込む。それからすぐに大きなスーツケースみたいなものを抱えて、部屋に戻ってきた。そこからいくつかの部品らしきものを取り出して、手早く何かを作り始めている。
「何をしておる?」
東方不敗の問いに、キョウジは振り向きもせずに答える。
「ちょっと、護身具を………」
(『護身具』……のう……)
キョウジの手元を見ながら、東方不敗は少し呆れるやら感心するやらしてしまう。彼の手元から次から次へと魔法の様に生み出されていくそれは、訳のわからない形をした物もあるし、およそ法治国家の日本においては所持が許されない様な物にも見える。
(相変わらず、人間離れしておる奴よのう……)
自分の人間離れした強さを棚に上げて、彼はひとしきり唸り続けていた。
「何!? 何なの!?」
街の境界線付近で留まり続けていたレインは、警官隊の肩越しに見える異常な光景に激しく戸惑っていた。
最初は街中に、何か黒い影が走っているな、と言う程度にしか見えなかった。だが、妙だとも思った。実際、街の中の住人は全員退避させられていて―――――中にはドモン達以外に人間はいない筈であったのだから。
しかし、徐々に増えて行く黒い影。訝しく見ているうちに、黒い影の一体と、何故か視線が合ったように感じた、その瞬間。
「ギシャアアアアアアア!!」
黒い影達が奇声を上げながら、一斉にこちらに向かって突進して来た。
「――――――!!」
驚くレインたちと、色めき立つ警官隊。だが黒い影達の突進は、唐突に何かにぶつかったような格好になって止まった。それこそが東方不敗が仕掛けた結界の為せる業なのだが、当然レインや警官隊たちには、何が起こっているのか把握できる筈もなく。
その光景を見た市民の間に、パニックが起きかけた。
「下がって!! もっと下がって!!」
警官隊が銃を構えながら皆に呼びかける。しかし、恐慌状態になった街の人たちの叫び声で、その指示もかき消されて行った。
「隊長!! 発砲許可をください!!」
警官の1人が、黒い影に銃を向けながら叫ぶ。
隊長格の警官は、一瞬迷った。この得体のしれない黒い影は、街の人たちに危害を加える可能性が高い。十二分に、発砲要件を満たしているようにも感じる。しかし、この黒い影達の行動は、何か壁の様な物に阻まれており、その向こうで壁を叩いて騒いでいるだけなのだ。もしもこちらが不用意に発砲して、この黒い影を阻む『壁』の様な物を壊してしまったとしたら。
それだけではない。もしも発砲した銃声に驚いて、街の人たちがさらなるパニックを引き起こしたら。
「…………!」
背中に、嫌な汗が伝う。
難しい判断に、どうする、と、考えていた時に、中から『それ』は起きた。
ドコオッ!!
派手な音を立てて、粉じんが舞い上がる。それと同時に、巻き上げられ、弾き飛ばされたと思しき黒い影達が、粉々に四散して行くのが見えた。
「そこ!! もっと離れてくれッ!!」
若い男性の声が響く。それに正気に帰った警官たちが、慌てて皆を後ろに下がらせた。
ドオンッ!!
派手な轟音と共に、壁を叩いていた黒い影達が文字通り四散していた。
「レイン!! 無事かッ!?」
爆発の煙が収まると同時に、赤いマントをなびかせた青年が、皆に向かって叫ぶ。
「ドモン!!」
彼女の声を聞いた青年が、それを見て安心したような笑みを見せた。だが、安心してばかりもいられない。青年――――ドモンの後ろに、複数の黒い影が、また迫ってきている。
「ドモン!! 後ろ!!」
レインの叫び声に、ドモンが振り向くよりも早く、彼の背後で轟音が上がり、黒い影達が吹っ飛ばされていた。
「シャリーたちも無事か!?」
ドモンの後ろから、チボデー・クロケットがファイティングポーズを崩さぬまま、顔を出す。
「チボデー!!」
彼と視線が合ったクルーであるギャルズたち4人も、嬉しそうに手を振っていた。
「シャリー! レインや、皆を頼むぞ!!」
「分かったわ! 任せて!!」
チボデーの言葉に力強く頷くシャリーに、彼も唇の端を少し上げた笑みを見せると、踵を返して、また黒い影達に向かって行った。
「これは一体何なんだ!? 君たちは一体―――――!」
警官隊の隊長の問いに、ドモンはぶっきらぼうに答える。
「あまり詳しい事は言えん。どうしても俺たちの正体を知りたければ、内閣総理大臣にでも聞いてくれ」
「……………!」
「それよりも、あんたたちはもっとこの街の境界線から皆を下がらせる事に専念してくれ。今は、師匠の張った結界がここを守っているが、この先はどうなるか分からん」
「な…………!」
絶句する隊長に、横から貴族然とした長髪の青年が、ドモンの言葉を補足するかのように、静かに語りかけて来た。
「あの黒い影達の目的は、『人間の命』です」
「―――――!」
「影達は、『命』の波動に惹かれて集まってきます。ですからお願いです。もう少しこの結界から離れてください。その方が影達を我々におびき寄せることができる。戦いやすくなりますので――――」
「しかし……! それでは君たちが―――――!」
「心配は無用です」
青年は優雅に笑うと、手をばっと広げる。その手には、無数のナイフが握られていた。
「我々には、対抗できる手段がありますので―――――」
そう言いながら、青年が手を手を振ると同時に、無数のきらめきが影に向かって迸る。ナイフは過たず影達を貫き、それを粉砕していた。
「ですから下がって!! どうかお早く!!」
青年はそう言いながら、フェンシングの剣を構えて影達に突っ込んで行く。
「……………!」
警官隊の隊長は、しばらくその男たちの戦いを茫然と見つめていたが、彼らの戦いが影達を圧倒していると見て取ると、自分たちの役目を理解した。彼らの戦いを助けるために、自分たちは、何を置いても街の人たちの安全を確保する事こそが重要なのだと。
「みなさん!! もっと下がって!! 下がってください!!」
警官隊はそう叫びながら街の人々を誘導して行く。その横で隊長が自分の上司である局長に連絡を入れていた。
「お願いします!! 避難指示範囲を拡大するよう要請してください!!」
トランシーバーに向かって、彼は言葉を続けた。
「現場の判断です!! 市民の命を守るためです!! お願いします!!」
悲鳴と怒声の中、彼は必死に上司に頼み込んでいた。
また街中で、ドオン!! と轟音が響き渡っていた。
(……やった……! 仕留めたぞ………!)
奈落の底に落ちて行く鬼蜘蛛党の頭首を見つめながら、少年ハヤブサは小さなため息を吐いていた。
手応えはあった。腹を切り裂き、この高さから落ちれば、いくらあの男が超人的な強さを誇っていたのだとしても、もう助からないだろう。
「……………」
無言で刀の露払いをし、鞘に納める。
分かっている。こんな事をやったところで、殺された里の者たちが帰って来る訳ではない。
空しさが襲う。
だが、人を斬った事に後悔は無かった。殺らなければ、こちらがやられていた。
守りたければ、斬らねばならぬ。
自らの手を、汚さねばならぬ。
これは、ハヤブサが幼いころから教え込まれてきた鉄則だった。
「鬼になれ。そうしなければ、守る者も守れぬ」
父のこの教えには納得している。斬った相手も、斬られて当然の奴だ。
なのにどうして―――――
人を斬った後、胸が痛むのは何故なのだろう。
やれやれ、元の修行に戻るか、とハヤブサが小さくため息を吐いた、その刹那。
上空から、何者かが落ちてくる気配がする。
「――――――!?」
見上げた先に、何か見覚えのある朽葉色の忍び装束が。
ドスン!! と、どこか間抜けな音と共に、先程の男が落ちて来た。
「な―――――!」
呆気にとられるハヤブサに向かって、男が引きつった笑顔を見せてくる。
「た……ただいま……」
「『ただいま』などと言っている場合か―――――ッ!!」
思わずハヤブサは、大声を張り上げていた。
「ふざけるなッ!! 何でまた貴様がここに居る!? 斬られた腹の傷はどうした!?」
「ええと、それは、その………」
何故か歯切れの悪い返事をしてくるその男に、ハヤブサのイラつきはさらに募る。ハヤブサは無言で抜刀すると、おもむろにその男の喉元に、刀の切っ先を突きつけた。
「手を上げろ!! そのまま、動くなよ……!」
「…………!」
男は、言われたとおりの姿勢になる。目の前に差し出された男の腹をハヤブサは検分する。しかし、そこには切り裂かれた朽葉色の忍び装束はあっても、その下の腹は傷一つ無く綺麗な物だった。
「………どう言う事だ? これは……!」
茫然としているハヤブサに、男が声をかけてくる。
「……少し事情を説明したい。これを退けてくれないか、ハヤブサ」
「信用できるか!!」
ハヤブサは頑なに刀を突きつけ続ける。男は少し困ったように笑うと、腰にさしている刀を、おもむろにハヤブサの方に差し出した。
「私は、今ここで君と争う気はない。ほら、武器を取りあげろ」
「……………!」
「ほら、早くしろ。そうしなければ、君は私と話もしてくれないのだろう?」
「何か、小細工をしかけては――――」
「いない。こんな距離で小細工を弄したとしても、私だってただでは済まない。そんなつまらない事はしないさ」
「………………」
「とにかく君と話がしたい。私の望みはそれだけだ」
ハヤブサは推し量る様に男を睨みつけていたが、やがて男の腰から刀を取りあげると、それを出来るだけ遠くの方に放り投げた。それから2、3歩下がって、刀の切っ先を下げる。
「話とは何だ? つまらない事だったら承知しないぞ……!」
(まるで鞘を持たぬ剥き出しの刀身の様だ……。青いな……)
少年ハヤブサの全身から迸る殺気に、シュバルツは苦笑する。
だが無理からぬこととも思う。
20歳かそこらで常人にはとても到達できぬ高みに上り詰めるハヤブサではあるが、最初からそうであった訳ではない。そこに至るまでの、修行の過程があるのだ。この少年が収まるべき『鞘』は、これから自分で作っていく事になるのだろう。
「まず、ハヤブサ……。聞くが、ここは『里』ではどう言う所になるのだ?」
「その問いに、答える義理はあるのか?」
ギッ! と、睨みつけてくるハヤブサの視線を受け止めながら、シュバルツは言葉を続けた。
「ああ。知りたいな……。どうやら私たちは、この空間に『閉じ込められた』様だから」
「何っ!?」
驚くハヤブサに、「証拠を見せてやる」とシュバルツは軽く言うと、おもむろに背後の崖から飛び降りた。
「な―――――!!」
慌てて崖に駆け寄り、鬼蜘蛛の頭首が落ちて行った場所を覗き込むハヤブサ。すると、自分の『背後』にその男が『上から』降りて来た。
「………………!」
「な……。御覧の通り、崖から飛び降りようが、強制的にここに戻されてしまう様なんだ」
男は苦笑しながら、ハヤブサにそう説明をした。
「そんな馬鹿な―――――!」
ハヤブサは踵を返して、自分がこの場所に入る時にくぐり抜けた鳥居の下まで走る。
そこから一歩、彼が外に出ようとすると、頑丈な壁の様な物に当たって、ハヤブサの身体はそのまま弾き返されてしまった。
「そ、そんな……!」
少年ハヤブサは、もう一度鳥居の下から外に出ようと試みる。だが結果は同じで、また彼の身体は弾き返されるだけであった。
「ぐっ!!」
「ハヤブサ!!」
後から追いかけてきたシュバルツが、彼の身体を助け起こそうとする。しかし。
「俺に触れるな!!」
激しい拒絶の意志をぶつけられて、シュバルツはそれ以上、彼に近付けなくなってしまった。起きあがったハヤブサは、ふらふらと鳥居の下まで歩いて行くと、そこから出られない事を確認して、ただ茫然としてしまっていた。
「そんな……! 父上……ッ!」
通り抜けられない壁をバン! と、悔しそうに叩いて、そのまま肩を震わせてしまっているハヤブサ。
(ああ、子どもだな)
シュバルツは少し複雑な思いで少年ハヤブサの後ろ姿を見つめる。彼としても、ここに閉じ込められてしまう事は、予想だにしていなかった出来事なのだろう。
しかし、仮にも『敵』と認識している自分に対して背中を見せて、随分と無防備に泣くものだ。この少年は、自分に後ろから討たれるかもしれないと――――考えもしないのだろうか? それともこれは、彼が無意識に、こちらを信頼していると思ってもいいのだろうか?
そうだとしたら、もう少し、泣かせてやりたい。だが、このままでは埒が明かないことも事実だ。
シュバルツはとにかく、状況を打開するために、ハヤブサに声をかけることにした。
「ハヤブサ……」
「何だ!?」
噛みつく様に返事をしてくるハヤブサに、シュバルツは苦笑する。だが、それには構わず言葉を続けた。
「………よかったら、教えてくれないか? 里の中でどう言う位置づけの場所なのだ? そして君は、ここに何をしに来ているのだ?」
「……………!」
「今――――里は襲われているのだろう? 本来ならば、里を守って戦いたいのではないのか?」
「うるさい!! 元はと言えば貴様が――――!!」
「………そうだったな……」
ハヤブサの憎悪を真正面から受け止める。今――――自分はハヤブサにとって、何故か『仇』となって見えてしまっているらしかった。
(これは……おそらくハヤブサの『精神世界』と、『彼を蝕む者』の為せる技なのだろうが……)
シュバルツは考える。気を失う直前の状況を鑑みるに、自分はおそらく、現実世界でハヤブサを蝕む者に、一度捕らえられたと考えて良かった。気を失う直前、無理やり眠りに引きずり込まれた感覚。その後の闇の世界は、おそらく、ハヤブサを蝕んでいる物の世界だろう。そこに在った悪意と憎悪は、自分を捕らえ、そして殺そうとしていた。
だが、その中にポツリと小さくあった光―――――これこそが、ハヤブサの『心』の世界なのだと判断してよさそうだった。
その中に子どもの姿となって、閉じ込められてしまっているハヤブサ――――
(これは、おそらく彼を導いてやらないと駄目だ)
シュバルツは、この世界での己の役割を、直感的に理解した。
彼が、この世界から再び、外の世界に出られるように。
彼が、子どもから、大人の姿に戻れるように。
そうしなければ、彼は何時まで経ってもこの世界から出られず、下手をしたら、彼を蝕んでいる邪悪な物に、彼の『心』が完全に食われてしまうかもしれない。それは、ハヤブサの現実世界の肉体の死をも、意味しているとシュバルツは感じた。
その事態だけは何としても避けねばならぬ。
自分は、ハヤブサを守りたいのだ。そして、救いたいのだ。
その為に恨まれようが憎まれようが、一向に構わないとシュバルツは思った。
要は、ハヤブサを助ける事が出来さえすれば、それでいいのだ。
「…………!」
面に穏やかだが哀しげな笑みを浮かべた鬼蜘蛛党の頭首の顔に、ハヤブサは何か引っかかるものを感じる。
何故だろう、知っている。
あの彼の、哀しげな眼差しを、自分はどこかで見た事がある。
何処だろう。
何故だろう。
落ちつかない様な気持になる。
大切な物。
ひどく、大切な、モノ。
思い出さなければいけない様な気がした。
―――――思イ出スナ………
不意に、脳裏に仄暗い声で、何者かに呼び掛けられる。
――――アノ者ハ、『仇』ナノダロウ? ナラバ、深ク考エルナ……
「う……………!」
――――思イ出セ……。アノ者ニ殺サレタ里ノ者タチヲ………引キ裂カレタ、赤ン坊ノ姿ヲ………
「…………!」
――――オ前ハ、タダソノ心ガ命ジルママニ………アノ男ヲ恨ンデオレバヨイノダ………
それだけを言うと、仄暗い声は去って行った。ハヤブサは正気に戻るために、ブン、と、頭を強く振った。
確かに、目の前に居る男は『仇』
自分の、憎むべき『仇』だった。
(惑わされるな……)
ハヤブサは、強く己に命じる。
目の前の男の言葉にも。先程響いて来た、あの暗い声にも。
信じるべきは自分の『心』だ。そして、今までの経験と修行だ。
迷うな。
惑わされるな。
そして―――――躊躇うな。
父から教えられた、『生きるための鉄則』を、ハヤブサはもう一度頭の中で復唱する。頭に血が上り過ぎていると感じた彼は、一度、大きく深呼吸をした。
「だいたい! 俺がここで何をしていようと、お前には関係ないだろう!? 何故そんな事を聞きたがるんだ!!」
噛みつく様に問い返してくるハヤブサに、男は事もなげに答えた。
「決まっているだろう。ここから出るためだ」
「………………!」
絶句するハヤブサに、男は更にたたみかけて来た。
「言った筈だ。この空間は『閉じられている』と。この封印を解くためには、ここで君がしようとしていた事こそが、鍵を握っているはずなんだ」
「………………」
鬼蜘蛛党の頭首の言葉を暫く吟味するかのように押し黙っていたハヤブサであるが、やがてその口を開いた。
「ここから出て………貴様は、何をしようと言うつもりなんだ?」
「さあな………」
「もしも、再び里を襲う、と言うつもりなら―――――」
「………殺すか?」
男から問い返されて、ハヤブサは思わず、カッと頭に血が上った。
「当たり前だッ!! 『出られたら』などと言わず、今すぐ貴様を殺してやるっ!!」
抜刀して、一直線に男へと向かって行く。
「お……おい! ちょっと待て………!」
対して男の方は刀も持たず丸腰だったが、ハヤブサはそれには構わず、男に斬りかかって行った。放っておけば里に害を加えると分かっていて、このまま見過ごすわけにはいかないと思った。
ただ、男の動きは素早かった。一撃必殺のつもりで自分は刀を振り回しているのに、自分の刃は男にかすりもしない。紙一重で、ひらり、ひらりとかわされている。
「おのれッ!!」
更に振りかぶろうとした時、男の手がハヤブサの手を掴んできた。
「―――――!!」
ギョッと見上げるハヤブサを、男はジロリ、と睨んでくる。
「………全く……! 人の話を聞けッ!!」
男はハヤブサの手から強引に刀を捥ぎ取ると、彼の身体を蹴り飛ばした。
「ぐッ!!」
吹っ飛ばされたハヤブサは、すぐに体勢を立て直し、短刀を構えたが、刀を持った男に立ち向かう事には二の足を踏んだ。短刀で切りかかるには、手足のリーチも含めて、子どもである自分はあまりにも不利過ぎると、悟ったからだ。
(斬りに来るか!?)
短刀を持って構えて、男の様子を伺う。だが男は、奪った刀を手に持ったまま、構えるでもなくじっと静かに佇んでいた。
「言っただろう、ハヤブサ……。私は、君とは争う気などないと」
「その言葉……どこまで信用できる?」
短刀を構え、男を睨みつけながら、ハヤブサが問う。その問いに、男も苦笑していた。
「……無理に総てを信用しろとは言わん。ただ、私は君に伝えたいんだ。もしも、君が私をどうしても殺したいと言うのなら―――――」
「……………」
殺したいに決まっている、と、口の中でハヤブサが呟く。すると男が、意外な事を伝えて来た。
「この刀では、無理だぞ」
「えっ?」
瞬間何を言われたか分からずに、目をぱちくりさせるハヤブサに、男はにこりと微笑みかけると、おもむろに自分の腕に刀を向けた。
「見ろ、ハヤブサ」
その言葉が終わると同時に、男は自分の腕を一刀のもとに斬り落とす。
「な―――――!」
驚き、息を飲むハヤブサの目の前で、男は斬り落とした腕を拾い上げると、切り口にピタリとくっつけた。それから腕を押さえて半刻もせぬうちに、男の腕が何事も無かったかのように元に戻り、普通に動く様になっている。
「な………! 馬鹿な………!」
「………御覧の通り、私は少し特殊体質でね……。普通に刀で切られても、このようにすぐに治ってしまうんだ」
「……………!」
「勿論、殺されてしまっても、2、3時間後には息を吹き返すぞ。君に斬られた腹の傷だって、綺麗に消えていただろう?」
「………すると貴様は、『不死の人外』だとでも言うのか……?」
茫然としながらも、男の言葉を何とか理解したハヤブサが、ポツリと呟く。男は「そうだ」と頷いた。
「唯一、私を死に追いやれるとしたら、それは『龍剣』と、その『使い手』なのだが――――」
「―――――!!」
ギョッと目をむくハヤブサに、男は更に衝撃的な事を言ってきた。
「リュウ・ハヤブサ……。君こそが『龍剣』に選ばれた『使い手』なのだろう? なのに、何故―――――君は今、それを持っていないのだ?」
「『使い手』!? 俺が!?」
(やはり……『使い手』としての自覚が無いのか……)
シュバルツの言葉に驚いてしまっている少年ハヤブサを見ながら、彼は確信を深めた。だからこそ龍剣は、彼の傍を離れ、自らを『封印』してしまっているのだろう。自覚のない『使い手』の魂を、己が妖力で食ってしまわないように。
思い出さなければ駄目だ、ハヤブサ。
自分が何者であるのか。
その業、その能力を。
お前を蝕む『邪悪な物』が、お前の魂を喰い尽くしてしまう前に。
「ああ。君は龍剣に『選ばれて』いる。間違いなく、『使い手』になる筈なんだ」
「そんな………!」
シュバルツの言葉が俄かに信じられないのか、少年ハヤブサは茫然と呟きながら、その場にへたり込んでしまっていた。
「………俺に、そんな能力は無い筈だ……。父上も、『お前にはまだ早い』と……。なのに……」
「父君が、君をここに来させたのか?」
男の言葉に、ハヤブサは素直にこくん、と頷いていた。
「里が襲われた時―――――」
ハヤブサは話しながら、相手の男の顔をちらりと見る。
目の前に居るのは、間違いなく里を襲って来た鬼蜘蛛党の党首。血に飢えた瞳をぎらつかせながら、残虐に赤子を引き裂いていた姿を、忘れる事など出来ない。
なのに何故―――――自分は、この男とこんな話をしようとしているのか。自分で自分の行動が、ハヤブサは不思議で仕方がなかった。
それに目の前に佇むこの男から感じる、違和感は何なのだろう。
赤子を引き裂いていた時のあの男と、今の目の前に居るこの男を、何故かイコールで結び付ける事が出来ない。この静かな佇まいの男が、本当にあの残虐な行為をした人物なのかと疑いたくなるほどだ。
(しかし……『外見だけで判断するな』とは、父上も仰っておられたしな……)
ここまで思い至って、ハヤブサはとりあえず、あれこれと考え込む事を止めた。
自分の身体の秘密をあっさりと曝し、会ったばかりの自分に向かって『龍剣の使い手』と言いきったこの男と、話をしてみたいと言う好奇心の方が、ハヤブサの中では勝ってしまっていた。
「父は皆を守るために、敵と戦っていた。俺はそれをお助けしようと傍に走り寄って行った。そうしたら―――――」
「リュウ!! お前は里の奥の祠に行き、『龍剣』を手に入れて来い!!」
敵と戦いながら、ハヤブサの父―――――ジョウ・ハヤブサは叫ぶ。それにハヤブサは否やを唱えた。
「何故ですか!? 父上! あれは里の秘宝中の秘宝。選ばれし者にしか、それは手にする事が出来ないと―――――!」
「今その龍剣の力が必要なのだ!! 早く行け!!」
「でもそれは、父上の役目では―――――!」
「違う!! それは、お前でなければならぬのだ!!」
「…………!」
父に強くそう言い切られて、ハヤブサは絶句する。
「行け!! 早く!! そして、皆を救うのだ!!」
「父上……!」
「リュウ様!! お早く!!」
その声に振り返ると、里の者たちも皆、各々の手に戦うための武器を持って、父の後に続いていた。
「私たちは大丈夫です!! ですから早く!!」
「首尾よう龍剣を手に入れて、早く戻って来て下せぇ!!」
「それまで我々が、リュウ様に変わってジョウ様をお守りいたします故――――!!」
「皆……!」
しばらく茫然としていたハヤブサであるが、やがて、皆の声に後押しされるようにその顔を上げ、踵を返した。そして、里の奥の祠を目指した。背後に、燃え上がる炎と、人々の悲鳴と怒号を感じながら―――――
石段を駆け上がり、いくつもの鳥居をくぐり抜ける。その先に、目指す祠はあった。
酷く静謐で、どこか、素朴ささえ感じさせる小さな祠。
(龍剣は!?)
その中で、ハヤブサは懸命に目的の物を探す。すると、祠より更に奥まった場所に在る小高い丘の上に、淡い輝きを放つそれを見つけた。
「…………!」
ハヤブサがその傍に走っていくと、何がどういう仕組みになっているのか、透明な巨大な『石』の様な物が、そこに淡い輝きを放ちながら浮いていた。そしてその中に、龍剣が収められていたのだった。
(これは……どうやって取り出せばいいんだ……?)
ハヤブサが茫然と見つめていた矢先に、上空から『闖入者』が降って来て―――――
そして、現在に至る、と言う訳であった。
話を終えた切り、座り込んでしまっているハヤブサの傍に、男は歩み寄って来ると、「ほら」と、言いながら、手に持つ刀を差し出してきた。
「えっ?」
「返すよ。君の刀だろう?」
「な…………! 正気か!?」
唖然とするハヤブサに、男はにこりと微笑みかける。その笑みを『どこかで見た事がある』と、感じてしまうのは何故なのだろう。
「言った筈だ。リュウ・ハヤブサ……。私は、君と争う気はないと」
「……………ッ!」
ばっと、ひったくる様に剣を手に取りかえす。それを鞘に収めながらじろりと男を睨みつけると、男は苦笑しながら口を開いた。
「どうしても、私を斬りたいか? 切り刻みたいなら付き合うぞ? 死なないから、本当に切り刻むだけになるが――――」
「もういい!! そんな不毛な趣味は無い!!」
怒鳴りつけて、プイッと視線を逸らした。本当に男の方が、自分の事を敵視も警戒もしていないのだと感じて、何だか悔しくて腹立たしい気持ちになる。こいつを『仇』だと、睨みつけている自分の方が、まるで馬鹿みたいではないか。
(『龍剣』だと、自分は死ぬのだと言っていたな……)
男の言葉を反芻して、ハヤブサはギリ、と歯を食いしばっていた。
(見てろよ……! 必ず龍剣を手に入れて、この男を慌てさせてやる……!)
そこまで思い至ってから、ハヤブサは一つ大きなため息を吐いていた。
(それにしても馬鹿としか言いようがないな。この男は……。自分のそんな大きな身体の秘密を、あっけなく俺などに話して………)
敵視も警戒もしていないのにも程があり過ぎる。まさに、毒気が抜かれるとはこのことだとハヤブサは感じた。
それにしても妙だ。
この『毒毛が抜かれる』感覚を、自分は、前にもどこかで味わっていた様な気がする。
それは、何処なのだろう。
何故なのだろう。
思い出せそうなのに思い出せない。それが、少し歯痒くもあった。
「これが、その『龍剣』だ……」
ハヤブサは男と共にこの龍剣の前まで話しながら歩いて来て、不思議な感覚に襲われる。
『龍剣』にまつわることすべて、里の中では秘中の秘とされてなければならない物だ。それを―――――
自分はどうして、他所者にこんなにも軽々しく、それを話しているのだろう。
「……………」
無言で龍剣を眺めている男の横顔に、ハヤブサは改めて問いかけた。
「問う。お前は、本当に『龍剣』が目当てではないのか?」
男はちらりとハヤブサを見やると、再び龍剣に目を移しながら言った。
「ああそうだ。私は龍剣を手に入れようとは思わない。あれは『魔剣』だ。それは――――君の方がよく知っているだろう?」
「…………!」
「あの剣の危険さを少しでも理解している者ならば、それを自分の物にしようなどとは思わない物だがな」
(確かにそうだ)
男の話を聞きながら、ハヤブサはどこかで納得していた。この龍剣は、『妖刀』の類だった。剣自体に意志があり、その『使い手』を選ぶ。剣に選ばれなかった者がそれを強引に手に取ると、剣自体が牙をむき、その者の魂を喰らうと言う。現に、何人もの血ぬられた犠牲者の話を、ハヤブサも父親から伝え聞いていた。だからこそ龍剣は里の奥に封印され、厳重に守られて来たのだが。
(しかし……この石に覆われた龍剣を、どうやって取り出せばいいのか……)
ハヤブサがそう思案していた、まさにその時。
「ハヤブサ!!」
男の声がしたかと思うと、いきなり自分の身体が抱きかかえられ、強引に飛ばれた。
「―――――!?」
それと同時に、自分たちが居た場所が、ドコォッ!! と、音を立てて穿たれる。
「な…………!」
茫然としている自分の顔を、男が覗き込んできた。
「怪我は無いか?」
「よ、余計な御世話だ!! 離せっ!!」
はっと我に帰ったハヤブサが軽く足掻くと、男はあっさり彼の身体を解放していた。
「………どうやら、『守護者』がお出ましの様だな……」
「―――――!」
男の言葉にハヤブサが顔を上げると、あわく光を放つ『石』の上に、仁王の様な恰好をした者が姿を現していた。身体全体が白い光に包まれ、筋肉質な両の腕には、二振りの大剣が握られていた。
その者は無表情のままにふわりと音も無く地面に降り立つと、こちらを睨み据えて来た。
(龍剣を欲する者は誰だ?)
まるで、そう問いかけるかのように。
「……………!」
ハヤブサがそれに応えるかのように剣を構えようとすると、男がスッとその傍を離れた。
「…………?」
窺うように男の方をハヤブサが見ると、男は言った。
「これは、君が戦うべきだ」
「―――――!」
「これは、君の戦いだ。………そうだろう?」
(確かにそうだ)
男の言葉に、ハヤブサも一応納得する。龍剣を手に入れるために、ここに来たのは自分だ。だからこれは、自分が挑むべき戦いである事、ハヤブサも十分承知している。
しかし――――
ハヤブサは守護者に向かって刀を構えながら、男の方にもちらりと視線を走らせる。
自分があの守護者と戦っている間、男の方から邪魔が入らないか―――――という懸念故であった。
その視線の意味に気付いた男の方が、やれやれと肩をすくめる。
「ハヤブサ……。心配せずとも、私はお前の邪魔をしたりはしない」
「本当か?」
眉をひそめるハヤブサに、男は小さくため息を吐いて答えた。
「言った筈だ。私は君と争う気はないし、ここから出たいのだと。そして、ここから出るためには、君が龍剣を手に入れてくれないと困るんだ」
「困る?」
怪訝な顔をするハヤブサに、男は更に言葉を続けた。
「これは私の推測だが………君が龍剣を手に入れれば、この閉じられた空間も開いて、外に出られるようになるのではないのか?」
「…………!」
「何時までも二人で、ここに閉じこもっている訳にはいかないだろう。ここから出て―――――互いの目的を果たさなければ」
「『目的』……貴様の『目的』は、何だ?」
『龍剣を手に入れる』と言う、自分の目的は明白だ。しかし――――里を襲って来た筈のこの男の『目的』がいまいち見えて来なくて、ハヤブサは少し困惑する。しかし、そんなハヤブサを、男は突き放すように言った。
「私の目的など――――君には関係ない事だろう」
「関係ないだと!? 里を襲っておいて――――!!」
色めき立つハヤブサに、男はまたもやれやれと肩をすくめた。
「……分かった。ならば、こうしよう。君が龍剣を手に入れたら、私も君に我が『目的』を話す」
「本当か?」
問うハヤブサに、男は頷いた。
「ああ。私は君に、嘘はつかないよ」
「…………!」
(およそ、『忍者』らしからぬ奴だな………)
ハヤブサは男の言葉を聞きながら、強くそう思った。忍者の本質は危道。だましだまされるのが常であると言うのに。
「嘘をつかない」と言った男のこの言葉は、果たしてどこまで信じられるものなのだろうか。
(頭からこの男を信じるのは危険かもしれない……。だが………)
ハヤブサは、自分から少し離れた所で、丸腰で佇んでいる男を見る。
今のところこの男の行動は一貫している。この男は本当に―――――自分に龍剣を手に入れさせようとしている事だけは、どうやら間違いが無い様だ。
ならば
ハヤブサは、剣を改めて構える。
自分は、龍剣を手に入れるまでだ。そうすれば―――――男の『本心』も、見えてくる物があるだろう。
「いざ参る」
少年ハヤブサは、『守護者』に向かって正眼を向けていた。
第3章
東京の街の一角で、黒い影達とシャッフルの紋章を持つ者たちとの戦いが、未だ続けられていた。彼らの拳が、剣が、振るわれるたびに、影達は細かい粒子となって四散して消えて行った。
「一体いつまでこんな事を続ければいいんだ!?」
目にもとまらぬ連続パンチを繰り出しながら、チボデー・クロケットが叫ぶ。
「次から次へと―――――倒しても、きりがないぜ!!」
「泣きごとなど聞きませんよ、チボデー・クロケット」
フェンシングの剣を激しく振るいながら、ジョルジュ・ド・サンドが口を開く。
「この影達が居なくなるまで、戦うまでです。それが人々のため――――如いては、マリアルイゼ様のためです!」
「はっ! お前は二言目にはそれだな!」
この気真面目な騎士道を貫くフランス人青年に、チボデーは半ば呆れたようにため息を吐く。
「姫様のため、姫様のため―――――って、お前はそれで恥ずかしくないのかねぇ?」
「何を言っているのです? 貴方もそんなに大差ないでしょう?」
チボデーに嫌みを言われても、ジョルジュの涼しい顔は崩れない。
「貴方だって、部屋を飛び出す時に大切な方の名を叫んでいたでしょう」
「そ、それは―――――!」
ぐっと言葉に詰まるチボデーに、ジョルジュはフフフ、と笑いかけた。
「戦う理由なんて、皆似たような物です。それで良いじゃありませんか」
「そ、そうか……? いや、そうなのか………?」
ジョルジュの言葉に、納得しながらも何か違和感を感じてチボデーは首を捻ってしまう。自分がシャリーたちに向ける感情と、こいつがマリアルイゼ姫に向ける感情って、果たして同じような物なのだろうかと。
「ほらほら、手が止まっていますよ、チボデー」
ジョルジュの指摘に、チボデーもはっと我に帰る。
「今は、無駄話をしている時ではないでしょう! 一体でも多く、敵を倒さなければ――――!」
ジョルジュが目に留まらぬ手さばきで、次々と短刀を投げつけて行く。
「それもそうだ、なッ!!」
チボデーも負けじと高速パンチを繰り出す。二人は再び、『影』たちとの戦いに没頭して行った。
「ガイア・クラッシャー!!」
アルゴ・ガルスキーの拳が地面を割り、その衝撃波が次々と地面を穿ちながら拡散し、影達の大軍を粉砕して行く。その周りでサイ・サイシーが中国拳法の棒術で、次々と影達を薙ぎ倒していた。
「なあ、アルゴのおっさんよ!」
戦いながらアルゴに近づいたサイ・サイシーが声をかける。
「何だ?」
短く返す屈強な戦士に、少年であるサイ・サイシーはニヤッと笑みを見せた。
「どっちが沢山あいつらを倒せるか、競争しないか?」
「フン、くだらんな」
アルゴはサイ・サイシーの提案を一蹴する。
「数とか武功とか――――そんなものを競うために戦ってなどいない。ただ、敵は排除するのみだ」
「それはそうだけどさ」
アルゴの言葉にサイ・サイシーは口を尖がらせる。アルゴの言わんとしていることも『戦士』としては納得できるが、血気盛んな彼としては、やはり、『競争』と言う刺激が欲しいのだ。
ふとサイ・サイシーの視界に、同じく敵を薙ぎ倒しまくっているドモンの姿が飛び込んでくる。
「兄貴~~~~!」
ドモンならば、きっと自分の提案に乗っかってくれるだろうと確信したサイ・サイシーは、喜々として彼の方に向かって走って行った。
「超級!! 覇王!! 電影弾!!」
自らを一個の光の玉と化して、ドモンは次々と影達を薙ぎ倒して行く。そこに、サイ・サイシーが走り込んできた。
「兄貴~~~♪」
「どうした!? サイ・サイシー!!」
戦いの勢いのまま、ドモンが鼻息荒く問い返してくる。サイ・サイシーは人懐こい笑顔を浮かべながら、ドモンに提案して来た。
「なぁ兄貴! これからどっちが沢山敵を倒せるか、競争しないか?」
「は? 何を言っているんだ? お前」
アルゴと同じような反応を返してくるドモン。だが、サイ・サイシーは知っていた。ドモンはアルゴよりも、はるかに血気盛んな性質である、と言う事を。
「今はそんな事をしている場合じゃないだろう! 敵を一体でも多く倒さなければ――――」
「あれっ? 兄貴、俺に負けるのが怖いの?」
安っぽい挑発をしてみた。すると、案の定と言うべきか―――――ドモンは容易く頭からそれに乗っかってきた。
「何ぃ?」
「俺なんかもう、軽く500体ぐらは倒してるもんね~♪ 兄貴には無理な数だったかな~?」
「何おう!? お前が500体なら、俺はもう1000体以上は倒しているッ!!」
「じゃあどっちが多く倒せるか競争する? 俺は10000体ぐらい倒しちゃうけど」
「お前が一万なら、俺は一億万体だッ!!」
(五月蝿い………)
小学生並みの喧嘩を始めたドモンとサイ・サイシーにアルゴは少しうんざりする。
彼からしてみれば少々理解に苦しむところだ。そんな不毛な口論をする間にも、敵を一体でも二体でも倒せばいいのにと思う。しかし、何故彼らはそれをしないで、馬鹿みたいな事に時間を費やしているのだろう。
(シュバルツ殿がいれば……二人にここで鉄拳制裁を振るってくれているところだろうがな………)
アルゴ・ガルスキーは、はぁ、と、ため息を吐く。日頃からどれだけシュバルツがドモンの面倒を見てくれているか、こういう時によく分かる。
自分は正直シュバルツほどお人好しではない。不毛な言い争いをしている二人を放っておいてもいいのだが―――――
とりあえず、邪魔だった。
「ガイア・クラッシャ――――ッ!!」
アルゴの放ったそれは、言い争いをしている二人をも巻きこんで、物の見事に影達を薙ぎ倒していた。
「おいっ!! アルゴ!!」
「何するんだよ!? おっさん!!」
当然巻き込まれた二人から文句が出るが、アルゴはどこ吹く風だ。
「うるさい。とっとと戦いに戻れ!」
それだけを言うと、アルゴはまた影達に攻撃を仕掛けている。あまりにも簡潔に正論を返されたので、二人は反論する言葉を失ってしまった。
「~~~~~~~~ッ!」
2人はしばらくアルゴや互いをギリ、と、睨みつけ合っていたが、やがて「フン!」と、踵を返した。
「見てろ!! 絶対にお前より多く敵を倒してみせるッ!!」
「へへ~んだ!! 兄貴こそ、後で咆え面をかくなよ!!」
憎まれ口をたたき合いながらも、二人もまた、影達の戦いに没頭して行った。
「フフフフ……。やっておるな………」
その頃キョウジの家で結界を張り続けている東方不敗は、そう独りごちながらにやりと笑っていた。結界の中心に居る彼には、どうやら中で起こっている事が手に取るように分かるようだった。
その横で、キョウジが一心不乱に、何かの装置の様な物を作っている。何に使う物かはその形状だけではよくわからないが、この状況下でキョウジは無駄な物を作る様な事は無いだろう、と、東方不敗は思っていた。
その装置も、もう少しで完成しそうな気配を見せている。東方不敗はキョウジに声をかけることにした。
「キョウジよ」
「はい。何でしょう? マスター」
手を止めずに、返事をしてくるキョウジ。
「この後の戦局―――――お主はどう読む?」
将棋の話をする様に、東方不敗はキョウジに問いかけていた。東方不敗はキョウジとこのような『戦談義』をする時間が、とても好きだった。
「あまり楽観視はしていません。ですから、備えています」
「備える?」
聞き返す東方不敗の目の前で、キョウジは部品を落としそうになる。「おっとっとっと!」と、彼は慌てて部品を持ち直して、また組み上げ始めた。
「人間の命を屠り、自身に取り込むために、『邪神』はハヤブサの身体から影達を放った。だけど、その目的は、達成されてはいない………」
話しながらも、手は猛スピードで作業を進めている。そのスピードたるや、最早神業クラスだと東方不敗は思った。
「『邪神』はそろそろその原因を突き止め、そして、考えるでしょう。自分の動きを制限している者は何か………。そして、それを取り除くには、どうしたらいいか………」
「うむ…………」
「それが見えてくると―――――『急がねばならない』と、思うんです」
確実に悪意が
邪気が
近づいてきているのが分かる。
だからキョウジは焦っていた。
早くしなければ、外に居るドモン達の頑張りが、マスターの結界が、総て無駄になってしまうと分かるから。
(そろそろじゃな……)
東方不敗もまた、部屋に満ちてくる邪気の濃度の上昇具合から、『邪神』が次の一手を打ってくると感じ取っていた。
おそらく『邪神』は、結界を壊す事を考える。ここに『邪気』が満ちて来たのは、邪神の方が、結界を壊す手段を悟ったからに他ならない。
そう。
今――――邪神たちの影を引き止める結界を張っているのは東方不敗。
彼を仕留めることができれば、結界はたちどころに壊れ、外に居る人間たちの命を、存分に屠ることができるだろう。
そればかりか、ここには内側から邪神に乗っ取られそうになっている、ハヤブサとシュバルツの身体もある。
東方不敗以外の『何者か』の結界のおかげで、内側からハヤブサが乗っ取られるのをかろうじて阻止している状態であるが、これが、外側からもハヤブサやシュバルツの身体に攻撃を加え、それを取り込む様な事態になってしまったら。
いかに忍者二人の精神力が屈強な物でも、外側と内側の両面から邪神に攻撃されてしまっては、ひとたまりもないだろう。そこから最悪のシナリオに転がり落ちて行ってしまうことが―――――容易く想像出来た。
(その事態は避けねばならぬ)
東方不敗は邪気払いの香の煙を見つめながら、そう決意していた。
別に自分にとって、街に居る人間たちが邪神に襲われようがどうしようが、どっちでも構わなかった。地球人類の殲滅を一度でも企てたが故に、今でも東方不敗は人間の醜さ、汚さを十分承知しているし、命をかけて守る物でもないと思っている。
しかし―――――自分が密やかに、主と仰ぐと決めているキョウジが、邪神によって人々が傷つき、殺される事を望んでいない。主が望まない事を、それに仕える者が違える訳にはいかないのだ。それが出来ずして―――――どうしてこの先、キョウジを主と仰ぎ続ける事が出来ようか。
(しかし……この状態で戦う事は、想像以上に骨が折れそうじゃな………)
結界を張りつつ、ハヤブサとシュバルツの身体を守ろうとする、キョウジを守る。これは、かなり難易度が高いミッションだと東方不敗は感じていた。
だが、やらねばならぬ。
この状況になることを承知で、自分はここに居る事を選んだのだ。それを、今更怖じ気づくわけにもいかない。
それが出来ずして、何がシャッフル同盟の筆頭、『キング・オブ・ハート』か。
「……そろそろ来るぞ。キョウジよ……覚悟はできていような――――」
バキバキと指を鳴らしながら、不敵に笑う。しかし、東方不敗の額には、脂汗が浮かんでいた。
「待ってください。後少し――――」
装置を組み上げているキョウジの手の動きが、更に加速する。その目の前で、ゆらりと黒い影が揺らめき―――――何かの形を為して行った。
来る―――――!
戦いの予感に東方不敗の血が沸騰する。
殺気と邪気が充満し、この部屋の空気は今にも破裂しそうになっていた。
影が獣と人の混じり合った様な形を為し、その目に鋭い眼光を宿らせる。
口から鋭い牙を覗かせはじめた。
「キョウジよ!! 下がれっ!!」
「―――――!」
東方不敗がそう叫ぶのと、キョウジが手元のスイッチを押すのが、ほぼ同時だった。
バシッ!! と、音を立てて、キョウジの組み上げた装置から青白い光が爆ぜ、それが東方不敗とキョウジ、そして、忍者二人が寝ているベッドを取り囲むように走る。
「ギャッ!!」
そしてその光が、キョウジに襲いかかろうとしていた獣の影を、弾き飛ばしていた。
「吻ッ!!」
その隙を突いて、東方不敗の正拳が、影に炸裂する。ふっ飛ばされた影は、哀れそのまま壁に激突して―――――四散していた。
「ま………間に合った…………!」
その声に東方不敗が振り返ると、キョウジが手元に在るスイッチの様な物を握りしめたまま、肩で息をしている。額からは、汗も滴り落ちていた。
「キョウジ。お主………何を作った?」
構えを解いて問いかける東方不敗に、キョウジは苦笑気味の笑顔を見せた。
「マスターの結界を張る作業の肩代わりになる物を………。マスターの代わりにこいつが結界を張ってくれます。これでマスターは、結界を張る事を気にすることなく、自由に動く事が出来る筈です」
「……………!」
かなり驚いた東方不敗であるが、ためしに結界に『気』をやることを少し止めてみる。これで普通なら、自分が張った結界は切れてしまう事になるのだが、結界がそのまま機能し続けている事が、東方不敗にも分かった。
「ついでに、この部屋にも軽く結界を張らせていただきました。ベッド周りだけですけど、さっきみたいに、影の侵入を一瞬ですが拒む事が出来ます。これで多少戦いやすくなると思うのですが―――――」
「でかした、キョウジ。よくやってくれた」
東方不敗は素直にキョウジに礼を言う。
結界に気を配らなくていい事と、相手に強制的に隙を作らせる機会があると言うだけで、戦いやすさが格段に違ってくるからだ。
「それにしてもキョウジよ……。一体どうやってこの装置を作り上げたのだ?」
「ええと、マスターの身体から出ている『結界の波動』を分析して―――――」
そう言ってキョウジが装置について説明して行くのを、東方不敗は半ば顔をひきつらせながら聞いていた。
自分が結界を張り出してからここに至るまでの僅かな時間で、よくぞここまで解析して、この仕組みを作り上げたものだ。あまりにも天才過ぎてひっくり返りたくなるのは気のせいなのだろうか。
(それにしても、これだけの才覚があると言うのにこ奴ときたら――――)
東方不敗は知らずため息を吐いてしまう。
何故―――――大望も野望も抱かずに、大学の一非常勤講師としてくすぶっているのだろうか。彼ほどの才があれば、それこそ、何にでもなれるだろうに。
「ただ………この装置は『電気』で動いています」
ショットガンの様な物を手に持ち、弾を装填しながらキョウジは言葉を続けた。
「今は街のライフラインが稼働していますから、特に問題はありませんが―――――それが破壊された時が問題ですね。活動限界時間が生じます」
「それは、どれぐらいじゃ?」
問いかける東方不敗に、キョウジは苦笑しながら答えた。
「自家発電の装置に切り替えて、およそ72時間と言ったところでしょうか。それ以上となると、少し難しいですね……」
「72時間か………なる程のう」
東方不敗はにやりと笑った。戦いに制限や困難はつきものだ。こういう条件が有った方が、寧ろ自分としては燃えられた。
「短期決戦―――――望むところよ!!」
バコォッ!! と、音を立てて、東方不敗の拳が炸裂し、また一つ影を屠っていく。
「さあ! 雑魚共!! かかって参れ!!」
喜々として戦う老人の背後で、キョウジはショットガンを構えながら、もう一台自家発電機を作った方がいいだろうかと考え始めていた。
「うおおおおおおっ!!」
少年リュウ・ハヤブサと、龍剣の『守護者』との戦いは、いつ果てるともなく続いていた。シュバルツは、それを静かに見守っていた。
仁王の格好をした守護者は、双剣を振り回してハヤブサと相対する。ハヤブサはそれに互角に渡り合っているようにも見えたが、やがて、徐々に仁王に押されつつあるように見えた。
(やはり……子どもの格好のままでは不利だな……。リーチも短いし、力も押し負けているように見える………)
シュバルツは、ハヤブサの戦いを見守りながら、そう分析していた。彼が『龍剣』に『使い手』として認められるようになるまでは、まだ少し時間がかかりそうだった。
(ハヤブサが自分の本来の姿を思い出す事が出来さえすれば……話は早いのだろうが―――――)
そこまで導いてやるには、どうすればいいのだろうかとシュバルツが思案をしていた時―――――ふと、背後に寒気を感じた。
「―――――!?」
振り返ると、背後の空間にひびが入り、そこから巨大な怪物のような黒い影が、強引にこちらに入り込もうとしている。鋭く長い爪が妖しい輝きを放ち、ぎらついた眼光でシュバルツを睨みつけていた。
(まずい……! 防がねば――――!)
強くそう感じて、刀を挿しているはずの腰に手をやるが、そこに得物は無かった。シュバルツの刀はハヤブサに取り上げられ、かなり離れた所の地面に突き立てられていたのだ。
刀を取りに行くか、と、シュバルツは一瞬思う。しかし、すぐに考えを改めた。
もしも、自分が刀を取りに行くそぶりを見せれば、それだけで、ハヤブサの戦いの邪魔をしてしまう事になる。自分は「邪魔をしない」と、彼と約束をした。それは、守られねばならぬと、彼は思うのだ。
だが、このままこの怪獣じみた影の侵入を許してしまうのもきっとよくない。この空間はハヤブサの『心』―――――何としても守らなければと、シュバルツは強く思った。
(ならば、どうする?)
シュバルツは咄嗟に周りを見渡して、自分の近くにある朽ちかけた観音像の背中に、ボロボロに錆びついた剣が背負われているのを見つけた。
(これを借りよう)
シュバルツは観音像に向かって手を合わせて一礼すると、その背中から、そっと剣を引き抜いた。
「……………」
剣を中段に構え、目を閉じる。
心の中に思い描くは、滴り落ちる一滴の水。
集中する。
その水滴に。
目の前を落ちて行こうとする、それを―――――
刀の光が一刀両断にした瞬間、シュバルツはカッと目を見開いた。
朽ちかけている刀の刃に、あり得ない程の輝きが宿る。
『明鏡止水』―――――
彼の『極意』の発動であった。
「いざ、参る」
チャッと、刀を正眼に構え、シュバルツはその怪物の真正面に立っていた。
ガツン!!
何十合と打ち合った刀が弾かれ、少年ハヤブサの身体は後方に弾き飛ばされた。
「くっ!!」
素早く体勢を立て直し、仁王を睨みつける。
仁王は息一つ乱さず、ただ静かにそこに立っていた。対して自分の呼吸は上がり、乱れて行く一方だ。
酷く勝ち目のない戦いをしているように感じられて、ハヤブサはギリ、と、歯を食いしばる。
(あきらめる訳にはいかない)
それでも重い足腰に鞭をうち、刀を上げた。
自分ならば龍剣を取って来られると信じてくれた父のためにも。
襲われている里を、救うためにも―――――
「叭ッ!!」
もう一度、立ち向かう。
ぶつかっていく。
自分は―――――それしか出来ないから。
ガンッ!!
ガツンッ!!
刀の打ち合う音だけが、辺りに響く。
太刀を相手の身体に何とか届かせようと試みるが、目の前の仁王には、驚くほどに隙が無い。自分の太刀は総て防がれ、それどころか、向こうの太刀が徐々に自分に肉薄してくるのが分かる。
(くそっ!)
ハヤブサはギリ、と、歯を食いしばっていた。仁王に対して有効な突破口を見いだせない自分が、情けなくて悔しくてたまらない。
(何か手は無いのか――――!? 何か手は―――――!)
そう思案をしながら戦い続けている時、その光景は、偶然ハヤブサの視界に飛び込んで来ていた。
それは、「自分の戦いの邪魔をしない」と、言っていたあの男。
その男が、いつの間にかまばゆい輝きを放つ刀を手に、こちらに背を向けて立っている。
そして、その男の真正面には、その男の何倍もの大きさを誇る、巨大な怪獣の様な化け物の影―――――
「―――――!?」
異様な光景に、ぎょっと目をむくハヤブサ。だがその光景は、それだけでは終わらなかった。
怪獣が唸り声を上げながら、巨大な爪を振り下ろしてきた刹那―――――朽葉色の忍び装束の主が、宙に飛んだ。
「叭――――――――ッ!!」
ストン、と男が地面に着地すると同時に、怪獣の影が頭から腰にかけて唐竹割にされた。
文字通り、美しいまでの『一刀両断』―――――ハヤブサは知らず、己が戦いを忘れて見入ってしまう。
そしてそれが、よくなかったのだろう。
「ハヤブサ!!」
男の叫び声を聞いた瞬間に、自分は何者かに強く殴られてしまっていた。
そのまま彼は、昏倒してしまう事になるのだった。
「………ハヤブサ……! ハヤブサ……!!」
次に目を開けた時、男が心配そうにこちらを覗き込んでいる姿が視界に飛び込んできた。
「―――――!」
慌てて飛び起きた瞬間、自分の額から落ちてくる濡れた冷たい布。
腕や足やらに巻かれている数々の包帯。
どうやら自分は、男に『介抱』されてしまったのだと感じて、ハヤブサは動揺を禁じ得なかった。
「離せっ!!」
男の手を振り払い、距離を取る。
男はしばし目をぱちくりとしばたたかせていたが、やがてその面にフッと笑みを浮かべた。
「………それだけ動けるのなら、大丈夫そうだな。良かった……」
そう言って、男はやれやれと立ち上がる。
「……………!」
その男の様を見て、ハヤブサは何故か苦い気持ちに襲われた。
(……どう言うつもりだ!? 俺の里を襲ってきた男が――――)
本来ならば、素直に礼を言わなければならない事、ハヤブサも十分承知している。だが、目の前に居る男は、あくまで『仇』なのだ。それに「礼」を言うと言う行為には、どうしても抵抗を感じてしまう。
だが―――――
自分が気を失う直前に見た、あの男の動き。戦い――――
あれだけの大きさの化け物を一刀両断にしていた。
凄まじいまでの動き、技の切れ――――
どれだけの剣の腕をもてば、あれだけの技が出来るのだろう?
純粋にそこに惹かれ、興味を持ち始めていた時―――――男から、再び声をかけられた。
「ほら、水と食料だ。食え」
「―――――!?」
ギョッと目を見開くハヤブサの傍に、男はそれをコトン、と置くと、すぐに立ち上がった。
「勘違いするなよ。これを用意したのは私ではない。そこに居る観音様だ」
「はあ!?」
目を白黒させるハヤブサに対して、男はちらりとこちらを見ると、すぐにフイ、と視線を逸らした。
「信じる、信じないは勝手だがな……」
そう言いながらシュバルツは、ハヤブサを介抱している時に自分が見た光景を思い出していた。観音像の影から伸びて来た白い手が、そっと握り飯を作り、置いて行ったのを。
自分に、こういう「食料」は要らないから、きっとこれは、ハヤブサのためのもの――――シュバルツはそう思っている。
「……………」
ハヤブサはしばらく逡巡するように皿に乗っている握り飯と、傍に置いてある竹筒を見つめていた。
「食事はきちんと取れ。そうしなければ、戦えるものも戦えん」
男はそう言うと、自分にくるりと背を向けると、すたすたと歩いて行った。離れたところにどかっと腰を下ろして、そこに身体を落ちつける。
「……………!」
眉唾な話をして食事を置いて行く男に、ハヤブサも何かを思わないでもない。だが、この男が自分に害意があるのならば、こんな風に介抱したり食事を差し出してきたりはしないだろう。守護者にやられて気を失っている間に、殺す機会など―――――彼にはいくらでもあった筈なのだから。
(なる様になれ)
意を決して、握り飯の一つを口にほおばる。
(………! うまい………)
絶妙な塩加減で握られたそれは、ハヤブサの空腹を満たして行った。
一つ目の握り飯を完食し、二つ目に手を伸ばした時、ハヤブサはふと思った。この食料を、自分だけが食べていいのだろうかと。この閉じられた空間で、食料は、分け合わねばならないのではないのだろうかと。
だからハヤブサは、男に声をかけていた。
「………おい」
「何だ?」
顔を上げてこちらを見てくる男をまともに見ることができず、つい、ハヤブサは視線を逸らしてしまう。だが、意志は伝えねばならないと決意をし、ハヤブサは再び口を開く。
「お前は……食べないのか……?」
「ああ―――――」
ハヤブサのその言葉を聞いた男は、くすりと笑う。
「私は、不死の特殊体質だと言っただろう。生きるのに『食料』は要らないんだよ」
「……………!」
「それよりも、君こそ私を気にかけている場合か? 私は『仇』なのだろう?」
「―――――!」
「それなのに……君は、優しいんだな。よく、そう言われないか?」
「か、勘違いするなよ!! お前の身を案じた訳じゃない!!」
ハヤブサは苦し紛れに大声を出していた。
「飢えてふらふらになっているお前を討ちとっても、自慢にもならないし、後味が悪いだけだからな!! だからそうならないように声をかけただけなんだ!!」
「そうか」
男はそう言ったきり、また視線を逸らして、静かに座りなおした。ハヤブサは、耳まで朱に染まるのを感じた。
(またやってしまった……! 『敵』に気をかけるなど――――絶対にやってはならぬと父上にも注意されていたのに………!)
そう。
忍びの世界において、倒すべき相手に余計な情けをかけることは、時に、自分や仲間の命を危険にさらす事に繋がってしまう。
だから、戦いに情けや迷いは禁物だった。
『敵』は『敵』
そう断じたなら、迷わず討つべきなのだ。
それなのに―――――
意識のない自分を介抱したり
食事を差し出してきたり
武器を取りあげられている状態を、甘んじて受け入れていたり―――――
とにかく目の前に居るこの男の言動行動すべてが奇天烈だった。
何故この男は、自分にこうも世話を焼いてくるのだろう?
『龍剣を手に入れさせるため』と言う目的があるにしても、少し度が過ぎている様な気がする。それこそこちらがうっかり『恩義』を感じてしまいそうになるほどだ。
だから、それを返すつもりで声をかけてしまったのも、また事実だった。
どう言うつもりなのだろう。
恩義をかけたふりをして―――――こちらの動揺を誘っているとでも言うのだろうか。
里を襲ってきたのに。
赤子を残忍に引き裂いていたのに。
そのたたずまいは
その優しさは
一体何だと言うのだろう。
本当にこの男は―――――俺の『仇』なのだろうか。
(あ………そう言えば……)
二個目のおにぎりを完食した時に、ハヤブサはふと思い当った。
「おい」
思い当った事実を確認するべく、ハヤブサはもう一度、男に声をかける。
「何だ?」
「お前の刀………さっき、妙な輝きを放ってなかったか?」
気を失う直前に見た、男の戦いの中で見た刀の輝きを思い出す。それに対して男は目をぱちくりとさせていた。
「刀?」
「そうだ。……あの刀、何か特別な力があるのか?」
あの輝き、切れ味―――――刀の方に、何か特別な力や『銘』があるのならば、それを知りたいと思った。
対して男は少し首を捻っていた。
「……あるのかもしれんが、私にはよくわからん」
「え?」
きょとん、とするハヤブサに、男は苦笑した。
「分からないって………お前の刀ではないのか?」
「あれは借り物の刀なんだ。私の刀は、君に取りあげられていたから――――」
「―――――!」
はっと気がついてハヤブサは、男の刀を取りあげて放り投げた方に振り返る。すると、その視線の先には、自分が地面に突き立てた時の状態のまま――――ピクリとも動かされていない様子の刀が鎮座していた。
「な………!」
茫然とするハヤブサに、男は再び声をかける。
「何度も眉唾な話をして申し訳ないが――――私が使った刀は、あの観音様からお借りしたものなんだ。あの像の背に背負われていた刀をお借りして――――」
「今どこにあるんだ!? それは……!」
「元に在った場所に返したぞ?」
男の言葉を聞いて、ハヤブサは弾かれたように走り出す。祠からはずれたところにポツンとある、小さな観音像の背を覗き込んだ。そしてそこには、男の言葉通りに鞘におさめられた刀が。
すらり、と、ハヤブサがその刀を抜いてみて――――――絶句した。
何故なら、その刀は―――――刀身がボロボロに錆びて朽ち果てていたのだから。
(馬鹿な……! あいつはこんな刀で、あの化け物を斬り伏せたとでも言うのか!?)
あの美しいまでの一刀両断
それを、こんな刀でやってのけたと言うのなら
「……………!」
ハヤブサは、己が身体に震えが走るのを感じる。
勿論、畏怖もある。いとも簡単に、不可能と思える事をやってのけたその剣の腕前に、舌を巻くばかりだ。
しかし――――彼は同時に『歓喜』にも震えていた。
見つけた
いい『修行相手』を
この男と自分の剣の腕の『距離』を知りたい。
この男と互角に渡り合う
いや、凌駕するほどにならなければ――――――
きっと、『龍剣』は手に入らない。
これは、確信だった。
ばっと顔を上げて、ハヤブサが男の方を見ると、男も立ち上がってこちらを見ている。
「この刀で………お前はあの巨大な化け物を倒したのか……?」
ハヤブサが問うと、男は「そうだ」と頷いていた。
ハヤブサは無言で踵を返すと、男の刀を突き立てている所まで全力で走る。刀を地面から引き抜くと、男に向かって投げてよこした。
パシッと刀を受け取る男に向かって、ハヤブサは叫んだ。
「俺と、勝負しろ!!」
「―――――!」
少し驚いたように見る男の視線を、まっすぐ受け止め、睨み返す。
「ただし、全力で――――手加減なしでだ!!」
そう。
彼の真の強さを見てみたかった。
龍剣を手に入れるためにも。
その先へ、自分が進むためにも――――
もしかしたら、この戦いで自分は、命を落としてしまうかもしれない。
(それでもいい)
ハヤブサは強く思った。
この男の全力を対処できないようなら、この先に進むことも不可能だ。
そうなってしまったら、目的が果たせない自分は、もう死んだも同然だった。
だから、男には全力で戦ってもらわねば困るのだ。
そうでなければ――――
その『先』へは進めない。
(ハヤブサ……!)
刀を油断なく構え、真っ直ぐこちらを見つめてくる少年ハヤブサの眼差しを、シュバルツも真正面から受け止める。
(どうやら、修行をつけても大丈夫そうだな)
ハヤブサの瞳が憎悪に曇っていない事を見て取って、シュバルツの顔に小さな笑みが宿る。流石にハヤブサだ。彼の『精神』は―――――やはり強い。
「いいだろう。相手になってやる」
手にした刀を中段に構える。この小さな『龍の忍者』に失礼のない様に。
「いざ―――――」
二人の間を、里の風がヒョオ、と、音を立てて吹き抜ける。
龍剣を得るための忍者たちの戦いが、今まさに、始まろうとしていた。
ドゴオッ!!
「覇ッ!!」
ドゴオッ!!
「吻ッ!!」
シュバルツとハヤブサが眠るキョウジの部屋の中で、東方不敗とキョウジの戦いは続けられていた。キョウジがショットガンを撃ち、敵の動きが怯む、あるいは止まったところを東方不敗が次々と仕留めて行く。
「どうした雑魚共!! かかって来んかぁ!!」
喜々として構える東方不敗の横で、キョウジがふうっと小さく息を吐いていた。
(やっぱり難しいな……。戦いながら、もう一台自家発電の装置を作ると言うのは……)
ショットガンの弾込めをしながら、周りの状況を確認する。すぐに発砲する必要性を感じなかったキョウジは、素早くショットガンの弾を精製する作業に取り掛かった。魔法の様に動くキョウジの手元から、あっという間に10発程の弾が作られ、そこに『結界の波動』を注入する装置に掛けられていく。
今のところ敵の数もそんなに多くなく、強さもまだそれほどでもないため、こうしてショットガンの残弾を戦いながら増やして行くことができるが―――――それでも、これをするので手一杯だ。とても自家発電機を作る、ましてや折り鶴を直す作業までは、手が回らない。
(フフフ……キョウジは戦いのセンスも、なかなかの物じゃな……)
この戦い、まだ自分1人でも余裕で対処できるが、キョウジのサポートのおかげで随分と戦いやすくなっている。キョウジの射撃は正確無比。それに数多いる敵の中で、どの敵が自分たちにとって一番の脅威となるか、瞬時に判断している。それは、自分たちと敵との位置関係を正確に把握していなければ、到底できない技だと東方不敗は感じていた。
射撃の腕を褒めると、キョウジは苦笑しながら頭を振る。
「そんな大したものじゃないですよ。射撃の正確性が要らないから、わざわざショットガンを選んでいるんです」
「なるほど……」
確かに、ショットガンの弾は放たれた瞬間、プラスチック製の弾が破裂し、その中に入れられていた無数の金属製の小さな弾が銃口から放射線状に広がり、一定範囲に均等に広がって着弾する。故に精密な射撃を必要とせず、動く対象にも当てやすい。その威力は近接戦闘において、存分に発揮される物だった。
それでも先程からキョウジが撃つ弾に無駄弾など無い。一体一体着実に仕留めて行く様は、見事と言うほかはなかった。
「十二王方牌大車併―――――ッ!!」
複数の敵を同時の屠る東方不敗の大技。「爆発!!」と叫ぶ東方不敗の声と共に、技をかけられた敵たちが、一斉に爆ぜた。家じゅうに爆風が巻きあがり、ガラスが割れ、壁に穴が開いた。
「フフフ……他愛も無い奴らじゃの……」
そう言って笑う東方不敗の横で、キョウジは顔をひきつらせながら苦笑している。
(いろいろ壊れちゃったなぁ……。後で直すのが大変だぞこれは……)
でも東方不敗ばかりを責められない。自分のショットガンも、家中の細々とした物を壊しているのだから。
「まだまだ来るぞ!! 油断するでない!!」
構えながら東方不敗は、改めて自分が守るべき者たちを確認する。
守るべきはキョウジ。結界を発生させる装置。そしてどうでもいいが、ベッドで眠り続ける忍者たちの身体―――――
本当なら東方不敗にとって、キョウジ以外はどうでもいい。だがキョウジが、他の者たちを守りたいと願っている。
ならば、その願いは叶えられなければならぬ。自分は、それを叶えるために動く。それが―――――『仕える者』としての義務だと東方不敗は思った。
「…………!」
キョウジもショットガンに弾を込め、撃鉄を起こす。まだ次から次へと、床から黒い影達が立ち上がって来るのが見えた。
(キリが無いな………)
キョウジはギリ、と、歯を食いしばった。この戦い―――――本当に、終わりが来るのだろうか?
ふと、自分の背後で眠り続ける忍者たちの姿が、視界に飛び込んでくる。
(弱音を吐くな)
キョウジは頭をふり、顔を上げた。
この二人を守り抜く。そう決めたのは自分だ。
ならばそれを貫け。何が何でも――――
(何が壊れてもいい。せめて……我が家のライフラインだけは、壊れませんように………)
今――――総ての装置の命を繋いでいるのは『電気』だ。これが気にせず使えるのと、時間を限られてしまうのとでは、戦いの難易度がぐっと違ってくる。そう言う最悪の事態だけは、起きないで欲しいとキョウジは祈っていた。
だが。
そう言う時に限って、望んでいない事態は起きてしまう物で。
ドオオオオン!!
派手な爆発音が鳴り響くと同時に、部屋の電気が一瞬消える。そしてすぐに復活したが、キョウジは口の中で小さく悲鳴を上げていた。
「キョウジよ。今のは?」
東方不敗の問いに、キョウジはひきつった笑みを浮かべるしかない。
「多分、電気のライフラインが断たれました……。今の衝撃で……」
「ほう、そうか」
キョウジの言葉に東方不敗はにやりと笑う。この老人にしてみれば、今の状況こそが願ったりかなったりと言った所なのだろう。
対してキョウジは大きなため息を吐きながら、頭を抱え込んでいた。
(ああ~………電気がやられちゃった……。やったのは誰だ……? やっぱり、ドモンかな~………)
弟の大胆で大雑把で、力強すぎる戦いを思い浮かべて、キョウジは泣きそうな気持になって来る。
そして皮肉にも―――――キョウジの読みは当たっていた。
ガシャン!! と、派手な音を立てて倒れる電柱。バシバシッと漏電した音が起き、周りの街灯がフッと一斉に消える。停電が起きたのは、一目瞭然だった。そんな光景を、ドモン・カッシュが鼻息荒く見つめている。
「よしっ!! 今ので2千体は倒したな……!」
そう言って握りこぶしで小さくガッツポーズを作るドモンに、チボデーから多少揶揄する様な突っ込みが入って来る。
「相変わらず大雑把な戦いをする奴だなぁ。もうちょっとスマートに戦えないのか?」
「うるさい!! 人の事が言えるのか!?」
「う………!」
ドモンの切り返しに、チボデーもぐっと言葉に詰まる。それもそのはずで、彼の決め技―――――『豪熱マシンガンパンチ』も、強力なパンチをマシンガンの様に無数に放ち、多数の敵を倒す大技だ。あちこちの家の壁が、彼のパンチによって穿たれ、破壊されまくっていた。
「フ……全く、仕方のない人たちですね」
ジョルジュが長い前髪をかき上げながら、気障に笑う。
「もう少し、周りに配慮して、華麗に戦えないのですか? 無意味な破壊は騎士道に反する物ですよ?」
そう言いながら身を翻したジョルジュの手元から、無数の光が放たれる。シャッフル同盟の『ジャック・イン・ダイヤ』の特殊な波動を込められたそのナイフは、次々と影達を破壊して行った。
「フ……周りを破壊しない戦い……完璧ですね」
そう言いながら前髪をかき上げるジョルジュを、チボデーとドモンがあんぐりと見ていた。
「なあジョルジュ、真面目に聞いていいか?」
「何です?」
「お前、そのナイフ一体何本持っているんだ?」
「そうだ。それは俺も真面目に聞きたいぞ?」
疑問を呈してくるチボデーとドモンに、ジョルジュはフフフと軽く笑った。
「それは………御想像にお任せします」
まるっきり答える気が無いジョルジュの様子にチボデーもドモンも、ただ茫然とするのみである。そこに、威勢のいい火龍が飛び込んできた。
「あ~~~らよっと♪」
火龍の技を放ったサイ・サイシーが、ドモンの目の前に威勢良く飛び込んでくる。
「兄貴~♪ そんな所でのんびりしていていいの? 俺もう今ので9500体倒したよ?」
「フン!! 残念だったな!! 俺は今ので10015体目だからな!!」
「うそだぁ! 500体ぐらいサバ呼んでるだろ!!」
(五月蝿い………)
少し離れた所から、アルゴ・ガルスキーが、かなりうんざりした様子でその言い争いを見ていた。
本当に―――――どうしてこんな無駄な言い争いに時間を割いているのだろう。だいたい、そんな一人10000体も倒せるほど敵は出現していない。自分の感覚から鑑みるに、今のところせいぜい一人当たり3000体と言ったところだろうか。
理解しがたい。
ギャーギャー口を動かしている暇があるのなら、1体でも2体でも、敵を倒せばいいのに。
(シュバルツ殿がいてくれたら……)
もう何度、これを思った事だろう。
「馬鹿者ォ!!」
と、的確にドモンを殴って軌道修正を絶妙なタイミングで出来るのは、やはり、あの人しかいない。時々敵を倒す作業から脱線するほかの仲間に、アルゴはため息を吐く。おそらく、敵を倒す速度が、全然違って来ているだろう。
こいつらを放っておいて、自分だけ敵を倒す作業に専念してもいいが―――――
やっぱり鬱陶しかった。
「ガイア・クラッシャ――――ッ!!」
ドコオッ!! と、派手な音を立てて地面を穿ちながらアルゴの技は進む。それをチボデーとジョルジュは避けたが、言い争いに夢中になっていたドモンとサイ・サイシーは、もろにそれを喰らった。影たちともども、ドモン達も一緒になって吹っ飛ばされて行く。
「おいっ!! アルゴ!!」
「何するんだよ!? おっさん!!」
しかし腐っても『キング・オブ・ハート』と『クラブ・エース』の紋章を男たち。すぐにダメージから立ち直って、アルゴに詰め寄っている。
「フン!!」
最早説教する気にもなれないアルゴは、二人に背を向けて戦いに戻っていく。
「ガイア・クラッシャ――――ッ!!」
近くにいたらそれに巻き込まれると感じた二人は、慌ててその場から飛びのいた。
その様を見ていたチボデーが、ポツリと一言呟く。
「実際、アルゴの奴が一番周りを破壊しているよなぁ……」
「……ですよねぇ……」
チボデーのその言葉に、ジョルジュも反論の余地を持たない。そんな彼らの目の前で、ガイア・クラッシャーによって穿たれた地面から、破壊されたと思われる水道管から、勢いよく水が噴き出していた。
(うっ……うっ……! 絶対無理だって……! 戦いながら発電機を作るなんて………!)
ショットガンに弾込めをしながら、キョウジは半泣きになっていた。
凄い無茶ぶりだ。
敵に対応して、シュバルツとハヤブサを守りながら弾を補充し、発電機を作り上げるなんて、いったいどんな無理ゲーなんだ。こんな事なら、まだ『しょ●んのアクション』のえげつない罠にかかってわめいていた方が数千倍ましだ。
(こんな時、シュバルツがいてくれたら………!)
キョウジはため息を吐きながら、ベッドの上で眠るシュバルツの顔を見つめる。こんな時――――彼がいてくれたら、壊れた電線の修理に走ってくれるのに。
ちょっとキョウジはシュバルツがいてくれた場合を少し頭でシミュレーションしてみる。
「ああもう!」
そう叫びながら工具を抱えて飛びだしたシュバルツは、停電の原因である電線が分断した場所に辿り着く。
そこでドモンを説教している間に今度は別の場所が断線して――――
「私は電気工事技師か!!」
と、怒鳴りながらあちこち走りまわる彼の姿が目に浮かぶようだ。
駄目だ。
戦いが終わった後で、静かに切れている彼からドモンと一緒に小1時間八つ当たりに近い説教を喰らうコースが目に見えてくるようだ。
(やっぱり自力で何とかしなきゃ駄目なのか……)
そう思いながら、眠っているシュバルツを少し恨めしそうに見るキョウジ。今都合よく起きろシュバルツ、と、念を送ってみるが、当然そんな物でシュバルツが起きる筈もなく。
「キョウジ!! この戦い、72時間以内に決着をつけるぞ!!」
目の前で東方不敗は東方不敗で、とても嬉しそうに戦っている。そこに「あの………発電機を作りたいんですけど………」などと提案しようものなら、
「馬鹿者!! 男児ならば潔く、短期決戦で決着をつけんか!!」
と、身も蓋もなく怒鳴りかえされるのが目に見えるようだ。
(ああもう………!)
キョウジは深いため息を一つ吐いた後―――――顔を上げた。
仕方がない。
やるしかない。
とにかく――――絶対に『保険』は必要なのだから。
(見極めなければ……)
ショットガンに弾込めをしながら、キョウジは東方不敗の方を見る。
今までは、この人の戦いをフォローする戦いを、自分はしてきた。しかし、この先は違う。
この人が、この状況下で何処まで自分を守って戦えるか、見極めなければならないと思う。
まだ動きに、技に、余裕がある様に見える東方不敗。もう少し、自分が戦いに手を出すのを止めても、大丈夫なように見える。
ならば、自分は少し、戦いに手を出すのを止めてみる。
その間に――――きっと、発電機を作っていく隙も、見つけることができるだろう。
キョウジは片手でショットガンを構えながら、もう片方の手で工具箱を引き寄せていた。
(フフフ……。キョウジめ……。また何か考えておるな……)
キョウジの戦い方が変わったこと―――――気づかぬ東方不敗ではない。
だがどう変わろうと、自分のやる事に変わりはない。
自分はただ――――キョウジを守り抜くのみなのだ。
キョウジがどのような手を打とうと、それを信じ抜くのみなのだ。
「さあ!! もっとかかって来んか!!」
戦いの喜びに震える老人の瞳に、さらに凶悪な光が宿り始めていた。
「へっくしょん!」
間抜けなくしゃみを放ってしまった瞬間、ハヤブサの刀が身に肉薄していた。
「おっと!!」
すぐにシュバルツは、体勢を立て直して避ける。大きな隙を見逃して、「チッ!」と、舌打ちをする少年ハヤブサの姿が、すぐ目の前に在った。
そのまますぐに、剣の打ち合いが始まる。激しい金属音と青白い火花が、二人の間に爆ぜた。
太刀を合わせながら、シュバルツはどこか懐かしささえ感じる。こんな風に真剣に、ハヤブサと剣を交えるのは、一体、いつ以来だろう?
鋭い打ち込み―――――だが。
「甘い!!」
僅かに生じた隙を突いて、シュバルツはハヤブサの身体に、剣の峰を入れる。
「ぐっ!!」
吹っ飛ばされて尻餅をついたハヤブサに、男からの容赦ない指導の声が飛ぶ。
「切っ先を簡単に下げるなと言っただろう!! 今みたいに打ち込まれるぞ!!」
「…………!」
ギリ、と歯を食いしばった少年ハヤブサであるが、すぐに立ち上がり、こちらに向かってくる。
(やはり強いな、ハヤブサは………)
『仇』と目している男から剣の指導を受けるなど、彼にとっては屈辱以外の何者でもないだろうに。それらをすべて飲み込んで――――目的のために突き進むハヤブサの強さ、したたかさは、やはり得難いものだと思うのだ。
早く思い出せ、ハヤブサ。
お前は間違いなく――――龍剣に選ばれし『龍の忍者』なのだから。
(強い……!)
剣を振るいながら、ハヤブサは男の強さに改めて、ある種の敬意を払う。
最初に『本気を出せ!』と、挑みかかった勝負は、あっという間に終わった。
刀を構えて睨み合っていた――――と思った刹那、男の姿が自分の視界から消えた。
「―――――!?」
あいつは何処だ、と探す間もなく、あっという間に自分の身体が吹っ飛ばされる。何が起こったか分からぬうちに、気がつけば自分の喉元に、男の刀の切っ先が突きつけられていた。
「勝負あったな」
そう言いながら、刀を引く男。自分は、あまりにも男との腕の差が開きすぎている事実に、茫然とするしか無かった。
(これからどうすればいいのだろう)
己の剣の腕の未熟さを痛感して、座りこんでしまっているハヤブサに、男から声がかけられる。
「君は攻撃を仕掛けようとする瞬間に、刀の切っ先を下げ過ぎる癖があるな。直した方がいい」
「…………!」
驚いて顔を上げるハヤブサに、男から更に声がかけられる。
「座り込んでいる暇は無いぞ」
「―――――!」
「もう一勝負―――――行くか?」
「望むところだッ!!」
そしてそのまま何度も男に挑みかかって―――――現在に至る。
男が修行をつけてくれるのはありがたいのだが、本当に――――いいのだろうか?
確かに、男の目的は『自分に龍剣を手に入れさせる事』――――だ。それに向かっての男の言動行動は一貫しているように見える。
しかし。
男の『目的』が、いまいち明確に見えてこない。
自分に龍剣を手に入れさせて―――――一体、どうするつもりなのだろう。
「ここから外に出たい」
男はそう言った。
しかし―――――外に出る以外に、何か目的は無いのだろうか?
(それに、妙だ)
戦いながらハヤブサは、時折奇妙な感覚にとらわれる。
早く鋭い、男の剣。
だが自分は、何故かこの男の剣を知っている様な気がする。妙な懐かしさすら感じて戸惑ってしまう。
何故だ?
この男と太刀を交えるのは、ここが初めての筈なのに。
時折感じる―――――妙な懐かしさは何なのだろう?
ガツン!!
何度目かの太刀を合わせて、体を入れ替えた時―――――男が提案してきた。
「少し休憩をしよう」
「まだ戦える!!」
息巻く自分に、男が苦笑しながら宥めて来た。
「落ちつけハヤブサ。私を相手に燃焼し切ってどうする」
「……………!」
「君が真に戦うべきは、あの『守護者』だ……。そうだろう?」
この言葉に、ハヤブサは反論の余地を失う。あきらめたようにどかっと座ると、男が竹筒を差し出してきた。それを少々乱暴にひったくると、男は軽く苦笑しながら少し離れた場所に腰を落ち着ける。つかず離れずと言ったところの位置―――――それが、今の二人の距離感だった。
こくこくと水を飲み、一息を吐く。落ちついてくると、脳裏に描くのは先程の男との戦いだった。
太刀捌き。
何処を踏みこんで、どう打たれたか。
次はどうすればいいか。
打たれないためには。
打ちこむためには―――――
無意識のうちに口が動き、手が動く。
(熱心だな………)
その様を見て、シュバルツは感心するやら呆れるやらしてしまう。剣術の修行に余念がないハヤブサ。なる程、強くなる訳だ。
飽くことない強さへの求道―――――その根源に、流れる物は何なのだろう。
知りたいと思った。
しかし、今のハヤブサからは、絶対にそれを聞きだす事は不可能だろう。自分は『仇』と憎まれている。そんな人間に、自分の根本に流れる大切な物を、おいそれと話してくれるとは思えない。
今はそれよりも、ハヤブサの修行の手助けをするべきだ。それが―――――この世界の自分に課せられた、役目なのだろうから。
「―――――!」
ふと気配を感じて振り向くと、龍剣の前に『仁王』が姿を現して、こちらを睨み据えていた。
――――龍剣を、欲する者は誰だ?
静かにそう、問いかけるかのように。
「ハヤブサ」
呼び掛けると、少年ハヤブサも気がついたのか、剣を手に立ち上がった。ふうっと小さく息を吐き、歩み始める。そして、自分の横を彼が通り抜ける時――――ある事実に気がついた。
(背が伸びた?)
そう思いながら後ろ姿を見送ると、子供じみていた彼の背格好に、いつの間にか青年の匂いが混じり始めている。声も、少年の高い声から大人の低い声への過渡期なのか、少し低く、かすれ気味になっていた。
(成長している………? そうか、ここは彼の『心』の世界なのだから―――――)
彼の心が少しずつ己を取り戻して行くたびに、彼の外見も成長する。そう捉えてよさそうだった。
(思い出してくれ、ハヤブサ……。お前の本来の姿を――――)
ハヤブサの後ろ姿を、シュバルツは祈るように見つめる。彼が総てを思い出すために、自分は、どうすればいいのだろう。
「…………!」
ふと、強烈な殺気を感じてシュバルツは振り返る。
すると、空間に『ひび』が入り、その隙間から巨大な黒い化け物の様な塊が、こちらを覗いていた。ひびの淵に鋭い爪をかけ、こちらの空間に強引に入り込もうとしている。ぎょろり、と、鋭い眼光がシュバルツを睨み据え、巨大な口から牙を覗かせながら、唸り声を上げていた。
(ハヤブサの戦いを、邪魔させる訳にはいかない)
強くそう感じて、シュバルツは抜刀しながら黒い化け物の方に歩き出す。どんな形の化け物なのか見極めようとシュバルツが目を凝らすと、こじ開けて入ってこようとしている化け物の後ろに、もう一つぎょろりと光る眼光がある。
(2体か………)
シュバルツは小さく息を吐くと、改めて刀を構えなおしていた。
「フン! 他愛ない奴らよ」
この部屋にいた最後の『影』を四散させると、東方不敗はふうっと息を吐いていた。顔には不敵な笑みが浮かんでいるが、額からは汗が滴っている。
(す、すごい……!)
キョウジは東方不敗の後ろ姿を、ある種の畏敬と感慨を持って眺めていた。
ある程度結界に守られているとはいえ―――――最後の方は、ほぼ自分は手助けをしなかった。それであれだけ自分たちの周りをひしめいていた、有象無象の影達を、総て屠ってしまうとは。
この人の強さは本当に底が見えない。
一体――――どれほどの力を秘めているのだろう?
「フフフ……キョウジよ……。わしの力を測りおったな?」
にやりと笑いながら図星を突いてくる東方不敗に、キョウジも苦笑するしかない。
「あはは………ばれてました?」
「あれだけ手助けをしておった物が止めば、どんな鈍感な者でも気が付く。………どうじゃ? キョウジよ……。ワシの力――――お主の期待に見合う物であったか?」
「想像以上でした」
キョウジは素直な感想を述べる。それを聞いた東方不敗は、満足そうにその面に笑みを浮かべた。内心主と仰ぐキョウジに認められた事が、東方不敗にとって喜ばしい事であるのだろう。
「一まず攻撃は止んだようじゃが……油断するでないぞ? 敵の数も強さも――――こんな物では済まぬじゃろうからな」
「そうでしょうね……」
キョウジは硬い表情で、手元の作業を続ける。発電機がおよそ半分ほどまで組み上がろうとしていた。
やれやれ、と、東方不敗が一つ息を吐いた時――――『それ』は、姿を現した。
それは、一つの鋭い『殺気』の塊だった。
「―――――!」
それに気がついて振り向いた東方不敗は思わず息を飲み、キョウジは知らず叫び声を上げそうになっていた。それもそのはずで――――そこに居たのはリュウ・ハヤブサの姿形を模した、化け物であったのだから。
勿論、ハヤブサその物の形をしている訳ではない。身体中にごつごつと鋭い突起が生え、一目でそれが黒い影の亜種であることが、分かるようになっている。しかし、その歩き方、体の運び方が、『ハヤブサ』その物であったから―――――
「ほう……」
東方不敗はバキバキと指を鳴らしながら、キョウジを庇うように前に出ていた。
「なかなか面白き姿形、気配を纏う者よ……。じゃが……その腕はどうかな……?」
それに、ハヤブサの形をした影が答えることはない。影は無言で距離を詰めてくると、背中に挿してあった剣を抜き放った。
「…………」
キョウジも手元の作業を止め、無言でショットガンを構える。この影から放たれる異様なまでの殺気が、彼の警戒心をMAXに跳ねあげていた。それは東方不敗も同じなのだろう。正眼で構えをとり、油断なく身構えている。
しばし、耳が痛くなるほどの沈黙が、部屋の中を覆う。
じりじりとした殺気が満ちに満ちて、空気が破裂しそうだとキョウジが感じたその、刹那。
ダンッ!!
激しい踏み込み音と共に、東方不敗と影の、双方の身体がぶつかり合った。
「―――――!」
刀に対して武器も持たず丸腰で―――――と、キョウジの顔色が変わるが、その心配は杞憂であったとすぐに悟る事になる。東方不敗は相手の刀を避けながら、器用に組み合っている。
全く伯仲した戦い。しかし、刀と徒手ではリーチの差がいかんともしがたく、少し東方不敗が押されているようにも見えた。
「マスター!」
だからキョウジは自分の手元に散らばる工具からバールの様な物を掴み取ると、迷わず二人の戦いに向かって投げつけた。それを影の方が刀を使って避ける。くるくると宙を舞うバール。それを、東方不敗がパシン、と、音を立てて掴み取った。
「フフフ………」
良き得物を得た――――と、言わんばかりに東方不敗はバールの様な物を構える。そこに、影が無言で斬りかかってきた。
ガキッ!!
ガツン!!
激しい剣撃の応酬の中、白刃がきらめき、青白い火花が飛ぶ。
(速い……!)
動体視力はとても良いキョウジであるが、この二人の戦いは追い切れない。援護のタイミングを掴むことができず、ただ固唾をのんで見守るしか無かった。
「――――!」
宙に飛ぼうとした影の足を、東方不敗のもう一つの得物である白い布が絡め取る。
そのまま強引に、ドスン、と、床に叩きつけられる影。
「死ねい!!」
そこに東方不敗が間髪入れず襲いかかる。ここで勝負は決まった――――――かに見えたのだが。
「ぬうっ!?」
仕留めたと思った瞬間、影の姿が東方不敗の目の前からフッと消える。彼の拳は空しく床を穿っていた。バキッ!! と床板が割れ、辺りに木片が四散する。
「キョウジ!!」
「―――――!」
影の生き先を瞬時に悟った東方不敗は、キョウジに向かって叫ぶ。呼びかけられたキョウジも躊躇わなかった。上空からこちらに向かって跳躍してくる影に向かって、迷わずショットガンをぶっ放す。
ドコオッ!!
ショットガンは確かに、影の身体に命中した。だが影は、己の身体の一部が吹き飛ばされようとも、全く怯まなかった。そのまままっすぐ突っ込んでくる先には、ベッドの上で眠り続けるハヤブサの身体が。
「くっ!!」
キョウジは咄嗟に己の身をその上に投げ出して、ハヤブサを庇う。凶悪な刃が、キョウジの背中に達しようとした、その瞬間。
作動したベッドの周りの結界が、バシッ!! と、音を立てて影の身体を叩く。
「ギャッ!!」
悲鳴を上げる影。そしてその一瞬に生じた隙が――――彼の命取りとなった。東方不敗の右手が、影の首根っこをガシッと掴み取る。
「死ねい!! ダークネス・フィンガ―――ッ!!」
掌から発せられた元『キング・オブ・ハート』の紋章の光が、影の首根っこに直接たたき込まれる。
「――――――ッ!!」
影は叫び声にならぬ悲鳴を上げながら、四散して行った。
「キョウジ………怪我は無いか?」
「はい……。ありがとうございました……」
東方不敗に礼をいいながら、キョウジはそろりとその身を起こす。
それにしても、手ごわい敵だった。動きと言い強さと言い―――――まさか、こちらのショットガンの攻撃が、ほとんど通用しないだなんて。
(これは……もう一段階波動の強い弾を放てる武器を用意した方が、良いのかもしれないな……)
さてどうしたものかとキョウジが思案しながら工具類を見つめていた時。
「キョウジ!!」
少し切羽詰まった響きを湛えた、東方不敗の声が響き渡った。不思議に思って顔を上げると、東方不敗がこちらを庇うように立って、身構えている。
(…………?)
身構える東方不敗が酷く警戒心を顕わにしている。それを不思議に思ったキョウジが東方不敗の視線の先を追いかけて―――――
「な――――――!!」
思わず、息を飲んでいた。
何故ならそこには、先程の『ハヤブサもどき』の影が2体、抜刀しながらこちらに近づいてきつつあったから―――――
(嘘だろう……!? 一体だけでも手こずったのに……ッ!)
「……………」
その想いは東方不敗も同様なのだろう。その面に、いつもの不敵な笑みはない。それどころか、彼の額からは汗が滴り落ちている。
これは、かなりまずい。
そう感じたキョウジは懐から携帯電話を取り出すと、迷わず弟の番号を押していた。
その頃、ドモンはと言うと。
「あっ!! サイ・サイシー!! それは俺の獲物だぞ!!」
「へへ~んだ! おあいにく様! ぼうっとしている兄貴が悪いんだよ~だ!」
「クッ……! 言わせておけば……!」
そう言って歯ぎしりするドモンの後ろから、チボデーとジョルジュが歩いて来ている。
「あちらのブロックには、もうほとんど敵影はありませんね……」
「そうだな。随分と少なくなっちまったものだ」
「向こうの敵も、もう居ないぞ」
そう言いながら、アルゴ・ガルスキーの巨体も、のそりと姿を現した。
「これは……どう言う事なのでしょう?」
閑散とした夜の街を見つめながら、ジョルジュが呟く。
「これで終わりか? そんな訳無いよなぁ」
チボデーの言葉にアルゴも頷いた。
「これで終わりなら、敵が弱すぎる……。我々全員が、出向いてくるほどでもない」
それもそうですね、と、ジョルジュが小さく返事をする。その目の前では、相変わらずドモンとサイ・サイシーが、残った敵の撃破の奪い合いをしていた。
「邪魔だッ!!」
「兄貴こそ!!」
全く白熱した、ある種の子供じみた戦い―――――だがそれも、ドモンの懐の携帯が鳴った瞬間に終わりを告げた。
(兄さんからだ!!)
相変わらず兄からの着信に敏感な弟は、2コールと待たずに電話を取った。
「兄さん!? どうしたッ!?」
「あ……ドモン? 今、話しても大丈夫か?」
「ああ! 全く問題ない!」
影を撃破しながら、ドモンは鼻息荒く答える。何時どんな状況であろうと、兄と話をする事に、自分的には全く問題は無かった。
「そうか……」
兄から、穏やかな返事が返ってくる。しかし、その声に―――――若干切迫した色を感じるのは何故なのだろう。
「兄さん? どうした?」
「いや……その………うわっ!?」
キョウジの悲鳴と共に、携帯の向こうから激しい衝撃音とノイズが聞こえる。
「兄さん!? 兄さんッ!!」
―――これは、兄が危機に陥っている――――!
そう直感的に感じてしまったドモンは、気がつけば猛然とダッシュをしていた。
「あっ!? 兄貴!! どこ行くんだよ―――ッ!!」
間髪入れずサイ・サイシーもその後を追いかける。
「お、おい!?」
「どうしました!?」
脱兎のごとく走りだしたドモンを追いかけて、チボデーとジョルジュも続いた。
「……………」
アルゴはしばらくその後ろ姿を見送っていたが、残った影達を撃破しつつ、のそりとその後について行った。
「キョウジ!! 大丈夫か!?」
東方不敗に少し乱暴に庇われたキョウジが、「平気です……」と、打ちつけた頭をさすりながらも身を起こす。そんな自分たちの周りを、『ハヤブサもどき』の2体が、取り囲んでいた。
(どうする?)
ショットガンを構えながら、キョウジは自問する。とりあえず、弟と連絡はついた。今彼が何処にいるのかにもよるが、最低5分以内には、ここに駆けつけて来てくれるだろう。
問題はそのドモンが来るまでの間、どれだけしのげるか―――――総てはここにかかっていた。
東方不敗が1人だけで戦うのならば、特に問題がある訳ではない。今目の前にいるモンスターが更にその数を増やそうとも、彼は問題なく戦える筈であった。
だが―――――今東方不敗は、自分と、シュバルツとハヤブサの身体を守るというハンデを背負ってしまっている。肉弾戦を得意とする格闘家にとって、自分の行動範囲を大幅に制限されてしまう事は、かなりの不利を被ることになった。
(せめてシュバルツが起きてくれていたら……!)
キョウジはほんの少し、恨めしい気持ちを込めて眠るシュバルツを見つめる。しかし、いくら見つめた所で彼が起きる筈もなく、状況が進展する訳でもない。彼はため息を吐きながら、いろいろとあきらめるしか無かった。
(どうする?)
もう一度、己に問いかける。
手に持つ武器は、役に立たない。それは、先程の戦いで証明されていた。それに、自分の体術が、あの『ハヤブサもどき』に通用するとも思えない。今のままでは完全に、自分は東方不敗の足手まといだった。それなのに――――
「良いか!? キョウジよ!! ワシの傍から離れるでないぞ!!」
東方不敗は自分にぴったりとくっつき、全力で守る構えを見せている。
全く困った人だ。
この戦いに入る前―――――『自分の身の安全は保証しない』と、言ったくせに。どうしてそんなにまでして―――――自分なんかを守ろうとするのだろう。
(何とかしなければ……)
キョウジはグッと歯を食いしばっていた。
何もかもを覚悟して、ここに残ったのは自分だ。だから、東方不敗の足手まといになっている場合ではないのだ。戦わなければならない。だがそのためには―――――
「………マスター……」
そろりと声をかけてくるキョウジに、東方不敗は鋭く反応した。
「どうした? キョウジ……」
「後5分以内に、ドモンが来ます」
「…………!」
「マスター……正直に答えてください。この状況、あとどれぐらいしのげそうですか?」
「……………」
キョウジの問いかけに、東方不敗は沈黙を返す。つまり、彼の力を以ってしても、あと5分しのぎ切るのは厳しいと言う事なのだろう。キョウジはそう判断した。恐らくこのままだと、東方不敗は最悪キョウジを守る事だけを優先して、シュバルツやハヤブサの身の安全を保障しなくなる可能性が高い。今は二体しか出現していない『ハヤブサもどき』が、この後増えない、と言う保証も、どこにもないのだから。
それでは駄目なのだ。
自分は―――――ハヤブサやシュバルツを守るために、ここに残っているのだから。
「武器を一つ、作ろうと思っています」
「―――――!」
キョウジの提案に、東方不敗がピクリと反応する。
「ただ………作る時間が………」
「どれぐらい要る?」
東方不敗はすぐに問いかけて来た。
「2分あれば………」
「2分じゃな!? よしっ!!」
東方不敗はガバッと顔を上げる。
「任せよキョウジ!! この東方不敗、2分くらいの時間をお主に提供する事など、造作も無い事じゃあ!!」
ダンッ!! と、強く踏み込み、バールの様な物を手にして構えをとる。虎の様な気迫が、辺りを睥睨した。
「頼みます」
キョウジは短くそう言うと、フ―――ッと大きく息を吐いた。それから静かに、目の前に並ぶ工具たちを見つめる。
今から自分は、『武器』を作る事のみに専念する。
その間、自分の身を守ることは―――――
考えない。
(勝負!!)
ガバッと工具と材料をひっつかみ、キョウジは作業を開始する。それと同時に『ハヤブサもどき』たちも、一斉に彼らに襲いかかって来ていた。
「猪口才なッ!!」
叫ぶ東方不敗は、バールの様な物を振り回しながら片方に対応し、もう片方の影には自分の腰紐に『気』を込めて、棒の様な状態にして対応していた。二体の黒い影と、東方不敗がぶつかり合うたびに、青白い火花がガキン、ガキッ! と、音を立てて飛び散っていく。キョウジを『守る』ことに専念する東方不敗は、その場を動かない。そこで行われる戦いは、まるで力強い武闘の舞を見ているが如くだ。
「ギャッ!!」
影の一体が結界の力に弾かれて悲鳴を上げる。
「――――!」
すかさず東方不敗が止めのダークネス・フィンガーを見舞おうとするが、間一髪避けられてしまった。
(チッ!! もう少し踏み込んで来おったら、仕留めておれたものを……!)
軽く舌打ちをしながら、東方不敗はもう一度、キョウジが張ってくれている結界の範囲を確認する。これを活かそうと、時折東方不敗は誘いをかけてみるのだが、敵もそれを意識しているのか、深く踏み込んでは来ない。少し間合いを開け気味に、刀と手裏剣で攻撃を仕掛けて来るのみだった。
時に手裏剣が、キョウジの身体を掠めて床に突き刺さる。
「……………」
だがキョウジは、それに頓着することなく武器を組み立てる作業を続けている。相変わらず、凄まじいまでの集中力だ。
「我が王の戦い! 誰にも邪魔はさせぬ!!」
東方不敗は吠え、彼の気力が膨れ上がる。白い布がしなり、刀を、手裏剣を、ことごとく退ける。『ハヤブサもどき』の影二体を相手に、互角以上の戦いを、彼は繰り広げていた。
しかし。
「むっ!!」
その奥からもう二体、ハヤブサもどきの影が抜刀しながら近づいて来ているのを見て、東方不敗の額のしわが、さらに深くなる。
(おのれ……!)
普通に考えるならば、ここはもう潮時だ。キョウジの身体を抱えて逃げ、外の仲間たちと合流するのが戦いの常道だった。
だが、キョウジは今まさに、己の戦いを続けている。それを邪魔するのは東方不敗としても本意ではない。それに自分は約束した。キョウジに『2分』の時間を提供すると。それは――――必ず果たされなければならぬと東方不敗は思うのだ。それが出来ずして、何が『キング・オブ・ハート』、何が『王の戦いを守る者』か。
「うおおおおおおっ!!」
獣の様な咆哮が、辺りの空気を揺らす。
守る。
何が何でも。
この腕一本折れようとも。
足がもげようとも――――
「爆発!!」
グワンッ!! と、派手な轟音を立てて、影の一体の身体が爆ぜる。
(よしっ! 一体仕留めた!!)
そう思って顔を上げる東方不敗の視界に、さらに二体の『ハヤブサもどき』の影が迫って来ているのが見える。
「…………!」
(まだか!? キョウジ!!)
東方不敗は思わず、キョウジの方を振り返っていた。
彼の高速で動く手元から、魔法の様に武器が作り上げられて行っているのが見える。
後少し――――
東方不敗はギリ、と顔を上げ、歯を食いしばっていた。
負けぬ。
退かぬ。
守り切って見せる――――
状況は5対1。ダン!! と、激しい踏み込み音と共に振られるバールは、3本の刀を防ぎきる。東方不敗の周りを舞う白い布は、無数の手裏剣を叩き落としていた。
「覇ッ!!」
発頸を伴って繰り出される東方不敗の短く鋭い突きが、一体の影をまた葬り去る。これで4対1。仕留めた『ハヤブサもどき』の影から、間髪入れずに別の影が斬りかかって来る。
「吻ッ!!」
バールと刀がぶつかり合い、青白い火花が飛ぶ。その刹那、不吉な音を立ててしなるように飛んでくる一つの黒い影が。
『それ』が影の操る鎖鎌であると気づいた時には、既にそれはキョウジの頭上に在った。
「―――――!!」
当然キョウジは武器を作るのに集中していて気付く筈もない。助けるために手を伸ばそうとして、それが間に合わないと東方不敗は気付いてしまう。
「キョウジ!!」
絶望に染まる叫び。その瞬間、キョウジの身体がフッと動く。彼がそこから横に転がった瞬間、彼の元居た場所に鎖鎌がドカッと音を立てて突き刺さっていた。素早く起き上がり、体勢を立て直したキョウジの手には、狙撃用のライフル銃が。
東方不敗の影から転がり出たキョウジに向かって、一体の影が斬りかかっていく。
タア―――――ン!
間髪入れず、乾いた銃声が響き渡る。キョウジの放った弾丸は、斬りかかろうとして来たモンスターの眉間を過たず打ち抜いていた。打ち抜かれたモンスターは、身体をのけ反らせながら、細かい粒子となって四散して行く。
「効いた!!」
自分の武器選択が正しかった事が証明されたキョウジから、安堵の色が混じった叫び声が上がる。それを見た東方不敗も、「うむ、見事!」と、唸り声を上げていた。
「キョウジよ。その銃と先程持っていた銃――――一体、何が違うのじゃ?」
東方不敗は再びキョウジを守る体勢を立て直しながら、彼に問いかけてくる。
「発射できる『弾』の種類が違います。広範囲に小さな威力で当たるか、小さな範囲に1点集中で強力な威力を伴って当てるか―――――ただ、それだけです」
キョウジはそう答えながら、再びライフル銃を構えた。
「だけど、これはあくまで『狙撃』に特化した銃で―――――近接戦闘には向いていないんですけど……ね!」
タン! と、再び乾いた音をたてた銃は、それでも確実にもう一体のモンスターを葬り去っていた。
(ほう……。やはり、なかなかの腕じゃな……)
キョウジの銃の腕を見た東方不敗は、心の中で素直に賛辞を送る。やはりこの男の『戦いのセンス』は、悪くない。
「ドモンが来るまで、後3分弱じゃな!」
東方不敗はそう言って顔を上げる。
「よしっ! キョウジよ!! しのぎ切るぞ!! 援護は任せた!! 好きに撃てい!!」
「はい!!」
キョウジの返事に、東方不敗は満足そうに頷くと、再び影達との戦いに身を投じていた。それを見ながらキョウジは、フ―――――ッと大きく息を吐くと、ライフルを手に周りの戦況を見渡していた。
先程の狙撃で2体倒していたが、また4体増えて、6対2の状況になっている。
(影の増えるスピードが………上がってきているな………)
それだけ『邪神』の方が、ここを攻略する事に、力を入れて来ていると言う事なるのだろう。
「ダークネス・フィンガ―――――ッ!!」
自分のすぐ近くで戦っている東方不敗。その背中越しに、彼はこの場にいるモンスターたちと、その動きを把握する事に努める。
(射撃のコツは、体幹と呼吸だ)
脳裏に、ハヤブサの声が浮かぶ。ハヤブサは、自分に戦いの稽古をつける時に、折に触れ、射撃も教えてくれていた。彼自身、弓の名手でもあったからだ。
「戦いで、どんなに呼吸が乱れていても、狙いをつける時は、それを落ちつける。いや、止めるぐらいでも良い――――」
射撃に必要なのは、敵に囲まれても動じない冷静さ。そして、銃を構え続けていても、ぶれない体幹の強さ。だから体幹を鍛えろ、と、ハヤブサによく言われたものだ。
「そして、戦場全体を見渡す目だ。狙撃は、近くの敵を片っ端から撃つ事がいいとは限らない。最も効果的なポイントを攻撃してこそ、狙撃はその威力を発揮するんだ。尤も……お前なら、説明しなくても分かっていると思うがな……」
(ハヤブサ……)
キョウジは頭の中で、ハヤブサの教えを反芻する。
まだまだ、こんな風にハヤブサから教えを請いたい。
話がしたい。
だから、死なないでくれ、ハヤブサ。
こんな『邪神』なんかに、負けないでくれ。
敵の、味方の動きを読め。
戦場の、空気を読め。
そうすれば、撃つべき敵は、おのずと見えてくる筈だ。
そして見えた時は迷わず
引き金(トリガー)を引け。
タァ――――ン!!
銃声と共に、また屠られる敵。影達は少し怯み、東方不敗の攻撃は、俄然勢いを増した。
「フハハハハ!! さあ!! かかって来んか!! 雑魚共ォ!!」
喜々として戦いに向かって行く老人。その後ろで、キョウジは撃つべき次の敵を模索する。
(しのげるか……?)
一体葬ったのに、また二体増えている。数的不利な状況に変わりはない。
「うおおおおおっ!!」
数体を相手取り、戦い続ける東方不敗。キョウジは、その援護に専念する。二人とも次々と敵を仕留めるのだが、仕留められるのと同じか、それ以上のスピードで敵も増殖していた。倒しても倒してもきりがない状況とは、まさにこのことだ。
(数に押される……! このままでは……!)
キョウジはギリ、と、歯を食いしばった。
だが、弱音を吐く訳にも、逃げ出すわけにもいかない。ドモンが来てくれるまでおそらく後少し。何が何でも、しのぎ切らなければ―――――
「――――!」
『ハヤブサもどき』の刀が、東方不敗の肩を掠める。
「マスター!!」
「案ずるなキョウジよ!! こんな物はかすり傷じゃ!!」
滴る血を拭うこともせず、東方不敗は構えをとった。
「この程度で!! このワシを倒せるなどと思うなよ!!」
老人の『闘気』が、さらに膨れ上がっていく。この人は――――一体どこまで強くなると言うのだろう。
(負けてはいられない。私も)
東方不敗とは対照的に、キョウジは氷の様な冷静さをその面に宿らせていた。
心乱されていては、狙撃が出来ない。
集中――――――
集中しなければ
「…………」
次に打つべき敵に狙いをキョウジが定めた時―――――おもむろに部屋のドアが、バン!! と、乱暴に開けられた。
「兄さんッ!!」
息せき切って部屋に掛け込んで来たドモンの視界に、ハヤブサと背格好のよく似たモンスターの姿が飛び込んでくる。ただでさえ『兄の危機』だと頭に血が上っているドモンの沸点は、一気に限界点を突破してしまった。
「おのれッ!! ハヤブサぁ!! また兄さんにちょっかい出しに来たのか!? 今日と言う今日は、もう許さん!!」
ドモンのその叫びを聞いた東方不敗とキョウジは、思わずズルッとこけそうになった。
「いや、ドモン……。それハヤブサじゃないし、本物は寝てる……」
一応キョウジはぼそっと弟に呼びかけてみるものの、ドモンの方が既に聞いていない。一番最初に視界に飛び込んできた『ハヤブサもどき』との戦いに、もう夢中になっている。その姿を見て「阿呆弟子じゃな……」と呟く東方不敗に、キョウジも返す言葉が浮かばなかった。
「うおりゃああああっ!!」
一体目のハヤブサもどきとドモンの戦いは、あっという間にドモンの勝利で終わった。地面に叩きつけられたモンスターは、あっという間に粉々の粒子になって四散して行く。
「どうだ!! 思い知ったか!!」
と、鼻息荒く顔を上げたドモンの視界に、今度こそ複数の『ハヤブサもどき』の姿が飛び込んでくる。
「な、何だこれはぁ!?」
「ドモン!!」
やっと状況を把握してくれたか、と、キョウジがドモンに呼びかけた、その矢先。
「おのれ!! ハヤブサめ!! 今度は分裂して兄さんにちょっかいかけようって言うのかっ!?」
「……………!」
そのボケボケな発言に、東方不敗とキョウジは今度こそ、ズルッとこけた。おかげで東方不敗はモンスターの刀を受けそこないそうになり、キョウジは持っている銃を暴発させかける。二人とも軽くピンチに陥りかけたが、そこは流石に東方不敗。すぐに立て直していた。
「この……! 馬鹿弟子があっ!!」
しかし、弟子のあまりのぼけっぷりに、拳骨を振るわずにはいられなかったらしい。彼が叫び声とともに振るった渾身の拳は、凄まじい拳圧を伴って、複数のモンスターを巻き込みながらドモンを直撃していた。
「うおっ!?」
これには流石にドモンも面食らってしまう。吹っ飛ばされて目を白黒させている所に、師匠の怒声が飛んできた。
「全く……! 貴様は本物と偽物の区別すらつかんのか!? 貴様ほどの馬鹿を見た事が無いわ!!」
「うるさい!! ここぞとばかりに師匠面をしやがって!! 兄さんを守ろうと一生懸命戦っている俺の、どこが悪い!!」
「状況を読めと言うのじゃ!! この馬鹿弟子が!!」
キョウジは口論を始めた師弟を半ば顔をひきつらせながら見つめていた。何だかこの先、果てしなく嫌な予感しかしない。
「お前のそのとぼけた発言のせいで、こちらがどれだけ危険な目に遭ったと思っておるのだ!? 本物と偽物の区別もつかん眼(まなこ)なら、くりぬいてその上に銀紙でも貼っておけい!!」
「おのれ言わせておけば、好き勝手言いやがって……!!」
「あ、あの……マスターにドモン? あんまりそう言う口論をしている場合でもない様な気が――――」
一応キョウジは、そろりと二人に忠告してみる。しかし、割と頭に血が上ってしまっている二人には、案の定と言うべきか、キョウジの声は全く聞こえていないようであった。
「もう完全に頭に来た!! 師匠!! 今日と言う今日は決着をつけてやる!! 俺は今日こそあんたを超えるッ!!」
「面白い……! やれるものならやってみろ!! この馬鹿弟子がぁ!!」
そう叫びながら東方不敗が構えを取ると、ドモンも負けじと構えをとる。
「言われずともっ!!」
そしてそのまま二人が本当に戦い始めたりするものだから、キョウジは本当に途方に暮れて、頭を抱え込んでしまう。
(あ~~………始まっちゃった……。どうしてこの二人が戦いの場で揃うと、話すより先にこういう展開になってしまうんだろう……)
一応二人の戦いは、周りのモンスターたちも巻き込む形になってはいる。しかし、二人の視界から、完全に自分の事が忘れ去られてしまっているように感じるのは、気のせいなのだろうか。
(……つまり、自分の身は自分で守れってことなのかな……。別に良いんだけどさ。最初からそう言う約束だったし……。ああでも―――――)
キョウジは多少恨めしさを含んだ眼差しで、眠り続けるシュバルツを見つめる。こういう時こそシュバルツがいてくれたら、と、思わずにはいられなかった。彼がいてくれたら、少なくとも自分の身の安全の心配する事は、必要なくなるのに。
「起きろ~」
そう言って、眠るシュバルツの身体をツンツンと突いてみるのだが、やはり、強制的に眠らされている彼が、起きる筈もなく。キョウジははあ、と大きなため息を吐いていた。
(いや、しっかりしろ、キョウジ・カッシュ! 元々シュバルツとハヤブサを守るために、私はここにいるのだから――――)
守ろうとしているのに、頼ってどうする、と、キョウジは己を叱咤する。いつの間にかシュバルツに頼ることが習慣化してしまっている、己の思考回路に苦笑していた。
幸いな事に、モンスターたちの注意も、ドモンと東方不敗の戦いの方に奪われている。こちらに襲いかかってくる気配は無いようであった。キョウジは銃を抱えて、大きく息をフ―――――ッと吐いた。
「……………」
もう一度、自分が張った結界の範囲と、今の敵と味方の位置関係を把握する。
(とにかく今は、自分の身を守ることを最優先にしよう。援護は、可能な時にするようにすればいいか)
そう考えてキョウジがもう一度銃を構えなおそうとした時、部屋のドアが開いて、また人が入ってきた。
「兄貴~! って、何だ!? この部屋!!」
「何だ、外に敵がいないと思ったら、こんな所にいたのかよ!」
「そして、あの御二方は、敵をそっちのけで戦っている、と」
ジョルジュが部屋の中で互いに戦い続けている東方不敗とドモンを見つけて、呆れたようにため息を吐く。
「兄貴にマスターアジア!! 俺とも手合わせをしてくれよ~!!」
そう言って少年が喜々として戦いに混じっていく様を、チボデーとジョルジュが呆れたように見つめていると、キョウジからそっと呼びかけられた。
「チボデーにジョルジュ! ちょっとこちらへ来てくれないか?」
「お、兄さん! そんな所にいたのか?」
「どうしたのですか?」
敵の間をかいくぐりながらこちらに来てくれた二人に、キョウジはホッと胸を撫で下ろしていた。
「見てのとおりさ。部屋の中に強力な敵が湧き始めて――――」
「確かに、そうみたいだな……」
部屋の中に湧いている敵の様子を見ながら、チボデーが少し唖然としている。対してジョルジュは納得したように頷いていた。
「なるほど……外の敵が減って行ったのは、私たちが倒し続けたせいもあるのでしょうが、『邪神』がここに戦力を集中させたせいもあるのですね。一体一体から、先程の敵とは比べ物にならない邪気の強さを感じます」
「外の敵は、減っているのか?」
キョウジの質問にチボデーが頷く。
「ああ。俺たちがここに来る頃には、もうほとんどいなくなっていたぜ」
「チボデー! 油断は禁物です。こちらに敵が来ますよ!」
ジョルジュの叫びに皆がはっと顔を上げると、確かに、東方不敗たちの戦いに巻き込まれていない影達が、抜刀しながらじりじりとこちらに向かって来ているのが見えた。
「……………!」
キョウジが銃を構えて息を詰めると、チボデーとジョルジュがゆらりと立ち上がる。そのままスッと、戦う態勢に身構えていた。
「チボデー、刀に対して素手は危険だ。これを」
キョウジがそう言ってバールの様な物を渡そうとすると、チボデーはにやりと笑った。
「兄さん。気持ちはありがたいが心配は無用だぜ。俺は、ボクサーだ」
「しかし………!」
「ボクサーにとって、『剣』は拳だ。手に持つ『剣』は、却って邪魔になるからな」
そう言いながらチボデーは、フットワークを利かせながらファイティングポーズをとる。チボデーの刻む、軽快な足のリズムが、辺りに響き渡った。その横でジョルジュが、無言でフェンシングの剣を構えている。
「shooooot!!」
その掛け声と共に、チボデーが動いた。間合いに入ってきたモンスターに向かって、猛然とラッシュを仕掛けて行く。
(なるほど、旨いものだな)
その戦いぶりを見て、キョウジは納得もし、感心もしていた。敵に向かって怒涛の如く繰り出されるパンチは、相手を防戦に追いこみ、刀が振るわれる事を防いでいる。しかし、よくもまあ刃物を持っている相手に向かって、あれだけ打ちこみが出来るものだ。下手をしたら拳が寸断されかねないのに―――――そう言う事を恐れたりはしないのだろうか?
一瞬の隙を突いて懐に潜り込んだチボデーから、強力なアッパーカットが繰り出される。
「ジョルジュ!!」
敵が宙に浮いたのを見計らって、チボデーが叫んだ。
「お任せを!!」
それに応えたジョルジュの手元から、複数の白刃がきらめきながら放たれる。それは頭から腹にかけて縦一線にモンスターに的中すると、そのモンスターはあっという間に細かい粒子となって四散して行った。
「フ……我々の手にかかれば、こんなもの――――」
「ジョルジュ!! 伏せろ!!」
彼の言葉が終わらないうちに、キョウジの叫び声が飛んでくる。
「――――!」
弾かれる様にジョルジュが伏せると、間髪入れずに銃声が響いた。
タァ――――――ン!
「ギャッ!!」
ジョルジュのすぐ後ろにいたモンスターが、キョウジの放った弾丸によって眉間を撃ち抜かれ、倒れて行く。
「油断するな!! 次が来るぞ!!」
次弾を弾倉に込め、素早く銃を構えるキョウジ。
「助かりました! ありがとうございます!」
「礼は良いから」
律儀に礼を言ってくるフランス人青年に、キョウジは銃を構えたまま答える。
「ジョルジュ! 行くぞ!!」
チボデーの呼び掛けにジョルジュも応え、再び3人は戦いの中へと、身を投じて行った。近接戦を得意とするチボデーに、中長距離に対応できるジョルジュ。時々キョウジの援護射撃も入り、その戦いは順調なようにも見えた。
しかし。
「兄さん!!」
「―――――!」
チボデーの叫びにキョウジがはっと気づいた時、既にその敵は、彼の間近に迫っていた。
「しまっ……!」
キョウジが銃口をその敵に向けるよりも早く、振り下ろされようとする刀。ジョルジュも短刀を投げようとするが、間に合わないと気づいてしまう。
皆の脳裏に最悪のシナリオがよぎり、場の空気が凍りつく。
だが、そのモンスターの刀が振り下ろされることは無かった。
何故なら―――――
ドグワッシャアアアアッ!!
派手な音を立てて、東方不敗がそのモンスターの上から強烈な蹴りを入れて来たからである。
「フン……! ワシの目の前で我が主を刀の錆びにしようとするなど、100万年早いわ!!」
キョウジを庇う様にして立ち、東方不敗は四散して行くモンスターをねめつけていた。
「マスター!?」
驚いて見上げてくるキョウジに、東方不敗はフン、と、鼻を鳴らす。
「お主がどこまで戦えるか見ておったが……やはり、まだまだの様じゃな」
「……見ていてくださってたんですか……?」
茫然と問い返してくるキョウジに、東方不敗は「当たり前だ」と、答えた。
「お主はワシが、『我が主』と認めた存在。主を守るのは、武人として当然の務めであろう?」
「そ、そうなんですか……」
東方不敗の言葉に、キョウジはひきつった笑みをその面に浮かべるしかない。
東方不敗の想いは大変ありがたいのだが、キョウジには、この人は、どうにも自分を買いかぶり過ぎている様な気がしてならなかった。それにしてもこの人は、ドモンとの戦いに熱中していたように見えたのに――――
(私の方にも気を配る余裕があるとは……やはり、ドモンはまだまだ未熟、と言う事になってしまうのかな)
「兄さん!! 師匠!!」
東方不敗から少し遅れて、ドモンもキョウジの元に駆けつけてくる。
「ドモンよ。キョウジはワシが守る。お主は、敵と戦う事に専念せい!」
「分かりましたっ!」
兄の安全がとりあえず確保されたと悟ったドモンは、すぐに戦いの場へと戻っていく。頭に血が昇りやすい弟ではあるが、こういう切り替えの早いところが、ドモンのいいところだとキョウジは思った。
「では我々も」
そう言ってチボデー達も戦いに戻ろうとする。それを、「ちょっと待ってくれ」と、キョウジが引き留めた。
「大丈夫だとは思うけど、戦いに入る前に、一つだけ注意しておいて欲しい事があるんだ」
「注意ですか?」
少し意外そうな声を上げるジョルジュに、キョウジは頷いた。
「ああ。分かっているとは思うけど、今この辺り一帯は停電に陥っている。今、ここの電力を賄っているのは、この、自家発電機なんだ」
キョウジはそう言いながら、自分の近くにある機器を二人に見せる。
「これが、街の境界線に張られている結界と、ハヤブサの延命装置を動かす電力を供給している。これが止まると大変な事になるんだ……。だから、この家の何を壊してもいいけど、この周辺の機器だけは壊さないように戦って欲しい」
「ああ……ドモンの奴が電柱ぶっ倒していたからなぁ……」
しみじみ言うチボデーに「あ……やっぱり?」と、キョウジも苦笑するしかない。その向こうでドモンが「おりゃああああああ!!」と、叫びながら敵を殴り飛ばし、屋根を壊していた。
「真・流星胡蝶剣―――――!!」
その隣でサイ・サイシーも究極奥義を繰り出して暴れている。見る見るうちに、屋根やら壁やらが、跡形もなく破壊されて行く様が見えた。
「ふい~。こいつら、やっぱり外の奴らより手ごわいなぁ」
ストン、と床に着地したサイ・サイシーが、棒を片手に構えをとりながら、率直な感想を述べる。
「ああ。こいつら『龍の忍者』の動きをコピーしている様な奴らだからな……!」
トン、と、その横に身軽に着地したドモンもまた、改めて構えをとりながら、口を開く。
「『龍の忍者』!? 兄貴はそいつとも、戦った事があるの!?」
サイ・サイシーの問いに、ドモンは振り向きもせずに答えた。
「言っただろう。あいつはよく兄さんにちょっかい出しに来ると。だから、俺はそのたびに手合わせをして―――――」
抜刀しながら近づいてくる一体の『ハヤブサもどき』に向かって、ドモンは躊躇いもせずに踏み込み、突っ込んで行く。ドモンは鉢巻を器用に使って『ハヤブサもどき』から刀を絡め捕ると、そのまま拳と拳の応酬に、勝負を移行させていた。
「こいつは確かに強い………! だが―――――」
一瞬の隙を突いたドモンの強烈な右ストレートが、化け物の身体にもろに入った。
「オリジナルほどではないッ!!」
そのままゴッド・フィンガーを炸裂させ、また一体、モンスターを屠っていく。
「おいらも負けてらんねぇ!!」
サイ・サイシーはそう言うと、彼もまたモンスターたちとの戦いにその身を投じていた。
「よし! じゃあ俺たちも行こうぜ!」
チボデーがそう言って立ち上がりかけた時、ジョルジュの顔色が変わった。
「ちょっと待ってくださいチボデー! 一番の『破壊魔』が、もうすぐここに来ます!」
「えっ?」
ジョルジュのその言葉に、キョウジと東方不敗はきょとん、と、目をしばたたかせる。しかしチボデーは、憶えがあるのかはっと顔色を変えていた。
「確かにそうだな!! 『あの技』をここでやられるとまずいぜ!!」
「ええ!! この部屋どころか、家ごと吹っ飛ばされかねません!!」
「と言う訳で兄さん! 俺たちはちょっと外に出てくる!」
「えっ? あ、ああ………」
「東方不敗マスターアジア! キョウジ殿を頼みます!!」
「フン! 言われずとも!」
茫然とするキョウジを尻目に二人は立ち上がると、再び戦いをかいくぐりながら部屋から出て行った。
「破壊魔って………?」
(ああ……なる程のう……)
顔に疑問符を浮かべるキョウジに対して、東方不敗は顎を扱きながら頷いていた。何か、思い当たるところがあったらしい。
「…………」
その頃噂のアルゴ・ガルスキーは、外の敵を倒しつつ、その巨体をのそりと移動させながら、キョウジの家の前まで来ていた。家の中から濃厚な『邪気』を感じた彼の足は、自然と家の方へと向かって行く。
家の傍まで来ると、中から戦いの衝撃音と叫び声が聞こえ、破れた窓や壁の間から、敵と戦っているドモン達の姿が見えた。
(なるほど……。外の敵は、ここに来ていたのか……)
アルゴは、戦っているドモン達の様子と、敵の放つ『邪気』の濃さからそう判断する。そして―――――彼はこう断を下してしまった。
この状況、家ごと『ガイア・クラッシャー』で吹き飛ばした方が、話は早い、と。
「ガイア・クラッ………!!」
「おお――――ッと!! まった―――――――ぁッ!!」
間一髪のところで、チボデーが飛び込んでくる。制止が間に合ったと悟って、チボデーもジョルジュも、ホッと胸を撫で下ろしていた。
「敵を一網打尽に出来る物を……何故止める?」
少し納得のいかないような表情を浮かべながら、アルゴが問いかけてくる。その問いに、チボデーから少し遅れて到着したジョルジュが丁寧に答えていた。家ごと破壊してはならない、その理由を。
「なるほど、分かった」
ジョルジュの説明に納得してくれたのか、アルゴが大きく頷く。
「要は、ハヤブサ殿とシュバルツ殿。それと、キョウジ殿の傍にある発電機を壊さなければいいのだな?」
「ええまあ、そうなのですが――――」
「ならば、戦い方を変えよう。このアルゴ、己が拳のほかに、もう一つ得意とする得物がある」
「へえ~。それはどう言う―――――」
ものだ? と、問いかけようとしたチボデーの前に、『それ』が出されて、チボデーもジョルジュも、若干ひきつったような顔になる。何故ならアルゴの手には、「どこから出した!?」と、突っ込みを入れたくなるような、鎖に繋がれた巨大な刺付きの鉄球が握られていたからだ。
「え……? おい、まさか家の中でそれを振り回す気じゃあ………」
チボデーの問いが終わらぬうちに、アルゴが玄関のドアをバン! と、乱暴に開け放つ。入ったところで『ハヤブサもどき』のモンスターたちと、早速視線が合った。
「グラビトン・ハンマ―――――ッ!!」
叫び声と共に、振り回される鉄球が、容赦なく壁や窓を破壊して行く。ついでにモンスターたちも、一緒くたに吹っ飛ばされていた。
(あ……確かに、破壊魔だ………)
アルゴ・ガルスキーのある意味豪快すぎる戦い方に、キョウジももう顔をひきつらせながら見つめるしか術は無い。キョウジの家は最早、シュバルツとハヤブサが眠る寝台の周りを除いて、無事である所を探すほうが困難な状況になりつつあった。
(うわあ………。後片付けが……!)
部屋の中の惨状を見ながら、キョウジは深いため息を吐く。これだけ辺りが破壊されていても、まだ一般人の死人が出ていない事が、せめてもの救いだろうか。
(それにしても……戦いが終わった後の事を考えてしまう自分って―――――)
自分の思考回路のおかしさに、ふとキョウジの顔から笑みがこぼれた。
今は、『邪神』との戦いの真っ最中で、これから先も、どういうふうに戦いの流れが転がっていくか、全く読めないのに。
戦いに勤しむ、弟と、その友人たちの顔を見る。
自分の傍で生き生きと戦う、東方不敗の顔を見る。
何故なのだろう。
戦いに『負ける』と、想像する事の方が、はるかに困難であった。
それだけの面子が揃っていると、キョウジは感じていたのだ。
(とりあえず私は、予備の自家発電機の制作を急ごう)
キョウジはそのまま発電機の制作を再開する。そして、眠り続けるシュバルツを見ながら、起きたら死ぬほどこき使う事になるな、と、苦笑するのであった。
第4章
手応えは感じていた。
確実に、自分は強くなっていると言う手応え。
男との修行は、確かに自分の剣技を磨いていた。
「ほら」
ある程度修業を終えると、男は祠の裏から握り飯を持って来て、そっと差し出してくる。 そして、自分から離れたところにどかっと腰を落ち着ける。
そんな光景が、もうハヤブサの中では当たり前の物になりつつあった。
差し出される握り飯は、相変わらず美味い。
(このままでいいのだろうか)
握り飯をほおばりながら、ハヤブサは思う。
目の前にいる男は、自分の里を襲った『仇』の筈だ。それなのに―――――
こうして、『龍剣』を手に入れるための修行を、手伝ってくれている。
良いのか?
このままで、本当に良いのだろうか?
この男が俺に龍剣を手に入れさせる、その『真の目的』は何だ?
俺が龍剣を手に入れることで、この男に、何のメリットがあると言うのだろう?
考えれば考える程、訳が分からなくなってくる。
だからハヤブサは、気がつけば男に声をかけていた。
「おい」
「何だ?」
離れていると言っても、声をかければ聞こえる程度の距離なので、男はすぐに振り向く。
「お前、何を考えている?」
その質問に男は「特に何も」と、返してくる。質問の内容が抽象的過ぎたと感じたハヤブサは、もっとストレートな質問をぶつけることにした。
「お前は……本当に、俺の『仇』なのか?」
「…………!」
男は一瞬目を見開いた後、ハヤブサから視線を逸らして少しの間沈黙をする。
ハヤブサはその横顔を、知らず懸命に見つめていた。
敵なのか
それともそうじゃないのか
はっきりして欲しい。
自分は、それが一番知りたいのだから。
もし、「違う」と一言。
一言で良い。
そう言ってくれたなら、俺は―――――
男はハヤブサのその視線に気がついたのか、ハヤブサの方に振り向いた。
やがて、その面にフッと、穏やかな笑みを浮かべる。
「違う」
「―――――!」
思わず、弾かれるように立ちあがりかけるハヤブサ。だが、ハヤブサが声を上げるより先に、男からピシャリと冷水をかけられた。
「――――と、言えば、君は私を信じるのか?」
「…………!」
絶句し、茫然とするハヤブサに、男は更に言葉を重ねて来た。
「他人を、そんなに簡単に信じてはいけないと―――――君は誰かから学ばなかったのか?」
「あ…………!」
(リュウ。お前は優しすぎる。簡単に、人を信じすぎる)
ハヤブサの脳裏に、父であるジョウの、渋い表情が甦る。
(我々の生きる世界は謂わば、闇の道。近づいてくる他人をすべて撥ねのけろとも言わんが、信じすぎてもならぬ。そんな甘い考えでは、この先、到底生きてはいけまいぞ)
「……………ッ!」
(違う)
父の言葉に対してそう叫びたい自分がいるのに、叫ぶための一歩を踏み出す事が出来ない自分もまた、そこにいる。
でも確かにそうなのだ。
自分が生きる忍びの道は、闇の世界の道。
生きるために騙し、裏切るのは当たり前の世界。
そんな中を生き抜いて来た父の言葉は、どこまでも正しく、否定できない重みがあった。
信じてはならぬ。
弱さは呪いだ。
優しさは、足枷だ。
――――本当に?
本当に、そうか?
もしも、何もかも信じてはならないと言うのなら。
今、この手の中にある握り飯の美味さも。
目の前の男が繰り出す剣の美しさも。
信じてはならない、と、言うのだろうか――――
もしも、そうだと言うのなら
それはあまりにも―――――
「……………ッ!」
ハヤブサはいたたまれなくなって、すくっと立ち上がった。
ごちゃごちゃと考えすぎてしまっている自分を自覚したが故に、クールダウンする必要性を感じたのだ。
立ち上がり、無言で歩きだす自分を、男も黙って見送っていた。
男から離れて少し歩いた所で、目的の場所にハヤブサは到着していた。閉じられたこの小さな空間内では、そんなに長い距離を移動する事は無い。しかし、この空間の中に『これ』があって良かったと、ハヤブサは思った。
そこには、小さな石が鎮座していた。
そしてその前には、小さな花立てと線香立てが設えられてある。
そう、それは『墓』だった。
幼いころに死に別れてしまった友人の―――――
「……………」
ハヤブサはその前に座り、手を合わせて祈りをささげる。
自分の心と向き合いたい時に、ハヤブサはよくここに来ていた。
どんなに周りが信じられなくなっても、この友人だけは信じられる存在だった。
何故なら彼は、最期まで自分を守って、死んで行ってしまったのだから。
幼いころに、自分は母を亡くしていた。
だが、『母が居ない』と言う事で、多少なりとも喪失感があっても、自分は特段、淋しさを感じることは無かった。何故なら自分には、乳母と乳兄弟がいたからだ。
その乳母は優しく、少し年上の乳兄弟は、本当の兄弟の様だった。
乳兄弟の名は『タケル』と言った。
その乳母とタケルのおかげで、母とか、家族と言う物を、理解するのに苦労は無かった。そして、タケルの父は、わが父であるジョウに仕える武人であった。
「と、言う事は、俺も大きくなったら、父上みたいにお前に仕えることになるのかな」
「そうなの?」
「ああ。だからリュウ。お前も、お前の父上殿に負けないぐらい、強くなれ」
そう言って、俺の頭を優しく撫でる。其れがタケルの日課の様になっていた。
タケルと打ち込む剣の修業は、厳しい時もあったが、楽しかった。
タケルがいてくれたから、どんな辛い修行にも、耐えられた。
大汗をかいて帰ってきた時に、乳母がよそってくれた白いご飯は、堪らなく温かくて、おいしかった。
そうして修行に励むハヤブサの剣の腕は、元々の高い素質も手伝ってか――――子どもながらに大人にも引けを取らない物へと成長して行っていた。
そしてそんな中、『悲劇』は起きた。
「ジョウの息子がいたぞ!!」
散策のために里の周辺にタケルと出て来ていた時、運悪く里を狙う忍者団と遭遇してしまった。怒号と共に、彼らは一斉に、自分に襲いかかって来た。
「逃げろ!! リュウ!!」
子どもたちは必死になって逃げる。だが大人と子供のリーチの違い。そして、多勢に無勢―――――ハヤブサたちが追いつめられるのに、そう時間はかからなかった。
「……………!」
やむを得ずハヤブサは、抜刀して立ち向かった。皮肉な事に、これが彼にとって初めての『実戦』となった。
教えられた通りに刀を振るい、相手を斬り伏せる。
「ぎゃあ!!」
相手の身体から飛び散る、生温かい鮮血。『人を斬った』と言ういやな感触と共に、それはハヤブサの身体をどろりと濡らした。
「――――――ッ!」
噎せかえる血の匂いと、斬られた痛みでのたうちまわる相手。ある種凄惨な光景に、ハヤブサの心は恐怖に鷲掴まれてしまう。
「リュウ!!」
タケルの声が、自分をはっと正気に戻す。「逃げよう!!」と腕を引っ張られて、固まりそうだったハヤブサの足が、ようやく動き出した。
よく見たら、タケルの身体も血だらけだ。そして、その顔色は蒼白で、その腕も震えていた。
(守らなければ)
強く思った。
タケルは自分を守ってくれた。
だから、今度は自分が守らなければ。
その為に――――自分は強くなった筈なのだから。
走った先に、また敵が現れた。どうやら、回り込まれていたらしかった。
「りゃああああああっ!!」
ハヤブサは、躊躇わずに踏み込んだ。
『守る』ために血に汚れるのが自分の役割なのだと、子どもは既に『理解』していた。
迷わずに振り切られた白刃は、大人3人をあっという間に斬り伏せた。
――――とどめを刺せ!
頭の中に、父ジョウの声が響く。
「……………!」
だがハヤブサは、その声に頭をふった。
もう相手に、戦闘を継続する能力は無い。それで、充分じゃないのか。
それに、動く事が出来ずに呻いている相手に、刀を振り下ろすなんて―――――
命までは奪わない。
だからお願いだ。
どうかそのまま帰ってくれ―――――
その願いと共に続けられた戦い。
しかしやがて、それは最悪な形でしっぺ返しを食らう事になってしまった。
「危ない!!」
叫び声と共に、タケルが飛び込んでくる。
「―――――!」
自分が振り向いたときには、既にタケルは、斬り伏せられた後だった。
それも、自分が片腕を斬り落とした男によって―――――
「あ……あ……! タケル………! タケル―――――ッ!!」
その後のことは、よく憶えていない。
ただ、里の者たちが助けに入ってくれて、もう動く事のないタケルの『遺骸』を、何とか里に連れ帰れた事だけは、何となく記憶に残っている。
(俺のせいだ……!)
ハヤブサは、己が剣の『甘さ』を悔いた。
父の教えに背いて、とどめを刺さなかった戦いを悔いた。
馬鹿だ。
馬鹿だ。
自分みたいな非力な子どもが何かを『守ろう』と言うのなら―――――
それ以上の犠牲を、自分に課さねばならなかったのに。
戦いながら自分は、己が『心』を守ってしまった。
其れが―――――この結果を招いたのだ。
タケルの死は、ほぼ自分のせいだ。
それを責めて欲しくて。
詰って欲しくてハヤブサは、乳母夫婦の元に足を運んだ。
「すみません……!」
夫婦の顔を見るなり、涙ながらにハヤブサは、頭を下げた。
彼らの『宝』であるタケルを奪ってしまった。
これは、一体どう償えば、良いと言うのだろう。
だが、夫婦は、ハヤブサを責めなかった。
「リュウ様……! 貴方だけでも、無事で良かった……!」
そう言って乳母は、涙を流しながら抱きしめて来た。
「タケルは、最期まで役目を全うしたのです。タケルは、我等の誇りです」
タケルの父も、その瞳から涙を零しながら、しかし、気丈にそう言った。
「でも―――――! タケルは……!」
反論しようとしたハヤブサの言葉は、父であるジョウに押しとどめられた。
「リュウよ……。お前は、その身に刻まねばならぬ。お前を守るために、村の皆は命をかける。お前は、そう言う『立場』にあるのだと」
「何故ですか!? 私の命もタケルの命も、同じ『命』の筈です! 私の命を守るために、他者の命を犠牲にするなど、あってはならぬ事ではないのですか!?」
「そう。『命』に優劣も貴賎も無い。みな平等なものだ」
子どもながら「命」の本質を理解している聡い我が子に、ジョウは心の中で感心する。しかし、その面には眉をひそめ、渋い表情を作り続けた。
「だがリュウよ……。お主は将来この里を背負って立つ身。その事を、強く自覚せねばならぬ」
(本当は、それだけではない)
我が子にそう諭し続けながらも、ジョウは知っていた。この目の前にいる少年こそが、里で長い時に渡ってその出現を待ち続けていた、正式な『龍剣』の使い手―――――『龍の忍者』となり得る素質の持ち主であることを。それを守るために、里の者たちは皆命をかける。『頭領の息子である』と言う以上に、その理由は里の中では重きを置いていた。それほどまでに―――――この隼の里にとって『龍の忍者』の出現は、悲願であったのだから。
「その身に刻め。タケルの死を。そして考えろ。守れなかった『命』と、その原因を」
「…………!」
「彼の死を―――――決して無駄にしてはならぬ」
そして、タケル荼毘に付された後、里の中でも『聖域』とされる、龍剣を封印する祠の傍に埋葬された。そこに、小さな墓が建てられた。
その日を境に、ハヤブサの剣の修業はますます熱を帯び、苛烈な物へとなって行った。
忘れるな。
タケルを守れなかったのは、自分が弱かったからだ。甘い戦いをしたからだ。
強く
強くならねばならぬ。
自分を守るために、誰かが犠牲になる。
そんな悲劇を、二度と繰り返さないためにも
皆が自分を命がけで守ると言うのなら、自分も、皆のために命をかけよう。
守られるよりも、自分が、皆を守れるような人間になろう。
躊躇うな。
守るために、他者の命を奪う事を。
必要とあらば、自分は『鬼』にも『修羅』にもなろう。
敵に赦しは請わない。
殺したことで被る『恨み』も『業』も、総て背負って生きて行く。
そして―――――
忘れるな。
タケルがくれた優しさを。
乳母夫婦がくれた愛情を。
忍びの道は危道。
騙しだまされるのは当たり前の世界。
闇撃ちも裏切りも日常になる世界を、これから自分は生きて行く。
だけど忘れるな。
自分に敵意や悪意を向けてくる人間ばかりではなく、優しさをくれる人間も、必ずいると言う事を。
親が子を想い、子が親を想う。
手を差し伸べあい、助け合う人々がいる。
そんな優しい世界が必ずあるのだと、信じ続けて生きて行こう。
現にタケルが、そうだったから。
命尽きるその寸前まで、彼は自分に手を差し伸べ続けてくれたのだから―――――
(タケル………)
守れなかった苦さを噛みしめ、
そして、彼への感謝の気持ちを心に満たす。
死して、もう二度と、会う事の出来ないタケル。
だが死んでいるからこそ―――――彼を信じることに、迷いは無かった。それは、酷く皮肉な話ではあるのだけれど。
(あの男の真の目的は分からん……。だが、あの男の『剣』は信じられる……。そうだな?)
墓に向かって手を合わせながら、ハヤブサは己の考えを整理する。
敵だと息を巻き、悪意と敵意で以ってあの男を斬り捨てるのは簡単だ。だが、それをするにはあの男の剣は美しすぎた。真っ直ぐで、何故か優しさすら感じた。
そして時折、妙な懐かしさすら感じる。これは一体何なのだろう。
あの男の『剣』と、俺に龍剣を手に入れさせると言う『目的』だけは、どうやら本物の様だ。信ずるに足りる物だとハヤブサは思った。
もしかしたら、自分が龍剣を手に入れた途端、あの男は自分を裏切るかもしれない。
だが、それはそれでいいか、とも思った。
裏切られたら―――――その時は、その時だ。
(それに、もしかしたら…………)
心の片隅に、ちらりと疑念が湧いた。
――――自分ハ、アノ男ノ事ヲ、無理ヤリ『仇』ト思イ込マサレテハイナイカ……?
あの男の剣や気配から、邪悪な者の匂いを感じ取れない。だからこそ、そう思う事が、ハヤブサの中ではむしろ自然だった。
勿論、確証を持てる物ではない。だから、口に出すことは憚られたのだが。
「……………」
フッと小さく息を吐いて、ハヤブサが立ち上がり振り向くと、じっとこちらを見ている男と、視線が合った。
二人の間に、しばしの沈黙が走る。
先に口を開いたのは、男の方だった。
「……それは……『墓』か?」
「ああ、そうだ」
男の問いに、ハヤブサは多少ぶっきらぼうに答えた。
「俺の幼馴染の墓だ。俺がまだ小さい頃、守ってくれて……そして、死んでしまったんだ……」
「………そうか……」
そう言ったきり、男は再び沈黙してしまう。
(里の『仇』に―――――話すべきでもなかったか……?)
瞳を曇らせながら佇む男を見つめながら、ハヤブサはふとそう思った。
タケルの墓は、今の自分にとっては『原点』とも言える場所。出来れば誰にも踏み荒らされたくない、とても大事な場所だった。だから、「貴様には関係ない!!」と、突っぱねても良かった。
しかし今のハヤブサは、何故か男をそんな風に切り捨てる気にはなれなかった。
それよりも、見てみたいと思った。
今の話を聞いて、この真っ直ぐで綺麗な剣を振るう男が、どのような行動をするのかを。
もしも、こいつが真の悪人ではないのなら―――――
「………その、ハヤブサ……」
長い沈黙を破って、男は少し躊躇いながらも口を開いて来た。
「何だ?」
「私も……その墓に、手を合わさせてもらっても………良いか………?」
「―――――!」
予想通りと言うか、予想以上の言葉を返してくる男に、ハヤブサは半ば呆れかえってしまう。
(もう分かった……! お前、絶対に里を襲った張本人じゃないだろう!? 何だ!? その人のよさげな言動行動は―――――!)
軽く眩暈を覚えながらも、ハヤブサは「ああ、良いぞ」と返事をする。すると男は「ありがとう」と、その面に優しい笑みを浮かべて、踵を返す。
「お、おい! 何処へ――――!」
ハヤブサが問いかけた所に、男はすぐにそこに帰ってきた。その手の中には、小さな赤い花が握られていた。
(ああ……滝の傍に咲いていた花か……)
男は墓の前で静かに膝を折ると、その前にそっと小さな花を置く。どうやら、お供えをしてくれているようだった。
(手ぶらでも構わないのに………律儀な奴だな……)
ハヤブサは呆れたようにため息を突きながら、男を見つめる。拝み方も丁寧で、そこには死者に対する労りと敬愛が見て取れた。
(やはり、違う)
ハヤブサは確信する。
この男は絶対に、里を襲ってはいない。
赤子を残忍に引き裂いていた奴が、例え「フリ」だけだとしても、ここまで丁寧に墓を拝むなど、出来る芸当ではないからだ。命を軽んじている奴ならば、どうしてもその動作の端々に、その匂いが滲み出てくる物なのだから。
(ならば、俺の目の前にいるこの男は一体誰だ……?)
疑問に思って目の前の男を見つめる。
何故この男は、自分にとって『仇』の格好に見えてしまっているのだろう。
するとその時。
(リュウ様……! どうぞ……!)
明るい声と共に、墓に供えられていた花と同じ物を差し出す小さな手が、脳裏にフラッシュバックする。
「―――――!」
何だ?
自分はあの花を、ここ以外のどこかで見た様な気がする。
しかし、それは何処だ……?
どこで見たんだ……?
(リュウ………)
不意に耳元に、懐かしさを含んだ声が響く。
よく見ろよ、と、小さな手が墓の前の男を指し示す。その手につられる様にハヤブサは墓の前の男の姿を見て―――――
「―――――!?」
そこに居たのは、革のロングコートを着た青年だった。その青年の後姿を見て、ハヤブサの心が酷くかきむしられるような痛みを覚える。
何だろう、この衝動は。
何だろう、この焦燥感は。
ひどく懐かしいヒト。
大切な、ヒト。
思い出さなければならない様な気がした。
ああ、誰だ?
誰だ、誰だ?
「―――――」
その名が、喉元まで出かかっている様な気がする。
なのに―――――自分はどうしても、それを思い出せなかった。
「どうした? ハヤブサ」
「…………!」
はっとハヤブサが我に帰ると、『仇』の姿形をした初老の男性が、じっとこちらを見つめている。ハヤブサは懸命に、目の前の男の中に、先程の青年の姿を求める。しかし、やはりと言うべきか―――――あの青年の面差は、もうどこにもなかった。
「いや、何でも無い……」
ハヤブサは懸命に、平静を装って答える。しかし心の中は、荒れ狂う海の如く激しい波が立っていた。
(幻………?)
今のは一体、『誰』だったのだろう。
どうして、こんなにも心が波立つのか―――――
知りたい。
お前は
お前は 誰だ?
だが同時に、ハヤブサの心に響く、「思イ出スナ!」と、制止する声。
「…………!」
不思議な事に、その声は二方向から聞こえて来ていた。つまり、「思い出してはいけない」と制止している者が、少なくとも二人以上はいる、と言う事だった。
(どういうことだ? これは……!)
ハヤブサは疑問に思うが、すぐに思いなおした。
今は、彼の正体について詮索する時期じゃない。
つまりはそう言う事なのだろう。
「……………」
男はしばらく推し量る様にハヤブサを見つめていたが、やがて「修業を始めよう」と、二振りの剣を取り出した。
ハヤブサも抜刀し、無言で剣を構えなおした。
男は今――――――仁王の戦い方を完全にその身に再現をして、ハヤブサとの剣の修業に取り組んでいた。
自分の戦い方のスタイルを完全に変えて、尚もこの強さ――――この男は、一体どれほどの腕を持っているのだろう。
「お前の方が、強くなる」
男は時々、こう言って自分を励ましてきた。
「だから、早く強くなれ。ハヤブサ」
ハヤブサは、フ――――ッと大きく息を吐いて、精神を集中する。
迷いなくまっすぐな太刀筋を手に入れるためには、余計な雑念を捨てねばならぬ。
怒りを恨みを、捨て去らねばならぬ。
そうして心穏やかに刀を構えていると―――――見えてくる物がある。
太刀を通して伝わってくる、男の『人格』の様な物。
優しさ。
温かさ。
そして、言いようのない懐かしさ―――――
きっと、俺は知っている。
この男の太刀を、知っている。
「―――――」
心の奥底では、男の真の名を叫んでいる自分を自覚する。
見極めろ。
この男の『正体』を。
恐れることは無い。
この男は『仇』に見えていても、絶対に里を襲った張本人ではないのだから。
(ハヤブサ……)
シュバルツは戦いながら、真っ直ぐに向かってくるハヤブサを見つめる。
ハヤブサの齢は、もう16前後には達しているだろうか。手足はすらりと伸び、少年の高い声から大人の低い声に変わった。少年の美しさより、青年のたくましさの色が濃くなる。長く伸びた琥珀色の髪が、ふわりと風に揺れる。そして、成長期を迎えたハヤブサの容姿は、今まさに美しい盛りであった。
『仇』と恨んでいる人間から『剣』を教わる―――――自分はハヤブサに、どれ程の怒りと恨みと、苦痛を与えてしまっているのだろう。それなのにハヤブサは、その修業についてくる。彼の懐の深さと精神力の強さには、シュバルツもただただ舌を巻くばかりだ。
怒りや恨み、そして、哀しみに充ちあふれ、雑念だらけだった彼の太刀筋も、今はそれらが影をひそめ、代わりに真っ直ぐで迷いなく、力強い太刀筋が、表に出てくるようになる。
シュバルツにとっては、ある意味懐かしくもある太刀―――――きっと、ハヤブサが『龍の忍者』としての資質を取り戻すのも、あと少しだ。
彼が『龍の忍者』として総てを取り戻したなら―――――自分はもう、その役目を終えていい。ハヤブサを導く、『師』としての役割も。『仇』として恨まれることも。
ハヤブサ……。
ハヤブサ、お前は
『龍の忍者』として総てを取り戻した時、どうするのだろう。
やはり、『仇』としての私を、討ちたいと願うのだろうか?
「……………」
それでも良いか、と、シュバルツは思った。
神をも滅殺する力を持つ龍剣と龍の忍者。その力は、『悪魔の細胞』と呼ばれた『DG細胞』をも滅殺出来る。それ故にハヤブサは、『DG細胞』で構成されている自分の身体を破壊する事が出来る、数少ない人間の1人だった。
ここはハヤブサの心の中。そして、自分も精神体の存在であるとはいえ、本気を出した龍の忍者に龍剣で斬られてしまえば、自分もただでは済まないだろう。下手をしたら、精神体も現実世界の肉体も、死を迎えてしまう可能性が大いにある。
だがここで葬られるのなら―――――酷く幸せなことだと、シュバルツは思った。
ハヤブサの心の中で死ねるのなら、文字通り、彼と一つになれる。彼の中に自分は溶け込み、彼の一部になる事が出来るのだから。
それは、抗いがたい甘やかさを伴って、シュバルツを誘惑していた。
彼の中で死にたいと、願うようになっていた。
そして、そんな彼の心の動きを、『邪神・ラクシャサ』はほくそ笑みながら見ていた。
――――イイゾ……後少シダ……。
漆黒の闇の中、ラクシャサは残忍さを滲ませながら嗤う。
龍の忍者が最愛の人をその手で殺す。その瞬間に、この『怨の術』は完成を迎える。
自分の犯した過ちに対して彼の放つ絶望、憎悪、恨みが―――――この身が龍の忍者の身体を乗っ取り、現世に完全復活を果たすための、大いなるエネルギーになる事だろう。拠り代になる龍の忍者の身体も龍剣も――――我が身体の元になるのに相応しい存在だった。
だから、恨め。
憎め、リュウ・ハヤブサ。
お前の目の前にいる男は、紛う事なきお前の『仇』
お前の手で、存分に屠るが良い。
人間界で、このラクシャサと戦おうとする者たちが、何かちょろちょろ動いてはいるが、龍の忍者の封印の力には到底及ばぬ。故に確信する。我が完全復活まで、あと少しなのだと。
ククククク…………
仄暗い笑い声が、漆黒の闇の中に響き渡っていた。
「少し休憩しよう」
観音像の裏からいつもの如く握り飯と竹筒が出て来たのを見て、シュバルツはハヤブサに声をかけた。
「ああ」
青年になりつつあるハヤブサは、素直に応じてくる。刀を収めて、互いに礼をする。そして、一息ついているハヤブサに、シュバルツはそっと食事を差し出した。それから彼に背を向け、すたすたと歩いて行き、彼から離れたところに腰を落ち着ける。ここまではいつも通り―――――だが、その後が違った。
腰を落ち着けてふっと息を吐くシュバルツのすぐ後ろに、ストン、と誰かが座る気配がする。
「?」
振り向いて――――シュバルツは、ぎょっと目を剥いた。何故ならそこには、おにぎりを手に持ったリュウ・ハヤブサの姿が在ったからだ。
「な、何だよ?」
ハヤブサの方も男が驚いている気配を感じ取ったのか、おにぎりをほおばりながら、少し決まり悪そうにこちらを見ている。
「あ……! いや、その………」
いかん、と思いながらも、シュバルツは狼狽を隠す事が出来ない。慌てて視線を逸らしながら、何とか気持ちを落ち着けようと努力する。
(な……! 何で、ハヤブサは私の傍に寄って来たんだ……? 『仇』の傍で飯を食べても、落ちつかないし、おいしくないだろうに……!)
食事ぐらいゆっくり食べたいだろう、と、シュバルツは四方を見渡して、ハヤブサから離れるために腰を上げようとする。すると、ハヤブサに服の裾を掴まれた。
「別に離れなくてもいいだろう? 何か問題でもあるのか?」
「う………!」
ハヤブサに真顔で言われて、有効な反論が思い浮かばなかったシュバルツは、あきらめたようにストン、と、その場に腰を下ろす。それを見届けたハヤブサは、またおにぎりを頬張り始める。暫し、二人の間に沈黙が舞い降りた。
(……そう言えば……手合わせ以外で、こんなにハヤブサの近くに身を置いたのは、久しぶりだな……)
すぐ近くにハヤブサがいる―――――少し前までは、自分の中でそれは当たり前の風景だった。「シュバルツ、シュバルツ」と、まとわりつかれて、少し鬱陶しいぐらいだった。それなのに、今こうして傍に腰を落ち着けていると言うだけの事を、『懐かしい』と、感じてしまう自分がいるだなんて。
覚悟は、決めていたつもりだった。
ハヤブサに『仇』とみられている以上、彼から自分に好意的な眼差しを送られてくることはまずあり得ない。向けられるのは『敵意』と『拒絶』、下手をしたら『憎悪』にまで、発展してしまっているかもしれない。
自分は、それらの眼差しを受け止めるしか術がなかった。
仕方がなかった。
自分は、ハヤブサの『誤解』を解くための有効な手立てを、持ち合わせてはいなかったのだから。
恨まれているのなら、恨まれたままで良い。
自分は、彼のために出来る事をしよう。
そう強く決意をして、彼の前に剣を持って立つ。
それでも
それでもやはり、辛かった。
『好きな人』に敵意を向けられ続ける状態と言うのは―――――
消耗するし、疲れる。
傷ついている『ココロ』を、否が応でも自覚する。
出来ればもう一度、穏やかに笑いあいたい。
そんな時間を望むのも―――――もう無理なのだろうか。
自分には、『過ぎた幸せ』なのだろうか。
「…………」
シュバルツはちらり、と、ハヤブサの様子を伺い見る。
握り飯を食べ終わったハヤブサは、静かにそこに座り続けていた。
(どうして、彼はわざわざ私の所に寄って来たのだろう)
出来ればその理由を、聞いてみたいと思った。もしかして、『誤解』が解けたのだろうか?
(いや……そんな筈は無いよな……。甘い期待は、しない方がいい……)
シュバルツはふっと苦笑して、座り直す。しかしやはりと言うべきか、何となく落ち着かない。
(……悩んでいても仕方がない。とにかく、話しかけてみよう)
シュバルツは暫し逡巡しながらも、何とかそう決心を固めた。
話しかければ、返って来る言動行動で、相手の心を推し量れるはず。拒絶されれば、黙ればいいだけの話じゃないか。先程の修行の、太刀の運び方の注意でも良い。対仁王戦の、戦い方の対策でも良い。とにかく、話題には事欠かないのだから。
「ハヤブサ……」
「……………」
シュバルツはそろりと声をかけてみる。しかし、ハヤブサからの返事は無い。
(やはり、話したい訳ではないのかな?)
そう思ってシュバルツがハヤブサの方に振り返った時、彼の身体が、ぐらり、と傾ぐ。
「ハヤブサ!?」
驚くシュバルツが声を上げる目の前で、ハヤブサはバタン、と、地面に倒れ込んでしまった。
「ハヤブサ!? おい……!」
しっかりしろ――――! と、叫びかけたシュバルツの目が、点になってしまう。何故なら地面に倒れ込んだハヤブサから、すやすやと穏やかな寝息が聞こえて来たのだから。
「え……!? ちょっ……! 何でこんな無防備に――――!」
この世界に入ってから、ハヤブサがこんな風に眠りこけるのは、実は初めての経験ではなかった。身体が急激に成長する際、莫大なエネルギーを消耗するのだろう。まるで繭を作って脱皮をするが如く、彼は眠ったり起きたりを繰り返していた。
(今が見た目が16、7歳ぐらいだから……次に起きた時は、20歳ぐらいにはなっているかな)
眠るハヤブサの横顔を見つめながら、シュバルツはもの思う。ハヤブサが龍剣の真の使い手になったのは、20歳ぐらいの時と聞く。だからこの眠りから覚めた時、彼は『龍の忍者』としての、総ての資質を取り戻している可能性が高い。
それにしても、今のハヤブサは本当に妙だ。
少し前ならば、同じ眠りに落ちるにしても、かなり警戒をしてこちらから隠れるようにして眠っていた。それなのに今は、まるで無防備にこちらに寝顔を曝している。
どう言う事なのだろうか?
少しは、自分に対して『信頼』を、置いてくれるようになっているのだろうか。
(いや、そんな筈は無い……。今回だって、きっと、急激すぎる眠気に対処し切れなかったから――――)
シュバルツはそう自分を納得させようとするのだが、やはり、どこかふに落ちない。それならば何故、彼は食事をするときに、わざわざこちらに寄って来たのだろう。他にも腰を落ち着ける場所はいくらでもあるし、私は彼の傍から意図的に離れたのに。
(やはり、誤解が………)
ここまで思って、シュバルツは再度頭をふる。
(いや、甘い期待はしない方がいい)
龍剣を手に入れるための手伝いをする、と、自分は言った。もしかしたらその目的だけは信頼されての、この行動なのかもしれないのだ。龍剣を手に入れるまでは、私がハヤブサに危害を加えることは無いと、そう信じてくれているから――――
(ハヤブサ………)
シュバルツは、愛おしさを込めて、ハヤブサを見つめる。
『人を好きになる』と言う気持ちは、まことに厄介だ。どうして――――自分でもままらない感情に振り回されて、彼の言動行動に、一喜一憂してしまうのだろう。
分かっている。
見返りを求めるから、苦しい。
見返りを求めるから、切ない。
『アンドロイド』である自分は、ハヤブサにそんな事を願う資格も本来ならばないはずだ。なのにどうして――――
彼の気持ちを浅ましくも乞ゆる気持ちを、止めることが出来ないのだろう。
(もしも、彼が『龍の忍者』として総てを取り戻したなら、私のことも思い出してくれるか……?)
またも湧きでてくる甘い期待。しかしシュバルツは、それも頭を振って否定をした。
(無理だな。20歳のハヤブサと私は、未だ出会ってもいない。会ったことすらない物を、どうして『思い出す』事が出来るんだ)
だから仕方がない。
良いんだ。
ハヤブサが無事に龍剣を取り戻しさえしてくれたなら、私はそれで――――
それ以上、何を望むと言うのだろう。
―――ソレニ………コノママ私ノ事ヲ忘レ去ッテシマッテイタ方ガ………ソノ方ガ、彼ニトッテハ幸セナノカモシレナイ………。
フッと浮かんで来てしまったネガティブな考えに、シュバルツは苦笑する。
でも確かにそうなのだ。
『DG細胞』と『死体』から出来ている、自分を愛する異常性。
『DG細胞』に感染するリスク。
それらから、彼を解放する事が出来るのなら―――――
恨まれたまま死ぬことも、また『良し』と、言えるのではないだろうか。
(とにかく、今は彼の眠りを守ろう)
シュバルツは刀を抱えたまま、改めて座り直す。
未来が、どう転ぶかなんて誰にも分からない。
だけど、どうなっても受け入れる覚悟だけは決めようと、シュバルツは思った。
不意に、『何か』の気配を感じて、シュバルツは振り返る。
「…………!」
振り返った先には、あの観音像が居た。
祠から外れた所に鎮座して、何時もハヤブサに食料を差し入れてくれている観音像。しかし、何故かそこから妙な気配が漂って来ていたから、シュバルツは少し眉をひそめた。
「…………?」
よく見ると、その観音像は涙を流していた。
そして、聞き取れないほどの小さい声で、何かを訴えていた。
「―――――」
シュバルツはその声を聞き取ろうと、懸命に耳を澄ます。100m先の針が落ちる音すらも捉えられる彼の優秀な聴力は、やがてそのかすかな音を拾い始めた。
――――リュウ…………リュウ………
(ハヤブサの名だ)
どうやらその観音像は、ハヤブサに対して何かを訴えかけていると気づく。
――――ああ………急いで………
――――もう、時間が無い………!
(時間が無い!? どう言う事だ……!?)
首をかしげるシュバルツの前に、パラパラと小さな礫の様な物が落ちてくる。
「?」
不思議に思って上を見上げるシュバルツの視界に、無数の小さな亀裂の様な物が走っている空が飛び込んでくる。
「な…………!」
絶句すると同時にシュバルツは瞬時に『理解』した。
このハヤブサの『ココロ』の様な空間を守っていたのはこの観音像で―――――その結界の力が、もう限界を迎えつつあるのだと言う事を。不可思議にも思うが、よく考えれば当たり前の話だ。ここは、自分が取り込まれた『化け物』の様な物の精神世界。そんな中に、こんな穏やかで美しい世界がある事こそが、奇跡の様な物なのだから。
グルルルルルルル………
亀裂の隙間から不吉な唸り声が響いてくる。この世界に入り込もうとしていたモンスターたちが、虎視眈眈とこちらを狙っているのだろう。
(ハヤブサ……!)
シュバルツは、自分のすぐ近くで無防備に眠りこけているハヤブサを見る。
(とにかく、何が何でも、このハヤブサだけは守り抜かなければ)
シュバルツがそう強く決意をして、刀の柄に手をかけた、刹那。
目の前の空間に亀裂が走り、パラ……と、小さな礫が落ちる。その隙間から外の世界を覗いた瞬間、そこに懐かしい顔を見て、シュバルツは思わず叫び声を上げていた。
「キョウジ!!」
「シュバルツ!?」
「どうした!?」
叫ぶキョウジに、東方不敗が鋭く反応する。
「そ、そこにシュバルツが……!」
懸命に見つめるキョウジの視線の先に、空間の亀裂の様な物があり、その奥にシュバルツの姿があるから、東方不敗も知らず息を飲んでしまう。
「キョウジ!! マスターアジアもそこにいるのか!?」
シュバルツの呼び掛けにキョウジは頷く。
「ああ。マスターもドモンも一緒だ! シュバルツこそ、独りか!? ハヤブサは傍にいないのか!?」
「ハヤブサなら、私のすぐ後ろにいるが……」
キョウジの質問にシュバルツは少し怪訝に思いながら答える。すると、キョウジから驚いた様な声が帰ってきた。
「後ろ!? その後ろにいるのが、ハヤブサなのか!?」
「!?」
キョウジが振り向くと、ハヤブサが寝ていたところに、『繭』の様な物があるから、シュバルツもかなり驚いてしまう。
(眠っている間にこうなったのか!? そうか……! ハヤブサ自身次の目覚めで完全に『龍の忍者』としての資質を取り戻すから――――)
まるで、幼虫からさなぎを経て、成虫に変化するが如くだな、と、シュバルツは軽く苦笑する。
しかし、妙な納得もしていた。それだけ『龍の忍者』としての資質を身体に得ると言う事は、莫大なエネルギーを消耗すると言う事なのだろう。
そうならば、眠りに落ちる前の彼の奇妙な行動も、ふに落ちてくる。
彼は、自分がこうなる事を予知していたのだ。だから、身の安全を少しでも確保しようとしていたのならば―――――
(………と言う事は、やはりお前は、ほんの少しでも私の事を信じてくれたんだな。ありがとう。お前にとっては、『仇』に見えているはずなのに……)
普通ならば酷く困難な事を、よくぞやってのけてくれた、と、シュバルツは嬉しくなる。知らず、その面に、穏やかな笑みが浮かんでいた。
「ああっ!! 空間が閉じる!!」
キョウジの叫び声に、シュバルツもはっと顔を上げる。見ると、キョウジと繋がっている空間の小さな裂け目が、塞がろうとしていた。
「キョウジ!! シュバルツに意識を繋げよ!!」
東方不敗が叫びながら、その空間に手をかざしてくる。
「い、意識を繋げる!? どうやってですか!?」
戸惑うキョウジに、東方不敗は尚も呼び掛けた。
「何でも良い!! とにかくシュバルツに呼びかけ続けるのじゃ!!」
頷いたキョウジは、懸命に空間の裂け目に向かって声をかけ始める。
「シュバルツ!! シュバルツ!!」
「キョウジ……!」
「シュバルツ!! 帰って来てくれ!!」
「……………!」
キョウジの言葉に、瞳をはっと見開くシュバルツ。
「お願いだ!! 帰って来てくれ!! お前が居ないと困るんだ!!」
「キョウジ……!」
「シュバルツ!! お願いだから!!」
「兄さん!! シュバルツがそこにいるのか!?」
叫び続けるキョウジの横に、ドモンが入ってきた。
「ああ、ここに――――」
キョウジに指示されるままにドモンも亀裂に目をやり、その向こうにいるシュバルツと
視線が合う。
「シュバルツ!! いや、兄さん!!」
「ドモン……!」
茫然とするシュバルツであるが、こちらを懸命に見つめる兄弟たちの背後に、モンスターが迫っている事に気づいてしまう。
「ドモン!! 後ろだ!!」
「――――!!」
ドモンがキョウジを庇いたてするよりも早く、もう一つの影が兄弟たちを守る様に割って入ってきた。ジョルジュ・ド・サンドの後ろ姿であった。
ジョルジュは剣でモンスターを退けると他の場所で戦う仲間たちに呼びかけた。
「皆!! ここにきてドモン達を守ってください!! ここが重要な局面!! 今が戦いの要です!!」
「よし来た!!」
「おいらに任せろって!!」
「承知した」
ジョルジュの呼び掛けに応じて、チボデーが、サイ・サイシーが、アルゴが、空間に向かって手をかざす東方不敗と、空間に向かって呼びかけ続ける兄弟たちを背後に守るように立つ。その『陣』の中で、自分たちの安全が確保されたと判断したドモンは、再び裂け目の向こうにいるシュバルツに呼びかけ始めた。
「兄さん!! 兄さん!!」
「ドモン……!」
「兄さん!! 帰って来てくれ!!」
弟が、自分に向かって懸命に手を伸ばしてくる。
「お願いだから………キョウジ兄さんを独りにしないでくれ!!」
「―――――!!」
はっと弾かれた様に、シュバルツはキョウジの方を見る。キョウジは、食い入るようにこちらを見つめていた。
「シュバルツ……!」
「キョウジ……!」
「兄さん!! 俺の手に掴まって!!」
空間の裂け目を強引にこじ開けたドモンの手が、シュバルツに向かって伸びてくる。その横から、キョウジの手も一緒にその空間に入ってきた。
「シュバルツ……!」
「兄さん……!」
「あ…………!」
懸命にこちらに向かって伸ばされてきた二つの手は、シュバルツの心を揺さぶるには充分だった。
(そうだ……! 私は帰らないと……! あの二人が待つ場所に………。『家族』が待つ場所に帰らないと―――――!)
「……………」
ふらふらと伸びる、シュバルツの手。だがその時、彼の足元にハヤブサの繭がこつん、と、音を立てて当たった。
はっとシュバルツは我に帰る。
(駄目だ……! まだ帰れない。ハヤブサに龍剣を得させるまでは――――!)
分かる。
今ここで、総てを投げ出して帰ってしまっては駄目だ。
そんな事をしてしまったら、何のためにハヤブサがここで頑張ったのか、何のためにあの観音像がここに結界を張り続けたのかが、分からなくなってしまう。総ての努力が水泡に帰す―――――そんな予感がした。
シュバルツは、きっと顔を上げた。
キョウジとドモンをまっすぐ見つめながら、叫ぶ。
「キョウジ! ドモン! 済まない……! まだ、私はそちらにはいけない……!」
「シュバルツ!!」
「兄さん!!」
懸命に叫び、必死に手を伸ばしてくる二人に、シュバルツは優しく微笑みかけた。
「だが、待っていてくれ……! 必ず帰る!!」
「―――――!」
「ハヤブサもつれて、必ず帰るから……!」
「シュバルツ……!」
「兄さん!!」
「ドモン、キョウジをよろしくな」
「―――――!」
思わず言葉を失ってしまうドモンに、シュバルツはにこりと微笑みかける。その瞬間。
バシン、と、乾いた音を立てて、その亀裂が閉じてしまった。
「シュバルツ!!」
「兄さんッ!! 兄さ―――――ん!!」
「く………!」
キョウジのすぐ横で、東方不敗の呻き声が聞こえる。思わずキョウジは顔を上げていた。
「大丈夫ですか!?」
「ああ。大事ない。それよりも、見よ」
東方不敗の指し示す先には、空間に『ゲート』の様な穴が開き、その向こうに暗黒の空間が広がっていた。
「さすがにシュバルツ達の居る所に直通の通路を作るのは無理であったが、お主たちの呼び掛けのおかげで、彼の『邪神』の内部に直接入り込む事が出来る通路を作ることは出来た………」
「……………!」
「これで、こ奴の内部に入り込んで、直接対決に持ち込むことも可能になった訳だが……」
ここで東方不敗はフッと小さな息を吐く。
「かなりの危険を伴う事も、また事実だ。現に、この『ゲート』を使って、『邪神』がさらに強力なモンスターをこちらに送り込んでくることも可能になる、とも言えるからな」
「うえ~~! おっかね~~~~!」
戦いながら東方不敗の話を聞いていたサイ・サイシーから、少しおびえた声が上がる。東方不敗はキョウジに視線を移した。
「どうする? キョウジよ……。このゲートは閉じても良いが……」
「……………」
東方不敗の問いかけに対して、キョウジはすぐには答えず、沈黙を返した。
こちらから攻撃を仕掛けられると言う点においては、魅力的な提案ではある。しかし、『邪神』と直通の通路が出来てしまうと言う事は、かなりの危険を伴う事も、また事実だ。
(さてどうする)
そうキョウジが思案している最中に、隣にいたドモンが声を上げた。
「行けるのなら、迷うことは無いじゃないか。俺は、行くぜ!」
「ドモン……!」
驚いたように見上げてくる兄をまっすぐ見やると、弟は言葉を続けた。
「あのままシュバルツを独り、放ってはおけないし、それに―――――」
「それに?」
「絶対にハヤブサを、抉るように一発ぶん殴ってやる!!」
「―――――!」
目をぱちくりさせる東方不敗とキョウジの前で、ドモンは拳を強く握りしめていた。
「よくも兄さんを危険な目に遭わせやがって……! こんなの、ぶん殴ってやらなきゃ気が済まない!!」
そう言いながらぶりぶりと怒っているドモンを見ながら、東方不敗は呆れかえり、キョウジはいつしか苦笑していた。
(つまりこれは、ドモンなりに『ハヤブサが心配だ』と、言っている様な物だな……。全く、素直じゃないんだから……)
「ドモンよ。どうしても行くのか?」
東方不敗の問いかけに、ドモンは睨みつけるように頷いた。
「ああ、師匠! 止めても無駄だぜ!!」
弟子の答えに、東方不敗はやれやれとため息を吐いた。
「見ての通り、中は暗黒の空間だ。入ったところで、シュバルツ達の居る場所に辿り着けるかどうかも分からん」
「…………」
その言葉にドモンは沈黙を返し、キョウジは確かにそうだな、と、頷いた。
「それでも、お主は行くのか?」
「愚問だ!! 俺は行く!! 俺に兄さんが、見つけられない筈が無い!!」
「――――!」
ある意味、もの凄い事を云い切ったドモンのその言葉に、その場にいた全員が目をしばたたかせる。チボデーが小さく「ブラコン……」と、呟いて、隣のジョルジュにど突かれていた。
「だ、そうじゃが………キョウジはどう思う?」
少々呆れながらも東方不敗はキョウジに意見を求める。それにキョウジは、意外にもにこやかな笑みを浮かべながら答えた。
「私も、ドモンの意見に賛成です。このままここで受け身で戦っているより、踏み込める時に踏み込んだ方がいい」
「……………!」
「それに、ドモンならば、きっと大丈夫――――」
キョウジは、ドモンをまっすぐ見つめながら、言い切った。
「彼ならば絶対に、シュバルツを見つけ出して来てくれるでしょう」
そう。
キョウジには確信めいた想いがあった。
先の『龍の勾玉』の事件の折りに、シュバルツは勾玉を生み出した「化け物」の力によって、自身の身体に持つ『DG細胞』が暴走しかけていた。
そんなシュバルツを救い出してくれたのは、他でもないドモンだった。彼の持つ『紋章の力』は化け物の悪意と攻撃を跳ねのけ、無明の暗闇の中からシュバルツを取り戻してくれていた。
だから、きっと今度も大丈夫――――
彼の『力』は闇を切り裂き、彼自身が『光』となって、必ず二人を救い出してくれるだろう。
「うむ…………」
キョウジの言葉に、東方不敗も愛弟子を改めて見つめる。
ドモンは確かに、その身に『光』を纏っていた。そして、闇の『瘴気』を跳ねのけていた。しかし本人は、その『光』を纏っている事にすら、無自覚なのだろう。この邪悪な『瘴気』が漂っているこの空間で、その影響を全く受けずに独り、立ち続けているドモンの存在は、ある意味稀有であると言えた。
「よし、分かった。ドモンよ、行くか?」
「はい!!」
東方不敗の問いかけに、ドモンは勢いよく答える。これからの戦いの方針が固まった。
「じゃが、独りで行くのは危険だ。何人か連れて行くが良い」
「師匠は?」
「ワシはここでゲートの安定を図らねばならぬ。連れて行くのなら、ワシ以外でだ」
「分かりました!」
返事をしたドモンが、シャッフルの仲間たち4人を見つめる。4人は暫し互いに目を見合わせたが、全員がドモンについて行く事を望んだ。
なので。
4人が次に取った行動は、戦いながらのじゃんけんであった。
「じゃんけんポンっ!! あいこでしょっ!!」
男4人の、野太い、元気な声が響き渡る。誰ひとりとして退く気のないこのじゃんけん大会は、かなり白熱した物になった。
「しょっ!! しょっ!! しょっ!! しょっ!!」
「……器用ですね。よく、モンスターたちと戦いながら、あれだけのじゃんけんが出来る物だ」
関心するキョウジに、東方不敗はフン、と鼻を鳴らす。
「あの程度の事、出来ねば武闘家とは言えん」
「そ、そうなんですか?」
面にひきつった笑みを浮かべるキョウジの横で、ドモンが4人のじゃんけん大会を、
「良いなぁ……。俺もやりたい……」
と、心底うらやましそうに見つめていた。
やがて。
「やった―――――!!」
と、叫び声を上げる勝者と
「あ~~~~………!」
と、ため息を吐く敗者にその4人は別れた。どうやらついて行くのはチボデーとジョルジュ。残るのは、アルゴとサイ・サイシーに決まったらしい。
「………と、言う訳で、俺らに決まったぜ! ドモン、よろしくな!」
にこやかに笑うチボデーとは対照的に、サイ・サイシーは不満げだ。
「ちえっ! オイラも行きたかったのに……!」
「すまないね。だけど、こちらの守りもお願いしないといけないから――――」
少し気の毒そうにキョウジが声をかける。すると、サイ・サイシーの方が何故かはにかんた表情を浮かべた。
「いいよ、こっちの戦いだって重要だろ! おいらたちに任せとけって! なっ! アルゴのおっさん!」
サイ・サイシーに声をかけられたアルゴ・ガルスキーは、無言で、しかし、力強く頷いていた。
「サイ・サイシー! アルゴ! 兄さん達を頼む!」
ドモンに声をかけられたサイ・サイシーは、その面に笑顔を浮かべる。
「ドモンの兄貴も、気をつけて行けよ!」
「こちらは、任せておけ」
アルゴの言葉にドモンも頷き返す。そのままゲートに向かって歩を進めようとした弟に向かって、兄が声をかけできた。
「必ず、帰って来いよ」
「兄さん……!」
振り向く弟に、兄は屈託のない笑みを浮かべた。
「外で待っている、レインちゃんのためにも」
「分かってる」
兄の言葉に対して、ドモンも笑顔で頷いた。
「兄さんの為にも、必ず帰ってくる!」
「―――――!」
知らず目をしばたたかせるキョウジの視界に、ジョルジュにど突かれているチボデーの姿が入って来る。また彼は、何か余計なひと言を口走ったのだろう。
「ではドモン! 行けい!! そして、存分に戦ってくるが良い!!」
「分かりました!!」
ドモンは力強く頷くと、ゲートの中に入って行った。チボデーとジョルジュも、その後に続いた。
「さて! おいらたちも頑張るか!! アルゴのおっさん!! 後れをとるんじゃねぇぞ!!」
「言われずとも」
そう言いながら、二人とも再びモンスターたちとの戦いに戻る。キョウジの横で、東方不敗はゲートに手をかざし続けていた。
(アルゴとサイ・サイシーだけでは、ここの戦力的に少しの不安が生じるのも事実。しかし、ドモンに『独りで行け』と言うのも危険すぎるし………)
かといって、今自分がこのゲートに『気』をやることを止める訳にもいかない。さてどうしたものか、と、思案に暮れる東方不敗の横で、キョウジが何やら猛スピードで何かを作り上げている姿が見える。
まさか、と、思いながらも東方不敗がキョウジに問いかけてみると―――――
「すみません。後少しで、ゲートの『波動』が読み取れますので――――」
「…………!」
一応、キョウジが『優秀な』科学者で技術者である、と言う事は分かっているつもりではいる。しかし、あまりにもその優秀っぷりに、時々裏拳で突っ込みを入れたくなるのは何故なのだろう。
対してキョウジの方は、やる事の多さに知らず眩暈を覚える。だけどここで総てを投げ出して倒れる訳にもいかない。危険を顧みず闇の世界に乗り込んで行ったドモンのためにも。ハヤブサと共に、そこに囚われているシュバルツのためにも。
(お願いだ……! 皆、無事に帰って来てくれ……! 信じているから……!)
ゲートを東方不敗の代わりに固定する装置を作りながら、キョウジはそう祈り続けていた。
皆、彼にとっては失ってはならない、大切な人たちだった。
(ドモン……。キョウジ………!)
閉じてしまった空間の向こうで、懸命に手を伸ばしてくれていた二人の顔を思い出す。
(ありがとう)
勇気がわいた。
戦う勇気が。
剣を構え続ける希望が――――
知らなかった。
自分のことを無条件に思い続けてくれている人がいる、というだけで
人の『ココロ』は、こんなにも励まされるだなんて。
二人がこちらに伸ばして来てくれた手には、それほどの力があった。
(単純なのだろうか)
たったそれだけのことに勇気づけられる自分にシュバルツは苦笑してしまう。
だけど――――
あの手は、確かに自分を強く支えていてくれた。
そうしている間にも、空間に亀裂が走り、広がり始める。隙間から入れる小さなモンスターたちが、結界内に侵入し始めていた。
「………………」
シュバルツは息を大きく吐きながら、静かに抜刀する。
守る。
ハヤブサの身も、自分の身も。
懸命に自分に向かって手を伸ばしてくれたあの二人を、これ以上哀しませたくないと、願う。
「来い!」
迫りくるモンスターたちに向かって、正眼で構えた。
「ギシャアアアアアアッ!!」
シュバルツの声に応えるように、一斉にかかってくるモンスターたち。 その間を、白刃が一閃する。あっという間に最初にかかって行った集団が弾き飛ばされた。
だが、物量で勝るモンスターたちは、次々と波状攻撃を仕掛けてくる。
蹴る。
殴る。
弾き飛ばす。
斬り倒す―――――
四方から襲い来るモンスターたちを、次々と撃退していたシュバルツであるが、隙を見つけて繭となっているハヤブサの身体を抱えて跳躍した。四方八方から襲われる見通しのいいこの場所に、地形的不利を感じたが故だった。
何度かの跳躍を繰り返し、モンスターの群れをかきわけ、目的の場所にたどり着く。
そこは、『龍剣』が封印されている場所だった。
剣を封印している石柱の様な物が、高々と聳え立ち、この世界の天と地を支えているようにすら感じられる。この石柱を背にして戦えば、とりあえず背後から襲われる心配は不要になりそうだった。
シュバルツは『繭』になっているハヤブサの身体をそっと下ろすと、その前に立ち、改めて剣を構えなおした。
守る。
このハヤブサは、何としても守り切って見せる。
大丈夫。
恐れるな。
希望はあるんだ。
『龍の忍者』の完全復活という希望が――――
それさえ果たされれば、自分はもう、ここの世界での『役目』を終えていい。
その後でならば、ここで闇に呑まれようが、ハヤブサに恨まれたまま殺されようが、どうなっても構わない―――――シュバルツは、そう思いかけた。
だがそのたびに
「帰って来てくれ!! シュバルツ!!」
必死に叫んでいたキョウジの姿を
兄弟たちが伸ばしていた手を
シュバルツは思い出す。
「兄さん!! 兄さん!!」
弟が、必死の形相で叫んでいる。
「お願いだから………キョウジ兄さんを独りにしないでくれ!!」
(ああ、本当にそうだな)
自分が見ていないと、何かと口実をつけて、すぐにいろんなことをさぼりたがるキョウジ。
どこか飄々としていて、つかみどころがなくて――――でも、自分と話すときは、心底楽しそうに笑うキョウジ。
彼ほど強くて
でも、彼ほど『孤独』な存在を、シュバルツは他に知らない。
大切だった。
ハヤブサやドモンとはまた違った意味で、特別で、大切な人だった。
その人の「帰って来い」という願いを、自分が踏みにじるわけにはいかない。
シュバルツは強くそう思って、剣を上げ続けていた。
そんなシュバルツが龍剣を封印している石柱の傍で、暫くモンスターたちと戦い続けていた時に――――それは姿を現した。
それは、ハヤブサと戦い続けていた『仁王』であった。
石柱から静かに現れた仁王は、二振りの剣を手に、静かにこちらに視線を合わせてくる。
(まさか……! もう『試練』の時間なのか!? ハヤブサがまだ目覚めていないのに……!)
シュバルツは咄嗟に『繭』になっているハヤブサを見る。ハヤブサの方はピクリとも動かない。昏々と繭の中で眠り続けているようであった。
(どうする!?)
龍剣を手に入れるべきは、『龍の忍者』になるべきなのは、あくまでもハヤブサ。自分が、この仁王と戦う訳にはいかないのだ。
「く………!」
シュバルツは仁王をけん制しながらモンスターたちと戦い続ける。仁王はしばらくそれを静観し続けていたが、その手に持つ刀の切っ先が、ピクリと動いた。
「――――!」
シュバルツの身体は、咄嗟にハヤブサを庇うために動く。戦っていたモンスターを弾き飛ばして、仁王とハヤブサの間に体を入れた。仁王がハヤブサに斬りかかるのを、防ぐためであった。
無言で、突進してくる仁王。
やむを得ずシュバルツは、仁王に対して構えをとる。
振り上げられる仁王の剣。
ダンッ!! と、激しい踏み込み音と同時に振り下ろされたその剣は―――――
「ギャッ!!」
シュバルツに襲いかかろうとしていたモンスターの方を、切り裂いていた。
「……………!」
思わず仁王を見つめるシュバルツ。仁王は無言でその横に立つと、同じく『繭』となっているハヤブサを守るかのように構えをとった。
(そうか………! 仁王はある意味『龍剣の意思を体現する者』であるから――――)
そう。
『龍剣』も待っているのだ。
自分の封印が解かれる瞬間を。
真の主が、自分をその手に取る瞬間を。
だから、仁王がハヤブサを守るという行動は、ある意味当然のものであると言えた。
「よし!」
シュバルツもまた、モンスターたちに対して、改めて剣を構えなおす。それから仁王と視線を合わせると、仁王も頷き返してくれた。
(共に戦おう)
声なき声で、そう言われた気がした。
自分は独りではない。それにこの空間内で、ハヤブサに味方をしてくれる者がいる。そう感じられるだけで―――――何と心強いものなのだろう。
(ハヤブサ……! 何としても、お前を守り切って見せる……! だから、早く目を覚ましてくれ………!)
祈るような思いで、シュバルツはモンスターたちと戦い続けていた。
そんな仁王とシュバルツの戦いを、少し離れた場所から観音像が、涙を流しながら見守っていた。
(リュウ……! リュウ……! 早く、目覚めてください……! もう、時間が………!)
その観音像の上空に広がる空間のひび割れが、ビシッと音を立てて、また、大きく拡がっていった。
(おのれ………! あと少しで………! あと少しで、あの男の心を掌握できていたものを………!)
漆黒の闇の中で『邪神』ラクシャサは、ギリ、と歯ぎしりをしていた。
あのシュバルツとかいう男の心は、もう闇に落ちかけていた。後こちらがほんのひと押しするだけで、生きる気力を失い、絶望して―――――『怨』の術を完成させる最高の『駒』が出来上がるところであったのに。
その寸前のところで、人間たちの呼び掛けにあい、それを邪魔されてしまった。
今、あの男の心には、生きるための『希望』の光が眩いほどに灯ってしまっている。自分からしてみれば、これほど厄介で邪魔なものは他になかった。
(キョウジ・カッシュに、ドモン・カッシュか……! 人間の分際で、どこまでも目障りな奴らめ………!)
邪神の殺気は、今―――――明確にこの二人に向かいつつあった。
邪神のあからさまな『殺意』は、キョウジ達の戦場に、当然のごとく変化をもたらせ始めた。
(何だ……?)
戦場の空気の流れが変わったような気がして、キョウジは顔を上げた。
それまでキョウジは、目立った動きさえしなければ、モンスターたちから標的にされることはなかった。だが今は――――何故かモンスターたちの殺気が、自分の方に集中して向かって来ているように感じられるのは、気のせいだろうか。
「くっ!!」
襲い来るモンスターたちの攻撃を、何とか体を転がしてかわす。しかし、キョウジがそれまで触っていた『装置』が、目の前で壊されてしまっていた。
「あ~~~~~っ!!」
思わず悲鳴をあげてしまうキョウジ。
「どうした!?」
問い返してくる東方不敗に、キョウジは多少ひきつった笑顔を返す。
「いえ……作りかけの方の発電機が壊されてしまったので………」
キョウジの言葉に、東方不敗は「何だ、そんな事か」と、フン、と、鼻を鳴らした。
「そのような物を未練がましく作ろうとするでない! 男だったら潔く、短時間勝負を挑まぬか!!」
「そ、それはまあ、そうなんですけどね……」
キョウジがそう返事をしている間にも、モンスターたちはキョウジに向かって攻撃を仕掛けようとしてくる。
「わっ!! また!!」
すばしっこく器用に、猫のようにその攻撃をかわしまくるキョウジ。だが同時に、「おかしい」とも感じていた。
何故だ?
何故―――――モンスターたちの殺気が、こんなにも自分に集中しだした?
モンスターたちの攻撃を、何とかかわすことはできる。しかしこのままでは――――今まで戦いの合間を縫って出来ていた工作作業を、まるで進める事が出来ない。
「キョウジ!!」
東方不敗も、モンスターたちの動きの変化を敏感に感じ取ったのか、逃げ回るキョウジにぴったりとくっついてくる。
「マスター! 私はいいですから、シュバルツとハヤブサの方を……!」
「何を言うのじゃキョウジ!! お主を守らずして何を守れというのじゃ!!」
「いや、ですから……本来守らなければならないのはあの二人な訳で――――」
キョウジがそう説明している間にも、モンスターたちはキョウジに殺到してくる。東方不敗はことごとくそれを退けていた。
「おのれ!! わしの目の前で我が主に傷をつけようとするなど、100年早いわ!!」
そう言ってキョウジを守る様に構えをとる東方不敗の後ろで、キョウジは頭を抱えてしまっていた。
(どうすればいいんだ……! このままではシュバルツとハヤブサの方まで防御が行き届かない……! あの二人こそ、本当なら守らなければいけないのに――――)
今のところ、サイ・サイシーとアルゴが、あの二人の周りを守ってくれている。だけど、敵も徐々に更に強力な物になりつつあるだけに、今の状態は好ましいものであるとは言えなかった。
ならば、どうするべきなのか。
しばらく思案していたキョウジであるが、やがて、ポン、と、己が柏手を打った。こんなの、考えるまでもなく、己が取るべき行動は一つだと気づく。
モンスターの攻撃がやんだ一瞬の隙をついて、キョウジは東方不敗の影から転がり出ると、猛然とダッシュを開始した。
「あっ!! キョウジ!? どこへ行く!?」
当然それに後れをとるような東方不敗ではないので、彼の後ろにぴったりとくっついてくる。キョウジは東方不敗を引き連れたままシュバルツ達が眠るベッド脇に来ると、そこでくるりと向きを変えた。背後から、標的である自分を追いかけて来ていたモンスターたちと、視線が合う。
「……………!」
攻撃される、と、キョウジが思う間もなく、東方不敗がそのモンスターたちを一蹴した。
「猪口才な!!」
そのままモンスターたちに向かって構えをとる東方不敗。キョウジはほっと胸をなでおろしていた。
(これは、賭けだ)
眠り続けるハヤブサとシュバルツを見つめながら、キョウジは思った。
何故自分が、いきなりモンスターたちの攻撃対象に挙がってしまったのかはわからない。だが、あからさまに狙われている自分。だから本来なら――――戦略的に考えても、モンスターたちの攻撃の対象を分散させるために、自分はこの二人からは、離れるべきなのでは、と思う。
しかし哀しいかな――――自分の腕はモンスターたちと互角に渡り合えるほどではない。そんな自分が「囮」としての役割を担おうとしても、役に立つどころか皆の戦力を分散することになり、却ってその行為は足手まといにしかならないと、キョウジは結論付けざるを得なかった。
それならば、「狙われている者が一点に集まる」というリスクを背負ってでも、守られるべき者どうして固まっているに限ると、そう考えた。
「ぬおおおおおおっ!!」
そして、案の定東方不敗は、自分を守ることを最優先にしながらも、結果的にシュバルツもハヤブサも守ってくれている。今のところこれでいいのかとキョウジは思った。
しかし――――
「まだまだぁ!! かかって来んかぁ!!」
東方不敗が鬼の形相を浮かべながら、阿修羅のごとく奮戦している。このままでは、東方不敗に負担がかかり過ぎているように思えた。でも、その負担を軽くするために、自分は、どうすればいいというのだろう。
「グラビトン・ハンマ――――――ッ!!」
野太い叫び声とともに巨大な鉄球が飛んで来て、周りの敵が一掃される。驚いてキョウジが振り向くと、アルゴ・ガルスキーがその巨体を揺らしながら、のそりとこちらに向かって来ていた。
「サイ・サイシー!! こちらに防御の『陣』を張るぞ!! マスターアジアを援護するのだ!!」
「OK!!」
少し離れた所で戦っていたサイ・サイシーが、アルゴの呼び掛けに明るく応える。近づいてきた二人に、安城というべきか、東方不敗からは怒声が飛んだ。
「フン!! 誰がお主らに援護を頼むと云った!?」
そう言って睨みつけられるが、しかしアルゴも怯まない。
「別にお前のためではない。キョウジ殿とシュバルツ殿と……ドモンのためだ」
「……………!」
「この二人に何かあったら、ドモンが悲しむからな……」
「おいらだって!!」
アルゴの反対側から東方不敗の傍に回り込んできたサイ・サイシーが、元気よく答える。
「お家再興のために、そしてドモンの兄貴のために――――――何よりここは、最高の修業の場だ!!」
二人の言い分を黙って聞いていた東方不敗であるが、やがて、フン、と大きく息を吐くと、改めて敵に向かって構えなおした。
「よかろう!! 二人とも……わしの足を引っ張るでないぞ!?」
「「言われなくとも!!」」
三人のやり取りを黙って聞いていたキョウジであるが、やがてその面に小さな笑みを浮かべた。
(良かった………)
援護を申し出て来てくれたアルゴ。必要とあれば、自分も東方不敗に口添えするつもりでいた。しかし、その必要もなさそうだった。三人は、初めて共闘するとは思えないほど息ぴったりに目の間の敵と戦いを繰り広げている。
これで暫くは持ちこたえられそうだ。しかし………。
「……………」
キョウジはため息を吐きながら、少し離れたところに転がる工具箱を見る。逃げ回る時に、持って移動する事が出来なかった。あれが無いと何もできない。自分が明確な『標的』になってしまっている今、戦いの合間を縫ってあれを取りに行くのは、ほぼ不可能に近かった。そんな事をしたら、ここにいる皆に多大な迷惑をかけてしまう。
(大丈夫だ……。落ちつけ……)
キョウジは深呼吸をして、ともすれば焦りそうになる気持ちを落ち着ける。今の発電機も、あと少なくとも1日半以上は稼働する。すぐにどうこうなることもない。工具箱を取りに行くチャンスも、発電機をもう一度作るチャンスも、必ず来るはずなのだから。
(シュバルツ……! ドモン……! そしてハヤブサ……! 皆、どうか無事で――――)
必ず帰って来てくれ。
闇の世界につながるゲートを見つめながら、キョウジはそう祈り続けていた。
「うおりゃああああああっ!!」
闇の中、ドモンの雄叫びが響き渡る。
モンスターたちの攻撃は苛烈を極めたが、ドモンは特段慌てることもなかった。ここは敵の世界の真っ只中。モンスターたちが大挙して襲ってくるのは、ある意味当たり前でもあったからだ。
ドシャッ!!
モンスターであった残骸が、地面にもろい音を立てて叩きつけられる。それに数体のモンスターが巻き込まれて四散していた。
「ふ~。おっかねぇなぁ」
額の汗をぬぐいながら一息つくチボデーに、ドモンはフン、と、鼻を鳴らしていた。
「そんな奴ら、物の数でもない。それよりも……兄さんはどこだ?」
「闇の世界ですからね……。そんな簡単にはみつからな―――――」
そこまで言ったジョルジュの言葉が止まってしまう。何故なら彼らの目の前に、探していたシュバルツその人が現れたからだ。
「ドモン……」
その人は、優しく微笑みながら近づいてくる。
「兄さん……」
「随分探したぞ……。危ないじゃないか。こんなところまで私を追って来て―――――」
つい、と、その手が、ドモンに向かって伸びて来た、その、刹那。
「ゴッド・フィンガ―――――ッ!!」
いきなりドモンの黄金に輝く右手が、シュバルツの首元に掴みかかった。
「なッ!?」
「ド、ドモン!?」
驚くチボデーとジョルジュを尻目に、ドモンの右手はますます輝きを放ちながら、シュバルツの首元を締め上げていく。
「ぐ………!」
「おのれ偽物!! よくもそんな格好で、俺の前にのこのこと姿を現したな!?」
「――――!?」
「偽物!?」
その言葉が終わると同時に、シュバルツの像がグニャリと歪む。いびつな形をしたモンスターがその正体を現した瞬間。
「ヒート、エンドォッ!!」
黄金の光に首根っこを破壊されたモンスターは、そのまま四散して行った。
「ドモン、大丈夫ですか?」
走り寄るジョルジュに、まだ少し怒気を食んでいるドモンが「平気だ」と、無造作に答えていた。
「それにしてもドモン。よくあれが『偽物』だって、分かったな」
少し感心するチボデーに、ドモンは振り向きもせずに答える。
「当たり前だ!! あんな物が兄さんであってたまるか!!」
「―――――!」
「先を急ぐぞ。この世界の奴らがどんな小細工を仕掛けてくるか分からん。一刻も早く、本物の兄さんを見つけなければ……」
ぶっきらぼうにドモンはそう言い放つと、すたすたと歩き始めていた。
「行きましょう、チボデー」
「ヘイヘイ……っと」
ジョルジュに促されながらチボデーも、ドモンの後に続いた。
それから先の道行きでも、3人はモンスターの群れに出くわす。その中には、シュバルツの姿形をした物も、必ずと言っていいほど混じっていた。
だが、そのたびに。
「ゴッド・フィンガ―――――ッ!!」
ドモンの黄金の右手が、シュバルツの『偽物』を有無を言わさずに粉砕して行った。
「おい、ちょっとドモン!」
あまりにも躊躇なくシュバルツの偽物を討滅していくドモンに、たまりかねたチボデーが思わず声をかけていた。
「なあ、参考までに教えてくれないか? お前はいったいどこで、シュバルツの『本物』と『偽者』を見分けているんだ?」
「確かに、そうですね……」
ジョルジュもチボデーの言葉に同意していた。ドモンがあまりにも迷わずにシュバルツの姿かたちをした物を倒していく姿を見ていると、こちらの方がひやひやしてしまう。もしも、本物のシュバルツが混じっていたら、どうするつもりなのだろうかと。
「よろしければ、私にも教えていただけませんか? そうすれば、我々もぐっと戦いやすくなりますので――――」
「……フン、簡単なことだ」
チボデーとジョルジュの言葉を聞いていたドモンが、おもむろに答えた。
「『本物』ならば、俺のあんな無造作な攻撃が、当たるわけがない」
「……………!」
「避けられない奴は『偽物』だ。ただ、それだけのことだ!」
ドモンの、ある意味ものすごく乱暴な理屈に、チボデーもジョルジュも、空いた口がふさがらなくなるのを感じる。
(い……! いやいやいや、それはそうかもしれないか……! 危ないだろう!? 『本物』だって、調子が悪かったりしたら、攻撃が避けられないことだってあるかもしれないのに………!)
「何考えているんだ!? 奴は……! 本物のクレイジーだな……!」
狂気じみている、と、頭を抱えるチボデーの横で、ジョルジュはある意味、納得もしていた。
「確かに常軌を逸しているようにも見えますが………それだけドモンは、シュバルツの腕に対して盤石の信頼を置いている、と言えなくもないですね……」
ため息交じりに言葉を紡ぎながら、ジョルジュは内心こうも感じていた。ドモンのシュバルツに対する想いというのは、『信頼』というよりも最早『信仰』に近いのではないだろうかと。
それはさすがに口に出すのは憚られたので、黙ることをジョルジュは選択したのだが。
「………『信頼』、ねぇ」
チボデーも何かを含むように、ポツリとそう漏らしたのだが、頭をガシガシと2、3回かきむしると、ドモンにもう一度声をかけた。
「ドモン」
「何だ?」
「じゃあ俺たちも……今度シュバルツの姿をした奴を見たら、遠慮なく攻撃を仕掛けてもいいか?」
「……………!」
ピクリ、と、ドモンの眉が一瞬動くが、「ああ、いいぞ」と、言いながらすたすたと歩き出していた。
実はドモンは、本当はもう一つ、目の前のシュバルツが本物か偽物か、決定的に見分ける手段を一つ持っている。だがそれは、あまりにも腹立たしいから決して口に出すつもりはなかった。それを認めることは、ドモンにとっては非常に癪に障る事であったからだ。
それは何か―――――答えは、簡単だった。
そのシュバルツが、隣に『龍の忍者』であるハヤブサを連れているかどうか。
ただそれだけが、本物と偽物を見分ける、決定的な証拠だと思っていた。
「必ず帰る!」
あの兄は、そう言った。
ハヤブサを連れて、必ず帰るからと。
兄は口に出したことは、必ず実行する人だ。その兄が、ハヤブサを救うために来ているこの世界で、ましてハヤブサと合流しているあの状況で、そこから一人でうろうろしていることなど、まずあり得ない。あの兄ならば、絶対にハヤブサを助けだして、ハヤブサと共に居るはずだ。もしくは、ハヤブサを助けるために、自分の身を犠牲にするか――――
最悪な場合、ハヤブサだけが助け出されて、この世界を独りでうろうろしている可能性だってある。
(……そんな事、させてたまるか……!)
ドモンはギリ、と、拳を握りしめていた。
自分は、兄を助けだすためにこの世界に来ているのだ。例え世界のために兄がその身を犠牲にしようとしても、自分は断固として、それを拒絶する。何が何でも兄を助けだす。それが出来ずして、何が『キング・オブ・ハート』か。
(……見てろよ……! シュバルツの偽物はぶん殴る! ハヤブサは、見つけ次第何が何でもぶん殴る!!)
まったく何だってんだ。
ハヤブサの奴、兄さんにつき纏って、あまつさえ、余計な苦労を背負わせやがって………!
こんな按配で、後から後から腹の底から湧いてくる怒りの虫が、どうにもこうにも収まらない。
「兄さんは、俺だけのものだ―――――ッ!!」
闇の世界の中心で、訳の分からないことを叫ぶドモンを、チボデーとジョルジュも呆れかえりながら見守るしかなかった。
「……もしも、『ブラコン世界一決定戦』とかいう大会があったなら……あいつは間違いなく『キング・オブ・ブラコン』だな………」
ポツリと零されるチボデーの言葉を、ジョルジュもさすがに否定できないで苦笑を返すしかなかったのだった。
(おのれ……! いったいどうなっているのだ!? これは………!)
邪神ラクシャサは、漆黒の闇の中でその見えざる拳をきつく握りしめていた。
全く以って予想外だ。龍の忍者以外にあれだけ腕の立つ人間が、この世界にいたとは。
仕留めたいのはキョウジ・カッシュとドモン・カッシュ。それは揺るぎない。この二人を殺す事が出来れば、今行われている人間たちの抵抗など、雲散霧消することは目に見えている。
だからそれを実行したいのだが。
「おのれッ!! 我が主を害そうなどと、このワシが許さん!!」
キョウジ・カッシュの前に立ちはだかる男が、こちらの攻撃をことごとく跳ねのけてしまっている。所詮は多勢に無勢だと、モンスターの数で押しているのだが、男の気力は消耗するどころか、逆に跳ねあがっていくばかりだ。
おまけにこちらの世界に入ってきたドモン・カッシュはというと――――
「偽物は飽きたッ!! 本物はどこだぁ!!」
繰り出していくモンスターたちを次々と撃退しながらまっすぐ突き進んで来ている。全く躊躇のないあの攻撃の仕方。まるで、『近づく者皆ぶん殴る』と決めているような節さえ感じられる。
何故だ?
人間はみな――――大切に思う者が近づいてきたら、攻撃を止めるのではないのか? あんなに躊躇なく拳を振るえるものなのだろうか?
もしも、そうではないというのなら、あのドモン・カッシュという男には、シュバルツの本物と偽物を区別する明確な指針を持っている、ということになる。
だとしたら、それは何だ?
どこで奴は、本物と偽物の区別をつけているというのだろう。
「この、『キング・オブ・ハート』の紋章にかけて!!」
「この戦い!! 絶対に負けられんっ!!」
空間を超えて、師弟の手の甲に、同じ『キング・オブ・ハート』の紋章が輝きだす。
「ドモンの兄貴が頑張ってる!!」
「そうだ!! 俺たちも!!」
東方不敗の傍で戦うサイ・サイシーとアルゴの手の甲にも。
「負けてらんねぇ!! 敵をぶちのめす!!」
「退けぬ戦い!! それは我らも同じこと!!」
闇の世界で戦うチボデーとジョルジュの手の甲にも、同じく『シャッフル同盟』の紋章が輝きを放ち始めていた。
今――――紋章の輝きが時空を超えて共鳴をして、戦う男たちの力を最大限にまで引き上げようとしていた。
(おのれ………!)
邪神・ラクシャサは焦り始めていた。
このままでは龍の忍者の身体を拠り代にするどころか、自分自身が内面から破壊されかねない。それほどまでの勢いを、人間たちから感じつつあった。
(何か手はないのか……! 人間たちの勢いを崩す、何か手は――――!)
闇の中、邪神は懸命に、人間たちにつけ入る隙を探し続けていた。
観音像の張った結界は、ボロボロと崩れつつある。
その中でシュバルツと仁王は、龍の忍者の繭を守りながら、懸命に戦いを続けていた。
襲い来るモンスターたちは徐々に強く、物理的にも精神的にもその凶暴さと邪悪さを増して行っていた。
「まだまだぁ!!」
シュバルツは襲い来るモンスターたちを、それでもことごとく退け続けていた。
帰る。
帰るんだ。
キョウジの元へ。
ドモンの元へ。
ハヤブサを連れて――――!!
涙を流し続けている観音像。
感じる。
観音像の祈りが。
キョウジの心が。
ドモンの声が――――。
それは私に、勇気をくれた。
「……………!」
ふと後ろを振り返ると、ハヤブサの『繭』にひびが入っているのが見える。
きっと、龍の忍者が覚醒するまで、あと少し。
仁王像もそれを感じているようで、時折ハヤブサの方に視線を走らせては、シュバルツの方を見て頷いてくる。その所作に、少し嬉しそうな色が混じっているのは気のせいだろうか。
そうだ。龍剣も待っている。
『真の主』に手に取ってもらえる日を、心待ちにしている。
だから、早く
早く帰って来い。ハヤブサ―――――
――――龍ノ忍者ガ龍剣ヲ手ニ入レタラ………ソノ後、オ前ハドウスルツモリダ……?
不意に、誰かの声が心に響く。
シュバルツはその声に律儀に答えた。
(知れたこと。この世界から、ハヤブサと一緒に出るのみだ)
――――龍ノ忍者ガ、オ前ヲ『仇』ト憎んでイテモカ………?
「――――――!」
シュバルツは一瞬眉をひそめるが、すぐに顔を上げた。
(ハヤブサが龍剣を手に入れさえすれば、それでいい)
それ以上にも以下にも、シュバルツは望みがなかった。だからシュバルツは、迷わずそう答えた。
――――ナラバ、オ前ハモウ『用済ミ』トイウワケダナ……
「…………!」
痛いところをつかれたシュバルツは、ぐっと言葉に詰まる。その『声』は、更にたたみかけてきた。
――――ダガ、祝ウベキ事デモアル……。ヤット、アノ龍ノ忍者ヲ、オ前ノ持ツ『闇』カラ解放デキルノダ。ソウダロウ……?
違うと叫びたい。
だけど、叫べない自分をシュバルツは感じてしまう。
確かにそうなのだ。
今――――ハヤブサは完全に自分のことを忘れてしまっている。
それならば
それならば、いっそ、このまま
このまま―――――自分は忘れ去られてしまった方が、ハヤブサのため―――――
それは、日ごろから心の片隅で考えていたことでもあった。
自分が、自然のものから生まれたものではない、いびつな存在であったが故に。
キョウジの前から
ドモンの前から
ハヤブサの前から――――
消えてしまったほうがいいのではないかと、そう考えることがないわけではなかった。
だけどそれをしたら、酷く悲しませてしまう人たちがいる。
シュバルツにもそれがわかっている。だから、普段はなるべく表には出さぬよう、それは心の奥深くにしまわれていたものであったのだが。
だが、その『声』によって心の奥底がかき乱され、ふっとその考えが表に出てきてしまった。
そう。
自分さえ消えれば。
自分さえ、消えてしまえれば―――――
(——―――捉えた!)
時間にして、シュバルツが闇に捕らえられたのはほんの一瞬。だがその一瞬は、ラクシャサにとっては十二分な時間だった。ハヤブサを闇に落とすための最高の『駒』を手に入れるべく、ラクシャサは手を伸ばす。
動きが止まってしまったシュバルツ。捕らえるのは容易いように思えた。
しかしここで、ラクシャサにとって思わぬ邪魔が入ることになる。
だれあろうそれは、隣で戦っていた『仁王』であった。
仁王は、もともと『龍剣』の化身。だから、仁王にとって、主であるハヤブサを守る行為は、ある意味当然なものであるといえた。
だが仁王は、シュバルツに危機が迫っていると悟った瞬間、勝手にその体が動いてしまっていた。
シュバルツに対して『恩』があるわけでも
『義理』があるわけでもなかった。
ましてや、主と認めているわけでもなかった。
しかし―――――
ハヤブサと自分が戦っている間、じっと真剣にこちらを見つめていたシュバルツ。
それが、ハヤブサに剣の稽古をつけるとき、仁王である自分の動きを、完璧にその身に宿すことにつながっていた。
その真摯な剣に対する姿勢に、心動かされたのだろうか。
『情』が移ったのだろうか。
それは、仁王自身にも最早わからない。
だが、体は勝手に動いていた。
ガキッ!!
「―――――!」
自分のすぐ背後で響いた剣撃音に、シュバルツははっと我にかえる。
振り向くと、仁王が自分のすぐ背後で、自分を庇うように立ち、いずこからともなく攻撃を仕掛けてきた黒い触手のような物を、剣ではじき返している姿が視界に飛び込んできていた。
「すまん!」
図らずも仁王に庇われたと悟ったシュバルツは、慌てて戦いに戻る。振り返り仁王に礼を言うと、仁王は『気にするな』と言わんばかりに片手を上げた。自分を庇ってもどこもけがをしていない様子の仁王の姿に、シュバルツもほっと胸をなでおろす。
(よかった……。それにしてもどうしてしまったんだ? 私は……! 戦いの最中に『気』を抜くなど………!)
あからさまに動きを止めて、ぼうっとしてしまっていた自分。いったいどれくらいの間そうしてしまっていたのだろう? こんなことは、絶対にやってはいけないことだ。幸い、あの『仁王』に助けられたからよかったようなものの――――
そう、助けてくれた。
自分は、あの仁王に助けられたのだ。
何故だろう。
あの仁王に自分を助ける理由など、あろうはずもないのに。
(後で、仁王にもハヤブサにも、礼を言わねば)
シュバルツがそう思って、ハヤブサのほうに振り向いた、その瞬間。
悲劇は、突然起きた。
いきなり、肩から背中にかけて、肉を切り裂かれるような痛みに襲われる。
「うあっ!?」
敵は近くにはいないはずだった。周囲の安全にも気を配って、それからハヤブサのほうに視線を動かしたはずであるのに。
なのに何故―――――!
驚いたシュバルツが振り返ると、苦悶の表情を浮かべながら、シュバルツに向けて刀を構える仁王の姿が、その視界に飛び込んできていた。
「な…………!」
仁王は苦しそうに、その手に持つ剣の切っ先を震わせている。そしてその腹には、どす黒く禍々しい光を放つ、触手の一部のような物がめり込んでいた。
(これは――――!)
シュバルツはすぐに悟った。
仁王のこの腹の傷は、先ほど自分を庇ったときに、自分の身代わりに受けた傷なのだと。
そして、今自分に向けて刀を構えている、仁王のその動きは
仁王自身の意思によるものではないのだと。
「―――――!?」
そのころ、シュバルツの眠るベッド脇で佇んでいたキョウジも、異変に気付いていた。
眠るシュバルツの表情が、一瞬苦しそうにしかめられたかと思うと。
ジワリ、と、寝台の上から液体のような物が、床に向かって伝い落ちてくる。
「な…………!」
キョウジは慌てて寝台の布団をめくり、シュバルツの体を見る。寝台は液体でびしょぬれになっていた。ガバッとシュバルツの体の向きを強引に変えると、シュバルツの方から背中にかけて、袈裟懸けのように切り裂かれた傷が。
「シュバルツッ!!」
キョウジはたまらず悲鳴のような声を上げていた。
「どうした!?」
キョウジの叫びに、東方不敗が敏感に反応する。東方不敗が振り向くと、途方に暮れたような表情を浮かべるキョウジと、視線が合った。
「シュバルツが………! シュバルツが、傷を………!」
「傷だと!?」
返事をしながら東方不敗は首を捻る。この戦いの最中、シュバルツが傷を負うようなことは、一切無かったはずだ。それが、何故このようなことに――――?
「きっと、あちらの世界で、シュバルツに何かあったんだ………!」
キョウジの言葉に、東方不敗もなるほど、と、納得する。
「ガタガタ騒ぐでない、キョウジ。戦っておれば、傷の一つや二つ、作ることもあるだろう」
キョウジに、というよりは、自分に言い聞かせるつもりで、東方不敗は口を開いた。戦いの最中に心乱されることは禁物であった。動揺より生じるわずかな隙が、一歩の遅れとなり、致命傷にもつながりかねないからだ。
「それにシュバルツは『不死』のはず。少々傷を負ったところで、そのように騒ぎ立てる必要もなかろう?」
シュバルツの身体の成り立ちを熟知している東方不敗は、そう言ってキョウジを落ち着かせようとする。しかしキョウジは、その言葉に頭を振った。
「治っているのなら、私も悲鳴を上げたりはしません……! でも、この傷は――――」
「………! 治っておらんのか!?」
東方不敗の言葉に、キョウジは黙って頷いていた。
(治りそうにないな………)
はっ、はっ、と、小刻みに息をしながら、シュバルツは背中の傷の状態を分析する。
戦いの最中に傷を受けるのは日常茶飯事なので、シュバルツも、自分の傷の状態を素早く把握することができた。この傷は致命傷ではない。しかし、いつもなら自身の傷を勝手に治し始める『DG細胞』の自己再生能力が、なぜか働いていないように感じられた。どうやら、何か特殊な力を伴った攻撃を、受けてしまったようであった。
シュバルツの視界に、苦し気に頭を振る、仁王の姿が映りこむ。
(私のせいだな………)
攻撃を仁王から受けたシュバルツ。しかし、彼はその仁王を、恨む気にはなれなかった。
何故なら仁王は、自分を助けてくれた。その身を挺して、自分を守ってくれたのだ。
そのせいで、仁王が今まさに苦しんでいるというのなら―――――
それは紛れもなく、自分のせいだとシュバルツは思った。
(助けなければ)
強く思う。
この仁王の姿は、本来なら自分がこうなるはずだったものなのだから。
しかし、助けるためにはどうすればいいというのだろう。
「く…………!」
刀を上げ、思考をしようとする。だが、背中の痛みと熱が、その思索の邪魔をした。
(ハヤブサ……! キョウジ……! ドモン……!)
悲しませたくない人たちの名を呼びながら、シュバルツはともすれば頽れそうになる膝を、懸命に立たせ続けていた。
「シュバルツ!! シュバルツ!!」
キョウジは懸命に呼びかけ続ける。そうしている間にも、シュバルツの表情は苦しそうに歪み、傷口から溢れ出た液体は床に伝い落ち続けていた。
(そうだ……! とにかく……! とにかく、治さないと……!)
シュバルツが自力で治せないというのなら、自分が治すしかない。キョウジはとっさに手元の工具箱をまさぐろうとして―――――
「あ…………!」
肝心の工具箱を、敵の真っただ中に置いてきてしまったことに気付く。
シュバルツのために、それを取りに行きたい。しかし――――
バシッ!!
自分が少しでも前に出ようものなら、モンスターたちからの攻撃が自分めがけて雨あられと降り注いでくる。とても工具箱を取りに行けるような状況ではない。工具箱を見つめながら歯噛みしていると、東方不敗が声をかけてきた。
「キョウジ!! お主ならシュバルツを治せるのではないのか!?」
東方不敗の問いかけに、キョウジは頷く。
「たぶん、治せると思います。ですが――――」
キョウジの目線の先にあるものを東方不敗も見つけて、「道具箱か……」と、納得した。
「待って居れ、キョウジ! それぐらい、いまわしが――――」
東方不敗はそう言って、道具箱に向かって一歩、踏み出そうとする。すると、モンスターたちの攻撃が、自分ではなく背後のキョウジに向かって殺到するのを感じ取った東方不敗は、慌てて元の位置に戻った。
「ぬうううっ!!」
白い布を振り回しながら、モンスターたちの触手やら剣戟やら弾丸のようなものを弾き飛ばす。自分はキョウジを守りたい。そしてその意思を叶えたいと願っている。しかし、自分がここを離れたばかりにキョウジがやられてしまっては、それこそ本末転倒ではないか。
「キョウジ殿!! シュバルツ殿がやられたのか!?」
「シュバルツのおっさんがどうかしたのか!?」
そのころになって、キョウジを守るように東方不敗を援護していたアルゴやサイ・サイシーにも、背後に起きている異変が伝わる。もう少し平和な時であったならば、サイ・サイシーの「おっさん」発言に誰かから何がしかのリアクションがあったであろうが、酷く差し迫った状況であったため、それは、華麗にスルーされていた。
「あちらの世界で、シュバルツが怪我をしたみたいなんだ……! それが、シュバルツ本人では治せない類の物らしくて―――――!」
「――――!」
「キョウジ殿では治せないのか!?」
アルゴの問いかけに、キョウジは頷いた。
「たぶん、治せると思う……。でも、そのためには道具が――――」
キョウジが悔しそうに視線を走らせるその先に、道具箱を見つけた二人は、当然それを取りに行こうとする。
しかし――――
「くそっ!!」
モンスターたちの攻撃が苛烈すぎて、とても前に進めるような状況ではなかった。サイ・サイシーが悔しそうに舌打ちをしているその横を、アルゴがズイ、と、前に進み出ようとする。
「アルゴ!! 『ガイア・クラッシャー』を撃つこと、まかりならんぞ!!」
アルゴの意図をいち早く察した東方不敗が叫んでいた。
「…………!」
少し不満げに東方不敗に視線を走らせるアルゴに、キョウジも頼み込む。
「私からも頼む……! これ以上ここのシステムにダメージを与えることはできないんだ。町の外に張り巡らされている結界、ハヤブサの延命装置、その他諸々の備えに対する電源が今絶たれてしまったらどうなるか――――分かるだろう!?」
「……………」
キョウジの言葉に、アルゴも納得せざるを得ない。しかし、『ガイア・クラッシャー』を使えないとなると、あの道具箱まで、どのように足を延ばしていけばいいというのだろう。
「シュバルツ!! シュバルツ!!」
3人の男たちがこの状況に歯噛みをしているその背後で、キョウジは懸命にシュバルツに呼びかけ続けていた。
このまま彼を失いたくない――――その願いを込めて、必死に叫んでいた。
兄の叫ぶ声は、時空を超えて、闇の世界を疾駆する弟の耳に届いていた。
「兄さん!?」
ぎぎっと足を止めて、獣のように鋭い目つきであたりを睥睨するドモン。
「どうした!?」
「シュバルツさんが見つかったのですか!?」
聞いてくるチボデーとジョルジュにドモンは振り返りもせずに答える。
「違う!! だが、今……確かに兄さんの声が聞こえた!」
がるるるる、と、唸り声すらあげそうなドモンの様子に、チボデーは少し呆れてしまう。だがドモンは、ひたすら兄の気配を探すようにあたりを見回していた。
「兄さん……! どこだ……?」
その声に応えるかのように、微かだがキョウジの声が聞こえてくる。
「………ルツ! ……シュバルツ!」
「兄さん!? 兄さん!!」
「………! ドモンか!?」
兄弟たちの意思が通じ合った瞬間、ドモンの前にキョウジのヴィジョンが現れた。
「兄さん!? どうした!?」
「ドモン……! シュバルツは見つかったのか!?」
「いいや、まだだ! 今探している――――」
ここまで言ったとき、ドモンは、キョウジの顔色がひどく悪いことに気が付いた。
「兄さん!? どうしたんだ!? シュバルツに何かあったのか!?」
「……………!」
いきなり核心を突いてくるドモンに、キョウジは瞬間言葉を失う。このまま真実を話していいものかどうか迷った。もしも、シュバルツの危機に、ドモンが動揺する、もしくは暴走するかしてしまったら――――
だが次の瞬間、キョウジはブン、と、頭を一つ振った。
ドモンはもう、昔の甘えてばかりの弟ではない。数々の経験を経て、一人前の戦士になっているのだ。そして何より、弟を信頼して、この闇の世界に彼を送り出したのは自分だ。迷っている場合でも、兄としての体裁を取り繕っている場合でもないと思った。
だから、キョウジがいうべき言葉は一つだった。
「………ドモン!」
「兄さん!」
「助けてくれ!!」
「――――!」
ギョッと目をむくドモンに、キョウジはさらに言葉をつづけた。
「シュバルツがそちらの世界でどうやら怪我をしているみたいなんだ……! それが、自力では治せないものらしくて………!」
「な―――――!」
「キョウジさんでも治せないのですか!?」
問いかけてくるジョルジュに、キョウジは軽く首を振る。
「わからない……。でも、できうる限り治す努力はするつもりだが―――――」
「なんてこった……!」
ジョルジュの横で、チボデーが舌打ちをする。その横から、ズイ、と、ドモンが進み出てきていた。
「わかった! 絶対にシュバルツを探し出す!! で、兄さん!! シュバルツを見つけたら、俺たちはどうすればいい!? 何か治療のためにできることはあるか!?」
シュバルツの危機を聞いても、冷静に対応してきた弟の様子に、キョウジは小さく胸を撫で下ろした。やはり弟は、数々の修羅場を潜り抜けて、もう、一人前の戦士になっている。
「怪我をしているシュバルツを見つけたら、可能な限り速やかに、こちらの世界に連れてきてほしい」
キョウジ曰く、今シュバルツは、精神と体が分離してしまっている状態にあるという。
だから、その状態が治れば、DG細胞が持つ自己治癒能力が高まって、治せる確率もずっと高くなるはず――――というのが、キョウジの読みだった。
「わかった!」
「O.K!! 任せな!! 兄さん!!」
「シュバルツさんは、必ず見つけ出して見せます!!」
「ああ。頼む」
キョウジの言葉に、全員が頷き返す。これからの行動指針が固まった。
「よしっ!! 急いでシュバルツを見つけるぞ!!」
「しかし……この闇の世界の中、どうやってシュバルツを探し出せばいいんだ?」
「そうですね……。せめて何か、手掛かりのようなものがあれば――――」
考え込む3人に、声をかける者がいた。
「焦るな、ドモン。こういう時こそ、『明鏡止水』だ」
「―――――!!」
ギョッと顔を上げる3人の視線の先に、キョウジの微笑んだ顔があった。
「――――て、シュバルツならこう言うんだろう?」
「あ………!」
「確かにそうだよな……」
「我々としたことが……焦って、見失うところでしたね……」
皆でそう言って笑いあう。場の空気が、少し和んだ。
「兄さん! 待っててくれ……! 必ず、シュバルツを助け出すから……!」
ドモンの言葉にキョウジが頷く。そして、彼のヴィジョンは闇の向こうに消えた。
「……よし! もう時間的猶予もない。皆、今から早急にシュバルツを探すぞ!」
ドモンが皆のほうに向きなおって、声をかける。
「しかし、どうやって――――?」
問いかけるチボデーに、ドモンは迷いなく答えた。
「『明鏡止水』の発動だ」
「―――――!」
「兄さんがヒントをくれた……。もともと我ら『シャッフル同盟』は、戦いの行方を見守る役目を与えられている者。『明鏡止水』を発動させて、なおかつ『戦いの波動』を感じ取ることができる『紋章の力』を最大限に発揮させれば――――」
「………! なるほど……! 『戦いの波動』が出ているところにシュバルツさんがいる、ということなのですね!」
ジョルジュの言葉にドモンも頷く。
「ああそうだ。この世界で戦っている者と言ったら、おそらく俺たちかシュバルツか――――最悪、ハヤブサの野郎ぐらいのものだろうからな!」
「なるほど、考えたなドモン!」
にやりと笑うチボデーに、ドモンもフン、と、鼻を鳴らした。
「時間がない。とにかく急ぐぞ」
3人は、誰からともなく手を取り合い、一つの小さな輪になる。
「では、始めよう。皆、全神経を――――紋章に集中させてくれ!」
「応っ!!」
闇と静寂の中、佇む3人の男たち。
だが、その外から見える静かな様子とは裏腹に、男たちの神経は極限まで集中し、研ぎ澄まされていた。やがて、皆の右手の甲に、各々が持つ『シャッフルの紋章』が浮かび上がってくる。
紋章の発露―――――それと同時に、3人の男の身体から溢れ出す、眩いまでの黄金の輝き―――――
それはあたかも、この空間に一つの太陽が生まれたが如くであった。闇の中、その輝きを見つめていたモンスターたちも、その光の勢いに押されて近づくことができない。
いや、それでも近づいていくモンスターも当然いた。しかし、男たちのそばに到達する前に、光の力に撃たれ、引き裂かれていく。結果モンスターたちは、ただ遠巻きに見守ることを選択せざるを得なくなっていた。
(兄さん……! どこだ……? 兄さん……!)
己が体から発する光が、モンスターを引き裂いていることにすら気づかぬドモンは、必死に兄の気配を探し続ける。そして、張り巡らされた紋章の力は、やがて、遠くの方に、小さく輝く淡い光を捉えた。そして、その中に、背中に大きな切り傷を作って、苦しげに刀を構えるシュバルツの姿が―――――
「兄さんッ!!!!」
それと認めた瞬間、ドモンは猛ダッシュを開始した。
「うぉっ!? ドモン!?」
「我々も行きましょう!!」
そしてその光景は、チボデーとジョルジュにも見えていた。彼らも間髪入れず、ドモンの後を追い始めたのだった。
「く…………!」
乱れがちになる呼吸を、何とか整える。
霞みがちになる視界に、何度も頭を振った。
今倒れるな。
今倒れてはだめだ。
シュバルツは、懸命に自分に言い聞かせていた。
自分の背後でハヤブサの『繭』が、もう半分破れかけている。きっと、龍の忍者の完全復活まであと少し。あと少しなのだ。
目の前で仁王が苦し気に呻いている。
震える切っ先がハヤブサの方に向こうとするのを、自身で何度も押しとどめていた。
(仁王に、ハヤブサを討たせてはだめだ)
仁王の願いは、ハヤブサを守ること。
龍の忍者となったハヤブサに、再び龍剣を取ってもらうこと。
そのために、今までハヤブサを見守ってきたのだ。
それなのに、私の代わりに敵からの攻撃を、その身に受けてしまって――――
それを、邪悪な力に捻じ曲げられて、自らの手で踏みにじるような真似など、絶対にさせてはならないと思った。
何とかしたい。
できうるならば、仁王も助けたい。
だがそのために、自分が出来ることは何だ。
その手段を考えたいのに、痛みと熱が邪魔をしてくる。
シュバルツは内心舌打ちをしていた。
いつもならば、頼みもしないのに勝手に治してくるくせに。
どうしてこう肝心な時に、治ろうとしないのだろうかこの身体は―――――!
(………ルツ! ……シュバルツ……!)
――――キョウジ!?
微かだが、シュバルツの耳がキョウジの声を捉えていた。こちらの身を案じるように、懸命に叫び続けるキョウジの声を――――
そうだ。死ねない。
死ぬわけにはいかない。
待っていてくれる人がいる。
帰らなければ、哀しませてしまう人がいるのだから――――
(キョウジ……! 案ずるな……。必ず帰るから――――)
約束したのだ。
自分は
キョウジと
それを、違(たが)えるわけにはいかない。
かすかに聞こえるキョウジの声を支えとするように、シュバルツは剣を上げ続けていた。
「シュバルツ!! シュバルツ!!」
キョウジは懸命に、シュバルツに呼びかけ続けていた。それをやめてしまったら、シュバルツに二度と会えなくなる。そんな予感が、彼を突き動かしていた。
「…………!」
自分が呼びかけるたびに、眉をひそめて、苦しそうに呻くシュバルツ。
きっと、聞こえている。
私の声が、きっと彼には聞こえているんだ。
治してあげたい。
すぐにでも。
しかし―――――
「……………っ!」
キョウジは歯を食いしばりながら床に転がる工具箱を見つめる。距離にしてわずかなのに、それが、恐ろしく遠くに感じられた。
もちろん、前面で戦っている東方不敗やアルゴやサイ・サイシーも、今の事態がわかっている。皆が皆あの工具箱を取りに行きたいと願っているが、キョウジや眠るハヤブサたちへの身体に対するモンスターたちの攻撃が凄まじく、なかなかその隙を見出すことができない。
だが、いつまでもこのままで良いわけがないのもまた事実。少しモンスターたちの攻撃が緩んだ瞬間、サイ・サイシーは決意を固めた。
「………おいらが行くよ」
「サイ・サイシー!?」
「マスターアジア! アルゴ! おいらには構わないで! 兄ちゃんたちを守ることだけに集中してくれ!」
そういうや否や、サイ・サイシーの小さな身体が、あっという間にモンスターの群れの中に突っ込んでいく。
「サイ・サイシー!!」
「アルゴ!! 気を抜くでない!! 横ががら空きになるぞ!!」
「――――!!」
そう。サイ・サイシーが退いた分、二人にかかってくる守備的負担は増える。東方不敗とアルゴは、それをカバーするかのように動き回らなくてはならなくなった。
「へっ!! あ~らよっと!!」
モンスターたちの間に突っ込んでいったサイ・サイシーは、その小さな体を生かしながら、ちょこまかと素早く動き回り、モンスターたちの攻撃を器用に躱していく。何体かのモンスターを殴ったり蹴倒したりしながら、サイ・サイシーは工具箱のところまで、何とかたどり着いた。
「キョウジの兄(あん)ちゃん!!」
「――――!」
振り向くキョウジの視界に、工具箱を高々と掲げるサイ・サイシーの姿が。
「受け取って!!」
ポン、と、高々と放り投げられる工具箱。それと同時に、サイ・サイシーの小さな姿がモンスターたちの中に飲み込まれていった。
「サイ・サイシーッ!!」
「キョウジよ!! 工具箱から目を離すでない!!」
東方不敗の怒鳴り声に、キョウジもはっと我に返る。キョウジが見上げると、星空の下、月明かりに照らされた工具箱が、放物線の最高点に達して、ゆっくりとこちらに向かって降りてきている。
そして、それをモンスターたちが手をこまねいてみている訳はなかった。その工具箱を叩き壊そう、奪い取ろうと、ありとあらゆる攻撃を仕掛けてくる。
「ぬううううっ!!」
それを東方不敗が白い布一本で対応し、一蹴していた。その近くで、アルゴが四方八方から襲い掛かってくるモンスターたちに、獅子奮迅、八面六臂の働きで対応している。
「――――ッ!」
キョウジもまた、モンスターの飛び道具にかすり傷を負った。だが、工具箱に向かって手を伸ばすことを、彼は決してやめたりはしなかった。
伸ばした手の先に、工具箱がゆっくりと落ちてくる。4メートル、3メートル、1メートル、50センチ……
バシッ!!
軽快な音を立てて、工具箱がキョウジの手に収まる。
「よしっ!!」
全員の声が重なった。
「サイ・サイシーは!?」
「分からん、あ奴はどうなった!?」
キョウジの声に東方不敗が案ずるように辺りを見回す。その時アルゴが、巨大な鉄球を敵の一角に向けて投げつけた。
「グラビトン・ハンマ―――――ッ!!」
ドカッ!!
派手な音を立ててモンスターの群れの一角が破壊される。
「うひゃっ!!」
その下からサイ・サイシーがそろそろと這い出てきていた。
「ふい~~~! おっかなかった~………!」
「大丈夫か!? サイ・サイシー!!」
キョウジの問いかけに、サイ・サイシーが頷く。
「おいらは大丈夫! それよりもキョウジの兄ちゃん!! シュバルツの方を早く!!」
「分かった!! ありがとう!!」
キョウジは笑顔で頷くと、シュバルツの方に向き直る。工具箱を手早く開けると、早速中から道具を取り出して、シュバルツの身体を直し始めた。もうこうなると、キョウジは近くに矢玉が飛ぼうが爆弾が破裂しようが、全く気にも留めなくなる。相変わらず、凄まじいまでの集中力だ。
キョウジがその作業に入ったのを見届けてから、サイ・サイシーはようやく自身の肩口の傷を抑えた。
「痛ててててて………」
「大丈夫か?」
アルゴの問いかけに、サイ・サイシーはにこりと笑う。
「平気だよ。これぐらい」
「………………」
「ドモンの兄貴だって頑張っているんだから―――――」
そういうサイ・サイシーの右手の甲に、『シャッフルの紋章』が浮かび上がっていた。闇の世界のドモンたちの紋章に呼応して、輝きを放っているようだった。
「確かにそうだな………」
アルゴもまた、シャッフル同盟の一員。己の紋章の輝きに、同じことを感じているようだった。
「よいか皆の者!! ここが戦いの正念場じゃ!! 気を引き締めてかかれい!!」
「応ッ!!」
戦う男たちの士気は、今―――――最高潮に高まっていた。
「―――――!?」
背中に伝わってくる暖かい感触に、シュバルツの身体が瞬間びくっとはねた。それと同時に、背中の傷が少しずつだが塞がってくる感触も得る。
(これは………キョウジ!?)
傷口から流れ込んでくる、懸命な想い。暖かい想い。
その力強さは―――――確かに、シュバルツの背中を支えてくれていた。
(ありがとう……キョウジ……)
敵と戦いながら、シュバルツは心の中で手を合わせる。
私は大丈夫だ。
まだ、戦い続けることができる。
だからハヤブサ。
あとはお前だけなのだ。
その繭から出て来い。
早く
早く―――――
その時、剣の切っ先を震わせ、あがき続けていた仁王の―――――瞳の色が変わった。
まるで血の色のような紅。
仁王の精神が、邪悪なものに完全に乗っ取られようとしているのが分かった。
「駄目だ!!」
シュバルツは咄嗟に、仁王とハヤブサの間に体を入れて、その攻撃を防ぐ。だが負傷をした彼の身体では、防御するので精一杯だった。
仁王とハヤブサは、いずれ決着をつけねばならないと思う。
だがそれは、『今』ではない。
邪悪に憑りつかれた仁王が、繭のままのハヤブサを斬ってしまう―――――こんな結末だけは、絶対に迎えさせてはならないと思った。
どうすればいい?
どうすれば、仁王を邪悪から解放してやれるのだろうか。
(やはり、あの腹に刺さった触手か……?)
シュバルツは、刺さった仁王の腹に根を広げようとしている、触手のかけらを見る。素手で無理やり引き抜くことも考えたが、DG細胞で構成されているこの身体で、触手に直接触れることはためらわれた。それをして、あの触手が持つ強烈な『負』の力にDG細胞が引っ張られてしまったら、それこそ自分の身体がどうなってしまうのか分からない。そんな最悪な事態に陥ることだけは、絶対に避けねばならぬとシュバルツは思った。
ならば、『明鏡止水』を発動して、刀であの触手を粉砕する選択肢が正しいのであろうが―――――
(く…………!)
身体を襲う、焼け付く痛みと熱。
いくらキョウジに治療をされ、背中を支えられているとはいえ―――――
モンスターたちに間断なく襲われているこの状況では、ハヤブサの繭と己が身を守ることで正直精一杯だ。明鏡止水を発動して、あの触手だけを切り刻むことは、かなり困難なことのように思われた。
(だが……やらねば……)
シュバルツは歯を食いしばった。
あの仁王を倒すべきなのは、あくまでもハヤブサ。自分がそれに手を出してしまってはいけないのだ。それをしてしまったら、今までの皆の努力が、それこそ無に帰してしまう―――――そんな、予感がしていた。
だから、これは最早『できる、できない』の問題ではない。何が何でもやらねばならぬ命題なのだ。
(せめて……私にもう少し、『力』があれば………!)
ドモンに宿る、シャッフルの紋章の力でもいい。
ハヤブサに宿る、龍の力でもいい。
せめて、力があったなら
せめて、人間であったなら―――――
今ここで迎える事態も、少し違ったものになったのだろうか。
ブン! と、シュバルツは頭を振った。
無いものねだりをしても仕方がない。自分は自分でしかない。やれることを、やるしかないのだ。
「く…………!」
背中にキョウジの意思を感じる。
「生きろ」という力強い意志。
大丈夫。
これを感じられるうちは、頑張れる。まだ、戦うことができる。
集中―――――
とにかく、集中だ。
モンスターたちの攻撃を退けながら、痛みをなるべく遠くの方に感じようとする。しかし、ひきつる痛みと熱が、容易にそれを許してはくれない。しかも仁王が、またハヤブサに向けて剣を振るおうとしている。
「―――――!」
シュバルツはそれを、かろうじて受けた。しかし仁王の太刀は、先ほどのそれよりも、格段に重い物になっている。仁王に対する『邪悪なもの』の支配が、それだけ強烈なものになってきているのだろう。弾き飛ばされぬように踏ん張るが、そのたびに背中の傷が悲鳴を上げた。
(だめだ……! これ以上は、加減できそうにない……っ!)
仁王を斬りたくはない。
助けたい。
だがこのままでは―――――
その時だった。
ばりっと大きな音を立てて『繭』が裂け――――――中から、ハヤブサの手が出てきた。それを認めた瞬間、シュバルツは思わず叫んでいた。
「ハヤブサ!!」
まどろみの中、ハヤブサは遠くの方で自分を呼ぶ声を聴いていた。
酷く、懐かしい声。
酷く、大切なモノ。
焦燥に駆られて、その瞳を開ける。
暗闇の中、立ち上がろうとして、背中に何かが当たった。
「――――――」
強引にそれを突き破って立ち上がる。
バリッ!! と、大きな音を立てて『繭』が裂け―――――ハヤブサは久しぶりに、外の空気に触れた。一つに束ねた琥珀色の長い髪が、ふわりと弧を描いて風に揺れる。
「ハヤブサ!!」
もう一度、自分を呼ぶ声が響いて、ハヤブサははっと顔を上げる。すると、革のロングコートを着た青年が、懸命にモンスターたちの攻撃を防いでいる後姿が、視界に飛び込んできた。
「ハヤブサ!! 龍剣を取れ!!」
「―――――!」
「早く!!」
(龍剣――――!?)
ハヤブサは、咄嗟に周りを見渡す。すると、自分のすぐ近くの石柱の中に鎮座している、愛刀である龍剣を見つけた。
ハヤブサは、その辺にある物を軽く取るかのように、全く無造作に手を伸ばしていた。
何故か、石柱に阻まれるとは考えなかった。
剣を手に取れると確信していた。
そして―――――その通りになった。
龍剣は、まるでそこにあるのが当然と言わんばかりに、ハヤブサの右手に収まっていた。
それと同時に、ハヤブサの身体から、溢れ出す『龍の燐気』
それが一陣の風となって、辺りに吹き荒れた。
その風は、圧倒的だった。
そこにいる、すべてのモンスターたちを怯ませていた。
(そうか……! これが、『龍の忍者』―――――)
シュバルツもまた、同様だった。
龍剣を右手に下げ、ゆっくりと歩きだすハヤブサの姿を、ただ固唾を飲んで見守っていた。
その姿は美しく、犯しがたい強さと輝きを放っていた。
そして、ひどく見知った姿でもあった。
そう―――――これが、『リュウ・ハヤブサ』
彼本来の姿なのだと、シュバルツは思った。
紅の瞳をした仁王が、魅入られたようにハヤブサに斬りかかっていく。
ハヤブサはそれを、一刀の元に斬り伏せていた。
全てが一瞬の、あっという間の出来事だった。
灰燼に帰していく仁王。その面に、一瞬、満足げな笑みが浮かんだように見えたのは気のせいなのだろうか。
ただ―――――シュバルツは悔いが残った。
仁王をまともな状態で、ハヤブサと戦わせてやりたかった。
「……………」
仁王を斬った後、静かに辺りを見回していたハヤブサであるが、おもむろに印を結びだした。
「ナウマクサンマンダ バサラ ダンセンタ―――――」
その呪文に応えるかのように、巨大な黒龍が、その身体から舞い上がる。ハヤブサが『呪』と共に印を結び終わると同時に、黒龍は、天地をつんざくような咆哮を上げながら、周りのモンスターたちに襲いかかっていった。そしてあっという間に、その場にいたモンスターたちを、葬り去っていったのだった。
後にはただ――――呆然とそれを見守る、シュバルツだけが残されていた。
(ハヤブサ………!)
酷く懐かしい横顔に、シュバルツは胸を締め付けられる想いがする。
もしかして彼は、自分のことも思い出してくれているのだろうか。
シュバルツは、ハヤブサに向かって一歩、踏み出そうとする。
しかし、それよりも早く、ハヤブサはシュバルツに龍剣を向けた。煌く白刃が、シュバルツの喉元に突き付けられる。
「約束通り、俺は、龍剣を手に入れた」
色素の薄いグリーンの瞳がシュバルツを鋭く射すくめる。そこからは、何の感情も読み取れない。
「次は、お前の番だ………。お前の『真の目的』を聞かせてもらおうか」
「……………!」
覚悟はしていたつもりだった。
しかし、シュバルツは、目の前が真っ暗に染まっていくのを感じていた。
どうして―――――こんなに傷ついたような気持になるのだろう。
ああ―――――やはり、ハヤブサは
私のことを、思い出してはいない………!
「……………」
ハヤブサは、目の前の男を見つめながら、先ほど見た革のロングコートの青年の面影を必死に探していた。
あの青年。
あの青年は、何だったのだろう。
どうして、こんなにも胸がかき乱されるのだろうか。
しかし、刀の向こうにいる者は、自分が『仇』と憎んでいた男―――――
(だが……お前は違うだろう?)
刀越しに男を検分しながら、ハヤブサは考えていた。
少なくともこの男は違う。
断じて、自分の『仇』などではない。
この男の、今までの言動行動を見ていれば分かる。この男を『仇』と憎むのは、おそらくお門違いだ。
ならば、この男は何者だ?
この男は、敵なのか味方なのか。
はっきりさせたい。
お前は 誰だ。
(ハヤブサ……!)
白刃の向こうにいる『龍の忍者』となったハヤブサを、シュバルツは見つめる。
彼の身体から溢れる『龍の燐気』そして力―――――
どれをとっても自身の『DG細胞』を、十分破壊し得るものだとシュバルツには分かってしまった。
故に、誘われた。
甘やかな―――――『死』への、誘惑に。
もとより自分は、自然な形で生まれたものではない。『死体』と『DG細胞』―――――デビルガンダムの大量殺戮の果てと、キョウジの科学者としての『禁』を破った行為の結実が自分を作った。
いわば、キョウジの『罪』の証――――シュバルツは、自分という存在を、そう理解している。
もちろん、キョウジにとって『自分』という存在が『罪』だけではないのだということを、シュバルツは知っていた。現に、今も伝わってくる。背中の傷を懸命に治してくれているキョウジの気配。『生きろ』という熱い想い―――――。
それを感じるたびに、シュバルツは『生きて帰らなければ』と思う。
しかし―――――
これは、チャンスでもあった。
キョウジを『罪』から、解放してやれるチャンス。
『自分』といういびつな存在を、この世から抹殺してしまえるチャンス。
『DG細胞』で構成されている自分の身体は『自己再生』をしてしまうため、自分で自分の存在を消すことができない。だから今―――――目の前に広がる『死』へと誘う穴には、強烈に惹きつけられた。しかも、その力を持っているハヤブサには、自分に関する記憶がない。
今なら
今なら、死ねるのだ。
ハヤブサを傷つけることもなく、ひっそりと。
DG細胞に感染する恐怖から
そしてこの、空虚なアンドロイドに、彼の愛を消耗させる行為からも
ハヤブサを、解放してやることが―――――
「く…………!」
背中の傷が、ツキリと痛んだ。
「……………」
ハヤブサの突き付けた剣を、男は無言で見つめていた。その瞳はひどく穏やかで、何故か、どこかしら寂しげですらあった。
頭の中で警鐘が鳴る。殺してはいけない。きっと、目の前の男は今ここで殺すべきではないのだと。
なのに―――――
(喰ワセロ!)
「…………!」
先ほどから手に持った『龍剣』が、強烈にハヤブサに訴えかけてくる。
喰ワセロ!
喰ワセロ!
コノ男ノ『魂』ヲ―――――
コノ極上ノ魂ヲ、喰ワセロ!
(そうか……! これが、『妖刀』たる所以………!)
ハヤブサは、ぎり、と、歯を食いしばっていた。
龍剣が『妖刀』である、と、かねてから聞いていたことがある。刀自体が持ち主を選び、その主が気に食わなければ、刀の方がその持ち主を『喰って』しまうのだと。
ハヤブサは唐突に理解した。
これは、刀から問われているのだ。
お前は、自分の声に負けずに、斬る者を選べるか? と――――
斬ラセロ!
喰ワセロ!
刀は執拗に訴えてくる。
目の前にいる男の魂は、刀にとってはそれほどまでに、得難い獲物のように見えているようであった。
(うるさい、黙れ……!)
ハヤブサは、刀を握る手にありったけの『気』を込めた。
冗談ではない。
貴様の持ち主は、この俺だ。
お前に何を喰らわせるかは――――
俺が 決める。
「……………」
男は無言で龍剣を見つめていたが、やがて、ふっと小さく息を吐いた。
「そうだな……。お前が龍剣を手に入れたら、私の目的を話す。そういう約束だったな……」
男はそう言うと、龍剣からすっと体を引いた。そのまま石柱から離れ、少し広い空間に出ると、帯刀の状態でハヤブサに相対しながら静かに立つ。
まるで果し合いでも始めそうな間合いと雰囲気――――ハヤブサがそれに訝しんでいると、男が静かに口を開いた。
「では……語るとしようか。私の『真の目的』を――――」
その言葉が終ると同時に、男の身体から放たれる異様なまでの『殺気』
それは、辺りの穏やかな空気を切り裂き、龍の祠の静謐な空間を、一変させていた。
「な…………!」
ハヤブサは、思わず息を飲んでいた。
今まで男と修行で相対したことは何度もあったが、これほど明確な殺気をぶつけられて来たのは初めてだ。知らず、龍剣を握る手に力が入る。龍剣の切っ先が、ピクリと動いた。
男の方も、ハヤブサの龍剣の動きに合わせたかのように抜刀する。白刃がギラリと攻撃的な光を放ち、彼が本気でこちらを斬ろうとしているのが、否が応でも伝わってきた。
(ここにきてこの殺気……! まさかこいつ、最初からこれが目的だったのか? 俺が龍剣を手に入れたところで、龍剣ごと、俺を葬り去ろうと目論んでいたのか!?)
自分が歩むのは修羅の道。土壇場での裏切りも、ある意味当たり前の世界だった。男がこんな風に豹変しても、それはそれで『あり』だった。故に、ハヤブサの背中に、ジワリ、と、いやな汗が伝い落ちる。腕の中の龍剣も男の殺気に中(あ)てられたのか、小さく振動しながら、ますます大きな声で訴えてきた。
アイツハ敵ダ!
斬ラセロ!
喰ワセロ!
「…………ッ!」
ハヤブサは、ぎり、と、歯を食いしばっていた。
(ハヤブサ………!)
シュバルツの心は、恐ろしいほどの静寂の中にいた。
ここにきて、むしろ心は凪いでいた。
斬られたかった。
斬られてしまいたかった。
龍の忍者となった、ハヤブサに―――――
だからシュバルツは、ありったけの殺気を放った。
何故だろう。
きちんと相対しなければ―――――
『斬ってもらえない』
そんな予感がしていた。
(すまないな……キョウジ……)
シュバルツは、心の中でキョウジに謝る。
もしも、私がここで死んでも、どうかハヤブサを恨まないでくれ。
私は望んでこれをした。望んでハヤブサに、斬られることを選んだのだ。
ありがとう。
私はもう十分だ。
私は皆から、十分すぎるほどの、幸せをもらった。
だからいいんだ。
今ここで、たとえ死んでしまったとしても―――――
悔いなく死ねる。
「………………!」
男の尋常ならざる殺気に、空気が痺れる。龍剣を構える手が、汗に濡れた。
男は、完全にこちらを殺す気だ。一刀の元に斬り捨てるつもりで、こちらに向かってきている。
斬らねば殺(や)られる。
斬らねば――――
(本当に、そうか?)
ここで、ハヤブサの頭の中に疑問が沸いた。
この男を斬ってはならない。斬りたくはない―――――それは、ハヤブサの正直な気持ちだった。
この男は、自分の里を襲った張本人では断じて無い。それどころか、自分の修業を手助けしてくれていた。陰に日向に、自分を支え、導いてくれていた。いわば、『恩人』と言ってもいい。ここまで自分を支えてくれた男が、この局面でいきなり自分を斬ろうとするだろうか?
それはどう考えても不自然すぎる。不自然すぎるのだ。
――――斬ラネバ殺ラレルゾ!!
誰かの声が、強く訴えてくる。
それは、龍剣の声かもしれないし、別の誰かの物かもしれなかった。
だがハヤブサは、そんな事はどうでもよかった。
誰に何を言われようとも、目の前の男を斬りたくはなかった。自分の方には、男を斬る明確な理由が、何もなかったのだから。
では、こんなに殺気を漂わせている、男の『真の目的』とは何だ?
ハヤブサは懸命に、今までの男の言動行動を思い出す。
龍剣を、自ら手に入れる気はないと言った。
俺に龍剣を手に入れさせるという目的の元、男の行動は一貫していた。
そして俺は、龍剣を手に入れることができた。男の言葉によると、自分が龍剣を手に入れることができれば、この閉じられた空間から抜け出せるという。
(しかし……もうこの状態だと、龍剣を持ってなくても外に出られそうだがな……)
ハヤブサは渋い顔をしながら、あちこちに亀裂が走り、ボロボロになっている祠の結界の状態を見る。どうやらこの結界と龍剣の間には、結界を解く『鍵』のような明確な関係があるわけでもなさそうだった。
では、龍剣を手に入れた俺に、あの男は何を望む?
いったい何を―――――
「……………!」
ハヤブサはここで、ある可能性に行き当たっていた。
(クククク……。まさかあの男が、こちらの期待通りの動きを、してくれるとはな………)
漆黒の闇の中、ラクシャサは邪悪にほほ笑む。予定では、シュバルツを操り、ハヤブサに彼を殺させて―――――龍の忍者が絶望の淵に叩き落されたところを、『憑代』として乗っ取るつもりであったのだが。
何故かこちらが操らずとも、ハヤブサに斬られたがっているシュバルツ。
非常に好都合だった。このままいけば、こちらの魔力を消耗せずとも、龍の忍者の身体を容易く手に入れることができるだろう。
(龍の忍者にかけてある『まやかし』を解くのは、あの男が斬られてからで良いな……。さあ、存分に絶望するのだ。リュウ・ハヤブサ………)
ラクシャサは、己が解放される瞬間を、今か今かと待ち構えていた。
(まさかこいつ……! 俺に斬られたがっている………?)
剣の修業をつける前に、あの男の身体は龍剣でなければ殺すことはできないと、確かにハヤブサは男から説明を受けていた。
もしも
もしも万が一、男の目的がそれだとしたら。
死ねない自分の身体を抹殺するために。
龍剣に斬られるために、俺の修業を手伝ったのだとしたら―――――
今、こうして目の前で凄絶な殺気を漂わせながら立っている男の言動行動の辻褄が、ハヤブサの中ですべて合ってしまう。
「……………!」
あまりのことに、背中に寒気が走った。それと同時に、自分の中で怒りにも似た感情が、あとからあとから湧き上がってきた。
(……ふざけるな……!)
きつく龍剣を握りしめ、歯を食いしばる。
この男にどんな事情があるのかは知らない。
だが、男の自殺願望に、付き合う義理は無いと思った。
生きてこそ―――――
生きるからこそ、前に進める。罪を犯していたとしても、償う機会に恵まれるのではないのか。
それを、安易に死を選ぶなど許せない。
死んでしまったらそれまでではないか。
何もかもが途中で途切れて、そこで終わってしまうのではないのか。
自分は人間で、命に限りがある身だから、『不死』の苦しみなんて知らないし、理解もできない。
だがこの男を、自分の手で今ここで殺したくはなかった。
仇でもないし、男の事情を何も分からないのに『敵だから』という短絡的な理由だけで、切り捨ててしまいたくはない。繰り返し言うが、自分の方には男を斬る理由など、全くないのだから。
(男を斬らない決意をする……やはり、俺は甘いのかな)
ハヤブサはそう感じて、知らず、苦笑してしまう。
「『敵』と断定したならば、情けなどかけず、迷わず斬り捨てろ」
これが、自分が歩んでいく世界のセオリーであるのだから。
それなのに、自分は今また、『敵』かもしれぬ相手に、要らぬ情けをかけようとしている。父がそれを知ったら、また、大目玉を喰らってしまうことだろう。
だけど、自分はまだ足掻いているのかもしれない。
人間に、世界に、問いかけたいのかもしれない。
信じていい、優しい『光』はここにあるのかと。
修羅だけではない、裏切りだけではない綺麗な世界が、まだそこにあるのかと。
信じたい。
信じさせて、くれ。
男から放たれる殺気は空気を切り裂き、はち切れんばかりに膨れ上がっている。手にした白刃がギラリと不吉な光を放ち、『お前を殺す』と明確な意思を伝えてきている。
それなのに、自分は、この男をまだ信じようとしている。この決断はおかしい。まったく、狂気じみている。
だが―――――賭けてもいい。
この男は、おそらく自分を斬っては来ない。
陰に日向に俺の修業を支え続けてくれていたこの男が、この土壇場の局面で、いきなり自分を裏切ると考える方が、自分にとっては不自然すぎるのだから。
――――モシ、本当ニ斬ラレタラ、ドウスル?
誰かの声が、頭に響く。ハヤブサはそれに、微笑みながら頭を振った。
斬られるのなら、それもいい。
だが、龍剣の声に負けて、自分の恐怖心に負けて――――
斬らなくてもいい男を斬る。この男の自殺の手伝いをする。それだけは――――
絶対に、いやだ。
龍剣よ。お前が喰らうものは、俺が決める。
たとえ死んでも、お前の言いなりになど、なってやらない。
男の足が、ジャリ、と音を立てて半歩、動く。
ハヤブサはそれに合わせるように、ふっと小さく息を吐きながら、龍剣を中段に構えなおした。
アイツハ敵ダ!! 斬ラレルゾ!!
殺セ!!
殺セ、殺セ!!
頭の中に声が響く。
生存を願う本能が、警鐘を鳴らし続ける。
だがハヤブサは、それらの声たちを力づくでねじ伏せた。
自身に問いかけ続ける。
あの男は、名を上げるために、俺を殺すような奴なのか?
――――否。
答えは断じて否である。
今までの、男の所作を思い出す。施された優しさを思い出す。
………充分に、信じられると思った。
これだけの殺気を浴びてなおも、目の前の男を信じようとしている自分は、実際狂気じみていると思った。『龍の忍者』として生きていくには、信じられぬほど、愚かな決断なのかもしれない。
だが構わなかった。
もし、万が一あの男が本当に俺を殺しに来ていたのだとしても。
俺の命を欲するのなら、くれてやる。
悔いはなかった。
それだけの物を、自分は男から受け取っているのだから。
だから、『俺は』斬らない。
たとえ、どうなっても。
どんなことがあっても―――――
男がさらに、じり、と、間合いを詰める。
膨れ上がった殺気は辺りを焦がし、もう弾け飛ぶ限界を訴えていた。
(来る)
龍の忍者は静かに――――その時を待った。
パラリ、と音を立てて、ひび割れた結界の礫が地面に落ちる。
それと同時に、二人の男が同時に地面を蹴った。
ダンッ!! という激しい踏み込み音とともに、男の裂帛の気合と白刃が迫る。
その時、ハヤブサは―――――
ガツン!!
ぶつかり合った二つの影。
(今だ!)
わが事成れり――――とほくそ笑んだラクシャサは、その瞬間、ハヤブサにかけていた『まやかし』を解いた。
さあ、お前が殺した相手を見ろ。
そして、存分に絶望の悲鳴を上げるがいい。
一陣の風が、二人の間を吹き抜ける。それと同時に、ハヤブサに施されていた『シュバルツ』に関する記憶の封印も同時に解けた。ハヤブサの脳裏に、一気に流れ込んでくる、愛おしい人の記憶。
「……………!」
ハヤブサは、自分と戦っていた男が最後に取った姿勢のまま、佇んでいる目の前の愛おしい人の姿を見る。
「シュバルツ……」
シュバルツは、優しく微笑んでいた。
そして、下段から逆袈裟切りにハヤブサを斬りに来ていたはずの彼の手には―――――
刀が、握られていなかった。
「ハヤブサ……」
ハヤブサに名を呼ばれたことにより、シュバルツは、彼が自分のことを思い出してしまったことを知る。
嬉しくもあり―――――同時に、胸が締め付けられた。
どうして――――彼は、思い出してしまったのだろう。
そして、どうして―――――
彼は、私を斬ってはくれなかったのだろうか。
ハヤブサは、シュバルツが振った剣を全く避ける気もなく、その懐に飛び込んでいた。彼の手に煌く白刃。それは、自分を逆袈裟切りに斬り上げる物であったのに――――
ギリギリのところで、刀を放棄したシュバルツの手。空を切った風は、ハヤブサの身体を優しく撫でた。
そして、ハヤブサの龍剣は―――――
彼の首を斬るギリギリのところで寸止めをされていた。
「お………!」
ハヤブサの中で、複雑な感情が渦を巻く。
どうして―――――
どうして気づかなかったんだ? 俺は。
この戦い方も
あの優しさも―――――
全て、お前の物だったのに。
しかも、どうして―――――
目の前の愛おしい人は、儚さを漂わせる笑みを浮かべながら、少し寂しそうに首元に当てられた龍剣を見ていた。
どうして………俺に殺されたがっているんだ!? こいつは!?
訳の分からない、感情が溢れた。
あり得ないほど、むかついた。
本当に本当に、『斬らない』と決意していて良かった。
一歩間違えれば、本当に取り返しのつかないことを、してしまうところだったのだから。
「シュバルツ……! お前……!」
「ハヤブサ………」
愛おしいヒトの、静かな声。どうして、忘れていたのだろう。
「お前……! どうして………!」
ハヤブサの問いかけに、シュバルツはにこりと微笑みかけた。
――――斬ってくれて、よかったのに
声なき、シュバルツの声。思わずハヤブサは叫んでいた。
「止めてくれ!!」
目の前で怒鳴られて、シュバルツは知らず息を飲む。そんな彼を、ハヤブサはぎゅっと抱きしめていた。
「そんな簡単に、『俺に殺されてもいい』だなんて、言わないでくれ、シュバルツ……!」
「ハヤブサ……」
「お前、絶対分かっていないだろう。お前を斬った俺が、お前を喪った俺が、どんなに悲しむか………どんなに苦しむか………!」
「―――――!」
「そんな地獄のような苦しみなど、俺には耐えられない……! お前が死ねば、俺も生きてはいないから」
自分たちは比翼の鳥。連理の枝。
ハヤブサはシュバルツと自分の関係を、そうだと思っている。たとえ片方がアンドロイドで、片方が人間で―――――共に死ぬことができない運命だとしても。
彼が、自分より先に死ぬのであれば、喜んで共に死ねる。
ハヤブサはそう確信していた。
「ハヤブサ……!」
驚くシュバルツの身体を、ハヤブサはさらに強く抱きしめる。愛おしいヒトが、もうどこにも逃げていかないように。
「よかった………!」
ぽつりと、呟く。
「……………?」
怪訝な表情を浮かべるシュバルツに、ハヤブサはさらに語り掛けた。
「『お前』と分からなくても、俺は、お前を斬らない決意をしていた」
「な…………!」
「たとえ、俺にとってお前が『仇』の姿に見ていたとしても―――――お前は、十分に信頼するに足る存在だったから……」
「ハヤブサ……!」
「『斬られてもいい』と思えた存在が、また、お前で良かった……」
「…………!」
「『お前』をちゃんと、信じられてよかった………!」
そういってシュバルツをぎゅっと抱きしめるハヤブサの、その手が震えていた。
(ハヤブサ………!)
シュバルツもまた、返すべき言葉をなくし、ハヤブサを抱きしめ返すことしかできなかった。
ハヤブサから伝わってくる、『愛している』という熱い想い――――。
久しぶりに浴びる、彼からの愛情のシャワーだった。
彼に抱きしめられながら、自分は、ずっとこうされたかったのだと、シュバルツは気づいてしまう。
この愛情のシャワーを、自分はどれほど渇望していたのだろう。
本当は、よくないことだ。
こんな風に、彼を求めてしまうことは、きっとよくないことなのだ。
彼の『人間として』の幸せを願うのなら
自分は、身を引かなければならないのに――――
どうして
どうしてこんなにも
幸せを感じてしまうのだろう。
それは、忍者たちにとっては久々の再会であった。
特にハヤブサは、危うく愛おしいヒトをこの手で殺めそうになっていた事実に驚愕し、震え、そして安堵のため息を漏らしていた。それゆえに、張り詰めていた『気』が一瞬緩んでしまったことを、誰が責められるだろう。
そしてその隙を逃すほど―――――邪神ラクシャサは、甘い存在ではなかった。
バカメ!!
悪意の塊のような触手が、ハヤブサに向かって伸びる。それに、シュバルツの方が一瞬早く気が付いた。
ドンッ!!
シュバルツは無言で、ハヤブサを弾き飛ばす。そして、ハヤブサと切り結ぶ際に刀を捨てていたシュバルツは、触手を防ぐ手段を、持ち合わせてはいなかった。
いきなりシュバルツに弾き飛ばされたハヤブサであったが、咄嗟に受け身を取ってシュバルツの方に向き直る。
そして彼は見てしまった。
自分の背後から伸びてきた黒い触手のようなものが、シュバルツの腹に突き刺さっていくのを。
そしてその時、ドモンもその空間に走りこんできていた。
そこで彼もまた、見てしまう。
シュバルツが、ハヤブサを庇って、攻撃を受けてしまった瞬間を。
「シュバルツ!!」
「兄さん!!」
悲鳴のような絶叫が、辺りにこだましていた。
第5章
(おや?)
邪神ラクシャサは、すぐに気が付く。今攻撃を仕掛けた者の、その身体の異常性に。
人間ではない、異物でできたその身体は―――――自分の『負の魔力』と、不思議とよく馴染んだ。
(なんと………! 龍の忍者以上に、わが『憑代』となるのにふさわしき存在が、ここにいるとはな………!)
ラクシャサはほくそ笑みながら、捕まえた獲物を我が物にするべく、攻撃を開始していた。
「く………! う…………!」
腹に突き刺さった触手が、シュバルツの身体を侵食していくのが分かった。
「おのれッ!!」
すぐにハヤブサは、シュバルツに刺さる触手を龍剣で断ち切った。しかしそれで、ラクシャサの悪意に満ちた魔力が止まるはずもなく。
シュバルツは『人間』の形をすぐに保てなくなってしまった。
ボコッ!! ボコォッ!!
不吉な音を立てて、歪に変形していくシュバルツの身体。
「シュバルツ!!」
ハヤブサは咄嗟に、シュバルツのわずかに残る右手に必死に手を伸ばし――――そこを握りしめていた。
「―――――!?」
シュバルツを突然襲った悲劇は、当然外界でキョウジが懸命に治療をしている『本体』の方にもすぐに影響を及ぼしていた。
ブシュッ!! と、音を立てて、シュバルツの腹の付近が突然裂ける。
「な―――――!!」
驚いたキョウジが、慌ててそこに手を伸ばそうとした、刹那。
ドグワァッ!!
轟音を立てて、シュバルツの腹から無数の触手のようなケーブルが伸びる。
「いけない!!」
それがDG細胞が暴走したせいだと気付いたキョウジは、すぐに腹の傷口に高圧電流を流し込む。そのショックで、ケーブルの動きがピタッと止まった。
「止まったか!?」
東方不敗がそう声を上げた、次の瞬間。
ドゴォッ!!
キョウジの治療をあざ笑うかのように、爆音とともにさらに多くの触手のようなケーブルが、シュバルツの腹から飛び出してくる。それは、隣で寝ていたハヤブサの身体をも巻き込んで、うねりながら、一つの巨大な『樹』のように成長していった。
「シュバルツ!! シュバルツ!!」
「危ない!! キョウジ!!」
なおもシュバルツの治療を続けようとしたキョウジであるが、このケーブルの勢いに巻き込まれたら危険だと判断した東方不敗がそれを無理やり止めた。シュバルツに縋ろうとするキョウジを強引に引き剝がして、そこから横っ飛びにジャンプする。それと同時に、キョウジのいたところに伸びてきた触手のようなケーブルが、獲物を捕らえられずに空回りするような動きをするのが見えた。
「そ、そんな……! シュバルツ!! シュバルツ――――ッ!!」
「キョウジ!! 危ない!! 落ち着かんか!!」
「放してください!! マスター!! シュバルツを助けないと!!」
キョウジは叫びながら、東方不敗の腕から逃れようと必死に足掻く。だが、東方不敗は頑としてそれを聞き入れなかった。東方不敗にとっては何を置いてもキョウジの命が最優先であるが故に、たとえ彼の意思に反していたとしても、その命に危険が及ぶようなことを、許すわけにはいかなかった。シュバルツの元に向かおうとするキョウジを、必死に押さえ続ける。
そしてその行為は、東方不敗にとっては、敵の前に無防備にその背中を晒すことにつながった。当然周りのモンスターたちが、そんな隙だらけの東方不敗の姿を見逃すわけもなく―――――ここぞとばかりに彼に向かってモンスターたちが殺到し始めた。
「…………!」
当然それに、東方不敗も気づく。しかし彼が、自身の保身のためにキョウジを手放すことを選ぶはずもなく。モンスターたちのいくつかの攻撃が、キョウジを押さえ、庇い続ける東方不敗の背中にダメージを与えた。
「ぐうっ!!」
悲鳴はかみ殺すが、低い呻きは漏れる。その声に、キョウジはようやく状況に気付き、東方不敗の腕の中で暴れるのをやめた。
「マスター!!」
「案ずるでない! こんなものは、かすり傷じゃ!!」
「で、でも………!」
言っているそばから、さらに殺到してくるモンスターたちの攻撃。
「マスター!!」
顔色が変わるキョウジ。しかし、東方不敗がキョウジを庇うことをやめるはずもなく。彼はキョウジを深く抱き込みながら、襲い来る背中の痛みを予感した。だがその予感は、見事に外れることとなった。
バシッ!! バシッ!!
東方不敗とモンスターたちの間に飛び込んできた小さな影が、彼への攻撃をことごとく蹴散らす。
「大丈夫か!?」
声をかけてきたサイ・サイシーに、東方不敗もその身をのそりと起こした。
「………礼は言わんぞ!」
「要らないよ!」
東方不敗の言葉に、少年もぶっきらぼうに答えた。
「おいらが助けたのは、キョウジの兄ちゃんだ!」
サイ・サイシーの言葉に東方不敗はフン、と、鼻を鳴らし、キョウジはかなり冷静さを取り戻していた。
そうだ。自分の不用意な行動は、皆を思わぬ危険に晒してしまうことにつながるのだ。落ち着いて、冷静に事を判断せねばならぬと、キョウジは自分で自分に喝を入れる。
「……………」
自分が押さえつける手を緩めても、シュバルツの方に不用意に走っていこうとしないキョウジの様子に、東方不敗もようやく安堵のため息を漏らす。キョウジをモンスターたちから背中で庇いながら、皆の方に向き直った。
「あれは……シュバルツ殿なのか?」
サイ・サイシーより少し遅れて二人のそばにやってきたアルゴが、『樹』のように聳え立つ黒いケーブルの塊を見ながら、問いかけてくる。それに、キョウジはほぞをかみながらも頷いた。
「ああ……。残念ながら、そうみたいだ……」
「シュバルツがあんなになるなんて…………ドモンの兄貴は何をしているんだよ!?」
「ドモン………!」
サイ・サイシーの言葉に、キョウジは、異界に行っている弟の言葉を思い出す。
「兄さんのために、必ずシュバルツを連れて帰ってくる!!」
あの弟は、確かにそう言い切っていた。彼は今、どこで何をしているのだろう? シュバルツがこうなってしまったことに、彼は気づいているのだろうか?
「案ずるな……。あ奴はわしも認めた『キング・オブ・ハート』………必ずこの状況を打破する力を持っておるはずじゃ」
キョウジを庇い、周りの様子を見ながら、東方不敗が口を開く。巨大な『樹』のように形を変えてしまったシュバルツが、まだそこにじっととどまって沈黙していた。すぐにこちらを襲ってくるような様子が見えなかったが故に、戦場に少しの静けさが舞い降りていた。ただ、その『樹』の足元で、発電装置がバチバチと青白い火花を飛ばしながら不吉な音を立てている。
(ダメージを喰らったな………)
キョウジはほぞをかみながら、発電装置の様子をじっと見つめていた。あのまま放っておけば、あれが壊れてしまうのもおそらく時間の問題だろう。壊れてしまったときのことを考えると――――キョウジは、背中に寒気が走るのを禁じ得なかった。結界が壊れて、町中にモンスターが溢れて―――――
できれば、直しに行きたい。
だが今、それを選択するのは危険すぎた。あの状態になっているシュバルツと発電機の距離が近すぎるが故に、下手をしたら、ここにいる全員が、あれに巻き込まれてしまいかねない。そうなってしまったら、もっと最悪な事態になる。それは、断固として避けねばならぬと強く思った。
(有効な手立てがない……。どうすればいいのだろう……)
キョウジは、拳をぎゅっと握りしめる。
だが考えることを止めるわけにはいかなかった。立ち止まってあきらめてしまったら――――すべてがそこで、終わってしまうのだから。
(シュバルツ……! ハヤブサ……! ドモン……!)
変わり果ててしまったシュバルツの姿を、キョウジは祈るような思いで見つめ続けていた。
(く………そ………っ!)
悪意の塊のような嵐の中で、ハヤブサは『シュバルツ』の手を握り続けていた。
すっかり変わり果ててしまったシュバルツの姿。
しかし、この手は。この右手だけは―――――
まだ、彼のヒトの面影を留め続けていた。
「シュバルツ……!」
ハヤブサが時折呼びかける声に、目の前の『シュバルツ』からは咆哮にも似た苦しそうな声が上がる。
おそらくシュバルツには、自分の声が聞こえているのだ。
彼を乗っ取ろうとしている邪悪な存在と、まだ戦い続けているのが分かった。
助けたい。
助けてやりたい。
自分を庇ったせいで―――――
彼はこんな風になってしまったのだから。
悪意の嵐は激しく、時折ハヤブサは、彼のヒトの右手を離しそうになる。
だがそのたびに――――
(ダメ………! 離シテハダメ………!)
か細いが、ひどく強い響きを持った声が、自分の脳裏に響く。
手と手が握り合っている部分に、淡い光が宿っているのが見える。
分かる。
きっとこれが、今のシュバルツをかろうじて守っているのだということが。
だが、このままではだめなこともまた事実だ。
シュバルツを助けるために、今自分ができることは何なのだろう。
「シュバルツ!!」
ハヤブサの呼びかけに、『シュバルツ』からは苦しそうな呻き声が返ってくるのみであった。
(いやだ………! いやだ………!)
悲鳴を上げながらも、懸命に抗う。
侵食してくる『悪意』は、自分を強引に闇の中へと引きずり込もうとしているのが分かった。
いやだ………!
そこには堕ちたくない……!
それをしてしまったら、哀しませてしまう人がいる。
苦しませてしまう人がいる。
だから―――――!!
その思いを嘲笑うかのように、闇の中から仄暗い笑いが返ってきた。
――――滑稽ダナ……。オ前はモウ、十分『邪悪』ナ存在でアルノニ……?
そう言いながら声の主は、シュバルツに見せつけてくる。
お前の身体は、『DG細胞』と『死体』という、歪な物でできているのだと。
お前が出来るまでに、沢山の人の血が流れ、死んでいったのだということを。
お前は、まさしくキョウジの『罪』キョウジの『罰』――――
お前が死ぬだけで、いったい、どれほどの人が救われることだろう。
(キョウジ………!)
知っていた。
自分は、キョウジの『罪』の証。
自分は存在し続けているだけで――――キョウジに『罪』を突きつけ続けてしまっていると、言うことを。
だけど―――――
「帰ってきてくれ!! シュバルツ!!」
懸命に伸ばされてくる手とともに伝わってくるキョウジの想いは、それだけじゃない。『罪』だけではないのだ。
絶対にこれ以上、キョウジを哀しませる真似だけはするわけにはいかなかった。
――――随分ト、往生際ガ悪いコトダナ……
闇からの声は、失笑を交えながら、尚も続く。
――――お前ハ、生キテイルダケデ他人ヲ暗黒ノ世界に巻キ込ム存在なノダゾ……? ミロ……! オ前のソノ手ノ先ニいル者ヲ………。
「…………!」
声に導かれるままに顔を上げて――――シュバルツは息を飲んだ。
何故ならそこには、嵐のような悪意の塊に翻弄されながらも、懸命に自分の右手を握り続けているリュウ・ハヤブサの姿があったのだから。
(ハヤブサ……!)
『このままでは奴もわが魔力に巻き込まれ―――――やがて、消滅するであろうな………』
「―――――!」
やけにはっきりと聞こえてきた『声』に驚いてシュバルツは振り返る。すると、そこには長い二本の角に銀色の長髪をなびかせ、紫黒色のマントを羽織った青白い肌の巨大な男が立っていた。
『ククク……。貴様の身体は、本当にわが魔力によく馴染むな……。吾が己が実体を得るまで、あと少しだ……』
そう言って金色の瞳を怪しく光らせる。邪悪に笑う口元には、二本の鋭い牙が光を放っていた。
(そんな………!)
改めて、自分の身体のいびつさ、邪悪さを突きつけられた格好になってしまったシュバルツから、絶望の呻きが漏れる。そんな彼に、ラクシャサは、更に畳みかけてきた。
『無駄な抵抗はよせ。もういい加減、あきらめて楽になれ』
事実、ラクシャサは、もうほとんど己が実体を復活させることに成功していた。
後、ほんの一握り―――――
一握り残るシュバルツの自我が、ラクシャサの復活を阻んでいる。
それゆえに、ラクシャサは、それを潰すことに全神経を注いだ。
かろうじて残るシュバルツの自我は、ハヤブサに繋がれている手と、そこに張られている小さな結界によって保たれているようなものだ。だからまず――――その手を引き剥がすことが肝要と悟った。
『龍の忍者の手を離せ。お前は、己が死に、あの男を巻き込むつもりなのか?』
先ほどからラクシャサは、手を離させようとハヤブサの方にも攻撃を加えている。しかし、どんなに殴っても斬りつけても――――龍の忍者の方は、頑としてその手を離そうとはしない。
『ほら……手を離してやれ。でないと――――』
シュバルツの目の前で、ドカドカドカッ!! と、激しい音を立てて痛めつけられるハヤブサの身体。
「ぐ………!」
動きが思うように取れない中、それでもハヤブサは何とか体を動かして、致命傷を受けることだけは避ける。
背中に背負う龍剣は、まだ抜かない。
分かる。
これの出番は今ではない。
必ず――――『抜き時』があるはずだ。
それまで、この手は絶対に離さない。
離してなどやるものか。
(シュバルツ………!)
ハヤブサは祈るようにシュバルツの手を見つめながら、虎視眈々と『その時』を狙っていた。
(ハヤブサ……!)
シュバルツの目の前で、ハヤブサは傷だらけになっていく。
(だめだ……!)
耐えられなかった。
見ていられなかった。
自分のせいで、もうこれ以上ハヤブサが痛めつけられることは―――――!
『まだ、足りぬか……? では、もう一度――――』
ラクシャサが手を振り上げ、更にハヤブサに攻撃を加えようとする。その瞬間、シュバルツはたまらず叫んでいた。
「や!! やめてくれっ!!」
シュバルツの悲鳴に、ラクシャサは我が意を得たりとばかりににやりと笑う。
『ほう……? 我に『止めろ』と言うからには、わが意に従う決意ができたのか………?』
ラクシャサの言葉に、シュバルツは頷いた。頷くしかできなかった。
『邪神』が復活するのであるならば、『ハヤブサ』という龍の忍者は、人類にとっての希望になる。邪神を討滅するための希望―――――それを、自分のためだけに、失ってしまうわけにはいかないと思った。
「ああ……。だから、彼にこれ以上攻撃を加えることは――――もう、止めてくれ………」
悄然と言うシュバルツに、ラクシャサは笑いが止まらなかった。
『クククク……。よかろう。ならば、さっさと手を離せ』
ラクシャサは手を下ろし、少し身を引いてシュバルツに命じる。
もちろん、このままシュバルツの言うとおりにハヤブサから手を引く気はなかった。
二人の手が離れ、シュバルツの身体を完全に乗っ取った瞬間に、龍の忍者にも手を下す準備をしていた。
折角体の中に取り込み、ここまで痛めつけた龍の忍者――――
確実に葬ることができる機会を、見逃すわけにはいかないのだ。
(ハヤブサ………!)
涙の向こうに霞む龍の忍者を、シュバルツは愛おしさを込めて見つめる。
今までありがとう。
こんな私を、愛してくれて――――
私はもういいんだ。
もう、十分、幸せだった。
このまま邪神に乗っ取られたとしても、龍の忍者となったお前に討滅されるのであれば―――――
もう 私の方には 悔いは な い
「…………」
シュバルツはそっと、ハヤブサから手を離そうとする。だがその動きを敏感に感じ取ったハヤブサの方から、怒声が上がった。
「ふざけるな!! 何故手を離そうとしているんだッ!!」
ハヤブサの剣幕に、手を離そうとしていたシュバルツの動きが止まる。それを確認してから、ハヤブサはもう一度、シュバルツに呼びかけを始めた。
「シュバルツ……! そこに、居るんだろう……?」
手を離そうとした、ということは、シュバルツの『意識』がまだそこにあるという証拠だ。たとえ目の前にその姿が見えなかったとしても、愛おしいヒトはそこにいるのだと確信して、ハヤブサは声を上げた。
「シュバルツ……! お願いだ、答えてくれ……!」
目の前に居るのは歪な姿をした『化け物』
周りに広がるのは、死臭と腐敗臭の漂う絶望の世界。
だが、居る。
俺の愛おしい――――大切なヒトは、必ずそこにいる。
恐れるな。
よく見極めろ。
必ず――――見つけ出してやるから。
「シュバルツ……!」
二人の手の間で光っている淡い光が、ゆっくりとだが、その強さを増し始めていた。
「何だ!? こりゃあ!!」
ドモンの後を追って結界内に飛び込んできたチボデー・クロケットが、素っ頓狂な声を上げる。それもそのはずで、彼らの目の前には今――――見たこともないような歪で巨大な形をした、『怪物(モンスター)』のような物が、不気味な唸り声をあげながら鎮座していたのだから。
「ドモン!! 早く攻撃を!!」
二人から少し遅れて走りこんできたジョルジュが、ナイフを手に構えながら叫ぶ。それを、ドモンの悲鳴のような声が制した。
「二人とも待ってくれ!!」
「どうした? ドモン!」
「なぜ、止めるのです!?」
二人の問いかけに、ドモンは少しためらってからその口を開く。
「……あれは、兄さんなんだ……!」
「ええっ!?」
「あれが、シュバルツだというのですか!?」
息を飲むジョルジュの横で、チボデーが小さく「Oh !! my god !!」とため息を吐く。ドモンは、歯を食いしばりながら頷いた。
自分だって、にわかには信じがたい。
できれば、あれはシュバルツではないと否定したい。
だが――――自分は、目の前で変容していくシュバルツの一部始終を見てしまった。
見てしまった以上、否定はできない。あれは、『シュバルツ』の変わり果てた姿なのだ。
ハヤブサを庇って、彼はああなってしまった。ある意味、兄らしいと言えば兄らしいのだが。
「しかし……! だとしたら、俺たちはどうすればいいんだ!?」
「そうです! 我らの紋章には、DG細胞を討滅する力がある! もし、我らがあれに攻撃を加えたら、下手をしたら、シュバルツ殿をも殺してしまいかねない!」
「そうだ……! だから、攻撃を加えるのは、もう少し、待ってくれ……!」
苦虫を噛み潰したような表情を浮かべて、ドモンは言う。だがチボデーは、納得できなかった。
「気持ちは分かるが……あれを、あのまま放置するわけにもいかないだろう!? それはどうするつもりなんだ!?」
「分かっている!! だから、見極めている………!」
「見極めている?」
問いかけるジョルジュに、ドモンは頷いた。
「師匠は言った……! ただ破壊のために、やみくもに拳を振るうべからず……。打つべき時、打つべき敵を、必ず見極めろ、と……」
――――シャッフルの紋章の力は、ただ、破壊するのみにあらず。救う力も、必ず持っているのだ……。
自分に『キング・オブ・ハート』の紋章を伝授するとき、自分の師である東方不敗は、そう教えてくれた。『破壊』と『救い』――――その両方を持つが故に、シャッフル同盟の面々は、歴史の戦いを見守る役目を与えられ、それを全うしてきたのだろう。
変わり果ててしまったシュバルツ。しかし、それはそこに鎮座したまま、沈黙を守っている。周りを攻撃しようとも、破壊しようともしていない。
兄はまだいるのだ。
あそこに。
ならば、あれの『核』となっている、兄の『本体』はどこだ。
ドモンは先程から、懸命にそれを探していた。
救うべきは、兄の『本体』
そしてその近くに―――――必ず、打つべき『敵』もいるはずだ。
(そういえば、ハヤブサの野郎もあれに巻き込まれていたな……。まあ、あいつはどっちでもいいが、存外あいつのそばに兄さんがいる可能性も――――)
そこまで思い至ってから、ドモンはブン! と、頭を振って、己が考えを否定する。
(あいつの力を借りるなんてもってのほかだ!! 俺は、自力で兄さんを探してやるんだからな!!)
若干の私情を交えながらも、ドモンは右手に紋章を光らせながら、懸命に打つべき『敵』を探し続けていた。
「シュバルツ……!」
自分の呼びかけに、ピクリ、ピクリと反応を返す右手。
いるのだ。そこに。
俺の愛おしいヒトは、まだ――――!
(そうだ……! 試してみる価値はある……!)
ふと思いついたハヤブサは、片方の手で『印』を結ぶと、おもむろに邪気払いの『真言』を唱えた。
「ナウマク サマンダボダナン ――――インダラヤ ソワカ―――――ッ!!」
ハヤブサの発した言葉は、『呪』となって、『モンスター』の中を切り裂く。
果たしてそれは、モンスターの中から、ハヤブサの大切なヒトの姿を、うっすらと浮かび上がらせ始めた。愛おしいヒトは涙を浮かべながら、懸命にこちらを、案じるように見つめている。
「シュバルツ!!」
「…………!」
自分にしっかりと視線を合わせ、明確に呼びかけてきたハヤブサに、シュバルツは知らず息を飲んでいた。
『おのれ! 小細工を――――!』
ラクシャサは、すぐに龍の忍者に攻撃を開始する。意志を持って、襲い来るケーブルや刃物。悪意の嵐に翻弄される中、それでもハヤブサは身を捻って、何とかそれらを躱した。かすり傷を負う。しかし、今はそれに構っている暇はない。
「オン ビセイシャラ ジャヤ ソワカ―――――」
印を結び、真言を唱えるハヤブサの身体に、光が灯る。
「叭――――――ッ!!」
その光は、ハヤブサの裂帛の気合とともにシュバルツに注がれ――――ともすれば霞みがちになる彼の姿を、明確に浮かび上がらせ始めた。
「シュバルツ……!」
「ハヤブサ……!」
涙を湛えて、懸命にこちらを見つめてくる愛おしいヒト。相変わらず美しいと、ハヤブサは素直に思った。
「シュバルツ……! 助けに来た……!」
そう呼びかけるハヤブサに、しかしシュバルツは頭を振った。
「ありがとう、ハヤブサ……。だが、私はもういいんだ……。どうか私のことはあきらめて、このまま帰ってくれ……」
「シュバルツ!? 何故だ!!」
当然その言葉に、ハヤブサが納得するはずもなく、噛みつくように食い下がった。それに対してシュバルツは、面に寂し気な笑みを浮かべて、答えた。
「何故って……。分かるだろう? 私の身体はもう、『邪神』に乗っ取られてしまって――――」
今や、自分のこの身体は、見る影もないほどに、歪に変形してしまっている。
驚くほどに『邪神』の『魔力』とよく馴染むこの身体を持った自分は、やはり、自然界の中で生きていくには、あまりにも不自然で、歪すぎる存在だった。
もうきっと、このままここで討滅されてしまった方が、世のため人のため――――
「ふざけるなっ!! お前、本気でそんなことを思っているのか!?」
ハヤブサの怒声に、シュバルツははっと顔を上げる。すると、かなり怒気を食んだ表情をしたハヤブサが、こちらを睨み付けていた。自分の手をしっかりと握りながら、もう片方の手で印を結び続けているハヤブサ。何らかの『呪』を発動しているのか、その身体が青白く光り始めている。
「ハヤブサ……!」
「お前に、『帰ってきてほしい』と望んでいる者はいないのか!? その人たちのために――――お前は生きようとは願わないのか!?」
「…………!」
(帰ってきてくれ!! シュバルツ!!)
叫びながら、必死にこちらに手を伸ばしてきていた、ドモンとキョウジの姿が脳裏によぎる。だがシュバルツは、すぐに頭を振った。
「しかし……私の身体は、もう――――」
「お前の身体が、どうしたって?」
シュバルツの言葉を遮るように、ハヤブサが言葉を発する。彼を包む青白い光は、更にその輝きを増していた。闇の中で灯り続けるそれは、まるで炎が燃え立つように揺らめき、辺りを照らし始めている。
「お前の身体が歪で穢れている? この世で最早生きていけないほど、邪悪な存在だって?」
ハヤブサから発した光は、二人の握られた手を通して、シュバルツに注ぎ込まれ続けていた。
「お前――――自分の身体をよく見てみろ! どこが歪んでいる!? どこが穢れているんだ!?」
「―――――!」
その言葉に、はっと弾かれたように―――――シュバルツは己が体を確認する。するとそこには、失われたはずの自分の手が、足が―――――綺麗な形を保ったまま、そこにあった。
「こんな………!」
信じられぬ思いで、シュバルツは自分の身体を確認する。『人間』の形を取り戻した身体。乗っ取られる前と唯一違うところと言えば、服を纏っていない、ということだけだろうか。
「お前は、『邪神』に乗っ取られてなどいない。お前はお前のまま――――綺麗で、穢れのない存在のままだ」
「…………!」
「こっちへ来い! シュバルツ!!」
ハヤブサは叫んだ。
必死だった。
自分はこのままどうなってもいい。
ただ―――――愛おしいヒトの『生』を、『幸せ』を、一心に望んだ。
「俺の名を呼べ!! 『生』を望め!!」
今行っているのは『魂込(たまごめ)の術』――――この術は、シュバルツから自分の名を呼んでもらうことで完成する。邪神からシュバルツを取り戻すために、ハヤブサは懸命に手を伸ばした。
「皆のために―――――『生きる』と叫べ!!」
「あ…………!」
差し出されたハヤブサの手が、涙で滲む。
鷲摑まれた、心が震える。
いいのか?
いいのだろうか?
こんな、私のような危険な存在が―――――
「帰ってきてくれ!! シュバルツ!!」
(……………!)
ふいに、脳裏に自分に向かって手を差し伸べてくれていた、キョウジとドモンの姿が浮かぶ。
「キョウジ兄さんを、独りにしないでくれ!!」
ドモンの必死な叫びが、心を打った。
「シュバルツ!! 俺は望む!! お前と、共にあることを――――!!」
ハヤブサを包む青白い炎のような光は唸りを上げ、辺りを眩いほどに照らしている。その光が、静かに自分を包んでいくのが、シュバルツには分かった。
その光から、ハヤブサの想いが流れ込んでくる。
――――共に、生きよう。
そんな、熱い想いが、シュバルツを包み込んできた。
「俺の名を呼べ!! そこから出て来い!!」
「あ…………!」
「俺を信じて!! 自分を信じて――――!!」
「…………!」
ハヤブサの言葉が、ハヤブサの心が
シュバルツの耳朶を
心を打つ。
いいのか?
いいのだろうか?
私のような存在が―――――
この世に生きていても
『生きたい』と言っても――――!
涙があふれる。
心が震える。
この胸に満たされていく熱い想いを
自分は、何と呼べばいいのだろう。
「そこから飛べ!! シュバルツ―――――ッ!!」
ハヤブサの想いを乗せた、青白い光が爆ぜる。
シュバルツの方も、それに応えるかのように、すべての迷いを吹っ切った。
「ハヤブサ……! ハヤブサ!!」
生きたいと
愛おしい人たちの元に帰りたいと
願うシュバルツが、叫びをあげる。
その、刹那。
バンッ!!
大きな音を立てて、シュバルツを捕らえ、その体を覆っていた触手のようなケーブルたちが砕け散った。目の前の視界が開け、こちらに呼びかけ続ける龍の忍者の姿が、はっきりと見える。
シュバルツは迷わなかった。
「ハヤブサ!!」
光の導くままに、シュバルツはケーブルを蹴って、そこから飛び出していく。
その瞬間、彼の身体は眩いばかりの金色の光に包まれていた―――――
「見えた!! 兄さん!!」
その光は、外側から兄を懸命に探していたドモンの視界に飛び込んできていた。そして、そのそばにいたチボデーとジョルジュの視界にも。
「あれか!? ドモン!! あれがそうなのか!?」
「あの『光』が、シュバルツ殿なのですか!?」
二人の問いかけに、ドモンは頷いた。
「ああそうだ!! あれは、兄さんだ!! 兄さんは、あそこにいるッ!!」
叫ぶと同時にドモンの拳が金色に輝きだす。彼の『闘気』が爆発的に膨れ上がった。
助けるべき『兄』の居場所は分かった。あとは、打つべき敵の本体を見つけるだけだ。
「俺は行くッ!! 援護を頼む!!」
「ああ!!」
「お任せを!!」
二人の返事を聞いて、ドモンは構えを取り、強く踏み込む。彼を中心とした、『闘気』の風が舞い起こり、赤いマントと鉢巻きが、まるで踊るかのようになびいた。
「行くぞ!! ジョルジュ!!」
「ええ!! チボデー!!」
ドモンの闘気に応えるかのように、二人の闘気もまた、膨れ上がっていく。
――――『機』は満ちた。
ドモンは迷わず、大地を蹴った。
「俺たちも続くぞ!! 遅れるな!!」
「ええ!! 我らの拳!! 『援護』のために!!」
シャッフルの紋章を持った者たちの外からの攻撃が、今まさに始まろうとしていた。
「シュバルツ!! シュバルツ……ッ!」
モンスターの中から飛び出してきてくれた愛おしいヒトを、ハヤブサは今、しっかりと抱き締めていた。
ああ
こんな風に愛おしいヒトに触れるのは
いったい、何時ぶりだろうか?
「ハヤブサ……!」
シュバルツもまた、ハヤブサの胸の中で歓喜に震えていた。
ありがとう、ハヤブサ
お前の言葉は私に勇気をくれた。
生きる勇気を
信じる勇気を
そして、愛し、愛される喜びを
ああ
いいのだろうか?
こんなに幸せで―――――
一方で驚いたのは、邪神ラクシャサである。
まさかこんなにあっさりと、自分の『核』となるべき『モノ』が、身体から分離して、外に出ていくなどと、思ってもみなかったのだから。
『おのれッ!! 人間の分際で――――!!』
『核』がなければ、自分の復活の工程が滞ってしまう。当然ラクシャサは、怒りに震えた。
『『それ』は、我の物だ!! 返せ!!』
ラクシャサから二人に向かって、四方八方から攻撃が開始された。
「オン マイタレイヤ ソワカ――――」
印を結ぶハヤブサから、新たに紡がれる『真言』
ハヤブサの周りで燃えるように揺らめいていた青白い炎のような光が、バンッ!! と、音を立てて、綺麗な球状に形を変えた。それは、ハヤブサとシュバルツを中に包み込み、ラクシャサの攻撃から、二人を守った。
「シュバルツ!! 絶対に、この結界から外には出るなよ!!」
印を結び、結界に『気』を込めながら、ハヤブサは叫んだ。
奇跡的にラクシャサの『核』から逃れることができたとはいえ、シュバルツはまだ『呪』によって、その霊体を具現化している、か細い存在であることに相違ない。その身体が少しでもラクシャサに触れてしまえば、また強引に、その『核』へと戻されてしまう事だろう。そうなってしまったら、もう一度このように助け出すことは、ひどく困難なことになってしまう。
冗談ではない、と、ハヤブサは強く思った。
ここでシュバルツを失ってしまっては、例えその後にラクシャサを倒したとしても、その勝利の意味は自分にとっては皆無に等しいものとなる。シュバルツがいないその後の自分の『生』に、いったい、何の意味があるというのだろう。
だから、失うわけにはいかない。
何が何でも
この命に代えても
絶対に、守り切って見せる――――!
「叭―――――ッ!!」
ハヤブサは、結界の強度を最大限に上げる。
ラクシャサの絶え間ない攻撃を、すべて弾き返す。
だが、邪神の邪悪な意志を持った攻撃は、術者にダメージを与えてきた。
「ぐ………!」
堪えるが、それでも低い呻きが漏れる。
「ハヤブサ!!」
案ずるような愛おしいヒトの悲鳴に、ハヤブサは振り向き、少しの笑みを見せた。
心配するな。大丈夫だ。
そう意思を伝えるのに、どうして――――この愛おしいヒトは、涙を浮かべて心配そうにこちらを見つめているのだろう。
(ハヤブサ……!)
ハヤブサを見つめながら、シュバルツは唇をかみしめていた。
額から流れ落ちる汗。
印を結ぶ手が、小さく震えている。
ラクシャサから攻撃を受けるたびに、低い呻きが唇から漏れている。
分かる。
ラクシャサの『核』から脱出できたとはいえ、まだここは、ラクシャサの体内に等しい場所だ。その中で、彼の邪神の邪悪な魔力をすべて遮断する結界を張り続ける――――その行為が、どれだけハヤブサに消耗を強いているか、想像するに難くなかった。
酷くダメージを受けているはずなのに
それでもこちらに『心配するな』と、笑みを浮かべることができる、優しい人。
そんな彼に、自分は
何をしてあげられることができるのだろう――――
(何もできないな……私は………)
代わりに結界を張ることも、ハヤブサの前に立って戦うことも出来ない自分。
シュバルツは、己の無力を痛感する。
どうして―――――
こんなにも、役に立たない自分を、ハヤブサは―――――
「………………」
ボウ、と、音を立てて、ハヤブサの張る結界が燃える。
『呪』とは、心の具現化だ。結界に込められているハヤブサの『心の声』が、そのまま『呪』によって具現化されているシュバルツにも流れ込んできた。
――――生きよう。
その声は、シュバルツに呼びかけてきた。
――――生きよう。
――――生きよう。
――――共に、生きよう。
帰るんだ。
絶対に。
俺たち二人で。
愛すべき人たちの待つ、あの場所へ――――
キョウジの顔が
ドモンの顔が
隼の里の人たちの顔が
次々と訴えてくる。
帰ってきて
どうか無事で――――
待っているから
(ああ、本当にそうだな)
シュバルツもまた、強く想った。
一心に、こちらの無事を祈ってくれている人たちがいる。
その人たちを、哀しませるわけにはいかないのだと。
(帰ろう。二人で)
いつしかシュバルツは
ハヤブサのそばに立ち、その背中にそっと手を添えさせていた。
独りじゃない。
死ぬときは、共に。
そして、生きるのも 共に――――
その想いを込めて、シュバルツは、ハヤブサのそばに立ち続けていた。
「…………!」
背に添えられてきた愛おしいヒトの手。
この手が、自分にどれだけの『力』を与えてくれているか、このヒトは分かっているのだろうか?
そうだ。
俺は今、独りではない。
愛すべきヒト。守るべきヒト。
そのヒトのために、俺はここに立っている。戦っている。
恐れも迷いも消える。
このヒトのためなら、どんな苦痛にも耐えられた。
なんとも単純な自分の『心』――――もう、龍の忍者は苦笑するしかない。
だが自分は、どこまでも強くなれる。
こんな風に、想い、それだけで、幸せになれる相手と巡り会えた。
これは、自分の人生において――――どれだけ幸運なことなのだろう?
さあ、来るなら来い。
打つなら打て。
この程度――――凌ぎきってみせる。
闇の中、更に煌々と輝きを増す、ハヤブサの結界。
(な………何だ……!? これは………!)
攻撃を加えながら、邪神ラクシャサは戸惑うばかりだ。
何故?
何故だ?
如何に『核』を奪われたとはいえ、吾は『神』だ。
その吾が―――――
どうして、人間如きの『結界』を破ることができない?
馬鹿な………!
吾の力が、人間より劣っている――――?
そんな筈は、ない。
そんなことが、あってたまるか――――!!
『目障りだ!! 死ねい!!』
さらに激しくなる、ラクシャサの攻撃。
四方八方から、刃物や武器が降り注いできた。
「ぐっ!!」
さすがに堪えることが出来ず、小さな悲鳴が上がる。
「ハヤブサ!!」
「案ずるな!! この程度………問題ない!!」
歯を食いしばりながら、ハヤブサはそろりそろりと龍剣に手を伸ばしていた。
どれほど激しく攻撃をされようが、自分は、凌ぎきる自信があった。
しかしこのままでは――――優しすぎる愛おしいヒトが、邪神から攻撃される俺の身を気遣うあまりに、結界の中から勝手に出て行ってしまいかねない。そうなってしまったら、最悪の結果しか待ち受けてはいない。あまりここに留まり続けるのは得策ではない、と、ハヤブサは判断していた。
とにかく一度シュバルツをラクシャサの身体の外に出す必要がある。
今のままではこの愛おしいヒトの状態は不安定なままで―――――また、ラクシャサに取り込まれてしまいかねないからだ。
そのための打開策がほしい。
一瞬で良い。脱出するための隙が欲しい。
何か、手はないか?
何か手は―――――
ハヤブサがそう必死になって模索し始めた時―――――『それ』は起きた。
ドカン!!
派手な音がして光が爆ぜ、空間が衝撃で揺らされる。
『――――――!?』
「何だ!?」
その場にいた全員が状況を把握しきれず息を飲み、辺りを見回していると――――すぐにまた、第2、第3の衝撃波が、激しく空間を揺らし始めた。
「豪熱マシンガンパ―――――ンチ!!」
「ローゼス・ハリケ―――――ン!!」
ラクシャサはここで、初めて外から攻撃して来ている者の存在に気付く。そしてその姿は、ハヤブサたちの視界にも捉えられていた。
「チボデー!! ジョルジュ!!」
シュバルツの叫びに、ハヤブサが振り向く。
「知っているのか!?」
「ああ。彼らは弟のドモンと同じ、『シャッフル同盟』の仲間で――――」
シュバルツのその言葉が終らぬうちに、また空間に、『ドカン!!』と、ひときわ激しい衝撃音が響く。ラクシャサの身体を構成していたケーブルや肉片が飛び散り、空間に、少しの風の流れをもたらした。
そんな中を、ぱきっとケーブルを踏み砕く音を立てながら、一つの影がそこに入ってくる。その陰の正体を見極めた瞬間、シュバルツから素っ頓狂な声が上がった。
「ド、ドモン!?」
「………! 兄さん! やっと見つけた………!」
赤いマントと鉢巻をなびかせながら、金色の光をその身に纏った『キング・オブ・ハート』―――――ドモン・カッシュがその空間に入ってきた。彼は兄であるシュバルツの姿を認めた瞬間、心底ほっとしたような表情をその面に浮かべたのだった。
「シュバルツ……キョウジ兄さんが待ってる。一緒に帰ろう」
ドモンはシュバルツに向かって、一直線に歩を進めてくる。それにハヤブサが待ったをかけた。
「待てっ!! ドモン・カッシュ! シュバルツを俺の結界から出そうとするなよ!!」
「なんだ、居たのか。リュウ・ハヤブサ」
「『居た』もなにも――――最初から俺は、シュバルツのそばに居るが?」
ハヤブサの顔を見て、あからさまに嫌そうな顔をするドモンに対して、ハヤブサもしれっと言葉を返す。ドモンに好かれようが嫌われようが、一向にお構いなしと思っている節があった。ドモンもそれが面白くないのか、ますます眉間にしわを深く寄せる。
「兄さんを離せ!! 兄さんは、俺が助けるんだ!!」
「人の話を聞いていなかったのか? シュバルツを結界から出したら駄目だと言っているんだ!」
「お、おい、二人とも!」
シュバルツは慌てて、喧嘩になりそうな二人を止めた。
「今は喧嘩などしている場合ではないだろう? 第一ここは敵の真っただ中で――――」
「そんなことは分かっている!! 俺は何でハヤブサの野郎が、兄さんにべったりくっついていないといけないんだと聞いているんだ!!」
「ドモン、私は別にハヤブサにくっついているわけではないんだ。これは、必要にかられた措置で――――」
「おい、この馬鹿に事の顛末の説明は必要か?」
ハヤブサが、心底うんざりといった表情でシュバルツの方を見る。シュバルツも眩暈に襲われるのを感じた。ハヤブサとドモン――――この二人がそろうと、とても心強いのだが、どうしてこの二人は、こうも仲が悪いのだろう?
「おい! 貴様……! 俺のことを『馬鹿』と言ったか?」
ハヤブサの言葉に、要らぬ反応を示すドモン。それに対してハヤブサも、別に悪びれもせずに口を開いた
「ああ。それがどうかしたか?」
「貴様に『馬鹿』呼ばわりされる筋合いはない!! 俺を『馬鹿』と言っていいのは師匠と兄さんだけだ!!」
(あ、そうなんだ)
ドモンの言葉に妙な感心をするシュバルツを尻目に、不毛な言い争いは続行された。
「お前、ちょっとは自分の馬鹿さ加減を真面目に考えた方がいいぞ? 二人から『馬鹿』呼ばわりされているというのに――――」
『おい!! 貴様ら!! いい加減にしろっ!!』
ここでラクシャサの怒鳴り声が、この言い争いに割って入ってきた。3人が振り向くと、怒りでわなわなと震えるラクシャサの姿が視界に飛び込んでくる。
無理もないな、と、シュバルツは思った。今の今まで、ものの見事に、華麗に無視されていたのだから。
『人間の分際で、吾に恐れもせぬとは何事か!! 貴様らの立場を、もう一度思い知らせてくれる!!』
ラクシャサからの攻撃が、ドモンに向かっていく。しかし――――
「吻!!」
ドモンはラクシャサからの攻撃を、あっという間に粉砕した。
『な―――――!』
息を飲むラクシャサ。それと同時にあることに気が付いた。ドモンの身体を包む金色の光。それが、自分を構成している『モノ』を、強制的に消滅させていっている、という事実に。
(この男は本当に危険だ!! 何としても、ここで葬り去らなければ――――!!)
ドモンを見るラクシャサの目つきが変わった。
「おい、今のうちに脱出するぞ」
ドモンとラクシャサが相対しているうちに、ハヤブサはシュバルツにそう声をかける。しかし、シュバルツからは猛反対された。
「何を言っているんだ!? ハヤブサ!! こんなところにドモンを独り置いて行けというのか!?」
「完全に置いていくわけではない。一旦お前を外に出すだけだ」
「駄目だ!! 弟を置いて私だけ脱出するなんて―――――そんなことは出来ない!!」
「あの馬鹿を見てみろ!! ちょっとぐらい置いて行ったって大丈夫だ!!」
ハヤブサの視線の先には、ラクシャサの攻撃を端から粉砕しているドモンの姿がある。その戦う姿は危なげはなく、このままここを任せてもいいぐらいだと思った。しかし、シュバルツは尚も頭を振った。
「それでもここは、邪神の体内だぞ!? 万が一の間違いが起こらないとも限らない!!」
「だから!! 弟よりもお前の方が、今はもっと危ないんだ!!」
ハヤブサはそう言って、何とかシュバルツを説得しようと試みるのだが、シュバルツの方が頑として、首を縦に振ってはくれない。
(この………兄馬鹿め!!)
この事態にハヤブサは内心泣きそうになる。しかし、そんなシュバルツに対して、ハヤブサもこれ以上強く言うことは出来なかった。自分の身よりも、弟を守ろうとする――――彼がそう言うヒトであることは、自分も百も承知だった。そんな彼だからこそ、自分は、好きになったのだから。
(これが、惚れた弱みってやつかな……。結局俺も『馬鹿』なのかな……)
ため息を吐くが、どうしようもない。ハヤブサは、開き直ることにした。
絶対に、このヒトは弟を守るために動く。
俺は、それに後れを取るな。
何が何でもこのヒトを、守り切って見せる――――!
ハヤブサは自身の意識を、ドモンとシュバルツの動きに向けて、何が起こっても対処できるようにそっと身構えた。
「貴様が今回の黒幕か……! お前を倒せば、すべての片がつくって事だな?」
ラクシャサの攻撃をすべて退けたドモンが、指をバキバキと鳴らしながら、一歩前に踏み出す。それを、歯噛みしながら見つめていたラクシャサであるが、不意に小さく息を吐くと、その面ににやりと笑みを浮かべた。
『いかにも我がこの戦いを仕掛けた者だ……。面白き『気』を纏う人間よ』
フオン、と、音を立てて、ラクシャサの右の掌に、黒い球体状の物が浮かび上がってくる。
『吾の攻撃をすべて退けたその腕は見事………。なれば、これはどうかな……?』
そのままラクシャサは、無造作にその黒い球体を放り出した。それは、空気のように軽い物なのだろう。ふわふわと宙を漂いながら、ゆっくりとドモンの方に近付いていく。
「フン―――――」
ドモンは鼻を鳴らしながらそれを見ていたが、やがて、おもむろに拳を構えた。
「何を企んでいるかは知らんが、こんなもので俺を倒せるものか!」
(あ………! あれは………!)
対してハヤブサは、その球体の危険性をいち早く察していた。ハヤブサは一度ラクシャサと戦って、それを封印することに成功している。それ故に、対ラクシャサの知識には一日の長があった。
「待てっ!! ドモン・カッシュ!!」
ハヤブサは必死に呼びかけようとした。その球体状の物に、攻撃を加えてはいけないと。
だが当然、そんな制止が間に合うはずもなく、ドモンの拳は球体に向かって動いた。
「―――――!」
それは、シュバルツにしてみれば脊髄反射のようなものだったのだろう。
ハヤブサの様子から弟の危機を察してしまった兄の身体は、勝手に動いていた。
(やっぱりか!)
シュバルツが動くと察していたハヤブサも、間髪入れずに動いた。
すべては、愛おしいヒトを失いたくない――――その一心からであった。
ドモンの拳と、球体が接触したその瞬間。
弾け飛んだ球体から、放射線状に勢いよく飛び出してくる――――質量を伴った『闇』
「ドモン!!」
その闇が弟に襲い掛かる前に、兄の身体が弟を庇う。そしてその庇うシュバルツの前に、ハヤブサが体を入れた。
ドゴオオオオオオッ!!
轟音とともに、その一帯は闇に包まれて―――――
そこが静けさを取り戻した時には、その場所には誰もいなくなっていた。邪神ラクシャサを除いて―――――
「ククッ………フハハハハハ!」
邪神の、勝ち誇った笑い声が、辺りに響く。
「思い知ったか! 人間共め! わがディメンション・ホールの力を!! 貴様たちは次元と次元のはざまに落ちた!! 己が無力を呪いながら、そこで朽ち果てていくがよい!!」
ただ、自分の『核』となるべきものまで、一緒に次元のはざまに落としてしまったのは残念だった。あれだけは手元に残して、着実に自分の中に取り込みたかったのだが。
ただラクシャサは、無言で復活した自分の身体と、手足を見る。このまま地上に出ても、問題ないほどに身体は出来上がっていた。それに、自分が人間界へ進出するのを阻んでいた龍の忍者の結界も、今はもうない。
(完全復活に足りなかったエネルギーは、人間界で補えばよいか)
ラクシャサはそう判断すると、もう一度あの闇の球体を今度は己が掌から三体生み出した。己の身体を、人間界に運び上げるために。
『クククク………。待っておれ、人間共め………』
フオン、と音を立てて、闇の球体が不吉な輝きを帯びる。それがそのままどんどん膨れ上がり――――
球体同士が接触した瞬間、凄まじい轟音と粉塵が巻き上がった。
そして、それらが収まり、辺りに静けさが戻ったとき―――――
その空間には、もはや誰の姿もなかった。
「ぐっ!!」
「うわっ!!」
間抜けな悲鳴とともにチボデーとジョルジュがキョウジたちのそばに現れた時、そこにいた一同は、ただ目を丸くするしかなかった。
「チボデー! ジョルジュ!」
「どうしたんだよ!? ドモンの兄貴は一緒じゃないのか!?」
アルゴとサイ・サイシーの呼びかけに、チボデーは肩をすくめるしかなかった。
「いや、それが―――――俺達にもよくわからないんだよ」
「ええ………敵に攻撃を仕掛けていたら、急に激しい爆発が起こって―――――」
「ドモンはどうした!?」
キョウジの問いかけに、チボデーは首を振るしかない。
「ドモンは、向こうの世界でシュバルツとハヤブサを見つけたんだ。だが、俺たちがそこにたどり着いたときには、シュバルツがもう既に敵の手に落ちて、その姿が変えられていて―――――」
「それでもドモンは、その中にシュバルツさんの『本体』を見つけたようなんです」
補足説明をするように、ジョルジュが口を開く。
「ドモンはその『本体』のほうに飛び込んでいったんです。我々は外から援護しようと攻撃を仕掛けていたら、いきなり爆発が起こって………」
「おい!! 何だこりゃあ!?」
ここでようやく現実世界でも変わり果ててしまったシュバルツの姿に気がついて、チボデーが素っ頓狂な悲鳴を上げる。
「まさか………?」
問いかけるジョルジュに、キョウジは苦い顔をして頷いた。
「そう………あれは、『シュバルツ』だ………」
その刹那、激しい地鳴りと唸り声が、辺りの空気を揺らす。ドグワッ!! と、響き渡る粉塵を伴った轟音。そして、これまで沈黙を守っていた『シュバルツ』が、ここで初めて動いた。その身体が一回り大きくなり、盗聴部分にヒトの形をした『モノ』が現れる。
「クククク………初めまして、かな? 人間共よ……」
「……………!」
それを見聞きした瞬間、キョウジは全身が怒りで総毛だつのを感じた。何故ならその『モノ』は―――――『シュバルツ』の形を模していたのだから。
「そして……すぐに別れることになる……。貴様たちは―――――」
「――――お前、何者だ? シュバルツはどうした!?」
静かだが、ひどく鋭い響きを持った声が、ラクシャサの言葉を遮る。ラクシャサがそちらに視線を向けると、自分が模した格好と同じ姿をした男が、そこに佇んでいた。
「ほう……面白き姿をした者よ。お前は何者だ?」
「シュバルツはどこだと聞いている!!」
ラクシャサの問いを聞き終わるより先に、声を荒らげるキョウジ。それに『シュバルツ』の格好を模したラクシャサは、冷笑を以って答えた。
「吾が、シュバルツだ」
「嘘だ!! お前はシュバルツではない!!」
ラクシャサの言葉を一刀両断にするキョウジ。いつもの穏やかな彼の様子からは、考えられない激しさだった。東方不敗はそんなキョウジの様子を見て、その面ににやりと笑みを浮かべた。普段温厚なこの男が隠し持つ鋭い牙―――――それが剥き出しになる瞬間を見るのは、やはり、何度見てもいいものだと、東方不敗は思った。
それに、キョウジがこれだけ激高するということは、相手は『邪悪』以外の何者でもなく、それは存分に叩きのめしていい、ということになるのだから。
(さあ……わが主はお怒りだ。フフフ……腕が鳴るわい)
東方不敗は今――――歓喜に震える自分の身体を、抑えるのに苦労しなければならなかった。
「シュバルツはどこだ!? シュバルツを出せ!!」
そんな東方不敗の心情を知ってか知らずか、激高するキョウジの言葉はなおも続いた。
「クククク………知りたいか?」
シュバルツの姿を模したラクシャサは、キョウジを嘲るように、楽しそうに笑う。非力な人間が吠え立てたところで、痛くも痒くもない。暇つぶしの余興に過ぎないからだ。
「シュバルツとやらは、死んだぞ? 吾に敗北して、消えたのだ」
こう言えば目の前の人間は傷つき、己が無力を悟って首を垂れると思った。しかし、目の前の小さな人間は、首を垂れるどころか、ますますこちらを睨み付けてきた。
「『死んだ』と言うのなら―――――死体を出せ」
「…………!」
「それを見ないと、私は納得などしないぞ。早くしろ」
こちらの言動行動に怯むことなく、しかも、ある意味非常識な要求をしてくる静かな低い声。ラクシャサは、非常に面白くなかった。己が頬がひきつるの感じた。
(人間ごときが………!)
理解に苦しむ。
非力なくせに、どうして自分に立ち向かってくるのだろうか。
ざわつく。
イラつく。
こいつだけは―――――徹底的に叩きのめさなければ気が済まない。
「お主……その容姿、『シュバルツ』ととても縁の深い者だな………? しかも、この作り物のこの身体―――――造ったのは、お主か?」
「そうだと言ったら?」
キョウジの低い声に、ラクシャサは口の中で「クッ」と暗く笑った。
「人間が作った物にしては、ずいぶんと『業』の深い物で作られているな………。吾は『邪神』と人に呼ばれるものなれど、その吾の力が、よく馴染む」
「…………!」
「礼を言おう、人間よ……。この暗黒の身体と力、気に入ったぞ。人類を滅ぼした暁には、お主を吾らの末席に加えてやらんこともない。お主は十分『邪悪』だ……」
そのままラクシャサは、高らかに嘲るように笑い続ける。キョウジはそれを、冷めた目で見ていた。
今更だ。
自分の罪が重なって、沢山の血が流れて―――――
その果てに、シュバルツが産み出されたことは、十分承知している。
自分が罪にまみれているのも、邪悪と言われても仕方のないことも、事実だから受け止められた。
そこから目を背けるつもりも、逃げ出すつもりもない。
ただ――――
(シュバルツ………)
きっと、シュバルツを傷つけてしまった。
罪のない彼に『罪』を突き付けてしまう。業を背負わせてしまう―――――ただそれだけが、キョウジにとっては苦かった。
(……………!)
こちらが嘲っても、まるで顔色を変えずにこちらをまっすぐ見据えているキョウジの態度に、ラクシャサのイラつきはさらに募った。
「思い上がるなよ!! 人間が!! 貴様など――――わが拳一振りで、簡単に潰れるのだからな!!」
無造作に振り上げられた拳が、キョウジに向かう。
だがそれが、キョウジの身体に到達する前に、東方不敗が立ち塞がった。
「吻ッ!!」
銀髪の老人は、邪神の拳を弾いて一蹴する。
「―――――!」
少し眉を吊り上げる邪神に、東方不敗はにやりと笑みを見せた。
「猪口才な……! 我が王に用があるのなら、ワシを通してからにしてもらおうか!」
(………その『王』っての、やめてもらえないかな~………)
苦笑するキョウジに気付いているのかいないのか――――老人は嬉々として構えをとる。
キョウジも、特にそれに対して何も言わずに黙っていた。嬉しそうな東方不敗の機嫌を損ねるのは、きっとよろしくないことだと思うのだ。
「キョウジよ……。あ奴をどのように倒すことを望む? 蟻のように踏みつぶすか、粉微塵にするか――――」
「マスターの意のままに――――と、言いたいところですが、少しだけ、倒すのを待ってもらえませんか?」
「ほう……何故じゃ?」
疑問の視線を投げかけてくる老人に、キョウジは邪神のほうを見据えながら答えた。
「マスターは、あの中に………ドモンの気配を感じますか?」
「気配じゃと?」
東方不敗は鸚鵡返しに答えてから、改めて邪神のほうに視線を送った。キョウジに請われるままにドモンの気配を探ってみるが、愛弟子の気配はそこには感じられなかった。
「何も感じぬが………」
感じたままをこたえる東方不敗に、キョウジはまた、別の質問を投げかけてきた。
「では――――マスターは、ドモンが『死んだ』と思いますか?」
「―――――!」
キョウジの質問に、少し驚く東方不敗。だが彼には確信があった。「ドモンは死んではいない」と。それを東方不敗がキョウジに告げるよりも先に、そのそばにいたサイ・サイシーが口を開いた。
「ドモンの兄貴は死んじゃいないよ!!」
「…………!」
「おいらには分かるんだ!! 紋章が教えてくれているよ!! ドモンの兄貴は生きているって!!」
そう言いながらサイ・サイシーは、キョウジに向かってシャッフル同盟の『クラブ・エース』の紋章をかざす。それは、シャッフル同盟のほかの面々も同じ想いのようで、皆右手の紋章を光らせながら、各々頷いていた。
「だろうな。私もそう思う」
キョウジは邪神を見据えながら、言い放った。
「ドモンにシュバルツ―――――そして、ハヤブサまでもが揃っている状況で、こんな邪神に後れを取るなど、あり得ないんだ!!」
ラクシャサは、己の頬が引きつるのを感じた。目の前のキョウジは、その面にやけに穏やかな笑みを浮かべていた。その態度に、どうしようもないほどの腹立たしさを感じるのは何故なのだろう。
「そう――――ドモンたちは死んではいない。だが、あの邪神によって、どこかに閉じ込められている可能性はある……」
キョウジの言葉にマスターアジアの眉がピクリと動き、皆がキョウジに注目をする。
今、この戦いの指揮を執っているのはキョウジ。誰もがそう感じ取っていた。
「皆の力を合わせれば、あの邪神を倒すことは簡単だ。だが、あの邪神を今倒してしまうことで、ドモンたちがその次元に、閉じ込められっぱなしになってしまったら――――?」
「……………!」
「それに、あの『邪神』はおそらく完全復活には至っていない。わざわざシュバルツの姿を模していること、そして、全体的に動きが鈍く、半植物のような形態をとっていることを見てもわかる」
「ほう…………」
キョウジの言葉に、邪神の頬がひくひくと引きつる。
いろいろとこちらのことを見透かすような発言―――――この男は危険すぎると断を下さざるを得なくなった。
「いちいちこざかしい奴め!! 吾の力が完全ではないかどうか、貴様自身で確かめてみるがよい!!」
叫ぶラクシャサから、雨あられと降ってくる攻撃弾。
だがキョウジは、それを見ても避けようともしない。微動だにせず、立ち続けていた。
そして当然、それを黙って見ている東方不敗ではない。
「しゃらくさい!!」
キョウジの前に立ち、その攻撃を老人はすべて防ぎきる。そのまま、ラクシャサと東方不敗の戦いは続き、まるで、一騎打ちのような様相を呈してきた。
その間、キョウジはその場から一歩も動かない。東方不敗の後ろで、じっとラクシャサを見据え続けていた。
「おい、兄さん! 無茶しすぎだ!! いくらあの邪神に腹を立てたからと言っても――――!」
その場から一歩も引こうとしないキョウジの様子を見かねたチボデーが、こそっと声をかけてくる。それに対してキョウジは、ふっと相好を崩した笑みを見せた。
「すまないな。私はあの邪神に対して、そんなに腹を立てているわけではないんだ。ただ―――――見てくれ」
キョウジは顎をしゃくって、チボデーに邪神の足元にある発電機の方を指す。発電機はいびつに歪み、バチバチッ! と、放電しながら不吉な音を立てていた。
「発電機が………壊れたみたいだ……」
「ええっ!?」
「なんですって!?」
「嘘だろう!?」
「…………!」
キョウジの言葉に、シャッフルの面々が、一様に息をのむ。
発電機が壊れる―――――それが、どういうことを意味するか、皆が察してしまったからだ。
「おそらく、結界も切れている………。あの邪神が人間を襲いだすのも、もう時間の問題だろうな……」
キョウジは拳を握りしめながら、邪神を見据え続けていた。
「邪神が人間を襲い、力を蓄え、完全復活をしてしまったら、それを倒すのはひどく困難なものとなる。だから、それを阻止するために、私たちは動かなければならないんだ」
その言葉に、皆が察した。これからの自分たちの役割を。
「OK ‼ わかったぜ! 兄さん!!」
「我々の役目は、ドモンたちが帰ってくるまであの邪神を引き付け、足止めをすることですね!」
「へっ! あんな奴相手にするなんて、朝飯前だぜ!!」
「…………!」
アルゴは相変わらず口を開かない。その代わり、胸の前で掌を拳で、バシン!! と、叩いた。戦いに向けての気合は、十分のようであった。
「それでは皆――――頼みます」
「応ッ!!」
キョウジに応えて、皆がそれぞれの場所に散っていく。各々の右手には、シャッフルの紋章が煌々と輝きを放っていた。
――――ドモン!!
――――私たちは、ここで戦い続けます!!
――――おいら、信じているから……!
――――必ず帰って来い!! ドモン・カッシュ!!
4人の胸に宿る願いは、皆、同じだった。
「フフフフ……相変わらず、無茶をしおるな……」
皆がそばを離れたのを確認してから、東方不敗はキョウジに向かって口を開く。
「邪神を挑発するはいいが、お主の行動、いささか蛮勇だぞ。それとも……お主は、ワシの腕を試したいのか?」
東方不敗のちょっと揶揄とも取れる物言いに、キョウジは苦笑するしかなかった。
「すみません……。でも、人々を守るには、この方法しか思い浮かばなくて……」
実際、自分が邪神と直接戦えるだけの腕がないから、こんなやり方はかなり無責任なものだと言われても仕方がなかった。何が何でも自分を守ろうとする東方不敗の腕を、実際当てにしすぎている。
「よい。キョウジよ。お主はワシの腕が、あの邪神に後れを取るものではない――――と、思ったからこその策なのであろう?」
そうです、と、キョウジが頷くと、東方不敗は満面の笑みをその面に湛えた。
「よかろう!! キョウジよ!! この東方不敗! お主の期待に見事応えて見せようぞ!!」
ダン!! と、強く踏み込むと同時に、東方不敗の身体から、ふつふつと強い闘気が沸き上がる。その強さ、激しさは、邪神ですら看過できないものとなっていった。
(それにしても解せんな……。キョウジは『人々を守りたい』と言っていたが……その『人々』とやらは、キョウジに何かをしてくれるものなのか?)
邪神に対して構えを取りながら、東方不敗の脳裏にそんな考えがふっとよぎる。
人は元々利己的なものだ。簡単に裏切るし、自分のために他人を踏みつけることなど平気でする。故に、人類など、こちらが命を懸けてまで守る必要はない。滅ぶのならば、滅んでしまえばいい、というのが東方不敗の考え方だった。
しかし、キョウジは少し違う考え方をする。
「そうですか? 私も結構利己的な人間ですよ?」
将棋をしながら他愛もない話をしていた時、ふっとそんな言葉がキョウジから漏れた。
「私は、平安無事に日々を暮らしていきたいだけです。それが叶うのなら、なんだってします」
いまいち話が見えずに首をひねる東方不敗に、キョウジはにこりと微笑みかけた。
「平安無事に暮らしたいのなら――――周りが平和でなければ、それは叶わないでしょう?」
「……………!」
「だから、それが脅かされて――――自分にそれが、対抗できる手段があるのなら、動く。ただそれだけのことです。そのために周りにどう思われようが評価されようが、それは私にはどうでもいいことだと――――そう思っています」
「それはそうかもしれぬが――――」
そう言いながら東方不敗が、盤上に駒を置いた瞬間、キョウジから声をかけられた。
「ん? マスター? その手はそこでいいんですか?」
「何?」
「そのまま行くと、私はあと3手ほどで王手で、マスターは詰みになりますが――――」
「ぬおっ!?」
東方不敗は慌てて盤上の戦況を見るが、自分が致命的なミスを犯したことは、もはや明白であった。
「うぬぬぬ………!」
頭抱えて唸ってみても、戦況は覆るはずもなく、東方不敗はきょう3度目の投了をせざるを得なかった。
「じゃ、約束通り、仕事に戻ってもいいですか?」
にこりと微笑みながら立ち上がるキョウジを、東方不敗は歯噛みしながら見送るしかない。
「キョウジよ!! 仕事とやらが終われば、またここに来い!! 今度こそ、返り討ちにしてくれる!!」
鼻息荒くそう言う東方不敗に、キョウジは「はいはい」と苦笑しながら頷く。キョウジが書斎に引っ込んだ後も、リビングに残った東方不敗は一人、盤上に残った駒を見ながら、自分が投了をするまでの流れに思いを馳せていた。
「……………」
勝ち負けはどうあれ、やはり、キョウジと将棋を打つのはいい。何一つとして無駄な手がなく、一つの駒に、二重三重の意味と罠を持たせている。これを読み解くのも楽しいし、これだけの手応えのある勝負をしてくれる相手もなかなかいない。やはり、東方不敗にとって、「キョウジ」という存在は、得難いものだった。
それ故に、歯痒くもある。これだけの才覚を持ちながら――――どうして、こんな都会の片隅でくすぶり続けていられるのだろう。
『世界平和』を望むのなら、その志を引っ提げて、天下に躍り出ればいいのだ。
自分の才覚に見合うだけの地位と権力を得て、そこで、その夢を実現すればよいのだ。自分は、それを全力で支える。それなのに、何故それをしないのだろう。
(まあ良い……。今は、その問題に熱くなっても仕方がない。今は、目の前の敵を倒すことが先決――――)
東方不敗は改めて構えなおした。
自分は、キョウジがどこで何をしていようが、その望みを全力で支える。それが、自分の役目なのだ。
キョウジには感謝している。
彼はいつだって―――――自分に戦う『動機』をくれる。
この東方不敗という男、実は、自分のためにふるう拳を持ち合わせてはいなかった。
彼の拳は如何なる時でも―――――誰かのために振るわれている。
キョウジが『自分のため』と言いながら、人々のために戦うと言うのなら。
自分もまた、同じ大義を背負うまでだ。
「まだまだぁ!! かかってこんか!! モンスターめ!!」
邪神の攻撃をはじき返しながら、東方不敗の闘気は天井知らずの勢いで膨れ上がっていった。
「こざかしい!!」
しかし邪神も負けてはいない。触手のようなケーブルを使って、辺りに攻撃を加える。この特殊なモノで構成された身体は、多少の攻撃を受けようが、すぐに再生をしてくれる。しかも、破壊された場所は、それ以上の強度を伴って復活してきていた。
「はははは!! ますます気に入ったぞこの身体……!! まさに、吾のために作られたようなものだ!!」
まだまだ強くなりそうな予感に、ラクシャサは歓喜に打ち震えていた。
どれだけ攻撃を加えられようが、今の自分にとっては痛くもかゆくもない。この目障りな人間たちを始末するのも、時間の問題のように思われた。
ドカッ!!
ラクシャサの振るった一つの触手がアパートの壁を穿ち、そこにあった棚を破壊する。礫が四散し、ラクシャサの目の前で立ち続けるキョウジの頬を打った。
「―――――っ!」
血が伝い落ちる。
それをぬぐうためにキョウジが手を動かすと、そこに一羽の折り鶴が舞い落ちてきた。
「……………!」
(直してあげたかったのに……)
直すどころか、ずたずたに傷つき、今は見る影すらなくなってしまった折り鶴たち。キョウジの胸が締め付けられた。
そっと手に抱え込んで、必ず直してあげるからと、祈る。それと同時に、今は行方が分からなくなっている、3人に思いを馳せた。
(シュバルツ……ドモン……ハヤブサ……。今、どこにいるんだ………?)
結局こういう時、自分は祈るしかできない。ひどく無力な存在だった。
どうか、無事で
無事で―――――
その時、折り鶴は、キョウジの掌の中で、小さく震えていた。だが、キョウジがそれに気づくことはなかった。
「ハヤブサ!! ハヤブサ!!」
(ああ、兄さんの声だ)
まどろむ意識の中、ドモンは兄の切迫した響きを持つ声を、聞くとはなしに聞いていた。
(俺は、どうしていたんだろう? 一体、何があったのだろう?)
ゆるゆると意識を覚醒させながら、これまでの経緯をドモン・カッシュは懸命に思い出す。
そうだ。
確か、邪神の中に、シュバルツがいるのを見つけて――――
それを取り戻すために、邪神の中に飛び込んで―――――
運良く、シュバルツと、ついでにハヤブサの野郎も見つけた。
そしてその傍に、今回の件の黒幕と思しき奴もいた。そいつが変に笑いながら、こちらに攻撃を仕掛けてきたものだから、迎え撃とうと思って――――
あの黒い球体に触れた瞬間、こちらに向かって襲い掛かってくるようにあふれてくる闇。
「ドモン!!」
避けなきゃ、と、思うよりも先に、兄の身体が自分に覆いかぶさってきた。間髪入れずに激しい衝撃に見舞われて――――
そして、現在に至る。
衝撃の割に怪我をしていない事実に、自分はまた、兄に庇われてしまったのだと知る。
(兄さんは――――!?)
慌てて周りを見渡して、ボロボロに傷ついて倒れているハヤブサと、それに必死になって呼び掛けている、シュバルツの姿を見つけた。
「兄さん!!」
ドモンが呼びかけると、シュバルツは振り向いて、少しほっとしたような表情をした。
「ドモン……気が付いたのか……」
だがシュバルツの顔色は悪いまま、再びハヤブサの方に向きなおっている。
「う……! う……!」
ハヤブサは身じろいでいる。大怪我をしているようだが、意識はあるようだ。
は、は、と、短く荒い呼吸をしている龍の忍者は、その手に印を結び続けていた。
「ハヤブサ……! 私を庇って……!」
「―――――!」
シュバルツのその言葉に、ドモンはすべてを悟る。
つまり、ケガをしそうになった自分を、兄が庇って
その兄を、ハヤブサが庇ったのだということを
「どうして……!」
呆然とつぶやくシュバルツの目の前で、ハヤブサが、ぐ、ぐ、と、その身を起こそうとしていた。
「馬……鹿………野、郎……ッ!」
「ハヤブサ……!」
「言ったはずだ……! お前はまだこの世界では不安定な存在だと……! お前が少しでも、あの邪神に触れれば………! お前はまた……『核』として取り込まれて……! もう助けられなくなって……しまう………!」
「…………!」
ハヤブサの言葉にシュバルツは息を飲み、ドモンの眉が吊り上がる。
「絶対に……! 俺の結界から……出るなよ、シュバルツ……!」
荒い息をしながら、印を結び続ける龍の忍者。ドモンが周りを見渡すと、弱々しいが、自分と兄の周囲を、結界が覆っているのが分かった。ハヤブサは怪我をしているが、傷口から血が滴り落ちるままにしていた。彼は、自身の手当てよりも、結界を張り続けることを優先しているようだ。………ただひたすら、シュバルツのために。
「………………」
ドモンはふっと、小さく息を吐くと、 自身の周りに金色の『気』を張り巡らせた。それは一つの玉となって、シュバルツとハヤブサの周囲を覆う。
「………ったく……。結界ぐらい俺が張ってやるから、傷の手当てをしろ」
ぶっきらぼうに言い放つ。ハヤブサが少し伺うようにこちらを見るから、ドモンは、何故か居心地が悪い思いがした。
「礼は言うぞ! 兄さんを助けてくれたからな!」
ツーン、と、そっぽむくドモンにハヤブサは苦笑すると、ようやく結んでいた印を解いた。
「………ッ、う………!」
ガクッとくずおれる身体。それを、シュバルツが慌てて支えていた。
「ハヤブサ……! 大丈夫か……?」
「ああ………」
優しく抱き留めてくれるシュバルツに、ハヤブサは、すり、と、甘えるように身を寄せる。
「ところで、シュバルツ……」
「どうした? ハヤブサ……」
「お前、いつの間に服を着ているんだ?」
「はい?」
ハヤブサの言葉に、きょとん、とするシュバルツとドモン。シュバルツは、いつもの革のロングコートの姿になっていた。
「いつの間にって……いつまでも素っ裸でいるわけにはいかないだろう? ちょっと念じたら、服はすぐに出てきたぞ?」
「…………!」
「兄さんがいつまでも裸だと落ち着かないからな……。ちょうど良かったんだ」
シュバルツの言葉にうんうんとうなずくドモン。その横でハヤブサは、がっくりと頭を垂れていた。
(そ、そんな……! せっかく久しぶりに、シュバルツの素肌を堪能できると思っていたのに……!)
知らず、地面にのの字を書きながら、しくしくと泣き出してしまうハヤブサ。
「何泣いているんだ? お前……」
そんなハヤブサをシュバルツはあきれたように見つめ、ドモンは阿呆かとため息をついた。
「なんだ、元気そうじゃないか。兄さん、こんな奴、心配するだけ無駄だぞ」
「それはそうかもしれないが――――」
あきれ返りながらも、ハヤブサの治療に取り掛かるシュバルツ。ハヤブサが持っている傷薬を傷口に塗り込み、包帯を巻く。あれだけの状況で、体に深くダメージを負っているのに、致命傷は受けていないハヤブサの身体。さすが、龍の忍者と言ったところだろうか。
「ところで、ハヤブサ」
「なんだ? ドモン・カッシュ……」
シュバルツの治療を受けながら、ハヤブサが顔を上げる。視線が合ったのを確認してから、ドモンは口を開いた。
「お前は、さっきのあの球体の攻撃がどういうものか知っていたな? お前はあいつと戦ったことがあるのか? あいつはいったい何者なんだ?」
「あいつは、邪神『ラクシャサ』だ……。あいつはとにかく、人間というものを敵視している。事あるごとに、人類を滅ぼそうとしてくる奴なんだ……」
とある任務を遂行していた時、その黒幕が邪神ラクシャサだった。壮絶な戦いの末――――自分は、その封印に成功していたはずなのだが。
「俺が衰弱したと同時に、封印の力も衰弱したと見えるな。封を破って、出てきてしまったらしい……」
話しているうちに、シュバルツの治療は終わったらしい。「ありがとう」とハヤブサが声をかけると、シュバルツはにこりと笑みを返していた。
今回はハヤブサに助けられたようなものだし、兄に仲のいい友人がいる、ということ自体はいいことだと思うのだが、ドモンにしてみればやはり、何となく面白くはなかった。兄にあんな風に治療をしてもらうのは、自分だけでいいと、どうしても思ってしまうのだ。
「封印をした、ということは、一度奴と戦って勝っているんだな? じゃあ、ここはどこだ? ここから脱出することは可能なんだろう?」
むかつく気持ちを堪えて、ハヤブサに問いかける。しかし、どうしても口調がぶっきらぼうになることを、ドモンは抑えられない。
「ああ。ここは次元の狭間だ。……気をつけろよ。外の乱流に流されてしまったら、どこに飛ばされるか分からん……。しっかりと結界を張って――――流されないようにするんだ……」
そう、ドモンに忠告をするハヤブサだが、やはり、どこか苦しそうだった。
「ここから脱出することは可能か?」
問いかけるシュバルツに、ハヤブサは少し難しい顔をする。
「可能なことは可能だが……自力では難しいな……」
あの時は、隼の里の者たちが、懸命に呼びかけてくれた。その声を頼りに、自分は、奇跡的にこの空間から脱出することができたのだ。
「あの時は、隼の里も襲われたからな……。皆が懸命に呼びかけてくれたのだが……」
「『これ』は、外からの導になるんじゃないのか?」
ドモンがそう言いながら、右手の甲をかざす。そこには『シャッフル同盟』の『キング・オブ・ハート』の紋章が、輝きを放っていた。
「俺たちシャッフル同盟は、紋章を通してつながっているんだ。今――――この紋章を通じて、ほかの仲間たちが戦っているのが分かる」
そう。
紋章から仲間たちの想いが伝わってくる。
「早く帰って来い」
彼らは口々に、そう呼びかけ続けてくれていた。
「よし、ドモン・カッシュ。その紋章の声を頼りに……この空間を進むことは可能か?」
ハヤブサの問いかけに、ドモンはフン、と、鼻を鳴らす。
「俺を誰だと思っている! それぐらいは、朝飯前だ!」
いかん、とは思いつつも、どうしても口調がぶっきらぼうになるドモン。ハヤブサの方も、ドモンがこちらに愛想がないのはいつものことなので、特段気にすることもなかった。
「じゃあ……任せていいか? 『キング・オブ・ハート』」
「フン!!」
ドモンは勢い良く、くるりと踵を返す。しかし、すたすたと2、3歩歩きかけたところで、ぴたりと足を止めてじっと立ち止まってしまった。
「……………」
じっと紋章を見つめ続けるドモン。どうやら紋章から聞こえてくる声を、聞き取るのに必死なようだった。
「………結界を張る役を、代わってやろうか……?」
せめて、ドモンにかかる負担を少しでも軽くしてやろうかと、ハヤブサが申し出る。しかし、ドモンはその申し出をバッサリと拒否した。
「余計なお世話だ!! お前にやれたことが、俺にやれないはずがない!!」
「…………!」
「いいから大人しくしていろ!! お前は怪我人なんだから――――!!」
「お、おいドモン――――!」
ドモンの口が過ぎている、と感じ取ったシュバルツが、たしなめるように口を開く。だが、ツン、と、そっぽを向いたドモンは、さらにぶっきらぼうに言葉をつづけた。
「兄さんと俺を助けてくれた、その恩義を返させろ!!」
「――――!」
きょとん、と、目を見開くハヤブサに、「今回は特別だからな!!」と、ドモンは乱暴に告げると、再び紋章の方に向いて、その声に集中しだした。シュバルツはやれやれ、と、一つ息を吐き、ハヤブサは軽く苦笑していた。
「やれやれ……すまないな、ハヤブサ……。素直じゃない弟で………」
「いや、いい」
自分に対してつっけんどんにならざるを得ないドモンの気持ちも分かる。彼は嫉妬しているのだ。自分とシュバルツの仲が良すぎることに。
しかし、それを言うなら自分だって同じだ。自分だって―――――シュバルツがドモンに対して向ける眼差しには嫉妬している。ドモンはキョウジとはまた違った意味で、シュバルツにとっては『特別』だった。
シュバルツは、彼のためならばどんな苦難も耐えるだろう。そして、『弟』であるドモンの存在は、『兄』であるシュバルツを支え、強くしている。そんな風にシュバルツを支えることができるドモンが、ハヤブサは心底羨ましかったりした。
自分は、どうだろうか?
果たして、自分はシュバルツにとって『特別』になれているのだろうか。
自分にとってシュバルツは―――――何物にも代えがたい、もう特別な存在なのに。
こんなこと、気にしてもせんの無いことだとは分かっている。
だが―――――どうしても、そう問いただしたくなる夜もあった。
我ながら、馬鹿だなと思う。
自分がシュバルツを好きなら―――――自分の心を信じて、ただ一途に貫けばいいものを。
「………………」
少し進んでは立ち止まり、少し進んでは立ち止まりを繰り返す、ドモンたち一行。
しかし、しばらくすると、徐々にドモンの歩むスピードが上がりだした。どうやら、この空間で紋章の声を聴く作業に、ようやく慣れだしたらしい。
「順調だな……」
ハヤブサを支えながら歩くシュバルツが、ぽつりと漏らす。だが、ハヤブサは浮かない顔をしていた。
(このままいけば――――そろそろ『来る』か………?)
前に戦った時もそうだった。
この空間から何が何でも自分たちを出したくないとラクシャサが目論むのならば、そろそろ仕掛けをしてくる頃合いだった。
悪意の塊のような邪神、ラクシャサ。
その仕掛けというのが、こちらの嫌なところを突いてくるのは確実だった。そして、自分の核となるべきシュバルツを、特に集中して狙ってくるだろう。
できれば、この愛おしいヒトを、そんな目には合わせたくはないが―――――
この時、少し先を歩んでいたドモンの足が、ぴたりと止まる。
そして、拳を構えてファイティングポーズをとった。どうやらこの先に、何らかの異常を検知したらしい。
(来た………!)
ハヤブサもまた、シュバルツを守って立とうとする。だが、シュバルツにそれは窘められてしまった。
「お前は、じっとしていろ……。私が守るから――――」
「シュバルツ……!」
優しい言葉に嬉しさがこみ上げるが、同時に複雑な気持ちにもなる。
今――――危ないのは、シュバルツの方であるからだ。
邪神ラクシャサは、核になるはずであったシュバルツに執着している。3人の中でも特に、シュバルツへの攻撃が激しいものになるだろう。
「…………」
ハヤブサは、フ―――ッと深く息を吐くと、結界を張る印を結ぶ準備をしておくことにした。最悪の場合でも、せめて、愛おしいヒトだけでも守り通せるように。
「……………」
静かにファイティングポーズをとり続けていたドモンであるが、やがて、何かに気が付いたのか、拳を鋭く振りぬいた。
「吻ッ!」
パキ、と、音を立てて、ドモンの拳から細かい光の粒が四散する。何かの礫が飛んできているようだ。ドモンは難なくそれを払いのける。礫の数が二つ三つと、徐々に増えていったが、それも危なげなく対処していた。
「フン、この程度の攻撃――――」
「ドモン!! 気をつけろ!! 周囲から来るぞ!!」
「――――!」
シュバルツの声にドモンがはっと顔を上げると、無数の礫が周囲を取り囲み、こちらに向かってきているのが見えた。
「猪口才なッ!!」
ドモンは鉢巻を額からとって、ピン、と、両手でまっすぐ伸ばした。すると、鉢巻きが固い槍のようなものに変化していた。己の『気』を鉢巻きに送り込み、鉢巻きの硬度を変えたのである。
シュバルツもまた、礫に対して構えをとった。
「シュバルツ!! 礫に直接触れることは避けろよ!!」
「分かってる!!」
間髪入れずに飛んできたハヤブサの声に応えると、シュバルツは持っていた二本の刀を抜刀した。そのままドモンとシュバルツは、ハヤブサを守るように互いの背で庇いあうと、四方八方から襲い来る礫に、見事に対応していた。
「へっ! 俺と兄さんに対して、こんな攻撃が通用するものかっ!!」
「ドモン・カッシュ!! 油断するな! 『次』が来るぞ!!」
「!?」
ドモンがハヤブサの声に驚いて振り向いた時には、もう彼らの上空には、巨大な手があった。そのままその手はブオン、と、不吉な風切り音を立てながら、彼らに猛スピードで近づいてくる。まるで小さな虫の命を、無造作に奪うがごとくに。
「な―――――!」
「ドモン!!」
息をのむ弟に、兄の身体が覆いかぶさってくる。
「兄さん!?」
守ろうとしているのに、これではあべこべだと、ドモンは悲鳴を上げそうになる。しかし、その手が皆の身体に届くことはなかった。
「オン マイタレイヤ ソワカ――――」
真言に合わせて、ボウ、と、青白い炎のような光を放ちながら、ハヤブサの結界が立ち上がる。それは3人の身体をすっぽりと覆うと、巨大な手の攻撃を拒絶した。
バアンッ!!
結界と衝突した手が、激しい音を立てる。
「ぐうっ!!」
その衝撃は術者に跳ね返る。たまらずハヤブサは、小さな悲鳴を上げていた。怪我をした身体――――痛みを、堪えきれなかった。
「ハヤブサ!!」
案ずるように身を起こすシュバルツに、ハヤブサは笑みを浮かべる。
「問題ない……。大丈夫だ……」
「しかし……!」
「馬鹿野郎!! 怪我人が何をやっているんだよ!?」
ドモンの怒声にハヤブサもシュバルツに向けていた表情とは打って変わってしかめっ面を向ける。
「……だったらもう少し結界の強度を上げろ……」
「言われなくともやっているっ!!」
バンッ! と、音を立てて、ドモンの周りに金色の結界の光が爆ぜる。
「それに、こんな攻撃など――――!」
ぶわっと音を立てて再び振りかぶってくる巨大な手を、ドモンはきっと睨み据える。
「石破!! 天驚拳――――――!!」
迫りくる掌に合わせて、ドモンから金色の気合弾が放たれる。それは、巨大な掌に『驚』の文字を刻み込んで―――――それをあっという間に粉砕していた。
「この俺には通用しないんだよ!!」
フン! と、鼻息荒く言い放つドモンに、ハヤブサは「そうか」とだけ答えると、結んでいた印を解いた。
「おい! それだけか!?」
ひどくあっさりと引き下がった龍の忍者に、ドモンは少し違和感を覚える。いつものハヤブサであるならば、こんな時、自分に対して嫌みの一つぐらい言ってきそうなものであるのに。
「………何か、問題でもあるのか?」
じろりと睨んできたハヤブサの所作が、少ししんどそうな物であることに、ドモンは気づいてしまう。しかし、「別に」としれっと返した。ハヤブサを素直に心配することが、ドモンにはどうしてもできないのだ。
「ドモン、余計なことに気を回すな。攻撃に警戒しつつ、紋章の声を聴くことに集中しろ」
シュバルツからそう声をかけられる。ドモンは素直に頷いた。
「ハヤブサ……。大丈夫か?」
ドモンが頷いたのを確認してから、シュバルツはハヤブサに声をかける。ハヤブサは「ああ」と答えるが、その息遣いがやはり、少し苦しそうであった。
(ハヤブサを守りたい……。しかし、彼を守るには私はどうすればいい……?)
シュバルツがそう考え込む横で、ハヤブサもまた、考えを巡らせていた。
(やはり……先ほど食らったダメージが響いている……。結界を完璧に張ることができるのも、あと3回が限界、と、言ったところだな……)
せめて、気力の回復が望めればいいのだが、この空間ではそれも難しいだろう。シュバルツを助けるために、結界の張り時、力の使い時を精査せねばならぬとハヤブサは思った。
「兄さん、行くよ。動けるか?」
ドモンに声をかけられて、忍者たちは立ち上がる。そのまま歩みだそうとした時、仄暗い笑い声があたりに響き渡った。
―――――ククククク………。面白きことよ……。お主らはまだ、ここから脱出できる気でいるのか………?
前方に影が揺らめき、ボウ、と音を立てて巨大な角を生やした長髪の男の姿が形作られていく。
「ラクシャサ――――!」
ハヤブサがポツリと漏らした言葉に、シュバルツもドモンも驚き――――そして、警戒感を露わにしていた。
「ああ。脱出できる気でいるとも! 貴様を倒してな!!」
ドモンがバキバキと指を鳴らしながら、一歩前に踏み出そうとする。
「行くな!! ドモン・カッシュ!! それはまやかしだ!!」
「――――!」
ハヤブサの声に、ドモンは踏みとどまる。それにシュバルツはほっと胸をなでおろし、ラクシャサは頬を引きつらせていた。
「クククク……。久しいの、龍の忍者……。お主とここで会うのは二度目だったな……」
「……………」
ハヤブサは、ラクシャサの言葉に沈黙を返す。ラクシャサはにやりと笑うと、手を軽く振った。再び礫が一行を襲う。
「そんな攻撃は通用しないと言った!!」
一声吼えたドモンから放たれる石破天驚拳は、その礫たちをあっという間に一蹴した。
「そのようだな……」
ラクシャサはにやりと笑うと、戦い方と、その標的を変えた。
「まったく……お主らも酔狂よな……。何故その『化け物』を守ろうとしている?」
「―――――!」
その言葉にシュバルツは「自分のことを言われた」と思い、ハヤブサは、「愛おしいヒトを侮辱された」と思い、ドモンは「何を言っているんだ? こいつ」と、眉をひそめた。
「化け物? ここに化け物などいないぞ?」
「居るではないか。貴様の後ろ――――」
その言葉が終わらぬうちに、ドモンの拳がブオン、と、音を立てて放たれる。だがそれはむなしく素通りして、そこにいるラクシャサが『まやかし』であると、証明されただけだった。
「ここに『化け物』などいないっ!! 居るのは兄さんだけだ!!」
ドモンが吼えるのを、ラクシャサはにやにやと笑いながら聞いていた。
「この光景を見ても――――貴様らはそいつが『化け物ではない』と、言えるのか?」
「何?」
訝しむ一行の前の視界に、スクリーンのような物が浮かび上がってくる。そこに映し出されたものを見て、シュバルツは思わず叫び声をあげていた。
「キョウジ!!」
キョウジは既に、あちこちにかすり傷を作っていた。
それでも彼はまっすぐと立ち、強い視線をあるものに向け続けていた。
だが、その周りにあるケーブルのようなものがのたうつのを見た瞬間、シュバルツは悲鳴を上げそうになってしまった。
分かってしまったからだ。
あのケーブルは、『DG細胞』が暴走したが故に、出てきてしまったものなのだと――――
そして、そのケーブルを辿っていった先にある、そそり立つ樹のような、巨大なケーブルの塊、さらに、その上に形作られているものを見て―――――
「――――――!」
シュバルツは声にならない悲鳴を上げていた。
何故ならそこには、紛うことなき『自分』の姿が形作られていたからだ。
(そ、そんな……! 私が……! 『私』が、キョウジや皆を―――――)
知らず、よろめいてしまう身体。
それを、ハヤブサが無言で抱き止めていた。
シュバルツに少し余裕があれば、ハヤブサが唇を噛み切ってしまうほどに、それを噛み締めていると気づくことができたであろう。だがシュバルツは、そこまで冷静になれなかった。
(ああ……! キョウジ……ッ!)
小さく震える身体。
低い呻き声が、その唇から漏れる。
また――――また、突き付けてしまった。
キョウジの『罪』を
また彼に、突き付けてしまったのだ。
どうして
どうして―――――
「クククク……お主の身体は、確かに我が頂いたぞ。よほど邪悪な物で出来ていると見えるな。主の身体………この吾の力によく馴染む……」
シュバルツが激しく動揺していると見て取ったラクシャサは、我が意を得たと言わんばかりに楽しげに口を開いた。
「分かったであろう? そこにいるのは『化け物』だと。お前らがどんなにそれを否定しようと勝手だが、そこにいる『シュバルツ』とやらは、もう帰る身体すら無いのだ……!」
そのまま、耳障りな高笑いが、辺りに響く。
「……………!」
ドモンもハヤブサも、怒りが最高潮に膨れ上がっていた。
はらわたが煮えくり返っていた。
(くそ……!)
できれば、今すぐにでも一矢報いてやりたい。
どうやって、あいつを殺してやろうかと算段する。
しかし――――目の前にいるラクシャサが、まやかしに過ぎないことはとうに承知していた。今のままでは、何も打つ手がないのが現状だった。
悔しい。
悔しい。
あまりにも―――――無力。
「違う!!」
そのとき力強い声が、辺りに響いた。
皆が驚いて顔を上げると、スクリーンの向こうにいるキョウジが、声を上げていた。
「違う!! シュバルツは、必ず帰ってくる!! お前などに――――消されはしない!!」
「何度言ったら分かる!? 吾が『シュバルツ』だ! 見よ!! この身体の力を――――!!」
キョウジと相対している『ラクシャサ』が、己の力を誇示するかのように触手のようなケーブルを振り上げる。それは一直線にキョウジへと向かった。しかし、彼の身体にそれが到達する前に、東方不敗によって、それは破壊されていた。
ドグワッ!! と、派手な音を立てて四散したそれは、細かい破片となって、周りにいる人々を傷つける。だが、キョウジはそこに立ち続けていた。怯むことなく、『ラクシャサ』を睨み続けていた。
「見よ!! この身体!! この破壊力!! お主らがどんなにこちらを攻撃したところで、この身体は甦る!! 吾を倒すことなど不可能だ!!」
ゲラゲラと笑いながら、力を誇示するようにケーブルたちを振り回す。
チボデーたちもそれらをよけながら、懸命に攻撃をするのだが、彼の邪神の言葉通り――――こちらの攻撃の力が吸収され、邪神の力に変換されていくのを手助けしているように感じられるだけであった。
「畜生! これじゃきりがないぜ!!」
「しかし――――! ここで私たちがこれを放り出すわけには……!」
チボデーの悲鳴にジョルジュが答える。だが彼も、戦えば戦うほど、こちらが不利になっていくように感じられる状況に歯噛みしていた。
「ドモンの兄貴はまだかよ!?」
サイ・サイシーの問いかけに、明確な答えを返せる者は誰もいない。その横でアルゴが、無言で「ガイア・クラッシャー」を放っていた。
「…………!」
キョウジの前で構えをとりながら、東方不敗もまた迷いの中にあった。
戦っても相手に利するだけのように見えるこの状況。セオリー通りいくのなら、いったんこの場は放棄して、作戦と戦力を立て直すのがベストの判断のように思えた。
しかし―――――キョウジが。
自分が『主』と仰ぐキョウジが、ここから一歩も引く構えを見せない。
ここで戦う自分たちの腕を信頼しているのか。
それとも、自分たちの後ろにいる人々の安寧を願っているのか。
それとも、信じているのか?
ドモンが
ハヤブサが
そして、シュバルツが
この状況から帰ってくると………!
信じるのは大いに結構だが、根拠もなくやみくもにただ信じる行為は危険すぎるともいえた。仲間を信じすぎたばかりに、ここで全滅の憂き目にあってしまうのなら、それは『蛮勇』という愚かな行為と何ら変わりがないからだ。後に待ち受けているのは、ただ、最悪な事態だけだ。
決断することも必要だった。
仲間を切り捨てる、非情な決断をする勇気。
(キョウジは、優しすぎるからな……)
東方不敗は覚悟を決める。
必要とあるのならば、自分がその断を下す覚悟を。
自分にとっては何より優先すべきはキョウジの命。
彼さえ無事でいてくれるのなら――――この先、如何様にも状況を立て直すことができる。
そう信じ切れるほど、東方不敗にとって『キョウジ』という存在は絶対的だった。
「キョウジよ。この戦況をどう読む?」
東方不敗はキョウジにそう問いかけた。この先の自分の行動を、決断するために。
「厳しいですが、チャンスはあります」
東方不敗の問いかけに対して、キョウジの口調は冷静そのものだった。『情』ではなく、『智』でこの状況を判断している証だった。
「ほう……? 何故そう言い切れる?」
「『あいつ』はまだ――――『核』となる『シュバルツ』を得ていませんから――――」
キョウジはそう言ってにこりと微笑むと、今度は邪神に対して問いかけ始めた。
「なあ? そうだろう? お前はその中に、まだ『核』を得ていないのだろう?」
「……………」
邪神からの答えはない。だがキョウジは、構わず続けた。
「『核』を得ていないお前はただ――――自分の『神気』によってのみ、その動力源を得ているんだ。だから、今は力を吸収しているように見えても、やがて、限界が来る――――」
「…………!」
その言葉に邪神は絶句し、周りで戦っている者たちの表情は、ぱっと明るいものになった。
「本当かい!? それは!!」
サイ・サイシーの問いかけに、キョウジは優しく頷く。
「ああ。本当だ。『核』を得ていない以上、あいつはこれ以上進化のしようがない。後は力が飽和したら――――崩れ去るのみだ」
そう。キョウジは知っていた。
DG細胞が真にその『核』を得て、暴走したらどうなるか―――――そのスピードと強さを、彼は身をもって知っていた。
強大な強さだった。
とても、手が付けられなかった。
その一薙ぎは周囲を破壊しつくした。
その炎は、街を焼き尽くした。
DG細胞が真に暴走を始めたら、こんな風に足元に立って、平気でいられるはずがない。
相手がまだ、ただの空の器だとわかる。だから、ここから退く理由もなかった。
退けば――――相手に『時間』を与えてしまえば、それこそ、こちらが不利になるだけだ。
「なるほど………」
東方不敗も、キョウジの言い分には一応納得はした。
しかし、今の戦況がかなり不利なものであることに変わりはない。
どこまでここで粘るか、見極めねばならぬと思った。
「…………」
その時、モニター越しにキョウジの姿を見つめていたハヤブサが、あることに気付く。
「おい……! 見ろ、ドモン・カッシュ」
だからハヤブサは、すぐにドモンに声をかけていた。
「あのキョウジの手元をよく見ろ……。何か、光っていないか?」
「手元?」
きょとん、としながらドモンがキョウジの手元を見ると、確かに、キョウジが何かを大事そうに抱えていて、それが、白い光を放っているのが見える。
「キョウジ!! キョウジ!!」
ハヤブサが、キョウジに呼びかけを始めた。
「お前も呼んでみろ、ドモン・カッシュ」
「兄さんに、聞こえるのか!?」
驚くドモンに、ハヤブサはさらに言葉をつづける。
「分からん。だが、呼びかけてみる価値はある……。あれは、時空を超えるような――――そういう類の波動を感じる光だ」
「まさか………?」
ドモンは半信半疑になりながらも、キョウジに呼びかけを始める。
「兄さん!! 兄さん!!」
「キョウジ!!」
シュバルツもまた、キョウジに呼びかけを始めた。すると、こちらの声が聞こえたのか―――――キョウジがきょろきょろと辺りを見回し始めた。
「ドモン? シュバルツ?」
「キョウジ!!」
「…………!」
ここでキョウジは初めて、この声が自分の手元から聞こえていたと悟る。そっと覗き込んで――――驚いた。何故なら掌の中で折り鶴が淡い光を放ち、その中にドモンとシュバルツとハヤブサの姿を映し出していたのだから。
「ドモン!!」
思わず叫んでしまうキョウジに、その場にいた全員の注目が集まった。
「何っ!?」
「ドモンの兄貴が見つかったのか!?」
「分からない……! 少し、待ってくれ……!」
キョウジは戸惑いながらも、再び折り鶴に向かって声をかけた。
「ドモン!! ドモンなのか!? 今どこにいるんだ!?」
「詳しくはわからない。でも、全員無事だ! 安心してくれ、兄さ――――!」
ここでドモンの映像が、強制的に電源を落とされたかのように、ぶちっと切れた。
「おのれ!! もう許さぬ!!」
現実世界のラクシャサと、異世界のラクシャサが、同時に叫ぶ。
「先ほどの言葉と言い、今の出来事と言い――――!! キョウジとやら!! 貴様はもう、絶対に許さん!!」
「……………!」
「貴様だけはこの吾が!! 直々に踏みつぶしてくれる!! 覚悟しろぉ!!」
グワッ!!
無数のケーブルが、キョウジに向かって襲い掛かっていった。
「兄さん!? 兄さん!!」
ドモンたちの方も、いきなり消されてしまったキョウジの映像の名残に向かって、必死に声を上げていた。そこに、ラクシャサの耳障りな高笑いが響いてきた。
「クククク……! 貴様らもここまでだ……! 今――――現世とこの次元との繋がりを、総て絶った!!」
「なにぃ!?」
ギリ、と、歯を食いしばりながら睨み付けるドモンを、ラクシャサは愉快そうに笑いながら見下ろす。
「貴様らはこの次元の嵐の中で――――朽ち果てるが良い!!」
高笑いとともに、ラクシャサの姿が消える。それと同時にたちまち空間の磁場が乱れ、激しい嵐のような現象に包まれていた。
「う……ッ! く………ッ!」
瞬間的に、結界を張っているドモンへの負担が大きくなったのだろう。ドモンが苦しそうなうめき声をあげていた。
「大丈夫か!? ドモン!!」
シュバルツの案ずる声に、「平気だ!」と、ドモンは答えてみせる。彼は一つ大きく深呼吸をすると、『気』を入れなおしていた。バシン!! と、周りに張られている結界から音が聞こえて、結界の中の空間が安定したものになる。
「しかし……これからどうする? ここから脱出しなければならないが――――」
シュバルツの言葉に、皆がそれぞれ脱出の方法を思案する。すると、ドモンが突然声を上げた。
「シュバルツ! あそこに兄さんがいる!!」
「何っ!?」
「どこだ!?」
驚く忍者たちに、ドモンは指示(さししめ)して見せた。
「ほら、あそこ――――!」
ドモンの指さす方向に、忍者たちも目を凝らす。
すると確かに、小さいが、きらきらと光り輝く白い光を見つけた。
「確かに……あれは、キョウジの手元で光っていた光と、同じ類のもののようだが………」
「じゃあ、あの光は、兄さんたちの世界とつながっているのか!? あそこに行けば、この次元から脱出することも可能なんだな!?」
矢継ぎ早に問いかけてくるドモンに、ハヤブサは少し難しい顔をする。
「分からんが……行ってみる価値はあるな……」
そうこうしているうちに、光が小さくぼやけていこうとしている。
「大変だ!! 追いかけないと――――!」
そう叫んだドモンが、足を踏み出そうとして―――――そこで、止まってしまった。どうやら、何らかの不具合を感じたらしい。
「どうした? ドモン」
「いや、それが………」
シュバルツの問いかけに、ドモンは軽く口を濁す。そこにハヤブサが声をかけてきた。
「………前に進もうとすると、結界の強度、大きさが―――――保てなくなる………か?」
「―――――!」
ハヤブサの指摘に、絶句するドモン。
違う――――! と、彼は叫びたかったが、その通りなので、反論するべき言葉を失ってしまった。
「別に、恥じることでも何でもないぞ、ドモン・カッシュ……。この時空の嵐の中でそれに逆らって進もうとすれば、それなりの力を必要とする……。それこそ、よほど結界を張りなれた術師のような存在でなければ、結界の強度を保ちつつ、進むことなど、ほぼ不可能なのだから………」
(くそ………!)
ハヤブサの言葉を聞きながら、ドモンは歯噛みする。
おそらく自分一人だけなら、自分の周囲に結界を張りながら進むことも可能だ。
しかしそれは――――この空間で、シュバルツと離れることを意味する。
この時空の嵐の中で離ればなれになってしまうことは何としても避けたかった。下手をしたら、これが今生の別れにもなりかねないからだ。しかもこの兄は、弟である自分が無事に脱出できる術を持っていると知れば、「自分に構わずお前だけでも行け」と、言い出しかねない。
それだけは絶対に嫌だった。
脱出は皆でしなければ意味がない――――ドモンは、そう思っている。
「………お前一人がここを進む分の結界は、問題なく張れるんだな?」
ハヤブサの言葉に、ドモンは素直に頷く。ここは、意地を張っている場合ではなかった。
「……………」
しばらく思案をしていたハヤブサであるが、やがて、決意を固めたようにその顔を上げた。
「分かった……。俺が、シュバルツと自分の分の結界を張ろう」
「ハヤブサ!?」
「…………!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツとドモンは息をのむ。
「それは、ありがたい話だが――――」
ハヤブサの申し出をすぐに受けようとするドモンに対して、シュバルツは首を横に振っていた。
「だめだ! ハヤブサ、お前は重傷を負っているんだ! 今お前が無理をしてそんなことをすれば、お前の身体が――――!」
「じゃあ、生き延びるために、お前はどう行動をとるんだ? お前がここで犠牲になろうとすれば、そこにいる弟も、必然的に巻き込まれようとするぞ」
「――――!」
シュバルツの言葉を遮るように出てきたハヤブサの言葉に、彼は絶句してしまう。
「あ…………!」
呆然と、弟の方に視線を走らせると、懸命に縋るようにこちらを見つめている、ドモンと視線が合った。
「そうだよ、兄さん……! 俺は、いやだ……!」
そう言いながらドモンは、シュバルツの手をぎゅっと握ってくる。
「兄さんだけを犠牲にして助かるのは、俺はもう絶対に嫌だっ!!」
「ドモン……」
「それにシュバルツ。お前は絶対に帰らなければならない理由があるはずだ」
「理由?」
小首をかしげるシュバルツに、ハヤブサは頷く。
「そうだ……! キョウジのために――――」
「……………!」
「キョウジが産み出したモノは、決して邪悪な物ではない、ということを証明するために」
「―――――!」
「お前は、それこそキョウジの一生涯を通して、それを彼に証明し続けていく義務があるのではないのか!? シュバルツ!!」
「あ…………!」
このハヤブサの言葉は、本当に胸に刺さった。
でも、そうなのだ。
自分が生まれ落ちたのは、確かにキョウジの罪と涙の果て。
自分を構成しているモノは、キョウジが殺してしまった人間の遺体と、暴走したDG細胞。
だが――――そこにあったキョウジの『心』は、とても綺麗な物だったはずだ。
そうだ。帰らなければ。
自分の存在は『罪』だけではないと、キョウジに伝え続けるために。
彼の元に、帰らなければ――――!
シュバルツの瞳に、俄然強い光が宿り始める。それを見たハヤブサは、やれやれと小さく微笑んだ。
「話は決まったな……」
そんなハヤブサに、シュバルツは申し訳なさそうな瞳を向けた。
「すまない、ハヤブサ……。私が、自分で結界を張ることさえできれば――――」
そう。
シュバルツは『気』を使う精神的な技の発動は、全くと言っていいほど出来なかった。この現象には、生みの親であるキョウジも首をひねるしかない。何せその技の極意を知っていたとしても、それを体現することができないのだから。
つまるところ、機械仕掛けの身体と普通の人間の、決定的な違いがここだということなのだろうか。
苦虫を噛み潰したような顔をするシュバルツに、ハヤブサは優しく微笑みかける。
「気にするな……。俺も、自分が生き延びる確率が高い方を、選んでいるに過ぎないのだから………」
「ハヤブサ………」
「その代わり――――」
ハヤブサはシュバルツの肩に、ポン、と手を置く。
「俺は正直、結界を張ることでもう手一杯になる……。だからシュバルツ、お前が、俺の身体を運んでくれるか?」
「分かった。それは、任せてくれ」
シュバルツが笑みを見せてくれたのを見て、ハヤブサもまた、安堵の息を吐く。
そう。生き延びるのなら、皆で――――
それは、3人の間で一致した気持ちであった。
「話が決まったのなら、行こう。早くしないと、光を見失ってしまう」
ドモンの言葉に、皆が頷いた。
「では……やるぞ」
ハヤブサはふーっと大きく息を吐くと、静かに印を結びだした。
「叭――――――っ!!」
真言を唱え、『気』を入れる。シュバルツとハヤブサの周りを、ハヤブサの結界が覆った。それを確認してから、ドモンが結界を一人分の大きさにまで縮める。
「……………!」
外の時空の嵐の衝撃が、もろにハヤブサにかかってくる。それ故に、彼の口から小さな呻き声が漏れた。
「大丈夫か?」
シュバルツが心配そうにのぞき込んでくる。平気だ、と、頷いた。このヒトを守り通さなければならないのに、痛いとかしんどいとか、言っている場合ではないと思った。
ただ、結界を張ることだけに集中する。
雑念は捨てた。愛おしいヒトに、これ以上余計な心配をかけないように。
「……………」
時空の嵐を突き破るように、ドモンが進んでいく姿が見える。その後を追うように、シュバルツが自分を抱きかかえながら進んでいた。
「―――――ッ!」
進めば進むほどに、抵抗が激しくなってくる時空の嵐。ハヤブサはそれを、歯を食いしばりながら耐えていた。
時折、シュバルツが自分を抱きかかえている手に力を入れているのが分かった。
自分の身を、案じてくれているのだと悟る。……無上の幸せを感じた。
(ああ、このままここで死んでもいいな)
ともすれば、霞みそうになる意識の中で、朦朧とそんなことを思う。だがそのたびに、ハヤブサは頭を振った。
(だめだ……! ここで死んではだめだ……! ここで死ねば、シュバルツを巻き込んでしまう……!)
自分の命が尽きるのはいい。
だが、ここで結界が解けてしまえば、シュバルツはこの時空の乱流の中に独り、放り出されることになってしまう。死ねない身体を持ったシュバルツは、下手をすれば永遠に、時空の狭間を彷徨わなければならなくなるかもしれないのだ。
(それは駄目だ……!)
ハヤブサは強く想う。
シュバルツを、そんな哀しいめに遭わせたくはない。自分が願うのは、ただ愛おしいヒトの幸せそうな笑顔だけだ。
「シュバルツ!」
叫ぶキョウジが、嬉しそうにシュバルツを抱きしめる。シュバルツもまた、キョウジを幸せそうに抱きしめ返す。
そんな光景が、見たいと思った。
それを見届けてから死ねたら―――――最高だ。
苦しい。
目が霞む。
ドモンの背中越しに小さな光が煌く。
あの光
あの光さえ、見失わなければ――――
ああ
遠い
後、どれぐらいだ?
「ハヤブサ……。大丈夫か?」
優しい問いかけに、頷く。だが、笑顔を見せられているかどうかは自信がない。普段から、あまり笑いなれてはいないから。
それにしても気のせいだろうか。
先ほどから、光が揺らめいているように見える。
「……………?」
いや、気のせいではない。
先ほどから光が、小さく右に左に揺れている。
ハヤブサが目を凝らすと、それはだんだんと鳥の姿へと、その形を変えていった。
「鳥だ……」
どうやら前を行くドモンにも、光が同じように見えているようで、ドモンもぽつりとつぶやく。
その鳥は、まるでこちらを導くかのように、嵐の中を静かに、しかし力強く飛び続けている。一同はその鳥の後を、懸命について行っていた。
「キョウジッ!!」
東方不敗がキョウジを抱きかかえ、横っ飛びに飛ぶ。襲い来る触手たちから、間一髪、キョウジの身を守った。
「おのれ!! 逃がさぬ!!」
東方不敗が体制を立て直すよりも前に、ラクシャサは再び触手たちにキョウジを襲うよう命じる。
「おおっと! 行かせるか!!」
「ローゼス・ハリケーン!!」
チボデーとジョルジュが、その触手たちを破壊した。「ギャッ!!」と、悲鳴を上げ、一瞬怯むラクシャサ。その隙に東方不敗はキョウジを抱きかかえ、建物の影に隠れることに成功していた。
「大丈夫かい!? キョウジの兄ちゃん!!」
サイ・サイシーの問いかけに、「ああ」と、キョウジは笑顔を見せる。
「キョウジよ。ここは危険じゃ。もう少し下がって――――」
一息ついた東方不敗が、そう言いかけて言葉を止める。何故ならキョウジが、懸命に己が手の中を見つめていることに気付いたからだ。
「どうした? キョウジよ」
「あ………マスター……」
東方不敗の問いかけに、キョウジが顔を上げる。
「さっきからこの折り鶴が、光っているように見えて―――――」
「光っているだと?」
キョウジに言われるままに東方不敗も折り鶴を覗き込むと、なるほど、確かに、淡い光を鶴が纏っているように見えた。
「……この鶴は、さっきドモンたちの世界とこちらをつないでくれたんです。だからもしかしたら――――この『光』が、ドモンたちをこちらの世界をつなぐ物になっている可能性が高くて―――――」
「……………!」
その時、キョウジたちが身を隠している建物の壁を、ラクシャサが攻撃してきた。ドカン!! と、辺りに轟音が響いて建物が揺れ、瓦礫が四散し、粉塵が舞い踊った。
「おのれ!! キョウジめ!! どこへ逃げようと無駄だ!!」
さらに触手を振り回し、建物を破壊しようとする。その前にアルゴ・ガルスキーが立ちはだかった。
「ガイア・クラッシャ―――――ッ!!」
アルゴが拳で砕いた地面から、バキバキと音を立てて、巨大な壁のようなものが立ち上がってくる。それがラクシャサの触手を阻み、進路を阻んだ。
「おのれ!!」
ラクシャサはその壁を壊そうと躍起になるが、次々と隆起してくるその壁は、なかなか思うように破壊が進められない。
「フェイロン・フラッグ!!」
その間をサイ・サイシーがちょこまかと動き回り、旗状の武器でラクシャサを攻撃していた。そのおかげで東方不敗とキョウジの間に、少しの間会話をする余裕が生まれた。
「マスター………」
「うん?」
「この鶴を、預かっていただけませんか?」
「何故じゃ?」
怪訝な顔をする東方不敗に、キョウジは軽く笑みを見せた。
「この鶴は今――――絶対に失ってはならない物です。ならば、あの邪神に集中的に狙われている私が持つよりも、マスターが持たれていた方が―――――」
「馬鹿者。絶対的に大切な物であるならば、なおさらお主が持っておけ」
キョウジの提案を、東方不敗は一蹴する。
東方不敗にとって、絶対的に大切な物は、ただキョウジのみ。それ以外はなかった。
そのキョウジが『大切だ』というのなら、大切なもの同士で固まっておけばいいと、東方不敗は思う。その方が、守りがいがある、というものだった。
「しかし……! 私の身に何かあって、この鶴が駄目になってしまったら――――」
「馬鹿者!! お主の身に何かあるはずなどあるか!!」
「……………!」
東方不敗の怒鳴り声に、キョウジは思わず気圧されてしまった。
「ここにおる皆が、お前のことを守る!! この状況で、お主の身に危険など、及ぼうはずがない!!」
「え………? え……?」
「そうだぜ、兄さん。それにその鶴は、お前さんが持っていた方がいい」
戸惑うキョウジに、チボデーが声をかけてきた。
「ドモンは……師匠のことも俺たちのことも、とても大切に想ってくれているのは分かっている。だけどこの中で、一番ドモンに声を届かすことができるのは、兄さんなんじゃないのか?」
「そうなのか?」
チボデーの言葉に、キョウジは目をぱちくりとさせる。「でもそれだったら、きっとレインちゃんの方が――――」
「まあ、レインは確かにこういうシチュエーションでは適任だが、今、いないしな」
キョウジの言葉にチボデーは苦笑するしかない。
「きっと異世界にいるドモンだって、兄さんの声が聞こえたら、きっと必死になってそちらのほうに行こうとするさ。なんてったってあいつ、兄さんのことが大好きだからな……」
筋金入りのブラコンだから――――と、一言余計なことを呟いて、チボデーは後ろにいるジョルジュにどつかれていた。
「アハハハ……でも、分かったよ、ありがとう」
キョウジは苦笑しながらも、チボデーに同意した。
「何とか、ドモンに呼びかけ続けてみる」
そう言うキョウジの手の中で、その折り鶴は、淡い光を放ち続けていた。
「く……! う………!」
懸命に堪えようとするが、どうしても低い呻きが漏れる。
荒れ狂う時空の嵐の中、重傷を負った身体で、結界を保ち続けることが、ハヤブサにとって徐々に困難なものになりつつあった。
(まだだ……! まだ……力尽きるな……!)
それでも自身を叱咤激励しながら、懸命に結界を張り続けるハヤブサ。
「ハヤブサ……!」
愛おしいヒトの、心配するような声が聞こえてくる。
ああ
案ずるな。
俺は―――――大丈夫だから………
「…………!」
不意に、脇腹のあたりに生暖かい感触を得る。
邪神よって傷つけられた傷口が、裂けたのだと悟った。
(どうか、シュバルツには気づかれませんように……)
ハヤブサは懸命に、そう祈る。
そう。
今、傷口が裂けているとシュバルツに悟られてしまったら――――心優しい兄弟のことだ。自分たちが助かるチャンスを棒に振ってでも、こちらの身体を治そうとしてしまうかもしれない。
それではだめなのだ。
自分の望みは、この愛おしいヒトの幸せ。それ以外は、無いのだから。
自分はどうなってもいい。この二人だけは助かってほしい。
「ハヤブサ……」
愛おしい人が、こちらの身体をぎゅっと抱きしめてくる。
ああ、もう十分だ。
十分俺は、幸せだ。
だから、俺はもういい。
だがもし、この世に『神』とやらがいるのならば、お願いだ。
この二人だけは、どうか助けてほしい。
霞ゆく意識の中、ハヤブサはただそれだけを、懸命に祈り続けていた。
―――――リュウ……
―――――リュウ……
不意に、自分の名を呼ばれたような気がして、ハヤブサは目を開ける。すると、いつの間にか自分は暗い空間の中に独りで佇んでいて、目の前には、大きくて美しい一羽の鶴が、そこに鎮座していた。
――――リュウ……
(……………?)
優しい女性の声が響く。
初めて聞くような声であるのに、どこか、懐かしさを感じるのは何故なのだろう。不思議に思って、ハヤブサは首をひねった。
―――――リュウ……。よくここまで、頑張ってこられましたね……
優しい声は、目の前の鶴から発せられている、と、気づくのに、少し時間がかかった。呆然と鶴を見つめるハヤブサの前で、鶴から聞こえてくる優しい声は、なおも続いた。
――――さあ、ここが「出口」です……。ためらわずに撃ってください……。
そう言いながら、鶴は大きな羽を広げて訴えかけてくる。
「ま、待てっ!」
ハヤブサは思わず声を上げていた。
「お前は何者だ!? 何故わざわざそんなことを俺に――――」
このとき鶴が、ふっとその面に優しい笑みを浮かべたように見えたのは何故だろう。
――――あなたのそばに………いてあげられなくて………ごめんなさい……
「…………?」
――――でも………私は………いつも、見守っています………。貴方のことを……。
どうか、幸せになって、と、その優しい声は言った。その瞬間、ハヤブサは気づいた。目の前にいる――――鶴の真の正体に。
「母上!!」
声を上げた瞬間、ハヤブサは現実世界に引き戻されていた。
「…………!」
戻されたと同時に、自分にぐっとかかってくる時空嵐の衝撃。
腕に伝い落ちてくる、生温い液の感触に、片口の傷も裂けたのだと悟る。朦朧としてくる意識――――血が流れすぎていた。
それでもかすむ視界の中、目の前を飛ぶ、光る鳥の姿を探す。するとその鳥は、すぐに見つけることができた。
時空嵐の中、飛んでいるように見えるその光る鳥。しかし、それはよく見ると、一か所に留まり続けていた。そして、羽を大きく広げていた。
ここが出口だ。
撃て。
そう訴えていた、あの鶴と同じように――――
その瞬間、ハヤブサは己が為すべきことを悟った。
「ドモン・カッシュ!!」
それ故に、ハヤブサは声を張り上げていた。しかしそれをした瞬間、腹から何かが逆流してきて、ハヤブサはそれを吐いた。ボタ、と、赤い鮮血が、視界に飛び込んでくる。
「ハヤブサ!!」
愛おしいヒトの悲鳴のような声が、辺りに響く。しかしハヤブサは、それには構わずに叫び続けた。
あと少し
あと少しなのだ。
あと僅かでいい。
印も絶対に解いてはやらない。
だからあと少しでいい。
結界よ
どうか保ってくれ――――!
「あの鳥を撃て!!」
「――――!?」
何を言われたのか瞬間的に理解できず、眉をひそめるドモン。しかしハヤブサは、かまわず続けた。
「あそこが出口だ!!」
「な――――!」
「ハヤブサ………!」
「撃て――――ッ!! ドモン・カッシュ!!」
叫び終わった後、ハヤブサは激しく噎せ、咳き込んだ。ぼたぼたと、鮮血が落ちた。しかし、それでハヤブサの結界が揺らぐことはなかった。震える手で、彼は印を結び続けていた。
「ドモン!!」
シュバルツもまた、そんなハヤブサを支えながら、まっすぐにドモンを見つめていた。
「兄さん……!」
そのシュバルツの揺るぎない視線に、ドモンも悟った。兄は龍の忍者を信じたのだと。ハヤブサは、『真実』を叫んでいるのだと―――――
「分かった……! 任せろ!!」
ドモンは大きく息を吸い込むと、マスターアジア直伝の最終奥義を放つ準備をしていた。
「おのれッ!! 人間風情が――――!!」
邪神ラクシャサの身体が一段と大きくなり、さらにその力が増した。荒れ狂う触手のようなケーブルは、アルゴの作った壁を破壊し、彼を弾き飛ばしていた。
「ぐうっ!!」
「おっさん!!」
アルゴに気を取られ、叫ぶサイ・サイシー。その一瞬の隙に、彼もまたラクシャサによって、壁にたたきつけられていた。
「許さぬ!! 許さぬぞ!! 吾の邪魔ばかりしおって―――――!!」
暴走する邪神の力はとどまるところを知らず、周りを破壊しつくしていく。
「おい兄さん!! 本当にこいつの力に、飽和状態が来るのか!?」
チボデーが、痺れを切らしたように叫び声をあげた。先ほどから彼は、何度も己の必殺技である『豪熱マシンガンパンチ』を邪神に叩き込み続けている。しかし、一向に衰える様子を見せない邪神の力に、根を上げそうになっていた。
「……………!」
キョウジも歯噛みしながら、邪神を見つめていた。
核を持たないDG細胞の暴走体は、やがて限界を迎えて死滅する――――これは、データに基づいて実証されている、確かな物だった。しかし、その力の限界量がどこにあるのか、キョウジも明確に指し示すことができないから、ただ、唇をかみしめるしかない。
「チボデー!! 弱気は禁物です!!」
仲間の悲鳴を察したジョルジュから、檄が飛ぶ。
「我々が今、ここから退くわけにはいかない!! いいですか!? 今は、私たちができることを――――!!」
「ジョルジュ!!」
ドカッ!!
あっという間に、チボデーとジョルジュも、邪神のケーブルに薙ぎ払われ、轟音とともにその身を叩き付けられてしまう。
「猪口才な!! ダークネス・フィンガ――――!!」
だがその隙をついて、東方不敗が邪神の頭頂部分に攻撃を仕掛ける。ドグワッ!! と、派手な音を伴って邪神の頭の部分が吹っ飛ぶ。頭を失った邪神は、その動きを止めた。
「やったか!?」
手応えあり、と、東方不敗が振り返る。だが次の瞬間。
グジュリ、と、音を立てて、蘇る頭頂部。東方不敗が息を飲むよりも早く、その身体から何の予備動作もなく唐突に生えたケーブルが、彼に襲い掛かっていた。
「うぐっ!!」
薙ぎ払われてしまう東方不敗。キョウジの前が、ついに、がら空きになってしまった。
「追い詰めたぞ……! キョウジ・カッシュ――――!」
勝ち誇ったように見下ろす邪神。キョウジはただ、息をのむよりほかはなかった。
迫りくる邪神を前に、キョウジの思考はぐるぐると回る。
(戦う?)
無理だ。自分に、邪神に対抗し得るだけの力など、あろうはずもない。
(逃げる?)
それも無理だ。背を向けた瞬間、自分はあの邪神に、打ち据えられてしまうだろう。
「……………!」
死を覚悟した。だが、掌の中にある光を放つ鶴だけは、何としても守らねばならぬと思った。この光はおそらく、異世界で彷徨っているであろう弟たちを、導いてくれているはずなのだから。
(ドモン――――!)
せめて、腹の下に鶴を抱え込み、覆いかぶさるようにして守った。
「ははははは!! 何の真似だ!? そのまま踏みつぶされることを望むか!!」
邪神が嘲笑いながら、キョウジに向かって一歩、踏み出そうとする。その刹那。
「ガイア・クラッシャ――――ッ!!」
「フェイロン・フラッグ!!」
キョウジと邪神の間の床が突如として隆起し、そこに突き刺さった何本もの旗が爆発した。
「うおっ!?」
怯む邪神に、無数のパンチのラッシュが襲い来る。
「豪熱!! マシンガンパンチ!!」
「ローゼス・ハリケーン!!」
激しい嵐と爆発が起き、邪神の進路を阻んだ。
「甘すぎるぜ!! 邪神のおっさんよぉ!!」
サイ・サイシーが身軽に少林寺の構えをとる。
「俺たちを、そんな簡単に抜けるとでも思っていたのか?」
チボデーがフットワークを利かせながら、ボクシングスタイルで構える。
「我らシャッフル同盟――――そんなに簡単にやられるようにはできてはいない!!」
短剣を構えるジョルジュの後ろで、アルゴが無言でファイティングポーズをとっていた。
「フン……そうでなくては困る」
その間に東方不敗が、邪神からキョウジを庇うようにその間にのそりと立つ。
「この程度でやられるような輩に、先代たちは紋章を託しはせぬわ」
そう言って構えをとる東方不敗の腕から、血がしたたり落ちていた。
「マスター! 血が………!」
案ずるような声を上げるキョウジに、東方不敗は振り向きもせずに答える。
「騒ぐでない! この程度――――掠り傷にもならんわ!!」
「しかし………!」
「それよりもキョウジよ! お主はドモンへの呼びかけに集中せい! お主の身は、我らがきっちり守ってやろう程に――――!」
「マスター………!」
「さあ! 皆の者!! ここが正念場ぞ!! 心してかかれい!!」
東方不敗の呼びかけに、皆が「応!!」と応える。それを見たキョウジも――――腹を決めた。
(そうだ……! とにかく、ドモンたちに呼びかけ続けてみないと……! この光には、それだけの価値があるのだから………!)
キョウジは鶴を両の掌にそっと乗せると、目を閉じて祈るように念じ始めた。
(ドモン……! シュバルツ……! ハヤブサ……!)
この声はきっと皆に届く――――
キョウジは、そう信じることにした。
「……………」
鳥の形をした光を見ながら、ドモンは、『石破天驚拳』の構えをとる。しかし、彼の中に少しの迷いが生じていた。
ハヤブサは、あの鳥を撃てという。
あれが出口だからと。
しかし――――
(いいのか?)
あの光は、今まで自分たちを導いてくれた、いわば先導者だ。
それを撃ってしまうことで、自分たちは導を失ってしまうことにはならないのだろうか? ここからの脱出の術を、失ってしまったら………。
「……………!」
ギリ、と、歯を食いしばるドモン。
ハヤブサを疑うわけではない。しかし、確証がほしかった。
「あの光を撃っていいのだ」という確証が。
それを得ずして撃つのは―――――
その時だった。
(ドモン……! ドモン……!)
耳慣れた声が、響いてくる。
「…………!」
ドモンが驚いて目を凝らすと、光の向こうに兄であるキョウジの姿が浮かんできた。
(ドモン……! こっちだ……! こっちへ来い!)
兄は手を広げ、懸命にこちらに呼び掛けてくる。
「兄さん………!」
ドモンは旅愁と焦燥にかられながら、兄に問いかけた。今すぐ兄に会いたいと願った。
「兄さん……! そこが出口なのか? そこに行けば、会えるんだね!?」
その問いかけに、兄は笑顔で頷く。それを見て――――ドモンの腹も、ようやく固まった。
「分かった!! 兄さん!! 我が拳に、もはや一片も迷い無し!!」
ドモンの右拳に『キング・オブ・ハート』の紋章が輝き、彼の身体が黄金の輝きに包まれる。彼の奥義――――『明鏡止水』の発動であった。
「俺の拳が光って唸る!! 勝利をつかめと、轟き叫ぶ!!」
吹き荒れる時空嵐の中、ドモンの身体から発せられる黄金の光が、辺りを引き裂くように輝きを迸らせる。
「…………!」
ハヤブサの結界にかかってくる『圧』も、当然相当な物になってくる。だがハヤブサは、歯を食いしばってそれを懸命に耐えた。
愛おしいヒトを守り抜く。
ハヤブサの心には、ただその願いのみが宿っていた。
「受けよ!! 我が流派『東方不敗』の最大にして、最強の奥義!!」
ドモンの掌の中で貯められた『気弾』が、今――――最大限に膨れ上がっていく。
「爆熱!! 石破!! 天驚拳!!」
凄まじい轟音とともに、熱と光を伴ったそれは、まっすぐその鳥に向かっていく。その瞬間、辺りはまばゆいばかりの光に包まれていた。
「う………! う………!」
光が爆ぜ、爆風が渦を巻く。
次元を突き破ろうとする衝撃が、ハヤブサたちを襲う。
「ぐ…………!」
(切れるな! 破れるな……!)
押しつぶされそうな衝撃の嵐の中、ハヤブサはただそれだけを祈った。
愛おしいヒトを、キョウジの元に帰したい。
二人で、幸せそうに笑いあっていてほしい。
それ以外の、望みはなかった。
それが叶うのならば、自分の身はどうなってもいい。
必要ならば、この命だって喜んで差し出す。
だからお願いだ。
今だけ、どうか
どうか―――――
「ああ……! ハヤブサ……!」
ハヤブサの顔色は悪く、口の端から血がしたたり落ちている。
印を結ぶ、その指先が震え続けている。もう限界が――――近いのだろう。
もういい、止めてくれ!
もうシュバルツは、ハヤブサに向かって何度、そう叫びそうになったか分からない。
だが、叫べなかった。
ハヤブサの命がけの行為を止める手段など、自分は持ち合わせてはいなかった。
止めるべきではない。
止めるべきではないのだ。
彼の『パートナー』でいたいと、そう望むのならば。
自分に出来ることといえば
ハヤブサの身体をしっかりと抱きしめて
ここから脱出しようとしているドモンの後ろを、離れずについていくことぐらいだ。
確かに、自分はキョウジの元へ帰りたいと願っている。
だがそれは、ハヤブサの命と引き換えにしてまで、叶えたい願いではなかった。
今ここでハヤブサを殺してしまうぐらいなら、自分独りで次元の狭間を永遠に彷徨ったほうが、余程ましだった。
「ハヤブサ……!」
苦しむハヤブサの身体を、せめて抱きしめる。
万が一結界が解けて、時空の嵐の中に投げ出されたとしても――――何が起こっても、せめて彼の身体を守れるように。
(本当なら、彼だけでも……現実の世界に返してやりたいのだがな……)
今の段階では、自分にそれができるだけの有効な手段を持ち合わせていない事実。重くシュバルツの胸に突き刺さった。
なんて、無力。
なんて無力なのだろう。
「うおりゃあああああああっ!!」
黄金の光を纏ったドモンが、撃ち抜いた鳥の方に向かって真っすぐ突き進んでいく。シュバルツもそのあとに続いた。進めば進むほど、前方に明るい光が射し込んできて、周りが明るくなっていくのが分かった。
「頑張れ!! ハヤブサ!! 後少しだ!!」
出口が近いと確信したシュバルツは、ハヤブサを励ますために声をかける。しかし、龍の忍者から反応が返ってくることはなかった。彼は蒼白な顔色をしたまま――――唇を真一文字に引き結んで、印を組み続けている。もうこちらに応える余裕すら、彼にはないのだろう。
「壁がある――――!」
前方を進んでいたドモンから、声が上がった。石破天驚拳と共に飛び続けていた鳥が、その壁の向こうにすっと消える。そのあとに天驚拳が、間をおかずに壁に激突した。雷鳴のような轟音とともに、あたりに衝撃波が走り――――その壁にひびが入る。
(出口だ……!)
直感的にそう判断したドモンは、再び構えをとった。
「撃ち抜く!! 兄さん、下がってて!!」
「――――!」
ドモンの言葉に、シュバルツははっと息をのむ。
そして、覚悟を決める。
もしかしたら次に受ける衝撃で、もうハヤブサの結界が、保てなくなるかもしれないからだ。
シュバルツは瞬時に、ありとあらゆる事態をシミュレートする。
(結界が解けてしまっても、一瞬でいい。外の世界とつながった瞬間に、ハヤブサをそこに放り込むことが出来さえすれば――――!)
外の世界にはキョウジがいる。彼ならば、ハヤブサを助けることができるだろう。
シュバルツはハヤブサを抱きしめる手に、ぐっと力を入れていた。
「石破!! 天驚拳!!」
ドモンから放たれた天驚拳が、凄まじい轟音を伴って、壁に激突する。
光が爆ぜ、粉塵が舞い上がる。
振動が
衝撃波が
ハヤブサの結界を襲う。
「――――――」
龍の忍者はとうとう、物も言わずに昏倒してしまった。
「ハヤブサ!!」
シュバルツは覚悟を決めた。
ついに結界が切れ―――――
「……………」
(切れない?)
ハヤブサは昏倒し、いつその術が切れてもおかしくない状態であるのに、相変わらず自分の周りは、静寂が保たれたまま――――結界が張られていると悟る。
(まさか………ハヤブサが………?)
ハヤブサは、印を結んだまま昏倒していた。もしかしたらその状態でも結界を張り続けることは可能ではあろうが、強度と安定性に支障が出てきてもおかしくはないはずだった。
(私が結界を張れるわけはないし……。では、いったい誰だ? 誰が、何が――――この安定した結界を、張ってくれているんだ?)
疑問に思ったシュバルツは、周りを見渡す。そしてそこで、あるものを見つけた。
そこにいたのは女性だった。白い着物を着た女性――――
異様な状況であるはずなのに、シュバルツは何故か恐怖は感じなかった。
それどころか、どこかで会ったことがあるような感じすら覚えた。こちらを守るように広げている手が、時々おにぎりや飲み水を差し出してきたあの白い手に似ている、と、思ったからであろうか。
「……………」
戸惑うようにその女性を見つめていると、その女性の白い面にフッと笑みが浮かんだ。
「―――――」
女性が、囁くように言う。シュバルツがそれに応えようとした時。
「兄さん!! 外に出られる!! 行こう!!」
ドモンから声をかけられ、シュバルツははっと顔を上げる。
「分かった! 今行く!」
力強くそう言うと、彼もまた、ハヤブサを抱きかかえて立ち上がっていた。
「おのれ!! 人間風情が――――!!」
ラクシャサの身体が、また一回り大きくなる。攻撃してくる触手のようなケーブルの数も武器の種類も、さらに増えた。
「くそっ!! 本当にきりがないぜ!!」
「チボデー!! 弱音は禁物です!!」
ラクシャサの攻撃に対処しながら悲鳴を上げ気味になるチボデーを、ジョルジュが励ましていた。
「負けてたまるかよ!!」
サイ・サイシーがフラッグを昆のように回しながら構える後ろで、アルゴも鉄球を振り回している。しかしすでに、皆の身体は傷だらけになっていた。
(消耗が激しすぎる……! まだか……? ドモン……! ハヤブサ……! シュバルツ……!)
キョウジは戦況を見つめながら、歯を食いしばっていた。
退くわけにはいかない。退けば、敵に利するだけで、何のメリットもない。
それに今、自分たちが退けば――――あの邪神による人間への虐殺行為が始まってしまう。
それだけは、何としても避けねばと思った。自分たちは意地でも、ここに踏みとどまらなければならないのだ。あの邪神と戦えるだけの力を持っているのだから。
しかし、今の状態は、まさに不毛な消耗戦をしているとも言えた。このままでは皆が疲弊して――――あの邪神が倒れるよりも先に、こちらの戦線が崩壊してしまう恐れすら出てきていた。
(大丈夫……。ドモンたちは強い……)
キョウジは祈るように、自分に言い聞かせ続けていた。
邪神の中に閉じ込められているあの3人が出てきてくれさえすれば
きっと今の戦況も、逆転できるはずだ。
あのドモンが
ハヤブサが
シュバルツが
あんな邪神なんかに、後れを取るはずはないんだ。
必ず出てくる。
必ず帰ってきてくれる――――!
祈り続けるキョウジを、東方不敗が懸命に守り続ける。
その時だった。
ふいに、キョウジの脳裏に、こちらに向かって飛んでくる鶴のイメージが浮かぶ。それと同時に、その鶴を追うように、力強くこちらに突き進んでくるドモンたちのイメージが―――――
「ドモンたちが出てくる!!」
気が付けばキョウジは、考えるよりも先に、その言葉を発していた。それほどまでに、彼らにとって、それは待ちわびたことであったから。
「本当か!?」
東方不敗をはじめとした皆が、キョウジに注目してくる。キョウジは、力強く頷いた。
確信があった。
ドモンたちはもう、本当にすぐそこまで来ている。
「出てきます!! あそこから――――!!」
キョウジは、邪神の胸のあたりを指しながら、心の中でカウントダウンをする。
(3…………2…………1…………!)
「来い!! ドモン!!」
キョウジが叫ぶと同時に、邪神の胸の辺りが眩く光る。
ドオオオオオオン!!
轟音とともに、爆ぜた邪神の胸から、輝く二つの光球が飛び出してきた。その中にはためく赤いマントと、そのあとに続いて出てきたハヤブサを抱きかかえるシュバルツの姿を見た瞬間のキョウジの心の中に広がる安堵感は、如何ばかりのものであっただろう。
「兄さん!!」
ドモンもまた、こちらを見つめてほほ笑む兄の姿に、胸を撫で下ろしていた。戦いの中にあって、兄がこうして無事でいることを、ドモンは天に感謝する。その後ろでストン、と着地したシュバルツが、腕の中のハヤブサに呼びかけていた。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
「う…………!」
シュバルツに呼びかけられたハヤブサが、うっすらと瞳を開ける。
「あ………? シュ……バ、ルツ………?」
「ハヤブサ――――」
シュバルツは優しく微笑みながら、気を失っていてもなお、固く結び続けていたハヤブサの手の印の形を解いた。これはもう、必要のないものだからだ。
「ハヤブサ……。私たちは、助かったんだ………」
そっとハヤブサの手を握り、言葉をつづける。
「守ってくれて……ありがとう」
「シュバルツ………!」
そう言って綺麗に微笑む愛おしいヒトを見つめながら、ハヤブサもまた、安堵の吐息を漏らしていた。自分は、彼のヒトを守りきれたのだと知った。
「……………」
ドモンは、シュバルツとハヤブサが優しく微笑みあっているのをなんとなく憮然とした想いで見つめていた。
兄に、仲がいい友人がいるのはいいことだと思う。それなのに、『面白くない』と感じてしまうのはなぜなのだろう。自分だって、もう少し力があれば、兄を完璧に守れたのにと思うのだ。
まあ、100歩譲って、あの状態で最後までシュバルツを守ってくれた、その根性は認めてやってもいいが――――
「ドモン!!」
ドモンが振り返ると、キョウジが走り寄ってきていた。
「兄さん!」
「ドモン、大丈夫だったか……? 心配したぞ」
こちらの手を握り、見つめてくるキョウジの瞳が潤んでいる。余程心配していてくれたのだと知った。
「うん……。俺は大丈夫だよ。ありがとう……」
兄の手を握り返しながら、微笑み返す。兄の愛情を感じることができたドモンは、少し落ち着くことができた。
「兄さん、俺よりも、あっちのハヤブサの方を見てやってくれ。酷い怪我をしているんだ」
ハヤブサにむかつきを感じていたとしても、シュバルツを守ってくれた恩がある。それは返さなければならぬ、と、ドモンは律義に思っていた。
「――――! 分かった!」
キョウジは踵を返して、シュバルツとハヤブサの方へ走っていく。ドモンがその後姿を見送っていると、東方不敗が声をかけてきた。
「ドモン、待ちくたびれたぞ」
「師匠!」
「見よ。あれが、わしらが倒すべき敵だ」
「…………!」
東方不敗に指示されるままに、ドモンが顔を上げる。すると、胸の辺りを破壊され、もがき苦しんでいる邪神ラクシャサの姿が視界に飛び込んできた。
「………でかいな……」
ドモンが素直な感想を漏らす。自分が異世界で見た邪神は、こんなに巨大ではなかったはずだが――――
「あ奴はどうやら、シュバルツのDG細胞を依代に選び、現世に復活しようと目論んだようだな。その力を使って我らの攻撃のエネルギーを吸収し、巨大化していったのだ」
ここまで話してから、東方不敗はフッと笑う。
「じゃが……心臓に当たる『核』を奪われた。あ奴ももう長くはないであろうな……」
「……………!」
ドモンと東方不敗は、邪神に取り込まれかけていたシュバルツの方に視線を移す。ちょうど、キョウジがハヤブサを介抱しているシュバルツのところに、走り寄って膝をついているところであった。
「シュバルツ! ハヤブサ!!」
「キョウジ……!」
「二人とも、大丈夫か!?」
「私は平気だ。だがハヤブサが――――」
話しながらシュバルツは、キョウジにハヤブサが見えるように体制を変える。シュバルツの腕の中で、ハヤブサが低く呻いていた。
「………心配、するな……。俺は……平気――――」
「平気なわけないだろう!! こんなに傷だらけになって――――!!」
キョウジは今まで大事に持ち続けていた折り鶴をそっと横に置くと、ハヤブサの状態を検分しだした。
(傷だらけじゃないか……! それに、出血もひどい……。早く手当てをしないと――――)
ここまで思ってから、キョウジはあることに気付く。
(……筋肉の量が、戻ってきている?)
ここに寝たきりで、点滴を受けていたハヤブサの身体は、やせ細っていた。しかし今、いつもの忍者スーツを身にまとったハヤブサの身体つきは、健康な時のそれと、何ら変わりがないような気がする。
(どういうことだろう……。ハヤブサにかけられていた呪いのようなものが解けたから、こうなったのだろうか……)
いろいろと詳しく調べたいこともあるが、今はとにかくハヤブサの身体を手当てすることが先決だと思った。
(あ……でも、救急箱………どこ行ったっけ……)
自分のアパートすら、もうほぼ跡形もないほど破壊されつくしているこの状況。道具一つ探すにも、かなり困難な状態になっていた。それでも探さなければ、と、キョウジは立ち上がる決意をする。
「シュバルツ、ハヤブサの応急手当てをしておいてくれないか? 私は救急箱を探して――――」
その言葉が終わらないうちに、ダメージにのたうっていた邪神が吼えた。
「おのれ!! 許さぬ!! 人間どもめ!! よくも吾の心臓を!!」
胸に空いた穴を塞ぎきらないうちに、邪神は目をぎらつかせ、目標を探す。そして、少し離れたところでハヤブサを抱きかかえている、シュバルツの姿を見つけた。
「『心臓』は大人しく―――――吾の中に戻れ!!」
邪神から伸びた触手のようなケーブルが、うなりをあげてシュバルツに襲い掛かる。
「―――――!」
それを見たハヤブサが、シュバルツを庇おうとあがき――――シュバルツは、ハヤブサとキョウジの両方を守ろうと手を伸ばす。しかし、忍者二人の動きをキョウジが制した。(動かなくていい)と、手を上げて伝える。
そして、キョウジの言葉通り、動く必要はなかったと忍者たちはすぐに悟ることとなる。
触手がキョウジたちに届く寸前、一つの影がその前に飛び込んできた。ドォン!! と、派手な音を立てて触手と影がぶつかる。そして次の瞬間――――ばらばらと崩れ去っていったのは、攻撃を仕掛けてきた触手の方であったのだから。
「フン……。わしの目の前で、我が王に傷がつけられるとでも思っておったのか!?」
触手を砕いた東方不敗が、キョウジを庇うように立ち、邪神を睨み付けている。その後ろでキョウジは、苦笑いにも似た笑みをその面に浮かべていた。自分は王じゃないですよ、と、東方不敗に言い続けているのだが、どうやら彼の方に、一向にそれを聞き入れる気はないらしい。困ったものだ、と、キョウジは思った。
「……シュバルツ、ハヤブサを守っていてくれ。多分この戦いは――――」
後少しで済む、と、キョウジが言うよりも先に、ハヤブサから声が上がった。
「その必要は、ないぞ……! キョウジ………!」
そう言うと、ハヤブサはシュバルツの腕の中からふらふらと身を起こした。その腕の中には、キョウジが持ち続けていた折り鶴が、あった。
「オン バザラユ セイ ソワカ――――」
真言を唱え、印を結ぶハヤブサの手の中に、ポウ、と、白い光が宿る。それが、折り鶴に宿っていた淡い光と混じり合って、やがて、ハヤブサの身体に吸収されていった。フ――――っと大きく息を吐いたハヤブサが、立ち上がる。
「ハヤブサ……! まだ立ったりしては―――――!」
止めようとするキョウジを、龍の忍者が手で制する。
「傷は塞いだ。大丈夫だ」
「でも―――――」
「あの邪神………封印するのは、俺の『仕事』だ」
そう言ってハヤブサは、多少ふらつきながらも歩き出していく。
「ハヤブサ……」
心配そうに見送るキョウジの横で、シュバルツもため息を吐いていた。
「あいつはああなったら、もう誰にも止められないからな………」
やがてシュバルツも、すっと立ち上がる。
「仕方がない。ハヤブサにばれないように、こっそり後をつけるか………」
「シュバルツ……」
キョウジが心配そうに見上げてくる。それを見たシュバルツは、にっこり微笑んだ。
「心配するな、キョウジ。私は決して無茶はしない。ハヤブサについていくのも、保険のようなものだから」
「でも………」
「大丈夫だ。これだけの面子がそろっているんだ。私の出番もほぼないだろうし、何より、もう負ける気もしない。それに……」
「それに?」
問い返すキョウジに、シュバルツは少しいたずらっぽくウインクをする。
「もし、万が一私に何かあっても――――ドモンやハヤブサ、そしてお前が、また、助けてくれるんだろう?」
「…………!」
一瞬目をぱちくりとさせるキョウジに、シュバルツはにこっと微笑む。キョウジは軽く咳払いをしてから「当たり前だよ!」と、少し強い口調で言った。
「貴方は、皆にとってかけがえのない存在なんだ! だからシュバルツ、絶対に約束してくれ! 決して自分をないがしろにしない、無茶をしないと……!」
「ああ、分かっている」
シュバルツがそう言って頷いたのを見て、キョウジもようやく納得したように頷いた。
「じゃあ、行っておいで」
キョウジに頷き返したシュバルツの姿が、すっと見えなくなる。そのまま彼は、気配を消してハヤブサについて行ったのだと知れた。
「……じゃあ、私もそろそろ、『戦いの後』の準備をするかな……」
キョウジはそうひとりごちると、彼もまた、立ち上がっていた。
「師匠!!」
邪神とにらみ合っている東方不敗のところに、ドモンが走り寄ってくる。その後ろから、チボデーたちシャッフルの面々も続いていた。
ドモンの顔を見て、東方不敗はにやりと笑う。勝利への道筋が、見えたと悟った。
「さあ、『キング・オブ・ハート』 おぬしの戦い、見せてもらうぞ?」
「言われずとも!!」
東方不敗の言葉に、ドモンは鼻息荒く答える。東方不敗は後ろに下がり、代わりにドモンたちが前に出てきた。
「おのれ!! 人間どもめ!! あくまでも吾の邪魔をするというのか!?」
肥大化したラクシャサが、復活しないケーブルを振り回しながらわめいている。
「ああ。悪党を許す拳は、あいにくと持ち合わせてはいないんでね!」
そう言ってチボデーがファイティング・ポーズをとる。
「そうですね。闇から生まれたものは、闇に帰るべきです!」
ジョルジュは作法にのっとって、フェンシングの剣を構えた。
「いい加減あきらめろよ!! おっさん!!」
構えるサイ・サイシーの後ろで、アルゴがガン、ガン、と大きな音を立てて、おのれの大きな拳を胸の前で合わせている。みな――――それぞれ気合十分のようであった。
「行くぞ!! 我らシャッフルの力――――今こそ一つに合わせる時!!」
ドモンの声に、皆が「応!!」と、答える。皆の手の甲に、それぞれのシャッフルの紋章が光りだしていた。
「さあ!! 勝負だ!! 邪神め!!」
「ほざけ!! 人間如きが――――!!」
邪神とドモンたちが、真正面からぶつかり合う。
拮抗した戦いになるかと思いきや、その勝負はあっさりと決まった。
肥大化し、『核』を失ってしまった『邪神』
それに対して、真の紋章の仲間が集結した『シャッフル同盟』
その力の差は歴然であった。
ぶつかり合ったその瞬間――――すでに勝負は決していたのである。
「ぎゃああああああああ――――ッ!!」
断末魔の悲鳴を上げながら、邪神の身体がぼろぼろと崩れ落ちていく。
「やったのか………!?」
崩れ、焼け落ちていく邪神の身体を見つめながら、ドモンがつぶやく。その時、背後から「いいや、まだだ!!」と、声が飛んできた。
「――――!?」
驚いて振り返ると、そこにはリュウ・ハヤブサの姿があった。彼は龍剣を抜刀しながら、こちらに一直線に走ってくる。
「こいつには『本体』がいるんだ!! そいつを仕留めないと、終わらない!!」
叫びながら彼は、崩れ行くラクシャサの身体に斬り込んでいく。
「何っ!? どこだ!? それは!!」
問いかけるドモンに、ハヤブサは振り向きもせずに答えた。
「だが――――こいつ『本体』の場所は、もうわかっている!! こいつと戦うのは、これで『二度目』だからな!!」
そう言いながら斬り進んでいく龍の忍者。その刀の走りには、迷いがなかった。
「…………!」
ドモンも、間髪入れずにハヤブサの後について行く。
それは彼が、『あること』に気付いたからに他ならなかった。
「お前の『本体』―――――それは、ここだッ!!」
龍剣が、吼えるような呻りをあげてその場所を一閃する。
ラクシャサの『根』の部分を奥深くまで斬り込んだ龍剣は、寸分違わずにその『本体』を捉えていた。
根っこの部分から露出したその黒い球状の物は、パンッ!! と、乾いた音を立てて、真っ二つに割れていた。
二つに割れた球状の物体から、黒い靄のようなものが出てくる。これこそがラクシャサその物であった。ハヤブサは『気』を込めて、再びラクシャサを『封印』しようと試みる。
(く………!)
しかし、少し前まで衰弱し、今また、大怪我をして弱り切っている龍の忍者。「封」の術が、完璧には発動しなかった。
(馬鹿め!! この隙に、逆に貴様の身体を乗っ取ってやる――――!!)
ラクシャサが高笑いをしながら、ハヤブサに襲い掛かろうとした、その瞬間。
ラクシャサの前に突然、赤いマントが翻った。
「――――!?」
(なにぃ!?)
ラクシャサとハヤブサが、同時に息をのむ。
「吻っ!!」
ドモンの黄金に輝く右手は、確実にラクシャサの魂を捉え――――そして、砕いて行った。邪神は、なんとも耳障りな悲鳴を残して、跡形もなく消えていった。
「……………」
ドモンが振り返ると、茫然とこちらを見つめている、リュウ・ハヤブサと視線が合う。
「………助けてくれたのか……?」
問うてくる龍の忍者に、ドモンは「チッ!」と、舌打ちをした。
「勘違いするなよ!? 俺はお前を助けたんじゃない!! お前の後ろにいる兄さんを助けたんだ!!」
「―――――!」
ぎょっとしてハヤブサが後ろを振り返ると、シュバルツがその姿を静かに現す。そこで初めてハヤブサは、シュバルツが極限まで気配を消して、自分の後ろについてきていたのだと気付いた。
「あのまま放っておけば、兄さんがお前を庇おうとしただろう。兄さんに何かあったらたまらないから、守っただけのことだ!!」
「……………!」
「ドモン……」
シュバルツに静かに見つめられ、ドモンはいたたまれなくなったのか、ふい、と、視線をそらした。
「これで『借り』は、返したからなっ!!」
ドモンは大声で怒鳴ると、すたすたと歩いて行ってしまった。その後姿を茫然と見送っていたハヤブサは、やがて、ポツリと漏らした。
「………これは、礼を言われた、と、解釈していいのか……?」
「すまないな。素直じゃない弟で……」
苦笑しながら言葉を紡ぐシュバルツに、ハヤブサは頭を振った。
「いや、いい。礼を言わねばならんのは、寧ろこっちだ……」
フッと小さく息を吐いてハヤブサは龍剣を収めると、真っ二つに割れた黒い球をそっと拾い上げていた。
「……もう、それは害のない物なのか?」
問うてくるシュバルツに、ハヤブサは静かに微笑み返す。
「あれだけダメージを受けたから、当分の間、この邪神ラクシャサの復活はないだろう……。しかし、相手は神だ。完全に討滅することも不可能だろうな……」
ここまで話したハヤブサは、やれやれとため息を吐いた。
「今度はもっと……俺が多少弱ったぐらいではびくともしないぐらいの封印の仕方を、考えねばなるまいな……」
そう言って球を見つめていたハヤブサの身体が、ぐらりと傾ぐ。
「ハヤブサ!!」
シュバルツが慌ててハヤブサの身体を支える。
「大丈夫か!?」
声をかけるシュバルツに、ハヤブサはその腕の中で苦笑を返した。
「大丈夫……と、言いたいところだが、さすがに少し身体に堪えているみたいだな……」
「ハヤブサ……」
やはり、無理をさせてしまったと、シュバルツの瞳が曇る。
いつもそうだ。
どうしていつもハヤブサは
こんな無茶ばかり――――
「シュバルツ……」
対して龍の忍者の方は、今まさに幸せの絶頂であった。
や……やった……!
偶然よろけたおかげで、すんなりシュバルツの胸の中に入ることができた……!
異空間を抜ける時もシュバルツに抱きしめてもらっていたが、あの時は結界にかかってくる時空圧と戦うのに必死だったからなぁ。だが今は、俺たちの間を邪魔するものは何もない……!
この際だから、少し甘えさせてもらおう、と、ハヤブサはさらにシュバルツの身体に身を寄せる。案の定、シュバルツは優しく抱き留め続けてくれていた。
(ああ……! 最高だ……! このまま、時が止まってくれれば……!)
幸せな時間を堪能しながら、どうしてもその頬が緩みがちになる龍の忍者。身体の疲れも痛みも忘れて、しばし、シュバルツの腕の中の感触に酔う。
しかし、そんな時間は長くは続かないもので。
誰かが、シュバルツを後ろから、ガシ、と、抱きしめてきた。
(誰だ!? 俺とシュバルツの時間を――――!)
「シュバルツ………」
(キョウジか………)
降ってきた声に、抱きしめてきた者の正体を悟って、ハヤブサは小さくため息を吐く。
キョウジならば仕方がない、と、ハヤブサは思った。シュバルツとキョウジの間を邪魔してはならないと、心に誓っているのは自分だ。それ故に、シュバルツの腕の中からそっと身を起こすことを、龍の忍者は選択していた。
「ハヤブサ……大丈夫なのか?」
シュバルツが心配そうに問うてくるのを、ハヤブサは苦笑しながら頷いた。
「ああ……。俺は大丈夫だ。それよりも、キョウジの方に向いてやれ」
「あ………!」
ハヤブサに言われてシュバルツがキョウジの方に振り向くと、抱きしめてきたキョウジの身体が小さく震えていることに気付いてしまう。
「キョウジ……!」
「シュバルツ……! 良かった……!」
「…………!」
「帰ってきてくれて………本当に、よかった………」
「キョウジ……」
小さく震え続けるキョウジの背に、シュバルツはそっと触れる。酷くキョウジを心配させてしまったのだと感じて、シュバルツは申し訳ない想いでいっぱいになった。
「キョウジ、すまない……。心配をかけてしまったな……」
シュバルツの言葉に、キョウジはフルフルと首を振る。
「ううん……いいんだ。お前がこうして、帰ってきてくれたから――――」
そう言いながらキョウジが、シュバルツの身体をぎゅっと、抱きしめる。
(良かった………)
その光景を見ながら、龍の忍者の面にも、いつしか優しい笑みが宿っていた。
シュバルツとキョウジが再会を喜び合っている。
その姿は、自分が最も見たいと願っていたものだったから。
「……………」
二人の時間を邪魔してはならぬと、ハヤブサはくるりと踵を返す。しかし、次の瞬間発せられたキョウジの言葉に、ハヤブサの足は強制的に止められることになってしまった。
「シュバルツ………『後片付け』を、手伝ってくれるよな?」
「へっ?」
何かキョウジから、不吉なことを聞いたような気がして、シュバルツから変な声が出てしまう。ぱちくりと目をしばたたかせるシュバルツに、キョウジはなおも、さわやかに微笑みかけていた。
「だから、後片付け」
「えっ?」
「手伝ってくれるよな?」
「ええっと……後片付けとは――――」
「見てわからない?」
にこ―――っとほほ笑むキョウジの背後に広がるのは、瓦礫の山。
酷く嫌な予感に駆られて、シュバルツは背中からは大量の汗が流れ落ちていた。
「ま………まさか……」
ひきつった笑み浮かべるシュバルツを、キョウジはがしっと捕まえるように抱きしめる。
「ほら……私のアパートなんて、跡形もないし」
「…………!」
「邪神が暴れたとばっちりで、周りの家も崩れるとか無くなるとかしているし」
「ま、まてっ! キョウジ――――!」
シュバルツは思わず、叫び声をあげていた。
「まさかこの辺り一帯の、壊れている物全部を直す気でいるのか!?」
シュバルツの言葉に、キョウジはあっさりと頷く。
「そうだよ? 壊れた原因が私たちに関係ないとは言えないし、ここの人たちも、いきなり住む家がなくなっちゃったらかわいそうでしょ?」
「それはそうかもしれないが――――」
シュバルツは軽く咳払いをする。キョウジの言っていることは、あまりにも現実離れしすぎていると思うのだ。
「しかしキョウジ……! 言っていることがむちゃくちゃだぞ!? 直すために払う手間と労力は惜しまないつもりだが、いくら私が全力で取り組んでも、一朝一夕で終わる代物ではないぞ。材料の調達とか、住んでいた人たちとの交渉とか――――」
「いやだなぁ、シュバルツ。誰が『普通の手段』でこの辺りを直すって、言った?」
「へっ?」
再び目をしばたたかせるシュバルツに向かって、キョウジはある物を見せつけるように差し出す。
「直すのには――――『これ』を使うつもりだよ」
それが何かと悟った瞬間、シュバルツの顔色が、みるみる蒼白なものになっていった。
それは、この世には絶対に出してはいけないモノ。
普通ならば、研究所の奥深くに、厳重に封印されてなければならない『新種のアルティメット細胞』という代物であったからだ。
「キョウジ!? それは――――!」
「大丈夫。これは凶悪性が無い方の細胞株だよ。これが、壊れた物を直していったのを、シュバルツも実験に立ち会って確認しただろう?」
「それはそうかもしれないが――――」
シュバルツは立ちくらみを起こす自分を止めることができない。
「それでも危険すぎる!! 万が一間違いが起こって暴走でもしたらどうするんだ!?」
「うん。そうだね。だから、扱いには細心の注意を払わないといけないと思ってる。私とシュバルツが主体になって、この細胞を制御して――――」
「『制御して』じゃない!!」
シュバルツはたまらず大声を張り上げていた。
「キョウジ!! これはまだ実験の検証段階で、現実に使っていい代物じゃないんだ!! 使うのにしたって慎重を期さないと――――!!」
「じゃあシュバルツは、どうやってこの惨状を立て直すつもりだ?」
「――――!」
キョウジに突っ込まれて、シュバルツは咄嗟に反論することができない。
「直すことができる手段が、私たちにはあるんだ。だからそれは、有効に使うべきじゃないのか? それに万が一この細胞がDG細胞化して暴走したとしても、止めることができる人たちが、ここには沢山いるだろう?」
この言葉に、東方不敗以下全員の視線がキョウジに集まる。確かにキョウジの言う通り――――シャッフルの紋章を持つ者と、『龍剣』を持つ龍の忍者は、暴走したDG細胞を消滅させる力があった。
「実験のための『安全弁』のような物までここに揃っているのに―――――それを活かさないなんて勿体ないよ! シュバルツ!!」
そう言いながらにじり寄ってくるキョウジの瞳が、皆のために役立つことがしたい、というよりも、完全に「この新しいアルティメット細胞の実験をしたい」と訴えてきている。
(こ………この、マッドサイエンティストが――――!)
シュバルツは立ちくらみを覚えながら、ただ呆然とするしかない。そこに東方不敗が「キョウジよ……」と、声をかけてきた。
(マスターアジア……!)
シュバルツは一縷の望みをかけて東方不敗の方を見る。
キョウジは、自分たちシャッフル同盟の力を実験の安全弁呼ばわりしたのだ。これは、かなり失礼なことに当たるのではないかとシュバルツは思うのだ。これに東方不敗が激怒して、『そんなくだらない事に我らの力など貸さんぞ!!』とでも言ってくれれば、キョウジも、この無謀な実験をあきらめてくれるのではないかと願う。
しかし。
「キョウジが望むのなら、わしは一向にかまわぬぞ?」
寧ろ喜んで協力しよう、と、続いた東方不敗の言葉に、シュバルツはズルッとこけるしかなかった。
「やった―――ッ!! ドモンももちろん協力してくれるよな?」
嬉々として万歳と手を上げるキョウジが、ドモンの方に振り返る。もちろん、兄が大好きな弟が、キョウジに反対するはずもない。
「ああ。当然だ! 俺の力が兄さんの役に立つのなら――――」
「まあ、これも人助けだな」
チボデーが腕をぐるぐると回しながら近寄ってくる。
「再生のために必要であるならば、我が力、喜んで差し出しましょう!」
ジョルジュが微笑んでそう言えば、その後ろからサイ・サイシーが「おいらだって!」と、ひょこっと顔を出す。そこから少し離れたところで、アルゴ・ガルスキーが、ドン! ドン! と、音を立てて自らのこぶしを胸の前で合わせていた。皆の意見に賛同して、そのための気合を十二分に己に注入している、と、言ったところであろうか。
「みんな……! ありがとう……!」
その輪の中でキョウジが、爽やかに微笑んでいる。その様子を見ていたシュバルツは、ひっそりと頭を抱えてしまっていた。
(ど……どうして皆、気が付かないんだ……! あそこにいるキョウジが、完全に世のため人のためなどではなくて、『実験をしたい』というエゴで突き動かされている、という事実に………!)
あの爽やかな笑みの向こうに、マッドサイエンティストの影がちらついているのがはっきりと見える。どうして自分だけが、それに気づいてしまうのだろう。やはり、自分は彼の『分身』で――――自分の大元には、彼の『良心』が色濃く流れているからであろうか。
シュバルツが、はあ、とため息を吐きながら頭を垂れていると、龍の忍者からそろりと、声をかけられた。
「大丈夫か? シュバルツ……。俺も手伝うから――――」
「……………」
シュバルツはチラリ、と、ハヤブサの方に視線を走らせると、
「………いいから、怪我人は無理せず寝ていろ………」
ため息交じりにそう言われる。ハヤブサは苦笑するしかなかった。事実、一応『呪』で傷口を塞いでいるとは言え、身体はまだ、本調子とは程遠い状態であったから。
「しかし、寝ていろと言われても――――」
だがハヤブサも、なおも反論しようとする。大体、これだけ破壊された状態では、自分が身を休めるところなどないし、何よりも、愛おしいヒトが困っているのなら、手を差し伸べたいと、ハヤブサは願っていた。
「いや、しかし……お前は本当に、ゆっくり休んでいないといけない」
何だったら、今すぐ隼の里に帰るか、と、シュバルツが言うより先に、キョウジから呼びかけられた。
「ほら! シュバルツ! まず治療室を直すよ! ハヤブサの治療をしなくちゃ――――!」
瓦礫の山の真ん中で、妙にテンションが上がっているキョウジが、元気いっぱいに叫んでいる。
「やれやれ……。分かったよ……」
深いため息を吐きながら、シュバルツが重い腰を上げて立ち上がる。そのあとに龍の忍者も続いて歩き出した。笑顔で手を振っているキョウジの背後から、朝日が昇り始めていた―――――
最終章
食べる。
食べる。
とにかく食べる。
ガツガツと、がっつくように食べるハヤブサの両隣には、山のように空になった茶碗が積み上げられていた。
あまりにも凄まじいハヤブサの食欲の前に、シュバルツもキョウジも、ただ呆然とするしかない。開いた口が塞がらないシュバルツとキョウジの前に、龍の忍者からまた茶碗が差し出されていた。
「おかわり」
邪神の騒ぎが終息し、街に落ち着きを取り戻したころ――――再び隼の里から与助が訪ねてきていた。
「あれ? 与助さん?」
出迎えたキョウジの前に、ドスン! と、大きな荷物を下ろしてから、ぺこりと頭を下げた。
「すみません、すっかりリュウさんがお世話になってしまって――――」
「ああ、そんなこと気にしなくていいのに」
フッと優しい笑顔を見せるキョウジの前に、突然与助は深々と頭を下げた。
「あの……! すみませんっ!!」
「えっ?」
「本当に……! すみませんっ!!」
「ち、ちょっと与助さん、どうして謝るの?」
訳が分からずに問い返すキョウジに、与助は申し訳なさそうに首を振る。
「いえあの………。リュウさんの体調が戻ってきていると連絡を受けたので――――」
そう言いながら与助は、運んできた米俵を差し出した。
「こちらを、どうかお納めください!」
そう言って、実直な青年が頭を下げる。それを見たキョウジは、慌てて恐縮しだした。
「ちょ……! ちょっと……! 見舞金もたくさんもらっているのに、さらにそんなに貰ってしまうと――――!」
「いえ……! とにかくお納めください! 絶対に必要になってきますので――――!」
「えっ?」
きょとんと眼をしばたたかせるキョウジ。その時部屋の中からシュバルツが出てきた。
「キョウジ……ちょっと買い物に行ってきてもいいか……って、与助、来ていたのか」
シュバルツの言葉に、与助も「お久しぶりです」と頭を下げる。
「シュバルツ。買い物って?」
問い掛けるキョウジに、シュバルツは軽く笑みを返す。
「いや、ハヤブサが少し食欲が出てきたらしくてな。腹が減ったと言い出したものだから――――」
「あ、じゃあさっそくご飯を炊きましょう。私も手伝いますよ」
そう言いながら、与助は一升炊きの炊飯器をドン、と床に置く。
絶対にこれが必要になる、と、言った与助を、シュバルツとキョウジは半信半疑で眺めていたのだが――――果たして、与助の言葉通りになったのだった。
「よく食べるねぇ」
もう何杯おかわりしたのか分からないハヤブサを見つめながら、キョウジがポツリと感想を漏らす。その横で、与助が苦笑していた。
「すみません……! リュウさんは、大怪我したときなど、『食べて治す』的なところがあって、任務で負傷して里に帰ってきたときなどは、一時的に食欲が跳ね上がったりするのですが………」
今回は衰弱していた期間が長かった分、その反動がひどいのではないか。与助はそう予測していた。そして、見事にその通りになっていた。
「ご馳走様でした」
龍の忍者は静かに茶碗を置き、胸の前に礼儀正しく手を合わせて挨拶をする。その所作だけを見ていたら、静かな食事風景を想像するものだが、大量に積み上げられた茶碗が、先ほどの豪快な食事風景の名残を漂わせていた。
「さてと……」
大きく息を一つ吐くと、龍の忍者はおもむろに立ち上がった。
「腹ごなしの修行に出るか。シュバルツ、ちょっと付き合え」
「馬鹿! すぐに動こうとするな! いくらなんでも内臓を少しぐらいは休ませないと………!」
「平気だ。腹八分程度で止めてあるからな」
(あれで腹八分!?)
食べた量と積み上げている茶碗の高さに、キョウジは呆然とするしかない。
「シュバルツ行くぞ! 俺は早く身体を動かしたいんだ!」
そう言うハヤブサは、もう玄関から外に出ていこうとしている。
「しょうがない奴だな……」
シュバルツも少し苦笑しながら、玄関の方へと向かっていった。
忍者二人が出て行ったのを見送ってから、キョウジはやれやれ、と、テーブルの上を片付け始める。
「手伝います」
与助もすぐに飛んできて、皿洗いを手伝い始めた。
暫くキッチンに、水音と皿を洗う音が響く。
そして部屋の隅で点いていたテレビが、数日前の騒動について、コメンテーターたちが語り合っていた。
「あの爆発音は、いったい何だったんですかねぇ?」
「巨大な影を見た、という目撃情報も、何件かあるようですが……」
「あの中で戦っている人たちを見た、と、言う情報は確かなのですか?」
「警察や政府に問い合わせても『情報収集中だ』と、はぐらかされている……。これではいかんと思うのですよ。我々国民の知る権利が脅かされていることになるのですから」
「しかし……ならば何故、あの付近で行われたであろう戦いの爪痕が、何も残っていないのでしょう?」
これには、その場にいるコメンテーターたちは、誰一人として納得のいく答えを導き出せる者はいない。テレビの中の出演者たちが眉根を寄せる中、すべての真相を知る部屋の中の青年は、上機嫌で鼻歌を歌いながら皿洗いをしていた。
楽しみが増えた。
この辺りの細胞株たちが、今後どうなっていくのかを、見守る楽しみが。
決して公にしてはいけない案件ではあるけれども。
いつか――――この実験の結果から、何か世の役に立つような技術やデータを、得られればいいと、願う。
「キョウジ殿……。すっかり世話になってしまって――――」
最後の一枚を洗い終わった与助が、少し恐縮気味に声をかけてくる。それに対してキョウジは優しい笑みを面に浮かべて答えた。
「うんん、それはこっちだって……。ハヤブサには、どれだけ世話になっているか分からない。だからこれは、お互い様だよ」
「それでも……リュウさんの食事の量が………」
申し訳なさそうに口を開く与助に、キョウジも苦笑するしかない。
「ああ……びっくりするほどよく食べるね。薄々思ってはいたんだけど、ハヤブサって内臓が丈夫だよね」
「すみません……。後少ししたら、量も落ち着いてくるだろうとは思うのですが……」
「後少しって、どれぐらい?」
キョウジの問いに、与助は少し首を捻った。
「さあ……。倒れていた期間よりは、短いと思うのですが――――」
二人がそんな会話をしているときに、いきなり玄関のドアが、バン! と、派手な音を立てて開く。
「ハヤブサ!! 勝負だぁ!!」
キョウジの弟であるドモン・カッシュが、叫びながら勢いよく部屋に乱入してきた。兄と与助の姿をキッチンで見つけ、目的の人間とシュバルツがいないことに、ドモンはすぐに気づく。
「あいつはどこへ行った!?」
きょろきょろと部屋中に目線を走らせる弟に、キョウジは呆れながらも答えた。
「外に出て行ったよ。腹ごなしの運動だって」
「何ぃ!? おのれっ!! この前の勝負からの勝ち逃げは許さんぞ!!」
そう叫ぶや否や、弟は慌ただしく家から出ていく。
嵐が過ぎ去った後のように呆然とする与助に対して、キョウジは、当分退屈しなくて済みそうな予感に、少し心を躍らせていた。
「シュバルツ。打ち込みに付き合ってくれ」
キョウジのアパートから少し離れた郊外に、ハヤブサとシュバルツは足を運んでいた。少し拓けた平地に出ると、ハヤブサはシュバルツに木刀を投げてよこす。シュバルツがパシン、と、音を立てて木刀を手にしたのを確認してから、ハヤブサは己が手にした木刀を軽く素振りして、改めて構えた。
「……………」
シュバルツも、ハヤブサから少し距離を置いて、木刀を右手に無造作に下げて立つ。
一見、突っ立っているだけのようにも見えるが、それでいて、その姿には恐ろしいほど隙がない。シュバルツもハヤブサも、剣の達人であった。それが故に、木刀も真剣と同じぐらいの破壊力を持ちえた。
緊張感のある稽古ができる予感に、ハヤブサは大きく一つ息を吐いて、木刀越しにシュバルツを見る。なぜか、妙な懐かしさを感じた。
なぜだろう、と、少し考えて、やがて、ふと思い当たった。
(ああ。あの男の立ち方だな)
異世界の隼の里での修行に付き合ってくれた『仇』の姿をしていた男。あの男の立ち方に、とてもよく似ていると思った。
当たり前だ。
あの男はシュバルツで――――あの世界でも、ずっと俺を守り続けてくれていたのだから。
どうして――――
今になれば、よくわかる。
どうして自分は、この事実に気付くことができなかったのだろうか。
この立ち方もあの構え方も
シュバルツ以外にはあり得なかったのに。
ハヤブサが間合いを詰めると、シュバルツも中断に構え、すっとそれに合わせてきた。
最初は牽制をし合い、そして、互いを探るような打ち込み。
ガツ! ガツン! と、木刀が交わる音が辺りに木霊する。
打ち込む。
受け止められる。
弾かれる。
いなされる――――
(届かせたい)
ハヤブサの振るわれる太刀が、次第に熱を帯びるようになってきた。
心が、あの少年だった自分に戻る。
自分の太刀を、この目の前の強い男に届かせたい。
どうすれば届く?
どうすれば―――――
考え続ける。
がむしゃらに剣を振るう。
目の前の男を見つめ続ける。
ただ一点の隙を探り、そこに打ち込んでいく。
(鋭い――――!)
ハヤブサの太刀を受け続けながら、徐々に強く鋭くなってくるその太刀筋に、シュバルツは内心舌を巻く。
彼もまた、少年だったハヤブサとの打ち合いを思い出していたからだ。
まっすぐに力強く、振り下ろされてくる彼の太刀の美しさ。それは、少年のころから変わっていない。
ただ、今のハヤブサの太刀には重さがあった。確固たる意志があった。
自分は、『龍の忍者』としての使命を全うするのだという意志。そして、強い覚悟――――
それが太刀に乗り、シュバルツに襲い掛かってくる。
「く…………!」
それでも、シュバルツはそれを受け止め続け、太刀を合わせ続けていたのだが、ふとした弾みに隙ができてしまったのだろう。ハヤブサの太刀に、自分の太刀が弾き飛ばされてしまった。
「―――――!」
「覚悟!!」
ハヤブサは相手を押し倒し、その上に馬乗りになり、その喉元に太刀を突きつける。
相手の命を奪うために幼いころから叩き込まれた行動を、龍の忍者は忠実に再現していた。
「………………」
突きつけられた太刀の先にいるのは、穏やかな眼差しをした愛おしいヒト。そのヒトは自分と目を合わすと、にこりと優しく微笑みかけてきた。
「強くなったな」
その一言に、シュバルツもまた、あの異世界の隼の里での修行を思い出していたのだと、ハヤブサは悟る。
「シュバルツ……!」
彼もまた、同じ気持ちで戦っていたのだと分かって、ハヤブサは嬉しくなってしまった。
愛おしさの命じるままに、ハヤブサはシュバルツの唇を求める。
「あ…………」
薄く開いた唇から舌を忍ばせ、口腔を弄り、そこを優しく吸い上げた。
「ん…………」
その優しい感触に、ハヤブサは酔う。
もうずいぶん長いこと―――――彼に触れていない事実に、ハヤブサは気づいてしまっていた。
知らず、挿し込まれる舌の深度が深くなる。求める気持ちに歯止めがきかなくなる。ハヤブサは、いつしか彼の唇を、強く吸い上げていた。
「んんっ!」
呼吸を奪われてしまったのか、愛おしいヒトが腹の下であがきだす。
ああ、逃げないで。
逃げないで、くれ。
無我夢中でその唇を求め、呼吸を奪い続けていた。
「……………」
長い長いキスから、ようやく彼のヒトを解放する。
トロン、と、瞳が潤み、飲みきれなかった唾液を唇の端から垂らしながら、息を喘がせている愛おしいヒト。ハヤブサの心が、妖しく波立った。
よくぞまあ―――――
自分はこの美しいヒトに、長い間触れずにいられたものだ。
「シュバルツ………」
愛おしいヒトをさらに暴き立てようと、彼のコートに手をかけた瞬間。
いきなりシュバルツの右手が、彼の鳩尾を抉った。
「うげっ!!」
完全に不意を突かれてしまって、カエルの潰れたような悲鳴を上げながら、のたうち回ってしまうハヤブサ。それをしている間に、シュバルツはハヤブサの腹の下から逃れてしまっていた。
「これ以上はダメだぞ。ハヤブサ」
ものすごく冷たい響きを持ったシュバルツの声が、ハヤブサにのしかかってくる。
「な……! 何故だ……っ!?」
腹の痛みよりも、シュバルツの言葉の方に傷ついて、ハヤブサは少し泣きそうになる。そんなハヤブサを、シュバルツは少しジト目で睨み付けながら、呆れたように口を開いた。
「何故もなにも―――――お前、まだ身体が完治していないだろう?」
「―――――!」
「お前の唾液を診れば分かる」
シュバルツはそう言いながら、口の周りについているハヤブサの唾液をぺろりと己が舌で舐めとる。アンドロイドであるシュバルツは、口で含んだ物を舌の上で成分が分析できるようになっているのだ。
「まだまだ、健康な時からは程遠い。治るまでは、『そういうこと』は禁止だからな!」
「ええ~~~~~!?」
「『ええ~~~~~!?』じゃないだろう!? ハヤブサ!! まだ完全に身体は治っていないんだ! 無茶をして、ぶり返しでもしたらどうするんだ!?」
「うううう………」
不平に唇を尖らせ、低く呻くが、シュバルツのこういう診断はひどく正確であることを、ハヤブサも理解していた。だから、シュバルツの言うことを聞いて、ここは引っ込むべきだと理性は強く訴えるのだが。
(我慢できるか―――――ッ!!!!)
龍の忍者は声を立てずに吼えたてていた。
冗談ではない。
あの状態でこのままお預けなど―――――本当に『蛇の生殺し』状態ではないか。
触れたい。
一度だけでも。
どれだけお前に触れていないと思っているんだ。
このまま無理やり、押し倒してしまおうか―――――と、言う物騒な考えにハヤブサがとらわれ始めた時。
「やっと見つけたぞ!! ハヤブサ!! この前の勝負の続きだ――――ッ!!」
シュバルツの弟であるドモン・カッシュが元気いっぱいに乱入してきたが故に、ハヤブサの中のいろいろな下心が、ここで一気に粉砕されてしまう。
「上等だ!! 返り討ちにしてやるッ!!」
鋭く叫んだ龍の忍者が、ドモンに向かって力強く踏み込んでいく。その瞳から、うっすらと光るものが零れ落ちているように見えるのは、気のせいだろうか。
シュバルツは、しばらくかかりそうな一騎打ちを見守るべく、近くにあった大木の幹に、やれやれ、と、その背中を凭れかけさせた。
そんな3人の上には、抜けるような青空が広がっている。
優しい風を頬に感じながら、今日もいい天気になりそうだなと、シュバルツはその空を見上げていた―――――
了
ご愛読、ありがとうございました。
また後日、改めてあとがきを書きに来させていただきます。
龍と剣と、その拳と
やっと書き終わりました。
今回も読んでくださった方、ここだけを読みに来てくださった方、こんばんは。初めまして。空由佳子と申します。
今回の小説も、長くなったなぁ。すみません、短くまとめるのが苦手なもので……。
後、今回の小説ほど、行き当たりばったりな感じで書いたものもなかったです。普通はもう少し、ここに伏線を張ろうとか、こういう風な展開にしようとか思いついてから物語を書くものだと思うのですが、今回は、『なんとなくこういう感じで!』みたいなプランしか立てずに、ほぼ見切り発車状態で書いてしまいましたので、最初の方を読むと実は赤面したりします。「うわ~! 今と全然違うことを考えていたわ~!」みたいな感じで。
風呂敷を広げるだけ広げて、どうやってたたもうかと苦心した感じです。
なので、読めば読むほど、矛盾点、回収し忘れている伏線、突っ込みどころが満載だと思います。
ああ、未熟なんだなぁと鼻で笑っていただければ、これ幸いかと存じます。
なんだかんだ言って、この作品は二次創作。人様の作り上げた世界観とキャラクターを頼りに書き上げています。
一からオリジナルの作品で勝負していない私は、だから所詮は『なんちゃって作家』 世界の片隅で、目立たずひっそりと存在しているのがふさわしいのだろうとなと思っています。
でも万が一、この作品を見て、何か感じたり、面白いな、と思ってくださった方がいらっしゃいましたならば。
感想、コメントなど、Twitter、ブログの方に寄せてくださいましたならば、また、明日への活力になると思いますので、気が向きましたらで結構です。どうかよろしくお願いいたします。
そして、この素晴らしいキャラクター達を生み出してくださった、元の原作者様方に、心よりの感謝を申し上げます。
やっぱり書きたいのはこの人たちで、心は何度もこの人たちに帰ってしまうから、私は結局ずっとこの人たちを書き続けてしまうのだろうなぁと思います。
またお話の神様が私の中に降りてきて、新たな話をかけそうになったら、ひっそりとここに舞い戻ってきますので、その時は、またどうかよろしくお願いいたします。
それまで、私のこと忘れないでいて下さったら幸いですが………忘れられてしまうのだろうなぁ。
存在しているのかしていないのかわからないぐらい、微妙な存在の物書きですのでね……。
だからある意味気楽といえば気楽なのですが。
では皆さま! 万が一次回作がありましたならば、またそこでお会いしましょう!
その時まで、どうかお元気で!!