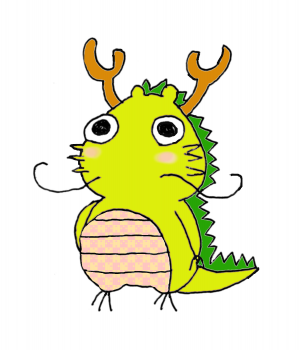ただひたすらに、君を想う。
皆様こんにちは。空由佳子と申します。
またまた小説を思いついてしまったので、こそっと上げさせて頂きたいと思います。
ただ今回の私の小説は、いつもと少し趣向が違います。根本に流れているのは、ハヤブサさん×シュバルツさんですが、ハヤブサさんが『受け』に回ります。相手はというと、ハヤブサさんの幼馴染で同じ忍者仲間のハヤテさんという方です。
人間関係の構図としては、
ハヤテさん → ハヤブサさん × シュバルツさん
と、なります。
この矢印の意味、掛け算の意味が分からない方は、閲覧されないことを強くお勧めいたします。殿方同士が絡む、いわゆる一つの『BL小説』でございますので。序章からそう言う描写がございます。楽しめる方だけ、どうかお楽しみください。
登場人物を紹介させていただきます。
リュウ・ハヤブサ …… この物語の主人公。「龍の忍者」の肩書を持つ、最強クラスの忍者。
シュバルツ・ブルーダー …… 腕利きの忍者にして不死のアンドロイド。リュウ・ハヤブサの恋人。
ハヤテ …… 霧幻天神流18代目党首の忍者。リュウ・ハヤブサの幼馴染。
キョウジ・カッシュ …… アンドロイドであるシュバルツを創り出した科学者。
あやね …… ハヤテの部下。党首であるハヤテに想いを寄せている。
主な登場人物としては、これぐらいでしょうか。
この話、もしかしたら昼メロ臭が漂うかもしれません。幸せな話ではないかもしれませんが、丁寧な心理描写が出来るように頑張ります。
序章
何がいけなかったのだろう。
何を間違ってしまっていたのだろう。
いくら考えても、正しい答えなど出る筈も無いのに――――
座敷牢の窓からのぞく薄い月明かりを見つめながら、リュウ・ハヤブサはぼんやりと物思う。しばし、部屋に差し込むその光に視線を漂わせていると、自分の中に打ち込まれている楔が動いて、いきなり思考を現実に引き戻された。
「どうした、リュウ……」
「あ…………」
自分のすぐ目の前には、自分の『親友』であるハヤテの、凛とした顔がある。今、ハヤブサを貫いているのは、その『親友』であった筈のハヤテその人であるから、ハヤブサはその事実に途方に暮れてしまう。一体自分は、どうすればいいと言うのだろう。
「リュウ……」
熱い声で名を呼ばれ、腰の動きが速くなる。
「あ……! あ………!」
ハヤブサはそれに、涙を飛び散らせながら小さく喘ぐしか術を持たない。ハヤテの指が、ハヤブサの髪を優しく撫でる。彼の指の間から、ハヤブサの琥珀色の細い髪が、さらりと零れた。二人の動きに合わせて、床がきしきしと音を立てて軋む。そしてそのたびに、ハヤブサの首と手足に繋がれた鎖が、チャリ、と、冷たい金属音を奏でていた。
「ハヤテ……!」
親友の名を呼びながら、ハヤブサは愛おしいヒトに想いを馳せる。
(シュバルツ……!)
窓から差し込む月の光が、次第に暗く霞んで行った。
第1章
「ハヤテ!」
骨董商との商談が終わり、その帰りの駅で珍しく親友の姿を見つけたハヤブサは、思わず声をかけて走り寄っていた。「ハヤテ」と呼ばれたその青年も、走ってくるハヤブサの姿を認めて、ふっと相好を崩した笑顔を見せる。
「リュウ……」
「久しぶりだな。元気だったか?」
「ああ。お前も、息災で何よりだ」
ハヤテも、ハヤブサと同じ忍びの者で、霧幻天神流18代目の党首でもある。霧幻天神流はハヤブサのそれとはまた違い、忍びの「掟」にも厳格な流派であるが故に――――党首であるハヤテの身は多忙を極めていた。こうして、里以外の外界で会う事自体、本当に稀な事であったのだ。
ハヤブサにとってハヤテは、幼馴染でもある。久しぶりに会ったその友人に、積もる話も沢山あった。
「どうだ? 寿司でも食べながら、一献傾けないか?」
そう言って誘ってくるハヤブサに、ハヤテもまんざらでもない笑みを浮かべた。ハヤテにとっても、ハヤブサとの時間は、心安らぐ一時であったからだ。
「そうだな……。ゆっくりお前と話したいが……」
しかし、党首としてのスケジュールが立て込んでいるハヤテの身には、あまり自由時間がない。ハヤテは、名残惜しそうに微笑んだ。
「あいにく、時間がなくてな……。だが、茶を一杯、お前と飲むぐらいには、時間が取れそうだ」
「そうか……。じゃあ、決まりだ」
ハヤブサが嬉しそうに微笑むから、ハヤテもつられて、その表情がほころぶ。二人は肩を並べて歩き出した。
「……ったくキョウジの奴……! 人使いが荒い――――」
同時刻。ブツブツと文句を言いながら、シュバルツ・ブルーダーもまた、その駅に来ていた。キョウジに頼まれた本をようやく探し当て、帰路についている途中だった。
キョウジの欲しがる本は、たいていマニアックすぎて発行部数自体が少なく、しかも絶版になっていたりして、普通の本屋には置いていない。その為シュバルツは、ネットを調べたり、図書館を回ったり、古書店を巡ったりして、その本を探し出さなければならなかった。
(しかしキョウジめ……。一体、どこでこんな本の情報を仕入れているんだ……?)
疑問に思って、軽くため息を吐く。図書館巡りも古書店巡りも嫌いではないと言うか、寧ろ好きな方なので、苦になったりはしないが、こちらの情報収集能力を試されているのではないかと感じる時もある。今はまだこうして見つける事が出来る物ばかりだが、そのうち、本当に入手不可能なやつを頼まれたらどうしようか――――などとシュバルツが思考している時、リュウ・ハヤブサの姿を目の端に捉えた。
(ハヤブサ……!)
特に今日、ハヤブサと会う約束をしている訳ではない。
だが、せっかく会えたのだから、声をかけるぐらいは良いだろうと思って、シュバルツはハヤブサに向かって一歩、踏み出そうとする。だが、それをしようとした瞬間、ハヤブサの方が、ある青年の方に向かって嬉しそうに声をかけていた。
「ハヤテ!」
ハヤブサから声をかけられた青年も、振り向いてハヤブサの姿を認めると、嬉しそうに微笑んでいる。端正な顔に笑顔が宿ると、驚くほど柔らかい印象を、その青年は周りに与えていた。シュバルツは何故か、二人の邪魔をしてはいけないと感じて、咄嗟に二人から身を隠していた。
(……………)
物陰からそっと、二人の様子を覗き見る。
ハヤブサは、ハヤテと言う青年に、嬉しそうに話しかけていた。ハヤテと呼ばれた青年の方も、それに優しい笑みを浮かべて応えている。それでいて、その立ち姿には一分の隙もない。そして、その視線の配り方、身体の使い方に忍び独特の物が窺えるから、彼もまた、『忍び』の者であると容易に察知する事が出来た。
二人は和やかに何事かを話し合った後、そのまま肩を並べて歩き出していた。
(何だろう……? 友人かな……?)
その姿を見送りながら、シュバルツは暫し思考にふける。それにしても少し驚いた。たいてい他人に会う時仏頂面になっている事が多いハヤブサが、あんなに嬉しそうな顔をして微笑むなんて。
しかし、考えてみれば当たり前の話だ。自分に出会うまでのハヤブサの人生にも、彼の積み重ねて来た時間があるのだ。彼が大切に思っている『友人』の一人や二人いた所で、別におかしくは無いと思った。
(それにしても………)
ハヤテとハヤブサが共に並んで歩いている姿を見ると、妙に『似合いだ』と感じてしまうのは何故なのだろう。やはり忍者どうし、纏っている空気が同じだからなのだろうか。それとも―――――
肩を並べて親しげに歩く様子は、まるで『恋人同士』の様でもある。そう思い至った瞬間、シュバルツの胸にツキリ、と鈍い痛みが走った。それと同時に、胸の奥に、何だか黒いもやもやとした塊が、蟠(わだかま)って居座り始める。これではいけない、と、シュバルツは思った。
(今ここで、声をかけるのは止めよう。後日、ハヤブサに改めて聞けばいいだけの話だ)
シュバルツはそう決意すると、踵を返してすたすたと歩き出した。彼は、予定していたルートを変更して、キョウジの家に帰る段取りをつけていた。
「それにしてもリュウ。お前、表情が明るくなったな」
駅の近くの和菓子屋で茶をすすりながら、ハヤテはハヤブサに対して正直な感想を伝える。
「そうか?」
少し驚いたように顔を上げるハヤブサに、ハヤテは頷いた。実際、先程から話をするハヤブサの表情は、以前よりも明るくて柔らかい。そんなハヤブサの表情を見るのは嫌いではない(寧ろ好きだ)なので、ハヤテも、自然と優しい気持ちになれるのだった。
「ああ。だが俺は、そんなお前の変化は、いいことだと思うぞ?」
「う………!」
正直な感想を述べる。するとハヤブサが、酷く照れたように下を向くから、ハヤテはうっかり彼を抱きしめそうになってしまう。だがそんなことはおくびにも出さず、面は鉄壁のポーカーフェイスを貫いていた。
「リュウ、何か、お前に良い事でもあったのか?」
しかし、彼の表情が柔らかくなった原因を知りたいハヤテは、ハヤブサにこの質問を投げかける。すると、ハヤブサがますます赤面してはにかんだ表情を見せるから、ハヤテは内心小躍りをして、心の中で神に手を合わせていた。
ああ神様、感謝します。
こんなに可愛らしいハヤブサの姿が拝めるだなんて――――
どうして彼は今、こんなに柔らかい表情をしているのだろう。
「ハヤテに会えて嬉しい」
そう言う理由で彼が今この表情をしているのだとしたら――――こんなに幸せな事はないのに―――――
だが次の瞬間、ハヤブサの口から零れてきた言葉は、ハヤテの心を打ち砕くには充分な物だった。
「実は俺……今……『恋人』が出来ていて……」
「―――――!」
ハヤブサのその言葉に、ハヤテは飲みかけていたお茶を零しそうになってしまう。だが、そこは流石に忍びの党首。彼は、そんな内心の動揺などおくびにも出さずに、茶をすすり続けていた。
「ほう、それは、良かったな」
茶を飲み、少し心を落ち着けてから、ハヤテは口を開く。自分がどれだけハヤブサの事を好きなのかを改めて突きつけられて、ハヤテは内心苦虫を噛み潰していた。
だが仕方がない。
好きな人の『幸せ』を願うのも、確かに愛情の内なのだと、ハヤテは自分で自分に言い聞かせていた。
「………で? お前の心を射止めたのは、どんな幸運な女性なのだ?」
だからハヤテはこう聞いて――――総てをあきらめるつもりでいた。
そして彼は、実際、自分の想いを押し殺す事が出来たであろう。ハヤブサの口から出てきた言葉が、『この女性を好きだ』と言う物であったならば。
だが実際は―――――。
「……………」
ハヤブサは、しばし湯呑の中でゆらゆらと揺れる緑茶を見つめながら、思考に耽っていた。
後から思えば、ここでハヤテとの会話を切り上げても良かった。
『友人』との会話なのだ。そんなに微に入り細に入り、話す必要も無かったのだ。だけどこの時ハヤブサは、『ハヤテには、隠し事をしたくない』と考えていた。
幼いころから、ハヤテは特別な『友人』だった。その友人にこそこそと隠し事をするのは、ハヤブサとしても本意ではなかった。
『男』を好きになってしまったと言えば、もしかしたらハヤテから、奇異の眼差しで見られるかもしれない。最悪、侮蔑されて離れて行かれるかもしれない。
だがハヤブサは、それ以上にハヤテに嘘をつく事を潔しとは出来なかったのだ。それに、自分達忍者の間で『衆道』は、そんなに珍しい事でもなかったという事実も、ハヤブサの背中を後押ししていた。
だから彼は、こう口を開いた。
「実は……俺が好きになったのは……『男』なんだ………」
「―――――!」
ハヤテの茶を飲もうとしていた手が、ピクリ、と、止まる。
(侮蔑されるかな?)
ハヤテの少しの動きに、ハヤブサは知らず身構えてしまう。茶をその手に持ったまま、静かに座り続けているハヤテからは、相変わらず何の感情も読み取れない。
「……………」
沈黙が続く。
時間にしては短いものだったのかもしれないが、1秒が永遠にも感じられそうな空気の重たさに、ハヤブサは息苦しさを感じていた。
(何でもいい……! 何か言って欲しい……!)
そう願うのだが、何故かハヤテの顔をまともに見る事が出来ない。踏ん切りをつけられないまま、ハヤブサが湯呑の茶を見つめていると、ハヤテが目の前のテーブルに、空になった湯呑をコトリ、と、音を立てて置いた。それをきっかけに、ハヤブサが顔を上げると、酷く穏やかな様子のハヤテと、視線が合った。
「そうか………」
友人は、短くそれだけを言った。そしてそれだけで――――ハヤブサは理解した。友人は、男を好きになってしまった自分を、受け止めてくれたのだと言う事を。
そうだ、と、言って、ハヤブサは微笑む。それに、ハヤテも微笑み返してくれたように見えた。
「さて、残念だが、そろそろ俺は行かねばならぬ。ではハヤブサ、またな」
そう言ってハヤテは立ち上がると、静かに喫茶店から出て行った。ハヤブサも会計を済ませて喫茶店を出ようと立ち上がろうとして―――――テーブルの上の会計伝票が、いつの間にか無くなっている事に気づく。
(またやられた……! ハヤテの奴め! 誘ったのは俺なのに……!)
会計伝票は、つい先程までテーブルの上に確かに在った。だから、今回の会計伝票争奪戦は、自分の負けなのだとハヤブサは悟った。悔しいが、ある意味仕方がないのかとも思った。今回の自分は、ハヤテの前に、割と隙を大きく見せてしまっていたのだから。
(次は絶対負けない……! だが、次にあいつと会えるのは、いったいいつなのだろう……)
そう感じて、ハヤブサは首を捻ってしまう。それほどまでに、霧幻天神流の党首であるハヤテとプライベートで会うのは、難しい事になりつつあった。小さくため息を吐きつつ、ハヤブサもまた、喫茶店を後にする。外に出ると、午後の優しい光が、ハヤブサの瞳を打った。
(シュバルツに、会いたいな……)
ハヤテに、彼のヒトについて話したせいだろうか。『約束の日』までまだ少し日はあるが、ハヤブサは無性に愛おしいヒトに会いたいと願っていた。
家に帰り、キョウジに本を渡したシュバルツだが、胸の奥に宿る「もやっ」とした蟠(わだかま)りは消えない。これではいけない、と、彼はキョウジに一声かけてから、外へと出て行った。そのまま郊外の森に入ると、彼はそこで木刀の素振りを始めた。自分の中に『雑念』や『邪念』が湧いた時は、こうやって修業をするに限るのだ。
嬉しそうに笑うハヤブサが居た。
それを優しく見つめる青年が居た。
栗色のセミロングの髪を無造作に一つに束ね、穏やかな眼差しでハヤブサを見つめる青年。二人が並び立つと、それはとても美しい一枚絵の様だった。思わず「ずっと見つめていたい」そう感じてしまうほど――――。
何故なのだろう。
纏っている空気が同じだからなのだろうか。
それとも、二人の共有して来た『時間』の長さが、そういう雰囲気を作り出しているのだろうか。
結構な事ではないか。
ハヤブサに親しい『友人』が居るという事は。
これは素直に祝福するべき事で、こんな風にこちらがイラつく必要など何一つ無――――
(でも、好きなのだろうな)
不意にシュバルツは思った。
ハヤブサの方はどうか知らない。
だが、あの青年の方は。
優しい眼差しでハヤブサを見つめていたあの青年の方は、ハヤブサの事を好きなのではないだろうかと感じる。少なくとも、『友人』以上の感情で――――
そしてそれに、もしもハヤブサが気がついたとしたら。
彼はどうするのだろう。
彼は、あの青年と私の、『どちら』を選ぶのだろう。
そこまで思い至ってしまってから、シュバルツは「はっ!」と気がついて頭をふる。
(馬鹿な事を――――! 『選ばせる』など、おこがましいではないか! そうなった場合、身を引くのは私でなければならない筈だ!)
あの青年は『人間』
私は、『アンドロイド』
そして『人間』であるハヤブサの、その隣に居るべきはどちらか。そんなの、考えるまでも無く、答えは一つだ。
勘違いするなよ。
思い上がるなよ、シュバルツ・ブルーダー。
お前は元来、人間の横で『恋人』などと大きな顔をして居座って良い存在ではない。人間ではない、歪な物で構成されている人工物の自分は、それこそ『道具』の扱いで充分なのだ。飽きるまで使ってもらって、飽きたらそのまま打ち捨てられたって文句は言えない。言う資格など無い。それで充分なんだ。それで――――
(分かっていないなぁ。お前は……)
不意に脳裏に、ハヤブサの優しい声が響く。
(俺は『お前』だから、こうして触れていたいと、願うのに――――)
「…………ッ!」
違う、駄目だ――――! と、シュバルツは何度も己を否定する。
勘違いするな。
思い上がるな。
お前は『モノ』だ。『道具』なんだ。
『道具』だから、使ってもらえるだけでいい。打ち捨てられたって、文句は言えない。
『道具』が『人間』と対等でいようなどと、それこそおこがましすぎる。
ならば何故
何故
こんなにも、『ココロ』が軋む?
ハヤブサの愛情が離れて行くかもしれない、と、思っただけで、何故そんなにも嫌がっているのだ。
離レナイデ
行カナイデ
そうやって、泣きわめきそうになる自分が居る。
そんな事、許される筈も無いのに―――――
たかが『道具』の分際で―――――!
こんなのは『邪念』 まさしく、『邪念』だ。
断ち切れ。
今こそ。
その手で―――――!
「叭―――――――ッ!!」
シュバルツは、目の前の大木に向かって、木刀を一閃させる。正しく『明鏡止水』の極意を発露させているのならば、目の前の大木は、木刀によって一刀両断される筈であった。
しかし。
次の瞬間、ガキッ!! と鈍い音を立てて砕けたのは、木刀の方だった。
「…………!」
シュバルツはしばし呆然と、その砕けた木刀を見つめていたが、やがて、背後の木の幹に、その身をトン、と、凭れかけさせた。
「ハハ……。弱いな……。私は………」
邪念と雑念だらけの己が剣に、シュバルツは苦笑する。泣きたくも無いのに、勝手に涙まで零れおちて来た。
ハヤブサに想いを寄せている『人間』が居る――――
たったそれだけのことで、何故ここまで動揺しなければならないのだろう。自分の心の弱さに、シュバルツはほとほと嫌気がさしてしまう。
(このままではいけない)
そう強く思ったシュバルツは、己が顔を上げた。こういう時にこそ行くべき、己のもう一つの『修行の場』が在る。それに、思い至ったのだ。
シュバルツは静かに、その森から姿を消した。。
後には木立の間を縫う風だけが、残されていた。
(よし! 今日のロードワークは終わったな……。後は……)
額から流れる汗を拭いつつ、ドモン・カッシュは大きく息を吐く。
『キング・オブ・ハート』としての使命を背負っているのも勿論のことだが、もうすぐ『格闘家』としても大事な大会が近い。だから修業に手は抜けない。益々精進しなければ―――――と、ドモンが顔を上げた瞬間、一筋の鋭い殺気が、彼に襲いかかってきた。
「―――――!」
バシン!! と、その拳を受け止めて、襲って来た者の顔を見て、ドモンは素っ頓狂な声を上げてしまう。
「兄さん!?」
そう。彼に襲いかかって来たのは、兄キョウジの『影』にしてアンドロイドのシュバルツそのヒトであったから、彼はとても驚いてしまっていた。キョウジもシュバルツも、ドモンにしてみれば紛う事無き大事な『兄』だ。だから彼はシュバルツの事も『兄』と呼び、とても慕っていた。
「ドモン! 少し――――組み手に付き合え!!」
一の拳を受け止められたとみたシュバルツは、その言葉の終わらぬうちに、もう次の手を繰り出してくる。ドモンはそれを紙一重でかわしながら、その瞳には不敵な色を宿らせて始めていた。
「良いぜ! 俺もちょうど――――組み手相手を探していた所だッ!!」
繰り出されてきたシュバルツの拳を弾いて、ドモンは距離を取る。何故兄が急にこんな組み手を挑んできたのかは分からない。だが、ドモンは、兄の方の事情を慮ると言う事はしなかった。
実際、兄と拳を交えるのは楽しい。
大好きな兄に修業をつけてもらえると言うのであるならば、それこそ、願ったり叶ったりだ。
それに拳を交える方が――――何百と言葉を交わすより、自分としては兄と雄弁に会話ができると言うものだ。
「来い!! ドモン!! 手加減なしだ!!」
ファイティングポーズを取る兄が、嬉しい事を言ってくれる。
「言われずともッ!!」
ドモンも喜々として、自分の『闘気』を爆発的に膨れ上がらせた。元よりシュバルツ相手に手加減などしたら、こちらがやられてしまうのだ。
「行くぞっ!!」
「来い!!」
ドンッ!! と、派手な音を立てて、兄弟たちは今――――全力でぶつかり合い始めたのだった。
ドモンの拳はひたすら真っ直ぐだ。
そして、純粋で、混じり気のないひたむきな闘気を帯びて、こちらに向かってくる。
(さすがだな! ドモン!!)
弟の拳を受け、時にかわしながら、シュバルツもまた歓喜に震える。
真っ直ぐな闘志。
迷いのない拳。
弟の『心・技・体』どれをとっても充実している事が伝わってきた。
これだ。
自分はこれが、見たかったのだ。
これに対応するためには、自分もまた、無我の境地に身を置かねばならぬ。
雑念を持ち、邪念を抱けば――――この『キング・オブ・ハート』の拳に、自分はあっという間にやられてしまうだろう。
可愛いだけだった『弟』が、幾多の試練を乗り越え、友を得て、一人前の戦士へと成長して行った。
そんなお前を、誇りに思う。
そして、そんな『弟』が―――――誇りに思えるような『兄』でありたい。
ドモンの拳は、シュバルツの背筋を正し、心持を正しめる。
この弟が居てくれて良かったと、シュバルツは今――――心から感じていた。
(兄さん……!)
シュバルツと組み手をしながら、ドモンもまた歓喜に震える。
シュバルツの拳は厳しい。だが、どこかに必ず優しさを秘めている。
自分の師匠はあくまで東方不敗マスターアジアだ。だが、このシュバルツの拳にも、自分は確かに教えられ、守られ、そして導かれてきた。
俺の、誇るべき『兄』――――
兄さん、俺は
そんな貴方の背中に、少しは追いつけているのだろうか?
「でりゃっ!!」
繰り出した渾身の一撃がいなされ、返り討ちにあう。よろけた所に迫って来る拳を、逆にカウンターで返した。
「やるな!」
不敵に笑うシュバルツに、ドモンもまた、挑戦的な笑みを返す。
「まだまだ!」
こんな楽しい時間、簡単には終わらせたくないとドモンは願った。だがその組み手の終止符は、意外なところからもたらされる事になる。
「シュバルツさんが来てるの?」
全く予想だにしなかった所から―――――と言うか、二人の戦っていた場所が、いつの間にか家の玄関の付近に移動していた物だから、不意打ち的にドアが開き、いきなり二人の傍にドモンの恋人であるレインが出現したような格好になっていた。
「――――!? レイン!?」
「わ……!? ちょっと……ッ!!」
いきなり現れたレインにシュバルツは気を取られ、ドモンは振るった拳を止め損ねた。
結果。
バキャッ!! と、派手な音と共にシュバルツは吹っ飛ばされ、数メートル先の地面に叩きつけられてしまう。
「わっ!? 兄さん!?」
「シュバルツさん!!」
2人が慌てて駆け寄ると、シュバルツが苦笑しながらその身を起こしてきた。
「いや~、参った……。ドモン、すっかり強くなったなぁ」
「ご、ごめん! 兄さん! 拳を止められなくて―――」
謝りながら手を差し出してくるドモンに、シュバルツも笑顔を返しながらその手を掴む。
「平気だ。よそ見をした私だって悪い」
「ごめんなさい! 私がもっと確認してドアを開けていれば――――」
「いや……私たちも、周りの状況確認を怠っていた。レイン、君に怪我はなかったか?」
シュバルツの言葉に、レインは「はい」と頷く。
「そうか……良かった………」
シュバルツは軽く手足を動かして、身体の異常がないかを確認する。幸いにして、どこにも異常は見当たらなかった。あった所でこの身体は治ってしまうから、さして問題にもならないのだけれど。
そしてシュバルツは、ドモンと手合わせをする前よりも、自分の心が落ち着いている事を自覚する。やはり――――弟の存在とその拳が、自分には一番良い薬だとシュバルツは思った。
(それにしてもこの状況……やはり、私の方が弟離れが出来ていない事になるのかな。いったい私は何時になったら、弟から卒業できるのだろう……)
そう感じて苦笑する。この様子だと、自分が弟から卒業できるのは、まだ当分先の様な気がしないでもなかった。服についていた汚れを軽く落とすと、シュバルツは二人の方に改めて振り返った。
「邪魔をしたな、ドモン。じゃあ、私は帰るから――――」
「えっ? 帰っちゃうの!?」
シュバルツのその言葉に、レインが素っ頓狂な声を上げた。「えっ?」と、シュバルツが振り向くと、レインが縋るような眼差しでこちらを見ている。
「お願い、シュバルツさん! 夕食を食べて行ってくれない? マスターから野菜を大量に送られて来て、その処理に困っているの!」
「へっ?」
と、言って固まるシュバルツの横で、ドモンもまた目をぱちくりとしばたたかせている。
「えっ? 師匠から野菜って……」
「あの台所に積み上げている段ボール全部よ!! 貴方見てないの!?」
「えっ? あれ全部!?」
「そう! あれ全部!」
(『あれ全部』って……どれぐらいなんだろう……)
2人の会話を聞きながら、シュバルツは多少引き気味になる。このぶんだと夕食を食べた後、絶対手ぶらでは帰れない流れになりそうだった。
「なんだ。俺はてっきりあれ全部レインの美容セットの類かと……」
「それだけ気を遣わなきゃいけない程、私の肌がぼろぼろだって言いたいの!?」
ゴイン! と、小気味いい音を立てて、レインの鉄拳制裁が飛ぶ。哀れドモンは、頭に巨大たんこぶを作って突っ伏す羽目になってしまった。
「と言う訳でシュバルツさん。夕食を食べて行ってくれないかしら?」
ドモンを殴り伏せたレインが、とてもいい笑顔で振り向きながら誘ってくる。これは、絶対に断ってはいけない流れになってしまったとシュバルツは悟った。
「わ……分かった……。だが、一度家に帰っても良いか?」
「えっ? どうして?」
小首をかしげて疑問を呈するレインに、シュバルツは宥める様に言葉を続ける。
「私一人だけ、そんな贅沢に預かる訳にもいかないだろう? キョウジも呼んでくるから」
シュバルツのその言葉に、ドモンもレインも、その面にとても嬉しそうな表情を浮かべた。
「えっ!? 兄さんも!?」
「そうね! ぜひ、そうしてくれる? 待ってるから!」
二人のその言葉に、シュバルツもまた、その面に笑みを浮かべた。キョウジは本当に、この二人に慕われていると思った。
「じゃあ、また後でな」
そう言うと、シュバルツはキョウジを呼ぶべく、踵を返してそこから立ち去って行った。
「えっ? レインが?」
数刻後、シュバルツに買って来てもらった本を読みながら、実験のデータをまとめていたキョウジが、少し驚いた様な声を上げていた。
「ああそうだ。夕食を振るまいたいと言われて――――」
「やった――――!! 久しぶりに、まともな夕食が食べれる――――!!」
「喜びすぎだ! キョウジ……。まあ、気持ちは分からんでもないが――――」
キョウジが手放しで喜ぶ様に、シュバルツも苦笑しつつも嬉しくなってしまう。無理もない。キョウジはここのところ実験が忙しくて、まともに家に帰れていない状態が続いていたからだ。
「でかした! シュバルツ! でも、どうしたんだ? ドモンの所に行っていたのか?」
「ああ。まあ――――」
キョウジからの質問に、シュバルツは少し視線を泳がせる。
「……ドモンも、もうすぐ格闘大会が近いだろう? だから、稽古をつけに行っていたんだ」
当たらずとも遠からずの事を言う。本当は、自分の気持ちを整えるために、ドモンの拳を求めに行ったのだが。
「ふ~~ん?」
キョウジはしばらくそんなシュバルツをじっと見つめていたが、フッと笑顔を見せると、いそいそと立ち上がった。
「じゃあ、急がないとな! ドモン達も待っていてくれているんだろう?」
「ああ。そうだな」
シュバルツがそう返事をした時、キョウジの手元の携帯電話が鳴った。
「はい、もしもし」
キョウジが電話に出ると、その向こうからアカサカ教授の声が聞こえて来た。アカサカ教授とは、キョウジ達の父であるライゾウ・カッシュの師に当たる人で、キョウジがこの研究室に復帰するにあたって、かなりの尽力をしてくれた人物でもある。相当な高齢で人当たりも良く、研究室の皆に『おじいちゃん先生』と呼ばれて慕われている存在でもあった。
「教授? どうしたんですか?」
キョウジの問いかけに、アカサカ教授の、か細い、頼り無さげな声が聞こえてくる。
「キョウジ君……。今から……研究室の方に出てこられないかのう……?」
「えっ? ど、どうしたんですか……?」
若干嫌な予感を感じながらも、キョウジは教授に問いかける。すると教授が、途方のくれた声で返事して来た。
「じ、実は……この前、キョウジ君がデータをまとめてくれた、ラットの一群が居ったじゃろう……?」
「ええ、あのラットたちですか? あれはちゃんと分別して、ゲージに入れた筈ですが……」
「そ、それがのう、キョウジ君……」
アカサカ教授が泣きそうな声で言葉を続ける。
「さっきうちのミーコが、ラットのゲージをひっくり返して……」
「へっ?」
「せっかくキョウジ君が分別してくれたラットが、ごちゃ混ぜになってしまって……」
「へっ?」
「ミーコを押さえて、部屋も閉めて……ラットは研究室から外に逃げてはおらんと思うのじゃが……わし独りでは、どうにもならなくてのう………」
「――――――」
あまりの事態に、キョウジは思わず絶句してしまう。割と、研究室に閉じこめられて、そのまま帰れなくなるコースが決定したように感じた瞬間だった。
「はい……はい……。分かりました。すぐ行きますので―――――」
そう言って、キョウジは携帯の通話を切る。
はあ、と、ため息を吐きながら顔を上げると、同じく複雑な表情をしてこちらを見ているシュバルツと視線が合った。
「……行くのか?」
そう聞いてくるシュバルツに、キョウジも頷く。
「仕方がないよ。アカサカ教授の頼みじゃね~………」
「まあ、確かに……断れないよなぁ……」
しみじみと返してくるシュバルツに、キョウジも『だろ?』と、言った後、大きなため息を一つ吐いた。
「それにしても……研究室に、できればミーコちゃんは入れないで欲しいんだけどなぁ……」
「そうだな……。アカサカ教授も、あれが無ければいい人なのだが……」
二人が同時に大きなため息を吐いた所で、キョウジがおもむろに手元の携帯電話を操作しだした。
「……仕方がない。ドモンには断りの電話を入れて――――」
「その必要はないぞ、キョウジ」
「えっ?」
驚いたキョウジが顔を上げると、にっこりと微笑んだシュバルツと視線が合った。
「教授の研究室には私が行こう。キョウジは、ドモンの所へ行って、夕飯を御馳走してもらえばいい」
「で、でも―――――!」
「こういう時に遠慮する必要はないぞ、キョウジ。それにお前には、栄養が必要だろう?」
「そ、それはそうかもしれないけれど……! でも――――!」
この局面で、変に遠慮しようとするキョウジにシュバルツは苦笑する。彼からしてみれば、面倒くさい事、嫌な事を自分に押し付ける様で、気が引けてしまっているのだろう。だが逆だ。こういう時にこそ、自分はキョウジに頼って欲しいと願っている。アンドロイドである自分には――――実際、固形物の『栄養』など必要ないし、キョウジの役に立てる事こそが、自分にとっては何物にも代えがたい喜びなのだから。
「心配するな。ネズミを捕まえるだけだろう? すぐに終わらせて、私もドモンの家に行くから」
「うん………」
まだ曇った表情をしているキョウジにシュバルツは苦笑すると、その肩をポン、と、叩いた。
「じゃあキョウジ。一つお願いをして良いか?」
「何? シュバルツ」
「レインの料理を、少しでいいから私のために取っておいてくれ」
「――――!」
目をぱちくりとさせるキョウジに、シュバルツはにっこりと微笑んだ。
「レインの料理は……『愛情』が沢山入っているから、好きなんだ」
「なるほど……!」
シュバルツの言葉に、キョウジも合点がいったように頷いた。シュバルの身体を構成しているDG細胞は、人の『ココロ』を動力源(エネルギー)にする物だ。だからシュバルツは、食事を採る時はそれ自体の栄養を食べているのではなく、それに込められた『ココロ』を消化するのだろう。レインの料理はシュバルツにとって、そういう意味では間違いなく『極上の料理』と言っても過言ではなかった。
「分かったよ! シュバルツ! そう言う事なら喜んで!」
キョウジの表情に、ようやく笑顔が宿る。それを見てシュバルツもまた、満足そうに頷いた。
「じゃあキョウジ、ドモンとレインによろしく言っておいてくれ」
「シュバルツこそ――――アカサカ教授の事よろしく」
「余計な仕事が増えても、文句は言うなよ?」
「仕方がないよ。多分教授は、『そういう』仕事も用意して、こちらに電話して来ていると思うから……」
キョウジの的確すぎる分析に、シュバルツも苦笑するしかない。あの『おじいちゃん先生』は、キョウジによく微妙な雑用をついでに持ち込んでくる。それだけ当てにされていると言う事なのだろうが、こちらの仕事が増えるのは、多少困りものだった。もしかしたら教授に、キョウジがどれだけ仕事をこなせるのか、測られている気がしないでもなかったが。
「じゃあ、また後で」
そう言って、キョウジとシュバルツは別れた。
その日の夜更け。
シュバルツは、やれやれとため息を吐きながら、キョウジのアパートの玄関までたどり着いていた。
(……案の定、遅くまでかかってしまったな……。結局、ラットの捕獲だけじゃなく、データの取り直しや整理の作業にも付き合わされたから……)
そんなシュバルツの手には、他の実験のデータも持たされている。これらのデータも、改めて整理しなおさなければならないらしい。流石に今夜はもう遅いからと、教授の許可を得て、シュバルツはそのデータを家に持ち帰っていた。キョウジの仕事が増えた事になるのだが、これぐらいの量であればキョウジならば問題なく対処できると、シュバルツは判断していた。逆に仕事を持ち帰らずに手ぶらで帰った方が、キョウジが却って変わり身を頼んだ事を恐縮してしまう事をシュバルツは知っていたのだ。
(しかし、随分夜も更けてしまったな……。どうする? レインの手料理は食べに行きたい所ではあるが――――)
時計は、もう夜の12時近くを指している。いくら兄弟とは言え、訪問するには、いささか遅すぎる時間だとシュバルツは思った。特に早寝早起きが習慣化しているドモンなどは、とっくに寝入ってしまっている事だろう。
こっそり家に侵入して、キョウジに声をかけて、レインの料理を少し分けて帰って来ようか――――と、シュバルツが考えていた時、いきなり背後に何者かが降り立つ気配がした。
「―――――!?」
シュバルツがばっと振り向くと、その視線の先にリュウ・ハヤブサの姿が在ったから、シュバルツはかなり驚いてしまう。
「ハヤブサ!?」
シュバルツが声を上げると、ハヤブサが少しばつが悪そうにしながら声をかけて来た。
「悪い、シュバルツ……。その……『約束の日』まで、まだ日にちが在ることは承知しているのだが……」
「……………」
じっとこちらを見つめてくるシュバルツの視線を感じながら、ハヤブサは言葉を続けた。
「その……気に食わなければ殴ってくれていい。だが……どうしても、お前に会いたくて」
「――――!」
息を飲むシュバルツを、ハヤブサがじっと見つめてくる。
「少しでいい。触れたいんだ」
「ハヤブサ……」
玄関先で佇むシュバルツに、ハヤブサは更に一歩、近付く。
「駄目か……?」
愛おしくて、大切なヒト―――――本当ならハヤブサは、毎日でもシュバルツに会いたい。そして触れたいと願う。だけど、自分の身体を構成している『DG細胞』の歪さと闇を、誰よりも理解している愛おしいヒトは、それがハヤブサに感染して、彼がDG細胞の闇に巻き込まれてしまう事をひどく恐れていた。
だからシュバルツから提案された『逢瀬は1週間に1度』という条件を、ハヤブサは律儀に守り続けている。こちらを愛してくれているからこそ、そう言う条件を提示せざるを得ないシュバルツの気持ちも、分かり過ぎるほど分かるからだ。
それでも―――――
彼への愛おしさが抑えきれず、狂おしい程に触れたくなる夜がある。今がまさに、その状態だった。ハヤテに、恋人の存在を告白したせいだろうか。無性に彼を欲していた。
総てに、などと贅沢な事は言わない。せめて、唇だけでもいい。
この、目の前の綺麗なヒトが、自分の恋人なのだと改めて主張したかった。彼の魂の清らかさと優しさに、狂おしい程触れたかった。
「……………」
いつものシュバルツであったなら、このハヤブサの申し出を、「駄目だ!!」と、一蹴していた所であろう。だが、この日の彼は少し違った。
このまま家に入っても、キョウジはドモンの家に行っていて居ない。
そして、ハヤブサが昼間、会って嬉しそうに話していた青年の存在。
それらの要因が、シュバルツの心にも火を点けていた。
彼に深く愛される事を求めていた。
だからシュバルツは、「分かった……。いいぞ」と頷いた。
「シュバルツ……!」
それが素直に嬉しいハヤブサは、夢見心地のまま彼に抱きつき、そしてキスをしようとする。だが寸前の所で、シュバルツの持っていた分厚い書類に阻まれた。
「馬鹿! ここでそういう事をするなといつも言っているだろう!」
「そうでした………」
書類に鼻をしこたま打ち付けたハヤブサは、涙目になってその場にうずくまっている。それを見たシュバルツは、やれやれとため息を吐いた。
「荷物を置いて着替えてくるから、少し待っていろ」
そう言ってシュバルツは、いったん家の中に入る。だが、数分もせぬうちに、すぐに出て来た。
「待たせたな。行こう」
ハヤブサはそんなシュバルツを見て、幸せそうに頷いていた。
「えっ? ……ああ………うん……」
それからしばらくして、ドモンの家でちびちびと酒を飲んでいたキョウジの手元で、携帯が鳴った。キョウジが出てみると、それはシュバルツからの電話だった。
「うん……うん……分かった。ありがとう……」
返事をするキョウジの声を聞きながら、レインがキッチンで、次のつまみを用意している。
「うん。こちらの事は気にしないで。ゆっくりしておいで――――」
そう言って、キョウジは携帯の通話を切った。
「今の誰? シュバルツさん?」
つまみを持って来ながら問いかけてくるレインに、キョウジは笑顔を向ける。
「そうだよ。あいつ、今日はこちらに来られないって」
「あらら……。お仕事が忙しいの?」
レインの問いかけに、キョウジは軽く肩をすくめる。
「いや、仕事は終わっているらしいよ。だけど、家に帰ったらハヤブサが来ていたみたいで……今日はそのまま、ハヤブサと飲みに行くみたい」
「まあ……ハヤブサさんとシュバルツさんって、本当に仲がいいのね……」
「あははは……そうだね」
レインの言葉にキョウジはもう苦笑するしかない。本当に、見ているこちらがため息が出る程、二人は深く愛し合っているのだから。
実際、幸せそうなシュバルツを見るのは大好きだ。こちらも、幸せな気持ちになれるから。彼の存在が、誰かの深い幸せに繋がっていると言うのなら――――シュバルツを作った自分も、何か救われたような気持ちになれる。だから、この二人の関係は、出来るだけ長く続いて欲しいとキョウジは願っていた。
「じゃあ、シュバルツさんが来ないのなら……この眠っているドモンは、私たちが何とかしなきゃいけないって事になるわね」
レインがため息交じりに机に突っ伏して眠っているドモンを見つめる。ドモンは、「兄さんが起きているのなら俺も起きている!」と、キョウジの隣で酒を飲みつつシュバルツを待っていたのだが、日頃の健康的な生活習慣には勝てず、睡魔の前にその膝を屈していた。彼は幸せそうな寝顔をその面に浮かべながら、「むにゃ……もう、食べられないよ………」などと、牧歌的な寝言を呟いていたりする。
「こらっ! ドモン! 起きろ!」
と、キョウジが軽く小突いても、少し表情をしかめるぐらいで、起きる気配を全然見せなかった。キョウジはやれやれ、と、ため息を吐いた。
「仕方がないな。じゃあ、兄ちゃんが久しぶりにドモンを担ぎますか……」
そう言うとキョウジは、眠っているドモンの身体の下に、器用に自分の体を入れて、ドモンを肩に担ぎあげ、背負うような格好になった。
「さすがキョウジさん! 力強いわね~!」
感心することしきりなレインに、キョウジは少し困ったような笑みを浮かべる。
「折に触れてシュバルツやマスターやハヤブサが、『お前も少しは体を鍛えろ!』と言ってい面倒を見てくれる物だから――――自然と力がついちゃったみたいだ。でもまだシュバルツほどじゃないよ。あいつだったら、眠っているドモンを『お姫様だっこ』とか、余裕で出来るだろう」
「カッシュ兄弟のお姫様抱っこ……うん。悪くないわね」
レインが頭の中でそれらを想像して、1人、楽しそうに頷いている。それを見たキョウジが「勘弁してくれ」と、顔をひきつらせていた。その背中でドモンが、「兄さん……」と、呟きながら、幸せそうに眠り続けていた。
ホテルの部屋に着いた忍者たちは、どちらからともなくキスを交わして――――それから互いに深く求めあった。特にシュバルツの振る舞いは情熱的で――――それはハヤブサを大いに楽しませ、そして満足させた。
だが、少し情熱的に過ぎる様な気もする。
シュバルツのそんな僅かな変化にも気がついて、気になってしまうハヤブサは、ひとしきり彼の中に『精』を放った後、繋がったまま後ろから抱き締めて、そしてそっと、問いかけた。
「……どうしたんだ? シュバルツ……」
「……え……? 何……が………?」
何度も上り詰めさせられた所為か、シュバルツの呼吸が乱れ、その身体が小さく震えている。涙で潤んだ瞳が可愛らしくて――――嗜虐心が煽られてしまう。
熟れきっている乳首にそっと手を這わせてやると、「ああっ!!」と、叫びながら、腕の中でその身体が反り返って乱れた。
「ふふ………」
乱れる彼がもっと見たいから、両方の手で乳首を弄ぶ。
「や……! あ……! あ………っ!」
涙を飛び散らせながら喘ぐ、愛おしいヒト。そのヒトの手がハヤブサの腕に伸びてくる。
だけどその手は、彼の身体を弄んでいるこの腕を払いのけることなく、そっと優しく添えられてきた。どのように触れられようとも、どのように蹂躙されようとも――――それを『赦す』と言う、彼の明確な意思の顕れ。そこに、彼の確かな『愛情』を感じられるから、ハヤブサは嬉しくなってしまう。
だからこそ、愛おしいヒトの僅かな変化が少し気になった。
何故今宵に限って―――――こんなにも情熱的なのか。
ハヤブサは己自身を、ズルッとシュバルツの中から引き抜く。
「あ………! 何……で……!」
あからさまに抗議の声を上げる愛おしいヒト。ハヤブサはそれを苦笑しながらなだめる様に抱きしめると、彼の顔がよく見える様に、少し体勢を変えた。自分の腹の下にそのヒトを組み敷きながら、質問を続けた。
「やはり……この程度では足りないか?」
「―――――!」
自分が、今どれだけはしたない想いを口にしてしまったのかに気がついて、シュバルツの頬が、カッと朱に染まる。
気づかれてしまった。
自分の方が――――ハヤブサを、強く欲しがっている、と言う事に。
「す……! 済まない……! 私とした事が――――」
慌てて視線を逸らし、身体の下から逃げ出そうとするシュバルツ。だがそれを、ハヤブサが許す筈もない。グッと体重をかけて、その動きを封じ込める。
「あっ!」
「逃げるな……。お前がそう想ってくれているのは悪い事じゃない。俺としては、寧ろ嬉しい――――」
「で……でも……!」
困惑したように、何事かを話そうとするシュバルツのその唇を、ハヤブサは己が指でそっと塞ぐ。
「俺の事を心配したりする前に――――一つ、質問に答えてくれ、シュバルツ」
「…………?」
「どうして……今宵は、いつにも増して情熱的なんだ? 何かあったか?」
「――――!」
はっと息を飲むシュバルツに、ハヤブサの真摯な眼差しが重なる。
「俺は……何か、お前を不安にさせる様な事でも、したか……?」
「ハヤブサ………」
「シュバルツ………」
ハヤブサの指が、シュバルツの頬を優しく撫でて、乱れた髪をそっと整えて行く。
「…………」
そんなハヤブサの様子を見ながら、シュバルツは(ハヤブサには隠し事が出来ないな)と、感じていた。
どうして――――彼には伝わってしまうのだろう。
自分の心が、不安に揺れ動いてしまっている事が。
どうして――――
シュバルツは観念したように小さく息を吐くと、少しばつが悪そうな表情を浮かべた。
「……実は昼間……駅で、お前を見かけたんだ」
「駅?」
目をぱちくりとさせるハヤブサに、シュバルツが苦笑しながら続ける。
「声をかけようとしたのだがな……。お前に、先客がいたようだから、遠慮させてもらったんだ……」
そう。たったそれだけのこと。取るに足らない些細なことだ。
この程度で、揺れ動いてしまう自分の『ココロ』が、むしろ滑稽に感じるほどだった。
「駅………ああ、『ハヤテ』の事か?」
対してハヤブサは、きょとん、とした表情を浮かべている。彼にとっては本当に、『些細な事』に当たるらしい。
「………『ハヤテ殿』の事を、聞いても……?」
だからシュバルツは、そろり、と尋ねた。
自分に、ハヤブサの総てを知る権利も、ましてや束縛する権利など持ち合わせていない事も、十二分に承知している。当たり障りのない範囲でハヤブサから教えてもらえればそれでいいし、彼が答えたくない物であれば、この問いはすぐに引っ込めるつもりでいた。
しかしハヤブサは、その問いにさらりと答えた。
「ああ。ハヤテは俺の『幼馴染』で――――『霧幻天神流』の18代目の頭首だよ」
「『霧幻天神流』―――――忍びの中の、名門じゃないか!」
シュバルツが驚きの声を上げると、ハヤブサも苦笑した。
「ああそうだ……。あいつはあの若さであの一門に認められて――――『霧幻天神流』を束ねているんだ。凄いだろう?」
「すごいな……確かに、凄い………」
シュバルツはそうやってひとしきり感心した後、はたと気が付いた。
「お前だって伝説の『龍の忍者』じゃないか! それは凄くないのか!?」
「う…………!」
何とも言えない顔になって絶句するハヤブサを見て、シュバルツは少し笑った後、小さくため息を吐いた。
「なるほど……『伝説』同士の組み合わせか……。確かに、似合いだ……」
(対して私には何も無い……。人間ですらない……。こんな存在が、ハヤブサの傍に居るなんて………やはり、不釣り合い――――)
「シュバルツ」
ハヤブサが名を呼ぶと同時に、いきなり唇を塞いでくる。
「んう……! ん………!」
口腔深くを蹂躙され、呼吸が奪われる。
シュバルツは酸素を求めて足掻くが、唇が一瞬でも離れることすらハヤブサは赦してくれない。苦しくて四肢が突っ張る。仰け反る胸を、ハヤブサの指が愛して来た。
「んく……! んあっ!!」
やっと許された呼吸に、シュバルツは喘ぐ。だが、間髪入れずにハヤブサが喉元に噛みつく様に吸いついてくる。チュッ、チュッ、と音を立てて、そこを執拗に吸われた。指はその間ずっと、シュバルツの胸を弄び続けている。
「はあっ!! ああっ!!」
いきなり激しくなる愛撫に、シュバルツはただ翻弄されるしかない。身をのけ反らせながら必死にそれに耐えていると、ハヤブサに身体をぎゅっと抱きしめられた。
「あ……? ハヤブサ……?」
ハヤブサの腕の中でシュバルツが茫然としていると、ハヤブサから声を掛けられてきた。
「シュバルツ……」
震えるシュバルツの身体を抱きしめながら、ハヤブサは言葉を続ける。
「お前、もしかして『嫉妬』しているのか?」
「―――――ッ!!」
カッと、朱に染まる頬。図星を指されてシュバルツは焦った。
逃げ出したくなって足掻くが、ハヤブサはそれを許してはくれない。
「答えてくれ、シュバルツ」
「う…………!」
「お前は……『嫉妬』をしてくれているのか……?」
逃げも隠れも出来ない所に、ハヤブサの真摯な眼差しがぶつかる。
「……………」
シュバルツはあきらめたように、小さく息を吐いた。
「……そうかもな……。私は確かに、『嫉妬』をしているのかもしれない………」
(でも駄目だ。本当は……。こんなに執着しては――――)
人間ですらない、まして、自分の身体を構成している『モノ』は、何時かハヤブサを殺してしまうかもしれない。
だから自分は、何時でも身を引けるようにしておかなければならないのに――――。
その『可能性』を僅かに感じ取っただけで、こんなにも軋んでしまう『ココロ』
気づかれてはいけなかった。
彼に執着してしまっている自分を、ハヤブサに感づかれてはならなかった。
そうでなければ、ハヤブサから身を引くべき時に、彼にいくばくかでも負担をかけてしまう事になる。それを、シュバルツはひどく恐れた。
(大丈夫だ。何てことはない事なのだから……)
無理やりにでもそう思って、シュバルツはその面に笑みを浮かべる。だけど、ハヤブサの唇は、彼の瞳から零れ落ちる涙を掬い取っていた。
その唇の感触に、思わず「あ」と、声を上げるシュバルツ。涙を一通り掬い終わると、ハヤブサはシュバルツを嬉しそうに抱きしめて来た。
「嬉しいよ……シュバルツ……! 泣くほど嫉妬してくれているだなんて――――!」
「馬鹿っ!! 違う!! 別に嫉妬して泣いている訳では――――!!」
慌ててシュバルツは言い訳をするが、ハヤブサの方が既に聞いては居ない。シュバルツに頬ずりをしてから、うんうんと頷いている。
「そうか~。俺もついに、お前にここまで想ってもらえるようになったんだな……! 頑張った甲斐があった……!」
「だから違うって、ハヤブサ――――!」
「嬉しい……! もっと嫉妬をしてくれ、シュバルツ……!」
そのままハヤブサは、唇を求めてくる。
(ああもう………!)
ハヤブサにされるがままになるしか術を持たないシュバルツは、あきらめたようにそれを受け入れる。
ハヤブサの言っている事は当たっている。
当たっているから、厄介だ。
こんな事、本当はよくない事なのに。
彼のためを思うのなら。
彼の幸せを願うのなら。
なのに何故―――――
自分に触れて「愛している」と言っている時のハヤブサは
こんなにも幸せそうなのだろう?
「……言っておくが、俺はもうずっと前から、相当嫉妬していたんだからな?」
「―――――!?」
ハヤブサの言葉に、ぎょっ、となるシュバルツ。
「な、何で……?」
問い返してくるシュバルツに、ハヤブサは「分かっていなかったのか?」と、言わんばかりの眼差しを向けて来た。
「お前、キョウジの身代わりで大学の講師をしている時、学生や同僚の奴らと、結構べたべたしているだろう」
「はあ?」
シュバルツは思わず目を丸くする。
「それだけじゃない! 研究所に居る時だって、そこの教授や研究員たちと親しげに話をして―――――!」
「何を言っているんだ!? お前は! 学生は質問をしてきただけだ! 同僚とだってテストの打ち合わせやら実験の部屋の確保などの事務連絡で――――!」
「『カッシュ先生~! ここが分からないんです~!』なんて言いながら、お前の肩に手を回してきた学生なんか見た日には、うっかり『絶技』を発動しそうになったぞ」
「阿呆か――――――ッ!!」
ハヤブサのこの言葉には、シュバルツも思わず鉄拳を振るっていた。
「大学とかで絶対にそんな事をするなよ!? キョウジに迷惑がかかるんだから――――!!」
「分かっているよ」
シュバルツに殴られて吹っ飛ばされ、涙目になりながらハヤブサは起き上がる。
「だけど、心配なんだ! お前があまりにも可愛らしくて色っぽいから、悪い『虫』がついてしまわないかと……!」
「心配しなくとも、そんな特殊な目で私を見ているのは、世界でもお前ぐらいしかいないぞ」
呆れてそう言い放ちながら、シュバルツはようやく大学で会った時のハヤブサの態度がやけにつっけんどんだった訳を、理解していた。知らない人の間に来ているから、彼の仏頂面が酷くなっている訳ではなかった。彼もまた――――嫉妬してくれていたのだ。自分に近寄って来る人間すべてに。
生活して行く以上、人間関係をすべて断ち切る事など出来ない。だから、ハヤブサのこの物思いは、ある意味非常に迷惑な物であるとも言える。
なのに――――『嬉しい』
そう感じてしまうのは、何故なのだろう。
対してハヤブサは「分かっていないなぁ」とため息をついていた。
「お前、少し自覚した方がいいぞ? 自分がどれだけ周囲に可愛らしさと色気を振りまいているか――――」
「心配するな! 例え万が一私に手を出してくる人間がいたとしても、ちゃんと対処するさ。お前以外に、身体を許したりはしない!」
「絶対だな?」
「―――――!」
急接近してきたハヤブサの顔を見て、シュバルツは「しまった!」と、思った。自分がいま割と『語るに落ちた』内容の発言をしてしまったと自覚する。だがもう遅い。ハヤブサの面に、これ以上ないと言う程の幸せそうな笑みが浮かんでいる。『覆水盆に返らず』とは、まさにこのことだとシュバルツは思った。
「嬉しい……。お前も、俺の事を好いていてくれるんだな……」
「ハヤブサ………あ…………」
優しく唇を塞がれ、シュバルツはまた、ベッドに押し倒されてしまった。
「ん………。んう………」
優しく長い口付け―――――シュバルツはいつの間にか、その熱に酔わされてしまう。
「……………」
『それ』から解放した時に、シュバルツが見せるトロン、とした表情。この恍惚とした表情を見る瞬間が、ハヤブサはたまらなく好きだった。
このヒトの凄絶な色気と妖艶さに拍車がかかる。それを暴き立て、時に引き裂きたくさえなってしまう衝動にかられる。
自分の中に眠る、凶悪とも言える『熱』と『想い』を、存分に解放させて―――――それを受け止めきってくれる、ヒト。
たまらなく愛おしかった。
どうしようもなく、大切だった。
「シュバルツ……」
ハヤブサはそっと彼のヒトの胸を弄びながら、耳元に息を吹きかける。
「あ………!」
ピクリ、と、反応するシュバルツの耳元に、ハヤブサは囁きかける。
「まだ、足りないんだろう?」
「あ………! あ………!」
指の動きに合わせてしどけなく乱れて行くヒト。これがシュバルツの答えだと、ハヤブサは悟った。
「続きをしようか、シュバルツ……」
嫉妬をする必要もないくらい、俺はお前を愛しているのだと―――――お前に分かってもらうまで
俺はお前を愛すから
何度でも
何度でも
「ハヤブサ……。あ!!」
シーツの衣擦れの音。
シュバルツのしどけない喘ぎ声に合わせて、チュ、チュ、と水音が響く。
きしきしと、ベッドが軋みだして―――
再び忍者たちは、深い愛の世界に、溺れて行くのだった。
次にシュバルツがふっと瞳を開けた時、幸せそうにこちらを見ているハヤブサと、視線が合った。
「起きてたのか?」
問いかけるシュバルツに、ハヤブサが笑顔を見せる。
「寝顔を見てた……。お前は、眠っていても綺麗なんだな」
そう言いながら、ハヤブサの手がシュバルツの顔にかかる髪に触れる。
「馬鹿。そんな訳があるか」
苦笑しながら照れたような顔をするシュバルツ。至福のひと時だった。
何時までもこうしていたい。
でも、ここに浸ってばかりいられない事も、忍者たちは知っていた。
互いに――――帰るべき場所が在るから。
「『約束の日』は、明後日だな……」
起きあがって身支度を整えながら、ハヤブサがポツリと言った。
「明後日にもこうやって……会ってくれるか?」
「――――!」
少し驚いた様な顔をするシュバルツに、ハヤブサの熱い視線が被さって来る。
ハヤブサは願う。本当なら、毎日でもこうして会いたいぐらいなのだと。
しばらく推し量るようにハヤブサの顔を見つめていたシュバルツであったが、やがて、やれやれとため息を吐いた。
「『嫌だ』と言っても……お前は来るのだろう?」
「分かっているじゃないか」
悪びれもせず言い切るハヤブサに、シュバルツは苦笑する。
「分かったよ、ハヤブサ……。明後日に会おう」
「本当か!?」
嬉しそうに問うてくるハヤブサに、シュバルツも少し照れながら頷く。
「ああ。私も『会いたい』と、思っていたから―――」
「……………! やった~~~~~~!!」
シュバルツの言葉に、ハヤブサが歓喜の叫び声を上げる。嬉しそうにはしゃぐハヤブサを、シュバルツは少し複雑な面持ちで見つめていた。
良いのだろうか?
このままずるずると、ハヤブサに押し切られてしまう様な気がする。
だけど、自分も『会いたい』と願ってしまっているものだから―――――困った物だとシュバルツは思った。
「シュバルツ」
別れ際、ハヤブサは優しいキスをくれる。いつものように。
「じゃあまた―――――明後日に会おう」
そう言って、ハヤブサと別れた。
この時彼の後ろ姿が、朝陽の中に溶けて行くように見えたのは何故なのだろう。
後に、シュバルツは思う。
もしもこの時、ハヤブサを待ち受ける『運命』を知っていたなら
自分はどうしただろう。
それでも自分は、ハヤブサと別れる道を選んだだろうか――――
それは、永遠に答えのでない『問い』となって、シュバルツの心に蟠り続ける事になるのだった。
『隼の里』に帰ったハヤブサを待ち受けていたのは、霧幻天神流からの正式な使いの者だった。
「『龍の忍者』である、リュウ様の力をぜひともお借りしたい。どうか、当方の里の方に来てくださいますよう――――」
(珍しいな……。わざわざ外部の俺に、頼みごとをしてくるとは――――)
霧幻天神流の忍者たちは、総じて一流の者たちばかりだ。例え厄介事が生じたとしても、一族の力でたいていの問題は解決できる。故に、こんな風に外部の忍者の力を借りようとする事自体が、大変稀な事であったのだ。
しかし、親友であるハヤテからの正式な使い。断る理由が、ハヤブサの方には無かった。
「分かった。『すぐに向かう』と、ハヤテに返事をしてくれ」
「御意」
短くそう言って、使いの忍者は消える。ハヤブサも、すぐに霧幻天神流の里へ向かう事にした。
(何か、相当な厄介事とみて良いな……。明後日会う事になっている、シュバルツにはどう伝えようか……)
ハヤブサは少し思案したが、すぐに顔を上げた。
(とにかく、ハヤテから話を聞いて、それから判断しよう。会えるようなら会うし、無理なら理由をちゃんと話して断ればいいだけの話なのだから……)
シュバルツは少し残念がるかもしれないが、話せば分かってくれるヒトだ。だから、そのためにもハヤテの目的を知りたいと思った。
ただ、事が切迫しているようなら、1日がかりで会う事は無理になるかもしれない。その時は、せめて唇だけでも触れさせてもらえればと願う。それに、自分と1日過ごせないと知ったシュバルツが、がっかりする顔を見てみたいような気もする。この願いは、不謹慎な物かもしれないが――――
「ハヤテの所へ行く。場合によっては滞在が長期になるかもしれない。後の事は、よろしく頼む」
ハヤブサは里の者にそう言い置くと、ハヤテの元へと向かった。
霧幻天神流の里に着くと、出迎えの者がすぐにハヤテの元へと案内してくれた。
「………………」
だが、里の雰囲気が微妙におかしい。皆、何気ない風を装っているが、妙にピリピリとした、殺気の様なものを感じる。
(やはり……ただ事ではないな……。一体、何があった……?)
疑問に感じながらもハヤブサは、ハヤテの元へと向かう。頭首の館の、公の物事を執り行う部屋で、ハヤテは待ち受けていた。
「よく来てくれたな、リュウ」
そこには、穏やかな――――『いつも通り』の親友の姿があったので、ハヤブサは、いくばくかの安心を覚える。ただやはり、ハヤテ以外の者からは、ピリピリとした気配を感じていた。何かに対してひどく警戒している様な―――――そんな感じだった。
(こんな中でも『頭首』であるハヤテは『いつも通り』か………なるほど)
このような状況下で、1人、穏やかな気配を保っているハヤテにハヤブサは感心する。頭首までこの雰囲気に呑まれてしまっては、この村の者は皆、浮足立ってしまうだろう。それを押さえてのこの佇まいは、流石ハヤテだと思った。
「お前が呼ぶのなら、何時だって俺は駆けつける。それにしてもどうした? ハヤテ。一体、何があった?」
礼に則って刀を置いて座り、ハヤテにそう声をかける。それに対して、ハヤテは穏やかに微笑んだ。
「ありがとう、リュウ。その前に、遠路疲れただろう。茶でも一杯飲まないか?」
ハヤテの言葉に合わせて、女中たちがハヤブサとハヤテの前に茶を置いて行く。綺麗な緑茶と、和菓子を差し出された。
「ありがとう」
ハヤブサが、差し出された茶を飲み干す。それを見届けてから、ハヤテが口を開いた。
「実はな、リュウ……。頼みがある」
「ああ。頼みとは―――――」
何だ? と、問う前に、ハヤブサは激しい眩暈に襲われた。
「う………!?」
意識を保とうとして、保てなくなる。茶に何かを入れられたと悟った時には、既に遅すぎた。
「ハヤ……テ……? おま………」
ハヤテが、こちらを見ている。その面には、相変わらず穏やかな表情が浮かんでいた。
ばたっと、ハヤブサが倒れてから、ハヤテは立ち上がり、その傍に歩み寄る。そっとその頬に触れても、ハヤブサは身じろぎ一つしなかった。
「『薬』がよく効いた様だな……。御苦労」
女中たちにそう言うと、彼女たちは頭を下げて静かに下がっていく。
「リュウ……。頼みと言うのはな……」
ハヤブサを優しく抱き抱えながら、ハヤテは静かに言った。
「『俺の物になってくれ』って、事だよ……」
ハヤテの指が、ハヤブサの髪を撫でる。その腕の中で、ハヤブサは静かに眠り続けていた――――。
それから二日後の、夜。
時計の針は深夜12時を指そうかと言うところだが、キョウジは独り起きて、パソコンへと向かっていた。
(ハヤブサの『血』は……やはり、常人とは違って、かなり特殊な物だな……。これが、シュバルツと深く交わっても、『DG細胞』には感染しない原因なのだろうか……)
血液のデータ。
DNAのデータ
どれも普通の『人間』ではあり得ない数値をキョウジに見せつけている。
そして、『DG細胞』と、シュバルツを構成している『DG細胞』の違い――――。
(まだ、断定できない……。もっと、調べないと―――)
キョウジがコーヒーを飲みながら、次の資料の作成と、実験の段取りを考えかけていた時、玄関先で、カタリ、と、小さな物音がした。
「?」
不思議に思ったキョウジが振り返ると、そこには朝からハヤブサに会いに行っているはずのシュバルツの姿があったから、キョウジはかなり驚いてしまう。
「シュバルツ!? どうした!?」
慌てて立ち上がり、キョウジはシュバルツの傍に駆け寄る。ハヤブサに会いに行った時のシュバルツは、たいていハヤブサに引きとめられて、次の日の朝に帰って来る事が常となっていた。なので、こんな時間帯に帰って来る事など、普通、あり得ない。
「キョウジ……」
現にシュバルツは、酷く心細そうな顔をしている。何か異常事態が起きたとしか思えなかった。
「どうしたんだ? シュバルツ……! ハヤブサと喧嘩でもしたのか?」
その問いかけに、シュバルツは首を横に振る。そして、逆に問いかえされた。
「キョウジ……。ハヤブサから、何か連絡があったか……?」
「えっ? いや、何も……」
キョウジの言葉に、シュバルツも「そうか……」と、静かに返す。
「どうしたんだ? シュバルツ。喧嘩したんじゃないのなら、どうして――――」
懸命に問いかけるキョウジに、シュバルツはポツリ、と、返した。
「………来なかったんだ……」
「えっ?」
何を言われたのか瞬間分からずに、茫然とするキョウジに、シュバルツは更に言葉を続ける。
「ハヤブサが、来なかったんだ………」
「えっ? え………?」
状況がいまいち飲み込めないキョウジに、シュバルツは少し苛立ちを覚えた。
そう―――――これは、『異常事態』だ。
「来られないなら来られないでいい! だけどあいつは―――――そうなった場合、必ず何らかの形で連絡をよこしてくる筈なんだ! 黙って約束を破る様な奴ではないんだ!」
「――――!」
「それが……私やキョウジにまで、連絡も何も無いなんておかしいんだ……! 連絡を取りようがない程の『何か』が、ハヤブサの身に起きているとしか思えなくて……!」
「シュバルツ……」
「ハヤブサ……! 何があった……? 一体、どうしてしまったんだ……!」
シュバルツが疲れ果てたかの様に、その場に座り込んでしまっている。無理もないな、と、キョウジは思った。恐らく彼は朝からずっと――――ハヤブサを待ち続けていたのだろう。僅かな手掛かりも見落としてはならぬと、ずっと神経を張り巡らせ続けていたのだろう。ハヤブサの事を想いながら――――
「シュバルツ。ひとまず落ち着こう?」
キョウジは、そっとシュバルツに声をかける。
「もしかしたらハヤブサから、私宛にメールが入っているかもしれない。それを、もう一回確認してみるよ。とにかく中に入って、落ちついて――――それから対策を考えよう。ね?」
キョウジの言葉にシュバルツもこくりと頷く。それを見て、キョウジも微笑んだ。
「それに、次の日の朝にハヤブサから『済まない!』なんて平謝りに謝られる連絡が入るかもしれないよ? 今頃ハヤブサの方が、『シュバルツに連絡しなきゃ……!』なんて、焦っていたりしてね」
「そうかもな……」
キョウジの言葉を聞いて、シュバルツの面に少しの笑みが浮かぶ。
「だいたい、シュバルツは心配し過ぎなんだよ! まあ……私も、人の事は言えないけどね」
(そうかもしれないな)
キョウジのこの言葉には、シュバルツも苦笑するしか無かった。自分は確かに、ドモンの事と言い、キョウジの事と言い、ハヤブサの事と言い――――心配し過ぎる傾向が、あるのかもしれない。
(杞憂に終わればいい。自分のこの物思いが……)
キョウジの後を付いて行きながら、シュバルツはそう祈らずにはいられなかった。
だが、次の日も、その次の日も―――――ハヤブサから連絡が入ることはなかった。
シュバルツが、自身の悪い予感が的中してしまった事を悟るのに、そう時間はかからなかった―――――
第2章
自分の口の中を、甘い液体が通っていく。
甘い味。甘い匂い――――
「ん…………」
ハヤブサはこくん、と、咽を鳴らしてそれを受け入れる。
そしてそのたびに、自分の身体が熱くなり、そして、甘く疼いた。
優しい手が触れる。
愛おしいヒトを彷彿とさせた。
(誰だろう……。シュバルツかな……?)
ハヤブサはしばらく、その手に身を委ねかけていたが、やがて、ある事に気付いた。
(違う―――――! シュバルツは、こんな触れ方をして来ない……!)
「く…………!」
まどろみかける意識を、無理やり覚醒させる。
そして、飛び込んできた親友であるハヤテの顔に、ハヤブサはかなり驚いた。
「気が付いたか?」
「あ……………!」
『いつも通り』の親友の穏やかな顔。だがハヤブサは、自分の置かれている異様な状況に、更に驚かされることになった。
まず自分の服は脱がされ、一糸纏わぬ格好になっていた。更に、自分の手足と首に鉄の輪がはめ込まれ、それが鎖に繋がれている。そして、手首の鉄輪同士ががっちりと繋がれ、手の自由が実質奪われていた。
「あ………? ハヤ、テ………?」
「気が付いたか? リュウ……」
ハヤテが優しく微笑む。その手が、するりとハヤブサの胸元に滑ってきた。
「は……! あ………ッ!」
電流が走り抜けるような甘い刺激に、ハヤブサの身体が勝手に跳ね、甘い声が出てしまう。
(イケナイ!!)
ハヤブサの中で、それに対する強い拒絶反応も同時に起きる。この熱にこのまま身を委ね続けていると、どうなってしまうのか―――――ハヤブサは知っていたからだ。
自分が、この熱に溺れたいのはシュバルツと居る時だけだ。だからハヤブサは、必死にその腕の中から逃れた。
「止め……! 止めろ……ッ!」
ハヤテの手を拒絶し、身を捩ってそこから離れる。だが、体勢を立て直そうとして――――自分の足腰に、全く力が入らない事に、ハヤブサは気が付いた。
「あ………?」
ガクン、と崩折れる身体に茫然としていると、そこにハヤテが近づいてきた。
「驚いたな……。この薬をそれだけのんで、まだそれだけ動けるとは……」
「薬………?」
は、は、と、短く息を乱しながら、ハヤブサは問いかける。それに対してハヤテは短く言い切った。
「媚薬だよ」
「な―――――!」
息を飲むハヤブサに、ハヤテは優しく微笑みかける。
「我が里に古くから伝わる、秘伝の薬だ。ただ、効き目が強すぎてな……。常人ならば、小さじ3杯飲んだ所で発狂してしまうところだが――――」
「ハヤテ………!」
「お前は、もう9杯もこれを飲んでいる」
「―――――!」
「こんな風に――――」
ハヤテは手に持っている小鬢の中の液体を、くっと口の中に含むと、グイ、と、ハヤテは、ハヤブサの腕を引いた。
「あ…………!」
抵抗する間もなく、ハヤテの唇がハヤブサのそれに重ねられる。差し込まれた舌を伝って、あの甘い液体が口の中に入ってきた。
「ん…………!」
この液体を拒絶しなければならない、と、ハヤブサも頭では分かっている。
だけどどうした事か――――口は、舌は、咽は――――勝手にその液を求めて、飲みほして行く。こくん、と、咽が音を立てて、ハヤブサはそれを受け入れた。
「や………! あ………あ………!」
飲み終わった後、体勢を保っていられなくなったハヤブサが崩折れそうになる。それを、ハヤテが優しく支えた。
「ほら……これで10杯目……。もう、動けないだろう?」
「あ…………!」
震えるハヤブサの顎を、ハヤテは捉える。
「リュウ………」
そのままもう一度、その唇を求めた。
「――――ッ!」
だがハヤブサは、懸命にそれを拒絶した。自分が『こういう事』をしたいのは、シュバルツ以外には居ないのだから。
「……………!」
ハヤテは少し淋しげに瞳を曇らせると、外に向かって合図を送る。すると、ハヤブサの手首に繋がれている鎖がジャラジャラと音を立てて動き、彼は両腕を高く上げて、拘束されるような格好になった。
「リュウ………」
抵抗できず、無防備に晒されたハヤブサ自身に、ハヤテは優しく触れてくる。
「や……! 止め……ッ!」
「こんなに張り詰めさせて……辛いだろう?」
そのままそこを、扱き始めた。
「は………! ああ………!」
「一回抜いてやる。楽にしていろ……」
あふれ出て居る先走りが、ハヤテの指に絡みつき、クチュクチュと卑猥な水音を立てる。
「いや……! いやだ………!」
「嫌がっている割には、腰が動いているが……」
「そ、そんな……ッ! ――――あっ!!」
ハヤテの指摘通り、ハヤブサの腰は刺激を求めて扇情的に動いていた。更にハヤテのもう片方の手が、ハヤブサの胸に伸びて来て、そこを弄び始める。
「はあっ!! ハヤテッ!! 止め……ッ!」
「いいぞ……。リュウ……。そのまま……」
「あああっ!! ああああ………ッ!!」
ぴゅく、と、音を立てて、ハヤブサはついに達してしまった。
「あ…………!」
脱力してしまったハヤブサを、ハヤテが優しく支える。だがハヤテの、ハヤブサを暴き立てる手は止まらなかった。
「抜いたのに固いな……。流石だ」
「ハヤテ……ッ!」
ハヤテに一度抜かれた事と、状況を把握し始めて、少し混乱が解けたハヤブサが、『親友』である筈のハヤテを睨みつけていた。
「……何故、こんな事をする!? お前は本当に、俺の『親友』のハヤテか!?」
それに対してハヤテは、静かな―――――だが少し、淋しげな笑みを浮かべて、ハヤブサに答えた。
「ああ。『ハヤテ』だよ」
「な…………!」
「間違いなく―――――お前の『親友』の、『ハヤテ』だ……」
「そんな………!」
「ならば、いろいろと答えてやろうか? 俺の生年月日。家族構成。趣味。好きな食べ物。お前との幼少期からの思い出総てを――――」
「分かった! もういい!!」
ハヤブサは思わず叫んでいた。目の前の『ハヤテ』が紛れもなく自分の親友の『ハヤテ』である事を突きつけられて、ハヤブサはどうしたらいいか分からなくなるほど途方に暮れてしまう。
「そ、それでは何故………!」
「リュウ………」
「何故だ!? ハヤテ!! 何故俺にこんな事を―――――あっ!!」
ハヤテに再び己自身を扱かれだして、ハヤブサは再び乱れざるを得なくなってしまう。腰が扇情的に揺れ、鎖がヂャラヂャラと音を立てた。
「まだ……分からないのか? リュウ……」
それをしながらハヤテは、ハヤブサの耳元で囁きかける。
「ん……! な……何……が……?」
「俺は、お前が好きなんだ」
「――――――!」
ハヤテの衝撃的な言葉に、ハヤブサは思わず息を飲んでいた。
「好きだ……! リュウ……!」
身体を密着させて、ハヤブサを愛し続けながら、ハヤテは熱い声で囁く。
「い……何時から、だ……?」
「ん?」
「何時から、お前は……俺の事を………?」
それに対して、少しおびえたように問い返してくるハヤブサ。ハヤテは苦笑しつつも、腕の中に捕らえて居る彼の人に、愛おしさばかりが募った。
「ずっとだ……! 子どもの時からずっと――――!」
「な――――!」
絶句するハヤブサを、ハヤテは優しく抱きしめた。
子どものころから、「お前は頭首になるのだ」と自分の運命を周りに決定づけられ、常にその期待と重圧を、自分に課せられてきた。
それに応えるのは自分の中では当然のことであった。そして、それをすることで、自分の妹達を、そして周りの者たちを守れるのであると言うのなら、尚の事――――その道を進む事に、迷いはなかった。
だがその道は当然、修羅の道だ。
突きつけられる選択肢は過酷で、背負うべき責任と言う名の荷物は重過ぎて――――
子ども心にもう何度
「止めよう」と
「死のう」と
思った事だろう
だがそのたびに―――――
「ハヤテ!!」
自分に手を差し伸べてくれる、同世代の人間がいる。
その存在こそが――――リュウ・ハヤブサだった。
リュウ・ハヤブサは、忍び修行のために、時折隼の里から、霧幻天神流の里に来ていた。
ハヤテと同世代と言う事もあって、ハヤテとハヤブサはよく修業を共にしていた。
きっかけは、本当に些細なことだった。
「ハヤテは、偉いな」
ふとした折に、ハヤブサの口から零れ落ちた言葉。
「えっ?」
きょとん、目をしばたたかせるハヤテに、ハヤブサは微笑みかけた。
「だって、そうだろう? その歳でもう頭首の自覚があって、ちゃんと責任を背負っている。普通はそんな事、なかなかできない」
「そうか?」
「そうだよ。俺ならとっくに逃げ出している所だ」
(嘘を言うな)
ハヤブサの「逃げだす」と言う言葉には、ハヤテも心の中で異を唱える。およそリュウ・ハヤブサと言う人間程、「逃げだす」と言う言葉とは無縁な人間も居ないだろうとハヤテは思う。それほどまでに、彼は常に苦しい修行の中にその身を置いていた。彼の前に二つ選択肢があれば、彼は必ず修羅の道の方を選んでいた。
常人には耐えがたき、凄絶なまでの修業――――それを為し得ているが故に、彼の剣の腕は、既に同世代の中でも突出した輝きを放っていた。
そんな人間に、『偉い』と、自分を認めてもらえるような事を言われる――――それは、ハヤテにとっては衝撃だった。
それは、周りの大人たちからは、決してかけられぬ言葉だったから――――。
「『頭首』だから、それが出来て当たり前」
そんな眼差しと、そう言う声を、常に浴び続けて来たのだから。
「ハヤテ」
微笑みながら差し出されたその手に、自分はどれだけ救われ、そして、支えとなった事だろう。
ハヤテはいつしか、ハヤブサと会うのを心待ちにするようになっていた。
そして、歳と共に、しなやかに力強く―――――美しく成長して行く、ハヤブサ。
それを隣で見続けながら、ハヤブサに対する憧憬にも似た気持ちが、ハヤテの中で恋心に変わっていくまで――――そう時間はかからなかった。
(この想いを、打ち明けてしまおうか)
自分の隣で無防備に笑う友人を見ながら、何度そう思った事だろう。
だが肝心の友人の方が、色恋沙汰にはどうも興味が無いらしい。彼はただ武骨に、一途に――――剣の道を邁進し続けて居た。もしも迂闊に告白などしたら、こうやって隣で微笑んでくれて居る彼を、永遠に失ってしまうかもしれない。
(お前が俺の隣に居て、笑ってくれているのならば、良いか)
修羅の道を生きるこの強く美しい友人は、誰の物にもなりそうにない。
それに、自分は『頭首』――――いずれ里のために、周りに定められた相手と結ばれ、子を作らねばならなくなるだろう。自分に、自由恋愛など、許される筈も無いのだから。
触れよう、自分の物にしようなどと、贅沢な事は言わない。
これからも、俺の『友人』として、俺の隣でそうして笑っていてくれ。
お前が、俺のために動いてくれるように、俺も、お前のために動こう。
そして、お前の幸せを―――――俺も願っているから。
「恋人が出来たんだ」
柔らかい笑顔で、嬉しそうに話すお前。
ついに、この時が来てしまったかと覚悟を決める。
だけど、ハヤブサの口から「恋人は『男』だ」と聞いた瞬間、ハヤテの世界の中で――――何かが音を立てて壊れてしまった。
何故だ。
何故だ、リュウ。
『男』を恋人にするのなら―――――何故、俺を選んではくれない?
俺は、ずっとお前を見ていたのに。
子どものころから、ずっとお前を恋い慕いながら、見つめていたのに――――!
「愛している、リュウ……!」
ハヤテの愛撫の手が激しくなる。ハヤブサの物が大きくなり、愛液が溢れる。ビクン、ビクンと、彼の腰が揺れていた。
「ん……! は……!」
「また、イクのか?」
「いや……! いや、だ……!」
「抵抗しても無駄だよ、リュウ……」
そう言いながらハヤテは、ハヤブサの耳に優しくキスをして、その乳首を優しく摘まみあげた――――その瞬間。
「あ……! ああっ!!」
びゅくびゅくっと、音を立てて、ハヤブサはまた、達してしまった。
「――――――ッ!」
ガク……と、力が抜け、震えるハヤブサの顎を、ハヤテは捉える。
もう一度、その唇を求めた。
だがハヤブサは――――懸命に身を捩って、それを拒絶する。
「リュウ……」
ハヤテは淋しそうに瞳を曇らせると、震えるハヤブサの身体を強く抱き寄せた。
「………お前がそこまで想いを寄せている――――『恋人』って誰だ?」
「――――!」
ビクッと身を強張らせるハヤブサ。ハヤテは、二度抜いても尚も固いハヤブサのそこに、もう一度手をあてがった。
「は………!」
「教えてくれよ、リュウ……」
そのまま亀頭を、優しく撫でさする。
「ん…………!」
その刺激では物足りないのか、ハヤブサの腰がもどかしげに揺れ出した。
「教えてくれたら、もっと気持ち良くしてやる」
「断る……ッ! 手を……どけろ……!」
「自分で腰を振っているのに……素直じゃないな。お前は……」
「う………! く………!」
「お前は今――――『自制心』がとても弱くなっている。腰の動きが止められないだろう?」
「ううっ! あ………!」
ハヤブサは、懸命に腰の動きを止めようとする。だがハヤテの言う通り――――快感に流されてしまう自らの身体は、刺激を求めてしまう。浅ましい腰の動きが、止められなかった。
「ああ……! ハヤテ……!」
「可愛いよ、リュウ……」
「あ………! あ………!」
「フフ………」
ハヤテはハヤブサから出る先走りの液をその指に絡めて、わざと水音が出る様な触れ方をする。ハヤブサのそれがそこに擦りつけられるたびに響く卑猥な水音が――――ハヤブサの耳を犯し、その自尊心を砕いて行った。
「いやだ……! 止めてくれ……! ハヤテ……!」
「止めるも何も……。お前が自分でしているんだ」
「く………! ううっ!」
ハヤブサの瞳から涙が飛び散り、その身体がぶるりと震える。また、絶頂が近いのだと悟った。
「教えろよ……。お前の『恋人』は、誰だ?」
「う……! はあっ……! ああっ!!」
びゅく、と、溢れた精が、またハヤブサの前方にパタパタと落ちる。ハヤテはもう一度、ハヤブサの唇を求めた。
「いや……! やだ……!」
ハヤブサは懸命に抵抗をしようとする。だが、三度も抜かれて脱力してしまった身体に、ハヤテに抵抗し得るだけの力があろう筈もない。
「んう……!」
ハヤテに、深く奪われてしまう唇。ハヤブサはしばらく、ハヤテにされるがままにそれを受け入れていたが、やがて思い出したかのように抵抗しだした。ハヤテの舌に、がり、と、歯を立てる。
「――――――ッ!」
予期せぬ痛みに飛びのくハヤテを、ハヤブサが涙を溜めた瞳で見つめる。
「ハヤテ……!」
泣きぬれた愛おしい人の痛ましいその瞳に、ハヤテの中の『良心』が揺さぶられる。だが、それを自身の中から追い出すかのように、ハヤテはハヤブサを殴りつけた。
「ぐっ!」
ハヤブサの呻き声に、ハヤテの心も何故か軋む。
愛おしいリュウ
本当はこんな風に――――踏みにじりたくはなかった。
だが、自分を選ばずに、他の人間を『パートナー』として選んでしまった、お前。
何がいけなかったのだろう。
自分の何が、足りなかったのだろう。
このやるせなさ、空しさを――――一体どうすればいいと言うのだろうか。
「まだ抵抗できるのか……。薬の効き方が、甘い様だな……」
そう言いながら、ハヤテは懐から小さなケースを取り出す。
「今度は別の『薬』で……続きを楽しむとしようか」
「…………!」
ハヤブサに見せつけるかのように、ハヤテはケースのふたを開け、その中のクリーム状の薬を、己の指に塗りつけ始めた。
「ハ……ハヤテ……。それは……?」
少しおびえたようにハヤテを見つめるハヤブサをちらりと見やると、にやりと笑いかけた。
「媚薬だよ」
「――――ッ!」
「今度のはさっきのよりもっと強烈だ……。リュウ、人体で一番物の吸収率がいい場所は、どこか知っているか?」
「…………あっ!!」
沈黙を続けようとするハヤブサの舌を、ハヤテは無理やり引っ張りだす。
「ここだよ。舌の裏――――」
「えあ………ッ!」
薬に塗れたハヤテの指が、ハヤブサの舌の裏を滑ってゆく。とろりとした甘い感触と匂いが口の中に広がり、そして――――
「あ……! あちゅい………!」
身体の火照りがさらにひどくなり、ハヤブサは、ろれつの回らない甘い悲鳴を上げなければならなくなった。
「いいな……。お前の痴態は……」
ハヤテはそう言いながら、自分の指に付いた薬をべろりと舐めとる。
「俺も……止まれなく、なりそうだ……」
そう言うハヤテの瞳には、かつてない程の『雄』の欲望の光が、ぎらついていた。彼自身もまた含み続けて来た「薬」に溺れて――――後戻りできなくなっていた。
「ハ……ハヤテぇ……!」
「この薬は、皮膚からも吸収されるんだ……。だから、ここにも塗っておこうな」
ハヤテの指が、ハヤブサの両の乳首に薬を塗りつける。
「ああっ!! はあんっ!!」
「ここにも………」
ペチャ……と、音を立てて、鬼頭の割れ目から裏筋にかけて塗りつけられる、媚薬。
「ああ……! 熱い……! あちゅい……ッ!!」
身体の火照りに耐えきれず、身体がしなり、腰が揺れ――――ガチャガチャと鎖を鳴らしながら、媚態を曝してしまう、ハヤブサ。それに眩暈を覚えながら、ハヤテはハヤブサを抱き寄せる。
どうしようもなく愛おしい、リュウ。
その総てを穢さなければ――――もう、おさまらない。
「ここは、どうだ……?」
足を開かされ、じゅぶ、と、音を立てて、媚薬まみれのハヤテの指が、ついにハヤブサの中に侵入してくる。
「あああっ!! あああああっ!!」
熱に溺れるハヤブサが、その指を拒絶し切れる筈も無く――――それどころか、挿れられた衝撃で、またハヤブサは達してしまった。
「またイッたのか……」
またハヤテは、ハヤブサの唇を奪う。
「ん………っ!」
もうハヤブサは、それに抵抗できない。されるがままにハヤテの舌を受け入れ、そして、指を受け入れていた。
「もう『ここ』で、お前は恋人を何度も受け入れているのか……?」
ハヤブサの片足を持ちあげ、股を大きく開かせて、ハヤテは指の侵入を更に深める。それに対してハヤブサは、必死に首を横に振っていた。
「ち、違……ッ! あいつ……『シュバルツ』は……! 俺にこんな事はしなか……ッ!!」
「――――抱かれていないのか!?」
「―――――!!」
ハヤテの叫び声に、ハヤブサは一瞬正気に戻る。
自分が今――――『シュバルツ』の名を叫んでしまった事を悟る。
だがもう遅い。
『シュバルツ』の名は――――ハヤテの脳裏に、しっかりと刻み込まれてしまった事だろう。
「答えろ、リュウ」
ズブ、と、指の本数が増え、犯される深度が深くなる。
「あ………!」
喘ぐために開いた口の中に、容赦なく塗りつけられる媚薬。ハヤブサは再び、薬の『熱』の中に溺れて行った。
「お前の恋人は……お前を、抱いていなかったのか……?」
「ああ……。俺が……『タチ』だったんだ………」
ハヤブサは朦朧とした意識の中、ハヤテに答え続ける。媚薬によってもたらされる『熱』は、最早ハヤブサの総てを、押し流してしまっていた。
「信じられんな……。お前ほどの身体を目の当たりにして、それを抱かないとは――――」
グッとハヤブサの腰を抱き寄せ、自分の方に臀部を突き出させるような格好にさせる。肩から背中にかけて流れるハヤブサの琥珀色の長い髪が、さらりと床に向かって零れ落ちて――――彼の腰から臀部にかけての綺麗な曲線を、さらに扇情的に引き立たせていた。
「違う……! シュバルツは……! あいつは……!」
この期に及んで、まだ他の男の名を縋る様に呼ぶ愛おしい人。ハヤテの目の前が真っ赤に染まった。
「まあいい……! お前は、俺が奪う。良いな、リュウ……!」
「ああ……! いや……! いやだ……!!」
頭をふり、涙を飛び散らせるハヤブサには構わず、ハヤテはその秘所に猛る己をあてがう。
彼の『初めて』を奪う―――――その、黒い喜びに震えた。
「愛している……! リュウ……!」
ハヤテはそれだけを言うと、ハヤブサの秘所を己自身で一気に貫いた。
「ああっ!! ああああ―――――ッ!!」
指とは比べ物にならない程の圧迫感と違和感にハヤブサは悲鳴を上げ、しかし熱で火照る身体はあっという間に絶頂へと導かれてしまう。また彼は果ててしまい、前に白い液体の水たまりを作った。
「は……! 良いぞ……! お前の内側(なか)は――――!」
ハヤブサの身体を強くゆすりながら、ハヤテもまた『熱』に溺れて行く。
幼いころからずっと、恋焦がれていたハヤブサ。
その身体を、今、自分が抱いているのだ。紛れもなく――――
抑えていた想いを解放させているが故に、もうハヤテは止まれなかった。
例えこの行為が、ハヤブサを傷つけるだけの物だと分かってはいても――――
この狂おしいまでの愛おしさを、どうやって止めろと言うのだろうか。
「ああっ!! ああっ!! ああああっ!!」
媚薬の力が、ハヤテの律動が――――ハヤブサの何もかもを狂わせる。
かつてない程の『熱』――――
狂おしい程の『快感』――――
その向こうにハヤブサは、ただただ愛おしいヒトの姿を求めた。
シュバルツ
シュバルツ
叫んで手を動かそうとするが、何故か、手が動かない。
誰かに優しく、手を握りかえされる。
シュバルツ?
そう問うと、相手は「お前の恋人だ」と、答えて来た。
恋人?
恋人は――――シュバルツだ。
シュバルツ
シュバルツ
何処だ………?
「居ない」
その声は答えて来た。
そいつはここにはいない。
お前の恋人は俺だ。
俺を見てくれ。
いやだ
シュバルツ
シュバルツに、会いたい
小さい子どもの様に駄々をこねて泣く。
優しく抱きしめられ、宥められるようにキスをされた。
身体の中で爆ぜる熱に、自分が誰かに抱かれている事を思い出す。
いや、いや、
仰け反る身体に、また快感が与えられた。
ああ――――気持ち い い 。
シュバルツ
シュバルツ……!
更に、与えられる快感。
ぐちゅぐちゅと、肉がぶつかる音と卑猥な水音が響く。
気持ち、いい
気持 ち い い
踏みにじられているのに
犯されているのに――――
どうして――――?
いや……!
いやだ……!
シュバルツ……!
「リュウ……!」
ああ
熱い……!
身体の中で爆ぜる熱。
誰か止めて
止めてくれ
助けて……!
助けてくれ、シュバルツ……!
「愛している、リュウ……!」
「んうっ!! んんっ!!」
舌を絡め捕られ、強く吸われる。
胸を優しく弄られながら、また果てる。
果てたのに――――赦してくれない。
愛撫は、容赦なく降り注いでくる。
いやだ
助けて
もう―――――壊れる
シュバルツ……
シュ バ ル ………
「――――――」
声にならない悲鳴を上げて、ハヤブサはその意識を手放す。それと同時にハヤテも最後の『精』を―――――ハヤブサの中に放っていた。
「――――ッ!」
はあっと、大きく息を吐いて、ハヤテは自分の物を、ハヤブサの中からずるっと音を立てて引き抜く。すると、ハヤブサの秘所から、ゴポリ、と自身の白い残滓が大量に溢れ出て来た。
「……………」
ハヤブサの顔にかかる、乱れた琥珀色の髪をそっとのける。気を失っているハヤブサの頬には涙が流れ落ちていて、その身体には、痛々しい程の愛撫と暴力の跡が刻まれていた。
自分に抱かれながら、目の前のこの愛おしい人は、最後まで他の男の名を呼んでいた。
分かっている。
今の行為は、決して『同意』の上に成り立っているのではない、と言う事だ。
ハヤブサにとっては、強姦以外の何物でもなかっただろう。
酷い事をしてしまった。
だが――――不思議と後悔はなかった。
子どものころから温めて来た大事な『想い』を、自分は今―――――確かに一つ、成し遂げたのだから。
それほどまでに、ハヤブサが欲しかった。
自分には、どうしても必要だったのだ。
彼の手が
その存在が――――
知らず、暴力で手折ってしまうほどに。
頬に流れる涙を、そっと唇で掬ってやる。
自分の暴力によって倒され、穢された龍の忍者の姿も――――素直に美しい、と、思えた。
(今は、他の男の事を想っていても良い、リュウ……。だけど覚えていてくれ。俺は必ず、お前を手に入れて見せる……! 身体も、そしてその心も――――!)
ハヤテはもう一度、ハヤブサの頬に優しくキスをすると、身支度を整えて立ち上がった。
「シュバルツ……」
リュウの忍者が縋るように呼んでいた、男の名を口にしながら、静かに部屋から出て行った。
「―――――ッ!!」
数刻後に、龍の忍者は目を覚ました。跳ね起きようとして、手の自由が利かず、手首足首、そして己の首に、鎖がじゃらりと重しの様に垂れさがっていて、ハヤブサを部屋に縛り付けていた。
自分の身体は裸のまま。そして――――汚れ切っていた。そろり、と、身を起こすと、秘所からハヤテの愛の名残が零れ落ちてくる。
「あ………! あ………!」
とろ、とろ、と流れ落ちてくるそれは、ハヤブサに容赦のない現実を突きつけて来た。
自分は、ハヤテに『奪われて』しまったのだと。
(ハヤテ……!)
身を起こしていられなくなったハヤブサは、ぽすん、と、布団に倒れ込んでしまう。
―――愛している、リュウ……。
犯されている最中、何度も聞かされた言葉。何時からだとハヤブサが問えば、ハヤテは「子供のころからだ」と答えていた。
(子供のころから……? そんなに……そんなに長い間、俺の事を……!?)
全然気がつかなかった。まさかあのハヤテが――――自分を、そんな眼差しで見つめていただなんて。
だけど、考えれば思い当たる節もある。
自分と会う時、ハヤテはいつも柔らかい笑顔だった。忍びの頭首として、常に厳しい立場に立たされていたにもかかわらず、いつも自分には――――静かな笑顔を向けてくれていた。
そして、彼の隣はとても居心地が良かった。
あれは、ハヤテの『人格』が為せる業なのだと、ハヤブサは勝手に思っていたのだが、それは、もしかしたら違っていたかもしれなかった。ハヤテが懸命に努力して――――『俺のため』に、居心地を良くしようとしていてくれたのだとしたら。
(ああ……!)
ヒトに深く恋をして――――初めて分かることもある。
ハヤテと自分は同じなのだ。人を深く愛している、という点においては。
愛するが故に、そのヒトを優しく見つめ
愛するが故に、そのヒトが自分の隣に少しでも長く居てもらえるように努力をする。
振り向いてもらえただけで嬉しい。
笑顔を見せてくれれば、極上の幸せ――――
逢えぬ日は、胸をかきむしりたくなるほど苦しい。
そんな切ない想いを、ハヤテに、子どものころからずっと、させ続けていたのだとしたら。
それに気付けなかった自分は――――どれだけハヤテを傷つけ、踏みにじってしまっていた事だろう。
(ああ、だから)
ハヤブサは思う。
この暴力は、ハヤテの悲鳴なのだ。
堪えに堪え、ひた隠しに隠していた自分への想いが、こんな形で暴発してしまったのだと。
(ハヤテ……!)
酷く切なくて、涙が溢れる。
もしも
もしも、もっと早く
ハヤテの想いに気づいていたなら
自分はどうしていただろう
今とは違った未来が、あったのだろうか――――
だけど
だけど自分は、出会ってしまった。
あの、健気な『光』に―――――
そのヒトはただ―――――自分の心の一番深い場所に、するりと入り込んで来ていた。
自分の何を、暴くでもなく。
自分の何を、否定する事も無く。
自分でもどうしようもない、心の奥深い柔らかいその場所に入り込んで――――そっと寄り添ってくれていた。
そのヒトは誰よりも深い闇に塗れ、孤独の中に居たのに。
優しい『光』を、俺にくれた。
闇の中に生きるが故に、時に何も信じられなくなりそうな俺に、「大丈夫だ」と、その背中を押してくれた。
そして、「幸せになれ」と、言ってくれた。
「じゃあ、お前は!?」
叫ぶ俺に、そのヒトは小さく頭をふった。
「私は、良いから」
そのヒトは、『見返り』を求めてはいなかった。
我慢が出来なかった。
何故
何故
優しい『光』を内包したお前が、そんな救いのない闇の中に、独り、佇んでいなければならないのだ?
どうして、そんな孤独な場所から、他人の幸せを願えるのだ?
生まれて初めて、他人を欲した。
その手を取りたいと、強烈に願った。
生きるのならば、共に。
幸せになるのならば、共に――――
なのに、彼を覆う闇は深すぎて――――俺は、なかなかそこにたどり着けない。
業を煮やした俺は、半ば無理やり、その身体を奪った。
身体を繋げれば、せめて――――俺も、彼のヒトを覆う闇に、一緒に塗れる事が出来るのではないか。そう思ったからだ。
「駄目だ!! お前に、DG細胞が――――!!」
抱こうと、犯そうとしている俺を、案じる言葉しか言わないお前。どんなに凌辱しようとしても、それは、変わらなかった。
愛してる
お願いだ
抱かせてくれ
それが駄目なら殺してくれ――――!
懸命の懇願。
それを、そのヒトはついには受け入れてくれた。
初めからがっつきすぎた俺を赦して、背中を優しく撫でてくれた。
「しようがない奴だな」
そう言って優しく笑う、その笑顔が好きだった。
身体を繋げて、共有する時間を持つようになって――――『想い』は廃れるどころか、ますます募った。
お前の事を知りたい。
もっと、もっと
俺の事も知って欲しい。
もっと、もっと――――
それはハヤブサが味わう、人生で一番優しい時間かもしれなかった。
(シュバルツ……。心配しているかも、しれないな………)
座敷牢の窓から差し込む月明かりをぼんやりと見つめながら、ハヤブサは思った。ここに監禁されてからどれぐらいの時が過ぎたのかは分からないが、もしかしたら、『約束の日』が来てしまっているかもしれない。
実は、定期的に会うようになってから一度だけ――――ハヤブサは『約束の日』をすっぽかしそうになった事がある。
―――と、言ってもわざとではない。全くの不可抗力だった。
明後日はいよいよ「約束の日」――――ハヤブサが浮き立つ想いであれこれ準備をしている所に、急な仕事が舞い込んだ。
敵の規模も小さく、大きな事件でもなさそうに見えたため、ハヤブサは早急に片づけるつもりでその現場に向かった――――それが、間違いの元だった。
想像以上の難敵と事件に手こずり、無事に事件(それ)は解決したものの、ハヤブサ自身も重傷を負った。やっとの思いで日本に帰りついた時には、『約束の日』が終わろうとしている時間帯だった。
(さすがに、もう居ないだろうな……)
痛む身体を引きずりながら、それでもハヤブサはシュバルツとの待ち合わせ場所に赴く。怪我をしているのだから、早く里に帰るべき――――と、ハヤブサも頭では分かっていた。だがどうしても――――ハヤブサはその場所に行きたかった。
手当てをするにしても、命が尽きるにしても
シュバルツに会える可能性があるその場所に、居たかった。
(シュバルツ……!)
彼がいつも凭れかかって待っている、大木の根元に、ハヤブサが倒れ込もうとした、瞬間。
「ハヤブサ!!」
飛び出してきた愛おしいヒトが、自分の身体を支えてくれた。
「……待ってて……くれたのか……?」
「当たり前だろう!! 今日は『約束の日』だ!!」
弱々しく問う俺に、シュバルツから怒鳴り声が飛んできた。
「ああもう―――! こんな大怪我をして――――!!」
バリバリと自らのシャツを引き裂きながら、シュバルツが応急手当てを施してくれた。
「来られないなら来られないでいい!! 一本連絡を入れてくれ!!」
「シュバルツ……」
「心配するから……!」
「――――!」
手当てをするシュバルツの瞳から、涙が零れ落ちていた。
「お前の身を案じて、気が気で無くなるから――――!」
泣いているシュバルツが可愛らしくて愛おしくて、ハヤブサは思わず微笑んでしまう。
「笑い事じゃない!」
と、こっぴどく怒られた。
その後キョウジの家に連れて行かれて治療を受けた。そこで、キョウジにも散々怒られた。
怒り方が同じだったから、やはり『魂』は同じなのだな、と、変な所で感心した。
(会いたい……)
窓から差し込む月明かりを見ながら、ハヤブサは願う。
強そうに見えて、存外、涙脆いお前。
俺の事を心配して、泣いてしまっているかもしれない。
(泣かせるつもりはなかったのに……)
連絡のとり様がない現状に、ハヤブサは途方に暮れてしまう。
それに―――――
(ハヤテ………)
愛している、と、何度も言った幼馴染。
本気だ。
彼は本気で俺を捕らえ、そして奪いに来ている。
それに自分は、どう応えれば良いと言うのだろう。
ハヤテの事も大切だ。
大切だから――――途方に暮れた。
自分が愛しているのはシュバルツだ。でも――――
座敷牢の窓から差し込んでいた月明かりが、また、雲に覆われて見えなくなった。
それから何日か経ち、ハヤテがまた、座敷牢にやってきた。
ハヤブサは相変わらず鎖に繋がれたまま、薄い布の着物を一枚、その身に纏う事を許されているだけだった。
「ハヤテ……」
じゃら、と、鎖の音を鳴らしながら身を起こすハヤブサを、ハヤテは静かに見つめていた。
「リュウ……」
顎を捉え、唇を求める。ハヤブサはそれを、身を捩って拒絶した。
少し、哀しげにその行為を見つめていたハヤテであったが、すぐに無表情になり、口を開いた。
「………キョウジ・カッシュ……」
「――――!」
はっと息を飲むハヤブサを、ハヤテが冷たい目で見降ろす。
「某大学の、非常勤をしているようだな……。その傍らで、その大学から派生した研究院にも所属していて――――」
「や!! 止めろッ!!」
ハヤテの言葉を、ハヤブサの大声が遮る。ハヤテが何を言わんとしたのか、察してしまったからだ。
「ハヤテ……! お願いだ……! キョウジに手を出すのだけは、止めてくれ……!」
「……………」
懇願するハヤブサを、見下ろすハヤテの眼差しは、冷たいままだ。自分の幼馴染の、キョウジに対する確かな殺意を感じてしまって、ハヤブサは焦った。そんな哀しい事を、ハヤテにさせてはいけないと思った。
「な……何でも、する……!」
「……………」
ピクリ、と、ハヤテの眉が動く。それに対して、ハヤブサはもう一度懇願した。
「何でも、するから……!」
「本当だな?」
無表情のままのハヤテに、ハヤブサは頷く。するとハヤテは、無造作に命じた。
「服を脱げ」
「…………!」
「その着物は、肩の所の紐を引けば、簡単に外れるようになっている。早くしろ」
「………分かった……」
龍の忍者は立ち上がり、紐を引く。薄い着物はあっさりとその役目を放棄し、ハヤテの前にハヤブサの裸体を惜しみなく曝した。それを一通り堪能したハヤテは、ハヤブサの前に座ると手招きをした。
「そのままこちらに来て……『お前が自分から俺にキスをする』んだ」
「あ…………!」
「どうした。早くしろ」
「……………ッ!」
ハヤブサはハヤテに近づくと、静かに腰を下ろす。そのまま顔を近づけようとするハヤブサに、ハヤテはもう一言声をかけた。
「分かっているな、リュウ。『恋人にするように』キスをするんだ」
「……………」
一瞬、躊躇うようにその身を震わせたハヤブサだが、やがて、そっと、ハヤテの唇に、その唇を重ねて来た。
「ん…………」
躊躇いがちに、挿しこまれる舌。その身が、小さく震えていた。
(恋人に、そんな風に震えながらキスをするのか? お前は……)
キョウジのために―――――そして、恋人であるシュバルツを守るために、あっさり自分の身を投げ出すハヤブサの姿に、ハヤテは少しの怒りを覚える。ハヤブサの身体を強く抱きしめると、自分の口の中をそろそろと動く彼の人の舌を捕まえて、乱暴に吸い上げた。
「んう……!」
くぐもった悲鳴を上げるハヤブサを、そのまま布団に押し倒す。逃げ場のなくなったハヤブサの口腔を、存分に蹂躙した。
「ん………! ん………!」
キスをしながら、ハヤテの指がハヤブサの肌の上を滑る。
「ふ……! ん………ッ!」
「もっと……大きな声を上げて……感じてくれ……」
チュ、チュ、と、ハヤブサの肌の上に音を立てて唇を落としながら、ハヤテがさらなる痴態を要求してくる。
「んあ………! あ………ッ!」
「何でもする」と、ハヤテに言ってしまった以上、ハヤブサがそれに逆らえる筈もない。求められるままに声を上げ、その身をしならせ始めた。
「ハヤテ……」
ハヤテの名を呼び、乱れながら、ハヤブサの心はシュバルツの事を考えていた。
自分は、ハヤテの事を『親友』だと思っていた。それが、こんな風に想われていたとは、想像もしていなくて。
でも――――それはシュバルツも同じだったかもしれなかった。
『想い』を告げるまで、自分の横で穏やかに笑っていたシュバルツ。
自分は、そんなシュバルツを熱い想いで見つめていたが、シュバルツはそうじゃなかったかもしれなかった。自分の事を『親友』だと信じ切っていて――――
それがいきなり押し倒されて、半ば無理やり身体を奪われる。
(ああ、同じだ)
ハヤブサは思った。
今の自分と、あの時のシュバルツは、丁度同じ立場なのだと。
酷く、戸惑っただろう。
恐怖を感じたかもしれない。
無理もない。
信じていた者に――――ある意味、裏切られた事にもなるのだから。
ああ
酷い事をしてしまった。
酷い事を――――してしまった。
(シュバルツ……!)
ハヤブサの瞳から、はらはらと涙がこぼれる。
「何故泣く……?」
ハヤテの唇が、それを優しく掬う。
分かる。
ハヤテは本気で、自分の事を愛してくれている。
この前の愛撫(それ)と違って、今のハヤテはとても優しい。
どうして―――――自分はそれに、真っ直ぐ答えられないのだろう。
その事実が、酷く哀しかった。
でも、自分が愛しているのはシュバルツ唯一人。
それは変えられない。
変えられない のだ。
「泣くな……」
優しい声と共に、愛されていく身体。そんな風にされると、余計に涙が止められなかった。
「ああ………!」
身をしならせるハヤブサの動きに合わせて、手足に繋がれた鎖が、じゃら、じゃら、と、冷たい音を奏でる。それをハヤテは、苦い思いで見つめていた。
分かっている。
今、ハヤブサが自分にその身を赦しているのは、鎖に繋がれているからだ。そして、恋人を守るためだ。
決して――――自分を愛しているから、ではない。
今は良い。
それでいいんだ。
いつか――――その気持ちを、俺に向けてくれるのなら。
その為に、丁寧に愛す。
想いを込めて、その身体を抱く。
自分の『想い』が、ハヤブサに届くと信じて。
「ああっ!! あ……! あ……!」
肉がぶつかる音と、水音が響く。
鎖がうねる音も、激しくなる。
(シュバルツ……! シュバルツ……!)
犯されながらハヤブサは、ただひたすらに、愛おしいヒトの事を想い続けていた。
第3章
「えっ? リュウさんですか?」
ハヤブサからの連絡を数日間待って、彼の身に何らかの異常が起きたと9割がた確信したシュバルツは、まず、隼の里を訪れていた。自分と別れた後、ハヤブサは里に帰っていた筈だからだ。
「そうだ。ちょっと用事があって来たのだが……」
里の雰囲気は平和そのものだった。だからシュバルツも、何気ない風を装って問いかけた。村の物に余計な心配をかけるのは、ハヤブサとしても本意ではないだろうからだ。
「リュウさんなら『霧幻天神流の里』に行くって言っていただろう」
喜助の言葉に、隣に居た三郎太も頷く。
「リュウさんが帰ってきた時、あの里から正式な使いが来ていて――――」
「珍しいもんだよなぁ。あの里からハヤブサさんに助力を請いに来るなんて」
颯太の言葉に与助も苦笑する。
「あの里の忍者たちは、私たちと違ってみな優秀ですからね……。たいていの事は、あの一族の中で解決できてしまう物ですが……」
「おお~い! たった今、リュウさんから手紙が来たぞ!」
皆が話している所に、ハヤブサからの手紙を持って、小六が走り込んでくる。
「長老様には、今見せて来たところだ。やはり、あちらの『里』での滞在が、少し長引くらしい――――」
「そうか……。やっぱりなぁ」
「リュウさんも大変だなぁ」
「しかし……あちらの里の忍者たちも手こずって、リュウさんも帰って来られないなんて、一体、どんな事が起きているんだ……?」
「手紙には『心配無用』と書いてはいるが……」
「その手紙、見せてもらっても良いか?」
皆がそれぞれ話している所に、シュバルツが声をかける。「良いですよ」と、喜助がすぐにハヤブサの手紙を渡してくれた。
「…………」
目に映るのは、確かに、ハヤブサの筆跡の手紙だ。文章も普通で、特段、変わったところはない。
だが、あまりにも普通すぎる手紙に、シュバルツは却って異常な物を感じた。
こんな普通の手紙を書く事が出来るハヤブサが――――何故、自分にだけ、連絡をよこして来ないのだろう。
(行き違ったのだろうか)
もしかしたら、ハヤブサからの連絡が自分の所に入っていて、それに自分が気が付いていないだけかもしれない可能性も考える。しかし、あれだけ確認を重ねたのだ。それでも見落としていると言う事は考えにくい。
キョウジからの連絡も、未だに無い。彼の方にも、おそらくハヤブサからの連絡は入っていないのだろう。
じゃあ、この『普通すぎる』手紙は一体。
シュバルツがそう思いながら手紙を見つめていると、手紙から、微かに『声』が聞こえて来た。
(……………)
「―――――!」
手紙を書く時、文字を書く時――――人は、多かれ少なかれ、それに『ココロ』を込める。そして、シュバルツを構成する『DG細胞』は、人の『ココロ』に感応する細胞だ。
その声を「聞いてしまった」シュバルツは、やはり、ハヤブサが何らかの異常事態に巻き込まれてしまったのだと確信する。知らず、手紙を持つ手に力が入っていた。
「しかしどうする? 我々も何人か、天神流の里の方に様子を見に行った方がいいんじゃないのか?」
喜助の声に、シュバルツははっと我に帰る。
顔を上げると、喜助の言葉に小六が首を振っていた。
「いやあ、止めておいた方がいい。天神流の里は、うちの里と違って、忍びの規律が厳格だ。おまけに、余所者にもかなり排他的だ。あの里に出入りを許されているリュウさんの方が、余程稀な存在だと思っておいた方がいいと思うがな」
「それはそうかもしれないが――――」
小六の言葉に喜助が苦い顔をする。
「それでも、リュウさんがすぐに帰って来られない程の事が起きているんだろう? 手助けぐらい求めても――――」
「そうは言ってもなぁ……。あそこの忍者たちはみな優秀だし……」
「そうそう。俺らが行っても逆に足手まといになりかねないよ」
小六の言葉を受けて、颯太があっけらかんと答える。
(そうか……)
喜助達の話を聞きながら、シュバルツは状況を整理して行く。どうやら霧幻天神流の里に潜入しようとする事は、相当骨が折れる作業になりそうだった。
「しかし残念だな。ハヤブサがいないのなら、私は退散するとしようか」
与助に手紙を返しながら、シュバルツは面に笑顔を浮かべる。それに対して与助は、少し残念そうな表情をした。
「帰られるんですか? もっと、ゆっくりして行ってくださっても良いのに」
「そうですよ! 子どもたちも喜ぶし!」
「後でリュウさんが聞いたら、絶対に悔しがるだろうなぁ。『お前たち! 何で引き留めておいてくれないんだ!』って……」
「リュウさん、本当にシュバルツさん一筋だからなぁ」
忍者たちの話にシュバルツも苦笑するしかない。
「じゃあまた」
そう言って帰ろうとするシュバルツを、与助が引き留めた。
「シュバルツさん。もし、リュウさんに伝言なら、私が承りますが……」
「いや、キョウジからの伝言なのでな。ハヤブサに直接伝えたいんだ。また、出直してくるよ」
シュバルツはそう言って、隼の里を後にした。
(やはり、もう間違いない……。ハヤブサは、何らかの異常事態に巻き込まれている……)
歩きながらシュバルツは思った。ハヤブサは今――――無事でいることは確かだが、自分の意志では身動きが取れない状態にあるのだと。隼の里に届いたあの手紙が、総てを物語っていた。里の者たちに余計な心配をかけたくない、と言うハヤブサの気持ちが、痛いほど伝わって来ていた。
そして――――
(……タスケテ……)
本当に微かに聞こえて来た、小さな小さな声――――
この声を自分は、聞いてしまった。
誰にも気づかれない。そして、自分だけが分かる、このハヤブサの『異常事態』
いや、分かる様にハヤブサが仕向けてくれていたのかとも考えられるが――――
分かるのならば、動かねばならぬとシュバルツは思う。
もう自分は何度も何度も、ハヤブサに助けてもらった。
だから、自分がハヤブサに救いの手を差し伸べる事に、躊躇う理由は全くないのだ。
(しかし……『霧幻天神流』とは全く縁もゆかりも無い私が、どうやってあの名だたる忍者の里に接近する……?)
シュバルツの情報収集能力もそれなりにある。少し調べれば、霧幻天神流の里の位置も、問題なく特定できるだろう。
だが、問題はその後だ。
正当な理由も無く、あの里に近づく事はおそらく出来ないだろう。どの忍者の里もそうだが、里の防衛網の備えは、それなりにあるとみて良かった。
自分が霧幻天神流の里に潜入して、見つかって、そして殺されてしまうのは一向に構わない。だが、捕まって、ハヤブサの足手まといになってしまう事だけは避けねばならぬと思った。助けに行って、逆に迷惑をかけてしまうなど、論外だ。
ただ、霧幻天神流の頭首ハヤテとハヤブサは幼馴染だった筈だ。天神流の里と隼の里に、敵対関係がある訳でもない。それが、何故ハヤブサの『自由意思』が奪われるような事態に―――――
(……………!)
ここでシュバルツは、駅で見かけた時の、ハヤテの、ハヤブサに向ける眼差しを思い出す。
ハヤテは、とても優しい眼差しでハヤブサを見つめていた。
――――好きだ……
その眼差しが、声なき声で、ハヤブサにそう訴えかけていた物だとしたら。
(まさか……?)
ハヤブサがハヤテに捕らえられている――――そんな嫌なヴィジョンが、一瞬、頭の中によぎって、シュバルツは慌てて頭をふってそれを否定する。
いや、まだだ。
まだ、断定はできない。
本当に――――霧幻天神流の里が危機に陥っていて、あの里に居る者たち全体が、己が自由意思で行動できなくなっている可能性も、否定できないのだから。
(とにかく、霧幻天神流の里について、もう少し情報を集めよう。そうしなければ接近も出来ない)
シュバルツはそう決意して、ハヤブサといつも落ち合っている例の森へと足を向ける。
里に、己が手紙を出す事が出来たハヤブサ。
だからもしかしたら――――あの『例の場所』に、何らかの方法で、彼から連絡が入っているかもしれないのだ。
森まで走り、一縷の望みをかけてその場所を見るシュバルツ。
だが、やはりと言うべきか――――
ハヤブサからの手紙は、無かった。
(ハヤブサ……!)
シュバルツは拳を握りしめて、空を見つめるよりほかなかった。
それから更に数日が過ぎた。
(霧幻天神流の里の位置は特定できた……。後は……)
忍びこむルート、逃走経路の確保、やらねばならぬ下準備は多岐にわたる。
調べている間に、霧幻天神流の里自体が、何らかの異変に巻き込まれたと言う話は聞かなかった。だから、『異常事態』が、ハヤブサだけにピンポイントで起きている物なのか、それとも里の中全体でそれが起きている事を、外部に漏れないよう厳重に秘されている物なのか、それは分からない。
ただ、相手は名だたる忍者集団の里だ。準備をしすぎてもしすぎる事はない。
(ハヤブサが無事かどうか、確認するだけだ……。そうすれば……)
とりあえず無事であるならば、霧幻天神流の者たちと事を構えるつもりはない。自分は、すぐに退散するつもりだった。
そう考えながら歩を進めていたシュバルツの足が、ピタリと止まる。ある異変に気付いたからだ。
(……………?)
シュバルツの足が止まったのに合わせて、彼を尾行していた者の足もピタリと止まる。
(……何だ……?)
唐突に足を止めたシュバルツの意図が読み切れなくて、尾行者は戸惑う。刹那――――シュバルツの姿が、フッと消えた。
「――――!?」
尾行者が慌ててシュバルツの後を追おうとする、その背後に、いきなり彼は現れた。
「私に、何の用だ? 先程からつけて来ているようだが」
「――――ッ!」
相手は小刀を振り向きざまに振るって、シュバルツを牽制する。菖蒲色の短い髪がふわりと揺れ、薄桜色の長い蝶結びの帯が、しゃらりと流れた。小柄だが、勝気で、少し影を帯びた深い茜色の瞳が、シュバルツを射すくめる。
(女か!?)
瞬間的に殺気を緩めるシュバルツ。それを見て、くのいちの方の殺気も緩んだ。
「……貴方、シュバルツ・ブルーダーね」
「そうだ。お前は何者だ?」
小刀を構えるくのいちに対して、シュバルツは抜刀もせず、ただ静かに見つめている。シュバルツに戦闘意思がないと判断したくのいちもまた、その構えを解いた。
「私は霧幻天神流、ハヤテ様の一の部下、あやね」
『霧幻天神流』の名に、シュバルツの眉がピクリ、と、動く。
「『霧幻天神流』の者が、私に何の用だ?」
「私は、貴方と戦うつもりはないわ」
そう言いながら一歩身を引いたあやねの動きに、シュバルツもそれ以上踏み込むのを止めた。
「ハヤテ様から、貴方がた二人には手を出すな、と、厳命を受けている。私は、それを破って貴方がたに刃を向ける者が里から出ないかどうか、見張っていただけよ」
「……………!」
あやねのこの言葉に、シュバルツはいろんな意味で息を飲んだ。
まず、この短期間で自分達のある程度の事情を探られてしまった事。これは、さすが一流の忍者集団と言うところだろうか。
そして、『自分達には手を出すな』と、頭首であるハヤテが命を下したと言う事は。
(まさか……?)
ハヤテがハヤブサを捕らえるために、自分達の命を狙うと脅迫した可能性が――――
違う、と、シュバルツが己が頭に浮かんだ考えを否定しようとした時、あやねが口を開いた。
「だけど、私の用事はそれだけじゃない」
「…………?」
少し眉をひそめるシュバルツに、あやねは一歩踏み出してきた。その瞳に、切迫した輝きを湛えて――――
「お願い……! リュウ様を………! そして、ハヤテ様を助けて!!」
「―――――!?」
意外すぎるあやねの言葉に、シュバルツはただ戸惑うばかりだ。
「……どう言う、事だ?」
問いかけるシュバルツを、あやねは真正面から見つめる。
「多分、私が今ここで話すより、実際見てもらった方が早い」
「……………!」
「だから、里の内部に手引きいたします」
「な―――――!」
息を飲むシュバルツを、あやねはただ静かに見つめ続けた。
「私の言葉を信じる、信じないは貴方の自由。だけど信じるならば――――明後日の亥の刻にここに来て」
私は、待っているから――――そう言い置いて、あやねは消えた。後にはただ、独り佇むシュバルツだけが残された。
(どうする?)
あやねの言葉を反芻して、シュバルツは自問自答する。
『助けて――――』と、言った時の彼女の言葉と態度は真剣そのものだった。そして、助けを求めるために、自分を里の内部へと手引きしてくれると言う。
彼女の申し出が真実ならば、これほどありがたい事はなかった。天神流の里の者たちと無用な事を構えずに、里の内部を探れる事になるのだから。
(だが『それ』をして、彼女に何かメリットがあるのか?)
ここでシュバルツは考え込んでしまう。完全に里に縁も所縁も無い自分を内部に招き入れると言う事は、それだけで、里の規律に大きく違反している事になるだろう。下手をしたら彼女自身が『裏切り者』の汚名を受け、里から裁きを受けてしまうかもしれない。
ただでさえ忍びの掟に厳格な霧幻天神流の里にあって、彼女が率先してそれをやるだけの、めぼしい理由が咄嗟に見当つかなくて困った。どちらかと言えば、自分を捕らえるための『罠』だと判断した方が、しっくりくる。
しかし――――
――――ハヤテ様から、貴方がた二人には手を出すな、と厳命を……。
――――私は、貴方と戦うつもりはないわ……。
――――お願い……! リュウ様を………! そして、ハヤテ様を助けて!!
彼女のあの必死な様子に、嘘偽りはないと信じたい。それに、もしも彼女が『本当に』救いを求めて、懸命に自分に手を伸ばしているのなら、それを振り払うような真似は出来ないと強く感じた。
(行くか)
シュバルツはそう決意する。
騙されても良い。彼女の、あの必死な様を信じたい。それに万が一騙されて捕らえられて、自分がハヤブサの前に引っ立てられたとしても、『自分』ならば、ハヤブサにとっての人質とはなり得ないのだ。殺されても死なない自分の事を、ハヤブサはよく承知してくれている。例え彼の目の前で喉元に刀を突きつけられても、自分が引き裂かれようとも――――彼ならば、迷わず自分自身にとってベストの選択をしてくれる事だろう。
(『不死の恋人』……そういう意味では、とても都合の良い存在なのかもしれないな………。だからハヤブサは、私を恋人に選んでいる可能性もあるが――――)
そこまでシュバルツが思い至った時、心の中で、不意にハヤブサの「馬鹿野郎!!」と、大きく怒鳴る声が響いて来た。
「お前に敵から刃を突きつけられて、暴力を振るわれて――――俺が、平気でいられると思っているのか!?」
「ハヤブサ……」
敵に捕らえられてハヤブサの目の前で『人質』としての交渉材料にされた後、殺された、あるいは痛めつけられて解放された自分を介抱しながら、ハヤブサはよくそうやって怒鳴ってきたものだった。
「身を切られる思いがした……! 生きた心地がしなかった……! お前がこのまま目を覚まさなかったらどうしようかと――――!」
済まなかったな、と、笑いながらハヤブサの頬に触れると、その手を、とても大切な物の様に両手で包みこみ、愛おしむように頬ずりしてくれる――――そんなハヤブサが、好きだった。「愛されている」と感じられて、幸せだった。
自分の身は、どうなっても良かった。そんなハヤブサを助ける事が出来るのなら。
(ただ、キョウジの身の安全の確保だけは、しておいた方がいいかもしれないな……。キョウジを人質に取られたら、自分もハヤブサも、本当に身動きが取りづらくなってしまう)
シュバルツはそう断を下すと、彼もまた、その場からフッと姿を消した。後はただ、木立の中を風が吹き抜けて行くのみであった。
シュバルツが家に帰ると、キョウジは読んでいた本から顔を上げた。
「お帰り、シュバルツ。ハヤブサは、どうだった?」
「キョウジ……」
「あまり、よくない状況なのか?」
「―――――!」
自分が一声発しただけで、いろいろと察してくれるキョウジ。いくら自分同士とはいえ、そんなに自分は分かりやすい表情をしていたのかなと、シュバルツは少し苦笑してしまう。
「はっきりした事はよくわからん。ただ、あまりよくない事になっている可能性もある」
「……もしかして、私は身の安全を、確保した方が良いレベルなのか?」
「……………!」
そのキョウジの言葉に、シュバルツは咄嗟に返事を返す事が出来ない。それを見て、キョウジはにこりと微笑んだ。
「……分かった。ドモンに連絡をとるよ」
そう言いながらキョウジは、手元の携帯を操作し始める。「済まない」と頭を下げるシュバルツに、「良いって」と、ひらひら手を振って応えた。
キョウジが、ドモンの携帯を鳴らしてから3コール目ぐらいで、彼は出たらしい。
「ああドモン? 悪いんだけど、ちょっと――――」
キョウジの言葉が終わらないうちに、玄関のドアが、バン!! と大きな音を立てて開かれる。2人がびっくりしてその方に振り返ると、携帯電話を握りしめて、息せき切って走ってきたと思われるドモンの姿がそこにあった。
「兄さん!? 兄さんがピンチなのか!?」
「いや、ピンチと言う程の物でもないんだけど」
噛みつかんばかりに問いかけてくるドモンに、キョウジが軽く笑って答える。
「シュバルツが、少し用事で私の傍から離れるんだ。その間、お前に私の警護をお願いしても良いか?」
「シュバルツが!?」
びっくりして振り返るドモンに、シュバルツが頷く。
「ああ。そんなに長くはかからない。用事を終えたらすぐに帰って来るつもりだが、一応、念のために……な」
「……………」
暫く、『兄』であるシュバルツの顔を推し量るようにじっと見つめていたドモンであったが、やがて、得心したように頷いた。兄には兄の、大事な戦いがあるのだと、彼なりに納得したのだろう。
「分かった! シュバルツ! キョウジ兄さんの事は任せてくれ! この俺が、必ず守りとおして見せるからな!!」
そう言って笑顔を見せるドモンに、シュバルツも笑顔を返す。これで、キョウジの当面の安全は、確保されただろう。
「あまり神経質にキョウジを守る必要はないぞ、ドモン。一応、『念のため』の処置だから」
あのあやねと言うくのいちの言葉を信じるならば、ハヤテの方に、キョウジや自分をすぐに害そうと言う気は無い様だった。だから、すぐに危機が差し迫っているという訳ではないのだ。
だが、忍びに目をつけられている可能性がある以上、備えすぎるほど備えておく事にこしたことはないとも思った。
「ドモン、ちょっと待っていてくれ。荷造りをするから」
キョウジがそう言いながら、手早く自分の必要な荷物をトランクの中に詰め込んでいた。キョウジが一度断を下したら、その行動はとても素早い。
「私の事は心配いらない。だから、安心して行っておいで」
そう言って微笑むキョウジの笑顔が、シュバルツにはとても心強く感じられた。
それから数日後。
あやねの指定して来た時間よりも早く、シュバルツはその場所に行き、あやねを待った。
そして数刻と経たぬうちに、あやねもやってきた。
「来たのね」
声をかけて来たあやねに、シュバルツも「ああ」と、静かに頷く。
「じゃあ、約束通り案内するわ。ついて来て」
そう言って踵を返す彼女の薄桜色の蝶結びの帯が、誘う様にしゃらりと流れた。シュバルツもその後に従って、走り出した。
それからどれほど走っただろうか。
森を抜け、山を越え―――――ある崖の中腹にある小さな小さなほら穴の前で、あやねはその足を止めた。
「このほら穴は、霧幻天神流の里と繋がっている。このほら穴の存在を知っているのは、私と、ハヤテさまの妹であるかすみ姉さましかいない――――」
そう言いながらあやねは、ほんの少し目を細める。
自分達の宿命も知らなかった幼いころ、あやねとかすみは、歳が近い事もあってよく一緒に遊んでいた。その遊びの中で、このほら穴を見つけた。
「これは、私たちだけの秘密ね」
そう言って優しく笑ったかすみを、あやねも姉の様に慕っていた。
だが、時が経ち、かすみが霧幻天神流の表の一族である『天神門』に、そして自分が裏の一族である『覇神門』に分けられたその日から、二人を取り巻く環境は一変してしまった。
かすみは、くのいちの長としての教育が施され、あやねは、その『影』となることを決定づけられた。あやねの存在は表から抹消され、ただかすみの『影』として生き、そして死ぬよう、命じられたのだ。
忍びの中でも光の中で生きるかすみを、ただ影から見つめるしか無い日々――――あやねは、歯を食いしばってそれに耐えていた。だがある日突然、かすみが何もかもを捨てて里から抜けだして、その日々が唐突に終わりを告げた。この時胸に去来した想いを、あやねはどう表せばいいと言うのだろう。
そして、かすみが里から抜ける時の脱出経路も、このほら穴だった。
「今からここを走り抜ける。でも、ほら穴自体が小さいから、貴方は苦労するかもね。どう? ついて来られるかしら?」
問うあやねに、シュバルツは事もなげに頷いた。
「問題ない。行ってくれ」
ならば、と、あやねはほら穴の中に身を滑り込ませる。シュバルツも、その後に続いた。
狭いほら穴の中を、あやねは全力で走る。だが、驚いたのは、自分よりはるかに上背のあるシュバルツが、自分から全く遅れることなくその後を付いて来た事だ。ちらりとその様に視線を走らせると、シュバルツは狭い岩の間をどうすれば通れるのか瞬時に判断して、器用にその体を運んでいる。
優れた忍びは空間把握能力にも優れ、狭い場所でも問題なく戦う事が出来ると言う。
(さすが……リュウ様の『想い人』になるだけの事はある……)
あやねは感心しながら、ほら穴の中を走り抜けていた。
目的の小屋は、ほら穴を出てからすぐそこにあった。
首尾よくその小さな小屋に入ることができたあやねとシュバルツを、1人の忍びが待ち受けていた。
「あやね様」
「連れて来たわ。『鏡(かがみ)』」
鏡と呼ばれた忍びは、あやねに向かって軽く頭を下げる。年配の女性の忍びの様であった。あやねは鏡に頷き返すと、シュバルツの方に振り返った。
「今から、ハヤテ様とリュウ様の間に何が起こっているのか、貴方に見せるわ。『鏡』はその術に長けた忍びよ。彼女の術で、今から、あのハヤテ様の屋敷の中で起こっている事を、ここに映し出す。いいわね」
あやねの言葉にシュバルツが頷く。それを確認してから、あやねはもう一度口を開いた。
「ただし、何を見ても、どんな事を聞いても――――絶対に声を上げたりしないと約束して。でないと、ハヤテ様にこの術が気づかれてしまう。そうなればすべてが終わりよ。ハヤテ様もリュウ様も、救えなくなってしまうから」
「一つ、聞いても良いか?」
あやねの言葉を聞き終わってから、シュバルツが問いかける。「何?」と、少し眉をひそめた彼女に、シュバルツは言葉を続けた。
「君がそう言うふうに動いている事を、ハヤテ殿は承知していないのか?」
「ええ。これは、私の独断よ」
あやねはさらりと答えた。彼女は何でも無い風に装ってはいるが、これはある意味頭首の意向を無視して話を進めていると言う事になる。周囲にばれれば彼女自身が里の規律に従って、詰め腹を切らねばならなくなるだろう。
「今から起こることは――――絶対に、貴方も知っておくべきだと思うから」
それほどまでに、必死なのだ。
彼女が、命をかけてこちらに何かを伝えようとしているのが分かる。だからシュバルツも、それを受け止めて頷いた。
「分かった……。約束しよう」
シュバルツから『約束』と言う言質を取れた事に、あやねもその面に少しの笑みを浮かべる。だがすぐに、その表情は硬く引き締まった。
「もうすぐハヤテ様が自分の館にお戻りになるわ。『鏡』、始めて」
「御意」
あやねの言葉を受けて、鏡がその術を発動し始めた。3人の前に、ボウ、と、光の玉が浮かび上がり、その中にハヤテの屋敷の中の光景が、浮かび始めた――――
まず、部屋の中に居る人物を、その術は捉え始めた。
その人物は、鎖に繋がれていた。白い薄衣の着物を身に纏い、いつもは一つに束ねている琥珀色の長い髪を、さらりと流れるままに任せている。
(ハヤブサ……!)
シュバルツはまず、ハヤブサの置かれているあまりに異常な状況に、息を飲んだ。だが、声を出してはならぬと、必死に堪える。シュバルツの目の前に居るハヤブサは、布団の上に身を置いて、固い表情で正座をしていた。
そこにハヤテが部屋に入って来る。顔を上げるハヤブサの表情は、強張ったままだった。
「リュウ」
ハヤテの呼び掛けに応じて、ハヤブサは立ち上がった。そのまま肩の紐を引くと、着物はあっさりとハヤブサの身体から脱げ落ち、その身体をハヤテの前に曝していた。
「……………」
ハヤブサはそのまま歩を進めると、ハヤテにキスをしていた。この流れはハヤブサにとっては『儀式』の様な物で、特に何も感じなくなっていた。
そのまま押し倒され、唇を深く奪われる。
「ん…………」
ハヤテの指が、肌の上を滑り始める。
「あ……! ああっ!!」
その指の動きに合わせてハヤブサは喘ぎ、そして、乱れ始めて行った。
(こんな………!)
目の前で繰り広げられている光景に、シュバルツは身体の震えを止める事が出来ない。ある意味、自分の嫌な予感が、的中してしまった事になるのだから。
ハヤブサは、ハヤテが求めるままに唇を赦し、その愛撫に応じている。全く、『恋人同士』が行う様な愛の行為だ。ハヤブサの身体が、不自然に鎖が繋がれている事を除けば。手首足首に絡まるその鎖は、いつでもハヤブサの自由を奪う事が出来るようになっているのだろう。それにしても―――――
(どんな事情があるにせよ、こんな事は他人が覗き見ていい物ではない。一体彼女は何を考えて、私にこんな物を見せるのだ!?)
思わず、あやねの方を振り返る。今自分は、どんな表情をしているのだろう。そんな事を慮る余裕さえ、シュバルツにはなかった。
振り返ったシュバルツと視線が合ったあやねは、瞬間身を固くしていた。だが彼女は、シュバルツから視線を逸らすことなく、寧ろ食い入るように見つめて来ていた。
お願いだ。見続けてくれ。
彼女の視線が、そう訴え続けていた。
「……………!」
その視線の必死さに、彼女もまた、命をかけてそれをしていると言う事を、シュバルツは思い出していた。
(それほどまでに、私に伝えたい事が在るのか……?)
彼女のそんな気持ちも無下にしてはいけないと思い、シュバルツはもう一度向き直る。
しかし、目の前で繰り広げられている光景は、自分にとってはかなりきつい。自分は結局―――――恋人を、寝取られた事になるのだろうか。
(恋人……)
シュバルツの胸が、ツキリと痛む。
彼は自分の恋人だと叫ぶココロと、今ならば、彼をDG細胞の影から解放してやれるのだと、叫ぶ理性がせめぎ合った。
「ああっ!! あ………っ!」
ハヤブサの身体がしなり、長い髪が身体の動きに合わせてさらさらと流れる。
「んく……! んあ……! ああ……!」
その様は、酷く妖艶だった。そして、素直に美しいと感じた。
こんな美しい人に愛されていた事自体が、奇跡に思えるほどだった。
(ハヤブサ……!)
ハヤブサは、どう思っているのだろう。
もしも、ハヤテ殿の愛を受けて、『幸せだ』と感じているのならば
私は、もう―――――
シュバルツがそう思っていた時、『それ』は起きた。
「………シュバルツ……!」
「―――――!」
は、と、息を飲むシュバルツの目の前で、その小さくか細い声はなおも続いた。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
声の主は、ハヤブサだった。彼はハヤテに抱かれながら、浮かされるようにその名を口にしていた。まるで、縋るように――――。
「リュウ……! お前は、またその名を――――!」
忌々しそうに叫ぶハヤテに、ハヤブサもはっと我に帰ったようだった。
「ハヤテ……!」
「お前を抱いているのは俺なのに……! お前は、いつになったら俺を見てくれるんだ……!?」
「は、ハヤテ……! 済まない……! そんなつもりでは――――!」
「そんなつもりじゃないと言うのなら、どう言うつもりなんだ……! いつまでもいつまでも、あの男の名を呼んで――――!」
「ハ……ハヤテ……! あっ!!」
怯えたように後ずさろうとしていたハヤブサを捕まえて、ハヤテが小瓶から取り出したクリーム状の物を、彼の身体に塗りつけ始める。
「や……! 止め……! 薬を使うのは、止めてくれッ!!」
ハヤブサが身を捩りながら、悲鳴の様な声を上げる。しかし、ハヤテの手の動きは止まらない。
「忘れさせてやる……。溺れさせてやる、リュウ……! お前の中から、その男の幻影を追いだすまで――――!」
「ハヤテ……! あっ!! ああっ!!」
薬を塗り終えたハヤテが、再びハヤブサを貫く。貫かれた衝撃で、ハヤブサが果てたのが見えた。だが、ハヤテがその攻め手を緩めることはない。ハヤブサの腰を抱え込んで、尚も掻き回すようにそこに楔を打ち込み続ける。ぐちゅぐちゅと濡れた水音と、肉のぶつかる音が辺りに響き渡った。
「ああっ!! ハヤテッ!! ハヤテぇ……!!」
「リュウ……! リュウ……!」
「ハヤテ……! ハヤ………ああっ!!」
再びハヤブサが、達するのが見えた。それと同時にハヤブサの中で、何かの箍が外れてしまったらしい。うつろな眼差しのハヤブサが浮かされたように口にするのは、また――――「シュバルツ」の名前だった。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
「リュウ……!」
自分と繋がって居る筈のハヤブサが、また、違う男の名を呼んでいる―――――その事実が、ハヤテの目の前を『絶望』の二文字に染め上げる。
「ああ……! シュバルツ……!」
涙を流すハヤブサが、縋るように宙に手を伸ばす。ハヤテがそれを優しく握りかえしてやると、「違う」と、振り払われた。
「いやだ……! シュバルツ……! シュバルツ……!」
「リュウ!! 気がついてくれ……! その男はここにはいない! 居ないんだ!!」
悲痛な叫び声を上げるハヤテの声が聞こえていないのか、尚もシュバルツの名を呼び続けるハヤブサ。縋るように伸ばされた手は、空しく宙を彷徨い続けていた。
(こんな……!)
目の前のハヤブサの姿が霞む。
どうして――――
何故だ、ハヤブサ……!
どうして、そんなにまで私の名を………!?
シュバルツは、己が身体の震えを止める事が出来ないでいた。
(もう、充分だわ)
あやねは思った。シュバルツに見せたいのは、今のハヤブサとハヤテのやり取りだった。
ハヤテに抱かれながら、シュバルツの名を呼び続けるハヤブサ。
このままでは、ハヤテも、そしてハヤブサも、壊れて行くしかないと分かる。
二人とも、自分にとっては大切な人だ。だから、何とかしたいと願った。
そのためには、ハヤブサがその名を呼び続ける「シュバルツ」の協力が、絶対に必要だとあやねは感じたのだ。
その為の現状を、シュバルツに見せる事が出来た。ならば、これ以上、彼に見せ続ける訳にはいかないと思った。
だから、あやねは鏡に術を止めるよう指示を出そうとする。しかしその動きを、シュバルツが手を上げて制した。
(――――!?)
驚いて顔を上げるあやねに、シュバルツは手を上げたまま、静かに首を横に振る。
(もう少し、見させてくれ)
その瞳が、確かにあやねにそう訴えていた。
「…………!」
何故――――?
あやねは茫然とシュバルツを見つめる。
シュバルツとハヤブサは、恋人同士であったと聞いている。ならば、この目の前で繰り広げられる光景は、シュバルツにとっては見るに堪えない物である筈だ。
現に、彼の手が震えている。
瞳からは、光る物が零れ続けている。
なのに何故――――?
これ以上何を、みたいと言うの……?
自分もそうだ。
自分も、この光景を見続けるのは辛い。
何故なら自分も――――ハヤテに恋をしているのだから。
分かっている。
ハヤテが、自分の想いに応えてくれる可能性など、皆無に等しいと言う事を。
それでも
それでも――――
何故、今ハヤテの愛を受けているのが自分ではないのだろう。
自分ならば、喜んでハヤテに愛されるのに。
こんな風に、ハヤテを哀しませたりはしないのに――――
「シュバルツ……! あ……! あ……! シュバルツ……ッ!」
ハヤテに深く穿たれながら、尚もハヤブサはその名を呼び続けている。ハヤテがどんなに呼びかけても、ハヤブサはその名を呼ぶ事を止めなかったから――――ハヤテも、ついに切れてしまった。
「リュウ!! その名を呼ぶのは止めろ!!」
怒りに猛るハヤテの手が、ハヤブサの首に伸びてくる。その手は、ハヤブサの首を鷲掴みにした。
「お前を抱いているのは俺だ!! 俺なんだッ!!」
「ぐ……! う………ッ!」
首を絞められたハヤブサは、その呼吸を奪われる。そしてそれ故に、ハヤテを受け入れている秘所がひくひくと蠢き、ハヤテ自身を強く締めつけた。
「――――――ッ!」
その衝撃で、ハヤテは果ててしまう。その間首を絞められ続けたハヤブサもまた、崩折れるように倒れて、その意識を手放していた。
「リュウ……ッ!」
ハヤテが必死に、気を失ったハヤブサに呼びかけている。ぱしぱしと頬を軽く叩くと、ハヤブサが僅かに身じろぎをした。
「リュウ……!」
ハヤブサから帰ってきた反応に、ハヤテが、瞬間柔らかい表情をする。その瞳から、光る物が零れ落ち始めた。
絞められて、鬱血しだしたハヤブサの首周りに、ハヤテは優しく唇を落とす。
「リュウ……! どうして、俺は……!」
ハヤテは涙を零しながら、ハヤブサの身体を優しく丁寧に清めて行く。暴力を、振るってしまうつもりはなかったのだろう。それをしながらハヤテは、時折「済まない。済まない」と、ハヤブサにひたすら謝り続けていた。
自分は、ハヤブサが欲しかっただけだ。
ただ愛し、愛されたかっただけだ。
それなのに、どうして――――
自分が欲すれば欲する程、ハヤブサが遠くなっていってしまっている様な気がする。
今、こうして気を失っているハヤブサの身体に刻まれている物は、愛し合った後と言うより、暴力とレイプの後のようだ。
どうして
どうして
こんなつもりではなかったのに――――
「リュウ……!」
ハヤテは泣きながら、ハヤブサの身体をぎゅっと抱きしめると、布団を改めて敷き直して、そこにハヤブサをそっと横たえさせた。唇に優しくキスをすると、ハヤテは静かに部屋から出て行った―――――
「……………」
その一部始終を見届けてから、シュバルツはあやねの方に振り返った。それに気が付いたあやねが、鏡に合図を送る。それを見て鏡は、術を解いた。
「……どう? 分かったかしら? 私が言った意味が……」
「そうだな……」
シュバルツは静かに言葉を続けた。
「このままでは確かに……ハヤテ殿もハヤブサも……壊れてしまう……」
(…………!)
シュバルツのその言葉を聞いて、あやねは自分がシュバルツに伝えたかった事が、正確に伝わったのだと悟った。内心ほっと胸を撫で下ろし、自分の役目はほぼ終わったのだと知った。
「お願いします……! どうかリュウ様を……! そして、ハヤテ様を助けてください!!」
だからあやねは、懸命に懇願をした。
この現状を訴えるために、あやねは自分が里の規律も、そして人としての道も、踏み外してしまっているという自覚があった。その為に自分は、どう思われようと、そしてどうなろうとも構わない。
だけどハヤテを、何とかこの現状から救い出したい。その強い想いが、あやねを突き動かしていた。
「ハヤテ様は、本当はお優しい人なんです!! 元来なら――――こんな風に他者を踏みにじる様な御方じゃないんです!!」
「そうだろうな……。そして、ハヤテ殿は、本当にハヤブサの事が好きだ……」
「――――!」
ポツリと紡がれたシュバルツの言葉に、あやねははっと、息を飲んだ。
「ど、どうして、そんな事が分かるの……?」
問うてくるあやねに、シュバルツが明確な理由を話す事はなかった。代わりに、あやねにこの言葉を投げかけた。
「そして、君も……ハヤテ殿の事が――――」
「ち、違う!!」
シュバルツの言葉を、あやねは強く否定した。自分の気持ちを見透かされてしまったような気がして、酷く居心地が悪かった。
「ハヤテ様の事を気遣うのは、『一の部下』として当然の務めだ!! それ以上の想いは何も無い!!」
「そうか………」
自分の言葉にそう返したシュバルツが、腕を組んで部屋の一点を見つめている。これ以上、シュバルツが自分の気持ちに対して踏み込んでくる気配がない事を感じ取ったあやねもまた、シュバルツに対して構えるのを止めた。
「……………」
部屋の一点を見つめたまま、沈黙を続けるシュバルツ。その姿は、何か熟考をしている様子を伺わせた。
(何を考えているのだろう)
あやねもまた、そんなシュバルツを静かに見守る事を選択していた。
そうして、どのくらい時が経っただろう。
「あやね殿。もう一度、手引きを頼めるか?」
振り返って、そう問いかけてきたシュバルツに、あやねははっと顔を上げた。
「確かに……このままではよくない。どうなるかは分からないが、私なりに手を打って見ようと思う」
「では――――!?」
縋るように見つめてくるあやねに、シュバルツは少し苦笑した。
「だが……あまり結果には期待しないでくれよ。もしかしたら、君が望む通りにはならないかもしれない。……それでも良いか?」
問うシュバルツに、あやねは力強く頷く。
「構いません。どうなろうとも、私はハヤテ様をお支えするだけだから」
今のまま、互いの気持ちが宙に彷徨い、どちらの手も届かないまま二人が自滅して行く状態よりは、少しでも何らかの進展があった方が、はるかに良いだろうとあやねは思っていた。だから、彼女に迷いはなかった。
「そうか………」
あやねの言葉に、シュバルツの面に笑みが浮かぶ。
「済まないが、少し時間をくれ。準備ができたら君に連絡をしよう。その手段は、どうすればいい?」
「私の使命は、里の者たちが貴方がたに手を出さないように見張ること―――――。だから、私はいつでも貴方たちの傍に居るわ」
シュバルツの問いかけに、あやねはさらりと答えた。
「呼んでくれれば、私はいつでも姿を現す」
「そうか」
あやねの答えに、シュバルツも頷く。こうしてこの夜はあやねと別れ、シュバルツは霧幻天神流の里から脱出をしていた。
(ハヤテ殿は、ハヤブサの事が好きだ……。それは、もう間違いない……)
天神流の里からキョウジの家へと帰る道すがら、シュバルツは己が考えを整理していた。
おおよそ、その人の人柄は、事に及んでいる最中よりも、後戯の方に色濃く出てくるとシュバルツは思っている。その最中は熱情に流され、行為も本能に任せるままになるが、一段落ついて冷静になった時――――人は、本来の人格が顔を出す物なのだ。
だからシュバルツは、ハヤテの後戯が見たいと思った。その為に、最後まで見続けていたのだ。
ハヤテは、気を失ったハヤブサを、とても丁寧に扱っていた。まるでこの世に二つとない宝物のように―――――
ちゃんとハヤテは、ハヤブサの事を愛している。おそらくハヤブサは、幸せになれるだろう。ハヤテの愛を、受け入れる事が出来さえすれば。今、ハヤブサがそれを出来ないでいるのは、唐突に自分との関係を断たれてしまったからだ。まだ会うつもりで、関係を続けようと望んでいた所でこうなってしまったから、ハヤブサの手が宙を彷徨ってしまうのだろう。
だから、ハヤブサと自分は、話し合わねばならぬとシュバルツは思った。
きちんと話し合って、そして、ハヤブサは選ぶべきなのだ。己が未来を。自身が進むべき道を――――。選ぶ事が出来さえすれば、ハヤブサは、どっちつかずの今の状態から、一歩、前に進める筈なのだ。そうすれば、ハヤブサの手が空しく宙を彷徨う事も、無くなるだろう。
その為に自分が出来る事は、指し示すことだ。ハヤブサの進むべき道の片方を。そして、手を差し伸べることだ。ハヤブサの未来の選択肢の一つとして――――
その為には、覚悟を決めねばならぬ。
ハヤブサの総てを引き受ける覚悟を。
霧幻天神流の総ての者たちを、敵に回す覚悟を。
だがこれは、自分の生みの親でもあり、分身でもあるキョウジを巻き込みこんでしまう事も意味する。
(いいのだろうか)
シュバルツは躊躇いを覚える。
自分は良い。自分は、元々キョウジの『影』にして『忍者』 自分の成り立ち自体も特殊で、ある意味闇の世界に生きるしかない存在なのだから。
だけど、キョウジは違う。
キョウジは普通の人間で、デビルガンダムの呪いの様な物から奇跡的に解放されて、ようやく平穏な生活を手に入れた所なのだ。それを、自分のわがままで、再び闇の世界に引きずり込むような真似をする事は、果たして許される事なのだろうか。
わがまま。
そう、これは自分の我がままだ。
ハヤブサを手放したくない。
添い遂げたい。
そう願う、自分の全くの我がままだっだ。
いいのか。
本来ならば、ハヤブサに相応しいパートナーが現れた時点で、自分は、身を引かねばならない存在の筈なのに。
だが―――――
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
あのような状態になっても、まだ自分の名を呼び続け、手を伸ばし続けるハヤブサ。
お前が、そうやって私に手を伸ばし続けてくれるのであるならば――――
自分が、それから逃げてはいけないと思う。
同じように手を伸ばし、それに応えなければならないと、思うのだ。
そのためにも、キョウジの意見を聞きたい。
キョウジの気持ちを知りたい。
自分の『ココロ』は、間違った物なのだろうかと。
(キョウジ……!)
疾走するシュバルツの姿を、月明かりが優しく照らし出していた。
キョウジが大学から帰って来ると、部屋の中でシュバルツが待ち構えていた。
「シュバルツ、帰っていたのか」
キョウジの言葉に、シュバルツが「ああ」と答える。その様子に何かただならぬものを感じたのか、キョウジはデスクに座りカバンを置くと、すぐにシュバルツの方に向き直った。
「どうしたんだ? シュバルツ」
「えっ?」
「顔色がよくないな……。もしかしてハヤブサが、相当悪い事に巻き込まれているのか?」
「……………!」
キョウジの指摘に、シュバルツは本当に驚いてしまう。自分は、普通にしていたつもりだが――――そんなに、自分は分かりやすい表情をしていたのだろうか。だんだん自分のポーカーフェイスに自信が無くなってくるシュバルツに、キョウジは少し苦笑した。
「心配しなくても大丈夫だよ、シュバルツ。貴方のそんな僅かな変化に気づくのは、私ぐらいな物だから」
(もしかしたら、ハヤブサも気づくかもしれないけどね)
キョウジはそう思ったが、口には出さなかった。自分は、シュバルツの『製作者』―――――ある意味『親』の様な物だ。だから、子どもの僅かな変化にも、気づきたいと願っている。
「よかったら、話してくれないか? シュバルツ……。何か、私が力になれる事が、あるかもしれないし」
「キョウジ……」
シュバルツはしばらく、キョウジの方を見つめていたが、やがて何かをあきらめたように小さくため息を吐いた。
(キョウジには、本当に隠し事が出来ないな)
そう感じて苦笑する。
しかし、深い所で包み隠さず、本音で話す事が出来る相手がいると言うのは、シュバルツにとっては素直にありがたい事だった。
「分かった、キョウジ……。総てを話そう。お前に、判断を仰ぎたい事もあるし――――」
こうしてシュバルツは、キョウジに話し始めた。霧幻天神流の頭首、ハヤテの事。ハヤテとハヤブサの関係、そして、今ハヤブサが置かれている状況を――――
シュバルツが話している間、キョウジはじっと聞き続けていた。
そして、シュバルツの話が一段落した所で、おもむろに問いかけて来た。
「シュバルツは……どうしたいの? ハヤブサとの事を……」
いきなり核心に斬り込んでくるキョウジに、シュバルツは一瞬、返答する事を躊躇う。
だが、自分の持つ『答え』は既に決まっている。だから後は、一歩踏み出すだけだった。
自分の選んだ『答え』が、正しいのか間違っているのか、それは、分からないけれども。
「私は……ハヤブサに、手を差し伸べようと思っている……」
「―――――!」
キョウジが、少し驚く気配を感じ取りながら、シュバルツは言葉を続けた。
「あんな風になってもハヤブサが、私の名を呼び続けてくれているのなら―――――私は、それに応えなければならないと思うんだ」
「シュバルツ……!」
「勿論、道義的に問題がある状況なのは分かっている……。そして、本来ならば、自分が身を引かねばならない状況であることも」
「…………!」
そう。
ハヤテと自分。
『人間』と、歪な物で構成された『アンドロイド』
どちらがハヤブサの恋人に相応しいかなど、考えるまでも無く答えは出ている。
それでもハヤブサが、私を求め、その手を伸ばしていると言うのなら。
自分は、その手の受け皿になるべきだと思う。そうしなければ―――――きっともう、誰も前には進めない。その場に立ち止まり続けて、やがて、自滅してしまうだろう。
ハヤブサには、選択肢が用意されるべきだ。
そして、彼自身がそれを選びとるべきなのだ。
私と生きるのか。
それとも、ハヤテ殿と生きるのか。
その未来を――――
「それでも私は、望んでいる……。ハヤブサとの未来を」
「…………!」
「そう望んで手を差し伸べなければ―――――ハヤブサは、真の意味で選べないと、思うんだ……」
「シュバルツ……」
「だが、この道は修羅の道だ」
シュバルツは己が手を見つめながら、静かに言葉を紡ぎ続ける。
「ハヤブサがそう決断すれば、霧幻天神流の者たちを、完全に敵に回す事になる……。そうなれば、隼の里の者たちも、そして、キョウジ……お前も、二度と平穏な生活を望めないようになってしまうかもしれない……」
「………………」
「それでも……それでも、『ハヤブサと共に居たい』と――――そう願う、私の『ココロ』は……間違っているのか? キョウジ……!」
「シュバルツ……!」
瞬間キョウジは目を見開いたが、やがて、優しい笑みをその面に浮かべた。
シュバルツの『ココロ』の在りようが、『間違っている』とか『正しい』とかは、それは誰にも判断できない事だと思う。出来るとしたらそれは、人を超越した『神』と呼ばれる存在だけだろう。
だけど、たった一つだけ、自分にはっきり言える事がある。
それは、シュバルツが下した決断ならば―――――それがどのような物であれ、自分は全面的に支持する、と言う事だった。
シュバルツの事だ。熟慮に熟慮を重ねて、そこに至ったのだろう。
ならば、その決断を自分がどうこう言う必要はない。ただそれを、手助けしてやればいいのだと思った。それが自分の役割なのだと、キョウジは感じていた。
「『ココロ』に、正しいも間違いもない。だから、私はその判定をする事は出来ないけれど………貴方がそう判断を下したのならば、私はそれでいいと思うよ、シュバルツ」
「しかし、キョウジ……! 私は―――――」
シュバルツが何を言わんとしているのか、何となく察したキョウジは、シュバルツの唇を、己が指で優しく塞ぐ。それ以上言葉が紡げなくなって、怪訝な顔をするシュバルツに、キョウジは優しく微笑みかけた。
「貴方に、一つ言わせて」
「キョウジ……?」
「幸せになろうとする事を―――――躊躇ってはいけないよ、シュバルツ」
「……………!」
「私は、今も昔も変わらず願っている。貴方の『幸せ』を」
そう。
最初に『DG細胞』として、自分の前にそれが姿を現した時から、キョウジは願っていた。
突出し過ぎた特性を持つが故に、『役に立たない』と、廃棄されかかったそれを、キョウジが拾い上げた。自分の境遇と、この細胞の境遇が、何故かとても似ていると感じてしまったから、放っておけなかった。
人はこの細胞の事を『危険な細胞』だと言う。
何故だ?
優しい『ココロ』を向け続ければ――――ちゃんと、穏やかに優しく応えてくれるのに。
それを証明したくて、作り上げたアルティメット・ガンダム。しかしそこに襲いかかってきた悲劇。暴走してデビルガンダムと化してしまったガンダムは、辺り構わず破壊し、大量殺戮をし始めた。それを止めたい、弟を守りたい、と、キョウジの祈りにも似た思いが作りだしたモノこそが――――「シュバルツ」と言う存在だった。
自分の拾い上げたモノ。
作り上げたモノが、今度こそ幸せになって欲しいと願う。
これは、誰に何と言われようとも、譲れない想いだった。
「だからお願いだ、シュバルツ……。私を『枷』にして、自分の幸せを躊躇う様な事だけは、止めてくれ……。それは、私が最も望まない事だから」
「キョウジ……!」
「大丈夫だって、シュバルツ。私たちは独りじゃない。頼れる人たちがちゃんと居る。私が身を守る術などいくらでもあるし、どうとでもなる」
はっと息を飲むシュバルツに、キョウジはにこりと微笑んだ。
「だから貴方は、貴方の思うままに――――『想い』を遂げておいで」
「キョウジ……ッ!」
いつしかシュバルツの瞳から、大粒の涙が零れ落ちていた。
どうして
どうしてキョウジは――――
いつも、他人(ひと)の事ばかり
それに対してキョウジが答える。
『他人』じゃないだろう、シュバルツ
私たちは一蓮托生
運命共同体の様な物だ
だから、ある意味自分を優先している様なものだよ、と
でも
でも、キョウジは
キョウジの幸せは――――――
それは、前にも言った筈だよ
そう言って、キョウジは笑う。
『貴方の幸せが、私の幸せだ』と………。
幸せになる機会(チャンス)があるのなら
どうか、躊躇わないで
勇気を出して
「勇気………」
シュバルツは、己が手を再びじっと見つめた。
「そうだな……。私には今、確かに勇気が必要だ」
「シュバルツ」
キョウジがシュバルツに、手を差し伸べる。シュバルツがその手に己が手をそっと添えると、キョウジがぎゅっと握りかえしてきた。
「大丈夫……。恐れないで。貴方が貫こうとしている道を、迷わないで」
手から流れ込んでくるキョウジの『心』は、ただただ温かくて優しい。シュバルツは瞳を閉じて、それを感じ取っていた。
「貴方は、決して独りではない。どんな時でも、どんな事になろうとも―――――私は、貴方を支えるから」
キョウジの心は優しく、シュバルツのココロを包み込んでくれる。
いつも、いつでもキョウジの心は、確かに自分の力になる。勇気になる。
どうして――――こんなにも、彼の言葉に救われるのだろう。
「貴方のために、そして、ハヤブサのために………行っておいで」
ありがとう、キョウジ。
そう言い置いて、シュバルツはキョウジの前から姿を消した。
「あやね。居るか?」
夜半に、以前あやねと会った場所でシュバルツが呼びかけると、あやねはすぐに姿を現した。
「こちらの腹は決まった。済まないが、もう一度ハヤブサの所に手引きしてくれないか?」
「分かったわ」
あやねは軽く頷くと、すぐに言葉を続けた。
「手配に少し時間がかかるかもしれないが、出来次第声をかけるわ。だから、それまで待っていてくれる?」
それにシュバルツが「ああ」と頷く。それを確認してから、あやねはシュバルツの前から姿を消した。
(ハヤブサ……)
誰もいなくなった森の中で、シュバルツは独り、ハヤブサに想いを馳せる。
鎖につながれ、喘いでいたハヤブサ。こんな事を想ってしまっては不謹慎なのだろうが、その姿はとても妖艶だった。そして、素直に美しいと感じた。
知らなかった。
誰かに抱かれるハヤブサの姿が、あんなに綺麗だったなんて――――
そんな想い人の姿を見て、シュバルツも何かを感じたり、思ったりしない訳ではない。
だが―――――
(私がハヤブサを抱く……?)
そこに思い至ると、シュバルツは戸惑ってしまう。そんな事は許される筈もないと思った。自分の、呪われているも同然の物をハヤブサの中に流し込むなんて―――――それこそ『悪魔』の所業ではないか。
いくら自分と触れ合い、そして抱いても平気なハヤブサであると言っても、それとこれでは接触の仕方も浸食のレベルも、比べ物にならない様な気がした。やはり駄目だ。自分がハヤブサを、抱く事など出来ない。
(それに……)
鎖に縛られている状態を受け入れているハヤブサ。あの程度の鎖であるなら、彼が本気を出して逃げようと思えば逃げられるだろうに。彼が、あえてそれをしないと言う事は。
何かを人質として取られて、身動きの出来ない状態になっているのか。
それとも―――――
ハヤテを傷つけたくなくて、敢えてそれに縛られているのか。
もしも、ハヤブサの縛られている理由の中に、後者が色濃くあるのだとしたら。
彼は、私が手を差し出した所で、その手を取ることはないだろう。ハヤテと共にある事を選ぶ筈だ。
だとしたら、これはハヤブサの気持ちに踏ん切りをつけさせるための行為。
自分たちの関係に終止符を打つための、『儀式』の様な物になるのだ。
そういう意味でも『覚悟』を決めねばならぬとシュバルツは思った。
ハヤブサを、失ってしまう覚悟を――――
(きついな……)
彼の愛情を失ってしまうのは、正直辛い。
それでも。
それでも――――今、ハヤブサの二つに裂かれてしまっている心を、修復する事が出来るのなら。
彼のその後の人生が、幸せな物になるのなら。
自分が身を引く事など―――――容易い事だった。
大丈夫。
ハヤテは、ちゃんとハヤブサを愛している。
それを受け入れられれば、ハヤブサは充分幸せになれる筈だ。
恐れる事は何もない。
自分はただ――――ハヤブサの幸せだけを、願っているのだから。
ツキリと痛む自身のココロを宥めながら、シュバルツは独り、森の中に佇んでいた。
(あれから、幾日が過ぎただろう)
座敷牢の窓から差し込む僅かばかりの月明かりを眺めながら、龍の忍者はぼんやりと考えていた。大分夜も更けて来たが、ハヤテはこの部屋に姿を現さない。今宵のハヤテの来訪はもうないのだろうなと、ハヤブサは思った。
ハヤテはこの里の頭首として、大変忙しい毎日を送っている。自分を抱きに来るのは、まとまった時間が取れた時だけの様だった。
その時は、自分をがっつく様に求めてくるハヤテ。
(きっと、必要なのだろうな)
ハヤテの行為を受け入れながら、ハヤブサは漠然と考えていた。その気持ちは自分にも覚えがあったからだ。
自分がシュバルツを抱く時も、がっつく様に抱いていた。彼の中の光に触れたくて、その優しさが、確かに自分の方に向いているのか確かめたくて――――
それが故に、何度も抱いた。確かめるように、執拗に暴き立てた。
(しょうがない奴だな)
そう言って苦笑しながらも、優しく抱きしめてくれるシュバルツが、好きだった。
自分にとっての『シュバルツ』が、ハヤテにとっての『自分』に当たるのだろう。どうしてそうなるのかは理解に苦しむが、無下にはできないと思った。ハヤテは幼馴染で、自分にとっては大切な『友人』だったから。彼の役に立ちたいと願う自分の気持ちは、今も昔も変わらないのだから。
ならば、ハヤテの愛を素直に受け入れれば良いのにと思う。
だが、こんな時でさえ、自分が会いたいと願うのは、シュバルツ唯一人だった。
全身をハヤテに穢されている自分に、そんな資格などもう無い事は嫌と言うほど分かる。
だけど、こんな時だからこそ、自分が縋るのはシュバルツとの記憶だった。
シュバルツを愛し、愛された優しい記憶。
それが、壊れそうになる今の自分を支えていた。
シュバルツ。
シュバルツ。
(会いたい……!)
叶わないのは分かっている。
だがそれでも、ハヤブサは、月明かりの向こうに愛おしいヒトの姿を探してしまう。
声が聞きたい。
もう一度触れたい。
触れて欲しい。
そのうちなる優しい『光』で、もう一度俺を包んで欲しい。
分かっている。
叶わぬ願いだ。
それでもまだ
尚もそれが欲しいと足掻き続けている、俺はいったい何なのだろうか。
「……シュバルツ………」
闇に落ちて行くしかないと分かっているその言葉を、ハヤブサは呟く。帰って来るのは、沈黙ばかりの筈であった。
だがしかし、その日の夜は、少し違った。
「………ハヤブサ……」
「――――――!!」
聞こえる筈の無い声が聞こえて、ハヤブサは思わず跳ね起きてしまう。
「シュバルツ……?」
闇の中、懸命に目を凝らすが、そこには、闇ばかりしか見えない。
(幻聴か……)
この手の幻聴はある意味聞き慣れた物でもあったので、僅かばかりの失望感と共に、頭を垂れる。だが、その『幻聴』は、さらに続いた。
「ハヤブサ………」
「シュバルツ!?」
まさか、と、顔を上げるハヤブサの目の前に、優しく差しこんでくる月の光。
「……………!」
その月明かりの下に、夢にまで見た愛おしいヒトの姿があったから――――
「シュバルツ……!」
無我夢中で手を伸ばそうとするハヤブサの手首から垂れ下がった鎖が、『じゃらり』と音を立てる。それが、ハヤブサを一瞬にして現実に引き戻した。
「ハ……。俺も焼きが回ったな……。こんな所にシュバルツがいる筈ないだろう……」
胸をかきむしられる程愛おしい幻影を見つめながら、ハヤブサはため息を吐く。すると、今度はその『幻影』が苦笑しだした。
「勝手にヒトを幻にするな。ちゃんと、私はここに居るよ」
「―――――!!」
はっ、と、息を飲みながら顔を上げるハヤブサに、シュバルツはにこりと微笑みかける。
「シュバルツ……!? 本当に……!?」
震える声で問いかける自分に、シュバルツは「ああ」と頷き返してくれる。
「ああ………!」
会いたかった。
会いたかった。
もう一度手を伸ばそうとして―――――自分の今の状態を、ハヤブサは思い出してしまう。
鎖につながれ、全身をハヤテに穢されてしまっている自分は、彼を裏切っているも同然だ。シュバルツに触れる資格などありはしない―――――そう思った龍の忍者は、硬い表情をして、その手を下におろしてしまった。
「ハヤブサ……」
ハヤブサの事情を知り、何となくその気持ちを察したシュバルツの瞳が、哀しみゆえに曇る。
(構わないのに)
ハヤブサがどんな状態であろうと、自分がハヤブサを愛している事に変わりは無い。だから、シュバルツはその一歩を踏み出す事を、躊躇わなかった。スッと静かに進んでくるシュバルツの足。ハヤブサは思わずそれから逃れようとして、後ずさろうとする。だが自分が動こうとするたびに、『じゃらり』と音を立てる鎖。その音が、ハヤブサを暗澹たる気持ちに落とし入れ、その音を聞きたくないが故に、彼はその場で身を固くして、小さくうずくまることしか出来なかった。
「……………」
シュバルツが、すぐ近くで座る気配がする。
「……触れても、良いか……?」
優しく問うてくる声。だがハヤブサは、それに小さく首を横に振った。
「シュバルツ……」
その名を口にした瞬間、ハヤブサは人目もはばからずに泣き出してしまいたくなる衝動にかられる。だが、懸命に堪えた。いつ、ハヤテがこの部屋にやって来るかも分からぬこの状況。シュバルツの身を、危険にさらす訳にはいかないと思った。
「せっかく来てくれたのに悪いが……どうか、このまま帰ってくれ……」
「ハヤブサ……!」
「俺は良い。それよりも、ハヤテがいつ来るかも分からないんだ。だからどうか、このまま―――――」
「ハヤテ殿は、今宵里にはいない……」
「―――――!!」
驚いて顔を上げるハヤブサに、シュバルツは静かに頷いた。
「……ここに、手引きをしてくれた者が居るんだ。今、部屋の外を見張ってくれている」
部屋の外ではあやねが、油断なく辺りを見回しながら立っていた。
そして、『ハヤテの屋敷を警護する』と言う理由で、あやねの息のかかったくのいちたちの一隊が、この屋敷を囲んでいた。
「今は詳しくは言えないが、その人が、私がもう一度この里から出るまでの間、私の安全を保障してくれると言った。私は、その言葉を信用できると思う」
「本当に……?」
茫然と呟くハヤブサに、シュバルツは頷いた。
「だから、ハヤブサ……」
シュバルツがもう一度、手を伸ばしてきた。
「……触れても、良いか……?」
「―――――!」
ハヤブサが身を引こうとするよりも早く、シュバルツの手が、ハヤブサの頬に触れて来た。
「シュバルツ……!」
頬に触れてくるシュバルツの手は、ただ、優しい。ハヤブサは、堪えに堪えていた物が、ついに、溢れだして来てしまった。
「シュバルツ……ッ! シュバルツッ!!」
叫びながらハヤブサは、シュバルツの胸に飛び込む。その身体に縋りつくと、シュバルツも優しく抱きしめ返してくれた。
「あ………! あ…………!」
後から後から溢れてくる涙。ハヤブサは、それが流れるままに号泣した。
懐かしい匂いがした。
優しい感触に包まれた。
自分は――――ずっとこうしたかったのだと、気づく。
ああ―――――
やはり、死ぬほど
愛おしい――――――
そうして、どれぐらい泣き続けた事だろう。
少しずつ落ち着きを取り戻してきた自分に、シュバルツが優しく声をかけて来てくれた。
「……落ち着いたか……?」
「ああ………」
優しく温かいシュバルツの胸。
ずっと、ここでこうして居たいと、願う。
だけど、もう自分には、そんな資格など無い、と言う事を、ハヤブサは分かり過ぎるほど分かっていた。だからハヤブサは、シュバルツの腕の中からそっと、抜け出した。
「ありがとう……シュバルツ……。会えて、嬉しかった……」
「ハヤブサ……」
もう充分だ。
だから、ここから出て行ってくれ――――と、ハヤブサが言うより先に、シュバルツが口を開いた。
「私の質問に、答えてくれハヤブサ」
「質問?」
少し小首を傾げるハヤブサに、シュバルツが頷いた。
「ああ……。だいたいの事情は、協力してくれている人から聞いたが――――私は、お前の口からはっきりと聞きたい」
はっ、と、表情を強張らせるハヤブサに、シュバルツからの質問は続いた。
「お前は………ハヤテ殿に、抱かれているのか?」
「―――――!」
いきなり核心を突いてくる質問。
ハヤブサは少し躊躇ったが、頷くしかないと悟った。
「ああ……。そうだ………」
ここに捕らえられてからずっと、自分はハヤテに抱かれ続けている。今の自分の身体は、頭の先から足の先まで、ハヤテの刻印が刻まれているも同然だった。
そうか、と、小さく返事をしたシュバルツが、再び口を開いた。
「ではハヤブサ……。この鎖――――」
そう言いながらシュバルツが、自分を繋いでいる鎖の一つを、じゃらりと音をさせながら手に取る。
「お前の力量なら、この程度の鎖、断ち切れぬ事はないだろう。それを、敢えてしていないのは、何故だ?」
「――――――!」
これにはハヤブサも、本当に絶句するしかない。
確かにそうだ。この程度の鎖なら、自分は、簡単に断ち切ることができる。だが敢えて、ハヤブサはそれをしていなかった。
その理由は―――――
「隼の里か……? それとも、『キョウジ』か………?」
「……………ッ!」
シュバルツの鋭すぎる指摘に、ハヤブサは言うべき言葉を失ってしまう。
どうして
どうして、この愛おしいヒトは
自分の総てを、こうもあっさり見抜いてしまうのだろう。
「やはり、そうか……」
ハヤブサから返事が返って来ない事で、シュバルツは更に確信を深めた。
やはりハヤブサの繋がれている理由の一つに、『人質』は確かにある。
(だが、それだけじゃないだろう……? お前が繋がれている理由は……)
今からそれを、自分は確かめねばならぬとシュバルツは思った。そうしなければ、ここからハヤブサを連れ出すことも、自分が身を引くこともできない。前に進むためにも、ハヤブサが鎖に繋がれる事を選択している『真の理由』と、向き合わねばならぬのだ。
その上で、ハヤブサは選ぶべきと思った。
自分と生きるのか。
それとも、ハヤテと生きるのか。
その未来を―――――
例え、ハヤブサがどのような未来を選ぼうとも、幸せになって欲しい。
自分の願いは、それしかないのだ。
そう思うと―――――ココロが少し、軽くなった気がした。
シュバルツは覚悟を決めると、一つ大きく息をした。
待っていろ、ハヤブサ。
今―――――お前を縛る『人質』と言う鎖を、断ち切ってやる。
シュバルツが背中に背負っていた刀を持ち替えて、居合抜きの構えをする。
(斬られる……?)
ハヤブサは漠然と思ったが、何故か恐怖は感じなかった。
斬られるのなら、それで良かった。
寧ろ、愛おしいヒトに引導を渡されるのなら―――――
それはきっと、本望だった。
「動くなよ」
静かな声音と共に、刀を構えるシュバルツの身体から、『気』が発散され、高まっていく。
ハヤブサは静かに目を閉じた。
(そのまま、俺を斬って欲しい)
そう願いながら―――――
抜き手は一瞬だった。
もしも傍に人がいたとしても、その刀身のきらめきを見る事が出来た者は一握りしかいなかったであろう。刀は目的を果たし、もうその鞘に戻っていた。
パチン、と、刀を収める音がすると同時に、ハヤブサを拘束していた手首、足首、そして首に取りつけられていた鉄の環がそれぞれ真っ二つになり、その役目を終えていた。
「……………!」
久しぶりに鎖から解放され、軽くなった己の身体にしばし呆然としているハヤブサに、シュバルツが声をかけてくる。
「――――キョウジからの伝言を伝える」
「―――――!」
はっと顔を上げるハヤブサに、シュバルツの真っ直ぐな視線がぶつかる。
「キョウジは言った……。『私を枷にするな』と」
「…………!」
「もしも、キョウジを守るためにお前が犠牲になっていると言うのなら……それは、止めて欲しい。それはキョウジも、そして私も――――最も、望まない事だから」
「シュバルツ……」
茫然と見つめてくるハヤブサに、シュバルツはにこりと微笑みかけた。
「あまり、私たちを見くびるな。ハヤブサ! 私たちは、決して孤立無援な訳じゃない。ちゃんと、頼れる仲間がいる。お前も含めて……」
「あ………!」
「隼の里の者たちだってそうだ……。皆、お前の事を案じていた。お前一人を犠牲にする事を、彼らは決して望まないだろう。お前を支えたいと……そう願っているはずだ」
「……………っ」
「だから、ハヤブサ………」
シュバルツはすっと、己が手をハヤブサに差し出した。
「もし……お前が『人質』と言う枷だけに縛られているのなら、私はお前のその手を取ろう。案ずる事は何も無い。私は、お前を全力で支える。今までお前が、そうして来てくれたように――――」
「シュバルツ……!」
ハヤブサはただ茫然と、シュバルツが差し出してきた手を見つめていた。
夢の様だった。
シュバルツから、こんな風に言ってもらえるだなんて――――
自分がこんな状態になっても、彼からの優しさ、愛情に、何一つ変わる物はないのだと思うと、余計に感極まる物があった。
(手を、取りたい)
ハヤブサは願う。
シュバルツの手を取りたい。
彼と共に生きたい。彼となら――――人生のどんな試練だろうと、乗り越えて行けるだろう。
鎖から解き放たれ、自由になったハヤブサの手が、ピクリと動く。
だが―――――
(好きだ……! 愛している、リュウ………!)
切羽詰まった声で囁きかけてくるハヤテの声。
(好きだった……! 子どものころからずっと―――――!)
(ハヤテ………!)
子どもの時から、自分に対する想いを秘め続けていたハヤテ。それに今まで全く気付く事の出来なかった自分は、どれだけハヤテの心を踏みにじり続けていたのか分からない。
それに対する詫びすら、自分はハヤテにできていないと言うのに。
今――――シュバルツの手を取ることは、そんなハヤテと完全に決別してしまう事を意味した。自分の愛する者、大切な者たちを守るために、ハヤテに刃を向けなければならなくなるのだ。
(ハヤテに刃を向ける………?)
ハヤブサはそれを想像しようとして、それが酷く困難なことであると気づくのに、そう時間はかからなかった。
幼いころから共に修業し、支え合い、お互いを高めあってきたハヤテ。
彼は自分の大事な戦友であり――――そして、『親友』でもあった。
やはり駄目だ。
俺は――――――
そんなハヤテに、刃を向けられない。
「……………ッ!」
僅かに持ちあがり、震えていたハヤブサの手。
その手は確かに、シュバルツの方に向かおうとしていた。だが彼は、それを途中で下ろしてしまった。
「シュバルツ……」
うつむくハヤブサの瞳から、涙がパタっ、パタっ、ときらきらと光りながら零れ落ちていった。それはひどく美しくて、そして哀しい涙だと、シュバルツは思った。
「シュバルツ……! 済まない……! 俺は………ッ!」
「ハヤブサ……」
顔を上げた龍の忍者は、シュバルツをまっすぐ見つめながら決然と言った。
「俺は……! ハヤテを裏切れない………ッ!」
「――――――!」
ある意味、覚悟していたハヤブサの言葉。
それなのに、こちらの『ココロ』が軋んで、悲鳴を上げるのは何故だろう。
少し、天を仰ぐシュバルツに、ハヤブサの言葉はなおも続いた。
「裏切れない……ッ! 裏切ることが、出来ないんだ………ッ!」
そのままぽろぽろと、大粒の涙を零し続けるハヤブサ。
「そうか………」
シュバルツは、それ以外に言うべき言葉が無かった。
ハヤブサがハヤテへの気持ちを大事にしたいと言うのなら、自分は、それに口を出す権利など無い。その気持ちを、尊重するだけだった。
彼は、大量に血が流れない道を選んだのだ。
ある意味、ハヤブサらしいと思った。
彼は元々人斬りなど好まぬ、心優しい性格であるのだから。
それにしても――――
シュバルツの『ココロ』は、軋み続ける。
自分は結局、ハヤブサに『振られた』ことに、なるのだろうか。
(でも、それで良いんだ)
シュバルツは懸命に、無理やりにでも自分にそう言い聞かせ続けた。
やっと、彼をDG細胞の脅威から、闇から、解放する事が出来たのだから。
ハヤブサは、ハヤテに愛されて、幸せになることができるだろう。
幸せになって欲しい――――
そう、願う。
「分かった……」
シュバルツの面に、笑みが浮かぶ。
だがハヤブサには、それが泣いている表情であると分かった。
酷く傷ついているのに。
泣き叫んでいるのに。
こちらに心配かけさせまいと、無理やりにでも面に笑みを浮かべる事が出来る。
そんな表情をさせたくなくて
そんな彼を抱きしめたくて
自分は、彼の手を取ったと言うのに――――
結局自分もまた、彼にそんな表情をさせてしまう事になった。
どうして
何故――――
何をやっているのだろう、俺は。
シュバルツ
シュバルツ
今すぐにでも、抱きしめたいのに――――
それは、許されざる事だとハヤブサは悟っていた。
もう、この手は、彼に触れる事が出来ない。
自分は、『ハヤテと生きる』と、そう決めてしまったのだから。
「泣くな……」
優しく、声をかけられる。
それにハヤブサは、頭をふった。
無理だ。シュバルツ。
この涙を止める方法なんて―――――
俺は、知らない。
「ハヤブサ……。幸せに、なってくれ……」
「……………!」
ハヤブサは、瞬間目を見開いた後、「ああ」と、頷いた。
その時、ハヤブサの面には、穏やかな微笑が浮かんでいた。
(『幸せ』になることなど無理だ)
ハヤブサは思う。
自分の『幸せ』は―――――シュバルツ、お前と共に在ることでしかないのに。
自分の心はもう、闇に沈んで行くしかないのだと言う事を、ハヤブサは知っていた。
それでも、シュバルツに対して微笑みかける事が出来たのは、彼に心配をかけさせたくない一心であった。自分に対して、彼に未練を残させたくない一心であった。
済まない、シュバルツ。
俺は、お前の手を取り続けるつもりでいたのに。
お前と一生、添い遂げるつもりでいたのに――――
俺は、お前を裏切ったんだ。
お前の手を振り払い、別の男の手を取ったんだ。
お前の方こそ、こんな薄情な男の事など早く忘れて―――――
どうか、幸せになってくれ。
「ハヤブサ……」
ハヤブサがあまりにも綺麗に笑うから、シュバルツの心もまた、かき乱された。
自分が、彼をどれだけ好きか。
自分が、彼にどれだけ支えられてきたか―――――
嫌でも、突きつけられてしまう。
涙が、堪えられなかった。
想いが、溢れた。
済まない、ハヤブサ。
これが最後だから―――――
「ハヤブサ……ッ!」
自身の中の愛おしさが命じるままに、彼は行動していた。
シュバルツはハヤブサの懐に飛び込むと、その唇を奪っていた。
「んう………! ん………!」
瞬間驚いて、固まるハヤブサだが―――――すぐに目を閉じて、それを受け入れていた。
シュバルツが挿し入れてくる舌を絡め取り、夢中で吸い合う。
ああ
やはり
誰よりも愛おしい、大切なヒト。
そのキスは、涙の味がした。
「………………」
キスを終え、離れたシュバルツは、笑顔だった。
そして、涙を流していた。
「元気で………」
光る物を飛び散らせながら、彼は自分の前から踵を返し、そして、姿を消した。
「シュバルツ……ッ! あ………! あ………!」
ハヤブサは声も涙も、最早抑えることなく号泣していた。
好きだった。
どれだけ、愛していたか。
どれだけ、彼が大切だったか―――――
でも、もう鎖を解かれても、一歩も動けなかった自分。
それが総てだった。
それが答えだった。
ハヤテを踏みにじってまで――――自分は、幸せにはなれないのだ。
どうして
どうしてこんな事になってしまったのだろう。
幼馴染を傷つけ続け
大切なヒトを、裏切って泣かせて―――――
自分は、いったい何のために存在しているのだろう。
誰かもういっそ、俺を殺してくれ。
要らない。
こんな自分など。
大切なヒトを傷つける事しか出来ないと、そう言うのであるのならば
消えてしまえばいい。
呪われてしまえばいい。
こんな自分などもう要らない。
要らないんだ。
「リュウ様……」
そこに、おずおずと声をかけてくる者がいた。ハヤブサが顔を上げると、あやねの姿がそこに在った。
「あやね……」
「リュウ様、大丈夫ですか……?」
あやねが案じる様に問いかけてきながら、自分の傍に腰を下ろす。それを見て、シュバルツをここに連れて来てくれたのは彼女なのだと、ハヤブサは悟った。
「お前が、手配してくれたのか……」
ハヤブサの言葉にあやねは頷く。
「ええ、リュウ様……。でも――――」
ただ、あやねは戸惑ってもいた。自分は、てっきりシュバルツの差し出した手に、ハヤブサはついて行くと思っていたからだ。
なのに――――
まさか彼らの方が、ハヤテのために、自分たちの想いを封じ込める選択をするとは。
ハヤテの一の部下として、ハヤテを想う者として、ハヤテを大切に想ってくれた彼らの気持ちは、ある意味嬉しい。
でも―――――どうしても考えてしまう。
本当に、これで良かったのだろうか?
これは本当に、ハヤテのためになったのだろうか?
「案ずるな、あやね……」
表情を曇らせるあやねに、ハヤブサは優しく言った。
「多分、これで良いんだ……」
「リュウ様……」
笑顔なのに、まるで泣いているように見えるハヤブサの表情に、あやねの胸も締め付けられる。きっと、これで良い筈など無い。良い筈など無いのだ。
だが、彼女は為すべき事があったがために、グッと歯を食いしばった。ここに『侵入者』があった事を、ハヤテに悟られてはならないのだ。
だから彼女は顔を上げて、再びハヤブサに声をかけた。
「リュウ様、お辛いでしょうが、もう一度鎖にお繋ぎいたします」
そう言ってあやねがハヤブサの手を取ろうとする。ハヤブサの鎖を解く事を、ハヤテはまだ許可していないのだ。それなのに鎖から解かれたハヤブサの姿を見てしまったら、ハヤテがハヤブサやこの牢番の者たちに、どんな制裁を課すか分からない。しかし、ハヤブサは首を横に振って、それを拒否した。
「良い。鎖は不要だ。あやね」
「で、でも……! それでは、リュウ様が――――!」
ハヤブサの身を案じるあやねに、ハヤブサは静かに笑顔を見せた。
「大丈夫だ。もし、鎖を解いたことで受けるペナルティがあると言うのなら……それは俺が受ければ良いだけの話だから……」
「で、でも………!」
尚も戸惑い続けるあやねに、ハヤブサの言葉はなおも続いた。
「それに、ここに侵入者があった事を、完全にハヤテから隠すことは不可能だ……」
「……えっ……?」
「あいつの事だ。部屋のあちこちに、俺たちにも分からないような仕掛けを施してあるに違いないんだ。それを見て、この部屋に侵入者があった事を、あっという間に見抜いてしまうだろう」
「そ、そんな……!」
「だからこういう事は……下手に隠し立てしない方が良いんだ。このままハヤテに会って、あったままの事実を、話してみようと思っている……」
「リュウ様……!」
「勿論、手引きしてくれた者たちの事は絶対に言わない……。ありがとう、あやね……。ハヤテや、俺の事を案じてくれて……」
「…………!」
ハヤブサのこの言葉に、あやねは、自分がもう出来る事は何も無いのだと悟った。
でも。
でも本当に、これで良かったのだろうか?
何か―――――救いようのない、大きなひずみを生みだしてしまった様な気がする。
何とかしてあげたい。
だけど、自分ではもうどうする事も出来ない。
あやねは、酷く後ろ髪を引かれる想いで、部屋から出て行った。
彼女が部屋から出て行った後、ハヤブサは布団の上に座りなおして正座をした。
そして――――そのまま、ハヤテが帰って来る事を、ひたすら待ち続けた。
夜半。
『仕事』を終えて帰ってきたハヤテは、いつものようにハヤブサがいる座敷牢に向かう。
そして――――そこに居たハヤブサの姿を見て、絶句していた。
「リュウ……!? お前………!」
何故なら、ハヤブサを繋いでいた筈の鎖が、全部断ち切られてしまっていたから。それなのに、逃げるどころか部屋の真ん中で正座をしているハヤブサの姿に、酷く戸惑ってしまう。
「…………」
ハヤブサは、しばらくそんなハヤテをじっと見つめていたが、やがて黙って三つ指をついて頭を下げた。
「リュウ? これは一体、どう言う事だ?」
ハヤブサが頭を上げるのを待ってから、ハヤテは声をかける。
「鎖はどうした!? 一体何が――――」
「シュバルツが来た」
「―――――!」
ハヤテが話し終わらぬうちに、ハヤブサがそう口を開く。
「シュバルツがここに来て、俺の鎖を断ち切ったんだ。……どうか、ここの牢番の者たちを責めないでやって欲しい。あいつもまた、腕利きの忍者だ。ここに忍び込む事など、あいつにとってはそう難しい事でもないのだから――――」
そう言いながら、ハヤブサはハヤテの前に、己を繋いでいた鎖を差し出す。首の所を繋いでいた鉄輪が、見事に真っ二つになっていた。
「……………!」
その剣の腕に、ハヤテもまた驚嘆せざるを得ない。余程の腕が無ければ、このような事など出来る筈もないのだから。ハヤテが茫然としている間にも、ハヤブサの言葉は続いていた。
「シュバルツは俺の鎖を断ち切って………共に逃げようと、手を差し出してきたんだ」
「な…………!」
ハヤブサは、シュバルツを愛していた筈だ。
自分に抱かれている最中にも、その名を呼んでしまう程に――――彼を、愛していた筈だった。
それでは何故だ?
それほど恋い慕う人から、手を差し伸べられたのなら――――
「………お前は……何故、ここに居るんだ?」
そのハヤテの質問に、ハヤブサはひどく穏やかな笑みを浮かべた。
「俺は……その手を、取らなかったんだ……」
「リュウ……!」
「俺が決めたんだ……。自分の意志で、『ここに残る』と………」
「……………!」
ハヤテは、半ば夢見心地でハヤブサの言葉を聞き続けていた。
信じられなかった。
本当に、ハヤブサは
自分の意志で、あいつよりも俺を選ぶと――――
そう、言ったのか?
「だからお願いだ、ハヤテ……。ここに侵入者を赦した件、俺の鎖が断ち切られた件で、牢番や他の者たちに制裁を科すことは止めてくれ……。もし、この件で何らかの『罰』が必要だと言うのなら、それは俺が――――」
話している最中のハヤブサの頬に、ハヤテの手が触れてくる。
「リュウ……! 本当に……?」
「えっ?」
「本当にお前は………『あいつよりも俺を選ぶ』と……そう、言ってくれたのか……?」
「…………!」
瞬間、ハヤブサの瞳が見開かれる。
脳裏に、愛おしいヒトの影がちらつく。
だが、もう後には引けない状況であることを、ハヤブサは理解していた。
決めたのだ。
自分はもう
ハヤテのためだけに生きると。
「ああ……。俺は………」
頬に触れる手を意識しながら、ハヤテの瞳をまっすぐ見つめながら、ハヤブサは応える。
「決めたんだ……。お前と共に、生きると……。『ハヤテ』……!」
ハヤテの名を口にするたび、ハヤブサの心がズキリ、と、音を立てて軋んだ。
何故なら――――その名を口にするたびに、ハヤブサは、心の中で愛おしいヒトの影に、刃をつき立て続けていたから。
それは、まさしく自分の半身を殺す行為だった。
それは、自分の心を殺し続ける行為にも似ていた。
絶望に染まるハヤブサの瞳から、涙が零れ落ちていく。その涙を――――ハヤテの手が、優しく掬い取っていた。
「リュウ……!」
対してハヤテは、歓喜に震え続けていた。
幼いころから大事に想い続けていた人が
やっと―――――この手に、落ちて来てくれたのだから。
「ああ……! リュウ……!」
愛おしさが抑えられないハヤテは、そのままハヤブサの唇を奪う。
「ん………っ!」
消えていく。
かき消されていく。
シュバルツの唇の感触が――――
(思い出すな……!)
ハヤブサは懸命に自分に言い聞かせ続ける。
彼の手を振り払った俺に、彼を想い続ける資格など無い。
消せ。
消すんだ。
もう二度と、思い出せないように―――――
その想いとは裏腹に、心は悲鳴を上げる。
忘れるのは嫌だと、拒絶する。
この声は聞かない。
悲鳴は黙殺する。
愛おしいヒトの影には、刃をつき立て続ける。
死んでしまえば良い。
早く
早く―――――
「愛している……。リュウ……」
ハヤブサを押し倒したハヤテが、彼の肌を暴き立て始めた。
「ああ……っ! あ………!」
甘やかな声を上げるハヤブサが、初めてハヤテの身体に、縋る様に触れて来た。
「リュウ……!」
その手を、自分に掴まらせるように、ハヤテはその背へと導く。
深く唇を奪いながら、ハヤブサを貫くと、彼はくぐもった悲鳴を上げながら、自分の身体に抱きついて来た。律動を深めるごとに、彼の縋りつく力も強くなる。
「ああっ!! ハヤテッ!! ハヤテぇ!!」
彼の嬌声の中に、『シュバルツ』の名が混じることはなかった。ハヤテは、ついにハヤブサが、心も身体も、自分を受け入れてくれたのだと悟った。
「愛している……! リュウ……!」
「ハヤテ……! ああ………!」
腹の下でぽろぽろと涙を落とすハヤブサが、限りなく愛おしい。
「泣くな……」
涙を掬い取る唇を、ハヤブサは瞳を閉じて受け入れていた。
それは、ハヤテにとっては夢の様なひと時だった。
自分を受け入れてくれたハヤブサを、無我夢中で貪っていた。
そして、夜が明けると同時に、ハヤテはハヤブサを、座敷牢から出していた。
もう、彼を縛るための鎖は必要ない――――そう感じたが故の、処置であった。
久しぶりに部屋の外に出たハヤブサは、庭で一つ大きく伸びをした。
「……済まなかったな、リュウ……」
そんなハヤブサの横で、ハヤテが少しばつが悪そうに口を開く。
「ん?」
「その……お前を長い事、閉じ込めてしまって……」
「ああ………」
ハヤブサは、少し相槌を打った後、その面にふわりと笑みを浮かべた。
「俺は、気にしてはいない。だから、お前も気にするな」
体調はどうだと問うハヤテに、ハヤブサは問題ない、と、多少ぶっきらぼうに答えた。
ただハヤブサは、ポツリと小さく言った。
「……日差しが、眩しいな……」
それが、久方ぶりに朝日を浴びた、龍の忍者の言葉であった。
第4章
「兄さん、シュバルツは?」
キョウジのアパートを訪ねて来たドモンが、書斎に居たキョウジを見つけてから、そう声をかけた。手には、彼が格闘大会で勝ち得た、大きな優勝トロフィーが握られている。
「ああ……今日は『所用がある』とかで、朝から出かけているよ」
「ええ~~~~!?」
ドモンは小さく不満げな声を漏らすと、残念そうに優勝トロフィーを見つめていた。
「残念だな……。せっかく兄さんやシュバルツに、このトロフィーを見てもらおうと思っていたのに」
「シュバルツと二人で、テレビで見ていたよ。よく頑張ったな、ドモン」
キョウジの言葉にドモンは少し照れくさそうに笑みを浮かべる。
「じゃあさ、兄さん!」
「何だ? ドモン」
「シュバルツが帰って来るまで、俺ここで待っていていい? 戦いの講評を聞きたいし、また修業をつけてもらいたいしさ!」
「う~~~~ん………」
ドモンのその言葉に、キョウジは少し難しい顔をする。
「待っていても構わないが、おそらく今日は帰って来ないぞ?」
「えっ? 何で?」
きょとん、とするドモンに、キョウジは少し苦笑しながら答えた。
「今日は――――シュバルツにとっては『特別な日』だから」
そう。『特別な日』
シュバルツにとっては『特別な日』
それは、週に一度、ハヤブサと会うと決めていた―――――『逢瀬の日』であった。
(あれから、もう半年か……)
シュバルツはいつもの木の所に凭れかかりながら、独り、いつものように待ち続けていた。
分かっている。
待ち人は来ない。
半年前に、その手は取れないと、はっきりと振られていた。
それを百も承知で、それでもシュバルツは、独り佇み続けていた。
天神流の里から帰ってから、キョウジには事のあらましを報告していた。
「そうか……」
静かに話を聞き続けていたキョウジだが、やがてポツリと口を開いた。
「ハヤブサらしいね………」
そうだな、と、シュバルツが答えた所で、彼の感情が堰を切って溢れた。デスクの椅子に座るキョウジの膝に縋りついて、大泣きに泣いた。
そんな自分を、キョウジは何も言わず、ただ優しく髪を撫で続けてくれていた。
「ねえ、シュバルツ。私たちは祈ろう」
少し落ち着いてきたシュバルツに、キョウジがポツリと声をかける。
「ただ、ハヤブサの幸せを………」
「そうだな……」
涙を拭いつつ、シュバルツも頷いた。
「本当に……その通りだ……」
それからは、本当にいつも通りの日常が過ぎて行った。ただ、ハヤブサに会えない事を除いて―――――
穏やかな日常を過ごさせてくれる、キョウジの配慮は素直にありがたかった。
だが、日常が穏やかであればある程―――――失った物の空洞は、心に突き刺さって来るのも事実だ。だからシュバルツは、週に一度ここに来て、その空洞に浸りきることにしていた。
よく哀しみも苦しみも日にち薬だと言われるが、今、この胸に抱えている物は、どんなに日にちが経った所で癒せる物ではない、と言う事を、シュバルツはうすうす気づき始めていた。
当たり前だ。
ハヤブサは全身全霊で、自分を愛してくれていた。そして、支えてくれていた。
失った物は、決して小さい物ではないのだ。
(ハヤブサ……今、お前は幸せか……?)
シュバルツにとって、最大の気がかりは、まさにそれであった。
ハヤブサと別れてから実は一度だけ、シュバルツはハヤブサからの手紙を読んでいた。
と、言っても、ハヤブサからシュバルツに宛てられた物ではない。彼から、里に向けて書かれた手紙を、与助が血相を変えて持って来たのだ。
「シュバルツさん!? どう言う事ですか!? リュウさんと『断交状態』って……!」
天神流の里にハヤブサが滞在するようになってから1カ月目に、そんな手紙が隼の里に届いていた。それには、天神流の里の滞在が長引きそうだと言う事と、シュバルツとは今、断交状態にあるから、皆もそう心置く様に――――と、言った事が書かれていた。
「ああ、本当だ」
それにシュバルツは、極力穏やかに答えた。それは事実だし、自分たちの間では、もう話し合いは済んでいる事であったからだ。
「な、何かリュウさんの方が、失礼な事をしたのでしょうか……! まさかと思いますが、リュウさんが浮気したとか―――――」
「そんなんじゃない」
シュバルツは苦笑しながら、それに返事をした。
「ハヤブサはそんな事をする奴じゃない。これには、深い事情があるんだ。私たちは、お互いに話し合って納得して、そうなっているのだから……」
「……………!」
シュバルツの言葉を、与助はただ茫然と聞くしかなかった。しかし、俄かには信じられなかった。ハヤブサもシュバルツも、互いをこれ以上無いと言うほど愛し合っていると、与助の眼にも映っていたからだ。
それを、こんなにあっさり――――『断交』など出来るものだろうか?
「ハヤブサの手紙……」
シュバルツからの言葉に、与助ははっと我に帰る。
「見せてもらってもいいか?」
「えっ? ああ、どうぞ……!」
少し戸惑いながらも、特に反対する理由も無かったので、与助はシュバルツに手紙を渡した。その瞬間、シュバルツが一瞬顔をしかめたように見えたから、与助は思わず「大丈夫ですか?」と、問いかけてしまう。
それにシュバルツは「ああ。大丈夫だ」と、答えてから、ハヤブサの手紙を読みだした。
筆跡は確かにハヤブサの物で、文章も自分と断交していると言う件以外は、至って普通の内容の物だ。
ただ―――――
「済まなかったな。ありがとう」
シュバルツから手紙を受け取りながら、与助は改めてシュバルツに問いかけていた。
「シュバルツさん……! 本当に『断交』なんてしてしまわないですよね!? これは、一時的な物ですよね……?」
与助の問いに、シュバルツは穏やかな笑みを浮かべる。
「それは分からない……。ただ、私とハヤブサは、互いを憎み合ったり、いがみ合ったりして別れた訳じゃないんだ……。だから――――」
モシモ、ハヤブサノ方カラ助ケヲ求メラレレバ私ハ―――――
そう言いかけて、シュバルツははっと思いとどまる。
今のハヤブサの傍には、彼を愛しているハヤテ殿がいるのだ。
そこに私が介入する余地などある筈も無く、私がハヤブサの傍に行った所で、迷惑にしかならないだろう。そして、ハヤブサの方から助けを求めてくることも、おそらく、あり得ない。
「……とにかく、私の方は心配いらないと、ハヤブサに会う機会があれば、そう伝えておいてくれ」
「シュバルツさん……!」
穏やかにそう返事してくるシュバルツに、与助も、これ以上何も言えなくなってしまっていた。
(ハヤブサ……)
あの手紙を手に取った瞬間の感覚を、今でもシュバルツは鮮明に思い出す事が出来る。
鈍い痛みが、手に走った。
突き刺さるような哀しみが――――心を打った。
手紙には、書かれた文字には、その書いた主の『ココロ』が宿る。
少なくとも、里への手紙を書いていた時のハヤブサの心境は―――――辛苦に満ちていた、と言う事だ。
(ハヤブサ……。どうしてそんな気持ちを抱えて手紙を……? 別れた私の事なら、気にしなくともいい。お前の決断を私は尊重しているし、お前の幸せだけを、私は祈っているのだから……)
だが、その気持ちすら伝える術を持ち合わせていない自分に、シュバルツは苦笑する。だが仕方が無い。『別れる』とは、そう言う事なのだから。
ハヤブサが、幸せでいるのかどうか。
シュバルツは、ただそれだけが気がかりであった。
ハヤテは、間違いなくハヤブサを愛している。
彼ならば、いついかなる時でも、ハヤブサを愛し、守るために行動をしてくれるだろう。そしてきっと、ハヤブサも―――――
彼の愛情がハヤテに向けば、きっと、似合いだ。
誰もが見惚れる、素晴らしいパートナー同士になれるだろう。
「…………!」
そう思う時、ココロが軋んでしまうのは何故だろう。
素直に心から『おめでとう』と、言えないのは何故なのだろう。
ハヤブサ
ハヤブサ
(会いたい……!)
せめて一目で良い。今のハヤブサに会いたかった。
ハヤテの横で、これ以上ないと言うほど幸せな表情を浮かべて、笑っているハヤブサを見たかった。そうすれば―――――完膚無きにまで叩きのめされて、いろいろあきらめる事が出来るのに。自分が身を引いた甲斐もあるのに。
(そう言えば……ここは、ハヤブサの気に入りの場所だったな……)
二人で待ち合わせをした時、ハヤブサは、よくここから見える小さな沢で、釣り糸を垂れていた。2人が初めてキスを交わしたのも、ここだった。
この場所は、思い出が多すぎる。
二人で沢を泳いだり
あの木の下で――――――
(……………!)
うっかりその時のハヤブサの息づかいや体温を思い出しそうになって、シュバルツはブンブン、と、頭を振る。
忘れようとしても、忘れられる筈もない。
愛おしさと、恋しさばかりが募っていく。
どうして
どうしてこんなにも、会いたいと願ってしまうのだろう。
自分はアンドロイドで。自分の身体を構成している物も歪すぎて―――――おおよそ、人間の『パートナー』としては、これ以上ふさわしくない存在であるのに。いつか、身を引かねばならぬと分かっていたのに――――
自分が酷く執着質で、粘着的な性格をしているのではないかと感じてしまって、シュバルツは途方に暮れてしまう。
ここは元々、ハヤブサが気に入っていた場所だ。だから、ハヤテの元に居るハヤブサが、特に自分に会いたいと思う訳でもなく、またここに来る可能性だって無きにしも非ずだ。
身を引くと、会ってはならぬと分かっていると言うのなら―――――自分は、今すぐここから立ち去るべきだ。ここは元々ハヤブサの領域(テリトリー)。本当なら、自分はここに居てはいけないのだから。
なのに
何故
立ち去れないのだ。
どうして―――――
ここから一歩も動けないのだ。
会いたいと
抱きしめて欲しいと
どうして、願ってしまうのだろうか。
こんなのは駄目だ。
駄目だと、分かっているのに―――――!
「ハヤブサ……」
溢れる涙を押さえる事も出来ず、シュバルツはその場にうずくまってしまう。きっと今日もまた―――――こんな事をしながら、ずっとここに居続けてしまうのだろう。
我ながら本当に呆れる。
自分の願いがもう一度叶う可能性など、皆無に等しいと言うのに。
ハヤブサのためにもハヤテのためにも、自分は、彼らの前からその存在を消さねばならないと言うのに。
でも………
それでも―――――
(せめて……こうやって想い続ける事だけは……許してくれないか? ハヤブサ……)
せめて、君を想う。
せめて、君の幸せを、願う。
誰にも知られる事のないシュバルツの涙が、そっと風の中へと散って行った。
その頃龍の忍者はと言うと――――天神流の里で、病の床に臥していた。
シュバルツの手を拒絶してから、常に自分の心を殺し、そして、引き裂いてきたハヤブサ。
まるで、自分を呪い続けるかのようなその行為は、ハヤブサの心と、そして身体をも蝕んで行く。
それでもハヤブサは、ハヤテの愛に応えようと努力していた。
自分を『好きだ』と言ってくれたハヤテ。
彼には―――――何の落ち度もないのだから。
だが、ハヤブサが『ハヤテ』と、その名を呼ぶたびに、心の中によぎるのはあの愛おしいヒトの影。
違う。
これは違う、と、ハヤブサは何度もそれを否定する。
その影に、刃をつき立てる。
だがその刃は、そのまま自分に跳ね返ってきた。
痛い。
ココロが痛い。
早く死ねばいい。
死んでしまえばいい―――――
彼のヒトを思い出しても、何も感じなくなるくらい
ココロが、死んでしまえば良いのに――――――
それは、緩慢な自殺を試みるに似ていた。
龍の忍者は、日々、衰弱して行った――――――
「リュウ……!」
勿論ハヤテが、ハヤブサが目の前で弱っていくのを、手をこまねいて見ている訳ではなかった。
名医がいると聞けば、どこへでも駆けつけ、里につれて来た。
身体に良い薬があると聞けば、どのような手段を用いてでも、それを手に入れた。
だが、どの医者も薬も――――ハヤブサに対して有効な治癒手段にはなり得なかった。
「リュウ……。お前、また食べていないのか……?」
ハヤテが頭首としての用事を終えて、里の外から帰って来ると、ハヤブサに出されたと思われる夕食が、綺麗にそのまま残っていた。上半身を布団から起こして、窓の外を見ていたハヤブサが、ハヤテの姿を認めてふわりと微笑む。
「ハヤテ……。帰っていたのか」
「リュウ……! お前、また痩せたんじゃないのか……!?」
ハヤテの指摘に、ハヤブサは苦笑するしかない。
「済まない……。でも……食べられなくて………」
「お前の好きな物ばかりじゃないか……! それでもか?」
それにハヤブサは困ったように微笑むだけだった。
「……………ッ!」
もちろんハヤテは、「食べられない」というハヤブサに、何とか食事をさせようと試みていた。無理やり口に食事を詰め込んだこともある。とにかく栄養を取ってくれなければ、治る物も治らないからだ。元気になって欲しい一心であった。
しかし。
「う………ッ! ガホッ!!」
「リュウ!!」
そのたびにハヤブサは、口に入れられた物を、全部吐いてしまう。
慌てて介抱しようとするハヤテを、ハヤブサは懸命に押しとどめようとする。
「駄目だ……。ハヤテ……! 汚れる……ッ!」
「何を言っているんだ、リュウ!! 吐くなら、ちゃんと吐け!!」
「ハヤ……ううっ! ぐ……!」
結局ハヤブサは、胃液まで吐いて、そしてようやく落ちついた。茶と、梅干しを僅かばかりかじり―――――その日の夕餉は、それで終わってしまった。
そんな事が度々続いた。
琥珀色の長い髪をさらりと流し、色白で、薄絹の着物を纏ったその人は、痩せてやつれて来た事で、その美しさと儚さに、一層拍車がかかっていた。
「リュウ……」
まるで、呼び止めて繋ぎとめておかなければ、そのまま天に召されてしまいそうな気さえする程に―――――
「ハヤテ………」
ハヤテの呼び掛けに、ハヤブサはふわりと笑って答える。自分がその肩に触れると、ハヤブサもその手にそっと、己が手を添えて来てくれた。
「今日は……抱かないのか……?」
そして、その笑顔のまま、そう聞かれる。
「……………!」
自分が弱り切っているのに、なおも身体の関係を望んでくるハヤブサに、ハヤテも、狂気じみた何かを感じぬわけではない。
だが、求め続けなければ。
俺には、お前が必要だと、そう言い続けなければ―――――
目の前のこの美しい人を、完全に失ってしまいそうで怖かった。
何とか自分に繋ぎ止めたくて、失いたくなくて――――ハヤテは今宵も弱り切ったハヤブサを抱いた。
「ああ……! ハヤテ……!」
幸せそうに微笑み、自分の身体に縋りつき、甘やかに喘ぐハヤブサ。
自分は―――――確かに、ハヤブサを手に入れていた。
これは、自分が望んだとおりのハヤブサの姿だ。
だが。
どこかから、誰かの、別の声がする。
――――本当ニ、ソウカ?
「…………!」
――――本当ニ、コレハ、オ前ガ望ンダ『ハヤブサ』ノ姿 ナノカ?
ハヤテは、懸命に頭を振った
気づきたくない。
気づいてはいけないと思った。
自分の愛情が、まさにハヤブサを壊して行っているなどと―――――
気づいてしまえば自分は、ハヤブサを手放さざるを得なくなってしまう。
それだけは嫌だ。
それだけは出来ないと思った。
そうやってハヤブサが衰弱している間にも、『龍の忍者』に対する仕事の依頼が、皆無な訳ではなかった。
だがハヤテは、それをことごとく退けていた。こんな状態のハヤブサに『仕事』をさせる事など―――――それこそ、自殺行為だ。
しかし、そんなハヤテの防御網をかいくぐって、ハヤブサが仕事の依頼を知ってしまう事もある。ハヤブサがその仕事を受けようとしたと知って、ハヤテは激怒した。
「そんな身体で仕事など受けようとするな!! リュウ!!」
「しかし……!」
「いいか!? 俺がいない間にもう一度、そんな事をしようとしてみろ……! 座敷牢に監禁するからな!!」
「ハヤテ……!」
バン!! と、荒々しい音を立てて襖を閉めて、廊下を歩きだそうとしたハヤテの目の前に、『老中』格の者たちが控えていた。黙ってその前を通り過ぎようとするハヤテを、その男たちが呼び止めて来た。
「……一体いつまであの『龍の忍者』を手元にとどめ置かれるおつもりなのか?」
「あのような半死人のような『龍の忍者』など――――役立たずどころか厄病神の様な物ではないか」
「おかげで我が里も、余計な手間と仕事が増える一方だ」
「若、あのような者など、早急に隼の里の方にお返ししてしまいなされ」
「待たれよ、あのような状態で龍の忍者を里に返せば――――隼の里から、我等の里に言いがかりをつけられかねない」
「左様。あの者が勝手に病を得ていると言うのに、さも我々が悪いように言われてしまうぞ……!」
「全く……下手に『知名度』があるから手出しも出来ん……! まさに『厄病神』―――――」
「黙れ!!」
ハヤテはたまらず、大声で怒鳴りつけていた。
「良いか!? リュウ・ハヤブサの処遇は、俺が決める!! 誰であろうと、口出しすることは許さん!!」
「若………!」
老中たちは、一瞬静まり返ったが、すぐに口を開いて来た。
「なれば、あの者の病を、早急に治す手を打ちなされ」
「左様。あの者がここで勝手にあのようになっておるから、こんな事になっておるのですぞ」
「忍びは己が身体が『資本』であると言うのに―――――『龍の忍者』ともあろう者が、何を考えておるのか」
「お前たちの意見は、我が腹にとどめ置く!! 良いから下がれ!!」
ハヤテは怒鳴り散らして、ようやく老中たちを下がらせる事に成功した。それをしてからハヤテは、はっと我に帰って後ろを振り返った。
ここは、ハヤブサの部屋から近すぎた。今のやり取り―――――ハヤブサは、聞いてしまっているのではないだろうか。
慌てて踵を返して襖をあけると、ハヤブサは上半身を起こして、窓の外を眺めていた。振り返ってハヤテの姿を認めると、ふわりと微笑む。
「ハヤテ……」
その笑みが、少し哀しげであったので、ハヤテは思わず問いかけていた。
「リュウ……。もしかして、今の話を………」
「ああ……。聞いていた。耳が痛いな……」
「……………!」
ハヤテは、思わず唇を噛みしめていた。
やはり、聞かれてしまっていた。
あんな酷い言葉達を―――――ハヤブサに聞かすつもりなどなかったのに。
無言で、崩折れるように座り込み、俯いてしまうハヤテに、ハヤブサがそっと声をかけて来た。
「ハヤテ……」
「何だ……。リュウ………」
「もしも………俺の存在が、お前に迷惑をかけている、と言うのなら―――――」
「リュウ!!」
ハヤテは、思わずハヤブサの襟首を掴んでいた。
「あっ!!」
「何時俺が、お前の存在を迷惑だと言ったんだ!? 何時俺が、お前を厄病神だなどと言ったんだ!!」
「……ハヤテ……ッ!」
首を絞められて苦しいのか、ハヤブサがくぐもった悲鳴にも似た声を上げる。ハヤテがはっと我に返って手を離すと、ハヤブサは苦しそうに咳き込みだした。
「リュウ……!」
茫然とハヤブサを見つめるハヤテに、呼吸が落ち着いてきたハヤブサは、にこりと微笑みかける。
「……平気だ……。大丈夫、だから……」
(そう言えば、あのヒトもよく、こんな事を言っていたな)
ハヤテに「平気だ」と言いながら、ハヤブサはそんな事を思い出して―――――その胸に、ツキリと鈍い痛みを走らせた。
あのヒトも、こう言ってよく笑っていた。
俺に、心配かけさせまいとして。
あのヒトも―――――
知らない。
思い出さない。
思い出しては、駄目だ。
「――――――ッ!」
ハヤテは、思わず唇を噛みしめていた。
「………平気な訳、ないだろう……!」
絞り出すように、ハヤテは言った。
「平気な訳無いだろう!? あんな事を言われて―――――!!」
「だが……本当の事だ……」
ポツリと零すように言われて、ハヤテは思わず絶句していた。
「俺が『役立たず』なのも、この里にとって『厄病神』的になってしまっているのも……全部、本当の事だ……」
「リュウ……ッ!」
「ハヤテ……」
儚く微笑むハヤブサに、ハヤテはたまらなくなる。
気がつけばハヤブサの身体を押し倒して、その肌を暴き立て、自分の腹の下で喘がせていた。
「ハヤテ……! ハヤテ……!」
すっかり細くなったその腰を捕らえて、深く突きさしてかき回す。衰弱し切ったその身体は、最早他人を受け入れる余裕などないだろうに、それでもハヤブサは、ハヤテの背中に縋る様に手を回し、荒ぶるハヤテの動きを受け止め続けていた。
「あ………! あ………!」
やるせない。
苦しい。
切ない――――
この行為ですら、ハヤブサを消耗させるだけなのだと言う事を、最早ハヤテも理解している。
だが、自分でもどうしようもない程狂おしい彼への想いを、一体、どうすればいいと言うのだろうか。
「ハヤテ……! あ………!」
カクン、と、糸が切れたかのように、ハヤブサはその意識を手放していた。
「リュウ……! リュウ……!」
ぱしぱしとハヤブサの頬を叩くと、彼が僅かばかり身じろぎをする。
(生きてた………)
ほっと安堵の吐息を洩らしてから、ハヤテは、強烈な自己嫌悪に襲われていた。
疲れた。
一体いつまで―――――自分は、こんな物想いを繰り返さなければならないのだろう。
自分は、ハヤブサを生かしたいのか。
それとも、殺してしまいたいのだろうか。
イッソ、コノ手デ 殺シテ シマッタ 方 ガ―――――
「……………!」
ブン! と、頭を強く振って、ハヤテはその考えを否定する。
自分は、ハヤブサに傍に居て欲しくて、こんな強引な手段を取ったのだ。
それを殺してしまうなど―――――それこそ、本末転倒ではないか。
何故、こんな事になってしまうのだろう。
自分は、ただハヤブサを愛したいだけ。
そして、愛されたいだけだ。
たったそれだけの事が
どうしてこんなにも、難しく感じるのだろう―――――
「………………」
無言で、ハヤブサのいる部屋から出るハヤテ。廊下を数歩歩いた所で、今度はあやねとはち合わせた。
「あやね………」
「……………」
あやねは、哀しみを帯びた瞳でハヤテをしばらく見つめていたが、やがてその瞳を伏せ、頭を下げてハヤテの前から立ち去った。
(何か……言いたい事があるのか? お前は………)
ハヤテは、そんな義妹で、一の部下である彼女の後ろ姿を、ただ、黙って見つめ続けていた―――――
それから更に数週間が過ぎ、龍の忍者は、ついに、枕も上がらぬ重体となってしまった。
「……御重体でございます……。このうえは、生まれ育って慣れ親しんだ環境に、お返し致すのが一番かと……」
「な―――――!」
医者がそう言って頭を下げるのを、ハヤテは、ただ茫然と聞いていた。
「馬鹿な――――! お前は、里でも一番の医者の筈だろう!? それが何故……! どうして、治せないんだッ!!」
思わず、医者の襟首を掴んでくってかかってしまう。医者は狼狽しながらも、何とか言葉を続けていた。
「お……恐れながら、申し上げます……! 薬も治癒の秘法も――――その方が『生きよう』と言う意思が無ければ効かぬ物にございます……! ですが、あのリュウ・ハヤブサ様からは……! その肝心の『意志』が感じられぬのです……ッ!」
「―――――!」
ハヤテは、その言葉に衝撃を受け、医者から手を離してしまう。医者は暫し咳き込んでから、更に説明を続けた。
「治癒の秘法を施して、私は感じました……。あの方は、既に何度も何度も――――自分を殺しておられる。御自分への殺意が強すぎるのでございます。それが、我等の治癒の法を跳ねのけ、薬を効かなくしているのです」
「な…………!」
絶句するハヤテに、医者は問いかけて来た。
「何か……あの方が御自分を殺し続ける理由を、ハヤテ様はお心当たりはございませぬか……?」
「………………!」
「そして、ハヤテ様……。もう一つ申し上げたき儀がございます」
「何だ?」
問い返すハヤテに、医者は畏まって頭を下げた。
「これは私見ではございますが、リュウ・ハヤブサ様は………『人間』と言うよりは、『龍』に近しいお身体を持っていると、お見受けいたしました」
「龍………!?」
少し驚くハヤテに、医者は頷く。
「あの御方は『龍』でございます……。それを、『人間』が鎖でつなぎ止めておくなど、所詮無理な話ではございませぬか……?」
それだけを言い置くと、医者はハヤテの前から立ち去った。ハヤテは、ただ黙って、その姿を見送っていた。
(自分を殺し続けている……? リュウが………?)
ハヤブサは昏々と眠り続けている。その傍らにハヤテは腰を下ろし、その寝顔を見つめていた。
静かに眠り続けるハヤブサの表情は、やつれているとはいえ、穏やかな物で、とても内面に、そんな葛藤がある様には見受けられない。
「リュウ………」
ハヤテは、ハヤブサの髪をそっと撫でる。すると、ハヤブサの方が、僅かばかりの身じろぎをした。ツ……と、一滴の涙が、その頬を伝う。ハヤテが、そっとその涙を救うと、ハヤブサの唇が動いた。
「シュバルツ……」
「――――――!」
絶句する。
息を飲む。
その名は、大分前に聞かなくなっていた。だからてっきり、ハヤブサの中ではけじめがついたもの、と、思っていたのに。
まだ、想い続けていたと言うのか。
リュウ、お前は―――――
もう一度、ハヤブサの唇が動く。
「シュバルツ……」
だがハヤブサは、その名を口にした途端、苦しそうに頭を振りだした。
「だ……駄目だ……! 駄目だ……! 思い出しては……!」
「リュウ………!」
「ハヤテ……! ハヤテ……! ハヤテが………!」
そのまま、酷くうなされだすハヤブサ。彼の瞳から、血の色の涙が零れ落ち始めた。
「ハヤテ……ッ! 俺は……ッ!」
「リュウ!!」
たまらずハヤテは、ハヤブサを揺り起こす。
「―――――――!」
はっと、目を開けたハヤブサは、目の前のハヤテを視界に捉えたその一瞬――――――酷く哀しげな瞳をして、それから、ふわりと微笑んだ。
「ハヤテ………」
「リュウ………!」
ハヤブサが、ふらふらと手を伸ばしてくる。そっと優しく握りかえしてやると、ハヤブサは、酷く幸せそうに―――――笑った。本当に、酷く、幸せそうに――――
「―――――――」
そして、そのまま糸が切れたかのように、昏倒してしまった。
「リュウ!! リュウ!!」
必死に呼びかけると、ハヤブサは僅かに身じろぎをする。ハヤテはホッと胸を撫で下ろした後、その瞳から大粒の涙を零し始めた。
(リュウ……! お前本当は……願っているのではないのか……? 『会いたい』と……)
会いたいと
愛したいと
願っているのではないのか。
お前が心から愛した
あの、『最愛のヒト』に―――――
願っているのに、ハヤブサは
ずっとその願いを押し殺して
殺し続けて―――――
『俺のため』に………!
「リュウ………!」
たまらずハヤテは、ハヤブサの身体を抱きしめていた。
馬鹿な奴だ……!
恋人と共に幸せそうに居たのを、無理やり自分の方に引きずり込んだのは俺だ。
そのまま強引に自分の物にして、お前を踏みにじって―――――
今ならば分かる。
自分は、ただ子供じみた独占欲を満たそうとしていただけだ。
お前に、振り向いて欲しくて。ただ、それだけの理由で。
なのに、お前は―――――
理不尽な事をした俺を、責めるでもなく
それどころか、俺を愛そうと努力してくれていた。
でも、お前の真っ直ぐな心は、嘘がつけないから―――――
結局お前は、自分の心と体を壊して行かざるを得なくなってしまったのだ。
そんなになってまで、俺を愛そうと、尽くそうと、してくれたお前に
俺は一体、何をしてやれるのだろう―――――
ハヤテは、はらはらと涙を落としながら、ずっと、ハヤブサの枕元で彼の寝顔を見つめ続けた。そして、考え続けた。
そうやって――――どれだけの時が、経っただろう。
(……今なら、まだ間に合うだろうか………)
里の医師たちも匙を投げた、ハヤブサの身体。
だが、もしも
生きる気力を、彼が取り戻してくれるのなら―――――
『龍の化身』と言わしめたリュウの事だ。
もしかしたら、彼は死なずに済むかもしれないのだ。
丑三つ時を過ぎて、払暁近くになる頃に、ようやくハヤテは顔を上げた。
やはり俺は、リュウには生きていて欲しい。
生きていて欲しいのだ。
「リュウ……」
そっとハヤテが彼に触れると、ハヤブサは薄く瞳を開けた。
「ハヤ……テ……?」
「少し、外に出ようか」
そう言って、ハヤテはハヤブサを、抱き上げていた。
漆黒の闇の中を、ハヤテは走る。腕の中に、リュウの忍者を抱きかかえたまま―――――
(天神流の里を出たな………)
ハヤテの腕の中で、ハヤブサは何となくそう感じていた。里の門を抜け、深い森が辺りを覆う。
ハヤテが、どこに向かって歩を進めているのかは知らない。だが、自分はもう、ハヤテに身を委ねる以外に術を持たなかった。このまま打ち捨てられるか、殺されるかしても、それはそれで構わないと、ハヤブサは思った。
自分が死ねば、里の者たちは哀しむかもしれない。だけど里の者たちには、自分がいつ使命の途中で命を落とすか分からない事を、常に言い含めてある。自分の死が、隼の里と天神流の里の間に禍根を残す可能性は少ないだろうが、それだけは避けねばならぬと、ハヤブサは考えていた。
そして………もしかしたら、シュバルツも
俺が死んだと知ったら―――――
(……………!)
ここまで考えたハヤブサは、ブン! と、頭を強く振った。
あのヒトの事は、もう思い出してはいけない。
自分にはもう―――――そんな資格も無いのだから。
なのに、いちいち悲鳴を上げる『ココロ』
心底煩わしかった。
早く
早く―――――このまま、死んでしまえればいいのに。
ハヤテは終始無言であったが、その胸は温かい。
(ハヤテ………)
ともすれば朦朧としそうになる意識を抱きかかえながら、ハヤブサはハヤテの胸に、身を委ねていた。
そうして、どれぐらいハヤテは走り続けた事だろう。
人里に下り、それなりに建物も密集している街の中の一角で、ハヤテはその足を止めた。
「着いた………」
ハヤテのそう言う声が聞こえて、ハヤブサは瞳を開ける。そして、自分の視界に飛び込んできたその光景に、龍の忍者は思わず声を上げそうになる。
何故なら自分の目の前には―――――キョウジのアパートが在ったのだから。
「……………!」
知らず、ハヤテの腕の中で、ハヤブサは身を固くしてしまう。それにハヤテは軽く苦笑すると、その場にそっと腰を下ろし、そしてハヤブサを見つめた。
「リュウ………」
「ハヤ、テ………?」
ハヤテの意図がいまいち読み切れないのか、ハヤブサが不安そうにハヤテを見つめている。ハヤテは穏やかな笑みを浮かべると、ハヤブサの琥珀色の髪を優しく撫でた。指の間から長い髪がさらりと零れる。改めて――――彼への愛おしさを感じた。
愛おしいからこそ、願う。
彼には、生きていて欲しい。
笑っていて欲しい。
幸せになって欲しい―――――
その気持ちに、嘘偽りなど無かった。
だから、やっと、こう言える。
胸を張って、こう言えるのだ。
「リュウ……今まで、済まなかった………」
「…………?」
きょとん、と小首を傾げるハヤブサに、ハヤテは苦笑する。何故謝られているのか、おそらくハヤブサは理解してはいないのだろう。だがハヤテは構わず続けた。
「俺は……お前を、解放しようと思う………」
「ハヤテ………!」
息を飲むハヤブサの髪を、ハヤテは優しく撫でる。
どうか、間に合っていてくれ。
彼の、命の火が消えてしまう前に。
生きる『気力』をもう一度
その手に取り戻して欲しいと、ハヤテは祈り続けていた。
「今まで、本当にありがとう、リュウ……。もう俺は、充分だ……」
「ハヤテ……! しかし――――!」
何事かを反論しようとするハヤブサの額に、ハヤテは優しくキスをする。
「……………!」
茫然と、動きを止めるハヤブサに、ハヤテは改めて微笑みかけた。
「愛している……。リュウ……」
「ハヤテ………!」
「愛しているからこそ……俺は、お前に死んで欲しくはない。生きて欲しい。そう、望んでいる―――――」
「ハヤテ………」
「笑ってくれ、リュウ」
ハヤブサの瞳をまっすぐ見つめながら、ハヤテは言葉を続けた。
「明るい陽の下で、明るく闊達に笑うお前を、もう一度、見せてくれ」
愛している。
好きだった。
「ハヤテ!」
どんなに辛い修行を終えた後でも
笑顔でこちらに手を差し伸べ続けてくれたお前が―――――
そして、彼を心の底からの笑顔に出来るのは、俺ではない。
悔しいが、俺ではないのだ。
「ただ……俺はお前を手に入れてから、キョウジ・カッシュに見張りをつけていはいない。だから……お前の想い人が、お前を未だ想い続けているかどうかまでは知らない」
「…………!」
「それでも……お前は、『シュバルツ』に会いたいと――――そう言うのか?」
(嘘だ。本当は知っているけどな。シュバルツが、未だにお前を想い続けている事を――――)
その事実を知っていなければ、自分は大事な人をわざわざ託しにこんな所まで来はしない。それでもハヤブサにそう言ったのは、彼の意思を確認するためでもあった。
もしも、彼が自分の想いを打ち砕かれる可能性を潔しと出来ないのであれば、自分は、彼をもう一度天神流の里に連れて行くことも考えていた。だが―――――ハヤブサの方に、迷いはなかった。
「ああ……。行くよ……」
即答して来た龍の忍者に、ハヤテは少し、天を仰いだ。
「そうか……」
だが同時に、納得もしていた。
傷つくことも恐れずに、前に進む事を選択できる。
それでこそ、お前だ。
それでこそ、俺の愛した『龍の忍者』だ。
「では……行って来い。………立てるか?」
「ああ………」
ハヤブサは頷くと―――――ふらふらと、その足で立ち上がった。
枕も上がらぬ重体と、医師も「もう駄目だ」と匙を投げた、その身体であるのに。
生きる気力が、戻りつつあるのか。
俺の決断は、間に合ったのだろうか。
彼は―――――死なずに済むのであろうか。
ああ
どうか生きて
生きてくれ。
「ハヤテ………」
呼び掛ける声にはっと顔を上げると、ハヤブサがこちらを気遣うように見ていた。
(お人好しだな、お前は……。俺の事など気にせずに、そのまま行けば良いものを――――)
ハヤブサのそんな所作にハヤテは苦笑すると、ハヤブサを促すように手を振った。
「行け。お前の思うままに――――」
道路一本隔てた所にキョウジのアパートがある。その出入り口まで自分が抱いて連れて行ってやっても良いが、自分も、ハヤブサに対して未練が無い訳ではない。もう一度その身体に触れてしまえば、手放す勇気が挫折しそうで怖かった。
それに、愛する人が別の男の所に走るのを目の前まで手助けしてやる程、自分はお人好しでもないのだから。
「……………」
ハヤブサは、そんなハヤテを暫くじっと見つめていたが、やがて、軽く頭を下げてから踵を返した。そのまま、ふらふらとキョウジのアパートに向かって歩き出す。一歩、一歩、おぼつかない足取りだが、確実に前へと進む。
「リュウ!」
ハヤテは、そんなハヤブサの後ろ姿に呼びかけた。
「もしも、振られたら俺の所に来い! 面倒見てやるから―――――!」
その言葉に、ハヤブサからの返事はない。しかし、彼の右手がふらふらと上がった。ちゃんと自分の声が聞こえていたのだとハヤテは感じて、少し胸を撫で下ろす。
行け。
そして、生きてくれ。
ハヤテはハヤブサがその道路を渡りきるまで、その後ろ姿を見つめ続けていた―――――。
シュバルツ……
シュバルツ……
その姿だけを求めて、龍の忍者は足を前へと動かす。
手を振り払ってしまってから、もう半年以上経つ。
だから、彼が自分の事を忘れてしまっていても、新しい恋人が出来ていたとしても、文句を言う資格はないのだと、ハヤブサは思った。もしかしたら、自分を待っているかもしれないなどと、都合のいい夢は見ない。
だけど、一目、会いたかった。
罵られても良い。
殴られても良い。
蔑まれても良い―――――。
会いたかった。
最期に、彼の姿を見て死ぬ事が出来るのなら―――――
自分は、それで充分だった。
地面がぐにゃぐにゃと揺れ、ともすれば倒れ込みそうになる。
視界が時々、黒に染まる。
だけど、足を止める事だけは、しない。
ただひたすら、キョウジのアパートに向かって、歩く。
会いたい。
会いたい。
シュバルツ………!
龍の忍者は、あるだけの気力を振り絞って―――――歩を進め続けていた。
キョウジ・カッシュは朝の日課をこなすために、アパートのドアを開けていた。
夏場の朝の5時ともなると辺りは既に明るく、昼間は容赦のない猛暑に曝されるこの場所も、少し涼しげな空気が感じられる。最初は億劫だったこの朝のロードワークも、今ではすっかりキョウジの中では習慣となっていた。
(今日も1日、平常心で……。シュバルツに引きずられて、あまり暗くならないように……)
ハヤブサと別れて以降のシュバルツは、常にどことなく暗い影を背負っているように見える。
無理もないなとキョウジは思った。
あれだけ深く愛された愛情を、そんな簡単に忘れ去る事など、なかなか出来はしないだろう。別れたのだから割り切れ、と、言われても、それは無理な話と言う物だ。
(それにしてもシュバルツは……やっぱり、ずっとハヤブサの事を想い続けてしまうのだろうなぁ………)
思い込んだら一途だから――――と、思った所で、キョウジは我が身を振り返る。
シュバルツの性格のベースとなっているのは自分だ。
だからもしかしたら――――自分も、そうなってしまうのだろうか。
誰かを本気で好きになったら、例え振られたとしても、ずっとその人の事を想い続けてしまうのだろうか。
(しんどそう……いやだなぁ)
そんな経験は、出来ればしたくないなぁと苦笑しつつも、少し、シュバルツが羨ましくもあった。それだけ深く愛せる様な人に、自分も、何時か巡り合う事が出来るのだろうか。
それは、苦しくて切ない事かも知れないが、ある意味幸せな事なのかもしれない、と、キョウジは感じていた。
たった1人で良い。
生涯をかけて愛し抜ける人を得られたら、どれだけ自分の人生が豊かに色づく事だろう。
アパートの階段を下り、外に出る。
さあ、走り出そうと顔を上げた時、視界に1人の人間の姿が飛び込んできた。
その人は、酷くふらついていた。
そしてその顔を見て―――――キョウジの顔色が変わった。
「ハヤブサ!!」
思わずその名を呼んで、キョウジはその傍に走り寄っていた。
「あ……? キョウ……ジ……? キョ、ウジ………か………?」
ふらついていたハヤブサが、顔を上げる。
そして、キョウジの姿を認めて、微笑んだ。
「ハヤブサ!? どうしたんだ!? 一体何が――――!!」
走り寄るキョウジの目の前で、ハヤブサは倒れそうになる。それを、キョウジが慌てて支えた。
「―――――ッ!!」
そして、その身体を支えた瞬間、キョウジは絶句する。
この人の身体は―――――こんなに軽かっただろうか?
「ハヤブサ……?」
抱き止めるその身体が、痩せ細っている。
とぎれとぎれになる呼吸。
全く力の入っていないその身体の様子に、キョウジはハヤブサが、かなり危険な状態にあることを察した。
だから彼は、思わず叫んでいた。
「シュバルツ……! シュバルツ!! お願いだ!! 来てくれ!!」
キョウジの叫び声に反応して、すぐにシュバルツは姿を現した。
「どうした? キョウジ。一体何……が………!」
シュバルツもまた、キョウジが抱き止めているその人物の姿を見て絶句していた。
まさか
まさか
何故、こんな所にハヤブサが―――――!?
「シュバルツ!! ハヤブサを頼む!! 私は、いろいろ用意してくるから――――!!」
感慨に浸る間もなく、シュバルツはキョウジからハヤブサを託される。シュバルツもまた、ハヤブサのその身体を抱きかかえて、絶句していた。
この人の身体は、こんなに軽かっただろうか?
この人の身体は―――――こんなに、痩せ細っていただろうか?
「な……何で………!」
彼を抱きしめながら震えるシュバルツに、ハヤブサも気が付いたのか、その顔を上げた。
「シュバルツ……? シュバルツ………なの、か……?」
「ハヤブサ……ッ!」
全く力の入っていない、弱々しい声に、シュバルツは歯噛みする。どうしてこの人は―――――こんなにも衰弱しているのだろうか。彼を愛する、ハヤテの庇護があった筈であるのに。
「ハヤブサ……! 何故だ……ッ!」
その身体を抱きしめながら、問いかけずにはいられなかった。
「ハヤブサ……ッ! 何故だ!? 何故、こんな事になった!? ハヤテ殿は、お前を愛していたのではなかったのか!?」
その問いに、腕の中のハヤブサは、ふわり、と柔らかい笑みを浮かべた。
「ハヤテは………俺の事を、これ以上ないくらい、愛してくれたよ………。だけど……俺が………」
そう言いながら、龍の忍者は、ふらふらとシュバルツの頬に手を伸ばす。
「俺が………俺の方が………駄目、だったんだ……」
「な……何で………!」
茫然と問い返すシュバルツの頬を、ハヤブサの手は優しく撫でた。そして、「分かっているだろう?」と、微笑んだ。
「俺は………お前じゃなきゃ、駄目……なんだ………」
「――――――!」
「お前でなければ………駄目、なんだ……よ………。シュバル、ツ………」
「ハヤブサ………ッ!」
シュバルツはいつしか、大粒の涙を流していた。
そう。
あの時ハヤブサは―――――『選んで』いた。
周りに血を流させない、自分一人が『犠牲』になる、道を―――――
だけど、あの時どうすれば良かった?
どうすればよかったんだ。
「ハヤテを裏切れない」
そう言って、泣いていたお前を。
無理やりその手を引っ張ったところで、ハヤブサはきっと、それを潔しとは出来なかっただろう。
ハヤテを裏切ってしまった己を責めて。責め抜いて―――――
それは重い『枷』となって、ハヤブサを苦しめる。シュバルツにはそれが分かった。だから、自分はハヤブサの手を離したと言うのに。ハヤテならば、きっと、ハヤブサを幸せにできる。そう信じて。
なのに―――――
どうして
どうして、こうなってしまった?
「シュバルツ……。顔を………よく、見せてくれ………」
「ハヤブサ………」
龍の忍者の懇願に、シュバルツは静かにその面を向ける。
だが、涙が後から後から溢れるのを、止める事が出来なかった。微笑む事も出来なかった。ただ、ハヤブサの力無いその身体を、ぎゅっと抱きしめ続けていた。
「シュバルツ………会いたかった………」
対して龍の忍者は、幸せそうに微笑んでいた。
「………会いたかったよ……シュバルツ………」
「シュバルツ!! ハヤブサは―――――!」
走り込んで来たキョウジに、シュバルツは振り返る。
「………眠ったみたいだ……」
「……………!」
「しばらく………寝かせておいてあげよう………」
腕の中のハヤブサは、穏やかな寝顔をしていた。
そんな龍の忍者の寝顔を、朝日が優しく照らし続けていた――――――
最終章
「寝るなああああ―――――――――ッ!!」
いきなりのキョウジの大声に、混濁しかけていたハヤブサの意識がはっと覚醒する。そこに、さらにキョウジの怒声が飛んできた。
「寝るな!! 今寝るな!! 本当に、冗談じゃない!!」
「キョ、キョウジ?」
見たことも無い様なキョウジの剣幕に、シュバルツも呆然としてしまう。
「今ここで死ぬなんて、絶対に許さないよ!! ハヤブサ!! シュバルツをあれだけ泣かせて―――――!! こっちは貴方に対して言いたい事が沢山あるんだッ!!」
「……………!」
キョウジの言葉にハヤブサは息を飲み、シュバルツは何故か動揺していた。
「や……! キョウジ……! 私は、別に―――――」
「シュバルツは黙って!! ハヤブサを受け入れる態勢が地下に出来ているから、早くそこに運んで!!」
「わ……! 分かった……!」
キョウジの剣幕に押される形でシュバルツは立ち上がる。
「ハヤブサ!! 寝るなよ!!」
地下に走る道すがら、キョウジはそう怒鳴り続けた。
「絶対に―――――『生きる』と強く思って!!」
地下に走り込んだキョウジとシュバルツは、ハヤブサの身体を手早く寝台に寝かしつけると、延命のための処置を施して行く。
(血圧が低いな……。心音も弱い………!)
ハヤブサの身体から上がってきたデータを見て、キョウジは歯噛みする。どの数値も、決して楽観できない状態であると指し示していた。そうこうしているうちに、ハヤブサが昏倒してしまう。また、意識の混濁を起こしてしまったようだ。
「ハヤブサ!! ハヤブサ!!」
シュバルツが懸命に呼びかけると、彼の脳波に反応があった。
「シュバルツ!! 彼に呼びかけ続けて!!」
心肺停止状態になった場合に備えて、電気ショックの準備をしながら、キョウジは叫ぶ。
人の聴覚は、死の直前まで残り、脳にその音を流し続けていると言う。
絶対に、ハヤブサはシュバルツの声を聞いていると確信したキョウジは、シュバルツを励まし続けた。
「ハヤブサ!! 死ぬな!!」
シュバルツもまた、ハヤブサの手を握りながら、懸命に呼びかけ続けた。
「生きてくれ!! ハヤブサ!!」
「……………」
脳波の反応と共に、微かにシュバルツの手を握りかえす、ハヤブサの手。
『生きよう』とする意志を、そこに感じた。
だからこそ、助けたい。
助けたいんだ。
キョウジは祈るような想いで、懸命にハヤブサの延命治療を続けていた――――――
そうして、どれぐらい時が経っただろう。
「……………」
キョウジは無言で、倒れ込むようにデスクの椅子に、腰を落とした。大きく息を一つ吐いて、頭にかぶっていた白帽を取り、額の汗を拭う。
目の前の寝台には穏やかな表情をして眠る龍の忍者の姿があり、その近くに在る心電図は、ピッ、ピッ、と、安定した心音を刻んでいた。血圧も、若干低めながらも安定している。そのデータはどれも、目の前の患者の容体が、ひとまず落ち着いたと言う事をキョウジに示していた。
(良かった……。とりあえず、ひと山越えた………)
ギ、と、音を立ててデスクの椅子に凭れかかっていると、シュバルツが声をかけて来た。
「キョウジ。何か食べたほうがいい。私が作ってこよう」
シュバルツのその言葉に、しかしキョウジは苦笑しながら頭をふる。
「いや……シュバルツは、ハヤブサの傍に付いていてくれ。飯ぐらい、自分で何とかするよ」
そう言って立ち上がろうとするキョウジを、シュバルツは強引に押しとどめてくる。
「キョウジはずっとハヤブサの治療で、休んでいなかっただろう? とにかく栄養をとって、少し休んでくれ。今お前に倒れられたら適わん」
そう言ってシュバルツは地下室から出ていく。キョウジはその後ろ姿を、やれやれと、ため息を吐きながら見送っていた。
しかし、シュバルツの言うことも一理ある。ハヤブサの治療を開始してからこっち、自分は、ほぼ不眠不休の状態であったから。押し寄せてくる疲れと戯れていると、目の前の龍の忍者から声をかけられた。
「…………キョウジ………」
「ハヤブサ!? 気が付いた!?」
「………『寝るな』……と、言ったのは、お前……だろう……」
「…………!」
龍の忍者のその言い分に、キョウジは少し感心するやら呆れかえるやらしてしまう。この患者は、自分の言う事を律儀に守ろうとしていた事になるのだから。
しかし同時に安心もしていた。
『医師の言う事を聞く』と言う事は、患者の方に治ろうと言う意思があることの表れだからだ。きっとハヤブサの身体は、時間はかかっても、ちゃんと快方へと向かって行くだろう。
「………シュバルツは………?」
ハヤブサの問いに、キョウジはふわりと笑う。
「今、私の食事を作りに行ってくれているよ。すぐに帰ってくる」
「そうか………」
少し安心したように息を吐くハヤブサを見て、キョウジは苦笑した。ハヤブサは、本当にシュバルツを求めていて、そして好きなのだなと感じてしまう。それにしても大したものだ。こんな状態になってもハヤブサは、まだ自分とシュバルツを見間違わないとは。
変な所に感心していると、またハヤブサから「キョウジ……」と、声をかけられた。
「どうした? ハヤブサ……」
ハヤブサは、キョウジの方をちらりと見やると、少しばつが悪そうな表情をした。
「………何か、俺に……文句があるんじゃないのか……?」
「ああ。あるよ。たっぷりとね」
「……………!」
憮然と言い放つキョウジに、ハヤブサの顔色が少し変わる。それを見て、キョウジは苦笑していた。
「だけど今は言わない。もう少し貴方が元気になってから、言わせてもらう事にするよ。だいたい、今言った所で、右から左に流れていくだけだろう?」
「う…………!」
キョウジの的確すぎる分析に、ハヤブサも二の句が継げなくなる。それを見て、キョウジは少しおかしそうに笑った。
「だから今は、ゆっくり体を休めてくれ。早く私の文句を聞いてもらうためにも、ね」
「分かった………」
ハヤブサがそう返事した所で、ドアをノックする音が響き渡る。キョウジが返事をすると、シュバルツが部屋に入ってきた。
「キョウジ、飯が出来たぞ。……って、ハヤブサ、起きたのか」
「シュバルツ……」
シュバルツの姿を見たハヤブサが、身を起こそうとする。それを見たキョウジから「こら~。起きようとしない!」と、たしなめられて、龍の忍者は渋々起きるのをあきらめた。
「栄養だけは計算してある。ただし、味は保証しないぞ」
「充分だよ、シュバルツ。ありがとう」
シュバルツに返事をして、キョウジはデスクの椅子から立ち上がった。
「じゃあ、私はご飯を食べて、少し休ませてもらうよ。シュバルツ、ハヤブサをよろしくね」
「ああ、分かった」
「でも、何かあったら呼んで。すぐに来るから――――」
そう言い置いて、キョウジは部屋から出て行った。後には、シュバルツとハヤブサだけが残された。
「シュバルツ………」
ハヤブサがそっと呼びかけてくる。
「どうした? ハヤブサ……」
シュバルツは寝台の傍まで来て、枕元近くの椅子に腰を落とす。そして、ハヤブサの手を、優しく握りかえしていた。
(この手……覚えがある……。俺の意識が朦朧としていたとき、ずっと握っていてくれた手だ………)
死への闇に引きずり込まれそうになっていた時、この手が支えてくれた。
何度も何度も、名前を呼ばれた。
死ぬな!
生きろ!
優しい手に、強く励ましてくるその声に、自分も必死にしがみついていた。
昏睡から覚めた、今なら分かる。
シュバルツが必死に、自分に呼びかけを続けてくれていたのだろう。
「…………ッ!」
何故なのだろう。
どうしてなのだろう。
自分は一度、この手を振り払ってしまったと言うのに――――
「どうしてだ……シュバルツ………」
ハヤブサの瞳から、いつしか涙が溢れだしていた。
「ハヤブサ……?」
怪訝な顔をしながらも、シュバルツはハヤブサの頬を伝う涙を拭う。
「どうして………俺を、責めないんだ……?」
「責める?」
きょとん、とするシュバルツに、ハヤブサはなおも言葉を続けた。
「俺は………お前の手を、振り払ってしまったのに………!」
「ああ………」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツもやっと納得したかのように頷く。しかし、シュバルツの手はハヤブサの涙を拭い続けた。そして、その表情は、穏やかその物だった。
「……私の事で、お前がそんなに気に病む必要はない。あの時、私たちは話し合って、お前が断を下した。あの時は、お互いにそれが最善と信じて――――その道を選んだのではないのか?」
「シュバルツ………!」
「ならば、この事で……どちらが責めを負うとか、そう言うのはおかしい……。それに、今回の件は、私にだって非がある。そうやって苦しんでいたお前を、助けることもできなかったのだから……」
「ち、違う……! それは、俺が勝手に―――――!」
そう言って慌てて身を起こそうとするハヤブサを、シュバルツが優しく押しとどめる。
「な………。だから、お前は、必要以上に自分を責めるな。今は、ゆっくり休んで……身体を治す事に専念してくれ……」
「……シュバルツ………ッ!」
ハヤブサは己が頬を優しく撫で続けるシュバルツの手を抱きかかえるようにして握りしめると、そのまま、泣き伏してしまった。
ただひたすらに優しく、総てを許してくれる、お前。
もう二度と、裏切りたくはなかった。
哀しませたくはないと思った。
「ハヤブサ……」
握られている手にハヤブサの涙を感じながら、シュバルツはもう片方の手でハヤブサの髪を撫でる。
(そんなに、私の事で自分を責めなくて良いんだ、ハヤブサ……。『人間』ではない私は、お前の永久のパートナーにはなり得ない。私はお前にとって、一時的な寄り処の様な存在で良い。何時、お前の都合で打ち捨てられても構わないのだから――――)
でもこの想いは、口に出しては言わない。
言えばきっと、ハヤブサを烈火のごとく怒らせてしまう――――そんな予感がする。
何故だろう。構わないのに。
自分は、そう言う存在の筈なのだから――――
(ハヤブサ………)
ただ、打ち捨てられても、別れられても
自分は何時までもハヤブサを、想い続けてしまうだろう。そんな予感がする。
それだけは、どうか
どうか許して欲しいと、シュバルツは願った。
龍は、ただひたすらに優しい、愛おしいヒトの事を想って泣いた。
人外の物は、そんな彼を愛し続けたいと願った。
そんな二人の姿を、夜の帳が、優しく覆って行った―――――
ただひたすらに、君を想う。
どうも、こんにちは。空由佳子と申します。
今回の小説も、無事書き終わることができました~。
いかがでしたか?
カップリングなど毛色の違う挑戦だったので、書いている方は楽しかったですが、読んでいる方は………どうだったんでしょう。
感想頂けると嬉しいし、励みにもなりますので、よろしければお願いします。……と言って、来る感想は、ないだろうなぁ。
ものすごく孤独な作業ですが、私はこうやって書く事をしばらくはやめられそうにもありません。
この人たちの事が大好きですし、なんとてもう生きがいになっちゃっています。
言っちゃなんだが東南海地震が来たら、徳島在住の私は、多分無事では済まない。最悪、死に至ってしまうかもしれない。
そうなったときに『書いておけばよかった』と、後悔だけはしたくないですので。
ある意味黒歴史にもなるから死ぬ間際に『消しておけばよかった』と、後悔するかもしれませんが。
そして、たとえ生き残ったとしても、しばらく小説どころではなくなるだろうから、平和なうちに、書けるだけ書いておこうとも思っています。なんとて世界中で私だけしか書いていないカップリング。書きがいはあります。語り合える同士には恵まれませんが(涙)。
さて、次回作ですが、これの続編っぽい物が一つ思い浮かんでいます。
久しぶりに東方不敗師匠なんかも出して、派手なアクションものにしたいですね! でもそのためには物語のプロットを一度大学ノートに書いて、組み立てて、破たんの出ない内容にしないといけない……。この作業が楽しくもあり、厄介な物でもありますが、頑張ります。
それではまた。
もし縁があれば、次回作でお会いしましょう。