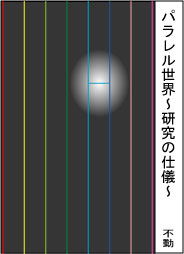
パラレル世界~研究の仕儀~ 『A』
第一話 理想的な関係
中学3年になって2ヶ月が経つと、クラスの雰囲気が少し湿っぽくなっていた。そんな中、倉木秋彦は静かに論文を読んでいた。
10分の休憩中にこんなもの読んでいると茶化されそうなので、白地のカバーを付けてカモフラージュしていた。
「また読書かよ」
この短い休憩時間でも、秋彦に話しかけるクラスメイトがいた。彼は、茶髪で少したれ目だった。
「なんか用?」
秋彦は本を閉じて、そのクラスメイトに視線を移した。
「特に用はねぇ~よ」
進級して仲良くなった大貫信也が、ダルそうに答えた。
「そっ」
これは何度目かのやりとりだったので、素っ気なく返した。
「信也は、受験勉強とかはしないのか?」
「別に、行きたい高校なんてねぇよ」
「え、卒業後に働くってこと?」
「んなわけねぇ~だろ」
「だよな」
この学校は進学校で、卒業後に就職する人は滅多にいなかった。
「信也は、成績良いからどこでも受かるんじゃない?」
突然、秋彦の後ろから声が聞こえた。
振り向くと、クラスメイトの古賀浩之が立っていた。彼とは、2年の時から一緒のクラスだった。
「よせよ」
浩之の言葉に、信也が嫌そうに頭を掻いた。
「口と態度が悪くなければ、好青年に見えるのに」
浩之はそう言って、眼鏡のフチを指で摘まんだ。彼は真面目で通っていて、口調も堅苦しかった。
「そんなくだらねぇ~理由で、変えるつもりはねぇ~よ」
「もったないないことだね」
信也の答えが気に入らないようで、不満顔で秋彦の机の隣に立った。
この二人は、クラスの中でも仲の良い友達だった。
「二人は、成績が良いから羨ましいな」
ここは空気を読んで、そう振る舞ってみた。
「秋彦も頑張れば、成績ぐらい簡単に上がるよ」
それに対して、浩之が模範的な返しをしてきた。
「成績なんてどうでもいいだろ~。俺的には、おまえに彼女がいるのが羨ましいんだが」
信也にとっては、成績より彼女が欲しいようだった。
「だったら、ナンパでもしてみたら?」
ここは友達らしく、的確のアドバイスをしておいた。
「ちげぇ~よ。おまえの彼女が羨ましいんだよ」
理不尽なことに、さっきとは違う言葉が返ってきた。
「緒方聖奈か。確かに彼女は美しいよな」
浩之が信也に同調するように頷いた。
緒方聖奈は秋彦の幼稚園からの幼馴染で、中学に上がる頃に強引に付き合わされていた。彼女は、この学年では有名人で誰からも慕われる存在だった。
「まあ、俺からしたら腐れ縁に近いけどな」
ここは一般的な謙遜で切り抜けることにした。
「何、この勝利者発言?」
「ふっ、腹立たしいことだね」
しかし、それが不評のようで二人から反感を買ってしまった。
「まあ、いいじゃん」
秋彦がそう言うと、タイミング良く授業開始の本鈴が鳴った。
「あ~あ。結局、アキの自慢話で終わったな」
自分から切り出した癖に、その発言は理不尽極まりなかった。
「そうだね。全く不愉快だよ」
浩之も便乗するように、捨て台詞を残して席に戻っていった。
「面倒臭いな~」
その二人の嫌味に、秋彦は溜息をついて小声で愚痴った。
午前の授業が終わると、いつものように聖奈が秋彦を迎えに来た。
「秋彦。帰りましょうか」
聖奈は長く艶やかな黒髪を手に掛けながら、優雅な立ち振る舞いと滑らか口調で話しかけてきた。
「そうだな」
今日は土曜日なので、午前授業のみだった。秋彦はクラスメイトの視線を感じながら、聖奈と一緒に教室を出た。
「論文は読めた?」
登校時にその話をしていたので、気になっていたようだ。
「いや、無理だった」
「やっぱりね。っていうか、中3で論文読むとか普通しないんだけどね」
「授業が暇でな。当たり前のこと聞かされても、眠くなるだけだ」
学校の授業は小学生で終えているので、退屈で仕方なかった。今は独自に研究のかたわら、大学准教授の父親から論文を取り寄せてもらい、読み漁っている状態だった。
「やっぱり天才は違うわね~」
「天才じゃねぇって」
「謙遜しちゃって~」
「頼むからそんなこと言わないでくれ」
「え~、本当のことでしょう」
「もうやめよう」
このやり取りは飽きるほどしているので、強制的に打ち切った。
「そういえば、アー君はどこの高校行くの?」
聖奈は誰もいないことを確認して、昔から言い慣れているあだ名で呼んだ。
「ん?家から近い公立高校かな」
あの高校は偏差値も高くなく、今の成績でも簡単に入れそうだった。
「じゃあ、私もそこね」
聖奈は、迷うことなく進路を決めた。
「セナは成績良いんだから、もっと上に行けるだろう」
秋彦も聖奈を馴染みのあだ名で呼んでいた。
「学校なんて興味ないわよ」
「そうか」
これは聖奈の意志なので、秋彦からはこれ以上は何も言えなかった。
「あ、そうだ。明日、休みだからテスト勉強しましょう」
聖奈が今思い出したように、嬉しそうな笑顔で提案してきた。
「またかよ」
これはテスト前には、何度もやってることだった。
「という訳で、明日アー君の家に行くわね」
秋彦の面倒臭そうな顔を無視して、勝ってに予定を決めた。
「好きにすればいいよ」
テスト前でなくても、毎日家に来ているので断っても意味はなかった。
平屋の自宅に入ると、当然のように聖奈も入ってきた。これはいつものことなので、特に気にはならなくなっていた。
聖奈もいるので、リビングのソファーで論文の続きを読むことにした。
「えへへへ~」
すると、聖奈が嬉しそうに寄り添ってきた。
「いや、重いって」
笑顔でもたれ掛かる聖奈を、いつものように軽く突き放した。
「それにしても細かいわね~」
聖奈が論文を見て、そんな感想を口にした。
「まあ、関数だからな」
読んでいるのは、四次関数の論文だった。
「数学の固有名詞は、ホント理解できないわ」
「まあ、数学は特有だからな~」
秋彦は適当に答えながら、論文を読み進めた。
「暇じゃない?」
「ん?暇だけど、アー君と一緒だから問題ないよ。むしろ、ずっとこうしていたい」
そう言うと、組んでる腕に力を込めた。
「あ、そう」
聖奈を気遣ったつもりだったが、余計だったようだ。
少し遅い昼食を終えると、聖奈は用事があると言って帰ったので、自室で論文を読むことにした。
しばらく論文に集中していると、鍵を掛けた玄関から音がして、部屋に聖奈が入ってきた。昔から聖奈の出入りが頻繁にあるので、父親の了解を得て合い鍵を渡していた。
「こんばんは」
聖奈は、笑顔で挨拶してきた。自宅で着替えてきたようで、淡い紺のブラウスに赤紫のタックスカートだった。
「あ、もうこんな時間か」
気づくと、もう6時を回っていた。
「電気ぐらい点けないと」
聖奈はそう言いながら、部屋の電気を点けた。
「今から夕飯作るから」
「あ、ああ。ありがとう」
倉木家は父親と秋彦の二人暮らしで、父親は家を空けることが多かった。その為、家事全般は秋彦がしていた。それを見兼ねた聖奈が、夕飯だけでも用意すると頑なに言うので甘えることにしていた。
「今日もここで食べるのか?」
「勿論♪」
ここ最近になって、聖奈は自宅に帰らず、倉木家で食べるようになっていた。
「おじさんとか何か言わないのか?」
「最初は言ってたけど、アー君への愛を訴えたら苦笑いで頷いてくれたわ」
「あ、そう」
その内容は聞きたくなかったので、話を切り上げることにした。
「今日、道春さんは帰ってくるの?」
「あ~、そうだな。確認してみよう」
父親にメールしようとすると、もう既に今日も帰れないとメールが送られていた。
「実験で忙しいみたいだな」
秋彦は、回転椅子を回して聖奈に伝えた。ここ最近、父親は大学に泊まり込んで帰ってこないことが多くなっていた。
「そっか。じゃあ、今日もアー君と二人っきりなんだね~♪」
聖奈には嬉しいことなのか、満面の笑みで部屋から出ていった。
1時間後、聖奈の作ってくれた料理を食べる為、ダイニングの椅子に座った。
「アー君」
食べ始めようとすると、聖奈が秋彦を呼んだ。
「なんだよ」
「アー君は、どこにも行かないよね」
「なんだよ唐突に」
「最近、あの部屋で実験してるでしょう」
聖奈は、ダイニングから見えない壁の奥の部屋を指差した。
「それといなくなる意味がわからない」
「だって、やってることって空間の屈折現象でしょう。それで別次元が開いて、いなくなっちゃうとか」
「・・・さすがに考えすぎだろ」
「可能性としてはあるじゃない」
「相変わらず、考えが飛躍するな~」
「もしアー君がいなくなったら、私生きていけないわ」
「だから、考えすぎだって」
聖奈の空想が広がり過ぎる前に、ここで止めることにした。
「私的にはこの研究は、もうやめて欲しいんだけど」
「それは無理」
秋彦は自分の研究する為、自宅で頻繁に実験をしていた。研究資金は、秋彦自身が株と外為で数十億まで膨らんでいた。
「研究をやめるくらいなら、学校をやめる」
正直な話、学校をやめて研究に没頭しようかと思っているのだが、聖奈が強く反対するので、仕方なく学校に通っていた。
「それは絶対ダメ!」
「じゃあ、研究もやめない」
「うう~~~」
これには聖奈が、不満そうな顔で唸った。
夕飯を食べ終わり、秋彦が食器を洗っていると、隣に聖奈が顔を出した。
「どうした?」
秋彦は皿洗いを中断して、聖奈の方を向いた。
「家から帰って来いって、メールきたんだけど」
「じゃあ、送ろう」
「そうじゃなくて、今日泊まっても良い?」
「ダメだ」
「え~、どうせ明日も来るんだし、泊まった方が効率良いわよ」
「おまえな~。そんなこと言うから、おじさんから呼び戻されるんだよ」
この近所では、倉木家はあまり良い印象ではなかった。
「それだけが原因じゃないけどね~」
「まあな」
父親は近所付き合いは皆無なので、周りにあることないこと好き勝手言われていた。
「とにかくもう帰れ」
「はいはい、わかりましたよ」
聖奈はそう言いながら、キッチンから出ていった。
「いや、だから帰れって」
しかし、洗物を終えてもリビングでくつろいでいた。
「え、うん。9時に帰るわ」
「はぁ~、こういうことすると、詰られるのは俺なんだけど」
昨日、これを言ったらすぐさま帰ったので、同じことを言ってみた。
「ちゃんと釘刺してるから大丈夫よ」
「どういうことだ?」
「アー君のこと悪く言ったら、許さないって言っておいたわ」
「あ、そう」
聖奈の行動力に呆れながら説得は諦めた。
「じゃあ、俺は実験室にいるから」
さっきの論文で気になったことがあったので、実験でそれができるか検証してみたかった。
「ダメ。ここにいて」
しかし、聖奈が真剣な顔で止めてきた。
「理由を聞こうかな」
「お願い」
理由はないようで、悲しそうな顔で頼まれた。
「はぁ~、わかったよ」
こうなると押し問答になるだけなので、いつも秋彦の方が折れていた。
結局、9時まで不毛なテレビを見る羽目になってしまった。
「そろそろ時間だぞ」
早く実験したかったので、聖奈に急かすように言った。
「う~ん。もうそんな時間なんだね」
黙って寄り添っていた聖奈が、秋彦の肩に顔を埋めながら呟いた。
「俺と一緒にいて楽しいか?」
秋彦は、基本自分から話をしなかった。というか、難し過ぎて聖奈にはついてこれなかった。
「楽しいと言うより、落ち着くかな~」
「そうか」
「アー君は、私といるの嫌?」
これは何度目かの質問だったので、聖奈が不安に思ったようだ。
「う~ん。正直に言うと困ってる」
「どういうこと?」
「恋人になっても、セナをどう接していいかわからない」
「今のままでいいわよ」
困った秋彦を見て、聖奈が優しく微笑んだ。
「だったら、恋人じゃなくてもいいだろう」
接し方は恋人になる前と同じなので、恋人になるのは不要に思えた。
「それはダメ」
「う~ん。難しいな」
秋彦にとって恋愛は、論文を理解するより難しかった。
「そろそろ送るよ」
「あ、うん。そうだね」
聖奈が立ち上がったので、秋彦も一緒に立ち上がった。
「あ、そうだ」
「え、何?」
秋彦が玄関前で立ち止まると、後ろからついてきた聖奈の不思議そうな声が聞こえた。
「恋人同士って、抱き合うのが普通って聞いたけど、本当か?」
これは信也から聞いたことだった。
「え、あ、うん。そういう人が多いかもね」
これには珍しく戸惑いながら答えた。
「そっか」
それを聞いて、とりあえず恋人らしいことをしてみることにした。
「え、ちょ、ちょっと!」
急に抱きしめられたことに、聖奈の動揺が伝わってきた。
「う~ん。セナの臭いがする」
「わ、わわわ」
いつもは聖奈からくっついてくるのだが、この抱擁には消極的だった。
「嫌だったか?」
予想以上に動揺しているので、ゆっくりと聖奈から離れた。
「え、い、嫌じゃないけど、急だったから」
聖奈とは長い付き合いだが、秋彦からこんなことをしたのは初めてだった。
「抵抗あるならもうしないけど」
聖奈の反応を見る限り、あまりして欲しい感じではなかった。
「え、そ、それはして欲しいけど・・・」
急に聖奈の声が小さくなり、秋彦には聞こえなかった。
「どうした?珍しくしおらしいな」
こういうのを見るのは、小学生の時以来だった。
「う~、馬鹿!」
「なんでだよ!」
聖奈の理不尽な罵倒に思わずつっこんでしまった。
「もう帰る!」
それが気に入らなかったのか、聖奈が急に不機嫌になり、大股で秋彦の前を素通りした。
玄関で靴を履き、聖奈と一緒に家を出た。外は暗く、街灯が等距離間で地面を照らしていた。
黙ったまま二つ隣の緒方家まで歩くと、聖奈が急に立ち止まった。
「アー君。今度抱きしめる時は、私の許可を得てからして」
そして、不機嫌そうに注意してきた。
「あ、ああ」
これには理不尽さを感じたが、反論するとさらに悪化するので従うことにした。
「じゃあ、おやすみ」
聖奈の表情が一転して、笑顔で別れの言葉を口にした。
「お、おやすみ」
この変わりようにはついていけず、苦笑いで軽く手を振った。
聖奈が家に入るのを見て、すぐさま自宅で実験をすることにした。
実験部屋は改装していて、周辺に迷惑を掛けないように窓をなくして、完全防音にしていた。
今日の実験は、一ミリ立方の空間に膨大なエネルギーを集めるとどう変化するかの検証だった。これをすると、家庭電力ではすぐにショートしてしまうので、投資で得た資産で特注の発電機を買っていた。
それを稼働させて、いつもように電流の微調整から始めたが、今日は発電機の調子が悪く、エネルギーが周りに拡散して不安定な状態になっていた。
「う~ん。使いすぎたかな?」
発電機を買って1年近く使い続け、時にはフル稼働してた時期もあった。
しばらく調整しても直らないので、今日は諦めることにした。
「ふう~。残念」
秋彦はそう呟いて、発電機の電源を落そうとした。
その瞬間、バチィと音と共に発電機のモーターが異常な音を鳴らしてフル回転し始めた。
「ヤバい!」
電力メーターをフルスロットにしていることを思い出したが、時すでに遅く膨大なエネルギーの光が部屋全体を包み込んだ。
第二話 二つ目の可能性
「いたっ!」
秋彦は、頭の痛さで目が覚めた。
「あ、あれ?」
周りを見ると、見慣れない部屋で横たわっていた。朝のようだが、部屋のカーテンは閉め切っていて、部屋全体は薄暗かった。
「む、ほこりっぽい」
部屋には、物が乱雑していてほこりが舞っていた。一言で言うとゴミ屋敷みたいだった。
あまりの不快さに部屋のドアを開けると、今度は見慣れた廊下を目にしたが、ゴミ袋や弁当箱の空き箱が散乱していた。
「は?」
この状況には頭が真っ白になった。
ふと気づくと、手には見たことのないスマートフォンが握られていた。
「え、ここって・・俺の家?」
部屋の間取りから言えば、今出てきた部屋は実験室のはずだった。
「え~っと、昨日は実験していて、発電機の誤作動で異常なまでのエネルギーが部屋に拡散したんだっけ?」
口にして状況を理解しようとしたが、なぜここが自分の家なのかは理解できなかった。
考えても答えが出ないので、スマートフォンをポケットに入れて、家の状況を確認することにした。
「あ、父さん」
実験室からリビングに行くと、父親がソファーで寝ていた。しかし、周りはゴミだらけで、自分の家とは思えなかった。
「ちょっと、父さん。起きてくれ」
この混乱している状況では、誰かに説明して欲しかった。
「う・・ん」
父親がゆっくりと目を開けて、顔を秋彦の方に向けた。髭は3日は剃っておらず、髪の毛はボサボサで洋服もあちこち汚れていた。風貌は父親だが、雰囲気はかなり違っていた。
「どうかしたか?」
父親がしゃべると、口からアルコールの臭いがした。
「父さん、なんでお酒なんか飲んでるんだ?」
父親はアルコールに弱く、酒は滅多に飲まないはずだった。
「は?何言ってるんだ?」
これには父親に訝しげな顔をされた。
「・・・」
この返事からして、あまり下手な質問はしない方が良さそうだった。
「父さんの仕事ってなんだっけ?」
少し聞き方を変えて、外堀から埋めていくことにした。
「おまえ、喧嘩売ってんのか!」
質問が悪かったようで、いきなり激怒されてしまった。
「え・・・」
秋彦が知ってる父親は、こういう時は冷静に馬鹿にするのだが、ここまで感情的になられると別人に見えてしまった。
「面倒臭いな~」
ここで言い合うと話が進まないので、話し方を変えることにした。
「父さん。この家の状況と現状を報告してくれ」
「な、何言ってんだ、おまえ」
息子の変わりように、さすがの父親も動揺を見せた。
「ごめん。戸惑うのもわかるけど、一番混乱してるのは俺なんだよ」
「お、俺?」
秋彦の言葉遣いに違和感があるようで、父親が驚きの顔をした。
「俺の話をする前に、今の父さんの状況を教えてくれ」
「ど、どうしたんだ、おまえ」
「それはこっちの台詞」
父親とやり取りをしている限り、仕事をしているとは到底思えなかった。
「はぁ~、仕方ない。俺の状況から話すよ」
父親の返答がなかなかないので、こっちの状況を話すことにした。
一通り話すと、父親の表情は真剣そのものになっていた。
「そ、そうか・・信じられんな」
「それはこっちも同じ」
こんな現象、研究者である親子には信じられるものではなかった。
「で、こっちはどうなってるんだよ」
この家の状況を見ると、一刻も早く掃除をしたかった。
「父親としては恥ずかしい限りだが、無職だ」
「だろうな」
「お、驚かないんだな」
部屋の状況と、父親の返事を聞けばすぐにわかることだった。
「で、母さんは?」
「8年前に交通事故で亡くなってる」
「そうか。そっちは変わらなかったのか」
「変わったというならそれからだ。国が傾いてな。公務員が大幅削減になって、大学をクビになった」
「最初に切られたのか?」
「あ、ああ。恥ずかしながら」
本当に恥ずかしいようで、指で頬を掻いた。
「それで?」
「え~、ほら、今まで研究以外したことなかったから・・・」
言いにくいのか、言葉がはっきりしなかった。
「再就職に失敗した・・と」
「まあ、あり大抵に言えば」
「はぁ~」
これには大きな溜息が漏れた。
「こ、こっちだって頑張ったんだぞ!」
「頑張ってその結果じゃあ褒められない」
「せ、正論を言うなよ」
息子の辛辣な言葉にがっくりと項垂れた。
「で、国が傾いた原因は?」
「あ~、なんだっけな~。確か金融ショックがどうたらこうたら」
「あ~、こっちでも社会情勢には疎いのか」
「わ、悪い」
酔いは完全に醒めたようで、しおらしく頭を垂れた。
「あとは・・・俺の現状だな」
「え、あ~、まあ、頑張ってるみたいな?」
父親の煮え切らない返事に嫌な予感がしたが、避けては通れなかった。
「ちゃんと言ってくれ」
「成績は下位で、運動音痴。いじめを受けている感じだ」
「最悪だな」
「だ、だから、家にかくまっている状況だ」
「はぁ~、親子揃ってニートですか」
これは頭を抱える大問題だった。
「じゃあ、収入源は何?」
「雀の涙ほどの生活保護です」
税金を食い潰している罪悪感はあるようで、本当に申し訳なさそうな顔をした。
「ちっ、国のせいで国に世話されてるなんて、面白くもない冗談だな」
これには自分のプライドを粉々に砕かれた気分に駆られた。
「ん?母さんの交通事故での慰謝料は?」
「使い果たしました」
「ダメ人間」
父親の金銭管理は、こっちでもルーズのようだった。
「ところで、なんで酒なんて飲んでるんだよ。アルコール弱いだろ」
「や、ヤケ酒」
「アホか!」
これには思わず父親を罵倒してしまった。
「申し訳ない」
完全に親子の立場が逆転していた。
「それで、生活保護でもう就活する気無しってわけ?」
「いや、そういう訳じゃないが、研究以外適職がなくて」
「視野が狭いな~」
研究者一筋な性格も、ここでも変わらないようだった。
「あと気になってるんだけど、俺の態度とかってどんな感じだった?」
「う~ん。ほとんど引きこもって、あんまり話はしなかったな~」
「人間不信的な感じ?」
「そうそう、そんな感じ」
秋彦の的確な言葉に嬉しそうに相槌を打った。
「ヘタレめ」
これには自分への怒りが込み上げてきた。
「もう一つ、二つ隣りに緒方聖奈っている?」
「あ、ああ。おまえの幼馴染ね」
「セナはいるのか」
「学校じゃあ、優等生みたいだぞ」
「セナが優等生?」
いつもテスト勉強で教えてあげて、やっと上位の成績を保っていた聖奈が、優等生になっているのは驚きだった。
「まあ、おまえから聞いたのは2年前だけどな」
どうやら、情報源は自分のようだった。
「事情はだいたい呑み込めたよ」
あまり信じられないことだが、パラレルワールドというものが実際にあることが、自身の体験で立証できた。しかし、証明しようにも記憶全体がここに飛んでしまっては、証明するのは無理だった。
「ちっ、こんな体験、自分が不利になるだけで何の意味もないな」
自分で状況を整理しても、愚痴しか出てこなかった。
「ん?ってことは、あっちにはあっちで影響があるのか?」
「そ、それより、どうやって入れ替わったんだ?」
秋彦の独り言に、父親が食い気味に聞いてきた。どうやら、この現象の経緯が気になって仕方ないようだった。
「事故だから説明できない。それに実証しようにもこの体は自分だし、記憶の証明なんてしようもない」
「ま、まあ、そうだな。せいぜい精神疾患扱いされるだけだな」
父親も冷静になったようで、パラレルワールドへの立証が難しいことをわかってくれた。
「まずは、父さんの意思を聞こうか」
ここは気を取り直して、父親のこれからの意向を聞くことにした。
「これからどうしたい?」
「は、何が?」
秋彦の言ってることが理解できないようで、素で聞き返された。
「このままくすぶるつもり?俺はごめんだな、こんな生活」
「そ、それは・・・」
返事に窮してるようだが、今の現状から目を背けたいという意思だけは、はっきりと伝わってきた。
「聞き方が悪かったな。俺と一緒に研究とかしてみない?」
「で、できるのか?」
研究と言う言葉に惹かれたようで、身を乗り出してきた。
「父さんさえ、協力してくれてるならな」
「す、する。なんでもするぞ」
「そ。じゃあ、まずは家の掃除からしようか」
正直、もうこのゴミの山には我慢の限界だった。
「は?」
掃除することが意外だったようで、ポカンとされた。
「父さんが片づけ出来ないのは知ってるから、俺の指示通り動いてくれ」
大掃除の時は、ほとんど秋彦の指令のもとで父親を動かしていた。
「わ、わかった」
秋彦の強引さに少し押され気味に返事をした。
父親には家全体のゴミの収集を命じて、秋彦は自分の部屋を整理することにした。
「なんだこれ?」
入ってすぐに、その言葉が口に出た。部屋にはゲームや漫画が散乱していた。自分の全く興味のない物ばかりで、見知らぬ他人の部屋に入った気分になった。
「本当に俺か?」
この状況には、頭を抱えて本気で悩んでしまった。
秋彦自身、興味がないので捨てるかどうか悩んだが、自分の判断で捨てるのは気が引けるので、整理整頓だけにしておいた。
作業を始める前にポケットに違和感を覚えて、スマートフォンがあることを思い出した。
「俺がスマホ持つなんてな~」
セキュリティの低いスマートフォンは、心配性の秋彦にはそぐわないものだった。
スマートフォンで秋彦の現状を確認しようと電源を入れたが、ロックが掛かって見ることができなかった。
「こっちの俺も心配性みたいだな」
秋彦はそう呟いて、スマートフォンの電源を切った。
夕方までに全体の掃除を終えると、父親が驚いた顔をしていた。
「本当に凄いな。自宅じゃないみたいだ」
「いつもはこんな感じにしてる」
秋彦としては、この状態が日常だった。
「じゃあ、夕飯作るからテレビでも見ててくれ」
昼は冷蔵庫にあった弁当だったので、夕飯は作ることにした。
「料理もできるのか?」
「あっちでも、父さんと二人暮らしだぞ」
「そ、そうだったな」
「全く、こっちの俺はかなり無能だったようだな」
「いや、おまえが有能過ぎると思う」
秋彦の愚痴に、父親が間髪入れずつっこんできた。
「まずは、今の全財産を把握しておきたいな」
それによって料理の献立を決めることにした。
「すまん。借金してる」
「くっ、こっちも無能だったか」
この事実に思わず悪口が出た。
「お金の管理は、これから俺がする」
「え?」
「あっちでもそうしてる」
「そ、そうか。じゃあ、頼むよ」
父親から、借用書と今ある全財産を渡された。
「生活保護の支給はいつ?」
「来週」
「きっついな~」
この金額では、二人分の食費ですべて吹っ飛ぶ額だった。
「これから禁酒な。あと、一日二食」
「何!」
「文句ある?」
父親が抵抗を示したので、睨むかたちで威圧した。
「ないです」
情けないことにその一睨で簡単に平伏した。
「生活保護で借金してるなら、投資口座の開設もできんな~」
この現実には先行きが不安になった。
「買い物行くけど、部屋は散らかすなよ」
「あ、ああ」
掃除の後だった為、ジーパンとTシャツに着替えてから家を出た。
外の景色は大して変わっていなくて、少し安心した。金融ショックがあっても、地域はさほど変わらないようだった。
「変わってるのは人間関係だけなのかな?」
ここにきて人の変化には驚いたが、使ってる器具や家電はあっちと変わらなかった。
スーパーは緒方家の前を通るので、何気に緒方家を確認したが外観は全くの同じだった。
「ってことは、ここではセナと恋人じゃないんだな」
この事実を口にすると、少し寂しい気もした。
スーパーで手早く食材と調味料を買って、来た道を戻った。
「あっ」
最悪なことに緒方家の前で、聖奈と鉢合わせしてしまった。艶やかの長髪も優雅な立ち振る舞いも、あっちと全く変わってなかった。日曜日ということもあり、白の七分丈のシフォンブラウスに淡い赤のキャロットスカートの私服だった。
しかし、ここでは恋人ではないので、素っ気なく素通りすることにした。
「ふん。もう引きこもりはやめたの?」
聖奈の蔑みの声が、後ろから聞こえてきた。とても聖奈とは思えない辛辣な言葉に、思わず振り返ってしまった。
「へぇ~、ここではそんな感じか」
あまりの新鮮さに、思ったことをそのまま口に出してしまった。
「は?」
それが癪に障ったのか、不快感をあらわにした。
「セナって、俺と幼馴染だよな~」
自分に対しての態度を確認しておきたいので、流す感じで聞いてみた。
「せ、セナって・・・気安く呼ばないでよ。あなたとは、ただ近所なだけでしょう」
「ふ~ん。そっか」
聖奈の気持ちの揺らぎを感じて、どこかで関係がこじれたと推測した。
「じゃあな」
これ以上は訝しがられるので、帰ることにした。
「ちょっと待ちなさいよ」
しかし、強い口調で引き止められた。
「あなた、本当に秋彦?」
女の勘は鋭いと言うが、どっちの聖奈も勘は鋭いようだった。
「・・・違うって言ったらどうする?」
ここは意味深な言葉で返すことにした。
「ど、どういう意味よ」
「さあ~な」
それだけ残して、悠然と家に帰った。
夕食は父親と二人揃って、テレビを見ながら食べた。息子手作りの夕食は、父親には大好評だった。
「これからのことなんだけど」
夕食後、秋彦がそう切り出すと、父親の動きがビタッと止まった。
「仕事辞めて、勉強してた?」
「し、してない」
「今日までダラダラしてただけ?」
「あ、ああ」
「人って落ちる時は、どこまでも落ちることがここで証明されたな」
「め、面目ない」
「これからやることは一つだな」
買い物しながらいろいろ考えたが、父親の答えで一つに絞ることにした。
「やっぱり、仕事・・か?」
この年で再就職が怖いようで、弱々しい声で聞いてきた。
「まあ、そうだけど。こんなだらけた生活送っている人間が、いきなり仕事してもうまくいかない」
脳を急に働かせてもうまくいかないように、肉体も同じだと思っていた。
「よって、これから勉強することを義務付ける」
生活保護を切り詰めて、借金を少しずつ返す手もあるが、それでは時間が掛かる上、資金も貯まらないことは明白だった。
「1年分の論文をジャンル問わず掻き集める。それをできるだけ詰め込んでくれ」
「無理だ!」
さすがに膨大な論文の理解は無理があったようだ。
「論文のほとんどは英文だし。こっちは翻訳しながら読むだけで、どんだけ時間掛かると思ってるんだ」
「ああ、それ。俺が翻訳するから、安心してくれ」
「は?」
「あと、どこの言葉もほとんど翻訳できるから、わからなかったら俺に頼んでくれ」
論文を読む為、英語を主軸にいろんな文字を勉強していた。しかし、敢えて読めるだけでしゃべれる訳ではなかった。
「・・・おまえ、本当に秋彦か?」
さすがにここまで有能だと、気味悪さが強く出たようだ。
「そうだよ。こっちで育ってはないけどな」
洗物を終えて、父親には唯一自宅にあった自分の論文を再読させて、秋彦はネットで今の社会情勢を調べておくことにした。
深夜3時まで調べて、この世界の情勢の七割は理解できた。
「マジかよ」
理解できた上での感想がそれだった。
「たった一人の死で、ここまで乱れるものなのか」
亡くなったのは、海外の大型金融会社社長の突然死だった。それが原因で金融会社全体が揺れに揺れ、全世界が大打撃を受けていた。
その中でも、一番打撃を受けたのが日本だった。国民の知らない所で、この金融会社に多大なお金をつぎ込んでいて、大規模な損失に繋がっていた。それが原因で公務員の大幅削減を行っていた。
「昔の政府って、馬鹿だったのか?」
一般的に最初に切るなら、政治家だろう。次に役所、最後に教師、警察、自衛隊のはずだった。
しかし、政治家は報酬削減だけして、公務員全体の大幅削減を行っていた。そのせいで、地域の労働組合が司法に訴えたことで、役所も学校、警察が一時期機能不全に陥った時期があったようだ。
「結局、どっちも身の保身にはしってるな~。見苦しいことこの上ない」
これを見るだけで、気が滅入ってしまった。
「この情勢だと、生活保護抜け出せても口座開設も厳しいな~」
株価を見る限り、ここ最近の株は安定していて、全世界の情勢を見ても株価が急激に動くような情報はないようだった。
「まあ、今あっても困るか」
口座開設してない状態で、そんなことになったら苛立ちが募るだけだった。
もう遅いので、今日はここまでにすることにした。
「はぁ~、先が思いやられる」
ベッドに横になると、これから先の未来が見えなかった。昨日まで研究に費やすことしか考えてなかったが、これからは生活費と研究資金を稼がなくてはならなかった。
「スタートからやり直し・・か」
これを口にすると、思わず溜息が漏れた。
第三話 親の矯正
朝10時に目覚めて、リビングに行くと、父親が論文と格闘していた。
「どう?」
「あ、ああ。自分の学力低下を実感してる」
「だろうな」
数学の関数なんて日常では使わないので、忘れるのは至極当然だった。
「今から朝食作るけど、仕事での知り合いとは連絡取れる?」
「あ、あ~、もう連絡取ってない」
「じゃあ、知ってる限りでいいから、電話して論文とか掻き集めてくれ」
「え、いや、だから、連絡取ってないって」
「今から取れ」
秋彦は、脅すように笑顔で命令した。
「は、はい」
父親の返事を聞いてから、朝食の準備を始めた。
朝食後、三人と連絡が取れたようだった。
「いつ会えそう?」
「明日は、平日だから一人しか約束できなかった」
「その人は仕事してないのか」
「ああ、あいつは特許持ってるから、それだけで食っていけるんだ」
「特許か・・その手もあるか」
そうは言ったが、技術の特許は逆算しても4年以上は掛かりそうなので、頭の片隅に置くだけにした。
「あとの二人は、いつ会えそうなんだ?」
「あっちの返事待ちだな。たぶん、日曜日とかになりそうだ」
「まあ、こればかりは仕方ないか。あとは、ネットで補うしかないな」
「でも、なんで論文なんだ?」
「研究が被ったら無駄だから」
「まあ、確かに」
「正直言うと、ここではどこまで研究が進んでいるかも興味ある」
「なるほど」
これには研究者として納得してくれたようだ。
夕方になり、秋彦は不愉快な気分で父親のいるリビングへ向かった。
「進んでる?」
秋彦の呼びかけに、父親が読んでいた論文から顔を上げた。
「ど、どうした?機嫌が悪いな」
「残念なことに、ここは1~2年遅れてるみたいだ」
「そ、そうなのか?」
「経済が落ち込んだせいで、研究費も縮小されたみたいだな」
「まあ、こっちもクビになったしな」
そう言うと、溜息をついて項垂れた。
「あと、ネットに公開されてる論文を翻訳してプリントアウトしといたから、1週間以内に読み終えてくれ」
秋彦は、数冊に及ぶ論文を父親に差し出した。
「こ、こんなに・・・」
「これは父さんの昔の研究テーマに近い物ばかりだ」
「そ、そうか」
調べ上げてわかったことだが、論文の結果は一緒だが、内容の表現は変わっているものが多かった。
「で、そっちはどう?」
「あ、ああ。少しずつだが思い出してきた」
「まあ、無理に詰め込んでも仕方ないから、自分のペースでやっていいよ」
父親は無理させると体調を崩すので、あまり強制することはできなかった。
「なんか急に優しくないか?」
「父さんの体質は熟知してるからな」
あっちでの父親は研究に没頭するせいで、何度も体調を崩すことがあった。
「無理させて、倒れられたら効率が悪い」
「息子に言われると、立つ瀬ないな」
「あっちではよく倒れてたよ」
「そうなのか。まだ公務員なのか」
「うん。准教授になって雑務に追われてるから、深夜に泊り込みで研究に没頭してる」
「う、羨ましい」
「こっちとしては、3日連続で泊まられるのは困るんだがな」
「あっちでも迷惑掛けてるのか」
「まあな」
「頼りない父親で申し訳ない」
「そう思うなら、これから頑張って欲しい」
「ど、努力します」
夕食の準備を始めようとすると、玄関のチャイムが鳴った。
「こんな時間に誰だ?」
「多分、学校の連絡プリントを渡しに来たんだろう」
「ああ、なるほど」
玄関を開けると、聖奈が不機嫌そうに直立不動で立っていた。
「あ~、なんか用?」
ここでは恋人ではないので、素っ気ない態度を取った。
「引きこもりの癖に、横柄な態度ね」
しかし、聖奈には偉そうに見えたようだ。
「そういう皮肉はいらんから、用件を言ってくれ」
「明日から中間テストだから、学校に来いって。あと、校内プリント」
そう言うと、手に持っていたプリントを渡された。こっちでは秋彦と聖奈は同じクラスのようだ。
「ボランティアね~」
プリントには、ボランティア募集のお知らせが書いてあった。
「ありがとう」
一応届けてくれたので、お礼は言っておいた。
「もう学校辞めたら?」
玄関を閉めようとすると、聖奈が蔑視の眼差しでそう言ってきた。
「そうだな。明日退学届けを出しておこう」
別に行く必要もないので、それを受け入れることにした。
「え、辞めるの!」
自分で薦めてきたのに、その本人が驚きの声を上げた。
「まあ、低レベルの教育は意味ないしな」
「て、低レベルって・・その学校で成績悪いじゃない」
「ああ、そうだったな」
言われてみれば、立場的には違和感のある発言だった。
「じゃあ、訂正しよう。セナに迷惑掛けるから辞める」
わざわざ伝言とプリントを渡しに来てもらうのは、秋彦としても申し訳なかった
「だ、だから、気安くセナって呼ばないでよ」
「あ~、昨日も言ってたな。なんって呼んでたっけ?」
「聖奈でいいわ」
「あんまり変わらんだろう」
あまりにも呼び慣れていないので、嫌な顔で拒否してみた。
「・・・本当に秋彦?」
「ああ。見たまんまだろう」
「対応が全然違うわ」
「そうか。心変わりしたからかもな」
「秋彦は、そんな軽口は言わなかったわ」
「心変わりしたからな」
「・・・」
同じ答えに、聖奈の表情が険しくなった。
「何があったのか説明してくれない?」
「心変わりについての説明か?」
「人は、そんな極端に変われないわ」
「それは人それぞれだろう」
「少なくとも秋彦はそうじゃないわ」
「なんでそう言い切れる?」
「腐れ縁だからよ」
「気安く呼び合えない仲なのに、よくそう断言できるな」
「・・・」
秋彦の意地悪な返しに、聖奈が不満そうに睨んできた。
「どうしたんだ?」
少し長かったようで、父親が玄関まで出てきた。
「あ、緒方さん」
父親が聖奈をさん付けで呼んだ。
「道春さん。秋彦の様子がおかしいんですけど」
秋彦越しに、聖奈が父親に話を振った。
「あー、いろいろと事情があってね」
さすがにこの状況を説明できないと思ったようで、曖昧に返した。
「まあ、セナには関係ないから」
「それは酷くないか」
これには父親が、聖奈の顔色を窺うように言った。
「もう学校も辞めるし、この家に来る必要もなくなる」
「え!学校辞めるのか?」
「だって、無駄だし」
父親の驚きを流すように吐き捨てた。
「明日、論文回収ついでに退学届を出しに行くから」
「え、急すぎないか」
「引きこもりになったのはいつからだっけ?」
「あーっと、2ヶ月前?」
あまり自信がないのか、最後に疑問符が付いていた。
「1ヶ月半前です」
父親の言葉を訂正するように、聖奈が割って入ってきた。
「1ヶ月半・・ね」
逆算すると、進級して半月の間にいじめにあったようだ。
「そうだな。じゃあ、なんとか教師を理詰めで説得してみよう」
「それ、反感買わないか?」
これには父親から呆れ気味に指摘された。
「じゃあ、泣き落とすか」
「特別教室行き確定ね」
今度は、聖奈からはっきりと断定された。特別教室は生徒一人に対して、教師と二人の精神科医を付けて、更生させるという国が決めた制度だった。
「最終手段としては、学校を脅すか」
「お、脅すって・・本気で言ってるの?」
「ああ。今の現状を考えれば、こっちの方が簡単だ」
「・・・」
その答えに不信感を持ったようで、訝しげに秋彦を見つめた。
「もう帰れ」
聖奈には関係ない話なので、ここで帰すことにした。
「お邪魔します」
それが癇に障ったのか、秋彦を押しのけるように玄関に入ってきた。
「いや、帰れよ」
秋彦がそう言うと、聖奈が父親を背にして睨んできた。
「もしかして、俺のこと好きなのか?」
積極的に関与してくるので、本気で嫌われてはいない気がした。
「な、何言っての、この馬鹿!」
あっちではベタベタ引っ付いてくるが、こっちでは正反対で辛辣な態度だった。
「もしかして、あっちではそうなのか」
秋彦の事情を知ってる父親が、興味深そうに聞いてきた。
「恋人」
「マジで!」
これには本当に驚いた顔をされた。
「え、何が?どういうこと」
一人置いてきぼりの聖奈が、秋彦たちに説明を求めてきた。
「説明しても信用しないかも」
父親は息子の言葉を信じてくれたが、幼馴染でしかない聖奈が信じてくれるとは思えなかった。
「聞いてみないとわからないでしょう」
「じゃあ、簡潔に言うが、パラレルワールドって知ってるか」
「知ってる」
「それ」
「は?」
「だから、パラレルワールドの一つと入れ替わったんだよ」
「・・・何言ってんの?」
やはり、一般感覚では理解は難しいようだった。
「これで信じられないなら、説明しても無駄だから帰れ」
「あー、信じる信じる」
「何、その棒読み?」
明らかに信じている人の台詞ではなかった。
「っていうか、セナは俺に興味あるのか?」
「はぁ!何勘違いしてるのよ!」
「怒鳴るなよ」
「秋彦が変なこと言うからでしょ!」
「変なこと言ったか?」
秋彦自身そうは思えなかったので、父親に聞いてみた。
「微妙」
これに父親が、困った顔で首を捻った。
「まあ、いいや。とにかく今は入れ替わってるんだよ。証明は無理だから、個人で判断してくれ」
「ファンタジーね」
「そうだな。だが、俺にとっては現実になってしまっている」
時計を見ると、6時半になっていた。
「もう帰れ」
「なんでよ」
「時間的にも、親が心配するだろう」
「まあ、そうね」
そう言うと、聖奈はポケットから携帯電話を取り出し、電話を掛けた。
「ちょっと遅くなるから」
電話相手にそれだけ伝えて、携帯を仕舞った。
「これで話し合えるでしょう」
「やっぱり好きなのか?」
「同じこと言わせないで」
二度目ということもあり、目だけで威圧された。
「で、そのパラレルワールドの一つって、どうなってるの?」
図々しくもソファーに座って、経緯を聞いてきた。
「俺とセナが恋人になってる」
「最悪ね」
「そうか?あっちのセナは、すごく幸せそうな顔してるぞ」
「ま、まあ、その可能性もあるってことね」
「そうだな。どこで逸れたんだ?」
「普通、それ聞く?」
「セナの反応を見る限り、態度はきついが俺を気に掛けているように見える」
「か、勝手な解釈しないでよ」
「そうか~?態度見れば、かなりわかりやすいんだが」
「ふん。それは大きな勘違いよ」
秋彦の指摘に、聖奈が素っ気ない態度で顔を逸らした。
「で、どこで疎遠になったんだ」
「そうね。私に彼氏ができた頃かしら」
「へぇ~、彼氏いるんだ」
個人的には複雑だったが、ここは淡泊に言っておいた。
「ごめん、今の嘘。告白はされたけど、付き合わなかった」
「謝るなら、最初からそう言えよ」
これにはさすがに呆れるしかなかった。
「嫉妬して欲しかったんだろう」
「道春さん。勝手な解釈はやめてください」
「すみません」
聖奈の冷徹な眼差しに、父親が簡単に屈した。
「こっちのセナはツンデレだな」
「誰がツンデレよ!」
ツンデレというのは認めたくないようで、物凄い形相で怒鳴られてしまった。
「ったく、あなたは本当に秋彦じゃないのね」
このやりとりで、パラレルワールドを信じてもらえたようだ。
「話を戻すと、彼氏ができたと嘘をついたら、それから疎遠になったのよ」
「自ら身を退いたのか」
「そういうことになるわね」
聖奈はそう言いながら、寂しそうに溜息をついた。
「そっちの私もこの嘘ついた?」
「いや、中学になったら付き合ってと言われた」
「せ、積極的なのね」
「まあな。恋人になっても接し方は変わってないけど」
「どう接してるのよ」
「セナがベタベタ引っ付いてくるから、俺はそれに身を任せてる」
「・・・ちっ」
秋彦の話が気に入らないようで、聖奈が舌打ちした。
「帰る」
そして、不機嫌そうに聖奈が帰っていった。
「なんだあれ?」
「多分、羨ましかっただろうな」
息子の疑問に、父親が微笑ましそうな顔で答えた。
「はぁ~、夕食は遅れそうだな」
秋彦は、時計を見て溜息をついた。
「本当に退学するのか」
父親が再び話を蒸し返してきた。
「どうせ引きこもりだしな」
「これを機に復帰したらいいだろう」
「俺にいじめを体験してこいと言うのか」
「いや、そういうつもりで言ったわけじゃないんだが」
引きこもりになった理由を思い出したようで、苦い顔で言い繕った。
夕食後、父親に論文の補てんをするように簡潔に解説した。
「す、凄いな。本当にこの論文を理解してるのか」
「疑ってたのかよ」
「いや~、ここまでとは思わなくて」
「この研究は、父さんから良く聞かせれてたからな」
「ん?秋彦と研究テーマは一緒じゃなかったのか」
「父さんは大学でしてるんだから、俺はできないだろう」
「ああ、それもそうだな」
「俺の研究は、空間の屈折現象だよ」
「は?」
「決められた空間に膨大なエネルギーを与えると、空間にどんな影響が出るかを実験してた」
「い、家でか?」
「ああ。株と外為で資金を稼いで、あの部屋を改装したんだ」
秋彦は、奥の部屋を指差して言った。
「羨ましい生活だな~」
「でも、学校はセナにせがまれて通ってた」
「女には弱いんだな~」
「惚れた弱みだな」
好きな人に必死で頼まれたら、強気に断ることができなかった。
「それはわかる気がする」
父親もその事を思い出したのか、懐かしむように視線を上に向けた。
この後、深夜まで父親に工学の基礎知識を教えた。
「あとは、応用するだけだから。それは自分で考えてくれ」
全部教えると発想力が無くなるので、自力でさせることにした。
「お、おう」
「大丈夫か?」
「ああ、悪い。ちょっと理解が追いついてない」
「まあ、それもそうか。もう何年も勉強をしてないもんな」
こういう正直さは、父親の長所だった。
「わからなくなったら、また聞いてくれ」
秋彦は自分の部屋に入り、退学届を書きながらこれからの計画を考えた。
第四話 幼馴染の奇行
翌朝、けたたましい玄関のチャイムで目を覚ました。時計を見ると、まだ7時になったばかりだった。
「誰だよ。こんな時間に」
秋彦は、重いまぶたを擦りながら体を起こした。寝たのは3時だったので、かなり寝不足だった。
リビングに行くと、父親が怯えながら秋彦を見た。
「しゃ、借金取りかも」
「あ~、そういえば、借金してたな」
父親に言われて、借金している金融会社を思い浮かべた。
「おかしいな~。こういう取り立ての会社はないはずなんだが」
昨夜、借用書を確認したが、一般的な金融会社ばかりだった。
「父さんは、隠れておいてくれ。俺が対応するから」
父親の怯えように、相手の対応は難しそうだった。
「いや、ここは居留守を使った方がいいって」
「大丈夫だ。その時は法に訴えるから」
秋彦は寝癖を整えながら、玄関のドアを勢いよく開けた。
「うるせぇ~よ!」
借金取りを一喝する為、大声で怒鳴っておいた。
「わっ!」
しかし、そこにいたのは聖奈だった。
「って、なんだ。セナかよ」
これには思いっきり肩透かしをくらってしまった。
「いきなり開けないでよ。驚くでしょう」
「何度もチャイム鳴らすな。借金取りかと思うだろう」
「だって、何回押しても出てこないもの」
「だったら、電話でもしろよ」
「秋彦の家って固定電話ないし、携帯の番号も知らないのよ」
こっちでは聖奈と電話番号を交換してないようだった。考えてみれば友達でも恋人でもないので、番号交換してなくても不思議ではなかった。
「で、用件はなんだよ」
「今日から中間テストって言ったでしょう」
「ああ、聞いたな」
「だから、迎えに来たんじゃない」
「えっと、昨日の話聞いてた?」
これには聖奈の記憶力が心配になってしまった。
「退学届出すんでしょう」
「知ってるなら、迎えに来るのはおかしいだろう」
「そうね」
秋彦の指摘に、聖奈がしれっと答えた。
「・・・迎えにきた理由を聞こうか」
「先生に頼まれたからよ」
それを聞いた瞬間、秋彦はドアを閉めた。
「え、ちょ、ちょっと!今の嘘!嘘だから開けて!」
聖奈がドアを必死に叩きながら、大声で叫んだ。
「うるさいって」
秋彦はドアを開けて、聖奈を注意した。
「お邪魔します」
再び閉められることを恐れたのか、秋彦を押しのけて家に入ってきた。
「勝手に入るなよ」
「外で話してると目立つでしょう」
「俺をほっといて学校に行けば、問題は解決するだろう」
「それだと私の早起きが無駄になるでしょう」
「知らねぇ~よ」
聖奈の的外れな返しに呆れ気味につっこんだ。
「なんだ。緒方さんだったのか」
奥に隠れていた父親が、ホッとした顔で出てきた。
「おはようございます。道春さん」
「あ、ああ。おはよう」
父親は、恐縮しながら挨拶を返した。
「早く着替えてよ」
聖奈が秋彦を見て、淡泊に指図してきた。
「俺の意思にその選択肢はないんだが」
「も、もし学校に行くのが怖いなら、わ、私が一緒に登校してあげるわ」
恥ずかしいのか、少し言葉に動揺が見られた。
「・・・」
「・・・」
あまりのツンデレっぷりに、親子二人言葉が出なかった。
「な、なんか言いなさいよ」
親子の呆れ顔に、聖奈が言葉を求めた。
「これは押し問答になるな」
こっちの聖奈も頑固なようで、拒んでも引きそうになかった。
「どうするんだ?」
父親が困った顔で小声で聞いてきた。
「父さんは、ちょっと席外してくれない?」
「あ、ああ。そうだな」
秋彦の意思を汲んだようで、父親が奥の部屋に引っ込んでくれた。
それを確認して、聖奈をダイニングの椅子に座らせた。
「さてと、セナの意思を聞こうか」
聖奈の正面に座って、秋彦から切り出した。
「い、意志って何よ」
「セナが迎えに来たってことは、俺を辞めさせたくないってことでいいんだよな」
「・・・」
本音は言いたくないようで、無言の返しをしてきた。
「俺には素直になってくれない?」
「・・・い、いまさらできない」
もうこの性格が定着してしまったようで、本音を小声で呟いた。
「こっちのセナも新鮮だな」
いつも大胆な聖奈に対して、こっちの聖奈は愛くるしいものがあった。
「な、何よ~」
秋彦の視線に、聖奈が不満そうに唸った。
「抱きしめていい?」
あまりの愛くるしさに抱きしめたくなった。こういう気持ちになったのは初めてだった。
「は、はぁ!な、ななな何言ってんの!」
「まあ、嫌ならいいが」
嫌々するのも悪いので、すぐに身を引いた。
「も、もし許可したら、学校行ってくれる?」
「え、それはない」
聖奈の恥じらいの言葉に即答で否定した。
「な、なんでよ!」
「それとこれとは話が別だ」
抱擁だけで、学校に行くのは割に合わなかった。
「恋人になるなら、学校行ってもいいぞ」
これは聖奈からダメな秋彦を引き離すための方便だったが、あわよくば恋人になりたいという思いもあった。
「え!あ、え~、っと。う~ん」
「嫌なら交渉は決裂だ」
予想通り言葉に詰まったので、ここで話を切ることにした。
「ほら、もう行け」
秋彦は時計を指して、聖奈に登校を促した。
「こ、恋人は状況的に難しいけど、い、一緒にいることはできると思う」
「どういうことだ?」
「が、学校に行ってくれればわかる」
「あ~、いじめられてるからか?」
こっちの聖奈も世間体を気にしているようだった。
「そ、それは私が止めるけど、そうじゃなくて・・・」
「歯切れ悪いな。はっきり言え」
「あ、秋彦を好きな人がいる」
「はぁ?引きこもりの俺を?」
「う、うん」
「でも、それが恋人になれない理由にはならない気がするが」
「その子、秋彦に熱入れていて」
「関係ないだろう」
「・・・」
それは論点をズラしているだけで、恋人になれない理由にはならなかった。
「セナの言いたいことは、疎遠になってる自分がいまさら恋人になれないってことか」
「そ、そんな感じ」
「そっか。じゃあ退学するか」
自分を好きという子は秋彦には面識もないので、付き合う気はなかった。
「そ、それは困る」
「なんで?」
「じ、実は昨日ここに来るのは、その子だったんだけど・・・秋彦の様子が変わってたから、私が強引に引き受けたの」
「俺に気を使ったのか」
「ま、まあ、そんな感じ」
さっきから聖奈の挙動がおかしかった。
「それと俺が退学することと関係があるのか?」
「引き受ける時、学校に来させるからって約束しちゃったから」
「そんなの知るか」
それは聖奈で約束したことであって、秋彦には全く関係なかった。
「う~、そ、そんなこと言わないでよ~」
「ほら、早く行かないと遅刻するぞ」
「あと40分あるわよ」
急かしたつもりだったが、登校までの時間には余裕があった。
「もう諦めろよ」
「それができればここに来てないわ」
「そいつとの約束がそんなに大事か?」
「そ、そうよ。別に、私が秋彦に学校を辞めて欲しくないとかは関係ないから」
もう清々しいほどのツンデレっぷりだった。
「可愛いこと言うな~」
「な、何がよ」
聖奈にはその自覚がないようで、秋彦の言葉に怪訝な顔をした。
「もういい加減察しろよ。俺が学校に行くと、いろいろとまずいだろう」
「なんで?」
「俺にはこっちの現状がわからないんだぞ。そんな俺が登校したら、いろいろと問題が出てくる。そうなるぐらいなら、ここで学校を辞めた方が問題が少なくて済む」
「うっ、ぐ。そ、それはそうだけど」
これには反論できないようで、言葉に詰まった。
「それにセナは、俺への違和感でそいつの代わりにここに来たんだろう?だったら、このまま退学した方が無難だ」
もう押し問答は嫌なので、ここで畳み掛けることにした。
「ま、まさか、秋彦なんかに言い包められるなんて・・・」
その言葉から察するに、今までは押しに弱かったようだ。
「わかったら、もう諦めて学校に行け」
秋彦は時計を見て、二度寝を考えていた。
「なら、その問題を一緒に考えてあげるから」
「なんで疎遠だったはずのセナが、俺を必死に引き止めるんだ?」
「そ、それは・・・」
「俺に会いたいなら、この家に来ればいいだけだし、わざわざ学校に拘る意味はなんだよ」
「・・・こ、怖いのよ」
「何が?」
「あ、浅田さんが」
聖奈が怯えた様子で、誰かの名前を口にした。
「誰、それ」
「クラスメイトの浅田織姫」
「おり・・ひめ?ああ、あの茶色縁の眼鏡掛けてる地味な子か?」
「あ、知ってるんだ」
「ああ、名前が変わってるから覚えてる。でも、あっちでは話したことないぞ」
「まあ、性格が正反対だもんね」
「でも、浅田が怖いのか?」
「怖いと思ったのは、最近なのよ」
聖奈が少し声のトーンを落として、神妙な面持ちになった。
「なんかあったのか?」
「私が電話番号知らないのって、急に秋彦が携帯を変えたからなのよ」
「それが問題なのか」
「それがね、変えた理由が浅田さんらしいの」
「どういうことだ?」
「これは友達から聞いたんだけど。浅田さんと携帯ショップまで行って、秋彦に買わせたみたいなの」
「何それ?」
経緯が気持ち悪くて、眉間に皺が寄った。
「あ~、ちょっと待ってくれ。確認してくる」
これには父親にも事情を聞く必要が出てきた。
父親の部屋に入ると、律儀に論文を読んでいた。
「話は終わったのか?」
「確認したいことがあるんだけど」
「なんだ?」
「俺の携帯って、いつ変えた?」
「携帯ってスマートフォンか?」
「ああ」
「確か・・登校拒否の1週間前かな」
「ありがとう」
父親にお礼を言って、自分の部屋にあるスマートフォンを持って、ダイニングに戻った。
「どうだった?」
「この携帯、引きこもりの1週間前に変えたらしい」
秋彦はそう言って、スマートフォンをテーブルに置いた。
「そう、なんだ。中は見たの?」
「ロックが掛かって見れない」
秋彦たちは、黙ったままスマートフォンを見た。
「なあ、俺って本当にいじめられてたのか」
あまり信じたくない可能性を感じて、再び聖奈に聞いてみた。
「私から見たら、いじめというよりからかわれてたように見えたけど。秋彦からしたら、いじめらてると思ったんじゃないの?」
「からかわれてると思った要因は?」
「浅田さんとゲームの話で盛り上がってる時に、何度かからかわれてただけだし」
「それだけ聞くと、確かにいじめとは違う気がするな~」
「でしょう!」
自分の判断が間違っていないことを、強調するように語彙を強めてきた。
「で、浅田を怖いと思った理由は?」
「え、あ、ああ。ほら、プリント持ってくるのを強引に引き受けた時に、滅茶苦茶睨まれたのよ~」
「それが怖かったと」
「本当に怖かった」
そのことを思い出したようで、少し身震いしていた。
「浅田がこの家に来たことはあるか?」
「何度もあるよ。私がプリント渡しに来たのは、昨日が初めてだし」
「う~ん、そうか。ちょっと、父さん呼んでくる」
部屋にいる父親に声を掛けて、ダイニングまで来てもらった。
「浅田って、よくこの家に来る?」
隣に座ってもらった父親に、秋彦から話を切り出した。
「ああ、何度かプリント渡しに来てもらってるが」
「その時、俺はどうしてる?」
「あ~、なんか会えないって言って、部屋から出てこなかった」
「返事はどんな感じだった?」
「そうだな。かなり怯えてた気がする」
それを聞いて、聖奈と無言で目を見合わせた。
「仮説だけどさ。登校拒否になったのって、浅田が原因じゃないか?」
「有り得るわね」
「ってことは、俺が学校に行くの危険じゃない?」
「・・・」
こうなってしまっては、ロックの掛かっているスマートフォンが気になって仕方なかった。
「私、学校行くわね」
聖奈は態度をひるがえすように、ここから立ち去ろうとした。
「おい、余計な問題を浮き彫りにしておいて逃げる気かよ」
「こっちも本意じゃないわ。もう説得できなくなったんだから」
最後の言葉は、少し恨み言のように聞こえた。
「そうだな。これで退学して、浅田との関係も打ち切ろう」
「本当に辞めるのね」
ここにきて、初めて寂しそうな顔をした。
「これで腐れ縁も切れるから良いだろう」
「・・・馬鹿」
秋彦の言葉が気に入らないようで、罵倒してから玄関へ向かった。
「また来る」
聖奈はそれだけ言って、家から出ていった。
「さて、二度寝するか」
眠気には勝てそうになかったので、もう一度寝ることにした。
「え、朝ご飯は?」
父親が驚いて、朝食を要求してきた。
「一日二食って言ったはずだが」
「空腹で、頭が働かない」
「仕方ないな~、今日だけだぞ」
家には余分な食材がないので、財布の小銭を手渡した。
「か、カップ麺一つ分か」
「昼食はちゃんと用意するから」
「わ、わかった」
父親から返事を聞くと、自然と欠伸が出た。
秋彦は部屋に戻り、倒れ込むようにベッドに横になった。
第五話 退学者と研究者
少し早い昼食を終え、学校に電話で退学する旨を伝えると、一度父親と来て欲しいと言われたので、30分後にアポイントメントを取った。
「そんな早々に決めていいのか?」
「結果が変わらなければ、早い方がいい」
「まあ、本人がそう言うならそれでいいか」
「父さんは、あまりしゃべらなくていいから」
「そうしてくれると助かる」
「問題は浅田だな」
秋彦はスマートフォンを見て、何度目かのロック解除を試みた。
「ちっ」
自分の思いつく番号を入力したが、ことごとくはずれだった。
「父さんは、なんか思いつく番号ないか」
秋彦はそう言って、父親にスマートフォンを手渡した。
「う~ん。そうだな」
父親も協力的に考えつく番号を入力した。
「ダメだ。わからん」
一通りやったようだが、どれも違っていたようだ。
「う~ん。スマホのパスワード解除は面倒なんだよな~」
最終手段としてはパソコンに繋げて、強制的にパスワードを解除するしかなかった。
「そんなことできるのか」
「やり方は簡単だけど、時間は掛かる」
「どれぐらい掛かるんだ?」
「スマホのプログラムは見たことないから、1時間は掛かりそうだ」
「早っ!」
「そろそろ時間だから、着替えてくれ」
父親の驚きを無視して、学校へ向かうことにした。
ここでは父親の車がないので、徒歩で向かうことにした。
「私服でいいのか?」
家を出ると、父親が服装を指摘してきた。
「この後、論文取りに行くからな」
「本当に一緒に行くのか」
「勿論だ。その人たちに研究の進捗を聞いておきたいし」
「熱心だな」
「知識欲だな」
こっちの論文を見る限り数年遅れているが、研究には派生もあり得るので、聞いておくことに損はなかった。
「学校に着くまで、父さんの研究テーマを決めとこうか」
「え、おまえの研究はいいのか?」
「俺の研究は、危険だから封印する」
「それもそうだな」
息子の今の現状に、父親が気の毒な顔をした。
「一応、俺も入れ替わるために装置を買わないといけないんだが・・金が掛かるんだよな~」
「い、いくらぐらい掛かるんだ?」
値段を聞くのが、怖いのか少し躊躇いが見られた。
「あっちでは、エネルギー発生装置と発電機だけで2500万は掛かったな」
これは他の設備と部屋の改装代抜きの値段だった。
「ま、マジで?」
「ああ、特注品だからな」
研究費全体では、軽く数億は使っていた。
「だから、最低3000万は欲しいな」
「さ、3000万」
途方もない金額に眩暈がしたようだ。
「でも、これはあくまでも、俺が入れ替えるための装置だからな。父さんの研究費も考えると、数億の資金は欲しいな」
「え、俺の研究費も考えてくれるのか」
「あんな堕落した父親は見たくない」
「す、すまん」
自分の不甲斐なさに 申し訳なさそうに謝った。
「そう思うなら、努力してくれ」
「ぜ、善処する」
父親と話していると、学校が見えてきた。
「でも、理想は大学復帰だな」
「ああ、それは俺も望んでる」
未だに大学には未練があるようで、真剣な顔で頷いた。
「臨時職員とか考えなかったのか」
「募集がなくて」
「そうか。それなら仕方ないな」
父親と学校に入り、指定された校長室まで歩いた。
「さて、とっとと終わらすか」
「そ、そうだな」
秋彦は軽い感じで言ったが、父親は緊張した声だった。
「失礼します」
父親を先頭にすると、場を仕切られる恐れがあるので、自分が前に立つことにした。
校長室には校長と学年主任。そして、担任が座っていた。
華奢で白髪交じりの担任に勧められ、三人の正面に座った。
「じゃあ、これを」
秋彦は学生鞄から退学届を取り出して、禿げ上がった小太りの校長の前に置いた。
「辞める理由を聞いておきましょうか」
担任が率先して、父親に聞いた。
「僕から答えますよ」
一応目上の人なので、一人称は変えておいた。
「そう」
秋彦の言葉に、担任が少し動揺していた。
「理由は、もう通う意味がないからです」
秋彦が理由を言うと、父親以外全員が唖然とした。
「ここでの教育は、僕にとっては低レベルですから退学します」
「な、何を言ってるんだ?」
これに反応したのは、いつもジャージ姿の学年主任だった。
「君は、成績も悪・・良くないじゃないか」
父親を気にしたのか、担任が言葉を途中で変えた。
「低い点数なんて、簡単に取れるでしょう」
「じゃあ、今までわざとその点数を取っていたと?」
怪訝な顔の学年主任が、率先して聞いてきた。
「そうなりますね」
ここで気圧されると、主導権を奪われるので軽い感じで答えた。
「そんな理由で辞められるのは、学校としては困るんだが」
それを見兼ねたのか、校長が溜息交じりに言ってきた。
「学校の体裁なんて、生徒である僕には関係ありませんよ。体裁が気になるなら、僕が辞める理由を適当に改ざんしても構いません」
「か、改ざん?」
これに校長が驚きの顔を示した。
「ええ、精神疾患とかで良いんじゃないですか」
「倉木。おまえ、ふざけて言ってるのか?」
さすがにこれには学年主任が、怒った顔で迫ってきた。
「ふざけてませんよ。体裁が気になるようなので、そう提案させてもらっただけです」
「・・・本当に倉木君?」
担任が驚いた顔で、本人確認してきた。
「ええ。見たままですよ」
その疑問は予想されていたことなので、しれっと答えておいた。
「他に退学されると困るのなら、こちらから提案してあげますけど。何かありますか?」
「ここで辞めても倉木君の為にならないと思うんだが」
「自分のことは自分でやりますよ。学歴を気にしてるなら、問題はありません」
それよりも資金集めが問題だった。
「お互いの為に、ここで引いてくれませんか」
「倉木。おまえ何言ってるんだ?」
これには学年主任に呆れ顔をされた。
「こっちも予定がありますから、早めに受理してくれると助かります」
秋彦の横柄な態度に、この場にいる全員が言葉を失った。
「学校辞めてどうするんだ?」
学年主任は、感情を抑えて聞いてきた。
「それはプライベートなので、言う必要はありませんね」
「倉木!」
秋彦の答えが気に入らなかったようで、怒りをあらわにして勢いよく立ち上がった。
「お、落ち着いてください」
これに担任が慌てて、学年主任を押さえた。
「じゃあ、問題を大きくしますか?」
「も、問題?」
体を押さえられてる学年主任が、怪訝な顔で復唱した。
「ええ。例えば、不登校になった生徒を1ヶ月半もほったらかした・・とか」
秋彦は、済ました顔で校長を流し見た。
「なっ!」
これには校長が激しく反応を示した。その隣を見ると、学年主任と担任も校長と同じ顔をしていた。
三人の反応を見る限り、学校側から秋彦の不登校には対応してこなかったようだ。
「が、学校を脅すのか」
「人聞きが悪いですね。例えばの話ですよ」
学年主任に演技たっぷりの微笑みを向けて答えた。
「まあ、あとは校長先生の判断に委ねます」
「わかった。受理しよう」
「ありがとうございます」
校長の迅速な対応に、秋彦は軽く頭を下げた。
「こ、校長!いいんですか」
学年主任は納得できないようで、校長に詰め寄った。
「特別教室に行かせたくない理由で、対応してこなかったのは事実だ」
「そ、それは・・・」
特別教室は民間委託なので、学校側としては不名誉なことだった。
「じゃあ、僕らはもう帰りますね」
退学届を受理してもらったので、もうここに用はなかった。
「本当にいいんですか」
担任が秋彦ではなく、父親の方に聞いた。
「ええ、息子の考えを尊重しますよ」
父親はそれだけ答えて、担任に会釈した。
二人は黙ったまま、学校を後にした。
「本当に辞めてしまったな」
父親が学校を振り返って、そんなことを口にした。
「いいんだよ。これからやることはいっぱいあるんだから」
「まあ、そうだな」
息子の答えを聞いて、少し諦めた顔で歩き出した。
「それにしても、良くあんな脅しをかけたな」
「あんまり長く交渉すると、あっちが意固地になるからな」
「だからって脅すかな~?」
「うまくいったからいいだろう」
「今のおまえは怖いな~」
父親が軽いノリで皮肉ってきた。
「それより、約束の時間は何時だっけ?」
「昼と言っただけだから、別に何時でもいいと思う」
「そうか」
駅で三駅先までの切符を買って、空いてる電車に乗った。
「あと、今から会う人は少し変な奴だけど・・・」
言葉にしにくいのか、言葉が途切れてしまった。
「研究者は、ほとんど変だろう。俺と父さんが良い例だ」
「り、理解してくれて助かるよ」
自分も含まれてことが、複雑のようで苦い顔をした。
駅を出て、人通りの少ない商店街を通り抜け、大通りの横断歩道を渡り、その正面の小道の住宅街に入った。
「富裕層が多い場所だな」
この住宅街には、豪邸が数多く立ち並んでいた。
「ああ、ここ辺りは一坪の値段が高いらしい」
父親はそう言いながら、一つの家で足を止めた。
「確か・・ここだった気がする」
「でかいな」
そこは一際大きい土地だった。門扉は板張りの大門で、とても研究者の家とは思えなかった。
父親が恐る恐るチャイムを押した。最近までニートしていた父親としては、他人の家を訪問するのは抵抗があるようだ。
しばらくすると、インターホンから返事があった。
「あ、久しぶりだな~。ミッチー」
インターホンから軽い挨拶が聞こえると、門がゆっくりと開き始めた。
「ミッチーって呼ばれてたのか」
「あ、ああ。大学時代にな。それ以来、疎遠だったが」
「よく電話番号知ってたな」
「研究者で番号変える奴は、滅多にいないからな~」
「あ、それわかる」
それは大いに納得できる話だった。
門が半分ほど開くと、奥の玄関から一人の男が出てきた。彼はだぼだぼのTシャツに、裾の整えてないブラウンのスラックスを履いていた。
「ん?」
男が秋彦に気づいて、歩行を緩めながら近づいてきた。
「誰だ?」
男は秋彦を指差して、父親に疑問を投げかけた。父親の言うとおり、少し常識はないようだった。
「初めまして。倉木秋彦です」
秋彦は、礼儀正しく会釈した。
「倉・・木?おお、もしかしてミッチーの息子か!」
「あ、ああ」
男の勢いに、父親が戸惑い気味に苦笑いした。
「あんまり似てないな」
本当に常識がないようで、秋彦に自己紹介もせずに思ったことを口にした。
「急な頼みで悪いな」
「別に構わん。最近、実験もうまくいかなくてな~。1週間ぐらい息抜きしてた」
「長い息抜きだな」
「そうか?長い時は1年何もしないこともあるぞ」
二人は、秋彦抜きで話を進めた。
「初対面で失礼ですが、まずは家に招いてもらえませんか」
このまま立ち話を聞くより、秋彦からお願いすることにした。
「あ、ああ。すまないな」
「あと自己紹介もお願いします」
「それは悪かったな。太田貫禄だ」
「カンロクって・・もしかして、磁気浮遊の第一人者の太田貫禄さんですか」
「まあ、そう言われることもあるけど、あんまりそれで呼んで欲しくないな」
太田は目を逸らして、渋い顔をした。
「わかりました。太田さんでいいですか」
「ああ、それで頼む。まあ、上がってくれ」
太田はそう言って、家に招いてくれた。
家は淡いグレーの二階建てで、窓の少ない立方体を重ね合わせたような建物だった。
「そうそう。俺の研究論文って言っても、まだ完成してないぞ」
太田が歩きながら、父親の用件についてそう切り出した。
「あ~、論文読みたいって言ってるのは息子だから」
父親が気まずそうに秋彦を指差した。
「え?何それ」
これには驚いて、親子を交互に見た。
「未完でも構いません。あなたの研究はとても興味深いです」
「理解できるのか?」
「安心してください。父親よりは理解力はあります。あと学術書もあれば、お借りしたいのですが」
「・・・」
秋彦の注文に、太田が唖然とした顔をした。
「り、立派な息子だな」
「そ、そうなんだよ。最近、本当に自分より優秀になってしまってな」
太田の取り繕いに、父親が困った顔をした。
「お互いニートだろう」
これには呆れ声でつっこんだ。
太田の後に続くと、リビングらしき所へ招かれた。
「あんまり人を招くような家にしてなくてな。適当に座ってくれ」
「なんでこんなバラバラなんだ?」
父親は、不思議そうに部屋を見渡した。中央には膝まである長机があったが、一人用のソファーにパイプ椅子。そして、座椅子といろんな椅子が置いてあった。
「あ~、実験によって座るのが変わってくるからな」
そう言うと、部屋から出ていった。
「物は多いみたいだな」
秋彦は、床に散らばっている金属の部品を手に取った。
「これは設備を解体したのか?」
ねじの部分を見ると、少し傷ついていた。
「本とか資料は、この部屋にはないみたいだな」
「そうだな」
「っていうか、太田さんと知り合いとは驚きだな」
「いや~、大学の頃は、あそこまで有名になるとは思わなかったけどな~」
父親が昔を思い出すように、視線を天井に向けた。
「コーヒーしかないけど、それでいいよな」
太田が三つのコーヒーカップをお盆に乗せて持ってきた。
「まあ、味は自由に調整してくれ」
そう言うと、長机にある砂糖とクリープを中央に置いた。
「ミッチーって、今どうしてるんだ?」
「大学をクビになってな。今は生活保護を受けてる」
「ほー、それは羨ましい」
「そうか?研究に没頭できる方がいいだろう」
「まあ、没頭できるだけならいいんだが。国も民間も成果求めるんだよ」
「確かに。でも、カンロクは特許があるからもう成果はいらないだろう」
「それがそうでもないんだよ。民間に勤めていたら、辞めても余計なしがらみがついてくるんだよ」
「そりゃあ、大変だな」
「ホント面倒臭いんだよ。少し困っただけでわざわざ聞きに来るし、開発の手伝いをして欲しいとか言ってくるし」
「でも、辞めてるんだろう?」
「ああ。辞めたんだが、特許料を盾に名誉会長とか変な役職に就かされてな」
太田は溜息交じりに、コーヒーを飲んだ。
「会社としては、名前が欲しかったんですね」
磁気浮遊の第一人者を、会社として手放したくないだろう。
「そうだろうな。俺としてはもう若手に譲りたいんだが」
「まだ四十歳だろう」
父親が意外そうな顔で指摘した。
「四十なんて研究者としては、もう爺だろう」
太田にしてみれば、研究者はこの歳で定年のようだ。
「でも、研究はしてるんだろう」
「ああ、一人でな。趣味みたいなもんだ。会社の為じゃねぇよ」
太田はそう言いながら、子供のようにはにかんだ。
「それより、ミッチーはもう研究してないのか」
「生活保護だぞ。無理に決まってるだろう」
「ああ、それは悪かった」
この失言には、友達特有の軽いノリで謝った。
「そろそろ本題に入ってもいいですか」
話も途切れたので、ここは秋彦から切り出した。
「そうだったな。論文だっけ?」
「そうですね。それより太田さんの実験室を見せてもらいたいですね」
正直、こっちの方を最優先にしたかった。
「実験室?う~ん、見てもつまらんぞ」
「そんなことないです!」
太田の言葉を打ち消すように、力強くそう言った。
「そ、そうか」
その迫力に気圧されたようで、少し引き気味な表情をした。
太田に連れられて、玄関の正面の階段を下り、地下の実験室に入った。
「防音も兼ねて、地下に造ってるんですね」
「ああ、密閉空間は実験には最適だからな」
「それはわかります」
これは大いに納得できるものだった。
実験室に入ると、一面視界が開けた。正面に巨大な鉄球のような物が宙に浮いていた。その上下に磁石らしき物があり、左右には制御装置があった。
「おお」
これは興味深く見入ってしまった。
「む、これってスパコンじゃないですか」
入り口の横に大型のコンピュータが並んで置いてあった。
「あ、ああ。計算が多いからな」
「スペックは?」
「四ペタだな」
「凄いですね」
あっちに居た時、スーパーコンピュータを取り入れたかったが、部屋が狭くてできなかった。
「今、計算中ですか?」
画面を見ると、数字が凄い勢いでスクロールしていた。
「それは同じ現象が起きないかの検証だよ」
「なるほど。それでこの研究の論文ってありますか?」
「あ、ああ。まだ未完成だけどな。というか、君には難しいと思うんだが」
「そうかもしれませんね」
専門的には少し違うので、それは否定できなかった。
太田が端の長机にある分厚い紙の束を、秋彦に手渡した。
「ありがとうございます」
秋彦はお礼を言って、論文を読み始めた。
「ミッチーの息子は変わってるな」
「最近までは引きこもりだったんだがな」
「学校行ってないのか」
「今日、辞めてきた」
「はっ?」
これには驚いたようで、声が張っていた。
そんな父親たちの世間話を聞き流しながら、手早く論文を読み上げた。
結果から言うと、読んだことのある物だった。あっちでは完成していたが、ここではまだ肝心なことに気づいていないようだった。
「ありがとうございます。とても興味深かったです」
それでも内容は素晴らしいことに変わりないので、誠意を込めてお礼を言った。
「ど、どういたしまして」
太田は少し戸惑いながら、論文を受け取った。
「あと、学術書などありましたら、お借りできないでしょうか」
「あ、ああ。学術書ね。あれは二階の書庫にある」
「案内してもらっていいですか」
「ああ、構わないが」
太田は、秋彦に圧倒されながら実験室を出た。
かね折れ階段を上がって、長い廊下を歩いた。
「ここだ」
そして、二つ目の部屋で足を止めて振り返った。
部屋に入ると、正方形の部屋を詰めるように、四方に本棚が設置されていた。
「凄いな」
これには父親が、驚きの声を上げた。
「まあ、ここはそういう風に造ってもらったからな」
本棚はスライドさせるタイプのようで、本棚の奥にも本棚が並んでいた。
「奥の本は昔のですか」
「ああ、基本的に手前のが最近の物だな」
「こんなに多いとは思いませんでした」
秋彦としてはあれば儲け物だと思っていたが、ここまで大量だと1日では精査できそうになかった。
「太田さん。何度か通ってもよろしいですか」
「え、ああ、いいけど・・・」
秋彦の積極性に引き気味に許可してくれた。
秋彦は2時間近く、学術書を読み漁った。
「そろそろ帰らないか」
「ああ、うん。わかった」
だいたい借りるものは決まったので、父親に従うことにした。
「すみませんが、これだけ借りていいですか」
「え、そんなに借りるのか」
息子の持った十数冊の本を見て、父親が驚いた顔で指摘してきた。
「ああ、好きに持っていってくれ」
「悪いな」
太田に気を使ったようで、父親が友達のノリで悪びれた。
「今日はありがとうございました」
玄関で太田に深々とお辞儀して、感謝の意を伝えた。
「いや、君には感心させられたよ」
「そう・・ですか?」
「ああ、集中力と知識への貪欲さは、最近忘れかけてたものだ」
「まあ、誰でも行き詰ることはありますよ」
「ははっ、耳が痛いな」
太田が空笑いして頭を掻いた。
「君が研究者になったら、ぜひ論文を読ませて欲しいものだ」
「残念ですが、これまでの研究は破棄するつもりです」
パラレルワールドに移動してしまう実験は、危険すぎて封印するしかなかった。
「は?その歳で研究してるのか」
「ええ、まあ。でも、研究の経緯と結果は文字に起こしていませんし、これからも起こすことはないでしょう」
「何かあったのか?」
「誰も幸せになれない事象が起こってしまいました」
「その事象にメリットがないのか」
「はい。恩恵もない上に証明もできません」
「・・・そうか、それは残念だな」
秋彦の意思を汲んでくれたようで、これ以上は聞いてこなかった。
「あ、そうそう。反発力の計算も重要ですけど、地球の引力も含めた計算もしてみたほうがいいですよ」
ここまでお世話になって帰るのは申し訳ないので、研究へのヒントを教えることにした。
「・・・」
太田は驚いた後に、何かに気づいた表情になった。
「それでは、これで失礼します。ほら、帰るよ」
それを見て、父親を急かすように玄関を開けた。
「あ、ああ。今日はありがとな」
父親は少し戸惑った返事をして、太田に感謝の言葉を口にした。
「感謝するのは、俺の方かもしれない」
「は?」
「悪い。やることできたから、もう帰ってくれ」
「あ、そうなのか。じゃあな」
「ああ、またな」
秋彦は玄関のドアを開けた状態で、二人のやり取りを見ていた。
父親と大門を出て、帰り道を歩いた。
第六話 ギャンブル
帰りの電車に乗ると、座席に新聞が置いてあった。
「なんだスポーツ新聞か」
経済新聞なら読んでみようと思ったが、スポーツ新聞は読む気はなかった。
「お、競馬か~。一時期ハマったな」
父親が新聞の表欄を見て、そんなことを口にした。
「もしかして、借金したのって競馬?」
「あ、ああ」
秋彦の睨みに、委縮するように視線を逸らした。
「クズ野郎」
「そ、そんなこと言うなよ。こっちだって家計を少しでも楽にしようとやったことなんだから」
「それで借金したら、本末転倒だろう」
「うぅ、返す言葉もない」
この正論には言い返すことができず、元気なく項垂れた。
「そういえば、駅の近くに競輪場があったな」
「ああ、競輪でもスッたよ」
「ちっ」
知りたくもない事実に、父親を睨んで舌打ちした。
しばらく、秋彦は黙ったまま新聞を読んだ。
「ちょっと競輪場行くか」
そして、新聞を八折りにして座席を立った。
「は!なんで?」
これには驚いたようで、父親が声を張り上げた。
「元を取り戻すんだよ」
「その発想は危険じゃないか」
「まあ、依存症が陥る言い訳だな」
駅に着いたので、父親と降りることにした。
「安心してくれ。一回しか賭けないから」
「え、いくら賭けるんだ?」
「さあ、配当によるな~」
「高額配当なんて難しいだろう」
「そうだな。三連単狙わないと難しいな」
「三連単って良く知ってるな。競輪したことあるのか」
「ないよ。これに書いてあっただけだ」
秋彦はそう言って、持ってる新聞を軽く振った。
「言っとくけど、別に闇雲に賭けるわけじゃないから」
「分析とかするのか」
「当たり前だ。じゃなきゃ、やらん」
改札を抜け、数百メートル先の競輪場へ向かった。
「っていうか、父さんは分析しなかったのか」
「したけど・・全部外した」
「あっそ」
父親の分析能力のなさに、息子として情けなくなった。
競輪場に着くと、中年の男女が多く見られた。
「平日にここにいる人は、人として嘆かわしいな」
あまりの活気良さに思わず本音が漏れてしまった。
「そんなこと言うなって」
父親が周りを気にして、秋彦に注意してきた。
「まあいいや。まずは、これまでの結果を見て来てくれ」
秋彦はそう言って、父親に新聞を手渡した。未成年が行くと訝しがられるので、父親に任せることにした。
「わ、わかった」
父親は、秋彦に言われるがまま競輪場の中に入っていった。
しばらくして、父親が新聞を握りしめて出てきた。
「こんな感じになってた」
父親から新聞を受け取って、レースの結果を見通した。
「今日のレースって、あと何回ある?」
「三レースだな」
「そう」
秋彦は次のレースを見る為、外に設置してある液晶画面に目をやった。
「父さん。三連単の人気を確認してくれ」
「あ、ああ。わかった」
父親は戸惑いながら、再び競輪場へ入っていった。
秋彦は二レース見て、いろいろ分析してみた。
「最後のレースで賭けるか」
「大丈夫なのか?」
「さあな。所詮、運試しだし」
「運試しなのに、二レース見る必要あるのか?」
「運も実力だろう」
「物は言い様だな」
この言い回しには少し呆れ顔をした。
「とりあえず、8ー4ー5の三連単で」
財布から500円を取り出して、父親に手渡した。
「まあ、無難な金額だな」
少し安心したのか、父親から溜息が漏れた。
「でも、8ー4ー5って当たらないだろう」
「普通は賭けないな」
「言ってることと、やってること矛盾してないか?」
「そうだな。まあ、4の選手がカギになるな」
「この選手って、今日のレースで下位を争ってるだろう」
「いいから、買ってきてくれ」
もうすぐレースが始まるので、少し急かすように言った。
「わ、わかった」
父親が不満一杯の顔で、車券を買いに行った。
レースが始まると、父親が少し興奮気味に画面を見つめた。
「あんまり熱を入れるな。またギャンブルにのめり込む羽目になるぞ」
「そ、それは否定できない」
「賭け事はあくまで冷静に見ないと、破滅するだけだ」
「あ~、それ実践した」
「ったく、少しは学習してくれ」
「そう・・だな」
秋彦の指摘で、少しは冷静さを取り戻してくれたようだ。
そんなやり取りをしている間に、最後のレースが終わった。
「当たったな」
秋彦は、画面を見たまま淡泊に言った。
「あ、ああああ、あた、当たった」
父親の方は、動揺のあまり声が乱れに乱れていた。
「落ち着け」
「痛っ!」
挙動不審の父親の二の腕をつねって、感情を抑制させた。
「痛いだろう」
「動揺するな。変な奴が絡んでくるだろう」
「あ、ああ」
言いたいことは伝わったようだが、動揺は納まっていなかった。
「早く換金しに行ってくれ」
自分で行くことも考えたが、年齢確認されそうなので、父親に行ってもらうことにした。
「あ、入れ物がなかったら、この鞄に入れてくれ」
秋彦は、学術書の入っている鞄を父親に持たせた。
「失くすなよ。大事な学術書が入ってるんだから」
「わ、わかった」
父親は、挙動不審な状態で競輪場に入っていった。
「これで借金はなくなるな」
高額配当の金額を確認しながら、これからのことを考えた。
しばらく未来予測をしていると、鞄を両手で抱えた挙動不審の父親が出てきた。その後ろから警備員もついてきた。
「す、凄い金額だ」
父親が駆け寄ってきて、興奮気味に目を輝かせた。
「帰るぞ」
「あ、ああ」
警備員は競輪場内までいるようなので、さっさと敷地内を出ることにした。
競輪場を出ると、予想通り警備員はついてこなかった。
「そんな警戒してたら、大金持ってるって言ってるようなもんだろ」
秋彦は呆れながら、父親から鞄を奪った。
「す、すまん。こんな大金見たことなくて・・・」
「じゃあ、家で見慣れてくれ」
ここまで動揺されると、息子としては恥ずかしくて仕方なかった。
歩いていると、どこからか視線を感じたので、チラッと後ろを確認した。
「つけられてるな」
人通りの多い場所なので、誰かまでは特定できなかった。
「え、そうなのか」
秋彦の言葉に機敏に反応して、後ろを振り返った。
「あからさまに反応しないでくれ。あっちも気づくだろう」
「あ、それもそうだな」
「歩きながらでいいから聞いてくれ」
秋彦は小声で、これからの対応策を父親に伝えた。
「そこまで細かく決めるのか」
「まあ、杞憂で終わるならそれでいいんだが」
人通りの多い交差点を曲がり、すぐ横にあるショッピングモールに秋彦一人で入った。
父親は何食わぬ顔で、そのまま家とは反対の方向へ歩いた。
秋彦は尾行している相手を確認する為、ショッピングモールの入り口を注意深く観察した。
「って、あいつらかよ」
入り口付近で挙動不審になった相手を見て、思わず溜息が漏れた。尾行してたのは、古賀浩之と大貫信也だった。
「あいつら、ここでは不良なのか」
信也はこっちでも茶髪だったが、制服を完全に着崩していた。浩之の方は眼鏡を掛けておらず、赤黒い髪で耳にはピアスを付けていた。
相手は確認できたので、気づかれる前に撒くことにした。
「あれ、秋彦?」
ショッピングモールを適当に徘徊していると、制服姿の聖奈と出会ってしまった。
「・・・」
追っ手を撒いている途中なので、無視することにした。
「って、ちょっと無視しないでよ!」
「あ~、今忙しいんだ。ここはお互いのためにシカトしてくれ」
「何かあったの?」
「それを知りたきゃ、1時間後に家に来い」
秋彦はそれだけ言って、周りを警戒して歩き出した。
「じゃあ、今から一緒に行くわよ」
聖奈が視線を外しながら、秋彦の隣に並んできた。
「一緒にいたい気持ちはわかるが、今は構っている暇はない」
「な、何、勘違いしてるのよ。べ、別に一緒にいたいとか思ってないし」
「悪いけど、セナと一緒だと目立つから、勘弁してくれないか」
「目立つって何よ~」
言い方に不満があるのか、膨れっ面な顔をした。
「おまえは可愛いからな。他人の目を引くんだよ」
「か、可愛いって・・・」
聖奈が怯んで顔を赤らめた。聖奈は綺麗と言われるより、可愛いと言われる方が嬉しいことは知っていた。
「じゃあ、俺はもう行くから」
恥かしがっている聖奈を残して、この場から立ち去った。
30分ほど徘徊してから家に帰ると、父親と聖奈がダイニングでお茶を飲んでいた。
「って、1時間後って言ったのになんでいるんだよ」
「私、そんな約束してないわ」
聖奈がお茶をすすりながら、しれっとそんなことを言った。
「そ、それより、そっちは大丈夫だったのか」
父親が心配そうに、秋彦に近づいてきた。
「ああ、問題ない。そっちは?」
「こっちも特に何もなかったよ」
「まあ、あの二人は父さんと面識もないもんな」
「ついてきてたのが、誰かわかったのか」
「同級生だよ」
ここではクラスメイトかはわからないので、同級生に留めておいた。
「え、なんの話?」
蚊帳の外の聖奈が、話に割って入ってきた。
「いや~、さっき信也と浩之につけられてな」
秋彦はそう言って、聖奈の隣に座った。
「誰?」
「大貫信也と古賀浩之だよ」
「あ~、あの不良二人組か」
「あ、やっぱりこっちではそうなんだ」
「あの二人、結構性質悪いらしいから注意した方がいいわね」
「あっちでは優等生なんだけどな」
「え、そうなの!」
「まあ、信也の茶髪は変わってなかったけど、浩之はかなり違っていたな」
「どう違うのよ」
「黒髪に眼鏡掛けてる」
「ぷっ!」
それをイメージしたのか、聖奈が思いっきり噴き出した。
「あ、父さん。明日、生活保護の取り下げに行ってくれ」
秋彦は、正面の父親にそう頼んだ。
「はっ?」
「資産ができた以上、不正受給になる」
「な、なるほど」
「あと、学術書も読んでおいてくれ」
さっき借りてきた学術書を鞄から取り出して、父親の前に置いた。
「あ、ああ。って、これ英文なんだが・・・」
「次のページに翻訳載ってるから」
「そうなのか」
父親はそう言いながら、学術書を捲っていった。
「セナ。笑いすぎだぞ」
その間、隣で聖奈がずっと笑っていた。
「だって、あの古賀君が眼鏡って・・・くくくっ」
聖奈は、笑いを堪えながら顔を伏せいた。
「じゃあ、俺はパスワード解読するから」
秋彦は、二人を置いて自室に入った。
スマートフォンとパソコンを接続すると、聖奈が入ってきた。
「ノックぐらいしろ」
「あ、ごめん」
聖奈が謝って、開けたドアをノックした。
「もう遅い」
「細かいわね~」
「それよりなんか用か」
「本当に辞めたの?」
「ああ、今日辞めてきた」
「よく辞めれたわね」
「まあ、学校側の弱味を突けばすぐだったよ」
「う~ん、聞くべきか悩む言い方ね」
「セナは辞めないから、知る必要はないな」
「その理由では悩んでないわよ」
聖奈が小声で不満を吐いた。
「それはそうと、浅田に何か言われたか?」
「え?特に何もないけど」
「これから関わる可能性はあるか?」
「多分、明日秋彦が辞めたことを担任が伝えるから、話しかけられる可能性はあるわね」
「そうか。なら、しばらくここの出入りは控えて方がいいかもな」
「なんでよ?」
「浅田と鉢合わせしたら、面倒事が増えるぞ」
「あ~、それは絡まれるかもしれないわね」
その場面を思い浮かべたようで、苦い表情をした。
秋彦はパソコンに向かい、スマートフォンのロック解除を始めた。
「何してるの?」
「これの中身を見るんだよ」
聖奈に見せつけるように、スマートフォンを左右に軽く振った。
「解除できるの?」
「簡単だろう」
スマートフォンのプログラムは見たことはなかったが、時間を掛ければ済む話だった。
「私にはさっぱりわからないわね」
さすがにアセンブリ語はわからないようで、秋彦の横で険しい顔をした。
20分掛けて、パスワードの場所を特定した。スマートフォンのプログラムはパソコンとさほど変わらなかった。
「あ~、桁が少ないな」
パスワードを書き換えようとしたが、桁数が少なかったので、今後のことも考えて解読に留めることにした。
「あとは処理能力に任せよう」
「え、もう終わったの?」
「まあな」
秋彦はそう言って、椅子の傍に置いた鞄を膝に乗せた。
「え、何?」
興味深そうにパソコン画面を覗いている聖奈を見ると、顔を赤らめて少し距離を取った。
「まあ、いいか」
お金を出すか悩んだが、金銭欲のない聖奈には見せても問題ないと思った。
「え、何それ」
鞄からパンパンの封筒を取り出すと、聖奈が驚いた顔をした。
「金だ」
聖奈にそう答えながら、パソコンの隣に三つの封筒を並べた。
「お、お金?」
「ああ。競輪で大穴当ててな」
秋彦は、一つの封筒の中身を見せた。
「す、凄い」
これには目を見開いて、札束を凝視した。
「い、いくらあるの?」
「は?」
まさか聖奈から、そんなことを聞かれるとは思わなかった。
「1200万はあるな」
「そ、そう」
聖奈は動揺しながらも、お金からは目を離さなかった。
「欲しいのか?」
その異様な視線に少し不信感が芽生え、試すように挑発してみた。
「えっ!」
「・・・ここのセナは欲深いな」
聖奈の驚いた反応に、秋彦はがっかりしてしまった。
「なあ、セナ」
秋彦は椅子を回転させて、聖奈の方を見上げた。
「10万あげたら、恋人になってくれるか」
「は・・な、何言ってるのよ!」
これには驚いた顔で、秋彦を見つめた。
「どうなんだ?」
「な、ならないわよ。お金で恋人になれなんて失礼よ!」
少し迷いも見られたが、後半は力強く拒否してきた。
「そうか」
この答えにはホッとして頬が緩んだ。
「な、何がおかしいのよ」
「いや、嬉しいんだ。お金でなびくならもう来るなって言ってた」
「た、試したの?」
「ああ、金への執着を感じたからな」
「失礼な人」
秋彦の対応が気に入らなかったようで、頬を膨らませて不機嫌そうな顔をした。
「そこは許してくれ。好きな人が障害になると、一個人として不安定になるんだ」
秋彦は封筒を置いて、引出しから借用書と未使用の封筒を取り出した。
「す、好きって、よくそんな軽々しく言えるわね」
好きという言葉が恥ずかしいのか、聖奈が顔を赤らめて呟いた。
そんな聖奈を無視して、各会社の返済金額を一つずつ封筒に入れた。
「こうやって見ると、凄い金額ね」
「そうだな」
「反応が淡泊ね。見慣れてるの?」
「ああ、あっちにいた時は数十億はあったな」
「えっ!」
「まあ、預金通帳でしか見たことないけどな」
聖奈の驚きをスルーして、淡々と作業しながら応じた。
「秋彦って何者なの?」
「ただの研究者だよ」
秋彦は1万円を抜き出して、それを聖奈の前に突き出した。
「この1万円は口止め料だが、セナは受け取るか?」
「い、いらない」
「そうか」
これで貰っても嫌いにはならなかったが、断ってくれたことは嬉しかった。
「何、その顔。むかつくわね」
「こっちでも俺の好きなセナで嬉しいよ」
「だから、す、好きって軽々しく言わないでよ」
「セナも素直になればいいだろう」
「ふん」
ツンデレにはハードルが高いようで、本音を言うのを拒否した。
「そろそろ帰ったほうがいい」
気が付くと、もう7時を回ろうとしていた。
「あ、本当だ」
聖奈を玄関まで見送ると、何かを思い出したように振り返った。
「ま、また来てもいい?」
「ああ、浅田のことが片付いたらな」
「じゃ、じゃあ、落ち着いたら、この番号に連絡して」
聖奈は目を合わさず、ポケットからノートの切れ端を差し出した。
「ああ、わかった」
それを受け取ると、聖奈がすぐに背を向けて玄関を開けた。
「さよなら」
そして、その一言だけ口にして玄関のドアを閉めた。
夕食を食べ終わり自室に戻ると、ロックの解析が終わっていた。
「これって・・・」
ロックナンバーを見て、なんとも言えない気持ちになってしまった。
「こっちではお互い素直じゃないのか」
秋彦はロックを解除して、スマートフォンの中身を確認した。
「・・・怖っ」
一通り見ると、恐怖のあまり身震いした。
スマートフォンにはメールや着信、仕舞いにはSNSまでにも浅田織姫の履歴が羅列していた。
「これは登校拒否になるな」
そう呟くと、着信音が鳴り響いた。着信履歴を見る限り、電話があることは予測していたので、特に驚きはなかった。
「う~ん。今回は見送るか」
スマートフォンを机に置いて、ひとまず今日はスルーすることにした。
着信が留守電に変わり、浅田の声がスマートフォンから聞こえてきた。
『あ、あの、前のことは謝るから、連絡欲しいな』
電話が切られたので、留守電とメール、SNSを登校拒否をした日から遡って確認した。
「くだらねぇ~」
あまりのどうでもいい喧嘩に、頭が痛くなった。
SNSでオンラインゲームの話があったので、今後のことを考えてログインしてみることにした。
「う~ん」
ログインしてみたが、やり方が全くわからなかった。
「興味のないことを調べるのは苦痛だな~」
ゲームの目的と操作方法を読んだが、興味がなさすぎて頭を抱えてしまった。
「うん。俺は無理だ」
オンライン上での会話が面倒すぎて、ゲームを断念することにした。
「これは困った」
ゲームができない以上、浅田との会話でボロが出るのは確実だった。
しばらく考えた結果、聖奈に頼ってみることにした。
『も、もしもし?』
見知らぬ番号だからか、少し訝しげな声だった。
「秋彦だけど」
『え、どうしたの!』
秋彦だとわかると、気さくな声に変わった。
「ちょっと相談があってな」
秋彦は、ゲームのことを簡略的に伝えた。
『ごめん。私もゲーム関係はしないから、力になれそうにないわ』
「そうか。友達でゲームに詳しそうな人いないか」
『え、う~ん、どうだろう。明日、聞いてみようか?』
「明日になると、浅田が来そうなんだが」
『あ、そっか』
「まあ、しょうがないな。浅田を傷つけてしまうが、辛辣に拒絶しよう」
『え、傷つけるの?』
「浅田と喧嘩してるんだが、ゲームの話なんだよ」
『何、その馬鹿みたいな理由』
「知らん。そのゲームやってみたけど、苦痛でできなかった」
『なんかそれ、わかる気がする』
「というわけで、話が噛み合わない以上、強く拒絶しないと引き離せない気がする」
『そこまでする必要あるの?』
「SNSのやり取り見てる限り、俺にかなりご執心のようでな。もう会いたくないと言っても引きそうにない」
『そ、そこまでなの?』
「ああ、さっきも着信があったばっかりだ」
『好意を持ってる人を拒絶するの?』
「結果的にそうなるが、喧嘩の原因を作ったのは浅田だ」
『え、そうなの?』
何か腑に落ちないのか、声が少し低くなった。
「もしかして、浅田に同情してるのか」
『うん、少しだけ。好意が裏目に出たのね』
「恋愛じゃあ、よくあるんじゃないのか」
一度、それで聖奈と喧嘩したこともあった。
『ねぇ、浅田さんを傷つけないで欲しいんだけど』
「それは無理だ」
『きっぱり言うのね』
「今まで無視している時点で、もう傷つけてるだろう」
『それもそうね』
「あまり長引かせると、引くに引けなくなる」
『で、でも・・・』
「ここでの俺は優しかったか?」
聖奈の声に被せるように、こっちでの自分の性格を聞いてみた。
『え、あ、うん。優しすぎて、いつも自ら身を引いていたわ』
「そうか」
電話やSNSを無視していたが、着信拒否やブロックは一切していなかった。これは彼の甘さでもあったようだ。
「じゃあ、セナが浅田を説得してくれ」
『え!』
「俺がやれば、確実に浅田を傷つける。それが嫌なら、セナに動いて欲しい」
『む、無理』
「セナならできると思うけどな」
『な、なんでそう思うの?』
「浅田を傷つけて欲しくないんだろう。その言い分は、自分が傷ついた経験があるから言えることだ」
『・・・』
「自分と同じ思いをして欲しくないなら、セナが救ってやれ」
『秋彦は、そういうことはないの?』
「俺の場合は、傷つくことも必要だと思ってる」
『そういう考え方もあるかもね』
「そこはセナに任せる」
『ま、任せるって・・・』
「何もしなくてもいいし、浅田と話し合ってもいい」
流れ的に試すかたちになってしまったが、聖奈の性格を知るには良い機会だった。
『秋彦って、ずる賢いね』
秋彦の意図を察したのか、少し嫌そうな声だった。
「そろそろ終わるか」
『そうね』
気づけば、かなりの長電話になってしまっていた。
「おやすみ」
『うん。おやすみ』
聖奈の返事は、とても温かい声だった。
第七話 登校拒否の原因
次の日、父親と一緒に役所と金融会社に行き、生活保護の辞退と借金の返済を済ませた。
家に帰り、テーブルに現金を広げて残金を数えた。
「思ったより残ったな」
借金返済しても、手元には800万円近く残っていた。
「これ、どうするんだ」
父親が興奮気味に現金を凝視した。
「300万を口座に預金して、300万は投資。残りは生活費」
「研究はできないのか」
「これだけじゃあ、半年もしないうちに枯渇する」
「だよな~」
父親は現実を突きつけられ、がっくりと肩を落とした。
「まずは預金してきてくれ」
600万円を分けて、父親の前に置いた。
「お、おう」
「一人で大丈夫か?」
父親のぎこちない返事に不安感が湧き出てきた。
「ま、任せろ」
大金を持つことの責任感からか、声から動揺が伝わってきた。
「一緒に行こうか?」
「・・・頼む」
これではどっちが保護者かわからなかった。
午後2時に銀行に行ったが、思いのほか時間が掛かってしまった。
「ちっ、なんだよ。あの銀行員」
帰り際、秋彦は銀行を後ろで見ながら舌打ちした。
「まあ、急な大金の振り込みだからな~」
「ったく、日頃はマニュアル人間の癖に」
「預金はできたからいいだろう」
「父さんも悪いからな」
「す、すまん」
父親が預金したいと窓口で言ったが、挙動が怪しかった為、銀行員に警戒されてしまった。
「全く、念の為持ってきた車券が役立つとは思わなかったよ」
最終的には競輪の車券を見せて、やっと預金できたのだった。
「帰ったら、父さんはネットで株と外為の口座開設してくれ」
「それをして何するんだ?」
「資金を増やす」
「大丈夫なのか?」
「どうだろうな。やってみないとわからん」
「借金はしないでくれよ」
「任せてくれ。といっても、今の情勢はさざ波程度だから、すぐにトレードはしないよ」
この情勢で投資するのは、一番危険な行為だった。
「俺は、買い物行くから先に帰ってくれ」
ちょうどスーパーを通ったので、買い物をしておくことにした。
「一緒に行こうか?」
「気遣いは嬉しいが、余計な物買いそうだから帰ってくれ」
「し、信用ないな」
「ギャンブルしてた時点で、信用度はゼロに等しい」
「・・・秋彦は手厳しいな」
これには反論できないようで、苦笑いして頬を掻いた。
秋彦は一人で買い物を済ませ、足早に帰路に就いた。
その途中、最悪なことに信也たちと鉢合わせてしまった。学校帰りのようで、制服姿だった。
「お、倉木じゃん」
信也がダルそうに声を掛けてきた。こっちを知ってるのは、昨日のことで知ったので不思議ではなかったが、どういう関係かはわからなかった。
「こんにちは」
とりあえず様子見をする為、挨拶をしてみた。
「昨日、なんで逃げたんだよ」
「なんの話?」
「昨日、モール辺りで逃げたろ」
「だから、なんの話?」
「おいおい、白切る気かよ」
こっちでの信也は頭が悪いようで、一向に話が進まなかった。
「なんの話か知らないけど、何か用だった?」
「金貸してくんね」
信也が軽い感じでカツアゲしてきた。
「金融会社に行けばいい」
人通りもあるので、ここは嫌味を込めて答えてみた。
「は?未成年には貸してくれないじゃん」
「じゃあ、両親に頼んで借りればいい」
「おいおい、おちょくってんのか」
「それはこっちの台詞だ。普通、同級生に金なんて貸すわけないだろう」
「おいおい、どうしちゃったんだよ。前は気前よく貸してくれたじゃん」
「なら、それを返してから言ってくれ」
こっちでは信也にお金を貸したようだ。
「ほら、返せよ」
秋彦は挑発するように、お金の返却を求めた。
「は?ねぇ~よ」
これには怒りをあらわにして、威嚇するように睨んだ。
「なら、貸す必要はないな」
これ以上話しても意味はないので、この場を立ち去ることにした。
「ちょっと顔貸せ」
しかし、信也が秋彦の前に立ち塞がってきた。
「残念だが、無理だ」
秋彦はレジ袋を少し上げて、行けない理由をアピールした。
「ここで殴られたいのか」
「ははっ、それは面白い。この人通りの多い場所で殴ったら、警察に厄介になるんじゃないか?」
スーパーに近いこともあり、人通りが多かった。
「てめぇ、ふざけんなよ」
秋彦の挑発に、信也がブチギレ寸前まできていた。
「落ち着け、信也。ここで問題を起こせば、特別教室行きだぞ」
浩之の方は冷静なようで、周りの目を気にしていた。
「浩之。あとは任せた」
これ以上の挑発は事を大きくするだけなので、さっさと身を引くことにした。
歩きながら後ろを警戒したが、二人は追ってくる気配はなかった。それに安堵して、溜息が漏れた。
家に帰ると、予想外な来客がいた。
「あれ?父さんは?」
秋彦はレジ袋を冷蔵庫前に置いて、ダイニングの椅子に座っている聖奈に尋ねた。
「気を使ったみたいで、部屋に居るわ」
「そうか。で、なんで居るの?」
「う、うん。話し合ったらこういうことになった」
聖奈はそう言いながら、隣にいる浅田織姫の方を横目で見た。浅田は低身長でクリッとした目に茶色縁の眼鏡を掛けていて、下を向いて秋彦と目を合わせなかった。
「結論を聞こうか」
冷蔵庫に買った物を入れて、聖奈の正面に座った。
「ご、ごめんなさい」
突然、浅田が立ち上がって深々と頭を下げた。その時、ボブの髪型が前に垂れ下がった。
「・・・謝るんだな」
これには少し驚いて、浅田の方を見た。
「どこまで知ってるんだ?」
状況が掴めず、聖奈に抽象的に聞いてみた。
「う~ん。説明したんだけど、人格が入れ替わったと思ってる」
「まあ、間違ってはいないな」
秋彦にとっては、その認識でも構わなかった。
「本当にアキ君じゃないんだね」
秋彦の言動を見た浅田が、悲しそうな顔をした。
「ご、ごめん。私のせいだよね」
「は?」
「あたしが追い込んじゃったせいで、精神を病んじゃったんだよね」
「あ~、それは違う・・・」
「あたし、責任取るよ!」
秋彦が否定しようとしたが、浅田の力強い言葉で遮られた。
「せ、責任?」
「うん。未成年だからできることは限られるけど、身の回りの世話はできるよ」
この申し出は、酷く迷惑なだけだった。
「気持ちだけ貰っておくよ」
「・・・優しい」
浅田が両手を合わせて、何かに感動していた。
「浅田は謝りに来たのか?」
「え、あ、うん」
聞き方に違和感があるようで、かなり戸惑った返事をした。
「で、できれば浅田じゃなくて、姫って呼んで欲しいな」
「あー、前はそう呼んでた?」
「う、うん」
この事実には、自分自身に頭を抱えた。
「ひ、姫」
正面の聖奈が、複雑そうな顔でぼそっと呟いた。
「悪いが、姫とは呼べない。理由は呼び慣れてないことと、呼ぶのが恥ずかしい」
「そ、そんな・・・」
これには悲しそうな顔で俯いた。
「呼んであげたら?」
浅田に同情したのか、聖奈が軽い感じで言ってきた。
「いや、無理だ」
「たかだかあだ名でしょ。私のことだって、セナって呼んでるし」
「あれは呼びにくいから簡略しただけだ」
「浅田より姫の方が呼びやすいでしょ」
「姫って呼ぶぐらいなら、アサって呼ぶ」
「・・・捻くれてるわね」
さすがにこれには呆れたようで、溜息交じりで微笑んだ。
「う~、仲良いね」
聖奈とのやり取りに嫉妬したのか、浅田が不満そうに呟いた。
「た、ただの腐れ縁だから、に、睨まないで欲しいわ」
浅田に恐怖を抱いている聖奈には、睨まれてると感じたようだ。
「アサは、これからどうしたいんだ?」
「姫って呼んでくれないの?」
「人格が入れ替わるまで、絶対呼ばない」
「今のアキ君は頑固なんだね」
「まあ、人格が入れ替わるまで会わない方がいいかもな」
「え、嫌だ」
この答えには強い意志を感じた。
「俺は、ゲームの話はできないぞ」
「え、なんで?」
「ゲームの記憶がないからだ」
「そう・・なんだ」
これにはがっかりして肩を落とした。
「じゃあ、オンゲーもできないの?」
「ああ、無理だ」
ここを曖昧にすると、後々が面倒なのできっぱり言い切っておいた。
「あと、アサには注意して欲しいんだが、分単位の連絡はやめてくれ。無視され続けてる理由も、それが原因だから」
電話やメールを分刻みでやられると、返すタイミングを失うのは当然だった。
「そ、それは薄々感じてた」
「でも、引けなかったか」
「自分でも制御できなくて。ごめんなさい」
浅田は、落ち込んだように謝った。
「だ、だからね。許してあげて欲しいのよ」
聖奈が浅田のフォローに入った。
「許すと言われても、俺が判断するべきじゃない」
別に浅田とはクラスメイトというだけで、話したのも今日が初めてだった。
「とりあえず、俺の人格が変わるまで会わない方がいいと思うんだが」
「いつ、変わるの?」
「最低で2~3年かも」
「そ、そんなに・・・」
浅田にとっては長いようで、絶望的な顔をした。
「長くてどれくらい?」
今度は聖奈が、浅田に代わって聞いてきた。
「情勢にもよるからわからん。10年かもしれないし、20年かもしれない」
「それって、一生変わらない可能性もあるってこと?」
「それも有り得る。もともとこうなった原因も明確にはわかってないからな」
自分で口にして、考えなようにしていた絶望感が募ってきた。
「これから俺は忙しくなる。二人に構っている余裕は正直なくなる」
「忙しいって、何するの?」
浅田は心ここに非ずなようで、代わりに聖奈が聞いてきた。
「まずは資金集めだ。その後に設備を充実させる」
設備を自分で作るという手もあるが、専門外なので余計時間が掛かりそうな気がした。
「元の秋彦に戻したいのなら、できるだけ関わらないで欲しい」
秋彦の拒絶に、浅田がすすり泣きしてしまった。
「秋彦は、私の努力を無駄にするのね」
それを見て、聖奈が嫌な顔をして責めてきた。
「悪いな。ここに連れてきた時点でそう言うつもりだった」
「秋彦の馬鹿」
この罵倒は、甘んじて受けることにした。
「話は以上だが、二人はどうしたい?」
一方的な宣言は嫌だったので、二人の意見も聞いておきたかった。
「え、どうしたいって?」
これには聖奈が、不思議そうな顔をした。
「人格の違う俺と会いたいかって話だ」
「嫌な聞き方するわね」
「事実を言ってるだけだ」
「それを聞くなら、浅田さんを宥めてからにしてよ」
未だ泣いている浅田を見ながら、秋彦を責めてきた。
「俺、こういうの苦手なんだがな」
聖奈に言われては、何もしない訳にもいかなくなってしまった。
秋彦は座ってる浅田の横にひざまずいて、浅田を見つめた。
「アサ、もう泣かないでくれ」
しかし、何を言っていいかわからず、結果的に言い聞かすかたちになってしまった。
「う、うん」
それが功を奏したのか、顔を赤らめて泣き止んでくれた。
「で、どうする?」
秋彦は椅子に座って、この場を仕切り直した。
「あたしは、人格が変わってもアキ君はアキ君だから会いたい」
「私も同じかな~」
聖奈は、浅田に便乗するように言った。
「わかった。じゃあ、日曜日に2時間だけ会おう」
「え、会ってくれるの!」
これには浅田が、嬉しそうに喜んだ。
「でも、かなり細かく決めるわね」
聖奈の方は少し不満そうな顔だった。
「こっちは家事全般する上に、勉強もしないといけないんだぞ」
「なら、家事を手伝うわよ」
「必要ない」
「即答するのね」
「当たり前だ。同級生にそんなことしてもらいたくない」
あっちでは恋人という理由で強引に炊事をしていたが、ここでは聖奈もただの同級生でしかなかった。
「まあ、言いたいことはわかるわね」
「だから、日曜日に会うだけでいいだろう」
これ以上の譲歩はする気はなかった。
「だってさ。浅田さん、どうする?」
「うん。それでいいよ」
これには浅田も納得したようで、表情は晴れやかだった。
「話は変わるが、携帯をスマホにしたのはなんでなんだ?」
これは気になっていたので、浅田に対して聞いてみた。
「え、それはSNSができない携帯だったから、変えてもらったんだよ」
「番号まで変えた理由は知ってるか?」
「うっ!そ、それは、その・・・」
この指摘には、答えにくいようで言葉を詰まらせた。
「その反応だと、セナへの嫉妬か?」
「う、うん」
浅田は気まずそうに、聖奈を横目で見た。どうやら、番号を変えた本当の理由は、浅田にも教えなかったようだ。
「アキ君って、ゲーム以外の話って緒方さんの話ばかりだったから」
「え、そうなの?」
これは意外だったようで、聖奈が驚いた顔をした。
「ご、ごめん。緒方さんは悪くないんだけど。その、ずっと好きなんだな~って思いが伝わってきて、その・・・」
本人の前では言いづらいのか、なかなか言葉が出てこなかった。
「でも、現実にはずっと避けられてたんだけどね」
それを思い出したのか、聖奈が複雑そうに頬を掻いた。
「その理由は別にある」
「もしかして、あの嘘?」
「それもある」
秋彦はそう言って、スマートフォンを指で操作した。
「沢口健一郎って知ってるか」
そして、画面に出ている名前を声に出した。
「さわ・・ぐち、君?」
「沢口」
浅田は不思議そうな顔だったが、聖奈の方は嫌悪感たっぷりな顔になっていた。
「沢口君はクラスメイトだよ。っていうか、アキ君の友達じゃないの?」
浅田には、沢口と友達という認識のようだった。
「なんでそう思うんだ?」
「だって、番号とメアドをあたしに聞いてきたし」
「友達なら俺に聞くだろう」
「うん。それ、あたしも思ったけど。その時アキ君休んでたから、急ぎの用なのかな~って思って」
秋彦との関係性を勘違いして、教えたのは致命的だった。
「沢口って、私に告白してきた人よ」
「え、そうなの!」
聖奈の言葉に、浅田が驚きの声を上げた。
「まあ、フッたけどね~」
沢口が嫌いなようで、聖奈が悪びれることなく言い放った。
「それが原因だ」
秋彦は受信メール画面を開いて、スマートフォンを二人の前に滑らせた。
「え、何が?」
「読んでみろ」
口頭で説明するより、メールを読ませた方が早かった。
二人は顔を近づけながら、それを読み始めた。
「スクロールすると、その前のメールも読めるから」
秋彦が登校拒否になった理由は、聖奈にフラれた沢口の八つ当たりだった。内容は秋彦のせいでフラれたとか荒唐無稽なものばかりで、最終的には学校に来るなに変わっていた。
「何これ?気持ち悪い」
これには聖奈が超不機嫌になり、低い声が漏れた。
「完全な言い掛かりだね」
浅田も怪訝そうな顔で感想を漏らした。
一通り読むと、二人とも不快感をあらわにしていた。
「あたしがプリント持ってくる時に限って、家に行くってメールしてるね」
「それが浅田さんと会わなかった理由なのね。私が来た時にもメールを五通も送ってるわね」
浅田が来る日には、必ず沢口が訪問するようなメールが届いていた。
「もう学校も辞めたから、メールもこなくなるだろう」
実際、毎日送られるひがみのメールも今日は一通も送られてこなかった。
「原因つくったのって、私?」
「そうなると、それを手引きしたのは、あたしってことになるけど?」
聖奈と浅田が、状況の解析をお互い確認した。
「沢口の八つ当たりだから、どっちも悪くないな」
こればっかりは責める相手は、沢口しかいなかった。
「もう時間も時間だし、今日は帰ってくれ」
外は既に赤みがかっていて、日が沈みかけていた。
「あ、そうね」
聖奈が時間を見て、横に置いてあった鞄を持った。
「じゃあ、これからは日曜日に会ってくれるのね」
「まあ、会いたければの話だがな。それはそっちから連絡してくれ」
正直な話、秋彦としては積極的に会いたくはなかった。ここで思い入れを強めては、帰ることが困難になりそうだったからだ。
「一人2時間?」
浅田が上目使いで、甘えた声で聞いてきた。
「二人で2時間だ」
「そう」
これには残念そうに肩を落とした。
二人を玄関まで見送って、父親の部屋へ向かった。
「ネット口座の申し込みした?」
部屋に入り、背中を向けている父親に声を掛けた。
「ああ、しておいた。資料は明日以降にくるみたいだ」
「そうか。明日は買い物行くから、荷物持ち頼む」
「何か買うのか?」
「ああ、調理器具とパソコン一式だな」
「え、パソコン買うのか?」
「ああ、今のスペックじゃあ、トレードに支障きたすし、一台だけじゃあ即座に対応できない」
「そういうものなのか」
「情報戦だからな」
「買うなら、ネットでもいいだろう」
「自作するから、パーツを買いに行くんだよ」
「え、パーツの種類とかわかるのか?」
「まあな。市販されてるのはオールマイティな物だからな。自分で組み立てた方が経費も浮くし、自分好みに改造できる」
「あ、ああ、わかった」
秋彦の説明に、父親が気圧されたような返事をした。
「あと、夕食は7時ぐらいだから」
父親にそう伝えて、時間まで学術書を読むことにした。
第八話 聖奈と浅田の告白
「なあ、もう帰りたいんだが・・・」
荷物を持った父親が、うんざりした顔で言ってきた。
買い物に来て、既に2時間は経過していた。
「ああ、そうだな」
調理器具はすぐ決めたのだが、パソコンの処理能力には拘りたかったので、電気街を彷徨っていた。
「ここにはないみたいだから、オークションで落とすか」
「え!それするなら、最初からそうしてくれよ」
「オークションって、ガセとかぼったくりが多いし、良い物ほど値段が高くなるから見つけるのが大変なんだよ」
「じゃあ、ネットで正規品のパーツ買えばいいだろう」
「昨日調べたけど、売り切れてるんだよな~」
「じゃあ、入荷するまで待つしかないな」
「まあ、型落ちは売ってたけどな」
「それじゃあダメなのか?」
「う~ん。最終的にそれになる可能性もある」
あったら儲け物と思っていたので、ないならないで仕方なかった。
「帰るか」
長時間歩き回って足に疲労感を感じたので、探すのを諦めて帰ることにした。
家でパソコンを組み立てていると、スマートフォンから着信音が鳴った。画面を見ると、聖奈の名前が表示されていた。
「もしもし」
『今から行ってもいい?』
「・・・昨日の話聞いてたか?」
『日曜日に会うんでしょう』
「なのに、なんで来るんだよ」
『え、別に会うんじゃなくて、家にお邪魔するのよ』
「一緒だろっ!」
こっちでの聖奈は、思考回路が滅茶苦茶だった。
「そんなに俺に会いたいのか」
ここまで来ると、本気で好きと言ってるのと変わらなかった。
『え、いや、別に・・・』
自分の行動に気づいたのか、突然しどろもどろな声になった。
『ほ、ほら、また来ていいって、前に言ってたでしょう』
前のことを思い出したのか、それを引き合いに出してきた。
「だから、日曜日に2時間だけ会う約束したんだろう」
あの時は日時までは指定してなかった。
『えっと、来たら迷惑?』
「いや、嬉しいんだが・・・」
『じゃあ、今から行くわね』
秋彦が最後まで言う前に、聖奈が嬉しそうに言って電話を切った。
「最後まで聞けよ」
スマートフォンから流れるビジートーンを聞きながら、誰もいない部屋で一人愚痴った。
「お邪魔しますっ♪」
聖奈が上機嫌で家に入ってきた。学校帰りのようで制服姿だった。
「今日もテストだったのか」
時間帯的にテスト期間中でなければ、こんなに早い下校はありえなかった。
「うん。今日で終わり♪」
テストから解放された喜びが強いのか、満面な笑顔を見せた。
「アサはいないのか?」
てっきり一緒に来ると思っていたので、聖奈の後ろを確認した。
「え、呼んだ方が良かった?」
浅田の名前に少し不満そうな顔をした。
「いや、別に」
浅田を呼ばれても、話す話題は思いつかなかった。
父親のいるリビングを素通りすると、聖奈が父親に軽く挨拶して、秋彦の部屋までついてきた。
「あれ?散らかしたわね」
聖奈が部屋を見て、床に転がっているパソコンのパーツを拾った。
「悪いが、失くすと動かなくなるから触らないでくれ」
「あ、ごめん」
聖奈は謝って、拾ったパーツをその場に置いた。
「何してるの?」
「見てわかるだろう。パソコンを組み立ててるんだ」
「そんなことまでできるの?」
「誰でもできるように作られてる」
秋彦はそう言って、組み立てを再開した。
「凄いね」
そんな秋彦を見て、聖奈はベッドに座った。
「ところで用はないのか」
「え、特にないけど」
「じゃあ、ここに来たのは俺と一緒にいたいからか?」
「はぁ、別にそんなことないし!」
「うん。その反応は実に可愛い!」
ツンデレな態度を見たくて、ついつい煽ってしまった。
「あ、あんまりからかわないで欲しい」
自分が踊らされてると察したようで、恥ずかしそうにそっぽを向いた。
「え、チャームポイントなのに?」
「私は、別にそこを魅力だと思ってないわよ」
「可愛いのに・・・」
「うううっ」
秋彦の呟きに、聖奈は複雑そうに唸った。
「そういえば、テストはどうだったんだ?」
「え、テスト?」
急に話題を変えたので、返事に動揺が見られた。
「終わったんだろう」
「結果はわからないわよ」
「自分で採点ぐらいできるだろう」
「それは教師の役目よ」
「もしかして、自己採点できないのか」
「二度もテスト見たくないのよ」
「二度も見る必要もないだろ。テスト受けたんなら、それで採点できるはずだ」
「それができるなら、テストの意味がなくなるわよ」
「それは言えてる。実際、俺には無意味に等しかったし」
「もしかして、自分が天才ってアピールしてるの?」
「いや、事実を言ってるだけだ」
「正直、嫌味にしか聞こえない」
「それはあっちのセナにも言われたな」
「秋彦って、本当に頭良いの?」
ここにきて猜疑心が芽生えたのか、訝しげな顔で聞かれた。
「自分では頭良いなんて思ったことない」
「嫌な返しするわね」
「自分で聞いておいて、そんなこと言うなよ」
「テストしてみてよ」
聖奈はそう言って、鞄を漁り始めた。
「そんな時間ないんだがな~」
ただでさえ時間が惜しいのに、テストなんて無意味なことはしたくなかった。
「これは秋彦への挑戦よ」
「なんの挑戦だよ」
この言い回しには呆れるしかなかった。
「そもそも俺が答えても、聖奈には答えがわからないから意味なくないか」
「答案もらったらできるでしょう」
「なら、答案を貰ってからしないか」
「・・・それもそうね」
この合理的な意見には納得したようで、問題用紙を鞄に戻した。無駄な時間を割かなくて済んだことに安堵して、パソコンの組み立てを再開した。
数分間、この部屋に作業の音だけが響いた。
「暇だったら、帰ってもいいぞ」
「私が勝手に来たんだし、気を使うことないわ」
聖奈が立ち上がって、秋彦の作業を興味深そうに覗き込んだ。
「ねぇ、勉強するって昨日言ってたけど、どんな勉強してるの」
「ん?これだ」
目の前の本棚にある学術書を取って、聖奈に手渡した。
「これは何?」
「研究者の論文だ」
「え、理解できるの?」
「できなきゃ、ここに置かないな」
「ふ~ん」
聖奈が流し読みで学術書のページを捲っていった。
「基本、英文なのね」
「ああ。英文が主流だからな」
「良く理解できるわね」
「理解が遅くても、勉強すれば誰でも理解できる」
「理想論ね」
「そうだな。思考回路が違えば、勉強しても理解は無理だな」
「それもあるけど。私が言いたかったのは、人は怠惰も堕落もするってことよ」
「確かに間違ってないな。父さんで実証されてる」
「・・・そう返されると思わなかった。今のは取り消すわ」
これには複雑な顔で前言を撤回した。
「は?必要ないだろう、事実なんだから」
「事実だとしても、道春さんの評価を下げるのは気が引けるわ」
「安心していい。父さんへの評価はゼロに等しい」
「え、そうなの!」
「ギャンブルで借金したからな」
「あ~、そうなんだ」
これは知らなかったようで、精一杯の苦笑いをした。
「で、でも、ギャンブルで取り返したんでしょう」
「それは俺の功績だ」
「少しは道春さんを持ち上げたら?」
「父さんは、煽てるより貶した方が成長するんだよ」
「そういうものかな~」
聖奈はそう言いながら、学術書を本棚に戻した。
「え~と、秋彦ってさ。お金儲けとか得意なの」
「はぁ?金儲けに得意も不得意もないだろう」
「そうかな?」
「金銭の損益は駆け引きか対価だけだ。あ、犯罪もあったな」
「犯罪の部分は聞きたくないけど、駆け引きと対価って何?」
「投資か労働だ。投資は労働者へのお金の献上で、労働は投資者への時間の献上だな」
「労働で稼いでも借金してる人はなんでだと思う?」
「労働より投資額が多すぎたんだろうな。ちなみに、ローンも投資だ」
「消費も投資なの?」
「当たり前だ。消費は自分への投資だ。生きられなきゃ、労働もできないからな」
「でも、贅沢品とかは生きることと関係ないと思うけど」
「贅沢品なんて、自分の欲を満たすんだから投資に決まってるだろう。それを買う為に働いてる人もいるし」
「じゃあ、欲しい物がない人は?」
「そういう人間のほとんどは、他人への献身で動いているな。贅沢品と同じで自己満足の一種だな。まあ、ペットを飼ってるのと同じだ」
「最後の言い方は棘があるわよ」
秋彦の言い回しに少し困った顔で注意してきた。
「それならさ、税金はどうなるの?」
「税金は国への投資だろう。それがなくなれば、国が立ち行かなくなり犯罪が横行する」
「国は、安心安全な社会を担保してるのね」
「そういうことだな」
「良くできた社会ね」
「ここまで遠回しに話したが、そろそろ本題に入ってくれないか」
秋彦はパソコンを組み立てをやめて、聖奈の方に振り向いた。
「そうね。言いにくいけど、親が借金してるのよ」
聖奈は観念したように、身内の現状を吐露した。
「そっちもか」
この事実には同情心が芽生えた。
「お互い、親には苦労するな」
「あっちは隠してるみたいだけどね」
「じゃあ、なんで知ったんだ?」
「家に電話があってね」
「金融会社だったか」
「うん」
そのことを思い出したのか、悲しそうに肩を落とした。
「で、セナはどうしたいんだ?」
「え?どうって・・・」
「そもそも、借金額はいくらなんだ?」
「し、知らない」
「情報不足も甚だしいな」
「自分でもそれは思ってるわ」
「残念だが、セナにできることはない」
この国は、親の借金を未成年が清算できる見込みはほとんどなかった。
「で、でも、秋彦はできたじゃない」
「競輪のことか?」
「そ、そうよ」
「あれは、父さんの協力がないとできないことだ。未成年ができるギャンブルは宝くじだけだ」
「じゃ、じゃあ、道春さんに頼んで、秋彦が予想してくれれば・・・」
「もし当たったら、親にどう説明するんだよ」
「うっ、そ、それは・・・」
「セナの未来予測は、相変わらず未熟だな」
そこが可愛いところでもあるが、それはここでは言う必要はなかった。
「まずは、親と話し合え。話はそれからだ」
秋彦はそう言って、パソコンの組み立てを再開した。
「あ、それと競輪で当たったのは、まぐれだからな。そこに希望を見出すなよ」
競輪のことを勘違いしているようなので、念の為に補足しておいた。
「・・・帰るわ」
言い負かされたことがショックなのか、悄然とした顔で立ち上がった。
「そうか」
聖奈を見送る為、作業を中断した。
「秋彦って、少し冷たいね」
部屋に出る前に、聖奈が寂しそうに呟いた。
「感情で同情は買えるかもしれんが、金は稼げん」
「それに意地悪」
秋彦のボケがウケたようで、聖奈が表情を綻ばせた。
「借金してる家庭なんて、この国に数えきれないほどいる。未成年のセナが、それを気にする必要はないと思うが」
「今の秋彦といると、世の中が軽く見えるわね」
「言葉にすれば軽いだけさ。やって初めて苦労がわかる」
「未成年の私には重い言葉ね」
セナは部屋を出て、リビングの父親に挨拶して玄関に向かった。
「また明日も来ていい?」
玄関のドアを開けて、少し恥ずかしそうに秋彦を横目で見た。
「好きにしたらいい」
「ありがとう」
秋彦の答えに、聖奈がお礼の言葉を口にして出ていった。
部屋に戻る途中、父親がリビングのソファーから顔を出した。
「来た時と機嫌が変わってたけど、なんかあったのか?」
主語が抜けていたが、聖奈のことを言ってるようだ。
「親の借金で悩んでるんだとよ」
「な、なるほど」
自分も同じ経験をしているからか、返事に動揺が見られた。
「父さんは、セナの家庭の事情は知ってるか?」
「全く知らない」
「だろうな」
あまり期待してなかったが、堂々と言われると呆れるしかなかった。
「そういえば、知り合いとは連絡取れた?」
「あ、ああ。一人は明日なら大丈夫って言ってたな。もう一人は土曜日かな」
「明日か・・時間は聞いてるのか?」
「午前中しか空いてないってさ」
「そうか。仕事は何してるんだ?」
「私立大学の准教授だよ」
「私立大学?どこに住んでるんだ?」
この近辺に私立大学なんて聞いたこともなかった。
「隣の県だ。新快速で4駅だったかな」
「なら、9時にお邪魔しようか」
「まあ、無難だな」
「じゃあ、そう伝えておいてくれ」
「わかった」
父親はそう言って、テーブルにある携帯を手に取った。
部屋でパソコンの組み立てを終わらせたが、一つだけパーツが足りなかった。足りないパーツをネットオークションで探すと、即決価格が設定された良い物があったので、すぐに落札しておいた。
夕食後、リビングで父親と論文を検証していると、スマートフォンに着信があった。
「ちっ、誰だよ」
父親との討論が盛り上がっていたので、着信音に邪魔されてしまった。
「もしもし」
自分の部屋に入り、スマートフォンの通話を押した。
『あ、アキ君?織姫だけど・・・』
「ああ、何か用か?」
画面で浅田だとわかっていたので、そのまま話を進めた。
『えっと、その、さ、沢口君のことなんだけど』
「沢口?何かあったのか」
『う、うん。緒方さんが一緒に懲らしめようとか言ってて』
「は?」
聖奈から何も聞いていなかったので、驚きで言葉が出なかった。
『アキ君をいじめたことが許せないみたいで』
「せっかく俺が退学したのに、なんでわざわざ波風立てるんだ?」
『多分、ずっと好きだったんだよ。沢口君のせいで、引き離されたのは事実みたいだし』
「ん?でも、セナは彼氏がいるって嘘ついてたはずだが」
『そのことで誤解を解こうとしたけど、無視され続けてたみたい』
「その原因が沢口ってことか」
『うん』
「全く、沢口はとことんタイミングが悪いな」
『ホントだね。狙いすましたように緒方さんから嫌われるね』
「いまさら仕返しなんて、意味ないから止めてくれ」
『あたしもそう言ったけど、かなり熱を入れていてやめてくれそうにないの』
「それは困ったな」
『うん。だから、こうして電話したんだけど』
「わかった。俺から説得しておこう」
『あ、ありがとう。お願いするね』
「ああ」
あまり気は進まなかったが、余計なとばっちりの可能性もあるので、聖奈には大人しくしてもらうことにした。
『あ、あと、その、い、今のアキ君って、緒方さんのことは好きなの?』
「ああ、好きだ」
『ど、堂々と言うんだね』
秋彦の迷いのない答えに、浅田は呆れた声で空笑いした。
『やっぱり幼馴染には敵わないのかな』
「それは元の人格に確認すればいい」
『それでも答えは一緒だと思う』
それは秋彦もそう思っていた。
『あたし考えたんだけど、身を引こうと思う。緒方さんには勝てないし』
「もう会わないってことか?」
『ううん、違うよ。友達のままでいさせて欲しいの』
「それでいいのか?」
『うん。アキ君と一緒に居るだけで楽しいし、幸せなの。それ以上は贅沢だと思う』
「そうか」
これは個人の価値観なので、余計なことは言うべきではなかった。
『でも、これは今のアキ君にしか言わない』
「なんでだよ」
『恋はライバルがいた方が燃えるんだよ』
「なんだそれ?」
浅田の矛盾した言葉に思わず笑ってしまった。
『あたしはあくまで引き立て役で、二人の仲を思いっきり掻き乱すの』
「それは楽しそうだな」
『うん、楽しいと思う』
それを思い浮かべたのか、楽しそうな声だった。
『・・・アキ君、大好き』
浅田が少し間を置いて、今日一番の明るい声で告白してきた。が、少し泣き声も交じっていた。
「ありがとう。俺もそういう素直なアサは好きだぞ」
これは最初で最後の告白だと感じたので、秋彦なりに誠意を込めて応えた。
『やっぱり、今のアキ君も優しいね』
泣くのを堪えたような鼻声だったが、嬉しそうな声が返ってきた。
『そろそろ切るね』
「ああ、また日曜日にな」
『メールとかSNSはできないの?』
「そんな時間はないな」
『そっか。ちょっと残念だね』
「悪いな」
『しょうがないよ。あたしのせいでもあるんだし』
「言っておくが、アサのせいじゃないぞ」
『本当に優しいんだね』
自分が気遣われてると思ったようで、優しい声で言ってきた。
「そのことは日曜日に話そう」
このまま説明するのは時間が掛かりそうなので、今日は諦めることにした。
「じゃあな」
『うん』
浅田の返事を聞いて、電話を切った。
「長かったな、誰だったんだ」
リビングに戻ると、父親が視線を学術書から離した。
「浅田だ」
内容は言えないので、淡泊にそう答えた。
「あ、そうそう、カンロクから電話あったぞ。ありがとうだとさ」
「お礼を言うってことは、成功したんだな」
「もしかして、あの時助言したのか」
「ああ、あっちでは論文は完成してたからな」
「なるほどな」
「あれが成功したら、あらゆる物が磁力で浮かすことができる」
「え、あっちではそうなってるのか?」
「いや、開発中だ。製品化するのには、どんな物でも時間が掛かるんだよ」
「まあ、そうだよな~」
父親が納得したように首筋を掻いた。
「それよりさっきの続きだ」
「え、まだやるのか!」
「当たり前だ。これは父さんの研究テーマを決めるものでもあるんだからな」
「重ね重ね世話を掛けるな」
「そう思うなら、嫌そうな顔をするな」
その後、2時間にわたり議論を交わした。
第九話 講義と雑談
「あんまり収穫はなかったな」
秋彦は歩きながら、隣の父親に溜息交じりに話しかけた。父親の二人目の知り合いは三瀬麗花という女性で、専門分野が生態医学だった。その分野は、秋彦には完全に専門外だった。
「いや~、あんなに驚いた三瀬を見たのは初めてだったな」
父親の方は久しぶりということもあり、息子の存在を忘れるぐらい会話を楽しんでいた。
「あっちも独身みたいだし、結婚してみたら?」
「あ~、無理。三瀬は怒ると怖いんだ」
「怒ったら、誰でも怖いだろ」
「三瀬の場合は、ヒステリックになるんだ」
「そうか」
これ以上は野暮なので、話を終わらせることにした。
「秋彦は、母親が欲しいのか」
「そんなこと思ったことないけど、父さんがしたいなら別に構わないと思ってる」
「まあ、そういうのは職に就いてから考えよう」
「ああ、それは言えてるな。そろそろ就職活動に移るか」
「・・・そうだな」
就職活動が不安なのか、少し表情が強張っていた。
「不安なら、知り合いに紹介してもらうのも手だぞ」
「それは嫌だ。なんか恥ずかしい」
「そんなプライドは邪魔だから捨てろ」
「ううぅ、わ、わかった」
秋彦の睨みに、父親が怯みながら了承した。
「じゃあ、今から三瀬さんに電話して、助手を募集してないか聞いてくれ」
「え~、三瀬に頼むのか~」
「私立大学なんだから、口利きできる余地があるだろう」
「でも、あの大学って工学分野はなかったと思うぞ」
「だから、それを聞くんだよ」
「さっき話したばっかりで、電話は気が引けるんだが」
「できることは早く済ませた方が、今後の対策も変わってくる」
駅に着いて、二人は切符を買った。
「電車乗るから、後ででいいか?」
「そうだな、帰ってからにするか」
父親の言うことももっともなので、ここはマナーを優先することにした。
電車に乗って、最寄駅まで父親とこれからのことを話し合った。
家に帰って、すぐに三瀬に電話させたが、助手の募集はないようだった。
株と外為の投資会社から資料が届いていたので、父親に申請書に必要事項を書かせて、郵便局へ向かわせた。その間、秋彦は父親の職をネットで探した。
「研究員の募集は少ないな」
その上、父親と専門分野が違っていて、とても採用してくれそうになかった。
3時間後、聖奈が不機嫌な顔で来訪してきた。今朝、電話で沢口に何もするなと、釘を刺したことが不満なようだった。
「どういうことか説明して欲しい」
部屋に入ると同時に、聖奈が問い質してきた。
「何が?」
「だから、沢口に何もするなって」
「そんなことしても、セナの気が晴れるだけで、またこっちにとばっちりを食う可能性がある」
「そうならないようにするわよ」
秋彦の言い分に、聖奈が膨れっ面で反論した。相変わらず、聖奈の未来予測は欠けていた。
仕方がないので、別の切り口から攻めることにした。
「沢口に報復するなら、無視することが一番だ。余計なことすると、好意を持たれたと勘違いされるかもしれないぞ」
沢口のメールを見る限り、その可能性は否定できないことだった。
「・・・確かに、それはあり得るわね」
聖奈もそれを見ているので、荒唐無稽とは言えなかった。
「だから、沢口には完全無視で報復してくれ」
「・・・」
「頼む」
ここまで言っても葛藤しているようなので、もう頭を下げてお願いするしかできなかった。
「はぁ~、わかったわよ。ずっと無視しておけばいいのね」
「ああ、そうしてくれ」
少しだけ申し訳なく思ったが、今後のためにも堪えて欲しかった。
「あ、パソコンの組み立て終わったのね」
聖奈が床に置かれたパソコンを見て、完成したと勘違いした。
「いや、まだ動かない」
「え、なんで?」
「部品が一つ足りない」
「まとめて買わなかったの?」
「探してた物がなくてな、昨日ネットオークションで落札したばかりだ」
「ふ~ん。何が足りないの?」
「どうせ言ってもわからんだろう」
「聞いてみないとわからないでしょう」
「GPUコアだ」
「え~と、GPUってなんの略だっけ?」
やはり聞いてもわからないようで、精一杯な質問をしてきた。
「グラフィックプロセッシングユニットだ」
「・・・そうそう、今日テストがまとめて返ってきたわ」
これ以上の会話は厳しいと悟ったようで、苦笑いで話題を変えてきた。
「そういえば、まとめて返すんだったな」
聖奈の通っている学校では、テストが終わった次の日には全教科のテストを返すのが通例だった。
「じゃあ、今日は授業なかったのか」
「うん」
しかも、全教科の答え合わせだけで丸々1日費やしていた。
「という訳で、今日は秋彦の学力を試します♪」
聖奈が楽しそうに、鞄からまとめた問題用紙を取り出した。
「しょうがないな」
面倒を避けるためではあったが、自分から言い出したことなので、テストを手早く済ませることにした。全教科は時間が掛かるので、五教科だけにしてもらった。
それを1時間ほどで終わらせて、聖奈に採点してもらった。
「そ、そんな馬鹿な」
採点が終わると、聖奈が驚愕の声を上げた。
「気は済んだか?」
「あ、秋彦に負けるなんて・・しかも、全部満点」
本当にショックのようで、座っているベッドに後ろに倒れ込んだ。
「セナ。その体勢はパンツが見えるぞ」
制服のスカートは丈が少し短いので、座ってる秋彦からは見えそうだった。
「えっ!」
聖奈が大慌てて、上半身を起こしてスカートを押さえた。
「み、見た?」
「いや、見えてないけど」
「そ、そう・・・」
聖奈は赤面しながら、気まずそうに視線を外した。
「あ、しまった!」
秋彦はあることに気づいて、思わず声を上げた。
「え、どうしたの?」
「テストの点で、セナと勝負すれば良かった」
「それしてどうするのよ」
「いや、負けたら言うこと聞いてもらおうと思ってな」
「え、な、何するつもりだったの」
不安と恥ずかしさが入れ交じったような顔で、チラチラと秋彦を見た。
「ちぇ、おしいことしたな」
いまさら内容を言っても、意味はないので答えないことにした。
「え!何するつもりだったの」
それが不安を煽ったのか、あからさまに挙動不審になった。
「そういえば、両親とは話せたのか」
「え、ここで話題変えるの!」
「もう意味ないし」
「いや、私は気になるんだけど」
「別に大したことじゃない」
「じゃあ、言ってよ」
「やってくれるなら言う」
「ひ、卑怯」
秋彦の意地悪な返しに、苦虫をかみ潰したような顔をした。
「で、両親に聞けたのか?」
「諦めたわ。秋彦の言うとおり、私には何もできそうにないし」
そう自虐すると、深い溜息をついた。
「賢明だな」
昨日の帰る姿を見て、聖奈から言い出せない気がしていた。
「だから、社会人になってから聞くことにした」
秋彦の言いなりになるのが癪だったのか、精一杯の反抗を見せた。
「そうか」
これ以上は緒方家の問題なので、秋彦には口は出せなかった。
その後、聖奈がテストの間違えた部分を執拗に聞いてきた。
「なんで間違えたかなんて、自分で調べろよ」
「秋彦に聞いた方が早いでしょう」
「・・・」
その台詞はあっちの聖奈にも言われたことがあった。
「いいか、セナ。自分で調べた方が身に付くんだぞ」
なので、同じように言い聞かせてみた。
「何、説教?」
「やっぱりセナだな~」
この同じ返しには自然と頬が緩んだ。
「む、今、馬鹿にした」
「可愛いと思っただけだ」
これ以上は不機嫌になるので、褒め言葉で機嫌を取った。
「そ、それずるいわよ」
言われたことは嬉しいようで、必死で不満な表情をつくっていた。
聖奈が帰り、夕食の準備をしていると、父親がずっと電話をしていた。
夕食が出来ても電話しているので、父親に睨みを利かせて強制的に切らせた。
「誰と話してたんだよ」
「み、三瀬。久しぶりだったから、話すことが多くてな」
「ふ~ん」
これには父親の再婚のことを深く考えさせられてしまった。
「まあ、本人が決めることだからいいか」
が、お節介はしたくなかったので、本人の意思に任せることにした。
夕食後、父親の就職活動のことを考え、来週から職業安定所に通ってもらうことにした。
「気が重いな」
「日頃、何もしなかった付けだと思ってくれ」
父親の愚痴に呆れ気味に指摘した。
「はぁ~、就職できるかな~」
「すぐは無理だろうな」
長期間、無職だった人を雇ってくれる所は滅多にないことは推測できた。
「まあ、最初は情報収集から始めればいい」
「情報収集?」
「まずは、自分ができそうな仕事をプリントアウトして、職業訓練の資料も持ってきてくれ」
「なんか、職安に行ったことのあるような言い方だな」
「ネットに書いてある」
「え、それじゃあ、職安行く必要なくないか?」
「ネットに書き込まれても、職安に登録しないと応募できないだろう」
「そ、それもそうだな」
秋彦に圧倒されたのか、父親が怯みながら頷いた。
「それに職安で相談でもしてもらえば、ネットに掲載してない募集も紹介してくれるかもしれないしな」
「わ、わかった」
自分で行動することが不安なのか、項垂れるように返事をした。
土曜日になり、最後の父親の知り合いと公立大学の教授室で面会した。
「素晴らしい」
大学の教授である土屋道徳が、興奮気味に秋彦を絶賛した。彼は典型的な数学者で、ボーダーのポロシャツに紺のスラックスを履いていた。
「その歳でゼータ関数と数論的関数を理解できるなんて、僕は初めてみたよ」
興奮が収まらないようで、肩まである長髪を揺らしながら、細身の体を前に出してきた。
「それを知ったのは最近ですけど」
秋彦は、つくり笑顔で謙遜の言葉を口にした。
「いや~、大したものだよ」
「あ、あの、それで土屋さんは、空間と引力の概念を研究してるんですよね」
土屋の感心を聞き流すように、こっちのことを最優先にした。
「え、ああ、そうだね。まあ、数学者のやることなんて、誰も注目しないよ」
「まあ、実用的な成果は乏しいですからね」
「画期的なんだけどね」
「ええ、それは大いに同意します」
「こんな若者が理解してくれるなんて、これほど嬉しいことはないよ」
「そ、それで迷惑でなければ、これまで成果をお聞きしたいのですが」
また話が脱線しそうなので、必死で話を戻した。
「あ、あ~、そうだったね。公式がないから説明が長くなるんだが」
「構いません。ぜひご教授ください」
秋彦は、視線を正して頭を下げた。
「・・・その姿勢をうちの生徒たちに見せてあげたいよ」
土屋が寂しそうな顔で、ゆっくりと立ち上がった。
それからは専門用語が飛び交い、父親だけが置いてきぼりのかたちの講義が2時間続いた。
「素晴らしい1日だった」
講義を終えた土屋が、大満足な顔で秋彦たちを見送った。
「また、いつでも来てくれ」
「はい。その時はまたお願いします」
秋彦はそう言って、深々と頭を下げた。
「長かったな」
大学を後にすると、父親が呆れた様子で切り出してきた。
「いや~、有意義だったよ」
「そうか。こっちは全くわからなかったよ」
「それは勉強の差だから仕方ないさ」
「はぁ~、親として頑張らないとな」
「お、その意気込みはいいな」
別に煽るつもりではなかったが、やる気になってくれるのは嬉しかった。
家に帰って、今日学んだことと自分の研究を重ね合わせてみたが、失敗の危険度を考えると、やはり研究は封印するしかなかった。
そんなことを考えていると、オークションで落札したGPUコアが届いた。
「これで完成か?」
宅配便の中身を気にした父親が部屋まで来て、興味深そうに聞いてきた。
「ああ」
秋彦は上機嫌で、最後のパーツをはめ込んだ。
「あとは投資口座が開設できれば、すぐに始められるな」
とりあえずパソコンを立ち上げて、性能を確認した。
「増えると良いな」
「幸先悪いこと言わないでくれ。増やすんだよ」
「あ、そうだったな。すまん」
秋彦の指摘で失言だと気づき、申し訳なさそうに謝った。
「父さん。一つ頼みがあるんだが」
「なんだ?」
「物置にある物って捨てられない?」
あっちでは実験室として使ってた場所が、ここでは物置として使われていた。
「ん~、まあ、片づけはできるけど、捨てれない物ばかりだな」
「母さんのばっかり?」
「ああ」
掃除した時、それは気づいていた。
「肩身として残すのはいいけど、減らしてくれないか」
「え?」
「あっちでは俺が、強制的に五つまでにしてもらったよ」
その時は父親とかなり揉めたが、秋彦が強引に母親の物を捨てたのだった。
「なんでそんなことを・・・」
「そういう物を見ると、死にたくなるんだよ」
あの日のことを思い出すと、自己嫌悪で自殺衝動に駆られることが多かった。
「だからさ。捨てて欲しいんだ」
「自分のせいだと思ってるのか」
「ははっ、あれは俺のせいだろう」
母親の死は、秋彦の不注意で起こった事故だった。
「・・・」
これには父親が黙ってしまった。
「母さんを殺した俺としては、母さんの物を見るのもつらいんだ」
あの時のことを考えたくなくて、秋彦は勉強に没頭し、果てには研究まで行きついたのだった。そして、父親も研究することで、その悲しみを忘れていた。
「こっちの二人は凄いな。母さんの物を置いておけるんだから。俺は、耐えられなかったよ」
「ただ置いてあるだけだ。見ることはあまりしない」
父親はそう言って、悲しそうに項垂れた。
「捨てるのが嫌なら、整理ぐらいはしてくれ」
こっちの秋彦はどうかはわからないので、あまり強引なことはできなかった。
「わかった」
秋彦の頼みに、父親が力なく答えた。
これがきっかけで、1日中父親と気まずい雰囲気になってしまった。
日曜日の午後、浅田と聖奈が家に来た。外で会うことも考えたが、誰かに見られて噂されるのは気が引けるので、家に招くことにした。浅田は、ボーダーの薄手の長袖にフレアスカートで、聖奈はレースのブラウスに九分丈のカーゴパンツだった。
「あ~、これが自作のパソコン?」
部屋に入るまで挙動不審だった浅田が、興奮気味に自作のパソコンに飛びついた。
「スペックは?」
浅田にはパソコンの仕組みがわかっていそうなので、チップセットの詳細まで答えた。
「最新なんだ。いいな~」
浅田が羨ましそうに自作パソコンを見つめた。
「最新なの?」
黙っていた聖奈が、秋彦に小声で聞いてきた。
「まあ、処理速度だけはな。他は旧型だ」
必要なパーツだけだったので、量産型のパソコンよりは安く済んでいた。
「これだったら、オンゲーもなめらかに動くよ」
「いや、俺はしないから」
「あ、そうだったね」
興奮しすぎて、秋彦の現状を忘れてしまったようだ。
「それより、ずるいよ。聖奈と隠れて合うなんて」
浅田が聖奈のことを名前で呼んだ。
「え、言ったのか?」
「う、うん。織姫と話してたら、口が滑っちゃって」
聖奈は、気まずそうに視線を逸らした。聖奈の方も浅田を名前で呼んでいるようだ。
「まあ、別に責めないけどさ~。これから抜け駆けはダメだからね」
「ちゅ、注意するわ」
聖奈が申し訳なさそうに、つくり笑顔をした。土曜日に来なかったのは、浅田に釘を刺されたからのようだ。
「で、外出も危険だし、何するんだ?」
秋彦は頭を掻きながら、椅子に腰かけた。
「話しかできないわね」
「え、ゲームとかできるでしょう」
聖奈の意見に、浅田が当たり前のように言った。
「私は、そういうのやらないわね」
「やったら面白いって」
二人は話しながら、自然にベッドに座った。
「ゲームって、やらされてる感強くて、したくないのよね」
「それは先入観だよ」
「それはそうかもしれないけど・・・」
「それに、アキ君が戻ったら話も弾むし」
ここは聖奈にもメリットがあると思ったのか、浅田が言葉を強めて言った。
「う~ん」
これには聖奈が、難しい顔をして唸った。
「それは二人の時にやってくれないか」
ただでさえ、2時間の制限を決めているのに、ゲームでその時間を潰すのは不毛に思えた。
「え~、なんでよ~」
「俺がゲームをする気がないからだ」
「う~ん、今のアキ君は頑固だった」
秋彦の宣言に、浅田が聖奈と同じように唸り声を上げた。
「それより、アサには事実誤認を解いておきたいんだが」
「事実誤認?」
秋彦は、ここで入れ替わった経緯を説明した。
「ファンタジー?」
最後まで聞いた浅田の感想は、聖奈と同じだった。
「残念だが事実だ。証人は俺だけで他に証明しようがないがな」
「じゃあ、あたしがアキ君を追い詰めたこととは関係ないの?」
「ああ、全くない」
「そっか。良かっ・・て、良くないよ!」
自分の責任ではないことにホッとしたようだが、考え直して力強く訂正した。
「これって、今のアキ君のせいじゃん」
「ああ、悪い」
「あ、でも、入れ替わったからこうして会えてるわけでもあるし。う~ん、責めるに責められないね」
浅田が困った顔で、独り言のように悩んでいた。
「それ、私も悩んだ」
聖奈も同じく悩んだようで、嬉しそうに浅田に同調した。
「だから、今のアキ君は頭が良いんだね」
「そうなの!五教科満点だったのよ!」
浅田の言葉に、聖奈が興奮気味に強調した。
「ふ~ん。パラレルならそれもあるんだね」
「不思議な世界よね」
二人は、今の現状に個々の感想を漏らした。
「まあ、俺からの話は以上だ。あとは好きに話せ」
「好きにって言われてもね」
聖奈が困った顔を浅田に向けた。
「じゃあ、世間話でもする?」
「あたしの世間話はゲームなんだけど」
「私は、雑貨用品かな」
二人の趣味の違いが浮き出てきた。
「俺は、世界経済だな」
一応、流れとして秋彦も答えておいた。
「見事にバラバラね」
「うん。どれも関連性がないものばかりだね」
聖奈に同調するように、浅田が困った顔をした。
「あ、そうだ。もう一つ二人に聞きたいんだが、前の俺はどんな性格だった?」
今まで失念していたが、このことは是非二人に聞いておきたかった。
「それ、前に私が答えたでしょう」
「いや、詳細に教えてくれ。セナには、母さんが亡くなった時の俺の反応だな」
「そ、それは言いたくないわ」
これには聖奈が、悲しそうな顔で拒んだ。
「どうして?」
「痛々しかったからよ。私もその影響を受けたせいで、両親から秋彦とはあまり付き合うなとも言われたし」
「なんだ。俺と一緒か」
「秋彦もそうだったの?」
「まあな」
「今の秋彦にそんなイメージないけど」
「まあ、半年ぐらいは落ち込んだよ。その後は、悲しみと向き合わなかった」
「そっか。こっちは数年引きずってたわ」
「それは凄いな」
これは秋彦には真似できないことだった。
「あの~、あたしが知らない話はあまりして欲しくないんだけど・・・」
辛気臭い話に、浅田が申し訳なさそうに割って入ってきた。
「悪いな。俺が気になったんだ。で、アサはどうだ?」
「う~ん、そうだね。典型的なゲームオタクだね」
「それは別の意味で痛々しいな」
「それって、あたしも痛々しいってことなんだけど」
「・・・そうだな」
本音を言うか悩んだが、ここは正直にいこうと思った。
「否定しないんだ!」
これには浅田が、つっこみを入れるように勢いよく立ち上がった。
「別に、今の俺に言われても問題ないだろう」
「さすがに同じ顔と声で言われたら傷つくよ」
「それは悪かった。前言を撤回しよう」
「全く、これからは注意してよね」
浅田が膨れっ面で、ベッドに座り直した。
その後、二人から秋彦の性格を詳細に聞いた。
「ふ~ん。臆病者なんだな」
それが秋彦が出した結論だった。
「え、私たちの話を聞いてた?」
「ああ。俺からすれば、臆病者にしか映らん」
「はぁ~、本当に捻くれてるわね」
聖奈が呆れ気味に溜息をついた。
「俺が聞きたいことは、もうないから勝手に話していいぞ」
「なんか投げやりだね」
今度は浅田が呆れ気味に言ってきた。
「じゃあ、俺がいた世界経済とこっちの世界経済の違いを話そうか」
「ごめん、興味ない」
本当に聞きたくないようで、浅田がばっさりと切り捨てた。
「じゃあ、これからどうするかを決めるか」
秋彦は、今後の話す内容を三人で話し合うことにした。
結局、なんの話をするのかまとまらず、一人一人が好きなことを話すという混沌とした場に成り下がってしまった。
「もう2時間経ったから帰れ」
時計を見ると、時間を少し過ぎていた。
「なんか凄く話が流れるわね」
「う、うん。なんか話の振り幅が凄かったね」
聖奈と浅田が、顔を見合わせて最後は苦笑いした。
「じゃあね、秋彦」
「またね、アキ君」
玄関まで見送ると、二人は軽く手を振って帰っていった。
数日後、読み終わった学術書を太田家に返しに行くことにした。
「どうだった?」
「いつでもいいだとさ」
父親に訪問の連絡してもらうと、意外なことに快諾してもらえた。
「じゃあ、今から行こうか」
「え、今からか!」
父親は、職業安定所から帰ってきたところだった。
「ああ、なんか予定があるのか?」
「いや、ないけど・・・」
「じゃあ、行くか」
渋る父親を強引に連れて、太田家へ向かった。
「ようこそ」
太田の服装は、ラインのポロシャツに白のスラックスだった。
「悪いな」
「ミッチーの息子には、頭が上がらないからな」
「なんだ、それ」
これには父親が、困った顔で空笑いした。
太田は研究の経緯を説明しながら、前と同じようにリビングに招かれた。
「うまくいきましたか?」
「ああ」
秋彦の笑顔に、太田も笑顔で返した。
「君の研究を是非聞きたいな」
「前にも言いましたが、僕の研究は証明できません」
「それでも聞いてみたい」
「やはり、研究者ですね」
「君も同じだろう」
これにはお互い笑い合った。
秋彦は、研究のテーマとここに至った経緯をこと細かく話した。
「なるほど。確かに、危険が大きい上に証明もできないな」
太田が真顔でそう結論付けた。
「だが、面白い実験ではある」
「どういうことですか?」
「君の研究と俺の研究を重ねてみないか」
「太田さんも同じこと考えるんですね」
「やはり、君も考えたか」
「ええ、何度かですが。しかし、危険すぎます」
「確かに、失敗の代償は大きいな」
これには難しい顔をして、声のトーンを落とした。
「あっちでは、研究資金はどうしてたんだ?」
「自分で稼いでましたよ。主に投資で」
「投資って、株とかか?」
「主に外為ですね」
「凄いな。いくら稼いだんだ?」
「ざっと数十億は」
「ははっ、大人顔負けだな」
「ただ運が良かっただけです」
「それは謙遜だな。運が良くてもそんなには稼げない」
さすがに民間で働いていた太田には、すぐに見抜かれてしまった。
「まあ、研究者に傲慢はいないか」
太田が思い直して、そんなことを口にした。
「今は生活保護で受けてたんだっけ?」
「いや、もう辞退した」
これに父親が淡泊に答えた。
「就職したのか?」
「最近、職安に行ってるな」
「どういうことだ?」
父親の言ってることに矛盾を感じたようで、秋彦に説明を求めてきた。
「僕が競輪で大穴当てたんですよ」
あまり言いたくなかったが、話の流れで避けられなかった。
「ギャンブルかよ」
「誰かさんが借金してなきゃ、する気もなかったんですけどね」
秋彦は、責めるように父親を横目で見た。
「借金してたのか?」
「あ、ああ」
「ミッチーはどうしようもないな」
「もう責めないでくれ」
二人の非難に、父親は居心地悪そうに委縮した。
「で、いくら当てたんだ?」
「1200万ぐらいです」
「おお、それは凄い」
「借金返済で800万になりましたけど」
「ミッチーの息子は有能過ぎるな」
太田が感心しながら、父親の方を見た。
「ホント有能過ぎて立場がないよ」
「親としてはそうかもな。だが、ミッチーの息子は将来有望だ」
太田は嬉しそうな顔で、秋彦を称賛した。
「ですが、僕はパラレルワールドの一つの可能性ですよ。もともとはゲームオタクみたいですし」
「それを聞くと、あっちの俺がどうなっているか気になるな」
「今とさほど変わりませんよ。ですが、名誉会長なんてしてませんでしたね。あと、僕に見せた論文は完成してました」
「なるほど。世界経済が変われば、研究も遅れる・・か」
「ええ、お金の流れが悪くなりますから、当然そうなりますね」
こればかりは、どうしようもないことだった。
「君は、これからどうするんだ」
「どうするとは?」
「元の世界に戻りたいのか?」
「ええ、恋人がいるので」
「ここでは恋人ではないのか」
「残念ながら違いますね」
「恋人の為に戻りたいか。天才でも恋をするのか」
太田は苦笑して、よくわからないことを口にした。
「ふむ。アッキーに協力しよう」
「あ、アッキー?」
急にあだ名で呼ばれ、思わず復唱してしまった。
「カンロクがあだ名で呼ぶ時は、そいつを認めた証だ」
父親が笑いながら、そんな説明をした。
「アッキー。これから共同で研究しよう」
「共同でですか?かなり危険ですよ」
「だからこそやるんだよ。というか、個人的には興味深い」
「太田さんの協力の申し出は嬉しいですが、今の僕の資金では実験設備は整えられません」
「安心してくれ。俺が全部出す」
「設備に最低2500万は掛かりますよ」
「なんだ、それだけでいいのか」
個人では大金のはずだが、太田にとっては安い金額だったようだ。
「本当にいいんですか?」
「ああ、勿論。アッキーは、一刻も早く戻りたいんだろう」
「まあ、そうですけど」
「なら、遠慮するな。といっても、俺の研究の為でもあるんだがな」
「僕の研究は、強力な磁力を生みますからね」
一か所にエネルギーを与えるので、自然と電磁力が発生していた。
「一つだけ、条件があります」
秋彦は今後のことも考えて、条件を付けることにした。
「なんだ?」
「失敗する条件は教えられません」
これを教えると、太田自身も巻き込まれる可能性があるので、それだけは避けておきたかった。
「わかった」
秋彦の意思を汲んでくれたようで、快く頷いてくれた。
それからは、太田と一緒に設備を整えながら、お互いの情報を交換した。
第十話 善意とお節介
1年後、秋彦の実験設備が完成した。
「ようやく完成したな」
「ありがとうございます」
秋彦はそれを見て、太田に感謝の言葉を口にした。
「いや、感謝するのはこっちだ。いろいろ研究も進んだ上に、金も入ってきたからな」
あれから、秋彦の助言で太田の研究は成功して、会社から大金を貰っていた。
「それは僕がいなくても出来たことですよ」
「アッキーは、本当に謙虚だな」
「そうかもしれませんね」
「すぐに戻るのか?」
「何も言わずに行くことも考えましたが、お世話になった人には挨拶してからにします」
「まあ、それがいいだろう」
「一度、帰りますね」
「明日には戻るのか」
太田が寂しそうな顔で言った。
「そうなりますね」
秋彦は、名残惜しい気持ちで太田家を後にした。
今日はちょうど日曜日なので、聖奈と浅田に別れを言えることができた。
家に帰ると、リビングで父親が勉強していた。
「もう慣れた?」
「ああ、おかえり。人に教えるのは苦手だったが、最近は慣れてきたよ」
「人は、適応能力があるからな」
研究職がなかった為、父親には半年前から教職員に就いてもらっていた。
「まあ、教員資格を取れたのは救いだったな」
「それも秋彦のおかげだけどな」
「資格取ったのは父さんなんだから、そんなこと言う必要ない」
秋彦はそう返して、自分の部屋に入った。
そして、机の引き出しから通帳と印鑑を持って、リビングに戻った。
「ほら」
「え、何?」
秋彦が差し出した物を見て、父親が首を傾げた。
「あんまり資金は増やせなかったけど、あとは父さんが管理してくれ」
「・・・もう完成したのか」
秋彦の言動で、もういなくなると悟ってくれたようだ。
「明日、入れ替わるよ」
「そうか」
父親はしんみりとした顔で、通帳と印鑑を受け取った。
「投資口座はそのままだけど、使うなら最低限の世界情勢を学んでからにしてくれよ」
「ああ、わかった」
「あと、家事は二人で手分けしてやれ。どうしても無理なら、セナを頼れ」
「そ、それは避けたいな」
「そう思うなら、自分たちだけでなんとかしてくれ」
「頑張ってみる」
父親は、頼りなさそうに尽力の言葉を口にした。
「俺の言いたいことは以上だが、父さんからは何かあるか」
「今までありがとう」
「どういたしまして」
お礼を言われたので、とりあえず答礼しておいた。
「本当に戻れるのか」
「わからない。最悪の場合、別の俺になるかもしれん」
「それは怖いな」
「失敗を恐れたら、研究者じゃない」
「リスクが高過ぎだろう」
「おっ、父さんにしては的確な指摘だな」
父親の成長に少し嬉しくなった。
「でも、やらないと替わらないからな」
「危険を冒してまでするなら、やめて欲しいんだが」
「気持ちだけ貰っとくよ」
「そうか」
息子の迷いのない答えに、父親が諦めたように身を引いた。
しばらくすると、聖奈と浅田が来訪してきた。聖奈は薄手の無地のチュニックで、下は膝丈のカットソースカートに黒のレギンスを履いていた。浅田の方は白の薄手のシャツに黒のジャンパースカートだった。
秋彦は、二人に明日入れ替わることを伝えた。
「え、完成したの?」
これには聖奈が、驚いた表情をした。
「だから、あとは任せる」
二人には、元の秋彦のことは頼んでいた。
「本当に戻れるの?」
「わからないけど、やらないと替わらない」
父親と同じことを聞かれたので、同じことを返した。
「それはそうだけど・・・」
この答えは不満だったようで、眉間に皺を寄せて目を逸らした。
「そっか。なんか名残惜しいね」
浅田の方は寂しそうな顔をした。
「アサは、元の俺が良いだろう」
「結局、最後まで姫って呼んでくれなかったね」
「俺は、初志貫徹だからな」
「意地っ張りだもんね~」
浅田は笑いながら、秋彦をからかってきた。
「とりあず、今日で俺との会話も終わりだ」
「あの~、一つ聞きたいんだけど」
聖奈が軽く手を上げて、元気なく質問してきた。
「なんだ?」
「明日、見送りに行ってもいいかな?」
「明日って学校だろう」
「休む」
ズル休みに罪悪感はあるようで、小声でそう言った。
「あっ、あたしも休むよ」
聖奈に便乗するように、浅田が軽い感じで欠席を決めた。二人は、なぜか一緒の高校に進学していた。
「え、別に、私に合わせて休む必要ないわよ」
「ん?聖奈、それ勘違い。あたしも見送りたいだけよ」
「あ、そう」
浅田の指摘に、聖奈が恥ずかしそうに俯いた。
「二人はもう仲良しだな~」
1年の間に、聖奈と浅田は一緒に買い物する仲になっていた。
「まあ、趣味は合わないけどね」
「そうね」
これには聖奈も静かに同意した。
「でも、好きな人は被ってる」
「か、被ってないわよ!」
ツンデレの聖奈は、未だに秋彦を好きとは認めていなかった。
「実に可愛い」
「本当だね」
秋彦の一言に、浅田も笑顔で肯定した。
「も~、二人してからかわないでよ」
これはもう日常茶飯事になっていた。
「あっちのセナにも、是非ツンデレになってもらおう」
この可愛さは秋彦にはツボだった。
「・・・バカ」
聖奈が顔を赤めて小声で非難した。
その後は、ちょこちょこ聖奈をおちょくりながら、最後のおしゃべりを終えた。
「えっと、もう時間だけど」
が、二人とも帰ろうとはしなかった。
「今日で最後なんだから、夕方までいるわよ」
聖奈は時計を見てから、当たり前のように言った。
「そうだね。今日はできる限り一緒に居ようか」
「まあ、最後だからいいか」
浅田の言葉が少し気に掛かったが、これで最後なので二人に委ねることにした。
「じゃあ、出かけようよ」
「あ、それ良いね」
聖奈が楽しそうに、浅田の提案に乗った。
「え~、面倒~」
さすがにこれには気乗りしなかった。
「いいでしょう。最後ぐらい」
浅田は、不満そうに頭を掻いた。この1年間、三人で一度も外出はしたことはなかった。
「最後の最後で、面倒事起きたらどうするんだよ」
「二人でなんとかするよ」
浅田が聖奈の肩に手を置いて、秋彦に笑顔を見せた。
「うん。なんとかする」
これには聖奈が、真剣な表情で頷いた。
「わかった」
これ以上は無駄な時間になるので、二人を信じることにした。
浅田と聖奈は、はしゃぎながら駅周辺のショッピングモールに入った。
「ねえ、ここに入ろう」
聖奈が目を輝かせながら、有名な雑貨店を指差した。
「買う物あるのか?」
「特にないけど、見るだけでも楽しいわ」
「あ、そう」
そう言われては、秋彦からは何も言えなかった。
聖奈の後ろにつきながら一通り見回ると、工具類の所に浮遊型の方位磁石があった。
「お、珍しいな。これは買っておくか」
「何かに使うの?」
「さあ、必要ないかもしれない」
使い道は明確だったが、本当に必要な物ではないので、曖昧にしか答えられなかった。
方位磁石の会計を済ませると、今度は浅田に勧められるかたちでゲームセンターに入った。
「う~ん。やることがないわね」
浅田のしているゲームを後ろから見ながら、聖奈が困った顔で呟いた。
「む、ここは何も言わない」
浅田が次戦に行く間に、不満そうに注意してきた。
「ご、ごめん」
これには聖奈が、申し訳なさそうに謝った。浅田への恐怖心は1年前ほどなかったが、注意されると委縮するのは今でも変わらなかった。
「ふぅ~、しょうがない。クレーンゲームでもしようか」
浅田がゲームにわざと負けて、溜息をつきながら立ち上がった。
すると、秋彦の視野に信也と浩之が入った。あちらは、まだ気づいてないようだった。
「いや、もうここから出よう」
二人に気づかれる前に、ゲームセンターから出ることにした。
「あ~、そうね。ほら、織姫行くよ」
「え、ちょ、ちょっと!」
聖奈も二人を視認したようで、浅田を強引に引っ張って、ゲームセンターを後にした。
「もー、なんなのよ~」
「見つかったら、面倒な奴がいたんだよ」
浅田は気づいていなかったようなので、誰かは特定させずに答えた。
「ほら、中学の時の問題児二人よ」
「え・・・あ~、あの特別教室に連れて行かれた二人?」
「そっ。関わったら面倒だからね」
「確かに面倒ね」
これには納得したようで、それ以上は言わなかった。
「もう帰るか」
「え~、まだ4時でしょう」
「もう十分だろう」
「足りないよ~」
浅田が子供のようにごねてきた。
「でも、このモールからは出た方がいいかも」
「それはそうね」
聖奈の意見も考慮したようで、ここからは出ることには賛同した。
「で、どこか行くところはあるのか?」
ショッピングモールを出たところで、二人に聞いてみた。
「近くにお勧めの雑貨店があるわ」
聖奈が元気よく、店のある場所を指差した。
「もう雑貨はいいだろう」
「うん。もういらない」
秋彦に被せるように、浅田がきっぱりと拒否した。
「じゃあ、どこ行くのよ~」
雑貨を否定されたことに、聖奈が不満そうに言葉を強めた。
「う~ん。ネットカフェ・・とか?」
浅田が苦笑いしながら、自信なさそうに提案した。
「そんなことでよく外出しようとか言えたな」
二人の行動範囲の狭さに呆れてしまった。
「他に行くところがないなら、書店に行こう」
目的はないが、二人に連れ回されるよりかは幾分マシだった。
「またモールに戻るの?」
「いや、駅前の書店だ」
「でも、あそこって小型店舗よ」
「そうだな」
聖奈の言葉を聞き流しながら、書店の方に歩き出した。
書店で時間の潰せる本を探していると、二人が後ろからついてきた。
「どうした?」
それが不気味で後ろを振り返った。
「何が?」
「いや、書店で集団行動っておかしいだろう」
「書店なんていつでも来れるよ」
浅田が拗ねたように棚の方に目をやった。
「そうね。最後なんだから単独行動は控えましょう」
聖奈も浅田に賛同するように、浅田と反対の棚に目をやった。
「なら、家に帰るか?」
二人の意見に呆れながら、帰宅を提案してみた。
「それはそれで違う」
「うん。そういうことじゃないのよね」
結局、二人は外出したいだけで、どこに行きたいかは考えていなかった。
「じゃあ、なんか奢ろうか?」
これでは切りがないので、適当なフード店で時間を潰そうと思った。
「え、何かプレゼントしてくれるの!」
が、聖奈には誤解するかたちで伝わった。
「あ、それは嬉しいね」
浅田もその誤解に乗ってきた。
「う~ん。まあ、欲しいものがあれば、それをプレゼントしよう」
ここまで嬉しそうな顔をされると、違うとは言えなかった。
「じゃあ、雑貨店に行きましょう」
「あ、ああ」
聖奈に手を引かれ、ショッピングモールとは別の雑貨店に案内された。
「さっきより楽しそうね」
はしゃぎながら雑貨を選ぶ聖奈を見て、浅田がおかしそうに笑った。
「まあ、アサも好きなの選んでいいぞ」
「う~ん。確かに、ゲームソフトをプレゼントされてもあんまし嬉しくないし、ここで選ぶのもいいかもね」
そう言うと、聖奈と一緒にプレゼントを選び始めた。
しかし、選ぶだけで1時間も悩んでいた。
「おい、そろそろ決めろよ」
浅田の方はなんとか決めたが、聖奈は未だに悩んでいた。
「うぅ・・どうしよう。決められない」
聖奈は泣きそうな顔で、秋彦に訴えてきた。
「今、一番欲しいのでいいだろう」
「それが選べたら苦労しないわよ」
「じゃあ、せめて数を限定してくれ」
秋彦は、横にあった買い物カゴを聖奈に持たせた。
「わ、わかった」
自分の決断力のなさに、さっきまでの元気はなくなっていた。
「実用的な物にすればいいのに」
それを見ていた浅田が、呆れたように口にした。
「アサは、それでいいのか?」
「え?勿論♪」
浅田が選んだのは、シンプルなディスクボックスだった。
「じゃあ、アサの分は買っておくか」
「そうだね。聖奈は長引きそうだし」
レジに向かう途中、浅田が何かを見つけて足を止めた。
「あと、これもいい?」
浅田はそう言って、手に持った小さなキーホルダーを見せた。
「ああ、いいぞ」
別に一つとは言っていないので、そのキーホルダーも買ってあげることにした。
浅田へのプレゼントを買って、聖奈のところに戻った。
「絞れたか?」
「え、あ、うん。一応・・・」
聖奈の持っているカゴには、数個の品物が入っていた。
「じゃあ、これ全部買おう」
予想以上に少なかったので、全部プレゼントすることにした。
「え!いいの?」
「ああ。二人には、俺の面倒見てもらわないといけないし」
今後のことを考えるのは、秋彦には不毛ではあったが、この二人の行く末は幸せであって欲しかった。
レジで会計を済ませて、それを聖奈に手渡した。
「あ、ありがとう」
そのプレゼントを満面な笑顔で受け取った。
「じゃあ、帰るか」
「そうだね」
日も沈み始めたので、今度は浅田も引き止めはしなかった。
「明日って、どこに集合するの?」
雑貨店を出ると、浅田が振り返って聞いてきた。
「午前10時に俺の家だな」
「わかった。じゃあね♪」
浅田とは帰り道が逆なので、ここで別れた。
「俺らも帰るか」
「うん」
浅田を見送ってから、聖奈と一緒に帰路に就いた。
「今日はありがとう」
その道中、聖奈が照れながらお礼を言ってきた。
「まあ、最後だしな」
「そう・・だね」
秋彦の返しに、聖奈が悲しそうな声になった。
「しんみりするなよ。セナには笑って見送って欲しいんだから」
「う、うん」
元気づけようとしたが、空振りに終わってしまった。
「セナに聞きたいことがあるんだが」
励ますことは諦め、話で雰囲気を変えることにした。
「何?」
「なんでアサと同じ高校にしたんだ?」
聖奈の偏差値なら、もっと上を狙えていた。
「そういえば、秋彦には言ってなかったわね。単純に沢口と同じ高校なんて不愉快だからよ」
「あ~、なるほど」
これは大いに納得できる理由だった。
「でも、よく沢口の進路を知ったな」
「本当に危なかったわ。ギリギリになって知ったから、慌てて近場の高校に決めたのよ」
「じゃあ、アサとは偶然同じ高校になったのか」
「うん」
別に、浅田と話し合って決めた訳ではなかったようだ。
家に着いたので、聖奈と別れることにした。
「じゃあな」
「秋彦は、寂しくないの?」
「は、何が?」
「だって、明日で・・・」
その後の言葉が続かないのか、気まずそうに視線だけ逸らした。
「元々、俺はここには居なかったんだ。だから、ここに居るべきは俺じゃない」
「そ、それでも!」
「やめよう。いまさら議論の余地はない。1年間の異常が正常に戻るだけだ」
「秋彦は、それでいいの?」
「ああ、これ以上あっちのセナに寂しい思いはさせたくないしな」
「・・・私も寂しいよ」
「それなら、入れ替わった後に恋人にでもなればいい」
「そういうことじゃ・・ないわよ」
「セナへの思いは、俺である限りどこに居ても変わらない」
「それはどういう意味よ」
「好きってことだ」
「そ、それは織姫にも聞いたけど、秋彦からのアプローチは全くないわよ」
聖奈は、恥ずかしそうに口元を震わせた。
「お互い捻くれてるからな。待つのが嫌なら、セナからアプローチすればいい」
「それができれば苦労してないわよ」
素直になることが未だに恥ずかしいようで声が小さかった。
「なら、アサに奪われるだけだ」
少し危機感を持たすかたちで、家に歩き出した。
「ちょ、ちょっと!」
これには慌てた様子で呼び止めてきた。
「あ、そうそう、言うの忘れてた」
秋彦は足を止めて、ポケットからスマートフォンを取り出した。
「このロックナンバーはセナの誕生日だ」
そして、それとなく両想いということを伝えた。
「じゃあな」
ここで聖奈の反応を見るのは無粋なので、すぐに聖奈を背にして歩き出した。
翌朝、秋彦が朝食の用意をしていると、玄関のインターホンが鳴った。
「誰だよ」
コンロを使っていたので、手が離せなかった。
「あ、三瀬かも」
父親がリビングから顔を出した。
「今日、平日だろう?なんで来るんだよ」
ここ半年前から、三瀬の出入りが激しくなっていた。
「悪い、秋彦のこと教えた」
「言ったのかよ」
「いや~、話の流れで」
父親が悪びれながら、玄関へ向かった。
「お邪魔しま~す」
三瀬は、気軽い感じで入ってきた。彼女は、いつものように長髪を適当に後ろで束ねていて、Tシャツにジーパンというラフな格好だった。
「こんな朝早く、どうしたんですか」
秋彦は嫌味を込めて、三瀬に用件を尋ねた。
「え、だって、今日で入れ替わるんでしょう。見送りぐらい必要だと思って」
三瀬が不思議そうに首を傾げた。
「いや、そこまでしてもらう必要ありませんよ」
「なんだよ~、感謝はあっても邪険にすることないじゃん」
「父さんと結婚してくれるなら、感謝しましょう」
「え、あ、う~ん。それは無理」
これは何度目かの誘導だったが、いつものように乗っては来なかった。1年前は二人に任せようと思っていたが、全然進展がないので、秋彦から二人に結婚を薦めていた。
「来るなら、せめて時間帯ぐらい考えてください」
「あ、私の朝食もお願いしてもいい?」
「近くに喫茶店がありますから、そこで食べて来てください」
「む、相変わらず、道春の息子は冷たいな~」
「母親になってくれるなら、優しくしましょう」
「そんなに結婚して欲しいの?」
「ええ、父さんは頼りないですから」
「あはははっ、厳しいね~」
三瀬は大笑いして、父親の背中を叩いた。
「それより、学校はいいんですか?」
いつものやり取りを終え、話を本題に戻した。
「ああ、休んだよ。見送りもあるけど、本当に入れ替わってるのか見て見たいしね」
「替わった後なら見れますけど、入れ替わる瞬間は見れませんよ」
「え、なんでよ」
「入れ替わる実験は広範囲ですからね。僕の入れ替えを見れば、三瀬さんも入れ替わる可能性があります」
「じゃあ、見なくていいや」
秋彦の見解を聞いて、すぐに意見をひるがえした。
結局、三瀬の朝食も作り、三人で食卓を囲んだ。
「いや~、おいしかったよ」
三瀬はそう言って、満足そうな笑顔を見せた。
「もう、これで食べ納めですけどね」
「ん~、それは惜しいな~」
ここ最近よく夕飯を食べに来るので、名残惜しく感じたようだ。
「そうですね。これでもうお金を徴収できなくなりますね」
あまりによく来るので、お金を徴収していた。
「っていうか、ここの食事って高くない?」
三瀬が不満そうに、1000円札を秋彦に渡した。
「それが嫌なら、父さんと結婚してください」
「でも、これで終わりでしょう」
「ええ、この間に結婚してくれなくて残念です」
ここまでお似合いなのに、結婚しないことが不思議だった。
時間になるまで、自分の身の回りの整理をしておいた。その間、リビングから二人の楽しそうな声が聞こえてきた。
10時になる5分前に、浅田と聖奈が訪ねてきた。今日の二人は、無地のシャツにデニムパンツと、無地のカットソーにスキニーパンツという目立たない服装で合わせていた。
「あ、三瀬さん。来てたんですね」
「緒方に浅田も来たんだ。学校はどうしたの?」
「それは三瀬さんもでしょう」
三瀬の言葉に、聖奈が笑顔で返した。
「じゃあ、行くか」
このまま会話させておくと長くなるので、さっさと太田家に向かうことにした。
「あたし、あの人苦手だな~」
浅田が前を歩いている三瀬を見て、独り言のように呟いた。
「まあ、元気すぎるからな」
確かに三瀬と会話すると、疲れることは身を持って体験していた。
「だから、アキ君も受け入れられないんじゃないかな」
「その時は、二人でどうにかしてくれ」
「そこは丸投げするんだ・・・」
浅田が顔を歪めて、秋彦を責めてきた。その会話を聞いていた聖奈も嫌な顔をしていた。
「いや~、モテるね~」
三瀬が秋彦たちを見て、微笑ましい表情でからかってきた。
「私もそんな時代があった・・気がする」
「なかっただろう」
三瀬の曖昧な記憶に、父親が事実を突きつけた。
「そ、そんなことないよ。こ、告白されたことだってしばしばあった・・ような」
そこも曖昧のようで、最後は声が小さくなった。
「まあ告白はされてたな、同性に」
「ちょっと、道春!余計なこと思い出させないでよ!」
「自分が言い出したことだろう」
二人は、楽しそうに会話を繰り広げていた。
「やっぱ、父さんは三瀬さんと結婚するべきだよな」
「まあ、お似合いではあるわね」
これには聖奈も同じ意見のようだった。
「お似合いだけど、結婚はして欲しくはないね」
今後のことが心配なのか、浅田としては反対のようだった。
駅に着き、五人で電車に乗った。
「なんか五人行動って目立つな」
秋彦は電車を降りて、溜息交じりで呟いた。
「うん、そうだね。目立った原因はわかってるんだけど」
浅田も同意するかたちで、チラッと父親と三瀬を見た。
「三瀬さんの声ってよく通るわね」
聖奈の方は、困った顔で三瀬を見た。三瀬の声は、一車両に全体に響き渡っていて、ずっと乗客から睨まれていた。
「みんな、どうしたの?」
その本人は周りには気づいておらず、父親とずっと盛り上がっていた。
「三瀬さん、少し周りに気を使ってください」
これは秋彦から注意を促した。
「あ、もしかしてうるさかった?」
ようやく気づいたようで、口に手を当てて驚いた。
「ええ、もう少し声を下げてください」
「ごめん。注意するわ」
これには申し訳なさそうに謝った。自分の短所を改めるのは三瀬の良いところだった。
商店街を通り、太田家に着いた。
「げ、なんで三瀬がいるんだよ」
三瀬を見て、太田が嫌な顔をした。
「何よ、その態度」
これに三瀬が、横柄な態度で返した。
「おまえが苦手なんだよ」
「そういうこと本人の前で言うかな?」
「聞かれたから答えたまでだ」
「相変わらず、屁理屈な人ね」
二人は、昔から仲が悪かったようだ。
その二人の罵り合いを聞きながら、地下の実験室に招かれた。実験室の横にもう一つ部屋があり、そこは太田に作ってもらった秋彦の実験室だった。
「じゃあ、あとはよろしく」
その扉の前で振り返って、最後の言葉を口にした。
「あっちでも頼む」
父親が優しい顔で、軽く手を振った。
「あっちで私は知り合ってないの?」
「ええ、三瀬さんと太田さんは知り合ってません」
あっちでは情報には困っていなかった為、二人とは全く面識はなかった。
「それは俺としては残念な話なんだよな~。本当にもったいない話だ」
太田にはそのことを話していたので、淡泊な言い方だった。
「いろいろ新鮮で楽しかったわ」
浅田は寂しそうな顔で、精一杯微笑んだ。
「あ、あの、し、失敗しても私は受け入れるから」
聖奈が泣くのを我慢して、必死で思いを伝えた。
「じゃあ、もう行くよ」
浅田と聖奈にそう言って、自分の実験室に入った。
部屋は密閉空間で、外には被害が出ないように設計していた。
「始めるか」
秋彦は気持ちを整えて、電力メーターをフルスロットルにして、太田には教えていない発電機の小さな穴にブラスチックの棒を差し込んだ。
すると、バチィと音と共に発電機のモーターが異常な音を鳴らしながら、あの時と同じようにフル回転を始めた。こうなるように設計してもらうために、半年も余計に時間が掛かってしまった。
秋彦は方位磁石を取り出して、入れ替わるまで磁場がどうなるかを検証した。これは最後の確認でもあった。
「やっぱりダメか」
そう呟くと同時に、周りが光で包まれた。その光は、あの時とは少し違って見えた。
第十一話 更なる試練
目を覚ますと、そこは真っ白な天井があった。
「帰ったのか?」
体を起こすと、病室のようだった。
「あ、秋彦。良かった、無事みたいね」
秋彦がその声の方を見ると、懐かしい顔がそこにあった。その瞬間、失敗したと強く思った。
「急に倒れたって聞いたから、びっくりしちゃったわ」
そこにはセミロングにニットトップとクロッドパンツを着た女性の姿があった。秋彦の覚えている顔よりは少し老けていたが、確実に母親だった。
「母・・さん」
言葉にしたが、懐かしさと罪悪感とが入り混じった心境だった。
「どうしたの?痛いところとかある?」
母親が心配そうに顔を覗き込んできた。
「・・・」
ここは正直に人格が入れ替わったと、伝えるべきかを悩んだ。秋彦の記憶では、母親は現実的で頭が固いので、この事実を受け入れてくれそうになかった。
「父さんは?」
なので、ここは無難な父親から打ち明けることにすることにした。
「今日は仕事よ」
よくよく考えてみれば、今日は月曜日だった。
「ところで、どこで倒れたんだっけ?」
「え、学校よ」
「あ、そうだったな」
「本当に大丈夫?」
「ああ」
あまり話すとボロが出るので、返事は単調にすることにした。
「少し頭が混乱してるんだけど・・・」
ここは後先を考えて、行動することにした。
「倒れて何時間経ってる?」
「えっと、30分ぐらいかな」
「そう」
倒れたことはわかったが、病室にいることは不自然だった。
「なんで保健室じゃないんだ?」
「え、何言ってるの?」
秋彦の言葉がおかしかったのか、母親が怪訝な顔をした。
「学校の向かいが病院だから、学校には保健室はないわよ」
「あ、そうだったな」
通っている高校は家の近くで、その向かいは病院になっていた。
「もう帰ろう」
「え、検査とかした方がいいんじゃない?」
「いや、必要ない」
「なんか少し変わったわね」
母親が息子の態度に少し違和感を感じたようだ。
「そうだな。少し考え方が変わったかもな」
ここでごまかしても、こっちの秋彦の性格がわからない以上無意味に等しかった。
「や、やっぱり検査を・・・」
「いらないって」
母親の言葉を振り払うように、足早に病室を出た。
「ちょ、ちょっと、どうしたのよ~」
その後ろから母親が、慌てて追いかけてきた。
「秋彦、本当にどうしたのよ~」
病院から家に帰ると、母親が訝しそうな顔で聞いてきた。
「ちょっと、今は一人にしてくれ」
秋彦はそれだけ言って、自室に入った。
部屋は自分の部屋だったが、棚の位置机の位置が入れ替わって、ベッドの色も少し違っていた。
それより今の世界情勢が気になって仕方なかった。
2時間近く情報収集していたが、母親が何度か邪魔してきた。
「ちょっと邪魔しないでくれ」
これはかなり煩わしかったので、部屋の前で母親に注意した。
「な、何してるの?」
「ちょっと、ネットで調べ物を」
情報収集と言うと、違和感があるのでそれらしい理由にしておいた。
そのあと、夕方まで世界情勢と日本の現状を調べ上げた。
「なんだこれ?」
世界情勢はあまり変わらなかったが、日本の法律が大きく違っていた。医療制度が皆保険ではなく、徴収制度に変わっていた。一番変わっていたのが結婚制度だった。
「同棲婚って、なんの冗談だよ」
少子化の上、男女の価値観が結婚に向かわなくなったことで、国が同棲婚を認めた形になっていた。
「ったく、政治家は頭が固いな~」
結婚制度を読み上げる度、その言葉が何度も口に出てしまった。
「また資金集めからか~」
自分の今の現状を思い出し、振り出しに戻されたことへの絶望感を感じながら、父親の帰りを待った。
しかし、父親は帰ってこなかった。
「ここでも研究一筋か」
帰ってこない理由は、こっちでも同じだった。
仕方がないので、父親に電話して強制的に帰ってきてもらうことにした。それを母親が訝しげな顔で見ていた。
「ほ、本当にどうしたの?」
「だから、ちょっと変わっただけだ」
「・・・」
秋彦の説明が不服なようで、怪訝な顔をされた。
父親が帰ってきて、自室で前と同じように入れ替わった旨を説明した。母親がいると話が進みそうになかったので、退場してもらった。
「そうか・・信じられんな」
ここでも父親は変わっていなくて、同じ台詞を口にした。
「とりあえず、母さんが生きてることに驚いている」
「そっちにはいないのか?」
「ああ、俺のせいで死んでる」
「そ、そうか」
言葉が見つからないのか、気まずそうに視線を逸らした。
「あと、緒方聖奈はいるか?」
これは個人的に聞いておきたかった。
「事故で・・・」
父親が悲しそうに首を振った。
「もしかして、8年前の事故か?」
「あ、ああ」
経緯を聞くと、母親が秋彦を庇ったところは一緒だったが、その車がハンドルを切ったことで、聖奈が巻き込まれてしまったようだ。
「結局、元凶は俺・・か」
この事実には、自己嫌悪に陥ってしまった。
「げ、元気出せよ。あれは事故だったんだ」
「そうだな。もう過ぎたことは戻せないからな」
ここは気を取り直して、今の現状打破に集中することにした。
「ここまで話したけど、母さんは信じてくれると思うか」
「多分、無理」
「だろうな~」
母親と接してみて、とても信じてもらえそうになかった。
「お金の管理は誰がしてる?」
「母さんだ」
「だよな~」
父親が管理していない以上、母親の説得は必須だった。
「ここにきて、母さんが壁になるか」
自分のせいで亡くなった母親が、ここで障害になるなんて、なんとも嫌な因果だった。
「太田貫禄って知ってるか?」
最後の頼みの綱は、太田だけになってしまった。
「あ、ああ。大学での友人だが、なんで知ってるんだ?」
「あっちで知り合ったからだ」
一応、ここでも太田は磁気浮遊の第一人者だった。
「そうか。でも、大学以来音信不通だぞ」
「だから、連絡取ってみてくれないか」
「え~、いまさらか?」
「お願い!」
これには頭を下げて、誠心誠意で頼み込んだ。
「・・・わかった」
父親は、息子の懇願に渋々頷いてくれた。
「助かるよ」
「でも、連絡取れるかはわからないぞ」
「なんとか取り次いでくれ」
「あ、ああ」
ここまで言われるとは思わなかったのか、少し困った顔で頬を掻いた。
それからしばらくは、母親を欺きながら退屈な学生生活を送っていた。空いた時間で、ここでの論文や世界情勢の確認をした。
「カンロクは、アメリカにいるみたいだ」
1週間後、父親がなんとか太田と連絡を取ってくれたようだが、日本には滞在していなかった。
「マジか・・・」
最後の頼みの綱が切られたことで、絶望感が襲ってきた。
「もう父さんに頼るしかないな」
現状的には、もうこの方法しか取れなかった。
「な、何するんだ?」
この1週間、秋彦の性格を目の当たりにした父親は、少し怯え気味に聞いてきた。
「一つは母さんに事実を伝える」
「信じてもらえるのか?」
「かなり薄いな。最悪の場合、精神科に入院だ」
「母さんじゃなかったら、冗談だと笑い飛ばすんだが、残念ながらやりそうな気がするな」
秋彦の例え話が、あながちありえないことはないようで、苦笑いで肯定された。
「もう一つは、父さんに投資をしてもらいたい」
「と、投資?」
「ああ、口座を開いてくれれば俺が全部引き受ける」
しかし、これは母親の同意が必要だった。
「この二つの内、父さんはどれを選ぶ?」
「二つしかないのか?」
「他に思いつくなら、是非とも教えてもらいたいね」
秋彦は溜息をつきながら、背もたれに全体重を乗せた。このままでは成人になるまで身動きできなかった。
「そもそも、なんで投資なんだ?」
「元に戻るには設備が必要になるからだよ」
しかし、それでも戻れなかった状況を考えると、戻れる確率が絶望的に思えてきた。
父親にあの時と同じような説明をすると、難しい顔で悩み始めた。
「凄い金額だな」
「だからこその投資なんだよ」
「確かに、短期間なら投資じゃないと無理だな」
「で、どっちがいいと思う?」
「無難に投資かな」
父親が手堅い手段を選んだ。
「なら、なんとか母さんを説得してくれ」
「え!一人でか?」
「俺が介入したら、違和感でるだろう」
「ま、まあ、そうだな」
「あと、口座開設は株と外為の二つだから」
「わ、わかった」
父親はそう言って、自信なさそうに部屋から出ていった。
「次の入れ替わりは、かなり掛かりそうだな」
投資で資金を集めても、母親がいる限り実験設備の設置は難しそうだった。それを考えると、危険を覚悟で母親に全部話した方が先が開けるような気がした。
「困ったな~」
しかし、母親の心配そうな顔を見ると、あっちでの事故の罪悪感が込み上げてきて、打ち明けることに及び腰になっていた。
「はぁ~」
先の見えない未来に、落ち込むように深い溜息をついた。
母親の生存は嬉しかったが、逆に聖奈が亡くなったことは残念で仕方なかった。どの世界でも万全な世界はありえないと悟り、確認できない世界に思いをはせるのだった。
パラレル世界~研究の仕儀~ 『A』


