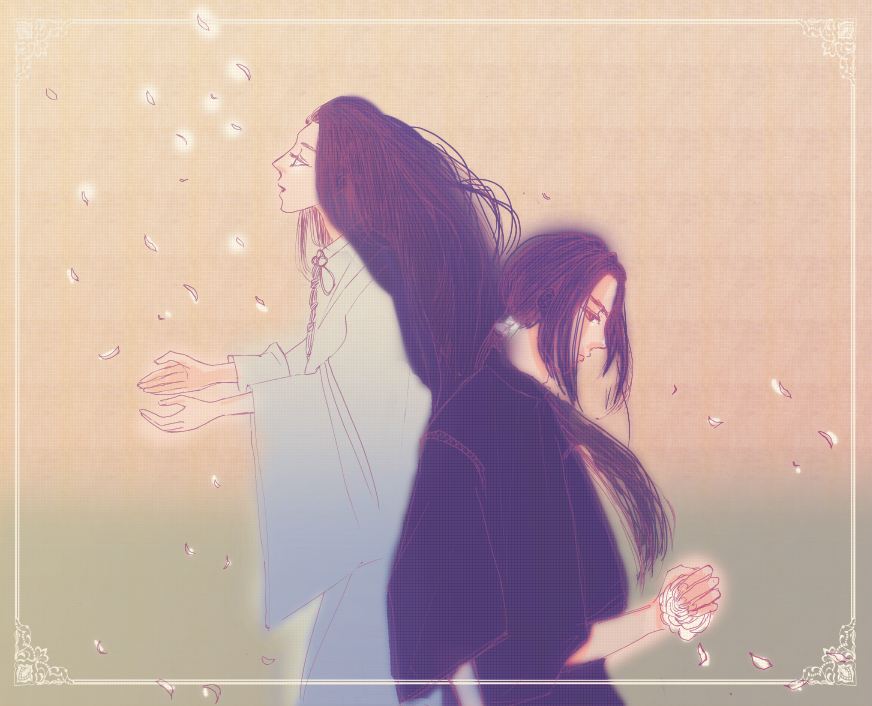
白い現 第四章 再会 四
離れがたく思いながらも風見鶏の館から帰宅する真白。剣護と荒太と共に帰る途中で、因縁の人物との思わぬ再会を果たす。
第四章 再会 四
四
そろそろ帰らなければ祖母たちに怪しまれる、という時間になっても、真白は中々怜の傍を離れようとはしなかった。
「こおら、しろ。いい加減、帰るぞ。ばあちゃんたちが待ってるだろうが」
「うん………」
剣護の言葉にそう生返事(なまへんじ)は返すものの、怜の枕辺(まくらべ)に据えた腰を上げようとしない。
そんな真白を見て、怜が真顔で言う。
「――――真白、今日このまま泊まってく?」
「良いの!?」
「良くありません!!嫁入(よめい)り前(まえ)の娘がっ」
「阿呆言うな、江藤っ!それはいずれ俺が言うべき台詞(せりふ)や!!」
怜の言葉に喜色(きしょく)を露(あら)わにした真白に対し、剣護と荒太の二重奏(にじゅうそう)が響いた。
お前でもねーよ、と剣護が荒太の頭をはたく。
「まあ、冗談(じょうだん)は置いとくとして。俺は大丈夫だから、真白。もう今日は帰るんだ。太郎兄をあまり困らせちゃ駄目だよ」
「うん……。――――次郎兄、明日来たら、ドロンッて消えてたりしない?」
古い言い回しに、思わず怜は笑いそうになる。
「しないよ。物理的(ぶつりてき)に不可能だ。それより俺は、期末試験のほうが心配だよ。陶聖に転入してから、まだ一度も真白に勝ててないからね。何とか兄として面目躍如(めんもくやくじょ)しないと」
「うん……。あ、そうだ。明日、小太郎(こたろう)、連れて来ようか。可愛(かわい)いし。ベッドで大人しくしてるしかない時とか、癒(いや)されるよ?」
真白の目が、良い案を思いついた、と言うように輝く。
「――――――いや。気持ちは有り難いけど、遠慮(えんりょ)しとくよ」
「真白、男子高校生相手にテデイベアをごり押しするんじゃない」
ダメだこいつは、と剣護が真白の両脇(りょうわき)に手を入れるとヒョイと持ち上げ、無理やり怜から引き離した。腕力(わんりょく)と長身(ちょうしん)の成(な)せる業(わざ)だ。おおー、と遥が素直に感心した声を上げ、真白が宙で足をバタバタさせる。
「じゃあな、次郎。念の為、荒太がこの小僧を置いててくれるらしいから。………まあ、安心して休め」
言葉とは裏腹(うらはら)に、剣護の顔には、危(あや)ぶむ色がある。
こいつで大丈夫か、という顔で指差された遥は、些(いささ)かふくれた。居並ぶ面々の中でもとりわけ幼い容姿(ようし)が、一層(いっそう)、子供っぽく見える。怜の表情にも、不安と懸念(けねん)が浮かんでいた。
「………中学生だろう?大丈夫なの。家の人が心配するんじゃ」
「ああ、その辺の心配はいらんで、江藤。そいつの家、大家族な上に滅茶苦茶(めちゃくちゃ)、放任主義(ほうにんしゅぎ)やから。こう見えてそれなりに腕も立つしな」
「こう見えてって何ですかー。それなりにって何ですかー」
遥が荒太の下す評価に、口を尖(とが)らせ不満そうな声を上げた。
まだ名残惜(なごりお)しそうな真白を引(ひ)っ張(ぱ)るようにし、剣護は要と舞香に挨拶(あいさつ)した。
「じゃあ、今日は、本当に御厄介(ごやっかい)になりました。…恐縮(きょうしゅく)ですが、怜のこと、よろしくお願いします。あと、もう一人、余分(よぶん)な頭数増やしてすみません。また明日、様子を見に来ますんで」
そう言いながら頭を下げる。
「気にせんといてください」
微笑みながら要が言う。
「そうよお。あんな可愛い子の面倒なら、いつでも見てあげるわ。大歓迎よ。あのおまけの子も、ご飯はちゃんと食べさせるから。真白、モデルになる約束、忘れないでね」
「―――――はい。…頑張ります」
舞香の言葉に、手首をしっかり剣護に確保された真白が頷いた。
やだ頑張ることなんてないのよー、と舞香が可笑(おか)しそうに笑い、手を振った。
三人が電車に乗って揺られるころには、夏の長い日も落ちかけていた。真白を間に挟み、剣護と荒太はそれぞれ座席に腰を落ち着けている。
車窓(しゃそう)からはオレンジ色の残照(ざんしょう)が見える。
「…………」
日が沈んで尚(なお)、空に残る夕日の光に照らされた真白の表情は、少し硬い。
瞳はぼう、として、心ここにあらずと言った風情(ふぜい)だった。
恐らくまだ、怜のことで頭が一杯なのだ。
〝前生のトラウマで、家族を亡くすってことにえらく敏感なんだ〟
(それは解るけど―――――――)
荒太としては、存在を忘れられているようで、悔しいような寂しいような気分になる。
彼女の気を逸らすべく、口を開く。
「…真白さん、舞香さんに、ステンドグラス、教えてもらうんやて?」
その問いかけに、夢から覚めたような顔で真白が荒太を見た。
「―――――うん」
「ふうん………」
荒太が、何気(なにげ)ない風(ふう)を装い相槌(あいづち)を打つ。
そこで真白は、どこか躊躇(ためら)いがちに口を開いた。
「あの、荒太君は、…その、―――――ガラスは、好き?」
(どういう質問だ、そりゃ)
黙って聞いていた剣護が、ズリ、と脱力(だつりょく)した。
荒太は頷きながら真面目に答える。
「うん。結構、好き」
(……………何だ、この会話)
どうにも聞いてると突っ込みを入れたくなる、と思い、剣護は、こいつらの声は音楽だ、バックミュージックだ、と自分に言い聞かせた。加えてこの場においては、自分の存在がひどく野暮(やぼ)なものになっている気がした。
(俺ってもしかしてすげー邪魔者(じゃまもの)?)
そう思ったが、まあ良いか、当分は邪魔してやれ、と開き直る。
「そっか」
真白が微笑む。
「……あの、お家でコースターとか、使ったりする?」
「――――――うん。すごく、よく使うよ。しょっちゅう」
荒太の肯定には力(りき)が入っていた。
「そっかぁ……」
安堵(あんど)したように笑う真白を見て、顔には出さないものの、剣護は複雑な気持ちになった。
(…解りやす過ぎる……)
素直と言えば聞こえは良いが。
大丈夫か俺の妹は、と思わず心配になる。
舞香からの情報も合わせれば、荒太の誕生日プレゼントに、ステンドグラスで作ったコースターを贈(おく)ろうと考えている、と丸わかりだ。
「―――――剣護先輩って、誕生日は…」
「俺?四月。四月八日。何だ、別に今更(いまさら)プレゼントはいらんぞ」
ふと今気付いたように、荒太に訊かれて答える。剣護は現在、十八歳だ。
「いや、せやのうて、真白さんから何貰うたんですか」
「革製のブックカバー。俺様に相応(ふさわ)しく、知的なチョイスだろ」
ふふん、と自慢(じまん)げに剣護は笑みを浮かべる。
「剣護、今年は受験生だし、そういうのが良いと思ったの」
「へえ……」
補足(ほそく)して説明する真白の微笑みに、荒太は面白くなさそうな顔をする。
剣護は笑いをかみ殺していた。
「江藤は?」
「次郎兄は、まだだいぶ先。十二月だったよね、剣護?」
「うん、確か」
「じゃあ、あいつ俺より年下の期間があるんや」
少し愉快(ゆかい)そうに、荒太が言う。
「そう、私よりもだよ。次郎兄なのに、何だか変な感じ。荒太君も、今はまだ私より年下だね」
「…まあね。――――――何笑うてるんですか、剣護先輩」
「いや別に?」
まだ含(ふく)み笑いをしている剣護に、真白はずっと気にかけていた問いを口にした。
「ねえ、剣護。…次郎兄の御両親に、連絡とかしないで良いのかな?…もう大丈夫って言っても、ひどい怪我をしたんだもの」
これに剣護が答える。笑みが引っ込み、少し考える面持ちになった。
「ああ…、それがあいつ、今、親御(おやご)さんとは半(なか)ば絶縁状態(ぜつえんじょうたい)で――――。その代わり、あいつを赤ん坊の時からずっと可愛がってくれてる祖父(じい)さんがいて、学費(がくひ)や生活費(せいかつひ)なんかは、その祖父さんが出してくれてるらしい。だから連絡するとすりゃそっちが先なんだが…お年寄り相手に、無闇(むやみ)に心配かけるのもな……。まあ、そのへんは次郎が自分で判断するだろ」
「へえ…」
荒太が新事実を聞いた、という顔をする。
真白もこの話は初耳だった。
(お母さんに、〝親不孝者〟って泣かれた、って言ってたものね。……次郎兄には、本当に、私たちと、そのお祖父さんしかいないんだ―――――――………)
彼の孤独を、真白は思った。
怜は誰より、前生の記憶を一途(いちず)に思っている。
けれどその一途さは、どこか哀しい。
(何が正しいと、言えるものでもないけれど……。次郎兄は、あんなに何でも出来て大人っぽいのに、見ていて危なっかしい気持ちになる時がある。私がそう感じるくらいだもの、剣護は、きっともっとそう思ってる。…私が次郎兄の為に出来ることがあれば、何だってするのに)
真白が考え込んでいると、突然わしゃわしゃ、と髪を荒っぽくかき回された。
「わ…、何、剣護!?」
「―――――あんまり考え過ぎんなよ。次郎はあれで芯が強い。何たって俺が、この世で一番信頼してる男だからな。…多少の問題は、自分で向き合って何とかしてみせるさ」
「……うん」
髪の毛を押さえながら真白は、安心させるように笑いかける剣護の顔を見た。
緩む気持ちに、自分が思い詰めていたと知らされる。
(…剣護はいつも、こうだなあ)
頼もしい長兄(ちょうけい)。優しい次兄(じけい)。そしてまだ幼い末弟(まってい)。彼らの為なら、理屈抜きにどんなことでも頑張れると真白は思う。
(それに、今はもうそれだけじゃない。大事な人が、たくさん増えた。多分これからも―――――――)
電車が停車し、乗って来た中年のサラリーマンが向かいの席に座った。
顔はずっと俯(うつむ)きがちで表情も見えないが、どことなく陰気(いんき)な印象を受ける。
ガタンガタン、と電車が揺れる。
一瞬、目に見える光景が暗転(あんてん)したような間があった。
(――――――あれ?)
気付けば、電車に座るのは真白とそのサラリーマンだけだった。
いつの間にか剣護も荒太も姿を消し、他の乗客の姿も見当たらない。
(え、どうして)
慌てて周囲を見回す。
ガタンガタン、と電車が揺れる。
「………久しいな……」
向かいに座る、男が言った。
低く、湿(しめ)り気(け)を帯びたような声だった。
(え――――――?)
「久しいな、小野若雪(おののわかゆき)」
そう言って顔を上げた男の左顔面は、焼(や)け爛(ただ)れたあとの、ケロイド状になっている。
真白の喉(のど)まで、悲鳴が出かかった。
クッと男が笑う。
「醜(みにく)いか?これは、お主の兄が所業(しょぎょう)よ。かくも非情(ひじょう)なるは、前生(ぜんしょう)における血筋(ちすじ)ゆえか?」
ここに至り、真白もようやく悟った。
この場は、通常の空間ではない。何らかの手段で、剣護や荒太と切り離されたのだ。
雪華を呼ばなくては、と思う。
「――――――あなた、誰」
「つれないな、小野若雪。前生で私から全てを奪ったお主が、涼しい顔で私の素性を問うとは!私は片時(かたとき)も忘れなんだと言うのに――――――。その、善良ぶった、白い顔。私の足の腱(けん)を切り、御師(おし)としての回国(かいこく)を不可能にした、忌(い)まわしき白い手!!」
唾(つば)を飛ばし、激(げき)した様子で男は言い募(つの)る。
そこまで聞けば、もう男の正体は明らかだった。
くらり、と目眩(めまい)がする。
「…あなた…山田(やまだ)、正邦(まさくに)………?」
(血の匂いがする―――――違う、あれは過去だ。もう遠い、過去の話。過去の傷)
しかし今、現に目の前にいる存在は。
ビジネス・スーツの男は、歪(ゆが)んだ笑みを片頬(かたほお)に浮かべた。
――――――忘れてしまいたい過去の具現者(ぐげんしゃ)。
悪夢のような再会だった。
ガタンガタン、と電車が揺れる。
「じゃあやっぱり…、剣護に呪詛(じゅそ)を放ったのは、あなただったの……」
〝もうすぐ、懐かしい顔に出会えるよ。尤(もっと)も彼は、〟
そうだ。チャコールグレーのスーツの男は、確かにそう言っていた。
今生(こんじょう)にて再会する相手が、必ずしも慕(した)わしい存在とは限らない。
〝―――――尤も彼は、君が憎くて仕方がないようだがね〟
「ふん、気付いておったか。その通り。私が魍魎と手を組んだのも全て、憎きお主らをこの手で殺さんが為。…――――二番目の兄が、深手(ふかで)を負うたようじゃな?死に至らなんだとは、実に残念」
真白は目を見張ったまま、尋ねた。
「―――――若雪のしたことを、それ程に恨んでいるの?…あなたの足の腱を切ったのは、若雪にとっても悩んだ末の、ギリギリの選択だったのに―――――――…」
正邦の顔が、一層皮肉(いっそうひにく)げに歪(ゆが)む。
ここまで歪んでしまっては、喜怒哀楽のどれを表現したいのかすら判らない。
「ああ、ああ、私の命を奪うことで、己の手を汚さぬ為の、最良の選択であったな、確かに!!あのあと――――お主に命じられた通り、国造様(こくぞうさま)に御師職(おししき)と室(むろ)を返上(へんじょう)したのち、妻と子と郎党(ろうとう)を連れ私は出雲を去った。されど、つき従ってくれた僅(わず)かな郎党(ろうとう)も、……不具(ふぐ)の身となった私を次第に見捨て、一人二人と離れて行った」
ギリッと正邦は歯軋(はぎし)りした。
「何より、出雲大社の御師という立場を失った私には、妻子や家臣を養うたづきが無かった。妻は、私や娘を喰わせる為に、私に隠れて――――身を売ろうとした。……私は、私はそれを斬った。そして…娘も病で死んだ時、私もまた、発狂(はっきょう)して果てたのじゃ――――――………。今生にてその経緯(いきさつ)を思い出した私は、小野若雪、お主とお主の兄弟に、必ず復讐(ふくしゅう)してやると誓った」
真白は、ただただ茫然(ぼうぜん)としていた。
「どう…して、自分の奥さんを、斬ったの?」
ギロリ、と正邦が目を上げた。
「知れたこと。あれが、沙耶(さや)が、不貞(ふてい)を働こうとしたからじゃ」
「不貞って……それは――――、でもそれは、あなたや娘さんの為でしょう?」
「それでもじゃ!沙耶が、他の男の慰(なぐさ)み者(もの)になるなど、耐えられよう筈も無い!!」
「―――――――だから殺したの」
真白の言葉に、正邦の血走った目が震えるように揺れた。
(……こんな人でも―――――、奥さんを愛してたのか。こんな人でも、奥さんのことが…、娘さんのことが…、大事だったんだ―――――――……。…驚くことじゃない。若雪だって、その可能性は何度も考えた)
その末の苦渋(くじゅう)の選択は、しかし正邦を生き地獄に突き落とした。
真白は、わななく唇を一度引き締めたあと、口を開く。
(頭が痛い――――痛い。何てひどい、頭痛)
「…どうして、自分の大事な人を殺してしまったの。自分の一部を殺すのと同じことなのに――――…」
「黙れ。私の舐(な)めた辛酸(しんさん)を知らぬお主が、したり顔で物を申すな。お主が所業の果てであろうが。お主が望んだことであろうが!!」
真白は無言で首を横に振る。
(望んでない。望んでなんていなかった。そんなこと―――――――)
訊かずにはいられなかった。気付けば口が動いていた。
「私は、あなたを殺していたほうが良かったの?」
誰か他人が喋(しゃべ)るもののように、真白は自分の声を聴いた。
〝アナタヲコロシテイタホウガ―――――〟
正邦が即座に答えを返す。
「ああ、その通りじゃ。いっそ、ひと思いにな……」
真白は、正邦を真正面から見つめた。
―――――釈迦の月は隠れにき 慈氏の朝日はまだ遙か――――――
釈迦(しゃか)の死後、弥勒菩薩(みろくぼさつ)が衆生(しゅじょう)を救うまでの約束は遠い先の世。
五十六億七千万年の先。
救いの手が人に及ぶまでには、余りに遠い―――――――。
(遠い………。神仏が、人の苦悩に追い付くには)
唇から、言葉がこぼれ落ちる。
「…勝手だわ」
「――――何?」
「あの時、私があなたを殺していれば、残された奥さんや娘さんは、まだ幸せだったの?突然、何の前触(まえぶ)れも無く夫を、父親を殺された彼女たちが、耐(た)え難(がた)い苦しみを負わないとでも思うの?」
正邦を、睨(にら)み据(す)える。
「―――――――私は思わない。だって若雪は、突然、前触れも無く父を、母を、兄弟を皆殺されて、ものすごく苦しんだもの!死んでしまいそうなくらい、気が狂いそうになるくらい、悲しかったもの」
それは未だに夢に見る程の、喪失感(そうしつかん)。
嘗(かつ)て十四歳の若雪が、全てを失った瞬間―――――――。
(今の私より、若雪は幼かったのに)
「………そう仕向けたのは、他ならないあなたでしょう。………あなたはまだ、自分が若雪にした仕打ちの意味も、奥さんたちの思いも、まるで解ってない―――――……」
正邦の目は忙(せわ)しなく動き、返す言葉を探していた。
その時。
耳をつんざくような大きな音が響き、車内の空間に突如(とつじょ)、亀裂(きれつ)が走った。
真白が首を巡らせる。
「おいてめー、山田正邦。俺の妹、苛(いじ)めてんじゃねえよ。勝手な理屈ばっか抜かしやがって、ふざけんな」
剣護が上半身だけ亀裂から出して、正邦に対し吠(ほ)えるように言う。
その後ろから、荒太も顔を覗(のぞ)かせた。
「痛い。俺の足踏んでます、先輩。この異空間を破ったんは俺ですよ。抜(ぬ)け駆(が)けせんといてください」
「剣護…。荒太君」
剣護と荒太が、先を争うように空間の裂(さ)け目(め)から抜け出て、真白の前に着地した。剣護が正邦を見る目は燃えるようで、反対に荒太の目は氷のように冷たい。
「―――私は、間違っていない」
唸(うな)るように正邦は言い、その場から姿をかき消した。
「どの口がほざく…待ちやがれ、この野郎」
「剣護っ」
泥のような皮膚。一つ目の化け物の拳が、剣護を襲った。
「――――――またこいつか!」
紙一重(かみひとえ)でそれを避けると、剣護は臥龍(がりゅう)を呼ぼうとした。しかしそれより早く「雪華(せっか)!」と叫ぶ声が響き、その魍魎の手首から先がスッパリと切り落とされた。
魍魎が激しい叫び声を上げ、あたりに濃い腐臭が満ちる。
振り返った先には、雪華を構えた真白がいた。
瞳は、底光りしている。
「剣護。荒太君。手を出さないで」
静かな声だったが、剣護も荒太も、その声に動きを封じられた。
従わざるを得ない静やかさだった。
音を立てず、圧倒的に降り積もる白い雪のような。
もう一体の魍魎の、襲い来る腕をすり抜けながら、その胸に雪華を突き立てる。
「私がやる。――――――呪詛返(じゅそがえ)しはしない。直接、斬る」
そう宣言すると、返す刃(やいば)で三体目の胴(どう)を薙(な)いだ。
白く細い腕が俊敏(しゅんびん)に見せる閃(ひらめ)きは、美しい。
真白の動きは、さながら流麗(りゅうれい)な舞だった。
(肉を斬り払う感触。斬る感触。あの時も。正邦の足を斬った、あの時も)
雪華を振るいながら、真白は泣いていた。
〝私は、間違っていない〟
(違う!そんなことない。間違っていないのは、私だ。私のほうだ―――――)
旋回(せんかい)するような身ごなしで、涙を散らしながら二体目の喉(のど)を掻(か)き切る。
(私のほうが、間違っていない。――――――返り血が飛ぶ。構うものか)
一体目の肩を削(そ)ぐ。
今生において、真白はこれまでどこか戸惑いつつ、本能のままに雪華を繰(く)っていた。
それが、どのように動けば相手が斬れるか、皮肉なことに今では良く理解出来た。
理解出来れば、その先は呆気(あっけ)ない程に容易(たやす)い。
心は泣きながらも、真白の剣筋(けんすじ)は冴(さ)え渡(わた)っていた。
(私は、間違ってない。間違ってない。間違って、いない)
溢(あふ)れる涙で、魍魎の姿がぼやけたところで、意識が途切(とぎ)れた。
電車の中で真白の姿が忽然(こつぜん)と消えたあと、荒太が魔を祓う秘文(ひぶん)を唱えて空間を切り開くまで、しばしの時を要した。その間も、真白と山田正邦の遣(や)り取(と)りは、二人の頭に直接響くように傍受(ぼうじゅ)されていた。
魍魎を倒し切ったところで倒れた真白の手と顔は、返り血に塗(まみ)れていた。それを見て取った剣護は、すぐさま彼女と空間に伊吹法(いぶきほう)を施(ほどこ)した。
電車からバスに乗り換え、真白を家まで運ぶ間、剣護も荒太も無言だった。
沈黙したまま、気を失った少女を背負う剣護と一緒に歩む荒太は衆目(しゅうもく)を集めたが、二人共それを気にも留めなかった。
もう日はとうに落ち、どこからともなく虫の音が聴こえてくる。人が夏の暑さに対応しようとする横で、既に秋は近付いて来ているのだ。
剣護が、バスから降りて少し歩んだあたりで、背中の真白が何か呟(つぶや)いた。
「…てない…」
剣護と荒太がハッとして真白を見る。
「―――――しろ?」
剣護が背に向けて呼びかけた。
「…たし、まちがって…い……たろ、あに?」
それは夢現(ゆめうつつ)でこぼれた呟きだった。
「――――――ああ、お前は間違ってないよ。真白」
すう、と再び真白が静かになる。
背負う妹の身体は既に熱を帯びて、剣護の背中までじわりと温(ぬく)めていた。
耐え切れないように剣護が、低い怒声(どせい)を発する。
「ふざけるな…。くそっ」
剣護にとって正邦は、前生で自分を、若雪を除いた家族皆を、殺した相手だ。それを少しも省みるところのない正邦に、怒りが込み上げるのは当然だった。その上正邦は、勝手な理屈で真白を逆恨(さかうら)みし、再び自分たちを殺そうと目論(もくろ)んでいる。気を失い、魍魎の血と、涙に濡れた真白の顔を見た時に剣護の胸に込み上げたのは、山田正邦に対する紛(まぎ)れも無(な)い殺意だった。
荒太は、しばらく黙って剣護と真白の二人を見ていた。
「……真白さん、ちゃんと反論(はんろん)してましたね。自分が信じる正しさを、言うてた。怯(ひる)まんと。…強かったですね。――――――綺麗な剣舞(けんぶ)やった」
哀しいくらいに、と荒太が続ける。
「――――――どうして真白ばかりが、痛手(いたで)を負わなければならない。人として転生し続ける道を選んだことは、許されないことなのか?どれ程の苦痛と引き換えなら、真白の選択と釣(つ)り合(あ)うって言うんだ」
滅多(めった)に無いことだが、剣護は静かに激昂(げっこう)していた。
先を行く剣護の表情は、荒太には見えない。
ここに至るまで剣護は、なぜついて来るのだ、と荒太に問いかけもしなかった。
その後ろ姿に、荒太は穏やかな声をかける。
「……剣護先輩。俺ら、死なんようにしましょうね」
「あ?」
唐突(とうとつ)な荒太の言葉に、剣護が振り返る。
「今回の、江藤の件で、よう解ったでしょう。真白さんが一番泣くんは、俺たちが傷を負うたり、…死んだりした時です。真白さんを守るんももちろん大事ですけど、そこを忘れたら、彼女をほんまの意味では守り損なうて思うんです」
「………賢いこと言うな、荒太」
感心したような剣護の声に、荒太は少し笑う。苦いものの混じった笑みだった。
「賢い、ですかね。―――――俺、嵐の時に、一回やらかしたから。若雪どのが、死に近付いて行くんが怖あて、ちょっとおかしなっとったんや。自分の命を使うても、運命違(さだめたが)えの術をやろなんて思うて。……結果、彼女を自害に追い込んだ。ほんまに阿呆やったわ………。真白さんのこと考えるんなら、一人も死なんと一緒に生きてくよう、思わなあかん。せやから俺は、石にかじりついてでも生きますよ、剣護先輩」
荒太の言葉のあと、剣護からの反応は中々返って来なかった。
虫が鳴いている。空には一つ、二つと星が瞬(またた)いて、もうすぐ真白の家が見えてくる。
「――――――荒太。お前の家って、外泊にはうるさいほうか?」
「え?いえ、前もって言うてたら、そないには……」
「じゃあ今晩、真白についててやれるか。多分こいつ、また寝込むだろう。…嫌な夢とか、見るかもしれない。お前が妙(みょう)な真似(まね)しないって誓(ちか)って約束するなら、ばあちゃんたちを俺が説得してやるよ。風呂や飯なんかは家(うち)で面倒見てやる」
振り向いた剣護の目は静かだった。
「どうだ――――――――?」
荒太の顔には最初、驚きの表情が浮かんでいたが、やがて真摯(しんし)な目をして顎(あご)を引いた。
「約束します」
間違ってない。
間違ってない。
私は、間違ってない――――――。
ああ―――――でも、また魍魎を滅した。殺した―――――――――。
血を浴びて。血に塗れて。
生まれ変わっても、やはり私の手は血に染まるのか。
(…選んだのは、私だ)
間違ってない。
間違ってない。
真白は闇の中で、その言葉だけをひたすら、後生大事(ごしょうだいじ)に胸の内で繰り返していた。
その言葉に縋(すが)りついていなければ、後悔の海に溺(おぼ)れて、沈んでしまう気がした。
もしも、あの時、違う決断をしていれば。
その考えに囚(とら)われてしまえば、もう終わりだ。
自分を信じられなくなる。
信じて生きていけなくなる―――――――――。
(だってあなたは、私から奪ったじゃないの)
父も母も、兄も弟も、世界の全てだった命を、奪っていったではないか。
(私を責めるなら、返してからにして―――――――)
時を巻き戻して、奪い去ったものを返してから物を言え。
あの血の海を無かったことに出来るなら。
「…真白さん」
躊躇(ためら)いがちな声が、真白の意識を覚醒(かくせい)させた。
暗闇に、一条の光が差し込むように。
心配そうに覗(のぞ)き込(こ)む顔は兄ではなかった。
「………荒太、君」
(血の海が無ければ―――――嵐どのとは出会えなかった。荒太君とは、出会えなかった)
やり切れない思いに涙が溢(あふ)れ、真白は布団(ふとん)に顔を押し付けた。
(どうしてこうなんだろう―――――――どうして。人の世は、どちらかを選択せずにはいられないように出来てる)
ベッドの上で身体を丸く縮めて、真白は泣いた。
「――――嵐どのに、荒太君に逢いたかったよ……っ」
「……知ってる」
「でも、太郎兄たちを亡くしたくもなかったの―――――――…!!」
「当たり前だよ。解ってる」
「荒太君のことが、好きだよ――――――」
「それも知ってる」
「私、――――魍魎を斬って、……ち、血で、汚れた……。―――――嫌いに、なった――――――?」
「ならない」
一晩中、真白は眠っては目を覚まし、荒太に何かを言ったり、問いかけたりした。荒太は真白の言葉に一つ一つ律儀(りちぎ)に応じた。長い夜になった。そうして気が付けば空が白(しら)んで、また新しい一日が始まろうとしていた。
白い現 第四章 再会 四


