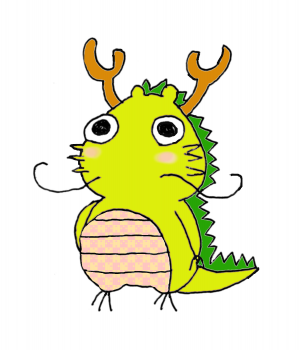されど、龍は手を伸ばす。 ――無双OROCHI異聞録―――
皆様こんにちは。はじめまして。空 由佳子と申します。
ハヤブサさん×シュバルツさんの妄想ワールドが、まだ脳内で元気に続いております。今回はそれが「無双OROCHI 2」の舞台だとどうなるかな~と、突っ走った結果、生まれてきた小説です。
なので、主人公はハヤブサさん。ヒロイン(!?)は、シュバルツさんとなります。これが無理、理解できないと言う方は、どうか全力でUターンなさるよう、ご忠告申し上げます。読む人を選んでしまう小説で、本当にすみません。
一応、軽く登場人物紹介をさせていただきます。
・リュウ・ハヤブサ………この物語の主人公。『龍の忍者』と、あだ名される超忍。妖蛇の出現により生じた時空の歪みに、シュバルツとともに巻き込まれる。
・シュバルツ・ブルーダー………その身体をDG細胞により構成されているアンドロイド。ハヤブサの想い人。ハヤブサとともに時空の歪みに巻き込まれるが……。
・キョウジ・カッシュ………シュバルツの人格の元になった科学者。
・左慈………三国時代に生きた方術師。ハヤブサを遠呂智の戦場へと導く。
・かぐや………時を渡る能力を持つ巫女。その力を駆使し、滅びに瀕した人間たちを助けていく。
・遠呂智………世界を滅ぼす妖蛇の元。破壊神となり、世界を破滅へと導いていく。
・百々目鬼………遠呂智軍の将の一人。
・素戔鳴………仙界軍の将。
私の前の小説を読んでくださった方は分かると思いますが、この小説にも多少の色気のある場面は出てまいります。でも、前の小説ほど多くはないです。後、キョウジ兄さんもシュバルツさんも、結構それなりにひどい目に遭ってしまいますので、(エロい方面ではないですが)そう言うのが苦手という方も、遠慮してくださった方が良いかもしれません。
後、「無双OROCHIワールド」を題材とさせていただきますが、何故遠呂智様が生まれたかとか、どうやって遠呂智様が倒されたかということについては、あんまり詳しく書く気がありません。ハヤブサさんとシュバルツさんのワンエピソードに、全力を注ぐ構えでございます。そうしないとめんどくさ……いえいえ、話が長くなりすぎてしまうような気がいたしますので……。どうしてもその辺を詳しくお知りなりたいと言う方は、どうか、ゲームの方でご堪能くださいますよう、お願い申し上げます。
後、ゲームに出てくる136人全員小説に出すことも、かなり不可能ですからね? 話の流れで絡めそうな方々だけ、出すようにさせていただきます。何人出せるかなぁ(遠い目)
それでは、読めるよという方だけ、どうかお進みください。今回も、よろしくお願いいたします。
序章

龍の忍者は、酷く平和な日常を過ごしていた。
時折、忍者としての『仕事』は入るが、どれも大きな仕事ではない。些細なデータ収集だったり、ちょっとした物を手に入れてきたり……。ハヤブサの力量からしてみれば、どれも軽いと言えるものばかりだった。
平和な日常。
平和すぎる日常。
「平和なのはいいことだ」
少し前のハヤブサであるならば、そうは思いつつも、多少己を持てあまし気味になっていたであろう。
だけど、今は――――
普段の忍び装束よりは、ずっと軽装で、少し長めの茶色の髪を一つに無造作に束ね、それをなびかせながら―――ハヤブサは走る。その足が、自然と早い物になっていく。
当然だ。
今日は、『約束の日』
『あのヒト』は、そこに居てくれるだろうか――――
東京の都心から少し離れた郊外にある森。そこに少し深く分け入っていくと、小さなせせらぎに行きあたる。その近くの大きな樹の幹に凭れかかる様にして、『愛おしいヒト』は腕を組んで立っていた。
「シュバルツ……ッ!」
その姿を確認するなり、ハヤブサはシュバルツに抱きついていた。
「ハヤ――――んぅっ!」
名前を呼ばせる間すら惜しんで、ハヤブサはその唇を奪う。その口腔を、深く貪る。
「ん……! ん、ん……!!」
呼吸すら奪われてしまった愛おしいヒトが、苦しそうにくぐもった声を漏らす。だけど、足りない。1週間彼に会えなかった自分の苦しみや切なさは、こんな物じゃないのだ。
「んんっ! ん……う……!」
それを少しでも分かって欲しくて、ハヤブサは、背後の樹にシュバルツの身体を押しつけながら、さらにその口腔を弄った。
「…………はあっ! んぐ……!」
一瞬だけ呼吸を許して、さらに深く。
「………ふ……」
腕にしがみつく様に掴まっていたシュバルツの手から、力が抜けていく。
「……………」
膝からズ、ズ、と、崩折れていく、愛おしいヒトの身体。ハヤブサもそれを追いかける様について行き、最終的にその身体の上に覆いかぶさるような姿勢になった。
「シュバルツ……」
その頬を撫でながら、そっと呼びかけてやると、押し倒されたような格好になった愛おしいヒトが、少し戸惑ったような表情になって、こちらを見上げてくる。
「ハヤブサ……」
潤んだ瞳と、上気した頬が、こちらの劣情をどうしても煽ってしまう。その事にこのヒトは気付いているのだろうか?
「今すぐお前を抱きたい……! 抱いていいか?」
「えっ………?」
腹の下の愛おしいヒトが、驚いた様に見上げてくる。
「こ、ここでか?」
確認するように聞いてくるシュバルツに、ハヤブサは頷いた。
「当たり前だ。もう移動する手間すら惜しい」
「し、しかし………!」
シュバルツは、少し否を唱える。深く森の中に入っているとはいえ、一応、近くには小さな街がある。何時ここに人が来るかも分からないのだから。
「俺はもう待てない、シュバルツ……!」
首に巻かれているスカーフを、強引に剥ぎ取り、現れた白い首筋に、噛みつくようにキスをした。人が来たって、構うものか。
「あっ!!」
愛おしいヒトの身体がビクン、と跳ねる。その反応を目の前で見てしまった瞬間、ハヤブサの中で何かが音を立てて切れてしまった。もう――――もう待てない。今すぐその身体を、抱きたい……!
抵抗されたらその動きを封じるつもりで、彼のコートからベルトを引き抜く。もう俺は充分待った。1週間。焦がれるように――――待ち続けていたのだから。
「ま、待って……! ハヤブサ……!」
「待てない」
ダンッ! と、シュバルツの両手を頭上に一括りで押さえつけ、それをベルトで縛ろうとする。
「待ってくれ……! ハヤブサ……! 抵抗は、しない…! しないから……!」
「――――!」
シュバルツを縛ろうとしていたハヤブサの手が、ピタリと止まる。
「だから、お願いだ……。服を破る事だけは、止めてくれ……」
震えながら紡がれる、可愛らしい懇願。
『抱いていい』そう、許可が下りたことで、ハヤブサの瞳から切迫した光が消える。
「分かったよ……」
ハヤブサはにやりと笑うと、可愛らしい懇願をしてきた唇を、優しく塞いだ。
「ん…………」
それをしながらハヤブサは、シュバルツの服をゆっくりと乱して行く。わざと羞恥を煽る様に、ゆっくりと――――
「あ…………!」
腹の下で震えながら羞恥に耐える、愛おしいヒト。だが、「抵抗をしない」と約束をしたシュバルツは、己の身体を隠すことすらしない。そのいじましい様に、愛おしさと、嗜虐心が募る。
ああ――――
愛しても、愛しても、愛したりない。
どうして――――こんなにも愛おしい存在が、この世にいるのだろう。
「シュバルツ……」
はだけさせられた服の間から現れた白い肌に、想いを込めて唇を落とす。
「あっ!」
跳ねる愛おしいヒトの身体。胸に指を這わせれば、そこはもう芯を伴って勃ち上がっていた。
(もしかして、シュバルツも焦がれていたのだろうか)
腹の下で喘ぎ、乱れ始めているシュバルツを堪能しながらハヤブサは思う。少しの愛撫で熟れてしまっているシュバルツの身体。もしも、彼の方も1週間に1度の俺との逢瀬を指折り数えて待っていてくれていたのだとしたら―――――
こんなに、嬉しい事はない。
「あっ!! ああっ!!」
彼の身体と繋がり、深く穿つ。
普段はなかなかその身体を許してくれないシュバルツであるが、今から24時間は違う。
何をしても、どのように抱いても――――彼は、赦し続けてくれる。俺だけの、シュバルツになってくれる。二人の間では、そう言う『約束事』が交わされていた。
ここで、シュバルツについて語っておかねばなるまい。
シュバルツは実は、人間ではない。科学者であるキョウジ・カッシュと言う人間が、暴走した『デビルガンダム』にその身を取り込まれかけた際、弟であるドモン・カッシュを守りたいと強く願ったが故に、シュバルツは誕生した。キョウジ・カッシュの分身として。アンドロイドの身体を持って。
その『材料』には、人間であったシュバルツ・ブルーダーと言う人の『死体』と、『DG細胞』が使われている。
『自己再生』『自己増殖』『自己進化』の3大理論が備わっている『DG細胞』 その細胞は、傷ついても自分で再生し、その環境に適応しようとより進化をし、仲間を増やすべく増殖をする。
そのエネルギー源は『人の心』だ。それが枯渇しない限り、その細胞は半永久的に活動する事が出来る。故に、シュバルツは『不死』となった。エネルギー源である『キョウジの心』が存在する限り、その身体は何度でも再生するのだ。
これだけだと、この細胞には恵まれた力があり、その恩恵をシュバルツは受けているように見えるが、実は、危険な細胞でもある。何かのきっかけで暴走をしてしまうと、総てを飲み込む勢いで『増殖』し、暴走する力を『自己進化』させ、傷つけられてもあっという間に『自己再生』するという、手に負えない『化け物』を作りだす事になってしまう。キョウジが取り込まれかけた『デビルガンダム』が、まさにその状態だった。
それ故にシュバルツは、自らの身体に潜む歪さと危険性を、よく理解していた。
そして、自分が生み出される過程において、生みの親であるキョウジが犯してしまった『罪』も、よく理解していた。
強大な力を持つガンダムを作ってしまったが故に、母は殺され、暴走する力を止められなかったが故に、多くの人々の命を犠牲にしてしまった。自分の元となったシュバルツ・ブルーダーも、その一人だ。自分は、多くの人々の『血』と、キョウジの『涙』の果てに、産まれ落ちているのだと。
だからシュバルツは、既に深い闇に塗(まみ)れ、そこに堕ちている。普通ならもうそこで、世の中に絶望し、境遇を呪い、人の世を憎んでもおかしくは無いのに。
なのに彼は――――顔を上げて独り、そこに立っていた。
彼の心の元になったモノが、『キョウジの良心』であった故に。
そのヒトは、人を信じ、世を信じた。
そして、その力は、弱き者を守るために使われた。
「キョウジが、自分を作ってしまった事を、これ以上後悔しないように」
ただそれだけを願って、そのヒトは動いていた。
この深い闇を纏った健気な『光』――――愛おしくて、愛おしくて堪らなかった。
だから――――
「んっ! あ、あっ……! ああっ!!」
腹の下で愛おしいヒトの身体が、弓なりにしなる。
喘ぐ口から、僅かに舌が差し出される。あれは、口付けを欲しがっているサイン。ハヤブサは、優しくそれを叶えてやる。
「ふ………ん………」
腕の中で、甘く蕩けていくシュバルツ。その耳元で「愛している………」と、注ぎ込むように囁いてやれば、愛おしいヒトの身体が、ぴくん、と、跳ねた。
「あ………!」
逃げようとする耳を捕まえて、もう一度。
「愛している……。シュバルツ……!」
「駄目……! あ……!」
身を捩ろうとする愛おしいヒト。それをハヤブサが許すはずもない。捕まえて、何度でも――――何度だって、囁いてやる。
「愛している……」
「あ……! ハヤブサ……ッ!」
シュバルツが、堪らない、といった風情で抱き締めてくる。酷く情が深いこのヒトは、愛されるよりも愛したいのだろう。だけどこのヒトは、自分が誰かを愛してしまってはいけない、と、思っている。自分は『アンドロイド』で、しかも『DG細胞』という危険な物質で構成されている身体なのだから、人と深く関わってはいけない。愛されていても、常に身を引けるようにしておかなければならないと、真面目に考えているのだ。
そんな事、させないけどな。
シュバルツを愛しながら、ハヤブサは強く思う。
お前が逃げて行っても、追いかけて――――抱きしめる。
俺がそれを出来るうちは。
俺は構わないんだ、シュバルツ。お前からDG細胞を感染させられたとしても、たとえ、殺されてしまったとしても――――。
もう俺は、お前に深く囚われてしまっているも、同然なのだから。
だからどうか――――お前も愛する事を、躊躇わないでくれ。
「ああっ!! ああああ……!!」
びゅく……と、シュバルツから精が放たれる。
ガク……と、力が抜けて行くシュバルツの身体を支えて、さらに挿入を深めた。
「駄……目……! ああっ!!」
後ろから抱き締めて、シュバルツの乳首を擦りながら、耳元で優しく囁いてやる。
「愛している……」
「はあ、あ、ん……!」
「愛しているんだ、シュバルツ……!」
「あ……! ハヤブサ……! ハヤブサぁ……!」
身体を優しくゆすられながら、シュバルツは切なそうに頭を振る。小さく震え続けている唇。まるで、何かを堪えているかのように見える。
一体、何をそんなに堪えている?
もしも――――愛の言葉を堪えているのならば、どうか、それを我慢しないで。
ハヤブサは、愛の言葉を封じ込めようとするそのつれない唇を、少し乱暴に塞ぐ。
「んうっ! んんっ!! ん、ぐ……!」
それからもう一度、耳元で囁く。
「愛している」
「う……あ………!」
切なそうに頭を振り、涙を飛び散らせるシュバルツ。散々蕩けているように見えるのに、まだ、それを堪える理性が残っているのだろう。
恐ろしく忍耐強くて、美しいヒト。
だけど、今は邪魔だと感じる。
その『強さ』が――――
俺の前だけでいい。総てを曝して。お前の身体も。その心も――――。
俺は、お前の『総て』が欲しい。
お前の『全部』を、俺に寄越せ。
そう願ってしまうのは、傲慢なのか。
お前の総てを手に入れたいと願うのは、俺には過ぎた幸福(こと)なのだろうか。
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
想いを込めて、その身体を優しくゆする。感じる所を擦り続ける。
「あっ! あ……! ああ……ん……」
腕の中で愛おしいヒトが可愛らしく喘ぎ、よがる。
淫らで、官能的なシュバルツ。
もっと――――もっと、蕩けて。
『我慢』しないで。
「ああ……! は、あ……!」
喘ぐシュバルツから出される、キスのサイン。顎を捉えて、深く塞ぐ。強く口腔を弄りながら、身体をゆすり続ける。
「んっ! んぅ……! んうう……!」
チュッ、チュッ、と、互いに口を吸い合う水音が響く。
「……はっ! ああっ!!」
キスが終わると同時に、ドプッと、音を立てて、シュバルツがまた果てた。力が抜けて行くシュバルツの身体を捉え、もう一度、耳元で囁く。
「愛している」
「あ……! あ……!」
懸命に何かを堪える様に、震えるシュバルツの唇。
言って。
聞きたいんだ。俺は。
お前の口から、『その言葉』を――――
「ハヤブサ……ッ!」
縋る様に名前を呼ばれて、愛おしいヒトから強く抱きしめられる。
そのとたんに、シュバルツの全身が、雄弁に語りだす。
――――愛シテイル………
『言葉』以外で、その『言葉』を――――
抱きしめてくる、腕の強さが。
何度も触れてくる唇が。
揺らめいてしまっている腰が。
甘く締めつけてくる秘所が――――
――――愛シテイル………
もうお前は、何度も俺にそう言っているも同然なのに。
どうして
どうして、言ってくれないんだ。『その言葉』を。
俺は、お前の口からそれが聞きたいのに――――
「ハヤブサ……! あ……! あ……! ハヤブサぁ……ッ!」
縋る様に名前を呼ばれる。シュバルツに乞われるままに身体を密着させて、挿入をグッと深めてやれば、愛おしいヒトが嬉しそうに耳にキスをしてきた。
「気持ちいい……」
しどけないため息と共に、耳元で小さな声でシュバルツにそう言われてしまっては。
ハヤブサの僅かに残っていた『理性』も、吹っ飛ぶほかに道は無くて――――
後はただ、肌と肌の擦れ合う音と、水音と、獣の様な呻き声と、官能的な啼き声が―――――辺りに響く、だけであった。
何度かシュバルツに『精』を叩きつけて、ようやくハヤブサは人心地がつく。脱力してしまってシュバルツの上に倒れ込むと、シュバルツから手が伸びて来て、そっと優しく抱きしめられた。そのまま、頭から背中を優しくあやすように撫でられる。
抱かれた後シュバルツは、意識があれば必ずこの抱擁をしてきた。
どのように抱いても、それを『赦す』と言うシュバルツの意志が、強く伝わって来るこの抱擁。ハヤブサはこの抱擁を味わうのも、堪らなく好きだった。
――――愛シテイル………
ほら……。やっぱりお前は、この抱擁でもそう言ってくれているのに。
どうして、口に出してそれを伝えてくれないのだろう。
それとも、それを望むのは、贅沢な事なのか――――
「……落ち着いたか……?」
「ん………」
声をかけてきたシュバルツの肌に、甘えるように身を擦り寄せる。
愛おしくて、愛おしくて、愛おしくて――――つれないヒト。ほんの少し腹が立つから、指の腹でシュバルツの乳首を軽く弄ってやった。
「――――あっ!」
その刺激に、自分の身体の下の愛おしいヒトがぴくん、と、跳ねる。その可愛らしい反応に気を良くしたハヤブサは、しばらくシュバルツの乳首を軽く弄び続けた。
「んっ! や…! あっ…! ハヤブサ……!」
性感帯への刺激に、身体の下の愛おしいヒトは喘ぎ、乱れる。だが、ハヤブサを抱きしめるシュバルツの手は、ただひたすら優しくハヤブサの髪や背を撫で続けていた。
分かる。
このままもう一回、お前の身体を欲しがったとしても――――
お前は優しく、それを赦してくれるのだろう?
『好きだから』赦してくれる。赦し続けてくれる。
際限なく受け入れてくれる、お前の深い『愛』
今の俺は、それが分かってしまうから――――
「シュバルツ……」
想いを込めて、唇を求めると、愛おしいヒトもそれに応えてくれた。
「ん…………」
そのまま、互いの想いを確かめ合うような口付けを交わす。今はこれで――――もう、充分だ。
そう感じたハヤブサは、シュバルツから身体を離す事にした。
「……んっ! ああっ!」
引き抜かれた瞬間、シュバルツから声が上がり、彼の中から自分の出した残滓が流れ落ちてくる。
「洗ってやろうか?」
そうハヤブサが苦笑交じりにシュバルツに声をかけると、「だ、大丈夫だから……!」と、声を上げながら、愛おしいヒトが慌てて身を起こしてきた。しかし身を起こした瞬間、体内から更に名残が流れ出てくるものだから、シュバルツは「あ………!」と、小さく叫んで、そのまま固まってしまった。
「大丈夫か?」
「馬鹿っ! 出し過ぎだ……!」
顔を真っ赤にしながら抗議の声を上げる愛おしいヒト。その可愛らしい姿に、ハヤブサの頬もどうしても緩みがちになってしまう。
「仕方がなかろう。こちらは1週間『も』お前に触れられなくて、我慢していたのだから……」
「『も』じゃないだろう! ……まったくもう!」
シュバルツがそう言いながら、近くのせせらぎにザブン、と、飛びこむ。少し潜って泳いでから、ザバッと、水中から顔を出した。どうやらそのまま、身体を洗うつもりらしい。
「こういう逢瀬は、1週間に1度で充分だろう?」
身体から水を滴らせながら、シュバルツが川の中から言い返してくる。
「充分だなんて――――」
シュバルツの言葉にハヤブサは反論しようとして――――思わず、目をそらしてしまった。川の中のシュバルツの姿が、あまりにも強烈な色香を放っていたからだ。
(あいつ……! 本当に自覚が無いのか!? これだけ俺の心を揺さぶっておいて―――!)
シュバルツの身体なら、何度だって抱きたい。毎日だって抱きたい。
自分はそう、願ってしまうほど、彼に引きつけられていると言うのに。
肝心の、愛おしいヒトの方が、自分が放ってしまっている色香自体にまるで無自覚すぎて困る。「何でそんなに抱きたがるんだ」と言わんばかりの反応に加えて、今もまるで無防備に、自分に対してその水に濡れた肢体を曝している。
その身体を、俺がどういうふうに見ているか――――知らないお前ではないだろうに。愛されている自覚があるのかと、つい、問いただしたくなってしまう。
俺の前だけでそう無防備ならば、まだいい。
俺以外の奴に、その綺麗な肌を曝したりはしていないだろうな――――
(……………!)
ここまで考えたハヤブサは、ブン! と、頭を振る。
(シュバルツが浮気? あり得ないだろう)
シュバルツは、必要以上に誠実で、義理堅い男だ。一度操をささげた相手には、頑なにそれを守りとおそうとするだろう。俺への恋愛感情がどうこうという以前に、それが『人の道』だと彼は真面目に思っているから――――
分かっている。
シュバルツは、絶対に、俺を裏切らない。
俺が、シュバルツを絶対に、裏切らないように。
ハヤブサは、周囲の枯れ木を手早く集めて火を起こすと、自身も川の中に入った。身体を洗うのと、自分の頭を冷やすのも、目的だった。
とにかく、せっかくシュバルツと一緒に居られるのだ。つまらない物想いに無駄に時間を費やすよりも、彼との時間を楽しみたい、と、ハヤブサは思った。
実際、シュバルツと一緒に過ごす時間は楽しい。
教養も深く、『忍者』と言う同じ世界を共有しているせいか、歯ごたえのある会話ができる。未だ出会ってそんなに時間は経っていないはずなのだが、もう10年以上も共に時間を過ごした知己と、会話をしているような錯覚に陥ることもあるほどだ。
それに、彼と共に居るとハヤブサは、改めて自覚する事が出来る。
人の世の『優しさ』を、まだ自分は、信じていいのだと――――
人が人を思いやる優しい『世界』が、『光』が、確かにそこにあるのだと、信じる事が、出来るのだ。
仕事柄、人の暗黒面や血なまぐさい世界ばかりを見てしまうハヤブサにとって、これはかなり貴重だった。彼のおかげで自分は、そう言う優しい世界を見失わないで済んでいる。何故なら―――シュバルツ自身が闇の中に在っても、優しい『光』を内包している存在であるのだから。
「シュバルツ」
自身も身体を洗いながら、ハヤブサはシュバルツに声をかける。
「何だ?」
「身体を洗い終わったら、とりあえず、何か食べに行っていいか?」
「ああ。構わないが……」
「よし、決まりだ」
シュバルツの返事を聞くと、ハヤブサは早々に川から上がった。頭も無事に冷やす事が出来た。シュバルツと愛を確かめ合うのは、また夜の楽しみにすればいい。今日という日は、夜通しシュバルツを抱くことだって、彼は赦してくれるのだから。
火に当たり、身体を拭きながら、今日はシュバルツとどこを巡ろうかと、ハヤブサは考えていた。
それから24時間、忍者たちはいつもどおりに過ごした。史跡を巡ったり、顔なじみの古美術商の所に顔を出したり、キョウジに頼まれた専門書を探して、本屋を巡ったり。
そして、夜になれば宿に泊って、体力の許す限り、ハヤブサはシュバルツを何度も求めた。シュバルツもまた、ハヤブサに何度もその身体を開き、赦し続けた。
「んあっ! ああっ! ああ……!」
犯される刺激に感じてしまって、自分の腹の下で艶めいた声を上げながら、白い身体をのたうちまわらせる愛おしいヒト。ハヤブサはその妖艶な景色に酔い続ける。
もっと――――もっと、俺を感じて。
もっと、乱れて。
何もかも、分からなくなってしまうぐらい、蕩けて――――
そして、もう一度、俺に聞かせて。
お前が封じ込めようとしている『愛の言葉』を。
もう一度、俺に、囁いて。
その願いを込めて、ハヤブサはシュバルツの身体に触れる。乳首を擦り、牡茎を弄ぶ。
「ああっ! 駄目……! ハヤブサ……ッ!」
「駄目じゃないだろう。そんなに乱れて――――」
「あ……! ああ……!」
股をひらいて、腰を自ら揺らめかせ、どうしようもない痴態を曝す愛おしいヒト。そこまで――――そこまでお前は、俺に『開いて』くれているのに。
蕩けているように見えるのに、心の最後のひとかけらを渡してくれないつれないヒト。
欲しい。
俺はそれが、欲しい、のに。
今宵も、ハヤブサの願いは叶えられないまま―――夜は更けて行くばかりだった。
「はあ………」
『約束の24時間』を終えて、どうにかこうにかハヤブサと別れる事に成功したシュバルツ・ブルーダーは、軽くため息をついていた。
(全く……どうしてあいつはああも際限なく私を求めてくるんだ……。訳が分からん)
夜から朝にかけて、「もういいだろう」と言いたくなるくらい、散々私を抱き倒していると言うのに。いざ、別れの時間が近づいてくると、未練たっぷりに『別れたくない』と、駄々をこね出すハヤブサ。必死になだめすかして、何とか別れようとするのだが、ハヤブサがなかなか放してくれないものだから、最終的にはいつも、怒鳴りつけなければならなくなってしまう。
おかしい。
何でこんなにハヤブサに懐かれてしまっているのだろう。
私がハヤブサを『好きだ』と、思った理由は実に単純なものだ。
最初に自分がハヤブサと会ったときは、敵同士だった。
私は、生みの親であるキョウジを守護する者。そしてハヤブサは、そのキョウジを狙う者であったが故に。その戦いは、避けられぬものとなった。
ハヤブサも私も、互いを本気で斬るつもりでぶつかり合った。二人の力量はほぼ互角であったため、一瞬も気を抜けない戦いとなった―――筈だった。
だが、この戦いで、私の方が先に致命的なミスをした。
自分達の戦いに巻き込まれかけた少女に気を取られ、私はほぼ条件反射的にその少女を守ってしまった。一瞬、目の前に居るハヤブサのことすら忘れてしまって―――
当然ハヤブサは、斬るつもりでこちらに攻撃を仕掛けて来ている。その前で、大きな隙を見せてしまった自分。斬られても仕方が無い展開だった。
だがハヤブサは、そんな私を斬らなかった。
そして『斬られなかった』と悟った瞬間、私はハヤブサに対する敵意と抵抗の意思を放棄してしまった。
ハヤブサは、見逃してくれたのだから。ハヤブサを斬ろうとしていた自分を、斬る事が出来る千載一遇のチャンスを。こんな事――――普通はあり得ない。
闇の世界で生きてきたはずなのに、稀有な優しさを持った人。
そんな人に向ける刃を、私はあいにくと持ち合わせてはいなかった。
「斬られても良いから話がしてみたい」
そう思った。
「ハヤブサになら、斬られてもいい」と。
その時にもう、『好きだ』と、思ってしまっていたのかもしれない。
だが、この身体は命を内包していないが故に、斬られても甦ってしまう。だから、結局この想いも、欺瞞でしかないのだけれど。せめて、彼に対しては、信頼の扉を開け続ける。決して、自分からは閉ざしたりはしない。そう在り続ける事が、自分がハヤブサに返す事が出来る精一杯の『誠意』だと思った。それしか、自分はハヤブサに返す物がなかったから――――
そんな私に対して、ハヤブサは本当にいろいろと心配してくれた。
怒ってくれた。
泣いてくれた。
そして、手を差し伸べ続けてくれた。
私が不死の化け物だと知っても、その態度は変わる事は無く、むしろ余計に距離を縮めて来て――――
「抱きたい」と、言われて、拒めなかった。
「斬られてもいい」と、思っていたと言う事は、割と「何をされてもいい」と思ってしまっているも同然なのだと言う事を、私はその時悟った。
でもまあ、私の身体は男の造りをしているし、人間でもない。
抱き心地も良いものではないだろうから、そのうちにハヤブサも飽きるだろうと思っていた。
だけど、ハヤブサの方がいくら私を抱いていても「飽きる」と言う気配を見せない。
「飽きないのか?」
試しに私は、ハヤブサにそう聞いてみた。
「……心外だな。俺の、お前への『想い』は、そんな物だと思っていたのか?」
「いや、そう言う訳では―――――んう!」
いきなり強引に唇を塞がれ、そのまま押し倒されてしまう。
「………教えてやるよ。俺がどれだけ、お前に焦がれているかを――――」
「あ…………!」
あっという間に抵抗する手段を封じられ、服をはだけさせられて――――
いろいろとされた揚句に、最後にはきっちりと『気持ち良く』されてしまった。
「……………」
よく分からないが、つまり、ハヤブサがまだしばらく私に飽きるつもりはないと言う事だけは、よく分かった。
「愛している……」
睦言の最中でも、そうでなくても、よくそうやって愛を囁いてくれるハヤブサ。
とても嬉しいのだが、心苦しくもある。
良いのだろうか? 私は人間ではないが故に、ハヤブサの生涯のパートナーには、決してなり得ない存在なのに。まして、私を構成している『DG細胞』が何時ハヤブサにその牙を剝くかも、分からないのに。
だから、私は愛の言葉をハヤブサに返せない。
返してはいけない――――
ハヤブサにだって、いつかは『人間の』パートナーが出来るかもしれない。そうなったときに、自分はいつでも身を引けるようにしておかねばならない。常に自分の立場を、わきまえておかねばならない、と、思うのだ。
なのに――――
「愛している……」
自分を捕まえてそう囁くハヤブサが、酷く幸せそうだから困ってしまう。拒めない。強く振り払う事が出来ない。
何故だ?
何故、そんなに幸せそうに――――私に愛を囁けるのだろうか。
彼の「愛している」と言う言葉に決して応える事の出来ない私は、彼の心を一方的に消耗しているも同然なのに。
どうして、ハヤブサは――――
――――愛している……
「…………」
(きっとハヤブサは、恋の『熱病』にかかっているような状態なんだ……。だから結局、私に対する想いが醒めてくれるのを、待つのが正解なのかもしれないな……)
半ばあきらめにも似た気持ちと共に、シュバルツはそう結論付ける事にした。
幸せそうに笑っているハヤブサ。
そんな彼を、見つめる事が出来るのは、嬉しい。
自分の、ハヤブサに対する願いは
『幸せになって欲しい』
ただ、それだけだったから。
彼が、私の横に居て――――『幸せだ』と感じてくれているのならば。
私はそれを、受け入れ続けるだけだと、思う。
しかしこれは、彼に『DG細胞に感染する』と言うリスクを背負わせる行為でもあるので、シュバルツにとっては、いささか複雑でもあるのだが。
(だいたい、キョウジもキョウジだ……。どうして――――私とハヤブサがつきあう事を、強く止め立てしてくれないんだ?)
キョウジは『DG細胞』の発見者にして、アンドロイドである自分を制作した科学者だ。だから、『DG細胞』が背負うリスクを、誰よりも理解している人物でもあるのに。
―――シュバルツ……。貴方が幸せならば、私はそれで良いと思うけど……。
そう言ってにこにこと微笑むキョウジは、この問題についてこれ以上取り合う気はないようだった。
でも、それで片づけてしまっていいのだろうか?
事がDG細胞なだけに、あまり楽観するのは良くない様な気もするのだが―――
(それに、『私の幸せ』を、キョウジは気にしてくれているようだが、私からしてみればキョウジ……お前こそ、幸せになって欲しいのだが……な……)
キョウジのアパートの玄関先まで帰ってきたシュバルツは、そう感じてため息を吐く。
もともと自分は、キョウジの心から派生して生まれた、いわばキョウジの『影』だ。つまり私は『キョウジの紛い物』と言っても良い存在なのだから、私の事など気にせずに――――キョウジはもっと、自分のために生きても良いと、思うのに。
なのに『本体』であるキョウジが『影』である私の事を気にして――――これでは、本末転倒なのではないかと感じてしまうのだ。
本当は、自分こそが、『キョウジの幸せ』を、真っ先に考えなければならないのに――――
でも、難しい。
『キョウジの幸せ』って、何だろう……?
その為に、自分はどう動けば、良いのか――――
などと、少し小難しい事を考えながら玄関のドアを開けたシュバルツの耳に、いきなり大音響のゲーム音の様な音が飛び込んでくるから――――彼はかなり、面食らってしまっていた。
「やった………!」
ゲームのコントローラを握りしめたキョウジ・カッシュは今、歓喜の渦の中に居た。それもそのはずで、彼は今、遂に、成し遂げたのだ。
「やった―――!! ついにこの『風の中のシルエード・タクティヌス・東南プロジェクトダイブ・フォーチューン』の100面をクリアしたぞ――――!!」
思わず彼が、そう歓喜の叫び声を上げた瞬間。
バン!!
いきなり背後の部屋のドアが、乱暴にひらく。
「……………」
そのままドアを開けた主が、出入り口付近で仁王立ちのまま沈黙を貫くから――――キョウジは、背中から嫌な汗が流れ落ちて来てしまった。
「あ、あれ~? ……何やら背後から、殺気の様なものを感じる……」
「おい……。何だ、この部屋の惨状は……」
「え?」
シュバルツの低い声に、キョウジが多少笑顔をひきつらせながら振り向く。
「『え?』じゃないだろう!? キョウジ!! 周りを見てみろ!! ゴミだらけじゃないか!!」
シュバルツの指摘通り――――キョウジの周りには食べ終わったポテトのくいかすや袋、ジュースの空き缶や空のペットボトル、そして紙くず等が、あちこちに散乱しているのだった。
「ごめん、ごめん。後で片づけようと思って――――」
シュバルツの指摘にも、キョウジは特に悪びれもせずに、あっけらかんと謝って来る。
「後でって……! お前なぁ、ゴキブリさんとお友達になりたいのか!?」
「いやぁ、そう言う訳でもないんだけど……」
「だったら今すぐ片づけを……!」
「ああ、待って、シュバルツ」
「何だ?」
「このゲームのED見たらするから……もうちょっとだけ、待ってくれる?」
「……………!」
キョウジの面白すぎる言い分に、シュバルツは激しい眩暈を感じる。思わず『阿呆か―――!!』と、怒鳴り付けそうになったのだが――――シュバルツも、ここはぐっと堪えた。
(いやいや、落ちつけシュバルツ・ブルーダー。私だってハヤブサと遊んできた様なものだ…。キョウジが遊んでいるからって、それを一方的に責められる訳が無いだろう…!?)
大きく深呼吸をして、気持ちを落ち着かせる。とりあえず、キョウジの見ているゲームが終わったらすぐに片づけが始められるよう、彼は掃除機を引っ張り出してくる事を選択した。その横でキョウジがテレビ画面を見ながら「ラミリオちゃん可愛いな~」などと、のん気に個人的な感想を述べたりしている。
「あ~……隠しステージは出なかったか……。う~ん……スコアが足りなかったかな~?」
「キョウジ……終わったのなら片づけをはじめてくれ。掃除機をかけるから」
「はいはい。はいはいっと……」
シュバルツがため息交じりに掃除機をかけ出した横で、キョウジもパタパタとごみの片づけを始めた。
「ところでキョウジ」
シュバルツが掃除機をかけながら、キョウジに声をかける。
「何? シュバルツ」
「お前、明日の準備は大丈夫なのか? 明日、確か大学の講義の日だろう?」
「ああ、大丈夫だよ。レジュメの準備は出来ているし、後は小テストの採点だけだ」
「……おい、まさかこれがそうとか言う訳じゃないんだろうな?」
シュバルツがキョウジの机の上にあるテスト用紙の束を見つけて指摘する。それは1枚目の3問目まで丸つけが為されていて――――後は、白いままで放置されていた。
「うん、よく分かったねぇ?」
「分からいでか!!」
シュバルツは思わず大声を張り上げてしまう。
「ゲームの誘惑に負けるのが早すぎだろう!! せめて1枚ぐらいは採点してからにしろ!!」
何か、そういう問題でもない様な気もする事を叫ぶシュバルツに、キョウジも苦笑しながら答えた。
「ごめん、ごめん。50面のあの弾幕の避け方を思いついちゃったら、どうしても試さずにはいられなくなっちゃって――――」
「……………!」
「それに、テストの採点作業って、苦手なんだよ。単調すぎると言うのかなんというのか……。どうしていちいち丸バツをつけて、優劣を決めなきゃいけないんだ? 答えも皆、同じようなものばっかだし」
「……答えが同じような物になるのは、仕方がないだろうキョウジ。数式の答えは一つだ」
「『一つ』とは限らないだろう? 一つの数式から、いろんな可能性のある答えが出てくるかもしれないし――――」
まるで禅問答だな、と、シュバルツは苦笑しながらも答えた。
「それはそうかもしれないが……小テストの問いで要求する答えじゃないだろう? それにテストの目的は、自分の教えた事がどれだけ理解されているか、こちらが知るための物じゃないのか?」
「それはそうかもしれないけどさ」
「だったら、ゲーム何ぞに油を売っていないで、さっさと取りかかれば……」
「だからだよ」
「何だ?」
「だから、テストの成績をつけていると、自分の講師としての成績をつけられているようで――――」
そう言いながらデスクに座ったキョウジは、テスト用紙の上にゴン、と、頭を突っ伏して、しくしくと泣き出している。
「皆が皆同じ所を間違えていると、私の教え方が下手くそなのかと思ってしまうし……」
「そうやって泣いても、採点作業は代わってやらんぞ」
「うぐっ……!」
シュバルツにスパン、と、そう言われて、キョウジも苦笑しながら顔を上げた。
「嘘泣き、ばれてた?」
「ばれいでか!!」
シュバルツの毒づきにキョウジは声を立てて笑い、シュバルツは、はあ、と、大きくため息を吐いた。
「……とにかく、さっさと採点作業を終わらせろ、キョウジ……。その後ならば、ゲームをしようが何をしようが、私も文句は言わないから……」
「は~い」
キョウジが軽く返事をしながら赤ペンを取り出す。どうやら、採点作業に取り掛かる気になったようだ。やれやれ、と、掃除機を片づけようとしたシュバルツに、キョウジが声をかけてきた。
「じゃあシュバルツ……。ひとつお願いがあるんだけど……」
「何だ?」
「……ご飯、作ってくれる?」
「はい?」
振り返るシュバルツに、キョウジがにっこりと笑みを浮かべる。
「ほら……私は今から採点に忙しいから……作ってくれると助かるんだけど」
「あ、あのなぁキョウジ……。私は味覚が無いから、ご飯を作るのは―――」
シュバルツの言う通り、彼はアンドロイドであるが故に、その舌には『味覚』が無い。だから、料理の味の保証が出来ない分、『料理を作る』と言う行為に、シュバルツは少し不安を覚えるのだ。
「でもシュバルツは、コーヒー淹れるのうまいじゃん」
「あれは、身体が覚えているんだ」
ぶっきらぼうにシュバルツは答える。
そう、あれはキョウジの『記憶』によるものだ。『旨いコーヒーが飲みたい』と、キョウジが何度も何度もコーヒーを淹れて、自分好みの分量と時間と温度を編み出した。自分はそれを、忠実に再現しているにすぎない。
「じゃあ、大丈夫だよ。料理も体で覚えれば――――」
「『体で覚える』と簡単に言うがな、キョウジ……」
ため息交じりに零し気味になるシュバルツに、キョウジがやんわりと言葉を返す。
「料理は、作れるようになっておいた方がいいよ、シュバルツ……。人間の間に混じって生きて行くのならば、特に」
「キョウジ……」
「それは絶対に、自分の『助け』となるから――――」
「…………」
しばらく推し量るようにキョウジを見つめていたシュバルツであるが、やがて「分かったよ」と、観念したように踵を返した。掃除機を片づけた彼は、その足で台所へと向かっていく。
「味は、期待するなよ?」
「作ってくれるものなら、何でもおいしいよ」
キョウジの言葉に、シュバルツも「気持ちは分かるが…」と、苦笑する。確かに、人に作ってもらったご飯は、ありがたいものだ。
「しかしキョウジ……」
「何? シュバルツ」
昼食の準備をしながら声をかけてきたシュバルツに、キョウジが答案用紙から目を離さずに返事を返す。
「何時までもこうやって私に世話を焼かせてないで、嫁さんを貰ったらどうだ?」
決して自分がキョウジの世話を焼くのが嫌、と、言う訳ではない。シュバルツにとって、寧ろキョウジの役に立てるのは、楽しいし、嬉しい。だけどやはり―――良いのだろうか、とも考えてしまう。やはり、『人間の女性』がキョウジの側にいる方が、彼のためには良いのではないかと、思ってしまうのだ。
「…………嫁さん、ねぇ」
シュバルツのその言葉に、キョウジは少し考え込むようなそぶりを見せる。
「………私はそれよりも、ドモンとレインちゃんの子供を早く見たいよ」
「キョウジ……」
振り返るシュバルツに、キョウジは少しむくれた顔を見せた。
「全くあの二人は、いつになったら私に二人の赤ちゃんを抱っこさせてくれるんだ?」
ブツブツ文句を言いながら答案用紙の採点をしているキョウジに、シュバルツも苦笑するしかない。
「そればかりは縁の物だからなぁ。私たちが気を揉んでも仕方がなかろう」
「そりゃそうだけどさ」
採点をしているキョウジの赤ペンが、リズムよく動いている。どうやら、興が乗ってきたらしい。
「二人の赤ちゃん、きっと、可愛いだろうな~」
「まあ、そうだろうな」
シュバルツの食材を刻む包丁も、リズムよく動きだす。どうやら、メニューが決まったらしい。
「はあ~……赤ちゃんの、おむつを替えたい。抱っこして、おしっこ引っかけられたりしてみたい」
「ドモンの時は、大変だったものなぁ」
キョウジの言葉にシュバルツもキョウジの幼いころの記憶を呼び起こされて、苦笑してしまう。
「そんでもって、大きくなった子供に『おじちゃん』って、呼んでもらうんだ」
「『おじちゃん』……まあ、確かに『伯父』になるな……」
「それで、レインちゃんが大変な時は、ベビーシッターに頼まれて行ってあげたりして――――」
「そうだな、育児はやはり、助け合い――――」
「主に、シュバルツが」
キョウジの言葉にうんうん、と、頷いていたシュバルツが、ズルッとこけた。
「何で私なんだ!!」
怒鳴ってくるシュバルツに、キョウジはしれっと反論する。
「だってそうだろう? 私は平日の昼間とかだと仕事で家にいないし、お前の方が手が空いている事になるんだし、実際私よりも体力があるし――――」
「う………!」
「どうするんだ? お前。実際そうなるぞ? ドモンが『兄さ~ん、助けて~~!』って、絶対呼びに来るぞ?」
「そ、そうなのか?」
キョウジのリアルな物言いに、シュバルツもだんだんその気になって来てしまう。育児書でも買って、読んだ方がいいんじゃないかとシュバルツが思い出した時――――キョウジの手元の携帯電話が鳴った。
「はい。もしもし?」
キョウジが電話に出たので、シュバルツはとりあえず昼食の準備の続きをする事にした。材料を刻み、鍋に油を敷いて熱し、そこに手際よく材料を投入して、炒めて行く。どうやら彼は、炒飯をメニューに選択したらしい。
シュバルツが調理の音をさせている間、キョウジは電話の相手と話し続けていた。どうやら、知り合いの大学教授からの電話らしい。
「ええ……はい……はい……。大丈夫ですよ。ええ……もうすぐ出来ますので―――」
ピ、と、キョウジが音を立てて電話を切ると同時に、シュバルツの料理も出来上がった。
「ほらキョウジ、出来たぞ……。調味料は適当だから、味の保証はしないが――――」
「……………」
キョウジが電話を持ったまま固まっているから、シュバルツは少し不思議に思った。
「キョウジ?」
シュバルツに声をかけられたキョウジが、ゆっくりと振り向く。顔にひきつった笑みを浮かべながら――――
「シュバルツ………」
「ど、どうした? キョウジ……」
キョウジの顔色に、シュバルツの方も悪い予感しかしない。
「……さっきの電話………今度の学会の会報の原稿を教授に頼まれていて、その確認の電話だったんだけど……」
「ま、まさか………」
生唾を飲み込むシュバルツに、キョウジがにっこりと頷く。
「うん。すっかり忘れてた」
「な――――!」
固まるシュバルツを尻目に、キョウジはひきつった笑みを浮かべながら、ポリポリと頭をかく。
「いやあ、そう言えば、仕事の合間に教授に頼まれていたんだよな……。何か返事をした様な気がするんだけど、そのまま放置していた様な―――」
「ち、ちなみにキョウジ……」
ズキズキと痛む頭を押さえながら、シュバルツは問いかける。
「何? シュバルツ」
「そ、その原稿の締め切りは、まさか……」
「え? え~っと………明日?」
「何!?」
二人の間に流れる気まずい沈黙は、シュバルツの怒鳴り声によって破られる事となった。
「馬鹿も――――ん!!! だから用事を頼まれたらきちんとメモをしておけとあれほど言ったというのに……!!」
「ご、ごめん、シュバルツ! てな訳で今から私は原稿に取り掛かるから――――採点やっておいてくれる?」
「こらっ!! 結局こうなるのか!! て言うかキョウジ!! 昼食は!?」
「原稿書きながら食べる~」
「物食いながらあれこれしようとするな――――!!」
シュバルツの怒鳴り声が、平和な午後の青い空に吸い込まれていく。
こんな風に平和な日々が、これからもずっと続いて行くのだと、そのときはただ漠然と思っていた。
こんな平和が続くなんて、誰にも何の保証も無いのに。
誰もがそう信じて疑わなかった。
だから、決して忘れていた訳ではなかった。なのに、いつの間にか忘れてしまっていた。
『災厄』は何時だって
突然やって来るのだ、と、言う事を――――
第1章

仕事のために海外に出ていたハヤブサは、久しぶりに日本に帰って来た空港のロビーを、いそいそと歩いていた。
少しだが、シュバルツやキョウジに土産話も出来た。ちょっとした土産も手に入れた。
明日は約束の日だ。それに間に合う様に、帰って来れて良かったと、ハヤブサは思う。
真面目なシュバルツの事だ。もしも約束の日にその場所に自分が現われなかったら――――ひどく心配させてしまいそうな気がした。尤も、それをシュバルツに言ったら、本人は素直には肯定しないだろうが。
一刻も早くシュバルツに触れて、抱きたい。
少しきつめの『仕事』を終えた後のハヤブサは特に、それを強く望む。
だけど今は、里の方に任務の報告に行かねばならないので、ハヤブサの足は里へと向かっている。愛おしいヒトとの逢瀬は明日だ。残念だが、楽しみに取っておく。
里方面へ向かう電車の切符を買い、それに乗り込む。ここまでは、いつも通りの日常の風景。だがそれが――――突然、破られた。
「何だ!? あれは!!」
乗客の叫び声に、電車の振動にまどろみかけていたハヤブサも顔を上げる。周りの乗客たちは既に、窓の外を指さして驚いたり息を飲んだりしている。ハヤブサもそれにつられる様に窓の外に視線を移して――――絶句した。
「な―――――!」
あまりにも突然それが視界に飛び込んできたため、ハヤブサは一瞬自分が映画でも見ているような錯覚に陥ってしまった。それほどまでに――――視界に飛び込んで来た物は、『異質』だった。日常生活に溶け込ませるには、あまりにも違和感の塊すぎた。
何故ならそれは――――
巨大な『龍の首』であったのだから。
グオオオオオ――――ッ!!
龍の首と電車の距離は、幸いにしてそんなに近くではなかった。だが、その龍の天地をつんざく様な咆哮は、電車の窓ガラスをびりびりと揺らす。そしてその口からは巨大な熱球が吐き出されて――――
ドオオオオン!!
熱球が街中で爆ぜる。その衝撃波で電車の窓ガラスが割れ、激しく車体が揺らされたが故に、電車の緊急停止装置が作動した。電車の中は割れたガラスによる怪我人で溢れ、あっという間にパニック状態に陥ってしまう。
(緊急事態――――!)
そう悟った龍の忍者は、電車を飛び下りる事を選択した。とにかく、あの暴れる『龍の首』を何とかしなければと強く思った。
走りながらいつもの黒の忍び装束になる。背にある『龍剣』を意識しながら、ハヤブサは龍の首へと向かって行った。『忍者』と言う仕事柄、ああ言った妖異の類とも何度か対戦した事のあるハヤブサではあるが、唐突に現れたこの龍の首には、どうしても違和感を禁じ得なかった。
まず、何と言っても目を引くのは、その巨大さだ。
龍の近くにある高層ビルが、思わずジオラマの物に見えてしまうほど、その龍は巨大だった。自分は懸命に距離を詰めているはずなのに、一向に龍との距離が縮まったように感じられない。自分の遠近感が狂ったような錯覚を覚える。
そしてその龍がもたらす凄まじいまでの破壊力――――
その龍が通った後は、見事に瓦礫の荒野と化していた。まるで、「ありとあらゆる生命を、自分は認めない」とでも言わんばかりの破壊行為。何もかもが――――常識を逸脱しすぎている。その圧倒的な力に、うっかり「神々しさ」まで感じてしまうほどだ。
(これほどの『妖異』を、一体誰が、何のために出現させた?)
ハヤブサは走りながら、思わず考え込んでしまう。
普通『妖異』と言うのは、まず術者がいて、それが召喚術を行う事によってはじめて現世に実体を伴って姿を現す事が出来るものだ。しかし、あれだけの大きさのクラスの妖異を召喚するとなると、かなりの力を持った術者でも、およそ単独では無理な話である。何人もの術者が組織立って、計画的に術を施さなければ――――おそらくこれだけの妖異は召喚できないであろう。だから、それをした犯人は単独ではなく、かなり強い力を持った組織犯であろうと推測できる。
では、それほどの力を持った『組織犯』が、このタイミングで『ここ』にこの妖異を召喚する、その『意図』は何だ?
それが読み切れなくて、ハヤブサは困惑してしまう。
ここは確かに日本の『首都』である東京に間違いはないが、『都心』からはかなり離れた郊外だ。何か重要な施設や建物がある訳でもない。術者たちが、ここに妖異を召喚する『目的』と『メリット』が、いまいち見えてこないのだ。
全く『意図』が見えない強力すぎる『妖異』
強い違和感を覚える。
何故だろう。
激しく――――嫌な予感がした。
それにしてもあの『場所』が気になる。
龍が暴れているあの場所は
キョウジのアパートの近くなのではないか――――?
ハヤブサが『龍の首』に近づくにつれて、逃げ惑う人々の数は増え、道路は瓦礫とガラスが四散し、怒号と悲鳴と、車のクラクションが渦巻く。あちこちで煙が上がり、火事が発生している。人々の流れに逆らって走り続けていたハヤブサであるが、それは最早困難となり、彼はビルの壁や屋根を通路に選ばざるを得なかった。壁を走り、屋根から屋根へと飛び移り、ハヤブサは『龍の首』へと近づいて行く。
ところどころに怪我人が呻いて、動かぬ死体が転がっているのを、走りながら眼の端で捉えた。さながら、内戦地のような惨状――――ハヤブサは思わず、「ここは日本か?」と、疑いたくもなってしまう。
巨大な『龍の首』は、咆哮を上げながら火の玉を吐き散らし、無軌道に破壊活動を繰り返していた。
(キョウジやシュバルツは無事だろうか)
ハヤブサにとって今、唯一にして最大級の心配事はそれであった。
キョウジの傍にはシュバルツがついている。だから、大丈夫だと信じたい。
だが、シュバルツは『不死』であるが故に、キョウジの身を守るためならば、己の身を平気で投げ出してしまう傾向がある。キョウジの『死』が、自分の『死』に直結していると言う理由以上に、シュバルツはキョウジをとても大事に想っているから――――
心配だ。
無茶していないか。
怪我をしていないか。
とても――――心配だった。
(だが今は、あの『龍の首』をなんとかせねばならんか!)
ハヤブサは顔を上げ、走る速度を速める。
そう。この騒ぎの総ての元凶は、あの『龍』 それさえ仕留めれば、この一連の騒ぎも収まるはず。しかし、あの巨大な龍に対して向かっていく自分は刀一本。いささか無謀すぎるようにも思えた。
だがやらねば。
自分には――――戦える手段があるのだから。
それにもしもシュバルツが無事なら、戦っている自分に気づいて、合流してくるかもしれない。シュバルツは、そう言う奴だとハヤブサは思った。彼ならば、決して自分を独りで戦わせようとはしないだろう。
龍が放つ火の玉を避けながら、ハヤブサはひたすら龍との距離を縮めて行く。
背に背負った『龍剣』の柄に手をかけ、抜刀しようとした。だが、それをする前に――――ハヤブサの視界に1羽の隼の姿が飛び込んでくる。それは、キョウジの側に常に待機するよう、ハヤブサが命じていた鳥であった。
隼は、主であるハヤブサの姿を確認すると、甲高い声で一声、鋭く鳴いた。そのまま上空を何度か旋回すると、また、元来た方向へと頭を返す。まるでハヤブサに「ついて来い」と、言っているかのように。
(――――――!)
ハヤブサは、猛烈に嫌な予感に襲われる。
あの隼は、キョウジからの伝言を預かっていなかった。にも拘らず、あの鳥は自分を探していた。それは、おそらくあの鳥自身が、そうした方がいいと判断したからに他ならない。
(これは……キョウジの身に、何かあった……?)
キョウジの事だ。この非常事態に在っても、彼はパニックになったりするような人間ではない。もし彼自身があの隼に気づいているのであれば、彼は絶対に、何らかの方法で伝言をあの隼に託しているはずだった。この状況で、キョウジが自分に連絡を取らないなど、あり得ないからだ。
それをキョウジがしていなかった、と言う事は
キョウジの身に、それが出来ないだけの『何か』が
起きた可能性が―――――
「―――――ッ!」
ブン! と、頭を振って、ハヤブサはその考えを懸命に打ち消す。
キョウジの傍にはシュバルツが居る筈なのだ。キョウジが傷つけられようとするのを、シュバルツが黙って見ているはずがない。キョウジが傷を負う前に、シュバルツの方が、もっと酷い傷を負ってしまうに決まっている。それでもキョウジが身動きが取れなくなる、と、言う事は、二人ともが酷い傷を負っているとしか――――
違う。
そんな事は無い。
無い、と、信じたい。
悪い予感。
嫌なイメージ。
ハヤブサは、懸命にそれらを振り払いながら走る。
龍の忍者は今や、キョウジとシュバルツ、二人の無事を確認する事を、とにかく最優先事項にしていた。こうしている間にも、巨大な龍の首は暴れまわり、沢山の怪我人や死人が出ている事は分かっている。だから本来なら何を置いても、それを倒す事を最優先にするべきなのに。
だが例え、「私情に走っている」と、誹りを受けようとも、ハヤブサは二人の無事を確認せずには居られなかった。それほどまでに――――ハヤブサにとって、二人の存在はとても大事な物になっていたのだ。
(無事なのを……生きているかを、確認するだけだ。それさえ出来れば、俺は――――)
心おきなく『龍の忍者』の使命に戻れる。
だから
だから、お願いだ。
二人とも、どうか無事で――――
無事で、居てくれ。
隼に導かれるままに走るハヤブサは、いつしか龍が破壊しながら通った時に出来たと思われる、瓦礫の道の様な所に出てきていた。この辺りは最早、どこが家でどこが道路だったのかすら分からないほど、破壊の限りを尽くされていた。
瓦礫と煙と、物言わぬ骸が転がる。濃厚な『死』と『破壊』の匂いに満ちた世界。
ふと前方に、何かが動く気配を見つけて目を凝らす。
どうやら、人のようだ。それも、見知った革のロングコートを着て、見慣れたシルエットをしている――――
「シュバルツ!!」
ハヤブサは思わず大声でその名を呼び、無我夢中で走りだしていた。
(良かった。無事だった)
少し、安堵の息を漏らす。
当たり前だ。シュバルツは『不死』なのだから――――
頭ではそう分かっていても、やはり、彼の無事を確認できる事は、ハヤブサにとっては喜ばしい事だった。シュバルツもまた、腕の立つ忍びである。この状況で彼と合流出来れば、素直に心強い。
そして、シュバルツが『生きている』と言う事は、キョウジもまた『生きている』と言う事になる。キョウジの話によれば、二人の生死は連動しているはずなのだから――――
シュバルツの側に、自分を導くように飛んでいたあの隼も降り立っている。やはりあの隼も、自分をここに連れて来たかったのだと知る。きっと、キョウジが身動きが取れない状態になっているから、救援の手が必要だと感じたのだろう。
どちらにしろ、あの隼のおかげで二人をこうして発見できた。あいつには、後でお礼の餌をやらなければ――――と、思いつつ、ハヤブサはシュバルツの側に近づいて行って―――――
絶句した。
何故なら
シュバルツの『左腕』が、
『無かった』のだから――――
左肩から先を失くし、体内のメカの部分を露出させ、そこからバチバチッ、と、放電の音をさせている愛おしいヒト。少し歪な形になってしまったそのヒトが、ハヤブサが近づいてきた事にすら気づかずに、必死に、目の前に横たわる『キョウジ』の身体に呼びかけている。
「キョウジ……! キョウジ……ッ!」
ハヤブサは、そんなシュバルツに声をかけようとして―――――さらに、鈍器で殴られたような衝撃を受けた。
確かに、そこに横たわるのは『キョウジ』の身体。
だが、その身体には
首から上が―――――
『無かった』
シュバルツは必死に呼びかけている。
「キョウジ……! キョウジ……!」
キョウジ『だった』身体に向かって――――
(何を、やっているんだ。こいつは)
ハヤブサは、己が顔が引きつるのを感じる。
(動く訳無いだろう。そんなに呼びかけても――――)
「キョウジ……!」
シュバルツの右手が、キョウジの身体をゆすっている。
「キョウジ――――」
だが、キョウジ『だった』身体から、反応が返って来る事は最早無い。
当たり前だ。
そいつはもう――――
『死んで』いるのだから。
「……………ッ!」
ああ
首の無い、死体。
自分は、よく見た。
『見慣れている』
ただ、その『死体』の人間を、自分が詳しく知っていたか、いないか――――
違いは、ただそれだけだと、悟る。
たったそれだけの、違い。
なのに―――――
ハヤブサはいつしか、唇をきつく噛み締めていた。
どうして、こうも
目の前の光景を、受け入れ難く感じてしまうのだろう。
「キョウジ……! ああ……!」
左腕を失ったシュバルツの身体は、よく見ると、左足も膝から下が千切れかかっている。脇腹もえぐれ、露出したメカから放電音が響いている。そこまでもう、自分の身体がボロボロになっていると言うのに。
「どうして……! キョウジ……!」
シュバルツの瞳には、キョウジしか映っていなかった。哀しい程に。愚かなほどに。
愛おしいヒトは、尚もキョウジに呼びかけ続けている。
「キョウジ…! キョウジ…!」
震える声で。上ずった声で。
残った右手で身体をゆすり、呼びかけ続けている。
まるで、動かなくなった『親』を目の前にして、どうしたらいいのか分からなくなって――――途方に暮れてしまっている、幼子の様に。
やめろ。
そいつはもう死んでいるんだ。
もう――――どんなに呼びかけても
お前に応える事は、出来ないのに。
ああ――――
見ていられない。
ハヤブサは、天を仰ぐ。
自分は、『間に合わなかった』
二人の上に降りかかってしまった、悲劇に。
自分は、『間に合う事が出来なかった』のだと、ハヤブサは悟った。
「シュバルツ……」
ハヤブサはシュバルツの右側に座り、キョウジの身体をゆすり続けている彼の手に、そっと己が手を添える。
「ハ、ヤブサ……!」
ようやくハヤブサの存在に気付いたシュバルツが、縋るように見つめてきた。
「ハヤブサ……! キョウジが……! キョウジが――――」
蒼白な顔色のシュバルツに、ハヤブサは静かに頷き返した。そして、物言わぬキョウジの手に、そっと触れる。当たり前だがキョウジの手は――――もう、冷たくなっていた。
「……………」
ハヤブサはキョウジの左手から、彼がいつも身につけている腕時計を外す。その時計も、主と同じように壊れてしまっていて、もう、時を刻むのを止めていた。10時26分。キョウジが亡くなったのは、この時刻なのだと知る。
この時計は、キョウジの『形見』
だから持つべきは、シュバルツなのだとハヤブサは思った。
腕時計を外したキョウジの手を取って、そっと、彼の胸の前で手を交差させる。
今、自分が為すべき事は、死者を『死者』として丁重に、尊厳を以って扱う事なのだとハヤブサは思った。
そして、気づいてくれ。
受け入れてくれ、シュバルツ。
キョウジはもう――――死んでいるのだと言う事を。
『遺髪』も、キョウジの形見としてシュバルツに持たせてやりたいとハヤブサは願って――――キョウジの首から先を見る。だがそこにあるのは、キョウジの身体から流れ出た血溜まりだけだ。完全に消失してしまった、キョウジの頭。一体、どこへ行ったのだろう。
瓦礫に紛れて押し潰されてしまっているのか、それとも、完全にあの龍に食われてしまったのか――――
ハヤブサは、広大に広がる瓦礫の山を見て、ため息を吐く。
どちらにしろ、今キョウジの頭を探しだす事は、不可能に近そうだった。
それにしても、こんなに綺麗に首を刎ね飛ばされているのだから、キョウジはおそらく、苦しむ間すら無かったであろう。それが、せめてもの救いか――――と、思ってしまってから、ハヤブサは、ブン、と、首を振る。
(救いって――――『救い』って、なんだよ)
ハヤブサは、己で己を嘲笑う。
ここにはもう、『悲劇』しかないのに。
「シュバルツ……」
ハヤブサはシュバルツにそっと、キョウジの時計を差し出す。
「―――――ッ!」
だがシュバルツは、キョウジの時計から、まるで怯えるように一歩、身を引いた。
無理も無い、と、ハヤブサは思った。
受け入れられないのだろう。
いろいろと。
キョウジが、死んでしまった事も。
キョウジを――――自分が、『守れなかった』事も。
そして、何よりも――――
ドオオオオン!!
龍が暴れまわる衝撃の振動で、ハヤブサは、はっと、我に帰る。
本当なら、キョウジの骸を丁重に弔ってやりたい。だが今は、そんな時間も与えられてはなさそうだ。あの破壊と殺戮を繰り返している龍を、何とかしなければ。
(だが、シュバルツは―――――シュバルツは、どうする?)
ボロボロに傷ついて、今にも壊れそうな様相を湛えている愛おしいヒト。今このヒトを、独りにしてしまってはいけない、と感じる。それにここは、あの龍との距離が近すぎる。戦うにしても、逃げるにしても、ここからシュバルツを移動させなければならないと、ハヤブサは強く感じていた。
「シュバルツ」
ハヤブサはもう一度、シュバルツにキョウジの腕時計を差し出す。だが愛おしいヒトは、首を横に振るばかりで――――それを受け取ろうとしない。
ならば、とハヤブサは、今度はシュバルツに手を差し出す。「ここから移動しよう」と言う意思表示だ。だがシュバルツは、それにも頭を振った。
「い……や………。嫌、だ……!」
「シュバルツ……!」
「だ……だって……! キョウジが……! キョウジが……!」
「―――――!」
「キョウジが……ここに、いる……の…に……ッ!」
ハヤブサは、思わず歯噛みしてしまう。
いないだろう。
キョウジはここにはいない。
そこにあるのは、キョウジ『だった』骸だけだ。
キョウジは、もう居ない――――
何故、それが分からないんだ、シュバルツ。
いや……『分かりたくない』のか――――
それとも、自分の方が『キョウジの死』と言う物を、ことのほか冷静に受け止め過ぎているのか。
『死』に慣れ過ぎている自分を感じて、ハヤブサは少し、自分で自分に嫌気がさしてしまう。
グオオオオオ―――――!!
すぐ近くで暴れまわる圧倒的な破壊神。その口元が光を帯びる。
「シュバルツ!!」
ハヤブサが強引にシュバルツを抱えて横っとびに飛ぶのと、破壊神から光の弾が放たれるのが、ほぼ同時だった。
ドオオオオン!!
大音響と共に、二人が先ほどまで居た場所に光弾が命中し、爆ぜる。凄まじい勢いで周囲の瓦礫が巻き上げられ、熱風が二人を襲う。
「…………ッ!」
ハヤブサは風圧に煽られながらも、何とかシュバルツを庇いながら地面に着地した。そのまま間髪入れずに走りだす。この破壊神の前で、足を止めてしまうのは危険だと判断した。
だが、自分達の背後に上がる炎を見て、腕の中に居るシュバルツが暴れ出した。
「嫌だぁぁ!! キョウジッ!! キョウジ――――!!」
「シュバルツ!! 暴れるな!!」
ハヤブサは走りながら叫んで、シュバルツを落ち着かせようとするが、シュバルツは尚も、足掻く事を止めようとしない。
「下ろせっ!! 下ろしてくれ!! ハヤブサッ!!」
「何を馬鹿な事を言っているんだ!! 駄目だ!!」
「良いから下ろしてくれ!! どうせ、私は――――!!」
「――――ッ!」
ドンッ!!
ハヤブサは思わず足を止めて、シュバルツの鳩尾を殴りつけていた。愛おしいヒトは低く呻いて、そのまま意識を手放してしまう。
ハヤブサは、シュバルツの身体を抱えなおすと、再び走り始めていた。
(どうせ、私は――――!!)
そこから先の言葉は言わせたくなかったし、聞きたくも無かった。
もういい。
もう良いんだ、シュバルツ。
お前はもう、充分傷ついているのに。
ああ。
あの背後の炎の中には、キョウジの亡骸があると知る。
キョウジ
キョウジ
済まない。
お前を弔うことすら、してやれなくて――――
走り続けなければならないのに、変に視界が霞む。
悔しい。
悔しくて、情けなくて、仕方がない。
自分は結局――――誰ひとりとして、救えなかったのだから。
グルルルルル………。
龍が発する低い唸り声が、頭上から降ってくる。
目障りなのか。死滅した荒野の中で、『動いている』俺の姿が。
ハヤブサは、涙を振り払って走り続ける。
冗談じゃない。
この唐突に現れた破壊神なぞに
何でもかんでも、思い通りにされてたまるか――――!
顔を上げて、瓦礫の荒野を見据える。破壊神が、自分に向かって攻撃を仕掛けてくる気配を濃厚に感じとる。
どこを走れば良い?
この攻撃をしのぐために、自分はどこを走れば――――
ウオオオオオ―――――ッ!!
天地をつんざく咆哮と共に、破壊神が猛烈なスピードで自分に向かって迫ってきた。
「―――――ッ!」
ハヤブサは、咄嗟に崩れかけたビルらしき建物の中に横っとびに飛び込む。そのすぐ背後を、龍の鋭い牙が通り過ぎた。
ガンッ!!
龍の身体がビルの壁を掠めて、破壊する。飛び散った壁やガラスの破片が、床に倒れ込んだハヤブサたちの上に、ばらばらと降り注いできた。
「く…………!」
腹の下にシュバルツを抱きかかえるようにして庇いながら、ハヤブサはそれに耐える。既にボロボロなシュバルツの身体。これ以上、彼に傷を負わせたくは無かった。
グオオオオオ――――ッ!!
ガオオオオ――――ッ!!
外では破壊神が咆えて暴れまわっていた。
自分達を『仕留めた』と思って喜んでいるのか。
見失ってしまって腹立たしくて吠えているのか。
それとも――――自分達の存在すら、もう気にも留めていなくて、ひたすら破壊活動を続けているのか――――。
無軌道に暴れまわる破壊神の気持ちなぞ分かりたくもない。
こいつをここに召喚した奴らの思惑なぞも知った事ではない。
ただ――――絶対に、許せないと思った。
どれだけ殺した?
どれだけ、破壊したのだ。
よくもキョウジを………。
シュバルツを――――
(シュバルツ……)
ハヤブサは、腹の下で気を失っているシュバルツの顔を見る。
愛おしいヒトの頬には涙が光っていた。ハヤブサはその涙を、己の唇でそっと掬う。シュバルツから聞こえてくる規則正しい呼吸音に、ハヤブサは少し安心を覚えた。
死なない
『死ねない』
愛おしい、ヒト
想いを込めて、キスをする。
すまない。
すまない。
キョウジを……守って、やれなくて――――
(外は、どんな按配だ……?)
戦うにしても、逃げるにしても、外の様子を確認する必要がある。そう感じたハヤブサが、シュバルツから身を離した瞬間。
ドオン!!
「――――!?」
大音響と共に、いきなり地震の様な、激しい揺れに見舞われる。ハヤブサは咄嗟にシュバルツの上に身を投げ出すように覆いかぶさって、その揺れをしのいだ。ビルの崩れかけた壁や天井から、パラパラと礫が落ちてくる。腹の下にシュバルツを庇いながら、このビルが、崩れないで欲しいと一心に祈っていた。
やがて、揺れが収まり、辺りに静けさが訪れる。
ハヤブサはそれにほっとすると同時に、少し訝しくも思った。
妙だ。
静かすぎる。
あの『龍』は、どうなった?
まさか、消えてしまったのか?
(確かめなければ)
ハヤブサが強くそう感じて、窓から外の様子を見ようと、再びシュバルツから身を離した、刹那。
「う…………」
愛おしいヒトが、小さく身じろいで、瞳を開けた。どうやら先程の揺れのせいで、意識を覚醒させられてしまったらしい。
「シュバルツ」
ハヤブサは、外の様子を見に行く事をあきらめた。今は、シュバルツの方から目を離してはいけないと、強く感じていた。突然、己の半身とも言えるキョウジを失ってしまったシュバルツ。あらゆる意味で『危険だ』と思った。
「……………」
愛おしいヒトは、ハヤブサの呼び掛けには答えずに、無言で身を起こしている。
千切れかけていた左足は、もう元に戻ろうとしていた。抉れた脇腹の傷も、もうほとんど治りかけていた。失くしてしまった左腕は――――
「―――――」
少し力を入れると、ズボッと、音を立てて『生えて』来た。
シュバルツがその左手に「動け」と命じると、その手は思い通りに動く。しばらく確認するように、左手を握ったり開いたりしていたシュバルツであるが、やがて、「フ………」と、小さく笑いだした。
「シュバルツ……」
呼び掛けるハヤブサには答えず、目の前の愛おしいヒトは、尚も小さく笑い続ける。
「フ……ククク……」
「……………!」
妙に暗い響きを含んだその笑い声に、ハヤブサは背中に寒気が走るのを覚える。もう一度声をかけようと試みたが、咽の辺りで声が引っ掛かってしまって、巧く声が出せなかった。
「クク……アハハハハ……」
(何なのだろうな……。私は……。こんな事が出来るのに――――)
それは、シュバルツにとっては何もかもが突然だった。
あの『破壊神』とも言える『龍の首』は、なんの予兆も無く、本当に唐突にここに現れた。ただ、現れた場所が問題だった。そこは、キョウジのアパートの、ほぼ真下であったからだ。それがキョウジとシュバルツにとって、最大級の『不幸』であったと、言えた。
いきなり足元の床が抜け、家が破壊される。だがそれでもシュバルツは、咄嗟にキョウジを守らなければと、彼に向かって手を伸ばした。
自分の、すぐ近くに居たキョウジ。四散する壁と家具の破片の向こうに、驚いたようにこちらに振り向くキョウジの姿がある。そしてそれが――――シュバルツが見た、『生きている』キョウジの、最後の姿となってしまった。
グオオオオオッ!!
激しい轟音と共に、キョウジを庇おうとしたシュバルツの身体が、何者かに弾き飛ばされる。全身を襲う激しい痛みと共に、シュバルツの意識も混濁してしまって――――
気がついたときには、辺り一面瓦礫の山と化していた。
「う…………」
シュバルツは起き上がろうとして、自分の身体のバランスが、うまくとれない事に気づく。酷く激痛の走る左肩に手をやると、左肩から下の部位が、無くなってしまっている事に気付いた。立ち上がろうとして、左足も、千切れかかっている事に気づく。
「……………」
酷い大怪我をしている事になるのだが、シュバルツは、特に自分の身体の異常には頓着しなかった。どうせ、左足はくっつく。左腕だって、生えてくる。
それよりも、今はキョウジだ。キョウジを――――探さなければ。
ウオオオオ――――ッ!!
巨大な龍の首が暴れまわり、街を破壊しているのを、シュバルツは目の端で捉える。あれが家が壊れた原因かと、シュバルツは悟った。
「キョウジ!」
叫びながら、辺りを見回す。千切れかかった左足のせいで、うまく立つ事が出来ない。こういう時、シュバルツは少しイラつく。どうせ治るのだから、早くくっついてしまえば良いのにと、思う。
「キョウジ!」
もう一度呼びかけるシュバルツの声に、しかし、キョウジからの返事は無い。
「く………!」
立ち上がって、シュバルツはキョウジの姿を求めた。
「キョウジ!」
自分とキョウジの生死は連動している。キョウジが死ねば自分も死ぬ。しかし、自分は『生きて』いる。意識があり、動く事も出来る。だからきっと――――キョウジも『生きて』いる筈だ。
そう言う希望を持って、シュバルツはキョウジの名を呼び、探し続けた。だが、キョウジからの反応が、一向に返ってくる気配が無い。
「キョウジ!」
シュバルツは、少し焦り始める。
どうした? キョウジ。
何故、返事をしてくれない?
気を失ってしまっているのか。
それとも怪我をして、動けない状態になってしまっているのか――――
怪我をしているのなら、早く
早く、治療をしてやらないと――――
動きにくい身体に鞭を打って、シュバルツはキョウジを探し続ける。
やがて、瓦礫の隙間から、倒れている人間の足がのぞいているのをシュバルツは見つけた。
(キョウジの足だ!!)
そう認識した瞬間シュバルツは、弾かれるようにその足の側に走り寄っていた。
「キョウジ……! キョウジッ!!」
必死に呼びかけながら、キョウジの身体の上に幾重にも重なっている瓦礫を、シュバルツは懸命に取り除く。常人よりもはるかに力のあるシュバルツであるが、さすがに片手で瓦礫を取り除く作業は困難を極めた。キョウジの上から瓦礫をどけようと力を込めるたびに、傷つき、露出している身体のメカの部分から、バチバチッ! と、電気の音が漏れる。
身体を襲う激しい痛みに、シュバルツは、膝をつきそうになってしまう。
でも――――今、倒れる訳にはいかないと感じる。
瓦礫の間に埋もれてしまっているキョウジ。きっと、彼の方が痛い。彼の方が苦しい――――
死ぬな、キョウジ。
今、助けるから。
ゆっくりとだが確実に、キョウジの身体の上から瓦礫が取り除かれていく。膝が見え、腰が見えた。腹の上の瓦礫をどける。胸が見えた。後少し。
「キョウジ……!」
キョウジの上に乗っている、最後の瓦礫をどける。ああ良かった。これでキョウジを、助けられ―――――
だが現れたのは、首から上が無い、キョウジの身体。
「え……? キョウ、ジ……?」
シュバルツは激しく混乱する。自分が今、何を見ているのか、理解する事が出来ない。立っていられなくなった彼は、その場にペタン、と、座り込んでしまう。
(これは、何? これは一体、何だ?)
何を見ているのかが分からなくて、シュバルツは目の前に横たわる身体を、何度も凝視する。
(だって、これは、キョウジだろう? キョウジの、身体だろう?)
ナノニドウシテ―――――
首 カラ ウエ ガ、無イ ノ ?
「キョウジ……!」
呼び掛けて、その手に触れる。彼のその手は―――――酷く、冷たかった。
「キョウジ――――」
ドウシテ?
ネエ、ドウシテ?
ドウシテ キョウジ ハ 起キナイ ノ ?
理解不能。
理解、不能――――
「シュバルツ……」
誰かの手が、そっと自分に触れてくる。
(五月蝿い)
シュバルツはそれを無造作に払いのけていた。そのままふらり、と、立ち上がる。
何だ。どこも痛くない。
もう、立ち上がる事が出来るじゃないか。
「フフフ……あは……アハハ……」
誰かの、乾いた笑い声が響く。
可笑しかった。
可笑しくて可笑しくて――――仕方が無かった。
何故だ。
何故――――無くなったのが、私の首ではなかったのだ。
私の首ならば、後からいくらでも生えてくるのに。
どうして――――無くなったのが、キョウジの首なんだ。
キョウジの首は――――一つしか、無いのに。
それに、どうして―――――
どうして―――――私は、『生きて』いるんだ?
おかしい。
おかしいだろう。
キョウジが死ねば、私も死ぬはずだったのに。
オリジナルの『キョウジ』が死んで、紛い物である『私』が生きているはずがない。
それなのにどうして――――私はまだ、『生きて』いるんだ?
(ああ、そうか)
シュバルツは、乾いた頭で、不意に悟る。
(これは、きっと夢だ。私は、性質の悪い夢を、見ているんだ)
きっとそうだ。
そうでなければ――――
私が、『生きて』いる筈がない。
(覚めなければ)
そう。早く起きないと。
キョウジが、待っているかもしれないし。
目を、覚まさないと。
だけど、そのためには、どうすればいいのだろう。
(痛い目に遭えば、目が覚めるだろうか)
シュバルツは、懐に忍ばせている短刀を取り出す。鞘から刀身を抜き放つと、刃の白銀色の光が、シュバルツの瞳を打った。ああそうだ。これは『作業用』によく研いである得物だから――――
さぞかし、斬れる事だろう。
「馬鹿っ!! 止めろ!!」
叫び声と共に、誰かが短刀を持った腕を掴んでくる。
「邪魔をするな!!」
シュバルツはそれを、乱暴に振り払った。誰か知らないが、邪魔をしないで欲しい。
これが『夢』なら私は覚めたい。
それに、もしも本当にキョウジが死んでいると言うのなら――――
私は今度こそ、『死ねる』かもしれない。キョウジが死んでいるのに、私が『生きて』いるのは、おかしいんだ。だって、キョウジが死ねば、私も死ぬはず、なのだから。
「シュバルツ……ッ!」
渾身の力でシュバルツに振り払われたハヤブサは、踏ん張る事が出来ずに吹っ飛ばされてしまった。背中を壁に打ち付け、息が一瞬出来なくなる。
だけど、止まっている場合ではない、と、ハヤブサは感じる。ぐずぐずしていると、シュバルツが自傷行為を始めてしまうのが、目に見えていたからだ。
駄目だ。
止めろ、シュバルツ。
そんな事をして――――何になると言うのだ。
死ねないのに。
お前は、死ねないのに。
そんな事をしても、お前が無駄に苦しむだけだぞ。
「シュバルツ!!」
もう一度、ハヤブサはシュバルツの腕に掴みかかる。
「離せッ!!」
シュバルツは、容赦なく邪魔者を排除しようとする。ハヤブサは殴られて、また振り払われてしまった。振り払われた拍子に、シュバルツの短刀がハヤブサの頬を掠め、軽く切れてしまう。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは、切ない想いでシュバルツを見つめる。
ああ。
シュバルツにはきっと、目の前に居る俺の姿が、見えていない。
キョウジを失った哀しみが深すぎて。
自分を責める気持ちが、苛烈すぎて。
完全に心を閉ざしてしまっているシュバルツは、周りの状況が、全く見えていないのだ。
悔しい。
こんな時に、どうシュバルツに接すればいいのか。
その術を、知らない自分が――――
だけど、駄目だ。
シュバルツの身体が目の前で傷つけられる事を、ハヤブサは絶対に許したくは無かった。例えそれが、シュバルツ自身の手によるものであろうとも。
止めなければ。
このままでは、自分で自分を許せないシュバルツが、何度も死のうと試みて、でも、そのたびに死ねなくて――――結果として、何度も何度も自分を殺す行為に走ってしまう。
そんなのは嫌だ。
彼を、そんな風に独りで、苦しませるぐらいなら。
「シュバルツ!!」
ハヤブサはもう一度、シュバルツの腕に掴みかかる。
「また……! 邪魔をするなッ!!」
しかし、ハヤブサを『ハヤブサ』として認識していないシュバルツは、自分の行動を邪魔してくる相手を容赦なく殴りつけ、振り払おうとする。
「く………!」
だが今度は、ハヤブサもシュバルツの手を離さない。殴られても、踏ん張り続ける。そうしてしばらく忍者二人は、取っ組み合いの様な状態になった。
「シュバルツ……!」
そんな中、ハヤブサは懸命にシュバルツに呼びかける。だが、目の前の愛おしいヒトは、ハヤブサの方を見ようとはしない。シュバルツの空虚な眼差しには、何も写されていないのだと知る。
シュバルツが求めているのは、キョウジだけ。
キョウジだけが、今のシュバルツを救える。
キョウジだけが、今のシュバルツを癒す事が出来る。
だけど――――キョウジは、もう居ない。
分かっている。
言葉を届かすことすら出来ない俺では、シュバルツを救えない。
だけど、嫌だ。
シュバルツ、お前を
『独り』で苦しませる事だけは
絶対に――――!
「離せ……! 離せぇぇぇッ!!」
ドカッ!!
「く……う……!」
シュバルツに渾身の力で殴られたが故に、ハヤブサはよろめき、シュバルツの腕から手が離れてしまう。その隙を衝いて、愛おしいヒトが、自分に短刀を突き立てようとするから――――
「シュバルツ!!」
その短刀よりも早く、ハヤブサはシュバルツの懐に潜り込み、彼を強く抱きしめていた。
だが、突き立てられようとしていた短刀は、止まらない。シュバルツの短刀は、そのまま、ハヤブサの背中に浅く刺さってしまう。
「うぐ……ッ!」
「―――――!」
短刀で、確かに何かを刺した感触を得たのに、自分に痛みが無かった事と、自分を抱きしめてきたぬくもりに驚いて――――シュバルツは、ようやく動きを止めた。
「シュバルツ……」
動きを止めたシュバルツに、ハヤブサはもう一度、呼びかける。
「あ…………!」
「シュバルツ……!」
「あ………ハ……ヤ、ブ…サ……?」
「シュバルツ――――」
シュバルツが、ようやく自分を認識してくれた事に、ハヤブサは安堵のため息を漏らした。だけど、油断はできない。ハヤブサは、さらに強く、シュバルツを抱きしめる。
「な………何、を……!」
「……………」
「は…離せ……!」
「嫌だ」
「ハヤブサ……ッ!」
ハヤブサの強引ともいえる抱擁に、シュバルツは戸惑ってしまう。
彼の抱擁から、ぬくもりが伝わってくる。
だが、止めて欲しいと、シュバルツは思った。
自分は、こんな風に優しくされていい存在なんかじゃない。
キョウジを、守る事が出来なかった自分は、裁きを受けるべきで、罰せられるべきで、今ここに、存在していてはいけないのだ。
消えなければいけない。
消えなければ――――
「シュバルツ……」
抱きしめている自分を『ハヤブサ』と認識し、動きを止めたシュバルツ。しかし、彼の右手には短刀が握り込まれ、ハヤブサの背に――――シュバルツ自身に向けられたままだ。シュバルツはまだ、自分で自分を許そうとはしていない。今自分が離れたら、たちどころに彼は自分を刺してしまうだろう。
駄目だ。
シュバルツの自傷行為には『終わり』が来ない。死ねないから――――無限ループの様に続いてしまって、終われないんだ。
そこまでの苦しみを、お前が味わう必要はない。お前はもう、充分失って、苦しんで、哀しんでいるのだから。
あの時、お前がキョウジの側に居た、と、言うのなら。
キョウジを守ろうとしなかった筈がない。
守ろうとしたのだろう。
手を、伸ばしたのだろう。
現にお前は――――大怪我をしていたではないか。
そんなお前を、『守ってくれなかった』と、キョウジが恨んでいるとでも思うのか?
そんな風にお前が苦しむ事を――――キョウジが望んでいると思うのか?
違うだろう?
キョウジの『望み』は――――そうじゃ無いだろう?
「ハヤブサ……! 離れろ……!」
シュバルツから低い声で要求される。それにハヤブサは、頭を振った。
「嫌だ」
「ハヤブサ……ッ!」
短刀を握りしめながら、シュバルツは辟易する。この短刀は、自分に刺したい。なのに、このままでは――――ハヤブサの身体が邪魔で、刺す事が出来ない。
何故、邪魔をする?
何故、こんな事をするのだ、ハヤブサ。
キョウジを守れなかった私にはもう、存在意義が無い。
消えなければ。罪をかぶらなければ。罰を、咎を与えられなければならない。
オリジナルが死んで、紛い物が生きていてはいけない。
消えたいんだ。
邪魔を、しないでくれ……!
シュバルツは、もう一度要求する。
「退け」
「嫌だ」
「ハヤブサ…! どうして―――!」
自分を強く抱きしめながら、首を横に振り続ける龍の忍者に、シュバルツは困惑してしまう。
「どいてくれ! ハヤブサッ!!」
「嫌だ」
「どけっ!! 退かないと―――!!」
シュバルツは、短刀を振りあげた。脅すつもり――――でも、かなり殺気を込めた。ハヤブサに、自分から離れて欲しかったから。
「シュバルツ……」
だが、ハヤブサは、短刀を振りあげるシュバルツを、ますます強く抱きしめてくる。
「……刺すのか…?」
酷く穏やかな声で、ハヤブサに問われた。
「―――――ッ!」
シュバルツは、咄嗟に答えを返す事が出来ない。刺したいのはハヤブサではなく、自分自身なのだから。だけど、このまま退いてくれないと言うのなら、間違ってハヤブサの身体を刺してしまうかもしれない。
自分でも、酷く愚かな事をしていると、シュバルツは頭の隅でちらりと思う。
だけど―――もう、どうしようもない。
自分でも、どうしても自分が許せないのだから。
こんな自分に、もう優しくしないで欲しい。
放っておいて欲しい、と、シュバルツは願っていた。
「……………」
ハヤブサは、短刀を振りあげたまま震えるシュバルツの身体に密着しながら、瞳を閉じて、口を開いた。
「……いいぞ。刺せ。俺を、刺せ」
「な――――!」
絶句して、息を飲むシュバルツに、ハヤブサは更にたたみかけてくる。
「俺は……構わない。そのまま、刺せ」
「な、何を……!」
「シュバルツ……」
ハヤブサは、願う。
俺は、止めたい。
お前が、自分で自分を傷つける事を。
死ねなくて、無限地獄の様なループの中で、苦しみのたうつのを。
止めさせたいんだ。
だけど、どう言えば止まるのか。
どうすれば、お前にそれを止めさせる事が出来るのか――――
いくら考えても、自分にはその『手段』が無い事に気づいてしまう。
それほどまでに、シュバルツが負った傷も絶望も、深いものだと分かってしまうから。
「身体を繋げた」と、言っても、まだシュバルツと知り合ってから、そんなに歳月も経っていない俺。
所詮は、『赤の他人』――――シュバルツとキョウジの間に流れていた濃密な『時間』と『絆』には、まだ遠く及んでいないのだと思い知る。現に、シュバルツが苦しんでいる肝心な時に、俺の『言葉』はなんの力も持たないのだから。
「愛している」
そう言った所で、今のシュバルツを救う事など出来ない。哀しいけれど、それだけは分かる。
ならば、せめて。
せめて――――
「……もしも、『キョウジを守れなかった罪』が、罰せられる必要がある、と、言うのなら………」
「―――――ッ!」
ビクッ! と、硬直するシュバルツの身体。ハヤブサは構わず続けた。
「……俺だって、『同罪』だ。俺だって……キョウジを、守れなかった……」
「な――――! 何を……!」
ハヤブサの言葉に激しく動揺してしまうシュバルツ。その身体が、小刻みに震える。
「何を……言っているんだ、お前は……!」
ハヤブサの言っている事を、『理解したくない』
そう思ってしまった。
だから――――
「勝手な事を言うな!! キョウジの事は、お前には関係ないだろう!?」
酷い暴言を吐いてしまう。だけど、ハヤブサは動じなかった。
「……そうだな。きっと、俺の気持ちは、お前のキョウジを想う気持ちに比べたら、はるかに『軽い』………」
苦笑しながら、そう言葉を紡ぐ。シュバルツに傷つけられたがっている自分は、今の彼の言葉すら、『ぬるい』と、感じてしまっていた。
「だが……俺だって、キョウジの事を守りたい、と、願っていた……。それは、真実(ほんとう)だ……」
そう。稀有な頭脳を持ちながら、多くを望まず、いつもにこにこと笑っていた穏やかな青年。シュバルツを、この世に生み出してくれた人。自分にとっても、大事な人だった。守りたい、と、願った。
「だが……守れなかった……」
「ハヤブサ……!」
「キョウジの命が消えゆく瞬間……俺は、その場に居ることすら、出来なかったのだから……」
壊れたキョウジの時計が指していた10時26分。俺は、おそらく電車の中に居た。
シュバルツがすぐ近くに居て、それでも、守り切れなかったキョウジ。俺が近くに居たからと言って、状況がそう変ったとも思えないが――――。
それでも、考えてしまう。
もしかしたら
もしかしたら――――
何かを、変える事が出来たのではないかと。
あの時、少し余裕を持たせて、帰りの飛行機を一本遅らせなければ。
里に行こうとせず、シュバルツの顔を見に、素直にキョウジの家に足を運んでいれば。
もしかしたら、『運命』を変えられたかもしれない。
キョウジが生き永らえて、シュバルツが悲しまない『未来』も、あったかもしれないんだ。
こんな『たら、れば』などと、未練たらしく思っても仕方が無いのかもしれないけれど――――
「俺にも『罪』がある。お前と、『同じ罪』が―――」
「…………ッ!」
キョウジを、守れなかった『罪』
お前を、悲しませてしまった『罪』
絶望するお前を、救えない『罪』
もしかしたら、俺の方が罪深いのかもしれない。
「だから、シュバルツ……。お前が、自分の『罪』を許せない、と言うのなら……」
「……………」
シュバルツから言葉は返ってこない。だがハヤブサは、構わず続けた。
「お前と同じ『罪』を持つ俺を……どうか、許さないで」
「―――――!」
「お前が自分に下そうとしている『裁き』を……どうか、俺にも下して、くれ……」
そう言ってハヤブサは、瞳を閉じ、シュバルツの身体をぎゅっ、と、抱きしめる。
俺に、お前を救う術が何も無いと言うのなら。
せめて
せめて、お前と同じ『罪』を、俺も被ろう。
お前と同じ『苦しみ』を、俺も味わおう。
尤も、俺は『不死』ではないから、一度しかその『苦しみ』を、味わうことが出来ないけれど。
簡単に死んでやる気は無い。俺は命ある限り、お前を抱きしめ続ける。だから、一思いには、殺さないで。1分でも1秒でも長く――――お前を抱きしめさせてくれ。
これは、酷く自己満足で勝手な『想い』だと、充分分かっている。
こんな事を言った所で、やった所で、真にシュバルツの苦しみを救える訳でもない。シュバルツの自傷行為も、もしかしたら、止めさせられないかもしれない。
だけど駄目なんだ。
目の前でシュバルツが傷つき、のたうつのだと分かっていて――――それを黙って見ているなんて、俺にはどうしても我慢が出来ない。耐えられないんだ。
もしも、俺にそんなシュバルツを止める力が無いと言うのなら――――
もう、こんな『俺』など要らない。今すぐ死んだ方が、よほどマシだと本気で思った。
シュバルツ
シュバルツ
すまない。
こんなことしか、言ってやれなくて。してやれなくて――――
もっと、気の利いた事が言える人間であればよかった。
もっと、ちゃんと、シュバルツの事を慰められる人間であればよかった。
今ここで、お前を抱きしめている俺が、『キョウジ』であれば、よかったのに。
キョウジの代わりに、俺が死ねばよかったんだ。
そうすれば、今お前が感じている苦しみも絶望も――――少しは違った物に、なったのだろうか。
「シュバルツ……」
(愛している………)
この言葉を言った所でシュバルツの救いにはならない。だから、言わない。言えない。だけど――――だから、せめて、『想い』を込めて、ハヤブサはシュバルツの身体を抱きしめる。
ああ
もしも、このままシュバルツに殺されるのなら俺は――――
『本望』だ。
「…………ッ!」
シュバルツの、短刀を持つ手が震える。
ハヤブサは、知らない。
シュバルツの身体を構成している『DG細胞』は、人の『ココロ』に感応する細胞。故に、DG細胞は、その『能力(ちから)』で、ハヤブサの心の声を拾って、シュバルツに聞かせてしまうのだ、と、言う事を。
(愛シテイル………)
自分を抱きしめているハヤブサの身体から流れ込んでくる、強い『想い』
愛シテイル
愛シテイル
愛シテイル
「何で………ッ!」
キョウジを守れなかった自分は、『罰』を与えられなければならないのに。
ハヤブサから与えられる温もりに動揺する。
降り注いでくる『愛の言葉』に辟易してしまう。
どうして
どうして
どうしてハヤブサが、私の『罪』を被らなければならないのだ。お前は――――何も悪くないのに。
ハヤブサは私にお前を『刺せ』と言う。
どうして
刺せる訳、ない。
刺せる訳、ないじゃないか。
そんなお前を―――――
「……あ………!」
いつしかシュバルツは、大粒の涙を零していた。振り上げた短刀を持っていられなくなって、手から滑り落ちて行ってしまう。カラン、と、乾いた音を立てて、短刀がハヤブサの足元の床に転がった。
「シュバルツ……?」
少し驚いて顔を上げるハヤブサの視界に、シュバルツの泣き顔が、飛び込んでくる。
「どうして……! どうして……ッ!」
大粒の涙を零す、愛おしいヒト。
「シュバルツ……」
静かに見つめるハヤブサの目の前で、立っていられなくなってしまったのか、シュバルツの身体は膝から崩折れて行く。ハヤブサもシュバルツの身体を支えながら、ゆっくりと彼と一緒に膝をついた。
「キョウジ……ッ! あ……あ……!」
床に、パタっ、パタっ、と、音を立てて、シュバルツの涙が落ちる。ハヤブサがそんなシュバルツをあやすように、彼の髪を優しく撫でた、刹那。
「キョウジ……ッ!! うわああああ―――――ッ!!」
シュバルツが泣き叫びながら、ハヤブサの胸に飛び込んできた。そのまま彼は、ハヤブサの胸にしがみつく様にして、慟哭する。
「シュバルツ……!」
彼の悲痛すぎる泣き声に、ハヤブサの胸もいたむ。だけど一方で「これで良いんだ」と、ハヤブサは思っていた。そう――――人の『死』は、ちゃんと哀しむ方がいい。暗く笑いながら刀を振り上げ、自分で自分を傷つけようとするよりも。こうやって泣いた方が、余程『健全』なのだ、と、ハヤブサは感じていた。
「キョウジ……ッ! ああ……! キョウジ……ッ!」
胸の中のシュバルツは震え、泣き叫び続ける。
悔しいのだろう。
無念なのだろう。
目の前に居たのに、守れなかったキョウジ。彼の伸ばした手は、『災厄』によって食い千切られてしまった。キョウジの首と共に――――
どうして
どうして
腕の中の愛おしいヒトは、泣きながら問い続けている。
どうして 届かなかった
どうして 間に合わなかった
どうして………『私』は、生きているんだ?
「シュバルツ……!」
シュバルツのその問いに返す言葉を、ハヤブサは持たない。
軽く刺された背中よりも
シュバルツに縋る様に掴まれている腕が、
涙を受け止め続けている胸が―――――痛い。
悲痛すぎる慟哭。
良いんだ、シュバルツ。
存分に泣け。
存分に、喚け。
お前が知ってしまった『絶望』は、『孤独』は、『哀しみ』は――――
もう、誰にも救えはしないから。
せめて、俺は傍に居る。
お前を癒せなくても、救えなくても。
せめて、俺は、傍に居るから――――
だから……キョウジを想い続けるお前の側に居続ける事を、どうか。
どうか、許して欲しい―――――
ハヤブサはシュバルツの髪や背を、優しく撫で続ける。
「お前は『独り』じゃないんだ」
「俺が、傍に居る」
そう伝えたくて、彼はそれをし続けた。
(キョウジ……)
涙にくれるシュバルツを抱きしめながら、ハヤブサは『キョウジ』に想いを馳せる。
こんな事を想ってしまっては不謹慎なのだろうが――――羨ましい。
こんなに、シュバルツに想ってもらえて。
俺が、死んでもシュバルツは
こんなに、泣いてくれるのだろうか――――?
――――あなたと話すの、私は割と好きだよ………。
ふと、ハヤブサの脳裏に、優しい声が響く。
(キョウジの声だ)
ハヤブサはすぐに分かった。
今自分は、キョウジとの記憶を思い出しているのだと知る。
「何故?」
不思議に思って問い返す自分に、キョウジは屈託のない笑みを見せた。
「何故なんだろうな……。自分でも、うまくは言えないんだけど」
そう言いながらキョウジは、缶コーヒーをすすっている。彼はブラックを、よく好んで飲んでいた。
「……きっと、『安心』するんだ」
「……安心?」
意外な言葉に少し驚いて問い返すと、キョウジは少し困ったような笑みを浮かべた。
「うん。貴方と話していると、強く感じる事が出来るんだ……。『ああ、私とシュバルツは、やっぱり違うんだな』って………」
「キョウジ……」
「変な言い方だけど、『ちゃんと別々なんだ』と感じられて、安心するんだよ」
そう言った後キョウジは、缶コーヒーを一気に飲み干した。
「……そういうものか?」
その感覚がいまいち理解できないハヤブサが首をかしげると、キョウジも苦笑する。
「そう言うもんだよ。外見もほとんど一緒だし、考え方も、ほぼ似ているし――――大学や研究所に、私とシュバルツが入れ替わって顔を出しても、気づかれる事なんてまずないしね」
「……それはそいつらが鈍感過ぎるんだ」
ぶっきらぼうにそう言い放つハヤブサに、キョウジも声を立てて笑う。
「だから……私とシュバルツは『違う』って言ってくれる人の存在って、すごく貴重だよ」
「う……そうか?」
なんだかものすごく褒められたように感じられてしまって、ハヤブサは少し、照れてしまう。そんなハヤブサにキョウジはにこっと微笑みかけると、凭れかかっていた壁から、身を起こした。
「……だから、これからもシュバルツや私に会いに来てよ。多少、シュバルツに冷たくされようとも、めげずにさ」
「うぐ……ッ!」
キョウジの言葉にハヤブサは嫌な事を思い出して、頭を抱えてしまう。シュバルツに冷たくされると、地味に凹んでしまうハヤブサなのである。
「……どうしてシュバルツは……」
ブツブツと小声で愚痴りながら、キョウジの前でよく地面に『の』の字を書いていた。キョウジは、そんな俺を否定せずに優しく見守ってくれていた。キョウジは、俺の事を『貴重だ』と、言ってくれていたが、俺からしてみれば、キョウジの方が余程『貴重だ』と思った。自分が、気兼ねなく情けない姿を見せる事が出来る、数少ない『友人』であったのだから。
(キョウジ………)
優しかったキョウジ。
よく笑っていたキョウジ。
好きだった。
シュバルツとはまた違った意味で、大好きな人だった。
『忍者』にしては、甘すぎるシュバルツの性格。
この性格は、キョウジの物だ。
このシュバルツに『キョウジの魂』が入っていなければ俺は――――
ここまでシュバルツに惹かれる事は、無かっただろう。
この『魂』だから
この『ココロ』だから
俺は――――
「キョウジ……ッ!」
いつしかハヤブサも、シュバルツを抱きしめながら涙を流していた。
大事だった。
守りたいと願った。
まさかこんなに早く
こんなにあっさりと
失ってしまうとは―――――思ってもいなくて。
「ふ……! う……!」
堪え切れぬ、嗚咽が漏れる。シュバルツを抱きしめている手に、知らず力が入ってしまう。そしてそれは、当然腕の中で泣いている愛おしいヒトにも伝わってしまって。
「…………?」
ハヤブサの腕の震えに気がついたシュバルツが顔を上げると、はらはらと、静かに涙を落としている彼の姿が飛び込んでくる。
「あ…………!」
ハヤブサのその姿を見た瞬間、シュバルツも悟ってしまう。
『同じなのだ』と
自分とハヤブサは今
同じ『喪失』の哀しみを抱えている――――
だからだろうか。
願ってしまった。
ハヤブサを、慰めたい。
それもある。
でも、それ以上に
「……………」
シュバルツは、自ら動いてハヤブサの唇を求める。
最初は触れ合う程度に浅く。
そして―――――
「ん………ッ!」
呼吸もできなくなるほど、深く。
深く、その唇を求めた。
「シュバルツ……?」
いきなり唇を求められ、茫然と見つめ返すハヤブサの視界に、潤んだ瞳のシュバルツの姿が飛び込んでくる。
「ハヤブサ……」
シュバルツの瞳が、唇が――――ハヤブサに訴える。
『温モリ』ガ、 欲シ イ
キョウジを失ったばかりで、こんな事を想ってしまうのは不謹慎なのかもしれない。
もしかしたら、キョウジを失ってしまった喪失感に耐えられなくて、ハヤブサからもたらされる温もりに逃げ込もうとしているだけなのかもしれない。その為に、自分の事を『好きだ』と言うハヤブサの気持ちを、利用しようとしている風にも思える。
だけど今は、その温もりが、欲しかった。
例えそれが、刹那的な物であったとしても――――
今だけでいい。
『独りじゃないのだ』と、感じたかった。
同じ『哀しみ』を背負ってくれる人がいるのだと――――
『誤解』でもいい。
そう思い込みたかった。
この『孤独』を、ハヤブサと分かち合いたかった。
一瞬でいい。温めて欲しい、と、願った。
同じ『喪失の哀しみ』故に、涙を流しているお前に――――
ハヤブサ。お前は……
こんな時に、こんな風に、お前を求めてしまう私を
軽蔑、するか………?
ダンッ!!
「―――――!」
気がつけばハヤブサに押し倒されていたから、シュバルツは呆然としてしまう。そんなシュバルツのすぐ目の前に、ハヤブサの切なそうな顔があった。
「シュバルツ……!」
明らかに自分を求めてきている愛おしいヒトの様相に、ハヤブサは少し戸惑う。
先程から明らかにあの『龍』の気配が消えて――――静まりかえっている外の様子も気にかかる。
だが――――
愛おしいヒトが自分を求めてきているのに、それを回避する術なんて、あいにく持ち合わせてなどいなかった。お前が求めてくれるのなら、俺はいつでも構わない。
しかし
「いいのか……?」
その頬を撫でながら、問う。
キョウジの『死』故の哀しみに包まれている今のシュバルツの心は、隙だらけだ。
そこにつけ込むように俺が抱いてしまっても、良いのだろうか?
「…………」
シュバルツは、瞳を閉じて、頬を撫でるハヤブサの手に己の手を添えると、それを慈しむように頬ずりをする。それだけで――――ハヤブサにはもう、充分すぎた。
「シュバルツ!!」
「んう……っ!」
舌で愛おしいヒトの口腔を深く弄りながら、ハヤブサは慣れた手つきでシュバルツの服を乱して行く。現れた白い肌に、優しく唇を落としてやると、シュバルツの身体がビクン、と、跳ねた。
「あ……! ハヤブサぁ……!」
その瞳から、涙が飛び散っている。
震えながら俺に身体を開いて行く、愛おしいヒト。その肌のあちらこちらを愛撫し、口付けを落としてやると、堪らない、と、言ったふうに、ギュッ、と、抱きしめ返されてきた。
「済まない………」
耳元で、小さくそう謝られる。こんな時に―――求めてしまってすまない、と、何度も何度も。
「謝るな……」
ハヤブサはそれを否定しながら愛撫を進めた。
俺は構わない。
構わないんだ、シュバルツ。
俺への良心の呵責なんて、いちいち感じなくてもいい。
お前が必要とするのなら――――『俺』などいくらでもお前にやる。お前が立って歩いて行くために、それが必要だと言うのなら。
だから、もっと求めてくれ。
乱れてくれ。
どうか――――我慢、しないで。
「キョウジ……! あ……ッ!」
そこまで叫んでしまってから、シュバルツがはっと我に帰る。
「シュバルツ……」
静かに呼びかけるハヤブサの下で、シュバルツががたがたと震えだした。
「あ……! 私、は……!」
「いい。気にするな」
ハヤブサはそう言いながら、シュバルツの頬に優しくキスを落とす。
「で、でも……!」
シュバルツは激しく動揺する。抱かれながら、目の前に居る人と違う人間の名を叫んでしまうなんて――――こんなの、規約(ルール)違反だ。
「大丈夫だ、シュバルツ。俺は分かっている。分かっているから……」
耳を愛撫しながら、囁く。
お前がキョウジをこれからも想い続けてしまう事、俺は分かっているから。
「あ…………」
「だから、もっと乱れて。ちゃんと叫んで」
胸の頂に進んできた指が、そこをくにくにと弄ぶ。
「は、あっ! ん…! あ……!」
「堪えないで。何もかも――――」
もう片方の手で、シュバルツ自身を刺激してやる。
「ああっ! あ…! や……! あ……!」
ハヤブサの手の動きに合わせて、揺らめいてしまうシュバルツの腰。相変わらず、素直で、淫らで、可愛らしいヒトだと、ハヤブサは思った。
「挿入るぞ……」
想いを込めて、シュバルツに繋がる。優しく、だが深く――――その身体を抉った。
「あああっ! 深……! 深……い……ッ!」
慣れない体勢と深度に、悲鳴を上げる愛おしいヒト。だがハヤブサはその姿勢のまま、さらに深くシュバルツを貫いた。「お前は独りじゃない。俺が側に居る」その事を――――彼に分かってもらいたくて。
貫いた。
何度も
何度も
「あああっ! ああっ! ああああ……!」
奥深い刺激に、叫びっぱなしになってしまう愛おしいヒト。ビュル……と、音を立ててシュバルツが果てるのが見えた。だけど、止めてなどやらない。ハヤブサは更に、その行為を続ける。
俺はお前が欲しいんだ。
もっと
もっと
身体をゆすられながら、ハヤブサ、ハヤブサ、と、愛おしいヒトが何度も名を叫ぶ。だけど、その中に時折『キョウジ』が混じる。そのたびにハヤブサは、その唇に優しく触れた。
「愛してる……」
「は……! あ………ッ!」
そう。素直に叫んで。堪えないで。
キョウジを想い続けるお前を――――俺は、愛すから。
「ああっ! も……! ハヤブサ……ッ!」
腕の中で愛おしいヒトが仰け反り、快楽の限界を訴える。
それでもまだ――――
まだ、止めてなどやらない。
こんなものではないのだろう?
お前が今、感じている『孤独』は――――こんな物では、埋まらないのだろう?
欲しがってくれ。
もっと
もっと
(今だけ、どうか――――邪魔しないでくれ)
静かな外の気配に、ハヤブサは祈る。
シュバルツを、満たしきるまでは、どうか。
このヒトが、『孤独』と『絶望』を忘れ去る刹那のために――――どうか。
少しでもこの時間が長く続いて欲しいと、ハヤブサは祈った。
「うあっ! ああっ!! あああっ!!」
ゆすられ続ける身体と、悲鳴のような嬌声。
結局シュバルツが意識を手放すまで――――その行為は続けられていたのだった。
第2章

「…………!」
見慣れぬ景色に少し驚いて、シュバルツは飛び起きる。身体の上に被せられていたロングコートがずれて、肌が露出する。どうして自分が服を着ていないのかシュバルツは一瞬考えて、その経緯を思い出して――――複雑な感情に襲われた。一体自分は泣けばいいのか、恥ずかしがればいいのか。こんな時……どんな表情をすればいいと言うのだろう。
(そう言えば、ハヤブサは?)
先程まで自分を強く愛してくれたハヤブサの姿が見えなくて、シュバルツは思わずその姿を求めてしまう。
「ハヤブサ……?」
小声で呼び掛けると、すぐに返事が返ってきた。
「気がついたか?」
「――――!」
声のする方にシュバルツが目を凝らすと、崩れかけた窓のすぐ近くの壁際に、龍の忍者の姿があった。
ハヤブサ、と、シュバルツが声をかけようとする前に、ハヤブサが口を開いた。
「起きられるか?」
ハヤブサの問いにシュバルツは素直に頷く。そろり、と身を起して彼は「あ………!」と、声を上げてしまう。身体の中から先ほどの『名残り』が流れ出てきたからだ。
「大丈夫か?」
「ちょ、ちょっと待ってくれ……!」
顔を赤らめながら恥じらう愛おしいヒトの様子に、思わずハヤブサの頬も緩んでしまう。もう何度も味わっている感覚のはずなのに、その度々に初々しい反応を返してくる彼の姿が可愛らしくてたまらない。
(もうそろそろ、『現実』に引き戻しても、大丈夫だろうか)
いつもどおり服を着ているように見えるシュバルツの姿に、ハヤブサは思う。本当ならもっとゆっくり、傷ついたシュバルツの心を癒してやりたい。だが今は――――
「……今の状況を、話しても――――大丈夫か?」
ハヤブサは、シュバルツに問う。『恋人』としてではなく『龍の忍者』として。そうしなければならないほど、今は『非常事態』だった。
「――――!」
ハヤブサの言葉に、ロングコートの袖に手を通していたシュバルツの動きが一瞬止まる。だが、彼の真剣味を帯びた眼差しに、シュバルツもすぐに「ああ」と、頷き返した。キョウジを失って混乱していたシュバルツではあるが、あれだけの事が起こったのだ。あの龍の首の件も踏まえて、今が楽観できるような事態ではない、と言う事は、何となく理解できていた。
「まず、あの『龍の首』だが――――」
シュバルツの様子を伺いながら、ハヤブサは話を切りだす。キョウジの命を奪い、シュバルツを傷つけた最大の元凶である『龍の首』――――出来れば、避けて通りたいところであろう。
だがハヤブサは、敢えてこれを一番に話す事を選んだ。
あれだけの『災厄』を撒き散らして消えた『龍の首』
自分はあれを許す事が出来ないし、討たねばならないと思っている。その為に今から、あの龍の後を追うつもりだった。
だけど、シュバルツを独り置いて行くことも、今のハヤブサには出来かねた。
だから――――
シュバルツにも、あの龍の首に共に立ち向かって欲しい、と、ハヤブサは願っていた。共に闘えるのならば、こんなに心強い事は無いと、素直に思う。
だが一方で、それを無理強いする訳にもいかない、とも思っていた。あの『龍の首』は、シュバルツにとっては最大級のトラウマと言ってもいい物に、なってしまっているだろうから。『立ち向かえない』と言うのなら、それもまた已む無し、と、思わざるを得ない。
その場合は、戦うのは、自分独りで充分。ただ、傍には居て欲しい、と、願う。
「彼を、独りにはしない」
そう、心の中で誓っている、自分のエゴイスティックな願い故に。
「…………!」
愛おしいヒトは、一瞬表情を強張らせたが、またすぐに平静を取り戻した。あの『龍の首』を話題にしても、冷静に話が出来そうな彼の様子に、ハヤブサはとりあえず胸を撫で下ろす。このまま話を進めても問題ないと判断したハヤブサは、口を開いた。
「どういう訳か、今は消えてしまっているようだ」
「……消えた?」
怪訝そうな顔をして、鸚鵡返しに返事してくるシュバルツに、ハヤブサは頷く。
「外の気配を探ってみろ。静かなものだろう?」
「そう言えば………!」
ハヤブサに指摘されて、シュバルツも初めて、あの龍の存在が消えている事に気づく。そして、キョウジが死んでから、ハヤブサに抱かれるまでの間の自分の行動の記憶が、かなり曖昧になってしまっている事にも。
もしかして自分は、その間にハヤブサにかなり守られて、相当迷惑をかけてしまっているのではないだろうか。
「ハヤブサ………!」
「ん?」
「ハヤブサ……! 私は――――」
シュバルツの態度と眼差しから、彼が自分に要らない気を回してきそうな気配を感じたハヤブサは、やんわりとそれを押しとどめた。
「おっと……謝るのも、礼を言うのも、まだ早いぞシュバルツ。話はまだ、終わってはいない」
「しかし……ハヤブサ……!」
「………あんまりしつこいと、もう1回抱くぞ?」
「う………!」
頬を赤らめながら、言葉を詰まらせる愛おしいヒト。あまりにも可愛らしいから、真面目にもう一度触れたくなってしまって、ハヤブサは慌てて頭をふった。今はそれどころではない、と、必死に自分に言い聞かせてから、改めてハヤブサは口を開く。
「お前の『弟』や、マスターアジアとも、連絡が取れない――――」
「ドモン……!」
不意に思い出してしまった弟の存在に、シュバルツの身体がビクッと、硬直する。
そうだった。ドモン……。
ドモンに、キョウジが亡くなってしまった事を、伝えなければと思う。
あの兄思いの弟は、どうするだろう。
キョウジを守り切れなかった自分を、詰るだろうか。責めるだろうか。
「許せない」
そう、思うだろうか――――
(いっそ、その方がいいかもしれないな……。すっきりして……)
いつしかシュバルツの面に、自嘲的な笑みが浮かぶ。
「キョウジを守る」と言う最低限の役目を果たせなかった自分は、そうやって詰られ抜いて然るべき存在なのだから。
「……………」
『弟』の存在を匂わせたことで、シュバルツが落ち込んで行くのを、ハヤブサは黙って見つめていた。ある程度そうなるだろうと予測はついていたので、特段驚きもしない。大方シュバルツは、また、自分で自分を責めてしまっているのだろうと、容易に想像がつく。あれだけの事があったのだ。すぐに立ち直れと言っても、それは無理な話だ。
(だが、あの弟は、お前を責めたりはしないと思うぞ、シュバルツ……)
実際目の前にドモン・カッシュが居る訳でもないので、これはハヤブサの想像でしかない。だがあの朴訥な弟は、キョウジとシュバルツを、二人とも同じくらい大事に想っていた。だから、どちらか片方を失ったからと言って、残った片割を責める様な事は、あの弟は絶対にしないだろう。どちらかと言うと、残った片方を抱きしめて「兄さん……!」と、泣き叫びそうだ。
(きっと……ここに居るのが俺ではなく、弟のドモン・カッシュであったなら、シュバルツも『兄』としての顔をちゃんと作って、もう少し早く立ち直るのだろうが…な……)
ハヤブサはそう感じて苦笑する。
シュバルツ――――と言うか、キョウジは、弟であるドモンの前では、ちゃんと『兄』であろうとし続けていたように見えた。それほどまでに、キョウジにとって『弟』と言う存在は、とても大切で、守るべき存在でもあり、また、支えにもなっていると知る。
(……やっぱり、俺は、まだまだだな……)
少し、淋しさを感じて、ハヤブサは小さなため息を吐いた。
分かっている。
キョウジにも、ドモンにもなれない、俺。
俺は『俺』のまま――――シュバルツを、支えて行くしかない。
無い物ねだりをしても、仕方が無いのだ。
「落ちつけシュバルツ……。『連絡が取れない』とだけ、言っているんだ」
「――――!」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツは今度は別の心配に襲われる。
「『連絡が取れない』って――――まさか……!」
キョウジの様な事が、ドモン達の方にも――――!?
思考がそう行きついてしまったシュバルツの顔色が変わる。
何てことだ。
キョウジの事に気を取られ過ぎて、ドモン達の事をすっかり失念していた。
あんな事があったのだ。
無事でいる保証など、誰にもどこにも無いのに――――
「大丈夫だ。落ちつけシュバルツ」
シュバルツのこういう反応もある程度予見していたハヤブサは、苦笑しながらシュバルツを諭す。
「しかし……!」
「連絡が取れない『原因』は、ちゃんと分かっている…。だから、落ちつけ」
「……………?」
ハヤブサの言っている事が咄嗟に理解できないシュバルツは、怪訝そうに眉をひそめた。
「……どういう、事だ?」
問うてくるシュバルツを、ハヤブサは手招きする。
「ちょっとこちらへ来て、窓から外を見てみろ。面白い物が見れるぞ?」
「……面白い物?」
ハヤブサに招かれるままに、シュバルツも窓際へと近づいて行く。崩れかけた窓から外を見たシュバルツは、一瞬自分の視界に飛び込んできた『物』が信じられなくて、思わず「えっ?」と、声を上げていた。
それもその筈だ。
彼の目の前には今――――
巨大な、『自由の女神』の銅像が、あったのだから。
「何だ? これは……!」
茫然と問うシュバルツに、ハヤブサは答えを返す。
「『自由の女神像』だ。……知っているだろう?」
「知ってはいるが―――そうじゃなくて!」
事態を咄嗟に受け入れる事が出来なくて、シュバルツは少し混乱する。自分達は確か、日本の東京の郊外に居たはずで――――そこから一歩も外に移動していない筈なのだ。なのに何故――――アメリカのニューヨークになければならない『自由の女神像』が、自分達の目の前にあるのだろうか?
「私はどうしてこれがここにあるのかと、聞いているんだ!」
「さあな。俺にも分からん」
ハヤブサはククッと小さく笑う。その笑い声に、少し楽しそうな響きが混じっているのは、気のせいだろうか。
「どういう事だ……? 私たちはニューヨークにいつの間にか、移動させられたとでも言うのか……?」
自由の女神像の周りには、あのニューヨーク独特の摩天楼がそびえている。あの龍の首によって破壊されつくした光景が、夢だったのではないかと思えてしまうほど――――その町並みは、綺麗な物だった。
「ここが単純に『ニューヨークだ』と、断定出来ればいいのだがな……」
「………何?」
ハヤブサの言葉に少し不吉な物を感じて、シュバルツは思わず振り返ってしまう。
「まだ何かあるのか?」
そんなシュバルツにハヤブサはにこりと微笑み返すと、踵を返しながらシュバルツに声をかけた。
「もう少し上の階から外を見てみるか?」
ハヤブサの誘いに、シュバルツも同意をし、歩きだした。
「ここらでいいか……。シュバルツ、ここから外を見てみろ」
ハヤブサに言われたとおり、窓から外を見るシュバルツ。視界が高くなった分、遠くまで見渡せた。
「あのビルの間に、変わった物が見えないか?」
ハヤブサに指さされた方向にシュバルツも視線を走らせて―――――
「な…………!」
絶句した。摩天楼の中には、絶対にあり得ないであろう建物が、存在していたからだ。
「あれが『何』か……分かるか? シュバルツ」
「日本の……『城』か……? 随分変わった形をしているが……」
その建物を見ながら、シュバルツが感じたままを答える。
小高い山の上に石垣が築かれ、その山頂にひときわ高くそびえる天守閣がある。七重に重なるその天守は、階層ごとに色が分けられ、ある層は、日本の城によくある独特の白塗りの壁に、漆黒の縁取りの窓。ある層の壁は青く彩られ、赤い壁の層は八角形にかたどられている。最上階は総て、金色で彩られていると言う―――何とも豪奢で、奇抜な形の城だった。だがとても美しい、と、シュバルツは素直に思った。
しかしやはり――――摩天楼の間にあるのは、不自然すぎた。
「そう、日本の『城』だ。……ではシュバルツ、あれが何城か分かるか?」
ハヤブサが、少し楽しそうにシュバルツに問うてくる。
「いや、そこまでは――――」
シュバルツは素直に答える。ハヤブサと史跡を巡る様になってから、それなりに歴史に関する知識も増えて、城や城跡にも多少明るくなったと思うのだが、残念ながらあのような城を、自分はまだ見た記憶が無い。
「……分からなくて当然だ。あの城は、既に焼失して、現代には存在していない筈の物なのだから」
「……と、言うと?」
問うシュバルツに、ハヤブサはにやりと笑う。
「あの城は、おそらく『安土城』だ」
「え……?」
ハヤブサの言っている事が咄嗟に理解できなくて、茫然とするシュバルツ。そんなシュバルツに、ハヤブサは更にたたみかけてくる。
「しかも、織田信長が造った、安土桃山時代の――――な……」
「え……? え………?」
「俺も、資料でしかあの城の姿を見た事は無いが―――――」
ハヤブサもまた、あの城を眺めているが、その横顔が、どことなく楽しそうだった。
「あの奇抜な形、天守閣の高さ、色遣いは――――織田信長が作った『安土城』以外には考えられないんだ」
「い、いや……。ちょっと、待て……!」
シュバルツは、ハヤブサの話について行きかねて少し混乱する。
「何で……ニューヨークの摩天楼の間に、日本の昔の『安土城』が……? こんな……目茶苦茶じゃないか……!」
そう言って茫然とするシュバルツに、ハヤブサも苦笑を返す。
「そう……。『目茶苦茶』なんだ。時代も、場所も――――」
「――――――!」
「だから、言っただろう? シュバルツ。ここがニューヨークだと簡単に断定はできないと」
「…………!」
「そう言う場所に、俺たちは居る。いや、『巻き込まれた』と言った方が―――正しいかな……」
だから、ドモン達とも連絡の取りようが無いんだ、と、笑うハヤブサに、シュバルツはもう頭を抱えるしかない。
「……よくのんきに、笑っていられるな……」
「仕方がない。もう笑うしかない状況だろう」
「……それはそうかもしれないが……」
シュバルツは、はあ、と、ため息を吐いて、頭を抱えていた手を下ろす。確かにこの状況――――ハヤブサの言う通り、いろいろと開き直っていくしかなさそうだ。
「こうなってしまった『原因』は何か、見当はついているのか?」
明確な答えが返って来る事を、特に期待もせずに、シュバルツはハヤブサに問うてみた。『原因』が分からなければ、対策も立てられないし、手の打ちようもない。何かその手掛かりになる様な物があれば――――ぐらいの気持ちだった。だがハヤブサからは、意外な答えが返ってきた。
「『原因』の見当はついている」
「本当か!?」
驚き振り返るシュバルツをちらりと見ながら、ハヤブサは続けた。
「おそらく――――あの『龍の首』だ」
「―――――!」
「……あの『龍の首』には、とてつもなく強い『魔力』と『妖力』が備わっていた……。恐らく、世界を軽く、握りつぶせるほどの………」
シュバルツに話しながらハヤブサは、あの『龍の首』と相対した時の事を思い出していた。唐突に現れ、キョウジの命を奪って行った『龍の首』――――あれからは、今まで自分が屠ってきたどの敵よりも強い『魔力』と磁場の乱れを感じた。あれが無軌道に暴れまわったおかげで、時間軸と次元に乱れが生じて――――『世界』と『世界』にあり得ない繋がりを作り上げてしまったのだろう。それこそ、摩天楼の向こうに『安土城』が見えている、今の景色のように。
そして、自分達はそれに巻き込まれてしまった。あの時、あの龍の近くに居たが故に。
「シュバルツ……。俺は、あの『龍の首』の後を、追おうと思っている……」
「ハヤブサ……!」
驚き、息を飲むシュバルツに、ハヤブサは微笑み返す。
「『誰かを、世界を救う』とか、そう言う物じゃない…。ただ――――俺が、そう言う『性分』なだけなんだ……」
背に背負っている『龍剣』を意識しながら、ハヤブサは言葉を紡ぐ。
キョウジの仇を討ちたい。それもある。
だが、それ以上に――――
『妖異』と戦う術を知っている自分。その自分が、『あれ』を見てしまった。
見てしまった以上――――それを『無かった事』には出来ない。追って、戦わねば――――そう、思っている。それが、『龍の忍者』として生きる、自分の使命なのだと。
そう言う生き方しか自分は知らないし、それを止めてしまったら、自分は『自分』を許せなくなってしまうだろう。ハヤブサは、そう思った。
「だから………」
シュバルツ、ついて来てくれるか。ハヤブサがそれを口にする前に、シュバルツが口を開いた。
「私にも、手伝わせてくれないか? ハヤブサ……」
「……………!」
驚きに目を見開いて見つめるハヤブサを、シュバルツもまっすぐ見つめ返す。
「足手まといにはならないつもりだ。……あまり、役に立たないかもしれないが……」
シュバルツがそう言い淀んでしまったのは、少し自分に自信を失くしてしまっているせいだった。
キョウジを守ると言う使命に、失敗してしまっている自分。だから正直、『誰かを守る』と言う行為には、まだ自信が持てない。もしかしたら、また失敗してしまうかもしれない――――そんな恐怖が、自分に付き纏っている。
だけど、そこから怯えて逃げて――――その結果、ハヤブサまでも失ってしまったら。
自分は、もう二度と自分を許せなくなってしまう――――そんな気がしていた。
怖くても、進まなければ。
シュバルツは、怯える己を叱咤する。
大丈夫。ハヤブサは充分『強い』 実質的な『守り』は要らない。
自分がハヤブサに手を貸すのは、最後の最後。ハヤブサに求められたその一瞬に、手を貸す事が出来ればいい。それが出来さえすれば――――ハヤブサを充分守れるはずだ。その瞬間、『死なない』自分の身体は、きっと役に立つ事だろう。そう、信じる。
「シュバルツ……!」
強張った表情をしながらも、自分を見つめてくる真っ直ぐな眼差しを逸らさないシュバルツ。愛おしさがこみ上げた、から。
ハヤブサは思わず、シュバルツの身体を優しく抱き寄せていた。
「あ………!」
小さく声を上げて、腕の中で身じろぐ愛おしいヒトの耳元で、ハヤブサは囁く。
「嬉しいよ……シュバルツ……! ありがとう……!」
「ハヤブサ……」
少し戸惑った様な声を上げるシュバルツの身体を、ハヤブサは更に強く抱きしめる。
戦いは、1人でも平気だ。
だけど知らなかった。
「独りじゃない」
そう思える事が、こんなにも力をもたらしてくれるだなんて――――
お前が側に居てくれるのなら、俺はもう
何も、恐れる事は無い。
「じゃあシュバルツ。今から行くぞ、と、言いたいところだが――――」
シュバルツから身体を離したハヤブサが、自分の懐をまさぐる。
「その前に、これを渡していいか……?」
ハヤブサからシュバルツに差し出した物が、その手の中でキラリ、と、光を放った。
「―――――!」
『それ』が何かを確認したシュバルツは、思わず息を飲んでいた。何故ならそれは――――『キョウジの壊れた腕時計』で、あったのだから――――
「これは、キョウジの物だから………お前が持つべきだと、俺は思う」
「……………」
ハヤブサの言葉には答えずに、その腕時計をじっと見つめているシュバルツ。
(シュバルツに差し出すのは、早すぎただろうか)
目の前の愛おしいヒトのその様に、ハヤブサは少し心配になる。
これは、キョウジの『遺品』
キョウジは、もうこの世には居ないのだと、シュバルツに認識させてしまう物。
キョウジを守れなかった現実を、シュバルツに突きつけてしまう物でもある。
だから本来なら――――もう少し時間を置いてから、差し出すべき物なのかもしれない。
この事実は、それほどまでにシュバルツの心を深く傷つけているのだから。
だけど、シュバルツにはその事実に、立ち向かって欲しい、と、願った。
逃げるのではなく
避けるのではなく
怖がるのではなくて
受け入れて欲しい。
前に進むためにも。
受け入れる事が出来なければ
立ち向かう事も、出来ないのだから――――
(それに、キョウジ……。お前も、シュバルツと共に在る方がいいだろう? 俺の懐に居るよりも……)
ハヤブサは、腕時計を見つめながら、そうキョウジに語りかける。
もちろん、この腕時計は、単なる『物体』でしかない。『キョウジの魂が宿っている』なんて、非現実的な事を、ハヤブサは考えない。
だけど、あのキョウジなら、望む筈だ。
『ココロ』は、シュバルツと共に在りたい、と。
シュバルツに寄り添いたい、と――――
そう願う筈だと、ハヤブサは思う。
だから、気休めでも、この時計はシュバルツに持っていてもらいたい、と、願った。
それに、戦いが始まってしまったら、こんな風にシュバルツに腕時計を渡す事が出来る機会も、無くなってしまうかもしれない。そして、戦う以上、自分の身に『万が一』の事が起きないとも限らない。
その時に『渡しておけばよかった』と、後悔だけはしたくなかった。
常にそうやって死を意識して行動してしまう自分に、ハヤブサは苦笑する。
だけど、仕方がない。
自分は、そういう世界に身を置いているのだから。
「…………ッ」
暫く、逡巡するようにハヤブサの手の中の腕時計を見つめていたシュバルツであるが、やがて、意を決したようにそろそろと手を伸ばしてくる。ハヤブサは、そんなシュバルツの手を優しく取ると、そっと、その掌の上に、キョウジの腕時計を置いてやった。
「……………」
シュバルツがじっと、手の中の腕時計を見つめている。その眼差しに、乱れが無い事を確認してから、ハヤブサは声をかけた。
「………良い時計だな」
その時計に対する、正直な感想を述べる。すると、シュバルツからも答えが返ってきた。
「二十歳の誕生日の時、父さんが買ってくれたんだ……」
「あ」と、ハヤブサは思う。
今――――『キョウジ』がしゃべっている。
だが、特別驚く事ではない。
シュバルツもまた――――『キョウジ』なのだから。
自分は、割と簡単にキョウジに会えてしまう事実に、ハヤブサは少し泣きそうになる。
「……もしも直す事を望むなら、腕のいい職人を紹介してやれるが……」
声が震えないように注意しながら、ハヤブサは言葉を紡いだ。
自身がアンティークショップを経営するハヤブサ。だから、自分にも多少時計を直す腕はある。だけど、その時計はシュバルツやキョウジにとって大切な物なのだから、ちゃんとした職人に、きちんと直してもらう方がいいだろうと思った。幸い自分には、そう言う伝手もある。
「……………」
シュバルツはしばらく考え込むようにその時計を見つめていたが、やがてポツリと口を開いた。
「少し……考えさせてくれ……」
「そうか……分かった」
ハヤブサは、シュバルツが時計を受け取ってくれた事に、とりあえずほっと胸を撫で下ろす。
後は、シュバルツ自身が考えて、結論を下すだろう。自分は、それを見守るだけだ、と、ハヤブサは思った。
「……………」
シュバルツはしばらく手の中の壊れた腕時計をじっと見つめていたが、やがて、それを両手でそっと包み込んだ。
(キョウジ……済まない……)
心の中で、静かにキョウジに語りかける。
お前を守り切れなかった痛み、苦しみ、後悔、贖罪の気持ち――――
忘れるつもりはない。当分、自分で自分の事も、許せそうにない。
だけど、済まない。今から、しばらくの間だけ――――
私は、お前の事で嘆くのを、止める事にする。
やらなければならない事が、出来たから………
それが終われば、私はきっとお前のために、また涙を流すから。
だから済まない。今から、少しの間だけ――――
哀しむ事を止めてしまう事を、どうか許して欲しい。
(……………)
当然だが、シュバルツの問いかけに、『キョウジ』からの返事が返って来る事は無い。だけどシュバルツは、懐にそっと腕時計をしのばせると、己が顔を上げた。為すべき事を、為すために。
「待たせたな」
そう、穏やかな声音で声をかけてきたシュバルツは――――もう、『いつものシュバルツ』であったから。
「もういいのか?」
そう聞く事さえ、愚問の様にハヤブサには思えた。
シュバルツが立ち直ったのなら、自分が彼に言うべき事は一つだ。
「行こう。シュバルツ」
その言葉にシュバルツは、静かに頷いた。
摩天楼の間を、忍者たちは静かに進んで行く。
高層ビルが立ち並ぶ大都会のはずなのに――――街の中は、恐ろしい程人の気配が無い。ここが、自分達が知っている「ニューヨーク」ではない事は、もう明白だった。空は暗く曇り、ビルの間を吹き抜ける風からは、『妖魔』の気配を感じさせた。
「ハヤブサ……」
後ろからついてくるシュバルツから、そっと声をかけられる。
「何だ?」
「『龍の首を追う』と、言っていたが……どうやって追うつもりだ?」
「『魔』の気配だ」
ハヤブサはシュバルツからの質問に、振り向きもせず、歩きながら答えた。
「あの『龍の首』からは、強い魔力の波動を感じた。だから、その後を追うつもりだ」
「……そんな事が出来るのか?」
問うシュバルツに、ハヤブサはにやりと笑う。
「あいつの魔力の気配は、半端なく強かったからな……。姿が見えずとも、追う分には問題ない」
そう言いながらハヤブサは、摩天楼のビルの間をすたすたと進んで行く。シュバルツもその後に続いた。
暫く、静かな道行きが続く。だが、それもそう長くは続かなかった。
「ハヤブサ……」
再びシュバルツから、声をかけられる。声をかけられる理由を察知しているハヤブサも、無言で頷いた。
囲まれている。
それも、複数の気配に。
「……………」
足を止めた忍者二人の前に、ビルとビルの間から、気配の元となった者たちが姿を現す。人間と同じように手足を有していたが、それぞれが、角や鋭い牙を有していた。猪の様な容貌をしている者もいれば、一つ目の者もいる。皆が皆、人肌とは程遠い、青白い肌をしている。
(異形の者か)
ハヤブサは、仕事柄こういうのも見慣れているので、特に驚きもしない。異形の物たちは皆それぞれ、手に斧や槍やこん棒と言った武器を持っていた。
「……人間の匂いがするな……」
そう言って、殺気だった目をぎらつかせる異形の者たち。お世辞にも、友好的とは言えなさそうだった。
「こんな所に迷い込んでくる、馬鹿が居たぜ」
ハヤブサとシュバルツが、二人だけなのを見て取った妖魔たちから、嘲笑する様な声が上がる。手に持った得物で威嚇するようにしながら、妖魔たちは忍者二人をゆっくりと取り囲んだ。
「久しぶりに人間の肉が食えるな」
「固そうだぞ? うまいのか?」
「俺の分の分け前は、あるんだろうな―――」
各々が物騒な事を口走りながら、妖魔たちはじりじりと包囲を詰めてくる。それを見ながらハヤブサは、小さく息を吐いた。
(無駄な戦闘は、なるべく避けたかったのだがな……)
「シュバルツ……走るぞ。ついて来れるか?」
龍剣の柄に手を伸ばしながら、ハヤブサはシュバルツに問いかける。
「話し合いは……」
「……通用すると、思うのか?」
殺気立つ妖魔たちを、顎で指しながら問い返す。それにシュバルツも「確かに……」と、苦笑しながら首を横に振った。もうここは、強行突破するしかなさそうだ。
すらり、と、音を立てて、ハヤブサは龍剣を抜き放つ。それを見た妖魔たちは笑いだした。
「見ろよ! こいつ戦う気で居るぜ?」
「多勢に無勢だ。無駄な抵抗は止めて、大人しくやられろ!」
嘲笑う周囲の声。それがまるで聞こえていないかのように、ハヤブサは一歩、前へと踏み出す。
「……押し通る」
低く、強い意志を孕んだ声が響く。それと同時にハヤブサから、鋭い殺気が迸った。
「――――!」
殺気に当てられた妖魔たちの何人かが、少し怖じ気たように後ろに下がる。ここで彼らは気付くべきだった。今――――目の前で龍剣を抜き放っている男の危険さに。自分達の生存確率が、限りなく零に近づいている、と、言う事に。
だが、それは無理からぬことでもあった。
彼らはハヤブサたちが居た世界とは違う世界から現れた妖魔であるが故に――――知らなかったのだ。『龍の忍者』の強さを。その恐ろしさを。知っていれば、一目散に逃げる事も、出来たであろうに。
ダンッ!!
鋭い踏み込みと共に、ハヤブサが龍剣を一閃させる。すると、彼の前方に居た妖魔たちが、声を上げる間も無く吹っ飛ばされた。
「行くぞ!!」
龍剣が妖魔たちを倒してできた空間に、ハヤブサは躊躇うことなく突っ込んで行く。シュバルツもまた、その後に続いて走り出した。そのまま忍者二人は一対の風になって、妖魔たちの間を走り抜けて行く。
「やっちまえ!」
もちろん、妖魔たちも黙って見ている訳ではない。たった二人だけなのだからと果敢に武器を振りあげて風に挑んで行く。
だがある者は、武器を振り下ろす前に。
またある者は、何が起こったのか気づく前に――――ことごとく風によって斬り伏せられていた。幾百もの妖魔たちの間を忍者たちは走り抜けているはずであるのに、二人に敵する者は誰もおらず、まるで、無人の野を走り抜けるが如くであった。
「ハヤブサ! どこへ向かうんだ!?」
妖魔たちを薙ぎ倒しながら、シュバルツが叫ぶ。
「あの『安土城』に向かう!」
ハヤブサも妖魔を蹴散らしながら答えた。
「安土城に?」
少し意外そうな声を上げるシュバルツに、ハヤブサが
「……物見遊山目的ではないぞ?」
と、言ってくるものだから、シュバルツは危うくズルッと、こけそうになった。
「こんな時に何を言っているんだ!? お前は!!」
乱戦の中、ハヤブサをどつく訳にもいかないので敵をどつき倒しながら、シュバルツは怒鳴りつける。そんなシュバルツに、ハヤブサも苦笑しながら答えた。
「冗談はともかくとして……あの安土城から強い妖魔の気配を感じるんだ。だから、行って確認をしたい」
「なるほど……」
ハヤブサの言葉にシュバルツは納得する。しかし、ハヤブサの方に安土城に対する下心が無かった訳ではない。焼失して現在には資料でしかその姿を見る事が出来ない安土城と思われる城が、今目の前にある。
妖魔の力によって出現した『それ』は、紛い物である可能性が極めて高いが――――。
それでも、見てみたいと思った。
織田信長が天下布武のために建造したと言われる安土城を、この目で。
どこまで資料通りなのか、そうじゃないのか――――学術的好奇心が疼くのを、止める事が出来ない。だから、『物見遊山』なんて言葉が、つい、ポロっと出てきてしまう。
(シュバルツが共に居てくれるから――――これもまた『逢瀬』だよな……)
戦いながらこんな事を思ってしまってはいけない事なのかもしれないが、ハヤブサは今、確かにこの道行きを楽しんでいる自分を感じ取っていた。
「速度を上げるぞ…! ついて来れるか?」
戦いながら愛おしいヒトに問いかける。すると「勿論」と、力強い返事が返ってきた。
「ならば、いざ――――!」
ビルの間を走り抜ける忍者たちの『風』は、さらに勢いを増して行った。
摩天楼をを難なく突破し、安土城の麓まで足を運んできた時、シュバルツが「少し一息入れよう」と、提案してきた。ハヤブサも素直にそれに従った。
近くに流れるせせらぎの水を、シュバルツが『毒見』する。
「この水は、飲んでも問題なさそうだぞ、ハヤブサ」
口の中で水の解析を終えたシュバルツが、そう言いながら振り向く。アンドロイドであるシュバルツの舌は、味覚が無い代わりに口に含んだ物の成分を、分析できるようになっていた。
「そうか」
シュバルツの言葉にハヤブサは微笑む。この状況下で、飲み水の心配をしなくていい事実は、素直にありがたかった。
「こういう時、便利だな。お前は……」
自身も川の水を口に含み、携えている竹筒に水を入れながら、ハヤブサは素直な感想を漏らす。それを聞いたシュバルツから、笑みが返ってきた。
「フフ。そう思ってくれるのなら、嬉しいよ」
穏やかで優しい微笑み。戦いの合間の、一時の安らぎだった。
竹筒の蓋をキュッ、と、音を立てて閉めながら、ハヤブサは立ち上がる。小高い山の上にそびえる安土城の天守閣を、見つめた。
「……やはり、あそこなのか? 『妖魔』の気配を感じるのは……」
黙って天守閣を見つめるハヤブサに、シュバルツが近寄って来る。
「そうだ。あの天守閣から、強い妖気を感じる。あそこに、あの龍の首の置き土産か、その手掛かりになる様な物があればいいのだが……」
「そうか……」
シュバルツもハヤブサと同じように天守閣を見上げながら、呟く。
「やはり、城に潜入するとなると、それなりに骨が折れるんだろうな……」
「いや。資料によると信長は、安土城の防衛には重きを置いていない。あれは天下に号令する事が目的で建てられた城だから――――」
潜入するのは容易いだろう、と言うハヤブサに、シュバルツも頷く。
「後は、あれが本当に『資料通り』の安土城であるかどうか……だがな」
「……随分、楽しそうだな」
「分かるか?」
「顔がにやけてるぞ」
シュバルツに指摘されて、ハヤブサも苦笑するしかない。
仕方がない。実際、楽しいのだから。
「じゃあ、行くか!」
ハヤブサは、外していた覆面をかぶりなおす。シュバルツも頷いて――――忍者二人は再び、走りだした。
安土城内で、左慈元放は辟易していた。
突如として現れた妖蛇『遠呂智』――――そのせいで、この人間の『世界』は滅亡に向かいつつある。
もちろん、人間たちは懸命に抵抗を試みた。だが、妖蛇の力はあまりにも圧倒的で、人間たちは次々と倒されて行く。このまま滅びるのは時間の問題――――そう思われた時、神仙界より1人の巫女が遣わされたことで、状況が徐々にではあるが変わりつつあった。
その巫女の名は『かぐや』――――彼女は、1人の人間の時間を巻き戻せる力があった。
その能力を使って人間たちは、妖蛇によって倒されて行った仲間たちを、1人、また1人と助け出して行く。蜘蛛の糸をたどる様なか細い作業――――だが、そのおかげで、僅かではあるが、希望が見えてきた。人間が、妖蛇に対抗し得る力を取り戻す『希望』が――――。
かくいう自分も、その能力によって助け出された一人だ。法術師である左慈は、その時願い出ていた。
「人間たちの力は、今のままではあまりにも無力。妖蛇に対抗し得る力を持つ人間を、もっと集めて参りましょう」
「左慈殿がそう仰るのなら――――」
西涼の若武者、馬超は戸惑いながらも左慈の行動を許してくれた。この馬超は、最後まで妖蛇に抵抗を続けていた人間の1人で、彼の過去を遡っていく事からこの抵抗は始まったのだ。
「では、左慈様……この『縮地の護符』を、授けましょう」
巫女のかぐやが、長い黒髪をなびかせながら、楚々と左慈の前に進み出てくる。
「この札は、一度だけ、望む場所に渡る力を持ちます。きっと、貴方様の助けとなる事でしょう」
左慈はその札を受け取り、人間たちの陣屋から一時離れた。
それからの左慈は、妖魔の気配の強い場所を、あえて渡り歩いていた。何故左慈がそう言う行動をとったのかと言うと、理由はただ一つ。自分は、『強い人間』を欲していたからだ。
これだけ瘴気の強い魔の気配に囲まれていても、それをものともせずに戦う人間。魔を打ち払う力を備えた人間。それを見つける事が出来れば、妖蛇を倒すための助力を請うつもりでいた。
だが、遠呂智の強い気配を追い続けていた左慈は、この安土城の城内で、思わぬ足止めを喰らう事になる。襲ってくる妖魔の数の多さもさることながら、天守閣の奥に一体、巨大な妖魔が待ち受けていたからだ。
その妖魔は、『阿修羅像』の姿を模していた。
3面に頭があるせいで、その妖魔には死角が無く、6本ある腕が変幻自在に形を変えて、左慈に攻撃を加えてくる。時折腕から無数の刃が派生して、それが左慈めがけて飛んできていた。
「うむッ!!」
左慈は、自身が持っている札を盾の様に変化させて、その攻撃を何とかしのぐ。だが、防ぎきれなかったいくつかの刃が、左慈の身体を掠めた。その攻撃が止んだと思ったら、間髪入れずに周りの妖魔たちが左慈に攻撃を仕掛けてくる。
(……この戦場……いささか小生には、荷が勝ちすぎるか……!)
左慈は、妖魔たちに応戦しながら、歯を食いしばっていた。周りに群がる雑魚妖魔たちは、何とか対応できる。しかし、あの奥に陣取る阿修羅像を模った妖魔は――――。
ブオンッ!!
唸りを上げて攻撃して来た阿修羅像の腕を、左慈は横っとびにかわす。
「ぬんっ!!」
札に『気』を込めて、周囲の敵を吹き飛ばす。練り上げた『気弾』を、阿修羅像に向かって放ってみるが、阿修羅像の腕によって弾き返されてしまう。どうしても、自分の攻撃は、あと一歩と言う所で阿修羅像には届かない。どう考えても、このままここで戦い続ける事は、自身にとって得策とは言えなかった。
(仕方があるまい。一時撤退も已む無し……!)
そう思った左慈が、その部屋の入り口から階段の方へ向かおうとする。だが、その動きを察知した阿修羅像がその目を光らせ――――総ての出入り口を封殺してしまった。まるで、今目の前に居る獲物を、逃がすものかとでも言わんばかりに。
「く………!」
八方ふさがりの状況――――だが左慈は、まだあきらめたくは無かった。
時を遡れる『かぐや』という巫女のおかげで、やっと、少しずつだが見えてきた希望の光。今はまだ、吹けば飛びそうなほどかよわい光だが、それを助けたい、と、願う。
その為に、こんな所で倒れる訳にはいかないのだ。
自分はまだ――――何も為し得ていないのだから。
「はああああっ!!」
左慈の『気』を乗せた札が、周りの妖魔たちを吹き飛ばす。だがその妖魔たちの影に隠れて、阿修羅像の腕が伸びてきていた。左慈はそれに、気づくのが一歩遅れてしまった。
「ぐはっ!」
しなりを伴った腕の攻撃に、左慈の身体は弾き飛ばされてしまう。壁に叩きつけられ、一瞬呼吸ができなくなった。
「やっちまえ!!」
それを見た妖魔たちが、左慈に殺到しようとした、刹那。
「うおおおおおおっ!!」
ドコォォォォン!!
派手な轟音と共に、部屋の一角の出入り口の襖が吹き飛ばされる。そこから影が二つ、その部屋に飛び込んできた。影の一つが左慈の前に着地すると、あっという間に彼に殺到して来た妖魔たちを弾き飛ばしてしまう。
「――――!?」
驚いて顔を上げる左慈の視界に、革のロングコートを着た青年の後姿が飛び込んでくる。
青年は左慈を庇うようにその前に立つと、妖魔たちを牽制するように構えた。
「お怪我はありませんか?」
その青年は首を少し動かして、丁寧に問うてくる。左慈が頷くと、青年の口元が僅かにほころんだ。
刹那、再び阿修羅像が攻撃を仕掛けてこようとする。しなりを上げて襲いかかって来る腕――――だが、それが二人の所に届く事は無かった。
「りゃああああああっ!!」
裂帛の気合と共に、その腕は一太刀の元に斬り落とされる。切り離された腕は攻撃を仕掛けようとした勢いのまま床に落下し、その近くに居た妖魔たちを次々と倒して行った。悲鳴を上げて逃げ惑う妖魔たちの間から、黒い影が勢いよく飛び出してくる。
「ハヤブサ!!」
「シュバルツは、その人を頼む!!」
黒い影は壁を走りながら叫び、シュバルツと呼ばれた青年は「承知!」と、短く叫ぶと、再び左慈に話しかけてきた。
「助太刀いたします」
そう言いながら、襲いかかってくる妖魔たちを撃退するシュバルツを見て、左慈もようやく、立ち上がる事が出来た。
「小生の事は良い。それよりも、あの阿修羅像を――――」
シュバルツと共に妖魔たちと戦いながら、左慈は言う。今ここで一番厄介なのが、あの敵だからだ。だがそれに対してシュバルツは、屈託のない笑みを浮かべて答えた。
「ハヤブサの事なら、心配要りません。何せ、あいつは――――」
壁を走るハヤブサに向かって、阿修羅像の腕が再び襲いかかって来る。ドオン!! と、轟音を立てて腕が壁に激突すると同時に、ハヤブサは壁を蹴って跳躍していた。唸りを上げて襲いかかって来る腕を、宙でトンボを切ってかわす。彼が龍剣を一閃させると、また、阿修羅像の腕が斬り落とされた。そのまま彼は、阿修羅像の残った腕の上にストン、と着地する。
覆面の間から覗く色素の薄いグリーンの瞳が、阿修羅像の妖魔を鋭く見据える。
当然、阿修羅像の妖魔が、そんなハヤブサの行動を許すはずもない。乗られた腕を激しく振り回し、ハヤブサを振り落として、攻撃を加えようとした。だが次の瞬間、腕の上から龍の忍者の姿がスッと消えた。
ハヤブサの姿を見失ったせいなのか、阿修羅像の動きが一瞬止まる。
「叭(ハ)――――――ッ!!」
その隙をついて、裂帛の気合と共に龍の忍者が上空から降ってくる。
ドカッ!!
龍の燐気を纏ったハヤブサの愛刀龍剣は、主の注文通り、阿修羅像を上から真っ二つに切り裂いた。
「堊堊堊堊堊堊堊堊(ああああああああ)―――――!!」
断末魔を上げながら、阿修羅像の妖魔は粉々に砕け散っていく。像の部分が破片となって雲散霧消し、最後にどす黒く妖しい光を放つ、黒い玉が現れる。その玉を、龍剣は過たず串刺しにしていた。玉は最期にぶるり、と、一震えしたかと思うと、黒煙をその身から吐き出して――――真っ二つに砕けて床に転がった。
「充分『強い』ですから………」
ハヤブサが妖魔を倒した事を確認してから、シュバルツは左慈の方に振り返る。
「……その、ようだな……」
半ば茫然と見つめる左慈の目の前で、ハヤブサは龍剣をブンッ、と、露払いをしてからその身を鞘に納めていた。
「わ……! わ……!」
頼みにしていた阿修羅像をあっさり屠られた妖魔たちは、すっかり怖気づいてしまう。
「ひいいいっ! 逃げろ――――ッ!!」
その叫び声と同時に、彼らは、蜘蛛の子を散らすように逃げて行った。
「………………」
ハヤブサは逃げる妖魔たちには目もくれず、砕けた玉を検分している。
(……これは、あの『龍の首』の一部か……?)
手に取った玉からは、もう何の邪気も力も感じない。恐らく、あの『龍の首』から落とされた魔道の欠片があの像に入り込んで、ああいう妖魔にならしめてしまったのだろう。
それにしても、あれだけ強く感じていた『龍の首』の気配が、再び遠いものになってしまった。また一から探りなおしか――――と、ため息をついた時、先程助けた道士風の男から、声をかけられた。
「ご助力、感謝いたす。見事な腕前じゃな……」
「…………!」
道士風の男の後ろから、シュバルツもついて来ていたのを見て、ハヤブサも立ち上がった。
「妖魔の気配を追っていた所に、たまたま御身が居ただけの事だ。礼を言われるほどの事でもない」
ハヤブサは丁重に答えたが、道士風の男に対して警戒心を抱いていない訳でもなかった。何故こんな妖魔だらけの所に、たった一人で居たのか気にかかる。見たところ、人間の様であるし、邪気を感じると言う訳でもなかったのだが。
「魔を追っている?」
ハヤブサの物言いに、左慈は顔を上げる。
「もしや貴殿が追っている『魔』と言うのは、巨大な『龍の首』の様なものであろうか?」
「――――! その『龍の首』について、何か知っているのか?」
自分の言葉にそのような反応を返してきたハヤブサに、左慈は、ふっと顔をほころばせた。
「『あれ』を追っている、と、言うのなら、丁度よい。小生の知っている事を話して進ぜよう」
「……………」
左慈の言葉にハヤブサとシュバルツは互いの顔を見合わせ、推し量る様に左慈の方を見つめる。
「……そう、警戒しなさんな。我らの目的は、同じである故――――」
「………と、言うと?」
問うシュバルツに、左慈はひょうひょうと答えた。
「お二人とも、腰を据えて話をしませんかな……。幸いにして、妖魔の気配も今は遠く、ここは織田信長公が建てた、安土城の天守閣の中……。戦の事を論ずるには、ふさわしき場所かと存ずるが――――いかがかな?」
「…………!」
左慈の言葉にシュバルツとハヤブサにも特に反対する理由が無い。二人は、素直に従った。
「まず、小生の方から名のろう……。小生は名を左慈、字を元放と申す」
3人は畳の上に円形に座り、まず左慈がそう言って拱手して挨拶をした。二人ともそれに挨拶し返そうとして――――その動きがピタリと止まる。
「左慈?」
「元放?」
確認するように聞いてくる二人に、左慈は「如何にも」と頷き返す。二人はその言葉に返事をして、自分達も名乗らなければならない、と、頭では分かっている。だが、頭が真っ白になってしまっていて、なかなか次の言葉を紡ぐ事が出来ない。
「如何為された?」
左慈が二人の様子を怪訝に思って、問いかけてくる。
「あ………いや――――」
左慈に慌てて返事を返しながら、シュバルツもハヤブサも、自身の背中から変な汗が流れ落ちてくるのを止める事が出来ない。何故なら、二人ともが――――『知っていた』からだ。『方術師の左慈』と言う存在を。『三国史』と言う、歴史上の書類の上で。
だから、本当に自分達が知っている『左慈』と言う存在なのか確かめたくて、シュバルツは、つい、こんな質問をしてしまう。
「あ……あの……失礼を承知で、質問させていただきますが……」
「何じゃ?」
「も、もしかして……『劉玄徳』と言う方を、ご存知だったり……します、か……?」
その質問に、左慈はふっと相好を崩した笑みを見せた。
「おお……大徳をご存じか。流石に大徳じゃ。その名が、ここにあっても広く知れ渡っていると見える――――」
「…………!」
左慈がそう言って嬉しそうに笑うのを見て、シュバルツもハヤブサも、もう茫然とするしかない。この左慈と言う存在は、3世紀の中国において、当時『魏』という国を作りつつあった曹操と言う人間に、「玄徳の方が人徳が厚いから、国を彼に譲れ」などと大胆不敵な物言いをして、曹操を翻弄したと伝えられている人物だ。そんな人間と、時を越えて出会ってしまったという事実に、シュバルツは、少し心が躍ってしまった。
(す……すごい人と、出会ってしまった……! 帰ったら、早速キョウジに――――)
ここまで思ってしまってから、シュバルツは、はっと、我に帰る。
(馬鹿な事を―――! キョウジはもう、居ないのに――――!)
そう。死んでしまっているキョウジには、もう話をする事も話を聞く事も出来ない。当たり前のことだ。
それでも自分は、思ってしまうのだろう。呼び掛けてしまうのだろう。
何かあるたびに、「キョウジ、キョウジ」と。
話がしたくて。
でも――――出来ないから、この『想い』は結局、黙殺して行くしかない。
改めて、自らの『片割れ』を失ってしまったのだという事実を痛感する。
自分はこれから先、後何回、こんな風に言葉と心を噛み殺して行かなければならないのだろう――――?
そう感じてしまって、シュバルツは少し、切なくてうんざりする。
どうしようもなく、感じてしまう『孤独』が―――酷く苦かった。
おかしい。
独りは慣れている、と、思っていたのに。
「シュバルツ……?」
ハヤブサに呼びかけられて、シュバルツは、はっと、現実に引き戻される。
「あ……済まない……」
慌ててその顔に、笑みを浮かべる。
ちゃんと笑わないと。心を、麻痺させないと。
「キョウジの事で哀しむ事を、今は止める」
そう、心に誓っているのだから――――
「……………」
ハヤブサは、そんなシュバルツの様子をじっと眺めていたが、やがて、小さなため息と共に前を向いた。本当なら、今すぐにでも抱きしめて、シュバルツを慰めてやりたい。だけど今は――――非常事態であるが故に、それは出来ないと感じる。
結局、シュバルツ自身の『強さ』に頼るしかないのか、と、ハヤブサは思った。
ハヤブサは、ポン、と、シュバルツの肩を軽くたたく。「俺が、傍に居る」せめて、シュバルツにそう合図を送ってから――――彼は左慈に話しかけた。
「俺の名は、リュウ・ハヤブサ。『忍者』を生業とする者だ」
「……私は、シュバルツ・ブルーダー。同じく」
ハヤブサに少し遅れてシュバルツも名乗り、軽く頭を下げる。
「ほう……『忍者』か……。と、言う事は、服部半蔵や、くのいちと言った者たちの様な物なのかな?」
「―――――!」
左慈の口から思わぬ名前が出た事に、ハヤブサとシュバルツはまた絶句してしまう。
「……そ、その人たちを……ご存知なのですか?」
動揺を隠せずに問うシュバルツに、左慈は穏やかな笑みを向けた。
「よく知っておる。ここは、『そう言う所』なのだ……。時を越え……場所を越え……普通なら、会わぬ縁の者たちが、こうして巡り合う……」
左慈の言葉に、もう茫然とするしかない二人。だが、妙な説得力がその言葉にはあった。現に、自分達の目の前に居る左慈が、その言葉の証明なのだから。
「こうなった原因は分かっておる……。総ては魔王『遠呂智(オロチ)』の仕業だ」
「魔王?」
「遠呂智?」
左慈の言葉を復唱する二人に、左慈は、穏やかな微笑みを浮かべて頷く。
「『遠呂智』について………話しても、よろしいかな?」
その言葉に、忍者二人に異論があろう筈もない。二人は黙って頷いた。
遥かなる太古――――遠呂智は神仙界で大罪を犯した。その罪故に、遠呂智は幽閉されていた。
だが、妖魔妲己が、遠呂智の封印を解いたことで状況は一変する。
解放された遠呂智は、妖魔の大軍を率いて時空を乱し、今の世界を創り始めた。そしてそこに『強い人間』たちを引きずりこんだ。その人間たちに戦いを挑み――――屠るために。そして当然、唐突にその世界に巻き込まれた人間たちは、為す術もなく蹂躙されて行く。
だが、人間たちもいつまでもやられっぱなしではない。生き残った者たちが手を携えて結集し、遠呂智に対抗していく。
そしてついに――――遠呂智は倒された。それが、『一度目』の戦いだった。
「一度目?」
疑問を口にするハヤブサに、左慈は頷く。
「そう――――戦いは、これで終わりではなかった……」
遠呂智の創り上げた世界に巻き込まれた人間たちは、元の世界に帰る術を失ったまま、この世界で暮らしていた。ある者はこの世界の頂点に立とうと覇権を争い、ある者は、自身の強い『武』を持て余すが故に、乱世を求め、またある者は乱世からの平穏を求め、国を創り、その中で生活を営んだ。
そんな中、半妖の存在となった平清盛と妖魔妲己が、巫女である卑弥呼の力を借りて、遠呂智の復活を画策した。そして、その目論見は見事に成功し、遠呂智は完全復活を遂げる。より強力な力を携えた、『真・遠呂智』として――――。
「卑弥呼に平清盛……時代が滅茶苦茶だな……」
そう言って苦笑うシュバルツに、左慈も苦笑を返す。
「そうだ……。遠呂智が創り上げたこの世界は、まだ成長し続けておる……。巻き込む時代や人間の数を、次第に増やしながら、な」
「……………」
左慈の話を聞きながら、ハヤブサは考え込む。もしかして――――あの『龍の首』も、遠呂智のそんな力の現れであったのだろうか?
人間たちは、再び遠呂智に立ち向かう。そして今度は―――神仙界も黙ってはいなかった。遠呂智に対抗する人間たちを助けるべく、太公望が、女媧(じょか)が、伏犠(ふっき)が、遠呂智の世界に入り込み、人間たちに手を貸して行く。そして人間たちは、またも遠呂智を打ち破った。
「そして世界は、再び平穏を取り戻した………かに見えた……」
「……と、言うと?」
「………また、遠呂智が復活したのか?」
腕を組みながら問うハヤブサに、左慈は頭をふる。
「……あれは、『遠呂智』なのであろうか……」
忘れもしない。
劉玄徳が遠呂智亡き後に創り上げた―――小さいが、平和な国。
突如として異世界に飛ばされた人間たちであったが、彼らはよくその世界に順応していた。何も無い荒れ地を耕し、作物を植え、家畜を飼いながら――――生活を営んだ。そんな劉備の元に徳川家康と言う人物も身を寄せて、国造りに参加した。
結果そこは、民は活気にあふれ、子供たちの笑い声が絶えない国に育った。
(さすがは大徳)
うららかな日差しの中、民たちと共に歩む劉備たちの姿を、左慈も穏やかな気持ちで眺めていた。
涙が出るほど平和な日常。
だがそれは――――ある日唐突に破られる。
巨大な『龍の首』の出現によって――――。
「…………!」
左慈の言葉にシュバルツとハヤブサは息を飲む。
自分達の日常も、ある日唐突に破られた。あの巨大な『龍の首』によって。
そう。何時だって、唐突だ。
『災厄』は何の前触れもなく、いつだって、唐突に訪れる。
戦を好まず、平和を求めていた劉備が創り上げた国。とはいえ、まだ散発的に戦は続いている状態であるから、その国に、自衛のための手段が備えられていなかった訳ではなかった。だが、その自衛手段は、あくまで『人間相手』の物であった。あの巨大な妖蛇の出現は、何もかもが想定をはるかに越えていた。
それ故に、対応できなかった国は、あっという間に妖蛇によって蹂躙されてしまう。
自分は、何もできなかった。
その国が、妖蛇によって徹底的に破壊されつくして行くのを。
ただ、見ていることしか出来なかった――――。
「その混乱の中、大徳の行方は分からなくなった……。国は、妖蛇によって、徹底的に破壊された……」
「左慈殿……」
「…………」
左慈の話を聞きながら、ハヤブサは、あの『龍の首』が通った後に出来たと思われる光景を思い出していた。『死』と『破壊』の匂いしかしなかったあの光景。あの龍は、まるで生きとし生ける者の『命』すべてを、否定したがっているかの様だった。
「もちろん、人間たちも必死の抵抗を試みた。だが如何せん、妖蛇の力は強力すぎた……」
左慈は淡々と、苦い記憶を話す。妖蛇と、妖魔軍の前に次々と打ち倒されて行った、英傑たちの記憶を。
「あの妖蛇は滅びを求めている。そして、現に――――この世界は、滅びに向かいつつある……」
そのあまりにも圧倒的な破壊力の前に、仙界より遣わされてきた仙人達にも現段階では何も打つ手が無かった。彼らは対策を探るべく、神仙界へと引き上げた。残された人間たちは――――それでも必死に抵抗を続ける。何度敗北を繰り返しても、あきらめずに妖蛇に挑み続けた。
「そして……生き残った『将』と呼べる人間が、ほんの一握りの数しか居なくなってしまった時、神仙界から『かぐや』と言う巫女が、ようやくこの世界に入り込む事に成功した……」
「かぐや?」
まるで、おとぎ話に出てくる人物の名前の様だと思いながら問い返すシュバルツに、左慈は頷く。
「『かぐや』と言う巫女は、人間一人の『時間』を巻き戻す事が出来る……」
それが行われた結果、何が起きるか。
一つの戦いの前に、その未来を『知っている』人間が出現する事になる。この戦いを行った結果、この選択肢を選んだ結果――――未来がどうなるか。それを知っている人間が。
人間は、失敗した経験の中から学び取る。たくさん泣いて、後悔した人ほど、同じ轍を踏まないように考え抜いて――――違う未来を選びとっていくのだ。
そして、その戦いで死んだはずの人間を、助けることが可能になっていく。そうして、少しずつではあるが、この世界の『歴史』が、変わりつつあった。
「人間は再び、力を取り戻しつつある。だがその力は、まだあまりにも小さい……」
やっと、灯り始めた妖蛇に対抗する希望の光。それを、もっと強力に燃え立たせるためには、もっと力が必要な事を、左慈は痛感していた。
だから。
「貴殿らにお願いしたい……。どうか、妖蛇討滅のための我ら討伐軍に、力を貸して頂きたいと」
左慈は、穏やかだが、熱を持った眼差しで、目の前の忍者二人を見つめる。前の歴史では、出会う事が無かったこの縁。これも歴史が変わりつつある事の証明なのだろう。
特に、自分が手を焼いた妖魔を、いともたやすく一刀両断もとに屠ったこのリュウ・ハヤブサと言う人間の力は、絶対に欲しいと左慈は思った。
「どうかこの通り……この左元放、頭を下げて、お願いいたす」
そう言いながら、左慈は、忍者二人に向かって頭を下げる。その左慈の姿に、忍者二人の方が慌ててしまった。
「左慈殿……! どうか面を上げてください! そのような事をなさらずとも我ら二人、左慈殿に同行させていただきますから……!」
「…………!」
左慈は、自分の側に駆け寄って来て、そう声をかけてきたシュバルツと言う青年の顔を見上げる。自分と目が合ったシュバルツは、穏やかな眼差しで微笑みながら頷くと、ハヤブサの方に振り返った。
「いいよな? ハヤブサ」
確認するように問うてくるシュバルツに、ハヤブサも苦笑しながら頷く。
「お前がそう言うのなら……俺に、異論は無い」
元より自分は、あの妖蛇を追うつもりでここに居る。そして、その妖蛇に対抗するための討伐軍が結成され、そこに自分の力が必要だと言ってくれるのなら。
「かたじけない……! では、早速――――」
左慈がそう言いながら立ち上がろうとした、瞬間。
ドォン!!
凄まじい轟音とともに、地震の様な激しい揺れに襲われる。3人ともその場から立ち上がる事も出来ずに、ただ揺れに耐えるしかなかった。
(この揺れは、もしかして……!)
ハヤブサは少し、嫌な予感に襲われる。自分達が東京から今の異世界に飛ばされた時も、似たような揺れを味わったから。
やがて、揺れは収まり――――辺りに静寂が訪れる。
「……あれだけの揺れで崩れないとは……やはり、日本の建築技術は大したものだな」
的を得ているんだが得ていないんだが分からない事を言いながら立ち上がるシュバルツに、ハヤブサも苦笑する。でも、確かにそうなのだ。あれだけの揺れ――――この城が崩壊しなくてよかったと、素直に思う。
「では二人とも……早速小生の後に――――」
そう言いながら二人を外に案内しようとする左慈に、ハヤブサが待ったをかけた。
「その前に、外の様子を確認した方がいい」
「何故だ?」
特に殺気も危険な気配も感じないが、と、問うシュバルツに、ハヤブサは少し眉をしかめながら答えを返す。
「……俺たちが、東京からここに飛ばされた時も――――似たような揺れを感じたんだ」
「―――――!」
ハヤブサの言葉に左慈は弾かれる様に窓の外を見て――――額に手を当てながら、ため息をついた。外の景色が一変してしまっていたからだ。先程まで見えていた摩天楼の景色が消え――――今度は、辺り一面『砂漠』に覆われてしまっている。
「こ、これは……!?」
茫然とするシュバルツに、左慈は首を振りながら答える。
「あの妖蛇が現れてから、この世界は………崩壊へと向かいつつある。特に、妖魔の瘴気が濃いこの辺りは、地軸も時間軸も不安定なのだ……」
だから下手をしたら、このまま時の狭間を彷徨い続ける事になりかねない。最悪の場合、この世界の消失に巻き込まれて、自分の存在そのものが消えてしまう事だってあり得る。
「……そんな危険な場所と知って――――何故貴殿は、ここに居たんだ?」
問うハヤブサに、左慈はふっと、穏やかな微笑みを返す。
「そうだな……小生は求めていたのかもしれん……。このような『縁(えにし)』を」
滅びに瀕した前の歴史では出会えなかった縁を。あの強力な妖蛇に対抗し得るだけの力を。
人一人の時間を巻き戻せる力によって、生まれ出てきた希望。今は時間を巻き戻せる人間の数も少なくて、戻れる時間も救える人間も限定的だが――――少しずつでもその細い糸を手繰り寄せて行けば、いつか救えなかった大徳も救えるようになるかもしれない。それが左慈の最終的な望みだった。
「それに出会った今……いつまでもここに居る理由は無い。早速皆の居る所に案内致そう。幸い、かぐや殿から、『縮地の札』を頂戴しておる故――――」
そう言いながら、左慈は懐からかぐやからもらった札を取り出す。かぐやの話によればこの札は一度だけ、札を持つ者をかぐやの側に運ぶ事が出来る物らしい。ただそのためには、時間と地軸の波を越えて行く必要があった。
(かぐや殿は、こうなる事を見こしておったのかもしれぬな……。感謝せねば……)
札を見つめながら、左慈は聡明な巫女かぐやに思いを馳せる。
「時間の波の中で、はぐれたら大変だ。各々が手を取り、小生からはぐれぬようにしてもらいたい」
左慈の言葉に忍者二人は頷くと、まずハヤブサがシュバルツの手を取り、それからハヤブサの方が左慈に手を差し出してきた。左慈も頷きながらその手を取ると、かぐやからもらった縮地の札を眼前に構え、『気』を込める。左慈の方術の発動だった。
「―――では、お二人とも……。参りましょうぞ―――」
左慈の言葉と共に、縮地の札が光を放ち始めた。
札の輝きを確認しながら、左慈の手は、札と共に印を結ぶ動きをする。
「梵!」
叫ぶと同時に左慈が札から手を離すと、札はそのまま空中に固定されていた。そこから四方にわたって光の筋が伸びて行く。その光は、3人をぐるりと取り囲むような動きをしながら、その本数を増やして行った。
「これは?」
問うハヤブサに、左慈は振り返らずに答える。
「結界じゃよ……。時空の世界は妖魔が潜む場所でもあるし、その波にのまれてしまったら、本当にどこのどの世界に飛ばされてしまうかも分からぬ……。そうならぬための、備えの様なものだ」
左慈の言葉にシュバルツは(なるほど)と、納得する一方で妙な違和感も感じていた。
何故だろう?
ハヤブサに掴まれている方の手が――――ちくちくと痛い。
それに、妙な息苦しさも感じる。
「どうした? シュバルツ」
ハヤブサに呼びかけられて、シュバルツは、はっと、我に帰る。
「何でもない」
慌てて笑顔で取り繕う。ただでさえ、彼に迷惑をかけてしまっている自分。これ以上、彼に心配をかけられない。足手まといになっては駄目だと思った。
そんなシュバルツを少し訝しく見つめていたハヤブサであったが、彼も少し、違和感を感じていた。
おかしい。
どうして――――シュバルツの手を握っている方の手が、こんなにも痛むのだろう?
この状況で、俺もシュバルツも、手に何かを仕込むはずもないのに。
「ム………」
結界を練り上げる作業をしている左慈も、また戸惑っていた。
あと少しで、この結界は完成する。なのに何故か――――最後の一枚扉に等しい結界の壁を、どうしても閉じ切る事が出来ない。
妙だ。
この結界の完成を阻む、この違和感の塊は、『何』だ?
左慈は、魔よけの結界を完成させようと、懸命に『気』を込める。
だが、左慈の目の前に立ちはだかる違和感の塊は、彼が結界を作り上げようとするのを頑なに拒んだ。
そうこうしている内に、目の前にブオン、と、音を立てて『時空の道』が現れる。左慈の目の前で固定されていた札が、吸い込まれるようにその道の中へと入っていく。
(已むを得ぬか……)
左慈は少し深いため息をつきながら、動いて行く札を見つめる。
もうかぐやの『縮地の札』の術は、発動してしまっている。結界がしっかり閉じ切れていないのが気にかかるが、あの札を見失う訳にもいかないと思った。
仕方がない。
閉じ切れなかった結界は、時空の道を歩きながらでも、閉じるしかない。
「では―――御二方とも、参ろう」
左慈は後ろの忍者二人に声をかけると、札の後から時空の道へと一歩、足を踏み入れていた。
そこは不可思議な世界だった。
暗い場所なのだが、周りが見えない訳でもない。激しい乱流の様な流れが見え隠れしていて、その向こうに――――様々な『場所』や『人』や『物』が、走馬燈の様に現れては猛スピードで消えて行く。これこそが『時間の流れ』であり、巻き込まれてしまったならば、ただでは済まないだろうと言う事が、容易に想像できた。
「吩!」
そんな中、左慈はもう一度結界を閉じようと、術にありったけの『気』を込める。その、刹那――――
「うわあああああっ!!」
後ろから激しい悲鳴が上がったが故に――――左慈は『違和感』の正体に気づく事が出来た。
「何と……!?」
振り返って、絶句する。
何故なら、自分の作った『結界』が――――シュバルツに向かって攻撃を仕掛けていたからだ。幾重にも重なった光の帯がシュバルツを取り囲み、この結界の中から邪魔者として『排除』しようとしている。
「シュバルツ!? ――――うぐッ……!」
当然、結界の攻撃はハヤブサにも及んできた。彼が、シュバルツを離そうとしないが故に。
「左慈!! これは一体、どういう事だ!?」
結界の攻撃に抗いながら、ハヤブサは叫ぶ。
「い、いや……どういう訳か、小生にもよく――――」
左慈も、咄嗟に何が起こっているのか理解できなくて、ただ茫然とするしかなかった。
どういう事だ?
自分は、ただこの二人を時空の波から守りたくて、この結界を張ったと言うのに。
それが、何故――――
「…………!」
その瞬間、彼の『法力』が、シュバルツの正体を捉える。
左慈には見えてしまった。
シュバルツの、身体の中が。
『人間』とは違う―――――機械だらけの、身体の中身が。
「馬鹿な――――!! そなた、人間ではないと言うのか!?」
左慈は思わず、悲鳴のような叫び声を上げてしまっていた。
「そうだ……! シュバルツは人間ではない!! それが何か、問題でもあるのか!?」
叫ぶハヤブサに、左慈は頭をふる。
「小生の結界は『人間』を守るために作られたものだ……。故に、『人間』以外の存在がこの結界の中に入るのを、拒絶する仕組みになっておる……」
「な――――!」
絶句するハヤブサに、左慈も苦い顔を見せるしかない。
不覚だった。
あのシュバルツと言う青年からは、全く『魔』の気配など感じなかった。寧ろ彼から漂う気配は、清々しい程に澄み切っていたから――――。
だから、自分は全く疑いもしなかった。
彼が『人間ではない』と言う可能性など、微塵も考慮しなかった。
自分の見通しが甘すぎた事に、左慈は激しく後悔する。
何と言う事だ。
次元の道に入る前に、もっとよく確認するべきだった。
これは100%、こちらのミスだ。
「う……! ぐ……ああっ!!」
バチバチと音を立てて容赦なくシュバルツを攻撃していた光の帯たちが、遂に、彼を結界の外へと放り出してしまう。彼の身体は時間の奔流に引っ張られ、そのまま流されて行きそうになった。
「シュバルツ!!」
それをハヤブサの手が拒んだ。彼は結界の中から手を伸ばし、流されて行きそうになるシュバルツの身体を必死に繋ぎ止める。
だが、ハヤブサのその行為を、閉じようとする結界の『術』が許すはずもない。術を完成させるために障害となっているハヤブサの手を、容赦なく攻撃し始めた。
「ううっ……! ぐ……!」
シュバルツを掴んでいるハヤブサの手に、白い光の帯が集まり、バチバチと激しい音を立てている。
(いかん―――!)
事態を楽観できないと察知した左慈は、何とか術を立て直そうとする。しかし、今更結界の性質を、組みなおすことなど不可能に近かった。しかも、自分が術を強化しようとすればするほど――――シュバルツを拒絶する力が強くなって行くだけだと悟る。
「ハヤブサ!!」
ハヤブサの身を案じて、シュバルツから悲鳴の様な声が上がる。
「案ずるな!! この程度……問題ない……ッ!」
「しかし―――!」
「お前は……俺の事より、自分の事を……考えろッ!!」
「…………!」
「今……実質的に危険に曝されているのは……! お前の方だぞ!?」
嵐の様な時間の奔流の中に曝されているシュバルツの身体。これに巻き込まれてしまったら――――いくら『死なない』身体を持つシュバルツとはいえ、どうなってしまうか分からない。
それに俺は、自分に誓った。
『絶対にシュバルツを、独りにはしない』と。
だから、俺はこの手を離さない。
誰に何にどう否定されようとも。
絶対に――――だ。
バシン、バシン、と、音を立てて光の帯がハヤブサの腕を叩く。シュバルツの手を握っている自身の手にも、酷い痛みが走る。その手を離せ、離せ、と、訴えてくる。
「う……! く………!」
「ハヤブサ!!」
再びシュバルツが案ずる様な叫び声を上げる。
何故だ。
何故、そんなに心配そうに――――俺を見つめている?
こんな痛みなど、何ともないものなのに。
この手が、離れてしまう恐怖に比べたら。
お前を、失ってしまう恐怖に比べたら――――
「リュウ・ハヤブサよ……」
左慈の呼び掛けに、ハヤブサは睨みつけるように振り向く。
「シュバルツの手を離せ、と、言うのなら……俺は、受け付けんぞ……!」
「分かっておる……」
左慈は、ハヤブサに答えを返しながらほぞを噛む。
本当ならば方術師として、ハヤブサに『その手を離せ』と言わなければならない事を、左慈はとっくに自覚している。
だけど、左慈自身も―――それを言う事が出来なかった。
何故ならシュバルツは、自分を助けてくれた―――いわば『恩人』だ。
頭を下げた自分にすぐ駆け寄って来て、共に行く事を同意してくれた青年でもある。
そんな心優しい青年を、時空の嵐の中に放り出すような真似など、左慈自身にも、できようはずが無かった。
しかし――――
「俺たちは、このままでいい!」
手に襲いかかる激しい痛みに耐えながら、ハヤブサは叫ぶ。
「このまま何とか――――この時空の道を、抜けられないのか!?」
「それは無理だ……」
ハヤブサの問いに、左慈はそう答えざるを得ない。
「結界が閉じれぬ事によって、かぐや殿の『縮地の札』の術にも、ほころびが生じている……。それを直さぬ限り、この道を前に進む事は出来ぬ」
「ならば、俺の手を離せ!!」
左慈の答えに、ハヤブサは即答を返す。
「――――!」
「俺は……シュバルツと共にある方を選ぶ……! 悪いが、俺たちの事はあきらめてくれ……!」
「何と………!」
ハヤブサの言葉に、左慈は息を飲むしかない。
何と言う事だ。
このハヤブサと言う青年は――――それほどまでに、このシュバルツと言う青年の傍に居る事を望むのか。自身が時空の乱流に巻き込まれても、構わない、と言うほどに。
「お前ひとりならば、ここを切り抜けられるだろう……? さあ、手を離せ!!」
「……悪いが……それも、無理だ……」
「…………!」
今の左慈は、ハヤブサの言葉を否定し続けることしか言えない。それが情けなくて――――左慈はいつしか、唇を噛みしめていた。
「そなたの身体は、既に、小生の術に組み込まれておる故――――」
そう言いながら左慈は、憂いを帯びた眼差しでハヤブサを見つめる。
実はもう、ハヤブサが先程から何度も何度も、自分の手を振り払おうと試みているのを、左慈は知っている。だが、どんなに足掻こうとも、自分とハヤブサの手が離れる事は無い。何故なら――――。
「……どういう、事、だ……?」
眉をひそめながら問いかけてくるハヤブサに、左慈は静かに答える。
「そなたの身体と小生の身体は、既に、『結界の一部』と、言う事だ」
結界を作り上げる時、左慈は、時空の波にさらわれてしまったとしても、互いの身体が離れる事が無いように、身体の中にも術を通して繋がりを編み込んだ。その編み込みの糸を、シュバルツの身体にも届かせようとして、人間ではない彼の身体が、それを弾いていたのだと――――今となってはよく分かる。
術を組み上げる時に感じた軽い『違和感』を、どうしてあの時自分はもっと突き詰めなかったのか。苦すぎる後悔を、噛みしめる。
だが―――今となっては、何もかもがもう遅過ぎた。
「小生の『結界の術』が、そなたの身体の中深くにも、編み込まれておる故――――」
「な………!」
「そなたがシュバルツ殿と繋いでいる手に、激しい痛みが走っているのではないか?」
「…………!」
「それこそが、そなたの身体に結界の術の作用が働いている、何よりの証拠だ……。だから今、この結界を無理に壊そうとしたら、小生の身体もそなたの身体も――――」
「黙れ!! それ以上口を開くな!!」
ハヤブサは、思わず叫んでいた。
それ以上先を聞いてしまったら、シュバルツは『選んで』しまう。
自分の身を犠牲にして、周りを助ける方を――――。
そんな事、させたくは無かった。
「く……そ………ッ!」
自分の手が激しく痛む事に、ハヤブサは憤りを覚える。
「ふ……ざ、ける……な……ッ!」
俺は、愛おしいヒトに手を伸ばしているだけだ。
なのに、俺の身体がシュバルツを拒絶しているだと……?
冗談じゃない。
俺は、絶対にシュバルツを離さない。
拒絶なんか、して、たまるか――――!!
「ハヤブサ……」
呼びかけられて顔を上げると、酷く穏やかな顔をして微笑む、愛おしいヒトと視線が合った。ただ、それを見たハヤブサは、猛烈に嫌な予感に襲われた。
条件が、揃いすぎている。
シュバルツが、己の身を犠牲にしようとする条件が――――。
「シュバルツ……! 手を、離すなよ……!」
念を押すようにシュバルツに声をかける。それに対してシュバルツは、にこ、と、その顔に人懐こい笑みを浮かべた。
「離さないよ」
「…………!」
優しくそう言われて、ハヤブサは少し拍子抜けする。
「そうか……? なら、良いが………」
少し戸惑い気味に言葉を紡ぐハヤブサに向かって、シュバルツからもう片方の手が伸ばされてきた。その手は、二人を繋いでいる手に、そっと優しく添えられてくる。
だがその瞬間、二人の間に激痛が走ったので、忍者二人は悲鳴を懸命にかみ殺さなければならなかった。
「う………!」
「くぅ………ッ!」
(くそっ……! 一体、何なんだ……!)
ハヤブサは、悔しくて唇を噛みしめる。
愛おしいヒトは、ただ優しく触れてきているだけのに――――どうしてこんな、耐えがたい痛みを感じなければならないのだ。
嫌だ。
こんなのは――――
哀しすぎる。
「ハヤブサ……」
愛おしいヒトは、ハヤブサの手を慈しむように包み込んでいる。
だが、酷い痛みも同時に感じているのだろう。彼の端正な眉が、少しひそめられていた。
それでも優しく微笑み続けるシュバルツは――――素直に美しい、と、感じた。
「お願いだ……。私の質問に、答えて、くれないか……?」
ぽつりと、落とされる様に紡がれる言葉。どうしても、ハヤブサの中の嫌な予感がかき立てられる。だけど「何だ?」と、問い返した。シュバルツの言葉一つ一つすら、時空の波の間に落としてしまいたく無かった、から。
「ハヤブサは……私が『不死』である事を、受け入れてくれたよな……。そして、そんな私に『愛している』と……言ってくれたよな……」
「―――――!」
「……今でも、そうか……?」
優しいが、憂いを帯びた眼差しで、シュバルツはこちらを見つめてくる。
「……今でも……お前は……そう、思って……くれているのか……?」
「シュバルツ―――!」
何故、シュバルツがこんな質問をしてきたのか。ハヤブサは、咄嗟にその真意を測りかねる。
だけど、どういう訳か胸が詰まった。
何故だシュバルツ。
何故――――今更俺の気持ちを確かめる様な事を聞くのだ。
俺はもう、何度もお前にそう言っているのに。
俺が愛するのは、後にも先にもお前ただ1人だと言う事を。
なのに、どうしてそれを聞く?
俺の言ったこと――――お前は、信じていないのか?
「――――『その言葉』を、今、所望か……?」
問い返すハヤブサに、シュバルツはにっこりと微笑んだ。
「ああ……。私は貪欲だからな……」
「シュバルツ……!」
「今――――『その言葉』が、欲しいんだ」
「―――――ッ」
『その言葉』を言うくらいなら、いくらでもできる。だけど、今言うのは躊躇われた。
儚げな、綺麗な笑みをその面に浮かべているシュバルツ。
猛烈に、嫌な予感がかき立てられた。
「……ハヤブサ……」
ハヤブサが黙っていると、シュバルツからもう一度、呼び掛けられる。
「シュバルツ……」
「お願いだ……言ってくれ……『その言葉』を……」
「…………」
ハヤブサは、言葉を返す事が出来ない。言ってしまたら最後、シュバルツが離れて行ってしまいそうな気がする。
「……駄目か……?」
シュバルツの声音に、懇願の色が濃く混じる。本当に今―――『その言葉』が、欲しいのだろう。
「…………ッ!」
だけど、嫌だ。
言えない。
言ってしまったら、お前は――――
「そうか………」
まるで、何かをあきらめるように、シュバルツがその瞳を閉じる、から。
「待てっ! シュバルツ!!」
ハヤブサは思わず、弾かれるように叫んでいた。
「……愛している……!」
「…………!」
ハヤブサのその言葉に、彼の後ろにいた左慈は思わず息を飲む。だがハヤブサは、構わず続けた。自分のこの気持ちは――――嘘偽りのない正直な気持ちだ。だからもう、誰に聞かれようが、どう思われようが――――ハヤブサは別に構わないと、思った。
自分は、もう何も要らないのだ。
シュバルツが、傍にいてくれさえすれば。
「愛している……! だから、絶対に手を離すな!!」
祈る様に、ハヤブサは叫ぶ。
例え、どんなに否定されても。
何を犠牲にしてでも。
自分は絶対に――――この手を離したくないと、願う。
「絶対に……俺から離れようなんて……考えるな……!」
シュバルツと繋がる手に、ぐっと力を込める。痛みで痺れて、もう半ば感覚が無くなって来ている手。だけどまだまだ――――自分はシュバルツを離す気は無かった。
キョウジを失ったばかりで、その傷がまだ癒えていないお前。
それを『独り』にだなんて――――出来ようはずがない。
「ハヤブサ……」
穏やかな笑みを浮かべるシュバルツに向かって、ハヤブサは尚も叫び続ける。
「……愛している……!」
たとえ、同じ言葉がシュバルツから返って来る事は無いと、分かっていても。
この言葉は、時空の波に向かって、一方的に消耗されるだけの物だとしても――――。
「愛している……! シュバルツ……!」
お前が、『欲しい』と言うのならいくらでもやる。こんな『言葉』でいいのなら、いくらでも――――。
だから。
だから、シュバルツ……!
「ハヤブサ……」
穏やかに微笑むシュバルツのその瞳から、一滴の涙が零れおちる。
「…………!」
驚き、息を飲むハヤブサに向かって、シュバルツが口を開いた。
「嬉しい……。ありがとう、ハヤブサ……」
「シュバルツ……!」
愛おしいヒトが、あまりにも酷く綺麗に微笑むから、ハヤブサは息が詰まりそうになる。
止めろ。
止めてくれ。
こんな時に……。
そんなに綺麗に――――笑わないでくれ……!
「ハヤブサ……。私も……お前の事を――――」
「シュバルツ!! 待て!!」
「―――――」
時空の嵐の中で、『その言葉』は、確かに、ハヤブサの耳に届いた。
「あ…………!」
『その言葉』に、ハヤブサが茫然とした、刹那。
ドカッ!!
シュバルツは懐に忍ばせていた短刀を一閃させて、ハヤブサと繋がる自らの腕を、斬り落として、いた。
「――――!!」
そのままシュバルツの姿は、息を飲み絶句するハヤブサの視界から、あっという間に時空の流れに呑まれて消えた。何もかもが、一瞬の出来事だった。
「あ………! あ………!」
ハヤブサは、ただそこに残された、シュバルツの手を見つめる。
何も言えなくて、何もできなくて、息の仕方すら、忘れそうになって。
それでも主を失くしたその手が、しっかりと自分の手を握っていたから――――
「シュ、バ……ル…ツ……」
切なさが、愛おしさが、哀しみが――――胸を、かきむしった。
(何と……あの青年は……!)
ハヤブサの後ろで一部始終を見つめていた左慈も、ただ茫然とするしかなかった。
この状況。あの青年が自らを犠牲にしなければどうする事も出来なかった。だがそれを、何の躊躇いもなくやってのけてしまうとは―――――。
あのシュバルツと言う青年は、間違いなく『魔』と呼ばれる様な存在ではない。だが皮肉な事に、彼が居なくなってしまった事によって、かぐやの縮地の術を阻む物も、自分の結界の完成を阻む物も無くなってしまったのは事実だ。現に、左慈が軽く『気』を込めるだけで、簡単に結界は修復してしまう。
それと同時に、ハヤブサの手に残されていたシュバルツの手が、パン、と、乾いた音を立てて粉々に砕け散った。
「あ………ッ!」
ハヤブサは、シュバルツの『手』だった物が光の粒子となって、きらきらと光を放ちながら結界の外に出て行くのを――――茫然と見守るしか出来なかった。ハヤブサの手元には、ただ、シュバルツがつけていた白い手袋だけが――――残された。
「……シュバルツ……!」
哀しみに沈むハヤブサから零れ落ちる言葉。左慈はそれを、拾い上げる事が出来なかった。
「…………」
ただ無言で術を練り直し、時空の道を抜ける作業に集中していた。こんな場所は、早く抜けなければ、と、思った。
紛れもなく自分が、あの二人を引き裂いてしまった。
そう言う苦い後悔だけが、左慈の胸に残った。
暗い時空の道を抜け、二人の身体は明るい光に包まれる。
足元にしっかりとした地面の感触を得て、周りの景色も固定される。それは、安定した時間軸の中にたどり着いた事を、二人に示していた。
「…………」
周囲の安全を確認してから、左慈は結界の術を解く。左慈と繋がれていた自分の手が、自由になったと悟ったハヤブサは、多少乱暴に左慈の手を振り払っていた。
「ここは……京の『五条大橋』と、言う場所だ……。そして、その向こうに見える奇妙な建物群の中に、おそらくかぐや殿が居る筈だ……」
左慈の言葉にハヤブサが振り返ると、確かに、古い日本の町並みの景色の向こうにあるには不似合いな、高層ビルの群れが林立していた。だが――――来た時に見たニューヨークの摩天楼とは、また違ったビル群だった。どちらかと言えば、香港辺りの景色と言われた方が、しっくりくる。
「……………」
無言でビル群を眺めるハヤブサを、左慈もじっと見つめていたが、やがて、意を決したように彼に声をかけた。
「……小生を、斬るかね?」
「………何?」
振り返るハヤブサの視線をまっすぐ受け止めながら、左慈は言葉を続ける。
「シュバルツ殿を、あんな目にあわせてしまったのは……間違いなく、小生のミスだ……。だから、もし――――そなたがそれを、許せない、と、言うのであれば――――」
斬られても仕方が無いし、文句も言えない、と、左慈は思う。
ただ、斬られるのであるならば、少しの間だけ、猶予が欲しいと左慈は願った。
せめて、妖蛇討伐のために集まりつつある人間たちの元に、彼を連れて行くまでの間だけでいい。自分の命を存(ながら)えさせて欲しかった。
彼が、仲間に加わる事を確認した後ならば、自分はもう、斬られてしまっても構わない。左慈はそう思うほどに、このリュウ・ハヤブサと言う忍者の腕に、価値を認めていた。
「……………」
そんな左慈を、しばらくじっと無言で見つめていたハヤブサであるが、やがて小さなため息と共に、左慈から視線を逸らした。
「……シュバルツは、おそらくそんな事を望まない。だから俺も、お前を斬らない」
「…………!」
驚き、息を飲む左慈の気配を感じながら、ハヤブサはなおも言葉を紡ぐ。
「それに、シュバルツの事なら―――ある意味、心配はいらない」
「……? と、言うと……?」
ハヤブサの言葉の意味を図りかねて、眉をひそめる左慈に、ハヤブサは説明を続ける。
「あいつは『不死』だ」
「な…………!」
そう。
『キョウジの死』という制約が外れてしまった今の彼は、完全に『不死』の存在だ。
「だからあいつは、絶対に生きている……。どこに居ようと、どんな状況にあろうとも……」
左慈に――――と、言うよりは、自分に言い聞かせるように、ハヤブサは言葉を紡ぐ。
そうだ。
絶望する事も、悲観する必要もない。
あいつは、必ず生きているんだ。ならばこの先、再び巡り合う可能性も、決して零ではないではないか。
(それにしてもあいつ……! どう言うつもりで俺に『あの言葉』を言ったんだ……!)
腕を斬り落とす直前、シュバルツは確かに言った。
「愛している……」
ちゃんと聞こえた。彼の唇も、確かにそう動いていた。
どう言うつもりだシュバルツ。
今までどんなに散々蕩けさせて『その言葉』をこちらが要求しても――――絶対に、言ってはくれなかったのに。
なのに、何故。
あんな時に。あんなにあっさり。しかも素面で――――!
「愛している……」
何故だシュバルツ。
何故あのタイミングで、俺に『その言葉』を渡した?
「俺と話せるのは、これが、最後」
まさか、そう思ったからじゃないだろうな。
冗談じゃない。
ふざけるな。
「愛している」と言っておいて、そのまま言い逃げするなんて、この俺が許さない。
おまえがどこに隠れようが潜んで居ようが、絶対に見つけ出して、嫌と言うほど抱いてやる。
そして、泣いたって喚いたって、もう2度と離してなんかやらないからな。
覚悟していろ。
忍者の執念深さを、舐めるなよ――――!?
「ハヤブサ殿……?」
窺う様に左慈に声を掛けられて、ハヤブサもはっと、我に帰った。
「あ、ああ……何だ?」
「ハヤブサ殿は……」
「ハヤブサでいい」
ハヤブサは、多少ぶっきらぼうに左慈にそう返した。『殿』付きで呼ばれるのは、何となく落ち着かない気持ちになる。
「ではハヤブサ……。そなたは、これから――――」
「……討伐軍の所に、案内してくれるのではないのか?」
「…………!」
ハヤブサの言葉に、左慈は驚きを隠せない。あの二人を引き裂いてしまったも同然の自分。そんな自分の願いなど、反故にされても仕方が無いと思っていたのに。
少し驚いた後、黙りこくった左慈を見て、ハヤブサも何となく彼の想いを察知した。
「シュバルツを捜索する事を、あきらめる訳ではない。だが……俺の本分は、あくまで『妖蛇を退治する事』だ」
「…………!」
「だから、そちらを優先させるだけの事だ。それに……『時間を巻き戻せる』と言う巫女の能力(ちから)にも、少し興味があるしな……」
左慈の話では、この巫女の能力によって、運命が変わり、助け出された人間たちも既に何人かいるとのことだった。
ならば。
ハヤブサは思う。
あの運命を変えられないだろうか? シュバルツとキョウジの上に降りかかった、あの悲劇を。
首の無いキョウジの遺体に縋って泣くシュバルツの姿を、『無かった事』には出来ないだろうか。
キョウジの死には、あの妖蛇が強く関わっている。だから、その妖蛇を倒したうえで、もう一度、『あの時間』に自分が戻る事が出来るのなら――――。
否定できるかもしれない。あの運命を。止まってしまったキョウジの時間を、再び取り戻す事が、出来るかもしれないのだ。
自分でも、ばかみたいな夢を見ていると思う。
分かっている。普通なら、無くなった命は、二度と返ってこないものなのだから。
だけど、もしも、あの運命を変える道があると言うのなら――――
どんな事をしてでもいい。その為に、自分がどうなろうとも、何を犠牲にしようとも構わない。
あの運命を否定する未来を、選びとりたい、と、ハヤブサは願っていた。
「ふむ………」
しばらく推し量る様にハヤブサの顔を見つめていた左慈であったが、やがて、彼なりに得心したのか、頷いた。
「あい分かった。ならば、かぐや殿の所にご案内致そう。……シュバルツ殿の捜索は、小生も出来得る限り協力致す故」
「ありがたい」
左慈の言葉に、ハヤブサは素直に頭を下げた。時空の波の中に見失ってしまったシュバルツの姿。『生きている』と確信が持てるとはいえ――――この地形も時間軸も目茶苦茶になっているこの世界で、どこに飛ばされたかも分からないシュバルツを探し出す事は、困難を極めるだろうこと――――ハヤブサは、充分に予見できていた。さながら大海の中に落としてしまった、一粒の真珠を探し出す様なものだ。だから、協力者は1人でも多い方が、素直にありがたかった。
だけど、必ず会える筈――――ハヤブサは、強くそう信じることにした。
死なない身体を持つシュバルツ。そして、この妖蛇の影響が色濃くにじみ出るこの不安定な世界。その中で、シュバルツの剣の腕、知略、力量――――放っておかれる筈がない。
必ずあいつは、世に出てくる。どんな所に居ようと、どんな形であろうと。自分は、それを捕まえれば良いだけの話だ。
絶対に、逃がさないからな。シュバルツ。
覚悟してろよ――――!?
「それではハヤブサよ……参ろうか」
左慈の言葉にハヤブサも頷き、五条大橋を渡りかけた途端。
「待て待て待て待てい!!」
いきなり大音声で呼び止められた。
足を止めた二人の前に、身の丈9尺はあろうかと思われる、大男が立ちはだかった。
「そこの二人、待てい! 特に、そっちの黒装束のお前! 足を止めろ!!」
「…………!」
名指しされたも同然なハヤブサは、少し舌打ちしながら足を止める。
「……何用だ? 急いでいるのだが」
「急いでいるのか? なら、そんなに長く引き留めはしない。俺様の用事は、すぐ済む」
そう言いながら大男はにやりと笑う。その男は、白い頭巾をかぶり、僧兵の様な格好をしていた。手には、その巨躯にしても更に不釣り合いに感じるほどの、巨大な篭手がはめられている。
「すぐに済む……と、言うと?」
問う左慈に、その男は、フン、と、鼻を鳴らして答えた。
「その黒装束の男が刀を置いて行ってくれたら――――ここを通してやるよ」
「――――!」
自分の愛刀を要求してくる身の程知らずな大男に、ハヤブサの端正な眉が一瞬釣り上がる。
「俺様は、武器の収集が趣味なんだ」
だが、大男の方も、ハヤブサの鋭い一瞥に怯むどころか、悪びれもせずにさらに要求してくる。「武器の収集が趣味」と言うだけあって、彼の背中に背負われている葛篭(つづら)の中には、沢山の武器が収められていた。
「お前の刀が、さっきから妙な『気』を放っているのを感じる。ぜひ、俺様の手持ちに加えたい」
「…………」
酷く不躾な要求をしてきた大男をハヤブサは静かに見つめていたが、やがて、小さなため息と共に、大男から視線を逸らした。
「……この刀は、そんな生易しいものではない。とにかく、先を急ぐ。通らせてもらうぞ」
そう言うとハヤブサは、構えることすらせず、全く無造作に歩き出した。あまりにも無防備に大男との距離をハヤブサが詰めてくるから――――男の方も、一瞬虚をつかれたような格好になる。
「―――へえ。良い度胸をしているじゃないか……」
男は笑いながらそう言ったが、内心は腸(はらわた)が煮えくりかえっていた。
(野郎! 俺様の言う事を無視かよ!? 舐めやがって……!)
そうこうしている間にも、ハヤブサがどんどん自分に近づいてくる。刀を構えるでも、自分に警戒するふうでもなく、本当に横をすり抜けようとしている風情に、男の怒りはますます煽られてしまう。
(見てろよ―――! 近くに来たら、有無も言わさずブッ飛ばしてやる!!)
男はそう決意すると、自身の肺に、深く息を取り込んだ。向こうがその気なら、こちらもぎりぎりまで何気ない風を装ってやる。あの黒装束の男が自分の横に来た瞬間を、狙うのだ。ぶっ飛ばして、川の中に落としさえすればこちらの物だ。泳ぎなら、誰にも負けない自信があった。
目の前の大男がそのような事を考えていると気づいているのかいないのか――――ハヤブサの無防備な歩む姿は変わらない。すたすたと歩くハヤブサの身体が、大男の横に、まさにすれ違おうとした、その瞬間。
ドンッ!!
大男の籠手とハヤブサの龍剣が、激しい音を立ててぶつかり合った。ぶつかり合った衝撃で周りの空気が揺れ、橋が激しい音を立てて軋んだ。
「……へえ、小さい割には強いんだな……! ぶっ飛ばすつもりでいたのに……ッ!」
籠手でハヤブサの龍剣とぎりぎりと鍔迫り合いをしながら、大男がにやりと笑う。
「………ッ!」
(それはこっちの台詞だ……! この……! 馬鹿力、め……ッ!)
ハヤブサも大男を橋の上から叩き落とすつもりで、龍剣を振るった。なのに――――受け止められてしまった。しかも、籠手で刀を押し返してくる力は、こちらと互角か、それ以上の物だ。
二人の間でぎりぎりと音を立てて、全く動かなくなってしまった龍剣と籠手。このまましばらく、膠着状態に陥ると思われた、その矢先。
「…………」
大男の顔が、にやりと凶悪に歪むと同時に、籠手から「ガチャリ」と、不吉な音がする。
「――――!」
ハヤブサがそれに気づいて顔を上げると同時に、その籠手からいきなり火球が発射された。
ドォン!!
橋の上で火球が、派手な音を立てて爆ぜる。
「な………!」
その攻撃を全く予想だにしていなかった左慈は、思わず息を飲んだ。今の一撃、ハヤブサは避けられたのであろうかと危惧してしまう。
「はっ! やったぜ!!」
大男は、自分の勝利を確信していた。鍔迫り合いからのこの攻撃――――今までこれをかわした人間を、自分は1人しか知らない。そして、そんな腕を持つ人間など、そうそういる筈もない事を、大男は熟知していた。
(すぐ近くに奴の身体は転がっていないな……。川にでも落ちたか?)
大男がそう思いながら、欄干から川を覗き込もうとした瞬間――――いきなり背中に背負っている葛篭の鎖が切れて、背から滑り落ちた。
「――――何っ!?」
地面に落ちた葛篭から、集めた武器が派手な音を立てて転がる。振り返った大男の視界に、欄干の上にストン、と、バランスよく着地する、龍の忍者の姿が飛び込んできた。
「…………」
そのハヤブサの姿を認めた大男の顔が、不意に真顔になる。構えていた籠手を下におろして、戦闘姿勢を解除した。
葛篭の鎖が切れたと言う事は、あの男には、自分を斬るチャンスが在ったのだ。この勝負、完全に自分の負けだと大男は悟る。この攻撃をかわされたのは、これで、2回目だ。
「やるな……。俺様の籠手のからくり、よくぞ見破った」
素直に相手の技量を認めるしかなかった。
「……………」
大男の言葉に、ハヤブサは特に返事をしなかった。自分はその手合いの武器と戦う事が初めてでは無かった故に、対処できた。ただ、それだけのことだと思った。裏を返せば、齢24歳にして、ハヤブサが既に、それだけの実戦経験を重ねてきたことを意味する物でもある。
「俺様の攻撃をかわしたお前に敬意を表して……名を聞いておこうか」
そう問うてくる大男の視線は、あくまでまっすぐで真剣そのものだった。それを無下にする理由が、ハヤブサの方にも特に無かったので、名乗りを上げる事にした。
「我が名は、リュウ・ハヤブサだ」
「リュウ・ハヤブサか……なるほど……」
大男の方も、にやりと笑うと、名乗りを上げた。
「俺様は、武蔵坊弁慶だ」
「弁慶?」
大男の正体が「弁慶」と分かって、ハヤブサは思わず素っ頓狂な声をあげてしまう。
まただ。
また――――歴史上のちょっとした有名人と、邂逅してしまった。と、言うか……。
「『実在』したのか……?」
つい、こんな変な言葉を呟いてしまう。それもそのはずで、『武蔵坊弁慶』とは、一時期、歴史学上で、その実在すら疑われた人物であったのだから。
だが当然、弁慶の方はハヤブサの言っている言葉の『意味』が理解できない。
「何だって?」
怪訝な顔をしながら問い返してくる弁慶に、ハヤブサもはっと、我に帰る。
「あ、ああ……済まない……」
謝りながら、ハヤブサは慌てて欄干から橋の上へと飛び下りた。自分が本当にかなり変な言葉を呟いてしまった事に気がついて、自身の背中から変な汗が滴り落ちるのを、止める事が出来なかった。
しかし、武器収集癖のある、怪力の僧兵――――言われてみれば、目の前の男はこれ以上ないと言う程「武蔵坊弁慶」の特徴を醸し出していたのに。どうしてそれに気づかなかったのかと、ハヤブサは少し自分で自分を揶揄してしまう。いつの間にか、彼と戦う気も、ハヤブサの中から失せてしまっていた。
それにしても、「弁慶」がここにいる、と言う事は――――。
「源義経はどうした? 一緒ではないのか?」
好奇心に負けて、つい、こんな事を口走ってしまう。
だが、「武蔵坊弁慶」と言えば、源義経を敬愛し、その生涯を義経と共にした事で有名な将でもある。その弁慶が、義経から離れるなど、ハヤブサからしてみれば考えられない事だと思った。だから、そう聞いてみたのだが。
「―――義経様を、知っているのか!?」
ハヤブサの言葉に、弁慶の方が弾かれた様に反応した。
「ああ、いや……『知っている』わけでは、ない………」
弁慶の縋るような眼差しに、ハヤブサは戸惑ってしまう。もしかして、彼の前でこれは迂闊な物言いだったかと、少し後悔した。
「頼む!! どんな些細なことでもいい!! 何か知っている事があるなら教えてくれ!!」
「…………!」
「頼むよ!! もうずっと探しているんだ!! あの、訳の分からない場所に巻き込まれた時に、はぐれてしまって――――!!」
「―――――!」
弁慶のその必死な様が、ハヤブサの身にはつまされる。
この弁慶の姿は、そのまま自分の姿だ。きっと自分も、「シュバルツを知っている」と誰かに言われたら、こんな風に必死に、その情報に縋りついてしまうのだろう。
「源義経……。そうか……。そなた、あの若武者の知り合いか……」
それまで二人から少し離れた所で静観していた左慈が、ふらりと会話に入って来る。
「爺さん、何か知っているのか!?」
かぶりつく様に左慈に迫ってくる弁慶に、左慈も少し残念そうに首を振る。
「いや……先の戦いで、少し一緒に戦ったが――――あの妖蛇が出現して以降、小生も会ってはおらぬ」
「………! そ、そうか……」
左慈の言葉に、弁慶はがっくりと、うなだれるしかなかった。
「義経様……一体、どこにいるんだ……。こんなに、探しているのに……」
「『義経様』と、言う所を見ると、そなたは、あの若武者の――――」
「俺様は、『一の家来』だ。義経様は、俺の生涯の君主なんだ……」
弁慶は、ため息交じりに言葉を紡ぐ。
自分と義経は、平清盛を戦いながら追っていた。だが、いきなり時空の歪みに巻き込まれて――――気がつけば、この異世界に紛れ込んでいたのだと。
「義経様が、そう簡単に死ぬわけがねぇ……。あの御方の事だ。きっと、この妖魔だらけの異世界に在っても、絶対に戦い続けているに決まっている……」
だから、弁慶はそう信じて――――妖魔たちを倒しながら、この地を彷徨い歩いた。
だが、歩けども妖魔を倒せども――――なかなか、義経に繋がる手掛かりを、得られない。そうこうしているうちに、この『五条大橋』に辿り着いた。それは弁慶にとって、よく見知った懐かしい景色だった。
「俺様は、ここで義経様と出会ったんだ……。さっきみたいに、刀狩りをしている時によ……。そう、思い出しちまったら、もう、ここから一歩も動けなくなっちまって――――」
「…………」
しんみりとそう語る弁慶に、ハヤブサも声をかける事が出来ない。今のハヤブサには、弁慶の心が痛いほどよく理解できた、から。
「ふむ………」
そんな弁慶に、左慈が顎の白髭をしごきながら声をかける。
「……と、言う事は、そなたは義経公に会うために、ここで刀狩りをしていたのかね? ここで刀を狩っておれば、また義経公に会えると信じて――――」
「いや? 武器収集は、正真正銘、俺様の趣味だ」
「…………!」
あっさり弁慶にそう言い返されて、左慈もハヤブサも思わずズルッとこけそうになる。
(こ……! この野郎! 思わずお前にしんみりしてしまった、俺の心を返せ――――!!)
そう怒鳴りつけてやりたいのを必死に堪えるハヤブサに気づいているのかいないのか――――弁慶は、橋の上に転がった己の収集した武器を、葛篭の中に収め直していた。
「全く……ここの妖魔たちは、良い得物を持ってなくていけねぇや。あれからいっぱい妖魔を倒したってぇのに、俺様のお宝が一向に増えやしねぇ」
ぶつくさと文句を言いながら、武器を収めた葛篭を再び背負いなおそうとして――――鎖が切れている事を思い出す。
「あっ! しまった……! 予備の鎖も無いじゃねぇか! 畜生!! 参った……! どうやって持って行けばいいんだ?」
弁慶の、粗野だが愛嬌のある物言いに、左慈は顔が引きつるのを押さえる事が出来ず、その後ろでハヤブサが痛むこめかみに指を当てている。しばらく二人は、葛篭を背負えなくて四苦八苦している弁慶の姿を無言で見つめていたが、やがてハヤブサが、ため息交じりに彼に声をかけた。
「これを使え」
ぶっきらぼうにそう言いながら、弁慶に鎖を投げ渡す。
「おっと……!」
黒光りする鎖が、じゃらっと、音を立てて、弁慶の手の内に収まる。
「おお……すまねぇな……。でも、良いのか?」
「構わん。元々お前の鎖を斬ったのは俺だ。だから、しばらくはそれで凌いでくれ」
「ありがたい! ……けど、一つ質問しても良いか?」
「何だ?」
「お前、その『なり』で、どうやってこの鎖をしまっていたんだ?」
弁慶の、ある意味尤もな質問に、左慈も思わずハヤブサの姿をまじまじと見つめてしまう。確かに、上から下まできっちり身体の線が出てしまう忍者スーツを着ているハヤブサに、余分な荷物を持っておく余裕があるとは思えない。
だがハヤブサは、そんな二人の視線を特に気にする訳でもなく、さらりと返した。
「……企業秘密だ」
「きぎょう……? 何だって?」
意味の分からない単語に眉をひそめる弁慶だが、ハヤブサはそれに説明する義務が付加するとは思っていなかった。
「俺は『忍者』だからな……。荷物をたくさん持ち運ぶ心得があるだけだ」
「……よく分からんが、『山伏』みたいなものか? なるほど……」
当たらずとも遠からずと言った内容を言いながら、葛篭に鎖をかけ直し、弁慶は再びそれを背負いなおす。
「……義経公に会わせてやる事は出来ぬが……お主が追っていた『平清盛』に会わせてやる事は出来るやもしれぬ」
「本当か!? 爺さん!!」
左慈の言葉に、またも被りつく様に反応する弁慶。それに左慈は、髭をしごきながら頷いた。
「小生の記憶に間違いが無ければ、この先の戦場に、確か平清盛が居た筈だ……」
そう。
遠呂智の力に魅入られ、『半妖』の存在となっている平清盛は、人の心を支配し、操る能力を手に入れていた。前の歴史ではこの戦いで、多くの武将たちの心が支配されてしまい――――討伐軍の力が大幅に削がれた戦いでもある。
もし、この戦場で平清盛の術を打ち破る事が出来れば、沢山の武将を救いだす事が出来て、これから先の歴史も変わっていく事になるだろう。
「……俺は、その術とやらを破ればいいのか?」
ハヤブサの言葉に、左慈は頷く。
「左様。……やってもらえるかね?」
「術の出所さえ捉えられれば、問題ない」
事もなげに言う龍の忍者に、左慈は笑顔を見せた。ハヤブサのこの言葉が「はったり」ではない、と言う事を、左慈はよく理解していた。
「……と、言う事は、あんたたちは今から、平清盛を討ちに行くのか?」
「そう言う事になるな」
ハヤブサの言葉に、左慈も頷く。
「―――なら、俺も連れて行ってくれ!!」
弾かれた様に弁慶は叫び、二人の前に跪いた。
「頼む!! 義経様は、清盛を追っていたんだ……! ならば、清盛を追って行けば、必ず義経様とも会えるはずなんだ!!」
弁慶は必死の形相で頭を下げる。それを左慈とハヤブサは、無言で見つめていた。
「なあ……! 頼むよ!! 絶対に、足手まといには無らねぇから!!」
「小生の方に、異論は無いが……」
そう言いながら、左慈はハヤブサの方を見る。自分の意見を求められていると悟ったハヤブサは、ため息交じりに口を開いた。
「……好きにしろ」
弁慶の気持ちが痛いほど分かるハヤブサにも、反対する理由など無い。
「本当か!?」
二人の言葉を聞いた弁慶の表情が、ぱっと明るい物になった。
「ありがてぇ!! これから妖魔をバッタバッタと倒して! 絶対に、義経様の所までたどり着いてやるからな!!」
鼻息荒く立ち上がる弁慶に、左慈は苦笑し、ハヤブサはため息をつく。
だがハヤブサは、内心祈らずには居られなかった。
叶えばいい。
「義経に会いたい」と願う、弁慶の望みが。
その望みが叶えば、きっと、自分も希望が持てると思った。
いつか、シュバルツと再会できる、という希望が――――。
「それはそうと――――おい、ハヤブサ……とか言ったな?」
いきなり弁慶に声を掛けられて、ハヤブサははっと、我に帰る。
「何だ?」
振り向くハヤブサに、弁慶がずい、と、近寄って来た。
「お前の得物がどうしても気になる……。なあ、触っても良いか?」
「……………!」
(こ、こいつ―――! まだ俺の刀をあきらめていなかったのか!?)
弁慶の言動から、自分の刀への強い執着を感じてしまって、ハヤブサは呆れかえってしまう。どうやら、この弁慶と言う男の武器収集癖と言うのは、相当な物の様だ。
「駄目だ!」
一言の元に却下してやった。だが、弁慶の方も負けてはいない。すたすたと歩を進めるハヤブサの周りを付き纏うように歩きながら、再び声をかけてくる。
「そんな冷たい事言わずに……」
「断る!」
「ちらっと……! 一瞬だけでもいいからよ」
「断ると言った筈だ!」
「いいじゃねぇか! ちょっと触るぐらい――――」
それまですたすたと歩んでいたハヤブサの足が、ピタリと止まる。
「……『この刀は、そんな生易しいものではない』……俺は、そう言った筈だ」
「へえ……? と、言うと?」
きょとん、とする弁慶を、ハヤブサは振り向いて、正面から見据える。
「……この刀には、『龍』が棲まう。持ち主を選ぶんだ」
背に在る龍剣を意識しながら、ハヤブサは言葉を紡ぐ。
「龍?」
目をぱちくりさせる弁慶に、ハヤブサは更にたたみかける。
「故に、刀の意に沿わぬ者がこれを手にすれば、喰われる事になるぞ?」
「―――――!」
そのハヤブサの言葉と気迫に押されてしまったのか、弁慶がぐっと黙り込む。それを見たハヤブサは、ふい、と踵を返すと、またすたすたと歩き出した。
「持ち主を選ぶ―――つまり、『妖刀』ってことか……」
ハヤブサから少し離れた所で、弁慶がポツリと呟く。
「これは……ますます欲しくなっちまったじゃないか……」
(…………!)
その独り言を、弁慶から少し離れていた所を歩いていた左慈が、聞いていた。
(………やれやれ。この男は『僧侶』の格好をしているはずなのだが……随分と『欲』にまみれた僧も、居たものだの……)
左慈がそうため息をついている前で、また弁慶がハヤブサににじり寄っている。
「いいじゃねぇか! ちょっとぐらい触らせろよ!」
「断る!」
「すぐ返すから! なっ? 見るだけでも……!」
「くどい!」
「ハヤブサよ……」
じゃれ合っているようにも見える二人の間に、左慈が苦笑しながら割って入る。
「ずいぶん確信を持ったように足を運んでおるが……そなたはもしかして、どこに向かうべきか、もう見当はついておるのか?」
左慈の言葉に、ハヤブサは頷き返した。
「この辺りは、既に『妖気』に満ちている……。あの妖蛇の物ではないが、かなり強い――――」
「へっ? そうか? 俺様は何にも感じねぇぞ?」
目をぱちくりさせながらそう言う弁慶に、左慈はもう苦笑するしかない。これだけの妖気が漂っている中でのその鈍感ぶりは、逆に大物だと言えない事も無かった。
「では、参ろうか。平清盛を討ちに――――」
「応!!」
左慈の言葉に弁慶は力強く声を上げ、ハヤブサは静かに頷いた。
こうして、この異界でのハヤブサの戦いが、幕を開けて行ったのだった。
「失った物を取り戻す」
その想いを秘めた、戦いが。
第3章

平清盛の邪法を討ち、討伐軍に無事、合流を果たしたハヤブサたちの前に、思いもかけぬ人物の姿があった。
「義経様!!」
討伐軍の将たちの間に、自分の求める主君の姿を認めた弁慶は、その前に走って行って跪くと、溢れる涙を押さえる事が出来なくなってしまった。
「義経様……ッ!! よく……! ご無事で……ッ!!」
「弁慶……」
義経も、泣き崩れる弁慶の前に膝を付き、その肩をねぎらうように撫でる。
「済まなかったな、弁慶……。心配を、かけて……」
「いいえ!! 俺は、信じていました……ッ! 義経様は、きっと……! きっと、無事だと……!」
弁慶は、それ以上言葉を紡ぐ事が出来なかった。ひたすら涙を零し、嗚咽を漏らす弁慶を、主である源義経は、柔らかい笑みを浮かべてその労をねぎらっている。伝承通りの、爽やかな好青年だな、と、ハヤブサは思った。
(良かったな……)
感動の主従再開を、ハヤブサも心から祝う。
そして、それをしながら眼の端で、陣の中にシュバルツの姿を求めるが、やはりと言うべきか――――彼の姿はここには無かった。
(当然だな……。そんなに簡単に再会できる訳が無い……)
だけど、絶対にあきらめる気は無い。
ハヤブサは懐に忍ばせてあるシュバルツの手袋を、強く意識する。
今はこれだけが――――彼が確かに自分の前に存在した『証』だった。
「俺はこの世界に来て、そこにいる太公望殿に助けてもらったんだ。だから今こうして、討伐軍に参加させてもらっている」
義経がそう言いながら、顔を『太公望』の方に向ける。
(太公望だと――――!?)
予想だにしなかった太古の偉人の名が挙がったのに驚いて、ハヤブサも思わず義経につられてそちらの方に視線を走らせてしまう。すると、その視線に気がついたのか――――それまで書類に目を落としながら何事かを仲間と話していた白髪の『青年』も、こちらを振り向いた。
「左慈。ご苦労だったな」
そう言いながら、すたすたと歩いてくる道士風の格好をした青年に、左慈は拱手をして、頭を垂れる。だがハヤブサは、身動きもできずに固まってしまっていた。『太公望』という名前。そして、伝承よりもはるかに『若い』その容姿。
太公望と言えば、周の文王に仕えた時に、既にかなりの高齢であったと伝え聞いていた。それが、こんなに若い『青年』の様な容姿をしているとは――――。
ハヤブサがそうやって固まっていると、『青年』太公望は、フフフ、と、軽く笑って声をかけてきた。
「人の子よ……お前も……『未来』から来た者か?」
「えっ?」
太公望の質問の意図が分からず、返事に困窮するハヤブサに、太公望はクククっ、と、少し何かを含んだような笑みを見せた。
「全く……人の子の『伝承』の『既成概念』は面白いな……。私が老人だろうが青年だろうが―――大勢には何の関係もなかろうに……」
「…………!」
少し揶揄される様な物言い。だが、このおかげでハヤブサは、一気に素に戻る事が出来た。
そうだ。
自分はここに、戦いに来たのだ。
失った物を、取り戻すために――――。
ハヤブサは、無言で太公望を真正面から見据える。太公望も、しばらくそのハヤブサの視線を受け止めていたが――――やがて、何か得心したように、その顔に笑みを浮かべた。
「お前が先程、平清盛の術を破った者か……なるほど……」
そこまで言った太公望の涼やかな眼差しが、もう一度ハヤブサを捉える。
「―――名を、聞いておこうか」
「リュウ・ハヤブサだ」
「『ハヤブサ』か……。その恰好から察するに――――」
「彼は、『忍者』だ」
ハヤブサの後ろから、左慈が太公望に声をかける。
「『忍者』か……。そうか……」
太公望は、ククククッと、小さく笑うと、手に持っていた打神鞭を、パチン、と鳴らした。
「では、ハヤブサとやら。早速働いてもらうぞ? わが軍は今、圧倒的に人手も物資も足りぬ。やってもらわなければならない事が、山積しているのだ」
「分かった」
太公望の言葉に、ハヤブサは頷いた。
こうして――――ハヤブサは妖蛇討伐軍の一員に、迎えられたのだった。
それからのハヤブサは、多忙を極めた。
徐々に人員が集まりつつある討伐軍とはいえ、まだ規模は小さく、妖蛇に対抗するには圧倒的に戦力が足りない。故に、討伐軍にいる将たちは全員、休む間も惜しんで戦場を駆け回っていた。ハヤブサも、戦場での情報収集、潜入活動など、仕事の場は事欠かなかった。その上、時には戦いの場に駆り出される事もあった。
それをしながらハヤブサは、シュバルツの情報を探し続ける。
諜報活動の合間に。潜入の合間に。時に、戦いながら。
「こういう男を知らないか?」
話が聞けそうな者には、誰かれ構わず声をかけた。
しかし、哀しいかな――――シュバルツに繋がる情報には、なかなか巡り会えなかった。
戦いが進むにつれて、軍に加わって来る人間たちも、多種多様を極めた。
ジャンヌ・ダルク、関羽、アキレウス、妲己、卑弥呼、伊達正宗……まるで、歴史上の有名人のオンパレードだ。
(この光景を、シュバルツが見たら、何と言うだろう)
どうしても、ハヤブサは心の端で彼を探してしまう。シュバルツと、話がしたい。彼となら――――今、自分が歴史上の人物に会って、少し浮足立ったりもどかしく思ったりする気持ちを、分かち合う事が出来るのに。
シュバルツに会いたい。
彼に会って話したい事、聞いて欲しいと願う事が、まるで雪の様に、ハヤブサの心に降り積もって行く。
そして、かぐやの『時を巻き戻せる能力』によって、救われた命も何度も見てきた。
それを見るたびに、ハヤブサは強く想う。
あきらめたくない。
キョウジの事。
シュバルツの事――――。
きっと、出逢える。きっと、救える。
そう、強く信じ続ける事が、今や、ハヤブサにとっての唯一の『希望』となっていた。
信じ続けなければ――――孤独に負けて、自分はもう立って歩くことすら、出来なくなってしまいそうだったから。
こんな所で、立ち止まりたくは無い。負けたくは無い。膝を付きたくない―――と、願った。
人知れず、そんな孤独な道行きをしていたハヤブサではあるが、彼は幸いな事に、忍者としても戦士としても、非常に優秀な部類に入っていた。任務は着実に遂行し、戦場に出れば、その強さ故に功を立て、名を上げた。
そして、それをし続ける、と、言う事は、周りの英雄たちに認められていく、と言う事にも繋がっていった。
最初の内は、『異世界から来た、黒づくめの無愛想な忍者』と、言う感じで遠巻きにハヤブサの事を見守っていた英雄たちが、彼の腕を認め、次第に、仲間として受け入れ始めて行く。
戦場で、気さくに声をかけられたり、陣屋で、手合わせを志願されたり、時に、宴席に誘われる事もあった。
普段なら、そういう誘いにはあまり乗らないハヤブサではあるが、今は違った。非常事態である事は勿論だが、それ以上に、シュバルツに関する情報を欲していた。ひとかけらでもいい。英雄たちが話す言葉の裏側に、シュバルツに繋がる物があればと、ハヤブサは英雄たちと言葉をかわし続けていた。
しかし、どんなに探しても、見つからないシュバルツ。
ハヤブサの中に、『孤独』が降り積もっていく。
どうして、見つけられないんだ。
こんなに――――探しているのに。
(もし―――このまま、シュバルツを見つけられなかったら、どうなってしまうのだろう)
そんな事、考えたくもないが、どうしても考えてしまう。
皆の話では、この世界は徐々に崩壊に向かって進んでいると言う。もしも、このままシュバルツを見つけられずに、自分だけが元の世界に戻る事になってしまったならば。
「愛している……」
自分に微笑みながら、そう言ってくれたシュバルツもまた、世界の崩壊に巻き込まれ、消える事になるのだろう。そうなると、元の世界に帰った時、俺に「愛している」と言った事実自体がそこにいるシュバルツの中では『無かった事』になってしまうのだ。
いいや、それだけじゃない。
死ぬ事が出来ないシュバルツは、世界が崩壊して、消えてしまった後も――――ただ1人、次元の狭間を彷徨ってしまうかもしれない。誰とも接点を持つ訳でもなく。未来永劫、ずっと『独り』で―――――。
嫌だ。
そんな哀しいのは嫌だ……!
ハヤブサは、強く頭をふる。
このままでは本当に、自分に向かって「愛している……」と言ってくれたシュバルツを、文字通り犠牲にしてしまう事になる、と、気づく。そして、元の世界に戻ったとしても、自分の中で「シュバルツを犠牲にしてしまった」と言う事実は、決して消える事は無いだろう。
そんな重い十字架、背負いきる自信など無い。
だから、絶対に見つけないと。
見つけ出して、やらないと。
シュバルツ……お前は一体、どこに……?
どこに、居るんだ……?
「……………」
戦から帰ってきたハヤブサは、無言で陣屋の中に入ってきた。今回の戦も、討伐軍の勝利で終わっていた。出迎える諸将の歓喜の声が上がる中、ハヤブサは1人、すたすたと歩を進めていた。
「ハヤブサ殿!!」
そんなハヤブサの姿を認めた徐晃(じょこう)と言う武将が、彼に声をかけてきた。
「此度の戦場での働き、誠に見事! よろしければ、また一手手合わせ願いたい!」
この徐晃と言う武将は、一途に武門の道を極めようとしていた。ハヤブサも、そう言うまっすぐな想いを乗せた太刀は嫌いではなかったので、頼まれれば手合わせをしていた。しかし今は、そんな気分にはなれなかった。
「……済まないが、後にしてくれないか?」
顔に何とか笑みを浮かべ、丁重に断る。
「あ………わ、分かり申した」
そう言いながら徐晃が一歩身を引くと、ハヤブサはその前を、すたすたと歩いて行く。
「…………?」
そんなハヤブサの様子に何故か少し違和感を感じて、怪訝そうに見送る徐晃の後ろから、宮本武蔵がひょこっと顔を出してきた。
「武蔵殿」
気づいた徐晃が振り返ると、武蔵はハヤブサの方を見ながら少し表情を曇らせる。
「……どうしたんだ? あいつ……」
「ハヤブサ殿が、どうか致したか?」
「ありゃ、敗残兵の足取りだぜ……。勝ち戦だって言うのによ」
「―――――!」
武蔵に指摘されて、徐晃も初めて違和感の正体に気づく。
「どうしたのでござろう……? 戦場で、あれほど功を立てたと言うのに……」
徐晃から零れ落ちる言葉に、武蔵も首を捻るしかなかった。
「…………!」
腰を落とすのに手頃な切り株があったので、ハヤブサはそこに崩れるように座り込む。
とにかく疲れた。
酷く――――疲れていた。
確かに、今日の戦には勝った。だが――――今日も、シュバルツに繋がるような情報を、自分は入手する事が出来なかった。この体たらく。情報戦に関して言うのならば、自分はもうずっと、負け戦を続けているも同然だった。
どうして。
何故――――見つけられないのだろう。
自分の見通しが、甘すぎたのか。
探し方が、まだ足りないのだろうか。
(シュバルツ……)
もう、どれぐらい会っていないのだろう。
指折り数える事も嫌になるぐらい、今はシュバルツが遠かった。
やはり………シュバルツが見通した通り、あれが『最後』だったのか?
『最後』だから――――「愛している」と、言ったのか。
嫌だ。
あきらめたくない。
出会えると、救えると――――まだ、そう信じていたい。
(だから、立ち上がらなければ)
ハヤブサは、己をそう叱咤する。
こんな所で嘆いていても、何も状況は変わらない。
分かっている。会いたいと、救いたいと、そう望むのならば――――立ち上がらなければならない。動き続けなければならない。求め続けなければ、ならないのだと。
だけど――――疲れた。
酷く、疲れた。
やはり、自分には過ぎた幸せなのだろうか。
「愛している」と、言ってくれたシュバルツを、もう一度、この手に手繰り寄せたいと願うのは。
自分には、許されざる事なのだろうか。
(ああ、馬鹿な事を考えている)
ハヤブサは、自分の思考がかなりネガティブなものになっている事に苦笑する。
きっと、疲れているせいだ。
疲れているから――――こんな馬鹿な事を思ってしまうんだ。
しっかりしろ、リュウ・ハヤブサ。
お前がシュバルツをあきらめてしまったら、誰が彼をこの世界から元の世界に連れ出すんだ。
(立ちあがろう。立ち上がらなければ)
ハヤブサは強く己に命じる。だけど、泥の様に重い身体は、なかなか言う事を聞いてくれなかった。
会いたい。
シュバルツに……会いたい。
焦がれる想いは、もう限界に近かった。
許されるならば、声を張り上げて泣き崩れてしまいたい程に。
「…………」
その場に座り込んで、頭を垂れ続けるしか出来ないハヤブサ。
しかし、そんなハヤブサに近寄って行って、声をかけた人間がいた。
「ハヤブサさん♪」
その声と気配で、自分に声をかけてきたのがくのいちだとハヤブサは気付く。くのいちは、忍者と言う割には言葉遣いが独特で、酷く明るい雰囲気を醸し出していた。ハヤブサも最初の内は、その彼女の独特な雰囲気に戸惑ったものだが、今は、かなり慣れた。それに彼女は、その言動からは想像もつかないほど、しっかりとした仕事をこなす忍びでもある。
「どうした……? また、任務か……?」
その彼女が、わざわざ自分に声をかける時は、任務がある時だけだ。だから今回もそうかと思って、ハヤブサは問いかける。
「ううん、違うよォ」
だが、ハヤブサの問いかけを、くのいちは明るく否定した。
「そうか………」
これ以上、彼女との会話を続ける気も無いハヤブサは、そのまま黙り込んでしまう。だがくのいちは、ハヤブサの前から去らず、更に声をかけてきた。
「ハヤブサさんは、人を探しているのかにゃん?」
「…………!」
くのいちから、いきなりこの話題に触れられた事に驚き、思わず顔を上げてしまうハヤブサ。ハヤブサと視線が合った彼女は、無邪気な笑みを浮かべた。
「だったら、その人の情報を、渡すなり~♪」
「え………?」
「こういうのは、みんなで探したほうが、早く見つけられるにゃん♪」
そう言って笑いながら、彼女はハヤブサに手を差し出す。
「あ………!」
確かにそうだ。そうなのだが――――。
ハヤブサは、いきなりの彼女からの申し出に、戸惑ってしまった。
いいのだろうか?
シュバルツを探し出したいと言う願いは、あくまで自分の個人的なものであって、妖蛇討伐には何も関係が無い。ハヤブサはその事を、よく承知していた。妖蛇討滅に向かって、それぞれがそれぞれの任務を背負い、戦っている中――――自分の願いだけで、皆に余計な負担をかける訳にはいかない、と、思った。
「くのいち……気持ちはありがたいが――――」
だが、ハヤブサが断るよりも前に、他の武将たちが二人の傍に寄ってきた。
「何? どうした?」
「ハヤブサ殿は、人を探しているのでござるか?」
「うん♪ 戦場に出るたびに、あちこち聞いて回っているなり~♪」
「えっ? 人を?」
「ああ、そう言えば――――」
「ハヤブサ殿が―――如何致したのだ?」
「お……! おいっ! くのいち――――!!」
目の前で起こっているあまりにも急激な話展開について行きかねるハヤブサは、思わず大きな声を上げてしまう。それは結果として、皆の注目を一斉にハヤブサに集める事になってしまい――――龍の忍者は、さらに戸惑ってしまった。
「…………」
皆の注目を浴びて、どうしたらいいのか分からずに沈黙してしまうハヤブサに、島左近が声をかけてきた。
「ハヤブサさん。どうしたんですかい? 人を探してるって……」
「あ……ああ……」
これ以上、ごまかす事も言い逃れもできそうにない、と、感じたハヤブサは、とりあえず顔を覆っている面を外した。それが、自分の事を気にかけて集まって来てくれている武将たちに対して行う、最低限の礼儀だと思った。それと、今から自分が話す事に、隠し事はない、という気持ちの表れでもあった。
「確かに俺は……人を探している。こちらの世界に来る時のごたごたで――――はぐれてしまったんだ……」
ハヤブサのその言葉に、武将たちの顔が一様に曇る。ここにいる皆は、あの妖蛇が引き起こした混乱のせいで、多かれ少なかれ、仲間たちとの離死別を味わっていたからだ。
「だが、あいつは簡単に死ぬような奴じゃない……。きっと、どこかで生きているはずなんだ……。俺はそれを、見つけたいんだ」
「ハヤブサさん………」
「……………」
ハヤブサの言葉に、その場に沈黙が広がる。
ただ、ハヤブサは、話しながらだんだんと落ち着いて来ている自分に気がついた。
話を、聞いてもらえた。
想いを、吐き出した。
ただそれだけで――――随分気持ちが楽になるのだと言う事を、自分はもうずっと、忘れていた様な気がする。シュバルツやキョウジがいた頃は、普通に、当たり前に――――自分の気持ちを、彼らは受け止め続けてくれていたから。
自分がどれだけ彼らに支えられていたかを、ハヤブサは改めて思い知った。
だからこそ、助けたい。
助けたいんだ。
「だから……その……」
ハヤブサは、その先の言葉を言い淀む。
シュバルツの捜索を、皆に頼むのは心苦しかった。あくまでこれは自分一個人の願望。妖蛇討滅と言う使命には、何の関係も無い事であったから。
ただ、話を聞いてもらえて、自分の気持ちを整理する機会を与えてくれた事に対する『礼』は、ちゃんと言わねばならないと思った。だが、その二つを相手に伝えようとした時、どのように言葉を紡げばいいのか分からないから――――口から言葉が出て来なくなってしまう。こういう時、自分は口下手で、自分の意志を人に伝え慣れていないのだ、と言う事を、ハヤブサは改めて痛感した。
「つまり…………その……」
「…………」
しばらく言葉がつまったようになっているハヤブサを、皆は黙って見つめていたが、やがて島左近が、軽くため息をつきながら声をかけてきた。
「分かりました。ハヤブサさん……」
そう言いながら、ずい、と、ハヤブサに差し出される、島左近の手。
それを、少し驚いた様に見つめ返すハヤブサに、左近は再び声をかけた。
「じゃあ、その人の情報を、よこしてくださいよ」
「…………!」
左近のその手と言葉に、一瞬固まったハヤブサであるが、すぐにはっと、我に帰った。
「いや……その……! 俺が言いたいのはシュバルツを探して欲しい、と、言う訳ではなくて……!」
「ハヤブサさん」
遠慮しようとするハヤブサに、左近のたしなめる様な声が被さる。
「あんた、今更何を言っているんですか。俺たちはもう――――仲間でしょう?」
「―――――!」
「仲間なら、仲間が困っている時に手を差し伸べる……当たり前でしょ?」
「あ…………」
「そうですよ。ハヤブサさん」
戸惑うハヤブサに向かって、竹中半兵衛が声をかけてくる。
「俺としては、ずっと今まで黙って居られたって事の方が、寧ろ軽く傷つくんだけど」
「いや、そう言うつもりではない……!」
ハヤブサは、慌てて半兵衛の言葉を否定する。
「皆に秘密にしているつもりは無かった。ただ、シュバルツを探し出す目的は、俺の個人的な願いだ。妖蛇討滅に、直接関係する事ではない――――」
「だから……黙っていた?」
左近の言葉に、ハヤブサは頷く。それに半兵衛は、柔らかい笑みを、その面に浮かべた。
「良いんじゃないですか? 個人的な願い――――上等ですよ」
「…………!」
驚くハヤブサに、半兵衛はにこっと微笑みかける。
「俺たちの戦いだって、最初はそんな願いから始まったんだ……。『何で、あの時先に行ってしまったのだろう』『何で、あの時あの策を選んでしまったんだろう』って……ね」
「うむ! その願い無くば、儂はもうとっくに死んでおった!」
黄忠の言葉に、馬超も頷く。
「そう! 仲間の『願い』は皆の『願い』! 皆の熱き想いは――――時に、天命をも動かす!!」
馬超が槍を構えながら、強く叫び出す。この馬超は、正義感が強い好青年なのだが、時々その想いが行き過ぎるのか、こんな感じで暴発する事がある。
「総ては! 正義のために!!」
「そう! 義のために!!」
同じく馬超と変に意気投合して、想いが暴発し気味になる直江謙続が、馬超の横でポーズを取り出した。
「はいはい。二人の熱い想いは分かった。だが今は、ハヤブサの話を聞く方が大事なんさ」
そう言いながら豊臣秀吉が、恰好をつけている二人を、隅の方に追いやろうと試みる。
「ぬっ!? 秀吉殿!! 何をする!?」
「そうだ!! 我らの正義の心! まだ語りつくせておらぬ!!」
「幸村!! お前も一緒に!!」
「い、いやぁ、私は……遠慮しておきます」
向こうの方で、半ばど突き漫才風になっている武将達を、ただ茫然と見守るしかないハヤブサ。そんなハヤブサに、半兵衛が改めて声をかけてきた。
「だから、個人的な『願い』も、ちゃんと叶えましょうよ。ハヤブサさん。それがもしかしたら、意外な感じで妖蛇討滅に役に立ったりする事になるかもしれないんだし」
「そうだ……龍の忍者よ……」
皆の言葉に戸惑っているハヤブサの横に、いつの間にか服部半蔵が立っていた。
「半蔵……」
振り返るハヤブサに、服部半蔵は口元に笑みを浮かべる。
「お前は『隻手の声』を聞いた……。そのお前ならば――――皆の意、汲み取れよう……?」
「…………!」
そう。両手の場合は、合わせれば、音は鳴る。だが、『隻手』――――片手の場合、どうすればいいか。これは以前、ハヤブサが服部半蔵から問いかけられた問答だった。
片手だけでは、どう頑張っても音はならない。それでも、その音を聞きたい場合、どうすればいいのか。
ハヤブサは考えに考えて――――やがて、半蔵に呼びかける。
「半蔵。片手を出せ」
半蔵の差し出した手に、ハヤブサの片手が重なる。二人の間に『パン!』と、小気味よい音が響いた。
そうだ。
独りではどうにもならない事でも、二人ならば。
あるいは、皆でならば―――――
隻手の声が、聞ける。望みを、叶えられる。独りでは届かなかったシュバルツに、たどり着く事が出来るかもしれない――――。
「済まない……。感謝する」
龍の忍者は、素直に頭を下げようとする。だがその動きを、皆が制した。
「おっと、ハヤブサさん。頭下げる前に、その人の情報を」
「さっさと情報を、渡すなり~♪」
「どんな人なのか、教えてくれる?」
「あ、ああ……分かった……。シュバルツと言うのは――――」
ハヤブサはそう言いながら、懐から携帯電話を取り出す。この中に、シュバルツの写真が収められているからだ。慣れた手つきで電源ボタンを押して――――携帯の電源が、入らない事に気づく。
(嘘だろ……!? ここに来て電池切れとか……ッ!)
いくら押してもうんともすんとも反応してくれない携帯電話に、龍の忍者は泣きそうになっていた。
「ハヤブサさん、それは……?」
問う左近にハヤブサは苦笑しながら携帯電話の操作をあきらめる。
「……これは、俺が居る世界ではよく使われる物だ……。この中に、シュバルツの写真が入っていた物だから――――」
「写真?」
「写し絵みたいなものだ。その人の姿を、微に入り細に入り、詳細に記録する事が出来る……」
「ふうん……?」
興味深そうに携帯電話を見つめる竹中半兵衛。
「まあ尤も……『電池』が無いから、これはもう使い物にならないのだが……」
ハヤブサはそう言いながら、携帯電話を懐にしまう。便利なんだか不便なんだか分からない、現代の文明の利器に、もう苦笑するしかなかった。
『電気』が無いこの世界。充電できない事は分かっていたから、ハヤブサは大事に大事にこの携帯を使って来た。聞き込みの時以外は決して使わず、夜通しシュバルツの写真を見つめていたい気持ちも、ずっと押し殺してきた。その甲斐あってか、よく――――ここまで電池が保ってくれたもの、と、逆に思わなければならないのかもしれない。
「『電池』って……何だ?」
当然、武将たちの間から、疑問の声が上がる。ハヤブサは『説明するのは難しいから』と、その質問を何とかかわした。こういう瞬間は、否が応でも自分と武将たちの間に、大きな時の隔たりがあるのだと言う事を、改めて感じてしまう。
「そう言えば……ハヤブサさんて、もの凄い未来から来てたんですよね……。あまりにもこの陣内に溶け込んでいるから、時々忘れそうになるよ」
そう言いながら半兵衛が、ポツリと漏らす。
「未来は――――平和に、なってますか?」
「さあな………」
ハヤブサは、その問いかけに、それだけを返した。
ただ、自分の様な者が存在していける世界と言うのを鑑みると、一言に『平和』とは言えないように思う。もし、世の中が真に平和であるのならば――――『龍の忍者』は必要が無いから、その居場所を失ってしまう事だろう。
自分の様な者が存在する世界と言う事で、察して欲しいと思うほかなかった。
「それよりもハヤブサよ……。シュバルツとかいう将の情報はまだか?」
豊臣秀吉からの催促に、ハヤブサもはっと我に帰った。
「あ、ああ……済まない。シュバルツと言うのは――――」
ここまで話して、ハヤブサの口が止まってしまう。口下手な自分は、『シュバルツ』を表現し切るだけの語彙力が無い事に、気がついてしまったからだ。
「シュ、シュバルツと言うのは………」
「うんうん」
皆の注目が、一斉にハヤブサに集まる。
こんな風に注目を浴びる事に慣れていないハヤブサは、背中から変な汗が流れ落ちるのを止める事が出来ない。だけど、ここで逃げ出すわけにもいかないから、ハヤブサは必死で己を叱咤する。
「背……背が高くて……黒髪で……」
「うんうん」
「茶色の……革の、ロングコートを着ていて……」
「ロングコート? それ何?」
「革? 獣の皮を、鞣(なめ)した奴の事か?」
「お市ちゃんみたいに、毛皮かぶってんの?」
「…………!」
(ああ……! 時の隔たりが……ッ!)
「ロングコート」と言う単語が通じない時点で、ハヤブサは頭を抱えてしまう。その後も懸命に彼は、シュバルツを説明するための言葉を重ねていくが、彼が説明すればするほど――――武将たちの頭の中に描かれていくイメージは、シュバルツ本人からかけ離れて行くばかりだ。
「茶色の陣羽織を羽織っているってことでいいの?」
「髪がはねているってことは、仁王様見たいに怒髪天を付いている状態なんかのう?」
「革を被っているってことは、オオカミ頭をした奴を探せばいいってことかもしれないぜ」
「黒髪の長身、と言うだけでは分からん! もっと何か特徴は無いのか?」
「特徴……」
内心泣きたい気持ちでいっぱいのハヤブサであるが、それでもシュバルツの情報を伝えようと懸命に頭を捻る。こうなったら、意地でもシュバルツの事を、きちんと皆に伝えなければならない、と、ハヤブサは強く決意していた。
(あの覆面を被って行動していれば目立つだろうが……覆面をかぶってはいないだろうな……。ここでは、正体を隠す必要も無いのだし――――)
あのドイツの国旗をカラーリングした覆面は、かなり強烈な特徴を放っていると言える。しかし、それを被っていないシュバルツを説明しようとしたら――――一体、何をどう言えばいいと言うのだろう。
「そうだ!! ハヤブサさん!! 絵を描いてみてよ!!」
「えっ………『絵』………!?」
思いもかけぬ提案に、目を白黒させるハヤブサに、それを提案した甲斐姫(かいひめ)が頷く。
「うん。絵なら、ハヤブサさんも伝えられるでしょ?」
そう言いながら甲斐姫は、いそいそとハヤブサの前に紙と筆を持ってくる。それをハヤブサは、顔をかなりひきつらせながら見つめていた。何故なら――――
「さあ、ハヤブサさん! 早く!」
「う………」
甲斐姫に急かされるままに、ハヤブサの筆が、自信無さげに紙の上に落とされた――――。
結果。
「………これは……人?」
ハヤブサから渡された絵を見ながら、甲斐姫は首を捻っている。
「……随分………なんともはや……」
横で絵を覗き込んだ徐晃も、これをどう表現すればいいのか、悩んでいるようだった。
「ある意味……『芸術』と、言えない事も無いね~」
半兵衛が苦笑いながら、その絵をそう評する。その言葉の向こうで、龍の忍者が気の毒なほど落ち込んでいた。
そう。
ハヤブサは――――全くと言っていい程、絵心が無かったのだった。
「全く……情けない奴だな……。剣の道に通じる者は、絵の道にも通じているはずだぞ?」
ハヤブサの絵を見ながら、宮本武蔵が呆れたようにため息をついている。
(そりゃ、お前はそうかもしれないが……ッ!)
宮本武蔵は、剣の達人であると同時に、絵画、書、共に優れた作品を世に残している芸術家でもある。現在で、彼の親筆が発見されようものなら、その値段は軽く数千万以上する物になるのだ。
て言うか、豊臣秀吉、黒田官兵衛、真田幸村、源義経など、その直筆の書が発見されるだけで、億単位の金が動く様な人たちが目の前で並んでいるこの状況。アンティークショップ経営のハヤブサにとって、割と俗っぽい『想い』が疼かないでもない。それどころか、はっきりいって宝の山の中にいる様なものだ。
武将たちの携えている武器を見て、
「ここは宝の山だぜ……!」
と、舌なめずりした弁慶の事を、自分も揶揄出来ないなと、思ってしまう。
だが――――
(ここで俺が、この人たちに一筆書いてもらって持って帰っても――――骨董的には何の価値もつかないんだろうな……。俺が持つこの紙には『歴史』が宿らないから……)
自分の中の俗な想いが疼くたびに、ハヤブサはそう考えてこの葛藤に終止符を打つ。
やはり、骨董と言うのは、その時代から現代に至るまでの歴史の積み重ねが無ければ、その価値は認められない。いくら目の前で、本人にサインしてもらった親筆であったとしても、書いている紙が現代の物であるならば、それは『本物』とは鑑定されない。『直接会った』という主張も、戯言として処理される事だろう。
それでも筆跡の鑑定材料としては使えるから――――ハヤブサは、あわよくば何人かの書や花押を貰おうと、実は秘かに思っている。だがそれも、シュバルツに無事会えた後の話だ。
(しかし、どうすればいいんだ……)
シュバルツに関する情報を伝える手段に困窮するこの事実。写真も使えない。言葉も駄目。絵も絶望的となると――――
あまりにも八方ふさがりな状況に、本当に泣きたくなるハヤブサ。だがそんな彼に、思わぬところから助け船が出された。
「どれ……小生が、シュバルツ殿を見せて進ぜよう」
それまで皆から少し離れた所で様子を見ていた左慈が、ふらりとその環の中に入って来る。
彼は懐から札を取り出すと、文言を唱え、印を結んだ。
「現!」
左慈が鋭く叫んで札を振ると、彼の前に、ポウ、と、音を立てて一人の青年の姿が浮かび上がってくる。
「――――――!」
ハヤブサは、思わず大声で叫びそうになってしまった。そこには、紛う事無くシュバルツの姿形をした者が、立っていたから――――。
(シュバルツ――――!)
固まって動けなくなってしまうハヤブサ。武将たちはそんなハヤブサの様子に気づく事無く、左慈が出現させた『シュバルツ』の周りに集まって来る。
「これが、シュバルツさん?」
「陣羽織じゃないじゃねぇか! これがハヤブサの言っていた、ろんぐ何たらとか言うやつか?」
「毛皮も被っておらぬな……」
「東洋の服装と言うよりは、西洋の服装に近い感じですわね……」
武将たちが各々シュバルツを見た感想を言い合っている中、賈詡(かく)と言う武将が左慈に声をかけてきた。
「左慈殿は、どこでシュバルツ殿を知ったのですかな?」
「ここに来る少し前じゃ……。その時にシュバルツ殿と少し言葉を交わした故、こうして『再現』する事が出来る」
「ハヤブサさん! シュバルツさんはこの人で間違いないんだな?」
島左近の問いかけに、ハヤブサは一瞬茫然とした後、はっと我に返って「ああ……」と、かろうじて頷いた。それほどまでに――――彼は、左慈が出したシュバルツの姿にくぎ付けになってしまっていた。
「じゃあこれは、左慈さんの『方術』で出しているの?」
小喬(しょうきょう)が無邪気に左慈に聞いてくる。その言葉に、左慈は頷いた。
「左様。故にこれは、実体が無い『幻』の様なものだ……。だから、触れる事が出来ぬであろう?」
「本当だ~! 面白い~!」
左慈の言葉に小喬がきゃらきゃらと笑いながら、シュバルツの像に触れようと試みて触れられないのを楽しんでいる。
「こ、こら……! 小喬止めないか……!」
それを夫である周喩が、困惑しながら止めようと試みて失敗していた。小喬が触れようとするたび、シュバルツの像が微妙に揺れる。結局姉である大喬が「こらっ!!」と、彼女を一喝するまで、その微笑ましい(?)行為は続けられる事となった。
「誰かこの中で、この者を見た者は?」
左慈の問いかけに、武将たちは皆一様に首を横に振る。どうやらこの中には本当に、シュバルツの姿を見た者はいないようだった。
「よしっ! じゃあみんな、この武将の顔を覚えて、何か分かった事があったらハヤブサに報告してやってくれい!」
豊臣秀吉の言葉に、武将たちはみな頷いて――――また、それぞれの持ち場に戻っていく。
(もう、ここにいる者たちは、一通り見たであろうか……)
左慈は、周りを見渡しながら、方術で出したシュバルツの像を収めようとする。だが、左慈はそれをする事が出来なくなってしまった。何故なら――――じっとシュバルツの像を見つめる龍の忍者の眼差しに、気づいてしまったからだ。
「…………」
ハヤブサは、酷く切なそうに、思い詰めた眼差しでシュバルツの姿を見つめている。あの猛々しい龍の忍者の姿からは想像できないほど――――その姿は、哀しみに満ちていた。
「…………」
左慈は、シュバルツの姿を消せないまま――――龍の忍者の姿を見つめる。暫く、左慈とハヤブサの間に、奇妙な静寂が流れた。
(シュバルツ……!)
最初に動いたのは、龍の忍者の方であった。彼はまるで引き寄せられるかのように、ふらふらとシュバルツの像の方に足を進めていく。
シュバルツ
シュバルツ
(触れたい……!)
そう祈るハヤブサの手が、ゆっくりとシュバルツの像に伸ばされていく。
だが、方術によって出現させられている『シュバルツ』には、実体が無い。
ハヤブサの差し出された手は、当たり前の様に空を切った。
「…………!」
「――――もう、消してもよろしいかな?」
茫然と己が手を見るハヤブサに、左慈の声が重なる。
「―――――!」
その言葉にはっ、と、我に帰ったハヤブサは、「ああ」と、短く頷いた。それを見た左慈が手に持っている札を振ると――――シュバルツの像が、すう……と、消えて行った。
(シュバルツ……!)
それでもハヤブサの目が、勝手にシュバルツの残像を探してしまう。あれは幻で――――そこにはもう居ないのだと言う事を、ハヤブサも頭では理解しているのに。
「……如何かな? 小生の『方術』は」
立ちつくす龍の忍者に、左慈から静かに声をかけられる。
「あ……ああ、大したものだ……」
ハヤブサは、素直にその腕前を認めた。あれは、どこからどう見ても『シュバルツ』だった。左慈のこの技が無ければ――――自分は絶対に、手を差し伸べてくれた皆に『シュバルツ』の事を伝えきれなかったであろうから。
「済まない……礼を――――」
そう言いかけたハヤブサを、左慈は手で制しながら首を振る。
「余計な気遣いは無用。小生は、小生の仕事をしたまでだ」
そう。
シュバルツを時空の彼方に追いやってしまったのは、紛れも無く自分。
故に、こんな事をした所で――――罪滅ぼしにすらならないだろう。
左慈はそう自覚していた。
「人の心の隙間に入り込み、惑わすのが『方術』の本質。故に術の精度を上げれば、動かす事も、触れることすら、できるようになる」
左慈は淡々と言葉を紡ぐ。
「もしも望むなら――――今度は、そう言う幻を見せて進ぜる事も出来るが……」
「やめてくれ!!」
ハヤブサは思わず、強く声を上げてそれを否定した。
そんな事をされてしまったら、自分は間違いなく確実に左慈の『方術』に溺れてしまう。ハヤブサにはそういう自覚があった。あのはっきりと『幻』と分かっているシュバルツの像を見ただけで、こんなにも心が乱されているのだから。
どれだけ自分がシュバルツに会いたがっているか、否が応でも自覚させられてしまう。
ハヤブサは、それが苦しかった。
(それにしてもこの青年は、「シュバルツ」に対して恐ろしい程無防備になる……。これが、悪い方に転がらねばよいが……)
ハヤブサの抱える大きな『心の隙』が見えてしまう左慈は、少し危惧を覚える。いずれにしても、早くシュバルツを見つけ出さねばならないと感じていた。ハヤブサのためにも。妖蛇との戦いに、勝利するためにも。
「……これからもこんな風に、時々シュバルツ殿の『面通し』を行っても、よろしいかな?」
これからも度々、シュバルツの幻を見せるが大丈夫か、と、左慈は龍の忍者に問う。
その言葉に、ハヤブサは黙って頷いた。
それからもハヤブサは、シュバルツの姿を求め続けた。だが今度は、独りの道行きでは無かった。武将たち各々が、シュバルツを探してくれるようになっていた。
しかし、戦いが進んでも、シュバルツに繋がる情報は、一向に手に入ってこない。
新しい戦場に進んだ将たちも、新しく仲間に加わった将たちも、左慈に『シュバルツ』の幻を見せられても――――皆、首を横に振るばかりだった。
「……………」
ハヤブサは度々、陣屋の中に座り込む事が増えて行った。
どうして。
どうして会えないんだ、シュバルツ。
こんなに――――探しているのに。
もう、本当にシュバルツに会う事は出来ないのか。
自身の中に生じる絶望の闇に、ハヤブサは飲まれそうになる。
あきらめては駄目だ。
もう何度、そう己を叱咤した事だろう。
「愛している……」
そう言ってくれたお前を、あきらめてしまうのは嫌だ。
やっと……やっと、お前は俺に想いを渡してくれたのに、それを最後にしてしまうなんて嫌だ。
『想い』が通じ合えたのなら――――何もかもが、これからじゃないか。
それともシュバルツ……。
お前の方は、もう望んではいないのか? 俺に会うことを。
『心』を渡してしまったら、お前はそれで満足してしまっているのだろうか。
それで『望んで』彼の方が、もう自分の前に姿を現す気が無いのだとしたら。
「…………!」
ハヤブサは、ブン、と、首を振る。
あきらめたくない。
手繰り寄せたい。
そう決意しているのは自分ではないか。
だったら――――自分はそれを、為し続けるだけだ。
シュバルツがどう思って居ようが、それは、関係無い。
こうして、龍の忍者はまた立ち上がる。シュバルツに再び出会えると信じて――――。
じりじりと焦れる様な葛藤に、耐え続けるしかないハヤブサ。
だがついに――――その葛藤に終止符が打たれる時が来た。
『シュバルツ』につがなる情報が、とある武将から討伐軍にもたらされたのだ。
その武将の名は『典韋(てんい)』と言った。
新しく討伐軍に加わった彼は、左慈の出すシュバルツの幻の像の前で、難しい顔をして首を捻り続けていたが、やがて、ポツリと口を開いた。
「こいつ……どっかで、見た事があるぞ……?」
「何っ!? 何処だ!? それは!!」
その言葉が終わると同時に、いきなり黒い影に胸倉をひっつかまれるように詰め寄られるから――――彼はかなり面食らってしまう。
「うわっ! なんだなんだ!?」
「答えてくれ!! 何処だと聞いているんだ!!」
「ハヤブサ殿!! 落ちついて!!」
真田幸村が、典韋に詰め寄るハヤブサを、何とか落ち着かせようとする。しかし、ハヤブサが、止まろう筈も無かった。
「頼む!! 答えてくれ!! お願いだ!!」
必死に典韋の胸倉をつかみ、喰い下がる。
やっと――――やっとつかんだシュバルツへの手掛かり。絶対に、手離せないとハヤブサは強く思った。
「ちょっ……! 苦しい!! この……離しやがれ!!」
ハヤブサに締め上げられるような格好になって、呼吸をするのも困難になった典韋は、強引にハヤブサを振りほどく。振りほどいた後、彼は、軽く噎せた。
「答えないなんて、言ってねぇだろう……! ちょっと待ってくれ…! 今、思い出すから……!」
「……………!」
典韋にそう言われて、ハヤブサもようやく少し、落ち着きを取り戻す。「すまん」と、小さく一言謝ると、龍の忍者は一歩、後ろに下がった。
ハヤブサが離れたことで、典韋の方もようやく落ち着く。だが――――食い入るようにこちらを見つめてくるハヤブサの眼差しに気づいて、軽くため息をつきながら、ポリポリと頭をかいた。
(こいつも……誰か大切な人を、探しているんだろうな……)
自分も、つい先程まで主である曹操の行方を捜していた。曹操の情報が無いか、必死に探しまわっていた自分の姿を思い出すと、この黒装束の男の気持ちも、分からないでもないと典韋は思う。だから彼も――――必死に頭を捻った。
(何処で見たんだっけか……。 何処で……)
ここ暫くの間の自分の行動を、懸命に頭の中で反芻して――――ようやく彼は、求めていた答えにたどり着く。
「ああ―――そうか……! 思い出したぞ……!」
その言葉と同時に、ポン、と、音を立てて自分の手を鳴らす典韋。それを見たハヤブサの姿勢が、知らず、前のめりな物になる。そんなハヤブサが、また、典韋に掴みかかっていかないように、彼の両脇を真田幸村と趙雲が必死に押さえていた。
「何処だ――――? 何処で、見たんだ……?」
切迫したように問うハヤブサをちらりと見やりながら、典韋は答える。
「だが……おめぇの探している奴とは違うかもしれねぇぞ? それでも……」
「愚問だ……! どんな些細なことでもいい――――答えてくれ!」
「分かったよ」
彼は、一つ小さなため息をつくと、話し始めた。今から自分が話そうとしているこの人物が、目の前で自分の事を縋るように見つめてくるこの男の、求めている人物であればいい。そう、祈りながら――――。
「あれは、多分2カ月ぐらい前の事だ。わしは、曹操様の命を受けて、情報収集をするためにあちこちを巡っていた。その時に立ち寄ったある村で、こいつと似たような奴を見かけたんだ……」
この長身の青年と自分が邂逅したのは、ほんの僅かな時だった。だが、その青年は、典韋の心に強烈な印象を残していた。何故なら――――
「あいつ……割とひょろっこく見えたのによ……。すげぇ怪力だったんだ」
「怪力なの?」
問うてくる甲斐姫に、典韋は頷く。
「だってあいつ……村人が数人がかりで斬り倒した大木を、ひょいっと、片手で持ちあげたんだぜ? それで、持ちあげた後も、涼しい顔をしてやがるんだ……!」
その青年の、常識では考えられない怪力ぶりに驚いた典韋は思わず、彼を呼びとめていた。
「お……おいっ! お前!!」
「何ですか?」
唐突に声をかけた、いかつい戦士然とした典韋の容貌にも、特に怯む事無く――――その青年は静かな眼差しを向けてきた。警戒するそぶりも見せないが、その立ち姿に微塵も隙が無かったが故に、典韋はますますその青年が気に入ってしまう。
だから――――
「お前……うちの軍に、来る気は無いか?」
気がつけば、そう彼に声をかけていた。
「え……? 軍……ですか?」
驚いた様に目を見開く青年に、典韋は大きく頷く。
「うちの大将は、お前みたいなのが大好きなんだ! きっとお前、気に入られると思うぜ!!」
「大将、と言うと……?」
「曹孟徳様だ! 名前ぐらいは、聞いた事があるだろう?」
「ああ………」
青年は、少し驚いた様な顔をした後、笑顔を見せる。優しい笑顔だと典韋は思った。きっと、曹操の事を知っているからこその、この笑顔なのだろうと感じた。
「な? わしが曹操様に紹介してやるから――――一緒に来いよ!」
典韋は熱心に青年を勧誘をする。たいして、青年の方が少し困ったような笑みを浮かべた。
「いや……私は、まだここの村人たちに、『恩』を返せていない」
そう言って青年は、典韋の勧誘を断り続ける。律儀な義理堅さを感じた。この青年を曹操に紹介したら、ますます気に入られるだろうと典韋は強く確信した。
「そうか……。じゃあ、ここはとりあえずあきらめるが……また、曹操様を連れて、ここに来るからな! そん時は、良い返事をしてくれよ?」
典韋はそう言って、その青年と別れた。
(シュバルツだ………!)
ハヤブサは、典韋の話を聞きながら、強くそう確信していた。
間違いない。シュバルツだ。
シュバルツ。
シュバルツ。
そんな所にいたなんて……。
ああ―――――やっと
捕まえた。
シュバルツに繋がる『糸』を。
「頼む!! そこに案内してくれ!!」
ハヤブサは、懸命に典韋に頼みこむ。やっとつかんだシュバルツへの手掛かり。絶対に手放しては駄目だと思った。
「ええっ!? いや……『案内しろ』と、言われても……!」
典韋は戸惑ったように頭をかく。
「場所を、憶えていないのか?」
幸村の問いかけに、典韋は首を振る。
「いや、場所は憶えているさ! 後で、曹操様を連れて行かなきゃならねぇと思ったから――――」
「だったら――――!」
ハヤブサは食い入る様に典韋を見つめる。それに対して、典韋は少し困ったように首を捻った。
「でもよ。2か月も前の話だぜ? それにその間に、妖蛇が出現したゴタゴタもあったから、あの村が、その騒ぎでどうなったか分からねぇし、まだそいつがそこにいるかどうかも――――」
「それでもいい!! シュバルツが、そこに『居た』のなら――――!!」
「…………!」
ハヤブサの張り上げる声に、陣屋にいた一同が驚いて、ハヤブサの方に振り返る。皆の注目を一身に浴びる格好になったハヤブサだが、彼は、その眼差しには気づかない。彼の視界には、シュバルツの情報を持っている典韋の姿しか、映っていなかった。
「頼む!! 俺をそこへ連れて行ってくれ!! そこにシュバルツが居たのなら、何らかの『痕跡』が、必ずあるはずなんだ!!」
そう。
例えシュバルツがそこにいなかったとしても、そこに『居た』と言うのなら。
その村からどっちに行った、と言う情報が得られるだけでも、大分助かる。後を、追う事が出来る。シュバルツに会える可能性が、限りなく0%ではなくなるのだ。
「どうか、お願いだ……! 俺に、シュバルツの後を……追わせてくれ……!」
頼み込みながら立っていられなくなるハヤブサは、膝を付き、手を地面に付いた。そして、必死に頭を下げる。もう――――ほぼ、土下座のような格好だ。
「お、おい……!」
「お願いだ……! どうか……!」
(ああ、酷く不格好な頼み方をしている)
頭を下げながら、ハヤブサは思う。だけど、なりふりを構っている場合ではないと、ハヤブサは感じていた。やっと手に入れた、シュバルツに関する情報なのだ。ここからシュバルツを手繰り寄せられるのなら――――自分は笑われようがけなされようが、一向に構いはしなかった。
「え……えっと……」
討伐軍に加わって早々、いきなりこんな風に縋られるように頭を下げられると思っていなかった典韋は、本当に面食らってしまう。しかも、周りの武将達からも変に注目を浴びているし、ハヤブサと同じように、自分に向かって頭を下げている武将まで居るから――――典韋は、かなりいたたまれなくなってしまった。
「お、おいっ! 頭を上げろ! 止めろって!!」
叫び声を聞いて、ハヤブサが頭を上げる。すると、彼と視線が合った典韋が、気まり悪そうに頭をポリポリと掻いていた。
「『案内しない』なんて、一言も言っていないだろう? そんな必死に頭下げんなよ……!」
「では――――!?」
目を見開くハヤブサに、典韋はにかっと笑って頷く。
「良いぜ! 案内してやるよ! これも何かの『縁』て奴だな」
「―――――!」
その言葉に対して礼を言わねば、と、ハヤブサが口を開くよりも早く、周りの武将たちからわっ! と、歓声が上がった。
「良かった……!」
「良かったでござるなぁ!!」
「ハヤブサさん! 良かったね♪」
武将たちが二人の周りに群がって、口々に祝福の意を述べてくれている。まさか、自分とシュバルツの事を、こんなにもたくさんの人たちに喜んでもらえるとは思っていなかったから――――ハヤブサは、その環の中で柄にも無く照れてしまっていた。
「その……感謝、する……」
それでも何とか、小さな声で礼を返す。それを聞いた武将たちは、皆うんうん、と、頷いた。
「ハヤブサは、本当に一生懸命探していたもんねぇ。だから、神様がご褒美をくれたんだよ。うん♪ いい子、いい子♪」
豊臣秀吉の妻で、何故か忍者仲間でもある「ねね」が、そう言いながらハヤブサの頭をよしよしと撫でるから――――彼は本当に、気の毒なほど真っ赤になってしまっていた。
「………! ね、ねね様に、頭を撫でてもらえるなんて――――」
それを加藤清正が、心底うらやましそうに見ているから、その隣にいた前田利家が、
「清正? 落ちついとこう? な?」
と、必死に彼をなだめなければならなくなった。
「よしっ! じゃあ早速――――」
典韋がそう言って、ハヤブサを案内しようとするのを「待て」と、引きとめる者が居た。皆が振り返ると、そこには太公望の姿があった。
「典韋とやら……一つ問う。お前が行こうとしている村は、どちらの方にある?」
唐突なその質問に、典韋は一瞬目をしばたたかせるが、すぐに答えを返した。
「確か……わしが先程居た村から、北に約20里ほど行ったところだったかな?」
「北……なるほど、丁度進軍方向と言う訳か」
そう言って、しばらく何事かを考えているように見えた太公望であったが、やがて顔を上げると、持っていた打神鞭をパチン、と、鳴らした。
「ならばハヤブサよ……。典韋と共に偵察を兼ねて、行って来てくれ」
「承知した」
頷いて立ち上がるハヤブサに、何人かの将が共について行こうとする。
「……偵察だと言っておろう? あまり何人もついて行くな」
「…………!」
苦笑しながら太公望にそう諭されて、将たちの足が止まる。「仕方が無いな……」と、彼らは口々に呟きながら、ついて行くのを断念したようだった。
「では――――」
ハヤブサと典韋は軽く頭を下げて、陣屋から出ていく。それを見送る将たちの中で、まだ――――ついて行く事をあきらめていない人間が居た。甲斐姫である。彼女はハヤブサたちを見送った後、友人である孫尚香(そんしょうこう)に、こそっと声をかけていた。
「ねぇねぇ、尚香」
「何? 甲斐」
「私たちも、後からこっそりついて行かない?」
「ええっ!? 駄目よ!! 太公望さんも『駄目』って言っていたじゃな……!」
「シ―――ッ! 声が大きい!」
「ご、ごめん……!」
甲斐姫の指摘に、慌てて孫尚香も口を押さえる。二人は周りを見渡して、自分達がほかの武将たちから注目を浴びていないのを確認してから、再び口を開いた。
「……だから『こっそり』って言っているじゃない! 後ろからついて行くだけよ」
「良いけど……何で、そんな事をするの?」
至極まっとうな疑問を返してくる孫尚香に、甲斐姫は『分かっていないなぁ』と言う眼差しを向ける。
「だって、ハヤブサさんがあれだけ熱心に探していた人なんだよ? その人と、感動の再会を果たす訳でしょう?」
「まあ……そこにハヤブサさんの探している人がいるなら、そうなるわね」
「だからよ!」
甲斐姫は、握りこぶしを作って力説する。
「ハヤブサさんが、その人とどんなふうに再会するのか……見たいと思わない!?」
「えっ!?」
「やっぱり泣いたりするのかな……! それとも、いきなりぎゅ―――って、抱きしめるのかなぁ……!」
「か、甲斐……?」
いきなり瞳をキラキラさせて妄想を語りだす甲斐姫に、孫尚香は若干引き気味になっている。だが甲斐姫は、それに構わず先を続けた。
「そんな感動的な場面があるって分かっているのに、見逃しちゃうなんて勿体ないと思わない!? やっぱりここは、感動のおすそ分けをしてもらわなくちゃ!」
「そ……そう言う、ものなの?」
「そうよ! 『乙女』としては、『感動する』って事が、重要なのよ!!」
甲斐姫は、ここぞとばかりに主張する。
「『感動する心』が、乙女心に磨きをかけて、明日の幸せへと繋がっていくのよ!! 尚香だって、『感動の再会』は、好きでしょう!?」
「う……まあ、否定はしないわ……」
自分も過日、生き別れた兄や父と再会した時は感動して泣いてしまったし、甲斐姫が、主である北条氏康と再会した時も、貰い泣きをしてしまったものだ。
「ね!! 明日の活力のために、感動の再会を、見に行きましょうよ!!」
甲斐姫は強引に孫尚香を誘う。
「で、でも……! 勝手にここを抜け出しちゃ――――」
「大丈夫よ!! これだけ人数が居るんだもん! 私たち二人が居なくなったって、すぐに分かりはしないわよ!」
結局孫尚香は、甲斐姫の熱意に押し切られる形で、ハヤブサたちの後を追って陣屋を出て行く事となった。
(……丸分かりだがな……)
陣屋から出ていく甲斐姫と孫尚香を、太公望は少し呆れながら眺めていた。それにしても『人の子』と言う物は本当に、見ていて飽きないと太公望は思う。どうして――――自分とは直接関係の無い出来事で、こうまでも泣いたり笑ったりできるものなのだろうか。
(まあ、あの二人が今ここを抜けても、作戦に支障をきたす訳でもない……。好きにさせておくか)
そう思った太公望が踵を返そうとして――――同じ神仙仲間である女媧(じょか)が、こちらをじっと見つめている事に気がついた。
「どうした? 女媧……」
「坊や……」
太公望は女媧に『坊や』と呼ばれる事に、少し何かを思わないでもないが、それに目くじらをいちいち立てる事は、とうの昔に止めていた。永き時を生きる、強さと威厳を兼ね備えたこの女戦士からしてみれば――――周りの者など皆、ひよっこの様に映っている事だろうと、彼は自分で自分をそう納得させている。
ただ――――その女仙が少し、浮かない顔をしていたから、太公望は何事だろうと思った。
「――――坊や……私も、ハヤブサたちの後を追って、良いか?」
「えっ?」
「どうした? お前もあの姫さんたちと同じように――――『感動』とやらが、欲しくなったのか?」
女媧の言葉に怪訝そうに眉をひそめる太公望の後ろから、その言葉を聞きつけた同じ神仙仲間の伏犠(ふっき)が、からかうように声をかけてくる。
「そんなものではない! 馬鹿!」
それを女媧は、一言の元に斬り捨てた。それを聞いた伏犠が「おお、怖い怖い」と、おどけたように太公望を盾にして女媧から隠れようとする。しかし女媧の方は、伏犠のからかいに、それ以上のってこようとはしなかった。
「私が……今、陣から離れることで、何か不都合はあるか?」
女媧は、確認するように太公望に問う。それに対して、太公望は首を横に振った。
「いや、特に問題は無い。しかしどうした? 何故また急に、ハヤブサの後を追おうなどと――――」
太公望の問いかけに、女媧はその美麗な眉をひそめたまま答える。
「………嫌な、予感がするんだ」
「嫌な予感?」
「どうした? それは、仙女の『お告げ』って奴か?」
少しおどけながら言う伏犠に、しかし女媧の硬い表情は変わらなかった。
「『そうではない』と……言いたい所、だが……な」
「…………」
そのまま黙り込んでしまう女媧に、伏犠はポリポリと頭をかきながらため息をつく。
「……仕方がない。女性の『勘』は、古来より当たる物であることだし――――」
そう言いながら、ちらりと太公望の顔を見る伏犠。
「御二人が陣を離れても―――とりあえず問題は、無いが……」
出陣の許可を要求されていると感じ取った太公望は、苦笑しながらそう言った。その言葉に伏犠は、にんまりと笑顔を見せる。
「よしっ! 坊主の許可も得た事だし、儂らも行くとするか!」
そう言って、陣屋から出ようとする女媧と伏犠に、もう一人、声をかけてくる者が居た。
「その道行き……小生も、ご一緒させていただいてよろしいかな?」
「左慈……」
振り返る女媧の前で、左慈は恭しく拱手して、頭を下げる。
「ハヤブサ殿とシュバルツ殿の件では、いささか小生も、思う所がある故――――」
そう。
あの二人を引き裂いてしまったのは、紛れも無く自分の『術』のせいだった。左慈は、その事を後悔しない日は無かった。だから、ハヤブサとシュバルツが無事に再会できるためならば、自分は何でもするつもりだった。
女媧が「不吉な予感がする」と言うのなら――――なおさら、看過できなかった。
「……儂は、別にかまわないが……」
ちらりと女媧の方を見やりながらそう言う伏犠に、女媧も「私にも、異論は無い」と、あっさり許可を出した。二人ともが、左慈がシュバルツを熱心に探していた事を、知っていたからこその許可であった。
「では、行くとしますか!」
伏犠の言葉と共に、神仙二人と方術師もまた、陣屋から出て行ったのだった。
ハヤブサと典韋の後を、少し遅れて甲斐姫と孫尚香が、さらにその後を女媧と伏犠と左慈がついて行く。だが、と、言うべきか、当然、と言うべきか――――甲斐姫たちの尾行は、あっという間にハヤブサに看破されてしまった。
「……いつまでついてくるつもりだ?」
足を止め、自分達が隠れている所を正確に見つめてくるハヤブサに、隠れていた二人は、もうごまかしはきかないと観念するしかなかった。
「そ、孫呉のお姫様と、北条氏康んとこに仕えているお姫さんじゃないか!! 何でこんな所に!?」
「ご、ごめんなさい!」
素っ頓狂な声を上げる典韋に、孫尚香は慌てて謝る。
「勝手について来たのは悪かったわ……! でも、良いでしょう? 絶対に、邪魔はしないから!!」
その隣で甲斐姫が、必死に拝むようなポーズでハヤブサたちに頭を下げてくる。
「……………」
ハヤブサは、黙ってそんな二人の様子を眺めていたが、やがて、小さなため息と共に踵を返した。
「……勝手にしろ」
「えっ!? じゃあ、ついて行っていいの!?」
「『来るな』と、言っても――――来るのだろう?」
「うん♪ よく分かったわね!」
ハヤブサの言葉にも、明るく前向きに、あっけらかんと返事をする甲斐姫。彼女は良くも悪くも―――常にポジティブな物言いをする姫であった。
「え………ええ~~~~?」
唖然とする典韋を尻目に姫たち二人はきゃあきゃあと喜びを爆発させていた。
「やったね♪ 尚香! 許可が下りたよ!」
「そうね! 甲斐! 良いお土産話が出来るわ♪」
「お、おい! ハヤブサ……良いのか?」
「別に構わん。潜入や暗殺といった、特殊な任務を請け負っている訳でもない」
多少顔をひきつらせながらであるが、ハヤブサは問いかけてくる典韋に答える。向かっているのは、特に戦場にもなっていない様な普通の村であるようだし、正直なところ、『帰る、帰らない』で押し問答している時間すら惜しい、と、ハヤブサは思っている。
一刻も早く、前に進みたかった。
そして早く――――シュバルツに、会いたかった。
「ま、まあ……お前がそれでいいのなら、わしも別に、構わねぇけどよ」
多少首を捻りながらも、どうやら典韋も納得したようだった。
「ついてくるのは自由だが――――自分の身は、自分で守れよ」
ぶっきらぼうな物言いをしながら、すたすたと歩き出すハヤブサに、姫たちは「は~い♪」と、明るく元気に返事する。こうして四人になった一行は、シュバルツが『居た』という村に向かって再び足を進め始めた。
途中、典韋が世話になったと言う村で休憩を入れてから、一向は北へと向かう。
特に何の変哲もなく過ぎていく、平和な道のり。だが、道も半ばを過ぎた頃――――一行は、前方に小さな異変を発見する。一条の『黒煙』が、天高く上がっていたのだ。
「何? あれ……」
煙に目を凝らす甲斐姫に、孫尚香も「さあ……」と、首を捻る。
「たき火かのう……?」
典韋の言葉に、ハヤブサは首を振る。
「違う。焚き火にしては大きすぎる――――!」
その言葉を言うや否や、ハヤブサはいきなり全力で走り出した。
そう。狼煙でもない、たき火でもない、あの大きな煙が意味する物は。
(まさか――――! 村が襲われている……!?)
そんな馬鹿な、と、ハヤブサは何度も自分に確認する。だが――――あの煙を自分は知っていた。あれは、戦場に上がる煙だ。間違いない。前方で、恐らく村が――――焼かれている。
「ハヤブサさん!!」
大声でハヤブサを呼びとめようとする甲斐姫たちの前に、いきなり女媧が現れる。
「女媧様!?」
驚く孫尚香には目をくれず、女媧は厳しい顔で前を見据えていた。
「やはり、嫌な予感が当たった!」
「何だ、何だぁ!?」
戸惑う典韋に一緒にいた伏犠が、苦笑した顔を向ける。
「済まないな……。貴公らの後を、つけさせてもらっていたのだ」
3人は、左慈の方術によって結界を張り――――限界ぎりぎりまで気配を消して一行の後をついて来ていた。その結界がいきなり解かれたが故に、典韋たちの前に、いきなり神仙たちが現れたように見えたのだ。
「あの者を追うぞ……! 悪い事が起きる―――!」
そう言うや否や、女媧もハヤブサの後を追って、全力で走りだす。
「何それ!? 何なのよ!!」
目の前で起こる展開について行きかねる甲斐姫も孫尚香も、戸惑いながらも皆につられるように走り出した。
(ハヤブサ殿―――――!)
左慈は祈る様な想いで、はるか前方を走るハヤブサの小さな背中を見つめていた。
ハヤブサは、必死に走っていた。
何故あの村が襲われなければならないのか。
シュバルツは無事なのか。
そもそも、あの村にシュバルツはまだ居るのか。
さまざまな想いが、胸の内に交錯する。しかし、何もかもが『そこ』に行って確かめなければ――――分からないことだらけだ。
だから、ハヤブサは懸命に足を動かし続ける。ただひたすらに、シュバルツの無事だけを祈りながら。
やがて、走り続けるハヤブサの視界に、一つの小さなシルエットが飛び込んでくる。
「…………!」
そのシルエットは、酷くふらついていた。
だけど――――自分はそのシルエットを、よく見知っていた。
そう。
あれは。
見間違える筈も無い、あのシルエットは――――!
「シュバルツ!!」
ハヤブサは大声を上げると、さらに走るスピードを加速させていた。
「シュバルツ!! シュバルツ!!」
自分の呼び掛ける声に、愛おしいヒトはふらり、と、顔を上げる。
「あ……ハヤブ、サ……? ハ、ヤブサ……なの……か……?」
「シュバルツ―――!」
よろり、と、よろめくシュバルツを、ハヤブサは抱き止めようとする。だが愛おしいヒトは、一歩、踏みとどまった。
「この子を……! どうか……!」
そう言いながら、腕の中に抱え込んでいた子供を、ハヤブサに渡そうとする。だが子供の方が、ハヤブサに抱かれる前に自力で地面に降りた。
「俺は大丈夫だよ!! それよりもシュバルツさんの方が――――!!」
「――――」
子供が地面に降り立ったのを確認したシュバルツは、そのまま倒れそうになる。それをハヤブサは、慌てて支えた。
「ハヤ……ブサ………」
「シュバルツ……!」
ハヤブサはシュバルツを抱きしめようとして――――彼の背中に矢が無数に突き刺さっている事に気づく。
(…………!)
あまりの傷のひどさに、ハヤブサは歯を食いしばった。『死なない』とはいえ、『治る』とはいえ―――――酷い怪我だと思う。
それでも。
「大丈夫か? シュバルツ……。矢を抜くぞ」
ハヤブサは、心を鬼にしてそう言った。矢が刺さりっぱなしでは、治る物も治らないだろうと思ったからだ。だが――――愛おしいヒトは、その言葉に首を横に振った。
「駄目だ……。止めて、くれ……」
「シュバルツ……! 何故――――?」
疑問を呈すハヤブサに、腕の中のシュバルツは、優しい笑みを浮かべた。
「治せなくて……。傷が―――」
「……え……?」
何か、信じ難い言葉を聞いた様な気がして、ハヤブサは思わずシュバルツを凝視してしまう。
「え……? え……?」
震える手で、シュバルツの傷に触れる。深々と背中に突き刺さった矢。そこから青白く光る傷口が、ひびの様に広がっていた。
明らかに『普通じゃない』傷口――――しかもそれが、徐々に拡がりつつあるのが、目に見えて分かった。パリ……パリ……と、そこから、小さな音が聞こえてくる。
「シュ、バルツ……?」
何が起こっているのか、「理解したくない」と、ハヤブサは思った。
こんなこと――――あり得ないのだから。
「……ハヤブサ……」
愛おしいヒトが、微笑みながら手を伸ばしてくる。
酷く綺麗で――――優しい笑みだと、思った。
「良かった……。最期に……お前に、会え……て……」
シュバルツはそう言いながら、ハヤブサの頬を優しく撫でる。
「―――最期?」
不吉すぎる言葉に、ハヤブサは思わず反応してしまう。
「何を………」
頬を撫でるシュバルツの手にも、徐々に青白いひびが浸食して来ている。
「……何を、言っているんだ、お前は―――――」
パリ……パリ……と、聞こえ続ける小さな音は、シュバルツが『壊れていく音』なのだとハヤブサは悟ってしまう。
こんな事、悟りたくない。
悟りたく、無い、の に
「死ぬ訳無いだろう!? だってお前は――――『不死』の筈じゃないのかっ!?」
思わず大声で叫んでしまう。自分に言い聞かすつもりで。シュバルツに、言い聞かすつもりで――――
だがそれを聞いたシュバルツは、困ったように微笑んだ。
「済まないな……。でも……これで、良いんだ……」
「シュバルツ――――!」
「これで……良いん、だよ……。ハ……ヤブサ……」
「―――――ッ!」
ここで、ようやく女媧たちがハヤブサに追いつく。
「あ………!」
女媧と伏犠と左慈は、ハヤブサの腕の中のシュバルツを見て、『救えない』と悟り――――典韋と孫尚香と甲斐姫は、ただ茫然とするしかなかった。
「……何よ……これ……!」
絞り出されるように落された甲斐姫の言葉が、総てを物語っていた。
自分達は、こんな『悲劇』を見たかった訳ではないのだと。
「こんな……『人』でもない、『魔』でもない――――中途半端な存在の……私が……いつまでも……生きていては、いけなかった……」
「違う!! 何を言っているんだ!! お前は――――!!」
壊れていくシュバルツの身体を、『生』を、つなぎ止めたくて、ハヤブサは必死に叫ぶ。
悔しかった。
悔しくて、仕方が無かった。
何故
何故、こんな哀しい言葉を聞かなければならない。
他ならぬ、お前の口から――――!
「でも……これでいい……。これで……良いんだ……。やっと――――ああ……やっと………」
「シュバルツ!! 駄目だ!!」
ハヤブサは懸命に目の前の現象を否定しようとする。
だけど、シュバルツの消えゆく『命』を止められる物は、そこには何も無かった。
「ハヤブサ……。今まで……ありがとう……」
「シュバルツ……ッ!」
綺麗に微笑むシュバルツの顔に、青白いひびが入っていく。
「こんな……私を……愛して……くれて……あり が――――」
パン! と、乾いた音を立てて、愛おしいヒトの身体は、ハヤブサの腕の中で粉々に砕け散った。
後にはただ――――空蝉の如く、ロングコートだけが、残された。
「あ………? あ………!」
不意に軽くなった腕の中を、ハヤブサは何度も確認する。
愛おしいヒトは、さっきまで、確かにここにいた。
ここにいた。
ここにいた。
ここにいたのに―――――!
何故?
どうして?
どうして、居なくなっ――――――!
「あ………! あ―――――!」
カラン、と、音を立てて、ハヤブサの足元にシュバルツに刺さっていた矢が転がる。その矢羽に見覚えがあった女媧は、思わず声を上げていた。
「これは……! 仙界軍の……!」
「『仙界軍』? じゃあの人は、仙界軍に襲われたって事なの……?」
「―――そう言う事に、なるな……」
孫尚香の問いに、女媧が頷く。そしてその言葉を裏付けるかのように、前方から軍隊の影が近づいてきていた。
「ムッ! いかん――――!」
その軍の軍旗を確認した伏犠が声を上げる。
「まずいぞ……! あれは、素戔鳴(すさのお)軍じゃ!」
「ええっ!?」
その言葉に、姫たちの顔色が変わる。だが、典韋は1人、きょとん、としていた。
「素戔鳴軍の――――何がまずいんじゃ?」
「まずいよ!! 典韋さん!! あいつのやばさを知らないの!?」
「待って! 甲斐……! 典韋さんは最近ここに来たばかりだから、知らなくて当然よ」
孫尚香にそう言われて、甲斐姫が「あ……!」と、口に手を当てる。自分一人だけが状況を理解できていないと感じ取った典韋は、もう一度問い直した。
「お、おい! 教えてくれよ!! 何がどうまずいんじゃ!?」
「……素戔鳴………あいつは、仙界軍の将だが、いささか考えが極端すぎてな……」
険しい表情のまま、女媧が典韋に答える。
「人間の力など、取るに足らぬもの。『魔』は、徹底的に排除すべきものだと、思っているのだ……!」
「な――――!?」
何か、自分とは絶対にそりが合わないような考え方を聞いた気がして、典韋は思わず息を飲む。
「なんて失礼な野郎だ!! ここはいっちょ、わしが思い知らせてや――――!!」
「やめておいた方がいい」
典韋が言い終わらないうちに、伏犠の声が重なる。
「素戔鳴の強さは、お主らの世界でいう所の呂布か、それ以上の者に匹敵する……。下手に挑めば、返り討ちにあうぞ?」
「……げっ……!」
伏犠の言葉に、思わず典韋は息を飲んだ。呂布と言えば、魏の将が5人がかりで挑んでも、それを赤子の様にあしらった猛者だ。それと同等か、それ以上の強さとなると―――――ここにいる皆が、その名を聞いて顔色を変えるのも頷けた。
「とにかくここは一旦引くぞ……! あの軍を前に、これだけの戦力では話にならぬ!」
伏犠の言葉に、皆が頷く。だが1人、その言葉に頷かない将が居た。
シュバルツのロングコートを抱きかかえたまま止まっていたハヤブサである。彼は、乾いた頭で皆の話を聞くとは無しに聞いていた。
そして知る。シュバルツを討ったのは、「素戔鳴」であると言う事を。
そして――――その軍隊が、今まさに、目の前に居る、と、言う事を。
(許サナイ……!)
ドクン! と、音を立てて、ハヤブサの目の前が紅に染まる。
あいつが、シュバルツを傷つけたのか。
「生きていてはいけなかった」などと、言わせたのか。
あんなに哀しい涙を流させて
あんなに哀しい笑みを浮かべさせて
許サナイ……!
許サナイ、許サナイ、許サナイ、許サナイ……!
ヨクモ……!
ヨクモ、シュバルツヲ―――――!!
「あ……あ……! うあ―――――!」
見ツケタ。
怒リト、絶望ト、憎悪ノ「ハケ口」 ヲ。
突然、辺り一帯を、信じられないほどの咆哮が襲う。
「何!? 何なの!?」
あまりにも凄まじい轟音であったため、一行はその咆哮がハヤブサから発せられている物と知るまでに、少し時間がかかった。
「いかん――――!」
まず方術師である左慈が、ハヤブサの異変に気付いた。
ハヤブサの『龍剣』から発せられているどす黒い『気』が、ハヤブサを取り囲み、飲み込もうとしている。それと同時に、ハヤブサ自体からも禍々しい『気』が発せられて―――――
「ハヤブサ殿!! それ以上怒りに呑まれてはならん!!」
左慈は懸命に方術を用いて、ハヤブサを止めようとする。だが左慈の術は、ハヤブサの身体に届く前に、禍々しい『気』の塊によって拒絶されてしまった。
「ぐっ!!」
術の反動をもろに受ける格好になった左慈は、そのまま後方に弾き飛ばされてしまう。
「左慈さん!?」
走り寄ってきた孫尚香に助け起こされながら、左慈は尚も龍の忍者に術を届かせようとしていた。
「何としても――――あれを止めなければ……!」
「な、何だ!? 何が起こっているんだ!?」
状況が理解できなくて説明を求める典韋に、左慈は応えた。今の逼迫した状況を、一刻も早く皆に分かってもらうために。
「リュウ・ハヤブサの中で、『力』の暴走が起こりつつある……!」
「力の暴走……?」
鸚鵡返しに聞いてくる甲斐姫に頷いて、左慈はさらに続けた。
「あのまま彼を前に進ませれば――――あの者は暗黒面に堕ちてしまい、二度と人としての『生』は、望めなくなろうぞ―――」
「ええっ!?」
「何だって!?」
「ハヤブサさんっ!!」
ハヤブサはふらり、と立ち上がると、龍剣をゆっくり抜き放った。右手に握りしめられた龍剣が、紅く妖しい光を帯びる。まだ人を1人も斬っていないのに――――もう幾百もの血を吸っている様な、禍々しい光がその剣に宿っていた。
殺シテヤル……!
殺シテヤル……!
殺シテヤル……!
(ソウダ! 殺セ!!)
ハヤブサの頭の中で、何者かの声が響く。
(殺セ!! 殺セ!! 皆殺シダ!!)
「ハヤブサさん!! 駄目っ!!」
甲斐姫が必死に呼びかけるが、当然その声はハヤブサの耳には入らない。
左手で握りしめているシュバルツのロングコート。それが、今のハヤブサの総てだ。
この、ロングコートの中に入っていたモノを返せ。
返せないのなら―――――
死 ネ
一歩、ハヤブサが足を踏み出した瞬間、ボコッ!! と、音を立てて、彼の身体のあちこちから突起の様な形状をしたモノが生える。ハヤブサの中に流れる『龍の血』が今――――彼を『人間』たらしめる事を止めさせようとしていた。
「私が感じた『嫌な予感』の正体は、こいつか!!」
ハヤブサの変化を見て取った女媧が、細剣を抜き放つ。このままハヤブサの暴走を放っておけば、新たな破壊神を生まれさせてしまうと悟った。
「凍てつけ!!」
女媧が細剣を振ると同時に、無数の氷塊が彼女の周りに現れる。その礫たちは、明確な意思を持って『ハヤブサ』に襲いかかった。ドドドドッ! と、音を立てて氷塊はハヤブサにぶつかり――――その足を、凍らせることに成功する。
「女媧様! 止められたの!?」
「―――いや! まだだ!!」
孫尚香の問いかけに、女媧は険しい表情を崩さないまま術を続ける。彼の足を止めるには、まだ術の力が足りないと感じていた。
「うおおおおおおっ!!」
『ハヤブサ』は、一声高く吠えたかと思うと、凍りついた足を地面からもぎ取る様に強引に動かす。案の定『ハヤブサ』の歩みは止まらず、彼が人間から破壊神へと変化していく動きも止まらなかった。
「く……! 伏犠ッ!!」
『ハヤブサ』に術を引きずられるような格好になった女媧が叫ぶ。
「やれやれ! 仕方が無いのう!」
女媧に呼ばれた伏犠が、『ハヤブサ』の針路に立ちはだかる様に飛び出して来て、大剣を構えた。
「ちぇいさ―――――ッ!!」
裂帛の気合と共に、伏犠は大剣を地面に突き立てる。突き立てられた剣先から、ドゥッ! と、音を立てて光が迸った。伏犠の司る大地の力が『ハヤブサ』に襲いかかる。
「グ………!」
『氷』と『地面』の両方から足を絡め捕られたが故に、さすがに『ハヤブサ』の動きも止まる。そこに、左慈の投げた『札』が、『ハヤブサ』の背中に貼りついた。
「滅!!」
左慈がそう叫ぶと同時に、背中に貼りついた札から彼の方術が発動し――――バシバシッ! と、音を立てて『ハヤブサ』の身体を打った。
「――――――」
ここでようやくハヤブサは、その動きを止めてその意識を失う。声も無く昏倒した彼の姿は――――もう、元の『人間』の姿に戻っていた。それを確認した方術師と神仙たちは、はぁ、と、大きなため息をついた。
「だ、大丈夫……なのか?」
ハヤブサが動かなくなって、神仙たちが構えを解いたのを確認してから、典韋が恐る恐る声をかけてくる。
「『大丈夫』じゃないかもしれんが……まあ、大丈夫じゃろうな。『魔神』に変わる事は……もう無いじゃろうよ」
伏犠の言葉に呼応するように、女媧も細剣を収めながら呟く。
「……全く……とんでもない奴だな。こいつを止めるのに、我ら3人がかりとは――――」
見下ろす女媧の足元で、意識を失って倒れているハヤブサ。その頬には、涙が光っていた。左手には、シュバルツのロングコートがしっかりと握りしめられたまま――――。
「ハヤブサさん……」
いつしか甲斐姫は、ポロポロと涙を零していた。
あれだけ探していた人と、やっと再会できたと言うのに――――この結末は、あまりにも哀しすぎる。
「さあ、いつまでもぐずぐずしてはおれん。素戔鳴軍がここに来る前に、我らは引き揚げるぞ」
伏犠の言葉に、皆は改めて頷いた。
ハヤブサを襲った悲劇は、討伐軍の皆にたちどころに知れ渡る事となった。それ故に――――陣屋は、かつてないほど重苦しい空気に包まれていた。
そんな中、太公望はハヤブサたちが向かう筈だった村に、改めて偵察隊を派遣していた。
何故――――極めて普通の村と思われる所を、素戔鳴軍が襲ったのか。その理由を知りたい、と、太公望は思っていた。
「お前様……」
ハヤブサの様子を見に行っていたねねが、秀吉にそっと声をかけてくる。
「ねね……。どうじゃった? ハヤブサの様子は……」
「そ、それが……。目は、覚めたみたいなんだけど……」
「―――――!」
幕舎の寝台の上でその身を横たえさせられていたハヤブサは、意識が覚醒した途端、ガバッ、と、跳ね起きた。
(悪夢を見ていたような気がする……。シュバルツが消える悪夢を……)
そう、あれは夢だったんだ。
『不死』であるシュバルツが、俺の腕の中で砕け散る筈がない。
ハヤブサはそう思おうとして――――己の腕の中にある、シュバルツのロングコートに気がついてしまう。
「あ………!」
握りしめていた、愛おしいヒトのロングコート。それは、さっきまで、シュバルツが確かにそこに居た、証。そして自分はそれを――――守れなかったと、突きつけられる『現実』でもある。
間に合わなかった。
また
また
間に合わなかった。
キョウジも。
そして、シュバルツも――――
(何なのだろうな……。結局、俺は……)
守りたいと
生かしたいと願った人を、守り切れない自分。
どんなに剣の腕が立とうとも、忍術を極めようとも――――
肝心な時に、役に立たないのであるならば。
それはそこらに転がっている木偶人形と、何ら変わりは無いではないか。
(これから……どうすればいいのだろう)
シュバルツを探し出した。
そして、喪ってしまった。
ならばこの先、自分はどうすればいいのだろう。
歩けない。
立ち上がれない。
もう――――息をすることすら、億劫だった。
(シュバルツ……)
何も、見たくは無かった。
愛おしいヒトの姿以外は、もう何も。
「……ずっと、形見のロングコートを抱きかかえて、虚空を見つめてて……。もう、私もどう声をかけて良いか分からないよ……。あまりにも、哀しくてさ……」
そう言いながら涙をぽろぽろと零すねねに、秀吉もため息をつくしかなかった。
「そうか……。ねねが声をかけられないのなら……よっぽどじゃな……。暫く――――様子を見る意外に無いのかのう」
そこに、村に派遣されていた偵察隊が帰ってくる。それに秀吉が声をかけるより先に、その帰還を待ちかねていた太公望が声をかけた。
「どうであった? 村の様子は……」
「全滅」
偵察隊の一員である服部半蔵が、短く簡潔に答える。それに補足する様に、偵察隊の案内役を務めていた伏犠が説明を加えた。
「惨(むご)いものじゃ……。人も妖魔も――――皆、死んでおった」
「妖魔?」
意外な単語を聞いた事に、太公望が反応する。村人と仙界軍の兵士の死体があるのなら、まだ話は分かる。なのに何故――――そこに『妖魔』の死体まであるのだろうか?
「……その村に、何か変わった物は在ったか?」
問う太公望に、共に偵察に行っていた魏の将張遼も首を捻る。
「さあ……。特に、何か変わった物があったようには思えぬ。果樹類と稲作を営んでいたようだが……皆、焼かれ、踏み荒らされておった……」
「…………」
張遼の言葉に、太公望は顎に手を当てて考え込む。本当に――――何処にでもある様な、普通の農村であったようだ。なのに何故、素戔鳴軍に完膚なきまでに叩き潰されなければならなかったのだろう?
(これは……村人たちが何か、素戔鳴の逆鱗に触れる様な事をした、と、考えるのが正しいか……?)
ここまで考えて、太公望はまた首を捻ってしまう。
しかし分からない。普通の農村の村人たちがどうやったら、素戔鳴をそこまで怒らせる事が出来ると言うのだろう。
「……………」
事の原因を探ってみたい気もする。しかし、総てが灰燼に帰した今、それを探るのは困難を極めるだろう。それに、この村の出来事は、妖蛇討滅には直接関係は無さそうな事象ではある。このまま捨て置いても、特に問題があるとは思えなかった。
(どうする……。このまま先へ進むのも手だが……)
腕を組みながら考え込む太公望。だが、そんな彼の考えを知ってか知らずか――――待ったをかける人間が居た。
「よくない!」
その人間は腰に手を当てて、陣屋の真ん中でもう一度、大声で叫ぶ。
「よくない! よくないでしょ! 何なのよ? これはぁ!!」
その人間は、甲斐姫であった。彼女は仁王立ちになって、怒りを顕わにしている。
「か、甲斐……ど、どうしたの?」
陣屋の真ん中でわめいている友人に、孫尚香が心配しながら声をかけると、甲斐姫ががっつく様にくってかかってきた。
「どうしたもこうしたもないわよ尚香!! このままでいい訳が無いって言ってんの!!」
「だ、だから……何が?」
「誰か一人が哀しいままで――――先に進んじゃ駄目だって、言っているのよ!!」
「――――!」
「何よ!! この哀しい雰囲気!! こんなままで――――あの妖蛇に立ち向かえるって、まさか本気で思っているの!?」
「か、甲斐……!」
孫尚香は思わず息を飲む。それは自分も強く思って――――叫びたい言葉であったから。
「駄目よ!! 絶対ダメ!! 幸せになるなら――――みんなで幸せにならなくっちゃ駄目なの!!」
「また、小僧の青臭い主張が始まったな」
甲斐姫の叫びを、彼女の主君である北条氏康は、少し離れた所で苦笑しながら聞いていた。こんな子供みたいな甘い想いが押し通る程、今の世の中は甘くない事を氏康は重々承知している。しかし彼は、彼女のそう言う青臭い所が嫌いではなかったので、敢えて黙って見守る事を選択していた。
そして彼女の大声は、当然、幕舎の中で悄然としているハヤブサの耳にも飛び込んで来ていた。
(……………!)
彼女の皆の幸せを願う声は、ハヤブサの瞳にほんの少し、正気の光を灯らせる。
「ねえ! また、いつもみたいに、かぐちんの力を使って過去に帰って、あの人を救う事は出来ないの!?」
彼女のその言葉はそのまま、ハヤブサも大声で叫びたい言葉であった。だから本当なら、甲斐姫に叫ばせるのではなく、自分があの真ん中にいって叫ばなければならないと思う。
だが彼は、その言葉を叫んでもそれが叶えられない事に、気づいてしまっていた。
今のところ、あの村に居たシュバルツの過去にかかわりがある武将と言えば、典韋だ。しかし――――
「……そんな事が出来るのか?」
驚いた様に甲斐姫に声をかけてくる典韋を、彼女は真っ直ぐ見据える。
「そうよ!! 典韋さんが居た村も、その力を使って、村の人たちを助ける事が出来たんだよ!!」
「そうなのか!?」
「そうですよ。典韋殿」
あんぐりと口を開けている典韋に、賈詡がずいっと進み出てくる。
「あの村に向かう典韋殿を、ここに居る武田信玄殿と上杉謙信殿が見かけていて、このお二人の過去に戻って典韋殿と合流できたから――――典韋殿が居た村を助ける事が出来たんです」
「そうだったのか……」
賈詡の言葉に、武田信玄と上杉謙信が頷いている。それを見た典韋は、もう茫然とするしかない。
でもそうなのだ。
あの時、妖魔に襲われた村を守るために、1人で奮戦せねばならないもの――――と、典韋は覚悟を決めていた。しかし、いいタイミングで出現してくれた援軍に助けられて、村は事なきを得た。そして自分も、無事に討伐軍に合流できたのだ。
時を遡る力に、自分もいつの間にか助けられていたのだと悟った典韋は、ただただ感心するしかなかった。
「確かに……素戔鳴様の襲撃に遭われる前の村とあの方に接点のある方を見つける事が出来れば――――村も、あの方も、御救い奉る事が出来るやもしれません」
少し離れていた所で甲斐姫を見つめていた巫女かぐやが、長い黒髪をなびかせながら、楚々と前に進み出てきた。
「あんた……時間を、遡れるのか?」
「左様にございます」
典韋の問いかけに、かぐやは丁寧に頷く。
「ならよ! わしの過去はどうだ!?」
かぐやの言葉を聞いた典韋が、ずいっと前に進み出てくる。
「2カ月ぐらい前になるが、確かにわしは、あの男とあの村で会っているんだ! そのわしの過去に戻れば――――」
「……残念ながら典韋様……。それは、不可能にございます」
「ええっ!?」
「何でじゃ!?」
「……………!」
かぐやから発せられる否定の言葉に、典韋と甲斐姫は息を飲み、ハヤブサは幕舎の中で、シュバルツのコートをきつく握りしめていた。ある程度予測はついていたとはいえ――――改めて口に出されると、やはり、きつい。
かぐやはその瞳を哀しげに曇らせながら、言葉を続けた。
「甲斐様……。お忘れですか? 時を遡る力にも、『限界』がある、と、言う事を……」
「え………?」
「今居らっしゃる典韋様と、その2か月前の典韋様の間には――――『妖蛇の出現』と言う事象が、発生してございます」
「あ………!」
不可能である事の理由を悟った甲斐姫は息を飲み、事情が呑み込めない典韋はきょとん、としている。
「おいっ! どうしてなんじゃ!? ちゃんと説明してくれ!!」
納得いかない、と、言わんばかりに声を上げる典韋に、かぐやは静かに説明を続けた。
「何度も申しあげている事なのですが、時を渡る力と言うのは、大海の中を、細い絹糸の様な縁をたどって渡って行く様なもの……。故に、その力はとても弱く、越えられない『壁』も存在するのです」
「『壁』だと?」
「あの妖蛇の出現は……空間と時間を捻じ曲げるほどの強い乱れを、この時空に発生させてしまっています。それを越えられるのは、女媧様や妲己様と言った、神仙界の者だけ……。『人間』である典韋様の縁では、この妖蛇の発生前と発生後の世界を繋ぐ事が出来ないのです……」
「と……言う事は、つまり……」
「典韋様の縁では……あの時間の典韋様には、戻れない、と、言う事です……」
そう言い切ってしまってから――――巫女かぐやは、哀しそうに瞳を伏せた。自分の力には限界があり、今のままではハヤブサも、ハヤブサが救いたい、と、願っている人も、あの村も――――何も救う事が出来ない。かぐやは己の無力を痛感するしかなかった。
「……せめて、他に誰かハヤブサが探している者を見た、と言う存在があれば、状況も変わって来るのだろうがのう……」
伏犠の言葉が空しく響き、ハヤブサも幕舎の中で唇を噛みしめるしかなかった。
そう。
自分は、散々探した。散々、聞いて回った。
シュバルツを見た者はいないか――――武将達を片っ端から捕まえて、問いかけた。
そして、やっと見つけたのが、この『典韋』と言う武将だったから。
その縁が使えないと言うのなら――――他に何をたどって、あのシュバルツにたどり着けばいいと言うのだろう。
やはり、救えないのか。
俺は、シュバルツを救う事が出来ないのか。
深い絶望が――――ハヤブサの心を支配しそうになる。
「そんなこと分かってる!! 分かってるわよ!!」
甲斐姫はたまらず大声を張り上げていた。
自分だってそうだ。妖蛇が出現したと同時に行方不明になってしまった、主君である北条氏康を救えなくて――――妖蛇出現の『壁』をどうしても越えられなくて、散々泣いた一人であったから。
でも、主君である氏康は救えた。
救えたではないか。
「でも! このままじゃ駄目なの!! 絶対、駄目なの!!」
甲斐姫は必死に叫んでいた。このまま自分が声を上げる事を止めてしまったら、あの悲劇がまかり通ってしまう――――そんな気がしていた。それだけは絶対に嫌だったし、許してはいけないと思った。
だってあの人は――――あんなに必死になって、探していたではないか。それが報われないなんて、あまりにも哀しすぎる。
「何か方法は無いの!? 何か方法は――――!!」
「――――ねえ。いつまでこんな『茶番』をやっているつもりなの?」
その時、懸命に叫ぶ甲斐姫に、冷水を浴びせるように声を出した者がいた。妖孤妲己である。彼女はもともと妖魔軍の遠呂智の傍に身を置いていた者であったが、いろいろな紆余曲折があり――――今は、討伐軍の一員として、その身を置いている。
「別に、あの村で何が起ころうが何人死のうが――――私たちの行軍には関係ないでしょ? さっさと先に進みましょうよ。それに、私は嫌よ。素戔鳴さんと無駄に関わり合いになるなんて――――」
「うるさい!! 誰もあんたになんか聞いていないし、頼んでもいないでしょ!? ちょっと黙っててよ!!」
妲己の冷たい物言いに、しかし甲斐姫の方も負けてはいない。大声で怒鳴り返して、ギリッ! と、妲己を睨み返していた。
「んまぁ! 無礼な小娘ね! 口のきき方がなっていないわよ!?」
自分に無礼を働いた小娘を、妲己もじろりと睨み返す。それでも甲斐姫のまっすぐな視線が自分から逸らされる事が無いから――――妲己の中で嗜虐心が、軽く疼いた。
「でもね? 子猫ちゃん。良い事を教えてあげるわ……? 貴方がいくらここでわめいても――――状況は、何も変わらないのよ?」
「うるさい! そんなこと――――!」
「あらだって……このままじゃ、何も打つ手が無いのが、現状でしょう?」
「…………!」
妲己の言葉に、甲斐姫は絶句してしまう。そんな彼女を見て、妲己はその面に、勝ち誇ったような笑みを浮かべた。
「いい加減に学びなさい……? 世の中は、くだらない子供じみた情熱がおし通るほど、甘いものじゃないって事を」
「うっ……! ぐ……!」
甲斐姫はぎりぎりと歯を食いしばるしかなかった。妲己に、何か反論したい。言い返してやりたいのに――――反論できない事に、彼女は気付きそうになる。
こんなのは、嫌だ。
こんなのは、否定したいのに――――
「…………ッ!」
その悔しい想いは、幕舎の中でシュバルツのロングコートを握りしめているハヤブサも同じだった。
シュバルツの『過去』に戻るためなら――――あのシュバルツを救う事が出来るのならば、自分は、どんな事をしてでもそれを成し遂げたい。必要ならば、あの妲己にだって、頭を下げる用意はある。
だけど、駄目なのだ。
ここにいる誰もが――――あのシュバルツに繋がる『縁』を、持ち合わせてはいない。自分も、あの神仙たちですらも――――
哀しいかな、打つ手が無いのが容赦ない『現実』だった。
悔しい。
悔しい。
どうしていつも、手が届かないのだ。
シュバルツ。
シュバルツ……!
手繰り寄せたいのに――――!
「ねえ……! ねえ! 誰かいないの……? あの人の過去に、繋がれる人が――――!」
それでもあきらめきれないのか、甲斐姫の震える声が陣屋に響く。その声に、ハヤブサの胸も、締め付けられた。
いない。
居ないんだ。
居ればとっくに、俺はそいつと共にシュバルツの過去に飛んで行っている。
「ねえ……! 誰か……!」
甲斐姫の言葉に答えられない武将たちは、皆下を向いたり、彼女から目を逸らしたりするしかない。
「甲斐……」
友人である孫尚香は、そんな彼女の姿が見ていられなくて――――いつしかポロポロと涙を零していた。
(茶番………。確かに、『茶番』だな……)
太公望はそう感じてため息をつく。今この時点では打つ手が何も無いのだから、妲己の言うとおりに先に進むのも一つの手かもしれないと思う。更に進んでこの世界の過去を変え続けていけば――――思わぬ縁も生まれて、この悲劇も、救えるようになるかもしれないのだから。
「誰か……ッ!」
尚も必死に呼びかける甲斐姫を、妲己は冷笑しながら見ている。
(やれやれ……この喧嘩、小僧の負けだな……)
北条氏康は苦笑しながら大きく息を吐いた。だが、『仲間』の悲劇を嫌だと叫び、何とかしたいと言うまっすぐな想いを皆の前で主張した彼女は、紛うことなく自分の自慢の部下だ。だから、労ってやりたい、と、氏康は思った。
煙管をくゆらせながら、氏康は甲斐姫に向かって一歩、踏み出そうとする。
その時の、事だった。
「ぼ……僕の――――」
震える子供の声が、甲斐姫の声に応えるように陣屋に響く。
「ぼ、僕の『過去』では……駄目、ですか………!?」
その声と言葉に驚いて――――陣屋に居た全員が、そちらの方に振り返る。するとそこには、信長の妹であるお市に連れられた子供が、遠慮がちに立つ姿があった。
「あなたは……!」
その姿に、甲斐姫は憶えがあった。それは、シュバルツが守り抜いた――――今となっては、あの村の戦でたった一人の生存者となってしまった子供だった。
「ごめんなさい……。奥で休むように言ったんだけど、この子、どうしてもって、聞かなくって……」
子供の手を引きながら、お市が申し訳なさそうに瞳を伏せる。子供はお市の着物の裾をぎゅっと、握りしめながら立っていたが、やがて、伏し目がちに落していた視線を、甲斐姫の方に上げた。
「話……全部、聞いて、ました」
「…………!」
「僕の村……『全滅』なんですよね……? みんな……死んじゃったんですよね……?」
震えながら問う子供に、そこに居る武将たちの息が詰まる。そんな中、お市が必死に子供をなだめようとした。
「そ、そんな事無いわよ……! 待っていれば、きっと――――」
「だって!! ここには誰も居ないじゃん!! 待っていても来ないじゃん!! おとうも、おかあも――――!!」
「―――――!」
子供の張り上げる声に、大人たちは沈黙を余儀なくされる。子供の方は叫んだ事で、堪えていた物が溢れだしてきたのか――――瞳から、大粒の涙を零し始めた。
「だって……! あれだけいろんな人たちがいっぱい来て……! あちこちから火が上がって……ッ! 分かるよ……。助かったの……僕だけなんでしょう……?」
そう言いながらしゃくりあげる子供に、誰もがかける言葉を失ってしまう。お市は、そんな子供を労わる様に、優しく背中を撫で続けていた。
「そこのお姉さんは……『過去に戻れる』って、言った……! 本当に……そんな事が出来るんですか……?」
子供に、涙目を向けられたかぐやは、静々とその前に歩を進めると、子供の目線に合わせるように、その膝を付いた。
「確かに……私の力を用いれば、それは可能にございます。ですが――――」
「じゃあ!! じゃあ、助けてよ!! 村のみんなを!! おとうをおかあを!! あの人を――――!!」
縋るように上がる事共の叫び声に、辺りは水を打ったように静まり返った。そんな中、その叫び声を聞いたハヤブサは、思わず幕舎の中から飛び出してきていた。
「ハヤブサ……! 大丈夫なのかい?」
飛び出してきたハヤブサに気がついたねねが、彼に声をかける。しかし、彼はそれに気づかないほど――――子供の姿だけを食い入るように見つめていた。
「お願いします……! 僕の過去に戻って……」
静まり返った中、子供のしゃくりあげる声が響く。
(…………!)
ハヤブサはいつしか、シュバルツのロングコートをきつく握りしめていた。
あの子供――――
あの子の中に、シュバルツに繋がる『糸』がある。
縋りつきたい。今すぐにでも。
「俺と一緒に過去に戻ってくれ!」
あの子の前で、そう叫びたかった。
だが――――
(いいのか……?)
龍の忍者は、何度も己に問い返してしまう。
いいのか? いいのか?
相手は身体を張って戦う『戦士』ではない。護られるべき『子供』だ。しかも、その子が『戻る先の過去』は――――
「……………」
必死な眼差しでこちらを見つめているのに、走り寄ってこない龍の忍者。「ですが―――」と、言ったきり、沈黙してしまう巫女かぐや。
(……感じている、『躊躇い』は一緒か……)
そのほかの武将たちも、少し難しい顔をして子供を見つめている。その理由を何となく察知した島左近は、ポリポリと己が頭をかいた。
この子に問わねばならないと思った。
「いいのか」と。
本当に――――「いいのか」と。
左近はゆっくりと子どもの方に歩を進めると、その前にどかっと腰を下ろした。
「……坊主。名前は?」
「ケイタ……」
しゃくりあげながらも名を名乗った子供に、左近は優しい笑顔を見せる。
「いくつになった?」
「10歳だよ」
「そうか……」
10歳ならば、ある程度の分別はつくだろうと、左近は判断した。
「ケイタ……。おっちゃんは、一つお前に問うぞ? お前は懸命に『過去に戻ってくれ』と、叫んでいるが、それがどういう事なのか――――お前は分かっているのか?」
「え………?」
左近の質問の意味が咄嗟に分からず、茫然とするケイタに、左近は更に説明を加えた。
「つまりお前は………もう一回、あの戦場を体験する事になるんだ」
「―――――!」
「妖魔も、仙界軍の兵士もいっぱい来て、あちこちから火の手が上がって――――怖かっただろう?」
「あ………!」
左近の言葉に、ケイタはがたがたと震えだす。無理も無い、と、左近は思った。村が一つ、全滅させられるほどの戦場だ。ケイタ自身も、何度も命の危機を感じた事だろう。
「そこにお前は、もう一度戻る事になる……。それだけじゃない。今は助かったけど、今度はそこで命を落としてしまうかもしれない――――」
左近は淡々と言葉を紡ぐ。ケイタには、よく考えて選んで欲しいと思った。過去に戻る意味を。戦場に戻る怖さを。そこに放り込まれてしまったら――――子供であるケイタは、自分で自分の身を守りきれないのだから。
「いいのか? それでも」
島左近は、正眼でケイタを見据えた。
死ぬかもしれない。守れないかもしれない。いいのか。いいのか、それでも。
その『願い』に――――命を賭すだけの覚悟が、お前にはあるのか。
「う……! うう……ッ!」
ケイタは己の着物の裾をぎゅっと、握りしめて歯を食いしばっていた。思い出す。悲鳴と怒号が飛び交っていた、あの日の夜。燃え上がる炎。血と死の匂い――――。
その中で、隠れて震えるしか出来なかった自分。もう一度あそこに、自分は戻る……。
(怖い……!)
嫌だ。逃げたい。
本能的に、ケイタは思う。
だけど。
ああ、だけど―――――
優しかった父と母。
最期まで自分を守ってくれた、あの人。
それを、取り戻す事が出来る、と、言うのなら。
「……いいよ……」
振り絞る様に、ケイタは叫んだ。
「僕は死んでもいいから―――――おとうとおかあと、あの人を助けて!!」
その叫びと同時に――――ケイタの前に、ダンッ! と、音を立てて黒い影が飛び込んできた。ハヤブサである。彼はケイタの前に手を付くと、深々と頭を下げた。それ以外に――――この子の決意に応えるには、どうすればいいと言うのだろう。
「済まない……! ありがとう……!」
そう言いながら、ハヤブサはただひたすら、ケイタの前で頭を下げ続けていた。堪えようとして、堪え切れぬ涙があふれる。
無理もない。
彼はやっと、捕まえたのだから。
シュバルツに繋がる、糸を。
「ケイタ……! お前の望みは、そのまま俺の望みだ。だから俺は……それを叶えるために、最善を尽くす……!」
「あ………!」
目の前に現れたこの黒装束の武将に見覚えのあったケイタは、思わず声を上げる。この人は確か、シュバルツの最期を看取った人だと思った。
抱きしめていた。
泣いていた。
そして――――咆えた。
「怖い」と思うよりも、胸が締めつけられた。
人は、あんな風に叫べるものなのかと、思った。
ケイタはふと、ハヤブサの手の中にある物に気づく。
「シュバルツさんのコート……」
知らずケイタは、想いを口に出していた。
「ずっと……持っていたんですか……?」
「ああ……離し損ねてしまっていたな……」
ケイタの問いかけに、ハヤブサはその面に笑みを浮かべる。そうすると龍の忍者は、驚くほど柔らかい印象を人に与えるから――――その場にいた者は思わず目を奪われていた。そして、気づく。今まで自分達は、ハヤブサの笑顔を見る機会がほとんど無かったと言う事に。
「俺の名は、リュウ・ハヤブサ。よろしく頼む、ケイタ」
そう言いながらハヤブサは涙を拭いて、ケイタに手を差し出す。ケイタがそれにおずおずと応えた所で――――武将たちの祝福の波が、一気に二人に押し寄せた。
「よかった……!」
「よかったでござるな! ハヤブサ殿!!」
「素晴らしい!! 二人とも!! 感動した!!」
「ちょっと! 押さないでよ!! 私だって祝福したいのに!!」
「ケイタ! イイ子、イイ子♪ 大丈夫だよ! ハヤブサは絶対に、ケイタの願いを叶えてくれるから―――」
「ああっ! ねねさま! そいつの頭を撫でるのならば、俺の頭も撫でてください!」
「おいっ! 清正! どさくさに紛れようとしてるんじゃねぇ!」
武将たちの手荒い祝福に、もみくちゃにされる二人。その騒ぎを、妲己は呆れた目で眺めていた。
「はぁ……馬鹿馬鹿しい。自分達には直接関係ない事なのに、どうしてこうなっちゃうのかしら」
「これが人間と言うものだ、妲己……。少し、面白いと思わないのか?」
妲己の独り言に反応した女媧に、妲己はため息を返す。
「人間っていうのは、弄んで消費するものよ」
ある意味妖孤らしい物言いに、女媧は軽く苦笑する。自分の言い分が軽く流されたと知った妲己は、フン、と、鼻を鳴らした。
「どうなったって知らないからね? 他人事に要らない首を突っ込んで――――」
「妲己ちゃん! そんな憎まれ口を聞いたらアカン!」
踵を返して歩き出そうとした妲己の前に、そう言って少女『卑弥呼』が立ちはだかる。この天真爛漫な少女は何故か、妲己にとても懐いてしまっていた。
「ひ……卑弥呼……!」
妲己も何故か彼女には強く出られないらしく、多少引き気味になってしまっている。ちょっと顔が引きつり気味になっている妲己に、卑弥呼は屈託のない笑顔を向けた。
「ああいう、ケイタ君みたいな一途な子は、うちは大好きや! 妲己ちゃんやってそうやろ? ここは一緒に、応援せな!」
「あ……! いや……! 別に、私は――――」
「うそやん妲己ちゃん! 妲己ちゃんにも、優しい所があるくせに!」
「卑弥呼、それは――――」
「あかん! うちもケイタ君を応援しよ! な~! 私も一緒に祝わせて~な~!」
そう言いながらこの無邪気な少女は、くるっと踵を返して、武将たちの祝福の輪の中に加わって行く。妲己が討伐軍に加わる事が出来たのは、この少女の一途さに因るところが大きい。この少女が、仙界軍に襲われていた妲己の庇護を討伐軍に求めて――――それが実現していたのだった。
「はあ……調子狂うわ……」
ため息交じりに卑弥呼の後姿を眺める妲己を、伏犠は苦笑しながら見つめていた。
お前もまんざらではなさそうだぞ、と、妲己に対して思ったが、口に出す事は遠慮していた。そう言った所で――――この妖孤が、素直にそれを認める訳は無いだろうから。
「おお~い! 皆の衆! ちと喜びすぎじゃ! まだ何も解決しとらん! 総てはこれからじゃぞ!?」
秀吉の声に武将たちは皆、はっと我に返って祝福の輪を解く。皆が離れてくれたことで、ようやくハヤブサは、ほっと息を付く事が出来た。
「ハヤブサはこれからどうするんじゃ? もう、すぐに過去へと飛ぶんかね?」
秀吉にそう問われたハヤブサは、静かに首を横に振る。気持ち的には、確かにすぐにでも過去へと飛んでいきたい。
しかし――――
「過去に戻る前に……ケイタ、頼みがある」
「何……?」
きょとん、とこちらを見つめてくるケイタに、ハヤブサは、その端正な眉を少し曇らせながら言葉を続けた。
「襲われた時の状況を――――教えてくれないか?」
「――――!」
ハヤブサの問いに、ケイタの身体がビクッ! と、強張る。
無理も無い、と、ハヤブサは思った。本来ならば、思いだすことすら辛い記憶だろう。
「無理にとは言わん。だが……出来れば、聞いておきたい」
しかしハヤブサは、心を鬼にして、敢えて問うた。
「何が起こったのかを知っていれば………こちらも、対処のしようがあるから――――」
「う………!」
ケイタは震える手で、着物の裾をぎゅっと、握りしめていた。そのまましばらくその場で逡巡している風に見えたケイタであったが――――やがて、意を決したように顔を上げた。
「わ……分かった……」
蒼白な顔だが、力強い眼差しで、ケイタは頷く。その様子を見た太公望は、フ、と、小さく笑いながら二人に声をかけた。
「ハヤブサ、ケイタ……立ち話も何だ。この続きは、幕舎の中で聞かないか?」
太公望の提案に二人は頷き、ハヤブサは立ち上がる。
「お茶とお菓子を用意してきますね」
お市はそう言い置いて、陣屋の奥へと消える。ハヤブサとケイタは、太公望の導きに従って、近くの幕舎の中へと、その身を移した。
設えられた椅子の上にケイタは少し慣れない感じで座る。ハヤブサはその横に来て、椅子には座らずに――――ケイタと同じ目線になる様に、床に膝をついて座った。以前シュバルツに、「子供と話す時は、子供と同じ目線の高さになった方がいい」と、教えてもらった事を思い出し、彼は律儀にそれを実践していたのだった。
ケイタは今から、辛い記憶を語るのだ。ならば、その負担を、少しでも軽くしてやりたい、と、ハヤブサは思った。尤も――――自分の気遣いが、どこまでケイタに有効な物であるのかは、自信が無い所ではあるのだが。
そこから少し離れた所に太公望が立ち、他の武将たちは幕舎の中に入りきらないから、と、皆追い出されていた。お市が机の上にお茶とお茶菓子を置いて、一礼して退出していく。静かになった幕舎の中で、ケイタはしばらくお茶からゆらゆらと立ち上る湯気を眺めていたが、やがて、意を決したようにハヤブサの方に顔を向け、話を始めた。
ハヤブサの知らない、シュバルツの『足跡』を。そしてあの日――――何が起こったのかを。
「あの人――――シュバルツさんは、空から降ってきたんだ」
「空から?」
問い返すハヤブサに、ケイタは頷く。
「うん。忘れもしないよ。あれは村の祭りの日だったんだ。その時に―――――」
ケイタが住む村の多くの人たちは桃と水稲を栽培して生計を立てていた。村ごと異世界に飛ばされても、その生活は変わらなかった。その村で作る米も桃も大変出来がよく、求めに来る人も多かったことが幸いしていた。
「今年もいい実がたくさん生る様に、土地神様にお祈りしなくちゃならねぇなぁ」
毎年桃の花が咲くころに、その年の豊作を願って祭りを開くのが、その村では習慣となっていた。祭りの準備も滞りなく進み――――皆で土地神様に祈りを捧げる。その儀式をしている最中に、『それ』は空から降ってきた。
「うわ……ッ! ちょっ……! 退いてくれええええええ!!」
響き渡る大声に、皆が声のした方を見上げると、何かが空から猛スピードで落ちてくる。しばらくそれを茫然と見ていた村人たちであるが、やがて、それの落下地点がこの近くであると悟った瞬間、皆蜘蛛の子を散らすように、その場から離れた。
ドンッ!!
大きな音と共に、『それ』が地面に着地する。村人たちは、それが『青年』であると認識するまでに、少し時間がかかった。何故なら皆、空から降ってきた物体から距離を取り、物陰に隠れていたからである。
青年はしばらく着地の衝撃に無言で耐えていたようであるが、やがてポツリと一言呟いた。
「……何も、壊していないようだな。よかった……」
その声が妙に優しい響きを含んでいたのと、周りを気遣う様な所作がその青年から見られたから――――隠れていた村人たちが、おずおずと顔を出す。それに気づいた青年が、村人たちと顔を合わせる。
「…………」
「…………」
暫く奇妙な沈黙が、その場を支配していた。やがて、目の前に設えられている祭壇と、その雰囲気から―――――青年の方が、自分が何らかの儀式を邪魔してしまったのではないかと気づいた様だった。
「あ……その……」
「何だべ……?」
「もしかして、お邪魔だったのでは、ない……でしょう、か……?」
おずおずと聞く青年の言葉に、村人たちは互いに顔を見合わせる。
「ああ……これは――――」
「邪魔……と、言うより――――」
村人たちが小声で意見を交わし合っている中、1人の老婆が声を上げた。
「この人はもしかして――――今年の『神様』じゃねぇのか?」
「へっ?」
素っ頓狂な声を上げる青年に対して、周りの村人たちはそれぞれに口を開いた。
「ああ。『神様』だな」
「そうじゃ。そうに違いない」
「へぇ、今年は『人間』の形をした、『神様』になるのか」
「え……えっと……」
村人たちの会話を聞いていた青年の方が、徐々にひきつった笑顔になって行く。
「お邪魔しました」
そう言って踵を返そうとする青年を、村人たちは必死に引きとめた。
「まま、待って下せぇ!」
「悪いが私は『神様』とかいうものではない。儀式の邪魔をした事は謝らせてもらうが……」
「神様でも神様ではなくても――――とにかく、待っていただけますか!?」
「いや、しかし………!」
「お願いします!! どうか――――」
村人が数人がかりで引き留めて、ようやく青年は足を止めた。その青年に、村人は代わる代わる説明をする。今行っていた祭りの儀式は、その年の『神様』を召喚する物なのだと。そして、その祈りの最中に祭壇の上を通った『生き物』を、その年の『神様』の代理の者として祀り―――豊作を祈る物なのだと。
「蛙の時もあったなぁ」
「毛虫の時もあったべ」
「ハエの時は大変だったよなぁ。もうどれが『神様』だったか、しまいには分からなくなっちまって――――」
そう言って村人たちは、屈託なく笑う。その横で青年は、頭を抱えてしまっていた。
「すごい風習だな……。でも私は、祭壇の上を通ったものではないし―――」
「でもお前さん、落ちてくる時祭壇の真上から落ちてきたべ」
必死に反論しようとする青年を、村人の意見が遮る。
「んだんだ、確かに真上だった」
「ワシも見たぞ? ぶつかるかと思った」
「しかしお前さんは――――なして空から降ってきたんだべ?」
「そ、それは……その……!」
村人たちからの問いに、どうやら青年は明確な答えを持ち合わせてはいないようだった。返答できずに困っている青年に、老婆が声をかける。
「ならやっぱり……お前さんは『神様の意志』でここに来たんだなぁ」
「えっ――――?」
固まる青年の前で村人たちは互いに頷き合う。
「そうじゃ。そうに違いない」
「すごいな。人型の神様なんて、初めてだぞ」
「めでたい! 早速宴の準備を――――」
「ちょ……ッ! ちょっと待って……! 待ってください!!」
動きだそうとする村人たちを、青年の大声が引き留める。振り返った村人たちの前で、青年はとても困惑した表情を見せていた。
「そんな風に祀り上げられても困る……! 何度も言うが、私は『神様』ではないし、それに―――――」
「それに?」
「私が悪人だったら――――どうするつもりなんだ?」
青年の言葉に、一瞬村人たちはきょとん、としたかと思うと、大笑しだした。それを茫然と見つめている青年に、村人たちは声をかける。
「駄目だよ、お前さん……! 『悪人』と言うのなら、もっと『悪人』らしくふるまってもらわないと――――!」
「いや、しかし……!」
何事かを反論しようとする青年に、村人たちは更に声をかけてくる。
「お前さんは、ここに着いて一番に、祭壇の事を気にしたべ? そんな悪人なんているのかぁ?」
「さっきからこっちに気を使う様な事ばかり云っておるし」
「そんな優しげな眼差しで、『悪人』と言われてもねぇ」
「う………!」
村人たちの言葉に、困惑した表情を浮かべながら言葉を詰まらせる青年。そんな青年に、1人の老人が声をかけてきた。
「そんなに心配しなさんな。お前さんが悪人だろうが善人だろうが――――わしらは同じようにお前さんを祀る。それが、この村で古くから続いてきた伝統だからじゃ。そうする事によって、わしらは代々、この土地の『土地神様』のご加護を頂戴しておる」
「貴方は?」
問うてくる青年に、老人はにっこりと笑って、自分はこの村の長老で、今回の祭りの司祭をしていると答えた。
「お前さんが悪人ならば、土地神様の機嫌が悪いと言うだけの話じゃ。どのような仕打ちをされようとも、それで土地神様の機嫌が直るのならば、我らはそれを甘んじて受ける」
「な――――!」
息を飲む青年の顔色が、みるみるうちに蒼白になって行く。それだけで、長老が青年の事を信じるには充分すぎた。こんなにこちらの事を心配する色を浮かべる目の前のこの人が、悪人の筈がない。
「じゃが……今年の土地神様は、機嫌がいいようだ。お前さんみたいな人がここに贈られてきたのだから……」
「あ…………!」
茫然と立ち尽くす青年に、長老はにこりと笑いかける。
「だから申し訳ないが、しばらくの間――――『神様の代理』として、ここに留まってはくださらんか? もうあんたは、儀式の条件を満たしてしまっている。今更他に、代えもきかなくてのう」
長老の言葉に、周りに居た村人たちがうんうん、と、頷く。
「いや……だが、私は――――!」
戸惑いながら、尚も遠慮しようとする青年。しかし村人たちも、必死に食い下がった。
「頼みます! どうか……!」
「神様の機嫌を損ねたら、今年の農作物は不作になっちまう!」
「もてなし方に問題があるのなら、直しますから――――!」
「いやだから……ッ! 私は、その………!」
「お願いしますだ! どうか、これも人助けだと思って――――!」
「――――ッ!」
青年はしばらく何かを言いたげに手をばたつかせていたが、やがて、頭をグシャッと一掻きすると、深~いため息をついて、うなだれた。
「……………」
「……………」
また暫く、奇妙な沈黙がその場を支配する。
「あの、もしもし……?」
「……………」
「大丈夫だか?」
「……………分かった」
「えっ?」
問い直す村人に、青年は半ばやけくその様に叫んだ。
「ああもう分かった! 暫くの間でいいのならここに居るから――――そうやって頭下げるのは止めてくれ!!」
「本当だか!?」
青年の言葉に、村人たちは下げていた頭を上げる。確認するように見つめてくる村人たちに、青年は頷いた。
「ああ。乗りかかった船だ。少しの間でいいのなら――――」
「やった――――!! 『神様』が滞在を承諾してくれたぞ――――!!」
とたんに、喜びを爆発させる村人たち。茫然とする青年を囲んで、彼らの動きは俄然、慌ただしいものへとなっていった。
「宴だ宴だ! 酒が飲めるべ!!」
「蔵からとっておきの酒を持って来てくれ!」
「料理も用意しているから、すぐに食べられるだよ!」
「さあさあ、『神様』もこちらへ――――」
「いや、だからちょっと――――!」
手を引こうとする村人に、青年は待ったをかけた。
「済まないが、『神様』と言うのは止めてくれないか? 私にも一応、名前があるんだ」
「何とお呼びすればいいんだべか?」
素朴に問うてくる村人たちに、青年は苦笑する。
「私の名は、シュバルツ・ブルーダー。だから、『シュバルツ』と呼んでくれ」
「シュバルツ……様?」
「『様』は要らないよ」
青年は優しくそう言ってくれたのだが、村人たちは全力でそれを遠慮した。仮にも『神様』なのだ。そんな恐れ多い事、出来ようはずもない。シュバルツのこの要望は、却下されてしまった。
「さあさあ、どうぞこちらへ――――!」
村人たちは改めてシュバルツを宴席へ招く。シュバルツも苦笑しながら宴席に加わった。
「さあ、今日は仕事を忘れて飲むべ!」
村人たちの『乾杯』の声が響く。
春のひと時、村人たちはその年の宴をいつ果てるともなく楽しむのだった。
宴の次の日。
「あれっ!? 大変だ!! 寝てた!!」
本来ならば『神様』の傍で『不寝番』をしていなければならない者の叫び声が響き渡って、宴の席上で眠りこけていた村人たちも、一斉に目が覚めた。
「どうしたべ? トヨ作さん」
「あ、いや……それがその―――――」
しどろもどろになりながらもトヨ作は説明をする。自分が寝てしまっている間に、シュバルツの姿が見当たらなくなってしまった、と、言う事を。
「何をやってるだ!? トヨ作さん!! 不寝番が寝ちゃあだめだべさ!!」
「いやぁ、面目ねぇ! 起きているつもりだったけども―――」
慌てて村人たちはシュバルツの姿を探そうとする。そのシュバルツは、割とすぐに見つかった。彼は女たちと共に、宴席のすぐ近くにある井戸の傍に居たのである。
「あんたたち、起きたのかい?」
走ってきたトヨ作たちの姿を認めた女の1人が、彼らに声をかける。
「あ~! 良かった……! 見失っちまったかと思った……!」
「おめぇたち、何をやっているだ?」
問いかける男たちに、女たちの方は少し興奮気味に話しだした。
「聞いとくれよ! すごいんだよ、この人!! 井戸を使いやすいように改良してくれて――――!」
「汲み上げがしやすいように、滑車みたいなものを取り付けたんだ」
井戸の傍で作業をしていたシュバルツが振り向く。
「簡単なものだが、てこの原理も応用しているから僅かな力で水を上まで運んで来られると思う。昨日、歓待してくれたからその礼代わりに――――」
ここまで話し終えたシュバルツだが、ここで言葉を失ってしまう。何故なら――――その場にいた村人たちが全員、シュバルツに向かって伏し拝みだしたからだ。
「ええっ!? ちょ、ちょっと……! 何を――――!」
慌ててシュバルツは村人たちに声をかけるが、村人たちの方がなかなか頭を上げようとしない。
「……神様だ」
ぼそりと聞こえてきた言葉に、シュバルツの表情が引きつる。
「はい?」
「神様だ!! 本物の神様が降臨してくださった!!」
「すごい!! 何というありがたい事じゃ!!」
「神様!! ありがとうございます!!」
「いやいや!! ちょっと待ってくれ!! 私は『神様』じゃない!! ただ昨日の礼を――――!!」
必死にシュバルツは叫ぶが、村人の方が聞いていない。シュバルツを取り囲んで、尚も伏し拝み続けている。
「ありがたや……! ありがたや……!」
「神様……! 貢物をはずみますから、うちの井戸も――――!」
「だからっ!! そうやって拝むのは止めてくれと言っているだろう!! 頼むから、顔を上げてくれ――――ッ!!」
「…………!」
シュバルツの大声に、ようやく村人たちは拝むのを止めて顔を上げる。しかし皆の表情が一様に曇り、心配そうにシュバルツの方を見つめていた。
「駄目だっただか……?」
「おらたちは、神様を怒らせてしまっただか……?」
「神様じゃないし、怒っても居ない――――」
頭を抱えながら、シュバルツは言葉を紡ぐ。
「とにかく――――『神様扱い』だけは止めてくれと言っているんだ……。井戸の方は、ぼちぼちとやらせてもらうから、順番に待っていてくれ」
シュバルツのこの言葉に、村人たちの間からどっと歓喜の声が上がる。そして伏し拝もうとして――――また、シュバルツに怒鳴られていた。
「あの人は自分の事を『神様じゃない』って盛んに言っていた……でも――――」
ケイタは今でも秘かに思っている。あの人はやっぱり、『神様』ではなかったのだろうかと。
天から降ってきたし、力も強いのに、とても優しかった。
そんな人が村のために戦い、最期まで自分を守ってくれた事、決して忘れてはいけないと、思う。
「…………」
ケイタの話を聞きながら、ハヤブサは泣きそうになるのと笑いそうになるのを、必死に堪えなければならなかった。
シュバルツからしてみれば、歓待されたその御礼に、少しでも村人たちの負担が軽くなる様にと、自分の出来る範囲の事をやっているにすぎない。しかし、それをすると村人たちから過剰に感謝されて、ますますありがたがられてしまう。だから、シュバルツもその誠意を、少しでも返さなければならない、と、真面目に思ってしまって――――
(『誠意』のループが出来上がっている……。シュバルツの奴、大変だっただろうなぁ……)
誠意には、誠意で応えてしまう、真面目で律儀なシュバルツ。
そんなシュバルツを――――ずっと、横で眺めて居たかった。
「あの人には、ずっと、助けられっぱなしだった……」
紡がれ続ける、ケイタの言葉。
ある時、積み上げていた丸太を束ねていた紐が切れて、崩れ出す丸太の山。それにケイタは巻き込まれそうになる。
しかし。
「大丈夫か?」
片手で丸太の束を押さえて、自分を覗き込んできたあの人。『助けられたのだ』とケイタは悟った。そして周りの大人たちは、その場面の一部始終にただ茫然としていた。
まず、ケイタとシュバルツの間には、かなりの距離があった。しかしシュバルツは、周りに居た大人たちの中で誰よりも早く、ケイタの居る所にたどり着いていた。しかも彼は、崩れそうになった丸太の束を片手で押えて、涼しい顔をしている。
「な、何だべ? 今のは……!」
「さっきまでここに居たシュバルツさんが、なしてあそこに居るだ?」
「片手で……何ちゅう力……!」
当のシュバルツは、ケイタの安全を確認してから、ほっと息を吐く。そして丸太の山を直そうとして――――ようやく自分が周りから変に注目を浴びる事をしてしまっている、と言う事に気付いた様だった。
「あ……! これは、その……!」
慌てて丸太から手を離すシュバルツ。そのまま丸太は重力の法則にしたがって、シュバルツの身体の上に崩れてきてしまう。
「うわ~~~ッ!?」
間抜けな悲鳴と共に、シュバルツの姿は丸太の山に隠れて見えなくなってしまった。
「シュバルツさんっ!!」
皆が悲鳴のような叫び声を上げながら、丸太の山に近づいてくる。心配する皆が丸太をどけようとするより先に、シュバルツの方がその隙間から顔を出してきた。
「すみません。丸太の山を崩してしまって――――」
そう言って屈託なく笑うシュバルツの姿に、その場に居た村人たちは皆、腰が抜けてしまっていた。
ずっとこんな調子で、皆を助けてくれていたシュバルツ。力がとても強い、と、周囲に知れ渡ってからは、農作業や畑の開拓で、主に力が要る仕事なども率先して引き受けてくれていた。とても忙しそうにしていたのに――――合間を見つけては、自分の様な子供たちとも、よく遊んでくれていた。
ケイタは、助けてもらってから、よくシュバルツの傍に居るようになった。
両親が畑や田んぼに出ていて忙しそうにしていたから、と言うのもある。彼の傍に居れば、友達にも会えたから、と言うのもある。だがそれ以上に―――
彼に、恩を返したい、と言う思いが強かった。
自分は子供だから、出来ることも少ないけれど――――何か、彼の手助けをしたい、と、願うようになっていた。
花の時期も終わりを迎え、桃の畑は受粉と摘果の時期を、同時に田植えの準備も始まり、村は慌ただしい季節を迎えた。この時期は大人から子供まで、皆総動員で農作業を進めていく。もちろんシュバルツも、皆と共に農作業を手伝っていた。そんな中――――ちょっとした事件が起こった。
「う、うわあっ!! 妖魔だ!! 妖魔がいるぞ―――!!」
桃の畑に響き渡る悲鳴。皆がそちらの方に走って行くと、そこには身体の小さな妖魔が、足を押さえてうずくまっていた。妖魔の後ろには、ちょっとした崖が聳えていて――――どうやらこの妖魔は、その崖の上から落ちて来たらしかった。
人間とは違う青白い肌。小さいながらも鋭い牙が見え隠れする口。その異様な風体は、人間たちの警戒心を煽るには充分すぎた。当然、第一発見者となってしまった村人も、その妖魔を目の前に腰を抜かして怯えてしまっている。
小さな妖魔の方も、桃の林の間からたくさん現れた人間たちに驚き怯え、小さな牙を剝きだしにしながら唸り声を上げている。しかし、足を痛めたせいで逃げる事が出来ないようだった。
どうする、と、その場に居た大人たちが考えるより先に、シュバルツが走り寄っていた。
「怪我をしているじゃないか――――!」
大丈夫か、と、聞きながらシュバルツはその近くに腰をおろして、小さな妖魔に手を差し出す。だが怯えきってしまっている子供の妖魔は、その手に向かって思いっきり噛みついた。
ガキッ!!
「――――ッ!」
何故か響き渡る鋭い金属音と共に、シュバルツの端正な眉が少し、顰められる。
「シュバルツさんっ!?」
驚いて駆け寄ろうとする周りの人たちを、シュバルツは手を上げて制した。
「――――来るな。大丈夫だから……」
優しいが、鋭い響きを持った声音で皆を足止めしてから、彼は改めて、妖魔の子供に向かって微笑みを返す。
「済まないな。あまり美味くないだろう?」
そう言って優しい笑みを浮かべながら、妖魔の子供が噛むに任せているシュバルツ。妖魔の子供は、しばらくシュバルツの手に牙を立てていたが、やがてシュバルツの方に敵意が無いと悟ったのか――――噛みついていた手から、そっと口を離した。
触れてもいいか、と、問うシュバルツに、妖魔の子供は震えながらも頷く。
「……折れてはいないようだな……。これは痛むか?」
シュバルツがその足をくっと捻ると、妖魔の子供はギャッ! と、悲鳴を上げた。
「捻挫しているようだ。冷やさないと――――」
シュバルツはそう言いながら、懐から何やら取り出している。どうやら、治療道具のようだった。
「これは『湿布』と言う物だ。君に効くかどうかは分からないが……しばらく、患部に当てておくといい」
そう言いながらシュバルツは、湿布を妖魔の子供の足にあてがい、その上から包帯を巻きつけて固定していく。その手際の良さに、村人たちは皆ぽかん、と、口を開けながら眺めているしかない。彼は治療を終えると、再び妖魔の子供に、「何処から来たんだ?」と、尋ねた。
すると妖魔の子供は、黙って崖の上を指す。やはりそうか、と、シュバルツは小さく頷くと、村人たちの方に振り返った。
「この子を元いた場所へ送って来る。済まないが、少しの間抜けるぞ」
それだけ言うと、シュバルツは妖魔の子供を抱きかかえながら立ち上がり、崖の方へと歩いて行く。
「待って下せぇ、シュバルツさん! その崖を登るなら、縄を使って――――!」
「必要ない。大丈夫だ」
シュバルツはそう言うと、妖魔の子を抱いたまま、崖をひょい、ひょい、と、身軽に駆け上がって行く。それを見た村人たちはもう、茫然とする以外に無かった。
「あの御方は、猿(ましら)か何かか?」
ポツリと零された誰かの言葉に、誰からともなく反応が返ってきた。
「いや、天狗様じゃろう。何と言ってもあの御方は――――」
「神様じゃなぁ」
「んだ、神様だ」
「神様だものなぁ」
そう言って村人たちは、シュバルツの方に向かってこっそりと拝みだす。面と向かって拝むとシュバルツに怒られてしまうので、最近村人たちは、この様にこっそりと拝むようになっていた。もちろん、ケイタもそれに倣っていた。
「しかし、どうしてあの御方は、自分の事を『神様』だと認めないんだべ?」
「あそこまでいろいろできる御方、神様以外に考えられねぇのになぁ」
「ずいぶんと謙虚な神様も、居たもんだべ」
シュバルツが崖の上に上っている間、大人たちはそう言った話題で話に花を咲かせる。ケイタもそれに内心強く同意しながらも、崖の上を一心不乱に眺めて、シュバルツが帰って来るのを待っていた。
やがて崖の上に、ひょこっとシュバルツが現れる。
「あ、シュバルツさんだ!」
ケイタの叫び声に、皆話をピタリと止める。シュバルツは崖を登った時と同じように、帰りもひょい、ひょい、と身軽に所々に着地しながら降りてきている。
「待っていてくれたのか? 済まないな」
ストン、と着地して開口一番にそう言うシュバルツに、村人たちも微笑みかけた。
「いやいや、もうすぐおやつの時間だし、わしらもちっと早めの休憩を取っておったところじゃ」
「あの妖魔の子は、どうなったんだべ?」
「『母親』が待っていたよ」
村人の問いかけに、シュバルツも笑顔を返しながら答える。『母親』は、崖の上で心配そうにうろうろしていた。シュバルツが妖魔の子を返すと、親子は強く抱きしめ合っていた。そして、何度も頭を下げながら、森の奥へと帰って行ったのだと、伝えた。
「村ごと変な場所に飛ばされてからこっち、妖魔がいる、と、風の噂では聞いた事があるだが……実際見たのは初めてだなぁ」
1人の言葉に、皆が一様に頷く。そう言う言葉が出てくるほど、この辺りで妖魔に遭遇する事は、本当に稀だった。
「……親が子を思う気持ちは、皆一緒だ……。それは妖魔だろうが人間だろうが、変わらない……」
シュバルツがポツリと紡ぐ言葉に、皆も異論は無かった。
「さあ、皆で休憩にするべ!」
その声を合図に、皆がそれぞれの場所から畑の一角に集まって来て、各自休憩をとる。シュバルツも皆と共に腰を落とし、ケイタもその近くに座った。
そのまましばし、皆の間で談笑に花が咲く。
「あの人は、いつもにこにこ笑ってくれていた。でも――――」
いつもシュバルツの近くに居たケイタだからこそ――――気づいてしまう、事もある。
時々シュバルツが、酷く遠くを見つめるような視線になる、と、言う事に。
ふとした合間。
ほんの一瞬――――
あの人の視線が、翳(かげ)りを帯びる。
その時、シュバルツの眼差しは、たいてい空の果てを眺めていたから――――
二人きりになった時、こっそり聞いた。
「シュバルツさんは………」
「ん?」
「『帰りたい』の?」
「…………!」
この人は、空の彼方から来た。だから、もしかして――――
思ったんだ。
帰りたいんじゃないかと。
自分が、元居た世界に。
「……………」
ケイタの質問に、しばらく黙って――――また、空の果てを見つめるシュバルツ。たがやがて、その横顔に柔らかい笑みを浮かべた。
「『帰りたい』……か……。どうだろうな……」
懸命に見つめるケイタの方に、シュバルツは優しく振り返った。
「私にも、よく分からないよ………」
そのままシュバルツの手が、ケイタの頭をくしゃっと、撫でる。酷く淋しそうな笑み。だがそれも、すぐに掻き消えた。
「さ、仕事仕事! 後もうひと踏ん張りだ!」
そう言って鼻歌を歌いながら、また歩き出すシュバルツ。
「あ………!」
置いて行かれないように、ケイタは後を追いかける。シュバルツは振り返ってケイタを待って――――また、一緒に歩きだしてくれた。
限りなく、優しい人。だけど、酷く淋しそうな表情を見せる人。
どうすれば、その淋しさを、消してあげる事が出来るのだろう――――
「……………」
(シュバルツ……)
ハヤブサは、ケイタの話を聞きながら、焦がれる気持ちを抑える。
もし――――今お前が目の前に居たのなら
きつく抱きしめて、決して離しはしないのに。
「それからしばらくして――――また、村の近くに妖魔が現れたんだ……」
ケイタの話は続く。妖魔を見た村人たちは、その異様な風体に、また驚いた。しかしシュバルツは――――その妖魔に見覚えがあったようだ。
「君たちは、あの時の……!」
声を上げるシュバルツに妖魔の方も気づく。少し縋る様な、助けを求める様な妖魔の視線に、シュバルツはその親子の方に走り寄っていた。
近くに着たシュバルツに、その妖魔はおずおずと、山菜やら木の実やらをたくさん盛り付けてある入れ物を差し出す。
「まさか……わざわざ礼を言いに来たのか……?」
シュバルツの言葉に妖魔は頷くと、深く頭を下げる。入れ物を差し出すその手が――――がたがたと小刻みに震えていた。『殺されるかもしれない』その恐怖を強く感じながらも、この妖魔は命をかけて、こうして礼を言いに来たのだと、その場に居た全員が悟った。
「済まない……。ありがとう……」
シュバルツは、妖魔の差し出した品物を受け取った。妖魔の方も安堵したのか、大きな息を一つ吐いて、その面に笑みを浮かべた。妖魔の親子は、そのまま踵を返そうとする。それを、村人たちの声が引き留めた。
「お前たち! ちょっと待ってけろ!」
「お土産持って来た者を、手ぶらで返しちゃだめだ!」
「シュバルツさん! その人たちを引き留めて!」
「えっ!? あ、ああ」
「お~い! みんな! 少し野菜を持って来てくれ~!」
村人たちはてきぱきと動いて、あっという間に妖魔の親子たちの前に、野菜の山を築きあげてしまう。
「少ないけど、持って帰ってけろ! お返しの品だ!」
「…………!」
妖魔の親子はしばらく茫然とそれを眺めていたが、おずおずとその野菜を持って帰れる範囲で受け取って――――また、森の奥へと帰って行った。
それからしばらくして、今度は年老いた妖魔と、そのお付きの者が村を訪ねてきた。聞けば、あの親子がいる村の、長老格の妖魔であると言う。今度は村人たちも、妖魔を怯えずに受け入れた。たちまちのうちに、その妖魔たちを歓待する席が設けられた。
「それにしても、『妖魔』って言うのは、もっとおっかない物だと思っていただ」
「んだんだ。意外と、話せるもんだべなぁ」
村人たちの言葉に、長老格の妖魔も笑みを浮かべながら答える。
「そりゃあ、中には人間を攻撃対象にしている連中もおる……。じゃが、わしらのいる村の者たちは違う。人間と争う事を、望んではおらぬ」
だから、一括りに『妖魔』だからと、むやみに攻撃しないでいてくれると助かる、と、その長老は言った。
「そんなに心配しなくとも、おらたちは農業するしか能が無いべ」
「んだんだ。鍬より重いものなんて、持った事ねぇし」
「鍬……結構重くねぇか?」
「あれっ? そうだったべか?」
飽く事も無く続けられる談笑。穏やかな歓談の時が流れた。
「それにしても、この前の山菜とかキノコ、美味かったべ! あんな物が食べられるとはなぁ」
「わしらの村の近所の山には、沢山自生しておるものじゃ。よろしければ、村の若い物に案内させますぞ?」
「本当だか!?」
「それじゃ、こちらも御礼に何か差し上げねばならねぇなぁ」
こうして、妖魔と人間の間に、交流が生まれて行った。妖魔の村とその村が比較的近い場所にある事が分かってからは、互いに人と物が行き交うようになった。農作業を手伝ったり、山菜や農作物の知識を交換し合ったりした。妖魔の子供たちも、よく村に遊びに来るようになった。人と妖魔の子供たちが、入り混じって遊ぶ。もちろんケイタも、その中に混じって、共に遊んだ。
月日は流れ、やがて桃の収穫の季節を迎える。
「今年も桃が、きちんと実ってくれたなぁ」
「これでまた、おらたちもおまんま食いっぱぐれねぇべ」
「これも全部、土地神様のおかげだべ」
そう言いながら、皆の視線が自然と、シュバルツの方へと集まって来る。皆の視線の意味をを何となく察したシュバルツが「こらっ!」と、叫ぶと、皆慌てて彼から視線を逸らした。
「どうして皆、私の事をいつまでも『神様』扱いするんだ……。「違う」って、何度も言っているのに……」
はあ、と、ため息をついて頭を抱えるシュバルツの横で、ケイタは声を立てて笑う。もう村では、それは日常の光景だった。
「やっぱりこの樹の桃が、今年も一番調子がいいな……? 何でだ?」
ある一本の桃の木の前で、孫六が首を捻っていた。
「どうしただ? 孫六」
「この木……やけに桃の調子が良いと思わねぇか? 肥を変えた訳でも、特別手入れをした訳でもないのに……」
「そう言えば――――」
村人たちが見上げる桃の木は、確かに、他の樹に比べて倍近く実を付け、しかもどの桃も出来が良かった。
「ちょっとシュバルツさんにこの樹の桃を食べてもらうべ?」
村人の1人が走って行って、シュバルツを呼んできた。
「どうした?」
「ああ、シュバルツさん。実は――――」
走ってきたシュバルツに、村人たちは説明する。数ある桃の木の中で、この木だけが、何故か実の付き方が異常なほどに良いと言う事を。
「気にする事の程の物でもないのじゃろうが……何故か、気になってのう……」
そう言いながら孫六は、また木を見上げている。
「そう言えばこの木だけ、元から村に在った木では無かったように思わねぇか?」
「そうだったっけか?」
「んだんだ。他の木は、間違いなく最初からおらたちの村に在った木だが――――この木だけは、こちらの世界で新しく手に入った木だ」
「手に入ったと言うより、おらたちの桃の畑の中に、一本だけこれが生えていた、と、言った方が正しくねぇか?」
「まあ……確かに、そんな感じだな……」
「…………」
村人たちの話を聞きながら、シュバルツも考え込む。一本だけ実のなり方が異常に良い木……。本来ならば単純に、農作物の出来の良さを、喜ぶべき事なのだろうが――――。
「元からここに在った木だと言うのなら……土が、この木とよく合っているからではないのか?」
農業の事は門外漢だが、と、シュバルツは言いながらも推論を呟く。
「うう~~ん……。そうかも知れないが……」
孫六はシュバルツの言葉に、まだ少し難しい顔をしていた。
「シュバルツさん、一応、あの木の桃を取ってきましただ。ぜひ、食べてみてけろ!」
村人がそう言って差し出すその桃を、シュバルツは一口、かじった。
「……! こ、これは……!」
「どうしただ!? シュバルツさん!」
「甘いな……。すごく、糖度が高い――――」
「糖度?」
きょとん、とする村人に、シュバルツは苦笑しながら説明を加える。
「甘さを表す指標ってところかな。すごく、良い桃だと思うよ……。しかし――――」
「何だべ?」
「……………」
しかし、と、言ったきり、黙りこくってしまうシュバルツ。かじった桃をじっと見つめて、何やら考え込んでいるように見えた。
「どうしたの?」
問うケイタに、シュバルツは笑みを見せる。
「いや……不思議な桃だな、と、思って……」
「『商品』としては、問題ないじゃろ?」
聞いてくる村人に、シュバルツは頷いた。
「ああ。大丈夫だと思う」
「じゃあ、早速出荷作業に入るべ! もう行商人や買い付けの人たちが来ているだ! 忙しくなるだよ!」
「作業を手伝いに来てくれている妖魔の方たちにも、桃を持って帰ってもらわねぇとなぁ」
「これが終われば今度は『感謝の祭り』だ! だから、頑張るべ!」
そう言いながら村人たちは、また各々の持ち場に戻って行く。シュバルツもそれに倣おうとして――――その足が、ふと止まった。
「『感謝の祭り』……か……」
そう小さく独りごとを言って、また、空の果てを眺めるシュバルツ。
「…………!」
ケイタはいたたまれなくなって、シュバルツにギュッ、と、抱きついていた。
「ケイタ?」
ケイタのいきなりの行動に、シュバルツは少し驚いて、「どうした?」と、問うてくる。だがケイタはそれには答えず、さらに強く、ぎゅっとシュバルツにしがみついた。
(出て行くかも、しれない)
『感謝の祭り』が終われば、その年の神様の役目もほぼ終わりだ。だからこの人は、この村から出て行ってしまうかもしれないと、思った。
嫌だ。
引き留めたい。
ずっとそばにいて欲しい――――
そう願う一方で、どこかで「引き留めてはいけない」とも、ケイタは感じていた。
神様にだって、神様の行くべき場所がある。だったら――――この人がこの村を出て行こうとしても、それは止められるべきではない。自分達の村はもう、充分な恩恵を受けたのだから。
だから、何も言えなくなって――――ただ、しがみつくしか出来ないケイタ。
「どうしたんだ?」
「…………」
シュバルツにそう問われても、ケイタは無言でシュバルツにしがみついている。シュバルツはそんなケイタに少し苦笑すると、ポン、と、頭の上に手を置いて来た。
「………抱っこか?」
「ち、違うよ!!」
シュバルツからの提案に、ケイタは慌てて身を離した。そして気付く。自分は今この瞬間、もの凄くこの人に甘えてしまっていた事に。こんな風に甘えるなんて、最近は、親にもしていなかった事なのに。
「お……俺は10歳になったんだから、もう甘えたりしないんだ!」
少し意地を張って、あの人より前を歩く。シュバルツは苦笑しながらも、後をついて来てくれた。
「そうか……10歳か……」
「そうだよ! もう10歳だから、1人前の年齢なんだ!」
「そうだな……10歳なら……もう、自分の事は、自分の意思で決めて良い年齢だ」
「そうなの?」
振り向くケイタにシュバルツは頷く。
「そうだ。私にも弟がいるんだが……ちょうど君ぐらいの時に、あいつは自分の行くべき道を見つけて、歩きだして行ったよ……」
「『神様』にも、弟がいるの!?」
ケイタの質問に、シュバルツはズルッとこけそうになる。
「だから『神様』じゃないって言っているだろう! 私にだって、父や母、そして兄弟がいるんだ!」
ただその後、シュバルツは小声で何かぼそり、と、一言呟いた。しかしその言葉を、ケイタは聞き取る事が出来なかった。
「……? シュバルツさん、何か言った?」
だから問い返したと言うのに、シュバルツは「別に」と、首を横に振るばかりだった。
そんなシュバルツの態度に、ケイタも、それ以上踏み込めない何かを感じ取ってしまう。だから、ケイタも「そうなの?」と、返すしかなかった。
しばらく無言で、そのまま歩く二人。だが、少し歩いたケイタは、また、足を止めて振り返った。
「ねぇ、シュバルツさん」
「ん?」
「『神様』じゃないのなら………」
ズット、傍ニ イテ クレル ?
そう問いかけようとして、ケイタは止めた。
なぜか、こう聞いてしまった方が――――酷くシュバルツを困らせてしまいそうな気がしたから。
(ケイタ……神様の傍に居るのは良いけど、あまり困らせる様な事をするんじゃないよ。神様のご意志を、ちゃんと尊重しないと駄目だ)
あまりにもシュバルツの傍にくっついている自分を心配して、たびたび両親がそう忠告してくれていた事を思い出す。危うく甘えて駄々をこねそうになっていた自分。気をつけなければと思った。この人はとても優しい人だから、尚更。
「やっぱり、何でもないよ……。じゃ、俺は今日は、あっちの畑の手伝いに行くね!」
元気良くそう言って、ケイタは走りだした。今から少しずつでも、自分はシュバルツから離れていかなければならない、と、思った。この人が村を離れる時―――要らぬ心配をかけさせないように。淋しいけれど、きっとそうする事が、自分がこの人に出来る、一番の恩返しになるのだろう。
(頑張ろう。シュバルツさんに、「ケイタは、この村は、もう大丈夫なのだ」と、思ってもらえるように)
走りながらケイタは、いつしか歯を食いしばっていた。
こうして桃の出荷作業も順調に進み、明日は『感謝の祭り』と言う所まで来た。
そしてその夜――――悲劇は起きた。
「大変だ!! みんな逃げろ!!」
皆が寝静まった真夜中の村に、突如として響く大声。寝ぼけ眼で村人たちが外を見ると、一匹の妖魔が叫んでいた。
「逃げろ!! 逃げて――――!」
ドッ! と背中に矢が当たって、その妖魔は絶命する。それと同時に、四方八方から、いきなり鬨(とき)の声が上がった。
「な、何だ!?」
茫然とする村人たちの視界に、無数の妖魔たちの姿が飛び込んでくる。その手には皆―――武器の様な物を携えていた。
「今からこの村は俺たちの物だ!! 人間たちは出て行け!! 皆殺しだ!!」
その声がきっかけとするかのように、妖魔たちは村に雪崩れ込んできた。そのままあちこちから火の手が上がり、虐殺行為が始まる。戦う術を知らない村人たちは、パニックに陥るしかなかった。
「どう言う事だ? 今まで人間と妖魔は、仲良くやっていたのではないのか?」
ハヤブサの質問に、ケイタは震える。
「確かに、あの村の妖魔の人たちとは、仲良くなっていた……。でも、襲って来た妖魔たちは、別の所から来たみたいだった………」
ここから先のケイタの記憶は混乱し――――途切れ途切れの物になる。
聞こえてくるのは、悲鳴、叫び、怒号――――
煤けた匂い。転がる死体。天まで上がる火の粉。
「逃げろ!!」
時折、あの人の声が聞こえる。でも……でも――――
「何処へ逃げればいいの――――!?」
そう叫んだ女の人が、殺されるのを見た。
逃げなければと、強く思う。
だけど、生まれてからずっと、この村から出た事が無い自分は、何処へ逃げたらいいのか分からない。ここより安全な場所なんて――――他に知らなかった。
それでも、足を止める訳にはいかないから、ケイタは必死に村の中を逃げ惑う。両親とは、とっくにはぐれてしまっていた。
不意に、目の前に妖魔が立ちはだかる。
「ひっ!!」
怯えるケイタ。しかしその妖魔は、手を差し出してきた。
「あ………?」
茫然とするケイタの目の前で、いきなりその妖魔は、別の妖魔に殺される。殺した妖魔は、ケイタを見るなり武器を振りかざしてきた。
「いやだああああっ!!」
無我夢中で、踵を返す。後ろで何か物音がしたが、怖くて振り返る事など、ケイタには出来なかった。闇の中、炎の明かりに照らされて浮かび上がる影は、いつの間にか妖魔だらけになっていた。あちこちから悲鳴と怒号と、戦いの音が聞こえる。もう、何を信じたらいいのか――――ケイタには分からなくなりつつあった。
不意に、いつもかくれんぼでよく隠れる、涸れ井戸を見つける。
(きっと……ここなら、鬼に見つからない………)
疲れ果てていたケイタは、吸い寄せられるようにその中に入った。
もう疲れた。
もう嫌だ。
怖い。
怖い………!
ケイタは涸れ井戸の上をむしろで蓋をすると、その中にじっと息をひそめて身を小さくしていた。そうする以外、他に何ができただろうか。
だが井戸の蓋は、無情にもすぐはがされてしまった。
「ヒャハハハハ!! 人間の子供がいるぞ!!」
井戸の中を覗き込んで来た妖魔の、甲高い笑い声が響く。ケイタは、もう悲鳴すらあげられない。
「――――ッ!」
ただ、身を小さく丸くすることしか出来ないケイタ。濃厚な死の予感に、恐怖するしかなかった。だが――――
ドカッ!!
「ぐうっ……!」
妖魔の呻き声とともに何かが倒れる音がして、代わりに耳慣れた声がケイタの耳に飛び込んできた。
「ケイタ!!」
井戸を覗き込んできたその人は、ケイタに向かって手を差し出してきた。
「………! シュバルツさん!!」
ケイタは、無我夢中でシュバルツに向かって手を伸ばす。力強い腕が、彼を地上へと引っ張り上げてくれた。
「うわああああ―――!! 怖かった……! 怖かったよぉ――――!!」
張り詰めていた物が切れてしまったのか、シュバルツの腕の中で泣きじゃくってしまうケイタ。シュバルツはそんなケイタを、しばらくあやすように優しく背中を撫でてくれていたが、やがて、ケイタに小さく呟いて来た。
「……済まないが、少しの間でいい。泣きやんでくれないか? 未だ戦いの途中だ」
「あ………!」
シュバルツの肩越しに、妖魔に取り囲まれている現実を知ったケイタは、身を固くしてしまう。シュバルツはそんなケイタを片手に抱いたまま、もう片方の手に握られた刀で周りを牽制していた。
「やっちまえ!!」
子供を抱えて身動きが取れないと見て取った妖魔たちが、一斉にシュバルツに向かって襲いかかって来る。
(やられる――――!)
強くそう感じたケイタは、目をぎゅっと閉じてシュバルツにしがみついた。だが―――ケイタの予測に反して、やられたのは逆に妖魔たちの方だった。シュバルツが片手で振るった刀に、皆弾き飛ばされてしまっていた。
「ギャッ!!」
「グワッ!!」
妖魔たちが吹っ飛ばされて、二人の間に僅かな空間が出来る。
「走るぞ!!」
シュバルツはケイタを抱きかかえたまま、妖魔たちの間をすり抜けるように走り出した。
「おのれ!!」
だがやはり、妖魔たちの方もそんな二人の動きを許しておくはずもない。次から次へとその進路に立ちはだかり、二人を殺そうとする。シュバルツはそんな妖魔たちの動きに、抜け目なく対応していたが――――
「ま、待って下せぇ!! お、俺は――――!!」
ある妖魔に斬りかかろうとした時、いきなり目の前で命乞いをされる。
「――――ッ!」
斬ろうとしていたシュバルツの刀が、ピタリと止まる。しかし乱戦の中で刃を止めると言う事は、敵に大きな隙を与える事につながってしまう。
「隙あり!!」
そこにつけ込むように繰り出された別の妖魔の刃が、シュバルツの肩を斬り裂いた。
「ぐぅ……ッ!」
「シュバルツさんっ!!」
目の前で飛び散るシュバルツの鮮血に、ケイタは悲鳴を上げる。
「く………!」
シュバルツは身を低くして踏ん張ると、懐から何かを取り出した。それを彼が地面に叩きつけると、ドンッ! と言う音とともに、あっという間に周りが白煙に覆われてしまう。妖魔たちが煙の中で混乱している隙に、二人は何とかその場から脱出する事に成功していた。
シュバルツは、村の外れまでケイタを抱きかかえてくると、そこで彼を下ろした。
「誰も居ないな……。何人かは、確かにここに連れて来たのだが……」
「シュバルツさん、怪我を―――!」
シュバルツから下ろされたケイタは、彼から身体を離したことで――――ようやく、シュバルツの身体が既に傷だらけである事に気がついた。
「な……治さないと……! シュバルツさん……!」
青ざめて震えるケイタに、シュバルツは優しく微笑みかけてきた。
「大丈夫だよ……。すぐ、治るから――――」
「う、嘘だ! 傷がすぐ治るなんて、そんな話、聞いたことないよ!!」
シュバルツが『優しい嘘』を付いていると察したケイタは、懸命に叫ぶ。それに対してシュバルツは、少し苦笑気味の顔をケイタに見せた。
「本当だ……。ケイタ……私は絶対に、お前に『嘘』はつかないよ」
そう言うとシュバルツは、破れているコートの袖をまくって、腕を見せた。
「ほら……少し前に斬られた傷だが、もう、治って来ているだろう?」
「…………!」
ケイタは茫然と、シュバルツの腕を見る。確かにその腕は、傷一つ無いように見える、綺麗な物だった。コートの袖は確かに切り裂かれ、そこに血が滲んでいたと言うのに。
「ど……どう言う事なの……? まさか、本当に――――」
「『神様』では、無いな……。私は、そんな良い『モノ』じゃない」
ケイタの言葉を、シュバルツはきっぱりと否定する。
「で、でも……! だって――――」
しかしケイタも納得できなかった。こんな、傷の治りの早い人間など見た事が無い。それなのに『神様』ではないと言うのなら、この人は一体、何者だと言うのだろう。
「とにかく違う。私は断じて、『神様』と言われるような存在ではない」
そう言いながら優しく笑うその人は、哀しそうに瞳を伏せた。
「第一……私が本当に『神様』とか言うものであるならば………私は『神』失格だろう。村を……こんな………」
「―――――!」
シュバルツの言葉に、ケイタはショックを受ける。
違う。
違うのだ。
村が襲われたのは、絶対にシュバルツのせいではない。それくらいなら、自分にも分かる。
文句を言いたくて――――神様のせいにしたくて、シュバルツを『神様』扱いしたがっている訳ではないのだ。
「ち、違う……! 違うよ、シュバルツさん……!」
だから慌てて、シュバルツにそう告げる。しかし、目の前の優しい人は、ケイタの話を最後まで聞こうとはしなかった。
「フフ、優しいな。ケイタは……」
シュバルツはそう言うと、ケイタの肩にポン、と手を置いてくる。
「それよりケイタ……よく聞くんだ。ここからこの道なりに少し行った所に、岩場に隠れたほら穴がある。今――――何人かをそこに避難させている所なんだ」
「………! 僕以外にも、助かっている人がいるの!?」
驚くケイタにシュバルツは頷く。
「少しだけだけどな」
そう言ってシュバルツは、淋しそうに笑った。
「ケイタ。お前は今からそこに行ってくれるか?」
「分かった……。けど、シュバルツさんは?」
問い返すケイタに、シュバルツは首を振った。
「私は……もう少し、皆を探しに行くよ」
「――――! 一緒に来てくれないの!?」
弾かれるように叫ぶケイタに、シュバルツは困ったような笑みを浮かべる。
「済まないな……。でも、助けを待っている人が、まだ村の中に居るかもしれない。ケイタ……さっきの、君みたいに」
「あ…………!」
シュバルツにそう言われてしまっては、ケイタも返す言葉が無くなってしまう。でも、不安だった。今―――唯一信じられる存在であると言ってもいいシュバルツから離れる事が、ケイタには恐ろしく感じられてたまらない。
「大丈夫だ。岩場のほら穴は外から見たら分かりにくいかもしれないが、見張りの『妖魔』がその近くに立ってくれている……」
「――――ッ!」
『妖魔』と言う言葉に、思わず身を固くしてしまうケイタ。ケイタの頭の中には、どうしても――――げらげらと笑いながら、自分に武器を振りかざして来た妖魔のイメージが、強く思いだされてしまう。
「ケイタ――――」
シュバルツは、そんなケイタの想いを何か察したのか、ケイタの手を優しく握りながら話を続けた。
「妖魔と言うのは、確かに――――恐ろしくて、忌み嫌われる存在だ。だけどあの村の中には………お前たち人間を守るために、戦っている妖魔たちもいる。……それを、忘れないで欲しい」
「…………!」
シュバルツの言葉に、ケイタもはっと、思い当たる。確かに、自分に手を差し伸べてくれていた妖魔も居た。
でも、だからこそ――――危ないのではないかとケイタは思う。
あの村の中は今や、誰が敵で誰が味方なのか、分からない状態になっているからだ。
「さあ、時間があまりない。ケイタ……お前は行くんだ」
そう言って、シュバルツは立ち上がる。
「シュバルツさん!」
ケイタはシュバルツを引き留めたくて、声を上げる。しかし、シュバルツを止める力が、ケイタにあろう筈も無かった。
「ケイタ……お前は、生きろよ」
それだけを言うとその優しい人は、再び戦場へと踵を返して行った。
(シュバルツさん……!)
ケイタはシュバルツに握られていた手を、ギュッと包み込む。シュバルツに言われたとおり、自分は「生きねば」と、思う。だから、顔を上げて――――道の向こうのほら穴に向かうべきだと考える。
しかし――――
(怖い――――!)
ほら穴へと続く道は、真っ暗だった。その暗さが、ケイタの歩きだそうとする意志を阻ませた。1人で、ほら穴まで歩いて行ける自信など無い。それならいっそ――――
(待とう)
ケイタは草むらの中に身を隠しながら、いつしかそう決意していた。
(怒られてもいい。シュバルツさんを待とう。あの人は絶対、戦いが終わればここに来る筈だから……)
酷く我が儘な選択をしている、と、ケイタも自分で自分を揶揄するしかない。だが、そう決意してしまえるほどに――――ケイタはシュバルツの傍から離れがたく感じていたのだった。今―――ケイタが心から信じられる、と、思えるのは、シュバルツだけだったのだから。
(シュバルツさん……!)
ケイタは草むらの中で身を小さくしながら、祈るようにシュバルツを待ち続けていた。
村の方から聞こえてくる怒号と悲鳴、戦いの音は止む事が無い。
時折あの人が、村人たちを助けだして来て、「ほら穴へ―――」と、導く声が聞こえる。助け出された村人たちは皆、シュバルツも共に逃げるようにと声をかけるのだが、彼は頑なに拒否して、また戦場へと舞い戻って行っていた。
もし、助け出されていた村人たちの中に、ケイタの父と母がいたならば、ケイタもほら穴の方へ向かっていただろう。だが、シュバルツが助けた村人たちの中に、ケイタの両親の姿を見る事は無かった。
故にケイタはシュバルツを待ち続けた。息を殺し、草むらの中に、その身をひそめながら――――。
そうして、どのくらいシュバルツを待った事だろう。
暫くしてケイタは、村の方から戦いの音が小さくなっている事に気がついた。
(戦いは……終わったのかな……?)
ケイタはそろそろと、草むらの中から身を起して、村の方へと振り返る。そこで彼は、驚くべき光景を目にする事になった。
ドンッ! と、音を立てて何かが吹っ飛ばされてきて、木の幹に叩きつけられる。そのままずるずると力無く地面に滑り落ちてきた人がシュバルツである、と、悟った瞬間、ケイタは悲鳴をあげそうになってしまった。それを、懸命に口を押さえて堪える。
シュバルツの身体には、既に何本もの矢が刺さり――――あちこちが切り裂かれていて、苦しそうに肩で息をしていた。それでも彼は、ふらふらと立ち上がり、また、刀を構える。
「…………」
シュバルツが正眼で見据える先から、1人の男がゆっくりと姿を現してきた。
「……まだ、粘るのか……。あきらめの悪い奴よ……!」
そう言って大男は不敵に笑う。その男の姿を見た瞬間、その風体の異様さに、ケイタは更に息を飲んだ。
(何……? あの人は、仁王様……!?)
黒褐色の肌に白銀の長い髪。瞳の色は紅に燃え上がり、筋肉たくましい腕には、金色の刺青が刻み込まれていた。そして金色の髪飾りと炎の光背(こうはい)――――あまりにも人間離れした姿。そしてそれは、ケイタが思わず「絵本で見た仁王様だ」と、思ってしまった程に、妖魔ともまた違った雰囲気をその男は醸し出していた。
男の後ろから、白藍色の衣をまとって、弓矢を構えた『兵士』たちが出てくる。その統率された様子から、「仁王」の部下たちなのだとケイタは悟った。部下たちは矢を弓につがえると――――無言でシュバルツに狙いを定めはじめた。
「…………ッ!」
刀を構えるシュバルツの表情が、一層険しい物になる。たいして仁王は、不敵な笑いをその面に浮かべながら、顎をしゃくって無造作に部下に命じた。
「討て」
矢が放たれる当時に、シュバルツの姿がそこからフッと消える。それから数瞬もせぬうちに、いきなり仁王の前にシュバルツの姿が現れる。ガンッ!! と、激しい音を立ててぶつかり合う剣撃。
「刎(ふん)っ!!」
力勝負で押し勝ったのは、またしても仁王の方だった。彼は剣を振り切り、シュバルツを吹き飛ばしてしまう。それと同時に周りの兵士たちから、また一斉に矢が放たれた。
「く………!」
シュバルツは弾き飛ばされながらも、懸命に襲い来る矢に対応する。だが、防ぎきれなかった最後の一本が、彼の肩に突き刺さった。そのまま彼は、ガクッと地面に膝をついてしまう。
「――――ッ」
それでも彼は顔を上げ、刀を構える。その様を見た仁王の方が、面に笑みを浮かべた。
「………ほう、まだ闘志を失わぬとはな……。しかし――――!」
その時、二人から少し離れた場所で、ドカン!! と、何かが爆ぜる音とともに、巨大な火柱が上がる。
「な――――!」
その火柱が上がった『場所』を悟ったが故に、シュバルツの顔色が変わった。そう――――そこは、「ほら穴」があった場所だったからだ。
「汝(なれ)が、何かを懸命に守ろうとしていたのは、分かっていた!」
茫然と火柱を見つめるシュバルツに向かって、無慈悲なる『神』の声が飛ぶ。
「だが――――残念だったな……。汝が守ろうとした最後の者たちも、灰燼に帰した。後は……汝だけだ」
「ああ………!」
仁王の言葉に打ちひしがれたのか、シュバルツはガクッと頭を垂れてしまう。その瞳から、きらきらと光る物が零れ落ちていた。
「………何故だ……!」
シュバルツから、絞り出される様な声が発せられる。
「『神』とは、人を守るものだろう!? それなのに何故――――このような事を………!?」
「『神』とは――――『人を裁く者』だ!!」
「な…………!」
仁王の言葉に、シュバルツは言葉を失ってしまう。
「少なくとも……吾(われ)の『神としての役割』は、そうだ」
「…………!」
シュバルツは、ギリ、と、歯を食いしばっている。ケイタはただ、二人の会話を茫然と聞くしかなかった。
「ここの村人は……罪を犯した。なれば、罰を与えられなければならぬ!」
傲然と言い放つ仁王に、しかしシュバルツも反論する。
「何故だ……! ここの村人たちは、真面目に土地神を崇めていた……! 野心も抱かず、無益な殺生もせず――――平和に暮らしていた筈だ! それなのに、何故――――!?」
「『妖魔』と交わっていたであろう!! この村は―――!!」
「な――――!」
仁王の言葉に、シュバルツとケイタは絶句する。
「しかもそれだけでは飽き足らず、吾の『仙桃』を妖魔の手に触れさせ、揚句、『報酬』として分け与えた!! 村人達は『仙桃』を売り利益を得て、それを私物化した!!」
(『仙桃』――――?)
ケイタには、仙桃の単語の意味が分からず、首を捻るしかない。対してシュバルツの方は――――何か、思い当たる節があったようだ。「そうか、あの桃が……!」と、合点がいったように独り頷いている。
「どうだ……! これだけ罪を犯せば、裁きを受けるのは自明の理であろう!!」
そう言いながら怒れる仁王は一歩、前へと進み出る。それに対して尚もシュバルツは首を振った。
「それでも――――村人たちは知らなかったんだ!! あれが『仙桃』だなんて……! それに村人たちはあの桃を――――!」
「黙れ!! 人間ですら無いモノが、何をぬかすか!!」
(えっ………?)
仁王の言葉に、ケイタはただ茫然とするしかなかった。
「吾には見えるぞ……! その身体、『何』で出来ておる物なのか……!」
「う………!」
怯むシュバルツに、仁王は更にたたみかけてくる。
「何と不自然でいびつで………『邪悪』な物で出来ておるのか!」
「…………!」
(シュバルツさん――――!?)
ケイタは混乱しながらシュバルツを見つめる。
どう言う事なの?
シュバルツさんは
人間じゃ 無い――――!?
「そんな『モノ』が、人間のふりをし、善良なふりをして人間たちに近づく……! 汝(なれ)の様なモノが、一番性質が悪い!!」
「…………ッ!」
仁王に糾弾されて、シュバルツの身体が小さく震えているのがケイタには見える。それと同時に、ケイタは仁王の『言葉』の方に違和感を感じ始めていた。
ねぇ
ねぇ 待って
「人間じゃない」ことは そんなに 悪い事 なの ?
「汝の様なモノが居るから――――いつまでも、妖魔にたぶらかされる人間が後を絶たん! 大方今回も、汝がここに居る人の子たちをたぶらかして、妖魔と人とを繋いだのであろう!!」
「………! ち、違………!」
否定しようとするシュバルツの声は小さくて――――途中で消えてしまう。彼はそのまま、下を向いてしまった。
(違う――――!)
たいしてケイタの方が感じている違和感は、ますます強くなっていった。
待って――――
シュバルツさんは 僕たちを
「たぶらかしていた」?
違う
違うよね?
だってシュバルツさんは
一度も僕たちに『嘘』を言っていない。
「神ではない」と、懸命に言っていた。
でも、その後に『自分は人間だ』とは
あの人は一言も言わなかった。
だから僕たちは、余計にあの人を『神様』だと信じてしまって――――
「汝の様なモノこそ、この世に存在してはならん! 人の子とこれ以上かかわり合いになる前に、真っ先に滅されなければならんモノなのだ!!」
待って……!
ねえ、待って……!?
その人は、そこまで言われなければならないほどに 何か『悪い事』をしたの?
してない。
していないよね?
あの人はただ、助けただけだ。
怪我をした『妖魔の子』を――――
それが そんなに 悪い 事 な の ?
「……………」
だがシュバルツは、仁王の言葉に何一つ反論する事無く、握っていた刀を地面に置いてしまった。その様を見た仁王の面に、フッと笑みが浮かぶ。
「……やっと、観念したか……。最初から、素直にそうしておればよい物を―――」
「…………」
座り込み、下を向いたシュバルツの瞳から、光る物が零れ落ち続けている。もう彼は、仁王の言葉に対して、何も反論する事も、言い訳する気すらないようだった。
(どうして―――? どうして? シュバルツさん……!)
ケイタは、そんなシュバルツを食い入るように見つめる。
おかしい。
おかしいよ。
だって、貴方は何も悪くないのに――――!
逃げて
シュバルツさんお願い。
逃げて―――――!!
ケイタの祈りも空しく、ただそこに座り込み続けるシュバルツ。そんな彼に向かって周りの兵士たちが再び弓で狙いを定め、仁王がその傍に歩み寄って行く。
「村人たちも、今頃汝を受け入れた事を後悔し、恨んでいる事だろう。だが―――安心するがよい。吾がきっちりと、汝に引導を渡してやろう程に」
(――――――!)
この仁王の一言は、ケイタの心に怒りの火をつけた。
違う――――!
どうして、恨まなければならない?
他の人はどうか知らない。でも、少なくとも僕は、恨んでなどいない。
あの人には、助けてもらった。
優しさをたくさんもらった。
今だってそうだ。僕たちを助けるために、この人は走りまわって傷だらけになって――――
元よりこの人は、この村の人間ではない。自分達とは縁も所縁も無いヒトなのだ。そして力も強く、剣の腕も立つのだから、この村が妖魔に襲われた時点で、1人逃げようと思えば、逃げ切れたはずなのに。
それなのに、逃げる事をせず、村に留まり、皆を守ろうとしてくれたヒト。
それだけで――――もう、充分ではないのか。
そこには、ただ『感謝』しかない。『恨む』だなんて、とんでもない。
それを……
それを―――――
ただ、『人間じゃない』と言うだけで
『妖魔を助けた』と、言うだけで
そのヒトの総てを
そんな風に、否定しないで――――!!
シュバルツの傍に来た仁王が、剣を最上段に振りかぶる。彼にとどめを刺すために。
「心おきなく――――闇に帰――――!」
「違あああああ―――――う!!」
気がつけばケイタは、渾身の力を込めて、叫び声を上げていた。
「―――――!」
叫び声を上げたが故に、皆の視線がそこに集まる。
もう逃げる事も隠れる事も出来ない、と悟ったケイタは、立ち上がった。
だけど、足が震える。息が勝手に乱れる。泣きたくも無いのに、涙がこぼれた。
「…………!」
シュバルツと視線が合う。驚いたようにこちらを見つめているその姿は、自分を助けた時よりもさらに、ボロボロに傷ついていた。
そして、仁王とも視線が合う。この瞬間ケイタは「あ、死んだ」と、思った。絶対的な力を持つ、怒れる『神』――――この圧倒的な存在の前では、自分はひどく矮小な存在でしかないのだと、思い知ってしまう。
だけど、ネズミにもネズミなりの矜持がある。
どうせ自分はもう死ぬ。だけど―――どうしても伝えたい言葉が出来てしまった。
ならば、叫ばねばならぬ、と、ケイタは思う。
自分以外に、叫ぶ人間が居ない、と言うのなら、尚更。
せめて死ぬ前に、声を上げねばならぬのだと、思った。
シュバルツの唇が「ケイタ」と、動くのがはっきりと見えた。
(ごめんなさい、シュバルツさん……)
ケイタは心の中で、謝った。
僕は貴方に『助けて』とは言わない。言えない。
もう、本当に充分だ。ありがとう。これ以上は、何も望まない。
本当は――――助けてあげたい。
いますぐにでも、ここから 貴方を助けだして、あげたいんだ。
だけど、立ち上がった所で、叫んだ所で、何も状況を変えられないと気づいてしまう。
恐ろしい程に
絶望的なまでに―――――自分は、無力だった。
でも――――ならばこそ
だからこそ、叫べ。
例えそれが総ての人から『お前は間違っている』と否定される物であったとしても
自分がその『想い』に対して、堂々と胸が張れるのなら。
ごめんね、シュバルツさん。
絶対に――――僕を『助けよう』なんて、思っちゃ駄目だよ。
「…………」
仁王が、無言でケイタの方に身体を向ける。それだけで、ケイタは全身に、雷を打たれたかのような恐怖を覚える。だけど、踏ん張った。叫ぶためには、ここで負けるわけにはいかないのだ。
「……そ………」
やっとのことで絞り出された声は、信じられない程に上ずっていた。
「何だ?」
無慈悲なる神の問いかけ。ケイタは、ひきつる己の口を懸命に叱咤する。
負けるな。
立ち上がったのなら、ちゃんと叫べ。
最期まで――――
「そ……そのヒトは……何も、悪くないッ!!」
「―――――!」
自分の言葉に、周りの大人たちが息を飲む気配が伝わってくる。
言った。
言えた。
言えたじゃないか。
足が震える。膝が、おかしい程に笑っている。
心臓が、今にも口から飛び出してきそうだ。
だけど、もう、僕は―――――
「ぼ……僕は……!」
ひきつり、もつれる舌。
それを、懸命に叱咤する。
「ぼ、僕は……絶対に――――」
叫べ。
今こそ。
『想い』を込めて――――
「僕は、絶対に……シュバルツさんを、恨んだりはしない!!」
ケイタが叫び終わった後、辺りは水を打ったような静けさに覆われた。そんな中、ただ―――叫び終わったケイタの荒い息づかいだけが、響いていた。
どうだ。
言ってやった。
言ってやったぞ。
これが、僕の中の『想い』 僕の中の『真実』――――
神様の、一方的な物差しだけでは、決して測り得ないモノ。
誰に何と言われようとも、自分はこれを曲げる気はない。
今ここで殺されると言うのならば、尚更だった。
仁王はしばらく頬をひきつらせながらケイタを見つめていたが、やがて、ため息とともにポツリと漏らした。
「……やはり、穢れたネズミは、穢れたままか……」
「………ッ!」
分かっていたこととはいえ――――絶望的なまでに話の通じない『神』に、ケイタは唇を噛みしめるしかない。
だけど、不思議と『後悔』だけは、無かった。この『想い』はきっと、黙殺してしまう方が、苦しかった。
(シュバルツさんに、少しは伝わっただろうか)
ケイタは思う。
少なくとも自分は、『後悔』などしていない。
この人に出会えたこと。
過ごした日々。
そこにはただ――――『感謝』しかないのだ。
それをちゃんと、伝える事が出来ただろうか。
「……………」
仁王が無言で、手を上げる。それが振り下ろされた瞬間、周りの兵士たちが自分に向かって矢を放って――――そこで、自分の人生は終わるのだろう。
もう少し、何か言ってやりたい。でも駄目だ。旨く考えがまとまらなかった。
ごめんね、シュバルツさん。
せめて逃げて。
僕が殺されている間に。
「死ね」
無情なる神の声が響く。
「…………!」
ケイタは目を閉じて、迫りくるその時を待った――――
刹那。
信じられぬ事が起こった。
兵士たちが放った矢よりも早く、一陣の『風』が、ケイタの身体をかっさらって行ったのだ。
「何っ!?」
風の正体を看破した仁王が、驚愕の声を上げる。だが無理からぬことであった。その風は――――ボロボロに傷つき、もう動くことすらできそうになかったシュバルツその人であったのだから。
「シュバルツさん!?」
ケイタを庇い、抱きかかえた瞬間、シュバルツの身体に何本もの矢が刺さる。ウ、と、シュバルツから、小さな呻き声が上がる。それでも彼は走る事を止めなかった。ケイタを抱きかかえたまま――――疾風の如く、走り続けた。
「シュバルツさ……!」
「黙ってろ……! 舌を噛むぞ!!」
シュバルツの背後から怒号が上がり、矢が飛んでくるが、彼の足は、見る見るうちに兵達を引き離して行く。こうして二人は、戦場から脱出する事に成功したのだった。
だが、傷だらけのシュバルツが、全力で走れる時間は―――そう長くは続かなかった。
あっという間に息が上がり、走り方もふらついたものになる。だがそれでも―――彼は走るのを止めようとはしなかった。
「シュバルツさん……! もういいよ! 下ろして……!」
たまらずケイタは叫ぶ。しかしシュバルツは頭を振った。
「もう少し……。君の安全が確保できたら……な……」
そう言って、走り続けるシュバルツ。もうこの人は、死ぬまで自分の事を守って走る気なのだと悟ってしまって、ケイタはたまらなくなってしまった。
結局
結局最後まで
自分はこの人に守られてしまった。
自分達のために、ボロボロに傷ついてしまった人。
この人のために、僕は
何を、してあげる事が――――出来たのだろう。
「ケイタ……」
苦しげな息をするシュバルツから、そっと呼びかけられる。「何……?」と、問い返すと、その人は綺麗な笑みを浮かべた。
そして言った。
たった、一言だけ――――
「ありがとう……」
「―――――!」
(何故………!)
勝手に涙が、とめどなく溢れた。
どうして
どうして
『お礼』を言われる様な事なんて
何一つ、出来ていないのに――――
ボロボロと泣き続ける自分に
「泣くな」と、小さく声をかけられた。
無理だよ、シュバルツさん。
こんな時のこんな涙。どうやって止めたらいいのか―――全然、分からないよ。
「シュバルツ!!」
響き渡るハヤブサの声。ここでようやくシュバルツは、ハヤブサと再会した。
そして、消えてしまった。
永遠に――――
「……………」
ケイタは話しながら、いつしかまた涙をポロポロと溢れさせていた。
悔しかった。
悔しくて仕方が無かった。
総てにおいて――――あまりにも、無力であった自分が。
「ねぇ……。教えてよ……」
静まり返った幕舎の中に、少年の嗚咽が響く。
「僕たちは……そんなに、悪い事をしてしまったの……? 妖魔の子たちと遊ぶ事は、そんなに悪い事なの……?」
少年の問いかけに、明確な答えを返せる者は、そこには誰もいなかった。
「『人間じゃない』ことは……そんなに、悪い事なの……? もう『生きていてはいけない』って、言われるほどに……?」
「ケイタ………」
ハヤブサはそっと、ケイタを抱きしめていた。
「よく、戦った」
この小さな戦士に、そう言ってやりたかったから――――
「う……あ……! うわああああああ――――!!」
ハヤブサに抱きしめられたケイタは、声を張り上げて号泣していた。堪えていた物が、溢れだして来てしまったのだろう。
ハヤブサは、ただ黙ってケイタの背中を撫で続けていた。そうする以外に、子供を慰める術をハヤブサは知らない。ただ―――存分に、泣かせてやりたい、と、思った。
(シュバルツ……)
ケイタを腕の中で慰めながら、ハヤブサは愛おしい人に想いを馳せる。
それだけの目に遭いながら……それでも、お前から最期に出てくる言葉は――――
「ありがとう」
なのだな。ケイタにも。そして、俺にも――――
誰かを恨むでもなく。
復讐を、願うでもなく―――――
「こんな私を、愛してくれて、ありがとう」
(……………!)
その姿は、なんて愚か。そして………なんて、愛おしい―――――
ハヤブサは、ケイタを抱きしめる腕に、少し、力を込めた。
「……ケイタ。取り戻すぞ………!」
「え………?」
「絶対に――――シュバルツと、お前たちの村の未来を取り戻す!」
力強く断言するハヤブサの姿に、ケイタの瞳から、また涙があふれ出した。
「本当に……? 本当に、助けられるのかな……?」
「ああ。必ず助ける。……約束しよう」
「………うん」
「だから、泣くな……」
「うん―――――」
頷くケイタだが、涙を止める事は出来なかった。ハヤブサは、そんなケイタが落ち着くまで――――ずっとやさしく抱きしめ続けているのだった。
(ハヤブサさんって………)
ハヤブサの腕の中で落ち着いて来たケイタはふと思った。
(シュバルツさんに、似てる……?)
そう感じられて、ケイタは不思議に思う。
(何故だろう。背格好は全然違うのに――――)
ハヤブサの腕の中で、そう物思いにふけっていると、ハヤブサから声をかけられた。
「……落ち着いたか?」
「…………!」
(ああそうか………声―――――)
ケイタはようやく、自分の感じていた物の正体に気がついて、思わずハヤブサの顔を、じっと見つめてしまう。
この人の『声』が、シュバルツさんに似ているんだ。
「………どうした?」
じっとこちらを見つめてくるケイタに、ハヤブサは問い返す。
「あ………えと………」
少ししどろもどろになりながらも、ケイタは口を開いた。
「あの……『似ているな』と、思って……」
「何が?」
「声が……その、シュバルツさんに……」
「ああ………」
その言葉を聞いたハヤブサが、少し苦笑気味の笑顔を見せる。
「よく言われるんだ……。そんなに似ているか?」
「うん」
素直に頷くケイタに、ハヤブサも「そうか」と、笑顔を返した。
「龍の忍者よ。行くのか?」
ケイタが落ち着いたのを見計らってから、少し離れた所に立っていた太公望が、ハヤブサに声をかけてきた。
「ああ」
ハヤブサは迷いなく頷く。シュバルツに繋がる糸は、もうここにある。ならば、躊躇わずにそれを掴むだけの話なのだと、ハヤブサは思った。
だが太公望は、少し難しい顔をしていた。
「かなり厳しい戦場の様だ。それに……その少年の話は断片的すぎて、戦場の全体像を把握するには至っていない――――」
「それでも構わない。俺は、行く」
太公望の言葉に、それでも龍の忍者はきっぱりと言い放った。
「守りたい物は、もう――――分かっているのだから」
「そうか………」
ハヤブサの意志が固いと悟った太公望は、これ以上彼を引き留めることは不可能だと知った。
(今までも人の子は、不可能を可能にする奇跡をいくつも見せた……。この厳しい戦場も、人の子たちの『願い』が結実するのであれば、もしかしたら………)
いささか楽観的過ぎると思わないでもないが、太公望は今回も、人の子の底力に期待した。自分が手を貸すのは、その力が及ばなかった時にすればいいと、思った。これはある意味――――人の子が怒れる『神』に挑む戦いでもあるのだから。
「では、人の子の力―――見せてもらうぞ」
「言われずとも」
太公望の少し挑戦的な物言いに、ハヤブサも即答する。その横でケイタも頷いていた。
「ではハヤブサ……。戦いに連れていく人選はそなたに任せる。過去に連れていける人間の数は、限られているのでな」
「分かった……。だが少し、待ってくれ」
「?」
太公望とケイタが見守る前で、ハヤブサはシュバルツのロングコートの一部を裂いた。そしてそれを、己が龍剣の柄へと巻きつける。
これは、『証』だ。シュバルツを守れなかった『証』――――
何時もいつも、悲劇に間に合わない。こんな連鎖は、もう終わりにしなければならない。
待っていろ。シュバルツ。そしてキョウジ……。
お前たち二人の『失われた時間』を、必ず取り戻して見せるから。
お前たち二人が居ない未来など
俺は断固として拒絶する――――!
「待たせたな……。行こう」
ハヤブサの言葉にケイタも頷き、二人で幕舎の外に出て行こうとする。すると、とたんに幕舎の出入り口付近で、大きな物音と土埃が上がった。
「わ、わ! こっち来る!」
「おい! ちょっとどけって!」
「痛い! 押さないでよ!」
「ちょ……! それ以上押されると――――!」
ドドドドッ!! と、音を立てて、出入り口付近で武将たちが折り重なって倒れて、幕舎の出入り口付近を塞いでしまった。ハヤブサとケイタはそれを茫然と見つめ、太公望はその後ろで額に手を当てていた。
「やれやれ……人の子は、どうしてこうも好奇心が強いのだ。後でちゃんと説明をするというのに――――」
太公望の言葉に、折り重なって倒れている武将たちは、苦笑するしかなかった。
太公望が一通りの事情を皆に説明した後、改めてハヤブサは、武将たちと向き合う。過去で共に戦う者を選ぶために。
「ハヤブサ殿……。我等の中の誰が選ばれても、我々に異存はない」
「だから、お主の望むとおりに選ぶがええ」
秀吉の言葉に、皆がうんうんと頷く。
「……………」
対してハヤブサは、少し考え込んでいた。
ここに居る武将たちは、皆――――それぞれに腕が立つし、何よりも、自分の個人的な望みに、とても親身になってくれた。ケイタの話に、涙を流していた者も居た。本当に――――誰を連れて行っても、その戦場で頼れる仲間になると知る。
ならば、『何』で共に闘う仲間を選ぶべきなのか。
これはもう――――『想い』の問題なのだと、ハヤブサは思った。
だから――――
ハヤブサは、ある人物の前に歩を進めると、手を差し出した。
「えっ……! 私……!?」
手を差し出された甲斐姫は、茫然としながら問い返す。それに対してハヤブサは「そうだ」と、頷いた。
「あの時……お前が声を上げてくれなければ、ケイタの声を聞く事も、出来なかったかもしれない……」
シュバルツの死に打ちひしがれて、ただ茫然としているしか自分は出来なかった時に、彼女が『否』の声を上げた。上げた声にケイタが応えた。だから、今がある。
「だからこれは……俺なりの『礼』のつもりだ……。だが行く先は、過酷な戦場だ。だから、無理にとは言わん。嫌なら、断ってくれても――――」
「ううん! 嬉しい! ありがとう!」
ハヤブサの言葉が終わらぬうちに、甲斐姫が叫んだ。
「絶対……! 絶っっっ対にシュバルツさんを助けるわ!! 私、頑張るから!!」
甲斐姫の言葉にハヤブサも頷く。やはり思った通り――――彼女が皆の幸せを願う気持ちは、人一倍強い。その想いの強さに賭けてみたい、と、ハヤブサは思った。『神』と戦う必要があると言うのならば、尚更。
「ケイタ君、よろしくね」
優しく、そう声をかけてくる甲斐姫に、ケイタも頷いた。
「後もう1人、連れていける。そのもう1人は、お前が選んでくれ」
「えっ? いいの?」
頷くハヤブサに、甲斐姫は笑顔を見せた。
「分かった! じゃあ……尚香! 今回も、力を貸してくれる?」
「勿論! 甲斐の頼みなら、喜んで!」
甲斐姫の差し出す手を、孫呉の弓腰姫が掴む。
「人選は終わったようだな」
過去に戻る3人が出揃った所で、太公望が声をかけてきた。頷く3人に、太公望は「ならば――――」と、笑顔を見せる。
「一つだけ、私から助言をしてやろう。耳を貸せ」
太公望は3人に何事かを耳打ちして、その場から離れた。
「では皆さま……こちらの『光陣』にお進みくださいませ」
時を渡る能力を持った巫女かぐやが、ケイタを含めた4人を光陣へと導く。光陣の中に4人が入ったのを確認してから、かぐやはケイタの額に手をかざした。
「『過去』とは、その方の心象風景の中にございます。ケイタ様、どうか瞳をお閉じください」
言われたとおりに瞳を閉じるケイタに、かぐやから更なる声が重なる。
「そして……思い浮かべられませ。貴方様が御救いしたいと願う、人々の顔を――――」
「……………!」
(僕が………僕が『救いたい』と、願う人達は――――)
ケイタの脳裏に、懐かしい人々の顔が浮かぶ。そして、もちろんシュバルツの顔も。
(神様……! もしも、やりなおす事が許されるのなら、僕は、あの人たちを――――)
ケイタの額にかざしているかぐやの掌から、白く優しい光が溢れる。その光に4人の身体が包まれて、光陣の中から消えて行った。
(行ったか……)
4人の姿が光陣の中に消えて行ったのを確認してから、太公望は踵を返す。歩きだそうとすると、近くに控えていた妲己から声をかけられた。
「……本当に行かせちゃったのね……。知らないわよ? どうなっても――――」
「心配か?」
問う太公望に妲己はフン、と、鼻を鳴らす。
「まさか! あの人たちがどうなろうと私の知った事ではないわ。ただ……素戔鳴さんが激怒しているのでしょう? そんな所にわざわざ行くなんて、正気の沙汰じゃないって、言っているの」
「心配せずとも女狐。お前の手を煩わせるような事態にはならないさ」
妲己の揶揄を、太公望は軽く受け流した。リュウ・ハヤブサは、あれでかなり優秀な戦士であるし、もしもあの破壊神と化した遠呂智を倒そうと言うのなら、『素戔鳴』と言う壁も、いつか絶対に越えていかねばならないものだと太公望は確信していた。あの素戔鳴に、人の子の力を認めさせなければ、おそらく、先に進む事は出来ないだろう。
「それにしてもお主……あの3人に、何を耳打ちしておったのじゃ?」
伏犠の問いかけに、太公望は事もなげに答える。
「あの村人たちの『避難場所』だ」
「避難場所……」
「そうだ。あの戦場で一番難しいのが『村人を守る事』だ……。これを失敗したら、おそらく総てが瓦解する――――」
「なるほど……確かに――――」
太公望の言葉に、女媧が顎に手を当てて頷く。ハヤブサやケイタの話から察するに、守るべき目標となっている『シュバルツ』と言う人物は、何が何でも村人たちを守ろうとするだろう。村人たちを守りきらない限り、シュバルツもまた、無事ではいない可能性が高くなる。救おうとするならば、そういう意味では最も厄介な人物であると、言えた。
「で、坊やは何処を、避難場所に勧めたのだ?」
「あの村から一番近い場所に在る、劉備の領内に在る城だ」
伏犠の問いかけに答えながら、太公望の眼差しが少し遠い物になる。
「劉備……なるほど、確かに義に厚い劉備であるならば、避難民を受け入れる事を躊躇わぬだろうな」
「……………」
女媧の言葉には応えず、太公望はずっと空の果てを眺めていた。
(そう……確かに、劉備ならば、避難民の受け入れを躊躇わない……)
だが問題は、避難民たちと共に、彼らを守ろうとして道行きを共にするであろう『妖魔』の存在――――これが、太公望の思考に微妙な暗雲を投げかけていた。今まで『妖魔』と戦っていた人間たちが、いきなり人間を守ろうとする妖魔の存在を受け入れられるかどうか。これは、かなり微妙な問題だと太公望は感じていた。
(この戦いにおける神がふる『サイコロの目』が、良い方に出ればいいのだがな……)
戦いに向かったハヤブサたちに、自分の力を及ばせる事はもう出来ない。後は、人間たちの力量に頼るしかないのだ。だからこそ人の子は、自分達のその手で、運命を切り開く権利を持っているとも言えるのだろう。
どうか今回の戦でも、運命を、未来を――――自らの手で勝ち取って欲しい。
太公望はいつしか、祈るような想いで、暗雲たなびく空の果てを眺め続けて居るのだった。
第4章

次にケイタが目を開けた時、彼は既に、懐かしい風景の中に居た。
桃の木や田畑、そして村の家屋が、何もかも美しいままに、その姿をとどめている。周りを見渡すと、近所の人や友達と言った、懐かしい人々の姿もあった。
「これは……私たち、時を越えたの?」
「これが、あの村……? 綺麗……」
ケイタの後ろで甲斐姫と孫尚香が、茫然と呟いている。その近くには当然、ハヤブサの姿もあった。
(これは……本当に、時を遡れたの? ならば――――)
「ハヤブサさん! こっちだよ!」
見知ったかつての風景の中、ケイタはハヤブサの名を呼んで走りだす。この時間帯、シュバルツはいつも果樹園を広げるための開拓作業を手伝っているはずだった。だから、一刻も早くハヤブサにシュバルツを会わせてあげたくて、そして自分も会いたくて――――ケイタは走りだす。ハヤブサたちもそれに続いた。
そして――――
「じゃあ、私はこれを向こうへ運んでくるよ」
そう言って大きな丸太を抱え上げる、シュバルツの姿を見つけたのだった。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは思わず、声を上げる。その声に「え………?」と、反応したシュバルツが、振り返った。
「え……! え……? ハヤブ、サ……?」
ケイタと共にこちらに歩いてくるハヤブサの姿にシュバルツは動揺を隠せず――――持ちあげた丸太を取り落としてしまう。派手な音を立てて丸太は転がり、周りから注目を浴びてしまうのだが、彼にはその事を慮る余裕さえなかった。それほどまでに、シュバルツにとってハヤブサの出現は、唐突すぎる出来事だった。
「な……何で――――」
「シュバルツ………」
対するハヤブサは、たまらずシュバルツの傍に駆け寄る。一刻も早く、彼に触れたくて。愛おしいヒトが本当にそこに居るのか、確かめたくて。
だから、シュバルツに避ける暇すら与えずに、その身体を抱きしめた。
「お……! おい……!」
腕の中で愛おしいヒトが、戸惑ったように小さく声を上げるが、それすら抱きしめてしまいたくて――――ハヤブサは、彼を抱きしめる腕に、さらに力を込めた。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
ああ
生きている。
動いている。
触れられる――――
幻じゃない。砕け散ったりもしない。
ここに居る。
ここに、居るんだ。
「シュバルツ……ッ!」
堪えようとしても堪え切れぬ想いが、ハヤブサの中から次々と溢れ出てきてしまう。それは涙と言う形になって、ハヤブサの頬を濡らした。泣いている場合ではない、と、懸命に思うのだが、自分でも、自分の涙が、もう止められなくなってしまって――――
「あ………あ………!」
気がつけば、ハヤブサはシュバルツを抱きしめながら号泣に近い形で泣き叫んでしまっていた。
「ハヤブサ………」
シュバルツはそんなハヤブサに戸惑いを覚えながらも、その背中にそっと片手を回してくる。そのまま彼は、ハヤブサが泣きやむのを待つかのように、優しく彼を抱き返し続けるのだった。
ケイタと甲斐姫と孫尚香は、そんな二人の邪魔にならないように、少し離れた所からその光景を見守っていた。
「良かった……」
そうケイタが小さく呟く声に、甲斐姫もうんうんと頷いた。
「そう……そうよ……! こういうのが見たかったのよね……!」
「甲斐……もしかして、泣いてる?」
「だ……だって、仕方ないじゃない。私こういうのホント弱くて――――」
孫尚香の問いかけに、甲斐姫は慌てて涙を拭いながら答える。ハヤブサがどれだけ懸命にシュバルツを探していたか。その姿を知っているだけに、今のハヤブサが涙に、どうしても胸を打たれてしまう物があるのだ。
「それに……尚香だって泣いているじゃない!」
甲斐姫の指摘に、孫尚香も苦笑する。
「えへへ、ばれてた?」
「分かるわよ! それだけ瞳に涙を浮かべていたら―――」
「でも……甲斐……」
「何? 尚香」
「やっぱり流すなら……こういう涙の方がいいわね……」
「うん……」
孫尚香の言葉に、甲斐姫も強く同意した。
「ケイタ?」
不意に名を呼びかけられてケイタが振り向くと、そこにはケイタの父が立っていた。
「あ、おとう!」
ケイタが嬉しそうに声を上げる。それに対して父は、きょとん、とした表情をその面に浮かべていた。
「お前、どうしてここに居るだか? 今日は、あっちの果樹園の手伝いをしているのではないだか?」
「あ……うん。そうなんだけど――――」
父の問いかけに、ケイタはしどろもどろになりながら答える。この状況、どう説明すればいいのか――――巧い言葉が見つからなくて困ってしまった。
「それと、この方たちはどうなすったのだ? シュバルツさんの知り合いか?」
父と一緒に畑の開墾作業をしていた別の人間からも声をかけられる。
「ええと、知り合いと言うか――――」
「どう説明すればいいのかしら。難しいな……」
質問に咄嗟に応える事が出来ずに甲斐姫と孫尚香が四苦八苦していると、また別の村人から声が上がった。
「シュバルツさんの知り合い、と言う事は……この方たちも『神様』じゃねぇのか?」
「…………!」
そのとんでもない言葉に、シュバルツに抱きついて泣いていたハヤブサも含めて、3人ともがズルッ、と、こけてしまった。
「おお、きっとそうじゃな。そうに違いない」
「めでたい! 神様が増えた!」
そう言いながら盛り上がりそうになる村人たちを、甲斐姫と孫尚香が慌ててなだめた。
「違う違う! 違いますってば!」
「えっ? 違うだか?」
「ごめんなさい、おじさん……。私たちは『神様』とかじゃなくて――――ただの人間なんです」
申し訳なさそうにそう言う孫尚香に向かって、村人たちはきょとん、としたまなざしを向ける。
「人間? 神様じゃなくて?」
「そんなにめんこいのに――――女神様じゃないだか?」
「ちょっとどうする尚香!! 私、女神様だって~!!」
「お、落ちつこう? 甲斐……。そこは冷静に否定する所でしょう?」
「やだもう、ちょっと! 困ったな~……! そんなに褒められても、何にも渡せないわよ!?」
「駄目だ……。言われ慣れない言葉に、完全に舞いあがっているわ……」
その向こうで泣いていたはずのハヤブサが――――今度は、笑いをこらえるのに必死になっていた。
「お、おい、ハヤブサ?」
「ク…………」
「大丈夫か? 泣くか笑うか、はっきりした方が――――」
手から伝わるハヤブサの背の小刻みな震えを、少し心配したシュバルツが口を開く。
「シュバルツ……」
「何だ?」
「ここの人たちは――――ずっと、こんな調子なのか……?」
「えっ?」
「ケイタから聞いた……。お前、『神様』扱いされているんだって?」
「―――――!」
ハヤブサの言葉に、ぐっと言葉を詰まらせたような、困惑した表情を浮かべるシュバルツ。そんな彼を見た瞬間、ハヤブサの中で何かの箍が外れてしまい――――ついに彼は、声を立てて笑い出してしまった。
「わ、笑う事無いだろう!? 私だって困っているんだ!!」
顔を真っ赤にして、困ったように叫ぶシュバルツ。
(ああ、やっぱり可愛らしいな、お前は……)
そんなシュバルツの様を見て、ハヤブサは思わず和んでしまう。
ああそうだ。
俺はずっと――――
お前と、こんな風に話がしたかったんだ。
「困っているのなら――――もっとはっきり『神』である事を否定して、『自分は人間だ』とでも言えばいいのに」
「そ、そんな……! 駄目だろう……?」
「何故?」
「それを言ってしまったら、私は偽りを言う事になってしまう。私はここの人たちに――――『嘘』は言えない!」
シュバルツのその言葉を聞いたハヤブサが、フ、と、優しく微笑む。
「そうか……。相変わらず、真面目だな……」
「悪かったな。融通が利かなくて――――」
そう言いながらシュバルツが、少しむくれたようにそっぽを向くから、ハヤブサは苦笑してしまう。
「責めているんじゃない。褒めているんだよ」
「どうだか……!」
そう言うシュバルツが、じと目でこちらを睨んでいる。
律儀で真面目で――――表情豊かなシュバルツ。
ああもう本当に可愛らしい。
今すぐにでも、押し倒してしまいたい――――
(いや待て! 今はそれどころじゃないだろう!?)
ハヤブサは、己の脳内がピンク色に染まりそうになるのを、必死に押しとどめる。
まだだ。
シュバルツに触れるのは、まだ早い。
これからこの村とシュバルツには、大きな試練が待っている。
それを乗り越えてからでないと――――彼を抱きしめてはいけないと、ハヤブサは感じていた。
「あの~……お取り込み中、すみませんが……」
それまで二人の会話を茫然と傍観していた村人の1人が、おずおずと声をかけてきた。
「ええと、シュバルツさん……? この方たちは一体……? 御知り合いだか?」
「あ、ああ……。この男はリュウ・ハヤブサと言って――――私の知り合いだ。あの二人は………」
「あ、私たちの事?」
シュバルツの言葉を聞きつけた孫尚香と甲斐姫が、たたたっと、小走りにシュバルツ達の傍に走り寄って来る。
「北条氏康が家臣、成田氏長が娘、甲斐!」
「同じく、孫文台が娘、尚香!」
「私たち、遠呂智討伐軍に加わっていて――――そこのハヤブサさんとも一緒に戦っているの!」
「遠呂智……!」
『遠呂智』と言う単語に、シュバルツの顔色が若干変わる。だが、村人たちはきょとん、としたままだった。
「『遠呂智』って、何だべか?」
「え……ええと、どう説明すればいいのかな……」
「大きな『妖魔』の親玉、と、言えばいいのかしら。遠呂智は人間を滅ぼそうとしていて――――」
「……ちゅう事は、あんたたちは妖魔を退治しに来たのか?」
孫尚香の言葉を聞いた、村人たちの顔色が変わる。
「お願いしますだ! ここに居る妖魔たちは――――どうか、見逃してやって下せぇ!」
「この妖魔たちは、人間を襲う事はしねぇ! 農作業も手伝ってくれる―――いい妖魔たちなんだ!!」
そう言いながら、土下座しそうな勢いで、村人たちは懇願してくる。
「だ、大丈夫よ!! ちゃんと、分かっているから――――」____
村人たちの言葉に、甲斐姫は慌てて手を振ってその意志が無い事を伝える。
「妖魔と一口に言っても、いろいろいることぐらいもう分かっているもの。私たちが倒したいのは『遠呂智』だけよ」
優しくそう言う孫尚香の言葉に、村人たちはホッと胸を撫で下ろし、少し遠くで作業をしていた妖魔たちが、その場で頭を下げていた。
(本当に……人間と妖魔たちが、一緒に作業をしているんだな……)
そこに在るのは、とても平和な光景その物だとハヤブサは思う。どうしてこれが、許されざるものになってしまうのだろう。
「……と、言う事は、あんたたちは『神様』じゃなくて、『人間』……?」
「そうだ」
「……と、言う事はもしかして………」
「何だ?」
問うハヤブサに、村人は恐る恐る、と言った按配で訊ねてくる。
「あんた方はもしかして………『神様』を、迎えに来たのではないだか?」
「―――――!」
あながちその指摘が間違ってはいないだけに、ハヤブサは返す言葉を失ってしまう。そんなハヤブサの態度に、村人たちは「やっぱり……」と、その肩を落としていた。
「思えば今年の『神様』は、わしらには過ぎた神様じゃった……。いつまでもお引き止めしては、礼に反してしまうかもしれんのう……」
「いやだから、私は『神』とか言う物じゃなくて――――」
シュバルツは懸命に腕を振ってそう言うのだが、村人たちの方がまるで聞いていない。皆で肩を落として――――どんよりと、その表情を曇らせ続けていた。
「そうじゃ……。『神様』には、神様の行くべき場所、為さねばならぬ事がある……。わしらの望みだけで――――いつまでもここに縛り続けて良い物ではない」
「もう少し……ここに居て欲しかったがのう……」
(あ……! もしかして……!)
皆の話を黙って聞いていたケイタだが、ここである考えに行きあたった。
もしかして、
今ここでシュバルツをハヤブサたちと共に村から送り出す事が出来たなら
彼だけでも、確実に助けられるのではないだろうか――――?
だからケイタは、ハヤブサの傍に駆け寄って叫んだ。
「ねぇ、ハヤブサさん! 今の内にシュバルツさんと一緒に村から出て!」
「―――!?」
このケイタの突拍子も無い言葉に、ハヤブサをはじめとしたその場に居た大人たちは全員息を飲む。だがケイタは構わず続けた。それほどまでに、ケイタの『シュバルツを助けたい』と願う気持ちは強かった。
「だってそうでしょう!? 本当ならば、あの日の祭りが終わればシュバルツさんの『神様』としての役割は終わっているのに! それを、僕たちがここまで無理を言って引き留めたんだから――――!」
「何を言っているだ! ケイタ!」
「そうだぞ!? それに明日は、収穫を祝う『感謝の祭り』だ! それまでは『神様』には村に居てもらおうって、皆で話し合って決めたべ!」
「明日!? 明日が感謝の祭りなの!?」
驚いた様に声を上げるケイタに、大人たちの方も驚いた。
「そうだぞ、ケイタ。何をそんなに驚いているんだ?」
「お前、大丈夫か?」
「明日だなんて……! そんな……!」
ケイタの記憶によると、村が襲われたのは、祭りの前の日の夜。つまり、今晩――――。
あまりにも時間が無さ過ぎる事実に、ケイタは茫然とするしかなかった。
「ケイタ? どうした?」
流石にケイタの様子がおかしいと感じたのか、シュバルツがケイタの顔を覗き込んでくる。
「シュバルツさん……!」
ケイタはどうしたらいいか分からなくなって、シュバルツの顔を、ただ縋るように見つめ返すことしか出来なかった。
この人を、『死』と言う運命から逃れさせたい。
今、村から出て行ってくれたら、確実にそれが可能なのに――――
「ケイタ君、それは駄目よ」
不意に、甲斐姫の声が響いて、ケイタは弾かれた様に振り向く。すると、真剣な眼差しをした甲斐姫と、視線が合った。
「その選択肢は、残念だけど私は選べない。絶対にダメ」
「そ、そんな……! でも――――!」
「そうね。その選択肢は、私も『選びたくない』わ」
ケイタが何か言おうとするのを、遮る様に孫尚香が口を開く。
「そうだな。俺も――――」
ハヤブサも、それに同意するように口を開いた。
「選びたくない。恐らく、シュバルツもそれを望まないから――――」
「? 皆、さっきから何の話をしているんだ?」
1人、話が見えないとどうしても感じてしまうシュバルツが、きょとん、と4人の顔を見回している。ハヤブサが、そんな彼に声をかけた。
「シュバルツ……」
「何だ? ハヤブサ」
「少しいいか? 大事な話があるんだ」
「…………!」
酷く真剣な眼差しでこちらを見つめてくるハヤブサに、シュバルツも、これを無下にしてはいけないと感じた。
「分かった」
シュバルツが頷いたのを確認してから、ハヤブサは村人たちにも声をかけた。
「済まないが、シュバルツをしばらく借りるぞ。大事な話があるから……」
「あ、ああ……。わしらは別に構わないが、もしかして、もう村から出ていくだか?」
村人の言葉に、ハヤブサは首を振る。
「いや……すぐに出て行く気はない。ただ、少し大事な話をしたいから、席をはずしてくれると助かる」
「そう言う事なら――――」
村人たちはハヤブサの言葉に頷くと、「休憩に行くべ」と互いに声を掛け合ってそこから歩きだした。
「あ……僕は……」
ケイタは、向こうに歩き出そうとしている父について行くか、それともここで残るかで迷う。父もこちらを振り返っていたから、父の方に足が向きかけたが、ハヤブサに「ケイタもここに居てくれ」と、声をかけられたので、ケイタもここに残る事になった。
「あまりシュバルツさんたちに迷惑をかけるなよ?」
父はそう言い置いて、ケイタと別れた。
「……………」
周りに村人たちが居なくなったのを確認してから、ハヤブサはシュバルツの方に向き直り、口を開く。
「シュバルツは俺と別れる前――――左慈と『巫女かぐや』の話を聞いた事を覚えているか?」
「確か、『時間を巻き戻せる能力』を持った巫女の話か? ああ、憶えている。だが、それがどうかしたのか?」
「俺たちは、その能力を使ってここに来たんだ」
「……え……?」
シュバルツは、ハヤブサの言っている言葉の『意味』を咄嗟に計りかねて、きょとん、としてしまう。ハヤブサは、そんなシュバルツに言い聞かせるように、もう一度、言葉を重ねた。
「つまり俺たちは『知っている』んだ……。これからこの村で何が起こり、皆がどういう運命をたどるのかを――――」
「……と、言うと?」
「いいか、落ちついて――――よく聞いてくれシュバルツ」
ハヤブサは、自身にも言い聞かせるように言葉を紡ぐ。ここでまずシュバルツを説得できなければ、皆の運命を覆すことはかなり難しくなってしまうだろう。だから慎重に言葉を選びながら――――シュバルツに少しでも伝わるよう、祈りながら話を進めた。
「今晩から明日の朝にかけて――――この村は『妖魔』と、それ以外の者たちに襲われる」
「何っ!?」
全くの寝耳に水な情報に、シュバルツは驚きを隠しきれない。
「馬鹿な……! ここに来ている妖魔たちは――――!」
「善良な妖魔たちなんだよな? 見れば分かる」
村人たちと一緒に、農作業を手伝っていた妖魔たち。子供たちも、人間と妖魔混じり合って、皆で一緒に遊んでいた。まさに、平和そのものと言った光景だった。
だからこそ、『妖魔に襲われる』と聞いて、俄かにそれを信じられないシュバルツの気持ちも分かる。
「襲って来たのは、別の所に住む妖魔たちなんだよ。シュバルツさん」
ハヤブサの言葉を補足するように、ケイタが口を開いた。
「『この村は自分達に物にする』『人間たちは皆殺しだ』て、叫びながら、妖魔たちが襲って来て―――」
そしてケイタは話し始めた。あの夜自分が経験した、恐怖の出来事を――――。
戦う術を知らないが故に、一方的に虐殺される村人たち。
それを守ろうと、ここに通って来ていた妖魔たちが戦いに雪崩れ込んできたが故に、誰が敵で誰が味方か分からなくなる極限まで混乱し切った戦場。
シュバルツは、そんな地獄絵図が繰り広げられていくのを、ただ茫然と聞くしか出来なかった。
「それでもシュバルツさんは、何人かの村人たちを助けてくれたんだ。僕も、助けてもらった……。だけど……」
「だけど……?」
「『妖魔』ともまた違う、仁王様みたいな人が来て――――結局皆、殺されちゃったんだ……」
「な―――――!」
あまりの結末に、絶句するシュバルツ。ケイタは、哀しそうに瞳を伏せた。
「僕が……僕だけが、あの日の夜を生き残る事が出来たんだ……。シュバルツさん。貴方が……最期まで僕を、守ってくれたから――――」
「…………!」
「ねえ、シュバルツさん……」
ここまで話し終えたケイタの瞳から、大粒の涙がこぼれ始める。いろいろと、溢れる想いを堪え切れなくなってしまったのだろう。
「お願い……! 今の内に、逃げて……!」
「な――――!」
「シュバルツさんは何も悪くない……! 皆の無理を聞いて、今までこの村に留まってくれていただけなのに、あんな風に死んで欲しくない……!」
「死ぬ!? 私が!?」
あまりにも意外な言葉を聞いたから、シュバルツは思わず聞き返してしまう。それに対して、ハヤブサが頷いた。
「ああ、そうだ……。お前は死んでしまったんだ……。俺の目の前で……」
「……冗談だろう……?」
『キョウジの死』が、『自分の死』に直結すると言う制約が外れてしまった今、自分は完全に不死の人外の筈だ。それなのに『死』を迎えると言う事実に、シュバルツはただただ驚愕するしかない。
「『嘘』や『冗談』で、こんな事が言えると思うのか?」
対してハヤブサの眼差しは、真剣そのものだった。
「それともケイタが――――お前に嘘をついているとでも、思うのか?」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは首を振るしかなかった。
そうだ。
ケイタはまっすぐで、正直な子だ。
その彼が、自分にわざわざ嘘をついているとは、到底思えなかった。
「しかし、何故……」
まだどうしても腑に落ちなくて、シュバルツは思わず疑問を口にしてしまう。
「何故この村が、そんな風に襲われるような事態になった……? ここの村人が、妖魔や仁王から襲われるような咎を犯しているとは、思えないのだが……」
「妖魔たちの方の動機は知らん。だが、もう一つの『仁王』――――『素戔鳴』の動機は分かっている」
「……と、言うと……?」
問うシュバルツに、ハヤブサは少し苦い顔をして答える。
「ここの村人たちは、『素戔鳴』と言う神の怒りを買ったんだ」
「な――――!」
息を飲むシュバルツに、孫尚香が補足するように説明を加える。
「『素戔鳴』と言う人はね、シュバルツさん……。『妖魔』を、徹底的に排除しなければいけない、って、考えている人なの」
「――――!」
その一言で、シュバルツはある程度悟ってしまう。ここの村人たちのどういう行動が、素戔鳴と言う神の怒りを買ってしまったのかを。
「もう一つ言うと、シュバルツ……。ここに生えている桃の木の中に、一本だけ、仙桃の木が在る筈だが……分かるか?」
「仙桃……。―――! まさか、あれが……!?」
「分かるの!?」
甲斐姫の言葉にシュバルツは頷く。
「ああ……。一本だけ、妙に生りがよくて、その成分に『薬効』の効果が含まれている桃が在ったから――――」
「『薬効』って……?」
きょとん、とする甲斐姫に、シュバルツは説明を続ける。
「かなり強力な『治癒』の効果を含んだ薬の成分が、その桃には含まれていたんだ。あれを食べれば、普通の人間でも、多少の怪我ならあっという間に治してしまう事が出来るだろう」
(ほう、怪我を……なるほど、な……)
ハヤブサはその情報を、腹の中で反芻する。
「その仙桃の木が、素戔鳴の持ち物だとして……その実を妖魔に食べさせたり、持ち帰らせたり、『売り物』として人々の間に流通させたのだとしたら――――」
「あ…………!」
シュバルツはようやく合点がいく。
妖魔を忌み嫌う神の物を、勝手に妖魔に触らせる――――これだけで、素戔鳴と言う『神』を、激怒させるには充分すぎると想像できた。
しかも、この村の『人間』と『妖魔』の間に交流を産ますきっかけを作ってしまったのは、他ならぬ自分なのだとシュバルツは悟ってしまう。だから、茫然と呟いた。
「何てことだ……! それでは、この村を滅ぼすきっかけを作ってしまったのは、ほぼ、『私』と言う事になるのではないか……?」
「シュバルツ……」
「私が……あの時、妖魔の子供を、助けてしまったから――――」
「違うよ!! シュバルツさん!!」
ケイタは叫びながら、シュバルツにギュッ、と抱きついた。
「シュバルツさんは何も悪くない……! だってシュバルツさんは、困っている人に、手を差し伸べただけでしょう!?」
「ケイタ……」
「それの何が悪いの!? 何が間違っているの!? 『妖魔』だって言うだけで、『人間じゃない』って言うだけで――――『その存在は間違っている』って、どうして言ってしまえるの!?」
「…………!」
ケイタの言葉に胸が詰まって、シュバルツは何も言えなくなってしまう。
「そんなの……おかしいよ……! 絶対に、おかしいよ……!」
震えるケイタの背中を、黙って優しく撫でるしか出来ないシュバルツ。そんな二人の様子を見ていた甲斐姫が、口を開いた。
「そうね……私も、貴方たち二人は、間違っていないと思う」
「甲斐……」
声をかけてきた親友に、甲斐姫は少し潤んだ瞳を向けた。
「こんな人たちを裁こうとする――――神様の『価値観』が、おかしいのよ」
親友の言葉に、孫尚香も同意するように頷いた。
「そうだな……『神』の価値観が、いつも100%正しいとは、限らない――――」
それまで黙っていたハヤブサも、口を開く。
「『神の裁き』とは、時に無慈悲で、理不尽さを伴うものだ。だからこそ、『神』であるとも言えるが、な……」
『神』と名乗る存在と、幾重にも戦いを重ねてきた『龍の忍者』であるからこそ――――辿り着いたハヤブサの『神』に対する独自の視点であった。『神』とは、絶対的で、時に独善的とも言える強い価値観を持っているものだ。だからこそ、それをひっくり返そうと言うのなら、こちらもそれ相応の強い覚悟を以って望まなければならない、と、思う。
「だからシュバルツさん……! 今の内に逃げてくれたら―――!」
ケイタのその言葉に、しかしシュバルツは首を振る。
「そんな事は出来ない。ケイタ……」
「で、でも――――」
「神の怒りを買う一因を私も作ってしまっている以上……私だけ逃げる訳にはいかんだろう。『責任』は取らないと――――」
「シュバルツさん……!」
案ずるように見つめるケイタに微笑みかけてから、シュバルツは立ち上がった。
「ハヤブサ……」
「何だ? シュバルツ」
「『素戔鳴』と言う神の怒りを解く事は……もう本当に、不可能なのだろうか?」
「――――馬鹿な事は考えるなよ……! シュバルツ……!」
ハヤブサは思わず、シュバルツを睨みつけてしまう。
「素戔鳴の怒りは、もうこの村全体に及んでしまっている。老人から子供まで、この村の住人総てを、殺しつくさずには居られない程に――――」
総てが焼き払われ、皆殺しにされてしまっていた村。あの光景が、何よりの証拠だ。素戔鳴の怒りの凄まじさが、嫌と言うほど伝わってくる。
「…………!」
「お前一人が犠牲になって村人たちの命乞いをした所で――――素戔鳴は、決して聞きいれはしないだろうよ。お前を殺して……村人たちも同じように殺すだけだ」
「ハヤブサ……!」
冷たさと怒りを含んだハヤブサの言葉と眼差しに、少し怯んでしまうシュバルツ。ハヤブサはそんなシュバルツをしばらく無言で見つめていたが、やがてその眼差しに、強い憂いの色を帯びさせた。
「シュバルツ……」
そしてそのままハヤブサは、愛おしいヒトの体を強く抱きしめる。強く、強く――――
「あ……? ハヤブサ……?」
ハヤブサのその唐突な行動に戸惑いながらも、それを拒否せずに、ハヤブサのするがままに任せているシュバルツ。
ああ――――
愛おしさがこみ上げる。
なのに
なのに、どうして このヒトは
『生きる』と言う選択肢を
すぐには選んでくれないのだろう。
俺は、願っているのに。
お前と共に生きる『明日』を
強く願っているのに――――
「シュバルツ……」
想いを込めて、耳元でその名を囁く。
「……ッ! ちょ……ッ! ハヤブ、サ……!」
腕の中で愛おしいヒトが、ビクッ! と、反応をした。
相変わらず感度がよくて、可愛らしい反応をするシュバルツ。思わずこのまま、本当に押し倒してしまいそうになる。
だけどハヤブサは、それを懸命に堪えた。
今はそれどころではないし、何よりも確認しておかなければならない事が一つ、在ったからだ。
「シュバルツ……一つ、聞いていいか?」
「な、何だ?」
二人だけの間で確認したい事がハヤブサにはあるのだと悟ったシュバルツが、戸惑いながらも彼に応える。
「お前……今『傷を治せない』なんて事は、ないよな……?」
「……ああ……治せるぞ? 全く問題なく……。だが、それがどうかしたのか?」
「本当か?」
ハヤブサの方から珍しく念を押されたから、シュバルツの方も、ハヤブサが一番納得するであろう答えを、提示する事にした。
「本当だ……。だってほら……斬り落とした左手が、ちゃんと生えているだろう?」
そう言いながら少し申し訳なさそうに笑って、自分の左手をハヤブサにひらひらと振って見せるシュバルツ。それを見た刹那、ハヤブサの中でシュバルツと別れた瞬間がフラッシュバックの様に甦ってきてしまう。
「お、お前なぁ……! 頼むから二度とああいう事はするなよ!? 俺はあれほど『手を離すな』と、お前に言ったのに――――!」
「だから、手は離さなかっただろう? 腕は斬り落としたけれども」
「そう言うのをやめろと言っているんだ!! そんな風にお前に守られても! 俺はちっとも嬉しくない!!」
「仕方が無いじゃないか!! あの時はああしなければ、皆共倒れになるしかなかった訳だし―――」
「それでも! おまえと別れた後、俺がどれだけ落ち込んだか――――!」
そのままぎゃあぎゃあと、口論を始めてしまう忍者二人。それを、孫尚香と甲斐姫とケイタは、顔をひきつらせながら眺めていた。
「な、なんかこう……同じような声の口論って、意外に迫力あるわよね……」
「そ、そうね……甲斐……。何か、止めるに止められないわね……」
「で、でもお姉さん……そろそろ二人を止めてくれた方が……。もう、あんまり時間も無い様な気が……」
「で、でも……どうやって止める……?」
甲斐姫の問いかけに誰も答えが返せないまま、しばらく忍者二人の不毛な口論を眺める一時が続くのだった。
「とにかく……一つ忠告しておく。シュバルツ……お前はこの先の戦いで、傷が治せなくなるんだ」
シュバルツと口論しながらも、ハヤブサは何とか己の伝えたい言葉にたどり着く事が出来た。これをきちんと伝えておかなければ、本当に話にならない。それを聞いたシュバルツが、驚きで目を見開く。
「……! それは本当なのか?」
「本当だ……。冗談で、俺がこんな事を言うと、思うのか?」
忘れたくても忘れる事が出来ない。
再会した時に既に傷だらけだったシュバルツは、俺の腕の中で「傷が治せない」と言った。そしてそのまま砕け散ってしまった。跡かたも無く――――
その時の感触が、まだ自分の両方の腕に生々しく残っている。
嫌だ。
あんな風に、お前を失ってしまうのは――――
「俺の読みでは、おそらく『素戔鳴』たち神仙は、DG細胞を消滅させる力を持っているのだろう。素戔鳴は、お前の『正体』を看破していたようだし……」
「…………!」
素戔鳴はシュバルツの事を『不自然でいびつで、邪悪なモノで出来ている』と評した。
冗談ではない。
そんな言葉を、シュバルツに聞かせてたまるか――――!
「だから忠告しておく……。この先神仙界の者たちと敵として遭遇しても、お前は絶対に戦うな。そこで傷を負ってしまえば、お前は死ぬ事になる」
「あ………!」
自分の言葉に茫然とするシュバルツを、ハヤブサは歯噛みしながら見つめる。
(キョウジが居れば……お前がそんな傷を負おうとも、おそらく治す事が出来るのだろうが………)
シュバルツの元になっているのは『キョウジの強い意志』だ。キョウジがシュバルツの存在を望む限り、シュバルツはそこに『シュバルツ』として在り続ける事が出来るのだろう。
だが――――キョウジが死んでしまっている今、シュバルツの根幹を支える物が、とても弱くなっている事に気づいてしまう。DG細胞を滅する存在と当たってしまったら、今のシュバルツにはそれに抗う術が無いのだ。
皮肉なものだ。
こんな形でシュバルツとキョウジの強い結びつきを、痛感させられる事になるなんて。
救わなければならない。
あの、首を刎ねられたキョウジを。このままでは死に向かうしかないシュバルツを。
おそらく、シュバルツの死の運命を覆さなければ、あの瞬間のキョウジの死の運命も覆す事は出来ない。これは、確信だ。
この二人が居ない未来なんて――――俺は、絶対にごめんだ。
「絶対に……自分の『死』を、望むなよ。シュバルツ……」
ハヤブサはシュバルツに、強くそう要求する。
この戦いはある意味、永遠に死ぬ事が出来ずに彷徨う可能性があるシュバルツにとっては、『死』を迎える絶好のチャンスと言えるかもしれない。自身が死ぬ時に「これでいい……。これで、良いんだ」と、何度も呟いていたシュバルツ。だからもしかしたら、あの瞬間のシュバルツは、『生』が途切れる無念よりも、『呪いに近い身体からの解放』を、喜ぶ気持ちの方が強かったのかもしれないのだ。
でも、嫌だ。
絶対に、嫌だ。
例えシュバルツが、自身の死を強く望んでいたのだとしても。
己の宿命から解放される事を望んでいたのだとしても――――。
生きて。
生きてくれ、シュバルツ。
せめて、俺の目が黒いうちは――――
「俺は……お前の死を否定するために、ここに来たんだ!」
なんて、わがままな願い。シュバルツが、己の宿命から逃れるチャンスを、自分のエゴイスティックな想いだけで奪ってしまっているのかもしれないのに。
だけど、絶対に譲れない想い。
叶えたい、願い。
想いと願いを乗せて――――ハヤブサは、真っ直ぐにシュバルツを見つめる。
「ハヤブサ……」
シュバルツは、しばらくそんなハヤブサの視線を受け止め続けていたが、やがて、小さく頷いた。
「分かった……。気をつけるよ」
シュバルツが頷いたのを受けて、ハヤブサも自身を納得させるように頷いた。
「お話、終わった?」
ケイタがシュバルツのロングコートの裾を軽く引っ張りながら、声をかけてくる。
ああ、と、頷く忍者二人に、甲斐姫と孫尚香も近づいて行った。
「ならば急ぎましょう、二人とも……。もうあまり、時間が残されていないわ」
「早く村人たちを避難させないと――――」
「そうだな」
そう言いながら頷くハヤブサに対して、シュバルツは少し難しい顔をした。
「しかし……村人たちを、何処へ避難させればいいんだ?」
「当ては無いのか?」
問うハヤブサに、シュバルツは苦笑しながら肩をすくめる。
「困った事に、私はこの村に来てから、まだ村の外の様子をそんなに見に行けてはいないんだ」
「珍しいな……。お前が周囲の哨戒に行かないなんて」
「仕方が無いだろう。この村に来てすぐ、『神』なんてものに祀り上げられたせいで――――私が少しでも姿を消すと、この村中の人間が大騒ぎしてしまうんだ」
今だって、ほら、と、シュバルツが少しそちらに視線を移すと、少し離れた所で村人が1人、こちらの様子を伺いながら立っているのが見えた。
「毎日一人か二人、ああやって私の『付き人』になる村人が居るんだ。まあ、昔から伝わる『神』を祀る風習の中ではよくある話だし、悪意のある『監視』と言う訳でもないから邪魔ではないのだが……どうにも、動きにくくてな……」
「なるほど……」
シュバルツの話を聞きながら、ハヤブサは苦笑してしまう。彼の様なお人好しを村の中に閉じ込めるには、なかなか有効な手段を村人たちは選んでいるようだ。
「当てが無いのなら……俺から一つ、避難先の提案がある」
「本当か?」
振り向くシュバルツにハヤブサは頷いて見せた。
「ここから西に10里ほど行った所に、劉玄徳の統治下にある城がある。そこなら、おそらく村人たちが助けを求めて逃げ込んでも、その門が閉ざされる事は無いだろう」
「劉玄徳……」
その名を聞いたシュバルツは、少し考えるような仕種をした後、「確かに、そうかもしれないが……」と、呟いた。
「玄徳様を知っているの!?」
孫尚香の言葉にシュバルツは頷く。
「ああ……。直接会った事は無いが、噂はいろいろと伝え聞いている。何でも、民を思いやる仁君なんだとか――――」
「ええそうよ! 玄徳様は、とっても懐の深い方なの!」
シュバルツの言葉に、孫尚香がまるで自分が褒められたかのように誇らしそうに頷くから――――それに少々疑問を持った甲斐姫が、彼女に探りを入れてきた。
「ねぇ、尚香?」
「何? 甲斐」
「貴女、やけに『玄徳様』の事を、熱く語るわねぇ? 貴女、まさか――――」
「あれ? 言ってなかったっけ? 玄徳様は、私の夫よ?」
「ええっ!?」
甲斐姫がやけに大仰に驚くから、孫尚香の方も逆にびっくりしてしまう。
「ど、どうしたの……? 甲斐……」
「うそでしょ……!? 貴女に何となく好きな人がいるっていうのはうすうす気がついていたんだけど、まさか結婚までしていただなんて……!」
「ご、ごめんね? 何か、言いだせなくて……!」
「い……いいの……。でも、そうか~……。尚香と二人で『モテ系女』を目指したかったのに……。は……ははは……」
乾いた笑い声を立てて「どうして私だけ……いつまでも男っ気が無いのかしら……」と、言いながら、気の毒なほど落ち込んで行く甲斐姫。ハヤブサが「大丈夫か?」と、声をかけると「うん、大丈夫……」と頷きはするが、あまり大丈夫でもなさそうだった。
「しかし、玄徳殿の城に避難先を頼るにしても、まだ少し問題があるな……」
ぼそりと呟くシュバルツに、ハヤブサが振り返る。
「問題、とは?」
「おそらく一緒に避難することになるであろう、『妖魔』の存在だ」
「……………!」
シュバルツの言葉に、その場に居た全員がはっと我に帰る。
「『妖魔』が民たちと一緒に居ても……玄徳殿は受け入れてくれるのだろうか?」
「そ、それは……」
甲斐姫とハヤブサは、咄嗟に答えを返す事が出来なくて戸惑ってしまう。だが、孫尚香だけは明確な答えを叫んだ。
「大丈夫よ!! 玄徳様は本当に困っている人たちを、絶対に見捨てたりはしないわ!!」
「尚香……」
「少なくとも、私は――――玄徳様をそう言う人だと信じているから!!」
きっぱりとそう言い切る孫尚香に、シュバルツもその面に笑みを浮かべた。
「そうだな……。愚問だった。済まない……」
「いえ………」
シュバルツの言葉に、孫尚香も少しはにかみながら首を振る。
「避難先について納得できたのなら、急ごう、シュバルツ。襲撃されるのは今夜だ。それまでに、村人たちの避難を始めなければ――――」
「そうだな」
頷いて歩きだそうとするシュバルツのロングコートの裾を、ケイタが引っ張って止めた。
「あ、あの……! ごめんなさい……」
「? どうしてお前が謝るんだ?」
問い返すシュバルツに、ケイタはうつむきがちに答えた。
「だ、だって……あまりにもみんなを説得する時間が無さ過ぎて……。僕がもっとちゃんと考えて、時間を巻き戻してもらえば――――」
「大丈夫よ! ケイタ君!」
案ずる様なケイタの声に、甲斐姫の明るい声が被さる。
「村が襲われる前の時間に帰って来れただけでもラッキーなんだから! とにかく私たちのやれる事を、全力でやりましょ!」
甲斐姫の言葉に、皆が頷く。
「最後の問題は……私たちが避難を呼び掛けて、それに皆が素直に従ってくれるかどうかだな……。皆の危機意識はかなり低い。『襲われる』と聞いて、それを信じてくれるかどうか―――」
「それでも、やらねばならない。皆を説得して、非難させる事が出来なければ――――」
シュバルツの言葉を受けて、ハヤブサが続ける。
「皆、死ぬ事になるんだ」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは一つ、大きく息を吐いた。
「とにかく、やれるだけの事をやろう。皆に避難をするよう話してみる」
シュバルツがそう言いながら歩き出し、皆がその後に続く。付き人となっている村人の傍まで行くと、シュバルツが口を開いた。
「済まないが、長老と村長と、各組の組頭を集めてくれないか? 私から火急の話があるからと」
「わ、分かりました」
シュバルツの伝言を受けた村人が、村の奥へと向かって走り去っていく。
「私たちも急ごう」
シュバルツの言葉を受けて、皆も一斉に歩き出す。
こうして――――村人たちとシュバルツを救うための戦いが、幕を開けたのだった。
「襲われる!? この村が!?」
『火急の話がある』と、シュバルツが告げたにもかかわらず、村人たちは農作業を終えてからのおっとり刀で集会所に集まってきたため、もう既に陽はだいぶ西へと傾きかけていた。そこで、全員がそろうのを待ってから発せられたシュバルツのこの言葉に、村長が素っ頓狂な叫び声を上げる。
「本当ですか!? その話は……!」
確認するように問うてくる村長に、シュバルツは頷いた。
「ああ。残念ながら本当だ。ハヤブサたちは、その事を知らせにわざわざここに来てくれたんだ」
「…………!」
シュバルツの言葉に茫然とする村人たちの前に、ハヤブサは出て行き、軽く頭を下げてから話しだした。
「今夜、この村は襲われる。これは、俺が掴んだ確かな情報だ」
そう言いながらハヤブサは、少し歯噛みしていた。
(しかし……こういうまだるっこしい事をせずとも、シュバルツが『神託が下りた』と言って、『襲撃されるから逃げてくれ』と、叫んだほうが話は早くないか? 幸いにして、あいつは『神』として信じられているのだから――――)
そして当然、ハヤブサはこの案をシュバルツに提案しているのだが、それはものすごい勢いで却下された。
「そんな事……! 言える訳無いだろう! 私は『神』じゃないのに―――!」
これが却下したシュバルツの言い分だった。
それでも今は非常事態なのだから、少し位『神』を詐称しても……と、ハヤブサは思わないでもないが、シュバルツは少しでも、村人たちに『嘘』は付きたくないのだろう。真面目すぎるシュバルツ。でも、そう言う所も『好き』と感じしまうのだから、ハヤブサは苦笑してしまう。これがきっと、世に言う『惚れた弱み』と言う奴なのだろう。
「だから忠告する。今の内に村から脱出して欲しい」
ハヤブサのその言葉に、その場は水を打ったような静寂に包まれる。だがやがて、少しずつだが村人たちから、反応が返ってきた。
「そ、そんな……逃げろと言われても………」
「まだ残っている桃の収穫、どうするべ……」
「田の周りの草刈りも、残ってるし……」
「肥だって、やらなきゃなんねぇべ……」
「そ………!」
そんな事を言っている場合か――――!? と、ハヤブサは大声で叫びたくなってしまう。危機感が無いにも程があり過ぎる。米の世話も桃の収穫も――――死んでしまえば、何もできなくなってしまうと言うのに。
だがハヤブサはそれを懸命に堪えた。
感情に任せて怒鳴りつけて、見捨てるのはひどく簡単だ。だがそれをしてしまったら、結局、誰も救えなくなってしまう。村人たちが自主的に『避難しよう』と決意するまで、根気良く説得を続けるしかないのだと、ハヤブサは感じていた。
しかし、『知らない』と言う事は恐ろしい事だ。
これから何が起こるのかを知っていれば――――村人たちは、なりふり構わずここから逃げ出すのだろうに。
「お、襲われるのは……もう、決まっている事なのじゃろうか……?」
老人がおずおずと聞いてくる。それにハヤブサは、容赦なく頷いた。
「ああ。残念ながら……もう、避けようがない――――」
「そ、そんな………!」
茫然と座り込む老人に変わって、近くに居た青年が声を発した。
「一体誰が、この村を襲うんだ……?」
「んだんだ。この村には米と桃しか無ぇべ。他は何も無いと言うのに――――」
「最初に襲ってくるのは『妖魔』の連中だ」
ハヤブサは、この集会所の末席に座っている妖魔の方に視線をちらりと走らせながら、口を開いた。もちろん、ケイタから話を聞いているハヤブサは、ここに居る妖魔たちがこれから起きる襲撃には無関係である、と言う事は百も承知していた。
だが、襲ってくる者が『妖魔』である以上――――彼らも無関係では済まされないと、ハヤブサは思った。もしかしたら、襲ってくる妖魔たちの方の『動機』を、彼らなら何か知っているのではないかと感じる。この妖魔のこの村を襲う動機は――――ケイタの話だけでは、分からなかった情報の一つだったから。
「何を言っているだ!?」
「妖魔の人たちが、ここの村を襲う訳ねぇべ!」
案の定、妖魔を全く敵視していない村人たちからは、そのような声が上がる。だが、その席に座っていた妖魔は、何か襲われる理由が思い当たるのか、浮かない顔をしていた。
「――――どうした?」
その様子を目ざとく見つけたハヤブサが、妖魔たちに声をかける。
「い、いや……何でも――――」
少し年配の妖魔が慌てて取り繕おうとするが、その傍に控えていたもう一人の妖魔が、何かを堪えられないと言うように声を上げた。
「す、すいません……! 実は――――!」
「おい……! 余計な事を言うんじゃない!」
年配の妖魔が、若い妖魔のその動きを止め立てしようとする。
「本当にどうした? 大丈夫か?」
流石にその様子を看過できないと感じたシュバルツが、少し心配そうに声をかける。それに対して年配の妖魔を首を横に振って『心配しないで欲しい』と、意志を伝えようとしたが――――それを若い妖魔が押しのけて、シュバルツの前に進み出てきた。
「シュバルツさん……! すみません! 話を聞いてください!」
「馬鹿っ!! 余計な事を――――!」
「親父さん!! もう駄目だ!! ここは話を聞いてもらおう!!」
「しかし、それでは余計な迷惑を――――!」
「でも!! 『襲われる』と聞いたら、もう黙ってはいられない!! 連中は、ついにここにも手を伸ばす気なんだ!!」
「何か知っているのか!? この村が襲われる『理由』を――――!」
「…………!」
ハヤブサの叫び声に妖魔二人は言い争いを止め、村人たちも驚いた様に妖魔たちを見つめている。何とも言えない沈黙が支配する中、シュバルツが改めて口を開いた。
「貴方がたの話を聞こう……。よかったら、話してくれないか?」
「…………」
しばしの沈黙の後、年配の妖魔は力が抜けた様に座り込んでしまう。それを受けて、年若い妖魔が口を開いた。
「………実は、うちの村は、少し前から嫌がらせを受け続けているんだ……」
「―――――!?」
予想だにしなかったその言葉に、その場に居た者は皆息を飲む。そんな中、その年若い妖魔の話は続いた。
「うちの村が人間と交流を持つのを、面白く思わない連中が居るんだ。そいつらが、いろいろと口を出すようになって来て――――」
(人間連中と仲良くしようだなんて、馬鹿じゃないのか?)
(人間なんてのは、俺たちからしてみれば家畜みたいなもんだ! そいつらと共存しようだなんてばかげている!)
(人間連中など――――搾取しつくしてから、駆逐すればいいのだ!)
(違う! 人間は心優しく、知恵と勇気も持ち合わせている。その技術とわしらの知識とを交流させて、共存する事も可能だ!)
(人間が、わしらみたいな異形の者と――――本気で共存できるとでも思っているのか!?)
(最終的に忌み嫌われて―――排斥されるのが落ちだ!)
それでもその村の長老は懸命に人間との共存を訴え続けるが――――周りの妖魔たちからは理解されず、次第にその村への周囲の妖魔たちからの嫌がらせもエスカレートして行った。
「最近は、子供たちも村に居るのは危険だから、ここの村に遊びに行かせる親も増えてきていて―――」
「そんな目に遭っているのなら、何故今まで何も言ってくれなかっただか!?」
ここまで妖魔の話を黙って来ていた村人の方が、思わず声を上げる。
「もし、何か話してくれていたら――――!」
「これは、わしら『妖魔』の内での問題だ!!」
それまで黙っていた年配の妖魔が、叫び声を上げた。その語気と言葉に気圧されて、村人たちは黙りこくってしまう。静まり返ったその場をフォローするかのように、若い妖魔が再び口を開いた。
「確かに、妖魔の中の問題と言うのもある。だが――――俺達はそれ以上に、あんたたちに迷惑をかけたくなかった」
「…………!」
息を飲む皆の前で、その若い妖魔の話は続く。
「ここに居る人たちは皆、善良で、戦う事を知らない。それに、人間と交流を持つ事を望んだのは、俺たちの方だ……。その為に周りと起きたトラブルは、こちらの責任だから――――」
「ち………!」
違う――――! と、シュバルツが叫ぶよりも先に、村人たちの方が声を上げていた。
「それは違うべ!!」
「んだ!! 困った時はお互い様だ!! そちらだけで、背負い込むことは無いだ!!」
「もっとも……わしらは、戦う事は出来ないから、あんまり当てにはならないかもしれないが――――」
「あ…………!」
茫然とする妖魔たちを、村人たちが取り囲んでその手を取る。
「でも……困った事が起きているのなら、ちゃんと話して下せぇ!」
「そうだ……! あんたたちには本当に、いっぱい助けてもらっているのだから――――」
「皆で考えることで……何か解決策も、浮かぶかもしれんしのう」
「……………」
ハヤブサとシュバルツは、そんな村人たちと妖魔たちの様子をしばらく黙って見つめていたが、やがて、ハヤブサの方が、シュバルツの肩をポン、と、たたいて口を開いた。
「……なるほど、良い村だな。ここは……」
「ハヤブサ……」
「お前が、命かけて守ろうとしたのも、よく分かるよ」
「…………!」
少し驚いたようにこちらを見るシュバルツに、ハヤブサは軽く微笑みかけてから、妖魔たちを取り囲む輪の方に、歩を進めた。もう少し詳しく、妖魔たちに話を聞くために。そして――――『ある事』を、確かめるためでもあった。
「済まないが、少し話を聞かせてもらってもいいか――――?」
「あ、ああ……。別に、構わないが……」
妖魔たちは、この見慣れぬ黒の忍者に戸惑いながらも頷いた。
「お前たちは……確か、ここの農作業を手伝って、その『報酬』として、農作物を受け取っているのだったな?」
「ああそうだ。俺たちもそれでかなり助かっている」
ハヤブサの言葉に妖魔たちが頷く。それを確認してから、ハヤブサは次の言葉を発した。
「では――――その報酬の中には、『桃』も当然含まれていたな?」
「勿論だ。ここの人間たちは、桃の栽培が本当にうまい」
「もったいない程、持ち帰らせてくれたな」
「だから――――その中でも特に美味い桃を、長老が話し合いの席で他の妖魔たちにも分け与えて――――」
「――――分け与えたのか!?」
ハヤブサの声音に鋭い物が混じっていたから、妖魔たちも、その周りに居た村人たちも、少し驚いてしまう。
「わ、分け与えたぞ……? 人間の素晴らしさを、皆に伝えたかったから――――」
「な、何か問題が、在るだか……?」
「いや………」
ハヤブサはそう返事をしながら、唇を噛みしめていた。
(やはりそうか……! 総てはあの『仙桃』が原因になっている……!)
仙桃の存在に気付いた妖魔たちが、それを我が物にせんと、この村を襲い――――自分の持ち物が妖魔に渡ったが故に、素戔鳴が激怒する。
完全に襲撃される要素がそろいすぎている。
もう、この村が滅びるのは避けられない――――。
何故『仙桃』みたいなモノが、この村に紛れ込んでしまったのか。これさえ無ければ、この村も、この妖魔と人との交流の結末も、もっと違った物になったかもしれないのに。
「ハヤブサ? どうかしたのか?」
シュバルツに声を掛けられて、ハヤブサははっと、我に帰る。
「ああ……何でもない。ただ、もう戦いは避けられない、と思っただけだ」
「――――!」
ハヤブサの言葉に、皆が息を飲む。
「そ、その戦いを避ける方法は無いだか?」
「話し合いは……」
「無理だな。世の中には、『話が通じない相手』と言うのも居るんだ」
ハヤブサは、村人たちの希望を斬って捨てる。少しでも早く、避難する事を決意してもらうために。
「だからもう一度言う。一刻も早く、逃げてくれ」
ハヤブサの言葉に、辺りはまた水を打ったような静けさに覆われる。
しばらくこの沈黙が続くかと思われたが、妖魔たちがまず、その沈黙を打ち破った。
「と、とにかく襲われると分かっているのなら――――わしらの村にも避難を呼び掛けてくる。こちらの避難の手伝いにも来よう。時間が無いのだから、早く動いた方がいい」
「そうだな……! 親父さん、急いで帰ろう!」
妖魔たちの方が、周りに流れる不穏な空気を感じ取れていた分、ハヤブサの言葉が素直に腹に落ちていたようだった。
立ち上がった妖魔たちはそのまま集会所の出入り口から出て行こうとする。だが出ていく直前、妖魔たちは立ち止まって振り返った。
「……済まなかったな……。きっと、こうなってしまったのは、わしらのせいだ」
「……………!」
「ワシらが人間たちとの交流を望んでしまったから………。だが、こうなった以上責任は――――」
「それは違うわ!!」
甲斐姫の強い言葉が、妖魔の言葉にかぶさる。
「誰が悪いとか、誰かのせいとか――――そう言うのは絶対に違う! こうなったのは、もう誰のせいでもないのだから……!」
「し、しかし………!」
茫然とする妖魔たちに、甲斐姫はなおも言葉を紡ぐ。
「もしも……『悪い』と思っているのなら、生きて」
「…………!」
「甲斐………」
「ちゃんと生きて、これから先の『行動』で、責任を示すべきだわ」
その場に居た皆が、彼女の言葉に息を飲む。
「あ…………!」
妖魔たちもしばらく茫然としていたが、やがてはっと我に帰った。
「わ……分かった……。とにかく、村に帰って皆に避難を勧めてくる」
「親父さん、急ごう!」
「ああ、そうだな」
そう言って妖魔たちは頭を下げると、慌ただしく集会所から出て行った。
その様子を黙って見送る甲斐姫の傍に、孫尚香が近づいてくる。それに気づいた甲斐姫が、ポツリと言葉を零した。
「……死ねば、責任取れるって訳でもないでしょう………」
「ええ、そうね」
その言葉に孫尚香も頷く。
「本当に……そう思うわ……」
妖魔たちが去った方を、しばらく沈黙の中で見守っていた村人たちであったが、やがて、長老が声を発した。
「……仕方がない。我々も、避難の準備に取り掛からねば―――」
「長老様!」
「あのお嬢さんの言う通りじゃ……。死んでしまっては何にもならん。生きてこそ……進むべき道も見えてこよう……」
長老は甲斐姫の方を見つめながら言葉を紡ぐ。
「じゃ、じゃが……桃の収穫は――――」
「田んぼの世話は――――」
しかし村人たちからは、まだぼつぼつと反論する言葉が帰って来る。
(無理もない)
長老は思った。
まだ――――この土地や畑に対して、皆、未練を捨て切れていないのだろう。
「皆の気持ちはよく分かる………」
だから長老は、皆を諭すように口を開いた。
「祖先の代から何十年もかけて、わしらはこの田畑を育て上げてきた。わしら百姓にとって、田畑の土は宝じゃ。これは一朝一夕にできるものではないと言う事、よく分かっておる……。一度失ってしまえば、もう取り返しがつかぬと言う事も」
皆がしん、と、静まり返る中、長老の言葉はなおも続く。
「離れがたく思うのは、無理からぬことだ……。じゃがな……。よく考えてみて欲しい。死んでしまったら、総てが終わりじゃ。新しく稲や桃を植える事も、その土地を育てていくことも――――もう二度と、出来なくなってしまう……」
「長老様………」
「それに、我らの伝統や農法が絶えてしまう事を………土地神様は喜ばれるかのう……?」
そう言いながら長老は、シュバルツの方に視線を投げかけてくる。
「―――――!」
シュバルツは瞬間驚いたが――――すぐに長老の意図するところを悟った。
彼はシュバルツに、皆が避難を決意するための『後押し』の役目を望んでいるのだ。『土地神』の『代理』として――――。
(……私は『神』ではないのだが………)
軽くため息を付きながらも、シュバルツは長老の意思をくみ取る事を選択した。自分の誠意の在り方と皆の命――――比べるべくもない。命の方が、はるかに大事だ。
せめて、自分が土地神の代理を詐称する事で、本物の土地神の怒りに触れない事を祈るしかなかった。
「………ここの『土地神』は、皆が死ぬ事を望んではいないと思うぞ。ここから離れて、生き永らえてくれる事を望むだろう」
長老の言葉を受けて、シュバルツが口を開く。
「本当だか?」
問うてくる村人に、彼は頷いた。
「ああ……私を『土地神の代理』と、信じてくれるのなら――――」
シュバルツは、そう言いながら己の胸に手を当てる。まるで、祈りを捧げるような仕種にも見えた。
「少なくとも『私』は、そう望む」
「シュバルツさん……」
「……………」
シュバルツの言葉に、しばらく考え込むように沈黙していた村人たちであったが、やがて意を決したようにその口を開いた。
「分かりました……。皆、避難の準備を始めよう」
「そうだな……。とにかく生きねば――――」
「そうか……よく、決意してくれた」
皆の言葉に長老は微笑み、その隣に居た村長も頷いた。
「では皆――――急いで避難の準備をしてくれ。出来た者から集会所前の広場に集まって、皆で共に逃げよう」
村長の言葉を受けて、村人たちは立ち上がり、各々避難の準備をするべく、集会所を後にしていった。
(……良かった……)
ハヤブサはそんな村人たちの様子を見ながら、ほっと胸を撫で下ろしていた。
村人たちが、避難する事を決意してくれた。とりあえず、第一関門を突破だ。
ただ、避難を始める時間が遅いのが少し気になった。妖魔たちが襲って来るまでに、あとどのくらい、時間に猶予があるのだろう。
「……………」
ふと見ると、愛おしいヒトがその瞳に、少し思い詰めた光を宿して立ち尽くしていたから―――ハヤブサは、思わず声をかけていた。
「シュバルツ……?」
「ハヤブサ……」
「どうした……?」
ハヤブサの問いかけに、シュバルツはその面にどこかぎこちない笑みを浮かべる。
「あ……ああ、何でも――――」
「『何でもない』って言う表情ではないがな」
「……………」
ハヤブサの指摘に、黙りこくってしまう愛おしいヒト。ハヤブサはしばらくそんなシュバルツの傍に立ち、じっとその横顔を見つめていたが、やがてため息交じりに口を開いた。
「……あまり責任を感じすぎるなよ、シュバルツ………」
「…………!」
少し驚いた様にこちらに振り返るシュバルツを、ハヤブサはまっすぐ見つめる。
「甲斐姫もさっき言っていたが、こうなってしまったのは誰のせいでもないんだ。現に、誰もお前を責めてはいないだろう」
「…………」
ハヤブサの言葉に、しばらく揺れる瞳をこちらに向けていたシュバルツであるが、やがて、ポツリと言葉を零した。
「……『神』とは……一体、何なのだろうな……」
「シュバルツ……」
「信仰の厚い村人たち……心優しい妖魔たち……それが何故、こんな事に……」
「『神』とは――――『神』だから、万能であるとは限らないぞ」
「ハヤブサ……」
ハヤブサの言葉に少し驚いた様な視線を向けるシュバルツに、ハヤブサは少し苦笑しながら、言葉を続けた。
「少なくとも、『神』と名乗る存在と言うのは、えてして傲慢で、横暴なものだ。実際、聖書などを紐解いてみても、悪魔が殺した人間の数より、神が殺した人間の数の方が多かったりするしな……。だが、そうかと思えば、本当に人を殺める力など無い、無力な『神』も居る」
素戔鳴の様に、人に裁きを下すような戦いの神が居るかと思えば、ここの土地神の様に、姿を現す事もせず、ただそこの農作物を豊かに実らせるための力しか持たない神も居る。
どちらも同じ『神』だ。ただ――――もしも、ここの土地神が滅びゆく村の運命を憂い、それでも何とかその運命から村人を守りたいと願って、自分の『形代』として、シュバルツを選んだのだとしたら。
(考えすぎか……)
そう感じてハヤブサは、さらに苦笑する。
神をも滅する『龍の忍者』―――故に、自分は『神』など信じていない。
自分は、為すべき事を為すだけだ。守りたいモノを、守る。その為に障害になり得る物があると言うのなら――――自分はそれを、たたき斬るだけなのだ。その相手が『神』だろうが『人間』だろうが『妖魔』だろうが、それは、変わらない。
「ここの『土地神』は、農作物を実らせ、ここの村人たちに充分な恩恵を与えている。もうきっちりと、役目を果たし終えているんだ。だから、ここの村人の『安全』を守ると言うのなら――――それはまた、別の者の役目になるのではないか?」
ハヤブサの話を黙って聞いていたシュバルツであったが、やがて小さな声で、ぽそりと落とすように呟いた。
(淋しくは無いのだろうか?)
「シュバルツ……」
その声が聞こえてしまったハヤブサは、思わずシュバルツの肩を抱き寄せたくなってしまう。
いつもそうだ。
このヒトは――――
か弱き者の、声なき声を拾おうとする。そしてそれに寄り添おうとする。
その底抜けの優しさが、堪らなく愛おしい。
「淋しい……まあ、淋しいだろうな」
だからハヤブサは、シュバルツのその言葉に踏み込んだ。彼の傍には自分が居るのだと、シュバルツに分かってもらうために。
「――――!」
驚いた様に振り返るシュバルツに、ハヤブサは軽く笑みを返してから、口を開いた。
「淋しくない訳がない――――」
今までこの土地を大切に育て、祀ってくれた村人たちと別れを告げるのだ。もしも『土地神』と言うのが本当に居るのなら、淋しさを感じない筈がない。
だが、それでも
それでも――――
「済まぬが、少しよろしいか?」
長老から声を掛けられて、ハヤブサははっと我に帰る。
「あ、ああ……何だ?」
振り返るハヤブサに、長老はまず頭を下げた。
「かたじけない。襲撃の件を教えてくれたこと――――感謝申し上げる」
「礼を言われるほどの事ではない。『情報』を掴んだら、知らせる。忍びとして、当然の働きをしたまでだ」
「それでも……知らせてくれなんだら、我らは全員死を迎えるしかなかった。何度感謝しても足りないぐらいじゃ」
「礼を言われるのはまだ早い。まだ『襲撃』から、全員助かった訳でもないのだから――――」
ハヤブサはそう言って、長老が頭を下げようとするのを拒む。
「確かに、そうじゃな……」
長老もその言葉に納得したのか、頭を下げるのを止めて、顔を上げた。
「では、ハヤブサ殿……。質問をしてもよろしいか?」
頷くハヤブサに長老も頷き返すと、言葉を続けた。
「我らはこの村から避難するとして――――一体、どこへ避難すればよいのじゃろうか……?」
「そうじゃのう。我々はこの村からあまり外に出た事がない者ばかりじゃ。『逃げる』と一言で言われても、何処へ逃げたらよいのやら――――」
長老のそばに付き人のように従っていた壮年も、そう言って首をひねる。
そう。この避難先の問題は、この事件の一番のネックとなっていた。それが見つけられなかったばかりに先の歴史ではシュバルツも苦戦し、結果として、ケイタ以外の全員が死ぬ運命をたどってしまったのだった。このやりなおした時間軸の中で――――もう一度、同じ過ちを繰り返す訳にはいかない。
「避難先については、俺から提案がある」
「……! と、言うと?」
「ここから西に10里ほど行った所に、劉玄徳と言う人物の統治下にある城がある。そこならば――――ここの人間が避難して行ったとしても、問題なく受け入れてくれるだろう」
「劉玄徳……」
だが長老は、その名を口にしながら、首を捻っていた。
「はて……。あまり聞かぬ名前じゃのう」
「ごく最近、近くの城を統治下に置いた者ですよ」
付き人の壮年が、長老に説明するように口を開いた。
「農作物の行商の折り、一度だけその城下町に立ち寄ったが……『可もなく不可もなく』と言う感じじゃったのう。ただ、その城の者たちが『劉玄徳』の悪口を言っている、と言う事は無かったと思うのじゃが……」
「……………」
その言葉に、長老はしばらく考え込むように沈黙していたが、やがて、意を決したように顔を上げた。
「……とにかく、今の我々はハヤブサ殿やシュバルツ殿の言葉を信じて、避難をするしかない。急いで準備を進めよう」
長老の言葉に付き人である壮年も頷き、二人とも集会所を後にした。
「…………」
長老を見送るシュバルツの視線から、やはり、思い詰めたような色は消えない。
「シュバルツ」
ハヤブサは、思わず声をかけていた。
「――――!」
「責任を感じるお前の気持ちは分からないでもないが――――頼むから、死ぬ事だけは、考えないでくれ」
「ハヤブサ………」
「お前が、ここの人たちの『死』を望まないのと同じくらい、お前もまた、『死』を望まれていないのだと言う事を――――忘れないでほしい」
「……………」
ハヤブサの言葉に、しばらく黙って耳を傾けていたシュバルツであったが、やがて、その面に笑みを浮かべた。
「ああ……分かっている。ありがとう」
綺麗な笑みだが、どこか儚さを感じさせるその微笑みに、ハヤブサはたまらなく不安を覚えてしまう。
(守らなければ)
改めて、そう強く決意する。
しっかりしろ、リュウ・ハヤブサ。
お前はそれを為すために――――この時間軸に飛び込んできたのではないのか。
「ケイタ君たちも、避難の準備をしているわ」
それまで末席の方で控えていた甲斐姫が、ハヤブサたちの所に寄ってきた。その後ろから、孫尚香もついて来ている。
「これで何とか……皆で生き延びられればいいのだけれど……」
孫尚香の言葉に、ハヤブサも頷く。
「そうだな。戦い慣れていない民を守りながらの撤退戦になる。これは、かなり厳しい戦いになるだろう」
もう辺りは、かなり薄暗くなってきている。迫りくる戦いの気配を、ハヤブサは濃厚に感じ取っていた。もしかしたらもう、村を襲おうとしている妖魔の一団は、すぐそこまで来ているかもしれない。
「確かに、厳しい戦いになるわね……。でも、きっと、大丈夫!」
「どうして、そう思うの?」
問いかける孫尚香に、甲斐姫は力強く言った。
「だって、『独り』じゃないんですもの」
「…………!」
甲斐姫のその言葉に、皆が互いの顔を見合わせた。
そうだ。
今から戦いに望むのは、決して自分独りではない。同じ想いを胸に戦う『同志』が居る。
それを忘れなければ――――
「絶対に、皆で生き延びて――――『過去』も『未来』も、書き換えてやっちゃいましょうよ!」
甲斐姫の言葉に、皆が頷く。いささか楽観的ともとれる言葉ではあるが、その明るさと強さに、ハヤブサも今は素直に感謝した。そう――――信じることで、手繰り寄せる事の出来る未来だって、きっと、在る筈なのだから。
「それじゃ、避難を急ぎましょう! 尚香! 先導役は、尚香に任せていい?」
「いいけど――――どうして?」
甲斐姫の言葉に、少し首をかしげる孫尚香に、甲斐姫はにこりと微笑みかけた。
「だって、今から向かうのは、玄徳様のお城なんでしょう?」
「――――!」
「だったら、貴方が一番先頭に立って、開門を呼びかける方が話も早いと思うの。いざとなったら、援軍だって頼めるかもしれないし」
甲斐姫のその言葉に、孫尚香もようやく納得した。
「分かった。任せて!」
力強く頷く孫尚香を見届けてから、ハヤブサも口を開く。
「―――殿(しんがり)は、俺が務めよう」
「ハヤブサ……!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは息を飲む。何故なら、撤退戦における『殿』はとても重要で――――と、同時に、非常に生存率が低くなるポジションでもあったからだ。撤退する味方を追おうとしている敵の士気は高く、それを足止めするのは容易ならざる事であった。この役目を負ったたいていの者は、ここで命を落としかねないほど―――難しい役割だった。
「ハヤブサ……! 殿は、私が――――」
だからシュバルツも、そう口を開いた。キョウジに次いで、ハヤブサまでもを喪ってしまいたくはない。強くそう感じたが故のシュバルツの言葉だったが、ハヤブサは頑なに頭を振った。
「いや……殿は、俺が務める。悪いが、いくらお前の頼みでも、これは譲れない」
「しかし……! 『不死』である私の方が――――」
「忘れたのか? この戦いは、お前が傷を治せなくなる相手が出てくると言った筈だ。そんな敵とお前を、戦わせる訳にはいかん!」
「…………!」
絶句して、息を飲むシュバルツに、ハヤブサは優しく微笑みかける。
「シュバルツ……お前は、皆のために動け」
「ハヤブサ……!」
「皆を助けるために――――生きてくれ」
「……………」
暫く、何かを推し量る様に、黙ってハヤブサの言葉と視線を受け止め続けていたシュバルツであったが、やがて、何かを吹っ切るかのように頷いた。
「分かった……。では……お前の言葉に、甘えさせてもらう」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサは笑みを浮かべながら頷いた。
(ならば私の役目は、このシュバルツさんと言う人のフォローをする、と言う事ね)
甲斐姫は、忍者二人を見つめながら秘かにそう決意していた。
この戦いの勝利条件を、彼女は実によく理解していた。シュバルツを守り切って、戦いを終わらせなければ――――どんな形であれ、この戦いに『勝利した』とは言い切れない。
だから、意地でも守り通さなければ。
ハヤブサさんのためにも。
ケイタ君のためにも。
それが、皆の望みだから。
絶対に、絶対に――――最後は皆で笑顔にならなきゃいけないの。
シュバルツを失った絶望のあまり、魔神へと暴走しかけたハヤブサ。
あんな哀しい結末は――――もう、見たくない。
(問題は、私の技量が、何処まであの人について行けるか、なんだけど……)
シュバルツを見つめながら、甲斐姫は思う。このシュバルツと言う人は、かなり腕が立ちそうだ。下手をしたら、ハヤブサと互角ぐらいに――――。
「…………!」
弱気になりそうな己を、甲斐姫は首を振って叱咤する。
しっかりしなさい、甲斐。
貴女だって、『熊姫』と異名をとる女戦士でしょう? 伊達に周りから恐れられてはいないわよ。
見てなさいよ……?
絶対に、遅れなんかとってやらないんだから――――!
「どうした?」
「―――――!!」
いきなりシュバルツから声を掛けられたから、甲斐姫は思いっきり動揺してしまう。
「えっ? えっ……? 何……?」
「いや……先程から、ずっと私を見ていただろう?」
「う、あ……そう、だっけ……?」
「どうした? 私に、何か用か?」
「え……えっと……用、と言うか、何と、言うか――――」
そう言いながらしどろもどろになっている友人を、孫尚香は頭を抱えながら見守っていた。シュバルツを見つめていた友人のあの目つきは、惚れた晴れたのものではない。戦いを挑むような目つきだったからだ。
(もう……! 甲斐ったら……! 貴女は一応『女』で、向こうは『殿方』なんだから、見つめるにしたってもう少し目つきに気を使えばいいのに……!)
あれではまるで喧嘩を売っているみたいだと、孫尚香はこの不器用すぎる友人にため息をつく。甲斐だって、黙って立っていれば、もの凄く可愛らしい女性なのに――――。
「つ、つまり……! その――――」
「…………?」
きょとん、とするシュバルツに向かって、甲斐姫はやがて顔を真っ赤にしながら、思いきった様に、ビシッと指を指した。
「ああああたしは絶対に、負けないんだからね!?」
「…………!」
その言葉に茫然とするシュバルツからくるりと踵を返すと、甲斐姫は耳まで真っ赤にしながら、友人の腕を引っ張って、集会所から外に出ていった。
「ほらっ! 尚香! 行くわよ!! 皆が集まってきちゃう!!」
「ちょ、ちょっと甲斐! 待ちなさいってば……!」
「な、何なんだ……? 一体……。私は彼女に、何かしたのか……?」
女性二人が出て行った方を見つめながら、シュバルツがポツリと呟く。その後ろで、「ブ……クク……」と、笑いをかみ殺す声がした。その声に気付いたシュバルツが振り向くと、ハヤブサが懸命に笑いをこらえる姿が、彼の視界に飛び込んできた。
「ハヤブサ……」
「元気な娘だろう? 彼女は――――」
クククク、と、小さく笑いながら、ハヤブサは言葉を紡ぐ。
「真っ直ぐで、明るい――――。俺は、彼女のこの一途さと明るさに、大分救われた所がある……」
そう。
彼女が皆の前で声を張り上げなければ、今自分はこうしてシュバルツの前に、立つ事が出来なかった。そういう意味では、彼女にはいくら感謝してもしたりないぐらいだと、ハヤブサは思っている。
だがシュバルツは、ハヤブサの言葉に目をぱちくりさせると、少し面に複雑な笑みを浮かべながら口を開いた。
「珍しいな……。お前が女性を褒めるなんて」
「そうか? 俺は別に、女性蔑視などしていないつもりだぞ? 人として感心したら、素直に褒める。当たり前のことではないか」
「ハヤブサは――――」
「何だ?」
「ああいう娘が………好みなのか?」
自分から視線を逸らしながら、少しはにかみ気味に問うてくるシュバルツ。
「――――!」
ハヤブサはシュバルツのその態度に、ピン、と来る物があった。だから思わず、シュバルツに問いかけてしまっていた。
「シュバルツ」
「な、何だ?」
「お前、もしかして今――――『妬きもち』を、妬いている?」
「な―――――ッ!」
思いもかけないハヤブサのこの言葉に、シュバルツの表情が一瞬で強張る。だがシュバルツの頬が、耳まで真っ赤に染まっているのを、ハヤブサは見逃さなかった。図星を指されて、動揺してしまっているのだろう。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは思わず、満面の笑みになってしまった。
まさか
まさかお前が
『嫉妬』してくれるだなんて――――!
「ち、違う! 焼きもちなど妬いていない!!」
対してシュバルツは、一歩、身を引いていた。
「わ、私はただ――――お前に好きな人が出来たのなら――――んう!!」
ハヤブサは強引にその唇を奪っていた。舌を深く差し入れ、その口内を、思いっきり弄った。
「………! ちょ……ッ! ハヤ……! んっ……!」
ハヤブサの強引ともいえる口付けに、シュバルツは軽く抵抗をする。しかしハヤブサがそれを許すはずもなく―――逃げるシュバルツを捕らえて、口付けを続けた。それでも懸命に身を引こうとするシュバルツの背中が、ドン、と、音を立てて壁に当たる。
「ま、待て……ッ! あ……ッ! ん………」
逃げ場を失ってしまったシュバルツは、抵抗を止めて、ハヤブサの口付けを大人しく受け入れていた。暫く、口内を深く弄られ、吸われる水音が辺りに響く。
「は……あ………」
口付けが終わった後、シュバルツは奪われた酸素を求めて、少し喘ぐ。飲みきれなかった唾液が溢れて、唇が濡れ、瞳が潤んでいる。いつ見ても、何度見ても、飽く事のない美しさと色気を備えている事を、このヒトは気付いているのだろうか?
「シュバルツ……」
想いを込めてその頬を優しく撫でると、シュバルツは少し怒ったような眼差しを向けてきた。
「馬鹿っ! 誰かに見られたらどうするつもりなんだ!?」
「どうせ誰も入って来ないさ。それに、見られたって、構うものか」
「な………!」
絶句するシュバルツに、ハヤブサは不敵に微笑みかけると、言葉を続けた。
「俺は別に、本当に構わないんだ、シュバルツ……。誰に見られようが、それでどう思われようが――――俺は、お前しか欲しくないのだから………」
「ハヤブサ……」
「だから、お前が俺から勝手に身を引こうとするのは許さない」
「――――!」
「『俺の幸せ』は、俺が決める。頼むから、それを勝手に定義づけないでくれ……」
「あ………」
少し困惑したように瞳を揺らめかせるシュバルツに、ハヤブサは微笑みかけると、もう一度、囁きかけた。
「そばに居てくれ、シュバルツ」
「ハヤブサ……」
「俺の、傍に―――」
そのままハヤブサは、シュバルツの唇を今度は優しく塞ぐ。
「ん……ッ!」
一瞬腕の中で、身体を強張らせる愛おしいヒト。だがすぐに力を抜き――――口付けを受け入れてくれた。
「ん………ふ………」
そのまま、想いを確かめ合う様な、優しいキスを交わす。至福のひと時だった。
シュバルツ
シュバルツ
俺はお前とこうしているだけで――――勿体ない程幸せなのに。
お前以外、もう何も要らないのに――――
ああ
今すぐお前のその身体を
暴いて
晒して
奪い尽くして、しまいたい――――
「…………」
でも、分かっている。
今は駄目だ。
この戦いを乗り越えて、シュバルツの『未来』を確保しない限りは。
「愛している……シュバルツ……」
口付けを終えたハヤブサは、シュバルツの唇に優しく触れながら、愛を囁く。
「ハヤブサ……」
思い詰めた色を湛えて揺れる、愛おしいヒトの瞳。
「愛している」
その言葉を俺に返してはいけない、と、真面目に思ってしまっているから、苦しんで――――。
お前がそうやって、俺への愛ゆえに苦しんでいる姿に気づいてしまうたびに
俺がどれほど幸せを感じてしまっているか、お前は、分からないだろう。
ああ
やっぱり、最低だな、俺は。
お前は、苦しんでいるのに――――
俺は今
「死んでもいい」
そう思えるくらい――――幸せだ。
もういい。
今は、これで――――
「続きはまた、戦いが終わってから――――だな……」
「あ…………」
ハヤブサはそう言いながら、ようやくシュバルツを解放する。身体がいきなり自由になって、少し戸惑った様な声を上げ、茫然としていたシュバルツであったが、やがて、己が手で自分の唇に触れ、頬を朱に染めながら、頷いた。
「……そうだな……。続きは、戦いが終わってから………」
「戦いが終わったら――――俺に抱かれてくれるんだな!?」
「――――!」
ハヤブサのその言葉に、瞬間的に我に帰るシュバルツ。はっと、自分の目の前を見ると、ハヤブサが『してやったり』と言わんばかりの笑みを浮かべながら、じっとこちらの顔を覗き込んでいる。
「いや……! 待て……! 確かに、今の言葉は――――!」
シュバルツは慌ててさっきの言葉を取り消そうとしたが、ハヤブサの方が既に聞いていなかった。
「やった――――!! シュバルツから言質を取ったぞ――――!!」
満面の笑みを浮かべながら、シュバルツの周りをはしゃぐように飛び跳ねていた。
「ま、待てっ! ハヤブサ!」
「やった♪ やった♪ 言質♪ 言質♪」
「お、おい……! ハヤブサ……!」
「戦いが終わったら~~♪ シュバルツと~~~♪」
「~~~~~~ッ!」
シュバルツの話を聞かずに、彼の周りをはしゃぎながら飛び跳ねているハヤブサ。シュバルツは頭をグシャッと掻きながら、しばらくそんなハヤブサの様子を呆れるように眺めていたが――――やがて、観念したかのように一つ、深いため息をついた。
「……ハヤブサ……分かった……」
「シュバルツ?」
「分かった……! 戦いが終わったら、ちゃんとお前に抱かれてやるから―――そうやってはしゃぎまわるのは、止めろ―――ッ!!」
シュバルツの大声に、ハヤブサの動きがピタリと止まる。
「本当か?」
確認するように覗き込んでくるハヤブサに、シュバルツは渋い顔をしながらも頷いた。
「ああ……武士に二言は無い!」
そう言い放った後で、シュバルツは、少し真面目な顔になってハヤブサを見つめ返す。
「だから――――ハヤブサ……」
「何だ? シュバルツ……」
「絶対に――――死んだりするなよ……?」
「―――――!」
思いもかけないシュバルツの言葉に息を飲むハヤブサに、更にシュバルツからの言葉が被さって来る。
「お前こそ、どんな状況になっても………『生きる』と言う選択肢を捨てる事だけは、しないと約束してくれ……!」
そう言って、真剣な眼差しで、こちらを見つめ返してくる愛おしいヒト。
(シュバルツ……)
ちゃんと愛おしいヒトに愛されている自分を感じられて、ハヤブサは何とも幸せな気持ちになる。
「愚問だ。お前を抱くまで、俺は死なない」
ハヤブサはそう言って、シュバルツを安心させるために、微笑んだ。
だが実際は――――その『約束』を守る事はとても困難である事を、ハヤブサは知っていた。民を守りながらの撤退戦の殿。ただでさえ難しい任務であるのに、この戦いに加わってくる『素戔鳴』――――この存在が、彼の心に暗雲を投げかけていた。
遠呂智に立ち向かうための戦いの中で、ハヤブサも既に何度か、素戔鳴と直接剣を交えたことがある。だがその時の戦いの結果は、いずれも素戔鳴の方に軍配が上がっていると言っても過言ではなかった。
「素戔鳴様と邂逅されても、絶対に剣を交えられませぬよう――――」
初めて素戔鳴と相対した時、巫女かぐやがそう言って忠告してくれた事を思い出す。
だが、戦いの最中、幸か不幸か戦場で素戔鳴と邂逅してしまったハヤブサは、武人として『手合わせをしてみたい』と言う好奇心が抑えきれず、忠告を無視して素戔鳴に挑んだ。
しかし――――
ガキッ!!
「――――!」
自分の必殺の剣が、いとも簡単に素戔鳴に見切られて、止められてしまったから、ハヤブサは息を飲んだ。しかも、それどころか――――
「吩ッ!!」
「ぐあっ!!」
素戔鳴の無造作に振るわれた剣が、ハヤブサを傷つけ、彼の体力を容赦なく奪う。
「く………!」
このまま素戔鳴とまともにやり合うのは分が悪い、と判断したハヤブサは、素戔鳴から距離を取りつつ、その戦いの敵方の総大将を討ちとる方を選択していた。総大将を討ちとり、素戔鳴から戦う理由を奪えば―――その場から素戔鳴は退くだろうと判断したからだ。
幸いにしてハヤブサのその読みは当たり、総大将を討つと素戔鳴も退き、討伐軍はその戦いを無事乗り切る事が出来た。
だが、今度の戦いはそうはいかない。
素戔鳴は正真正銘の『総大将』と言う形でこの戦場に乗り込んでくるし、彼の目的は、この村に住んでいる村人と人と交流をした妖魔に裁きを与えること―――それを成し遂げるまでは、素戔鳴が戦場を引く事は無いだろう。そして、性質の悪い事に、彼はシュバルツのDG細胞を、消滅させる力を持っている。
絶対に、シュバルツと素戔鳴を、戦わせる訳にはいかない。
村人たちと妖魔を討つ事を目的としている素戔鳴。その目的を、絶対に受け入れられないシュバルツ。そして、シュバルツの存在自体を、決して許す事の出来ない素戔鳴――――。そんな二人がぶつかり合ってしまえば、その先に待ちうけているのは、悲劇しかないのだ。そしてその結末を、俺は絶対に受け入れる事が出来ないのだから。
殿の俺が、引きとめるしかない。
一分でも一秒でも長く、素戔鳴の足を。自分の前に。
(できるのか……? 俺に――――)
龍の忍者は自分に問いかける。
―――やるしかない。
ここまできたら、出来る出来ないの問題ではない。やらねばならないのだ。
これを乗り越えなければ、自分の望む未来が得られないと言うのであれば。
「ハヤブサ……」
ハヤブサの微笑む顔を見たシュバルツだが、彼の瞳から憂いの色が消える事は無かった。
(おかしいな)
ハヤブサは、微笑みながら秘かに首を捻る。
もしかして、シュバルツに何か伝わってしまっているのだろうか? 自分がこのまま、ここで死んでもいい―――――と、覚悟を決めてしまっている事が。
シュバルツ。
俺は、別に構わないんだ。お前の未来を繋ぐために、その代償として俺の命が必要だと言うのなら。
俺は何時だって――――喜んで、この命を捧げる。その覚悟がある。
シュバルツ、お前は生きて。
どうか、生きて。
そして――――お前の手で、キョウジの未来を取り戻してくれ。
『遠呂智』を倒した後、かぐやに頼んで、キョウジが死んだあの時間に戻してもらう事が出来れば――――あの『大蛇』が出現しない時間軸で、喪われたキョウジの時間を、再び動かす事が出来るだろう。
ただ――――済まないな。
俺はお前に、一つだけ我が儘を言わせてもらう。
俺は例え自分が『死ぬのだ』と分かっていても、どうしてもお前の手だけは――――離せそうにない。自分が生きている間に、お前に『自由に生きろ』とは、どうしても、言ってやれないんだ。
俺が死んだ後なら良い。
お前が誰を愛そうが、誰と幸せになろうが――――俺がそれに、口を出す権利など無いのだから。
幸せに、なってくれ、シュバルツ。
どうか、幸せに――――
だが――――俺が生きている間だけは。
息絶える最期の瞬間まで、『お前は俺の恋人なのだ』と――――そう、思わせてくれ。そうすれば俺は――――幸せな気持ちのままで、黄泉に旅立つ事が出来るから。
済まないな、自分のことしか考えていなくて。
俺の『死』は、もしかしたら、お前を傷つけてしまうかもしれないのに――――。
だが、不死のアンドロイドであるお前。生身の人間である、俺。
こういう別離は、いずれ来る。
それがただ――――早いか遅いかだけの違いだった。
(ハヤブサ……!)
シュバルツは目の前の想い人の、微笑む顔を見る。
自分に触れられる事を無邪気に喜び、いつもどおりにふるまっているように見えるハヤブサ。彼の言動と行動は、決して生きる事をあきらめてはいない。
なのに、何故。
何故――――その瞳の奥に宿っている悲壮な光が消えないのだ。
その瞳は、今から死にゆく者の瞳だ。
(嫌だ……!)
シュバルツは、強く思う。
キョウジに次いで、ハヤブサまでもを失ってしまったら――――
自分は今度こそ、絶望の淵から立ち直れないかもしれない。大切な人を続けざまに二人も失って――――その哀しみに耐えきる自信など無かった。そんな事になるくらいなら、自分がどうにかなってしまった方が、何十倍もましだと思う。
ハヤブサもキョウジも、貴重な命をその身に宿す『人間』だ。なのに、その人たちが死んでしまって、機械仕掛けの、紛い物の存在の様な自分だけが生き残ってしまうなんて、絶対におかしい。誰かが、何かの犠牲が必要だと言うのなら――――それは、自分が請け負うべき事なのだと、シュバルツは思っている。
まして、この先に向かう戦場が、かつて自分が死んでしまったと言う戦場であるのならば尚更――――ハヤブサに、その犠牲の肩代わりをさせてはいけない、と、思った。
「ハヤブサ……!」
「ん?」
「やはり、殿は私が――――!」
「駄目だ、シュバルツ」
ハヤブサは、シュバルツの申し出を頑なに斬って捨てる。
「言った筈だ……! お前は、皆のために動けと」
「……………!」
「村人たちは皆、お前を信頼している。俺が動くよりも、きっとお前が先導した方が、より多くの村人を守れるはずだ」
「…………」
ハヤブサの言葉に押し黙ってしまったシュバルツに、ハヤブサは、改めて微笑みかけた。
「生きろ、シュバルツ」
「―――――!」
「皆のために……生きてくれ」
「ハヤブサ……」
(……皆のために……『俺のために』生きてくれ、とは、言わないのだな……)
シュバルツは強く確信する。ハヤブサはやはり、『死』を覚悟しているのだと。
「分かった……」
シュバルツはもう一度、とりあえず納得したふりをする。
しかしシュバルツは、秘かに決意していた。絶対に――――絶対に、ハヤブサを守って見せる。この戦いでハヤブサを決して死なせはしないのだと。
大丈夫。ハヤブサは、充分強い。手を差し伸べるのは最後の最後。その一瞬に、自分が間に合えばいいのだから。
「…………」
忍者二人がそうやって話し合っているのを、建物の外から甲斐姫と孫尚香が覗き込むように見ていた。
「え……? え……? あの二人って、『そう言う』関係なの……?」
そう言いながら頬を赤らめ、少々動揺を隠せない孫尚香に対して、甲斐姫は普通に見ていた。
「ああ……やっぱり、そうじゃないかと思っていたけどね~」
「え? ……え? か……甲斐は、おかしいとは思わないの?」
「何が?」
「だ、だって……『男』同士で――――」
「ああ―――そんなの、当たり前でしょ?」
「えっ!?」
驚く孫尚香に対して、甲斐姫はしれっと答える。
「私の周りじゃ、割とよくある話だわよ。俗に言う『衆道』ってやつね」
「え……? よく、あるの……?」
問い返す孫尚香に対して、甲斐姫は頷いた。
「うん。割と普通にあるわよ。多いのは、主君と家臣の間かな。互いの絆を深めるのに、臥所を共にするのが手っとり早いらしくて―――」
そこまで話した甲斐姫が、「へっ」と、少し毒づいた様な笑みを見せる。
「全く……ちょっと良い男って言うのは、どうして男に走るのかしらね。ここに、こんなに可愛い女が居るっていうのにさ」
そう言う甲斐姫の口から、何か「ふへへへへ……」と、干からびた笑い声が聞こえてくる。
「か、甲斐……。ええと、あの……」
孫尚香は、乾いて行く友人の笑いを、どう慰めて良いのか分からず――――言葉を失うしかなかったのであった。
「お姉さんたち、シュバルツさんは?」
「ひゃうっ!?」
ケイタから、不意打ちの様に声を掛けられて、孫尚香と甲斐姫は、はっと我に帰る。見ると、ケイタをはじめとした村人たちが、徐々に広場に集まりつつあった。
「ハヤブサさん! シュバルツさん! そろそろ村の人たちが……!」
恋人同士の貴重な時間を邪魔するようで、孫尚香は多少気が引けたのだが、そう声をかけた。すると、ハヤブサとシュバルツは振り返って、「今、行く」と、すぐに答えてくれた。
「シュバルツさん!」
集会所から出てきたシュバルツに、ケイタが走り寄って来る。その後ろから、彼の父と母もついて来ていた。
「何時もケイタが世話になりっぱなしで―――」
そう言って頭を下げる父に、「いえ、こちらこそ……」と、シュバルツが挨拶を返している。その後ろから外に出てきたハヤブサの姿を、孫尚香は見るともなしに見ていたが、ハヤブサの取った行動に、少しはっとした。
ハヤブサは、刀の柄に、静かに口付けをしていた。その柄には、シュバルツのロングコートの切れ端が巻かれている。あの時、ハヤブサの腕の中で死んでしまったシュバルツの――――
「……………!」
孫尚香は、何故かその姿を凝視してはいけない様な気がして、慌てて視線を逸らした。何か、神聖な儀式をしている様な――――そんな印象を受けたからだ。
(ハヤブサさんて……本当にシュバルツさんの事が好きなんだ……)
そう感じられて、勝手に頬が赤面した。もしかしたら、人が人を恋慕う気持ちには、その対象が男だろうと女だろうと、関係ないのかもしれない――――そう思えた。
(……玄徳様……)
孫尚香は、今は離ればなれになってしまっていて、なかなか会う事の出来ない大切な人に、想いを馳せる。
「尚香殿……」
いつも穏やかで、優しい笑顔で自分の事を見守ってくれる大切な人。その人と離れ離れになってしまっている今――――自分は、時々だけどどうしようもない淋しさを感じる時がある。
玄徳様もそうなのだろうか。
あのハヤブサさんと言う人と同じように、あの人も、私の事をあんな風に、想ってくれているのだろうか――――。
もしもそうなら、この淋しさも、少し報われるのに。
(とにかく、甲斐も言っていたけど、絶対に皆を助けなくてはいけないわね。私は私の役目を頑張らなくっちゃ!)
ハヤブサさんの願い。ケイタ君の願い。皆叶えばいいと、自分も願う。孫尚香は少し祈る様に自分の胸の前に手を当ててから、その顔を上げた。彼女が皆の傍に走り寄って行くと、甲斐姫から声をかけられた。
「尚香! もうみんな、揃っているって!」
その近くに控えている長老も、甲斐姫の言葉に頷いた。
「うちの村の人間は、これで全部じゃ」
その言葉に孫尚香は頷くと、村人たちに声をかけた。
「じゃあみんな! 私が案内するわ!! ついて来て!!」
皆で頷いて、移動を始めた。皆の未来をかけた戦いが今、静かに始まりを告げたのだった。
「みんな! ついて来てる!?」
先頭を歩く孫尚香が、闇の中、後ろを振り返り問いかける。何だかんだと村を出るのが、かなり夜が更けてからになってしまった。村人の列の中間あたりをシュバルツと甲斐姫が警護にあたり、一番後ろからハヤブサがついて来ている。
(だいぶ遅くなってしまったな……。妖魔が襲ってくるのは、いつぐらいだ?)
妖魔が襲って来たのは、皆が寝静まってから――――と言うケイタの話を思い出しながら、ハヤブサは、辺りの気配を探り続けていた。もうこの状況は、いつ妖魔に襲われてもおかしくは無いと感じていた。
ただ、シュバルツが独りで戦った前の歴史とは違って、襲われる前に、村人皆が村から脱出する事に成功している。それだけでも、ここから後の戦いの展開は、ずいぶん変わって来る筈だった。
不意に、何かが焼け焦げるような匂いが漂ってくる。それと同時に、何かが爆ぜて、燃える音も――――
(来た………!)
四人が四人とも、そう感じて覚悟を決める。それと同時に、村人たちの間から、叫び声が上がった。
「何だ!? あれは!!」
「火だ!! 炎が上がっている!!」
「あれは――――妖魔たちの村がある方角じゃないだか!?」
(そうか……! 妖魔たちの村が、先に襲撃されて――――!!)
炎を見上げるハヤブサの目の前の林の木々が、ガサガサと音を立てて揺れる。そこから黒い影が飛び出してきた。
「――――!!」
戦うために身構えるハヤブサ。だが、飛び出してきたのは女性型の妖魔と、その子供たちであった。
「助けて!!」
彼らは口々にそう叫びながら、必死にこちらに向かって走って来る。それに真っ先に反応したのは、やはり――――シュバルツであった。
「孫尚香!! 走れ!!」
彼は走ってくる妖魔たちの集団を、村人たちの集団に迎え入れながら、そう叫んだ。
「えっ――――!」
瞬間的に状況が把握できず、少し戸惑う彼女に向かって、尚もシュバルツから声が飛んだ。
「走れ!! 走れと言っているんだ!!」
「え……っ!? で、でも――――!」
「先頭が足を止めるな!! 走れ!! 一刻も早く、皆を連れてここから離脱するんだ!!」
シュバルツの叫ぶ言葉の意味を把握した甲斐姫も、孫尚香に向かって声を上げた。
「そうよ!! 尚香!! 走って!!」
「甲斐――――!」
「後ろの心配はしないで!! みんなを、必ずあなたに追いつかせるから――――!!」
「分かったわ!!」
その声に孫尚香は力強く頷くと、「みんな!! ついて来て!!」と叫びながら走りだした。その声に弾かれるように、村人たちも一斉に走り出す。
「あんたたちも一緒に行くべ!!」
そんな中でも村人たちは、逃げて来た妖魔たちに手を差し伸べる事を忘れなかった。妖魔たちを集団の中に受け入れ、その人数を増やしながら、孫尚香の後をついて行く。
「わ、私たちも、一緒に逃げて良いの……?」
中には、村人たちと一緒に逃げる事を躊躇う妖魔も居た。
「大丈夫だ!!」
その声に、シュバルツが力強く頷く。
「そうよ!! 大丈夫!!」
甲斐姫も同じように頷いた。
「この先にお城があるの。そこに居る人は、きっと貴方たちも同じように受け入れてくれるはずだから―――!」
シュバルツと甲斐姫のそんな声を聞きながら、ハヤブサは1人、沈黙の中に居た。刀の柄に手をかけながら、そこに独り、静かに佇み続けている。
そう。
逃げる民や妖魔たちを守り導くのが、シュバルツ達の役目。
自分の、役目は――――
逃げる妖魔たちの間に混じって、武器を振りかざして突っ込んでくる妖魔を見つける。
「死ね―――――ッ!!」
ハヤブサに向かって、真っ直ぐに突っ込んでくる妖魔。
「――――!」
ドンッ!!
それに反応して、鞘から抜き放たれたハヤブサの龍剣は、武器を振りかざした妖魔の首を、過たずに刎ね飛ばした。首を飛ばされた妖魔の身体が、周囲の妖魔たちを巻き込みながら、後方へと吹っ飛ばされて行く。
(今、飛ばされた妖魔たちの中に、逃げて来た者もいたかもしれない)
ハヤブサはそんな事を思ったが、すぐに顔を上げた。
自分の役目は、戦うこと。
迷うな。
躊躇うな。
刀を振り、命を奪うという行為を。
守りたい者を、守るためにも――――
「斬られたくない者は、武器を捨てよ!!」
刀から妖魔の血を滴らせながら、龍の忍者は大音声で呼び掛ける。
「武器を捨てぬ者は、敵対する者と見なし、容赦なく斬る―――」
そう言いながらハヤブサは、再び刀を構える。その身体から発せられる鋭い殺気を前にして、目の前の妖魔たちの何人かは、武器を捨てた。それでも、半数以上の妖魔たちは、まだ武器を持っている。
(なるほど……これでは見分けがつかないな……)
そう感じてハヤブサは苦笑する。
ケイタが、「誰が味方で誰が敵か、分からなくなる」と、言っていた。確かにこれは、その通りの状況の戦場だ。『独りで』民を守りながら戦うのであるならば、相当苦戦しなければならないだろう。
だが今は――――
「シュバルツ!!」
ハヤブサは、愛おしいヒトに、そして、戦場においては、頼もしい相棒に呼びかける。
「何だ? ハヤブサ」
逃げて来た妖魔たちを誘導しながら、返事をしてきたシュバルツに、ハヤブサは軽く微笑みかけると、言葉を続けた。
「守りは任せたぞ――――」
それだけ言い置くと、龍の忍者は抜刀したまま走りだした。妖魔の集団の中に飛び込んだ黒い影は、たちまちのうちに周囲の妖魔たちの身体を撥ね上げ、屍の山を築き上げていく。
自分は、戦いに専念する。
血を流すこと。
手を汚すこと。
これこそが、自分の役目なのだから。
「ハヤブサ……!」
シュバルツは、ハヤブサの鬼気迫る様な戦いを、しばし呆然と見つめていたが、やがて彼も顔を上げた。
(そうだ……! 今は1人でも多く、皆を助けなくては――――!)
ハヤブサの話によると、この戦いは、前の歴史では自分を含めてケイタ以外が全員死を迎えると言う結末に達したと言う。自分はともかく、ここに居る皆は――――何としても守りたい、と、願った。その為にここに来ている、ハヤブサたちの頑張りを、無駄にしないためにも。
シュバルツもまた、守るための剣をふるうべく、走りだしていた。
孫尚香の先導と、ハヤブサが後方で頑張っているおかげで、村人たちの集団は、村から目的の城へと、着実に移動しつつあった。しかし、妖魔軍の猛攻に曝されているに等しい状態であるが故に、村人たちや妖魔たちの間で、少しずつ犠牲者が出始めても居た。
「ああ……!」
甲斐姫の目の前で、また1人、村人が流れ矢に当たって命を落として行く。彼女は、守れなかった無力を痛感して、ギリ、と、歯を食いしばるしかなかった。
(まずい……! 私って本当に、役に立っていない……!)
ケイタから話を聞いて、覚悟をしていたとはいえ――――敵と味方の区別がつきにくい戦場での戦いにくさを嫌と言うほど実感する。誰を守って、誰を斬ればいいのか――――咄嗟に判断できないこの状況は、彼女の振るう刃をどうしても一歩遅らせてしまっていた。
「大丈夫か!?」
鈍る刃を携えているが故に、時々シュバルツに庇われ、助けられてしまう始末だ。本当ならば、自分がこの人を、守らなければならないのに。この人の、足を引っ張っている場合ではないのに――――。
(負けるもんか……!)
甲斐姫は自分で自分を叱咤する。
しっかりしなさい、甲斐。
落ち込んでいる暇があるなら、悔しがっている暇があるなら――――一歩でも二歩でも、足を動かすの。一太刀でも二太刀でも、刀を振るうの。
例え非力でも、力が及ばなくても良い。
自分の出来る精一杯を、やり続けるのよ。
ふと、甲斐姫の視界に、転んだ子供と、それに向かって武器を振りあげている妖魔の姿が飛び込んでくる。
「このぉ!!」
叫びと共に彼女から繰り出された鞭のようにしなる剣が、子供に攻撃を加えようとした妖魔を弾き飛ばした。
「大丈夫!?」
甲斐姫が倒れた子供に走り寄ると、その子供――――ケイタが顔を上げた。
「ケイタ君!!」
「あ……! お姉さん……!」
「しっかり! 怪我は無い!?」
そう言いながら助け起こす甲斐姫に、ケイタは「大丈夫」と、頷いた。
「お父さんとお母さんは!?」
服に着いた土を払い落しながら、甲斐姫が尋ねると、ケイタは弱々しく首を振った。
「わ、分からない……。はぐれてしまって……」
「ケイタ!!」
呼び掛けられる声に二人が振り向くと、人ごみの中からケイタの父親が走り寄ってきていた。
「おとう!!」
叫びながら手を伸ばすケイタに、父親も「良かった……! 無事だったか……!」と言いながら、ケイタの身体を抱きあげた。
「ありがとうございます……! 息子を、助けていただいて――――」
「お礼は良いから、息子さんの手を、ちゃんと握っててあげてくださいね」
「は、はい――――」
父親の言葉に笑みを浮かべる甲斐姫。その背後で、ガキン!! と、いきなり剣撃の音が響く。
「――――!」
驚いて皆が振り向くと、甲斐姫に斬りかかろうとした妖魔たちを、丁度撃退しているシュバルツの後ろ姿があった。
「あ………!」
また、守られたのだと悟った甲斐姫が、思わず声を上げると、その声に反応したシュバルツが、こちらに振り向く。そしてその面に、「フ……」と、優しげな笑みが浮かんだかと思うと、すぐにそこから姿を消した。もう次の戦いの場へと、その身を移しているのだろう。
「…………!」
(やっぱり、敵わない……!)
強くそう感じてしまって、知らず己が刀をぎゅ……と、握りしめる甲斐姫。そんな彼女に、ケイタが声をかけてきた。
「お姉さん……。シュバルツさん、大丈夫かな……」
「ケイタ君……」
不安そうな瞳を揺らすケイタを安心させようと、甲斐姫は懸命にその面に笑みを浮かべる。
「大丈夫よ! ケイタ君……。あの人は、強いんだもの――――」
「うん……。でも……あの人、もう、傷だらけだった……」
「―――――!」
その言葉に息を飲む甲斐姫。その目の前で、ケイタの瞳から涙が零れ落ちる。
「ねえ……。大丈夫かな……? また、シュバルツさんが死んじゃったりしたら―――」
「そんな事はさせない! 大丈夫よ!!」
ケイタの言葉を、甲斐姫の力強い言葉が遮った。
「絶対に、シュバルツさんを死なせはしない……! 私たちは、そのためにここに来たんでしょう?」
「お姉さん……」
「だから、泣いている場合じゃないわ、ケイタ君。あの人を守ろうと思うのなら、一歩でも二歩でも、前に進むの。絶対に私たちが、生きる努力を最後まで怠ったら駄目なの」
「うん………」
ケイタは、頬に流れる涙を、グシャ、と、手で拭う。そうして顔を上げた息子に、父親が声をかけてきた。
「ケイタ、行こう」
その言葉に、ケイタは「うん」と頷くと、父親と一緒に再び走り出した。
(良かった……)
甲斐姫は、少し安堵の息を吐きながら、その親子の後ろ姿を見送った。
よかった。とにかく、1人守れた。
(まあ私が、一人二人と守っている間に……シュバルツさんの方は10人、20人と守っているんだけどね……)
そう感じてしまって、甲斐姫は苦笑する。
このシュバルツと言う人は、とにかく動きが早い。そして強い。この集団を守るために、何処を庇って敵の何処を叩けばいいのか――――ちゃんと理解して的確に動いている。それでも傷だらけになっているのは、私と同じように敵と味方の区別があの人にもついていないから。それでも、あれだけ早く動けると言う事は、やはり、私よりも状況判断が早いからなのだろう。
(やっぱり、私はまだまだだな……)
自分の未熟さを痛感して、苦さと悔しさを噛みしめる。
でも――――
甲斐姫は顔を上げた。
落ち込むのも、反省するのも後だ。
とにかく今は動く。動き続ける。
自分の目的を、望む未来を――――あきらめないためにも。
「負けるもんかああああっ!!」
甲斐姫は一声、強くそう雄たけびを上げると、再び戦いの場へと、足を踏み入れて行った。
殿(しんがり)を務めるハヤブサの戦いは、今のところ順調だった。
民を守ると言う行為をシュバルツ達に任せているおかげで、戦いそのものに集中できているからであろう。危機らしい危機に陥ることも無く、押し寄せる妖魔軍に当たる事が出来ていた。
ただ、一つだけ、問題があった。その『問題』とは――――
「ハヤブサ……」
戦いの最中、そうやって時々声をかけてくる、シュバルツの存在であった。
「ハヤブサ……。これより後ろに生きている村人たちはいない。少し退こう」
彼はそうやって戦いの節目節目で声をかけてきて、殿である自分が逃げる村人たちからあまり離れすぎないように気を配ってくれている。こちらの退路を、常に確保してくれていた。
「……………!」
しかし、ハヤブサはその状態に歯噛みしていた。
シュバルツの気の配り方、戦い方は、全く持って間違っていない。ある意味撤退戦の、正しいやり方であるとも言える。
でも、駄目なのだ。今のこのままの状態では、絶対に駄目だ。
自分は、シュバルツから離れたいのだ。
この戦いの相手が妖魔の軍団だけであったなら――――この状態をキープし続けていても、何ら問題は無かっただろう。しかしこの後、この戦場には確実に『素戔鳴』が乗り込んでくると分かっている。
その素戔鳴とシュバルツを邂逅させる事を、ハヤブサは何としても避けたかった。
素戔鳴はシュバルツを見つけてしまった瞬間に、確実に彼はシュバルツを、抹殺すべき標的にしてしまう。そして素戔鳴には、シュバルツの身体を構成しているDG細胞を破壊する力が備わっているから厄介だった。
何としても、素戔鳴とシュバルツを会わせてはならない。会わせてしまったら最後、シュバルツに襲いかかる悲劇を避けうる事が、酷く困難になってしまう。あの素戔鳴を前にして、シュバルツを庇いながら戦うなど、今の自分にはほぼ不可能に近かった。
だからシュバルツを、何としても引き離さなければならない。
素戔鳴と戦うつもりの自分から。
出来れば、この戦場からも。
なのにシュバルツの方が、自分の傍から離れようとしない。
既にハヤブサは、この戦場でシュバルツを撒こうと何度か試みている。しかしそのたびに、シュバルツについて来られてしまって、その試みはことごとく失敗してしまっていた。
「民たちを放っておいて、大丈夫なのか!?」
問いただすハヤブサに、シュバルツは笑顔を見せる。
「彼女たちが守ってくれている。問題ないよ」
なかなか優秀だな、彼女たちは――――――と、そう微笑みながら答えるシュバルツのその言葉に、ハヤブサは頭をかきむしりたくなってしまう。
(何としても、シュバルツを撒かねば……! しかし、どうしたものか―――)
そう思案に暮れるハヤブサの視界に、一本のつり橋が飛び込んできた。そのつり橋を、民たちが次々と渡って行っている。
―――しめた……! 我が事成れり……!
ハヤブサは内心そうほくそ笑むと、何気ない風を装いながら殿としての戦いを続けていた。
妖魔たちの攻撃を防ぐハヤブサの背後で、民や共に逃げる妖魔たちが、次々とその吊り橋を渡り終えていく。
「ハヤブサ!!」
案の定、村人たちが全員渡り終えた時点で、シュバルツが自分に声をかけてきた。そしてそのまま、シュバルツは橋の渡り口で留まり続けている。こちらが橋を渡るまで、そこから彼が動かないつもりでいるのは明白だった。
(シュバルツ……)
彼の律儀さと優しさに、どうしようもない愛おしさを感じながら、ハヤブサはシュバルツに近づいて行く。シュバルツを先に吊り橋に入らせて、自分もその後に続いた。そして、吊り橋の半ばまで差し掛かった時。
ハヤブサはいきなり、龍剣を無言で一閃させた。
「――――!?」
ガラ……と、音を立てて足場の吊り橋が崩れる。吊り橋を中程まで渡り切っていたシュバルツは、咄嗟に前方の岸へと跳んだ。そして(ハヤブサは!?)と、振り返って絶句する。何故なら彼は――――シュバルツとは反対側の岸に着地していたからだ。
「ハヤブサ!?」
茫然とこちらを見つめるシュバルツに、ハヤブサはにこり、と、微笑みかけると、そのまま踵を返して、走り去って行った。追手の妖魔がひしめく森の方へと向かって――――
「ハヤブサ!? ハヤブサ!!」
シュバルツが懸命に呼びかけるが、ハヤブサから答えが返って来る事は無かった。ただ、森の奥から鬨の声と、戦いの音が聞こえてくるだけだった。
「ハヤブサ……! 何故だ……!」
茫然と呟くシュバルツの後ろで、甲斐姫と孫尚香もまた、絶句していた。
(ハヤブサさん……! それほどまでに、シュバルツさんの事を守りたいと……!?)
二人ともがこの後、素戔鳴がこの戦場に現れる事を知っていた。そしてその素戔鳴が、どれぐらいの強さを誇るものなのかも。ハヤブサはその素戔鳴に、たった一人で挑もうとしている。いくらハヤブサが『強い』とはいえ――――1人で挑むには、素戔鳴はあまりにも強大すぎる敵だと知れた。
それなのに、1人で素戔鳴に挑もうとしているハヤブサの、その真意は何か。
考えるまでも無く、答えは一つだ。
「シュバルツさん……。私たちは、先を急ぎましょう」
だから甲斐姫は、シュバルツにそう声をかけた。それが、ハヤブサの望みだと悟ってしまったから。
「――――! 馬鹿な……! ハヤブサを、置いて行けと言うのか!?」
シュバルツの言葉に、甲斐姫は頭をふる。
「ううん、置いて行く訳じゃない……。でも今は、先に進む事を優先すべきだわ」
「――――!」
「先に進んで村の人たちの安全を確保して――――一刻も早く劉備様の援軍を仰ぐ。これが今……私たちに出来る、最善の策だと思うの」
「しかし……!」
甲斐姫の言葉に納得できないのか、シュバルツはまだハヤブサが去った向こう岸の方を、茫然と見つめている。
「行きましょう、シュバルツさん……。ハヤブサさんが、時間を稼いでくれているうちに」
甲斐姫は真正面からシュバルツを見つめながらそう言った。しかしシュバルツは、其れを拒否するかのように首を振った。
「こんな橋を落とした所で稼げる時間など僅かな物だ……! 川を渡る手段など、いくらでも――――」
「それでも!!」
甲斐姫はシュバルツの言葉を遮るように、声を張り上げていた。
「それでも、橋をまっすぐ渡ってくるよりは、はるかに時間を稼げる!! ハヤブサさんが稼いだ時間は、僅かなものだろうとも―――決して無駄なんかじゃないわ!!」
(違う、分かってる)
甲斐姫は叫びながら、内心ほぞを噛んでいた。
ハヤブサさんが本当に時間を稼いだのは、敵を足止めするためじゃない。シュバルツさんのためだ。シュバルツさんを、自分から少しでも遠くに遠ざけたいのだ。素戔鳴と、戦わせないために――――。
(しっかりしなさい、甲斐)
甲斐姫は、もう一度己を叱咤する。
絶対に、シュバルツさんを足止めしてみせる。
ハヤブサさんの命がけの行為に応えるためにも――――。
比翼の翼の片方を失って、片方が泣く。
あんな悲劇的な結末なんて、私だって、もう見たくない。
「行きましょう! シュバルツさん! 村人たちのために――――!」
「…………!」
真正面から見据えてくる甲斐姫の言葉に、シュバルツの瞳が困惑の色に揺れる。そこへ、馬のいななきと共に、孫尚香が二人に声をかけてきた。
「甲斐!!」
「尚香! どうしたの!? その馬は……!」
いつの間にか馬上の人となっている孫尚香の姿に驚いて、甲斐姫が声をかけると、孫尚香は面に少し笑みを浮かべながら答えた。
「近くの農家に貸してもらったの! ほかにも何頭かいたから借りてきた!」
そうなんだ、と、答える甲斐姫に、孫尚香は馬から降りずに言葉を続けた。
「甲斐!! 私はこの馬で一足先に玄徳様のお城に行くわ!! この事態は、もう援軍を呼んできた方がいいと思うの!!」
「そうね……! 確かに……」
そう言う甲斐姫の横で、シュバルツも頷く。
「じゃあ、行くわ!! 甲斐! みんなをお願いね!!」
「分かったわ! 任せて!」
甲斐姫が頷いたのを確認してから、孫尚香は馬首を返した。
「何人か、ついて来て!!」
その声に呼応するかのように、村人の中の青年たちが馬に飛び乗り、妖魔たちの中でも足の速い者たちが、その後に続いた。
「私たちも行きましょう! シュバルツさん!!」
孫尚香が走り去って行くのを見送りながら、甲斐姫もシュバルツに声をかける。
「しかし……!」
シュバルツの瞳が揺れる。「ハヤブサを置いて行く」と言う行為に、抵抗感を覚えるのだろう。
でも駄目なの。
私は貴方を、行かせはしない。
だって、ハヤブサさんは望んでいないから。
貴方が戦場(ここ)に留まり続ける事を――――
「行きましょう! 皆のために―――!」
真っ直ぐにシュバルツを見据える甲斐姫の瞳は、逸らされる事がない。対してシュバルツの瞳は、揺れ続けたままだ。
「お願い! シュバルツさん!!」
甲斐姫は、言い方を変えて懇願する。
「私1人じゃ、これだけの人たちを守りきれない!!」
「…………!」
甲斐姫の言葉に、シュバルツは言い返す言葉を失う。ただ茫然と立ちすくむシュバルツに、声をかけてくる者が居た。
「シュバルツさん……」
その声にシュバルツが振り返ると、ケイタが心配そうな眼差しでこちらを見つめていた。
「ケイタ……」
ケイタ以外の村人たちも、同様にシュバルツを案じるように見つめている。
「あ…………!」
(生きろ、シュバルツ)
不意にシュバルツの脳裏に、ハヤブサの声が響く。
(皆のために……生きてくれ)
(ハヤブサ………!)
シュバルツも、今はハヤブサの救援には行けないのだと、悟らざるを得なかった。
信じるしかない。
ハヤブサの強さを。その力を。
大丈夫だ。
ハヤブサは、そう簡単にやられる奴じゃない。
待っていてくれ。
必ず――――お前を助けに戻るから。
「分かった……行こう」
シュバルツが下した決断に、甲斐姫をはじめとした皆の顔に、ほっとした笑みが浮かぶ。
「では、我々もなるべく急ごう。一刻も早く、劉備様の城へ、向かうのじゃ」
長老の言葉に皆が頷き、村人たちは再び移動を開始したのだった。
シュバルツから首尾よく離れる事が出来た龍の忍者は、妖魔の軍深くに斬り込んで行った。何せ、退路の事は考えなくていい。守るべきは、自分の体一つだけでいい。だから、酷く気楽な戦いだった。孤独な道行きでもあるが、悲嘆する事は何も無かった。何故なら、自分はいつもこうやって、『独り』で戦ってきたのだから。
後は『素戔鳴』を。
あの横暴な軍神を、待ち受けるだけだった。
「こいつ! 橋を落としやがったな!?」
「無意味な事を――――!」
「わざわざ、死にに来た様なものだ!!」
周りの妖魔たちから、罵声を浴びる。
(何とでも言え)
ハヤブサは思う。
あの橋を落とした所で、追手の足を止められるとは思っていないし、戦略的に重要な場所でも何でもない事は百も承知だ。
ただ自分は、シュバルツを遠ざけられれば良かった。
シュバルツがこちらに来る事を、一瞬でも困難な状況にする事が出来さえすればよかったのだ。
シュバルツを、素戔鳴と戦わせずに済むのならば俺は――――何だってやる。
「叭(ハ)―――――――ッ!!」
ハヤブサが裂帛の気合を乗せて龍剣を振るうたび、妖魔の首が飛び、屍が築き上げられていく。
「な……なんて奴だ……!」
自分達の軍の中をまるで無人の野を行くが如く走り抜ける龍の忍者に、周りの妖魔たちは、次第に及び腰になって行く。そんな中、ハヤブサもまた無軌道にその中を走り回っているのではなかった。彼は、『ある者』をひたすら探し続けていたのだ。
そしてついに――――それを、見つけた。
妖魔軍を指揮していた百々目(どどめ)鬼(き)は、いきなり黒い風に急襲された。
「むぅッ!?」
咄嗟に長い腕と籠手で対応をする。それでも襲って来た衝撃は重く、強烈な物だった。ギャリイッ!! と、派手な音を立てて青白い火花が散り、受けた百々目鬼は数十センチ、後ろに下がる事を余儀なくされる。
「―――百々目鬼! また貴様か!」
「むっ! 貴様は――――黒の忍者!」
ガンッ!! と、金属音が響いて、黒い影が二つに分かれる。
そう、ハヤブサは妖魔軍を指揮している者を探していた。指揮している者を倒しさえすれば、後の妖魔軍団は烏合の衆と化す。そうなれば、民を守りながら戦わねばならないシュバルツ達でも、十分対応できる筈だった。
「貴様……! よく、我の邪魔をしに来るな……!」
長い腕を構え、ハヤブサを牽制しながら百々目鬼が怒気を顕わにする。
「…………」
対してハヤブサは、無言で龍剣を正眼に構えながら、ジリッジリッと間合いを詰めた。この百々目鬼と言う妖魔は、遠呂智軍の中でも好戦的な部類に入る妖魔で、最初に遠呂智が討伐された後も、単独で人間と敵対し、よく襲いかかっていた。この妖蛇が復活してからの歴史の流れの中でも、遠呂智軍の中枢に位置している平清盛の配下となり、たびたび討伐軍に襲いかかってそれを苦しめている。故に、百々目鬼とハヤブサは、よく戦場で顔を合わせる、変な顔なじみにもなっていた。
「『仙桃』を作る村人たちを逃がしたのは貴様だな? 一体奴らを何処へやった?」
「………答える義理は無い」
百々目鬼からの問いかけを、一刀両断に斬って捨てる。ハヤブサから明確な答えが返って来る事を百々目鬼の方も期待していなかったのか、フン、と、一つ息を吐いた。
「……まあ良い。人間などいなくとも、『仙桃』は我ら妖魔が頂く。我等妖魔が育てた方が、『仙桃』も、喜ぶ事だろう」
「―――――!」
ピクリ、と、ハヤブサの眉が釣り上がる。
(『人間など皆殺しだ!』と、言いながら、妖魔たちが村を襲ってきた原因は、これか………!)
「隙あり!!」
叫びながらハヤブサに襲いかかって来た妖魔を、振り返りもせずに無言で斬り下げる。ドオッ! と、音を立てて妖魔が倒れると同時に、ハヤブサの身体から凄まじい殺気が放たれた。
「………いささか、人間を軽んじすぎてはいないか……?」
龍剣から血を滴らせながら、再び百々目鬼との間合いを詰める龍の忍者。しかし、百々目鬼の方も負けてはいなかった。
「フン………草木の声も聞けぬ人間に、何程の事が出来ると言うのか―――!」
「…………!」
二人の将同士のぶつかり合いに、周囲の妖魔たちは皆気圧されて、少し距離を開けて固唾をのんで見守っていた。二人の間に殺気は満ち、このまま大将戦に突入するかと、思われた、まさにその時。
ドン! ドン! と、地鳴りのように戦場に響き渡る、統一された足音。
「ムッ!」
「――――!」
声高く響き渡る、仙界の戦士たちの歌声。
(来た………!)
その声と足音を聞きながらハヤブサは思った。
この歌声と足音は、素戔鳴が戦場に入る前に必ず行う『儀式』――――言わば、神からの『警告』だった。この歌と音を聞いて、我の力を知る者は、戦場から消えよ。さもなくば、容赦はしない――――これは、そう告げているのだ。不遜な神から与えられる、最後の『慈悲』と言うふうに、取れなくも無かった。
「こ、これは……まずいぞ……?」
「素戔鳴だ………!」
素戔鳴の力を知る妖魔たちが、早くも浮足立ち始めている。素戔鳴軍の声と足音は、絶大な効果を伴って戦場を席巻していた。
「告!!」
白藍色の衣装をまとい、足をふみならして歌う兵士たちの前に立つ、黒色の肌に金色の炎の刺青をまとった仁王が、拳を振り上げ高々と告げる。
「吾、これより戦闘に入る!! 罪を犯した人の子には裁きを!! 妖魔どもは殲滅すべし!!」
ドオオオオッ!! と、仙界軍の兵士たちの間から、高らかな鬨の声が上がる。
「行けい!!」
素戔鳴が抜刀した剣を振ると同時に、仙界軍の兵士たちが、一斉に戦場へと突撃を開始した。
「――――チッ!」
素戔鳴軍の突撃を知った百々目鬼が、小さく舌打ちをする。
「おい! 黒の忍者!」
「……………」
百々目鬼の呼び掛けに、ハヤブサは少し刀を下ろすことで応えた。
「一時休戦と行こうじゃないか……この戦場、長居は無用!」
「――――まだ人間を、追うか?」
ハヤブサの問いに、百々目鬼は頭をふった。
「今は、素戔鳴から逃げるのが先決――――」
それだけ言うと、百々目鬼は武器を収めて身を翻し、ハヤブサの前から走り去って行った。大将が逃げ出した妖魔軍団は、たちまちのうちに統制を失ってしまう。
「う、うわ……! 逃げろ!!」
「でも……どっちへ逃げれば良いんだ!?」
「……………」
迫りくる仙界軍の鬨の声に、混乱をきたす妖魔軍の中で、ハヤブサは1人、沈黙の中に居た。
ここだ。
ここからが勝負だ。
自分は何処まで、素戔鳴を足止め出来るか――――
「……………?」
ふと気がつくと、自分の背後に――――と言うよりも、自分の背後を守るように立って構える、妖魔の一団が居た。
「なっ!? お前たち――――!」
驚いて振り向くハヤブサに、妖魔の1人が『笑って』答える。どうやら、村を手伝いに来ていた妖魔たちらしかった。
「お前たち……! ずっと、共に戦っていたのか……?」
ハヤブサは、少なからず動揺してしまう。
ずっと自分は――――『独りで』戦っていたのだと、思っていたのに。
妖魔の1人が頭をかきながら口を開いた。
「戦っていたと言うか、逃げ損ねたと言うか……」
「いやあ、強いなぁ。あんた」
「邪魔にならないように、後ろからついて来たようなもんだ」
「……………!」
妖魔たちの言葉に、ハヤブサは言葉を失う。まさか自分は、『味方』である妖魔も斬り捨ててしまってはいないだろうか――――
ブン! と、ハヤブサは頭を振る。
迷うな。
恐れるな。
自分の刀が、自分の手が
『命を奪う』行為をすることを。
汚れるのは――――百も承知。
ただ己は、為すべき事を、為すだけだ。
ハヤブサは、フッと、一つ小さく息を吐くと、口を開いた。
「……お前たちに、改めて忠告しておく。これ以上、ここに留まろうとするな」
「へっ? 何でだ?」
きょとん、とする妖魔たちを、ちらり、と一瞥すると、龍の忍者は口を開いた。
「これより先は、戦う相手は妖魔たちではない。神仙界の者になる」
妖魔たちの間に紛れている間は、同士討ちを恐れる事も手伝って、乱戦の中、何となくやり過ごす事も出来ただろう。だが、今から戦う仙界軍と妖魔の者たちは、その外見が違いすぎる。そして、仙界軍の者たちは『妖魔』と見るや、真っ先に殲滅対象とみなして攻撃してくるだろう。
それにしても、この妖魔たちは知らないのだろうか? これから突入してくる素戔鳴の強さを。知っていれば、普通は逃げだす事を選択するだろうに。
「……だから、早く逃げた方がいい。それに俺は、自分の戦いで忙しい。お前たちの身を守るという事は、一切しないぞ――――」
「……………」
ハヤブサの言葉に、妖魔たちは沈黙を返してくる。ハヤブサはもう一度妖魔たちをちらり、と見ると、少しばつが悪そうに言葉を紡いだ。
「ただ……その……退路となるべき橋を落としてしまったのは、悪かったが……」
「……………」
ハヤブサの言葉に、しばらく沈黙をしていた妖魔たちであったが、その中の1人が、ため息を付きながら頷いた。
「分かりました……ハヤブサさん……」
「お、おい……!」
1人の妖魔の言葉に、もう一人の妖魔から、少し抗議めいた声が上がる。だが、頷いた妖魔は、抗議の声を上げた妖魔をなだめるように、声をかけた。
「行こう。この方の戦いの、邪魔をしちゃいかん」
「あ…………」
「わ……分かった……」
彼らはようやく納得したのか、とぼとぼとした足取りで、ハヤブサの傍から離れて行った。その後ろ姿があまりにもさびしそうなので、ハヤブサは、思わず声をかけてしまう。
「首尾よく川を渡ってくれよ! 幸運を祈る!」
その言葉に、妖魔たちは手を上げて答える。そして彼らは、背後の森へと消えて行った。
(………礼を言うのを、忘れてしまっていたな……)
1人そこに残ったハヤブサは、ふとそう思った。もしかしたら自分でも気づかないうちに、何度も彼らに助けられていたのかもしれないのに。
シュバルツ――――あいつならば、同じような立場に立たされた時、真っ先に礼の言葉が出てくるのだろう。何の臆面もなく――――
――――ありがとう……。
そう言って、綺麗に微笑むシュバルツの姿を、簡単に思い浮かべる事が出来る。それほどまでに、ハヤブサにとってその光景は、見慣れた物となっていた。
(やはりこういうのは、日頃からちゃんと言っていないと咄嗟の時に出て来ないものだな……。気をつけねばいかんと思うのだが……)
コミュニケーションの取り方が酷く不器用な自分を感じてしまって、ハヤブサは少し頭をかく。こういう時に、素直に感謝の言葉を伝える事が出来るシュバルツが、少し羨ましかった。
得難いヒト。
愛おしいヒト。
だから、ちゃんと守りたいと――――願う。
(シュバルツ……逃げ切れよ)
大切なヒトを胸に思い描きながら、ハヤブサは静かに刀を構えなおして、仙界軍を待ち受けていた。
「急いで!! もっと急いで!!」
馬上の人となった孫尚香は、可能な限り馬に拍車をかけ続けていた。
「尚香さん!! 無茶だ!! これ以上飛ばしたら、馬が潰れちまう!!」
疾走する孫尚香を同じように馬で追いかける青年が、馬上で悲鳴のような声を上げる。
「ごめんなさい!! でも、みんなの命がかかっているのよ!!」
孫尚香は祈る様に叫んでいた。
「一刻も早く援軍を頼まないと、皆、死んでしまうわ!! だから、城まで保てばいい!!」
そう。一人素戔鳴の前に残ったハヤブサを救うためにも、今逃げている村人たちを無事に逃がすためにも――――絶対に援軍は必要不可欠だ。自分達だけで対処しようとしては、絶対に駄目だと孫尚香は強く感じていた。悔しいけれど――――自分達だけでは、今の事態を打開するには力不足なのだ。
(一番いいのは、あの城に玄徳様が居て、関羽さんや張飛さん、趙雲さんの援軍を頼めることなんだけど……)
玄徳の配下である五虎将の力は強力だ。その力を借りる事が出来れば、村人たちを救出する事も、素戔鳴と戦っているハヤブサを救出する事も、おそらく可能になるだろう。
(だけど……もしも――――)
馬を走らせながらふと思った。確かに、今向かっている城は、『玄徳の領地にある城』だ。だが果たして、その城に彼は今居るのだろうか? 居るのと居ないのでは――――その後の展開が、大分違って来てしまう様な気がする。
(それでも……!)
孫尚香は顔を上げた。
例え一軍でも、一部隊でも良い。その力を借りる事が出来れば、助けられる人数も増えてくるはず――――そう信じて、孫尚香は馬を走らせ続けた。
「城が見えたわ!! もう少し!!」
疾走する孫尚香の眼前に、目指す城の城壁が徐々に近づきつつあった。
素戔鳴の襲来は、逃げる村人たちの状況の方にも、変化をもたらしていた。
素戔鳴軍の猛攻に曝され、逃げ惑いながら川を次々と泳いで渡ってくる妖魔たち。その妖魔の群れが、逃げる村人たちに追いついて来たのだ。「助けてくれ!!」と叫び、命乞いをする者。村人たちが、武器も持たず抵抗する術がない者たちだと知ると、武器を振りかざして襲いかかって来る者。「人間は死ね!!」と、最初から敵意をむき出しにしてくる者――――それらの者に対抗するべく、共に逃げていた妖魔たちが戦いに加わりだしたものだから、村人たちの周りは、混乱を極めていた。
流れ矢に当たって命を落とす者。妖魔に襲われて絶命する者が続出する。それはいくらシュバルツや甲斐姫が奮戦したと言っても、防ぎきれるものではなかった。
それでも『逃げ方』を知っているシュバルツは、懸命に防戦する。
ドカン!!
戦う妖魔たちの間に仕掛けていたクナイの導火線から火薬に引火し、辺り一帯に派手な炸裂音と煙が充満する。
「な、何だぁ!?」
「うわっ!!」
妖魔たちが混乱している間に、シュバルツと甲斐姫は、生き残った村人たちを混乱の渦から救い出す事に、何とか成功していた。
「大分……人数が減ってしまったわね……」
助けられた村人たちを見渡しながら、甲斐姫はポツリと零した。
まだ上がる息を何とか整えようと試みながら、彼女はほぞを噛んでいた。
悔しい。
どうしてこうも私は――――無力なんだろう。
「……………」
シュバルツはそんな甲斐姫や村人たちから少し離れた所で、じっと茂みの外の様子を伺う様に立てっていたが、何かの気配を感じたのか、いきなり刀を逆手に構えて飛び出した。
シュウ、と音を立てて、シュバルツの鋭い一閃が茂みに近づいて来た妖魔の喉元に迫る。
「う、うわっ!! 待って下せぇ!!」
刀を突き付けられた妖魔から悲鳴が上がる。
「――――!」
妖魔の喉を掻き斬ろうとした、シュバルツの刀が寸前の所で止まった。その妖魔は、子供を抱きかかえていた。
「シュバルツさん!!」
「ケイタ!?」
抱きかかえられていた子供は、ケイタだった。ケイタは妖魔の腕から下ろされると、嬉しそうにシュバルツに駆け寄って、飛び付いた。
「―――――ッ!」
だが、ケイタに飛び付かれたシュバルツから、小さな呻き声が上がる。驚いたケイタが顔を上げると、シュバルツの左腕に大きな傷があり、腕が今にも千切れそうになっていた。
「シュバルツさん……! 怪我を――――!」
「大、丈夫だ……。 すぐ……治る、から……」
「あ………!」
嘘だ――――! と、言いかけたケイタは、はっと止まる。そう言えばこのヒトは『前の歴史』の時も「傷はすぐ治る」と、言っていた事を思い出したからだ。「本当に?」と、問うと、目の前の優しいヒトは、「ああ」と、頷いた。
「この傷は……すぐに治る……。ケイタ、私はお前に、絶対に『嘘』は付かないよ」
そして、前の歴史と同じ事を――――また、言われた。
「で、でも……!」
しかし、ケイタはその傷の大きさに戸惑う。こんなに大きな傷が「すぐに治る」だなんて、いくらなんでも俄かには信じ難かったからだ。
「えっ? シュバルツさんが怪我をしているだか!?」
ケイタとシュバルツの会話を聞きつけた村人から、驚いた様な声が上がる。
「えっ? シュバルツさんが!?」
「怪我を?」
「神様が!?」
その声が村人たちの間にまたたく間に伝わって、村人たちがパニックを起こしそうになる。
(まずい――――!)
その様子を見ていた甲斐姫の身体が、考えるよりも先に動いていた。
「大丈夫よ!! みんな!!」
シュバルツの腕の傷を村人たちから隠すように、その間に彼女は飛び込んで行く。
「この人の傷は、すぐに治るんだから……! ちょっと待っててね!」
そう言いながら彼女はシュバルツの方に向き直ると、懐から素早く白い布を取り出した。
「ちょっと痛むけど、我慢して」
彼女は小声でシュバルツにそう言うと、手近にあった木の枝を拾い、シュバルツの千切れかけた腕を強引にくっ付けた。
「――――ッ!」
シュバルツの小さな呻き声を小耳に捉えながら、くっつけた場所に添え木をして、慣れた手つきで白い布を腕に巻きつけていく。
「……手慣れているな」
シュバルツのその言葉に、甲斐姫は顔もあげずに手当てを続けながら答えた。
「戦の時、家臣や兵士たちが、みんなこうやってよく怪我をするから――――でも、簡単な、治療もどきみたいなものよ。後で、ちゃんとした薬師(くすし)に、診てもらわないと――――」
そう言っている間にも、甲斐姫はシュバルツの腕に、白い布を巻き終えていた。
「ほら、出来た! これでもう、この人は大丈夫よ!」
そう言って、笑顔を作って村人たちの方に向き直る。
だが実際は、シュバルツの傷は深刻な物だと甲斐姫は分かっていた。最悪の場合、腕を切断しなければならなくなるかもしれない。
しかし村人たちは、しばらくあんぐりとシュバルツの方を眺めていたが、やがて皆が、その面に笑顔を浮かべ始めた。
「ほんに、その方の言う通りじゃ」
「シュバルツ様は――――大丈夫そうじゃな」
「いやよかった。目出たい事じゃ」
(えっ………!?)
村人の言葉に違和感を感じた甲斐姫は、思わずシュバルツの方に振り返っていた。そして、声も出せないほどに驚いてしまう。何故なら――――くっつけた方のシュバルツの手の指が、ひらひらとちゃんと動いていたからだ。
(えっ!? ちょっと……何!? おかしいでしょこれ――――!)
あれだけ腕が千切れかかっていたのだ。何もかも切断されているはずなのだから、あんな応急手当てをしただけで、手の指までもが動く筈がない。そう感じてパニックになりかかる甲斐姫に向かってシュバルツはにっこりと微笑みかけると、口を開いた。
「ありがとう。すっかり良くなった。君のおかげだ」
「え……? いや、あの……!」
ちょっと待って、何かがおかしい――――と、甲斐姫は口を開きたかったが、シュバルツの方がその間を与えてくれなかった。
「さあ! 申し訳ないが、少しずつでも移動しよう。追手に追いつかれないうちに――――」
シュバルツの言葉に村人たちはみな頷いて、また、移動を始めた。
しかし、納得いかないのは甲斐姫である。
あれだけの大怪我をしたと言うのに、あの回復具合――――やはり、どう考えてもおかしい。それに、その事実を村人がすんなり受け入れているのも、何か違和感を拭えない。
その疑念を晴らしたくて、甲斐姫は近くを歩く村人に、そっと声をかけていた。
「ねぇ、ちょっと」
「何だべ?」
振り返った、人の良さそうな青年に、甲斐姫は思いきって聞いてみる。
「さっきのシュバルツさんの怪我の治り方……何か『変だな』って、感じないの?」
「ああ……」
青年は、少し考えるように天を見上げると、やがて、何でもない事のように口を開いた。
「別におかしい事は無いべ? だってあの方は、神様だからなぁ」
「――――!?」
ギョッと固まる甲斐姫に、周りの村人たちが次々と口を開く。
「んだんだ。あの方は神様だ」
「神様だなぁ」
「神様が、我々を守ってくださる。ありがたい事じゃ」
「――――――」
ケイタから話は聞いていたが、村人たちのあまりにも朴訥すぎる信仰心に、甲斐姫は眩暈を覚える。しかし、ああも簡単に目の前で奇跡のような事柄を起こされてしまっては、うっかり「神様」と信じ込んでしまいたくなる気持ちも、分からないでもなかった。
このままでは埒が明かないと感じた甲斐姫は、シュバルツに直接確かめる事にした。
「ねえ、ちょっと」
シュバルツの傍まで近づいて行って、そっと小声で呼び掛けてみる。
「何だ?」
甲斐姫は、しばらく何かを躊躇う様に逡巡していたが、やがて思い切ったように顔を上げた。
「貴方は一体、何者なの?」
「――――!」
ストレートに、この質問をシュバルツにぶつけた。少し驚いたようにこちらを振り返るシュバルツに、しかし甲斐姫の視線が逸らされる事は無い。
「腕が千切れかかるほどの大怪我をしていて――――それが、応急手当てをしただけで、あんなに指までもが動くほど、治る筈がない」
「……だからそれは、君の力で――――」
「ごまかさないで」
素っとぼけようとしたシュバルツに対して、甲斐姫はズバッと斬り込んだ。
「本当に――――貴方は『何者』なの?」
「……………」
シュバルツはしばらく推し量る様に甲斐姫を見つめていたが、それでも彼女の視線が逸らされる事は無い。シュバルツは、少し何かをあきらめたようにため息をつくと、やがて口を開いた。
「……そうだな。確かに私は――――人間ではない」
「――――!」
驚き、息を飲む甲斐姫に向かって、シュバルツはにっこりと微笑みかける。
「こう言えば……満足か?」
「…………!」
ピシャリ、と、何故か冷水を浴びたような気持ちになる。笑顔のシュバルツからは、明らかな拒絶の意志を感じたからだ。
「ご、ごめんなさい! そんなつもり――――」
「そんなつもりじゃなかった」と、甲斐姫は言いかけて止めた。そんなつもりじゃないと言うのなら、どう言うつもりでそんな事を言ったのだ。全くの詭弁だ。下種の勘繰りに近い形で、シュバルツの領域にうっかり踏み込んでしまったのだと悟って後悔してしまう。
(駄目だな……どうして私ってこう……)
軽く自己嫌悪に陥ってしまってほぞをかんだ。だが、よくよく考えてみると、彼が死ぬ時に、およそ人間らしからぬ死に方をしていた事を思い出す。あんな、身体がばらばらに砕け散る様に亡くなってしまうなんて――――どう考えたって、普通じゃない。
彼が人間じゃない。普通じゃないと言うのはよく分かった。
でも――――ならば本当に、あの人は『何者』だと言うのだろう?
あんな『奇跡』を軽々と起こしておいて、それでも神じゃないとなると――――
甲斐姫は再び思考を巡らせようとして、いきなりそれを中断させられてしまった。
先を歩くシュバルツが、手で「止まれ」と合図を送ってきたからだ。
「………!」
はっと、気がついた甲斐姫は、村人たちに音をたてないようにと合図を送ってその場に制止させると、自分も得物を構えて、油断なく辺りを見回した。そうだ。今は自己嫌悪に陥って居ようが何をしようが―――――村人たちの安全を確保するのが、自分の役目なのだと自覚する。身構える甲斐姫の視線の先で、シュバルツが刀の柄に手をかけながら、茂みの間から窺うように前方を覗いていた。
「……………」
しばらくの沈黙の後に、こちらに振り返ったシュバルツの面に、フッと優しい笑みが浮かぶ。
「驚かせて悪かったな……。大丈夫だ」
そう言いながら、ガサッ、と、わざと少し大きな物音をさせて、シュバルツはその先に踏み込む。その音に気が付いた『妖魔』たちと『人間』たちが、一斉に振り返った。
「あ……! あんたは……!」
「シュバルツさん!!」
シュバルツの姿を見た『村人』たちが、嬉しそうに駆け寄って来る。そこには、先程の混乱から逃げ延びた、また別の村人たちと妖魔たちが集まっていたのだ。
「おとう!! おかあ!!」
村人たちの間に、自分の両親の姿を見つけたケイタは、嬉しそうに駆け寄る。ケイタ達のほかにも、互いの無事を確認し合って喜ぶ、村人たちの輪ができていた。
「良かった……。貴方がたが助けてくれたのか?」
村人たちの輪を、少し離れた所から見守っている妖魔たちに、シュバルツがそう声をかける。声をかけられた妖魔は、少し照れたようにグシャッと頭をかいた。
「いやぁ、あんたが逃げるための隙を作ってくれたおかげだよ」
「それに、村人たちも俺達を信じてくれたから――――すんなり助け出す事が出来たんだ」
「そうか………」
そう言って笑みを浮かべるシュバルツの目の前で、喜びの涙にくれる村人たち。しかし、助かった村人たちの中には、自分の求める者の姿がなくて、がっくりと肩を落とす村人も居た。悲喜こもごもだった。
それでもやはり――――この邂逅は、逃避行の中にあって、ちょっとした慶事には違いなかった。
「では行こう。追手に追いつかれないうちに」
シュバルツの提案に皆が頷く。こうして、少し人数の増えたその集団は、再び城を目指して移動を開始していた。
仙界軍と妖魔たちの戦いの合間を縫うように、龍の忍者は疾走していた。自分が求める者は――――ただ一つだ。
(居た……!)
紫黒(しこく)の肌に、金の刺青。月白(げっぱく)色の怒髪天に、炎の光背、金色の瞳――――戦場で邂逅するには、最も危険な存在。本来ならばその姿を見たら、直接剣を交える事は、断固として避けなければならない所だ。
だが。
だが今は――――
(シュバルツ………)
ハヤブサは、瞳を閉じて、愛おしいヒトに想いを馳せる。
笑った顔、怒った顔、潤んだ瞳、濡れた唇、艶めいた肢体――――
(愛している……)
確かに俺にそう言った、お前の言葉。
(シュバルツ……俺も――――)
愛 シ テ ル
想いをこめて、刀の柄に巻きつけてあるロングコートの切れ端に、そっと唇を落とす。
ああ。
このまま、お前を守って死ねるのならば俺は―――――
本望だ。
戦場を見渡しながら、素戔鳴は少しざわついた気持ちになるのを押さえられなかった。
気に入らない。
とにかく――――気に入らない。
人と妖魔に『裁き』を下すべくあの村に向かえば、既にもぬけの空であった。まるで――――こちらの襲撃を、予測していたが如くに。
(どう言う事だ? 吾がこの村を襲う事、誰に話したと言う訳でもない。部下たちが、あらかじめその情報を、村の者たちに渡すとも考えられない――――)
にもかかわらず、村人たちは村から逃げ出していた。村に、人の死体も妖魔の死体も、田畑も踏み荒らされたような跡も無かったから、おそらく妖魔から襲撃される前に。何故村人たちは、これらの襲撃を察知する事が出来たのだろう?
何か、自身の中で割り切れないものを感じる事態に、素戔鳴はざわつく様な苛立ちを押さえる事が出来ない。その原因を特定するためにも、逃げ出した村人たちに、早く追いつかねばならぬと思っていた。行く道すがら、村人たちの物と思われる荷物や、時に死体が点在しているから、逃げた方角は、おそらくこちらで間違いないのであろう。
「さっさとこ奴らを蹴散らして、村人たちを追うぞ!! 皆!! 我に――――!!」
続け、と、言いかけた素戔鳴が、不意に、自分に向かって矢の様に迫ってくる鋭い殺気を捉える。抜き身のまま下げていた天叢雲(あまのむらくも)の剣を、咄嗟に殺気に向かって薙ぎ払う様に振り抜いていた。
ギャリィッ!!
派手な金属音と共に、自分のたちが『受け止められた』感触を得る。
「――――!?」
「チッ!!」
舌打ちをしたのはハヤブサである。この奇襲で、あわよくば一太刀でも素戔鳴の身体に浴びせたいと思っていた。それが――――かわされてしまったのだから。
「吩!!」
素戔鳴は、力を更に込めて、強引に剣を振り抜く。自分の刀を受け止めていた黒い影を、弾き飛ばす事に成功した。
「く…………!」
剣圧すらもが刃となって襲い来るのを、ハヤブサは懸命に防ぐ。身体をくるりと回転させて、素戔鳴から少し離れた地面に、ハヤブサは着地した。
「――――ムッ! 汝(なれ)は……人間か?」
ハヤブサの姿を認めた素戔鳴が、少し意外そうに口を開く。だがその問いかけに、龍の忍者は答えない。ただ全身に殺気をまとわりつかせて、戦闘意思を顕わにした。とにかく素戔鳴を、自分に引きつけねばならぬ、と、思ったから。
(何と、猛々しい『気』を纏いつかせた者よ……)
素戔鳴は、目の前の黒の『忍者』と思われる人物から放たれる殺気の鋭さに、少し目を細める。『軍神』としての、血が騒いだ。
だが、相手が『人間』なればこそ、確かめねばならぬ事がある。
「汝が『人間』であれば問う――――。あの村の人間を、逃がすよう手引きしたのは、貴様か?」
「……………」
その質問に、ハヤブサは沈黙を以って答える。否定とも肯定とも取れる仕種だが、素戔鳴はそれを、『肯定』したものとして、と捉えた。
「手引きした者ならば………あの村の人間が、『何』をしたのか、其れを承知でやったのであろうな――――」
「……………」
その問いにも答えず、チャッ、と、音を立てて、ハヤブサは龍剣を構えなおす。
ああ、そうとも。
百も承知で、俺はそれをした。
だから――――何だと言うのだ。
「………なるほど。汝も『裁き』を所望か……」
この不遜とも言える挑戦者に、素戔鳴は己が頬が引きつるのを感じる。
(だが、相手はたかが人間)
傲慢な神は、口の端だけを持ち上げて笑う。
どうせ勝負は、一瞬で付く。
この身の程知らずの挑戦者に――――『神』の力、思い知らせてくれる!
そう決意した素戔鳴が、天叢雲の剣を持ち上げるよりも早く、ハヤブサが動いた。
「叭――――――ッ!!」
身を低くして、地を這うような姿勢から、逆袈裟掛けに龍剣を迸らせる。
「――――ムッ!」
その攻撃に、一瞬身を引くのが遅れた素戔鳴。チッ、と、音を立てて、龍剣の刃先が素戔鳴の頬を掠め、その肉を斬り裂いた。
(入った!)
だが浅い。もう一撃、と、ハヤブサが更に踏み込もうとした瞬間。
「おのれ!!」
素戔鳴の怒声と共に、天叢雲から迸った光が、雷撃となってハヤブサを襲う。
「ぐあっ!!」
雷で撃たれたような衝撃を全身に浴び、ハヤブサの意識が一瞬飛んでしまう。そこにさらに追い打ちの雷(いかずち)が飛んで来て、ハヤブサの身体は後方へと吹っ飛ばされてしまった。
「滅!!」
逃すものかと言わんばかりに、さらに素戔鳴が召喚した風雨が、刃の様な力を伴ってハヤブサに襲いかかる。
「ぐッ……!」
身体を樹に叩きつけられ、避けようのないままに素戔鳴の風雨に晒されるハヤブサ。やはり一気に、体力の半分以上を持っていかれてしまった。
本来ならば、ここで素戔鳴から距離を取って体勢を立て直し、味方の援軍を得てから戦うのがベストの方法だ。だが――――今はその選択肢を取る訳にはいかない。ここで味方の援軍を望んでいたら、『シュバルツ』が確実に来てしまう。その事態だけは、絶対に避けねばならない。避けるために――――俺はここに居るのだから。
逃げるな。
倒れるな。
素戔鳴を、引き留め続けろ。
俺の命ある限り――――
「……………」
ハヤブサは、多少ふらつきながらも立ち上がると、懐からある物を取り出した。そしてそれを、素戔鳴にわざと見せつけるかのように、ゆっくりと、自分の前面へと持ってくる。
「な―――――!」
その『物』の正体に気がついた素戔鳴は、思わず絶句してしまっていた。何故ならそれは――――村に生えていた『仙桃』であったのだから。
ハヤブサは、顔を覆っている覆面を取ると、敢えて笑みを浮かべながら、その仙桃にかぶりついた。そのままむしゃむしゃと、食べ始める。
「な……! な………!」
素戔鳴が息を飲み、震えている気配を感じ取りながら、龍の忍者は手の中の仙桃を平らげた。べろり、と口の周りに付いた仙桃の汁を舌で舐めとりながら、ハヤブサは素戔鳴に対して、ここで初めて口を開いた。
「……甘い。なるほど、良い桃だな。これは……」
「―――――ッ!」
「身体の傷も治って来ている……。なるほど。これが『薬効』の成分の効果か……」
身体の傷が治る感覚を得ながら、ハヤブサは少し、愛おしいヒトの気持ちを理解する。『怪我をしても治ってしまう』――――なるほど、これなら確かに、無茶の一つもしてしまいたくもなるというものだ。
「………貴様、何もかもを本当に理解して、それでも敢えて村人を逃がした、と、言う訳だな……!?」
素戔鳴の問いかけに、ハヤブサは口の端を吊り上げた笑みで答える。
「如何にも」
「………そうか……」
この目の前の人間の傲岸とも言える態度に、素戔鳴はかつてない程の腹立たしさを覚える。怒りで身体が震えるなど、久しぶりに味わう感覚だった。
決めた。
この人間だけは―――――
骨も残らぬほどに、粉砕してやる……!
「吾を怒らせたこと――――後悔させてくれる!!」
素戔鳴の荒々しい闘気が、爆発的に膨れ上がる。だが、龍の忍者も負けていなかった。ハヤブサの身体からも――――龍の燐気が溢れだしてくる。
何度も同じ攻撃が俺に通用するかどうか――――やってみれば良い。
見ろ。
見ろ。
素戔鳴の攻撃の合間にも、必ず隙がある筈なのだから。
耳が痛くなるほどの闘気が充満する中、素戔鳴とハヤブサは、再びぶつかり合おうとしていた。
「開門!! 開門!!」
城の門の近くまで馬を走らせてきた孫尚香は、城壁に向かって大声を上げた。その声を聞きつけた兵士が、城壁の上から顔を出す。
「何者か!?」
「劉皇叔が妻、孫尚香!!」
問いかけてきた兵士に、孫尚香は大音声で答えを返す。
「お願い!! 門を開けて!! 私は援軍を頼みに来たの!!」
「援軍?」
「この先に――――助けを待っている人たちが居るのよ!!」
兵士はしばらく孫尚香の顔を黙って見つめていたが、やがて、「報告してくる。しばし待て――――」と、言い置いて、城内へと姿を消した。
「……………」
(お願い……! 早く……!)
焦れるような想いで、馬上で待つ孫尚香。やがて城壁に、ある人物が姿を現した。
「――――関羽将軍!!」
その人物の姿を認めた孫尚香が声を上げる。身の丈9尺、流れるような豊かな髯を湛える偉丈夫は、時の帝に『美髯公』と称された。劉備と義理の兄弟の杯を交わしている、とても劉備と近しい存在の者であった。そして彼は、蜀の五虎大将の筆頭にも挙げられている。
関羽は、城壁の上から馬上の孫尚香に鋭い視線を走らせると、声をかけてきた。
「尚香殿……。一体、何用ですかな?」
「援軍が欲しいのよ!!」
孫尚香は、関羽の問いかけに即答する。
「援軍?」
少し眉をひそめる関羽に、孫尚香は尚も声を上げた。
「この先に、助けを待っている人たちが居るの!! その人たちのために、門を開けて――――援軍を出して欲しいの!!」
「…………」
関羽は左手で、その豊かな髯をしごきながらしばらく推し量る様に孫尚香を見つめていたが、やがておもむろに口を開いた。
「尚香殿は――――」
「何?」
「何故今、ここに居られるのか?」
「えっ?」
関羽の問いかけの意味が分からず、思わず問い返してしまう孫尚香に、彼は更に問いかけてきた。
「奥方様は今――――玄徳の兄者の傍から離れて、孫呉の者たちと共に行動をされているはず」
「―――――!」
「それが何故今――――単独で、ここに来られたのか?」
「あ…………!」
孫尚香はここで、ようやく『時間軸を遡る事の危うさと不自然さ』に気づく。確かに、本来の時間の流れの歴史の中では、今この瞬間の自分は劉備の元を離れて、孫呉の皆と共に妖魔と戦って転戦していた。それがいきなり単独で、援軍を求めてここに現れるのは、いろいろと説明がつかないほど不自然すぎると悟ってしまった。
「ええと……その………」
そして悟ってしまったが故に、孫尚香は説明する言葉に困窮してしまう。あそこに居る関羽は、巫女かぐやと未だ出会っていない。故に、かぐやの『時間を遡れる能力』について説明をした所で――――おそらく分かってはもらえないだろう。
「……………」
返す言葉に窮してしまって、黙ってしまった孫尚香に、関羽は少し冷たい視線を浴びせる。
「……とにかく、事情がはっきりとせぬうちは、我が城からは援軍は出せぬ。お引き取り願いたい」
「…………! 待って!!」
そう言って、踵を返して城内に消えていこうとした関羽を、孫尚香はあわてて呼び止めた。今、この城の門が閉ざされるのは、絶対に困る。そうなってしまったら、この後此処に逃げ込んでくる村人たちも妖魔たちも、ハヤブサもシュバルツも――――誰ひとりとして救えなくなってしまうのだと悟ってしまう。悲劇を回避するためにも、今、自分が絶対にあきらめては駄目なのだと孫尚香は強く思った。
「関羽さん!! 話を聞いて!! 本当に、この先で困っている人たちが居るのよ!!」
「……………」
「お願い!! その人たちのためにも――――一部隊でもいい!! 門を開けて!! この城から援軍を出して!!」
「……………」
「父上」
場外の孫尚香からの必死の懇願に沈黙を返し続ける父の姿を見かねたのか、関羽の養子である関平が、関羽に声をかけてきた。この実直な息子は、遠呂智戦の混乱の後、しばらく織田信長の傍で仕えていたが―――今は所用でたまたま父親の居るこの城に帰ってきていた。
「仮にも殿の奥方に当たる人が、ああやって頼まれているのです。それを黙殺し続けるのは、良くないのではないのでしょうか?」
ある意味、至極まともな意見を述べてくる息子に、関羽は小さく息を吐くと、おもむろに口を開いた。
「関平。確かに、今場外で叫んでいるあの方は、兄者の奥方に見える。だが――――あの方は、本当に、『兄者の奥方』か?」
「えっ?」
父親の言った言葉の意味を咄嗟に計りかねて、きょとん、とする息子に、関羽は言い聞かせるように言葉を続けた。
「何者かが、奥方様の姿を模して――――我らの前に現れた可能性もある」
「ええっ!? まさか……!!」
驚愕の声を上げる息子を納得させるべく、関羽は逆に息子に問い返した。
「では何故――――孫呉の者たちと共におらねばならないはずの奥方が、今、我々の前に単独で現れるのだ? 我らが聞いている奥方の行動とは、話が合わなさすぎる。不自然すぎるのだ」
「…………!」
「それに………」
「それに? まだ何か、あるんですか?」
「あの尚香殿は……何故『妖魔』と、一緒に居るのだ?」
「――――!」
「我らが戦うべき相手である『妖魔』と共に居る者を――――どうやって信じればよいと言うのだ。最悪『妖魔』が尚香殿に変装して、この城を乗っ取ろうと策を仕掛けてきている可能性もあるのだ」
「そ、そんな……! しかし――――!」
関平は、父の言葉に戸惑いながらも、城外に居る孫尚香を改めて見つめる。彼女は縋るような眼差しで、懸命にこちらを見つめていた。
関平の目には、あの孫尚香が偽物だとは俄かに信じ難かった。しかし、ならばなぜ、彼女の後ろに妖魔たちが控えているのか。それを自身で納得させるだけの理由を、自分の中で見つける事も出来ない。それもまた、紛れもない事実だった。
「関羽将軍!! お願い!!」
城外の孫尚香は、尚も縋るように呼びかけてくる。
「援軍を……!! せめて、一部隊でもいいから――――!!」
「父上……!」
孫尚香の必死な様に、関平は父親を振り返る。
「父上……! やはり、援軍を出しましょう。あの様子では、本当に助けを求めている者が居るのかもしれません」
「ならん、関平」
「しかし……! 父上!」
「あの尚香殿が、妖魔の手先であれば、何とする?」
「………!」
「その者の言葉を信じて門を開けた結果――――この城を妖魔たちに奪われる事になったら、この城の中に居る領民たちはどうなる? 兄者からお預かりした、この城はどうなる?」
「そ、それは………!」
関平は関羽からの問いかけに、咄嗟に言葉を返す事が出来ない。
「とにかく、事の真意を見極めるまでは、我らは下手に動かぬ事――――これが、留守を預かる者の役目だ。良いな、関平」
「はい………」
父の言葉に強く否を唱えられず、頷くしか無い息子。それほどまでに、父の言っている言葉は、正論であったのだから。
(駄目だ……! 埒が明かない……!)
強くそう感じた孫尚香は、もう一度声を上げた。
「関羽将軍!! 劉備様は――――玄徳様は、何処!?」
こうなったら、玄徳と直接交渉した方が早い――――孫尚香は、そう判断した。
そう、あの人ならば、きっと、躊躇わない。
「助けを求める人が居る」と聞けば、何の躊躇も無しに、すっと、その手を差し伸べてくれるだろう。孫尚香には、それが分かった。分かっているから――――その姿を求めた。
「お願い!! 玄徳様に会わせて!!」
一縷の望みに縋る様に、彼女は声を上げる。だがそれは、次の瞬間無残に打ち砕かれる事となった。
「兄者は留守だ」
「な………! そんな――――!」
関羽の非情とも言える言葉に、孫尚香は、目の前が真っ暗になって行くのを感じていた。
「叭―――――――ッ!!」
乱戦の中、龍の忍者の『飯綱落し』がさく裂する。その技を喰らった仙界軍の兵士たちが、たまらず吹っ飛ばされて行った。
「おのれ!! ちょこまかと――――!!」
怒気を食んだ素戔鳴の声が、戦場に響く。素戔鳴は、先程からハヤブサに何度も攻撃を仕掛けようと試みて、それがことごとく失敗していた。思わぬ者たちに阻まれて、ハヤブサを攻撃しづらくなっていたのだ。
その者たちとは一体誰か。――――それは、自軍の仙界軍の兵士たちであった。
そう。
ハヤブサは知っていた。
独りで大軍と戦う時――――何を利用するべきなのかを。
仙界軍は、確かに強い。それを束ねる素戔鳴の強さたるや、言わずもがなのレベルだ。
だが、兵士たち個々の戦いの力量は、やはり、ハヤブサのそれには劣る。だから、それらを手玉にとり、利用する事は、ハヤブサにとっては容易かった。
乱戦の中、素戔鳴との距離に注意しながら、ハヤブサは兵士たちの身体を利用する。飛んでくる矢を防ぐために。素戔鳴の攻撃から身を守るために。そしてあわよくば――――素戔鳴にダメージを与えるために。
「おのれ!!」
素戔鳴の方も、自軍の兵士の身体を自分が傷つけてしまう事を嫌っているのか、飛んでくる兵士の身体を避けたり、受け止めたりしながらハヤブサを追ってくる。これは少し意外だった。素戔鳴ほどの闘気をまとった傲岸なる『神』――――兵士たちの安全など顧みもせずに、自分に攻撃を仕掛けてくる、と、思っていたから。
「素戔鳴様!!」
兵士たちもそんな素戔鳴を崇拝し、慕っているように見える。人望はとても篤いように見えた。だからこそ兵士たちは、無抵抗の村人にも容赦なく剣を振るえるのだろう。素戔鳴がそれを望むのならば。
「……………」
戦いながらハヤブサは思う。
もしも出会い方が、立場が違っていたなら――――酒の一つでも酌み交わせたかもしれない。このような人物は、個人的に嫌いではなかったから。
だが今は。
ドカッ!!
素戔鳴が振り下ろそうとする剣先に向かって、仙界軍の兵士たちを弾き飛ばす。
「ぬうっ!! おのれっ!!」
憤怒に満ちた素戔鳴の声を聞きながら、ハヤブサは仙界軍の中を走り回る。
今自分が為すべきは、時間を稼ぐこと。素戔鳴を引き付けること。そして、あわよくば討ち取ること。
為すべきを成せ。
守りたい者を、守りきるために。
だが素戔鳴も、愚者ではない。いく度目かのハヤブサの攻撃を他の兵士たちと共に巻き込まれるように喰らった時に、素戔鳴も悟ってしまった。自分の周りの『何』が、戦いをさせにくくしているのかを。
そして悟ったが故に、素戔鳴は次の命令を周りの者に下す。
「皆の者聞けい!! そ奴を無理に倒そうとするな!!」
「素戔鳴様!?」
「し、しかし……!」
素戔鳴のためにハヤブサを倒そうとしていた兵士たちから、戸惑う様な声が上がる。だが軍神は、そんな兵士たちを制するように、ずい、と前に進み出た。
「お前たちは手を出すな……。これは、吾の獲物ぞ――――」
「…………!」
素戔鳴から滲み出る気迫に圧倒されるように、兵士たちは素戔鳴の前から退き、ハヤブサへと続く道を開ける。兵士たちが退いたのを確認してから、素戔鳴は次の命令を、兵士たちに下した。
「隊を半数に分ける。一の隊から四の隊までは、このまま村人たちの追跡に移れ!!」
「はっ!!」
素戔鳴の命令を受けた兵士たちは、その指示に従って動き始める。
「チィッ!!」
仙界軍をシュバルツの元に行かせたくないハヤブサは、何とかそれを阻止しようと、動こうとする。しかし。
「吩ッ!!」
素戔鳴の振るった剣圧が、刃となってハヤブサを襲った。それに気づいたハヤブサは、咄嗟に龍剣を振るって、何とかそれを防ぐ。
「――――ぐッ!!」
それでも素戔鳴の剣圧は、びりびりと痺れるような衝撃をハヤブサの手にもたらした。
「何処へ行こうとしている……。汝(なれ)の相手は、この吾ぞ――――」
自分から背を向けて、兵士たちの後を追おうとしたハヤブサに対して、素戔鳴は面ににやりと笑みを浮かべる。
「…………!」
ピクリ、と、眉を吊り上げるハヤブサに対して、素戔鳴は、少し愉快そうに笑った。
「……顔色が変わったな? 逃がした村人たちの中に、余程汝が守りたい者が居ると見える――――」
見透かすような素戔鳴の物言い。だが、ハヤブサがそれに言葉を返す事は無かった。ただ龍剣を握りしめながら、無言で素戔鳴を睨みつけている。
「だが――――残念だったな……。汝も村人たちも、既に我を怒らせすぎている……。滅びは、逃れられぬ運命(さだめ)と知れ」
「…………」
その言葉にも、ハヤブサは無言のままだった。チャキッと音を立てて、ハヤブサは龍剣を構えなおす。
知っている。
素戔鳴が『神』と呼ばれるに相応の存在であること。そして、その怒りを買ってしまっていると言う事実も。
(だからどうした)
ハヤブサは、強く思う。
自分は既に、何度も『神』に等しい存在の者たちと戦い、そして、それを屠って来ている。故に、自分は『神』と言う存在を信じていない。神の怒りも呪いも――――もう十二分に味わっている。
『神』などいない。自分は、『神』には絶対に祈らない。
『望み』とは
『願い』とは
自分の力で手繰り寄せるものなのだ。
俺の望みは、シュバルツとキョウジが二人揃って幸せそうに笑っている未来を手に入れること――――
それが叶うのであるならば、自分はどうなっても構わないと思った。
ただ――――
(シュバルツ……!)
出来れば、シュバルツの元に仙界軍の兵士たちを行かせたくはなかった。兵士一人一人の力量で言うなら、決してシュバルツを倒せるほどの物ではない。ただシュバルツの後ろには、それよりもさらに非力な村人たちが居る。
シュバルツは、村人たちを守るためならば、その身を顧みようとはしないだろう。
心配でたまらなかった。
仙界軍の兵士たちにも、素戔鳴ほどの力では無いにしろ、DG細胞を消滅させるだけの力が備わっていたのだとしたら。
「……………!」
(焦るな………!)
ハヤブサは歯を食いしばって、強く己に言い聞かす。
どちらにしろ、今自分がやるべきは、素戔鳴を足止めする事。そして、あわよくば討ち取ること――――。素戔鳴を討ちとるか、戦闘不能にしさえすれば、今の仙界軍には、これ以上この戦場で戦い続ける理由はなくなってしまう筈なのだから。
信じるしかない。
シュバルツを。そして、仲間たちを。
彼らは絶対に――――仙界軍の兵士ごときに後れは取らない筈なのだと。
「素戔鳴とシュバルツを邂逅させない」
これが、悲劇を回避するうえでは、絶対に欠かせない条件の筈なのだから。
「さあ、猛(たけ)き者よ!! 吾と一騎打ちを再開――――」
素戔鳴のその言葉が終わらぬうちに、ハヤブサが動いた。龍剣を下段に構え、低い姿勢を保ったまま――――猛然とダッシュして素戔鳴へと迫って行く。
「小癪な!! 性懲りもなく!!」
素戔鳴は天叢雲を構えて、再びハヤブサに雷撃を喰らわせようとする。だが、その寸前の所で、いきなり龍の忍者の姿が消えた。
「何っ!?」
瞬間ハヤブサの姿を見失って、辺りを見回す素戔鳴の頭上から、鋭い殺気が降ってくる。
「叭―――――――ッ!!」
ガキッ!!
「ぐ………!」
ハヤブサの渾身の一撃は、素戔鳴の光背の一部を確かに砕いた。その気迫と剣圧に押される形で、素戔鳴の体が僅かによろめく。
踏み込むには絶好の機会。だがハヤブサは、それ以上素戔鳴に攻撃を仕掛けようとはせず、ストン、と地面に着地すると、今度は素戔鳴の戦いを見守る兵士たちに向かって、猛然と突っ込んで行く。兵士たちの間に黒い影が飛び込むと同時に、またも飯綱落しがさく裂する。何人かの兵士たちがそれに巻き込まれ、倒されて行った。
「おのれ!!」
兵士たちの混乱を鎮めるように素戔鳴は叫んだ。
「散れっ!! 散開せよ!! 固まっておってはならん!!」
「素戔鳴様!!」
「奴に無理に戦いを挑むな!! 自分の身を守る事に専念せよ!!」
そう言いながら素戔鳴はハヤブサを追うが、兵士たちの間を縫うように走りまわる龍の忍者――――ともすれば、その姿を見失いそうになる。
(おのれ……! 奴め、相当戦い慣れておるな……! 何と言う戦巧者か―――!)
多勢に無勢の戦い方をよく知っている龍の忍者に、素戔鳴は内心舌を巻く。
(だが、その戦い方ではスタミナの消耗も激しかろう。この素戔鳴を前にして、その戦法がいつまで通用するかな?)
ハヤブサの姿を見失わないように注意しながら、素戔鳴はハヤブサの後を追う。いずれにしても、自分の絶対的有利な状況に変わりはないのだから。
久々に味わう戦の歯ごたえに、素戔鳴の口元に、いつしか笑みすら浮かんでいた。
ハヤブサは走りまわりながら、素戔鳴に対する攻略の糸口を探る。
素戔鳴への攻撃の基本はヒット&ラン。一撃加えたら素早く離脱する。素戔鳴の体を崩したからと言って、欲張って2撃、3撃と加えていくと、必ずと言っていい程手痛い反撃を喰らってしまう。焦らないこと。欲張らないこと。確実に『一撃』を与えること――――それだけを心掛けて、ハヤブサは素戔鳴に相対していた。
だがその戦い方を以ってしても、素戔鳴相手に互角に渡り合う事は困難であった。ハヤブサが攻撃を仕掛けようとした瞬間、素戔鳴から雷撃が放たれる。
「ぐはっ!!」
攻撃を仕掛けようとしていたが故に、一瞬身を引く事が遅れたハヤブサの身体に、雷撃が当たる。
「く………!」
だが幸いにして、気を失うことは免れたおかげで、その後の追攻撃は、喰らわずに済んだ。転がりながらそれらの攻撃をかわすと、ハヤブサはまた、素戔鳴から離脱して、攻撃の機を伺うことにした。
(……どうやら、気絶効果のある雷を打てる範囲は、存外狭い様だな……)
それをしながらハヤブサは、少しずつ素戔鳴の戦い方を分析していく。何とか素戔鳴を倒すための糸口を見出したかった。それが出来なければ、シュバルツを悲劇から救う事など出来はしないのだから。それにしても、雷や風雨と言った、自然現象を操る素戔鳴の能力は、やはり厄介だ。流石に『神』を自負するだけの事はある――――と、言ったところだろうか。
だが、自分も負けるわけにはいかない。
『神』と呼ばれる存在など、既にこの手で何度も倒している。目の前に居るこの素戔鳴とて、例外ではない。必ず――――倒すために必要な攻略の糸口が、見えてくる筈なのだから。
「―――――!」
不意に背後から鋭い殺気を感じたが故に、龍の忍者は転がってそれをかわす。ガバッと跳ね起きて龍剣を構えながら殺気を感じた方を見据えると、素戔鳴が手を伸ばした姿勢のままで、にやりと笑いながらこちらを見ていた。
「ほう、今のもかわしたか……。中々に勘の良い――――」
「……………!」
(いつの間に背後に回られた!?)
素戔鳴のその動きに、ハヤブサは驚愕を禁じ得ない。自分は、めいいっぱい走り回って素戔鳴から距離を取っているつもりであったのに。
だが、驚き戸惑っている暇などない。
攻めろ。
一瞬でも――――踏み込めそうであるのならば。
「りゃああああああっ!!」
裂帛の気合とともに、ハヤブサは龍剣と共に素戔鳴へと突っ込んで行く。
「小癪な!!」
素戔鳴も、天叢雲の剣を振りかぶって、ハヤブサの剣撃を受けて立つ。
ガキンッ!!
派手な金属音と共に、両者の剣撃はぶつかり合った。そのまま二人の間で鍔迫り合いの様な状態になる。
「…………ッ!」
「おのれ………!」
ぎりぎりと刀同士を擦り合わせながら、至近距離で睨み合う二人。だがここでも、軍配は素戔鳴の方に上がった。力で押し勝った素戔鳴の刀が、ハヤブサの体を崩す。
「死ねい!!」
素戔鳴の容赦ない剣撃が、体勢を崩して無防備になったハヤブサに襲いかかる。たまらずに吹っ飛ばされたハヤブサの身体は、背後の樹の幹へと叩きつけられてしまった。
「ぐ………!」
力無く、ずるずると木の幹を滑り落ちてくる龍の忍者に向かって、周りの仙界軍の兵士たちから矢が放たれる。それに気付いたハヤブサは、何とか体を捻ってそれらをかわした。しかし、避け損ねた最後の一本が、右腕に深く突き刺さってしまう。
(チッ! 仕方がない……!)
やむを得ずハヤブサは、矢を抜いた後にまた仙桃を懐から取り出して、それを食べていた。
「貴様!! まだそれを持っておったのか!?」
素戔鳴が怒りを顕わにしながら、雷撃を放つ。龍の忍者は、それを横っとびにかわした。
(仙桃の減りが早い……やはり、もう少し持っておくべきだったか)
想定以上に自分が負傷してしまう事実に、ハヤブサは歯噛みする。だが後悔しても仕方がない。今はこれで――――全力で事に当たらなければならないのだ。
(それにしてもあいつは………よく独りで、この状況を戦いぬいたな)
仙桃を食べ、素戔鳴との距離を確認しながら、ハヤブサは愛おしいヒトに想いを馳せる。
シュバルツはたった独りで村人たちを守りながら、この難敵と戦ったのだ。無茶苦茶にも程がある。こんな状況、独りで対応し切れるはずがない。
逃げる方がよほど楽だっただろう。だがあいつは、ひたすら剣を構え続けた。最期まで守る事を――――あきらめなかった。
だから、俺も。
俺も最後まで、戦いぬく。絶対に、あきらめてなどやらない。
生身の人間である俺。不死の人外であるお前。
故に俺は、どう足掻いても――――お前と同じ苦しみを、背負ってやる事が出来ない。
だが、戦う『姿勢』だけならば―――――
お前と同じ場所に立つ事が、出来るのだ。
唯一俺が、お前と同じ景色を見れる場所
それが戦いの場だと言うのなら
俺も
最期まで
それを見続けさせてくれ
素戔鳴の攻撃範囲は広く、一撃一撃が強い。
だがやはり、力でねじ伏せるタイプの攻撃ゆえか、そのほとんどが前方に集中している。『全方位』型の攻撃ではないのだ。
だから――――
つけ込むとすれば、背後――――!
兵に紛れて走りまわる龍の忍者はもう一度、素戔鳴に急接近を試みる。地面すれすれから素戔鳴に向かって振り抜かれた龍剣は、見事素戔鳴の体を捉えていた。
「ぬおッ!?」
身の丈9尺はある素戔鳴の巨体が、ハヤブサによって高々と打ち上げられる。その後を追う様に、龍の忍者は飛び上がった。
「叭――――――ッ!!」
空中で素戔鳴の身体を背後から羽交い絞めにし、綺麗な放物線を描いて錐揉みしながらハヤブサは素戔鳴の身体を地面に叩きつける。ハヤブサの『飯綱落し』が、初めて素戔鳴に決まった瞬間だった。
ストン、と音を立てて地面に着地した龍の忍者は、眼前に倒れている素戔鳴を見る。飯綱落しを決めた本人が、まだ少し信じられない心地がしていた。
(飯綱落しが決まった……! だが、この程度で奴が倒れる筈がない)
倒れている素戔鳴に対して、ハヤブサは油断なく身構える。その周りを、主が倒されて激昂している兵士たちが取り囲んできた。
「おのれ!! よくも素戔鳴様を!!」
「許さん!!」
口々に怒声を上げながら、次々とハヤブサに襲いかかってくる。
「チイッ!!」
そんな兵士たちの攻撃を、ハヤブサは抜かりなく対応していた―――――刹那。
ドゴォッ!!
倒れていた素戔鳴の身体から、爆発的な『闘気』が放たれる。
「おのれッ!!」
怒りとともに振るわれた天叢雲の剣圧が、無数の刃となってハヤブサたちに襲いかかってきた。
「く………!」
ハヤブサは咄嗟に龍剣を構えてそれらを防ぐが、凄まじい怒りを伴った素戔鳴のパワーは、ハヤブサに攻撃を仕掛けていた周りの兵士たちの身体ごと、彼を吹き飛ばしてしまう。ハヤブサは樹の幹に身体を容赦なく叩きつけられてしまった。
「………ッ」
一瞬息ができなくなって、ハヤブサは軽く喘ぐ。それでも何とか戦闘態勢に戻ろうと足掻くハヤブサの前に、素戔鳴がゆっくりと迫ってきた。
「おのれ!! 人の子分際で、よくも吾に傷をつけさせてくれたな!?」
叫ぶ素戔鳴の後ろで、兵士たちが隊列を作って弓を構え始める。
「許さん……!」
ギリ、とハヤブサを睨みつける素戔鳴の眼差しが、紅に燃え輝いていた。
「…………」
口の中に溜まってきた血をペッ、と吐きだした後、龍の忍者も再び刀を構える。
(今までの戦いが前哨戦。これからが本番と言ったところか……なるほど)
どんどん状況は厳しくなりつつあるのだが、ハヤブサの面には、いつしか笑みすら浮かんでいた。自分の中に宿るある種凶悪とも言える闘争本能が、これ以上ないと言うほど満たされているからだろうか。
さあ、この戦神ともいえる素戔鳴を相手に、俺は何処まで戦えるか。
勝負――――!
ハヤブサの身体からもまた、龍の『燐気』が放たれる。
戦神の『闘気』と龍の『燐気』――――この二つの大きな『気』が、戦場で再びぶつかり合わんとしていた。
村から脱出して、必死の逃避行を続ける村人たちの前に、目的の城の姿が見えてくる。
「城壁が見えた! この森を抜ければ――――!」
「おお!」
「助かった……!」
シュバルツの声に、喜びの声を上げる村人たち。だがその時、彼らは背後に迫る、鬨の声を聞いた。
「――――追手か!?」
振り返るシュバルツの視界に、白藍色の服を着た兵士たちが、武器を振りかざしながらこちらに突進してくる姿が飛び込んでくる。
「あれは……仙界軍――――!」
その正体に気付いた甲斐姫の顔色が変わった。何故なら、『仙界軍』こそが――――シュバルツを『死』に至らしめる力を持っていると、彼女は知っていたからだ。だから彼女は、迷わず叫ぶ事を選択した。
「シュバルツさん、気をつけて!! 彼らの攻撃は――――貴方を破壊し得る力を持っている!!」
「――――何っ!?」
驚いて振り向くシュバルツに、甲斐姫は頷いた。
「本当よ!! 時間を遡る前の歴史の中で、仙界軍にやられて、貴方が粉々に砕け散る瞬間を、私たちは見たの!!」
「…………!」
「だから貴方は絶対に仙界軍と戦っては駄目!! みんなを連れて――――早く逃げて!!」
ここだ、と、甲斐姫は思った。
悲劇を回避するための――――ここがまさに正念場なのだと。
「あ…………!」
それに対してシュバルツは思いだしていた。
「この先神仙界の者たちと敵として遭遇しても、お前は絶対に戦うな」
そう忠告してくれていた、ハヤブサの言葉を――――
「そうか……! そう言う事か……!」
シュバルツは、これでようやく納得する。何故ハヤブサが、戦略的に何の意味も持たない橋を落としてまで、独り、戦場に残ろうとしたのかを。
総ては………村人たちを守るためではなかった。『私を守るため』に―――――!
(あの馬鹿……!)
ハヤブサは最初から知っていたのだ。この戦場に乗り込んでくる仙界軍の存在を。
村人たちと共に居る時に仙界軍に襲われてしまえば、確かに自分は、無傷で居る事など実質不可能になってしまうから――――。
「シュバルツさん!! 納得したのなら早く!!」
急かすように叫ぶ甲斐姫の声に、シュバルツははっと我に帰る。迫りくる仙界軍。そして、自分の背後には村人たち。確かに、迷っている暇はないと感じた。
「いや、逃げる訳にはいかん。戦わねば――――」
「何を言っているの!? シュバルツさん!!」
シュバルツの言葉に仰天してしまった甲斐姫は、思わず叫んでいた。
「忠告したでしょう!? 仙界軍には貴方を破壊する力があるって――――!」
「私に少し考えがある。ここは任せてくれないか?」
甲斐姫の言葉が終わる前に、シュバルツが口を開いた。
「えっ?」
何を言われたのかが瞬間的に理解できず、きょとん、とする甲斐姫に、シュバルツは微笑みかけながら――――さらに言葉を続けた。
「幸いな事にここは森だ……。だからこそ――――使える『策』がある」
「策?」
「ただし、少々荒っぽいがな」
そう言ってシュバルツはにやり、と笑うと、甲斐姫に次の指示を出す。
「だから済まないが……君は今から少しの間でいい。村人を連れて全力で城に向かって走ってくれないか?」
「そ、それは良いけど……何故?」
「私の傍に居ると、皆の命の保証が出来ないからだ」
甲斐姫の問いかけに、シュバルツがそう答えを返す。
「だから、私の傍からなるべく離れてくれると助かる……。頼めるか?」
「分かったわ……。でも――――」
頷いた後に、少し異を唱えようとする甲斐姫に、シュバルツは苦笑気味の笑顔を見せる。
「心配せずとも、私もこのような所で死ぬ気はないさ。自分独りの身だけならば、どのようにでも守れる」
「あ…………!」
シュバルツのその言葉に、甲斐姫もようやく納得する。確かに、守る対象が背後に居ると居ないとでは、戦いやすさが断然違ってくる。それに、あの追手の軍団の中には、素戔鳴が居るような気配がない。そして、この人は充分強い。ならば、シュバルツの力量を信じて――――今は、独りにする方がいいかもしれない。
「分かったわ」
そう得心すると、甲斐姫は立ち上がる事を選択した。
「村人たちの事は私に任せて。でも……貴方も充分気をつけてね?」
「ああ」
シュバルツが頷くのを確認してから、彼女は村人たちの方に振り返る。
「さあみんな立って!! 今から全力で、城に向かって走るわよ!!」
「わ、分かりました!」
「お~い、皆の衆! 走るぞ~!!」
「走れない者には、手を貸してやれ!」
村人たちも妖魔たちも――――互いに手を取り合って走る体勢に入る。
「行けっ!! 走れ!!」
シュバルツの声と同時に、皆は一斉に走り出した。
(シュバルツさん……!)
ケイタは走りながら、一瞬シュバルツの方に振り返る。
シュバルツは、その面に綺麗な笑みを浮かべて佇んでいた。その姿に、何故かケイタの胸が締めつけられた。
(大丈夫……また、会えるよね? シュバルツさん……!)
ケイタは、そう祈らずには居られなかった。
「……さて、私も急ぐか」
村人たちが走り去ったのを見届けてから、シュバルツもまた、その場を後にしていた。
「あの森に入ったぞ!! 逃がすな!!」
素戔鳴の命で村人たちを追いかけていた仙界軍は、逃げる村人たちの姿を視界に捉えたことで、勢いが増して行く。だがその前に、1人の男が立ちはだかった。茶色の革のロングコートを身に纏ったその男は、抜き身の刀を一本片手に携えて、無造作にそこに立っている。
「ムッ!? 何者だ!?」
「恐れるな! 相手は1人だ!!」
「構う事はない! 突っ込め!!」
仙界軍は怒号を上げて、シュバルツを目指してと言うよりは、彼の背後にある森を目指して突っ込んで行く。刹那――――シュバルツが動いた。
フッと、彼の姿が消えたかと思うと、いきなり仙界軍の兵士の目の前に現れる。
「何っ!?」
彼は驚いている間に、シュバルツによって高々と打ち上げられてしまう。後ろから羽交い絞めにされ、綺麗な放物線を描いて錐揉みしながらその兵士は地面に叩きつけらた。彼もまた、『飯綱落し』を自身の決め技として、持っていたのだ。
「な………!」
「こ、こいつ―――!」
兵士たちは、いきなり目の前に現れたこの男が、先程戦った黒の忍者と同じぐらいの強さを保持していると悟って動揺してしまう。その隙をシュバルツは逃さなかった。兵達の集団に突っ込んで、さらにその動揺を煽る様にその集団の中を駆け回り、混乱を助長していく。彼が懐から投げた焙烙玉や火薬付きのクナイが、ドカン! ドカン! と、あちこちで爆ぜて、炎と煙を巻きあげていた。
「皆落ちつけ! 体勢を立てなお――――!」
混乱の中、指揮をとろうとした隊長格の何人かが、シュバルツによって倒されてしまう。村人たちを追跡しようとした何隊かは、完全に統制を失って瓦解して行った。
それでもよく訓練されている素戔鳴の兵達は、村人の追跡をあきらめず、その後を追おうとする。だからシュバルツも、敢えてその兵士たちを森へと誘い入れた。先程自分が仕掛けた、火計の『爆心地』へと――――
ドカン!!
派手な音を立てて、森の中から巨大な火柱が上がる。
「おお……!」
「何だ何だ?」
驚き振り返る、村人と妖魔たち。その燃え上がる炎を見ながら、甲斐姫がポツリと言った。
「きっと、シュバルツさんよ……!」
「え?」
傍に居た青年がその小さな声に反応する。甲斐姫はそちらには振り返らずに、ただひたすら炎だけを見つめていた。
「きっと……シュバルツさんの『策』が、成功したんだわ……!」
「そ、そうだべか……」
「やっぱりすげぇな……あの方は……」
皆はしばし、魅入られたようにシュバルツが上げた炎の柱を見つめていたが、やがて甲斐姫ははっと、我に帰った。こんな事をしている場合じゃない。もう、悲劇を防ぐためにも、動き始めないと、と強く思った。
「みんな! よく聞いて!」
故に甲斐姫は村人たちに呼びかける。
「もう城は目と鼻の先よ! みんなはこのまま――――城に向かって走り続けて欲しいの!」
「あ、ああ……わしらはそれで構わないが……」
「お姉さん―――! シュバルツさんは、どうするの!?」
村人たちをかき分ける様にケイタが進み出てきて叫ぶ。ケイタは不安でたまらなかった。あの佇んでいたシュバルツの笑顔が、あまりにも綺麗過ぎたから――――。
どうしても嫌な予感が頭によぎってしまう。
あの人の姿を見るのが、
あれで最後になってしまうのではないかなんて――――!
「大丈夫よ、ケイタ君」
ケイタの想いを察したのか、甲斐姫が力強く頷く。
「私は今から、あの人の所に向かう。必ず、連れて帰ってくるから――――」
そう。
とにかくあの人を、『独り』で素戔鳴の所に向かわせてはいけない。
行くのなら皆で。出来れば、援軍を連れて。
そうしなければ、この悲劇は回避できない。
甲斐姫は、そう強く確信していた。
「だからケイタ君は、皆と城へ向かって……。 ね?」
甲斐姫に諭すように言われて、ケイタもようやく頷く。
「わ……分かった……」
その言葉に、甲斐姫も微笑みながら頷いた。
「よしっ! じゃあ、俺らはもう少し走るべ!! 後、もうひと踏ん張りだ!!」
「ああ! 我らも協力する! 絶対に皆で城にたどり着こう!」
村人と妖魔たちが、手を取り合って互いを激励し合う。
(この人たちは、きっと大丈夫ね。必ず城にたどり着くはず)
甲斐姫はそう確信すると、「じゃあ、お願いね」と、言い置いて踵を返して走り出した。シュバルツを戦場から離脱させるために――――。
火勢の強い所を避ける様に、甲斐姫は森の中を走る。シュバルツの姿を求めて辺りを見渡していると、幸いな事に、すぐに彼の姿を見つける事が出来た。
「シュバルツさん!!」
「ああ、君か。ちょうど良かった」
シュバルツの方もどうやら甲斐姫を探していたようで、彼女が呼びかけるとそう言いながらこちらへ近づいてくる。
「シュバルツさん! 今の内に皆と城へ――――」
そう呼びかける甲斐姫に対して、しかしシュバルツは頭をふった。
「いや……悪いが、私は城へは行かない」
「…………え?」
何か聞いてはいけない言葉を聞いた様な気がして、甲斐姫は思わず聞き返してしまう。
「ど……どうして?」
「こちらに進軍して来ている兵士の数が、多すぎるんだ………」
甲斐姫の動揺に気づいているのかいないのか――――シュバルツは言葉を淡々と紡ぎ続ける。
「いくらハヤブサが『独り』で戦っているとはいえ――――あいつなら、これぐらいの力量の兵士たちなら、充分に足止め出来る筈なんだ」
それが出来ていない、と言う事は
それが『出来ない』事態が、ハヤブサの方に起こったとしか思えない。
シュバルツはそう考えていた。
「だから、私は今から、ハヤブサの方へ向かおうと思う。君は、皆と一緒に城へ向かって――――」
「そ、そんな……! 駄目よ!!」
嫌な予感が当たってしまったと悟った甲斐姫は、思わず大声で叫んでいた。
どうして
どうして分からないのだろうか、この人は。
ハヤブサさんは、決して貴方に『助けて欲しい』とは望んでいないのに。
貴方に『死んで欲しくない』から、独りで戦う事を、選んだのに――――。
分かる。
ハヤブサさんは今、素戔鳴と戦っている。
そこにこの人を向かわせてしまったら――――絶対に『悲劇』を止める事は出来ない。
これは、甲斐姫の中の確信だった。
だから、止めないと。
何が何でも、引き止めないと。
「………何故だ……?」
しかし、甲斐姫の想いを図りかねるシュバルツからは、疑問を呈する言葉が出てきた。
「君は先程から、ハヤブサを助けに行く事を反対する事ばかり云うな……。何故だ? 君はハヤブサを見捨てたいのか?」
「違う違う!! ハヤブサさんを――――『仲間』を見捨てたい訳無いじゃない!!」
「――――!」
甲斐姫の大声に、シュバルツは一瞬気圧される。彼女の瞳からは涙があふれ、その拳が震えていた。今まで共に戦ってきたハヤブサは、もう自分達にとっても大切な仲間だ。決して、見殺しにして良い存在なんかじゃない。
素戔鳴と独りで戦っているハヤブサは、助けに行かなければならないと、分かっている。あれは、誰か一人の力で抑え込めるような――――そんな生易しい相手ではないのだから。
「だけど駄目なの!! 貴方が独りで行くのは――――絶対に駄目なの!!」
「何故だ………?」
「何度言ったら分かるのよ!! シュバルツさん!!」
甲斐姫はいつしか大声を張り上げていた。
必死だった。
この悲劇へ悲劇へと転がろうとしている流れを、どうにかして引き止めたいと願った。
「……死ぬのよ!? 貴方……!」
「…………!」
「『仙界軍の人たちと戦ったらいけない』って、ハヤブサさんも言っていたじゃない!! 貴方を死なせたくないからハヤブサさんは――――!」
「『死なせたくない』と言うのなら、私も同じだ……。私だって、ハヤブサを死なせたくはない――――」
「あ………!」
シュバルツの静かな反論に、甲斐姫は一瞬言葉を失ってしまう。
同じだ。
二人ともが――――同じ事を、願っている。
恐ろしい程の『両想い』
だからこそ、何と――――厄介なものなのだろう。
「さあ、もう行かせてくれないか……。ハヤブサを、助けに行きたい」
そう言って、シュバルツがずい、と、前に進み出ようとする。その行く手を、甲斐姫が両手を広げて立ち塞がった。
「その気持ちは分かるけど……! でも、待って……! せめて、援軍が来てから――――」
「援軍は、おそらく来ない……」
「な――――!」
シュバルツの言葉に絶句する甲斐姫に、彼は更に言葉を重ねてきた。
「もしも、先に行った孫尚香の援軍の要請がスムーズに行っているのであれば、時間的にも距離的にも――――もう援軍と合流できていなければおかしい……。それが出来ていないと言う事は――――」
「………!」
「おそらく、援軍の要請に失敗しているのだろう……」
「そ、そんな………!」
的確に現状を分析するシュバルツに、甲斐姫は反論できる言葉を持たない。茫然と佇む甲斐姫にシュバルツは優しく微笑みかけると、再び己が望みを告げた。
「さあ、だからハヤブサを助けに行かせてくれないか? 彼を死なせたくないんだ」
「…………ッ!」
甲斐姫は歯を食いしばった。
シュバルツの言い分も分かる。素戔鳴と戦っているハヤブサの方を、楽観視してはいけない事は分かっている。
だが、ハヤブサの気持ちも分かる。ハヤブサは『シュバルツに死んで欲しくない』と、望んでいる。彼を死なせたくない一心で、今も命をかけて懸命に戦っている。そこにシュバルツを行かせてしまったら――――その努力を全部、水の泡にさせてしまう。そんな予感がした。
結果、シュバルツを失ってしまって慟哭する。あんな、悲劇的なハヤブサの姿を、また見てしまうくらい、なら。
駄目だ。
やはり、止めないと。
何が何でも、引き止めない と。
「…………ダメ……!」
震えながら、涙を流しながらも甲斐姫は、尚も両手を広げてシュバルツの前に立ちはだかった。
「村人は……村人たちは……どうするの……?」
震える声で問う。だが、その問いの答えはあっさり返されてしまった。
「もう城は目と鼻の先だ。村人たちが城の前で助けを求めれば、劉備殿の事だ。例え城に劉備殿の部下しかいなかったのだとしても、それを無下にはしないだろう」
「……………!」
何処までも正論なシュバルツの言葉に、甲斐姫は反論の余地を失って行く。確かにそうなのだ。今の時点では、シュバルツの提案に乗る事こそが――――『正しい』
でも、駄目なのだ。
このままでは絶対に、駄目だ。
このまま流れに任せていけば――――また、シュバルツもハヤブサも『救えない』と悟る。
そんなのは、嫌だ。
絶対に 嫌だ。
「さあ、もう良いだろう。君も村人たちと共に、劉備殿の城へ行ってくれ。その方が1人でも2人でも――――村人たちを救える筈だ」
「………そうよ。『救いたい』のよ……!」
「…………?」
不意に紡がれた甲斐姫の言葉の真意を測りかねて、シュバルツは少し首を捻る。甲斐姫はたまらず叫んでいた。涙を飛び散らせながら――――
「そうよ!! 私は救いたいのよ!! ハヤブサさんも!! 村のみんなも!! そしてシュバルツさん……! 貴方も!!」
「…………!」
「貴方を死なせたくなくて……救いたいと願って、ハヤブサさんは頑張っている!! 貴方が死ねば、哀しむ人が居るのよ!! 何故そんな単純な事が分からないの!? シュバルツさん、貴方は――――!!」
甲斐姫の怒鳴り声に、シュバルツは押し黙ってしまう。甲斐姫は尚も懸命に叫び続けた。とにかくシュバルツに分かって欲しい、独りで行くのは思いとどまって欲しい――――そう、彼女は祈り続けていた。
「ハヤブサさんは、ずっと、貴方を探してた……! やっと見つけた貴方を目の前で失って……ハヤブサさんがどれだけ哀しんだか分かる……!? 今だって……1人戦いの場に留まったのも、貴方に『生きて欲しい』と願っているから――――!」
「そう……そうだな……。ハヤブサは………」
不意に響いてきたシュバルツの声に、甲斐姫は顔を上げる。すると、少し哀しげに微笑むシュバルツと、視線があった。
「こんな私に、手を差し伸べてくれた……。それこそ、命かけて――――」
歪な『モノ』で構成されているこの身体故に、自分は普通に生きて、死ぬ事が出来ない。
ハヤブサが懸命に伸ばして来てくれている手を取るには、自分は既に、闇にまみれすぎているのに。
「それでも構わない」
ハヤブサは、笑ってそう言ってくれた。
「愛している」
そう言って、抱きしめてくれた。
これ以上
何を望めと言うのだろう。
「そんなハヤブサだからこそ……私は――――」
得難い人。
貴重な、優しさを持っている人。
だから
だからこそ――――
「救いたいんだ」
「―――――ッ!」
何処までいっても話が平行線のままである事に、甲斐姫は思わず天を仰ぐ。ハヤブサを助けに行きたいと願うシュバルツの意志は、酷く固いのだと悟らざるを得なかった。
でも
それでも――――
「シュバルツさん………」
甲斐姫は小さく息を吐くと、静かにシュバルツに呼びかけた。
「ハヤブサさんは、決して貴方に『助けて欲しい』なんて望んではいないわ……。それでも………」
行くのか、と、問う甲斐姫に、シュバルツは迷うことなく頷いた。
「ああ………行く」
「……………」
甲斐姫は、酷くやるせない気持ちになっていた。
どうしてだろう。互いが互いを、これ以上ないと言うほど思いやっているのに――――。
何故
どうして
行きつく先には、『悲劇』しか待ち受けていないの――――?
(駄目だ……! やっぱり止めないと……!)
このままシュバルツがハヤブサを助けに行けば、確かにハヤブサの身体は救えるかもしれない。でもその結果、シュバルツが死んでしまったとしたら。
それは、ハヤブサの心を絶望へと叩き落とすものだ。
やっぱり駄目だ。
何としても、止めないと。
「貴方の考えは……変わらないのね。分かったわ……!」
甲斐姫は、自分の得物である金拵(きんこしら)えの『浪切』と呼ばれる形状の剣を、ジャッと、音を立てて構える。この剣は鞭状になっていて、伸縮自在の独特の動きをする武器であった。
「だけど、私の考えも変わらない。……はっきり言うわ。ハヤブサさんは、貴方が自分を助けに来る事など望んではいない。そして、貴方は『独り』でハヤブサさんを助けに行くべきではない。どうしても行きたいと言うのであるならば……少なくとも援軍を待って、皆で一緒に行くべきだわ」
「確かにそうだ。理屈で言うならば、君の言っている事は正しい――――」
甲斐姫にそう答えを返しながらもシュバルツは、ハヤブサの瞳に宿っていた悲壮な光が気になっていた。
あれは、死を覚悟していた者の光だ。
戦いに赴くにあたって、自分達戦士は多かれ少なかれ、『死』は覚悟する物だ。しかし、あのハヤブサの瞳に宿っていた光は、酷く色濃かった。はっきりと、自分の『死』を意識していると分かった。そして、本来の歴史であれば、そこは私が命を落とした戦場――――
ならば、死ぬべきは私で、ハヤブサではない。
犠牲の肩代わりなど――――させてはいけないのだ。
「だが……私は行く。済まないが、援軍を待っていたのでは、間に合わない」
これは、シュバルツの中の確信だった。ハヤブサは今――――恐ろしい難敵と当たっていて、酷く苦戦していると、感じ取っていた。
「そう………」
甲斐姫は小さく息を吐くと、鋭い眼差しをシュバルツに向けてきた。
「でも……『分かったわ。行ってらっしゃい』と、私も言う訳にはいかないのよ」
ジャッ! と音を立てて、甲斐姫の意志を乗せた金拵えの浪切が、シュバルツに向かって動く。
「だって、約束したから……! ハヤブサさんと――――」
「約束?」
怪訝そうに眉をひそめるシュバルツに、甲斐姫の鋭い声が飛ぶ。
「『必ず、貴方を助ける』って………!」
「―――――!」
「その『約束』を交わした以上、私は絶対に、それを違える訳にはいかないの」
そう。
ハヤブサさんはこの戦場に来る時、私に手を伸ばしてくれた。他にも頼れる仲間がいたと言うのに――――。
私は『悲劇は嫌だ』と、子供じみた声を上げただけ。それをあの人は馬鹿にしたり失笑したりせず、それを拾い上げてくれた。「礼のつもり―――」そう言って、手を差し伸べてくれた。
嬉しかった。
だから、そんなハヤブサの願いを叶えたい、と、願う。
例え、どんな手段を使おうとも――――
「だから止めるわ。貴方を……。どんな事をしてでも」
そう言いながら甲斐姫はずい、と、前に進み出る。
自分が理解している限り、目の前に居るシュバルツと言う人は、おそらく特異体質を持っている。自分が少々怪我をしても、それが治ってしまうのだ。
そして、あの人に完全に止めを刺せるのは、おそらく神仙の力を持つ者だけ。素戔鳴は、まさしくそれに該当する。それ以外の者がこのシュバルツに攻撃を加えても、この人にとってはさして問題にはならないのだ。何せ、『治せる』のだから。
「悪いけど、貴方の腕一本脚一本――――もらうつもりで、止めるわよ!」
その言葉が終わると同時に、甲斐姫から凄まじい殺気が放たれる。
(治せるのだから、問題ないでしょ?)
浪切を構える彼女から、そう言う『心の声』が聞こえてきた。
「…………!」
本気だ、と、シュバルツは思った。
本気で彼女は、自分に勝負を挑んで来ている。
「そうか……」
シュバルツはしばらくそんな彼女を静かに見つめていたが、やがて意を決したように頷いた。
「いいだろう。この勝負、受けて立とう」
その言葉を受けて、甲斐姫は身構える。だがシュバルツの方は微動だにしない。ただ静かに――――そこに佇んでいるだけだ。
「…………!」
しかしシュバルツのその姿に、甲斐姫は逆に歯を食いしばった。シュバルツはただ棒立ちに立っているだけの様であるのに、その姿からはなかなか隙が見いだせなかったからだ。
(できる……! やはり―――この人は強い………!)
浪切を握る手に、ジワリと汗が滲み出てくる。しかしここで引く訳にはいかない。甲斐姫は気を取り直した。
負けるもんか……!
ここでこの人を行かせてしまったら、絶対に私は死ぬほど後悔してしまいそうな気がする。
だから絶対に
負けるもんか―――――!
二人の間を、ひゅう、と風が吹き抜ける。
カサ、と、音を立てて木の葉が二人の間の地面に落ちた瞬間――――甲斐姫が動いた。
「やああああああっ!!」
甲斐姫の意志が、彼女の手を通して浪切に伝わる。金拵えの鞭状の刃が、命を宿したようにうねり始めた。ジャッ!! と、音を立てて、浪切がシュバルツの足を食い千切ろうとした刹那。
ガンッ!!
甲斐姫の手を激しい痛みが襲い、彼女の手から浪切が、はるか上空へと奪われてしまう。
武器を失い、無防備になった彼女に、尚もシュバルツが間合いを詰めてくる。
(斬られる――――!)
そう感じた彼女が、身を固くした瞬間。
ふわり、と、いきなり彼女の身体が優しく抱きしめられた。
「――――!?」
瞬間、何が起こったのが理解できずに混乱する彼女の耳元で、シュバルツが小さく囁いた。
「ありがとう………」
それだけを言い置くと、シュバルツは甲斐姫の身体からするり、と、手をほどいて――――森の奥へと独り、消えて行ったのだった。
(ああ、ハヤブサは、大丈夫だ)
森の中を走りながらシュバルツは思った。
きっと大丈夫。
彼は決して『独り』ではない。
彼にはもう『仲間』が居る。
彼の事を思いやり、支えようとする仲間が――――。
だから、大丈夫。
私が側に居なくとも、もう、大丈夫なのだ。
彼は仲間たちに支えられ――――
そして、立ち直って行く事だろう。
ハヤブサ
どうか、幸せに。
今度こそ、幸せに、なってくれ。
私は、もう充分だ。
お前に愛されて――――
もう本当に、充分幸せだったから。
変に霞む視界。
それを振り払う様に、シュバルツは走る。
キョウジの時は、間に合う事が出来なかった。
だから、今度は間に合わせる。
きっと、ハヤブサを守って見せる――――!
燃え盛る森の中を、シュバルツはハヤブサが戦う戦場に向かって、疾風の如く走り抜けていった。
「何……? 何なの……?」
独り、そこに残された甲斐姫は、立っていられなくなって膝からがくりと崩折れて行った。
どうしようもない無力感に襲われてしまう。
元より、自分とシュバルツの間に、多少の実力差がある、と言う事は分かっていた。叩きのめされるのは、百も承知だった。だけど相対した時シュバルツは――――それすらしてくれなかった。1人の『戦士』として扱ってもらえず、ただ軽く、いなされてしまっただけだったと悟る。
「あ……! あ………ッ!」
悔しい。
悔しくて涙があふれる。
いくらなんでもこれはない。
こんなのってない――――
悔しい。
あまりにも無力な自分が――――
悔しい。
本気で役に立たなかった自分が――――
後から後から嗚咽が漏れ、止めようもない涙があふれる。
何もかも抑えられなくなってしまった甲斐姫は、しばらく己が身体を抱え込むようにして、声を張り上げて泣いていた。静かなる森の中に、彼女の誰にも届く事のない慟哭が、響き渡る。
そうやってどれくらい――――泣きつくした事だろう。
ふと顔を上げると、自分の得物である浪切が、地面に力無く横たわっている姿が見える。
(まだ……まだ、あきらめるな!)
「…………!」
不意に、誰かの声が響く。
(こんな所で泣いている場合じゃない)
その声は、自分を叱咤してきた。
あきらめて、泣き崩れるのは簡単だ。
だけど、そうじゃないでしょう。
まだ状況を変えるために、足掻ける道が、貴方にはあるでしょう?
ならば、ちゃんと足掻け。
最後まで――――
ぐしっと、涙を拭くと、甲斐姫は立ち上がった。
使い慣れた獲物を拾い上げると、大きく息を吐く。
行こう。
あきらめずに、今の自分が打てる最善の手を打とう。
総てが終わった後でなら、泣く事なんて、いつでもできるのだから。
「尚香……!」
甲斐姫は、自分が行くべき場所に居る人物の名を小さく呟くと、再び走り出していた。
シュバルツが森の中で上げた巨大な火の手は、当然城に居る関羽や、そして、その前に居る孫尚香にも見えていた。
「何……? 何が、起こったの……!?」
「追手だろうか……?」
孫尚香と、その周りに居る者たちが不安がれば、
「父上……!」
「む………」
城壁の上に居る関羽父子も、上がる火の手に何か感じる物がある様であった。
「関羽将軍!! お願い!!」
もう一度、孫尚香は城壁の上に居る関羽に呼びかける。
「この先に――――助けを待っている人たちが居るのよ!!」
そう言って孫尚香は、懸命に関羽を見つめる。そのまっすぐな眼差しは、決して逸らされる事はない。
「むむっ」
関羽は髯をしごきながら、少し考え込んでしまっていた。前方の森で火の手が上がった所を見ても、この前方で何かが起こっている事は、ほぼ間違いないと見て取れた。しかし、関羽には孫尚香の後ろに控えている『妖魔』の存在が、どうしても引っかかってしまう。
「………………」
妖魔たちの方も、先程からちらちらと関羽がこちらに視線を走らせている事に気がついていた。自分達の存在が、援軍に二の足を踏ませている――――そう感じ取った彼らは、孫尚香の方へと寄って行って、小声で話しかけた。
「尚香さん……やはりワシらの存在が、邪魔になっているのでは……?」
「我らはここで、離脱した方が――――」
「何を言っているの!? 貴方たちには、何もやましい所など無いでしょう!?」
傍から離れようとした妖魔たちを、彼女は大声で引き留める。
「貴方たちは何も悪い事をしていない! だから堂々と胸を張って――――ここに居なさい!」
「尚香さん……」
「しかし――――」
「そうだべ。あんた方は、何も悪くない」
戸惑う妖魔たちに、同じように孫尚香に付き添ってきた村人たちが声をかける。
「おらたちは一蓮托生だ。あんた方を見捨てて、自分達だけ助かろうなんて考えてねぇ」
「あんたたちがこの城に受け入れられない、と言うのなら、おらたちもこの城に入るのをあきらめるだけの話だ。だから気にするな。傍におったらええ」
「…………!」
村人たちの言葉に、その場から去りかけていた妖魔たちの足が止まる。それを見た孫尚香は頷いて――――再び前を向いた。
「関羽将軍!! お願い!!」
もう一度、孫尚香は関羽に呼びかける。
「助けを求めている人たちのために――――門を開けて! 援軍を出して!!」
「父上………!」
孫尚香たちの間で交わされた会話の内容が聞こえていただけに、関平は父親の方を振り返る。関平にはあの妖魔たちが、どうしても『悪』だとは思えなかった。
「父上……! 門を開け、援軍を出しましょう! あの様子では、本当に助けを求めている人たちが、居るやもしれません」
「む………」
息子の言葉に関羽は唸るが、しかし彼の険しい表情は変わらない。あの者たちの言葉を信じて、城の門を開けるのは簡単だ。だが万が一、騙されていた時の事のリスクを考えると、どうしても城の門を開ける事に、二の足を踏んでしまう。
確証が――――確証が欲しかった。
あそこに居る孫尚香は間違いなく本物で、門を開けても良いのだと言う確証が。
『騙される事が常』と言う戦場にあって、信じることの難しさを、関羽は痛感していた。
「関羽将軍……!」
孫尚香は、関羽に呼びかけながら、歯を食いしばっていた。
玄徳の傍に居る時はあまり感じないのだが、こんな時どうしても痛感してしまう。自分は所詮、政略結婚で玄徳に嫁いできた身。玄徳は愛してくれているが、その家臣たちからは、自分は決して認められている存在ではないのだと言う事を。もしも、自分がもっと彼の奥方として家臣たちに信頼されていたならば――――この援軍の呼び掛けも、もっとスムーズに事が運んで行っただろうに。
「…………ッ」
でもここで、自分がこの城の開城と援軍をあきらめてしまう訳にはいかない。後からここに逃げてくる、村人たちや妖魔たちのためにも。彼らの生き残る道を、自分が閉ざしてしまってはいけないのだ。悔しさを噛み殺して、孫尚香は顔を上げ続けた。自分は、訴え続けるしか術がないと知っていた。
やがて、火の手から追われるように――――森の中から村人たちが飛び出してくる。
そして、その間に混じる様に妖魔たちも。
「――――ムッ?」
村人たちの間に混じる妖魔たちの動きを見て、関羽は我が目を疑った。何故なら、その妖魔たちが――――村人たちを助けているように見えたからだ。
「…………!」
関平にも妖魔たちが村人たちを助けているように見えたらしく、同じように息を飲んでいる。
(いいや、まだ分からない)
しかし関羽は城門を開ける事をまだ躊躇う。妖魔たちの動きが、偶然、そんな風に見えただけかもしれない――――どうしても、そんな事を考えてしまう。そこに、皆から少し遅れて、甲斐姫が走り込んできた。
「尚香!! こんな所で何やってんのよ!?」
「甲斐!?」
友人の怒鳴り声に驚いて、孫尚香は振り向く。そして、その友人の横に、もう一人この場にいなければならない人物の姿が無い事に気が付いた。
「甲斐――――シュバルツさんは?」
孫尚香のその問いかけに、甲斐姫の顔が、くしゃっと哀しげに歪む。
「行っちゃったわ……! ハヤブサさんを助けに……!」
「ええっ!?」
友人の驚く声を聞いた瞬間、甲斐姫の中で何かが堪えられなくなってしまったのか、彼女は大粒の涙を流し始めた。
「私………止められなかった……」
「…………!」
「止めたかったのに………何にも、できなかっ………!」
「甲斐………」
そのまま泣きじゃくりだす友人の姿に、孫尚香もかける言葉を失う。そのまましばらく、甲斐姫の嗚咽だけがそこに響き渡っていたが、やがて、このまま膠着状態ではいられない事に彼女は気が付いた。何故なら――――森の中から、シュバルツの火計をかいくぐった仙界軍が現れたからである。
「仙界軍が……!」
「――――!」
孫尚香の声に、泣きじゃくっていた甲斐姫もはっと、顔を上げる。森の中から抜け出してきた仙界軍が、隊列を整えて、こちらに向かって突進してくるのが見えた。
「このぉ!!」
泣いている場合じゃないと悟った甲斐姫が、涙を散らしながらも踵を返す。そんな友人の姿を見て、孫尚香もまた覚悟を決めた。
「みんな!! なるべく城門の方へ下がって!!」
村人たちにそう呼びかけながら、彼女もまた、仙界軍の方へ向かって馬を走らせる。今はとにかく一人でも二人でも、村人たちを救わねばと思った。関羽からの信頼を得られない以上、態度で訴えるしかないのだ。
「待って下せぇ!! 尚香さん!!」
馬を駆って村人たちの最後尾に向かおうとした孫尚香を呼びとめる者が居た。村人たちと共に逃げてきた、妖魔たちである。
「我々も戦います!」
「わしらは鋭い牙と爪を持っている。人間たちよりは役に立つだろう」
「貴方たち……!」
振り返る孫尚香を、妖魔たちは真剣なまなざしで見つめる。その眼差しがぶれないと見て取った彼女は、妖魔たちの申し出を受ける事にした。今は1人でも2人でも村人を助けるために、手が必要だったから。
「じゃあ、お願い!!」
短く叫んで、孫尚香は馬に拍車をかける。その後を、妖魔たちが続いた。そして彼らは、迫りくる仙界軍に立ち向かっていく。
「…………!」
そして当然その動きは、城壁の上から事の次第を見守っていた関羽親子にも、はっきりと見えた。
(もう間違いない。あの妖魔たちは、人間たちを助けている……!)
関平は強く確信した。
駄目だ。このままではいけない。
あそこに居る人と妖魔は――――『助けなくてはいけない』類の者たちなのだと。
「父上!!」
父に反対されても、もう自分は出陣するつもりで、関平は父に声をかける。そうして彼が振り向いた時――――父の姿はもうその隣には無かった。
「あ、あれ? 父上?」
関平が戸惑っている間に、もう関羽は城門の前に居た。赤兎馬に跨り、門番に強く命じる。
「門を開けよ!!」
その声に畏まった門番たちが慌てて城門を開く。門が開くと同時に城門から飛び出した関羽が、大音声で呼び掛けた。
「そなたたち!! 早く城の中へ入れ!!」
「え………?」
一瞬、何が起こったのか分からずに茫然とする村人たちに、尚も関羽が呼びかける。
「さあ早く!! 敵が来る前に!!」
「父上!!」
城壁の上から呼び掛ける息子に、関羽が振り向き、叫んだ。
「関平は村人たちを城内へ導け! ここに居る妖魔たちと兵達との間に、混乱を起こさせぬように!!」
「分かりました!!」
その声を残して、実直な息子の姿が城壁の上から消える。
「さあ! 城内へ!!」
関羽の再び呼びかける声に、村人たちがようやく我に帰る。「行くべ!」と、口々に叫びながら、彼らは城内に向かって走り出した。
「さあ! こちらへ!! 皆は炊き出しの用意をしろ!!」
関平とその部下たちが、民たちを城の中へ導いて行く。入るのを少し躊躇っていた妖魔たちも、兵達がその手を取って城内へと導いた。
「出陣するぞ!! 我と共に来い!!」
関羽の呼び掛けに、彼直属の部下たちが城門に素早く参集し、関羽と共に城外へと飛び出した。関羽の駆る赤兎馬は、彼をあっという間に仙界軍と戦う孫尚香の元へと導いて行く。
「尚香殿!!」
「関羽将軍!!」
「――――誠に、申し訳ない!」
孫尚香の傍まで来た関羽は、そう言ってその頭を下げた。その姿を見た孫尚香は、思わず息を飲んでしまう。
「…………!」
「不覚であった……! この関羽、眼が曇っており申した。これより改めて、この関雲長、尚香殿の助太刀を致す!」
「関羽将軍……!」
孫尚香は何かがこみ上げてくるのを押さえる事が出来ず、思わず顔を覆っていた。何かが――――報われた気がした。
「さあ尚香殿! 敵を蹴散らしまするぞ!」
そう言いながら関羽が、青龍偃月刀を構えて赤兎馬に拍車をかける。
「ええ!」
孫尚香もグイッと涙を拭って、その顔を上げた。
城から飛び出した関羽軍は、破竹の勢いを以って仙界軍に当たる。それでも何とか関羽軍と互角に渡り合おうとした仙界軍ではあるが、あっという間に勝敗は決してしまった。
「て、撤退――――! 撤退せよ――――!!」
その叫び声とともに、仙界軍の兵士たちは、蜘蛛の子を散らす様に城の前から撤退していく。
「あ! 逃げるか!? 待て!!」
叫びながら追おうとした兵士たちを、関羽が押しとどめた。
「追わずとも良い。深追いは禁物―――」
「尚香!! 関羽様!!」
二人の姿を認めた甲斐姫が、撤退する兵士たちの間を縫う様に走り寄ってきた。
「甲斐!!」
「良かった……! 援軍を出してくれたんだね!」
「あい済まぬ。少し遅くなり申した」
そう言いながら関羽は、馬上からではあるが、甲斐姫にも丁寧に頭を下げる。それに甲斐姫も慌てて礼を返してから――――少し縋る様に関羽を見つめてきた。
「関羽様!! お願い!! 援軍に来てくれたのなら、まだ後二人、助けて欲しい人たちが居るの!!」
「二人?」
怪訝そうに首を捻る関羽に、甲斐姫は尚も言葉を続ける。
「そう。ハヤブサさんとシュバルツさん。ハヤブサさんが難敵を独りで食い止めてくれたおかげで、私たちはこうして脱出できたの……! シュバルツさんは、それを独りで助けに行ってしまって―――!」
「何と……!」
息を飲む関羽に向かって、甲斐姫の懇願の声が飛んだ。
「お願い関羽様!! 二人を助けて!! このままではどちらか片方が死ぬか、最悪、二人ともが死んでしまうわ!!」
「甲斐………」
「そんな哀しいのは、私はもう嫌!! 嫌なのよ……ッ!!」
その後は言葉にならず、泣き崩れてしまう甲斐姫。彼女の中で、様々な想いが渦巻いているのだろう。
「あい分かった。この関雲長、そのような者たちを捨て置く訳にはいかぬ―――」
「……………!」
関羽の力強い声に、甲斐姫は顔を上げた。
「ただちに参ろう……! して、その者たちは今、何処で戦っている?」
「目の前の森を抜けて、川を渡った向こう側にもう一つ森がある。そこで私たちは、ハヤブサさんとはぐれたの!」
「承知した! では行くぞ!! 赤兎!!」
関羽の呼び掛けに応える様に、赤兎馬も高くいななく。
「飛ばすぞ!! ついて来い!!」
関羽が勢いよく赤兎馬に拍車をかけると、それに応えた赤兎馬が、猛然と走りだした。『人中の呂布、馬中の赤兎』と、称えられ、1日に千里を走ると万人に謳われるその赤毛の『汗血馬』は、関羽をあっという間にはるか前方へと運んでいく。
「関羽様に続け!!」
兵士たちも関羽に負けじと、馬に拍車をかけ、全力で走りだした。
「誰か私にも馬を貸して!」
甲斐姫が叫ぶと、兵の1人が走り寄って来くる。
「姫様! これをお使いください!」
そう言って、自身が乗っていた馬を貸してくれた。
「ありがとう!!」
甲斐姫は短く叫ぶと、馬に飛び乗り、馬に『走れ』と命を下した。彼女の願いを聞き入れた馬が、力強く走りだす。
(援軍は来た……! お願い、ハヤブサさん、シュバルツさん……! どうか、持ちこたえて……! どうか、早まらないで――――!)
間に合え、
間に合え、
馬に拍車をかけ続けながら、彼女はいつしか、それだけを懸命に念じていた。
ガツン!!
ガツン!!
黒耀色の肌の仁王に、黒い影が何度もぶつかる。そのたびに、その周りには青白い火花が舞い踊り、その衝撃波で周りの木々が揺らされていた。
「おのれ!! ちょろちょろと!!」
素戔鳴の持つ天叢雲の剣先から、青白い稲妻が迸る。
「――――!」
ハヤブサはその稲妻の軌道を読み――――間一髪で急所を外した。だがその稲妻は、ハヤブサの右腕を容赦なく穿った。
「ぐ………!」
咄嗟に身を翻し、素戔鳴から距離を取る。ここぞとばかりに襲ってきた兵達を、左手一本で何とか対処した。だが利き腕を失ってしまっては、素戔鳴と渡り合う事は実質不可能になってしまう。やむを得ずハヤブサは、また仙桃を口にした。
(最後の1個か………)
右手が治る感触を得ながら、ハヤブサは何とも言えない気持ちになる。
素戔鳴の攻撃を、何度もこの身に喰らいながらも、ようやく――――奴の攻撃のパターンが見えてきた。
後一つ、確かめてみたい事がある。
後少し。
後少しなんだ。
「何時まで隠れておる気だ!!」
素戔鳴の剣圧が、ハヤブサが身を隠している木の幹を襲う。バキッ!! と、派手な音を立てて幹が砕けると同時に――――龍の忍者がその影から飛び出した。そのまま龍の忍者はまるで風の様に戦場を駆け回り、もう一度素戔鳴に急接近を試みた。
ハヤブサの動きに合わせて、素戔鳴の天叢雲の剣が振られる。
剣の動きから刃の様に飛んでくる剣圧を、ハヤブサはその軌道を読んでかわす。だが完全にかわしきれる訳ではない。身体のあちこちが鎌鼬にあった様に裂け、血が滲み出てきた。
だが龍の忍者はひるまない。血をその身から飛び散らせながらも、素戔鳴に向かって突っ込んで行く。
「りゃああああっ!!」
渾身の一撃――――
だが龍剣は素戔鳴の身体には届かない。ガキン! と、青白い火花が飛び散り、また寸前の所で素戔鳴に止められた。ち、と、ハヤブサは小さく舌打ちをするが、直ぐに次の一手に移行する。素戔鳴の傍に長居をするのは禁物だった。
「逃がさぬ!!」
ハヤブサが自分から離れる事を許さないと言わんばかりに、素戔鳴は競り合っている剣を強引に振り切る。そのまま龍の忍者を力任せに地面に叩きつけるつもり――――だがそれは、ハヤブサにするりとかわされた。そのまま龍の忍者の身体が、くるくると猫の様に宙を舞う。
「――――!」
空中でハヤブサは、自分の着地地点を狙って周りの弓兵が、射かける体勢に入っているのを見て取る。ハヤブサは咄嗟に懐から手裏剣を取り出して、兵達に向かって投げつけた。何人かの兵士たちには、それで牽制の効果は充分にあったが、如何せん弓兵の数が多すぎる。だからハヤブサは――――
強引に空中で姿勢を変え、木の上を着地地点に選択した。がさり、と、音を立てて龍の忍者の身体が茂った木々の枝の間に入って行く。
「死ねい!!」
それを素戔鳴が黙って見ているはずもない。彼の振るった渾身の一撃が、ハヤブサの着地した木を容赦なく破壊した。
「…………!」
木と共に、その身体を吹っ飛ばされてしまうハヤブサ。だが何とか受け身を取り、頭を庇った。おかげで気を失うという最悪の事態は免れたが――――それでも体のあちこちを木の幹や地面にぶつけた。横隔膜が痙攣し、一瞬息ができなくなる。
「隙あり!!」
そこに容赦なく、仙界軍の兵士たちが襲いかかってくる。ハヤブサはそれを転がってかわし、何とか体勢を立て直すと、また、走りだした。
(休む間も与えないと言う事か……。流石に、よく訓練されている)
噎せそうになるのを何とかこらえる。こんな場所では、一瞬たりとも隙を見せれば終わりだった。
「逃がさん!!」
素戔鳴の怒号と共に、凄まじい剣圧がハヤブサを襲う。噎せるのを堪えた分、それに対する反応が、ハヤブサの中で一歩遅れた。受けきれなかったハヤブサは、また、弾き飛ばされてしまう。彼の身体は、ドンッ!! と、派手な音を立てて木の幹に叩きつけられ、そこに更に、素戔鳴の部下たちが放った弓矢が襲い来る。
「――――ッ!」
動かない身体に鞭うって、懸命に身を捩って龍の忍者はその攻撃を避ける。だが、最後の一本が、左腕に突き刺さってしまった。
「ぐ…………!」
焼け付くような痛みをこらえながら、ハヤブサは立ち上がる。ゆっくりとこちらに向かって足を進めてくる素戔鳴に向かって、龍剣を向け、構えた。
「どうした……? もう、『仙桃』は食べぬのか……?」
揶揄するような素戔鳴の物言い――――だがそれに、ハヤブサは特に答えなかった。怪我をしたのは左腕だけ。まだ、戦闘に支障が出る訳ではなかった。
あきらめない。
まだ――――あきらめたくない。
シュバルツ……! お前を守るために……!
(最善は、こいつを倒すことだが……)
そう思いながらハヤブサは、素戔鳴を見据える。
この相手は、間違いなく今まで戦った相手の中でも最強クラスに当たる敵。流石に――――『神』と名乗るだけの事はある、と、思った。
だが、どんな相手であろうとも、必ず攻撃できる『隙』があるはず。ハヤブサはそれを、何とか見つけ出したいと足掻いていた。せめて一太刀。一太刀でいいのだ。それを素戔鳴に浴びせる事が出来れば、例え自分が倒されても、後で戦う者たちへの負担が、かなり違ったものになって来るであろうから。
龍剣を構え、息を吐く。
素戔鳴が一歩、こちらににじりよってきた瞬間、もう一度、龍の忍者は全力で走りだした。素戔鳴に太刀を届かせるために、ハヤブサは何度でもこの強敵に立ち向かっていく。
ガツン!!
地面すれすれから繰り出されたハヤブサの太刀が、またしても素戔鳴に阻まれる。そうなるのは分かっていたから、ハヤブサは次の手を繰り出す。
もう一度。
ギンッ!!
乾いた金属音が、素戔鳴の耳のすぐ横で響く。
だが、この圧倒的な力を持つ軍神は、特にそれに頓着する事も無く、天叢雲を龍剣に擦り合わせながら、大上段からハヤブサの面を狙う。
「吻(ふん)!!」
ハヤブサはそれを首を横に動かしてかわす。振り向きざまに龍剣を横に振り上げ、素戔鳴の胴を狙った。ガンッ! と、激しい金属音と火花が飛び散り、それも防がれる。
ここで一度離脱する。
素戔鳴の傍に、長居は禁物。
あきらめない。
太刀が届くまで――――もう一度。
スタミナの消耗が激しい。
息が上がりそうになるのを懸命に堪える。
ハヤブサが走るのを目で追っている素戔鳴。その手に握られている天叢雲が、眩しい程の光を帯びているのが見える。
――――来る!
ハヤブサはここで、走る方向を急転換させた。ハヤブサの読み通り――――その直後、彼の居た場所が素戔鳴から放たれた雷によって砕かれる。次の雷が放たれるまでのタイムラグは、およそ3秒。その僅かな隙に――――龍の忍者は素戔鳴に肉薄した。
「ぬっ!!」
突如として眼前に迫ってきた黒い影に、しかし素戔鳴は動じない。雷をその剣に帯びさせたまま、ハヤブサから繰り出された剣を受けた。
ガキンッ!!
派手な火花と、金属音が飛び散る。そのまま鍔迫り合いの状態になると、素戔鳴の面に勝利を確信したような笑みが浮かんだ。
「――――ッ!」
その瞬間、ハヤブサも半歩ほど僅かに体を引く。
そうだ。
お前がその攻撃を仕掛けてくるのを――――ある意味、こちらも『待っていた』のだから。
「愚か者!!」
素戔鳴の身体が瞬間的に光を帯びると同時に、凄まじい稲光の嵐がハヤブサを襲う。
「ぐ…………!」
凄まじい衝撃と剣圧に、ハヤブサは吹っ飛ばされないように耐える。身体のあちこちに、鋭い痛みが走る。だが――――こちらの読み通り、自分の意識が持って行かれる事はない。そう。素戔鳴から繰り出される雷の力も、この距離で受ければ、こちらが気を失うことはないのだ。
踏ん張る。
自分の四肢に、異常が出ていないかを確認する。
動く――――思い通りに。
よし、良いぞ。
このまま、後一太刀、動いてくれ。
自分が知りたいのは、この後だ。
「我が力!! 思い知れ!!」
雷撃を放った直後、素戔鳴の左手が動いて雨と風を呼ぶ。その瞬間、踏ん張り続けていた龍の忍者が、動いた。
「な―――――!」
普通なら気を失うか、雷撃に吹っ飛ばされているはずのターゲットが、いきなり目の前で動いたと認めた瞬間、素戔鳴も驚愕に襲われた。故に、右手に握られている天叢雲に、『動け』と命じるのが一瞬遅れた。
ドンッ!!
凄まじい衝撃音と共に、影が二つに分かれる。一つの影は投げ出されて、地面にもんどりうって倒れ込み、もう一つの影は――――その場にガクッと膝を付いた。
「う…………!」
受け身すら取れずに倒れ込んだハヤブサは、起き上がろうとして、それか叶わない事に気づく。見ると、自分の左足の膝から下が、変なふうに折れ曲がっていた。
(しまった……! 足をやられた……!)
「おのれ、やりおるな……! だが、手応えはあった!!」
そう言いながら膝をついていた素戔鳴が、剣を支えに立ち上がる。振り向いた素戔鳴の、左肩から胸にかけて、斬られた跡があった。
(浅かった……! 踏み込みが、足りなかったか……)
そう感じて、ハヤブサは目を閉じて歯噛みする。せめて利き腕の方を、奪ってやりたかった。
しかし、立ち上がることすら出来ない現状。そんな自分を、素戔鳴率いる仙界軍が、武器を構えて取り囲む。
(ここまでか………)
龍の忍者は、死を覚悟した。
「汝(なれ)の腕、人間にしては見事――――。もう少し深く踏み込まれておったなら、吾は骸になっていたかもしれぬ」
そう言いながら素戔鳴は、己が斬られた部位を撫でさする。浅いとはいえ、それなりにダメージはあったようだ。
「大技を放った後は、必ず隙が出来るものだ……」
そう言いながらハヤブサは、己が顔を覆っている覆面を外す。相手に最期の礼をつくす意味合いもあるが、それよりももっと――――相手の『油断』を誘うつもりで、ハヤブサはそれをしていた。
そう。
ハヤブサは、まだあきらめてはいなかったのだ。
素戔鳴に、ダメージを与える事を――――。
自分が、もう死ぬのは分かっている。その運命を、今更覆そうとは望んでいない。
ただ、まだ立って歩ける素戔鳴。お前をそのままにしておけば――――
お前は、村人たちを――――シュバルツを、また追って行ってしまうだろう?
させない。
そんな事は。
俺は、シュバルツを守りたい。
それが叶うのであるならば――――何だってする。
「あの雷の多段攻撃の後、風雨を呼ぶ時――――お前は、割と隙だらけになる。そんな状態であると言うのに、『神』特有の、その間一切の攻撃を受け付けない守りを、その身につけているという訳でもない………」
だから、俺が放った普通の攻撃でも、あの瞬間なら割とお前に入るんだ、と、話すハヤブサに、素戔鳴は、ほう、と、少し感心した様な声を上げた。
「大したものよ……。未だ年端もいかぬ若造の様であるのに――――」
「…………」
素戔鳴の言葉に、ハヤブサは穏やかな笑みを浮かべる。
素戔鳴に感心されて満足したかのように見えたが、そうではない。彼はこの時、全く別の事を考えていた。
(今なら、言えるかな)
死の運命を目前にして、ハヤブサは愛おしいヒトに想いを馳せる。
今なら
今なら――――言ってやれるかもしれない。
シュバルツに。
「もう、俺の事など忘れて、自由に生きろ」と……。
今なら、俺から彼の手を、離してやれるかもしれないんだ。
(ああ、でも、伝える術がないな)
そう感じて、ハヤブサは少し苦笑してしまう。
元の世界であったならば、ここに隼を呼んで来て――――最期の手紙を託す事が出来ただろうに。
(まあ、今の状況では――――それすら、させてはもらえないだろうがな……)
素戔鳴と、仙界軍に囲まれたこの状況。
手紙を託す事はおろか、そんな手紙を書くことすら、許してはもらえないだろう。
何せ、今の自分は謂わば『罪人』
素戔鳴に、『裁き』を受ける立場の人間であるのだから。
事の正邪はどうであれ、俺は目の前の『神』であるこいつを既に怒らせすぎている。もしも殺されるのならば――――もう、骨すら残してもらえないほどのダメージを、与えられる事になるだろう。
良いだろう。
それこそ、望むところだ。
『遺体』さえ発見する事が出来なければ――――
シュバルツもそのうち、俺をあきらめる事が出来るだろう。
シュバルツ。
シュバルツ。
今、一番会いたいヒト。
でも、一番会ってはいけないヒト。
ここには来るなシュバルツ。
俺は、お前に助けられる事など――――決して望みはしないから。
ただ、許されるのならば最後に――――
もう一度、その肌に触れたかった。
分かっている。
それこそ、贅沢な望みだ。
愛している。
最期の瞬間まで。
俺が、お前を想い続けてしまう事だけは――――
どうか、許して欲しい。
「良い表情だ……。覚悟は、出来たか?」
穏やかな笑みを浮かべ続けるハヤブサに、素戔鳴は、死への覚悟が整ったものと受け取る。素戔鳴の手の内で、天叢雲の剣がきらりと光った。
「……………」
だがハヤブサは、その問いかけには黙して答えない。
愚問だ。
『死への覚悟』など――――とっくに出来ている。
ただし――――貴様も道連れだ。
さあ、寄って来い。
もっと近くに寄って来い。
こんな事もあろうかと、自爆するつもりで身体に仕込んだ火薬。これが、役に立つ時が来た。
殺せないまでも――――この戦場から撤退せざるを得ないほどのダメージを、最期にお前にくれてやるから。
準備は既に整っている。後は、手元にある発火布に、刺激を与えて火を起こすだけ。爆発まで、1秒とかからないだろう。
だから、そのままもっと――――近寄って来い。
「人の子にしては、汝はよく戦った。その闘志に敬意を表し、吾直々に――――貴様に引導を渡してやろう……」
そう言いながら、黒褐色の肌をした仁王が、ハヤブサの目の前に立ちはだかる。それでも、ハヤブサの穏やかな表情は変わらない。ただ、この景色が、自分がこの世で見る最後の風景なのだとハヤブサは思った。
もういい。
もう充分だ。
シュバルツ。
お前を守って、死ねるのなら――――
素戔鳴が、天叢雲の剣を最上段に振りかぶる姿が見える。ハヤブサはただ、静かに目を閉じた――――
その時。
「ハヤブサ!!」
「――――!」
聞きたかった声。だけど、最も『聞いてはいけない声』を、聞いた様な気がしたかと思うと。
自身の身体がいきなり強引に、一陣の風にかっさらわれたような感覚を得た。そのまま抱きしめられ、ずるずると地面を滑る様に移動する。庇われているのか、地面に擦られるような感覚は、自分の体には与えられない。しかし、折れた左足が千切れそうになったが故に――――ハヤブサに激痛がもたらされてしまう。
「うぐッ……! ああっ!!」
堪え切れず、上がってしまう悲鳴。
「ハヤブサ!?」
その悲鳴に反応するように、ガバッと跳ね起きる――――シュバルツ。
(ああ………!)
会いたかった。けど、今、一番会いたくはなかった愛おしいヒトのその姿に、ハヤブサは知らず歯を食いしばってしまう。
何故、来た。
何故――――来てしまったんだ、シュバルツ。
俺は、お前に『助けて欲しい』などと、決して望みはしなかったのに……!
そんなハヤブサの心情を知ってか知らずか、跳ね起きたシュバルツは、ただハヤブサの身体を案じていた。
「どうした!? ハヤブサ! 何処を――――」
その瞬間、ハヤブサの折れ曲がった左足を認識したシュバルツは、思わず息を飲んでしまう。
「足を――――! ハヤブサ……!」
手当てをしなければ、と、シュバルツはハヤブサの足に手を伸ばそうとする。しかし、それをする事が出来なかった。何故なら、彼の背後から、素戔鳴の低い声と鋭い殺気が襲いかかってきたからだ。
「………何だ? 貴様は………!」
「――――!」
はっと、弾かれた様に振り向いて、刀を構えるシュバルツ。そんな彼を、憤怒の形相で見据える、素戔鳴の姿があった。
「何者だ? 貴様は――――!」
「…………?」
目の前の仁王からの質問の意図が少しわからず、刀を構えながら眉をひそめるシュバルツ。だがハヤブサは、素戔鳴が何に対して怒り、何を言わんとしているのかがよく分かった。分かってしまったから――――そこから先の言葉を素戔鳴に言わせたくなくて、シュバルツに聞かせたくなくて、足掻こうとする。
「シュバルツ………うぐッ!!」
だが思うように動かない身体。激痛を堪えられずに悲鳴が上がる。
「シュバルツ……聞くなッ!」
「ハヤブサ……?」
駄目だ。
駄目だ、シュバルツ。
お願いだ。俺の事などこのまま見捨てて――――
今すぐ、ここから逃げてくれ。
だが、ハヤブサの願いを聞く者はそこにはおらず、無情にも、素戔鳴の言葉は紡がれ続けてしまう。
「何と邪悪な……! 何故、貴様の様な物が、人の子の傍をうろついておるのだ!!」
「――――!?」
「吾には見えるぞ……! 貴様のその身体―――――何と不自然でいびつで、邪悪な物で出来ておるのか!!」
「な………!」
素戔鳴の言葉に息を飲むシュバルツ。そんな彼に、目の前の仁王は更にたたみかけてくる。
「そんな『モノ』が、善良なふりをし、人の子に近づく……。その行為が、どれだけ人の子を危険に曝している事か――――汝は分かっておるのか!?」
「……………!」
「汝は、この世に存在していてはならぬものだ!! 今すぐ、抹消されるべきものなのだ!!」
素戔鳴の言葉に呼応するかのように、兵士たちがその周りに集まって来て弓矢をつがえ、シュバルツに狙いを定め始める。
「あ…………!」
シュバルツは、ただ茫然とするしか術はなかった。何故なら――――素戔鳴に指摘された事は、自分自身も常日頃から、薄々感じていた事であったから。
だけど、自分がそれを口に出してしまえばキョウジが哀しむ。キョウジを責める事に、繋がってしまう。
それだけは、嫌だった。
自分は、キョウジの罪と涙の果てに、この世に生まれ落ちたモノ。それは充分分かっている。そしてそれ故に―――キョウジがずっと苦しみ続けている事も。
だからなおの事、自分はキョウジを責めたくなかった。守りたい、と、願った。
そしてその願いを実行するために、シュバルツは、自身の罪の意識に蓋をする。
無理やり、それを心の奥底に沈めて――――
自分は、罪に塗れていようとも、顔を上げ続ける事を選択した。
だけど、改めてそれを外から指摘されてしまうと――――
隠していた、罪の意識が浮上する。
無理やり閉じていた蓋が、開きそうになる。
「…………ッ!」
知らず、下がってしまう剣先。折れそうになる膝。
だがその時、彼の後ろでか細い声がした。
「シュバルツ……ッ!」
ハヤブサ――――!
瞬間的に、我に帰るシュバルツ。
そうだ、ハヤブサを。
ハヤブサを、守らなければ。
その為に――――私はここに来たのだから。
目の前に居るのは、手負いの仁王。
大丈夫。
まだ――――『逃げられる』
ハヤブサを生かすためなら、自分はどうなっても構わなかった。
「シュバルツ……!」
龍の忍者は足掻き続ける。
何故。
何故来たのだ、シュバルツ。
聞かせたくなかったのに。
素戔鳴から発せられる、お前を傷つけるその言葉を
絶対に、お前には聞かせたくなかったのに――――!
「う……! く………!」
立ち上がりたい。
今すぐ素戔鳴を、ぶん殴ってやりたい。
何故。
何故今、動く事が出来ないのか、この身体は――――!
その時シュバルツから、ハヤブサにだけ聞こえるような小さな声で、そっと呼びかけられた。
「ハヤブサ……」
「…………?」
「目を伏せろ」
「――――!」
その一言で、これから何が起こるのか察したハヤブサは、言われたとおり目を伏せる。二人の忍者のその動きに気づかない素戔鳴は、部下たちに矢を『放て』と、命を下そうとした。
その瞬間。
ピカッ!!
シュバルツの手の内から、眩いばかりの青白い光がさく裂する。
「何っ!?」
素戔鳴や兵達が、その光に視界を奪われた刹那――――忍者たち二人は、その場から脱出する事に成功していた。視力が戻った素戔鳴は、その事実に激怒する。
「何をしている!! 早く追え!!」
突如として光の渦に襲われ、動揺している部下たちに向かって、素戔鳴の叱咤する声が飛ぶ。
「特に後から現れた黒髪の男――――奴こそ絶対に逃してはならん!! 見つけ次第、必ず滅殺せよ!!」
「は、はっ!!」
視力の戻ってきた兵達が、素戔鳴の命に従い、森の中を走りだして行く。
「奴は怪我人を抱えている……! そう遠くへは逃げられまい―――」
だから、必ず見つけられるはず。
素戔鳴はそう強く確信して、また自身も森の中へと分け入って行った。
そこから少し離れた場所で、シュバルツはハヤブサを地面に下ろしていた。とにかくハヤブサの折れた脚を早く手当てしなければ、最悪彼は、足を失わなければならなくなってしまう。素戔鳴から早く逃げなければならない事は分かってはいたが、ハヤブサの手当てをする事が、シュバルツにとっては何よりも重要な――――最優先事項になっていた。
地面に下ろされたことで、ハヤブサは身を起こそうとする。
「シュバルツ……!」
とにかく、シュバルツに言いたい事がたくさんあった。それを言おうとして、ハヤブサは口を開こうとする。
「シュバルツ……! お前――――うあッ!!」
だが足の方に激痛が走って、ハヤブサはそれが出来なくなってしまった。シュバルツがハヤブサの折れた左足を強引にくっ付けて、そこに添え木をしたからである。そのまま彼は、懐から包帯を取り出すと、慣れた手つきで足に包帯を巻きつけていく。
「ううっ! くう……ッ!」
足からもたらされる痛み故に、ハヤブサの思考はマヒして、その言葉も奪われてしまう。
(くそっ……!)
シュバルツに治療を施されている間、ハヤブサは口を開く事をあきらめざるを得なかった。
「……これで、しばらくは大丈夫だろう。済まなかったなハヤブサ。少し手荒くなってしまって……」
そう言いながらシュバルツは、ようやくハヤブサの足から手を離す。足はきちんと固定されて、綺麗に包帯が巻かれていた。
「……………!」
だが、痛みが治まる訳ではないから、ハヤブサの呼吸は自然と短く、荒い物へとなって行く。身体に寒気が走るのを感じる。おそらく――――熱も出てきているのだろう。
「シュバルツ……ッ!」
「時間がない、ハヤブサ。行こう。私に捕まって――――」
「―――――ッ!」
バシン!!
乾いた音が、森の中に響き渡る。ハヤブサが、シュバルツの差し出してきた手を、乱暴に振り払ったのだ。
「ハヤブサ……?」
手を振り払われたシュバルツが、茫然とハヤブサを見つめる。その視線の先で――――ハヤブサの身体が、小刻みに震えていた。
「………まず、助けてくれたこと……そして、治療をしてくれた事……礼を言わせてもらう」
苦しい息の下、それでもハヤブサは何とか言葉を紡ぐ。
素戔鳴に追われる身。今は、一刻も早く逃げなければならない事は、ハヤブサも分かっている。
だが――――それ以上に、シュバルツに言いたい事、ぶつけたい気持ちがハヤブサの中で渦を巻いて出口を求めて暴れまわっていた。それを吐き出さなければ自身が窒息してしまう。そう感じてしまうほどに、その衝動は激しかった。
「だがな……シュバルツ……!」
「ハヤブサ……」
「何故来た!?」
「――――!」
「俺は言った筈だ、シュバルツ……! 『お前は、仙界軍とは戦うな』と……! 仙界軍は、お前を破壊する力を持っている……! その攻撃がお前に当たっただけで……矢が掠めただけで――――お前は死ぬんだぞ!?」
「…………!」
「それなのに……! 何故、こんな所に来たんだ! シュバルツ!! 俺は、望みはしなかったのに……! お前に助けて欲しいなどと、決して望みはしなかったのに――――!」
シュバルツは、そんなハヤブサを少し哀しげな眼差しで見つめていたが、やがて口を開いた。
「では、ハヤブサは……逆の立場になった時……私か危険にさらされていると知れば―――――お前は、助けに来ないのか?」
「――――ッ!」
痛い所を突かれて、ぐっと言葉に詰まるハヤブサ。
来ない訳がない。
来ない訳がないではないか。
今の状態がまさにそうだ。
このままではお前が死んでしまうと悟ったからこそ俺は―――――
こうして、単身で敵と戦っていたと言うのに。
それを、助けられてしまって、却ってお前を危険にさらす原因になってしまうなどと――――それこそ本末転倒ではないか。
「納得したのなら行こう、ハヤブサ。私はお前を助けたい」
そう言いながらシュバルツは、またハヤブサに手を伸ばしてくる。しかしハヤブサは、尚もその手から一歩後ずさった。
「…………ッ! 駄目だ……!」
「ハヤブサ……」
「シュバルツ……せっかく来てくれたのに悪いが、このまま、1人で行ってくれ」
「な………!」
ハヤブサの言葉に息を飲むシュバルツ。ハヤブサは、そんなシュバルツをなだめるかのように、顔に少しの笑みを浮かべると、言葉を続けた。
「俺はいい。この傷だ。もう、一歩も動けない――――」
足からもたらされる激痛のせいで、先程から意識が朦朧としている。寒気も依然続いている。熱が上がり続けているのだろう。
お世辞にも、この先の戦いに、役に立つ体調とは言えない。このままシュバルツと共に行けば、足手まといになってしまうのは目に見えていた。
そんな事になるくらいなら。
シュバルツが死んでしまう原因の一翼を、自分が担ってしまう事に、なるくらいなら。
今ここで――――死んでしまった方が、はるかにましだった。
「俺を抱えて、素戔鳴の追跡を受ける事がどれほど危険な事か――――分からないお前ではないだろう? だから、このまま独りで行ってくれ、シュバルツ……! 俺は、お前の足手まといにはなりたくないんだ」
「ハヤブサ……!」
「頼む……! このまま俺の事は置いて――――」
「嫌だ」
龍の忍者の懇願に、しかしシュバルツは首を横に振った。
「シュバルツ……!」
「嫌だ」
「駄目だ! 俺はもう――――!」
「嫌だっ!!」
「…………!」
張り上げられる、シュバルツの悲鳴のような大声に、ハヤブサは一瞬気圧されてしまう。だけど、またすぐ気を取り直した。今ここで、シュバルツを危険に曝すような選択肢を、選ぶ訳にはいかないのだ。
「シュバルツ……! 頼むから――――」
「嫌だ! 嫌だ!! 嫌だっ!!」
シュバルツは激しく頭を振った。まるで小さな子供の様に、言う事を聞いてくれそうにない愛おしいヒトのその様子に、ハヤブサは辟易してしまう。
「シュバルツ……!」
「ではハヤブサ――――! お前に問うが……」
そう言いながら顔を上げたシュバルツの瞳からは、涙が零れ落ちていた。
「お前は……! 私とお前が逆の立場だったら………私が『死ぬ』と分かっている状況で、それでも私が『置いて行ってくれ』と頼んだとして――――お前は、私を置いて行くのか!?」
「――――!」
「置いてなど行かないだろう!?」
シュバルツの言葉に、ハヤブサは反論の言葉を失ってしまう。
確かにそうだ。
もしも逆の立場で、シュバルツが絶対死ぬのだと分かっている状況の中で、彼にそれでも『置いて行ってくれ』と頼まれたとしても――――
絶対にそれは聞き入れられない。
何が何でも連れて行こうとするだろう。例え、殴ってでも蹴ってでも。
『生きて欲しい』
そう、願ってしまう。
――――愛しているから。
「私も同じだ!!」
涙を飛び散らせながら、シュバルツは叫ぶ。
「私もお前と同じ理由で――――今、ここに居る!!」
(え…………?)
何かとんでもない言葉をシュバルツから聞いた様な気がして、ハヤブサはしばし呆然としてしまう。
「ハヤブサ………!」
シュバルツの手が、そっと、ハヤブサの手に添えられてくる。
「生きてくれ、ハヤブサ……」
「シュバルツ……」
「私に……お前を、守らせてくれ………!」
その手がハヤブサの頬まで、優しく滑ってきたかと思うと。
「シュ、バ――――ん……ッ!」
ハヤブサの唇が、シュバルツの唇にそっと塞がれた。
そのままハヤブサの口内が、シュバルツに優しく吸われる。
(シュバルツ……!)
シュバルツからの口付けを受けながら、ハヤブサはたまらなくなる。
そんな事をされてしまったら、愛おしさが溢れてしまう。
押さえていた『欲』が、堪え切れなくなる。
もう一度、シュバルツを抱きたいと
触れたいと
願ってしまう。
(生きたい………!)
お前と、共に――――
(駄目だ……! そんな事を思っては――――!)
ハヤブサは、自身の中にもたげてきた『欲』に、懸命に抗おうとする。
シュバルツに、自分を守らせる様な事をさせては駄目だ。そんな事をさせてしまったら、それこそ彼は自身の身を顧みることなく、守ろうとする対象を守りぬいてしまうだろう。だがそれは、仙界軍が相手では、文字通りシュバルツを殺す行為になってしまう。
それは嫌だ。
自分が、シュバルツの死の原因の一翼を担ってしまう――――そんな事になるぐらいなら、今ここで死んでしまった方が、よほどマシだとハヤブサは思った。
だから、振り払わなければならない。
シュバルツからの口付けを、拒絶、しなければならないのに――――
心とは裏腹に、ハヤブサの手はシュバルツを抱きよせてしまう。ハヤブサの舌は、シュバルツの口腔深くへと侵入してしまう。
「ん………! んぅ……!」
腕の中で、呼吸を奪われてしまった愛おしいヒトが、くぐもった声を漏らす。
振るえるその身体を、きつく抱きしめる。
愛おしい――――
なんて、愛おしいのだろう。
「……………」
口付けが終わった後、シュバルツがハヤブサの身体を、そっと優しく抱きしめてきた。
「ハヤブサ……」
耳元で、囁かれる。
「私と一緒に……来て、くれるか……?」
「…………!」
(駄目だ……! 振り払えない――――)
この優しさを
愛おしさを
拒絶できない――――
愛おしいヒトからのこんな説得は、ある意味卑怯だ。
こんなの絶対に、逆らえる訳無いではないか。
「分かった……。行こう」
ハヤブサは、頷かざるを得なかった。
「ただ一つ、条件がある。シュバルツ」
頷く代わりに龍の忍者は、ある条件をシュバルツに提示する。
「条件?」
小首をかしげるシュバルツに、ハヤブサはにこりと笑った。
「俺を連れていくのなら――――『背負って』連れて行ってくれ」
こうしてシュバルツは、ハヤブサを背負って森の中を移動する事になった。シュバルツはハヤブサを背負ったまま、森の中を軽快に走り続けている。
(これで……少なくとも、シュバルツの『背中』は守れる……)
シュバルツの背中に背負われながら、ハヤブサはそんな事を考えていた。
忍者が逃走する際に置いて、仲間の身体をその背に背負うのは、ある意味常套手段だ。こうしておけば、後ろから弓を射かけられても斬りつけられても、仲間の身体が盾代わりになる。走って逃げる本人の生存確率は、ぐっと上がると言う訳だ。
だからこの場合、背負われる物は仲間の『遺骸』であると言うのが普通だ。自分の身体も守れるし、仲間の遺骸も持ち帰れて、弔ってやることもできる。利用できる者は何でも利用する――――ある意味、忍者らしいサバイバル術であると言えた。
自力で、立って歩く事も出来ない自分は、戦闘においては何の役にも立てない。ならばせめて――――こうして背負われることで、彼の盾代わりになりたかった。このまま彼の背を守って死ねるのであるならば――――それもまた、本望ではないか。
(それにしても………)
ハヤブサは、先程シュバルツから説得された一連の流れを思い出して、改めて赤面してしまう。本当に、酷くストレートに、シュバルツの気持ちを直接ぶつけられて来てしまった。こんな事、初めてだ。
「それにしても今日のお前は、やけに素直だな」
だからつい、こんな言葉も出てきてしまう。自分の頬が、酷く緩んでしまうのを押さえる事が出来ない。こんな事を考えている場合ではないと、ハヤブサは重々承知しているのだが、それほどまでに―――――彼は今『幸せ』だった。
「そうか?」
それに対してハヤブサを背負っている愛おしいヒトは、普通に答えを返してくる。それでは少し味気ないから、ハヤブサは、少しシュバルツをつつく事にした。
「そうだとも。お前、さっき俺に対して自分が言ったこと――――分かっているのか?」
お前と同じ気持ちだと叫ばれ、キスをされる。
こんなの――――『愛している』と言われているも同然だ。
この言葉は、今までどんなにこちらがシュバルツに要求しても、決して言ってくれない物だったのに。
「ああ………」
しかし、ハヤブサのその問いかけにシュバルツは軽く相槌を打つと、何でもないような感じで答えを返された。
「私が素直になった方が、お前を説得しやすいと思ったんだが――――読み通りだったな」
「――――!」
そう言って目の前の愛おしいヒトがにこりと笑う。そんなシュバルツの姿に、ハヤブサは軽くショックを受けていた。
(う……嘘だろう!? さっきのシュバルツのあの一連の言動行動は、計算ずくの物だったのか……ッ!?)
もしそうだと言うのなら、自分は、シュバルツの目論見に完全に頭から引っ掛かったと言う事になる。彼の掌の上で完璧に踊らされてしまった自分を自覚してしまって、ハヤブサはしくしくと泣き出してしまった。
「ひどい……! 俺の純情を、シュバルツに弄ばれた……!」
「別に、弄んだつもりはないぞ」
ハヤブサの抗議に、シュバルツは苦笑しながら答えを返す。しかし、納得のいかないハヤブサは、ブツブツと文句を言いだした。
「チクショウ……! 無事に帰れたら、絶対に、お前を嫌って言うほど抱いてやるからな……!」
「あはは…………抱かれてもいいが、無理だな」
「何故だ?」
ハヤブサの問いかけに、目の前の愛おしいヒトは、少し何かを考えるような間を置いてから、応えてきた。
「だって……お前、足の怪我が――――」
「ああ………」
シュバルツの、ある意味最もな危惧に、ハヤブサは己が動かない左足を意識する。確かにこの足の状態では、何かと不自由は付き纏いそうだった。しかし、こんな不自由など、些細なことだ。
「別に問題ないだろう。お前が俺の上で動いてくれれば――――」
「おおっと!! 足が滑った!!」
ゴ~~~~~ン
間抜けな音と共に、ハヤブサの背中が手近にあった木の幹に、思いっきり打ちつけられてしまう。
「いっ………!」
あまりにも不意をつかれたため、しばらく声も出せずにのたうちまわる龍の忍者。シュバルツはそんなハヤブサをしばしジト目で睨みつけていたが、「フン!」と、小声で言うと、また走り始めた。
「おまっ……! 俺一応怪我人で……!」
涙目になりながら抗議の声を上げるハヤブサに対して、シュバルツからは容赦のない声が飛ぶ。
「阿呆か!! 何故私がお前にそこまでサービスしてやらねばならんのだ!? 怪我が治るまでそういうことは禁止だ!!」
「ええ~~~~~~!?」
「ええ~~~!? じゃないだろう!? ハヤブサ!! 怪我はちゃんと治さないと――――!」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサはまたしくしくと泣き出してしまう。
「ひどい……! もう1カ月以上も、お前に触れていないのに………!」
「さっき口付けをしただろう? それで我慢しろ」
「あんなので満たされるか!! もっとお前の奥深くにまで侵入して、ぐちゃぐちゃに掻き回さないと――――!」
「……もう一度、足を滑らせてやろうか?」
足を止めて低い声で言ってくるシュバルツに、ハヤブサもさすがにやばいと思ったのか、懸命に首を横に振った。
「………俺が悪かった。もう言いません」
「よし」
シュバルツは短くそう言うと、また走り始めた。ハヤブサはやれやれ、と、ため息をつくと、シュバルツの背にポス、と、音を立ててもたれかかった。
(……でも結局、俺が本気で求めたら、シュバルツはそれに応えてくれるんだよなぁ。基本、こいつはお人好しで、優しい奴だから………)
事に至るまでが難儀な奴だが、いざ褥に突入すると、自分がどういうふうにシュバルツに触れても、彼から拒絶された事があまりない事に、ハヤブサは気づいている。だからこそ、彼が嫌がる事はしたくはないし、大事に抱いてやりたいと思うのだ。
(……早く、シュバルツに触れたいな……)
そう思って、彼の髪に顔をうずめたその時。
パリ………
(―――――!?)
自分の耳が、何か聞いてはいけない不吉な音を捉えた様な気がして、ハヤブサは思わず顔を上げていた。
何だろう、今の音は。
まさか――――
「居たぞ!!」
大声が響き渡ると同時に、パン! パン! と、空中で何かが炸裂する音が響き渡る。仙界軍の兵士たちに発見されてしまったようだ。
「シュバルツ!!」
「飛ばすぞ!! ハヤブサ!!」
ダン!! と、激しい音を立ててシュバルツが加速すると同時に、背後から兵士たちが放った矢が飛んでくる。
「―――――ッ!」
その矢が近くを掠めるたびに、ハヤブサは身が縮む思いをする。この矢一本一本に、シュバルツを破壊してしまう力があるのだと思うと、恐怖で叫び出しそうになってしまう。
(俺に当たるのは良い……! だが、シュバルツには当たってくれるな――――!)
そうやって祈りながらシュバルツの背にしがみつくしか出来ない自分の現状が、堪らなくもどかしかった。
それでもさすが、シュバルツと言うべきか。
彼は、その背にハヤブサを背負いながらも、仙界軍からの攻撃をあしらう様にかわしていた。その動きには、余裕さえ感じられる。
しかし仙界軍の方も負けてはいない。個々の動きはシュバルツには劣るが、彼らは『集団』と言う力を生かしてシュバルツに挑んで来ていた。彼に休む間を与えず、その攻撃は徐々にシュバルツに肉薄してくる。
「もらった!」
シュバルツの死角から、仙界軍の兵士が飛び出してくる。
「――――!」
その反対側からは、弓矢も飛んできていた。このままではどちらかの攻撃をかわせたとしても、どちらかの攻撃がシュバルツの身体に当たることは避けられない。
「く………!」
しかもシュバルツが、背後に背負う自分の身体を守ろうとしたのがハヤブサには分かってしまったから――――
「守るな!! シュバルツ!!」
ハヤブサは叫ぶと同時に、自分の太腿の所に挿してあるクナイを、襲ってきた兵士に向かって投げつけていた。クナイは見事、襲ってきた兵の眉間に命中する。その間にシュバルツは、自分に向かって飛んできていた矢を何とかかわしていた。それでも最後の一本が、ハヤブサの腕を掠めてしまう。
「く………!」
「ハヤブサ!!」
「平気だ……! この程度……問題ない!」
そう言いながらハヤブサは、もう次のクナイを手に取る。
「俺の事はいい……! それよりもお前は、ここを突破する事だけを考えろ!」
「――――!」
「こいつらの攻撃が少しでもお前に当たれば、お前は終わりなんだ……! それを、忘れるなよ!!」
「ハヤブサ……!」
そう言いながらクナイを握るハヤブサは、もう敵の方しか見据えていない。その姿を見たシュバルツも、「分かった」と、前を向いた。今は二人で力を合わせて、この危地を脱出するしかないのだ。
足が折れ、そこから来る熱で意識も朦朧としているだろうに、それでもまだ、自分を守ろうとしてくれるハヤブサ。死に場所を定め、死を覚悟していた彼を、無理やり頼み込んで連れて来たのは自分だ。だから――――だからこそ、願う。何としても、ハヤブサを守り抜きたいのだと。
(くそ……ッ!)
クナイを投げただけで、息が乱れそうになる今の自分の状態を、ハヤブサは歯噛みする。
シュバルツを守りたい。足手まといにはなりたくない。彼の盾になりたいと――――願う。
(集中……集中するんだ……!)
手にあるクナイは後5本。投げ時を見極めなければとハヤブサは思った。
ふうっと、大きな息を吐き、ハヤブサは呼吸を整える。
とにかく、シュバルツに敵を近づけさせない事が絶対条件だ。手が使えないシュバルツは、接近戦はどうしたって不利になる。それを防ぐのが自分の役割なのだ。
矢と兵士が、また同時に襲いかかってくる。ハヤブサの放ったクナイは、また過たずに兵士の眉間を割った。その間にシュバルツは矢を避ける。そして間髪入れずに、また矢と兵士。今度は兵士の数は二人になった。
「兵は任せた!!」
「――――!」
シュバルツのその言葉に、彼からの盤石の信頼を感じる。どんな励ましの言葉よりも、心強かった。兵の動きを読んで、迷わずクナイを放つ。仕留めた。眉間を打ち抜かれた兵士たちが、もんどりを打って倒れる。クナイは後2本。
「武器を所望か?」
シュバルツに問われる。
「俺のクナイの数を、憶えていたのか?」
問いに問いを返すハヤブサに、シュバルツはにこりと笑った。
「相手の武器の数を覚えておくのは、常識だろう?」
「それはそうかもしれないが……」
そう答えながら、ハヤブサは少し落ち着かない気持ちになる。一体自分は、シュバルツにどこまで把握されてしまっているのだろう? 先程の説得のされ方といい、もしかしたら自分は一生シュバルツには頭が上がらないのではないだろうかとさえ、思えてきてしまう。
「飛び道具が良いよな?」
シュバルツにそう問われて、ハヤブサははっと我に帰った。
「ああ、そうだな……」
手裏剣もあるのだが、と、ハヤブサが言う前に、シュバルツが動いた。
「よし、任せろ」
ダンッ! と、派手に足音を立てて方向転換される。彼の目の前には1人の弓兵が居た。
「わ………!」
驚いた弓兵が矢をつがえる前に、シュバルツはもうその眼前に肉薄していた。
ガンッ!!
シュバルツの蹴りが、弓兵から武器をはるか上空へと奪う。
「おのれッ!!」
仲間がやられたと知り、攻撃してくる兵士をハヤブサはクナイで撃退していた。残りあと一本。
「これももらうぞ!」
シュバルツが兵の背に背負われていた矢筒も上空へと蹴りあげて――――
その両方ともが、見事ハヤブサの手の内に収まっていた。
「ナイスキャッチ! ハヤブサ」
振り向いたシュバルツから笑顔で言われる。ハヤブサは「ああ」と答えるが、内心冷や汗をかいていた。
「お前なぁ……! あまり敵に接近するなよ? かすり傷を負いでもしたら―――」
「大丈夫だ。まだあの程度の兵の矢に当たるつもりはない。それに……」
「それに?」
「当たりそうになっても、お前が守ってくれるんだろう?」
「―――――!」
シュバルツのその言葉に目をぱちくりさせるハヤブサ。シュバルツはにこりと笑うと、再び前を向いて走り出した。
(見抜かれている……。ああもうちくしょう……! 可愛いなぁ……!)
シュバルツのその言動と行動に、うっかり萌えてしまうハヤブサ。頭がくらくらしてしまっているのは、熱のせいばかりではないだろう。
頼られている。
信頼されている。
それがハヤブサには、堪らなく嬉しかった。
もしかしたら、こうやって自分が舞い上がってしまう事も、シュバルツの計算の内には入っているのかもしれない。しかしそれでいいのだとハヤブサは思う。愛おしいヒトの掌で転がされ続ける今の状態は、決して悪いものではない。寧ろ、心地いいくらいだ。
乱れそうになる息を整えながら、矢をつがえ、構える。突進してくる兵士たちに向かって、矢を放つ。その矢は、過たず兵士たちを仕留めていた。
一見、順調そうに見える逃避行。しかし、仙界軍の兵士たちによる組織だった追跡は、止む気配がない。
(そう言えば、素戔鳴はどうした?)
ハヤブサは、周りの兵士たちの気配を探りながら、ふと思った。
素戔鳴が、あのまま大人しくシュバルツの追跡をあきらめるとは思えない。
それなりに数が倒されているとはいえ、組織だった攻撃を続けている仙界軍の兵士たち。
これらの攻撃が、総て、素戔鳴によって仕組まれているものだとしたら。
―――嫌な、予感がした。
その旨をハヤブサがシュバルツに伝えようとした、刹那。
パリッ、と、音がして、自身の左側に帯電の気配を感じ取る。素戔鳴の雷撃が来る――――と、確信したハヤブサは、迷わず叫んだ。
「シュバルツ!! 右奥に向かって跳べ!!」
「――――!」
シュバルツは、ハヤブサの言葉に従って迷わず跳ぶ。その直後、彼らの居た場所が雷撃によって激しく穿たれた。
「な、何だ!?」
驚くシュバルツに、ハヤブサが声をかける。
「素戔鳴の雷撃だ!! シュバルツ!!」
「な…………!」
「気をつけろ!! すぐに次が来るぞ!!」
ハヤブサの言葉通り、素戔鳴の雷撃は次々と、シュバルツの足元を狙って放たれてくる。シュバルツはそれを、走り抜けたり跳んだりしてかわしていた。そこに更に、仙界軍の兵士たちが、シュバルツの着地地点を狙って矢を放って来る。
「させるか!!」
ハヤブサも負けじと矢を放ち、兵士たちを牽制しようとするのだが、如何せん矢を放ってくる兵士たちの数が多すぎた。矢と雷撃をかわすシュバルツの着地のタイミングと姿勢が、徐々にシビアな物へとなって行く。
そして何度目かの雷撃に襲われた時――――シュバルツはついに、バランスを崩してしまった。
「うあ……!」
「シュバルツ!!」
「――――!」
転びそうになりながらも、咄嗟にシュバルツはハヤブサを庇う。おかげでハヤブサは地面に投げ出されずに済んだが、それでも転倒してしまった忍者二人に襲いかかってきたのは最悪の展開だった。
雷光を帯び、青白く光る天叢雲の剣を携えて、素戔鳴が近づいてくる。
「―――――死ね」
無情の宣告と共に、素戔鳴が剣を最上段に振りかぶろうとした刹那。
一本のクナイが、シュウッ! と、音を立てて素戔鳴の右手首に突き刺さっていた。
「ぬうっ!?」
あまりにも不意をつかれたため、素戔鳴は天叢雲の剣を落としてしまう。驚いてクナイが飛んできた方を見ると、それを投げた格好のまま、肩で息をしながらこちらを睨みつけている龍の忍者の姿があった。
(素戔鳴が武器を落としている……! 今のうちに――――!)
シュバルツは体勢を立て直して、ハヤブサを抱えて素戔鳴の前から逃れようとする。しかし、周りを弓兵にぐるりと取り囲まれてしまい、下手に身動きできない状態になってしまった。しかもハヤブサが、素戔鳴からシュバルツを庇うようにその前に出て、シュバルツがそこから出ようとするのを押さえこむようにしている。
「シュバルツ……! 絶対に俺より前に出るなよ!!」
シュバルツをその身の後ろに庇いながら、ハヤブサは思った。
素戔鳴が武器を落としているこの状態。シュバルツの力と脚力であるならば、確かに、この危地を脱出する事は出来る。しかし、『無傷』で脱出する事は、ほぼ不可能に近かった。間違いなく、何本かの矢はその身に受けてしまう。しかも、シュバルツは脱出するとなると、間違いなくこちらを庇おうとするだろう。
そんな事をさせてしまったら、総てが終わりだ。シュバルツの『死』の運命が、避けようのないものになってしまう。
嫌だ。
絶対に。
俺はシュバルツを守りたい。
守りたいのに――――。
何故。
激痛が走り、全く力が入らない左足にハヤブサは歯噛みする。
何故今、動く事が出来ないのか、この身体は――――!
今なら、分かるのに。
素戔鳴の剣の軌道がどう動くか。その剣先から、雷撃がどう走るのか――――
その攻撃を受け続けたおかげで、手に取る様に読む事が出来る。
今の自分なら、素戔鳴の攻撃に対処する事が出来るのだ。――――身体さえ、動けば。
それが思うように動かない自分の身体。
ハヤブサにはひどく腹立たしく感じられた。
「ハヤブサ……!」
ハヤブサに庇われながら、シュバルツは辟易していた。
本当ならば、無理やりハヤブサを抱きかかえてこの場を脱出しなければならないと、シュバルツは分かっている。
もう充分だ。
ここまで必死に自分の事を守ってくれようとしているハヤブサ。それを守って死ねるのならば――――もうここで死んでも悔いはないと思えた。罪にまみれたこの身には、もう充分すぎる程の幸せを、味わっているように思う。
しかし。
しかし何故か、シュバルツは今のハヤブサに手出しができなかった。
今――――ハヤブサの意に反して自分が動いてしまったら
彼に酷く残酷な傷を負わせてしまう事がシュバルツには分かってしまったから。
まだハヤブサは、戦い続けている。
剣を上げ続けている。
助けなど、決して求めてはいない。
ならば自分は、見守るべきなのだ。このハヤブサの戦いを。彼のパートナーで居たいと願うのならば。
それほどまでに――――シュバルツはハヤブサから、鬼気迫る何かを感じ取っていた。
「大したものよ。また汝(なれ)に、傷を負わされてしまうとは――――」
仁王は不敵に笑いながら、右手首からハヤブサのクナイを無造作に抜く。血にまみれたクナイを素戔鳴は足元にカラン、と、音を立てて転がしてから、ゆっくりと天叢雲の剣を拾いなおした。
ハヤブサの方もまた、龍剣を抜刀する。その様子を見た素戔鳴は、思わず目を細めていた。
「ほう………そんな状態でまだ抜刀するとは……。汝はよほどの戦い好きか、その後ろに居る『モノ』を守りたがっているように見ゆるな――――」
「……………」
素戔鳴のその言葉に、しかしハヤブサは答えない。苦しそうに肩で息をしながら、素戔鳴を睨み据えていた。
「汝に問う。その後ろに居る『モノ』は……それほどまでに守るべき価値のあるものなのか?」
「……………」
その問いにも、ハヤブサは答えない。素戔鳴は、フッと、小さくため息を吐いた。
この問いに、目の前の忍者から答えが返って来ても来なくとも、別にどちらでも構わなかった。あれは自分にとっては、酷く邪悪な物の塊で、滅殺するべき対象である事実に変わりはないのだから。
ただ、そんな物を必死に守ろうとしている目の前の忍者が、酷く滑稽で、哀れにすら思えた。
「討て」
素戔鳴は部下たちに、無造作に命じる。兵士たちはその命を、忠実に実行した。
「――――ッ!」
ハヤブサは、総ての矢を弾き返す。それを見た素戔鳴は、第二波を放つよう命じる。それもまた同じように弾き返された。
「…………!」
重傷を負っているはずの目の前の忍者の神業に、素戔鳴は息を飲む。肩で息をしているその忍者の眼光から、なおも闘志が消えることなく輝いている。これは侮らず――――自ら手を下さねばならぬと素戔鳴は判断した。
右手の天叢雲を握り直し、そこに雷光を宿らせる。今度こそ勝利を確信して――――素戔鳴は再び部下に命じた。
「討て」
部下たちが矢を放つと同時に、自分もまた天叢雲の剣から雷撃を放つ。この攻撃を避ける事は、あの忍者には不可能。今度こそ目の前に二つの遺骸が転がっている――――そう確信していた素戔鳴は、しかし驚愕で目を見開く事となった。
「何っ!?」
避けられたからだ。目の前の忍者に。自分達の攻撃が。
信じられない事にその忍者は、後ろのモノを抱きかかえて横っとびに『跳んで』いた。自分は、間違いなくあの忍者の足を叩き折っている。そしてあれだけの傷を負っている身体。もうその場から一歩も動けないふうであったと言うのに。
「う……! ぐ………ッ!」
ただ、傷だらけのハヤブサは、もうあまり遠くへは跳べない。そして、シュバルツを庇って跳んだため、その身体には矢が何本も刺さっている。
「ハヤブサ!! ハヤブサ!!」
驚愕したのはシュバルツも同じだった。
無茶苦茶だ。
まさか――――ここまで傷だらけのハヤブサが、自分を庇って跳ぶなんて。
「ハヤブサ……!」
シュバルツの何度目かの呼び掛けに、ようやく龍の忍者は瞳を開けた。
「……シュバルツ……。怪我は……無い、か……?」
「…………!」
(何故………!)
シュバルツはたまらず天を仰ぐ。
何故だハヤブサ。
何故、そこまで――――
「………大したものよ。まだ、そこまで動けたとはな……」
「――――ッ!」
素戔鳴の声にビクッと反応した龍の忍者は、またシュバルツを庇うような動きをする。彼をその背に守り、龍剣を構えた。
「ハ……ハヤブサ……!」
(もうこれ以上は無理だ)
そう判断したシュバルツは、ハヤブサの前に出ようとする。しかし、またしてもその動きを、龍の忍者が阻んだ。ハヤブサは彼の手を掴み、自分の意志を強く伝える。「絶対に、前に出るな」と――――
「ハヤブサ……! 何故――――!」
「……………」
シュバルツの問いかけにハヤブサは答えない。ただひたすら素戔鳴を睨み据え、龍剣を構え続けている。まだ、まだ彼は、戦う気なのだ。
でも
でもこれ以上は本当に駄目だ。
止めないと――――
彼の方が死んでしまう。
「ハヤブサ……! もういい……!」
だからシュバルツは必死にハヤブサに呼びかける。
もういいのだ。
もう充分だ。
これ以上私なんかを守って――――
彼が死んでしまう必要なんてない。
「もう良いんだ……! ハヤブサ……!」
そう言ってシュバルツは、ハヤブサの手を振りほどこうとする。しかしハヤブサがそれを拒否した。
「駄目だ!」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの手をますます強く握ってくる。重傷を負っているハヤブサの何処にこんな力が残されているのか、不思議に思えるほどだった。
「ハヤブサ……! 手を離せ……」
「駄目だと言っている!」
「しかし、このままでは――――!」
「俺は大丈夫だ!! だから、絶対に前に出るな!!」
「………この局面で、まだ闘志を失わずか。人の子にしては、大したものよ……」
ジャリ、と、足音を立てながら、素戔鳴がゆっくりと近づいてくる。その間もハヤブサの剣先は下がらず、視線が逸らされる事も無い。その様を見た素戔鳴は口の中で「惜しいな」と、呟いた。
「汝に今一度問う。汝の背後に居る『モノ』は、そうまでして守る価値のあるものなのか?」
「……………」
ハヤブサは、しばらく苦しそうに肩で息をしながら素戔鳴を見据えていたが、やがて今度はその問いに応えた。
「………ある。俺にとってシュバルツは……何よりも得難い、大事なヒトだ」
「その『モノ』の本質は『悪』だ。捨て置けば人の子の世界に害をなすやもしれん。――――それでもか?」
「―――――!」
素戔鳴のその言葉にハヤブサの眉が釣り上がり、シュバルツは息を飲む。だが、ハヤブサは迷わなかった。
「世界がどうとかなどは知らん……。ただ、『俺』にとってのシュバルツは『光』だ……。絶対に、失いたくないと願う程の――――」
「光だと?」
問い返す素戔鳴に、ハヤブサは面に笑みを浮かべる。
「お前や世界に、理解など求めてはいない……。ただ、俺にとってはそうだ。だから、守る」
例え、全世界がシュバルツの存在を許さなくとも。
お前が間違っているのだと否定されたのだとしても――――
俺は
俺だけは
シュバルツと共にある方を選ぶ。
それだけのものを、俺はもうシュバルツから受け取っているのだから。
「俺は絶対に、シュバルツを否定しない!!」
「…………!」
ハヤブサの言葉に素戔鳴は顔をひきつらせ、シュバルツはまた別の意味で息を飲む。ハヤブサ以外の二人ともが言うべき言葉を失い、辺りにはただ、龍の忍者の肩で息をする苦しげな息づかいだけが響き渡っていた。
「そうか………惜しいな………」
やがて素戔鳴は、そう言いながら瞳を閉じる。自分にとってはシュバルツは紛れもない害悪。故に、滅さなければならない。それはもう変えようがなかった。
ただ、自分と戦い、自分の身にこれだけの傷を負わせ、なおかつボロボロになりながらも闘志を失わないこの忍者には、ある程度の敬意を払いたいと思った。――――同じ、戦士として。
このままここで終わらせるのは惜しい。出来ればもう一度、剣を合わせたいと願った。
そうであるが故に、素戔鳴はシュバルツに声をかけていた。
「そこのお前……シュバルツとか言ったな」
「何だ?」
素戔鳴から声をかけられたシュバルツが、顔を上げる。
「汝はそこの忍者――――ハヤブサを助けたいか?」
「―――――!」
素戔鳴のこの言葉に、忍者二人が同時に息を飲む。
素戔鳴が何を言わんとしているのか察してしまったハヤブサは、思わず叫んでいた。
「貴様……! 何を言い出す!?」
「汝は黙っていろ。吾はこの『シュバルツ』と話をしている」
「黙れ!! 貴様がシュバルツの名を、軽々しく口にするな!!」
言い終わると同時にハヤブサから凄まじい殺気が放たれる。だが、素戔鳴は動じなかった。
「交換条件だ。シュバルツ……。汝が吾に大人しく斬られると言うのであれば――――」
「黙れ!! 聞くな!! シュバルツ!!」
叫ぶと同時に、ハヤブサから手裏剣が放たれる。だがその手裏剣は、素戔鳴の身体に到達する前に、天叢雲の剣によって弾き返されてしまった。
「猪口才(ちょこざい)な!!」
怒鳴り声と共に、ハヤブサに向かって振り下ろされる剣。そこから発せられる剣圧が、刃となって容赦なくハヤブサに襲いかかってくる。
「――――ぐッ!!」
既に満身創痍のハヤブサが、それを防ぎきれる訳も無く、彼の身体は更に切り刻まれてしまう。立て膝を付いた姿勢も保てなくなってしまったハヤブサは、そのまま前のめりに、ドウ、と、音を立てて倒れてしまった。
「ハヤブサ!! ハヤブサ!!」
「う………う………」
必死に呼びかけるシュバルツに答える様に、ハヤブサが僅かに身じろぐ。だが、彼の身体のあちこちが裂けて、そこから血が滲み出てきていた。
「ハヤブサ………!」
あまりにも傷だらけなハヤブサのその姿に、シュバルツは彼にかけるべき言葉を失ってしまう。そこに素戔鳴が声をかけてきた。
「急所は外した。すぐに死ぬようなことはない」
「―――――!」
「だが……早く手当てをせねば、死ぬかもな」
「……………!」
(ハヤブサ………!)
シュバルツは傷だらけの龍の忍者を見つめる。ハヤブサの命と自分。どちらが大事か。そんなもの、考えずとも、答えは一つだ。
「………本当に、私が黙って斬られれば、ハヤブサを見逃してくれるのか?」
「ああ。吾は、約束は守る」
先程自分が言いかけた事を把握していたシュバルツに、素戔鳴は満足する。シュバルツはそんな素戔鳴をじっと見つめていたが、やがておもむろに口を開いた。
「お前が追っていた、村人たちは………?」
「―――――!」
シュバルツの言葉に、一瞬目をしばたたかせる仁王であったが、やがてその面にふっと笑みを浮かべた。
「吾もこの傷だ。これ以上追う事は出来ぬ。汝が大人しく斬られるのであれば、あの村人たちの無礼も不問に付そう」
応えながら素戔鳴は、『シュバルツ』の抜け目のなさに苦笑する。だが村人たちの働いた無礼とシュバルツの存在。それのどちらを優先的に裁かねばならないかと問われれば、素戔鳴はシュバルツの方を選ぶ。それほどまでに、素戔鳴にとってシュバルツが持っている『害悪』の可能性は脅威だった。
それにしても、自分は村人たちを裁きに来たのに、この目の前の忍者二人にまんまと防がれてしまった事になる。そこは、自分の負けを認めねばならぬと素戔鳴は思った。ただ、このまま『シュバルツ』を滅する事が出来るのであるならば、今回の戦果はこれで充分と言えるものになるだろう。
「分かった」
素戔鳴の言葉にシュバルツは柔らかな笑みを浮かべると、ハヤブサの方に向き直った。
「ハヤブサ……」
傷だらけの龍の忍者のその頬に、そっと優しく触れる。
「シュバルツ……ッ!」
ぐ、ぐ、と、身を起こそうと足掻いているハヤブサ。しかし、彼はもう、自力ではその身を起こせないようだった。
「ハヤブサ……もういい」
「……止めろ……!」
「もう良いんだ、ハヤブサ……。充分だ。今までありがとう……」
「よせ……!」
必死に足掻き続ける龍の忍者。それを宥めるかのように、シュバルツは彼の背を優しく撫でた。
「ハヤブサ……。私は幸せだった。お前に出会えて……お前と、過ごせて――――」
「止めろと言うのに……ッ!」
ハヤブサは懸命に足掻き続けた。
必死だった。
止めろ。
止めてくれ。
何故、そんな言葉をお前の口から聞かねばならない。
まるで……そんな……
遺言、みたいな言葉を――――!
「お前には本当に、感謝の言葉しかない……。ありがとう。私を否定しないでくれて。ありがとう。私を、受け入れてくれて……」
「シュバルツ……!」
「知らなかった……。世界でたった1人でも、私を否定しない存在が居てくれる、と知るだけで………こんなにも、幸せな気持ちになるんだな……」
「――――ッ!」
そう言って綺麗に微笑むシュバルツの瞳から、一筋の涙が流れ落ちていたから、ハヤブサはたまらなくなる。
違う。
嫌だ。
俺はお前からそんな言葉を聞きたくて
そんな表情を見たくて
ここまで頑張ってきた訳じゃないんだ。
嫌だ。
止めてくれ。
死なないでくれ―――!
叫びたいのに、声が出ない。
シュバルツを止めたいのに、身体が動かない。
「ハヤブサ……本当に、ありがとう」
「シュバルツ……ッ!」
「元気で」
そう言って離れて行ってしまう、シュバルツの優しい手。
違う。
止めろ。
俺を守って『死』を選ぼうとするな。
そんな事をするくらいなら、いっそここで俺を殺してくれ……!
俺はお前を守りたい。
守りたい。
守りたいのに――――!
「…………!」
どう、すればいい?
もう本当に、手はないのか?
シュバルツを『死』の運命から逃れさせるための、何か手段は――――!
「―――――!」
ここでハヤブサの脳裏に、ある考えが閃いた。
ある。
あるじゃないか。
シュバルツを『守る』ための、最後の手段が―――――!
だが、これは賭けだ。
危険な賭け――――
これをやったからと言って、シュバルツを100%守れると言う保証はない。下手をしたら、自分ともども、共倒れになってしまう可能性もある。
しかし素戔鳴に斬られてしまったら、シュバルツは本当に終わりだ。粉々に砕け散って、確実にこの世から消滅してしまう。だが今思いついた方法をとれば、シュバルツの死の可能性が限りなく100%ではなくなるのだ。
ならば、やらねば。
ぐずぐずしている暇はない。早くしなければ素戔鳴がシュバルツを斬ってしまう。それだけは何としても阻止したい。
(動け……!)
ハヤブサは、自分の四肢に鞭うつ。
頼む、俺の身体……!
後少しでいい。動いてくれ――――!
カタン、と、シュバルツが刀を置く気配がする。
そのまま彼は、ハヤブサの横から立ちあがると、素戔鳴に向かって歩を進め出した。
「………もう、良いのか?」
こちらの出した条件をあっさりと飲んだシュバルツを、少し意外に思いながらも素戔鳴は彼に声をかける。それに対して、シュバルツはただ静かに頷いた。
「ああ。もう、別れは済んだ」
「そうか………」
チャキッ、と、音を立てて天叢雲の剣を構えながら、素戔鳴は目の前の青年を検分する。
この青年は今から死ぬと言う身であるのに、その瞳は静かに澄み渡り、恐れの色も迷いの色も浮かんでいない。こちらの視線から、瞳を逸らす事も無い。死に向かうその姿勢は、全く持って見事としか言いようがなかった。
「……………」
(『個人』として見るならば、この青年は全く善良であろうに……な)
ハヤブサのために、村人たちのために、その身を潔く投げだす青年。その行動からは『邪悪』の気配が全く感じられない。これが普通の『人の子』であったなら、素戔鳴も素直に感嘆し、好意を持てた事であっただろう。ハヤブサがこの青年を懸命に守ろうとした、その気持ちを少し、理解する。
しかし、シュバルツの身体を構成している物に潜む『悪』の気配が、素戔鳴の『軍神』としての部分を刺激していた。やはりこれは、滅さなければならないものだと強く思う。
「……潔くその身を差し出した汝に免じて、せめて苦しませずに、あの世へ送ってやろう」
「…………」
最後通牒を出し、剣を振りかぶる。しかし、目の前の青年の穏やかな気配は変わらない。
(惜しいな………)
ちらりと湧いた感情を、すぐに打ち消す。命を砕く覚悟を、その剣に伝えた。
「死ね」
その言葉と共に素戔鳴は剣を振り下ろす――――はずであった。
だがそれをする前に、シュバルツの背後から手が伸びてきて、いきなり彼を背後に引き倒していた。
「な―――――!」
驚愕したシュバルツの視界に飛び込んできたのは、引き倒した自分の上に馬乗りになる龍の忍者の姿であったから、シュバルツは更に驚いてしまう。
「ハヤブサ!?」
「―――――!?」
2人が息を飲む気配を感じ取りながら、ハヤブサはシュバルツの上に乗って抑え込む。
「う………ッ!」
手足に力を込めると身体中に激痛が走り、シュバルツの上に血が滴り落ちた。
「ハヤブサ!? 何をしている!? 離せ!!」
「………嫌だっ!」
「ハヤブサ……ッ!」
シュバルツはハヤブサの身体の下から逃れようと、手足に力を込める。しかしどうした事か――――瀕死の筈のハヤブサの抑え込む力は凄まじくて、それを振り払う事が出来ない。
「ううっ………!」
だが痛みは堪えられないのだろう。ハヤブサの口から呻き声が漏れ、滴り落ちる血は止まらない。しかしそれでも龍の忍者は頑なにシュバルツを抑え込み続けた。まるで、「死んでも離すものか」とでも、言わんばかりに
(何故だ……! ハヤブサ………!)
自分が足掻けば足掻くほど、ハヤブサを苦しめるだけだと悟ってしまったシュバルツは、抵抗できなくなってしまった。フッと手足の力を緩めると、ハヤブサの面に少しの笑みが浮かんだ。
「―――ハヤブサよ。これは一体何の真似だ?」
自分の裁きに横槍を入れられた格好になった素戔鳴が、不快感をあらわにしながら忍者二人を見下ろしている。
「……済まない。無礼は詫びる。だが……後生だ……! もう少しだけ、時間をくれ……!」
顔を上げ、必死に頼み込むように素戔鳴を見つめる龍の忍者。
「今更、こ奴の命乞いなどは――――」
「今更、『助けてくれ』などとは言わない……! シュバルツの命乞いも、しようとは思わない……!」
「ならばなぜ、このような事を?」
「彼と……末期の話がしたい……!」
「何?」
その言葉に、素戔鳴は少し眉をひそめた。
「シュバルツの方は、話は済んだと言っていたが?」
「俺の方の話が、まだ済んでいない――――」
肩で苦しそうに息をしながら、ハヤブサは必死に懇願した。
「お願いだ! 少しでいいんだ……! 彼と話す時間をくれ……! もう死に向かう身なれば、それぐらいの情けはあってもいいはずだ……!」
「……………」
素戔鳴は推し量る様に、二人の様子を無言で見つめていたが、やがて、構えていた天叢雲の剣を下に下ろした。
「よかろう……。少しの間、待ってやる」
そう言うと素戔鳴は2、3歩下がって、二人から少し距離を開けた。それを見たハヤブサは「感謝する」と、軽く頭を下げた。
それをしてからハヤブサは、腹の下の愛おしいヒトの方へと向き直る。
「ハヤブサ……」
こちらの名を呼びながら見つめてくるシュバルツの瞳には、こちらを案じる色しか浮かんでいない。これから殺されると言うのに、最後まで優しさを失わないシュバルツ。愛おしさが、溢れてしまう。
「シュバルツ……」
想いを込めて、その頬を優しく撫でる。それをしながらハヤブサは、シュバルツにそっと語りかけた。
「シュバルツ……頼みがある」
「何だ?」
「俺と一緒に……死んでくれないか?」
「―――――えっ……?」
何か聞いてはいけない、不吉な言葉を聞いた様な気がして、シュバルツは思わずハヤブサを凝視してしまう。
「な……何を……」
「俺と一緒に、死んでくれないか、シュバルツ」
腹の下で震える愛おしいヒトに確認するように、ハヤブサはもう一度言った。
「何を、言っているんだ……? お前は――――!」
こちらの言っている事を理解したシュバルツの顔色が、見る見るうちに変わって行く。
「シュバルツ……」
「何を馬鹿な事を言っているんだ!? ハヤブサ!! 駄目だ!!」
案の定シュバルツは怒りだした。当然だ。自分の身はとことん顧みない奴だが、『命』の重みと大切さをよく理解している。今だってそうだ。俺の命を救うためなら、自分の身がどうなっても構わないと、本気で思ってくれている。
だけど俺だってそうだ。シュバルツを救うためなら、自分の身はどうなってもいい―――そう、思っている。そこは、譲る事が出来なかった。
「俺の身体には自爆用の爆薬が仕掛けてある。これは、俺の身体と、その周囲を――――粉々に吹き飛ばす程度の威力を備えたものだ……」
「―――――!」
「元々これは……素戔鳴と相討ち用に、準備したものだがな……」
そう言いながら苦笑する龍の忍者を、シュバルツは何とも言えない気持ちで見つめる。やはりハヤブサは、この戦いに赴く前から『死』を覚悟していた。過去に自分が『死んだ』と言うこの戦場の厳しさを、シュバルツは改めて痛感する。益々彼に、自分の犠牲の肩代わりをさせてはならない、と、思った。
「今から俺は……これを発動させようと、思っている……」
「な―――――!」
「このままでは、二人……どうせ、共倒れだ……。ならば俺は――――お前と、共に死にたい」
「そ、そんな………!」
自分が死ぬのはともかく、今ここでハヤブサが死ぬ必要などまったくない。強くそう感じたシュバルツは、何とかハヤブサを説得しようと試みた。
「馬鹿な事を考えるのはよせ、ハヤブサ……! 私が死ねば、素戔鳴はお前に手を出さないと言っているんだ。あの素戔鳴の言葉は信用できると私は思う。今ここでお前が死ぬ必要など全く――――」
「……お前が死ねば、俺はこの爆薬を作動させるぞ」
「―――――!」
シュバルツの言葉を遮るように紡がれたハヤブサのこの言葉に、シュバルツは思わず息を飲んでしまう。
「何故………!」
茫然と問い返すシュバルツに、ハヤブサは震えながら答えた。
「お前を喪った苦しみと絶望と孤独を――――『もう一回味わえ』と、お前は俺に言うのか……?」
「……………!」
「お前……絶対分かっていないだろう……! お前を喪って、俺がどれだけ哀しんだか……! どれだけ苦しんだか――――」
「ハヤブサ………!」
「お前を救えずに、またあの地獄を味わうぐらいなら――――今ここで、死んだ方がましだ……! お前を救いたくて……俺はここまで来たのに――――!」
「あ………!」
「このままでは、俺もお前も助からない……。ならばどうせなら、俺はお前と共に死にたい……」
シュバルツの頬を優しく撫でながら、ハヤブサは切々と彼に語りかける。
「俺と一緒に、死んでくれ、シュバルツ……」
(嘘だ。俺は嘘を言っている)
そう。
これこそが、ハヤブサの仕掛けた『策』だった。
確かに今のままでは、シュバルツもハヤブサも、助かる見込みがない様に思える。
しかしハヤブサは、シュバルツと共に死ぬ気などなかった。
正確に言うなら―――――自分の『死』にシュバルツを道連れにする気などなかった。
シュバルツを殺す事が出来るのは、仙界の力を持つ者たちだけ。自分では、彼を殺す事は出来ないのだ。龍剣を使わない限りは――――。まして爆薬で吹き飛ばしたぐらいでは、彼は死なない筈だった。
だが今、シュバルツはかつてない程自分の『死』を、濃厚に意識しているはずだ。
だからこそ。
だからこそ、だ。
騙されて欲しかった。
この自分の詭弁に。
気がつかないで欲しかった。
この言葉のからくりに。
今からお前を殺すのは、『素戔鳴』じゃない。『俺』なんだ。
『俺』ならば―――――お前を殺せない、はずだろう?
例えその身体を粉々に吹き飛ばして爆殺したとしても、3時間後にはDG細胞自身の再生力によって、お前を生き返らせる筈なんだ。
(問題は……素戔鳴がDG細胞の特性を、どこまで把握しているか、なのだが……)
その神通力によって、シュバルツの身体を構成している物の正体と禍々しさを、ある程度見抜いた素戔鳴。彼の視界には、シュバルツがどういうふうに映っているかが分からないから、ハヤブサは少しの不安を覚える。この身体に仕掛けている爆薬で、シュバルツの身体を充分粉々に砕く事は出来るだろう。だがそれで、素戔鳴がシュバルツを『死んだ』と認めてくれるかどうか――――総てはそこにかかっている、と、ハヤブサは思う。
それで『死んだ』と判断してくれればよし。だが、もしも―――――細胞一つ一つが生きている、滅さなければ、と、素戔鳴が判断してしまったら。
だからこれは、賭けなんだ。
危険な賭け――――
爆薬を作動させてしまったら、自分は確実に死んでしまう。死んでしまったら、もうその後は、どう足掻いてもシュバルツを守ってやる事が出来なくなってしまうのだから。
だけどこの方法ならば、シュバルツの『死』へと向かう運命を、一瞬でも歯止めをかける事が出来る。そのまま素戔鳴がシュバルツの『再生』に気がつかなければ、この危地から逃れることも可能だ。
だからお願いだ。シュバルツ。
どうかこのまま、俺のこの言葉に騙されてくれ。
『共に死ぬ』と、頷いてくれ。
『俺ではお前を殺せない』その事実を、
今だけでいい。どうか、思い出さないでくれ……!
祈るように見つめる龍の忍者のその視線の先で、シュバルツが大粒の涙をポロポロと零し始めた。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
「シュバルツ……」
「嫌だ……! ハヤブサ……! 死なないでくれ……!」
縋る様に懇願される。
きっと、今この瞬間も――――彼の方も、考えてくれているのだろう。
俺を、何か生かす手段はないか。何か、助ける方法はないか――――
必死に、考えてくれているのだろう。
でも、もういい。
もう良いんだ、シュバルツ。
お前を守って死ねるのなら―――――俺は、それでいい。
だからハヤブサは、面に笑みを浮かべながらこう言った。
「嫌だ……。お前こそ……俺を、置いて逝かないでくれ」
「――――ッ!」
「共に……死んでくれ、シュバルツ……」
「ハヤブサ……ッ!」
「俺と、共に――――」
「…………ッ!」
ぽろぽろと、大粒の涙を零し続ける愛おしいヒト。
泣き顔ですら、素直に美しかったから――――ハヤブサは、こんな時ですら幸せな気持ちになってしまう。不謹慎なのだろうが、自然と頬が緩んでしまっていた。
「………私には、『魂』が無い……! だから……死んでも、お前と同じ所に逝けないかもしれない――――」
「シュバルツ………!」
「それでも……お前は、『私と共に死ぬ』と、言うのか………?」
「…………!」
(騙されてくれた………!)
ハヤブサは知らず、歓喜に震える。
ああ、良かった。
これで、俺は――――
シュバルツを守って、死ねる。
「ああ……。もう、独り残されてしまうのは、嫌だ」
想いを込めて、その頬を撫でる。
済まないな、シュバルツ。
酷いよな。爆殺なんて……。
本当は、こんな酷い目に遭わせずに、ちゃんとお前を守ってやりたかった。
こんな風にしかお前を守ってやれない俺を
どうか、許して欲しい――――
「ハヤブサ……!」
ぽろぽろと涙を流し続ける愛おしいヒト。
何故、泣く?
何故、泣くのだシュバルツ。
俺はこんなにも――――幸せなのに。
でも、お前を独り、残して逝ってしまう。
もしも、お前がそれに気が付いたら――――恨まれて、しまうかな。
「酷い、酷い」と
詰られて、しまうかな。
俺の事は、恨んでくれても、詰ってくれてもいい。
生きて。
生きてくれ、シュバルツ。
そして、俺に縛られることなく
自由に何処へでも、羽ばたいて行ってくれ。
(ああ、でも、今度もこの気持ちを伝える術がないな)
そう感じてハヤブサは苦笑する。
何てことだ。
愛おしいヒトは、目の前に居るのに――――
だけど駄目だ。
今、お前にこれから先生き残る可能性がある様な事を匂わせてしまったら。
何もかもがばれてしまう。自分の企みが。シュバルツにも、そして素戔鳴にも。
それでは、意味がない。
だから、何も言わずに逝く。
許せ、シュバルツ。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
ヒック、ヒック、と、しゃくりあげる愛おしいヒトが、そっと手を伸ばしてきた。
「ハヤブサ……ッ!」
縋る様に、腕を掴まれる。その涙が、その行為が、俺を思いやる故の物であると言うのなら
俺は何と、幸せ者なのだろう。
愛している。
最期まで。
涙に濡れたお前の顔――――これが人生最後の光景か。
それも悪くはない。あの刀を振りあげた仁王を見るよりは、百倍いい景色だと思う。
だが出来得るならば――――お前の笑顔が見たかった。
駄目か。
駄目だな。こんな状況でシュバルツは、笑える訳がない。
それこそ、贅沢過ぎる望みだ……。
思えば俺は、お前を泣かせてばかり、怒らせてばかり、困らせてばかり――――だったな。
やはり俺は、『恋人』としては、ろくでなしの部類に入るのかな――――
「……話は付いたか?」
少し離れた所で静観していた仁王が、声をかけてくる。
「ああ。話は付いた」
ハヤブサは素戔鳴の方に振り向き、答えた。
さあ、ここからが勝負だ、素戔鳴。
このままシュバルツが『死んだ』と思わせる事が出来さえすれば――――
この勝負、俺の勝ちだ。
「では、黒の忍者よ。そこから退け。吾はシュバルツを滅殺せねばならぬ」
チャッ、と、音を立てて天叢雲の剣を構えながら、素戔鳴が近寄ってくる。それをハヤブサが「その必要はない!」と、制した。
「……どう言う、事だ?」
そう言いながら眉をひそめる仁王に対して、ハヤブサがにやりと笑いかける。
「事の決着は、俺たちが自分でつける、と言う事だ――――」
「―――何だと?」
思わず素戔鳴は警戒してその足を止めていた。
何故なら――――龍の忍者の眼差しが、まだ勝負を捨てていないように感じられたからだ。
(少し遠いな……)
ハヤブサは、素戔鳴と自分達の距離が少し開いている事に苦笑する。この距離では、自分達の自爆に、素戔鳴を完全に巻き込むことは不可能だ。
だが、それもいいか。
二人の最期を、邪魔されたくない、とも思う。
「ハヤブサ……!」
涙に濡れた愛おしいヒトから、縋る様に名を呼ばれる。
そんな風に呼ぶな。
キスをしたくなるではないか。
「シュバルツ……」
想いを込めて、その名を呼ぶ。
それをしながらハヤブサは、自身の懐をまさぐって、発火布と導火線を握り込んだ。これを強く引っ張れば――――自身に仕掛けてある火薬に引火する手筈となっていた。
(愛している……)
最後に
「キョウジによろしく」
それ位は言っても、許されるだろうか。
そう思いながらハヤブサが、発火布を握る手に力を込めようとした瞬間。
その場に一人の兵士が慌てふためきながら入ってきた。
「ご、ご注進!! ご注進申し上げます!!」
「何事か!?」
振り向く素戔鳴に、兵士は膝をついて畏まると報告を始めた。
「この先の村人たちが逃げ込んだ城から、劉備軍が兵を出した模様です!! その数およそ五百!!」
「何っ!?」
「劉備軍は村人を追った我が軍を蹴散らしながら、こちらに鬨の声を上げながら進軍しています!! 我が軍と、敵対する模様です!!」
「何だとォ!?」
その兵士の報告に、驚いたのはハヤブサたちも同じだった。
(援軍だと?)
振り向くハヤブサの視界に、珍しく焦りの色を面に出している素戔鳴の姿が飛び込んでくる。
「援軍……彼女たちの援軍の要請が、成功したのか……?」
「…………!」
自分の腹の下で茫然と呟くシュバルツの言葉に、ハヤブサもようやく得心する。
(そうか……! 甲斐姫と孫尚香たちが――――)
ハヤブサの脳裏に「悲劇を書き換えてやっちゃいましょうよ!」と、明るく笑っていた彼女たちの姿が思い浮かぶ。そうだ。戦っていたのは俺独りではない。彼女たちの頑張りが、実を結んだのだと悟った。
「う………ッ!」
それと同時に、クラリと感じる眩暈。ハヤブサは、自分が重傷であった事を思い出してしまう。
「ハヤブサ!?」
シュバルツが身を起こして、ハヤブサの身体を抱きとめてきた。
(だ……駄目だ……! まだ、力を抜いてしまっては……ッ!)
まだ危地を脱した訳ではない――――。ハヤブサはそう分かっているから、必死に身体に力を入れようとする。だが、一度力が抜けてしまった傷だらけの身体は、ハヤブサの気持ちとは裏腹に、なかなか力が入ってはくれなかった。
「して、劉備軍の将は誰か!?」
問う素戔鳴に兵が答えようとする。
「はっ! 将の旗印は――――」
その言葉を最後まで言いきるより前に、馬のいななきと共に、一体の人馬がそこに飛び込んできた。
「我こそは関羽!! 字を、雲長と申す者なり!!」
燃えるような赤い毛色の馬に乗った、身の丈9尺の流れる様な髯をその面に湛えた偉丈夫が、大音声で名乗りを上げる。
「ここに村人たちの危機を救った義士二人が居ると聞き、救援に参上いたした!! その義士に至る道を開けよ!! 邪魔立てする者は容赦なく斬る!!」
叫びながら関羽は、戦場を見渡す。そして、傷だらけになって倒れているハヤブサと、それを抱きかかえるようにして支えているシュバルツと、その二人の前に刀を構えて立っている、素戔鳴の姿を見つけた。
「あれか……! どうやら、間に合ったようだな……」
飛ばしてきた甲斐があった、と、関羽は安堵のため息を漏らす。その主人の声に応える様に、赤兎馬がブルル、と、低く嘶(いなな)いた。
「すごいな……。関羽殿に救援に来ていただけるとは……!」
「……そうだな……」
歴史上の有名人に会って、軽く感動しているシュバルツに、ハヤブサもその気持ちが分かって少し苦笑してしまう。しかし、まだ油断してはいけない、と、自身を強く戒めていた。何時でも自爆できるようにと、ハヤブサの手には、まだ導火線と発火布が握り込まれたままだった。
「素戔鳴様!!」
仙界軍の兵士たちが、関羽から素戔鳴を守る様に、二人の間に割って入ってくる。
「どうやら其方が、この軍を率いる者であるようだな……。名を、聞いておこうか」
関羽は赤兎馬から降りて、青龍偃月刀を構えながらゆっくりと歩み寄ってくる。それに対して、まず仙界軍の兵士たちが吠えたてた。
「黙れ!! 人の子の身でありながらその口利きは、無礼であるぞ!!」
「まず我らが相手だ!!」
口々に叫びながら、兵士たちは一斉に関羽に襲いかかって行く。
「下がれと言っておる!!」
一喝と同時に振り回される青龍偃月刀は、襲ってきた兵士たちを次々と跳ね飛ばしていく。蜀の五虎将の筆頭と謳われる関羽。その名に恥じないだけの強さを、彼は兼ね備えていた。
「ぬうう………ッ!」
自陣の旗色の悪さに、素戔鳴はいつしか唇を噛みしめていた。
何と言うことだ。
あともう少しで、あの『化け物』を討滅する事が出来たものを――――
兵士たちを一通り打ち払った後、関羽は素戔鳴の方に改めて一歩、踏み出した。
「手負いの身か――――」
青龍偃月刀を構えながら、関羽は呟いた。目の前の仁王然とした男は、刀を握る右手と、左の肩口から腹にかけて傷を負っていた。
「……どうしてもここで戦うと言うのなら受けて立つが、出来ればここを引き上げる事を忠告する。もうすぐここに、我が直属の部下500騎が討ち入ってくる。見たところ、部下の消耗も激しい様子。退かれるのであれば、拙者も追いはせぬ」
関羽の言葉が終わると同時に、彼の背後から激しい鬨の声と蹄の音が鳴り響いてくる。関羽軍がすぐ近くに迫っている事を、素戔鳴に知らせるものであった。
関羽と言う人間は、およそ義人である。その武は弱気を助け、強きを挫くために振るわれる。「追わない」と言った彼の言葉通り、青龍偃月刀を構えてはいるが、手負いの素戔鳴に対して、それ以上踏み込んでくるような気配はないようであった。
「…………!」
自分の状態、部下の消耗を考えても、関羽の忠告通り引き上げるしかない。そう感じて、素戔鳴は唇を噛みしめる。
しかし――――
素戔鳴の視界に、ハヤブサを抱きかかえたシュバルツが映る。
あの『化け物』
あの『化け物』を、そのまま人の子の傍に放置しておく訳には――――
故に素戔鳴は見ていた。
狙っていた。
最後まで――――シュバルツ唯一人を。
手負いの素戔鳴に対して、『追わない』と踏み込まなかった関羽。
「う………ッ!」
自身の身体の痛みに耐えきれず、体勢が崩れてしまったハヤブサ。
「ハヤブサ!? 大丈夫か!?」
その彼を気遣う様に、素戔鳴から視線を逸らすシュバルツ。
その瞬間―――――『悲劇』は起きた。
「隙あり!!」
素戔鳴の裂帛の叫びと共に、彼の強い意志を宿した刃が、シュバルツ達に襲いかかる。
「―――――!」
既に刀を置いてしまっていたシュバルツ。
しかし、シュバルツの脳裏には、「ハヤブサを守らない」と言う選択肢は存在しなかった。それ故に彼は、素戔鳴の刃の前にハヤブサを庇うようにその身を投げ出して――――
ドンッ!!
あまりにも総てが一瞬であったため、誰も何もできなかった。
「引き上げるぞ!!」
素戔鳴は一声上げると、部下を引き連れて潮の様に撤退した。
「素戔鳴様!」
声をかけてくる部下をちらりと見やると、素戔鳴は呟くように声を出した。
「手応えはあった……。あの『化け物』は、もう長くはあるまい」
(え………?)
ハヤブサにとってそれは『無音』の中で起きていた。
(え………? え………?)
何故
何故
はっきり分かるのは
自分を『庇った』愛おしいヒトの身体が
何 かに 斬られ テ
力無くその場に崩折れる、シュバルツの身体。
「シュバルツッ!!」
ハヤブサの悲鳴のような絶叫が、森にこだましていた。
「ハヤブサ………」
その叫びに応える様に、愛おしいヒトが顔を上げる。その背中には、肩口から背の中央部まで、袈裟切りにざっくりと斬られた跡が走っていた。
「―――――!」
衝撃を受けるハヤブサの耳に、パリ………パリ………と、小さな音が飛び込んでくる。
「何故………! 何故………!」
この哀しい音は、シュバルツが『壊れていく』音――――そう悟ってしまっているハヤブサは、思わず絶叫していた。
「何故俺なんかを守った!? 何故あの攻撃を避けなかったんだ!! シュバルツ!!」
そう。ハヤブサには分かってしまった。
あの攻撃をシュバルツがもろに受けてしまったのは、シュバルツが自分を庇ってしまったから。
その言葉に対してシュバルツは、その面に優しい笑みを浮かべる。
「あはは……。本当に、そうだな……。一番ベストだったのは、お前を抱えて飛べればよかったんだが――――」
ドサリ、と、音を立てて、シュバルツの左腕が、地面に落ちる。
「もう………そんな力も……私には、残っていなくて……」
「な――――!」
斬られた場所以外の所からシュバルツの身体が崩れて、ハヤブサは更に衝撃を受けた。
「どう言う、事だ………?」
茫然と、呟く。
「どう言う事だ!? 何故だシュバルツ!! お前まさか――――既に斬られていたのか!?」
ハヤブサの叫びに、シュバルツは微笑みながら「そうだ」と頷いた。
「い……何時だ……?」
震えながら問うハヤブサに、シュバルツは淡々と答え続ける。
「最初に……お前を庇った、あの時に……」
「―――――!」
「避けきれなくて……少し、掠ったみたいなんだ……」
「シュバルツ……!」
「駄目だな……。確かに、お前が言った通り……全然、治せなかったよ……。ハヤブサ……」
「―――――ッ!」
ここでようやく、関羽より遅れてきた部下たちが、この場所に到着していた。兵士たちの間に混じって、孫尚香も、甲斐姫も。
そして、見てしまう。傷だらけになって倒れているハヤブサが泣き叫び――――その視線の先で、静かに壊れていくシュバルツの姿を。
(何てことなの……!? やはり……間に合わなかった………!)
自分達の力が及ばなかった事に、甲斐姫は息を飲み、孫尚香は天を仰いだ。誰しもが、言うべき言葉を失っていた。
「もう……敵はいない……。だから……自爆なんて、考えるな。ハヤブサ……」
「シュバルツ……! 嫌だ……!」
嘘だ。
嘘だ。
シュバルツは俺を助けた時点で、もう自分が助からない事を知っていた。
それでも
それでも彼が
その事実を黙っていたのは
「お前を、守りたかった……。ハヤブサ……」
「シュバルツ……!」
「どんな手を使っても……後でどんなにお前に恨まれようとも…………お前を、守りたかったんだ………」
「…………ッ!」
「キョウジの時は………守れなかったから………」
「シュバルツ………ッ!」
「守れて、良かった……」
ゆっくりと、壊れ続けていたシュバルツの身体。
その事実を、もっと早くに明かされていたら。もっと早い段階で、俺がそれに気づいていたら。
俺は絶望してしまって――――生きる気力も失せてしまっていた事だろう。
シュバルツにはそれが分かっていた。だから彼は、その事実を隠して。
与え続けてくれていた。俺が、生き延びるための――――『希望』を。
「だから、死ぬな………」
微笑みながら紡がれるシュバルツの言葉。
「死なないでくれ、ハヤブサ……」
その言葉に、ハヤブサはぐっと拳を握りしめる。
「馬鹿か……ッ!」
自分に向かってハヤブサは、その言葉を吐きだす。
結局
結局俺は―――――
シュバルツに、何もしてやる事が出来なかった。
彼を助けるどころか
彼が死ぬ原因の一翼を、担ってしまったんだ。
どうして
どうして
どうして――――
「ハヤブサ……今まで、ありがとう……」
同じ事を、言われる。
「嫌だ……!」
せめてもの、否定の言葉を吐く。
だけどそんなもので、目の前の『現実』が変わる訳でもなく。
「私は……これで、良いんだ……。だから……私の事は、もう―――――」
「よくない!!」
「―――――!」
ハヤブサの絶叫に、シュバルツは瞬間息を飲む。
「良くない……! 独り残される、俺の気持ちは……! 俺の気持ちはどうなるんだ!!」
「ハヤブサ……」
ハヤブサの悲痛な訴えに、どうしてやることもできないシュバルツの瞳が揺れる。
「……済まない、ハヤブサ……。でも、お前は独りじゃない。共に戦ってくれる仲間が――――」
「『仲間』はいるさ!! 確かに!! 支えてくれる仲間が!! 志を共にする同士が――――!!」
ハヤブサはいつしか、拳を叩きつけて絶叫していた。
どうして
どうして目の前のこのヒトは、自分の『価値』が分からないのだろう。
お前を失いたくない。
失いたくないから、俺はこうして頑張ってきたのに――――!
「だけど……! 俺にとってのお前は――――『お前』しかいないのに………どうして、それが分からないんだ!! シュバルツ!!」
「ハヤブサ……」
「シュバルツ……ッ!」
茫然と佇むシュバルツに向かって、ハヤブサはぐ、ぐ、と、手を伸ばす。
何としても触れたかった。
嫌だ。
逝かないでくれ。
消えないでくれ――――!
「ハヤブサ………」
シュバルツの、もうほとんど動かなくなっているであろう右手が、ピクリ、と、動いた。
「ハヤブサ……あ、り……ガ――――」
パリン、と、音を立てて、そのヒトは砕け散った。最期まで、優しい笑顔の残像を残したまま―――――
「あ……あ………! あ―――――!」
やっとの思いで掴んだロングコート。だけどそこには、コートしか無かった。
何故
どうして
どうして、シュバルツは――――
「―――――」
ハヤブサは何事か短く言葉にならない叫びを上げたかと思うと、そのまま意識を手放してしまった。
「ハヤブサさんっ!!」
孫尚香は彼を介抱しようと駆け寄って、傷だらけのその姿に絶句する。
(どうして……? どうして……? これだけ強く願って、これだけ頑張ったのに――――)
叶えられない願いがある。
止められない悲劇がある。
甲斐姫にはそれが、哀しくてたまらなかった。自分の無力が、悔しくてたまらなかった。
「この世に神様は居ないの……?」
彼女の呟きに、答えを返せる者は誰もいなかった。
「――――――!」
幕舎の寝台の上でハヤブサは目を覚ます。
(ここは何処だ……? 俺は、確か戦いの途中で――――)
ガバッと起き上がった瞬間に、全身に走る激痛。
「うあ………ッ!」
堪え切れずに悲鳴を上げると「気が付いたかい?」と、声をかけられた。
「―――――!」
驚いたハヤブサが顔を上げると、ねねがこちらを心配そうに覗き込んでいた。
「大丈夫かい? ここが何処で、今がどういう状況か、分かる?」
「あ…………」
ねねに問われてハヤブサは、今までの状況を思い出そうとして――――手に握り込んでいた、シュバルツのロングコートに気づく。
「――――――ッ!」
はっと、息を飲むハヤブサ。
この空蝉の様なロングコートが、総てをハヤブサに伝えてきた。
「お前はまた、シュバルツを守れなかったのだ」と。
「あ…………!」
コートを握りしめ、小さく震えるハヤブサに、ねねは静かに声をかけてきた。
「……その足の治療、『あの人』がしてくれたのかい?」
「…………!」
目を見開くハヤブサの視界に、綺麗に添え木されて包帯を巻かれた、自分の足が映る。
(……済まなかったなハヤブサ。少し手荒くなってしまって……)
そう言って微笑みながら、自分の足から手を離した愛おしいヒト。
シュバルツ。
あの時お前の身体は――――
もう、壊れて行っていたのに。
「……綺麗に、手当てをしてくれているね……。薬師の方も褒めていたよ。『最初の応急手当てが無ければ、足を切断しなきゃいけなかったかもしれない』って……」
「あ………!」
(……死なないでくれ、ハヤブサ……)
結局俺は――――
シュバルツに、最後まで守られ て
「…………」
暫くして、幕舎からねねが出てきた。それに気が付いたお市が足早に寄ってくる。
「あの……どうでした? ハヤブサさんは……」
「泣いてるよ」
短くそう言って、幕舎の方に振り返るねね。お市もつられるように幕舎の中に視線を走らせて――――息を飲んだ。
そこには寝台の上で、シュバルツのロングコートを抱きしめる様にして震えている龍の忍者の姿があったからだ。
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
彼の悲痛な嗚咽が外まで漏れ聞こえてくる。ハヤブサのその姿と声に、お市まで貰い泣きしそうになってしまった。
「ああやって、ちゃんと泣いているんだ……。だから今は、そっとしておいてあげよう」
「ねね様……」
うっすらとその瞳に涙を浮かべているお市に、ねねは優しい笑顔を向けた。
「涙は、自分の心を癒すんだ。だから、ああやって泣いているハヤブサは、いつかちゃんと、必ず前を向ける」
「…………」
ねねのその言葉に、お市もついに泣き出してしまった。ねねは苦笑しながら、その肩を優しくポンポンと叩く。
「だから私たちは、それまでハヤブサを見守ろう? ね?」
「はい………」
お市は、涙ながらに頷いた。
一方太公望の前では、関羽と孫尚香と甲斐姫が、今回の戦の顛末の報告がおこなわれていた。
「……以上が、私たちの戦いの総てです……」
そう、淡々と報告していた孫尚香であるが、報告が終わると同時に涙を流し始めた。堪えていた物が、溢れだしてしまったのだろう。
「ごめんなさい……! 私がもう少し、しっかりしていれば――――」
報告の途中から、既にしゃくりあげていた甲斐姫は、涙ながらに謝罪の言葉を口にする。それに対して「いや、違う」と、声を上げたのは関羽だった。
「一番責めを負うべきは拙者だ……。拙者がもう少し早く、尚香殿を信じられていたら………もう少し、あの仁王に対して踏み込めていたら――――」
「関羽将軍……」
戦が終わって城に帰った後も、ずっと硬い表情を崩さなかった関羽。彼は目の前であの『悲劇』を見てしまったのだ。目の前に居ながらそれを防ぐ事が出来なかった事実は、彼に想像以上に重くのしかかって来ているのだろう。
「…………」
太公望は、孫尚香たちの報告を、終始無言で聞いていた。打神鞭を両手で持ち、無表情でその場に佇んでいる。
「太公望殿、お願いがござる」
やがて関羽が、何かを思い切ったように顔を上げ、太公望に声をかけてきた。
「何だ?」
「拙者を――――もう一度、過去に戻してはもらえないだろうか?」
「何?」
関羽のその言葉に、少し眉をひそめる太公望。それに対して関羽は、ガバッとその前に膝を付き、頭を下げて懇願しだした。
「あの時、拙者がいろいろと決断出来なかったばかりに、結局、あの義士たちを救う事が出来なかった……! これは、拙者にとって一生の不覚でござる! 出来ればもう一度過去に戻り、今度こそ、あの二人を救いたいのだ!!」
「…………!」
「関羽さん……!」
関羽の言葉に、泣きじゃくっていた孫尚香と甲斐姫もピタリと泣きやみ、思わず顔を上げていた。それに対して太公望は、腕を組んで、小さく息を吐いていた。
「……関羽将軍。話を聞く所によれば、素戔鳴と言う仙界の将軍の目には、あの『シュバルツ』と言う青年は、人の子にとって『害悪な存在』と言うふうに映っているようだ。下手をしたら本当に、そなたたち人の子に、害を為すかもしれぬ。それでも――――将軍は、かの青年を助けたいと言うのか?」
太公望からの試すような質問に、しかし関羽は迷わなかった。
「無論だ」
力強く頷く。
「あの青年は、他者を守ると言う事に何の躊躇も無かった。最期まであのハヤブサと言う青年を守りとおしていた。そのような事をする青年が『悪』とは、拙者には到底思えぬ」
「たとえそれが『人間』ではないとしてもか?」
更に試すような太公望の質問にも、関羽は揺るがなかった。
「『良い行い』をする者に、『人』も『妖魔』も、その区別をされるべきではない」
「―――――!」
「たとえあの青年が『人』であろうが『妖魔』であろうが、あの青年の行いは『善良』だ。ならば、助けるべき者だと、拙者は思う!」
後の世に『神』にまで祀り上げられる篤実な男が、こう断言する。それに対して太公望は「ふむ」と頷いてから、孫尚香と甲斐姫の方に視線を走らせた。
「そなたたちは、どう思う?」
「あの人は、村人たちにとても慕われていました。私も、あの人が『悪』だとはとても思えません。助けることが可能なら、助けるべきと思います!」
そう言い切る孫尚香の横で、甲斐姫も頷いていた。
「私はあの人がどれだけ村人を守るために身体を張っていたか、一部始終見ていました! あの人は絶対に『悪人』なんかじゃありません! あの人は、あそこであんな風に死んでいい人なんかじゃないんです!!」
「そうか……」
太公望は、手の内で打神鞭をトントン、ともてあそびながら眼を閉じていた。何事かを熟考しているかのようにも見える。と、そこに、1人の人間が乱入してきた。
「シュバルツを助けるために、俺を過去へ戻してくれ!!」
「―――――!」
その声の主の正体を知った皆は、一様に息を飲んでしまう。何故ならそれは――――先程戦場から大怪我をして帰って来て、幕舎に伏せっていた筈の、リュウ・ハヤブサの姿がそこにあったからだ。
「駄目だよ! ハヤブサ!! 大人しく寝ていないと――――!」
そう言って必死にハヤブサを引き留めようとするねねの手を払いのけると、彼は太公望の方へふらふらと歩み寄ってきた。
「お願いだ……! 俺を過去へ戻してくれ……! 今度こそ、シュバルツを助けたいんだ!!」
そう。
自分は、もう何度も素戔鳴と刀を合わせた。
素戔鳴の剣の軌道がどう動き、雷撃がどう走るか――――それこそ、今の自分ならば、手に取る様に分かるのだ。
ならば、立ち止まっている暇はない。
すぐにでも、愛おしいヒトをこの手に取り戻したいと、願う。
例え皆に反対されても、自分はもう引く気はなかった。
「無茶だよハヤブサ!! まずは身体を――――!」
「……………」
太公望は、フッと小さなため息をつくと、つかつかとハヤブサの方へ歩み寄ってきた。
「リュウ・ハヤブサよ」
怜悧な声でハヤブサに呼びかけると、彼はおもむろに打神鞭でハヤブサの折れている方の足を打った。
「うぐッ!」
当然その衝撃に今のハヤブサが耐えきれる訳もなく、彼は太公望の前に膝をついてしまう。そんなハヤブサに向かって、太公望は打神鞭を眼前に突きつけてきた。
「まず貴様は――――傷を治せ! その身体で過去へ飛んだ所で、一体何が出来る!?」
「…………!」
正論を言われて、ハヤブサはギリ、と、歯を食いしばった。
確かにそうなのだ。まずは、身体を治さなければならいと言う事を、ハヤブサも頭では理解していた。
だが今回の戦で、ケイタ達親子は助かっているし、村人たちと妖魔たちも、ある程度は助けられている。戦の功績的には満足してしまってもいい様な内容なのだ。それに皆が納得してしまって、シュバルツが置き去りにされてしまう――――そうなってしまう事を、ハヤブサはとても恐れていた。
「焦るな、龍の忍者」
ハヤブサのそんな心情を何となく察したのか、太公望が苦笑しながら諭す様な声を出す。
「誰も、『シュバルツ』を助けないとは言っていない。ただ、今はまだその時期ではないと言っているのだ」
「…………!」
驚き、息を飲むハヤブサに向かって、太公望は更に言葉を続ける。
「関羽将軍も、もちろんハヤブサ、お前も――――過去に戻ってもらう必要があるが、今すぐは駄目だ。いろいろと段取りを踏む必要がある」
ここまで言うと太公望は、ハヤブサから視線を上げて、時を渡る能力のあるかぐやの姿を求めた。
「かぐや! かぐやはいるか!?」
「はい、ここに―――」
太公望の呼び掛けに応じて、なよ竹の巫女かぐやが、楚々と前に進み出てきた。
「かぐやよ。一つ確認したいのだが――――ここに居るハヤブサとシュバルツの間には、過去の接点が出来ている。と、言う事は、ハヤブサの縁を使って、先程の戦に戻ることは可能だな?」
「はい。左様にございます」
太公望の確認に、かぐやは頷いた。
「ケイタ様の縁をたどり、ハヤブサ様が過去に行かれた事によって、ハヤブサ様とシュバルツ様の間には、新たな縁が産まれてございます。ですから、ここにいるハヤブサ様の縁を使って、先の戦の場に戻ることは可能にございます」
かぐやの説明に、太公望は「うん」と頷く。それから彼は関羽たちの方に振り返り、おもむろに口を開いた。
「そなた達の報告のおかげで、先の戦の状況が手に取る様に分かった。そして――――お前たちの戦に『何』が足りなかったのか、もな」
「…………?」
太公望が言わんとしている事が咄嗟に分からず、皆が怪訝な顔をする。それに太公望は「フフフ」と、笑みを浮かべると、パシン、と、打神鞭を手の内で鳴らしてから、言葉を続けた。
「……状況のお膳立てをしてやる」
「お膳立て?」
きょとんとする甲斐姫に、太公望はにやりと笑う。
「どうせなら、『全員』を助けないか?」
「え………?」
「村人が全員逃げられるように……あの青年を悲劇から助けられるように――――」
話しながらつかつかと歩く白髪の青年は今、完全に『策謀家』の顔をしていた。
面白い。
これは『運命の女神』からの挑戦状だ。
あの戦場が生贄として、村人の、そしてシュバルツとか言う者の『血』を何が何でも欲していると言うのなら――――
覆してやる。
この私の智謀で。
「この私が、状況を整えてやると言っているのだ。全知全能たるこの私がな」
「―――――!」
酷く不遜で、傲岸な物言い。しかし、それだけの事を言っても許されるほどの知略を、この太公望は兼ね備えていた。その彼が今――――本領を発揮しようとしているのだ。
「要は、あの日に至るまでの時間軸の中で、村人たちが最良の判断を取れる様に、そして、素戔鳴軍を迎え撃つ事が出来る様に――――状況を転がしてやればよいのであろう? 何、ちょっとしたパズルを組み上げる様なものだ。まあ、人の子たちの努力が相応に必要にはなってくるが――――」
そう言いながら太公望は、関羽たちの方にちらり、と視線を走らせる。すると、その視線を受けた関羽たちや、その周りの武将たちも――――目つきが変わった。太公望の挑戦的な物言いを、受けて立とうと言う眼差しだった。
その意気やよし、と見て取った太公望が、もう一度パシン、と、手の内の打神鞭を鳴らす。
「よし――――! では、使える『縁』は全部使う!! かぐやよ! 存分に働いてもらうぞ!!」
「は、はい!」
「では、半兵衛! 左近! ついて来い!! 生き残った村人たちと妖魔たちの話を聞きに行くぞ!! 片っぱしから、一人残らずだ!!」
「うえ!? マジですか!?」
「はいはい、分かりましたよ」
名指しされた竹中半兵衛は悲鳴を上げ、島左近は苦笑しながらその腰を上げる。そのほかにも何人か「私も手伝います」と、自主的について行く武将たちが居た。
「そして、龍の忍者!」
「――――?」
陣屋を出て行く直前の太公望に呼びかけられ、ハヤブサは振り向く。すると、太公望の方もゆっくりと振り向いて、打神鞭をピシッと、ハヤブサの方に向けてきた。
「最終的にはお前の『縁』を使う。だから、それまでに絶対に傷を治しておけ」
「言われずとも」
太公望の言葉にハヤブサは即答する。それを見届けた太公望は、フッとその面に笑みを浮かべると、すぐに踵を返した。
「では行くぞ!! ぐずぐずするな!!」
「ちょ、ちょっと待ってくださいよ! ねぇそこの君、生き残った村の人たちっていったいどれぐらいいるの?」
半兵衛の問いかけに、近くに居た兵が慌てて答える。
「あ、はい。きちんと把握している訳ではないのですが、100人弱ぐらいは、少なくとも……」
「100人!?」
「妖魔たちの数も合わせると、もっと増えると思います」
「う~ん……思ったよりは少ない、かな?」
そう言って苦笑する島左近に、半兵衛は顔をひきつらせながら答える。
「でも、どの程度まで詳しく話を聞けばいいのかも検討がつかないし……。うわ~! 意外に難作業かもしれないなぁ」
「……まあ、手分けして聞き取りましょう。皆でやれば、早く済む筈です」
そう言って励ましてくる真田幸村に、島左近も一つ、大きく息を吐く。
「……後は、使える『縁』がどれぐらいあるか、ですな。沢山あればいいんですが――――」
左近の言葉に、皆一様に頷いた。
「……どうしたんだ? あの坊やは」
太公望が陣屋から出て行った後、女媧が伏犠に声をかけてきた。
「いつも冷静なあの坊やが――――何だか、怒っているようにも見えるが」
女媧の言葉に伏犠は、はははは、と、軽く笑ってから答えを返した。
「……怒っておるのだろう。あの坊やは基本、人の子の方に肩入れをする。今回あれだけたくさん人の子たちに目の前で泣かれて、黙っていられなくなったのだろう」
伏犠のその言葉に、女媧もなるほどな、と、苦笑を返す。
「まあ、どっちにしろ、久々に本気を出した坊やを見られると言う訳だ。楽しみになってきたのう!」
そう言ってカラカラと笑う伏犠の横で、女媧は少し考え込んでいた。
「それにしても、二度も助けられなかったあの青年が少し気になるな……。変な『運命の悪意』に絡まれてなければいいが……」
「運命の悪意? 何じゃそれは?」
「たまにあるんだ。何をやっても、どうやっても救えない『命』と言うのが……」
「…………!」
小さく驚く伏犠に、女媧も苦い顔を見せる。
「もし、あの青年がその『運命の悪意』に魅入られていたら厄介だ。何度そこでその時間軸をやり直しても、どうやっても死んでしまう可能性がある。そうなってしまうと、我々も運命の階段(スパイラル)に取り込まれて――――」
「……同じ時間軸を、何十年、何百年と繰り返してしまう可能性があるのか?」
伏犠の質問に、女媧はそうだと頷いた。伏犠はしばらく考え込むように顎に手を当てて沈黙していたが、やがて、ぱっと明るい笑顔をその面に浮かべて顔を上げた。
「……それは笑えん話じゃが……しかし、大丈夫だろう」
「――――! 何で、そう思うんだ?」
問い返す女媧に、伏犠はあっけらかんと答える。
「ここに居る連中は、皆、そう言う『死』の運命を覆して来た者ばかりじゃ。今だって見てみろ。あの妖蛇に対抗する事など不可能と思われていた人の子たちが、それを可能にしつつあるじゃろう?」
「それはそうかもしれないが――――」
伏犠のこの言葉には、女媧も反論する言葉を失う。確かにそうなのだ。一度妖蛇の攻勢によって、滅びの淵まで追いこまれていた人の子たち。それが今や、妖蛇に対抗する兵力は膨れ上がり、それを攻略する糸口まで掴み取ろうとしている。最初2、3人の武将しかいなかった討伐軍の状態を考えると、それこそ、信じられない快挙だと言える。
「だから、今回もきっと大丈夫じゃ! それにあの坊やも手を貸すんだ。人の子たちの底力を信じようぞ!」
そう言ってカラカラと笑う伏犠の横で、女媧は小さくため息を吐いていた。
「……全く、楽観的でいいなお前は……。少し、羨ましいぐらいだ」
「そうか? お主こそ、あまり悲観的にはならぬ方がいいぞ? でないと――――」
「でないと――――何が言いたい?」
「…………!」
女媧がじろりと睨んでくるので、伏犠は慌ててその口を塞いだ。女性に対してかなり失礼な物言いをしようとしていた事に気付いたからだった。
「何でもないが…………聞きたいか?」
「聞きたくない!!」
つっけんどんに答えを返してくる女媧に、伏犠はまたからからと笑った。
「まあ、まずは坊やのお手並みを拝見といった所かのう。我々にも出番があると良いがな」
「……………」
伏犠のその言葉には、女媧は答えを返さなかった。ただ――――今度こそ、ハヤブサの願いが叶えばいい。女媧はいつしか、祈る様にそう思っていた。
第5章
ブン!!
幕舎の中に、木刀が空を切る音が響き渡る。寝台の上で身を起こしているリュウ・ハヤブサが木刀を素振りしている音だった。あちこち傷を負ったその身体には白い包帯が巻かれているが、ハヤブサの素振り自体の動きはとても綺麗な物だった。
ブン!!
彼は目を閉じ、左手一本でひたすら素振りを続けている。木刀は正中線からまっすぐに、迷いなく振り下ろされ続けている。もうどれくらい彼がそれを続けているのかは不明だが、彼の上半身からは汗が滴り落ちていた。
「お、やっているな」
ハヤブサにそう声をかけながら、宮本武蔵が幕舎の中に入ってくる。ハヤブサは素振りを止めて顔を上げると、その面に笑みを浮かべた。
「木刀の貸与、感謝する。良い木刀(もの)だな」
「何、戦の合間に手慰みに作ったものだ。良かったらそのまま使っていてくれ。こういう時――――素振りをする得物は要るだろう?」
「そうだな……」
ハヤブサはそう言うと、一つ大きな息を吐いて、木刀を中段に構えた。そして左手一本でまた素振りを始める。
ブン!!
また、迷いなく綺麗に振り下ろされる木刀。
「…………」
武蔵はしばらく腕を組んでハヤブサが素振りをする様子を見守っていたが、やがてふっとその面に笑みを浮かべた。
「……ハヤブサ。早く傷を治せよ。また、お前と手合わせがしたい」
武蔵のその言葉に、ハヤブの面にも笑みが浮かぶ。
「……そうだな。こちらからもぜひ――――」
「こらっ! 早く傷を治したいのなら、あんまり無茶しちゃ駄目だよ!? ちゃんと休んでないと、また傷が開いたりするんだから――――」
「――――!」
そこにねねが入ってきたため、二人の会話は中断される事となった。ねねはハヤブサに持ってきた食事を脇へ置くと、すたすたと傍に寄ってきた。
「気分はどうだい? 顔色は、だいぶ良い様だね」
「ああ。無理はしていない。ただ……少しでも身体を動かしておかないと、なまってしまうからな」
「そうだぞ? 素振りは剣士にとっては呼吸をするようなものだ。こんなの、無理の内にもはいらねぇよ」
武蔵のその言葉に「ふ~ん、そんなもんかねぇ」と呟くと、持ってきた手ぬぐいと包帯を取り出した。
「ほら、とりあえず木刀を置いて、これで汗を拭きな。終わったら、包帯を取り替えてあげるから」
ねねの言葉に、ハヤブサも大人しく従った。
「――――うん! たいぶ傷も良くなってきているね。若いって良いね~!」
ハヤブサの包帯を変え終わったねねが、そう言って満足そうに頷いている。しかしそれに対してハヤブサは、「もっと早く治って欲しいのだがな……」と、少し零し気味に呟く。彼の視線の先には、折れて動かない足が横たわっていた。
「こればっかりは仕方がないよ。日にち薬だ」
ねねはそう言いながらハヤブサに食事を差し出す。
「ほら、これをしっかり食べて、少し休みな。ちゃんと食べて、ちゃんと寝る。これが結局、身体を治すのには一番効くんだから」
ハヤブサは寧々から黙って食事を受け取ると、丁寧に手を合わせて食事に向かって一礼をして――――それから食べ始めた。
(……食欲もある様だね……。良かった……)
ハヤブサの食事の様子を見ながら、ねねは秘かに胸を撫で下ろす。一番最初にシュバルツを失った時のハヤブサの様子からすると、今の彼はずいぶんと落ち着いているように見える。やはり、過去に戻ってシュバルツを救える『希望』があると言う事と、太公望の「最後にはお前の『縁』を使う」と言う言葉が、ハヤブサを支え、立ち直らせているのだろう。
しかし――――
「……………」
ねねは、無言でハヤブサの寝台の横に立てかけられている龍剣の柄を見る。そこに巻かれているシュバルツのロングコートの切れ端が、いつの間にか二つになっていた。
(……人の『死』に慣れる事なんてない……。やはり、ハヤブサは傷ついているし、苦しんでいる……)
この切れ端の数が、そのままシュバルツを救えなかった『回数』だ。おそらく自戒と自責の念が込められているであろうその切れ端に、ねねは何とも言えない気持ちになる。
でも――――だからと言って、今のハヤブサに自分が何を言ってあげられるだろう。
そう考えた時に、言ってあげられる言葉が咄嗟に思い浮かばなくて、ねねは少し困ってしまう。結局はハヤブサ自身の『強さ』に頼るしかない、静観するしかないのかなと、苦笑するしかなかった。
「ところで――――太公望の策ってあれからどうなっているんだ? ちょっとは進んでいるのか?」
武蔵からの質問にはっと我に帰ったねねは、「え~と……」と、首を少し傾げた。
「何かいろいろやっているみたいだけどね。傍から見ていても訳が分からなくて――――」
ねねがそう言っている間にも、幕舎の外から太公望の話し声が聞こえてくる。何人かの武将に指示を出し、その後ろからかぐやがいそいそとついて行っていた。また誰かを、『時渡りの術』で過去へと送るらしい。
暫く無言でその様子を幕舎の中から見つめていた3人であったが、やがてハヤブサがポツリと口を開いた。
「……俺は、早く傷を治さなければならないな……」
「焦るなよ、ハヤブサ」
その声を聞き咎めた武蔵が、そうハヤブサに声をかけてくる。
「そうだよ、ハヤブサ。今はきっちりと怪我を治す事だけを考えるんだ」
ねねも笑顔でそう声をかけてきた。
「太公望だって、ハヤブサの怪我が治るのをちゃんと待ってくれるよ。だから、良いイメージを持つんだ。今度はきっと、何もかもがうまくいくってね」
「イメージか……」
茶から立ち上る湯気を見つめながらハヤブサはポツリと呟く。
「………………」
そのまま押し黙ってしまうハヤブサ。その姿は思い詰めているようにも見えるし、何かに集中しているようにも見えた。
「ハヤブサ? 大丈夫かい?」
「―――――!」
ねねに声を掛けられて、ハヤブサははっと我に帰る。
「ああ………」
軽く答えて茶をすすった。その様子にねねは苦笑すると、一つ息を吐いてハヤブサから離れた。
「とにかくゆっくり食べて、良く休むんだよ? 食器はそのまま置いておいてくれたら、また下げに来るから――――」
「ありがとう」
そう言って軽く頭を下げるハヤブサにねねも笑顔を返すと、そのまま幕舎から出て行った。「無理するなよ」と、言い置いて、武蔵もその後に続いて出て行く。
「……………」
独り残されたハヤブサは、また、茶から立ち上る湯気をじっと眺めていた。
「……ハヤブサ、ちゃんと休むかねぇ」
ねねが、後ろからついて来ている武蔵に言うともなしに呟く。それに対して武蔵は「さあな」と肩をすくめた。
(ありゃあ「休め」と言った所で、休むような雰囲気ではないな……。さっき茶を黙って見つめていた時も、思い詰めると言うよりは、何かに集中していたような感じだった……。まあ、だからこそ一流の『剣士』たりえるのだろうが……な)
『強さ』は、本人の資質だけでどうにかなる物ではない。強いと言われる人たちは皆、常人の何十倍もの努力をして、力と資質を磨き上げているものなのだ。
(俺も負けてらんねぇな……。修業しないと――――)
武蔵は大きく息を吐いて前を向くと、愛刀を片手に歩きだしていた。
(イメージ……。確かに、俺はイメージしているな……。素戔鳴と戦う時のイメージを……)
幕舎の中でハヤブサは、茶の湯気を見つめながら、イメージを始める。描く相手は、あの素戔鳴の姿だ。
あの剣がどう動くか。
雷撃がどう走るか。
攻撃のモーションは。
それをどうかわすか。
受けるか。
何処で踏み込むか。
イメージしろ。
可能な限り。
イメージ
そして、集中―――――
「…………」
ハヤブサは湯飲みを傍らに置くと、また木刀を握りなおして左手一本で素振りを始めた。刀を振る時に一番重要なのは左手の動きだ。その基本動作を何度も確認するように、ハヤブサは木刀を振り抜く。
まっていろ、素戔鳴。
今度こそ、お前を倒す。
そしてシュバルツ
今度こそ――――お前を、守り抜いてみせる!
幕舎の中を、木刀の空を裂く音が何度も響き渡る。ハヤブサの身体からはまた、汗が滴り落ち始めていた。
巫女かぐやは辟易していた。
とにかく太公望からは次から次へと術の要求が来る。しかも、飛ばす時間軸も戦場もバラバラと来ているものだから、彼女自身目が回りそうになっているのだ。
「だ、大丈夫? かぐちん!」
そんな彼女の横で、甲斐姫が心配そうにしていた。
「お水を持って来たよ! とにかく飲んで、一息入れて?」
そう言いながら甲斐姫は、かぐやに向かってコップに入った水を差し出す。
「ありがとうございます。甲斐様……」
かぐやは甲斐姫からコップを受け取ると、こくこくと水を飲み干した。いつもしとやかな彼女からしたら勢いが良すぎるほどの飲み方なのだが、水一杯も飲みかねるほど、彼女は休む間もなく術を発動させ続けていた。
「助かりましたわ、甲斐様。ありがとうございます」
「甲斐『様』なんて呼び方は止めてよ。甲斐『ちん』で良いって言っているのに」
そう言って笑う甲斐姫の表情に、哀しげな陰りがあるから、かぐやも瞳を曇らせてしまう。
「甲斐様……大丈夫ですか? 戦から帰ったばかりなのですから、少し、お休みになられた方が――――」
「ううん、大丈夫だよ。私はどこか怪我をしている訳でもないから――――」
そう。
私は守られていた。
いつだって
何時だって―――――
だから
「それよりも、かぐちんの事手伝わせて。あんまり役に立たないかもしれないけど、何かしていた方が落ち着くから――――」
「甲斐様……」
あまりにも哀しげな微笑みを浮かべる友人に、かぐやもさすがに心配になる。そろり、と、かぐやから彼女に伸ばされる手。だが、それが届く前に、またも太公望から呼び出しがかかった。
「かぐや!! 何をしている!! 次の術の準備だ!!」
「は、はい! ただいま参ります!」
かぐやは太公望にそう返事をすると「それでは甲斐様、また後で」と、言い置いてそこから走り去って行った。
「かぐや、待ちかねたぞ」
かぐやが太公望の元に行くと、次の戦場に行くであろう武将たちが、もうそこで待っていた。
「申し訳ございません。すぐ、準備いたします」
かぐやがそう言って術の準備をしている横で、太公望がそこで待機している徐晃と張遼に何事かを耳打ちしている。どうやら、次の戦場でやっておいて欲しい事の確認の様だった。
「承知いたした。この張遼、そのお役目を果たして御覧にいれる」
「徐公明、確かに承った!」
「うむ、頼んだぞ」
二人は太公望に頷いてから、かぐやの方へ歩み寄ってくる。
「では、御二方とも、思い浮かべられませ。貴方方が向かうべき戦場を――――」
二人の武将を光陣へと招き入れたかぐやは、時渡りの術を発動させる。また、今回も滞りなく術をかけられた事に、かぐやはホッと息を吐いた。
「かぐや、大丈夫か?」
そんな彼女に女媧が声をかけてきた。
「頻繁に術を発動させすぎだ。少し、休んだ方が――――」
「いえ、大丈夫です」
かぐやはその言葉に首を振る。
「太公望様の策、私も早く推し進めたいのです」
「それは……何故だ?」
少し、怪訝な顔をして問う女媧に、かぐやは「それは……」と、言ったきり言い淀んでしまう。ただ、そう言いながらちらりと視線を走らしたその先には、遠くの方を見つめながら佇んでいる、甲斐姫の姿があった。
「………友人のため、か?」
女媧の言葉に、かぐやは静かに頷いた。
「沈む甲斐様のお心を御救いするには、先の悲劇を早く御救いするしかないかと――――」
「なるほどな……」
かぐやのその言葉に、女媧はため息を付きながら顔を上げる。落ち込む甲斐姫の姿が、かぐやに発破をかけてしまっているようだ。そんな事はないと思いたいのだが、そうなる事も太公望の計算の内に入っているのではと、勘繰ってしまいたくもなる。
「……頑張るのは良いが、本当にきつくなってきたら、ちゃんと私に言えよ? 私が坊主にきっちりと話してやるから」
「ありがとうございます、女媧様……」
女仙二人がそうして話している横で、呉の軍師二人―――呂蒙と陸遜が額を付き合わせて悩んでいた。
「……それにしても厄介だな……。敵の見分けがつかない戦場と言うのは――――」
「本当にそうですね……。見分けがつかないと、咄嗟の時にどうしても動くのが一歩遅れてしまいます」
「尚香様が――――姫様が言われていた不自由を、何とかして解決して差し上げたいが、はて、どうしたものか―――――」
と、そこに上半身に龍の刺青を施し、巨大な鈴を身につけた甘寧(かんねい)と言う武将が顔を出してきた。
「何でぇ、そんな事なら味方になる妖魔たちの方に、目印を付けちまえばいいじゃねぇか」
「…………えっ?」
顔を上げる軍師二人に、甘寧は目をぱちくりとさせた後、にやりと笑いながら言葉を続けた。
「俺が『湖賊』だった時によく使った手だ。少数の兵で大勢の大軍に夜討ちをかける時に有効だったんだよ。味方の兵の方に、大きなガチョウの羽根を目印につけておいて――――」
「それだ!!」
いきなり呂蒙が大声で叫ぶから、後の二人がびっくりして耳を押さえてしまう。
「り、呂蒙殿!?」
「それだ……! 甘寧の言うとおりだ!! あの妖魔たちに、目印になる様なものをつけてもらおう!!」
「そ、それはそうですが……」
「つけてくれるかね? て言うか、何をつけるんだ?」
甘寧の疑問には応えずに、呂蒙は立ち上がった。
「半兵衛殿!! 半兵衛殿はいらっしゃるか!?」
「――――半兵衛殿なら、村人たちと妖魔たちの証言をまとめ上げた所で―――――『起こさないでください』という立て札を立てて、幕舎の中で寝ていますよ」
呂蒙の呼び掛けに、半兵衛ではなく、長い黒髪をさらりとなびかせながら、もう一人の呉の軍師がそこに入って来て答えた。
「周瑜殿!」
「今までどちらにいらしていたんですか?」
陸遜の問いかけに、「ああそれは――――」と、周瑜が軽く言い淀んでいると、彼の後ろから妻である小喬がひょこっと顔を出してきた。
「周瑜様も、その作業を手伝ってたんだよね~」
彼女のその言葉に、周瑜は軽く咳払いをする。
「ああ、まあその……私もそれなりに、時間があったからな……」
「そうですか……。しかし、半兵衛殿に話が聞けないとなると……弱りましたな」
「呂蒙殿? どうされた?」
周瑜の問いかけに、呂蒙はポリポリと頭をかく。
「いや……今思いついた策を実行しに、過去の妖魔の村に行きたいのですが、どの妖魔の『縁』を使っていいのかが、我々では分かりかねるので………」
「―――ここに、村人たちの証言をまとめた書があるぞ」
「――――!?」
「こちらには、妖魔の証言をまとめた書が」
「しゅ、周瑜殿? これは一体――――」
茫然と問う陸遜に、周瑜は軽く咳払いをすると、言葉を続けた。
「大したものではない。半兵衛殿がまとめたものを写しただけのものだ」
「それにしても……あれだけの短時間でよくもまあここまで――――」
周瑜からその書物を受け取った呂蒙が、感心しながらパラパラと頁をめくっている。それほどまでに村人たちと妖魔たちの証言が、よくまとめられたものになっていた。
「当たり前だ! 優秀な者たちが皆で協力したのだ! 出来が悪ければ、逆に困る」
そう言いながらそっぽを向く周瑜だが、呂蒙の方が既に聞いていない。書物を集中して読みふけっている。
「よしっ! この辺りの妖魔たちに早速声をかけてみよう! 行くぞ陸遜!!」
「はい! 分かりました! 呂蒙殿!!」
言うが早いが、二人はあっという間に幕舎の外に飛び出して行ってしまう。
「あ!! ずるい!! おっさん!! 俺も置いて行くなよ~!!」
そう叫びながら甘寧も二人の後を追って幕舎から出て言ったものだから、中には周喩と小喬の二人だけが残される事となった。
「……………」
無言で椅子に腰を下ろす周瑜。そんな彼を、小喬が覗き込んできた。
「周瑜様、疲れてる?」
「………疲れてなどいない、と、言ったら嘘になるな。さすがに疲れた……」
「周瑜様、頑張ったものね」
「仕方がないだろう……。尚香様に、あんな哀しげな顔をされてしまっては――――」
小喬の言葉に苦笑を返す周瑜に、彼女も笑顔を返す。
「じゃあ、頑張った周瑜様をお慰めするために、私は歌を歌ってあげるね!」
その言葉が終わってすぐに、幕舎の中に愛らしい歌声が響き始めた。周瑜は目を閉じ、愛妻の歌声にしばし、その耳を傾けるのだった。
一方、かぐやの傍で彼女の世話を焼いていた甲斐姫の前には、孫尚香が来ていた。その隣には、甲斐姫の主である北条氏康の姿もあった。
「甲斐……大丈夫? ちゃんと休んでる?」
「ううん、私は大丈夫。そんなに疲れている訳ではないから――――」
友人の気遣いに、甲斐姫は笑顔で答える。そんな甲斐姫の様子を、孫尚香はしばらく無言で見つめていたが、やがて意を決したように声をかけてきた。
「甲斐……私たち今から、『過去』へ行くの」
「えっ…………?」
「太公望様の命令で……。私にも、状況を転がすために出来る事があったみたい」
「そうなんだ……」
孫尚香の言葉に、甲斐姫は一瞬複雑な表情をする。だがすぐに、その面に笑みを浮かべた。
「すごいじゃん!! 頑張って来てよ!!」
「甲斐………」
無理やり笑みを浮かべている友人の姿に、孫尚香は逆に瞳を曇らせた。
「私はここで……応援しているからさ」
「一緒には来ないの?」
「えっ………?」
友人の言葉に驚く甲斐姫に、主である北条氏康が声をかけてきた。
「今から行く過去に、後もう一人だけ連れて行く事が出来るんだ」
「だから甲斐……。私は、貴方に一緒に来て欲しいんだけど……」
そう言って孫尚香は、甲斐姫に手を差し出す。
「あ…………」
甲斐姫は、しばし友人の差し出された手を眺めていたが、一歩後ずさって首を振った。
「ううん、遠慮しとく」
「甲斐………」
瞳を曇らせる友人に、甲斐姫は努めて笑顔を見せた。
「あ、ほら! 頑張っているかぐちんの事をほっとけないっていうかさ! もうちょっとだけ、ここで落ち着いておきたいっていう感じで……!」
そう明るく切り返してくる甲斐姫を見て、孫尚香の瞳はますます曇ってしまう。そんな二人の様子を見て、氏康はふっとため息をつくと、甲斐姫の頭に手を伸ばしてきた。そのまま彼の武骨な手が、彼女の頭をグシャッと、撫でる。
「………坊主、お前がそう言うなら、もう無理に誘いはしねぇが……あんまり考えすぎるなよ」
「御館様……」
「無い頭で考えた所で――――ろくな答えなど出やしねぇんだからな」
「な――――! 余計なお世話ですっ!」
眉を吊り上げて怒る甲斐姫に、北条氏康は軽く笑った。
「そう言い返せるのなら、大丈夫だな。坊主、留守は任せたぞ」
「は、はい!」
氏康の言葉にしゃきっと姿勢を正した友人の姿を見て、孫尚香もようやく笑顔になる。
「じゃあ甲斐。行ってくるからね」
「うん! 御館様! 尚香! 気をつけてね!」
ぶんぶんと元気よく手を振って、二人を見送る甲斐姫。そんな彼女に見送られながら、氏康と孫尚香は、かぐやの『光陣』の中へと進んで行って、そのまま消えて行った。
(いいな……。尚香には、できる事があるんだ………)
二人を見送った後、甲斐姫は何とも言えない気持ちになる。
本当は、少しも大丈夫ではなかった。
「考えるな」と言われても、どうしても考え込んでしまう。
あの戦で自分は
どうすれば
どうすれば――――よかったのだろう。
守られてばかりだった。
本気で役に立たなかった。
あの人に、余計な怪我を負わせて
止める事が出来ず
揚句――――間に合う事も出来ずに
「…………!」
ギュッと、握りしめられる拳。
何がいけなかったのだろう。
何を、間違ってしまっていたのだろう。
ただ明確に分かる事は、『今の自分は力不足だ』と言う事だけだった。
悔しい。
強くなりたい。
強くならねばならない。
だけど、一朝一夕で強くなれる訳など無い事も、彼女はよく分かっていたから。
「……………」
何をどうすればいいのか分からなくなって、彼女は立ちつくしてしまう。
先程の友人の誘いを断ったのもそうだ。
自信が無かった。
もしも自分が戦いに関わったせいで、また尚香たちの足を引っ張ってしまったら――――
そう考えてしまうと、身動きが取れなくなってしまう。
こんな自分が、堪らなく嫌だった。
でも、ならば、どうすればよかったと言うのだろう。
いくら考えても、答えなど出はしないのに。
「甲斐様……? 大丈夫ですか?」
「――――!」
目の前に自分を気遣う様な、かぐやの優しい顔があって、甲斐姫ははっと我に帰った。
(いけない……! 何をやっているの!? 甲斐! かぐやの方が大変なのに―――)
甲斐姫は一つ息を大きく吸い込むと、おもむろに両の手で自身の頬を、パシン! と、強く叩いた。
「か、甲斐様!?」
「おっしゃああっ! 気合注入!!」
茫然とするかぐやの前で甲斐姫は、一声、そう雄たけびを上げると、ニカッと笑ってかぐやの方に振り返った。
「大丈夫だよ! かぐちん! 心配してくれてありがとう!」
「か、甲斐様……!」
そろり、と、かぐやの手が甲斐姫の方に伸ばされようとする。だがすぐに、太公望の彼女を呼ぶ声が飛んで来て、その動きを遮った。
「かぐや!! 何をしている!! 次の術を急げ!!」
「――――ほら、かぐちん、呼んでるよ。行って来ないと」
「ですが、甲斐様……!」
「私は大丈夫だよ! それよりも、かぐちんお腹すいてない? おにぎり握って来てあげるね!」
そう言うと甲斐姫は、小走りに走りだした。
(とにかく今は、後方支援に徹しよう)
術をかけ続けるかぐやを、せめて力づけてあげられるように。
戦に向かう皆に、余計な気遣いをさせないように――――
それが、今自分の出来る精一杯なのだと、彼女は感じていた。
(甲斐様……)
無理して笑い続ける友人の姿に、かぐやの胸が締め付けられる。
(やはり……早く、先の悲劇を御救いしなければならない……)
強く感じてかぐやもまた顔を上げた。太公望がどうやって時間の流れを書き換え、状況を動かしているのかが自分では分かりかねるが、前に進んでいるのは確かな事なのだろう。
だから、自分は太公望の求めるままに、術を発動させ続ける。
友人の真の笑顔を取り戻すためにも――――
「今度こそ、悲劇を救う」
皆がそれぞれ強い想いを込めて、動き続けていた。そうして、幾日かが過ぎて行った――――。
「……………」
寝台に腰をかけ、日課の素振りを終えたハヤブサは、ふうっと息を一つ吐いていた。
身体に巻かれていた包帯は、大分取れた。痛みも、かなりましになって来ていた。ただ一ヵ所を除いて――――
「…………」
ハヤブサは立ち上がろうとして、足に力を込める。しかし。
「――――ぐッ!」
激しい痛みを感じて立つ事に失敗してしまう。
(……当たり前か。完全に折れていたんだ。そう簡単にくっ付く筈がない――――)
そう感じて、ハヤブサは思わず苦笑してしまう。こんな怪我、簡単に治るのはシュバルツぐらいなものだ。当たり前な話だが、こんな時、自分はどうしたって普通の人間であると言う事を、否が応でも痛感せざるを得ない瞬間でもある。
(やはり……俺にはDG細胞は感染(うつ)らないのか……。あれだけ濃密に触れ合っているのに……)
そう感じて、ため息をつく。シュバルツならばこんな怪我、1時間としないうちに治ってしまうのだろう。
感染(うつ)してくれていいのに。
ハヤブサは強く思う。
俺も、お前と同じ『人外』になれれば――――
お前が今感じている苦しみや孤独を、共に背負ってやる事が出来るのに。
『お前は独りじゃない』
本当に、そう思わせてやる事が出来るのに――――。
だが現実は、何処まで行っても自分は人間の身体のままだ。ため息を付きつつ、ハヤブサは杖を持って寝台から立ち上がろうとする。体力づくりとリハビリを兼ねた歩行訓練に出るつもりであった。―――と、そこに、伏犠がかぐやを伴って入ってきた。
「よう、ハヤブサ。調子はどうじゃ?」
そう陽気に声をかけてくる伏犠の後ろで、かぐやが軽く頭を下げてくる。ハヤブサも立ち上がるのを止めて、寝台に腰を下ろしたまま軽く会釈をした。
「おかげで怪我はだいぶ良くなりました。しかし……」
そう言いながらハヤブサは、動かぬ己が足に視線を落とす。それを見て伏犠は「ふむ」と、一声発すると、持ってきた袋の中からある物をハヤブサに差し出した。
「…………!」
それを見たハヤブサの顔が、一瞬強張る。何故なら、伏犠の手の中にあった物が『仙桃』であったからだ。
「ああ、そう警戒せんでも良いぞ?」
ハヤブサの『仙桃』に対する複雑な心情を察した伏犠が、苦笑しながら声をかけてくる。
「これはわしの管轄する農園で採れた、正真正銘、わしの手持ちの『仙桃』じゃ。変なしがらみも無い故、遠慮せずに食べてもらって構わん」
「……………」
ハヤブサは、とりあえずそれを無言で受け取ったが、すぐにそれを食べる気にはなれなかったようだ。
「気持ちはありがたいが……何故、これを俺に?」
至極もっともな質問を、ハヤブサは伏犠に投げかけてきた。
「うむ、それはじゃな……」
「太公望様の『策』が滞りなく進み……後は、ハヤブサ様を待つだけになりましてございます」
伏犠の後を受けて、かぐやが答える。その言葉に、ハヤブサは驚いた。
「本当か!? それは……!」
「はい。ですので、早急にハヤブサ様の傷を癒すようにと……。私も治癒の術の心得がございますので、微力ながらお手伝いさせていただきたく存じます」
そう言って頭を下げるかぐやに、ハヤブサはただただ息を飲むしかない。
「存外、早く策が進んだようじゃ。その進捗ぶりに、太公望の方が目を回しておったぐらいでのう!」
「…………!」
「さあ、ハヤブサ様、仙桃をお召しになってください。その力を借りて、ハヤブサ様の足の傷を治します故――――」
「何故だ………?」
思わず仙桃を持つハヤブサの手が震えてしまう。
「何故、とは……?」
「『シュバルツを助けたい』と言うのは、妖蛇討伐には全く関係の無い話だ。俺の個人的な願いなのに、何故皆そこまで………」
「それはもう、言わずもがなじゃろう、ハヤブサ」
ハヤブサの言葉に伏犠は苦笑する。
「『仲間』の危急には、手を差し伸べずには居られない――――それが、人の子と言う者ではないのかね?」
「――――!」
「ここに至るまでにお主は、仲間のために戦い続けてきた。皆を助けておるのだ。それが実を結んだ。……ただそれだけの事と、わしは思うぞ」
「あ…………!」
茫然とするハヤブサの肩を、伏犠がポンとたたく。
「だから堂々と仙桃を食べて、身体を治せ、ハヤブサ。今はまだ、状況が整っただけにすぎん。総てはこれからだ」
「分かった」
伏犠の言葉に、ハヤブサもようやく仙桃を食べる決意がついた様だ。彼は伏犠に向かって軽く頭を下げると、仙桃をかじった。一口食べるごとに仙桃の薬効成分がハヤブサの身体に沁みわたり、力がみなぎってくる。
「ハヤブサ様、怪我をなさっている方の足をお出しください」
仙桃をハヤブサが食べ終わるのを待ってから、かぐやは彼に声をかけた。言われたとおりにハヤブサが足を出すと、玉串である榊の枝を、そっとハヤブサの足に当てた。
「……………」
口の中で誦が詠唱されると同時に、榊の枝が金色に光り出して――――
「―――――」
足からもたらされていた痛みと熱が、劇的に引いて行くのが分かる。ハヤブサは目を閉じて、その感覚を味わっていた。
「もういい筈じゃ。ハヤブサ、立ち上がってみるんじゃ」
伏犠に声を掛けられて、ハヤブサは立ち上がってみた。
立てる。
今までどおりに。
ハヤブサが『歩け』と命を下すと、足は主の命令を忠実に実行した。
「大丈夫そうか?」
問うてくる伏犠に、ハヤブサはこくりと頷く。
「少し身体を動かしたい。時間を貰えるか?」
「勿論」
ハヤブサの言葉に2人が頷くのを確認してから、彼は木刀を引っ提げて幕舎から出ていく。するとそこに、宮本武蔵が待ち構えていた。
「ようハヤブサ。手合わせの相手を探しているんだろう? 俺でよければ相手してやるぜ!」
その横に何人かの武将たちが控えていたが、皆頭にこぶを作ったり、手を痛そうに押さえたりしている。どうやら、ハヤブサと手合わせするための順番争いが、つい先程までそこで行われていたらしい。そして、勝ち上がった勝者が宮本武蔵と言う訳だ。
(―――面白い!)
俄然、龍の忍者の闘争心に火が点いた。木刀を握りしめるハヤブサに、武蔵から問いかけられる。
「真剣でやるか?」
その問いに、しかし龍の忍者は首を振った。
「木刀で充分だ」
ハヤブサにしてみれば久しぶりの実戦だ。寸止めの感覚に、少しの不安を覚える。それに、武蔵ほどの技量の持ち主であれば、例え木刀であろうとも、充分に真剣同等の威力を発揮し得た。
陣屋の中でも少し広い空間がある場所に移動して、二人の剣士が相対する。その周りを二人の戦いを少しでも見ようと、武将たちが取り囲んだ。
ハヤブサが一振りの木刀を正眼に構え、武蔵が二振りの木刀を構える。ただの手合わせとはいえ――――二人の剣士から漲る気迫は、実戦その物の様であった。
(イメージ……。イメージしろ……)
ハヤブサは、武蔵の姿の向こうに、素戔鳴の姿を思い浮かべる。自分が相対し、絶対に越えなければならないその姿を。
(ム…………)
ハヤブサから漂ってくるただならぬ「気」の気配に、武蔵の方も油断なく身構える。
身体中の警報が鳴っていた。
少しでも気を抜いたら――――
ヤラレ ル
ドン!! と、激しい音を立てて、龍の忍者が踏み込んでくる。
「――――!」
その鋭い突きを、武蔵は二本の木刀で受けた。
もう一度、ハヤブサは踏み込みと共に木刀でなぎ払う。
ガキッ! と、激しい音を立てて、木刀同士がぶつかり合った。しばらくそうして二人の間で、激しい木刀のぶつかり合いの応酬が起きる。ガツン! ガツン! と、音が鳴り響く中、取り囲んでいた武将たちも皆、固唾をのんで二人の戦いを見守っていた。
ガキン!!
何合目かの太刀を合わせた瞬間、いきなりハヤブサの姿が武蔵の前から消えた。
「――――!?」
「消えた!?」
「違う!! ハヤブサ殿は消えてはいない!!」
徐晃の叫びに張遼が答える。
「ハヤブサ殿は、上だ!!」
張遼の指摘の通り、上を見上げると高々と跳び上がっている龍の忍者の姿が見える。そのままハヤブサは大上段に振りかぶって、裂帛の気合とともに武蔵に襲いかかってきた。このままこちらを真っ二つにする構えだ。
「叭――――――ッ!!」
「なめるなぁぁぁぁっ!!」
武蔵も二振りの木刀を振りかざした。真っ直ぐに突っ込んでくる相手。対応する手はいくらでもあった。
ガキィッ!!
激しくぶつかり合う音と同時に、交錯する二つの身体。折れた木刀の切っ先が、ドスッと音を立てて地面に突き刺さった。みると、武蔵の二振りの内の一本の木刀が、へし折られていた。
「……………」
そしてハヤブサも武蔵も――――互いの喉元に、それぞれの木刀の切っ先が突きつけられている。
「相討ちか」
そう言って木刀を引くハヤブサに
「違う。俺の負けだ」
と、武蔵が答える。
「それは、何故でござるか?」
張遼も二人が相討ちだと思っていたので、少し意外に感じて武蔵に問う。すると武蔵は地面を見つめて何かを探すような仕種をして、やがて求める物を見つけたのか、それを拾い上げた。
「お前、上から俺に接近しながら、俺に向かってこの礫(つぶて)を投げただろう」
そう言いながら武蔵は、ハヤブサに向かって手の中の小さな礫を差し出す。
この礫はハヤブサから放たれて、自分の右肩に当たった。殺傷能力の無い小さな礫は、武蔵の着物に柔らかく当たってそのまま地面に落ちた。だがこれが、クナイや棒手裏剣と言った武器だったらと思うと、武蔵は背中に寒気が走るのを感じる。利き腕の方の肩をやられてしまった自分は、その後の剣を振る事など出来なかったであろう。
「これを俺は避けきれなかった。この時点で、勝負は俺の負けなのさ」
そう言って苦笑する武蔵に、徐晃も張遼も「なるほど」と、納得する。ハヤブサは、武蔵の言葉を聞きながら木刀を収めて、彼に向かって静かに頭を下げていた。剣の達人である武蔵の動きは、素戔鳴の一つ一つの技の動きに比べると、はるかに隙が小さいものだと言って良い。それでも、あの礫を彼の身体に当てる事が出来た事は、ハヤブサにとっては大きな収穫であると言って良かった。この技が武蔵に通用したと言う事は、素戔鳴にも間違いなく入る筈だ。
それにしても恐るべきは武蔵のその慧眼だった。
あの小さな礫一つ放つ自分の動きを見逃さず、その意をくみ取った。
次は――――同じ手は二度と、通用しないだろう。
「ハヤブサ、『素戔鳴』は強かったか?」
「――――!」
不意に武蔵にそう問われてハヤブサは少し驚いたが、素直に頷いた。
「そうか」
ハヤブサの答えに武蔵は満足そうに頷くと、その面にニカッと笑みを浮かべた。
「ハヤブサ! 今度は絶対勝てよ? で、帰ってきたらもう一回手合わせをやろうぜ!」
「承知した」
ハヤブサも頷き、ほっと一つ息を吐いた。以前と同じかそれ以上に動いてくれた身体が、ハヤブサには素直に嬉しく感じられた。
(良かった……。これでもう一度、シュバルツを助けに行ける……)
とにかく一度龍剣を取りに幕舎に戻ろうと、ハヤブサは踵を返す。そこで、木陰から隠れるようにこちらの様子を伺っていた甲斐姫と、ばったり目があった。
「――――!」
甲斐姫は一瞬強張った表情を見せたが、すぐに踵を返して走り去って行ってしまった。
甲斐姫はあの戦から帰って来てからずっとこんな調子で、まだ一度も口をきいていない。ただ、あんなに明るく闊達だった姫が、ずっとふさぎ込んでいるのが、ハヤブサには気になっていた。
「…………」
夢中でひとしきり走った後、甲斐姫は後ろを振り返る。誰も追って来ていない事を確認してから、彼女は足を止めて、ほっと息を吐いた。
(良かった……。ハヤブサさん、身体治ったんだ……)
これであの人は、もう一度、あの戦場へ行くのだろう。
助けられなかった人を助けに――――。
強い人だと甲斐姫は思う。
対して自分は駄目だ。
本当ならばもう一度、自分もあの戦場に舞い戻って、何もかもをやり直してみたいとも願うけれども。
「…………!」
(駄目だ………!)
甲斐姫はそう思って頭を振る。
前の戦場でも、全く役に立てなかった自分。行った所で、また、同じように役に立てなかったら。また――――あの『悲劇』が防げなかったら。
怖イ……!
今度こそ、自分は立ち直れなくなってしまうかもしれない。
そう感じてしまうと、自分の足は全く動かなくなってしまう。
駄目だ、こんな事では、と、自分で自分を強く叱咤してみるけれども、一旦怯えてしまった自分は、本当にもうどうしようもなくて。
「……………」
でも、ハヤブサさんの身体は治っていたから、きっと、すぐにでもあの戦場に行くのだろう。ならば、見送りに行かないと、と、甲斐姫は思う。
大丈夫。
きっと、今度あの戦場に行く時にあの人が手を伸ばすのは、私ではない。
もっともっと頼れる仲間が、彼の周りには居るから――――
ふうっと、一息大きく吐きだすと、甲斐姫は太公望とかぐやの居る方に向かって歩き出していた。
「来たな、リュウ・ハヤブサ。身体は大丈夫か――――などと聞くのも野暮、と言うものだな」
太公望の言葉にハヤブサは無言で頷く。気力体力ともに充実している。今すぐにでもあの戦場に戻り、シュバルツを助けに行きたいぐらいだった。
頷いたハヤブサに、こちらが憂える事は最早何も無いのだと悟った太公望は、フッと軽く笑ってから口を開いた。
「では……約束通りお前の『縁』を使って、あの戦場へ飛んでもらう。一度に過去へ飛べる人数は限られているのでな……。また、お前が共に戦う仲間を選んでくれ」
「分かった」
ハヤブサはそう頷いて振り返ると、武将たちが皆こちらをじっと見つめている。どの武将たちも皆『自分を連れて行ってくれ』と訴えているのが分かった。
だが、ハヤブサは最初に声をかける人物を、既に心に決めていた。だから、武将たちの間に分け入ってその人物の姿を求め、見つけたと同時に迷わず手を伸ばした。
「えっ………?」
ハヤブサから手を伸ばされた甲斐姫は、何度も確認するように、ハヤブサとその手を見る。しかし、自分に向かって伸ばされた手は微動だにしないし、ハヤブサの視線も逸らされる事はない。
「え……? え……? 私……? どうして――――」
かなり戸惑っている甲斐姫に向かって、ハヤブサは自分が手を伸ばした理由を口にした。
「もしも、お前が先の戦いで何か戦いに手を抜いたとか、判断を誤ったと俺が感じていたなら――――こうして、手は伸ばさぬだろうな……」
「…………!」
「お前は、常に全力だった。その時その時で、出来る最良の手を、お前は打っていた筈だ」
「あ…………」
「俺も、そうだ……。それでも、防げなかった悲劇。この無念は、同じ戦場でしか晴らせない……。俺は、そう思っている………」
普通なら、取り返せない。
悔しいまま、悔やんだまま
一生この傷を負い続けなければならない所だ。
だが、取り返す機会(チャンス)がある。
かぐやのおかげで。皆のおかげで。
ならば――――
「行こう、お前も」
龍の忍者は、真っ直ぐ手を差し伸べる。
「敗けっぱなしは、悔しいだろう」
「―――――!」
良いのだろうか。
許されるのだろうか。
もう一度自分が、あの戦いに挑んでも――――
甲斐姫は、まるで何かの許しを請うかの様に、周りを見回す。すると、自分のすぐ近くで控えていた、主である北条氏康と、目があった。
「御館様……」
茫然と自分を見つめてくる部下に、北条氏康はその面にふっと笑みを浮かべる。
「遠慮する事はない。行って来い」
「で、でも………」
完全に怯えてしまっている自分。
踏み出す勇気が、一歩持てなかった。
「あの龍の忍者のいうとおりだぜ、坊主。……本当は、お前だって分かっているんだろう?」
「………?」
眉をひそめて、怪訝な表情を浮かべる甲斐姫に向かって氏康は尚も言葉を続ける。
「あの戦場で受けた屈辱は、同じ戦場じゃねぇと返せねぇって事に」
「―――――!」
「だから、お前は行って来りゃあいい。堂々と――――借りを返して来い」
「あ…………!」
もう一度甲斐姫は、ハヤブサの方に振り返る。
龍の忍者の視線はぶれない。手も、差し出されたままだ。
「………!」
(怯えるな)
また、誰かの声が心に響く。
ああそうだ。
逃げるな。
踏み出さなければ
何も動きださない――――
「分かった……。ハヤブサさん……」
甲斐姫は意を決したように、ハヤブサの手の上に、その手を乗せた。
「今度こそ――――全力で頑張るから……! また、よろしくお願いします!」
それに対してハヤブサは、その面に優しい笑みを浮かべる。
「今度『も』全力で、だろう? こちらこそ、よろしく頼む」
「う………!」
ハヤブサの言葉に甲斐姫は少し息を飲み、氏康は大笑しだした。
「確かに! うちの坊主は何時だって『全力』だな」
「お、御館様……! そこまで笑う事はないでしょう!?」
甲斐姫の抗議する言葉に、氏康はますます笑い出してしまう。場の雰囲気が、少し和やかな物になった。
「甲斐が行くなら、私もまた、一緒に行くわ」
甲斐姫の前に、そう言いながら孫尚香が進み出てきた。
「良いでしょう? 甲斐」
「もちろん!! 尚香!! 喜んで!!」
友人の申し出に、甲斐姫がようやくいつもの彼女らしい笑顔になる。
「―――人選は、終わったようだな」
太公望に声を掛けられてハヤブサが頷いた。それを見て太公望もにやりと笑うと、手に持っている打神鞭をパシン、と鳴らした。
「では、今話した通り、お前たちにはあの戦場に飛んでもらう。今度こそ村人たちとシュバルツと言う青年を救い出し、素戔鳴に打ち勝つのだ!」
「言われずとも」
と、ハヤブサが頷けば、後ろに控えていた孫尚香と甲斐姫も頷く。3人の士気が高い事を感じ取った太公望は、満足そうに頷いた。
「いいか。私はありとあらゆる縁を使って、あの時間軸の歴史に干渉してきた。今からお前たちが飛んでもらう時間は、最初にお前たちが飛んだ時と同じだが――――あの村を取り巻く環境も、大分変わっているはずだ。村人たちとシュバルツのお前たちに対する反応も、違った物になるだろう」
「え……? それはどう言う――――」
「行けば分かる」
疑問を呈す甲斐姫に、太公望はにやりと笑って答える。
「もちろん、変えられない流れもある。あの村に仙桃が生え、村人たちが妖魔たちとの交流を持ち、素戔鳴の怒りを買う。これは、もう私でも手出しができない流れになっていた」
(そうか……。まあ、そうだろうな)
ハヤブサは太公望の話を聞きながら、妙に納得していた。
確かにあの村人たちならばシュバルツを受け入れ、そしてシュバルツは妖魔の子供を助けてしまうだろう。例え、それをしたせいで自分が死ぬと分かっていても――――
だが、シュバルツはそれでいいと思った。
そんなシュバルツだからこそ、俺はあいつを好きになったのだから。
「だから、その後の流れが村人たちにとって少しでも楽になる様に、少々細工をさせてもらった。まあ、その細工を整えるのが、骨が折れる作業ではあったのだがな」
そう言って太公望はフフフ、と笑う。『骨が折れる』と言った割には楽しそうにそれを語っているように見えるのは、やはり太公望が根っからの『策士』であるが故だろうか。
「―――状況は整っている。故に、後はお前たちが選びとって行くだけだ。村人たちのために、お前が救いたい者のために、何が最良か――――よく考えて、掴み取って行け」
「分かった」
頷くハヤブサに太公望も頷くと、かぐやの方に振り向く。その意をくみ取ったかぐやが、静々とハヤブサたちの前に進み出てきた。
「では皆様……『光陣』の方へ、お進みくださいませ」
かぐやの導くままに、3人は歩を進めようとする。―――と、そこに、彼らを呼びとめる者が居た。
「尚香殿。ハヤブサ殿」
「関羽将軍!」
少し驚いた顔を見せる孫尚香に向かって関羽は軽く頭を下げると、おもむろに口を開いた。
「これから拙者も、過去に戻り申す。ハヤブサ殿達とはまた違ったルートを使うが、あの場所のあの城に、拙者も戻る手筈でござる」
「関羽様も……?」
問い返す甲斐姫に、関羽は頷いた。
「故に尚香殿。貴女が城からの援軍が必要と思えば、迷わずに来られよ」
「―――――!」
「貴女が呼びかけてくだされば、拙者はすぐにでも城を出る。例え兄者に反対されようとも、軍師殿の命に逆らう事になろうともだ」
「あ…………!」
関羽のこの言葉に、三人ともが息を飲む。
しかしこれは、確かに心強い言葉だった。少なくとも村人たちの援軍と受け入れ先が保証されている事になるのだから、それだけでも随分展開が違ってくる事が分かる。
「分かったわ。関羽将軍、お願いね」
「承知」
笑顔を見せる孫尚香に、関羽も頷く。今――――総ての状況が整ったと悟った。
(待っていてくれ、シュバルツ……! 今度こそ、お前を助けるから……!)
柄に巻きつけられているシュバルツのロングコートの切れ端を、ハヤブサは意識する。
もう、あんな哀しい想いを味わいたくはない――――そう強く願いながら、一歩、光陣に向かって足を踏み出そうとする。と、そこに太公望が声をかけてきた。
「ハヤブサ」
「………?」
振り返る龍の忍者の瞳をじっと見据えていた太公望であったが、やがて、口を開いた。
「……絶対に、最後まで油断するなよ?」
「?」
油断など端からする気も無いが、太公望の少し思い詰めた瞳が気になったので、ハヤブサは彼の話を聞く事にした。
「私はあの時間軸に対して、打てる限りのありとあらゆる手を打ったつもりだ。恐らくお前たちや村人たちにとって、最良の選択肢が用意されるようになっているはずだ。だがそれでも――――『シュバルツ』と言う青年を、100%助けだせると言う保証が出来ない」
「と、言うと?」
「これは万が一の話だが――――その青年が『運命の悪意』に取り込まれていた場合だ」
「―――――!」
「こいつに魅入られると厄介だ。そうなった場合、我々がどんなに手を尽くしても、その人物は『死』へと追い込まれてしまう可能性がある。……こちらの取り越し苦労だとは思いたいが、その可能性も0ではないので、お前に忠告しておく」
「……………!」
太公望の話を聞きながら、ハヤブサは思わず息を飲んでいた。
だが確かに、シュバルツは同じ戦場で既に2度、命を落としている。こちらの力不足に因る所が大きいだろうが、妙な悪運も付いて回っている様な気もした。「2度ある事は3度ある」とも言う。もしもシュバルツが、その運命の落とし穴にはまり込んでいたのだとしたら。
「その上で敢えて、お前に言う。運命に打ち勝て! ハヤブサ!!」
「――――!」
ハヤブサの眼差しを、太公望の真摯な眼差しが射抜く。
「村人とその青年を助け出し、素戔鳴に、運命に――――人の子の力を見せつけてやれ!」
太公望の話を聞きながら、ハヤブサは少し驚いていた。普段理知的で、とても冷静な印象を与える太公望の瞳の奥に、こんなにも熱い物が燃えたぎっていたとは知らなかった。だがそれだけに、この件に、太公望が本気で取り組んで居てくれている事も分かった。そして、その期待を裏切るべきではないと言う事も。
「承知した」
ハヤブサは短くそう答えると、踵を返した。龍剣を握る手に、少し力を込める。すると、愛刀からも、何事か小さく答えが帰ってきた様な気がした。
この戦い。いずれにしても絶対に負けられない。
強く、そう思った。
「ではハヤブサ様……。強く想い浮かべられませ。貴方様が戻りたいと願う時を。貴方様がお救いしたい人を――――」
光陣に入ったハヤブサたちに、かぐやがそう声をかけながら手をかざす。彼女の手から、眩い程の光が溢れてきた。
(俺が……俺が『戻りたい』と思う場所は……『救いたい』と願う人は――――)
強く
強く脳裏に思い描く。
(シュバルツ……)
愛おしいヒトと再会した、あの瞬間を――――
「―――――」
ハヤブサたちの身体は光陣の中で光に包まれて
そして、消えて行った。
「………行ったか」
「はい……滞りなく――――」
太公望の呼び掛けに、かぐやが振り返る。それを見た太公望は、満足そうに頷いた。
「ではかぐや……。後少し、働いてもらうぞ。総ては、手筈通りに――――」
「はい。心得ております」
かぐやは一礼すると、静々と歩き出す。その後ろ姿を見送りながら太公望が一息ついていると、伏犠と女媧が近寄ってきた。
「無事、行ったのう」
「ああ、そうだな」
「……勝てると思うか? 素戔鳴に、『運命』に――――」
女媧の問いかけに、太公望は苦笑しながら答える。
「勝ってもらわねば困る。妖蛇を倒すためには、素戔鳴は絶対に乗り越えねばならぬ相手だからな」
「我ら神仙界の者が、もう少し手出しせんでも良かったのか?」
伏犠の問いかけに、太公望は少し遠い目になった。
「構わん。この戦いの目的は、飽くまでも人の子の力を素戔鳴に示す事にある。人の子の力が素戔鳴を超え得ると証明して初めて、妖蛇に対抗する道筋も、見えてくると言うものだ」
「ふうむ、そんなものかのう」
太公望の言葉に、伏犠は顎に手を当てて考える仕種をする。その横で、太公望が大きく伸びをした。
「さて、私は少し休ませてもらうぞ? 後の事はよろしく頼む―――」
「休むって……どこへ?」
問いかける女媧に太公望は短く「昼寝だ」と言い放つと、すたすたと歩いて行ってしまった。
「全く……あの坊やは……」
呆れかえる女媧に対して、伏犠は苦笑する。
「仕方があるまい。ここ数日、ろくに寝もせずにいろいろやっておったようだし」
「まあ、確かにな……」
伏犠の言葉に女媧も反論の余地を失って、納得するしか無かった。それほどまでに、ここ数日の太公望の働きぶりは、目を見張る物があったからだ。
「坊やの仕事が……きっちり実を結べばいいが――――」
「そうじゃのう。今こそ、人の子の力が問われる時じゃ。旨く行ってくれればよいがのう」
雲が覆った空の彼方に、小さな青い空がのぞいている。
伏犠にはそれが人の子の間に灯った小さな希望の様に見えていた。
(この青い空が、もっと大きく、一面に広がってくれればいいが……)
そんな事を思いながら、彼はその小さな青空を、飽く事もなく眺めていた――――。
第6章
次にハヤブサが目を開けた時、あの村の風景が、目の前に広がっていた。
「こ、これは……」
「私たち……戻れたの……?」
ハヤブサの横で、甲斐姫と孫尚香が茫然と呟く。
「そうらしいな」
そう言いながらハヤブサも、周りの様子を見回していた。
ここは確かに――――あの村の風景だ。あの時見たものと同じ風景。
ただ違うのは、今回はケイタの『縁』を使っていないから、自分達の横にケイタの姿が無い――――ただそれだけだと、ハヤブサは感じていた。
(シュバルツは、何処だ……?)
確か以前の時間の中で聞いたケイタの話によると、この時間帯はいつも畑の方の手伝いをしていると言うシュバルツ。早く彼に会いたいと願い、ハヤブサが一歩、足を進めようとした時。
「誰だ!? お前たちは!!」
鋭い一喝を浴びて、思わず足が止まってしまった。ふと見ると、村の男衆たちが、鋤や鍬をその手に構えて、警戒心も顕わにこちらを睨み据えている。
「――――!?」
流石にハヤブサもこれには驚いて、慌てて顔を覆っている覆面を外した。ここまで警戒される理由がまるでわからず、ハヤブサは困惑してしまう。
「いや……その……」
敵対する気が無い意志を示そうとするのだが、村人たちは後ずさるばかりだ。
と、そこに甲斐姫と孫尚香が、ハヤブサの前に飛びだしてきた。
ハヤブサを庇う――――と言うよりは、怪しい物を村人たちから隠す、といった色合いが強かった。
「ご、ごめんなさい! 私たち、怪しい者じゃないんです!」
「私たち、シュバルツさんに会いに来たんですけど……」
「何だ、お前さんたち、シュバルツさんの知り合いだっただか?」
そう言うと同時に、村人たちの警戒心がふっと緩む。
「ちょっと待ってけろ! シュバルツさんを呼んでくるから!」
見覚えのある、朴訥な村人たちの姿に戻って、ハヤブサたちはホッと胸を撫で下ろしていた。
「それにしても、ずいぶん警戒されちゃったわね。どうしたのかしら?」
孫尚香の言葉に、甲斐姫も首を捻る。
「やっぱり……ケイタ君が居ないせいかな?」
前の歴史ではケイタと一緒にこの村に来た。確かに、今回はその縁を使っていないから、ハヤブサたちの傍にケイタはいない。しかし――――
「いや、これはそんな単純な問題でもなさそうだ」
周りの様子を見ながら、ハヤブサが口を開く。確かに、村人たちはあからさまに敵意を向けてきてはいないが、こちらの事をまだ少し、遠巻きに警戒している。以前の歴史の村人たちには、明らかに見られなかった反応だ。
(これが、太公望がこの時間軸に手を加えた故の物なのか? しかし――――)
それを判断するには、まだ材料が少なすぎると感じたハヤブサが少し考え込んでいると、そこに村人たちに伴われて、シュバルツが姿を現した。
「ハヤブサ!?」
愛おしいヒトがこちらを見つけて、走り寄ってくる。
「シュバルツ……!」
(ああ、生きている)
当たり前の話だが、立って動いているシュバルツの姿を見て、ハヤブサは素直に嬉しさを感じてしまう。だが、涙を流す事も、その身体を抱きしめる事もしない。まだ、戦いは始まったばかり。彼を完全に助け切るまでは、油断してはいけないのだとハヤブサは感じていた。
それでも、ハヤブサが驚くほど柔らかい表情をしていた事に変わりはない訳で。
それを見ていた孫尚香が、甲斐姫に小声で囁いてきた。
「今度こそ、ちゃんと助けたいわね」
その言葉に、甲斐姫も頷く。
「ええ、本当に――――」
この戦いが、皆がこのように幸せそうな笑顔で終われればいい。
甲斐姫も心底、そう祈っていた。
「それにしてもハヤブサ……。よく来てくれたな。もう会うことは難しいと思っていたが――――」
「お前、俺を舐めているのか?」
シュバルツのその言葉に、思わずハヤブサは彼を睨みつけてしまう。
「随分探した……! この俺が、お前を見つける事を、簡単にあきらめる――――とでも思っているのか?」
「いや、そう言うつもりではないが……」
ハヤブサの言葉に、少し困惑したような表情を見せる愛おしいヒト。ハヤブサはそんなシュバルツに笑顔を見せながら、その肩を叩いた。
「とにかく、会えて良かった……。嬉しいよ、シュバルツ……」
「ハヤブサ……」
「シュバルツさん、その人たちは誰?」
シュバルツの脇から、ケイタがひょこっと顔を出してくる。どうやらこの時間軸でも、ケイタはシュバルツの傍にくっついているようだ。
「ああ、こいつはリュウ・ハヤブサと言って、私の知り合いだ。そして、そちらの二人は……」
「あ、私たちの事?」
シュバルツと視線が合った女性二人が、ケイタの前に進み出てくる。
「『はじめまして』 私の名前は孫尚香よ」
「それで、私の名前は甲斐。よろしくね。ケイ――――」
ドカッ!!
いきなり孫尚香が甲斐姫をどつき倒したものだから、甲斐姫はびっくりしてしまう。
「痛い!! 尚香!! 何するのよ!?」
「それはこっちの台詞よ!! 貴女こそ、いきなり何を言い出すのよ!?」
「えっ?」
少し眉をひそめる甲斐姫を、孫尚香がガシッと抱きかかえて、その耳元で小声で囁く。
「いい? 私たちとこのケイタ君は、あくまでも『初対面』なのよ? それなのに、名前を知っていたらおかしいでしょう!?」
「あ…………!」
孫尚香の指摘に、甲斐姫もようやくどつき倒された事に合点がいった。
確かにそうだ。
今目の前に居るケイタは、自分達と共に時を遡っている訳ではないから、自分達の事を知っているはずもない。それなのに自分がケイタの名を呼んでしまうのは、おかしいにも程がある事象だった。
「そっか………」
甲斐姫は、納得したようにポリポリと頭をかく。ただ、前の時間軸の中で、ケイタと少し仲良くしていた甲斐姫は、一抹の淋しさを感じた。たった1人でもシュバルツのために叫び、皆のために涙を流し、自分の事を『お姉さん』と慕ってくれたあの少年は、ここにはもう居ない。そんな経験を、ケイタは『していない事』になってしまっているのだから――――。
だけど、今目の前に居る少年が、そう言う優しさと強さを兼ね備えている事に間違いはない。だから、今度のケイタともきっと仲良くなれるだろうと、甲斐姫は確信していた。
ケイタが怪訝そうな顔をしてこちらを見つめてくる。それに対して孫尚香たちは苦笑した。
「あははは……。何でも無いのよ」
「それよりもあなた、名前は何て言うの?」
「ケイタだよ!」
孫尚香の質問にケイタが元気に答える。これでケイタの名前を出しても不自然じゃなくなったと感じて、3人はホッと胸を撫で下ろしていた。
「君たちは、ハヤブサと仲間になっているのか?」
シュバルツの質問に、女性二人はこくりと頷く。
「はい、そうです」
「私たちはハヤブサさんと共に、妖魔を倒すために――――」
「何っ!? お前さんたち、妖魔を倒しに来ただか!?」
孫尚香の言葉に、村人たちから鋭い反応が帰ってくる。
「――――!?」
ハヤブサたちが驚いて周りを見回すと、最初に会った時と同じように、殺気だった眼差しで村人たちが鋤や鍬を構えながら、こちらを睨みつけていた。
「あ……! ちょっと、待って……!」
自分の発言が軽はずみだった事に気がついて、孫尚香は慌てた。
「私たちは、その……!」
「待ってくれ! この人たちは信用できる。大丈夫だから……!」
その時、シュバルツがハヤブサたちと村人たちの間に割って入ってきた。
「シュバルツさん……! しかし―――!」
「『妖魔』と言うだけで、襲ってくる人間たちもいるし――――」
「ハヤブサたちは違う。話せばきっと分かってくれる」
ハヤブサたちをその背に庇うように立って、村人たちに話すシュバルツ。こちらを絶対的に信頼してくれている彼のその様に、ハヤブサもつい、嬉しくなってしまう。
しかし、先程からの村人たちの過剰な反応が気になった。
一体この時間軸で、何が起きていると言うのだろう?
「まあ、シュバルツさんがそう言うのなら……」
村人たちもシュバルツの言う事に、渋々ながらも納得してくれたようだ。
「少し、ハヤブサたちと話がしたい。時間をくれないか?」
「ああ、わしらは別に構わないが――――」
「シュバルツさんが抜ける間、わしらはどうすんべ?」
「そうだな……。農作業と見回りの二手に分かれて行動してくれ」
(見回り?)
やはり、村人たちは何かに警戒している――――ハヤブサは、そう感じた。
「分かりました。ほら、行くべ!」
「おお~い! お前たち! 隠れてなくでも大丈夫だぞ~!」
村人たちの呼び掛けに応じて、妖魔たちが次々と姿を現してくる。
「あ………!」
「そう言えば、妖魔たちの姿が見えないと思ったら――――」
甲斐姫たちもハヤブサも、少し驚いていた。この村人たちと妖魔たちは、また前の時間軸とは違う行動を取っている。
「…………」
(太公望の奴……ここの人たちに、一体何をやったんだ?)
ハヤブサがそうため息をついていると、ケイタが声をかけてきた。
「ねえシュバルツさん、僕はどうしようか?」
「ケイタは、妖魔の子供たちの所へ行って『大丈夫だから』と、声をかけてやってくれ。怯えているといけないから――――」
「うん、分かった!」
元気良く返事をして、ケイタはそこから走って行った。そこには、ハヤブサたちとシュバルツだけが残された。
「……済まないな。少し、バタバタしていて――――」
そう言って振り返るシュバルツに、ハヤブサも笑顔を返すと話を切りだす事にした。
「いや、構わない。それよりもシュバルツ……。2つか3つ、確認したい事項があるのだが」
「確認?」
小首をかしげるシュバルツにハヤブサは頷き返すと、そのまま話を続けた。
「まず……お前はこの村に来て、やっぱり『神様』扱いされているのか?」
「――――何で分かった!?」
ギョッとなって問い返してくるシュバルツ。その様が、あまりにも可愛らしかった物だから――――
「プ………クク………」
ハヤブサは笑いが堪え切れず、つい、腹筋をひきつらせてしまっていた。
「わ、笑う事無いだろう!? 私だって困っているんだ!!」
シュバルツのその言葉に、さらに腹筋が崩壊してしまうハヤブサ。笑っている場合ではない――――と、必死に自分に歯止めをかけようとするのだが、頬を赤く染めて困っているシュバルツを見てしまうと、やっぱり笑いが堪えられなくなってしまう。
(あ、なるほど、確かに可愛らしいかも)
甲斐姫もそんなシュバルツの様子を見ながら、ちょっと納得してしまう。だから、つい、ポロっと聞いてしまった。
「シュバルツさん、あの……」
「何だ?」
「やっぱり、あの『変な儀式』のせいなんですか?」
「そうなんだ。たまたま私がこの村に落ちて来た場所が、どうも祭壇の上だったらしくて――――」
と、ここまで口走ったシュバルツが、はたと気がつく。
「……何故、君たちがこの村の『儀式』を知っているんだ?」
「…………!」
(やばっ! 私、またやっちゃった!?)
慌てて口を押さえる甲斐姫。しかし、それにハヤブサがフォローを入れてきた。
「ああ。俺たちは『知っている』んだ。ある程度だが、この村の事を――――」
「………? どう言う事だ?」
ハヤブサの言っている事が理解できず、眉をひそめるシュバルツ。そんなシュバルツに対して、ハヤブサは単刀直入に話をぶつける事にした。
「俺たちは『未来』から来た存在だからだ」
「………えっ?」
茫然と呆けるシュバルツに向かって、ハヤブサはもう一度、念を押した。
「俺たちは知っているんだ。ある程度だが、この村でお前が何をしたか、そして、この村がどう言う末路をたどるか……」
「――――!?」
驚き、表情を強張らせるシュバルツに、ハヤブサはたたみかけるように言った。
「知っているんだ。その結末を見ているんだ。俺は、それを否定したい」
その言葉に、ハヤブサの後ろで甲斐姫と孫尚香が頷いている。シュバルツはただただ呆然とするしか無かった。
「ハヤブサ……? 一体―――」
「俺の話を……聞いてくれるか? シュバルツ」
その言葉に、シュバルツは茫然としながらも頷いた。
「襲われる!? この村が!?」
ハヤブサの話を黙って聞いていたシュバルツが、思わず声を上げる。その言葉に、皆が頷いた。
「ああ。襲われる。このままこの村に留まり続けていれば全滅だ」
「…………!」
ハヤブサの言葉に茫然とするシュバルツ。ただ、前に話した時と、シュバルツの反応が微妙に違っている。だからハヤブサは、その違いが何なのかを、少し確かめてみる事にした。
「何故襲われるか……分かるか?」
「………原因は、いろいろ考えられるが………」
(やはり………!)
ハヤブサは確信した。やはりこの時間軸の村人たちとシュバルツは、かなりの危機感を持っている。『襲われる』と聞いても、それが絵空事ではないと、容易く想像できる環境に居るのだ。
(いけるか……?)
自分が飛んできた時間軸が、前と同じ時であるのならば、襲撃を受けるのは今夜。前の時は、陽が沈んでからの脱出劇になってしまったために、かなりの犠牲が出た。しかし、今すぐにでも村人たちが行動に移してくれれば。
「ここの村人たちは、妖魔たちと交流を持っているのだな。やはり、妖魔の子供を助けたことがきっかけか?」
「ああ。怪我をした子供を助けた。もともとこの近くに住む妖魔たちは、人間との交流を望んでいた。だから、手を取り合う事は容易かった……」
ハヤブサの質問に、シュバルツが答える。だが、ここから先のシュバルツの話は前の時間軸の物とは違っていた。妖魔たちと交流を重ねて行くうちに、村人たちの方が、妖魔の村で起きていたほかの部族からの嫌がらせに、気がついていたのだ。
「皆で話し合って対策を立てたりしたのだがな……。何せ、相手と話し合うことは難しいし、村人たちも妖魔たちも、戦う事を望んではいないし――――」
しかも、嫌がらせは止む事も無く、日々悪化しているらしい。近頃では子供を村に置いておく事に危険を感じたのか、人間の村の方に我が子を預ける妖魔の親も増えていると言う。
「子供たちの世話は、ケイタ君がしているの?」
甲斐姫の質問に、シュバルツが頷いた。
「ああ。ケイタを中心に村の子供たちが交代で妖魔の子供たちの遊び相手をしてくれている。母親たちの間にも交流が生まれて、料理のバリエーションが増えた、と、喜んでいる人もいたな」
シュバルツは少し目を細めて語る。苦しみの中にも、ちゃんと喜びを見出している人間と妖魔たちを、誇らしく思っているのだろう。
「しかし、この辺りも戦の匂いがきつくなって来ていてな……。この村から行商に出た者が、戦禍に巻き込まれたりする事が増えてきた。それに、噂で聞いた話だが、山向こうにあった別の妖魔の村が、人間に襲われたりしたらしい。だから皆、ピリピリしているんだ。何時ここも襲撃されるか分からないから、ここから避難するべきか、それとも留まるべきか、連日話し合いが行われていて――――」
(こ、これは………!)
3人は、思わず息を飲んでいた。
既にこの村から『逃げる』ことも視野に入れている村人たち。これなら、こちらの呼び掛けに、素早く応じてくれるかもしれない。
それにしても恐るべきは、太公望の策略だ。
前の時間軸とは全く違う村人たちの動き。彼らがこう思うようになるまでに、一体どれほどの手を打ってきたと言うのだろう?
「シュバルツ、お願いだ。今すぐここから、村人たちを避難させる決断をしてくれ!」
だからハヤブサは、迷わず呼び掛けていた。今――――今逃げだす事が出来れば、皆の生存確率がぐっと上がるのだ。生き延びるチャンスを、掴み取って欲しい、と、願った。
「ハ、ハヤブサ?」
「言った筈だ。俺たちは『未来から来た存在』だと。だから、この村がいつ襲撃されるか、ある程度予測ができるんだ」
「それは………何時だ?」
息を飲み、問うシュバルツに、ハヤブサは言いきった。
「今夜」
「―――――!」
「今夜、この村は襲撃に遭う。襲ってくるのは百々目鬼率いる妖魔の軍団たちだ」
「百々目鬼……! やはり――――」
「百々目鬼の名を、知っているの?」
問う孫尚香に、シュバルツは頷く。
「ああ。この辺り一帯で、今一番活発に動き回っている妖魔の軍団だからな……。何でも、『遠呂智』が復活するとかで、軍を大きくしたり、物資を調達するのに躍起になっているらしい。しかし………」
「しかし……何だ?」
少し考え込むように腕を組んだシュバルツが、確認するようにハヤブサに問う。
「今夜襲われるのは……確かな情報なのか?」
「俺達を疑うのか?」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは首を振る。
「疑う訳ではない。ただ……確証が欲しい」
村人たちを全員ここから避難させるとなると、それこそ一大事だ。皆この土地や場所に愛着がある。百姓なだけに、畑でやらねばならない事も山積している。それらを一旦断念させて避難を呼びかけるには、こちらにも確固たる確証が欲しい、と、シュバルツは思った。
「分かった……。俺たちが未来から来たと証明すればいいのだな? 造作も無い事だ」
ハヤブサは頷くと、シュバルツの前に手を突きだした。
「ではまず一つ。俺たちは今この村に来たばかり。この村の者たちとは、ケイタの名を聞いた以外、ろくに話もしていない。にも拘らず、この村の事情を知っている」
「――――!」
「この村独自に伝わる儀式のせいで、お前が『神様』扱いされている事。あそこに居る村人は、神としてのお前の付き人だ。違うか?」
シュバルツは思わず息を飲んでいた。「確かにそうだ」と頷くシュバルツに、「そうか」とハヤブサは答えた。付き人である村人は、前の時間軸に来た時と同じ人間だった。神事に関する人選は、だいたい当番制になっているのが基本だ。これは、どの時間軸であろうが、おいそれと変わらない事象なのだろう。
「二つ目。妖魔と交流を生むきっかけとなった事件を当ててやろうか? 桃の畑の裏山の崖から落ちて来た妖魔の子供を、お前が助けた。そしてその母親が、山菜を持って礼を言いに来た――――」
「その通りだ……」
「三つめ。この村の桃の畑には一本、妙に生りの良い桃の木があるだろう。その桃には薬効成分が含まれていて――――」
「分かった! もういい!」
シュバルツは思わず叫んでいた。こうもずばずばハヤブサに村の事を言い当てられると、感嘆するを通り越して、思わず寒気すら感じてしまう。
「ハヤブサ……。やはり、お前は――――」
「分かってくれたか? シュバルツ……。俺がこれだけ知っているのは、既に一度聞いているからだ。これより少し先の、未来のお前から………。お前にとってはリアルタイムで進んでいるこの時間も、俺にとっては過去の時間――――一度、経験している時間なんだ」
そして俺は、お前を助けられなかった。二度も、お前を死なせてしまった。
死なせたくない。今度こそ。
そう――――強く、願う。
「シュバルツさん。私たち、貴方たちを助けに来たんです」
「今度こそ、皆を助けたい――――そう願っています」
ハヤブサの心を代弁するように、甲斐姫と孫尚香が口を開く。
「シュバルツ……」
「……………」
ハヤブサからも懸命に見つめられ、さすがにシュバルツも、遂に決意したように顔を上げた。
「分かった……。皆を至急集めよう」
シュバルツの言葉に、3人ともがその面に安堵の色を浮かべる。とりあえず、第一関門突破だった。シュバルツはすたすたと歩き出すと、付き人として待機していた村人に声をかけていた。
「済まないが、長老と組頭以上の者を、集会所に集めてくれ。私から緊急の話があるからと」
「分かりました。妖魔たちの方はどうします?」
「そちらにも声をかけてやってくれ。大事な話だから――――」
「分かりました」
話を聞いた村人が、固い表情で走り出していく。
「何か……空気が違うわね。もしかしたら、うまくいくかしら」
「そうね……。皆が、早く脱出を決意してくれれば――――」
そう話す女性たちの横で、ハヤブサも頷いていた。
危機意識が高い村人たちの裏に、太公望の影がチラチラと見え隠れする。
「状況はお膳立てしておいてやった。だから、後はお前たちが掴み取れ」
そう言って不遜に笑うあの白髪の青年の顔が、浮かんでくるようだ。
(やってやろうではないか……! 必ず皆を、そしてシュバルツを、救って見せる――――!)
ハヤブサはそう決意しながら、空の果てを睨み据えているのだった。
シュバルツの呼び掛けに応じて、村人たちと妖魔たちは、すぐに集会所に集まってきた。
もう何度も何度も皆でこうして集まっているのだろう。少し慣れたような感じが、集会所の皆から伝わってきていた。
「おっと、すみません」
少し遅れてはいって来た妖魔が、入り口近くに居た甲斐姫の肩にぶつかる。
「あ、いえ……」
振り向いた甲斐姫は、妖魔の姿を見て軽く驚いた。何故なら、その妖魔の額には鉢巻の様な布が巻かれ、皆そこに大きな鳥の羽を挿していたからである。
「あの、すみません」
思わず甲斐姫は、その妖魔を呼びとめていた。
「ん? 何だ?」
振り返った妖魔に、甲斐姫は鳥の羽を指しながら聞いてみた。
「あの……それは?」
「ああ、この額のヤツか?」
問われた妖魔は額の羽根を触りながら屈託なく笑う。
「これはまあ、『友好の証』って奴だな! 『俺たちは人間を襲いません』って言う、まあ、印みたいなものだ」
「村の奴らは、そんな印わざわざつけなくても、と、言ってくれたんだが――――」
甲斐姫たちの会話に、別の妖魔が入ってくる。
「近頃、妖魔も人間も、戦に巻き込まれたりして物騒だろう? 万が一この村が、他の妖魔に襲われたりして戦場にならないとも限らねぇ」
「そん時に、皆が俺達をちゃんと区別できるようにってな! これをしておけば、お前たちも俺たちも――――混乱しなくて済むだろう?」
「ええ! ええ、確かに――――!」
甲斐姫は思わずこくこくと頷いていた。敵と味方の妖魔の区別がつかなくなる心配が、これでかなり解消される事になる。この配慮は、本当にありがたかった。
「すごいわ! 誰の提案なの?」
問う甲斐姫に、その妖魔は少し決まりの悪そうな笑みを見せる。
「いやこれは、俺たちの発案じゃなくて……」
「ちょっと前に、俺たちの村を訪ねて来てくれたお武家さんたちの提案なんだよ。えらい老け顔の奴と、鈴の音がうるさい奴だったけどな」
その話を横で聞いていた孫尚香が、横で思わずブホッと吹き出していた。
「ど、どうしたの? 尚香……」
「い、いえ、ごめんなさい……。その人たちって、『呂蒙』と『甘寧』って名前じゃなかった?」
「ああ、1人はそんな名前だったかな? でももう一人は――――」
「あいつの名前『おっさん』じゃなかったのか!?」
その言葉を聞いた瞬間、孫尚香の腹筋は崩壊してしまっていた。
「どうしたの? 尚香、大丈夫?」
気遣ってくる友人に「何でもない」と返して、必死に笑いを収めようとするのだが、一度緩んでしまった腹筋は、どうにも戻りそうになかった。
「あの~。そろそろ話を始めるが……大丈夫だか?」
村人にそう声をかけられるまで、集会所には彼女の明るい笑い声が響いていたのだった。
「今日集まってもらったのは他でもない。百々目鬼軍に大きな動きがあった。それを皆に報告しようと思う」
シュバルツの言葉に、村人たちが固唾をのんで注目する。重苦しい空気の中、シュバルツは言葉を続けた。
「百々目鬼軍の次の攻撃目標が、どうもこの村らしい。ハヤブサたちはその動きを掴んで、私に知らせに来てくれたんだ」
「――――! そうだったんですか……」
村人たちの注目が、一斉にハヤブサたちに集まる。それに3人はそれぞれが軽く頭を下げて答えた。
「何時、相手は襲撃を仕掛けてくるか……までは、分かりますか?」
村人からの質問に、シュバルツはしばし間を置いてから答えた。
「ハヤブサからの情報によると―――――今夜だ」
「今夜!?」
「それはまた、急な………」
シュバルツの言葉に、村人たちがざわめき立つ。動揺する空気を押さえるように、シュバルツが声を上げた。
「皆、聞いてくれ! 前々から話していた通り、この村では敵を迎え撃つ事は出来ない。皆で避難する事を提案する」
「しかし……! 避難と言っても……!」
「何とか――――この村に留まる事は、出来ない物ですかいのう……?」
老人の言葉に、シュバルツは首を振った。
「前にも話したと思うが、この村は見晴らしの良い平坦な場所にある。敵の侵入を防ぐ術もなければ、皆の安全を確保できる場所も無い。ここで敵を迎え撃つには、不利過ぎるんだ」
「そ、そんな………!」
「やはり……村を捨てて、逃げるしかないのか――――?」
村人たちの空気が、重苦しくなっていくのが分かる。そんな中、村長が口を開いた。
「避難するのは仕方がないとして……避難先はどうする? 我々を受け入れてくれるような所は、あるのか?」
その問いかけに、ハヤブサが立ち上がった。
「避難場所については、俺から提案がある。ここから西に10里ほど行った場所にある、劉備殿が統治する城だ」
「劉備殿……」
『劉備』の名に、場が少しざわつく。
前の時間軸では、村人たちは『劉備』の事をあまり知らなかった。だが、この時間軸では――――
「劉備殿か……確かに、あの方ならば、わしら民を受け入れてはくださるだろうが――――」
「民を思いやる、名君だという噂だからな……」
「城下町にも行商に行ったが、そんなに悪い印象は受けなかったなぁ」
ぼそぼそと、そう話す声が聞こえる。どうやらこの村人たちは、ある程度『劉備』と言う人物を把握しているようだった。
「しかし……我らはともかくとして、妖魔の方々も、劉備殿は受け入れてくれるか――――?」
「―――――!」
1人の村人の言葉に、話をしていた村人たちもはっと息を飲む。再び重い空気がその場を支配しそうになった時、「大丈夫です!」と、声を上げる者が居た。彼女はすくっと立ち上がると、大声で名乗りを上げた。
「私の名前は孫尚香! 劉玄徳の妻です!!」
「玄徳様の!?」
「おお………!」
ざわめく村人たちを鎮めるように、孫尚香は言葉を続ける。
「玄徳様は、困っている人たちを見捨てる様な方じゃありません! 必ず、受け入れてくれます!」
「あの城に居る関羽殿には事情を説明してある。こちらが避難して行っても、必ず門を開いてくれる筈だ」
孫尚香をフォローするように、ハヤブサが口を開いた。
「ハヤブサ……!」
「そうでなければ、俺だってそこを避難先に勧めたりはしない。絶対に大丈夫だ」
驚いたようにこちらを見るシュバルツに、ハヤブサは微笑みかけた。
「だから安心して、避難を進めて欲しい」
「分かった」
シュバルツはハヤブサの言葉に頷くと、改めてもう一度、皆に呼びかけた。
「聞いての通りだ。もう一度言う。皆、今すぐこの村から避難をしてくれ」
シュバルツの言葉に、村人たちはシン、と静まり返る。
(避難をしなければならない、と、頭では分かっているのだろうが、納得できないのだろうな……。事実、今は桃の収穫期だ。やらなければならない仕事が山積しているし、明日は感謝の祭りもある)
村人たちの気持ちを慮って、シュバルツは瞳を曇らせる。と、そこに今まで黙っていた長老が立ち上がった。
「……皆、避難の準備を始めよう」
「長老様!?」
驚く村人たちを鎮めるように、長老は振り向いた。
「これは、天の御意志だ」
「しかし………!」
意見を述べようとした村人の1人を手で制すると、長老は言葉を続けた。
「ここを離れがたく思う皆の気持ちも分かる。我ら百姓にとって土地は財産であり、命だ。我らは何十年もかけてこの地をここまでに育ててきた。それを手放してしまえば、元に戻すのに、また莫大な労力がかかる事も分かっている」
(ああ、前の時間軸でも同じような事を、この人は言ったな……)
長老の話を聞きながら、ハヤブサはそう感じていた。違うようで同じ時間をたどっている。繰り返される事もあるのだろう。
「しかし、それも死んでしまえば総てが終わりだ。我々は幸いにして、襲撃される事も、そこから逃げる術も、指し示されている。ならば……生きるために差し出されている手を、掴むべきではないのか」
「長老様……」
「それに、土地神の代理であるシュバルツ様も『逃げよ』仰っておるではないか。我らはここで死ぬべきではない。生きるべきなのだ」
「―――――!」
長老の言葉にシュバルツは驚き、村人たちははっと気が付いた様にシュバルツを見る。
「我らは今一度、考えねばならんのだ。なぜ今年に限って神様が『人型』であったのか。我等に意志を伝える『言葉』を持ちえた存在であったのか……その、意味を」
長老の言葉に静まり返る村人たち。あちこちで、咽び泣く声すら聞こえてきた。
「土地神様の……強い『意志』を感じぬか?」
「……………」
長老のその言葉に、シュバルツは答えなかった。ただ、彼の拳が強く握りしめられ、小さく震えている事に、ハヤブサは気が付いていた。
「分かりました……」
やがて、下を向き、咽び泣いていた村人たちが顔を上げる。
「長老様、シュバルツさん……我々は、避難の準備を始めます」
「何がどうなろうと……生きる事が、大事だからのう……」
「みんな………」
硬い表情をしていたシュバルツの瞳が、哀しみゆえに曇る。
「済まない……! 私の力が足りなかったばかりに――――」
「気にする事無いだ! シュバルツさん!」
頭を下げようとしたシュバルツの動きを、村人たちが止めた。
「これは仕方のない事なんだ。シュバルツさんのせいでは絶対に無いから――――」
「そうだべ。あんたはよくやってくれている。寧ろこちらがお礼を言わねばならないぐらいだ」
「……………!」
村人たちにそう言われ、シュバルツの面に笑みが浮かぶ。
「ありがとう………」
その表情に、村人たちの顔も和み、場が和やかな物になる。
だがハヤブサは見ていた。
シュバルツの拳がきつく握りしめられ、小さく震え続けているのを。
ただずっと、見つめ続けていた――――。
「それでは、わしらは避難の準備をするべ!!」
「準備ができたものから、広場に集合だ! 急ぐべ!!」
村人たちはそう言いながら、慌ただしく集会所を出て行く。
「親父さん。わしらも避難を手伝った方がいいんじゃ――――?」
「そうじゃな……。急いで村に帰って、若い物を連れて来よう」
そう言って集会所から出て行こうとする妖魔たちを、ハヤブサが「待ってくれ!」と、呼び止めた。
「貴方がたの村も、避難した方がいい。百々目鬼軍の攻撃対象に、貴方がたの村も入っている。百々目鬼は人間と妖魔が交流する事を、極端に嫌っているから――――」
「―――――!」
「下手をすると、人間たちの村よりも、先にそちらが襲われるかもしれない。だから、村人たちと共に逃げた方がいい」
「……その情報は、確かなのか?」
問い返す妖魔たちに、ハヤブサは頷いた。
「親父さん……」
「うむ………」
ハヤブサの言葉に、しばし考え込んでしまう妖魔たち。
「どうかしたのか?」
問うハヤブサに、妖魔たちは少し茶を濁したような返事を返してきた。
「いや………わしらが村人たちと、逃げたとして……」
「避難先の劉備殿は、それを受け入れてくれるか? わしらの存在が、却って皆の足を引っ張る事になるのなら……」
「………………!」
妖魔たちとハヤブサの会話を聞いていたシュバルツの顔色が変わる。だが、ハヤブサは動じなかった。
「それは大丈夫だ。俺は言った筈だ。城に居る関羽殿には、総ての事情を説明したと。この村の人間が、妖魔たちと交流を持っている事を関羽殿は承知してくれている。共に避難しても、何ら問題はない」
「……その話は本当か?」
「………この首を、賭けても良い」
妖魔たちの問いに、ハヤブサは視線を逸らさずに答える。
「たとえ兄者に反対されようと、軍師の命にそむこうとも、拙者は必ず城の門を開ける」
そう言って送り出してくれた関羽の姿は、充分信ずるに値すると、ハヤブサは思っていた。
「……………」
妖魔たちはしばらくそんなハヤブサを推し量る様に見つめていたが、やがて小さく息を吐き、顔を上げた。
「……分かった。では、わしらの村の者にも、避難を呼びかけよう」
「親父さん!」
「百々目鬼の奴らが襲ってくるのなら、この村とわしらの村、同時に攻撃を仕掛けてくることも十分あり得る。もうここらで、潮時なのかもしれぬ」
「…………ッ!」
悔しそうに下を向く若い妖魔の肩を、『親父さん』と呼ばれている妖魔がポン、と叩いた。
「さあ、我らも人間たちの手伝いをしよう。そして……人間たちの『好意』に、甘えよう」
「分かりました」
「ではシュバルツさん、長老様、また後で――――」
そう言い置くと、妖魔たちもまた、足早に集会所を後にしていた。
「……………」
人気もまばらになった集会所で、ハヤブサは佇むシュバルツに声をかけようとする。だがそれより早く、長老と、それに近しい者たちが、二人に声をかけて来た。
「シュバルツ殿……そして、ハヤブサ殿……。此度は我らのために、尽力いただいて……この御恩、本当に、どう報いて良いのか分からぬぐらいじゃ。心より、感謝申し上げる」
その言葉に対して、シュバルツは頭を振った。
「いや……私など、大して役には立っていない。それよりも、村を離れる決断をさせてしまった事……本当に、申し訳ないと思っている」
「これも時世じゃ。仕方があるまい」
そう言って、長老は穏やかに笑う。その横で、老婆がにこやかに笑いながら口を開いた。
「それにしても……本当に、お前さんはよくこの村に来てくださったものじゃ。やはり、土地神様が、お前さんを呼んだんじゃろうなぁ」
「長老様……おばば様……何度も申しあげておりますが、私はそういう物ではなくて――――」
「いや………お前さんがここにいなければ、この村はもっと早い段階で滅びの道を歩んでいたやもしれぬ。それを、よくここまで保たせてくれた。この混乱した世界の中で、わしらがいつも通りの生活を送れたのも、お前さんがいればこそじゃ……。本当に、ありがとう……」
「……………!」
その言葉に対して、シュバルツは歯を食いしばっている。ぐっと拳が更に握りしめられるのが、ハヤブサからは見えた。
「きっと、土地神様は今回の災厄を感じ取られておったのだろう。それをわしらに伝えるために、お前さんを選んだ―――――わしらは、そう思っておる」
「だからお前さんは堂々と――――今まで通り、わしらを導いてくれたらええ。お前さんは常に、わしらの事をよく考えてくれておる。わしらにはそれが分かっておるから、何も心配せんでええよ」
そう言うと、老人たちも集会所から出て行った。シュバルツはそれを、頭を下げて見送っていた。
「………………」
シン、と静まり返った集会所。その中で孫尚香は、横に居る友人にそっと声をかけていた。
「甲斐……私たちも、外に出ましょう」
「えっ? 何で? 尚香」
疑問を呈する友人を、孫尚香は軽く小突く。
「馬鹿ね。こういう時は気を利かせてあげるものよ。あの二人は恋人同士なんだから――――」
「あ………!」
孫尚香の言葉に、甲斐姫もようやく納得する。彼女たちはそのまま黙って、そっと集会所から出て行った。後にはシュバルツとハヤブサ――――二人だけが残された。
「シュバルツ」
ハヤブサは、そっとシュバルツに声をかけた。ずっと硬い表情をしている愛おしいヒトが、心配だった。
「ハヤブサ……」
「大丈夫か?」
「――――!」
ハヤブサの言葉に、一瞬はっと、息を飲むシュバルツ。
「ああ。大丈――――」
その言葉と共に、シュバルツはその面に笑みを浮かべようとして、失敗していた。それどころか、彼の瞳からは堪え切れぬように涙まで零れ始めていた。
「シュバルツ……」
「済まない……! ハヤブサ……。泣くまい、と、思っていたのに――――」
そう言いながら、必死に涙を拭う、愛おしいヒト。
「駄目だな……。お前の顔を見ると、変に緩んでしまって――――」
「……………!」
ハヤブサは思わず息を飲んでいた。
今
今、シュバルツは何て言った?
「俺の顔を見ると、気が緩む」
そんな事を、言っていなかったか……?
嬉しい。
お前にとって俺がもう
それほど、特別な存在になっている――――と、言うのなら。
「…………」
ハヤブサはそっとシュバルツの頬に手を伸ばす。そこが、シュバルツの限界だったらしい。
「ハヤブサ……ッ!」
ハヤブサの手が触れると同時に、シュバルツが彼の胸に飛び込んできた。
「ふ……! う………ッ!」
そのまま縋りつく様に、腕の中で泣き始めるシュバルツ。肩を震わせ、声を殺すように泣くこのヒトが、堪らなく愛おしかった。
「シュバルツ……」
ハヤブサはかのヒトを抱きしめて、その髪を優しく撫でる。すると、腕の中の愛おしいヒトが、堪え切れぬ想いを、ポツリポツリと吐き出し始めた。
「何故……! 何故だ……!」
「シュバルツ……」
「この村の人たちも……妖魔たちも……ッ! 慎ましやかに……穏やかに、交流していただけだ……! なのに、何故――――!」
「…………!」
「そのすべてが、『悪い』みたいに言われなくてはならないんだ……! どうして、理解……されないんだ……!」
「――――!」
ハヤブサは、はっと気づく。
この村に来た時から、とても危機意識が高かった村人たち。それは裏を返せば、この村がここに至るまでに何度も何度も危ない目に遭ってきた、と言う事に他ならない。そして、妖魔たちの村に起きていた他の部族からの嫌がらせにも村人たちは気付いていた、と言う事は。
シュバルツがそれに、対処しなかった筈がない。この誠実な男が、他の部族の妖魔たちに、理解を求めなかった筈がないんだ。
そのたびに踏みにじられ、罵詈雑言を浴びせられる。
―――どれほど辛かった事だろう。
そして、神と祀り上げられたが故に、その孤独を誰にも吐き出す事が出来ずに――――
「揚句……村人たちにも、妖魔たちにも……『村』を捨てさせる決断をさせてしまった……。私は何も状況が変えられずに……! 結局私は……何もできなかっ………!」
そのまま後は言葉にならずに、腕の中で咽び泣く愛おしいヒト。
「シュバルツ……!」
ハヤブサはただ、震えるその身体を抱きしめるしか、術がなかった。
違う。シュバルツ。
違うんだ。
お前は既に、この村と妖魔たちを守っている。
ここに居る人たちにどういう悲劇が襲いかかってくるのかを
お前が、俺たちに教えてくれた。
その身を二度も犠牲にして
お前が、教えてくれたんだ。
だから――――『今』がある。
皆を助けられる可能性のある『未来』の扉が
開けられようとしているんだ。
だけど、今のお前にそれを伝える術がない。
あの時に死んでしまっているお前にとっては
その経験自体『無かった事』になってしまっているのだから。
自身が経験していない事を話されても、それには何の実感も伴わないだろう。
こうしてシュバルツと認識している事実がずれ、彼に話せない事が増えて行く。時を遡るとは、そう言うことだ。
自然の理を捻じ曲げている歪さを、痛感せざるを得なかった。
「シュバルツ……」
だけど、このままシュバルツが傷つきっぱなしでいい筈がない。何とか慰めたくて、ハヤブサは必死に言葉を探した。
「シュバルツ……! 大丈夫だ……!」
「ハヤブサ………?」
「周りからどんなに罵倒されようとも、理解されずとも――――村人たちも妖魔たちも、交流を続けているのだろう?」
「ああ………」
腕の中で、涙ながらに頷く愛おしいヒト。
「ならば、大丈夫だ。お前が選びとった道は、決して間違ってなどいない」
「…………!」
「『捨てる神あれば、拾う神あり』だ。シュバルツ……。お前たちの心を理解してくれる存在も、きっと現れる」
「ハヤブサ………」
「現に、俺たちがそうだ。そして、城に居る関羽殿も――――」
「――――!」
それだけじゃない。
この状況を作り出すために、あの陣屋に居た大半の人たちが動いてくれていた。
そして、皆が願っていた。
『救いたい』と――――
もう既にお前の心は
あれだけの人たちの心を動かしているのだ。
「だから、大丈夫だ。シュバルツ……。お前は、堂々と胸を張って――――」
「でも……! でも――――!」
シュバルツは、ハヤブサの言葉を遮るように叫ぶ。
「私は皆に、この土地から離れる選択をさせてしまった……! 私はここの土地神から、あれだけ熱心に祀ってくれていた村人たちを、取り上げてしまう事になるんだ……!」
「―――――!」
「それなのに……! どうして誰も私を責めないんだ!? どうして、こんな事をする私を、『神の代理』だなんて認めるんだ……ッ!」
「シュバルツ……!」
「どうして……! 結局私は何もできずに――――!」
そう言って泣きじゃくる、愛おしいヒト。
「…………!」
ハヤブサは慰める言葉を失ってしまって、ただ、抱きしめることしか出来なくなってしまった。
本当に、どうしてやればよかったと言うのだろう。
この村は今夜、間違いなく襲撃を受け、滅ぶ運命にある。このままここに留まり続ければ、全滅する事は避けられないのだ。
それでも皆を救おうと願うのであれば、こちらが「逃げろ!」と、言ったタイミングで、村人たちが迅速に動く必要がある。動いてもらうには、村人たちの間に、相当の高い危機意識を植え付けなければならない。
しかしそれは同時に、村の平安を願うシュバルツの気苦労を増やし、苦しめる事に他ならなかった。平和に過ごし、明日も同じように朝日が昇ると村人が信じたままでは、誰も救えないのだから。
それは何とも皮肉な話だった。村が平和なままであれば――――シュバルツはここで、穏やかな日々を過ごす事が出来たであろうに。
「シュバルツ………」
ハヤブサはせめて、想いを込めてシュバルツの身体を抱きしめた。
「大丈夫だ、シュバルツ……。俺はたとえどうなろうとも、絶対に――――お前の味方だから……」
そう。
それだけは伝える。
それだけは、自分の中では絶対的に揺らがない物だから――――
「ハヤブサ……」
腕の中で、涙をぽろぽろと零し続ける愛おしいヒト。
「済まない……!」
また、謝られる。
このヒトはいつもそうだ。
謝る必要なんて何もないのに。
お前は、やっと気持ちを零せたんだろう?
やっと、涙を流せたんだろう?
ならば、存分に泣いてくれ。
心を零してくれ。
俺は受け止め続けるから――――
「謝るな……」
シュバルツを抱きしめながらハヤブサは今、確かにこれ以上ないと言う程の幸せを感じていた。
「………………」
忍者二人がそうしているのを、外から女性二人もこっそりと見ていた。
「うっ……く……! ひぐっ……!」
甲斐姫がその光景を見ながら、涙をぼろぼろと零している。
「甲斐……ちょっと泣きすぎよ………」
あまりにも嗚咽を漏らす友人をたしなめるように、孫尚香が声をかける。それに対して、甲斐姫も反撃に出た。
「しょうがないじゃない! 私こういうの本当に弱くて……!」
「それならそれで、もうちょっと声を殺しなさいって。中の二人に気づかれたらどうするの?」
「もう! 尚香だって、泣いているくせに……!」
「そ、それは……! でもあなたほど泣いてませんから!」
「ぐ……! 言ったわね……!」
悔しそうな顔を見せる甲斐姫に、孫尚香はにやりと笑いかける。
「ほらほら、悔しかったら、早く泣きやみなさいよ?」
「うるさい! 言われなくったって――――!」
「あの~、すみません」
いきなり不意打ちの様に声をかけられ、女性二人がビクッと小さく飛びあがった。恐る恐る振り返ると、村人が1人、立っていた。
「な、何?」
顔をひきつらせながら何とか笑顔を作る甲斐姫たちに向かって、村人はきょとん、としながらも用件を切り出した。
「シュバルツさんは居るだか? ちょっと確認したい事が……」
「えっ!? シュバルツさん!?」
女性二人は慌ててしまった。シュバルツはまだハヤブサの腕の中で泣き続けている。出来ればもう少し――――そっとしてあげたいところだったからだ。
「ちょ、ちょっと待って! 居るには居るんだけど……その……!」
「立て込んでいると言うか……出なおした方が良い様な気が――――」
そう言って女性二人は、シュバルツとハヤブサの姿を村人から何とか隠そうとする。しかし哀しいかな――――集会所の建物自体に扉が無く、窓も、あけすけの状態だった。女性二人の努力空しく、結局村人は、ハヤブサに凭れかかって泣きじゃくるシュバルツの姿を見てしまう。
「……………!」
村人はしばし息を飲んでそのまま固まってしまう。
「あ、あの~……大丈……夫、ですか?」
「こ、これは、その……つまり………」
孫尚香と甲斐姫は、固まった村人の様子に心配して声をかけた。だが村人はそれには答えず、茫然と踵を返した。
「シュバルツさん……!」
そう言いながらとぼとぼと歩いて行く足取りが、とても重く、暗い。まるで今から、通夜か葬式にでも行くような雰囲気だ。それを見送った女性二人は、おろおろするより道が無く。
「尚香……どうしよう……!」
「ど、どうしようと、言われても――――!」
そうやってうろたえている所に、また別の村人がやってくる。
「あの……シュバルツさんは……」
「あ……! ちょっと待って……!」
「今は……その……!」
女性陣二人は必死に中の忍者二人を村人から隠そうとするのだが、やはりその努力は徒労に終わり、中の様子を見た村人が衝撃を受けて、やはり足取り重くそこから立ち去って行く。そう言う事が、何回か繰り返された。孫尚香も甲斐姫も、最初は必死に村人たちに対処しようとしていたが、しまいの方は二人の間にもあきらめムードすら漂っていた。村人たちは皆一様に――――とぼとぼと足取り重く、そこから去っていく。
「尚香……ど、どうすればいいのかな……」
「さ、さあ……も、もう、なるようにしか……ナラナインジャナイカナ……」
甲斐姫の問いかけに、孫尚香も苦笑いするしか無かった。
「……………」
やがて落ち着いたのか、シュバルツはハヤブサから身体を離した。
「……落ち着いたか?」
「ああ……。済まなかったな……。醜態をみせた……」
「謝るな。何度言わせる気だ」
「いや、しかし……迷惑を――――んう!」
ハヤブサが強引にシュバルツの唇を奪ったから、シュバルツはこれ以上言葉を紡げなくなってしまう。
「ん……う………」
口腔を深く弄られ、舌を強く吸われ――――呼吸が奪われる。長い長い口付けから解放された時、シュバルツは酸素を求めて喘がなくてはならなくなった。
「迷惑ではない――――と、何度言ったらお前は分かってくれるんだ?」
ハヤブサは、シュバルツを逃がすものかとでも言わんばかりに彼の首の後ろに手を回し、シュバルツの利き腕を捕まえてがっちりと固定している。
「ハヤブサ……」
「お前が俺の前で泣く事を――――俺が嫌がるとでも? お前の心を、俺が欲しがらないとでも、思っているのか?」
「いや、そう言うつもりでは……」
何か危険な物を感じて、シュバルツはハヤブサから一歩、身を引こうとする。だが彼がそうする事を、ハヤブサが許す筈もない。捕まえている腕を、彼は更に強く握った。
「あっ!」
その小さな悲鳴を聞いた瞬間、ハヤブサの中で何かがぶち切れそうになってしまう。
「俺は欲しいんだ……! お前の心も……! その身体も――――!」
「ハ、ハヤブサ……!」
「シュバルツ――――」
押シ、倒シタイ
抗いがたい欲望が、鎌首をもたげてくる。
無理もない。
もう2カ月以上も―――――シュバルツの最奥に触れていないのだから。
枯渇して、もう死にそうだ。
だがまだ――――シュバルツを完全に悲劇から救えている訳ではない。
ハヤブサはそう感じて、己が理性を必死に総動員する。
今は、まだ駄目だ。
シュバルツを、完全に自分の手に取り戻すまでは――――!
「……………」
僅かに、腕の力を緩める。だが、シュバルツは逃げなかった。
「ハヤブサ……?」
それどころか、こちらを気遣うように呼びかけられ、そっと手が触れてくる。「ハヤブサからは逃げない」と言う、明確な意思の表れだった。それを見てハヤブサは、ようやく落ち着く事が出来た。シュバルツの心の所在を、思い出したからだ。
シュバルツの心は、常に俺に寄り添っている。
だから、恐れるな。
目の前のこの愛おしいヒトは
俺がどう触れようとも、絶対に拒絶などしないのだから――――
意を決して、シュバルツを解放する。
「……とにかく、俺の前で泣いたぐらいの事で、いちいち謝らなくて良い。俺は別に構わないのだから」
寧ろ嬉しいぐらいだ――――そう言ってそっぽ向くハヤブサに、シュバルツは思わず苦笑してしまう。
「ああ。分かった……。済まな――――」
「…………」
ジロリ、とハヤブサに睨まれて、シュバルツは慌てて口を塞ぐ。
「いや……。ありがとう……」
「よし」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサは頷いて踵を返す。だが内心は――――飛び跳ねまわって叫びたい気持ちでいっぱいだった。
(ああもう可愛い! 可愛すぎる! 俺のシュバルツ……! 今すぐ抱きしめて、押し倒してしまいたい!)
ハヤブサが内心そう言いながらじたばた転げまわっている事に気づいているのかいないのか――――シュバルツが苦笑しながら声をかけてくる。
「さあ、皆を避難させないといけないな。ハヤブサ……また、力を貸してくれるか?」
「無論だ」
そう言って、二人が手入り口の方に顔を向けた時、中をおずおずと覗き込んでいた女性陣二人と目が合った。
「…………!」
変な所を見られたのではないかと、少し顔を強張らせるシュバルツ。ハヤブサはそんなシュバルツを女性たちから庇うようにその前に出ると、「どうした?」と、声をかけた。尤も、自分の気持ちはもう彼女たちにはばれているので、それでどう思われようが、自身は全く頓着しないのだが。
「あ………えと………」
女性たち二人は、少し逡巡するようにこちらを見ていたが、やがて意を決したように、孫尚香の方が声をかけて来た。
「シュバルツさん、あの……」
「………? 私に用か? どうした?」
ハヤブサの後ろから出て来て、シュバルツが近寄ってくる。
「はい……。あの……ちょっと、外に、見てもらいたい物が――――」
「……………?」
孫尚香に導かれるままにシュバルツは外に出て、彼女に示された方を見て――――息を飲んだ。
「………! これは――――!」
シュバルツが驚くのも無理からぬことであった。何故なら、彼の目の前の広場には、綺麗に設えられた祭壇と、そこに整然と祀られた、お供え物の山があったからである。
祭壇に向かって拝んでいた村人の1人が、集会所から出てきたシュバルツに気がついて、声をかけて来た。
「あ、シュバルツさん」
「これは、どうしたんだ……? 避難の準備は――――」
問うシュバルツに、声をかけてきた村人は微笑みかける。
「何時でもすぐ逃げられるように、避難の準備は出来ていただ……。ただこれは、今までお世話になったこの土地と、土地神様に――――感謝の心を捧げたい、と、思って……」
「これは本当なら、明日の感謝の祭りで供えられる筈の物だったのだがのう」
シュバルツに気が付いた別の村人が、話に入ってくる。
「わしらがここまで無事に生活出来て、良い桃を収穫できたのも、土地神様の御加護があっての事じゃ……。だから、礼を言わねば、罰が当たると言うものじゃ」
そう言って村人は、祭壇の方に手を合わせて頭を下げる。
「シュバルツさん……。えと……つまり、この人たちは………」
おずおずと、甲斐姫が声をかけて来た。
「泣いている、貴方の姿を見て………」
「―――――!」
「どうも……ここの『土地神様が泣いている』と、感じちゃったみたいで………」
「えっ?」
思わず変な表情を浮かべて聞き返すシュバルツに甲斐姫は頷くと、更に説明を続けた。つまり、泣いているシュバルツの姿を見た村人たちが、とぼとぼと集会所を後にしたかと思うと、同じように泣きながら、誰からともなく祭壇の準備を始めたのだと。そして見るみるうちに祭壇の上は、お供え物であふれかえっていったのだと。
「ここの村人たちは、本当に……ここの土地神様が、大好きなんですね………」
そう言う甲斐姫の瞳も、涙ぐんでいる。
甲斐姫は以前この村を訪ねてきた時、村人たちの朴訥ともいえる信仰心に触れていた。だから、この村人たちの行動も、素直に腹に落ちたのである。
「あ…………!」
茫然としているシュバルツの肩を、ハヤブサがポン、と叩いた。
「どんな形であれ、ちゃんと村人たちはお前の心を受け取っている」
「ハヤブサ……」
「お前がこの村の人たちを守るために、どれだけ心を砕いて来たか――――ちゃんと、伝わっているんだ……」
「…………!」
だから大丈夫だ。何も心配するな。と、言うハヤブサに、シュバルツは少し複雑な表情を見せる。そこに、ケイタをはじめとした人間と妖魔の子供たちが、「シュバルツさん!」と、走り寄ってきた。
「ケイタ! みんな!」
子供たちと同じ目線になる様に座りながら彼らを迎えたシュバルツが、ケイタに問いかける。
「妖魔の子たちはどうするんだ? 一旦自分達の村に帰るか?」
シュバルツの問いかけに、妖魔の子供たちは首を振った。
「ううん、今、お姉ちゃんが1人、村の方に走って行ってくれたよ! 僕たちはここに居るから、迎えに来てもらって、一緒に逃げようって!」
「みんなが居てくれるから、ぼく、怖くないよ!」
「あのね、さっき、おばちゃんからお菓子もらったの!」
そうやって皆が口々に元気よく答えてくるのを、シュバルツは「そうか」と、穏やかに微笑みながら聞いていた。すると、その中の1人がシュバルツに声をかけて来た。
「……シュバルツさん……泣いていたの?」
「えっ?」
きょとん、とするシュバルツの瞳の付近を、その子供は指差した。
「だって……涙の跡が……」
「あ…………!」
慌てて瞳の周りをごしごしと拭く。
「あはは……ごめん、ごめん。大したことじゃないから――――」
そう言ってシュバルツは顔に笑みを浮かべるのだが、子供たちの方は逆に、ふにゃ、と、涙で表情が歪んで行った。
「嫌だ……! シュバルツさんが泣いたら、嫌だよう~~~!」
「僕たちも、悲しいよ~~~!!」
そう言いながら子供たちが、次々と泣き出してしまう。
「ちょ……ッ! 本当に大したことないって、言っているのに――――!」
シュバルツは慌てて子供たちの頭を撫でたり肩を抱いたりするのだが、子供たちの泣き声の大合唱は、ますます大きくなっていくばかりで。
「こらっ! お前たち!! シュバルツさんに迷惑かけちゃだめって、言っているだろう!!」
村人の1人が、子供たちに声をかけてくる。しかし。
「おっちゃんだって、泣いているじゃないか!」
「うるさい!! おっちゃんだって……! おっちゃんだってだなぁ……!」
ボロボロと涙を零していたその村人は、子供たちと一緒に泣きだしてしまった。
「大作さん! 泣くのやめろって! でないとわしだって……ッ!」
そのまま次から次へと大泣きする連鎖が大人の方にも広がって行く。
「いやあの! 私はもう泣いてなどいないから――――!」
シュバルツは必死になって呼び掛けるのだが、村人たちの方が既に聞いていない。そのまま大泣きの大合唱が始まってしまう。
「何か……すごいな……」
ある意味収拾がつかない目の前の事態に、ハヤブサももう苦笑するしかない。
「済まないな……。こちらの感情に、時々こんな風に過剰に反応されることがあって……。なるべく感情の起伏を面に出さないように、注意してたんだが――――」
頭をかきながらそう言うシュバルツに、ハヤブサも「そうか」と返事をする。シュバルツの気苦労の一端を、垣間見た気がした。
「しかし、まずったなぁ。うっかり緩んでしまったのは、私のミスだ」
「―――どうして、緩んだんだ?」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサは少し意地わるく問いただす。それにシュバルツが一瞬言葉にぐっと詰まった後、じと目でこちらを睨んできた。
「……どうしても、私の口から言わせたいか?」
「いや? 別に?」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサは素っとぼける。
シュバルツの気持ちは分かっているから、改めて確認する必要はない。強いて言うなら、彼をからかって遊びたいだけだった。
「―――もう、知らん!」
そう言いながら、赤くなってそっぽを向く愛おしいヒト。ハヤブサは思わず声を立てて笑っていた。至福のひと時だった。
「冗談はともかくとして……良くも悪くも、情が深い村だな。ここは……」
「ああ。そうだな」
ハヤブサの言葉にシュバルツも頷く。
「朴訥で、とても優しい。だが、この人たちのそんな所を、私は気に入っている」
そう言いながら村人たちを見つめるシュバルツの瞳に、どこか誇らしげな光が宿っているのは気のせいだろうか。
だが、こういう村人たちだからこそ――――いきなり闖入してきたシュバルツを受け入れ、妖魔と交流を持つ事も、可能にしたのだろう。その外見の恐ろしさに惑わされる事も無く。
ある意味得難く、そして優しい人たち。
シュバルツが命がけで守ってしまうのも無理からぬことだと、ハヤブサは思った。
しばらくそうして、泣き声の大合唱をしていた村人たちであったが、やがてその中の1人が、とんでもない事を叫び出した。
「よしっ!! 今日はもう、土地神様を偲んで、飲むべ!!」
「ちょ……! ちょっと待ってくれ!! 流石にそれは止めてくれ!!」
流石に今の言葉に肝を冷やしたハヤブサは、思わず叫んでいた。残念ながら敵の襲撃はもう間近。のん気に宴会など開いている時間は無かった。
皆の注目を集めたハヤブサが訴える。それで皆も、ようやくはっと我に帰ったようだった。
「そうだな。今はこういう事をしている場合では無いべ」
「とにかく早く、脱出しないと―――」
皆は口々にそう言うのだが、村人たちはそこから動こうとしなかった。まだ、未練の様な物があるのだろう。
(これは……何か区切りをつけさせてやらないと、皆、動けないだろうな……。しかし、どうしたものか――――)
シュバルツがそう考えていると、そこに村長と長老がやってきた。
「シュバルツ殿……。少し、見ていただきたい物があるのですが、よろしいですかな?」
「あ、ああ。構わないが……」
「では、こちらへ―――」
そう言って、村長と長老がシュバルツを導く。村人たちの間を通り抜け、祭壇を通り過ぎ――――広場の一角に生えている、大きな樹の所に案内された。
「シュバルツ殿、これを御覧くだされ」
長老が指し示した先の木の根元に、その小さな祠はひっそりと在った。
「それは……! もしかして――――」
シュバルツの言葉に長老が頷く。
「左様。お察しの通り、ここの土地神様を祀った最初の祠じゃ。今広場にある祠は、皆がお参りしやすように新しく建て直したものじゃが……神様の本体は、こちらに御祀りしてある」
言い終えた後長老は、作法に則り祠の前に膝をつく。手を合わせ、口の中で何事かを小さく呟いた後、祠の扉をカタン、と開けて、中から小さな『石』を取り出した。
「こちらがその『本体』ですじゃ。この村を開いたご先祖が、川から流れて来たこれを拾い上げたとか、その昔、村を守るために犠牲になった者の墓石の一部だとも、伝え聞いておる」
取り出した『石』を広げた白い布の上に置いて、両掌の上に包むように持って、長老はシュバルツに見せる。何処にでもある普通の石の様だが、その丸い石は、何となく人型を模しているように見えなくも無かった。
「その御先祖がこの石のために祠を立て、祀ったところ――――村の田畑はよく潤い、豊作が続いたと……。それ以来、わしらはこれを土地神様として受け継ぎ、豊作のお約束をしていただいていた様な物じゃ……」
「……………!」
長老の言葉を聞きながら、シュバルツは拳を握りしめていた。
分かっている。
ここの人たちにとって、土地神を祀る事はもちろんの事、今まで育ててきた田んぼや畑の土が――――何物にも代えがたい宝だった。自分も農作業の手伝いをして、それが骨身に沁みて分かっていた。農作物を作るための『土』は、一朝一夕で出来る物ではないのだと。
だから、できるだけこの場所で村人たちを守ってあげたかった。
それが叶わずに、今日のような事態を迎えてしまったのは、ただひたすら自分の力不足によるところが大きいのだと、シュバルツは自分を責めていた。
「シュバルツ殿?」
村長に声を掛けられて、シュバルツははっと我に帰った。
「大丈夫です。どうぞ、続きを――――」
シュバルツに促されて、長老は話を続ける。
「シュバルツ殿……。わしは、この『本体』を、わしらと共に連れて行こうと思っておるのじゃが……どうだろうか?」
「―――――!」
「『土地神様』は、わしらにとってはもう村の守り神も同然じゃ。とても離れがたく感じておる。新しい土地でも『村の守り神』として、御祀りしたいのだが……」
「……………」
(私は決して『土地神様』と言う者の代理の者などではない……。でも、これはいくら言っても分かってはもらえないのだろうな……)
長老の話を聞きながら、『土地神の代理としての意見を求められている』と感じて、シュバルツは苦笑していた。本当に自分が『村の守り神』と言う類の者であるのなら、そもそも村人たちをこの村から追い出さねばならない様な事態になどさせはしない。この時点で、自分はもう充分村の守り手としての役割を失敗していると言って良いのに。
どうして――――誰も自分を責めないのだろう。
何がいけなかったのか。
何を間違ってしまっていたのか。
ずっと己に問い続けてしまう。
考えた所で答えなど、でる筈もないのに。
これはもう、気持ちの問題なのだ。
長老が「共に行きたい」と言うのであれば、御神体も共に行かせてあげれば良いと思った。これだけ熱心に祀ってくれた村人たち。神様だって、離れがたく感じるだろう。もしも本当に――――この『神様』が、自分と同じ考え方をする、と、言うのなら。
「長老様のお心のままに……。共に行かれるのであれば、そうした方がいいと私も思います。その方が、『神様』も喜ばれるでしょう」
だからシュバルツも、長老にそう答えた。そしてそうしたことで、もしも天罰が当たると言うのなら――――その天罰は、どうか自分に。
彼はそう祈っていた。
「そうですか……。シュバルツ殿が、そう仰られるのなら」
長老は満足そうに頷くと、祠に向かって恭しく礼をした。
「では、土地神様……。今まで本当にこの地でのたくさんの恩恵を、どうもありがとうございました。良く肥えた田畑、綺麗な水――――これは、このままここに置いて行きます。どうか、次にこの地に入る者たちに、この恵みが受け継がれますように――――」
そう言って長老が祠に向かって頭を下げる。すると、いつの間にか長老の後ろについて来ていた村人たちも、一斉に祠に向かって頭を下げていた。
「そして、誠に勝手な我らの望みですが、もし、これから我らの向かう新しい地で、また、貴方様の御神体を、『村の守り神』として、御祀りさせていただきとう存じます。どうかそれをお許しいただきたく―――伏してお願い申し上げまする」
長老が御神体を、捧げ持つようにして礼をする。頭を下げている村人たちの間から、すすり泣く様な声が上がっていた。無理からぬこと――――と、誰もが思った。皆が皆、この地から離れがたく思っているのだから。
――――と、その時、優しい風がそよ、とふいた。
その風に乗って、ふわり、ふわりと村人たちの上に、ある物が舞い落ちてくる。
「桃の花だ!」
それに気付いた誰かの声に、皆が一斉に顔を上げた。そして、自分達の目の前に、確かに落ちて来たその桃の花に、皆が驚いた。何故なら、今は桃の収穫の時期。花など咲いているはずもないのだから。
「こ、これは一体……?」
「どう言うことだべか……」
突如として現れた桃の花の舞に、村人たちはただ茫然とするしかない。「うわ~! すご~い!」と、子供たちは無邪気に喜び、女衆たちの中には「綺麗……」と、見とれる者もいた。
「……………」
ハヤブサの目の前に、ひとひらの桃の花が舞い落ちてくる。掌を差し出すと、その薄紅色の桃の花は、彼の手の上にふわりと収まった。
(これは……どう判断すればいいんだ? 特に不吉なものを感じる訳ではないが……)
桃の花を運んできた風はひたすら優しく、花の乱舞は美しかった。誰もがしばらく花吹雪の中に言葉も失って佇んでいると、そこに小さな声が聞こえた。
「―――――」
「シュバルツ。お前、何か言ったか?」
最初ハヤブサは、シュバルツの声だと思った。だからその声を聞いた時、彼にそう問いかけてみたのだが。
「いや、私は何も……」
しかし問いかけられたシュバルツは、そう言って首を横に振るばかりだ。
「じゃあ、今の声を、お前は聞いたか?」
「声? 何か声がしたのか?」
「!?」
怪訝な顔をしながらこちらを見るシュバルツ。どうやら彼は、今の声を聞いてはいないようだ。
(どう言うことだ? 今確かに、俺には『声』が聞こえたのに――――)
酷く小さくか細い物だったか、自分の耳は確かにその声を捉えていた。シュバルツは忍者として、自分と同じくらいの技量を持っている。だから、あの程度の小ささの声ならば、彼の耳ならば捉えられる筈なのに。
不思議に思ってハヤブサが首を捻っていると、村人たちの間からもざわめきが上がっていた。
「今、誰かが何か言ったべ?」
「いや、俺は何も聞いてねぇ」
「私も何も――――」
「おらには聞こえた。何か言っていたな」
「えっ? そんな声しただか?」
どうやら村人たちの間でも、聞こえている者と聞こえなかった者が居るようだ。
だが、一番如実にその声を捉えていたのは、どうやら子供たちの様だった。
「声が聞こえたよね!」
「うん! 聞こえた!」
「とっても優しい声だったよ!」
「僕にも聞こえた!」
「その声は、何て言っていたの?」
騒いでいる子供たちの近くに居た甲斐姫が問いかけると、子供たちは嬉しそうな笑顔を見せて答えた。
「『大丈夫だよ』って、言ってた!」
「――――!」
その言葉に、周りに居た大人たちは皆、一様にはっと息を飲む。
「うん! 言ってたね! 『大丈夫だよ』って!」
「うん! そう聞こえた!」
「『大丈夫』なんだって!」
「『大丈夫だ』って!」
「こ、これは……! 長老様……!」
子供たちの声を受けて長老に問いかける村長に、長老も頷き返した。
「うむ……。間違いない。これこそ、『土地神様』のお声なのじゃろう……。信じられぬ事じゃが――――」
そう言いながら長老は、茫然と桃の花が舞う空を見上げる。いろいろと説明が出来ない事象。この小さな村には今――――確かに『奇跡』が舞い降りていた。
「長老様は、御声は聞かれたのですか?」
村長の問いに、長老は笑顔を返す。
「ああ。確かに聞こえたぞ? この年老いた耳にも、はっきりとな……」
そう言うと、長老は立ち上がった。村を導く者としての、役目を果たすために。
「さあ、皆の衆。立ち上がろうぞ。これは土地神様の御意志だ。我等に『生きよ』と言う――――」
「長老様!」
「今、この地を離れねばならぬ我らは、最大級の不幸に見舞われているのかもしれぬ。しかし、その先の未来は、必ず明るく開けておるのだ。それならば、何を恐れる事があろうか」
「おお……!」
「確かにそうじゃ……!」
長老の言葉に、村人たちの意気が上がる。
「さあ皆、参ろうぞ! 明日を生きるために―――!」
オオッ! と、村人たちの間から歓声が上がる。その光景に、ハヤブサはホッと胸を撫で下ろしていた。どうやら村人たちは、スムーズに避難を開始してくれそうだ。さしずめ、第一関門突破と言ったところだろうか。
「それではみな、準備ができた者から村の西の境に集まってくれ。妖魔の方々と合流でき次第、速やかに出発をしよう」
「劉備様の城には、私たちが案内します!」
村長の言葉に続いて、甲斐姫と孫尚香が手を上げる。彼女たちの導きに合わせて立ち上がろうとした村人たちであったが――――そのうちの1人が声を上げた。
「長老様……。この飾り付けたお供え物は、どうしますか?」
その言葉に、村人たちの足が止まる。普通なら、片づけなければならないところだ。だが、しばらくそれを静かに見つめていた長老は、やがて静かに首を振った。
「……これは、このまま置いて行こう」
「長老様!?」
驚く村人たちに語りかけるように、長老は口を開いた。
「この供物は、神様に捧げた我らの『心』じゃ……。拠ってこれは、このままここに置いて行く」
「長老様……!」
「…………!」
これにはハヤブサとシュバルツもさすがに驚いた。間もなくここは襲撃の憂き目に遭う。このような物など真っ先に破壊され、略奪されてしまうだろうに。
「確かにそうじゃ……。じゃがそれでも――――『証』を残しておきたい。我らは確かに、ここに居たのだと。我らは確かに、この土地を愛していたのだと………」
自己満足な想いかもしれないがと苦笑する長老に、シュバルツは首を振った。それ以外――――何を言う事が出来ただろうか。踏みにじられる事を承知で、それでもきれいに飾りつけられてある供物の数々が、酷く切なかった。
「では皆――――急ぐのじゃ! 襲撃されぬうちに、脱出しよう!」
村長の言葉に皆が頷き、動き始めた。シュバルツも皆を手伝うために歩き出そうとした時、彼のロングコートの裾を引っ張る者が居た。
「シュバルツさん」
振り向いた視線の先には、ケイタが居た。
「どうした? ケイタ」
シュバルツがいつもの様にケイタの目線の高さに屈むと、声をかけてから少し考え込むようにしていたケイタが、思い切ったように声をかけて来た。
「ねえ……今の声って、やっぱりシュバルツさんなんでしょう?」
「えっ?」
少し面食らった様に問い返すシュバルツに、ケイタは尚も言葉を続ける。
「シュバルツさんが、僕たちを安心させようとして――――」
「あはは……残念ながら、違うよ」
そう言って優しく笑うシュバルツに、ケイタはなおも食い下がってくる。
「だって……! あの声はシュバルツさんにそっくりだったよ!? だから僕は――――!」
「ケイタ……。残念ながら私は、その『声』を聞いても居ないんだ」
「えっ? でも――――!」
「本当だ……。前にも言っただろう。『私はお前に、絶対に嘘はつかない』と……。誓って私はあの時何も言ってはいないし、やっても居ない」
「そうなの?」
怪訝な顔をするケイタに、シュバルツは優しく微笑みかけた。
「本当だって。第一、これだけたくさんの桃の花を、どうやって用意するんだ」
そう言ってシュバルツは、落ちている桃の花を拾い上げてケイタに渡す。
「……そうだけど……」
シュバルツから渡された桃の花を見つめながら、ケイタはまだ納得しかねているようだった。
「だって、シュバルツさん、時々魔法を使ったし」
「…………!」
ぼそっとケイタから言われる言葉にハヤブサは吹き出しそうになり、シュバルツも苦笑するしかない。
「あれは『手品』と言って、ちゃんとタネも仕掛けもあるものなんだ」
「本当に?」
少し疑いの眼差しを向けてくるケイタに、シュバルツは苦笑しながらも頷き返す。
「本当だよ。そうだ、今度タネを教えてあげよう。約束するよ」
「本当に!?」
シュバルツのその言葉を聞いたケイタの顔が、ぱっと明るい物になる。
「無事に避難が出来たらな」
そう言いながら笑うシュバルツに、ケイタは「うん! 分かった!」と元気良く頷き返すと、踵を返して走り去って行った。やれやれ、とシュバルツがため息をつきながら身を起こすと、後ろからハヤブサに声をかけられた。
「相変わらず、子供の前で手品をやったりしているのか?」
「仕方がないだろう? 度重なる他の部族からの嫌がらせや襲撃で、子供たちも皆怯え気味になっていたから――――」
「そうか……」
今のシュバルツの一言で、ハヤブサは、彼がどれだけここで八面六臂に走り回っていたのかを察してしまう。つまりシュバルツは農作業の手伝いだけではなく、妖魔たちの村に対する嫌がらせや襲撃の対応、さらには子供たちの心のケアまでやっていたのだ。その間に村長や長老の相談に乗ったり、妖魔たちの村の方まで足を運んでいたのだとしたら、それこそ休む間もなかっただろう。よくぞここまで頑張って来れたものだと、逆に感心してしまう。
「しかしお前は、本当に子供をあやすのがうまいな」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツは苦笑する。
「8歳年下の弟をあやした経験が生きているだけだ。そんな特別な事じゃない」
シュバルツはそうさらりと言ってのけるが、子供の相手をするのがいまいち苦手な自分からしてみれば、怯えた子供たちの心をほぐし、笑顔を引き出す事の出来るシュバルツは、充分尊敬に値するとハヤブサは思うのだ。
村の西側の方が、少しざわつき始めた。どうやら、妖魔の村から避難をして来た者たちが到着したらしい。妖魔たちは皆頭に布を巻き、大きな鳥の羽を挿している。どうやら本当に、この妖魔の村全体の妖魔たちが、その羽をつけているようだった。
「シュバルツ殿!」
村に来た妖魔たちの内の1人が、シュバルツに気がついて声をかけて来た。それに気が付いたシュバルツも、そちらに向かって走って行く。
ハヤブサはそのシュバルツの後は追わずに、ケイタの後を追う事にした。少し、確かめたい事があったからだ。
求めていたケイタの姿はすぐ見つかった。彼は自分の荷物を担ぎながら、妖魔の子供たちを集めているところだった。
「ケイタ!」
ハヤブサが声をかけると、ケイタは少し驚いた様に振り向いた。
「わっ! びっくりした! えっと……ハヤブサ、さん?」
「ああそうだ。俺の名前はリュウ・ハヤブサだ」
ケイタに名乗りながら、ハヤブサは少し複雑な心情を味わう。前の時間軸ではそれなりに親しくなれていたケイタ。だが、この時間軸ではまだ、初対面に近いのだ。ケイタのどこかよそよそしい態度にハヤブサは少し淋しさを覚えるが、これも仕方がない事だろうと思う。時間を遡るとは、そう言うことだ。シュバルツに守られて、1人生き残ってしまった事も、村の襲撃から命からがら皆で逃げた事も、ケイタにとっては『無かった事』になってしまっているのだから。
「お前に確認したい事がある。少し、良いか?」
気を取り直してハヤブサは、ケイタに話しかける。彼がどう言う子供かは分かっているので、他の子たちに話しかけるよりも、ハヤブサにしては随分気楽に声がけられていた。
「はい。良いですけど……」
少し怪訝な顔をしながらも、こちらに向き直り、まっすぐ見つめてくるケイタ。ハヤブサはそんなケイタと同じ目線の高さに身を屈めると、聞きたい事を切り出した。
「お前が聞いた、例の『声』の事なのだが――――」
「はい」
「そんなに、シュバルツにそっくりだったか?」
「…………!」
その確認に、ケイタは少し驚く。だがちょっと考えてから、彼はすぐに答えを返してきた。
「うん。間違いないよ。あれは、シュバルツさんの声だと僕は思ったんですけど……」
ケイタのその言葉に、ハヤブサは「そうか」と頷くと、すぐに立ち上がった。
「済まなかったな。これで用は終わりだ」
「もういいの?」
問うケイタに、ハヤブサは頷く。
「ああ。俺も確認したかっただけだから」
「確認?」
小首を傾げるケイタにハヤブサは答えを返す。
「ああ。俺もあの『声』は、シュバルツの物だと思ったから――――」
他に自分と同じような聞こえ方をした者が居たかどうか、確認したかっただけだとハヤブサは言った。
「でも、シュバルツさんはあの時、何もしゃべってはいないんでしょう?」
「そうらしいな」
ハヤブサの言葉にケイタも「そうなんだ……」と口の中で呟きながら、尚も首を捻っていた。
「どうした?」
「あ……えと、その……」
ハヤブサに問い返されて、ケイタはしどろもどろになってしまう。ケイタはハヤブサとシュバルツの声がとても似ている事に気づいてしまった。だけど、それをハヤブサに告げていい物かどうか、迷っていた。
ハヤブサも、ケイタがこちらをちらちら見ながら口ごもっている理由を何となく察してしまう。小さなため息をつきながら答えた。
「……残念ながら、俺もあの場では口を開いていない。言っただろう。俺もあの声を聞いたと。よくシュバルツと俺の声は似ていると人には言われるが――――」
「すみません! 僕も、貴方に最初声をかけられた時、てっきりシュバルツさんに声をかけられたのだと思って――――!」
だから、とても驚いてしまってすみません、と、ケイタが必死に謝ってくる。それに対してハヤブサは、多少苦笑しながら首を振った。
「別に謝られる事ではない。気にするな」
「でも……シュバルツさんでも、ハヤブサさんでもないとなると、あの声は一体……? やっぱり、神様だったのかな……?」
「さあな………」
ケイタの問いかけに答えながら、ハヤブサは空を見上げていた。
自分とシュバルツとよく似た声の持ち主を、自分はあと1人、知ってはいるが――――。
(まさかな………)
何処までも抜けるような青い空に、もう、桃の花は舞ってはいなかった。ただ、ハヤブサの頬を撫でるその風は、何処までも優しかった。
村の西の出入り口の所に、人も妖魔もどんどん集まってくる。
「よし! 皆、各組ごとに点呼を取っておいてくれ! 馬が要る者も言ってくれよ! 手配してあるからな!」
シュバルツがそう指示を出しながら、皆の間を縫うように歩いている。そこに、ハヤブサが追いついて来た。
「馬があるのか?」
ハヤブサは少し驚いていた。前の時間軸の中では、馬など――――数えるほどしか村にはいなかった筈だからだ。
「ああ。数日前だが『馬商人』と、ここの村から行商に出ていた者が知り合いになって――――」
「馬商人?」
何となく太公望の匂いを感じ取りながらもハヤブサは問い返した。
「ものすごく格安で、良い馬を沢山買わせてくれたんだ。この辺りも不穏になって来ていたし、馬は必要だと感じていたから、こちらとしてはものすごく助かったのだが……」
「そうだな……。わしらも気の毒だからもう少し値を上げてくれても良いと言ったのだが――――」
二人の会話に、村人が1人入ってくる。どうやら、彼がその行商に出ていた本人の様だった。
「そんなに安かったのか?」
問うハヤブサにシュバルツがため息をつきながら話す。
「だって馬50頭を桃10個と交換してくれたんだぞ!? そんな無茶苦茶な話があるか!?」
「―――――!」
あんぐりと口を開けるハヤブサに、シュバルツの力説はなおも続く。
「しかも! 渡された馬に問題でもあるのかと思ったら! 皆健康体だし毛艶も良いし、よく走るし――――!」
「何か、西涼の方で育った馬だとか言っていたなぁ? その馬商人は……」
村人のその言葉に、思わずハヤブサは問いかけてしまう。
「そ、その馬商人って、大きな筆を持っていなかったか?」
「よく分かっただな!?」
村人のその言葉に、彼はひっくり返りそうになってしまった。
「五郎さん、もう一人商人さんが居たべ? 何か変わった武器を持っておったが……」
「あれは『撃剣』と言う武器だ。紐に繋がった剣を操って戦うんだ」
「はあ~……さすがシュバルツさん」
「……………!」
感心する村人たちの横で、ハヤブサは痛む頭を必死に押さえていた。
(馬商人と言うのは、馬岱殿に徐庶殿だな……! それにしても太公望め……! 本当にあからさまな介入を――――!)
「おまけにその商人、『これから必要になるだろうから』って、火薬まで分けてくれたんだ……! ハヤブサ、どう思う?」
「……良いんじゃないのか? 人の好意は素直に受けておけば」
ひきつるハヤブサの顔に気づいているのかいないのか、シュバルツはため息をつきながら尚も零している。
「さすがにそれだけもらってこちらが桃10個では気の毒だったのでなぁ。一応商人達を引き留めて、何とかこちらが備蓄している米と野菜をせめて渡そうとしたんだが――――」
「『そんな大量に持って帰れないから』とかなんとか言われて、断られちまったんだよなぁ。あの人たち、あれで商売成り立つんじゃろうか?」
「そんな事言いながら五郎さん、無理やり持たせてたじゃないか」
「そりゃあそうじゃろう。あれだけ親切にしてくれた人、手ぶらで返しちゃったら罰が当たるべ」
「あの~、ちょっと良いですか?」
皆がそうやって話し込んでいる所に、声をかけてくる者が居た。振り返ると、そこに孫尚香が立っていた。
「どうした?」
問いかけるハヤブサに、孫尚香は真剣な眼差しを向けてくる。
「シュバルツさん……。馬があるのなら、何頭かお借り出来ないでしょうか?」
「それは構わないが……何をするつもりなんだ?」
「少し早いかもしれないけれど、劉備様の城に援軍を頼みに行きたいの」
「えっ?」
少し驚くシュバルツに対して、ハヤブサは全く動じずに声をかける。
「もう、行くのか?」
ハヤブサの言葉に孫尚香は力強く頷いた。
「甲斐と話し合って決めたの。これだけの大人数が移動するんですもの。助けの手は絶対に多い方がいいと思うの」
「それはそうかもしれないが――――」
孫尚香の言葉に、しかしシュバルツは異を唱える。
「我々と劉備殿の間には、接点がない。君の気持ちはありがたいが、劉備殿にあまり迷惑をかける訳には――――」
「……そうだな。孫尚香、行ってくれるか?」
「ハヤブサ!?」
驚くシュバルツに振り返ると、ハヤブサは言葉を続けた。
「確かに、彼女たちの言うとおりだ。これだけの人数が動くんだ。全員を守り切るには、援軍は絶対に必要だ」
「しかし……!」
「馬は何処だ? 案内してやってくれ」
ハヤブサのその言葉に、1人の村人が頷いて、孫尚香に声をかけた。
「分かりました! こちらです!」
「ありがとう!」
その言葉を残して、孫尚香は踵を返していく。
「ハヤブサ……! 大丈夫なのか?」
シュバルツの問いかけにハヤブサは頷く。
「大丈夫だ、シュバルツ。言った筈だ。劉備殿の城に居る関羽殿は、総てを承知してくれていると」
「ハヤブサ……」
「信じてくれシュバルツ。俺たちは皆を救うために、ここに来ている。その為に動いているのだから―――」
「…………」
シュバルツはしばらく、じっと推し量る様にハヤブサを見つめていたが、やがて、フッと小さく笑った。
「分かった……。信じよう」
「シュバルツ……!」
その微笑みがあまりにも綺麗だったものだから、ハヤブサは思わず彼に触れたくなってしまう。
(いやいや! 無いだろう!? 俺!! 今はそれどころではないし、第一周りは人だらけだ!!)
必死に自分の理性を総動員して、ハヤブサは自分の右手を押さえる。かなりシュバルツに飢えてしまっている自分。迂闊に触れてしまったら、いろいろと歯止めが利かなくなりそうで怖かった。
しかしそうやって自分の中の葛藤が激しくなってくると、どうしても面に出てくる挙動が不審な物になって来るらしく。
「ハヤブサ? どうしたんだ?」
シュバルツが怪訝な顔をしながら問いかけてくる。何かいろいろと伝わらなくていい物が伝わってしまったらしい。
「いや……何でも無い」
懸命に平静な気持ちを手繰り寄せて返事を返す。
(いかんいかん、緩んでしまっては――――)
どうも太公望のあちこちにちりばめられている助けの影を意識してしまうと、ともすれば無意識のうちに油断しそうになってしまう。
(しっかりしろ、リュウ・ハヤブサ。まだ、誰ひとりとして助けられていない。悲劇を回避できてなどいないのだから――――)
必死に自分に言い聞かせ、自分の腹を締め直した。
そうだ。油断などしてはいけない。
まだ彼らを助けられると決まった訳ではないのだから。
「そうか。なら良いが……」
シュバルツは首を捻りながらも、そう言って引いてくれたから、ハヤブサもほっと、小さく息を吐いた。
「シュバルツ殿!」
その声に振り向くと、長老がこちらに向かって手招きをしていた。
「長老? どうしました?」
シュバルツが長老の方に向かって走って行く。ハヤブサもその後に続いた。
「シュバルツ殿……! 避難に入る前に預かって欲しい物がある事を思い出してのう。探しておったのじゃ」
「預かる? 私がですか?」
不思議そうな顔をするシュバルツに向かって、長老は懐からある物を取り出す。
「これじゃ」
「――――――!」
シュバルツは思わず息を飲んでいた。
何故ならそれは、長老が祠から取り出した『土地神様』の形代として祀られていた石だったからである。
「今、シュバルツ殿は土地神様の『代理』じゃ……。ならば、これは貴方が持って然るべきものではないかと、わしは思う」
そう言いながら長老は、シュバルツに向かってその石を差し出す。しかしシュバルツは、それから距離を取るように一歩身を引いた。
「いえ……。そのままどうか長老がお持ちください。それは、私ごときが触れていい物ではありません」
「何故じゃ?」
シュバルツの言葉に納得できない長老が、問い返してくる。長老からしてみれば、これを持つのにシュバルツほどふさわしい人間は他にいないと思っていたからだ。
「何度も申しておりますが、私はたまたまこの村に流れ着いただけの者です。決して神の代理と言う者ではありません」
「しかし、村人の誰もがシュバルツ殿を『土地神様の代理の者』として既に認めておる。これを懐に収めておったとしても、誰からも文句なぞ出ないと思うが……」
「『文句が出る出ない』の問題ではなく、私がそのような神聖な物に触れる訳にはいかないのです」
長老の言葉に、尚も首を振り続けるシュバルツ。その間にハヤブサは、シュバルツがどうしてこんなに頑なに長老の申し出を断り続けるのか―――――その理由を察してしまった。そしてそれを、彼の口から言わせたくない、と、思った。
だから――――
「私は『不浄』――――――イテッ!!」
案の定、けしからん事を口走ったシュバルツの足を、思いっきり踏んづけてやった。
「何をするんだ!? ハヤブサ!!」
「悪かったな。文句は後で聞く」
涙目になって抗議してくるシュバルツをやんわりと手で制しながら、ハヤブサは長老に向かって口を開いた。
「俺は、シュバルツにそれを持たせるのは反対です。長老、貴方が持たれていた方がいい」
「何故じゃ?」
不思議そうに問うてくる長老に、ハヤブサは言葉を続ける。
「戦いが始まれば、こいつは皆を守るために動く。それはつまり――――」
ハヤブサは、少しきつめの眼差しを長老に向けた。
「真っ先に、『死地』に飛び込んで行く事を意味する」
「―――――!」
「おまけに村人を庇いながらの戦いになるから、こいつが傷を負わない訳がない。故にこいつがそれを持ったら、いたずらに形代の石を危険に曝すことになるんだ」
「ハ、ハヤブサ……!」
ハヤブサの言葉に茫然としてしまうシュバルツ。だが、ハヤブサの言う事はいちいち尤もなので、それに対する反論の言葉を持つ事が出来ない。たいして長老の方も「むむむ……」と、唸るしかなかった。
「形代の石を確実に守るためにも、そしてこいつのためにも――――その石は貴方が持っていてくれた方がこちらも助かる。こいつに、余計な負担をかけたくない」
「……………」
ハヤブサの言葉に目を閉じて、しばらく考え込むようにしていた長老であったが、やがてその顔を上げた。
「分かりました。貴殿の言う事も尤もじゃ……。なればわしが、これを責任もって預かるとしよう」
「助かります」
ハヤブサは長老の言葉に丁寧に頭を下げる。この『土地神』からは、今のところ不吉な物を感じる訳ではなかったが、物が『御神体』なだけに、不用意にそれを傷つける事を、ハヤブサは何としても避けたいと思った。『神の呪い』とは、時に理不尽な物である。御神体が傷つけられた事によって、その呪いが自分に牙を剝く分には一向に構いはしなかったが、万が一シュバルツにそれが向いてしまったら。
それを考えると、背筋に寒気が走る。
いろいろとお膳立てをしてくれた太公望のためにもシュバルツのためにも、不確定的な危険な要素は少しでも減らしておきたい、と、ハヤブサは考えていた。
シュバルツはそれを複雑な気持ちでそのやり取りを見守る。そこに、武装した妖魔の一団がやってきた。
「長老殿! シュバルツ殿!」
「――――!」
妖魔たちが手にする黒光りする武器に、一瞬反応してしまうハヤブサ。だが、ここが村の中であると言う事と、額に挿してある鳥の羽根で、彼らが味方だと知って構えを解いた。本当に、咄嗟に敵味方の区別がつくと言う事は、素直にありがたかった。
「長老殿……シュバルツ殿……。このたびは、我らの同族が――――本当に、申し訳ない!」
「ちくしょう! 百々目鬼の奴め……!」
長老たちの傍に着くなり、妖魔たちは次々とわびの言葉を言いながら頭を下げる。それに対して長老とシュバルツは、慌てて妖魔たちが詫びるのを止めさせようとしていた。
「どうかお手を上げてくだされ。そなた達のせいではない」
「しかし――――! シュバルツ殿のおかげで一時期は大人しくなっていた奴らなのに………!」
「百々目鬼軍の後ろ盾を得た途端、急にまた暴れ出しやがって――――!」
「こちらの村まで襲おうだなんてとんでもない野郎だ!! 畜生! 返り討ちにしてやる――――!」
「『お前のおかげ』って……戦ったりしたのか?」
ハヤブサの問いかけにシュバルツは頷く。
「ああ。妖魔と人間が交流する事に、異を唱えてくる者などいくらでもいる。話し合いが通用する相手ならばよかったのだが、そうではない相手も居たからな……。やむを得ず」
「この人凄ぇんだぜ!! 向かってくる相手を1人も殺さずに撃退して――――!」
「あんな戦い方もあるんだなぁ。俺たち、感心しちまってたよ」
「あれは私1人の力ではない。貴方がたが協力してくれたからこそだ」
妖魔たちの言葉に、シュバルツは少し難しい顔をして答える。
「だが……今となっては考えてしまうな……。『これでよかったのだろうか』と……」
そう言うシュバルツの面に、自嘲的な笑みが浮かんだ。
シュバルツが嫌がらせをしてくる他の部族の妖魔たちを1人も殺さずに撃退し続けたのは、ひとえに対話の窓を閉ざしたくないからであった。妖魔の村の長も対話を望んでいたし、1人でも殺してしまったら禍根を残してしまう。それに、嫌がらせや襲撃もエスカレートするのではないかと考えたからだ。
もちろん、この村の妖魔たちの大半は、自分のやり方に賛同してくれていたが、中には「甘すぎる」と言ってくる者たちも居た。
―――そんな生易しい戦い方をしているから、奴ら図に乗ってくるんですせ!
―――あんな奴ら、一度本格的に叩きのめした方がいい。こちらがいくら話しても、分かってもはらえないのだから――――
その意見に対してシュバルツも懸命に説得し続けた。
―――それでも、1人でも殺してしまえば総てが終わりだ。対話の窓は閉ざされ、貴方がたの平和を望む気持ちも、相手には完全に伝わらなくなってしまう。
―――お願いだ……! もう少し時間をくれ! 何とか襲撃を止めるよう、長と共に説得を続けるから――――
だが、その努力も空しく、結局村人たちや妖魔たちにも、村を捨てさせる選択をさせてしまった。結局自分は何も事態が変えられず、今日を迎えてしまったのだ。
どうすればよかった?
どうすれば今の事態を回避できたのだろうか。
ずっとそう問い続けてしまう。
考えた所で、答えなど出る筈もないのに。
「……殺さなかったのは正解だったな、シュバルツ。1人でも殺してしまっていたら、おそらく今日を迎えられてはいなかった。俺の救援は間に合わなかっただろう」
「―――――!」
思いもかけぬハヤブサの言葉に、シュバルツは驚いて顔を上げる。
「一人でも殺せば、次から次へと殺して行かなければならなくなる。命を奪うとは、そういう負の連鎖に巻き込まれることを意味する。そうなってしまったら、この村はもっと早く、襲撃の憂き目に遭っていただろうな」
「ハ……ハヤブサ……」
「その御方の言う通りじゃ。シュバルツ殿が支えていてくれたからこそ、わしらは今日まで無事に過ごせた。桃の収穫も無事にできた。それが、何よりの事じゃ」
長老の言葉に、妖魔たちも頷く。
「確かにそうじゃな……。人間たちと交流したいと願っていたわしらの願いを、この方は叶えてくれた。素晴らしい世界を、わしらに見せてくれた」
「戦い方も、教えてくれたしな」
「どれもシュバルツ殿が、この村に来てくれたおかげだな」
「いや……私はきっかけを作っただけにすぎない。その後の交流は貴方たちの力で―――」
(そうやって『弱者』に何のためらいもなく手を伸ばす事が出来るっていうのが、どれだけすごい事か――――当の本人がまるで分かっていないのが困るな……。こういう事は、誰でもできる事ではないのに……)
懸命に謙遜するシュバルツを、ハヤブサは苦笑しながら見守る。シュバルツはかなり有能なのに、それをまるで無自覚なのが、堪らなくもどかしくて、そして愛おしいと感じていた。
「シュバルツ殿……いろいろあったが、我らは人間と交流を持てた事だけは、絶対に後悔はしない」
「――――!」
妖魔の言葉に、村の長老も頷く。
「そうじゃな。この方々と我々は、こうして手を取りあえた。種族が違えども、妖魔と人間は、共存する事が出来るのだ」
「我らは誰に何と言われようとも、この取り合った手を、離すつもりはないから――――」
「みんな………」
しばらく茫然と皆を見つめていたシュバルツであったが、やがて皆から視線を逸らして背を向けてしまった。その肩が小刻みに震えている。どうやら、感極まって泣いてしまっているようだった。
「駄目だ……! こんな時に………ッ!」
肩を震わせるシュバルツが、必死に涙を拭っている。泣きやもうと努力しているのだろう。
(本当に、こんな時に……冗談じゃない)
その後ろ姿を見ながらハヤブサは、悶々としてしまう。
(お前……! 俺を煽っているのか? 抱きしめたくなってしまうではないか! そんなお前の姿を見てしまったら――――!)
だが今、それをする訳にはいかないとハヤブサも分かっている。触れてしまったら、止まる自信なんてない。絶対に最後まで突っ走ってしまう。そんな事をしている場合じゃない。まだ、誰ひとり助けられていないのだからと、ハヤブサは必死に自分に言い聞かす。
だけど、彼の肩を震わせて立つ後ろ姿が、あまりにも可愛らしくて愛おしいものだからたまらない。それを抱きしめられないとか、自分にとっては最早拷問の様な空間だ。
「シュバルツ殿………!」
「…………ッ!」
シュバルツのその姿を見て、妖魔たちと長老がうるうると涙ぐみ始めている。
(ああもう――――)
何か、いろいろと堪え切れなくなってしまったハヤブサは、シュバルツの傍に行って、声をかける事を選択した。このまま独り悶々としていては、自分がおかしくなってしまいそうだったからだ。
「シュバルツ……」
「あ……ハヤブサ……」
ハヤブサに気が付いたシュバルツが、懸命に涙を拭っている。
「少し、待ってくれ……すぐ、泣きやむから――――」
そう言って無理やり微笑む愛おしいヒト。胸が締め付けられて、強くない理性がぐらぐらと傾ぐ。ハヤブサは、何かいろいろとあきらめたようにフッと、小さく笑うと、シュバルツの肩にポン、と、その手を置いた。
「今すぐお前に、キスをしても良いか?」
「は?」
「だから、お前にキスを――――」
ドカッ!!
いきなりハヤブサは、シュバルツに無言で殴り倒された。
「痛い!!」
すぐにガバッと跳ね起きるハヤブサ。そこにシュバルツから怒鳴り声が降ってくる
「阿呆か!! こんな時に何を考えているんだお前は――――!?」
「仕方がなかろう。お前があまりにも可愛――――」
ドカッ!! バキッ!!
再びシュバルツから、容赦のない鉄拳制裁がハヤブサに飛んだ。
「全く……! 暫くそこで寝ていろ!!」
そうぶりぶり怒りながら、シュバルツはその場からすたすたと歩いて行ってしまう。その一部始終を見ていた妖魔たちと長老は、ただ茫然とするしか無かった。
「……あの人でも、怒る事あるんだなぁ」
「当たり前だろう。よく考えれば『人間』なのだから……」
「いや、その括りはおかしいだろう。それを言うならあの人も生きている、『感情』があるんだ、と、言った方が正しい」
「そりゃあそうだな。我ら妖魔にも、『感情』はあるからなぁ」
妖魔たちがそう議論している横で、長老が倒れているハヤブサに声をかけていた。
「そなた……大丈夫か?」
「いてて……。シュバルツの奴……容赦なく殴りやがって……」
ブツブツ言いながら起き上るハヤブサを、長老はしばらく黙って見つめていたが、やがて探る様に声をかけて来た。
「……あのように怒らせる事を言うとは………そなた、もしやわざとか?」
「何の話だ?」
それに対してハヤブサは、しれっと返事を返す。そんなハヤブサの様子を見て、長老はやれやれと苦笑するしか無かった。
(わざと怒らせて涙を止めてやるとは……やれやれ、不器用すぎる優しさを、持った御仁じゃな……)
「さて……我らも急ごう。襲撃をされる前に、ここから脱出しなければ」
長老の言葉に皆は一様に頷いた。
「シュバルツさん! それに、ハヤブサさんも――――!」
二人の姿を認めた甲斐姫が手を上げ、声をかけてくる。
「…………!」
その言葉を聞いたシュバルツが驚いた様に振り向くと、ハヤブサが憮然とした表情で、シュバルツのすぐ後ろについて来ていた。
「もう立ち直ったのか?」
そう言いながら浴びせられるシュバルツの冷たい視線を、龍の忍者は鉄面皮で跳ね返す。
「フ……あの程度の打撃、俺にとってはむしろご褒美だ」
「変態」
しかし、ぼそっとシュバルツから言われたこの言葉は、さすがに跳ね返し損ねた。地面にめり込むように座り込んだ龍の忍者は、そのまましくしくと泣き出してしまっている。
「だ……大丈夫、なんですか?」
そんな二人の様子に少々驚いた甲斐姫が、恐る恐ると言った按配で聞いてくる。それに対してシュバルツは、つっけんどんに答えた。
「そいつに対してそんな気は、使うだけ無駄だぞ」
「そ、そうなんですか?」
「ううう……。シュバルツが冷たい………」
「さっさと立ち上がれ! 鬱陶しい!」
「え~っと、ハヤブサさん? 一応、報告しておいていい?」
座り込んでいるハヤブサに対して、同じように座りこんで甲斐姫が話しかけてくる。「いいぞ……」と、ハヤブサが力無く言うと、「うん、分かった」と、甲斐姫も頷いて話し始めた。
「尚香が一足先に、劉備様の城に行ったわ。村人と妖魔たちを、それぞれ二人ずつ連れて行ったから――――」
「二人ずつ……『前と同じ』様にか?」
顔を上げて問い返すハヤブサに、甲斐姫はにこりと笑う。
「ええ。『前と同じ』に」
「そうか………」
これで、関羽が孫尚香の姿を城外に認めた時、迷いなく援軍を出せるだろう。そう確信したハヤブサは、立ち上がった。村人たちを避難させるための準備は、総て整ったと感じた。
「シュバルツさん! 全員揃いました!」
「こちらもだ! もう何時でも出発出来るぜ!」
村人たちと妖魔たちから、それぞれ声をかけられる。周りを確認するように見渡すシュバルツに、皆が頷いた。
「では、行こう! 劉備殿の城へ――――!」
こうして、村人たちと妖魔たちは、城へ向かって移動を開始した。始まったのだ。今度こそ、皆が生き延びる道を掴み取る、戦いが。
難民となってしまった村人たちと妖魔たち。だがその道行きは、大きな混乱も無く、整然としたものであった。甲斐姫が先頭に立って一団を先導し、村人たちの周りを武装した妖魔たちが守り、ハヤブサが殿を務めている。シュバルツはその一団の中間から後方の辺りで、何かあったらすぐに何処へでも対応できる場所に位置していた。
天気も良く、陽もまだ高い。このまま何事も無ければ、無事に劉備の城にたどり着けそうであった。
(やはり、馬が居るのはいいな)
集団の最後尾から皆を眺めながら、ハヤブサは思う。歩くのが困難な者や荷物を載せたり引いたりしながら、馬達は進んでいる。やはり、それがあると無いとでは、進むスピードが断然違ったものになっていた。
集団の中からは雑談が聞こえ、時折、笑い声すら聞こえてくる。状況が状況で無ければ、まるで皆でハイキングにでも来ているような様相だった。
(前の時間軸では、襲撃されたのは夜だ。今回も、そうであるのならばいいが……)
平和な道行きながらも、龍の忍者は油断なく、辺りに『気』を張り巡らせていた。それ故に―――――龍の忍者はその気配を捉えた。
「―――――!?」
何かの鋭い視線を感じて、ハヤブサは振り返る。それと同時に茂みの中から何かが走り去る音がした。ざっと、ハヤブサがその茂みに飛び入ると、前方に猛スピードで走り去っていく妖魔の姿が視界に飛び込んでくる。
「…………!」
ハヤブサは無言で小弓を構え、矢を放とうとする。だがそれよりも早く、その妖魔は姿をくらましてしまっていた。
(――――チッ!)
ハヤブサが小さく舌打ちをしていると、彼の動きについて来ていた妖魔に声をかけられた。
「ハヤブサさん? どうしたんですかい?」
「済まないが、シュバルツに知らせて来てくれないか?」
ハヤブサは、走り去った妖魔の方を見やりながら言葉を続ける。
「『斥候』が居た。襲撃があるかもしれないと」
「…………! わ、分かりました! すぐ、知らせてきます!」
ハヤブサの言葉を聞いた妖魔が、慌てて踵を返して走って行く。
(やはり……! このまますんなりとはいかないか。あの斥候、仕留められればベストだったのだろうが……)
ハヤブサは見失った妖魔の方を見やりながら、ギリ、と、歯を食いしばっていた。
「百々目鬼様!! 報告いたします!!」
妖魔と人間の村を襲撃するべく、準備をしていた百々目鬼の元に、放っていた斥候が帰ってくる。
「何だ?」
「今から襲撃に行く所の妖魔と人間の奴らが、村より脱出しているようです!」
「何ぃ!?」
全く意想外の報告に、百々目鬼は思わず瞠目してしまう。
「どう言うことだ……?」
「我らの襲撃が、奴らにばれたのか?」
周りの妖魔たちからも、どよめきの声が上がる。村人たちが寝静まったところを、夜襲するつもりで準備を進めていた。戦う事もろくに知らない、素人同然の集団。踏みつぶすように蹂躙できると信じて疑っていなかった。それがまさか、先手を打たれて逃げ出される事になるとは。
「我らの中に、『内通者』でもいるんじゃないのか?」
誰かの放ったこの一言に、その場に居る者たちの間に流れる空気が、一気にとげとげしい物へと変わる。
「な、何を言うんだ!!」
「そう言う事を言い出すお前が、一番怪しいんじゃないのか!?」
「何だとォ!?」
「人間なんぞに迎合する輩が、我らの中にもいると言う事か!?」
まさに一触即発の不穏な空気が漂い始めた時、百々目鬼が口を開いた。
「奴ら、『仙桃』を持ちだしているのか?」
「いえ、そこまでは」
斥候に当たっていた妖魔が首を振る。
「ただ、それなりに荷物は持ち出して避難していたようですから、もしかしたら、仙桃も持ち出しておるやもしれません」
「そうか………」
斥候のその言葉に、百々目鬼はしばらく考え込むように顎を手に当てていたが、やがて、瞳をぎょろり、と妖しく光らせながら、皆の方に振り返った。
「………今から討って出るか」
「百々目鬼様!」
言い争いを止めて、皆が一斉に百々目鬼に注目する。
「元々あの村の妖魔の奴らも、そして村人も――――戦いにおいては素人同然。わざわざ夜襲なぞかけなくとも良いと思っておった。踏みつぶすように蹂躙できるだろう」
「では――――?」
気色立つ妖魔たちに、百々目鬼は頷く。
「だいたい、人間なんぞと共存しようなどと言う主張を聴くだけでも虫唾が走ると言うのに、仙桃まで手に入れておる。あんな奴らには過ぎた代物だ。我らが手に入れた方が、余程有効に使えると言うものだ」
百々目鬼のその言葉に妖魔たちは頷き、「そうだ、そうだ!」と、迎合の声を上げる。それに百々目鬼は目を細めながら満足そうに頷くと、さらに言葉を続けた。
「奴らがこちらの襲撃を予測して逃げだしたと言っても、所詮老人、女子供が居る集団。そんなに足も速くない筈だ。奴らの持ち出した食料品や家財も、総て奪い尽くしてやるとするか」
オオッ! と、妖魔たちから声が上がる。軍の皆が血に飢え、意気も高いと見て取った百々目鬼は、号令を下す事にした。
「よしっ!! 出陣だ!! 人間どもから分捕った者は、皆我が物にして構わぬぞ!!」
その言葉に百々目鬼軍の者たちは、歓喜の声を上げたのだった。
「―――――!」
かぐやの光陣に入り、彼女に導かれるままに目を閉じた関羽が次に目を開けた時、望む時間軸の城の中に居ると悟った。ただ、目の前に居る人物に驚いて、思わず声を上げてしまった。
「兄者!?」
前の時間軸ではいなかった筈の、劉備の姿がそこに在ったからだ。
「どうした? 関羽。何を驚いている?」
「あ……。いや………」
劉備に聞かれて、関羽は返事に窮してしまう。どうしてここに劉備が居るのか――――今の自分は咄嗟に理解できないからだ。
「どうしたよ? 兄貴?」
「――――!」
さらに張飛まで現れて、関羽はさらに混乱する。
(こ……これは……! まさか、太公望殿の『策』の為せる業か?)
そう思いながら周りを見回すと、孔明と趙雲の姿まであった。
(もう間違いない……! これは、太公望殿の介入が働いているのだ。しかし、何故――――?)
「関羽殿? 如何為された?」
余程自身の動揺が表に漏れていたのだろう。孔明からも怪訝そうに問いかけられるから、関羽は、いろいろと観念する事にした。
「申し訳ない……。少し、拙者の方にも事情があって……。軍師殿、少々状況を整理させていただいてもよろしいか?」
「ええ。それは構いませんが……」
関羽の言葉に、孔明は白扇を手の中でゆっくりと揺らめかせながら答える。関羽はそんな孔明に向かって軽く一礼をしてから、玄徳に向かって話しかけた。
「兄者……。兄者は確か、張飛を連れて北方で曹操殿と相対していたのではないのか?」
そう。
これが時を遡る前の時間軸での、関羽が記憶している玄徳の行動だった。玄徳と張飛は曹操軍と。そして孔明と趙雲は東の方で孫堅軍と戦っていた筈である。
平和裏に過ごせる国を作ったと言っても、それは玄徳が治める領地の中での話だった。まだまだ国境付近では余断を許さず、散発的な戦が時々起っていた。だから劉備軍も戦力を分散して、それぞれが国境付近の守りについていたのだが。
「ああ……。確かに私は張飛と共に曹操殿と戦っていた。だが少し前に、『遠呂智が復活したから人間同士手を携えねばならぬ』と、曹操殿と休戦協定を結んだではないか」
「えっ?」
「忘れちまったのか? 兄貴?」
茫然とする関羽に向かって、張飛が更に言葉を続けてくる。
「ほれ、この前襄陽で戦った時によ。関羽の兄貴が救援に駆けつけて来てくれたじゃないか。その時に――――」
「―――――!」
この言葉で関羽はようやっと、張飛の言っている事の『内容』を理解する。
(そうか……! 確かに拙者は少し前に、太公望殿の指示で襄陽の戦いへとかぐやの光陣で跳んだ。それが、ここへと繋がって来ていたのか……)
あの時はただ、太公望に命じられるままに襄陽の戦いへ駆けつけ、劉備軍を勝利へと導いた。それが、曹操軍との休戦協定にまで繋がって行くとは、夢にも思っていなかった。
「……と、言う事は、孫堅軍と戦っていた軍師殿と趙雲の方も――――?」
関羽の問いかけに趙雲は頭を振る。
「いえ、我々は特に何かした、と言う訳ではないのですが――――」
「孫堅軍の方から、休戦協定を持ちかけて来たのですよ」
軍師孔明が、静かに答える。
「確かに……遠呂智が復活した、と、あっては、人間同士が争っている場合ではありませんからね……。孫堅殿が手を引かれるのであれば、我々の方から戦をしかける理由もありませんから……」
「孫堅が手を引いたのは、確かなのか?」
問いかける関羽に、孔明は頷いた。
「何でも、尚香殿と北条氏康殿が、孫堅殿に休戦協定を結ぶよう、強く働きかけてくれたようです。ですから確かな物でしょう。孫堅殿が不意をついて、我々に戦を仕掛けてくる事はない筈です」
「……………!」
孔明のこの言葉に、関羽の脳裏にある光景が浮かび上がる。シュバルツの『死』の際に、自分の傍で泣き崩れていた孫尚香と甲斐姫――――二人の女性の姿が。
(そうか……! 甲斐姫のために氏康殿が……そして、尚香殿が……!)
「それにしても、皆でそろうのは本当に久しぶりだよなぁ。やっぱり、皆で一緒に居るのが一番良いぜ!」
張飛の言葉に、関羽ははっと息を飲む。
そうだ。自分達は国造りのために、そして国を守るために――――それぞれがばらばらの場所で行動せざるを得なかった。それが、今この瞬間、この城に皆がそろうために、曹操や孫堅をはじめ、どれだけの人の協力と働きかけがあったのだろう?
これは、太公望の緻密な計算と過去への介入と、それに協力した皆が築き上げたからこそ舞い降りた、小さな奇跡と言って良かった。
関羽の脳裏に、ある光景が浮かび上がる。
着の身着のままでボロボロになりながらも、手を取り合いながら助けあっていた妖魔と村人たち。
傷だらけのハヤブサを抱きかかえ、それを守るために、素戔鳴の攻撃の前にその身を投げ出したシュバルツ。
(いけるか……? 今度こそ……!)
目の前に並ぶ、玄徳をはじめとした頼もしい仲間達を関羽は見つめ、想う。
救えるか?
今度こそ
村人たちを 妖魔たちを
そして、あの二人を――――
いや、救えるかではない。救わねばならぬ。
今この瞬間を迎えるために力を貸してくれた、多くの人々のためにも
自分はそれに、応えねばならぬのだ。
それが出来ずして、何が『武人』か――――!
「兄者! お願いがあります!」
「ど、どうした?」
いきなり義弟が思い詰めたような眼差しで声を上げるから、玄徳は少し驚いてしまう。
「実は――――」
関羽がこれから起きる『事件』に皆の協力を仰ごうと、口を開いた瞬間――――1人の兵士が広間に入ってきた。
「ご報告申し上げます!」
「どうした?」
問い返す劉備に、兵士は畏まって拱手してから口を開く。
「はっ! 城外に孫尚香様がお見えです! 開門を呼びかけています!」
「尚香殿が?」
怪訝な顔をする玄徳に対して、関羽は「来た」と、思った。少し早いと思いもしたが、孫尚香が自ら判断してこのタイミングで来たのだろう。
もう、判断を誤る訳にはいかない。
関羽は、強くそう決意していた。
「尚香殿が……どうしたのであろうか?」
「とにかく、行ってみましょう」
孔明の言葉に皆が頷き、兵の案内に従って、部屋を後にした。
門の櫓の上から城外を見下ろすと、馬に乗った孫尚香が、村人と妖魔数人を引き連れて、こちらを見上げていた。
「玄徳様!?」
城外から玄徳の姿を認めた孫尚香が、驚きの声を上げる。彼女も、この城にまさか玄徳が居るとは、思ってもいなかったのだろう。
「尚香殿!? 如何為された!?」
玄徳の呼び掛けに、孫尚香は声を張り上げた。
「玄徳様!! お願いがあるの!! この先に助けを求めている人たちが居るの!! だから、門を開けて、援軍を出して欲しいのよ!!」
(……………!)
その孫尚香の姿に関羽は確信する。もう間違いない。自分はここで、出陣する事を躊躇ってはならないのだ。孫尚香もこちらの判断を誤らせないように、敢えて妖魔たちを連れて来てくれたのだろう。彼女のその心遣いに、関羽は感謝していた。
さあ、自分は自分の役割を果たさねばならぬ。
皆に救いの手を、差し伸べるために――――
だから関羽は、玄徳に向かって大声で呼びかけた。
「兄者!!」
「ど、どうした? 関羽」
関羽からいきなり大声で呼びかけられたので、玄徳は少しびっくりする。戸惑い気味に振り返る義兄(あに)に向って、関羽は膝をついて頭を下げた。
「お願いでござる。どうか、拙者に出陣の許可を――――!」
「……………!」
関羽のいきなりのこの申し出に、玄徳は驚き、孔明は少し眉をひそめる。だが関羽は、もう後に引くつもりも無かった。例え出陣の許可が下りずとも――――強引に出て行くつもりで、関羽は頭を下げていた。
「あ、兄貴? いきなり何を言い出すんだよ?」
いつもなら、血気にはやって出陣したがる自分を関羽は止める側に回っていたから、率先して出陣を願う関羽の姿に、張飛も少し戸惑い気味になっている。趙雲は、ただ黙ってそんな関羽を見つめていた。
「玄徳様!! お願い!!」
「兄者!! どうか――――!」
玄徳は、しばらく思案するかのようにじっと押し黙って孫尚香と関羽を見続けていたが、やがて、おもむろに口を開いた。
「関羽………」
「兄者……!」
玄徳は、見上げる関羽をまっすぐ見つめてくる。
「お前は……『城を開けて出陣するべき』――――そう、思っているのだな?」
その言葉に関羽は頷いた。
「尚香殿の後ろで助けを求めて居る者たちは、間違いなく――――『救わねばならない者』たちです」
「そうか………」
玄徳は関羽の言葉に一つ頷くと、躊躇うことなく言い放った。
「よし。出陣を許可する! ただちに城門を開けよ!」
「わが君! 少し、お待ちください!」
だがこの玄徳の言葉に、反対の声を上げる者が居た。軍師孔明である。
「孔明?」
「わが君、門を開けるのは少々お待ちください。不審な点があります。それを、見極めねばなりませぬ」
「軍師殿? 不審な点、とは?」
問いかける趙雲に孔明は穏やかな視線を向けると、白扇を揺らめかせながら言葉を続けた。
「尚香殿は確か――――今は孫呉の者たちと行動を共にしているはずです。なのに何故、いきなりここに現れたのでしょうか? 孫堅殿から伝言を預かっているふうでもなく、しかも、妖魔を引き連れて――――」
(……………!)
孔明の言葉を聞きながら、関羽はギリ、と、歯を食いしばっていた。
だが、孔明の気持ちも分かる。自分は前の時間軸で、まさしくそれに引っかかってしまっていたからだ。
しかしもう、同じ過ちを繰り返す訳にはいかない。いざとなれば、たとえ軍紀違反の汚名を着ようとも――――関羽はそう思いながら、拳をきつく握りしめていた。
「確かにそうだな……」
孔明の言葉に玄徳は一度頷く。しかし、次に玄徳の口から出た言葉は、その場に居る全員を驚かせた。
「だがな、孔明。私は決定を覆すつもりはない。関羽の出陣を、許可する」
「兄者――――!」
「わが君……!」
息を飲む孔明を玄徳は正面から見つめ返すと、言葉を続けた。
「孔明……。関羽は、私の義弟(おとうと)だ。そして、尚香殿は私の妻だ。この二人の言葉を信じる事が出来ずして、この玄徳――――明日から何を信ずればいいと言うのだ?」
「しかし………!」
「それに、妖魔であろうが人間であろうが、この私に助けを求めて来ている者が居るのならば、それを受け入れるべきだ。そうでなければ、この玄徳を頼って来てくれる者が、明日から1人もいなくなってしまうぞ――――」
(…………!)
玄徳の言葉を聞きながら、関羽は身体が震えてしまうのを感じる。
そうだ。この人は、こういう人だ。
こういう決断が、出来る人なのだ。
もしもあの時間軸でも玄徳が自分の隣に居てくれたならば
自分は、あんな過ちを犯さずにすんだであろう。
ああ。やはり、間違っていなかった。
自分が主と仰ぐのは、後にも先にもこの人しかいない――――
関羽は強く、そう思っていた。
「分かりました」
劉備にこうも強く言われてしまっては、孔明としてもこれ以上反対する事は出来ない。彼も頷いた。
「では関羽。尚香殿と共に行ってくれるか?」
「はっ!」
「兄者! 俺も行っても良いか!? 何だか面白そうだ!!」
張飛の言葉に玄徳は苦笑する。
「張飛が行くのなら趙雲も一緒に連れて行け。張飛……くれぐれも、暴れすぎるなよ」
「分かってるって!」
「では、行って参ります」
関羽に続いて張飛、趙雲も櫓の上から駆け降りて行く。皆が出て行ってから、玄徳は孔明の方に振り返った。
「……済まなかったな、孔明。だが私は、例え裏切られたとしても、助けを求めてくる尚香殿を突き放すような真似は――――」
「大丈夫ですよ、わが君。尚香殿に続いて関羽殿もあのような反応を見せた、と言うことは、本当に助けを求めている者が居るのでしょう」
そう言ってから、孔明は少し苦笑気味の笑顔を見せる。
「ただ……私の役目は『疑うこと』です。ですから、こうして苦言を呈する事もありますが――――」
「ああ。分かっている……。いつも済まぬな。ありがとう」
「いえ………」
孔明は改めて、玄徳に向かって一礼をする。
「それでは、関平と共に炊き出しの準備をしてまいります」
「ああ。頼む」
その言葉を受けて、孔明も関平と共に玄徳の前から退室した。
ただ孔明は、玄徳の前から退去した後、関平にひそかに耳打ちする事を忘れてはいなかった。
「関平……炊き出しの用意をするとはまた別の部隊を、秘かに城内に潜ませておいてください」
「――――!?」
ギョッと驚く関平に対して、孔明は静かに言葉を続けた。
「これは、念のための措置です」
「念のため……ですか?」
聞き返す関平に、孔明は頷いた。
「ほぼ心配ないとは思いますが、万が一、あの尚香殿が偽物で、城内の民やわが君が危険に曝されないとも限りませんから――――」
孔明のこの言葉に、関平は生唾を飲み込む。
「わ、分かりました……。城内の民たちには気取られぬように、秘かに兵を配置しておきます」
「頼みます」
関平は律儀に孔明に対して一礼をすると、踵を返して足早に走り去って行った。一人残った孔明は、一つ大きく息を吐く。
「さて、私は炊き出しの準備をしましょうか」
彼はそう独りごちると、今度は炊き出しをする場所、材料の調達、鍋の数などを頭の中で計算し始めていった。
村人たちと妖魔隊の集団が移動する速度は、次第に早くなっていた。
「襲撃があるかもしれない」と言うハヤブサからの情報が、彼らの足を速めさせていた。
「落ち着いて! 大丈夫だ! 必ず皆を守るから――――!」
ともすればパニックに陥りそうな村人たちを、シュバルツが呼びかけて支える。その声に呼応するかのように、人も妖魔も、互いを支え合って走り続けた。その集団の最後尾を守っていたハヤブサであったが、ついに百々目鬼軍の上げる砂埃が、彼の視界に飛び込んできた。
「先に行け!! 早く!!」
ハヤブサは足を止めて、皆に先に進むよう促す。殿の役目を果たすべく、龍剣の柄に手をかけて、構えた。
「我々も戦います!!」
そんなハヤブサに、武装した妖魔の一団が声をかけてくる。
「いや、お前たちは――――」
妖魔たちの戦いの能力がどれほどのものか測りかねたハヤブサは、彼らの申し出を遠慮しようとした。しかし、そんな彼に声をかける者が居た。
「この者たちの実力は、なかなかのものだぞ。私が保証する」
「シュバルツ!」
驚くハヤブサの眼前で、愛おしいヒトがにこりと微笑む。
「ついに来たようだな」
そう言いながら彼もまた、百々目鬼軍の上げる砂埃を見据える。
「我々は、いつでもいけますぜ!!」
「あいつら……! もう許せねぇ! 八つ裂きにしてやる――――!」
「まあ待て。落ちつけ」
彼の周りに集まって、いきり立つ妖魔たちを宥めてから、シュバルツはハヤブサに声をかけた。
「この者たちは、私と共に妖魔の村で戦ってくれた者たちなんだ。戦い方も、熱心に学んでくれて――――」
「我々も、自分の村を守る必要があったからな」
「シュバルツ殿の修行は、本当にきつかった……。だがおかげで、こちらもだいぶ鍛えられた」
妖魔たちのそんな話を聞きながら、ハヤブサは、シュバルツがかつて弟に修業をつけて、一人前のファイターになる手助けをしていた事を思い出す。ハヤブサはこの話を、シュバルツとキョウジの弟であるドモンから直接聞いていた。
そうだった。元々こいつは、こんな風に世話焼きな奴だった。
(……て、言うか、農作業の手伝いに子供たちの世話、妖魔の村のトラブルの対処に加えて、彼らに修業をつけていただと? こいつ本当に、寝る時間あったのか!?)
ハヤブサは思わず、愛おしいヒトの顔をまじまじと見つめてしまう。
「どうした?」
「い、いや、別に………」
シュバルツに問われてハヤブサは視線を逸らした。しかし、知らず深いため息を吐いてしまう。
(これだけいろいろと『出来る奴』なのに……こいつの自己評価は恐ろしく低いんだよなぁ。一体どう言うことなんだ……)
もっと自分が有能であることを自覚しても、別に罰など当たらないと思うが――――
そんな事を考えてしまうハヤブサの目の前で、妖魔たちがシュバルツに声をかけていた。
「シュバルツ殿……まさか、この期に及んでも『殺しては駄目だ』などと、言わないよな?」
シュバルツは妖魔のその言葉に、目を閉じてしばらく沈黙していたが、やがて、ため息と共に顔を上げた。
「やむを得ないな……。もう、話し合いなどと言っている場合ではない」
向こうは完全に、こちらを蹂躙するつもりで来ている。そんな相手に、もう手心を加える余地はなかった。
「ハヤブサ。劉備殿の援軍は、あてにして良いのか?」
「…………!」
シュバルツからの問いに、ハヤブサは一瞬考える。だがすぐに「ああ」と頷いた。あの孫尚香の援軍の要請に、あの関羽が応えぬ筈がない。
「そうか……。なら、援軍が来るまでが勝負だな。何処まで持ちこたえさせることができるかだ」
シュバルツのその言葉に、皆が頷く。ハヤブサも、入りかけていた肩の力が少し抜けた。
そうだ。前の時とは状況が違う。
あの時は夜で、敵味方の区別もつかなかった。そして、素戔鳴の襲撃がいつあるかも分からない、切迫した状況だった。そしてここに至るまでに、既に村人が何人も犠牲になっていた。
しかし今は違う。陽の光の元、味方の妖魔たちが額に挿している鳥の羽根のおかげで、敵味方の区別がつく。避難も早く始めたおかげで、まだ誰も犠牲になっていない。問題は素戔鳴の襲撃がいつあるかだが、百々目鬼軍と素戔鳴軍の間に協力関係は存在しない。百々目鬼軍の襲撃と、素戔鳴軍の襲撃は、全く別物と考えて良いだろう。
まだ油断はできないが、素戔鳴軍が来ないのなら、この戦場にかかってくる負担が全然違ってくるはずであった。
「正真正銘、撤退戦と言う訳だな」
そう言うハヤブサにシュバルツも頷く。
「ああ。だから皆に指示を出して、前の部隊を最小限に、そして、後方の守りを厚くする」
そう言いながらシュバルツが、拾った木の枝で即席の陣形図を書いて行く。
「殿はハヤブサを中心として、お前たちで勤めてくれ。ただ、決して突出しすぎず、無理はしないこと。常に味方との距離を意識して、敵を一隊ずつ、確実に仕留めて行ってくれ」
「分かりやした」
「任せておいて下せえ!」
意気高く頷く妖魔たちに、シュバルツも笑顔を見せる。そしてハヤブサの方に視線を移し、少し真剣な眼差しをした。
「ハヤブサ……。お前がこの戦いの要だ。頼んだぞ」
その言葉に、龍の忍者は我が意を得たりと言わんばかりの笑みをその面に浮かべた。
「任せておけ」
実際ハヤブサは、天にも昇らんばかりの心地であった。シュバルツから盤石の信頼を感じる――――それがどんなに喜ばしい事か。その信頼に全力で応えねば、と、ハヤブサは拳を握りなおした。
「それでは、頼んだぞ」
そう言うとシュバルツは、踵を返して走り出した。前方の部隊に指示を出しに行くのだろう。
「…………」
ハヤブサはその愛おしいヒトの後ろ姿を見送ると、前方の百々目鬼軍へと視線を返した。その軍隊が巻き上げる砂埃を、厳しい目つきで睨み据える。その手が龍剣の柄に伸びると同時に、武器を構えた妖魔たちが、ハヤブサの後ろを守る様に固めた。
「シュバルツ殿がやけにあんたの腕を買っていたが、あんた……強いのか?」
そのうちの妖魔の1人から、そう問われる。ハヤブサはそれに、振り向きもせずに答えた。
「俺は、為すべき事を為すだけだ。俺の腕は、お前自身が見極めろ」
その言葉に、妖魔たちもにやりと笑う。
「へっ! 言いやがるな!」
「そうまで言うならその力……存分に見極めさせてもらう」
「……好きにしろ」
後ろでいきり立つ妖魔たちに、ハヤブサは多少苦笑しながら言葉を返す。なる程、シュバルツが『腕が立つ』とお墨付きをしただけの事はある。彼らからは、それぞれ自らの技量に対する自信の程がうかがえた。
「………来るぞ!」
迫りくる砂埃と怒号に、ハヤブサは龍剣を抜刀して身構える。後ろの妖魔たちもそれに倣った。
(シュバルツ……待っていろ……! 今度こそこの戦いに勝利して、お前とキョウジの未来を取り戻してみせる!)
強い決意と共に、龍の忍者は今まさに、敵を迎え撃たんとしていた。
「敵が来たの!?」
先頭を走っていた甲斐姫は、背後からの情報に驚きの声を上げる。
「…………!」
行かなければ、と、甲斐姫は後ろを振り返ったが、すぐに頭を振った。自分は今、先頭を走っている。その自分が、足を止めてしまう訳にはいかないのだ。
「みんな!! 走って!! 足を止めては駄目!!」
懸命に声を張り上げて、皆を先導する。すると、そんな彼女に声をかけてくる者が居た。
「お姫さん!! あんた、戦えるだか!?」
「えっ!?」
驚く甲斐姫に、その村人は更に言葉を続けてきた。
「あんた、武装して、立派な武器を身につけているではないか……。戦えるだか!?」
その問いに甲斐姫は、戸惑いながらも頷く。
「え、ええ。一応……。人並みには――――」
「ならば頼む!! 皆のために、後ろの守りについてくれ!!」
驚き、意気を飲む甲斐姫に、村人は必死の形相で言葉を続けてきた。
「おらは農作業しかしたことが無くて、戦い方はよく分からない……。だけども、皆を守りたい! おらは村からよく行商に出ていた。だから、劉備殿の城へも、皆を案内できるから――――」
「…………!」
「だから頼む!! お姫さんは、皆を守りに行ってやってくれ!! シュバルツさんも『後ろの守りを厚くしろ』と言っていた……! こんな、何も出来ねぇおらみたいな人間でも、何かの役に立ちたいんだ!!」
そう叫んで必死に頼んでくる村人。彼女は一も二もなく頷いた。
「分かったわ……! まかせて。皆の案内をよろしくね!」
「ありがとうごぜぇます!!」
その村人に案内を任せると、甲斐姫は踵を返して走り出した。
(ここからね……! いよいよ、『借り』を返せるときが来た……!)
甲斐姫はそう感じて、拳を握りしめていた。
氏康やハヤブサが戦う前に言っていた通り、この戦場で受けた屈辱は、この戦場でしか返せない。普通ならばこんな機会も無いままに――――苦い後悔を噛みしめ続けなければならないのだ。だからこれは――――本当に、皆が与えてくれた、絶好のチャンスなのだと、甲斐姫は感じていた。
(見ていて……! 御館様……! 尚香……! 今度こそ、私は後悔の無い様に戦って見せる――――!)
甲斐姫の決意に応えるように、腕の中の金拵えの鞭が、チャリ、と、音を立てていた。
妖魔たちは敵も味方も、驚嘆の中に居た。
前方にターゲットである村人たちの逃げる集団を捉えた百々目鬼軍は、そのまま何の問題も無く蹂躙できるものと信じて疑っていなかった。だから、目指す集団の最後尾に、剣を構えて立っている黒の忍者を見ても、特に何も警戒せずに突っ込んだ。
だが、百々目鬼軍の妖魔たちは、すぐにそれを後悔する事になる。
黒の忍者に斬りかかろうとした瞬間、ドン!! と、激しい音がしたかと思うと先頭の妖魔十数人が、何も出来ずに吹っ飛ばされた。
「――――!?」
そのまま百々目鬼軍の妖魔たちは、黒い風になす術もなく斬り裂かれていく。あっという間に龍の忍者の前には、妖魔たちの屍の山が築かれた。
「えっ? えっ? 何じゃ? これは!?」
ハヤブサの後ろで構えていた妖魔たちも、目の前で繰り広げられる龍の忍者の圧倒的なその強さに、ただただ呆然とするしか無い。
「これ全部、あいつがやっているのか? 強すぎじゃねえのか!?」
「て言うか、俺らの方に全然敵が回って来ないんだが――――」
「さすが、シュバルツ殿が認めただけの事はあるな……」
シュバルツに修業をつけてもらっていた時も、その強さの底が知れないと思っていたが、今目の前に居る「ハヤブサ」と言う男の強さも、どれぐらいのものか計り知れない。自分たちも修行をして、いい加減強くなったと思っていたのだが、まだまだ世界は広いのだと認識せざるを得なかった。
「だが、いつまでも呆けている訳にはいかねぇな!」
「ああ! 俺たちもちゃんと、仕事をしねぇと――――!」
ハヤブサの後ろで妖魔たちも改めて構えなおし、また、それぞれの戦いへと没頭して行くのだった。
「何をやっている!? 行軍がさっきから止まってしまっているではないか!!」
先陣に続いて二の陣を進んでいた百々目鬼が焦れたように怒鳴り声を上げる。相手はろくに戦うこともできない府抜けた妖魔たちと村人たち。すぐに蹂躙できるものと信じて疑っていなかっただけに、思わぬ足止めは、百々目鬼のいらつきを倍増させた。そこに先陣から、ほうほうのていで軍使が百々目鬼の前に転がりこんでくる。
「も、申し上げます!」
「何だ!?」
「村人たちの殿に、やけに強い男が一人おりまして、その男のせいで我が軍は足止めを喰らっております!」
「……何だとォ?」
百々目鬼は思わずその軍使を睨みつけてしまう。
「そんな馬鹿な話があるものか! あの村に居る連中は、戦うこともろくにせず、口先ばかりの府抜けた連中だと聞いていたぞ!?」
「し、しかし……! 現に我々は、足止めを喰らっておる訳ですから……!」
軍使はたじたじになりながらも、何とか云い返す。とにかく百々目鬼に現実を認識してもらわなければ、手の打ちようがないと感じていた。その軍使の言葉に、百々目鬼はチッと、軽く舌を打ちならす。
「何処だ!? その男は――――! 案内しろ!」
忌々しそうに言う百々目鬼の言葉に、軍師は少し胸を撫で下ろしながら、「こちらです!」と、案内を始めた。
ハヤブサが戦う戦場から少し離れた小高い丘に、その軍使は百々目鬼を導く。そこで百々目鬼が目にした光景は、丁度龍の忍者が『飯綱落し』を炸裂させた瞬間であった。
(リュウ・ハヤブサ……!)
その技を見た瞬間、百々目鬼は黒の忍者の正体を看破する。百々目鬼は妖魔軍の中でも好戦的な部類に入り、たびたび遠呂智討伐軍の者たちとも事を構えていた。それ故に、よく戦場に出てきていたハヤブサとは、変な顔なじみになっていたのだ。
「なるほどな。奴ならば、こちらの軍を蹴散らしてもおかしくはないかもしれぬ」
戦うハヤブサの姿を見下ろしながら腕を組み、独りごちる百々目鬼であったが、少し納得しかねるところもあった。
(それにしても何故……リュウ・ハヤブサほどの者が、こんな無名の村の奴らを守るために、わざわざ出張ってくる? 奴らの軍には神仙界の者もいる。こんな僻地の仙桃を求めずとも、その供給源はいくらでもあるだろうに……)
そう感じて首を捻っては見るが、考えた所で答えなど出ようはずもない。
「百々目鬼様……」
周りに居る部下たちから上がる情けない声に、百々目鬼ははっと我に帰った。一つ大きなため息をつくと、百々目鬼は部下たちに指示を出す。
「お前たちは阿呆か!? 数ではこちらが圧倒しているのだ!! リュウ・ハヤブサがいくら強いと言っても所詮は1人だ! 奴を避けて、三方向から包み込むように人間共を粉砕しろ!!」
「は、はっ!!」
百々目鬼の言葉を受けて、部下たちが三方向へと散って行く。その後ろ姿を、百々目鬼は忌々しそうに睨みつけていた。
「むっ!?」
百々目鬼軍の動きに現れた変化に、気づかぬハヤブサではなかった。
(しまった――――! 奴ら、三方向から――――!)
殿である自分を避け、百々目鬼軍はこちらを包み込むように、側面へと回り込もうとしている。
(どうする!?)
龍の忍者は懸命に考える。しかし、いくらハヤブサの足が速いと言っても、自分が動き回れる範囲には限界がある。数に任せて三方向から一斉に攻め立てられてしまっては、それを完全に防ぎきる事など不可能だ。
良い策が浮かばない事にギリ、と、歯を食いしばるハヤブサ。すると、戦場の右側の方から、ドカン!! と言う轟音と共に、巨大な火柱が上がった。
(シュバルツ――――!)
その火柱を見た瞬間、ハヤブサは何が起こったのかを即座に理解した。だから叫んだ。
「お前たち!! 腕に覚えがあると言ったな!?」
後ろで戦っていた妖魔たちに呼びかける。すると彼らも、戦いながらもすぐに返事をしてくれた。
「へ、へい!!」
「あんたほどじゃねぇですが、あんな連中に後れを取る俺たちではありません!」
「シュバルツ殿に鍛えられていますから――――!」
「ならば、左翼の方へ行ってくれ!!」
「左翼ですか!?」
聞き返す妖魔たちにハヤブサは頷く。
「ああそうだ。右翼の方はおそらくシュバルツが守ってくれている。だから、左側の守りの方を厚くして欲しい」
「分かりやした!」
ハヤブサの言葉に妖魔たちも納得する。
「しかし、ここの守りはどうするんです?」
「ここは、俺独りで充分だ」
問う妖魔たちに、ハヤブサは即答した。恐ろしく傲岸な物言いだが、それに納得できるだけの強さをこの龍の忍者は発揮していた。確かに、ここを守るハヤブサを突破できないからこそ、百々目鬼軍は迂回を選択しているのだから。
「分かりやした! では、我々はそちらへ向かいます!」
「ハヤブサ殿も、御気をつけて!!」
妖魔の一団はそう言葉を残して、踵を返して走り去っていく。
「さあ、来い!!」
一人残ったハヤブサは、刀を正眼に構えなおしていた。
ドンッ!!
ドンッ!!
シュバルツが投げた焙烙玉があちこちで弾け、襲いくる百々目鬼軍を撃退する。あちこちから悲鳴と怒号が上がり、逃げ惑う村人たち。
「大丈夫だ!! 走れ!!」
パニックになりそうな村人たちを、シュバルツが懸命に支え、導く。その声を受けて、妖魔たちも村人たちも、互いに支え合いながら戦場を走り抜けた。
「みんな! 頑張って!!」
ケイタも大人たちの間に紛れて、妖魔の子供たちや友達に声をかけながら走る。不意に、そのうちの妖魔の子供の1人が、つまづいて転倒してしまった。
「大丈夫!?」
ケイタは足を止め、妖魔の子を助け起こしに戻る。
「死ねい!!」
そこに迫りくる百々目鬼軍の刃。
「―――――!」
ケイタは咄嗟に、妖魔の子を庇うように抱きしめた。自分の身体に刃が刺さろうが、とにかく腕の中の子だけは助かって欲しい、と願った。
ドスッ!!
何かが切り裂かれる音がする。
だが、自分の身体には何時まで経っても痛みが襲ってこないから、不思議に思ったケイタが顔を上げると、そこには百々目鬼軍の妖魔を倒したシュバルツの姿があった。
「大丈夫か!?」
手を差し伸べ、真っ直ぐ問うてくるシュバルツに、ケイタは茫然としながらも頷く。そのままシュバルツは「立てるか?」と、ケイタ達の手を引いて、立ち上がらせてくれた。
「あ、ありがとう」
「礼はいい。とにかく走れ!」
そう言っている間にもシュバルツは、かかってくる百々目鬼軍を次々と撃退していた。
「わ、分かりました! 行こう!」
ケイタは妖魔の子供の手を引くと、再び走り出していた。
シュバルツの動きは速く、視野も広い。そして、彼は目に見える総てを救おうとしていた。その為に自分の身体が多少傷つこうが、まるで頓着していないようだった。
「く、くそっ!」
「なんだ!? こいつの強さは……! 化け物か!?」
ハヤブサ以外は対して強い者はいないだろう、とタカをくくっていた百々目鬼軍の面々は、シュバルツの八面六臂なその動きに、ひたすら翻弄されるしか無かった。
「逃げろ!! 早く!!」
戦いながら助けた村人たちに呼びかける。
「あ、ありがとうございます……!」
「礼は良いから、早く!」
守る。皆を守る。
その願いを乗せて、その刃は振るわれた。
だが、弱い者をその背に守る戦いは、彼の身体に徐々に大小さまざまな傷を刻みつけて行く事になる。
腹立たしい。
傷を負うことで、動きが鈍くなってしまうこの身体が。
反応が、一歩遅れてしまうことが。
どうせ治るのなら、今治れ。
皆を守れるのなら、このまま真に『化け物』になってしまっても良い。
視界の隅で、転ぶ幼子の姿を見つける。そのすぐ傍に、百々目鬼軍の妖魔が迫っている。
「駄目!」
母親が子供を守ろうとその身を投げ出す。
「く………!」
シュバルツの身体が、考えるよりも先に動く。
理屈じゃない。
自分の目の前で、自分以外の誰かが傷つくのはもう嫌だ。
守る。
絶対に。
ドンッ!!
地に倒れ込んだ母子を斬ろうとした妖魔に向かって、シュバルツは体当たりをする。当たられた妖魔は、そのまま物も言わずに吹っ飛ばされた。
「立てっ! 早く!!」
母子を助け起こそうとするシュバルツに向かって、尚も百々目鬼軍の妖魔たちが殺到する。母子には、シュバルツの背後に迫る刃が見えてしまったが故に、その顔色が変わった。
「――――!」
当然その凶刃には、シュバルツも気づいていた。だが、この母子を助けない限り、自分がここから退くことはあり得ない。守るために、肉を切らせて骨を断つ覚悟を決める。
まさにその時。
「このぉ!!」
叫び声と共に、金拵えの鞭の刃がしなりを上げる。ドカッ!! と、物と物がぶつかり合う音がしたかと思うと、シュバルツに襲いかかっていた妖魔たちが、軒並み吹っ飛ばされていた。
「君は………!」
自分と妖魔の間に飛び込んできた人物に、シュバルツは少し驚く。何故ならそれは、村人たちを先頭に立って案内していた筈の、甲斐姫であったから。
「……………っ!」
甲斐姫はしばらく無言で肩で息をしていたかと思うと、もの凄く険しい目つきをシュバルツに向けてきた。それはもはや『睨んでいる』と、言っても良かった。
「…………?」
助けてくれた礼を言いたいのだが、彼女が睨んで来る理由がさっぱり分からないので、シュバルツはしばし、首をかしげる。そんな彼に向かって、甲斐姫は金拵えの鞭をビシッと向けた。
「……貴方は知らないかもしれないけれど、私は前の時間軸で同じように皆を守ろうとして………でも、守り切れなくて―――――役に立たなかった自分が、心底悔しかったの」
唐突に始まった彼女の独白を、シュバルツは無言で見守っていた。
「前の時間軸の戦いが終わってからも、私はずっと考えてた……。どうすればよかったんだろう、何がいけなかったんだろうって」
「…………」
「私が一度に守れるのは、どう足掻いたってせいぜい一人か二人。その間に貴方はたくさんの人を守っていた……。現に、私も何度も守られた……。そして、貴方に多くの傷を負わせてしまった……」
そして自分は、傷だらけのまま再び戦場に舞い戻ろうとするシュバルツを、止める事さえできなかった。あまりにも未熟だった自分。ただ、苦い後悔だけが残された。
「だから、ずっと考えていたの。もしも、また同じ戦場に、私が戻る事が出来たら――――」
彼女の腕の中の、金拵えの刃がきらりと光る。
「皆を守る貴方を、私が守る!!」
「―――――!」
驚き、息を飲むシュバルツを、甲斐姫はまっすぐ見つめる――――と言うよりは、睨み据えていた。もしも、ここに彼女の友人である孫尚香が居たならば、「目つきに気をつければ良いのに」と、必ず言った事だろう。
「その方が、効率よく皆を守れると言う、事実に気が付いた!!」
「……………!」
呆然としてしまうシュバルツに、甲斐姫は更にたたみかけて来た。
「私が守れるのは1人か2人。その間に貴方は、10人も20人も守る。だから、私が守る人間を貴方に絞れば………私もたくさんの人を守れる。どう? 理屈はあっているでしょう?」
「そ……それはそうかも、しれないが……」
この甲斐姫の、ある意味めちゃくちゃな理屈に、どう言葉を返していいのか分からなくて戸惑うシュバルツに、彼女の金拵えの刃がビシッ! と、向けられた。
「だから私はこの戦場で、皆を守る貴方に追いついて――――絶対に、守ってみせる!!」
甲斐姫の眼差しに、挑戦的な光が宿る。
「絶対に……負けないんだからね!?」
彼女の向けられる真っ直ぐなその視線は、決して逸らされることはない。
守る――――と言うよりも、まるで戦いを挑まれているかのような甲斐姫の様子に―――――シュバルツの中の『何か』が疼いた。
そう。
挑まれたら修業をつけたくなってしまうと言う、彼の中の『何か』が。
「フッ、面白い!」
シュバルツの方の瞳にも、俄然挑戦的な光が宿る。
「ならば、君がどれだけ私の動きについて来られるか、試させてもらおうか! 行くぞ!!」
そう叫んだシュバルツの姿が、甲斐姫の前からフッと消える。
「上等……! 行くわよ!!」
甲斐姫もそこから、猛然とダッシュを開始した。
村人たちは、ただ茫然としていた。
いや、村人たちだけではない。共に逃げていた妖魔たちも。そして、百々目鬼軍の妖魔たちすらも。
「どうした! どうした! どうしたああああああ――――ッ!!」
先程から、やけにテンションの高い風が走り回っている。その後ろから「負けるもんかああああっ!!」と、甲斐姫が突進するように走っていた。
「な、何だべ? 今のは……」
「今の……まさか、シュバルツ、さん?」
「ま、まさか――――」
茫然と呟く村人たちの横を、また風が「ははははは!」と、高笑いをしながらすり抜けて行く。村人たちの中には、しばらくそれに目を奪われて、走るのを止めてしまう者も出てくる始末だ。
「何をしている!? 走れ!!」
そう言う者たちは、戻ってきたシュバルツに喝を入れられて、また、慌てて走り始めていた。
「こんちくしょオオオッ!!」
甲斐姫は歯を食いしばりながら走り回っていた。
覚悟をしていたとはいえ、シュバルツの動きはとにかく早い。想像していたよりもずっと――――下手をすれば、見失いそうになってしまう。
「どうした!? 足が止まっているぞ!!」
そのたびに向こうから声をかけられるものだから、甲斐姫の闘争心に、ますます油が注がれてしまう。
「おのれ!! 絶対負けない!!」
「そらそら!! まだまだスピードを上げるそ!!」
「クッ……! こっちだってッ!!」
戦場を走り抜け、敵を倒し、味方を助け続けるシュバルツに、食らいつく様について行く。
それでも時折シュバルツから、こちらを気遣われたり守られたりするから――――ますます甲斐姫は意地になってしまう。
(負けるもんか……! 絶対に――――!)
ふとシュバルツが、転んでしまった老婆を助ける。
「!!」
甲斐姫はここだ、と、ばかりに踏み込んだ。
「ひゃははは!! 馬鹿め!! 隙だらけだ!!」
案の定、そんなシュバルツに斬りかかって行こうとする百々目鬼軍の妖魔が居たから――――
ガキッ!!
甲斐姫の金拵えが、その妖魔を過たずに仕留めた。
どうだ! と、言わんばかりに鼻息荒く振り返る甲斐姫に、シュバルツはフッと柔らかい笑みを見せて応える。
「まだ行くぞ!! ついてこれるか!?」
「当然でしょ!! 舐めるんじゃないわよ!!」
「上等だ!!」
そう言うや否や、また、猛ダッシュを始めるシュバルツ。甲斐姫も、負けずにそれについて行く。
「絶対に、負けるもんかああああっ!!」
甲斐姫の元気すぎる叫び声が、戦場に響き渡って行った。
その頃、走り続ける村人たちの先頭の方でも変化が起こっていた。目指す劉備の城の方から、土煙が上がっているのが見えたからである。
「何だ?」
訝しむ村人たちと妖魔たちの視界に、一騎の赤毛の馬に乗った武将の姿が入ってくる。その武将は、見る間にこちらの集団の方に近づいてきた。豊かな髯を湛え、身の丈9尺の偉丈夫はこちらの集団を確認すると、大音声で呼び掛けて来た。
「その方らは、我が主、劉玄徳に庇護を求める者たちか!?」
「関羽将軍!!」
先頭に立って皆を案内していた村人が叫ぶ。彼は劉備の統治する城の城下町に行商によく出ていたが故に、関羽を多少なりとも見知っていたのだ。
「そうです! わしらは今――――百々目鬼軍の襲撃を受け、追われています!」
「この妖魔たちは、おらたちを助けてくれて――――!」
村人たちが口々に、関羽に向かって現状を訴える。その横で、妖魔たちが少し申し訳なさそうに、身を固くしていた。
その様を見た関羽は、哀しみ故に少し表情を曇らせる。
この妖魔たちは『妖魔である』と言うだけで――――人間からどう言うふうに見られ、どう言う誤解を受けてしまうのかを、理解してしまっているのだと感じた。現に、前の時間軸でまさに自分が、妖魔の存在故に村人たちや孫尚香を、誤解してしまった内の1人なのだから。
「心配するな。我々はそなた達の事情を、承知いたしておる」
だから関羽はまず、皆にそう呼びかけた。村人たちや妖魔たちが、安心して城に逃げ込めるように。行く道すがら、孫尚香と二人がかりで、張飛と趙雲にも、事情は説明済みだった。
「この辺りはまだ――――戦闘に巻き込まれてはおらぬな?」
問う関羽に、村人たちは頷く。
「へぇ。我々の方にまで敵は来てはおりませぬが、後ろの方の人たちが敵に襲われているようです」
その言葉が終わらぬうちに、後方から火柱が上がる。激しい戦闘が行われている事を、伺わせた。
「承知した。皆はこのまま走って逃げよ。間もなくここに、我が軍が援軍としてやってくる。その者たちと合流して、城へ逃げ込むのだ!」
「わ、分かりました!」
「おい! 皆、走るべ! もうひと頑張りだ!」
関羽の言葉に皆が頷き、互いを励まし合いながら走りだす。関羽は少しの間それを見送ってから、再び愛馬赤兎に拍車を入れた。
(助けなければ……! 今度こそ――――!)
前の時間軸に比べたら、逃げて来ている村人たちも妖魔たちも、その数がずっと増している。太公望の手助けが、うまくいった証拠なのだろう。
助けなければならぬ。
種族を越えて、手を取り合う者たちを。
それを助けようとしている者たちを。
関羽の脳裏に、傷だらけのハヤブサを抱きかかえていたシュバルツの姿が甦る。
前の時間軸では、シュバルツはハヤブサを庇って、跡形もなく崩れ去って消えてしまった。
およそ人間らしからぬ死に方――――彼もまた、『妖魔』かそれに類する物の類(たぐい)なのだろう。
(だからどうした)
関羽は思う。弱き者を守ろうとする者に、その出自の正邪など、問われるべきではない。関係ないではないか。
(間に合わせる……! 今度こそ――――!)
その決意を伝えるように、関羽は己の得物である青龍偃月刀を馬上で改めて構えた。
「おい! 大丈夫か!?」
ハヤブサから左翼を任された妖魔たちは、互いに声を掛け合いながら戦い続ける。何とか村人たちの犠牲は出さずに今のところは守り切ってはいるが、何と言っても多勢に無勢だ。数に任せて押してくる百々目鬼軍に、徐々に押されつつあった。
「ちぃっ! きりが無いぜ!!」
戦い続け、屠り続け――――もう皆が疲労困憊だった。だが、自分達から崩れる訳にはいかない、と、妖魔たちは必死になって武器を上げ続ける。
「頑張れ!! 泣きごとを言うな!!」
「しかしよ……」
「何だ? 蛟(みずち)」
「本当に、劉備軍からの援軍なんて来るのか? もしも、俺達の事で誤解されてしまっていたら――――」
「―――――!」
その言葉に話を聞いていた妖魔も一瞬息を飲む。しかしすぐに、頭を振った。
「それでも……ここの人たちを、見捨てられないだろう?」
「それもそうだな」
そう言って、泣きごとを言った妖魔も苦笑する。彼らは理解していた。ここは、自分達が崩れてしまったら終わりなのだと。
だから、歯をくいしばって耐え続ける。しかし、押し切られるのも時間の問題と思われた、まさにその時―――――
「うおおおおおおっ!!」
咆哮と共に、一等の燃えるような赤毛の馬に乗った武将が、青龍偃月刀を唸らせながらその戦場に飛び込んでくる。ドカッ!! と、派手な音を立てて、その武将は周りの百々目鬼軍の妖魔たちを一掃した。
「我が名は劉皇叔が義弟、関羽!! 字を、雲長と申す者なり!!」
「げえっ! 関羽!!」
「関羽だと!?」
「おお! 関羽将軍……!」
「あれが――――!」
関羽の名乗りに、敵からも味方からも、ざわめく様な声が上がる。百々目鬼軍の中にも、『関羽』の名は知れ渡っているようであった。
「皆の者!! もう少しで、我が軍の援軍がここに来る!!」
「―――――!」
関羽のその言葉に、戦場の空気が一気に変わる。それまで押され気味だった難民たちの妖魔軍の方に、俄然勢いが戻ってきたのだ。
「援軍だって!?」
「おお……!」
「助かるの!? 私たち……!」
「だから、今少し走れ!! もう我が援軍は、目と鼻の先だ!!」
関羽が青龍偃月刀で指し示す先に、はっきりと土埃が上がっているのが見える。関羽の言葉の通り―――劉備軍の援軍がそこまで来ている事が見て取れた。
(ハヤブサは、何処だ―――?)
関羽は民達を誘導し、百々目鬼軍を撃退しながら黒の忍者の姿を探す。援軍が来た事を、彼に知らせなければと思っていた。
そうしてしばらく敵を蹴散らし、援軍が来ている事を叫び、民達を誘導しながら戦い続けていた関羽であったが、やがて、1人の青年に声をかけられた。
「貴殿が、関羽殿か!?」
振り返る関羽の視界に、こちらに向かって走って来ているシュバルツの姿が飛び込んでくる。
「そなたは……!」
「私の名はシュバルツ・ブルーダーと申します。劉備殿が、援軍を出してくれたのですか!?」
「ああ………」
関羽はうっかりシュバルツの名前を呼びそうになったのだが、先にシュバルツの方から名乗ってくれたので、ほっと胸を撫で下ろしていた。
「そうだ。孫尚香殿の要請を受けて、兄者が決断を下してくださったのだ」
「そうですか……」
そう言葉を紡ぐシュバルツの後ろから、1人の女性が走ってきた。彼女はシュバルツに追いつくと、手を膝について前かがみの姿勢になって立ち止まり、苦しそうに肩でぜえぜえと息をしていた。
「大丈夫か?」
そう気遣うシュバルツに、彼女はきっと顔を上げる。
「まだまだぁ!!」
「…………!」
その目つきがあまりにも険しい物だったので、関羽は思わず身を引きそうになる。流石に『甲斐の熊姫』と異名を取るだけの事はある。ものすごい迫力だった。
「シュバルツ、ハヤブサは何処に居る?」
「ハヤブサですか?」
関羽の問いかけに、一瞬小首を傾げたシュバルツであるが、すぐに得心した。ハヤブサは戦う前、「関羽殿は総てを承知してくれている」と、語っていた事を思い出したからだ。きっと関羽とハヤブサの間には、この戦いに入る前に、事前に打ち合わせができているのだろう。
「ハヤブサは殿で戦ってくれています」
「そうか……」
シュバルツの言葉に頷くと、関羽は青龍偃月刀を構えなおした。自分が―――劉備軍の援軍が来たと、早くハヤブサに知らせねばならぬと思った。
「では拙者はハヤブサの所に参る。シュバルツ、そなたは―――」
「私は皆を誘導しつつ、援軍と合流致します」
打てば響く様な答えを返してきたシュバルツに、関羽は感心した。この青年は弱き者をその背に庇うだけでなく、その場の状況を判断して動く事が出来る。なかなか機転も利く様だ。典韋が曹操にこの青年を推挙しようとした、という話を聞いた事があるが、なる程、と、頷く事が出来る。きっと曹操も、彼の様な武将は気に入る事だろう。そして我が主玄徳も――――
「では、頼んだぞ」
関羽はシュバルツにそう言い置くと、赤兎馬に拍車をかけ直した。
シュバルツは赤兎馬と共に関羽に頭を下げてから、甲斐姫に振り返った。
「聞いての通りだ。援軍がこちらに向かっている様だぞ」
「はい! ……そっか……尚香が、やってくれたんだ……」
シュバルツの言葉に、甲斐姫が嬉しそうに微笑む。すると彼女の表情は、先程の睨みつけていた物とは一転して、柔らかい印象を人に与えた。
(ああ、可愛いな)
それを見つめるシュバルツの表情も、自然と柔らかいものになる。だが、彼はすぐにその表情を引き締めた。
「後もう一息――――ついて来れるか!?」
「行きます!!」
シュバルツの問いかけに、甲斐姫は噛みつかんばかりの表情を浮かべる。シュバルツはそれににやりと笑みを返すと、また前を向いた。
「では、行くぞ!!」
そう叫ぶや否や、シュバルツの姿がまたフッと見えなくなる。
「負(むぁ)けるもんかああああっ!!」
彼女もまた、村人たちや妖魔たちの間を、猛然とダッシュを開始していた。
手を取り合って走っていた村人たちと妖魔たちの前に、やがて軍隊が合流して来た。その軍隊には劉備軍の旗が掲げられ、その先頭で孫尚香が手を振っている。
「みんな、無事!?」
呼び掛ける孫尚香に、村人たちが走り寄っていった。
「我らは大丈夫です!」
「でも、早く助けて下せぇ! 後ろの方が戦闘に巻き込まれているみたいで……!」
「そうみてぇだな。鬨の声と戦いの音が、ここまで響いて来ていやがるぜ」
村人たちの懇願に、張飛が後方を覗き込むような仕種をする。
「だけど安心しな! 俺たちが来たからには、お前達にはもう指一本触れさせやしないからな!」
張飛の言葉に横にいた趙雲も頷き、村人たちからどよめきと歓声が上がる。中には、涙を流している者もいた。
「張飛どの! 我らは我らの役目を急ぎ果たしましょう!」
張飛の横にいた趙雲が、声をかけて来た。
「おう、そうだな」
趙雲の言葉に張飛は頷くと、後ろの自軍の兵士たちに声をかけた。
「よしっ! 野郎ども!! 自分がやるべきことは分かっているな!? 関羽の兄貴の兵士たちも――――!!」
その言葉に兵士たちから「おおっ!!」と、力強い返事が返ってくる。
「じゃあ、行くぜ!!」
張飛の号令に合わせて、兵士たちは一斉に駆け出した。
「走れない者はいないか!? この荷車に乗ってくれ!!」
「荷物も! 遠慮なく乗せてくれよ!!」
「馬の余分もある!! 疲れた者は乗ってくれ!!」
「女子供を優先しろよ!! 年寄りもだ!!」
兵士たちは村人たちの間に入って行くと、大声で呼びかけ、難民たちの手を取って行く。
「走る準備の出来た者たちから走れよ!! 村人たちを怪我させねぇ様にな!!」
兵士たちは手際よく、村人たちの誘導を始めた。あっという間に村人たちが逃げるスピードが、格段に上がり始めた。
「て、手慣れているわね………」
孫尚香がその様を、半ば茫然としながら見守る。
「慣れてるんだよ」
その声を聞いた張飛が、苦笑しながら答えた。
「玄徳様は、決して民を見捨てられる方ではありませんから――――」
趙雲も、孫尚香の言葉に答える。
「民が兄者を慕ってついてくるものだからな。俺たちも何度も民と一緒に逃げるうちに、要領を得てきちまったんだ」
良い事何だか悪い事なんだか――――そう言って頭をかく張飛に、孫尚香も笑顔を見せた。
「フフ……玄徳様らしいわね……」
そう、常に民に寄り添おうとする玄徳。為政者には大切なことだが、なかなかそれを実行できる人間は少ない。そんな玄徳だからこそ、自分は好きになったのだと孫尚香は強く思った。何故か、涙が出てくる。彼女はそれを、慌てて拭った。
「さあ、残りの半分は、百々目鬼軍と戦いに行くぞ!! 野郎ども!! ついて来い!!」
張飛の号令に、兵士たちから、おおっ!! と、力強い声が返ってきた。
「……どうした? もう、来ないのか?」
龍剣を構えて、じりじりと威嚇するハヤブサ。周りの百々目鬼軍の妖魔たちは、すっかり怖気づいていた。
「す……すげぇ……」
「ば、化け物だ……! 敵う訳無いよ……!」
彼の後ろで戦っていた味方の妖魔たちも、それは同じだった。
「強い……!」
「良かった……! この人が味方で……」
その戦いを見守りながら、安堵のため息が漏れる。それほどまでに、龍の忍者の戦いは―――――圧倒的だった。
「……………」
(このまま、攻め込むべきか……?)
戦いながらハヤブサは、度々そう思うようになっていた。しかし、そのたびに頭を振った。
まだだ。
まだ今は、攻め込むべき時ではない。
自分がここを離れてしまったら、戦列が間延びして、百々目鬼軍に付け入るすきを与えてしまう。それだけは、断固として避けねばならないのだ。今度こそ――――皆を救うのだから。
攻めるのは、援軍と合流してからだ。
自分にそう言い聞かせながら、剣を振り続ける。と、そこに、後ろから力強い馬の蹄の音が響いて来た。
「…………?」
振り返るハヤブサの視界に飛び込んでくるのは、燃えるような赤毛の馬と、青龍偃月刀を構えた武将。
「ハヤブサ!!」
関羽殿、と、ハヤブサが叫ぶよりも早く、関羽の方が声をかけて来た。
「今度は、間に合ったか!?」
「―――――!」
その言葉に、前の時間軸の戦場の事を思い出してしまって、ハヤブサの中に一瞬何とも言えない想いがこみ上げてくる。
前の時間軸では、自分はもう立ち上がる事も出来ない程ボロボロに傷つき、シュバルツを殺そうとする素戔鳴の前に、どうする事も出来ない状況だった。だが、今は違う。
シュバルツも村人も、そして妖魔たちも無事だ。素戔鳴の襲来もまだ無い。
間に合った。
関羽の援軍は、間に合ったのだ。
だからハヤブサも、黙って頷く。それだけでもう―――充分だった。
「そうか」
そう言いながら関羽も、満足そうに微笑んだ。
やがて後方から、シュバルツや劉備軍の面々がハヤブサたちの所に合流してくる。少し遅れて、甲斐姫も走って来ていた。
「ハヤブサ!」
「シュバルツ……!」
村人たちを庇いながら戦った割には、シュバルツが傷らけにはなっていなかったので、ハヤブサはとりあえず、ほっと胸を撫で下ろしていた。
「ハヤブサ、村人たちは皆、この戦場から離脱したぞ」
「本当か!?」
駆け寄ってくるなりシュバルツは、ハヤブサにこう声をかけてくる。あまりにも手際が良すぎる村人たちの避難に、ハヤブサは少し驚いた。それに対してシュバルツは頷きながら、さらに言葉を続けた。
「ああ。劉備軍の方たちが村人たちに手を貸して――――あっという間に戦場から離脱させてくれたんだ」
「…………!」
「何度も言うが、慣れているんだよ」
驚くハヤブサに、張飛が苦笑しながら声をかけてくる。その姿を見て、ハヤブサは更に驚いた。
(何故、張飛殿がここに……!? 前の時間軸ではいなかった筈だが……!)
「ん? どうしたよ?」
ハヤブサが息を飲んでいる気配を感じて、張飛が訊ねてくる。
「ああ、いや――――」
それに対してハヤブサは、少し返答に窮してしまった。まさか「前の時間軸ではいなかったはずだが……」などと、聞く訳にもいかないから、少し困ってしまう。
「張飛さんだけじゃないわ! 趙雲さんも、そして城には玄徳様も、いらっしゃったの! 私もびっくりしちゃった! こんな偶然、あるものね」
ハヤブサの驚きが分かる孫尚香が、助け船を出すかのように声をかけて来た。
(そうか……! それで、太公望は………!)
ここに至ってようやくハヤブサも、自分が療養している間に太公望がこの時間軸に対して打った手の全容を理解した。自分達の逃げ込む先の城に、関羽のみならず、劉備軍の主力が集まっている―――――こんな奇跡のような偶然を起こすために、太公望はどれだけの手を打ってきたのだろう?
もう本当に、この戦いは絶対に負けられない。
強く、そう思った。
「それにしても関羽の兄者の赤兎馬は速過ぎるよ! 追いつくのに少し時間がかかっちまったぜ」
そう言う張飛に関羽も苦笑する。
「あい済まぬな、張飛。ここの者たちはどうしても助けたかった故――――」
「確かに、そうですね……」
関羽の言葉に、趙雲が納得したように頷いた。
「種族を越えて助け合える人たちを、見殺しになど出来ませんから」
「そうだな……」
趙雲の言葉に、皆も頷く。
ここまできたら――――
もう、想いは一つだった。
「では、我らはこれより反撃に移るぞ!!」
関羽のこの言葉に、兵士たちも、そして、戦っていた妖魔たちも、「オオッ!!」と、歓声を上げた。ついに、待ちに待っていた時が来たのだ。
「もうここには、守るべき村人たちはいない……。君はどうする? 劉備殿の城の方へ行くか?」
そんな中、シュバルツは自分の後ろについて来ていた甲斐姫に声をかけていた。彼女の体力的にもきつそうだし、遠慮なく反撃に出て良い今、自分に対する護衛は必要ない、と、シュバルツは感じていた。
だが、シュバルツのその言葉に甲斐姫は首を振った。
「いえ、大丈夫です! 行きます!!」
彼女は肩で息をしながらも、きっと顔を上げる。その眼差しは、シュバルツを見つめると言うよりも、睨み据えていた。まるでこのままここから追い返されたら、100年先まで恨まれそうな目つきだ。
「ちょ、ちょっと甲斐……!」
友人のその目つきの悪さに孫尚香はちょっと引き気味になり、シュバルツも苦笑する。しかし闘志を失わないその彼女の姿勢に、もう少し修業をつけてやるのも良いかと彼は思った。
「よし! なら行くぞ!! ぼやぼやする様なら、置いて行くからな!!」
「望むところだ!!」
シュバルツの言葉に、甲斐姫は噛みつく様に答えを返す。
(こ、これって……私もついて行かなきゃいけない流れよね……)
一歩も身を引く気が無い友人のその様に、孫尚香は苦笑しながらも空気を読んだ。要するに自分に求められている役割は、シュバルツしか見えてなさそうな甲斐姫をフォローする事なのだと。
全員の準備が整ったと感じた関羽は、皆に改めて号令を出した。
「それでは皆の者!! かかれ!!」
その声を待ちかねていたかのように、それまでじりじりと退却していた妖魔軍とそこに加わった劉備軍が、一気に反撃に転じた。地を揺らすような怒号と共に、関羽が、張飛が、趙雲が―――――そして、ハヤブサとシュバルツに甲斐姫と孫尚香が加わった一団が、潮の様に百々目鬼軍に突っ込んで行く。
「む……! これは………!」
村人たちを守るという足枷が無くなった状態で、しかもこれだけの面々に攻め込まれてしまっては、いくら数では勝る百々目鬼軍も、ひとたまりも無かった。あっという間に戦線は瓦解し、戦況はひっくり返されてしまう。
「退けッ!! 退けぇ!! こんな所で命を落とす訳にはいかぬ!!」
機を見るに聡い百々目鬼は、全軍に退却命令を出す。百々目鬼軍はほうほうの体で、戦場から離脱したのだった。
「もう二度と来るなよ!! 今度民たちを襲ったら、承知しねぇからな!!」
退却する百々目鬼軍に向かって張飛が咆える。その後ろで、玄徳軍と妖魔軍が、揃って勝ち鬨を上げていた。
(良かった………)
ハヤブサは、独り静かに胸を撫で下ろしていた。
あの村の民達を、守りきれた。
シュバルツを取り戻すための第一関門を、確かに突破したのだと、ハヤブサは感じていた。
「終わ……っ、た………!」
皆が喜びの声を上げる中、甲斐姫はその場にへたり込んでいた。
とにかく、シュバルツについて行くのが精いっぱいという中、果たして自分がちゃんと戦えていたかどうかは分からない。それどころか、時折彼から何度か守られてしまったことも覚えている。やはり――――自分は、戦いにおいては未熟者なのだと、悟らざるを得なかった。
でも
それでも――――
前の時間軸の戦いのときよりは、比べ物にならない程傷を負っていないシュバルツの身体。
少しは、自分もこの戦いに貢献できたのだと、胸を張って良いのだろうか。
そんな事を思いながら、甲斐姫が座り込んで呼吸を整えていると、そこにスッと手を差しのべられてきた。
「立てるか?」
「…………!」
甲斐姫が驚いて顔を上げると、そこには柔らかい笑みを浮かべながら手を差し出す、シュバルツの姿があった。
「大、丈夫……です。立てます」
甲斐姫はそう言いながら自力で立ち上がろうとするが、一旦脱力してしまった手足は、なかなか力が入ってくれそうにない。それ見たシュバルツは、苦笑しながら甲斐姫の手を取り、支えてやる。それを受けて彼女もようやく、立ち上がる事が出来た。
「なかなか良い戦闘(ファイト)だった……。よく、頑張ったな」
「…………!」
シュバルツからのその言葉を聞いた甲斐姫は、瞬間信じられない心地になる。驚いた。まさかねぎらいの言葉を受け、しかも褒めてもらえるとは。
「ありがとう、ございますッ!!」
甲斐姫は慌てて、ぎこちなく礼を言いながら頭を下げる。そんな彼女にシュバルツは軽く笑みを返すと、さらに言葉を続けた。
「君はきっと、良い戦士になる。これからも鍛錬を続けてくれ。全く……君を見ていると、私の『弟』を思い出すよ。『弟』も君の様にまっすぐな性格なんだが――――ん? どうした?」
話を中断して、シュバルツは甲斐姫を覗き込む。何故なら立ち上がった筈の甲斐姫が、再びへなへなとへたり込んでしまっていたからだ。
「おい? どうした? 大丈夫か?」
シュバルツがへたり込んだ甲斐姫に、心配そうに声をかける。それに対して甲斐姫は、蚊の鳴く様な声で「大丈夫です………」と、返事を返しはするが、あんまり大丈夫でもなさそうだった。
(『弟』……! そりゃあ私は女らしくないし、別に女性扱いをして欲しい訳でもないけど………っ!)
甲斐姫の頭の上に今、『弟』という文字が切なくのしかかっていた。彼女は自分がどれだけ女らしくないかということを、改めて外から指摘されたような気持になって、軽くショックを受けているのだ。
「………………」
甲斐姫の気持ちも分かるが、女として見られないのも仕方がないと思ってしまう孫尚香は、顔をひきつらせて笑うしか無く、甲斐姫を見て、『弟』を思い出してしまうシュバルツの気持ちが分かるハヤブサも、頭を抱えてしまうしかない。シュバルツの『弟』は、『キング・オブ・ハート』の称号を受け継ぎ、人間離れをした強さを持つ、比類なき格闘家だ。その彼になぞらえるなど――――シュバルツからしてみれば、最高の褒め言葉のつもりなのだろう。
だが、甲斐姫はそんな事情を知らない訳だから、当然、単純に「男みたいだと言われた……」と、言うことになる訳で。
このからくりに1人気づいていない天然ボケな愛おしいヒトに、ハヤブサはため息をつきながら声をかける事にした。
「シュバルツ……」
「ハヤブサ……彼女が、急に――――」
そう言いながら心配そうに甲斐姫の様子を伺っているシュバルツ。その様があまりにも可愛らしいものだから、ハヤブサの中で本当に何かが切れそうになってしまう。「シュバルツ!!」と叫んで抱きしめそうになるのを、彼は懸命に堪えなければならなかった。
落ちつけ。
落ちつくんだ、リュウ・ハヤブサ。
まだ戦いは終わっていない。
今は――――まだ、その時じゃないんだ。
シュバルツを完全に、悲劇から取り戻せている訳ではないのだから。
ハヤブサが必死に自分を落ち着かせている横で、甲斐姫の方にも孫尚香が近寄ってくる。
「ほら……甲斐……。大丈夫? ちゃんと立って!」
「ははは……尚香、大丈夫よ……」
乾き切った笑いが、彼女の大丈夫じゃなさそうな加減を伝えてくる。孫尚香は苦笑すると、脱力し切った甲斐姫の腕を引っ張った。
「大丈夫か?」
そんな二人にシュバルツが心配そうに声をかけてくる。
「あ……はい! 大丈夫です。すぐに立ち直ると思うんで………」
孫尚香はシュバルツに返事をしながら、脱力し切った友人をずるずると引っ張って行く。
「ほらっ! しっかりしなさい! いい? 貴女には友人として忠告する事がたくさんあるんだからね?」
「そうなの………? あは……あははは………」
そのまま二人は、シュバルツ達の前から去って行った。
「どうしたんだ? 彼女は……」
甲斐姫が落ち込んだ原因が、全く分かっていないシュバルツの肩を、ハヤブサがポン、と叩く。
「『彼女』……そう、彼女は『女性』なんだ」
「ハヤブサ……」
「シュバルツ……。俺が言わんとしている事、分かるな?」
「えっ?」
「えっ?」
「………………」
ハヤブサは思わず、目をしばたたかせながら、シュバルツをまじまじと見てしまう。
「いや、だから、彼女は女性だから――――」
「ああ。女性だな。あの娘を見て、『男だ』と、言う奴はいないだろう?」
「…………」
「どうした? 何か問題でもあるのか?」
「いや、だからその――――」
そのまましばし、忍者二人の間に奇妙な沈黙が下りてくる。天然ボケなシュバルツの、きょとん、と見つめ返しているその眼差しが、あまりにも可愛らしいものだから、ハヤブサは思わず――――
「今!! 何をしようとした!?」
ハヤブサの手がシュバルツの顎に触れた瞬間、シュバルツはハヤブサを殴り飛ばしていた。だが腐っても龍の忍者なだけに、彼はすぐに起き上がってくる。
「いててて……。何も、殴る事はないだろう!?」
「いいや! 今お前、絶対に何かやましい事をしようとしただろう!!」
「ご、誤解だ!! 俺はただ――――!」
「じゃあ、さっき私の顎を捉えて――――その後、何をするつもりだったんだ?」
「えっ?」
きょとん、とするハヤブサを、シュバルツがじと~っと睨み据えている。
「え、えっと………つまりだな……」
「……………」
「つまりお前が―――――」
「……………」
言い訳をしようとするハヤブサに対して、降ってくるシュバルツの視線は冷たい。その冷たい眼差しを浴び続けたハヤブサは、何かをあきらめた様にフ……と、笑った。
「仕方がなかろう。お前があまりにも可愛らし」
ドカッ!!
再びシュバルツのきつい鉄拳制裁が、ハヤブサを襲うのだった。
「御二方とも、無事か?」
忍者二人がそうやってじゃれ合っている所に関羽が声をかけてくる。
「関羽殿」
関羽の姿を認めたシュバルツが、その姿勢を正した。ハヤブサもそれに合わせて身を起こし、関羽の方に向き直る。
「救援、心より感謝申し上げます。本当に助かりました」
シュバルツはそう言って、丁寧に頭を下げる。
「いや……此方こそ、間に合って良かった……」
関羽はそれに対して、柔らかい笑みを浮かべながら軽く会釈を返した。前の時間軸では傷だらけだった二人の姿。それを思うと、二人が傷を負うことも無くまっすぐ立っている姿を見るのは、関羽にとっては少し感慨深くもある。
「さあ、城に帰りましょう。きっと、殿もお待ちです」
趙雲にそう声をかけられ、皆はそれに従うことにした。
城に帰ると、広場で村の人たちと共に避難して来た妖魔たちが、丁度炊き出しのご飯を食べているところだった。
「あ、シュバルツさん!」
劉備軍と共に帰ってきたシュバルツの姿を認めたケイタが、嬉しそうにシュバルツの傍に駆け寄ってくる。
「みんな、大丈夫だったか?」
問うシュバルツに、ケイタは元気良く頷く。
「うん! みんな無事だよ! ちっとも怖くなかったよ!」
「お兄ちゃんが手を引っ張ってくれたもん!」
「兵隊さんたちも、みんな優しかったよ!」
口々にそう言ってくる子供たちに、シュバルツも「そうか」と、優しい笑顔を向ける。とても平和な景色――――ハヤブサはそれを、少し離れた所から見守った。子供たちに優しい笑顔を向けるシュバルツを見るのが、彼はとても好きだった。
「シュバルツ殿! ハヤブサ殿!」
劉備軍の中から二人の姿を見つけた村長と長老が、手を振りながら駆け寄ってくる。
「御二方とも無事でよかった……! 本当に、此度の事でどれだけ助けられたか……いくら礼を言っても足りないぐらいです。かたじけのうございました……!」
そう言って村長が頭を下げようとするのを、シュバルツは慌てて止めた。
「どうか、御手をおあげください! 第一、私は何もしていません。総ての手配はハヤブサが――――」
「いや、俺だけの力じゃない。これは皆の力で、勝ち取った勝利だ」
ハヤブサはそう言ってから、村長の方に視線を向ける。
「村長………村人の方に犠牲者は、出ていないのか?」
「ええ。出ていません。全員無事に、逃げ切る事が出来ました」
「わしらの方も、多少怪我人が出たが、全員生きているぞ」
そう言いながら妖魔の長もこちらに歩いてくる。その言葉を聞いたシュバルツはホッと胸を撫で下ろし、ハヤブサは小さくガッツポーズを作っていた。太公望はその言葉の通り、『全員』を救った事になる。本当に――――すごい事をやってくれた。
だが、まだだ。
まだすべてが終わった訳ではない。
まだ最大の難関が――――一つ残っている。
「劉備様だ!」
炊き出しをしていた兵士の間から上がる声に、皆がそちらに視線を向ける。すると、避難してきた村人たちに声をかけながら、確かに劉備その人が、こちらに向かって歩いて来ていた。その後ろからもう1人―――白羽扇を持ってついて来ている人物が見えた。
(うわ……! 諸葛亮殿だ………!)
その姿を認めた瞬間、シュバルツの中で機械の駆動モーターの回転数が跳ね上がり、その瞳が憧れと尊敬故にきらきらと輝きだした。無理もない。シュバルツ――――というかキョウジは、「諸葛亮」という歴史上の人物をかなり尊敬していた。その人物に直に会えるとか、まして話をするなど、それこそ天にも昇らんばかりの心地になってしまうのだろう。
「……………!」
当然シュバルツがそうやって舞い上がっている気配を、ハヤブサは敏感に感じ取ってしまう訳で。何となく『もやっ』とするハヤブサは、シュバルツの後ろにぴったりとくっつくと、ぼそりと小声で呟いた。
「………サインください、だなんて、叫び出すなよ?」
「………言わないよ。そんな事は」
ハヤブサの多少揶揄を含んだ物言いに対して、シュバルツの声が意外にも少し沈み気味だった。
(ああ、そうか………)
ハヤブサはシュバルツが沈んだ理由をすぐに理解した。つまり彼は、孔明に会った事をキョウジに話そうと思って――――それを、話す事がもう出来ない事を思い出してしまって、落ち込んでしまっているのだ。
(仕方がない奴だな……)
ハヤブサはポリポリと頭をかく。
そうやって孤独に震える姿を見てしまうと、こちらとしても抱きしめて、慰めてしまいたくなる。だけど、それは今すぐには不可能だから――――
ハヤブサはシュバルツの肩にポン、と手を置くと、もう一度その耳に囁きかけた。
「淋しいのなら、キスしてやろう―――――でッ!!」
シュバルツに、いきなり足を思いっきり踏んづけられたが故に、ハヤブサから悲鳴が上がる。
「……礼を言うぞ、ハヤブサ。おかげで、冷静になれた」
「ど……どういたしまして……!」
シュバルツの冷たい眼差しを浴びながら、涙目になってのたうちまわるハヤブサ。そうやってハヤブサが転げまわっている所に、劉備の方から「大丈夫なのか?」と、声をかけられた。
「劉備殿」
「劉備様!」
劉備の方から声をかけられた格好になった村長と長老と妖魔の長は驚いて、一様に膝をついて頭を垂れる。シュバルツとハヤブサもそれに倣った。
「ああどうか、そのように畏まらずに――――御手をおあげください」
穏やかな声に諭されて、村長たちが顔を上げると、劉備の笑顔がすぐそこにあった。彼も皆と同じように膝をついて、こちらを覗き込んでいたのだ。
「此度は大変だったな……。よく、我が城まで避難して来てくれた」
「そ、そんな……! 滅相もございません!!」
「わ、我々こそ、助けていただいて――――!!」
劉備のそんな対応に、長老も、妖魔の長たちも却って畏まって恐縮しまくっている。
(ああ、なるほどな)
ハヤブサはその光景を見て、1人苦笑しつつも納得していた。普通、一国一城の主という者は、雲の上の存在の筈だ。それが、こんな風に声をかけられてしまったら、かけられた方はすっかり舞い上がってしまって「この人は素晴らしい!」と、なってしまう。計算づくでやっているのか、それとも天然でやっているのかは分からないが、大した人心掌握術だ。
「住んでいた村が無事であれば良いのですが、もしそうでなかった場合、新しい村を開墾する事も含めて考えなければなりませんね……。これからの貴方がたの身の振り方なども」
劉備の横で、軍師孔明が同じように膝をついて口を開く。主君に合わせているのだろう。
「あ、ありがとうございます!!」
村長が、嬉しそうに頭を下げる。
「このままここで話すのも何ですから……少し、落ち着いた所で話しませんか? 貴方がたの方の話も聞きたいですし、これからの方針なども話し合いたいので」
「ああ、そうだな」
孔明からの提案に、玄徳も頷いた。村長や長老たちも頷いて、立ち上がる。
「その話し合い――――俺も同行させてもらって良いか?」
その時、それまで黙っていた龍の忍者が口を開いた。皆の注目が、一斉にハヤブサに集まる。
「そなたは?」
問うてくる玄徳に、ハヤブサは名乗りを上げる事にした。
「俺の名はリュウ・ハヤブサ。そして、こちらにいるのはシュバルツ・ブルーダー。共に『忍者』を生業としている者だ」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは玄徳に向かって軽く頭を下げる。
「忍者………」
考え込むような仕種をする玄徳に、孔明が補足説明を加えた。
「服部半蔵殿と一緒ですよ」
「おお、そうか……。家康殿の傍にいた――――」
「半蔵を知っているのか?」
玄徳の口から出た意外な名前にハヤブサが驚くと、玄徳がにこやかに答えてくれた。
「ああ。先の遠呂智討伐の折りに、共に戦ったのだ。あの後家康殿は、この国作りも手伝ってくれてな」
(ああ、そうか………)
確か、今の妖蛇討伐軍が結成されるより前に、人間たちと遠呂智は既に2度、戦っている。この時間軸も時代もバラバラなこの世界では、普通ではあり得ない人間同士のつながりが出来ていても、それは不思議ではなかった。
「このシュバルツ殿もハヤブサ殿も、我らのために非常に尽力してくださったのじゃ」
長老の言葉に、玄徳も「なるほど」と頷く。
「そう言うことならば、貴方がたもぜひ――――話に加わってください」
玄徳の言葉に、皆は素直に従った。
「ここならば、落ち着いて話もできよう。狭い所だが、入ってくれ」
玄徳が案内してくれたのは、炊き出しの広場のすぐ近くに設えられた幕舎の中だった。どうやらここが避難して来た者たちへの対応をする仮本部の様な物になっているらしかった。
「それにしても驚いたな………。妖魔と人間が、本当に手を取り合えているとは――――」
席に着くなり、玄徳が一番にそう口を開く。それに対して妖魔の長と村の村長は、嬉しそうに互いの顔を見合わせた。
「『妖魔』と言ってもいろいろいる。何も、人間に敵対心を燃やす部族ばかりとは限らぬ」
妖魔の長の言葉に村長も頷いた。
「んだ。この方たちと交流を持てて良かったと、わしらも思うておる。いろいろと農作業を手伝ってくれたし、わしらが知らない山菜や植物の事を、教えてくださった」
「じゃが……他の部族の妖魔たちは、わしらが人間と共生する事を選んだ事が、気に入らなかったようで――――」
そう言って哀しそうに眼を伏せる妖魔の長に、玄徳は「そうか……」と、労(ねぎら)うように声をかけた。
「貴方がたがこれから先も交流を望むのならば、我等としても出来得る限り協力しよう。新しい村を作るにしても、貴方がたと妖魔たちが、それぞれ行き来できるようにして――――」
「………その『先』の話をするのは、少し待ってくれないか?」
玄徳の言葉を遮る様に、龍の忍者が声を上げる。
「ハヤブサ?」
シュバルツが驚いた様にハヤブサの方に振り向き、玄徳も怪訝そうに眉をひそめた。
「それは、何故だ?」
「実は、この戦いはまだ終わってはいない」
玄徳の問いに、龍の忍者は明確な答えを返す。
「ここの村人たちや妖魔たちを襲撃しようとしている者が、まだ居るんだ」
「ええっ!?」
「本当だか!? それは……!」
「……………!」
ハヤブサのその言葉に、幕舎の中にいた者全員が息を飲む。
「それを撃退するまでは、この戦いが真に終わったとは言えない。だから、村人たちの身の振り方を考えるにしても、次の敵を撃退してからにして欲しい」
「そ、そんな……!」
「敵は、百々目鬼だけではなかったのか?」
長老たちの問いに、龍の忍者は頷く。
「残念ながら、そうだ」
「……その情報は、確かなのですか?」
それまで黙っていた孔明が、ハヤブサをまっすぐ見つめながら口を開く。穏やかながらも鋭い眼光。その光の前にはいかなる嘘もごまかしも、通用しないだろう。
未来で、自身が経験して来た事がらだから、この情報はこれ以上ないと言う程確かな物だ。だが、それを目の前の軍師孔明に、どのような言葉で以って説明すればいいと言うのだろう。
「…………」
ハヤブサが説明する言葉に窮していると、そこに思わぬ助け船が入ってきた。
「その者の言っている事は、真実(ほんとう)ですぞ。軍師殿」
そう言いながら身の丈9尺の流れる様な髯を湛えた大男が、幕舎の中に入ってくる。
「関羽殿!」
入ってきた関羽に、というよりも、関羽の発した言葉に驚いて、シュバルツが声を上げる。関羽はそれに軽く頭を下げて答えると、玄徳の方に向き直った。
「兄者。こちらにおいででしたか」
幕舎の中に入ってきた関羽の後に続いて、張飛、趙雲も入ってくる。
「関羽、張飛、趙雲、ご苦労だったな」
玄徳のねぎらいの言葉に、張飛が手を上げて答える。
「おう! 俺としてはちょっと物足りないぐらいの戦いだったがな!」
「民たちも大分落ち着いています。今、仮の寝屋になる幕舎を増設中です。夜には、皆幕舎の中で休めるようになるでしょう」
「うむ」
張飛たちの報告を聞き終わってから、玄徳は改めて関羽の先程の言葉の意を問うた。
「ところで関羽。先程のお前の言っていたことだが―――――それは、本当なのか?」
「そうです」
玄徳の問いに、関羽は迷うことなく頷いた。そして、ハヤブサの方に振り返る。
「ハヤブサ。先の戦いでは、あの仁王然とした男がいなかったが――――やはり、あれは百々目鬼とはまた別の勢力なのか?」
「ああ、そうだ。あれは……仙界軍の将だ」
ハヤブサは、関羽に答えながら心の中で強く感じていた。
力を借りねばならぬ。
素戔鳴と戦うために。
シュバルツを悲劇から、取り戻すために。
劉備軍の将たちの力を
稀代の天才軍師の知略を
立ち向かうために、借りねばならないのだ。
今、俺の目の前にこれだけの将がそろっている意味を考えろ。
将たちの後ろから、太公望が手を差し伸べている姿が見える。
彼は、こちらに投げかけているのだ。
生き延びたければ―――シュバルツを助けたければ、この手を取れと。
「その仙界軍の将が、村人たちと妖魔たちを討たんとしているんだ」
「…………!」
ハヤブサのその言葉に、妖魔の長と村長が同時に息を飲み、シュバルツが小声で「何故……!」と、呟いていた。彼らからしてみれば、この情報は本当に寝耳に水で――――仙界軍の将に命を狙われる理由など、全く思い当たらないのだろう。
「何度も確認して申し訳ないが………それは、確かなのか?」
玄徳の言葉に関羽が頷く。
「はい。兄者。細かな説明はここでは省かせていただくが、拙者とこのハヤブサは、確かに『見た』のです。その仙界軍の将の姿を。そして、彼の者が確かに、村人たちや妖魔たちを襲撃して来た所を――――」
「な…………!」
関羽の言っている事が俄かに信じ難くて、シュバルツは思わず関羽の方をじっと見てしまう。何か、辻褄の合わない様な事を言われた気がしたからだ。それは、玄徳や孔明の方も同じなのだろう。何かを推し量る様に関羽の方をじっと見つめていた。
「……………」
だが、当の関羽は全く動じる気配もなく、じっと玄徳の方を見つめ返していた。自分の言っている事に、絶対に嘘偽りはない――――それを、胸を張って証明したいのだろう。
だから、ハヤブサもそれに倣い、同じように玄徳をまっすぐに見つめた。必要とあらば、己の首すらも差し出す覚悟を決めていた。
しばし、幕舎の中を奇妙な沈黙が覆う。
先にそれを破ったのは軍師孔明の方であった。
「………何やら、込み入った事情がある様ですね……」
彼は一つ小さく息を吐くと、玄徳の方に振り返った。
「殿、少し場所を変えましょう。ここではどのような目や耳があるか分かりませんので……」
「それもそうだな」
孔明の提案に、皆は従うことにした。
こうして話し合いの場所は、城内の一室へと移された。だがこの話し合いは、最早軍議の様相を呈している事に、誰もが気付いていた。
「それでは関羽」
孫尚香や甲斐姫もその部屋に招かれ、皆がそろった所で、改めて玄徳が口を開いた。
「お前は、先程仁王然とした男が村人たちを襲撃したのを『見た』と、言ったな?」
「はい、兄者。確かに」
「どう言うことだ? ここの村人たちを襲ったのは百々目鬼軍のはず。それ以外に襲ってきた部隊など、居ない筈だが――――」
「恐れながら兄者。兄者の疑問はごもっとも。しかし拙者は見たのです。今とは別の時間軸で、村人たちを襲撃するためにやってきた、素戔鳴という武将を」
「……どう言うことだ?」
関羽の言っている事がいまいち理解し切れないのか、まだ眉をひそめ続けている玄徳。関羽は、そんな主に、ストレートな言葉を選ぶことにした。
「兄者。今、兄者の目の前にいる拙者は、ここより少し後の時間軸である、未来から来た存在です」
「!?」
「拙者だけではない……。ここにいるハヤブサも、そして、そこにいる尚香殿も甲斐殿も―――皆、拙者と同じように、未来から時を渡ってきた存在なのです」
「何と………!」
驚き、周りを見回す玄徳に、孫尚香が声をかけて来た。
「そうです、玄徳様……。私たちは、未来から来た存在なんです」
「かぐち……ええと、かぐやという巫女の能力で、それが可能になりました!」
「かぐや……というのは、仙女ですか?」
孔明の質問に、ハヤブサが頷く。
「そうだ。彼女は神仙界からこの世界に入ってきた巫女だ。彼女は、人一人の時間を、巻き戻すことができる能力を持っている」
「時を、巻き戻す……」
少し、難しい顔をして白扇を見つめる孔明に向かって、ハヤブサは更に説明を重ねた。
「神仙界の者たちが、この世界には彼女の能力が必要だと判断したが故に、彼女はここに送られてきたそうだ」
「―――――!」
ハヤブサのこの言葉に、孔明の切れ長の瞳が驚嘆故に見開かれる。流石は天才軍師。今の一言で、いろいろと察してくれたようだ。
「『時を遡る能力が必要』ということは………我々の未来は、暗雲に閉ざされていた――――と、言うことですか?」
「そうだ。近い将来、この世界に出現する『妖蛇』が、この世界を破滅へと追い込んで行く」
「それに対抗するために……時間を遡れる巫女の能力が必要であった……。そう言うことですか?」
孔明の言葉に、ハヤブサは「そうだ」と頷く。
「兄者。その妖蛇に対抗するために、人間達は勢力を越えて、討伐軍を結成しつつある。このハヤブサも、尚香殿も甲斐殿も、皆、討伐軍の一員なのだ」
「………なるほど、それで、ようやく納得がいきました」
関羽の言葉を受けて、孔明が顔を上げた。
「何故、尚香殿がいろいろと説明のつかないタイミングで、ここに現れたのかも………関羽殿が素戔鳴という、我々が邂逅していない筈の武将の名を知っているのも―――――皆、貴方がたが時を越え、未来から来た存在であるからだ、と、言うことですね?」
「そうだ。兄者や軍師殿にとって今、普通に流れているこの時間も、拙者にとっては過去――――つまり、一度経験した時間軸、という事でござる」
「俺たちはこの村の村人や妖魔たちを、何としても救いたい。前の時間軸では全員を救うことができなかった。だが今は――――こうして全員無事に城に逃げ込めた。今度こそ、皆を救うチャンスなんだ!」
「……………!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツも村長も妖魔の長も、それぞれに息を飲む。
「ど、どう言うことですか? ハヤブサ殿……」
「我々は前の時間軸では……死んでいた、ということですか?」
「ああ……。『全員』を助けるために、俺は既に2度、この時間軸をやり直している」
一度目は全滅。二度目は救えた人数は3割に満たなかった。
「ハヤブサ……。その話の流れで行くなら、まさか、私も………?」
信じられない、と、言った表情で問うてくるシュバルツに、ハヤブサは頷いた。
「そうだ。お前は時を越えていないだろう。それで総てを察してくれ」
「な…………!」
絶句するシュバルツを、ハヤブサは黙って見つめる。
「その戦いで……私は、『死んだ』のか……?」
「そうだ」
「…………!」
シュバルツはもう一度小声で「信じられない」と、呟く。無理も無い、と、ハヤブサは思った。『キョウジの死』という制約が外れた今、シュバルツは完全に『不死』の存在である筈なのだ。それが、覆されてしまったのだから。
「……なるほど、分かりました」
孔明の、静かな声が響く。
「わが君」
孔明の呼び掛けに、玄徳も頷いた。
「孔明。我々が救いの手を差し伸べるのに、躊躇う理由はない。出陣を、許可する」
「ありがとうございます」
孔明は一礼をすると、改めて皆の方に振り返った。
「では関羽殿、そしてハヤブサ殿……。皆を救うために、我々は『素戔鳴』という武将を倒す必要があるのですね?」
「そうだ。素戔鳴もまた、ここの村人たちと妖魔たちを狙っている。村人たちがここに逃げ込んだと知れば、素戔鳴は間違いなくこの城に兵を向けてくるだろう」
「何故、素戔鳴がこの者たちを狙うのか……その『理由』は、分かりますか?」
ハヤブサの言葉に、孔明が問い返してくる。ハヤブサはシュバルツの方をちらっと見た後、その問いに答えを返した。
「理由は簡単だ。ここの者たちは、『素戔鳴』という神の怒りを買ったんだ」
「何ですと!?」
「そんな、馬鹿な!」
全く覚えがないのだろう。村長と妖魔の長が、同時に声を上げる。それはシュバルツも同様だったようだ。
「何故だ……?」
問うてくるシュバルツに、ハヤブサは少し苦い眼差しを向ける。出来れば――――ここから先の話は、シュバルツには聞かせたくなかった。だが、この状況でそう言う訳にもいかないから、ハヤブサはあきらめたように目を閉じた。
「素戔鳴は仙界軍の将だ。だがその思考は、少し偏っている」
「と、いうと?」
シュバルツの問いにハヤブサは淡々と答える。
「人間は、取るに足らぬもの。妖魔は、徹底的に殲滅すべきものだと思っているんだ」
「―――――!」
「何だとォ!?」
ハヤブサの言葉に、その場にいた者は皆息を飲み、張飛はいきり立ちだした。
「俺の意見じゃない。素戔鳴の物だ」
噛みつかんばかりに睨みつけてくる張飛に対して、ハヤブサは少し鬱陶しそうに返す。関羽に「張飛、止めんか!」と、たしなめられて、張飛はブツブツ言いながらも後ろに下がった。
「そしてシュバルツ。あの村には一本、妙に生りの良い桃がある、と、言っただろう?」
「ああ」
シュバルツが頷くと、横から村長や妖魔の長も話に加わって来た。
「確かにあるな……。一本、とてもよく生る桃の木があった」
「あの桃の木の実は、おいしかったなぁ」
「その木になる桃は『仙桃』と言って、本来ならば、神仙界にしか生えぬ筈の物だ……。それが、この世界が作られる時のごたごたで、一本だけ村に紛れ込んでいたのだとしたら」
「…………!」
「その仙桃の持ち主が、素戔鳴であったとしたならば」
「あ…………!」
この説明だけで、シュバルツはいろいろと事情を察したのだろう。彼の顔色が、見る見るうちに、蒼白な物になって行く。
「シュバルツ殿? どうされた?」
対してまだ事情を飲み込めていないのであろう村長と妖魔の長が、心配そうにシュバルツの顔を覗き込んできた。
「あ……いや、大丈夫だ」
気を使われていると察したシュバルツが、懸命にその面に笑みを浮かべている。だが、蒼白な顔色はなかなか元には戻らなかった。
「なるほど、事情はだいたい分かりました」
そこで、それまで黙って話を聞いていた孔明が口を開いた。
「村長殿と妖魔の長殿は、とりあえず皆の所に戻り、人心を落ちつけてあげてください。この戦いを終わらせてから、今後の方針を改めて話し合いましょう。こちらの縻竺(びじく)と関平を、貴方がたにお付けします。何か不具合や、足りない物があれば、遠慮なくお申し付けください」
孔明の言葉に従って、関羽の息子である関平と、文官一人が前に出て、軽く頭を下げる。
「や、やはり……戦いは、避けられぬのじゃろうか?」
「もしや、我らのせいで――――」
「大丈夫ですよ」
心配そうに聞いてくる長たちに、孔明はにっこり笑顔を見せて答えた。
「戦いに関しては、貴方がたは何も心配する事はありません。とにかく今宵はゆっくり体を休めてください。もしかしたら、戦勝の宴で少し周りが騒がしくなるかもしれませんが――――」
「へっ?」
この孔明の物言いに、さすがに長たちもあんぐりと口を開けるしか無かった。まるで戦う前から100%こちらが勝つことが決まっている様な物言い。普通は、あり得ない。
「うちの軍師殿がこう言っているんだ。絶対、大丈夫だからな!」
張飛が笑顔で声をかけてくれれば、関平も苦笑しながら長達に近寄ってきた。
「さあ、行きましょうか」
朴訥な若者の案内に従って、長達はキツネにつままれたような顔をしながら部屋から出て行った。
「シュバルツ。お前は出て行かないのか?」
長達が出て行った後、ハヤブサはシュバルツにそう声をかける。しかしシュバルツから「えっ? 何故だ?」と、当然のごとく疑問形で返された。ハヤブサは口の中で小さく「チッ!」と、舌打ちをする。彼としては出来れば、シュバルツは戦いからは外れて欲しいと願っていた。
「では、改めて軍議を再開させましょう」
長達が出て行ったのを見送ってから、孔明は改めて口を開いた。
「まず……ハヤブサ殿」
「何だ?」
「貴方は『未来』から来たと言った……。と、言うことは、素戔鳴がどう動いてくるのか、ある程度は読める、ということですね?」
「ああ」
ハヤブサが頷くのを確認してから、孔明は質問を続けた。
「では……素戔鳴の襲撃がいつあるのか、分かりますか?」
「民達と共にこの城に逃げ込めたのは今回が初めてだ……。だから、この城に何時素戔鳴軍が押し寄せてくるかは分からん。だが、あの村にいつ襲撃に来るかは分かっている」
「それは……何時ですか?」
「今夜」
「……………!」
ハヤブサの言葉に、皆が息をのむ。
「村の皆が寝静まった夜半過ぎに、素戔鳴軍は襲ってきた。前の時間軸では、それが百々目鬼軍の襲撃と重なってしまったがために、大半の村人たちが死んでしまったんだ……」
そう言いながらハヤブサは、拳を握りしめていた。
前の時間軸も、その前の時間軸も――――百々目鬼軍と素戔鳴軍に同時に襲われたこの村は、敵も味方も分からない状態になって、大混乱に陥った。
この時間軸で、百々目鬼と素戔鳴の襲撃が別々な物になってくれて本当に良かったとハヤブサは思う。もしも同時に襲われていたら、素戔鳴軍に粉砕された百々目鬼軍の妖魔たちが、こちらに助けを求めて来るが故に、戦場はまた混乱状態になっていただろう。シュバルツみたいにお人好しな奴が、命乞いをしてくる妖魔たちを放っておく筈がないからだ。皆を助けようとして――――余計な傷を負ってしまうか、最悪『死』にまで追い込まれるに決まっている。
「なるほど」
白扇を揺らめかせながら、天才軍師の質問はなおも続く。
「では、ハヤブサ殿……。『素戔鳴』という武将の人物像を、分かる範囲で教えてください」
その言葉にハヤブサは軽く頷くと、腕を組んで答え始めた。
「素戔鳴は、仙界軍の将だ。そして、その『武』は神懸かって強い」
「『強い』とは……どのくらいだ?」
「強い」という単語に反応して、張飛が前のめりの姿勢になって聞いてくる。
「お前たちに分かりやすく伏犠の言葉で例えて言うなら……こちらの世界で言うところの『呂布』に匹敵するらしい。……俺は直接『呂布』という武将とは戦ったことはないから、その例えがふさわしいかどうかも分からんがな」
「呂布……!」
その言葉に、武将たちは皆息をのむ。だが、関羽と張飛と趙雲の瞳には、怖じ気るどころか挑戦的な光が宿っているのを、ハヤブサは見逃さなかった。流石は五虎将。皆がそれぞれ己の武に、かなりの自信を持っている様が見て取れた。
「素戔鳴は『神』と言うだけあって、雨と風と雷を――――その手で自在に操る。多少の攻撃を受けても怯まない。そして、素戔鳴の雷には、気絶効果を伴う物もある様だ」
「なるほど……」
「手ごわそうですね……」
「ああ! 早く手合わせをしてみてぇなぁ!」
張飛のその言葉が、関羽や趙雲の気持ちを代弁しているのだろう。二人ともがうんうん、と頷いていた。
「素戔鳴の性格は、どのような感じなのでしょうか」
「性格か………」
孔明の質問に、ハヤブサは暫し考え込む。
「剣を合わせた印象でしか語れないが、構わないか?」
「充分です」
確認するハヤブサに、孔明は頷き返す。それを見て、ハヤブサは再び口を開いた。
「素戔鳴は『神』であるが故に、その剣は強く、傲岸だ。だが、太刀筋に迷いはない。綺麗で、真っ直ぐな剣だ」
「傲岸で、真っ直ぐ……」
「そして、とても部下を思いやる一面も持っていた。兵士たちも、素戔鳴をとても慕っていたな」
「なるほど、よく分かりました」
「……? もう、良いのか?」
意外にも早く話を切り上げられた事に驚いて、ハヤブサは少し確認してしまう。それに対して孔明は、にこりと微笑んだ。彼にとって『情報』は、もうその程度で充分なようだった。
「作戦は決まりました。素戔鳴は今宵、その村に現れると言うのならば――――そこで雌雄を決しましょう」
「おっ! そうこなくっちゃ!!」
孔明の一言で、場の空気にピン! と、心地よい緊張が走る。張飛が待ってましたと言わんばかりに快哉を上げた。
「して、軍師殿はいかなる作戦で望まれるおつもりか?」
「罠を仕掛けましょう」
関羽の言葉に孔明はにこりと笑って答える。
「『傲岸で真っ直ぐな太刀筋』を持つ、ということは、存外根が単純な方なのかもしれません。挑発して誘い込む作戦が、有効でしょう」
(なるほどな……)
孔明の言葉にハヤブサは納得する。確かに、前の戦いのときも素戔鳴は、彼を挑発した自分を執拗に追いかけて来ていた。この『挑発』という手段は、素戔鳴には非常に有効に効くのかもしれない。
「少々お待ちください。この周辺の地形図を取ってきます」
孔明がそう言って場を外そうとした時、ハヤブサが待ったをかけるように声を上げた。
「作戦に入る前に――――申し訳ないが、一つ、俺の願いを聞いてくれないだろうか?」
「はい。何でしょう」
場を外そうとした孔明が、立ち止まってハヤブサの方に向き直る。
「実は次の戦いは、こいつを外して作戦を立てて欲しい」
そう言ってハヤブサがシュバルツの方を指さすから――――一同は驚いてしまう。玄徳にとってもこれは意外だった。ハヤブサに指さされた青年は、かなり有能な将であるように見受けられたのに。
「それは……何故ですか?」
それは孔明にとっても同じだったのだろう。ハヤブサに疑問を投げかけてくる。
「すまない。こちらにもいろいろと事情があるんだ」
「ハヤブサ!? 何故だ!!」
シュバルツにとってもそれは心外であったのだろう。ハヤブサに突っかかる様に問い返していた。
「シュバルツ――――」
ハヤブサは一つ小さく息を吐くと、いきなりシュバルツを押してきた。
「ハヤブサ!? ………あっ!」
そのままハヤブサに勢い良く押され続け、シュバルツは部屋の壁際まで追い込まれてしまう。そのままドンッ! と、壁に身体を押しつけられ、その首元に鞘のままの龍剣を押し当てられる。
そのまま殺気だった眼差しでハヤブサに睨みつけられるから――――シュバルツは激しく戸惑ってしまう。
「ハ、ハヤブサ……?」
「いいか、シュバルツ……! 今度の戦い、お前は絶対に出てくるな……!」
「だ、だから何故――――ウッ!」
グッと更に壁に押し付けられ、シュバルツは低く呻く。
「お前を、死なせたくないからだ……!」
「―――――!?」
ギョッと目を見開くシュバルツに、ハヤブサは更に言葉を続けた。
「前の時間軸で、お前は死んだと言っただろう! あれは、素戔鳴の仕業なんだ!」
「な………!」
「素戔鳴に限らず、神仙界の者は皆――――DG細胞を滅する能力を持っている。つまりお前は、仙界軍の者と戦ったら、その身に矢が掠めただけで死ぬんだぞ!?」
「…………!」
「だから絶対に、次の戦いには出てくるな……! いいな?」
「し、しかし………!」
「…………ッ!」
ハヤブサを茫然と見つめ返しながら、まだ何事かを反論しようとするシュバルツを、ハヤブサはギリ、と睨みつける。
どうして
どうして分からないんだ、こいつは
俺はお前を死なせたくないから、何度も時間をやり直して、こうしてここにいるのに――――!
龍剣を押し当てる手に、知らず更に力が入る。
「う……う……ッ!」
シュバルツが苦しそうに呻くが、ハヤブサは自分で自分が止められなかった。
いくらこちらが止めようとしても、『死』へと転がって行きそうになるシュバルツ。一体、どうすれば良いと言うのだろう。
このままここでこいつの息の根を止めれば、その運命も変えられるのだろうか――――
「ハ、ハヤブサさん……!」
「…………!」
いつの間にか甲斐姫がハヤブサのすぐ傍まで来て、泣きそうな顔をしてこちらを見ていたから、ハヤブサははっと我に返る。シュバルツを絞め殺さんばかりに押し当てていた龍剣を、スッと退けた。
「――――! ゴホッ!!」
いきなり肺に流れ込んできた大量の空気に、シュバルツは思わず噎せる。
ハヤブサはしばらくそんなシュバルツを無言で見つめていたが、そのまま黙って踵を返すと、すたすたと歩きだした。
(これで、俺を守るために戦いに出よう、などとは思わないだろう)
歩きながらハヤブサは、そんな事を考えていた。
これをしたことでシュバルツに嫌われようが恨まれようが――――一向に構いはしなかった。
要は、シュバルツが生きていてくれさえすればいいのだ。
もう二度と、その身体には触れられずとも、その優しさが自分に向けられなくなろうとも。
生きて、キョウジと二人、幸せそうに笑っていてくれさえすれば、自分はどう思われようともどうなろうとも――――それでよかった。
お前が守るべき民は、もう城内にいる。
もうお前が、戦う理由はない筈だ。
だから、絶対に出てくるな、シュバルツ。
素戔鳴の前には出るな――――!
「もう、よろしいのですか?」
シュバルツから離れてこちらに戻ってきたハヤブサに、孔明が声をかける。
「ああ。話は済んだ」
そう言って軍議に加わるハヤブサの後ろ姿を、シュバルツはただ黙って見つめていた。
「シュバルツさん……大丈夫?」
声をかけられた方にシュバルツが振り向くと、甲斐姫が今にも泣き出しそうな顔をして、こちらを見上げている。
「ああ。大丈夫だよ」
シュバルツは、フッと優しい笑顔を向けて、それに答えた。
「それにしてもハヤブサさん……何もあんなに怒ったふうに言わなくてもいいのに」
そう言う孫尚香に、甲斐姫が少しうつむきがちに答える。
「でも私……ハヤブサさんの気持ちも、分かるな……」
「えっ?」
驚く孫尚香の声を聞きながら、甲斐姫はシュバルツの方に振り向いて答える。
「だって……ハヤブサさん、もう何度も泣いているんですもの。シュバルツさん、貴方を喪って――――」
「…………!」
「シュバルツさん……私だってもう、あんな悲劇は見たくない……」
驚き、息をのむシュバルツを、甲斐姫は必死の眼差しで見つめる。
「あんな……救いのない悲劇は、もう沢山なの……!」
「か、甲斐……! 泣かないで……!」
甲斐姫の瞳から涙が零れ落ちそうになっているのを見た孫尚香が、慌ててなだめようとする。甲斐姫は涙を振り払うように頭を振ると、シュバルツに改めて声をかけた。
「だからシュバルツさん……! もう戦には出ないで、私たちと一緒に村の皆の手伝いに行きましょうよ!」
そう言う甲斐姫を、シュバルツは無言でじっと見つめる。
「そうね、私もそうした方がいいと思うわ」
その横に孫尚香も並んで、同じようにシュバルツを見つめて来た。
「……………」
シュバルツはそんな二人を無言で推し量る様に見つめていたが、やがてその面にフッと笑みを浮かべた。
「そうか……。そうだな……」
「……………!」
シュバルツが笑顔でそう言ってくれたことで、女性二人の表情にも笑顔が戻る。
「じゃあシュバルツさん! 早く行きましょうよ!」
甲斐姫が嬉しそうにシュバルツの手を取って引っ張って行こうとする。だがシュバルツは、それには乗らず踏みとどまった。
「いや……悪いがもう少し、ここに居させてくれ」
「シュバルツさん? でも……」
「もうここには用はない筈じゃ……」
不思議そうに見つめてくる甲斐姫と孫尚香に、シュバルツは笑顔を向ける。
「悪いが、もう少しの間だけ……な……」
「シュバルツさん……」
その後も女性二人はシュバルツを部屋の外に連れ出そうとするのだが、シュバルツはそこに留まり続けた。結局彼は、軍議が終わるまで、その部屋に留まり続けたのだった。
夜半。
闇に紛れて村に向かって静かに行軍する、一つの軍団があった。
素戔鳴軍である。
今から襲うのはごく普通の村であるが――――そこの村人たちは大罪を犯した。我が物であった筈の『仙桃』を私物化し、あろうことか妖魔に触れさせ、それを与えた。何と、汚らわしき事か―――――故に、裁かれなければならぬ。
妖魔がこの世に跋扈するべきではないし、人の子と妖魔が、交わりを持つような事など決してあってはならないのだ。妖魔は総て――――殲滅せねばらならぬ対象であるのだから。
素戔鳴が何故襲撃の時間を『夜』に選んだのか。その理由は簡単だった。
村人たちが寝ている間に全滅させる。闇の中に――――総てを、葬り去るためだった。
数刻ほどして、放った斥候が返ってくる。
「申し上げます!」
斥候は素戔鳴の前で膝をつき畏まると、おもむろに口を開いた。
「村の中を見て参りましたが、住人の姿は既にありません! もぬけの殻です!!」
「何だとォ!?」
素戔鳴は驚いて大声を上げる。
「真実(まこと)か!? 嘘偽りは申しておらぬだろうな――――!」
問いただす素戔鳴に、斥候は畏まった。
「決して偽りは申してはおりませぬ! 隅々まで見ましたが住人を見つけることは適いませんでした!」
「…………!」
素戔鳴は顎に手を当てて考え込む。
(どう言うことだ? 吾は事前に村を襲うような情報を外に漏らしなどしなかった。なのに何故……村人たちは姿を消した?)
「村が既に何者かに襲われたような形跡はあったか?」
斥候にそう問いただしてみる。妖魔と交流を持っていた村。野蛮な妖魔どもの事だ。こちらが襲うより先に村人たちを襲うことも、充分にあり得ると思った。
「いえ、全く……! 村に争ったような跡はありませんでした」
「ふむ………」
しばらくその斥候の前で考え込むようにしていた素戔鳴であったが、やがてその顔を上げた。ここでこのまま考え込んでいても、埒が明かないと思ったのだろう。
「とにかく村に案内いたせ。吾自ら検分してやろう」
「はっ!」
斥候は頭を下げると立ち上がり、踵を返して素戔鳴を導く様に歩き出した。素戔鳴も素戔鳴軍も、その後に続いた。
それから村まで数刻とかからずに着いた。
「……………」
確かに、人の気配が完全に断たれてしまっている村。ひゅう、と吹く風に乗って、空の桶がカラカラと転がって行く。
(妙だな……。本当に、村人の姿が見えぬ――――)
そう思いながら歩を進める素戔鳴の視界に、ある物が飛び込んできた。
妙にうず高く積み上げられたそれを見た時、最初素戔鳴はそこに異形の者が居るのかと思った。だがすぐに、そうではないと気づく。
それは、村人たちが土地神のために設えられた祭壇と、供物の数々だった。
所狭しと祭壇に並べられた野菜や酒、料理の数々。
その周りに、綺麗に供えられた花々。
これらを見ているだけで、この村人がどれだけ土地神を大切に祀っていたかが分かる。
(………………)
素戔鳴とて『神』の端くれ。これらの心のこもった供物の数々に、何かを思わないでもなかった。
だがしかし――――
素戔鳴は、一つ大きく息を吐いて、再び顔を上げる。
人の子とは誠に度し難い。
何故、神をここまで見事に崇められるのに、同じように妖魔も受け入れてしまうのか。
善にも悪にもふらふらと行き来する様は、まるで節操のない悪女の如しだ。
何故こうも弱く、不安定な存在がこの世にいるのか――――
そんな事を思い巡らせている素戔鳴の耳に、いきなり
「阿呆か――――――ッ!!」
と、大音量の怒鳴り声が飛び込んできたから、彼は思わずひっくり返りそうになってしまっていた。
時は今から数刻ほど遡る。
闇の中、足音も立てずに軽快に走る一つの黒い影があった。
リュウ・ハヤブサその人である。
彼は、素戔鳴を罠の地点まで誘い込む役を引き受けていた。その為に、村へと続くこの夜道を、1人駆けていたのであった。
「……………」
辿り着いた村は、当たり前の話だが、もぬけの殻状態になっていた。ただ意外だったのは、村が妖魔たちの手によっても荒らされていない事だった。敗走した百々目鬼軍はどうやらこの村に立ち寄ることなく、自分の拠点へと引き上げて行ったらしかった。
(村が無事なのを皆が知れば、喜ぶだろうな……。しかし、また元の場所に帰って来られるのだろうか? 同じような事が再々起きるようなら、この場所に住むのは不可能になるだろし……)
どちらにしろ、ここを戦場にする事は自分も避けねばならない、と、ハヤブサは思いを巡らす。
と、その時。
「―――――!?」
僅かだが、また何かの気配を感じて、ハヤブサは後ろを振り返る。だが、やはり誰もいない。
(気のせいか……? しかし……)
妙だ。
この気配は、森の中を独り走っている時から感じていた。
誰かが
何かが………
自分を『尾(つ)けている』様な―――――
(いや、まさか――――)
そんな筈はない、と、ハヤブサは懸命に、自分の考えを打ち消す。
あいつが来る筈はない。
軍議の席で、きっぱりと斬りつけてやったんだ。
『出てくるな』と強く忠告した。
それを押してまで出て来ているのだとしたら、それはよほどの『馬鹿』がやることだ。
あいつがそんな―――――
そんな………
「…………!」
しかし確かに、何かが『いる』
微かだが―――――何かが、こちらを伺っているような気配。
(……………)
ハヤブサは、小さくふっと息を吐く。
これは、確認、しなければ。
不意に小さく身を屈め、胸の前で印を結びながら、何事かを小さく唱え出す、龍の忍者。
(……………?)
その様子を、ハヤブサの読み通り、木の上から眺めていた者が居た。『彼』は、龍の忍者の呪文の詠唱が気になり、つい、聞き耳を立ててしまう。
「………………………」
そして、彼の優れた聴力が、龍の忍者の文言を捉えた時、その張り巡らされた『罠』に気づいてしまう。
「怨婆沙羅転達磨怨婆沙羅転達磨怨婆沙羅転達磨怨婆沙羅転達磨………」
(しまった――――! これを聞いては駄目だ! 離れなければ――――!)
気づいた時にはもう遅かった。彼が身を翻そうとするよりも早く、龍の忍者の必殺の呪文が、炸裂してしまう。
「達磨惨牙(ダルマサンガ)………虎崙焚(コロンダ)―――――――ッ!!」
べシャッ!! と、木の上から落ちてくる、追尾者。それを見た龍の忍者は、勝ち誇ったように笑った。
「フ……。キョウジや子供たちから聞いていたこの呪文が、これほど貴様に有効だとはな……!」
「ひ、卑怯だぞ!! それを聞いたら私が出てこざるを得なくなるのを知っていて――――!」
ハヤブサの言葉にシュバルツがガバッと、跳ね起きて答える。
「何が卑怯だ!! て言うか何でこの呪文がそんなにも有効なんだ!? 貴様……! 忍者のくせに乗りが良すぎるぞ!!」
「仕方がないじゃないか!! 子供たちから呼ばれたら、出て行くのが礼儀だ!!」
「そんな阿呆な礼儀があるか!! 忍者なら少しは忍べ!!」
「お前にだけは言われたくはない!! お前だって忍んでいないくせに――――!!」
およそ忍んでいない忍者二人の口論が、辺りに響き渡っていた。
「だいたいだな……シュバルツ……」
ハヤブサはぴくぴくと引きつるこめかみを押さえながら、その肺に思いっきり息を吸い込んだ。
「阿呆か―――――――ッ!!」
ハヤブサの渾身の叫びに、耳が思わずキ―――ン、となってしまうシュバルツ。そこにたたみかけるように、ハヤブサの怒鳴り声が降ってきた。
「何故来た!? 何故、こんな所に出て来たんだ!! シュバルツ!!」
「な、何故って……! それは――――!」
「俺は言ったよな!? お前に忠告したよな!? ここに出てくればお前は死ぬと――――!! それなのに何で……!! お前は、俺の話を聞いてなかったのか!?」
「いや……聞いてたけど……」
「聞いていたのなら、何故―――――!!」
「な、何だ!? 貴様らは……!」
「――――!」
忍者同士の言い争いに、突如として割って入ってきたその声に、二人ともがはっと振り返る。すると、わなわなと身を震わせながら、こちらを睨みつけている素戔鳴の姿が、そこにあった。
「………ッ!」
バッと、ハヤブサは素早く龍剣を抜刀し、シュバルツを庇うように構える。それに対してシュバルツは剣も抜かず、正対したままだった。
「汝(なれ)らに問う……。ここの村人を逃がしたのは、汝らの仕業か?」
その問いに、ハヤブサは沈黙を返そうとする。だが、彼の後ろから、反論する声が返ってきた。
「――――そうだ、と、言ったら?」
「…………!」
その言葉に素戔鳴の眉が釣り上がり、ハヤブサの顔色が変わる。
「お……おい、シュバルツ!」
「隠すことないだろう? 事実なんだし」
「馬鹿!! お前が素戔鳴の前で目立つような事をしたら――――!」
「……何だ? 貴様は――――」
案の定、シュバルツを目にとめてしまった素戔鳴が、怒気も顕わにこちらを睨みつけている。
(…………!)
ハヤブサは天を仰ぎたくなった。
どうして
どうしてこのヒトは
いちいち自分が傷つく言葉を、聞きに来るのか――――!
「何と邪悪な……! 何故、汝の様な歪な物が、ここにいる!?」
「――――!」
案の定、その言葉を聞いて息をのむシュバルツ。そこに素戔鳴が更にたたみかけてきた。
「何と言う村だ……! 妖魔に続いて、汝の様な物まで引き寄せていたとは――――!」
流石にこの素戔鳴の言葉には、ハヤブサもムッとする。シュバルツのみならず、村人たちの事まで悪く言われたのだから。
「汝の存在は許されぬ! 村人たちも同様だ!! 汝ら……村人たちを何処へ、やった?」
「―――答える義理は、ないな」
「――――!?」
自分が口を開くよりも早く、シュバルツが酷く挑発的な口をきくから、ハヤブサはぎょっと、愛おしいヒトの方を見てしまう。すると、シュバルツは笑みを浮かべながら素戔鳴を見ている。だが、それは爽やかな笑みとは言い難い笑みで、その瞳は笑っていない。どちらかと言えば、完全に据わっている。
「どうしても聞きたくば、力づくで来い!!」
しかも、完全に挑発モードになってしまっている。
「シュ、シュバルツ?」
思わずハヤブサはシュバルツに声をかけてしまう。
「どうした? ハヤブサ」
あくまでもにこやかに返事をしてくるから、ハヤブサは少し、落ち着かない気持ちになった。
「お、お前……どうした? 怒っているのか?」
先程から割と「らしくない」言動をしているシュバルツ。だからハヤブサはそう問うてみたのだが、それに対して、シュバルツはフフフと笑って答える。
「あいつを誘い込むのが、私たちの『役目』だろう?」
「――――! それはそうだが……」
「なら、問題ないだろう。それに、ほら――――」
「貴様ら……余程命が要らんと見ゆるな……!」
「…………!」
シュバルツが指さした先で、素戔鳴が完全にブチ切れた眼差しでこちらを見ている。
「私が出て行って『挑発』した方が、効果があると思ったが――――読み通りだったな」
「よ、読み通りって……! お前、まさか――――!」
軍議の輪から外されたのに、最後までその部屋に残り続けたシュバルツ。それはつまり、このためだったのだ。この戦いの作戦を、把握するために――――!
呆れかえるハヤブサに対してシュバルツは『にこり』と、笑っていない瞳を向ける。
「ほらほらハヤブサ、来るぞ」
「そこを動くな!! 小賢しい者どもめ……! まとめて始末してくれる!!」
そう言って素戔鳴が、天叢雲を振り上げながら、ザンッ!! と、踏み込んでくる。
「『待て』と言われて、大人しく待つ奴などいない!!」
そう言い放ったシュバルツは、さっと踵を返すと、脱兎のごとく走り始める。この行動にはハヤブサ以下全員が面食らってしまった。
「おのれッ!! 逃がすかッ!!」
「お、おい! シュバルツ!!」
一呼吸置いてから、その場にいた全員がシュバルツを追って走り出した。
こうして、対素戔鳴の戦いが、変な形で幕を開けたのだった。
「おいっ!! シュバルツ!!」
村から抜けて森に入ったところで、ハヤブサはシュバルツにすぐ追いついた。正確には――――シュバルツがハヤブサを待っていたのだが。
「シュバルツ!! お前……! 何を考えている!?」
ハヤブサはシュバルツの肩を捕まえて問いただした。
「何って……この作戦の成功を」
「いや――――俺が聞きたいのはそうじゃなくて!!」
「いたぞ!!」
仙界軍の兵士の声が響くと同時に、大量の矢が飛んでくる。
「―――――ッ!」
ハヤブサは龍剣を振るってその矢を叩き落とし、シュバルツがその後ろでひょいひょいと矢を避けた。
「シュバルツ!! 分かっているのか!?」
矢を叩き落としながらハヤブサが叫んだ。
「この矢が掠めただけで、お前は死ぬんだぞ!?」
「……そう、らしいな」
ひょい、ひょい、と、矢を避けながら、シュバルツは懐から短刀を取り出す。そして何を思ったのか――――いきなり自分の左手を、自身の腕から斬り落とした。
「――――!?」
ギョッと、目を剝くハヤブサを尻目に、シュバルツは素戔鳴に向かって切り落とした左手を、ポーン、と、投げつける。
「刎(ふん)ッ!!」
素戔鳴は目の前に飛んできた『異物』に対して容赦なく天叢雲を一閃させた。シュバルツの左手は、あっという間に粉みじんにされて、跡形も無く消し飛んでしまう。
「ああなるほど。確かに、これは私が戦っちゃいけない案件の人だ」
そうのんきに言っているシュバルツの左腕から、また左手がズボッと音を立てて『生えて』来ていた。
「なッ……! か……ッ! シュバルツ……ッ! おま……!」
「ほらほら、ハヤブサ。よそ見をしている暇はあるのか?」
「―――――ッ!」
振り向いたハヤブサに襲いかかってくる、大量の矢。
「死ねい!!」
更にこちらに向かって牙を剝く、素戔鳴からの雷撃。
「シュバルツ!!」
龍の忍者は咄嗟に、シュバルツを抱きかかえて跳んだ。雷撃をかわす。だが、矢をすべて避け切ることは出来なかった。一つの矢がその身に刺さってしまう。
「ぐっ!!」
「ハヤブサ!!」
ザンッ!! と、音を立てて茂みに飛び込む。そのまま忍者たちは、身を低くしてそこから走りだす。
「何処へ行った!?」
「探せ!!」
仙界軍の兵士たちの怒声が背後に聞こえる。
忍者たちは一時的に、仙界軍の猛攻から逃れることに成功していた。
周囲の安全を確認してから、ハヤブサは身に刺さった矢を抜く。抜く時の痛みで、ハヤブサは低く呻いた。
「クッ……!」
「ハヤブサ……。大丈夫か?」
「シュバルツ……! お前なぁ……!」
とにかくシュバルツに対して言いたい事が沢山あった。だからハヤブサは、怒鳴りつけてやろうと口を開ける。だが、そうやって口を開けた瞬間、シュバルツに何かを口にガボッ! と、押し込まれて、ハヤブサは口がきけなくなってしまう。
「……………」
押し込まれた物は、どうやら食べ物の様だった。口の中いっぱいに、甘い香りが広がる。龍の忍者はシュバルツを怒鳴りつけるために、口の中のそれを平らげることにした。シャクシャクと音を立てて、それがハヤブサの体内に吸収されていく。
「旨いか?」
聞いてくるシュバルツに、ハヤブサはとりあえず素直に頷いた。
「いや、旨いが――――そうじゃなくて!!」
「ああ、やっぱり――――傷が治って来ているぞ?」
「…………!」
そう――――食べさせられたのは『仙桃』であるが故に、ハヤブサの傷を癒したのだ。
「すごい効き目だな……。持って来て良かった。薬効成分があるとは知っていたが、自分の体ではその効果が分からなくてな。私は『人間』ではないし、自分の身体はすぐ治ってしまう代物だし――――」
「お、お前……まさか、それは……例の――――」
感心したようにハヤブサの傷を見つめているシュバルツに、ハヤブサは己が身体の震えを止める事が出来ない。
「ああ。村の『仙桃』だぞ? よく分かったな」
「分からいでか!!」
しれっと返すシュバルツに、ハヤブサは思わず怒鳴りつけてしまっていた。
「お前!! この『仙桃』は、この騒動の最大の元凶だぞ!! そんな物をお前が素戔鳴の前で持ち出したりしたら――――!!」
「最大級に『挑発』出来そうだな……。村人に怪我人が出たらいけないと思って、持って来たのだが――――」
「……吾が、どうしたって?」
「―――――!!」
その声に忍者二人が驚いて振り向くと、彼らの視線の先に、バチバチと帯電している素戔鳴の姿が飛び込んでくる。素戔鳴の怒りが凄まじすぎて、それが表に放電現象として現れてしまっているのだ。
「…………!」
ピク、と、顔をひきつらせるしかないハヤブサの横で、シュバルツが尚も懐から、巨大な袋を取り出した。
「まだ沢山あるぞ? ハヤブサ。何せ村人たちにどれだけ怪我人が出るか分からなかったから、ストックだけは常にたくさん用意しておくようにしておいたんだ」
そう言って、シュバルツは「サンタの袋か!!」と、突っ込みを入れたくなるような袋を、ハヤブサと素戔鳴の目の前にドン! と、置く。中には文字通り『大量』の仙桃があったから――――
「な………! な………! な………!」
素戔鳴の頬がぴくぴく、と、震え、龍の忍者は言うべき言葉を失ってしまう。
お前今までどうやってそれを持っていたんだ! と、突っ込みを入れる暇すらなく。
「死ね――――――い!!」
裂帛の叫びと共に放たれる素戔鳴の雷撃から、また忍者二人は必死になって逃げなければならなくなった。
「おのれ!! 逃げるな!! 待てい!!」
忍者二人を追いかけながら、素戔鳴は雷撃を放ち続ける。そしてその背後からも、矢が飛んでくる。ハヤブサは時折振り返りながら矢を叩き落とし、シュバルツはその背後でひょい、ひょい、と、矢を避けていた。相変わらず彼は、抜刀すらしていない。
「シュバルツ!!」
矢と叩き落としながらハヤブサが叫ぶ。
「ん? どうした? ハヤブサ」
「どうしたじゃない!!」
もの凄く危機的状況の筈なのに、ひょうひょうとしているシュバルツに、ハヤブサは思わず叫んでしまう。
「お前!! 今がどう言う状況か、分かっているのか!? 少しでも攻撃が当たれば」
「死ぬんだろう? よく分かっているよ」
「――――!」
ハヤブサの言葉が終わる前ににこやかに返事をしてきたシュバルツ。その笑顔に、何故か異様な物を感じてハヤブサは言葉を失ってしまった。そこにたたみかけるように――――シュバルツがいきなりハヤブサに向かって距離を詰めてくる。
「シュ、シュバルツ?」
「……………」
ハヤブサの呼び掛けにもすぐには応えず、笑顔のままひょいひょいと矢を避け続けているシュバルツ。しかしその笑顔か何故か怖くて、ハヤブサは思わずシュバルツに問いかけてしまう。
「ど、どうした? お前……様子が変だぞ?」
「そうか?」
しれっと返されて、息をのんでしまうハヤブサ。だがそれで、却って確信した。シュバルツは、やはり――――
「お、おまえもしかして……怒ってる?」
恐る恐る問いかけるハヤブサに、シュバルツは『にこり』と笑って答えた。
「ああ、怒っているよ」
「―――――!」
あっさり認めたシュバルツに、ハヤブサは思わず息を呑んでしまう。そんなハヤブサに対してシュバルツは恐ろしい程爽やかに微笑みかけて来た。
「……私も随分見くびられたものだな、ハヤブサ」
その穏やかな声音と笑みに、ハヤブサは背筋に寒気が走るのを感じた。
何故だ。
後ろで雷撃を飛ばしながら怒鳴りまくっている素戔鳴よりも
今――――目の前で微笑んでいるシュバルツの方が、はるかに恐ろしく感じる。
「私とて、一応武人の端くれだ。自分の身一つぐらい、何とでも守れる」
そう言いながらシュバルツは、素戔鳴と仙界兵の攻撃を避け続けている。忍者二人は近距離で会話をしながら避ける動作をし続けているが故に、その動きは完全にシンクロしていた。
「それなのにお前ときたら、私が戦いに出たらすぐに死ぬようなことを言う……。つまり私の力量は、お前の信用を得るには足りていない、と、言うことでいいのか?」
「ご………!」
誤解だ―――――! と、ハヤブサは叫びたかったが、喉に声が引っ掛かってしまって、うまく言葉を発する事が出来なかった。今ハヤブサは、完全に目の前のシュバルツに気圧されてしまっていた。
「心配するな! ハヤブサ! ろくに戦うことも出来ない私は防御に専念するさ! お前の戦いの邪魔をするようなことはしない!」
そう言って爽やかに微笑むシュバルツが、完全に笑っていない目をこちらに向けてくる。彼から殺気が漂っているように感じられるのも、最早気のせいではないだろう。龍の忍者は悟らざるを得なかった。自分は今――――最も怒らせてはいけないヒトを、怒らせてしまったのだと。
「それに、いざとなったら――――」
シュバルツの眼光が一瞬鋭く光ったかと思うと、いきなりハヤブサの身体を鷲掴む。
「へっ?」
間抜けな声を上げた龍の忍者の身体に、トスッ! と、一本の矢が刺さった。
「お前の身体を盾にしてでも私は逃げるから、大丈夫だ!」
「痛い!!」
叫びながら矢を抜くハヤブサの口に、またもガボッ! と、仙桃が押し込まれた。シャクシャクとそれを食べるハヤブサの身体の傷が、見る見るうちに治って行く。
「良かった……。また、治ったな!」
それを見て、にこやかに笑うシュバルツ。
「おのれまたしても!! それは吾の仙桃だと言うに――――!!」
背後の素戔鳴から、また無数の雷撃が放たれる。だが、完全に頭に血が上っているせいか、こちらに肉薄してくる雷撃は、それほど多くはなかった。狙いが定まっていないのだろう。
「……シュバルツ……! ちょ……!」
「仙桃はまだまだあるぞ? ハヤブサ! だから安心して――――戦ってくれ!」
「~~~~~~~~ッ!」
(こ、殺される……!)
後ろの素戔鳴にじゃない。目の前のシュバルツにだ。龍の忍者は今――――確かに恐怖を感じていた。知らなかった。こんなにも、穏やかな殺気が恐ろしいとは。
一体どうすればよかったんだ。
俺はただ、シュバルツに戦いに出て来て欲しくなかっただけだ。
その為に軍議から締め出したのが、まさかこんな形になって跳ね返ってくるだなんて。
あんな脅しみたいな忠告だけじゃなくて、いっそのこと、シュバルツをどこかに閉じ込めてしまえば良かったのか――――?
(えっ? シュバルツを閉じ込める?)
ハヤブサの脳裏に、不意にキョウジの姿がフラッシュバックしてくる。そのキョウジにハヤブサは問うていた。シュバルツを閉じ込めるには、一体どうすればいいのかと。
キョウジはとても爽やかに笑って答えてくれた。
「あははは……。無理無理。無理に決まってるよ」
「えっ? 何故だ?」
きょとんとするハヤブサに、キョウジは苦笑しながら答える。
「だってあいつ……縄抜けしちゃうし、壁抜けしちゃうし、姿消せちゃうしね」
「――――――!」
「それにいざとなったら、腕一本脚一本、犠牲にしてでも抜け出してくるよ。治せるって自分で分かっちゃっているから……。そんな惨い事、シュバルツにやらせたい?」
ブンブン! と、勢いよく首を振るハヤブサに、キョウジも声を立てて笑った。
「だから、シュバルツを閉じ込める、なんて、土台無理な話なんだよ」
「いや、しかし――――! それでも俺の仕事を勝手に覗きに来たりしている事があるから危ないんだ!! せめて、そう言うことは止めさせないと……! 俺の仕事は、きな臭い物が多いから――――!」
万が一の間違いがあったら困る、とぼやくハヤブサに、キョウジはにこりと微笑んだ。
「だからと言って、シュバルツの自由意思を縛る権利なんて、私には無いよ」
「それはそうかもしれないが……! いざという時、シュバルツを押さえる手段だって無いと、お前だって困るだろう!?」
「いや? 全然?」
「…………!」
ズバッとキョウジに切り返されて、ハヤブサは言葉を失う。
「だからシュバルツが『こう!』って決めた事を覆そうとするなんて労力の無駄だよ? ハヤブサ。そんなめんどくさい事、私だってしたくないから」
「めんど……!」
「だからいろいろとあきらめて――――頑張ってね。ハヤブサ♪」
そう言ってキョウジが爽やかに「あははは………」と笑って、その回想に終止符が打たれる。ハヤブサはこの空しい回想に、(キョウジの馬鹿野郎~~~!!)と叫んで、脱力しそうになった。
「ほらほらハヤブサ、何をぼさっとしている!」
「――――!」
シュバルツの声で、はっと我に帰るハヤブサ。振り返ると、仙界軍から大量の矢が放たれて、こちらに向かって来ている。
「――――いっ!?」
流石に身の危険を感じた龍の忍者が脱兎のごとく走りだす。シュバルツもそれについて――――というより、ちゃっかりハヤブサの前に立って、彼を盾にしながら走りだしていた。
「おのれッ!! 待て―――い!!」
素戔鳴の雷撃や仙界軍の矢をかわしながら、忍者たちは走る。その二人の動きのシンクロ率たるや、さながら『街の遊撃手ごっこ』の如きだ。
「――――クッ!」
時々ハヤブサが振り返って、矢を叩き落とす。仙界軍の攻撃が身体に当たり負傷したら、シュバルツから容赦なく仙桃を口の中に突っ込まれた。
「頑張れ! ハヤブサ! ファイト!!」
一つも笑っていない『笑顔』のシュバルツから、割と心のこもっていないエールを送られる。彼の持っている袋の中の仙桃も、一向に減る気配がない。
(うううう……! チクショウ……!)
ハヤブサは心の中で泣き伏しているが、面には出さないように努力していた。――――が、その努力も、そろそろ限界を迎えそうだった。
もう、本当に何なのだ。
いい加減にしろと言いたい。
いや、この場合、悪いのはやっぱり俺なのか――――!?
何てことだ。
俺はただ、シュバルツに死んで欲しくないだけなのに。
軍議の席でいきなり締め出してしまった事が、そんなに悪いことだったのか――――?
頼らないとか
力量を認めていないとか
そんな事を言ったつもりではなかったのに――――!
それでもシュバルツには死んで欲しくないから、ハヤブサは、ほぼ条件反射的に彼を守ってしまう。
そして、負傷する。
そのたびに無理やり仙桃を食べさせられようとも
冷たい眼差しを向けられようとも
やっぱり、好きなものは好きなのだ。
このままでは俺は殺されるかもしれない。
素戔鳴ではなく、シュバルツに殺されるのかもしれない。
「フ……! それも良いな……!」
ハヤブサはそう言いながら、いつしかその面に笑みすら浮かべていた。
愛おしいヒトに殺されるのなら―――――それこそ、本望ではないか。
だが、そのハヤブサのうすら笑いから何かを察したのか、シュバルツから
「変態」
と、冷たい一言がかけられる。龍の忍者は、真面目に心が傷ついた。
「~~~~~~~~ッ!」
ガクッと崩折れるハヤブサに、また、ぷすっと刺さる一本の矢。
「どうした? ハヤブサ。そろそろ攻守交代しようか?」
「―――――!」
(冗談ではない!!)
シュバルツのその言葉に、龍の忍者はガバッと立ち上がる。シュバルツと仙界軍を戦わす事だけは、断固として避けねばならないのだ。例えこの命に代えても。
「じゃあ、頑張るんだな! ハヤブサ!」
そう言いながらシュバルツは、またハヤブサの口にガボッ! と、仙桃を押し込んでくる。
(うううう……こんちくしょう――――!)
龍の忍者はとうとう、えぐえぐと泣き出してしまった。
決めた。
この戦いが終わったら、絶対にシュバルツを抱き潰す覚悟で、抱いてやる――――!
いやだって言われたって
泣いて許しを乞われたって
絶対に許してなんかやらないからな――――!
腕の中でその身を嫌という程のたうちまわらせて
あられも無い声で可愛らしく喘がせてやる―――――!!
もう2カ月近くもお預けを喰らっている状態のハヤブサは、もう正直ブチ切れる寸前だった。ハヤブサの中で何かの危険なメーターが、どんどん上がって行っている。だがシュバルツの方も怒りまくっているので、当然そんなハヤブサの中の危険な気配には気づかない。忍者二人の間に今――――妙な火花が散りつつあった。
「おのれっ!! ふざけるなッ!!」
素戔鳴は怒鳴りながら雷撃を放つ。腹立たしい思いでいっぱいだった。
前を逃げる忍者二人は、決して真面目に戦っている風ではない。特に、黒の忍者の前を逃げる黒髪の男は、抜刀すらしていない。なのに、こちらの攻撃が一向に当たらないとはどういうことだ。ふざけるにも程がある。こちらを舐めているのか――――!?
完全に頭に血が上ってしまった素戔鳴は、それ故に、気づくことができなかった。自分達が今、『罠』に嵌められている、ということに。
まずそれは、狭い山間の道に入った時に起きた。
パラパラ……と、礫が落ちて来たかと思うと、ドドドドッ!! と地響きを上げて、大量の巨大な岩が転がり落ちてくる。
「素戔鳴様!!」
部下の叫びにはっと気が付いた時には既に遅く――――何人かの兵がその岩に跳ね飛ばされていた。それと同時に頭上から取り囲むように響き渡る、銅鑼の音と鬨の声。
「――――!」
ばっと顔を上げる素戔鳴の視界に、劉備軍の旗が飛び込んできた。その中心に、白馬に乗り『竜胆』という槍を構えた黒髪の長髪の青年が、こちらを見下ろしている。
「討て―――――ッ!!」
青年の号令と共に、無数の矢が頭上から襲いかかってきた。
「クッ……! 走れっ!! 走れ――――ッ!!」
素戔鳴は隊を前に走らせて、何とかその山間の道から脱出した。
「おのれ……! 奴らは何処へ行った……?」
何とか岩と矢の嵐から逃げ切り、肩で息をする素戔鳴の視界の端に、森へと逃げて行く忍者たちの後ろ姿が映る。
「おのれッ!! 逃がすものか!!」
激昂する素戔鳴はその姿を見るや、なりふり構わず後を追いかけだす。
「す、素戔鳴様!!」
兵たちも慌ててその後に続いた。
「……奴らは何処へ逃げた?」
薄暗い森の中、素戔鳴は忍者たちの姿を見失ってしまう。――――と、そこに、ピシュン! と、音を立てて飛んでくる、一本の火矢。
「――――!?」
それが小さく盛り上げられた黒い砂の山に、命中した刹那。そこから四方に向けて――――火の柱が走った。
「むっ!! いかん!! 火計だ!! 退け――――ッ!!」
素戔鳴が気付いた時には既に遅く、あっという間に木々に火は燃えうつり、火の海に囲まれてしまう。更にそこでも、混乱を助長するかのように周りから響いてくる銅鑼の音と鬨の声。
「う、うわあっ!!」
「た、助けてくれ~!!」
兵達の悲鳴が交錯する。流石の素戔鳴軍も、炎の中、ただ混乱して逃げ惑うしか無かった。
「ぬうっ!! 小賢しい!!」
ブオン!! と、唸りを上げて素戔鳴から振り下ろされた天叢雲が、木々をなぎ倒し、炎の中に脱出路を作り上げる。
「皆の者!! こちらだ!! ついて参れ!!」
素戔鳴に導かれて、兵達は何とか炎の海から脱出した。
ほうほうの体で炎の海から逃れた素戔鳴軍の前に、小さな小川が現れる。
「応、丁度よい。皆の者、この川の水で火傷を癒せ!」
この小さなせせらぎに、兵士たちもほっと息を吐き、やれやれと流れの中に入った。
そして水浴びを始めた瞬間―――――
ゴゴゴゴゴ……
地を這う様な不吉な音に振り向く素戔鳴の視界に、鉄砲水が押し寄せてくる。
「な―――――!!」
素戔鳴は慌てて川から上がる。だが、逃げ遅れた兵士たちが、あっという間にその鉄砲水に呑まれて行ってしまった。
「ぬ、ぬう………ッ!」
またたく間に大半の兵士たちを失った事実に、素戔鳴は唇を噛みしめるしかない。と、そこに追い打ちをかけるように、鬨の声が響き渡ってくる。
「さあ! 野郎ども!! かかれぇ―――――ッ!!」
張飛の号令以下、劉備軍が一斉に素戔鳴軍に襲いかかって行く。この光景を見た瞬間、素戔鳴の目の色が―――――変わった。
「おのれッ!! 人間風情がっ!!」
ドォンッ!!
素戔鳴の身体から、凄まじい程の闘気が爆発的に膨れ上がって行く。その闘気は空に雲を呼び、雷を呼んだ。激しい雷鳴がとどろく中、素戔鳴の咆哮が響き渡る。その様は、まさに神の雄叫び――――であった。
「へっ! 面白ぇッ!!」
だが張飛も負けてはいない。素戔鳴の人間離れした咆哮を聞いても、臆するどころか喜々として突っ込んで行く。
「我こそは燕人(えんひと)張飛!! 素戔鳴とやら!! 勝負だあああッ!!」
ガンッ!!
素戔鳴の天叢雲と、張飛の蛇矛が真っ向からぶつかり合う。その衝撃で空気が裂け、土埃が舞い上がった。鬼気迫る合の打ち合いが、何合か続く。だがすぐに、素戔鳴の方に軍配が上がった。
「刎ッ!!」
天叢雲から放たれた雷の力が、張飛を弾き飛ばす。
「ぐわっ!!」
「張飛殿!!」
張飛の軍に追いついて来た趙雲が、張飛を案ずるように声を上げる。
「素戔鳴!! 今度は私の番だ!!」
若き青龍の志士が、竜胆を構える。
「我が名は趙子龍!! 素戔鳴!! 我が槍を受けてみよ!!」
名乗ると同時にシャッ!! と、音を立てて繰り出される、竜胆の一閃。
「ぬっ!!」
素戔鳴は僅かに体を動かしてかわすが、またすぐに竜胆の鋭い突きが襲いかかってくる。
「応ッ!」
流石に素戔鳴も、この槍には天叢雲の剣で対応していた。だが、繰り出される槍のスピードが、徐々に早いものになっていく。
「ハッ!!」
終には一度に2、3本の槍が繰り出されているように見えるようになった。対応していた剣がそのスピードについて行けず、素戔鳴の首飾りの一部が砕かれてしまう。
「猪口才なッ!!」
それに激昂した素戔鳴が、激しく咆えた。ブオンッ!! と、唸りを上げる雷撃が、咆哮と共に趙雲に襲いかかって来る。
「ぐッ………!」
たまらずに吹っ飛ばされる趙雲。その後ろから関羽が青龍偃月刀を振りかぶりながら突っ込んできた。
ガツン!!
「――――――ッ!」
『人の子』にしては重い太刀筋を持つその刃に、素戔鳴はギリ、と歯を食いしばった。だがそれは関羽の方も同様であった。自分は、この素戔鳴を真っ向から唐竹割にするつもりで斬りかかった。それが――――受け止められてしまったのだから。
(強い……! さすが、張飛と趙雲を退けただけの事はある……!)
だが、自分がここで引く訳にはいかぬ。
関羽は更に踏み込んで、偃月刀に意志を伝えた。
「うおおおおおおっ!!」
薙ぎ払おうとする青龍偃月刀が、唸りを上げる。
「ぬうううううっ!!」
大上段から振り下ろされた天叢雲の剣と偃月刀が、またしても真っ向からぶつかり合った。
ガンッ!!
「…………!」
ぎりぎりと鍔迫り合う二人。二人の間に青白い火花が散り、闘気の風が舞い上がる。
「おのれ……!」
素戔鳴の身体から、バシン! バシン! と雷撃が溢れだし、それが天叢雲に満ち始めた。その動きに、関羽は何がしかの異常を感じ取る。しかし、そこからどんな技が来るのか未知であるが故に、一歩踏み込むべきか下がるべきか、その判断に迷った。
その刹那――――
「関羽殿!! 一歩後ろへ!!」
「――――!?」
その声に弾かれる様に関羽はその身を一歩引く。瞬間、素戔鳴の雷撃が天叢雲から放たれた。
「ぐうっ!!」
避けきれず、雷撃に身を打たれるが、ふっ飛ばされるまでには至らない。だが、受けた衝撃の大きさゆえに、流石の関羽も体が崩れる。それを見た素戔鳴が、追い打ちをかけるべく、更に踏み込もうとした刹那。
関羽の影から、黒い影が飛び出してくる。
「――――!?」
あまりにも不意をつかれたため、素戔鳴は踏ん張るのが一歩遅れた。瞬間、黒い影から煌めいた白銀の光。
ドンッ!!
そこから持たされた、凄まじい衝撃――――素戔鳴は強制的に2、3歩後ろに下がらされてしまう。
「何奴!!」
叫びながら顔を上げた素戔鳴の視界に、黒の忍者の姿が飛び込んでくる。その黒の忍者は、忍者刀を抜き身のまま右手に持ち、ただそこに立っていた。だがどうした事か――――その姿には恐ろしい程『隙』が無かった。覆面の間から覗く色素の薄いグリーンの瞳が、鋭い光を放っている。
「ほう……汝は先程逃げ回っていた忍者。やっと、吾に向かってくる気になったのか?」
「……………」
素戔鳴の問いに、ハヤブサは答えない。ただ、その足を一歩、前に進めた。
「シュバルツを頼む」
横にいる関羽にだけ聞こえる様な声で、小さく呟く。
「…………!」
関羽は一瞬茫然としたが、すぐに「承知した」と、ハヤブサに道を譲った。振り返りながら、目的の人物を探す。
(待てよ……! この『黒の忍者』がここにいる、という事は………!)
素戔鳴もまた、思い出していた。自分が何故こうも激昂し、むきになって忍者たちを追いかけていたのか――――その、根源的な理由を。
目的のモノは、すぐに見つかった。
ひしひしと感じ取る。
人の子の間に混じる―――――『人ならざるモノ』の気配を。
「皆の者!! あれを討てい!!」
それ故に誰よりも早く、素戔鳴はシュバルツを指して、叫んだ。
「あの者は『魔』ぞ――――!! 絶対にその存在を、許してはならぬ!!」
「ははっ!」
素戔鳴の言葉に応じた仙界軍の兵士たちの視線が、シュバルツに注がれる。その瞬間、龍の忍者が動いた。
「覇――――――ッ!!」
凄まじい勢いで、素戔鳴にぶつかる。まるで、それ以上その命を下すことは許さない、とでも言わんばかりに。
「ぬっ!!」
素戔鳴も咄嗟に天叢雲で対応するが、その勢いを殺しきることは出来ず、またしても強引に2、3歩後ろに下がらされてしまう。
「貴様の相手は、この俺だ……!」
ぶつかってきた黒の忍者から、恐ろしい程の殺気が放たれる。
(ほう………!)
『人の子』にしておくには勿体ない程の荒ぶる殺気をその身に宿した黒の忍者。素戔鳴は思わず感心してしまう。驚いた。この者の身に纏っている『気』は――――
まるで、『龍』その物ではないか。
「素戔鳴様の御命令だ!!」
「素戔鳴様の御為に――――!!」
生き残っていた仙界軍の兵士たちが、口々に叫びながらシュバルツに殺到して行く。
「へっ! かかって来るなら、相手をしてやらぁ!!」
それを張飛が喜々としながら迎え撃っていた。その後に趙雲も続く。
今――――素戔鳴軍と人間たちの真正面からぶつかり合う戦いの幕が、開かれようとしていた。
「……凄まじき『気』だな。黒の忍者」
素戔鳴はそう言いながら、天叢雲を初めて構える。この相手はそうしなければならない程の相手だと、彼の中では警報が鳴り続けていた。
「…………」
対してハヤブサも、無言で龍剣を構える。前の戦で負傷してから療養している間中、ずっと思い描いていた相手。それが、目の前にいる。ともすれば高揚しそうになる心を押さえ、ただ、静かに息を吐いた。
「……戦いに入る前に、名を聞いておこうか。『龍』の忍者よ」
荒ぶる『龍』の気が、素戔鳴にはひどく心地が良かった。うっかり愛(め)でそうになってしまうほどだ。
「我が名は、リュウ・ハヤブサ」
黒の忍者は簡潔に答える。それに対して素戔鳴も、にやりと笑みを見せた。
「『リュウ・ハヤブサ』か……。覚えておこう」
そう言いながら素戔鳴も、ジリッと間合いを詰める。久しぶりに歯ごたえのある戦いが楽しめそうな予感に、胸が躍った。
互いに剣を構えながら、じりじりと間合いを測る。周りでは仙界軍の兵士たちと劉備軍との間で乱戦が起こっているが、二人の周りだけが、ただ切り離された空間であるかの如く、沈黙の中に在った。
果たしてその瞬間、一体どちらが早かったのか――――。
ダンッ!! という激しい踏む込み音と共に、互いの姿が、そこから消えた。
「叭――――――ッ!!」
「うおおおおおおおっ!!」
ドンッ!!
凄まじい音ともに、互いの剣撃がぶつかり合う。その振動は周囲の空気を裂き、土埃を舞い上げさせた。力は全くの五分と五分。そこから互いに一歩も引く気などない。すぐに、次の手が繰り出される。だがそれも、互いの身体には届かない。ならば、次の手を。
ガンッ!!
ガキッ!!
そのまま激しい剣の応酬が始まった。二人がぶつかり合うたびに、青白い火花が飛び散り、空気が裂け、周囲に振動が伝わった。
「ハヤブサ!!」
流石にハヤブサの身を案じてしまうシュバルツは、彼の傍に行こうとする。それを、押しとどめる者が居た。
「―――貴殿は絶対に、これより前には出るな」
「関羽殿!!」
驚いたシュバルツが関羽に声をかける。関羽は、シュバルツの方には振り向かず、ただ、青龍偃月刀を迸らせた。
「憤ッ!!」
その一振りは、シュバルツに殺到しようとした仙界兵達を跳ね飛ばす。
「拙者は約定を交わした。故に、拙者はそなたを守らねばならぬ」
「約定?」
シュバルツは不思議そうに関羽を見上げる。
「……それは、誰とですか? ハヤブサと、ですか?」
問うてくるシュバルツに、関羽はちらりと視線を走らせた。
「……確かにそれもある。だが、それだけではない」
「…………?」
「これは最早、拙者の『信義』の問題なのだ」
関羽はそれだけを言うと、青龍偃月刀を、ドンッ! と、音を立てて地面に立てかけた。
「故にシュバルツ! 拙者はそなたを守る!! 絶対に――――我の傍から離れるな!!」
そう言いながら関羽は、シュバルツに襲いかかろうとする仙界軍の兵士たちを、青龍偃月刀で薙ぎ払い続けた。
「……関羽殿……!」
シュバルツは、そこから一歩も動けなくなってしまった。
それほどまでに――――関羽と言う男から発せられた『信義』という言葉は、重さを伴ってシュバルツに響いていた。
「ぬうっ!!」
龍の忍者と素戔鳴の一騎打ちは、合の打ち合いを経るに従って、その激しさを増して行った。このままでは埒が明かないと感じた素戔鳴は、自身が神仙であるが故に持ち得た力――――雷撃を、戦いの手に加えることにした。
「覇っ!!」
鍔迫り合いからの雷撃―――この攻撃をかわしきれた者は皆無。素戔鳴が勝利を確信しようとした、刹那。
「――――!」
龍の忍者が、いきなり眼前から姿を消した。
「―――――!?」
素戔鳴が驚いている間に、雷撃の間からいきなり龍剣が突き出てくる。
ドンッ!!
それは、素戔鳴の体をいきなり高々と打ち上げた。その素戔鳴を追う様に、黒い影が跳び上がる。黒い影は空中で素戔鳴を羽交い絞めにすると、そのまま綺麗な放物線を描いて錐揉みしながら素戔鳴の体を地面にたたきつけた。龍の忍者の『飯綱落し』が炸裂したのだ。
「ぐ………!」
地面に叩きつけられた素戔鳴が、ゆっくりと起き上がる。
(何だ? 今のは………偶然か……?)
起き上がりながら、今の自分の動きと龍の忍者の動きを反芻する。おかしい。今のタイミングで攻撃を仕掛けられたと言う事は、こちらの雷撃を『避けられた』としか――――
(馬鹿な……!)
素戔鳴は、頭を振って今の自分の考えを否定する。
あり得ない。
こんなにもあっさりと――――自分の攻撃を見切られてしまう、など。
(もう一度だ!)
素戔鳴は、天叢雲を改めて構える。龍の忍者も、それに合わせて無言で構えた。
再び二人の間に満ち始める、殺気と気迫。
それが飽和状態になった時――――再び二人が、同時に強く踏み込んだ。
ガキンッ!!
交錯する影。ぶつかり合う剣撃――――
互いに一歩も引く気の無い戦いは、風を巻き起こし、その周りに火花を散らした。
雷鳴が轟き、雨が降り始める。文字通り、嵐を呼ぶ戦いとなった。その息の詰まる様な攻防を、いつしか敵も味方も自身の戦いを忘れて見入っていた。周囲には、ただ二人の剣撃と息遣いと、踏み込む音だけが響いていた。
(おかしい――――)
素戔鳴は戦いながら首を捻る。
剣の技量はほぼ互角。互いに拮抗した打ち合いをするが、決定打を与えるまでには至らなかった。ならばと素戔鳴から放たれる雷撃。これがどうしたことか、目の前の忍者に一向に当たらない。間一髪のところで、避けられてしまう。
(何故だ……?)
素戔鳴は思わず考えてしまう。
この忍者の動きは、吾の雷撃が『見切られている』としか――――
(馬鹿な……!)
素戔鳴はもう一度、自身の脳裏に浮かんだ考えを、強く否定した。
そんな筈はない。
初見の相手が簡単に見切れる程、雷撃の動きは甘くはない筈なのだから。
だが一度脳裏に浮かんでしまった考えを、簡単には否定できない現実。いつまでたっても忍者を捉えきれない自身の攻撃に、素戔鳴に焦りの色が浮かび始める。
その刹那――――
龍の忍者の姿が、フッと消えた。
「――――!?」
誰もが虚をつかれて、龍の忍者の姿を求めて視線を走らせる。
ただ、シュバルツだけは上を見ていた。ハヤブサが龍が駆け上がるが如く飛び上がった空を。
「―――――!」
シュバルツから一瞬遅れて素戔鳴も、ハヤブサの姿を視界に捉える。
(真上だと――――!? 愚かな!! 避けようも無い上空で、吾の攻撃を真正面から受けようと言うのか――――!?)
―――舐められている。
素戔鳴の心が、ざわ、と、波だった。
良いだろう。
汝が望むとおり
引導を、渡してくれる――――!
怒りを乗せた雷撃が、天叢雲に満ちる。後はそれを、上空から突っ込んでくる龍の忍者めがけて、振り抜くだけだった。
「はああああああっ!!」
裂帛の気合と共に、龍の忍者が上空から迫って来る。
「うおおおおおおおっ!!」
それに向かって素戔鳴が、天叢雲を振り抜こうとした瞬間。
上空から降ってきた稲光が、轟音を伴って、二人の近くの木を切り裂く。激しい光と衝撃が、辺りを席巻する。それ故に、その瞬間を見た者は、誰もいなかった――――
ストン、と音も無くハヤブサが地面に降り立つ。
そのまま暫し、互いに動かぬ残心状態が続いた。
回転して落ちて来た何かがドスッと地面に突き刺さり―――――
「うぐッ……!」
先に素戔鳴の体が崩れる。それを確認してからハヤブサは立ち上がり、振り返った。
「おのれ………!」
ガクッと膝をついた素戔鳴の右肩には、クナイが突き刺さっていた。
雷撃を放とうとした瞬間、天から走ってきた雷鳴。それとともに、このクナイは自分の右肩に襲いかかってきた。それに気を取られてしまった僅かな隙に、龍の忍者に右腕を切り裂かれ、天叢雲を奪われてしまったのだ。
そんな素戔鳴にハヤブサはつかつかと歩み寄ると、チャッ、と、音を立てて龍剣を向けた。
「悪いが俺は、お前と戦うのは初めてではない」
「な――――!」
驚き息をのむ素戔鳴に、ハヤブサは更に言葉を続けた。
「『前の時間軸』で、お前の攻撃を散々見せつけられているのだ」
「何だと!?」
「故に俺には、手に取る様に分かる。お前がどのような攻撃を繰り出すのか、どのように雷撃が走るか――――」
「…………!」
ぶるぶると小刻みに身体を震わせていた素戔鳴が、拳をぎゅっと握りしめた。
「……時を遡った……と、言う事は、巫女かぐやが、貴様たちに手を貸したのか……?」
「そうだ」
ハヤブサの肯定の言葉に、素戔鳴はギリ、と唇を噛みしめた。
「……何故だ……?」
絞り出されるように、素戔鳴は声を発した。
「巫女かぐやが……何故だ……!」
素戔鳴が何を言わんとしているのかをハヤブサは測りかね、その様子を静観する。すると素戔鳴は、弾かれたように顔を上げて叫んだ。
「人の子よ!! 汝らに問う!! 何故だ!? 何故その後ろに居る『化け物』を守ろうとするのか!? 時を巻き戻してまで――――!!」
「――――えっ?」
「化け物?」
張飛と趙雲が、驚いて素戔鳴が指さす方向に振り返る。その先には、青龍偃月刀を構える関羽と、その後ろに立つシュバルツの姿があった。
「関羽の兄貴が『化け物』な訳無いよな……。と、すると、後ろのあいつか……?」
「……………!」
張飛の言葉に、シュバルツの瞳が哀しみゆえに曇る。
「そうだ……! あれは人の形をしているが、人には非ず。その身は、酷く邪悪な物で出来ている……! 放っておけば、人の子の世に害を為すぞ!?」
素戔鳴の言葉に、周りの者たちが息をのむ気配が伝わる。
ハヤブサは、チッ! と、小さく舌打ちをしていた。
シュバルツの成り立ちがどうであろうと、身体を構成している者が何であろうと、自分にはさして問題にならない。シュバルツは『シュバルツ』だ。
自分にとっては愛おしくて、大切なヒトである事に変わりはないのだから。
だがハヤブサは、敢えて沈黙を選んでいた。
見極めたいと思った。
ここの者たちにこの素戔鳴の意見は、どう捉えられるのだろうかと。
自分は、何があってもシュバルツの味方だが――――
素戔鳴の意見がまかり通ってしまうようなら、今後の対応を考えねばならぬと思った。
素戔鳴の言葉に対してシュバルツは、(ああ、事実だ)と、だけ思った。
確かにそうだ。
私は多くの血と涙の果てに、生まれ落ちたモノ。
キョウジの動かぬ『罪』の証。
この身体は『DG細胞』と言う物で出来ているが故に―――
この細胞は常に、人間に害を為す可能性を秘めている。
れっきとした『事実』だ。
だから私は本当ならばここに存在していてはいけない。
今すぐ滅せられなければならぬモノ――――
その時関羽が青龍偃月刀の柄で、ドンッ!! と地面を叩いたが故に、その衝撃で、シュバルツの思考は中断させられてしまった。
「――――!」
はっと顔を上げるシュバルツの視線の先で、関羽が険しい顔をして素戔鳴を睨みつけていた。
「……拙者はこの者を守る。例えその身が何で出来ていようが、関係無い」
静かな物言いだが、酷く迫力があった。
「それは、何故か?」
問う素戔鳴に、関羽は答える。
「……『約定』を交わしたからだ」
「約定? それは、誰とだ? ここに居る、龍の忍者とか?」
怪訝な顔をして問う素戔鳴に、関羽は頭を振った。
「それもある。だが、それだけではない」
関羽は真正面から、素戔鳴を見据える。
「拙者が『約条』を交わしたのは、村人たちとだ」
「村人たちだと?」
素戔鳴は首を捻る。
「妙な事を言う……。関羽とやら。百歩譲って村人たちがいち早く汝らの城に逃げ込んでいたのだとしても、村人たちと汝の間に『約定』をかわし得る程の話し合いができる時間があったとは思えぬが?」
それに対して関羽は静かに首を振った。
「いいや、拙者は確かに『約定』を交わした。この時間軸の者たちとではない。前の時間軸で、命からがら村から逃げて来た者たちと――――だ」
「何っ!? 汝も時を越えし者か!?」
素戔鳴の驚愕の声に、関羽は「そうだ」と頷いた。
この悲劇を救う手段を模索するために、太公望が生き残った村人たちと妖魔たちに話を聞きに行く、と、言った時、関羽もその手伝いの人員として、名乗りを上げていた。
目の前で起こった悲劇を止める事が出来るのならば、その手助けをしたいと願った。
だが――――
実際村人たちに話を聞くのは、困難を極めた。
それは何故かと言うと、『シュバルツの死』を知った村人たちが、皆――――泣き崩れてしまったからだ。
「シュバルツさん……ッ!」
「どうして……! わしらなどのために……ッ!」
そう言って地面に突っ伏したり拳を叩きつけたりして泣く、村人たち。「これではどうしようもない」と、頭を抱えていた太公望の傍で、関羽は村人たちに懸命に呼びかけていた。
「頼む……! 皆の話を聞かせてくれ! 我等とてシュバルツ殿を助けたい……! 助けたいのだ!」
「本当に……助けてくれるだか?」
関羽の言葉に反応して、ようやく顔を上げ始める村人たち。そんな村人たちに、関羽は力強く頷いた。
「ああ……。必ず助ける。だから頼む……! そなた達の話を聞かせてくれ……! 拙者はあの悲劇を、目の前で見てしまった……! だから時間を巻き戻して、今度こそ――――救いたいのだ!!」
「……時間を巻き戻す……。そんな事が、出来るだか?」
茫然と聞き返してくる村人たちに、関羽は「ああ」と、力強く頷いた。
「本当に……シュバルツさん、死なないで済むようになるの……?」
「そうだ」
「じゃ、じゃあ、お願いします!」
「わしらの話が役に立つのなら、喜んで!!」
話がようやく聞けそうになった村人たちに様子に、太公望も苦笑する。
「では――――皆で手分けして、話を聞いて行ってくれ」
太公望の言葉を受けて、諸将は村人たちの間に入って行く。関羽もそれに倣い、入って行った。
こうして関羽は聞き続けた。
村人たちの話を。シュバルツがあの村で、どのように過ごしていたのかを――――
そして、最後には必ずこう言われた。
「必ず、シュバルツさんを助けてください!」
老若男女問わず、皆が口をそろえてこう言った。
そのたびに、関羽もこう答えた。
「あい分かった。必ず助ける」
1人1人と、そう『約束』をして、関羽は村人たちと別れた。
時を渡った今、あの城の中に逃げ込んできた村人たちの中には、そんな記憶などかけらも残っていないだろう。当たり前の話だ。村を襲撃され、命からがら逃げてきた事自体が、村人たちの中では『無かった事』になってしまっているのだから。
だが、関羽は覚えている。
村人たちの涙を。握ってきた手の強さを。
彼らの必死な願いを。
「必ず助ける」
そう交わした約束を。
覚えている以上、それは守らなければならぬと関羽は思う。例え相手に忘れられてしまった『約束』であろうとも、『無かった事』になってしまっている物だとしても。自分が一度引き受けた物ならば―――――それは、果たされなければならぬと思うのだ。
そうする事が自分の『信義』だ。
それ以外に生きて行く術を、自分は知らない。
それに――――
「……この者の出自や成り立ちがどうあれ、この者は村人たちを助けていた。弱き者を慈しみ、守ろうとする者であることを、少なくとも拙者は知っている!」
関羽はもう一度、その柄で地面をドンッ!! と、叩いてから、青龍偃月刀を構えた。
「なれば、拙者はこの者を守る!! これ以上の理由は必要ない!!」
「…………ッ!」
ギリ、と歯を食いしばる素戔鳴に向かって、張飛も口を開いた。
「俺も、関羽の兄貴に従うぜ!」
「…………!」
驚くシュバルツの目の前で、張飛も素戔鳴に向かって蛇矛を構える。
「細かいことはよく分からねぇが、関羽の兄貴について行けば間違いはないからなぁ!!」
「我が槍も、関羽殿の『信義』のために!」
そう言いながら趙雲も、素戔鳴に竜胆を向ける。
その光景を見ながらシュバルツは茫然としていた。
(皆……何故だ……? 何故――――)
素戔鳴の言う通り、『自分』と言う存在は罪に塗れているのに。
身体に刻まれた、『邪悪』な匂いは消えないのに――――
どうして――――
茫然と周りを見回していると、素戔鳴に剣を向けているハヤブサと視線が合う。すると、彼はひどく優しくシュバルツに微笑みかけて来た。
(良かったな……)
成り立ちがどうこうなんて、本当に問題じゃない。
ちゃんとお前の心を見て、為してきた足跡を見て――――受け止めてくれる人たちが必ずいるんだ。
「う…………!」
あまりにも優しくハヤブサに微笑みかけられたものだから、シュバルツは何となく落ち着かない気持ちになる。ばつが悪そうにハヤブサから視線を逸らした時、後ろの茂みから女性の声が響いてきた。
「あっ! 尚香! シュバルツさん居たよ!!」
その声のした方にシュバルツがはっと振り返ると、甲斐姫と孫尚香が茂みの中からかけてくる姿が視界に飛び込んできた。彼女たちは、あれからしばらくシュバルツと共に村人たちの世話をしていたが、夜半になってシュバルツの不在に気づき、慌ててあちこちを探し回っていたのだ。
「シュバルツさん……! 良かった……!」
シュバルツの姿を認めた孫尚香が、ポロポロと大粒の涙を零し始める。
「ちょ、ちょっと、尚香! 泣くのはまだ早いよ……!」
慌ててそう言う甲斐姫。しかし、孫尚香の涙はすぐには止まらなかった。
「ご、ごめん……! でも……! 無事な姿を見たら、つい……!」
(……………!)
彼女のその涙を見て、シュバルツもようやく気付いた。自分の勝手な行動が、どれだけの人を心配させてしまったのだろうと。
「尚香殿? 見つかりましたか?」
そう言いながら、彼女たちの後に続いて劉備も茂みの中から出てくる。その後から、諸葛亮の姿も続いた。
そして更に――――
「甲斐様……」
たおやかな女性の声が響く。その正体に気付いた甲斐姫は、思わず素っ頓狂な声を上げていた。
「か、かぐちん!? どうしてここに!?」
甲斐姫の言葉に、巫女かぐやはにっこりとほほ笑む。
「はい。太公望様のお力をお借りして……ここに参りました」
「フン―――全知全能の私の能力を以ってすれば、これくらいの事は、造作も無いことだ」
少し傲岸な物言いをする白髪の青年の横で、左慈が頭を下げる。彼は『事の顛末を見届けたい』と、太公望に強く願い出て、その供を許されていたのだった。元はと言えば自分の『ミス』のせいでこの二人は引き離され――――今に至っているのだから。
「素戔鳴様……」
「かぐや……!」
素戔鳴に名を呼ばれたかぐやは、丁寧に頭を下げる。どうやら二人は、知り合いの様であった。
「かぐや……! 汝ともあろう者が、何故このような者を守ろうとするのか!?」
素戔鳴の問いに、かぐやは穏やかに答える。
「総ては……『友人』のためにございます。素戔鳴様」
「友人だと?」
鋭く問い返してくる素戔鳴に、しかしかぐやは怯まなかった。
「はい……。私は此度の戦いを通して、初めて『友人』と呼べる方達を得ました」
穏やかに、しかし、きっぱりと答える。
「その方々の願いを、私は叶えたいのです」
「その者たちの願いが――――あのような『魔物』を守りたい、ということでもか!?」
素戔鳴の叫びに、かぐやたちははっとシュバルツの方に振り返る。
シュバルツはただ、静かにそこに佇んでいた。穏やかだが、少し憂いを含んだ眼差しでこちらを見つめている。
「……………」
太公望やかぐやがじっと検分するようにシュバルツを見つめても、彼は瞳を逸らさなかった。自分が『魔』であることを隠さない。認めているのだと言う彼の姿勢が、見て取れるようであった。
「……なるほど。確かに『魔』だな」
太公望が手の中で打神鞭を弄びながら、ポツリと呟く。
「だが、そんなに気を回し過ぎるほどの物でもあるまい。この者が持つ『邪気』など、微々たるものだぞ?」
「私もそう思います。素戔鳴様」
太公望の言葉を受けるように、かぐやも続いた。
「この方は確かに、人間ではありませんが、かように邪悪な気配を感じる者でもありません。この方の気配は、寧ろ清々しく澄み切っていると――――」
「だが、この者の持つ『邪気』が封を破られ表に出れば――――どれほど人のこの世に害を為すか――――分からぬ汝らではあるまい!? それでも、それを放置しろと言うのか!?」
素戔鳴の叫びに、しかし太公望はめんどくさそうに頭をかく。
「考えすぎだ! すぐにどうこうなることもあるまい。それに素戔鳴――――お前は少し、人の子を見くびり過ぎだ!」
「何?」
ジロリ、と睨んでくる素戔鳴に、しかし太公望も負けてはいない。傲岸な眼差しで見つめ返す。
「人の子は確かに弱いかもしれぬが、強いぞ? それこそ、こちらが想像している以上にな……」
「そうです、素戔鳴様」
かぐやも、懸命に言葉を続ける。
「人の子の力は、確かにか弱き物ではございますが、時に、こちらが驚くほどの力を発揮する事がございます。私もこの戦いを通じて、何度もその様な経験をさせていただきました。人の子たちは、確かに――――不可能を可能にする力を持ち得るのだと」
「しかし……!」
まだ納得しかねるような素戔鳴に、太公望はフフフと笑った。
「見た所お前は戦いに負けているようだが………お前を破った『龍の忍者』も――――『人の子』ではないのか?」
「――――!」
その言葉に虚をつかれたかのように、素戔鳴はハヤブサの方を振り返る。すると、酷く冷たい眼差しでこちらを見下ろしている、龍の忍者と視線が合った。
実際ハヤブサは、ブチ切れる寸前であった。
先程から黙って聞いていれば、素戔鳴はシュバルツを傷つける言葉しか吐いていない。本当ならば今すぐにでも――――黙らせてやりたいところだ。
今それをしないのは、素戔鳴に対して懸命に説得を続けている太公望やかぐやの顔を立てているからであった。それが無ければ、ハヤブサはとっくに素戔鳴を斬り捨てていただろう。
「素戔鳴殿」
それまで後ろで黙って話を聞いていた劉備が、前に進み出て来た。
「素戔鳴殿……。確かに我らの力は、貴殿にとっては取るに足らぬものかもしれぬ……。だが、少しでもいい。我らの力を、認めていただく訳には参りませぬか?」
「…………!」
「我らが力を合わせれば、どのような困難も乗り越えられる――――私は、そう信じているのです」
「むむっ」
劉備の言葉に、素戔鳴は少し難しい顔をする。確かに、自分は『人の子』たちと戦って負けた。だから太公望の言葉も劉備の言葉も、理解できない事ではなかった。
しかし――――
「……………」
素戔鳴はシュバルツと、その周りの人の子とを見比べる。確かに、ぱっと見人の子のそれと変わらず、寧ろ清々しい『気』をその身から漂わせているシュバルツ。だが、その奥底に潜む禍々しい程の邪悪な気配が、素戔鳴の『軍神』としての部分を刺激する。
この『魔』が封を破られ、世に放たれた時――――果たして人の子は、それに対抗し得るのか?
人のこの世界は、秩序は、どうなってしまうのだろうか。
それを考えると――――
とても看過など、出来なかった。
だから叫んだ。
「駄目だ!!」
「素戔鳴様……!」
かぐやが哀しそうな声を上げるが、素戔鳴は構わず続けた。
やはりその『魔』は滅すべき者――――彼はそう叫ぼうとした。だが、それは叶わなかった。何故なら――――背後からいきなり龍の忍者に、思いっきり殴り飛ばされてしまったからだ。
「ぐうっ!!」
地面に叩きつけられた素戔鳴の上に、龍の忍者が押さえつけるように乗って来る。起きあがろうとする素戔鳴の喉元に向かって、龍剣をつきつけた。
「お前、もう死ぬか?」
凄まじい殺気を、龍剣に伝える。事実、龍剣も喰らいたがっていた。『素戔鳴』と言う神の御霊を。
赦しがたい。
素戔鳴は既に二度、シュバルツを殺している。
そして今の言動行動――――彼は全くシュバルツを『理解』しようとしていない。ただ『滅殺すべし』の一点張りだ。絶望的に、話し合いが通じない相手なのだと感じる。
それならば、いっそ
いっそのこと――――
「……………!」
目の前の龍の忍者の明確な殺気に、素戔鳴はギリ、と歯を食いしばる。
ハヤブサは今――――完全に『人斬り』の目をしていた。
「ハ、ハヤブサ様!!」
素戔鳴の危地を感じ取ったかぐやが、慌てて声を上げる。
「どうかお許しを……! 素戔鳴様は、我が神仙界には無くてはならぬ御方なのです!」
かぐやの叫びに、しかしハヤブサは答えない。龍剣を素戔鳴に突きつけたまま、殺気を漂わせている。
駄目だ。
今ここでこいつを殺さねば――――
こいつはまた、シュバルツに害を為す。
「ハヤブサさん! 止めて!!」
甲斐姫もたまらず声を上げた。
今目の前で行われようとしているのは、『闘い』ではない。一方的な殺人だ。
戦の理で仕方がないこととはいえ、愛する人を守るためだとは言え――――
そのような事は、して欲しくないと願う。
だって友人であるかぐやは、素戔鳴の助命を願っているのだから。
「ハヤブサさん!!」
だが、その声がまるで聞こえていないかのように、龍剣を素戔鳴に突きつけ続けるハヤブサ。あまつさえ、その龍剣を振り上げようとしているようにすら見える。
「ハヤブサ様!!」
「ハヤブサさん!! 駄目っ!!」
「ハヤブサ!!」
「――――!」
愛おしいヒトの声に、ハヤブサの動きがビクッと止まる。そちらに視線を走らせると、そのヒトはこちらを必死に見つめていた。
(そんなことはしなくていい)
瞳がそう訴えて、懸命に首を振っている。ハヤブサは口の中で小さくチッ! と、舌打ちをした。
(お人好しめ!)
信じられない。
あれだけ好き放題言われたと言うのに、どうしてあいつはそれを許せてしまえるのだ。
しかし、愛おしいヒトがそれを望んでいないと分かると、自分の中の殺気が萎えてしまったのも事実だ。
「……………」
ハヤブサは小さく息を吐くと、素戔鳴の身体の上からゆっくりと退いた。
「去れ!」
短くそう言うと、龍剣を下げて素戔鳴に背を向ける。そのまま龍の忍者はすたすたと歩き出した。
「……………ッ!」
ハヤブサから解放された素戔鳴の身体が、わなわなと小さく震えている。
無理もない。
今彼は――――最大級の屈辱を感じていた。
戦いで人の子に敗れ、さらに命乞いまでされてしまったのだから。
(おのれ………!)
怒りで視界が真っ赤に染まる。龍の忍者の背中越しに、シュバルツの姿を見続けた。
あの魔物
あの魔物を
何としても、このまま放置しておく訳には――――!
「ハヤブサ!」
シュバルツが、関羽の影から出てくる。
この瞬間を、素戔鳴は見逃さなかった。
(今だ!!)
狙いすまして、雷撃を放つ。
だが次の瞬間。
ガキッ!!
龍の忍者が振り向きざまに、その雷撃を龍剣で撥ね返していた。
「な――――!」
息を飲む素戔鳴に、ハヤブサはにやりと笑いかける。
「……やると思った」
「…………!」
ギリ、と、歯を食いしばる素戔鳴に対して、ハヤブサは改めて龍剣を構えた。
「もし次に同じことをすれば――――かぐややシュバルツが止めても、俺は貴様を斬る」
声音は静かだが、そこから漂う明確な殺気。それが素戔鳴に『これは脅しではない』と悟らせた。
本気だ。
目の前の男は、本気で吾を斬ろうとしている。
そしてこの者は――――それが出来てしまうのだ。
「く…………!」
素戔鳴は認めざるを得なくなった。
もう本当に自分には、打つ手が無くなってしまったのだと――――
「引き上げるぞ!!」
素戔鳴は、そう号令を発する。生き残った兵士たちも、素戔鳴の号令に諾々と従った。
(終わったのか……?)
素戔鳴の後ろ姿を見送りながら、ハヤブサは龍剣を構え続ける。素戔鳴の姿が完全に見えなくなるまで――――龍の忍者はそれをし続けた。
(つ………!)
構えを解いた瞬間、龍剣を握っていた手にしびれを感じる。流石は素戔鳴―――――鋭い一撃だった。
「……終わったのかな……?」
甲斐姫が、信じられない、と、言った感じで茫然と呟く。事実、まだ夢見心地だった。村人たちも妖魔たちも、シュバルツも皆無事で――――こうしてここに立っていられるだなんて。
「そう……みたいね……」
孫尚香も同じ想いの様で、茫然と言葉を紡ぐ。その横で巫女かぐやも「甲斐様……」と、微笑みかけて来た。
(やれやれ。やっと終わったか……)
太公望もそう感じて、小さく一つ息を吐く。それにしても今回の案件は、少々手惑いはしたが、『素戔鳴に人の子の力を認めさせる』という点においては、収穫があったと言って良いだろう。これであの石頭も、少しは考えを改めてくれれば―――――と、太公望は思った。
関羽も無言で構えを解く。そこに張飛が「兄貴!」と、手を上げながら寄ってきた。
(やれやれ……小生は結局、何の役にも立てなんだな……)
左慈もそう感じて、苦笑しながらため息を吐く。二人には本当に申し訳ない事をしてしまったが、『悲劇』からあの青年を取り戻せたのなら、心の底から良かったと感じる。
「ハヤブサ!」
シュバルツが今度こそ、関羽の影から飛び出して、こちらに走り寄って来る。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは驚くほど柔らかい笑みを浮かべて、それを迎えた。
良かった。
今度こそ『悲劇』を、終わらせる事が出来た―――――
誰もがそう確信して
『油断』した
その一瞬だった。
音も無く飛来して来た、一本の 矢
それがシュバルツの脇腹に、突き刺さって いた。
「え………?」
茫然と見つめるハヤブサの目の前で、崩折れるシュバルツの 身体。
矢が飛んできた方に振り返ると、瀕死の仙界軍の兵士が弓を構えていた。
彼は最期の力を振り絞って――――矢を放っていたのだ。
「総ては……素戔鳴……様、の……御為に……!」
それだけを言って、その兵士は息絶えた。
「シュバルツッ!!」
ハヤブサは悲痛な声を上げながら、愛おしいヒトの傍に走り寄っていた。
「シュバルツ!! シュバルツ……! しっかりしろッ!!」
ハヤブサは叫びながら、愛おしいヒトの脇腹から矢を引き抜く。すると、ハヤブサの腕の中で愛おしいヒトがふっと瞳を開けた。
「ハヤ……ブサ……」
「シュバルツ――――」
懸命に見つめるハヤブサに、シュバルツは優しく微笑みかけた。
「済まないな……ハヤブサ……。確かに、全然……治せない、みたいだ……」
そう言う愛おしいヒトの身体から、パリ……パリ……と、哀しい音が響いてくる。この音はシュバルツが『壊れて行く音』だと、ハヤブサは知っていた。もう二度と――――聞きたくないと、祈っていたのに――――!
「嘘でしょう!? ここまでやって――――!!」
甲斐姫の悲鳴の様な声を聞きながら、太公望も呆然とするしかない。
(これが……! これが、『運命の悪意』か……!?)
この作戦、誰にも何も落ち度など無かった。にも拘らず、理不尽にまた命を奪われようとしている青年。これが『運命の悪意』と言わずして――――何だというのだろう。
「どいてください!! ハヤブサ様!!」
珍しい巫女かぐやの大声に、ハヤブサははっとシュバルツから手を離す。
「微力ながら、治癒の法を試してみます!」
そう言うや巫女かぐやは、シュバルツの傍に座り玉串を構えながら祝詞を詠唱して行く。玉串に金色の光がポッと灯る。それをシュバルツの身体にそっと当てた。
「う………!」
シュバルツが苦しそうに呻き、巫女かぐやの顔色も変わる。
「駄目だわ……! 治せない……! 何故――――!?」
命に代えてもと思っているのに―――! と叫ぶかぐやに、シュバルツは優しく微笑みかけた。
「いい……。そんな事……するな……。その気持ちだけで……もう、充分だから………」
「――――ッ!」
シュバルツの言葉を聞きながら、ハヤブサは天を仰ぐ。もしもシュバルツが『人間』であったなら――――かぐやの治癒の法も効いたであろうに。
だがシュバルツは人間ではない。
『人間』ではないのだ。
「でも……! 駄目……! 駄目です……! 貴方は『生』を、望まれているのに――――!」
悲痛な声を上げながら、それでも懸命に治癒の法を続けるかぐや。誰もが為す術も無く、ただ繰り返される『悲劇』を見守るしかない――――まさにそう思った、刹那。
まず最初に諸葛亮が、『それ』に気付いた。
(おや……何でしょう? あれは……)
シュバルツとかぐやの傍に――――うっすらと存在を感じる『何か』がそこにいる。
これは正体を確認した方がいいかもしれない。そう感じた諸葛亮は、かぐやの傍に歩み寄ると隣に座り、印を結んで呪文を詠唱しだした。
(うん? あれは……!)
その様子を見ていた左慈も、諸葛亮の目的に気づく。これは自分も手助けした方がいいと感じた左慈は、その場に座ると同じように印を結んで呪文を詠唱しだした。
やがて、二人の祈祷に応えるかのように、1人の人物がふわり、とその姿を現す。
その姿を認めた瞬間、ハヤブサは思わず大声で叫んでいた。
「キョウジ!!」
ハヤブサに『キョウジ』と呼ばれた青年は、ハヤブサの方に振り返るなり、にこり、と微笑んだ。
「ねぇハヤブサ。一つ、真面目に聞いても良い?」
あまりにもいろいろな事が一度に起きすぎて、多少混乱気味になりかけていたハヤブサであったが、キョウジに質問されたことで、はっと我に帰った。
「な、何だ?」
戸惑いながらも問い返す。キョウジに聞きたい事はいっぱいあったが、とりあえず彼からの質問に答えねばとハヤブサは思った。
「貴方は一体――――『何処』で私とシュバルツを見分けているの?」
そう言って苦笑する青年の姿は、何処からどう見てもシュバルツの物だった。だから周りの者は皆――――この青年は、シュバルツの霊体か何かだと思ってしまったのだが。
だがハヤブサは、茫然としながらも言葉を紡いだ。
「そんなの――――見れば、分かるだろう……?」
(いやいや。分からない。分からないから)
これは、その場に居たハヤブサ以外の全員が心の中で、満場一致で共有した意見であった。本当に――――これほど瓜二つと言っていい人間を、何故ハヤブサは、別の名前で呼ぶのだろう?
「そ、それよりもキョウジ……。俺から質問しても、良いか?」
「何?」
龍の忍者から『キョウジ』と呼ばれた青年が、小首をかしげる。この雰囲気も、本当に――――シュバルツとそっくりの物だった。
「お前は……やはり、『霊体』なのか……?」
「そうみたいだね。私の身体は死んでしまっているから――――」
割ととんでもない事を、この青年は軽く笑いながら答える。そのやり取りに太公望は思わず苦笑していた。どうやらこの『キョウジ』と呼ばれる青年は、とんでもなくのんきな人物か、あるいは、途方もない大物か――――のどちらかだと感じた。
「それではキョウジ……。お前は今までどこに居たんだ? そして、どうやってここに現れたのだ?」
ハヤブサのその質問に、キョウジは少し「ん~……」と、考え込む仕種をする。
「何処で何をやっていたかは、今は時間が無いから答えてあげられないけれど、私がどうやってここに現れたかは、答えられるよ?」
「じゃあ、どうやって現れたんだ?」
「うん。この人と――――あの人のおかげかな?」
ハヤブサの質問に頷いたキョウジは、そう言いながら諸葛亮と左慈の方を指し示す。
「…………!」
驚くハヤブサにキョウジはにこりと微笑みかけると、さらに言葉を続けた。
「この人たちが霊体を具現化できる祈祷をしてくれたみたいなんだ。だからこうやって、皆の目に触れることもできるし話もできる。だけど、あのおじいさんの方に負担がかかり過ぎているみたいだし、時間も限られている。だから――――早く用件を済ませてしまっていいかな?」
その言葉にハヤブサが左慈の方に視線を走らせると、確かに祈祷を行っている左慈の顔が、少し苦しそうに歪んでいる。ハヤブサは、一も二もなく頷いた。
「シュバルツは………気を失っているみたいだね」
そう言って覗き込むキョウジの視線の先で、シュバルツが目を閉じて、苦しそうに息をしていた。
「ハヤブサ。悪いけど、シュバルツの服をくつろげてくれる? 私はシュバルツの身体には、直接触る事が出来ないから」
「わ、分かった……」
キョウジの求めに応じて、ハヤブサはシュバルツのコートからベルトをはずし、ボタンをはずし、シャツのボタンをはずして行く。シュバルツの白い肌には、仙界軍の矢のせいで――――既に無数の青白いひび割れが走り、それが首のあたりまで達していた。今にも壊れて砕け散ってしまいそうなシュバルツ。ひび割れのせいで、意識の混濁が起きてしまっているのだろう。あまりにも痛々しいその姿に、ハヤブサは思わず叫び出しそうになってしまった。
「治せるのか?」
シュバルツの傷を検分するかのように見ているキョウジに向かって、ハヤブサは知らず縋りつく様に問いかけてしまう。それに対して、キョウジは力強く頷いた。
「うん――――『治す』よ」
「…………!」
力強くそう言い切られた事に、ハヤブサは息を飲んでしまう。そんなハヤブサに、キョウジはもう一度頷くと、治癒の祈祷を続けるかぐやの横に座って、金色に光る玉串に、そっとその手を添えた。
「手伝ってくれる?」
そう言って微笑むキョウジに、かぐやも頷いた。再び祝詞を紡ぎ、治癒の法を再開する。
すると―――――
ひびわれていたシュバルツの肌が、徐々に綺麗に戻って行くのが、ハヤブサの目にもはっきりと見えた。
(助かる……? 今度こそ、助けられるのか……?)
ハヤブサの中で今――――様々な想いが交錯し、渦を巻く。キョウジによって治癒されていくシュバルツの像が、自分の視界の中で変に歪んだ。ハヤブサはいつしか、大粒の涙をその瞳から零していた。だが、それにすら気がつかないほど――――彼はシュバルツの身体が治って行くのを一心に見つめていた。
(すごい………!)
巫女かぐやもまた、自身で治癒の法を施しながら、信じられぬ思いでシュバルツの身体を見つめていた。
この『キョウジ』と言う人間は何者なのだろう?
あれほど治せなかったシュバルツの身体を、こうも容易く治して行ってしまうなんて。
ふと、金色に光る玉串の上に、一粒の水滴が、ポツリ、と、落ちてくる。
「……………?」
怪訝に思ってかぐやが顔を上げると、自分の隣で玉串に手を添えているキョウジが、静かに涙を流している姿が、視界の中に飛び込んできていた。
「キョウジ様……? 大丈夫ですか……?」
何故かその姿から哀しみの波動が感じ取れたから、かぐやは思わず問いかけてしまう。それに対してキョウジは「大丈夫だよ」と、にこりと笑顔を見せた。
「それよりも――――早く、終わらせてしまおう」
キョウジにそう言われて、かぐやも頷く。かぐやは再び『治癒の法』に集中して行った。
シュバルツの身体はゆっくりと、だが確実に治って行く。
それをしながらかぐやは、横に居るキョウジの気配に気を配っていた。先程見せたキョウジのあの哀しげな涙が、少し気になっていたからだ。
だがシュバルツの治癒を進めて行っても、キョウジの方に何かを消耗したり、犠牲にしたりしているような気配は感じられない。彼の『気』は、ずっと継続して安定していた。
それでは、何故……?
その哀しげな涙は、一体何なのですか………?
そう問うこともできずに、シュバルツの治癒は推し進められていく。やがてシュバルツの肌の最後のひび割れが塞がると同時に、キョウジの手が玉串からそっと離れた。
「………出来た……」
ポツリと呟く彼の瞳から、また零れ落ちる一筋の涙。キョウジの言葉に顔を上げたハヤブサも、ようやくキョウジのその涙に気がついた。
「キョウジ、お前………泣いているのか?」
ハヤブサの問いかけに、キョウジはにこりと微笑んだ。
「あはは……ハヤブサだって、泣いているじゃないか」
「う……! こ、これは……!」
慌ててぐしっ、と、自身の涙を拭うハヤブサ。ようやく自分が、人目もはばからずに涙を落とし続けていた事実に気がついて、今更ながらひどく気恥ずかしさを覚えた。
「う…………」
シュバルツが低く呻いて身じろぎをする。どうやら、意識が戻ってきたらしい。
「シュバルツは……もう、大丈夫みたいだね」
その言葉に、ハヤブサははっと弾かれたように顔を上げた。
「ま、待て! キョウジ!」
「何? ハヤブサ」
「シュバルツと………話をしていかないのか?」
キョウジがこのまま黙って去りそうな予感がしたハヤブサは、思わずキョウジを引き留めていた。キョウジを喪って、ずっと孤独に震えていたシュバルツ。どんな形であれ――――キョウジと話をさせてやりたい、と、願った。
だがキョウジは、ハヤブサの問いかけに、少し申し訳なさそうに笑う。
「そうしてあげたいのは山々なんだけど……残念ながら、時間切れ、だ」
(あ…………?)
意識の混濁から戻ってきたシュバルツの前に、ぼんやりと視界が開ける。すると、そこに懐かしい人の顔と声があった。
「ハヤブサ、シュバルツをよろしくね」
その人は、笑顔だった。
自分の記憶の中と、寸分違わない笑顔――――
キョウジ、と、小さく呟く自分の声に、その人は振り向いてくれた。
「あ、シュバルツ。気がついた?」
「キョウジ………!」
だけどそれと同時に、ス………と、徐々に消えて行く、キョウジの身体。もう本当に――――『時間切れ』らしかった。
「シュバルツ………どうか、哀しまないで……」
消えながらその人は、優しく微笑む。
「ま、待て……! キョウジ……!」
シュバルツは懸命に身を起こそうとする。だけど、意識の混濁から戻ってきたばかりの身体は、なかなか思うように動いてくれない。
「私は、ずっと―――――」
「キョウジッ!!」
そのまま、大気に溶けるように消えて行ってしまったキョウジの身体。叫びながら伸ばしたシュバルツの手は、空しく空を切った。ただその瞬間、シュバルツの耳元を撫でた風は、とても優しかった。
「キョウジ……! キョウジ……ッ!」
シュバルツは空しく空を切った手を見てから、己の身体を抱きかかえるようにして小さく体を丸めると――――そのまま泣きじゃくり始めた。暫く辺りに、彼の悲痛な嗚咽が響く。そんなシュバルツに、そっと、慈しむように――――手を伸ばす者が居た。
「シュバルツ……」
ハヤブサは想いを込めて、愛おしい人の身体を抱きしめた。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
その手に気がついたシュバルツが、「ハヤブサ……」と、振り返る。ハヤブサは、そんな彼の身体を、ますます強く抱きしめた。
「シュバルツ……!」
腕の中に愛おしい人の感触を得ながら、ハヤブサはようやく、安堵の息を漏らした。何もかもが終わったのだと。
そして―――――
愛おしいヒトを
やっとこの手に、捕まえたのだと。
「悪いが、暫く二人きりにしてくれないか……?」
シュバルツをきつく抱きしめたまま、龍の忍者は思い詰めたような表情で、言葉を紡ぐ。
「それは構わねぇが……何でだ?」
きょとん、と問いかける張飛を関羽が軽くどついた。
「張飛よ。あの二人は久しぶりに再会して、まだゆっくり話も出来ていないのだ。積もる話もあるだろう」
そう言って踵を返す関羽の後を、張飛が「待ってくれよ~!」と、追いかける。その後に趙雲も、ハヤブサたちに軽く頭を下げてから、それに続いた。
「ハヤブサ殿、また会えますか?」
劉備の問いかけに、ハヤブサは笑顔を見せた。
「ああ。帰る前にそちらの城に寄らせてもらう」
ハヤブサの言葉に、劉備も笑顔になる。「では、引き揚げよう」と、自軍に命を下した。諸葛亮も、その後に続く。
「ではハヤブサ様……。こちらの陣に帰れる『光陣』を、劉備様の城に配置させていただきます」
そう言ってかぐやは頭を下げる。太公望に「ほどほどにしておけよ?」と言われ、ハヤブサは苦笑せざるを得なかった。
「……帰る前に一つだけ、そなた達に見せたい物がある」
左慈がそう言いながら、懐からある物を取り出す。
「これに、見覚えはありますかな?」
「こ、これは………!」
左慈に『それ』を見せられた二人が、同時に息を飲んだ。何故ならそれは、あの村で見た――――『形代の石』であったからだ。それが、真っ二つに割れてしまっている。
「ここに来る前に劉備殿の城に寄り、そこで、そなた達が助けた村の長老より、これを託された……。嘘か本当かは知らぬが、この石に訴えられたのだそうな。『ここに連れて来て欲しい』と…………」
「……………!」
シュバルツが差し出した手に、その石はそっと乗せられた。
「小生も半信半疑であったのだが、石から微かな『波動』を感じたのでな……。預かって参った。しかし、二つに裂けてしまってからは――――もうそれは、ただの石となっておる様じゃがな………」
「そうですか………」
そう言ってその石をじっと見つめるシュバルツと共に、ハヤブサもまた、黙ってその石を見つめた。不思議なこともあるものだ。もしかして、霊体となったキョウジとその石の間に、何か関係があったのだろうか?
左慈も、しばらく推し量る様にその石を見つめていたが、やがて小さく息を吐きながら、腰を上げた。
「では、小生もかぐや殿達と共に参ろう。要らぬ世話かもしれぬが、ここに結界を張っておく。これでしばらくの間、この空間は周りから切り離された状態になる。そなた達の姿も声も、外からは確認できなくなるだろう」
「えっ? ちょっとそれは――――!」
何事かを反論しようとするシュバルツの身体を、ハヤブサはギュッときつく抱きしめた。まるで、余計なことは言うなと言わんばかりの、腕の強さだった。
「感謝する」
ハヤブサの短い言葉に左慈も軽く頭を下げる。
「では――――ゆっくりな」
そう言い置くと、左慈もまた、太公望たちと共に帰路についた。
暫く、忍者二人になった空間に、沈黙が舞い降りる。
(私のこの体勢と格好……まずいんじゃないのか? とにかく服を直さないと……)
そう。治療を行ったが故にシュバルツの服は、前をくつろげさせられたままだった。今のままでは、ハヤブサの視線の前に自分の肌が曝されてしまっている。
「ハ……ハヤブサ? あの……」
おずおずと言った按配で口を開いたシュバルツに、ハヤブサは「ん?」と、視線を向けた。
「そろそろ……離してくれないか? その……服を直した――――あっ!?」
いきなりドンッ! という音と共にシュバルツの身体が強引に地面に押し倒されてしまったから、シュバルツはかなり慌ててしまう。
「ま……! 待ってくれ……! ハヤブサ……!」
「待てない」
切迫した色の輝きを湛えたハヤブサの瞳が、自分に迫って来る。
「止め……!」
軽く抵抗しようとしたシュバルツの両手は、頭上に一括りにされて抑え込まれてしまった。ハヤブサの下から逃れようとばたつかせていた足も、ハヤブサの足に抑え込まれて、抵抗する術を失ってしまう。
「シュバルツ……!」
熱に浮かされたように名前を呼びながら、ハヤブサが唇を求めて来た。
「んう………! ん………ッ!」
ハヤブサの熱い舌が、シュバルツの口腔を蹂躙する。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
何度も名前を呼びながら、深い口付けをする。ちゅくちゅくと音を立てて舌を吸いあげ、ハヤブサはシュバルツの呼吸を奪う事に専念した。
「んんっ!! や………!」
いつものシュバルツならばこれで大人しくなるのに、何故か今日に限って彼は抵抗を止めない。ならばとハヤブサは、責め手を加えることにした。空いている方の手でシュバルツの胸を弄り、敏感な部分を優しく刺激してやったのだ。
「ああっ!! 止め……! 止め、て……!」
必死に身を捩り、刺激から逃れようとするシュバルツが、可愛らしくて愛おしくてたまらない。
「シュバルツ―――――」
名を呼びながらハヤブサは、もう一度想いを込めてキスをする。その呼吸を奪う。手は、執拗にそこを刺激し続ける。
「んんっ! んんっ! ん………っ!」
それでも身を反らせながら抵抗を続けていたシュバルツであったが、やがてふわ……と、その身体から力が抜けて行った。どうやら強引に――――熱に酔わせることに成功したらしい。
「シュバルツ……!」
想いを込めてその名を呼ぶと、涙にうるんだ瞳で、見つめ返された。
「ハヤ……ブサ……」
だが今度は、まるで恐怖しているかのように、その身をカタカタと小さく震わせ始めるシュバルツ。まるで交わる事に慣れていない様な、未通女(おぼこ)い反応――――これはこれで悪くはないのだが、ハヤブサは少し小首をかしげた。
おかしい。
何をそんなに、抵抗する事があると言うのだろう?
だからハヤブサは、確認する事にした。
「どうした……? シュバルツ……」
ハヤブサの問いかけに、ビクッと、身体を振るわせるシュバルツ。やはり――――可愛らしいのだが、どこかおかしい。
「もしかして……俺に触れられるのが、嫌か……?」
「違う!」
シュバルツはその言葉は強く否定して、ぶんぶんと首を振った。
「なら何故――――?」
少し切迫した声で、シュバルツに問う。
実際ハヤブサはもう限界だった。久しぶりに触れる愛おしいヒト。早くその最奥に、触れたかった。
「そ……その……キョウジが……」
消え入りそうな声で、帰ってくるシュバルツの答え。
「キョウジ!? キョウジがどうかしたのか!?」
いきなり出て来たキョウジの名前に、ハヤブサは少し驚く。先程、霊体で現れたキョウジ。まさかシュバルツは、今もそのキョウジの存在を色濃く感じ取っているのだろうか?
「まさか――――キョウジがお前の中に居て、『嫌だ』と言っているのか……?」
恐る恐る、それは無いぞキョウジ、と、思いながらもハヤブサはシュバルツに問いかける。キョウジに嫌がられているのなら、かなり不本意だが引かねばならない、と、ハヤブサは思った。だがこの状況で、お預けとかは―――――正直、かなりきつい。
「ち、違う……! キョウジが嫌がっている、とか、そう言うんじゃ、無い……!」
馬鹿正直に答えてくれる、愛おしいヒト。あまりにも可愛らしくて、思わずハヤブサの面に笑みがこぼれた。
馬鹿だなぁ。
キョウジが嫌がっている――――と、言えば
俺は大人しく引いたのに。
「だったら――――!」
一刻も早くシュバルツと繋がりたいハヤブサは、その手で更にシュバルツを暴き立てようとする。
「で……でも! 待ってくれ! ハヤブサ……! キョウジが――――!」
まだ懸命にキョウジの名を叫ぶシュバルツに、ハヤブサの手の動きが止まった。
「キョウジが……どうした?」
問いかけるハヤブサに、シュバルツは恥じらいながらも答える。
「キョウジが……見ているかも、しれないのに……!」
「―――――!」
少し驚くハヤブサに、シュバルツは尚も言葉を続ける。
「見られているかもしれないのに……! 無理だ……! は、恥ずかしすぎて……ッ!」
そう言って耳まで真っ赤にして震える、愛おしいヒト。
「……………!」
ハヤブサは、瞬間息を飲んだが、同時に
(何だ、そんな事か)
とも思った。
ハヤブサの面に、少し嗜虐的な笑みが浮かぶ。「ク………」と、低い声を立てて、笑った。
「忘れたのか? シュバルツ」
「な、何を………?」
羞恥に震えるシュバルツの服を、さらに乱す。
「あっ! や………!」
外気に曝される肌の部分が増えて、シュバルツが再び抵抗しようとする。それを無駄だと言わんばかりに抑えつけると、真っ赤に染まっている頬を、わざと優しく撫でてやった。
「お前は……キョウジが死んでから既に一度、俺に抱かれているのに――――」
「――――!」
さっと顔色が変わるシュバルツに、たたみかけるようにハヤブサは言葉を紡いだ。
「お前から『抱いて欲しい』と求めて来たんだ。……覚えてないのか?」
「あ………っ!」
羞恥故なのか、瞳を潤ませて視線を逸らす愛おしいヒト。それを許したくないハヤブサは、顎を捉えて強引にこちらに向かせると、その唇を深く塞いだ。
「んく……ッ! んぅ……!」
「そのあられもない姿……お前はもう、キョウジに散々見せている事になるんだ……」
「あ……! う、嘘だ……! や……! んうっ!」
またハヤブサに、口腔深くを弄られる。暫くちゅくちゅくと吸われる水音が響いて――――
「……ふ…………」
抵抗しようと試みていたシュバルツの手足から、ふわ……と、力が抜けていくのが、ハヤブサにも分かった。唇を解放して、ハヤブサが愛おしい人の顔を覗き込むと、頬に一筋の涙を流しながら唇を噛みしめ、カタカタとその身を震わせる姿が、そこにあった。
苛めすぎたか、と、苦笑する一方で、どうしようもない愛おしさが身を焦がす。どうして――――めちゃくちゃにしたい程愛し抜きたい人が、この世に居るのだろう。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは己が服をかなぐり捨てるように脱ぐと、シュバルツに身体を密着させ、彼の身体をぎゅっと強く抱きしめた。
「あ………?」
肌と肌が触れあい、ハヤブサの『欲望の証』が身体に強く当たったため、シュバルツは思わず身を強張らせる。だがハヤブサはもう、本当に限界だった。その身体の震えも強張りも涙も――――全部、自分の物にしたかった。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
熱に浮かされたように、その名を呼ぶ。
「抱きたい……! お前が、欲しいんだ……!」
懸命に、訴える。知らず、自分の腰が動いて、シュバルツの身体に自身の『欲』を擦りつけてしまっている事にすら気づかずに、ハヤブサは訴え続けていた。
「あ………!」
その刺激に感じてしまって、無意識に声を上げてしまうシュバルツ。それを聞いた瞬間、ハヤブサは本当にブチ切れそうになってしまった。
だが懸命に堪えた。腕の中に居るのは、本当に、心の底から愛した愛おしいヒト。赦しを得ずにその身体を暴き立ててはいけない。強姦紛いの事をしてはいけないのだと自分に強く言い聞かせていた。
でも、欲しい。
欲しくて欲しくて――――もう、狂ってしまいそうだ。
「抱かせてくれ……! シュバルツ……!」
「ハヤ……ブサ……」
「欲しいんだ……! 受け入れて……!」
「…………ッ!」
ハヤブサの熱に煽られて、自身の身体にも熱が灯る。
あられもない姿を曝す事に対する羞恥の気持ちよりも、ハヤブサをいとおしむ気持ちの方が、シュバルツの中で勝ってしまった。
抱きしめられたが故に、ハヤブサから解放され、自由になったシュバルツの手が、ピクリ、と動く。その手は、おずおずとハヤブサの背中に廻されてきた。ハヤブサに、『赦し』の意思を伝えるためだ。
だがシュバルツは、赦しの意志を、その口で伝えることができなかった。何故なら、彼の手が、ハヤブサの背中に触れた瞬間。
「シュバルツ!!」
放たれた矢のように、ハヤブサはシュバルツの身体を激しく求めて来た。こうなってしまったら、シュバルツの口はもう、『赦しの言葉』を伝えるどころではない。ただ甲高い声で喘ぐ以外――――道がなくなってしまう。
入口を性急にほぐされ、身体のあちこちを乱暴に愛撫される。
「は……ッ! ああああ――――――ッ!!」
挿れられた衝撃で、シュバルツは果ててしまう。だがハヤブサは、その飛び散った精にすら気づかない程に、シュバルツの身体をゆすり続けた。奥へ奥へと、繋がりを求め続けた。
(ああ……完全に、飛んでる……)
身体を激しくゆすられながら、シュバルツはハヤブサの瞳を見て、思わず苦笑してしまう。こうなってしまったらもう、自分はハヤブサの方に正気の色が戻るまで、身体を許し続けるしか術がない――――という事をシュバルツは知っていた。
無理もない、もうかなり長い間、お互いに触れていないのだから、と、思う一方で、理解しがたい、とも思ってしまう。
どうして――――そんなになるまで、私の身体に溺れ続けられるのだろう。
私の身体なんて、抱いた所で何一つ良いことなんて、無いのに。
刹那、ハヤブサの楔が、シュバルツの奥深い所を捉える。
「―――――! あっ………!」
その甘美な刺激に耐えられず、シュバルツの身体が勝手に跳ねてしまう。
「駄目っ!! そこは……ッ!!」
許しを乞いながら、のたうちまわる。だが、シュバルツの身体がその刺激から逃れようとするのを、ハヤブサが許す筈もない。身体を羽交い絞めにする様に抑えつけながら、尚もそこを掻きまわすかのように、楔を打ち込み続けた。
「ああっ!! ああっ!! も……う……!」
涙を散らしながら頭をふり、シュバルツは限界を訴えるが、そこの声は、ハヤブサにはまだ届かない。
「ふあっ!! ああっ!!」
結局ハヤブサはシュバルツの中で3度吐精を果たすまで――――狂ったようにシュバルツを貪り続けたのだった。
「―――――」
とさり、と、脱力するようにシュバルツの上に倒れ込む、ハヤブサ。
(終わった……の、か……?)
全身にハヤブサの重みを感じながら、喘ぐように酸素を求め、身体の震えを止められないシュバルツ。久しぶりに最奥を嵐の様に攪拌された衝撃は、想像以上に大きかった。
「……………」
それでもシュバルツは、ハヤブサの背中にそっと手を回す。――――いつものように。
そして、そのまま髪から背を、慈しむように撫で続けた。
「シュバルツ………」
そのいつも通りの優しい刺激に、ハヤブサはふっと眼を開ける。そして顔を上げて――――シュバルツの身体を見て、その顔を少し強張らせた。痣だらけになってしまっているシュバルツの身体。「やり過ぎた」と、思ってしまっているのだろう。
「大丈夫だよ」
そう言って、優しく微笑む。
実際、どう扱われようと、どう穿たれようと――――自分は、平気だった。
ハヤブサに『満足』してもらえるのなら、それで良かった。
「シュバルツ……!」
しばらく茫然と愛おしいヒトを見つめ続けていたハヤブサであったが、やがて確認したかったことがあったのを思い出した。
こうやって乱暴に抱いてしまった自分を赦し、優しく微笑んでいる時のシュバルツは、自分に向かって声なき声で「愛している」と、言ってくれているサインだと言う事に、ハヤブサは気付いていた。
だけど―――――
「シュバルツ………」
まだシュバルツと繋がったまま、ハヤブサはその唇を求める。するとシュバルツも、優しく受け入れてくれた。そのまま互いの舌を絡め合い、優しく吸い合う。
「ん…………」
至福の様な口付けを堪能した後、ハヤブサはシュバルツに改めて声をかけた。
「シュバルツ」
「ん?」
「お前は………あの『時空の道』で、俺に「愛している」と、言わせた事を、憶えているか……?」
「―――――!」
瞬間、ビクッと強張るシュバルツの身体。
「あ…………!」
慌ててハヤブサの身体の下から逃れようとするシュバルツ。しかし、ハヤブサがそれを許す筈もない。体重をかけてその動きを封じ込めると、顎を捉えて強引にこちらを向かせた。
「逃げるな、シュバルツ」
「…………ッ!」
「この事を……覚えているんだな?」
ハヤブサの問いかけに、震えながらもこくりと頷く愛おしいヒト。ハヤブサはその反応に満足すると、更に問いかけを続けた。
「何故……あの時そんな事を、俺に言わせたんだ?」
「う…………!」
「答えてくれ、シュバルツ」
問いながらハヤブサは、指の腹でシュバルツの乳首をスリ……と、優しく撫でる。
「あっ!!」
感じて、仰け反ったシュバルツの首元に、チュッ、と、優しいキスを落とした。
「は……っ! あ………!」
「ほら……シュバルツ――――」
愛撫に反応して、プク、と熟れてきたシュバルツの乳首を、両方の手で摘まんだり擦ったりして嬲る様に弄ぶ。それをしながらハヤブサは、首元から鎖骨にかけて、優しくキスを落とす事を忘れなかった。
「あっ! あ……っ! 止め……!」
何度も上り詰めさせられて、敏感になってしまっているシュバルツの身体が、こんな優しい愛撫に耐えられるはずもない。ハヤブサの身体の下で、扇情的にのたうちまわってしまう。――――彼の望むままに。
「答えてくれないと……ずっと、このままだぞ?」
チュッ、チュッ、と、音を立ててキスを落としながら、ハヤブサはその妖艶な景色を楽しんだ。この質問に、そんなに答えを返して欲しいとは、実はハヤブサは思っていない。強いて言うなら、シュバルツを苛める口実を見つけて、それを楽しんでいるだけだった。先程素戔鳴と戦っていた時に、シュバルツに軽く苛められたから、それに対する報復の意味合いも、少し含んでいたりする。
「止め……! 止め、て……! ハヤブサッ……!」
「止めて欲しいなら………ほら………」
耐えられない、と、言わんばかりにその身をのけ反らせ、涙を散らしながら頭をふるシュバルツ。その様が、あまりにも可愛らしくていじましくて愛おしいから――――彼を苛める手が止まらない。ますます煽りたてるように、彼を攻め立ててしまう。
ハヤブサの唇がシュバルツの乳首に触れ、その手が、シュバルツの中心に触れた瞬間、シュバルツから悲鳴のような叫び声が上がった。
「ああっ!! 分かった……! 答える!! 答えるから……ッ!」
その言葉を聞いて、ハヤブサの面ににこりと笑みが浮かぶ。
「じゃあ、答えてくれ、シュバルツ」
攻め立てていた手を止めて、ハヤブサはシュバルツの顔を覗き込む。流れ落ちる涙を拭いてやりながら、髪を優しく撫でてやった。
「何故あの時――――あんな事を、俺に言わせたんだ?」
「……………」
はっ、はっ、と、短く喘ぎながら暫く潤んだ瞳でこちらを見つめていたシュバルツであったが、やがて、何かを観念したかのように、その瞳を閉じた。
「………『勇気』が、欲しかったんだ……」
「勇気?」
怪訝な顔をして小首を傾げるハヤブサに、シュバルツは頷き返すと、再び言葉を続けた。
「そう――――『勇気』……。あの時、私は独りで、時空の奔流の中に飛び込まなければならない、と、分かっていたから――――」
いくら自分が『不死』の身体を持っているとはいえ、時空の奔流の中は未知の世界。何がどうなってしまうかが分からない。何処に飛ばされるのかも、自分の身がどうなるかも、何の保証もない。
いや――――逆に『不死』の身体だからこそ、もしかしたら時空の狭間を永遠に彷徨い続けてしまうかもしれない。何処の世界ともつながれず、死ぬこともできずに――――
「笑ってくれていいよ、ハヤブサ。情けない事に、私はそれが怖くてな……。だから、お前の言葉に、縋りたかったんだ……」
「シュバルツ……!」
茫然とするハヤブサに、シュバルツはにこりと微笑みかけていた。
ハヤブサに囁かれた、愛の言葉。深く愛された記憶。
それが、自分の希望の光になると信じた。
例えこの先、永遠に彷徨わねばならなくなったとしても―――――
その光を抱いて行けば、孤独と戦えると思った。
どのような目に遭おうとも、自分の暗黒面には堕ちてしまいたくないと、願った。
孤独や絶望に負けて、DG細胞の『負』の面に自分が取り込まれてしまったら
哀しませてしまう人がいるから――――
「…………!」
「勿論、お前に愛されているのは、私も良く分かっていた……。だけど、自分に刻み込むために、あの時にお前の『言葉』が、どうしても欲しかっ………あ………!」
シュバルツはこれ以上、言葉を紡げなくなってしまった。何故ならハヤブサの唇が、彼の唇を優しく塞いでしまったからだ。
「……ん………」
優しい口付けをかわしながら、ハヤブサは泣きそうになってしまった。
どうして――――こんなにも優しくて健気な光があるのだろう。
嬉しい。
これほどまでに、自分の『愛』が、このヒトの支えになれていると言うのなら――――
「シュバルツ……!」
かつて無い程の幸せを噛みしめながら、ハヤブサはシュバルツを抱きしめていた。
「あ………!」
二人の身体がまだ繋がっているが故に、少しの衝撃で、シュバルツから甘やかな声が上がる。その声を聞いて、ハヤブサもまた、己自身がいきり立つのを感じていた。
今すぐにでも、もう一度混じり合いたい。
だけど、あと一つ、確かめたい事が残っている。
それはものすごく贅沢過ぎる事柄だとも思ったが、どうしてもそれをシュバルツに確かめてみたかった。
自分は今――――ものすごく貪欲になっている。
「じゃあシュバルツ……あと一つだけ、答えてくれないか……?」
「何だ……?」
その頬を両手で捉え、涙で潤んだその瞳をまっすぐ見つめながら、ハヤブサは問うた。
「お前はあの時……俺に『愛している』と、言ったよな?」
「―――――!」
それまでトロン、と、夢見心地の様だったシュバルツの表情が、今度こそ本当にビクッと強張った物になった。
「だ……! 駄目だ!! ハヤブサッ……!」
悲鳴の様な声を上げ、ハヤブサの下から必死に逃れようとする。だが、いきり立ったハヤブサをシュバルツは受け入れているが故に、その動きは、ハヤブサ自身に余計な刺激を与えてしまう事になった。
「――――ッ!」
たまらず緩くだが、律動を始めてしまうハヤブサ。
「ああっ!! 駄目……ッ! 止めてくれッ!!」
「お前が、誘うような動きをするからだ……!」
「ち、違う……! 誘ってなんか……ああっ!!」
尚も足掻こうとするシュバルツを、優しく、だが深い律動で引き留める。
「ああっ!! ああっ!!」
暫く、悲鳴のような嬌声を上げ、腹の下で足掻き続けていたシュバルツであったが、やがてあきらめたのか――――身体の力を抜いた。
「シュバルツ――――」
彼が大人しくなったのを見極めてから、ハヤブサはシュバルツに声をかける。
「お前が俺に『愛している』と……そう言ったのは、もう二度と会えない――――そう、思ったからなのか?」
「……………」
はっ、はっ、と喘ぐような呼吸をしながら涙を流し、震えている愛おしいヒト。その涙を優しく拭いながら、正面から問い続ける。
「答えてくれ、シュバルツ……」
「ハヤブサ……」
「お願いだから――――」
耳元に囁きかけて、優しく愛撫する。
俺はただ、確かめたいだけだ。
あの時本当に――――お前は俺に向かって「愛している」と言ったのかを。
「…………ッ」
しばらく、震えながら唇を噛みしめるようにしていたシュバルツであるが、やがて、涙を拭い続けるハヤブサの手に、そっとその手を添えて来た。もう――――逃れられない、と、思ったのだろう。
「ああ……そうだ……。私は、確かに………あの時お前に『愛している』と、言った………!」
「シュバルツ――――!」
茫然と息を飲むハヤブサの目の前で、シュバルツの瞳から大粒の涙が零れ始める。
「お前の言う通り……もしかしたらあれが、永久の別れになるかも――――と、思ったから……」
その涙は、拭っても拭っても、後から後から溢れてくる。まるで――――今まで抑えていた想いを、決壊させてしまったが如くに。
「最後に――――自分の『想い』を告げても………『許されるんじゃないか』って、思ったんだ………!」
「……………!」
(『許される』って、何に対してだ!?)
そう怒鳴りつけたくなるのを懸命に堪える。
どうしてこのヒトはいつもいつも――――何かに遠慮するような振舞いをするのだろう。
『愛している』
そう言う想いなら――――俺はいつだって渡してくれて構わないのに。
そう思いながら、多少顔が引きつり気味になってしまうハヤブサ。そんなハヤブサの様子に気づいているのかいないのか、シュバルツの独白はなおも続いた。
「覚えていておいて欲しいとか、助けに来て欲しいとか……そう言うつもりではなかったんだ……! ただ、自分のために―――――『想い』を告げておきたい。ただ、それだけだったんだ……!」
そう言って涙をぽろぽろと零す、愛おしいヒト。
「シュバルツ………」
愛おしさが、溢れる。
慈しむように涙を拭うが、腕の中の愛おしいヒトはそれを少し拒む様に頭を振った。
「でも……駄目だ……! ハヤブサ……! 私の想いを聞いては駄目だ……!」
「何故だ……?」
ハヤブサの胸が、切なさで締め付けられる。分かってはいたが、頑ななまでに愛し愛される事を躊躇おうとする愛おしいヒトが、哀しかった。
知らず、緩い律動を再開させてしまう。
「は……! あ………っ!」
「答えてくれ……。シュバルツ……」
シュバルツの言葉を奪ってしまわないように注意しながら、ハヤブサはシュバルツの身体を優しく愛した。顔を隠そうとした腕を退けて、その頬に先を促す様なキスをする。
「だ……だって……私は……!」
「うん」
ハヤブサに身体を優しくゆすられながら、シュバルツの独白は続いた。
「素戔鳴の言う通り、人間ではない……! 身体だって、危険な物で出来ている事実に、変わりはない……!」
「そうだな」
そんな事は分かり切っている――――と、言わんばかりにシュバルツの胸にキスをする。
「――――っ!」
ビクッ! と、跳ねるシュバルツの身体を抑えつけて、更に優しい愛撫を続けた。
「だから、私は……っ! お前の『パートナー』としては、ふさわしくな―――――あっ!?」
いきなり、ハヤブサの律動が激しいものに変わる。シュバルツの身体を『逃がさない』と言わんばかりに抱き寄せて、その最奥を容赦なく穿った。
「ああっ!! ああっ!! や……!! あああっ!!」
こうなってしまっては、もうシュバルツは乱れ喘ぐしか術がない。そんなシュバルツを、ハヤブサは更に追い込むように愛撫した。律動に口と手を加えて、シュバルツを高みへと導いて行く。
「ああっ!! 駄目だっ!! ああっ!! あっ!! あっ……!!」
嵐の様なそれに耐えられず、精を放ってしまうシュバルツ。
「―――――」
ガク……と、脱力してしまうシュバルツの身体を、ハヤブサは優しく抱きしめた。
「お前が、俺のパートナーにふさわしくない、だなんて……誰がそんな事を決めるんだ……!」
「ハヤ……ブサ……」
震えて、涙を流し続けるシュバルツの顎を捉えて、こちらに向かせる。
「俺が……! 俺が、愛するのは……! 後にも先にも、お前しかいないのに……!」
「ハヤブサ……! それは――――」
何事かを反論しようとしたシュバルツの唇を、ハヤブサは優しく塞いだ。
「……ん………」
しばらく、口付けの音だけが、辺りに響いて――――
「愛している……。シュバルツ……」
キスを終えた後、ハヤブサは想いを込めて、シュバルツに囁いた。
「…………!」
怯えて、身を引こうとするシュバルツを捕まえて、その耳元に囁く様に懇願する。
「言ってくれ……! お前も……! この言葉を……!」
「――――ッ!」
ブンブン! と、否定するように頭を振るシュバルツに、もう一度。
「お願いだ……! 怯えないで……!」
「し、しかし……!」
「俺も欲しいんだ! お前と同じ物が――――!」
「同じもの……? 何だ……?」
震えながら問うシュバルツに、ハヤブサは微笑みかけた。
「お前と同じ――――『勇気』が欲しい」
「――――!」
「お前が、俺の言葉を支えとしてくれたように、俺も……お前の言葉を支えにしたいんだ……!」
『龍の忍者』という肩書を背負っているが故に、自分が生きる世界は、決して平和裏な物ではない。寧ろ修羅の道だ。好むと好まざるとに関わらず、この身は戦いに巻き込まれる。または、そう言う使命を帯びる。自分は、ずっとそうやって生きて来た。それ以外の生き方を自分は知らないし、今更、その生き方を変えようとも思わない。
だから自分は、いつどこで野たれ死んでも、路傍の石の様にその屍を転がす事になってもおかしくはない。だからこそ―――――だからこそ、だ。
死ぬほど好きだと思った愛おしい人から愛された記憶は、必ず、自分の『勇気』になる。暗黒の世界を歩き続ける自分にとって、それは『希望の光』となる。
「お前と同じ、『希望の光』を――――」
「ハヤブサ……!」
「どんな泥の中からでも立ち上がる『勇気』を――――俺は、欲しいんだ……!」
「……………ッ!」
唇を噛みしめ、まだ何かを堪えようとしている愛おしい人の身体を、ハヤブサはそっと抱き寄せる。
「言ってくれ……! シュバルツ……! その唇で……!」
「ハヤブサ……ッ!」
懇願するように、シュバルツの震える唇に優しく触れる。
「だ、駄目だ……! 私は……! 私なんかが――――あ………ッ!」
再びハヤブサが、シュバルツと繋がっている腰を動かす。
「もう、手遅れだ。シュバルツ……! 俺はこんなにも深く――――お前に囚われているも同然なのに……!」
拒否をするように身を捩ろうとしたシュバルツの身体を捉え、ハヤブサは優しくゆすり続ける。たまらず、甘やかな嬌声をあげる愛おしい人の唇に触れ、もう一度、懇願をした。
「お願いだ、シュバルツ……!」
「あ……! あ……!」
「お前と同じ『勇気』を――――『希望の光』を―――――『もう一度』」
「…………!」
「『もう一度』………俺に、囁いて――――」
「ハヤブサ……!」
愛おしい人の瞳から、大粒の涙が零れ始める。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……ッ!」
縋る様に自分の名前を呼ぶ、可愛らしいヒト。その涙を唇で掬っている時、そのヒトからその言葉が、ついに漏れた。
「………愛している……!」
「…………!」
思わず顔を離して、愛おしいヒトを見つめてしまうハヤブサ。だがシュバルツは、そんなハヤブサから、涙にくれる瞳を逸らすことなく、もう一度、その言葉を口にした。
「……愛している……! ハヤブサ……!」
「シュバルツ……!」
「愛しているんだ……! ハヤブサ……!」
「シュバルツ……! ああ――――!」
夢見心地で、ハヤブサは今、シュバルツを抱きしめていた。
信じられない。
ついにシュバルツから、こんな言葉を聞ける日が来るなんて――――
ああ
今俺は
「死んでも良い」
そう思えるくらい、幸せだ――――
「ハヤブサ……ッ!」
腕の中で泣きじゃくる愛おしいヒトから声をかけられる。
「何だ? シュバルツ……」
その髪や背を撫でながら、優しく問い返す。
「一つだけ………約束をして欲しい事があるんだ……!」
「約束?」
きょとん、とするハヤブサにシュバルツは頷くと、涙にくれたその顔を上げた。
「ああ……。もしもお前に、『真に愛する人』が他に出来たら――――」
「――――!?」
ギョッと、目を見開くハヤブサに向かって、シュバルツの言葉はなおも続いた。
「迷わず私を捨てる、と、約束してくれ……! 私は……! お前の幸せの、邪魔をしたくはないんだ……!」
「な―――――!」
「お願いだ……! 私はやはり、アンドロイドだから――――んうっ!!」
馬鹿な事を言い出したシュバルツの唇を、ハヤブサは噛みつく様に塞ぐ。
「んんっ!! んぐっ……!!」
もう、本当に……!
本当に、このヒトは――――!
やっと、心を渡してくれたと思ったら――――!
酷く困難なこの恋の道のりに、ハヤブサはもう、苦笑するしかない。
仕方がない。自分は『そう言うヒト』だと言う事を百も承知で――――それでもこのヒトを、好きになったのだから。
これからずっと、それこそ自分の一生をかけて、分かってもらうしかないのかと思う。
「俺には、お前しかいないのだ」と、いう事を。
だが、とりあえず
今は――――
馬鹿な事を口走った愛おしいヒトに、このやるせない怒りをぶつける事を、ハヤブサは選択した。
「なるほど……。目茶苦茶に犯される事を、お前は望むのだな?」
「……えっ? あ――――!」
怒気を食んだ瞳でシュバルツを睨み、そう言うや否や、ハヤブサは彼の身体を乱暴に押し倒した。そしてそのまま、激しい律動とかみつく様な愛撫を始める。
「あっ!! ま、待って……!! ハヤブサッ!!」
シュバルツが悲鳴の様な声を上げるが、ハヤブサは最早聞く耳を持たない。そのままハヤブサは、シュバルツをのたうちまわらせることに専念する。
「やめっ……!! ああっ!! ああっ!!」
シュバルツの身体を知り尽くしているハヤブサは、乱暴に―――だが的確に、シュバルツを攻め立ててくる。結局シュバルツは、強制的に何度も高みへと追い詰められて――――
「ああ……! あ………っ!」
結局シュバルツが意識を手放してしまうまで――――ハヤブサのその行為は続けられたのだった。
第7章
(……ルツ……。……シュバルツ……)
誰かの、優しい声が響く。
自分の額に、誰かの優しい手が、ふわ……と、添えられた。
「シュバルツ……」
酷く、懐かしい声。
その声に導かれるように、シュバルツは瞳を開けた。
ぼんやりと開ける視界に、とても懐かしい笑顔が――――
「キョウジ!?」
叫びながら跳ね起きたシュバルツに、『キョウジ』と呼ばれた青年はにこりと微笑んだ。
「あ、シュバルツ。気がついた?」
「…………!」
全く『いつもの通り』なキョウジの姿に、シュバルツは少し拍子抜けする。何かいろいろと混乱してしまう所ではあるが、とにかく状況を把握するために、彼は周りを見渡した。
そして――――自分達が今、とても不可思議な空間に居る事に気づく。
「ここは……どこだ?」
思わずキョウジに問うていた。
それもそのはずで、シュバルツ達がいる周りには、見事なまでに何もなく、天も地も定かではない様な、ただ白い霧で覆われている様な空間であったからだ。
「……どうやら、貴方の『夢の中』、みたいだね」
問いかけられたキョウジも周りを見回しながら答える。
「貴方は今、深い眠りに落ちているから――――」
「眠りに?」
きょとん、とするシュバルツに、キョウジは頷いた。
「うん、眠りに」
「眠り………」
少し考え込むような仕種を見せたシュバルツを、キョウジは何故か、慌てて止めようとして来た。
「シュバルツ待って! あんまり『どうして自分が眠りに落ちたか』とか、深く考えない方が良い様な気が――――!」
だが、キョウジの制止は間に合わず、自分がどうしてこんなに深い眠りに落ちてしまったのか、その『過程』を思い出してしまう。
「…………! ―――――ッ!!」
「あ、ああ……思い出しちゃった?」
おずおずと聞いてくるキョウジに、シュバルツも咄嗟に言葉を返す事が出来ない。しばし、二人の間に奇妙な沈黙が流れた。
「………………」
「………………」
先に沈黙を破ったのは、シュバルツの方であった。
「そ、その、キョウジは……」
「な、何? シュバルツ……」
「み、見た……の、か? その……私とハヤブサが―――――」
出来ればキョウジには頷いて欲しくない、と、思いながらシュバルツは問いかける。しかし無情にも――――キョウジの頭は縦方向に動いてしまった。
「あ~~……え~~~っと…………うん」
「――――――!!」
絶句して、気の毒なほど顔色が目まぐるしく変わって行くシュバルツに向かって、キョウジは慌てて言い訳をしだした。
「いやそのっ!! そんなに具体的には見てないよ!? なるべく遠くの方に離れて、目と耳を塞いで、『見えない見えない~』ってしていたんだけど………!」
「………………」
「その…………何というか………」
「………………」
「すごかったね………。何かこう……『刺激的だった』と言うか――――」
「………ちょっと、あっちで腹搔っ捌いてくる」
そう言って顔を真っ赤にしながら踵を返すシュバルツに、キョウジは慌てて縋りついた。
「ちょ、ちょっと待ってよ!! シュバルツ!!」
「離してくれ! キョウジ!! あんな姿をお前に見せて、私はもう生きていられる気が――――!!」
「だからここは『夢の中』だから、切腹したって意味が無いんだってば!!」
「――――!」
はっと気がついて動きを止めるシュバルツに、キョウジもやれやれと、その手を離した。
「せっかくこうして会えたんだから、もっと話をしようよ、シュバルツ。私は、貴方に話したい事がいっぱいあるんだ」
「キョウジ………!」
キョウジのその言葉に、自分も、キョウジに対して積もる話を沢山抱え込んでいた事を思い出した。
何てことだ。あんなに、『キョウジに話したい』と飢えていたのに。
いざキョウジに会ってしまうと、そんな飢えすら忘れてしまって、普通に和んで話してしまっている自分が少し怖かった。習慣や慣れと言うのは、恐ろしいものだ。
「分かった……」
シュバルツが頷いたのを見て、キョウジもにこりと微笑んだ。
「まず――――状況を整理させてくれ、キョウジ」
シュバルツの言葉に、キョウジも「うん」と頷く。
「ここは………本当に、私の『夢の中』なのか?」
「うん、そうだよ。ここは貴方の夢の世界。だから貴方が望めば、何でもここに出てくる」
キョウジが、歩きながら説明を始める。その様子は、さながら大学の小講義でもしているような雰囲気だ。
「例えば貴方が『椅子に座りたい』と思えば椅子が出てくるし、『コーヒーが飲みたい』と思えば、コーヒーが出てくる。……ああ、すごいね。こうしている間にも、もう私の部屋が再現された」
そう言いながらキョウジが目の前のデスクに腰を落ち着けると、そこはもう、懐かしいキョウジのアパートの部屋だった。シュバルツにとっては日常の風景。今は妖蛇に破壊されてしまっていて――――もう見る事が出来ない風景でもある。
「……………」
シュバルツが少し感慨深くその光景を眺めていると、デスクの上を見たキョウジから、軽く悲鳴が上がった。
「シュバルツったら! 書きかけの論文まで再現してくれなくても良いのに―――!」
せっかく忘れていたのに――――! と、頭を抱えるキョウジ。それを見てシュバルツも、ようやく笑顔になる事が出来た。
本当に――――
涙が出るほど懐かしい、日常の風景だ。
「なるほど……ここが私の『夢の中』だと言う事はよく分かった」
そう言いながらシュバルツも、いつもの壁際のポジションに、腕を組んで凭れかかる。自分がキョウジと話す時は、いつもこうしていた事を思い出して、妙な感慨深さに浸りそうになった。それらを振り払う様に頭を振ると、シュバルツは話を進めることにした。
「ではキョウジ……一つ聞くが」
「何? シュバルツ」
「お前も、私の『夢の一部』なのか?」
「あははは……違うよ」
シュバルツの言葉を、キョウジは明るく笑って否定する。
「私だけは、ここでは異質の存在になるんだ。『霊体』になっているから、外からこうしてお前の心の中に、入り込む事が出来るんだ」
「霊体………」
「そう。ほら……私は、死んじゃっているからね」
「……………」
キョウジの話を聞いていたシュバルツの瞳が、見る見るうちに哀しみに曇って行く。
「………済まなかった、キョウジ。守れなくて――――」
「ああっ! 違うよ、シュバルツ! 謝らないでくれ!」
キョウジは駆け寄って来て、シュバルツの頬に優しく触れる。
「あの状況は、誰にも、どうしようもなかったんだ。誰だって、あんなのが急に自分の足元から襲ってくるなんて、想定しないだろう?」
「それは、そうかもしれないが………」
それでもと、シュバルツは歯噛みする。
いくら強い力を持っているとは言っても
肝心な時に守ろうとする人すら守れないならば
自分の『力』になど――――何の意味もないではないか。
「それに……私はこれから先の事、そんなに悲観はしていないよ」
「? どう言う、事だ?」
キョウジの言葉を瞬間理解しかねて、シュバルツは問い返す。それに対してキョウジはにこりと微笑んだ。
「だって、まだあきらめていない人がいるからね。失われた私の時間を、取り戻す事を――――」
「―――――!」
「ハヤブサだよ。あの人は、貴方の次に、私も取り返そうとしてくれている」
「ハヤブサが……!」
しかしどうやって、と、呟くシュバルツに、キョウジは答えを返した。
「私の死は、妖蛇が深く関わっている。だから、あの妖蛇を倒して、その上であの時間軸に戻る事が出来れば――――」
「妖蛇の出現自体が無かった事にされて……お前を、取り戻せると――――?」
「ご名答」
明るく答えを返すキョウジに対して、シュバルツは息を飲んでいた。
「本当に……そんな事が出来るのか?」
その問いに対して、キョウジは力強く頷いた。
「出来る。現に貴方も取り戻せたじゃないか。『運命の悪意』から――――」
「運命の悪意?」
「うん。本当なら貴方は、先の戦で死ぬはずだったんだ」
「な―――――!」
キョウジの言葉に、本当に絶句してしまうシュバルツ。
「それをハヤブサや皆が力を合わせて手を伸ばしてくれたから――――こうして、貴方を無事に取り戻す事が出来たんだ」
そう言いながらキョウジが、手の中からポウ、と、光の玉を発生させる。シュバルツがそこを覗き込むと、その中に、ハヤブサと、ハヤブサの腕の中で眠りこけている自分の姿が浮かび上がってくる。どうやらこれが、現在の自分達の姿らしかった。何処から取り出してきたのか、簡易の布団の様な物に二人の身体がくるまれている。自分を抱きしめて眠るハヤブサの頬には、涙が光っていた。
(ハヤブサ………!)
その涙に、何故かシュバルツは胸が締め付けられるのを感じる。じっとハヤブサを見つめるシュバルツを、キョウジもまた無言で見つめていたが、やがて、小さなため息と共に口を開いた。
「シュバルツ……貴方は知らなくてはいけない。ここに至るまでに何があったか……。私やハヤブサが、何をしてきたか――――」
「キョウジ……」
振り返るシュバルツに、キョウジはにこりと微笑んだ。
「情報の量は膨大だが、幸いにして貴方も私も今は霊体の状態だ。だから、この作業も時間的には一瞬で済む」
「…………!」
「シュバルツ、手を出して」
キョウジに言われるままに、シュバルツは手を差し出す。するとキョウジは、その手の上に、己が手を優しく重ねてきた。
「瞳を閉じて……。心を楽に――――」
その言葉と共に、キョウジの掌から光が溢れだす。
そしてシュバルツは知る事となった。
『死後』のキョウジが、何をしていたのかを。
そしてハヤブサが、如何にして自分を取り返してくれたのかを―――――
以後は、キョウジの視点で物語が進む。
足元の床がいきなり抜け、四散する部屋。飛び散る破片の中、シュバルツがこちらに向かって手を伸ばしている姿が見える。キョウジも、それに向かって手を伸ばさなければと思った。だが次の瞬間――――激しい衝撃に見舞われて、自分の意識はそこで途切れてしまった。
そして、次に目を開けた時には、辺り一面瓦礫の海と化していた。
(あれ? ここは何処だ? 私は一体、どうなっているんだ?)
きょろきょろと周りを見回すと、自分のすぐ頭上を、咆哮を上げて暴れまわり、街を破壊している巨大な龍の首がよぎって行った。キョウジはそれを見ながら、あれがこの瓦礫の山の原因か、と、何となく事態を把握する。
(それにしても……身体に痛みが無いって言うのも妙な話だよな……。あれだけ激しい衝撃を受けたと思ったのに――――)
と、ここまで思い至ったキョウジだが、すぐに自身に起きた状態異常に気がつく事になった。何故なら――――自分の身体がふわふわと浮いていたからだ。
(えっ? 何で私の身体が浮いて……? て、言うか、周りの物に触れない!)
瓦礫に触ろうとしたキョウジの手が、スカッ、スカッ、と、その瓦礫を先程から素通りしている。
嫌な予感がする。
この状況、統合的に判断するに
もしかして私って――――
………………死んだ?
チ――――――ン。
キョウジの頭の中に何故か、お鈴の音とお坊さんの「ご臨終です」という声が響き渡った。
い…………いやいやいや。
いや待て、キョウジ・カッシュ。とりあえず落ち着こう。
心を落ちつけて、深呼吸をする。吸って……吐いて……吸って……吐いて……。
よし、身体が軽くなった。
当たり前か。浮いているんだものな。
あははははは………は………。
不毛な独り会話を楽しんだ後、キョウジは己が身体を探すことに専念する。
自分の身体はすぐに見つかった。
瓦礫の下敷きになってしまっているその身体。瓦礫越しに見えた自分の身体は、首から上が――――無かった。
(……………!)
流石にキョウジも、この異様な光景には息を飲んでしまう。
しばらくその身体を見つめ、茫然としていたが、やがて、認めざるを得なくなってきた。
自分はやはり―――――死んだのだと言う事を。
「キョウジ!!」
シュバルツが、自分を呼ぶ声がする。
(ど、どうしよう――――!)
キョウジは何故か罪悪感にさいなまれてしまった。自分が死んでしまっている事を、とにかくシュバルツには知られたくないと思った。
「キョウジ!!」
シュバルツは左腕を失い、左足も千切れかけて、満身創痍の状態だった。それなのに自分の事などまるで顧みず、懸命に――――キョウジの名を呼び、探し続けていた。
(シュバルツ!! 私はここだよ!! 探し続けなくて良いよ!!)
シュバルツの傍に行って懸命に大声で叫んでみるのだが、当然のごとくシュバルツには聞こえていない。
(ど……どうしよう、どうしよう、どうしよう――――!)
自分を探さなくて良い。自分のあの身体を見て欲しくないとキョウジは願うが、それを伝える術がない事実に、焦りの色を濃くする。
ふと上空に、1羽の鳥が旋回しているのが見えた。
(ハヤブサの鳥だ!)
そうと悟った瞬間、キョウジは思いっきり口笛を吹いていた。吹いた後に、自分は霊体だから、聞こえる筈が無いと言う事実に気づく。しかし、その鳥は――――自分の方に向かって降りて来てくれた。
(この鳥……私が、視えているのか……?)
その隼と、視線がぶつかり合う。それが答えだとキョウジは感じた。
「お願いだ!! お前の主を……! ハヤブサをここに呼んで来てくれ!!」
隼は一声高く鳴くと、上空へと飛び立っていった。
ホッとしたのもつかの間、シュバルツはついに、キョウジの身体を見つけてしまう。
「キョウジ……! キョウジッ!!」
懸命に、キョウジの遺骸の上から瓦礫を退けようとするシュバルツ。
(シュバルツ!! いいって!! お願いだから、私の事なんか放って逃げてくれ!!)
キョウジは必死になって、シュバルツの傍で大声を出したり服を引っ張ろうとしたりして、彼を止めようとするのだが、やはり、その努力は徒労に終わってしまう。そしてついに――――シュバルツはキョウジの身体の総てを見てしまった。首の無い、キョウジの身体を。
「え……? キョウ、ジ……?」
そのまま ペタン、と、その場にへたり込んでしまうシュバルツ。
(だから言ったのに……!)
キョウジはそんなシュバルツを、歯を食いしばりながら見つめていた。
どうして
どうして私など、探したりしたんだ……!
あれほど止めたのに。
探すなって言ったのに――――!
「キョウジ……? キョウジ……!」
聞いたこともない様な上ずった声で、シュバルツが自分の身体に向かって呼びかけている。彼の右手が、自分の身体を起こそうと、懸命にゆすっているのが見えた。
(……………!)
ショックだった。
とにかく、衝撃を受けた。
自分の『死』が、こんなにもシュバルツにダメージを与えてしまうなんて、想像もしていなかったから――――
(私はここに居るよ)
そう言った所で、シュバルツにはもうこの声すら届かすことが出来ない。
もうシュバルツに、何もしてやれない自分が哀しくて悔しくて仕方がなかった。
「キョウジ……ッ!」
動かない身体に向かって懸命に呼びかけ続けているシュバルツの姿は、まるで親を失ってどうしたらいいか分からなくなっている幼子の様だった。
やめろ
やめてくれ
どんなに呼びかけられても、私はもう応えられないのに――――!
「シュバルツ!!」
あの隼が舞い降りてくると同時に、その主であるハヤブサがそこに来てくれた。
「―――――!」
ハヤブサは一瞬、キョウジの遺骸を見て息を飲んだ後、すぐにシュバルツの方に走り寄って行った。そのままシュバルツに声をかけ、自分の遺骸の方に歩み寄って行く。
「……………」
ハヤブサはひどく丁寧に――――自分の身体を『死者』として、扱ってくれた。キョウジの手を胸の前に交差させて、その前に頭を垂れている。
そのハヤブサの姿を見て、キョウジは何故かホッとしていた。
もう、『生』に対して足掻かなくて済むと思って、何かの肩の荷が下りた気がした。
ハヤブサがそうしてくれたことで、自分の『死』と言う物を改めて認識する事が出来る。よく分からないけれど、『死者』を『死者』として厳かに扱う行為にも、ちゃんと意味がある物なのかな、と、キョウジは漠然と感じていた。
ハヤブサの方は『死』を、ことのほか冷静に受け止めてくれているのに、シュバルツはそうではなかった。まだ遺骸に縋りつき、あまつさえ、離れるのを嫌がるようなそぶりすら見せている。
(駄目だって! シュバルツ!! あそこに居る『龍の首』が、見えていないのか!?)
キョウジは懸命に怒鳴って、シュバルツの服を引っ張ろうと試みているのだが、やはり、その総て空回っていた。だが、龍の首が火の玉を吐いた瞬間、龍の忍者がシュバルツを抱えて脱兎のごとく走りだす。
(速っ……!)
そのスピードに驚いたキョウジであるが、すぐにハヤブサたちに追いつく事が出来た。こういう時、『霊体』と言う物は非常に便利なのだなと思ったりもした。
ハヤブサは崩れかけたビルに飛び込んで、龍の首の攻撃を何とかしのいだ。
(良かった………)
ホッとしたのもつかの間、いきなり地震の様な激しい揺れに見舞われる。それと同時にビルの外側が、さっと暗黒に包まれた。
(――――!?)
キョウジがビルの窓から外をのぞくと、暗黒の中にいくつもの光が浮かび上がっては消えて行く、幻想的な世界がそこにあった。そして遠くの方に、巨大な龍の身体が光の間を縫うように、うねっている姿見える。
(何だ? これは……。何らかの異変に、私たちは巻き込まれたのか……?)
自分が霊体になっているせいだろうか。普段ならおそらく感じる事も出来ないであろう、あの龍からの『魔導』の力をビシビシと感じる。それなのに、今自分達がいる空間は、恐ろしい程静寂であった。
「う…………」
そんな中、シュバルツが低く呻いて覚醒する。龍の首から逃げる際、ハヤブサに半ば強引にその意識を奪われていたシュバルツであるが、今の揺れで、目が覚めてしまったらしい。
目が覚めると同時に、己が身体が回復する事を確認して、シュバルツは仄暗く笑いだした。
(シュバルツ……!)
キョウジはいたたまれない気持ちでそんなシュバルツを見つめていた。
キョウジの生死と自分の生死は連動している――――それはシュバルツにとっては、唯一の希望と言っても良い様な物であっただろう。キョウジが死ぬ時が、すなわちこの自分の歪な運命からの解放の時――――彼は、そう信じていた筈だった。
しかし、現実に起きた事は、そのすべてを否定する物でしか無かった。
今彼は、目の前に突きつけられていた。
『お前は、生きていない身体で死ぬこともできず、永遠に彷徨わなければならないのだ』と言う、容赦のない現実を。
もうシュバルツは、何者にも縛られる事もなく、誰よりも自由で
そしてそれは――――どうしようもない孤独の始まりでもあった。
それは、『受け入れろ』と言われても、簡単に受け入れられるものではないだろう。
『キョウジを守れなかった』という自責の念も手伝って、それは彼を、自傷行為へと走らせた。
「馬鹿っ!! 止めろ!!」
そんなシュバルツを、ハヤブサが身体を張って止めていた。
(……ハヤブサがいてくれて、本当に良かった……!)
キョウジはそんな二人を、がたがたと震え、大粒の涙を零しながら見つめていた。
今ここに、ハヤブサがいてくれてよかった。
龍の首が出現してから彼がいなかったら、シュバルツも本当に、どうなってしまっていたか分からない。
シュバルツが『シュバルツ』のままで踏みとどまれたのは、ハヤブサの支えに依るところが大きかった。
「キョウジ……ッ!」
座り込んだシュバルツが、自分の名を呼びながら号泣している。
泣かないで
泣かないで欲しい シュバルツ
私は――――貴方を、本当に地獄へと叩き落としてしまった、張本人なのだから――――
ごめん
ごめんね
貴方に伝えたい事、話しておきたかったこと――――
沢山、在ったね
こんなに早くお別れが来てしまうとは、正直思っていなかった。
シュバルツに次いでハヤブサも、涙を流していた。
暫く3人のいる空間は、ただ哀しみ一色に包まれる。
そんな中―――――
「ハヤブサ……」
涙にくれるシュバルツが、ハヤブサの温もりを求めだす。
ハヤブサも、シュバルツに求められるままに、それに応じていた。
(あ、ああ……愛し合うんだね……)
キョウジは邪魔をしたらいけないと、その場から離れる決意を固める。きっと、シュバルツのためにも自分のためにも、いつまでもシュバルツの傍に自分は留まらない方が良いのだと、キョウジは思った。
ビルの窓から外に出ようとして、最後にもう一度とシュバルツ方に振り返ると、切なさの中にも酷く妖艶な色を湛えてハヤブサを見つめる、シュバルツの姿がそこにあった。ハヤブサもそんなシュバルツを、熱い眼差しで見つめている。
(シュバルツはきっと、ハヤブサがいれば、もう大丈夫だよね……)
死後、自分がこれからどうなってしまうのかは分からない。だけど、死者には死者の、行くべき場所があるのではなかろうか、と、キョウジは何となく思う。ならば、自分はそこに赴くべきなのだ。これ以上――――生者の邪魔をしないためにも。
もう、未練はない。なのに、一抹の淋しさを感じるのは何故なのだろう。
(シュバルツ……さようなら……。ハヤブサ……シュバルツをよろしくね)
二人にそう伝えて、キョウジがビルの窓から一歩、外に出た瞬間。
「―――――!?」
いきなり、自分の霊体が、何者かによって強く引っ張られるのを感じた。
「えっ!? 何!? うわあああああ―――――!!」
間抜けな叫び声と共に、キョウジは為す術もなくそこへと導かれて行ったのだった。
ボフン、と、音を立てて、キョウジは時空の奔流からその空間へと引っ張りだされる。
「でっ!!」
それまでふわふわと浮いていた身体が、いきなり重力に従って落下したものだから、キョウジはしこたま腰を打ってしまった。
「いてててて………」
痛む腰をさすりながら立ち上がると、何やらどこからか、泣き声が聞こえてくる。
(何だ………?)
その声の主が『子供』の様であったのが気になって、キョウジはきょろきょろと、その声の主を探した。ここが何処であれ何であれ――――『子供』が哀しいままなのは、よくないことだと思うのだ。
声の主は、すぐ見つかった。
薄暗い空間の中、そこだけボウ、と、明かりが灯っているかのように輝いている場所がある。そこに白銀の長い髪を古風に結い、白に紫の色を重ねた神装束の衣服をまとった『子供』が、そこで哀しげな声を上げて泣いていたのだ。
キョウジはその子に声をかけようとして、一瞬、何故か躊躇われた。その子供自体が淡く輝き、その明りが、周囲を照らしている。あの『龍』とはまた違った、『神気』の様な物も感じる。それは、この子供が『人ならざるモノ』であると言う事を感じさせるには充分すぎる物であったからだ。
(………………)
だが、このままではこの子はいつまでたっても哀しいままだし、事態に何の進展もなく、埒もあかない。もし、目の前に居る子供が『神』で、自分が不可侵の禁を犯してしまっているのだとしても――――恐れる物は何も無い、と、思った。自分はもう、死んでしまっているのだ。失う物など、何も無い筈なのだから。
しかし、どう声をかけたものかと、子供との距離を歩いて縮めながら考えていると、その子の手元で淡く光り輝く『何か』が創りだされているのが見えた。それが、自分にはとても見知っていた物に見えたので――――キョウジは、思わず考えるより先にその子に声をかけていた。
「それは、桜の花? それとも、梅の花かな?」
「――――!」
ビクッ! と、振り返る子供に、キョウジは人懐こい笑みを浮かべて応えた。
「こんにちは」
「なっ! 何者じゃ!? 貴様は――――!!」
「え、え~~~っと、何者かと言われても……」
警戒心も顕わにこちらを睨みつけてくる子供に、キョウジは苦笑する。自分が何者かと説明し、怪しい者ではないと証明する事は、存外難しいものだ。
とりあえずキョウジは、自分が何者かということを説明してみることにした。
「私の名はキョウジ・カッシュ。28歳。男。学者をやっていました。ついさっきまで人間として生きていたんですけど、突然現れた『龍の首』みたいな物に襲われて、どうやら死んでしまって――――こちらに来てしまったようです……けど……」
「龍の首?」
白銀色の瞳を向けながら、小首を傾げる子供。その額には、三日月の文様が刻まれていた。キョウジは頷き返すと、「ここからそれが見えるかな?」と、何かを探すような仕種をして見せた。すると、遠くの方に、ボウ……と、龍の身体がうねっている姿が浮かび上がってくる。
「あれです。恐らくあれに巻き込まれて――――」
「そうか」
子供はそれだけを言うと、またキョウジから自分の手元に視線を移して、ぐじぐじと泣き始めた。
「だ、大丈夫か?」
睨まれはしたが、特に子供の方から強く拒否されるような様子もなかったので、キョウジはもう少しだけ子供の方に近寄って、その傍に座った。
「大丈夫ではない! これが泣かずにいられるか!!」
「ど、どうしてそんなに泣いているんだ? 私でよければ話を聞くよ?」
「………………」
そう言って顔を覗き込んでくるキョウジを、その子供はしばらく推し量る様に見つめていたが、やがて、ポツリ、ポツリ、と口を開いた。
「わ………吾を、熱心に祀ってくれていた、村の者たちが、居たのだが………」
「うん」
「い……戦に巻き込まれて……ッ! 皆、死んでしまって……ッ!」
「…………!」
その言葉には流石にキョウジも絶句するしかない。
「遺体も片付けられず、野ざらしのままじゃ……! だからせめて吾だけでも、皆を供養してやりとうて、その真似事の様な物をしておるのじゃが――――」
そう言って涙を流す子供の前に、小さな石が積み上げられている。供養塔のつもりなのだろう。
「じゃが………とても人数分の花を咲かせてやる事など出来ぬ! あまりにも――――哀しすぎて……ッ!」
そう言って、涙にくれる子供の手元から――――また一輪の、八重咲きの花が生み出されてくる。それはとても綺麗で、それでいて、何故か胸が締め付けられる色を湛えていた。
「そうですか……」
キョウジは短くそう言うと、胸の前で手を合わせて、その石積みの塔に向かって丁寧に頭を下げた。その仕草を見ていた子供が、遂に、声を上げて泣き始めてしまう。いろいろと堪えていた物が、堪え切れなくなってしまったのだろう。
「何故じゃ……! 何故吾は……このような事しか……! 花を咲かせることしか出来ぬのじゃ……! こんな事が出来た所で、何の役にも立ちはせぬと言うのに――――!」
そう言って顔を覆って泣き伏してしまう子供の手元から、また一輪、花が零れ落ちてくる。よく見ると、石積みの塔の傍には淡い光を放つ綺麗な花々がちりばめられる様に撒かれていた。この子が泣きながら――――それでもやっと、これだけ咲かせたものなのだろう。
「……………」
キョウジは黙ってその花々を集めると、その石積みの塔の周りを綺麗に飾り付けし始めた。やがて終わると、もう一度手を合わせて、その塔に向かって丁寧に頭を下げる。
「……貴方は『神様』なのか?」
頭を下げ終わったキョウジが、振り返りながら子供に問いかける。それに対して子供は、涙を拭いながら答えた。
「吾は、『神』などとたいそうな者ではない――――。じゃが、『人外』である事は、確かじゃな……」
懐から懐紙を取り出して、チーン! と、鼻水を拭く。
「一応、これでも吾は、300年生きておる」
「300年!?」
驚くキョウジにその子供に見える者は頷いた。
「でも、まだたった300年じゃ……。まだまだ『神農(しんのう)様』と比べたら、ひよっこも同然じゃ……」
「神農様?」
耳慣れない名前にキョウジがきょとん、としていると、子供に見える『神』は『心外だ』と言わんばかりに憤慨しだした。
「そなた! 神農様を知らぬのか!? 神農様はお偉いお方ぞ!! 医学にも農業にも全般に通じておられる、頭の良い御方なのじゃ!! 草や木も、神農様のためならば、喜んでその力を貸す程の御方なのじゃぞ!!」
「す、すみません! そちらの方は不勉強なので……!」
キョウジは慌てて平謝りに謝る。すると、『神』の方もフッと小さくため息をついた。
「……まあ良い。知らぬ事など、誰にでもある事じゃ……。それに、名を知らなんだぐらいで目くじらを立てるような事は、神農様も望まれぬであろう……」
「すみません、本当に……」
尚も恐縮して謝るキョウジに、「良い」と、『神』も頭を振る。
実際、この『神』は、キョウジに対してそんなに怒ろうと言う気は起きてはいなかった。それは、自分の建てた供養塔に、この青年が綺麗に花を飾り付けてくれたのを見た所為かもしれなかった。
「……それよりも、また、花を咲かそう……」
ポツリとそう言うと、また、花を咲かす作業に戻る。その両の手から、ふわりと八重咲きの小さな花が、また姿を現した。
「……綺麗な花ですね……」
キョウジが素直に感想を述べると、その『神』も、小さく笑った。
「……桃の花じゃ……。吾の村の者たちは、桃を大事に育てておった故――――」
そう言っている間にも、次から次へと桃の花は現れてくる。『神』は、もう泣いてはいなかった。否――――「泣いていない」と言うよりは、涙が涸れ果ててしまっている、と、言った方がしっくりくるようにキョウジは感じた。
「……どんな村だったか、聞いても良いですか……?」
遠慮がちに、ポツリと『神』に問うてみる。この神様は、少し自分の想いを吐き出した方がいいのではと、キョウジは思ったからだ。断られたら、それはそれで止むなしと思っていた。
「………………」
『神』は、暫くキョウジの方を推し量るように見つめていたが、フイ、と、視線を逸らして小さく笑った。
「……そうじゃのう……。どうせじゃから、聞いてもらおうか……」
それから『神』は語りだす。自分がどのようにして、あの村の者たちと縁づいたのかを――――
『神』の名は、『屁舞留(ひまる)』と言った。神仙界で生まれ落ち、そして神農の元で、修行する筈の者であった。何故、『修行する筈の者』であったのかというと、屁舞留はそれが出来なかったからである。何の間違いがあったのか―――――生まれ落ちたと同時に屁舞留の幼体は、人間界に落ちてしまったのだ。
人間界に落ちた屁舞留は、そのまま石になってしまった。
最初の内は助けを呼ぶために叫んだり足掻いたりしたものだが、そのすべてが徒労に終わってしまうと悟ると、屁舞留は50年で足掻くのを止めた。誰にも気づかれずにそのまま100年、川の清流に打たれ続けた。
流石に100年もじっとその場に留まり続けていると、いろいろ退屈になって来る。次の100年は、川の中を探索したり、野原を転がったり、あちこちを冒険して過ごした。と言っても所詮は石の身体。そんなに長い距離を動けた訳でもなく、身体の大きさもだんだん削られて、小さなものになって行く。
それでも、自然の理を沢山見知った。もうこのまま自分は削られ切って、消えてしまっても良いか、と、思い始めた200年目のある日、1人の男に自分の身が拾われた。
その男は何を思ったのか、自分のために祠を立て、祀り物をしてくれた。
いきなり、雨風をしのげる建物を貰い、更には、水や食料まで貰ってしまった訳である。この感激を――――どのように言い表せればいいと言うのだろう。
その男の祈りと貢物のおかげで、屁舞留は石の中から霊体を得るまでに霊気を回復する事が出来た。
(これは、何か恩を返さねばいかん)
未熟ながらに屁舞留はそう思ったので、夜な夜な石から抜け出ては、男と、男が耕している畑を見ながら考え続けた。そして、至った結論が、「畑の植物に、出来るだけ花を咲かせてやろう」と、言う事であった。
「花を?」
問うキョウジに、屁舞留は頷く。
「そう、花を――――。200年石の身に在ったおかげで、この程度の『奇跡』は起こす事が出来た。と、言うか……これしか吾は出来なんだから――――」
(そ、それって……立派に『豊作の神様』の仕事なんじゃあないかな~)
キョウジはそう思ったが、敢えて口には出さなかった。今は屁舞留の話を聞く事に専念するべきと思った。
当然、畑の作物は豊作になる。男は喜び、さらに熱心に祀ってくれるようになった。屁舞留も律儀にそれに応えた。結果――――男を中心としたその村は、徐々にだが、豊かな物になっていった。
「小さいが、良い村だった……。新しく始めた桃の栽培も軌道に乗って、何もかもがこれからって言うその矢先に――――」
「戦に巻き込まれて……皆、死んでしまったと?」
「――――――」
こくん、と頷く屁舞留に、キョウジも小さなため息をついた。
「それは……ちゃんと、供養しないと、ですね……」
そう言いながらキョウジは、再び屁舞留が咲かせた花を集めている。また、供養塔を綺麗に飾り付けてくれるつもりなのだろう。その心遣いは、屁舞留の瞳に、再度涙を呼びもどしてしまっていた。えぐえぐと泣き出す屁舞留。それを見たキョウジは思わず――――
ポンポン、と、その頭を撫でてしまっていた。
「キョウジ――――」
びっくりしたように屁舞留に見つめられて、キョウジもはっと我に帰った。
「ああ、えっと……! これは、ですね……!」
慌てて言い訳しようとして、割と言い訳不能な状態である事に気づく。
(何て事だ……! 私の馬鹿……! つい、弟を慰めていた習慣が――――!)
そう。キョウジは8歳年下の弟が泣くたびに、そうやって慰めて来た習慣があるのだ。だから目の前で年下に見える人物に涙を流されると、つい――――考えるより先に、手が勝手に動いてしまうのである。
「すみません!! 勝手に触ってしまって―――!」
慌てて謝るキョウジに、しかし屁舞留も首を横に振った。
「構わぬ。吾も、少しびっくりしただけだ……」
屁舞留は無言で撫でられた跡を自分の手で触る。自分の身体を他人の手で触られるのは、随分久しぶりだと思った。
「キョウジ……。もう一回、撫でてくれ」
乞われるままに、キョウジはもう一度、屁舞留の頭を撫でてやる。屁舞留はしばらくじっとキョウジの手の感触を、己が頭で味わっていたが、やがてポツリと呟いた。
「吾の村……キョウジにも、見せたかったのう……」
その言葉に、キョウジも優しく微笑む。
「綺麗な村だったのでしょうね……」
「そうじゃ……。とても綺麗だった。ほら、丁度あの村みたいに、桃の花がたくさん咲いて――――」
と、ここまで呟いた屁舞留が、怪訝な顔をして首を捻りだしている。
「どうしました?」
それに気がついたキョウジが問いかけると、屁舞留が目にとめた村を食い入るように見つめながら茫然と呟いた。
「………吾の村がある」
「えっ?」
瞬間、その言葉が理解できないキョウジに、屁舞留が更にたたみかけるように話しかけてきた。
「間違いない!! あの木、あの社――――どう見ても、あれは吾の村の物じゃ!!」
「え………? え………っ?」
茫然とするキョウジの手を、屁舞留が強引に引っ張る。
「行くぞ! キョウジ!! 事の真相を確かめねばならん!! ついてくるのじゃ!!」
「えっ? あの……っ! あ、あ~~~~~!?」
キョウジの間抜けな叫び声を残して、二人はその空間から村へと飛び立っていったのだった。
二人は村の中央の広場に、ふわり、と、風の様に降り立った。
だが、二人の姿を感知する物は、村には皆無なのであろう。村の者たちは皆そこに何も無いかのように、普通どおりにふるまっているように見えた。
(まるで、昔話の本の世界の様だな……。いつぐらいの時代のものだろう?)
そう思いながらキョウジが村の風景を眺めている横で、屁舞留が興奮を抑えきれないようにきょろきょろと周りを見回していた。
「何故じゃ!? 間違いない!! これは、滅んだ筈の吾の村じゃ!!」
「……それは、確かなのですか?」
水を差すようで申しわけない、と、思いながらも、キョウジは確認するように屁舞留に問う。それに対して屁舞留は、噛みつかんばかりに答えを返してきた。
「そうじゃ!! 間違いない!! これは、吾の村じゃ!! あそこを通っているのは大作じゃ! 裏に一町ほどの桃畑を持っておる! あそこに居るのは繁造。今年生まれたばかりの赤子がいる! 吾は、ここに通る村人の名前と家族構成を、皆言う事が出来るぞ!!」
「そうですか………」
屁舞留の言葉を聞きながら、キョウジはその原因を探ろうと考え込んでいた。何故――――滅んだ筈の村が、今またここに甦っているのだろう?
その考え込んでいるキョウジの横を、1人の子どもが走り抜けていく。
「ケイタ……!」
屁舞留に「ケイタ」と呼ばれたその少年は、広場をまっすぐ走り抜けると、大きな樹の元にある、屁舞留の社の傍で腰を下ろす。
「土地神様!! 見てよ!! 今日、俺算術で満点を取ったんだ!!」
そう言って嬉しそうに、土地神の社に向かって紙をかざす。確かにその紙には、朱色の墨で花丸が彩られていた。
「……ケイタは子供たちの中でも、特に熱心にああして吾に話しかけてくれておった。吾もケイタが大好きじゃ……」
そう言う屁舞留の眼差しが、本当に優しい色を帯びていたから、キョウジも思わずつられて微笑んでしまう。広場の反対側では、寺子屋が終わったのであろう、子供たちが元気な声を上げながら走り回っている。それを、周りの大人たちが声をかけたりしながら、優しい眼差しで見守っていた。その光景を見ながら、キョウジはこの村にうっかり郷愁(ノスタルジー)を感じて何故か涙が出そうになってしまう。皆が子供を大切にしているこの村を、キョウジはとても好きになっていた。
「ケイタ………」
屁舞留はしばらく、ケイタの隣に座って、うんうん、と、頷きながら話を聞いていたが、何を思ったのか、いきなりその表情を硬くした。
「………帰るぞ」
屁舞留は短くそう言うと、キョウジの手を取って、強引にそこから飛び去って行った。
「屁舞留? どうしたんだ? 一体――――」
あれほど懐かしそうにいろんなものを見て、嬉しそうにはしゃいでいた屁舞留の表情が、何故いきなりそんなに硬く暗い物になってしまったのか、キョウジは皆目見当がつかない。だから、その原因を知りたいと思って、また、屁舞留にもう一度、あんな風に笑って欲しいと願って、キョウジは懸命に問うていた。そして、何か自分が力になれる事があるのなら、手を貸してあげたいと思っていた。
「あの村は、貴方の村で間違いないんだろう?」
「ああ……。確かに、滅びる前の、吾の村で間違いはない……」
しかし、何故――――と、疑問を呈する屁舞留に、キョウジが苦笑しながら答える。
「……おそらく、『あれ』が原因なんじゃないかな」
キョウジが指を指した方に、咆哮を上げながら光の間を縫うように飛びまわっている妖蛇の姿があった。
「あいつが今、いろんな世界の時間軸と磁場を、ひっちゃかめっちゃかに掻きまわしているんだ。だから、時間軸の前後がひっくり返ったり、世界と世界にあり得ない繋がりが出来ている。そのせいで、あそこに村が出て来たんじゃないのかな」
あくまでも憶測だけど、と付け加えるキョウジに、屁舞留はちらりと視線を走らせると、やがてポツリと呟いた。
「……そうかもしれぬな。確かに、村は吾の村であったが、その周りの風景が――――吾の見知っていた物とは違うように感じた」
「せっかく、懐かしい人たちと再会したんだろう? なら何故――――そんなに暗い顔をしているんだ?」
「……………」
キョウジのその言葉に、屁舞留はしばらく押し黙っていたが、やがて、頭を抱え込みだした。
「そうか……キョウジには、見えていないのだな……。いいだろう、見せてやろう。吾の懸念の原因を――――」
そう言うと屁舞留は、睡蓮鉢に水をなみなみと注いでくる。
「この水を通して――――あの村を見てみるがよい。キョウジ」
「……………?」
屁舞留に言われるままにキョウジはその睡蓮鉢を覗き込んで―――――思わず息を飲んでいた。村の上空に、巨大な闇の塊が鎮座していたからである。
「な……! 何だ……? この黒い塊は……!」
「お前に分かりやすく言うのなら……『死神』の様な物だ……」
暗い表情をした屁舞留が、ポツリと、零すように呟く。
「前に、村が滅んでしまった時にも、村の上空に『あれ』が居たのだ……」
「…………!」
「『あれ』が現れた以上、もう、どのようにしても村の運命は変えられぬ。皆また――――死んでしまうしかないのだ……」
「な―――――!」
そんな馬鹿な、と、キョウジはもう一度、その水盆を通して村人たちの方を見る。すると、村人たちの方にも、皆一様に黒い塊が張り付くように乗っていた。中でも、ケイタと言う少年の肩に乗っている黒い塊は、一段と色が濃かった。
「こ、これは……? この色の濃さの違いは、一体何だ……!?」
「それは……皆の死期の違いを現しておる……。ケイタの方が、死期が近い、と、言う事じゃろうな……」
屁舞留がけだるそうに答える。キョウジはただただ、絶句するしか無かった。
「こんな……! こんな事って――――!」
キョウジの拳が小さく震える。
「これをこのまま放置しておいていいのか!? 何とかしないと――――!!」
キョウジのこの言葉に、屁舞留は面にびっくりしたような色を浮かべるが、すぐにその表情を硬くした。
「……無理じゃ。あれはが出て来てしまった以上、もうどうにもならぬ」
「どうにもならないかどうか、やってみないと分からないじゃないか!! ただ傍観しているだけだなんて――――!!」
「ではキョウジ、問うが……! 一体吾に、何ができる!?」
「……………!」
「吾が村の広場の真ん中で声を上げても、吾の声を聞く事の出来る者など誰もおらぬ!! そして、吾が出来るのは花を咲かす事だけ――――!! それで、どうやって皆の運命を変えよと言うのだ!? 土台、無理な話ではないか……ッ!!」
そのまま顔を覆って泣き崩れてしまう屁舞留。キョウジは、かけるべき言葉を失ってしまった。
しばらく、屁舞留の嗚咽だけがその場に響く。
そうやって、どれくらいの時が過ぎた事だろう。
「…………でも……!」
キョウジは、いつしか拳を握りしめていた。
「それでも――――!」
キョウジは地面に転がっていた石を拾い上げると、その黒い塊に向かっておもむろにそれを投げつけ始めた。
「な……何をやっておるのじゃ? キョウジ……」
唖然と、その様子を見守る屁舞留に、キョウジは振り向きもせずに答える。
「何って…………あの黒い塊を、何とか追い払えないかなと思って――――」
そう言って、ひたすらキョウジは石を投げ続ける。だが当然のごとく、石は虚空に吸い込まれるだけで、何がどうなると言う訳でもない。その呆れるほど無駄な行為に、屁舞留ですら思わず面に失笑に近い笑みが浮かんだ。
「無駄じゃ、キョウジ……。お主、吾を笑わせたいのか?」
「笑いたければどうぞご自由に……。ですが、私は大真面目です」
「キョウジ……」
「一生懸命に足掻いて、それでも駄目だったら仕方がない。けれど、何もしないで『無駄だから』とあきらめてしまう事だけは――――」
キョウジは、持っている石を渾身の力を込めて、闇に向かって投げつけた。
「私は!! 絶対に嫌だッ!!」
「キョウジ………!」
屁舞留はキョウジのその叫びに茫然としていたが、やがてポツリと呟いた。
「気持ちは分からんでもないが、その石を投げる行為は止めろ。本当に、無意味な事だぞ?」
「………ですよね」
屁舞留の言葉に、キョウジも苦笑しながら振り向く。だが彼は、まだあきらめる気はないのか、周りをきょろきょろと見渡していた。
「何か方法はないのか……? 何とかあの闇を払う、方法は――――」
「キョウジ……。その様に必死にならずとも良い。その気持ちだけで充分じゃ……。それに、あの者たちと主の間には、接点など何もないではないか。主がそんなに心を砕かずとも――――」
「それでも!! あそこに居る人たちが皆死んでしまったら、また貴方が独りで泣いてしまうのだろう!?」
「――――――!」
「私は……! 絶対に嫌だ!! そんな、哀しい事は――――!」
「キョウジ……!」
屁舞留は本当に、言葉を失って茫然としてしまう。
この目の前に居る青年は、一体何だと言うのだろう。
何故、こんな出会ったばかりの自分のために、見ず知らずの他人などのために、ここまで親身になろうとしてくれるのだろうか。
(吾の村の村人たちも、かなりお人好しな部類に入ると思っておったが……このキョウジと言う青年も、相当なお人好しじゃな……。それとも、『人の子』と言うのは、皆こういう者なのか?)
いつしか落ち込むことすら忘れてしまって、屁舞留がう~ん、と、考え込んでいると、不意にキョウジから叫び声が上がった。
「シュバルツだ!!」
「えっ?」
驚いて顔を上げた屁舞留の視線の先に、時空の道を渡ろうとしている3人の人間の姿が飛び込んでくる。そのうちの1人があろうことか、その結界の外に放り出されようとしていた。
(あのままだとシュバルツは、こちらに向かって流されてくるな……)
そう悟った瞬間、キョウジは屁舞留に向かって叫ぶように提案していた。
「屁舞留! シュバルツを貴方の村に飛び込ませてもいいか!?」
「えっ? それは、構わぬが……」
屁舞留はシュバルツの顔を見て、更に驚いていた。
「キョウジ……あの者の顔、お主とそっくりではないか。一体、何者なのだ?」
「その話は、時間がある時にでもゆっくりさせてもらいます。ちょっと、いろいろと複雑な事情があるので……」
「そうか? ……まあ、無理に話したくない事ならば、吾も敢えて聞きはせぬが……」
そう言う屁舞留に、キョウジもまた、笑みを返す。
「しかしキョウジ……あの状況から、どうやってシュバルツとやらを村に飛び込ませるのだ?」
「話は簡単です。あのままだとシュバルツは、結界の中の二人を守るために、おそらくあの手を離します」
「何っ!?」
驚き、息を飲む屁舞留に、キョウジは穏やかな眼差しを返した。
「時空の乱流の中にその身を放り出すなど、神仙界の者ですらやらぬ事ぞ……!? それを、あの者はやると言うのか!?」
「――――やります。シュバルツは、そう言う人です」
「…………!」
言葉を失う屁舞留に、キョウジは微笑みかけた。
「さあ、あまり時間が無い。シュバルツの身体が流れている方向からして、手を離した後、おそらくこちらに向かって流れてきます。それを捕まえるか方向転換させるかして、貴方の村に彼の身体を放り込む」
「う、うむ」
「出来ますか?」
「旨く出来るかどうか分からぬが――――出来るだけの事は、やってみよう」
そう言いながら、屁舞留はその手から蔓性の植物を編み出すように生やしている。それでシュバルツを捕まえるつもりなのだろう。
「来る!! 構えて!!」
キョウジの言葉に弾かれるように、屁舞留は蔓性の植物をネットの様に広げ、結界より外に出した。
「キョウジ! 吾の身体を押さえておいてくれよ!!」
結界の外にネットを出している屁舞留から、悲鳴の様な声が上がった。それだけ時空の乱流から受ける抵抗は、凄まじい物があるのだろう。それにキョウジも「はい!」と答えて屁舞留の身体を押さえる。しかし、時空の乱流に引きずられ、ともすれば二人の身体は結界の外に引っ張り出されそうになった。
そんな中、ハヤブサたちから手を離したシュバルツが、猛スピードでこちらに向かって流れてくる。それを、屁舞留の張ったネットが、バシン! と、音を立てて受け止めていた。
「屁舞留!!」
「ク……ッ!! こ、この……ッ!!」
ズズ、と、引きずられる屁舞留の身体。屁舞留は最初、シュバルツを捕まえた後、一度結界の中に引き込もうと思った。だが何故か、結界の中に引き込もうとする動きを拒否される様な抵抗を感じた。それが凄まじ過ぎて、屁舞留は結局シュバルツを結界に引き込む事を、断念せざるを得なくなる。
こうなればと、シュバルツの身体をただ村に叩きこむ事だけに専念する事にした。
「こ、この……! これで……どうだあああああっ!!」
何とかネットを村の方向に転換させて、シュバルツの身体を強引にそこから叩き出した。それと同時に屁舞留の作り上げた蔓のネットがバシン! と、音を立てて砕け散る。
「うあっ!」
「屁舞留!!」
弾き飛ばされて倒れそうになった屁舞留を、キョウジが支えた。だが反動が強すぎて、二人揃って尻餅をついてしまう。
「屁舞留! 大丈夫か!?」
「あ、ああ……。何とか、な……」
屁舞留はそう呟きながら、ゆるゆると身を起こす。
「それよりもキョウジ………」
「何だ? 屁舞留」
「あ奴は……無事に、村に着いたか?」
「――――!」
その言葉にキョウジが村の方を覗き込むと、丁度シュバルツが村に落下している最中だった。
「うわ……ッ! ちょっ……! 退いてくれええええええ!!」
落下地点に人の姿を認めたシュバルツが、悲鳴のような叫び声を上げる。それに気がついた村人たちも、慌ててそこから蜘蛛の子を散らすように逃げて行っていた。
「……無事、着いたみたいですよ?」
キョウジの言葉に、屁舞留もほっとしたような笑みを浮かべる。
「そうか……。いささか荒っぽい手段を取ったので、どうかと思うておったが、大丈夫だったようじゃな……。良かった……」
それから屁舞留も村の方を覗き込んで、何故かにやにやと笑い出した。
「おっ、丁度村は『儀式』の最中であったようじゃな……。キョウジ、見ておれ。中々に面白い物が見れるぞ?」
「儀式ですか?」
きょとん、とするキョウジに屁舞留はくすくすと笑いながら頷く。
「そうじゃ。毎年桃の花の季節に、あの村の者たちは、吾に今年1年の豊作を祈願する儀式を行うのだが………そのしきたりがなかなか面白くての。吾も気に入っておるのじゃ」
「儀式の、しきたり………と、言うと?」
「別に、血なまぐさい物ではないぞ? 吾は、平和主義者じゃからのう」
いささか嫌な予感を感じながらも問い返すキョウジに、屁舞留は、実に楽しそうに答えてくれた。
「実はのう……。儀式の最中に、一番初めに祭壇の上を通った『生き物』を、今年の『吾の代理の者』として崇めると言うしきたりがあるのじゃが――――」
「えっ?」
「ああ、案の定、今年の『吾の代理』は、あのシュバルツとやらに決定したようじゃ」
「えっ?」
茫然と見守るキョウジの目の前で、シュバルツが皆に「神様!」と、崇められだしている。それをシュバルツが必死に恐縮したり遠慮したり、逃げだそうとしたりしているのだが、村人たちに強引に押しとどめられていた。
「まあ、実際あの村にあの者を送り込んだのは吾の様なものだし、正真正銘『吾の代理』と言う事で間違いはないな。うん、何の問題もないじゃろう!」
「え~~~っと…………」
うんうん、と、1人納得したように頷いている屁舞留の横で、キョウジが顔をひきつらせながら頭をかいている。
「屁舞留……あの……」
「何じゃ? キョウジ」
「ちょっと確認させて欲しいんだけど……『貴方の代理』と言う事は、その……シュバルツはあの村で――――」
「うむ。『吾の代理』であるから、『神』として崇められる事になるじゃろうな」
「…………!」
ズバッと屁舞留に言い返されて、キョウジは言葉を失ってしまう。
「それにしても、『言葉』をしゃべる者が吾の代理になるのは初めてじゃ。今までは、虫や蛙と言った、ささやかな者たちばかりであったからのう!」
そう言って、からからと笑う屁舞留の横で、キョウジは頭を抱えてしまっていた。
(あちゃ~! どうしよう……! 『村に放り込む』と提案したのは確かに私だけれども、こんな大事になってしまうなんて――――)
どうしよう……。こんな事シュバルツにばれたら、絶対に恨まれるか怒られるかする――――と、ここまでキョウジの回想が進んだ所で、目の前に居るリアルタイムのシュバルツから「ほう!」と、声が上がった。嫌な予感しかしないキョウジが目を開けると、目の前のシュバルツが、その面にひきつり笑いを浮かべている。
「そうか……。私があの村に飛び込んだのは、裏にそう言うからくりがあったのか……」
(あ、あれ? やばい……! これは確実に、最低1時間以上の説教コースが用意されていそうな気がする……!)
「キョウジ―――――」
「あ~はははは! シュバルツ! お話は後で聞くから、今は続きを見ようよ。続きを~☆」
「……………!」
明るく笑って切り返してくるキョウジに、シュバルツもとりあえず黙ってくれた。しかし、自分に対して言いたい事が大量に心の中で浮かんでいるのか、そのこめかみに怒筋が浮かび、彼の背負っているオーラが黒く淀んで行っているのが分かる。
(あはははは……。いやだなぁ、書きかけの論文の事もあるし、何だかだんだん、生き還りたくなくなってきた……)
などと阿呆な事を考えるキョウジなのであったが、その回想はノンストップで続いて行く。
「で、でも……! 屁舞留―――!」
「ん? 何じゃ? キョウジ……」
シュバルツが自分の『代理の者』となっても特段気にもせず、のんきに構えている屁舞留に、キョウジは少し心配になってしまう。
「シュバルツをあのまま『神』として村人たちに拝ませておいていいのか? 下手をしたらあそこの人たちは、シュバルツの言う事なら何でも聞いちゃうって事になるだろう?」
「おお、そう言えば……そう言う事になるな」
「だったら、この状態は危険すぎないか!? シュバルツがもしも、とんでもなく極悪人だったら――――!」
「何を言っておるのじゃ? キョウジ。あの者が極悪人な訳無かろう」
「えっ?」
ずばりと屁舞留に真顔で切りかえされて、キョウジは瞬間、頭が真っ白になってしまう。
「い、いや……だって――――シュバルツがどう言うヒトか、貴方はまだよく知らな――――」
「他人のために、いとも簡単に自分を犠牲にする者なのだろう?」
「えっ?」
「お主、吾にそう言ったではないか。時空の道で、結界の中の二人を守るために、自分を犠牲にすると――――」
「……………!」
「そう言う人間を、お主の尺度では『極悪人』と言うのか?」
「え、えっと……それは、その………」
キョウジは返す言葉に困窮してしまう。そんなキョウジを暫くじっと見つめていた屁舞留であったが、やがてポツリと口を開いた。
「しかし、あのシュバルツと言う者………少し変わっておるな……」
「えっ?」
「『中身』が、普通ではない……。人間ではないのだな?」
「―――――!」
屁舞留の言葉に、キョウジは表情を硬くする。
「それに、あの魂の『波動』……あれはキョウジ、完全にお主の物だぞ? これは一体――――」
ここまで言葉を紡いでいた屁舞留が、ようやくキョウジのその硬い表情に気づく。
「……済まぬ。吾は、出過ぎた事を言ってしまったか?」
おろおろとしながら謝って来る屁舞留に、キョウジは少し哀しげな笑みを浮かべて首を振った。
「いえ……。ただ、見事な慧眼だと思って……」
「……………!」
思わぬキョウジの褒め言葉に、屁舞留は思わず顔を赤らめながらそっぽを向く。
「わ、吾とて一応神仙の端くれの者だ! この程度の事は、見るだけの能力を持っておるぞ!」
そう言いながら屁舞留はキョウジの方に、ちらりと視線を走らせる。キョウジは微笑んでいたが、その瞳には相変わらず哀しげな色を湛えたままだ。
「……キョウジよ。事情を聞いても良いか?」
だから思わず屁舞留は、そう口走っていた。
「吾で良ければ、話を聞くぞ?」
「……………」
その言葉にしばらく押し黙っていたキョウジであったが、やがて、何かを吹っ切ったかのように、フッと笑みを浮かべた。
「そうですね……。時間もある事ですし、聞いてもらいましょうか……。馬鹿な男の懺悔を――――」
こうしてキョウジは話し始めた。ただ淡々と、事実だけを、その唇は紡いでいく。DG細胞と、デビルガンダムと――――シュバルツが誕生する話を。そして、そこに起きた『悲劇』を。
「ううむ………」
話を聞き終わった屁舞留が、唸り声を上げている。
「……まるで哀しい神話かお伽噺を聞いていたようじゃ……。吾の理解の範疇を越えるところも多々あるが――――」
やがて屁舞留は、組んでいた腕を解き、その膝をポン、と叩いた。
「じゃが、シュバルツとやらの正体は、だいたい分かったぞ? あ奴は機械(からくり)人形の様な物で――――キョウジ、お主の『影』と言っても、差し支えのない物なのだな?」
「ええ、そうです……。私は、『シュバルツ・ブルーダー』と言う人の死体と、DG細胞を使って――――自分の全人格を、シュバルツに移し込みました……」
そう言ってキョウジは、拳を握り込む。
本当に――――シュバルツを誕生させる過程こそが『悲劇』 そして、紛う事無き自分の『罪』の証なのだ、と、キョウジは感じていた。だからそこから、自分は目を逸らしたり、誤魔化そうとしたりしてはいけないのだ。
まして、今話した相手である屁舞留は『神』だ。ならば――――自分の『罪』を裁かれたって、文句は言えない。そう思った。
「………………」
だが屁舞留は、しばらく考え込むような仕種をした後に、その面に『にかっ』と笑みを浮かべた。
「うん――――。ならば、シュバルツが『吾の代理の者』を務めても、本当に、何の問題もないな!」
「えっ?」
きょとん、とするキョウジをよそに、屁舞留はうんうん、と独り頷いていた。
「なるほど……あ奴に触れた時に感じた違和感は、あ奴が人間ではなかったからだな……。この結界は、神仙の者と、人間以外は拒む仕様になっておる故――――」
「……と、言うと、やはりシュバルツは『魔』の類になるのか?」
キョウジの問いに屁舞留は頷く。
「分類せよと言われたら、そうなるのであろうな……。尤も、あ奴から感じる『魔』の気配は微々たるものだが、その身体を構成している物が『違う』という点が、やはり大きく作用してしまう様じゃな……」
屁舞留の言葉に「なるほど……」と、しばらく考え込むようにしていたキョウジであるが、やがて、はっと何かに気が付いた様に顔を上げた。
「ええと、屁舞留?」
「何じゃ? キョウジ……」
「貴方の代理の者が『魔』の類の者でいいのか? ほらやっぱり、何かとまずいんじゃ……!」
「別に問題なかろう。あの者がお主の『影』というのなら、人格的にも問題なかろうし、ますます吾も安心と言うものじゃ」
「いや、だから」
「ん? 何じゃ?」
「そんな簡単に、私を信用していいのか? ほら、私は『悪人』かもしれないし……!」
「は? 何を言っておるのじゃ? キョウジ。 寝言は寝て言えよ?」
「……………!」
またも屁舞留にズバッと切りかえされて、キョウジは言うべき言葉を失ってしまう。
「お主こそ、あまり吾を見くびるな、キョウジ。お主が悪人かそうでないかぐらい、この屁舞留にも見分けはつくぞ?」
「し、しかし……」
「だいたい、お主が悪人であるならば、そんな風に見ず知らずの他人の死を、そこまで丁寧に悼んだりはせぬし、吾と吾の村の事も、嘲笑う事はあっても、懸命に何とかとしようとしたりはせぬではあろう? こんな事、どちらかと言えば面倒事だ。避けて通ったり、関わり合いになろうとせぬのが普通と思うぞ?」
「いや、でも……!」
「あきらめろキョウジ。お主は『馬鹿』がつくほどのお人好しの善人じゃ。今更――――悪ぶろうとするな」
「そ、そんな筈は……! 私だって人並みに、悪い事しているはずなのに……ッ!」
そう言いながらよろめくキョウジに、屁舞留は興味深そうに声をかけてくる。
「ほう? 例えば、どんな悪い事をしておったのじゃ?」
「小さい頃は、よく弟をからかって遊んでいたし……」
「まあ、普通男子(おのこ)は、年下の者をからかうものだの」
「学校の授業が退屈だったから、よく窓から外を見てぼーっとしていたり……」
「そう言う事をせぬ輩などおるのか?」
「研究に夢中になると、父さん母さんが『ご飯だよ~!』って、呼びに来ても気がつかなかったり、すぐに行かなかったり……!」
「それはいかんな。食事はちゃんと摂らねばならん」
「最近だと、面倒くさい事は何かと口実をつけて、全部シュバルツにやってもらったりしているのに―――!」
「その件は、後でシュバルツとやらに懺悔して、たっぷり説教をしてもらうが良いぞ?」
「嫌だ―――ッ!! シュバルツが説教を始めると、長いから嫌だ――――ッ!!」
そう言って寝っ転がってじたばたと暴れるキョウジに、屁舞留は呆れたように笑う。
「いい加減、あきらめよ、キョウジ……。その程度の悪事など、微々たるものじゃ。お主が『善人』である事実は動かしようがない。そして、その『影』も、また然りじゃ」
「ううう……そんな筈は……!」
まだえぐえぐと泣き続けるキョウジに屁舞留は苦笑すると、その顔を村の方へと向けた。
「それよりもキョウジ……見てみよ。まだ、村の上空には、あの『闇』が鎮座しておる」
「……………!」
「お主の『影』があの村に入った事……そして、村の『場所』が変わった事……それで、あの村の運命が変わればいいのだが……の」
(シュバルツ……!)
屁舞留の言葉に、キョウジは明確な答えを返せなかった。ただ今は、見守るしか術が無いのが現状だった。
そして、キョウジ達が見守る目の前で、シュバルツが井戸や道具を改良して、村人たちにありがたがられ、伏し拝まれたりしていた。
「ほう! 素晴らしいのう! 本当にそなたの『影』は、神様の様じゃな!」
そう言って満足そうに頷く屁舞留の横で、キョウジが頭を抱え、シュバルツが「私を拝むんじゃなあい!!」と、怒鳴り散らしていた。こうして、キョウジと屁舞留の『闇を払う戦い』が、静かに幕を開けたのだった。
闇を払う戦い――――その『奇跡の瞬間』は、割と早く訪れた。
一段と暗い闇を背負ったケイタが、材木を束ねた山の傍を通る。その瞬間、魅入られたように材木を束ねていた紐が切れた。
「――――!!」
その先の悲劇を予感して、キョウジと屁舞留が息を飲む。だが、材木の束が、ケイタを襲う事はなかった。
「大丈夫か?」
材木の束を片手で押さえ、涼しい顔をしてケイタを覗き込んでいるシュバルツ。
その瞬間。
ケイタの肩に張り付いていたどす黒い闇が、サアッ、と音を立てて彼から離れて行ったのだ。
「―――――!!」
自分達の見た物が俄かに信じられなくて、キョウジも屁舞留も呆然としてしまう。
「キ………キョウジ……」
「な、何だ……? 屁舞留……」
「い、今の……見たか………?」
「ああ……。見た……。見ました……」
「吾らは、夢か、幻を見ておるのではないのか……? どれ、ちょっとつねってみようか……」
そう言いながら屁舞留は、キョウジの太腿を思いっきりつねる。
「痛(いて)――――――ッ!!」
キョウジから、当然のごとく大きな悲鳴が上がる。それを見て、屁舞留はホッと胸を撫で下ろした。
「ああ、痛いのか……。やはり、夢ではないのだな? 良かった……!」
「いてててて……。どうせなら、自分の身体をつねってくれれば……!」
涙目になって抗議するキョウジに、屁舞留はしれっと答えを返す。
「仕方がなかろう。吾は、痛いのは好かん」
「そうですか……。あは……あはははは………」
自分のわがままを苦笑しながら許してくれるキョウジに、屁舞留の顔にも笑みが浮かぶ。やはりキョウジは、底抜けのお人好しだと屁舞留は思った。
「でもキョウジ……。あの闇を、確かにお主の影は払った……。と、言う事は……」
「そうです。運命は変えられる……!」
「変えられるのか……? 本当に、そうなのか……?」
茫然と呟く屁舞留の手を、キョウジは強く握る。
「ええ、そうです……! 現に、あの少年の闇は、払えたじゃないですか!」
「キョウジ……」
「信じましょう、屁舞留」
揺れる屁舞留の瞳を、キョウジの優しいが力強い眼差しが見つめる。
「必ずあの闇は――――打ち払う事が出来るのだと」
しばし呆然と、そのキョウジの瞳を見つめていた屁舞留であったが、やがてフッと、その面に笑みを浮かべた。
「そうか……そうじゃな……」
「屁舞留……」
「信じねば、奇跡も起きぬと言う……。信じてみようか、吾も。その奇跡とやらを」
屁舞留の言葉に、キョウジも笑顔で頷く。
「それではキョウジ、村の見回りに行くそ! 吾らにも、何か為せる事があるやもしれん!」
そう言いながら屁舞留は、強引にキョウジの手を引っ張る。キョウジも、苦笑しながらもその後に続いた。
それから月日はたって行くが、あの闇を払った奇跡はあれ以来見られない。村の上空にも、相変わらず『闇』は、鎮座したままだ。
(一体、何が原因でこの村は滅びるんだ……? 『天災』なのか、それとも『人災』故なのか……)
キョウジもその原因を考えて首を捻るが、一向に答えが見えてこない。
「キョウジ……。やはり、この辺りの地盤は安定しておる。地震とか、噴火と言った災害が起こる事は無さそうだぞ?」
この辺り一帯の地盤を調べていた屁舞留が、そう声をかけて来た。
「はやり病の気配もない……。この辺りは平和そのものじゃ。なのに何故、あの闇は消えぬのじゃ?」
屁舞留のその問いに、キョウジも明確な答えを返す事が出来ない。互いにう~ん、と考え込んでいる所に、ちょっとした事件が起こった。シュバルツが、怪我をした妖魔の子供を助けていたのだ。
「これが、『妖魔』と呼ばれる類の者か……。初めて見た……」
シュバルツに手当てをされている妖魔の子供を、屁舞留が興味深そうに眺めている。
「初めて見るのか?」
少し意外そうに聞いてくるキョウジに、屁舞留も振り向いて答える。
「ああ。この村が前あった世界でも、もしかしたら狐狸妖怪の類はおったかもしれぬが………こうして、目の前でじっくり見るのは初めてじゃ」
「そうですか……」
そう応えるキョウジの前で、シュバルツが手際よく妖魔の子の足の手当てを終えると、「元居た場所に返してくる」と、妖魔の子供を抱きかかえた。そのままひょい、ひょい、と、器用に崖を上って行っている。
「……お主の『影』は、本当に何でもできる、優秀な奴じゃのう! あ奴こそ本当に、『神』ではないのか?」
感心しながらそう言う屁舞留にキョウジも「止めてください!」と、怒鳴る。その周りで村人たちが、シュバルツに向かってこっそり手を合せて拝んでいた。
(ああもう………!)
この誤解が誤解を招く様な状況に、キョウジも頭を抱えるしかない。何てことだ。シュバルツは、自分が出来る事をしているにすぎないのに。
やがて崖の上から、シュバルツが帰ってくる。ストン、と、綺麗に着地したシュバルツを、村人たちが嬉しそうに迎えた。だが、そんなシュバルツを見た屁舞留は、何故か表情を硬くする。
「どうした? 屁舞留……」
そんな屁舞留の様子に気が付いたキョウジが声をかけると、屁舞留がどうしたらいいのか分からないと言った表情を浮かべて、こちらに振り向いた。
「キョウジ……」
「どうした? 顔色が悪いぞ?」
「……………」
しばし、何かを逡巡しているような様子を見せた屁舞留であったが、やがて、意を決したように顔を上げた。
「キョウジ……お主の『影』に、闇が貼り付いている……」
「えっ?」
キョウジは瞬間、屁舞留の言っている言葉の意味が分からなくて、きょとん、としてしまう。そんなキョウジに理解を促すように、屁舞留はもう一度叫んだ。
「シュバルツの背後に――――他の村人たちと同じように、闇が貼り付いておるのじゃ!!」
「ええっ!?」
その言葉が俄かに信じ難くて、キョウジは思わず叫んでしまう。それに対して屁舞留が縋るように言葉を続けた。
「本当じゃ!! 今から術でその様を見せてやるから、お主の目で確かめてみると良い!」
屁舞留が印を結んで呪を詠唱する。すると、特殊なレンズの様な物がキョウジの目の前に浮かんで来て、それを通すと、キョウジにも屁舞留と同じように『闇』を見る事が出来るようになった。そして、キョウジもそれを通して見てしまう。村の皆と同じように、シュバルツの背後に貼り付いている『死の闇』を。
「馬鹿な……! シュバルツは、不死の筈なのに――――!」
「『不死』だと?」
驚く屁舞留に、キョウジは頷いて返事をする。
「ええ。シュバルツはその身体を『DG細胞』と言う特殊な物で構成されている。だからシュバルツは、腕が千切れようが足が千切れようが、首が飛んでしまおうが――――DG細胞の『自己再生』によって組織が再生してしまうから、彼は死なないと言うか、死ねない筈なんだ……!」
「おお、そう言えば、『DG細胞』について、お主はそんな事を言っていたな」
キョウジの話を聞きながら、屁舞留もまた、DG細胞とシュバルツとキョウジとの関係を、キョウジ自身から説明された事を思い出す。
「なのに何故……? まさか、シュバルツも村の皆と共に、死んでしまう可能性がある、と、言う事なのか……?」
茫然と呟くキョウジ。シュバルツが『死ぬ』可能性を考えてはみるものの、いくら考えても、明確な答えなど浮かぼうはずがない。
「キョウジ……」
心細そうな屁舞留の声に、キョウジははっと我に返る。すると、屁舞留が縋るような眼差しで、キョウジを一心に見つめていた。
「大丈夫だよ」
優しい笑顔を、キョウジはその面に浮かべる。
「たとえ今、あの闇が浮かんでいたとしても、運命は変えられるかもしれないじゃないか。あの、ケイタ君の様に――――」
「……………」
キョウジのその優しい言葉と笑みに、屁舞留の顔もフッと緩んだ。
「そうじゃな……。運命は変えられる。吾らはさっき、それを見たばかりじゃったな……」
二人の目の前を、シュバルツとケイタが歩いて行く。ケイタに向けられるシュバルツの笑みは、キョウジの笑顔と同じように、優しい色を湛えていた。
「まだ起こってもいない事を、吾らがいつまでもぐずぐず悩んでいても仕方が無いの! キョウジ! とりあえず、吾らも為すべき事をしよう!」
そう言って屁舞留も、元気良く歩きだす。キョウジも、苦笑しながらそれについて行っていた。
妖魔の子供を助けた事をきっかけに、村と妖魔たちの間に交流が生まれる。元々、人間たちと交流する事を望んでいた妖魔たち。そして、それを受け入れる寛容さを持った村人たち。その異種族の交流が活発化するのに、そう時間はかからなかった。
涙が出るほど平和な日々が過ぎて行く。黙って見ていれば、こんな日々が永遠に続くのではないかと、つい、錯覚してしまいたくなるほどだ。
しかし――――村の上空を覆いかぶさる死の闇は、日々色を増すばかり。それが、屁舞留とキョウジの心にも、暗雲を投げかけていた。だが屁舞留は、そんな中でも『豊作の神』としての役割を忘れた事はなかった。
「この木には、栄養が足りておらぬ……。この木は、順調なようじゃな……」
一本一本の木に額を当て、その木の声を聞く。必要に応じて、その木に『神気』を注いだりしていた。
「屁舞留は、仕事熱心だね」
その様を見て、にこやかに言うキョウジに、屁舞留も笑顔で言葉を返す。
「……『約束』じゃからな……。村の皆との」
「『約束』と言うのは、土地神としての?」
キョウジの言葉に、屁舞留は頷く。
「そうじゃ。今年も豊作の祈願を受けたじゃろ? それに、村人たちは常に貢物も欠かさず、毎日挨拶もしてくれておるじゃろ?」
「確かに、そうですね……」
「時に、いろいろと語りかけてくれたり、様々な事を報告してくれる者もおる。吾はそれに、返事をする事が出来ぬと言うのに――――」
屁舞留の言葉に、キョウジも苦笑した。
「そうですね……。あれは語りかけると言うよりも、最早人生相談でしたね……」
「全くじゃ! 夫婦喧嘩の仲直りの方法まで、吾は責任取れぬと言うに――――!」
はあ~……と、深いため息をつく屁舞留に、キョウジも声を立てて笑った。
「出来ることも少ない吾を、こうして祀ってくれている。そんな皆の心を、無駄にする訳にはいかぬ。『約束』は――――守らなければ」
こんなのは、独りよがりな『想い』かもしれないが、と、苦笑する屁舞留に、キョウジは首を横に振った。その力を独善的に振るうのではなく、そっと、そこに静かに宝物を置いて行く様な力の使い方を、屁舞留はする。キョウジはとても好きだと思った。
「それにしてもこの『闇』……結局原因が分からないまま、ここまで来てしまいましたね……」
キョウジの言葉に屁舞留も「うん」と頷く。闇は今にも総てを飲み込んでしまいそうなほど――――暗い色を、その身に湛えていた。
「分からぬ……。村も平和そのもので、天変地異の疑いもないのに―――」
屁舞留の言葉に、キョウジも明確に答えを返せない。妖魔たちとの交流も順調、農作物も順調、なのに何故――――この村を覆う闇は、消えないのだろう?
「明日は『感謝の祀り』じゃ……。皆に過酷な運命が振りかかるより前に、沢山楽しい出来事があれば良いのじゃが――――」
祈るように紡がれた、屁舞留の言葉。
だがその祈りが
叶えられる事は――――
無かった。
悲劇はその日の夜に訪れた。
「屁舞留!! 起きろ!!」
キョウジの切迫した声に、屁舞留は飛び起きる。
「村が――――!! 村が、燃えている!!」
「何じゃとォ!?」
驚愕に見開かれた屁舞留の瞳に飛び込んでくる、村から上がる炎と黒煙。村が滅んだ『あの日』と同じ光景が、目の前に広がる。
「何故……? 何が、起きておるのじゃ……?」
目の前の光景を見たくなくて、信じたくなくて、屁舞留の身体はがたがたと震えた。
「何者かが、村に襲撃をかけて来た様なんだ!」
(戦――――!!)
キョウジの言葉に状況を理解した屁舞留は、ますます恐怖に襲われる。
つまりあの村は今――――戦う手段を持たない村人たちが、虐殺され、蹂躙されているのだと。
村が滅んだ、『あの日』の様に。
「屁舞留!! 村に行かないと――――!!」
叫ぶキョウジの声に、屁舞留の身体がビクッ! と、跳ねる。
「え………? 行………く………?」
目を見開いたまま固まって、機械人形のように振り向く屁舞留。
「行って………何を、するつもりじゃ…………?」
「何をって………!」
キョウジは屁舞留に懸命に声をかける。
「村の様子を見に行って、皆を助けるんだ!! 私たちにだって、何か出来る事があるかもしれないし――――!!」
「……無駄じゃ………」
キョウジの言葉を、静かに、だが言下に否定する。
「無駄って――――!」
驚き、息を飲むキョウジに、屁舞留の暗い目線が向けられる。
「行った所で、吾らに出来る事など何もない……。己の無力を痛感して、傷つくのはお主の方だぞ、キョウジ………」
そう、自分は嫌と言うほど経験した。
目の前で誰かが殺されようとも、それを助ける事も出来ない無力な自分を。
ただ命が零れ落ちて行くのを、眺めることしか出来ない空しい自分を。
いやという程、思い知らされた――――!
「それは、そうかもしれないけれど……! でも――――!」
屁舞留の的を得た忠告に、それでもキョウジは反論した。
「私は行かなくては――――! だってあそこには、シュバルツがいる!!」
「――――!」
「シュバルツは絶対、逃げ出さずにあそこで独り頑張っている! 皆を助けようと、戦い続けているんだ!!」
「キョウジ……!」
「ならば、私は行かないと!! 何も出来なくても、せめて、シュバルツの傍に―――!」
「…………!」
「お願いだ!! 屁舞留!! 私をあの村まで連れて行ってくれ!! 村に入るのが怖いのなら、その手前の所でもいい!! そこに降ろしてくれ!! 私1人では、この結界の空間からあの村の間にある時空の道を越える事が出来ないんだ!!」
キョウジの指さす先に、燃え盛る村の景色がある。屁舞留はギリリ、と、歯を食いしばった。
「屁舞留!!」
縋る様なキョウジの叫びに、屁舞留もついに――――頷いた。
「………分かった………」
「――――!」
「お主がそこまで言うのなら、吾ももう止めはせぬ。行こう」
屁舞留はそう言うと、静かに立ち上がり、キョウジの手を取った。
ふわり、と、音もなく、二人の身体は村から少し離れた所の桃畑の中に舞い降りる。幸いにして、まだここまでは、火の手も回って来ていないようであった。
「吾はここまでだ。後はキョウジ――――お主の好きにするが良い」
「ありがとう」
キョウジはそう言って踵を返すと、迷うことなく炎の上がる村の方へと走って行った。後には屁舞留が1人、桃畑の中に残された。
「………………」
屁舞留は無言で桃の木々を見つめながら、『あの日』の事を思い出していた。戦に寄って村が滅んだ『あの日』の事を――――
野党に襲われて、それまで続けられていた村の営みは、あっさりとそこで終わりを告げてしまった。
「止めろ!! 止めてくれ!!」
屁舞留は叫び、その暴力を止めさせようとするが、人界の物に触れられないこの身体では、どうする事も出来ない。
「神様――――!」
と叫び、絶命する者。男衆はもちろん、女子供、老人衆に至るまで容赦なく殺されて行った。生まれて間もない赤子も、斬り捨てられて動かなくなってしまった。
「何故――――! 何でじゃ!!」
動かなくなった赤子の手を取って、屁舞留は泣き叫んだ。だが当然、その慟哭すら、誰の耳に入る事もない。
何故、人の子は、他者に対してここまで非情な事が出来るのだろう。
理解できなかった。理解したくなかった。
村から上がる巨大な火の柱を、屁舞留は暗い眼差しで見つめる。きっとあの炎の下では、あの日と同じ惨劇が起きている。そう考えるだけで―――――屁舞留の前に進もうとする意志を奪うには、もう充分すぎた。
(……この桃の畑は、どうなるのだろう……)
例えここだけは無事に残っても、もう世話する者が居ない事になる。そうなったら、どうなってしまうのだろう。ぼんやりとそんな事を考えている屁舞留の耳に、馬のいななきと軍隊の足音が聞こえてくる。
「―――――ッ!」
ビクッ! と、身構える屁舞留の目の前に、仁王然とした将と、白藍色で統一された戦衣をまとった兵達が現れた。
「素戔鳴様、こちらです」
「うむ」
素戔鳴と呼ばれた、黒褐色の肌に金の刺青を施したその仁王が、ずいっと前に進み出てくる。「それでは皆の者―――」と、言いながら2,3歩歩足を進めた所で、桃の畑で立ちすくんでいた屁舞留と、ばったり目があった。
「神仙の子倅か――――」
屁舞留を見るなり素戔鳴は、こちらを検分するかのようにジロリ、と、こちらを睨んできた。
「――――ヒッ!」
その一瞥で、屁舞留は足がすくんでしまう。素戔鳴から溢れ出る『神気』が、自分のそれの比ではない事を感じ取ってしまったが故に、屁舞留は素戔鳴に恐怖した。
「……そこに居ては危ない。離れていよ」
「…………?」
意外にも優しい声をかけられたので、屁舞留はそろりと立ち上がり、素戔鳴に命じられるままに後ろに下がる。兵士たちも屁舞留の手を取って――――彼らの後ろへと、屁舞留の身体を下がらせてくれた。
屁舞留が後ろに下がったのを確認してから、素戔鳴は改めて兵達に命を下す。
「火矢を放て!!」
号令に合わせて、一斉に桃畑に向かって火矢が放たれる。そこはあっという間に、火の海と化した。
「な―――――!!」
あまりの光景に、屁舞留は絶句するしかない。
(何て事を!! ここは、この村の者が一生懸命に世話をし続けた畑なのに――――!!)
怒鳴らなければならない。叫ばなければならないと、屁舞留は本能的に一歩、前に進み出る。だが、振り返った素戔鳴と視線があった瞬間、屁舞留の言葉は総て、口の中から奥に呑みこまれてしまった。
「あ………! あ…………!」
馬鹿みたいに震えながら、そんな言葉しか言えない屁舞留。その様子から、少しその事情を察した素戔鳴が、口を開いた。
「汝は、ここの土地の者か?」
「う………! う――――」
否定の言葉も、肯定の言葉も吐けない屁舞留。そんな様子に素戔鳴は小さくため息を吐くと、言葉を続けた。
「あの木は吾の『仙桃』だ。それをここの人間たちが私物化し、あまつさえ妖魔たちにも与えたために、これを『処分』しに来た。こんな愚行をした人間共も妖魔共も――――最早、許す事は出来ん」
「―――――!」
絶句する屁舞留に、素戔鳴は、更にたたみかけてくる。
「何故汝の様な物がここに居るのかは知らぬが――――汝も、いつまでも人の子の様な妖魔と狎れ合う者どもの傍に何時までもいる必要はない。ここから離れる事を考えよ」
「……………!」
その素戔鳴の意見には違和感を覚えるが、反論する勇気など、屁舞留は持たない。ただ、馬鹿みたいに震える事しか出来なかった。
「では、行くぞ! 妖魔も人も――――殲滅する!」
素戔鳴はそう言うと、軍を村の方へと進めて行く。後には、ただ燃えて行く桃畑と、屁舞留だけが残された。
「あ………! あ………! あ―――――!!」
誰もいなくなってしまってから、ようやく屁舞留の口から声が漏れる。
「あああああっ!! ああ――――――ッ!!!」
屁舞留の絶叫は、燃え盛る炎の海にかき消された。
「止めろ!!」
キョウジは子供を抱きしめて庇う。だが、刃は庇った自分の身体をすり抜け――――子供の命を屠って行った。末期の声を上げることすら出来ずに、子供の命は天に還って行く。
「ああ………!」
自分の無力を嘆いて、キョウジは涙を流す。もう何度――――彼はその行為を繰り返した事だろう。分かっている。何にも触れられる事の出来ない霊体の今の自分の状態では―――――ここに存在しないのと同じだ。惨劇を止める事など出来ようはずがない。何も救えない。分かっている。分かっているけど――――!
ドカッ!!
妖魔たちを弾き飛ばして、シュバルツが走る。その手には、助けた子供を抱きかかえていた。
(シュバルツ……!)
1人を助けるシュバルツの周りでも、惨劇は繰り広げられていた。1人を救うのに、10人を見捨てなければならないこの現状――――シュバルツが歯噛みしているのが、キョウジにも見てとれた。
(人手が足りなさ過ぎる……! それに――――)
村のあちこちで、妖魔同士が戦っている姿が見える。どうやら妖魔の中にも、村人を殺そうとする者と、それを守ろうとする者が居るようであった。それ故に、振るわれるシュバルツの刀に『迷い』が生じている。誰が味方で誰が敵なのか――――シュバルツにも、区別がついていないのだろう。それは、シュバルツの反応を、一歩、遅らせる事に繋がってしまう。
「―――ぐッ!!」
シュバルツの足が切り裂かれる。だが、彼は踏ん張ると、再び走り始めた。
(シュバルツの怪我は……治りつつある……)
既に傷だらけになってしまっているシュバルツの身体だが、傷がゆっくりとだか、再生して行っているのが分かった。やはり、不死の身体を持つシュバルツ。妖魔が彼を攻撃したぐらいでは、死ぬようなことはないのだ。
しかし、屁舞留の話では、シュバルツに宿る死の影は消えてはいないと言う。
では一体何が―――――シュバルツを『死』へと導いてしまうのだろう?
「ああ………!」
1人を助け終えたシュバルツが、先程の場所に舞い戻って来て、転がる村人たちの遺体を見て、また、涙を流している。己の無力を痛感しているのだろう。
(シュバルツ……ッ!)
自分もまた、同じだ。
いや、シュバルツ以上に自分は無力だ。
自分は本当に――――何も出来なかった。
ただ、見届ける事しか出来ない存在に、何の意味があると言うのだろう。
「行った所で、吾らに出来る事など何もない……。己の無力を痛感して、傷つくのはお主の方だぞ、キョウジ………」
屁舞留のくれた忠告が、頭の中を回る。
本当に、その通りだと思う。
だけど――――
シュバルツは涙を拭いて、また立ち上がっている。
まだあきらめないのだ。彼は。
1人でも2人でも助けたいと――――願っている。
ならば、私も。
無駄と知りつつ、キョウジも顔を上げて走り出す。
1人でも2人でも、生存者を見つけたかった。
涙を流しながらも走りまわるシュバルツの、手助けをしたかった。
例え99回叫んで駄目だった事でも
100回目――――叫んだ時に、もしかしたら、何らかの奇跡が起きるかもしれないじゃないか。
そんな願いを抱いて、キョウジは走る。
やがて燃え盛る炎の中に、1人の生存者を見つけた。
「大丈夫か!? しっかり!!」
キョウジがそう声をかけると、倒れていた女性はキョウジと視線を合わせて、にこり、と、微笑みかけて来た。
「ああ、神様――――」
「……私が、見えるのか……?」
茫然とそう言うキョウジに、女性は頷いた。
「神様……。来てくださったのですね……」
女性の肩口から、激しく出血しているのが見える。
「止血を――――!」
キョウジは叫んで、女性の手当てをしようとする。しかし彼の手は、女性の身体に触れる事が出来ずに、空しく通り過ぎて行くだけだった。
「…………!」
歯噛みしながら己が手を見つめるキョウジに、女性は縋るように声をかけて来た。
「……神様……! 私の事は、良いから……! この子を……! この子を――――!」
そう言って女性がキョウジに差し出そうとする子供は、もう既に事切れていた。
泣き叫びたくなるのをぐっと堪えて、キョウジは女性に声をかける。
「ああ……分かった……。だけど、貴女も助からなければ………!」
そんなキョウジに、女性はふわりと優しい笑みを浮かべると、首を横に振った。
「私は……もう、良いんです……。それよりも、神様……! 私よりも、どうか……他の人たちを……!」
「駄目だ! 叫んで! 助けを呼んで――――!」
キョウジは必死に、女性に訴えた。
「私の声はシュバルツには聞こえない! だけど、貴方が叫べばその声は、きっと、シュバルツに届く! だからお願いだ!! 叫んで――――!!」
だが女性は、キョウジの言葉に首を横に振り続けた。
「神様……。貴方、だけ……でも……助かっ…………」
その言葉を最後に、女性の方も事切れてしまった。
「駄目だ!! 死んでは――――!!」
キョウジが叫ぶと同時に、燃えていた周りの壁が、ドドドドッ!! と、音を立てて崩れてくる。その瓦礫はキョウジの身体を素通りして――――死んだ母子の身体の上に崩れ落ちて行った。
あっという間に、周囲は炎の渦に包まれる。
なのに自分は、熱さも感じない。当然、自分の身体が燃えだす事もない。
何も、何も出来ない今の自分。
本当に――――無力だった。
「あ………! あ………!」
止めようもない涙があふれ、嗚咽が漏れる。
いくら泣いても周囲にこの声が聞こえる事はないから、キョウジは逆に安心して泣けた。
このまま本当に膝を折って――――ここで泣き崩れてしまいたくなる。
だけど――――
独り、走り続けるシュバルツの姿。
まだ彼は、あきらめていないのだろう。村人たちを、1人でも救う事を。
ならば、私も――――!
ぐしっと、涙を拭い、キョウジもまた立ち上がる。
見届けなければと思った。
シュバルツの、戦いを。
キョウジは立ち上がると、再びシュバルツの後を追って、走り出していた。
屁舞留はふらふらと独り、村の外れの森の中を歩いていた。するとそこに、茂みの中で1人、うずくまって震えているケイタの姿を見つけた。
「ケイタ………」
震えているケイタの背中には、死の影が張り付いてはいない。屁舞留は少しホッとして、ケイタの隣に座った。
「ケイタ……。怯えるな。そなたは大丈夫じゃ……。吾が側についておるからの……」
屁舞留がそう声をかけても、当然ケイタの耳には聞こえていない。震えながら縋るように「シュバルツさん……! シュバルツさん……!」と、小声で呟いている。
「ケイタ……」
屁舞留は少し淋しかったが、仕方が無い事だとも思った。自分は本当に――――今のケイタには何もしてやる事が出来ないのだから。ただ、触れられずとも、その背に手を伸ばさずにはいられなかった。その日一日あった事を、笑顔で報告してくれたあの明るい少年の姿を、もう一度見たいと願う。
しばらくそうしてケイタの横についていた屁舞留であったが、やがて、ケイタの背にも、死の闇が形成されつつある事に気づいてしまう。
「な……! 駄目じゃ!!」
屁舞留は慌ててその闇を追い払おうとした。だが、そんな努力を嘲笑うかのように、死の闇はケイタの背に集まって来るばかりで。
「止めてくれ!! 何でじゃ!! どうして――――!!」
そうやって屁舞留が懸命に闇と格闘している所に――――誰かがふわり、と、屁舞留の身体に触れて来た。
「――――!?」
屁舞留が驚いて振り向くと、そこにはキョウジが立っていた。
「キョウジ……!」
屁舞留に声をかけられたキョウジは、その瞳から大粒の涙を零し始めた。
「屁舞留……ッ!」
キョウジは泣きながら――――屁舞留の身体をぎゅっと、抱きしめて来た。
「キ、キョウジ!?」
「屁舞留……! 屁舞留……ッ!」
「ど、どうしたのじゃ……?」
戸惑いながら問うてくる屁舞留に、キョウジは震えながら言葉を紡ぐ。
「やはり……私が触れられるのは、屁舞留………お前だけ、なのだな……」
「―――――!」
「分かってはいた……! 分かってはいたけど……ッ!」
その後は嗚咽に紛れてしまって、言葉に出来ないキョウジ。
「キョウジ……!」
屁舞留はキョウジの手を、ぎゅっと握りしめた。
(だから言ったのに………!)
屁舞留は歯を食いしばる。行った所で何も出来ない。何も止められない。何も変えられない。ただ――――目の前の惨劇を、眺めているだけ。零れ落ちて行く命を、見送るだけ――――それが、今の自分達の存在だった。
酷く滑稽で、愚かな存在。叫び声一つすら、誰にも届かせる事の出来ない存在。
だけど屁舞留は、今こうして泣いているキョウジを嘲笑ったり非難したりする気にはなれなかった。
だってキョウジは、自分と同じ『地獄』を見て来たのだ。村が滅んだ『あの日』に、自分が体験したのと同じ『地獄』を。
ならば自分は、キョウジにどうしてやればいいのだろう。
何と、声をかければいいのだろう。
そんな事を考えながら――――屁舞留はキョウジの手を握り続けた。
やがて、ひとしきり泣いて落ち着いたのか、キョウジが顔を上げ、震えているケイタの存在に気づく。
「この子は……?」
「ケイタだ……。お主の『影』が助けてくれた――――」
キョウジの問いに答えながら、屁舞留は暗澹たる気持ちでケイタを眺めていた。ああ。やはり、ケイタの背に宿る死の影は、色濃くなっていくばかりだ。本当に――――どうすればいいと、言うのだろう。
「ならば、こんな所に1人で居ないで――――助かった皆と合流すればいいのに……」
「…………!」
振り向く屁舞留に、キョウジは涙を拭いながら答える。
「シュバルツが助けた村人たちが、集まっている場所があるんだ。そこに行けば――――」
屁舞留はその言葉に少し目を見開いた後、哀しそうに下を向いた。
「………無理じゃ……。あそこの者たちも、おそらく助からぬ……」
「な―――――!」
驚愕するキョウジに、屁舞留は淡々と言葉を続ける。
「あそこの洞窟も、死の影が濃厚に覆いかぶさっていた。恐らく近いうちに、あそこの者たちも全員、死を迎えるだろう……」
「そんな――――! じゃあ、こんな事をしている場合じゃない! 皆に逃げるように言わないと――――!」
「そう伝えられるのならば……! 運命が変えられるのならば! 吾とてそうしたい……ッ!!」
「…………!」
屁舞留の悲鳴の様な声に、キョウジは絶句してしまう。
「でも、無理なのだ……! 吾らには何も出来ぬ……! この戦場で、そう、学ばなんだのか!? キョウジ、お前は――――!!」
そのまま小さく身を振るわせる屁舞留の横で、キョウジもペタン、と、座り込んでしまった。
「何で……!」
このままではいけない、立ち上がらなくては――――と、キョウジは己を叱咤する。
だが、度重なる自分の無力さへの痛感は、彼から立ち上がる気力を奪うのに充分すぎた。
「何で―――――!」
そのまましばらく、キョウジの嗚咽が響く。屁舞留は、ただ黙って空を見上げた。
このキョウジは、そのまま自分の姿だ。
村を失って、ただ泣くしかなかった自分の姿。
どうすればいいのだろう。
このキョウジのために、何を自分はしてあげればいいのだろう。
不意に、ドンッ!! という大きな音が響いて、屁舞留の思考は中断させられてしまう。
「な、何じゃ!?」
驚いて、顔を上げる屁舞留の目の前で、シュバルツの身体が木の幹に叩きつけられ、ずるずると力無く地面に滑り落ちて来ていた。それを見た瞬間、屁舞留は思わずキョウジに呼びかけてしまっていた。
「キ、キョウジ……! お主の『影』が……ッ!」
そう言ってキョウジの方に振り返る屁舞留。その視線の先で、キョウジは涙を流しながら首を横に振っていた。
「……治せないんだ……! シュバルツの身体が……!」
「キョウジ……!」
茫然と、呼びかける屁舞留に、キョウジはもう一度哀しげな声を上げた。
「治せないんだ……! 治せなくて……!」
「…………!」
屁舞留は反射的に、そんなキョウジの手を握る。すると、キョウジから問いかけられた。
「屁舞留…………あの人たちは『神仙』の類の者なのか?」
キョウジの言葉に屁舞留が戦場の方を見ると、刀を構えるシュバルツの視線の先に、先程桃畑を焼いた、『素戔鳴』がゆらりと姿を現している。二人は戦っているようであるが、どう見ても、素戔鳴の方が圧倒的優位を保っていた。
「ああ。吾は生まれてすぐ人間界に落ちた故、神仙界の事はよく分からぬが――――あれは、おそらく神仙の将であろうな。それも、相当上位の者だ……」
屁舞留の言葉を黙って聞いていたキョウジであったが、やがて、小さなため息と共に口を開いた。
「……シュバルツが、『死ぬ』原因が分かった……」
「何?」
「神仙の者の力だ……。その力が宿る刃を受けると、DG細胞はその再生能力を失う。そのまま、壊れて行くしかないんだ……」
「――――!」
「シュバルツの傍にいて……何度も、何度も、治そうと試みてみたけど……ッ!」
シュバルツが仙界軍の矢をその身に受けた瞬間、身体に走った青白い『ひび』が、キョウジの目にははっきりと視えた。
この傷は『普通』じゃない。治せない――――そう悟ったキョウジは、シュバルツの身体を何とか治そうと試みる。だが、シュバルツの身体に触れることすら出来ないこの状態では、キョウジの伸ばした手はシュバルツの身体を、空しく通り抜けて行くばかりで。
「……何故……! どうしてだ……! シュバルツは『今』苦しんでいるのに――――!」
頭を抱えて、小さく丸くなってしまうキョウジ。
「こんな時に……! どうして私は……! シュバルツに対して……何も、してやる事が出来ないんだ……ッ!」
そのまま、キョウジは泣き伏してしまう。小さく丸くなった背中が、酷く痛々しかった。
「キ、キョウジ……!」
屁舞留は知らず、キョウジの背に手を伸ばしていた。
「キョウジ――――!」
何とかキョウジを、慰めたいと願う。だけど屁舞留も、この青年にかけるべき言葉を見つける事が出来ない。ただその背をさする以外に―――――術を持たなかった。
更に、そんな二人に追い打ちをかけるかのように、ドンッ!! と、音を立てて火柱が上がる。そこが、村人たちが隠れていた洞窟の方角だと悟った瞬間、キョウジは絶句して息を飲み、屁舞留はただ、哀しそうに瞳を伏せた。
「汝が、何かを懸命に守ろうとしていたのは、分かっていた!」
シュバルツに対して、仁王、素戔鳴の怒声が響く。
「だが――――残念だったな……。汝が守ろうとした最後の者たちも、灰燼に帰した。後は……汝だけだ」
「ああ……!」
仁王の言葉に打ちひしがれたのか、シュバルツはガクッと、膝をついてしまう。その瞳から、きらきらと光る物が零れ落ちていた。
「……何故だ……!」
シュバルツから、絞り出される様な声が発せられる。
「『神』とは、人を守るものだろう!? それなのに何故――――このような事を………!?」
「『神』とは――――『人を裁く者』だ!!」
「な…………!」
仁王の言葉に、シュバルツが息を飲む。だが屁舞留は、その言葉に『違和感』を覚えた。
『神』とは、『人を裁く者』なのか?
本当にそうか?
でもそれは、自分が感じていた『神』の在りようとは、酷く違う様な気がする。
神とは――――『人を見守る者』ではないのか?
「少なくとも……吾の『神としての役割』は、そうだ」
「…………!」
シュバルツは、ギリ、と、歯を食いしばっている。屁舞留も、ある程度「そうなのか」と、納得せざるを得なかった。一言に『神』と言っても千差万別。その役割も、おのずと違うものになって行くのだろう。
「ここの村人は……罪を犯した。なれば、罰を与えられなければならぬ!」
傲然と言い放つ仁王に、しかしシュバルツも反論する。
「何故だ……! ここの村人たちは、真面目に土地神を崇めていた……! 野心も抱かず、無益な殺生もせず――――平和に暮らしていた筈だ! それなのに、何故――――!?」
「『妖魔』と交わっていたであろう!! この村は―――!!」
「な――――!」
この仁王の言葉には、シュバルツも屁舞留も、そしてキョウジも絶句する。
それは、『罪』なのか?
ただ、その『種族』が違っている、と言うだけで――――!?
「しかもそれだけでは飽き足らず、吾の『仙桃』を妖魔の手に触れさせ、揚句、『報酬』として分け与えた!! 村人達は『仙桃』を売り利益を得て、それを私物化した!!」
(……………!)
屁舞留はギリ、と、歯を食いしばった。あの妖蛇の力によってこちらの世界に村が飛ばされてきた時に、一本だけ、村の物ではない桃の木が生えていたのは知っていた。
でも村の者たちはその桃もちゃんと手塩をかけて世話をしていたし、桃の木だって村人たちの世話に嬉しそうに応えていた。それを、こんな風に断罪されてしまうだなんて、誰が想像し得ただろうか。何かひどく理不尽な物を感じてしまって――――屁舞留は拳を握りしめていた。
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
その横でキョウジは、ひたすら身体を小さくして、涙を流し続けている。
「キョウジ……!」
屁舞留は、キョウジを素戔鳴から隠すために結界を張った。キョウジを守ってやりたいと言う想いもあったし、今は何故か――――キョウジの姿を素戔鳴から隠した方がいい、と、本能的に判断したのもあった。この心優しい青年が、とにかく傷つきすぎている。これ以上、傷つく事が無いようにと、祈る。
「どうだ……! これだけ罪を犯せば、裁きを受けるのは自明の理であろう!!」
そう言いながら怒れる仁王は一歩、前へと進み出る。それに対して尚もシュバルツは首を振った。
「それでも――――村人たちは知らなかったんだ!! あれが『仙桃』だなんて……! それに村人たちはあの桃を――――!」
「黙れ!! 人間ですら無いモノが、何をぬかすか!!」
容赦のない素戔鳴の断罪の声に、キョウジの身体がビクッと反応した。
「吾には見えるぞ……! その身体、『何』で出来ておる物なのか……!」
「う………!」
怯むシュバルツに、仁王は更にたたみかけてくる。
「何と不自然でいびつで………『邪悪』な物で出来ておるのか!」
「…………!」
「そんな『モノ』が、人間のふりをし、善良なふりをして人間たちに近づく……! 汝の様なモノが、一番性質が悪い!!」
素戔鳴の断罪は、尚も続く。キョウジはただ――――身を小さくして、涙を流しながら聞き続けるしかなかった。
どうして
どうして
本来、ここで責められるべきは自分だ。
自分が、シュバルツを作った。自分が、シュバルツをそう言うふうにしてしまった。
シュバルツは、何も悪くない。シュバルツはただ――――自分を助けようとして、犠牲になってしまっただけだ。彼が望んで『そう』なった訳ではないのに。
ああ―――――
今更ながら、何て重い十字架を、シュバルツに背負わせてしまったのだろう。
総ての『罪』は、自分にある。
だから、自分こそがあの仁王の前に立って、裁かれなければならないのに。
何故今――――断罪されているのがシュバルツなんだ。
どうして――――シュバルツに、あんな言葉を聞かせてしまっているんだ。
どうして自分は、そんなシュバルツを助けてやる事が出来ないんだ。
無力。
あまりにも、無力すぎる。
「キョウジ……! 落ちつけよ、キョウジ……!」
屁舞留はキョウジの手を握りながら、懸命に声をかけ続ける。
「お主は、何も悪くはない……! お主の『影』もじゃ……!」
実際屁舞留は、素戔鳴の言葉には違和感を強く感じていた。
妖魔と村人たちを、ずっと見知ってきたからだろうか。穏やかに交流をしてきた村人たちや妖魔たちに、後ろめたい所など何もない。そこまで断罪されるいわれもないようにすら思えた。
それとも、神仙の者たちと言うのは、皆、そういうふうに考えるものなのだろうか。
『妖魔』と言うだけで、『人間ではない』と言うだけで、許せない――――そう言うふうに思わなければならないのだろうか。それとも、そう言うふうに考えられない、自分こそが異質で、おかしい存在なのだろうか。
何が正解で、何が間違っているのかなんて、屁舞留には分かりかねた。
だけど、少なくとも――――あのシュバルツとこのキョウジが、そこまで断罪されなければならない程の『咎人』ではない。それだけは、確かなのだ。
だから屁舞留は懸命に――――キョウジの手を握って、「お前は悪くない」と伝え続ける。
だけど、身を小さくして泣き続けるキョウジは、ただ、首を横に振り続けるだけで。
「キョウジ……!」
屁舞留は後悔していた。
キョウジをここに連れてくるのではかなったと、悔いた。
自分は散々経験して、知っていた筈だったのに。ここに来ても、何も出来ない存在の自分は、ただ、傷つくしか出来無いと言う事を。
素戔鳴が、シュバルツに向かって剣を振り上げようとしている。もうシュバルツは、助からない。
とにかくこの悪夢のような空間が――――早く過ぎ去ってくれる事だけを、屁舞留は祈っていた。
だが、その刹那。
「違あああああ―――――う!!」
それまで二人の傍で、小さく震えていた少年が、渾身の叫び声を上げていた。
「――――!」
その場に居た全員の注目が、その1人の少年に集まる。
ケイタは、おかしい程に震えていた。だが、立ち上がっていた。素戔鳴に睨まれても、踏ん張っていた。
「そ……そのヒトは……何も、悪くないッ!!」
そして、その少年から発せられた、命がけの『言葉』
(あ…………!)
「助けて」でもなく、「お前のせいで―――!」という非難の言葉でもなく
この極限の状況で、ただただ、こちらを擁護してくれた、その言葉は
キョウジとシュバルツの心を打つには、充分すぎた。
この少年だけは、死なせたくない。
何としても――――守らなければ。
そう願って、でも、何も出来ないと分かっている自分は、思わずシュバルツの方を見る。
少年を見つめる、シュバルツの目つきが変わる。
素戔鳴に、それと気づかれないように、身構えている。
彼は本当に――――最後の力を振り絞って、この少年を守るつもりなのだと、キョウジは悟った。
「死ね」
無情なる神の号令と共に、兵士たちから一斉に、少年に向かって矢が放たれる。
その刹那、シュバルツが動いた。
矢よりも早く動いた彼の身体は、そのまま風の様に、少年の身体をかっさらって行ったのだ。
それと同時に、キョウジもまた――――屁舞留の結界から飛び出して、シュバルツについて行く。
「キョウジ!!」
そのあまりのスピードに、屁舞留は驚いた。
だが屁舞留もまた、慌ててその後を追いかけだす。
ただ、心の中は、信じられぬ想いでいっぱいだった。
あんなに傷だらけだったシュバルツの身体。
もう――――一動くことすら困難であるように、見えたのに。
(奇跡だ……!)
ケイタに宿りかけていた死の影が、完全に払われていく瞬間を見た。
これは、間違いなく、あのシュバルツが起こした奇跡だ。
キョウジが村に送り込んでくれた、シュバルツが起こした奇跡だ。
信じられない。
これが………『人の子』たちが持ち得る、底力だと言うのか――――
少年を庇った瞬間、シュバルツの身体に刺さる、何本もの矢。
さらに広がって行く、青白いひび割れ。たまらずキョウジは手を伸ばすが、やはり自分の手は、空しくシュバルツを素通りして行くだけだった。
(シュバルツ……! シュバルツ……ッ!)
ただもう、壊れて行くしかない、シュバルツの身体。今こうして走っている事自体が――――もう、奇跡の様だ。
走るシュバルツの像が、涙で変に歪む。
だけど、見届けなければと思った。
自分にはもう――――それしか、出来ないのだから。
「ケイタ……」
苦しい息の下で、それでもシュバルツは言葉を紡ぐ。
「ありがとう……」
(…………!)
キョウジはたまらず、声を上げて泣き伏したくなってしまった。
どうして
どうして、貴方の口からは
そんな綺麗な言葉だけが、零れ落ちてくるのだろう。
あれだけ傷つけられたのに。
あれだけ理不尽に、自分ではどうしようもない『罪』を責め立てられたのに。
何故、その『大元』を恨まないのか。
どうして――――自分の境遇を嘆かないのか。
貴方をそんな風にしてしまったのは―――――間違いなく、この私なのに。
どうして――――
「シュバルツ!!」
前方から走ってきた龍の忍者が、傷だらけのシュバルツを抱き止める。
(ハヤブサ……!)
キョウジの瞳から、次から次へと涙が溢れる。
あまりにも遅すぎた――――二人の再会だった。
震えるハヤブサの腕の中で、何度も「これでいい……。これでいいんだ……」と、言いながら、微笑んでいたシュバルツ。
「ハヤブサ……。今まで……ありがとう……」
「シュバルツ……ッ!」
「こんな……私を……愛して……くれて……あり が――――」
そのまま、ハヤブサの腕の中で、シュバルツは永遠に散って行った。キョウジは立っていられなくなって、その場にペタン、と、座り込んでしまった。
「キョウジ……!」
やっとキョウジに追いついた屁舞留が、一通りの状況を理解する。
だが、座り込むキョウジに、屁舞留はすぐには声をかけられなかった。あまりにも茫然自失としてしまっているキョウジ。その背中が、酷く痛々しかった。
不意に。
地の底から湧き出でる様な咆哮が、辺りに響き渡る。
あまりにも異様な、人間離れをした様な咆哮であったので、その『声』が、シュバルツのロングコートを握りしめている男から発せられていると気づくのに、屁舞留は少し時間がかかった。
それと同時に、男から発せられる禍々しいまでのどす黒い『気』
「キョウジ!!」
危険を感じた屁舞留は、座り込んでいるキョウジを咄嗟に庇った。その目の前で、黒装束の男が、まさに『魔神』へと変化しようとしていた。それを、男女の神仙の者たちと方術師が、懸命に止めていた。方術師に『封』を施された男が、声も無く昏倒する。
「な、何者なのじゃ……? あの男は……!」
騒ぎが鎮まったのを確認してから、屁舞留は思わずキョウジに問うていた。それほどまでに――――あの男から感じた『気』は、異様だった。
「……彼の名は、リュウ・ハヤブサ……」
泣きぬれたキョウジから、ポツリ、と、落とされるように、その言葉は紡がれた。
「……シュバルツを、とても大事に……想ってくれている……人、だよ……」
その後。
結局キョウジは、気を失ったハヤブサの事が気になって、そのままふらふらとついて来ていた。
気を失ってもシュバルツのロングコートを握りしめていたハヤブサ。ガバッと飛び起きて、その手にしたコートを見た瞬間、彼の、総ての動きが止まってしまっていた。
(ハヤブサ……!)
彼の悲痛なその姿を見て、キョウジも、どうしたらいいのか、本当に分からなくなってしまっていた。そのまま彼は陣屋の真ん中にふらふらと歩いて行くと、そこにペタン、と、座り込んでしまう。
霊体であるキョウジの存在は、当然、誰にも気づかれる事は無い。誰はばかることなく『泣ける』と気が付いたキョウジの瞳からは、また、はらはらと涙が零れ落ちて来ていた。
おかしい。
涙など――――当に枯れ果てている、と、思っていたのに。
(結局、何だったんだろうな……。私のした事は……)
屁舞留の村を守ることもできず、シュバルツを殺して――――
ハヤブサから、この上もなく大事なヒトを、奪ってしまった。
甘かった。
「シュバルツ独りを送り込めば何とかなる」なんて
思い上がりも甚だしい考えだった。
滅びた村の『運命』を覆すなんて
そんな簡単にできる事ではない。
どうすれば良かった?
本当に――――どうすれば良かったと言うのだろう。
「キョウジ……」
屁舞留は自身の周りに結界を張りながら、そろそろとキョウジに近づいて行った。
自分の霊力は弱い。だから、めったなことで人に見つかることはない、と、屁舞留も分かってはいたが、それでも――――こんなにたくさんの見知らぬ人の間に立ち入ることは慣れない事であったから、少し怖かった。
でも、それ以上に――――今のキョウジを放ってはおけないと思う。
屁舞留はキョウジに近づくと、その結界の中にキョウジの霊体をそっと取り込んだ。
「キョウジ……」
屁舞留が声をかけると、キョウジの身体がビクッ! と、反応した。屁舞留がキョウジに触れようとすると、彼は怯えたようにその身を一歩、後ろに下がらせた。
「キョウジ……」
屁舞留が少し、戸惑ったように声をかけると、キョウジはがたがたと震えながら、消え入りそうな声で謝罪してきた。
「屁舞留……。ごめん……。ごめんなさい……」
「キョウジ……何故、謝る?」
そう言いながら、屁舞留はそっとキョウジに触れる。だがキョウジは、その優しい手を拒絶するかのように、頭を振った。
「だ、だって……貴方の村を………結局、守ることもできずに………ッ!」
屁舞留は少し小さな息を吐くと、多少強引にキョウジの手を取った。
「それは、少し違うぞキョウジ………」
「で、でも屁舞留……!」
涙を流し続けるキョウジに、屁舞留は小さく頭を振る。
「……確かに、吾の居たあの村は滅んだ。だけどキョウジ――――最初に村が滅ぼされた時とは、また少し、状況が違っておるのじゃ」
「違う………? 何が………?」
問いかけてくるキョウジに、屁舞留は頷く。
「ああ。大分違う。それが何か、分かるか? キョウジ……」
屁舞留の問いに、当然キョウジは首を振る。屁舞留はにこりと微笑んだ。
「――――1人、助かっておるではないか!」
「独り……?」
「ああ。1人――――ケイタが助かっておる」
「ケイタ君が……」
確かにシュバルツは、あの少年を命がけで守った。だけど、独り。たった――――独りなのだ。
「でも………独りじゃ、どうしようも……」
震えながら零すキョウジの手を、屁舞留は力強く握る。
「そう、『独り』じゃ。でもキョウジ……。これはすごい事なのだぞ? 何故だか分かるか?」
屁舞留の言わんとしている事が分からず、首を振るキョウジ。屁舞留はそんな彼に――――もう一度、微笑みかけた。
「分かるか……? 『零』ではないのだ!!」
「…………!」
「『零』ではないと言う事は、すごい事なのだぞ? キョウジ! やがてケイタが大きくなり、家族を持つと、子供が生まれる! その子がまた伴侶を娶ると、孫が出来る! ケイタ1人から――――命が繋がって、またそこに村が出来るのだ!!」
「屁舞留……!」
「分かるかキョウジ……! 吾を助けてくれた男から出来た村の命が――――また、繋がって行くのだ!!」
そう話しながら、屁舞留もまた、涙を流していた。
だけどこれは、うれし涙なのだと屁舞留は思う。たった1人、あの薄暗い結界の中で、供養のために石を積んでいた時とは、状況が全然違っているのだ。
あの時は、全く先の見えない真っ暗な闇の中で、自分の身も朽ちて行くしかないと思っていた。
だけど、今は『光』がある。
『ケイタ』と言う『命』が繋がった、希望の『光』が――――
その光があるというだけで、どれ程心強い事だろう。
もちろん、新しく出来て行くその村で、自分が再び『土地神』として崇められる可能性など、皆無に等しい。
だけど、それでいいのだと屁舞留は思った。
自分は所詮、元々取るに足らない様な霊力しか持っていない身。そして、神仙界にも帰れず、もう朽ちて行くだけの存在なのだから、こうして祀りあげられていた事こそが、本来自分には望外すぎた幸せであったように思うのだ。
だから屁舞留は、想いを込めて、キョウジにこう言った。
「ありがとう、キョウジ……。お主は確かに、村を救ってくれた……。吾に『希望の光』を与えてくれたのだ……!」
「屁舞留……!」
だがその言葉を聞いたキョウジからは、さらに大粒の涙が零れ始めた。
「屁舞留………ッ!」
本当に――――忸怩たる思いだった。
こんなにも、心優しい屁舞留が居た村―――――何が何でも救わなければならなかったのに。
「だから、泣くな、キョウジ……。お主は本当に、ようやってくれた」
「違う、私は――――!」
頭を振って泣き続けるキョウジの髪を、屁舞留は優しく撫でる。
「それに、キョウジ……。吾も、そなたに謝らねばならぬ」
「えっ……?」
意外そうに顔を上げるキョウジに、屁舞留は申し訳なさそうな顔を向けた。
「お主の『影』を、犠牲にしてしまった事だ……。お主にとって、あれは『大事な者』であったのだろう?」
「―――――!」
「それなのに、あんな形で死なせてしまって………吾はそなたにどう言って、詫びれば良いのか……」
「そんな………!」
屁舞留にそんな事を言われてしまっては、キョウジはますます涙が止められなくなってしまう。
「『失った物』の多さで言うのなら……屁舞留、貴方の方が、はるかに多くて、大きいのに―――――!」
そのまま屁舞留の着物の裾を掴んで、泣き伏してしまうキョウジ。その涙を止める術を知らない屁舞留は、ただ、キョウジの髪を撫でながら、天を仰いでいた。
(もう少し、吾に『神力』があったのなら……)
思っても詮の無い事だ、と、屁舞留は分かってはいても、この時ばかりはそう願わずにはいられなかった。ただ、独りで涙を流していた自分の、その涙を止めたいと願って―――――この目の前の青年は、それこそ何の見返りも求めずに、自分に力を貸してくれたのだと言うのに。
それをこんなに傷つけて泣かせてしまって――――本当に、酷い事をしてしまったと、思う。
それでも、起こってしまった事の事実は動かしようが無いから、これはこれで受け入れて、前に進んで行くしかないのか、と、屁舞留が思おうとした時。
「よくない!」
自分達のすぐ近くで、力強い女性の声が響く。
驚いた二人が同時に顔を上げると、自分達のすぐ近くで、黒と赤を基調とした戦装束を身に纏った1人の女性武将が、腰に手を当てて叫んでいた。
「よくない! よくないでしょ! 何なのよ? これはぁ!!」
「か、甲斐……ど、どうしたの?」
そんな彼女に、他のショートヘアーの女性が、恐る恐る、と言った按配で声をかけてくる。彼女の言葉から、今叫んでいる女性の名前が『甲斐』と言う名であると分かった。
「どうしたもこうしたもないわよ尚香!! このままでいい訳が無いって言ってんの!!」
問うてきた女性に、その甲斐と言う女性は、まるで噛みつく様にくってかかっている。
「だ、だから……何が?」
「誰か一人が哀しいままで――――先に進んじゃ駄目だって、言っているのよ!!」
「――――!」
「何よ!! この哀しい雰囲気!! こんなままで――――あの妖蛇に立ち向かえるって、まさか本気で思っているの!?」
「……………?」
この叫ぶ甲斐と言う女性が、何を言わんとしているのかを瞬間的に測りかねたキョウジと屁舞留は、互いに目を見合わせて首を捻る。だが、その女武将は陣屋の真ん中で、尚も叫び続けていた。幸せになるのなら――――皆で幸せにならなければ、駄目なのだと。
「ねえ! また、いつもみたいに、かぐちんの力を使って過去に帰って、あの人を救う事は出来ないの!?」
「な……! 『過去』に帰るじゃと!?」
「そんな事が出来るのか!?」
驚くキョウジに、屁舞留は少し首を捻りながら答える。
「かなり強い『神力』を持つ、上位の神仙の者であれば、そんなことも可能なのかもしれぬな……。吾には想像もつかぬ事だが……」
そんな二人の視界に、1人の神々しい『気』を纏った1人の巫女が、楚々と歩み出てくる姿が飛び込んできた。どうやら彼女が――――過去に帰る術を持つ者であるようだった。
「確かに……素戔鳴様の襲撃に遭われる前の村とあの方に接点のある方を見つける事が出来れば――――村も、あの方も、御救い奉る事が出来るやもしれません」
巫女がそう言い切った事に、キョウジも屁舞留も驚いて息を飲む。
本当に、そんな事が可能なのだろうか。
あの戦を、あの悲劇を
『否定』するために、やり直す事が出来ると――――?
だが問題は、過去のシュバルツと接点のある者が居るかどうか、と、言う事であった。
1人、典韋と言う武将が名乗りを上げたが、彼の『縁』では妖蛇の力が邪魔をして――――シュバルツの過去に戻る事が出来ないと言う。
「何と言う事じゃ……! せっかく『道』が見えておるのに――――!」
歯がゆそうに叫ぶ屁舞留の横で、キョウジはポツリと呟いた。
「いや………。1人だけ、居る」
「何っ!? 誰じゃ!? それは!!」
いきなり屁舞留にくってかかられる様に迫られたから、キョウジの方もかなり面食らってしまう。
「うわっ!! 屁舞留!?」
「誰じゃ!? キョウジ!! 誰なんじゃ!! もったいぶらずに教えんか!!」
「ちょっ……! 屁舞留! 痛いって!! これじゃ話せないから離してくれ――――ッ!!」
キョウジの叫び声に、はっと我に帰った屁舞留。自分がかなりキョウジの襟首を乱暴に掴んで揺さぶっていた事に気がついて、慌ててその手を離す。手を離されたキョウジは、軽く咳き込んでいた。余程苦しかったらしい。
「す、すまんの。キョウジ……」
はにかみながら、顔を赤らめて謝って来る屁舞留に、キョウジも「いえ……」と、苦笑を返す。キョウジは呼吸を整えると、おもむろに話しだした。
「一人だけいるんです。あの村と過去のシュバルツに接点を持ち、なおかつ、妖蛇の魔力の影響も受けずに、過去に戻ることができる縁を持つ者が……」
「うん。だからそれは、誰なんじゃ?」
先を促すように聞いてくる屁舞留に、しかしキョウジは何故か、少し躊躇うような表情を見せた。
「だけど私は……その子の『縁』を使うのは、ちょっと考えてしまいますが……」
「その子?」
首を捻る屁舞留に、キョウジは頷いて答えようとする。だがそれよりも早く、その『縁』を持つ人物が、陣屋の広場に現れていた。
「ぼ……僕の――――」
『子供』の声が、そこに響く。
「ぼ、僕の『過去』では……駄目、ですか………!?」
「使える『縁』とは――――まさか、ケイタか!?」
おずおずと進み出て来たケイタに、屁舞留が驚きの声を上げる。それに対して、キョウジは頷いた。
「そう。ケイタ君ならば、あの村の住人だし、過去のシュバルツとの接点もある。だから、過去を戻るために必要な『縁』を持っている、という点では、これ以上ないと言うくらい、うってつけの人物だ。ただ――――」
「ただ―――――何じゃ?」
問い返す屁舞留に、キョウジは少し難しい表情をする。
「考えてみてくれ、屁舞留。ケイタ君が『過去』に戻ると言う事は――――」
「うん」
「もう一度、あの『戦』を、経験する事になるんだ」
「――――!」
キョウジの言葉に、屁舞留ははっと息を飲む。キョウジは、少し哀しそうに瞳を伏せた。
「自分で戦えて、身を守る術もある『戦士』であるならばまだいい。だけど、ケイタ君はそうではない。今回は運良く助かったけど、今度はもしかしたら死んでしまうかもしれないんだ」
「あ…………!」
「それでも屁舞留は……『もう一度命をかけて過去に戻ってくれ』と、あの子供に言えるか………?」
「…………ッ!」
キョウジのその言葉に、屁舞留も答えに窮してしまって唇を噛みしめる。
自分達が命をかけて、ケイタを守れるのならばまだいい。
だが自分達では――――現世の人間たちに関わる事が出来ない。ただ、傍観するしか出来ないのだ。
本当に、何も出来ないに等しい自分が、歯痒かった。
ケイタの声を聞いて、それまで幕舎の中で悄然としていたハヤブサが、広場の方に飛び出してくる。手には、シュバルツのコートを握りしめたまま――――
「ハヤブサ……!」
キョウジはハヤブサに声をかけるが、当然ハヤブサの方は気付かない。ただ、食い入るように一心に――――ケイタの方を見つめていた。
だがそれ以上踏み出さない、龍の忍者。
感じている躊躇いは、おそらく一緒なのだろう。
優しい人だな、と、キョウジは思った。
だからシュバルツも、ハヤブサの事を――――
この状況を見て独りの武将がケイタに問うていた。
良いのか?
本当に、良いのか。
お前は死ぬ事になるかもしれない。
それでも過去に、戻るのか。
その『願い』に――――命を賭すだけの覚悟が、お前にはあるのかと。
ケイタは叫んだ。
震えながら。
「僕は死んでも良いから、皆を助けて!」
その声に、龍の忍者が応えた。
「ケイタ……! お前の望みは、そのまま俺の望みだ。だから俺は……それを叶えるために、最善を尽くす……!」
そう言いながら、涙を流してケイタに頭を下げるハヤブサ。その姿を見ながら、キョウジもまた――――つられ泣きしそうになってしまって、慌てて涙を拭っていた。
本当に――――自分は霊体になってから、泣いてばかりだ。よくもまあ、これだけ自分から涙が出てくる物だと、キョウジも自身に呆れかえってしまう。
「ハヤブサ!! 良かったな!!」
ケイタと握手するハヤブサの周りを、あっという間に武将たちの祝福の輪が取り囲む。二人はその輪の中心で、もみくちゃにされてしまっていた。
その光景を見て、キョウジは悟る。
シュバルツと別れてから歩んできたハヤブサの道は
数多くの『仲間』を得るのにふさわしい物だったのだろうと。
「な? キョウジ。『零ではない』と言う事は、凄いじゃろう?」
屁舞留が笑いながら、キョウジにそう声をかけてくる。
「しかし、こんな風に繋がるとは思ってもいなかったがな!」
そう言って笑いだす屁舞留に、キョウジもようやく笑顔になった。
「それにしてもキョウジ」
「何? 屁舞留……」
「この『リュウ・ハヤブサ』と言う男……少々変わっておるな」
「えっ? 変わっているって?」
屁舞留のこの言葉に、キョウジも少々興味をかき立てられる。
「どのように『違う』のかな? ハヤブサは『人間』の筈だけど……」
キョウジの言葉に、屁舞留は「うむ」と頷いた。
「確かに、あ奴は『人の子』だ。だが、人の子にしては、少し……変わった『気』を放っておるな……」
「『気』ですか?」
問い返すキョウジに、屁舞留はハヤブサの方を見つめながら答える。
「うむ。あれは……まるで、『人の子』の身体の中に、『龍神』を封じ込めておる様な――――」
「…………!」
屁舞留のこの言葉に、キョウジもはたと思い当たる。
以前ハヤブサの血液を調べさせてもらった事があるのだが、確かに彼の血液からは、常人とは違うデータ値が叩き出されていた。それはつまり、そう言う事なのだろうか。
思わず、学術的好奇心が疼く。
知らず、自身の研究室をめがけて、キョウジは走り出しそうになってしまっていた。
(いやいや、落ちつけ、キョウジ・カッシュ……! ここは異世界だ。自分の研究室に戻ろうにも、戻りようが無いんだから――――)
そうやって1人でじたばたしているキョウジに気づいているのかいないのか、屁舞留は更に言葉を続けていた。
「キョウジ……あ奴、強いであろう?」
「そうですね……。常識では考えられないぐらいに」
苦笑しながら答えを返すキョウジに、屁舞留も「そうであろうな」と頷いた。
「吾からしてみれば、あれだけの物を内に抱えて、よく『人の形』を保っている物だ、と、思ってしまうがな……」
「そうですか……」
屁舞留に答えながら、キョウジは考え込んでしまう。
だいたい、ハヤブサと言いシュバルツと言い、それに自分の弟とその師匠。そして、その友人たちと言い、とにかく常識離れした強さを誇る『知り合い』が、自分の周りには多すぎる。だから、その辺りの感覚が多少麻痺気味になっているかもしれない、と、キョウジは思った。
(どっちにしろ、万が一帰ることができたら、ハヤブサの血液データをもう一度、洗い直してみる必要があるかもな……。屁舞留に良いヒントを貰ったし……)
今のところ、帰る伝手も手段もないけど、と、キョウジは苦笑する。
第一、もう死んでいる身だ。普通なら、このまま成仏しなければいけないのに。
いつまでも未練がましく意識のあるこの身――――一体、どう言う事だろう。
そうこうしている間にも、ハヤブサはケイタから話を聞き、時間を遡る決意を固めたようだ。握りしめていたシュバルツのコートをの一部を裂き、それを龍剣の柄に巻きつけていた。
待っていろ。シュバルツ。そしてキョウジ……。
お前たち二人の『失われた時間』を、必ず取り戻して見せるから。
柄に口付けながら、そう決意しているハヤブサ。
(…………!)
ハヤブサのその想いに、少し驚くキョウジ。ハヤブサが、シュバルツを取り戻したがるのは分かる。ハヤブサにとってシュバルツは、この上もなく大事で『愛おしいヒト』だからだ。だけどその上に――――自分の事も取り戻そうと考えていてくれていただなんて。
どうしてだろう?
シュバルツが居れば、もう私は居なくても――――
そんな風に物思うキョウジに、屁舞留が微笑みながら声をかけて来た。
「良かったの! キョウジ……。あの『龍神』は、お主を必要としておる様だぞ?」
「屁舞留……」
「あの龍神の力も加わる。今度はもっと、大きな『奇跡』が起きるやもしれぬな!」
そう言って楽観的に笑う屁舞留に、しかしキョウジは眉をひそめた。
「そうだと良いけど、あの戦場はそんなに簡単じゃない……」
全く身を守る術の無い村人たちを守りながらの撤退戦。それだけでも厳しいのに、敵味方の妖魔が入り乱れて、敵味方の区別がつかなくなる。さらに追い打ちをかけるように、素戔鳴と言う仙界軍の襲撃――――悪い事が重なり過ぎている。しかも、素戔鳴率いる仙界軍の攻撃は、シュバルツの再生能力を奪ってしまうのだ。
「少しでも……運命の『サイコロの目』が、良い物が出ればいいのだけれど……」
ハヤブサが連れて行く仲間を決め、時を渡ろうとしている。屁舞留もキョウジも、その後をこっそりついて行く事にした。
術の光の中から抜けると、そこはもう懐かしい村の風景だった。
「これは……私たち、時を越えたの?」
「これが、あの村……? 綺麗……」
ハヤブサと共について来た甲斐姫と孫尚香が、それぞれ感嘆の声を上げている。無理もない。彼女たちは、焼き払われた村の姿しか知らないのだから。
「ハヤブサさん! こっちだよ!」
時を越えた少年が、ハヤブサの腕を引っ張り走り出す。どうやら見せたい物があるようだ。そして暫く行くと、材木を抱えて村人たちと話しているシュバルツの姿を見つけた。
「シュバルツ……!」
ハヤブサは思わず、声を上げる。その声に「え………?」と、反応したシュバルツが、振り返った。
「え……! え……? ハヤブ、サ……?」
「シュバルツ……ッ!」
ハヤブサはそのまま、シュバルツに避ける暇すら与えずに、その身体を抱きしめる。「お……! おい……!」と、シュバルツが戸惑った様な声を上げるが、ハヤブサの抱きしめるその腕の力は、ますます強くなっていくばかりで。
「あ………! あ………!」
ついに、堪え切れなくなってしまったのだろう。ハヤブサはシュバルツを強く抱きしめながら、泣き始めてしまった。
(無理もないな)
キョウジは思う。
あの時空の道でシュバルツとはぐれて、実質どれぐらいの時がハヤブサの中で経っているのかキョウジには分かりかねるが、その間ハヤブサが、シュバルツを血眼になって捜し続けていたであろうことは、想像に難くない。しかも、やっと見つけたと思ったシュバルツは、いきなりハヤブサの目の前で砕け散ってしまっている。
立っているだけで
歩いている姿を見るだけで
そのヒトが『生きている』と実感するだけで――――
ハヤブサが泣き叫んでしまうのも、無理はないなとキョウジは思った。
「ハヤブサ……」
シュバルツも、ハヤブサのそんな姿に戸惑いつつも、そっとその背に腕を回している。泣き叫ぶハヤブサの姿に、何か感じるところもあるのだろう。
ふと見ると、少し離れた所でハヤブサについて来ていた女性二人も涙ぐんでいる。
(良かったな……)
キョウジも再会した恋人同士の抱擁を、素直に祝福していた。
そんな中、屁舞留が静かに桃の林の方に向かって歩いて行く姿が見える。キョウジは屁舞留の後を追いかける事にした。
「やはり、あった……」
桃の畑の中で、屁舞留は一本の木の前に来ると、そこで立ち止まった。
「屁舞留?」
「おう、キョウジか……」
呼びかけられた屁舞留が、穏やかな笑みを浮かべる。そのまま黙って、また、木を見つめ始めた。
「どうした? 屁舞留。その木は、一体……」
「『仙桃』じゃよ」
屁舞留は少し、哀しげに笑った。
「ほら……素戔鳴が言うておったじゃろう? ここに自分の『仙桃』があると……。それが―――――これ、じゃよ……」
「これが……!」
キョウジが見上げる先に立つ、一本の桃の木。その木は、桃を鈴なりに実をつけていた。
「……大丈夫じゃ……。そう、怯えるでない――――」
屁舞留は優しく木に触れると、そっとその木の幹に額を当てた。木の葉が、風もないのにざわ……と揺らめく。その音が哀しげに耳に響いたのは、キョウジの気のせいだろうか。
「そう……。そうじゃ……。そなたは悪くない……」
屁舞留はそう言いながら、目を閉じて木に額を当て続ける。しばらくそうしていると、歯のざわめきの音もだんだんと小さくなり、静かになって行った。
「よし……。良い子じゃな……」
そう言うと、屁舞留は木からそっと離れる。すると、それに応えるように、木から屁舞留の手の中に、桃の実がポトン、と、落ちて来た。
「……うん、甘い。美味じゃな」
シャクッ、と、音を立てて屁舞留が桃をかじる。
「キョウジもどうじゃ?」
もう一つ落としてきた桃を、屁舞留がキョウジに差し出した。
「え……? 何で? 現世の物には、触れない筈なのに……」
キョウジがそう言いながらも桃を受け取ると、屁舞留はにこりと笑った。
「これは、この木だけが時々くれる、霊体の様な物だ。だから、吾らの様な者でも触ることができる。この木なりの『礼』のつもりなのであろうな」
「そうですか……」
そう言いながらキョウジも、その桃をシャクッ、とかじる。口内に、甘くて優しい味が広がった。
「何故この木だけがこんな事が出来るのか、ずっと不思議であったが……この木が神仙界の物で、仙桃を生らす特別な木であったからなのだな。これでようやく得心したぞ」
そう言いながら屁舞留は、その桃の木を見上げる。木の刃の間から、優しい木漏れ日が屁舞留の頬に落ちていた。
「のう、キョウジよ……」
優しい風に吹かれながら、屁舞留がポツリと漏らす。
「今回の災厄の原因となってしまったこの桃の木だが……吾はこの桃の木の事を恨む気にはなれぬ……」
「屁舞留……」
「だって――――そうであろう? この木の何処に、『落ち度』や『咎』がある!?」
「…………!」
少し強い屁舞留の口調に、驚くキョウジ。屁舞留の言葉は続いた。
「この村が異世界に飛ばされてしまった時に、たまたまそこに紛れ込んでしまっただけではないか! そして、世話をしてくれた村の者たちに応えるために、実を生らしていただけだ! それなのに―――――『妖魔』とやらの手に触れただけで、それは断罪されねばならぬものなのか!?」
屁舞留の言葉を、キョウジは黙って聞いている。屁舞留の瞳が哀しげに歪んだ。
「かわいそうに……。 この木は怯えてしまっておったぞ。この先で起きる悲劇が、総て自分のせいなのではないかと苦しんでおった……」
「屁舞留………」
「植物は、想像以上に賢い――――。この木には、どうやら『先の戦』の記憶がある様じゃな……」
屁舞留がそう言いながら、その木の幹を優しく撫でる。そんな屁舞留の頬を、優しい木漏れ日が照らし続けていた。
「吾には分からぬ……! ただ『妖魔』と言うだけで、それの一から十まで嫌いぬかなければならぬものなのか? そう言う考え方をしなければ――――神仙としては、認められぬものなのか? そんなのって……! そう言う考え方は――――」
屁舞留は、拳を震わせながら叫んだ。
「絶対におかしい……! 吾には理解できぬ!!」
キョウジが、息を飲む気配がする。だが屁舞留は、構わず続けた。
「それとも、こんな風に考えてしまう吾の方こそが異常で、おかしいのか? 吾は間違ってしまっておるのか?」
屁舞留のその言葉には、キョウジは静かに頭を振った。
「何が間違っているとか……何が正しいとかは、私は判断は出来ないよ。ただ……」
キョウジの面に、笑みが浮かぶ。
「貴方のそういう考え方は、私は好きだ。いいと思うよ」
「キョウジ……!」
茫然と見つめ返す屁舞留に、キョウジは優しく頷く。それを見て屁舞留の面にも、ようやく柔らかい笑みが浮かんだ。
本当は、あの素戔鳴に今の考えを叫んでやりたい。
(だけど、無理じゃな……)
そう感じて、屁舞留は苦笑する。自分の『神気』と素戔鳴の『神気』どちらが強大かなんて、比べるべくもない。自分など、叫び声を上げる前に瞬殺されてしまうだろう。
だけどあの状況で、『違う!』と、叫び声を上げたケイタは、本当にすごいと思う。
そう尊敬すると同時に、屁舞留は少しケイタが羨ましくもあった。彼の上げた叫びで、キョウジやキョウジの影が、どれほど救われた事だろう。
自分も、そう言う者でありたかった。
キョウジ達を、救える存在であればよかったのに。
「――――!」
ふと、向こうから歩いてくる龍の忍者とシュバルツの姿を見て、屁舞留は慌てて物陰に隠れた。向こうからは自分の姿が見える事はない。心配ないと分かってはいるが、屁舞留は特に、あの龍の忍者の眼前に立つ事に、何故か恐怖を覚えた。
「屁舞留? どうした?」
きょとんとするキョウジを、屁舞留は懸命に手招きをする。
「良いからキョウジ! こっちへ来てくれ! 早く!」
「えっ? でも、シュバルツとハヤブサから隠れる必要なんて――――」
「良いから!! 早く!!」
屁舞留があまりにも必死に叫ぶものだから、キョウジも一応屁舞留に付いて木の陰に隠れた。そうとは気づかないシュバルツとハヤブサは、たわいもない話をしながら歩を進めて来て――――やがて、一本の木の前で、その足を止めた。
「シュバルツ……。これが、例の『薬効成分のある桃』が生る木か?」
そう言いながらハヤブサは、仙桃の木を眺めている。
「ああ、そうだ……。この木の桃に、かなり強力な薬効成分が含まれている」
「そうか……」
と、言ったきり、無言で桃の木を見上げるハヤブサ。
屁舞留は恐る恐るその様子を少し離れた木の陰から見守っていたが、木を見るハヤブサの視線に『殺気』の様な物を感じてしまって、屁舞留は知らず身を強張らせてしまう。
(こんな物がここにあるから……!)
龍の忍者の心の声が、こちらに響いてくる。屁舞留はそんなハヤブサの様子に恐怖を覚えた。
「キ、キョウジ……!」
思わず縋る様に、キョウジの名を呼んでしまう。
「どうした? 屁舞留」
「あ、あの男……ハヤブサは、あの木を斬るじゃろうか?」
キョウジはハヤブサの様子を見てから、屁舞留の方に振り返った。
「いや、斬らないと思うよ?」
「な、何でそう思うのじゃ……?」
おっかなびっくりといった按配で聞いてくる屁舞留に、キョウジは笑顔を見せた。
「だって、彼の傍にはシュバルツが居る。ハヤブサはシュバルツが嫌がることは絶対にしない筈だよ」
「そ、そうか……? しかし……!」
覗き込む屁舞留の視線の先に居る、龍の忍者。その目つきが、普通に怖い。完全に据わってしまっている目つきだ。それを見ていると、キョウジの方もだんだん自信が無くなってきた。
「だ、大丈夫だと、思うよ…………多分……」
「―――――!!」
キョウジのその言葉を聞いた屁舞留の顔色が、真っ青になってしまう。
「多分ではいかんのじゃ!! 何度も言うておるであろう!? この木自体に罪はないと――――!!」
「そ、それはそうかもしれないけれど……!」
「それに、あの木も心を痛めておると言っておるではないか!! それなのに、斬り倒すなどと暴力はいかんのじゃ!! 木が可哀想すぎる!!」
「いやだから、ハヤブサが木を斬ろうとしても、シュバルツがそれを止めるから大丈夫だと思うよ」
多分、と、キョウジは心の中で付け加える。
どうして「多分」となってしまうのかと言うと、ハヤブサが本気を出してあの木を斬り倒そうとした時が問題だと思ったからだ。本気を出したハヤブサは、シャレにならないレベルで強い。それこそシュバルツの制止が間に合うかどうか、微妙なくらいだ。
そんなこんなと屁舞留とキョウジが二人ですったもんだしているうちに、龍の忍者が木に向かって一歩、踏み出した。
「ひっ!!」
完全に怯えてしまっている屁舞留だが、仙桃の木から離れる事だけはしない。何としても守り抜きたいと、願っているのだろう。キョウジはそんな屁舞留の傍について、事の成り行きを見守ることにした。
「シュバルツ」
「どうした? ハヤブサ」
振り返った龍の忍者に、シュバルツは普通に答えている。特にハヤブサの態度から、何か警戒すべきものを感じている、と言う訳ではなさそうだった。
「この木の桃……食べさせてもらっても良いか?」
(し、食すのか!?)
龍の忍者のその言葉に屁舞留は思わず前のめりにこけそうになってしまう。しかしシュバルツの方は、特に何かを思う訳でもなく、普通に「ああ、良いぞ?」と、ハヤブサに返事をすると、慣れた手つきで桃の実をもいで、彼に渡していた。渡された龍の忍者が、それをシャリ、と、一口かじる。
「うん……。確かに甘いな。良い桃だ」
そう言いながら桃を食べる龍の忍者は、優しい笑顔になっていた。
(あ、あれ………?)
その姿を見て、屁舞留は拍子抜けをする。そんな屁舞留を見て、キョウジは苦笑していた。
(ま、まあ……ハヤブサの目つきは、普通にしていても少しきついな、と、感じる時があるからなぁ)
本人にその自覚があるかどうかは分からないが、ハヤブサは少々日本人離れをした、綺麗な顔立ちをしている。整いすぎた顔と言うのは、黙って立っていると、時に冷たい印象を人に与えてしまったりするものだ。
しかしハヤブサは、元来とても優しい人だ。
心を赦してくれた時に見せる笑顔は、とても柔らかい印象を周囲に与える。だから、ハヤブサはもっと笑顔を人に見せても良いんじゃないか、と、キョウジは思ったりすることもあるのだが。
だが彼は、戦いの中にその身を置かねばならない人。
そう簡単に――――人前で笑顔を見せられるものでもないのだろう。
「良い桃だろう? 村人たちが手塩にかけて育てているからな。しかし……それが、どうして――――」
ハヤブサと話していたシュバルツの瞳が哀しげに曇る。この桃と妖魔たちとのつながりが、村の襲撃に繋がってしまう事実が、彼の心に重くのしかかってしまっているのだろう。
「お前のせいでも、この桃のせいでもない。気にするな」
龍の忍者が桃を食べながら、ぶっきらぼうにそう言い放つ。
「ハヤブサ……」
「お前たちは、何も悪い事はしていない。だから、堂々と――――胸を張っていればいい」
(…………!)
ハヤブサのこの言葉には、屁舞留も心を打たれたようだ。その瞳が、感極まった涙で潤んでいる。
「キョウジ……。あ奴、良い男じゃの……」
そう言う屁舞留にキョウジもフッと笑顔を見せる。
「そうだろう? ハヤブサは、優しい人なんだ」
「シュバルツ。この桃、もう少しもらって行っても良いか?」
「ああ。構わないぞ? 好きなだけ持って行ってくれ」
ハヤブサの問いかけに頷くシュバルツの横で、屁舞留もうんうん、と、頷いている。
「構わぬぞ! そなたの様な者に食べてもらえるのなら、桃たちも本望であろう! いくらでも持っていくが良いぞ!?」
そうやってハヤブサに声をかけるのだが、当然ハヤブサには気づかれない。そのまま彼は桃を木からもぎ取っている。それでも屁舞留は、その姿を嬉しそうに眺めていた。
ただ、桃を捥ぎ取るハヤブサの口元に、微妙な笑みが浮かんでいる。
(あ、何か企んでいるな?)
キョウジはピンと来る物があったが、屁舞留のためにも敢えて黙っている事を選択していた。
『火急の話があるから』と、シュバルツが伝えていたにもかかわらず、集まりの遅い村人たち。やはり、彼らの危機意識は相当低かった。襲撃の事実をハヤブサたちが伝えても、俄かに信じ難い情報は、彼らの決断を鈍らせる。
しかし、妖魔たちの村を襲っていた他の部族からの嫌がらせの話、そして、ハヤブサたちが懸命に呼びかけを行ったおかげで、彼らはようやく村を離れて避難する決意を固めていた。
(夜も更けてきた……。妖魔たちや素戔鳴からの襲撃から、無事逃げ切ることができれば良いが――――)
そう思って表情を曇らせるキョウジの横で、しかし屁舞留は、少し明るい表情をしていた。何故なら――――
「キョウジ! 聞いてくれ! この村を覆っていた『死の闇』が、少し小さくなったぞ!」
「――――! それは、本当なのか!?」
驚くキョウジに屁舞留は嬉しそうに頷いた。
「本当じゃ……! つまりこれは、助かる人間が、先の戦よりも増える、と言う事じゃ!」
「そうか……」
屁舞留のその言葉を聞いて、キョウジも笑顔になる。しかし、屁舞留はまた顔を曇らせた。
「じゃが……。お主の影に宿る『闇』は消えてはおらぬ。そして、あの龍の忍者にも、『死の闇』が形成されつつある……」
「――――!」
息を飲むキョウジに、屁舞留は少し哀しげに笑った。
「じゃが、それはおぼろげな物じゃ。例えて言うなら、先の戦いのケイタの様な感じじゃな……。どちらに転ぶか分からん、と、言う事じゃ」
「ハヤブサが……!」
茫然と見守るキョウジ達の視線の先で、村人たちが移動を開始していた。次の戦いが始まりそうな気配を、濃厚に漂わせている。キョウジは、その後をついて行こうとした。それを、屁舞留が引き留めた。
「キョウジよ……。行くのか?」
キョウジは瞬間怪訝な表情をその面に浮かべたが、すぐに「ああ」と、頷いた。
「分かっておるとは思うが、吾らに出来る事は何もない……。戦いについてっても、己が傷つくだけだぞ。キョウジ……」
屁舞留のその言葉に、しかしキョウジは笑顔を浮かべた。
「ああ。分かっている。だがそれでも、私は行くよ」
「キョウジ――――」
屁舞留は少し、苦い顔をする。
自分達の姿など、どうせ誰にも見えないし、認知される事もない。
だから、この戦いに無理について行かずとも、『見守る』だけなら少し離れた所にある自分の結界の中で充分事足りると屁舞留は思った。
先の戦いで、キョウジはあれほど傷つき、苦しんだのだ。
ならば――――無理について行かずともいいのではないかと思う。
だがキョウジは、屁舞留のその忠告に首を振った。
「屁舞留……。確かに私の手は、誰も救えない。戦うシュバルツ達の力になれない事も、よく分かっている……」
「だったら――――!」
尚も引き留めようとする屁舞留に、キョウジは穏やかな笑みを返す。
「そう……見守るしか出来ない。それしか出来ないのならば、せめて――――せめて、彼らの傍で、見守りたいんだ。戦いの、一部始終を……」
「―――――!」
「傷つく事を恐れて、それすらも逃げてしまったら………私はもう、二度と彼らに顔向けできない。そんな気がする……」
だって彼らは逃げずに戦っているのに、と、キョウジは言った。屁舞留は、反論するべき言葉を失ってしまった。
「もっとも、こんな想いすら、結局は『自己満足』の類でしか無いんだろうけど……ね」
そう言って、少し哀しげに笑うキョウジ。屁舞留は首を振った。
(強いのう……キョウジは……)
素直にそう思う。
自分は、最初の戦で村が滅んだ時に、もう心が折れてしまっていたのに。
己の無力を呪い、不条理な戦を呪った。
わざわざ村の外の時空の空間に、自身の結界を作ったのもそうだ。
怖かったのだ。自分は。
村が滅んで誰も居なくなってしまったと知っていても――――あの惨劇が、また自分を追いかけて来そうで、怖かった。
だから自分は逃げた。
逃げてしまっていたのに。
だが目の前のこの青年は、自分が傷つく事を百も承知で、またその惨劇の中に身を投じようとしている。
思う。
『見守る』とは
こういう事ではないのか。
「『神』とは――――『人を裁く者』だ!!」
素戔鳴はそう言った。きっとそれは、『素戔鳴』と言う神の在り様。それはそれで、きっと『正しい』ことなのだろう。
自分は、『見守る』ことしか出来ない。
でもきっと、これもまた―――――神の在り様なのだ。
『見守る』ことで初めてなし得る、何らかの神の役割もあるのだろう。そう信じたい。
(怯えるな……!)
屁舞留は懸命に己を叱咤する。
大丈夫。
あの龍の忍者が引きつれてきた人の子たちが、村に覆っていた『闇』を、確かに少しだが、払った。
あの村の者が全員、死ぬことはないのだ。
命は、希望は繋がる。
大丈夫なのだ。
「じゃあ屁舞留。私は行くから――――」
そう言って踵を返そうとするキョウジを、屁舞留が引き留めた。
「待て、キョウジ」
「屁舞留?」
「吾も、お主について行く」
村から劉備の城へ避難して行く道中で、村人たちはまず妖魔たちの襲撃に遭った。あっという間に敵味方の区別がつかなくなり、戦場は大混乱に陥る。
そんな中でも人の子たちは連携して、何とかこの困難を切り抜けようとしていた。それぞれがそれぞれに――――己の出来る精一杯を成し遂げていた。傷だらけになりながらも、村人たちの集団は確実に劉備の城へと向かって行く。シュバルツ1人で戦っていた時とは、確実に違っていた。『1人じゃない』と言うのは本当にすごい事だとキョウジは思った。
それでも、皆が『守ろう』としていたその輪から、零れ落ちてしまう命はどうしても出てくる。
キョウジは、その1人1人の傍に行って、静かに目礼して手を合わせていた。すると、死した村人たちの身体から小さな光の玉が出て来て―――――静かに天へと還って行った。
「キョウジ……」
声をかける屁舞留に、キョウジは手を合わせながら答える。その瞳から、一筋の涙が零れ落ちていた。
「……『供養』の真似事、だよ……」
「…………!」
「おかしな話だけど……私が『死んだ』時……ハヤブサにこれをしてもらって、何故か……とてもホッとした事を覚えていたから――――」
「そうか……」
屁舞留がそう返事を返している間にも、キョウジはまた別の遺骸の所に行って手を合わせている。屁舞留が振り返ると、そこかしこに沢山の遺骸が転がっていた。
(キョウジは、これ全員に同じ事をするつもりなのであろうか……)
屁舞留は小さなため息を吐いてから、顔を上げた。
「お主独りでは大変であろう。吾も手伝おう」
「屁舞留……!」
キョウジが振り返ると、屁舞留はもう他の遺骸の前に行って、手を合わせている。しばらくそうして戦場を供養して回っていた二人であったが、やがて、戦いの方に動きがあった。ハヤブサが戦場にかかる橋を落とし、1人で戦う事を選択していたのだ。
「ハヤブサ!?」
落とされた橋の向こう側に居る龍の忍者に、呼びかけるシュバルツ。ハヤブサはにこりと微笑みかけると、踵を返して戦場へと向かって行っていた。その様を見て、屁舞留は茫然とする。
「馬鹿な……! あ奴は何で自ら進んで一人になったのじゃ!?」
「おそらく、この後襲撃してくるであろう、素戔鳴軍に備えるためだ……」
「何故じゃ?」
問い返してくる屁舞留に、キョウジは瞳を曇らせる。
「シュバルツと素戔鳴を邂逅させないためだ。神仙軍は、シュバルツのDG細胞を破壊してしまう力があるから――――」
「…………!」
キョウジの言葉に屁舞留は息を飲むしかない。
「馬鹿な……! あ奴はたった1人で、あの素戔鳴と戦うつもりで居るのか!?」
「そう言う事になるね……。そうしなければ、村人たちもシュバルツも救えない。ハヤブサは、そう考えているのだろう……」
無茶苦茶だ、と、屁舞留は思った。
いくら龍の忍者が『強い』とは言え――――
あれだけの『神気』を誇る素戔鳴に1人で挑むなど、正気の沙汰ではないと思う。
そうまでして――――
「そうまでして……ハヤブサはシュバルツを『救いたい』と、願っているのだろう」
「―――――!」
そうだった、と、屁舞留は思った。
ハヤブサは過去にシュバルツを目の前で失った時、『魔神』に暴走しかけている。
それほどまでに、あの男にとっては耐え難いのだ。
シュバルツを失う、と、言う事が。
だが、それだけの事をハヤブサがやっていても――――
「じゃが……お主の影に張り付いている『死の闇』は、まだそこに鎮座したままだぞ……」
「な――――!」
キョウジが息を飲む横で、屁舞留は哀しそうに瞳を伏せた。
ハヤブサの背に形成されつつある『死の闇』は、まだ色も薄く、はっきりとした形も為していない。しかし、シュバルツの背にあるそれは―――――どうしようもないほどはっきりと、その存在を屁舞留の瞳に訴えかけてくる。
死ぬのだ。
この男は死ぬのだと。
懸命に戦う龍の忍者の努力が総て徒労に終わってしまうのかと思うと、屁舞留はものの哀れすら覚えてしまう。
龍の忍者が懸命に手を伸ばしていても、その死の運命が覆る気配の無いシュバルツ。一体どうすればいいと言うのだろう。
対岸で茫然とハヤブサを見送っているシュバルツを、女性たちが懸命に説得している。彼女たちもまたシュバルツを生かすために、必死に働きかけを行っていた。シュバルツもそれに応じて、とりあえず村人たちと共に城へ向かう決意を固めてくれたようだ。
「屁舞留、私はシュバルツの後を追うが、貴方は――――」
どうする? と、キョウジが問う前に、屁舞留が応えた。
「吾も、キョウジと共に行くぞ」
こうして二人は、城へと向かうシュバルツ達の後を追った。
妖魔の軍に追われながら逃げる村人たち。
敵と味方の区別がつかない戦場は、混乱を極めていた。
流れ矢に当たって命を落とす者。妖魔に襲われて絶命する者が続出する。それはいくらシュバルツや甲斐姫が奮戦したと言っても、防ぎきれるものではなかった。
徒に犠牲が増えて行くこの現状――――キョウジも屁舞留も、ただ歯を食いしばって見つめているしかなかった。声は届かず、庇おうと差し出した手は空しくすり抜けて行くだけ。己の無力を痛感する。
(…………!)
そんな中、シュバルツは傷だらけになりながらも、何とか村人たちを守ろうとしていた。シュバルツが傷を負うたびに、キョウジの方にも同じ個所に痛みが走る。これは、気のせいなのだろうか。
だがシュバルツの身体のDG細胞は、ゆっくりとだが彼の傷を癒していた。
やはり、妖魔たちの攻撃では、シュバルツは死ぬことはないのだと知る。彼が『死』を迎えるとしたら、それは仙界軍の攻撃のみなのだ。
「……ハヤブサが戦っている方には……素戔鳴が来ているようじゃな……」
「…………」
『素戔鳴』と言う単語が、キョウジの心に暗雲を投げかける。
シュバルツは、行ってしまうのだろうか。
ハヤブサを守るために、素戔鳴の所へ。
例え、自分が死ぬと分かっていても――――
行く。
行ってしまうよな。
シュバルツは、そう言うヒトだ。
劉備の城が視界に入るぐらい近づいてきた。
それと同時に、仙界軍の兵士たちも、村人たちに迫って来る。
それを見たシュバルツがついに――――ハヤブサの方に行くと、断を下してしまった。
「駄目よ!!」
甲斐姫が懸命に、シュバルツを止めようとその前に立ちはだかる。
援軍が来るまで待って、と、呼びかける。
しかし、それでシュバルツが止められる筈もなく、彼女をすり抜けて、シュバルツは去って行ってしまった。後には座り込んで号泣する彼女が1人、残された。
援軍を待っていたのでは間に合わない。
そう言った、シュバルツの答えも正しい。
援軍と共に行動するべき。
こう主張した、彼女の答えも正しい。
だから、彼女にはあきらめないで欲しかった。
シュバルツを止められないのならせめて
せめて、援軍を
「駄目じゃ、キョウジ! 劉備殿の城に居る関羽と言う将軍は、援軍を出す事を渋っておるぞ!?」
キョウジから離れて一足先に城の様子を見に行っていた屁舞留が、涙を浮かべながらそう言って帰ってきた。
「――――! やはり………!」
援軍の遅滞が確固たるものになってしまって、キョウジは天を仰ぐ。
「もう、駄目なのじゃろうか……!? このままでは皆が――――!」
更に犠牲者が増えそうな予感に、屁舞留は震えている。キョウジは歯を食いしばると、屁舞留の手を取った。
「もう一度、彼女に呼びかけてみよう」
「え……っ!?」
驚いた屁舞留が顔を上げる。
「何を言っておるのじゃ!? キョウジ!! 吾らの声など聞こえぬと、あれほど――――!」
「それでも!!」
否定する屁舞留の声を、キョウジの大声が遮る。
「それでも……! 今、この現状を打開するには、彼女に動いてもらわなければならないんだ!! 劉備殿の援軍が無ければ、あの城の門が開かなければ、皆助からないのだから――――!」
「…………!」
息を飲む屁舞留を、キョウジはまっすぐ見つめる。
「無駄でも、呼びかけてみよう」
キョウジの手が、屁舞留の手を強く握った。
「力を貸してくれ、屁舞留」
まだ、あきらめたくない、と、キョウジは言う。その言葉に、屁舞留も頷いた。
「分かった……」
そう言う屁舞留にキョウジも「ありがとう」と微笑むと、二人で彼女の傍に立った。
あきらめるな!
まだ……あきらめるな!
そうやって、泣き続ける彼女に、何度呼びかけた事だろう。
一向に泣きやむ気配の無い甲斐姫の姿に、流石にキョウジも(無駄なのだろうか)と、思うようになってしまう。それを頭を振って振り払うと、また呼びかけ続けた。自分は、それしか出来ないのだ。99回叫んで駄目なら、100回叫ぶ。999回叫んで駄目なら、1000回叫ぶ――――キョウジはそう覚悟を決めて、呼びかけ続けた。
そうすればいつか
いつか、奇跡の『1回』が――――
「……………!」
泣いていた甲斐姫が、まるで何かを聞いたかのように、突如として顔を上げる。
そんな彼女に、キョウジはもう一度呼びかけた。
(まだ……まだ、あきらめるな!)
「あ…………!」
(こんな所で泣いている場合じゃない)
その声を、確かに『聞いた』彼女は、ぐしっと、己の涙を拭っていた。
あきらめて、泣き崩れるのは簡単だ。
だけど、そうじゃないでしょう。
まだ状況を変えるために、足掻ける道が、貴方にはあるでしょう?
ならば、ちゃんと足掻け。
最後まで―――――
そう感じた甲斐姫は立ち上がると、金拵えの武器を拾って、城に向かって走り出していた。
「…………!」
そんな彼女の後姿を見送っていたキョウジは、呆けたようにその場に座り込んでいた。
「大丈夫か!?」
驚いた屁舞留が、キョウジの顔を覗き込むようにして、その隣に座る。キョウジはゆっくりと屁舞留の方に顔を向けると、口を開いた。
「今………もしかして彼女に、私たちの声が聞こえた……?」
「分からん……。だが、お主の呼び掛けに反応したように、見えたな……」
「………………」
屁舞留のその言葉に、暫く呆けたようにその場に座り込んでいたキョウジであったが、やがて、「シュバルツ」と、小さく口の中で呟くと――――また、立ち上がった。
傷だらけのままで、ハヤブサの元へと向かってしまったシュバルツ。
彼の後を追わなければ、と、キョウジは思った。
「私はシュバルツの後を追うが………屁舞留はどうする?」
「ならば吾は、村人たちの後を追おう」
キョウジの問いかけに、屁舞留は即答した。
「残った村人たちが皆助かるかどうか―――――吾は、見届けねばならぬ」
あの龍の忍者や甲斐姫たちがこの村に入った瞬間、少しだけだが小さくなった『死の闇』
だから、見極めたいと、思った。
ケイタから始まった小さな奇跡。それが、どこまで広がって行くのかを。
「そうか……。分かった……」
キョウジはそう言って頷くと、シュバルツの後を追いだした。屁舞留もまた、村人たちと合流すべく、甲斐姫の後を追う。
聞こえない筈の『声』を聞いた甲斐姫。これもまた――――一つの『奇跡』だ。キョウジと共に居るようになってから、自分はこんな『奇跡』を見てばかりの様に思う。
もっと広がって欲しい。
こんな『奇跡』が。
キョウジの『影』に宿る闇も、何時か『奇跡』が起きて晴れてくれたらいいのに、と、屁舞留は祈るように願っていた。
キョウジはシュバルツの気配を追って、その後を追う。そして、木立の中に、座り込んで木の幹に凭れかかっているハヤブサと、その眼前に立つ仁王『素戔鳴』の姿を先に見つけてしまった。
ハヤブサの顔色は青ざめ、苦しそうに肩で息をしていた。敵を目の前にしても立ち上がらない龍の忍者を不思議に思って、キョウジはその原因を探ろうとして――――彼の左足の膝から下が、変なふうに折れ曲がっている事に気づく。
「―――――!!」
他にも身体に無数の傷が刻まれているハヤブサ。俄かに信じ難い光景を見てしまって、キョウジは大声で叫んでしまいそうになる。
「良い表情だ……。覚悟は、出来たか?」
そう問う仁王の視線の先で、穏やかな笑みを浮かべているハヤブサ。これは―――――どう見ても、『死』を覚悟して、受け入れている眼差しだ。
「駄目だ!! ハヤブサ!!」
堪え切れず、キョウジは叫ぶが、当然その声は誰にも届かない。そうしている間にも、素戔鳴はハヤブサとの距離を、さらに詰めて来た。
「人の子にしては、汝はよく戦った。その闘志に敬意を表し、吾直々に――――貴様に引導を渡してやろう……」
「ハヤブサ!!」
キョウジは叫んで手を伸ばすが、当然自分の声は誰にも聞こえず、その手が何かに触れることもない。自分はここに、居ないのと同じなのだ。ただ――――見守るしか出来ない。その事実に、キョウジは歯噛みする。
でも駄目だ、ハヤブサ
死ぬなんて――――!
キョウジの願いもむなしく、素戔鳴が剣を最上段に振りかぶる。そのままハヤブサは死を迎えるしかないのかと、キョウジが絶望しそうになった瞬間。
「ハヤブサ!!」
キョウジにとって、耳慣れた者の声が響く。
それと同時にそこに飛び込んできた風が、振り下ろされた素戔鳴の剣をかいくぐって、あっという間にハヤブサの身体をかっさらって行った。
「シュバルツ!!」
風の正体をいち早く看破したキョウジが叫ぶ。その先で、ハヤブサを庇ったシュバルツが、ガバッと起き上がっていた。ハヤブサの身体に起きている異変に、どうやら気づいたらしい。
「足を――――! ハヤブサ……!」
折れたハヤブサの足に手を伸ばして、シュバルツは治療をしようとしている。だがそれを、素戔鳴の震える声が遮った。
「………何だ? 貴様は………!」
「――――!」
はっと、弾かれた様に振り向いて、刀を構えるシュバルツ。それを、憤怒の表情を面に浮かべて、仁王は睨みつけていた。
「何者だ? 貴様は――――!」
「…………?」
目の前の仁王からの質問の意図が少しわからず、刀を構えながら眉をひそめるシュバルツ。その後ろで、龍の忍者が足掻いていた。彼は素戔鳴が何に対して怒り、何を言わんとしているのか―――――よく分かっていた。だから、シュバルツにそれを『聞かせたくない』と、願っていた。
しかし、ハヤブサの願いはかなえられず、素戔鳴の言葉はそのまま続いてしまう。
「何と邪悪な……! 何故、貴様の様な物が、人の子の傍をうろついておるのだ!!」
「――――!?」
「吾には見えるぞ……! 貴様のその身体―――――何と不自然でいびつで、邪悪な物で出来ておるのか!!」
「な………!」
素戔鳴の言葉に息を飲むシュバルツ。そんな彼に、目の前の仁王は更にたたみかけてくる。
「そんな『モノ』が、善良なふりをし、人の子に近づく……。その行為が、どれだけ人の子を危険に曝している事か――――汝は分かっておるのか!?」
「……………!」
「汝は、この世に存在していてはならぬものだ!! 今すぐ、抹消されるべきものなのだ!!」
素戔鳴の言葉に呼応するかのように、兵士たちがその周りに集まって来て弓矢をつがえ、シュバルツに狙いを定め始めた。
ああ――――
キョウジは、天を仰ぐ。
この断罪は、シュバルツが受けるべき物ではない。自分こそが、その前に行って裁かれなければならないのに。
シュバルツがそんな身体になってしまった事自体、彼の方には何一つ落ち度など無い。悪いのは、総て私だ。私のせいなのだ。それなのに。
どうして――――シュバルツが、そんな風に責められなければならないと言うのだろう。
小さく震えるシュバルツの身体。彼の動揺が見え隠れしていた。
だが、そんな彼を救ったのは後ろに居るハヤブサの存在だった。
「シュバルツ……ッ!」
足掻く龍の忍者から発せられたか細い声が、シュバルツを正気へと戻らせた。
彼は素戔鳴から逃げるべく、閃光弾をその手から放つ。その場に居る者たちの視界を奪って、とりあえず、その危地から脱出する事に成功していた。ハヤブサを抱えて走るシュバルツ。キョウジはその後をついて行く。
「……………!」
だが、キョウジは気付いてしまう。
シュバルツの身体に、素戔鳴の剣が掠めていたと言う事実に。
シュバルツを形作っているDG細胞が、もうゆっくりと壊れて行くしかないと言う事実に――――。
それでもシュバルツは、黙ってハヤブサの怪我の手当てをしていた。
『死』を覚悟していたハヤブサを、「生きろ」と、懸命に説得していた。自分が緩やかに壊れて行っている事を隠して―――――
そんなのは嫌だ、治したい、と願って、キョウジはシュバルツに手を伸ばす。
しかし、キョウジの手は、何度やってもシュバルツの身体に触れることすら出来なくて。
ごめん、ハヤブサ……。
ごめん、シュバルツ……。
忍者二人の逃避行を見守りながら、キョウジはただ涙を落とし続けていた。
この先には、もうどう足掻いても悲劇しか待ち受けていない。
どうして………。
どうして、こうなってしまうのだろう。
キョウジは、自らの無力を呪うしかなかった。
懸命に逃げていた忍者たちであったが、素戔鳴の組織だった攻撃に、ついに追い詰められてしまう。それでもハヤブサは、懸命にシュバルツを守ろうと足掻いたが――――
傷だらけのハヤブサが、素戔鳴の猛攻に耐えきれる筈もなく。
ついに龍の忍者は、その身を起こすことすら出来ないほどの傷を負って、倒されてしまう。
「ハヤブサ!! ハヤブサ!!」
「う………う………」
懸命に呼びかけるシュバルツに、ハヤブサはもう、僅かに身じろぐことでしか答えられない。そこに素戔鳴が、シュバルツに呼びかけてくる。ハヤブサを助けたければ、黙って自分に斬られよと。
「………本当に、私が黙って斬られれば、ハヤブサを見逃してくれるのか?」
「ああ。吾は、約束は守る」
シュバルツはそんな素戔鳴を、しばらく推し量るように見つめていたが、やがて微笑んで頷いた。素戔鳴の言葉は信ずるに足る――――そう、判断してしまったのだろう。
シュバルツはハヤブサに、最期の言葉をかける。
今までありがとう。
幸せだった。
元気で。
それだけを言うと、彼は刀をそっと置き、素戔鳴の方に歩を進めて行く。
(シュバルツ……!)
キョウジは大粒の涙を流していた。
シュバルツを守ってやることも、素戔鳴を止める事も出来ない自分。
見守ることしか出来ない自分。
ならばせめて
見守り続けなければ――――
キョウジはそう思うのに、視界は変に霞んで行くばかりだ。
駄目だ
駄目だ
どうして――――こうなってしまうのだろうか。
せめて、見届けなければならないのに。
素戔鳴に斬られるために、その傍に歩を進めたシュバルツ。
「………もう、良いのか?」
「ああ。もう、別れは済んだ」
「そうか………」
チャッ、と、素戔鳴の構える天叢雲の剣が音を立てる。
あっさり素戔鳴の言う事を聞いたシュバルツに対して、一瞬、仁王の瞳に慈悲の色が浮かんだようにキョウジには見えた。だがそれも、すぐに掻き消えた。
「……潔くその身を差し出した汝に免じて、せめて苦しませずに、あの世へ送ってやろう」
「…………」
素戔鳴から最後通牒を突きつけられても、シュバルツの穏やかな気配は変わらない。その姿が酷く綺麗で、哀しかった。
(シュバルツ……ッ!)
ハヤブサを守って死ねるから
これでいい
貴方はそう思っているんだろう?
だけど……
だけど―――――!
ハヤブサも私も
貴方の『死』など望んでいない。
だけど、それを止める術が無いから哀しい。
本当に
本当にどうすれば、良かったと言うのだろうか。
もう後は斬られるだけ――――素戔鳴が、天叢雲を最上段に振りかぶる。
だがそれに、待ったをかける者が居た。
ハヤブサである。
満身創痍の彼の何処に、そんな力が残されていたのか。
彼は『起き上がる』と、シュバルツを背後から引き倒して、その上に馬乗りになっていた。
「―――ハヤブサよ。これは一体何の真似だ?」
自分の裁きに横槍を入れられた格好になった素戔鳴が、不快感をあらわにしながら忍者二人を見下ろしている。
だがハヤブサも、懸命に素戔鳴に頼み込んでいた。彼と『最期』に、話す時間が欲しいと。
「お願いだ! 少しでいいんだ……! 彼と話す時間をくれ……! もう死に向かう身なれば、それぐらいの情けはあってもいいはずだ……!」
「……………」
素戔鳴は推し量る様に、二人の様子を無言で見つめていたが、やがて、構えていた天叢雲の剣を下に下ろした。どうやら、ハヤブサの懇願を受け入れてくれたらしい。
「よかろう……。少しの間、待ってやる」
そう言うと素戔鳴は2、3歩下がって、二人から少し距離を開けた。
(……何を、話すつもりなのだろう?)
キョウジは二人の会話が気になって、少し傍に近寄って、耳そばだてた。
そして知る。
ハヤブサは、己が身体に爆薬を仕掛けている事。
そしてそれを――――今から作動させるつもりである事を。
「このままでは、俺もお前も助からない……。ならばどうせなら、俺はお前と共に死にたい……」
シュバルツの頬を優しく撫でながら、ハヤブサは切々と彼に語りかけている。
「俺と一緒に、死んでくれ、シュバルツ……」
「…………!」
(違う―――――!!)
キョウジは即座に悟った。
嘘だ。ハヤブサは、嘘を言っている。
ハヤブサは、およそ『あきらめる』と言う事を知らない人だ。この状態になってもおそらくハヤブサは、シュバルツを助ける事をあきらめてなどいない。助けられる『策』を思いついたからこそ動いた。もう動く筈の無いその身体に鞭を打って――――
DG細胞で構成されているシュバルツの身体。実は、ハヤブサもDG細胞を滅殺する事が出来る。彼が扱っている特殊な妖刀『龍剣』――――これにありったけの『気』を込めてそれを振るえば、DG細胞を滅する事が出来るのだと、キョウジはハヤブサ本人から聞いた事があった。
だからハヤブサも、シュバルツを『殺そう』と思えば殺す事が出来るのだ。彼の愛刀『龍剣』を用いれば。
しかし、今ハヤブサが用いようとしているのは、身体に仕込んでいる『火薬』
それではシュバルツは殺せない。その瞬間、体は粉々に砕け散るかもしれないが、3時間後にはDG細胞の持つ『自己再生』が働いて、彼を甦らせる事が出来るのだ。そう、シュバルツが『普通の状態』であるならば――――
おそらく、ハヤブサはそれを狙っている。
そうまでして、彼はシュバルツを『助けたい』と願っているのだ。例え、それで自分が死んだとしても構わない。彼は、本気でそう思っているのだろう。
でも駄目だ。
駄目なんだ、ハヤブサ。
シュバルツは既に、素戔鳴の剣で傷を負ってしまっている。もう、彼の身体は、ゆっくりと壊れて行くしかないんだ。
そこに爆薬で粉々に吹っ飛ばされてしまったら、シュバルツも本当に『死んで』しまう。DG細胞の『自己再生』は、もう働かない――――!
このままではハヤブサは無駄死にするだけだ。
止めないと――――!
キョウジはそう強く感じて一歩、足を踏み出そうとする。
しかし、何故かそこから動けずにいた。
シュバルツと共に『死のう』としているハヤブサを、どうやって止めれば良いのか。
その有効な手段を、キョウジは思い浮かべられなかったからだ。
ハヤブサは、「シュバルツが死んでも、爆薬を作動させる」と言っていた。
つまり、シュバルツが死んだら、もう生きている気など無いと言う事だ。
もしも、あのハヤブサに
「もうシュバルツは助からない。だから貴方も、死ぬのを止めろ」
と、告げたらどうなるか。キョウジは容易く想像できた。
おそらく龍の忍者はこう答えるだろう。
「何だ。じゃあ……本当に、『共に死ねる』な」
そう言って幸せそうに笑いながら――――あっさり爆薬を、作動させてしまうだろう。
これは、ある意味チャンスでもあった。
愛し合う二人が、本当に『共に死ねる』機会(チャンス)。
「共に生き、共に死にたい――――」
ハヤブサは時々、シュバルツにそれを望む傾向があったから。
何と言う事だろう。
ハヤブサを『救う』ための手段が、本当に見つからない。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
優しく見つめるハヤブサの視線の先で、シュバルツが大粒の涙をポロポロと零し始めた。
「嫌だ……! ハヤブサ……! 死なないでくれ……!」
シュバルツも同じなのだろう。
ハヤブサを守りたい。死なせたくない。
だけど、その手段がどうしても見つからないから
もう、泣いて縋るしか道が無くて――――
だがハヤブサは、そんなシュバルツを見て、本当に幸せそうに笑った。
「嫌だ……。お前こそ……俺を、置いて逝かないでくれ」
その言葉に、シュバルツは言葉を失ってしまう。
「共に……死んでくれ、シュバルツ……」
シュバルツの頬に流れ落ちる涙を優しく拭いながら、ハヤブサは言った。
「ハヤブサ……ッ!」
「俺と、共に――――」
「…………ッ!」
そんな二人の様子を見て、キョウジは本当に途方に暮れてしまう。
これは、悲劇なのか?
それともハヤブサにとっては、シュバルツにとっては
これこそが――――『幸せな結末』になってしまうのだろうか?
だって、二人は共に死ねる。
本当に――――共に死ねて、しまうのだから。
でも『嫌だ』と、キョウジは思った。
こんな結末は――――あまりにも、哀しすぎる。否定したい。それともそう感じる事こそが、自分のエゴなのだろうか。
どうすれば、いい?
二人のために、私は一体どうすれば――――!
その時、森の中から一つの小さな光が、キョウジに向かってかけて来た。
「キョウジ!!」
「屁舞留!?」
その小さな光は、屁舞留の霊体であった。屁舞留はキョウジに向かって一直線に息を弾ませながらかけて来た。
「吾は、間に合ったか!? 二人はまだ、生きておるか!?」
「ひ、屁舞留? どうした?」
戸惑いながら問いかけるキョウジに、屁舞留はにこっとその面に笑みを浮かべながら応えた。
「喜べ、キョウジ!! 援軍が来るぞ――――!」
「ええっ!?」
驚くキョウジに屁舞留は嬉しそうに笑った。
「本当だ!! 彼女たちの援軍の要請に、城に居る関羽が、やっと答えてくれたのだ!!」
それと同時に、素戔鳴の方にも斥候から報告が入る。劉備の城から援軍が出て、自分達に敵対する様であると。その援軍がすぐ間近にまで、迫っていると。
「して、劉備軍の将は誰か!?」
問う素戔鳴に兵が答えようとする。
「はっ! 将の旗印は――――」
その言葉を最後まで言いきるより前に、馬のいななきと共に、一体の人馬がそこに飛び込んできた。
「我こそは関羽!! 字を、雲長と申す者なり!!」
燃えるような赤い毛色の馬に乗った、身の丈9尺の流れる様な髯をその面に湛えた偉丈夫が、大音声で名乗りを上げた。
「キョウジ!! 良かったな……! これであの二人も、助ける事が出来るぞ!!」
それに対してキョウジは、少し哀しげに首を横に振った。
「確かに……ハヤブサは、これで助けられるかもしれない……。でも、シュバルツは――――」
関羽は、素戔鳴に引き上げるよう忠告する。素戔鳴は、歯噛みしながらもそれに従った――――――かに、見えた。
しかし。
一瞬の隙を衝いた素戔鳴の無情の刃が、シュバルツの身体を貫いてしまう。それをすると素戔鳴は、潮が退くが如くそこから引き揚げて行った。
後に残されたのは、致命傷を負ってしまったシュバルツ。
「シュバルツッ!!」
ハヤブサの悲痛な叫びが、そこに響き渡っていた。
「な…………!」
茫然と息を飲む屁舞留の目の前で、シュバルツが「ハヤブサ……」と、微笑みながら顔を上げた。
「何故俺なんかを守った!? 何故あの攻撃を避けなかったんだ!! シュバルツ!!」
そう。ハヤブサには分かってしまった。
あの攻撃をシュバルツがもろに受けてしまったのは、シュバルツが自分を庇ってしまったから。
その言葉に対してシュバルツは、その面に優しい笑みを浮かべる。
「あはは……。本当に、そうだな……。一番ベストだったのは、お前を抱えて飛べればよかったんだが――――」
ドサリ、と、音を立てて、シュバルツの『左腕』が、地面に落ちる。
「もう………そんな力も……私には、残っていなくて……」
斬られた場所以外から、彼の身体が崩れた事に、ハヤブサも、そして周りの者たちも皆、衝撃を受けた。ただ、キョウジだけが1人、哀しげに瞳を伏せた。
「どう言う、事だ………?」
ハヤブサが、茫然と呟く。
「どう言う事だ!? 何故だシュバルツ!! お前まさか――――既に斬られていたのか!?」
ハヤブサの叫びに、シュバルツは微笑みながら「そうだ」と頷いた。
「い……何時だ……?」
震えながら問うハヤブサに、シュバルツは淡々と答え続ける。
「最初に……お前を庇った、あの時に……」
「―――――!」
「避けきれなくて……少し、掠ったみたいなんだ……」
「シュバルツ……!」
「駄目だな……。確かに、お前が言った通り……全然、治せなかったよ……。ハヤブサ……」
「―――――ッ!」
ここでようやく、関羽より遅れてきた部下たちが、この場所に到着していた。兵士たちの間に混じって、孫尚香も、甲斐姫も。
そして、見てしまう。傷だらけになって倒れているハヤブサが泣き叫び――――その視線の先で、静かに壊れていくシュバルツの姿を。
(何てことなの……!? やはり……間に合わなかった………!)
自分達の力が及ばなかった事に、甲斐姫は息を飲み、孫尚香は天を仰いだ。誰しもが、言うべき言葉を失っていた。
「もう……敵はいない……。だから……自爆なんて、考えるな。ハヤブサ……」
「シュバルツ……! 嫌だ……!」
シュバルツは、幸せそうに笑っている。愛する人を守りぬけたから。
ハヤブサは、絶望に顔を歪めている。愛する人を、守れなかったから。
「ハヤブサ……今まで、ありがとう……」
「嫌だ……!」
龍の忍者は哀しげに首を振る。
だけど、彼の願いを叶える手段は、ここにはもう何も無くて。
それでも、ハヤブサはシュバルツに向かって、必死に手を伸ばしていた。
願う。
触れたいと。
引き止めたいと――――
「ハヤブサ………」
全身にひびが入り、もうほとんど動かなくなっているであろうシュバルツの右手が、ピクリ、と、動いた。
彼も、願ったのだろう。
ハヤブサに、触れたいと。
だけど、その願いは、叶えられる筈もなく。
「ハヤブサ……あ、り……ガ――――」
パリン、と、音を立てて、そのヒトは砕け散った。最期まで、優しい笑顔の残像を残したまま―――――
「―――――――」
ハヤブサは何事か短く言葉にならない叫びを上げたかと思うと、そのまま意識を手放してしまった。傷だらけになったその手には、空蝉の如く空になった、シュバルツのロングコートが握りしめられていた。
その悲痛な姿に皆一様に、言うべき言葉を失ってしまう。中にはすすり泣き、嗚咽を漏らす者もいた。
「この世に神様は居ないの……?」
甲斐姫の呟きが、皆の気持ちを代弁していた。
キョウジはまたふらふらと、気を失ったハヤブサの後をついて行ってしまっていた。屁舞留も、その後をついて行く。
「――――――!」
寝台の上で目が覚めたハヤブサは、手の中にあるシュバルツのロングコートに気がつくと、声を上げて泣き出してしまっていた。握りしめられたロングコートが、ぐしゃぐしゃになってしまっている。キョウジは、そんなハヤブサを見ていられなくなって――――幕舎をそっと後にしていた。
(これから、どうすればいいのだろう……)
キョウジは陣屋の広場に歩を進めながら、漠然とそんな事を考えていた。
少ないとはいえ、村人たちも妖魔たちも、ある程度は助かっている。もうこれ以上「シュバルツを助けたい」と言う個人的な願いだけで、あの悲惨な戦場を2度も3度も繰り返させる訳にはいかないと思った。実際、この戦場の結末を否定したいと願って時を遡ったケイタ自身も、何度も危ない目に遭っていた。文字通り、命からがら――――今回は運良く助かった様な物だが、次はどうなるか分からない。
(もう、『村を救う』という観点から言うのなら――――この成果でも充分なんだよな……。でも、ハヤブサが………)
このままではハヤブサだけが、報われない。
「キョウジ……」
かけられた声にキョウジが振り向くと、そこに屁舞留が酷く申し訳なさそうな顔をして立っていた。
「キョウジ済まぬ……。またしても、お主の『影』を――――」
屁舞留の言葉に、キョウジは静かに首を振る。
「私たちの事は良いんだ……。それで助けられた人たちが居るのなら……。でも――――」
「龍の忍者か………」
言い淀んだキョウジの言葉に、屁舞留も瞳を曇らせる。
あの龍の忍者は、シュバルツを助け出せるまで、おそらくこの戦場を放棄する事はしないだろう。でも、絶望的に厳しい戦場――――このままでは龍の忍者も、あの村を覆う『死の闇』に囚われてしまう可能性がある。
どうすればいいのだろう。
自分は、助けてもらった村の『土地神』として、どうするべきなのか―――と、屁舞留が考え込んでいた時、陣屋の広場に集まっていた人間たちが、声を上げていた。あの青年――――シュバルツを、見捨てるべきではない、助けるべきだと。
傷だらけで動けない筈のハヤブサまでもが広場に出て来て懇願する。シュバルツを助けるために、自分を過去へ戻して欲しいと。
「焦るな。龍の忍者」
それまで黙って皆の話を聞いていた太公望が、ついに動き出した。
「どうせなら、『全員』を助けないか?」
「え………?」
太公望の真意が分からず、きょとん、とする皆に向かって、稀代の軍師は『策謀家』としての笑みを浮かべる。
「村人が全員逃げられるように……あの青年を悲劇から助けられるように――――」
状況のお膳立てをしてやる、と、笑う軍師に屁舞留は首を捻り、キョウジは茫然としていた。
「ど……どう言う事じゃ……? あの男は、何を企んでおるのじゃ……?」
戸惑いながら問う屁舞留に、キョウジが答えた。
「おそらく……あの村の『歴史』に介入する気なんだ……」
「介入じゃと?」
少し驚く屁舞留に、キョウジは頷く。
「ああ……。この戦いで、生き残った村人たちや妖魔たちがだいぶ増えた。そして、ハヤブサとシュバルツの過去にも『接点』が出来ている。恐らく太公望は、新たに出来たこれらの『縁』を使って、あの戦いに至るまでの歴史に『介入』するつもりなんだ……」
襲撃される前に、村人たちが素早く避難できるように。
敵味方が入り乱れる戦場の問題を、解決できるように。
難民の受け入れ先を、しっかり確保できるように。
「何故じゃ……」
屁舞留が、茫然と呟く。
「何故あの者たちは……吾の村の民達のために、そこまでして――――」
「きっと……あの人たちの中で、ハヤブサの歩んできた道が――――『彼の願いを叶えたい』と、思わせるのに十分な物だったから、だろうね……」
つまりここに至るまでの道のりで、ハヤブサ自身がその技量で、多くの人たちの『願い』を叶えて、救って来たからに他ならない。それが一本の大きな太い縄となって、死へと落ちて行く村人たちとシュバルツに、差し出されているように、キョウジには見えた。その編まれていく縄も、それを支える人数も、徐々に増えて行きつつある。
しかし、シュバルツがその縄を掴むのはおそらく最後。
彼は一番『死』に近い、最下層にその身を置いている。
果たして皆の手は
ハヤブサの伸ばされた手は
今度こそ、シュバルツに届くのだろうか――――
「では行くぞ!! ぐずぐずするな!!」
周りに喝を入れながら、軍師太公望が動き出す。
「私たちも行こう!」
キョウジは屁舞留に声をかけて、自身もまた、太公望の後について行った――――
「……ここから先は、貴方の知っている通りの戦いの展開になる。皆無事に――――あの戦場を抜けられた、と言う訳だ」
ここでキョウジがシュバルツに情報を渡す手を一度止めて、目の前のシュバルツに微笑みかけた。当のシュバルツは、ただただ呆然とするしか無かった。
「そんな……! じゃあ、私が経験したこの戦場は、ハヤブサたちにとっては――――!」
「そう。『3度目』と言う事になる。貴方は既に二度、死んでいるんだ……」
「……………!」
言葉を失うシュバルツに、キョウジは小さな息を吐くと、再びその面に笑みを浮かべた。
「多分ハヤブサは、貴方を救い出せればそれでいいと思っているだろうから、それだけの事があったと言う事は、絶対貴方には言わないと思う。でも、私は知っていて欲しかったんだ……。貴方を救うために、皆がそれだけ手を伸ばしてくれた、と言う事実を」
「ハヤブサ……!」
シュバルツは、自分を抱きしめながら眠る龍の忍者を見つめる。
何と言う事だろう。
自分は、もうハヤブサに、返しても返しきれないほどの『恩』を、受けてしまっている事になるのではないだろうか?
どうすれば、良い?
そんな彼に報いるために、自分はいったいどうすれば――――
「シュバルツ……」
キョウジに優しく呼びかけられて、シュバルツははっと、我に帰った。
「そう言えばキョウジ。屁舞留はどうしたんだ?」
キョウジの話を聞きながら、疑問に感じた事を、シュバルツは口に出していた。
キョウジが霊体になってから、常にその行動を共にしていた屁舞留。今この場に、キョウジと共に居てもおかしくはない存在なのに。
300年生きていると言っても、幼く、男とも女とも区別のつかない不思議な容貌をしていた屁舞留。シュバルツも会いたいと思った。
だがキョウジは、そんなシュバルツの問いかけに、少し哀しげな笑みを浮かべる。
「…………!」
割れてしまった土地神の形代の石と相まって、酷く嫌な予感に襲われた。
「まさか――――」
「シュバルツ………」
少し、逡巡しているように見えたキョウジであったが、やがて、意を決したように顔を上げた。
「そうだね……。話すか話すまいか、大分迷ったんだけど……やはり、貴方は知るべきだ」
そう言いながら、キョウジはシュバルツの手に、再び己が手を重ねてくる。
「キョウジ……」
「話すよ。総て。私と屁舞留が、あの戦いで何をしたのかを―――――」
キョウジの手から、再び光芒が溢れだす。
シュバルツはまた、キョウジの回想の世界の中に、入って行った――――
太公望が村人たちの話を聞いて、同時にかぐやの力を使って過去への介入を開始する。それと同時に村の方にも変化が現れ始めていた。村の上空に鎮座していた大きな『死の闇』の塊が、徐々に小さくなり始めて行ったのだ。
「す、すごい……!」
しばらく茫然とその様を眺めていた屁舞留であったが、やがて意を決したかのように立ち上がった。
「吾は決めたぞ。キョウジ」
「えっ? 何を? 屁舞留」
「ここの結界を廃棄して――――村の社に移る」
そう決断した屁舞留の行動は早かった。
居住していた結界内から必要な物だけを持ち出すと、キョウジを伴って村へと移り、時空の空間の中に浮かべていた結界を始末して、社の中に新たな結界を築き上げたのだ。
「元はと言えば、吾は最初、この社の中に住んでいたのだ……。村が襲われてからは、ここに居るのが怖くなってしまって――――あそこに逃げ込んでいた様な物だが……」
情けない話だがな、と、笑う屁舞留にキョウジは静かに首を振った。
「だが仮にも『土地神』と、祀られている者が、他所に逃げ込んでおっては話にならぬな。吾もここに留まって、今度の戦を見守ろうと思う」
「屁舞留……」
「ありがとうな、キョウジ。そなたのおかげだ」
「えっ?」
驚くキョウジに、屁舞留はにこっと微笑みかける。
「そなたが傷ついても傷ついても………何度も何度も立ち向かう『勇気』を見せてくれたから―――――吾もこうして、立ち向かう決心が出来た」
「えっ………!」
「だから、礼を言わせてもらう、キョウジ。お主は吾に、『勇気』をくれた」
「そ、そんな……! 私なんて、大したことはしていない。何も考えずに、ただ、突っ走ってしまっただけで――――」
顔を少し赤くしながら、しどろもどろになるキョウジ。そんなキョウジが面白くて、屁舞留も声を立てて笑っていた。
そんな中、社の結界に意外な人物が現れる。状況を動かすために走り回っていた、太公望その人が訪ねて来たのだ。
「――――!?」
ギョッ、と、息を飲む屁舞留とキョウジに、いきなり結界に入り込んできた太公望は、中をきょろきょろと見回しながら無造作に問うてきた。
「ここが『土地神』の結界か? ……と、言う事は、『土地神』はどっちだ?」
「――――!」
瞬間的に怯えの表情を浮かべる屁舞留。キョウジは屁舞留を守るようにその前に立つと、口を開いた。
「『土地神』は、この子です。私は、居候の様な者で――――」
太公望は敵ではない、と、分かっているから、キョウジはそんなに警戒はしなかった。ただ、何故ここを急に訪ねて来たのか――――その真意が分からず、少し戸惑ってしまう。
「なるほど……。お前が『土地神』か……」
太公望はしばらく屁舞留を検分するように眺めていたが、やがてポリポリと頭を掻きながら、フッと小さく息を吐いた。
「……やれやれ、全く穏やかな『神』もいたものだ。あの龍の忍者も、気の回し過ぎだな………」
「ハヤブサが?」
少し驚いた声を上げるキョウジに、太公望は意外そうに問うてくる。
「うん? お前は、あの龍の忍者の知り合いか?」
「ええまあ。いろいろと、紆余曲折がありまして――――」
そう言って茶を濁すキョウジに、太公望は、そうか、と、呟く。
「お前とあの青年――――」
結界の中からシュバルツを見つめながら、太公望は口を開いた。
「とてもよく似ているな……。それも、訳あり……か?」
「ええまあ――――」
探るような太公望の眼差しを受け止めながら、キョウジは頷いた。ふむ、と、顎に手を当てて考え込むような仕種を見せる太公望に向かって、それまで黙ってキョウジの影に隠れるようにしていた屁舞留が口を開いた。
「キ、キョウジも、そして、あのシュバルツも、罰せられるような『悪人』ではないぞ!? 吾らを助けてくれた者たちなのじゃ!! お願いじゃ!! この者たちに害を加える事だけは――――!」
「そのような事はせぬぞ」
太公望にあっさりそう言われて、屁舞留は思わずつんのめりそうになった。
「あの青年が、馬鹿がつくほどお人好しなのは、こちらも良く熟知している。それに、あの青年を救う事は、人の子たちの強い『望み』だ。それを違える訳にもいかんのでな」
「う………!」
太公望は手の中で打神鞭をポンポン、と、弄びながら「まだまだだな……。もうひと押しと言ったところか……」と、独りごちていた。静かに佇んでいるように見える太公望だが、その頭の中は、目まぐるしく動いているのだろう。
「ところで、『土地神』」
「吾の名は、屁舞留じゃ!」
ぶっきらぼうに太公望に呼びかけられて、屁舞留は思わず名乗ってしまう。太公望はそんな屁舞留をちらり、と見やると、少し唇の端を吊り上げた笑みを見せた。
「今回の戦――――お前たちも、何か動いてみないか?」
「えっ?」
太公望の意図を咄嗟に理解できず、屁舞留はきょとん、としてしまう。
「『土地神』として、民たちに何か働きかけても、別に罰は当たらんと思うぞ? お前はあれだけ村の者たちの信仰を集めているのだ。それを、活かさない手はない」
「…………!」
唖然、と、する屁舞留に向かって、太公望は少々傲岸、ともいえる笑みを向けて来た。
「何、お前たちが何かをやって、それが悪い方に転がりそうになっても――――私がそれを修正してやる。全知全能たる、この私がな」
「な…………!」
「――――さて、私は忙しい。これにて失礼させていただくぞ」
パシン、と、手の中の打神鞭を一打ち鳴らすと、青年太公望は、あっさり結界の中から出て行った。後には、あんぐりと口を開ける、屁舞留とキョウジが残された。
「………そんな……何か、働きかけろと言われても――――」
ポツリ、と、呟く屁舞留の手から、一輪の花が生まれて来ている。
「吾が出来る事と言えば、この『花を咲かす』ことだけじゃ……。他にどうしろと――――」
「屁舞留………」
そう言ってじっと手を見つめている屁舞留を、キョウジはしばらく見つめていたが、やがてその肩をポン、と、叩いた。
「自分の出来る事を、そんな風に決めつける必要はないんじゃないかな。もしかしたら、私たちにも、もっとできる事があるかもしれないし」
「しかし………!」
何事かを反論しようとする屁舞留に、キョウジはにこりと微笑みかけた。
「忘れたのか? 屁舞留」
「な、何を……?」
「前の戦いの時、私たちは声を届かす事が出来たじゃないか。彼女……甲斐姫に」
「――――!」
「だから、『何も出来ない』とか、『声も届かせられない』なんて、総てをあきらめてしまう事はないと思う。きっと何事も、『やってみなくちゃ分からない』なんだよ」
「キョウジ……」
「それに、私たちが何かをやって、それで状況がどう転がっても、あの人がフォローしてくれるらしいし、だから安心して――――」
「キョウジ……やはり、お主は『強い』な………」
「へっ?」
キョウジの言葉が終わらぬうちに発せられた屁舞留のその言葉に、キョウジは思わずきょとん、としてしまっていた。
「お主は本当に、前向きな発言しかせぬな……。しかし、それで、大分勇気づけられたものだ」
屁舞留の言葉に、キョウジは慌てて、首を横に振った。
「『前向き』とか、そんなんじゃないです。たんに、私があきらめが悪いだけで……」
「そうか? 『あきらめる』方が、随分楽だと思うのだがな」
「そうですか? あきらめない方が、私には容易く感じますが……」
キョウジのその言葉に、屁舞留は思わず彼の顔をまじまじと見つめてしまう。
この青年は、やはりどこか変わっている。
どうして――――そんな風に、強い意志を持ち続けていられるのだろう。
しばらくそう思いながら沈黙していた屁舞留であったが、やがて、何かを思いついたかのように、ポツリと口を開いた。
「……そうじゃ、キョウジ。お主、『呪』を使えるようになってみるか?」
「えっ? 『呪』ですか?」
驚いた様に鸚鵡返しに聞いてくるキョウジに、屁舞留は頷いた。
「そうじゃ。『呪』じゃ。ただし、吾もそんなに高位の呪術を持ち合わせておる訳ではないゆえ、簡単な物しか教えられぬがの……」
そう言いながら屁舞留は、また掌から花を生み出す。それに向かって口の中で誦を詠唱しながら印を結ぶと、ポン、と、小気味いい音を立てて、花の周りを透明な球体が覆った。
「これは、『封』を施す『呪』じゃ。これで、この花に触れる事は出来ぬであろう?」
「本当だ……」
屁舞留から渡された花が入った球体を、キョウジは興味深そうに触りながら見つめている。キョウジがそれをしている間に、屁舞留はもう一度口の中で誦を詠唱しながら、先程とは違う形の印を結んだ。すると、花を覆っていた球体がパチン、と、音を立てて消え――――キョウジの手の中に、花だけがふわりと舞い降りてきた。
「今のが、封印を解除する『呪』じゃ。『開く』『閉じる』この二つが、『呪』の中の基本中の基本となる。……どうじゃ? やってみるか?」
「ええ! ぜひ―――!」
キョウジが嬉しそうに頷いたのを見て、屁舞留の面にも笑みが浮かぶ。
「よし、では詠唱する誦を覚えるところから始めるぞ。その誦を唱えながら『印』を結ぶ。それをする時に、『気』を伝えることが肝要じゃぞ?」
そう言いながら屁舞留は、キョウジに誦を教え、印の結び方を伝授した。
「……よし、ではキョウジ。この花に向かって、先程教えた『封』を施す『呪』をやってみるんじゃ。心を静かに、物を『閉じる』イメージを印に乗せて――――」
キョウジは言われたとおり忠実に、誦を唱えながら印を結んでいく。
心静かに
印に『気』を乗せて
物を 『 閉 じ る 』
「覇ッ!」
キョウジが花に向かって『印』を放つと、花の周りをものすごく大きな角ばった黒い箱の様な物が出て来て、それを覆った。その箱はドスン!! と、大きな音を立てて、地面に落ちてくる。
「あ、あれ……?」
「―――――!?」
顔をひきつらせているキョウジの横で、その一部始終を見ていた屁舞留は、思わず息を飲んでしまっていた。
キョウジは生まれて初めて『呪』を使った筈だ。たいていの場合、それは不発に終わる。形にすらならない筈だ。それなのに。
この青年は、初めて発動させた『呪』で、もう形になっているだと―――!?
何と言う事だろう。
自分は、この『閉じる呪』を習得するまでに、少なくとも10年はかかった物だと言うのに――――
そんな屁舞留に気づかずに、キョウジは1人慌てふためいていた。
「あ、あれ~~~? 難しいな……。何でこんなに大きくなっちゃったんだろう……?」
「キョウジ――――」
「あ、屁舞留……。ご、ごめん、何だか変な具合になっちゃって……!」
「いや………」
屁舞留がキョウジに答えながら、キョウジが出現させた『箱』に触れる。箱はガチッと閉ざされていて――――中の花をしっかりと『封印』していた。
「ちゃんと封印されておる……。キョウジ、お主なかなか筋が良いな……」
「そんな事はないよ。屁舞留の教え方が良かったから――――」
「そうか? 吾はこの『呪』をここまでの形にするには、少なくとも10年はかかったがな……」
「あ………!」
屁舞留のその言葉を聞いて、自分がまた『やらかして』しまった事にキョウジは気付く。
キョウジ・カッシュと言う人間は、およそ『天才』と呼ばれるにふさわしい、類い稀なる才能の持ち主であった。彼の鋭い観察眼は、あっという間に物の本質を見抜き、彼の優れた身体能力は、その奥義をイメージ通りに再現する事を可能にする。
それが為に彼は、人が10年かけて会得する技術を、あっという間に我が物にしてしまえた。その高い資質は、彼が精神を『シュバルツ』に移植した時に、元のシュバルツが持っていたゲルマン忍法を、『我が物』として飲みこんでしまう事を可能にする程だった。
まさに『天才』
まさに『鬼子』――――
だが、そのような突出した能力は、時に、呪いでしか無くなる事がある。
あっという間に高みへと飛んで行ってしまうキョウジは、必ずと言っていいほど妬まれ、時に疎外された。理不尽な暴力を受けた事もあった。
この能力が余計なトラブルを巻き起こしている、と、気づいてからは、キョウジもできるだけ気をつけて、特に親しい人の前以外では、極力その能力を出さないようにしていたのだが。
今――――屁舞留の前で、うっかりその能力を出してしまった事になるのだ。キョウジの背中から、嫌な汗が流れ落ちて来ていた。
(やっちゃった……! 絶対に、屁舞留に嫌な思いをさせてしまっただろうな……)
このせいで、疎まれるのは仕方が無い。
だけど、ここまで仲良くしていた屁舞留に、嫌われてしまうのは淋しいと思った。
「キョウジ―――――」
「…………!」
屁舞留に呼びかけられて、キョウジの身体がビクッと、跳ねる。
ごめん、屁舞留。
キョウジが屁舞留にそう謝るよりも先に、屁舞留がキョウジの手を取った。
「何をそんなに怯えたような眼をしておる? 『呪』がうまくいったのだ! もっと、誇らしそうな顔をして良い所じゃぞ!?」
「え………っ?」
瞬間屁舞留に何を言われたのかが分からず、きょとん、としているキョウジに、屁舞留は更に微笑みかけて来た。
「もっと『気』の込め方に工夫を凝らせば、結界の大きさも強度も思いのままになるぞ? いやあ、キョウジは優秀じゃな! 教えがいがあると言う物じゃ!」
「い、いや……でも……!」
キョウジはかなり戸惑ってしまう。屁舞留が10年の年月をかけて、苦労して体得した物を、自分があっさりとやり遂げてしまったのだ。これはかなり、屁舞留に失礼な事をしてしまったのではないかと思う。
「何を言っておるのじゃ? キョウジ。人には皆、得意不得意、向き不向きがある。物事を体得する速さも、その容量の大きさも――――人によってまちまちじゃ。吾は別に、キョウジが吾よりも高位の術者になろうとも、それはそれで良いと思っておるぞ?」
「屁舞留………」
「ただ残念なのは……お主の能力に見合った『呪』を、吾が持ち合わせていない事だな……。それを学びたければ――――吾よりももっと高位の神気を持つ者を『師』とせねばならぬが……」
そう言ってう~ん、と、考え込む屁舞留に、しかしキョウジは首を振った。
「ううん……充分だ……。屁舞留……ありがとう………!」
それだけを言うと、キョウジは思わず屁舞留の身体を抱きしめていた。
嬉しかった。
自分のこの変な『能力』を、こんな風に笑って受け止めてくれた人は、両親以外では初めてかもしれなかった。
(キョウジ……)
キョウジに抱きしめられながら、屁舞留は思った。
この青年は、一体何者なのだろう、と。
元は、人の子だと言っていた。
しかし、死後霊体になってからも、こんなに明確に『人間』の形を保っている事など稀な例だ。しかも、キョウジは当たり前のように、神仙の類である筈の自分の身体に触れる事が出来ている。よくよく考えれば、普通の人間の魂を持つ者が、自分の身体に触れる事はおろか、結界をすり抜けてくる事など、出来る筈もないと言うのに。
本当に――――考えれば考える程、不思議な存在であった。
(だからと言って……『お主は何者だ?』と、キョウジに聞いた所で、『人間です』と言う答えしか返っては来ぬだろうな……。当たり前な話だろうが……)
本人さえ分からないその魂の正体。今は突き詰めても仕方が無い。
それをするのは、自分よりももっと上位の神気を持つ者の仕事だろう、と、屁舞留は思った。
それよりも、今は自分達が出来る事をするべきだ。
「さあ、キョウジ! あの太公望とやらの策に、吾らも乗る事にしようぞ! 吾らも出来る事をしよう! キョウジは『呪』の練習じゃな。もっと磨けば、必ず何かの役に立つじゃろう」
「屁舞留……」
そう言って明るく顔を上げる屁舞留を、キョウジはじっと見つめていたが、やがてその面に笑みを浮かべた。
「うん……そうだね。ありがとう……」
「さあ! 村の見回りに行くぞ! ぐずぐずするな!」
屁舞留は元気良く歩きだした。キョウジは苦笑しながら、その後をついて行った。
太公望の歴史への介入のおかげで、村の上空に鎮座していた『死の闇』が、どんどん小さくなっていく。だが――――それに比例するかのように、村を取り巻く状況は、どんどん悪化の一途を辿っていた。妖魔と村人たちの交流は、周りの理解を一向に得られず、他部族の妖魔たちからの嫌がらせは、日毎に増える一方だ。
それでもシュバルツは、この妖魔たちと村人たちを何とかして守ろうと、独り、走りまわっていた。農作業の手伝い、子供たちのケア、襲撃される妖魔の村への手助け、戦い慣れていない妖魔たちへの戦い方の指導、そして、連日行われている長達の話し合いへの参加等、本当に、腰を落ち着けて休む暇もない程になっていた。
「……………」
夜が深く更けても、シュバルツは1人、夜風に当たることが増えて来た。
おそらく村を取り巻く状況が厳しすぎて、眠ることもできなくなってしまっているのだろう。
(シュバルツ……)
キョウジはシュバルツの傍に行き、その姿を見守ることにした。
暫く夜空を見上げていたシュバルツは、やがて、一つ大きなため息を吐いた。
――――今日の話し合いも、結局何の進展も得られなかったな……。他部族の妖魔たちの主張は、『人間と狎れ合うなどもってのほか』の一点張りだし……。
「…………!」
黙っているはずのシュバルツから、声が聞こえてくる。それは、シュバルツの心の中で吐き出されている『声』なのだと、キョウジは悟った。
――――どんな事があっても村に留まりたい、と、願う皆の気持ちも分かる……。この土地も桃の木たちも、村人たちにとっては何物にも代えがたい物だ。一朝一夕で手に入る物ではないんだ……。
でも、万が一この村が襲撃された場合、迎え撃てる場所も、皆の安全を確保できる場所もない。ここから逃げろと、心を鬼にしてでも言わなければならないと、分かっている。
しかし――――
自分の願いとは裏腹に、周囲の状況は悪くなっていく一方だ。
やはり、私には大それたことだったのだろうか。
妖魔と人間――――この、異種間の交流を支える、と言う事は……。
もう少し、私に力があれば………!
(シュバルツ………!)
ひたすら己を責めているシュバルツの声に、キョウジは胸が締め付けられる。
こうして傍に居るのに、結局彼の何の役にも立てない自分が、キョウジは苦しかった。
ふと見ると、シュバルツの手の中で、何かが光を放っている。
(…………?)
キョウジが近づいて行ってみると、それは、キョウジの壊れた腕時計であった。
――――キョウジ……。
シュバルツがその腕時計を見つめながら、シュバルツの心の声は続いていた。
――――キョウジ……。ハヤブサ……。
こんな時、彼らが居てくれたら………!
(……………!)
シュバルツ、私はここに居る! ここに居るのに――――!
キョウジは懸命にシュバルツに向かって叫ぶが、当然その声は、シュバルツに届く筈もなく。
「………………」
暫く無言で腕時計を眺めていたシュバルツの面に、フッと、自嘲的な笑みが浮かんだ。
「馬鹿だな……。いくら求めても、この二人に会える筈はないのに……」
そう言って振り返ったシュバルツと、キョウジはばったりと視線が合った。
「シュバルツ……!」
思わずキョウジは、シュバルツに呼びかける。
「……………」
暫くこちらをじっと見つめていたシュバルツであったが、やがてその面に、優しい笑みが浮かんだ。
「シュバルツ!」
自分の姿が見えたのだろうかとキョウジは嬉しくなって、シュバルツに駆け寄ろうとする。だがシュバルツは、キョウジの身体をすり抜けて、後ろから歩いてきた村人に声をかけていた。
「何だ、まだ、起きていたのか」
「…………!」
「シュバルツさんこそ……寝なくて大丈夫なんですか?」
その村人は、今日1日シュバルツの傍に『神の付き人』として付いていた村人であった。
「私は大丈夫だ。それよりも、貴方こそ早く寝た方がいい。明日も忙しいだろうから」
「わしは大丈夫です。明日の朝で『お役目』は終わりですから」
「そうか」
その村人とシュバルツの談笑は、しばらく続きそうだった。キョウジはそっと、その場から離れた。
「キョウジ……。大丈夫か?」
その一部始終を見ていたらしい屁舞留から、そう声をかけられる。キョウジは多少苦笑気味になりながらも「大丈夫だよ」と、返事を返した。
「それにしてもお主の影……何か、不可思議な感じがするのう」
「不可思議って……何が?」
屁舞留の言葉に、キョウジは少し小首をかしげる。
「あ奴は、あれだけお主に向かって呼びかけていると言うのに、お主に対して肝心な所で心を閉ざしているように見える……」
「…………!」
「あれでは、お主がいくら呼びかけた所で、万に一つも気づく可能性など無いであろうな。いったいどうして――――」
「………仕方が無いよ」
屁舞留の言葉に対して、キョウジがポツリと答えた。
「きっと、辛すぎるんだ……。いろいろと……」
自分が死んだ時に、シュバルツは自傷行為に走ってしまう程、自分を責めていた。深く傷ついていた。
ハヤブサの支えもあって、今は普通どおり立ち直っているように見えるシュバルツ。
だけど、心の奥底ではそうではないと言う事を、キョウジは知っていた。
きっと、立ち直っている、と言うよりは、哀しむ心を無理やり『封じ込めている』と、言った方が正しい。そうしなければ前に進めない――――彼はそう思ったのだろう。
自分の『死』を、そんな風にいつまでも引きずって欲しくはない、と、キョウジは願っている。だけど、この喪失感ばかりは、本当にどうしようもないから厄介だ。やはり、『時間』に頼るしかないのだろうか。
「そうか………」
キョウジの話を聞いていた屁舞留が、一言、落とすように返した。
沢山の『死』を見て来た屁舞留には、キョウジの気持ちもシュバルツの哀しみも『理解』出来た。確かに、どうしようもない。どうしようもないものだが――――
それでも、願わずにはいられない。
「何時か……『影』の中の哀しみも溶けて、お主の呼び掛けに気づく事が出来るようになると、良いな……」
屁舞留の言葉に、キョウジは微笑みながら頷いた。
太公望の歴史への介入は続く。
日が経つにつれて、屁舞留の表情は明るくなっていった。何故なら、村の上空を覆っていた『死の闇』が、ほとんど見えなくなっていたからだ。ただ1つ――――シュバルツの背に張り付いている物を除けば。
「済まぬキョウジ……。何故なのじゃろうな……。お主の『影』にだけ……」
この話をする時、屁舞留は本当に、申し訳なさそうな顔をする。それに対してキョウジは、苦笑しながら首を振った。
「大丈夫だよ、屁舞留。そんなに気にしないで―――」
「しかし……!」
「いいから」
キョウジは優しく笑って、それから話題を変えた。
「それよりも見てくれ、屁舞留。私も大分、『呪』がうまくなったと思わないか?」
そう言いながらキョウジは、屁舞留の咲かせた花に向かって『呪』を放つ。その結界は、花の周りだけを小さく丸く、綺麗に覆っていた。
「確かに……。キョウジ、お主もうその『呪』は完璧じゃな!」
「ありがとう」
キョウジが指をパチン、と鳴らすと、花の周りを覆っていた結界は消え、花はふわりと地面に落ちた。
「それにしても屁舞留……。どうして、こんなに花を大量に咲かせて置いてあるんだ? 今は花を咲かせる時期でもないだろう?」
キョウジのその質問に、屁舞留はえへへ、と笑顔を見せた。
「ちょっと………内緒じゃ」
「え~~~~? 気になるなぁ。いい加減教えてくれても……」
「ど、どうでもいいじゃろう!? それよりもほら、今から昼の見回りに――――!」
キョウジと屁舞留がそうやってじゃれ合っている時に、村の中央にハヤブサたちの姿が唐突に現れた。
「あ…………!」
その姿を見た屁舞留の表情が、少し硬いものになる。
「そう言えば、明日が『感謝の祭りの日』だから……ハヤブサたちが来るのは、やはり、このタイミングになるんだね。と、言う事は、襲撃されるのも、『今夜』と言う事になるのかな?」
「分からん……」
キョウジの問いかけに、屁舞留は表情を硬くしたまま答えた。
キョウジ達の目の前では、ハヤブサたちが懸命に、村人たちに避難を呼び掛けてくれとシュバルツを説得している。だが屁舞留は、それを見届ける事はせず、踵を返して社の方に歩き出していた。
(屁舞留?)
屁舞留のそんな様子が気になって、キョウジはその後を追った。
「…………」
社の結界の中に入り込んだ屁舞留は、自分がたくさん咲かせてきた花たちの前に、無言で座り込んでいた。
「どうした? 屁舞留」
キョウジが呼びかけると、屁舞留はゆっくりと振り向いた。
「おう、キョウジか……」
顔に笑みは浮かんでいるが、その表情が何処となく淋しげな屁舞留。キョウジは少し気になったから、更に問いかける事にした。
「どうしたんだ? 屁舞留。さっきまであんなに楽しそうに話していたのに―――」
キョウジの問いかけに、屁舞留は苦笑する。
「いや、別に大した事ではない。ただ………」
「ただ?」
屁舞留は少し黙って、ポリポリ、と、頭をかいてから、また話し始めた。
「ただ……もしも今年『感謝の祭り』があるのなら――――この花を、村の皆にプレゼントしようかと思っていたのだが……」
「…………!」
「……無理みたいだな……。『感謝の祭り』など、開いている余地もない。襲撃されるのであるならば、あの龍の忍者が呼びかけた時点で、皆はこの村を放棄して、逃げねばならぬ」
「屁舞留……!」
何とも言えない表情を浮かべて、屁舞留を見つめるキョウジ。そんな彼に、屁舞留はフッと優しい笑みを向けた。
「そんな心配そうな表情をするでない! キョウジ……。吾はな、これでも嬉しかったのだぞ?」
「嬉しい?」
きょとん、とするキョウジに、屁舞留は微笑みながら頷く。
「考えてもみよ! 最初にお主と会った時に吾が咲かせていた花は、『供養』のための花であった。だがこの花たちは違う! 皆を『祝福』する事を考えて、咲かす事が出来たのじゃぞ?」
「あ………!」
「一人結界の中で石を積んでいた時とは、本当に、まるで状況が違う! 吾は、それが嬉しいのだ!」
だからこの花の事はいいのだ、気にするな。そう言って、屁舞留は笑う。
だけど、キョウジは複雑な気持ちになった。
本当に――――それで、良いのだろうかと。
「少し、シュバルツの様子を見てくるよ」
キョウジはそう言い置くと、屁舞留の社から出て行った。
以前の時間軸とは違い、村人たちはシュバルツの呼び掛けに素早く応じて、すぐに集会所に集まって来ていた。共に農作業をしていた妖魔たちもだ。皆表情は硬い。今日寝て、明日目が覚めても、今日と同じ1日が保証されている訳ではない、と言う事を、誰もが悟っているふうであった。
とても危機意識が高い村人たち。そんな村人たちに向かって、シュバルツが、ハヤブサが、そして甲斐姫たちが――――それぞれに避難を呼びかける。そしてついに、村人たちは村を離れ、避難する決心を固めてくれた。
(良かった……。このタイミングで避難してくれたら……)
それを見て、キョウジはホッと胸を撫で下ろす。
避難の準備をするために、村人たちも妖魔たちも、皆集会所から出て行った。後にはハヤブサとシュバルツ、二人だけが残された。
「シュバルツ」
「ハヤブサ……」
「大丈夫か?」
「――――!」
ハヤブサの言葉に、一瞬はっと、息を飲むシュバルツ。
「ああ。大丈――――」
その言葉と共に、シュバルツはその面に笑みを浮かべようとして、失敗していた。それどころか、彼の瞳からは堪え切れぬように涙まで零れ始めていた。
それまで、たった独りで、この日増しに厳しくなってくる周りの情勢から、村人たちを守っていたシュバルツ。いろいろと堪えていた物が、溢れて来てしまったのだろう。
「…………」
ハヤブサはそっとシュバルツの頬に手を伸ばす。
「ハヤブサ……ッ!」
ハヤブサの手が触れると同時に、シュバルツが彼の胸に飛び込んでいった。
何故、何故、と、シュバルツはハヤブサの腕の中で泣き続ける。
妖魔たちも人間たちも、ただお互いに、穏やかに交流をしていただけだ。
ただ、周りにはそれがまるで『理解』されなかった。
自分達に向けられるのは、曲解と誤解、偏見、差別――――
彼らの声は罵声にかき消されたまま、結局、村を捨てざるを得ない事態にまで至ってしまった。
何がいけなかったのか。
何を間違えてしまったのか。
自分が、非力すぎたのだろうか――――
次から次へと、シュバルツは抱え込んでいた心を、ハヤブサに落として行く。
ハヤブサは、そんなシュバルツを「大丈夫だ。大丈夫――――」そう言いながら、優しく抱きしめていた。その表情が、本当に、酷く幸せそうだったから、キョウジは少し驚いてしまう。
(ハヤブサは、本当にシュバルツの事が好きなんだな……)
腕の中で泣いてくれているのが嬉しい。
心を落としてくれているのが嬉しい――――
本気で、そう思ってくれているのだろう。
きっと、シュバルツは大丈夫だ。
ハヤブサが側に居てくれる限り、彼は決して孤独ではない。
どんな苦しみも悲しみも――――癒して行く事が出来るだろう。
そう感じられた事が、キョウジには嬉しかった。
だが、そうのんきに構えてばかりもいられない。
「シュバルツさんは居るだが?」
暫くすると、村人の1人がシュバルツの姿を求めて集会所に戻ってくる。
「ちょ、ちょっと待って! 居るには居るんだけど……その……!」
キョウジと同じように二人の様子を集会所の外から眺めていた女性二人が、慌てふためいた。
「立て込んでいると言うか……出なおした方が良い様な気が――――」
もう少しゆっくり泣かせてあげたい、と、思ってくれているのだろう。甲斐姫と孫尚香は、二人の姿を村人から必死に隠そうとしてくれている。だが、とても隠しきれるものでもなく。
結局村人は、ハヤブサに凭れかかって泣きじゃくるシュバルツの姿を見てしまう。
「……………!」
村人はしばし息を飲んでそのまま固まってしまう。
「あ、あの~……大丈……夫、ですか?」
「こ、これは、その……つまり………」
孫尚香と甲斐姫は、固まった村人の様子に心配して声をかけた。だが村人はそれには答えず、茫然と踵を返した。
「シュバルツさん……!」
そう言いながらとぼとぼと歩いて行く足取りが、とても重く、暗い。まるで今から、通夜か葬式にでも行くような雰囲気だ。それを見送った女性二人は、おろおろするより道が無く。
「尚香……どうしよう……!」
「ど、どうしようと、言われても――――!」
そうやってうろたえている所に、また別の村人がやってくる。
「あの……シュバルツさんは……」
「あ……! ちょっと待って……!」
「今は……その……!」
女性陣二人は必死に中の忍者二人を村人から隠そうとするのだが、やはりその努力は徒労に終わり、中の様子を見た村人が衝撃を受けて、やはり足取り重くそこから立ち去って行く。そう言う事が、何回か繰り返された。孫尚香も甲斐姫も、最初は必死に村人たちに対処しようとしていたが、しまいの方は二人の間にもあきらめムードすら漂っていた。村人たちは皆一様に――――とぼとぼと足取り重く、そこから去っていく。
「尚香……ど、どうすればいいのかな……」
「さ、さあ……も、もう、なるようにしか……ナラナインジャナイカナ……」
そう言って顔をひきつらせる女性たちに、キョウジも同意するしかなかった。
(仕方が無いな……。シュバルツはやっと心を吐き出す事が出来たんだ……)
だから、もう少しゆっくり泣かせてやりたい、と、キョウジも思う。この姿を見られたからと言って、シュバルツはともかく、ハヤブサは動じることもないだろう。この後どう状況が転がろうとも、ハヤブサならば切り抜けてしまえそうな気がする。
(それにしても、村の人たちは、どうするつもりなんだろう……)
泣いた姿を見せたからと言って、シュバルツと村人たちの間に築き上げられてきた信頼関係が、急にどうこうなる、と言う事はない、と、キョウジは分かっているから、特段心配している訳でもない。ただ、まるで葬式にでも行くような足取りで、皆落ち込んだように去って行ったのが少し気がかりだった。
(このまま家に引きこもってシュバルツと同じように泣きだしてしまって――――避難するのが遅れてしまったら厄介だな……。そんな事にならなければいいが……)
そんな事を思いながらキョウジが広場に佇んでいると、やがて、村人たちがポツリポツリと広場に戻って来だした。戻ってきた皆が皆――――手に各々『ある物』を持って来ている。
「……………」
キョウジはしばらく、それらを黙って眺めていたが、やがて目の前で起こっている事に居ても立ってもいられなくなって、あわてて屁舞留が居る社まで走って行った。
「――――屁舞留!!」
「わっ! キョウジか!? どうした!? そんな大声を出して――――!」
びっくりして振り向いた屁舞留の手を、キョウジは半ば強引に取る。
「屁舞留! 来てくれ! 見せたい物があるんだ!!」
「み、見せたい物!? な、何じゃ!?」
いつもよりもかなり強引なキョウジの姿に屁舞留は戸惑うが、キョウジはそれには構わず、屁舞留の手をぐいぐいと引っ張った。
「いいから早く!! とにかく見てくれ!!」
キョウジが屁舞留を広場まで連れてきた時には、『それ』はもうかなりちゃんとした形を為していた。
「こ、これは……!」
目の前に綺麗に設えられた祭壇。そこに並ぶ野菜や果物。川の物、山の物。綺麗に飾られた花々――――
それはまさしく、村人たちが土地神のために、毎年催してくれていた『感謝の祭り』その物の飾り付けであったから、屁舞留は目を丸くしてしまっていた。
「な……何が起こった……? 何がどうしてこのような物が――――」
茫然と言葉を紡ぐ屁舞留の横で、同じように集会所から出て来て茫然としているシュバルツに、甲斐姫たちが説明を始めていた。
「シュバルツさん……。えと……つまり、この人たちは………」
「泣いている、貴方の姿を見て………」
「―――――!」
女性たち二人のその言葉に、一瞬固まるシュバルツ。甲斐姫たちは更に説明を続けた。
「どうも……ここの『土地神様が泣いている』と、感じちゃったみたいで………」
「えっ?」
思わず変な表情を浮かべて聞き返すシュバルツに甲斐姫は頷くと、更に説明を続けた。つまり、泣いているシュバルツの姿を見た村人たちが、とぼとぼと集会所を後にしたかと思うと、同じように泣きながら、誰からともなく祭壇の準備を始めたのだと。そして見るみるうちに祭壇の上は、お供え物であふれかえっていったのだと。
「ここの村人たちは、本当に……ここの土地神様が、大好きなんですね………」
そう言う甲斐姫の瞳も、涙ぐんでいる。唖然としているシュバルツと共に、屁舞留もまた、言葉を失う以外になかった。そんな屁舞留の肩に、キョウジの手がそっと添えられる。
「良かったな、屁舞留。貴方はこれ以上ない、と言うぐらい、ここの人たちに慕われているんだ」
キョウジのその言葉に、屁舞留ははっと我に帰った。
「ち、違う……! 慕われているのは吾ではない! お主の『影』が、この村のために頑張って走り回ってくれたから――――!」
「それだって、貴方が毎日コツコツと、『土地神』としての仕事を積み上げていたからこそだ」
慌てて否定しようとした屁舞留の言葉を、キョウジは笑顔で切りかえす。
「ここの村人たちがどんな時でも、ちゃんと農作物の世話をしていたことも勿論大きいけれど、貴方だってどんな時でも、きちんと一つ一つの植物たちに声をかけ、『気』を送っていたじゃないか。それが、実を結んだんだよ」
「そ、そんな……! わ、吾は、吾が出来る事をただしていただけだ! ここの村人たちが居るのかいないのかも分からない吾の事を、熱心に祀ってくれていたから――――!」
それに応える術が、それしか無かったのだ、と、答える屁舞留は、かなり動揺しまくっていた。そんな屁舞留を不謹慎だが『可愛らしい』と感じてしまって、キョウジはちょっと苦笑する。
「貴方が『居る』――――と、思ったからこそ、皆はこうしていろんな儀式を行ったり、『名代』を立てたりしたんだろう?」
「―――――!」
「屁舞留……やはり貴方は、皆に愛されている、立派な『土地神』なんだよ」
「ち、違う……! 慕われているのは、そなたの『影』で――――!」
「そんなことないよ。その証拠に、ほら………」
キョウジが指し示す先で、村の者たちがいつの間には広場から祠の前に移動して、儀式に則って社から自分の『本体』である石を取り出していた。
「あ………!」
小さく声を上げる屁舞留の目の前で、長老がシュバルツに対してこの石の由来を説明していた。この石こそが、ここの土地神の『御神体』であるのだと。
「シュバルツは、あくまで貴方の『代理』――――『土地神』とは屁舞留、貴方の事なんだよ」
「…………!」
キョウジにそう言われて、屁舞留はぐっと言葉に詰まる。その目の前で、長老とシュバルツの会話はまだ続いていた。
「シュバルツ殿……。わしは、この『本体』を、わしらと共に連れて行こうと思っておるのじゃが……どうだろうか?」
「―――――!」
「『土地神様』は、わしらにとってはもう村の守り神も同然じゃ。とても離れがたく感じておる。新しい土地でも『村の守り神』として、御祀りしたいのだが……」
「あ…………!」
長老の底言葉に、屁舞留は本当に茫然としてしまう。
本当に――――?
本当に、皆はそこまで、吾の事を――――?
何故――――?
何故だ………?
吾は、本当に、神仙としても半人前で、出来ることも少ない、非力な身の上であると言うのに――――
「良かったな! 屁舞留!」
キョウジは本当に嬉しそうに、屁舞留に声をかけて来た。
「貴方はちゃんと、必要とされている――――! 貴方の心を、皆はきちんと受け取ってくれていたんだよ!」
「……………!」
「長老様のお心のままに……。共に行かれるのであれば、そうした方がいいと私も思います。その方が、『神様』も喜ばれるでしょう」
長老の問いに対して、シュバルツはそう答えた。否、それ以外の答えを、彼が持ち合わせているはずもなかった。
「………信じられぬ……」
目の前で起きている出来事を眺めながら、ポツリと呟く屁舞留。そんな屁舞留を、キョウジがツンツン、と突いて来た。
「花は? 屁舞留」
「えっ?」
何を言われているのかが一瞬分からなくて、きょとん、とする屁舞留に、キョウジは更に言葉を紡いでくる。
「屁舞留がせっかく用意していた花――――皆に、渡さなくていいのか?」
「えっ?」
「これってつまり――――『感謝の祭り』に相当するものだろう?」
「――――!!」
キョウジに言われて、屁舞留もようやく合点が行って、はっと息を飲む。
確かにそうだ。
設えられた祭壇。数々の供え物。
そして、村人たちから送られてくる、土地に対しての感謝の想い。
これを――――『感謝の祭り』と言わずして、何と言えばいいと言うのだろう。
今だ。
あの花々を渡すなら、今しかない。
でも―――――
屁舞留は躊躇ってしまっていた。
今まで、自分の存在を主張するような真似は、村人たちに対して屁舞留は決してして来なかった。
それをいきなり『神』の存在を匂わす様な事をしてしまっては、村人たちに気味悪がられたりはしないだろうか?
「何を言っているんだ? 屁舞留! そんな事ある訳無いだろう!?」
半ばあきれるようにキョウジは言うが、屁舞留は尚も戸惑っている。
「い、いや………しかし………」
そう言って、すっかり尻ごんでしまっている屁舞留。
「ああもう――――!」
そんな屁舞留を見て、キョウジはじれったくなってしまった。
屁舞留と、屁舞留の愛したこの土地から、とても離れがたく思っている村人たち。
そんな人たちの前で、『奇跡』と呼ばれるような現象を見せた所で、村人たちがそれを気味悪がるなんて、ある筈ないのに。
(お前たちが何かをやって、それが悪い方に転がりそうになっても――――私がそれを修正してやる。全知全能たる、この私がな)
あの傲岸な青年太公望のこの言葉も、キョウジの背中の後押しをした。
何事も、やってみればいいのだ。
もしそれが駄目な事であったとしても、修正してくれると言っているし、屁舞留の『存在』を匂わせる事が、そんなに悪い事であるとは、キョウジにはどうしても思えない。
「いろいろごちゃごちゃ考えるより――――とにかく、やってみれば良いんだよ。ほら――――」
キョウジは『呪』を発動して、屁舞留の社の中から花を取り出してくる。
「キ、キョウジ!? 待――――!!」
屁舞留が止める間もあればこそ、キョウジは取り出してきた花々を村の上空まで運んで行くと、そこで結界を解いて、花々を村人たちの上に降り注がせ始める。
「こ、これは一体……?」
「どう言うことだべか……」
突如として現れた桃の花の舞に、村人たちはただ茫然とするしかない。「うわ~! すご~い!」と、子供たちは無邪気に喜び、女衆たちの中には「綺麗……」と、見とれる者もいた。
「キ、キョウジ……!」
「屁舞留。見てごらん? 誰かこの花々を、気味悪がっているか?」
「―――――!」
キョウジに言われて、屁舞留は村人たちの方に振り返る。
すると、村人たちは皆あんぐりと口を開けて、舞い落ちる花の乱舞を見ているが、誰もその花を『不吉な物』として捉えてはいないようだ。あの龍の忍者――――ハヤブサでさえ、そうであった。手の中に一輪の花をふわりと捉え、それをじっと眺めている。警戒している――――と言うよりは、この花をどう判断していいのかが分からず、『戸惑っている』と、表現した方が正しい様な感じであった。
「この花々が舞う空に、『死の闇』は広がっているか?」
キョウジのこの問いかけに、屁舞留は黙って首を振る。
空は何処までも青く澄み渡り――――穏やかな光を湛えていた。
「なら、もう迷う事はないじゃないか。屁舞留も手伝ってくれ。残りの花々も、皆に届けてしまおう」
そう言いながらキョウジは、もう次の花々を上空まで運んで行っている。屁舞留も慌てて、その後に続いた。
「それにしてもキョウジ……。何時の間に『物を運ぶ呪』を会得したのじゃ? 吾はまだそこまで教えておらぬと言うのに―――」
「ああ、これは『開く呪』と『閉じる呪』を、応用したものなんだよ」
屁舞留の問いかけに、キョウジは事もなげに答える。
「まず、あの社の中の花のある空間の一角を『閉じて』――――」
そう言いながらキョウジの放った『呪』が、いくばくかの花々を、その球体の中に閉じ込めた。
「それから、社の中から上空へと通じる道を『開いて』――――」
開かれた『道』にしたがって、花々を乗せた球体は、上空へと舞い上がって行く。
「適度な高さまで持って行った所で、花を閉じ込めていた結界を『開く』」
パチン、と、キョウジの指が鳴ると同時に、結界から零れ落ちた花々は、人々の村に降り注いで行った。
「こうすれば、二つの『呪』しか知らない私でも、物を運べるんじゃないかと思って……。試してみたら、うまくいって良かった」
「……………!」
(見事――――!)
キョウジの、『呪』の本質を見抜く目の鋭さに、屁舞留はただただ驚嘆するしかない。
確かにそうだ。
この『開く呪』と『閉じる呪』と言うのは、『呪』の中でも基本中の基本。後の『呪』は、これをすべて応用しただけの物と言っていい。
それを、『呪』を習いたてのこの青年が、あっという間に看破してしまうとは――――!
キョウジならば、わざわざ高位の術師に師事せずとも、数年のうちに下手をしたら独学で、『呪』を極めつくしてしまうかもしれない。そう感じると、屁舞留は空恐ろしくさえあった。
この青年は本当に、一体『何者』だと言うのだろう。
何処まで上りつくして行ってしまうのか――――
そう感じている屁舞留に気づいているのかいないのか――――キョウジは花を降らせながら、しきりに村人たちに向かって「大丈夫だよ~!」と、叫んでいた。
「な、何故そんな風に叫んでおるのじゃ? キョウジ……」
少し戸惑いながらキョウジに問いかける屁舞留に、彼はにこりと微笑みかけた。
「だって……教えてあげたいじゃないか。この道行きは、『大丈夫』なのだと」
「――――!」
キョウジの言葉に屁舞留は一瞬目を見張るが、やがて小さなため息をついた。
「それはそうかもしれぬが……無駄じゃ。吾らの声など、皆に聞こえる筈が――――」
「ううん……多分、今なら聞こえるよ。私たちの声が――――」
「えっ?」
頭をふってそう答えるキョウジに、屁舞留はきょとん、としてしまう。それに対して、キョウジは苦笑した。
「屁舞留が教えてくれたんだよ? 『声』を届かすには、向こうの『心』を『開く』必要があると――――」
「えっ?」
「屁舞留が『シュバルツが私に対して心を閉ざしているから、私の声が聞こえない』って、教えてくれたから………思ったんだ。私たちが相手に声を届かせようと思うのなら、その心を開かせる『媒介』みたいな物があればいいんじゃないかって…………」
「あ…………!」
その言葉に、思わず息を飲む屁舞留。キョウジはにっこりとほほ笑んだ。
「今なら屁舞留の咲かせた花たちが、村人たちの心を開く『媒介』になっている。貴方に皆の意識が向いているから――――こちらの声も、届かすことができるんじゃないかって、思うんだ」
(キョウジ………!)
ただもうひたすら茫然とするしかない屁舞留に、キョウジは再び声をかけて来た。
「ほら、屁舞留も一緒に叫ぼう。花に『想い』を込めて――――」
「そ、そうじゃな」
キョウジの呼び掛けに、屁舞留もはっと我に返る。ここは素直に、それに応じる事にした。
優しい風に乗った花々の乱舞に、二人は想いを込めて叫ぶ。
大丈夫だよ
大丈夫――――
「……………!」
花をじっと見つめていたハヤブサが、はっと顔を上げた。
「シュバルツ。お前、何か言ったか?」
シュバルツにそう問いかけている。
(あ、聞こえたんだ)
キョウジはそう感じた。しかしハヤブサはシュバルツの方に振り向いた。どうやら今の声が、ハヤブサには『シュバルツの物』として感じられたらしい。
(まあ……『似た様な声』って言われるからなぁ。元が同じだから、無理はないけど……)
そう思って苦笑するキョウジの目の前でシュバルツが、「いや、私は何も……」と、頭を振っている。
「じゃあ、今の声を、お前は聞いたか?」
「声? 何か声がしたのか?」
「!?」
怪訝な顔をしながらハヤブサを見つめるシュバルツ。どうやら彼は、今の声を聞いてはいないようだ。
その周りでも、村人たちの間からざわめきが上がっている。
「今、誰かが何か言ったべ?」
「いや、俺は何も聞いてねぇ」
「私も何も――――」
「おらには聞こえた。何か言っていたな」
「えっ? そんな声しただか?」
どうやら村人たちの間でも、聞こえている者と聞こえなかった者が居るようだ。
だが、一番如実にその声を捉えていたのは、どうやら子供たちの様だった。
「声が聞こえたよね!」
「うん! 聞こえた!」
「とっても優しい声だったよ!」
「僕にも聞こえた!」
「その声は、何て言っていたの?」
騒いでいる子供たちの近くに居た甲斐姫が問いかけると、子供たちは嬉しそうな笑顔を見せて答えた。
「『大丈夫だよ』って、言ってた!」
「――――!」
その言葉に、周りに居た大人たちは皆、一様にはっと息を飲む。
「うん! 言ってたね! 『大丈夫だよ』って!」
「うん! そう聞こえた!」
「『大丈夫』なんだって!」
「『大丈夫だ』って!」
「こ、これは……! 長老様……!」
子供たちの声を受けて長老に問いかける村長に、長老も頷き返した。
「うむ……。間違いない。これこそ、『土地神様』のお声なのじゃろう……。信じられぬ事じゃが――――」
そう言いながら長老は、茫然と桃の花が舞う空を見上げる。いろいろと説明が出来ない事象。この小さな村には今――――確かに『奇跡』が舞い降りていた。
(そうか、こうすれば良かったのか)
『声が聞こえた』と、嬉しそうにはしゃぐ子供たちを見つめながら、屁舞留は何とも言えな気持ちになっていた。
そうか。
こうやって呼びかけてあげれば――――
村人たちに自分の声を、届かせる事が出来たのか。
どうして
「どうせ届かないから」と、早々にあきらめてしまったのだろう。
どうして自分は『呪』を使っていながら、この方法に気づかなかったのだろう。
もっといろいろ試してみれば良かった。
あきらめてしまわなければ良かった。
そうすれば――――
自分に毎日語りかけ続けてくれていた村人たちに、
もっとちゃんと、
何かを返す事が出来ただろうに。
自分の気持ちを伝える事が出来ただろうに―――――
過ぎ去った日々が、
今となってはただ、悔やまれた。
「屁舞留? どうした?」
自分を覗き込んでくるキョウジの顔が見えて、屁舞留ははっと、我に帰った。
「いや、すまぬ……。少し、考え事をしておった」
「考え事?」
小首を傾げるキョウジに、屁舞留は苦笑する。
「ただ少し……自分の不明を悔いておったのよ」
「屁舞留………」
そう言って柔らかく笑う屁舞留に、しかしキョウジの瞳は曇った。
キョウジは屁舞留の正面に座って、屁舞留と同じ高さの目線になると、その手を取って語りかけた。
「屁舞留……。もしも、私に対して何か言いたい事、吐き出したい事があるのなら………溜め込まずに、ちゃんと私にぶつけてくれ」
「キョウジ?」
「それをされたからと言って……私が貴方を恨んだり、嫌いになったりする事はない。黙って耐えられる方が、私には辛い」
自分の、この呪われたような変な能力を見せても、あっけらかんと笑って、受け入れてくれた屁舞留。
優しい屁舞留。
得難い『友』だと思った。
『人間』である自分が『神』である存在の屁舞留にそんな事を感じてしまうのは不謹慎なのかもしれないが――――
本当に、心の底からそう思った。
知らず、昔、同じように自分の能力を父と同じように優しく受け入れてくれた人の姿が、屁舞留の上に重なる。
その人は、父の親友で科学者だった。
その人の前でなら、キョウジは自分の考えを遠慮なく言えたし、能力を発揮できた。その人も――――優しく受け入れてくれていた………かのように見えた。
だが、同じ科学の分野を志し、その人の前で度重なってしまったキョウジの能力の披露は、その人を深く傷つけてしまっていた。優しかったその人が、自分や、自分の父と母に牙を剥かせるに十分な程の『殺意』を、その人の中に育てさせてしまった。
屁舞留は違う。そんな事にはならない。
そう信じたい。
だけど――――『心』ほど、不確かな物はないのだ。
傷つきやすく、脆いものはないのだ。
だからこそ美しく、愛すべきものなのだとも思うけれども。
『心』は、決して綺麗事だけではすませてはいけない物だと言う事を、キョウジはもう、知ってしまっていた。
「キョウジ………」
しばらくそんなキョウジを黙って見つめていた屁舞留であったが、やがてその面に、フッと柔らかな笑みを浮かべた。
伸びて来た屁舞留の手が、キョウジの頭をわしわし、と、多少乱暴に撫でる。
「な、何?」
驚いたキョウジが多少戸惑い気味になっているから、屁舞留は吹き出しそうになってしまった。
「……全く、お主は心配性なうえに苦労性じゃな! 吾にそんな無用の気遣いをするでない!」
「え……え……? でも――――」
「お主のその慧眼の鋭さも頭脳も――――もっと誇っても良い物じゃぞ? 確かに慎み深さも必要かもしれぬが、時には、胸を張ることも必要じゃ。なんなら、あの太公望殿の如くに、『自分は全知全能だ――――』と、言い張っても構わぬ」
「む……! 無理です!! 無理無理!! そんな、『全知全能』だなんて――――!!」
出来ることも少ないのに、と、キョウジは全力で首を振る。屁舞留は声を立てて笑った。
2人がそうしている間にも、村人たちと妖魔たちは劉備の統治する城に向かって、避難を開始しようとしている。屁舞留の本体である『石』は、長老が持って行ってくれる事になったようだ。
「吾は別に、お主の『影』に持ってもらっても何も問題があるとは思っていないがのう……?」
そうブツブツ言っている屁舞留の横で、シュバルツの気持ちも理解できるキョウジは、苦笑するしか無かった。
「そう言えば、屁舞留」
「ん? どうした? キョウジ」
「シュバルツの背中には――――まだ、『闇』が張り付いている?」
キョウジのこの質問を受けた屁舞留は、少し哀しげに瞳を曇らせた。
「そうじゃな……。残念ながら……」
「そうか……」
「他の者たちには、もうほとんど『死の闇』など張り付いていない……。なのに、何故なのじゃろうな……。お主の『影』にだけ――――」
そう申し訳なさそうに言う屁舞留に向かって、キョウジは軽く首を振った。
「大丈夫だよ。運命は、変えられるものなんだろう?」
「それはそうかもしれぬが――――」
「さあ、とにかくまた――――この戦いを見守ろう」
キョウジの言葉に、屁舞留も素直に従った。
太公望たちによって周到に用意された戦場は、戦っていて、全く危なげが無かった。
ハヤブサやシュバルツの腕の強さは言うに及ばず、さらにいち早く駆けつけて来た援軍によって、村人たちは全員、1人の死人も出さずに逃げ切る事が出来たのである。
「全員助ける」
そう言い切った太公望が、まさに有言実行をした事になる。村人たちと妖魔たちは互いの無事を素直に喜び、キョウジと屁舞留もホッと胸を撫で下ろしていた。本当に――――すごい事をやってくれていた。
「キョウジ……! 本当に、ありがとう……! お主の助力があればこそだ……!」
屁舞留はキョウジの手を握り、涙ながらにそう言葉を紡いでいる。
「何を言っているんだ屁舞留……! こうなる事が出来たのは、太公望殿やハヤブサたちのおかげで――――」
そう言うキョウジに、しかし屁舞留は頭をふる。
「いいや……。最初にお主が『影』を村に放り込んでくれた。そこから、皆の運命が変わって行ったのじゃ。キョウジ……。お主の投じた『石』が、見事に実を結んだのじゃぞ?」
そう。
自分一人だけでは、おそらく何も出来なかった。
泣いて皆の供養をするだけで終わっていた。
そこに、キョウジが忽然と現れて――――
手を差し伸べてくれた。
死者を悼んでくれた。
『運命』に対して怒り、そして、立ち向かってくれた。
あきらめない『心の強さ』を教えてくれた。
キョウジが送り込んだシュバルツが、ハヤブサを呼び
ハヤブサが、皆を呼び込んだ。
だから――――今がある。
それであるが故に、自分が謝意を示すのはキョウジ。
少なくとも屁舞留は、そう思っていた。
「さあ、後は、お主の『影』の死の闇だけが問題じゃな……。一体何故――――何時までもあ奴の背中に、張り付いておるのじゃろう?」
そう言って首をかしげる屁舞留に、キョウジがポツリと答える。
「それはおそらく、今夜あの村に襲撃をしようと企てている、素戔鳴のせいだろう……」
「――――!?」
「今、ハヤブサたちが退けた軍は、百々目鬼と言う妖魔軍だけだった。でも、あの時村に襲撃をかけて来たのは百々目鬼と素戔鳴――――。素戔鳴の方に襲撃時間を変更する動機が無ければ、おそらく夜半、素戔鳴は村に乗り込んでくる筈だ。村の皆に『天罰』を下すために――――」
「な――――!!」
屁舞留は思わず、息を飲んでしまっていた。
それはハヤブサも同じ考えなのだろう。合流できた劉備軍の軍師諸葛亮に、同じ事を話している。
そう、シュバルツの『死因』になるのは素戔鳴。
これ以外はあり得ない。
「ならばキョウジ! また戦いを見守りに行こう! もうあの『闇』は、お主の『影』だけになっておる! 今度こそ我らの手で、もしかしたら悲劇を止める方法を見つけられるやもしれぬ!」
そう言って屁舞留は立ち上がろうとする。だがそれを、キョウジが引き留めた。
「うん。そうだね。でもその前に、一つだけ、私の願いを聞いてくれないか? 屁舞留」
「願い? 何じゃ?」
きょとん、とする屁舞留に、キョウジは笑顔を見せた。
「屁舞留の『御神体』の石を、もっと近くで見てみたいんだけど」
「それはお安いご用じゃが……キョウジは変わっておるの。こんな物が見たいのか?」
キョウジに頼まれてから暫くして、屁舞留とキョウジは『御神体』の石の近くに来ていた。その石は、長老が休んでいる幕舎の中に設えられた、簡易の祭壇の上に大切に祀られていた。
「ほら、これじゃ……。最初はこれが吾の『神体』になる予定であったのだが、生まれてすぐ人界に落ちてしまったせいで、すっかり『石』になってしまった……。もうあちこち削られてしまっておるが、何となく体の形の名残があるじゃろう?」
「本当だ……」
キョウジがそう言いながらじっと石を眺めている横で、屁舞留もまた、少し複雑な顔をしながらその『石』を眺めていた。
(もう大分削られておる……。100年前にこの村の者たちに偶然拾ってもらって『土地神』として祀られてから、こうして『霊体』を得るまでに『神気』を回復する事が出来たが………もう、吾の寿命が来るのも、おそらく時間の問題であろうな……)
傷みも酷く、風化も激しい。この『神体』も『霊体』も、もう長くは保たないであろう。
人界に落ちてから300年。
いろんな事を経験させてもらった。
自分には勿体ない程の『奇跡』を、味わわせてもらった。
もう何時死んでも――――悔いはないと思う。
新しい土地に行っても、自分の事を『守り神』として祀りたいと言っていた村人たち。
その申し出はとても嬉しくてありがたいのだが、やはり、新しい土地に行くのなら、その土地に居る『神』を、『土地神』として崇めるべきなのではないかと屁舞留は思う。
おそらく、もう自分には――――新しい土地を肥えさせるだけの『神力』が、残っては居ないだろうから。
「ねえ、屁舞留」
キョウジの呼び掛けに、屁舞留ははっと我に帰った。
「な、なんじゃ? キョウジ……」
「この『石』の中に………入る事って出来る?」
「…………?」
何故キョウジがそんな事を言い出すのか、その意図がさっぱり分からない屁舞留は少し小首をかしげるが、すぐに頷いた。
「ああ。入れるぞ? この『石』もまた、吾の『家』みたいな物であるからな……。そうじゃ、キョウジも入るか?」
「えっ? 良いんですか?」
「勿論じゃ」
屁舞留は笑顔でそう答えると、キョウジをいざなって『石』の中へと入った。
「へえ……意外と温かいんですね……。『石』って言うから、もっと冷たい印象があったけど――――」
石の中に入ったキョウジが、興味深そうにあたりをきょろきょろと見回しながら、そう独りごちている。それを聞いた屁舞留が苦笑した。
「言うたであろう? この『石』は、吾の『家』の様な物であると……。この中で眠れば、それはそれは心地良いものなのじゃぞ?」
「そうなんだ……」
キョウジの返事を聞きながら、屁舞留はまた少し考え事をしていた。
(そうじゃな……『死ぬ』のなら、この中で死ぬのが良い……)
『無』からここに宿った『命』の様な物が、またここから『無』に帰るだけだ。だから屁舞留は、死ぬ事自体に恐れはなかった。きっとここでなら、母の胎内で眠る様に、安らかに『無』へと還って行けるだろう。
ただ―――――
キョウジ
彼を本当に『独り』にしてしまうかもしれない。
それだけが――――
ドンッ!!
「―――――!」
何かが『閉じる』音がして、屁舞留ははっと我に帰った。顔を上げると、キョウジがいつの間にやら石の外に出てしまっている。
「キョウジ……!」
慌ててその後を追いかけようとした屁舞留は、何か壁の様な物に阻まれて、そこから出られない事に気付いた。その壁の向こうで、キョウジが綺麗に微笑みながら、印を結んでいた手を下ろしている。彼の作り上げた結界が、この空間を閉じてしまったのだ。
「キョウジ!? 何を考えている!? 開けろ!!」
屁舞留は怒鳴って、中からバンバンと、結界を叩いてみるが――――それはびくともしなかった。
「屁舞留………短い間だったけど、今までありがとう」
「―――――!?」
「ここから先は、きっと私の『戦い』になるんだ。だから、行くよ」
「戦いに行くのなら、吾も共に――――!!」
そう叫ぶ屁舞留に、しかしキョウジは頭をふった。
「いや……屁舞留は、村の人たちが『そばに居てくれ』と望んでいる……。だから、村人たちと共に行かないと」
「な………!」
「屁舞留………貴方と過ごした時間は、私にとってはかけがえのないものになった。だから、絶対に忘れない」
本当に、ありがとう。
キョウジはそれだけを言うと、踵を返して屁舞留の前から走り去ってしまった。
「何を馬鹿な事をぬかしておるのじゃ!! キョウジッ!! 戻って来んか!! キョウジ―――――ッ!!」
後にはただ――――叫ぶ屁舞留だけが残された。
(これでいい……。屁舞留は、村人たちに必要とされている………)
屁舞留から離れて、シュバルツの姿を求めて彷徨いながら、キョウジは思った。
太公望があれだけ手を尽くしても、シュバルツに張り付いている『死の闇』は晴れなかった。それはつまり、シュバルツの闇を払う役割を背負っているのは、自分ということなのだろう。
ハヤブサが、皆が、懸命にシュバルツに向かって手を伸ばしている。でもこのままではその手を掴む事が出来ないシュバルのその背中を、皆に向かって一押ししてやる。それが自分の役割なのだとキョウジは悟った。
(『呪』の使い方は分かった……。後は、シュバルツに触れるための『媒介』さえ見つける事が出来れば……!)
キョウジは確信する。きっと自分は、今度こそシュバルツを『治す』ことができるであろうと。
だけど、『死滅』へと向かうDG細胞の自然の理をひっくり返す『呪』――――そこに、どれだけのリスクが伴うかキョウジには想像もつかない。下手をしたら自分の霊体自体が、完全に消えてしまう可能性だってある。
でも、それで良いと、キョウジは思った。
シュバルツは、ハヤブサに必要とされている。
屁舞留は、村人たちに必要とされている。
それに対して自分は、もう死んでいる身だ。ここで今更自分が消えてしまおうがどうしようが――――それこそ誰も悲しまないし、迷惑をかける事もない。
それが、総ての答えなのだ。
自分は、シュバルツのためならば喜んで消えられる。
元々シュバルツは、弟を守る目的で、自分の総てを注ぎ込んで作り上げた『影』
『身体』を置いて、『心』を託した存在だった。
バラバラになってしまった身体と心。
今度こそ本当に―――――一つになっても良い筈だ。いや、そうなるべきだ。
キョウジは強く決意して、シュバルツの姿を探す。
やがて、劉備の城の中から出て来て、孫尚香や甲斐姫と共に、村人たちの方へ足を運ぶシュバルツを見つけた。
(いた…………!)
彼はにこやかに笑いながら、村人たちの炊き出しの手伝いをしたり、子供たちの相手をしたりしている。キョウジはじっと、その様子を見守ることにした。
(いかん―――!! キョウジは死ぬ気だ――――!!)
結界の壁を叩きながら屁舞留は思った。
キョウジはあのシュバルツを救うために、『呪』を使うつもりなのだと、屁舞留には容易に想像が出来た。
だが、物を開いたり閉じたり、動かしたりといった簡単な『呪』であるならばともかく、『死』へと向かう自然の摂理をひっくり返すような強力な『呪』は、たいてい大きなリスクを伴う。下手をしたら、それを発動させた術者本人に反動が跳ね返って来て、死んでしまう可能性だってある。
『呪』を習い始めて短時間で、その本質を見抜いてしまったキョウジが、そのリスクに気づかぬ筈が無い。
彼はそれでもやる気なのだ。
それで自分が本当に消えてしまっても構わない――――彼は、そう思っているのだろう。
彼にとってはそれほどまでに、シュバルツが大事で。
そして、ハヤブサが大事で。
『救いたい』
そう願っているのだから。
キョウジがここに自分を閉じ込めたのは、彼がそれをしようとしたら、自分が止めに入ると分かっていたからだ。
当然だ。
自分は、キョウジに計り知れないほどの『恩』を受けた。
その『恩人』の完全なる消滅など――――誰が望むと言うのだろうか。
キョウジにそんな事をさせるぐらいなら自分が代わる。
その『呪』の反動は、自分が受ける。
だからキョウジ―――――早まるな!!
屁舞留は懸命に結界の壁を叩くが、それでも結界はびくともしない。試しに解呪の『呪』を唱えてみるが、結界の薄皮一枚はがす事が出来なかった。やはりキョウジの『呪』の技量は、あっという間に屁舞留のそれを凌駕しつつあるようだ。
(くそ……ッ! キョウジに『呪』など教えるのではなかった……!)
屁舞留は舌打ちして後悔するが、総ては後の祭りであった。今更この現実を、覆せる筈もない。
「誰か!! 誰か吾の声を、聞いてくれ!!」
屁舞留は必死に声を上げるが、それに帰って来る反応はない。自分の声がただ虚空に吸い込まれていくだけのような感覚に襲われて、早くも心が折れそうになる。
「…………ッ!」
だが屁舞留は、ブンッ! と、大きく頭を一つ振ると、また顔を上げた。
「誰か!! 吾の声を聞いてくれ!!」
もう一度、叫ぶ。
「誰か!! 誰か!!」
キョウジは、あきらめなかったではないか。
自分の声が届かずとも、手が届かずとも――――
何度も立ち上がり、立ち向かって行っていたではないか。
ならば、吾も、あきらめない。
そうでなければ、何のために、自分はキョウジと共に時間を過ごして来たのだ。
絶対に、絶対にあきらめてなどなるものか。
自分があきらめてしまったら、キョウジが消滅すると分かっているのであるならば、尚更。
「お願いだ!! 誰か!!」
叫び続けろ
『想い』を乗せて
叫び続けろ
声が枯れても――――
あの桃の花と共に、自分の声は、確かに皆に届いていた。
村人たちの中に、自分の声を捉えるための『回路』が出来ている筈なのだ。
ならばお願いだ。
あの時の奇跡を、今こそ、もう一度――――!
「誰か――――!!」
屁舞留は懸命に、叫び続けるのだった。
夜更け。
城下町の村人たちの幕舎の一角で、シュバルツの膝に寄りかかる様にして、ケイタが寝ていた。
「すみません、うちの息子が………」
その様子を見たケイタの両親が恐縮しきりと言った按配で、シュバルツに声をかける。それに対してシュバルツは苦笑を返した。
「大丈夫です。今日1日、子供たちの面倒を見てくれていたから、きっと、疲れたのでしょう」
ここは大丈夫ですから、貴方がたもどうか休んでください、と、シュバルツに言われ、ケイタの両親も頭を下げる。そのままそこから下がる二人と入れ替わる様に、孫尚香がシュバルツに声をかけて来た。
「今のところ、皆ゆっくり休めているみたい。何処にも異常はないわ。ケイタ君は………って、あら? 寝てる?」
孫尚香の言葉に、シュバルツが頷く。それを見た彼女の顔にも、柔らかい笑みが浮かんだ。
「そっか……。今日1日頑張っていたものね……。そうだ、毛布を持って来ましょうか?」
「いや、それには及ばない。もう少しケイタが深く寝たら、私が布団まで運ぼう」
「そう? じゃあ、お願いします。私は、甲斐と見張りを交代してきますね」
彼女はそう言って、シュバルツ達の居る幕舎から出て行く。刹那、シュバルツの瞳が鋭く光る。
彼はケイタを素早く布団に寝かしつけると、幕舎の中からかき消える様に居なくなってしまっていた。
(シュバルツ……やはり、行くんだな……)
ハヤブサや皆が、シュバルツを戦場に行かせないように、手を尽くしてくれていたのは、キョウジにも分かっていた。だけど、あの程度でシュバルツを思いとどまらせることは不可能である事を、彼は知っていた。
行こう。
静かにそう決意をして、彼もまた、シュバルツの後を追った。
「あれ……? シュバルツさん……?」
当然、孫尚香と交代して幕舎に来た甲斐姫は、彼の姿を見つける事が出来るはずもなく。
「シュバルツさん!? おかしいな……? 何処に行っちゃったんだろう――――?」
甲斐姫はそう独りごちながら、慌てて幕舎から出て行った。
それから、どれくらいの時がたった事だろう。
「…………?」
不意に、誰かに呼ばれた様な気がして、ケイタは目を開けた。
「シュバルツさん……?」
ぼんやりとする意識の中で、シュバルツの姿を探す。だが戦場に向かってしまっているシュバルツからは、当然返事が返って来る事はない。シュバルツの不在を悟って、ケイタはガバッと跳ね起きた。
(しまった――――!! お姉さんたちから、『シュバルツさんから目を離さないでね』って、頼まれていたのに――――!!)
焦りの色を隠せないケイタは、慌てて外に飛び出そうとする。するとそこに、また、誰かからの『声』が、ケイタの耳に届いた。
(誰か来てくれ!! 誰かここから出してくれ!!)
必死に訴えかけられる。ケイタはこの声に聞き覚えがあった。
(ええと………どこで聞いたんだっけ……)
ケイタは必死にそれに思いを巡らす。
そしてついに――――思いだした。
「その声は、土地神様!?」
叫ぶケイタに、土地神の方からも声が帰ってきた。
(その声は、ケイタか!?)
「はい! 土地神様!! どうしたんですか!?」
(…………!)
屁舞留はケイタと『会話ができている』と言う事実に身震いするほど感動した。
やった……!
ついに『届いた』のだ。
自分の声が――――
だがいつまでも、感動の余韻に浸っている訳ではないと悟る。
自分の為すべき事を、為さなければ。
(頼むケイタ! 長老の傍に吾の本体が祀られておる! そこまで来てくれ!!)
『土地神』の頼みに、この朴訥な少年が否やを唱える筈もない。
「分かりました!!」
ケイタはそう叫ぶと、真っ直ぐ長老の幕舎に向かって走り出していた。
「長老様!!」
「な、何じゃ!?」
何となく浅い眠りと戯れていた長老は、ケイタの叫び声であっという間に覚醒させられた。
「長老様――――! 『土地神』様が……!」
「どうしたのじゃ? ケイタ……。『土地神』様が、一体どうされたと――――」
長老の言葉が終わらぬうちに、1人の道士風の男が、ふらりと幕舎に入って来る。
「………何やらここから、騒がしい『声』が聞こえてくるようじゃが……」
「な、何じゃ!? その方は――――!!」
突然の珍客に驚いた長老は、咄嗟にケイタを庇うように、その道士風の男に振り返る。すると、道士風の男の後ろから、白髪の青年が苦笑しながら幕舎に入ってきた。
「その様に警戒するな。吾らは、怪しい者ではない故――――」
「し、しかし……!」
まだおろおろする長老たちに、もう一人――――巫女風の長い黒髪の女性が楚々と入って来る。
「お騒がせして申し訳ございません……。ですが、私たちはハヤブサ様の手助けをする者にござりますれば――――」
「ハヤブサ殿の?」
巫女のその言葉に、長老もようやく警戒を解いた。
「ここから、何やら人を呼ぶような声が聞こえたのだが……」
そう言いながら道士風の男がきょろきょろと辺りを見回している。それを見たケイタが、長老の影から出てきて叫んだ。
「きっと、あの『石』です! あそこに『土地神様』が――――!」
「ケイタ?」
少し驚いて振り向く長老を、ケイタはまっすぐ見つめ返す。
「だって長老様! この人たちは、ハヤブサさんを助けようとしているんでしょう!?」
「……………!」
「ハヤブサさんは、僕たちを助けてくれた! だったら今度は、僕たちがハヤブサさんを助けなくちゃ!」
ハヤブサは常にシュバルツのために動いていた。
そして、シュバルツは『土地神』の代理――――ハヤブサのために動くと言う事は、絶対に『土地神』のためになることだ。ケイタはそう信じて疑わなかった。
「………なるほど、確かに、何かいるようだな」
白髪の青年が手に持った打神鞭をポンポンと打ち鳴らしながら、その『石』をじっと見つめていたが、やがておもむろに、その石に向かって手をかざした。すると、その手から光が溢れだし、『石』の中に居る『モノ』を、皆の目に見えるように映し出す事に成功していた。
「ケイタ!! 長老!!」
太公望の『術』によって、自分の姿が皆に見えるようになったと悟った屁舞留は、迷わず声を上げた。
「土地神様!? 土地神様なの!?」
「これが………!」
初めて見る『土地神』の姿に息を飲むケイタと長老に向かって、屁舞留は尚も呼び掛けた。
「お願いだ!! 吾をここから出してくれ!!」
「えっ……?」
「だ、出せ、と、言われても………!」
「………なるほど、何か『結界』の様な物で、『封』をされておる様じゃな……」
戸惑う二人の横から道士風の男が一歩、石に向かって進み出る。
「お主……『術師』か!?」
一目で自分の今の状態を看破した道士風の男に、屁舞留は声をかけた。
「如何にも。小生は方術師で、名は左慈と申す」
「では左慈――――お願いだ!! この結界を破ってくれ!! 吾は行かねばならぬのだ!!」
その言葉を受けて、左慈は赦しを乞う様に長老の方に振り返る。他ならぬ『土地神』の願い故に、長老も一も二もなく頷いた。
「では――――破りまするぞ!」
左慈は『誦』を唱えながら、札で印を描く。
「破ッ!!」
裂帛の気合と共に、左慈の札が石に向かって飛ぶ。だが――――破られたのは札の方であった。札は真っ二つに裂けて燃え、左慈に術の反動が帰ってくる。
「ぐッ!!」
「左慈様!!」
「強力な結界であるな……! これをした術者は、相当強い『霊気』を湛えているとみゆる………!」
(やはり………!)
左慈の話を聞いた屁舞留は歯を食いしばった。キョウジの『呪』の力は、想像以上に大きく強くなっている。
だが、あきらめてしまう訳にはいかない。
自分は、何が何でも 外に出なければならないのだから。
「では、左慈!! 今度は内と外から同時に破の術を試みてみようぞ!!」
「心得た!」
屁舞留の呼び掛けに左慈が応じる。二人の術者が、同時に術の動作に入った。
「「破ッ!!」」
バンッ!!
派手な音を立てて、結界が砕け散る。石の中から屁舞留が、転がり落ちるように出て来た。
「だ、大丈夫ですか!?」
ケイタが驚いて声をかける。屁舞留はすぐにガバッと跳ね起きた。
「おのれキョウジめ……! くだらん策を弄しおってからに……!」
殺気だった眼差しで前を見据えながら、屁舞留は顔を上げる。その手は結界を叩きすぎて、既に血だらけになっていた。
「許さぬ……! 今すぐ後を追いかけ、て――――」
ここで屁舞留の姿勢が膝から崩折れ、皆の視界からその姿がフッと消える。
「太公望殿!?」
太公望の透視の『術』が消えてしまったのではと、左慈は驚いて彼の方に振り向く。しかし太公望もまた、何とも複雑な表情をその面に浮かべていた。
「いや……私も、透視の術を途切れさせたわけではない。ただ、先程の者の『気』が、あまりにも弱くてか細いから――――『捉えきれなくなった』と表現した方が、正しいだろうな……」
そう言いながら太公望は、手の中に光っていた『術』の光を収める。
「左様か……」
左慈は小さくため息を吐いた。
「先程の方は、何を言わんとしていたのでしょう……」
疑問を呈するかぐやに、答えを返せる者はいなかった。ただ1人――――ケイタを除いては。
「『連れて行って欲しい』って、言ってる!」
「ケイタ!?」
驚く長老に、ケイタはなおも言葉を続けた。どうやら――――ケイタにだけは、屁舞留の姿と声が、見聞き出来ているようだった。
「だって長老様……! 今でも土地神様は叫んでいるよ? 『連れて行け』って。シュバルツさんの向かった戦場に、連れて行って欲しいって!」
「…………!」
長老は半信半疑で御神体である『石』の方に振り返る。一瞬だけ見えた土地神の姿も今はなく『石』自体は何の変わりもないように見える。しかし、先程見た土地神の必死な様子と、ケイタのこの言葉――――嘘偽りを言われているようにも思えない。だが、「ここから戦場に連れて行く」と言う事は、この村の者達とは何の関係もない、ここに居る誰かに御神体である石を、託さなければならない、と言う事になる。
土地神自体が望んでいたとしても、村の者以外の余所者に『石』を触れさせても良いものだろうか。
長老はその判断に少し迷った。
「……確かに、何か『波動』の様な物は感じるがな……」
そう言いながら方術師の左慈が、石の傍で札をかざす。左慈の手の中の札は、その石から発せられるはどう故なのか、ピリピリと小さく揺らめいていた。それを見た太公望が、フ、と、小さく笑った。
「連れていけばよいではないか。その小さな『石』一つ。何かの邪魔になる訳でもあるまい」
太公望の言葉を受けた左慈が、長老の方に視線を送る。
「よろしいかな?」
左慈の問いかけに、ケイタからも「長老様!」と、縋るように見つめられ、長老も反対する理由が無くなってしまった。
「では――――頼みます」
長老は左慈に御神体の石を託した。その中で屁舞留は、ほっと息を吐いていた。
(良かった……。これで、キョウジの傍に、行ける……)
朴訥な、心優しい青年。
そして、恐ろしく高い資質をその身に持つ青年。
それが今――――自ら『消滅』を選ぼうとしている。
そんな事をさせては駄目だ、と、屁舞留は思う。
理屈ではない。
本能でそう感じていた。
彼には存在し続けていて欲しいと、願った。
(絶対に早まるなよ……! キョウジ……! 吾らが行くまで、消えるでないぞ……!)
結界の解けた石の中に身を落ちつけながら、屁舞留は間に合え、と、一心に祈っていた。
(く………ッ!)
結界を破られた反動は、当然術者であるキョウジにも伝わっていた。
(屁舞留………結界を破ったんだな……。意外に、早かったな……)
身を斬られるような痛みに耐えながら、キョウジは苦笑する。
仕方がない。所詮は付け焼刃の術者が作った結界だ。簡単に破られてしまって然るべきものなのだ。
(それにしても……結界を破られただけでこれならば…………壊れゆく物を食い止める『呪』を使った時、どれ程の反動が来るのだろう……?)
ネガティブな事を考えそうになって、キョウジはブン、と頭を振る。
今更怖気づく気も、後ろに引く気もない。
もう――――覚悟は決めていた。
目の前ではハヤブサとシュバルツが、素戔鳴と相対している。
しかし、庇う対象の村人もいなくて、誰が敵か味方か分からなくなるジレンマも解消されてしまっているこの戦場――――あの素戔鳴と相対しても、忍者二人は全く危なげなく戦っていた。下手をしたら、「ふざけているのか!」と、怒鳴りたくなるほどに。
「おのれっ!! ふざけるなッ!!」
素戔鳴も、それは感じているのだろう。怒鳴りながら雷撃を飛ばしまくっているのだが、一向に忍者たちに当たる気配が無い。それどころか、素戔鳴の攻撃を避ける動作に、ハヤブサの方は余裕さえ感じられる。
(無理もないな)
キョウジはそう思って苦笑した。
実際、ハヤブサが素戔鳴と相対するのは、これで3度目ぐらいだろう。しかも前の戦いで、ハヤブサは素戔鳴の攻撃をその身に散々喰らいまくっている。素戔鳴は、既に龍の忍者に手の内を曝してしまっているのだ。
神をも滅してしまう腕を持った龍の忍者が、同じ相手に二度も三度も不覚を取るとは思えない。
そうこうしているうちに、素戔鳴は罠にはめられてしまう。
岩攻め、火攻め、水攻め………素戔鳴軍の兵力は、あっという間に3分の1以下にまで削り取られてしまった。更にそこに、関羽、張飛、趙雲と言った、劉備軍の面々が、素戔鳴軍を取り囲んでくる。
ここで勝負あった――――普通ならば、そうなるところだろう。
だがここから、素戔鳴の執念が炸裂した。
シュバルツを『害悪』と判断し、『滅さなければならぬ』と言う執念。
それが、素戔鳴の闘志を燃え立たせ、挑みかかって行った関羽、張飛、趙雲を退ける。
結局、素戔鳴とハヤブサの一騎打ちに、総ての勝負の行方は託される事になった。
相対する二人の力量はほぼ互角――――だが紙一重の差で、ハヤブサの方に軍配が上がった。やはり、龍の忍者は、同じ相手に二度負ける、と言う事はないのだ。
その『からくり』をハヤブサが素戔鳴に説明すると、素戔鳴は烈火のごとく怒りだした。
「人の子よ!! 汝らに問う!! 何故だ!? 何故その後ろに居る『化け物』を守ろうとするのか!? 時を巻き戻してまで――――!!」
「…………!」
その言葉を聞いたハヤブサが、怒り故に眉を吊り上げ、シュバルツは哀しみ故に眉をひそめた。
キョウジは黙って天を仰いだ。
それは、シュバルツ自身が一番よく分かっている。
よく、分かっているから――――
「あれは人の形をしているが、人には非ず。その身は、酷く邪悪な物で出来ている……! 放っておけば、人の子の世に害を為すぞ!?」
その意見は正しい。
正しくないとは言えない。
全く反論する事の出来ない自分が、
キョウジは哀しくて悔しかった。
ああ
何て、重い 『十字架』 を
シュバルツ に
ドンッ!!
シュバルツの前に立っていた関羽が、その手に持つ青龍偃月刀を、思い切り地面に叩きつけたが故に、キョウジの思考はそこで中断させられた。驚いて顔を上げると、関羽が仁王立ちになって、素戔鳴を睨み据えている。
「……拙者はこの者を守る。例えその身が何で出来ていようが、関係無い」
静かな物言いだが、酷く迫力があった。
「それは、何故か?」
問う素戔鳴に、関羽は答える。
「……『約定』を交わしたからだ」
「約定? それは、誰とだ? ここに居る、龍の忍者とか?」
怪訝な顔をして問う素戔鳴に、関羽は頭を振った。
「それもある。だが、それだけではない」
関羽は真正面から、素戔鳴を見据える。
「拙者が『約条』を交わしたのは、村人たちとだ」
シュバルツ達が前の時間軸で助けた、生き残った村人たち。それが、関羽に涙ながらに訴えて来た。
「必ず、シュバルツさんを助けてください」
「あい分かった。必ず助ける」
1人1人と、関羽はそう約束した。そして、今に至る。
時を渡った今、あの城の中に逃げ込んできた村人たちの中には、そんな記憶などかけらも残っていないだろう。
だが、関羽は覚えている。
村人たちの涙を。握ってきた手の強さを。
彼らの必死な願いを。
「必ず助ける」
そう交わした約束を。
覚えている以上、それは守らなければならぬと関羽は思う。例え相手に忘れられてしまった『約束』であろうとも、『無かった事』になってしまっている物だとしても。自分が一度引き受けた物ならば―――――それは、果たされなければならぬと思うのだ。
「……この者の出自や成り立ちがどうあれ、この者は村人たちを助けていた。弱き者を慈しみ、守ろうとする者であることを、少なくとも拙者は知っている!」
関羽はもう一度、その柄で地面をドンッ!! と、叩いてから、青龍偃月刀を構えた。
「なれば、拙者はこの者を守る!! これ以上の理由は必要ない!!」
関羽に続いて張飛も趙雲も、シュバルツを守る様に関羽の傍に駆け寄り、武器を構えて素戔鳴に対して立った。
「……………!」
シュバルツが、「信じられない」と言わんばかりに息を飲み、
それに向かってハヤブサが、優しく微笑んでいる様が見える。
(良かった………)
キョウジの瞳から、自然と涙が溢れていた。
良かった
良かったな、シュバルツ
出自がどうとか、成り立ちがどうとか、本当に関係が無い。
シュバルツの『心』を見て、その『行い』を見て――――判断して、受け止めてくれる人たちが、ちゃんと居るんだ。
きっと、大丈夫だ。
私が完全に消えてしまっても、シュバルツは人間たちの間で、ちゃんと生きていける。
だから――――
キョウジがそこまで思った時、ふいに後ろから声をかけられた。
「………キョウジ……!」
「――――!」
驚いたキョウジが振り向くと、そこに屁舞留が立っていた。
「屁舞留……!」
結界が破られた事は知っているから、屁舞留の出現自体にキョウジは驚かない。
ただ――――少し『早すぎる』と、思った。
自分はまだ、『シュバルツを救う』と言う自分の役目を、成し遂げてはいない。
それを行ったが故に被らなければいけない『リスク』は、自分が被らなければならないのであって、屁舞留を巻き添えにしてはいけない、彼はそう思った。
しかし――――屁舞留はそれを望まなかった。
屁舞留はかなり怒気を食んだ視線でキョウジを睨みつけると、つかつかとその傍に歩み寄ってきた。
「この馬鹿もの!!」
怒声と共に振り上げられた屁舞留の手が、キョウジの腹の辺りを叩く。だがそれは、屁舞留の非力も手伝ってか、ぺちん、と、可愛らしい音を辺りに響かせていた。
「あの程度の結界で、本気で吾を閉じ込められると思うておったのか!? あまり吾を見くびるな! あんな物を破る事など、吾にとっては朝飯前じゃ!!」
(嘘じゃ。本当は、独りで破ることもできなくて、左慈と言う方術師の力を借りたけどな!)
怒鳴りながら屁舞留は、心の中で懺悔をする。
だけど腹が立つから――――その懺悔は、屁舞留の腹の中にしまい込まれる事になった。
「全く、くだらん『策』を弄しおってからに……! そんなに吾は、お主の戦いの同士としては、頼りがいの無い者だったのか!?」
「ち、違う! 屁舞留――――!」
キョウジは屁舞留に酷く誤解させてしまっていると悟って、慌てて叫んだ。
「『頼りがいが無い』なんて……! そんな事思わせるつもりではなかった。ただ、ここから先は、私自身の戦いだ。この戦いには『リスク』が高くつくから―――!」
「お主の戦いが終わっておらぬのなら、吾の戦いもまた、終わってはおらぬ!! 違うのか!?」
「―――――!」
屁舞留のこの言葉に、キョウジは一瞬気圧される。だがしかし、すぐに思いなおして口を開いた。
「だけど屁舞留―――! 貴方は村人たちに『土地神』として必要とされている。シュバルツだってそうだ! 村人たちや、ハヤブサに――――!」
「そうじゃ! お主の『影』は、吾の村のために働いてくれた、立派な村の一員じゃ!!」
キョウジの言葉を遮る様に、屁舞留は叫ぶ。今ここで、後に引く訳にはいかない、と、屁舞留は強く感じていた。
「『村の者』を救う戦いならば……! 吾もその戦いに参加する権利がある!! 違うのか!?」
「屁舞留………!」
「あれだけ村のために働いてくれたお主の『影』――――今更、『村と無関係の者』だなどと、吾は言わせぬぞ! キョウジ!!」
「…………!」
屁舞留のこの言葉に、キョウジは反論する言葉を失ってしまう。そんなキョウジの手を、屁舞留は縋りつく様に握った。
「キョウジ……! お願いだ……! 吾も最後まで、この戦いを戦わせてくれ……!」
「しかし……!」
「お願いだ……! 吾も、『土地神』としての責務を果たしたいのだ!!」
「屁舞留………」
屁舞留にそうまで言われてしまっては、キョウジもこれ以上強く反対できないと感じた。
「分かった……」
キョウジは観念したように、頷いた。
「ではキョウジ……。吾の手を取って、目を閉じてくれるか?」
「こうですか?」
キョウジは言われたとおりに屁舞留の手を取り、そして目を閉じる。すると、屁舞留の霊体が『誦』を唱えながらキョウジの霊体の中に『入って』来た。
「―――――!」
その独特な感触に、キョウジは一瞬身を強張らせるが、すぐに身体を包んでいた『違和感』は感じなくなった。その代わりに、身体に温かさが満ちて行く。屁舞留の『神気』が、キョウジの霊体になじんで来ているのだと悟った。
(分かるか? キョウジ……。今、吾はお主の中に入っておる。そのまま、主の『影』の方を見てみよ)
屁舞留に言われるままにキョウジはシュバルツの方に視線を走らせて、思わず息を飲んでいた。屁舞留にしか見えなかったシュバルツの背に張り付いている『死の影』が、自分の目にも、はっきりと色濃く見えるようになったからだ。
「こんな……! シュバルツ……!」
(……分かるか? キョウジ……。お主の『影』に張り付いている闇の色濃さが……。あ奴の運命は、まだ覆ってはおらぬ。そして、死期もかなり近づいてきておるのだ)
「…………!」
キョウジは信じられぬ思いでその『闇』を見つめていた。
今目の前で行われているこの戦いには、誰にも何にも落ち度がない。それなのに、シュバルツの『死』の運命がまだ覆せていないだなんて――――
(それを、お主は覆したいのじゃろう?)
「―――――!」
はっと、息を飲むキョウジに、屁舞留の声が語りかけて来た。
(あれを覆そうと言うのであれば、どう言うふうにやるにせよ、かなりのエネルギーを使うぞ。『呪』を習いたてのお主の力だけでは心もとないだろうから、吾が中からサポートしてやろうと言うのだ)
嘘だ。
本当は、キョウジ1人でも、それは可能であろうと屁舞留は感じ取っていた。
だけど、それを1人でやった場合、絶対にキョウジがただでは済まないだろうから――――
「屁舞留………」
戸惑うキョウジに、屁舞留の明るい声が響く。
(何、案ずるな、キョウジ。幸いにしてこの周りには、巫女、方術師と言った、吾らの助けとなり得る力を持った者たちもそろっておる。『呪』を発動させるのに必要な媒介も、すぐに見つかるであろうよ)
「……………!」
(太公望と言う者がここまで考えてこの面子をそろえたかどうかは定かではないが………この『偶然』は、我等にとってはありがたい事じゃ。だから、大事にせねばの)
屁舞留のこの言葉に、キョウジも拳を握りしめた。
そうだ。
もうここまできたら、腹を括るしかない。
シュバルツを救うために
躊躇いや迷いが、あっては駄目だ。
目の前では太公望や劉備たちが、素戔鳴に向かって説得を試みていた。
シュバルツは完全な『魔』ではない。そこまで神経をとがらせる必要はない。
人間と妖魔と神仙たちが力を合わせれば、どのような困難も乗り越えられるのではないかと――――
しかし素戔鳴は、「駄目だ!!」と、その説得を言下に拒否していた。やはり、あの軍神の目には、シュバルツの身体を構成しているDG細胞の危険性が、どうしても看過できないもの、として映ってしまっているのだろう。
だが次の瞬間、それまで黙っていたハヤブサが、素戔鳴を思いっきり殴り飛ばしていた。
「ぐうっ!!」
地面に叩きつけられた素戔鳴の上に、龍の忍者が押さえつけるように乗って来る。起きあがろうとする素戔鳴の喉元に向かって、彼は龍剣をつきつけた。
「お前、もう死ぬか?」
そう言い放つハヤブサの眼差しは、完全に『人斬り』の目をしていた。
「…………!」
初めて見ると言っていい、そのハヤブサの険しい眼差しに、キョウジは思わず息を飲み、キョウジの中に居る屁舞留は怯えた。
事実、ハヤブサは躊躇わないだろう。
例えその剣先に『神』が居たとしても。
一度『剣を振り下ろす』と決めたハヤブサは、迷わずそれを、成し遂げてしまう事を、キョウジは知っていた。
「ハ、ハヤブサ様!!」
素戔鳴の危地を感じ取ったかぐやが、慌てて声を上げる。
「どうかお許しを……! 素戔鳴様は、我が神仙界には無くてはならぬ御方なのです!」
「…………」
その声に黙して応えぬハヤブサに、甲斐姫もたまらず声を上げた。
「ハヤブサさん! 止めて!!」
しかし、その声がまるで聞こえていないかのように、龍剣を素戔鳴に突きつけ続ける龍の忍者。あまつさえ、その龍剣を振り上げようとしている。
「ハヤブサ様!!」
「ハヤブサさん!! 駄目っ!!」
「ハヤブサ!!」
「――――!」
シュバルツの叫び声に、ようやくハヤブサはその動きを止める。
シュバルツは必死にハヤブサを見つめ、首を横に振っていた。
「……………!」
それを見た龍の忍者は、小さく舌打ちをしながら素戔鳴の上から退いた。どうやら、シュバルツの『気持ち』の方を優先してくれたらしい。
「去れ!」
短くそう言うと、龍剣を下げて素戔鳴に背を向け、そのまま龍の忍者はすたすたと歩き出していた。
(終わったのか……?)
キョウジの中に居る屁舞留がそう問いかけてくる。しかし、キョウジは首を振った。
「いや、まだだ……! 素戔鳴は、まだシュバルツを狙っている」
前の時間軸でも、最後までシュバルツを狙い続けた素戔鳴。
だからきっと、この時間軸でも―――――
「ハヤブサ!」
シュバルツが、庇われていた関羽の影から出てくる。その瞬間、素戔鳴が動いた。
ガキッ!!
激しい金属音が爆ぜ、また静寂が訪れる。
展開が速過ぎて、何が起こったのか一瞬理解できなかったキョウジであったが、シュバルツと素戔鳴の間で振り向きざまに龍剣を抜刀している龍の忍者の姿を見て、ようやく状況を理解した。つまり、素戔鳴のシュバルツに対する攻撃を、ハヤブサがふせいだのだと。
「な――――!」
息を飲む素戔鳴に、龍の忍者はにやりと笑いかける。
「……やると思った」
「…………!」
ギリ、と、歯を食いしばる素戔鳴に対して、ハヤブサは改めて龍剣を構えた。
「もし次に同じことをすれば――――かぐややシュバルツが止めても、俺は貴様を斬る」
声音は静かだが、そこから漂う明確な殺気。それが素戔鳴に『これは脅しではない』と悟らせた。
「く…………!」
素戔鳴は認めざるを得なくなった。
もう本当に自分には、打つ手が無くなってしまったのだと――――
「引き上げるぞ!!」
素戔鳴は、兵達にそう命を下す。生き残った兵達は、諾々と従った。
最後まで龍剣を構え続けていたハヤブサであるが、素戔鳴の姿が完全に見えなくなった所でようやくその構えを解いた。それに合わせて、その場の空気も何となく緩んだ物になっていく。
「……………!」
だがキョウジは独り、緊張の中に居た。
まだだ。
まだ、シュバルツの背中から、『死の闇』は消えていない。
それどころか――――ますます色濃くなっていく闇の色。それは、彼の『死期』が近い事を警告していた。
(キョウジ……!)
キョウジの中に居る屁舞留も、同じように感じているのだろう。酷く緊張した声で、屁舞留から呼び掛けられた。
「分かっている……! 屁舞留……!」
キョウジは油断なく、辺りを見渡していた。
必ず来る。
シュバルツを『死』へと、導いてしまう何かが―――――
だがそれは、
何処から来るんだ――――?
刹那。
『死んだ』と思われていた仙界軍の兵士の1人が、そろりと動いた姿が、キョウジの目に飛び込んできた。その兵士はそろそろと矢をつがえ、狙いをシュバルツに定めようとしている。
「―――――!」
息を飲むキョウジの目の前で、今度こそシュバルツが「ハヤブサ!」と、叫びながら関羽の影から飛び出し、それをハヤブサが柔らかい微笑みで迎えていた。
誰も、あの兵士に気づいていない――――そう悟った瞬間、キョウジは『悲劇』が避けられないものと知る。
駄目だ!
キョウジがそう叫ぶよりも早く――――その矢はシュバルツの脇腹に突き刺さった。
「シュバルツッ!!」
ハヤブサの悲痛な声が響く。和やかだった場の空気が、一気に悲劇的な物へと変わった。
(さあ、ここからじゃな。キョウジ。用意は出来ているか?)
屁舞留の呼び掛けに、キョウジは頷いた。
「ああ。私はいつでも行ける。だけど、『媒介』となる物が、まだ――――」
「どいてください!! ハヤブサ様!!」
巫女かぐやが大声を出しながら、シュバルツの傍に駆け寄ってきた。
「微力ながら、治癒の法を試してみます!」
そう言うと巫女かぐやは、シュバルツの傍に座り、玉串を構えながら祝詞を詠唱して行く。シュバルツの身体にその玉串を当てると、それは、ポッと、金色の輝きを放ち始めた。
「見つけた! あれだ! あれが『媒介』―――!」
そう叫ぶキョウジに、屁舞留からも頷く気配が伝わってきた。
(そうじゃ。よく見つけたの。あれにお主の『呪』を乗せれば、お主の『影』にまとわりついている『闇』も、払う事が出来るやもしれぬ)
「分かった。やってみるよ」
そう言ってキョウジは、一歩、前に進み出ようとする。そこに、屁舞留が声をかけて来た。
(キョウジ……。分かっておるとは思うが、『呪』を行う時は『心』が大事じゃ。特に、これから行う『呪』は自然の理をひっくり返すような大きい物であるが故、心の平静さが特に重要になって来る。何が起こっても、絶対に平静さを保って――――『気』を乱すでないぞ?)
屁舞留の忠告に、キョウジは笑顔を見せる。
「ああ、分かっている……。気をつけるよ」
(吾もお主の『呪』をしっかりと支えてやるからの! だから安心して、やり遂げるのじゃぞ?)
「うん。ありがとう」
キョウジの冷静な様子に、中の屁舞留から微笑む気配が返ってきた。
(では、共に参ろうぞ! 戦いの場に――――!)
「そうだね。屁舞留」
こうして「二人」は、倒れているシュバルツの傍に、静かに歩み寄って行った。
「……じゃあ、まずは、気づいてもらう事から始めようか」
シュバルツの傍に歩み寄ったキョウジが、そう言いながら手で『印』を結ぶ。とにかくここの皆に、こちらの存在に気づいて認知してもらわなければならなかった。そうしなければ、『呪』を発動させるための『回路』が構築できないからだ。
「私はここに居る……! 誰か、気づいてくれ……!」
キョウジは目を閉じ、静かに呼びかけ続けた。
まず最初に、その場に居た諸葛亮がそれに気付いた。次いで、方術師の左慈も。
二人の祈祷が自分の霊体を包み、徐々に皆に視認できるように具現化して行く。
「……………!」
シュバルツを食い入るように見つめていたハヤブサが、こちらの気配を感じて顔を上げ、驚いて息を飲んでいる。その『視線』が合う。いつも見つめてばかりいたから、こうして自分の存在を意識してもらえるのは、随分久しぶりだな、と、キョウジは思った。
でも、シュバルツと間違えられるかな、と、思う間もなくハヤブサから声をかけられた。
「キョウジ!!」
一撃で自分の『正体』を看破して来た龍の忍者に、キョウジは少し面食らってしまっていた。言いたい事、話したい事はいろいろあった筈なのだが、思わず問いかけずにはいられなかった。
「ねぇハヤブサ。一つ、真面目に聞いても良い?」
「な、何だ?」
「貴方は一体――――『何処』で私とシュバルツを見分けているの?」
その問いかけに、龍の忍者は少し目をしばたたかせながらも、はっきりと答えた。
「そんなの――――見れば、分かるだろう……?」
そのハヤブサの言葉に対して、周りの皆は首を横に振っている。
(それはそうだよな)
ハヤブサ以外のここに居る人たちは、自分達の間にある特殊な事情を知っている者はいない。だから、外見が瓜二つの自分達を『別人』と見分けられなくても、それは仕方が無い事だとキョウジは思うのだ。
しかし――――それにしたって、どうしてハヤブサは、すぐに自分が『キョウジ』だと分かったのだろう。だいぶ前に死んでいる自分は、『もう居ない者』と、ハヤブサに認識されていても仕方がない。この姿だって『シュバルツの霊体』と、間違えられてもおかしくない物だったのに。
積もる話は沢山あった。
だけど今は、時間が無いと悟る。皆に認知されているこの状態を保てるのはあと僅かな間しか無い。その間に、『媒介』を通してシュバルツを治さなければ、と、キョウジは思った。
「ハヤブサ。悪いけど、シュバルツの服をくつろげてくれる? 私はシュバルツの身体には、直接触る事が出来ないから」
「わ、分かった……」
キョウジの求めに応じて、ハヤブサはシュバルツのコートからベルトをはずし、ボタンをはずし、シャツのボタンをはずして行く。シュバルツの白い肌には、仙界軍の矢のせいで――――既に無数の青白いひび割れが走り、それが首のあたりまで達していた。
今にも砕け散ってしまいそうなシュバルツ。それを見たキョウジは眉をひそめ、屁舞留は息を飲んだ。その傷のせいで、意識の混濁が起きてしまっているのだろう。シュバルツと話をするのは、今は不可能そうであった。
「治せるのか?」
縋りつく様な声にキョウジが顔を上げると、ハヤブサが必死の眼差しでこちらを見つめている。無理もない。もう彼は2度――――愛おしい人を目の前で喪っているのだから。
キョウジはそんなハヤブサを安心させるように微笑むと、力強く言い切った。
「うん――――『治す』よ」
そう。
シュバルツを喪ってハヤブサが泣く―――――こんな悲劇は、もう終わりにしなければならない。例え、この命に代えても。その為に、自分はここに居るのだから。
シュバルツのエネルギーの源になっているのは、キョウジの『ココロ』
シュバルツの存続を願うキョウジの強い『意志』が、シュバルツを生かし続けていた。
だから、キョウジは確信する。
きっと、自分ならば、シュバルツを治せる。自分の生命エネルギーをシュバルツに送り込む事さえできれば、彼を助ける事が出来るのだと。
キョウジは治癒の方を続けているかぐやの横に座ると、金色に光る玉串に、そっとその手を添えた。
「手伝ってくれる?」
キョウジがそう言うと、彼女も力強くなずいた。
再び始められるかぐやの治癒の祈祷に、キョウジの『呪』が重なる。
シュバルツへの『ココロ』の回路を『開く』
壊れゆくDG細胞の動きを『閉じる』
そして、そこに自分の生命エネルギーを―――――
(……………!?)
ここでキョウジは異変に気付いた。
確かに、『媒介』に添えられている自分の手から、シュバルツに向かって『生命エネルギー』は流れ込んでいる。
だけどこのエネルギーは自分の物ではない。
これは
屁舞留の――――!
(『気』を乱すでない!! キョウジ!!)
キョウジの心を察したかのように、屁舞留から強く叫ばれた。
(絶対に、『呪』を止めるなよ、キョウジ……! 今止めたら、総てが終わりぞ―――!)
「……………!」
キョウジは叫び出しそうになる己をぐっと堪えて、また『呪』に専念しだした。しかし、心の奥底が動揺してしまうのを、止める事が出来なかった。
(屁舞留……!? どうして――――!)
『呪』を続けながら問いかけるキョウジに、屁舞留から優しい気配が帰ってきた。
(気にする事はない、キョウジ……。これは、吾が自ら望んでやっている事じゃ……)
(そんな……! 何故だ!! このままでは貴方の『生命エネルギー』の方が、先に尽きてしまう!)
貴方を犠牲にしてしまう訳には、と、キョウジは心の中で叫ぶ。しかし屁舞留は、優しく首を振った。
(確かにそうだな……。だが、これでいいのだ、キョウジ……)
(屁舞留―――! 何故――――!)
(キョウジ……。今まで黙っておって悪かったが、実は、吾の寿命も、もうそんなに長くはない)
(―――――!!)
(『気』を乱すな!! キョウジ!!)
「――――ッ!」
屁舞留に怒鳴られて、キョウジは再び『呪』に集中する。そんなキョウジに向かって、屁舞留の独白は続いた。
(地上に降りて300年。村人たちの祈りで、何とかここまで生き永らえてきたが、吾の『神気』はもう尽きかけておるのじゃ。恐らく、新しい土地に行っても、もうその土地を肥えさす事も不可能である程にな……)
(そんな………!)
息を飲むキョウジに、屁舞留の優しい気配が帰ってくる。
(だからこれが……『土地神』としての、吾の最後の『役目』じゃ。キョウジ……)
(屁舞留………!)
(村を救ってくれた恩人の『命』を、吾に助けさせてくれ)
(で、でも……屁舞留――――!)
何とか屁舞留を助けたいと願うキョウジであるが、屁舞留が『呪』を止める事を拒んだ。
(『呪』を止めるなと言うに、キョウジ……! それに、目の前に居る龍の忍者の顔を見ろ)
「…………!」
屁舞留に言われてハヤブサの顔を見て、キョウジははっと目を見張る。
ハヤブサは、大粒の涙をその瞳から零し続けていた。
だがおそらく、本人は『泣いている』と言う事にすら気づいていないのであろう。ハヤブサはその涙を拭うこともせずに、一心不乱にシュバルツを見つめていた。その傷が治っていく様を、見つめ続けていた。
(お主はあの龍の忍者を――――もう一度、絶望の底に、叩き落としたいのか?)
「―――――!」
屁舞留に痛い所を突かれて、キョウジは返す言葉を失くしてしまう。
そうなのだ。
ハヤブサは既に二度、シュバルツを目の前で喪っている。そのうちの一回は、ハヤブサ自身が『魔神』に暴走しかけていた。
それほどまでにハヤブサにとってはは、耐えられないのだ。シュバルツを失ってしまう事が。
人生のパートナーとして、彼を求め、必死に手を伸ばしてくれている。
そんなハヤブサを助けるために、自分はシュバルツを治そうと、決意したのではなかったのか。
でも、それをする事によって
屁舞留が―――――
(吾の事は、気にするなキョウジ……。もう吾は、充分生きた)
それに対して帰って来る屁舞留の声は、あくまでも優しい。
(最期に……こんな風に、お主たちの役に立てるのなら、本望じゃ……)
屁舞留――――!
(村人たちも、きっと……吾のこの行動を、許してくれるだろう………)
『呪』を続けるために、懸命に心の平静を保とうとするキョウジ。
だが、屁舞留を失う哀しみを、どうしても堪える事が出来ない。その感情の発露は、涙の形となって、キョウジの頬を伝って行く。そして、治癒の法を続けるかぐやの玉串の上に、ぽたりと落ちた。
「キョウジ様……? 大丈夫ですか……?」
「――――!」
はっと我に返ると、隣にいる巫女かぐやが、心配そうにこちらの顔を覗き込んでいた。
「大丈夫だよ」
キョウジは懸命に、笑顔で繕う。しかし、涙だけは、どうしても堪えられなかった。
また、零れ落ちて行く涙。このままではいけないと思った。
「それよりも――――早く、終わらせてしまおう」
そう言いながら、キョウジはかぐやから視線を逸らした。とにかく自分のこの哀しみを、誰にも悟られては駄目だと思った。特に、目の前にいるハヤブサには――――
もしも万が一、シュバルツを助けるために『屁舞留』と言う小さな神の命を犠牲にしている、と、この二人が知ってしまったら――――
心優しい忍者たちの事だ。
シュバルツは「そんな事はしなくていい」と拒否するだろうし、ハヤブサも、「シュバルツが死を選ぶと言うのなら――――」と、言いながら、あっさり自分の命をシュバルツと共に投げ出してしまうかもしれない。
そんな事をさせては駄目だ。
こんな悲劇的な結末を迎えるために、ハヤブサは、皆は―――――ここまで頑張ってきた訳ではないのだから。
でも………
屁舞留が―――――!
(………泣くな、キョウジ………)
シュバルツが治っていくにつれて、か細くなっていく屁舞留の気配。もう屁舞留の最期が近いのだと、キョウジは悟った。
(……キョウジ……。吾は、幸せな人生だった………。村の皆と、会えて……。お主と……出会えて……)
キョウジは、何も言葉を返す事が出来なかった。今何か言えば、間違いなく自分は叫び出してしまうと思ったからだ。
(もし………あのまま、吾はお主と出会わなければ………泣きぬれたまま、事切れていた事であろう………。それを思えば……今は本当に、幸せじゃ………)
だから…………
ありがとう…………
そして、シュバルツの身体は治った。
そして、屁舞留の気配も完全に消えてしまった。
「………出来た……」
シュバルツを助ける事が出来たのは、素直に嬉しい。だけど、喪失の哀しみに耐えられない。堪え切れぬ涙が、零れ続けた。
「キョウジ、お前………泣いているのか?」
ここでようやくハヤブサが、キョウジの涙に気が付いたらしい。キョウジは、妙に可笑しくなってしまった。全く、ハヤブサはどれだけシュバルツしか見ていなかったんだ? 私はだいぶ前から泣いていたっていうのに。
「あはは……ハヤブサだって、泣いているじゃないか」
「う……! こ、これは……!」
ハヤブサが、慌てて涙をぐしっと、拭っている。どうやら彼は本当に――――自分の涙にすら気が付いていなかったようだった。
でもハヤブサは、哀しくて泣いているのではない。嬉しくて泣いているのだ。
シュバルツを助けられた事が嬉しくて――――泣いてくれている。
(良かった……)
キョウジも少し、冷静な自分を取り戻す事が出来た。
「う…………」
シュバルツが低く呻いて身じろぎをする。どうやら、意識が戻ってきたらしい。
「シュバルツは……もう、大丈夫みたいだね」
シュバルツのそんな様子を見て、キョウジは安堵の息を吐く。今ならきっと、シュバルツにも自分を認知してもらえるだろうから、話をする事も出来るだろう。
話がしたい。
でも今は、無理だと感じる。
自分を包む祈祷の術も、かなり弱まって来ているし、何より今は――――シュバルツと向き合って、冷静に話をする自信がなかった。
辛さに負けて
哀しみに負けて
シュバルツに泣いて、縋りついてしまいそうだ。
それでは駄目だ。
そんな事をしてしまったら、シュバルツに余計な心配をかけてしまう。
だから黙って去ろうとする。そこを、ハヤブサに引きとめられた。
「ま、待て! キョウジ!」
「何? ハヤブサ」
「シュバルツと………話をしていかないのか?」
(シュバルツ……!)
話したい。
話がしたい。
でも今は。
「そうしてあげたいのは山々なんだけど……残念ながら、時間切れ、だ」
もう、切れてしまいそうな祈祷の術。別れの時が近いと感じた。
せめて、笑顔を浮かべる。
自分はうまく、笑えているだろうか――――
「ハヤブサ、シュバルツをよろしくね」
その言葉に、龍の忍者は複雑な表情を浮かべる。優しい人なのだと思った。
この人が側にいる限り、シュバルツは、大丈夫だろう。
その時、小さくキョウジ、と、自分を呼ぶ声が聞こえた。振り向くとシュバルツが、目を見開いてこちらを見ている。
「あ、シュバルツ。気がついた?」
「キョウジ………!」
それと同時に自分を包んでいた祈祷の術が切れて行く。もう本当に――――『時間切れ』らしかった。
「シュバルツ………どうか、哀しまないで……」
時間がない中、それだけは伝える。
「ま、待て……! キョウジ……!」
シュバルツが、懸命に身を起こそうとして足掻いている。でも、先程まで死にそうになっていたその身体は、すぐに思う様には動かない様だった。
どうか、泣かないで。
哀しまないで。
「私は、ずっと―――――」
「キョウジッ!!」
ずっと、貴方の傍に――――
傍に、居るよ。
その声が、シュバルツに聞こえたかどうかは分からない。
ただシュバルツは、空を切った己の手を握りしめて、己の身体を抱きかかえるように泣き始めてしまった。
「キョウジ……! キョウジ……ッ!」
そんなシュバルツの身体を、ハヤブサが優しく抱きしめていた。
「シュバルツ……!」
「ハヤブサ……」
涙にくれるシュバルツを、ハヤブサが更に強く抱きしめる。
(良かったな……)
二人の上に襲いかかっていた悲劇に、ようやく終止符が打たれたのだと悟った。
そして、自分の役目ももう終わった。
そう感じたキョウジは、少しその場から離れる事にした。
1人で歩いているキョウジに、「キョウジ!」と、明るく声をかけてくる屁舞留はもう何処にも居ない。本当に―――――自分は『独り』になってしまったのだと、キョウジは悟った。
「う…………!」
堪えに堪えていた涙が、後から後から溢れてくる。耐えられなくなってしまったキョウジは、遂にその場に崩折れて、泣き伏してしまった。
「あ………! あ………!」
何故
何故
屁舞留――――!
キョウジは何度も何度も己に問い返してしまう。
これで良かったのか。
本当に、これで良かったのか。
他に何か、方法はなかったのか――――?
シュバルツを助けられたのは嬉しい。
だけどその為に、屁舞留を犠牲にしてしまう事はなかった。
いくら屁舞留の寿命がもう尽きかけている、と言っても
シュバルツを助けるために犠牲になるのは、やはり、自分の役目だったのではと、キョウジは思うのだ。
だって、屁舞留は望まれていたではないか。
村人たちが『共に居たい』と、望んでくれていたではないか。
同じように寿命を迎え、天に召されるにしても
大好きな村人たちに囲まれて、静かに最期を迎える道も、屁舞留にはあった筈なんだ。
それなのに
どうして―――――!
そうやって、どれだけ泣いていた事だろう。
小さくうずくまって、嗚咽を漏らし続ける自分に、声をかけてくる者が居た。
「貴方が、キョウジ殿ですか?」
「―――――!」
ビクッと、キョウジが顔を上げると、1人の青年が、静かにこちらを見つめていた。
その青年は、道士風の着物を身に纏い、銀髪の長い髪をそよと風になびかせている。そして、その背後に輝く金の光背と、そこから漂う穏やかな『神気』が、キョウジにこの青年が神仙の類である事を知らしめていた。
「あ………!」
慌てて涙を拭い、立ち上がる。
「すみません……! お騒がせをしてしまったでしょうか?」
恐縮して謝るキョウジに、その神仙の者も頭を振った。
「いえ……。私も貴方を探していたのです。一言、礼を言いたくて」
「えっ……? 礼を、ですか?」
神仙界の者から「礼」を言われる覚えが全くないキョウジがきょとん、としていると、その青年はにこりと優しく微笑んだ。
「屁舞留から話を聞きました。屁舞留が、貴方に大変お世話になったようですね」
「えっ!?」
意外すぎる言葉を聞いたキョウジが驚いていると、青年の方が名乗ってきた。
「我が名は、『神農』です」
「神農――――! 貴方が……!」
キョウジは思わず息を飲む。
『神農』と言えば、屁舞留が尊敬してやまない、神仙界の者の中でも、上位の『神気』を持つ者だ。それが、どうしてわざわざここに……? それも、『屁舞留から話を聞いた』って………!?
まさか―――――
「『屁舞留』は、今、ここにいます」
そう言いながら神農は、キョウジに手を差し出してくる。その手の中には、か弱く光る、小さな玉があった。
「これは――――?」
「これが、『屁舞留』です」
「…………!」
驚き、息を飲むキョウジに、神農は優しく微笑みかけて来た。
「屁舞留は、完全に消滅してはいません。『神気』を限界まで使い果たして、このような姿になってしまいましたが――――ちゃんと、命を繋いでいます」
「屁舞留……!」
信じ難い思いで、キョウジは神農の手の中に光る、小さな玉を見る。その玉は、あの屁舞留が纏っていた光と同じ、優しく淡い色を湛えていた。
「でも屁舞留は、もうすぐ自分の寿命が尽きると言っていましたが――――」
大丈夫なのでしょうか? と、問うキョウジに、神農は少し苦笑した顔を見せる。
「そうですね……。この子は生まれてすぐに人間界に落ちてしまいましたから――――神仙としての基本的な修行も、『神気』の蓄えも出来ていないままなのです。あまりにもか細い『神気』であったが故に、見つけるのに、100年かかってしまいました」
そう言って穏やかに笑う神農に、キョウジもあんぐりと口を開けるしかない。さすが神仙。100年単位で物を考えているような節があるんじゃないかと思ってしまう。
「あの清流の中で屁舞留を見つけてからは、時々様子を見に来ていたのですが……神仙界でする修行と同じように、充実した時を屁舞留が過ごしていたので、そのまま黙って見守ることにしていたのです」
そして、200年目に村人たちにその身を拾われた時には、屁舞留にはもう立派に『神仙』としての心構えができていた。村人たちの『祈り』を糧に、屁舞留は霊体を獲得して、村の『土地神』として、成長して行く。
「ですが、戦に遭い、『神気』を注ぎ続けた村が焼かれ、人々も死に絶え――――屁舞留はそれで、かなり消耗してしまっていたのも確かです。失った『神気』を、もう一度取り戻す術を持たない屁舞留は、あのまま放っておけば、本当に消失してしまっていたことでしょう」
その時に現れた、時空や磁場を乱す妖気を纏った『妖蛇』
その力によって、再び現れた『村』
そして、迷い込んできた『人の子』
どうなる事かと静観していたが――――
「屁舞留は……立派に役目を果たしましたね。褒めてやりたい。そう思います」
「……………!」
止めた筈の涙が、また思い出したように溢れだして来てしまって、キョウジは慌てた。
「貴方にも、礼を言わねば」
神農のその言葉に、キョウジは懸命に首を振る。
「違う……! 私は何もしていません……!」
村を救うために奔走したのは、ハヤブサやシュバルツ達だ。
村人たちの生活を支えるために、畑や植物に『神気』を注いでいたのは屁舞留だ。
自分はそれらを傍観していたに過ぎないのに――――
「でも、貴方は屁舞留を支えてくれた。喜びも哀しみも、共に分かち合った」
「いいえ……! 支えられていたのは、私の方です……! いつも、屁舞留は――――」
後はキョウジは、言葉にする事が出来なかった。
どんな時でも「キョウジ、キョウジ」と、屈託なく声をかけて来てくれた屁舞留。それに、自分はどれほど支えられた事だろう。
「ですが、貴方と共に過ごした時間が、屁舞留の『土地神』としての成長を促し、貴方の祈りと村人たちの祈りが――――屁舞留の命をかろうじて未来に繋がせた。それは、紛う事無き事実です。私も、この子を完全に失わなくて良かったと―――――心から、そう思っています」
「屁舞留……」
キョウジは涙を拭いながら屁舞留を見つめる。優しく淡い屁舞留の光が、とても愛おしかった。
「屁舞留は……これからどうなるのでしょうか……?」
キョウジの問いかけに、神農は優しく笑いかける。
「屁舞留は、今完全に『神気』を失っている状態なので、神仙界でそれが回復するまで、眠りにつく事になります。また回復をすれば、霊体を取り戻す事も出来るでしょう。もしかしたら、またどこかの『土地神』として、赴く事もあるかもしれません」
「また、屁舞留に会えますか?」
その問いかけには、神農は少し考え込んだ。
「………そうですね。貴方と屁舞留と、そして運命が望めば、また、会う事も出来るかも知れません。ただ………」
「ただ……何ですか?」
小首を傾げるキョウジに、神農は少し眉をひそめた。
「ただ……屁舞留の方が、貴方の事を覚えているかどうか……。屁舞留は、ほぼ死んでいるのと同じ状態です。回復した時に、記憶の引き継ぎが行われている可能性は皆無に等しい。もしも貴方と再会しても、屁舞留はそれと気づかないかもしれません……」
神農のその言葉に、しかしキョウジは笑顔を見せた。
「それは、構いません。屁舞留がもう一度元気になって、また、どこかであんな風に、土地を、人を愛して行くのなら――――私はそれで、充分です」
キョウジの言葉を聞いて、神農も「そうですか……」と、優しい笑顔を面に浮かべた。
「さて、それでは私はそろそろ行きます。屁舞留を早く回復させてやらねば……。キョウジ殿、本当にお世話になりました」
「いいえ……。こちらこそ、本当に、ありがとうございました」
そう言ってキョウジは神農に向かって頭を下げる。
変わり物の自分を、受け止めてくれた。
シュバルツを、助けてくれた。
本当に――――屁舞留には大恩を受けたとキョウジは思う。
「では―――――」
神農はそのまま掻き消えるように、姿が見えなくなってしまった。独りになったキョウジの頬に、また、一筋の涙が伝う。
………泣くな、キョウジ………。
何処からか、屁舞留の優しい声が聞こえる。
(そう言えば、自分もシュバルツに『泣かないで、哀しまないで』と、言ったよな)
そう思い出して、キョウジは苦笑していた。屁舞留がこの言葉を言った時は、自分がシュバルツと相対した時と、同じ心境だったのだろうか。
幸せで、満ち足りていて、でも別離の哀しさに胸が締め付けられて。
だとしたら、屁舞留を心配させてはいけないから、自分は、泣きやまなければならないのに――――。
「はは……。無理だよ、屁舞留……」
後から後から溢れてくる涙。自分は、泣くこと以外に、この喪失の哀しみを癒す術を知らなかった。
(屁舞留………どこへ行っても、どうか元気で――――)
心の中で屁舞留に別れを告げながら、キョウジは独り、涙を流し続けたのだった。
「………これで、私の話は終わり、だよ……」
キョウジはそう言いながら、握っていたシュバルツの手を、そっと離す。キョウジが顔を上げると、はらはらと静かに涙を落とし続けるシュバルツの姿が、そこにあった。
「シュバルツ……」
キョウジがそっとシュバルツの頬に手を伸ばし、涙を拭うと、シュバルツもようやく、その口を開いた。
「キョウジ……ッ!」
「うん」
「ハヤブサ……! そして、屁舞留も……! 私は一体、どうすれば………!」
そう言いながらシュバルツは、己の身体をぎゅっと抱き抱えるようにして震えながら、静かに涙を落とし続けている。キョウジは優しく微笑むと、シュバルツの肩にそっと手を置いて、口を開いた。
「生きなきゃ、駄目だよ。シュバルツ」
「―――――!」
「貴方は今、ハヤブサやその仲間の人たち、そして、屁舞留に望まれて、ここにいるのだから――――」
キョウジの手が、シュバルツの髪を優しく撫でる。
必死に手を伸ばし続けてくれた、ハヤブサや皆のためにも。
限界まで『神気』を与え続けてくれた屁舞留のためにも。
「ちゃんと、生きなくちゃ」
「キョウジ……ッ!」
いろいろと溢れてくる感情に、耐えきれなくなってしまったのだろう。シュバルツの瞳から、大粒の涙が零れ始めた。
「キョウジ……ッ! キョウジ……ッ!」
縋る様に名を呼び、肩を震わせるシュバルツ。キョウジはそんなシュバルツを、優しく抱きしめた。
「キョウジ――――!」
シュバルツもキョウジを抱きしめ、そして泣き続けた。
「シュバルツ……」
キョウジもシュバルツを抱きしめながら、いつしか涙を流していた。
(ハヤブサ………そして、屁舞留………ありがとう……)
心の中で、感謝の言葉を紡ぐ。
貴方たちはシュバルツに―――――生きる『動機』をくれたんだ。
泣きじゃくるシュバルツを、キョウジは優しく抱きしめ続ける。
すると、何処からか、シュバルツを呼ぶ声が聞こえてきた。
………ルツ……! ……シュバルツ……!
「…………!」
ビク、と、顔を上げるシュバルツ。
「ハヤブサが呼んでる……」
キョウジはそう言いながら、シュバルツからそっと離れた。
「キョウジ……!」
「ハヤブサが呼んでいる……だから、貴方は行かないと」
そう言うキョウジの面には、優しい笑顔が浮かんでいた。
「ま……! 待て……! キョウジ……!」
シュバルツは思わず、キョウジに手を伸ばしてしまう。
「何? シュバルツ」
顔を上げるキョウジに、シュバルツは問いかけた。
「このまま、もう会えなくなるって事は……ないよな?」
その問いに、キョウジはふっと、相好を崩した笑顔を見せる。
「あはは……大丈夫だよ。貴方とはきっと、またこうして夢の中で会えるから……」
「会えるのか……? 本当に……?」
問いかけるシュバルツに、キョウジは笑顔を向ける。
「ああ。恐らく先程の『呪』で、貴方と私の間に通信のための『回路』が生まれている。だから、貴方が望めば―――――きっとまた、私たちはこうして、会話ができると思うよ。でも、今は―――――」
キョウジはシュバルツをまっすく見つめて、口を開いた。
「『未来』で待ってる」
「―――――!」
「はるか『未来』で―――――私は貴方を待っているから」
「キョウジ……!」
「だから行って、シュバルツ。ハヤブサの元へ――――」
「キョウジ……ッ!」
「ハヤブサに、よろしくね」
突如として辺りを、明るい光芒が包む。
待ってる、シュバルツ――――
未来で
待ってるから―――――
光芒の中、溶けるようにキョウジの姿が消えた。
そして、自分を呼ぶハヤブサの『声』が、どんどん大きくなって行って―――――
「あ………」
フッと、目を開けたシュバルツの視界に、心配そうにこちらを覗き込んでいるハヤブサの姿が飛び込んできた。
「ハヤブサ……!」
「大丈夫か? シュバルツ……」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツに手を伸ばしてくる。その手は、シュバルツの頬に触れて、そこに伝い落ちる涙を優しく拭っていた。
「………私は、どれくらい眠っていたんだ……?」
ゆるゆると意識を覚醒させながら、シュバルツが問いかける。
「半刻も経っていないぐらいだ……。だからもう少し、寝かせてやっても良かったのだが……」
申し訳なさそうに、龍の忍者は口ごもった。
「その………うなされて、泣いていたから……」
「……………」
そろり、と、シュバルツが身を起こすと、身体の中から、先程の行為の名残が流れ出て来た。
(…………!)
その独特の感触に耐えながら、シュバルツは自分が意識を失うまで、ハヤブサに嵐の様に愛された事を思い出す。その後で続けてみたキョウジとの『夢』―――――シュバルツは少し、混乱気味になっていた。
「どうした? シュバルツ……」
また、涙をはらはらと流し始めた愛おしい人の様子に、ハヤブサは少し心配になる。
「ハヤブサ……」
自分の呼び掛けに応えて、シュバルツが泣きぬれた瞳をこちらに向けて来た。素直に美しいと感じると同時に、胸が締めつけられた。
悪夢にうなされる事が多いシュバルツ。
夢の中でこのヒトを守れない自分が悔しい。
どうして――――自分はいつも、このヒトの『悲劇』の傍観者でしか無いのであろう。
それとも、先程の行為で、自分は少しこのヒトを苛めすぎたのだろうか。
「大丈夫か……? きつく抱きすぎたか……? それとも、何か悪い夢でも」
「ハヤブサ……!」
ハヤブサがその頬に触れると同時に、シュバルツがためらうことなくハヤブサの胸の中に飛び込んできたから、ハヤブサは少し驚いてしまう。
「シュバルツ……?」
ハヤブサは戸惑いながらも、シュバルツを抱きしめ返した。
「どうした……?」
「ハヤブサ……ッ!」
ギュッと、縋られるようにシュバルツが身を寄せてくるから、ハヤブサの強くない理性が傾いでいきそうになる。それをぐっと堪えてシュバルツの背を優しく撫で続けていると、シュバルツがポツリポツリと言葉を紡ぎ始めた。
「夢を……見ていた……。キョウジの………夢………」
「シュバルツ………」
(生きていた頃のキョウジとの記憶を、夢見ていたのだろうか)
ハヤブサは最初、こう思った。しかし、次に紡がれたシュバルツの言葉で、彼は衝撃を受ける事になる。
「キョウジから……『総て』を聞いた………」
「―――――!?」
「キョウジが死んでから………今に至るまでの『総て』を――――」
「な……………!」
シュバルツの言葉を『理解』して、ハヤブサは激しく動揺してしまう。
「キョウジめ……! 余計な事を………ッ!」
彼にしては珍しく、悪態を吐く言葉が出てしまう。
先程『霊体』で出て来たキョウジ。あのキョウジが、シュバルツに総てを話してしまったのか。
知らなくても良かったのに。
俺が、二度もお前を助けられなかった事実など。
知らなくても良かったのに――――!
「ハヤブサ……!」
ぽろぽろと涙を零し続ける愛おしいヒト。対して、ハヤブサの動揺は深まるばかりだ。
シュバルツを救えなかったが故の自分の苦悩。
自分の涙。
こんな事を、目の前のお人好しなこいつが知ってしまったら――――
「シュ、バル………んっ!」
愛おしいヒトから唇を求められ、それを回避する術を持たないハヤブサは、そのまま受け入れてしまう。
優しいが、熱い接吻(くちづけ)―――――
それは、涙の味がした。
「……………」
口付けを終え、そっと離れると、涙を零し続ける愛おしいヒトと視線が合う。その表情が素直に美しくて妖艶で可愛らしいから、ハヤブサは知らず、眩暈を覚えてしまう。
「ハヤブサ……!」
「シュバルツ……」
「どうすればいい……? 私はもう、お前に償っても償いきれないほどの『大恩』を―――――!」
ハヤブサは咄嗟に、シュバルツの唇に自分の指を押し当てていた。まるで、それ以上言葉を紡ぐ事は許さない、と、言わんばかりに。
「『恩』だとか『義理』だとかで……俺はお前を、自分の横に縛り付ける気はないぞ?」
(嘘だ。本当は縛り付けたいけどな! 一生でもがんじがらめに俺の隣に縛りつけたいけどな!)
ハヤブサの本心はそう主張する。
こんな、義理と人情の塊のようなお人好しなこの男を、『恩』と言う鎖で縛りつける事が出来たなら―――――それこそ一生、こいつは俺に尽くして生きてくれるだろう。浮気などもせず、真面目に従順に―――――自分が一方的に搾取する関係になることすら、許してくれる確信があった。
でも、それでは駄目なのだ。
一方が一方を搾取して、『片方だけが幸せ』なんて関係にはなりたくない。シュバルツとは『対等』でありたかった。
シュバルツにも、選ぶ権利がある。
幸せになる権利がある。
「俺は、お前とは『対等』でありたいんだ」
だから、そう告げた。
これが、自分の心からの願いだ。
『選んで』欲しかった。
俺の傍にいる事を。
そして、幸せを感じて欲しかった。
……贅沢な望みかもしれないが。
俺の傍にいる事が『苦痛』でしか無いのなら、シュバルツは逃げていいし、そうするべきだとハヤブサは思った。
「ハヤブサ……」
ハヤブサのこの言葉に、しかし愛おしいヒトはどうしたらいいのか分からず、戸惑うばかりのように見える。ハヤブサは「やれやれ」と、ため息を吐いた。
「だいたいだな……。『助けられた』とか『恩を感じる』と言った類の物は、俺の方の台詞だ。今回の事件だって、俺はいったい何回、お前に助けられたと思っているんだ?」
「―――――!」
びっくりして目を見開く愛おしいヒト。
「えっ……? 私はそんなに、お前を助けたか?」
(おいおい、こいつ本気で言っているのか?)
あまりにも素っとぼけた事を言う愛おしいヒトに、ハヤブサはもう苦笑するしかない。よく「人に施した『恩』は忘れなさい」と、言われる物だが、まさかそれを『地』でやってのけている奴が目の前にいるとは思わなかった。
ハヤブサは頬をひきつらせながらため息をつくと、目の前で指折り数えてやる事にした。
「まず時空の道で、お前は自分の身を犠牲にして、俺と左慈を助けただろう」
「…………!」
シュバルツは少し驚いてから、慌てて首を振った。
「いやあれは……! もう身体は結界の外に放り出されていた訳だし、ああした方が手っ取り早いと思ったから――――!」
しかしその言葉が終わる前に、ハヤブサはもう次の言葉を紡ぐ。
「骨折した俺の足の手当てもしてくれたし」
「け、怪我した人が目の前にいたら、手当てするのが当たり前――――」
「本当に死ぬまで、俺の事を守ってくれるし」
「う……! それは………!」
さすがにこれには、シュバルツも旨い言い訳の言葉が出て来ない様だった。言葉に詰まって四苦八苦している愛おしいヒトに、ハヤブサは更にたたみかけた。
「これ以外にも、お前に俺が助けられた事を上げて行ったらきりがないぞ? これだけの『恩』を受けているんだ。それこそ俺は、一生お前に――――」
「止めてくれ!!」
大声を上げたシュバルツに、ハヤブサもとりあえず押し黙る。震えるシュバルツを、見守ることにした。
「そんな……! 『恩』とか『義理』を感じて、私に縛り付けられるような真似をするのは止めてくれ……! そんなのはおかしい……! 不自然だ……!」
(ああ、同じ事を言っているな)
そう感じて、ハヤブサは苦笑する。
シュバルツと自分の考えは――――結局同じなんだ。
「『恩』を売るつもりなどない。私は自分のためにやっているだけだ。単に、お前を目の前で失うのが嫌だから――――」
「俺も同じだよ、シュバルツ」
「…………!」
驚いて顔を上げるシュバルツに、ハヤブサは微笑みかけた。
「俺もお前を失うのが嫌だから、動いていただけだ。俺だって、自分のために『選んで』ここにいる」
「ハヤブサ……」
「だから、『恩』とか『義理』とか、お互いに感じる必要はないって事だ。そんな事を云っていたら、本当にきりが無くなるぞ?」
「しかし……!」
まだ納得しかねているのか、反論しようとする愛おしいヒト。ハヤブサは笑いながら優しくその身体を抱き寄せると、そっと囁いた。
「お前にだって、『選ぶ』権利がある。誰の傍にいるか、誰を愛するか――――。お前が俺よりも愛する人が他に出来て、その人の傍にいたいと願うなら―――――お前は、いつでもそちらに行って構わないんだ」
「な…………!」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツはさも心外だと言う顔をする。
「そんな事は絶対にしない! 私がお前より愛する人間なんて――――!」
「絶対だな?」
「―――――!」
ハヤブサに念を押されるように問われて、シュバルツははっと我に帰った。自分が思わず口走ってしまった内容が、割ととんでもなかった事に気がついて、シュバルツは慌ててしまう。しかし、もう遅い。目の前では龍の忍者が、「我が意を得たり」と言わんばかりの満面の笑みを、その面に浮かべていた。
「つまり、そう言う事だ」
「あ…………!」
「俺も、お前と同じように思っている……。愛するヒトは、お前以外に居ないと」
「ハヤブサ……!」
涙で潤んだ瞳で見つめてくるシュバルツに、愛しさが溢れる。身体をさらに密着させて、想いを込めて唇を重ねた。
「ん…………!」
瞬間強張ったシュバルツであるが、すぐにその身体から力が抜けて行く。優しく受け入れてくれているのが分かる。至福の一時――――ハヤブサは思わず、泣きそうになってしまった。
「……………」
優しい口付けを終え、そっと離れる。
一糸纏わぬ姿で、潤んだ瞳でこちらを見つめているシュバルツ。酷く美しくて、そして何処までも妖艶だった。素直に『押し倒したい』と、願う。
しかし―――――
「……………」
シュバルツの身体のあちこちに残る痣に、ハヤブサは眉をひそめる。
つい半刻ほど前までその身体を乱暴に穿ち、抱き潰す覚悟で抱いた。その名残が、彼の身体のあちこちに、まだ残っている。人より回復の早いシュバルツの身体であるが、それが追いついていない程のダメージを受けたと言う事になる。そんな彼を、今、これ以上抱くのは憚られた。
「夢の中で、キョウジは何と言っていたんだ?」
だからハヤブサは、敢えてキョウジに話題を振る。
ハヤブサにとってのキョウジは、敬愛すると同時に、自身に強く『理性』を手繰り寄せてくれる存在であった。それは、シュバルツにとっても同じなのだろう。彼の瞳にも、理知の光が宿っていた。
「キョウジは……『未来で待っている』と――――」
「…………!」
「『はるか未来で待つ』と………そう、言っていた………」
(キョウジ……!)
キョウジのその言葉で、ハヤブサは確信する。
やはり――――取り戻す事が出来るのだ。キョウジの失われた時間を。
あの『妖蛇』さえ、倒せさえすれば―――――!
「間違いなくキョウジは、そう言ったんだな?」
問いかけるハヤブサにシュバルツは頷く。
「そうか………」
ハヤブサはにこりと微笑むと、シュバルツの手を力強く握った。
「ならば行こう、シュバルツ。キョウジの未来を取り戻すために――――」
「ハヤブサ………」
「あの『妖蛇』さえ倒せれば、自分も助かる。キョウジは、そう言っているのだろう?」
「―――――!」
夢の中でキョウジが言っていた言葉と同じ言葉をハヤブサに言われて、シュバルツははっとする。
本当だ――――
本当にハヤブサは、全然あきらめてなどいなかった。
自分に次いで、キョウジも取り戻そうと、懸命に戦い続けてくれていたのだ。
「ならば、俺たちはもう、立ち止まっている暇はない。妖蛇を倒すために、進み続けなければ」
立ち上がったハヤブサは、シュバルツに向かって手を差し伸べた。
「シュバルツ、手伝ってくれるか?」
「勿論、ハヤブサ。喜んで――――」
そう言って自分の手を取ってくれたシュバルツに、ハヤブサも笑顔を見せる。
「なら、身体を洗って、服を着なければな。劉備殿の城に寄って、討伐軍に合流しないと」
「そうだな」
シュバルツはそう頷いてから、辺りをきょろきょろと見回す。どうやら、何かを探しているようであった。
「どうした? シュバルツ」
それに気が付いたハヤブサがシュバルツに声をかけると、「ああ、ちょっと……」と、返事をしたシュバルツが、目的の物を見つけたのか、身を屈めて、それを拾い上げた。
「『形代の石』か?」
シュバルツの手の中にあるそれを見たハヤブサが問いかけると、シュバルツも頷く。
「ああ……。これを、村人たちに返さなければ――――」
「確かにそうだな」
そう返事をするハヤブサに、シュバルツは頷くと、その石を胸の前で、ギュッと包み込むように握り込んでいた。
(ありがとう、屁舞留……! 貴方がくれたこの『命』を、私は絶対に、無駄になどしない)
忍者たちは身支度を整え、そして立ち上がる。
「じゃあ、行こう。シュバルツ」
ハヤブサに続いて、シュバルツも歩き出す。
自分の目の前を歩く、龍の忍者。
シュバルツはその後ろ姿を見つめながら、自分はこれから先も、この目の前の男を勝手に愛し続けてしまうのだろうな、と、感じていた。
例え、ハヤブサの気持ちが自分から離れて行ったとしても。
彼が死んでしまったとしても――――
想い続けてしまう事を、どうか許して欲しいと願った。
それだけの物を、もう自分はハヤブサから受け取ってしまったのだから。
ただ、自分は『人外』なのだから、その辺りはわきまえて――――
「シュバルツ」
いきなりハヤブサに声を掛けられて、シュバルツははっと、我に返る。
「な、何だ?」
「少し、気になった事を聞いても良いか?」
「? あ、ああ。いいぞ?」
小首をかしげながらもシュバルツは頷く。
「その『形代の石』の事なのだが――――」
ハヤブサは少し躊躇ってから、シュバルツに問いかけて来た。
「長老に預けた時は、そんな風に割れてはいなかったよな……。なのに、割れていた石。そして、左慈が言っていた『感じられなくなった波動』………。もしかして、お前が助かった事と、その石の間に、何か因果関係があったりする、のか?」
「―――――!」
シュバルツは一瞬その表情を強張らせたが、やがて覚悟を決めたかのように、その面に穏やかな、だが少し憂いを帯びた笑みを浮かべた。
「ああ……。この『土地神』が、自分を犠牲にして、私を助けてくれたんだ……」
「な―――――!」
予想外のシュバルツの言葉に、ハヤブサは衝撃を受けてしまう。いろいろな想いが自身の中で渦を巻くが、とりあえず一番率直に思った事が、口からポロっと出てしまっていた。
「『土地神』………本当に『居た』のか……?」
居てもいなくても、偶像を信仰の対象として祀りあげる。
八百万の神の信仰がある日本ではよくある話なので、ハヤブサは土地神の存在自体も、正直信じてはいなかった。だが、シュバルツのその言葉には、流石に動揺が隠せなかった。
「ああ……。可愛らしい、子供の様な容姿をしていた神様だったよ。キョウジがずっと、その神様の傍についていた様なんだ……」
「…………!」
「その神様と共に、キョウジは私たちの戦いを、ずっと見守ってくれていたんだ……。そして、三度目の戦いで私が死にかけたあの時に――――」
ハヤブサはシュバルツのその言葉で、いろいろと察してしまう。
本来ならば死にゆく筈だったシュバルツの運命を覆す。
天地の理をひっくり返す『奇跡』の代償として、その土地神は
自分の『命』を差し出したのだと――――
それ故にキョウジは、あの時涙を流していた。
惜別の涙を。哀しみの涙を。
何てことだ。
自分はそんなキョウジの心情を気づきもせずに――――!
そう思いながらハヤブサがふと顔を上げると、石をじっと見つめているシュバルツの瞳からもまた、涙が零れ落ちていた。
自分が助けられた事に、こんな犠牲が伴ってしまった事実――――まだ彼の中で整理し切れていないのだろう。
「ハヤブサ……。私は本当に、どうしたらいいんだろうな……。この土地神に対しても、村人たちに対しても―――――」
その言葉が終わらぬうちに、ハヤブサに抱きしめられたから、シュバルツは驚いてしまう。
「ハ……ハヤブサ……?」
「シュバルツ……」
ハヤブサは更に強くシュバルツを抱きしめると、言葉を紡いだ。
「劉備殿の城に寄る前に、あの村の社へ行こう」
「――――!」
「そして俺に、侘びを言わせてくれ……! 正直俺は、土地神の存在事態あまり信じていなかった。それどころか、少し悪いイメージすらあった。それをまず詫びたい」
「ハヤブサ……」
ハヤブサの告白を聞きながら、それは無理もない事だろうなと、シュバルツは思った。
ハヤブサは、神をも滅する龍の忍者。幾度も『神』と呼ばれる存在の者たちと戦ってきたであろうハヤブサであるが故に、『神』と言う存在と言葉に良いイメージが持てなかったとしても、それは仕方のない事だと思うのだ。
「そして、礼を……! どんな形であれ、お前が助かってくれた事は、俺にとっては何者にも代えがたくて、幸せな事なんだ……! お前を、失わなくて良かった。本当に、心からそう思っているから……!」
俺の大事なヒトを助けてくれて、ありがとう。
そう礼を言いたいと、ハヤブサは言った。
「大切にする……! シュバルツ……!」
「ハヤブサ……」
「俺は命ある限り……助かってくれたお前の『命』を、大切にするから……」
「…………!」
だから、礼を言いに行こう。
そう言うハヤブサに、シュバルツも一も二もなく頷いていた。
ふと、そんなシュバルツの耳元を、優しい風が撫でる。
―――生きなきゃ駄目だよ、シュバルツ。
風の中、優しい声が、シュバルツの耳に確かに届いた。
『命』を繋いでくれた屁舞留のためにも
貴方は、ちゃんと生きなくちゃ
(キョウジ……!)
光の中、微笑んでいるキョウジの姿が、見えた様な気がした―――――。
それから人間たちと神仙たちは、その力を結集して、ついに妖蛇と対抗し得る力を得た。
そして、総力戦の末に、ついに人間と神仙の連合軍は、妖蛇『遠呂智』を討滅した。
だが、遠呂智によって作られたこの世界は、その存在が滅んだが故に、消滅の一途をたどっていく事になる。地面がひび割れ、空が崩れ落ち始めた。
このまま皆――――時空の狭間に消滅するしか道がないのかと思われた瞬間、神仙たちが動いた。
「このまま、この者たちが消滅に巻き込まれるのは惜しい」
伏犠の言葉に、女媧も頷く。
「そうだ。我らにも、まだ出来る事がある筈だ」
「世界にほころびが生じた今ならば――――」
かぐやの言葉に太公望も続く。
「皆をそれぞれ、元居た場所に戻す事が出来る。そうだな? 素戔鳴」
その言葉に、素戔鳴は頷いた。
素戔鳴はその後の戦いの中で、次第に人の子たちの力を認めるようになり、ついにはその戦いに助力するようになっていく。
今ここにこの素戔鳴がいなければ、とても滅びゆく世界からすべての人の子たちを、元の世界に戻すことは不可能であっただろう。あの時、素戔鳴を斬る事を踏みとどまったハヤブサの判断が、ここに生きた。
「では、皆さま方――――『術』の用意を―――――」
そう言うかぐやの元に、走り寄って来る人間たちが居た。
ハヤブサとシュバルツである。
「かぐや、頼みがある」
龍の忍者はかぐやの傍に走り寄ると、おもむろに口を開いた。
「何でしょう? ハヤブサ様」
たおやかに問い返してくる仙女を、ハヤブサはまっすぐ見つめ返す。
「俺たちが、どうしても帰りたい時間軸があるのだが」
その言葉に、神仙たちは頷いた。
「諾」
「よかろう! きっちりと送ってやるぞ!」
「気をつけてな。縁があれば、どこかで会う事もあろう」
「全知全能の私がサポートするのだ。大船に乗った気でいろ」
「感謝する」
ハヤブサが短く謝意を述べて頭を下げ、踵を返そうとする。そこに、素戔鳴の声が追いかけて来た。
「シュバルツ。吾は汝に、一つだけ言い置いておく」
「―――――!」
ハヤブサが咄嗟に、シュバルツを守ろうとする。だがシュバルツはそれを手で制して、素戔鳴の前に進み出た。
「何だ?」
あくまでもまっすぐこちらを見つめてくるシュバルツの視線。それを見た素戔鳴の瞳に、一瞬穏やかな色が宿る。だが彼は、すぐに『仁王』の顔を作った。
「絶対に――――悪には堕ちるな!」
「…………!」
はっと息を飲むシュバルツに、素戔鳴は更に言葉を続けた。
「もしも汝が悪に落ちなば―――――吾は瞬時に駆けつけ、それを滅するであろう」
かなりきつい言葉ではあるが、シュバルツは素直に頷いた。
「ああ。肝に銘じる」
それに素戔鳴が頷いたのを見て、シュバルツは踵を返した。そして、ハヤブサもそれに続く。
「やれやれ。素直に『頑張れ』と激励してやればいいものを……」
ぼそりと呟いた伏犠の言葉を、素戔鳴が聞き咎めた。
「……! 何か言ったか?」
じろりと素戔鳴に睨まれて、伏犠は素っとぼける。
「いやぁ、別に……」
「――――フン」
その神仙二人のやり取りを、太公望も苦笑しながら見つめていた。
「さあ、皆さま―――――」
崩れゆく世界の中、かぐやのたおやかな声が響く。
「どうか、心に強く思い浮かべられませ。貴方が『帰りたい』と思う場所を。帰るべき世界を――――」
神仙たちの繋いだ手の間から、眩いばかりの光芒が溢れだす。
その光の中、ハヤブサはシュバルツに呼びかけた。
「シュバルツ」
「ハヤブサ――――」
穏やかに微笑む、愛おしいヒト。
その中にある願いが、自分と同じものなのだと言う事を、ハヤブサは改めて確認した。
「未来へ」
ハヤブサの伸ばしてきた手を、シュバルツが掴む。
「ああ。未来へ」
未来で 会おう
光の中、そう約束した忍者たちの手が、離れて行った―――――
最終章
「―――――!」
光に包まれたハヤブサが次に我に帰った時、自分は、某国の土産物屋の前に居た。
懐に忍ばせていた懐中時計で、日付と時間を確認する。それは自分が間違いなく『帰りたい』と願っていた日付と時間を指していた。
目の前には変わった形のアクセサリーがあり、店主がそのアクセサリーの由来について、熱心に説明してくれている最中だった。
そうだ。
今、この話を切り上げて空港に走れば、一本早い飛行機に乗れる。
ここで自分は迷っていた。
シュバルツと会う約束をしているのは明後日。早く日本に帰って里に報告に行った所で、その後、己を持て余してしまう事は目に見えている。それなら少しこちらでゆっくり土産でも探索して――――と、あの時の自分は思っていた。
だが。
(キョウジ――――!)
迷っている暇はないと感じる。
妖蛇を討滅した今――――キョウジを『死』の運命に向かわせる物は、もうないと信じたい。だがもし、あのシュバルツの時みたいに、理不尽な『死』の運命が、キョウジにとり憑いていたとしたら。
行かなければ。
強くそう感じたハヤブサは、空港に走る事を選択していた。
「店主、興味深い話をありがとう。これは、礼だ」
ピン! と、コインを店主に向かって放り投げて、龍の忍者はその場から消える。
「あ、ああ……毎度~!」
土産物が売れるよりも多くのチップを、その店主は手に入れていた。
空港に走り込み、搭乗手続きを済ませる。何とか、一本早い飛行機の席を取る事に成功した。案内に従って飛行機に乗り込み、焦る気持ちを抑えつけてシートに身を沈める。時計を見つめ、到着予定時刻を見て、頷く。このまま順調にいけば――――間違いなくキョウジが死ぬ『あの時間』より先に、キョウジのアパートに辿り着ける筈だ。
(だが……もしも万が一、何も起こらなかったら……?)
龍の忍者の脳裏に、ふとそんな考えが頭をよぎる。
もし自分がキョウジのアパートに走って行っても何も起こらなかったらどうなるだろう。
その場合、逢瀬の約束を破って、勝手にシュバルツに会いに行ってしまう事になるのだから、もしもシュバルツの方に時を越えた記憶がない場合、それこそ烈火のごとく詰られてしまうだろう。最悪、1カ月ぐらい会ってくれなくなってしまうかもしれない。
(……………!)
かなりきついが、それでもいいとハヤブサは思った。
考えてもみろ。
キョウジを失って正気を失くしてしまうほど憔悴してしまうシュバルツを見るよりも
自分が詰られたり罵られたりけなされたりする方が――――何百倍もましじゃないか。
良いんだ。
シュバルツとキョウジが幸せなら――――俺は、どうなっても。
そう言いながらも、龍の忍者はシートの上で膝を抱え込んでしまっている。
泣きたくもないのに、涙まで出て来た。
やはり、シュバルツやキョウジが居る心の奥深いこの場所は――――どう足掻いても、自分でも鍛えようがない、どうしようもない所なのだと知る。
それでも、この苦しみすら愛おしいとハヤブサは感じていた。
傍にいたい。
守り抜きたい。
愛し抜きたい。
そう思える存在があると言う事は、何と幸せな事なのだろう。
(『あの時間』を、キョウジが無事越えられるかどうか、確認をするだけだ……! それさえできれば俺は………!)
その後ならば、シュバルツからどう詰られても構わない。
言われるままに、すごすごと里に帰ろう。
ハヤブサはそう決意を固めて、『仕事』で疲れた体を休ませる事にした。日本で何が起きても良い様に、備えるために。
成田空港につき、電車の切符を買う。
もちろん行き先は、キョウジのアパートだ。
一本早い飛行機に乗れたおかげで、時間的にだいぶ余裕がある。このまま順調に電車を乗り継ぐ事が出来れば、『あの時間』には問題なく間に合うように思われた。
里への『任務完了』の報告は、申し訳ないけれど後回しだ。
報酬を受け取る事など多少遅くなっても構わない。
よくよく考えてみれば、仕事に終わった後にシュバルツに会える事ほど自分にとって喜ばしい報酬は他にないんだ。
笑顔が見られればいい。
でも、自分はシュバルツとの『約束』を破っている。だからそれは、望むべくもないだろう。
良いんだ。
せめて、二人の無事が確認できれば――――。
(………そう言えば『あの時』も、二人の無事を祈って、走っていたっけな……)
電車の中で、龍の忍者はふと、今はもう遠い記憶となった妖蛇出現の瞬間を思い出していた。飛び交う怒号と悲鳴の中、自分を導く様に飛んでいた隼に向かって、懸命に走っていた自分。あの時は本当に、心配で胸が押し潰されそうだった。
そうだ。
『あの時』も、こんな風に電車に乗っていて、それで『妖蛇の首』を――――
その時いきなり電車が、ガクン、と止まった。
「――――!?」
咄嗟にあの時と同じように窓の外を見るハヤブサ。しかし、窓の外にはいつも通りの日常的な街の風景が写し出されるだけであった。
「な、何だ?」
「変ねぇ……。こんな所で止まるなんて……」
それでも、いつもと違う電車の動きに、乗客たちも戸惑い気味になる。やがて、社内に、車掌の穏やかな声が響き渡った。
「申し訳ございません。ただ今信号機の故障により、電車を停止させております。復旧まで少々時間がかかります。今しばらく、お待ちください――――」
何の変哲もない電車のちょっとした『事故』
だがハヤブサは(来た………!)と、思った。
ここだ。
ここでもう動きださなければ、キョウジの『あの時間』には間に合わない。
これは、確信だ。
行かねば。
龍の忍者はおもむろに立ち上がると、車掌を探した。その姿を見つけると、切符を渡しながらこう言った。
「世話になった。済まないが、不足分の代金は、『隼の里』に請求してくれ」
「えっ!? お客さん!? あの、ちょっと……!」
戸惑う車掌が止める間もあればこそ。
龍の忍者は黒装束に身を包むと、窓を破壊してあっという間に電車の外へと飛び出して行ってしまった。
「あの……! ちょっと……! お客さ~~~~~ん!?」
後には間抜けに叫ぶ車掌と、周りの人たちの「忍者だ」「ニンジャ」「OH !! Japanize NINJA !!」と囁く乗客の声でその空間は溢れかえっていた。
キョウジのアパートに向かってひた走るハヤブサ。
しかし、周りに起こる「異常事態」に、少し辟易気味になっていた。
(くそっ! 何なんだ!? これは……!)
心の中で毒づいて、そう舌打ちをする。
街の景色は、まるで平和そのものだ。
しかし龍の忍者はここに至るまでに既に――――飛び降り自殺を3回、交通事故を5回、落下事故を2回、惨事に至る前に助けていた。日常生活の中でままある風景なのかもしれないが、それにしたって、目の前で起こる頻度が高すぎる。つい、咄嗟に助けてしまうがまるで、こちらが進むのを拒むかのように次から次へと起こって来る目の前の事象に、苛立ちが募るのを押さえる事が出来ない。
(………抑えろ……! こういう時こそ、冷静に………!)
焦りそうになる自分を、龍の忍者は強く叱咤した。
まるで、こちらを試しているかのように起きる事象の数々。
気にしすぎかもしれないが、これが、もし、『運命の女神』からの挑戦状だったら。
キョウジの命を救うために、必要な試練なのだとしたら。
そう思うとぞっとする。どれ一つとしておろそかにする訳にも行かないし、見捨てるわけにもいかない。
今ここに、時間を巻き戻せる巫女かぐやは居ないのだ。正真正銘の一発勝負。なればこそ、失敗する訳にはいかないと、ハヤブサは強く自分に言い聞かせていた。
道路に飛び出したベビーカーを、車に撥ねられる直前に救いだす。
「あ、あの、ありがとうございました……!」
震えながら紡がれる母親の礼の言葉を最後まで聞かずに、ハヤブサはその場から立ち去っていた。時間がない。急いでいる。もしかしたら忍者としては悪目立ちし過ぎているかもしれないが、とにかく放っておいて欲しかった。
自分が目指すのはキョウジのアパート。
確認したいのはキョウジの無事。
それ以外は自分にとって頓着すべき事ではないのだ。
刻一刻と進む時計。
壁を走り、屋根を走り、時に人助けをしながらハヤブサは進み続ける。
角を曲がる。
キョウジのアパートを、その視界に捉えた。
後少し。
ここでいきなり、ハヤブサの目の前で、水柱が勢いよく上がる。
「―――――!?」
どうやら地下の、水道管が破裂したようだった。
それに驚いたドライバーが運転を誤ったのか、制御を失った車がギャギャギャギャッ!! と、派手な音を立てて歩道に突っ込んで行く。
「くっ!!」
龍の忍者はその恐るべき動体視力と判断能力で、車の進路に居た老婆と子どもを抱きかかえて飛ぶ。二人を安全な場所に下ろすと同時に、制動を失った車に向かってハヤブサは飛んだ。その車は電柱にぶつかり、派手にスピンをしながら交差点に向かって突っ込んで行っていたからだ。そこに、大量の鉄骨を積んだ大型トラックが向かってくる。
(いかん――――!!)
双方を安全に助けることは無理、と、判断したハヤブサは、スピンする自動車とトラックの間にその身を置いた。スピンする車をドンッ!! と乱暴に蹴り飛ばして、その方向を変える。それと同時に突っ込んでくる大型トラック。それに撥ね飛ばされる直前、龍の忍者の身体は空にふわりと舞った。トラックにぶつかる、本当にぎりぎりのところを、彼はトンボを切ってかわす。
しかし、トラックのドライバーも、目の前の事象に驚いてしまったのだろう。突っ込んできたトラックも、そのバランスを失って横転していた。しかもあろうことか荷台のひもが切れて、鉄骨が派手な音を立てて四散する。
「―――――ッ!!」
龍の忍者は飛ぶ鉄骨の方向を見て、咄嗟に触れたり弾いたりして、その方向を微妙に変える。しかし、ハヤブサが弾き損ねた一本の鉄骨が、派手な音を立ててキョウジのアパートの窓に突き刺さってしまった。
「キョウジッ!!」
龍の忍者は大声で叫びながら、キョウジのアパートに走り込んでいった――――
ハヤブサは蹴破る様に玄関のドアを開け放つ。
「キョウジ!! 無事か!?」
大声で叫びながら、ドカドカと中に入って行った。靴を脱ぐべきかと一瞬迷ったが、鉄骨が飛び込んだ部屋の中はきっと、壁やらガラスやらの破片で大変な事になっているだろう。靴を脱ぐほうがかえって危ないと判断したハヤブサは、そのまま鉄骨が飛び込んだ部屋を目指す。
呼びかけても返事がないのが気がかりだった。
無事でいてくれ、キョウジ。
「キョウジ!!」
ハヤブサは問題の部屋のドアを勢いよく開け放って―――――
「……………!」
一瞬絶句した後、やれやれ、と、肩を落として小さなため息を吐いた。
目の前で座り込んでいたキョウジが振り返ってハヤブサの姿を認めると――――少し縋る様にハヤブサに声をかけて来た。
「あ……! ハヤブサ……!」
「キョウジ……! 無事だったか……」
「あ、ああ……。私は、無事だったんだけど――――」
顔面蒼白になっているキョウジが、ゆっくりと鉄骨の方に振り向く。鉄骨の下にシュバルツの身体があり、その首から上が無くなっていた。おそらくキョウジを飛んできた鉄骨から庇って――――その様な状態になってしまったのだろう。
「シュバルツ……! シュバルツが……!」
シュバルツを見つめながら茫然と呟くキョウジの背中越しに、ハヤブサは壁にかかっている時計を見る。その時計は、10時31分を指していた。それから更に、カチッ、カチッ、と、1秒ごとに秒針が進んで行く。
キョウジを失った10時26分は、とうに過ぎ去っていた。
キョウジの止まってしまった『時間』を、取り戻す事が出来たのだと―――――龍の忍者はようやく悟った。
「シュバルツ……!」
懸命にシュバルツに呼びかけているキョウジを見ながら、ハヤブサはもう一度、フッと小さなため息を吐く。
「キョウジ……シュバルツは、治せるのだろう?」
「ああ……。だけど――――」
何か言おうとしたキョウジを、ハヤブサは押しとどめた。
「済まないがキョウジ……おそらく、もうすぐここに警察が来る。だからその前に――――シュバルツの身体や部品だけを、片づけておいた方がいい」
「―――――!」
ハヤブサのその言葉に、キョウジもようやく我に帰ったようだ。
「わ……分かった……」
「立てるか?」
「うん。ありがとう」
ハヤブサが差し出した手を取り、キョウジはすっと立ち上がる。
「キョウジ、シュバルツの部品を集めてくれ」
ハヤブサの言葉に、キョウジが「わ、分かった……」と、パタパタと歩き出す。それを見ながらハヤブサは、シュバルツの上に乗っている鉄骨を除けようとする。すると、鉄骨の下で、首の無いシュバルツの身体が、ぐ、ぐ、と、立ち上がろうとしているのが見えた。それを見たハヤブサは、思わず苦笑してしまう。
「いいから死んだふりをしていろ。身体くらい、俺が運んでやるから」
その言葉を聞いたシュバルツの身体が、べシャッと潰れるように倒れる。この状態で起き上がろうとする事は、いくらシュバルツでも相当きつい様だった。
(それにしてもあの状態で動くって事は、やっぱり『生きている』ことになるんだよな……。だがあいつは一体どこで音を聞いて、どうやって身体に指令を出しているんだ?)
そんな事を考えながらシュバルツの身体を鉄骨の下から引っ張り出す。抱きかかえてやると、その身体から耳慣れた駆動音がした。
(ああ、生きている)
その音を聞いたハヤブサは、酷く安心する自分を覚える。
首の無い身体。
だけど、それは死体じゃない。ちゃんと、生きていると分かる。
不老不死の、俺の恋人。
とても――――愛おしかった。
「ハヤブサ、これで全部だよ」
キョウジの声を掛けられて、ハヤブサははっと我に帰る。顔を上げると、段ボールの中に部品の様な物を詰め込んで抱きかかえているキョウジの姿があった。
「やはり、地下に行くのか?」
ハヤブサの問いにキョウジは頷く。そのまま二人は、地下の研究室へと降りて行った。
研究室の寝台の上に『シュバルツ』を寝かしつける。よく見ると、首以外にも、あちこちに深い傷を負っていた。それがハヤブサに、鉄骨とぶつかった時の衝撃の凄まじさを伝えてくる。
(……もう少し、注意して対処してやればよかった……。何故あの一本だけ、弾く事が出来なかったのか……)
そう感じてほぞをかむ。己の未熟が悔しかった。
「大丈夫だよ。ちゃんと、治せるから……」
「――――!」
優しく声を掛けられて、ハヤブサははっと我に帰る。振り返ると、優しく微笑んでいるキョウジの姿がここにあった。
「キョウジ……」
笑顔のキョウジ。
だけど、注意しなければならないとハヤブサは思う。
この目の前の男は、本当にきつい時程―――こちらを安心させようとして、優しく笑ってしまう事を、自分はもう、知ってしまっているのだから。
だけど、今は。
「キョウジ……シュバルツを治してやってくれ」
そう言いながら龍の忍者は立ち上がる。
「それは勿論。でも、ハヤブサは………」
これからどうするんだと問われる前に、ハヤブサは口を開いた。
「『後始末』は引き受けた」
それだけを言い置くと、龍の忍者は地下室から出て行った。
それから数分も経たないうちに、『事故』が起こった現場の交差点には、救急車やらパトカーやらが駈けつけてくる。周りにも野次馬やマスコミが集まりだして、近辺は、あっという間に人だかりの山が出来上がってしまっていた。そしてそれは、当然鉄骨の刺さったキョウジのアパートにも押し寄せて来て。
「大丈夫ですか!?」
救急隊員と警察官が、キョウジの部屋に走り込んでくる。するとそこには
「あ……! はい……。私は、大丈夫です……」
と、少しびっくりしていると言った按配で座り込んでいる『キョウジ・カッシュ』の姿があったのだった。
それから数刻して、キョウジの家の地下室に、「兄さん!!」と、叫びながら彼の弟であるドモン・カッシュが走り込んでくる。
「ド、ドモン!?」
驚くキョウジの姿を見て、ドモンはようやく人心地がついたのか、ホッとその胸を撫で下ろしていた。
「良かった……! 兄さん、無事だったんだね!」
「あ、ああ。シュバルツやハヤブサが、私を助けてくれたからな……。それにしてもドモン、お前、どうしてここに?」
「どうしたもこうしたもないよ! 兄さん!! 昼食時にテレビを見ていたら、いきなり鉄骨の刺さったこのアパートが映し出されたから――――!」
取る物もとりあえず、キョウジのアパートに走ろうと思い立った矢先に、いきなり懐の携帯電話が鳴る。慌てて出ると、それはキョウジが『入院した』と言う病院からだった。
「それで、慌てて病院に走ってみると、そこには兄さんに変装したハヤブサの奴が居て、本物の兄さんはこっちにいるって教えてくれたから……」
「そうか………」
ドモンの話を聞きながら、キョウジは「後始末は引き受けた」と、言いながら部屋から出て行った龍の忍者の後ろ姿を思い出していた。つまり彼は、事故後に起こるごたごたの後始末を、一手に引き受けてくれていたのだ。自分の代わりとなって―――
(結局私は、またこの二人に助けられた事になるのだな……。どうして二人とも、いつもいつも、私の事を――――)
そう思いながら、キョウジはシュバルツの身体を見る。千切れてしまった彼の首は、もうほとんどくっつきかけていた。
(シュバルツ……。シュバルツはもしかして、こうなる事を知っていたのだろうか……? だから、朝からあんなに……)
実は今日はキョウジにしては珍しく、朝から機嫌が悪かった。
何がどうという訳でもない。何が悪いと言う訳でもなかった。
ただ――――虫の居所が悪いとしか言いようのない、訳の分からないイラつきに、朝から取りつかれていた。
これではいかん、と、何度も気分転換を試みてみるのだが、何をやってもうまくいかない。あきらめてデスクに座って、書きかけの論文に取り掛かってみたりもするのだが、一向に筆も進まない。
そして、この訳の分からないイラつきは、当然の如く傍にいるシュバルツに、『八つ当たり』と言う形になって現れていた。
「シュバルツ」
「どうした? キョウジ」
「気が散るんだ。悪いけど、少し離れていてくれないかな」
キョウジがこう言えば、シュバルツはたいてい大人しく傍を離れる。なのに今日に限って、なかなか彼が離れようとしなかったから、キョウジのイラつきは、さらに悪化してしまう。
「シュバルツ」
「ん?」
「私は『離れてくれ』と、言ったよな? なのに、どうして言う事を聞いてくれないんだ?」
「キョウジ……!」
何故か哀しげな眼差しをシュバルツから向けられるから、キョウジは少し戸惑ってしまう。
「済まない、キョウジ……! 後少しの間だけでいいんだ。ここに居させてくれないか?」
「駄目だ!!」
シュバルツの哀願に近い訴えを、キョウジは言下に退ける。
「私は今、1人になりたいんだ! 悪いんだけど、出て行ってくれ!」
「キョウジ……!」
「それとも何か? どうしても、私の傍にいなければならない、用事でもあるのか?」
「い、いや……そう言う訳でもないが……」
何故か、歯切れの悪い物言いをするシュバルツ。その態度に、キョウジの苛立ちは、ますます煽られてしまう。
「じゃあ、出て行ってくれ!!」
強く言い放って、部屋のドアを指す。
「…………!」
キョウジをしばらく茫然と見つめていたシュバルツであったが、やがて観念したのか、やっと頷いた。
「分かった………」
そう言ってシュバルツは、静かに部屋を出て行く。キョウジはやれやれとため息を吐いた。
自身の中の苛立ちを何とか宥めながら、デスクに座り直す。
もう一度、論文の続きを書き始めようとして―――――すぐに、そのペンが止まることになった。『ある気配』に、彼が気がついてしまったからだ。
「………シュバルツ」
キョウジが足元の『影』に向かって呼びかける。すると、「何で分かった!?」と、言いながら、シュバルツが足元の影から『生えて』来た。
「分からいでか!!」
キョウジは知らず、怒鳴り散らしてしまう。
「言っただろう!! 私にはお前の気配が分かってしまうんだと!! お前がどんなに気配を消しても、見つけ出す自信が私にはあるぞ!?」
「し……しかし、キョウジ……!」
だがキョウジに怒鳴られながらも、シュバルツも後には引かない。
「済まない……! 後少しの間だけでいいんだ……! 傍に居させてくれ……! 気配も消すし、お前の邪魔はしないから――――」
「『気配が分かる』と何度も言っているだろう!? お前の気配を感じるだけで、今は邪魔に感じてしまうんだ!!」
「キョウジ……!」
「お願いだ、シュバルツ。少しの間でいい。1人にしてくれ……! 私だってこれ以上、お前に八つ当たりなんかしたくない……」
「……………」
黙り込むシュバルツ。
かなりめちゃくちゃだが、ちゃんと筋は通して願い事をした。これで、聞いてくれないシュバルツではない筈だ――――と、キョウジは思っていた。
しかし、シュバルツはそこから動こうとしない。それどころか、さっきから何度も壁の方にちらちらと視線を走らせている。どうやら彼は、壁にかかっている時計を気にしているようであった。
「どうした? シュバルツ」
「な、何だ?」
「さっきから時計をちらちら見ているけど……何か、問題でもあるのか?」
「いや……」
また、茶を濁すような反応。キョウジの苛立ちが、さらに煽られてしまう。
「シュバルツ、いい加減に――――」
その瞬間、外でドンッ!! と言う大きな音がする。
「――――!」
素早く窓から外を確認したシュバルツが、「キョウジ!!」と、自分に覆いかぶさって来て――――
派手な轟音と共に、何かが破壊される音が、部屋中に響き渡る。
そして気がつくと、壁に巨大な穴が開き、部屋の中はぐちゃぐちゃに四散し、自分達は鉄骨の下敷きになっていた。
「シュバルツ……!」
茫然と呟く自分の目の前で、首から上がないシュバルツの身体が、ぐ、ぐ、と、鉄骨を持ちあげている。僅かに空いた隙間から、キョウジは何とか這い出る事が出来た。それを待っていたかのように、べシャッと潰れるシュバルツの身体。千切れた首からはみ出したケーブルが、バチバチと音を立てて放電していた。
「シュバルツ……! そんな……!」
どうして
自分は、理不尽に八つ当たっていたと言うのに。
ただ茫然と座り込むしかないキョウジ。そこに、ハヤブサが走り込んできたのだった。
「兄さん? 大丈夫か?」
「――――!」
はっと、我に帰るキョウジ。振り向くと、ドモンが心配そうな顔をして、こちらを覗き込んでいた。
「あ、ああ……。大丈夫だよ……」
弟に心配かけないように、慌てて笑顔を取り繕う。しかしドモンは、そんなキョウジの『笑顔』をじっと見つめて――――やがて、深いため息を吐いた。
「………大丈夫な訳無いだろ、兄さん。部屋があれだけ壊れていて、兄さんだけが無事って事は、シュバルツが兄さんを守ったんだろ?」
「……………!」
「それでシュバルツが、今も起き上がれないほどのダメージを受けたんだって、そんなの俺でも容易に想像できるよ。それで、兄さんがショックを受けていない筈がない」
「ドモン……!」
「そんなときに、無理して笑わなくていいよ、兄さん。俺は、大丈夫だから……」
「…………」
キョウジはそんな弟を暫くじっと見つめていたが、やがて、柔らかい笑みをその面に浮かべた。
「分かった……。ありがとう、ドモン……」
その笑みが、先程の笑顔と違ってとても自然で柔らかかったから――――ドモンの顔にも笑顔が浮かぶ。微笑みあう兄弟たち。その場の空気がしばし、穏やかな物になった。
(それにしてもシュバルツは……どうして、あんなに私から八つ当たられて、それでも傍から離れなかったのだろう?)
ゆっくりと治っていくシュバルツの身体を見つめながら、キョウジは不思議に思った。普通のシュバルツであったなら、自分が最初に『1人になりたい』と言った時点で、あっさり1人にさせてくれる。だから、あんな風に口論じみた事になるなんて、普通だったらあり得ない。
だがシュバルツは、頑なに自分の傍に居続けようとした。時計まで気にしながら。
もしも、シュバルツがいつも通り自分の要求を聞いていて、1人にさせてくれていたならば――――自分のデスクのある窓際から鉄骨が飛び込んできた瞬間に、自分の人生は終わっていた事だろう。それを考えると背筋に寒気が走る。よくシュバルツは、あんな風に怒っている自分から、離れずにいてくれたものだ。
それにしても何故だ……?
シュバルツの一連の行動は、あの瞬間にあの事故が起きると言う事を分かっていたとしか思えない。
どうしてシュバルツは――――
「う…………」
やがてシュバルツが、低く呻いて身じろぎをする。
どうやら、意識が覚醒するほどまでに、回復して来たようだった。
「シュバルツ……!」
ゆるりと瞳を開けるシュバルツを、キョウジとドモンが覗き込む。
「……………」
暫くこちらをぼんやりと見つめていたシュバルツが、唐突に跳ね起きた。
「キョウジ……!」
そっと伸ばされてきたシュバルツの手が、キョウジの頬に触れる。
「シュバルツ……?」
不思議そうにしながらも、キョウジがシュバルツのその手に触れた瞬間。
「キョウジ……! キョウジ……ッ!!」
シュバルツがいきなり、キョウジの身体をガバッと抱きしめて来た。
「!? ちょっ……! シュバルツ!?」
驚いたキョウジが悲鳴の様な声を上げるが、シュバルツの方は既に聞いていない。「キョウジ……!」と、その身体をぎゅっと抱きしめながら、涙まで流し始めている。
「シュバルツ……?」
「生きてる……! キョウジ……ッ!」
「―――――!」
「良かった……! キョウジ……! 良かった……ッ!」
その後は言葉にならず、ただ、嗚咽を漏らし続けるシュバルツ。キョウジを抱きしめるその身体が、小刻みに震えていた。
「シュバルツ……」
最初は驚き、戸惑っていたキョウジであったが、やがて、震えるシュバルツの背中に、そっとその手を回した。そのまま宥める様に慈しむように――――その背や髪を撫で続ける。
「う…………!」
困ったのはドモンである。兄二人が仲睦まじいのは良いのだが、今、抱きしめ合っている兄たちの居るこの空間に――――自分は激しく邪魔になっているのではと感じてしまうのだ。
そっと出て行くことも考えたが、今、下手に動いてしまったら、兄たちに気づかれてしまって―――――本当の『邪魔』になってしまうかもしれない。それだけは避けたいと思った。よく分からないが、シュバルツが珍しく感情を爆発させているのだから――――存分にそれをさせてやりたい、と、願った。
だから彼は、兄たちから少し離れた所で背を向けて座って、なるべく気配を消して小さくなっている事を選択した。自分の存在に気づかれるのは、兄たちが落ち着いてからでいいと思った。
そうして、どれくらいの時が流れた事だろう。
「……………」
落ちついたのか、シュバルツがようやくキョウジから離れる。
「……落ち着いた?」
そう声をかけるキョウジに、シュバルツはこくりと頷いた。
「済まないな……醜態を、見せた……」
シュバルツの言葉に、キョウジはフルフルと首を振る。
「ううん……私の方こそ、ごめん……。貴方は、私を守ろうとしてくれていたのに――――」
「そんな事は良いんだ、キョウジ。それよりも、お前が無事で良かった……。守れて、良かった……」
「シュバルツ……」
そう言うシュバルツの面に綺麗な笑みが浮かぶ。キョウジは少し気恥ずかしくなってシュバルツから視線を逸らして―――――そこでやっと、弟の存在を思い出した。
「え……ええ~~~っと……シュバルツ?」
「どうした? キョウジ……」
「じ、実は……ドモンも、ここに居るんだけど………お前、気がついて、た?」
「えっ?」
キョウジの言葉を受けて、シュバルツも辺りを見回す。そしてそこで、身体を小さく丸めて座り込んで、気まずそうにこちらを振り返って見ているドモンと、視線が合った。
「―――――!」
ギョッと固まるシュバルツに対して、ドモンは多少ひきつった笑顔を浮かべながら「に、兄さん久しぶり……」と、ひらひらと手を振る。それをしばらく茫然と見つめていたシュバルツであるが、いきなり無言で踵を返すと、そのままズブズブと、床の影に向かって身を沈めようとした。
「わ――――ッ!! 待って! 待って!!」
それを、慌ててドモンとキョウジが二人がかりで止める。
「離してくれキョウジ!! ドモンの前であんな醜態をさらして、もう割と合わせる顔がない様な気が――――!!」
「そんな醜態だなんて思ってないよ! 兄さん!! とにかく落ち着いてってば!!」
「う………!」
ドモンにそう叫ばれて、ようやくシュバルツも足掻くのを止める。
「とにかく礼を言わせてくれ、シュバルツ。……兄さんを守ってくれて、ありがとう」
そう言ってドモンはシュバルツの手を、ぎゅっと握る。
「ドモン……!」
ドモンの言葉を聞いて、シュバルツは多少ばつが悪そうではあるが、落ちついた様だった。
「それは……キョウジを守るのが、私の役目、だから……」
そう言いながらシュバルツはゴホン、と、軽く咳払いをする。その頬が、少し赤く染まっていた。それを見て、ドモンとキョウジは優しく笑う。その部屋の空気が、少し和やかな物になった。
「そう言えば、ドモン」
「何? 兄さん」
キョウジの問いかけに、ドモンは小首をかしげる。
「私に変装しているハヤブサを、1人にしておいていいのかな? そろそろ迎えに行ってあげた方が……」
「ハヤブサの傍にはレインがついている。心配はいらない」
「レインが?」
少し驚くシュバルツにドモンが頷く。
「ああ。1人にするのも不自然だからって、レインがあいつの病室に残って、俺を行かせてくれたんだ。でもあいつ、怪我なんてしていないんだろう? 何時までも『入院』させておく事なんて、ない様な気が――――」
「心配するな。もう『退院』してきた」
ドモンの言葉が終わらぬうちに、『キョウジ』がそう言いながら地下室の入り口から入って来る。その後ろからレインも続いて入ってきた。
「レインに口を利いてもらった。おかげで早く退院できたんだ」
そう言いながら『キョウジ』は、べりっと音を立ててその変装を取る。その下から、リュウ・ハヤブサの素顔が現れた。
「ええ。私が医師免許を持っている事を伝えて――――そうしたら、私の看護付きで、退院してもらって構いませんって事になったの」
そう言ってレインがにっこりと微笑む。場の空気が、少し華やいだような気がするのは気のせいだろうか。そんな事を感じさせてしまう程、この『レイン』と言う女性はとびっきりの『美人』であったのだ。
「そうか……」
「世話になったな、レイン」
レインの言葉に兄たち二人がにこりと微笑む。それにレインも「どういたしまして」と、笑みを返した。
「でも実際のところ……キョウジさんは大丈夫なの? もし、頭とか強く打っていたりしたら――――」
「私はぴんぴんしているよ。シュバルツが守ってくれたから、大丈夫」
少し真剣に聞いてくるレインに、キョウジは笑顔で答える。
「それならいいけど……」
しかし心配げな表情を崩さないレイン。やはり、医師として気がかりではあるのだろう。本当ならば、最低でも1日は、様子を見るために入院していて欲しい所なのだから。
「それよりも兄さん。今晩寝るところ、どうするんだよ?」
ドモンのその言葉に、一同ははっと我に帰る。
「あれだけ窓やら部屋やらを破壊されたら、しばらくここで寝泊まり出来ないだろう? どうするつもりなんだ?」
ドモンの言葉を受けて、ハヤブサも口を開いた。
「そうだな。今も外は現場検証のために、警察が規制線を引いている。本来ならば立ち入りは禁止だ。俺も『私物を取りに行きたいから』と言う理由で、警察に許可を得て入ってきたんだ。あまり長居は出来ないだろう」
しかしキョウジは、それに対してあっけらかんと答えた。
「や、別に……。壊れた建物ぐらい、すぐ直そうと思えば直せるけど……」
その言葉に、一同はズルッと、こけてしまう。
「に、兄さん……?」
ドモンはただ茫然とし、シュバルツとレインは、懸命に痛む頭と格闘していた。
「いや……。キョウジ……。お前がそう言う事が出来るのは知っているが、今ここで、それをするのは止めておいた方が良い……。悪目立ちをするぞ?」
キョウジを助けるためにここまで走って来る間に、散々悪目立ちをしまくった男が言う台詞ではないが、ハヤブサは一応『常識』の範囲を忠告した。この地下室に居る人間が全員割と『常識外』な物を持っている気がしないでもなかったが、一応それは、横に置いておいた。
「う~ん……やっぱ駄目か」
そうキョウジが苦笑しながら頷けば、
「駄目だろう。『常識』の範囲外だ」
と、シュバルツも頷く。
「そうね……。『常識』は、守らないとダメよね……」
レインも苦笑しながら言葉を紡げば、
「『常識』……めんどくさいけどな……」
と、ドモンも頷いた。
(何か……シュールな絵面だな……)
ハヤブサは妙な関心を感じながらも、話を進める事にした。先程も話したが、あまり時間がない。ぐずぐずしていると、警察が『キョウジ』を探し始めて、ここが発見されないとも限らなかった。
「住むところがないのなら、隼の里に来るのはどうだ?」
ハヤブサは一縷の望みをかけて、そう提案する。実際里には客人を滞在させるための家もあるし、キョウジとシュバルツであるならば、里の者たちも歓迎するだろうと思った。
そして何より旨く行けば、
シュバルツと、褥を共に――――
だがハヤブサの野望は、5秒で粉砕される事となった。
「隼の里かぁ……。残念だけど、職場から遠すぎるな……」
キョウジの言葉に、シュバルツも苦笑しながら頷く。
「そうだな……。確かに、ちょっと人里から離れ過ぎているよな……」
「~~~~~~ッ!」
二人の言葉に、龍の忍者はがっくりと膝を付く。
(おのれ……ッ! 忍者の里の立地条件め……ッ!)
そのまましくしくと泣き出してしまう。そんな龍の忍者を尻目にドモンが口を開いた。
「じゃあ兄さん! 家に来なよ!」
「えっ?」
きょとん、とするキョウジの手を握り、ドモンはさらに続ける。
「な!? そうしなよ! 遠慮する事なんてないからさ!!」
「いや、しかし……!」
「そうよ、キョウジさん!」
戸惑い気味になるキョウジに、レインも声をかけてくる。
「ドモンと二人であの家は、少し広すぎるわ! あの家は元々キョウジさんの家でもあるのだから、遠慮なんてしないで」
「いや、しかし……二人の新婚家庭を邪魔する訳には――――」
そう言って尚も遠慮しようとしたキョウジであったが、結局ドモンとレインの説得に押し切られる形となった。ドモンとレインに潤んだ瞳で見つめられたら、それを無下には出来ないキョウジなのであった。
「話は決まったか? キョウジ。ならば必要な物を持って、なるべく早くここから出た方が良い」
ハヤブサが、やれやれ、と、ため息を吐きながら立ち上がる。
「それもそうね。でも、出て行く時、どうすればいいのかしら。5人揃って出て行く訳にはいかないし……」
そう言って考え込むレインに、シュバルツが微笑みかける。
「その辺は問題ないだろう。キョウジとドモンとレインの3人で、堂々と正面から出て行けばいい」
「分かった。でも、シュバルツ達はどうするんだ?」
ドモンの問いかけに、シュバルツはにやりと笑う。
「ドモン。忘れたのか? 私とハヤブサは『忍者』だ。警察の目を盗んでここから脱出することぐらい、造作もない事だ」
その言葉に、横に居たハヤブサもうんうんと頷く。
「あ………!」
「なるほど……確かに、二人なら容易いだろうね……」
カッシュ兄弟も納得した所で、皆は頷き合った。
「じゃあ、ドモン、レイン、着替えとか取り出したいから、手伝ってくれる?」
キョウジの言葉にドモンとレインが頷く。
「じゃあシュバルツ、ハヤブサ。気をつけてね。また後で――――」
そう言い置いて、キョウジ達は地下室から出て行った。後には、忍者二人が残された。
「……良かったな。キョウジの時間を取り戻せて……」
皆が出て行ったのを確認してから、ハヤブサがポツリと呟く。それにシュバルツは「ああ」と頷いた。
「で、シュバルツ……どうだった? キョウジはやはり、自分が『死んだ』後の事を、憶えているのか?」
「いや………」
ハヤブサの言葉に、シュバルツはフルフルと首を横に振る。
「どうやら、憶えていないみたいなんだ……」
「――――!」
驚くハヤブサに、シュバルツは少し苦笑気味の笑顔を向ける。
「驚く事はない。これは、キョウジも予測していた事なんだ。ハヤブサみたいに、生きたまま時を遡った場合は、記憶の引き継ぎは可能になるけど、私は死ぬたびに、記憶がリセットされていた。だから死した状態の自分は、時を遡って生き還った時、もしかしたら、記憶の引き継ぎが出来ないのではないかと――――そう、言っていた……」
「そうか………」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサは少し複雑な気持ちになる。あの不思議な世界で経験したいろいろな事を、キョウジと共有できないのは、少し淋しい気がした。
「でも、良いんだ。キョウジが無事ならば、それで――――」
そう言うシュバルツの面に、優しい笑みが浮かんでいる。それを見て、ハヤブサもとても優しい気持ちになれた。
自分もそうだ。
どんな形であれ、キョウジとシュバルツが無事ならば――――こんなに嬉しい事はない。
「ハヤブサ……」
「どうした? シュバルツ」
顔を上げるハヤブサに、シュバルツは少しすまなさそうな表情を見せる。
「済まないが、家の再建とかキョウジの雑事とかで暫く忙しくなる。ゆっくり会えなくなるが……構わないか……?」
「―――――!」
その言葉に一瞬きょとん、としたハヤブサであったが、やがてその面にフッと笑みを浮かべた。
「ああ。構わない。仕方がないさ。あれだけの事故に遭ったんだ……。すぐに時間が取れぬのも無理からぬ話だ」
ハヤブサの言葉に、シュバルツがもう一度「済まない」と、頭を下げようとする。ハヤブサはそれをやんわりと制した。今は、大変な時だ。そんな時に、自分がシュバルツの重荷になる事だけは避けたいと思った。自分は、彼の支えになりたいのだから。
逢いたいのなら、自分が勝手にシュバルツに逢いに来ればいいだけの話だと思った。こんな事態だ。逢うための口実など――――それこそ、いくらでも出来るのだから。
(だが2週間も3週間も、シュバルツに触れられないとなるときついな……。無理やり押し倒さないように注意しなければ……)
「いつか必ず、お前とゆっくり話すための時間は作る」
シュバルツのその言葉に、ハヤブサははっと顔を上げる。すこしはにかんだ表情のシュバルツと、視線が合った。
「その………今回起こったいろいろな事が、まだ私の中できちんと整理できていなくてな……。落ちついて、考えがまとまってきたら……必ず、お前と話をするから………」
「シュバルツ………」
シュバルツの気持ちが、ちゃんと自分に向いている事が強く感じられて、ハヤブサは嬉しかった。彼への愛しさが、自分の中から溢れてしまう。
「だから………ん……っ!」
だから気が付いたらハヤブサは、彼の唇を奪っていた。愛おしいヒトの身体を逃さぬように強く抱きしめ、その口腔を深く弄る。その舌を優しく吸ってやれば、愛おしいヒトから「は………あ………!」と、甘やかな声が上がった。
腕の中で強張る身体に、こちらの体温も上がる。
押し倒したい。
奪い尽くしてしまいたい。
だが
今は――――
「………………」
ハヤブサはそっと、シュバルツを解放した。
未練はあるが、恐れる事はない。
彼の『ココロ』は――――確かに、俺と共にあるのだから。
「じゃあ、俺は一度里の方に帰る。一つ、『仕事』を終えて来ているんだ。その報告をしなければならないのでな」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツははっと顔を上げる。
「済まなかったな……。そんな、任務の途中にわざわざ――――」
「いい。気にするな」
「しかし……!」
申し訳なさそうな色をその瞳に浮かべて、こちらを見つめてくるシュバルツ。そのいじましい様に、ハヤブサのあまり強くない理性が、本当に傾いでいきそうになる。
だがそれを、彼は懸命に堪えた。
「今はそれどころではない」と、必死に自分に言い聞かせる。
そうだ、落ちつけ。
シュバルツは、『必ず時間を作る』と、言ってくれているのだ。ならば焦らずとも、ゆっくり彼を抱く機会は、この先必ずある筈なのだから。
「なら、俺は行く。シュバルツも、気をつけて脱出しろよ」
「ああ」
シュバルツが頷いたのを確認してから、龍の忍者は地下室から出て行った。
「……………」
シュバルツはしばらく、何かを物思う様にハヤブサに触れられた己が唇にそっと触れていたが、やがて顔を上げると、彼もまた地下室からその姿を消した。
そして、その部屋は、誰も居なくなったのだった――――――。
それからしばらくは、本当にバタバタとしている間に過ぎた。
警察の事情聴取、保険の対応、家の片づけ、たまに訪れるマスコミへの対応、そして、その合間を縫って仕事―――――それらを、キョウジとシュバルツは、互いに入れ替わりながらこなしていた。
もちろんハヤブサも、自身の『仕事』が入ればそちらの方を優先したが、可能な限りキョウジとシュバルツの手伝いに来ていた。触れる事は出来ずとも、元気そうにやっている顔を見られれば、ハヤブサはそれなりに満足できた。勿論、どうしても我慢できないときは、シュバルツの唇を奪ったりはしたが、それを許してくれる彼に、『愛情』を感じられたから、それで充分幸せだった。
ただ時折、自分が訪ねて来ている事が彼の弟にばれると、所構わず手合わせを挑まれるのが厄介ではあったが―――――2人の弟は稀代の格闘家なだけあって、骨のある組み手ができる。ハヤブサにとっても、それは良い修行になった。
そうやって日々を過ごしているうちに、少し、事態に落ち着きが見えてくる。そんな中シュバルツから「明日、ゆっくり話せないか?」と、声をかけて来た。それにハヤブサが、否やを唱える筈もない。こうして忍者たちは、久しぶりに二人だけの時間を持つ事になった。
もちろん、落ち合うのはあの郊外のいつもの森である。ハヤブサがそこに向かうと、いつもの木の所に、愛おしいヒトが、いつもと同じように木の幹に凭れてこちらを待っていた。
「シュバルツ!!」
シュバルツがこちらに気づいて振り向く。こちらの名を呼ぼうと唇が開かれた瞬間、ハヤブサはもうその唇を奪っていた。いいや、唇だけでは飽き足らない。口腔深くを蹂躙し、その呼吸を奪う。
「ん……ッ! んく……!」
愛おしいヒトが腕の中で、苦しそうにくぐもった声を漏らすが、その声すら奪ってしまいたくて、口付けを更に深めた。
欲しい。
愛おしくて愛おしくて――――何もかもが欲しくてたまらなかった。
「……………」
強引な口付けが終わった後には、ハヤブサはシュバルツを押し倒すような格好になっていた。自分の腹の下で愛おしいヒトが、少し戸惑ったような表情を見せている。飲み切れずに溢れた唾液が、彼の唇を魅惑的に濡らしているからたまらない。
「は……ハヤブサ……」
「シュバルツ………」
シュバルツの頬を撫でていたハヤブサの手が、そのまま彼の首元に滑って来てそのスカーフをはぎ取る。
「だ、抱くのか?」
言わずもがなな事を聞いてくる愛おしいヒトに、ハヤブサは苦笑した。
「当たり前だ。もう何日――――お前に触れていないと思っている?」
「……………!」
瞬間、驚いたように瞳を見開いたシュバルツであるが、やがて、何かをあきらめたように一つため息を吐いた。酷く切迫した、熱い眼差しで見つめてくる龍の忍者。彼がこういう瞳になっている時は、抵抗するだけ無駄だと言う事を、シュバルツはとっくに承知していた。
「分かった……。好きにしろ」
「シュバルツ!!」
許しの言葉を伝えると同時に、龍の忍者は弾かれた様にシュバルツを求めて来た。あっという間にコートのボタンが外され、シャツが強引に切り裂かれる。
「ば、馬鹿っ!! 服は破るなって―――――あっ!?」
現れた白い肌に、噛みつく様な愛撫をされる。それは、シュバルツの肌のあちこちに、キスの花を咲かせた。
「や………! あ………ッ!」
(待たせすぎたか)
ハヤブサが望むままに、その白い身体をのたうちまわらせながら、シュバルツは少し苦笑する。互いに忙しすぎて、なかなかまとまった時間が取れなかった。だから、仕方がないとは言え――――どうして、こんなに狂ったように、ハヤブサは自分を求めてくるのだろう。
謎だ。
何度抱かれても――――それだけが、謎だった。
「あっ!! ああっ!! ああああっ!!」
嵐の様な愛撫と律動に、シュバルツは喘ぎながら耐える。ハヤブサ、と、呼びかけると、手を優しく握りかえされた。
(愛シテイル………)
ハヤブサから流れ込んで来る熱い『想い』が、シュバルツの熱を煽り、快感を加速させる。いつしかシュバルツの方も、その熱に酔わされ、押し流されてしまって――――
しばらく森の中には、二人の愛し合う音だけが、響き渡っていたのだった。
「はぁっ!! ああ……ッ!! も……!」
身体をゆすられながら、シュバルツが限界を訴える。縋るように伸ばされてきた彼の手を、ハヤブサは優しく愛した。
「シュバルツ……! 一緒に……ッ!」
「あ……あ………! ああ――――ッ!!」
忍者二人は共に、今日何度目かのその瞬間を迎える。
「あ………!」
シュバルツの下腹部に、熱い迸りがじわりと広がる。しばらくその感触に彼は震えていた。
「シュバルツ……」
ハヤブサから唇を求められ、優しく吸われる。幸せだと感じてしまって――――涙が溢れるのは、何故なのだろう。
「―――――」
キスを終えたハヤブサが、脱力したようにシュバルツの上に倒れ込んできた。
「ハヤブサ……」
その髪や背を、優しく撫でる。自身の中のハヤブサへの愛おしさが命じるままに――――彼は、それをしていた。
(シュバルツ……)
シュバルツからの優しい抱擁を、彼は瞳を閉じて堪能する。たまらなく幸せな瞬間だった。
もう少し、彼が欲しい。
自身の中の凶悪とも言える衝動が、彼を欲してそう主張する。だが今は。
シュバルツから軽く身を離して、その顎を捉える。
「ん………」
ついばむような口付けを交わした後、ハヤブサはシュバルツの中から己自身を引き抜いた。
「……はっ! ああっ! んん……ッ!」
引き抜かれるその瞬間までビクビクと身を震わせ、可愛らしい反応をする愛おしいヒト。ハヤブサの面に、フッと優しい笑みが浮かんだ。
「大丈夫か?」
自身の汚れを紙で手早く処理をしながらハヤブサはシュバルツに声をかける。愛おしいヒトは、すぐに身を起こしかねるのか、ぐったりとその身体を横たえていた。
「……がっつきすぎだ、馬鹿……」
ぼそっと言われる言葉に、ハヤブサも苦笑するしかない。
「仕方がなかろう。長い事我慢していたのだから――――」
「2週間ちょっとだろう……? そんなに長く待たせた訳でもないだろうに……」
けだるそうに紡がれるシュバルツの言葉に、ハヤブサはがっつく様に反論する。
「20日間『も』だ! もうほぼ3週間だぞ!? 俺は3日に1度お前に触れたいって言っているのに――――!」
「……3日に一度は多すぎると、前にも言っただろう? 全く……あっ!」
そう言いながらゆっくりと身を起こしたシュバルツから悲鳴が上がる。ハヤブサを受け入れていた所から、残滓が流れ出してきたからだ。その量の多さにハヤブサは苦笑し、シュバルツはただ赤面するしかない。
「ああもう――――!」
シュバルツの姿がフッと消えたかと思うと、すぐ近くの川からザブン、と水音がする。どうやら彼は、自身の汚れを川の水で洗い流す事を選択したらしかった。
(ああ、綺麗だな)
彼の泳ぐ姿を見て、ハヤブサは思う。
川の中で、しなやかに踊る白い肢体。
彼の動きに合わせて、跳ねあがる水飛沫がキラキラと光る。
しばし泳ぎを止めて濡れた髪をかき上げる仕種も、堪らなく艶っぽくて――――
知らず、抑えていた筈の自身の欲望が、『ムラッ』と湧きあがって来るのを感じる。
(いやいや! 無いだろう!? さっきあれだけ抱いたのに――――!)
ハヤブサは強く頭をふると、手早く枯れ枝をかき集めて、火を起こした。燃え上がる炎を見つめながら、何とか自分の中の欲望と、折り合いをつける。
程良くそれが鎮まったところで、ハヤブサもまた川の中に飛び込んだ。身体の汚れを洗い流す事と、火照った身体を鎮めると言う、二つの目的があるが故に、飛び込んだその場所は、シュバルツから少し離れたところであった。
(それにしても、今日シュバルツと一緒にいられる時間って、後どれぐらいなのだろう)
泳ぎながらハヤブサはふと思った。
(1日だと嬉しいのだが……このあとちょっと話してすぐ別れるのであるならば辛いな……。別れ際に無理やり襲いかからないように注意しなければ……)
何故か少し泣きそうになりながら、龍の忍者は水の中を泳いでいた。
身体を洗い、一段落した忍者たちは、少し拓けた草原に出て来ていた。
シュバルツは新しいシャツを着ていた。どうやら彼は、ハヤブサにある程度服を破られるかもしれない、と、予測していた様であった。
「……………」
心地よい草原の風に吹かれながら、忍者たちはしばし沈黙する。
互いに話をどう切り出したものかと、窺っているようであるし、のどかで平和な景色を、味わっているようにも見えた。
「……平和だな……」
先に沈黙を破ったのは、龍の忍者であった。振り向くシュバルツに、ハヤブサは言葉を続けた。
「………こうしていると、あの時を越えた日々が、『夢だったのではないか』と、思う事があるんだ……」
「ハヤブサ……」
当たり前な話だが、平和な光景の続く日常に、あの『龍の首』が破壊した痕跡など、本のひとかけらも残ってはいない。遥か過去で、龍の首の元となる『遠呂智』は滅せられた。それ故に、あの龍の首の存在自体が『無かった事』になってしまっているのだから。
「……キョウジも、やはり、何も思い出さないのだろう?」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは苦笑しながら頭を振る。
「ああ……。もしかしたら、もう一度『霊体』になれば、思い出す事もあるかもしれないが……そんな事態を味わうのは、二度とごめんだ」
「確かにそうだな……」
シュバルツの言葉にハヤブサも苦笑する。
自分だって、もう二度と味わいたくない。キョウジやシュバルツを――――失ってしまう苦しみなど。
「だけど、あれは『夢』なんかじゃない……。その確証が、私にはある」
そう言いながらシュバルツは、懐から何かを取り出す。それは彼の手の中で、きらりと光を放っていた。
「それは――――!」
その『物』の正体に気づいて、ハヤブサは絶句する。何故ならそれは、自分がシュバルツに渡した、キョウジの『壊れた腕時計』であったのだから。
「ああ……。キョウジの時計だ。今キョウジの腕には、同じ物がつけられているから、どう言う訳かこれがこの世には2個あることになるのかな……」
そう言ってシュバルツは、この時計を優しい表情で眺める。
この時計は『証』だった。
自分達が時を越えた『証』
キョウジを守り切れなくて、一度死なせてしまった『証』
そして――――
キョウジが死した後も、自分が生き残ってしまう『証』でもあった。
「シュバルツ……」
時計を見つめるシュバルツの表情があまりにも穏やかであるが故に、ハヤブサの面に哀しみの色が浮かぶ。
何故
何故、目の前のこのヒトはそんなに穏やかな表情を浮かべていられるのだろう。
死ぬ事が出来ずに、永遠に彷徨わなければならない現実が
このヒトにはつきつけられているのに――――
そんなハヤブサの気配を察したのか、シュバルツが顔を上げて優しく微笑む。
「そんな心配そうな顔をするな、ハヤブサ! 私は自分の運命を悲観して、自棄になったりはしないさ。ただ、『キョウジと共に死ぬ』と言う選択肢が、消えただけの話だ。いざとなれば、ドモンの持つ『キング・オブ・ハート』の紋章の力でも、お前の龍剣でも――――DG細胞を滅する事が出来る。それで私は死ねるんだ。完全に『不死』と言う訳でもないのだから」
「―――――!」
「ただ……『覚悟』は必要だと思う……。何もかもを、受け入れるための『覚悟』が……」
愛おしい人たちと、別れる『覚悟』
たった独りで――――生き抜いて行く『覚悟』
総てを見届けるための 『覚悟』が―――――
「そのための『猶予期間』が、私にはまだある……。そう信じて、良いんだよな……?」
その為に、憶えておく。
キョウジから受けた『愛情』を。
ハヤブサから、死ぬほど愛された『記憶』を。
自分の支えとなってくれる、ドモンとレインの事も。
そして忘れない。
キョウジから託された、キョウジ自身すら忘れてしまった『魂の記憶』も。
助けてくれた屁舞留の事も、ずっと自分が覚えておく。
そうすれば、何時か遠い未来で生まれ変わった『屁舞留』と出会った時に
キョウジの代わりに自分が屁舞留に
「ありがとう」
そう伝える事が出来るのではないか。
そうならば、自分の『不死』である事にも、
ほんの少し――――『意味』を見出すことも、出来るのではないだろうか。
「シュバルツ……!」
気がつけばハヤブサは、シュバルツの身体を力いっぱい抱きしめていた。腕の中で愛おしいヒトが戸惑った様に身じろぎをするが、どうにも自分が止められなかった。
愛おしい。
愛おしくてたまらない。
この健気なヒトが――――
孤独な道を歩むと、決めてしまっているその覚悟が――――
改めて、ハヤブサは自分に誓う。
命ある限り――――自分は、このヒトを精いっぱい、愛し抜くのだと。
このヒトの、生きる『支え』となるために。
だが自分は、このヒトを『死』へと誘(いざな)える手段も持っている。
もしも自分が、自身の『死』を目の前にした時
自分はシュバルツを、どうしようと思うだろうか。
『生きて欲しい』と願うだろうか。
それとも『道連れにしたい』と、願ってしまうだろうか。
先の事はどうなるか、自分にも分からない。
だから今は。
彼と過ごす時間を、大切にしたい。
そう――――願う。
少しでも、自分と過ごした時間が、彼にとって楽しい物になる様に。
知らず、泣きそうになる。
ハヤブサは慌てて、涙の意味をごまかした。
実際――――彼に聞いて欲しい話も、あったからだ。
「シュバルツ……。俺の話も、聞いてくれるか……?」
「ああ……。構わないが……?」
疑問を呈しながらも頷いてくれるシュバルツにハヤブサは微笑むと、彼から身体を離して、一振りの木刀を取り出した。
「一応俺の方にも、今回の出来事が『夢ではなかった』という証拠の品がある。シュバルツ……これが何だか、分かるか?」
「木刀だろう? それがどうかしたのか?」
言わずもがなな事を言う愛おしいヒトに、ハヤブサは苦笑する。
「確かに木刀だ。だがこれは、ただの木刀ではない」
「…………?」
小首をかしげるシュバルツに、ハヤブサはズバリ言った。
「『宮本武蔵』が、手ずから作った『木刀』なんだ……」
「―――――!」
その一言で、シュバルツはある程度察してしまった。
そう。『宮本武蔵』と言えば、歴史上のビッグネームだ。もしも、その人物の作とされる物が現代で見つかったならば、それは国宝級の宝になるし、その価値たるや、計り知れないものとなる。
そしてハヤブサは、アンティークショップの経営者だ。
その骨董的価値が、誰よりも分かる人間であるが故に――――。
「それなのに……俺ときたら………」
「ど、どうした?」
若干嫌な予感に襲われながらも、シュバルツは問い返す。
「この木刀に……ッ! 本人の『銘』を入れてもらうのを、忘れていたんだ……ッ!」
「――――!」
ハヤブサのある意味やっぱりな物言いに、シュバルツはズルッとこけた。
骨董にあまり明るくないシュバルツにとっては、割とどうでもいいことなのだが、専門家のハヤブサにとっては、これは大問題に値する事らしい。
「本物なのに……ッ! 間違いなく、直接本人から手渡してもらった本物なのに……ッ!」
そう言いながら龍の忍者は、木刀を抱きかかえてしくしくと泣き出してしまっている。シュバルツは、顔をひきつらせながら起き上った。
「い、いいじゃないか……。それはそれで『家宝』として、大事に取っておけば――――」
一応慰めてみるが、龍の忍者は頭をふる。
「それはそうかもしれないが……『銘』が入っていれば、『間違いなく本物』と、証明できたのに……!」
「おい」
呆れかえるシュバルツをよそに、ハヤブサは1人のたうちまわっていた。
「どうしてそれをしてもらわなかったんだ!! 俺の馬鹿!! 本人から直接もらったのに! 本人が目の前にいたのに――――!!」
(……よく考えれば、私たちは凄い人たちと一緒にいたんだよな……。今でも信じられないぐらいだが……)
宮本武蔵や織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。源義経。劉備、関羽、張飛、諸葛亮、太公望――――どれをとっても、歴史にその名を刻んだ『偉人』たちだった。実際その傍にいるときは、その感覚も麻痺してしまっていたが、今考えれば考える程、凄い状況であったと思う。よくアンティークショップ経営のハヤブサが、俗な欲望に負けなかったものだと、今改めて感じる。
シュバルツはやれやれ、と、ため息を吐いた。
「ほらっ、ハヤブサ。お前の好きな寿司でも食べに行こう。今日1日かけて、お前を慰めてやるから」
「……本当か?」
涙目になって振り向くハヤブサに、シュバルツは苦笑しながら頷く。
「ああ。キョウジも言ってくれたんだ。『今日は1日、ゆっくりしておいで』と。だから、お前が迷惑でなければ、今日は1日、お前と共に――――」
「迷惑だなんてとんでもない! 嬉しいよ、シュバルツ!!」
シュバルツの言葉が終わらないうちに、ハヤブサが嬉しそうに起き上がって来る。
「…………!」
自分の『言葉』が、ハヤブサにとってもの凄く有効に利く事に、シュバルツは驚きを隠せない。だけど嬉しくもあった。自分が確かに、ハヤブサの支えとなれているのならば。
しかし。
「よしっ! じゃあ早速――――」
行こう、と、言ったハヤブサの語尾が、若干掠れている。どうやら今回の木刀の銘に対するダメージは、ハヤブサにとってはかなり深刻な物であるようだ。
シュバルツは苦笑しながら、ハヤブサの後をついて行った。1日かけて、ちゃんと慰めてやらねばと思った。
こうして、妖蛇の影響が無くなった世界で、皆がそれぞれの日常に戻っていく。
その中を、ただ優しい風が、吹き抜けて行ったのだった――――。
(了)
されど、龍は手を伸ばす。 ――無双OROCHI異聞録―――
やった……!
やりました……! ついに書き終わりました!
いやあ~~~~長かったです。
590475文字あります。400字詰め原稿用紙に換算すると、1477枚に相当しますよ。
馬鹿です。馬鹿の極みです。
そして、連載すること1年以上……うん。長くなるとは思っていました(^^;
何せ、同じ話を都合3回バージョンを変えて……キョウジ編を含めると4回か? 書かなければならなかったので、そうなるのかなぁと。
長いのと下手くそなのと内容が暗いのとが重なって、読者様はかなり減ったかと思われます。
いかんせん、この「無双OROCHI2」をやりながらネタを考えていて、最初に思ったことが、あ、これ死亡ネタが使えるんじゃね? だったので(^^;(←最低∑( ̄ロ ̄;!!!!)
こういう下種の極みみたいな発想をするから、私の考える話って、本当にろくでもないもののかなぁ、と、思ってしまいます。これで不快な思いをされた方いらっしゃいましたら、本当にごめんなさい(^^;
でも、例によって例のごとく、書いている方としては本当に楽しかったです(*^^*)
日記は、誰も応援してくれる人がいないときにも、自分のための唯一の応援歌になる。(斎藤茂太) 【名言ナビ】 http://www.meigennavi.net/word/284/284908.htm … #meigen #名言
この言葉の通り、この小説が、まさに自分にとっての応援歌でした。
どんなふうな状況になろうとも、自分がまっすぐ顔を上げられていたのは、この小説の積み重ねがあったからだとおもいます。ぶれない「芯」のようなものを、私に与え続けてくれました。
私にとって体験すること経験することは、すべて創作の肥やしなので、まさに毎日がいい勉強です。
まあ、こんな事を思ってしまうから、だから私は駄目なのでしょうけどねwwwww
そんなこんなでこの物語はいったん終わりますが、ハヤブサさんやシュバルツさんやキョウジ兄さんを書くことは、きっと私はやめないと思います。また勝手に書き続けて行くと思います。本当にね~……。この人たち以外『書きたい』と思える材料がないんですもの。困ったことに……。
そして、それをし続けている限り、私は日の目を見てはいけない物書きである事も、よく理解しています。
なんだかんだいって、この人たちは、私が生み出したオリジナルキャラクターではない。あくまでも、人様の作品からお借りしているものなのです。この物語も世界も、ゲームの世界から借りて来ている、いわば借りものだらけの世界観。こんな事をしている私よりも、自分のオリジナルの世界を作り上げて、オリジナルキャラクターで勝負している人たちの方が、よほど偉いし、尊ばれるべきものだと思うのです。私がやっている行為は、下手したら、『著作権の侵害』と、訴えられることになるのかな(^^;
でも、じゃあ、この人たちを「好きだ」と思う私の気持ちは、どこに昇華させればいいのだろう。
正式な作り手が供給してくれるものを、ただ待ち続けるだけが、正しい在り方なのだろうか?
それで十分な供給があるのなら、私だって文句は言わないで、おとなしく受け続けるのだろうけどね~。
ね~~~~~wwwww
ない。
どこにもない。
だから自分が書くしかない。
そんな感じでやってます(^^;
ご意見、感想、お待ちしています。
気が向いたらツイートしてくださってもけっこうですし、ブログの方に寄せて頂いても大丈夫です。作者は泣いて喜びます。
辛辣なご意見は心にとめさせて頂いた後、善処させていただきます(^^;
それでは、ここまで読んでいただいて、どうもありがとうございました(*^^*)
また、新しい物語が思いついたらば、書き始めるかもしれません。
その時にまたよろしければ、お付き合いください。
乱筆乱文失礼いたしました。