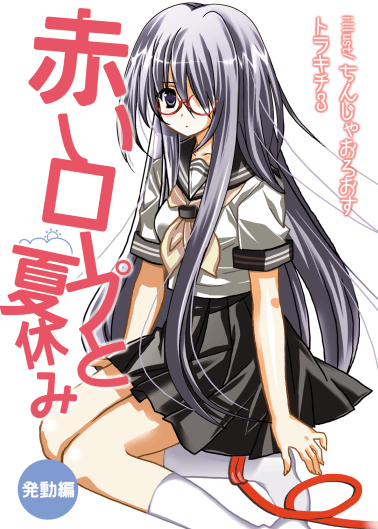
赤いロープと夏休み(1)発動編
【7稿】20140222
【6稿】20140118
【5稿】20131217
【4稿】20131215
【3稿】20131215
【2稿】20131214
【初稿】20131213
発動編
学校は、静寂に包まれていた。
俺は、ふと窓の外に目をやった。空は青く澄みわたり、白い雲がぽっかり浮かんでいる。高校に入学して3ヶ月。やっと新しい学生生活にも慣れてきたところだ。
「はじめ!」
いままでの静寂が破られ、教室はにわかに戦場と化した。今日は、夏休み目前の期末試験最終日。
試験問題をバサバサひっくり返し、さっそくコツコツと軽やかに答案用紙に答えを入れていくヤツもいれば、鉛筆を転がして、選択問題から解いているヤツもいる。答案を書いては、消しゴムでゴシゴシこすり、ビリっと答案用紙を破いているヤツもいる。
ともかく、みんな懸命に試験問題に取り組んでいる。
「英語は、苦手だ……」
俺は、最初の長文問題に目を通していたが、さっぱり理解できず一人つぶやいた。
チラリと教壇を見ると担任、かつ英語担当のゴジラことイワモト先生が教室を見渡している。イワモト先生は、巨漢でしかも顔がゴツゴツした強面だが、めっぽう涙もろい。海外で生活をしていたこともあってか、男子にはきびしく、女子には甘いところがある。当然、男子に人気はなくゴジラとアダナをつけていた。
英語なんて機械翻訳の開発がさらにすすめば、あとは、どう人とコミュニケーションをとるのかのほうが重要じゃないのか。
「いかん、いかん」
こんなことを考えたところで、目の前の試験から開放されるわけでもないし、さっさと試験を終わらせてようと気合をいれた。指先にグッと力が入り、最初の問題文にマークを付けたところでシャープペンンシルの芯がボキっと折れた。
その瞬間、折れた芯は、綺麗な放物線を描いて、左隣のカヨコの方へ飛んでいった。カヨコは、典型的なガリ勉メガネ女子で、しかも何かとヒステリックをおこす。
「ちょっと、シャープペンシルの芯、こちらにとばさないでよ」
カヨコの声が教室に響く。一瞬教室は凍りついた。カヨコは、こちらをキッと睨みつけてきたが、シャープペンシルの芯は、彼女の汗ばんだ額にペッタリはりついたままだ。
俺は、知らぬ存ぜぬを決めていたが、彼女の額に貼りついた芯をガン見してしまい、必死に笑うのをこらえてうつむいていた。
「スギモト、試験中は私語は慎むように!」
カヨコにゴジラの注意が飛ぶ。カヨコは、悔しそうに周りを見まわしたが、誰が芯を飛ばしたのかまではわかっていないようだ。あぶなかった。
時間が過ぎていく……。
「そこまで。エンピツをおけ! 答案用紙を後ろから前に送れ!」
ゴジラの号令がとぶ。あちらこちらからガヤガヤと声が上がり、俺は、答案用紙を前に送った。
ここ数日は苦悩の連続ではあったが、試験はこれですべて終わりだ。ただ、この英語だけは、全く手ごたえはない。まぁどうであれ、これで夏休みまであと1週間だ。
俺には、夏休みの初日には、楽しいことが待っているのだ。
実は、チャットルームで知り合ったハンドルネーム「ぽぽろん」とリアルで会う約束をしているのだ。高校に入学した頃から毎晩のようにチャットをしていたので、彼女に直接会えるのは実に楽しみだ。やはり、こういうときは男子がリードすべきなのだろうか。いや、ともかく、ネットで検索してデートプランも考えておかねばなるまいと妄想は膨らんだ。あれやこれや考えるだけで思わず顔がニヤけてしまう。
「一人ヘラヘラ笑って相変わらずキモイ……、頭、ぶっ壊れてるんじゃないの?」
となりの席のカヨコは、あきらかにバカにした目でこちらを見ている。
「ふん。お前には、まったくもって関係ない話だから!」
無視無視。こんなところでカヨコ相手にしてる暇はない。ネットでいろいろ情報を集めなければならない。俺は昼下がりの学校を後にした。
チャットをはじめたのは、中学生になったころだろうか。
きっかけは、ネットワークゲームの攻略サイトを探していて、有用な情報の出どころが、そのチャットルームにあることから興味がわいたのだ。
最初のうちは、ただログを眺めているだけだった。いれかわり、たちかわりいろんなヤツラがログインし、勝手なことばかり書き込む場所ではあったが、ハンドルネーム「ぽぽろん」だけは、そんなヤツラとはちがって、ルーム内での調整役をしていた。
調整役は、なにかと大変だ。ふざけて書き込むバカがいれば、それがもとで喧嘩になることは日常茶飯事だし、ゲーム初心者の繰り返される基本的な質問にも答え、ゲームをやりこんでいる廃人からは、さまざまな情報を聞き出すことまでやっている。
俺は、半年前からハマっているゲームに関しては、多少の知識と経験があるので、「ぽぽろん」を助けて調整役を手伝っていた。まぁ「ぽぽろん」のようには上手にさばけず、何度か火に油を注ぐ事態も招いたが、同じ境遇ということもあって「ぽぽろん」とも個別に会話をすることが増えたのだ。そして、夏休み初日にいよいよ会おうという約束をするまでになった。
「ぽぽろん」については、一つ年下の女子だということしかわからない。まぁ、容姿はわからないが、今までのチャットでお互いのことは理解しているし、あの調整役をこなせるコミュニケーション能力には敬服している。そんなこともあって、合えるのが楽しみでたまらないのだ。
ああ、夏休みが待ち遠しい。
~~
翌日、担任ゴジラから職員室に来いと呼び出しがあった。
職員室に入ろうと扉に手をかけると、中から絶叫が聞こえてきた。
「先生、そんなのイヤです、絶対に無理です!」
この声は、カヨコだろう。あいかわらずのわがままぶりだ。
ちょっとトラブルになりそうな予感が頭をよぎったが、思い切って職員室の扉を開けた。一礼して職員室にはいると、やはり、カヨコもゴジラに呼び出されていた。
「じゃ、そういうことだから、いいな」
ゴジラがそう話したところで、カヨコは、ゴジラを睨んでいたが、俺に気づくと、こちらも凄い視線が飛んでくる。カヨコは、俺の顔を睨んだまま、すぐ横を足早に通り過ぎると職員室から出て行った。
「なんだ、あいつ。」
「ところでタカシ、おまえ、英語の試験、ありゃなんだ?」
「へ? まぁ、自信はありませんが、ソコソコですかね」
「おまえのソコソコっていうのは、こういうことか?」
ゴジラは、100点中5点のタカシの答案用紙を見せた。
俺は息をのんだ。エンピツ転がし方式でも軽く25点はいけるはずだったのに、1問しか正解していない。
ゴジラは、深く息を吸うと、答案用紙を机においた。そして答案用紙の5点を指さし、コツコツたたきながら口を開いた。
「わかっているとおもうが、当然赤点だ。再度試験をおこなうからそのつもりでいろ。まぁせめて、追試で30点くらいはとってくれよ、いいな」
「はぁ」
しかし我ながらひどい点数だ。追試か、まだまだ夏休みまでは、きつい日々を送るハメになりそうだ。
「で、とりあえず、お前のことだから勉強もしないで追試に望みそうだから、今回もクラストップの成績だったスギモトくんに補講してもらうことをお願いしたところだ」
俺は、耳を疑った。
「スギモト……って、スギモトカヨコですか?」
「そうだ、お前たち友達なんだろう?」
「友達? そんな仲じゃないですよ。まぁ昔から知ってはいますけど」
「まぁ、いいから、スギモトに相談しろ。さっき話をつけたから」
「え? でもさっき絶対無理ですって絶叫が聞こえてましたけど」
「大丈夫だ。いいから、明日の放課後からがんばれ。追試まで時間がないぞ。いいな。」
一礼して職員室を出ると、さらに俺は落ち込んだ。よりによってカヨコに頭をさげなければならないのは屈辱だ。
学校の帰り道、俺は、カヨコと初めて会った時のことを思い出していた。
俺は、親の都合で小学2年生の夏に引っ越してきた。ドキドキしながら、教室で挨拶をし、そのとき横に座っていたのがカヨコだった。ツインテールが似合う彼女は、クラスの学級委員で、引っ越してきて間もない俺の面倒をいろいろみてくれていた。
ところが、小学5年生になった頃、彼女のじいちゃんが亡くなってからは、まるで人がかわったかのように勉強ばかりするようになって、一緒に遊ぶこともなくなってしまった。それ以来、常に学年トップの成績だったが、クラスメートからも常に浮いた存在になっていた。そしてカヨコは「性悪ガリ勉女子」と呼ばれていたのだった。
小学6年生の頃だったか、放課後、教室で俺とカヨコが2人になった際、俺はカヨコにそっと注意をしたことがあった。
「カヨコさぁ、最近クラスの連中からなんて言われているか知ってるか?」
「知らないし、興味もない」
カヨコは、俺の顔を睨みつけた。
「それから、ヤマモトくん、カヨコって名前で呼ぶのやめてくれない、子供じゃないんだしキモイのよ、ほっといてよ」
「ああ、そう……、心配して損したよ」
「ガリ勉でしょ」
突然カヨコがつぶやいた。
「なんだ、知ってんのか、「性悪ガリ勉女子」だぜ」
一瞬、カヨコの顔がこわばった。どうやら相当気にはしているようだ。しかし、直ぐに余裕の表情になり、言い放った。
「バカな奴らを相手にしている時間はないから、ほっといてよ」
カヨコはそういうと、教室を出て行った。それ以来、まともに話すらしていない。彼女は、俺を含めてクラスメート全員をバカ呼ばわりするヤツなのだ。
「はぁ」
俺は、大きくため息をついた。そんなカヨコに頭をさげて、勉強を教えてもらうことになるということは、考えただけ恐ろしい。おそらく、罵声をあびせられ、嫌な気分になるのは間違いない。
夜、いつもの時間より早めにネットへアクセスして「ぽぽろん」がやって来るのを待っていた。
ともかく「ぽぽろん」とのチャットでストレスを発散したかった。「ぽぽろん」がログインしてくると、俺は愚痴をぶちまけた。期末試験が散々だったこと、成績トップの女子と放課後に補講することになったこと……などだ。「ぽぽろん」は、最後まで真剣に俺の話を聞いてくれて気遣ってくれた。さらに、数日間だけガマンすればいいのではとアドバイスもくれた。
さすがの調整役だ。俺はだいぶ気分が晴れてきた。
その後、二人でパーティを組み、オンラインゲームで1時間ほど一緒に冒険に出かけ遊んだ。
そしてログオフする時間になると、ゲームのなかのキャラクターの決まり文句をもじって祈りを捧げてくれた。
「あなたの追試に、恵みがありますように」
「ありがとう。それじゃまた!」
俺は、すっかり気分が良くなっていた。
~~
翌朝、俺は、川沿のジョギングコースを走っていた。
毎朝6時に起きてジョギングをするのが日課だ。雨でないかぎり、小一時間程度走りこんでいる。走ることで、日頃のモヤモヤを整理することができる。昨日のカヨコの件についても覚悟ができた。ともかく頭をさげて、ああだこうだいわれても、追試で得点さえ取れればいいだけだ。そのためには手段を選ばずの精神で行くしかない。辛抱、辛抱!
空を見上げると、東の空から月が登り始めていた。朝日とのコントラストがあまりに綺麗だったので、みとれて走っていると、人にぶつかってしまった。
「あ、スイマセン」
あわてて、倒れた人に声をかけて驚いた。
倒れたのは奇妙な格好をした老人だった。もうすぐ夏だというのに魔道士のような長いローブを着て、数冊の古めかしい本をもっている。
「大丈夫じゃ、若いもんは元気じゃな」
老人は、何事もなかったかのように立ち上がりローブを手で払った。俺は、老人が落とした、数冊の本を拾い上げ、老人に手渡した。チラリとその本の中が見えたが、みたこともない言語でかかれた書物で内容はサッパリわからない。
「すいません。あまりに月が綺麗だったので、よそ見してました」
「ほう、月が綺麗だったと?」
「あ、はい」
老人は、じっと俺を見つめ、額に指を当てると何かつぶやいた。
その瞬間、俺は意識を失った。
「だいじょうぶですか?」
体をゆすられ、声をかけられた。
「あれ? あ、だいじょうぶです」
河原をジョギングしているランナーが、道端で倒れている俺に声をかけてくれたようだ。ゆっくり立ち上がると、手のひらに直径3cm程度の奇妙な赤い半透明の円盤をにぎっているのに気がついた。
「なんだこれ?」
さほど重くはないが、淵のところに意味不明の文様がほどこしてあり、透かして見るとなにやら赤い線が空中をとびまわっているのが見える。
「夢か? でもこの円盤は、あのじいさんのものかもしれないな」
ゆっくりコースを歩いて家に戻ることにした。途中、夫婦ランナーが自分を追い抜いていったので、例の円盤で二人を透かして見ると、二人の足には太い赤いロープで繋がって揺れているのが見えた。
なんとも不思議なことがあるものだ。
家にもどり、シャワーをあびて、学校に向かった。
街中をあるきながら、例の円盤でいろんな人をみてみると、どの人も足元から赤いロープがでており、それが町中とびかっている。
さらに、夫婦どうしだと太い赤いロープでつながっているのがわかった。
「これって、いわゆる運命の赤い糸ってやつか? でも糸というイメージではないな」
信号待ちをしながら、しばらく路上観察をしてみた。
「あ、ということは……」
俺は、自分の足元を見てみることにした。するとやはり赤いロープがでている。
「つまり、この先には将来結ばれる彼女がいるということ?」
さっそく、その赤いロープをずっと目で追いながら道を歩いていくと、学校に入る校門へ続いていたのだが、無残にもブッツリ切れていた。
「う、うそだろ! なんだよ!」
おもわず、俺は絶叫した。もしかしたら、俺には、将来結ばれるべく彼女なんていないのか。生涯ひとりでさびしい日々をおくるのか。
突然、絶望感が俺を襲った。
重い足取りで教室に到着する。
「おい、タカシどうした。顔色わるいぞ」
まわりの連中の声は聞こえたが、まったく相手にする気力がない。俺はまるで抜け殻のように自分の席についた。
「あいかわらず、ひどい顔。今日は特にね。そんなに補講するのが嫌い?」
「いや、そういう問題じゃない。補講はちゃんとうけるさ。」
さすがの隣のカヨコにさえ目をあわすことができなかった。カヨコも俺の顔には思いっきり引いているにちがいない。
「はぁ」
手のひらの赤い円盤を見つめながら、ため息をつく。どうせだから、クラスの連中もみてみよう。
早速かざして見てみると、みんな赤いロープがついているもののほとんどがブッツリ切れている。しかも、その切り口は、うごめいていて、なにやら相手を探しているようにも見える。
なんだ、みんな同じなんじゃないか。ということは、俺たちの将来はまだ確定していないってことなんじゃないか。
みるみる希望の光が見えてきた。
「よっしゃー」
思わず、力がみなぎり絶叫してしまった。
~~
俺は耐えていた。
放課後の少しばかり蒸し暑い教室。窓から、運動部の練習をする連中の掛け声がきこえてくる。そして、俺の前にいるカヨコは、散々俺の事をバカ呼ばわりし、それでも先生との約束だから仕方なく勉強をみてあげるのだから感謝しろと説教され、かれこれもう30分になる。
「そういうことだから、あなたの立場よくわかった?」
得意満面のカヨコの笑みには背筋が寒くなる。
「じゃ、試験の範囲は、ここからここまでだから……」
そういうと、俺の綺麗な教科書に印をつけた。
「っていうか、あなた教科書ひらいたことないの? なんで、こんなに新品同様なのよ」
「ええ、まぁ、おはずかしいかぎりです……」
カヨコは、各単元毎にスケジュールをきめて追試に望むことを話した。
「ともかく、まずは、単語を一日50個づつ詰め込むから。いいわね」
最悪だ。ともかくカヨコは凄い形相だ。こんな姿じゃ誰もが引くこと間違いない。
翌日もその次の日も、俺は耐えた。
放課後の時間は、カヨコとの熾烈な攻撃をかわしつつ英語に立ち向かわなけばならない。しかも、毎回、カヨコから宿題がでるので、「ぽぽろん」とのチャットをするヒマもなく、俺を心を癒してくれるものは、何もなくなってしまった。ともかくしばらくのガマンだ。
とはいえ、よくわからなかった英語だが、繰り返しやっているうちにだいぶ要領がわかってきた。
そして、今日も放課後の忍耐の時間がやってきた。
最初の30分の例の俺に対しての辱めはさらに度が増してきたようにも感じる。おもわず、両手で耳をふさいですべてを遮断したくなる衝動にかられるほどだ。
「まぁ、だいぶ、わかってきたみたいだけど、まだまだね。」
なんとも上から目線の言動に無性にカチンときた。
「はいはい、お嬢様。なんなりと……お申し付けください。もっと叱ってやってくださいまし」
何をおもったのか、俺は、つい面白半分にカヨコのことをカラかってしまった。
次の瞬間平手打ちがとんできた。
「ヤマモトくん。ふざけてるんなら、私帰るから」
いきなりカヨコが立ちあがると、俺のほうを睨みつけた。
俺は、ヒリヒリする左頬をガマンしながら、カヨコの顔を睨みつけ、静かに話をした。
「おまえさー、毎回毎回あの最初の30分はなんなんだよ。そんなに人のことをバカにして何がおもしろいんだ。俺もいままでガマンしてきたが、おまえ、その性格じゃ、この世の中でお前に味方するやつは誰もいなくなるぞ」
「あんたには、関係ないでしょう」
カヨコは、すこしヒステリックに答える。
「まぁ、いいけどさ、子供のころは、そんなんじゃなかったじゃないか、今のおまえの性格じゃ、彼氏はおろか、誰も近づかなくなるだろうし、まぁ生涯天涯孤独で、さびしく一人でババアになって、さびしい人生になること間違いなしだ」
「うるさい!」
「いい加減にしろよ、カヨコ」
カヨコは、すごい形相で俺を睨んでいた。
俺も負け時と睨み返した。すると急にカヨコの眉毛がさがり、目から涙があふれてきた。おどろいた。カヨコが、涙をこぼすとは思ってもみなかった。
「冗談だよ、冗談、昔のおまえを知っている俺としては、結構、残念なんだよ」
とあわてて、フォローをいれた。
しかし、逆効果だったのか、カヨコはうつむき、肩をふるわせ涙が机にポタポタ落ちた。
「もう、いい、二度とあんたとは話さない」
カヨコの絶叫が響き、何もかも教室に置いたまま教室の扉を渾身の力をこめて締めて出て行った。
俺は、机にこぼれたカヨコの涙の跡をじっと見つめたまま固まった。
~~
翌朝、いつもどおりにジョギングにでかけた。昨晩は、カヨコの涙をこぼすシーンが何度も何度も繰り返す夢でそのたびに目覚めてしまい、すっかり寝不足だ。
ふと目を東の空に目をやると、うっすら月が見えた。そういえば、月に見入ってぶつかった老人は夢だったんだろうか?
視線をコースに戻すと、突然目の前にあの老人の姿が見えた。
「あ、おじいさん。その後、だいじょうぶですか?」
「ああ、おまえさんか」
「そうそう、この間お会いしたときにこれを握っていたんんですが、これはじいさんの?」
そういうと、例の赤い円盤を老人に見せた。
「そうか、お前さんがもっていたのか。まぁ、しばらくは、お前さんが持っておけ」
「そういえば、これを通してみると……」
といいながら、老人を円盤を透かして見るとおびただしい数の赤いロープが老人からでていた。
「こ、これは」
「これは、運命の赤いロープじゃ。まぁ、まだお前は充分成長はしておらんようだな」
「どうして、じいさんには、こんなにたくさんのロープがくっついているんですか?」
「まぁ、私がこれらを管理しているのだから仕方ないじゃろ」
「管理? これって管理されているんですか」
老人は、微笑みながらうなずいた。
「そうだ、お前さん、自分のロープを育てたいとはおもわないか?」
「そりゃもう、誰かとくっつけられたらいいなとおもいますよ」
「ほぉ、いまどきの子供にしてはめずらしいな。それでは秘訣を教えるからよく聞け」
老人は、俺の額に手を当てなにやらつぶやいた。
「おまえは、なかなか見込みがありそうだが、まだまだ自分というものがわかっとらん」
そういうと老人は目を見開き俺を睨んだ。
「まぁ、人間は、誰しもそうなのだが、自分に素直に向き合うことが大切じゃ」
「べ、別に、俺はいつも素直ですよ。もともと」
「ウソをつくな、よいか、誰しも虚栄心、つまり、人によく見られたいと願うものじゃ、見栄を張るのは当然じゃろうし、ウソもつくものじゃ」
「そ、そりゃ、多少はありますよ」
「いずれ、お前は、そんな虚栄心を張るのが無意味と感じるほど素直になれるおなごと出会う事があるはずじゃ、ただ、その出会いのためには、人の心を観察して読み解けるようにならねばならん、常に自分に素直になに飾らずためらず接することじゃ、さすればそのロープは自然とたくましく成長するじゃろう、まぁ、逆に消えないようにすることじゃ」
「消えることもあるんですか」
「ある、人の心を読み、素直に行動できないようでは、いずれ消えてしまうぞ」
老人はそういうと、まるで虹が消えてしまうように消えてしまった。
「これは、夢か?」
タカシは、東の空を見上げたがつきはすっかり青空に溶け込んで見えなくなっていた。
その日は、カヨコは学校を休んだ。
彼女の机の上の涙の跡は、すっかり消えていたが、昨日の彼女の涙、震える声が頭をよぎる。俺は、罪悪感でいっぱいになった。
たしかに、カヨコの例の30分の説教は頭にくるが、そんなことは最初からわかっていたことだ。それに、今回の補講でだいぶ英語もわかるようになったのも事実なのだ。
俺は、ゆっくり目をつぶり、カヨコのことを考えた。そして、昔、彼女が一度だけ涙をこぼしたのを見たことがあったこと気づいた。あれはいつだったか……。
放課後、俺はカヨコの家を尋ねることにした。今朝の老人の話ではないが、ここは素直にあやまるべきだ。このままじゃ、俺も気分が悪い。もちろん、一度口に出してしまったものは、もう取り返しのつかないことは良くわかっていた。
「よし」
俺は気合をいれて、きちんと整理をつけるべくカヨコの家を目指した。
~~
家の呼び鈴を押すと、見覚えのある少女が戸口にでてきた。
「あ、スギモトカヨコさんいますか?」
「あー!タカシにーちゃん!」
俺は驚いた。カヨコの一つ年下の妹のサヨコだ。
サヨコはニッコリ微笑むと、俺の顔をじっと見つめた。
「タカシにーちゃん? 久しぶり!ねーちゃんに用事ですか?」
「ああ、カヨコ、今日学校休んだみたいだけど、どうしたのかとおもって」
「へー、タカシにーちゃん、昔から、ねーちゃんには、やさしいもんね」
「いや、そういうことではなくて」
サヨコは、いたずらっぽく微笑んだ。
「どうぞ、あがってください」
そういうと、スリッパをだしてくれた。
「しかし、サヨコちゃんも大きくなったね」
「でも、もう少し背は伸ばしたいんだけどね」
「そうか、もう中学3年生だもんね」
サヨコは少し背伸びをして、俺の肩と自分の背丈をくらべている。
「ところで、カヨコはどうしてる?」
「それがね、昨日学校から帰ってきて、ずっと部屋にこもりっぱなしでご飯も食べなくて」
「そう、実はね、昨日、俺、カヨコ泣かせちゃったんだよ」
サヨコは、びっくりしたように俺を見た。
「え? あのねーちゃんが、泣いたんですか?」
「そうだよ」
「ねーちゃんが、泣いたところなんかみたことない」
「そうなの?」
俺は、期末試験の結果が悪くカヨコに勉強を教えてもらっていることを話し、昨日は、少しばかり言い過ぎて泣かせてしまった経緯を説明した。
「そういえば、おねーちゃん、ここ数日、学校からかえってくると、逆に気持ち悪いくらいニコニコしてたんだけど、そういうことだったんだ」
「え?」
「タカシにーちゃんに勉強を教えるのが、楽しいって」
「そうなの? 俺にはすさまじい暴言をはいているんだけどね」
俺を罵倒するのがそんなに楽しかったのかと思うと、少しカチンときた。
「うーん、ねーちゃん、中学に入ってからは、ニコリともしなかったから、だからここ数日ニコニコしているのが気味悪いくらいだったんだ」
「たしか、小学校のころ、おじいちゃんが亡くなってから、急に変わっちゃった気がするんだけど」
サヨコは、すこし悲しそうにうつむきながら、つぶやいた。
「あの時は突然だったし、私も、ねーちゃんも、おじいちゃんのこと大好きだったし。その後もいろいろあったから、でもあの時もねーちゃん泣かなかったよ」
「そうなんだ」
俺はあまり詳しくは聞かないようにした。
「ねーちゃんなら、2階だよ」
そういうとサヨコが階段を指さした。
~~
昔は、よくカヨコの部屋にも遊びに行っていた。この階段もおぼろげながら覚えている。たしか、2階の一番奥の部屋だったはず。子供の頃は、良くふざけてこの階段から落ちたこともあった。思わず懐かしくてニヤニヤした。
廊下の突き当たりに、カヨコとプレートのかかった扉がある。
俺は、ドキドキしながら、カヨコの部屋の扉をノックした。
なんの反応もない。もう一度、強くノックをすると声がかえってきた。
「いいから、ほっといてよ」
カヨコの絶叫が聞こえる。これは、かなりヒステリックな状態になっていそうだ。果たしてこのまま話をすることができるのか、俺は心配になった。
「カヨコ、俺、タカシだよ」
突然、部屋の中でガタンという音がした。
「少し話をきいてほしいんだけど、いいかな」
「……」
「あのさ、カヨコ、俺さ……」
俺が話をしようとすると、部屋の中からさえぎるように声がした。
「あんたとは話はしないから、帰ってよ」
やはり、出直したほうがいいだろうか。一瞬そう思ったが、覚悟をきめた。
「まぁいいや、それじゃここで勝手に話をするから聞いてくれ」
不思議と俺は落ち着いていた。なにも気取ることはないし、素直に自分の気持ちをつたえればいいんだ。俺は、扉を背にして寄りかかり床に腰を下ろした。
「あのさ、昨日は、ごめん、すこし言いすぎたよ」
「……」
「いろいろ勉強おしえてもらってさ、おかげで英語も少しわかってきたよ」
「……」
「カヨコには、ほんと、感謝してるんだ」
「……」
「まぁ、おれはバカだし、勉強もきらいだけど、最近のカヨコはさ、俺の頭の中にいる昔のカヨコじゃないんだよ」
「……」
「昔さ、俺が引っ越してきたとき、友達ができるかどうかすごい不安でさ、最初にカヨコが優しくしてくれたよな、あの時すごくうれしくてさ、カヨコと一緒に遊ぶのが楽しかったんだよ」
「……」
「まわりの男子からは、なんだ、おまえ女子と遊ぶのか? ってずいぶんからかわれたけど、俺にはそんなのは関係なかったよ。楽しかったし」
しばらく、沈黙があり部屋の中から、か細い声が聞こえてきた。
「ず、ずるいよ……」
「うん?」
「ずるいよ、タカシ……」
「なにがさ?」
「なんで、そんな話をするのよ」
少しカヨコの声が震えていたのがわかった。
「昨日さ、正直、すごい頭にきてさ、ついカッとなってどなちゃったんだけど、おまえが涙がこぼすのを見たとき、思い出したんだよ」
俺は、昔、カヨコが涙をこぼしたときのことをはっきりと思い出していた。
「たしか小学4年生の運動会のときだったよ、クラス対抗リレーで俺の不注意でバトン落としたじゃないか」
「あ……」
「でさ、うちのクラスの連中は、逆転優勝だったのに、おまえがバトンを落とさなければってって責めたてられたじゃないか」
「……」
「あの時さ、カヨコが懸命に俺のせいじゃないと頑張ってくれたよな」
「……」
「あの時、カヨコが、俺をかばって、涙をポロポロ落としてたのを思い出したんだよ」
そう、あの時、カヨコは懸命に、勝ち負け関係なく、みんな頑張ったんだからいいじゃないかと俺を責めていたクラスの連中に泣きながら説得してくれたのだ。クラスの連中も、そんなカヨコの声に黙ってしまったのだ。
「俺、すごくうれしくてさ、絶対、来年はトップになると誓ったんだよ」
「え……」
「それで5年生のときは、トップになったんだぜ」
「……」
「おぼえてないだろうなぁ、その頃は、カヨコは勉強一辺倒だったから、ぜんぜん関心がないみたいだった」
「……」
「実のところ、俺は、それでもカヨコが喜んでくれるとおもってたんだけどさ、すこしさびしかったんだ」
しばらく、沈黙がつづいた。ドンと扉にカヨコがもたれる音が聞こえた。
「タカシ……そんな話……ずるいよ……」
カヨコの声は、震えてそのあと何か話しているようだが、聞き取れなかった。
「ごめんな、悪かったよ、でも、補講のことは、本当に感謝してるんだ。追試は明後日だけどさ、なんとか自信がついたよ、明日は、学校にこれるよな」
「うん……」
「まぁ、おまえも、いろいろな事があったみたいだけど、よろしくな」
「……」
「じゃ、またな」
一通り話をし終わって、俺が立ち上がろうとしたところで、カヨコが急に扉を開いた。扉に寄りかかっていた俺はそのまま後ろに仰向けにひっくりかえってしまった。
見上げると、カヨコが真っ赤に目をはらしてこちらをみている。
「タカシ……ごめんね……」
そういうと、大粒の涙がカヨコの目からポロポロと俺の顔に落ちてきた。
「あったかいな」
俺は、カヨコが愛おしいく見えた。まるで小学校時代に見せていたあのカヨコの面影だ。
「おいおい、な、泣くなよ、少しは、ご飯でもたべて元気出せよ」
「うん……」
「明日、学校でまってるよ」
俺は、カヨコを見つめた。俺はカヨコに、不思議なくらい素直に話をすることができた……。
「あ、それから、おまえ苺柄のパンツはやめたほうがいいぞ、子供じゃないんだから」
突然、カヨコがスカートをおさえ、顔を真っ赤にして部屋の扉を閉めた。
俺の頭に扉がゴンとあたり、そのまますごい力で廊下に押し出された。
「か、帰れ! ヘンタイ……バカ」
部屋の中からいつものカヨコの声が響いたが、クスクスと笑声が聞こえてきた。あれだけ元気なら大丈夫だろう。
~~
翌日、学校にカヨコの姿があった。いつもは、この世全てに不機嫌なオーラを発しているのだが、今日のカヨコは、ほほ笑んでいるように見える。クラスの連中も、そうしたカヨコの異変にザワザワしているのが感じられる。
「お、おはよう」
俺が声をかけると、キッと睨むのは、あいかわらずだ。
「まぁいいか」
昨日みせたあの面影はどこへいったんだ。
「おはよう、ヘンタイさん」
カヨコは、少し皮肉っぽく挨拶をしてきた。
「ともかく、今日一日で仕上げるから、覚悟しときなさいよね」
「おう、よろしくな!」
すると、カヨコが一瞬、微笑んだ。その笑顔があまりに可愛く見えて、なぜか俺の方が顔を真っ赤にしてしまった。
放課後、カヨコと最後の勉強を再開した。例の最初の30分はカットされ、これまでの復習と、間違いやすい部分についての確認をした。
俺は、いつもだと教科書やノートに目が行くのだが、先ほどの微笑みを思い出し、時よりカヨコの顔をチラチラみてみた。
なるほど、確かに嬉しそうだ。俺は、昔のカヨコのオーラを感じていた。
「どうしたの?」
「ああ、いや、なんでもない、カヨコ楽しそうだなって思ってさ」
「別に、そんなんじゃないけど」
プイと横を向きながらも、なぜか頬を赤く染めている。
もしかしてこれが俗に言うツンデレってやつなのかと、俺はニヤけてしまった。
~~
翌日の追試では、まるで前回の期末テストとはウソとおもうほど簡単だった。10分もしないうちに全部解答することができた。
ゴジラも驚いて俺の顔を見たが、その場で採点をしてもらうと90点だった。
「おい、ヤマモト、お前もう少し真剣に俺の授業受けろよな、こんな点数取れるなら、初めから取れよ」
「まぁ、ソコソコですよ」
「何が、ソコソコだ。スギモトに感謝しろよな」
「はい、まぁ、カヨコのおかげです」
「よし、帰ってよし」
学校の校門のところで、カヨコが待っていてくれた。
「カヨコ! 追試はバッチリ90点とれたぜ、ありがとな」
と声をかけた。
「あ、そう、私が指導したんだから当然でしょ、逆になんで満点でなかったのかが問題よ」
「ごめん、回答欄間違えた」
「ふっ、やっぱしマヌケね……バカ」
俺は、カチンときたが、まぁ、相変わらずの素振りだし、カヨコの横顔が嬉しそうにも見える。
「なぁ、一緒に帰ろうぜ!」
とカヨコの背中をポンと叩くと、カヨコは、キッとこちらを睨んだが、すぐに顔を真っ赤にして頷いた。
「いいけど……、き、気安く触らないでよ。ヘンタイ」
その夜、チャットで「ぽぽろん」と今までの経緯について報告をした。すると意外な返事がかえってきた。
「このあいだは、会えてよかったです」
「え? どこかで会った? 俺と?」
「タカシにーちゃん。これからも、ねーちゃんの事よろしくお願いします」
「え!「ぽぽろん」ってサヨコちゃんだったの?」
「えへへ、ねーちゃんには秘密だよ」
「なんか俺、いままで、随分恥ずかしい話もしたような気がするけど、忘れてくれよな」
「実は、ねーちゃんの事が心配で、おにーちゃんに相談するつもりでチャット始めたんだけど、ゲームにハマっちゃったんだ」
「でも、よく俺ってわかったね」
「えへへ、学校でゲームの話しとかしてなかった? ねーちゃんがよくブツブツ言ってたから」
「え? カヨコは俺の話なんかしてたの?」
「ふふ、いつもだよ。おにーちゃんの話になるとかなりムキになって話するから、聞きだすのは簡単だったよ!」
「そうなのか、そうだ、夏休み初日に会う約束だけど……」
「あ! 夏休みだもんね。できればねーちゃんと3人でどこかへ遊びに行きたいなぁ」
「まぁ、カヨコにもお礼しなくちゃいけないし、「ぽぽろん」にもお礼しなくちゃね」
「わーい! 楽しみ!」
「じゃ、また連絡するね」
「はーい」
こうして、俺の高校生初めての夏休みは無事始まろうとしている。
実は、例の赤い円盤で今の俺の足元をみたらどうなっているのか正直興味があったのだが、あえて見ない事にした。
これから先、何があってどうなるのか……そんなドキドキのお楽しみはとっておいたほうがなんとなくいいように思えたからだ。
赤いロープと夏休み(1)発動編


