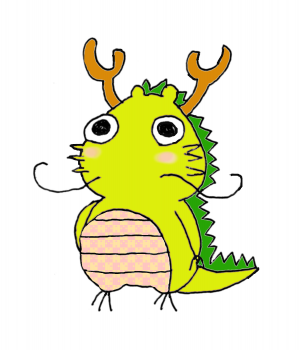プレゼント
お久しぶりです。
書きたい小説がまた浮かびあがってきたので、またこっそり上げさせていただくことにしました。お付き合いできる方は、またよろしくお願いいたします。
……と、言ってもBL小説です。
ハヤブサさん×シュバルツさん。
それ以外は何にもございません(笑)。
BLが苦手な方、このカップリングを不快に感じる方、そしてお子様は、閲覧されないことを強くお勧めいたします。大丈夫な方だけ、どうか本文へお進みください。
完全に趣味の世界になってしまってすみません(汗)。
また書きあげられるように頑張ります。
序
それは、うららかなある日の午後の事だった。
キョウジがたまたま通りかかった道の端っこで、誰かが座り込んでいる姿が見える。
(…………?)
見るともなしに何となく視線をそちらに走らせたキョウジは、座り込んでいる人物の正体を知って唖然としてしまう。それは――――『龍の忍者』と異名をとり、人から『超忍』と称され、その存在すら伝説とされている『リュウ・ハヤブサ』の――――しょげくりかえった姿だったからだ。
「ハ、ハヤブサ? ど、どうしたんだ?」
「キョウジ……」
思わず声をかけてしまったキョウジに―――ハヤブサは、この世の終わりの様な眼差しを向けて、応えた。
第1章
「どうしたんだ? ……と、事情を聴いても?」
近くにあった自販機で買って来たコーヒーを差し出しながら、キョウジはハヤブサの横に立つ。キョウジから差し出されたコーヒーの温かさに、ハヤブサは少し息を吐いた。
「………2週間……」
ポツリ、と、ハヤブサが零すように呟く。
「?」
「……もう、2週間……シュバルツに触れてない……」
「――――ッ!」
キョウジは思わず飲みかけていた缶コーヒーを噎せそうになった。て言うか、噎せた。
ゲホゲホと咳き込むキョウジの横で、龍の忍者が深~いため息をついている。
「何故だ……シュバルツ……」
「ああ……まあ、うん……」
シュバルツがハヤブサの出身地でもある『隼の里』に赴いた時から、キョウジは二人が「そう言う」関係になるのだろうな、と言う事は、何となく予測はしていた。しかしいざ、それを目の前に突きつけられると、軽く動揺してしまうのは何故なのだろう。
呼吸を落ちつけながら、平静を取り戻そうと努力するキョウジの横で、ハヤブサが尚も零すような言葉をつづけていた。
「………『里』にいた時は……あんなに触れさせてくれたのに……」
ハヤブサ自らが傷を負い、里が甲賀忍軍に襲われた時、シュバルツは助けてくれた。そして彼は、ハヤブサの傷が癒え、被害を受けた里の復興のめどが立つまで、里に留まり続けてくれた。
そして里では、シュバルツはハヤブサの『恋人』と言う扱いになっていたが故に、褥が同じだった。
流石にハヤブサの傷が完全に癒えるまでは、シュバルツはその身体をハヤブサに赦そうとしなかったが、傷が治ってからは―――逃げ場が無い事も手伝ってか――――ハヤブサが望めば抱かせてくれた。何と言っても褥が同じなのだ。愛おしいヒトがすぐ傍にいて、ハヤブサの理性がそうそう保つはずもない。
3日と空けずにシュバルツを求め、抱いた。
自分の腕の中で妖艶に乱れ、花開くシュバルツの姿を、ハヤブサは今でも鮮明に思い出す事が出来る。
でも、足りない。
彼に触れれば触れるほど――――もっともっと欲しくなる。
できればずっと、触れていたい。そう、望んでしまうほどに。
だが、里から出てキョウジの元に戻ったシュバルツは、以前にも増して触れさせてくれなくなってしまった。その身体を抱く事はおろか、口付けすらも、なかなか許してはくれない。あの里で過ごした蜜月期が、夢だったのはないかと、思えるほどに―――だ。
「シュバルツは俺の事が……嫌いになってしまったのか……」
そう言いながらハヤブサは、膝を抱えて座り込んで、地面に『の』の字を書いている。とても『伝説の龍の忍者』とは思えないほどの、情けない姿だ。
「いや…? シュバルツは……ハヤブサの事を『嫌い』とか、思っている感じでは……なかったけれど……?」
里から帰ってきたシュバルツが、キョウジに里の様子やハヤブサの事を話す時、彼の表情がとても優しいものになるのを、キョウジはずっと見ていた。里で過ごした時間は、確かに彼にとっては幸せな物だったのだろうと、キョウジには感じられて、嬉しかった。だから、キョウジはハヤブサに、思わずそう言ってみたのだが。
「なら何故……シュバルツは……。俺に、触れさせてはくれないんだ……」
「そ、それは……」
「さっきも……『せめて口付けだけでも』って……頼んでみたのに……」
そう言いながら暗いオーラを纏って、地面に『の』の字を書き続けるハヤブサ。聞かなくてもはっきりと断られた事が分かる。それこそ、気の毒なほどに。
「ま、まあ……シュバルツにも……いろいろ思う所が、あるんだろうね……」
気を取り直して、キョウジはハヤブサにそう声をかけてみる。シュバルツがハヤブサに身体を許さない理由が、キョウジには何となく察せられたから―――。
「……構わないのに……」
ハヤブサは、ポツリと言った。
「え?」
「……構わないのに……。俺は……シュバルツになら……殺されても……!」
「…………!」
「いっそ殺してくれれば良いのに……! このまま触れる事を許してくれないのなら―――!」
「ハヤブサ……」
そう言って下を向いて震えるハヤブサの姿を、キョウジは黙って見つめるよりほかは無かった。
そこまで思いつめているのならば、シュバルツの代わりに私を抱くか?
キョウジは、思わずそう言いそうになる。
だが止めた。
キョウジがそう言った所で、ハヤブサからは断られる事が目に見えていたからだ。ハヤブサが抱きたい、と、思っているのは、あくまでも『キョウジ』ではなく『シュバルツ』なのだから―――。
(不思議な縁だよなぁ)
キョウジは改めて思う。
自分が『シュバルツ』を創らなければ――――こうして、龍の忍者と話をすることもなかったであろう。シュバルツと自分は、ベースとなっている人格は同じだ。しかしやはり、何かが『違う』
そして、その『違う』部分に――――ハヤブサは強く惹かれているのだろう。
「……済まないな。醜態を、見せた……」
そう言うとハヤブサは、立ち上がった。
「気休めにしかならないかもしれないけど、その……元気、出して……」
歩き出したハヤブサの背中に、キョウジの声が追いかけてくる。その声に、ハヤブサは軽く右手を上げて答えた。しかしその立ち去っていく背中が、どことなく淋しげだ。
ゴン!
しかも電柱にぶつかって、頭を抱えている。
(だ、大丈夫かな……)
よろめきながら立ち去っていく龍の忍者を、キョウジは心配しながら見送っていた。
キョウジが家に帰りつくと、シュバルツが既に部屋の中にいた。腕を組んで壁にもたれかかり、ムスっとした顔をしている。何となく機嫌が悪そうだった。
(まあ、機嫌が悪い理由は……多分……)
キョウジは苦笑しながらも何気ない風を装って、シュバルツに声をかける。
「シュバルツ、帰ってたのか」
「ああ」
こちらに振り向きもせず、短い返事で答えるシュバルツ。やはり、機嫌は少し悪そうだ。だがキョウジは、そんなシュバルツをちょっとつついてみる事にした。
「さっきそこでハヤブサに会ったぞ」
「ハヤブサに?」
案の定、『ハヤブサ』と言う単語に反応してくるシュバルツ。キョウジは苦笑しながらも、更に言葉を重ねた。
「道端に座り込んでたぞ?」
「…………!」
「しかも、地面に『の』の字を書いてた」
「―――――!」
キョウジの言葉にシュバルツは一瞬絶句してから、深いため息を吐いた。
「ハヤブサ……! あの馬鹿!」
思わず、小さく毒づく言葉が出てしまう。
「……拒んでるのか?」
切り込んできた様なキョウジの言葉に、シュバルツは咄嗟に返事出来ない。瞳と唇が僅かに震え、彼はキョウジから目を逸らしてしまった。
(やっぱり、そうか……)
そんなシュバルツの様子に、キョウジもまたため息を吐いた。
「『口付け』ぐらい……許してやっても―――」
「駄目だ!! 分かっているだろう!? 私の身体は―――!!」
「シュバルツ……」
「――――ッ!」
今ここで何かを叫んでしまったら、たとえそれがどんな言葉であってもキョウジを責める事になってしまう。そう感じたシュバルツは、口をつぐんでしまった。
もう何度、夢を見た事だろう。
ハヤブサに抱かれるたびに、かなりの頻度で見てしまう『悪夢』
自分の横で眠っていたハヤブサが呻きだしたかと思うと、その皮膚がDG細胞によって、たちまちのうちに金属化して行き――――
「クククク……! フハハ! ヒャハハハハ!!」
脳まで達したDG細胞が、ハヤブサの人格を破壊し――――狂ったように嗤いながら『里』を攻撃して行く……夢。
自分のせいで。
自分なんかを、抱いたせいで。
駄目、だ。
ハヤブサ
駄目―――――!
「……ルツ! シュバルツ!!」
うなされていたのだろう。ハヤブサに起こされて、その夢は終わる。
「あ………!」
視界に飛び込んでくるハヤブサの顔を見て、シュバルツから安堵のため息と涙が零れる。それを見たハヤブサの表情が、切なそうに歪む。
「そんな風に泣くな……シュバルツ……」
ハヤブサの唇がシュバルツの涙を、そっとすくい取った。
「お前は独りじゃない……俺が、傍にいるから――――」
そう言いながら再び覆いかぶさって来る、ハヤブサの熱い身体。
「んっ……あ……!」
拒まなければならない、と、理性は訴えてくるのに、それよりも早くハヤブサの熱がシュバルツを捕らえてしまう。
「駄目、だ……! あっ……!」
愛シテイル。
愛シテイル。
愛シテイル。
奔流となって流れ込んでくる、ハヤブサの『想い』は、シュバルツから抵抗の意思を奪うには充分過ぎて。ハヤブサに愛を教え込まれた身体は、彼の愛撫に反応して、容易く火をつけられてしまう。
「んあっ! ああ……ッ!!」
後はもう、何も考えられなくなってしまって――――。
「だけど……ハヤブサの事を『嫌い』と言う訳じゃ、ないんだろう……?」
キョウジのその言葉に、一瞬こちらに視線を走らせるシュバルツ。怒鳴られるんじゃないか、と、感じたキョウジは思わず身構えてしまう。
だがシュバルツは、小さくため息を吐くと、静かに呟いた。
「そうだな……。『嫌い』じゃない……」
嫌いじゃない。
『嫌い』じゃないから、厄介だ。
ハヤブサが望む事ならば、何だって叶えてやりたい。それが、自分に出来ることであるのならば。
だけど、ハヤブサが望むのは――――自分と深く繋がること。
心も。そして、身体も―――。
心はともかく身体は――――危険すぎるとシュバルツは思う。
自分の身体を構成しているDG細胞が、何時ハヤブサにその牙を剝くか、分からないからだ。
「それでも構わない」
そう言って笑いながら、手を差し伸べてくるハヤブサ。
本当に命かけて、自分を愛してくれているのだと分かる。
だから自分も、『同じ物』をハヤブサに返したいと思って――――。
返せる『モノ』が、何も無い事に、気づく。
ハヤブサが望むのならば、手でも足でも目でも心臓でも――――おそらく自分は差し出す事が出来るだろう。でも、それは自分の身体から斬り落とした所で、また生えてくるような代物だ。そんな物に、一体何の価値があると言うのだろう。
命が無い、まるで空虚な器。
ハヤブサはそれに向かって、『愛』を囁いている様なものだ。
それどころか、『DG細胞に感染しかねない』と言うリスクまで、背負わせてしまっている。
生命に生命で以って答える事が出来ないのに。
同じ『愛』を、返す事が出来ないのに。
それなのにどうして。
どうしてハヤブサは―――――。
「シュバルツ……」
キョウジが小さくため息を吐きながら、言葉を続ける。
「世の中には……『DG細胞に感染しない人間』と、言うのも、いるんだぞ…?」
「――――!」
驚きで目を見開いたシュバルツは、思わず問い返していた。
「……そんな人間が、いるのか?」
「いる……。少なくとも、私は1人、知っている……」
「誰だ? それは……」
「お前も知っている人間――――東方不敗、マスターアジアだ」
「――――!!」
先の『デビルガンダム事件』の際、東方不敗はデビルガンダムを己の野望のために利用しようとしていた。故に、彼はデビルガンダムの近くにいた。DG細胞に、常に取り囲まれていた。
「だが、マスターは……最後までDG細胞に感染する事は無かった」
「それは……確かなのか?」
「そうだ……。私はこの話を、弟のドモンと―――マスター本人から、聞いた……」
―――あの細胞はもしかしたら、強い精神力を持っているものならば、その感染を、撥ねのける事が出来るのやもしれん。
キョウジと将棋をさしながら、東方不敗はポツリと言った。
―――お主も強い心を持っていたからこそ、暴走する細胞を抑えつけて『シュバルツ』を創る事が、出来たのであろう?
キョウジは、東方不敗のその言葉に返事を返さなかった。
ただ、DG細胞が心に感応する物であることは事実なのだ。
「マスターとハヤブサの戦いの技量はほぼ互角だ……。だから、もしかしたらハヤブサも」
「やめてくれ!!」
キョウジの言葉を、シュバルツの叫ぶような声が遮る。
「そんな……憶測で物を言う様な事は、やめてくれ……! キョウジらしくも無い……!」
キョウジらしくも無い――――シュバルツにしては珍しく、詰るような物言い。だが強く握りしめられたその拳が、震えていた。
「ごめん……悪かった……」
自分のうかつな言葉が、シュバルツを激しく動揺させてしまったとキョウジは悟った。DG細胞はシュバルツの根幹を握り込む物だけに、僅かな『希望』を持つことすらも、シュバルツにとってはとても困難な事なのだろう。
「いや……いい。済まない……私こそ……」
逆に謝ってくるシュバルツを、キョウジは少し淋しい想いで見つめる。
もっと、責めてくれていいのに。
自分は、それだけの事を言ったし、それだけの事を、してしまったのだから――――。
だが、シュバルツはその拳の震えを、もう収めてしまっていた。そして、キョウジと視線を合わせる事もしない。ただ静かにそこに佇んでいた。
いつもそうだ。
シュバルツは、どんな事があっても―――決してキョウジを責めようとはしない。
―――何故なのだろう。
責められないのか。
それとも、責めたくないのか――――。
(もっと……いろいろな事を『他人のせい』にする事が出来たら……少しは楽に生きられるのだろうか……)
何もかもを、自分で背負いこんでしまうシュバルツ。でも、それは、自分に対しても言える。ある意味融通の利かない性格に、キョウジも苦笑するしかなかった。
「……複雑だよな……。お互いに……」
深いため息と共に、キョウジはデスクに向かって座りなおす。キョウジから零れ落ちた言葉に、シュバルツから反応が帰ってくる事は、無かった。
それから幾日か過ぎた朝。手に白い封筒を持ったキョウジが、シュバルツに声をかけてきた。
「シュバルツ~。ちょっとお願いがあるんだけど……」
「どうした? キョウジ……」
天井裏から顔を出してきたシュバルツに特に驚きもせずに、キョウジは言葉を続ける。
「悪いんだけどさ…。ちょっとこの封筒を届けてくれない?」
「誰に?」
「ハヤブサに」
「―――――!!」
今、ある意味シュバルツが最も会いたくない人間の名前を聞いてしまったためか、彼の顔が引きつる。対してキョウジの方は、にっこりと微笑んだままだった。
「どうしても、彼に頼みたい事があってさ…。悪いんだけど」
そう言いながら、シュバルツに向かって白い封筒をずいっと差し出す。しかしシュバルツは、その封筒から距離を取る様に、一歩身を引いた。
「な、何で私がわざわざ……! お前がハヤブサに直接渡す手段はないのか?」
「あるにはあるんだけど……」
「じゃあ、それをすればいいだろう!? 私は遠慮させてもらう!」
「えっ? 何で?」
「何でって……! 分かっているだろう!? 今、私はハヤブサに会いたくないんだ!!」
(あちゃ~……)
今この場にハヤブサがいなくて良かったとキョウジは思った。もしも彼がいて、今のシュバルツの言葉を聞いたら、穴を掘って、その底に『の』の字を書きだしてしまうかもしれない。
「……でもなぁ、直接渡す手段と言うのが、ちょっと……」
「……どうした? 何か不都合でもあるのか?」
少しそれをするのを躊躇っているように見えるキョウジに、シュバルツは首をかしげる。対してキョウジは「大丈夫かな?」と、窓の外を見ていた。
「今は人通りも少なそうだから、通報される事は無いと思うけど……じゃあ、ちょっとやってみるよ?」
そう言いながらキョウジが窓の外に向かって「ピ~~~!」と、強く口笛を吹く。
すると。
10羽ぐらいの隼が、一斉に茶色い塊となってキョウジに向かって突進してきたのだ。
「な――――!!」
驚くシュバルツの目の前で、バサバサバサッ! と、激しい羽音が響いたかと思うと、あっという間にキョウジが隼まみれになってしまう。
「こういう事になるから―――ちょっと、遠慮したかったんだ」
身体のあちこちに隼を止まらせているキョウジが、その羽根の間から苦笑しながら言った。
「こ、こら!! お前たち! キョウジから離れろ!!」
シュバルツが叫ぶと、隼たちは一斉にキョウジから離れ、再び窓の外に飛び立って行く。
「ぷはぁっ! ありがと、シュバルツ。助かった……」
そう言いながらキョウジは、自分の身体についた隼の羽根を、パタパタと払っていた。
「キョ、キョウジ……! これは一体――――」
茫然と問い返すシュバルツに、キョウジののんきな声が返って来る。
「ああ……最初は1羽しかいなかったんだけど――――」
ある日、キョウジがいつもの様に読書をしていると、窓際に1羽の隼が飛来してきた。よく見ると、足に文がくくりつけられていた。
――――お前の周りに隼を待機させておく。俺に何か用がある時は、口笛を吹け。
ハヤブサからの伝言であると悟ったキョウジは、「了解」と付文をして、その隼に託した。それが最初のやり取りだった。
「だけど、日が経つごとに隼の数が増えてきちゃっているみたいで――――今じゃ、あんな有様に……」
「…………ッ!」
呆れかえったシュバルツは、空いた口が塞がらなくなるのを感じる。
「あの馬鹿…! 『加減』というものを知らんのか? ちょっと文句を言わないと―――!」
「おっ!? 『文句』を言いに―――会いにいくのか?」
じゃあ、ついでにこれを頼む、と、キョウジが再び白い封筒をずいっとシュバルツに差し出してくる。それを見たシュバルツは、ぐっと言葉に詰まった。
「い、いや……会いには行かない…。行ける訳無いだろう……!」
そういって、再びそっぽを向いてしまうシュバルツ。やれやれ、と、キョウジは肩をすくめた。
「会いに行ってあげれば良いのに……。きっと、ハヤブサは喜ぶと思うよ」
会いたい。
シュバルツに会いたい――――。
ハヤブサはそう思いながら、あの鳥たちを放している様な気が、キョウジにはしてならない。
きっと、あの鳥の数は、ハヤブサのため息の数なのだ。
ハヤブサがシュバルツを『好きだ』と、想う気持ちは、もっと単純で――――明快な物ではないかと、キョウジは思っている。
「駄目だ…! 私は、会う訳にはいかない……!」
しかしシュバルツは、頑なに頭を振る。
ハヤブサに会ってしまったら、彼の『熱』を拒めない自分は、また流されるままに彼に身体を許してしまいかねない。それは、ハヤブサにDG細胞に感染するリスクを、また背負わせてしまう事を意味する。
今まで無事だったからと言って、次も無事とは限らない。
自分にとってハヤブサは、とても大事な存在だ。
大事だから――――。
『DG細胞』と言う闇に、彼を巻き込んでしまいたくなかった。
「………分かったよ、シュバルツ……」
キョウジは大きなため息を一つ、吐いた。
「じゃあこの手紙は、あの鳥たちに渡す事にするから……せめて、合図の口笛は、お前が吹いてくれないか?」
「……私が呼んでも、あの鳥たちは来るか……?」
「来るさ。来ると思うよ。絶対」
キョウジは確信する。あれだけ訓練されている隼たち。まして、呼ぶ相手がハヤブサが愛おしく思っているシュバルツなのだから、何を置いても飛んでくるだろう。
いや、もしかしたら――――。
「………………」
しばらく何かを逡巡するかのように窓の外を見ていたシュバルツであったが、やがて意を決したように顔を上げた。
「キョウジ、ちょっと離れていろ」
シュバルツはそう言うと、窓の外に向かって思いっきり、口笛を吹いた――――。
「…………!」
鳥たちが襲来すると思って、シュバルツは軽く身構える。しかし、何故か一向に、隼たちは姿を現さなかった。
「…………?」
不思議に思ってシュバルツとキョウジが窓の外を覗き込むと同時に、凄まじい勢いで足音が近づいてくる。その足音は家の玄関の前まで達すると、壊れるのではないかと思うぐらい、勢いよくバン!! と、ドアを開け放った。
「今――――! 今、俺の事を呼んだだろう!? シュバルツ!!」
驚いた二人が振り返ると、息せききって走ってきたと思われるハヤブサの姿が、そこにあった。
「今――――俺の事を呼んだよな!? シュバルツ!!」
そう言いながら龍の忍者は、一応靴は脱いでからドカドカとキョウジの家に上がり込んでくる。余程全力で駆けてきたのだろう。彼の弾んだ息は、まだ整いかねていた。
「ち、違う!! 呼んだのは『お前の隼』であって――――!」
シュバルツは少し後ずさり気味になりながら答える。だが龍の忍者は『逃がさない』とでも言わんばかりに彼に詰め寄ってきた。
「『俺の隼』を呼んだのなら、『俺』を呼んだのと同義だ! だから来たんだ!」
(そりゃそうだよな)
と、苦笑うキョウジの目の前で、シュバルツはハヤブサによって壁際に追い詰められてしまう。
「何の用だシュバルツ……。会いたかったぞ……」
「ま、待てっ! ハヤブサ…! 何故私がお前を呼んだと思ったんだ!? キョウジの口笛かもしれないじゃないか!」
「俺の耳を見くびるな…! お前の口笛とキョウジの口笛を、聞き分けられないとでも思っているのか?」
「な、何を根拠に――――」
しどろもどろになりながら言葉を紡ぐシュバルツに、龍の忍者はにやりと笑いかける。
「『音』だ」
「音?」
「キョウジの口笛と、お前の口笛では――――音の高さが違う。そうだな……お前の方がちょっと低い。ほんの2ヘルツぐらいの違いだが――――」
「そんな微妙な違いを聞きわけたりするなッ!!」
ハヤブサの言葉に真面目に背中に悪寒が走ってしまったシュバルツは、思わずハヤブサを殴り倒していた。
「……忍者の耳がいいのは誇るべき事ではないか!! 何故、それを怒られなければならないんだ!?」
殴り倒されたハヤブサだが、すぐに起き上がってシュバルツに抗議をしだした。
「『耳がいい』と言うのはそう言う類の物じゃないだろう!? 遠くで落ちた針の音を聞くような、そんな耳の良さのはずだ!!」
「『誰が』合図を発したとか、そういう細かい所も聞き分けられなければ――――一流の忍者とは言えないと思うが?」
「――――ッ!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは返す言葉を失ってしまう。それを見たハヤブサは、にやりと笑って更にシュバルツに詰め寄ってきた。
「……心配しなくても、俺がここまで聞き分けられるのは、『お前』だけだ……」
「な…………!」
「お前の声……お前の言葉……絶対に、聞き違えるものか……」
「あ………!」
後ろに逃れようとしたシュバルツの背にドン、と壁が当たって、彼はこれ以上引き下がれなくなってしまう。そこにハヤブサの手が伸びて来て、左右の逃げ道も塞がれてしまった。
「会いたかった、シュバルツ……」
ハヤブサがそう言いながら、熱い眼差しでシュバルツを見つめてくるから、シュバルツは少し慌ててしまう。
「ちょ、ちょっと待て…! ハヤブサ……!」
「シュバルツ―――」
ハヤブサの手が、シュバルツの頬に伸びようとしたその瞬間。
「あの~……お取り込み中、すみませんが……」
それまで黙っていたキョウジののんきな声が、割って入ってきた。
「ごめんね? ハヤブサ。用があるのは私の方なんだ」
「えっ?」
驚いた様にキョウジの方に振り返る龍の忍者に、キョウジが済まなさそうな笑みを浮かべる。
「えっ? だって…! さっきの口笛は――――!」
「……私はキョウジに頼まれて、吹いただけだぞ」
憮然とした表情でシュバルツにそう言われ、ハヤブサはようやく状況を理解する。彼はたちまちのうちに―――――気の毒なほどに落ち込んで行った。立っていられなくなってしまったハヤブサが、がっくりと床に膝を付いている。
「……そんな、あからさまに落ち込まなくても……」
そんなハヤブサの様子を、キョウジは苦笑いながら見守っていた。
「それはそうだよな……。シュバルツが、俺なんかに用事がある訳ない……」
暗いオーラを纏った龍の忍者が膝を抱えて、ブツブツ言いながら床に『の』の字を書きだしている。
「どうせ、俺なんか……シュバルツに口付けの一つも許してもらえない……駄目な忍者なのだから………」
「だ、だから、それは――――!」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツが反応を返しかける。それに敏感に反応したキョウジとハヤブサが、一斉にシュバルツを見るから――――シュバルツは、またそっぽを向いてしまった。
ハヤブサから、深~~いため息が漏れる。
「……何の用だ……。キョウジ……」
(それだけ落ち込んでいても、一応用件は聞いてくれるんだ……。優しいと言うか、真面目だよなぁ……)
「まあ、用って言うのは『これ』なんだけど……」
そう言いながらキョウジは、先程から手に持っている白い封筒をひらひらと振ってハヤブサに見せた。
「はい、シュバルツ」
そしてそれを、キョウジはおもむろにシュバルツに渡そうとする。
「お、おい!? キョウジ…!」
驚くシュバルツを尻目に、キョウジはハヤブサに語りかけ続けた。
「私の用件を書いた手紙をシュバルツに渡しておくから――――後で、二人で見てくれないか?」
「――――えっ?」
何となく風向きが変わったような気配を感じたハヤブサが、思わず顔を上げる。逆に、シュバルツの方が、少し慌てていた。
「お……! おいキョウジ…! 私は――――!」
「……こうしてハヤブサが来てくれたんだ…。まさか、今更ぐだぐだ言ったりはしないよな?」
そう言いながらキョウジは、あくまでもにっこりと笑顔でシュバルツに白い封筒を差し出す。それを見たシュバルツは、ぐっと言葉に詰まってしまった。
「ほら、シュバルツ」
キョウジから半ば強引に押し付けられた白い封筒を――――シュバルツはついに、拒否し切れなくなってしまった。渋々ながらも封筒を受け取ったシュバルツを見て、キョウジは嬉しそうに頷いた。
「―――と、言う訳だから、ハヤブサ。後は、よろしくね」
「えっ? あ……ああ……」
何だか目の前で起こっている展開が、ハヤブサにとってはとても嬉しい展開になっている様な気がしてしまって、彼は逆に戸惑ってしまう。正直、キツネにつままれたような気分だ。
良いのだろうか?
シュバルツと一緒に行動させてもらえるなんて――――自分には幸せすぎる展開なのだが。
対するシュバルツは、白い封筒を手に、複雑な表情をして佇んでいた。
「シュバルツ……ハヤブサがその手紙を読み終わるまで、彼の傍から離れちゃ駄目だよ」
「―――――分かった……」
深いため息と共に返事をするシュバルツに、キョウジはもう一度「シュバルツ」と、呼びかけた。
「ちゃんと伝えなきゃ……伝わらない事も、あるんだよ」
「………!」
キョウジの言葉に、シュバルツはピクリ、と反応する。その横で、ハヤブサが怪訝そうな表情を浮かべながら、キョウジを見つめていた。
何だろう?
キョウジは何を、俺に言わんとしているのだろうか?
だがキョウジは、ハヤブサにその意図を読み取る時間を与えはしなかった。「よしっ!」と、短く一声上げて顔を上げると、強引に忍者二人の背中を押して、部屋から追い出す態勢に入ってしまう。
「じゃあ二人とも、行った、行った! 私は今からプログラムを組み上げる作業を始めるから――――邪魔をしないでくれるか?」
「お、おいキョウジ……?」
シュバルツの戸惑いの声も空しく、キョウジの部屋から忍者二人が出た途端、その部屋のドアはバタン、と、音を立てて閉められてしまった。
「…………」
茫然とドアを見つめるシュバルツの横で、ハヤブサは軽くため息を吐きながら頭をポリポリと掻く。何だかよく分からないが、どうやら自分は、この後のシュバルツを見守る事を、キョウジから任されたような気がしないでもない。
「――――仕方が無い。シュバルツ、行こう」
ハヤブサがシュバルツに声をかけると、彼は短く「ああ」と、返事をして、大人しく後からついて来てくれた。
「……………」
忍者二人が連れ立って歩いて行くのを、キョウジは窓からそっと見送っていた。
ハヤブサは、たいへん分かりやすくシュバルツの事が好きだ。
そして、おそらくシュバルツも――――。
二人は、両想いなのだ。
だけど、シュバルツの方が、ハヤブサの事を愛するのを躊躇っているようにキョウジには見える。
自分の身体の歪さゆえに。
自身を蝕む闇の、根深さゆえに。
愛したいのに愛する事が出来ないのは、とても哀しい事だとキョウジは思う。
ハヤブサは常に、シュバルツに向かって手を伸ばしている。その手を、シュバルツも取る事が出来れば良いのに。彼が、闇に呑まれて――――何もかもを、押し殺してしまわないうちに。
自分とはまた違った方向から、シュバルツに手を伸ばし続けるハヤブサ。その愛情が、シュバルツには必要になって来るのだ。これから彼が、人間の世界を生きて行く上でも。
だから、彼が怯えずに、ハヤブサの手を取る事が出来るようになる様に。
愛する事を躊躇わずに済むように――――。
「……研究、頑張るとするか……」
キョウジはそう独りごちると、書斎のデスクに座りなおす。パソコンのセキュリティを解除して、自分しか閲覧できない極秘資料にアプローチを開始した。
(DG細胞が『禁忌』でさえなければ……もっと、大っぴらに研究出来て、いろいろな発見も早まるのだろうけど……な……)
ため息を吐いてみるが仕方が無い。DG細胞の危険性は、キョウジも嫌と言うほど承知している。また、あんな悲劇を起こす訳にはいかないのだ。
(今日設けた、二人で過ごす時間の間に――――少しでも、互いの想いを伝えあえたらいいのだけれど……)
今、シュバルツはハヤブサに対して心を閉ざしかけている。このままではハヤブサの想いは空回るばかりで、互いに辛いばかりだろう。
シュバルツはハヤブサに対して少し心をぶつけるべきだと、キョウジは思う。
恐れる事は、何も無いはず。
だって、二人は『両想い』なのだから。
ハヤブサはきっと、シュバルツの想いを受け止めてくれるはずだ。
自身でドリップしたブラックコーヒーを口に含みながら、キョウジはパソコンの画面に集中して行った。
「……もう、そろそろいいんじゃないのか?」
キョウジのアパートから近郊にある、二人がいつも会っている森まで歩いてきたハヤブサは、シュバルツの方に振り返った。尤も、最近はシュバルツがここに来てくれる事は無かったから、二人で来るのはずいぶん久しぶりだとハヤブサは思った。
「ああ………」
シュバルツは相変わらず、複雑な表情をしながら、白い封筒を見つめている。そんな彼の佇まいすら、美しい、と感じてしまうから――――自分はよほど、『重症』なのだろうな、と、ハヤブサは己を苦笑っていた。
こうして、二人で歩いている道中だけで、ハヤブサは充分幸せだった。
本当はもう少し、彼に近づいて、触れたいのだけれど――――。
シュバルツがそれを望んでいないから、無理強いは出来ないとも思う。それよりも、今この瞬間の幸せを、少しでも長続きさせたいと、ハヤブサは願っていた。
シュバルツは、ハヤブサに白い封筒を渡そうとして、少し躊躇ってしまう。
(何故だ? キョウジ……。何故、こんな回りくどい方法でハヤブサに伝言を頼もうとする?)
キョウジの意図が、いまいち読み切れなくて、シュバルツは困惑してしまう。
『影』として、キョウジに関する事は何でも把握しておくべきだと思うのに、時々彼の事が分からなくなってしまうから、その対処に困る。
何故なのだろう。
相手は、ある意味『自分』で、元は、同じ人格のはずなのに――――。
「シュバルツ」
ハヤブサの、自分を呼び掛ける声に、シュバルツははっと我に返る。
「あ……ああ、済まない」
慌ててシュバルツが差し出した白い封筒を、ハヤブサは受け取った。
ガサガサと、ハヤブサが封筒を開ける音がする。シュバルツは、少し離れた所からそれを見守った。キョウジが書いた手紙の内容がとても気になるのだが、キョウジが手紙を送った相手はあくまでもハヤブサなのだ。それを、自分が勝手に読む訳にはいかないと、シュバルツは真面目に思っている。
「……………」
しばらく無言でその手紙を呼んでいたハヤブサであったが、やがて「ほう!」と、声を上げた。そして顔を上げたハヤブサが――――シュバルツの方を見て『にこり』と笑うから、シュバルツはきょとんとしてしまう。
「な、何だ? ハヤブサ……」
「シュバルツ。ちょっとこちらへ来て、お前もこの手紙を読んでみろ」
「…………?」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツも恐る恐る手紙を覗き込んで見る。それにしても、若干嫌な予感がしてしまうのは、何故なのだろう。
「……………」
しばらく無言で手紙を読んでいたシュバルツであったが、やがて「な――――!」と、声を上げてしまう。
「……キョウジはどうやら、俺に実験の『被験体』になって欲しいようだな」
「……馬鹿な…! キョウジ――――何を考えているんだ……!」
手紙のあまりの内容に茫然としてしまうシュバルツ。しかもその手紙には、こう続けられていた。
――――もちろん、『被験体』として身体を張ってもらう貴殿には、こちらからもそれなりの『報酬』を用意させてもらう。その『報酬』と言うのは――――
「『私を1日自由にして良い権利』だとォ!!?」
シュバルツは思わず、素っ頓狂な声を張り上げていた。
「なッ……! キョウジ――――こんなめちゃくちゃな……! おいっ! ハヤブ……サ………」
ハヤブサの方に振り返ったシュバルツの目が、点になってしまう。文字通りハヤブサが『舞い上がって』いたからだ。彼はものすごくいい笑顔をしながら踊る様に木に登って行っている。気のせいか、ハヤブサの周りに、花が飛び散っているようにさえ見えた。
「おいこらハヤブサ!! 降りて来い!!」
シュバルツの怒鳴り声に、ハヤブサもはっ! と我に帰った。
「ああすまん。つい、心の声が表に出てしまったようだ」
龍の忍者がそう言いながら、ストン、とシュバルツの目の前に降りてくる。その表情は真顔だが――――彼の周りには、飛び散った花の名残が漂っていた。
「…………で、どうするんだ? ハヤブサ。このキョウジの依頼を―――」
「どうするもこうするも――――」
シュバルツからの問いかけに、ハヤブサも『にやり』と笑みを返して答える。
「何と言っても、『キョウジ』からの頼みだ。それに、『報酬』も悪くない。――――流石はキョウジだ。どういう風に頼めば俺が頷くか、よく分かっている」
「な……! キョウジの『被験体』になるつもりなのか!?」
「『お前』次第だがな」
驚くシュバルツに、ハヤブサがずいっと詰め寄って来る。
「シュバルツ……まさかお前、『キョウジの研究に協力しない』なんてことはないよな?」
「――――ッ!」
痛い所を突かれて、シュバルツはぐっと言葉に詰まってしまう。キョウジが望む事ならば、自分も何だって協力してやりたい。だけど――――。
「だ、だが……『被験体』になるなんて――――!」
「どこぞの得体の知れないマッドサイエンティストならともかく……キョウジが、本当に俺の命を危険にさらすようなレベルで『実験』をする、とでも思っているのか?」
「う……! そ、それは……」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは反論の余地を失う。
確かにそうだ。キョウジは、自分の身体にはある意味容赦をしない男だが、他人の身体には人一倍気を使う。そのキョウジが他人の身体を使って『実験』をするのであるならば、その被験体のヘルスケアには、充分な注意が払われる事になるだろう。
「だから、俺の方には何も問題は無い。キョウジに協力する事も、やぶさかではない。だから後は――――『報酬』であるお前次第なんだ」
「…………!」
尚も詰め寄ってくるハヤブサから距離を取ろうとして――――シュバルツの背は、大きな樹の幹に阻まれてしまう。それを見たハヤブサは優しく笑いながら、そっと左手だけをその木の幹にトン、と置いた。
退路はわざと開けておいてやるが、シュバルツが逃げられない事をハヤブサは知っていた。自分は今――――シュバルツに対して『キョウジ』を人質に取っているも同然なのだから。
「もし、お前が『報酬』になる事を拒否すると言うのであれば、『龍の忍者』の身体を被験体として使用する『正当な』報酬額を、キョウジに請求する事になるが――――」
「正当な額……。い…いくらだ?」
生唾を飲み込みながら聞き返してくるシュバルツに、ハヤブサは笑顔を見せながら答える。
「そうだな……。実験内容にもよるが、下手をしたら億単位になるぞ?」
「お……億!?」
「当たり前だ。『龍の忍者』の身体の使用料は安くない。俺を雇おうと言うのであるならば、それぐらいが妥当だと思うが?」
そうなのだ。シュバルツの前では割と隙だらけで、情けない姿ばかり見せているハヤブサであるが、その腕は『伝説』と称されるほど強い。ミサイル、ヘリ、戦車など、ものともしない。場合によっては神をも滅してしまう。シュバルツが本気を出して戦っても、勝てるかどうかと言うほどの――――強さだ。
「そ、それでも……億と言うのは……!」
「軍備を増強して一個師団を雇って襲撃を仕掛けるのと、刀一本で片をつけてしまう忍者と――――同じ目的を果たすにしても、コスト的にどっちが安いと思っているんだ。哀しいかなこれだけの値をつけても――――俺に仕事を依頼したいと思う奴は、結構いるんだよ」
「――――ッ!」
ハヤブサのある意味生々しい言葉に、シュバルツはぐっと返事に詰まってしまう。確かにそうだ。ミサイル一発、戦車一台に――――億単位で金が飛ぶ。ハヤブサは、そんな中で『仕事』をしているのだ。
そこにいるのは紛れもなく、闇の世界の住人―――の姿だった。
「キョウジにそれだけの額が、払えるか?」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは首を振るしかない。
小さいアパートでつつましやかな生活をしているキョウジに、そんな蓄えがあるとは思えない。
「キョウジも、それが分かっている。だから……報酬が『お前』なんだ。俺はその報酬で満足している。この話を受けてもいいと思っている」
「あ………!」
逃げ場も無く、追い詰められていくシュバルツを、ハヤブサは優しく見つめる。
「どうするんだ? シュバルツ……」
「うう………」
「『報酬』に………なってくれるのか、くれないのか」
「…………っ」
(それにしてもなぁ……)
シュバルツをじりじりと追い詰めながら、ハヤブサは思う。
(それにしてもどうして、自由にして良い期間が『1日』なんだ……。俺はシュバルツが相手だったら、その期間が3日でも1週間でも――――)
「何だったら1カ月でも一生でも構わないのに!」
「おいっ! 何だ! 『一生』って――――!」
シュバルツの怒鳴り声に、ハヤブサははっ! と、我に返る。
「ああすまん。考えが口から出てしまったようだ」
ハヤブサは慌てて真顔を取り繕おうとするが、目元が緩むのを、どうしても抑える事が出来ない。それを見ていたシュバルツから、深~~いため息が漏れる。緩んでいるハヤブサの顔に、いろいろと毒気が抜かれてしまったらしい。
仕方が無い。
報酬になる期間はたった『1日』
『1日』だ。
『一生』とかではないのだから――――。
「……分かったよ。ハヤブサ……」
「シュバルツ!?」
「1日……私を、お前の好きにすればいい」
「………ッ! やった―――――!!」
シュバルツのその言葉に、龍の忍者の心にようやく『春』が訪れたのだった。
歓喜に震えるハヤブサは、文字通りまた木の上に『舞い上がって』行ってしまっている。木のてっぺんまで達したハヤブサは、涙を流しながらキョウジに向かって祈りをささげはじめた。
(ああキョウジ…! ありがとう……! 俺はもう、お前に一生ついて行くからな……!)
こんな機会を恵んでくれたキョウジに、感謝せねばならない。ハヤブサの中で、キョウジに対する『なつき度』が、20 上がっていた!
「おいっ! だから何でいちいちそうやって木に上って行くんだ!! こらっ!! 降りて来んか――――!!」
木の下では、シュバルツが顔を真っ赤にしながら怒鳴り声を上げていた。
「ああすまん。つい歓喜に我を忘れてしまって―――」
そう言いながら龍の忍者が、ストン、と、シュバルツの目の前に降りてくる。だがその表情は、最早隠しようもない程の喜びに満ち溢れていた。その表情を見たシュバルツが、大きくため息を吐く。
(こいつ……馬鹿じゃないのか。何で私を自由に出来る時間と億単位の金が、こいつの中では同等の取引として成立し得るんだ。こんなの、割に合わな――――)
ドン!!
激しい音を立てて、ハヤブサの両手がシュバルツの両肩を掠めて背後の木に当てられるから、シュバルツの思考はそこで中断してしまう。驚いたシュバルツが顔を上げると、真剣な眼差しをしたハヤブサと、目が合った。
「じゃあ、シュバルツ」
「な、何だ? ハヤブサ……」
「この『報酬』……今から、受け取ってもいいか?」
「い、今から!?」
逃れようのない熱い視線の前に、シュバルツは戸惑ってしまう。思わず逃げ道を探してしまった。
「キョウジに報告をしに行くのが先では……」
「『プログラムを組む作業をする』と、言っていただろう? 今キョウジの所へ行っても、邪魔になるだけだ」
「あ………」
ハヤブサの言葉にシュバルツは、先ほどキョウジから、半ば強引に追い出されるように家を出されてしまった事を思い出す。あの態度は確かに、「すぐに帰って来るな」と、暗に言われているような感じでもあった。
「シュバルツ……」
ハヤブサの手が、そっとシュバルツの頬に触れてくる。
それと同時に流れ込んでくる、ハヤブサの心の声―――。
触レタイ。
抱キタイ。
愛シテル――――。
「…………ッ!」
(また……DG細胞の共鳴が……!)
シュバルツを構成している『心』に感応してしまうDG細胞が、ハヤブサの声なき声を拾って彼に聞かせてしまう。その声の熱さ、激しさに、シュバルツの身体がビクン、と、反応をしてしまった。
「シュバルツ……」
もう一度ハヤブサが、シュバルツに声をかけてくる。その声に、少し懇願の色が混じっていた。
「あ…………!」
『報酬』になる、と、頷いてしまったのは自分。逃れられない、と、悟る。
『1日』だけ。
『1日』だけ、なのだから―――。
シュバルツは、観念したように瞳を閉じた。
「ああ……分かっ――――んんっ!」
シュバルツの承諾の返事を最後まで聞かずに、ハヤブサはその唇を奪った。もう――――待ち切れなかった。
(ああ……! 2週間と3日ぶり、8時間と46分ぶりに味わうシュバルツの唇……ッ!)
その久しぶりの感触に、ハヤブサは酔った。そして、歓喜に震えた。
いつもなら、ここに至る前にシュバルツに逃げられてしまっていた。だけど、今から1日はそうではない。彼は逃げずに、抵抗せずに――――ここにいてくれるのだ。
シュバルツに飢えていたハヤブサは、貪るようにその唇を味わう。深いつながりを求める彼は、いつしかシュバルツの身体を背後の樹の幹に押し付けていた。
そしてなおも侵入してくる、ハヤブサの熱い舌。
「ん……ッ! んうっ……!」
(駄目だ……! 呼吸が――――!)
深すぎるキスに、シュバルツは無意識のうちに酸素を求めてハヤブサを振りほどこうとする。しかし、それを許さないハヤブサの唇が、一瞬離れたシュバルツの唇を追いかけて来て、また塞いでしまう。舌を絡め捕られ、強く吸われた。
「んんっ……! んく……!」
呼吸も思考も、徐々にハヤブサに奪われて行ってしまう。
愛シテイル。
愛シテイル。
愛シテイル。
流れ込んでくる想いの激しさに、眩暈がする。身体の力が抜けて行く。
駄目だ……! もう、立っていられな――――――。
ズ……ズ……と、音を立てて膝から崩折れて行きそうになるシュバルツの身体を、ハヤブサの力強い腕が支えた。
「おっと……! 大丈夫か?」
「……あ………」
涙で潤んだシュバルツの瞳と、視線があう。上気した頬に荒くなった呼吸。飲み切れなかった唾液のせいで、潤んでいる唇――――何度見ても、心を奪われてしまう美しさだ。
このまま朝まで、シュバルツの身体を思う様に蹂躙してしまいたいという衝動にかられる。恐らく、自分はそれが出来るとハヤブサは確信する。それほどまでに――――自分は、シュバルツに飢えていたのだから。
だが、そうではない。
ハヤブサは、頭を振る。
今ここで、シュバルツを蹂躙するように抱いても――――得られるのは身体だけだと言う事を、ハヤブサは知っていた。それでは、意味が無い。
自分は、両方欲しいのだ。彼の、『心』も、そして『身体』も―――――。
彼の総てを手に入れたかった。
だから――――。
「デートをしよう。シュバルツ」
笑顔でそう提案するハヤブサに、シュバルツは瞳をぱちくりさせる。
「デート??」
「そう。デート。まだした事が無かっただろう? せっかくお前が俺のために、1日時間を空けてくれるのだから――――」
「……え…? えっと……?」
予想とはだいぶ違った展開に、シュバルツは半ば肩透かしを食らったような気分になる。この状況。絶対にハヤブサは、自分を蹂躙するように抱いてくると思っていたのに。自分は今ハヤブサの『報酬』で、自分を好きにして良い権利を、彼は持っているのだから――――。
「そうと決まれば行こう! シュバルツ! お前と一緒に見たい物、お前と話したいこと…………山の様にあるのだから――――」
ハヤブサはそう言うと、嬉しそうにシュバルツの手を引っ張りながら、走りだしていたのだった。
第2章
ハヤブサがシュバルツとの『デート』に選んだ場所は――――京都だった。交通網の発達のおかげで、キョウジ達のいる東京からでも2時間強あれば着く事が出来る。秋たけなわの日本の古都は、紅葉もちょうど見頃だった。
「寺や神社を巡るついでに、骨董店に寄ってもいいか? 店主から、『良い品物が入った』と、連絡を受けているんだ」
「骨董店??」
きょとん、とするシュバルツに、ハヤブサは笑顔を返す。
「ああ。実は俺、アンティークショップを経営しているんだ。………言ってなかったか?」
「―――初耳だ」
意外そうな顔をするシュバルツに、ハヤブサも苦笑する。
「まあ……バタバタしていて、話す間も無かったからな…。店番は里の者が交代でしてくれているんだが、俺も時々顔を出しているんだ」
ハヤブサの話では、その店が『龍の忍者』に接触する窓口になる事もあると言う。尤も、その店がそう言う役割を持っている事を知っている人間も、ごく僅かな人数に限られているようだ。
「西洋の古美術もいいが、やはり、日本の古美術もいい。時々『本物』を見ると、とても勉強になる」
だから今日はゆっくり回ろう、と言うハヤブサの言葉に、シュバルツの方も異存はなかった。そのまま忍者二人は、京都の街を歩きだした。
道々の紅葉を楽しみながら、史跡を巡り、そこに存在する古美術と歴史を楽しむ。
自身がアンティークショップを経営しているだけの事はあって、ハヤブサの歴史と古美術に対する造詣は深い。シュバルツは、そんなハヤブサの話を飽きることなく楽しんだ。だいたい、シュバルツの大元になっているキョウジが学者気質な性格をしている。それ故に、学術的好奇心が刺激される話は、シュバルツも好きなのだ。
それに、神社仏閣と言った静謐な空間は、とても心を落ち着かせてくれた。国の重要文化財にも指定されていると言う仏像に、時を忘れて見入ってしまう。ハヤブサが話してくれたこの仏像に関する『歴史』も――――鮮やかな彩りを添えて、シュバルツの心を魅了した。
「楽しいか?」
ハヤブサにそう声を掛けられて、シュバルツははっと、我に返る。楽しんでいる事を伝えるために素直に頷くと、ハヤブサも嬉しそうに微笑んだ。
「それは良かった」
ハヤブサはそう言うと、シュバルツの横にそっと並んで穏やかな顔で仏像を眺めている。
「……血なまぐさい世界、我欲にまみれた人間たちの間にいると、つい、忘れてしまいそうになるがな……」
シュバルツの隣で、ハヤブサがポツリと呟いた。
「神や仏に対する、美しい敬いの心を表現できるのも――――おそらく、人間だけなんだ」
『神』をも滅してしまう龍の忍者。故に自分は、神とか仏とかを信じている人間とは言い難い。だが、こうして仏像を見つめるのが好きなのは、そう言った人間の心の美しさを再確認できる場でもあるからだろう。
人は、醜いが美しい。
それを知っているからこそ、自分は、身体を張って戦う事が出来るのだ。
無辜の人々を、守るために。
そしてシュバルツ、お前の存在も――――。
「…………」
ハヤブサから妙に熱い視線を感じてしまって、シュバルツは何となく落ち着かなくなる。
「そ、その……ハヤブサ…」
周りに集まって来る変な空気を拡散させようと、シュバルツは口を開いた。
「何だ?」
「こ……骨董店の時間は、大丈夫なのか? あまりここでゆっくりしていては―――」
「構わないさ。連絡を受けてはいるが、『今日会う』と、約束している訳でもない」
ハヤブサは穏やかに笑いながら言葉を続ける。
「こういうのは『縁』の物だ。その品と俺に縁があるのならば、出逢う事も出来るだろう」
だから気にせず、ゆっくりしていいと笑うハヤブサに、シュバルツも「そ、そうか…」と、ハヤブサから視線を逸らしながら返事をする。そのはにかんだ横顔が、妙に可愛らしいとハヤブサには感じられてしまったものだから――――思わず手が出そうになってしまう。
(いやいや! 落ちつけ! 俺!! 周りを見てみろ!! 二人きりじゃないんだ!!)
理性を必死に動員して、動きそうになった右手を、左手で懸命に抑え込む。今、自分の『報酬』として横にいてくれるシュバルツは、逃げる事は無いのだ。逃げる事が無いからこそ――――今ここにいる時間を、シュバルツには楽しんで欲しいと思った。自分の思惑だけで、一方的に踏みにじるような関係には、なりたくはなかった。
(『報酬』として横に縛っておきながら――――贅沢な願いではあるが、な……)
ハヤブサは己の中に矛盾を感じてしまって、もう苦笑するしかない。だが、こうして横に縛りでもしなければ、シュバルツとゆっくり話が出来なかったのも、事実なのだ。
もっと、シュバルツの事を知りたいと思った。そして、もっと自分の事も彼に知って欲しいと思った。
だから、行き先は自分が決めるが―――歩くスピードは、シュバルツに合わせた。
表通りから少し道を入って、奥まった所にひっそりと佇んでいる、刀剣店の暖簾をくぐる。
「……おや、珍しい。今日は、お連れがいらっしゃるので?」
奥から出てきた顔なじみの老店主に、ハヤブサは穏やかな笑顔を向ける。
「ああ……。大切な、『友人』だ」
「それはそれは――――ようこそ。ハヤブサさんの御知り合いならば、こちらも歓迎いたします。どうか、ゆっくりなさってください」
店主の言葉に、シュバルツも丁寧に頭を下げた。
そのまましばし、『刀談義』に花を咲かせる。
「……やはり、ハヤブサさんの『龍剣』は、何度見ても唸ってしまいますな……見事な物です」
龍剣を鞘に収めながら、店主が呟く。その様を見て、シュバルツの方が逆に驚いた。『あの』龍剣が、ハヤブサ以外の人間に触られても、その牙を剝かないとは――――。
「ここの店主は、龍剣の『砥ぎ』を頼める、数少ない刀匠なんだ」
ハヤブサの言葉に驚いたシュバルツに顔を見られ、店主は少し決まり悪そうな笑みを浮かべる。
「たいしたものではありません。すこし、手入れが出来る程度ですよ…。これと同等の刀を打てと言われても――――なかなか打てるものではありません」
その老人の言葉に、シュバルツも納得する。それほどまでに、『龍剣』と言う刀は――――『特殊』だった。
「貴方……確か、シュバルツさんと仰ったか?」
「はい」
老店主に呼びかけられ、シュバルツは顔を上げた。
「貴方は何か……御自分の愛刀は持たれないのかね?」
「あ……いえ……」
店主からの意外な言葉に、シュバルツは少し慌ててしまう。
「私は恥ずかしながら――――特にこだわりがある訳ではないのです。何だか自分には、勿体ない様な気がしてしまって……」
「ご謙遜を……。貴方、相当使えるでしょう?」
店主の言葉に、穏やかだが少し斬り込んでくるような響きが混じる。
「いえ、本当に――――」
シュバルツは、店主の斬り込みをどうかわそうかと悩んだ。シュバルツの場合、刀に『切れ味』を求めてはいない。錆びた刀でも大木を一刀両断に出来る『明鏡止水』の真髄を極めている彼は、どんな刀でもそれを名刀として変化させ得る事が可能だった。故に、逆に刀匠が魂を込めて打った『銘入りの刀』を自分が持つ事は、その刀に申し訳ない様な気がしてしまうのだ。
自分には、メンテナンスもされていない様な、無名の刀一振りがあれば、それで充分だと思った。
「まあ、お前の刀の使い方は、少し特殊だからな……」
店主とシュバルツの間に流れる微妙な空気を何となく察したハヤブサが、苦笑しながら助け船の様な物を出す。それを聞いた店主が「そうですか……」と、少し残念そうに笑った。
「また、いつでもおいでてください。貴方に使われることで、喜ぶ刀もあるでしょう」
老店主はそう言って、忍者二人を見送ってくれた。
「お前、あの店主に気に入られた様だな」
そう言ってハヤブサが、シュバルツににこりと笑いかける。
「お前を、連れて来て良かった」
それに対して、シュバルツが少し複雑な表情を見せるから―――ハヤブサの足が止まってしまう。
「どうした? シュバルツ……」
「ああ、いや、その………」
ハヤブサの問いかけに、シュバルツが戸惑いながらも口を開いた。
「私は……今、お前の『報酬』のはずだろう……?」
「ああ、そうだな」
『報酬』と言う響きに、ハヤブサの胸がチクリと痛む。
「それなのに、どうして……。これでは、まるで――――」
ハヤブサと共にいる事で、図らずも与えられた、優しい世界、優しい時間、出逢い――――。
これではまるで、自分が『報酬』をもらっているような気さえしてしまう。そう感じてしまったが故の、シュバルツの言葉であった。それに対してハヤブサは、思わず苦笑してしまう。
(分かっていないんだな…。こいつは)
彼が自分の隣にいることで、どれ程自分が満たされているか―――彼は気付いていないのだろう。
彼の笑顔が、どれ程自分を幸せにしているのか――――分かっていないのだろう。
どうすれば伝えられる?
どうすれば、分かってもらえるのだろうか。この想いを――――。
シュバルツ。
シュバルツ。
俺はこんなにも――――幸せなのに。
「心配しなくとも―――俺は、充分『報酬』を受け取っている」
お前が、俺の横で笑ってくれている。
今はそれで、充分だ。
「ハヤブサ……」
「まあ、尤も――――」
戸惑いながらこちらを見ているシュバルツを、ハヤブサは笑いながら抱き寄せる。
「『夜』の報酬も……ばっちり貰うつもりでいるからな」
「――――ッ!」
耳元でそう囁いてやると、シュバルツの顔色が、耳まで朱に染まるから、『可愛い』とハヤブサは思ってしまう。思わず彼の唇を、また奪いたくなってしまった。
でもやめた。
今―――彼の唇を奪ってしまったら、それだけで終われなくなる自信がある。それこそ、人気のない所に彼を連れ込んで、無理やり押し倒して、最後まで突っ走ってしまいそうだ。
それで、シュバルツの『心』が手に入るのならば、俺は喜んでそうさせてもらうのだが――――。
それではお前は、手に入らないのだろう?
「ハヤブサ……ッ!」
顔を真っ赤にして怒る、愛おしいヒト。それを見ながらハヤブサは、声を立てて笑っていた。
「行こう、シュバルツ」
そうやって怒りながらでもいい。
側に、居てくれ。
今日1日だけじゃなく。
出来ればずっと――――。
龍の忍者はそう祈りながら、シュバルツに手を差し伸べていた。
忍者たちの道行きは続く。
骨董店。茶屋。『回っていない』寿司屋――――。
「おや? 珍しいね。連れと居るのかい?」
ハヤブサをよく知ると思われる店の人たちからは、決まってそう声をかけられた。
静かな空間。落ちついた時間。優しい人たち。
ハヤブサが一人で、紡いできた世界。
その中に身を置いて、シュバルツは思う。
『嫌い』じゃない。
いや、むしろ―――――。
「……………」
だから。だから、困る。
どうして――――ハヤブサの望みが『自分』なんだ。
そして、どうして――――自分の身体は『歪(いびつ)』なのだろう。
それこそ、ハヤブサを殺してしまいかねないほどに。
ハヤブサを、傷つけたくはなかった。
そして、彼を死なせたくも無かった。
きっと、ハヤブサのためには、『抱かれたくない』と拒むのが一番いいのだろう。でも、それは――――ハヤブサが一番望んでいない事だった。それをしてしまったら、彼をひどく傷つけてしまうと分かる。
だからと言って、このまま身体を許し続ければ―――いつか自分の身体が彼を殺してしまうかもしれない。自分の身体を構成しているDG細胞が、彼の身体に感染してしまう可能性が、どうしても否定できない。
どうすれば、いい。
どうすればいいのだろう。
ハヤブサのために、自分は一体どうすれば――――。
「シュバルツ?」
ハヤブサに呼びかけられて、シュバルツははっと、我に返る。顔を上げると、怪訝そうにこちらを見ているハヤブサと、視線が合った。
(しまった……!)
シュバルツは、自分の顔から『笑顔』がいつの間にか消えていた事を悟った。どうやら、考えていた事が自分の面に出てしまっていたらしい。
「何でもない。大丈夫だ」
シュバルツは、慌てて笑顔を取り繕う。だが――――その笑顔を見たハヤブサは、逆に瞳を曇らせた。
(無理して笑っている……)
辛いのなら『辛い』と。
嫌なのなら『嫌だ』と。
はっきり言ってくれていいのに、と、ハヤブサは思う。
だがシュバルツは――――苦しみも悲しみも孤独も、黙って独りで耐えてしまう。それはシュバルツの『強さ』でもあり『美点』でもあるのだが、過ぎた忍耐は、いつか彼を静かに壊して行ってしまいそうな気もしてしまう。
(俺では、駄目なのだろうか)
シュバルツを見つめながら、ハヤブサは思う。
彼の抱えている苦しみや孤独を、吐き出させてやることは出来ないのだろうか。その為に俺は――――彼の側にいるのに。
だが、笑顔のシュバルツは、ハヤブサがこれ以上踏み込んでくる事を拒否しているようにも見える。だからハヤブサも仕方なく――――『笑顔』のシュバルツに合わせて、笑みを返す。
そして、しばらく二人の間でかわされる、当たり障りのない『談笑』
だけど、少し目を離して振り返ると――――また、シュバルツの思い詰めた瞳がそこにあったから――――。
「シュバルツ……」
ハヤブサは思わず、シュバルツの頬に手を伸ばしていた。
「――――ッ!」
途端にビクッ! と、過剰に反応する、シュバルツの身体。ハヤブサは、これ以上彼に手を伸ばせなくなってしまった。
「シュバルツ」
でも、声をかける事はやめない。彼に手を伸ばし続ける事を、あきらめたくはなかった。
「……俺に、何か言いたい事があるのなら……どんな些細な事でもいい。ちゃんと言ってくれ」
「ハヤブサ……」
「俺は……聞く用意があるから―――」
少し驚いたようにこちらを見るシュバルツに向かって、ハヤブサは微笑みかける。ただ、うまく笑えているかどうかは、少々自信が無い。淋しかった。彼の支えになりたいと思うのに、自分はなれていない、と感じてしまうから――――。
臥所を共にするようになってから、もう何度、悪夢にうなされて泣く彼を見た事だろう。
そして、何度「大丈夫だ」と、無理やり笑う彼を見てきた事だろう。
そんなシュバルツが切なくて哀しくて愛おしいから―――――。
(つい、また身体を重ねちゃったんだよなぁ……)
それを思い出したハヤブサは、寿司屋のカウンターに己が頭を打ちつけたくなってしまう。阿呆か俺は。ここでもう少しシュバルツを気遣ってやって、彼が話をしやすい環境の一つでも作ってやれていれば良かったかもしれないのに――――。
だが、仕方がなかろうとも思う。
情事が終わった後で。
少し、乱れた髪をしたシュバルツが裸で隣で寝ていて。
涙で潤んだ瞳で「大丈夫だ」なんて微笑みかけられてしまったら。
俺の強くない『理性』なんて――――とっくに空の彼方じゃないか。
無理だ。
隔てる物が何も無い状況で、どうやって我慢しろと言うのだ。
(それで、却って嫌われちゃったのかもしれないよなぁ……。俺、いろいろやっちゃったから……)
そうやって考えて行くと、ハヤブサは自分がシュバルツに『嫌われる』要素も結構ありそうな気がして来て、軽く自己嫌悪に陥ってしまう。
(くそっ!)
少し自棄になって口に放り込んだ寿司からは、強い山葵の香りがした。
「ハヤブサ……?」
シュバルツの声に振り返ると、彼がこちらの事を気遣うように見ている。
(ああ……やっぱり、優しいよな……お前は――――)
そう感じてハヤブサは苦笑する。特殊な身体を持つが故に、お前はいつも、俺の何倍も苦しんでいるに違いないのに。
それでもまだお前は、目の前にいる俺の事を、気遣えてしまえるんだ。
その優しさは駄目だぞ、シュバルツ。
付け込まれてしまうから。
俺みたいな、男に。
「……出ようか」
ハヤブサはシュバルツにそう声をかけると、寿司屋のカウンターから立ちあがった。
外に出ると、陽はもう西に傾き、辺りを夜の帳が覆い始めていた。『秋の陽はつるべ落とし』とは、よく言ったものだ。吹いてくる北風が、ハヤブサの身体に必要以上に冷たく感じられてしまうのは、冬が近づいてきているせいばかりではないだろう。
「『宿』を、取ってあるんだ」
寿司屋から出て、少し歩いた所で――――ハヤブサはシュバルツにそう声をかけた。
「来て……くれるよな? シュバルツ……」
二人の間を、ひゅう、と、音を立てて北風がすり抜けて行く。
「ハヤブサ……」
シュバルツはただ、目の前で佇んでいる龍の忍者を見つめる。優しいのに、ひどく淋しげな瞳をした龍の忍者を。
(私はお前の『報酬』だろう? なのに何故―――わざわざ『意志』を聞くんだ、ハヤブサ……)
今、自分はハヤブサに対して、一切の拒否権が無い筈だった。ハヤブサが『来い』と言うのなら、自分は、頷くしかない――――筈なのに。
ハヤブサは、待っている。こちらの返事を。
ハヤブサは、聞こうとしてくれている。こちらの『意志』を。
仮にも私が『嫌だ』と言ったら――――彼は、どうするつもりなのだろう。
それすらも受け入れるつもりで…………こちらの意思を確認しているのだろうか。
『報酬』と言いながら今日1日、ずっと私の事をそうやって気遣ってくれていたハヤブサ。その彼が、私を望むのならば―――。
シュバルツは、頷く事を選択した。
「ああ……行く」
それを見たハヤブサは、嬉しそうに微笑む。
「そうか……」
だがその瞳に宿る、淋しげな影は消えなかった。
「ありがとう……」
そう言うとハヤブサは踵を返して、シュバルツの少し前を、歩きだした。
(ハヤブサ……)
前を歩くハヤブサの背を見つめながら、シュバルツは再び物思いに沈んで行く。
(ハヤブサ………何故、そんな淋しげな瞳を――――?)
分からない。
どうして。
彼の方には、何の落ち度もないのに――――。
もしも何か落ち度があるのだとしたら、それはきっと自分の方だ。きっと、自分は何か、ハヤブサにそんな瞳をさせるような事をしてしまっているのかもしれない。
駄目だ。こんな事では。
このままでは私は―――彼の『報酬』になるばかりか、苦しめてばかりいるのではないだろうか。
「ハヤブサ……」
彼に真意を確かめたくてシュバルツが声をかけると、ハヤブサは振り返った。
「どうした? シュバルツ……」
静かな笑みを湛えて、佇むハヤブサ。
「あ……その………」
だがシュバルツは、ハヤブサに声をかけてみたものの、何を聞けばいいのか、何を話せばいいのか――――しばし、戸惑ってしまう。結果として「済まない、何でも無い……」と、茶を濁すような言葉しか、言えなかった。
それを見たハヤブサは、「そうか……」と、優しく微笑む。だがその瞳に一瞬、泣きそうな色が宿ったのは気のせいだろうか。
ハヤブサは、再び前を向いて歩きだした。
「…………」
シュバルツはその後ろをついて行きながら、どうしても物思いに沈んでしまう己を止める事が出来ない。
ハヤブサが望むのは、私の身体。『宿に泊まる』と言う事は――――そう言う事なのだろう。
構わないと思う。
ハヤブサが望むのならば、私の身体など――――好きにしてくれて構わないのだ。なんだったら、殺されたっていいとさえ、シュバルツは思っている。
だけどこの身体は死なないが故に、その想いすら結局欺瞞に代わってしまう。ハヤブサは、自分のために命をかけようとしてくれているのに、自分は、どう足掻いたって同じ物を彼に返す事が出来ないのだ。
それどころかDG細胞を――――。
ハヤブサに――――。
(…………)
ああ、どうして。
どうしてこの身体は、こんなにも―――――。
(駄目だ……!)
シュバルツは強く頭を振る。
自分の『身体』の事で、シュバルツは嘆きたくはなかった。
だってこの身体は、キョウジが作った物なのだ。それを『嘆く』と言う事は、必然的にキョウジを『責める』ことに繋がってしまう。
それは嫌だと思った。
キョウジは、私を作る際に犯してしまった『罪』の事を、充分すぎるほど自覚している。
そして、今でも己を責め続けている事を――――シュバルツは知っている。
だから。
だからせめて、自分だけは。
身体の事も受け入れて――――前を向いていたいと思うのだ。
キョウジが、これ以上己を責めることが無いように。
そしていつか。キョウジに『お前を作って良かった』と、思ってもらえるようになるように。
だから、自分の身体の事で嘆きたくはない。きちんと受け入れて――――自分ひとりの胸に、納めなければならないと、思うのに。
「……俺に、何か言いたい事があるのなら……どんな些細な事でもいい。ちゃんと言ってくれ」
シュバルツの脳裏に、そう言って微笑んでいたハヤブサの顔が浮かぶ。
(ハヤブサ………)
ああ、でも――――仕方が無いではないか。私のこの身体の『苦悩』など、今更分かり切ったことなのだ。そんな事をハヤブサに零した所で、ハヤブサがこの問題に有効な解決策を持っている訳でもない。彼にとっても、いい迷惑にしかならないだろう。
今日1日、ずっと、自分の事を気遣ってくれていたハヤブサ。
これ以上――――彼に迷惑をかけられない。
ああでも――――。
ハヤブサの『想い』に真剣に応えようとすればするほど――――。
(怖イ……)
自分の身体が――――。
「…………」
ハヤブサは前を歩きながら、ずっとシュバルツが苦悩している気配を感じ取っていた。
(『嫌』なら……逃げてくれていいんだぞ? シュバルツ……)
もうキョウジの『実験』に協力してもいいだけの報酬は、充分受け取っているとハヤブサは思う。だから、シュバルツがどうしても自分に触れられるのが『嫌』だと言うのなら、逃げてくれても構わないのだ。
その為に――――自分はわざと、シュバルツの少し前を歩いている。
シュバルツが逃げ出したとしても、すぐに気付けないように。
その後を、追う事が出来ないように。
それだけの隙を充分与えながら、ハヤブサはシュバルツの前を歩いていた。
なのに、シュバルツはついてくる。
その瞳に、苦悩の色をにじませながら――――。
(きっと……『報酬』にならなければならない、と、思っているから……ついて来ているんだろうな……)
例え彼が自分に触れられる事を『嫌だ』と思っていても。
『報酬』になる、という約束を、守るために。
律儀で、真面目な奴なのだと思う。
そして、そんな所すら――――どうしようもなく、愛おしい。
(やはり……俺では駄目なのか……?)
シュバルツの瞳に宿る苦悩の色を見やりながら、ハヤブサは思う。
その苦しみを吐き出す相手は、俺では駄目なのだろうか。
シュバルツ、俺は―――。
今日の昼間、『喜び』を分かち合えたように。
お前とは、『苦しみ』も分かち合いたいんだ。
お前が苦しんでいるのならば。
その苦しみを、少しでも軽くしてやりたいんだ。
俺には、キョウジみたいにDG細胞に関する専門的な知識がある訳じゃない。だから、俺が支えてやれる事など、微々たるものかもしれないが――――。
それでも。
お前を独りで、苦しませたくはないんだ。
でないと俺は、お前からは何もかもを貰いっ放しと言う事になってしまう。二人並んでいて、俺一人が幸せで――――それでいいはずが無い。
俺がお前の側にいて、幸せを感じるように――――お前も、俺の側にいて『幸せ』を感じて欲しいと願う。……贅沢な、願いかもしれないが。
(……尤も、シュバルツが俺の事を『嫌って』いた場合は、俺の側にいない方が、幸せなのかもしれないんだけどなぁ……)
そう考えた瞬間、胸の奥に酷い痛みを感じる。身体が重くなって、足が地面にめり込むのではないかと錯覚を覚えてしまう。息をするのすら、辛くなる。
どうしてこんなに苦しいのだろう。
(きっと、シュバルツが……もう、俺の胸の奥の一番大事な所を、占拠してしまっているからだ)
星空を見上げながら、ハヤブサは想う。
身体は、いくらでも鍛える事は出来る。心だって―――ある程度、鎧で覆う事も出来る。
だが、シュバルツがいる心のこの場所は――――。
どう足掻いたって鍛える事の出来ない、最も無防備で、柔らかい場所だ。そこにシュバルツがいる。
そして、彼の一挙手一投足が――――自分のそこを揺さぶり、幸せにもして、傷つけもするのだ。ここまで自分の心に入り込んできたのは、後にも先にもシュバルツしかいない。
ああ。
やっぱり好きだ。
俺にはシュバルツしか――――。
ゴン!
鈍い音が響いて、ハヤブサは自分が電柱にぶつかった事を悟る。
「だ、大丈夫か?」
痛む頭をさすって涙目になっていると、シュバルツから声をかけられた。
(まだ……居てくれたのか。シュバルツ……)
シュバルツに心配された事が嬉しくて、ハヤブサは別の意味で泣きそうになる。
「大丈夫だ……」
無理やり笑った。旨く笑いたいと思った。
でも、良いのか。シュバルツ。
後少しで、宿に着くぞ。
宿についてしまったら――――俺は、歯止めが利かなくなるぞ?
嫌がるお前を、下手したら、無理やり押し倒してしまうかもしれない。
いいのか、それでも。
(もし俺が『逃げてもいい』と、シュバルツに言ったら……彼は、どうするだろう)
そこまで思って―――それを、言う事が出来ない己を、ハヤブサは自覚する。
済まないな、シュバルツ。
後少しだけ、俺に付き合ってくれ。
これが最後でも良い。どうしても――――。
どうしても、俺は――――。
オ前ノ肌ニ……触レタイ。
「……着いた……」
ハヤブサの声にシュバルツが顔を上げると、旅館の立派な門構えが、視界に飛び込んできた。
「ここの大将とは先代からの付き合いでな。京都に用がある時は、必ずここに泊まる様にしているんだ」
仲居に部屋まで案内してもらっている間、ハヤブサはシュバルツに語りかける。窓の外は暗くてもう良く見えないが、和式の建物の造りが、落ち着いた雰囲気をそこに漂わせていた。使い込まれた廊下だが、隅々まで清掃が行き届いている様が見て取れた。きっと、窓の外には美しい日本庭園が広がっているだろうことが、容易に想像できる。
「松の間にございます。どうか、ごゆるりとおくつろぎください」
仲居は二人を部屋まで案内すると、恭しく頭を下げて下がって行った。
心地よく整えられた、畳の部屋。襖を一枚隔てた隣の部屋に、『寝室』が在った。
(……………!)
その部屋の雰囲気が、あの『里』のハヤブサの部屋に似ていたものだから、シュバルツの心がどうしてもざわ、と、波立ってしまう。
激しく求められた夜の事を思い出す。
また、あんな風に抱かれるのだろうか――――。
「シュバルツ」
不意にハヤブサに呼びかけられ、シュバルツの身体がビクッ、と、跳ねてしまった。
「な、何だ?」
平静を装って返事をするが、所作がどうしてもぎこちなくなってしまうのを、シュバルツは抑える事が出来ない。そんな彼に、ハヤブサは優しく微笑みかけた。
「風呂に入って来るといい」
「ふ、風呂?」
どうしてもいろいろと何かを連想させてしまう単語に、戸惑い気味になってしまうシュバルツ。だがハヤブサは、そんなシュバルツから、ふい、と、視線を逸らしてしまった。
「ここの旅館の温泉は……広くて綺麗なんだ」
そう言いながらハヤブサは、窓から外の闇を眺めている。
「あ………」
『風呂』と言う単語に過剰に反応してしまった己を、シュバルツは少し恥ずかしく思ってしまう。
(何をそんなに意識しまくっているんだ、私は……。ハヤブサの方は、特にそんな事も思わずに、純粋に温泉を薦めてくれただけなのかもしれないのに……)
「わ、分かった……。入って来る……」
シュバルツはそう言うと、部屋に用意されていた浴衣を手に取る。だがその所作が、どうしてもぎこちなくなってしまうのを、押さえる事が出来ない。『意識しすぎだ』と言う事は自分でも分かっている。だが、この後の事を考えると、勝手に顔が火照ってしまう。どうしても平静ではいられなかった。
「ハ、ハヤブサは……どうするんだ?」
シュバルツはいつまでも窓際から動かないハヤブサの後ろ姿に声をかけた。ハヤブサがこの後どういうふうに自分に接してくるのか、知っておきたいと思った。―――覚悟が必要だったから。
「ああ……俺は――――」
だがハヤブサは、シュバルツの問いかけにすぐには答えなかった。
「後で行くよ」
しばらくの沈黙の後、シュバルツの方を一瞬見て、ぽつりと答えるハヤブサ。どうとでも解釈できる返事だった。
「わ……分かった……」
ハヤブサに呼ばれて、仲居がやって来る。温泉に案内して欲しい旨を仲居に告げると、彼女は快く承諾してくれた。仲居に導かれて、シュバルツはそっと部屋から出て行った。
(……それにしても、セックスの的になるって、酷くプレッシャーのかかるものだな……。毎回思うけど、世の女性たちは本当に大変だ……)
温泉へと向かう廊下を歩きながら、シュバルツはため息をつく。意識をすまいとすればするほど、却って変に意識をしてしまい、動作がおかしくなってしまう自分を止める事が出来なかった。絶対ハヤブサにも、変に思われてしまった事だろう。
(だけど、ハヤブサの方は冷静だったな……。『抱きたい』と思っている方は、案外そんな物なのかな……)
能動的に誰かを『抱きたい』と思った事がまだないシュバルツは、う~ん、と考えてしまう。でもハヤブサの先程からの態度も、少し気になった。あれは『冷静』と言うよりはむしろ――――。
『淋しそう』
そう形容した方が、しっくり来る気がする。
何故なのだろう。
昼間はあんなに楽しそうに、いろいろと話をしてくれたのに――――。
(もしかして私が……ハヤブサに何かをしてしまったのだろうか……)
人付き合いが何かと苦手な自分の事だ。ひょっとしたら自分でも気づかないうちに、ハヤブサに何かそういう表情をさせるような事を、してしまっているのかもしれない。
今日1日ずっと、自分の事を気遣ってくれたハヤブサ。その彼に、あんな淋しそうな表情をさせるのは、シュバルツとしても本意ではなかった。
彼には………彼こそ――――『幸せ』になって欲しいと、願うから。
(身体を赦せば……また、元の様に笑ってくれるだろうか……)
今とりあえずのハヤブサの望みは間違いなくそれだ。だから――――。
(……………)
そう考えてから、シュバルツはまた首を捻ってしまう。何故だろう。そう言う問題でもない様な気がする。ハヤブサが単純に私の『身体』だけが目当てなのであるならば、もっと短絡的に求めて来て――――とっくに自分は、彼に抱かれているだろうから。
だけど、それをしないハヤブサは、もっと別の何かを自分に求めて来ている様な気がする。『身体』以上の『何か』を――――。
でも。
分からない。
自分の『何』が、そんなに彼を引き付けているのだろう。
男の身体で。
まして、人間ですら無くて。
抱き心地だって、決して良い物ではないだろうに。
それどころか……。
DG細胞―――――。
彼ヲ
殺シテ
シマウカモ
(………怖イ…!)
(駄目だ、こんな事では…!)
シュバルツは頭を振る。抱かれるのを百も承知で、ここまでついて来たのは自分だ。だから、何もかもを自分で覚悟を決めて、受け入れなければならないのに。
だが、抱かれるたびに見てしまった悪夢の映像が。
DG細胞の脅威が。
どうしても――――シュバルツを責め苛んでしまう。
ハヤブサが望むのならば受け入れてあげたい。
だけど、それをした結果、ハヤブサにDG細胞を感染させてしまったら。
怖イ
怖イ
考えても仕方が無い。
自分の身体が『そう』だという事実は変わらない。
だから、受け入れなければならない。ちゃんと割り切って――――覚悟を決めなければいけないのに。
何故か――――今日に限って割り切れない。
ハヤブサを失いたくない。
ハヤブサを、傷つけたくない。
キョウジを責めたくない。
どうすればいいのだろう。
私は一体どうすれば――――!
「ああ、危ないですよ」
仲居に声を掛けられて、シュバルツははっと、我に返る。見ると、前から走って来ていた子供と、危うくぶつかりそうになっていた。咄嗟に避けたシュバルツの脇を、子供が元気よく走りぬけて行く。
「こらっ! 廊下を走っちゃだめって、言ったでしょう!?」
その後から、その子の母親と思しき女性が、声を張り上げながら子供を追いかけていた。すれ違いざまに、その女性から「すみません!」と、申し訳なさそうに声をかけられる。
「…………!」
それをきっかけにシュバルツの視界にようやく周りの状況が飛び込んでくる。
自分達はいつの間にか、旅館の宿の施設から温泉のある施設へと移動する渡り廊下に差し掛かっていた。そこをたくさんの人たちが行き交っている。親子連れ、老夫婦、友人同士と思われる人たち――――老若男女、ありとあらゆる世代の人たちが楽しそうに談笑したりくつろいだりしながら、そこを歩いている。
「今は紅葉の綺麗な時ですから……平日ですけど、たくさんの方がおいでて下さっているんですよ」
仲居が親切に、そう教えてくれた。
(そうか……。これだけの人がいたから、ハヤブサは一緒に風呂に行く事を遠慮したんだな……)
そう感じて、シュバルツは変に納得してしまう。ハヤブサとしても、これだけたくさんの人目がある中で、自分を抱く訳にはいかない、と、思ったのだろう。
とりあえず、風呂場で襲われる事は無くなったと感じて、シュバルツはホッと、胸をなでおろしていた。
少し歩いて行くと、大浴場への入り口が見えてくる。
シュバルツがそちらへ入ろうとすると、仲居に声をかけられた。
「お客様はこちらにご案内するようにハヤブサ様より託っております」
「えっ? あ、ああ……」
仲居に導かれるままに、シュバルツは再び歩き出した。
少し歩いて行くと、大浴場とは別の、こじんまりとした入り口が見えてくる。
「こちらです。どうぞ」
「ありがとう」
シュバルツは礼を言うと、中へと入って行った。
「ごゆっくり―――」
彼女は頭を下げると、シュバルツが中に入ったのを確認してから、ドアを静かに閉めた。そして、ある立て札をトン、と置いて去っていく。『本日貸し切り』――――その札にはそう記されて、あった。
こじんまりとした入り口とは裏腹に、中の脱衣場にはそれなりの空間があった。しかし、『貸し切り』となっているため、中にいるのは当然シュバルツ一人である。だが、シュバルツはその事実に気づいていない。
(こちらの方にはまだ人が回って来ていないのかな)
と、言うぐらいの認識でしかなかった。
「……………」
風呂に入るべくシュバルツは服を脱ごうとして―――ロッカーにトン、と頭を打ち付けてしまう。
(駄目だ……まだ、自分の心が整理できない……)
抱かれるのが分かっていて、ここまで来た。ハヤブサだって……私の身体の歪さを百も承知で、それでも『抱きたい』と求めて来ている。
だから、良いじゃないか。
彼を信じて――――この身をゆだねれば。
でも、それをして。
彼にDG細胞を感染、させてしまったら…?
そのせいで、彼を永遠に失ってしまったら――――?
怖イ
怖イ……!
「……………!」
(駄目だ……! また、堂々巡りになってしまっている……!)
考えても仕方が無い事を、また考えてしまっている。シュバルツは強く頭を振った。
(とにかく、風呂に入って落ち着こう)
そう決心した彼は、服を脱ぎ始める。シュル……と言う衣擦れの音を立てて、ロングコートが彼の肩から滑り落ちた。首のスカーフを解き、シャツのボタンをはずして行く。それをしながらシュバルツは、また、考えてしまう。結局自分は――――ハヤブサと、どうなりたいのだろう。
自分の身体の歪さを知っても、引くどころか、「何だ、そんな事か」と、受け入れてくれたハヤブサ。闇の世界に生きながらも、その優しさを失わなかったハヤブサ。
その証拠に、彼が1人で紡いできた『世界』は、とても優しかった。思わず自分も、ずっと身を置いていたい、と、願ってしまうほど――――。
その彼が、自分に向かって必死に、手を伸ばして来てくれている姿が見える。
その手をとりたくて。
その手を失いたくない、と、願ってしまって、私は――――。
スル……と、シャツが肩を滑り落ちて、シュバルツの白い肌が現れる。
(『身体』で……彼を、つなぎ止めている……?)
彼が望んできた『身体』―――それで、彼が自分に向かって伸ばして来ている手を、つなぎ止める事が出来るのなら。
身体を赦す事など、容易かったのかもしれない。
でもそれは、ハヤブサに多大なリスクを背負わせる行為だ。
分かっている。
真にハヤブサの事を想うのであるならば、今すぐこういう関係になる事を止めなければならないのだ。
止めなければならない。
ハヤブサをちゃんと拒絶しなければならない、と、理性は強く訴える。
でも、それをしてしまったら―――。
自分は永遠に、彼を失ってしまうと分かる。
何の落ち度も無く、懸命に、まっすぐに――――自分を想って来てくれているハヤブサを、手酷く傷つけてしまう事になるからだ。
耐えられるのだろうか。
シュバルツは、自問自答する。
耐えられるのだろうか。自分は。
あの優しさを――――失ってしまっても。
誰からも手を差し伸べられない無明の闇に、また独り舞い戻ってしまう事になっても……。
だが、身体を赦し続けて、彼にDG細胞を感染させて、死なせる事になってしまうのなら――――結果は同じだ。
ならばまだ、彼が『生きて』いる方が。
ああ、でも……!
ハヤブサ
ハヤブサ
どうしてだろう。
胸が苦しい――――!
(駄目だ。泣こう)
シュバルツはそう決意して、ベルトをはずす。気持ちを整理するために風呂に来たのに、整理するどころか、気持ちの乱れは刻々と悪化して行くばかりだ。いっそのこと、一度泣いたら少しはすっきりするかもしれない。
幸いな事に今は一人だ。そして、ここは風呂場だ。
だから『泣ける』と、シュバルツは確信する。
今ここでなら――――泣いても、誰にも聞こえないし、迷惑をかける事も無いだろう。
泣いている時に誰かが入って来ても、湯の中に潜ればいい。それをするだけで、頬を伝う涙を隠す事が出来るから。
とにかくハヤブサの前に出るまでに、自分の気持ちを何とか落ちつけておきたい、と思った。こんな乱れた気持ちのままでは、彼の『報酬』になるどころか、却って迷惑をかけてしまいかねない。『後から行く』と、言っていたハヤブサがいつ来るかは分からないが、それまでの間に、少しでも、乱れた気持ちを吐き出しておきたかった。
シュバルツは、そっとズボンから足を引き抜くと、一糸纏わぬ姿になる。折りたたんだ服をしまったロッカーに鍵をかけると、彼は静かに、脱衣所から風呂場へと続く扉を開けた。
天然の岩で形作られた、大きな浴槽がシュバルツの目の前に広がる。その横に、自然の岩場を生かしつつ設(しつら)えられた洗い場は、10人以上が一度に使っても問題なさそうだった。一番奥の壁全体が窓になっているようで、その向こうには露天風呂がある様にも見える。1人で入るには、いささか広すぎるなと、シュバルツは苦笑した。
「ここの旅館の温泉は……広くて綺麗なんだ」
(本当にそうだな……ハヤブサの言うとおりだ……)
胸が締め付けられ、身体が震える。
自分の視界が霞んで行くのは、湯気のせいばかりではないだろう。
「……ふ…! ……う……」
嗚咽が漏れそうになる口を押さえる。
今、自分は1人で――――この声は、誰に聞かれるという訳でもないのに、それでも彼は声を殺した。そうする事が、最早彼の中では習慣となっていた。
苦しい。
どうすれば。
どうすれば、いいのだろう。
頬に熱いものが伝い落ちる感触を得る。とにかくそれを一度洗い流そうと、シュバルツは桶を――――探そうとした、刹那。
いきなり背後に、濃厚な『人』の気配を感じる。
(えっ………?)
そしてそれは、間髪いれずにシュバルツを背後から抱きしめてきた。あまりにも不意をつかれてしまったため、彼はそれを、避けきれなかった。
「あっ…! な、何を―――!?」
「シュバルツ……ッ!」
「ハ、ハヤブサ!?」
抱きしめてきた主がハヤブサと悟って、シュバルツは激しく動揺してしまう。彼と向き合うための心の準備が、まだ出来ていなかったからだ。
「ずっと……こうしたかった……! シュバルツ……!」
だがハヤブサは、シュバルツのそんな心境を知ってか知らずか、彼を抱く手にますます力を込める。
触れたかった。
ずっとこうして彼に触れたくて触れたくて――――仕方が無かった。
シュバルツは、懸命に足掻こうとする。とにかく今は、ハヤブサから距離をとりたいと思った。
そうしないと、ばれてしまう。
自分が、泣いていた事が――――。
「ま、待て! やめろ! 誰かが、入ってきでもしたら―――!」
「『ここ』は、俺とお前の『貸し切り』だ…! 誰も入って来ない―――!」
「な――――!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは思わず息を飲んでしまう。
「……言っただろう? ここは『先代からの付き合い』だと。だから、俺の要求は、多少の無理でも聞いてもらえるんだ」
「あ………!」
「シュバルツ、愛してる……!」
耳元で囁きながら、ハヤブサはますますその身体をシュバルツに密着させてくる。耳をそのまま甘く噛んでやると、「あっ!」と、叫んだ愛おしいヒトの身体がぴくん、と、跳ねた。
「シュバルツ……」
止まれないハヤブサは、彼の首筋に唇を這わせる。
「……んっ! …ん……っ!」
愛撫にぴくぴくと反応する、シュバルツの身体。だが、腕の中の愛おしいヒトは、震えながらも自分の腕から逃れようとしている。その動きすら哀しくて愛おしいから――――ハヤブサは、さらに強くシュバルツの身体を抱きしめた。
「あっ…! やめっ……!」
シュバルツから抵抗の意思を示す声が上がる。だがハヤブサはそれには構わずに、強引に彼をこちらへ向かせようとした。シュバルツの唇が欲しかったからだ。
しかし、ハヤブサがその頬に触れた瞬間、彼はシュバルツの異変に気づいてしまう。湯に浸かっていた訳でもないのに、彼の頬がやけに濡れている事に。
「シュバルツ!?」
驚いて顔を見つめてくるハヤブサの目の前で、シュバルツの瞳から最早堪える事の出来ない涙が、ポロ……と零れ落ちて行く。
「シュバルツ……! お前――――?」
それを見たハヤブサは、思わず絶句してしまう。彼を捕まえていた手が、知らず緩んでしまっていた。
「泣いて……?」
何故、と、ハヤブサがシュバルツの頬に手を伸ばそうとした瞬間。
ドン!
ハヤブサはシュバルツに、突き飛ばされてしまう。そのまま無言で走りだしたシュバルツは、湯船に向かって飛び込んだ。
「シュバルツ!?」
シュバルツを追って、慌ててハヤブサも湯船に入る。しかし、湯船に入ったはずのシュバルツの姿を一瞬見失ってしまって、ハヤブサは焦った。
「シュバルツ!!」
やがて、ハヤブサの呼び掛けに応えるように、シュバルツの頭が湯船からパシャッ、と、音を立てて出てくる。しかし、そこはハヤブサの居る所から少し離れていて、しかもこちらに背を向けられているため、彼の顔を見る事が出来なかった。
(良かった……。逃げないでいてくれて……)
ハヤブサは、とりあえずほっと胸をなでおろす。シュバルツ、と、その後ろ姿に声をかけて、彼に近づこうとして――――その足が、止まってしまった。
何故なら、シュバルツが泣いている事に気づいてしまったからだ。
己の身体を抱え込むようにして――――がたがたと震えているシュバルツの後ろ姿。声を殺そうとして―――それでも漏れ出てくる嗚咽。ぽたぽたと滴り落ちている水滴は、風呂の湯ばかりではないだろう。
「シュバルツ……!」
その痛々しい後ろ姿にハヤブサは絶句してしまう。
(シュバルツ……! そんなに――――そんなに、嫌だったのか……? 俺に触れられる事が……!)
ハヤブサは、思わず目の前が真っ暗になる様に感じた。
だけど、思い当たる節もある。
里からキョウジの元に帰ってから今日まで、その身体を許そうとしなかったシュバルツ。
今日だって、夜が近づくにつれて、だんだんとその瞳に思い詰めた光を宿す事が増えて行ったシュバルツ。部屋で二人きりになった時の所作も、何だかとてもぎこちなくて――――。
――――嫌ダッタカラ。
そう考えると、ハヤブサの中で総て辻褄があってしまう。
「……………!」
胸の奥にかきむしられるような痛みを感じる。哀しくて情けなくて――――絶叫しそうになってしまう。
嫌 ダ
シュバルツ
嫌ダ―――――!
「……………」
だけど、シュバルツは――――。
ハヤブサは、思いなおす。
それだけ『嫌だ』と、思っているにもかかわらず……来て、くれたんだよな。俺と、ここまで……。
俺のためではない。『キョウジのため』にだ。キョウジの実験のために、俺の協力が必要だったから―――。
俺の事を『嫌だ』と、思っていても、耐えようとして。でも、耐えきれなくなって。
とても健気で、愚かな奴だと思う。
そして、そんな所すら、どうしようもなく、愛おしい。
それに
(初めてなんじゃないのか?)
ハヤブサは思う。
シュバルツが俺の前でこんなに感情をむき出しにするのは、初めてなのではないのか。
ずっと、周りの事を優先して自分の心を後回しにして、穏やかに微笑んでいたシュバルツ。
その彼が、真っ直ぐに『自分の感情』を吐露しているのだ。だとしたら、今ここにあるのは、紛れもないシュバルツの『心』だ。
それはある意味、ハヤブサが欲しくて触れたくてたまらなかった物―――だった。
だとしたら、受け止めたい。
例えシュバルツの心には、俺を傷つけるような言葉しか、もう無かったのだとしても。
それが、お前が俺に向けてくれる『心』だというのなら、俺は――――。
最後まで、受け止めたいんだ。
(済まないな、シュバルツ……)
心の中で詫びながら、パシャ……と、水音を立てて、ハヤブサはシュバルツに向かって一歩、踏み出す。
『嫌』なら、逃げてくれていいんだ、シュバルツ……。俺は、もう追わないから――――。
でも、逃げないというのなら。
これが最後でもいい。もう一度だけ――――。
触 レ サ セ テ
「シュバルツ……」
ハヤブサの呼び掛ける声に、シュバルツの身体がビクッ! と、震えた。
パシャ、と、音を立てて、ハヤブサは更にシュバルツに近づいて行く。
シュバルツは――――逃げなかった。がたがた震えながらも、そこに留まり続けてくれている。
愛おしい。
声を殺して泣くお前が――――。
哀しい。
お前のその『心』が――――。
哀しい。
哀しい。
これは報いなのか。
お前の優しさにつけ込んで、蹂躙するように抱いてしまった
俺に対する報いなのか。
俺の『想い』は、お前を苦しめるだけのもの、だったのか。
だけど――――。
だけど、シュバルツ。
俺は――――
俺は『幸せ』だった。
お前に出会えて。
お前に、触れられて――――。
俺は、確かに『幸せ』だったんだ。
だから、それだけは、伝える。
お前にどんなに嫌がられても、否定されても。
それだけは、俺の中では『真実』だったから。
どうか、それだけは――――伝えさせて、くれ
パシャ……と、ハヤブサが撥ねた水が、シュバルツに当たる。
手を伸ばせば、もう届いてしまう距離に来た。
(これが、最後)
ハヤブサはそう覚悟して、シュバルツに声をかけた。
「シュバルツ」
「――――ッ!」
震えている、愛おしいヒトの身体。それに向かってハヤブサは、そっと、手を伸ばす。振り払われたら――――もう、伸ばすのを止めるつもりだった。
ここにあるのはシュバルツの心。
だからハヤブサは、大切に、包み込むように手を伸ばす。
大切なヒトの、大切な心だから。
壊したくない。守りたい、と、願った。
優しく、そっと抱き寄せても――――シュバルツは動かなかった。だが、身体は硬直して、震え続けている。涙も流し続けている。
震えと涙を止めたくて、ハヤブサはシュバルツの身体を強く抱きしめそうになる。
けど――――それは出来ないと感じる。
シュバルツが自分に触れられる事を望まないのに、そんな事をしてはいけない、と、思った。
泣きそうに、なる。
シュバルツ
シュバルツ
こんなにも――――愛おしいのに。
振り払うなら、振り払ってくれ。
否定するなら、否定してくれていい。
俺は――――覚悟は、出来ている、から。
(きついけど、な……)
そう感じて、ハヤブサは苦笑する。
だが仕方が無い。
それこそ自業自得 なのだから。
「シュバルツ……済まなかった……」
ゆっくりと、言葉を選んで語りかける。
これが最後かもしれないから―――せめて、自分の『心』が伝わるように。
「お前が、俺に触れられるのが嫌だ、と、言うのなら……俺はもう、お前には触れない。触れないから――――」
シュバルツからは沈黙しか返って来ない。だが、ハヤブサは構わず続けた。
「せめて……『引導』は、お前の手で渡してくれないか……?」
「…………!」
腕の中で愛おしいヒトが、息を飲む気配が伝わってくる。ちゃんと自分の言葉が伝わっているのだなと感じて、ハヤブサは少し安心した。ただしその『安心』には、苦い味が混じっているけれど。
「俺の事を『嫌だ』でも、『愛せない』でもいい……。一言、言ってくれないか……?」
それを聞けば、きっと、俺はあきらめられる。あきらめられるから――――。
だからシュバルツ。どうか、お前の望むままに。
ただ、俺は
ずっとお前を
愛 シ テ イ ル
それだけ。
それだけだ。
「……………」
ハヤブサは、シュバルツにトン、と、頭をつけて、目を閉じて待った。
――――傷つけられる、瞬間を。
「……………」
パシャ、と、水音を立てて、シュバルツの手が、動いた。
「ハヤブサ……」
シュバルツの手が、ハヤブサの手を掴む。
「わ……………」
何か言葉を紡ごうとして、押し黙ってしまうシュバルツ。そのまま、掴まれている手に、ぐっと、力が入るから――――ハヤブサは『振り払われる』と、思った。だけど、自分がその手に力を入れる事はもうない。覚悟を決める。
シュバルツの身体の震えが大きくなり、はっきりとした嗚咽が漏れる。
「…………違う……」
絞り出されるような、声。
「………違う、違う! 違うんだッ!!」
「シュバルツ?」
シュバルツからいきなり出された大声に、ハヤブサは驚いてしまう。シュバルツは、そんなハヤブサの腕の中から、バッ! と、一歩、飛びだした。だがシュバルツは、握っているハヤブサの手を、決して離そうとはしなかった。そしてそのまま、彼はハヤブサの方に振り返る。
瞳から大粒の涙をぽろぽろと零しながら――――。
「違うんだ……ハヤブサ…! 私は……!」
頭を振り、涙を飛び散らせながら、シュバルツは大声で叫んだ。
「お前に触れられるのが――――『嫌』なんじゃ無いんだ……!」
(えっ……!?)
何かすごい言葉を聞いたような気がして――――ハヤブサはしばし呆然としてしまう。そんなハヤブサの目の前で、シュバルツの独白はなおも続いていた。
「済まない…! ハヤブサ……! 私は――――!」
「シュバルツ……」
「自分の、身体が―――――怖い……!」
「――――!」
ハヤブサは思わず、息を飲んでしまっていた。
(駄目だ…! こんな事を叫んでは―――!)
シュバルツの『理性』が、懸命に訴えてくる。
自分の身体の『歪さ』を、今更嘆いても仕方が無いだろうと。
こんな事を叫んだ所で、ハヤブサを困らせるだけだと。
だけど、触れてきたハヤブサの手が、あまりにも優しくて、哀しかったから――――。
止まれなく、なってしまった。
心がさらに――――千路に乱れた。
「怖い……! 怖くて仕方が無い…! この身体は、いつかお前を殺すかもしれない……!」
「シュバルツ……!」
「嫌だ……! 殺したくない……! 怖い……!!」
「…………!」
「だから私は……! お前のこの手を、離さなければいけないのに――――!」
泣きながら叫びながら―――シュバルツは、ハヤブサの手をますます強く握ってしまう。
そう。
ハヤブサの真の『幸せ』を願うのならば、自分はこの手を離さなければならない。
こんな、生きているのか死んでいるのかも分からない、中途半端な存在の自分。まして、肌を重ねたら――――そのせいで、彼を殺してしまいかねない自分。
理性は常に訴えている。
駄目だ。
ハヤブサを、自分に深く関わらせてはいけない。
彼を、振りほどかないといけない――――!
「それが分かっていて……! 分かっているのに、私は――――!」
「シュバルツ……!」
「離せなくて……! 手が……どうしても、離せなくて……!」
「――――!」
「駄目なのに―――! 私のこの身体は―――!!」
「シュ、バ……」
「違う……! キョウジ……! キョウジは、悪くない……ッ!」
「………!」
「キョウジが悪いんじゃない……! キョウジを責めたくない……!」
「シュバルツ……!」
「どうして……! キョウジ……! キョウジ…ッ!」
そのままシュバルツが、顔を覆って泣き崩れようとしたから――――ハヤブサの身体が勝手に動いてしまっていた。
「―――――ッ!!」
バシャッ!
ハヤブサがシュバルツを強く抱き寄せた故に、派手な水音が辺りに響く。そのまま強くハヤブサに抱きしめられるから、シュバルツはしばし、言葉を失ってしまった。
「あ…………!」
だが、肌と肌を密着させたが故に、シュバルツは気付いてしまった。ハヤブサの身体が、小刻みに震えている事に。
「あ……ハ、ハヤブ…サ……?」
その震えに戸惑っているシュバルツに、涙声のハヤブサから声をかけられた。
「大丈夫だ、シュバルツ……! 今、ここには俺とお前の二人しかいないから――――」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの髪を優しく撫でた。
「だから、泣いていい……! 泣いても、良いんだ…」
「――――!」
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
「あ…………」
強く抱きしめられるから、ハヤブサの涙をどうしても直に感じてしまう。でも――――だからだろうか。
(泣いても、いいの、か……)
素直に、そう思えたから。
「済まない……ハヤブサ……。じゃあ……少しの、間だけ――――」
そう言ってシュバルツは、ハヤブサの腕の中で再び泣き始めた。
腕の中で泣きじゃくる愛おしいヒト。
それを優しく抱きしめながら、ハヤブサもまた、涙を流していた。
だけど――――その涙には、かなりの嬉し涙が混じっている。
(済まないな、シュバルツ……。お前の『心』は哀しいのに……)
嬉しかった。
嬉しくて仕方が無かった。
だって、そうだろう?
「触れられるのが嫌じゃない」
「手をどうしても、離せない」
なんて――――
強烈な、『愛』の言葉じゃないか。
自惚れてもいいのだろうか。
シュバルツ、俺は――――。
お前にとって、少しは『特別』な存在に、なれているのだと。
「済まない……! ハヤブサ……」
腕の中で泣きながら、済まない、済まない、と、何度も謝る愛おしいヒト。
なぜ謝る?
なぜ謝るのだ、シュバルツ。
俺はこんなにも――――幸せなのに。
泣きじゃくるシュバルツの心は、痛くて、辛くて、哀しい。
なのに時折、シュバルツから零れる言葉に自分に対する『愛』が混じるから。
嬉しい。
嬉しい――――。
こんなシュバルツの『心』ならば、もっともっと浴びていたい、と、願ってしまうほど。
(ああ……。やっぱり駄目だな、俺は……)
シュバルツは辛くて泣いているのに、自分は喜びに震えて泣いてしまっている。
このままでは、やっぱり自分だけが、幸せだ。
シュバルツにも、『幸せ』を感じて欲しい。
でも、その為には、どうすればいいのだろう。
「駄目だ……! 済まない、ハヤブサ……!」
「シュバルツ……」
「止められなくて……涙、が……ッ!」
「大丈夫だ、シュバルツ――――」
ハヤブサは、シュバルツの髪を優しく撫でながら言った。
「時間はたっぷりある……。だから、ゆっくり泣いていい」
そう。
シュバルツは
ある意味やっと『泣けた』のだ。
『辛い』『苦しい』と――――やっと、言えたのだから。
だから、心行くまで泣いていいと思うし、そうするべきだと、思う。
「俺は大丈夫だから――――気にするな」
「ハヤブサ……!」
シュバルツの瞳から、また大粒の涙が零れる。
「済まない……!」
謝りながら、またこちらに身を寄せてくる、愛おしいヒト。
「謝るな……」
シュバルツの身体を優しく抱きしめながら、このまま時が止まってしまえばいいのに、と、ハヤブサは半ば本気で、祈っていた――――。
それからしばらくして、涙の止まったシュバルツが、浴槽の縁に腰をかけている。落ちついてはいるが、少しのぼせ気味のようだった。
(無理も無いか)
そう感じてハヤブサは苦笑する。なんだかんだと結構長い間、風呂に浸かっていたことになるのだから。
「……落ち着いたか?」
シュバルツにそう声をかけながら、ハヤブサもまた彼の隣りに腰をかける。冷やりとした外の空気が、火照った体には心地よかった。
「ああ……」
シュバルツは一つ大きく息を吐くと、ハヤブサに少し決まりの悪そうな笑顔を見せた。
「済まなかったな……。馬鹿みたいに、取り乱したりして……」
「謝るな。何回言わせる」
「だが、迷惑をかけ――――んっ……!」
何度言っても分かってもらえないから、思わずハヤブサはシュバルツの唇を塞いでしまう。
「……んっ! やっ…! んぅ………」
一瞬軽く抵抗をしたシュバルツであったが、ハヤブサがもう一度強引に唇を奪うと、今度は大人しくそれを受け入れていた。しばらくの間、舌と舌が絡まり、吸われる音が風呂場に響く。
「………迷惑などではなかったがな。俺としては――――」
やがて、シュバルツの唇を解放したハヤブサが、自身の口の周りに着いたシュバルツの唾液を舌でべろりと舐めとりながら、にやりと笑った。
「し、しかし……」
「もう一度、口付けが所望か?」
「あ……う……」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツが頬を赤らめながら下を向いてしまうから――――ハヤブサのあまり強くない理性が一気に傾いでしまう。
(シュバルツ……! お前、誘っているのか…!? その可愛らしさは最早反則だぞ……!)
「シュバルツ――――」
ハヤブサは一つ大きくため息を吐くと、シュバルツにずいっと詰め寄った。
「今すぐお前を抱きたい。抱いていいか?」
「えっ……!」
その言葉に身体をビクッ! と、硬直させ、怯えた表情を浮かべる愛おしいヒト。
だけどハヤブサは、もう迷わなかった。シュバルツの『怯え』の原因は分かっているから――――彼のその所作に、こちらがいちいち傷つくことはもう無い。
シュバルツは、「俺に触れられるのが嫌ではない」と言った。だから、その言葉を信じて突き進む。
「シュバルツ……」
熱を含んだ声でその名を呼びながら、その頬に触れる。
「…………ッ!」
こちらの手に、ビクッと過剰に反応するシュバルツ。瞳を閉じ、身体をカタカタと小刻みに震わせながら、こちらの手がその肌の上を滑るのを耐えようとしている。
(やはり、まだ怖いのか……)
今にも壊れそうな様相を湛えている彼を見て、ハヤブサの中で愛おしさと嗜虐心が綯い交ぜになる。このまま無理やり押し倒して、一気に蹂躙してしまいそうにさえなる。
おそらく、シュバルツはそれを許してくれるだろう。彼自身の持つ優しさゆえに。震えながらも逃げないでいるのは、そう言った心の現れなのだ。「『俺』が望むのならば、叶えてあげたい」と――――。
自身は心の中で、己の身体に対する恐怖と闘っているというのに――――。
その『優しさ』につけ込む事を、いくらでも許してくれるシュバルツ。
(駄目だろう、それでは……)
ハヤブサは頭を振る。このまま身体を蹂躙してしまったら、また、自分だけが幸せになって、シュバルツの心が置き去りになってしまう。それでは、先程心を抱きしめた意味が無くなってしまいそうな気がする。
自分は、シュバルツの心ごと、彼を抱きたいのだ。
容易く踏みにじる事を許してくれる存在だからこそ――――踏みにじりたくないと、願った。
「シュバルツ」
ハヤブサは、彼の頬を優しく撫でながら、愛おしいヒトに呼びかけた。
「俺の話を、聞いてくれるか?」
「話?」
きょとん、と、こちらを見るシュバルツに、ハヤブサは頷く。
「そう、俺とお前の『身体の話』を――――だ」
「――――!」
シュバルツの恐怖の根源に直接響く話題であるが故に、彼の身体が少し強張るのを、ハヤブサは見ていた。
「シュバルツ、俺は――――」
ハヤブサは少し考え込むように沈黙してから、再び口を開いた。
「俺はキョウジみたいに頭がいい訳じゃない…。だから、感覚的な物言いになって申し訳が無いが……俺は―――どうも、お前からDG細胞が感染する様には、思えないのだが」
「えっ……?」
その言葉に息を飲むシュバルツに、ハヤブサは笑いかける。
「そ、そんな……! だって、私の身体は……!」
「狂って『DG細胞』と化した、『アルティメット細胞』――――だったな?」
「――――!」
「言ったはずだ。俺は……。『キョウジから全部聞いた』と」
「あ…………」
そう。
シュバルツの身体は、キョウジが『造った』物だ。
狂って暴走したデビルガンダムに取り込まれかけたキョウジが、弟を守りたい一心で命をかけて造った。シュバルツ・ブルーダーと言う人間の『死体』と、狂って『DG細胞』と化した『アルティメット細胞』を使って――――。
その事の顛末一部始終を、ハヤブサはキョウジから直接聞いていたのだった。
だから、自分の身体を構成しているのは『DG細胞』
シュバルツは、そう認識している。
「だが、お前自体は暴走していない。お前の元になった『キョウジ』の人格も保たれたままだ。これは……他のDG細胞の感染者とは、明らかに一線を画すものではないのか?」
「そ、それは……!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは返す言葉を失ってしまう。
でも確かにそうなのだ。普通DG細胞に感染してしまった人間は、人格も何もかもを破壊されて、ただげらげら笑いながら他人を殺す、殺戮マシーンと化してしまう。自分の様に、人格も保たれて暴走もしないなんて、稀有な例だ。
「だ、だが、私がそうだからと言って………私の身体から、DG細胞が感染しないという保証は―――」
「では――――俺を見てくれ! シュバルツ!!」
ハヤブサはシュバルツの前で、腕を広げて見せた。
「俺はどうして……DG細胞の症状を、発症しないんだ?」
「…………!」
「あれだけ……お前を、抱いたというのに」
「あ…………!」
確かにそうだ。隼の里にいる時は、ハヤブサに身体を求められ続けた。夜の内に何度も抱かれた。そして、3日と空けずにそれが続いた。
「答えろシュバルツ。DG細胞が感染してから発症するまで―――潜伏期間はどれぐらいだ?」
「感染した動物や人間にもよるが、だいたい2週間程度………だが」
「なら――――最後にお前を抱いた時に感染したと考えても、俺はとっくに症状を発症していないとおかしいよな?」
「そ、それは……!」
「俺の身体を見てくれ……! どこか、DG細胞が感染している所が、あるか……?」
そう言いながらハヤブサは、何もかもを包み隠さずにシュバルツにその身体を晒す。ハヤブサの身体は、どこにも異常が無くて綺麗な物だった。だが、彼に欲情してしまっている己自身もあけすけに晒すから――――シュバルツは思わず、赤面して下を向いてしまっていた。
「な……無い、が……ハヤブサ………その……」
シュバルツが恥じらう原因を悟ったハヤブサも、「ああ……」と苦笑する。
「仕方がなかろう。俺は、お前を抱きたいのだからな。今すぐにでも――――」
「う………」
ハヤブサの自分に対する『熱』を間近に感じてしまって、シュバルツも、自身の身体に『熱』が灯るのを感じる。求められているのだから、応えてあげたいと思う一方で、どうしてもふんぎりがつかない自分がいた。
「ハ……ハヤブサ…。一つ、教えてくれないか……?」
「何だ?」
恥じらうシュバルツから漂う凄絶な色香に、ハヤブサは思わず理性が飛びそうになる。
だが懸命に堪えた。
震えながらも自分の側にいてくれるシュバルツ。彼は必ず自分に身体を許してくれると確信できるから――――いくらでも、待てると思えた。「触れられるのが嫌じゃない」「手を離せない」そう言いながら腕の中で泣きじゃくった彼の姿が、今のハヤブサを支えている。
「ど、どうして……『私』なんだ……?」
「何?」
シュバルツの質問の意図が一瞬飲み込めなくて、きょとんとするハヤブサに、シュバルツはもう一度、質問を重ねる。
「お、お前ほどの男なら……わざわざ私の様なモノを求めずとも、相手は引く手数多なのではないのか……? なのに、何故……」
「シュバルツ……」
ハヤブサは小さくため息を吐く。
自分から言わせてみれば――――シュバルツほど、自身の心を引き付ける存在などいない。それを、どう言えば目の前のこの美しいヒトに伝わるのだろう。
何度肌を重ねれば
何度唇を奪えば――――
それが、分かってもらえるのだろう。
(とにかく落ち着け)
ハヤブサは、己の劣情に鞭を打つ。
最初から、分かっていたはずだ。
その複雑な出自ゆえに、己の事を全く顧みないこの美しいヒト――――その『特別』になるのは、容易ならざる事なのだと。
身体を奪っただけでは――――その場所にはたどり着けないのだ。
伝えるしかない。
伝わるまで。
何度でも。
お前は俺にとって――――
既に『特別』なのだと。
「シュバルツ……」
ハヤブサは、シュバルツの手にそっと己の手を重ねながら、言葉を紡ぎ始めた。
「お前ならば、分かるだろう……? 俺たちの生きている世界は『闇』の世界だ。油断すればやられる。信じれば、裏切られる。『正義』が勝つとは、限らない……」
そんな世界で生き抜いて行くには、他者への気配りや優しさなど―――時に、呪いでしかなくなる時がある。そのせいで、命を落として行った者をたくさん見た。見捨てなければならない『命』も、沢山あった。
「甘さを捨てろ! でなければ、それが貴様の命取りになるぞ――――」
何度となく、忠告された。
だがそのたびに、「NO!!」と叫ぶ自分がいた。
『甘さ』は『悪』なのか。
『優しさ』は、不要の物なのか。
『弱い者』は、生きていてはいけないのか――――!?
否定したかった。
だが、自分が生きている世界は、そうではない。
人が人を食い物にする、真っ暗な世界。
生き抜くためには、非情に徹しなければならなかった。命乞いをして来た者でさえ――――時に、斬って捨てた。
「人殺し!!」
何度も、叫ばれた。
人は、醜い。
世界は、汚い――――。
その環に、確実に自分も入っている。
塗りつぶされそうに、なる。
「だけど、お前は躊躇わなかっただろう?」
「?」
不思議そうにこちらを見つめるシュバルツの手を、ハヤブサは少し強く握る。
「『弱者』に手を差し伸べる事を――――お前は、躊躇わなかっただろう」
「――――!」
それは、自分とシュバルツが一騎打ちをしている時に起きた。
自分達の戦いに巻き込まれかけた少女を、シュバルツは迷うことなく助けた。全く愚かな程無防備に。滑稽なほどに――――。
だがそれを、自分は『斬れない』と、思った。
それが、総ての始まりだった。
何て、甘い奴。
何て、馬鹿な奴。
こんな『忍び』が居るのか?
居て、いいのか――――?
「いいのだ」
そう言わんばかりに、その姿勢を貫くお前。
誠実に。愚直なまでに。
『甘さ』も『優しさ』も、あっていい。
『弱い者』に手を差し伸べる―――そんな『力』があったっていい。
人は、世界は醜いもの。それは、分かっている。
だけど、それだけじゃない。
信じていい、『優しい世界』も、確かにあるのだ。
ああ――――。
ずっと否定され続けてきた自分の中の『甘さ』を、初めて肯定された気がする。
「いいのだ」
「信じていいのだ」
「手を差し伸べて、いいのだ」
そう言って微笑む、優しい『光』がそこにあった。
「お前は、『光』だ。シュバルツ……」
「――――っ!」
「その『光』が、本当にそこにいるのか確かめたくて……。触れたくて、触れたくてたまらなくて俺は」
半ば強引に奪った。その身体を。
俺のこの『想い』は、お前を苦しめることになると知りながら――――。
「ハヤブサ……」
「よく考えろシュバルツ……。お前みたいな綺麗な魂が入っているその身体が――――」
ハヤブサはそう言いながら、握っているシュバルツの手にそっと唇を落とす。
「本当に……他人を殺してしまう様な物を、撒き散らす『元』になるとでも――――思っているのか?」
「そ、それは……!」
ハヤブサの言葉にシュバルツは戸惑ってしまう。
「で、でも――――私の、身体は……!」
「良いんだシュバルツ!! お前は―――!!」
「――――!」
「現に、俺は無事なんだ…! お前とこうして触れあっても…! 深く、身体を繋げても―――!」
「ハヤブサ……!」
戸惑い揺れるシュバルツの瞳を、ハヤブサはじっと見つめる。
「信じていいんだ……シュバルツ……」
自分には、DG細胞の専門的な知識がある訳ではない。だから、自分が言っている事には何の科学的根拠もない。空虚な理想論かもしれない。
本当に、シュバルツを構成しているDG細胞が特殊な物なのか、それとも、これだけ濃密に触れ合って、感染しない自分の方が特殊なのか、単に『2週間』と定義されているDG細胞の潜伏期間が実はもっと長いだけなのか――――それは、分からない。
(もしかしたらキョウジも……それを調べるつもりなのかもしれないな……。俺の身体を使って……)
ハヤブサはふと思った。
自分の身体を『被験体』として使いたいと言っていたキョウジ。もしかしたらDG細胞の感染と人間の身体の因果関係を、この機会に研究するつもりなのかもしれない。この身体を使って――――。
構わないと思う。
この優しい『光』が、何も恐れずに、幸せに生きて行く未来があるというのなら俺は――――。
この身体どころか
命だって、
くれて や る
だから――――
だから、シュバルツ。
信じてくれ。
お前と触れ合って、DG細胞の症状を発症していない俺を。
お前自身を――――!
「お前はもっと信じていいんだ!! シュバルツ!! お前を作ってくれたキョウジを!! そして――――お前自身を!!」
ハヤブサはいつしか叫んでいた。
祈るように。
捧げるように。
シュバルツの心に、届けと願う。
「そして、俺を信じてくれ!! お前と触れ合っても、DG細胞に感染していない俺を――――!!」
そう。
自分はDG細胞に『感染していない』
これだけは――――自分が胸を張って言えるたったひとつの『真実』
『真実』なのだ。
「ハヤブサ……!」
「シュバルツ、お前は――――!」
茫然とこちらを見つめるシュバルツの手を、ハヤブサはいつしか強く握っていた。
「俺の人生に……『光』を与えてくれた存在なのだぞ!!!」
「……………!」
シュバルツの瞳から、大粒の涙がぼろ……と、零れる。
良いのだろうか。
信じて、いいのだろうか。
キョウジを
自分を
そして――――
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
シュバルツの瞳から零れ落ちるそれは、堰を切ったように後から後から溢れてくる。もうそれは――――自分では、どうにも止められなかった。
「ハヤブサ!!」
シュバルツは涙を飛び散らせながら、ハヤブサの腕の中に、自ら飛び込んで、いた。
「あ…………!」
愛おしいヒトの思わぬ行動に、ハヤブサの身体が硬直する。
肌と肌が密着する。
その身体の震えを感じる。
耳に、シュバルツの嗚咽と吐息がかかる。
「シュバルツ……!」
押さえていた欲が、膨れ上がる。
血が沸騰する。
呼吸が荒くなる。
身体を強く抱き寄せて、自らの『欲』を押し当てて、そこに擦りつけてしまう。
「あっ……!」
腕の中で、愛おしいヒトからぴくん、と、反応が返って来るから――――ハヤブサの中で、何かが音を立てて切れそうに、なる。
「シュバルツ……シュバルツ……!」
熱に浮かされたようにその名を呼びながら、それでも残った最後のひとかけらの『理性』が、ハヤブサに働きかけた。
「いいのか……?」
耳に唇を押しあてて、問う。
「抱くぞ……!」
愛おしいヒトから、静かに答えが返ってくる。
「構わない……」
離れるどころか、さらに密着してくるシュバルツの身体。
「抱いて、くれ」
「―――――ッ!」
ハヤブサの中で、我慢に我慢を重ねていた欲望の堰が、ついに、音を立てて崩壊してしまっていた。
「シュバルツ!!」
止まれないハヤブサの熱は、強引にシュバルツの唇を奪う。まるで噛みつくように口付けをして、その口腔を貪った。
「うっ! んうっ……!!」
深すぎるキス――――
受けきれないシュバルツは、後ろへとバランスを崩してしまう。ザバン! と、音を立てて、二人の身体は湯船の中へと沈んでしまった。
水中でも、ハヤブサはシュバルツの身体を離さなかった。湯の中を漂いながら、尚もその唇を味わい続ける。しばらくして水面から顔を出してから、ようやくハヤブサは、シュバルツの唇を解放した。
「はあっ! はぁ……っ!」
酸素を求めて、喘ぐシュバルツ。だがハヤブサは、そんなシュバルツを休ませる気は毛頭なかった。背中から抱き寄せると、指でシュバルツの乳首を弄ぶ。
「あっ! ああっ!!」
バシャッ! と、水を撥ね上げながら、シュバルツの身体がしなる。その肌の上を、ハヤブサのもう一方の手が優しく滑っていく。脇腹から臍、そして、シュバルツ自身へと――――。
「うあ! あっ! ああ……!」
自身の一番感じる所を刺激されてしまって、シュバルツは身悶えるしかない。シュバルツの手が、知らず、縋る様にハヤブサへと伸ばされて行く。ハヤブサは、その手を自身の肩に摑まらせてやると、シュバルツの耳に、チュッ、と、音を立てて口付けをした。
「――――ッ!」
ビクン! と、跳ねる、愛おしいヒトの身体。その身体を抑えつけるように抱き締めると、今度は口と舌を使って、その耳を弄び始めた。「愛している」と、囁きながら、耳の中に舌を侵入させて、ぺちゃぺちゃと音を立てて舐めてやる。
「は…! あっ!! だ、駄目っ!! ハヤブ、サ…ッ!!」
その刺激から逃れようと、腕の中で身を捩ろうとするシュバルツ。だが、ハヤブサの腕が、それを許さない。
「あ……! あ……!」
耳を犯される音と、感じる所を擦られ続ける刺激に、シュバルツの身体がビクビクと震える。ハヤブサは、その身体に自身の身体を密着させて、その震えを愉しんだ。
(もっともっと――――乱れてくれ、シュバルツ……)
2週間と3日、18時間と35分ぶりに味わうシュバルツの身体だから。
存分に味わう。
存分に刻みつける。
俺がどれだけシュバルツに飢えていたか――――。
彼に分かってもらうまで。
「ああっ! ハ、ヤブサ……っ! ぅあっ!」
顎に手をかけ、その唇を求める。優しく唇を塞いでやると、シュバルツの身体から力が抜けて行くのが分かった。
「ふ……んぅ………」
それをしながらハヤブサの手が、シュバルツの臀部に伸びてくる。その手は双丘を撫でながら、シュバルツへの入り口を求めた。
「んんっ!」
つぷっ、と、突きいれられる2本の指。シュバルツの身体の反応に合わせて、バシャッ! と、周囲の水が撥ねる。
「ふあ…! んぅっ!!」
離れようとしたシュバルツの唇を許さず捕らえる。そのままハヤブサは、上と下からシュバルツを犯し続けた。
「ん……! んっ……!」
それを受け入れ続けるシュバルツの身体がビクン、ビクンと乱れる。
「んぅ……! んく……!」
彼の手が、ハヤブサの蠢く腕に触れてきた。
だがその手は、あくまでも優しく、その腕にそっと添えられるだけだったから――――シュバルツの『赦し』の意思を強くハヤブサに伝えてくる。ハヤブサの中の『熱』が、さらに煽られてしまう。
(挿入(ハイ)リタイ……)
強く願う。
と、同時に、シュバルツの方も自ら足を開いて行った。
「シュバルツ……!」
その恥じらいながらも妖艶な動きをする彼に、ハヤブサは思わず息を飲む。すると、それまで瞳を閉じて刺激を耐え続けていたシュバルツが、その瞳を開けてハヤブサを見た。
「ハヤブサ……」
涙を湛えたシュバルツが、優しく微笑みかけてくる。
それは、何とも犯しがたい美しさを湛えていたから、ハヤブサは知らず見惚れてしまう。何故だろう。彼はこんなにも――――自分に犯されていると言うのに。
「来てくれ……」
聖なる天使から紡がれる、妖艶な言葉。
「―――――!」
動きの止まったハヤブサに、シュバルツはもう一度、優しく微笑みかけた。
「大丈夫、だから……もう……」
自分の身体の奥底に灯った『熱』が、ハヤブサを望んでいる。
分かる。
『求める』とは、きっと、こういう事を、言うのだろう。
自ら足を広げながら――――シュバルツはそう感じずにはいられなかった。
「―――シュバルツ!!」
彼のその痴態と言葉に、ハヤブサは頭から突っ込んだ。彼の腰を強く抱き寄せると、そこに一気に自らの楔を深く深く打ち込んでしまう。
「うあ…! ああああ―――――ッ!!」
その性急過ぎる繋がりに、腕の中の愛おしいヒトから悲鳴が上がり、その身体が仰け反る。無理もない、と、ハヤブサは思う。久しぶりに自分を受け入れるシュバルツの身体。出来れば―――もっとほぐしてやりたかった。
だが、『来て』と言われ、あんな痴態を見せられてしまっては――――もう突き進む以外に、ハヤブサの選択肢はあり得なかった。狂ったように律動を繰り返しながら、シュバルツを貪るように求めてしまう。
「ああっ!! ああっ!! ハヤブ、サッ!!」
その大きすぎる刺激に耐えながら――――シュバルツは涙を飛び散らせていた。
でもその涙には、『歓喜』の色が確かに混じっていた。
嬉しい。
嬉しかった。
「信じていい」と、言われて――――。
分かっている。
ハヤブサの言葉には、何の科学的根拠もない。
自分の身体が『危険なモノ』で構成されている事実は、変わらない。
それが、キョウジの『罪』の塊であると言う事実も。
だけど。
だけど――――。
信じていいのだろうか。
自分を作りだす元になったのは、キョウジの『良心』
それを信じていいのだろうか。
キョウジの『心』は――――確かに、DG細胞の凶悪性に打ち勝っているのだと。
ああ―――――
キョウジ、
キョウジ……。
信じたい。
キョウジの『心』を信じたい。
その強さを、信じたい。
「信じていいんだ!!」
叫ぶハヤブサ。
自分と深く繋がっても、DG細胞に感染しないハヤブサ。
彼が今身体を張って証明してくれている、たった一つの『事実』
信じ、たい。
信じさせて、くれ。
お前の言葉を信じる 『勇気』 を――――
どうか、私に……!
「ああっ! ハヤブサ…! ハヤブサ……ッ!!」
涙を飛び散らせながら、縋る様に自分の名前を叫ぶ、愛おしいヒト。
その様に、ハヤブサの中で愛しさばかりが募っていく。
たまらずに穿ちながらキスをすると、シュバルツの方も積極的に舌を絡めて来てくれた。
「んぅ……。ん……っ」
ハヤブサ自身をきつく締めつけていたその場所に、柔らかさと甘さが宿り始めるから――――ますますシュバルツの身体に溺れて行ってしまう。
(シュバルツ……! シュバルツ……!)
たまらない。
こんなに愛おしい存在は他には居ない。
心も。そして、身体も――――。
だけど、一つだけ――――俺は、お前に告げない事がある。
それは
お前を抱く時
俺は必ず自身の『死』の可能性も、意識している、と言う事だ。
シュバルツが恐れている通り、自分にDG細胞が感染する可能性も決して0%ではない。何の保証も無いのだから――――。
だけど、自分が生きている『闇の世界』は、自分の『明日の生』を、必ずしも保証する場所ではない。いつ何時、どこかの路地裏で――――路傍の石の様に自らの死骸を晒す事になるか、分からない世界なのだ。
たくさんの血を吸ってしまっている自分の手。
今更、まっとうな人生を送れるとも思っていない。人並みの幸せなど――――望むべくも無かった。
そこに思いもかけず現れた、愛おしむべき存在。
その人が、自分の『想い』に応えてくれる。
――――望外の幸せだった。
だから。
だからこそ、だ。
(俺は……シュバルツに殺されたがっているのかもしれない)
ハヤブサはふと思った。
もしも、もしも――――『死』をもたらしてくる相手を選べるのならば。
ならば、俺は、シュバルツ――――お前がいい。
お前の手による『死』なら――――
俺は、喜んで受け入れられるだろう。
かつてお前が
「介錯の相手を選べるのならば、私はハヤブサ、お前がいい」
そう言ってくれたように。
シュバルツ……俺も。
首を刎ねられるなら、お前がいい。
お前が、いいんだ。
だけど――――誰よりも『命』を大切にするお前は
決して俺を殺す事を望みはしないだろう。
だから――――俺は、絶対にこの望みを、口にはしない。
お前を、哀しませたくは無いから。
これは、俺だけが望む
俺だけの『秘密』だ。
「あっ…! ああっ! ああっ!! だ、駄目っ……だ!」
穿たれながら感じる所を擦られ続け、シュバルツが限界を訴えてくる。
「は……あ……ッ! ああ!!」
ビクビクッ! と、シュバルツの身体が震え、ガクッと力が抜けて行く。どうやら、達してしまったらしい。シュバルツの前方の湯が、彼の『精』で白く濁って行く。
「ひどいな、シュバルツ……」
ハヤブサが「ククッ」と低く笑いながら、力の抜け切ったシュバルツの身体を優しく抱き寄せる。
「あ…………」
「俺がまだ達していないのに……先に『イク』なんて――――」
「す、済まな――――うあッ!!」
ハヤブサの手が、シュバルツの乳首を少し乱暴に摘まんだが故に、シュバルツから悲鳴が上がった。
「構わないさ……。久しぶりだったんだ。―――感じすぎたんだろう?」
そう言いながらハヤブサの手が、シュバルツの乳首を弄り回す。達したばかりでより敏感になってしまっているシュバルツの身体は、たまらず勝手に跳ねてしまう。
「あっ! ……やっ! ち、違……ああっ!!」
「いいさ…。俺は――――もう少し、愉しませてもらうから―――」
跳ねるシュバルツの身体を抑えつけて、さらに楔を奥へと打ち込む。
「あうっ!!」
一度達したが故に熱を持ち、程よくほぐれてしまったそこは、そのハヤブサの行為を容易く受け入れてしまう。
この柔らかい感触のシュバルツが、ハヤブサはたまらなく好きだった。この感触が味わいたくて――――ハヤブサはいつも、わざと先にシュバルツを追い込んだ。
感じやすく素直な身体を持つこのヒトは、こちらの目論見に簡単に引っ掛かってしまう。
それでも自分と一緒に達しようと、果てるのを懸命に我慢するシュバルツを堪能するもよし。
先にイッてしまったシュバルツを、言葉で責めながら、弄び気味に抱くのもいい。
はたまた『一緒にイキたい』と懇願する彼と共に、達するのも捨てがたい。
要するに――――このヒトは抱いていて、飽きる事が無いのだ。
身体を繋げれば繋げるほど――――尚の事、増す愛情があるばかりだった。
「ああっ!! ハヤブサ…ッ! ハヤブサぁ……! あ、あ……!」
最奥を攪拌されて、シュバルツの身体が仰け反る。そんなシュバルツの身体をハヤブサは捕まえると――――先程『精』を吐き出した、シュバルツ自身の様子を確かめるべく、手をそこへと伸ばしていた。
「あっ! 駄目っ!!」
ハヤブサが触れたそこは、貫かれ、内部を擦られる刺激に反応して、再び硬度を取り戻そうとしている。ハヤブサはにやりと笑うと、その亀頭の割れ目をカリカリと優しくひっかいてやった。
「ひっ!! う……ッ! あっ!!」
その刺激に、シュバルツのそこは素直に反応する。ハヤブサの手に、はっきりとした硬さを伝え、その指先には、風呂の湯以外の液体の感触を伝えてきた。
「シュバルツ……もう、こんなに――――」
ハヤブサは、シュバルツにわざとそこの状態を悟らせるように、全体をゆっくりと形どる様に触ってやる。と、同時に、その指に絡んだ先走りの液が、『ぬるり』とした感触をシュバルツに与えた。
「んっ! やっ、あ……!」
「硬くなっている……。感じやすいんだな」
「ち、違……! そんな風に、触られたら……ッ! 誰だって……!」
「俺がこんな風に触りたいのは――――お前しかいないぞ?」
「ふ……あっ!?」
再びズッ! と、音を立ててシュバルツの最奥を穿ち始める侵入者。ハヤブサの律動は、前にも増して激しくなって行く。
「あっ!! 駄目、だ!! イッた……ばかり、で……! ああっ!!」
暴走して膨れ上がっていくハヤブサの『熱』を、懸命に受け入れるシュバルツ。その様がとても健気で可愛らしいから――――愛おしさが止まらなくなる。もっともっと、欲しくなってしまう。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
うわ言の様に呼ばれる名前。
穿たれ、擦られ続ける体内。
触られ続ける身体――――。
これだけでも、充分おかしくなってしまいそうなのに。
愛シテイル
愛シテイル
愛シテイル――――
ハヤブサから絶えず降り続いてくる――――声。
その声は熱くて激しくて、時に凶悪な強さを伴ってシュバルツに降り注いでくる。
真っ直ぐでひたむきな、ハヤブサの――――『愛』
キョウジの『愛』とは、また違った形の……。
「ハヤブサ……! あ…! ハヤブサ……ッ!」
その声は、『自分と一つになりたい』と訴えてくる。
無理なのに。
自分とハヤブサは全く別の生き物だから、完全に『一つ』になどなれるはずもないのに。
なのにその声は、熱を伴って自分の内部へと侵入してくる。
そして、自分の中を攪拌して生じた熱を、感じる所へと集められてしまう、から。
「あっ!! 駄目……ッ!!」
ビクン、と、跳ねる身体。
その反応こそが、ハヤブサの熱をさらに煽ってしまっていると言うのに。
シュバルツの方も、自分で自分の身体を止める事が出来ない。
触れられて擦られて――――跳ねてしなってしまう。
「愛している…! シュバルツ……!」
耳に注ぎ込まれる、熱い声。
「――――ッ! ハヤブサ……」
(愛している。私も――――)
もう何度、そう返しそうになった事だろう。
だけどシュバルツは、そのたびに踏みとどまった。
自分は、『男』で、しかも『人間』ですらない。『人間』が永遠の愛を誓う相手には、決してなり得ないし、なってはいけない存在だと思う。
これはあくまでも一般的な理論かもしれないが、『人間』の究極の目的と幸せは―――やはり、生涯の伴侶を見つけて、その間に子を成し、その命と血脈を未来へ繋いで行く事なのではないかと思う。
だけど、自分とハヤブサの間では――――それは不可能だ。
『人間』と『アンドロイド』の交わり。そこから生まれるものは、何も無いのだから。
どんなに想い合っても、結実しない『愛』
自分とハヤブサの関係は、その場限りの刹那的なものだと言ってもいい。
だから。
だから自分は告げない。告げられない。この『想い』を――――。
ハヤブサが真の伴侶を得て、幸せを掴もうとした時に、この『想い』が彼の『枷』になってしまうのは、シュバルツとしても本望ではなかった。こちらの『想い』を知ってしまったら――――彼は、伴侶を得た後も気にしてしまうかもしれない。こちらの事を。何だかんだ言って、根が真面目な奴だから……。
構わない。
ハヤブサが幸せになるためならば、自分はいつでも身を引ける。『アンドロイド』たる自分は、人の『幸せ』の傍観者であるべきだから――――。
わきまえておかねばならない、と、思う。
『幸せ』になって欲しいと、願う。
キョウジも。
そして、ハヤブサも――――。
ああ――――。
ハヤブサから降り注ぐ、大きな『愛』のシャワーを浴びながら思う。
きっと、ハヤブサに愛される真の伴侶になれる女性は、幸せだろう。
これだけの愛を、受けられて――――。
………涙が零れる。
何故なのだろう。
「シュバルツ……」
ハヤブサの唇が、自分の流していた涙をそっと掬い取っていく。
「あ…………」
何故――――彼には分かってしまうのだろう。私が、泣いている事が。
髪も顔も、風呂の湯で濡れていると言うのに。
どうして――――
涙を掬っていたハヤブサの唇が、自身の唇へと滑って来る。
「ん…………」
ひどく優しく塞がれる唇。そのままちゅ、ちゅ、と、音を立ててついばまれる。
下は深く深く結合していると言うのに。
そこだけ――――とても、優しかった、から。
「んあ……! ハヤブ、サ……ッ!」
堪らなく、なる。
いつしかシュバルツは、ハヤブサの背に縋るように手を回していた。
「シュバルツ……ッ!」
シュバルツに『求められている』と感じたハヤブサの律動が、さらに熱を帯びて激しい物へとなっていく。
「ああっ! ハヤブサぁ!!」
ハヤブサを受け入れているシュバルツの身体が、弓なりにしなった。バシャッ! と、音を立てて周りの湯が撥ねる。
せめて。
せめて、憶えておく。
ハヤブサから、これだけ深く愛されたのだという記憶を――――。
そうすれば、万が一、彼と別れてしまった後も
『幸せ』な記憶だけを、持っていける、から。
「ハヤブサ…! ハヤブサ……!」
(愛シテイル)
言えない言葉の代わりに、『想い』を込めて、その名を呼ぶ。
「ハヤブサ……ッ! あっ! ああっ!!」
世界でたった一人の、大切な人の、名前だから。
せめて、『想い』を込めて。
「シュバルツ……!」
熱で浮かされたように、自分の名を呼ぶ愛おしいヒト。
特別な響きを持つその声は、ハヤブサの腹と背中に電流を走らせる。何故か、ひどく甘美に心に届いた。
「く……! う……ッ!」
それと同時に、シュバルツからもたらされる、甘い締め付け――――堪えようとするが、堪え切れなくなってしまって。
「――――ッ!」
「あ……! ああああ―――ッ!!」
ハヤブサもついに、シュバルツの中に果ててしまった。
(熱イ…………!)
ドクドクッ! と、体内に注がれるハヤブサの『精』の熱さに、シュバルツは震える。小刻みに震えるシュバルツのその身体を、ハヤブサはそっと抱きしめてきた。髪を優しく撫でられ、頬ずりをされる。―――ハヤブサの『優しさ』が伝わって来る、瞬間。シュバルツはこの抱擁が、とても好きだった。
(終わった……の、か?)
ハヤブサのその抱擁を受けながら、シュバルツの身体の震えは尚も止まらなかった。それほどまでに――――ハヤブサから受けた『愛』は、激しく大きい物だったから。
ズルッ、と、音を立てて、シュバルツの体内からハヤブサの物が引き出される。
「あっ! は……! んんっ!」
その出される感触に、シュバルツは思わず身悶えてしまった。大きく震えて、膝から崩折れそうになってしまう。
「おっと……! 大丈夫か?」
倒れそうになるシュバルツの身体を、ハヤブサの力強い腕が支えた。
「あ………」
そのまま彼の身体を抱きよせて、そっと自分の身体に凭れかからせてやる。すると、彼は大人しくハヤブサの腕の中に身を委ねてきた。自身の肩にシュバルツの手が添えられるように伸ばされて来て、すり……と、少し甘えるように身を擦り寄せられる。
(…………!)
達して熱を持ち、火照ったシュバルツの身体。
その身体が、小刻みに小さく震えているのを、腕の中に感じてしまう、から。
収まりかけていた自身の黒い欲望が――――どうしても頭をムクリともたげて来てしまう。
ふと見ると、シュバルツの背後の湯が、『精』の名残らしきもので白く濁っているのが見える。恐らく、彼の『秘所』からそれが流れ出て来ているのだろう。
ハヤブサの口元が、少し邪悪に歪む。
予定ではこの後、寝所に連れ込むつもりだったが――――。
もう少しだけ、風呂場で――――愉しむとしようか。シュバルツ……。
「シュバルツ……」
呼び掛けて唇を求めると、愛おしいヒトは素直に応じてきた。
「ん………」
想いを交わし合う様なキスをする。至福の瞬間だった。互いの唇が離れた後、ハヤブサはシュバルツの身体をぎゅ、と抱きしめる。
(!?)
だが身体が密着したが故に、シュバルツは気付いてしまう。ハヤブサの『そこ』が、また勃ち上がって来ている事に。
(……えっ? ちょ……っ! さっき、イッたばかりで……!)
思わず、ハヤブサから距離を取ろうとするシュバルツ。だがハヤブサの腕がそれを許さなかった。彼が腕の中から逃れようとするよりも早く、シュバルツの身体を強く捕まえてしまう。
「あっ!」
抱きしめられる強さに、小さく悲鳴を上げるシュバルツ。そんなシュバルツの耳に、ハヤブサの唇が押しあてられる。そして、こう囁かれた。
「……身体を洗ってやるよ」
「――――!?」
ハヤブサのその言葉に、シュバルツは思わずビクッ! と、身を強張らせた。こんな状態のハヤブサに『身体を洗ってもらう』なんて――――激しく、嫌な予感しかしない。
「い、いや……いいよ」
首を横に振るシュバルツに、ハヤブサは尚もにやりと笑いながらたたみかけてくる。
「まあ、そう遠慮せずに」
「いいって! 自分で洗える。子どもじゃないんだから――――!」
必死になって遠慮しようとしているシュバルツの耳元で、ハヤブサは小声でこう囁いた。
「『報酬』……」
「―――――!」
「『報酬』のはずだよな? 今、お前は……」
「うぐっ……!」
ハヤブサから痛い所を突かれて、シュバルツはぐっと言葉に詰まってしまう。
「『一日……俺の好きにさせてくれる』って、言ったのに……」
「~~~~~~ッ!」
「お前は俺に……『嘘』を言ったのか……」
「ううう………!」
(こ、こいつ……! このタイミングでこれを言うか―――!?)
ハヤブサに確信犯的に追い込まれている今の状況に、シュバルツの身体がわなわなと震える。
だが確かに、『報酬になる』と、頷いたのは、他ならぬ自分だ。
『1日好きにして良い』と、ハヤブサに言ってしまったのだから――――。
シュバルツには、観念する以外、選択肢が残されていなかった。
「う……う……分かった……」
「シュバルツ!?」
「お前の……好きに…すれば、いい……」
「――――ッ! やった―――――!!」
風呂場に、ハヤブサの歓喜の叫び声が響き渡る。彼は叫び終わると同時にシュバルツの身体を抱きかかえると、あっという間に彼を洗い場の所まで連れて来てしまった。
ドン! と、風呂場の椅子を置いてシュバルツをそこに座らせると、自分は鼻歌を歌いながら、手にボディーソープをつけて泡立てている。
「て、手で洗うのか?」
「当たり前だ。他に、何か洗う物があるのか?」
「う……それは……」
ハヤブサにスパンと切り返されて、シュバルツは言葉を失ってしまう。
「タオルでも用意出来ていたら良かったのだがな……ああ、それよりも――――」
ここまで話したハヤブサが、口元に「ククッ」と少し暗い笑みを浮かべる。
「……何を考えているんだ?」
ハヤブサの変ににやついている顔を、シュバルツがじと~っと睨みつけるから、「別に?」と、ハヤブサは素っとぼけた。今想像していた事は、とても口に出してなどは言えない。それこそ、俺だけの『秘密』だ。
それよりも――――今からシュバルツの肌を、この手で存分に堪能する事に集中する。それこそ――――身体の『隅』から『隅』まで。
「シュバルツ」
呼び掛けて唇を求めると、シュバルツはやはり、素直に応じてくる。
「……んっ……!」
舌を少し深く差しいれると、シュバルツからくぐもった声が漏れる。そして、その身体が少し震えていたから、男の嗜虐心が軽くそそられてしまう。――――可愛らしいヒトだ。心も、身体も……。
「じゃあシュバルツ……洗うぞ……」
背後に回って耳元でそう囁いてやると、愛おしいヒトの身体がビクン、と、跳ねた。
ペチャ……と言う音と共に、泡まみれのハヤブサの手が、シュバルツの身体に触れてくる。
「――――ッ!」
その独特の感触に、ブルッと震えるシュバルツ。そんな彼の身体を、ハヤブサの泡まみれの手が遠慮なく撫で回して行く。肩、腕、掌、指の一本一本まで――――必要以上に丁寧に。まんべんなく触れられて行った。
「ん……! や……!」
あまりにも丁寧に触れられるから――――シュバルツは逆に身を固くしてしまう。洗われている刺激だけで変に感じてしまう自分の身体が、とても淫らな物の様に思えてしまって、たまらなく恥ずかしかった。
「んっ……! く……!」
ハヤブサの手が自分の身体に触れるたびに、声が漏れそうになる口を、手で押さえて必死に耐える。
「ああ……そんなに、怯えないで…。可愛いヒト……」
「で、でも……!」
「俺は……洗っているだけだぞ?」
そう言いながらハヤブサの手が、するりとシュバルツの首筋を滑っていく。
「…………!」
もう片方の手が、わき腹を撫でる。
「……ふ……うっ!」
(た、確かに……洗っているだけ…なのに……!)
変に『感じて』しまう自分の身体にシュバルツは困惑してしまう。
おかしい。
どうして?
どうして――――。
ぶる……と、小刻みに震えるシュバルツの身体を、ハヤブサは背後から優しく抱き寄せてやると、そっと、その乳首を摘まんだ。
「は! ああっ!」
ビクン! と、跳ねてしまうシュバルツの身体。ハヤブサはにやりと笑うと、わざとそこを擦ったり弄り回したり揉んだりして――――愉しんだ。
「やっ……! ん……っ!」
「逃げるなシュバルツ…。洗えないだろう?」
「ふっ……! んんっ…!」
フルフルと首を振りながら、シュバルツは何とか身を捩ろうとする。だがハヤブサに優しく抑え込まれて、身動きが取れなくなってしまった。
「んっ! ……ふっ! ……く……」
動けなくなったシュバルツの胸の上を、ハヤブサの手が無遠慮に滑っていく。
「……ふっ! ふぅ……!」
胸ばかりを執拗に弄られて、シュバルツの身体がぴくぴくと震える。固く閉じられた瞳から、涙がじわりと滲み出て来ていた。
「んんっ! …く……!」
(懸命に声を殺して感じるのを堪えているシュバルツもそそられるが……そろそろ声も聞きたいんだよな……)
シュバルツの臍をゆっくりと丁寧に洗ってやりながら、ハヤブサは目論む。
(手が邪魔だな)
「シュバルツ。手を上にあげろ」
「…………!」
ハヤブサの突然の言葉に、シュバルツの身体がビクッ! と強張る。
「んんっ!」
シュバルツは懸命に首を振って、『嫌』と言う意思をハヤブサに伝える。だがその仕草は、ハヤブサの中の黒い劣情を、ますます煽ってしまうばかりで。
「シュバルツ。洗えないだろう?」
身体を優しく抱き抱えながら、胸の頂をそっと擦ってやる。もうそこはぷっくりと芯を伴って勃ち上がり、ハヤブサに快楽の限界を訴えていた。だからなおのこと――――ハヤブサはそこを、弄んだ。
「んっ! んぅっ!!」
ビクリ、と震えるシュバルツから、涙が飛び散る。その涙を、舌でペチャ…と、舐めとってやりながら、ハヤブサはわざと優しくシュバルツに囁きかけた。
「シュバルツ……。ほら……早く……」
「や……! いや、だ……!」
シュバルツは必死に抵抗をする。
こんなにじっくり愛撫をされてしまったら――――自分が、どんなあられもない声を出してしまうか分からない。堪らなく恥ずかしいから、勘弁してほしいとシュバルツは思った。だが―――その『痴態』こそ、ハヤブサが最も見たい物だったから、その抵抗は、却って『逆効果』になってしまう。
「お前に――――『拒否権』は、無いはずだが……?」
「――――ッ!」
わざと冷たく言い放ってやると、愛おしいヒトの身体が腕の中でぶるり、と、震えた。ハヤブサは「クッ」と低く笑うと、もう一度シュバルツの震えている耳に囁きかかける。
「ほら……腕を、上げて――――」
ハヤブサの言葉に、シュバルツもついに観念してしまったようだ。
「う、う……。く……!」
震えながらも口から手を離して、ゆっくりと両手を上げるシュバルツ。それを見たハヤブサがにやりと笑いながら、さらなる命令をシュバルツに下す。
「よし。その手をそのまま、頭の後ろで組め」
「な――――!」
驚き硬直するシュバルツの二の腕を優しく撫でながら、ハヤブサは微笑む。
「分かっているよな? シュバルツ……」
「………ッ!」
ハヤブサの言葉に従う以外、今の自分には選択肢が無い。シュバルツは言われたとおり、頭の後ろで両手を組んだ。
「いい子だ……」
ハヤブサの舌が、シュバルツの組んだ両手をペチャ…と、舐める。
「っ!!」
その刺激に、ビクリ、と震えるシュバルツの身体。
「そのまま――――動くなよ」
「う…………」
ハヤブサのその言葉に、観念したように瞳を閉じるシュバルツ。身体が震えて、頬に一筋の涙が流れる。ゾクッとするほどの美しさと色気に、ハヤブサの中で愛しさと嗜虐心が綯い交ぜになる。
「シュバルツ……」
想いをこめてその名を呼びながら、ハヤブサはシュバルツの脇の下にペチャ……と、泡だらけの手をつけた。
「んっ!」
その刺激にビクリ、と跳ねるシュバルツの身体。ハヤブサはそのまま、無防備に晒されている脇の下を『洗って』やる。じっくりと。丁寧に――――。
「ふっ! んんっ…! く、う……!」
どうしても『感じて』しまう、身体。だが声を出すことだけは――――懸命に唇を噛みしめて耐えた。懸命な抵抗――――――だが、その抵抗こそが、ハヤブサの黒い劣情を煽り続けている事に、シュバルツは気付けない。
つい、と、ハヤブサの指が、シュバルツの胸に滑って来る。
「は! あっ…!」
ふいに襲われた甘い刺激に、シュバルツから思わず声が上がる。その反応を見たハヤブサの口元が、にやりと歪んだ。そのままハヤブサの指が、シュバルツの乳首を嬲る様に弄び始める。
「んっ! や……っ! や…あ……っ!」
たまらずビクビクと跳ねる、シュバルツの身体。
「動くなシュバルツ。洗えない」
ハヤブサの言葉にシュバルツは頭を振る。
「あっ…! だ、だって……! そ、そこは、もう……何度も、洗って……っ!」
「何度も触るからな。ちゃんと『洗って』やらないと―――」
「そ、そんな……っ! ああっ!!」
しなるシュバルツの身体。芯を伴って張り詰め過ぎている乳首は、もう僅かな刺激にすら耐えられない。それなのに、ハヤブサの手に容赦なく触られるから――――シュバルツはもう、おかしくなってしまいそうになる。
「やめ…っ! も……! あああ……!」
押さえられず、漏れ出す声。
「まだだろう? シュバルツ……」
のたうつシュバルツの身体を愉しみながら、ハヤブサは尚も囁くように声をかける。
「え…? ま……だ……?」
「足が――――『下半身』が、まだだ」
「―――――!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは思わず息を飲む。今ですらもう、耐えられそうにないのに。これ以上、こんな愛撫が続いてしまったら――――。
「あ……! や……!」
「怯えないで……可愛いヒト……。ちゃんと『洗って』あげるから―――」
シュバルツの乳首を弄ぶ両手は、最早彼の身体を『洗って』などはいない。それをしながらハヤブサは、シュバルツに更なる『痴態』を要求する。
「だからシュバルツ……足を、開いて……?」
「そ、そんな……!」
恥ずかしい要求に、がくがくと震えるシュバルツの身体。
「だ、駄目…! 無理――――あうっ!!」
ハヤブサに、乳首を強く摘ままれたが故に、シュバルツから悲鳴が上がった。
「『無理』じゃないだろう? シュバルツ……」
背中やわき腹を優しく『洗って』やりながら、ハヤブサは言葉を続ける。
「お前はもう……何度も俺に、身体を『開いて』いるのに……」
ハヤブサの指が、シュバルツの腰骨の辺りをカリカリとひっかく。
「あっ!」
ビクッ! と、シュバルツの身が捩れる。呼吸が乱れ、涙が飛び散る。そんなシュバルツにハヤブサはもう一度、優しく囁きかけた。
「大丈夫だから……俺を信じて、足を、開いて……?」
ペチャ……と、ハヤブサの手が、シュバルツの内股に滑って来る。
「んっ! ……あ……!」
「ほら……シュバルツ……」
そのまますりすりと、ハヤブサの手に内股を優しく撫でられる――――から。
「う……く……!」
その刺激に合わせる様に、シュバルツの足が、ぐ、ぐ、と、開いて行ってしまう。
「あ……あ………」
手を頭の後ろに組んだまま、背の低い風呂の椅子にすわり、M字開脚をするような格好になってしまったシュバルツ。恥ずかしいのか固く目を閉じ、身体を小刻みに震わせている。上気した頬の上を、涙がツ…と、伝い落ちて行く。
(…………!)
ゾクッ! と、ハヤブサの背中を甘い電流の様な物が駆け抜けて行った。何とも妖艶な格好をしたシュバルツ。いつみても何度見ても―――――むしゃぶりつきたくなるような、美しさと色気だ。
(ああ――――やはり……美しいな。お前は……)
目の前の愛おしいヒトの『痴態』にくらくらする。自分の中の劣情が、はちきれそうになる。
だが、懸命に堪えた。
こんな風にゆっくりじっくりシュバルツを抱く事が出来るなんて――――めったにない出来事だと思うから。
(存分に、堪能させてもらうぞ……シュバルツ……)
ハヤブサはにやり、と笑うと、再びシュバルツの足を、べちゃり、と、音を立てて『洗い』だした。
「う………!」
その刺激にピクリ、と、反応するシュバルツの身体。そんなシュバルツの太腿の上を、ハヤブサの手がゆっくりと滑っていく。
「ん…! く………!」
「……勃っているな」
シュバルツの足を触りながら、ハヤブサはわざと彼の耳元でそう囁いてやる。
「や……! 言うな……ッ!」
上気した頬を更に真っ赤にして、頭を振る愛おしいヒト。
「仕方がなかろう。『見える』のだから――――」
ハヤブサは「ククッ」と低く笑いながら、足を丁寧に洗い続ける。でも、目は『そこ』を見ている。お前が感じてしまって、震えながら勃ち上がらせてしまっている『そこ』を――――。
そう。これは『視姦』だ。
俺はこれをするために、お前の手を封じて、足を広げさせたんだ。
「う……あ……!」
ハヤブサの視線に曝されてしまっているシュバルツの牡茎からは、切なそうに愛液が滴り落ちている。その口からは吐息が漏れ、腰が、もどかしそうに揺らめいていた。
(触って欲しいのだろうな)
シュバルツのその様を見ながらハヤブサは思う。
『そこ』は、身体は求めている。
刺激を――――。
解放、を。
だけど、俺は今はそこには触れてやらない。
そこに触れるのは、最後の最後。楽しみに取っておく。
お前が最高に、乱れ狂い咲く様を、見るために。
(シュバルツから『触って欲しい』と言われれば……別だがな……)
ハヤブサはそう思いながら、愛撫に耐えるシュバルツの方を見る。
「んんっ! ……くぅ…!」
愛おしいヒトは、目を固く閉じ、唇を噛みしめながら、必死に刺激を耐えている。何ともそそられる風情だ。
「は……あ……」
その口から時折、切なそうに吐息が漏れるから、堪らない。
官能的に揺らめく、腰。
――――求めているのだ。『身体』は。
だけどシュバルツは、決して自分から『触って欲しい』とは言ってこないだろう。
元々控えめな性格もあるのだろうが、その身体の複雑な出自が、シュバルツを更に禁欲的な性格に仕立て上げている。
何事に対しても、恐ろしく禁欲的(ストイック)な、お前。
彼はなかなか自分からは言わない。
自らの『要求』も。
『助けて』すらも――――。
お前は、もっと求めていいんだ。シュバルツ……。
その為に俺は――――お前の側に、居るのだから。
(もっとも……禁欲的なお前も、堪らなく魅力的なのだが……な)
そう感じてハヤブサは苦笑する。
要するに俺は――――『シュバルツ』ならば、どんなシュバルツでもいいんだ。
「ああ……駄目……」
身体が震える。
堪らない。
ハヤブサに、足を丹念に触られている事も。
彼に、感じて勃ち上がってしまっている自らの『欲情の証』を、見られてしまっている事も――――。
「ううっ! は……あ……!」
でも、それよりももっと、耐えられない事は……。
(触ッテ)
密やかにそう、願ってしまっている自分が居ること――――だった。
触ッテ
触ッテホシイ
一番、『気持チノイイ』トコロヲ――――
「ち、違う……駄目だ……」
口では懸命に否定する。
だが、心の中で渦巻く声は――――
触ッテ
触ッテ
ハヤブサ……
触ッテ
「や……そんな…こと……!」
思ってはいけない。
理性は懸命に訴えて、否定する、のに。
身体が火照る。
身体が望む。
彼の手を――――。
「ダメ……」
弱々しくなる、否定の言葉。
ハヤブサの手が時折、思わせぶりにその『近く』をスル……と、通る。
「ああ!!」
思わず身を捩る、シュバルツ。
逃げる方にではなく、『触れて欲しい』と、願っている方に――――。
でも、ハヤブサの手は、その近くだけを愛して、決して自分の望むところに来てはくれない。もどかしさが募って、おかしくなりそうになってしまう。
それなのに、耳元では囁かれる。
「震えているぞ」
「溢れているな……濡れて光っている」
「可愛いな。お前は……綺麗だ……」
(見られてる――――! それなのに、どうして……!)
シュバルツは、切なくて頭を振る。
ドウシテ、触ッテ クレナイ ノ ?
「ああ……いや……ダメ……」
呼吸が勝手に荒くなる。
涙が溢れる。
火照る身体を、我慢できない。
「は……あ……!」
触ッテ
触ッテ
駄目なのに――――。
こんな事を思っては駄目……なのに……。
「あ……! も……!」
(シュバルツ……)
ハヤブサは、そんなシュバルツの様を陶然と見ていた。
焦れて、呼吸を荒らげながら、自ら腰を揺らめかせるシュバルツ。
最高に――――甘美な眺めだと、思う。
もっと、眺めていたい。だがいい加減、次の段階に移らないと、こちらの『欲』の方もはちきれそうになっている。ハヤブサは「ククッ」と低く笑うと、シュバルツが『触れて欲しい』と願っている所の先端を、指先でピン! と、弾いてやった。
「はぁんっ!!」
艶めいた嬌声を上げ、全身をビクビクッと、震わせる愛おしいヒト。その様にハヤブサは満足すると、シュバルツに声をかけた。
「シュバルツ……もう、手を下ろしていいぞ」
「あ………」
身体を小刻みに震わせながら、手をゆっくり下ろして行くシュバルツ。そんな彼の腕を、ハヤブサは優しくマッサージしてやりながら、次の命令をシュバルツに下す。
「じゃあシュバルツ……立てってもらおうか」
「え……? 立、つ……?」
「そう……。まだ、『洗えていない』所が、あるだろう?」
「あ…………」
ドクン! と、シュバルツの中で鼓動が脈打つ。
甘く、恍惚とした『期待』への鼓動が――――。
「う………」
(ダメ……)
弱々しく理性が訴えるが、最早抗う事が出来ない。シュバルツはふらつきながらもハヤブサの命じるままに、立ち上がった。
「ここに来て、壁に手をついて、立つんだ」
「……………」
荒らぐ息を鎮めようとしながら、何とかそこまで歩くシュバルツ。かつて無い程張り詰めてしまっている自分自身がどうしようもなく、疼いた。
「ん………!」
変な声が出そうになるのを、必死に堪える。ハヤブサに言われたとおりの位置に立ち、壁に手をつこうとして――――気付く。これでは、ハヤブサに向かって腰をつきだすような格好になってしまうのではないか? 「どうぞ、挿れてください」と、言わんばかりの格好に……!
「あ………!」
ある意味、自分の気持ちを見透かされているような格好をさせられる事に、シュバルツは戸惑ってしまう。そんなシュバルツの気持ちを知ってか知らずか、ハヤブサは彼の手を優しく取って引き寄せた。
「大丈夫、シュバルツ……ちゃんと、『洗って』あげるから……」
「『洗…う』……」
うつろな瞳でハヤブサの言葉を反芻するシュバルツ。そこから漂う色香が、堪らない。
「だからシュバルツ……俺の、言うとおりに――――」
「あ……あ……」
抗えないシュバルツは、壁に手をついて、ハヤブサの望む格好になった。
「愛している……シュバルツ……」
そう言いながらハヤブサは、自分に向かって突き出されたシュバルツの双丘を、する…と、撫でてやる。
「あっ!」
ピクリ、と、反応をする愛おしいヒト。この腰から太ももにかけてのラインが、何とも魅惑的で、堪らない。
「洗うぞ」
そう声をかけてから、シュバルツの腰にペチャ……と、石鹸をつけた。
「…………ッ!」
ビクッ! と、跳ねるシュバルツの身体。
そのままハヤブサは、彼の引き締まった形の良い双丘を、じっくりと、丹念に『洗って』やる。
「んっ! ……や……あ! 何で……っ!」
シュバルツから、少し抗議の色の混じった声が上がる。
「ここも―――洗えてなかっただろう? シュバルツ……」
そう言いながら、シュバルツの双丘の弾力を、ぐにぐにと弄びながら、その手触りを愉しんだ。
「ああ……! は……あ……!」
切なそうに頭を振り、もどかしそうに腰が揺らめいてしまっているシュバルツ。焦れているのだ。かつて無い程に。求めたいのに、素直に求められない。そのジレンマが、彼の官能的な色香に拍車をかけている。
「や……! んんっ!」
苦しそうに息を荒らげ、身体を震わせているシュバルツ。
『欲しい』
一言、そう言える事が出来たなら――――シュバルツ、お前は楽になれるのに……。
焦れるシュバルツの身体を弄びながら、ハヤブサもまた、自分の劣情に鞭を打つ。
焦れているのはこちらも同じだ。
こんなに強烈な、愛おしいヒトの魅惑的な『痴態』――――。
油断したら、こちらの理性が持って行かれそうになってしまう。
(こうなったら、意地でもシュバルツから『欲しい』と言わせてやる)
ハヤブサはいつしか、強くそう決意をしていた。
ここまでこちらも我慢したんだ。愛おしいヒトの、最高に淫らな姿をこの目で見てみたいと―――望んだ。
シュバルツの双丘を弄んでいたハヤブサの手が、おもむろに彼の胸に伸びてくる。
「は! ああんっ!!」
予想だにしなかった所からの刺激に、シュバルツの身体がたまらず跳ねる。このヒトは、本当に、此処への刺激に弱い。
「すごいな……ここへの刺激だけで、イケるんじゃないのか?」
シュバルツの乳首を指先で嬲りながら、ハヤブサは彼の耳元で囁く。それに対してシュバルツは、嫌がる様に頭を振った。
「あっ! 駄目っ!! 違…う…! そこじゃ―――!」
「……『違う』? 何が違うんだ?」
「――――!」
ハヤブサの問いかけに、シュバルツは、はっと、我に帰った。自分が、とんでもない事を口走ってしまった事に気づいてしまう。だが――――もう遅い。シュバルツの『陥落』が間近だと悟ったハヤブサが、にやりと笑う。
「答えろシュバルツ……何が、『違う』んだ?」
シュバルツの乳首をすりすりと擦りながら、ハヤブサはわざと優しく聞いてやる。それに対してシュルツは「ああ……」と、震えながら、懇願するように呟いた。
「か、勘弁してくれ………あうっ!!」
乳首を強く摘ままれたが故に、シュバルツから悲鳴が上がる。
「言わなければ――――ずっと、このままだぞ?」
そう言いながらハヤブサは、再びシュバルツの乳首を優しく擦り始める。
「あ……あ……ダメ……」
その刺激にぴくぴくと身を震わせるシュバルツ。彼の腰が、もどかしげに揺れている。
触って欲しいのは『ここ』――――でも、そんな事、言える訳が無い。
「ほら……シュバルツ……」
ハヤブサの手が、思わせぶりに『その近く』を通る。
「教えてくれ……何が、『違う』んだ……?」
嬲る様に――――弄ぶように。そして、もう片方の手が、乳首を擦り続けている。
「い……いや……ダメ……!」
言える訳が無い。
そんな恥ずかしい事、言える訳が無い。
でも、胸への刺激が……気持ち良すぎて。
腰に溜まって来る熱が……もどかしくて。
「あ……! ああっ!!」
シュバルツはついに―――その刺激に耐えられなくなってしまった。
「や……あ……! ち……違う…の、は……あ…ッ! 『場所』だ……!」
「場所?」
「あ……『洗って』欲しい、場所……が……ッ!」
「…………!」
(やった……!)
ハヤブサの背中に、ゾクッと甘い電流が駆け抜ける。淫らなシュバルツが見られる予感に心が震えた。
「どこだ? 『何処』を洗って欲しいんだ?」
嬲る様な愛撫を続けながら、ハヤブサはシュバルツに問う。言わせてみたい。シュバルツの口から。『その言葉』を――――!
「ん……! ん……っ!」
頬を朱に染め、涙を流しながら首を振るシュバルツ。
洗って欲しい場所は、分かっている。切なく腰が揺れる。でも―――言えない。言えるわけが……ない。
「あ……! は……!」
でも、ハヤブサの愛撫が、シュバルツを追いこむ。
時々、軽く触れられる。
身体は激しく求めている。
もっと―――ちゃんと、触って――――
(ダメ……!)
「や……! 言えな……!」
は、は、と、息を荒らげながら、膝から崩折れて行くシュバルツ。ついに、立っていられなくなってしまったらしい。
「シュバルツ……」
優しく呼びかけながら――――でも、手はシュバルツを赦してやらない。執拗に、嬲る様に――――彼を追いかけて、愛撫を続けた。
「あ……! も……う……ハヤブサ……!」
身を捩って、懸命に愛撫から逃れようとする。だけど、力が入らない身体。弱々しくしなる動きは、ハヤブサの黒い劣情を煽り続けるばかりだ。
「ハヤブサ……! も……許し――――」
「許さない」
シュバルツの懇願を、一刀両断にする。自分が聞きたい言葉は一つだけだ。
「言え。シュバルツ……。どこを、触って欲しいんだ……?」
追い込む。徹底的に。
俺の手に堕ちてくれと、願う。
「あ……っ! はあっ!! あ……あ……」
切なく頭を振りながら、身体を震わせるシュバルツ。
限界――――何もかもが、限界だった。
でも、触って欲しい場所を、自分はどうしても言う事が出来ない。
言う事が出来ない……から……。
「は……ハヤ、ブサ……」
シュバルツは一瞬ためらった後、自分を愛し続けるハヤブサの手を取った。
「シュバルツ?」
涙で潤んだシュバルツの瞳と、視線が合う。
「ハ、ハヤブサ……。わ…私が、『触って』欲しいの、は……」
「…………!」
ハヤブサは、思わず息を飲んだ。シュバルツは今、確かに『触って』と、言った。もう自分が何を言っているのか、分からなくなってきているのだろう。熱情にかなり押し流されている、と、ハヤブサは感じた。
「さ……『触って』欲しいのは……」
頬を赤く染め、恥じらうようにその瞳を閉じるシュバルツ。ハヤブサの手を取った彼の手が、小刻みに震えていた。
「触って欲しいのは……どこだ?」
黒く甘い期待を込めながら、ハヤブサはシュバルツを見つめる。こんな瞬間でさえ、このヒトは素直に美しく、そして堪らなく妖艶だった。
ぐ、ぐ、と、シュバルツの手が、ハヤブサの手を『そこ』へと導く。
「さ、『触って』欲しいのは……ここ………」
ペチャ……と、音を立ててハヤブサの手に、シュバルツの牡茎が押し当てられる。彼の牡茎は、もう、愛液まみれになっていた。
「ここか? シュバルツ。ここを、触って欲しいのか?」
ハヤブサの指がシュバルツの愛液を絡め取りながら、くちゅくちゅと音を立ててシュバルツのそこを撫でる。
「あっ! ああんっ!!」
甘い悲鳴を上げ、ビクビクと震えるシュバルツの身体。
待ち焦がれていた刺激故に――――彼の中で、何かの箍が外れてしまう。
「さ…触って欲しい…! ここを…! ここを……ッ!」
はあっ、と、しどけないため息を吐きながら、ハヤブサに懇願するシュバルツ。そればかりか、彼の腰が自ら動いて、ハヤブサの手に牡茎を擦りつけようとさえしている。
「どういうふうに―――触って欲しいんだ? シュバルツ……」
ハヤブサは舌なめずりをしながらシュバルツに聞いた。かつて無い程乱れそうなシュバルツの姿に、黒い期待が膨らんで行く。
「あ……もっと、しっかり握って……もっと、擦って―――」
耳まで真っ赤にして、それでも懇願してくるシュバルツ。
その姿が、あまりにも可愛らしかった、から。
「しっかり……こう、か?」
きゅ、と、シュバルツの牡茎を握ってやる。
「ああああっ!!」
シュバルツから、悲鳴にも近い嬌声が上がる。歓びに震える身体を、ハヤブサは捕まえた。
「……擦るぞ」
耳元で囁いてやると、陶然とした表情のシュバルツがこくん、と頷く。軽く手を動かしてやっただけで、腕の中の愛おしいヒトは「ああっ!」と、叫んで大きく身を捩った。
「ああっ! ああっ! あ…ん……!」
くちゅくちゅ、と、愛液が擦れる音が風呂場に響く。ハヤブサの手の動きに合わせて、シュバルツの腰も揺らめく。愛液をとめどなく溢れださせているそこは、ハヤブサの手の中で正しく容量を増して行く。快感を求めるシュバルツは、ハヤブサが手を動かす事を止めてしまっても、彼自らの腰が揺らめき、ハヤブサの手が作った輪に、何度も自身を擦りつけてしまっている。
「ああ……! ああ……!」
「気持ちいいか? シュバルツ……」
ハヤブサの問いかけに、シュバルツはこくこくと頷く。
「気持ち……イイ…! あ……! イイ……!」
「………!」
かつて無い程、自らの快感に素直になっているシュバルツ。その妖しさと美しさに―――ハヤブサはたまらなくなる。焦れ切っている自分の欲が、どうしようもなく膨らんで行くのを感じた。
(シュバルツ……!)
想いをこめて、抱きしめる。
「ハヤブサ……! ああ……! ハヤブサ……!」
揺らめき続けるシュバルツの腰。もう彼は、自分で自分の動きを止める事が出来ないようだった。
「シュバルツ……」
ハヤブサの指が、優しくシュバルツの乳首を擦ってやると、シュバルツはいやいやをするように首を振った。
「あっ…! そこ、じゃ……無く、て……! もっと……別の、所を……ッ!」
「別の所………どこだ?」
「あ……あ……! 後ろ……! 後ろ、も……!」
「――――!」
シュバルツの思わぬ言葉に、息を飲むハヤブサ。
「中……! 触って……ッ!」
焦がれる様なシュバルツの声に、ハヤブサも突き動かされてしまう。
「ここか?」
つぷっ、と、シュバルツの中に突きいれられる、ハヤブサの指。
「ふあ……! あ……ッ!」
仰け反る、シュバルツの白い身体。だが彼は、もどかしそうに首を振った。
「あ…あ……! や……! も……『指』…じゃ、無くて…ッ! ハヤブサ……!」
「シュバルツ?」
「挿れてくれ……ッ! 欲しいんだ……! お前が――――」
「―――――!」
シュバルツのその懇願を聞いた瞬間、ハヤブサの中でも何かの箍が吹き飛んでしまっていた。
「シュバルツ!!」
気がつけばハヤブサは、己の身体の下にシュバルツを組み敷いて、貪るようにその身体を求め――――彼を、喘がせていた。
第3章
(阿呆か、俺は)
龍の忍者は膝を抱えて座り込んでいる。
(何をやっているんだ、俺は。本当に……どうしようもない阿呆だな)
彼の心の中は今――――自分を責める言葉でいっぱいだった。
(阿呆だ。馬鹿だ。最低だ。俺はどうしてこう……!)
本当に、今ならいくらでもそんな言葉を思い浮かべる事が出来る。それほどまでに――――ハヤブサの心は自己嫌悪の気持ちでいっぱいだった。
彼の目の前には、彼の自己嫌悪の元になっている愛おしいヒトが、浴衣姿で布団の上で力無く横たわっている。額の上には、冷やしたタオルと氷嚢が乗せられていた。
(シュバルツ……)
ぐったりと横たわる愛おしいヒトの身体を見ながらハヤブサは、『あの時』の事を思い出す。
「あっ! あ……! ああああ―――――ッ!!」
挿れた瞬間の衝撃で、シュバルツは果ててしまった。ビクビクッ! と、身体が震え、シュバルツの白い『精』が、パタパタっと音を立てて彼の前方の床に落ちた。そしてそれは、ハヤブサを受け入れているシュバルツの秘所に、甘い甘い蠢きと締め付けを、もたらしてしまう。
「―――――ッ!」
熱く熟れきったシュバルツの内側。そこからもたらされた甘い衝撃は、シュバルツと同じように焦れ切っていたハヤブサの『理性』をふっ飛ばすには充分過ぎて。
ダンッ!!
いつの間にかハヤブサは、シュバルツの方を思いやる余裕も無いまま、その身体を乱暴に組み敷いていた。
「シュバルツ!!」
無我夢中でその身体を求める。白い肌に跡がつくほどの口付けをして、自分の稚拙な独占欲を満たしていった。このヒトは俺の物だ。俺の物だ。俺だけの、物だ。
その乱れた顔、艶めいた声。
俺だけに、見せて。
俺だけに、聞かせて。
繋がりたい。
もっと――――もっと、深く。
感じたい。
シュバルツを。
感じさせたい。
このヒトの中を、自分だけでいっぱいに、満たしてしまいたい。
シュバルツ。
シュバルツ。
何て、愛おしいのだろう。
ああ
もう一度
甘く―――締め付け、て
それを求めてハヤブサは、シュバルツを犯す。
何度でも、何度でも………。
「ああっ!! ああっ!! ああああ……!」
シュバルツから悲鳴のような嬌声がひっきりなしに上がる。
苦しかっただろう。今思えば。
でも、あの時の俺にとっては――――それすら、極上の甘美な音色に聞こえてしまっていた、から……。
もっと聞きたい。
もっと聞きたい。
際限なく、求めてしまっていた。
だがシュバルツは、受け入れ続けてくれた。悲鳴を上げながらも、涙を散らしながらも………俺に身体を、赦し続けてくれた。
時折彼が俺に触れてくる手は――――とても、優しかった。
何度かシュバルツの中に己の『精』を叩きつけて、ようやく、俺の方に『理性』の光が戻ってきた時――――。
「ハヤブサ……」
腕の中で愛おしいヒトが、ふわ、と微笑む。
ひどく綺麗で儚げな笑みだったから、俺は思わず見惚れてしまっていた。
「シュバルツ……」
だが呼び掛ける俺に、目の前の愛おしいヒトはもう、答える事が出来なかった。
「――――………」
ぐら、と、その身体が傾いだかと思うと。
ザバン!!
派手な音を立てて、シュバルツの身体が湯船の中に沈んで行ってしまった。
「シュバルツ!?」
シュバルツを追って慌てて湯船の中に潜った俺の前には――――。
気を失って浴槽の底に力無く横たわる、彼の姿が、在った。
「シュバルツ!! シュバルツ!!」
抱き上げて必死に呼びかけると、腕の中の愛おしいヒトは僅かに身じろぎをする。
だけど、答えを返す事も出来ずに、すぐに意識を手放してしまうから、俺は慌てた。
とにかく、シュバルツの身体を拭いて、着替えさせようと脱衣場まで彼を抱きかかえて来て――――その身体の状態に、愕然としてしまう。
彼の身体は、痣だらけだった。そして、拭っても拭っても、ハヤブサの『精』が、流れ出てくる『秘所』――――。
自分は酷く暴力的に、シュバルツを抱いてしまったのだと――――ようやく悟った。
(阿呆だろう、俺は)
そして最初に戻る。
世界でたった一人の、愛おしいヒト。何よりも誰よりも、大切に慈しまなければならないのに。
がっついて、潰すほど抱いて、どうするんだ。
湯の中に沈むシュバルツの姿を見た時――――恐ろしかった。
殺してしまったかと思った。
シュバルツは、死なない。それは、分かっている。
でも、だからこそ――――死ぬような目に遭わせて良い筈が無いんだ。
(シュバルツ……)
カラン、と、音を立てて、シュバルツの額の上の氷嚢の氷が動く。
「う………」
唇から、薄く声が漏れる。意識の覚醒が、近くなってきているのだろう。
彼が起きたら、ものすごく怒られ、詰られるかもしれない。嫌悪されてしまうかもしれない。それだけの事を、自分は彼にしてしまったのだから。
だから本来ならば、正座をして、シュバルツが目覚めるのを待たなければならないのだが――――。
「あ……あ……! や……!」
手を頭の上に組んで、足を開いて、しどけなく腰を揺らめかせているシュバルツ。
「あ……! ああ……! イイ……! 気持ち……イイッ!」
くちゅっ、くちゅっ、と、音を立てて、自分の手に擦りつけられるシュバルツの牡茎。上気した頬。濡れた髪。漏れる吐息。うっとりとした、官能的な表情――――。
「挿れてくれ……ッ! 欲しいんだ……! お前が――――」
(…………!)
それらを思い出しただけで――――自分のモノが、元気になって、しまうから。
不覚にも、体育座りにならざるを得ないのであった。
何てことだ。
ものすごく極上な『おかず』を手に入れてしまった様な気がする。
あのシュバルツを思い出しただけで、2、3発は軽く抜けそうだ。
「……………」
ハヤブサは、目の前に横たわる、愛おしいヒトの肢体を見る。
(でも本人が目の前に居るのに……『おかず』も何も……なぁ)
出来ればその身体に触れて――――もう一度、あの甘さを味わいたい。シュバルツを腕の中で、官能的に啼かせてみたい。
下着もつけず、浴衣一枚で、そこに横たわっているシュバルツ。あの薄い衣の下には、極上の魂と身体があるのだ。それを想うだけで――――ハヤブサは生唾を飲み込んでしまう。
シュバルツ。
シュバルツ。
手を伸ばせば――――すぐ届く所に居るのに……。
(だからっ!! 違う!! 俺が抱きすぎたせいでシュバルツはこんなになっているのに!! 更に抱こうとして、どうするんだ!!)
ハヤブサは手近にあった柱に、ガンガン! と、頭を打ち付けていた。どうしてシュバルツが相手だと、自分はこうも際限無く欲情出来るのか。ハヤブサは自分で自分が嫌になってしまう。
不意に、旅館の時計が、午後10時の時報を鳴らす。
シュバルツとの『報酬』の契約は24時間。このヒトと時間を共有できるのも――――後少し。
(本当ならこの布団の中で……しっとりと愛を確かめ合った後――――朝までシュバルツを腕枕する予定で居たのに……)
愛おしいヒトを、抱いて眠りたかった。目覚めて一番に、腕の中で眠るシュバルツの顔を見たかった。あの隼の里の時の様に――――。
でも今は、それをする訳にはいかない。
シュバルツの隣で、何もしないで寝れる自信なんてない。絶対にまた、彼の事を犯してしまう。さっき―――シュバルツの事を、抱き潰しそうになっていたと言うのに。
(自業自得だろう?)
ハヤブサは苦笑する。
風呂場で最初にシュバルツを抱いた後、甘えるように、こちらに身を擦り寄せてきたシュバルツ。その身体が小さく震えていて、彼の秘所から自分の吐きだした残滓が流れ出していたから――――。
思ったんだ。
「洗ってあげなきゃ」
それが総ての、間違いの元だったんだ。
『報酬』として、横に居てくれるシュバルツが抵抗できないのをいいことに、じっくりたっぷりシュバルツを『洗って』しまった。
おかげて、焦れて乱れたシュバルツを堪能できた訳だが、自分もたっぷり焦らされていた訳で。だから、シュバルツに『来て』と言われて、理性がぶっ飛んでしまった訳で……。
(アホ―――――ッ!! 俺のアホ―――――ッ!!)
ハヤブサは思わず、畳の上を頭を抱えてごろごろと転がりまわりたくなってしまう。
結局俺は、自分自身の邪な気持ちに、負けてしまったんだ。あれほど「『報酬』だからと言って、シュバルツを踏みにじる真似だけはするまい」と、思っていたと言うのに……。
難しい。
ただ愛して、慈しみたいだけなのに。
どうして――――ただ隣で優しく手を握っているだけでは、満足できなくなってしまうのだろう。
どうして、深い繋がりを、求めてしまうのだろう。
シュバルツの総てが、欲しくて欲しくてたまらない。どんなに深く犯しても、決して自分の所有物になろう筈もないのに――――。
「ん…………」
声と共に、シュバルツの身体がもぞ、と動く。どうやら、意識が戻ってきたらしい。
シュバルツとまともに目が合わせられない、と、思ってしまったハヤブサは、シュバルツから少し離れた部屋の隅で、膝を抱えてその様子を見守っていた。
「……ここは……?」
ゆるゆると瞳を開けたシュバルツの視界に、見慣れない天井が飛び込んでくる。
(私はどうしたんだ? ここは、どこだ……?)
額の上で、氷嚢の氷がカラン、と、音を立てる。その冷たさを『気持ちいい』と感じて――――自分が風呂でひどくのぼせてしまった事を思い出す。その『のぼせた』原因を思い出して―――。
「う…………!」
思わず赤面してしまう。ハヤブサの愛撫に感じすぎてしまって、途中で訳が分からなくなってしまった。自分は、変な事を口走ったりはしていないだろうか。
(そういえば、ハヤブサは……?)
額の濡れタオルをずらしながら、シュバルツはハヤブサの姿を探す。ここに一緒にいなければならないはずの彼の姿が見えないのは、シュバルツに、少しの不安をもたらした。
「ハヤブサ……?」
シュバルツが呼びかけると、消え入りそうな声で「シュバルツ……」と、返事が返ってきた。シュバルツがそちらを見ると、膝を抱えて座り込んで小さくなっているハヤブサの姿を見つけた。
「ハヤブサ? 何をやっているんだ? そんな所で……」
「い、いや……その……」
シュバルツの問いかけに、ハヤブサはばつが悪そうな返事を返す。自分がシュバルツにしてしまった事を考えると、とても目を合わせられない。暴走しすぎにも程があり過ぎだろうと思った。
「……? どうした……? 具合でも悪いのか……?」
「そ、そんな事は無い……の、だが、その……」
それなのに、シュバルツの方から気遣う様な言葉をかけられるから、ハヤブサは更にいたたまれなくなってしまう。
(シュバルツ……お前、優しすぎるぞ……! 俺はこんな、ろくでなしなのに……)
仏かお前は―――! と、突っ込みを入れそうになったハヤブサの目の前で、シュバルツが身を起こそうとしているから、ハヤブサは更に慌てた。
「馬鹿っ!! 起きようとするな!!」
「だ……だが、お前が……」
「? 俺が、どうかしたか?」
怪訝な表情を見せるハヤブサに、シュバルツは一瞬ためらってから、改めて声をかけてきた。
「その……遠くて……」
「―――――!」
「近くに来て……くれな―――」
「これでいいのか?」
「!!」
シュバルツの言葉が終わらないうちに、龍の忍者の姿がシュバルツの枕元に飛んでくる。あまりにも高速移動をしたせいか、壁際にはハヤブサの残像が残っていた。
「あ……ああ……」
多少顔をひきつらせながらではあるが、シュバルツが笑みを見せてくれるから――――ハヤブサも、とても優しい気持ちになれる。身を起こそうとするシュバルツの動きを制して、彼の額に、そっと手を当てた。
「まだ少し、熱があるな……」
「そうか? 大分楽になったのだが……」
「いいから寝ていろ。まだ無理に起きようとするな」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツを布団に寝かしつけて、その身体の上に掛け布団をかけてやる。その間シュバルツがこちらを見る眼差しは、とても穏やかだ。
しかし、その優しい眼差しをまともに見ていられなくなるハヤブサは、つい、と、シュバルツから目を逸らしてしまう。
「そ、その……シュバルツ……」
「どうした…?」
「そ、その……わ……悪かったな……。何度も、何度も……強く、抱いてしまって……」
「ハヤブサ……」
「ほ……本当は、その……もっと、優しく抱くつもり……だったのに……」
言いながらハヤブサは、痣だらけだったシュバルツの身体を思い出す。本当に、どこをどうすれば、あんな全身に痣を作れると言うのだろう。どれだけシュバルツの身体を乱暴に組み敷いて、どれだけ激しく彼を求めてしまったのだろう。
恐ろしい。
いつか自分は、抱きながらシュバルツを殺してしまうかもしれない。
それに対してシュバルツは「ああ……」と、短く言葉を発すると、その面に笑みを浮かべた。
「気にしなくていい。だいたい、私の方も求めた様な気がするし……」
「――――! あの時のこと……覚えているのか?」
それに対してシュバルツは、少し苦笑する。
「いや……途中で、訳が分からなくなってしまったから、あまりはっきりとは覚えていないのだが……な」
「シュバルツ……」
「ただ…叫んでしまった事だけは憶えている……『欲しい』って……」
「―――――!」
ダンッ!!
「えっ……?」
何が起こったのか瞬間分からず、茫然とするシュバルツの身体の上に、ハヤブサの身体が覆いかぶさって来る。すぐ近くに、こちらを切なそうに見つめるハヤブサの顔が、あった。
「シュバルツ……」
熱を含んだ声で、名を呼ばれる。手が頬に伸びてくる。
(抱かれる……?)
シュバルツは漠然とそう思った。
構わない。
抱きたいのならば、抱いてくれていい。
ハヤブサが、望むのならば――――私は。
抱き潰されても、壊されても
構わないんだ。
シュバルツは瞳を閉じ、唇を薄く開けた。
そしてそのまま、ハヤブサに口づけられるのを、待った。
「……………」
しばらくの沈黙。だがシュバルツの予想に反して、ハヤブサの唇はなかなか下りて来ない。
「……………?」
不思議に思ったシュバルツが目を開けてみると―――頭を抱えて悶絶しているハヤブサの姿が飛び込んできたから、びっくりしてしまう。
「ハ、ハヤブサ!?」
驚いて声をかけるシュバルツと同時に、ハヤブサも口を開いた。
「いやいや!! 無いだろう!? 駄目だろう!? 俺!!」
「えっ?」
「ちょっとシュバルツに『欲しい』って言われたぐらいで……この反応は無いだろう!? 阿呆か俺は!! 阿呆か!!」
「え……え~っと……?」
「駄目だって!! さっきあれだけ散々シュバルツを抱いただろう!? シュバルツの身体を痣だらけにしているんだぞ!! それなのに、また彼を抱こうだなんて、どういう神経をしているんだ!! 俺は!!」
「ハ、ハヤブサ……? あの……」
「駄目だったら駄目だ!! 今は、シュバルツの身体を労わることが大事なんだ――――!!!」
「ハヤブサ! ちょと、落ちつけって!!」
「――――!!」
シュバルツに強めに声を掛けられて、ハヤブサははっと、我に帰った。
「い……今、俺は何か、口走っていたか?」
恐る恐ると言った風情で聞いてくるハヤブサに、シュバルツは苦笑を返す。
「……黙っていたつもりだったのか?」
「――――ッ!」
しばしの沈黙の後、気の毒なほど落ち込んで行く龍の忍者の姿。抱えた頭が地面にめり込むのではないかと思うほど、小さく丸くなっている。
「ハ、ハヤブサ……?」
シュバルツが声をかけても、丸くなってしまって動かないハヤブサ。
「ハヤブサ? 大丈夫か……?」
身を起こしながらもう一度シュバルツが声をかけて――――ハヤブサはやっとピクリと反応した。
「シュバルツは……」
小さな声で、問いかけられる。
「何だ?」
「どうして……俺を、責めないんだ……?」
「責める?」
きょとん、とした按配で返事を返すシュバルツに、ハヤブサは思わず顔を上げていた。
「だって、そうだろう!? あんなにお前を弄ぶように抱いて、揚句、こっちの理性が勝手に飛んで、お前の身体を、痣だらけにするほど求めて――――!」
「ハヤブサ……」
シュバルツは、少し驚いた様な表情になる。しかし、彼の穏やかな眼差しは、変わらなかった。
「私は………お前が、望むのなら――――」
「どうして――――そんなに、俺を赦すんだ!!」
「――――!」
いきなりのハヤブサの大声に、シュバルツは言葉を失くしてしまう。
「あんなに身体を痣だらけにされて、なのに何故………!」
思い出す。
脱衣場で見た、シュバルツのボロボロだった身体。
あんな風に身体を傷つけられて――――それを受けているシュバルツの方は、おそらく『快楽』よりも『苦痛』の方が大きかっただろう。
それなのにシュバルツは、どんな姿勢にさせようと、どんなふうに穿とうとも――――決して彼から拒絶される事は無かった。理性が飛んでいる自分ですら分かるほど、触れてくる彼の手は優しかったから――――。
「赦されている」と、分かった。
その底抜けの優しさと健気さ。
泣きそうに、なる。
「そ、それは……」
スキ ダカラ
オ前ノ事ガ、スキダカラ……
それが、シュバルツの持つ答え。
だけど、「それは……」と、言った後、沈黙してしまったシュバルツからハヤブサが受け取った『答え』は―――――。
私ハ、オ前ノ『報酬』ダカラ。
「――――!」
『報酬』ダカラ……
(そうだった……『報酬』――――)
ハヤブサは思わず、唇を噛みしめていた。
そう。彼は今、自分にとっての『報酬』なのだ。今シュバルツは――――自分に対して一切「NO!」と、言う事が出来ない。彼は、律儀にそれを守っているに過ぎないのだ。
それなのに俺は、際限なく赦さざるを得ないシュバルツを際限なく求めて。
「どうして赦すんだ」などと聞いて――――。
何てことだ。
真の阿呆は、俺か。
(ハヤブサ……)
シュバルツは、苦い顔をして唇を噛みしめているハヤブサを、少し淋しい気持ちで眺めていた。
分かる。
ハヤブサには、きっと、伝わっていない。
私の、「お前が好きだ」と、言う気持ちが――――。
きっと、『報酬』と言う言葉が――――ハヤブサに、この気持ちが伝わる事を邪魔しているのだろう。
でも、それでいいのだと、シュバルツは思う。
この気持ちは、伝わらなくていい。
伝えちゃいけない。
ハヤブサ、お前は
いつまでも、こんな中途半端なアンドロイドに、お前の『愛』を消耗していてはいけないんだ。
「ちゃんと伝えなきゃ……伝わらない事も、あるんだよ」
不意に、出立する時にキョウジが忠告してくれた言葉を思い出す。
(ああ、本当にそうだな、キョウジ)
シュバルツは思った。
伝えたい言葉ほど、ちゃんと伝えなければ伝える事が出来ない――――。
人間とはとにかく、厄介な生き物だと、思う。
でも、いいんだ。
これでいい――――。
(シュバルツ……)
ハヤブサは、目の前に居る愛おしいヒトを見つめる。
とても優しくて――――でも、儚くて。少し淋しささえ読み取れるような微笑みを浮かべている、愛おしいヒトを。
ああ
綺麗だ。
こんな時でさえ、このヒトは
とても綺麗だと――――思う。
対して、自分はどうだ。
シュバルツの『優しさ』につけ込んで、勝手に理性を飛ばして、このヒトの身体をぼろぼろにして。
それでも収まらずに、まだシュバルツの身体を求めている。欲しくて欲しくてたまらない。
まるで醜い『欲』の塊。
どうして
どうして――――
どうして、人はヒトを好きになればなるほど――――自分の醜さや情けなさばかりを知る事になってしまうのだろう。
シュバルツの一挙手一投足に一喜一憂して――――右往左往して、振り回されて、全然落ち着く事が出来ない、情けない自分。
人間的に全く成熟していない事を、改めて思い知らされるばかりだ。
嫌だ。
情けない。
恥ずかしい。
もう消えたい。
腹の中はもう――――ドロドロのぐちゃぐちゃ、だ。
それでも
それでも――――
たったひとつだけ言える事は
「シュバルツは何も悪くない」
と、言う事だけだった。
だって、そうだろう?
そこに『報酬』として、優しく俺の総てを赦し続けてくれているシュバルツの――――どこに、落ち度があると言うのだ。
俺が情けない奴だからって
腹の中が捩じ切れそうなほど、ぐちゃぐちゃになっているからって
シュバルツに『八つ当たる』ことだけは――――
絶対に、間違っている。
「シュバルツ……」
愛おしいヒトの名を呼んで、そっと手を伸ばす。
今、自分にとって唯一の救いは――――シュバルツが、こんな情けない自分でも、否定をせずにいてくれている事だった。『報酬』でも何でも、その底抜けの優しさを、今は、自分に向けてくれているのだから――――
これ以上、何を望むと言うのだろう。
頬に触れても、愛おしいヒトは表情を変えない。ただ穏やかに、こちらを見つめている。
分かる。
きっと、この手に力を入れて、強引にその唇を奪っても、その身体を押し倒しても――――彼は、優しく受け入れてくれるのだろう。
『報酬』ダカラ……
「…………!」
知らなかった。
好きな人が『報酬』になるって
案外、切ないモノなのだ…な……。
ハヤブサはシュバルツの身体を、ギュッと優しく抱きしめた。
「ハヤブサ……?」
腕の中で不思議そうに声を上げる、愛おしいヒト。でも、抵抗するでもなく、静かにこちらに身を委ねてくれるから――――
思わず、泣きそうに、なる。
「済まない、シュバルツ……」
抱きしめながら、ハヤブサは謝る。
「今だけ……少し、このままで……」
そう。
少しの間だけでいい。
シュバルツの優しさに――――甘えたかった。
腹の中がぐちゃぐちゃになってしまっている、情けない自分。
それを落ちつかせるために、彼の優しさが――――必要だった、から。
「ハヤブサ……」
腕の中で愛おしいヒトが、静かに頷く。
「分かった……」
そしてそのまま、背中に手を、回して来てくれるから。
「―――――ッ!」
本当に泣きそうに、なってしまった。
必死に堪える。だが、身体がどうしても、小さく震える。
きっと、シュバルツにも、伝わってしまっている事だろう。
だけど、それを否定せず――――優しく包んでくれる、お前。
ああ
やはり、堪らなく――――好きだ。
好きだ……!
だが自分の『好きだ』と言う言葉に、シュバルツから『同じ答え』が返ってくる可能性は、皆無に等しい。彼の複雑な出自と身体が――――シュバルツに、誰かを『好きだ』と、言わせる事を拒んでいる。
だから、最初から分かっていた。
この『想い』は――――絶望的な、片想いなのだと。
それが分かっていて――――好きになる事を、止められず
シュバルツの気持ちに、足掻く事を止められない、俺。
馬鹿だと思う。
だけど――――自分でももう、どうしようもないんだ。
シュバルツ
シュバルツ
愛シテイル
(ハヤブサ……)
シュバルツはハヤブサを抱きしめながら、ハヤブサから落ちてくる、心の声を聞く。
ハヤブサは、ひたすら自分を責めていた。
悲しいココロ
悲しいノイズ
なのに、彼からシュバルツに向けられ続けている心は――――
愛シテイル 愛シテイル 愛シテイル 愛シテイル
ただそれだけしか無かった、から。
「…………!」
ハヤブサの背中にまわしている手に、ぎゅっと、力が入ってしまう。
(愛している。私も……)
(好きだよ、ハヤブサ……)
伝えられないココロ。
伝えてはいけないココロ。
人でも物でもない、生きているのか死んでいるのかも分からない、中途半端な存在の自分。そんな自分に――――ハヤブサの生涯の愛を誓わせてはいけないから……。
お前と一緒に、歳を取れない。
お前と一緒に、死ぬことも出来ない。
共に生きるには――――どうしても、不自然すぎるんだ。
(ハヤブサの、『報酬』で良かった……)
ハヤブサを抱きしめながら、シュバルツは胸をなでおろしていた。
『報酬』ならば、ハヤブサに総てを赦しても――――不自然じゃ、無い。自分の気持ちに、気づかれる事も無いから。
『好き』だから、拒めなかった。
『好き』だから、総てを赦した。
ハヤブサ 私は
お前の『願い』を拒みたくは無いよ
出来ればお前以外
知りたくも 無いよ
愛シテイル シュバルツ……
(愛している。私も……)
返したい。
返してあげたい。
ハヤブサがくれているモノと、同じモノを。
だって、私は今―――――『幸せ』だ。
『想う人』から『好き』と、言われて――――
それだけで、満たされてしまう ココロ。
何と、単純なモノなのだろう。
同じ気持ちを、ハヤブサにも味あわせてあげたい。
幸せを、あげたい。
あげたいのに――――。
ハヤブサの気持ちが分かっていて
自分の気持ちが分かっていて
それをしない 私は
卑怯だ
卑 怯 ダ
「…………ッ!」
涙が溢れる。
(駄目だ…! 泣いては……)
必死に己を叱咤する。
だって、今辛いのは
ハヤブサの方、なのに
1人、幸せを貪っている私が――――泣いては駄目、だ。
でも、溢れる涙。震えてしまう、身体。
ハヤブサに、気づかれてしまう。
泣いては駄目、なのに――――。
「シュバルツ……?」
案の定、シュバルツが泣いている事に気付いたハヤブサが、声をかけてきた。少し身体を離して、こちらを伺うように見てくる。
見つめるハヤブサの目の前で、零れ落ちる涙。……堪え切れなかった。
「どうした……?」
問いかけてくる、優しい声。
「あはは……どうしたんだろうな……」
必死に笑った。ごまかしたかった。これ以上、ハヤブサに心配をかけたくなかったから――――
でも、うまい言い訳の言葉が出て来なくて困った。
「勝手に……涙が……」
そう言いながら、また零れ落ちる、涙。
「シュバルツ……」
ハヤブサは少し怪訝に思った。この状況で、どうしてシュバルツが泣く事があるのだろうか? 何か俺は、彼を泣かせる様な事をしてしまったのだろうか。
「はは……オーバーヒートでも……したのかな……」
そう言って涙を流す愛おしいヒトは――――無理して、笑っていた。
酷く綺麗で――――哀しい涙だと、思った。
「…………」
ハヤブサは、シュバルツの涙をそっと唇ですくい取る。でも、次から次へと溢れてくる涙が哀しくて―――――愛おしさが募った。
泣きやませたかったけど、自分は、慰め方を知らないから――――。
無理やり笑っているシュバルツの唇を、優しく塞いだ。
「ん………!」
瞬間驚いたシュバルツではあるが、すぐに目を閉じ、ハヤブサの口付けを受け入れた。
「ん……う……」
そしてそのまま、唇を優しく吸われてしまうから――――。
(抱イテ……)
シュバルツの身体に、ポッと、熱が灯ってしまう。
抱イテ
抱イテ欲シイ ハヤブサ
私ノコノ身体ヲ
今スグ オ前デ 満タシテ欲シイ――――
それは、『好き』だからこそ湧き出る――――『肉の欲』だった。
淋しさを感じるからこそ、深く繋がる事を、望んだ。
だが―――――
ハヤブサはシュバルツから唇を離すと、再びその身体をぎゅっと、抱きしめた。
「シュバルツ……済まない……」
「ハヤブサ……」
「泣いてしまうだなんて……無理を、させたか……?」
「―――――!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは軽く衝撃を受けてしまう。
「違う……! 無理など、していない……!」
本心からそう思って、シュバルツは訴える。ハヤブサに総てを赦したいシュバルツにとって、今『報酬』で居る状態は、寧ろ気楽だと言ってもいい。
(誤解だ――――!)
シュバルツはそう叫びたかった。
だが、ハヤブサはシュバルツの言葉を、誤解したまま受け取った。
(ああ……やっぱり、優しいな。お前は……)
そんな、泣くほど精神的に参っているのだろうに
それでも俺を気遣って、「無理していない」と、言ってしまえるお前。
(その哀しげな涙が……『オーバーヒート』なだけな訳がないだろう…?)
シュバルツの涙を指で掬い取りながら、思う。
「無理をしていない」のなら――――どうして「無理をして」笑うんだ。
「……今日は、もう休もう」
ハヤブサは、ポツリとそう言った。もう――――『報酬』ならば、自分は充分受け取っていると、ハヤブサは感じる。寧ろこれ以上何かを受け取ってしまったら、罰があたりそうな気さえしてしまう。
「もう充分だから………お前も、ゆっくり休んでくれ……」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの傍から立ち上がろうとした。
「ハヤブサ……!」
だが、シュバルツから離れようとした手を、逆に彼に掴まれてしまうから、びっくりしてしまう。
「シュバルツ?」
驚き振り返るハヤブサの視線の先に、少し縋る様な眼差しをした、愛おしいヒトの姿があった。
「どうした……?」
「あ……その……」
静かに問うハヤブサに、シュバルツは、少しはにかんだ表情を見せる。
「お……お前が、望む…のなら……私、は……」
「―――――!」
「そ……その……抱かれて、も……」
「……無理をするな。シュバルツ……」
「ハヤブサ……!」
顔を上げるシュバルツの視界に、ハヤブサの哀しげな笑みが飛び込んできた。
「お前の気持ちは嬉しいが……あれだけの目に遭ったんだ。身体の方だって、まだ本調子じゃないだろう?」
「身体なら、大丈夫だ!」
必死に叫んでしまうシュバルツ。
「お前の身体の回復が早いのは知っているが――――」
だが、シュバルツの『ココロ』は、ハヤブサには届かない。
「『心』の方は、そうはいかないだろう? あれだけ乱暴に抱かれて―――」
「そ、それは……! でも――――!」
オ前ニ触レラレルノナラ、ドウ触レラレタッテ、私ハ―――――
「とにかく、無理をするなシュバルツ…。過ぎた『セックス』は、拷問にだってなり得るんだ」
そう言ってハヤブサは、頭を振る。実際そうだ。口を割らせる手段に用いられるのが、殴る蹴るの『苦痛』だけとは限らない。快感で相手を追い込み、その人間の尊厳を貶める性行為も、時に立派な拷問手段となる。先程風呂場でしたシュバルツとの行為が、まさにそれに近かったのではないのかとハヤブサは不安になる。
誰よりも大切に慈しみたい人との性行為が、そんな拷問(もの)であっていいはずが無いのだ。
それなのに、まだ俺に身体を開こうとする――――お前。
健気すぎる。
愛おしすぎる。
「俺はもう、充分なんだ。シュバルツ……。俺はもうお前から、充分すぎるほどの『報酬』を、受け取った」
「ハヤブサ……」
「だから……安心して、休んでくれ……」
「…………」
「これ以上お前から『何か』を受け取ってしまったら……それこそ俺に、罰が当たるかもしれないし……」
そう言って軽く笑うハヤブサを、シュバルツは淋しい気持ちで見つめていた。
私の身体の事を気遣って、『もう求めない』と言ってくれるハヤブサ。
優しい ハヤブサ。
でも、ならば
「抱いて欲しい」と、願ってしまっている私の気持ちは――――どうすれば、いいのだろう。
(……………)
仕方が無い、な。
シュバルツは独り想う。
ハヤブサに『好き』と言う気持ちを告げないと決めている私は、『恋人』ではなくて、『報酬』のままだ。
『報酬』ならば―――――
自らの『欲求』を、彼に告げるなんて おかし い
「分かった……」
シュバルツは自らの心を封じ込める選択をした。
「お前が……それで、良いのなら……」
そう言って、微笑んだ。
(シュバルツ……!)
酷く綺麗で、儚げな笑みを浮かべる愛おしいヒト。
何故か、胸が締めつけられた。
本当は、これで良いはずが無い。
もっともっと抱きたい。
もっともっと、深く繋がりたい。
だけど、一度『赦す』と決めたら、とことんまで赦してくれる、お前。
そんなお前の優しさに、これ以上つけ込んでしまってはいけないとも思う。
これ以上――――彼に負担をかけられなかった。
(だけど、このまま別れてしまうのもなぁ……)
ハヤブサは、未練たっぷりに思う。
せめて――――シュバルツとまた会って、こういうふうに触れ合う時間を持ちたいと、願った。彼と別れて、また元の黙阿弥では、あまりにも淋しすぎる。
(2週間に1回はきつい…。せめて、1週間に一度だけでも、触れさせてくれたら――――)
本当は、毎日でも触れたい。でも、DG細胞の感染を恐れて、自分と距離をとりたがるシュバルツの気持ちも、分からないでもない。だから、せめて1週間に1度くらいの逢瀬は許して欲しいと思った。
でも、それすら許してもらえなかったら――――
あの、暴力的なセックスが、最後の触れ合いになる訳で……。
(そ、それはかなり、嫌だ……!)
正直、あの行為に及んでいた時の自分は、かなり理性が吹っ飛んでしまっている状態だったから、シュバルツの事も自分の事も、よく覚えていない。ただ、シュバルツと深く繋がりたくて――――がっつくように求めた事が、何となく記憶に残っている程度だ。
モウ一度、触レタイ……。
あんな風に、暴力的に貪るのではなく、もう一度。今度はシュバルツを、ちゃんと思いやる様に――――抱きたい。
未練。
分かっている。
これは、未練だ。
「シュバルツ……」
立ち上がりかけたハヤブサは、また、シュバルツの方に向き直る。
「どうした?」
相も変わらず、綺麗な、そして穏やかな笑みをその面に湛えている、愛おしいヒト。
その瞳に、若干哀しげな色が見え隠れしているのは、どうしてなのだろう。
キス、シタイ……。
正直に、思う。
シュバルツの唇に、もう一度、キスがしたい。
彼の浴衣の合わせ目に、どうしても目が行ってしまう。あの合わせ目を乱して、白い肌を露出させて――――
(いやいや!! 無いだろう!? 俺!! さっきシュバルツに、『もう休んでいい』と、言ったばかりじゃないか!!)
理性は懸命に訴えて、ブレーキをかける。
しっかりしろ、リュウ・ハヤブサ。
これ以上、シュバルツに負担をかけようとするんじゃない。
デモ……キス、グライナラ……。
自分の中の未練がハヤブサに囁きかける。
キスするだけならいいじゃないか。
ほんの少しだけなら――――
(駄目だって!! 絶対にキスだけでは、終われなくなってしまうから――――!!)
ああ、でも
シュバルツの瞳が
唇が――――
「ハヤブサ……」
愛おしいヒトから呼び掛けられる。
気のせいだろうか。
求メラレテ イル……?
そう感じてしまうのは――――
俺の願望が見せる、幻なのだろうか。
ああ――――
今すぐ、その肩に触れて
押し倒して、しまい たい
「シュバルツ……」
ハヤブサの手が、ふらふらと、シュバルツに向かって伸びて行った瞬間。
グ~~~! ゴキュルルル…! グ~~~~!
(…………!)
あまりにもでっかく響き渡った自身の『腹の音』に、ハヤブサは思わず絶句してしまう。
この腹の音はシュバルツの方にも聞こえてしまったようで、彼がきょとん、とした表情で、こちらを見ていた。
「ハヤブサ? どうした? 腹が減ったのか?」
「いや、そういうわけじゃ――――」
顔をひきつらせながら、必死に言い訳をしようとするハヤブサの腹が、またグ~~~~! と、大音量を奏でる。
「……減っている、みたいだな」
シュバルツはそう言うと、苦笑した顔を見せる。その彼からはもう――――自分を求めているような気配が、感じられなくなってしまっていた。
「いや待て、シュバルツ! 別にそんなに腹が減っている訳では――――!」
シュバルツに自分から離れて欲しくないハヤブサは、必死に彼を呼びとめようとする。
「無理をするなハヤブサ。何か食べれる物がないかどうか見てくるから」
「いや本当に―――!」
だが、制止したいハヤブサの手は間に合わず、シュバルツはすっと立ち上がってしまった。
「~~~~~~ッ!」
ハヤブサは思わず畳の上に突っ伏して、畳をバンバン! と叩いていた。
(どうして肝心な時に腹の虫が鳴るんだ!! あのまま行けば、間違いなくシュバルツを押し倒せていたのに―――!!)
そりゃまあ、認めるよ。
確かに俺は、早めの夕飯のために入った寿司屋で、あんまり食べてはいなかった。
あの時は、浮かない顔をして、それでも俺について来てくれるシュバルツの事が、心配でたまらなかったから――――。
食欲なんて、あろう筈もない。
そして更に、風呂場でいろいろ『やっちゃった』から――――
腹が減るのも、無理からぬことだとも思う。
「……………」
でも、先程のシュバルツのあの雰囲気は、何だったのだろう。
(ハヤブサ……)
そう言いながら、こちらを見つめてきたあの瞳は
あの唇は――――
俺ヲ、求メテ イタ?
(まさか………)
ハヤブサは頭を振る。
そんなはずはない。あのヒトが、まさかそんな……。
あれは、きっと幻だ。
俺の願望が見せた、都合のいい幻――――
「ハヤブサ? どうした?」
シュバルツに声を掛けられて、ハヤブサははっと我に返る。顔を上げるとシュバルツが握り飯が入った皿を手に持って、こちらを見ていた。
「部屋のテーブルの上に、これが置いてあったぞ」
そう言ってシュバルツは、おにぎりが二つ入った小皿をハヤブサに見せる。
「ああ……」
その小皿を見ながら、ハヤブサは思い出していた。確かあれは、風呂場で気を失ったシュバルツを介抱している時に、仲居が「夜食にどうぞ」と、持って来てくれたものだった。あの時は気が動転していて、とても飯など食いたいと思わなかったものだから、テーブルの上に置きっぱなしにして――――そのまま忘れていた。
「どうする? そちらへ持って行こうか?」
シュバルツの問いかけに、ハヤブサは首を振った。
「いや……そちらへ行って、食べるよ」
そう言うと、ハヤブサもそこから立ちあがった。
「それにしても……どうして人間、腹が減る事だけは忘れないんだ……」
握り飯の一つをほおばりながら、ハヤブサは、ハァ、と、ため息をつく。
「いいじゃないか。生きている証拠だ」
そう言って微笑む愛おしいヒトは、相変わらず綺麗な笑みをしている。
「そうだな……」
シュバルツにそう相槌を打ちながら、ハヤブサは少し淋しくなった。
食事を必要とする俺と、それを必要としないシュバルツ。
こういう時――――嫌でも自分とシュバルツの違いを痛感してしまうから、少し切ない。
でも、こういう違いを今更気にしても仕方が無い、とも、思う。
こういう所も『込み』で、俺はシュバルツを好きになったのだから。
「シュバルツ、お前はどうするんだ?」
握り飯の一つを完食したハヤブサは、2個目を手に取りながらシュバルツに問いかける。おにぎりが入った小皿は、2皿用意されていた。
「そうだな……。せっかくだから、一ついただくよ」
そう言うと、シュバルツもおにぎりを一つ手にとって、食べ始めた。
「どんな塩梅(あんばい)だ?」
ゆっくりと、噛みしめながらおにぎりを食べるシュバルツを見つめながら、ハヤブサは問いかける。アンドロイドであるシュバルツの舌には、味覚が無い。その代わり――――その舌で、口に入れた物の成分分析が出来るようになっている。
だから、シュバルツがこのおにぎりにどういう感想を持つのか、純粋に興味があった。
それに、分析をするために、彼がゆっくりと噛みしめるように物を食べる姿を見るのも、ハヤブサは、実は秘かに好きだったりする。
本当に――――可愛らしいヒトだ。一緒に居て『飽きる』と言う事が無い。
「……ミネラルが、豊富だ」
シュバルツは一口食べ終わった後、ポツリと言った。
「きっと、使われている塩や米が、良いものなんだろうな……」
そう言って、穏やかな表情をするシュバルツ。彼が、こういう表情をするのは、「いい物」を食べている時だから――――ハヤブサも、少し嬉しくなってしまう。
「じゃあ、横にある沢庵はどうだ?」
ハヤブサは、個人的にこの旅館の沢庵も好きなので、勧めてみる。
「沢庵か……」
シュバルツはハヤブサに勧められるままに、沢庵を一口、かじった。
(―――――!?)
クラ……と、一瞬、眩暈を感じたシュバルツは、動きを止めてしまう。
「……どうした?」
シュバルツの様子が少しおかしい事に目ざとく気づいたハヤブサから、声をかけられる。
「あ…ああ……いや、何でも――――」
ハヤブサの言葉に、はっ、と、我に帰ったシュバルツは、慌てて返事を返した。ただでさえハヤブサに心配をかけているのに、これ以上迷惑をかけられないと思った。
しかし、そんなごまかしが、ハヤブサに通用するはずも無く。
「大丈夫か? まさか、沢庵に何か悪い物でも」
「いや……そんな事は、無い…。沢庵の成分は、食物繊維と、塩と、ミネラルと、発酵――――」
また、クラ……と、眩暈を感じてしまうシュバルツ。
「シュバルツ!!」
倒れそうになったシュバルツを、ハヤブサは慌てて支えた。
「シュバルツ…! 大丈夫か?」
腕の中の愛おしいヒトに声をかけると、彼は笑顔を見せた。
「あ、ああ……大丈夫……」
だけど、その頬が上気し、瞳が潤んでいる。
「だけど…少し……熱くて……」
「……確かに、少し熱がある様だな…」
「――――ッ!」
ハヤブサがそう言いながらシュバルツの額に手を当てると、その身体がビクッと強張った。
「済まない……。やはり、無理をさせすぎたようだな……。シュバルツ、今日はもう休め」
ハヤブサはそう言うと、シュバルツの身体を軽く抱き上げる。『DG細胞』と言う、特殊な物質で構成されているシュバルツの身体。今日の一連の行動中に、彼の身体の中で、自分には分からない何か特殊な反応が起こってしまっているのかもしれない。
「ハヤブサ……」
布団の中にシュバルツを寝かしつけてやると、彼から呼び掛けられた。
上気した頬、潤んだ瞳、少し乱れた呼吸に襟元――――。
(う…………!)
ハヤブサのあまり強くない理性が、一気に傾いで行きそうになってしまう。
(いやいや! 無いだろう!? 俺!! こんな体調が悪そうなシュバルツを襲うだなんて――――!)
必死にそう考えて、ブレーキをかける。
よく考えろリュウ・ハヤブサ。
シュバルツの体調を悪くしたままキョウジの元に返す事になってしまったら―――――。
見える。
見えるぞ。
「へぇ~………『好きにして良い』とは言ったけど、まさか、壊してくれるなんて――――」
そう言いながら、笑顔で怒りまくっているキョウジの姿が、容易く思い浮かべられる。
こうなってしまうと、シュバルツに2度と会えなくなるどころか――――
「貴様ぁ!! よくも我が主を怒らせてくれたな!! この代償、高くつくと思えよ!?」
「おのれハヤブサぁ!! よくも、俺の兄さんを――――!!」
そう叫びながら、キョウジの後ろからあの馬鹿師弟二人が飛び出してくる姿が見える。
うわぁ、なんてことだ。
俺、割と簡単に死ねそうな気がしてきた……。
「ハヤブサ……? 大丈夫か……?」
半泣きになっていたハヤブサは、シュバルツにそう声を掛けられて、はっ、と我に返る。
潤んだ瞳のシュバルツと、視線が合う。だけどその瞳には―――こちらを純粋に心配している色が浮かんでいたから、ハヤブサは思わず、胸が締め付けられてしまう。
そんな風に、ただひたすら優しいお前。
駄目だ。
このヒトをこれ以上、自分の欲望の餌食にしてしまってはいけない――――
「俺は大丈夫だ…。それよりも、今はお前の方が心配だ。ゆっくり休んで、身体を治すことだけを考えろ」
そう言って布団をかけてやると、愛おしいヒトは優しい笑みを浮かべる。だけど、その瞳が変に潤んでいるから―――強烈な色香も同時に飛んできてしまう。
「お、俺は……こっちの方で、休んでいるから――――」
ハヤブサはそう言うと、シュバルツの布団から自分の布団を少し離して、そこで休むことにした。布団をくっつけて寝ていると、どうしても、襲いかかってしまいそうだった。
「じゃあ俺もそろそろ寝るが……何かあったら呼んでくれよ?」
そうシュバルツに声をかけると、愛おしいヒトは綺麗に微笑みながら「ありがとう」と、礼を言ってくれた。それだけで――――ハヤブサは充分幸せを噛みしめられた。
(もう……今回の報酬は、これだけで、本当に充分だな……)
手をつないで寝る。
寝顔を見守る。
選択肢はいろいろあるが―――――
どれも多分襲いかかってしまいそうなので、止めた。
「じゃあ、お休み」
ハヤブサはシュバルツにそう声をかけると、部屋の電気を「カチリ」と、消した。
部屋に眠るための静寂が訪れる。
「ん…………」
その中で―――シュバルツは、何故かなかなか寝付けずにいた。
(熱い………)
はあっ、と、思わずため息が出てしまう。
(おかしい……何で、こんなに身体が熱いんだ……)
布団を蹴飛ばし、浴衣を脱ぎ棄てたくなってしまう。そんな行儀の悪い事は出来ないので、じっと我慢をしているのだが、それすら辛い。
具合が悪くて熱が出ている……?
いや、違う。
この感覚には、覚えがある。
これは――――
風呂場で、ハヤブサに焦らされていた時の感覚に……似ている……?
まさか、と思いながらもシュバルツは、そろそろと己自身に手を伸ばす。するとそこは、もう既に勃ち上がり、愛液を溢れさせ始めていた。
(あ…………!)
自分の手が軽く触れただけなのに、ビクッと身体が跳ね、声が出そうになってしまう。
(ど……どうしよう…! こんな……!)
身体が火照る。
疼く。
触って欲しい。
擦って欲しい。
挿れて欲しい――――
完全に自分が欲情してしまっている、と言う事を、シュバルツは悟らざるを得なかった。
(駄目だ……! 浴衣もシーツも、汚れてしまうのに……)
シュバルツは必死に己を落ち着かせようとする。だが、そんな彼の想いとは裏腹に――――彼の牡茎からは、ますます愛液が溢れるばかりだった。
何故だ?
どうして、こうなった?
シュバルツは懸命に、原因を考える。
そして、行きついた結論は、自分がこうなる直前に、食べた『物』―――
(まさか……沢庵……!?)
まさかそんな、と、シュバルツは否定しようとする。
だけど、あれを一口かじった瞬間に感じた、眩暈。
もしかしたら、沢庵の中の何かの成分と、自分の身体を構成している細胞が特殊な反応をして――――自分にとって『媚薬』の様な効果を、もたらしてしまっているのかも、しれない。
(ん………!)
浴衣の布が、自分の勃ち上がってしまっている乳首を擦る。その刺激が耐えられなくて、シュバルツは思わず胸に手を当てる。だけど、今度はその手の刺激に感じてしまって――――気がつけば彼は、自分の指の腹で、自分の乳首を擦ってしまっていた。
(だ……駄目だ……! こんな、の……!)
理性は懸命に訴えて、指の動きを止めようとする。だけど、自分の意志とは裏腹に、指の動きはなかなか止まってくれない。どうしようもない身体の火照り――――シュバルツの瞳からは、いつしかジワリと涙が滲み出て来ていた。
(ハ……ハヤブサ……)
シュバルツは思わず、ハヤブサを求めてしまう。
どうしよう。
ハヤブサに抱いてもらって――――
この身体の疼きを、治めてもらおう、か。
でも―――――
シュバルツは頭を振る。
お前は、自分の性欲の『処理』のために、ハヤブサを『利用』するのか?
駄目だ。
自分は今――――ハヤブサにとっての『報酬』なのだ。
『報酬』が、受取人を自分のために『利用』しようとするなんて、おかしい。
(でも……このままでは―――!)
身体が熱い。
疼く。
耐えられない……!
息が乱れそうになるのを、かろうじて堪える。
このままでは、眠ることすらできそうにない。
(仕方がない。とにかく……『抜こう』)
シュバルツはそう決意する。とにかく――――自分の中の『欲望』を、少しでも吐き出したら、落ち着いてくるかもしれない。
ここでする訳にもいかないからと、シュバルツは身を起こそうとする。
だけど、『媚薬』の影響なのか――――身体に少しも力が入ってくれなかった。
「シュバルツ? どうした?」
そうこうしているうちに、気配を察したハヤブサが起きてしまう。
「あ……いや、何でも――――」
慌ててハヤブサから距離を取ろうと、試みるシュバルツ。だが、力が入らない身体は、すぐに彼をその場にへたり込ませてしまう。
「シュバルツ!?」
慌ててハヤブサはシュバルツの側に駆け寄る。
「大丈夫か?」
そう声をかけて、彼の身体に触れた瞬間。
「あ……ッ! ん……!」
彼から上がる妙に艶めいた声に、ハヤブサは驚いてしまう。
「ど、どうした?」
ハヤブサの戸惑う声に、シュバルツもはっと、我に返る。
「す、済まない……! これは別に、何でも無くて――――」
慌ててごまかそうとする。だけど、そんな物が、ハヤブサに通用するはずも無く。
「……『何でもない』と言う、風情ではないがな……」
ハヤブサは静かにそう言うと、布団の側に設えられていた行燈型の電器に灯をともした。すると、小さな電球の明かりの中に、浴衣をはだけて白い胸を覗かせて、切なそうに息を乱しているシュバルツの姿が浮かび上がって来るから――――ハヤブサは息を飲んでしまう。
何だこのシュバルツは。
体調が悪いと言うよりは、むしろ――――
「や……! 見るな……!」
そう言いながら愛おしいヒトが、しどけなく身を捩って自らの胸を隠そうとするから――――ハヤブサは思わず、その手を後ろ手に絡め取って――――その身体を抱き寄せていた。
「あっ!」
シュバルツの動きを封じ込めてから、ハヤブサはその胸に己の指を這わせる。するとその頂は芯を伴って既にぷっくりと勃ちあがり、コリコリとした感触を、ハヤブサの指の腹にもたらした。
「ああっ! だ、ダメ…! はあ…んっ…!」
言葉とは裏腹に、悦んでしまう身体。胸を軽く弄られているだけなのに、シュバルツの身体はどうしようもなく跳ねてしまう。
「熟れきっているな……。こっちはどうだ?」
ハヤブサはそう言う言いながら、シュバルツの下半身に手を伸ばして行く。
「やめ……! あうっ!!」
そこは最早浴衣越しにも分かるほど、勃ち上がってしまっている事を、ハヤブサに伝えてしまう。少しそこを撫でてやると、その近辺の浴衣が既に濡れそぼっていた。牡茎から溢れ出た愛液が、染み出して来てしまっているのだ。
「あ……! ああ……! あ…あ…っ!」
「すごいな……。こんなに――――」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの浴衣の帯を解く。すると浴衣は、シュバルツの身体を隠す役目をあっさりと放棄して、ハヤブサの視線の前に、主の身体総てを晒してしまう。熟れきって、今にもはち切れそうになっているシュバルツの牡茎が、そこにあった。
「何時からだ? シュバルツ」
震えるシュバルツの頬にチュッと音を立ててキスをしながら、ハヤブサは問う。
「お前はいつから、そんな風になっていたんだ?」
「あ……あ、あ……っ! はあっ!」
問われながら指先で、鬼頭を優しく撫でられるから、酷く感じてしまうシュバルツは問いに答えを返すどころではない。弱々しく頭を振るシュバルツに、ハヤブサの攻めの手は緩まなかった。
「ほら……シュバルツ――――」
ハヤブサのもう片方の手が、シュバルツの胸に伸びて来て、そこを弄り始める。
「ひあっ!! ああっ!!」
弱い所を同時に責められて、シュバルツはもうおかしくなりそうになってしまう。
「駄目…! も……イク……! イ……あ―――――!」
ビクビクッと震えて、達しそうになる身体。だがその寸前で、いきなりハヤブサの手がシュバルツの身体から離れた。
「あっ……!」
座っていることすら出来なくて、とさ……と、弱々しく蒲団の上に投げ出されてしまうシュバルツの身体。解放を許されなかった下半身が激しく疼き、ぴくぴくと、その身を切なく震わせていた。
「たったこれだけの愛撫で達しそうになるなんて……よっぽどだな……」
溜息を吐きながら、ハヤブサはシュバルツを見下ろす。
「す…済まない……ハヤブサ……」
「なぜ謝る」
震えるシュバルツの身体の上に、四つん這いに覆いかぶさりながら、ハヤブサはシュバルツに問いかける。
「何時からだ? シュバルツ」
「う………」
「何時からお前は、そんな風になっていたんだ?」
「あ…あ……」
はっ、はっ、と短く呼吸をしながら、潤んだ瞳でハヤブサを見上げてくるシュバルツ。そんな彼の姿に愛おしさがこみ上げてくると同時に――――己の胸が激しく締めつけられるのをハヤブサは感じていた。
このヒトはいつから――――こんなになるまで耐えていたのだろう?
「つい、さっきからだ……。『夜食』を…食べ終わった後……急に――――」
そう言いながら、ハヤブサから視線を逸らし、その瞳を閉じてしまうシュバルツ。
「夜食………」
シュバルツの言葉に、少し考え込むハヤブサ。
シュバルツのこの状態は、何らかの『媚薬』の様な物を口に含んでしまった、と、考えたほうがよさそうだ。だけど妙だ。アンドロイドであるシュバルツに、普通の人間仕様の『媚薬』が効くものなのだろうか?
(……………)
この旅館の者が一服仕込んだとも考えにくいし、同じ物を食べたはずの自分は、何ともなっていない。まあ尤も、自分はシュバルツに対して年中発情している様なものだから、薬を盛られていても、気づいていないだけかもしれないが。
それにしても――――
「シュバルツ……。どうして……」
駄目だ。言ってはいけない。
ハヤブサの理性は懸命に訴える。
だけど。
ああ、だけど。
「どうして……お前は――――」
分かっている。
このヒトは『助けて』とは
言わない。
言えない。
『報酬』だから。
このヒトは俺の
『報酬』だから―――――。
俺に、助けを求めてはいけない、と、思っている。
真面目に、『報酬』であろうと、してくれている。
分かっている。
シュバルツは、何も悪く 無い。
悪く 無い の に
でも――――
それでも………!
「何故、そんなになるまで一人で黙って耐えているんだ!? どうして―――俺を求めてはくれないんだ!!」
叫んでも仕方がない事を、叫んでしまう。こんな事、シュバルツにぶつけても、どうしようも無いのに。分かっていて――――ハヤブサは、もう、自分で自分が止められなかった。
「ハ、ハヤブサ……」
案の定、どうしようもない事を叫ばれた愛おしいヒトが、戸惑ったような表情を見せる。
「そ、そんな……だって……駄目、だろう……?」
「駄目!? 何が駄目なんだ!?」
「だ……だって……お前を…そん、な……『性欲』の、処理……みたいに―――」
「いいじゃないか!! 性欲の処理でも何でも――――俺を利用すれば!!」
ある程度予想をしていた通りの答えが本当にシュバルツから返って来て、ハヤブサは天を仰ぎたくなってしまう。
やっぱりそうだ。このヒトの中では、俺との関係は『報酬』以外の何物でも無くて、そこに想い想われる恋愛感情なんてものは存在しない。俺には、搾取されるだけでいい、と、思っている。求めてはいけない、と、思っている。
「俺は、お前が相手ならば……いくらだって、抱く事が出来るのに――――」
「ハヤ、ブサ……」
「それなのに、貴方は――――身体がそんな風になっていても、俺を求めてはくれない……!」
「ち、違う、ハヤブサ―――!」
シュバルツは思わず叫んでいた。
そんなつもりじゃない。
そんなつもりじゃなかったんだ。
そんな風に――――お前を傷つけるつもりでは……!
「違う!? 何がどう違うんだ!!」
ハヤブサはもう止まれなかった。一旦堰を切ってしまった感情は、後から後から奔流となって、ハヤブサの中から溢れ出て来てしまう。
報われないと分かっていても、足掻いてしまう自分の恋心が、どうしようもなく、苦しかった。
「さっきだって―――俺から逃げようとしていただろう!! 身体がそんなになっているのに、『何でもない』などと言って――――!!」
「ち、違う…! 逃げようとした訳では……!」
「貴方はいつもそうだ!! 何でもかんでも一人で抱え込んで耐えて!! 俺が側に居るのに、頼ろうともしてくれなくて――――!!」
「ハ、ハヤブサ……!」
違う。分かっている。
シュバルツが俺を頼らないのは、俺が頼るのに値しない、情けない人間だからだ。
『性欲の処理』にすら、頼ってもらえないのだってそうだ。
勝手に理性を飛ばしてしまって、彼の身体を痣だらけにするほど、乱暴に抱いてしまった―――自分。
そんな人間に
誰が『もう一度抱いてもらいたい』なんて
思うんだよ。
(くそっ!)
悪いのは自分。
未熟な自分。
分かっている。
分かり過ぎるほど――――分かっている。
でも……
それでも――――
叫ばずには、いられなかった。
「貴方を抱きたいって………俺のそう言う気持ちを、分かっていて……!」
「ハ…ヤブサ……」
「ひどいヒトだ……! 貴方は……!」
「――――――!」
「俺は一体何のために――――貴方の側に、居るんだッ!!!」
「あ…………!」
ハヤブサに叫ばれて、ようやくシュバルツは、自分の行動がどれだけ手酷くハヤブサを傷つけてしまっていたかを悟った。
「ハヤブサ……違………あっ!」
謝りたくて、誤解を解きたくて――――シュバルツは身を起こそうとする。だが、動こうとする身体を下半身の激しい疼きが、ズクン、と、音を立てて邪魔をする。
「う……く……ッ!」
僅かな刺激で、果てそうになる身体。
(ダメ、だ……! こん…な、時に……ッ!)
シュバルツは必死に耐えた。ハヤブサをひどく傷つけているのに、自分だけ果ててしまうなんて――――まさしく、淫乱以外の何者でもないじゃないか。
「う……う……」
「…………」
ハヤブサは、布団の上で身を丸くして、小さく震えているシュバルツの姿を暗澹たる気持ちで見つめていた。
惨めだ。
堪らなく。
シュバルツは何も悪くないのに、自分の気持ちに耐えられなくなって、一方的に彼を責めて、怒鳴り散らしてしまっている――――自分。
分かっている。
こんなのは、ただの『八つ当たり』だ。
「ああ……!」
はっ、はっ、と短く呼吸をしながら苦しそうに震えている愛おしいヒト。
イキたいのだろう。
果てたいのだろう。
何をそんなに、我慢しているんだ。
(満たしてやらないと)
ハヤブサは、思う。
このヒトの『心』は――――俺を求めては居なくても、身体は、強制的に刺激を求め、解放を求めさせられているのだから――――せめて、満たしてやらないと。
「ん………っ!」
身体の疼きに我慢できなくなってしまうシュバルツの右手が、ふらふらと『そこ』に向かって伸びて行く。それを見た瞬間、ハヤブサの中で何かが音を立てて『ブチッ』と、切れた。
「――――くそっ!」
そう短く叫ぶと、ハヤブサはシュバルツの身体を覆っていた浴衣を乱暴に剥ぎ取った。そしてそのまま彼の両手を強引に取ると、帯で後ろ手にきつく縛りつけてしまう。
「あっ! や……!」
愛おしいヒトが小さく悲鳴を上げるが、もうハヤブサは聞く耳を持てなかった。このヒトの『心』は、どう足掻いたって手に入らないモノ。それが――――よく、分かったから。
ならば、せめて。
お前の身体だけは――――俺が満たして、俺だけの物にしてやる。
「シュバルツ―――」
顎に手をかけ、シュバルツを強制的にこちらに向かせる。
「ハ、ヤブサ……」
愛おしいヒトは、ポロポロと涙を流していた。相変わらず綺麗で――――そして、哀しい涙だと思った。
可哀想に。
感じなくてもいい、俺への良心の呵責で苦しんでしまっているのだろう。
貴方がそんなに泣く必要はない。貴方は――――何も、悪くないのだから。
分かっている。俺が、悪い。
俺の、『弱い心』が――――。
「イキたいんだろう…? シュバルツ……」
「あ…………」
「イカせてやるよ……俺が――――」
「ハヤブサ……!」
「だから、シュバルツ―――」
ハヤブサは、指でシュバルツの涙を拭いながら、言った。
「せめて貴方の身体だけでも――――俺無しではいられないモノに、なってしまえば、良い」
「な――――んんっ!」
驚き息を飲むシュバルツ。その唇は、ハヤブサによって強引に塞がれていた。
そのままとさり、と、シュバルツの身体は布団に押し倒される。そこからハヤブサの舌が、シュバルツの口内に侵入してきた。そのまま、そこを弄られる。深く、深く――――。
「んうっ! んんっ!」
(ダメ、だ……! ハヤブサ……ッ!)
それと同時にハヤブサから哀しい心が流れ込んでくるから――――シュバルツはたまらなくなる。
傷つけてしまった。彼を。
そんなつもりじゃなかった、のに。
だけど、身体は確かに悦んでしまっている。
彼に押し倒されて、キスをされて――――淫らな歓喜に震えている。
(ダメだ……! こんな、の……は……!)
シュバルツは、快楽の波に必死に抵抗しようとする。
ハヤブサからこんなに哀しい抱擁を受けて、それを悦びたくは無い。感じたくは無いのに――――。
触ッテ
擦ッテ
犯シテ―――
私 ヲ 解放 シ テ 欲シ イ
何て、淫らな願い。淫らな身体。
何故
どうして
こうなってしまった?
「ハヤブサ……ッ!」
口が自由になったから、シュバルツは顔を上げて、ハヤブサに呼びかけようとする。
とにかく、謝りたかった。
誤解を解きたかった。
だが――――
「ハヤ……ああっ!!」
ちゅぷっと、音を立てて、シュバルツの牡茎がハヤブサの口に咥え込まれるから――――シュバルツは、言葉が紡げなくなってしまう。
「ひあっ!! あああっ!!」
そのままハヤブサの口と舌が、シュバルツの牡茎を愛して行く。感じる所を舐められ、吸われ――――シュバルツの下肢から背中にかけて、悦びの甘い電流が駆け抜けて行ってしまう。
「ハヤブサッ!! やめ……ッ!」
快感に仰け反る身体。だがシュバルツは、その感触に首を振って抗った。
「嫌だ! 止めて…くれ…ッ! 口でするのは――――!!」
懸命に懇願する。ハヤブサの口の中に自分の精を放ってしまいたくはなかった。自分の『精』だって、DG細胞の塊だ。それを、自分以外の人間の体内に入れてしまう行為は、シュバルツにとっては押し並べて恐怖以外の何物でもなかった、から。
もちろん、ハヤブサもシュバルツのそんな気持ちを分かっていた。
だから―――普段のセックスの時には、ハヤブサも、極力そう言う事をしないように心がけていた。
だけど、もう。
心は要らない。シュバルツの身体だけが欲しいと思っているハヤブサは、彼が嫌がると分かっている事を――――敢えて『した』
「口に出すのが嫌なら――――堪えて見せろよ」
わざと冷たく言い放って、ハヤブサは再びシュバルツの牡茎を愛し始める。
「そ、そんな……ッ! ああっ!! 嫌…! 嫌だあああっ!!」
悲痛な叫びを上げる、愛おしいヒト。
(嫌われてしまうだろうか)
ハヤブサはふと思う。だが、すぐに思いなおした。
嫌われるも何も――――お前は、シュバルツから愛されてすらいないじゃないか。
愛されてもいないのに、どうやって、嫌われる事が出来るんだ。
分かっていたはずだった。最初から。
このヒトの身体は――――このヒトに、誰かを『好き』と言わせる事を拒む。
だから、いくら自分がシュバルツの事を好きになっても、この想いは報われる事は無いのだと。
百も承知で―――――それでも、このヒトの事を好きになる事を止められなかった。
見返りなんて、要らない。
本気で、そう思っていた。
だけどいざ――――本当に自分の『想い』が報いられる事は無いのだ、と言う事実を目の前に突きつけられると―――――。
辛い。
疲 れ る
そして、こんな事でいちいち傷つき振り回される、自分の心の弱さが―――――たまらなく、嫌だった。
「んっ! くう……! や……! 嫌、だ……ッ!」
頭を振り、涙を散らしながら――――懸命に牡茎への愛撫に耐える愛おしいヒト。
(……結構、頑張るな……)
頭の隅でちらりと思う。咥える前からはち切れんばかりになっていたシュバルツの牡茎。愛撫を始めたら――――すぐに果てると思っていたのに。
「ああっ! 駄目っ! も……! 我慢…が……ッ!」
白い身体がのたうち、腰が揺らめく。もう限界が、近いのだろう。
「お願、いだ…! ハヤブサ……ッ! 離れて……!」
必死に懇願される。
この状況で、まだ自分を犯している相手を気遣えてしまえる愛おしいヒト。このヒトは――――そう言うヒトだ。
でも、やめて欲しいと思った。
その気遣い、その優しさは、俺の心に勘違いをもたらしてしまうから。
愛されているんじゃないか。
俺の『想い』に、応えてくれるんじゃないか。
そんな、報われない勘違いを――――。
期待して、やっぱり報われなくて、それでも足掻く事を止められなくて。
もうたくさんだ。
そう斬り捨ててしまえれば――――どんなに、楽になれるだろう。
「ハヤブサ…ッ! 嫌、ああっ! 離れて…! 離れ…てッ!」
「…………」
無言で、愛撫を続ける。
絶対に、離れない。離れてなんかやらない。
だって、こんなにも――――――まだ愛おしいのに。
「んっ! ……あっ! ああっ!!」
容赦のないハヤブサの牡茎への愛撫に、堪えに堪えていたシュバルツも、ついに限界が来てしまう。
嫌だ……!
イキたくない……!
こんな――――哀しい『ココロ』の中で……!
まして、ハヤブサの『口の中』に、だなんて……!
「ハヤブサッ!! 嫌…! はなれ…! ああっ!! いやだああああああ!!」
悲痛な叫び声を上げながら、シュバルツはとうとう、果ててしまった。
ドクドクッ! と、音を立てて、シュバルツの『精』がハヤブサの口の中に呑みこまれていく。
「ん…………」
ハヤブサはそれを、そこから口を離さずに、ごくごくと喉を鳴らしながらそれを受け入れる。
「やめてくれ……。飲まないでくれ……!」
愛おしいヒトから、泣きながら懇願される。だから、尚のこと――――ハヤブサはその行為を続けた。
「嫌だ……! どうして……!」
シュバルツの牡茎から『それ』が出なくなっても――――ちゅっ、ちゅっ、と、音を立てて丁寧に吸い上げた。まるで、一滴たりとも飲み残すものか、とでも言わんばかりに。
構わない。
これで、もしDG細胞に感染したとしても。
俺は、一向に構わないんだ。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
ヒック、ヒック、と、嗚咽を漏らしながら、こちらを見つめてくる愛おしいヒト。その泣きぬれた姿に――――愛しさと、嗜虐心が募った。
このどうしようもなく美しくて強いこのヒトを、地の底まで堕としてしまいたかった。
そうすれば、せめてその身体だけでも――――俺の物になるのではないかと、思ってしまえるから。
一度『抜いた』はずのシュバルツの牡茎が、また勃ち上がって来ている。媚薬の効果がまだ切れていないのだろう。――――幸いな事に。
(すごいな……)
ハヤブサは口の端を吊り上げて、嗤った。
こんな強力なシュバルツ専用の催淫剤。是非ともその材料を知りたいと思った。
(ハヤブサ……!)
シュバルツは、涙の向こうに霞むハヤブサの姿を見つめる。
初めてだった。
こんなに――――心を踏みにじられるように、愛撫されたのは。
それほどまでに、私は
お前の心を、傷つけてしまったのか……。
どうすればいい?
どうすれば、よかった?
誤解。
誤解なんだ。
頼らなかった、訳じゃない。
求めなかった、訳じゃない。
傷つけたかった、訳じゃないんだ。
だが―――――
「誤解だ!」
そう叫ぼうとして、シュバルツは、それが叫べない事に気づいてしまう。
だって、誤解を解こうとしたら、言わなければならなくなる。
「私はハヤブサ、お前が、好きなのだ」
と、言う事を……。
それは、言えない。
言わない。
言わないと、決めている。
ああ。だから。
(これは、報いなのだ)
シュバルツは思う。
ハヤブサの気持ちを分かっていて
自分の気持ちも分かっていて
それを、ハヤブサに告げようとしない、卑怯な私に対する――――『報い』
ハヤブサの気持ちを、一方的に消耗しようとしている、私に対する『報い』なのだ。
「ひどいヒトだ……! 貴方は……!」
涙ながらにハヤブサに言われた言葉。
本当に、その通りだと、思う。
懸命に、私に向かって手を伸ばして来てくれているハヤブサ。
私は、その手をどうしても取る事が出来ない。
お前が、私に差し出して来てくれているモノと同じ物を、私はどうしても、返す事が出来ないんだ。
ああ
どうか、お願いだ。
これ以上――――この空虚なアンドロイドにお前の心を消耗するのは止めて、くれ。
どう足掻いても、結局私はお前を傷つけることしか出来ないんだ。
ならばいっそ――――このまま、嫌われ抜いてしまった方が、良いのかもしれない。
「あ………ッ!」
ハヤブサに牡茎の先端を優しく撫でられ、シュバルツの身体が、ビクッと跳ねてしまう。
「………勃ち上がって来ているぞ」
「んっ! ……あ……!」
「すごいな……抜いたばかりなのに――――」
鬼頭の割れ目から溢れる愛液を指で絡め取りながら、ハヤブサはそれをシュバルツの牡茎に擦りつけるように愛撫して行く。くちゅくちゅと、卑猥な水音が辺りに響いた。
「や……! や……あ……!」
感じたくないのに、感じさせられてしまう。シュバルツはそれが哀しくて、いやいやと頭を振った。だけど、火照る身体はハヤブサの愛撫を悦んでしまう。身体の中心が、刺激を求めて切なく疼いていた。
「お……おかしいん、だ……。身体が、熱くて――――」
震えて、涙を流しながら言葉を紡ぐシュバルツに、ハヤブサはにやりと笑いながら答える。
「そうだろうな。お前はおそらく、『媚薬』の様な物を口に含んでしまっているんだ」
「媚薬………あっ!」
話をしながら、ハヤブサの亀頭への愛撫は続けられていた。
「あっ! ……あ……! は…あ……!」
「可愛いな。お前は……。綺麗だ……」
「や……! そん、な……こと…! ぅあっ!」
「乳首も勃って来ているぞ…。触って欲しいか?」
「んっ! や……! や、だ…あ……ッ!」
ハヤブサの言葉に身体を隠したくなって、シュバルツは思わず自分の手を意識する。だけど、浴衣の帯で後ろ手にきつく縛られているシュバルツの両手は、動いてくれそうになかった。
チロリ、と、ハヤブサの舌が、シュバルツの亀頭に触れる。
「ひっ!!」
ビクン!! と、跳ねて逃げようとするシュバルツの身体を、ハヤブサは無理やり抑え込む。そのまま舌先で鬼頭を愛し始めると、シュバルツは涙を飛び散らせながら頭を振った。
「や……! 止めて…! 止めてくれ……!」
「やめて欲しかったら、俺の質問に答えろシュバルツ」
「質……問……?」
はっ、はっ、と、呼吸を荒らげながら、潤んだ瞳でこちらを見つめる愛おしいヒト。綺麗で、可愛らしくて、愛おしいから――――ますます、苛めたくなってしまう。
「お前は一体――――何を食べて、そうなってしまったんだ?」
「――――!」
シュバルツが息を飲む気配が伝わってきた。
「あ…………!」
そしてそのまま、俺から目を逸らしてしまう、愛おしいヒト。
言える訳がない。
そうだろうとも。
お前を踏みにじっている今の俺に、そんな危険な情報を渡せるわけがない。
俺はな、シュバルツ。別にどっちでも構わないんだ。教えてくれても、くれなくても。
それをネタに、俺は。
オ前ヲ 苛メル ダケ ダカラ
シュバルツの牡茎の先端に唇をあてて、チュッと、音を立てて吸ってやる。
「ひっ!! やあっ!!」
口でされる事を嫌がり、必死に身を捩ろうとするシュバルツ。だが、ハヤブサがそれを許すはずもない。
「逃げるなよ。気持ち良いくせに」
跳ねるシュバルツの身体を抑えつけて――――チュッ、チュッ、と、吸い続ける。
「はっ! ああっ!! イヤだ…! 嫌だぁ……!」
「嫌なら――――何を食べてそうなったのかを」
「あ……あ……! お、教える……! 教えるから、止めてくれ…っ!!」
「――――!?」
あまりにもあっさりそう叫ばれた事に驚いて、ハヤブサは思わずシュバルツから手を離してしまう。シュバルツは、ハヤブサから『そこ』を隠すように身を捩って、布団の上で小さく丸くなると、再び口を開いた。
「教える……! だから……お願いだ、ハヤブサ……! 口ですることだけは……止めてくれ……」
「シュバルツ……」
「お願いだ……! どうか、それだけは……!」
そう言って、嗚咽を漏らしながら泣きじゃくる愛おしいヒト。小さく丸くなった背中が、小刻みに震えていた。
「……………」
その痛々しい後ろ姿に、流石にハヤブサの胸も締め付けられる。でも、こうなる事は百も承知で俺はそれをしているのだ。今更、後には引けなかった。
(それにしてもお前は……まだ俺を『嫌悪』すら、してくれていないんだろうな……)
『口でするな』と、言う事は、DG細胞を飲むなと言う事。まだ、犯している相手の事を思いやっている。そして、『媚薬』の情報を俺に渡すと言う事は、別に俺の事を信じているとか言う訳ではなくて、自分の身を守る意思が無いと言う、気持ちの表れ。
それは、俺が最初にこいつに会った時からそうだった。このヒトは、およそ『自分の身を守る』と言う行動をしない。その自身の特殊な身体故に――――。
分かっている。
どう足掻いたって、結局このヒトの『特別』には誰もなれないのだ。このヒトを作った、キョウジ以外は。
淋しい。
たまらなく、淋しかった。
ハヤブサは、震えるシュバルツの髪にそっと触れると、その頬に優しくキスをした。
「ハヤ…ブサ……」
「シュバルツ―――」
流れ落ちるシュバルツの涙を、優しく拭ってやる。でも、それをするハヤブサの口から零れ落ちる言葉は、冷たい物だった。
「じゃあ、教えろよ。お前は、何を食べてそうなったんだ?」
「あ…………」
震えるシュバルツの唇に、優しく触れる。
その情報、本当に俺に渡せるものなら渡してみろよ。俺は一切、手加減なんかしてやらないぞ?
「ん…………」
シュバルツは観念したように瞳を閉じると、震えるその唇を開いた。
「た……沢庵……」
「何?」
「……はっきりとは分からないが、多分……沢庵が、原因……」
「…………」
ハヤブサはシュバルツの傍から立ち上がると、隣の部屋のテーブルの上に置いてあるシュバルツの方に渡した小皿を見る。その皿の中には、沢庵が一切れ半残っていた。ハヤブサはその皿を手に取ると、再びシュバルツの方に近づいて行く。
「じゃあ、これを食べて見せろよ。お前が言った事が本当かどうか、俺が見極めてやるから」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの口元に沢庵を押しつける。
「あ…………」
「ほら、シュバルツ――――」
「…………」
シュバルツはハヤブサに命じられるままに口を開いて、沢庵を一口、かじった。
「――――んっ!」
シュバルツの口内いっぱいに広がる、沢庵の汁。それが吸収されるごとに、彼の身体全体に、甘い熱と衝動が走り抜けていく。
「んっ! んく…!」
その感覚に耐えきれず、シュバルツの身体が仰け反り、四肢が突っ張る。強制的に呼び起される、甘い熱。彼はこれ以上、沢庵を咥えていられなくなって――――
「……は……あ……」
彼は口から、沢庵をパサリと落としてしまった。
「……自力では食べられないのか…」
「…………っ」
はっ、はっ、と短い呼吸をしながら、涙を流す愛おしいヒト。心なしか、頬の上気の色も濃くなっているように見える。
「……………」
ハヤブサは、無言でシュバルツが落とした沢庵を拾い上げると、それをおもむろに自分の口の中に放り込む。先程のシュバルツの様子からすると、沢庵が彼にとっての『媚薬』となっていると言う情報は、あながち嘘と言う訳でもなさそうだ。
ならば。
小皿に残っていた沢庵も、口の中に放り込んで、よく咀嚼してやる。
そして――――
「んうっ!!」
噛み砕いてほぼ液体と化した沢庵を、シュバルツの口に『口移し』で流し込んでやった。
「んぐっ!! んんっ!!」
その感触に耐えかねるのか、ハヤブサの身体の下で、シュバルツの身体が仰け反り、足が突っ張る。その身が捩れる。口付けから逃れようとさえしているような動き――――ハヤブサはそれを抑え込みながら、シュバルツの口の中に沢庵を流し込み続けた。全部入れ終わるまで――――離してなんか、やらなかった。
「……………」
自分の口の中の沢庵が全部なくなったのを確認してから、ハヤブサはシュバルツから離れる。それから彼の口を、手で優しく塞いだ。せっかく口の中に入れた沢庵を、外に出されないようにするために。
それをしてからハヤブサは、シュバルツに命じる。出来るだけ、冷たい口調で――――。
「飲め」
「……………」
泪ぐんだ瞳で、しばらくハヤブサを哀しげに見つめていたシュバルツであったが、やがて、観念したようにその瞳を閉じた。
「――――ッ」
「ゴクッ」と、音を立てて、彼の喉仏が上下する。
刹那。
「……あっ! はあっ!!」
全身を、強烈な甘い電流と熱が襲う。海綿体に、強制的に熱が集められていく。胸の頂が痛い程突っ張る。身体の奥が、刺激を求めて強く疼き出す。
「あ……熱い…! 身体、が……ッ!」
解放を求める熱が、身体中で暴れまわる。
奥の疼きが我慢できず、胸の突っ張りが切なくて、海綿体が痛くて――――シュバルツは布団の上をのたうちまわってしまう。その姿が、どれ程ハヤブサの目に扇情的に映ってしまっているか、気づきもせずに。
「ああ……! ん……! く、う……!」
涙に濡れた瞳をとろんとさせて、息を荒らげ、何もかもを張り詰めさせて、身体を切なそうに揺らめかせているシュバルツ。その恐ろしく妖艶な姿に、ハヤブサは生唾を飲み込んでしまう。
「…………」
ハヤブサはそろそろと、シュバルツの勃ち上がっている乳首に、指を這わせた。
「はああっ!! ああっ!! 駄……あああっ!!」
ハヤブサは、乳首を指の腹で優しく擦っているだけ。なのに、シュバルツの身体はビクビクっと、過剰に反応した。どうやら『媚薬』の効果によって、このヒトのただでさえ感じやすい身体の感度が、何倍にも跳ね上がっているようだった。
「すごいな……」
しばらく陶然とシュバルツの胸を優しく弄んでいたハヤブサであったが、その張り詰めた乳首に、チュッと、音を立てて吸いついた。
「あっ!! ああんっ!!」
たまらず悲鳴のような嬌声を上げる、愛おしいヒト。
跳ねてしなるシュバルツの身体を抑えつけて、ハヤブサはその乳首を口に含んで、舌で優しく転がしてやる。それをしながらハヤブサは、空いている方の手をもう片方の胸に伸ばして行った。
「ふあッ!! ああっ!!」
優しくそこを摘まんでやると、愛おしいヒトの身体がビクン、ビクン、と跳ねる。ハヤブサはしばらくその舌と指で、胸を優しく愛し続けた。
「あっ!! 両方…は、駄目ッ!! 駄……あっ!! も…う……ッ!」
びゅく、びゅ……と、音を立てて、シュバルツは果ててしまう。彼の白い『精』が、ハヤブサの愛撫をしている頭や手に、ぺシャ…ッと、飛び散った。
「……胸への刺激だけで……イケたな」
シュバルツの飛び散った『精』を紙で拭いながら、ハヤブサはシュバルツに笑いかける。
「あ……あ……」
対してシュバルツは、涙を流しながらハヤブサから視線を逸らした。上気した頬は、羞恥故なのか、それとも『媚薬』の熱せいなのか――――それは、分からなかった。
ハヤブサがシュバルツの下半身に視線を移すと、さっき果てたはずの『そこ』がまた勃ち上がって来て、愛液を垂らし始めている。
(……全く、素晴らしい効き目だな、これは……。いくらでもシュバルツを抱けるじゃないか…)
ハヤブサはにやりと口の端を吊り上げて笑うと、シュバルツの股をわざと乱暴に大きく開く。
「あっ!?」
「『ここ』の具合は―――どうだ?」
胸と同じく刺激を求めているシュバルツの入り口は、既にひくつき――――妖しく蠢いていた。ハヤブサが指をつきいれてやると、そこは悦んでハヤブサの指を飲みこんで行く。
「あっ!! ぅあっ!! ああ…!!」
「柔らかいな……3本目も入りそうだ」
ジュブッと、音を立ててハヤブサの指が内側に入り込んでくる。指が優しくそこを擦り始めると、シュバルツの身体がたまらず跳ねた。
「ああっ!! 駄目っ!! そ、そんな、事………あっ!!」
ビクビクッとシュバルツの身体が震えたかと思うと、彼の白い『精』が、前方の床にパタパタっと落ちた。また彼は、達してしまったらしい。
「ああ………!」
涙を流しながら、小刻みに身体を震わせる愛おしいヒト。ハヤブサはそんなシュバルツの身体を抱き起こすと、後ろから優しく抱き寄せた。
「すごいな……イキっぱなしじゃないか……」
そう言いながらハヤブサが、シュバルツの頬に流れる涙を優しく拭ってやると――――腕の中で愛おしいヒトの身体がぶるり、と震えた。
「す……済、まない……ハヤブサ……」
「――――!?」
「で……出来なくて………我慢、が………」
「――――ッ!」
ズボッ! と、音を立てて、ハヤブサの指が強引にシュバルツの口の中に入り込んでくる。
「ふぐッ!? んぅ……!」
そのまま彼の指が、シュバルツの口腔を激しく犯し始めた。
「んぐ……! あ…が……! あ……ッ!」
それをしながらハヤブサは、唇を噛みしめていた。
(俺は、お前の身体を弄んでいるのだぞ…? なのに、何故――――謝ったりするんだ!)
このヒトはいつもそうだ。
いつも、いつも――――。
特別な恋愛感情が無くても、俺が蹂躙するようにその身体を抱いたり、殺そうとさえしたりするのを、赦してしまえるヒト。最初にその身体を強引に奪った時からそうだった。とにかく、親愛の情が深すぎる。
どうすればいいのだろう。
愛される『特別』にもなれないのなら、せめて嫌われる『特別』になってしまえればいいのに――――シュバルツは、それすらなかなかさせてもらえそうにない。
ハヤブサも自分で自分の気持ちが分からなくなってくる。一体俺は、シュバルツに好かれたいのか、それとも嫌われてしまいたいのか。
「ん……ちゅ……」
「――――!?」
突如として自分の指先を襲う感覚に、ハヤブサはビクッとなる。見るとシュバルツが、口の中に入れられているハヤブサの指を、舐めたり吸ったりしていた。
「シュバルツ……!」
「ん………」
ハヤブサに声を掛けられても、シュバルツはその行為を止めない。チュッ、チュッ、と、音を立てながら、優しく慈しむように――――ハヤブサの指を愛撫している。彼の閉じられた瞳からは、涙が一筋零れ落ちていた。
(ああ……そう言えば、我慢が出来ないと、言っていたな……)
シュバルツの愛撫を受けながら、ハヤブサは思う。再び張り詰めて来ている、シュバルツの乳首、牡茎――――。求めてしまっているのだろう。身体は。心の方は、俺を求めて居なくとも――――。
そっと、シュバルツの乳首に指を這わせ、そこを優しく擦ってやる。
「んっ! んんぅっ!!」
ビクッ!! と、身体が跳ね、涙が飛び散る。だがシュバルツは、震えながらも咥えているハヤブサの指を、決して離そうとはしなかった。
「ん……ふ……」
胸を弄られながらも、ハヤブサの指を求め、愛撫し続ける蕩けた表情のシュバルツ。
そそられる。
愛しさと嗜虐心が――――。
ああ――――
これが、本当に心から、シュバルツが俺を求めての行為であればいいのに。
分かっている。
これは、媚薬による熱に浮かされて居るが故の行為だ。
真に、俺を求めていると言う訳ではない。
俺ヲ 好キト 言ウ訳デハ 無 イ
シュバルツの口から指を引き抜いてやると、腕の中の愛おしいヒトは「あ………」と、少し淋しげな声を出した。
ハヤブサは、再びシュバルツの乳首と牡茎に指を這わせる。
「あっ!! あああっ!!」
正確に弱い所を責められたシュバルツは、ただ身悶えるしか無く。
「指を舐めてくれた礼だ……。ほら――――イカせてやるよ」
「ああっ!! はあ……ッ! あ…あ……!」
愛撫から逃れようとしているのか、それとも、自ら刺激を求めているのか――――ハヤブサの腕の中で身を反らせ、腰を揺らめかせている愛おしいヒト。どちらにしろその動きは、ハヤブサの愛撫を助長しているに他ならない。
「や……! 駄目っ!! も、う……我慢、が……ッ!」
「そのまま―――果ててしまえばいい」
「ああ……!! ああああ……!!」
ビュル……と、音を立てて、シュバルツはまた、達してしまった。
「―――――ッ」
ガクっと力が抜けるシュバルツの身体を、ハヤブサが優しく支える。
「気持ち良かったか?」
そう言いながら愛おしいヒトの頬を優しく撫でると、その身体がブルッと、震えた。
「あ…あ……駄目、だ……」
「シュバルツ?」
「ま、まだ……身体が、熱くて――――」
そう言って、はあっと、しどけないため息を漏らす愛おしいヒトの牡茎が――――また勃ち上がって来ている。
「すごいな……何回、抜けるんだ?」
そう言って「ククッ」と低く笑うハヤブサの言葉に、「ああ………」と、シュバルツは震えながら頭を振る。
「こんな……! どうして……!」
はっ、はっ、と短い呼吸をしながら、涙を流す愛おしいヒト。
「どうして……我慢、出来な――――」
「……『我慢』が、したいのか?」
「……え……?」
ハヤブサの言葉が咄嗟に理解できない、といった風情で振り返るシュバルツに、ハヤブサは口の端を吊り上げた笑みを見せる。
「させてやろうか? 『我慢』 を」
「え……? あ……」
「ちょっと待っていろ」
トン、と、シュバルツの身体を軽く押して、彼から離れるハヤブサ。シュバルツは彼に押されるままに、布団の上に倒されてしまった。
「ああ………」
震えながら、熱い身体を持てあますしかないシュバルツ。その間にハヤブサは、自身の荷物からある物を取り出してくる。
「シュバルツ」
その身体を抱き起こしながら唇を求めると、シュバルツは素直に応じてきた。
「ん……ふ……」
優しく唇を吸ってやりながら、ハヤブサはシュバルツの牡茎を弄る。
「んんっ!? んぅっ!!」
ビクッ! と、跳ねるシュバルツの身体を抑えつけながら、ハヤブサはシュバルツの牡茎の根元に、「カチッ」と、音を立てて、ある物を取り付けた。それは、シュバルツの牡茎に、締め付けるような鈍い痛みをもたらす。
「んっ! あ……ッ!」
痛みに耐えかね、思わずハヤブサの口付けから逃れてしまうシュバルツ。その様にハヤブサはにやりと笑うと、シュバルツを優しく後ろから抱き締めた。
「シュバルツ、見ろ」
「あ………?」
シュバルツが痛みを感じた自身の牡茎の根元を見ると、そこには金属性のリングの様な物が取り付けられていた。
「これはな……里に古くから伝わる『道具』だよ」
「どう……ぐ……?」
「そう――――ただし、『拷問用』だがな」
「――――!!」
目を見開き、息を飲むシュバルツに、ハヤブサはにやりと笑いかけた。
「言っただろう? 口を割らせる手段は、何も殴る蹴るの苦痛ばかりとは限らない。『快楽』だって、立派な拷問手段になるんだ」
「な…………!」
「今からそれを、たっぷりお前に教えてやるよ。シュバルツ―――」
「あ……! あ………!」
流石に恐怖を感じたのか、身を捩って腕の中から逃げ出そうとする愛おしいヒト。ハヤブサはその身体を優しく捕まえ、抱き寄せた。
「いいか? そのリングには、男性の射精を阻害する働きがある」
チュッ、と、音を立てて耳にキスをしながら、ハヤブサはシュバルツに囁きかける。
「つまりお前は、『イケなくなる』んだ」
「な……! そんな………!」
息を飲むシュバルツから、『怯え』の気配が伝わってくる。
「怯えないで……可愛いヒト……。ちゃんと悦くしてあげるから―――」
そして、堕ちてしまえば いい。
貴方なんか
貴方は、どう足掻いても俺に『心』をくれない。
くれないのだから――――
ならば、せめて
ソノ身体 ダケ デモ 堕トシテ ヤ ル
「まずは…リングがちゃんと機能しているか、確認しないとな……」
そう言いながらハヤブサは、再びシュバルツの乳首と牡茎に、指を這わせる。
「あっ!! ああっ!!」
先程の愛撫よりも激しく、その指はシュバルツを責めてきた。
「さっきみたいに――――イッても良いぞ」
「あ……あ……っ! ああああ………!」
腕の中でその身を反らせ、喘ぐ愛おしいヒト。『媚薬』の効果で熱を持ったその身体を追いこむのは、酷く簡単だった。
「あっ!! 駄目っ!! ああっ!! も……!」
ビクビクビクッと、震える愛おしいヒトの身体。どうやら、達してしまったらしい。
だが――――
「あ………!」
下半身に集まってきた熱が、望む解放を得られず、シュバルツは困惑する。
「ああっ! そんな……ッ!」
張り詰めた海綿体が切なくて、下半身の疼きが痛くて――――シュバルツは知らず腰を揺らめかせてしまう。だがシュバルツがどうその身を捩ろうとも、望む解放は得られるべくも無かった。
「フフ……機能しているようだな」
ハヤブサは、愛おしいヒトのその痴態に満足すると、シュバルツの身体をトン、と前に軽く押してやる。
「あ………」
とさり、と、あっさり前のめりに倒されてしまう、愛おしいヒト。ハヤブサはその腰を捕まえると、指でそこの状態を少し確認した後、己自身をシュバルツの『そこ』にズブ……と、音を立てながら突き入れた。
「ふあッ!! あああああっ!!」
中に入り込んで来る熱い肉棒の感触に、シュバルツは思わず悲鳴を上げる。
「柔らかいな……。もう、とろとろじゃないか……」
ハヤブサは陶然と呟きながら、シュバルツの牡茎のある方へと手を這わせる。それを手の中に包み込む感触を得ると、ハヤブサは優しくそこを擦りだした。
「や……! あ……っ!」
それと同時に、ハヤブサ自身も律動を始める。熱を持ち、蕩け切ってしまっているシュバルツの秘所は、ハヤブサの行為を容易く受け入れてしまっていた。
「ああ……! ああ……!」
ハヤブサの律動は、いつものそれと比べたらはるかに優しい物だった。だが『媚薬』の効果で感度を数倍に高められているシュバルツは、その刺激だけで、簡単に高みへと追い込まれてしまう。
「ああっ!! も……! くう……ッ!!」
ビクビクッ! と、シュバルツの身体が震える。だけど、牡茎の根元を締め付けるリングのせいで、シュバルツは望む解放を得られない。根元に熱い熱がたまって来るばかりで――――切なくて、シュバルツはもう、おかしくなりそうになってしまう。
「ああ……! あ……!」
頭を振り、涙を飛び散らせ、小刻みに震える愛おしいヒト。ハヤブサはその身体を優しく抱きしめてやると、顎を捕らえてこちらを向かせる。そしてその唇を、求めた。
「ふ……んぅ……」
出来得る限り、優しく唇を吸ってやる。このヒトが一刻も早く蕩けて、正気で居られなくなってしまえるように。
「シュバルツ……」
そうして再びその身体を優しくゆすり始める。
「あ……ッ! ああ……! 止め…! 止め、て……!」
「何を言うんだ…。まだまだ、これからだぞ?」
ぬちっ、ぬちっ、と、水音を立てて、シュバルツを犯し続けるハヤブサ。彼の張り詰めた牡茎にそっと手を添えてやると、シュバルツの身体がビクン! と、跳ねた。
「ハヤブサ……! あ……あ……! ハヤブサ……ッ!」
縋る様に名前を呼ばれる。もっとそれが聞きたくて――――愛液に濡れた牡茎を、優しく愛してやった。思わせぶりにリングに触れると、シュバルツから悲鳴が上がった。
「お……お願いだ…! ハヤブサ!! それを取って…! 取ってくれ……!!」
「シュバルツ……」
「く……苦しく、て……も、う………んぅ!」
かわいらしく要求してくる愛おしいヒトに、ハヤブサの嗜虐心が募る。その願いは聞いてあげられないから――――代わりに、その唇を塞いでやった。
まだだ、シュバルツ。
まだ俺は――――満足、していないぞ?
「ん………ッ! は……あ……」
口付けが終わって、力が抜けて行くシュバルツの身体をハヤブサが支える。その頬に優しく唇を落としながら、シュバルツに囁きかけた。
「リングを……はずして欲しいか…?」
ハヤブサの問いかけに、シュバルツはこくこくと頷く。
「は…外してくれ……! お願いだ……!」
ただでさえ、火照ってしまっている身体。その上に、ハヤブサから与えられる刺激で熱が蓄積されて、解放を許されないから――――シュバルツは気が狂いそうになってしまう。
「……全く、可愛いな、お前は……。愛おしいよ……」
「ハヤブサ……!」
ハヤブサは、シュバルツの頬に流れる涙を、そっと唇ですくってやる。
「心配するな…。ちゃんと、外してやるよ。ただし――――」
「………?」
涙に濡れた瞳でこちらを見つめ返してくるシュバルツに、ハヤブサはにやりと笑い返す。
「今からお前が、俺の言うとおりに動いて――――俺を『満足』させてみろ」
「――――!?」
「そうすれば……外してやるよ。『これ』を」
するり、と、ハヤブサにリングを触られ、シュバルツの身体がビクン! と、跳ねる。
「あ………!」
何を要求されるか分からない恐怖はある。だけど、ハヤブサの要求に、今のシュバルツが逆らえるはずもない。
「わ……分かった……」
彼は観念したように――――頷いた。
「いい子だ……」
ハヤブサはシュバルツの頬にチュッと、音を立ててキスをすると、シュバルツの中から己自身をズルッと引き抜いた。
「はあ、んっ!! く…う……っ!」
引き抜かれた瞬間、ビクビクッと震えるシュバルツの身体。彼はまた、達してしまったらしい。だが、シュバルツの牡茎の根元にとりつけられたリングが、彼の『精』の解放を拒む。根元に集められた熱が熱くて、張り詰めた海綿体が痛くて――――シュバルツは身悶えてしまう。
「あ……ああ………!」
布団の上でぴくぴくと震えながら、必死にその感覚に耐えるしかないシュバルツ。ハヤブサはそんなシュバルツからすっと離れると、隣の部屋に移動して、小さな明かりを灯し、座椅子の上に座った。
「さあ……こちらへおいで」
優しく、愛おしいヒトに呼びかけてやる。その呼び掛けに気付いたシュバルツが、「あ…………」と、顔を上げた。
「ん………!」
懸命に身を起こし、立ち上がる。張り詰めて、せき止められている下半身に、ずくずくと甘い痛みが走り、彼が足を一歩踏み出すごとに、切ない疼きが出口を求めて暴れまわって、シュバルツを責め苛んだ。
(ハヤブサ……!)
揺れる視界の向こうに霞むハヤブサの姿を、シュバルツは切ない想いで見つめる。
言葉と態度は優しいのに、どこか冷たさを感じさせるハヤブサ。まだ――――怒っているのだろう。
仕方がないと思う。
自分は、それだけの事を彼にしてしまっているのだから。
だから、どう扱われても、どのような目にあわされても――――ハヤブサに文句を言う気にはなれなかった。総ては自分の責任――――自業自得、なのだから。
ああ ハヤブサ
どうか気づいて。
これ以上――――貴方が私に関わり合っても、私は貴方を消耗させることしか出来ない。
空虚な存在の私は、貴方に何も返せない。
貴方には――――何のメリットも無いんだ。
だから、お願いだ。
この色欲に溺れるみっともない私を好きなように弄んでくれていいから――――
飽きたら、どうか、そのまま打ち捨てて欲しい。
私は、それで構わないんだ。
私は貴方に何かを言う資格はない。
だからもう、この『想い』は、永遠に貴方に届く事はないかもしれないけれど。
ワタシハ 貴方ガ スキダヨ ハヤブサ
スキ ダヨ………
(シュバルツ……!)
帯で後ろ手に縛られているが故に、何も隠す事が出来ず、媚薬で強制的に発情させられているが故に、何もかもを張り詰めさせて、愛液を滴らせながらおぼつかない足取りで、一歩ずつこちらに近づいてくる愛おしいヒト。
酷くあられもない格好をしているはずなのに――――このヒトにはやはり、どことなく誇り高い美しさが漂っている。
何故なのだろう。
もし、その背中に羽が生えていたのだとしても、もう何度もむしり取ってその身体を犯し抜いているはずなのに。
美しいヒト。
そして、恐ろしく孤独なヒト。
やはり、どうしようもなく――――惹かれる。
「…………」
自分に手折られるために傍に来たこの美しいヒトに、ハヤブサは優しく微笑みかける。
「さあ、おいで」
手を差し伸べる。
おいで。
傍においで。
優しく―――――狂わせて、あげるから。
「俺の上に跨って……膝を立てて、座って」
ハヤブサに言われたとおりの姿勢になるシュバルツ。
「そのまま、口付けを――――」
「分かった……」
前屈みになって、シュバルツはハヤブサに自ら顔を近づけて行く。
「ん………」
シュバルツからハヤブサに、差し入れられる――――舌。
「ん……う……」
ちゅっ、ちゅっ、と、互いの唾液が混じり合う水音が響く。ハヤブサはシュバルツからの口付けを堪能しながら、自らの手を、そっとシュバルツの牡茎にあてがった。
「んうっ!?」
感じる所にあてがわれた手の感触に、シュバルツの身体がビクン! と、跳ねる。だがハヤブサのその手は――――あてがわれるだけで、そこから動こうとしなかった。
「ん………!」
張り詰めた海綿体は刺激を求め、根元に溜まる熱は解放を求めて疼いている。なのに、ハヤブサの手はそこから動いてくれそうにないから――――シュバルツは焦れてしまう。知らず、彼の腰がピクリ、と動いてしまった。
それと同時に、すり……と、ハヤブサの手に、擦りつけられる格好になってしまうシュバルツの牡茎。
「んっ!!」
そこから甘い電流の様な刺激が、シュバルツの身体を走り抜ける。
その刺激が――――気持ち良すぎて。
焦れる身体が、それを我慢、できなくなって――――。
「ん……! んぅ……」
気がつけばシュバルツの腰が、勝手に揺らめいてしまっていた。すり……すり……と、シュバルツの牡茎が、ハヤブサの手に擦りつけられていく。
(だ……駄目、だ……! こんな、事を…しては……!)
シュバルツの僅かに残る理性が、懸命に腰の動きを止めろと訴える。だけど、彼の腰の動きは、シュバルツの想いとは裏腹に、勝手に大きくなっていくばかりで。
「んっ、ん…っ! ん…う……!」
牡茎から溢れる愛液が、いつしかハヤブサの手をぐっしょりと濡らす。それが牡茎の滑りを良くしてしまって、腰の動きがますます止められなくなってしまう。彼の腰が動くたびに、ぬちゅ、ぬちゅ、と濡れた水音が辺りに響いていた。
「ふ……んぅ……」
懸命に自分の口を吸いながら、妖しく腰を揺らめかせているシュバルツ。その淫らで可愛らしい彼の姿に、ハヤブサはほくそ笑む。そろそろ頃合いか、と、彼の牡茎にあてがっていた手でキュッ、とそこを握ってやれば、シュバルツの身体がビクン! と、跳ねた。
「あっ!!」
短く叫んで、思わずハヤブサへの口付けを途切れさせてしまうシュバルツ。それを見たハヤブサが、にこりと優しく微笑んだ。
「駄目じゃないか、シュバルツ……。まだ俺が『キスを止めて良い』って、言っていないのに……」
「あ………!」
ビクッ! と、申し訳なさそうに強張る愛おしいヒトの顔に、ハヤブサは苦笑してしまう。どうして――――お前はそんなに素直で、人がいいんだ。今の一連の流れ、お前の方に落ち度などないだろうに。
「す、済まな……!」
「詫びなど要らないよ」
シュバルツが謝ろうとするのを、ハヤブサはやんわりと止める。
「その代わり……『悪い』と思っているのならば、そのまま腰を動かし続けてくれるか…?」
「えっ……?」
一瞬何を言われたのか理解できずに固まるシュバルツに、ハヤブサはもう一度要求する。
「ほら……さっき、キスをしていた時みたいに」
「あ………!」
ハヤブサの要求の意味をようやく理解して、シュバルツの顔色が変わる。つまりハヤブサは、彼の手を使ってシュバルツに自慰をしろと言っているのだ。
「そ、そんな……! む、無理……!」
「無理じゃないだろうシュバルツ。さっき、あんなに自分で腰を動かしていたのに――――」
「あっ……!」
ハヤブサに指摘されて、シュバルツの顔色がカッと朱に染まる。それを見たハヤブサがにこりと優しく笑った。
「ほら……もう一度――――俺にその姿を、よく…見せて?」
「う……う………」
「ほら……シュバルツ―――」
言いながらそこを握っているハヤブサの手が、するっと動く。
「あっ!!」
「動けないなら……手伝ってやろうか? ほら……こんなに、濡らして――――」
そう言いながらハヤブサの手が、シュバルツの牡茎を優しく愛し始める。やわやわと鬼頭を包み込まれるように撫でられた。
「あ……! や……! あ…あ……!」
その優しい刺激に、今のシュバルツが耐えられるはずもない。媚薬で強制的に火照らされている身体は、ハヤブサの愛撫にあっさり陥落してしまう。
「う……! あ………」
再び揺らめき始める、シュバルツの腰。ぬちゅぬちゅと音を立てて、ハヤブサの手に彼の牡茎が擦りつけられ始めた。
「は……あ…あ……! ああ……!」
「そう―――いいぞ……その調子だ…。もっと、上体を反らして――――」
「あ……あ………」
「俺によく見えるように……そのまま、自分の悦いように、動いて―――」
「ふ……あっ! ああ……ッ!」
自分の、どうしようもない痴態をハヤブサに曝してしまっている――――嫌でもそう自覚させられてしまうシュバルツは、恥ずかしくてたまらない。止めたいのに、やめたいのに――――快感を求めて火照る身体は、彼の想いとは裏腹に、腰の動きを止めるどころか、どんどん勝手に加速していくばかりで。
「ああ……! ああ……! 駄…目っ! 駄目、だ……!」
「駄目なものか。そんなに、腰を動かしておいて―――」
「ち、違……! ああっ!! や、あ……!」
「フフ……可愛いな……。お前は……」
「ぅあ……! あっ! ああっ!! あああ…ッ!!」
煽られる熱。激しくなる腰の動き―――。
涙を飛び散らせて頭を振るのに、シュバルツは、もう自分で自分の動きが止められない。
根元に、また解放を求める熱がたまって来ている。「イキたい」と、身体が要求してくる。
でも――――イケない。
イケない。
(どうして……! 苦しい――――!)
「あ……! 無理…ッ! も……!」
あと少しで上り詰めてしまう――――その瞬間、いきなりハヤブサに手を離された。
「あっ!! ああ……! 何で……ッ!!」
思わず抗議の声を上げ、身を捩ってしまうシュバルツ。その愛おしいヒトの痴態にハヤブサはにやりと笑うと、怒張し切った己自身を、シュバルツの秘所にピタリとあてがった。
「あ………!」
「ここまでくれば……分かるよな……?」
ハヤブサの要求を悟ったシュバルツは、がくがくと震えだしてしまう。あともう少しで上り詰めてしまう身体。そんな状態で、ハヤブサを受け入れてしまったら、間違いなく達してしまう。
せき止められて、せき止められて、せき止められて――――苦しいのに、これ以上我慢できる自信が無かった。
「ハ、ハヤブサ……! リングを……!」
シュバルツは、自分の牡茎に嵌められているリングを、強く意識する。
「リングを……外して…くれ……!」
「何を言っているんだ。まだだ」
ハヤブサは、シュバルツの願いを一刀両断にする。
「俺は、まだ『満足』していないぞ? シュバルツ」
「あ…………!」
冷たく言い放たれるハヤブサの言葉に、シュバルツは茫然としてしまう。
でも、確かにそうなのだ。ハヤブサは、この行為に及んでから今まで、一度も『達して』いない。自分は、もう何度も何度も達して、果てているのに。
(ハ、ハヤブサを……『満足』させて、あげないと……)
震える心と、身体で思う。
自分は、ハヤブサに『ココロ』を渡してあげられないから――――せめて、『身体』だけでも、彼に捧げつくして……『満足』して、もらわないと……。
「……………」
観念したように瞳を閉じ、唇を噛みしめるシュバルツの頬に、涙が流れ落ちる。何とも美しくて――――そそられる姿だと、ハヤブサは思った。
「さあ、そのまま腰を落とせ」
シュバルツに命じる。冷徹に。
美しくて、可愛らしくて、どうしようもない程愛おしくて――――でも、その『ココロ』は誰の物にもならない、つれないヒト。
貴方なんて――――快感の中に溺れて、そのまま狂ってしまえば、いい。
そしてその果てに、どのような貴方が出てこようとも――――
俺ハ、ソノ『貴方』ヲ、愛ス カ ラ。
「さあ、シュバルツ――――」
ハヤブサに再度急かされて、シュバルツは震えながらも動き出す。
「う…………ッ!」
ハヤブサの起立した肉棒の上に、ゆっくりと落とされて行くシュバルツの身体。ズブ……と、音を立てて、シュバルツの『秘所』が、ハヤブサのそれを受け入れ始めた。
「は……う………ッ!」
腰を落として行くシュバルツの身体が、ぴくぴくと震える。
「挿入るだろう? お前の『そこ』は、もう蕩けてしまっているのだから―――」
「ん……っ! く………!」
ズブズブ、と、ハヤブサの肉棒が、シュバルツの内側(なか)深くに侵入してくる。
「は……あ……ッ!」
(ダメだ……これ以上は――――!)
これ以上彼を受け入れたら、自分は間違いなく果ててしまう――――そう感じたシュバルツの動きが、止まってしまった。果てたいのに、ハヤブサに嵌められたリングのせいで果てる事が出来ない。苦しくて苦しくて、もう気が狂ってしまいそうだった。
だが当然、シュバルツの動きが止まるのを、ハヤブサが許すはずも無く。
「駄目だな、シュバルツ……。ちゃんと腰を落としてくれないと――――」
ズクン! と、シュバルツの『そこ』を刺すように、ハヤブサの腰が動いた。
「あっ……!」
たったそれだけの動きで、シュバルツの『そこ』は、ハヤブサを最奥まで受け入れてしまう。
「あ…あ……! あああああ―――――ッ!!!」
腰から脳天にかけて、快感の波が一気に走りぬけて行く。シュバルツは絶頂へと、導かれてしまった。
なのに
イケない。
イケない。
果てれない。
どうして――――!?
「ああっ!! や……も……!!」
根元に溜まる熱が、シュバルツを責め苛む。
身を捩る。
腰を揺らす。
イキたい。
イキたい。
イキたいのに――――!
「シュバルツ……シュバルツ……」
ハヤブサは、悶え苦しむシュバルツの身体を、そっと優しく抱きしめた。そのまま優しく、乳首を擦ってやる。
「はあん!! ああんっ!!」
ビクビクッ! と、過剰に反応する愛おしいヒト。
「可愛い……シュバルツ。そのまま、動いて……?」
「はあっ!! ああっ!!」
「ほら……俺を『満足』させてくれるんだろう……?」
「あっ!! ああっ!! ああああ……!」
う、動かないと。
ハヤブサを、満足、させて、あげない、と。
ああ、でも、擦らないで。
そんな所を、擦らないで。
「俺は手を動かしてなどいないぞ……? お前が自分で擦りつけているんだ」
そんな……!
ああ……苦しい……!
奥に……当たって……!
「そこが好きなんだろう? もっと――――掻き回すように、動いて……?」
駄目……! も……!
リング、が…イタイ……!
苦しい……!
イタイ……!
苦しい――――!
「分かるだろう? 『それ』が、『拷問道具』だという意味が」
分からない……!
そんなの――――分からな…い……!
とにかく、苦しい……!
苦しい――――!!
ハヤブサ……!
タスケテ ハヤブサ
ズボッ! と、音を立ててシュバルツの口の中に、ハヤブサの指が突っ込まれる。
「ほら……これを、吸って――――」
「んっ!! んんっ!! ん…ぅ…!!」
ハヤブサに命じられるままに彼の指を吸い、腰を動かし続けるシュバルツ。ズチュッ、ズチュッ、と、秘所と肉棒の擦れ合う音が辺りに響き続ける。
「うぐ…! んうっ!! んあああっ!!」
叫び声と共にシュバルツの身体がビクビクッ! と、震え、ハヤブサにまた彼が絶頂を迎えた事を知らせた。だがそれは、望む解放を得られない、絶頂だった。
「か……は……ッ!」
ぶるぶると震えながら、止まってしまうシュバルツの身体。
(もう、そろそろ頃合いか……?)
そんなシュバルツの様子を見ながら、ハヤブサは思う。
この『拷問道具』の使用限界時間は半刻と伝え聞いている。それを過ぎると、拷問を受ける囚人の方に、いろいろと支障をきたしてしまう恐れがあるからだ。下手をしたら、死ぬ可能性だってある。
シュバルツは不死だ。だが、不死だからこそ――――ぎりぎりの配慮は、怠ってはいけないと思う。自分は、シュバルツを苦痛の中で壊したいのではない。快楽の中に溺れさせてやりたいのだから。
これ以上この責めを続けるかどうか、見極めなければならないと、思った。
(ア………!)
何もかもがホワイトアウトした真っ白な世界で、シュバルツは1人、思う。
ここは、どこだ?
私は――――何を、していたんだ……?
不意に、体内にハヤブサの肉棒の存在を感じ取る。
「あ………!」
そうだった……。ハヤブサ……。
私は、ハヤブサを『満足』させてあげないといけない……。
まだ、固い ハヤブサの 肉棒
まだ まだ
ハヤブサは、 『満足』 して いない
だから、 動かない、 と
「う…………」
動、け……。
動……け………!
シュバルツは、強く己に命じる。『動かす』ために、下半身に力を、入れた。
「あっ……! あ……!」
僅かに擦れるその衝動で、シュバルツはまた果てそうになってしまう。
だが、せき止められ続ける下半身の熱。それは、甘い痛みと切ない疼きを伴ってシュバルツを責め苛む。容赦なくたまり続けるそれは――――もう彼に、限界を訴えていた。
イタイ……!
苦しい……!
イタイ……!
イタイ―――――!
でも
ハヤブサ
ハヤブサ
ハヤブサが……
まだ――――
「……うっ! く………!」
ぬちっ、と、音を立てて、シュバルツの身体が動き出す。
「シュバルツ!?」
驚き、息を飲むハヤブサの目の前で、シュバルツの腰が、ゆっくりとだが、また揺らめき始めた。
「あ……! は……! あ、あ……」
「シュバルツ……? お前……?」
「だ……駄目…だ……。ハヤブサ……が……」
聞き取れないほどの小さな声で、シュバルツが、呟く。
「……? 俺が……何だ?」
「ハ……ハヤブサが……まだ……『満足』……して、いない……」
「――――!?」
「う……動か……ないと……。あ……! 動かな、いと……!」
「シュバルツ――――!」
絶句するハヤブサの目の前で、苦しそうに頭を振りながら、涙を飛び散らせながら――――それでも、シュバルツは。
「あ……! ハヤブサ……! ハヤブサ……ッ!」
健気にも、『動こう』と、するから――――
「馬鹿っ!! どうして――――!!」
ハヤブサは思わず、シュバルツの身体を押し倒して、いた。
馬鹿だろう。
馬鹿だろう、こいつは。
どうして――――そんなに俺に、尽くそうとするんだ……!?
俺は、お前の身体を苛めて、弄んでいるのというのに
どうして――――お前は……!
「シュバルツ……ッ!」
シュバルツの入り口を求め、繋がる。
出来得る限りの優しさで、そこをゆすった。想いを込めて、優しく、優しく――――
「ああっ! あ……!」
身体の下で可愛らしく喘ぐ、美しいヒト。愛おしさが、溢れた―――から。
思わずその唇を、優しく塞いでいた。
「ん…………」
シュバルツの身体から力が抜け、優しく蕩けて行くのが分かった。唇を離してシュバルツの頬を撫でると、涙で潤んだシュバルツの瞳と、視線が合う。
「ハヤブサ……」
「シュバルツ……」
優しく呼び掛けると、シュバルツは、その瞳からポロポロと大粒の涙を零し始めた。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
拭っても拭っても、溢れる涙。
「も……! イキたい……イキたい……!」
堪え切れずに、溢れだしてくる、言葉。
「イキたい……! イキたい……! イキたいんだ、ハヤブサ……!」
「シュバルツ……!」
「もう――――イカせてくれ!! ハヤブサぁッ!!」
「…………!」
自分の身体を満たすための、強い願い。強い要求。
初めて――――シュバルツから、それが聞けた様な気がする。
嬉しさと――――愛しさが、こみ上げた。
「分かった……」
ハヤブサはシュバルツの頬に流れる涙を唇で掬い取りながら、彼の牡茎に取り付けてあったリングを、カチッ、と、音を立てて取り外した。
「あ…………」
柔らかい吐息を洩らす愛おしいヒトに、ハヤブサはそっと囁きかける。
「もう――――いつでも、イッていいぞ……?」
そう言いながらハヤブサは、再びシュバルツの身体を、優しくゆすり始めた。
「あ……! ああ……! ああ……!」
繋がるその場所から、優しく甘い衝動が駆け上がって来る。揺れる上半身に、ハヤブサの唇が降って来る。
――――愛シテイル
その想いと共に、チュッ、と、吸われる身体。降り注ぐ優しさに、我慢、出来なくなってしまって――――。
「はあっ! あ……あ……! も……!」
ドプドプッ! と、音を立てて、シュバルツは果ててしまった。熱と痛みから解放された身体から、ふわ……と、力が抜けて行く。
「シュバルツ……」
繋がったままその唇を求めると、シュバルツも優しく受け入れてくれた。
「ん…………」
互いに舌を絡め合い、優しく吸い合う。それをしながらハヤブサは、シュバルツと繋がっている場所を意識した。まだ硬い自分の牡茎――――シュバルツの中で果てたいと、願った。
だから――――
キスをしながらハヤブサは、シュバルツへの律動を再開させてしまう。
「んうっ!?」
再びもたらされ始めた甘い刺激に、愛おしいヒトの身体がビクビクッ! と、跳ねた。
「んんっ!! んうっ!! んうっ!!」
腹の下で過剰に反応して乱れる、愛おしいヒトの身体。可愛い、と、思う一方で、ハヤブサは少し心配になる。もしかしてもう、「やめて欲しい」と、思われていたりはしないだろうか。現にシュバルツの方は、もう何回も果てている訳だし。散々俺に、弄ばれている訳だし。
「……………」
ハヤブサは動きを止めて、少しシュバルツの様子を見る事にした。
「あ……! ああ……!」
すると、小刻みに震えだす、シュバルツの身体。
「嫌だ……! どうして――――」
「シュバルツ……!」
嫌がる様に頭を振るシュバルツに、覚悟していたとはいえ――――少なからずショックを受けるハヤブサ。
(やはり、やり過ぎてしまったか……)
そう思って、シュバルツから離れようとした、刹那。
「嫌だ…ッ! 離れないで…! 離れないで…ッ! ハヤブサ……!」
(えっ――――!?)
何か、信じ難い言葉を聞いた様な気がして、ハヤブサの頭の中が、知らず真っ白になってしまう。
固まって、見返すハヤブサに、シュバルツの信じ難い言葉はなおも続いた。
「お願いだ……! もっと……! もっと挿入(はい)って来て…! 奥、に――――」
「お、奥……? こう、か……?」
シュバルツにねだられるままに、楔を奥に突きいれるハヤブサ。
「はああああん!!」
望む刺激を得られたのか――――愛おしいヒトの身体がビクン、と、跳ねた。
「ああっ!! そこ…ッ!! そこ……が!!」
「気持ち良いの、か……?」
律動を再開させながら問うハヤブサに、シュバルツはこくん、と頷いた。
「気持ちいい……! あ……あ……!」
はあっ、と切ない息を吐きながら、身を捩るシュバルツ。
「ああ……! もっと……! もっと……ッ!」
焦点の合っていない瞳で、うっとりと、うわ言の様に『おねだり』される。シュバルツは今、完全に快楽に押し流されて、正気を失ってしまっているのだと、ハヤブサは悟った。
「やめないで……! お願い…! もっと……!」
(シュバルツ――――!)
ハヤブサは、万感の思いでシュバルツを見つめる。
酷く淫らで 可愛らしい 愛おしいヒトの 姿。
こんなシュバルツに、会えるだなんて――――。
いいだろう。
お前の望むままに
『快楽』を、与えてやる。
絶対に、正気になんて
返してやらない――――。
ハヤブサは、シュバルツが「気持ちがいい」と言った所をめがけて、楔を打ち込む。それをしながらシュバルツの『感じる所』を、優しく撫でてやる。
もう、何度も何度も抱いた、シュバルツの、身体。
弱い所は、知りつくしていた。
「あ……! ああ……ッ! イイ……!」
「そこ……! そこ……! もっと……!」
「もっと、擦って……! 止めないで……!」
止まらない――――淫らで、素直な要求。
ハヤブサは全力で、それを満たすためだけに、動いた。
(絶対に……自分の『正気』を、飛ばすな――――!)
ハヤブサは、己に強く言い聞かせる。
どんなに淫らな愛おしいヒトの痴態を見せつけられようとも。
どんなに己自身を甘く締めつけられようとも。
絶対に――――己の『理性』を飛ばしてはならない。
それをやってしまったら、シュバルツの身体がどうなるか。
あの、痣だらけになった、痛々しい彼の姿を思い出せ。
絶対に、もう二度と――――彼を、あんな目に遭わせてはならないのだ。
今、シュバルツは―――『媚薬』の力で、酷く感じやすくなっている。
だから、僅かな動きと僅かな刺激だけで、充分、正気には返って来られない。
落ちついて――――彼の弱い所と感じる所を、やり過ぎないように、責めればいい。
それに、もしかしたら――――シュバルツを抱くのは、これが本当に『最後』になるかもしれない……。
ハヤブサは思う。
ここに至るまでの過程で、自分はシュバルツにかなり酷い事をした。そう自覚がある。彼が正気に戻ったら――――今度こそ、赦してもらえないかもしれない。
て言うか、これで許されたら――――逆に、おかしい。シュバルツの『正気』を、疑ってしまいそうだ。
だからなおさら―――ハヤブサは、シュバルツの身体を優しく愛した。
溺れさせて、溺れさせて、溺れさせて――――
シュバルツが正気に戻った後も、無意識のうちに、俺を求めてしまうようになってしまえば、いいと、願う。
「あああっ!! ああ……ッ!!」
ビクビクッ! と、愛おしいヒトの身体が仰け反り、震え、また『精』が放たれる。もう何度、彼は果てたか分からない。なのに、シュバルツのとろんとした瞳からは、正気に戻る気配が感じられなかった。
「ああ…! やあ……! もっとぉ……!」
しどけなく身を捩りながら、『おねだり』される。
(底無しだな……)
そう感じて、ハヤブサは苦笑する。
こんな淫乱なシュバルツ―――――悪くはない。いや、むしろ大歓迎だ。
そんな風に――――俺が『した』のだから。
「しょうがないヒトだな……」
そう呟きながらハヤブサは、またシュバルツの身体を優しくゆすり始める。
「あっ! ああっ!!」
また嬉しそうに喘ぎ始める、愛おしいヒト。至福の一時だった。
「あ……! キスを……! キスをして……!」
もう何度されたか分からない、キスのおねだり。ハヤブサはそれを叶える。何度でも、何度でも――――。
「ふ…………んう……」
要求が満たされた愛おしいヒトの秘所が、甘く蠢く。
(…………ッ!)
持って行かれそうになる理性を、懸命に踏みとどまらせる。このヒトを満たしきらないうちは、自分が理性を飛ばす訳にはいかないのだ。
「ん………」
舌を深く差し入れ、シュバルツとのキスに没頭する。シュバルツの方も、積極的に舌を絡めて来てくれる。このヒトはもしかしなくても、キスをするのが相当好きなのではないかと、思う。
嬉しい。
俺とのキスを、『好きだ』と思ってくれているのなら――――。
「シュバルツ……」
愛しさが溢れる。思わずその身体を、抱きしめた。
「ハヤ……ブサ……」
掠れた声で、名を呼ばれる。腕の中でその身体が、もぞ、と、動いたかと思うと。
「…………」
シュバルツから自身の耳に、チュッ、と、音を立てて、キスをされた。
「――――ッ!」
予想だにしなかった刺激に、思わずハヤブサの身体がビクッと跳ねる。
「シュ、シュバルツ!?」
思わず身を起してシュバルツを見つめると、淋しそうな瞳をした愛おしいヒトと、視線が合った。
「嫌だ……! 離れないで……! ハヤブサ……」
「う………!」
その懇願に、ハヤブサが抗えるはずもない。再び彼はシュバルツの身体に自身の身体を密着させる。すると。
「ん……ちゅ……」
再びシュバルツがハヤブサの耳に、『愛撫』を始める。彼はハヤブサの耳に舌を伸ばして口に含み、そこを吸ったり舐めたりしていた。
「う……く……ッ!」
(まずい……! 気持ち…良すぎる……ッ!)
愛おしいヒトからの思いもかけない行為に、どうしてもハヤブサの身体が『感じて』しまう。理性が持って行かれそうになってしまって、ハヤブサは焦った。
「シュバルツ……!」
咄嗟に、シュバルツの胸に手を這わせる。胸の頂を優しく転がしてやると、「あっ!!」と叫んだ愛おしいヒトの唇が、ようやく耳から離れた。そのまま乳首を指で優しく愛してやると、シュバルツの身体が、跳ねて乱れる。
「あ……! ああ……! ん、ん……ッ!」
「気持ち良いか…? シュバルツ……」
「ああん……気持ちいい……ハヤブサぁ……」
自分の指で、蕩けて行くシュバルツ。たまらなく可愛らしくて、愛おしかった。
「シュバルツ、愛している……」
思わず愛の言葉を囁いてしまう。もっと乱れて欲しくて、両方の指の腹で、シュバルツの胸を愛した。
「ああっ!! ハヤブサッ!! あ、あ……ッ!」
「シュバルツ……」
「あ…! ハヤブサッ!! ハヤブサぁ!!」
腹の下で弓なりにしなる、愛おしいヒトの身体。
(また、果てるのだろうか)
そう思いながらもハヤブサは、愛撫の手を止めない。果てるのなら、いくらでも果てればいい。俺は――――お前を満たしきる、だけだから。
胸を愛しながら、シュバルツの身体を優しくゆすり続ける。
「んあっ!! ああっ!! あ……!」
「ほら……また――――イってしまえばいい」
「ハヤブサ……ッ! あ……! も……!」
ビュル……と、シュバルツから『精』が放たれると同時に、『その言葉』が、彼の口から漏れた。
「好……き……! ハヤブサ……!」
(えっ…………?)
ぺシャッ、と、音を立てて、シュバルツの精が自分の腹にかかる。だが、そんな事にすら気づかないほど――――ハヤブサは茫然としていた。
何だ……?
え………?
今、何か……とんでもない言葉を、聞いた……ような……?
ハヤブサは、今何を言われたのか確かめたくて、思わずシュバルツに問いかけてしまう。
「シュバルツ……?」
「ああ……ん………」
「シュバルツ? 今――――何て言った? もう一度……」
「あ、熱い……! 嫌だ……。止まらないで……ハヤブサ……!」
焦れておねだりしてくるシュバルツに、ハヤブサは慌てた。
「あ……ああ、悪い……」
慌てて、律動を再開させる。優しくその身体をゆすってやると、シュバルツは再びふにゃ、と、蕩けた表情になった。
「あ……! ああ……! 気持ちいい……!」
「シュバルツ……? 今――――」
「ああ……! ああ……!」
(会話がかみ合わない……。当たり前か……)
完全に理性が飛んで、蕩けてしまっている愛おしいヒトの今の状態を見ると、会話が出来ないのは仕方がないことだと思う。
でも、ハヤブサは、少し切なかった。
今シュバルツの口から漏れたかもしれない、夢のような言葉を――――もう一度、聞きたかったのに。
(でも……有り得ないよな…。まさかそんな……)
だって、シュバルツの唇は今、『好き』と、動いた。
(俺の事を『好き』……? 違うだろ)
強引にその身体を奪ってから、彼が強く断れない優しさを持っている事につけ込んで、散々求めて――――搾取して、お前を欲望のはけ口にしてしまった俺。
今だってそうだ。
自分の弱さに負けて、八つ当たって、『媚薬』で強制的にその身体を火照らして、弄んで、蕩けさせているにすぎない。彼が自ら望んで、そうなった訳ではないのだから。
(きっと、都合のいい『幻聴』を聞いたんだ)
ハヤブサは、そう結論付ける事にした。
そう、きっと、当てられたんだ。媚薬で乱れる彼の痴態に。
願望が高じて、幻聴を聞いてしまったんだ。
あり得ないだろう。まさかそんな――――
「ハヤブサ……ハヤブサ……!」
縋る様に名前を呼ばれて、ハヤブサははっと我に返る。
「あ、ああ……どうした? シュバルツ……」
優しく律動をしながら、ハヤブサは問い返した。
「キスを……! キス、して……!」
「分かった……」
優しく唇を塞いでやる。今はとにかく、シュバルツを快楽の中に溺れさせ続ける事に没頭しなければ、と、思った。
キスをしながら乳首を指の腹で優しく転がしてやる。
「ん、んんっ! ん……う……!」
腹の下でシュバルツの身体がビクッと跳ね、その腰が揺らめく。まだ―――貪欲に求められているのだと、悟った。
「シュバルツ……」
繋がったまま、身体のあちこちに、優しくキスを落とし続ける。完全に蕩けて乱れ続けるシュバルツが、とても綺麗で――――愛おしかった。
もっともっと、そんな彼を見ていたい。
もっと、もっと――――
「ああ、あ………ハヤブサ……!」
切ない声で、名前を呼ばれる。
もっと、呼んで。
俺の名前を……
「あ……好き……! ハヤブサ……!」
(――――!?)
また、あり得ない単語を聞いた様な気がして、ハヤブサの動きが止まる。
(いやいや、無いだろう!? 何を聞いているんだ俺は!! シュバルツが、そんな)
「愛、してる……! ハヤブサ……!」
(――――!? ――――!? ――――!? ――――!?)
何か、絶対に聞けないはずの言葉の羅列を聞いた様な気がして、ハヤブサの頭の中が知らず真っ白になってしまう。
「いや……! ちょ……っ! シュバルツ……! おま……!」
「抱いて…! 抱きしめて!! ハヤブサ…!!」
「……………!」
「強く…! もっと強く…! お願い……!!」
「強く……こう、か……?」
ギュッ、と、シュバルツの身体を強く抱きしめてやる。すると、腕の中で愛おしいヒトが、はぁっ、としどけなくため息をついた。
「あ……! もっと、挿入(はい)って来て…! 深く―――」
シュバルツに乞われるままに、挿入をグッと深めてやる。
(…………ッ!)
自身への締め付けが甘く強くなり、酷く気持ちが良かった。本能のままに激しく律動したくなる己を、ハヤブサは懸命に抑える。
「………これで、いいのか…?」
シュバルツに問いかけるが、自身の声も呼吸も――――震えてしまうのを止める事が出来ない。そんなハヤブサの腕の中で、シュバルツもまた、しどけないため息をついていた。
「は……あ……。気持ちいい……」
うっとりと、呟かれる。
「……動いて……」
(………シュバルツ…!)
乞われるままに、律動を始める。熱くて気持ちがいいシュバルツの内側(なか)。自分の理性が持って行かれないように、ハヤブサは細心の注意を払わなければならなかった。
「ああっ!! ああっ!!」
腕の中で艶っぽい嬌声を上げるシュバルツ。愛しさが溢れた。彼を抱きしめる腕に、知らず力が入ってしまう。
「ハヤブサ…!! あ……! あ……!!」
「シュバルツ……!」
その時、愛おしいヒトの口からまた『その言葉』が漏れた。
「……愛してる……!」
「…………!」
驚き息を飲むハヤブサの耳元で、『その言葉』はなおも続いた。
「愛してる……! 愛してる……! 愛しているんだ、ハヤブサ……!」
「シュ、バ、ルツ……!」
「離さないで!! 離れないで…! ハヤブサ……!」
「シュバルツ……! お前……!」
「ああ……でも、ダメ……!」
「……………?」
ハヤブサの腕の中で優しく体をゆすられながら、シュバルツの独白はなおも続く。
「駄目だ……! こんな事……言っては、駄目だ……! 私は、アンドロイド、で……!」
「―――――!」
「DG細胞で……! 歪で……! ああ…! 邪魔に、なる……! 共に、生きれ、な……!」
「な…………!」
「好き……! ハヤブサ……! 愛してる……!」
「―――――ッ!!」
「幸せに、なって……! 幸せに……! 愛してる……! ハ、ヤ―――んぅ!」
思わずハヤブサは、シュバルツの唇を塞いでいた。
もう充分だった。充分すぎた。シュバルツの、気持ちを聞くのは――――。
(シュバルツ……! シュバルツ…! シュバルツ…ッ!)
無我夢中で口腔を弄る。その身体を強く抱きしめ、深く穿った。優しくなんて――――してやる余裕が無くなってしまった。
「んんっ!! んぐ…! んううっ!!」
口を塞がれたシュバルツから、くぐもった悲鳴にも似た嬌声が上がっている。優しくしてやらなければ、と、ハヤブサは思うが、どうにも自分が止められなかった。
(馬鹿だ……! 馬鹿だろ……!)
深く穿ちながらハヤブサは思う。
言わない、つもりだったのか?
お前は、俺に
『その言葉』を――――
愛している、ハヤブサ……
私は、アンドロイドで……
歪で……
共に、生きれな……
(……………ッ!)
どうして……! 何故……!
シュバルツ、お前は……!
何時からだ?
何時から、お前は………俺の事を―――――!
どう考えても、それは分からない。
だが――――シュバルツが自分の事を『好き』と考えると、ハヤブサの中でシュバルツの行動の辻褄の総てが合ってしまう。
『好き』だから、拒めなかった。
『好き』だから、総てを赦した。
『好き』だから、俺がDG細胞の脅威に巻き込まれる事を、恐れて。
『好き』だから、赦し続ける事を、悩んで。
『好き』だから、俺の幸せを、望んで。
歪すぎる自分は、その隣に、居てはいけないと、思って。
『好き』だから、そうと伝えられなくなって。
『好き』だから、その想いを、封じ込めようとして――――
『好き』だから
『好き』だから……
『好き』だから―――
(馬鹿だ……! 馬鹿だ……ッ!!)
こいつも相当馬鹿だと思うが、俺も相当馬鹿だ。
何故気付かなかった?
何故、気づく事が出来なかったんだ。
俺はこんなにも深く――――シュバルツに愛されていたのに。
思えばシュバルツは、いつも赦してくれていた。それこそ、『報酬』になる以前から――――。
俺がどんなふうに抱こうとも、どんなふうに穿とうとも。
抱き終わった後、『やり過ぎた』と、思っている俺に、シュバルツは。
「しょうがない奴だな」
そう、いつも笑って。
「お前が良いのなら、いいよ」
そう言って、赦してくれていた。
――――大好きなお前が満足したのなら、私はそれでいいよ……。
あれは、そう言ってくれていたのだ。
いつも、俺に多くを望まなかったシュバルツ。
どうして望んでくれないのだろう、と、俺はいつも思っていた。
本人の慎ましやかな性格が、『望む』と言う行為をさせないのか。
身体の『歪さ』がそれを拒んだのか――――。
それも確かにあるだろう。
でも、それだけではなかった。
必要なかったのだ。彼には。
『好きだ』と言う気持ちを、とっくに俺に預けていた彼は――――もう、満たされていたのだから。
だけど、自身の身体の歪さと、蝕む『闇』の根深さゆえに――――彼は、俺に『好きだ』と言う気持ちを伝えられない。
(…………ッ!)
ハヤブサは、忸怩たる思いだった。
馬鹿だろう、俺は。
ここまで分かっていて―――――!
言えないんだ。
シュバルツは。
『好きだ』と―――――!
言えないから、シュバルツは。
己の心を俺に預けて、封じ込める選択をしてしまった。だから、俺の目に映るシュバルツからは、彼の心を見つける事が出来ない。
俺は必死に探してしまう。彼の『心』を――――。
でも、見つからない。当たり前だ。
彼の『心』はもう――――俺にぴったりと寄り添っていたのだから。
それに気づかない俺は、必死にシュバルツの心を探して、求めて――――。
勝手に振り回されて、傷ついて、八つ当たって――――。
お前を、そんなになるまで追いこんでしまった。
なのにお前は、そんな俺を赦して……。赦し続けて――――
『好き』だから。
お前の事が、好きだから……。
そう言えない彼は、態度で俺に『好きだ』と、示し続けるしかなかった。
伝えられ続ける、シュバルツの『好きだ』と言う意志。
俺はそれに、気づかなければならなかったのに……!
どうして気付けなかった?
どうして
どうして――――!
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
いつしかハヤブサは、涙を流しながらシュバルツを抱きしめていた。身体が震え、嗚咽が漏れた。だが――――どうしてそれを、堪える事が出来るだろうか。
こんなにも愛おしいヒトから、こんなにも深く愛されていたのに。
「あ……あ……! ハヤブサ……ッ!」
腕の中でシュバルツが身じろぎをする。何かを求めるような動きだった。
キスをする。深く口腔を弄る。自然と律動が早くなる。止まらない。止められない。愛おしさが、溢れてしまう。
「ああっ!! あ……ッ!」
キスが終わると同時に、シュバルツはドプッ、と、音を立てて、また果ててしまった。
「は……あ……! ハヤブサ……! ハヤブサ…ッ!」
だがシュバルツの何かを求める動きは止まない。腕の中で、必死に何かを足掻いている。
「シュバルツ……!」
額に優しくキスをして、胸を優しく愛してやる。
「ああっ!! 駄目…ッ!! ハヤブサ…あ……!」
ビクビクッ! と、その身を震わせながらも、足掻く動きを止めないシュバルツ。
(もしかして、身体を離して欲しいのだろうか)
何を求められているのかが分からないから、ハヤブサはついそんな事を思ってしまう。
だけど、離さない。
離すものか。
こんなにも――――愛おしいのに。
嫌がられたって、もう絶対に離してやらない。
身体を強く捕まえて、深く穿ってやる。仰け反るシュバルツのその首筋に、噛みつくようにキスをした。
「ああ……! ハヤブサ……! も……!」
身体をゆすられながら、尚も足掻くシュバルツが叫んだ。
「解いて……ッ!! 腕の紐を、解いてくれ……ッ!!」
「―――――!」
シュバルツの叫び声に、ハヤブサもはっと我に帰る。そう言えば、シュバルツの腕を縛りっぱなしであった事に気づいた。
「あ……! す、すまん…!」
ハヤブサは慌ててシュバルツの身体を後ろに向かせて、腕を縛り付けていた帯を解く。シュバルツに縄抜けをされないようにと、きつく縛りつけられた帯(それ)は、シュバルツの腕に痛々しい痣を残していた。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
だがシュバルツは、自由になったその腕を躊躇うことなくハヤブサの方へと伸ばしてくる。
「シュバルツ……!」
茫然とその様を見守るハヤブサの頭を、シュバルツの腕がゆっくりと抱き寄せたかと思うと。
「……………」
チュッ、と、音を立てて、シュバルツの唇が、ハヤブサの頬に流れる涙を掬い取った。
―――――泣かないで……
耳元で、そう囁かれる。
「シュバルツ……! お前――――!」
茫然と見つめ返すハヤブサに、シュバルツはにこりと微笑みかけた。
「そんな事がしたくて、お前は……帯を解くように要求、してきたのか……?」
「……………」
とろんとした瞳のシュバルツから、その問いかけに明確な答えが返って来る事はない。だが、自由になったシュバルツの手は、ハヤブサの涙を拭い続けていた。
「シュバルツ――――!」
駄目だ……! もう……!
そんな、事を……されてしまっては――――!
「シュバルツ……ッ!!」
その身体を強く強く抱きしめる。強く、強く――――。
「あっ…! ハヤブサぁ……」
シュバルツからも腕が伸びて来て、自分の身体を抱きしめられる。
そうだ……!
何時だって、シュバルツは
俺が、抱きしめたら
抱き返してくれていたじゃないか――――!
(『好き』だから……)
そう、言われていたのに。
ずっと――――
ぐっと結合を深めると、腕の中のシュバルツの身体がビクン、と、跳ねた。
「ああ………!」
シュバルツの身体が、小刻みに震えている。媚薬で強制的に火照らされているその身体。感じすぎてしまうのだろう。
だが……もう………!
「シュバルツ……! 済まない……!」
その耳元で、謝る。
もう本当に――――優しくなんて、してやれそうにない。
お前への愛しさで、自分の身体が爆発してしまいそうだから――――。
「お前を……壊してしまうかも、しれない……!」
「ふ……あ……?」
「それでも……お前は、赦してくれるか……?」
分かっている。今のシュバルツから、この問いに明確な答えが返って来る事はない。
それでも問いかけたのは――――ハヤブサに残る、最後の理性の働きだった。
「………泣かないで、ハヤブサ……」
シュバルツからはただ――――その言葉が返ってくるのみであった。
「ああっ!! ああああっ!!」
びゅ……と、音を立てて、またシュバルツから『精』が放たれる。さっきからもう―――何度彼は達してしまったのか分からない。ハヤブサも、途中で数える事をとっくにあきらめてしまっていた。
ハヤブサの手が、すぐにシュバルツの『そこ』を確かめる。
「ああっ!! はあん…! あ、熱い……ッ!」
シュバルツの牡茎は、まだ硬さを保っている。彼の『秘所』も――――貪欲にハヤブサ自身を咥え込んでいた。
「シュバルツ……ッ!」
後ろから彼の身体を抱え込んで、楔を深く打ち込んでやる。
「だ、ダメッ!! 奥……! 当たって……!!」
深い律動を受け入れながら、シュバルツはうっとりと呟いた。
「気持ちいい………! あ……!」
びゅく……と、また、達してしまうシュバルツ。
だがもう、休ませてやる事なんて出来ない。力が抜けて行くシュバルツに向かって、強引に奥に入り込んで行く。
「あっ!! ああっ!! あ……! あ……!」
悲鳴にも似た嬌声――――感じすぎている身体は、もう限界に近付いているのだろう。
「愛している……シュバルツ……!」
抱きしめて、耳元で囁いてやる。
「あ……! あ、愛してる……! ハヤブサ……ぁ……」
蕩けた様な声で、確かに返って来る、言葉。
「愛してる……! 愛してる……! あ…あ、愛して…る……ッ!」
ゆすられるたびに、壊れたように、同じ言葉を繰り返す愛おしいヒト。
堰を切ったように繰り返されるその言葉は、ずっと、彼の中に溜め込まれていたものなのだろう。
もっと
もっと言って。
その言葉を――――。
「ああ……! だ、駄目……! そんな、事……を、言っては……!」
身を捩り、身体を離そうとするシュバルツ。
「私、は……アンドロ――――んう……!!」
ハヤブサは、シュバルツの唇を己の唇で塞ぐ。
聞きたくない。そんな言葉は。
俺が聞きたい言葉は、一つだけだ。
「んんっ!! んぐっ!! ん、んんぅ!! ん…!!」
深く深く口腔を蹂躙してから、もう一度、シュバルツの耳元に囁いてやる。
「愛している……! シュバルツ……!」
「ああっ!! 愛して、る……ッ! ハヤブサ…あ……ッ!!」
胸を弄られながら、シュバルツはまた果てた。
「いい子だ……」
チュッ、と、音を立てて、シュバルツの熟れきった胸に唇を落としてやると、「はあっ!! ああん!!」と、腕の中でその身体が仰け反り跳ねた。
「もっと…! 触って……ッ! もっと…もっとぉ……!!」
可愛らしいおねだり。もちろん、叶えてやる。
「ああ……! 気持ち、イイ……! 愛してる……!」
支離滅裂な言葉。焦点の合っていない、蕩けた瞳。
もう何を言っているのか――――彼は絶対自分でも分かっていないのだろう。
「愛してる……! 愛してる……! 気持ちいい……! 愛してる……!」
「シュバルツ……!」
「ああ……! 離さないで……! 離れないで……! ハヤブサ……!」
「分かってる……! 離すものか……!」
深く繋がりながら、シュバルツに囁く。
もう絶対に―――――離してなどやらないから。
だからお前も、もう俺に隠さないでくれ。
お前の持つ、その豊かな愛の世界を――――。
「あっ!! ああ……!」
ドプッ! と、音を立てて果てたシュバルツの身体が、ガクッと崩れる。でもハヤブサは、シュバルツのその身体を離さない。強く抱きしめて、さらにその身体をゆすり続ける。
「あ……! も……! 壊れる……ッ! 壊れてしまう……ッ!」
悲鳴のような嬌声。もう本当に――――限界なのだろう。
構わない。このまま壊れてしまっても。
壊れたお前だって、俺は愛すから。
柔らかくなってきたシュバルツの牡茎を捉えて、扱く。
「ああっ!! あ……!」
感じて、仰け反った胸を、優しく愛す。
「あ……! 気持ちいい……!」
シュバルツの腕が、自分の身体に触れてくる。でもその腕は、とても優しい。
赦し続けてくれる。シュバルツは。自分が壊れそうになっていても。
「愛している……! シュバルツ……!」
「は……あ…あ……愛して、いる……ハヤブサ……」
帰って来る、同じ言葉。同じ『想い』――――
それだけで、満たされていく『ココロ』
何と、単純なものなのだろう。
ああ――――俺は今
「死んでもいい」と、思えるぐらい
幸せだ。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
想いを込めて、身体をゆする。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……ッ!」
ゆすられながらシュバルツも、縋る様に、ハヤブサの名を呼び続けていた。まるでそれをしなければ、もう壊れてしまうとでも言わんばかりに。
「あ、あ……も……う……!」
ビクビクッ!! と、身体を震わせながら、シュバルツは最後の絶頂を迎えた。
「愛して……る……」
ふわりと花が散るように、シュバルツはその意識を手放した。
「…………ッ!」
シュバルツが果てた瞬間の締め付けで、ハヤブサもまた―――果てていた。心地よい脱力感が、全身を襲う。気を失ったシュバルツの身体の上に、ハヤブサもまた、物も言わずに倒れ込んでいた。
「……………」
力を抜き、身体を密着させて――――シュバルツの身体の感触を全身で味わう。相変わらず冷たいのだが、その中にほんのりとした温もりを感じる。『呼吸』をしているが故に、その胸がゆっくりと上下し、そこから規則正しい『駆動音』が聞こえて来ていた。
酷く人間臭い奴なのに、ちゃんと『アンドロイド』なのだから――――ハヤブサは少し切なくて、笑ってしまう。でも、この『駆動音』すら、ハヤブサにはとても愛おしくて、安心できる音となっていた。
「シュバルツ……」
気を失って動かないシュバルツの唇を、優しく塞ぐ。
(愛してる……)
何度も愛の言葉を囁いてくれた、その唇を――――
「……………」
ふうっ、と、大きく息を一つ吐いて、ハヤブサはシュバルツから己自身を引き抜いた。ズルッと音を立てて出てくる己自身と同時に、ドプッと、シュバルツの『秘所』から己の『精』が溢れ出てくる。
その量の多さに、ハヤブサは苦笑していた。出し過ぎだろう、と、ハヤブサは自分で自分を揶揄するが、仕方がなかろうとも思う。あんなに何度も何度も可愛らしく『おねだり』をされて、愛の言葉を紡がれてしまっては――――。
最早、我慢できる方が、おかしいと思う。
手近にある紙でハヤブサは自分の『精』を処理すると、手拭いに温泉のお湯を浸して来て、シュバルツの身体を拭いてやる。完全に気を失ってしまっているシュバルツは、身体を拭かれていても、ピクリとも身じろぎをしなかった。
本当は、風呂に入って、きちんと体の汚れを洗い流してやりたかったが――――。
媚薬で無理やり火照らされて、散々俺に弄ばれてしまったその身体。ゆっくり休ませてやる方がいいだろうと、ハヤブサは判断した。
彼の身体を拭き終わったハヤブサは、シュバルツの身体を抱きあげると、布団へと運んでやる。二組み敷いてある布団の、汚れていない方の布団にシュバルツの身体を横たえさせた。
(シュバルツ……)
ハヤブサはもう一度、シュバルツの唇にキスをする。それでも身じろぎをしない、愛おしいヒトは、深い眠りに落ちていた。
(好、き……! ハヤブサ……!)
(愛してる……! 愛してる……! 愛しているんだ、ハヤブサ……!)
ハヤブサは、頭の中で再生をする。その時の愛おしいヒトの姿と声を、何度でも、何度でも――――。
(愛してる……!)
(愛してる……!)
満ちて行く。満たされて行く、ココロ。
シュバルツに感じていた『飢え』が、徐々におさまっていく自分を、ハヤブサは感じていた。
嬉しい……。
いいのだろうか。こんなに幸せで――――。
嬉しい。
シュバルツの心が、確かに俺に向いていた事が。
シュバルツも、同じように感じてくれているのだろうか。
「愛してる」
俺が彼にこう囁いた時、彼も『幸せ』なのだろうか。
そうだとしたら
こんなに幸せな事は無いのに――――。
(離さないで……! 離れないで……! ハヤブサ……!)
睦言の最中に、シュバルツから時折漏れた、言葉。
それこそ、望むところだ。出来得る限り、叶えてあげたい。
だが―――――
身体の時間が止まり、永遠に生き続けてしまう可能性のある、シュバルツ。
たいして、身体に時間が宿り、命の限界がある、俺。
どうしたって、いずれ別れの時が来てしまうと、悟る。
それでも、「離れないで」とシュバルツが願っていると言うのなら
なんて哀しくて切なくて――――愛おしい、ものなのだろう。
今すぐ俺も不死の人外になりたい。
そうすれば永遠に――――シュバルツと、苦楽を共に出来るのに。
彼を独り、置いて逝かずに済むのに。
誰よりも愛情が深くて、優しいシュバルツ。
優しいのは――――それだけ彼が、『哀しみ』を知っているからだ。
孤独の苦しみを、知りぬいているからだ。
淋しいから、優しくなる。
淋しいから、相手の心に寄り添おうとする。
キスを好み、抱きしめ合う事を好み、相手を愛したがるシュバルツ。
時々甘えるように身を擦り寄せてくるもあるから、このヒトは存外、甘えたがりなのかもしれない、とも思う。孤独の中に、その身を置かねばならないヒトであるのに。
「……………」
心地よい疲労感とまどろみが、ハヤブサに降りてくる。無理もない。丑三つ時を過ぎて、もう朝の4時近く。もうすぐ、夜明けがやって来る。
部屋に暖気を入れてあるとはいえ、晩秋の明け方は、やはり冷える。
シュバルツの隣で休もうか、とも思うが――――。
眠りたくなかった。
初めてシュバルツが、「愛してる」と、自分に言ってくれたのだ。その寝顔を、ずっと見つめていたいと、思った。
(シュバルツ……)
深い深い眠りに落ちている、愛おしいヒト。
(愛している……)
ハヤブサは結局夜が明けるまで、シュバルツの寝顔を飽きることなく見つめていた。幸せの余韻が勿体なくて、眠る事など出来なかった――――。
最終章
暗闇の中、人が佇んでいる。
「ハヤブサ……!」
その人間の正体に気付いたシュバルツは、傍に駆け寄って行こうとした。
だが。
「近寄るな!!」
ある程度まで近づいた所で、ハヤブサに手を上げて制された。驚くシュバルツの目の前で、ハヤブサが哀しげな表情をしている。
「お前の気持ちは、よく分かった」
「…………!」
驚き、息を飲むシュバルツの目の前で、ハヤブサの独白は続いた。
「お前は俺を求めてはくれない。頼ってもくれない…。俺がどんなにお前の事を想っても、お前がそれに応えてくれる事は……無いのだな……」
「あ………!」
「もういい……! もう疲れた……!」
「ハヤブサ……!」
「お前を想い続けて……俺は、疲れてしまったよ……」
そう言って、心底疲れた様な表情を見せるハヤブサ。
シュバルツは、何かを言わなければと思った。だけど口を開こうとして――――自分は、何も言えない事に気づく。
「ハヤブサには、自分の心を伝えない」
彼はそう、決意をしてしまっていたのだから――――。
「結局俺は……お前のために、何の力にもなれなかった………」
「――――――」
そんな事は 無い。
お前が手を伸ばしてくれたことで、私がどれほど救われたか――――
その言葉は、シュバルツの口の中で、噛み殺された。
「もう、止めにするよ。お前を追うのは……。悪かったな…。今まで、付き纏ったりして――――」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは無言で首を振る。
ハヤブサが、謝る事は無い。
貴方は何も悪くないのに――――
言わない。
言えない。
何も、言えない。
「ありがとう」も
「済まない」すらも――――
何も、もう言えないんだ。
「じゃあ、俺はもう行く。二度と、会う事も無いだろう」
そう言って、ハヤブサは去って行った。
ハヤブサ
ハヤブサ
行カナイ デ
言えない。
言わない。
言っては駄目だ――――!
溢れる涙。
懸命に堪える。
漏れる嗚咽。
かみ殺す。
ハヤブサ
ハヤブサ――――
どうか 『幸せ』 に
『幸せ』 に なって――――
(シュバルツ……)
え…………!?
近くで響く優しい声。頬に触れてくる、優しい手。
それに驚いたシュバルツが顔を上げると、すぐ近くに、ハヤブサの優しい顔があった。
「あ……………!」
驚き戸惑うシュバルツの唇を、ハヤブサの唇が優しく塞ぐ。
(愛している……)
ハヤブサの声が、降り注いでくる。
どうして……?
ハヤブサ……。
どうして――――?
「シュバルツ……」
もう一度響いてくる、ハヤブサの声。
「起きろ……!」
(え……? お……き……?)
「――――――!」
シュバルツの意識が、一気に覚醒する。目が覚めたシュバルツの視界に、心配そうにこちらを覗き込む、ハヤブサの姿が飛び込んできていた。
「大丈夫か? シュバルツ……」
「あ…………!」
茫然とハヤブサを見つめるシュバルツに向かって、彼の手が伸びてくる。その手はシュバルツの頬に流れる涙を優しく掬っていた。
「……済まないな。もう少し寝かせてやりたかったのだが……」
「え………?」
「その……うなされていたようだったから……」
そう言いながらすまなさそうにこちらを見つめてくるハヤブサの瞳は、とても優しかった。
(これが、現実……? じゃあ、さっきハヤブサが去って行った方が、夢……?)
目の前のハヤブサの姿を見つめながら、シュバルツはしばし混乱する。
一体、私はどうしたんだ?
何があった?
何がどうして、こんな――――。
シュバルツは起き上がろうとして、自分が、服を着ていない状態である事に気づく。
(え……? どうして、私は服を着ていな………!!)
その瞬間、シュバルツは思い出す。昨夜あった『いろいろな』事を――――。
「あ………ッ!」
シュバルツが慌てて身を起こすと、彼の体内から昨晩の名残が流れ出してきたから、彼は思わず声を上げてしまう。
「うあ……!」
「ど、どうした!? シュバルツ……」
「あ……! いや、その、あの……!」
驚いて声をかけてきたハヤブサに、シュバルツが顔を赤らめながら、自分の背後を押さえる姿を見せるから――――ハヤブサも、何となく事情を察した。
「ああ………まだ、残っていたか? 全部拭いたつもりだったんだが……」
「う…………!」
苦笑しながらそう言うハヤブサに、シュバルツの顔色がますます赤くなってしまう。
それにしても昨日、私はどうしたんだ?
確か、私はハヤブサを傷、つけてしまって………。
「ハヤブサ……!」
シュバルツは思わず、ハヤブサの顔を見つめてしまう。昨日、あんなに冷たくて、怒っていた様なハヤブサ。それが何故――――今はこんなに優しい雰囲気で自分の側に居てくれているのだろうか?
あの夢の様に、ハヤブサが自分から離れて行ってもおかしくはないと、思っていたのに。
「ハヤブサ……! どうして――――」
「シュバルツ……」
ハヤブサが、シュバルツの肩に、ポン、と、手を置いてくる。
「お前は昨晩の睦言……どこまで覚えている?」
「ど、どこまで……とは……?」
怪訝な顔をして首をかしげるシュバルツに、ハヤブサは更に聞いてくる。
「だから……昨晩、自分がやった事とか、言った事とか……」
「う…………!」
ハヤブサのかなり際どい質問に、シュバルツの顔色が本当に真っ赤になる。シュバルツとしては正直なところ、あの『リング』を外されて以降の記憶がかなり曖昧になってしまっている。ただ、とても『気持ち良かった』と、言うことしか――――憶えていない。
だがそれを、ハヤブサにどう言えばいいと言うのだろう。
それにしてもハヤブサが、こんな質問をしてくる、と言う事は……。
「な、何か私は……おかしなことを、言ってしまったのか……?」
恐る恐る、と、いった按配で聞いてくるシュバルツに、ハヤブサはにやりと笑った。
「『もっと……! もっと……!』と、俺に何回も要求して来た事は……覚えているか?」
「な―――――ッ!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツの顔色が真っ青になる。
それを見た瞬間、ハヤブサは総てを悟ってしまった。
ああ、シュバルツはやはり、憶えてはいない。
おそらく、『リング』を外した辺りから。
俺に何度も愛を囁いてしまった事を――――憶えていないのだ。
「わ……私は……そ、そんな事を、言ったのか……?」
震えながら聞いてくるシュバルツに、ハヤブサは真顔で頷く。
「ああ。言ったな。何回も何回も――――」
「う………!」
「もう本当に……何回も何回も、要求されるから―――――」
ここでハヤブサの顔がふにゃ、と、柔らかい物になる。
「もう、そんなお前が……本当に、可愛くて可愛くて――――」
「―――なッ……! ちょ……ッ!」
顔を真っ赤にして固まってしまうシュバルツに対して、ハヤブサは「クククッ」と、笑った。
「そうか~。お前の弱点は『沢庵』だったのか~♪」
「うぐ……ッ!」
「それにしても、二切れの沢庵でああなるってことは……そうだ、今度里に来た時に、沢庵を丸ごと一本食べてみるか? もう本当に、どれだけお前が乱れてくれるか、楽しみ――――」
「いい加減にしろっ!!!」
ドカッ!!!
にやけるハヤブサに、シュバルツのきつい鉄拳制裁が飛んだ。
「馬鹿な事を言っていないで、冷水でもかぶって頭を冷やせ!! お前は―――!!」
そう言ってぶりぶり怒りながらシュバルツは、もう服を着こんでしまっている。
「ああ……せっかくの、シュバルツの裸が………」
ぼそりと言ったハヤブサの言葉を、シュバルツが聞き咎めた。
「……何か、言ったか?」
「い、いや……別に?」
じと目で睨みつけてくるシュバルツを、ハヤブサは素っとぼけてかわした。だが―――顔がにやける事を、押さえる事が出来ない。それを見たシュバルツが、毒気が抜かれてしまったのか、はあっ、と、大きくため息を吐いた。
「それで……ハヤブサ。お前は、もういいのか?」
「? 『もういい』って……何が?」
「何がって――――」
シュバルツは思わず問い返してしまう。実際不思議だった。どうしてハヤブサの機嫌が、こうも治ってしまっているのだろう?
「お前は、私に怒っていたのではないのか……? なのに――――」
シュバルツが言葉を紡ごうとする唇を、ハヤブサの人差し指が押さえた。
「シュバルツ……」
シュバルツに呼びかけるハヤブサの眼差しは、とても優しい。ただあまりにも優しいから――――シュバルツは何となく、落ち着かなくなってしまう。
「ハヤブサ……」
戸惑ったような眼差しを向けてくるシュバルツに、ハヤブサはにこりと笑って答えた。
「ああ……確かに、怒っていた様な気もするが………もういいよ」
「『もういい』って………だが、それでは……!」
「いや、本当にもういいんだ。お前にある程度八つ当たらせてもらって、こちらもすっきりしたし、それに――――」
「それに?」
怪訝そうに小首をかしげるシュバルツの前で、ハヤブサの顔がにへら、と、笑顔を作る。
「……あんなに可愛らしいお前の姿を見せつけられちゃあな~~♪」
「―――――ッ!!」
「『ああ、もっと……! もっと……!』なんて繰り返し要求されちゃったらそれこそおま」
ドスッ!!
ハヤブサの鼻先を掠めて、手裏剣が柱に突き刺さる。驚いたハヤブサが恐る恐るシュバルツの方に振り返ると、物凄く殺気だった眼差しで手裏剣と刀を構える、彼の姿があった。
「や、やだなぁ、シュバルツ……! 冗談だよ……! 冗談……!」
「……………」
あたふたするハヤブサに、シュバルツは尚も無言でにじり寄ってくる。
「わ、分かった……! もう言わない……! もう言わないから、お願いだから、その物騒な物をしまってくれ……! な……?」
必死に懇願してくるハヤブサの姿に、シュバルツもはぁっと、ため息をつく。どうやら、いろいろと毒気が抜かれてしまったらしい。
「まあ、お前がそれで納得したのなら、良いけど――――」
そう言って刀と手裏剣を収めるシュバルツ。
「…………!」
――――大好きなお前がそれで納得したのなら、私も良いよ……。
ハヤブサの脳の中で、シュバルツの言葉がどうしてもこう自動変換されてしまう。シュバルツは結局、昨晩のことすら赦してくれたのだ。あれだけひどい目に遭わされたと言うのに。
(やばい……! 俺って結構愛されている……!)
気をつけてみると、そこかしこにシュバルツの『愛』がちりばめられている事に気づく。そして、それに気づいてしまうと、ハヤブサは自分の顔がゆるんでしまう事を、どうしても抑えられない。
「……何、笑っているんだ?」
「いや……笑っているつもりはないのだが……」
勝手に緩む頬。
ピクリ、と、シュバルツの目元が引きつるから、また殴られるかな? と、思いながらハヤブサが身構えると――――シュバルツは頭を抱えはじめた。
「あ~~~! もう!! 出来れば昨晩の私の事は忘れてくれ!! あれは熱に浮かされていて、普通じゃない状態だったから……!」
そう言いながら頭をぐしゃぐしゃと掻きむしる彼に、ハヤブサも苦笑するしかない。
「……心配しなくとも、俺だってあんまり覚えてはいないさ。昨晩の事は……」
「えっ?」
驚いて振り向くシュバルツに、ハヤブサは頷く。
「そうなのか……?」
「だいたいだな……お前に『もっと……! もっと……!』と、言われた時点で――――」
「う…………!」
「俺の『理性』が―――保たれているとでも、思っているのか?」
「そ、それは……!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツも返す言葉を失ってしまう。でも確かにそうなのだ。シュバルツを抱いている時のハヤブサは、割と早い段階で『切れて』しまう事が多い。今回も、そうだったのだろうか?
「言っておくが、お前の『誘い』に対する俺の耐久性は、割と低いぞ?」
「低いって………!」
「限りなく『零』に近い。どうだ。すごいだろう」
「………自慢になるか…!」
そう言って胸を反らすハヤブサに、シュバルツは呆れかえってそっぽを向いてしまう。でも彼は、内心ほっと胸を撫で下ろしていた。
あの『リング』を外されてから以降の記憶が、曖昧になってしまっている自分。
『媚薬』の熱も手伝ってか、気持ち良すぎて。
『我慢』が出来なくなってしまって――――。
絶対にいろいろと、言っちゃったりやっちゃったり、してしまっている様な気がする。熱に浮かされた自分は、ハヤブサに対して何か言うつもりもない事を言ったりはしていないだろうか。
ハヤブサに『好き』と言う自分の気持ちを、うっかり伝えてしまってはいないだろうか。
「……本当に、お前も記憶が曖昧なのか……?」
ハヤブサに確認する様に問いかけてくるシュバルツに、ハヤブサも力強く頷く。
「ああ。残念ながら。あの可愛らしいお前を見た瞬間に、俺も理性が飛んでしまって―――」
「う………!」
「その後は、『気持ち良かった』ぐらいしか、憶えていない」
「そ……そうか………!」
シュバルツが、安心したように息を吐いているのを、ハヤブサは複雑な心境で見守った。
済まないな、シュバルツ。
俺は、微に入り細に入り覚えている。あの時のお前を。
お前が俺に囁いてくれた愛の言葉、一つ一つを
俺は絶対に、忘れるつもりはないから――――。
でも、お前がそれを俺に告げるつもりが無いと言うのなら
俺も、気づかないふりをする。
だから……
だから――――
「シュバルツ……!」
ハヤブサは、後ろからシュバルツに抱きついた。
「ハヤブサ……?」
怪訝そうに首をかしげながらも、それを振りほどこうとしないシュバルツ。愛しさが、溢れてしまう。
「愛している……シュバルツ……!」
「…………!」
「だから…………」
「だから………何だ?」
「……もう一回、沢庵を食べてみてくれないか? それでもう一回俺と」
シャッ!!
無言で抜刀された刀を突き付けられる。
「じょ、冗談だってば………!」
ハヤブサはまた懸命に、シュバルツに刀を収める様に、懇願しなければならなかった。
「もう! お前の前では絶対に物は食べない!!」
「そ、そんなつれない事言うなよ……! そんなに嫌なら、俺もお前には沢庵を勧めたりはしないから……!」
刀を収めながら顔を真っ赤にして、ぶりぶり怒りながら踵を返そうとするシュバルツの周りを、ハヤブサが必死につき纏っている。
「………本当か?」
足をピタリと止めて、ハヤブサをじと目で睨むシュバルツに、ハヤブサはこくこくと頷く。
「勧めない、勧めない。絶対に勧めない」
「…………そのにやけ顔でそんな事を言われてもな……」
「えっ!?」
「鏡を見てみろ! 説得力ゼロだぞ?」
「そ、そんな……!!」
ハヤブサは慌てて自分の頬を押さえるが、どうしようもなく緩んでしまっているのが自分でも分かる。いくら真面目な顔を作ろうとしても、頬の筋肉は3秒と保ってはくれなかった。
「無理だ! シュバルツ! こんなに幸せなのに、真面目な顔なんて作れない!!」
悲鳴の様な声を上げるハヤブサに、シュバルツも呆れかえってしまう。
「あのなぁ、ハヤブサ……いい加減に――――」
足を止めて振り返ったシュバルツは、いきなりハヤブサに抱きしめられてしまったから、言葉を失ってしまう。
「シュバルツ……!」
「ハヤブサ……?」
抱きついてきたハヤブサの身体が小さく震えていたから、シュバルツは少し戸惑う。
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
抱きついて来た腕に、ぎゅ、と、力が込められる。
「……………」
どうしたんだろう、と、思いながらも、シュバルツもハヤブサの背に、片手をそっと回してきた。
「シュバルツ……!」
嬉しくて嬉しくて、ハヤブサは思わず泣きそうになってしまう。
ほら――――
やっぱりシュバルツは
俺が抱きしめたら、必ず、抱き返してくれる。
(愛してる……)
きっと、今もそう言われているのだろう。
声無き声で―――――。
良いんだ、シュバルツ。
お前が『好きだ』と言う気持ちを伝えられない、と、言うのなら。
俺が、拾う。拾い続ける。お前の声を。
今度こそ、お前の気持ちを見失わないようにするから――――。
だから、こうしてお前の側に居続ける事を、どうか許して欲しい。
「どうした…? ハヤブサ……」
「シュバルツ……」
背中にまわされているシュバルツの手を意識しながら、ハヤブサは口を開いた。
「お願いだ……。これからも、少しでいい。こんな風に、お前と過ごす時間を俺にくれないか……?」
「……………!」
「ほんの少しでいいんだ……! お願いだ……!」
「少しとは………どれくらいだ?」
ハヤブサはシュバルツから身体を離して、にっこりと微笑む。
「そうだな……。3日に1度くらい?」
ズルッ。
シュバルツがこけた。
「なぁ、いいだろう? シュバルツ?」
ハヤブサがこけたシュバルツをツンツンとつつきながら、尚もお願いを重ねる。
「阿呆か――――ッ!! 多すぎるわ!! 3日に1度など、ほぼ毎日ではないか!!」
ガバッと起き上がったシュバルツが、ハヤブサを怒鳴りつけ出した。
「そんな事は無いぞ!? こちらは2日間『も』お前に会えない事を我慢するんだ! それ以上お前に会えないなんて、耐えられるか!!」
「何が2日間『も』だ!! お前との逢引きなど、1カ月に1度くらいで充分だろう!!」
「い……1カ月……だ、と……!?」
龍の忍者がよろめいてしまう。
「そ、そんな……! 1か月もお前に会えないとなると……お前に会えた時に、それこそ沢庵2本ぐらい食べてもらわないと…………!」
ハヤブサが小声でブツブツと、とんでもない事を口走っている。
「あ、あのなぁ、ハヤブサ……!」
「いや……2本でも足りないぐらいだな……。それこそ座敷牢に監禁して、1日中正気で居られなくなるぐらい発情してもらって―――」
「阿呆か――――――ッ!!!」
ドカッ!!
ハヤブサの妄想は、当然のごとくシュバルツの鉄拳制裁で討ち砕かれた。
「お前の脳の中はそんなことしか考えていないのか!? そんな変態じみたプレイには、私は断じて付き合わんぞ!!」
「じゃあ、3日に一度会ってくれるか?」
殴られた頭をさすりながら、涙目になっているハヤブサが、起き上がりながら懇願してくる。
「はい?」
「3日に一度だったら……まだ、普通の交わりで我慢できるから……」
「…………!」
シュバルツは激しい眩暈を感じる。
おかしい。
何でこんなにこいつに懐かれてしまっているのだろう。
「………3日に一度は多い。せめて、2週間に1度にしろ」
腕組みをしたシュバルツが、憮然と言い放つ。1カ月に1度の半分だ。シュバルツからしてみれば、かなり妥協した事になるのだが。
「に……2週間に、一度――――!?」
まだ龍の忍者はよろめいている。
「に……2週間もお前に会えないだなんて――――俺はもう、死ぬしかない……!」
「おい」
「死ぬ! 絶対死ぬ!! お前に枯渇して死ぬ!! 無理だ!! 耐えられない!!」
「おい! ハヤブサ――――!」
「いやだいやだ!! 2週間もシュバルツに会えないなんて、絶対に嫌だ――――!!」
「どこの駄々っ子だ!! お前は――――!」
寝っ転がってじたばたと暴れる龍の忍者に、シュバルツもため息をつくしかなかった。
「ああもう分かった!! 1週間に1度!! これでどうだ!?」
やけくその様に叫ぶシュバルツに、ハヤブサもようやく起き上がってきた。
「本当か!? シュバルツ!! 本当に、1週間に1度――――俺に会ってくれるのか!?」
ガバッとシュバルツの両手を握って、かぶりつく様に彼を見つめるハヤブサ。その勢いと視線の熱さに、シュバルツは戸惑ってしまう。
「あ、ああ……。お前が、そう望むのならば――――」
「………ッ! やった―――――!!!」
(あれ……? もしかしなくても私は、何か、嵌められた……?)
天にも昇らん勢いで、喜ぶハヤブサ。それを見ながらシュバルツは、複雑な心境になる。
ハヤブサが嬉しそうにしているのはいいのだが――――本当に、良いのだろうか?
彼がどんどん自分に深く関わろうとして来ている。本当なら、自分はそれを拒絶、しなければならないのに……。
彼にかかってくるリスクを考えても
彼の心の消耗を考えても
彼が、自分と関わっても良い事など、何一つ無―――――
「シュバルツ!!」
「あ………!」
ハヤブサに強く抱きしめられて、シュバルツが戸惑いの声を上げる。
「嬉しいよ……! シュバルツ……! ありがとう……!」
「ハヤブサ……」
シュバルツの瞳が揺れているのを、ハヤブサは見つめる。
(ああ、苦しんでいるのだな)
ハヤブサは感じ取る。
自分の身体の事を思って
俺の事を、想って――――
でも、お前は望んでいるのだろう?
「離れて欲しくない」と………。
「そばに居て欲しい」
そう、望んでいるのだろう。
でも、それを伝えてはいけない。俺をつき離さなければいけない、と思っているから、苦しんで――――
済まないな、シュバルツ。
俺はもう知ってしまった。
お前の心がどこにあるのかを。
お前が、何を望んでしまっているのかを。
「離れないで」
それを知ってしまったら、俺はもう―――――。
お前から離れる選択肢だけは
「選べない」
選びたく、無い。
「愛してる……シュバルツ……」
優しく、その唇を塞ぐ。
「ん…………っ!」
腕の中で瞬間、シュバルツの身体が強張る。
でも――――優しく、受け入れてくれる。
おずおずと、腕に添えられてくる、シュバルツの、手。
これがシュバルツの「愛シテイル」のサイン。
ああ―――――
幸せだ。
幸せすぎて、泣けてくる。
「んんっ! ん……う……!」
知らず深く、口腔を弄ってしまう。愛おしいヒトが腕の中で苦しそうにくぐもった声を漏らすが―――それすらも呑み込んでしまいたくて、さらにその身体を強く抱きしめた。
ハヤブサの中で、欲が膨らむ。
もっともっと、繋がりたい。
もっと、もっと――――。
だが………。
今は―――――
「……………」
そっとシュバルツから離れる。
「ハヤブサ……?」
少し不思議そうに見つめ返してくるシュバルツに、ハヤブサは微笑みかけた。
「今、午前8時46分。俺が、最初にあの森でシュバルツにキスをしてから、ちょうど24時間――――」
「…………?」
「『報酬』の、時間切れ――――だ」
「あ…………!」
茫然とハヤブサを見つめるシュバルツに、ハヤブサは優しい笑みを返す。
「ありがとう、シュバルツ……。俺はもう、充分な『報酬』を受け取った」
「ハヤブサ……!」
「だからもう……本当に、自由にしてくれていい……。済まなかったな、今まで……。ありがとう……」
「…………」
ハヤブサの言葉に、黙りこんでしまうシュバルツ。
(離れて行って、しまうかな?)
シュバルツの行動が読めないから、ハヤブサは少し不安になる。
だけど、この区切りは、絶対につけておかねばならないと思った。シュバルツをいつまでも『報酬』として横に縛り付けておく状態は、かなり魅力的ではあるのだが――――やはり、不自然だ。
シュバルツには、自分で選んで欲しいと思った。望んで欲しい。俺と共に居る事を。
密やかにそう望んでいると言うのなら、尚更。
その望みを叶えて欲しいと、願った。
俺が、自分からシュバルツから離れることはない。絶対に。
大丈夫だ。例え、今彼が離れて行ってしまっても、1週間後には、またこんな風に会う約束を取り付けているのだから。そうでなければ、とてもこんな風に手を離す事なんて出来なかった。
「……………」
シュバルツはしばらく何かを考え込むようにしていたが、やがて、その顔を上げた。
「ハヤブサは……」
「何だ?」
問いかけてきたシュバルツを、ハヤブサは優しく見つめ返す。ただその視線があまりにも優しかったから――――シュバルツは、少し落ち着かない気持ちになってしまった。
「この後……何か、用はあるのか………?」
「特に、何も用事はないが?」
きっぱりと、そう言い放つ。
シュバルツと会っているのに、それ以上の用事なんかある訳がない。あったとしても後回しにするし、握りつぶす。エージェントとして忍者として、その姿勢はいかがなものかと思ったりもするが、今はとにかく、彼を大事にしたかった。
「う…………」
少し頬を赤らめながら、ハヤブサから視線をそらしてしまうシュバルツ。
その可愛らしい彼の様子に、ハヤブサの強くない理性が一気に傾いでいきそうになってしまう。
いやいや、落ちつけ俺!!
今は、シュバルツの気持ちを優先させると決めているのだから…!
必死に自分を叱咤して、穏やかな心を手繰り寄せる。
今はとにかく何を言われても、受け入れることが肝要だと思った。
「そ……その………」
シュバルツは、ハヤブサにいきなり『自由にして良い』と手を離されて、戸惑っていた。
『ハヤブサの報酬』と言う立場を、瞬間忘れてしまっていた自分にも、戸惑っているし。
そして、何より―――――
ハヤブサに手を離されて
『淋しい』
と、感じてしまう事にも戸惑ってしまう。
だからつい、望んでしまう。
「もう少しだけ、一緒に居たい」
でも、ハヤブサにもハヤブサの都合と言う物があるだろうから、迷惑になるようなら、この願いはすぐに引っ込めるつもりでいた。なのに「用は無い」と、言い切られてしまう、ものだから。
「ハ……ハヤブサ……」
「何だ?」
「そ、その……ハヤブサ、さえ………よかったら……」
顔が火照る。舌がもつれる。
こういうふうに、人を誘い慣れていない自分に気づいてしまう。
今までずっとそう言う事をしなくても、特に不自由も不都合も感じた事が無かったから―――
でも、『二人で居る楽しさ』を、知ってしまったら――――
望んでしまう。
その時間が、続く事を。
「い……一緒に、東京まで……帰ら、ないか……?」
「……………!」
ハヤブサが息を飲む気配が伝わって来るから、シュバルツの顔がますます火照ってしまう。「らしくない」ことを言っているのは百も承知だ。ハヤブサの顔なんて、まともに見れないから、下を向いてしまった。
「む、無理にとは、言わないんだ……! そ、その…ハヤブサの、都合が悪ければ……!」
「何を言っているんだシュバルツ! もちろん、喜んで同行させてもらうよ」
「ハヤブサ……!」
顔を上げるシュバルツの視界に、満面の笑みを浮かべたハヤブサの姿が飛び込んでくる。
「シュバルツ……ッ!」
またハヤブサが、抱きついてきたから、シュバルツは驚いてしまった。
「ハヤブサ!? ちょっ……!」
「嬉しいよ……シュバルツ……! 『俺と一緒に居たい』って、そう、望んでくれたんだろう?」
「う………!」
確かにそうなのだ。図星を指されて固まるシュバルツを、ハヤブサは更に強く抱きしめてくる。
「俺も、お前の側に居たい。出来れば、ずっと――――」
「な……! ハヤブサ……!」
「シュバルツ、愛してる……」
シュバルツが何かを言おうとする前に、ハヤブサの唇がそれを塞いでしまう。
「んっ! ん…………」
一瞬強張るが、やはり、それを大人しく受け入れるシュバルツ。震えながらも、そっと添えられてくる彼の手に、シュバルツの『愛』を感じてしまって――――ハヤブサは止まれなくなってしまう。挿し込まれている舌の深度が、自然と、深い物へとなって行った。
「ん……う……! んく……!」
呼吸を奪われ、腕の中で愛おしいヒトがくぐもった声を漏らす。その身体が震えているのを感じる。愛おしい――――なんて、愛おしいのだろう。
止まれない。
もう―――――止まりたく、無い。
とさり。
「…………!?」
気がつけばシュバルツの身体は、ハヤブサによって押し倒されて、いた。
「なッ!? ちょっと……!」
「……………」
驚きの声を上げるシュバルツには答えず、ハヤブサは無言でシュバルツのコートを脱がそうとしている。
「………おい。何をしようとしているんだ?」
「何って、今からお前を抱きたくて――――」
するり、と、コートから引き抜かれるベルト。
「ちょっと待て! ついさっきまで散々抱いただろうが!! それなのに、まだ抱く気か!?」
「今から1週間、お前に触れられないだろう? だから、抱き納めにと思って」
「馬鹿やめろ!! こんな朝っぱらから――――!」
暴れてハヤブサの下から逃れようとするシュバルツを、ハヤブサが一瞬早く押さえつけてしまう。
「無理だ。お前がここに居るのに……!」
我慢なんか出来るか、と呟きながら、ハヤブサの手がコートのボタンをはずし始めた。
「いい加減にしろ!! こんな所を誰かに見られでもしたら―――!!」
ボタンをはずす手を止めようと、シュバルツが足掻く。
「心配しなくとも、こんな所に仲居は入り込んでは来ないさ。入って来たって、そのまま静かに出ていくだろうよ」
「そ、それでも……! あっ!! お前朝食はどうした!? まだ食べていないだろう!?」
「心配せずとも、お前が寝ているうちに食べた。だから次は、お前をおいしく頂こうかと思って――――」
「こらっ!! 人を食べ物か何かみたいに―――!!」
「俺にとってお前は…………とびっきり極上の、『スイーツ』みたいなものだ。だから……いくらでも食べたくなる……」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの頬にチュッ、と、音を立てて唇を落とす。それにシュバルツが「あっ!」と、声を上げてピクリ、と、反応するものだから、ハヤブサの劣情が、ますます煽られてしまう。
ダンッ! と、激しい音を立てて、シュバルツの両手が頭上に一括りにされて押さえつけられて、コートのボタンが総て外されてしまった。
「シュバルツ……愛している……」
シュル……と、音を立てて、シュバルツの首に巻きつけられたスカーフが解かれる。
「馬鹿っ!! 止めろっ!!」
身体の下で、愛おしいヒトが足掻いている。だけどそうやって足掻けば足掻くほど―――徐々にボタンが外されていくシャツは乱れ、白い肌が露出しやすくなっているのを、彼は気付いているのだろうか?
もうシュバルツの動き総てが――――ハヤブサにとっては、自分を誘っているようにしか見えない。
「あれだけ抱いておいて、まだ飽きないのか!? いい加減にしろ!!」
「飽きないな……。飽きるとか、あり得ないから」
「ハヤブサ……ッ!」
シュバルツは、とにかく困惑してしまう。
ハヤブサの、自分を求めてくる『ココロ』に際限が無いのも。
そんなハヤブサに「抱かれても良い」と、思ってしまっている『自分』がいる事にも――――。
でも駄目だ。
キョウジから離れて丸1日。
帰らないと。
そろそろ、心配、しているかもしれないし。
帰らないと。
コワイ
このまま、ハヤブサにずるずると、囚われっぱなしになってしまいそうで――――
「シュバルツ………」
シャツがはだけさせられ、シュバルツの白い胸が露わになる。そこにハヤブサの唇が、落とされようとした瞬間。
コンッ!
小気味良い音が響いて、ハヤブサの頭に何かが落とされた。
「―――――!?」
思わず殺気だって振り返るハヤブサの視界に、一羽の隼の姿が飛び込んでくる。キョウジの近くに『使い』として待機させておいた隼だと気づいて、ハヤブサはそれを無下にしてはいけないと感じた。この鳥がここに来たと言う事は、キョウジから何らかの伝言を預かっている可能性が高いからだ。
「ああ、お前か………」
そう言いながらハヤブサが身を起こす。シュバルツもそんなハヤブサの身体の下から這い出て、乱された胸元を押さえながら、助かった、と、ほっと、息を吐いていた。
近くに隼が落としたとみられる竹筒が転がっている。ハヤブサがそれを拾い上げて開けてみると、中からキョウジが書いたと思われる手紙が出てきた。
その手紙には、短くこう記されていた。
――――もしかして、延長希望?――――
「………………!」
酷く短い手紙。しかし、それだけで――――ハヤブサを『現実』に戻す威力は十二分にあった。
シュバルツは『報酬』
キョウジから提示された、『報酬』
自分は既に、その『報酬』を受け取ってしまっている。それこそ、充分なほどに――――。
だから今度は、キョウジの要望に、自分が応えなくてはいけない番なのだ。
それにしても、自分が受け取ってしまったこの『報酬』
もう自分は、キョウジから何を要求されても――――絶対に逆らえないと、悟る。それほどの物を、自分は受け取っているのだから。最悪、自分の命を要求されたとしても、それこそ自分は、黙ってそれを差し出さなければならないと、思う。
「………帰るか……」
苦笑しながらポツリと言うハヤブサに、シュバルツも「ああ……」と、頷いた。
忍者二人は東京から京都に来た時と同じように、帰りの交通手段も新幹線を選んだ。今からそれで東京へ向かえば、昼過ぎには着く事が出来るだろう。
(ム……いかん……睡魔が………)
新幹線のシートに座って暫くしてからハヤブサは、自分の瞼が急激に重くなってくるのを感じていた。まずい、とは思うが、無理からぬこと、とも思う。何せ、昨夜は一晩中と言っていい程シュバルツを抱いていて、その後は飽く事も無く彼の寝顔を見つめていて――――結局一睡もしていなかったのだから。
いかん、いかん、と思いながらも、カクン、と時々船を漕いでしまう事を、ハヤブサはどうしても抑える事が出来ない。しばらくそうやって彼が睡魔と戯れていると、隣に座っているシュバルツから、声をかけられた。
「……眠いのなら、寝ていろ。着いたら、起こしてやるから……」
「シュバルツ……」
ハヤブサが顔を上げると、シュバルツが苦笑しながらこちらを見ている。
ああ、そうだった。
今は――――『独り』じゃない。
何よりも大切で愛おしいヒトが、こうして、自分の側に居てくれる。
それは なんて 贅沢 で
幸せな 時間 なの だろう
「………ありがとう…。じゃあ、そうさせて……もら……」
その言葉を言い終わらないうちに、ハヤブサはストン、と、眠りに落ちていた。
「ハヤブサ?」
「………………」
シュバルツの呼び掛けに、ハヤブサから返ってくる答えは、穏やかな寝息ばかり。少しばかりシュバルツが彼をつついてみても、微動だにしない。ものの見事にハヤブサは、あけすけに、無防備に―――――その寝顔をシュバルツに曝していた。
(全く、そんなに隙だらけで………。私に寝首を掻かれるとか、こいつは考えないのか―――?)
あまりにも隙だらけなハヤブサの寝姿に、シュバルツは思わず苦笑してしまう。
だが、同時に嬉しくもあった。
ハヤブサがこうして眠りこんでいるのは、まあ、自身の『疲れ』もあるのだろうが、こちらに対して盤石の『信頼』があるからなのだろう。
そうでなければ、こんな風に、眠りこけたりはしないはずだ。
彼は、一流のエージェントで忍者。普通ならば、他人の前でこんなにも無防備な寝姿を晒すなど、あり得ないのだから。
信じてくれている。
頼ってくれている。
「嬉しい」
とても何気なくて、些細な出来事なのだけれども、嬉しい。
幸せを、感じてしまう。
良いのだろうか。
こんなに『幸せ』で―――――
「シュバルツ……」
そんな小さな幸せをシュバルツがしばらく噛みしめていると、ハヤブサから声をかけられた。
「ハヤブサ?」
呼びかけられた声にシュバルツは振り向くが、ハヤブサは、やはり眠ったままだった。どうやら、寝言を言っているらしい。
「シュバルツ……愛している……」
「―――――!」
軽く驚くシュバルツの前で、ハヤブサの顔がふにゃ、と、幸せそうに緩む。
「可愛いな……そんなに、乱れて……」
「……………!」
(おいっ!! 何の夢を見ているんだ!? 何の夢を!!)
思わず固まってしまうシュバルツの横で、ハヤブサの表情はひたすら緩みっぱなしになっていった。そんなハヤブサの寝顔を眺めていると、シュバルツの方も何だか毒気が抜かれてしまう。
(まあ、いいか……。今ぐらいは……)
小さくため息をついて、座りなおす。それにしてもどうしてハヤブサは、自分なんかに愛を囁いて、そんなに幸せそうに笑っていられるのだろう。私は男で。『アンドロイド』で。抱き心地だって、決していいものではないだろうに――――それを思うと、少々理解に苦しんでしまう。
でも…………
(愛している………)
そう言われる事に、喜びを感じてしまう自分がいる事も、また事実なのだ。
どうしよう。
本当は、よくない事だと分かっているのに………。
「ううう……嫌だ……! 2週間も、お前に会えないなんて……!」
幸せそうに緩んでいたハヤブサの顔が、一転して、哀しそうになっている。どうやら、夢の内容が変わってきたらしい。
「……絶対イヤダ……! 3日に1度じゃないと……!」
寝ながら駄々をこね出すハヤブサ。ころころと表情が豊かに変わって、面白い。この寝言、どこまで続くのだろうかと、シュバルツは苦笑いながらも見守っていたのだが。
「シュバルツ……沢庵を食べて……」
ドカッ!!
とりあえず、その寝言には鉄拳制裁を加えておくことにした。
「………おかしいな? 何だか頭が痛いのだが……」
東京についてシュバルツに起こされたハヤブサが、駅の構内で痛む頭をさすりながら首を捻っている。
「……寝違えでもしたんじゃないのか?」
真の原因を知っているシュバルツが、素っとぼけながらハヤブサにつっけんどんに告げた。
「そうか……? そんな寝方をしたっけなぁ……?」
「シートで寝ていたら、自分で気づかなくても変な姿勢になっている事はあるぞ」
そう言いながらすたすたと歩いて行こうとするシュバルツの後ろを、ハヤブサが追いかけてくる。
「あ、待てって、シュバルツ! 俺も、お前と一緒に行くから!」
「? もう、用は済んだんじゃないのか?」
そう言って怪訝そうに振り返るシュバルツに、ハヤブサが微笑みかけた。
「そうだな。『報酬』を受け取ったから、今度は、依頼を果たしに行こうかと思って」
「…………!」
ハヤブサの言葉に、シュバルツも夢から覚めたような気分になる。
そうだった。自分は、『報酬』
キョウジからハヤブサに提示された、『報酬』
キョウジの『依頼』は、ハヤブサに自分の『実験』に協力させること――――
キョウジの実験の内容がどんなものなのか、自分には分からないから――――少し不安になる。ただ、自分ととても深い係わりのあるハヤブサ。だから、実験も『DG細胞』関係の物になる可能性が大だ。
キョウジの事だから、ハヤブサの命にかかわる様な事はしない。大丈夫だと信じたい。
だけど、扱う物が「DG細胞」なだけに、万が一の間違いが、無いとも限らない。
「ハヤブサ………!」
顔を上げるシュバルツの視界に、ハヤブサの優しい笑みが飛び込んでくる。
「俺は大丈夫だ。キョウジの実験だし―――」
「しかし………!」
そう言うシュバルツの頬に、ハヤブサの手が伸びてくる。
「だから………そんな、泣きそうな顔をするな」
「あ………!」
ハヤブサに指摘されて初めて、シュバルツは自分の顔が、酷くこわばっていた事に気づく。
「す、済まない……! 何を、怖がっているんだろうな。私は……」
ハヤブサに触れられている頬を意識しながら、シュバルツは必死に笑みを浮かべようとする。だけど強張って、震えてしまっている頬は、うまく緩んではくれなかった。
どうして、キョウジの実験対象が、ハヤブサなのだろう。
自分ならば、どのような実験であろうと、耐えられるのに。分解されても、機能を停止させられたとしても――――構わないのに。
「シュバルツ………」
自分に心配かけまいと、必死に笑おうとする愛おしいヒト。そのいじましい様子に、ハヤブサの心の中から、彼への愛おしさが溢れてしまう。
キスをして、押し倒したい。
ここが、誰もいない場所ならば――――
だけど、ここは駅の構内。
それをするには、ちょっと人目があり過ぎる。
だから――――
「シュバルツ……このままだと俺は……ここで、お前にキスをしてしまう事になるが――――」
「え…………?」
「それでも………構わない、か……?」
一応、シュバルツに聞いてみた。
する事がする事だけに――――一応、彼の許可をもらった方がいいかな、と、ハヤブサは思っている。
「…………!」
ハヤブサのその一言で、シュバルツは瞬間的に現実に帰った。
人通りの多い駅の構内で、ちょっと美形な男二人が、意味ありげに見つめ合っている風景は日常の中に溶け込ませるには確かに異様で、周りには少し人だかりができつつある。
「あ………!」
そう小さく声を上げながら硬直するシュバルツに対して、ハヤブサは爽やかな笑みを浮かべながら、彼の肩にポン、と、手を置いた。
「俺としては、全世界に向かってお前が俺の恋人だと宣言してもいいのだが―――」
「な――――!」
「もうどうせだから、ここで最後までやっちゃ」
ドカッ!!
そんな馬鹿な意見を吐いたハヤブサは、当然のごとくシュバルツに殴り倒された。
「一度留置所にでもぶち込まれて、頭を冷やせ!! お前は―――!!」
顔を真っ赤にしてぶりぶりと怒りながら、シュバルツはすたすたと歩いて行ってしまう。
「シュ、シュバルツ……! ちょっと……待、って………」
その後を龍の忍者は、よろよろとふらつきながら、追いかけていく羽目になるのであった。
東京近郊のキョウジの家の近くで――――忍者二人は、まだ犬も食わない様な不毛な言い合いをしていた。正確にはシュバルツの機嫌が一方的に悪くて、それをハヤブサがなだめていると言う、状況なのだが。
「シュバルツ~。いい加減、機嫌治してくれよ~……」
「うるさい! 本当にさっきから馬鹿な事ばかり云って……! 貴様の頭の中はそれしかないのか!?」
「しょうがないだろう!? お前の前に出ると、俺はそういうふうに誘導されてしまうのだから……!」
「私は別に、そんな誘導した覚えはないのだが?」
「いや、されるな。どうしても」
「? 何故?」
不思議そうに振り向くシュバルツに、ハヤブサはにっこり微笑みかける。
「だって、お前可愛いんだもん」
「な…………!」
顔を真っ赤にして絶句するシュバルツに、ハヤブサは更にたたみかけてきた。
「お前、ちょっと自覚をした方がいいぞ? 自分がどれほど可愛らしさと色気を周囲にばらまいているか――――」
「ばらまいてなぞいない!! だいたい『可愛い』とか言われても、ちっとも嬉しくない!! いい迷惑だ!!」
「ほらほら、そうやってムキになって怒鳴り散らす所が可愛――――」
ドカバキッ!!
ハヤブサはまたもや、キョウジの家に入る前に完膚なきまでに叩きのめされる羽目になっているのであった。
「――――と、言う訳で、俺は無事に報酬を受け取ったから……」
忍者二人からキョウジはそう報告を受けているのだが、その顔が何故かひきつっている。何故なら――――ハヤブサが妙に傷だらけになっているし、その横に居るシュバルツが、妙に機嫌悪そうにしていたからだ。
「あの……本当に、『報酬』を受け取っているか……?」
キョウジは思わずハヤブサに確認してしまう。
キョウジにしてみれば、あの手紙をきっかけに、二人でゆっくりと話し合って――――お互いの距離が、少しでも縮まればいいと思っていたのだが。
何だか、目の前の二人の様子を見ていると、距離が縮まるどころか逆にひらいて行っているようにも見える。自分の気遣いが本当に『余計なお世話』になってしまっていないか、キョウジはちょっと心配になってしまった。
「俺は充分な『報酬』を受け取っている。心配するな」
ハヤブサがそう言ってキョウジに微笑みかける横で、シュバルツも口を開く。
「キョウジ。この万年発情男にたいして心配するだけ心の無駄だぞ」
「えっ? そうなの?」
問いかけるキョウジに、シュバルツがムスっとしながら答える。
「そうだ。こいつときたら、さっきから馬鹿な事ばかり云って――――」
「だって、お前が可愛――――」
「……………」
シュバルツがものすごく殺気だった目でハヤブサを睨んでくるから、ハヤブサは思わず、キョウジを盾にして、その後ろに隠れてしまう。
「わ、分かった……! もう、言わない……! もう、言いません」
「シュバルツ……。その顔、普通に怖いよ……」
苦笑しながらそう言うキョウジに、シュバルツもプイッとそっぽを向いてしまった。
「キョウジ……俺はもう、本当に充分な『報酬』を受け取った」
小さな声で話しかけてくるハヤブサにキョウジが振り向く。視線が合うと、ハヤブサが微笑みながら頷いた。
「だから――――どんな『実験』だろうと、つきあうぞ」
「ハヤブサ……」
ハヤブサのその様子からキョウジは察する。やはり、ハヤブサとシュバルツの間に、何らかの進展があったのだ。ただ、その進展があり過ぎて、二人の仲が変な方向に発展しているのだろう。どこをどういう風にしたら、今の二人の状態になるのかは、大いに謎だけれども。
「『報酬』には……満足してもらえたのかな?」
穏やかに問うキョウジに、ハヤブサも頷く。
「ああ……本当にもう、充分だ」
(愛してる……! 愛してる……! 愛しているんだ、ハヤブサ……!)
あの時のシュバルツの声、表情――――。
本当に、何度でも何度でも思い出せる。
死ぬほど好きだと思った人から、「愛してる」と言われる。
これ以上ないと言うほど――――幸せだ。
分かる。
この記憶を持っている限り俺は、死ぬ間際ですら――――幸せを噛みしめる事が出来るだろう。
それほどの『報酬』を、俺はもう手に入れてしまったのだから。
「そっか………」
キョウジは穏やかに微笑むと、デスクの椅子からそっと立ち上がった。
「じゃあ、こちらの『依頼』の方に移ろうかな…。ハヤブサ、ついて来てくれる?」
「分かった」
ハヤブサが返事をして立ち上がるのをシュバルツが見つめているが、その眼差しがものすごく心配そうだった。
(あ………なるほど、確かに、可愛らしいかも)
シュバルツのそんな様を見て、キョウジも素直にそう感じてしまう。そして、ちょっと恥ずかしくなる。シュバルツは、ある意味『自分』だ。だからもしかしたら、自分も誰かを心配している時――――あんな眼差しを、してしまっているのかもしれないのだから。
そして当然ハヤブサも、シュバルツのその眼差しに気づいてしまうわけで。
(ああもう……! なんて眼差しで見ているんだ、お前は……!)
酷く胸が、締め付けられる。
『実験』『依頼』『報酬』と言う単語を聞くたびに、泣きそうな眼差しになっているシュバルツ。そんな眼差しをして欲しくないから、『俺の事なんて心配しなくていい』と、言いたいから――――さっきからわざと怒らせるような言動行動を、していると言うのに。
それなのにシュバルツは、まだ、俺の事を心配してくれている。
怒っているのだから。
殴っているのだから。
俺の心配なんて、しなくていいのに――――。
俺の事を赦し過ぎだ。お前は。
俺はこんな、ろくでなしなのに。
(愛している、から………)
「……………!」
シュバルツの声なき声。拾ってしまって、耳が火照る。
実はハヤブサは『実験』と言う言葉には、あまり良いイメージを持っていない。
『龍剣』と言う特殊な剣を操る彼の『血』の能力。そして、あまりにも高い忍びとしての技量と身体能力を誇るが故に――――彼自身よく「マッドサイエンティスト」と呼ばれる類の人々に狙われてきた。時には捕まり、無理やり実験場に放り込まれた事もある。能力の限界を調べるために行われた実験は、苛烈を極めた。そのせいで、生死の境を何度彷徨ったことだろう。
今回は、キョウジが行う『実験』だから、そこまで苛烈な目に遭わされる事はないだろうと推測する。だが、自分が受け取った『報酬』の事を考えると、そこまでの目に遭わされたって文句は言えない。
それでもいい。
これが、シュバルツのために行われる『実験』だと言うのなら
俺の身体など、どのように使ってもらっても構わないのだ。
地下へと続く階段を下りていったキョウジが、ハヤブサを部屋の中へと導く。
「ここに研究施設があると言う事は、私たちだけの秘密だから――――ハヤブサも、他言無用で頼みますね」
笑顔でそう言ってくるキョウジに、ハヤブサは頷いた。部屋の中には薬品らしきモノの匂いが漂っていて、ちょっとした病院の施設の様だと、ハヤブサは思った。
「その辺に適当に腰をかけて、待ってて」
そう言いながら、キョウジの姿がパタパタと音を立てて、部屋の奥へと消えていく。部屋の出入り口付近では、後からついて来ていたシュバルツが腕組みをして壁にもたれかかっていた。
俺の事を見張ろうとしているのか、それとも、何の実験が行われるのかを見極めようとしているのか――――彼の静かなたたずまいからは読み取る事が出来ない。極力自分の感情を抑え込もうとしているようにもみえる。
板挟まれているのだろうか。
キョウジの意思を尊重したい気持ちと、俺を想う心の間で。
もしも彼が、苦しんでしまっているのだとしたら――――
「お待たせ、ハヤブサ………って、あれ?」
白衣を羽織り、手にいくつかの医療器具を入れたタッパーを持ってパタパタと歩いて来たキョウジが、ハヤブサの姿を確認した途端、動きを止めてしまう。何故なら彼が――――ものすごく幸せそうな顔をして、そこに座っていたからだ。
「え……? あれ……? 私がいない間に、何かあった……?」
「いや……特に、何も無いぞ?」
キョウジの問いかけにハヤブサが答えるが、その彼の頭上に、気のせいかお花が舞っている。そして彼の表情は、ずっと幸せそうに緩みっぱなしだった。
「シュバルツ……? これは、一体……?」
「私が知るか! こいつは今朝から、ずっとこんな調子なんだ!」
シュバルツの方に振り返って問いかけるキョウジに、シュバルツもそう言いながら頭を抱えてしまう。確かにハヤブサは、自分に会っている時に柔らかな表情をしている事が多い。しかし今朝からはどうした事か、その症状が酷くなっている様な気がするのだ。
一体、何がどうしてこうなった?
『媚薬』の熱で浮かされて、いろいろ私が言っちゃったりやっちゃったりした事が、原因なのだろうか。
でもその時の事を、彼も「よく覚えていない」と、言っていたし……。
「ま、まあいいや。とりあえず、こちらの用事も済ませてしまおう」
そう言いながら、キョウジが持ってきたタッパーの中から医療器具を一つ取りだす。
「それじゃあハヤブサ。腕を出して」
言われたとおりに出されたハヤブサの腕に、キョウジは駆血帯を巻きつけている。明らかに『注射』の準備だ。
「…………!」
それを見た瞬間、シュバルツの脳裏に嫌なビジョンがよぎる。
まさか
まさか、キョウジは
ハヤブサに直接『DG細胞』を移植しようとする気じゃ――――?
『DG細胞』の感染と発症、そして、その因果関係を人間の身体を使って調べようとするのに、ハヤブサの身体を使う可能性は大だ。自分と深く交じり合っても、DG細胞の症状を発症しないハヤブサ。この研究の『被験体』とするには、これ以上ない程うってつけの人材だ。
でも、DG細胞の生体実験なんて駄目だ。あらゆる意味で危険すぎる。
いくらハヤブサが実験の被験体にされることに同意していると言っても、こんな事は――――道義的に許される事じゃない。
キョウジのする事に反対はしたくない。
だけど………!
「それじゃあハヤブサ、少しチクッとするけど―――」
そう言いながらキョウジが、注射器を構える。
「問題ない。大丈夫だ」
そう言って、穏やかに微笑むハヤブサを見た瞬間――――シュバルツは、弾かれるように動いてしまった。
「ま、待て!! キョウジ!!」
「な、何!? シュバルツ……!」
急にシュバルツに大声をかけられたキョウジが、驚いて動きを止める。その手を、走り寄ってきたシュバルツが掴んできた。
「キョウジ駄目だ! いくらなんでも早すぎる! こんな実験は―――!」
「えっ!? 駄目だった!? 私はハヤブサの採血をしようとしただけだけど……?」
「へっ?」
きょとん、とこちらを見るキョウジと同じように、シュバルツもきょとん、としてしまう。
「採血……?」
「うん。採血。ちょっとハヤブサの血を貰おうかな~って、思って……」
そう言うキョウジの手元にシュバルツが視線を走らせると、彼の手に持っている注射器の中身は空っぽで、タッパーの中に入っている医療器具も、紛うことなく採血用の用具しかなかった。
「あ………!」
自分のとんでもない早とちりに茫然とするシュバルツ。それを見たハヤブサは、思わず――――
「シュバルツ……!」
彼の身体を、ギュッと、抱きしめて、いた。
「ハ、ハヤブサ!?」
「シュバルツ、嬉しいよ……! 俺の事を…心配、してくれたんだろう?」
「――――!」
ハヤブサに図星を指されたシュバルツの頬が、カッと、朱に染まる。ハヤブサは、そんなシュバルツの頬に優しく唇を落とすと、その耳元に囁いた。
「シュバルツ……愛している……!」
「ハ、ハヤブサ……! ちょっ……!」
「好きだ……! 好きなんだ……! 大好きだ……!」
「ば、馬鹿っ! 何を、言って……!」
「離さない……! 離したくない……! シュバルツ……!」
「あ………」
ハヤブサの手が、シュバルツの顎を捉える。そのまま、彼の唇を奪おうとした瞬間。
「あの~……お取り込み中、すみませんが……」
「――――――!!」
キョウジに声を掛けられて、忍者二人は、はっと、我に帰った。
「ごめんね? いちゃつくのならせめて、採血が終わってからにしてくれる?」
「うわ! は、はい!!」
キョウジの言葉にハヤブサは慌てて席に着き、シュバルツは顔を気の毒なほど真っ赤にして、思いっきり壁際に身を寄せている。
「あの……なんか、いろいろ、ごめんね?」
苦笑しながら採血の準備を再びし直すキョウジに、ハヤブサも「いや……」と、ばつの悪い返事をするしかなかった。ハヤブサが差し出した腕に駆血帯を巻き、手際よく採血を済ませて行く。
「採血をして……それから俺は、どうすればいいんだ?」
採血をされた腕の止血をしながら、ハヤブサはキョウジに問いかける。
「えっ? えっと……これで用事は、終わりだけど……?」
「えっ?」
きょとんとするハヤブサに、キョウジもきょとん、としてしまう。
「『えっ?』とは……?」
「いや、だって……実験は?」
「あ、うん。『実験』をする『材料』に、ハヤブサの『血』が欲しくて……」
「えっ?」
「えっ? 駄目だった?」
「いや、そうじゃなくて――――」
ハヤブサは茫然としてしまう。何か、自分がイメージして覚悟していた展開と、あまりにも違いすぎるからだ。
「俺の身体を使ったりはしないのか? 実験施設に放り込んで、今まで戦った敵と強制的に戦わせたりとか、身体能力を調べるために、他にもいろいろ――――」
「ぐ、具体的だね……。まさか、実体験?」
「い、いや……そう言う訳ではないが……」
キョウジの言葉を否定しながら、ハヤブサは変な汗をかいてしまう。こんな僅かな血の提供だけで、あれだけの『報酬』を受け取ってしまったのでは――――
あまりにも、いろいろとキョウジの方に、割が合わなさすぎる様な気がする。
「そ、その……『報酬』が……」
「えっ? 足りなかった!?」
「い…いや、報酬は、充分だ……!」
慌ててそう言うハヤブサに、キョウジはにっこりと微笑んだ。
「何だ、良かった……! 『血』とか『遺伝子』ってある意味究極の個人情報だから――――ハヤブサに嫌がられたらどうしようかと思ってたんだけど……」
「……………!」
キョウジの言葉に、ハヤブサは考え込んでしまう。
確かに、DNAはある意味究極の個人情報とも言えるが、そこまで神経質になる必要はあるのだろうか? いや、でも、キョウジほどの腕と頭脳を持つ科学者にDNAの情報を渡してしまうのは危険なのか? キョウジには確かに、それを利用し得るだけの才能を持っているのだから。良い方にも、悪い方にも――――。
でも、キョウジがそれを悪意を持って利用するとは考えにくい。
やはり、健康診断レベルの採血量でこの報酬を受け取ってしまうのは、気が引けてしまう。でも、『返す』と言っても返し様が無いし、絶対に返したくもないから――――余計に困った。
「……キョウジ……。これでは俺が『報酬』を受け取り過ぎと言う事になってしまう」
自分の正直な気持ちを、率直にキョウジに告げる。
あの晩受け取った『シュバルツ』は、本当に、一生ものの宝と言っても過言ではない物だったから。それに見合う働きを、自分はせねばならない、と、思うのだ。
「えっ? そうなの?」
問い返してくるキョウジに、ハヤブサは頷いた。
「もっと何か……俺に返させてくれ、キョウジ」
「……………」
キョウジを見つめるハヤブサの眼差しは、真剣そのものだ。
(ああ、シュバルツは……もうハヤブサに、それだけの事を言わせる『モノ』を、渡す事が出来たんだな……)
そう感じて、キョウジは嬉しくもあり――――少し、淋しくもあった。自分の大事な兄弟を手元から手放す様な、そんな複雑な気持ちに近いものを味わってしまう。
でもそれは、素直に喜ぶべきことではないのか。
シュバルツが、『シュバルツ』としての一歩を、踏み出して行った事になるのだから。
幸せに、なって欲しい。
シュバルツも、ハヤブサも。
自分も出来得る限り
その『幸せ』の手助けをするから――――
「………それじゃあ、ハヤブサ…。これからも、定期的に私の『健診』を受けに来てくれないか?」
「えっ?」
顔を上げるハヤブサに、キョウジはにっこりと微笑みかける。
「貴方のメディカル・チェックをしたいんだ。長期的に、調べてみたい事もあるし……」
そう。シュバルツと、深い交わりを持つハヤブサ。DG細胞は、本当にハヤブサには感染しないのか。だとしたら、その原因は何なのか。それとも、シュバルツを構成している細胞自体が特殊なのか――――可能ならば、調べてみたい。
その『被験体』にハヤブサがなってくれると言うのなら、まさにうってつけの人材だ。
「……………」
「もちろん、強制はしない。迷惑だと言うのなら――――」
ただ、『被験体』となると言うのであるならば、シュバルツとの関係を継続させ続けなければならない。そして、ハヤブサ自身にもリスクが伴う。物がDG細胞なだけに、万が一の間違いが、起こらないとも限らないからだ。
「俺は、構わないぞ。キョウジ」
「ハヤブサ……!」
即答して来た龍の忍者に、キョウジは少し驚いてしまう。
「それで俺が受け取った『報酬』を返せるのなら……容易いことだ」
そう言って穏やかに微笑むハヤブサは、もう覚悟を決めてしまっているのだろう。これからの生を、シュバルツと共に歩んで行く覚悟を――――。
「ハヤブサ……?」
シュバルツは、穏やかに微笑むハヤブサを、少しざわついた気持ちで見つめていた。
何故なのだろう。
ハヤブサに、何かさせてはいけない『決意』の様な物を、させてしまっている様な気がする。
もしかしたら自分は、ハヤブサを止めなければならないのではないだろうか。
そう強く感じたシュバルツが、一歩、足を踏み出そうとする。だが、その気配をいち早く察知したハヤブサが、シュバルツの動きを封じるべく口を開いた。
冗談じゃない。
シュバルツの側に居たい。キョウジとシュバルツの役に立ちたい。
そう願う俺の気持ちを、誰にも邪魔などさせるものか。
例えシュバルツ、それがお前自身であろうとも――――だ。
「ところでキョウジ」
「何? ハヤブサ」
「『定期的』に健診を受けに来いという話だが……どれぐらい間を置いて来ればいいのだ? やはり、3日に1回ぐらいか?」
ズルッ。
足を踏み出そうとしたシュバルツが、こけた。
「いや……3日に一回は、さすがに多いね」
キョウジが苦笑しながら言葉を続ける。
「やっぱり、半年に一回ぐらいかな」
「は、半年!?」
龍の忍者は立ちくらみを起こす。
「どうした? ハヤブサ」
倒れかけたハヤブサを心配したキョウジが問いかけると、ハヤブサが震えながら口を開いて来た。
「ままま、まさか……半年の間、シュバルツと触れ合ったりしちゃ駄目だとか……言わないよな?」
「ああ、それは大丈夫だよ」
キョウジはにっこりと微笑む。
「いつも通り――――『仲良く』してくれていたら……」
「………! やった――――!!!」
天にも昇らん勢いで喜び勇んだ龍の忍者は、早速シュバルツに抱きつきに行く。
「ハ、ハヤブサ!?」
「シュバルツ……! こうしてめでたくキョウジにも許可をもらった事だし、早速今から」
「何でそうなるんだッ!!」
そしてやはりと言うべきか――――シュバルツに殴り倒されてしまっていた。
「………全く…! どうしてあいつはあんな事ばかり云うんだ……!」
結局あれからシュバルツは、ハヤブサの『抱きたい』と言う願いを拒み通して、「1週間後じゃないと身体は赦さない!」と、怒鳴りつけて、ハヤブサをどうにかこうにか追い返していた。玄関のドアにもたれかかって、大きなため息を一つ吐く。
おかしい。
何であいつに、あんなに懐かれてしまっているのだろう。
「ハヤブサ……帰った?」
問いかけてくるキョウジにシュバルツは頷く。
「ああ……。帰った……。1週間後にならないと、来ないと信じたいが……」
「何か……シュバルツは、物凄くハヤブサに『懐かれて』いるよねぇ」
「キョウジもそう思うか?」
「思った……。ちょっと大きなわんこみたいで、可愛なと思ったけどね……」
「わんこ………」
キョウジのその発言に、シュバルツの脳裏に犬化したハヤブサの映像が浮かんで来てしまって――――笑いをこらえるのに、必死にならなければならなかった。
「ハヤブサとの1日……シュバルツは、楽しかった?」
「う~ん………」
キョウジのその質問に、シュバルツは少し考え込んでしまう。いろいろあった――――いや、あり過ぎた1日だった。でも、楽しかったと言えば、楽しかったのだろうか。
(ハヤブサ………)
シュバルツは、ハヤブサに想いを馳せる。
意外にも博識で、歴史や古美術に造詣の深いハヤブサ。
優しい人たちと、静かな時間を紡いでいたハヤブサ。
静かに立っていれば、それなりに格好いいのに。
ハヤブサが、自分だけに見せる表情は、驚くほどに色彩豊かだ。
泣いたり、笑ったり、怒ったり、時に冷徹だったり、欲を剥き出しにしてきたり。
(愛してる……)
何故、あんなに幸せそうに、愛の言葉を囁けるのだろう。
私はどう足掻いても、同じ物を返せないのに――――。
「シュバルツ」
不意にキョウジに呼びかけられて、シュバルツは、はっと我に帰る。
「な、何だ? キョウジ……」
慌てて返事をするシュバルツに、キョウジはにっこりと微笑みかけた。
「最後に私から、多分最もベタな言葉を、貴方に贈らせて」
「?」
きょとん、と、小首をかしげるシュバルツに向かって、キョウジは口を開く。
「『貴方の幸せが、私にとっての幸せ』――――だよ」
「――――!」
茫然とするシュバルツに、キョウジは更に微笑みかける。
「だから、幸せになってね。シュバルツ」
「な………! な………!」
そう言って、しばらく身体を小さく震わせていたシュバルツであったが、やがて弾かれた様に叫び出した。
「ずるい!! その台詞は、私がキョウジに贈りたい物だったのに―――!!」
「そうなの? でも先にシュバルツの方に幸せが訪れそうだったから……」
「のしつけて返すから、お前の方こそ幸せになってくれ!」
「ダメ~。返品不可。私はお前の幸せを、堪能する事にするから……」
「そ、そんな事言われても―――!」
「だから言っただろう? シュバルツ」
キョウジは同じ言葉をもう一度、シュバルツに贈る。
「『貴方の幸せが、私にとっての幸せ』――――だよ」
「だから!! その言葉は私がお前に―――!!」
明るい日差しが降りそそぐ部屋の中で、キョウジとシュバルツのじゃれあいともいえる言い合いは、まだしばらく続きそうだった。そんな二人が暮らす街の空は、今日も平和だった。
終幕
ご愛読、ありがとうございました。
プレゼント
どうも、こんにちは。空由佳子と申します。
いつも作品を読んでくださっている方、また、そうでない方も、ここの文章を見つけてくださって、どうもありがとうございます。心よりの感謝を申し上げます。
……それにしても、色気のあるシーンて、どうしてこんなに難しいんでしょう(笑)。
おのれ自身がそこに振り回されても駄目ですし、どこか冷静で、客観的な己を保ってないといけないのかな~と、何となく感じさせていただきました。まあそれは、文章を書くにあたって、全部に言えることかもしれませんが。
私自身は、とても楽しんで書かせていただきました。完全に自己満足の世界かもしれませんが、書きあげられて、今はとても嬉しく、ほっとしてもいます。
また気が向いたら、何か書くかもしれませんが、その時は、またこうして読んでいただけたら嬉しいです。
それでは。