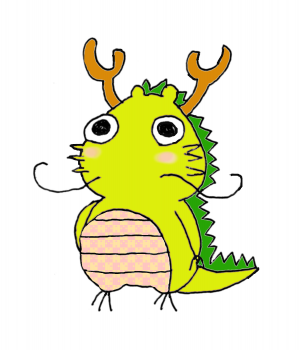美しいヒト
前の小説を書き終わった後、困ったことに、どうしても書きたくなった小説です。
だから思いきって書いてみることにしましたが、いかんせん『腐』要素が大変強い内容となってしまっています。苦手な方、理解できない方は、どうかご遠慮ください。
ちなみに『腐』の要素となっている掛け算は、ハヤブサさん×シュバルツさんです。このカップリング、『需要』あるのでしょうかね(笑)?
付き合えるよ~! という強者だけ、どうか御進みください(笑)。
登場人物を紹介させていただきます。
・リュウ・ハヤブサ ……伝説の『龍の忍者』 隼の里の次期頭首。
・シュバルツ・ブルーダー ……ゲルマン流忍術を使いこなす青年。実は、キョウジ・カッシュのコピーアンドロイド。
・キョウジ・カッシュ ……シュバルツの人格の元となった青年。
・隼の里の人々 ……『龍の忍者』をはぐくんだ里に住む人々。
・甲賀忍軍・百足衆 ……隼の里と『龍剣』を狙う忍者集団。
と、まあ、こんなところでしょうか。
それではよろしくお願いします!
序章
(ハヤブサ……)
消え入りそうな声が、俺の腕の中から聞こえてくる。
「シュバルツ……」
呼び掛ける俺の声にビクッ! と反応したシュバルツは、身をよじって逃げだそうとした。
逃げるな。
逃げないでくれ。
俺は夢中で押さえつける。
その頬にキスを落としながら、首に巻かれているスカーフを、シュル、と音を立てて取り払った。
「は……あ……っ」
それと共に現れる、無防備な首筋。
(ああ、この肌だ)
その白い首筋に、俺は何度も口付けを落とす。この肌の白さ、冷たさを――――俺は、どれだけ夢見た事だろう。
「あ……っ! 駄目……だっ……!」
俺がその肌に触れるたびに、ビクン、ビクン、と、身をよじって反応するシュバルツ。
(感じやすいのだな)
何故か嬉しく思いながら、更にシュバルツを暴きたてたくて、夢中で服のボタンをはずす。
「ハヤブサ……ッ!」
シュバルツが懸命に抗おうとする。身をよじって、自分の腕の中から逃げ出そうとさえ、していた。
何故逃げる?
ああ、逃げないで。
逃げないで、くれ。
しかしシュバルツは、弱々しいながらも抵抗する事を止めない。いつしか彼の頬に、涙が伝っているのが見えた。
「ハ、ヤブサ……ッ! 駄目だ……ッ!」
「シュバルツ――――」
何とか抵抗を封じようと試みながら、俺はシュバルツに呼びかける。
怯えるな。
逃げないでくれ。
俺は、お前を殺したいわけじゃないんだ。
ただ――――お前が、欲しいだけなんだ。
だからどうか、怯えずに。
俺を、受け入れてくれ……!
「いや……! 嫌、だ……ッ!」
だがシュバルツは、頭(かぶり)をふりながら叫んだ。
「キョウジ……ッ!」
「―――――!」
鈍器で殴られたような衝撃を受けるハヤブサの下で、尚もシュバルツは叫び続けた。
「キョウジ……! キョウジ……ッ!」
(シュバルツ――――!!)
目の前が真っ黒になる。
シュバルツに触れている手が、知らず震える。
駄目なのか!?
やはり――――俺では、駄目なのか……!?
お前が『触れたい』と。
『触れてほしい』と願う相手は。
『キョウジ』なのか――――!?
「シュバルツ! お前の目の前に居るのは『俺』だ!!」
たまらずハヤブサは、叫んでいた。
「俺を――――『俺』だけを、見てくれ!!」
まるで噛みつく様な口付けをする。
「ん……う…っ!」
呼吸を奪われ、口腔を蹂躙されたシュバルツの手から、力が抜けて行くのが分かった。パタ、と音を立てて、手が力なく横えられる。
「シュバルツ……」
抵抗が止んだと悟ったハヤブサは、シュバルツを口付けから解放した。
「ハヤブサ……」
見上げてくるシュバルツの瞳が、涙で潤んでいる。彼の頬には乱れた髪が付着し、その口許からは、彼が飲みきれなかった唾液が流れ落ちていた。ハヤブサによって乱された服から、白い肌が露出し―――何とも艶めかしい雰囲気を醸し出している。
(ああ……やっぱり、美しい……)
一気に手折って蹂躙してしまいたい気持ちと、この美しさをもう少し堪能したいと言う、どうしようもない欲の間で揺れ動く。その瞬間、僅かな隙が生じてしまったらしい。
「済まない、ハヤブサ…。私は―――!」
それだけを言うと、腕の中の美しいヒトは、細かい光の粒子のようになって、サアッ、と、音を立てて消えて行ってしまった。「シュバルツ!」と、叫んで伸ばされたハヤブサの手は間に合わず、空しく空を切るだけだった。
腕の中には、空蝉のごとく、ただロングコートだけが残った。
「シュバルツ……! 何故だ……ッ!」
ハヤブサは、ロングコートを抱きしめて咽び泣いていた。
その自身の泣き声で――――ハヤブサは『夢』から覚めた己を自覚した。
第1章
ハヤブサは辟易していた。
もうずっとだ。ずっと、こんな調子だ。
夢の中での話であるが、気がつけばハヤブサは、シュバルツを己の下に組み敷いている事が多くなっていた。そして、その身体を獣のように貪り蹂躙する事もあれば、先程(さっき)の様に「キョウジ!」と叫ばれて、逃げられてしまうことも多々あった。
(狂っているのか、俺は)
そう思いため息をついて、自嘲的な笑みを浮かべる。
狂う――――いっそ、狂ってしまった方が楽かもしれない。
自分のこの『想い』が、ある種狂気じみている物である事を、ハヤブサは充分すぎるほど自覚していた。
何故なら、シュバルツは、生物学上『男』の容姿をしていて。
そして彼は、『人間』ですら、無かったのだから――――。
それを『抱きたい』だなんて、およそ正気の沙汰じゃない。
シュバルツとの出会いは強烈だった。
先の『龍の勾玉』の事件の際、ハヤブサは、勾玉をその身に宿した『キョウジ・カッシュ』と言う青年を狙った。シュバルツは、そのキョウジを守護する者であったがために、必然的に二人はぶつかり合う事となった。
シュバルツには忍びの心得があり、そして、その剣の腕はハヤブサと互角の物だった。
いつ果てるともない剣の打ち合いが続いた。痺れるような一騎打ちだった。
だが、シュバルツは――――たった一人の子供を助けるためだけに、あっさり戦いを放棄してしまう。そのあまりにも愚直な姿を見てしまったハヤブサは、思わず彼を『斬り損ねて』しまった。
その『斬り損ねた』自分を、シュバルツの方が先に信じた。
信じたが故に、その後どんなにハヤブサがシュバルツに敵意を向けようか、殺意を向けようが――――一度開いた信頼の扉を、彼は自分から閉ざしてしまうような事は決してしなかった。
(斬るなら斬れ)と、シュバルツはハヤブサに手を広げ続けていた。
騙し騙される事が『常』である『闇の世界』に生きて行くには、それはあまりにも愚かで、誠意があり過ぎる姿だった。だが彼は、たった一人でその姿勢を貫き通していた。
見返りを求める事もせず。
己の身すら、顧みずに――――。
その姿に惹かれて行った。
どうしようもなく、惹かれて行ったのだ。
そして、シュバルツと瓜二つの外見を持つ『キョウジ・カッシュ』と出会い―――。
シュバルツとキョウジの間に起きた、『悲劇』を知った。
そして知る。シュバルツの正体を。
彼は死した人間の上に『DG細胞』でキョウジの情報を上書きされた、キョウジのアンドロイドなのだと。
『DG細胞』と言う特殊なモノで構成されているシュバルツの身体は、死ぬ事が無い。
生きていない身体。だけど、死ぬことも出来ない身体。
酷く不自然で――――歪(いびつ)な存在。彼は己の事を、そう定義づけていた。
だから、見返りなど、求める資格もない。
己の身など、顧みられない。顧みてはいけない。
そして、自分を産み出した『親』にも匹敵するキョウジを、ただ朴訥に守りたいと願う――――。
そんなシュバルツの姿を知れば知るほど、自分の中で彼に対する想いは、ただ増して行くばかりだ。自分がシュバルツに堕ちて行くのを止める手段など、ハヤブサの中ではとっくに崩壊していた。
「どうした? ハヤブサ」
目の前に居るシュバルツから声を掛けられて、ハヤブサは、はっと我に返る。
「あ、ああ。いや……何でも無い…」
シュバルツに答えを返しながら、ハヤブサは頭を振る。どうやら、自分は少し転寝(うたたね)をしてしまっていたらしい。
(……無理もないか。最近、特に変な夢ばかり見るから―――)
そう感じて苦笑する。夢の内容など、目の前の男にはとても言えない。
キョウジの住むアパートから少し離れた場所にある、郊外の森の中。ハヤブサは、ここで時折シュバルツに会う様にしていた。
(『逢瀬』だよな。これって……)
ほぼ一方的な想いだとは百も承知しているのだが、ハヤブサは、そう思わずにはいられなかった。それほどまでにハヤブサにとってシュバルツに会う事は、喜ばしい事なのだ。
シュバルツと会うならば、緑豊かな自然の中がいい―――と、ハヤブサは思う。
『自然』から一番程遠い身体をしているシュバルツにとって、ぐるり自然に取り囲まれる事など、自分の『歪さ』を際立たせる行為なのではないかと思う。
しかし、目の前に居る男は、穏やかな顔をしてそこに立っていた。
自らの『歪さ』を受け入れ――――なおかつ周りの世界を愛していなければ、こんな表情など出来ないであろう。彼の懐の深さと心根の美しさが、よく分かる瞬間でもある。自然を、穏やかな表情で愛する彼の姿を見るのが、ハヤブサはとても好きだった。
「……『任務』が終わったばかりなんだろう? 無理をせず、早く里に帰って休んだ方がいいんじゃないのか?」
「だから、こうして休んでいるんじゃないか」
シュバルツに心配された事が素直に嬉しいハヤブサの面(おもて)に、自然と笑みが浮かぶ。
「そうなのか?」
「そうだよ」
「…………」
しばらく無言でハヤブサを眺めていたシュバルツであったが、やがて小さくため息を吐いた。
「まあ……それでお前がいいのなら、良いけど―――」
シュバルツはそう言いながら、ハヤブサのいる近くの木に、トン、とその背を凭れかけさせる。そして腕を組んで、そのまま静かに佇んでいた。だが、彼のその姿には一分の隙もなく、彼の周囲を探る気配が、周りに張り巡らされているのが分かる。
(守ってくれているのか……)
『任務』を終えたばかりのハヤブサに、追手がかかっていないかを確かめるように。少し疲れ気味のハヤブサが、ゆっくり休めるように――――。これは、ハヤブサが特にシュバルツに頼み込んだ訳ではない。しかし、彼は黙ってそういう配慮をする。『シュバルツ・ブルーダー』とは、そういう男だった。
(今だけ、彼の好意に甘えよう)
ハヤブサはそう思って目を閉じた。
あと少しすれば、自分は『任務完了』の報告をしに、里の方へ戻らなければならない。
シュバルツも、キョウジの元へと戻っていくのだろう。
だけど、今―――自分を守るためにそこに佇んでいるシュバルツは、確実に俺だけのものだ。
俺の
俺だけの
シュバルツ。
もう一度お前に『触れたい』と、願ってはいけないのだろうか――――。
夢とも現実とも区別がつかぬまどろみの中で、ハヤブサはそう思っていた。
「……ハヤブサよ。お主は何か『未練』を抱えてはおらんか?」
「…………!」
今回の任務の事の顛末を里の長老に報告をしていたハヤブサは、長老からの思わぬ指摘に顔を上げた。
「お主から、らしからぬ『気』の乱れを感じる……」
そう言いながら、長老は目の前のハヤブサをじっと見据える。いつもの龍の忍者であるならば、どのような任務をこなした後でも、迷わず、恐れず、泰然としているものであるのに。
「未練………」
ハヤブサは心当たりがあるのか、長老とは視線を合わせず、虚空の1点をじっと見つめている。その様子を見た長老は、ため息を吐いた。
「……我ら忍者は、常に死と隣り合わせだ。誰もが、いつどこで、その命を落とすか分からん中で、生きている……」
そう。自分の様に、長く生きながらえてしまう者など稀だ。だから長く生きてきたという事は、それだけ多くの命が散っていくのを、見届けてきたという事でもある。
「生き延びるためには、目の前の事象に迷ってはならん。恐怖してはならん…。『未練』は、死への恐怖を産み、『恐怖』は、判断に迷いを生じさせる……。己の命を捨てる覚悟を持ってこそ、生き延びる道も開けてくると言うものだ……」
長老は、目の前に居る龍の忍者の身を案じてそう声をかけた。この龍の忍者の命まで見送る側にはなりたくない、と、願ったが故の、長老の言葉であった。
「……………」
ハヤブサは長老の言葉に答えは返さなかった。ただ、己の中の『未練』の原因に、想いを馳せ続けていた。
(『未練』―――確かに、『未練』かもな……)
ハヤブサは里の中でも一二を争う背の高さを誇る木の上に登り、そこから空に青白く輝く月を眺めていた。
ハヤブサがシュバルツに『性的に』触れたのはたった一度だけ。
たった一度――――深く、深く口づけた。
見せつけられたからだ。
シュバルツにとってキョウジはどうしたって特別な存在で――――。
それは、目の前に居る自分の存在をも、シュバルツの中から奪い去ってしまう程だった。
それが分かってしまって――――無性に腹が立った。
だから。
「俺もここに居るのだ」と、主張したくて、その唇を奪ったのだ。
その成り立ちに、人の『死体』が使われていると言うシュバルツ。だが、シュバルツからはそのような匂いはしなかった。そしてその口腔は、冷たくは無かった。寧ろ、想像していたよりもずっと温かかった。
じゃあ、その肌は?
シュバルツの、内部(なか)は……?
触れたい。
もっと知りたい。
刻みつけたい。
『俺』を叩きつけたい。
シュバルツが、俺の事を忘れようとしても、忘れられなくなるほどに。
キョウジでさえ触れる事の出来ない、深い、深いその場所に―――。
あの『美しいヒト』に、傷をつけてやりたいのだ。
それが叶うまで―――『死にたくない』
それが、ハヤブサの『未練』となった。
いつ死ぬのか自身でさえもわからない『闇』の世界で生きているが故に、その想いは一層強くなって行くばかりだ。
(シュバルツ………)
誰に忘れ去られてしまってもいい。
だが、お前にだけは――――覚えていて欲しいと願う。俺の事を。
キョウジと共に生き、キョウジと共に死ぬ運命のシュバルツ。
だが―――その呪縛から解き放たれ、永劫に生きてしまう可能性もあるシュバルツ。
どちらにしろ『共に生きる』とは、言ってやれない俺。
だから――――。
せめて、彼の 『傷』 に、なりたいのだ。
(―――『悪食』だぞ!)
冗談でカモフラージュしながらシュバルツに手を出そうとして、こちらの手を撥ね退けるたびに、そう言って怒っていた彼の顔が浮かぶ。自分の身体の歪さを自覚しているが故に、彼はそう叫ぶのだ。
(『悪食』……確かにな。『悪食』の上に、『横恋慕』だ……)
ハヤブサは己の事をそう感じて、低く笑う。
でも、もう、どうしようもないのだ。
どうしようもない程、惹かれる。
青白く輝く月の光に、愛おしいヒトの姿を重ねて手を伸ばす。光は掴む事が出来ずにただすり抜け、月に己が手も届く事は無い。これが現実だ。よく、分かっている。
ならば、自分の中に熱く燻ぶってしまっている想いを、どうすればいいのか――――。
今宵もまた、眠れそうにない。
そう感じて苦笑するハヤブサの姿を、月明かりはただ優しく照らし続けていた―――。
それから幾日か過ぎた。
草原の中を、一つの『任務』を終えた龍の忍者が、疾走する姿があった。諸々の事象を滞りなく片付け、後は里に『任務完了』の報告をするだけだった。
(よかった……。無事に『帰れる』……)
ハヤブサは安堵のため息を漏らして、そして、はっと我に返った。
(馬鹿な―――! 何故俺は『安堵』している…!?)
自分の命がつながった事に『安心』してしまうなんて、『未練』が、『執着』が、強くなってきている証拠だ。このままでは任務に支障をきたしかねない、と、ハヤブサは思った。
それにしても―――と、ハヤブサは目を閉じる。自分の住む世界と受ける『任務』の性格上やむを得ないのかもしれないが、どうしても目に飛び込んできてしまうのは、人の醜さ、世界の汚さばかりだ。
人は己の欲のために簡単に他人を蹴落とし、踏みにじる。踏みにじられた者は怨嗟の声を上げながら、さらに弱いものに牙をむく。『弱さは悪だ』と言わんばかりの現実が横行し、力無き者に、それを抗う手段は無い。一握りの強欲な強者がまかり通るのが現実だ。
人は、汚い。世界は、汚い――――。
だが。
ハヤブサは、胸の奥に居る愛しいヒトの姿を思う。
そのヒトは、見返りを求めずに愛をふるまう。無条件で、弱者をその背に守る。
その姿を見ていると――――まだ、信じられるのだ。
人の心の優しさを。世界の美しさを。
あの、明かりの灯る一つ一つの窓の中に、小さな幸せを紡いでいる命が確かに『あるのだ』と言う事を、信じる事が出来るのだ。
(あの森で、シュバルツに会ってから、里へ帰ろう)
実際に、『会おう』と約束をしている訳ではないから、その森に行った所で、シュバルツに会えるとは限らない。下手をしたら何日も待ちぼうけを喰らう可能性だってある。
だが今は―――無性に、シュバルツに会いたかった。
ただ、『会いたい』と、願った。
不意に。
周りに殺気が走るのを感じたハヤブサは、その足を止めた。
「…………」
無言で周りを見渡しながら、背に背負っている龍剣に手を伸ばす。
周りに見える草原の景色に変化はない。ただ風が、草を揺らす音が響き渡っているだけだ。
だが、居る。
確かに何かが――――こちらを狙っている。
ハヤブサの背後から、いきなり黒い影が無音で飛び出してくる。
「!!」
龍剣を躊躇うことなく鞘ばしらせる。ドスッ! と言う音と共に、黒い影がハヤブサによって真っ二つに切り裂かれた。ドオッ! と、音を立てて、斬り裂かれた者がハヤブサの足元に転がる。
「何者だ!?」
龍の忍者の問いかけに応えるように、周囲から三つの影が飛び出してきた。黒装束に身を包んだそれらは、銀色に光る刀を突き出しながら、一直線にハヤブサめがけて突っ込んでくる。
―――相打ち狙い!
そう悟ったハヤブサは、彼らと刀を合わせる事を避けた。刀を避けながら、一番初めに突っ込んで来た者の身体を串刺しにする。身体が刺さったままの龍剣を振り回して、襲って来た残る二人を撃退した。
「…………」
龍剣から血を滴らせながら、ハヤブサは周囲の気配を探る。4人を斬り伏せたと言うのに、周囲の殺気はまだ衰える気配を見せない。それどころか、その殺気は、ますます強くなって行くばかりだ。
(先程戦った組織の残党か!?)
ハヤブサはそう思いながら、倒れた刺客たちに目を走らせる。黒の忍び装束に身を包んだ刺客の腕の服の切れ間から、『百足』を模(かたど)った刺青が見えた。
(『百足』の刺青――――! 甲賀忍軍か!!)
相手の正体を悟ったハヤブサは、刀を構えなおした。甲賀忍軍は、ハヤブサの持つ『龍剣』をたびたび狙って来ている忍者集団だ。相手が『忍者』なだけに、何を仕掛けてくるか分からない厄介さがある。
強くなって行く殺気の気配。その数は確実に増えつつあった。読み取れる気配だけで――――30人はいる。
(――――死ニタクナイ……!)
思ってしまってから、はっと我に返る。怯えてどうする、と、唇を噛みしめる。
あさましい執着。
未練。
未練、なのだ。
気持ちを切り替えろリュウ・ハヤブサ。
今は、それどころではないはずだ。
だが、ハヤブサの中に生じた『未練』は、なかなか消えてくれそうになかった。
(シュバルツ……!)
声なき声で、ハヤブサは叫んでいた。
「………?」
何かの気配を感じたシュバルツが、ふと顔を上げる。
「どうした? シュバルツ…」
シュバルツが何かを訝しんでいる気配を察したキョウジが、学生のテストの答案用紙から顔を上げた。シュバルツと全く同じ容姿をした青年だ。キョウジは非常勤講師先の、学生の小テストの採点作業の真っ最中だった。
「ああ……いや、別に……」
キョウジの邪魔をしてはいけないと、シュバルツは笑顔で取り繕う。しかし、何故なのか――――『呼ばれた』ような感覚が、消えない。
「……………」
そんなシュバルツの様子をじっと見つめていたキョウジであったが、やがてポツリと口を開いた。
「シュバルツは最近、ハヤブサに会ってる?」
「ハヤブサに?」
オウム返しでキョウジに応えたシュバルツが、「ああ。たまに会っているが……」と、頷いた。それを見たキョウジが、笑顔になる。
「シュバルツってさぁ…。ハヤブサの事、どう思っているんだ?」
「ハヤブサ……」
キョウジの問いかけに、シュバルツは顎に手を当てて考え込みだした。
「ハヤブサは―――いい奴だ……ただ……」
「ただ?」
「……何と言うか、その……時々、『変』で……」
「『変』?」
キョウジの問いかけにシュバルツは頷く。
「ああ……。こちらの感覚的な問題なのかもしれないがな……」
そう言いながらシュバルツは苦笑する。
『龍の忍者』という肩書を背負っているが故に、ハヤブサは普段、険しい顔をしている事が多い。しかし、あの森で会うハヤブサは、とても優しい表情をする。『任務』から解き放たれ、元来彼が持っている『優しさ』が、前面に出てくるせいなのだろう。
しかし……何故なのだろう。
ときどき、彼の瞳に危うい光が宿っているように感じられるのは。
あの口付け以降、ハヤブサは何かと口実をつけて、こちらに触れてこようとする時がある。もちろん、本気で手を出そうとしていないのは分かる。反撃の余地は十分与えられているし、一度手を払いのければ彼はそれを引っ込めるからだ。『じゃれあい』と言ってもいい様なものだ。
ただ、手を振り払った後―――ハヤブサの瞳に宿る不安定な光が、自分がこれ以上ハヤブサから距離を取ろうとする事を拒む。
(逃げるな。消えるな―――)
懸命にそう訴えられるから、逃げ道を失ってしまう。
ハヤブサの前から自分が消えてしまう方が、きっとひどく彼を傷つけてしまうと悟る。
彼の前から消える気はない。逃げる気もないが、冗談めかして接触を求めて来られるから少し悩む。『歪な身体』を持つ自分が、あまり人間と過剰に接触をするのはよくない事だと思う。自分はともかく、相手がどうなってしまうか分からない危険性があるからだ。
(しかしなぁ……。私の身体の『成り立ち』をハヤブサは知っているはずなのだから、普通は私を『そういう対象』からは外すと思うのだがな……)
そう感じて、シュバルツは頭を抱えてしまう。何故か、こちらに触れたがっているように感じられるハヤブサ。性質の悪い冗談だと思いたい。
シュバルツが小さくため息を吐いた、その瞬間。
(――――)
「…………!」
まただ。
また、何かに呼ばれたような感覚。
何故だろう。
妙な胸騒ぎが、する。
「済まないキョウジ…。少し、出かけてくる」
「えっ? あ、ああ。気をつけて……」
慌ただしく出かけて行くシュバルツを、キョウジは採点作業をしながら見送った。
走る。
走る。
龍の忍者は、ただ草原をひた走る。
迫りくる殺気を携えた忍者軍団は、あからさまにこちらとの相打ちを狙って来ている。全員が、捨て身の戦法だ。
故に、こちらが立ち止まれば終わり。
太刀を合わせれば、終わり。
突っ込んでくる相手の太刀を紙一重でかわして、その首を刎ねる。一撃必殺。斬り損ねることすら許されない。二の太刀を許しても―――終わりだ。
(25……26……)
屠った命の、数を数える。返り血を浴びたハヤブサの忍び装束が、朱(あけ)に染まる。
止まるな。
迷うな。
ただ斬れ。
「27!!」
(後3人!!)
同時に黒い影が二つ、ハヤブサの前後から襲いかかる。どちらが先にこちらに到達するか、瞬時に判断した龍の忍者が、その身を横に滑らせる。
「はあああっ!!」
ハヤブサの一の太刀が一人目の胴を払い、返す刀がもう一人の首を刎ねる。
「後一人!!」
その声と同時に、一人の忍者がハヤブサの目の前に立ち塞がる様に現れる。
(正面!! 迂闊な――――!!)
相手の攻撃軌道を読んで、その間合いにハヤブサは踏み込む。その瞬間。
いきなり相手の腹の中から、刀が飛び出してきた。
「しまっ………!!」
ドスッ! と、音を立てて、相手の太刀がハヤブサの左足に突き刺さる。殺気の数を読み間違えていたが故に、身を引く事が1歩遅れた。仲間の身体を犠牲にした相手の太刀が、ハヤブサに届いてしまったのだ。
「くっ……! くそ……ッ!」
ハヤブサは、自分の足を刺した忍者を、袈裟切りに斬り捨てた。
「忍法『血蜘蛛』――――」
そう言って、相手は絶命した。
「…………」
しばらく、周囲の気配を探る。もう殺気は無い。ここでの戦闘は終了したと考えてよさそうだった。だがおそらく、立ち止まっていてはいけない。すぐに追手がかかる事だろう。自分が負傷した事、必ず別働隊に伝えている忍者がいるはずだから―――。
「――――ッ」
動こうとして、激しい眩暈に襲われる。刺された部位が、やけに熱を持っていた。
たまらず座り込むハヤブサ。衣服を割いて刺された場所を見ると、刀傷の周りに『蜘蛛』のような模様の痣が浮き出ていた。
(…毒を塗られたか……)
「くぅ……ッ!」
ハヤブサは、己が足の痣に刀を突き立て、毒血をかきだす。しかし、消えた痣は、すぐに浮かび上がってきた。毒が身体に回りだしていると知る。
止血のために太腿の付け根をきつく縛ると、ハヤブサは立ち上がった。とにかく、立って歩かねばならない。進まなければならない。
だがどこへ―――?
どこへ、行く?
(森へ………)
霞む意識の中、ハヤブサは『あの森』に向かう事を選択した。
そう。
命を落とすなら、『あの森』がいい。
死体でいい。
死体でいいんだ。
シュバルツ。
俺を――――見つけてくれ。
シュバルツ。
シュバルツ。
(会いたい……)
龍の忍者はふらつきながら、歩を進める。
せめて、せめて―――あの森まで。
望むなら、一目でいい。
死ぬ前に――――
シュバルツに……会いたいと……
願った。
森についたシュバルツは、いつもハヤブサが釣り糸を垂れている場所へと足を運ぶ。だが、そこにはハヤブサの姿は無く、小さな清流の流れる、平和な景色があるだけだった。
(……気の回し過ぎか)
そう感じたシュバルツは、小さくため息を吐いた。それにしても何だったのか、あの感覚は。誰かに『呼ばれた』様に感じたのだが……。
平和なら平和に越したことが無い。シュバルツはそう思って踵を返そうとする。その瞬間、何かの気配を感じた。
「…………?」
振り向いたシュバルツの視線の先に、倒れている人間の姿が飛び込んでくる。
「ハヤブサ!!」
それと気づいたシュバルツは、ハヤブサに向かって駆け出していた。
「ハヤブサ!? おい! ハヤブサ!! しっかりしろ!!」
ハヤブサの顔から覆面をずらし、その頬をぱちぱちと叩く。その声と刺激に、龍の忍者が微かに身じろいだ。
「……シュ、バルツ……?」
「ハヤブサ……大丈夫か?」
ハヤブサから反応が返ってきた事に、シュバルツは少し安心する。だがハヤブサの様子から、楽観はできないと悟る。忍び装束が血だらけで――――何よりも、ひどい熱だ。
「どこをやられた?」
ハヤブサの身体に傷が無いか手で確かめながら、声をかける。
「……足を……」
ハヤブサが苦しそうに足を動かす。シュバルツがそちらに目を走らせると、ハヤブサの左太腿に刀傷と、その周りに蜘蛛の形をした痣が浮き出ているのが見えた。
(何かの毒でやられたな…!)
「ハヤブサ……少し、『毒』の成分を調べるぞ」
シュバルツはそう言いながら、ライターで短刀の先を焼く。そして、蜘蛛の痣の上を少し切って、そこからジワリ、と滲み出てくる血に口を当て、チュッ、と、音を立てて吸いとった。
「―――――!」
自分の足にシュバルツから『キス』をされるような格好になったハヤブサは、思わず息を飲んだ。アンドロイドであるシュバルツは『味覚』が無い代わりに、舌の上で物の成分分析が出来るようになっている。だから、毒の成分を分析するために、彼はハヤブサの血を口に含んだのだが。
(この毒の成分は……)
ハヤブサの血を舌の上で転がしながら、シュバルツはそれを分析しようとした―――次の瞬間。
いきなりシュバルツの身体は、龍の忍者の膂力で持って押し倒されていた。
「――――!?」
咄嗟に何が起こったのか分からず混乱するシュバルツの上に、ハヤブサがのしかかってくる。毒と熱のせいで、ハヤブサの中で、いろいろと自制がきかなくなってしまっていたのだ。
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
潤んだ声でその名を呼び、夢中でその唇を求める。
「ハ、ハヤブサ!? あッ――――!」
抵抗する間もなく、シュバルツの唇はハヤブサによって塞がれてしまう。だが、ハヤブサの舌が口腔に侵入しようとするのを、シュバルツは懸命に抗った。手を使ってハヤブサの顔を抑え、身をよじって顔を逸らす。今キスをされるわけにはいかない理由を懸命に説明しようとする。
「ば、馬鹿! 私の口の中には今『毒』が入って――――んっ!! んぅ……ッ!」
半死半生のハヤブサのどこに、これほどの力が残っていたのか――――。
抵抗を試みたシュバルツの手は頭上に一括りにされて抑え込まれ、よじっていた身体は強引に元に戻された。説明をするために口を開けていたが故に、そこは舌の侵入を許し、あっという間に蹂躙され、そして何度も強く吸われてしまう。あまりにも――――あまりにも、強い力で。
「んく……! ………ん!」
(ハヤブサ……ッ!)
必要以上に熱いハヤブサの舌に、シュバルツは眩暈を覚える。
馬鹿……ッ!
ハヤブサ…!
お前は早く、治療をしなければいけないのに……っ!
「…………」
シュバルツは、身体の力を抜いた。とにかく、ハヤブサに治療を施すためにも、彼を落ちつかせることが先決だと思った。この状況で身体の力を抜くのは危険かとも思ったが、ハヤブサにこのまま力を使わせ続ける事の方が、もっと危険だと彼は判断したのだ。
「シュバルツ……」
シュバルツから抵抗の気配が止んだと悟ったハヤブサが、ようやく顔を上げてシュバルツの方を見る。
「ハヤブサ……」
ハヤブサの瞳に、ひどく不安定な光が宿っている。何かに怯えているような、何かに浮かされて突き動かされているような…そんな色を宿していた。今にも壊れそうなハヤブサ。毒による熱のせいなのだろうか。
ただ―――今、ハヤブサを自分が『拒絶』することだけは絶対にしてはいけない――――シュバルツには、何故かそれだけがはっきりと分かった
「ハヤブサ……。どうした……」
その面に笑顔を浮かべながら、シュバルツはハヤブサから解放された右腕を、彼の方へと伸ばす。『拒絶しない。怒っていない』その意思が伝わる事を祈るように、シュバルツはハヤブサの頬を優しく撫でた。
ただ、どうしたって手が小さく震える。殺されるのとはまた違った恐怖を感じる。――――何故なのだろう。
「私はここに居る…。どこにも行かない……」
「……………」
ハヤブサが、無言で見つめ返してくる。自分は、うまく笑えているだろうか。
「そばに居る……」
「シュバルツ……!」
「お前の側に、居るから――――」
「――――――」
まるで、シュバルツの言葉に『安心』したかのように、ハヤブサはその意識を手放した。どさっと音を立てて、ハヤブサの身体がシュバルツの上に倒れ込んでくる。
「………………」
シュバルツは、ハヤブサの身体の下から無言で抜け出し――――ほっと息を吐いた。
(とにかく、今は彼の治療をしなければ……)
先程のハヤブサの言動、行動にシュバルツはいささか思う所はあったが、ハヤブサの身体を治す事を、彼は優先した。皮肉な事に、ハヤブサの唾液にも『毒』の成分が混じっていたおかげで、彼はその成分を解析し終えていた。幸いな事に、今自分が持っている毒消しに、薬草を加えて調合する事で、この毒に有効な治療薬ができそうだった。
ただ、あまりここに長く留まってはいられないともシュバルツは感じていた。
激しい戦闘を終えたばかりとうかがい知れるハヤブサ。彼に『追手』がかかっている可能性もあるからだ。
(どうする?)
シュバルツは考える。彼をどこに連れていけばよいのか――――。
キョウジの所へ、と、シュバルツは一瞬思って、すぐに頭(かぶり)を振る。ハヤブサがろくに身動きできないこの状況。下手にキョウジを巻き込んでしまわない方がいい。狙われているのはハヤブサなのだから、ハヤブサの側に居ない方が、キョウジは安全だろう。
(隼の里の方に連れて行った方がいいか……)
手際良く解毒剤を調合しながら、シュバルツはそう考えていた。忍者の里として自衛手段のある隼の里であれば、おそらくハヤブサも安心して治療に専念できる事だろう。自分は、もしかしたら里の中までは入れないかもしれないが、ハヤブサとこの薬を里の人たちに渡す事が出来さえすれば、自分は役目を終えていいと思った。
出来た毒消しを、脚の傷に擦り込む。痛むのか、ハヤブサは小さく呻いた。
薬も飲ませようとする。しかし、意識が朦朧としているハヤブサは、うまくそれを飲む事が出来ない。
(仕方が無いな……)
シュバルツは口移しで、ハヤブサに薬を飲ませた。こくん、と、音を立てて彼の体内に薬が吸収されるのを見て、シュバルツはホッと息を吐く。
(さあ、里へ行こう)
意識の無いハヤブサを背負って、シュバルツは立ち上がった。
「龍の忍者に手傷を負わせただと!?」
とある洞窟のろうそくが照らす明かりの中で、白髪頭に白い顎ひげを蓄えた少し体格のいい老人が、部下からの報告に驚きの声を上げる。
「はっ。先発隊は全滅いたしましたが、最後の一人が奴に『血蜘蛛の術』をかける事に成功致しました」
先程の戦闘を淡々と、この部下は報告をする。彼には、戦闘に直接加わらず、事の顛末を頭領に報告する役割が与えられていた。
「ふむ……と、言う事は、龍の忍者は命を落とすか、そうならずとも深刻なダメージを被ったと言う訳だな……」
そう言いながら老人は髭をしごく。
(『龍剣』を手に入れる、またとない好機か)
「それで……龍の忍者はその後どうしたのだ?」
頭領からの問いかけに、部下が畏まる。
「それが……近くの森に逃げ込んだ事は突き止めたのですが……」
連絡係の忍者から情報を得た別の斥候隊がハヤブサを発見した時、彼は覆面をつけた男の背に背負われていた。その男が、こちらの気配に気づいたのか、不意に立ち止まる。しばらくこちらの気配を探るようにしていたが、やがてポツリと口を開いた。
「……味方ではないらしいな」
「――――!」
自分達の存在に気づかれたと悟った斥候の忍者たちが、その男の前に姿を現す。
「何者だ?……と、聞いていいのか?」
覆面の男からは、やけに穏やかな気配が漂っていた。こちらが彼を取り囲むようにしても、動じる気配すら見せない。斥候隊の忍者たちは、互いの顔を見合わせてから、口を開いた。
「我らは、貴殿の背に居る男に用がある。その男さえ置いて行ってくれたら、貴殿に危害は加えない」
「断る、と、言ったら?」
「…………!」
男の回答に、忍者たちは一瞬色めき立つ。しかし、すぐにそれは静かなる『殺気』へと変わって行った。
「断った場合は、敵とみなす」
そう言いながら忍者たちは、それぞれの得物に手を伸ばす。斥候隊のため、こちらの人数は3人と少ないが、相手は龍の忍者を背負っているために両手がふさがっている。勝ち目は充分ある様に思えた。
一人が鎖鎌をぶんぶんと音を立てて振り回し、一人が手裏剣を構え、一人が刀を構えている。そしてそのまま標的(ターゲット)に逃げられないように三方からじりじりと距離を詰めた。鎖鎌の男が先制攻撃を加える。目標が飛びあがった所を手裏剣の男が狙い打ち、万が一かわされても、着地する瞬間を刀の男が斬りつけてとどめをさす。言わば、三段構えの攻撃だ。この連携で、今まで何人もの敵を葬ってきた。今回も今までと同じ光景が見れるだろうと、男たちは確信する。
場に、耳が痛くなるほどの殺気が満ちる。
機は熟した、と見て取った鎖鎌を振り回していた男が、無言で攻撃を仕掛けた。ここで標的は飛び上がる―――はずであった。
「!!」
鎖鎌の男は目を見開いた。何故なら、目の前の標的はこちらの攻撃を少し身体を動かしてかわすと、躊躇う事無くこちらに向かって突っ込んできたからだ。
「猪口才な!! わしに倒されに来たか!?」
叫びながら男は、もう一方の鎌がついている方を標的に向かってなぎ払う様に振り回す。
「――――!」
ここでシュバルツは跳躍した。それと同時に手裏剣を持った男が攻撃を仕掛ける。だが飛び上がる瞬間、シュバルツの身体が僅かに左に動いていたために、手裏剣は彼の身体を掠めただけで逸れた。
「何をしている!! 追うぞ!!」
距離を詰めるべく走っていた刀の男が、そのまま森の中へ逃げて行くシュバルツの後を追う。だがシュバルツの動きは俊敏だった。木にかけのぼり、枝から枝へと狭い所をすり抜けるように走っていく。とても人一人背負っているとは思えないほどの身軽さと早さだ。下手をしたら木々の中、シュバルツの姿を見失いそうになってしまう。
「おのれっ!!」
木立の間から飛び出してきた標的に向かって男は手裏剣を投げつける。ドスッ! という音と共にそれは標的に刺さり、そのまま地面に落ちた。
「やったか!?」
手裏剣を放った男が成果を確かめるべく、地面に落ちた標的に近づく。だが彼はそれを確認した途端、「あ……!」と、短く声を上げた。それは、太い木の枝にロングコートをかぶせただけのものであったからだ。
「『変わり身の術』!! いつの間に……!」
歯噛みして周りの気配を探る。――――が、いくら探っても標的の気配は近くに無く、ただ木々の間を風がすり抜ける音がするだけであった。逃げられたのだと、男たちは悟った。
「見失ってしまったため……辺りを捜索中です」
「ムムムム」
頭領は唸った。恐らく標的は龍の忍者を『隼の里』に連れて行ったのだろう。あそこは『忍者の里』であるが故に、確固たる自衛手段があり、攻め入ろうとしたらなかなか難しいものがある。
しかし、龍の忍者がはっきりと負傷していると分かっている今、多少リスクが降りかかろうとも攻め時である事は確かだ。龍の忍者が健在かそうでないかで、あちらの戦闘力も大幅に違ってくるのだから。
「……よし、我らも動くか」
「九龍院様!」
頭領である九龍院輝宗の決断に、部下の忍者たちは色めき立つ。
「我らの宿願、この機を逃すべきではないと知れ。全力で隼の里を攻略し―――『龍剣』を手に入れるのだ!!」
「ははっ!!」
声と共に部下の忍者の姿は次々と消えて行った。ゆらり、と、ろうそくの明かりが大きく揺らめいた瞬間、頭領である九龍院の姿も消えた。
そしてそこには誰の姿も見えなくなった。ただ、消える運命を待つだけのろうそくが、静かに辺りを照らし続けていた――――。
第2章
(そろそろ隼の里が近い所だが……)
シュバルツは森の中、慎重に足を運んでいた。追手をうまく巻く事に成功したとはいえ、まだ油断は出来ない。背負っているハヤブサの熱も、依然高いままだ。余計な戦闘に巻き込まれる事は避け、なるべく早くハヤブサを里の者たちに渡さなければならない。
隼の里には一度ハヤブサに案内してもらった記憶がある。その記憶を頼りにシュバルツは足を進めているのだが、自分が里にたどり着けるかどうかは、結局里の人たちの『意志』次第なのだろう、と思う。自衛がしっかりしている忍者の里であるが故に、他所者が簡単に入り込めるようになっているとは思えない。最悪、斬られる可能性だってある。
(それでもいいか)
シュバルツはそう思った。自分は、ハヤブサと、この毒消しを里の者にきちんと渡せさえすればいいのだ。その後で自分の身がどうなろうとも、別にかまいはしなかった。殺されてしまおうが、どうせ―――嫌でも、甦ってしまう。
それに、ハヤブサと共に里に逗留したわずかの間、里の人たちは自分にとても親切にしてくれた。ほんの少しの時間だったから、里の人たちは自分の事などとうに忘れてしまっているかもしれない。でも―――自分は憶えている。あの優しい時間を。
それを思うと、自分は隼の里の人たちに、刃を向ける気にはとてもなれない。そんな事をするぐらいなら、自分が斬られた方がまだましだった。
「――――!」
不意に強い殺気を感じて、シュバルツは足を止める。それと同時に、タン! と、音を立てて、手裏剣が目の前の地面に突き刺さった。
(『どっち』の手の者だ?)
シュバルツは気配を探る。もし、ハヤブサの追手ならば、再び戦闘に入ってしまう事は避けられない。ただ―――先ほど戦闘をした忍者たちの物とは、『殺気』の気配が違うような気がした。
「この辺りでは見ない気配の者だな……貴様、何者だ?」
木立の間から声が聞こえる。しかし、声の主の姿は見えなかった。
「去(い)ね! ここは人がうろうろしていい場所ではない。これより先は、『龍』が住まう場所ぞ――――」
その言葉にシュバルツが鋭く反応をする。
「『隼の里』の者か!?」
「……………!」
シュバルツの問いかけに、張り詰めたような気配が返ってきた。
「―――だとしたら、何とする?」
「私は、貴方がたと戦うつもりはない!」
そう言いながらシュバルツは、己の顔から覆面を外す。
「私はただ、この背に居る者を――――」
「キョウジ殿ではないですか!?」
「――――!?」
驚くシュバルツの前に、木立の間から一人の忍者が姿を現した。
「キョウジ殿…! 覚えておいでですか? 私です! あの時、貴方を宿に案内させてもらった者です!」
そう言いながら若者もまた、己の顔から覆面を外す。
「…………!」
その顔にシュバルツも憶えがあった。確かにあの時、自分の破れた服をこの若者の祖母が繕ってくれて―――それをわざわざ長老の家まで届けてくれた、あの若者の顔だった。
「また、訪ねて来てくださったんですか!? ぜひ、里の方までご案内させてください! 祖母もきっと喜びます! 子供たちも――――」
この若者の言葉に、シュバルツの方が逆に驚いた。自分が里に逗留したのは、ほんの僅かな時間なのだ。ましてこの若者とは、宿に案内してもらう間に、二言三言話をしただけだと言うのに。
「……覚えていて、くれたのか?」
問うシュバルツに、若者は屈託のない笑顔を見せる。
「はい! 貴方の事はよく覚えています! 祖母も、子供たちも――――もう毎日の様に貴方の話をしていて……」
(ああ、やっぱり、優しい人たちだ)
そう感じたシュバルツの面(おもて)に、自然と優しい笑みが浮かぶ。だが、再会を懐かしんでばかりもいられない。肝心の用を伝えなければと思いなおす。
「実は、私が訪ねてきたのは、ハヤブサを里に送り届けるためだ」
「えっ―――?」
「戦闘中に負傷したらしい…。しかも、刀には毒を塗られていたようだ」
「…………!」
ここで初めて若者も、シュバルツの背に居るハヤブサの姿を見て絶句する。
「わ、分かりました。急いで里の方へご案内いたします」
そう言って若者があたふたと駆け出そうとする。それについて行こうとしたシュバルツに、声をかける者たちがいた。
「キョウジ殿。その背に居る者は我らがお運び致します」
シュバルツがそちらに振り返ると、忍者二人が膝をついて、彼の側に控えている。若者と同じ忍び装束を着ていたので、隼の里の者であると知れた。
「そうか…。では―――」
そう言ってシュバルツは、ハヤブサをその忍びたちに渡そうとする。しかし、それは叶わなかった。何故なら、ハヤブサは意識が無いはずなのに―――シュバルツのロングコートをしっかりと掴んで離そうとしなかったからだ。
これには忍者二人も困ってしまい、シュバルツも苦笑する。
「ハヤブサは、私が運ぼう」
シュバルツからの提案に、忍者たちも頷かざるを得なかった。
「では、拙者が一足先に、里へ知らせて参ります」
そう言って一人の忍者の姿が、フッと消える。
「さあ、キョウジ殿。こちらです!」
若者の言葉に、シュバルツも素直に従った。
「それにしても、見事な調合術ですな。よくこの毒に対応できる毒消しを作れたものだ…。後少し処置が遅れていたら、ここに居るハヤブサは命が無かったことでしょう」
ハヤブサの容体を診て、シュバルツの作った毒消しを見た薬師が感嘆の声を上げる。
「いえ、独学で学んでいた物の中に、たまたま知っている知識があったにすぎません。そう褒められてしまうと、却って面映(おもは)ゆい。……ですが、お役に立てたのなら、よかった…」
そう言ってシュバルツは、笑顔を浮かべる。薬学の知識はキョウジの物だ。だから、本当に礼を言われなければならないのは、キョウジではないかとシュバルツは思う。
「本当に、我ら『隼の里』の者は、先の勾玉の1件以来、貴殿には世話になりっぱなしだ。長老も後で礼を改めて言いに来るだろうが、先に里の組頭としてお礼を申し上げたい」
そう言って薬師と一緒に居た恰幅の良い壮年の男が頭を下げようとするのを、シュバルツは手で制した。
「それを言うのなら当方こそ、貴方がたとハヤブサ殿には助けてもらってばかりです。私は、その恩に報いるために動いたにすぎません。ですから―――どうか、そのようなお気遣いは御無用に」
「いや、しかし……」
シュバルツにそう言われて組頭は戸惑ってしまう。800年里に伝わってきた勾玉を浄化してくれた目の前の青年に対して、こちらが施した『恩』など、芥子粒の様な物なのではないかと思えてならない。こちらがした事と言えば、勾玉の情報を渡して、後は普通に宿に泊めただけだ。そのような些細な物が、この青年にとっては『恩』になり得るのだろうか。
「どうか―――」
しかし、目の前の青年の笑顔は、こちらが『礼』を言う事を頑なに拒否している。
――――きっと、『礼』を言わぬ事が、この青年にとっては最大級の『礼』になるのだろう。
組頭はため息と共に、自分をそう納得させることにした。
「では、我々はこれで下がりまするが……何か用があれば、この者にお申し付けください」
その言葉と共に、後ろに控えていた若者が頭を下げる。それは、シュバルツを里に案内してくれた若者だった。ドモンより、少し年下ぐらいだろうか。
「与(よ)助(すけ)と申します。どうぞなんなりとお申し付けください」
与助の言葉にシュバルツは頷く。それを見届けてから、薬師と組頭は退席した。
(熱が高いな……)
シュバルツは、ハヤブサの額にそっと手を当てる。ハヤブサの意識はまだ戻らない。苦しいのか、息づかいも少し荒かった。だがよく見ると、汗もかき始めている。もっと汗をかいてくれたら、熱も引き始めるかもしれない。
「与助。済まないがこれに水を入れて持ってきてくれないか」
そう言いながらシュバルツは、少し大きめな竹筒を与助に差し出す。
「分かりました」
与助は短くそういうと目の前からフッと消え、そして、すぐに水を入れて持って来てくれた。流石に彼も忍者だ。仕事がとても早い。
「―――ありがとう」
竹筒を受け取りながら礼を言うと、与助は嬉しそうに微笑んだ。
他に用はありませんか、と、問いかけてくる与助に、今は大丈夫だから、と、シュバルツは彼を下がらせた。そして、寝ているハヤブサに近づいて行く。水を飲ませるためだ。それと薬も飲ませる必要があると思った。
「ハヤブサ。…ハヤブサ」
ぱちぱちと、軽く手でその頬を刺激する。ハヤブサは僅かに身じろいだが、覚醒するまでには至らなかった。未だ毒のダメージから回復しきれていないのだろう。
(仕方が無いな……)
シュバルツは水を自分の口に含む。それをハヤブサに口移しで飲ませた。こくん、と音を立てて彼の身体の中に水が流れ込んで行く。それを確認したシュバルツは、ほっと息を吐いた。
(点滴が出来れば、もっと回復も早いのだろうけどな……)
そう感じて苦笑する。次に薬を、と、シュバルツがそれを口に含んでハヤブサの口に移そうとした瞬間。ハヤブサの手がいきなり伸びて来て、シュバルツの頭を抱え込むようにして引き寄せた。そしてそのまま、シュバルツから施された『口付け』を、さらに深く味わえるようにとシュバルツの口内に、自身の舌を滑り込ませる。
「う…! んんっ!?」
薬を飲ませようとしていたシュバルツは、それ故に身を引く事が出来ず、ハヤブサの舌が侵入してくるのを拒む事が出来ない。舌と舌が絡まり、強く吸われるのを、彼はされるがままに許すしかなかった。
「………ん……っ」
知らず、ハヤブサの寝ている蒲団をシュバルツは強く握りしめてしまう。もう薬は口の中から無くなっているから、いい加減離れたいのに、ハヤブサがなかなか放してくれない。病み上がりとは信じられないほどに、ハヤブサのシュバルツを捕らえる力は強かった。
「…………………」
彼がシュバルツを『解放』したのは、互いの口の中から薬が無くなってから、だいぶ時が経ってからだった。
「ハヤブサ……ッ!」
シュバルツが顔を真っ赤にしながら、ハヤブサから離れる。
「……今のは何だ? 薬か?」
そう言いながらハヤブサはペロリ、と舌なめずりをした。
「お前……ッ! いつから意識があったんだ!?」
シュバルツの問いかけに、ハヤブサは笑顔を見せる。
「お前に水を飲まされた時に…。嬉しいよ。お前から『口付け』をしてもらえるなんて…」
「『口付け』じゃない! 『口移し』だ!! お前に、薬と水を飲ませる必要があったから―――!」
「でも、今のは『キス』だろう?」
「――――!」
ハヤブサの言い分に咄嗟に反論できなくて、シュバルツは絶句してしまう。
「『キス』だよ」
ハヤブサはたたみかけるように、もう一度言った。
「……………」
シュバルツはそんなハヤブサを茫然と見ていたが、やがて呆れたようにため息を吐いた。
「………言っておくが、先程(さっき)のが初めてじゃないからな」
腕を組みながら、憮然と呟く。
「えっ?」
驚いて顔を上げるハヤブサをちらりと見やりながら、シュバルツは口を開いた。
「――――『口移し』だよ。何回お前に水や薬をこちらが飲ませたと思っているんだ?」
「ええっ!?」
シュバルツの言葉に、ハヤブサが思わず素っ頓狂な声を上げる。
(……嘘だろ? 覚えが無い……!)
そう思いながら、ハヤブサは震える手を己の唇にあてていた。何と言う事だ。せっかくシュバルツの方から何回も触れて来てくれていたと言うのに、自分の方に全く記憶が無いだなんて――――!
「――――――」
ハヤブサが何事かをぼそりと呟く。
「………何か言ったか?」
それを何となく聞き咎めたシュバルツがハヤブサに問い直す。それに対してハヤブサは「……何でも無い……」と、ただ苦笑するしかなかった。
(駄目だ…! とても言えない…! 『もう1回して欲しい』だなんて――――!)
そんな事を言った所で、シュバルツに「誰がするか!!」と、言われて殴られるのが落ちだ。ちょっと世知辛い気持ちになって、ハヤブサは小さくため息を吐く。今シュバルツに殴られたりしたら、とてもじゃないが身体の方が保(も)たない自信がある。
そんなハヤブサの様子をじっと見つめていたシュバルツであったが、やがて小さくため息を吐いた。
「……まあ、あまり無理をするな…。『毒』のせいで、実際お前は生死の境をさまよったのだから……」
そう言いながらシュバルツは、ハヤブサの枕元から立ち上がろうとする。その動きを見た途端、ハヤブサが蒲団から跳び起きようとした。
「どこへ行く!? うっ――――!」
だが、激しい眩暈に襲われて起き上がる事に失敗する。それでもロングコートの裾を必死に掴んできた。このハヤブサの様子に、シュバルツの方が逆に驚いてしまう。
「ハ、ハヤブサ!?」
「シュバルツ……! どこへ、行く……?」
顔を上げながら、必死の形相で言葉を紡ぐハヤブサ。ひどく強く引っ張られるコートに、シュバルツは戸惑った。
「ど、どこにも行かない……。ただ少し、座る場所を変えようかと思っただけで……」
『安静』が必要なハヤブサを眠らせるために、自分が近くに居ては邪魔になると思った。だから、少し身を引こうとしたにすぎないのに。
「なら……ここに……!」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツのロングコートを必死に引っ張る。
「……そばに……居てくれ……ッ!」
まるで絞り出すような声で、ハヤブサは叫んでいた。懇願。あまりにもはっきりとした――――懇願だ。
「わ、分かった……ハヤブサ……」
気がつけばシュバルツは、思わず頷いていた。
「どこにも行かない…。『約束』する……」
そう言いながらシュバルツは、ハヤブサの方に向いて座りなおす。
「『約束』……」
「お前が治るまで、な」
「……………」
シュバルツの言葉に『安心』したのか、ハヤブサの力がスッと抜ける。シュバルツは、そんなハヤブサの身体を布団へと戻した。
「とにかく寝ろ。まだお前の身体から『毒』は抜けきっていない…。だから、安静にしていないと……」
「『治る』までは……居てくれるんだな?」
シュバルツに布団を掛けられながら、ハヤブサがそう言って見上げてくる。
「ああ……『約束』するよ」
シュバルツから『約束』という言葉を引き出したが故に、ハヤブサは笑顔を見せた。シュバルツは、とても義理堅い男だ。『約束』と自ら言ったのだから、それを破るような事は決してしないだろう。
だから、安心していい。
安心して――――今は、眠ってもいいのだ。
目が覚めても、彼がいなくなったりはしていない。
『傍に居る』と、彼は約束してくれたのだから――――。
「シュバルツ……」
今なら、多少甘えても許されるだろう。そう感じたハヤブサは、シュバルツに声をかけた。
「手を……握らせてくれないか…?」
「あ? ああ。構わないが」
そう言いながらシュバルツは、ハヤブサに向かって手を差し出してくる。
「手袋を、外して――――」
「………!」
体温の無い自分の手は、『冷たい』だけなのに、いいのだろうか。一瞬シュバルツはそう思ったが、ハヤブサが望むのだからと、彼は右手で左手の手袋を外した。そしてそっと差し出されてくるシュバルツの手を、ハヤブサの熱を持った手が掴んだ。
「ああ……やっぱり、気持ちいいな…。お前の手は……」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの手を己の頬に当てる。熱を持った身体には、シュバルツの手の冷たさが、心地いいようだ。
「ゆっくり休め、ハヤブサ…。傍に居るから――――」
熱の無い自分の手が、ちゃんと役に立った事が嬉しいシュバルツの面に、自然と優しい笑みが浮かんでいる。
「…………ん……」
しばらくシュバルツの手を頬に当てて、その冷たさを堪能していたハヤブサであったが、やがてその手を両手で握り込むと、そのまま眠りに落ちてしまったようだ。規則正しく蒲団が上下し、それと共に静かな寝息が聞こえてくる。
(ハヤブサ……)
左手にハヤブサの熱を感じながら、シュバルツは障子の隙間からのぞく月を見上げていた。
―――やはり、ハヤブサは私に過度に触れたがっているのか……?
そう感じてシュバルツは、困り果ててしまう。何度もひどく性的に唇を奪われる事実が、シュバルツにそれを意識させてしまう。
自分の身体は『男』だ。
しかも、『人間』ですらない。
死した『シュバルツ』という人間の死体をベースにして、DG細胞でキョウジの情報を上書きされた、『アンドロイド』であると言うのに。
そしてハヤブサは、その事実を知っているはずだ。
自分の生みの親でもあるキョウジが、ハヤブサに直接、事実を総て打ち明けているはずなのだから…。
じゃあ何故。
シュバルツは自問自答する。
どうしてハヤブサは、自分に触れたがっているのだ。
こんな身体を『触れたい』、『抱きたい』だなんて――――。
どう考えてもおかしすぎる、だろ。
そしてもう一つ――――。
『抱かれる』という行為にも多少恐怖を感じるが、それ以上にシュバルツに恐怖を与えている存在がある。
それは――――『DG細胞』だった。
『DG細胞』とは、自己再生、自己増殖、自己進化の特性を備えた究極の生体物質だ。それによって構成されたモノは、死なない、壊れない、朽ちない身体を手に入れる事になるが、それと同時に、『自己増殖』の本能故なのか、他者へのどうしようもない攻撃衝動も持つ事になってしまう。他者を攻撃する事によってその細胞を『感染』させ、仲間を増やして行くのだ。当然その衝動に支配された人間や生き物は、自分の元の性格や尊厳を、完全に破壊されてしまう事になる。
そんな物騒なモノで構成されているはずの自分の身体であるが、他者への攻撃衝動も起きず、人格も保たれたままだ。これは自分の元になったキョウジの『精神力』がなせる業だった。
『弟を守りたい』という強い想いが、DG細胞が暴走する事を抑え込んだ。おかげで自己再生、自己増殖、自己進化の力は低く抑え込まれる事になってしまったが、こうして人格も保たれて、人間の間に混じって活動しても支障が無いようになっている。これは、素直にありがたかった。
だが、このような自分の身体が、『セックス』の様な濃密な他者との触れ合いをすると、『自分』は、そして『相手』は―――どうなってしまうのか。下手をしたらDG細胞が『暴走』して、相手にそれを感染させてしまいかねない。シュバルツはそれをひどく恐れた。
だから、自分は他人と濃密な接触をするべきではない。
もしも求められても、断固として『拒否』しなければならないのだ。
なのに――――ハヤブサ……。
シュバルツは頭を抱えてしまう。
戦いの最中に、無防備に自分が子供を助けた時、斬って来なかったハヤブサ。自分が命の無い、死なない身体を持つ空虚なアンドロイドだと正体を明かしても「何だ、そんな事か」と、ため息をつき、「馬鹿野郎!」と怒鳴りながらも、今までと変わらぬ態度で受け入れてくれたハヤブサ。
本当に、自分はどれだけそんな彼に助けてもらった事だろう。
ハヤブサは、とても大事な存在だ。「失いたくない」と、願った。
ハヤブサにDG細胞を感染させて――――その人格を破壊してしまうような行為は、絶対に避けなければならないのだ。
だから、拒否しなければならない。
ハヤブサがもし『それ』を求めて来ても、自分は絶対に拒否をしなければならないのに。
ハヤブサの瞳に宿る危うい光が、シュバルツが彼を『拒否』する事を頑なに拒む。
ほんの僅か、シュバルツが彼から距離を取ろうとすることすら、許そうとしなかったハヤブサ。今彼を拒絶してしまったら、DG細胞に感染させずとも、彼が壊れてしまう事が容易に分かる。それも避けたい。だから困る。「どうすればいいのだろう」
(『キョウジ』では、駄目なのか……?)
穏やかな顔をして眠るハヤブサに、そう問いかける。
キョウジも『男』だが、れっきとした『人間』だ。その身体は脈拍を伴っているが故に温かく、自分の大元となっているだけに、その外見も考え方も、自分とそんなに変わらない。『死体』で『DG細胞』という禍々しいもので構成されている自分の身体を抱くよりも、『人間』であるキョウジの身体を抱く方が、ハヤブサにかかってくるリスクもはるかに低く抑える事が出来るではないか。
(もっとも、『自分の代わりにハヤブサに抱かれてくれ』なんて人身御供的な事など、キョウジに頼めるはずもないがな…)
そう感じて、シュバルツは知らず苦笑してしまう。
(きっと、『逃げる』のが正解なのだろうな……)
もしもハヤブサが『抱きたい』と言って来た時に、『肯(イエス)』と言えないのであるならば、いつまでもそばに居るべきではない。きっぱりと離れるのが正解なのだ。例えどんなにハヤブサから恨まれる事になろうとも。
(だが、『逃げる』として……私は、逃げ切れるのか? 『龍の忍者』から……)
頭の中でシミュレーションをしてみるが、割と厳しい選択肢である事に気づく。自分一人だけならどうとでも逃げられるが、ハヤブサがもし本気でこちらを狙ってくるのなら、間違いなく『キョウジ』を狙ってくる。自分の弱点はキョウジだ。キョウジを捕られてしまったら、自分は本当に、その相手に対して手も足も出せなくなってしまう。
キョウジは『デビルガンダム事件』から奇跡的に生還して、やっと今の平穏な生活を手に入れたのだ。その生活を、自分の都合だけで破壊して、明日をも知れぬ闇の世界に、彼を引きずりこんでしまう訳にはいかない。
(やはり、私は『消える』べきなのだろうか……)
そう考えてしまってから苦笑する。
「じゃあお前、どうやって消えるんだ」
DG細胞で構成されているが故に、死なない身体になってしまっている自分。銃で頭を撃ち抜こうが、腹を搔き切ろうが、首を切り落とそうが――――2~3時間後には、甦ってしまうと言うのに。
唯一自分が『死』を迎えられる可能性があるのは、キョウジの『死』だ。自分は、キョウジの意識と心をエネルギー源にして活動している。それが彼が死ぬ事によって絶たれてしまった時、自分もまた活動を停止して『死』を迎える事が出来るのだろう。
でも、それは駄目だ。それこそ駄目だ。
自分が『死にたいから』という理由だけで、キョウジの人生を終わりにしていいなんて事には絶対にならない。自分の願いは『キョウジが生きて、幸せになる事』なのだ。キョウジの『生』を望みこそすれ、彼の『死』なんて絶対に望まない。例え自分がどうなってしまおうとも―――。
(唯一、DG細胞の活動を停止させて消滅させる事が出来る『紋章の力』を持つ、弟であるドモンも、私を撃ちたがっていないしな……)
ただでさえそれを嫌がっているドモンに、説明するのも困難な理由を引っ提げて「撃ってくれ」と頼んだ所で、絶対に彼はそれをしてはくれないだろう。
(同じ紋章の力を持つ東方不敗マスターアジアに自分を撃つように頼んでもいいのだろうが……)
マスターアジアなら、自分が「撃て」と頼んだらおそらく撃ってくれるだろう。でも―――何故だろう。あの男はキョウジの『意志』には絶対に逆らわない様な気がする。キョウジがシュバルツの『消滅』を真に望まなければ、彼がその拳を振るう事は、おそらくないであろう。
あの勾玉の事件の際、自分は消えていてもおかしくない状況だった。だが、キョウジが強く強く、自分の『生』を望んでくれた。だから、自分はここでこうして存在している事が出来るのだ。
その意思を、キョウジが覆すだろうか?
それを考えると、答えはNOの様な気がする。
(何てことだ……。割とものすごく『八方ふさがり』な状況だな……)
そう感じて、シュバルツはもう笑うしかない。だから、自分は思わず望んでしまうのかもしれない。「ハヤブサの行為は、性質の悪い冗談なのだ」と……。そうであるならば、今自分が考えている事も、ただの『取り越し苦労』で終わるのに。
(それに『約束』してしまったしな……。『治るまでは、そばに居る』って……)
そう思いながら、穏やかに眠るハヤブサを見つめる。
彼は信じてくれているのだ。自分とかわした『約束』を…。
闇の世界に生きる者にとって、他人を信じると言う行為は容易なことではない――――という事は、シュバルツも知っている。自分も、同じ闇の世界で生きる者であるが故に。
だから、余計に裏切れない。
ハヤブサから寄せられている全幅の信頼を、裏切ってしまう訳にはいかない、とも、思う。
(もし…ハヤブサが『抱きたい』と、言って来ても、自分の身体を抱く事で生じるリスクを説明して――――納得してもらうしかないのかな……)
シュバルツは、そう結論付けるしかなかった。その時に話を聞いてもらえるかどうかは分からないが、自分は、話をするしかない。こんな身体を抱いてはいけないのだと。
でも、どうして彼は……自分なんかを抱きたがるのだろう。
それが一番、理解に苦しむ。
こんな禍々しい身体……自分なら絶対『その対象』には選ばないのに。
(……………)
ハヤブサの手から伝わってくる温かさが、シュバルツの意識にまどろみを与える。出来る事と出来ない事がある自分の身体だが、『眠る事が出来る』というのは素直にありがたかった。夜は起きているには長すぎる。でも、眠っていたら、その間余計な事は考えずに済む。身体に休息が必要なように――――心にも『休息』が必要だと言う事なのだろうか。
(温かい……)
どうして、人の手のぬくもりは、心を『安心』させる作用があるのだろう。
シュバルツはそんな事を考えながら―――いつしかまどろみの中に、その心を委ねていた――――。
第3章
どこかで聞いた様な泣き声が聞こえる。
(ああ、ドモンの泣き声だ)
『キョウジ』である自分は、そう思った。それと同時にシュバルツは悟る。「ああ、これは夢なんだ。キョウジの『記憶』を見ているのだ」と……。
夢の中のドモンは、とても幼い姿だった。母親が恋しいぐらいの年頃の彼は、眠りたいのに母親がいないのが淋しくて、「お母さん、お母さん」と叫びながら、ぐじぐじと涙を流している。
「しょうがないだろう? 母さんは仕事で留守なんだから…」
泣き叫ぶ弟を抱っこしながら、懸命にあやす。背中を優しく撫でてあげたが、それでもドモンは泣きやまなかった。
(まあ、母親の抱き心地には叶わないよな……)
そう感じて苦笑するが、ドモンを放り出すわけにもいかない。今家には泣いても笑っても二人しかいないのだから。
「お兄ちゃんとねんねしようか。子守唄をうたってあげるよ」
そう声をかけると、涙で顔をぐしゃぐしゃにした弟が、「本当?」と言って顔を上げる。「うん」と言って笑いかけると、ドモンは泣きやんで「じゃあ寝る」と涙を拭いた。ドモンはどういう訳か、自分の歌う子守唄が好きらしい。自分ではあまり『上手い』とは思わないのだけど。
二人でベッドにもぐりこむ。ドモンの横に添い寝して、肩をポンポンと叩いてリズムをとりながら、小声で歌い始めた。
「…………」
もぞ、と、ドモンが自分の懐に潜り込んでくる。
(ああ、どうやら寝てくれそうだな……)
懐にドモンの温かさを感じながら、『キョウジ』である自分は、そう思った。ドモンのぬくもりが気持ちいいので、そっと頭を抱え込むように手をまわしてみる。
(……あれ? 小さいドモンの頭にしては、やけに大きい、ような……?)
そう思いながら、シュバルツは夢の中から覚醒して――――自分の置かれている状況に、目を剝いた。
自分が「ドモンだ」と思って抱き込んでいたのが、ハヤブサの頭だったからである。しかも、いつの間にかロングコートは脱がされて、スカーフも取り払われ、シャツもはだけさせられていた。そして、顕わになった胸元に、ハヤブサの顔がうずめられている。
つまり―――自分はハヤブサの布団に入って、彼と添い寝をしていたのである。
「な……! な……! な………ッ!!」
あまりの自分の状態にシュバルツから声が漏れる。その声に気づいて、ハヤブサの目が覚めた。
「あ……? シュバルツ……起きたのか……?」
そう言いながらハヤブサは、再びシュバルツの懐にもぞ、と、顔をうずめている。
「何なんだこれはああああっ!?」
シュバルツの大声が響き渡ると同時に、家の屋根から鳥たちが一斉に飛び立った。飯炊き女がやかんをひっくり返した。「お母さ~ん、あの声何~?」「しッ! 気にしちゃいけません!」という会話が、各家庭で繰り広げられていた。
大声を出すと同時に、シュバルツが布団から飛び退く。
「……そんなに大声出さなくても…」
思わず耳元で大声を聞く羽目になったハヤブサが、耳を押さえながら体を起こしている。
「な…ッ! これ……ッ! わた……! いっ……!」
シュバルツが顔を真っ赤にしながら、はだけた己のシャツを押さえている。(ああ、状況説明を求めているんだな…)と、シュバルツの意思を正確に把握したハヤブサが、ポリポリと頭をかきながら、口を開いた。
「別に大したことじゃない……。俺が夜目を覚ましたら、お前が寝てたから……」
「わ、私がお前の布団に潜り込んでいたのか!?」
「いや……お前は俺の手を握って、座ったままで寝ていたよ…。だから俺が―――」
微妙に座る姿勢のバランスを保ったままシュバルツは寝ていたが、今にも倒れそうだった。
(あのままじゃ、寝づらいだろう)
そう思ったハヤブサが身を起してシュバルツの身体に触れても――――彼は起きなかった。それどころか、ストン、と、ハヤブサの腕の中に身をゆだねてきたのだ。その無防備な姿に、ハヤブサの中で愛おしさと劣情が綯い交ぜになる。
(シュバルツ……)
ギュッと、その身体を抱きしめてみる。それでも彼は起きない。余程疲れているのだろう、と、ハヤブサは判断した。
このコートを着たまま布団に入ったら寝苦しいだろう、と思って、コートを脱がす。布団に寝かしつけ、スカーフを取り払い、シャツのボタンをはずしても――――彼は起きなかった。
――――襲イタイ……。
どうしようもない欲望が、自身の身体を支配する。だが、それと同時に激しい眩暈にも襲われた。
(……………ッ!)
まだ早い。と、ハヤブサは悟る。まだ、シュバルツを襲うには、自分の体力が回復していなさすぎる。今―――事を成し遂げようとしても、おそらく失敗して、シュバルツに逃げられてしまうのが落ちだ。
シュバルツからは『約束』という言質を引き出しているのだ。だから彼は逃げない。焦らなくても、逃げないのだ。必死に自分にそう言いきかす。焦るな。落ちつけ。もう『獲物』は――――俺の手の内に、あるのだから。
(…………)
でも、『触れたい』という欲望だけは、どうしても抑える事は出来ない。はだけたシャツの間から覗く肌に、ハヤブサは想いをこめて唇をそっと落とした。
想像していたよりも、ずっと弾力のある肌―――そして、ひんやりとした感触が心地よかった。自分が、熱が高いせいなのだろうか。
「…………」
自身の身を起こしているのも限界を感じたハヤブサが、シュバルツの横にそっと身体を横たえる。すると、自分の横に人の気配を感じたのか、シュバルツが寝ながらこちらを向いてきた。
懐に、潜り込めそうな隙間があったので、そっとシュバルツのそこに潜り込んでみる。
「…………」
すると、シュバルツが自分の背中に手をまわしてきた。ドモン、と、その唇が動く。
(ああそうか…。キョウジはこうやって―――弟を、寝かしつけてきたんだな……)
そう思いながらハヤブサは、少し弟であるドモンがうらやましくなった。このような愛情を、彼は産まれたときから浴び続けていたのだろうから。
シュバルツの肌に、自身の火照った額をくっつける。冷たさがひどく心地よかった。
(こうして触れているだけでも充分『幸せ』なのに――――どうして人は、その先を、その向こうを望んでしまうのだろう…?)
ハヤブサは意識をまどろみの中に遊ばせながら、ふとそんな事を考えていた―――。
「……コートを脱がして、布団の中に、寝かしつけた…。ただ、それだけの事だ」
何でも無い事のように装って、ハヤブサは冷静に言葉を紡ぐ。実際、そうじゃないか。ただ、横で添い寝しただけだ。(ちょっと触れたりはしたが)それ以上こちらは何もしていないのだから。
「何か問題でも?」
「――――問題は、あるな…」
シュバルツが服を直しながら、ため息をついている。
「あのなぁ、ハヤブサ…。お前は安静にしていなければいけないんだぞ…。それなのに、どうして私の方にまで気を回したりするんだ! 余計な体力を使う事になったんじゃないのか!? 隣でうっかり寝てしまった私も悪かったかもしれないが――――!」
(そういう理由で怒るのか?)
ハヤブサは思わず苦笑しながら口を開く。
「じゃあ、お前だったら逆の立場で、俺が隣で寝ていたら―――そのまま放っておくのか?」
「…………ッ!」
ハヤブサからの切り返しに、シュバルツはぐっと言葉に詰まる。確かにそうだ。自分が布団で寝ている時にハヤブサが転寝をしていたら―――楽な姿勢で寝てもらおうとしてしまうかもしれない。
「そ、それは――――でも、わざわざ同じ布団に入れなくても……!」
「しんどかったからな……。もう一組布団を用意できなかったんだよ」
ハヤブサからの切り返しに、シュバルツは更にぐぐっと言葉に詰まる。
「第一、俺の頭を抱え込んできたのはお前の方だしな」
「うう…………」
これにはシュバルツも本当に反論できない。隣に人が寝ていると「ドモンだ」と思って寝かしつけの体勢に入ってしまう、キョウジの習慣が仇になってしまった。
「そ、それにしたってシャツのボタンをはずしたのは……ッ!」
「……済まないな…。お前の身体の『温度』が気持ち良かったから―――」
そう言いながら、ハヤブサの身体がぐらりと傾く。
「ハヤブサ!?」
シュバルツが慌ててその身体を支える。額が、焼けるように熱かった。
「ほらみろ! まだ熱が高いのに、無理なんかするから―――!」
「そう……熱が高いから―――」
シュバルツに自分の身体をゆだねたハヤブサは、いきなりその腕に力を入れて、彼を布団の上に押し倒した。
「ハ、ハヤブサ!?」
驚くシュバルツの上に、ハヤブサの熱を持った身体がのしかかってくる。胸元にすっと伸びてきた手が、あっという間にシュバルツのシャツのボタンをはずしてしまった。
「……こうしていると……気持ちいいんだ……」
そう言いながら、ハヤブサが火照った顔を顕わになった胸元の所に寄せてくる。
「あ、う……!」
じかに触れるハヤブサの思わぬ熱に、シュバルツは知らず声を上げてしまった。
「シュバルツ―――」
シュバルツがハヤブサを押しのけようとするよりも先に、ハヤブサの方がシュバルツの上で全身の力を抜いて彼に凭れかかってくる。
「ハヤブサっ……!? ちょっ、……ッ!」
「…………」
どうやら本気で自分の『冷たさ』を必要としているように見えるハヤブサに、シュバルツは戸惑ってしまう。
「お、お前…! 目が覚めたのなら、薬…! 薬を、飲まないと……!」
それでも何とかこの体勢から脱出しようとして、シュバルツは必死に言葉を紡ぐ。病人相手に腕力にモノを言わせるのは避けたい、と、思った。
「……口移しで……飲ませてくれるか…?」
完全にシュバルツの上でくつろいでしまっているハヤブサが、とんでもない事を口走ってくる。
「な、何を言っているんだ!? お前は! 意識があるのなら自分で飲め!!」
「…じゃあ、俺はこの上から退かない……。ずっと、ここに居る……」
「寝言を言うな! だいたい、こんな所を誰かに見られでもしたら――――!!」
「―――何か、あったんですか!? 叫び声が―――!」
タン! という音と共に襖が開けられ、与助がそこに飛び込んでくる。そして―――布団の中に居る二人の状態を見て――――彼の目が、点になった。
「おっ、与助か……」
同じく与助と視線が合って茫然としているシュバルツの上で、ハヤブサが少し身を起して爽やかに笑っている。それを見た与助が、今度は真っ赤な顔色になった。
「すっ! すみませんっ!! 取り込み中だとは知らず――――!!」
そう言いながら実直な若者の姿が、襖の向こうへと消える。
部屋に、奇妙な沈黙が訪れた。
「………見られたな」
顔面蒼白になって固まっているシュバルツを見下ろしながら、ハヤブサはあくまで笑顔で彼に声をかける。
「……………」
「『誤解』されたかな?」
『誤解』じゃないのだが、と内心思いながら、ハヤブサはシュバルツを見る。対してシュバルツは―――まだ、固まったままだった。
「まあいいか! 忍者の間では、『衆道』は珍しい事ではないし―――」
そう言いながら、ハヤブサはあくまでも爽やかに微笑む。
「ハヤブサ…ッ!」
ここに来てついに、シュバルツの方の堪忍袋の緒が切れてしまった。
「お前……ッ! いい加減にしろっ!!」
本日二度目の叫び声と共に、ハヤブサはシュバルツからきつい鉄拳制裁を喰らったのであった。
「えっ? ハヤブサが?」
受話器の向こうからキョウジの声が聞こえる。
あの後シュバルツは与助を呼びなおしてハヤブサの着替えと朝食を頼み―――自分は、キョウジに連絡を取るために電話を借りる事を願い出ていた。隼の里はかなりの僻地にあるため、携帯の電波は入らない。外界との連絡手段は、唯一この宿に置いてある『黒電話』だけだった。
宿の主人に事情を話すと、彼は快くシュバルツに電話を貸してくれた。そして彼は今――――キョウジと話しているのである。
「ああ……。戦った相手の刀に毒が塗られていて、斬られてしまった様なんだ…。それで成り行き上、私が手当てを引き受ける事になってしまって―――」
そう言いながらシュバルツは、少し頭を捻る。おかしい。最初はハヤブサを里の人たちに渡したら、すぐに帰るつもりだったのに―――。
「そうか……」
受話器の向こうのキョウジから、少し声が途絶える。何かを考えているのだ、と、シュバルツは悟った。
「分かった…。じゃあ、ゆっくり手当てをしてあげなよ」
しばしの沈黙の後、キョウジから明るい声が返ってきた。
「こっちの事は心配しなくていいからさ」
「キョウジ……」
こちらのキョウジを案ずる声に、キョウジからくすくすと笑う声が返ってくる。
「ハヤブサは……お前の大事な『トモダチ』だろ?」
「『トモダチ』……確かに、『友人』なんだろうけどな……」
キョウジの言葉を、シュバルツは否定しなかった。ハヤブサは、自分にとっては間違いなく『友人』のはずなのだから。
「まあ、なるべく早く帰るつもりだが……キョウジ…。お前は一人で、大丈夫か?」
シュバルツの問いかけに、キョウジから明るい笑い声が返ってきた。
「大丈夫だよ。子供じゃないんだから」
「しかしなぁ、キョウジ……。お前はトラブルに巻き込まれる事が多いから―――」
そう言いながらシュバルツは、先の勾玉の事件の発端を思い出す。あの事件もキョウジが単独行動をしている時、自分の預かり知らない所でいきなり彼はそれに巻き込まれていた。だから、あまり長い間キョウジを一人にする事は、シュバルツにとってはとても心配な事であるのだ。
「何言っているんだよ、シュバルツ! あんな事は、滅多に無いって」
対してキョウジはまるで気にしていないようだった。心配性だな、シュバルツは。と、電話の向こうで明るく笑っている。
「でもまあ、シュバルツがそんなに心配してくれるんだったら……ドモンに連絡を取ろうかな。そうすれば、お前も安心だろう?」
キョウジからの提案に、シュバルツの顔にも笑みが戻る。
「まあ……な…。ついでにマスターアジアにも来てもらえ。お前が声をかけたなら、喜んで来てくれるんじゃないのか?」
「来てくれるかもしれないけど……あの人、ちょっと苦手なんだよなぁ。私の顔見るたびに『天下を取らんのか!?』みたいな事を言ってくるから……」
私は今のままで充分なのに、と、キョウジが少し零し気味に言うので、シュバルツもつられて苦笑してしまった。
「じゃあ、そろそろ切るぞ。借りている電話だから、あまり長話は出来ないんだ」
シュバルツからの提案に、キョウジも「ああ、分かった」と、素直に頷く。だが電話を切る直前、キョウジが声をかけてきた。
「シュバルツ」
だが電話の向こうのキョウジは、声をかけてきたきり沈黙してしまう。
「……? どうした? キョウジ……」
「あ……ううん、何でもない…。ハヤブサによろしく」
「ああ。そっちこそ、ドモンによろしくな」
「うん」
そうしてキョウジとの通話は切れた。
(……何故だろう。キョウジの声を聞くと、とても『安心』する……)
シュバルツは受話器を置きながら、そう思った。
自分の声とハヤブサの声と、キョウジの声。人には『似ている』と言われるけれども、自分に響くキョウジの声はやっぱり違う。とても安心できる―――特別な『声』だ。
今も彼の声を聞いて、自分がどれだけ励まされたか、きっとキョウジには永遠に分からないのだろう。そうシュバルツは感じて、知らず苦笑してしまう。
ああ。
やっぱりキョウジは、
どうしたって――――
自分の中では『特別』だ。
電話を借りた事を、宿屋の主人に礼を言うと、主人は人の良さそうな笑みを浮かべながら「構わないよ」と、応えてくれた。
(シュバルツ……)
キョウジは、携帯電話を握りしめたまま、立ち尽くしていた。
「……………」
キョウジは『知っている』のだ。ハヤブサのシュバルツに対する『特別な想い』を。
自分の、シュバルツに対する『想い』とはまた違った、深く激しい彼の『想い』を――――。
もしかしたらハヤブサは、この機会にシュバルツにその想いを告げるつもりでいるのかもしれない。キョウジには、何故かそう思えた。
でも、だからと言って
自分に何が、言えるだろう。
ハヤブサが『想い』をシュバルツにぶつけるか否か。
そしてそれをシュバルツが受け入れるか否か。
それを決める権利は、二人にしかないのに――――。
(もしかしたらシュバルツには……隼の里から帰って来ない選択肢だって、あり得る……)
ハヤブサのシュバルツを求め、必要とする力が強ければ強い程、彼はそれに応えようとするだろう。シュバルツは、そういう『人間』だと思った。だから、そのまま隼の里に留まり続ける事も、充分にあり得るのだ。
でも、それが普通だろう?
キョウジは自分に言い聞かせる。元は同じ人間の情報から派生しているモノとは言え―――シュバルツにはもうシュバルツの『生活』と『人格』が存在しているのだ。それを、いつまでもいつまでも自分の側に『影』として縛り付けておくなんて、それこそ不自然でおかしすぎる。
シュバルツには、選ぶ権利がある。
どこで生きて行くのか、誰の側に居るのか――――選択する権利があるのだから。
自分は、ただ見守るだけだ。
そして―――ただ、祈るだけだ。
シュバルツの『幸せ』を。
それ以外に――――何が出来ると言うのだろう。
もしかしたらそんな『権利』すら、本当は自分は持ってなどいないのかもしれないけれども。
キョウジは、携帯電話をキッチンのテーブルの上にトン、と置く。
「さあ……仕事に戻るか……」
そしてそう独りごちると、書斎に向かってパタパタと歩いて行った。
シュバルツが宿から出ると、そこに与助が待っていた。
「助かった…。ありがとう。『電話』の存在を教えてくれて…」
シュバルツが与助にそう声をかけると、彼は「いえ……」と、はにかむように答えながら、ポッとその顔を赤らめた。
(……やっぱり、『誤解』されているよなぁ。私とハヤブサの事を―――)
そう感じてシュバルツは苦笑してしまう。
「あのなぁ、与助……。一応言っておくが、私とハヤブサの間には、何も無いんだからな。あいつと私は『友人』の関係で――――それ以上でも、以下でもない」
「えっ? そうなんですか?」
だが与助は、そのシュバルツの言葉に対して意外そうな声を上げた。
「そうだ」
念を押すように頷くシュバルツに対して、与助はしばらく沈黙を返した。
「……でも、少なくともリュウさんの方は、貴方の事を『特別』だと見ている様な気がしますが……」
やがて与助は、ポツリとそう口を開く。
「―――! 何故、そう思うんだ?」
シュバルツは思わず足を止め、与助の方に振り返った。
「表情が、全然違うんです」
実直な眼差しを持つ若者が、言葉を紡ぐ。
「表情?」
怪訝そうに首をかしげるシュバルツに、与助は頷いた。
「リュウさんは、普段からあまり感情を表に出されない人です。隼の里を守る立場にあるからなのか、『龍の忍者』という類稀なる資質と肩書を持つ故なのか、私には分かりかねますが……」
話しながら与助は、ハヤブサの姿に想いを馳せる。その身に圧倒的な『強さ』と『技量』を兼ね備え、常に泰然としていて、孤独である事を恐れないリュウ・ハヤブサという存在は、与助にとっては深い憧れと尊敬を抱かせる存在であった。
「でも……最近のリュウさんは、どこかひどく、思い詰めたような眼差しをしている事が多くて……苦しそうで――――」
その姿を見るたびに、何か力になれないかと与助は願う。だが、ろくに彼に声もかける事も出来ない自分が、一体何の役に立つと言うのだろう。
「だけど、里に貴方が―――ええと、シュバルツさんでしたよね? すみません。ずっと私は貴方の事をキョウジさんだと思っていて……」
「ああ……別に、どちらで呼ばれようと、私は構わないのに……」
そう言いながらシュバルツは苦笑する。以前隼の里に滞在した時は、自分は『キョウジ』と名乗っていたし、実際自分は『キョウジ』でもあり、『シュバルツ』でもあるのだ。だからどちらで呼ばれようともシュバルツ自身は何の問題もないと思っているし、特にこだわりがあるわけでもなかった。
だがハヤブサが―――シュバルツが里の者たちから『キョウジ』と呼ばれる事を頑なに拒否した。
「彼の名は『シュバルツ・ブルーダー』だ。だから、彼の事は『シュバルツ』と呼べ」
ハヤブサが、シュバルツと会う里の者たちすべてに、そう言って聞かせたのだ。
「貴方が――――シュバルツさんが来てから、リュウさんの眼差しが全然違うんです。とても穏やかで……あんなに優しく、幸せそうに笑うなんて――――」
「…………!」
だから与助は悟る。きっと、このシュバルツという人が――――ハヤブサにとってはとても大切な『想い人』であるのだと。
対してシュバルツは愕然としていた。自分は、ハヤブサの穏やかな笑顔など、割とよく見ていたからだ。でもそれは、彼が『任務』とか『使命』から解放されて、一時の休息の時に見せる表情なのだと思っていた。
それが、違っていたのか。
彼が、自分だけに見せる『特別な』表情だったと言うのか――――?
「それなのに……『誤解』なんですか?」
「――――!」
二人の間に、サァッ、と、風が音を立てて吹き抜ける。
「リュウさんの『想い』は……貴方には届いていない、と、言うのですか?」
「与助……」
戸惑ったような表情を見せるシュバルツを、与助は懸命に見つめていた。ハヤブサのあれほどの想いが、シュバルツには届いていないだなんて、思いたくは無かった。
シュバルツは、言わなければならないと思った。
「誤解だ」と……。
歪なモノで構成されている自分の身体は、彼を受け入れる訳にはいかない。『自分を抱く事で生じるリスク』に、ハヤブサを巻き込んでしまう訳にはいかないのだから。
だが、与助のまっすぐな眼差しが、シュバルツを戸惑わせる。シュバルツがハヤブサを拒否する事を躊躇わせる。
やはり――――帰らなければならない……。
シュバルツは強くそう思った。
それも、なるべく早く。ハヤブサが治ればすぐにでも。
いや、それよりも―――治る目処がついたなら。
そうしなければ……。
拒否しきれない自分は、ハヤブサに流されて、押し切られてしまうかもしれない。
そういう訳には、行かないというのに。
ハヤブサを、『DG細胞』の餌食にしてしまってはいけないと言うのに……。
(私が『男』でもただの『人間』であったなら……今ここで感じる葛藤は、もう少し違ったものになったのだろうか……?)
そう感じたが故に、シュバルツの面に、複雑な表情が浮かぶ。
「シュバルツさん……?」
与助は不思議に思った。目の前のこの人は、リュウさんの事を拒否したい訳ではなさそうだ。なのに、何故――――哀しみの色と自嘲の色が、この人から強く読み取れてしまうのだろう。
何故、と、与助が問うよりも早く、シュバルツが踵を返した。
「行こう。ハヤブサが待っている」
それだけを言うと、彼はすたすたと歩き出した。与助は、ただ後ろからついて行くしか出来なかった。彼の後ろ姿は、与助からの如何なる問いかけも『拒否』しているようにしか見えなかったから―――。
二人の間に、重苦しい沈黙が漂う。しかしその沈黙は―――いきなり、思いもよらぬ方向から打破された。
「あっ! おっちゃんだ!!」
「―――!?」
シュバルツが驚いてその声のした方向を見ると、一人の子供が目を見開いて、シュバルツの方を指さしている。
(この子は……!)
シュバルツの方にも覚えがあった。以前隼の里に少しの間逗留した際、一緒に遊んだ子供たちの中の一人で――――。
思いだしたシュバルツがその子に声をかけようとするより先に、子供の方がもう動いていた。
「おお―――い! みんな!! おっちゃんが来てるぞ――――!!」
辺りをつんざく様なその子の叫び声が里に響き渡る。するとその声に合わせて、里のあちこちから子供たちの姿が一斉に目の前に現れた。
「えっ?」
「おっちゃんが!?」
「うそ! どこ? どこに!?」
「あっ! あそこだ!! ほんとだ!! ほんとにいた!!」
「おっちゃん…! おっちゃ―――――ん!!」
どこから沸いた!? と、思わず突っ込みを入れたくなるような子供たちの大群が、シュバルツめがけて突進してきた。
「おっちゃ――――ん!!!」
子供たちは躊躇うことなく、シュバルツに抱きついてくる。やっぱり5、6人が一斉に飛びかかってきた。
「うわ……っと……!」
6人までは何とか受け止めたシュバルツであったが、7人目でバランスを崩してしまう。それでも子供たちを怪我させないように器用に庇いながら、彼は尻もちをついた。
「おっちゃん! また来てくれたの!?」
「何時から来ていたの!?」
「また、遊べるんでしょう!?」
「一緒に遊ぼう! 遊ぼうよ~!!」
シュバルツをぐるり取り囲んだ子供たちから、次々と声をかけられる。
「シュバルツさん! 大丈夫ですか!?」
与助が走り寄って来て、案ずるようにシュバルツに声をかけてくる。それに対してシュバルツは笑顔を向けて答えた。
「大丈夫だよ…。しかし、皆私の事を覚えていてくれたのか?」
「覚えているよ! 当然じゃん!!」
与助が頷くよりも先に、子供たちの口が開いていた。
「おっちゃんが来てくれるのを、ずっと待ってたんだよ!」
「また遊んでよ! 僕あれから練習して、コマがうまくなったんだよ!!」
「ねぇ~! おっちゃん!!」
「あ…遊んであげたいけど……困ったな……」
子供たちにもみくちゃにされながらシュバルツは苦笑する。あまりハヤブサの傍から長時間離れ過ぎると、彼が無理をして布団から起き出して来そうな気がする。せっかく治りかかっているのだから、無理をさせたくはないと思った。
「リュウさんの家の軒先で遊んだらいかがですか?」
シュバルツの想いを何となく察した与助が、そう声をかける。
「いいのか? しかし……騒がしくしたらハヤブサに迷惑が―――」
「大丈夫ですよ。シュバルツさん」
それに対して与助は笑顔を返した。
「リュウさんはああ見えて、子供は好きなんです」
「そうなのか?」
「ええ。だからきっと、大丈夫です」
そう言うと与助は、子供たちに声をかける。
「よし、じゃあみんな、今日はあっちで遊ぼう。シュバルツさんも来てくれるから、大丈夫だよ」
「本当!?」
「やった――――!!」
「おっちゃん! 早く行こう!! 早く!!」
そう言いながら、子供たちが強引に手を引っ張ってくる。
(……そう言えばハヤブサは、子供を助けようとした私を斬らなかった……)
子供たちの力強さを感じながら、シュバルツは、ふと初めて彼と会った時の事を思い出していた。思えば『斬られなかった』と悟った瞬間、自分はハヤブサの事を信じてしまっていたのかもしれない。「この人は、弱き者をその背に守る優しい人なのだ」と…。
だから、「斬られても良い」と思った。
ハヤブサが自身の判断で、私に刃(やいば)を向けると言うのなら、その刃は、甘んじて受けようと。
(でも……結局斬られても私は甦ってしまうのだから、そう言う『想い』も所詮『欺瞞』にしかならないのだがな……)
そう感じたが故に、シュバルツの面に知らず自嘲的な笑みが浮かぶ。その表情に、一人の子供が気づいてしまったらしい。
「おっちゃん? 大丈夫か? どこか痛いのか?」
その子はそう言いながら、心配そうにシュバルツの顔を覗き込んできた。
「あ…ああ。大丈夫だよ…。ありがとう」
慌ててちゃんとした笑みを、顔に浮かべる。優しいな、と、声をかけると、その子ははにかんだような微笑みを浮かべた。
子供たちが側に居て良かった、と、シュバルツは思う。おかげで自分は、余計な事を考えすぎずに済むから―――。子供たちの明るさと力強さに、自分はどれだけ救われている事だろう。
(こうやって子供たちに『守られている』と感じるから――――私は『守りたい』と、思ってしまうのかもしれないな……)
子供たちに手を引っ張られながら、シュバルツはふとそんな事を考えていた。
(……遅い……)
一人部屋の中で布団に身体を横たえながら、ハヤブサはじりじりとした想いを持てあましていた。
大丈夫。
シュバルツは俺に黙って里から出て行ったりはしない。
そう『約束』をしたのだから――――。
必死に自分にそう言いきかす。
だから、信じて待つべきだ、と、理屈では分かっている。
だが、ハヤブサは不安だった。
「斬られても良い」と言って、その身を平気で投げ出すシュバルツだが、決して彼は「抱かれても良い」とは言っていない。寧ろ、『抱かれる』ことに関しては、はっきりと拒否している匂いすら感じる。彼自身の身体の歪(いびつ)さゆえに――――。
ハヤブサには分かっていた。
シュバルツは、恐れているのだ。
自分が『抱かれる』ことによって、自身を構成している『DG細胞』が、抱いた相手に感染してしまう事を―――。自分の身を一切顧みないシュバルツは、『男に抱かれる』という極限の状況下ですら、自分を抱こうとしている相手の事をまず思いやる。そう言う、優しすぎる――――美しすぎる『心』を持った、ヒトなのだ。
構わないのに。
ハヤブサは思う。
シュバルツを抱いて死ねるのなら――――ある意味、『本望』ではないか。
だが
シュバルツは
『そう』なる事を、決して望まない。
だから―――――かなり、厄介だ。
いざ事に及ぼうとしても、彼は決して同意をしてはくれないだろう。こちらの身を思いやるが故に。それでもシュバルツを抱こうとするのなら、彼を力づくでねじ伏せなければならなくなってくると悟る。『DG細胞』に自分が感染するかしないかなど――――実際に彼を抱いてみないと分からない。「自分は大丈夫なのだ」と証明するにしたって、事後でなければ―――それもできないではないか。
だから、早く自分の身体を治さないと。
頭ではそう思って、布団に身体を横たえ続ける事を、ハヤブサは選択する。
だが――――どうしたって、不安だった。
不安だ。
彼が、自分の視界に入っていないと、不安だ。
シュバルツがこちらの身を思いやるあまりに、『約束』を反故にして、黙って里から出て行ってしまう可能性が、無きにしも非ずだからだ。
だが違う。シュバルツは、そう言う男ではない。出て行く前には、必ずこちらに何か一言言ってくる――――ハヤブサは、必死に自分にそう言い聞かせていた。
(シュバルツ……早く姿を見せてくれ…。でないと、俺は……!)
布団から起き出して、様子を見に行こうか、と、ハヤブサが決意した時、軒先に子供たちが走り込んでくるのが見えた。
「おっちゃん!! ここで遊んでいいの!?」
「ああ。遊んで構わないが―――なるべく、静かにな。後、病人が寝ているから……家に入るのも、無しだ」
「は~~~い!」
元気に返事をする子供たちの真ん中に、シュバルツが立っているのが見える。
(よかった………)
彼の姿を確認したハヤブサは、上げかけていた頭を、再び枕に落とし――――ほっと、小さく息を吐いた。
「おっちゃん見てみて! 僕コマを回せるようになったんだよ!!」
一人の子供が嬉しそうに言いながらコマを持ってくる。その少年は、前にシュバルツがハヤブサの里を訪れた時に、「コマを回して」と、頼んできた子だった。慣れた手つきで少年がコマを放つと、コマは綺麗にバランスを保って、地面の上を勢いよく回りだした。
すごいな、と、シュバルツが褒めると、その子はえへへ、と、嬉しそうに胸を反らした。
「僕も回せるよ!」
「私だって!」
子供たちは口々にそう言いながら、コマを回しだす。
「おっちゃんも何かやってよ!」
一番最初にコマを回しだした少年が、シュバルツにねだってきた。彼は以前シュバルツが自在にコマを操った姿を見て、自分もああなりたい、とコマを一生懸命練習したのだ。だからもう一回、それが見たいと思った。
「えっ……? う~ん、と……じゃあ……」
その気配を何となく察したシュバルツは、一本の紐を取り出す。そして、回っている複数のコマの側に屈み込んだ。そしてしばらくそれをじっと見つめる。その姿は、集中力を高めているようにも、タイミングを図っているようにも、見えた。
「―――!」
シュバルツの紐を持った手が、ふっと素早く動く。すると次の瞬間、紐の上に回ったコマが4つ、見事に乗っていた。
「ええっ!?」
「うわぁ……!」
それだけでも充分に驚ける事であったが、彼はそのコマを紐の上に乗せたままさらに立ち上がった。そして子供たちににっこり微笑みかけると、彼は紐をくいっ、くいっと動かす。すると、その動きに合わせて4つのコマが、まるでお手玉のようにくるくるっと紐の上から宙へ、そしてまた紐の上へと回転運動をし始めたのだ。その魔法の様なコマの動きとシュバルツの手さばきに、子供たちはもう言葉を失うしかない。
「…………」
皆が皆口を半開きにしたまま、食い入るようにシュバルツが捌(さば)くコマの動きを見ている。
「よし! じゃあ、そこの前の4人、手を出して」
「…………!」
シュバルツの言葉に、まさか、と子どもたちは思いながらもおずおずと手を出す。以前シュバルツが一つのコマを操った時、最後は掌の上にコマを移してくれたものだが、まさか―――4つを一度にするつもりなのだろうか?
「よッ………と!」
シュバルツの掛け声に合わせて、コマが紐から跳ねて子供たちの手のひらめがけて降ってくる。トトト、と、音を立てて3つまでは掌の上に見事乗った。だが―――4つ目がバランスを崩して、掌から零れおちてしまった。
「ああ~! 駄目だな…久しぶりにやると…。やっぱり練習しないと―――」
そう言うシュバルツの顔に、少し残念そうな笑顔が浮かんでいる。
「でもすごいよ! おっちゃんすごい!!」
コマが手から零れおちた少年が、むしろ嬉しそうにシュバルツに声をかけてきた。
「どうやったらそんなこと出来るようになるの?」
「私もやってみたい!」
子供たちがコマを手に群がってくる。
「まあ、練習あるのみだな。まず、一つのコマを紐ですくう所から――――」
そう言いながらシュバルツの姿が、子供たちの間に混じる。
「……………」
ハヤブサは、布団の中から目の前の子どもたちとシュバルツの姿を見ていた。ひどく平和で、幸せな光景だと思った。
でも、何故だろう。幸せなのに、泣きたくなるのは。
何故だろう。こんなにも、胸が締め付けられるのは。
シュバルツ。
シュバルツ。
ああ――――やっぱり、俺は……。
どうしようもなく、お前が、好きだ―――。
好きだ………!
しばらくそうしてシュバルツを見つめていると、こちらの視線に気づいたのか、彼が子供たちの間から此方に向かってかけてきた。
「ハヤブサ? もしかして、起こしてしまったか?」
縁側から身を乗り出して、窺うようにこちらを見る。
「いや……起きてたよ」
そう言いながらハヤブサは、ゆるゆると身を起こした。その時ハヤブサの頬から―――一粒の滴が、流れて落ちる。
「ハヤブサ……?」
それを見咎めたシュバルツが、ブーツを脱いで部屋に上がってきた。
「どうした……? 泣いているのか……?」
「いや……『汗』だよ」
ハヤブサは、笑いながらそれを否定する。
「しかし……」
「『汗』……だ……」
念を押すように、ハヤブサはもう一度言った。だが、シュバルツと視線が合わせられずに、何となく逸らしてしまう。今、シュバルツに触れられてしまったら、それこそ見境なく彼を押し倒してしまいそうになる自分を自覚する。
駄目だ。と、ハヤブサは思う。
今は駄目だ。
自分の体調がまだ万全ではないし
何よりも――――子供たちが、居る。
ハヤブサは己が理性を総動員して言葉を紡いだ。
「……それにしても忌々しいな…。ひどい頭痛だ……」
「仕方がない。その『毒』の副作用だろう」
シュバルツは、淡々と言葉を続ける。
「汗もかいていると言う事は、明日には熱も下がる。恐らく、頭痛も今日よりはましになっているはずだ」
「……そうなのか?」
振り向くハヤブサに、シュバルツは頷く。
(明日には……かなり楽になっているのか……)
ハヤブサはそう思うと同時に、自分の中に押し込めているシュバルツに対する黒い欲望が頭をもたげてくるのを感じていた。
「だが、熱は下がったからと言って――――無理はするなよ。毒はまだ抜けきらないんだ。熱が下がっても3日は安静にしていないと、完治しないぞ」
シュバルツのその忠告に、ハヤブサは苦笑う。
「そんなに長く安静にしていたら……体がなまってしまうな……」
「仕方がないさ。その方が早く治るのだから―――」
「おっちゃ~ん! 何してるの~? こっちに来てよ―――!!」
軒下から、シュバルツを無邪気に呼ぶ子供たちの声が聞こえてくる。
「ああ、今行く!」
シュバルツが子供たちに明るく笑って答える。シュバルツは本当に、子供たちに慕われているようだった。
「しかしお前……本当に、子供たちと遊ぶのがうまいな……」
ハヤブサが素直な感想を述べると、シュバルツがちょっと苦笑交じりの笑顔で応えてきた。
「弟であるドモンがいたおかげかな……。なにせ、8つも年が離れていたんだ。面倒みている事も多かったから―――」
「それにしても……いいのか? 『おっちゃん』て、呼ばれているのは……」
「気にしないよ。28歳なんて、あの子らからしてみれば、紛れもなく『おっちゃん』だろう?」
そう言いながらシュバルツは、再び縁側から庭へと降り立つ。そして、子供たちの中へと混ざって行った。
再び軒先で繰り広げられる、平和な光景。
子供たちの元気な笑い声と、シュバルツの優しい笑顔―――。
ずっと、見て居たい、と、思った。『あの時』と、同じように。
思わず『時が止まれば良い』などと、祈りたくなった――――。『あの時』と、同じように。
(神や仏などとは一番縁遠い世界に居るはずなのに……どうして―――俺は『祈り』たくなるのだろうか……)
そう思いながらいつの間にか、ハヤブサの意識はまどろみの中へと落ちて行った。
「あの……夕餉の支度が出来ましたが……」
宵闇が迫る中、与助が部屋の中の二人にそう声をかけると、シュバルツが振り向く。しかし、ハヤブサからは反応が返って来なかった。
「リュウさんは……?」
「よく寝ている」
シュバルツがそう言って見つめる先で、ハヤブサが穏やかな寝息を立てていた。
「本当だ……」
与助はある種の感慨を持ってハヤブサの姿を見つめていた。このように無防備に眠るハヤブサの姿など、自分だけでは絶対に見る事が出来なかっただろうから――――。
「眠れるのなら、寝ていた方がいい……。結局それが、一番の回復への早道なんだ」
そう言いながらシュバルツもまた、ハヤブサを見つめている。与助がそちらに振り向くと、とても優しい眼差しをしたシュバルツの横顔が視界に飛び込んできた。それがとても綺麗で――――与助は思わず見入ってしまう。
(ああ、この人が……リュウさんの『想い人』なんだ…)
何故かそれが―――素直に与助の腹に落ちた。
「? どうした?」
与助の視線に気がついたのか、シュバルツが不意にこちらを見る。
「い! いえっ! 何でもありません!」
慌てて与助は回れ右をする。顔が、何故か勝手に火照った。
「ゆ、夕餉をお持ちします!」
そう言いながら若者は慌ててかけ出していた。
(……やっぱり、『誤解』されているよなぁ……)
与助のそんな様子を見ながら、シュバルツは小さくため息を吐く。もしかしたら、ハヤブサの方が『誤解ではない』と思って……その先を望んでいるのかもしれないけれども。
無理なのに。
シュバルツは思う。
自分の身体は、ハヤブサをどうあっても受け入れる訳にはいかないのに――――。
(やはり、明日ハヤブサの熱が引いていたら、帰ろう)
シュバルツはそう決意しながら、穏やかに眠るハヤブサを見た。ハヤブサの『想い』に応えられないのであるのなら、自分はいつまでもここに居るべきではない。早々に里から去るべきなのだ。きっとその方が――――お互いのためになるはずだ。
(この気苦労が……私の一方的な『誤解』であったのなら……それに越した事は無いのだが、な……)
シュバルツはそう思いながら、穏やかに眠るハヤブサの顔を見ていた。
夜更け。
喉の渇きと寝苦しさを感じたハヤブサが目を覚ました。
(いつの間にか眠ってしまっていたのか……シュバルツは!?)
真っ先にシュバルツの姿を求めたハヤブサは、少し離れた所に敷かれた布団の中で眠っている彼の姿を見つけて、ほっと息を吐く。
水分を取り、薬を飲む。寝汗のせいで濡れた着物を着換える。それから彼は、シュバルツの側に歩み寄って行った。
シュバルツは、規則正しい寝息を立てて、静かに眠っている。
(シュバルツ……)
シュバルツの寝顔を見ていると、自身の中で愛しさと劣情と、良心の呵責が渦を巻くのをハヤブサは感じる。この先自分がシュバルツに『しよう』としている事を考えると、とても平静ではいられなかった。
(今のままでは、駄目なのか?)
ハヤブサはあえて自問自答する。今でも、シュバルツは傍に居て、微笑みかけてくれて、自分の身を案じてくれている。彼の優しさは、充分自分に注がれているのだ。それで―――満足すべきなのではないのかと。
だが。
ハヤブサは苦笑う。
シュバルツの『愛情』は、とても広くて大きい。子供たちに向けられる笑顔と、自分に向けられる彼の笑顔。一体―――どこに違いがあると言うのだ。何も……何も、変わらないではないか。
それでは嫌だ。と、ハヤブサは思う。
自分は、彼の『特別』になりたいのだ。
彼の記憶の中で、ただ通り過ぎて行くだけの者ではなくて。
忘れたくても忘れられなくなるような――――そんな、存在に。
(そのために、今までの関係を壊してしまっても…? 彼が、もう2度と、自分に微笑みかけてくれなくなったとしても――――?)
ハヤブサは、自身に問いかける。
いいのか?
それで、いいのかと――――。
「……………」
(その方がいいかもな……いっその事―――『未練』が無くなって……)
ハヤブサの面に、自嘲的な笑みが浮かぶ。
このまま爆発しそうなシュバルツへの想いを抱えたまま死ぬのはあまりにも辛すぎる。軽蔑されても、嫌悪されても――――彼に想いをぶつけてしまった方が、よほど楽になれるのではないかと思うのだ。きっとその後ならば、もう自分はいつ死のうとも、後悔なく死ぬ事が出来るだろう。『人斬り』の任務にも、『龍の忍者』の使命にも――――迷いなく望めると言うものだ。
ただ、自分の『想いをぶつける』という行為の中には、シュバルツの思いや都合が入り込む余地はない。本当に、自分の欲求をぶつけるだけの、自己満足な行為だ。シュバルツは、自分と『そういう』関係になる事を決して望んでいない事が、ハヤブサには分かり過ぎるほど分かっている。だからそれが――――彼には、ひどく淋しく感じられた。
本当に、一方的な『想い』
絶望的な、『片想い』だ。
それでも……?
ハヤブサは、自問自答をする。
それでも―――――!
「シュバルツ……」
眠っているシュバルツの髪に、ハヤブサは想いをこめて触れる。
(たとえどうなろうとも、俺はお前を『愛している』――――どうか、それだけは……感じ取ってほしい……)
本当に勝手で―――どうしようもない『想い』だ、とハヤブサは苦笑する。
でも、本当に、どうしようもない。
もう――――どうしようもないんだ。
(これが……シュバルツと過ごす最後の穏やかな夜になるのかもしれない……)
シュバルツの寝顔を見つめながら、ハヤブサはふとそう思った。
同時刻。隼の里より少し外れた山中で、里の守り番と、甲賀忍軍との小競り合いが起きていた。結果はいつもの如く―――里の守り番側の勝利で終わった。
「……全く、何度挑んでも結果は同じというのに、大概奴らもしつこいな……」
斬り伏せた遺体から刀を引き抜きながら、守り番頭がぼそりと零す。
「おそらく、リュウさんが負傷した事を奴ら知っているんだ…。だから、必死なのであろうよ」
「こいつら、『龍剣』を狙っているからなぁ」
戦闘を終えた里の仲間たちが、次々と番頭の所に集まってくる。守り番に出ていた者全員の姿が見えたので、こちらの損害は軽微だと番頭は悟る。対する甲賀忍軍は、全滅だった。
「それにしても三郎太、よく相手から刀が奪えたものだな」
「あ……ああ。運が良かった……」
三郎太はそう言いながら立ち上がる。足を軽く負傷していた。折れた三郎太の刀が、足元に転がっている。
「もうすぐ交代の者が来る。それまではまた、各々持ち場に戻れ。今日はもう襲撃は無いと思うが、油断するな!」
「応!」
その声を残して、そこに集まっていた忍者たちは消えた。後にはただ、闇の静けさだけが残された―――。
翌朝。
シュバルツの診立て通り、ハヤブサの熱は下がっていた。頭痛も収まり、普通に朝食も取れていた。
「もう、大丈夫そうだな」
それを見たシュバルツが、微笑みながら言った。
「すっかり世話になった…。お前のおかげだ」
ハヤブサが礼を言うと、シュバルツは頭を振った。
「礼などいいよ。困った時は、お互い様だ」
「それよりも、お前……」
「何だ?」
「飯、食えたのか?」
そう言うハヤブサの目の前で、シュバルツがきゅうりの漬物を箸でつまんでポリ…と、食べている。
「……食えない、事は無い」
そう言いながらシュバルツは、普通に食を進めている。
「……味は、分からないけどな……」
「そうか……」
そう言ったきり黙りこくってしまったハヤブサを見て、シュバルツは笑みを浮かべる。
「ただ……『旨いんだろうな』とは、思うよ」
「―――どうしてそう思うんだ?」
「調味料のバランスとか……使われている野菜の新鮮さとか―――」
そう言いながらシュバルツは、口の中の物を咀嚼する。相変わらず何の味もしなくて、脳の中に浮かぶのは、数値化された成分のバランスデータだけだ。
でも――――。
時々出される料理の中には、分析しきれない『何か』が含まれている事がある。その値はとても大きい事もあれば、ごくごく微量の時もある。ただ―――この分析しきれない『何か』が含まれている割合が大きければ大きいほど――――その料理を食べた人の顔が、『幸せ』な表情になっている様にシュバルツには感じられた。
(きっと……これが作り手の『愛情』なのだろうな……)
そう思うと、いろいろと辻褄が合うから、シュバルツはとても幸せな気持ちになる。この朝食にも、その分析しきれない『何か』の割合がとても高い。だから、『残さず食べなければならない』と、思うのだ。
だが―――この料理が、自分の『エネルギー』の元にはなることはない。それを思うと少し切ない。かと言って、自分の中で消化吸収された料理が外に『排泄』される事もない。ならば、この食べた料理は―――一体どこへいってしまっているのだろう?
自分の身体なのに、この身体は……実際分からないことだらけだ。もっといろいろ『実験』出来ればいいのだろうが――――。
そこまで思いをめぐらした時、シュバルツの額に魚の骨が、コン! と、音を立てて当たる。
「!?」
驚いて顔を上げるシュバルツの視界に、ハヤブサが呆れたようにこちらを見てる姿が飛び込んでくる。
「隙だらけだぞ? シュバルツ。どうせまた、小難しい事でも考えていたんだろう」
「…………!」
「さっさと飯を終わらせよう。お前に、話したい事があるし―――」
ハヤブサの言葉に、シュバルツもピクリと反応する。
「そうだな……。私も―――」
シュバルツはカタン、と箸を置いた。
「お前に……話したい事が、ある……」
「――――!」
ハヤブサの朝食を食べる手が、ピタリと止まった。
「……何だ? 『話』って……」
ハヤブサは何気ない風を装ってシュバルツに話を促した。だが―――内心は、嫌な予感でいっぱいだった。
「あ、ああ……。実は……」
シュバルツも、少し言いにくそうにしている。
「そろそろ……暇乞いをしようかと、思って―――――」
「…………!」
鈍器で殴られたような衝撃を受けているハヤブサに気づいているのかいないのか――――シュバルツは言葉を続けた。
「もうお前も、大丈夫そうだし……キョウジもずっと独りにしていて、そろそろ心配だしな……」
「『キョウジ』……」
ハヤブサは懸命に堪えようとするが――――手が小刻みに震える事を止める事が出来ない。
「ああ……そうだな……。『キョウジ』が心配――――」
「ハヤブサ?」
ここに至ってシュバルツも、ようやくハヤブサの様子がおかしい事に気づく。
「ハヤブサ? 大丈夫か?」
「いや……何でも……。ただ少し……頭が、痛くて……」
「えっ……!」
驚くシュバルツの目の前で、ハヤブサが苦しそうに頭を抱えている。
「ハヤブサ!? どの辺りが痛いんだ!? とにかく横になって―――」
そう言いながらシュバルツが、ハヤブサの側に駆け寄った瞬間。
ドン!!
ハヤブサの右拳が、シュバルツの鳩尾にめり込んでいた。
「う……ッ! ハ……、ヤ……?」
そう言いながら意識を手放すシュバルツの身体を、ハヤブサが抱きとめていた。
(……全く、甘い奴だよお前は……。こんな『手』に、引っ掛かるなんて……)
クッ、と、のどの奥で笑いながら、ハヤブサはシュバルツの身体を抱きしめる。
もう離さない。
お前は――――俺の、モノだ。
「与助! 与助はいるか!?」
ハヤブサの呼び掛けに、与助がスッと姿を現す。お呼びで、と、言いかけた与助が、気を失っているシュバルツを抱きしめているハヤブサの姿を見て――――息を飲んだ。
「……今からしばらく、この家に誰も近付けるな。例え家の中から、どんな『叫び声』が上がろうともだ……」
「――――!」
ハヤブサの言葉に与助は息を飲む。だが、ハヤブサの思い詰めた眼差しの前に、与助に何が言えるだろう。彼は頷くしかなかった。そして悟る。今からハヤブサは――――『想い』を遂げるつもりなのだと。
「分かりました。お任せください」
「すまん」
それだけ言うと、ハヤブサは襖の向こうに姿を消した。シュバルツを抱いたまま―――。
「……………」
与助の脳裏に、シュバルツの哀しげな眼差しと、ハヤブサの思い詰めた表情が交差する。何故か、胸が締め付けられた。
(届けばいい。リュウさんの想いが、あの人に………)
暗雲たなびく里の空の下、与助は、そう祈らずにはいられなかった。
第4章
誰かが自分の身体にひどく優しく触れてくる。
(……う……)
シュバルツは思わず身震いをした。やめて欲しい、と、思った。だがその手はまた―――シュバルツに優しく触れてくる。
「……は………」
(嫌だ……)
その手を振り払おうとして手を動かそうとして――――自分の手が、ピクリとも動かない事に気づく。
「…………?」
(何だ……?)
朦朧とした意識を何とかはっきりさせようと、シュバルツは頭を振る。もう一度手を動かそうとして、手の動きが、ギッ、と、音を立てて、何かに阻まれていると悟る。
ゆるゆると目を開けると、やけに暗い部屋の景色が飛び込んできた。
(ここは……?)
シュバルツが状況を把握しようと周りを見回そうとした時――――。
「気がついたか?」
「…………!」
ハヤブサにそう声をかけられた瞬間、シュバルツは今までの過程を思い出した。
そうだ。私はハヤブサに暇乞いをしようとして。
ハヤブサが「頭が痛い」と言うから介抱しようとして……。
いきなり鳩尾を殴られ……て……。
「あ………!」
シュバルツは自分の置かれた状況を把握する。上半身の衣服は脱がされて、ズボン一枚だけの姿で彼は布団に横たえさせられていた。身を起こそうにも、手と腕が頭上で一括りにされて縄の様な物で拘束され、どこかにつながれているようであるが故に、シュバルツはそこから逃れる事が出来ない。そしてその縄は、シュバルツが腕を動かそうとすればするほど、喰い込んでくる仕組みになっているようだった。
「ハ…ヤブサ……?」
『状況』は理解できたが、何故、こんな事になったのかが、シュバルツは咄嗟に理解出来ない。誰が、何のためにこんな事を――――。
「まだ少し、混乱しているようだな……」
目が覚めて、状況を把握したようであるのに、自分を見上げてくるシュバルツの瞳に怯えの色も、殺気の色も灯らないのを見て、ハヤブサは苦笑する。
「お前を『そう』したのは、俺だよ」
「――――!?」
シュバルツの瞳が驚愕で見開かれる。
「お前の『ここ』を―――俺が殴って……」
そう言いながらハヤブサの手が、シュバルツの鳩尾付近をひどく優しく撫でる。
「――――!」
自分の肌の上をハヤブサの指が滑る感覚に、シュバルツの身体はビクリ、と身震いをしてしまう。
「……やけに感じやすいんだな…」
その様子を見たハヤブサが、のどの奥で「クッ」と、低く笑う。その言葉に、シュバルツの頬が、カッ、と赤く染まった。
「な……何故……」
シュバルツが信じられない物を見る様な眼でこちらを見上げてくる。
「ハヤブサ……? 何故……! 何故、こんな事を―――!?」
「………まだ、分からないのか? シュバルツ…」
そう言いながら口元だけに『笑み』を浮かべるハヤブサ。だが返ってくる『声』も、シュバルツを見つめ返してくる『視線』も、やけに冷たい。
シュバルツは俄かには信じられなかった。
今、自分の目の前に居る男は本当に――――あの、優しい眼差しでこちらを見つめてくれていたハヤブサなのだろうか?
「俺は――――お前を、抱きたいんだ」
「――――!!」
自分の言葉に息を飲むシュバルツを見て、ハヤブサは『満足』する。着ていた着物を脱いで上半身裸になると、彼もまた布団に横たわるシュバルツの上へとその身を移動してきた。トン、とシュバルツの身体の横に手を置いて四つん這いになると、自分の身の下でシュバルツが逃れようと身じろぎしているのが分かった。しかし、彼を捕らえている縄がぎしぎしと、音を立てるだけで、その努力は徒労に終わっている。
逃がさない。
逃がすものか。
俺はもう―――途中で止まる気も、無い。
「ハ、ハヤブサ……! 何を言って―――」
シュバルツが怯えた色をはっきりと浮かべてこちらを見ている。
「シュバルツ……」
ハヤブサは思わず、その頬に触れていた。怯えた彼の表情ですら、やけに美しく感じられたから――――。
「――――ッ!」
その手の感触に、シュバルツは思わず身じろぎをする。それがハヤブサの劣情を、さらに煽っているのだと言う事に、シュバルツは気付いていない。
「何を言っているんだ! お前は!! やめろッ!!」
恐れていた事が現実になったと悟ったシュバルツは、懸命に叫んだ。とにかくハヤブサを思いとどまらせなければいけないと強く思った。
「……シュバルツ…。俺が、嫌いか……?」
ハヤブサの哀しげな声が降ってくる。
「ち、違う!! 好きとか嫌いとか――――そういう問題じゃない!!」
シュバルツは懸命に頭(かぶり)を振る。自分の身体は『歪(いびつ)』だ。故に、自分の身体は他人に深く触れられるべきではない。抱かれてはいけないのだ。
「分かっているだろうハヤブサ!! 私の身体を抱いては駄目だ!!」
それを分かって欲しくて、懸命にシュバルツは叫ぶ。しかしハヤブサからは、尚も哀しげな声が返ってきた。
「………何故だ…?」
「な…! 何故って……分かっているだろう!?」
シュバルツは必死にハヤブサに問いかけた。彼は分かっているはずなのだ。自分の身体の『成り立ち』を。その『禍々しさ』を――――。それを、思い出して欲しいのに。
こちらがそう訴えかけるたびに、その瞳を哀しそうに曇らせるハヤブサの姿に、何故かシュバルツの方が泣きそうになってくる。
「わ……私は『男』で……!」
「ああ。『男』だな」
事もなげに返されるから、シュバルツは絶句しそうになる。それでも黙る訳にはいかないから、必死に言葉を紡いだ。
「に……っ! 『人間』で、すら……なくて……!」
「ああ。知ってるよ」
だからどうした、と、言わんばかりのハヤブサの態度に、シュバルツはたまらなくなる。
「ハヤブサ……ッ! 知っているのなら、何で――――!!」
シュバルツはいつしか涙を零していた。
おかしい。
おかしいんだ。
自分のこんな身体を『抱こう』だなんて、どう考えてもおかしすぎる―――!
「分かっているだろう!? 私の、『身体』は――――んっ!! んぅ……!」
『DG細胞』の塊だ―――と、叫ぼうとしたシュバルツの唇は、ハヤブサによって塞がれてしまった。まるで、その先を言う事は許さないとでも言わんばかりに。そのままハヤブサの舌がシュバルツの口腔に侵入し、その口内を味わいながらシュバルツの舌を強く吸いあげる。それが、何度も続いた。シュバルツの舌が逃げようとするたびに何度も何度も捕まえられ、そして吸われる。
「うっ……ふ……! んんっ……!」
(ハヤブサ……ッ! どうして―――!!)
ギチッ、と、シュバルツを拘束している縄が軋む。痛みと息苦しさで、シュバルツは自分がどうにかなってしまいそうだと思った。そうなる前に、ハヤブサに早く自分から離れて欲しいと、願った。
「ん…! ……は……あっ……!」
口付けから解放すると、シュバルツはすぐに顔を逸らした。酸素を求めるが故にその呼吸は短く荒くなり、手を拘束しているが故に、唇から溢れて零れ落ちる唾液を、彼は拭う事が出来ない。そして、頬を伝う涙――――。どれをとっても、美しすぎるとハヤブサは思った。
「……どうして……『抱いたら駄目だ』などと、言うんだ……」
指の腹で涙を拭いながら、ハヤブサは吸い寄せられるようにシュバルツの頬に唇を落とす。
「あっ…!」
唇の感触に身じろぐシュバルツ――――たまらなく、愛おしいと思った。
「こんなに……綺麗なのに―――」
その言葉を直接シュバルツの耳に注ぎ込んでやると、彼の身体がビクン、と、跳ねた。
「あっ! ち、違……っ! そんな……はず、は……っ!」
「……シュバルツ……」
想いをこめたハヤブサの唇が、耳から首、そして、胸へと滑っていく。
「……ん…! ……く……っ!」
シュバルツは震えながらその愛撫を耐えた。声を殺そうと、必死に唇を噛みしめている。だが、ハヤブサの唇がシュバルツの胸の頂に触れた瞬間、あまりにも甘い電流が彼の全身を駆け巡ったが故に、彼は思わず叫んでしまった。
「あっ! ああっ!!」
それと同時にハヤブサの右手が、シュバルツの脇腹を撫でながら彼の下半身へと降りて行こうとする。
「うあっ! あ…! い、いや…だ…っ!」
下半身へと近づいてくるハヤブサの手は、シュバルツに根源的な『恐怖』を与えた。自分が暴かれてしまう恐怖。自分が『自分』で無くなってしまう様な恐ろしい衝動――――それを感じたが故に、シュバルツの身体が思わず動いてしまう。
「やめっ……! やめろ!!」
動きを封じられていなかったシュバルツの足が、ドカッ!! と、音を立ててハヤブサの身体を蹴りあげた。
「うぐッ……!」
蹴りをまともに食らって吹っ飛ばされたハヤブサが、蹴られた腹を抱えてうずくまってしまう。それを見たシュバルツは、思わず息を飲んだ。破れかぶれで繰り出した一撃。ハヤブサは、『避ける』と思っていたのに。
「ハ……ハヤブサ―――」
シュバルツから名を呼びかけられ、彼を拘束している縄が、ギッ、と、音を立てて軋む。それだけで―――ハヤブサには『分かって』しまった。彼が――――シュバルツが、今、どういう気持ちで自分に声をかけたのかが。
「……案じたな? 俺の身を―――」
腹を抱えながら顔を上げ、ハヤブサはにやりと笑う。
「……………!」
図星を指されたシュバルツは、息を飲んだ。
「俺は、お前を『犯そう』としているのに……」
「ハ、ハヤブサ……!」
「そう言う、奴だよな……。お前は―――」
「あ…………!」
「そう言う、奴だよ」
そう言いながらハヤブサが「クッ」と、のどの奥で笑うから、シュバルツは返す言葉を失ってしまう。
「………………」
黙ってしまったシュバルツに向かって、ハヤブサが再び距離を詰めて来る。シュバルツの脇に手をトン、と、置くと、また彼の上に覆いかぶさってきた。
「俺を殺せ。シュバルツ――――」
「――――!?」
唐突に紡がれたハヤブサの言葉を、シュバルツは咄嗟に理解出来ない。
「俺に、『触れられたくない』と……『やめて欲しい』と、願うなら――――」
「な……何を……!」
何か恐ろしい事を聞いた様な気がして、シュバルツは知らず震えてしまう。
「何を……言っているんだ…! お前は――――!」
ハヤブサは、性質の悪い冗談を言っているのだと思いたくて、シュバルツはハヤブサの瞳(め)を見る。しかし、彼のシュバルツを見下ろしてくる眼差しは、真剣そのものだった。
「そ、そんな事……出来る訳ないだろう!!」
「出来る筈だ!! お前なら―――!」
シュバルツの言葉を言下に否定するかのように、ハヤブサは大声で叫んでいた。
「出来るだろう! お前なら……! 俺と互角の技術と体術を持っているのだから―――!」
「ハ……ハヤブサ……!」
息を飲むシュバルツを見下ろしながら、ハヤブサはなおも言葉を続ける。
「俺が…お前の動きを封じているのは『手』だけだ…。後はどこも戒めてなどいない。足も……! そして、口も――――」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの頬に指を走らせる。
「――――ッ!」
その感覚にシュバルツは思わず身じろいだ。封じられていない口と足を、知らず意識してしまう。
「そして……『お前を抱きたい』と、望む俺は……『武器』もつけずに丸腰で――――お前に対して、無防備だ……」
「ハヤブサ……ッ!」
「あるだろう? 俺を殺す手段など、お前ならいくらでも思いつくだろう?」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツを見つめる。そしてその姿は隙だらけだ。恐ろしい程に。
本気だ。
本気で彼は望んでいるのだ。
『殺せ』と……!
「そんな………!」
シュバルツは困惑する。自分は、ハヤブサの『死』を決して望まない。死んで欲しくないから、自分を抱く事を『やめろ』と、言っていると言うのに。
「ハヤブサ…ッ! どうして―――!」
「シュバルツ……」
困惑する表情を浮かべるシュバルツに、ハヤブサは優しく微笑みかけると、シュバルツの髪を撫でながら顔を近づけてくる。
「シュバルツ……ほら……」
「あっ……!」
シュバルツの口が少し開いた瞬間を狙って、ハヤブサの唇が重ねられてくる。そこから彼の舌が、シュバルツの口内に深く差しこまれた。
「んむ……! …う……!」
口腔をハヤブサの為すがままに蹂躙されるシュバルツ。そんな彼に、ハヤブサはもう一度声をかけた。
「俺の舌を噛み切れ……。簡単だろう…?」
そして再び差し込まれる舌。深く、深く―――。
「ふ……う…っ! んんっ…!」
(ハヤブサ……ッ!)
シュバルツの瞳に、再び涙がじわり、と、滲んできていた。
「どうして……噛み切らないんだ?」
チュッ、と、音を立ててシュバルツの舌を吸ってから、ハヤブサの唇はシュバルツから離れる。
「あっ……! は……はぁ……っ!」
口許から唾液を溢れさせながら、シュバルツの呼吸は荒くなって行くばかりだ。
「『嫌』なら……『やめて欲しい』なら――――」
すぐにハヤブサは、またシュバルツの呼吸を奪う。
「んぐ……! う……んぅ……!」
「俺を……殺せばいいのに……」
「そ、そん…な……っ! あ……! んぅ……っ! ……ふ…!」
ギチッ、と、音を立ててシュバルツを繋いでいる縄が軋む。その身体が小刻みに震えているのがハヤブサに伝わる。それでもシュバルツがハヤブサに歯を立てようとしないのを感じ取ったが故に、ハヤブサは一度シュバルツの呼吸を『解放』することにした。
「シュバルツ―――」
「はあっ! ……は…! ハ、ヤ…ブサ……!」
震えて、涙を流しながら見上げてくるシュバルツの髪を、ハヤブサは優しく撫でる。
無垢なシュバルツ。
愛おしいシュバルツ。
可哀想に。
俺みたいな男に魅入られさえしなければ、お前は――――
綺麗なままで居られた、のに。
「な……何故、だ…? ハヤブサ…。何故……!」
涙も震えも止められないままに、シュバルツは言葉を紡ぐ。
「どうして……『殺せ』だ、なんて……」
「死ななければ――――俺は、止まらないぞ」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの鎖骨に唇を落とす。
「は……っ!」
ビクン、と、跳ねるシュバルツの身体に、ハヤブサの劣情はさらに刺激される。
「俺は、お前を最後まで、抱く。もう―――そう、決めているんだ……!」
止められないハヤブサの唇は、シュバルツの脇の下へと滑っていく。
「ひっ! あ……っ! い、い…や……だ…!」
「『嫌』なら……俺を殺せ…! シュバルツ―――」
「そ、そんなこと――――出来る訳ないじゃないか……ッ!」
強制的に感じさせられる感覚に抗うように、シュバルツは叫んだ。
「私は…っ! お前には死んで欲しくない…! 失いたくないと――――思っているのに……っ!」
「俺は、お前を犯しているんだ…! それでもか?」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの二の腕を舐め上げて行く。
「あ…っ! ハヤブサッ! ハヤブサぁっ……!!」
救いを求めるようにシュバルツは叫び、その身体をしならせる。しかしハヤブサの愛撫の手は緩む事が無く、ギ、と、縄が音を立てて、シュバルツの腕に食い込んでいくばかりだ。
「こんな……! どうして―――!」
荒い息の下、それでもシュバルツは懸命に言葉を紡ぐ。
「どうしてだ……! ハヤブサ……ッ」
その問いかけには応えず、ハヤブサはシュバルツの胸の頂を口に含む。
「あっ! ああ……ッ!」
舌先で丹念にそこをいたぶってやると、シュバルツの口から堪え切れぬ高い嬌声が漏れた。その愛撫から逃れようと、懸命に身体を捩り、頭(かぶり)を振る。…涙が飛び散る。その様が、ハヤブサの劣情をさらに燃え上がらせている事に、シュバルツは気付く事が出来ない。
しなるシュバルツの身体を抑えつけ、もう一つの方の頂も口に含みながら、空いた方の頂も指で弄んでやると、そこは芯を伴って、ぷく、と勃ち上がってきた。
「あああっ! ハヤブサぁっ!! ああっ! や……め……っ!」
「……熟れてきたな……。感じているんだろう? シュバルツ―――」
『人間』と同じような反応をするシュバルツの身体にハヤブサは『満足』する。わざと嗜虐的な言葉をぶつけ、弄んだ。
「……う…! く……ッ!」
羞恥故にシュバルツの頬は朱に染まり、せめて声を堪えようと、下唇を噛みしめている。無駄な抵抗だと言わんばかりに指の腹で熟れた頂をこすってやると、たちまち彼の口から高い嬌声が漏れた。身体がしなり、腕に絡みついている縄が、ギチッ、と、音を立てる。
「……ハヤブサ……! …ハヤブサ……!」
空を見つめて涙を流すシュバルツから、うわ言の様に名を呼ばれる。まるで、縋るように―――。
(シュバルツ……!)
ハヤブサは唇を噛みしめる。分かっている。今、自分が行っている『行為』は、決してシュバルツの『同意』を得ている物ではないと言う事。―――そして、その事についてシュバルツから『同意』を得られる可能性など、永遠に無いと言う事を。
一方が一方を踏みにじる行為―――。シュバルツにとっては、まさに『凌辱』以外の何物でもないだろう。
だから、恨んでくれていいのに。
『嫌』なら―――殺してくれていいのに、と、ハヤブサは思う。
シュバルツからもたらされる『死』なら――――俺は、喜んで受け入れられる。
きっと、恍惚の内に、死ぬ事が出来るだろう。
なのに、目の前に居るこのヒトからは、恨みや殺気の色が感じられない。それどころか、ひたすら自分の名前を呼び続けられている。
まだ、信じていると言うのか。
お前を、踏みにじろうとしている俺を。
お前を、犯そうとしている俺を――――!
(………………)
ハヤブサは、せめて、シュバルツの髪を優しく撫でた。
止まれない自分。
後戻りできない自分は、もう、シュバルツの『声』に、応える事が出来ないから――――。
「……一つだけ……教えてくれ…ハヤブサ……」
髪を撫でられていたシュバルツが、荒い息を何とか整えながら、ポツリ、と口を開いた。その声に、ハヤブサの手がピクリ、と止まる。
「何をだ……?」
問いかけるハヤブサをシュバルツはちらり、と見やると、大きな息を一つ、吐いた。
「わ……私は……何か、してしまったのか……? お前に対して……。お前が……その…そんな風にせずには、居られない……ほど…に……」
(この期に及んで……まだ、自分を責めるのか? シュバルツ……)
そう感じたハヤブサは、知らず苦笑してしまう。
「違う……。お前は、悪くない」
ハヤブサはシュバルツの髪を撫でながら言葉を紡ぐ。
「悪いのは俺だ……。お前に一方的に魅入られてしまった……俺が――――」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの鳩尾付近に唇を落とす。
「あ……っ!」
小さくぴくんと跳ねるシュバルツの身体。ハヤブサは、唇をシュバルツの肌に密着させたまま、小さく口の中で言葉を紡いだ。
(―――好きだ……シュバルツ…。好きだ――――)
「ん、あ……っ」
肌の上を唇が動く感触にシュバルツの身体が跳ねて震える。今自分が言った言葉は、シュバルツに永遠に届かなくてもいいとハヤブサは思った。自分は、その想いをこめてシュバルツを抱くだけなのだから。
「あ…っ! ハヤブサ……ッ!」
ハヤブサからの愛撫に耐えながら、シュバルツは懸命に口を開いた。
「おねがっ……! お願いだ…! 私の……話、を……っ 聞いて――――」
「『抱くな』と言う話なら、聞けないぞ」
ハヤブサは、わざと冷たく言い放った。シュバルツの身体の秘密も、その身体を抱くリスクも――――自分は、とっくに承知しているのだから。
「そ…っ! それでも……! は……話、はなし…を……ああっ!!」
ハヤブサの唇がシュバルツの臍に触れ――――舌がその中に、侵入してくる。手が優しく脇腹を撫でて来て、シュバルツは跳ねる身体を押さえる事が出来ない。
「ハ、ハヤブサ…ッ! お願い…だ…! 話を……あ、うあっ……! 聞、い……っ!!」
「シュバルツ―――」
ギ、と、縄を軋ませながら身を捩るシュバルツの身体を抱き込んだハヤブサは、シュバルツのズボンに手をかけた。そのまま一気に、それを引きずり下ろそうとする。その瞬間、シュバルツの叫び声が、辺りに響いた。
「ああっ! キョウジッ!! ……キョウ、ジ……ッ!」
「…………!」
ハヤブサの手が、ピタリ、と、止まった。
「……? ハヤブ、サ……?」
愛撫の手が急に止まった事を怪訝に思ったシュバルツが、ハヤブサの方を伺うように見る。
「………………」
だがハヤブサの表情からは何の感情も読み取れず、彼からは沈黙が返ってくるばかりだ。
(今しかない……)
シュバルツは荒い息を整えて、震える唇をコントロールしようとした。これが、最後の機会(チャンス)なのだと悟る。ハヤブサに話を聞いてもらえる、最後の機会。ただ、今から自分が言おうとしている事の恐ろしさゆえに、シュバルツは、己が身がすくむのを感じる。
でも、言わなければと思った。
ハヤブサの身を、『守る』ために。
「………ハヤブサ…。『キョウジ』では―――」
ハヤブサが、ピクリ、と反応する気配を感じる。
「『キョウジ』では……駄目、なのか……?」
「…………何?」
「お前の、抱く…相手だ……」
(ああ、キョウジ……! 済まない……!)
シュバルツは心の中で、キョウジに詫びた。自分は今、とても酷い事を言っていると分かる。キョウジの意思を無視して、ハヤブサに人身御供的に、彼を差し出そうとしている。そんな事、許されるはずもない。
だが、そうしなければ……!
ハヤブサが――――!
「私は……『キョウジ』でもあるんだ……。そして……『キョウジ』は……紛れもなく『人間』だ……」
「シュバルツ―――」
「『私』みたいな……歪な身体を抱くよりも……よっぽど『自然』だと思わないか……?」
そう言いながらシュバルツは、ハヤブサを正面から見つめる。
泣きたくない。だが、涙が勝手に溢れる。
震えたくない。でも、身体の震えが止められない。
キョウジを裏切っていると言う確かな恐怖が、シュバルツを襲う。
だが、その恐怖は――――ハヤブサにDG細胞を感染させる恐怖に比べたら劣る。自分の『身体』が、『細胞』が――――ハヤブサを破壊してしまう恐怖に比べたら。
自分が地獄に堕ちてしまう方が、はるかにましだった。
キョウジ……。
キョウジ…済まない……。
私は――――『影』失格だ――――。
(ハヤブサ……)
涙の向こうに霞むハヤブサの姿を、シュバルツは見つめる。
オ前ニ、応エラレル 『身体』 デアッタナラバ、ヨカッタ ノニ。
「…………………」
黙したままのハヤブサが、手を伸ばしてくる。その手は、シュバルツの『首』に向かって来た。喉仏のある辺りに、ハヤブサの手がかかる。
(殺されるのだろうか)
シュバルツは漠然とそう思った。喉仏は人体の急所だ。ここを潰されれば――――簡単に、『人間』は死ねる。それでも、自分は『死ねない』けれども。
(引き裂かれるのなら、それでいい)
シュバルツはそう思って目を閉じた。
ハヤブサに、応えられない自分。
キョウジを、自分の身代わりに差し出そうとしている自分。
――――最低だ。
何度だって殺される事こそが、きっと自分にはふさわしいのだ。
「シュバルツ―――」
低い声で呼びかけながら触れてくるハヤブサの手は、シュバルツの喉仏を潰さなかった。そのまま、首から顎、そして、頬へと優しく触れながら移動してくる。
「ク……ッ」
唐突に響く、ハヤブサの低い笑い声。
「……お前は、本当に何も知らないのだな……。キョウジから、何も聞いていないのか…?」
「――――!?」
何か不吉な気配を感じ取ったシュバルツが目を見開くのを、ハヤブサが、低く笑いながら見下ろす。
「シュバルツ……。俺は、『知っている』んだ。お前の身体の成り立ちを……。その俺が」
グッ! と、肩を強く掴まれる。
「―――ウッ!」
そのあまりの力の強さに、シュバルツは思わず呻いた。
「お前を『抱きたい』―――と、思う事自体に、悩まなかったとでも…思っているのか?」
「ハ、ハヤブサ……?」
ハヤブサから醸し出される暗い雰囲気に、シュバルツは思わず気圧されていた。恐怖を感じるのに――――何故か、目が離せない。
「お前を抱く事で生じる『リスク』を知っている俺が――――お前と同じ魂を持つキョウジを――――『押し倒さなかった』とでも、思っているのか……?」
「な――――!!」
シュバルツは思わず絶句し、息を飲んだ。
「……どういう……こと、だ……?」
ハヤブサに問い返す、シュバルツの声が震える。それにハヤブサは、にやりと笑って答えた。
「……苦労したぞ。何せ、お前のキョウジに対するガードは固い。その『裏』をかかなければならなかったのだから――――」
そう。あの森で、シュバルツと会いながら、ハヤブサは『機』を伺っていた。
シュバルツの守護(ガード)からキョウジが離れ、自分が彼に接触できる機会を。その為にハヤブサは、シュバルツの信用を得、『油断』を誘う事に専念する。
そして、探り当てた、キョウジの守護ががら空きになる、貴重な空白期間。ハヤブサは、迷わなかった。一人家に居る、キョウジの元へと向かった――――。
「――――!」
ハヤブサの話を聞いたシュバルツは愕然とする。もしも、ハヤブサクラスの腕を持つ暗殺者がキョウジを襲った場合、自分は、キョウジを守りきれないと言う事になるのではないか―――!?
(キョウジ……!)
シュバルツは動揺する。
ハヤブサの侵入を許してしまった、自分の未熟さを責めるべきなのか。それとも、自分の『裏』を見事かいた、龍の忍者の腕前を認めるべきなのか。
キョウジは、書斎に一人でいた。書類の整理をしているのか、それとも探し物をしているのか――――。部屋の真ん中で2、3の書類の束に目を通しながら、彼は立っていた。
唐突に姿を現したハヤブサに、特に驚きもせずに声をかけてくる。
「ハヤブサ?」
キョウジの問いかけに、しかしハヤブサは黙して答えない。
「シュバルツなら―――今、私の代わりにちょっと出かけていて、留守だけど……」
「ああ、知っているよ……。『だから来た』んだ」
「えっ? それはどういう――――あっ!」
キョウジは、驚愕の声を上げていた。何故なら、ハヤブサにいきなり抱きすくめられたからだ。バサバサッ! と、音を立てて、キョウジが持っていた書類の束が、部屋に散乱する。
「キョウジ……ッ!」
熱を含んだ声で彼に呼びかけながら、ハヤブサはキョウジを抱き締める。シュバルツほど鍛えられていないキョウジの身体には、適度な柔らかさがあった。そして何より――――『体温』があった。『鼓動』があった。
シュバルツには無い、生きている人間の、『証』――――。
(きっと、こちらがまだ正しいのだ)
キョウジを抱きしめながら、ハヤブサは強く思った。
いくらこちらがシュバルツを愛おしく思い、その身体と繋がりたいと願い、押し倒した所で――――結果、シュバルツに『何』を突きつける事になる?
彼に、自分の身体の『歪さ』と『禍々しさ』を――――再認識させるだけではないか。彼の身体を構成しているモノは、おそらく他人との濃厚接触を、拒否せざるを得ないものだ。それを、自分の一方的な『想い』を押しつけて―――シュバルツをいたずらに苦しめさせるぐらいならば。まだ思う。『きっと、キョウジを抱く方が、正しいのだ』と……。
『死体』だぞ。
『DG細胞』の塊だぞ。
それを『抱きたい』だなんて――――およそ、正気の沙汰じゃない。
「ハ、ハヤブサ?」
腕の中のキョウジが、身じろいで動揺する気配が伝わってくる。ハヤブサは目の端で寝室を探すと、キョウジの身体を抱えたまま、そこへ向かう。ベッドを見つけると、ハヤブサはキョウジをそこへ押し倒し、自分もその上に覆いかぶさった。
「あ………!」
驚愕に目を見開くキョウジを、ハヤブサは見つめる。
同じ顔。
同じ声。
似たような体型。
そして、同じ『魂』……!
ああ――――。
きっと、『あのヒト』も、似たような反応をするのだろう。自分の腹の下に、その身体を組み敷いたならば。
キョウジ(シュバルツ)
キョウジ(シュバルツ)
シュバルツ。
シュバルツ……!
「……………」
そんなハヤブサの様子をじっと見つめていたキョウジであったが、やがて、顔に少し哀しげな笑みを浮かべた。
「ハヤブサ……。貴方がここに来たのは、『貴方の意思』? それとも――――『シュバルツの意思』?」
「――――!」
目を見開いて動きを止めるハヤブサに、キョウジは微笑みかけた。
「もし……シュバルツが『それ』を望んで、貴方にとっても『それ』必要であるのならば――――」
キョウジはそう言いながら、ハヤブサに向かって手を伸ばす。その手は、ハヤブサの頬を優しく撫でた。
「私は……このまま貴方に、抱かれても、いいけど………」
「キョウジ―――!」
思いもかけぬキョウジからの言葉に、ハヤブサは息を飲んだ。こいつは、あっさりと自分の身を投げ出すと言うのか。シュバルツのために。そして……俺のために。自分の身や、意思など、少しも顧みもせずに。
(これだ)
ハヤブサはため息を吐く。
大元になっているこの男からしてこの美しさだから――――。
シュバルツが、あんな風になるんだ。
「……『抱かれる』って、どういう事か分かっているのか?」
ハヤブサは、思わずキョウジに問いかけていた。それに対してキョウジは苦笑した表情を浮かべる。
「『知識』はあるよ。……経験は、無いけど……」
そう言いながらハヤブサの頬を撫でるキョウジの手が、小刻みに震えている。
「キョウジ……お前――――」
「あはは……。やっぱりちょっと、怖いみたいだ……。震えちゃってて、ごめん」
「…………」
「でも……貴方が抱きたいのは、『私』ではないでしょう?」
「―――――!」
図星を指されて、ハヤブサは息を飲む。
「何故だ……?」
問いかけるハヤブサに、キョウジは笑顔を見せた。
「だって……貴方の瞳(め)が言っているよ…。『抱きたいのは、私じゃない』って」
「キョウジ……!」
「『違う』って……そう、言っている――――」
そう言いながらハヤブサの頬を撫でるキョウジの手は、ただ、優しい。あまりにも、優しい手だった。ハヤブサは、堪(たま)らなくなる。
「…………ッ!」
しばらくその手を己が手で包み込んで頬にあてがう様にしていたハヤブサであったが、やがて「すまん」と、小さく言うと、キョウジの上から身体を離した。それを見たキョウジも、横たえられていた身を起こす。
「キョウジ……お前は、いつから気づいていたんだ? …俺の、気持ちに……」
ベッドから立ち上がりながら、ハヤブサは問いかける。だが、キョウジの方をまともに見る事は、どうしても出来なかった。
「割と最近……。ごめん、貴方のシュバルツを見る目が……すごく、優しくて――――」
気づいちゃってごめん、と、キョウジが小さく呟く。それに対してハヤブサは、少しばつが悪そうに頭をかいた。
だが、この気持ちがキョウジに気づかれていると言う事は、シュバルツにも気づかれているのだろうか? ハヤブサはそう思って、キョウジに問いかけようとする。
「キョウジ……。シュバルツ……は……その……」
しかしハヤブサは、うまくそれを言葉にする事が出来ない。それをキョウジが察して、答えを返した。
「シュバルツは……『気づいていない』と言うよりも、『気づかないふり』を、せざるを得ないだろうね……」
「――――!」
ハヤブサは、思わずキョウジの方に振り返る。キョウジは、そんなハヤブサと視線を合わすと、その瞳を哀しげに曇らせた。
「彼の身体を構成している『モノ』の事を考えれば――――分かるだろう?」
「…………!」
ハヤブサは、鈍器で殴られたような衝撃を受ける。
「『DG細胞』か……!」
ハヤブサが震えながら紡ぐ言葉に、キョウジは頷く。
「シュバルツの身体は、私にも、またシュバルツ自身にも……はっきりと分からない事がまだたくさんある…。まして、『セックス』なんて他人との濃密な接触をした場合、本当にどうなるか……。シュバルツ自身が暴走するか、下手をしたら、シュバルツを抱いた相手に、『DG細胞』を感染させてしまう恐れだってある――――」
それが感染してしまった人間はどうなるか。ハヤブサは知っていた。
細胞の『自己増殖』の本能に任せて、ただただ他を破壊する殺人鬼となり果ててしまう。殺して細胞をばらまき、仲間を増やして行くのだ。そしてそれは、細胞に己が総てを消費されつくしてしまうまで止まらない。
人格も何もかもを破壊しつくしてしまう―――まさに『悪魔』の細胞だった。
「シュバルツはだから……貴方の想いに応える訳にはいかない、と、思うだろう。貴方が大事であればあるほど―――なおさら」
「――――ッ!」
ハヤブサは、息が詰まりそうになるのを感じる。
頭では『理解』していたつもりだった。
それなのに、いざ、『言葉』にされて目の前にそれを突きつけられると―――平静でいられないのは何故なのだろう。
「貴方の『想い』に気づいてしまえば……シュバルツは、貴方から距離を取らざるを得なくなる…。下手をしたら、『消える』ことすら視野に入れて、行動を起こすかもしれない……。貴方を……『DG細胞』の脅威に巻きこむ訳にはいかないから――――」
「ふ……ざけるなッ!!」
気がつけばハヤブサは、大声で叫んでいた。
「ふざけるな…! ふざけるな!! ふざけるなッ!! どうしてシュバルツが『消える』とかしなければならない!? シュバルツは、何も悪くないだろう!?」
ハヤブサの言葉に、キョウジの面(おもて)に静かな笑みが浮かぶ。
「そうだね……。『シュバルツは』何も、悪くない……」
「それなのに…! 自身を病原菌か何かみたいに思って…! 人との距離を取って……ッ! あいつは……ずっとそうやって生きて行くつもりか!? ずっと、『独り』で―――!?」
叫びながらハヤブサは、闇の深淵に佇んでいた、孤独なシュバルツの姿を思い出す。
『命』が無くて、『歪な身体』を抱えているが故に、闇に沈み、闇にまみれながら、そこで独り静かに佇んでいたシュバルツ。そして、微笑んでいたシュバルツ。
ハヤブサが伸ばした手は、届かなかった。彼の沈んでいた闇が―――あまりにも、深すぎたが故に。
その手を、届かせたいと、願う。
シュバルツの手を、取りたいと―――願う のに。
無理なのか!?
永遠に!?
「何故だ―――!? 何が悪いんだ!? どうしてシュバルツが―――!!」
「………どうしても、『それ』が許せないと言うのであるならば、その原因を殺せ。諸悪の根源は、今、貴方の目の前に『居る』」
不意に響いてきた声に、ハヤブサははっと我に返る。声のした方を見ると―――キョウジが、静かな笑みを面に湛えてそこに『居た』
「キョウジ――――!」
「少なくとも、今のシュバルツの身体を『そう』いうふうにしてしまったのは、私だ。……紛れもなく」
そう言ってキョウジが、ハヤブサを静かに見つめる。
「……………ッ!」
キョウジの言葉に、ハヤブサは震える拳を握りしめた。
そうなのだ。シュバルツは、キョウジが―――『作った』。追い込まれ、自らデビルガンダムに取り込まれかけたキョウジが、それでも『弟を守りたい』と言う祈りを込めて―――彼は、シュバルツを作ったのだ。
そこに横たわるのは、どうしようもない『悲劇』
どうしようもない、『悲劇』なのだ。
「シュバルツが……お前の『死』など望まないのに――――そんな事、出来るか……ッ!」
ハヤブサは、吐き捨てるように、そう言った。
「だいたい……! お前が死んだらシュバルツだって死んでしまうだろうが…! お前たちはそういうふうになっていると―――!!」
「分からないんだ!! こればっかりは!! 私が『死んで』みないと――――!!」
「……………!」
それまで静かな雰囲気をその身に湛えていたキョウジから出されたいきなりの『大声』に、ハヤブサは思わず言葉を失ってしまう。
キョウジは、拳を握りしめ、その身を震わせていた。
「私の命とシュバルツは繋がっている―――と、シュバルツは言った…! でも、私とシュバルツが直接繋がっている訳じゃない! 見えている物だって違う! 彼の『意志』が、私に全部伝わっているなんて事もない…! もう彼は、独立した『一つの意思』なんだ!!」
声が震える。
涙が、溢れそうになる。
(泣くな…!)
キョウジは己を叱咤する。
このタイミングで涙を流す訳にはいかない。
シュバルツの事で、涙を流す資格なんて、自分には無い。
自分は、間違いなくシュバルツを地獄に叩き落としている張本人なのだから―――。
「『心をエネルギー源として、消費する』という定義だって、実は曖昧なものだ…。実際、本当に私の『心』が彼のエネルギー源になっているかどうかなんて、証明する手段は何一つない…。だから、私が死んでも……彼が生き残る可能性だって……あるんだ…!」
生き残る可能性。
生き残って『しまう』可能性。
死ぬ権利が奪われてしまっている生命体は、生きる権利が奪われているのと、同義だ。
せめて、それだけでも、何とかしてあげたいのに――――!
「キョウジ……」
ハヤブサは、迂闊に怒りを口にした事を悔いた。
誰よりも、誰よりも深くシュバルツの事を想い。
涙を流しているのは――――キョウジであるのに……。
シュバルツの境遇を嘆く事は、即、キョウジを責める事につながってしまう。
ひどい、矛盾だと――――思う。
「済まなかった……。俺は、余計な事を……」
詫びるハヤブサに、キョウジは頭(かぶり)を振る。
「ううん。いいよ……。寧ろ私は……嬉しかった…」
そう言う彼の意図が咄嗟に分からず、眉をひそめるハヤブサに、キョウジが笑顔を向ける。
「貴方は……シュバルツのために、怒ってくれたのでしょう?」
「…………!」
「シュバルツに……そう言う人がいるって、思えただけで……私は、嬉しい」
「キョウジ……!」
「ありがとう、ハヤブサ………」
「キョウジ……ッ!」
「あっ!?」
キョウジが短く悲鳴を上げた。何故なら、ハヤブサが再びキョウジを抱きしめていたからだ。
(ああ―――やっぱり、惹かれる……)
キョウジを抱きしめながら、ハヤブサは強く思った。
キョウジのこの『魂』に。
『魂』の、美しさに――――。
だが……。
「済まない……キョウジ……」
腕の中のキョウジに、ハヤブサは語りかけた。
「やはり俺は――――シュバルツが、好きだ……!」
「…………!」
腕の中で身じろぐキョウジに、ハヤブサは声をかける。
「この『想い』はもしかしたら、シュバルツを苦しめるだけの物になるかもしれない……。それでも、俺は……!」
「ハヤブサ……」
「好きなんだ……! シュバルツが…。どうしようもなく―――!」
「―――――」
腕の中で茫然とハヤブサの告白を聞いていたキョウジであったが、やがて、ふっと相好を崩した笑みをその面に浮かべた。
「駄目だよ……ハヤブサ。そう言うのは、ちゃんと本人に言わないと…」
私に言ってもシュバルツには伝わらないよ、と言うキョウジに、ハヤブサもそれもそうだな、と、苦笑いを浮かべる。二人はしばらく、そのままの姿勢で時を過ごした。
「ハヤブサ……。一つ、聞いても良いか…?」
不意に、腕の中のキョウジにポツリと問われる。
「貴方は……ドモンも、マスターもだけど……私とシュバルツを見間違えたことなんて、一度も無いよね……」
「……………!」
「どうしてなんだろう…? 研究所の人たちも……大学の人たちも……私とシュバルツが入れ替わって行動していても、少しも気づかれないのに……」
キョウジの問いかけに、ハヤブサはため息を吐く。
「……俺から言わせてみれば、お前とシュバルツは大分違うぞ…。見抜けない奴の方が、むしろ間抜けに思えるぐらいだ」
「そんなに違うかな? 容姿は、全く同じだと思うんだけど?」
「ああ。違うな。全然違う」
「そうなのかな?」
「ああ。そうだ」
憮然と答えるハヤブサに、キョウジが笑う。
「……ハヤブサ。そろそろ、シュバルツが帰ってくるから……」
「あ…。ああ、済まない」
ハヤブサは、慌ててキョウジを解放した。
「じゃあ…俺は、もう行く。―――すまなかったな、キョウジ…。突然、その……いろいろと……」
ばつが悪そうにそう言うハヤブサに、キョウジは頭を振る。
「ハヤブサ」
部屋から出ようとしたハヤブサを、キョウジが呼び止めた。振り向いたハヤブサに向かって、キョウジから何かが投げ渡される。
「これは?」
問うハヤブサに、キョウジから答えが返ってくる。
「持って行くと良い……。DG細胞の『抗体』だ」
「――――!」
「万が一DG細胞に『感染』しても、それを投与すれば、症状の発症を抑える事が出来るから……」
「キョウジ……」
ハヤブサは、手の中の抗体をじっと見つめる。
「……シュバルツに俺の『想い』をぶつけても構わない……。お前は、そう言いたいのか…?」
顔を上げ、キョウジにそう問いかけるハヤブサの視線の先に、キョウジの静かな眼差しがあった。
「私は、提示し、指し示すだけ。本当に選ばなければならないのは……貴方であり、シュバルツだ……」
「シュバルツを……『抱いても』構わないと―――?」
ハヤブサは、ストレートにこの言葉をキョウジにぶつける。自分の『想い』は、間違いなくそうなのだから。キョウジは、ハヤブサの言葉に一瞬目を見開いた後、
「シュバルツと貴方の関係にまで、口を出す権利など、私には無いよ」
と、笑顔で答えた。
「シュバルツにはシュバルツの世界があって――――彼にしか飛べない『空』があるはずなのだから……」
そう言いながらキョウジは、ただ空を見つめる。
シュバルツと一番深い場所でつながり、一番彼を縛り付けている男が、実は一番願っているのだとハヤブサは悟る。シュバルツの――――『自由』と『幸せ』を………。
キョウジとシュバルツ。この二人は、本当に不思議で―――複雑な関係だとハヤブサは思った。
「……抗体は、もらって行く…。使うかどうかは、分からないが……」
そう言いながら、ハヤブサは抗体を懐にしまう。出来れば、使いたくない、と、ハヤブサは思った。『暴走』していない、シュバルツを構成している、ある意味特殊なDG細胞を、一般的に語られる『DG細胞』と同じ物だと思いたくないのかもしれなかった。
「大丈夫なのだ」と、言ってやりたい。
お前は、他人(ひと)と触れ合っても大丈夫なのだと。
シュバルツにそう言ってやりたい―――と、ハヤブサは強く思った。
もっとも、自分の体質も『呪いを受け付けやすい』と言う厄介なものであるから、DG細胞と濃密に触れ合って、無事でいられる保証も無いのだけれども。
それでも、俺は。
彼に、触れたい。
触れたいのだ。
「キョウジ……。俺は、例えどうなろうとも、シュバルツを『愛している』……。それだけは、どうか憶えておいてくれ……」
龍の忍者はそれだけを言うと、キョウジの家から姿を消した―――。
「フフ……シュバルツは、愛されているよなぁ」
一人残された部屋で、そう呟くキョウジの頬に、伝い落ちてくる物がある。それは、堰を切ったように、次から次へと溢れ出てきた。
「あ……あれ? な、何で今頃――――涙なんか……」
止めたいと願うキョウジの心とは裏腹に、それはボロボロと音を立てて頬を伝い落ちて行く。
押し倒されて、怖かったのか。
抱きしめられて、驚いたのか。
責められて、辛かったのか。
シュバルツが愛されていると分かって、嬉しかったのか―――。
「はは……。駄目だ……。混乱、しているや……」
キョウジの胸の中で、様々な感情が渦を巻き、それが、涙と言う形を取って零れ落ちて行く。それを止める術など、キョウジの中ではとっくに崩壊してしまっていて。
淋しい。
何故かひどく、『淋しい』と、感じた。
(ハヤブサ……! どうか、シュバルツを――――)
『幸せに』と、祈る事など出来ない自分を、キョウジは自覚する。
それでも、願わずにはいられなかった。シュバルツの『幸せ』を。
もう彼は、充分すぎるほど苦しんでいるのだから――――。
(……どうしよう。もうすぐ、シュバルツが帰ってくるのに―――)
止められない涙と散らかった部屋。
どうやってシュバルツをごまかそうかと、キョウジは必死に考えていた――――。
(キョウジ――――!!)
ハヤブサの話を聞きながら、シュバルツはショックを受けていた。
ショックだった。
とにかく―――ショックだった。
ハヤブサとキョウジの間にそのような事があったと言う事など、自分はまるで気づく事が出来なかった。見事なまでにキョウジに秘匿されてしまっていた。
ハヤブサの話から推察された、『その日』の事を、シュバルツは思い出す。
あの日。自分が帰ってくると、キョウジは書類で散らかった部屋の真ん中で、茫然と座り込んでいた。
「……キョウジ? どうした?」
訝しんだシュバルツがキョウジに声をかけると、キョウジが振り向いた。瞳から涙を飛び散らせながら―――。
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
シュバルツの姿を認めたキョウジが、叫びながら、自分の懐に飛び込んでくる。
「キ、キョウジ!?」
シュバルツは戸惑いながらもキョウジを抱きとめた。
「どうした? 一体、何があった…?」
「シュバルツ……」
シュバルツの腕の中で、キョウジの身体が小刻みに震えている。
「シュバルツ……もう私―――死んでもいい?」
「はい?」
何か変な言葉を聞いた様な気がしたシュバルツは、思わずキョウジに問い返していた。
「もうヤダ……。もう死にたい―――」
「い、いやいやいやキョウジ…。何を言っているんだお前は―――」
何か、自棄になっている気配を漂わせているキョウジの様子に、シュバルツは少し慌てた。
「何もかもがもう嫌だ…。家に帰る―――」
「いやキョウジ。お前の家はここだろう? …って、キョウジ! 一体何があった? 話してみろ」
「………怒らないで、聞いてくれる…?」
シュバルツの腕の中で、キョウジがポツリと話しだした。
「ちょっと仕事の手が開いたから、溜まりまくっている書類を整理しようと思って………………シュレッダーにかけるファイルを…………マチガエタ」
「え?」
問い返すシュバルツだが、キョウジからは嗚咽が帰ってくるばかりだ。
「キョウジ。済まないがもう一度―――」
問いかけるシュバルツに、キョウジからは小さな声で答えが返ってきた。
「だから………その…………シュレッダーにかけるファイルを…………マチガエテ……」
「へ?」
「い……一番、最新のファイルを…………シュレッダーに…………カケチャッテ……」
「何っ!?」
ここに至って、ようやくシュバルツもキョウジが何か重大なミスをやらかしてしまった、と言う事を理解する。
「さ……最近の研究のデータとかが……皆、分からなくなっちゃって……バックアップ取って無かった物もあったのに………」
「キョウジ………」
「しかも、そ、それだけならまだ……良かったんだけど…………」
「ま、まだ、何かあるのか…?」
キョウジから醸し出される不吉な雰囲気に、シュバルツは、背中に冷たいものが流れ落ちるのを止める事が出来ない。
「じ……実は、シュレッダーにかけた書類の中に、学生のテストの解答用紙が………有った、みたいで………」
「な―――――!!」
シュバルツは思わず言葉を失ってしまう。こればかりはいくらキョウジでも、自分の力だけで復元する事は不可能だ。
「どうしよう……! 大事なテストだったのに………。責任問題だよ……! 私は、どうして――――!」
そう言いながらキョウジは、真っ青な顔色をして、がたがた震えながら涙ぐんでいる。
(……キョウジは、責任感が強いからなぁ……)
シュバルツは深~いため息を吐いた。今から自分の『やるべき事』について、覚悟を決める。
「……キョウジ。そのシュレッダーにかけた紙の欠片は、まだ捨ててはいないんだろうな……?」
「う、うん。まだシュレッダーの中のごみ袋の中にあるけど……。でも―――」
「なら、それをよこせ。私が復元してやるから」
「えっ…? で、でも―――他の書類も、一緒に混じっちゃっているから……」
「いいから! それをよこせ! 復元しないとまずいのだろう!? ほらっ! この辺りの書類を片づけて!!」
「あ…! う、うん、分かった……」
シュバルツに急かされて、キョウジが慌てて散らかった書類を片づける。片付け終わると、彼はシュレッダーの中からゴミ袋を取り出して、シュバルツの前に差し出した。床に置かれた瞬間、袋の中の無数の紙くずが、バフン、と、音を立てて跳ねる。シュバルツはもう一回、深いため息を吐いていた。
「……ちなみにキョウジ……。『これ』はいつまでに復元をすればいいんだ?」
シュバルツからの問いかけに、キョウジからひきつった笑みが帰ってくる。
「えっ!? ……ええ~っと………………『明日』?」
「何っ!?」
二人の間に、しばらく沈黙が舞い降りる。外でカラスが「アホー」と鳴いているのが聞こえてきた。時を知らせる時計の時報の音に、シュバルツの方が「ハッ!」と、先に我に帰る。
「ち……ちなみにキョウジ……。採点はもう終わっているんだろうな?」
「えへへへへ……………マダデス」
「この……ッ! 馬鹿者がぁ!!」
流石にここでシュバルツの拳骨が、キョウジに飛んだ。
「痛い!! だから『怒らないで聞いて』って言ったのに!」
シュバルツの地味に痛い鉄拳制裁を喰らったキョウジが、涙目になりながら抗議の声を上げてくる。
「痛いもくそもあるか!! だからいつも言っているだろうが!! 期限ぎりぎりまで仕事を溜めるなと!! どうしてお前はこういつもいつも―――!!」
「だ、だって……『採点作業ぐらい、すぐ終わる』かな~? と、思って……」
「確かに……何事もなければ、すぐに終わる作業だな……しかしだな……!」
「ご、ごめん……! やっぱり、大学側に事情を話して、『責任』とるから……!」
「そんな事はしなくていい」
シュバルツはため息と共に、己を落ち着かせる事に専念する。とにかく今は、不毛な言い争いに時間を消耗するよりも、一刻も早く回答用紙を復元した方がましだ。
「こちらは私がやるから――――とにかくお前は、失ったデータの復元作業をしろ」
「ええ~~~~!?」
シュバルツからの提案に、キョウジから心底嫌そうな声が上がる。
「何が『ええ~~~~!?』だ!! お前の事だ。どうせ数値は憶えているのだろう!?」
「そ、そりゃあ、憶えているけどさ……………(メンドクサインダヨナ)…………」
「………! 何か、言ったか?」
キョウジの声を何となく聞き咎めたシュバルツから、ものすごく殺気だった目で睨まれた。
「い! いえッ!! 何でもありません!! キョウジ・カッシュ、喜んでデータの復元作業に取り掛からせていだだきます! そりゃあもう! 心の底から喜んで―――!」
「御託はいいから、さっさとやれ」
シュバルツはため息と共にキョウジに声をかけ、シュレッダーくずの方に向き直った。
(引き受けたは良いが……これは、難作業だな……)
自分が今から取りかからなければならない『牛乳パズル』も真っ青なジグゾーパズルを目の前にして、シュバルツは頭を抱えていた。
それ故に、彼は気付けなかった。パソコンに向かうキョウジの瞳から、涙が一筋零れ落ちていた事に。
そして次の日にはもう―――キョウジは、『いつものキョウジ』に完全に戻ってしまっていた。
注意深くシュバルツに伏せられた、ハヤブサの件。
それでも――――だからこそ。
キョウジの口から出てくる。唐突に、ハヤブサの名が――――。
「シュバルツは最近、ハヤブサに会ってる?」
「会っている」と、自分が答えると、キョウジは嬉しそうに微笑んでいた。
「キョ…ウジ………!」
シュバルツは茫然と空を見つめていた。
キョウジは知っていたのだ。ハヤブサの『想い』を。今―――自分がハヤブサの元に行けば、『こう』なるのだと言う事を。
それなのに、キョウジからは何も伝えられなかった。それどころか、完全に伏せられてしまっていた。キョウジが、ハヤブサに押し倒されたことも。ハヤブサの自分に対する『想い』を告げられたことすらも。
あの時のキョウジの涙の意味。
もう少し自分は考えるべきだった。注意深くキョウジを見るべきだったのだ。
キョウジは本当に事が重大であればある程、それが必要であると彼が判断したのならば、その事を完全に一人胸の内に秘してしまう。そう言うキョウジの性格を、自分は分かっていながら――――!
自分が、気づかなければならなかった。
気づかなければ、ならなかったのに。
涙の意味を、完全にごまかされてしまっていた。
気付けなかった。
気づく事が出来なかった。
キョウジの事は、何でも分かっていると思っていたのに――――!
(キョウジ……ッ!)
シュバルツの瞳から、ポロ……と涙がこぼれる。
「シュバルツ……」
まるで、捨てられた子犬の様な眼差しだと、ハヤブサは思った。それ故に、ハヤブサはたまらなくなってしまった。
だから――――。
「シュバルツ……ッ!」
ハヤブサは思わず、シュバルツの身体を抱きしめて、いた。
「―――――ッ!」
腕の中のシュバルツが小さく声を上げ、その身体を硬直させる。だがハヤブサはそれに構わず、シュバルツの身体をさらに強く抱きしめ、己の身体を密着させた。
「シュバルツ……! シュバルツ!」
想いが溢れる。
ハヤブサ自身も、もうどうする事も出来ない、想いが。
「分かってくれシュバルツ……! 俺は―――『お前が』好きなんだ!!」
「…………!」
腕の中のシュバルツから、身じろぐ気配が返ってくる。ハヤブサはもう一度、シュバルツの身体を強く抱きしめた。そして顔を上げ、身体をシュバルツから少し離す。彼の目を見て話をしたいと思ったからだ。
「好きだ……! シュバルツ」
驚きで目を見開くシュバルツに、ハヤブサは更に声をかけた。
「愛している……! 好きなんだ……!」
「ハ、ヤ…ブサ……」
茫然と見上げるシュバルツの視線の先に、ハヤブサの優しい眼差しが、あった。あの、彼がシュバルツにしか見せない、優しい眼差しが――――。
ハヤブサは、シュバルツの頬を流れる涙を指の腹で拭い、髪を優しく撫でながら、言葉を紡いだ。
「俺が…『抱きたい』と、言って……それを『受け入れられない』お前の気持ちは……分かっている」
「……………!」
「お前の身体の成り立ちを考えると……お前の気持ちを考えると――――『無理だ』と思った。『抱いてはいけない』と、思った……。だから、俺は――――」
「ハヤブサ……」
「一度はお前をあきらめて……『キョウジ』を抱こうと、思ったんだ……」
そう語るハヤブサの瞳が、哀しみ故に曇る。シュバルツはそれを、ただ見守っていた。
「お前とキョウジはある意味一緒だ…。そして、キョウジは人間だ。そう思って……」
「……………」
「だが――――駄目だった」
「――――!」
「お前とキョウジの『違い』を……自覚するだけだったんだ……」
あの時。腹の下に組み敷いたキョウジを見つめながら、
自分ははっきりと求めてしまっていた。
キョウジではなく――――シュバルツの姿を。
「そ、そんな……!」
息を飲むシュバルツを見つめながら、ハヤブサは苦笑する。
「キョウジにも言われたよ……。『抱きたいのは、私ではないでしょう?』って……」
「…………ッ」
「シュバルツ―――」
シュバルツの髪を撫でていたハヤブサの右手が、耳に触れ―――それから頬へと移動してくる。
「俺は……『お前』に惹かれているんだ……。キョウジでは駄目だった…。キョウジでは――――やはり、違うんだ」
「ハヤブ……サ……」
「キョウジからは、『闇』の匂いがしない…! 俺と同じ『闇』の世界に生きる者の匂いが――――!」
ハヤブサは、いつしか必死に言葉を紡いでいた。シュバルツには『分かって欲しい』と思った。自分でももうどうしようもない―――この『想い』を。
「『闇』にまみれているのに……それでも美しく光を放つお前の『魂』―――俺は、それに、惹かれたんだ……ッ!」
再びハヤブサは、シュバルツの身体を抱きしめた。強く、強く――――。
「!!」
ビクッ! と、反応したシュバルツの身体が、腕の中で硬直し、震えている。
愛おしい。
堪らなく、愛おしいと、思った。
「シュバルツ……! 俺は、『お前』に触れたいんだ! 『お前』を抱きたいんだ!!」
いつしかハヤブサは、涙を落していた。
泣いたってどうにもならない。どうにもならないと、分かっているのに。
止められない。止める事が、出来ないんだ。
「このまま…お前に触れられないのなら―――俺はもう、死んだ方がましだ…! お前が、『ここに』いるのに――――!!」
「な…………!」
シュバルツから、息を飲む気配が伝わってくる。ハヤブサは構わずに続けた。
「だからシュバルツ……! いっそ俺を殺してくれ!! 俺に触れられるのが『嫌だ』と言うのなら――――!!」
「ハ、ヤ……ブサ……」
「『嫌』じゃないなら……受け入れてくれ………!」
「…………!」
無言で、ただ震えるシュバルツの身体を、ハヤブサは抱きしめ続けた。
「お前を『好きだ』と言う俺の気持ちを…………無視、することだけは……しないでくれ……!」
(ハヤブサ……!)
耳元で、ハヤブサの咽び泣く声が聞こえる。ハヤブサに触れられている―――身体が熱い。
どうすればいい?
どうすれば―――。
私は、ハヤブサに生きて欲しいと願うのに。
このままでは受け入れても拒絶しても―――彼が死んでしまいそうで怖い。
(自分が死ねたらいいのに)
シュバルツは思う。今、この状況から逃げるには、自分が死ぬのが一番いいのだろう。でも死ねない身体で―――ハヤブサもそれを知っているが故に、それは無意味なものとなる。ただの時間稼ぎにしかならない。
「シュバルツ……! 抱かせてくれ……!!」
ハヤブサは懸命に訴えかけていた。このままシュバルツを抱く事を止めるつもりはない。でもこのまま突き進めば、シュバルツを一方的に踏みにじる事になってしまう。
シュバルツは、踏みにじるにはあまりにも美しすぎた。
あまりにも愛おしすぎた。
同意が――――『同意』が欲しかった。
『抱いても良い、触れても良い』と言う同意が。
(勝手な願いだ)
ハヤブサは思う。
シュバルツは、『Yes』とは言えない。言えない身体なのだから。
だけど――――。
踏みにじりたくない、と、願う。
これは、最後の我がまま。最後の機会(チャンス)、なのだ。
「シュバルツ……! お願いだ……!」
腕の中で、硬直し続けるシュバルツの身体を、ハヤブサは懸命に抱きしめる。
「キョウジでさえ触れられない、深い場所に――――俺を」
「ハヤブサ……」
「俺を――――受け入れて、くれ……ッ!」
「……………ッ!」
シュバルツからは、沈黙が返ってくるばかりだった。「Yes」とも、「No」とも言えなくなってしまっているのだろう、と、ハヤブサは思う。シュバルツ自身が持つ、その優しさ故に。今の状態は、まさしく―――彼を追い詰めているだけだ。
分かっている。シュバルツから『返事』が返ってくる可能性など、皆無に等しい。
(やはり……無理やり抱くしかないのか……)
ハヤブサは思った。今更後戻りなんて出来ない。腕の中に愛おしいヒトがいるのに、何事も無かったかのように、解放するなんて出来なかった。
無理やり抱いて。
『二度と、顔も見たくない』と、思わせるぐらい彼を傷つけて。
そして―――彼の預かり知らない所で、自分は命を断とう。
ハヤブサが、そう決意しようとした時。
「ハヤブサ……」
シュバルツから、呼びかけられた。
「シュバルツ!?」
「……………」
それと同時に、シュバルツの身体に変化が起きる。
それまで硬直して震えていたシュバルツの身体から、力が抜けて行ったのだ。
「……シュバルツ?」
驚くハヤブサをシュバルツはちらりと見やると、彼は静かに目を閉じた。
「分かった……ハヤブサ……」
「……………!?」
「お前が……そこまで言うのなら……この身体――――」
ここまで話したシュバルツの唇が、一瞬震える。……恐怖ゆえに。
「お前の……好きに、すればいい」
「シュバルツ―――!」
驚きで目を見開くハヤブサを、シュバルツの静かな眼差しが見据える。
「だが……どうなっても、知らないぞ……!」
「……? どういう事、だ?」
「お前の、身体が――――んっ! う……!」
ハヤブサは、思わずシュバルツの唇を塞いでいた。そこから先の言葉は、言わせたくない、と思った。
「…………………」
散々口の中を蹂躙してから、ハヤブサはシュバルツを解放する。
「はぁ……っ! は……! ハ、ヤ……ブサ……ッ」
「シュバルツ……」
ハヤブサはシュバルツの顔を、包み込むように両手で抱え込んだ。今、シュバルツから言われた事を、もう一度確かめたくて。
「シュバルツ…! もう一度、言ってくれ。お前は―――俺を、受け入れて……くれるのか……?」
ハヤブサの問いかけに、一瞬シュバルツは身じろぎ、目を逸らそうとする。だが、ハヤブサがそれを許さなかった。自分をまっすぐ見て、応えて欲しいと思った。
「……ああ……。ハヤブサ……お前が、望むなら――――」
ハヤブサの視線から逃れる事をあきらめたシュバルツが、潤んだ瞳でこちらを見上げてくる。羞恥故なのか、その頬が朱に染まっていた。
「シュバルツ――――!」
ひどく艶めかしいシュバルツの様子に、ハヤブサはたまらなくなる。
「だがハヤブサ……! 私の、身体は――――んぅっ! んん……っ!」
先程よりも強い調子で唇が奪われる。舌が深く差しこまれて、口内を強く吸われた。
「んっ……! んく……! ……ふ……! ん…う……!」
呼吸を許されないシュバルツの身体が小刻みに震える。ハヤブサはその身体を強く抱きしめて、その震えを堪能した。
シュバルツ。
シュバルツ。
ああ、俺だけの――――!
俺だけの、ものだ。
「…ん……はっ…! …は……あ……っ」
解放されたシュバルツの口から、彼が飲みきれなかった唾液と、荒い息が漏れる。
「シュバルツ……分かっている。俺は、分かっているから――――」
シュバルツの身体の歪さも。それを抱くリスクも。
「ハ……ヤ、ブサ……」
「もう黙れ……」
そう言うとハヤブサは、再びシュバルツの唇を塞いだ。
唇を押しあてると、シュバルツは口を薄く開く。ハヤブサの舌がそこから侵入すると、シュバルツもおずおずと舌を絡めてきた。
「……ふ…。……ん……」
一方的に蹂躙するのではなく、互いに『合意』の上で行われている口付け―――その優しさと甘さに、ハヤブサは酔った。差し入れられる舌の深度が、自然に深いものへと変わっていく。
「……ん……んっ……!」
その深さに戸惑いながらも、懸命に受け入れるシュバルツ。だが呼吸が奪われるから、どうしても身体が小刻みに震えてしまう。そんなシュバルツの身体に、ハヤブサの指が触れてきた。その指は、シュバルツの胸の頂を優しくこする。
「んむっ!? んんっ!!」
突如として身体を襲った甘い刺激に、シュバルツの身体がビクン、と跳ねた。しかし、口付けを交わしたままであるから、声はすべて、ハヤブサの口腔へと吸い込まれてしまう。
「…んっ! んんっ! んぅっ……!」
ハヤブサはしばらく胸への刺激を続けて、シュバルツの声を吸い込む事を楽しんだ。刺激を送るたびに、シュバルツの身体が跳ねてしなる。
甘い刺激に弱い、シュバルツの、身体。
もっと、乱れて欲しい。
もっと―――自分を感じて欲しい、と思った。
「んあ…! ああっ! あうっ……!」
頃合いを見計らってシュバルツの唇を『解放』してやると、彼の口から高い嬌声が漏れる。
「あ…っ! いや…だ……! こんな、声――――ああっ!」
声を堪えようとするから、ハヤブサはもう一方の胸の頂も口に含んで弄ぶ。そんな事は許さない。俺は―――お前の声が、聞きたいのに。
「やっ……! あっ……! あ……っ!」
刺激から逃れようと、シュバルツは懸命に身体をしならせる。だが、そのしなりが―――却って、ハヤブサに自らの胸を押しつけるような格好になってしまっている事に、シュバルツは気付いていない。
時折シュバルツの腕に絡みついている縄が、ギチッ、と、音を立てて軋む。
(解かなければ)
シュバルツに愛撫を施している眼の端で、ハヤブサはそれを捉える。僅かに残っているハヤブサの『理性』が、『シュバルツの縄を解け』と、強く訴えかけてきた。
だがハヤブサは―――縄を解く事を選択できなかった。
『縄を解いてもシュバルツは逃げない』頭では、そう理解しているつもりだ。
しかし縄を解いてしまったら――――シュバルツに、逃げる口実を与えてしまいそうで怖かった。奇跡的に抱くことを了承してくれたとは言え――――逃げられないように繋ぎ止めて、追い詰めて、無理やり彼の承諾を引き出したにすぎないのだから。
これは、『戒め』なのだとハヤブサは思った。
シュバルツにと言うよりは、自分に対する『戒め』
おそらく、今―――自分がシュバルツに対して抱いている『想い』と、それを受けているシュバルツの『想い』は、全然違うものであるのだろうから。
勘違いしてはいけない―――と、思う。
シュバルツが腕を動かそうとするたびに締め付ける仕様になっている縄は、もう彼の腕に相当食い込んでいた。
(済まない。シュバルツ……!)
心の中で、彼に詫びる。
だがもう自分でも自分を止められない。
止める事が出来ないんだ。
お前の総てに触れて―――。
総てを、奪い去ってしまう、までは。
「うあ……っ! あ…っ! ハヤブサ……ッ!」
時折シュバルツから、切ない声で自分の名前を呼ばれる。それがハヤブサには、ひどく幸せに感じられた。
どうして―――好きな人の口から出る自分の名前は、
特別な『響き』を持って心に届くのだろう。
もっと、自分の名を呼んで欲しいと思った。
もっと、もっと。
「は……! あっ……!」
ハヤブサから施される愛撫に、シュバルツはただ身悶えるしか術は無かった。
的確に感じる所に優しく触れられ、舌で舐められ、時折強く吸われる。そんな事をされてしまったら、どうしたって身体が跳ねる。出す気もない高い声が、出てしまう。
そして、何よりももう一つ―――シュバルツを翻弄している『声』の存在があった。
その声は、時々しか聞こえなくて、とても小さいものだった。だがひどく生々しかった。
(抱キタイ)
その声は訴えてくる。
(触リタイ……)
「ああっ!! あ……っ!」
(何でこんな声が――――『声』が、聞こえる…?)
言っている言葉から、それがハヤブサから出ている物であるらしい、と、容易に推測できる。
暴キタイ……! 犯シタイ……!
挿入(はい)リタイ―――! 繋ガリタイ―――!
ハヤブサの生々しい、感情の嵐。
こんな声、聞きたくない。聞きたくない、のに。
どうして――――!
愛撫のほかに、その『声』にも嬲られるように翻弄されるから、シュバルツはたまらなくなる。身体をハヤブサに許すと決めたはずなのに――――逃げ出したくなってしまう。
(『ココロ』に感応すると言う、『DG細胞』のせいなのだろうか…?)
かろうじてシュバルツに残っている『理性』が、その声をそう分析する。ハヤブサの、最早抑えようもない激しい『想い』に、DG細胞が感応してしまっているのかもしれない。
「うあ、あ……っ! あうっ……!」
シュバルツがハヤブサの愛撫に反応し、声を上げるたびに―――ハヤブサから出る『声』も嬉しそうに勢いを増して行くのが分かる。それがシュバルツの肌を撫でまわし、あまつさえ中に侵食してこようとさえしてくる。
(怖い……!)
シュバルツは恐怖した。
この『声』に完全に飲み込まれてしまった時。
自分は一体、どうなってしまうのだろう――――?
「は……ハヤブサ……ッ!」
シュバルツは思わず、ハヤブサの名を呼ぶ。すると、ハヤブサの心のから『言葉』が返ってきた。
(好キダ……!)
「あ……! ん……っ!」
(愛イシテイル……シュバルツ―――)
「う、あ…っ! ハヤ、ブサ……あ……ッ!」
生々しい声の間に混じってくる甘い感情に、シュバルツは更に翻弄されてしまう。知らず身体が震え、涙が飛び散った。
「シュバルツ……怯えるな……」
シュバルツの反応から、『怯え』の匂いを感じ取ったハヤブサが、彼を落ちつかせるように声をかける。
「大丈夫―――大丈夫、だから………」
そう言いながらハヤブサはシュバルツの額に優しく唇を落とす。その一方で、ハヤブサの手が――――服の上からその存在を確かめるかのように、シュバルツの『そこ』に触れた――――。
「あっ!?」
一番の性感帯からもたらされる、甘い、甘い電流の様な刺激に、シュバルツは身悶えるしかなくて。
「あっ!! ああっ!! だ、駄目っ!! 駄目、だ…ッ!!」
思わず身を捩り、ハヤブサの手から逃れようとする。しかしそれより早くハヤブサの身がシュバルツの上にのしかかり、その動きを封じた。そして、そこを触り続ける。優しく、撫でるように―――。
「は……っ! あ……!! やっ…! ハヤブサ……!!」
「シュバルツ―――」
そこを優しく撫でていたハヤブサの手が、シュバルツのズボンにかかる。そして、窺うようにシュバルツを見た。
(脱がせてもいいか?)
そう聞かれていると、はっきりと悟る。
「………………!」
シュバルツは観念したように瞳を閉じると、腰を軽く浮かせた。ズボンを脱がせやすくするために。『総てを、ハヤブサに許す』そう、決めたのだから―――。
シュバルツの動きを見たハヤブサは、彼のズボンと下着を、ズルッ、と、一気に引きずり下ろした。
「あっ………!」
シュバルツの『そこ』が、外気と、ハヤブサの視線に晒される。ハヤブサの愛撫によって、シュバルツの牡茎は既に勃ちあがり、その先端からは先走りを滲ませていた。『人間』と同じように――――。
「シュバルツ――――」
ハヤブサは、ある種の感慨を持ってそれを見つめる。対してシュバルツは、目を固く閉じて、頬を上気させながら顔を逸らしていた。そこを隠したい、と思っても、手を封じられているが故に隠す事が出来ず、縄がギッ、と、音を立てる。
「あ……あんまり、見るな……!」
ハヤブサの視線をそこに感じてしまって、シュバルツは震えた。
「どうしてだ…?」
ハヤブサは問い返しながら、軽く違和感を覚えた。顔を逸らすシュバルツの態度から、『羞恥』以外の別の何かが滲んでいたからだ。
「だ…だって……。要らない、だろう……?」
「…? 何がだ?」
疑問を呈するハヤブサに、シュバルツの叫ぶような声が返ってきた。
「わ、私に……せ、『生殖器』なんか……ッ!」
「…………!」
シュバルツの言葉に、ハヤブサは思わず絶句してしまう。シュバルツは唇を震わせながら、言葉を続けた。
「『DG細胞』で出来ているこの身体が……『生殖行為』なんて……可笑しい、だけだ……!」
そう。身体の隅々まで『DG細胞』で出来ているこの身体が『生殖行為』をする、と言う事は――――『DG細胞』をばらまく事と、何ら変わりがない。
伴侶と決めた女(ひと)と、そこから生まれ出でる子供を、『DG細胞』の脅威に晒す事になってしまう。
そんなこと――――許されるはずも、無い。
絶対に、してはならない事なのだ。
なのに―――。
自分には、『性感』があって。
今も、ハヤブサの愛撫に感じてしまって、馬鹿みたいに勃ち上がってしまって。
『解放』を求めて、先走りを滲ませてしまっている――――。
こんな『モノ』があるから――――!
要らないのに。
こんな、『機能』なんか。
使えもしないこんな『モノ』が―――何の役に立つと言うのだ。
何で、『ある』んだ。
こんな『モノ』が。
「だから、要らない…! 要らないんだ……!」
ハヤブサは、そう言いながらポロポロと涙を落とし、唇を噛みしめるシュバルツを、ただ茫然と見ていた。己の身体の歪な成り立ち故に、己の性感すら肯定できないシュバルツの、『闇』の根深さを思い知る。
でも―――それならば。
尚更――――俺が、お前を――――。
「シュバルツ――――」
ハヤブサは、彼に呼びかけながら、右手でシュバルツの勃ち上がっているそれを、そっと包み込む。
「あっ!!」
短く叫んだシュバルツが、身を捩って逃げようとするのを、ハヤブサは足を使ってその動きを封じこんだ。
そのままハヤブサの右手が、シュバルツのそれを愛撫し始めた。溢れ出る先走りを己の指に絡めながら、それを潤滑油代わりにして、そこをしごきあげて行く。
「ああっ!! あっ…! だ、駄目だっ! …うあ、あっ……!」
突如として襲って来た甘い電流の嵐に、シュバルツの身体がのたうつ。嫌がる様に頭(かぶり)を振り、涙を飛び散らせた。
「ハヤブサ…ッ! やめ…っ、やめて…くれっ! おねがっ……あぁ!!」
「……シュバルツ……」
ハヤブサは、そんなシュバルツをなだめるかのように髪を撫でる。『そこ』への右手の愛撫を優しいものにしながら、そっとシュバルツの唇を塞いだ。シュバルツの呼吸を奪ってしまわないように注意しながら、静かに舌を絡めていく。
「……ふ…。……ん…、…んっ……」
その優しい口付けを受け入れていたシュバルツの身体が、ビクビクと右手の愛撫に反応しながらも、だんだんと力が抜けて行くのが分かった。
「………………」
シュバルツの力が抜けきったのを確認してから、ハヤブサは唇を離す。「シュバルツ」と、呼びかけると、涙で潤んで陶然とした表情のシュバルツと、視線があった。
「……ハヤブサ……」
(―――――ッ!)
そこから漂うあまりにも凄絶な色香に、ハヤブサは思わず我を忘れそうになる。だが、必死にこらえた。今はシュバルツを『解放』するのが先なのだと、懸命に自分に言い聞かせる。シュバルツに、己の根幹の一つである『性感』を、否定したままでいて欲しくない、と、思ったから――――。
「シュバルツ……愛している……」
耳元で、そう囁いてやると、シュバルツから小さく「あ、」と、声が返ってきた。
「だから……大丈夫なんだ……」
「……あ……?」
「大丈夫だから……もっと、乱れて……。もっと、『俺』を感じて――――」
「……え…? 何……? ―――あっ!」
そうして再び始まる、ハヤブサの愛撫の嵐。右手で『そこ』を刺激しながら、空いている方の手と口を使って、シュバルツの性感帯を乱して行く。
「あっ……! あ……っ! ああっ!!」
正しく弱い所を責められたシュバルツは、ただ喘ぐよりほかに道は無く。牡茎から溢れだす先走りは、ひたすらその量を増して行った。それはハヤブサに、シュバルツの身体にためられて行く快感の熱を、正しく伝えて行く物で。
―――イケナイ……!
嵐の中でシュバルツは思った。このままでは自分は、ハヤブサに向かって『精』を放ってしまう――――!
「ああっ!! ……ん…! くぅ……ッ!」
シュバルツは必死に唇を噛みしめた。もたらされる快感を、何とか受け流そうと努力する。自分は、『精』を放つ訳にはいかないのだから――――!
「……んっ! ……く……」
「シュバルツ……堪えるな……」
シュバルツが必死に堪えようとしているのを感じ取ったハヤブサが、愛撫の手を休めずにシュバルツに囁く。それに対してシュバルツは、懸命にふるふると頭を振った。
「で……でもっ! あ…! ハヤブサ……ッ!」
「大丈夫……。大丈夫、だから――――」
ちゅぷっ、と、音を立てて、ハヤブサの口がシュバルツの牡茎を咥え込んだ。
「――――! ―――あ! ――――ああっ!」
これまでと比較にならない強い快感に、シュバルツは思わず身悶えてしまう。
「駄目だっ!! そんな事をするなッ!! ハヤブサぁっ!!」
懸命に身を捩り、何とかやめさせようとするが、腕を繋がれ、腰を抱え込まれてしまっている状態で、シュバルツに何が出来ただろうか。ただハヤブサの愛撫を許していく以外に道は無かった。ちゅぷちゅぷと音を立てて愛されて行くシュバルツの牡茎は、ハヤブサの口の中で正しくその容量を増していく。
「……は…、あ……! はあっ!!」
知らず、シュバルツの口から切ないため息が漏れる。
こんなの知らない。
こんなの、どうしたって――――
(キモチイイ………)
思ってしまってから、はっと我に返る。違う。駄目だ! 私は、『精』を放つ訳にはいかないのに―――!
まして、ハヤブサの口の中にだなんて。
ゼッタイ、ダメ、ダ――――!
「駄目っ! やめっ! …て、くれ……っ! ハヤブサッ!」
叫びながらシュバルツは、必死に腰を引こうとする。だがその動きは、ハヤブサの口の中で却って牡茎を擦ってしまう結果となり、シュバルツに新たな快感をもたらしてしまう。
「ああっ! あっ! あ……ッ!!」
気がつけばシュバルツの腰が、勝手に揺らめいてしまっていた。新たな快感を求めて―――。
「駄目っ! 駄目、だ……ッ!」
僅かに残る理性が悲鳴を上げ、腰の揺らめきを止める。だが、そのたびにハヤブサの愛撫がシュバルツを追いこみ、再び彼の腰が、勝手に揺らめいてしまう結果となる。
「ああっ! あああ……ッ!!」
確かに迫りくる、『解放』の予感。シュバルツは頭を振ってそれに抗った。
「ハヤブサッ! やめて…! 離れてくれ……!」
懸命に懇願する。だがハヤブサの愛撫は止まるはずもなく。
「あ……んっ! くう……ッ!」
駄目だ、駄目だ、と、必死に頭の中で繰り返し、『解放』を拒むシュバルツ。だがそこに、ハヤブサの指が、今度はシュバルツの『内部(なか)』に、つぷっ、と音を立てて侵入してきた。
「んっ、あ……ッ! ああっ!!」
前への刺激と、後ろからのどうしようもない違和感に、シュバルツは激しく混乱する。
「やめて…! やめてく―――ああっ!! あっ! あっ…!」
ハヤブサの肩に掛けられたシュバルツの足が、ビクビクと跳ね、彼を繋いでいる縄が大きな音を立てて軋む。
「駄目っ! 駄目だ!! もう……これ以上は……ッ!!」
『精』を放つ事を避けられそうにない、と、悟ったシュバルツは、それでも懸命に叫んだ。
「ハヤブサッ! 本当に……あッ! くうっ! 本当に、離れてくれ!! でないと、私は……ッ!」
放ってしまう…!
お前の、口の中に――――!!
「いいぞ、シュバルツ…!」
ハヤブサはシュバルツを愛しながら言った。
「放て―――。大丈夫だ……!」
チュッ、と、音を立てて牡茎が吸い上げられる。その瞬間。
「………あっ! あ……ああああ――――ッ!!」
ドクン!
シュバルツはついに、果ててしまった。
「――――――」
高みへと追い詰められ、達してしまったシュバルツの身体から、力が抜けて行く。とさっと、音を立てて、彼の身体が布団の上に沈むように投げ出された。
「あ…………!」
『放って』しまった。
よりにもよって、ハヤブサの『口の中』に――――。
つ……と、頬を涙が伝い、身体が勝手にがたがた震える。
罪悪感。解放感。羞恥。そして――――確かに感じてしまった、快感。
ありとあらゆる感情が、シュバルツの中でごちゃ混ぜになる。脱力し、混乱していたシュバルツであったが、ハヤブサの動きを見た瞬間、彼は慌てて飛び起きようとした。
「駄目だっ! それを飲むな! ハヤブサ!! ……あっ…!」
ギッ、と、彼を繋いでいる縄が音を立て、シュバルツを強引に布団へと引き戻す。そんな彼の目の前で、ハヤブサは口の中にあるシュバルツの『精』を、ごくん、と、飲み込んでしまった。
「ハヤブサ……! 何で――――!」
怯えたようにこちらを見るシュバルツに向かって、ハヤブサはにっこりと微笑んで見せた。
「言っただろう? シュバルツ……。俺は、お前の総てが欲しいのだと。お前から出る物も…………そして」
ハヤブサの手が、シュバルツの足を持ちあげて、グイッと股を広げる。
「あっ!?」
強引に取らされた恥ずかしい格好に、シュバルツは戸惑いの声を上げる。
「お前のここも――――俺は、欲しいんだ……!」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツの『秘所』に、指を2本、ズッ、と、押し入れてきた。
「ああっ! 待てっ! 待ってくれ!! ハヤブサ……ッ!」
前への刺激とはまた違った感覚に、シュバルツは身悶える。だが、ハヤブサの動きは性急だった。入ってきた2本の指が、シュバルツの内側を擦りながら、押し広げる様にそこをほぐして行く。
「済まない、シュバルツ…! 俺は、もう待てない―――!」
ハヤブサの声に、切迫したような響きが混じる。実際、ハヤブサはもう限界だった。先程から見せられ続けているシュバルツの『痴態』に、ハヤブサ自身がもはや悲鳴を上げていたのだ。「早く、『そこ』に挿入(はい)りたい。繋がりたい」と―――。
初めてなのだから、優しくしてやりたい、と、僅かに残る理性が訴えるが、彼と一つになりたいと悲鳴を上げる衝動が、それをはるかに凌駕してしまっていた。
「ハヤブサ…ッ! あ!! ああっ!!」
ハヤブサの指が、シュバルツの『中』の性感帯に行きあたる。そこを指が擦るたびに、シュバルツから高い嬌声が上がり、白い足がびくびくと跳ねて震えた。
(見つけた……! ここだな…!)
3本目の指も挿入し、そこを集中的に攻め立てる。
「あぁっ!! やめっ…! んあっ……! そこっ…は……何か……が!!」
「シュバルツ――――」
ズルッと、指を引き抜く。そしてすぐさま、怒張し切った己自身をシュバルツのそこに当てた。もう――――本当に、限界だった。
「あ…………!」
ハヤブサがこれから『何』をしようとしているのか――――理解したシュバルツが、潤んだ瞳をハヤブサに向ける。優しくしてやりたい、という気持ちと、一気に蹂躙してしまいたい、という本能が、ハヤブサの中でごちゃ混ぜになる。ハヤブサは、一つ大きく息をすると、シュバルツに語りかけた。
「済まない、シュバルツ……。無理だろうが、なるべく力を抜け。苦しければ叫んでもいい」
「ハヤブサ……」
「俺は、お前が欲しいんだ…! 欲しくて欲しくて……もう、限界だ……!」
だから、済まない、と、ハヤブサはもう一度、シュバルツに謝る。対してシュバルツは、一瞬戸惑った。自分みたいな歪な身体が、ハヤブサを受け入れてしまってもいいのだろうかと。
「シュバルツ、息を吐いて」
だが、それを深く考える間も与えられず、ハヤブサから声をかけられる。
「余計な事は考えるな…。目を閉じて。『俺』だけを、感じて――――」
「………分かった……」
シュバルツは、言われたとおりに目を閉じた。この身体は、ハヤブサに許すと―――『受け入れる』と決めたのだから、と、覚悟を決める。何よりも、ハヤブサから激烈に「挿入りたい」と、望んでいる『声』が、シュバルツには聞こえていた。その願いを、叶えてやりたい、と、思ったから―――。
「……は……あ……」
恐怖を押さえ、シュバルツは力を抜いて息を吐く。それを待っていたかのように―――ハヤブサ自身がシュバルツの『秘所』に、ズッ、と、音を立てて侵入してきた。
「―――――ッ!!」
想像をはるかに超える圧迫感と違和感と痛みに、シュバルツは声にならない悲鳴を上げる。
「シュバルツ…! 力を抜けっ!」
ハヤブサからも悲鳴に近い声が上がった。予想をはるかに超える締め付けに、少し腰を進めただけで、何もかもを持って行かれそうになってしまう。それを、必死に堪えた。シュバルツの様子を見ながら、少しずつ、奥へ奥へと腰を進めていく。
「…はっ……はぁっ……! う、あっ! ハ、ヤ…ブサ……ッ!」
シュバルツは、懸命に力を抜こうとしていた。この身体はハヤブサに許すと――――何もかもを許すと決めたのだから、と、必死に自分に言い聞かせる。
だから、いいんだ。
自分はどうなろうとも。
このままこの身体が二つに裂かれようとも―――。
ただ……ハヤブサ…。
この身体が、お前を破壊してしまう事だけが、私には―――。
「シュバルツ…! 余計な事は考えるな……!」
ハヤブサから、切迫した様な声が上がる。
「ハヤブサ……!」
「いいから…力を抜け……!」
「あ………」
シュバルツは、実際不思議に思った。どうしてハヤブサには、自分の考えている事が、筒抜けになってしまっているのだろうと。
「シュバルツ―――」
ハヤブサの潤んだ声が、シュバルツの思考を中断させる。シュバルツは再び息を吐いた。
「……ふ……う……。……あっ!」
ズッ、ズッ、と、音を立てる侵入者が、タイミングを合わせてシュバルツをこじ開けて行く。
「………は…あっ! ん……くっ! ああっ! あ……!」
痛みと違和感に耐えるシュバルツの上に、ハヤブサの身体が覆いかぶさってきた。
「シュバルツ……」
ハヤブサから呼び掛けられる声に、シュバルツが目を開けると、潤んだ瞳のハヤブサと、視線があった。彼の頬が上気して、朱に染まっている。
「ハヤブサ……」
「……分かるか? お前の中に、俺が全部、入っている―――」
「あ………」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは己が下腹部の違和感と痛みを意識する。繋がって、一つになっている二人の身体は、かつてない程密着していた。
「ん……! んっ……!」
だがハヤブサが少し動くと、シュバルツの方に痛みと違和感がもたらされる。息を荒らげながら、懸命にそれに耐えるシュバルツの頬を、ハヤブサの手が優しく撫でた。
「済まない……。シュバルツ――――」
「ハヤブサ……?」
どうしてハヤブサが謝らなければならないのか。不思議に思って見上げるシュバルツに対して、ハヤブサが少し哀しげな笑みを見せた。
「お前は『初めて』だから……優しく、してやらないといけないのに……」
「……あ……?」
潤んだ瞳で見上げてくるシュバルツ。自分に犯されていても、熱を持ちながらも、なおも無垢さを保っているその瞳を見た瞬間――――ハヤブサの中でついに、何かが音を立てて切れてしまった。
「もう――――限界だ…! 動くぞ……!」
「………えっ? あ……。あっ!? ああっ!!」
突如として、身体を突きぬけるような激しい感覚に襲われるシュバルツ。ハヤブサの律動が始まったのだ。ハヤブサはシュバルツを求めて―――奥へ奥へと、突きあげる様に腰を進めて行く。
「ああっ!! ああっ!! うあっ!! ハ、ヤブサッ!!」
それは、シュバルツが耐えようとするには、あまりにも大きすぎる衝撃だった。ハヤブサの律動に会わせて、思わず声が出てしまう。
(シュバルツ―――! シュバルツ……ッ!!)
ハヤブサは、歓喜に震えていた。
あれほど願い、そして夢に見ていた、シュバルツの、身体。それが、今――――自分の『腹の下』にあるのだ。しかも、間違いなく自分に貫かれて繋がり、よがり、そして喘いでいる。
夢じゃない。
夢じゃ、無いんだ。
夢中でその身体を貪り、そして、求める。
「ハヤブサッ!! ああっ!! あっ! ああ……ッ!」
自分の律動に合わせて響く、シュバルツの高い嬌声。揺れる身体。跳ねる足―――。
涙を流しながら乱れる、愛おしいヒト。
もっと、乱れて。
もっと、俺を感じて――――!
(ハヤブサ……ッ!)
ハヤブサに刺し貫かれて叫びながら、シュバルツは戸惑う。
あまりにも激しい律動――――『痛い』のか、『気持ちいい』のかすらも、最早シュバルツの中では判断できない。
はっきりと分かるのは、自分に繋がっているハヤブサが、ひどく『気持ち良さそう』であると言う事だった。
でも―――そんなはずはない。
そんなはずはないんだ。
私のこの身体なんて――――ただ、『固い』だけじゃないか。
DG細胞で覆われている『これ』は、ほぼ『金属』なのに。
体温も、無い、のに。
「あっ! んあっ! ああっ……!!」
時折ハヤブサの手が、自分のあちこちに触れてくる。
激しく擦られる内側とは裏腹に、その手がひどく優しいから―――シュバルツは涙が出てしまう。勝手に身体が震えてしまう。
「……くっ……!」
自身をシュバルツに叩きつけながら、ハヤブサは辟易していた。
想像していたよりも、ずっと熱く蠢き、甘く締め付けてくるシュバルツの『内部』
貫かれて乱れるシュバルツから発せられる、凄絶な色香。
持って行かれる。
持って行かれてしまう。
ああもっと。
お前と繋がっていたいのに―――!
もっと…もっと……!
「シュバルツ……! シュバルツ…ッ!!」
「ハ、あ…っ! ハヤブサッ!! ハヤブサぁっ!!」
大きく震えてしなる、シュバルツの、身体。それに合わせて彼の『内部』が、一層甘く強く、ハヤブサを締め付けた。
「ああっ! もっ……う! 駄――――!!」
ドクン!!
下腹部に熱い迸りを感じると同時に、シュバルツはその意識を手放した――――。
「……………!」
シュバルツの中に己を叩きつけ、果てたハヤブサは、力なくその身体をシュバルツの上に投げ出した。身体を密着させながら、熱の余韻を味わい、荒くなってしまった息を整える。彼の身体の冷たさが――――火照った自身の身体には、とても心地よかった。
「シュバルツ……」
大きく息を吐いて、自身を落ちつかせたハヤブサがシュバルツに声をかける。
「…………」
「シュバルツ?」
「…………」
彼から反応が返って来ない事を不審に思ったハヤブサは顔を上げて―――ここでようやく、シュバルツが気を失っている事に気付いた。口が半開きに薄く開かれて、頬に涙を湛えたままのシュバルツが、力なくそこに横たわっている。
「シュバルツ……!」
(しまった―――! 『初めて』だから、優しくしなければと思っていたのに―――!)
慌ててハヤブサは、シュバルツから自身を引き抜く。ズルッと音を立ててそれが出てくると同時に、シュバルツのそこから自身の白い精液と、赤い『血』の様な物が出てくるからハヤブサは絶句してしまう。
腕に絡みつき、喰い込んだ縄。涙を湛えた頬。身体のあちこちに残る痣。そして、傷ついてしまった『秘所』――――。そうして気を失っているシュバルツの姿は、どこからどう見ても、『強姦』された後、にしか、見えなかった。
「シュバルツ……! シュバルツ……!」
頬を軽く叩きながら呼び掛けてみるが、シュバルツは気を失ったままだった。
(そうだ…! 縄を……! 縄を、解かないと――――)
ハヤブサは、シュバルツを繋いでいる縄を解こうとする。しかし、既にきつく締まっている上に、ハヤブサ自身の手も震えてしまっていて、うまく縄を解く事が出来ない。やむを得ずハヤブサは、ナイフでロープを断ち切った。ブツッ、と、音を立てて切れた縄が床に転がり、シュバルツの腕をようやく解放する。
その腕には、縄で拘束された跡が、痛々しい程に残されていた。
(こんな――――! シュバルツ……!)
ハヤブサは、震える手でシュバルツの手を取る。こんなに縄の跡が残ってしまった腕。彼に相当の痛みをもたらしていたはずだ。
それなのに、シュバルツは。
一度も『腕が痛い』とは
言わなかっ―――――!!
「……シュバルツ……ッ!」
ハヤブサはいつの間にか、涙を落していた。シュバルツは、許してくれていたのだ。自身が縄で繋がれていることも。こちらが半ば強引に、蹂躙するように抱いた事も―――。
だからこそ。だからこそだ。
彼を、優しく、抱いてやらなければならなかったのに―――。
繋がった瞬間に、完全に我を忘れてしまっていた。
夢にまで見たその身体、が、自分の腹の下にあるのが、嬉しくて。
ただただ、シュバルツの事を顧みる余裕もなく、彼を求めてしまっていたのだ。
「……………」
ハヤブサは震えながら、想いをこめてシュバルツの手の傷に口付けを落とす。その気配に、シュバルツが小さく身じろぎをした。どうやら、意識が戻って来たようだ。
凝視するハヤブサの前で、シュバルツの瞳が、ゆるゆると開かれる。
「ハ、ヤ……ブサ……?」
「シュバルツ………」
シュバルツと視線があったハヤブサは、一瞬身構えた。彼から『非難される』と、思ってしまったから―――。
実際、そうされても仕方が無い、と、ハヤブサは思った。
自分は、それだけの事を、シュバルツにしてしまったのだから。
ただ、彼を抱いた事自体は、後悔していない。
優しくしてやれなかった事だけが、ハヤブサにとっては心残りだった。
だがハヤブサの姿を認めたシュバルツの瞳には、怒りの色も、恐怖の色も、何も浮かばなかった。ただ―――ハヤブサの事を『案じる』色しか、浮かんでこなかった。
「ハヤブサ……どうした……。泣いているのか……?」
自由になったシュバルツの手は、ハヤブサの頬を優しく撫でた。
「シュバルツ……ッ!」
ハヤブサはたまらなくなった。ただひたすらに優しいこの人を、どうして自分は――――貪るようにしか、愛せなかったのだろう。
「済まない……腕……痛かっただろう……?」
そう言いながらハヤブサは、再びシュバルツの手の傷に、唇を落とす。せめて、もう少し早く解いてあげればよかったと後悔する。シュバルツを解放する事が出来なかったのは、ただひたすら自分が弱かったせいなのだと、ハヤブサは思った。
「あ………」
手の傷が、ハヤブサを責める格好になってしまっている事に気付いたシュバルツは、少し哀しげに瞳を曇らせる。
「気にしなくてもいいのに……。後30分もすれば、傷は綺麗に無くなるから……」
「――――!」
シュバルツの言葉に、ハヤブサは思わず絶句してしまう。
だが、シュバルツのその言葉を証明するかのように、ハヤブサが彼に刻みつけた愛撫の根跡が、かなり薄くなってきているのが分かった。
目に見える『身体の傷』を、決して留めておく事が出来ない、シュバルツの身体。そうして彼は、自身の傷が綺麗に治ってしまったら、「大丈夫だよ」と、にっこり笑ってしまうのだろう。例えどんなに、その『心』の方が傷だらけであったとしても――――。
本当に、自分に頓着しないシュバルツ。ハヤブサはまた、堪らなくなってしまった。
「シュバルツ……ッ!」
気がつけばハヤブサは、シュバルツの身体を力いっぱい、抱きしめて、いた。
「ハ、ハヤブサ!?」
抱きしめられたシュバルツから、戸惑いの声が上がる。
「シュバルツ……! シュバルツ……ッ!」
潤んだ声でその名を呼びながら、ハヤブサはシュバルツを抱きしめる。
「あ……! ハヤブサ……! ち、ちょっと、待……て……!」
腕の中のシュバルツの身体が、緊張して硬直しているのが分かった。腕の中から逃れようとするシュバルツの動きを封じ込める様に、ハヤブサは、さらに腕の力を込めた。
「大丈夫だ……! シュバルツ……! 『今』は、これ以上、何もしないから――――」
「ハヤブサ……」
「だからこのまま………触れさせて、くれ……!」
「………………」
しばらく沈黙していたシュバルツであったが、やがて大きく息を一つ吐くと、身体から力を抜いて行った。そして今度は、シュバルツの手が、ハヤブサを抱き返すかのように、彼の背中へと回される。
「シュバルツ……!」
シュバルツからの思いもかけないリアクションに、ハヤブサは驚いて顔を上げる。すると、少し呆れたようにこちらを見ているシュバルツと、目があった。
「本当にこれ以上……何も、しないんだな?」
「あ……ああ」
シュバルツの問いかけに、ハヤブサは頷く。ただ彼は、心の中で『今は』と、その後に言葉を付け加える事を忘れなかった。シュバルツと繋がれるのが、この1度限りだなんて―――ハヤブサには到底受け入れ難い事であったから。
出来れば、もっと触れたい。もう一度。
いや、一度や二度とは言わず――――『何度でも』
彼に触れたい、と、ハヤブサは願った。
「なら、いいけど……。ハヤブサ……お前、少し無茶しすぎだ……」
「えっ?」
驚いてシュバルツを見るハヤブサに、彼は苦笑を返してきた。
「熱がある」
「えっ!?」
「……おまけに、唾液の中の『毒』の成分も、また増えてきている……。しんどいんじゃないのか? 安静にしてなきゃいけないのに、こんな事をするから―――」
「あ…! いや、しかし―――!」
ハヤブサは、慌てて反論しようとする。確かに倦怠感はあるが、それよりも得られた解放感、充足感の方が、はるかに高い。今だって―――気分が高揚して、少し『気持ちいい』ぐらいなのに。
「とにかく、無茶をするなハヤブサ……。毒が抜け切るまでは、安静にして―――」
そう言いながらハヤブサの髪を撫でていたシュバルツの手が、ピタリ、と止まる。
『殺気』を感じたからだ。
それと、『火薬』の匂いも――――。
「ハヤブサ」
シュバルツの呼び掛けに、ハヤブサも頷く。二人は同時に、布団から跳び起きた。
突如として「ドォンッ!!」という爆発音が、辺りに響き渡る。空気を裂いて襲って来た衝撃波が、家の天井や壁をびりびりと揺らした。
「リュウさん!! 大変です!! 居住区が――――!!」
与助が血相を変えて、部屋へと飛び込んできていた。
第5章
ハヤブサとシュバルツがそこに駆け付けた時には、もう居住区は、火の海であった。
「火を消せ!!」
「敵襲だ―――!!」
「怖いよッ!! お母さん!! お母さ―――ん!!」
炎に追われて逃げ惑う人々。はぐれた我が子を探す親。火を消そうとする者たちが通路を行き交い、怒号と悲鳴が交錯する。
「どうした!? 何が起こった!?」
ハヤブサが、近くに座り込んでいた老人を見つけて声をかける。
「わ……分からない……。急に、火が、走って……!」
老人は、震えながら茫然と呟いた。
(火が走る―――? 火薬か……!)
意図的な奇襲の匂いを感じて、ハヤブサは歯噛みする。
しかし、妙だ。
里の守りは鉄壁のはずなのに。
これが敵の奇襲なのだとしたら、何故、こうもあっさり敵の侵入を許してしまった?
しかも、よりにもよって、一番備えの薄い、里の奥の『居住区』に―――!
「ああっ!! 家が―――!!」
与助の叫び声によって、ハヤブサの思考は中断された。ハヤブサがそちらの方を見ると、与助が燃える自分の家を見ながら茫然としている。
「……婆ちゃん…! 婆ちゃん、は……?」
逃げ惑う人々の中に、自分の祖母の姿を見つけられない与助が、震えながら呟いた。
「だ、誰か、家の―――! 私の祖母の姿を、見ませんでしたか!?」
行き交う人々を捕まえて、与助は必死に問いかける。誰もが『分からない』と、首を振る中――――一人だけ、応えてくれた人がいた。
「も……もしかして、ミツさんなら……まだ……あの中に――――」
その人は怯えたように震えながら、ある方向を指さす。その指先には、まさに今、燃えて崩れ落ちそうになっている、与助の家が、あった。
「そんな――――!」
与助は愕然としてしまう。自分はまだ、ここで祖母を失ってしまうだなんて、思ってもいなかったのに。
「婆ちゃん!! 婆ちゃん!!」
弾かれた様に与助が家に向かって突進しようとするのを、周りにいた人たちが止めた。
「与助!! 危ない!!」
「もう無理だ!! あきらめろ!!」
「い、嫌だっ!! 婆ちゃん!! 婆ちゃ――――ん!!」
いきなり背後でバシャッ! と、派手な水音がする。皆が驚いて振り返ると、頭から水をかぶって、空になった桶を放り投げているシュバルツの姿がそこにあった。
「シュバルツ!?」
驚くハヤブサにシュバルツはにこりと微笑みかけると、全く躊躇うことなく突っ込んで行った。燃え盛る、炎の海へと。
「シュバルツ!!」
「……………!」
彼を止めようとしたハヤブサの手は、空しく空を切る。与助はただ、そんな二人の姿を茫然と見ていた。
(ど……どうして、あの人が、婆ちゃんのために……!?)
「ギャッ!!」
突如として上がった悲鳴に皆が振り向くと、逃げ惑う人々を次々と斬り倒して行く黒い影がある。与助はすぐに悟った。あの、黒い影たちが、ここに火を放った張本人たちなのだと――――!
「おのれっ!!」
激昂してしまった青年が、その黒い影めがけて一直線に突っ込んで行く。
「与助!!」
叫びながらハヤブサは瞬間迷った。自分はシュバルツと与助―――どちらの後を、追うべきなのだろうかと。
「リュウさん!!」
混乱の中、ハヤブサの姿を認めた者たちが、何人か集まってくる。
「お前たち―――ここの住民の避難と誘導を任せてもいいか?」
「分かりました。でも、どこへ誘導をしたら?」
「長老の家だ。あそこなら守りも固い。里の外へ秘密裏に出られる抜け道もある―――」
「承知! おい! みんなかかるぞ! 女子供を優先的に避難させろ!!」
ハヤブサの命を受けた者たちが、一斉に散っていく。それを確認したハヤブサは、与助の後を追う事を選択した。
シュバルツは死なない。死なないのだ。例え炎の中に、その身を投げ出したのだとしても―――。だが与助は、死んでしまう可能性がある。まして与助の方は、完全に頭に血が上ってしまっている。今危険なのは彼の方なのだと、ハヤブサは判断した。
(だが、痛みや苦痛を感じることに変わりは無いのだろう? シュバルツ……。まして、『焼死』なんて、一番苦しい死に方だというのに)
そう思ってしまって、ハヤブサは歯噛みする。
(あいつ……! 無茶ばかりしやがって……! この戦いが終わったら、絶対一発ぶん殴る!!)
ハヤブサは強くそう思いながら、与助の後を追って行った。
少し離れた所から里に上がった火の手を眺めながら、甲賀忍軍の頭である九龍院はほくそ笑んでいた。
「フフフ……首尾よういったな……。さあ、我らも手筈通りに動くぞ」
「はっ!」
九龍院の後ろには、多数の忍者軍団が控えていた。その数およそ800人と言ったところだろうか。
「皆の者!! よく聞けい!! この奇襲によって、里の戦闘部隊も怪我人の世話や里を守るために手を取られる!! 頼みの龍の忍者も『忍法血蜘蛛』によって手負いの身だ! 我らが恐れるものは、最早何も無い!!」
九龍院の言葉に、忍者軍団から放たれる殺気が更に鋭いものになる。
「さあ行けい!! 女子供とて容赦はするな!! 里の者は殲滅しろ!! そして龍の忍者をいぶり出し、龍剣を何としても手に入れるのだ!!」
「ははっ!!」
言葉と同時に800人の甲賀忍軍は、隼の里を襲うべく、一斉に動き出していた。
ドォン!!
派手な轟音を響かせながら、与助の家が炎の中で崩壊する。それと同時に炎の中から、一つの影が飛び出してきた。その影は、着地と同時にガクっと膝を着く。それは、与助の祖母を腕の中に抱えたシュバルツの姿だった。
「ミツさん!!」
「おい!! 誰か水を持って来い!!」
二人の姿を認めた人たちが、血相を変えて叫ぶ。シュバルツの手も顔も黒く煤けて、ロングコートのあちこちがじりじりと音を立てて焼け焦げていたからだ。腕の中にしっかりと抱え込まれていた老女ミツは―――無事だった。
「私はいいから……この人の手当てを……」
「何を言っているんだ!! あんたは―――!」
弱々しくそう言うシュバルツに向かって、怒鳴り声が飛び、水がかけられる。あっという間にそこらじゅうから水が集められ、シュバルツに向かってかけられた。
「お……お前さんは、めちゃくちゃじゃ…ッ! 何で、来たんだ……!」
シュバルツの手から、里の者たちに手渡された老女ミツは、涙を流しながら叫んでいた。
「すみません……。『声』が、聞こえてしまった……ものですから……」
シュバルツが、苦笑しながら答える。
「わ……私ァ与助に叫んだんじゃ! 『来るな』と…! それなのにお前さんは―――!」
「ミツさん、興奮しすぎだ! 落ちついて……」
ミツを抱きかかえた里の者が彼女に声をかける。
「あんたも―――! 死ぬなッ! 死ぬんじゃないぞ!!」
シュバルツに水をかけていた村人が、懸命に叫ぶ。ロングコートが燃え、黒く煤けたシュバルツの身体を見ながら、必死になって祈っていた。これだけの火傷。普通なら、死んでもおかしくないほどの重症であったから―――。
「……………ッ」
焼け付く様な全身の痛みに耐えながら、しばらくじっと下を向いていたシュバルツであったが、不意に顔を上げた。
「後ろだ!!」
「えっ――――!?」
シュバルツの叫び声に、彼に水をかけていた男たちが、一斉に動きを止める。その背後から、彼らに攻撃を仕掛けようと、猛スピードで迫ってくる黒い影の姿あった。鞘ばしらせた刀が、ぎらり、と不吉な光を放つ。
ガンッ!!
影が振るった刀は、しかし誰の肉も斬れなかった。そうなる前に、シュバルツがその前に立ちはだかったからである。彼は素早く立ち上がりながら抜刀し、斬られそうになっていた者を押しのけながら影の刀を受けた。
「うわっ!?」
シュバルツに突き飛ばされた格好になった者はそのまま尻餅をつき、足元にあった水をたたえた桶が、バシャッ! と、派手な音を立ててひっくり返った。そのまま甲賀忍者とシュバルツの間で鍔迫り合いの状態になる。
「……う……ッ! く……!」
甲賀忍者の刀を受けながら、シュバルツは歯を食いしばった。炎によるダメージを受けた身体は、まだ完全に回復し切ってはいなかったのだ。普段の半分程度の力しか、出せていない。
「…………!」
切りかかってきた甲賀忍者にも、シュバルツの非力さが伝わったようで、ここぞとばかりに刀を握る腕に力を込めてくる。シュバルツの刀が、じりじりと押されて行った。
(遅い―――! もっと早く回復しろ! この身体……ッ!)
鍔迫り合いをしながらシュバルツは祈る。ここにいる人たちを守るためだったら、自分は完全な『化け物』になってしまっても構わないのにと。
「こいつ!! シュバルツさんから離れろ!!」
周りにいる男たちが、シュバルツと戦っている忍者に攻撃を仕掛けようとする。その気配を察知した甲賀忍者は「チッ!」と、舌打ちをしながら後退した。「待てっ!」と、追いかけようとする者を、「深追いはするな!」と、たしなめる声が止める。
「―――――ッ」
シュバルツは思わず膝をつきそうになるのをぐっとこらえた。この状況―――自分が今、倒れてしまう訳にはいかないのだ。
「済まない…。助かった」
穏やかにそう言いながら、シュバルツは刀を下ろす。
「いや……それよりもあんた――――『動ける』のか……?」
シュバルツに突き飛ばされた男が、茫然と呟く。彼の火傷の度合いから言うならば、動くことすらままならないはずであると言うのに。
「ええ…。貴方がたが水をかけてくれたおかげで――――」
シュバルツはそう言いながら、火傷で傷ついた顔の皮膚をぐっと手で拭う。するとその傷がはがれおち、下から綺麗な皮膚が姿を現した。
(特異体質―――!)
それを見た男は、思わず息を飲む。対してシュバルツの方は、穏やかな――――少し、哀しげな眼差しを湛えながら、そこに佇んでいた。ある種異様な沈黙が、しばらくの間そこを支配する。
言ってしまった。貴方の目の前にいるのは『化け物』なのだと。
「と、とにかく……ミツさんを長老の家に避難させよう。他の人たちも―――」
ミツをシュバルツから受け取った男の上ずり気味な声に、その場にいた全員が、はっと、我に返る。
「そ、そうだな……。今は、一刻を争う時だ。じっとしている場合じゃない」
尻餅をついたまま、茫然としていた男も、そう言いながら立ち上がった。
「他にも逃げ遅れた者がいないかどうか確認を! シュバルツさん! あんたも自力で動けるのなら、長老の家に避難を―――!」
「えっ……?」
男がまっすぐこちらを見ながらそう声をかけてきたので、シュバルツの方が逆に驚く。先程の仕種で、自分の体質が『普通じゃない』ことは、ここにいる人たちには伝わってしまったと思うのに。
「どうしたんだ? シュバルツさん」
戸惑ったような眼差しを向けてくるシュバルツに、男は問い返す。
「あ……いや……」
シュバルツは実際戸惑っていた。
「貴方は……私の事を、『不審』に思ったりは……しないのか?」
火傷を負ったはずの身体が、すぐに動けたり、傷が治ったり――――どう考えたって『普通じゃない』と――――『化け物』呼ばわりされてしまっても仕方が無いだけの事を、自分はこの人たちに見せてしまっていると言うのに。
「はあ?」
そのシュバルツの言葉に対して、男から呆れたような返事が返ってくる。
「何を言っているんだ、あんたは……。あんたはリュウさんを助けてくれた。そして今また、ここにいるミツさんを、助けてくれた」
その男の言葉に、周りにいる男たちは「うんうん」と頷く。
「だいたい、あんたはリュウさんの客人だし」
「家の倅(せがれ)も――――世話になってるしな」
「これだけ条件の整っているあんたを信じられなくて――――この先、何を信じればいいんだ?」
「あ…………」
里の人たちからかけられる、思いもかけぬ優しい言葉に、シュバルツは茫然とするしかなかった。
「ありがとう……」
自然と、その言葉が口から出た。それに対して男たちも笑顔を返す。優しい空気が、その場を包んだ。
(ああ―――やっぱり、いい所だ。ここは………)
シュバルツは、強くそう思った。異質な自分を、ここの人たちは普通に受け入れてくれる――――そんな、懐の深さを感じた。この人たちを守るためならば、自分は化け物でいいのだと、素直に思える。
「とにかく急ごう。火の回りも速い。一刻も早く―――皆を避難させないと」
「私も手伝おう」
シュバルツからの申し出に、男たちは顔を見合わせた。
「えっ……? いや、申し出はありがたいが、あんたは怪我を――――」
「もう、かなり動ける。大丈夫だ」
そう言いながらシュバルツは笑みを浮かべる。
「そ……そうなのか? じゃあ……」
男は戸惑いながらも、違和感を飲みこんだ。きっと、こういう事は深く考えない方がいいのだと、本能で判断する。実際今は、猫の手も借りたいところであるし。
「シュバルツさんは、俺たちと東周りに――――田兵衛の組は西周りにここを回ってくれ! 与六は、ミツさんを頼む!」
「任せとけって!」
「じゃあ、行こう!!」
男たちは頷き―――三方へとそれぞれ散って行った。
「うおおおおっ!!」
与助が怒りの咆哮と共に、また一人、甲賀忍者の命を屠る。そして、一人を斬った瞬間、その眼差しは、もう次の獲物を探し出していた。そしてまた、魅入られたようにその獲物に向かって行く。普段温厚な与助からは、考えられないような激しさだった。
「与助!! 待てっ!! 深追いするなッ!!」
ハヤブサは懸命に与助に呼びかけ、止めようとする。しかし、与助の方にはハヤブサの声が聞こえていないかのようであった。怒りにまかせて振るわれる刀は、止まる気配を見せなかった。
(うん? 何だ? この白く光る物は……)
不意にハヤブサは、目の前に一本の細い細い蜘蛛の糸の様な物が走っている事に気づく。よく見るとそれは、里の外から里の中へと引っ張られていた。まるで、『里へ入る安全な道筋はこれだ』と、誘うように――――。
「与助! 止まれっ!! 何か様子が変だ!!」
ハヤブサの叫び声に―――しかし与助は、反応を返さない。ぎらついた眼差しで、次の『獲物』を探している。
許さない……。
許さない!
よくも――――里を……! 婆ちゃんを……ッ!!
「うわあああああっ!! た、助けてくれぇぇぇ――――ッ!!」
「!?」
唐突に響いてきた助けを求める声に、与助とハヤブサが同時に振り向く。するとその視線の先には、複数の甲賀忍者に囲まれた里の若者の姿があった。
「三郎太!!」
「!!」
ハヤブサが弾かれた様にそちらへと走り出し、与助も、その光景を見て、ようやく我に返る。
―――私は今まで、一体何を――――!?
血で朱に染まった己が刀に、与助は茫然とするしかなかった。
「な、何でこいつら、俺ばっかり狙ってくるんだよォ!?」
甲賀忍者たちに囲まれながら、三郎太は悲鳴を上げていた。
「無駄だ――――。主は、どこへ隠れようとも我らには分かるようになっている」
「な……何で――――!」
「……教えて欲しいか?」
甲賀忍者の一人が、にやりと笑う。
「聞くなッ!! 三郎太!!」
声と共に、龍の忍者がその包囲の中に飛び込んできた。包囲の一角を切り崩したハヤブサは、三郎太の手を引き、強引にそこから出て行こうとする。だが―――三郎太が、その動きに逆らった。
「ど、どういうことだ!? 説明しろ!!」
ハヤブサの手を振りほどいて、甲賀忍者に説明を求める。逃げても逃げても追いかけられる理由を聞くまでは、安心して逃げる事も出来ないと思った。
「三郎太!!」
聞かせては駄目だと思って、龍の忍者は叫ぶ。しかし―――ハヤブサの想いとは裏腹に、甲賀忍者の口は開かれてしまった。
「主の刀だ……」
「刀!?」
「主は―――その刀を、どこで手に入れた?」
「…………!」
甲賀忍者に問われて、三郎太は刀を手に入れた経緯を必死に思い出す。この刀は確か昨日、里の守り番についていた時に甲賀忍者との小競り合いがあって――――その時に、手に入れた物、だった。
「その刀に―――『細工』が施されていたと、主は気付かなかったのか?」
「!?」
「その刀に――――蜘蛛の糸よりも細い、細い糸が繋がっている事を、主は気付かなかったのか?」
「な――――!」
三郎太はここで初めて気づく。自身の下げている刀の柄から出ているその『糸』に。
「その『糸』のおかげで――――我らは無事、こうして里に入る事が出来た」
「馬鹿な奴よ。我らがわざと、貴様に刀を渡したと気づかずに」
「いわば――――お前が手引きしたも同然だ……」
「先導役――――ご苦労だったな」
次々と言葉が投げかけられ、甲賀忍者たちの嘲笑する声が辺りに響く。
「あ……! 嘘だ……! 嘘だああああああっ!!」
三郎太の絶叫する声が、辺りに響き渡っていた。
「三郎太!! 落ちつけ!!」
ハヤブサが懸命に彼に声をかけるが、三郎太にはまるで効果が無いようだった。
「おまけにこうして『龍の忍者』まで連れて来てくれるとは、念の入った裏切り者だな」
「……………!」
その言葉に、ハヤブサがピクリ、と反応する。
「おかげで探し出す手間が省けた。貴様の命、今ここで始末してくれる」
ハヤブサたちは、あっという間に甲賀忍軍に取り囲まれてしまった。
「もう、この区画は誰もいないな!?」
炎の中、男の声が響く。
「こっちはもう誰もいない!! この人で最後だ!!」
別の男が、瓦礫の中から女性を一人助け出していた。
「皆急いで!! 長老の家へ―――!!」
そう叫びながら人々を先導していたシュバルツであったが、不意に彼の耳が、小さな音を捕らえた。
「どうした!?」
いきなり走り出したシュバルツに、一緒に誘導していた男が声をかける。
「あちらに―――まだ、人がいるんだ!!」
「本当か!?」
シュバルツが走りだすと同時に、3人の男たちが後からついてくる。シュバルツはこんな調子で、もう何人もの人を助けていた。だから、男たちも―――シュバルツの言葉を疑うことなくその後をついて行く。人手がいるなら、手伝うつもりで。そして、シュバルツを守るつもりでもある。
「どこだ!? どこから聞こえるんだ、シュバルツさん!」
「あの家からだ!!」
「あの家から!?」
一緒についてきた男の一人が、意外そうな声を上げる。先程自分が検分した時は、人の気配など感じなかったから――――。
それでもシュバルツは、無人の家に走り込んで声を張り上げる。
「誰か―――!! 誰か、いないか―――!?」
だが、返ってくる返事は無い。
(おかしい……。確かにさっき、私は声を聞いた様な気がしたのだが……)
「シュバルツさん……! さっきこの家は俺も見たが、誰も居な―――」
ガタッ。
不意に床板が外れて、その下から人間が出てくる。それは―――その家の、子供たちだった。
「栄太! ハナ!!」
「おっちゃん!? おっちゃ~~~ん!!」
シュバルツの姿を認めた子供たちが、懸命に手を差し伸べてくる。シュバルツも子供たちの身体を床下から引っ張り上げ、そして、抱きとめた。
子供たちはシュバルツの腕の中で安心したのか、声を上げて泣きじゃくりだす。
「よく、頑張ったな…。もう、大丈夫だ―――」
子供たちを安心させるように、優しくシュバルツは声をかけた。
「怖かった……ッ! 怖かったよう~~~!!」
「お母さん…! お母さんは……!?」
子供たちの問いかけに、シュバルツが後ろを振り向くと、男たちが『遺体』に毛布をかけていた。一人の男がシュバルツの視線に気づき、哀しそうに首を振る。
「……! 済まない……ッ! もっと早く……駆け付けていれば――――!」
そう言いながらシュバルツは、子供たちを強く抱きしめる。その肩が、小刻みに震えていた。
「……急ごう、シュバルツさん。ここもすぐ、火が回ってくる」
一人の男が、静かに、シュバルツにそう声をかけてくる。
「助かったこの子たちだけでも――――きちんと避難させないと……」
「ああ……そうだな……」
その言葉にシュバルツも頷いた。
「本当に、その通りだ……」
彼は涙を拭いて―――そして、立ち上がった。
家から飛び出したシュバルツ達は、ただひたすらに長老の家に向かって足を進めていた。辺りには、耳が痛くなるほどの殺気が満ちている。この集落を襲った忍者軍とはまた違う甲賀忍軍の『本隊』が、ここになだれ込んでくるのも時間の問題であるかのように思われた。
走りゆく道々で、甲賀忍者たちに襲われて斬られている里の人たちの『遺体』が、嫌でもシュバルツの目に飛び込んでくる。
「―――――ッ!」
シュバルツは歯噛みしていた。どうして―――自分は、もっと早く侵入者たちの存在に、気づく事が出来なかったのだろう。どうして、どうして―――!
こんな事、後悔しても、仕方が無い、のに。
「シュバルツさん!!」
不意に男からかけられる声に、シュバルツははっと我に返る。
「追手だ!! すぐ近くまで、迫って来ている!!」
「…………!」
男の声に振り向くと、黒装束に身を包んだ甲賀忍者たちが、土煙を上げながら、こちらへと迫って来ている姿が、視界に飛び込んできた。
「皆走れ!! とにかく走れ!!」
シュバルツの叫び声に、男たちは弾かれたように走る速度を上げる。
「おっちゃん―――! 僕たち、どうなるの?」
シュバルツの腕の中で、栄太が不安そうな声を上げる。
「心配するな! 大丈夫だ!」
シュバルツは、笑みを浮かべて力強く言った。とにかく――――この二つの幼い命は、何としても守らねばならない、とシュバルツは思った。
「うわっ!?」
走っていた一人の男が、躓(つまず)いて倒れる。
「!!」
それを見たシュバルツが、足を止めた。
「颯太!! 子供たちを―――!!」
「ほいきた!!」
シュバルツから子供たちを受け取った青年は、自分の役割を瞬時に理解して走りだす。その颯太の護衛のために、もう一人の青年も、彼について行った。それがシュバルツの願いだと、はっきり分かるからだ。
子供たちが青年に運ばれて行くのを確認したシュバルツは、転んだ男の元へと走り寄っていく。
「シュバルツさん!?」
転んだ男が、驚いた声を上げる。
「大丈夫か!?」
そう問いかけて来て、手を差し伸べてくるシュバルツを、男は茫然と見ていた。
「シュバルツさん、何故―――――!?」
逆に問い返してしまう。自分なんかに構わずに、先に走っていけば――――この人の脚力なら、逃げ切れただろうに。
「もらったァ!!」
ついに二人に追いついてきた甲賀忍軍の先鋒の一人が、シュバルツ達に向かって白刃を振るってきた。
「させるか!!」
それに素早く反応したシュバルツが、抜刀して対応する。あっという間にそこは、乱戦状態になった。
「喜助!! 立ち上がったのなら走れっ!!」
目の端で一緒にいた男―――喜助の動きを見たシュバルツが叫ぶ。だが、喜助は頭を振った。
「嫌だ!! 俺も戦う!!」
そう言いながらシュバルツの側に走って来て、刀を振るった。
「ここは、俺の里だ!! だから、守るんだ!!」
「――――!」
「俺の女房だって、子供だって―――無事に、長老の家に避難できた!! あんたのおかげだ!!」
だからこそ―――俺は引く気はない、と喜助は叫ぶ。彼の想いを止められない事を、シュバルツは悟った。
「分かった……。だが、無理はするな。機を見て、長老の家に向かう算段をするぞ」
シュバルツは、喜助にそう声をかけた。シュバルツは、里の人たちを守りたい、と、願っている。そして当然、喜助もその対象に入っていたのだから―――。
「承知した!!」
シュバルツの想いをある程度くみ取った喜助が、力強く頷いた。
ドォン!!
派手な轟音を立てて、ハヤブサたちの包囲網の一角が崩される。火薬の爆発から生じた黒煙の中から――――与助の声が飛び込んできた。
「リュウさん!! 三郎太!! 早く!!」
「……………!」
その声に鋭く反応したハヤブサは、三郎太の身体を強引に抱えあげると、黒煙の中へと飛び込んだ。
「待てっ!!」
甲賀忍者たちもハヤブサの走り込んだ黒煙の中に突っ込んで行く。だが―――ハヤブサの姿を捉える事は出来なかった。逃げられたのだと、悟る。
「おのれッ! 逃がすな!! 追えッ!! 追え―――――ッ!!」
忍者たちの怒号が、辺りに響き渡っていた。
「ここに来れば、しばらくは大丈夫か」
里の少し奥まった所に移動して、ハヤブサは三郎太を下ろす。下ろされた途端に、三郎太はハヤブサの手を振りほどいて叫んだ。
「リュウさん……! 何でだ!?」
「三郎太……」
「俺の事なんか放っておけばよかったのに…! 俺は、裏切り者だ!! 俺のせいで、里が……皆が――――!!」
そう言ったきり、三郎太は咽び泣いてしまう。
「……貴方のせいだけじゃないでしょう。それに、貴方が裏切った訳でもない―――」
与助が、三郎太に声をかける。
「で、でも……ッ! 刀の『仕掛け』に気付けなかったのは、俺だ……ッ! そのせいで、与助……お前の、家だって……!」
「……………!」
三郎太の言葉に、与助も思わず唇を噛みしめる。脳裏に、燃えて崩れ落ちそうになっている家の映像がフラッシュバックした。あの中から―――祖母が、自分に向かって何かを叫んでいたような気がする。
(そう言えば、あの人が――――)
自分が怒りに我を忘れる直前、燃え盛る家に向かって、頭から水をかぶって飛び込んで行ったシュバルツの姿を思い出す。あの人は、どうなってしまったのだろう。
「与助……。心配するな。恐らくお前の祖母は無事だ」
「リュウさん!?」
「………え…?」
ハヤブサから発せられた言葉に、若者二人は驚く。
「……あいつは、自分の身を顧みないめちゃくちゃな奴だが、助けだせる算段が立たなければ、絶対に飛び込んで行ったりはしない。『助けられる』と言う確信があったから、あいつは動いたんだ――――」
だから、きっと、彼は与助の祖母を助けている。
その為に、自分がどんなに傷を負おうと、それには構わずに。『再生』する身体を持つが故に、与助の祖母を助けた時に、家から脱出できる力さえ残っていればいい、と、考えるだろうから―――。
(全く……! 本当に、大馬鹿野郎だ……!)
ハヤブサはいつしか組んでいる腕に力が入っていた。いくら『死なない』とは言え、傷を負う。動けなくなる。痛みが無い訳ではない。平気なはずが無いんだ。それなのに、あいつは――――本当に自分の身を顧みないから。
「リュウさん……」
与助はそんなハヤブサの様子を見ながら、何とも言えない気持ちになる。あの人は―――リュウさんにとって、大切な人のはず。なのに不思議だった。どうして、リュウさんは、あの人の『身体』の心配はしていても、『命』の心配をしていないのだろう? それほどまでに、彼はあの人の事を信じているとでも言うのだろうか。あの人ならば、『絶対に、使命を果たして、生きて帰ってくる』と……。
そうだとしたら、少し羨ましいと思った。
そこまで、絶対的な信頼を寄せられるシュバルツが。
そこまで強く、他人を信じられるハヤブサが―――。
自分もいつか、そんな風に他人を信じられる人間になりたい。
与助はいつしか、そう思っていた。
「三郎太。お前は与助と一緒に、長老の家に避難しろ」
「――――ッ!」
「リュウさんは?」
与助の問いに、ハヤブサは笑みを浮かべる。
「奴らの狙いは、俺と、この『龍剣』だ。だから、俺と一緒にいない方が―――お前たちは、安全だ」
「そ、そんな……!」
茫然と呟く三郎太に対して、与助はハヤブサの言葉に頷いた。
「分かりました。―――三郎太、行こう」
「い、嫌だっ!!」
三郎太は、与助の出した手を振り払う。
「三郎太!?」
「わ、分かるだろう!? 与助……! 俺は、皆に合わす顔が無いんだ! 今回の襲撃で、命を落とした人……! 家を失くした人……! その人たちに俺は―――何と言って詫びれば――――!!」
「あの『糸』の事を知っているのは俺たちだけだ。口外はしない」
ハヤブサはそう言ったが、三郎太はなおも頭を振ってそれに抗った。
「で、でも、俺が知ってしまっているんだ!! 原因は―――『俺』なんだって……ッ!! なのに、皆の前で知らないふりなんて、俺は出来ない……! 出来ないんだ……!」
「…………」
ハヤブサは、そう言いながら泣く三郎太を無言で見つめる。彼にかけられる言葉が、見つからなかった。
だが、与助は違った。三郎太につかつかと近寄っていくと、いきなりその頬を平手打ちしたのだ。パン! と、乾いた音が、場に響き渡る。
「しっかりしてくれ! 三郎太!! 『皆に悪い』って思うのなら、尚更―――!」
「よ、与助……!?」
茫然と見つめ返す三郎太に、与助はなおもたたみかける。
「里はボロボロに傷ついて、家を失くした人もたくさんあって……ッ! そんな人たちを放っておいて、自分だけ死んで楽になろうと言うのなら――――僕は絶対に許さない!!」
「――――!」
与助の言葉に、三郎太は息を飲んだ。
「生きろよ! 三郎太……!」
「与助……」
「生きて――――里の復興を、手伝え!!」
力強くそう言って、与助は三郎太に手を差し伸べる。
「あ………!」
三郎太は、しばらくその手を掴むかどうか逡巡していたが、やがて―――その手を、与助へと差し出した。
「三郎太……!」
三郎太の手を掴んだ与助は、笑顔になる。
「それでいい。それでいいんだ……」
「……ウ……ウッ……!」
それに対して、三郎太はもう、ただ咽び泣くしか出来なかった。それでも与助と三郎太の手は―――しっかりと握り合われていた。
(もう、大丈夫だな)
二人の様子を黙って見つめていたハヤブサの面に、自然と笑みが浮かんでいた。
「じゃあ、俺はもう行く。お前たちも―――行け」
ハヤブサは短くそう言うと、二人の前から姿を消した。
「リュウさん……」
三郎太がハヤブサの去った方に足を進めようとするのを、与助が止めた。
「三郎太……私たちも」
「与助……待ってくれ…! リュウさん……やっぱり、熱がある……!」
「―――えっ!?」
三郎太の意外な言葉に、与助も思わずハヤブサの去って行った方を振り向く。
「だって、リュウさんの手――――今触れているお前の手よりも、明らかに熱かった……!」
「ええっ!?」
「リュウさん、確か『毒』にやられたって、言っていたよな……。もしかして、それがまだ完治していないんじゃ……?」
「―――――!」
与助は思わず、言葉を失う。だが確かにそうだ。2、3日前、あの人は生死の境を彷徨った。リュウさんの想い人――――シュバルツの薬と看病のおかげで、今朝には熱が下がっていたように、見受けられたのだが……。
(止める、べきだったんだろうか……?)
ずっとハヤブサの側についていた与助は、そう思った。今朝―――シュバルツを抱こうとしていた彼を。そして今―――独りで行ってしまった、彼を。
(無理だ)
与助は頭を振る。
あんなに思い詰めた瞳でシュバルツを抱きかかえていたハヤブサを。
そして、『龍の忍者』として、戦いに赴いて行ってしまったハヤブサを。
自分なんかが――――止められるはずも、ない。
「……援護を、呼ぼう」
三郎太が、ポツリとそう言った。
「いつものリュウさんならともかく―――あんなに熱が高いリュウさんを、一人で戦わすわけには、いかないよ」
「確かに……そうだね」
三郎太の言葉に、与助も頷く。
「与助、行ってくれるか? 援軍を呼びに―――」
「三郎太、お前は?」
三郎太からの提案に、与助は問い返した。
「俺は……リュウさんの戦いを『見守る役』をするよ。……忍者の戦いには、必ずそういう役割をする者が、必要だろう?」
「確かに……そうだけど」
三郎太の言葉に、与助も頷くしかなかった。確かにそうなのだ。忍者は古来より、戦う部隊とは必ず別行動をする者がいて、それが、戦いの顛末を見届ける役割をしていた。仮に戦った部隊が全滅したとしても――――その結末を、自分達を雇った雇い主や別働隊に、それを連絡する義務をその者は背負う。こうして忍者は、情報が滞ってしまう事を防いでいた。当然、今襲ってきている甲賀忍軍の方にも、その役割を負って見守っている者がいるだろうし、こちらも、龍の忍者の戦いを見守る者を、確保するべきなのだ。
しかし――――。
「三郎太、お前は……大丈夫なのか?」
与助は、三郎太の身を案じて問いかけた。三郎太は、先程まで自ら命を絶たんばかりの勢いで、落ち込んでいた。だから――――早まって、自ら死を選ぶような行動をしたりはしないだろうか?
「リュウさんの戦いを邪魔するような腕なんて、俺には無いよ」
案じるようにこちらを見つめてくる与助に対して、苦笑しながら三郎太はそう返す。
「安心しろ。見守る者の役割ぐらい心得ているさ…。リュウさんがどっちの方に進んで、どこで戦っているか分かる様に、目印を残しておくから―――」
そこまで言うと、三郎太は、ぐっと与助の肩を掴んだ。
「だから与助―――行ってくれ! リュウさんを守るために……!」
「分かった。三郎太……!」
三郎太の言葉に、与助は力強く頷く。死ぬなよ、と、三郎太に声をかけてから、与助が走りだそうとした瞬間。
「『龍の忍者』がいたぞぉォォォ――――ッ!!」
甲賀忍者の叫びが、辺りに響き渡っていた。
(リュウさん――――!!)
与助は、弾かれたように走り出した。
甲賀忍者の叫び声を聞きながら――――ハヤブサの心は、凪いだ海のように静かだった。
少し前まで感じていた『死』への恐怖も、この世に対する未練や執着も―――綺麗さっぱり無くなっている、己の心を自覚する。
(きっと、シュバルツに、触れる事が出来たからだ)
シュバルツの髪。瞳。唇。肌。涙。嬌声。乱れた姿。そして、熱く蠢く内部――――。
シュバルツは、総てを俺に赦してくれた。そして俺は――――その総てに触れる事が、出来たのだ。
分かる。
今死ねたら、きっと、俺は。
彼にとっての――――『特別』になれるだろう。
「とにかく、無茶をするなハヤブサ……。毒が抜け切るまでは、安静にして―――」
抱きついた自分を抱きしめ返して、髪を撫でながら案じる様に―――そう言ってくれたシュバルツの姿を思い出す。
あれだけでいい。
あれだけで――――充分俺は、
『幸せ』だ――――。
(―――――ッ!)
クラリ、と、一瞬立ちくらみを感じたが、すぐに頭を振ってそれを打ち払う。
十重、二重に、自分が囲まれている気配を、ハヤブサは察知する。
(それでいい)
ハヤブサは思った。
甲賀忍軍の注意が自分に向けば向くほど――――里の人たちの避難はしやすくなるし、生き延びる確率も高くなる。シュバルツは……あいつの事だ。動けるようになったら、すぐに里の人たちの避難を、手伝っているに違いない。あいつならば、きっと――――里の人たちを、守り抜いて、くれるだろう。
「……『龍の忍者』だな?」
「如何にも」
問うてくる甲賀忍者に、ハヤブサは無造作に応える。
「お命頂戴――――」
ギラリ、と光を放つ刀が、ハヤブサを取り囲んで行く。
ただでは死なない。なるべく長く時間を稼いで――――一人でも二人でも、巻き添えにしながら、死んでやる。
「いざ、参る」
龍の忍者は、改めて刀を構えなおすと、甲賀忍軍に向かって、その足をゆっくりと進めて行った。
喜助は、ただ驚いていた。
シュバルツの戦いに。その強さに。
甲賀忍軍を相手にこの人は―――一人で、互角以上の戦いをしている。
だがそれは、彼の『蛮勇』を誇る物ではない―――と、喜助は思った。
彼の動きは、「闘い」を熟知している事を現していた。
この集団は、誰を倒せば、どこを崩せば――――その統制が、乱れるか。彼は闘いながらそれを見抜き、効率よく敵を倒している。時に、地の利を生かし、時にこちらと連携しながら行われて行くその戦いは、まさに、この戦場を支配していると言ってもいい。
(さすが―――! リュウさんが、認めただけの事はある……!)
喜助はいつしか、畏怖と尊敬の眼差しを持って、シュバルツの後ろ姿を見ていた。
その戦場に、意外な人物たちが走り込んでくる。
「シュバルツさん!!」
「颯太!? 小六(ころく)!?」
二人の姿を認めたシュバルツが、驚いた様な声を上げた。この二人は先程―――子供たちを連れて、長老の家に向かったはずであったから。
「何故ここに!? 子供たちはどうした!?」
シュバルツの問いかけに、颯太が笑顔を見せる。
「大丈夫です! ちゃんと、長老の家に、送り届けてきました!」
「そうか……。なら何故、またわざわざここに戻ってきたんだ? そのまま向こうの守りについていれば――――!」
「俺たちも、そうしたかったんだけどな。シュバルツさん」
そう言いながら、小六が少し、苦笑ったような笑顔になる。
「皆が―――待っているんだ」
「待つ……? 何を……?」
「シュバルツさん。貴方を―――」
「な――――!」
シュバルツは思わず、息を飲んだ。
隼の里の長老の家は、いざという時にそこに籠城する事が出来るよう、ちょっとした『城』の様な作りになっている。周りには深い空堀が掘られ、ねずみ返しの様になっている石垣が、侵入者を防ぐ。背後は断崖絶壁に阻まれ、唯一、正面の出入り口前にある跳ね橋を上げてしまえば――――長老の家は、難攻不落の要塞へと、変貌を遂げるのだ。
颯太たちが子供たちを連れて、長老の家に駆け込んだのを確認した見張り番は、「これ以上跳ね橋をかけ続けておく事は危険だ」と、判断して、橋を上げようとした。
だが。
「待って下せぇ!」
懇願する様な声にが飛んで来て、門番は動きを止める。ふりかえると、そこには与助の祖母ミツが立っていた。
「申し訳ないが、門を閉めるのはもう少し待ってはくださらんか……? まだ、来てない者がおるのじゃ」
「え……?」
「あの若者が来ておらぬ……。あの、私を助けてくれた、あの若者が……」
「………!」
「そうだよ。まだ、おっちゃんが来てない」
その後ろに控えていた子供たちが、声を上げる。
「こらッ! お前たち―――。奥に行っていろと言っただろうが!!」
それを見咎めた門番の男が語気を強めたが、子供たちは首を振るばかりだ。
「ヤダ! ここで待ってる!!」
「ここを閉めちゃったら、おっちゃんが入ってこれないじゃない!!」
「おっちゃんは、ぼくたちを助けてくれたんだぞ!」
「だから待ってる!! 待ってるんだ!!」
「馬鹿者!! 助けてもらったのなら、尚更奥へ―――!!」
門番の男は子供たちを怒鳴るが、子供たちはこちらをじっと見つめ返して、その場を動こうとしなかった。
「……そう言えば、俺の女房も、あの人に助けてもらったんだ……」
横で銃を持って待機していた男が、ポツリと呟く。それがきっかけとなったかのように、そこに待機していた男たちから、次々と声が上がる。
「俺の、おふくろも……」
「ワシの、女房も……」
「源さんとこの子供も、助けられてなかったか……?」
「俺も、危うい所を、助けてもらった………」
そう言いながら、そこにいる男たちの目が、一斉に門番の方に向く。
「――――ッ!」
周りから異様なプレッシャーをかけられた格好になった門番は、しばらく頭をかきむしる様にしていたが、やがて、観念したかのように叫んだ。
「ああもう! 分かったよ!! 跳ね橋を上げるのは、もう少し待ってやるよ!! それでいいんだろう!?」
門番の男のその言葉に、周りの人間が一斉に笑顔になる。皆が口々に、「よかった、よかった」と、いいあった。
「但し――――危険だと感じたら、すぐに門を閉めるからな? それだけは承知しておいてくれよ。それが俺の『役目』だから……」
その言葉に、皆が頷いた。
「そんな……! 何故――――!」
茫然と呟くシュバルツに、小六が苦笑する。
「『何故』じゃないよ。シュバルツさん」
「そうだよ。貴方は一体、今までに何人の『命』を助けたと思っているんだ?」
颯太があっけらかんと話に加わってくる。
「わ……私は、当たり前の事を、しただけだ……。『助けられるから助けた』だけだ―――」
誰に何と言われようと『命』は尊いものだと思う。
だから、助けた。ただ、それだけの事なのに。
「『助ける』ことが当たり前なら、『助けられたことに感謝する』ことも、当たり前だろ? シュバルツさん」
動きが止まってしまったシュバルツを守る様に、颯太は太刀をふるいながら言った。
「――――!」
「皆、貴方に礼を言いたくて仕方が無いんだよ」
小六も同じように太刀をふるいながら、話を続ける。
「だから俺たち――――話し合って」
「3人でな」
今まで黙っていた喜助も、口を開く。
「決めたんだ。俺たちは、貴方を手伝うために動こうって――――」
「……………!」
「と、言っても、俺たちはリュウさんほどの腕は無い。だから、貴方を『守る』とまではいかないけれど……『手伝う』ぐらいなら、出来ると思うよ」
颯太が嬉しそうに笑いながら、そう言った。
「皆………」
シュバルツは、ただ茫然とするしかなかった。
『守りたい』『手伝う』『待つ』―――皆、その人たちの『好意』から出ている言葉なのだと分かる。優しい人たちなのだと思った。
嬉しい――――と、同時にシュバルツは思う。
いいのだろうか?
『命』の無い自分のために、『命』のある人たちを、危険に晒してしまって、いいのだろうか?
何か、恐ろしい事を―――自分は、ここの人たちにさせてしまっているのではないだろうか。
「シュバルツさん!!」
喜助の叫び声に、シュバルツははっと我に返る。自分に向かって振るわれてきた相手の刀を、すぐ後ろで喜助が受け止めていた。
―――しまった! 戦いの最中……!
シュバルツは、ブン! と、雑念を振り払う様に、頭を振る。
今は、余計な事を考えるな。
この人たちは、本当に命をかけて、自分の側にいるのだ。だから、自分も応えなければならない。その想いに。
守りたいと、願った。
ここにいる人たちは、何が何でも守って見せる。
例え、どんな事をしようとも。
「済まない、助かった」
そう言いながら、シュバルツも戦いに復帰する。
(どうする?)
シュバルツは戦いながら、状況を整理した。ハヤブサがどこにいるかは不明だが、里の人たちは、ほぼ長老の家に避難を終えている。そして―――自分が長老の家に行くのを、待ってくれている状態だ。
(やはり、隙を見て長老の家に向かうべきか?)
今一緒にいる3人を守ることだけを考えるのならば、そうするのが一番ベストなのだろうと、シュバルツは思った。3人と共に長老の家に走り込んで、跳ね橋が上がる寸前に、自分は踵を返して家から脱出すればいい。自分一人だけなら、本当にどうとでもなるのだから。
ただ―――ハヤブサが……。
シュバルツは、ハヤブサの事を思う。自分を抱いた後、ハヤブサは明らかに熱が出て来ていた。唾液に含まれている毒の成分の割合も、再び増えて来ていた。そして、この忍者隊は、明らかにハヤブサを狙っている――――。
普通の状態のハヤブサならば、それでも心配はないだろう。
だが今、毒の症状がぶり返してきてしまっているハヤブサでは―――。
ドォン!!
不意に上がる火薬の炸裂音に、全員の意識がそちらに向く。
それは、ここから少し離れた里のはずれで、火柱が上がっていた。
「な、何だ?」
「どうした?」
息を飲む皆の前で、また、ドォン!! と、音を立てて火柱が上がる。
(ハヤブサ……!)
シュバルツには分かった。あそこで、ハヤブサが戦っているのだと。それと同時に、ここで戦っていた忍者隊の半数近くが、火柱の上がった方へと踵を返して行く。ハヤブサとの戦いへ、加担しに行くのだとシュバルツは悟った。
(どうする?)
もう一度、シュバルツは自問自答する。皆を長老の家へと誘導するのなら、今がチャンスだが――――。
その時、脇の茂みがガサガサと音を立てて怪しく揺れる。そこから、黒い影が飛び出してきた。
「―――!」
「シュバルツさんっ!!」
影からシュバルツを守る様に、喜助と颯太が影とシュバルツの間に割って入る。だが、影の正体を悟った瞬間、二人は驚いた様な声を上げた。
「与助!?」
「シュバルツさん!? 皆――――!!」
与助はかぶっていた覆面を脱いで、皆の所に駆け寄ってきた。
「お前、無事だったのか!? 心配したぞ…!」
喜助が心配そうに声をかける。与助は喜助の目の前で、祖母の身を案じて揚句のはてに暴走していた。下手をしたら斬り死にしていてもおかしくは無かったのだから…。
「多分、私が死ななかったのは、リュウさんのおかげです……」
そう言いながら与助は、己が暴走していた時の、微かに残る記憶を必死に手繰り寄せる。自分が無我夢中で敵を斬りまくっている間―――ずっと耳の端に、ハヤブサが自分を追いかけて来てくれている声を聞いていた気がする。
おそらく、守っていてくれたのだろう、と、思う。
「おい与助。お前の婆さんは無事だぞ」
「えっ………!」
颯太からかけられた思いがけない言葉に、与助は思わず顔を上げた。
「本当だ。そこにいるシュバルツさんが、助けてくれたんだ」
「…………!」
与助と視線があったシュバルツの面に、少し困ったような笑みが浮かぶ。
(本当に――――リュウさんの言ったとおりだ……!)
あの、燃え盛る炎に向かって、全く躊躇わずに飛び込んで行った、シュバルツの姿を思い出す。あれだけの状況で、本当にこの人は、祖母を助けだせるという確信が、持てていたのか―――。
炎の中を突っ切ってきた割に、シュバルツの顔には傷一つついていなくて、綺麗だと思った。だが―――彼の着ている服の方が、あちこち焼け焦げ、擦り切れ、破れ――――もう、ボロボロだった。
―――あいつは、自分の身を顧みない、めちゃくちゃな奴だ。
ハヤブサはシュバルツの事を、そう評していた。「その通りだ」と、与助は思った。どこをどう走りまわれば、そんなに服をぼろぼろにしてしまう事が出来ると言うのだろう。
「それよりも与助―――ハヤブサは?」
「……あっ…!」
与助はシュバルツにそう声を掛けられて―――ようやくここに来た最初の目的を思い出していた。
「シュバルツさん……! お願いします!! リュウさんを―――!」
与助は必死に言葉を紡いだ。
「リュウさんを……助けてください!!」
「リュウさんがどうかしたのか!?」
小六が敵と戦いながら、与助に問いかけてくる。
「リュウさん―――高熱があるんです。それなのに、独りで戦いに赴いてしまって……!」
「な………!」
与助の言葉に全員が息を飲み、シュバルツは唇を噛みしめた。
(ハヤブサ……! やはり―――)
おそらく、毒の症状がぶり返してきてしまっているのだろうことが、容易に想像がつく。まだ身体がきちんと治ってもいないのに、無理に私なんかを抱いたりしたから―――。
どうすればよかったのか。
抱かれる事を、何としても拒むべきだったのか。
『帰る』などと、不用意に言うべきではなかったのか。
きちんと治癒するまで、黙って傍に、いるべきだったのか―――?
こんな事、今更考えても仕方が無い事だとシュバルツは分かっている。だが―――どうしても思わずにはいられなかった。『ハヤブサの熱は、自分のせい』ではないのだろうか、と……。
「早くリュウさんの所に向かった方がいいんじゃないのか!?」
敵との間合いを取りながら、颯太がシュバルツ達の側に寄ってくる。
「そうだな……だがまず、ここにいる連中を何とかしないと――――」
小六の意見に皆が頷く。半数近くの者が、ハヤブサの方に向かったとはいえ―――ここにはまだそれなりの数の忍者隊が残っていた。これらの者が無傷で長老の家に向かわれてしまっては、せっかく逃げた里の者たちの安全も保障できない。まして長老の家へと続く跳ね橋が、まだかけられっぱなしの状態だ。
(やむを得んか……)
シュバルツは拳を握りしめた。仕掛けている『策』を、実行するべき時だと悟る。
「皆、走れ!! 私について来い!!」
「!!」
シュバルツの叫び声に弾かれた様に、皆が一斉に走り出す。
「逃げるか!? 待てっ!!」
忍者隊も間髪いれずに後を追いだした。しばらくそうして走っていたシュバルツであったが、不意に踵を返して立ち止まる。
「……追って来たな? あの場に留まっていれば良いものを……!」
そう言って、静かな殺気を迸らせながらシュバルツがこちらを見てくるから、忍者たちの足が止まってしまう。
(何だ……?)
一人の忍者がシュバルツのそんな姿を見つめて――――そして、気づく。シュバルツの足元に、黒い粉が撒(ま)かれているのを。そしてその粉が、自分達の足元に点々と続いていると言う事に。そしてここは、四方を家に囲まれた狭い路地――――!
(しまった!! 火計―――!!)
そう悟った時には、もう遅かった。シュバルツが持っていた刀の鞘でドンッ、と、地面を叩くと、彼の足元からあっという間に炎がこちらに向かって走ってくる。またたく間に、忍者たちがいる所が、炎の海へと姿を変えた。
「ぎゃああああああっ!!」
シュバルツ達を追ってきた忍者たちが、断末魔の悲鳴を上げながら、炎の海の中で逃げ惑っている。
「す……すごい……!」
あまりにも鮮やかな火計の手並みに、喜助が茫然と呟く。それに対してシュバルツは、苦笑いを浮かべた。
「……済まないが、皆を助けたり戦ったりしている合間に―――仕掛けさせてもらった。出来れば使いたくなかったのだが……な。建物を焼いて、里を傷つける事になるから……」
シュバルツのその言葉に、皆が首を振る。
「『建物』なんか、またいつでも建てられるよ。シュバルツさん」
「そうだよ。今は、皆を守る事の方が重要なんだ」
「だいたい、焼き払った建物の数だけを言うなら、『あいつら』が焼いた方が、はるかに多いんだし」
そう言って皆が、うんうんと頷く。
「……………」
次々とかけられる優しい言葉に、シュバルツは笑みを浮かべる。だが、「ありがとう」と言うには、まだ早すぎると思った。戦いが、まだ終わった訳ではないからだ。
「……これからハヤブサの所に行かねばならないが……申し訳ないが、誰か一人―――長老の家に走ってはくれないか? いつまでも『跳ね橋』をかけたままでは、危険すぎる……」
そう言いながらシュバルツは皆を見渡した。長老の家に向かう甲賀忍者たちを引き留めるために、今までここで戦って来た。しかし、火計で打撃を与えたとはいえ――――ここから自分達が離れざるを得ない以上、長老の家に向かう忍者たちの動きを止める事は、実質不可能になってしまう。だからこそ――――防衛には、万全を期して欲しいと思った。
「……………」
しばらくお互いがお互いを、黙って見つめ合っていた男たちであったが、やがて小六があきらめたように口を開いた。
「……しょうがない。長老の家には俺が行ってこよう」
「小六……」
「ここで里の皆がやられちまったら、元も子もないもんな。説得は難しいかもしれないが、跳ね橋を上げるよう話してくる。……これで、いいんだろう?」
小六の言葉に、シュバルツは頷いた。
「行ってくれるか? 済まない……」
「いいって」
小六は軽く手を振った後、急に真顔になった。
「そう言う訳だから、喜助、颯太……。必ず、シュバルツさんを守ってくれよ。でないと、俺、里の皆に殴られそうだから」
「ああ! 任せとけって!」
颯太が己が胸を叩き、喜助が黙って頷いた。そう言って走り去っていく小六を見ながら、シュバルツも己が心にかかってくる暗雲を、今は無理やり振り払う。
今は――――立ち止まっている場合ではない。
自分は、自分のするべき事を、するだけだ。
この里の人たちを――――守るために。
そして、それをするためには、自分一人の力だけでは駄目だと言う事を、シュバルツは知っていた。
だから、今は借りる。
この人たちの、助けを。
「それじゃあ、与助。ハヤブサの所に案内してくれるか?」
「分かりました。こちらです」
頷いて走り出す与助の後に、皆が続いた。
ドオンッ!!
ハヤブサのすぐ近くで、焙烙玉が爆ぜる。
「ク……ッ!」
かろうじてこれをかわして、飛びのいた所に、二人の忍者に襲われる。一人目の太刀をかわして、続いて襲ってきた忍者の胴を撫で切りにした。返す刀で、もう一人の忍者の首も刎ねる。
「…………ッ」
息が上がり、どうしたって目が回る。だが、足を止める訳にはいかない。止めてしまったら、そこで終わりだ。再び焙烙玉が爆ぜ、炎に紛れて手裏剣が飛んでくる。ハヤブサはそれを刀で弾き返しながら、走った。
「………なかなかやりおるな。龍の忍者……」
ハヤブサから少し離れた小高い丘に、甲賀忍者の頭首である九龍院が陣取っている姿が見える。あいつを倒せば、この勝負は終わり――――。ハヤブサにも、それは分かっている。だが、九龍院に近づく事は、今のハヤブサには不可能に近かった。九龍院の周りには、甲賀忍者たちによって鉄壁の陣が布かれ、ハヤブサが彼に近づく事を拒んでいる。
「……ウッ……!」
時折、激しい眩暈がハヤブサを襲う。そのたびに止まりそうになる足をハヤブサは叱咤し、戦場を駆け続けた。
息が上がる。恐らく、熱もあるのだろう。
だが―――後悔はしていない。
この熱が、この症状が、シュバルツを抱いた故の物であるのならば、後悔など――――するはずもなかった。きっと、あのまま抱かずに『今』を迎えてしまった方が、自分はよっぽど後悔すると分かる。
「しかし、我らが秘伝の『毒』が効いていると見える……。そのように弱った体で、どこまでもつものかな……?」
九龍院のその言葉と共に繰り出される、甲賀忍者たちの嬲るような攻撃。ハヤブサはそれらをかわし、迎え撃ちながら走り続けていた。時間をかけていたぶる様に攻撃をし、身体に毒がまわって倒れた所を仕留める算段なのであろう。
「…………」
ハヤブサは、己に迫りくる『死』の影を、強烈に意識する。
だが、不思議と恐怖は無かった。心は、凪いだ海のように静かだった。
このような世界に生きる自分。天寿を全うして死ねるなどと、最初から思っていない。いずれは、シュバルツとも死に別れなければならないと、分かっている。死ねない身体を持つシュバルツ。まして、『キョウジと共に死ぬ』という呪縛から解き放たれ、永久に生きる可能性が彼にはある以上、どうしたって自分は、シュバルツより先に死ぬのだ。今死んでも、それが早いか遅いかだけの話だ。
想いは伝えた。想いは遂げた。だから―――悔いは無い。
生き延びる事は考えていない。
一人でも二人でも、多く敵を倒したい。
1分でも1秒でも、長く時間を稼ぎたい。
自分の願いは―――もう、それだけだった。
(ただ……奴らが狙っているこの『龍剣』を、素直にくれてやるのはもったいないな……)
ハヤブサはそう感じて苦笑する。
この『龍剣』は、いわくつきの妖刀で、刀がその『使い手』を選ぶ。認められなかった使い手は、刀に命を喰われてしまうが、刀が一度『使い手』と自身が選んだならば、『龍剣』はその絶大なる力を、惜しみなく助力してくれる。
ハヤブサはこれまでにも何度となくこの『龍剣』と共に、死線を乗り越えてきた。手にもなじんだ、ハヤブサにとっては無二の『相棒』だ。もし、自分が死ぬのならば、この刀をどうするべきか考えておかねばならない、とも、思った。
(リュウさん……!)
三郎太は少し離れた所から、ハヤブサの戦いを見ていた。
いつもなら、その圧倒的な力で持って敵をねじ伏せるように倒して行くハヤブサ。だが今、目の前にいるハヤブサの戦いからは、そのような姿が見受けられない。敵を倒しては行ってはいるが、動きも鈍く、力強さも無い。時折足が止まり、肩で息をしているのが分かる。
(…………!)
三郎太は、ぎゅっと、己が手を握りしめる。自分を助けてくれたハヤブサの手は、とても、熱かった。あんな高熱を出しながら、彼はたった一人で戦っているのだ。
(俺のせいだ)
三朗太はどうしてもそう思ってしまう。自分が細工された刀を拾ってしまったばっかりに――――。
でも、この戦いに、自分は手出しをしてはいけないと分かっている。自分は、『見守る役』なのだ。何があっても、今、目の前で行われている戦いの情報を、里の長老に報告する義務を背負っている。ならば自分は、見守るしかないではないか。
しかし………。
ぐら、と、バランスを崩すハヤブサの身体。三朗太は、思わず立ち上がりそうになる。
だがハヤブサは、何とか体勢を立て直し、甲賀忍者たちの攻撃をしのぎ切った。もうこんな事が、先程から何度続けられている事だろう。
(駄目だ…! このままでは……!)
助けたい、と、思う気持ちと、見守らなければ、と言う義務感が、三郎太の中で激しく交錯する。
(与助…! まだか―――!?)
援護を呼びに行った与助の姿を待ちわびる。早くしないと、本当にハヤブサが保たなくなってしまうのが分かる。『ハヤブサの死』を里の長老に報告するのは、まっぴらごめんだ、と、強く思った。
でも、自分なんかがリュウさんの戦いに手を出したとしても――――。
「くぅ……ッ!」
ハヤブサが、あからさまに体勢を崩し、足を止めてしまう。そこに、刀を振り下ろそうとする甲賀忍者の動きが、三郎太にはまるでスローモーションのように、はっきりと見えてしまった。
だから、思わず。
「リュウさんっ!!」
彼は声を上げ、気が付いたら手裏剣を、投げてしまっていた―――。
「何奴!?」
ハヤブサを斬る千載一遇の機会を邪魔された甲賀忍者が、怒気を食んでこちらを見る。
「三郎太!?」
驚きの声を上げるハヤブサの視線の先に、手裏剣を投げた体制のまま、茫然と固まっている三郎太の姿を捉える。
「あ………!」
「……ほう。ネズミが一匹、紛れていたか―――」
九龍院が、面白そうに声を上げた。
「奴を捕らえよ」
頭首の命じる声に、数人の甲賀忍者が三郎太を捕らえるために動き出す。
(しまった――――!)
三朗太は、慌てて踵を返す。とにかく逃げなければと強く思った。「捕らえる」と言う事は、ハヤブサに対して、あるいは、この里の人間たちに対して、自分を何がしかの交渉に利用するつもりなのだと悟る。
冗談じゃない。
三朗太は思う。
ただでさえ、皆を危険に晒す原因を作ってしまった自分なのに―――これ以上、皆の足手まといになってたまるか。
逃げるだけ、逃げる。
そして、捕らえられそうになれば………『自決』する。
そう決意して、三郎太は走っていた。
(三郎太……! 何故だ―――!?)
三朗太の方に向かおうとするハヤブサに、甲賀忍者の刃が向けられる。
「隙あり!!」
「――――ッ!!」
瞬間、白刃が交錯する。ドンッ! と、音を立てて転がった首は――――甲賀忍者の物だった。そのままハヤブサは、刀の露払いすらせずに、三郎太の方へ向かって走り出す。
「面白い。そのまま囲め」
ハヤブサの意図を悟った九龍院が、笑いながら部下たちに命じた。毒によって瀕死の龍の忍者。人質をわざと庇わせながら、いたぶる様にその命を奪うのも一興かと考える。血ぬられた経歴を持つが故に、長く長く苦しませて、のたうちまわらせながらの『死』こそが、きっとこの男にはふさわしいのだろう。そう考える九龍院の面には、いつしか邪悪な笑みが浮かんでいた。
九龍院の意思を正確に読み取った甲賀忍者たちが、ハヤブサの前の道をわざと開けつつ、三郎太を追いたてる。逃げ場をなくして立ちすくんでしまう三郎太の元に―――ついに、ハヤブサが追いついた。
「リュウさん!?」
「何をしている!? 三朗太!! 与助と一緒に避難したのではなかったのか!?」
「すっ、すみません! 俺は――――!」
そう言いながら顔面蒼白になって震える三郎太に、ハヤブサは小さく舌打ちをした。刹那、背後から鋭い殺気を感じる。
ガンッ!!
甲賀忍者から振るわれた白刃を、ハヤブサは真っ向から受け止めた。
「………くっ!」
そのまま刃を力任せに押し返す。
(やはり………!)
九龍院はほくそ笑んだ。龍の忍者は、あのねずみを庇うつもりでいる。
愚か者め。
あのような役立たずなど庇わずに、己の身だけを守っていれば――――。
もっと楽に、死ねたであろうに。
「………殺!」
九龍院の鋭い声に合わせて、甲賀忍者たちが二人を十重二十重と取り囲んで行く。
「リュウさん……!」
心細そうな三郎太の声に、ハヤブサは答えを返さなかった。静かに刀を構え、甲賀忍者たちを見据えている。ただ、その息が―――苦しそうに弾んでいた。
(……三郎太を抱えて、ここから脱出するのは…………無理だな……)
己の体力を鑑みたハヤブサは、そう結論付けざるを得なかった。
「死ねい!!」
叫び声と共に、忍者たちが次々とハヤブサたちを襲う。それをハヤブサは、三郎太を庇いながら懸命に弾き返した。甲賀忍者たちも、一度攻撃を弾き返されたらそれ以上踏み込んでこようとはせず、じわじわと包囲を狭めながら、様子を伺う様にしている。ハヤブサの消耗を待っているのは明らかだった。
(だ、駄目だ……! リュウさん――――!)
三朗太は唇を噛みしめた。このままではハヤブサが死んでしまうと悟る。自分なんかを庇ったせいで……!
もういい。
もういいんだ、リュウさん。
俺は、ここに、いちゃいけない――――。
俺さえいなくなれば。
リュウさんはもっと自由に戦えて、生き延びる事が出来る筈だから……。
すらり、と、音を立てて、三郎太は短刀を抜き放つ。自決の作法に則って、自身の首に、短刀を当てようとした。
だが――――それをする前に、ハヤブサから声をかけられた。
「三郎太……! 立てっ!!」
「リュウさん!?」
「短刀を――――『刀』を手にしたのならば……!」
「ち、違う…! これは―――!!」
「命を簡単に捨てる事など――――俺は絶対に許さない!!」
「…………!」
ハヤブサの思わぬ物言いに、三郎太は思わず息を飲む。
「で、でもリュウさん……! 俺は、里をめちゃめちゃに―――」
「『里』とは『人』だ!! 三朗太……!」
襲い来る甲賀忍者たちの攻撃を弾き返しながら、ハヤブサは叫んでいた。
「『場所』が『里』を作るんじゃない! 『人』が『里』を、作るんだ!!」
「リュ、リュウさ………!」
「俺は! 絶対にお前を見捨てない!!」
三朗太に叫びながらハヤブサは思う。
『人斬り』の自分が、『命』の大切さを説く――――なんて激しい自己矛盾だろう。
おまけに、この状況―――。自身の身を守るのも覚束ないのに、まだ尚且つ三郎太の身を守ろうとしている。出来もしない、幼稚な正義感を振りかざしているのと同じだ。
だが、この局面で、『三郎太を見捨てる』と言う選択肢を、どうしてもハヤブサは選ぶ事が出来なかった。三朗太は『里の人間』だ。そして自分は『里を守護する者』だ。
『守護する者』ならば――――例え一人であっても、里の人間を見捨ててはいけない、と、ハヤブサは思う。一人でも見捨てる選択をしてしまったら、その時点で、自分はもう『里を守護する者』の資格を失ってしまう気がする。
青臭い理論だと思う。
愚かな主張だと思う。
だが、それでも。
それでも俺は――――!
「…………ッ!」
しばらく、震える手で短刀を握りしめていた三郎太であったが、彼はついに顔を上げ――――その刀を振るった。
ドンッ!!
「ギャッ!!」
思わぬところから攻撃を喰らった甲賀忍者が、もんどりを打って倒れる。
「三郎太―――!」
振り返るハヤブサの視線の先で、三朗太が息を荒らげ震えながら、短刀を握りしめていた。彼はふらり、と立ち上がると、短刀から、長刀へと己が獲物を持ちかえる。自決をするためではない。戦うための構えだ。
「それでいい……」
ハヤブサは小さくそう言うと、再び甲賀忍者たちの方へと視線を返した。三朗太が立ちあがってくれたなら――――この絶望的な状況下から、脱出する糸口が見えてくるかもしれない。
「―――――ッ」
襲い来る激しい眩暈。ハヤブサは膝をつきそうになってしまう。
(まだ……! まだ倒れるな……!)
霞む視界の中、挑んでくる甲賀忍者たちの攻撃を懸命に弾き返す。
(三郎太が『生きよう』としているのに……倒れるな!)
自分に強く命じる。歯を食いしばり、顔を上げ続けた。
ああ、でも。
刀が、重い。
重いんだ。
駄目だ、倒れるな。
倒れるな。
倒れ――――。
ドカン!!
不意に甲賀忍軍の真ん中で、派手な炸裂音が響き渡る。それと同時に辺り一面に煙が立ち込めて、あっという間に視界が奪われてしまった。
「て、敵襲―――ッ! 敵襲――――ッ!!」
忍者たちの怒号が響き渡り、戦場は瞬く間に混乱状態に陥ってしまう。あちこちで、誰かが斬られる悲鳴と、怒号が交錯した。何者かが、この忍者団に奇襲をかけてきたのだと悟る。
「リュ、リュウさん!?」
「三郎太…! 側を離れるな……!」
ハヤブサは、咄嗟に三郎太の腕を掴み、身を低くした。こういう時は下手に動かない方がいいと、本能的に判断したのだ。
だが、この煙幕を張る戦法。
まさか。
まさか――――?
「ハヤブサ!!」
ああ。
自分の耳に飛び込んでくる、聞き間違いもしない声。
自分に向かって伸びてくる、白い手袋。
「……シュ、バルツ……」
ハヤブサの中で、張り詰めていた糸が、プツン、と、音を立てて切れてしまう。傾ぐ身体を、彼はもう止める事が出来なかった。意識を失う直前、誰かに抱きとめられた様な気がした。
ああ――――。
シュバルツの、匂いがする。
愛おしいヒトの、匂いが―――――。
「ハヤブサ……! ハヤブサ……!」
ぱしぱしと頬を叩かれる感触を得て、ハヤブサは意識を取り戻した。霞む視界に、シュバルツの心配そうな顔が飛び込んでくる。
「ここは……?」
問うハヤブサに、シュバルツが答える。
「あの戦場から少し離れた所にある廃屋だ。だが、あまりゆっくりしている時間は無い。お前の姿を求めている甲賀忍軍が、何をしだすか分からん……」
「そうか……。ウッ……!」
「ハヤブサ!? 無理に起きようとするな!」
身を起こそうとするのをシュバルツに押しとどめられる。シュバルツの肩越しに、三郎太や与助が、心配そうにこちらを覗き込んでいる姿が見えた。
「しかし……! 俺が、行かないと……!」
「そんな高い熱で―――無茶だ!」
「……『お前』に言われたく……ない……」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツから視線を逸らす。
無茶苦茶なのはどっちだ。
そのボロボロになっているロングコートは、何だ。
ハヤブサはそう、シュバルツに毒づきたかった。
どうせこいつは、そのボロボロになったコートの傷の分だけ、怪我を負いまくっているに決まっている。なのに治ってしまうから――――平気な顔を、しているだけだ。
「とにかく私に考えがあるから……。お前は、薬を飲んでゆっくり休め」
「こんな時に――――休んでなどいられるか……!」
そう言ってハヤブサは、シュバルツから出される薬を拒絶して、また身体を起こそうとしている。
(仕方が無いな……)
シュバルツはため息をついた。
出来ればこのような手段、とりたくはなかったが……。
「ハヤブサ……」
シュバルツの静かに呼びかける声に、ハヤブサが反応する。
「何だ―――うむッ!?」
ハヤブサは次の瞬間、くぐもった声を上げていた。何故なら。ハヤブサの唇が、シュバルツの唇によって塞がれてしまっていたから――――。
ハヤブサの口腔に、シュバルツの舌が侵入してくる。それと同時に、何か液体の様な物も。
「……ウ……んぅ……ッ!」
(薬―――!? しまった……!)
「……ふ……っ」
思わず、シュバルツに縋りつくような格好になるハヤブサ。これでは、飲みたくない、と思っていても、強制的に口に流し込まれるから、薬を飲まざるを得なくなってしまう。
シュバルツを振り払わなければ、と、ハヤブサも頭では分かっている。
だが、ハヤブサはそれをする事が出来なかった。
愛おしい―――シュバルツからの口付けを、ハヤブサが拒否できるはずもない。
「……………」
ハヤブサの喉が、『ごくっ』と、音を立てて上下するのを確認してから、シュバルツはハヤブサを解放した。
「……ッ! シュ、バルツ……! お前………ッ!」
薬が強制的に睡眠へと誘おうとするのを、ハヤブサは懸命に抗おうとした。
「……ドクター・ストップだ。ハヤブサ……。とにかく、今は休め」
「…………ッ」
ハヤブサの体勢が崩れるのを、シュバルツが支える。ハヤブサの身体を静かに床に横たえてから、シュバルツは立ちあがった。
ふと見ると、与助以下側にいた男4人が、全員回れ右をして懸命に、明後日の方向に視線を泳がせようと努力している。
「……済まなかったな。変なものを見せて―――」
シュバルツが苦笑いながら詫びを入れると、与助以下全員が、一斉に首を横に振った。
「い、いえッ! 別に……ッ!」
「わ、我々は何も見てませんッ!」
「いや~! 何だか今日は、暑いなぁ~。なぁ! 三朗太!」
「お、俺に振るなよ……!」
颯太からいきなり話を振られて、三郎太が心底困った様な声を上げる。場の空気が少し、和やかな物になった。
「……じゃあ済まないが、そのまま後ろを向いててくれないか? 少し着替えたいから―――」
そう言ってシュバルツが懐からある物を取り出す。それを見たハヤブサが、息を飲んだ。
「シュバ、ルツ……! それは……俺、の………!」
「そう。お前の服一式だ。悪いが、ちょっと拝借させてもらった。済まないな……。手くせが悪くて――――」
言いながらシュバルツが、いたずらっぽい笑みを浮かべる。そのまま彼は手早く着替えを始めて――――あっという間に『龍の忍者』の姿になった。
「どうだ…? 『お前』に、見えるか……?」
シュバルツは、自身の顔までもをハヤブサの物に換えてから、覆面を装着していた。どこからどう見ても『自分』にしか見えないその姿に、ハヤブサは絶句してしまう。
「――――ッ!」
駄目だ。シュバルツ。
駄目だ―――!
ハヤブサは懸命に身を起こそうとする。だが、それをする事は叶わず、重い頭が僅かに持ちあがっただけだった。
何故、そんな事をする。
何故、そんな事をするのだ。
止めないと。
シュバルツを、止めないと―――!
「与助…。確認したい事があるのだが……」
「はい! ……えっ? リュウさん!?」
シュバルツから声をかけられた、と、思って振り向いた与助の目が、点になる。
「え…っ? あれ?? リュウさんは、あそこで寝て―――??」
「『私』だよ。与助」
そう言ってシュバルツは、一瞬ハヤブサの顔のマスクをはいで、自分の素顔を与助に見せてから、にっこりとほほ笑む。
「シュ、シュバルツさん!?」
「フフ」
シュバルツが再びハヤブサの顔のマスクを戻すと、それはもうどこからどう見ても『リュウ・ハヤブサ』の姿にしか見えなくなった。茫然とする与助に、シュバルツは再び声をかける。
「確認したいのだが―――甲賀忍軍が狙って来ているのは、『ハヤブサの命』と『龍剣』で間違いないのだな?」
「え、ええ……。昔からあの人たちは『龍剣』を狙っていて――――『龍剣』を自分達の物にするためには、剣に選ばれた使い手が邪魔になりますから……」
与助は、里の長老から伝え聞いている話をそのままシュバルツに伝える。龍剣は、刀でありながら己が意志を明確に持つ『妖刀』だ。剣が『使い手』となる人間を選ばなければ、決してその力を人間に貸す事は無い。それどころか、不用意に手にした者の命を奪う事もある。
今、龍剣に使い手として選ばれているのはハヤブサだ。それ故に、ハヤブサの存命中は、龍剣はハヤブサ以外が扱う事が実質不可能な剣となっている。
「そうか……」
ハヤブサの姿になっているシュバルツはにっこり微笑むと、ハヤブサの方に振り返った。
「と、いう訳だからハヤブサ―――『龍剣』を借りるぞ」
「ま……! 待て……っ! この刀は……!」
ハヤブサはシュバルツに剣を取られまいと、抵抗しようとした。だが、薬の作用と熱のせいで思うように身体が動かないハヤブサに、何が出来たと言うのだろう。『龍剣』は、あっさりシュバルツの手に渡ってしまった。
「シュバルツ……! その刀は……っ!」
シュバルツを止めたくて、ハヤブサは懸命に声を張り上げる。しかしシュバルツからは、笑みが返ってくるばかりであった。
「分かっている。『妖刀』だろう? 決して使ったりはしないさ」
「……ちが……シュバルツ……ッ!」
「心配せずとも――――『刀』を敵に奪われる様な、へまはしないさ」
「…………ッ!」
「シュバルツさん、その刀……扱えるんですか?」
喜助が、恐る恐ると言ったふうに聞いてくる。
「『一太刀』だけだがな」
そう。以前シュバルツは、龍剣を偶然手にして、振るった事がある。『一太刀』だけ、龍剣はその力を貸してくれた。『一太刀』―――シュバルツは、それで充分だと思う。問題は、『どこで振るうか』―――ただ、それだけだった。
「だから済まないが……誰か『得物』を貸してはくれないか? 流石に甲賀忍軍の前に丸腰に近い状態で出て行くのはきついからな」
奴らから武器を奪ってもいいのだが、と、冗談めかして笑うシュバルツの前に、与助が進み出た。
「じゃあ、シュバルツさん。この刀を使ってください」
「お、おい! その刀は……!」
思わず声を上げる三郎太に、与助は微笑みかけてから、言った。
「いいだろう? 三朗太。この刀を『里を守るため』に使っても……」
「与助……!」
「私は信じています。シュバルツさん、この刀が、きっと貴方を守ってくれると――――」
「……………」
シュバルツはそんな二人の様子をじっと黙って見つめていたが、やがて微笑んだ。何か事情があるようだが、この刀を自分が使う方が、二人のためにはきっといい事なのだろうと察せられた。だから。
「ありがとう……」
シュバルツはその刀を、受け取った。
「じゃあ、私はもう行く。お前たちは……ハヤブサを頼む」
「シュバルツさん! 俺たちも―――!」
そう言って喜助と颯太が後をついて行こうとするのを、シュバルツは手で制した。
「『龍の忍者』は、独りで戦う者だろう?」
その言葉を残して、シュバルツは出て行った。
「シュバルツさん……」
去っていくシュバルツの後ろ姿を喜助たちは黙って見送るしかなかった。その後ろで、いきなりダン!! と、大きな音がする。二人が驚いて後ろを振り返ると、ハヤブサが無理やりその身を起こそうとしている。
「くそっ! 馬鹿野郎が……ッ!」
「リュ、リュウさん!? 駄目ですよ!! 寝ていないと……!」
与助がハヤブサを押しとどめようとするのを、ハヤブサは拒絶した。
「……馬鹿野郎が!」
叫びながらハヤブサは、もう一度床に拳を叩きつける。ダン!! と、派手な音が響き渡った。
何故、そんな事をする。
何故、そんな事をするのだ。
俺の代わりに『死地』へ赴くなどと――――!
駄目だシュバルツ。
駄目だ――――。
お前の『愛情』は大き過ぎる。
そして深すぎる。
勘違い、してしまいそうになるではないか。
俺を『守る』ために出て行ったお前を見てしまうと。
もしかしたらお前も、俺と同じ気持ちなのではないかと。
もしかしたらお前も、俺の事を『好いて』いてくれているのではないかと――――。
そんなはずはない。
そんなはずは、無いんだ。
あいつが誰かの『想い』に『特別』に応えるなんて、そんな事は――――。
あり得ない。
あいつの身体が、それを許さない。
「くそっ!!」
ハヤブサの拳が、また床を叩く。その横で、きちんと折りたたまれて置かれているボロボロのロングコートが、僅かに跳ねた。
「くそっ! ふざけるな……!」
常に誰かのために傷を作るから、ボロボロになっているはずのお前。躊躇なく、その身を投げ出してしまうお前。だから、せめて俺だけは。俺だけは、お前の事を守りたいと――――思っていたのに……!
この様は、何だ。
熱と毒でろくに動く事も出来ない、この様は。
「リュウさん……」
身を起こそうと足掻いているハヤブサを前に、与助はただ佇むしか出来なかった。
この状況。
自分は一体、どう動くべきなのだろうか。
リュウさんとシュバルツさんのために、自分は一体どう動けば――――。
「与助! 喜助! 颯太!」
「はい!」
不意にハヤブサに名前を呼ばれた男たちが反応する。彼らがハヤブサの側に駆け寄ると、ハヤブサがもっと近くに寄れ、と、手で合図をしてきた。
「お前たちに……頼みたい事がある……! 耳を貸せ!」
3人が、言われたとおりにハヤブサの側に頭を寄せる。その3人に向かって、ハヤブサが小さな声で何事かを託(ことづ)けた。
「リュウさん? 俺は、何を……」
ハヤブサに名前を呼ばれなかった三朗太が声を上げると、ハヤブサは彼に目線を走らせながら言った。
「三郎太―――。お前は、俺を守れ……!」
「えっ……?」
「残念ながら……俺は今、ろくに動く事も出来ん。俺の得物である『龍剣』も、あの馬鹿に捕られたままだし―――」
「あ………!」
「だからお前には……俺の『守護』と、この戦いの『見届け役』を命じる……。出来るな?」
「は、はい!!」
ハヤブサにまっすぐ見つめられた青年は即答する。それを見たハヤブサは、頷いた。
「この刀を使え、三郎太」
そう言いながら颯太が、自身の予備の刀を三朗太に差し出す。
「お前の刀も、シュバルツさんが持って行っているんだろう? だから、これを。二人ともが丸腰だと、具合が悪いもんなぁ」
そう言いながら軽く笑う颯太に、三郎太も笑みを浮かべた。
「では、お前たち……。頼んだぞ……!」
ハヤブサの言葉に、三人の若者は力強く頷く。
「任せてください、リュウさん」
「任務、確かに遂行いたします」
「よしっ! 一丁やるか!!」
「では行け! 隼の里の忍者の力――――奴らに見せつけてやれ!!」
「ははっ!」
ハヤブサのその言葉が合図であるかのように、忍び装束に身を包んだ男たちが一斉にその場から姿を消した。
「―――――っ」
それを見届けたハヤブサの体勢が、ガクっと崩折れる。
「リュウさんっ!!」
三朗太が慌ててハヤブサを支えた。三朗太の腕の中で、ハヤブサが身じろぐ。
「俺は……寝ない……!」
そう言うハヤブサの左手から、ポタっと血が流れ落ちる。彼はクナイの刃の部分を、きつく左手で握りしめていた。―――眠りに落ちないようにするために。
「リュ、リュウさん……! 左手が……!」
「……寝て……たまるか……っ!」
「リュウさん………」
三朗太は、クナイを握りしめたハヤブサの左手から血が流れ落ちるのを、黙って見ていることしか出来なかった。
廃屋から出て行ったシュバルツは、甲賀忍軍の前に姿を現した。
一人で。「真正面」から。
「出てきたな! 龍の忍者……!」
九龍院の声と同時に、甲賀忍軍が彼の周りを取り囲む。
「……………」
シュバルツは、無言で刀を鞘ばしらせる。鋭い殺気を身に纏わせながら、ゆっくりと足を進めた。
(ここからが勝負だ)
シュバルツは思った。外見は、いくらでも似せる事は出来る。声も、ほぼ一緒だから問題ない。問題は――――その『戦い方』だった。
「死ねぇッ!!」
殺気に当てられたように、忍者の一人が襲いかかってくる。
「!」
シュバルツはそれを逆袈裟斬りに一刀両断にした。刀すら合わせずに。
「おのれッ!」
斬りかかってきたもう一人の首を、容赦なく刎ねる。血飛沫が飛び散り、ゆっくりと歩くシュバルツの足元に、ドン、と音を立てて首が転がった。
「…………」
そのままゆっくり歩を進める。
足を止める事は、しない。
姿を消す事も、しない。
自分は『龍の忍者』
敵方に―――そう、信じこまさねば、ならないのだから。
「リュウ・ハヤブサ……」
突如として、目の前に現れたハヤブサの格好をした者に、九龍院は値踏みをするような眼差しを向ける。
(おかしい。奴は、『本物』か?)
先程まで戦っていた『龍の忍者』は、こちらの『毒』によって息も絶え絶え。最早立っているのもやっとという様相であったのに。目の前にいる『ハヤブサ』と思われる人間からは、そのような気配が感じられないのは何故だ。
(見極めなければ)
九龍院は思った。もしこの男が『影武者』であるのならば、せっかくあそこまで追いつめていたハヤブサを、みすみす逃がしてしまう事になる。そのような見え透いた策に、こちらが引っ掛かる訳にはいかない。
シュバルツは、ただ九龍院を見つめる。
『龍剣』と『龍の忍者』の命を狙っている首領。この戦い、あの男の首を取ればおそらく終わりだ。
ならば、自分は『まっすぐ』そこに行くだけだ。
『ハヤブサ』ならば―――きっと、そうする。
「うおおおおっ!」
かかってくる甲賀忍者たちを、シュバルツはあえて一刀両断にする。
斬る事を躊躇わない。命を奪ってしまう事――――容赦はしない。
ハヤブサの戦い方は苛烈にして峻烈。圧倒的『力』を以って戦場をねじ伏せる。スピードを得意とする自分の戦い方とは、全く違うものだ。そのような戦い方、自分はむしろ苦手だと言っていい。
出来れば、斬りたくはない。命を奪うのは、最小限度で押しとどめたい。
だが、ハヤブサは、絶対にそのような事は言わない。
ただ眼差しで威圧し、周囲に問う。
“お前はここで、死にたいか?”
“挑んでくるのならば、容赦はしない”
『気合』と『想い』を刀に乗せて、振り下ろす。
命を奪う相手を
せめて、苦しませぬ、ように。
龍の忍者の衣装が、甲賀忍者たちの血で朱に染まっていく。その中をシュバルツは、ただ歩を進めた。
(さすがに、隼流忍術は使えないから……違和感は拭えないだろうが……な)
そう感じてシュバルツは苦笑する。アンドロイドである自分は、人間が独特に放つ『気』を使った技を駆使する事は出来ない。そこが自分の限界でもあり、『健全な魂は、健全な肉体にこそ宿る』とは、よく言ったものだと思う。
だが、たった一つだけ。ハヤブサが使えて、自分も使える技がある。
それは――――。
ハヤブサの姿をしたシュバルツが、甲賀忍者の一人を高々と撥ね上げる。その後に続いてシュバルツは飛び上がった。
「ハ―――――ッ!!」
空中でその忍者を捕まえたシュバルツは、高速で回転しながら綺麗な放物線を描いて、その忍者を地面にたたきつけた。その衝撃で、周りにいた忍者たちが吹っ飛ばされて行く。
「飯綱落し―――!」
それを見た九龍院は息を飲んだ。あの技は―――確かに、『龍の忍者』にしか使えない、彼の代名詞と言ってもいい大技だ。
(たかが『影武者』に、この技が使えるのか?)
九龍院は思わず首を捻る。
無理だ。
あの技は―――『龍の忍者』にしか、使えないはずだ。
(やはり、奴は『リュウ・ハヤブサ』なのか……!?)
違和感が拭えないのが気になる。しかし、あの強さと動き……『リュウ・ハヤブサ』の物でなければ何者だと言うのだろう。
そして何より、背中の剣――――。
あれは『龍剣』だ。
「『滅』の陣!!」
九龍院は叫んだ。それは、今こちらに歩を進めている人物が、ハヤブサであると断定したが故の物だ。
「……影武者の可能性は?」
問いかけてくる傍らの忍者に、九龍院はポツリと返す。
「確かに、違和感は拭えん…。しかし、奴は『飯綱落し』をして見せた。背に背負っている物も、紛う事なき『龍剣』だ」
「……………!」
「『毒』の反応が見えないのも……奴を助けた仲間が、何らかの『術』をかけてその症状を押さえているのかもしれん。そのせいで、動きに少し違和感が出ている可能性もある」
「確かに……」
忍者は、いろいろな『術』に長けるものだ。隼の里に、自分達が知り得ない『毒消しの術』があってもおかしくは無い。
「奴を仕留める事に、全力を上げよ」
「はっ!!」
九龍院の言葉に、甲賀忍軍が動き始めた。
(かかった……!)
甲賀忍軍の動きにシュバルツは確信する。自分は「龍の忍者」だと、敵に信じさせる事に成功したのだと。
さあ、ここからだ。
どこまで自分は、『ハヤブサ』として戦えるか。
どこまで時間を稼げるか……!
(勝負―――!!)
前後から、二人の忍者が襲いかかってくる。前の忍者を撫で切りにし、返す刀で後ろの忍者を突きさした。シュウッ! と、音を立てて飛んできた手裏剣を、その忍者を盾にしてかわす。
「いやぁぁぁぁ!!」
斬りかかってきた忍者に向かって、串刺しにしていた忍者の身体を足で蹴飛ばして、刀を抜くと同時にそれをぶつけた。ぶつけられた忍者が吹っ飛ばされる。
間髪入れず手裏剣が飛んでくる。シュバルツはそれを、刀で弾き飛ばす。
「ムッ!」
焙烙玉が飛んでくる。シュバルツは躊躇うことなく猛然とダッシュした。前へ。ひたすら前へと。
「なっ! な……!」
信じられないスピードで距離を詰められた忍者が戸惑っている間にそれを斬り伏せる。それと同時にその影から3人の忍者が刀をこちらに向けながら突進してきた。
(懐に焙烙玉……! 自爆―――!!)
瞬時に判断したシュバルツは、その場よりノーステップで跳躍する。その瞬間、シュバルツの真下でガキッ! と、音を立てて3人の刃が交錯した。青白い火花が散り、刹那、そこが大爆発を起こす。
「いやああああああああっ!!」
高く飛びあがったシュバルツは、大上段に刀を振りかぶりながら重力に引かれるままに降りてきた。
ドカッ!!
一人の忍者が真っ向から唐竹割にされ、血飛沫を上げる。二つに裂かれた身体がドォッ、と音を立てて倒れると同時に、シュバルツはゆっくりと立ち上がった。
(退け)
シュバルツは、そう言いたかった。
退け。
退いてくれ。
これ以上無益な殺生はしたくない。
「………………」
だが、辺りを包む殺気は消えず、仲間を倒されて、尚も甲賀忍者たちの戦闘意欲は高まるばかりだ。
(やはり……あの男を仕留めねば、退かぬか……!)
苦い想いで、九龍院を見つめる。刀を濡らす血が、柄から手へと伝い落ちてくる。
(これが……! これが、ハヤブサの生きる世界……!)
知らずシュバルツは、唇を噛みしめていた。
「遠巻きにして、手裏剣で攻撃しろ!!」
「!!」
ぐるりと取り囲まれた忍者隊から一斉に手裏剣が放たれる。シュバルツはそれを――――「分身」で、かわした。
「何だと!?」
驚いている間に、信じられないスピードで『ハヤブサ』に距離を詰められる。あっという間に集団の中に入り込み、飛び道具が使えなくなってしまう。
接近を許したら真っ二つにされる。
相打ち覚悟の自爆を試みても、避けられてしまう。
(おかしい)
九龍院は思った。
人を斬れば、どうしてもその血と脂で、刀の切れ味は悪くなる。骨を斬れば、刃はかける。それなのに何故。何故――――奴の刀は切れ味が悪くなるような気配を見せないのだ? 龍剣は、相も変わらずその背に背負われたままであると言うのに。
「……奴が持っている、あの刀は何だ?」
思わず九龍院は、直近にいた側近に問う。しかし、その側近も首を捻るばかりだ。
「……さあ……。特に、『銘入り』と、言う訳ではなさそうですが……」
言っている傍から、またしても『ハヤブサ』が、仲間の身体を一刀両断にした。九龍院は驚愕の眼差しでその刀を見る。刀はもはや『血』で、真っ赤に染め上げられていた。
「―――――」
シュバルツは、とにかく感覚を麻痺させる。
心静かに。余計な事は、考えない。
ただ、目の前にあるものを、『斬る』『斬る』『斬る』
静寂の中に落ちゆく、その水の一滴をただ捕らえる。
『命』を奪うのならば、せめて。せめて――――苦しませぬ、ように。
それは、『錆びた刀で木を斬る』極意にも通じていた。
乱れたら、負け。
考えたら、終わりだ。
シュバルツは最早、殺気すらまとわずに斬り続けていた。
『ハヤブサ』の顔は、覆面で覆われているが故に見る事が出来ないが、もし誰かがそれをはいで覗き見る事が出来たならば――――ひどく穏やかなハヤブサの表情が、そこにあった事だろう。
『人』を斬り続けているとは、とても思えないほどに。
「ムムッ」
九龍院は歯噛みする。
(完全に誤算だ……! あの『毒』を押さえる手段が、隼の里にあったとは――――!)
「ハ―――――――ッ!!」
ハヤブサの叫び声と共に『飯綱落し』がさく裂し、また同胞たちが吹っ飛ばされて行く。少しずつだが確実に、九龍院とハヤブサの距離は狭まりつつあった。
「馬鹿な!! 毒の効き目はまだ現れないのか!?」
忍者たちの間から、悲鳴の様な声が漏れる。ハヤブサが何らかの『術』によって毒の効き目を押さえていると言うのなら、さらに毒を上から重ねればよい。そう考えて、皆は先程から毒をぬった刀や手裏剣を使用している。そして、実際それがいくつかハヤブサの身体にヒットしていた。『毒』は、確実にハヤブサの身体に入っているはずなのだ。
それなのに、ハヤブサの方に、未だ毒がまわっているような症状が現れない。
(毒を塗られていたか……。やはりな…)
シュバルツは、特に頓着はしなかった。
自分が『人間』ならば、『毒』も効いたかもしれないが……。
残念、私は『アンドロイド』
『毒』など――――効きはしない。
そのままシュバルツはひたすら前へと進む。
攻撃を避けるにしても『前』へ。
『斬る』にしても『前』へ。
ただひたすら、朴訥に前へ進む。
どうか前に立ちはだかるな。
私の狙いはあそこにいる甲賀忍軍の頭首、ただ一人なのだから。
「ム……!」
錐を押し込んでくるように強引に突破をしてくる龍の忍者に、九龍院は唇を噛みしめる。心なしか、自分の軍の旗色が悪いように見えた。
(おのれ龍の忍者……! たった1人…! たった1人にここまで押し込められるとは――――!)
その時、九龍院の横に控えていた側近が、自軍の異変に気づく。
(おかしい……? 心なしか人数が、減っているような……?)
首を捻って、もう一度戦場を見る。
龍の忍者にやられた事は仕方ないにしても、それ以外にも……。人数の減り方が激しい様な気がする。
(やはり、異変が起きている……?)
側近は懸命に戦場に目を凝らした。しかし、異変の原因を突き止める事は、なかなか出来なかった。
その頃、戦場の裏側では、無音の戦いが繰り広げられていた。ハヤブサの命を受けた3人の男たちの戦いである。彼らはシュバルツが戦っている戦場を各々3方向から取り囲み、戦場の端にいる者たちから少しずつ、抹殺して行った。『殺し』の音もたてず、末期の声すらあげさせない。
そうして少しずつ戦場にいる者たちの人数を減らして行きながら、彼らはある細工を施して行く。
そして――――。
「リュウさん!!」
「!!」
叫び声と共に、3人はそろってシュバルツの前に姿を現した。3人はシュバルツを守る様に構えて立つと、同時に懐から焙烙玉を取り出して、敵に向かって投げつけた。
ドカン!!
焙烙玉がさく裂すると同時に、一気に戦場に火が駆け抜ける。そして、瞬く間にあちこちから火柱が上がった。炎に包まれる格好になった甲賀忍者たちが、悲鳴を上げながら逃げ惑っている。
「こ、これは……!?」
茫然と呟くシュバルツに向かって、与助が振り向いて微笑みかける。
「本物のリュウさんからの命を受けて、貴方が戦っている間に仕掛けさせてもらいました。隼流忍法『火龍の計』です」
「ハヤブサが…?」
「リュウさんが、貴方一人だけを戦わせる訳が無いでしょう?」
「…………!」
驚いた様に目を見開くシュバルツに、3人の忍者が微笑みかける。シュバルツは、「ありがとう」と、素直に礼を言った。
「これで……この場から彼らが退いてくれればいいのだが……な」
そう言いながらシュバルツは、先程まで九龍院がいた辺りを見つめる。たくさんの『命』を屠った彼の刀から、ぽたり、と、音を立てて、血が滴り落ちていた。
「皆の物。よく聞け……。この戦い、我らの負けじゃ」
戦場から少し離れた所場所で甲賀忍者たちを集めた九龍院が、皆の前でそう切り出した。
「九龍院様!?」
「『龍の忍者』の健在が、我らにとって完全に誤算であった……。直に、体勢を立て直した隼の忍者団も、この戦いに加わってこよう…。そうなると、最早我らには、完全に勝ち目はなくなる……」
ここに至って甲賀忍軍の頭領は冷静だった。彼は、ここで仲間を全滅させるよりも、意志を後進に残す事を選択したのだ。
「お前たちは今の内に引いて、『龍剣』を手に入れる機会をまた待つのじゃ」
「分かりました。して、九龍院様は――――?」
「ワシは、あの『龍の忍者』と決着をつける」
その言葉に部下たちは息を飲む。
「それが、この戦いを挑んだワシのけじめ。そして、この戦いで死んで行った者たちへの手向けとなろう」
「……九龍院様……!」
あの龍の忍者に戦いを挑むと言う事は、戦えばどちらも無事では済まない予感をさせた。部下の間から、咽び泣く声が聞こえてくる。
「泣くな…。戦いを挑んだ時から、このような事も覚悟しておった事」
そう言いながら九龍院は立ちあがった。見上げる空には、いつの間にか満天の星空が輝いている。
「お主たちはこのまま脱出し、再起を図れ」
九龍院の言葉に従って、部下たちは脱出を始める。しかし一人だけ――――彼の傍から去らない部下がいた。
「お主――――!」
驚く九龍院に部下は顔を上げる。それは、九龍院の一の側近だった。
「どうか、私だけでも御供をさせてください」
「しかし……!」
「どうか、貴方の骨を拾う役目を……どうか……!」
側近の眼差しを見つめた九龍院は、彼の想いを止められない事を悟る。
「……好きにしろ…」
そう言って背を向ける九龍院に向かってその側近は満面の笑みを浮かべる。
「ありがとう、ございます!」
深々と頭を下げると、彼は嬉しそうにその後をついて行った。
「『龍の忍者』よ!!」
九龍院輝宗の大音声が、『戦場』に響き渡る。呼びかけられたと悟ったシュバルツは、応える代わりに1歩前へと進み出た。
「このたびの戦い……見事であった。おかげで当方は、800人いた同胞の、大半を失(うしの)うてしまったわ……!」
『ハヤブサ』の姿を認めた九龍院に、ある種の感慨が滲んだ表情が宿る。対してシュバルツは――――何も答えなかった。ただ、感情の読めない瞳で、九龍院を見据える。
「この戦、当方の負けだ。……だがワシとて、一軍を担う『将』として、この戦を仕掛けた意地がある」
「何が言いたい!?」
シュバルツの後ろで控えていた喜助が声を張り上げる。それに対して九龍院は持っている杖を『ハヤブサ』に突きつけながら言葉を発した。
「『龍の忍者』よ! 改めて貴殿に、一騎打ちを申し入れる!!」
「!!」
九龍院の言葉に、シュバルツの傍に控えていた3人の忍者たちが息を飲む。
「……この一騎打ちの決着を以って、この戦の真の決着としたい!」
「な―――! 勝手だ!! 今更そのような事を……!」
颯太が息まいて九龍院に反論しようとするのを、シュバルツが手で制した。
「どうだ……? 受けてくれまいか、『龍の忍者』……」
九龍院の指す杖と眼差しは、決して『ハヤブサ』から逸らされる事は無い。その場にしばし沈黙が訪れた。
「………分かった…」
やがて『ハヤブサ』のその声が、沈黙を破った。
「貴殿の申し入れを、受けよう」
そう言いながらシュバルツは、九龍院の方へと歩を進める。
「リュウさん!」
叫ぶ与助に、シュバルツは振り返らずに言った。
「皆……手を出すなよ。これは『俺』の戦いだ…!」
「…………」
『ハヤブサ』として九龍院との戦いを受けたシュバルツを、止められないと悟る。九龍院の方へと歩んで行くその後ろ姿を、皆は黙って見つめるしかなかった。
「………得物は変えずとも良いのか?」
3人の忍者から離れて、自分の方に歩み寄ってきた龍の忍者に、九龍院はそう声をかける。『ハヤブサ』の持っている刀は、たくさんの血を吸って、もうボロボロの状態であったからだ。
だがシュバルツは、短く「問題ない」と、言うと静かにその刀を構えた。すると、その刀が白銀色に輝きを帯び始める。『明鏡止水』の極意を極めている彼は、どのような刀であろうと、それを一流の名刀に変える事が出来るのだ。
だが九龍院は、俄かにそれを信じる事が出来なかった。ただ、自分と相対するような状況になっても『龍剣』を抜こうとしない龍の忍者に、
(舐められている)
と、強く思った。
「……どうやら、何が何でも貴公には『龍剣』を抜いてもらわねばならぬようだな……!」
低い声と鋭い殺気と共に、九龍院もまた、杖に仕込んであった刀を抜き放つ。刃渡りおよそ3尺はあろうかと言う、ひどく長い刀だった。そしてそれを静かに構えた。そのままの姿勢で、両者はしばし対峙する。
(ム……これは……!)
対峙してから、九龍院は気付く。
目の前のハヤブサが、ひどく穏やかな『気』を纏って刀を構えている事に。
九龍院にとっては意外であった。
『龍の忍者』と言えば、その背に龍を纏った、もっと猛々しいイメージを持っていたと言うのに。
目の前の龍の忍者は、ただ『静寂』であった。
風一つ無い湖面に、何一つ揺れる事の無い満月を、その面に映している水面の様に。
穏やかな静寂。
しかし、恐ろしく張り詰めた静寂。
九龍院は試しに『気迫』を、目の前にいるハヤブサに送ってみる。
気迫に、ハヤブサの湛えている『湖面』は揺れる。揺れるのは分かるが、それだけだ。ハヤブサの実体が、何とも捉え難い。まるで湖面に浮かぶ月の如く、こちらの気迫を受け流されているのが分かる。
(できる……! これは、油断ならぬな……!)
九龍院の額から、汗が一粒流れ落ちた。
刀を構え、『明鏡止水』の極意の中にその身を置いているシュバルツもまた、九龍院から発せられる『気迫』に、ただならぬものを感じていた。
九龍院輝宗は、外見は白髪白髭の老人であり、その体躯も雰囲気も、決して『若い』とは言えない物だった。だが―――そこから発せられる『気迫』は想像以上に強かった。少しでもこちらが気を抜いたら、それこそ気圧されてしまいかねないほどに。
しかも、その『気迫』の中に、何か――――『禍々しさ』まで感じる。
(何だ……?)
シュバルツはその『禍々しさ』の正体を探ろうとする。しかし、どうしても探り当てる事が出来ない。九龍院から発せられる、『闇』は、この戦いが一筋縄ではいかない、と言う警告をシュバルツに与えていた。
(さすが……忍者軍団の頭首になるだけの事はある……)
シュバルツの掌が、いつしか汗で湿り始めていた。
その静寂の中、両者は向き合う。
全く動きの無い、静かなる戦場。しかし、耳が痛くなるほどの殺気が、辺りの空気を覆っていた。対峙している二人から、いつしか汗が滴り落ちている。
(もう既に、見えない刃の応酬が、始まっている……)
この戦いを見守っている4人の忍者たちには、そう感じられた。
二人の間には、激しい剣撃の応酬が、もう何度も行われている。にもかかわらず、二人が二人とも全く動かないのは、それだけお互いの『隙』を見いだせていないのに他ならない。
二人の間を、一陣の風がヒョオッ、と、音を立てて走り抜ける。
それと共に流れてきた木の葉が、瞬間シュバルツの目を掠めた。
刹那――――九龍院が動いた。
「いやあああああああっ!!」
長刀を槍の様に構え、目にもとまらぬ速さで『ハヤブサ』に向かって突進して行く。
ガキッ!!
金属の交錯音と共に、青白い火花が飛び散る。シュバルツの持つ血だらけの刀は、九龍院から繰り出された渾身の突きを、見事受け止めきっていた。
「ムッ!!」
『初手』が防がれたと知った九龍院だが、動じる事は無かった。そこから素早く身を引くと、再び攻勢に転じた。
「ハ―――――ッ!!」
凄まじい勢いで剣先が繰り出されて行く。いわゆる九龍院の『三段突き』と言う攻撃だ。九龍院の相対した者は、たいていこの攻撃の前に敗れ去っている。九龍院の戦いを見守っていた側近は、これでこの勝負は決まったと思った。
だが――――『龍の忍者』はその攻撃を見切った。一、二段目を体を使ってかわし、三段目を刀で受ける。
ならばとばかりに、九龍院は更に踏み込んだ。三角飛びの様に角度を変え、もう一度龍の忍者に『三段突き』を仕掛ける。
ギャリィィィィッ!!
九龍院の長刀とシュバルツの刀が交錯し、青白い火花が飛び散る。
(長い得物は懐が弱い。懐に飛び込めば―――!)
シュバルツはそう判断して、刀を長刀に滑らせながら、九龍院の懐に飛び込もうとした。その瞬間。
(――――!?)
不意に脳裏によぎる、不吉なイメージ。
「…くぅ……ッ!」
斬りかかろうとした腕を止め、後ろに飛びのいて距離を取る。それを見た九龍院がにやりと笑った。
(踏み込んで来なんだか……。なかなか勘のいい……)
まあよい。踏み込んで来ぬのなら、この夜切刀の餌食にしてくれるだけだ。
再び九龍院が長刀を構える。刃が月明かりを反射して、ギラリ、と、青白い光を放った。
(何だ? 今のイメージは……!)
九龍院から距離を取って、刀を構えながらシュバルツは戸惑った。
一般的に長い得物を持つ相手と相対する時は、懐に飛び込むのがセオリーだ。懐に飛び込まれてしまっては、小回りの利かない長い武器には、かえって不利になるからだ。
それでは何故。九龍院の懐に飛び込もうとした瞬間、不吉な物を感じたのか――――。
分かる。
この『謎』を解き明かさなければ、おそらく自分は負けてしまう。
自分があの男に感じた『闇』の原因は何なのか――――。
「りゃああああああ――――ッ!」
考える間を与えるかと言わんばかりに、九龍院の長刀が、再び『ハヤブサ』を襲う。シュバルツはそれを紙一重でかわし、流し――――時に、刀で受けた。二人の刀が交錯するたびに、ガンッ! ガンッ! と、派手な金属音が響き渡り、青白い火花が飛び散る。
長刀を振り回す九龍院の、懐が再びがら空きになる。
(―――――!)
シュバルツは思わず、踏み込んで行きそうになる。だがやはり、同じように脳裏に不吉なイメージが浮かび、それが彼を踏みとどまらせた。
(どういう事だ!? こちらが懐に飛び込む事を、誘っているのか?)
問いかけるように九龍院を見る。しかし九龍院はただ不敵な笑みを浮かべるばかりだ。
ブオン!!
長刀が、唸りを上げながら地面すれすれを走る。足を狙って来たのだ。シュバルツは迷わず跳躍する。
「ハ――――――ッ!!」
重力と共に、渾身の力を込めて刀を振り下ろす。真っ向から唐竹割にするつもりだった。だが九龍院の太刀は、シュバルツの太刀を見事受けきった。青白い火花が散り、その場から押し返される。とても老人とは思えないほどの膂力だ。
「小癪な!!」
再び九龍院の激しい『突き』が『ハヤブサ』を襲う。二人の間で白刃が交錯し、青白い火花が飛び散った。そのまま二人の間で何合も何合も太刀が合わされる。
それはまさしく、死力を尽くした戦い。
『死合い』と呼ぶのにふさわしい戦いであった。
(九龍院様……!)
(シュバルツさん……!)
従者たちも、ただ固唾をのんで見守るしかなかった。二人の技量は、それほどまでに互角だった。
ガンッ!!
星空の下、二つの影が交錯して分かれる。もう何度、相手の太刀を打ち、打たれ、こうして来た事だろう。100合、200合。いや、もっともっと――――。
「――――――」
シュバルツは、息が乱れそうになるのを堪える。
この戦い、お互いに『決定打』が討てない以上、先に乱れた方が負ける――――シュバルツはそう感じていた。それは九龍院も同じようで、息一つ乱れていないように見えるが、その額から汗が滴り落ちている。
(『龍剣』を、使うか?)
シュバルツは背に背負っている『それ』を強く意識する。
一太刀――――一太刀だけなら、龍剣も自分に力を貸してくれるのだ。『今』が、その振るい時ではないのかとも思う。
(だが、『一太刀』で仕留められなかったら……どうする?)
龍剣は、正式な持ち手以外の命を喰らう妖刀だ。自分は刀に『持ち手』として正式に認められていない以上、二太刀目以降刀が力を貸してくれるとはとても思えない。下手をしたら喰われてしまう恐れがある。
まして、自分の身体を構成している『モノ』は、『負』の力に引っ張られやすい『DG細胞』だ。刀と同化して、『暴走』してしまう危険があった。そうなって前後の見境がつかなくなってしまった場合、目の前の九龍院を討つだけではなく、隼の里の人たちにまで、牙を剝いてしまいかねない。本物の『化け物』として―――――。
(…………!)
シュバルツは歯を食いしばる。
それだけは、何としても避けたいと、願った。
でも、ならばどうする?
既にボロボロになってしまっている刀を構えながら思う。たくさんの人を斬り、九龍院の重い太刀を受け続けているこの刀は、既にあちこちが欠け、見る影もない程痛みが激しくなってしまっている。後2、3回九龍院の太刀を受けたら、今度こそ折れてしまうかもしれない。
刀を構えると、悲鳴のような音がする。自身の『限界』を、訴えるような音が――――。
(どうする?)
シュバルツは迷う。
このままこの刀を折れるまで使うか、はたまた無謀を承知で、龍剣の一撃にすべてを賭けてみるか――――。
(―――――)
その時、シュバルツは小さな『声』を聞いた。
(何……?)
小さな
小さな声。
でも、確かに聞こえる――――。
(――――――)
(そうか――――!)
その瞬間シュバルツは、総てを『理解』した。
この戦いの結末を。
そしてそのために出来る、自分の『役割』を。
「ありがとう……」
小さく、礼を言った。
そして、今まで自分と共に戦って来てくれた刀を捨てた。
そして、背に背負う『龍剣』の柄に、手を伸ばす。
「ムッ!?」
ハヤブサの動きに、九龍院の表情も動く。
(やっと、『龍剣』に手をかけおったか! 龍の忍者よ!!)
九龍院も悟る。
ハヤブサは、次の一撃に総てを賭けてくるのだと。
「面白い!!」
九龍院の瞳に、俄然凶悪な色が宿る。改めて夜切刀を構えなおした。
(来い!! 龍の忍者―――!! 『龍剣』もろとも、貴様を砕いてくれるわ!!)
今度こそ、龍の忍者は懐に飛び込んでくる。
ならばこちらも、『全力』でそれに立ち向かおう。
九龍院は確信する。
この戦い。
ワシの
勝利だ。
「はああああああっ!!」
凄まじい気合と共に、ハヤブサが龍剣の柄に手をかけたまま走りだす。
「いえええええええっ!!」
九龍院もまた、裂帛の気合と共に、『突き』を繰り出すべく刀を動かした。
九龍院はイメージする。
ハヤブサはこちらの突きを見切り、懐に飛び込んでくる。
その瞬間が
勝負。
柄に手をかけたままの龍の忍者が狙ってくるのはおそらく居合斬り。スピード勝負になる。
だがこちらには――――。
シュウッ!!
案の定ハヤブサは、こちらの突きを紙一重でかわす。そしてそのまま、懐に飛び込んできた。
(今だ!!)
九龍院は本能の命じるままに、自身の『奥の手』を明かす。
それは――――。
ドスッ!!
肉が斬られる音と共に、ハヤブサと九龍院の間で『血』が滴り落ちる。
「ぐ……う………ッ!」
九龍院の懐から出た『もう一本の刀』が、ハヤブサの胸から背を貫いて、いた。
「か……隠し腕……!」
血を吐きながら呟くハヤブサに、九龍院はにやりと笑いながら返す。
「そうよ。ワシには、生まれつき腕が4本ある」
そう言いながら九龍院は、来ている着物をはだける。するとそこには、脇の下からもう一本腕が生え、その腕の先に握り込まれた刀が、ハヤブサを刺し貫いていた。
「……………!」
「たいていの者は、最初の三段突き、またはその後の隠し腕の奇襲で決着がつく…。それを貴様は――――よく、ここまで持たせた」
ハヤブサを貫いている刀に、ぐっ、と力を込める。ハヤブサが、苦しそうに呻いた。
「さあ、この勝負……ワシの勝ちだ。その背にある『龍剣』――――もらいうけるぞ……!」
そう言って、九龍院はハヤブサが龍剣を握っているであろう右手を見る。だがそこに、『龍剣』の姿は、無かった。
「!?」
驚愕した九龍院は、龍剣があったハヤブサの背を見る。だがやはり――――そこにも龍剣は『無い』
「き、貴様!! 『龍剣』を、どこへやった!?」
身体を貫く刀に力を込め、今にも事切れそうになっているハヤブサを揺さぶって問いただす。それに対してハヤブサは――――何故か『笑み』を浮かべているように、九龍院には見えた。
「………龍剣、は………」
そう言いながらハヤブサの右手が、力無く天を、虚空を指す。九龍院もそれにつられて見上げたが、そこには何も――――無かった。
「ふざけるなッ!! 龍剣は……! 龍剣は、どこだ!?」
「―――――」
「……答える気は無し…! そうか……!」
観念したように瞳を閉じるハヤブサに、九龍院も答えをあきらめる。
「―――ならば死ねい!!」
裂帛の叫びと共に、九龍院はハヤブサの身体を斬り裂いた。
バッ! と、血飛沫を飛び散らせながら、ハヤブサの身体はゆっくりと後ろへ倒れて行った――――。
「全く忌々しい……! 龍剣は、一体どこへ……?」
物言わぬ屍となったハヤブサを見下ろしながら、九龍院が独りごちていると、不意に声が響いた。
「ここだ!」
「――――!?」
九龍院はぎょっ! と、なって振り返った。何故なら――――聞こえてきた声が、倒したはずの『龍の忍者』と、全く同じ『声』であったから。
九龍院の目線の先、少し離れた小高い丘の上に、『龍の忍者』が立っていた。
「な……! 貴様は――――!!」
驚愕の声を上げる九龍院を見下ろしながら、ハヤブサは右手を天に向かって伸ばす。するとそこに、『龍剣』が、回転しながら落ちてきた。ストン、と、吸いつくように、龍剣はハヤブサの右手に収まる。『正当な』持ち主の元に。
「ば、馬鹿な……! 龍の忍者が二人…!? で、では……今ワシか倒したこいつは一体……!!」
問いかける九龍院に、ハヤブサが歩を進めながら答える。
「そいつは『影』だ。俺の『影』……」
「な――――!」
俄かに信じ難い九龍院は、倒れている『ハヤブサ』の覆面を剥ぐ。ハヤブサの顔が出てくる。だが、その『マスク』が、剥がれかかっているのが分かった。
(まさか―――!?)
震える手でそれを剥ぐと、ハヤブサとは全く違う男の顔が、出てきた。
(シュバルツ……!)
完全に『死んで』しまっているシュバルツの姿に、ハヤブサは歯噛みする。
あの瞬間、シュバルツは龍剣を抜かなかった。ただ、龍剣を天高く放り投げたのだ。龍剣を、元の持ち主に渡すために。九龍院の『奥の手』を、ハヤブサに『見せる』ために。
龍剣の声が、彼には聞こえていたのだ。
龍剣の、『主』を呼ぶ『声』が―――。
アイツ、私ノ『声』ヲ聞イタゾ。
龍剣が、ハヤブサの腕の中でそう語りかけてきた。
(ああ。そうだな……。あいつは、そう言う奴だ……)
ハヤブサも、言葉を返す。
(だからお前も、あいつに『力』を貸したんだろう?)
……………。
龍剣は、その問いには黙して答えなかった。
自分は、力など貸してはいない。
ただ、教えただけだ。
ハヤブサが、そこに『居る』と――――。
たった、それだけ。
それだけだ。
なのに――――。
「ありがとう」
「………………」
ハヤブサは、無言で歩を進める。この戦いに、決着をつけるために。
「う……む……ッ!」
九龍院は何故か気圧されていた。ハヤブサの持つ、圧倒的な雰囲気に。
ハヤブサはいつしか、龍の燐気をその身に纏っていた。ハヤブサの『怒り』が、龍剣の『怒り』が、燐気を呼び起こし、その周りに龍の姿を形作らせて行く。
「お……おのれ……ッ!」
九龍院は認めたく無かった。何もかも、認めたくは無かった。自分が『影』にまんまと騙されていた事も。そして今―――『龍の忍者』に気圧されている事も。
だが自分が、負ける筈は無い。先程まで戦っていた龍の忍者が『影』だと言うのならば、龍の忍者本人には、間違いなく『毒』は効いているはずなのだから。
「『毒』によって死にかけている貴様に、何が出来ると言うのだ!!」
九龍院は吠えた。4本の腕で、2本の刀を構えながら、龍の忍者に向かって突進して行く。
ハヤブサも吠えた。
「勝てると思うか!? 手の内を既に曝されてしまっている貴様が―――!!」
ハヤブサと龍剣が、龍の形となり、まっすぐ九龍院に突っ込んで行く。
ドカッ!!
勝負は、一瞬で決まった。
白刃と白刃が交錯し、ぶつかり合った二人の身体が体(たい)を入れ替えて着地する。
「ぐ………!」
先に動いたのは、九龍院の方であった。袈裟掛けに斬られた身体から、バッと血飛沫が飛び散り、体勢が崩折れる。
見事だと思った。
自分を、完全に『龍の忍者』だとこちらに信じ込ませた『影』
その身を賭して、こちらの手の内を、ハヤブサに曝した『影』――――。
自分は、『影』に負けたのだ。
「見、事……だ………」
それが、九龍院の末期の言葉であった。
「………………」
ハヤブサは無言で龍剣の露払いをすると、倒れているシュバルツの側に駆け寄った。
「シュバルツ……!」
名を呼び、その身体を抱きかかえる。だが当然、シュバルツからの反応は無い。
駆動音もしない。
呼吸音すらない。
胸から肩口にかけて、無残に切り裂かれている。その傷口に触れた瞬間、ハヤブサは絶叫しそうになった。
「―――――ッ!」
それを懸命に堪える。知らず、シュバルツの身体をぎゅっ、と、抱きかかえていた。
シュバルツは、死なない。
死なないのだ。
だから、大丈夫。
大丈夫――――の、はずだ。
「リュウさん……!」
「こ、こんな――――!」
いつの間にか与助や颯太たちもハヤブサの側に来ていて、茫然と佇んでいた。
「う……う………ッ!」
三朗太の咽び泣く声が聞こえる。
「泣くな…!」
ハヤブサはそれを、強い口調でたしなめた。必要無いからだ。泣く必要など全然ない。シュバルツは、『死んで』などいないのだから。
「貴様!! 何をしに来た!?」
喜助の鋭い声が響く。ハヤブサが顔を上げると、九龍院の側に一人の甲賀忍者の姿があった。だが、甲賀忍者の方に殺気は無く、ただ九龍院の屍を抱きかかえようとしている。主の遺骸を取りに来たのだと知れた。
「喜助。手を出すな」
刀の柄に手をかけ、甲賀忍者を威嚇するように睨みつけている喜助を制してから、ハヤブサは甲賀忍者に声をかけた。
「………去れ!」
ハヤブサのその言葉に、甲賀忍者は頭を下げてから、九龍院の遺骸を持ち去った。
「……リュウさん、何故です!?」
敵をあっさりと逃がしてしまったハヤブサに、喜助が抗議の声を上げる。その目が、涙ぐんでいた。
「たくさんの仲間が殺されて……揚句、この人まで死んでしまったと言うのに、どうして――――!」
「………お前たちに、言っておくことがある」
ハヤブサの低い声が、喜助の抗議を遮った。ここにいる4人だけには、事実を言っておかねばならない、と、思ったから。
「この男は……『不死』だ………」
「えっ!?」
「『不死』――――!?」
「な――――!」
「…………!」
ハヤブサの言葉に、4人ともが絶句する。その場にしばし、沈黙が訪れた。
「…………」
ハヤブサはもう1度、シュバルツの身体をぎゅっ、と抱きしめなおした。まるで、『何か』から守る様に――――。
最初に沈黙を破ったのは、喜助であった。
「リュウさん……。本当に、その人は、『不死』なのですか……?」
「ああ、そうだ」
喜助の問いに、ハヤブサが頷く。
「なるほど……。それで――――」
喜助はやっと得心した。どうしてシュバルツが、人の『命』を助けようとする時、全く己の身を顧みようとしないのか。燃え盛る家に飛び込む。倒れてくる材木の下に飛び込む。自分がどんなにダメージを受けようとも、助けようとした対象が無事ならば、それでにっこりと微笑んで――――。
いくら怪我の治りが人より早い『特異体質』と言っても、その行動は無茶苦茶すぎると喜助は思った。だから、颯太と小六、二人を呼んで「この人を守ろう」と、話し合った。自分達が側にいる、ついて行くことで、この人の無茶な行動を、少しでも止められれば、と、思ったから――――。
「『不死』だから……無茶をする……」
喜助はポツリと呟いた。
「この人もまた……『修羅の道』を、歩まれているのですな――――」
「…………!」
驚いて振り向くハヤブサの視界に、こちらに向かって頭を下げている喜助の姿が飛び込んでくる。その後ろで、颯太が窺うようにこちらを見ていた。
「リュウさん…。『不死』って事は、この人は……大丈夫なんですよね?」
「あ、ああ…。そうだ」
頷くハヤブサに、颯太はホッと胸をなでおろしていた。
「よかった~! 俺本当にどうしようかと思ったよ。『シュバルツさんが死んだ』なんて長老の家にいる奴らに報告したら、俺絶対袋叩きの目に遭いそうだったから……」
「……そうなのか?」
驚いて問い返すハヤブサに、颯太がうんうんと頷き返す。
「そうなんですよ、リュウさん。子供たちなんか『おっちゃんが帰って来るまで門なんか閉めさせない!!』って、門番を睨みつけていたんだから……」
「…………!」
それを聞いて唖然とするハヤブサを尻目に、颯太は『良かった、良かった』と、何度も頷いている。
「……よしっ! じゃあ、俺は一足先に長老の家に行って、事の顛末を報告してくる! 良い事は、早く報告しに行かなきゃいけないからなぁ」
「お、おい! シュバルツが『不死』って事は……!」
走って行こうとした颯太を、ハヤブサは思わず呼び止めた。シュバルツの『秘密』があまり人に知れ渡るのは、好ましくないように思えたから。だがそれに対して颯太は、にっこりとほほ笑みながら振り向いた。
「分かってますって! 『他言無用』でしょう? 皆には『シュバルツさんは無事だ』と言う事だけ、伝えておきます」
それだけ言うと、颯太はぺこり、と、頭を下げて、長老の家の方へと走って行った。
「もちろん、我々も決して口外はしません」
ハヤブサに向かって、喜助も口を開く。
「……だよな? 与助。三朗太」
喜助の問いかけに、二人も大きく頷く。それを見て、喜助も頷いた。
「……では、リュウさん。私どもも一足先に長老の家に参ります」
そう言うと喜助たちもまた、ハヤブサの前から姿を消した。
しばらく二人と一緒に歩いていた与助が立ち止まる。
「どうした? 与助」
立ち止まった与助に気がついた三郎太が振り向いた。それに与助が視線を合わせて、口を開く。
「悪いが……二人とも、先に行っていてくれないか?」
怪訝そうに首をかしげる喜助に、与助は笑顔を向ける。
「私は、またリュウさんの『お付き』に戻るよ」
何か手伝えることがあるかもしれないし、と、言って笑う与助に、二人も頷いた。
「じゃあ与助、また後でな」
二人が去っていくのを見届けてから、与助は振り向いた。
視線の先ではハヤブサが、ずっとシュバルツの身体を抱きかかえたまま、彼を見つめている。
入り込めない、二人だけの世界……。
何とも犯しがたい雰囲気を湛えている二人の様子に、与助は強くそう感じた。
ハヤブサに用事を言われる可能性があるから、ハヤブサの『お付き』に戻るのはもちろんのことだが、この二人だけの時間を、自分は邪魔するべきではないし、また、誰かに邪魔をさせても駄目だと思った。この貴重な時間を守るのも、自分の役割だと思った。
与助は、ある程度距離を置いた所に身を置いて、そこに静かに控える事にした。
(シュバルツ……)
ハヤブサは、シュバルツの身体を抱きかかえながら、その髪を優しく撫でる。人の『血』と、自身の『血』で、朱に染まってしまっている忍び装束。それは、ここでの戦いの激しさを、ハヤブサに容易に想像させた。
(馬鹿だな……お前は……)
薄く開かれたその唇から、呼吸音はまだ聞こえてこない。
(……本当に、還って来るのか?)
ハヤブサは少し心配になる。シュバルツの話では、完全に事切れてから復活するまでの時間はだいたい3時間前後と聞いている。
(3時間か……。長いな……)
以前も3日3晩、意識の無いシュバルツの側に付き添っていた事はある。だがこの時は、シュバルツは『呼吸』をしていた。生きていると分かった。だから、ある意味安心して付き添う事が出来たのだが、今回の場合、完全に事切れてしまっているから、何となく落ち着かない。九龍院に討たれてから、まだそんなに時間が経っていないから、少なくとも後2時間半は待たねばならないのだろうか。
動かないシュバルツの、薄く開かれた唇。
本当に、まだ呼吸をしていないのだろうか。
確認するために、ハヤブサは顔を寄せる。
そして――――。
シュバルツの唇の上に、そっと自身の唇を、重ねていた。
『死体』に唇を重ねる、と、言う事に抵抗は無かった。相手が『シュバルツ』であるならば、ハヤブサは何でも良かった。どんな姿であろうが、どんな形であろうが――――そこには、ただ、愛おしさしかない。
(シュバルツ……)
想いをこめてハヤブサは、さらに深くシュバルツに口付ける。
反応しない、愛おしいヒトの身体。それでも、ハヤブサの舌は、その口腔深くに入り込んで―――――。
(…………!?)
ある事に、気づく。
(『冷たい』―――――)
違う。
口付けならば何度も交わした。『生きている』シュバルツを抱く時に。
その時のシュバルツの口腔は、もっと温かかった。
『熱』があった。
なのに、今のシュバルツの口の中は
『冷たい』
「…………!」
(シュバルツ……! 何だよ、お前――――!)
思わずハヤブサは、シュバルツを見つめていた。
(あるんじゃないか……! 『体温』が―――!!)
「『体温』が無い、歪な身体」
シュバルツは、自分の身体の事を、そう評していた。
でもならば、今完全に事切れてしまっているお前のその『冷たさ』は何だ。
『違う』と分かる。
今は、『生きていない』と―――――。
(シュバルツ……!)
いつしかハヤブサの頬に、熱いものが伝い落ちていた。
確かに、アンドロイドであるシュバルツの身体は、『人間』よりは冷たい。
でも、その奥底には確かにあった。
生きている『熱』が。
『鼓動』が――――。
生きている『証』が、確かにここにあったのだ。
(シュバルツ―――!)
ハヤブサは、シュバルツの身体を強く強く抱きしめていた。
その腕の中で、小さな小さな音がする。DG細胞が、少しずつ少しずつ、身体の傷を治している音なのだと知れた。
(早く還って来い、シュバルツ)
シュバルツの身体を抱きかかえて、ハヤブサは空を見上げる。
「お前には、体温があるのだ」と、言う事を、ハヤブサは一刻も早くシュバルツに教えてやりたいと、思った。
(早く――――)
ハヤブサの頬を伝い落ちる涙を、抱きかかえられるシュバルツの頬を、いつしか朝日が照らし始めていた。
隼の里の長かった1日が今、明けようとしていた――――。
終章
シュバルツがキョウジの前から姿を消してから、もう2カ月近くが経つ。
(……やっぱり、もう帰って来ないつもりなのかな……)
論文を書いている手を止め、キョウジは窓の外の空を見上げた。
1カ月ほど前、シュバルツから電話があった。
「すまない! キョウジ……! 隼の里で少しトラブルがあって、その後処理に追われていて――――!」
里に唯一ある電話の復旧が遅れに遅れて、なかなか電話が出来なかったんだと、受話器の向こうでシュバルツが言った。その後ろで、里の子供たちだろうか。元気に笑いあっている声が響いている。
「……大変そうだね。こちらは大丈夫だよ。うん……うん……。心配しないで。ゆっくりしておいで――――」
借り物の電話だから、と、律儀に断ってから、シュバルツは電話を切った。相変わらずだな、と、キョウジは思った。
シュバルツがもうしばらく帰って来ない事を知って、キョウジは少し淋しさを感じる。だが、明るい子供たちの声に囲まれているシュバルツの声がとても元気そうだったから――――同時に嬉しさも感じていた。
きっと、シュバルツは『居場所』を見つけたのではないかと感じる。
シュバルツが『シュバルツ』として、居られる場所を――――。
(なら、帰って来なくても、仕方が無いじゃないか)
キョウジは自分にそう言い聞かせて、納得した――――――はずだった。
なのに何故――――自分はいまだにやめる事が出来ないのだろう。意識の端で、シュバルツを探してしまう事を――――。
探してしまうのは、ふとしてきっかけ。
コーヒーが飲みたい時。
本を読んだ時。
ニュースを見た時。
仕事に行き詰った時。
ドモンと話した時。
ついつい、意識の端がシュバルツを勝手に探してしまう。『いない』って、分かっているのに――――。
(もうやめなきゃ)
深いため息と共に、キョウジは空を見上げる。
もうやめよう。彼を勝手に求めてしまうのは。
良いじゃないか。シュバルツが幸せそうならば、それで――――。
(知らなかった…。私って結構、未練がましい性格しているんだな……)
そう思い続けて、早1ヵ月。少しも吹っ切れていない自分を感じて、キョウジは知らず苦笑する。参ったな。今までずっと『独り』でも平気だったのに。いつの間に、こんな――――
「そのような退屈な仕事をしておるから、余計な事を考えるのだ」
「マ、マスター!?」
驚いて振り向くキョウジの視線の先に、東方不敗マスターアジアの姿があった。
「烏龍茶を入れて来てやったぞ…。それとも、コーヒーの方が良かったか?」
「ありがとうございます。『烏龍茶』、頂きます」
そう言いながら、キョウジは盆から湯のみを受け取る。実際、今は烏龍茶の方がありがたかった。コーヒーは、どうしても思い出してしまうから。
シュバルツの、存在を。
「全く……。お主はいつになったら天下取りに動きだすのだ」
キョウジの近くのソファに腰をおろしながら、東方不敗がブツブツ文句を言っている。
シュバルツが帰って来なくなってから半月の段階で、キョウジがドモンに連絡を取ったら、すぐに何故か東方不敗の方が駆けつけて来てくれた。おかげでいろんな意味でトラブルに巻き込まれそうで巻き込まれない生活を送っているのだが、時々こういう事を口走って来られるから、キョウジは少し困る。
「だから何度も言っているじゃないですか。私はそう言うのには興味ありませんって」
「ム………」
笑いながらそう言うと、東方不敗はそれ以上しつこく言ってはこないので、何となく助かってはいるのだが。
(全く……こ奴の欲の無さは相変わらずじゃな……)
能力があるのに勿体ない―――と、東方不敗はキョウジを見るたびに思う。しかし、それも時間の問題だろうと、東方不敗は秘かに思っている。あれだけ能力のある青年を、世界が放っておくはずがない。いつか時期がくれば、雲を得た龍の如く、一気に天まで駆け上がるに違いない。
もちろん、時期が来なければずっと潜んだままで終わってしまうだろうが、それはそれで別にかまわない、とも思っている。側にいるだけで、そう言う『夢』をこの老骨に見せてくれる。それだけで―――東方不敗がキョウジの側にいる理由は、もう充分だった。
「キョウジよ。一服するのであれば、ワシと将棋をせんか? 今度は負けぬぞ?」
笑顔でそう言う東方不敗に、キョウジも笑顔を見せる。
「そうですね……。では、もう少しこの論文を進めてから――――」
そこまで話したキョウジが、不意に、ある『気配』を捉える。
この気配。
まさか……!
まさか――――!?
いきなりキョウジは立ち上がり、そして、走りだしていた。
(ずいぶん長い事留守にしてしまっていたが、キョウジは大丈夫だろうか……)
長い事連絡も取れず、留守にしてしまっていた。
もしかしてキョウジを怒らせてしまってはいないだろうか――――?
玄関先では、そんな不安な心を抱えたシュバルツが、今まさにインターホンを押そうとしていた瞬間だった。
バンッ!! と、勢いよくドアが開くから、シュバルツの方が逆に驚いてしまう。
「…………!」
「あ………!」
二人は、目を見開いたまま、しばし同じように見つめ合う。
「キョウジ…。その……」
先に沈黙を破ったのはシュバルツであった。長い間連絡しなかった事をシュバルツが詫びようとするのを、キョウジが遮った。
「シュバルツ……」
顔を上げるシュバルツの視界に、心の底より嬉しそうに笑うキョウジの姿が飛び込んでくる。
「お帰り」
そう言って差し出されてくるキョウジの手を見て、シュバルツもようやく笑顔になる。
「ただいま……」
ぎこちなくシュバルツも、キョウジの手を取る。
帰ってきて良かった、と、素直に思えた。それが―――とても嬉しかった。
「それにしても良かったのか…? 隼の里の方は――――」
そう言って問いかけるキョウジに、シュバルツは笑顔を向ける。
「ああ。復旧作業もほとんど終わっているし、私の方も、そろそろ『家』に帰りたかったし――――」
「……………!」
「? 私は何か、おかしなことを言ったか?」
驚いたようにこちらを見るキョウジを見咎めたシュバルツがキョウジに問いかけると、キョウジは慌てて首を振った。
キョウジは知った。こちらを『家』と言ったシュバルツ。
彼は―――自分の側に居続ける事を、『選択』してくれたのだと言う事を。
嬉しい――――けれど。
良かったの、だろうか?
もしかしたらシュバルツは
隼の里の方が――――。
「構わないさ。『家』に帰る事はシュバルツの望みだ」
キョウジが声のした方に振り向くと、ハヤブサが腕を組んで壁にもたれかかっていた。
「何か用があれば、俺の方が出向くから―――何も問題ない」
「あ…はは……そうなんだ……」
少し憮然とした表情でそう言うハヤブサに、キョウジは思わず苦笑う。
(『通い婚』?)
その言葉が喉まで出かかったが――――慌ててそれを飲み込んだ。こんな事を言ってしまったら、絶対に忍者二人にどつかれてしまう自信がある。
「……やれやれ、やっと帰ってきおったようだな―――」
「!!」
シュバルツが驚いて顔を上げると、東方不敗が腰に手を当ててそこに立っていた。
「シュバルツが帰って来たのなら、ワシの役目も終わりだな。帰らせてもらうぞ」
そう言いながら東方不敗は小さな手荷物を持って、玄関から出て行こうとする。それを、キョウジが呼び止めた。
「マスター!」
「うん?」
「あ、あの……ありがとう、ございました。いろいろと、本当に――――」
そう言って丁寧に頭を下げるキョウジに、東方不敗はふっと相好を崩した笑みを向ける。
「また、用があれば、いつでも遠慮なくワシを呼べよ、キョウジ―――」
それだけ言うと、東方不敗は出て行った。
「……マスターアジアが来てたのか?」
シュバルツの問いかけに、キョウジが苦笑しながら頷く。
「そうなんだ。ドモンに連絡を取ったら、何故かマスターの方が来てくれて……」
おかげで、『退屈』だけはしないで済んだ、と、笑うキョウジに、シュバルツが小首をかしげる。
「……? どういう事だ?」
「ああ、うん…。そろそろ来るころだと思うんだけど――――」
バンッ!!
キョウジの言葉が終わらないうちに、ドアが乱暴に開けられた。
「師ィ匠ォォォォ!! 昨日の肉まんの借りを返してやる!! 俺と勝負し―――!! あ……あれ?」
マスタ―アジアの弟子であり、キョウジの弟でもあるドモンが、師匠の代わりにシュバルツとハヤブサがいたので、しばし呆然としている。ドモン、久しぶり、と、シュバルツがあいさつすると、ドモンも慌てて挨拶を返した。
「そうだ兄さん! 師匠は!?」
肝心の師匠の姿が見えないのでわめく様にドモンが聞くと、「出て行ったぞ」と、憮然とした表情でハヤブサが呟く。
「おのれ! 師匠め!! さては逃げたな!? 師ィ匠ォォ!! 俺と勝負をしろォォ――――ッ!!」
嵐が通り過ぎるかのように、ドモンが去っていく。それを見届けてから、キョウジはにっこりと微笑んだ。
「毎日がこんな感じだったからね…。お陰様で―――」
「あはははは………」
キョウジの言葉から毎日の様子が伺い知れて、シュバルツももう苦笑うしかない。寧ろ、よくこのアパートが壊れなかったものだと感心すらしてしまう。
「それよりも……ねえ、シュバルツ」
「何だ?」
「久しぶりに―――シュバルツの淹れるコーヒーが飲みたいよ」
キョウジからの『おねだり』に、シュバルツも「仕方ないな」と、苦笑する。
「シュバルツの、コーヒー?」
顔に疑問符を浮かべているハヤブサに、キョウジは笑顔を向ける。
「うん。ハヤブサも飲ませてもらいなよ。とっても美味しいんだ―――」
「そ、そうなのか?」
キョウジの言葉に、ハヤブサも思わず前のめりになってしまう。
「あまり期待するなよ?」
コーヒーの準備をしているシュバルツの声が、キッチンから飛んでくる。キョウジのアパートから、久しぶりに明るい笑い声が響いていた。
そんな、午後のひと時を、優しい風が吹き抜けて行った――――。
ご愛読、ありがとうございました。
美しいヒト
無事、書き終わることができました。
ここまで読んでくださった皆様。そしてここだけ読んでくださっている皆様も、どうもありがとうございます。初めて「BL小説」と言う分野に挑戦させていただきましたが、なかなかどうして難しいものですね! 大変苦労いたしましたが、なかなかどうして楽しい作業でもありました。
少しでも、どなたかの心に響けば幸いです。
それでは、また。
何か作品が思いついたら、書きに来るかもしれませんが、その時は、よろしくお願いいたします。