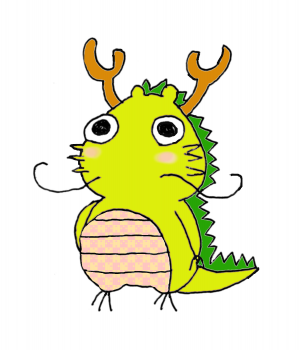おまけの小説(キョウジ兄さんたちに捧げる物語)
この作品は、先に私が書いた『キョウジ兄さんたちに捧げる物語』のラストに組み込むかどうか迷いに迷って、結局見送ったエピソードです。
どうして見送ったかというと、理由は簡単で『腐れ具合がひどくなっているから』なのです。でも、書きたかったので、書いちゃいましたが(笑)。
そう…。この小説は、過分に『BL要素』が含まれております。「苦手」とか、「理解できない」と、感じられる方は、どうかこのまま回れ右をされることをお勧めします。
ちなみに、その掛け算の要素になっているのは、ハヤブサさんとシュバルツさんです。このカップリングが受け入れられないと言う方も、どうぞ回れ右をなさってくださいと、ご忠告申し上げます。
それでもぜんぜんOKですよ~という方だけ、先に御進みくださいね。
それでは拙い文章ですが、どうぞお楽しみください。
あ、でも、濃厚な『絡みのシーン』を期待された方には、いささか物足りない展開かもしれません。
東方不敗が花を生けた花瓶を持って、キョウジの病室に帰ってくると、その入り口付近でドモンとレインが佇んでいた。見ると、ドモンの方は複雑な顔をしており、レインの方は―――何故か赤面している。
「……何をやっておるのだ? 二人とも、そんな所で……」
東方不敗に声をかけられたドモンが、「あ、師匠」と言った後、また複雑そうな顔をしている。
「い、いや、何と言うか、その……」
「へ、部屋に、ちょっと、入りづらくて……」
「部屋に?」
何を馬鹿な事を、と、東方不敗は言いながら、ドアの隙間から部屋の中の様子を見て――――二人の言葉に納得した。
優しい日差しの溢れる病室の中で、キョウジとシュバルツが穏やかな顔をして、何事かを話し合っている。それだけなら割と時々見かけてきた光景だが、よくよく見ると、二人の手がしっかりと握り合われているのだ。
たったそれだけの事なのに、その空間は何者も入り込めない様な雰囲気を漂わせている。
「…………」
無言で引き返してきた東方不敗に、ドモンが「入れないでしょう?」と、声をかけてきた。東方不敗も「ム………」と、唸るしかなかった。
しかし、悲しいかな、ここは『病院』である。
「キョウジ・カッシュさん。午後の検温の時間ですよ~」
職務を遂行するべく看護士が、キョウジ達がいる部屋に入ろうとする。
「あ、あの、ちょ、ちょっと待ってください!」
レインが慌てて看護士を制止しようとするが間に合わず、ドアが音を立てて開けられてしまった。
「あ……ご苦労様です」
そこには、ベッドの上でにこやかに微笑むキョウジの姿だけがあった。
「キョウジよ。調子はもうだいぶいいのか?」
午後の検温を終え、新しい点滴を打たれているキョウジに、東方不敗が声をかける。
「おかげさまで……。大分楽になりました」
そう言って微笑むキョウジの顔色が、最初の時よりだいぶ良くなってきている事に、東方不敗は胸をなでおろす。
「……意識も戻りましたし、熱も下がっているようですし……。明日、もう一度検査してみましょうか。結果を見て、これからの治療方針を考えましょう」
点滴を打ち終えた看護士が、キョウジの体温や血圧を記録しながらそう告げる。キョウジの容体が、どうやら快方に向かっていると感じたドモンとレインも、ほっと胸をなでおろした。
「ところで、シュバルツさんは?」
看護士が出て行ったのを見計らってから、レインはキョウジに問いかけた。
「あそこ」
そう言いながら、キョウジが天井を指さす。二人は天井を見上げてみるが、そこには、普通の天井の光景があるだけだった。ただ、ドモンには、シュバルツがそこに居ると言う気配が伝わっていた。東方不敗も、同様のようだった。
「皆、本当に――――」
ありがとう、と、改めて礼を言おうとしたキョウジだが、1人、礼を伝えたい人間がこの場にいない事に気づく。
「……ハヤブサは?」
「ん?」
「ああ、そう言えば……」
ドモンと東方不敗がハヤブサの姿を求めて辺りを見回す中、レインだけが「えっ? ハヤブサさんって?」と、きょとんとしていた。
「ああ……確か俺たちが兄さんを病院に連れて行っている間、ハヤブサにシュバルツの側についててもらってたんだけど……」
ドモンの言葉に合わせるように、皆の視線がシュバルツがいる天井の方に集まっていく。
(……………!)
ここに至ってシュバルツも、初めてキョウジの居場所をハヤブサから聞きだしてから、彼の存在が自分の脳内から完全にフェードアウトしていた事実に気づいた。
しまった――――!
私とした事が、ハヤブサに礼も云わずに……!
ハヤブサを追わねば、と、一瞬身体を動かしかけて、シュバルツは、何故か少しためらってしまう自分を感じてしまう。脳裏に、自分をベッドに押し倒して『衆道』がどうのこうのと、にっこり微笑みながら口走っていたハヤブサの姿がよぎったからだ。
「……ハヤブサを、つれてきた方がいいのか……?」
天井からシュバルツの声だけが降ってくる。
「できれば、お礼を言いたいのだけれど……」
キョウジの声に、少し懇願するような色が入っていたから、シュバルツは逆らえなくなってしまう。
「分かった……」
シュバルツは、ハヤブサの後を追う事にした。
(ハヤブサが向かうとしたら、やはり、『里』の方だろうな……)
そう見当をつけて、シュバルツは『隼の里』の方へと向かっていた。ハヤブサには、里の方に任務の完了を報告する義務があるはずだった。だから、多少の行き違いがあったとしても、里の方で待つ事が出来れば、必ず彼と合流できるだろう――――シュバルツはそう考えていた。
(問題は、ハヤブサの『案内』なしで、隼の里に入れるかどうかだが……)
ある程度の場所までは、おそらく行きつく事が出来るだろう。だが、そこから先に自分が踏み込めるかどうかは、里の人たちの『意志』次第だろうと思う。
「……………」
シュバルツは、あの優しかった里の人々に、想いを馳せる。
誰か一人でも、自分の事を覚えていてくれる人がいるだろうか――――。
ふと、前方に人の気配を感じて、シュバルツは顔を上げる。
その人間は、前方に流れる小さな清流に、釣り糸を垂れていた。
(ハヤブサ―――!)
目的の人物の姿を認めたシュバルツは、走る速度を落とし、そこに近づいて行こうとした。
だが。
何故か近づく事に躊躇いを感じたシュバルツの足が、勝手に止まってしまう。
気配を消して、ハヤブサから死角になるように、大きな樹の影にその身を置いた。
(………………)
とにかく、気持ちを少し整理してからハヤブサに声をかけようと思った。
(……全く! 何だって言うんだ…。そもそも、あいつが私に変なちょっかいばかり掛けてくるから――――)
シュバルツは腕を組んで考え込んだ。
こんな事で悩むのもばかばかしいと分かってはいるが、どうしても『衆道』とか言いながら微笑んでいたハヤブサのイメージが、シュバルツの中で引っかかってしまう。何でハヤブサは自分に向かってそのような事を口走ったのだろう。私は何か、あいつがそういう事を言ってくるような事をしてしまったのだろうか。
(……………)
考えすぎかとも思いたい。しかし、一度ならず二度までも、彼は自分を押し倒して来たのだ。果たしてこれを、『何事もなかった』と、素通りしてしまっていいのか―――。シュバルツは、その判断に迷う。
ハヤブサに百歩譲って『そっちの趣味』があったとして。
じゃあ、何故、彼はわざわざ自分に向かってそういう行動を―――。
それが一番、理解に苦しむ。
そりゃあ確かに、『裸』で眠りこけていた私も悪かったかもしれない。しかし、裸になったのだって、敵から攻撃されたのが原因であって、半ば『不可抗力』みたいなものではないか。
服をすぐに着なかったのも悪かったかもしれないが、まさか自分が『そういう』対象として見られているなんて、夢にも思わなかったから―――。
しかし……ハヤブサ……。
あいつは本当に、こちらの事をそういう『対象』として見ているのだろうか…?
「……………」
無いな。
それは、無い。
シュバルツは、半ば強引にそう結論付けた。
自分はそういう対象になるべきではないし、ならない自信もある。
大体、さっき押し倒されたときだって、ハヤブサは本気を出してこちらを抑えつけてはいなかった。捕られたのも右手一本で、左手はがら空き。反撃の余地は十分に与えられていた。
もし、ハヤブサが本気を出してこちらを抑えつけにかかってきたら、あんなものでは済まないはずだ。
(……まあ、『冗談』だったんだろうな……。あいつの『冗談』は、時々性質が悪いから――――)
シュバルツは知らず、ふっとため息を吐く。
こちらが不用意に肌を見せた姿が、ハヤブサにとっては目障りで、煩わしいものだったのかもしれない。
だいたいハヤブサは、『私』の正体を知っている。
知っていたら、普通は私をそういう『対象』からはまず外すはずだ。
私は――――。
ドンッ!
突然、『何か』がシュバルツの左耳を掠めて、背後の樹に到達する。
「――――!」
驚いたシュバルツが顔を上げると、彼のすぐ目の前にハヤブサの『笑顔』があった。そして、自分のすぐ傍を掠めた物が、ハヤブサの『右手』だったと理解する。
「よう、シュバルツ。どうした? わざわざ追って来てくれたのか?」
覆面もつけず、タンクトップとアーミータイプのズボンにブーツと言った、比較的ラフな格好をしたハヤブサが、にっこりと笑みを浮かべる。
「ハ、ハヤブサ――――」
シュバルツは、ハヤブサに曖昧に答えながら、反射的に身を引こうとしていた。目の前のハヤブサは、確かに『笑顔』だ。だが―――その目が笑っていない。何故か『殺気』すら感じてシュバルツは戸惑ってしまう。そして何より、この距離――――。ハヤブサが『近すぎる』と思った。
だが、シュバルツが身を引く事を、ハヤブサは許さなかった。
ドンッ! と、音を立てて、ハヤブサの左手が――――シュバルツの右耳を掠めて、彼の逃げ道をふさぐ。
(逃がさない)
そこにはハヤブサの明確な意思が存在していた。
「あ……その……」
シュバルツは、逃げるつもりが無い事、戦う意思が無い事をハヤブサに示すように、少し身体の力を抜く。
「ひ、一言『礼』を言いたくて……。いろいろと世話になったから―――」
そう言ってシュバルツは、申し訳なさそうに下を向く。そんなシュバルツの様子を、ハヤブサはじっと見ていた。
「キョウジも……お前には礼を言いたがっていた……」
「ああ………」
ハヤブサの笑みが、ふっと優しいものになる。
「構わないのに…。『龍の勾玉』の件では、礼を言わねばならぬのは、寧ろこちらだ」
そう言いながらハヤブサは、シュバルツから身体を離す。
「龍の勾玉は、無事に浄化する事が出来た。お前たちのおかげだ」
ハヤブサは、あの瞬間の事を思い出す。
キョウジの胸の前で光を放っていた勾玉は、そこから派生した小さな女の子と、その母親が天に還っていくのと同時に、細かな光の粒子となって消えて行くのを、自分も確かに見た。
あれ以来、勾玉の波動も全く感じられなくなったから、もう、200年ごとに誰かの身に悲劇が降りかかる事を恐れる必要もないのだろう。
(もしかしたら『勾玉』は、宿り主として、キョウジを『選んだ』のかもしれない)
ふとハヤブサは、そう思った。
そうでなければ、残月たちが一度手に入れた勾玉を簡単にロストする訳が無い。
きっと、キョウジに強烈に『惹かれた』のだ。
勾玉自身が封印の袋を突破して、飛びださずにはいられないほどに――――。
「ハヤブサ……」
ハヤブサが穏やかな表情で天を仰いでいるのを、シュバルツはただ見守った。
「この件では、お前たち二人には、本当に迷惑をかけてしまったな…。済まなかった……。
そして――――里の者を代表して、心よりの感謝を伝えたい」
ハヤブサの言葉に、シュバルツは首を振る。
「『龍の勾玉』を浄化したのはキョウジだ。だから、その言葉はどうかキョウジに」
「じゃあ、お前がキョウジにそう伝えておいてくれ」
「ハヤブサ……!」
この言葉に、ハヤブサがもうキョウジには会わずに里に帰るつもりなのだ、と言う明白な意志を感じて、シュバルツは何故か少し淋しさを感じてしまう。
「そうか……」
だがハヤブサにはハヤブサの事情がある。きっと、これ以上引き留めるのは野暮と言う物なのだろう。
しかしシュバルツは、「分かった」と、言う事が出来なかった。何故なら、そう言おうと彼が顔を上げた瞬間、視線が合ったハヤブサが、かなりの怒気を食んだ目でこちらを睨んでいたからだ。
「ハ、ハヤブサ?」
驚くシュバルツに、ハヤブサから思いもかけぬ言葉が投げかけられる。
「だがな、シュバルツ……。俺はちょっとショックを受けているんだぞ?」
「……え?」
「……俺は、あの後意識の無いお前をかくまって、3日3晩付き添ったんだ」
「――――!」
ハヤブサの言葉にシュバルツは、そんなに自分は気を失ってしまっていたのかと衝撃を受ける。
「それなのにお前ときたら、目が覚めたとたん『キョウジ』の事ばかり気にして――――」
「あ………!」
「揚句、キョウジの居場所を俺から聞きだした、と、思ったら、わき目もふらずにそっちに飛んで行ってしまって―――」
「う………!」
ハヤブサの鋭すぎる指摘に、シュバルツは二の句が継げなくなってしまう。
確かにそうだ。あの時自分は、キョウジの事で頭がいっぱいになってしまっていた。
目の前に居るハヤブサへの配慮すら、忘れてしまうほどに―――。
絶句するシュバルツに向かって、ハヤブサは乾いた笑みを向ける。
「所詮、俺の存在なんて、お前にとってはその程度のものだったんだな…。ま、分かってはいたけど……」
「そ、それは違う!!」
シュバルツは慌てて否定する。キョウジは大事だ。どうしたって大切だ。だが―――ハヤブサの存在も、自分の中では決してないがしろにしていいものではないと感じる。
「済まない、ハヤブサ…! 何を言っても言い訳にしかならないが、あの時私は、本当にどうかしていたんだ…! 『キョウジ』の事で、頭がいっぱいになってしまっていて―――」
懸命に言葉を紡ぐシュバルツを、ハヤブサは黙って見つめる。
「お前の事をその……無視してしまった格好になってしまった事は、本当に済まないと思っている。謝っても許されるものではないかもしれないが、心より詫びる…! 本当に、済まなかった……!」
そう言ってシュバルツは、頭を下げる。
「シュバルツ……本当に、俺に『悪い』って思っているのか?」
頭上から、ハヤブサの声が降ってくる。シュバルツは頷いた。
「ああ……。お前だって、私の中ではとても大事なんだ…。ないがしろにしていい存在なんかじゃないんだ……」
自分に、懸命に手を差し伸べてくれたハヤブサ。
怒ってくれたハヤブサ。
涙を流してくれたハヤブサ。
そんな彼を、『失いたくない』とすら、願ってしまいそうになる。
これは――――『エゴ』なのだろうか。
それなのに、どうして私はあの時
ハヤブサへの配慮を忘れてしまっていたのか―――。
どのような状況であろうとも、そんな事、許されるはずもないのに。
「じゃあシュバルツ……俺に『悪い』って思っていると言うのなら―――『証拠』を見せてもらおうか」
「証拠?」
顔を上げるシュバルツの視界に、腕を組んでにやりと笑いながら立つハヤブサの姿が飛び込んでくる。
「今から俺の言う事を一つ聞け。それが出来たら、許してやるよ」
「………!」
「やってくれるよな?」
ハヤブサからの提案に、シュバルツに拒否する理由もあろうはずがない。彼は頷いた。
「ああ…。分かった。それで、お前の気が済むのなら……」
この状況。ハヤブサに何を言われても、何をさせられても仕方が無いとシュバルツは思う。
しかし、何をすればいいのだろう。
また、『殴らせろ』とでも言われるのだろうか?
シュバルツは、覚悟を決める。
だが、ハヤブサから課せられたものは―――意外な事だった。
「目を閉じて、俺の名前を言え」
「えっ?」
「それが出来たら、許してやるよ」
「……それだけで、いいのか?」
シュバルツは思わず聞き返していた。この状況でふっかけられる『課題』としては、いささか簡単すぎやしないだろうか。もっと無理難題をつきつけられても、よさそうなものなのに……。
だが、ハヤブサは微笑みながら促してくる。
「もちろん。やってくれるよな?」
どうやらハヤブサが心底そう望んでいる様子に、シュバルツは頷くしかない。拒否する気もないが―――。
ただ、あまりにも簡単すぎる『課題』
若干嫌な予感がするのは何故なのだろう。
「……これでいいのか?」
とにかくシュバルツは、目を閉じる。
「ああ」
ハヤブサは頷いて――――シュバルツに先を、促した。
「さあ、俺の名を」
「分かった……」
シュバルツは、ハヤブサの『要望』に応えるべく、その口を開いた。
「ハヤ―――んんっ!?」
いきなり口を塞がれて、シュバルツはこれ以上言葉を紡げなくなってしまう。恐ろしく近くにハヤブサの『体温』を感じる。自分の開かれた口腔にハヤブサの『舌』が侵入し、蹂躙されて行くのが分かった。
(な……ッ! もしかしなくても……キス、され、た……!?)
状況を正確に理解して、咄嗟に身を引こうとしたシュバルツの身体を、ハヤブサの両腕が捕らえる。「逃れる事など許さない」と言わんばかりに抱きしめられ、角度を変えて更に深く口づけられた。
戸惑い逃げるシュバルツの舌が、ハヤブサによって捕らえられ、何度も強く吸われる。
「ん……ふ……ッ」
(苦しい―――! 息が……ッ!)
これがハヤブサの望みなのだとシュバルツは悟ってしまっているから、逃れる事が出来ない。
しかし、息が出来なくて苦しいので、シュバルツは思わずハヤブサに縋りつく様な格好になってしまう。
それにしても、長い。
長すぎる。
こいつ、いつまで私に口付けをしているつもりだ……ッ!
思わずシュバルツは、ハヤブサの肩をドン、と叩く。
それが合図となるかのように、ようやくハヤブサは、シュバルツを『解放』した。
「…………ッ!」
ハヤブサから少し距離を取る様に飛びのいたシュバルツの顔が、赤く染まっている。対してハヤブサは、冷静そのものだった。
「……旨いな。想像していたよりもずっと――――」
そう言いながらハヤブサは、舌なめずりをしている。それを聞いたシュバルツの顔色が、更に真っ赤になった。
「な――――!」
「……俺の『名前』に、『あ』のつく母音が多くて良かった」
そう言ってハヤブサが、にやりと笑う。
「ハヤブサ…! お前……ッ! いい加減にしろ!!」
シュバルツからハヤブサに向かって鉄拳が飛ぶ。だがそれが当たる直前、ハヤブサはするりとかわした。
「じゃあシュバルツ……『また』会おう」
「誰が会うか!!」
シュバルツの怒鳴り声に、ハヤブサの笑い声が返ってくる。
「キョウジによろしく――――」
それだけ言い残すと、龍の忍者の姿は今度こそ森の中へと消えて行った。
(あいつ…! 何を考えているんだ…ッ! ……て、言うか、『今の出来ごと』を、私はキョウジにどう報告すればいいんだ――――!)
思わぬ変な課題を背負い込んでしまった形になったシュバルツは、知らず頭を抱えてしまう。
そんなシュバルツの悩みもどこ吹く風と言わんばかりに、『隼の里』をその懐に抱える山の景色は、今日も平和だった。
シュバルツが、今日の出来事をキョウジに報告するか否か――――。
それは、みなさんの想像に、お任せする事にして、この物語のペンはここに置く事にする。
おまけの小説(キョウジ兄さんたちに捧げる物語)
いかがでしたでしょうか?
すみません。腐れていて…。趣味丸出しの展開で申し訳ありません。
これを先の話のラストに組み込もうとして―――(これを組み込んだら、本当に『BL小説』になってしまうやんか!!) と、気づいた私は、組み込むことを遠慮させていただきました。
ですから、これを読まれた方も、このエピソードをあの話のラストに持ってくるか来ないか―――。どうかご自分の中で、ご自由に決断なさってください(笑)ラストに組み込んでしまうもよし。全く独立した話として、楽しむのもまた良しです。
しかし…『絡み』のシーンって、本当に書くのが難しいですね。焼き切れそうになる『理性』を総動員して、読みやすい文章をと心がけたつもりですが、果たしてうまくいっているのかどうか……。謎です(笑)
私の拙い文章にお付き合いいただき、どうもありがとうございました。
また、何か思いついたら、勝手に載せにきま~す。