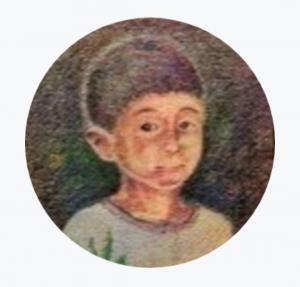ひまわり
毎年5月にひまわりの種を蒔くようになって、かれこれもう10年になろうとしている。年中行事の一つという感覚になっていた馴染みの作業だったが、今年は不幸があり予定通りとはいかなかった。
庭には雑草に混じってどくだみが生い茂り、白い綺麗な花を咲かせていたが、もうそろそろひまわりの種を蒔こうと、夕方幾分涼しくなってからそれらを取り除いた。普段しない作業だったから腰に鈍い痛みを感じ、適当な頃合いを見て作業をやめた。何も明日がないわけではない。今日いっぺんにやることはないではないか。そう思い直して作業をやめた。気づかない間にどくだみの匂いが手やシャツに染みついつて、風呂に入るまで取れなかった。
草取りをしたこの日の夕方でさえ、翌日のことは私には分からなかった。ちょうどこの日、草取りを終えた私は友人の見舞いに行った。だが、会わずに帰った。
翌朝、けたたましく電話が鳴った。友人が今さっき息を引き取ったという。2階で寝ている私の寝室のドアを母がガラリと開けた。昨年、母が軽度の脳梗塞を発症した時も、父が私の寝室のドアを血相を変えて開けたことを思い出した。朝早く、両親のどちらかが私の部屋のドアを開けに来るということは、何か良くないことが起こった合図なのである。
母が言葉を発するまでもなく、その顔を見た私は来るべきものが来てしまったと分かった。 両親は連絡を受けて足早にお宅へ向かったが、私は取り立てて急がなかった。もうそろそろ危ないと言うのであれば、何が何でも急いで駆けつけたと思うが、どんなに急いで駆けつけたところで、もう彼はいないのである。
「死んだ顔を見たってしょうがないじゃないの」
と言ったのは私の亡くなった祖母であったが、その言葉が頭の中に浮かんだ。私が対面した時、静かに旅立った友人の亡骸には、所々まだわずかに温もりが残っていた。
その温もりは、冬に使う湯たんぽだった。前の晩、床に入る時に沸かして湯が冷めた、翌朝の湯たんぽ、人肌のようにほんのり温かい、あの湯たんぽだった。
その日の夕方、私はひまわりの種を蒔いた。1月遅れではあったが、この日を友人の命日だけにしたくなかった。夏を迎え、このひまわりが咲く頃、自分は一体どんな気持ちで生きているのか。それを確かめたかった。
ある日、もうそろそろ開花ということを悟ったかのように、ひまわりは短期間でグングンと背を伸ばし 、蕾を大きく膨らませた。
背もいちばん高く、蕾もいちばん大きかったのがいちばん乗りで花を咲かせた。それから間もなくして、それにつられるように他の蕾も次々と花を咲かせた。どれも太陽が顔を出している方に向かって花を咲かせるものだから、私にはそっぽを向き愛想が悪いのは例年と同じだった。
あの日から今日まで、人の命が尽きた日から育ってきた花の命である。人の命も散るには幾分早すぎたが、花の命は人のそれよりももっと早い。そう思うと、このひまわりが愛しくてたまらなかった。あの日から命を繋いできたのである。思い出しては窓越しに眺め、夜たっぷり水をやり、蚊に刺されながら匂いも嗅いだ。甘い匂いは去年と何も変わらなかった。
あの日から、どうも暦の感覚が怪しくなった。息を引き取った日でさえ、時々葬儀が行われた日と勘違いしてしまうくらいである。どれくらいの月日が流れたのかさえ、分からなくなる時がある。そんな状態であっても、それだけの月日が流れたからこそ、ひまわりは咲いたのであり。
ふと気がつくと、昼間あれほど賑やかにやかましく泣いていた蝉の声は消え、夜になると鈴虫の鳴き声が聞こえ始めた。あれだけ首をピンと伸ばし、上を向いて咲いていたひまわりも頭(こうべ)を垂れ始めた。
まだまだ暑い日は続いているが、あの日から3ヶ月が経とうとしている。過ぎ行く夏を惜しむように、最後の一輪が花を咲かせた。
ひまわり
2025年8月25日 書き下ろし
2025年8月27日 「note」掲載