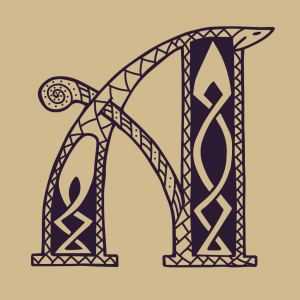訣れの儀式
たまに顔を出している某ミスキーサーバーの合同誌企画に別名義で寄稿した一般小説です。テーマは本。夫を喪った主人公の半日を描いています。
早春の蒼穹へ伸びる枝は、ほころび始めた梅の花で彩られている。冬の間に随分と味気なくなった庭の中で、紅白の花弁だけが鮮やかに春の訪れを告げていた。今からでも蝋梅を移植したら根付くだろうかというのが夫の冬ごとの口癖だった。
だが、もうその言葉を聞くことはない——永遠に。
掃き出し窓越しに中庭を眺めていた洋子は、ひとつ嘆息して仏間を振り返った。
夫の両親の位牌をおさめた仏壇の前にのべられた客用布団。そこに横たえられた夫の顔からは血の気が失せ、目も口もかたく閉じられている。
彼の心臓は昨日、その役割を終えた。洋子自身はおろか、持ち主である夫も予想外のことだったろう。
たしかに現役時代は絵に描いたような激務の中に身を置いていた。だが五十を過ぎ役員に進んでからは、会社から電車で二時間弱の場所にある実家に移り住み、口やかましくしていては下によくないからと仕事量を緩やかに減らしていった。六十になって完全に退いてからは、ゴルフと庭いじりに精を出す悠々自適な楽隠居を決め込んでいたのだが。
心臓への一撃とはよく言ったものだ。
——夫、清の死因は急性心筋梗塞だった。
つくりもののような夫の遺骸から視線を剥がし、洋子はふたたび庭に目を向けた。
マンション暮らしをしていた頃は植物の類いにまるで興味のなかった夫は、仕事に代わる生きがいとばかりにここ数年、庭の丹精に励んでいた。義父母が相次いで亡くなって以来、わいて出たように蔓延っていた雑草は根絶やしにされ、花壇に整え直された。生来の几帳面な性格と、仕事で培った、育てる手間を厭わない姿勢がうまく働いたのだろう。ほどなくして庭は夫のテリトリーになり、洋子が口を出す余地はなくなっていた。
そのうちに、夫の縄張りを眺めながら考えをまとめるのが洋子の習慣となっていた。もう主はおらず、劇的な変化があるはずもないのに、確かめるように草木のひとつひとつを目で追っている自分に気づき、苦笑をこぼす。そして頭を振った。
なにしろ急のことで、考えることは山のようにある。臨終の瞬間に立ち会えなかったこともあり、一夜明けてもいまだに実感がわいてこないが、目の前に積み上がった「片付けること」に向き合わなくてはならない。
通夜は明日の夜で告別式は明後日。
昨日の夕方、夫のなきがらとともに病院から付いてきた葬儀社の担当とひとまずそれだけは決めたが、細かい段取りは今日の午後に改めて打ち合わせることになっている。
昨日渡されたパンフレット——と言うにはだいぶ厚みのある手引きを頭の中に呼び起こし、何を決めておかねばならなかったか、ひとつずつ頭の中でページをめくる。どこかに遺族がすべきことをまとめたチェックリストがあったはずだった。
紙に記された内容を記憶に留めることを洋子は得意としていた。図解の多い冊子などであれば、画像の位置も含め精度高く頭の中で再現できる。おかげでライフワークとなった翻訳の仕事も、他人に比べて効率よく進められている気がする。もっとも、最近は原書と孤独に向き合う文芸翻訳ばかりで、社内翻訳者としてチームで仕事をしていた頃とは違う。他人と競っても、もはや意味はないのだ。
SEをやっている息子は、電子媒体で資料を渡されなかったことにぼやいていたが、洋子にとっては好都合だった。この記憶能力はディスプレイに映ったものには通用しないからだ。何故だかはわからないが、それが理由でいまだに電子書籍の類いは不得手だった。訳書の電子版を出したいという話を持ちかけられるたびに顔を顰めていると——自分で訳したはずなのに、内容が頭に入ってこず現物の確認に難儀するからだ——決まって夫は鷹揚な笑いとともに洋子を諭したものだった。
——どうしても電子だと確認できないなら、俺が代わりに読めばいいだけじゃないか。君よりも君の訳した文章を読み込んでいるんだからね。
そう、夫の清は洋子自身よりも洋子が訳したものを読んでいた。
もともとは同じ会社で翻訳を頼む側と頼まれる側で、清は洋子の訳文でいくつもの資料を作っていた。それが続けばいきおい、清の方が訳文に接する機会が多くなる。そしていつしか清は洋子が訳す際の癖に精通し、それだけでなく、あのときの訳はああだった、と諳んじられるようになっていた。
——あぁ、今度から誰に電子版を読んでもらおうか。
息子はだめだ。昔から読書にまるで興味がない。こちらに移住してから本格的に取り組み始めた文芸翻訳でいくつか訳書を出しているが、息子は一冊も目を通していないらしかった。無理して読ませるものでもないからと笑う洋子に、家族の仕事に興味がないなんてなぁ、と夫は寂しそうにしていたことが急に思い出された。
「母さん、昼メシ……何やってんだ、ぼうっとして」
昼食に呼びにきた息子の声に、洋子は肩を揺らした。物思いに耽っている間に随分と時間が経っていたらしい。
「葬儀社の人と打ち合わせすることを頭の中で整理していたのよ。呆けてなんて失礼な」
「いや、はたから見たらボーッと突っ立ってただけなんだけど……なぁ、本当に家でやるつもり?」
胸元に守り刀が置かれた遺体を見遣り、息子——靖一は問うた。父親譲りで主張の強い眉は顰められている。
義父母に倣い自宅で葬儀を行うことに、靖一はいい顔をしていなかった。滅多に客を招くことのない我が家が蹂躙されるようで気が乗らないのだ。生まれ育ったわけでもなく、ほんの数年しか住んでいないにもかかわらず、夫が亡くなった今、もう家の主人になったつもりらしい。
「お父さんが葬儀場が嫌いだったんだから仕方ないじゃない。心配しなくても仕切りは母さんがやるから任せなさい。それに詩織も知らないところでただじっとしているより、家の方が気が楽でしょう」
孫の詩織は五歳になるが、場所見知りをする性質で、慣れない場所に長時間いられない。よそよそしいセレモニーホールはなおさら苦痛だろう。だが自宅であれば、弔問客で多少忙しなくなってもそれほど影響はあるまい。いざとなったら自室に逃げ込むことだってできる。
「母さんがそう言うなら、まぁ、構わないけど」
「私のときはあんたたちのやりたいようにやればいいわよ。その代わり今回は私のしたいようにさせてもらうわ」
「わかったって」
両手をあげて降参の意を示す靖一にしかめ面で応じると、洋子はダイニングキッチンに足を向けた。
「——最後に、ご不明な点やご不安な点はございませんか?」
「大丈夫だと思います。もし何かあれば、式の前に確認させていただくので」
穏やかな笑みを浮かべながらも、テキパキと話す女性スタッフの宮内に洋子は頷く。
妻が喪主を務めるということで葬儀社が気を回した結果の人選かと思いきや、どうやらベテランらしい。隣に座る若手の男性スタッフはメモを取ることに徹して、ほとんど口を差し挟むことはなかった。
それは靖一も同様で、ときおり質問を差し挟む程度。それでも宮内は靖一の確認もとりながら話を進めていたが、途中から洋子が頷けば問題ないと判断したようで、気がつけばリビング代わりの茶の間には女二人の声だけが響いていた。
明日はどうぞよろしくお願いします、と玄関先で頭を下げた葬儀社の二人を見送り、洋子は一息つくためにダイニングキッチンに向かった。思っていたよりもスムーズに終わったとはいえ、二時間以上、打ち合わせをしていたのだ。こちらに越してくるのと同時に会社勤めを辞めた洋子にとって、久しぶりの長丁場。疲れていないわけがない。
とはいえ、磨りガラス越しに差し込む光は弱々しくなっており、空が夕闇に覆われるのもそう遠くないはずだ。
軽くつまめるものは戸棚にあっただろうかと思いながらキッチンの引き戸を開けると、冷蔵庫に向かって身を屈めていた息子の妻——香里がぎょっとした表情で振り返った。
「びっくりした。あ、夕食は私が作りますから、洋子さんは休んでいてください。打ち合わせ疲れたでしょう?」
結婚前から義理の母のことを名前で呼ぶ香里に、洋子は苦笑で応じた。
「そう、疲れたからつまめそうなものを探しに来たのに、見つかっちゃったわね。夕食なんて店屋物でいいわよ。お父さんのせいで昨日からバタバタしてるんだから」
義父の急死を気づかう配慮はありがたいが、夫に先立たれた哀れな未亡人を気取っている場合ではない。敢えて夫のことを腐すと、香里は眉尻を下げた。
「でも、明日になったらお義父さんのご霊前に好物を供える暇もないですよね? せっかくだから今日は好きだったものをみんなで囲めればと思って」
明日の通夜振る舞いは、清の友人がやっている鮨屋に頼んでいる。これは生前の清が冗談交じりに口にしていた希望のひとつだ。自分の葬儀ではあいつの握った寿司を親しい人間に振る舞いたい。そうしたら悔しさのあまり生き返れるかもしれないだろう、と。
どこまで本気で言っていたのかもはや知る由もない。だが洋子はそのとおりに手配した。なにしろ自宅葬儀は細々とした手間がかかる。頼れるものには頼ってしまった方が良い。
棚に引っ掛けてあるエプロンを手に取り、洋子はおどけた表情を浮かべた。
「……だったら私も作るわ。あちらで会ったときに香里さんの料理だけ褒められたら癪だもの」
「そんなことは……でも、手伝っていただけたら嬉しいです。レシピを訊きたいものもあったので」
「そんな大層なものはないけど、何を作るつもりだったの?」
「えぇとですね」
手の中の書き付けを開いた香里が読み上げたメニューに、洋子は目を瞬かせた。
「わぁ、すごい! ごちそう!」
仏間に続く座敷の中央、来客があるときだけ使う座卓に広げられた料理を目にした詩織は、目を輝かせた。待ちきれないように唐机に伸ばされた小さな手を、香里はピシャリとした口調で制する。
「おじいちゃんにご挨拶してからよ。ちょっと待ちなさい」
「えぇー? おじいちゃん、バイバイしちゃってもうもどって来れないんでしょ? なのにいただきますっていうの?」
邪気のない顔で首を傾げる詩織に、香里は顔をこわばらせた。五歳の娘は死というものの概念を、まだ飲み込みきれていない。祖父はもう二度と目を覚まさないことを、一日がかりでどうにか理解させたところだった。
「そう、遠くに行ってしまったの。だけど、こうやってお鈴を鳴らしてご挨拶をすればおじいちゃんには聞こえるのよ」
枕飾りの前に膝をついた洋子が、半分ほど開けた襖越しに声をかける。
「ほんとにぃ?」
疑わしそうな顔で近寄ってきた詩織は洋子と清の顔を見比べる。当然だが、清はぴくりとも動かない。詩織の眉根が寄った。
「えぇ。もっとも、疑っている人の声は聞こえないけどね。それに、そもそもご挨拶をしない子の声は聞こえないでしょうけど」
わざとのように意地の悪い物言いをすると、詩織は慌てた表情を浮かべた。座布団から洋子が退いてやると、詩織はおっかなびっくりといった様子で厚みのある正方形の上に正座する。普段使っている座布団は草臥れたものばかりで勝手が違うのだろう。
あっているか、と目顔で訊かれた洋子は頷き、横合いから鈴を鳴らした。
「えっと……おじいちゃん、いただきます」
半ば口の中でつぶやかれた挨拶の言葉は、かろうじて洋子の耳にも届いた。
「めしあがれ。おじいちゃんの分も食べてあげてね」
「いいの?」
自分の座布団に戻った詩織は、やったぁと小さく叫んで皿を手に取った。大皿に盛られた料理たちを吟味する視線は真剣そのものだ。香里が溜息交じりに釘を刺す。
「途中でおなかいっぱいにならないように、少しずつ取るのよ。全部食べるんでしょ?」
今日のメニューは和洋折衷、しかも子どもが好んで食べそうな味付けのものばかり。普段は自分たちの年齢と作り置きのしやすさから、食卓にはいわゆる田舎料理の類いが上ることが多い。だが今日のメニューは、詩織の誕生日か何かのようだ。おまけにすべて、清の密かな好物だったという。
「やっぱりはじめはねぇ、おじいちゃんがすきだったチキン!」
甘辛く味付けされ、ケチャップとコチュジャンで赤く光る手羽先に詩織の手が伸びる。とあるファミリーレストランの人気メニューを模したものだ。清と詩織が二人だけで訪れたときには必ず頼んでいたらしい。そういえば詩織の誕生日にそれらしいレシピのものを山ほど出した際、清もかぶりついていた。そのときは気にも留めなかったが、まさか好物だったとは。
他にもコショウを利かせたジャーマンポテトや具だくさんのミネストローネ、甘辛い餡をからめた肉団子などが並んでいる。
「こんなことならもっと洋食を作れば良かったかしらねぇ」
場違いな感が否めない筑前煮を取り分けてもらっていた詩織が、うーんとね、とつぶやいた。
「おばあちゃんにかくれて食べる……なんだっけ……はいとくかん? がスパイス、なんだって」
意味もわからないまま、清がかつて口にしたであろう台詞を反芻する。
「あの人は子どもになんて言葉を……」
洋子は呆れ、思わず溜息をつく。そこに詩織の言葉が被さった。
「あとねぇ、こういうのをたべたあとって、おばあちゃんのりょうりがもっとおいしいんだって。私もそう思う! だからママ、もっとニンジンさんとって」
思いがけない言葉に絶句する洋子をよそに、かぶりついていた手羽先の骨を放りながら靖一も頷いた。
「あぁ、たしかに。ドイツに住んでたときとか、夕食に和食のおかずがないと落ち着かなかったもんな」
靖一が小学生の頃、清の海外赴任で一時期ドイツに住んでいたことがある。
ちょうど洋子の目の前にあるジャーマンポテト——あちらではシュペックカルトッフェルン——は、そのときに覚えたものだ。日本に戻ってからも、靖一にせがまれてよく作っていたのだが、ビールのアテにちょうどいいと最後のひとかけらまで食べていたのは清だった。明日の弁当に詰めようと思っていたのに、と空になった皿を見ては小言をこぼしていたことを何故忘れてしまっていたのだろう。
バツの悪さを、ドイツ時代の靖一の口癖を引き合いに出して誤魔化した。
「よく言うわ。パンには合わないって文句言ってたでしょう」
「俺はともかく、父さんは一時帰国のたびに醤油やら鰹節やらを買い込んでたじゃないか」
「……そういえばそうね。日本にいたときより真面目にお出汁を取ってたわ」
日本の本社に呼びつけられるたびに、スーツケースいっぱいに日本の食材を買い込んできていた姿が甦る。たしかにあの頃の清は日本食を随分と美味そうに食べていたものだった。それで、食材やら調味料やらを手に入れるのに難儀しながらも、なんということのない和食を努めて用意していたのだ。
「……四十年も一緒にいれば大体のことを理解っているつもりだったけれど、そんなことないのねぇ」
揚げ焼きにされて焦げ目のついたジャガイモを箸でつまみながら、思わずつぶやきがもれた。
葬儀社の宮内に向かって、夫のことはよく分かっているから何でも訊いてくれて構わないと、とんだ大見得を切っていたことを今更悟り、急に心許なくなったのだ。葬儀の場で、思いもよらないことが起きないと良いのだが。
心なしか背筋を丸めた洋子の姿に、靖一と香里が顔を見合わせる。
洋子の目を盗むように食べていたものがあったとはいえ、結局のところ清は自分の妻がこしらえたものが好きだったのだ。そう二人は了解していたが、洋子には伝わっていないらしい。
「なぁ、母さん……」
「洋子さんはどんな料理でも、清さんが好きな味付けにできるじゃないですか。それが理解っているってことだと思います。私じゃ絶対に無理でしたもの」
洋子が不在にしているときなどに香里が一人で食事を用意すると、清の箸の進みは目に見えて鈍っていた。料理にケチをつけるようなことはないが、落胆していることはなんとなく解るものだ。洋子がよく作るメニューを出してもそうで、なるほど長年連れ添うとこうなるのか、と香里は感動すら覚えていた。そしていつか、靖一にとって自分の料理がそうなる日が来るのだろうか、とも。
だが洋子は相変わらず釈然としない表情を浮かべていて、つい、香里の語気が強くなる。
「私の手料理を靖一さんの好物にすることが目標なんですから、そんな顔しないでください!」
「え? あぁ、そう……そういうものかしら」
気圧され、思わず頷く洋子の隣で、靖一はなんともいえない表情を浮かべたまま、ミネストローネを啜っていた。
夕食後、洋子は一階の隅にある清の書斎に足を踏み入れた。
もとは納戸だったその部屋は、入った正面に壁と同じ幅の机が据えられ、残ったすき間を埋めるように天井までの高さの本棚が造り付けられている。越してきた当初は壁紙がいくらかのぞけていた本棚も、十年も経たないうちに種々の書籍がひしめき合い、いまや床を侵食するまでになっている。
還暦で勤め先の相談役から退くまではビジネス書の類いが優勢だった記憶があるが、久しぶりに目にした蔵書は随分と様変わりしていた。仕事がらみの味気ない本は机から遠い位置に追いやられ、手に届く範囲には園芸の雑誌から哲学書まで、種々雑多な書籍や雑誌、ムックが並んでいる。
引退して以降、清自ら書斎の掃除をしていたため、洋子はここ五年ほど、一切書斎に足を踏み入れることはなかった。興味がなかったということではない。
洋子も離れに仕事部屋を持っており、たとえ夫であっても不用意に覗き込まれたくなかったからだ。蔵書の半分程度は仕事の都合で購入した参考図書とはいえ、「複数ある参考図書から何故その本を選んだのか」を突き詰めていくと、自分の無意識が丸裸にされるようで落ち着かない気分になる。本棚を開陳することはすなわち、思考という最もプライベートな部分を晒しているのと同義だ。
それは清も同様だったのだろう。書斎にいる間はいつの間にかチャットアプリで連絡するようになり、よほど反応がないときも部屋の外から声をかけることが不文律となっていた。
「じろじろ見てしまって申し訳ないけど……先に逝ってしまったのだから諦めてちょうだい」
もはや届かない言い訳を口の中でつぶやき、洋子は本棚に顔を近づけた。
清は一定のルールに従って蔵書を分類し、本棚を構築しているようだった。図書館や書店で見る仕切りはないものの、同じテーマと思われる書籍や雑誌を選り集めておさめていることが見て取れる。
椅子を少し動かせば届いたと思われる範囲には、引退後に目覚めたであろう園芸や哲学書、そして小説が陳列されていた。特に小説は直近の直木賞作家の著作が並んでいて、フィクションに関してはミーハーだったらしいことが伺える。
こうして夫の本棚に相対してみると、あずかり知らなかった面がいくつも見えてくる。
特に、自分も所有している書籍が本棚にあるのを見つけて、なんともいえない気分になった。お互いに読んでいることを知っていれば、感想を言い合うこともできただろうに。だがそれももう、叶わない話だ。
せんのない悔恨を覚えながら並んだ背表紙を眺めていると、一冊だけ、小口がこちらを向いている書籍があることに気づいた。
A五判のソフトカバーだ。何度も読み直しているのだろう、角はすり切れ丸みを帯びている。ビジネス書の類いだろうかと思いながら手に取り、目を見開いた。
それは予想に違わずビジネス書だった。——それも、洋子が初めて手がけた訳書。
出版社からの献本は毎回手渡していたので、本棚にあることは不思議ではない。しかし何故隠すようにしているのだろうか。首を傾げながらページをめくり、ふたたび洋子は目を見開いた。
いくつもの文にマーカーが引かれ、余白にはびっしりと書き込みがされている。
内容についての覚え書きの類いかと思いきや、それは誤字脱字の指摘や訳文そのものに対する感想だった。
もう十年近く前に訳したもので、改めて読み直すと表現の稚拙さが目につき、清の感想——特に訳文に対する指摘には、ありがたさよりも理不尽な苛立ちが先立つ。
——言われなくてもわかっているわ、そんなこと。
書き付けられた鋭い指摘にプロとしての矜持を抉られつつも、右上がり気味の文字を追うことが止められない。中には「アドバイスは採用されなかったらしい」というものもあり、否が応でも当時のことが脳裡に甦ってくる。読み進めるうちに、書き付けられた清の言葉はいつしか思い出のよすがに変わっていった。
長年企業の社内翻訳者を務めていたものの、社外の編集者とやりとりしながらまとまった分量の英語を翻訳していく文芸翻訳はまるで勝手が違い、このときの洋子は生まれて初めて英語に向き合うことに苦痛を感じていた。しかし、ひとたび請け負った仕事を放り出すわけにはいかない。せめて気心の知れた清に客観的な意見をもらえればと、すきあらば訳文の相談をしていたのだ。
今思えばよく付き合ってくれたものだと思う。当時は既に役員で第一線を退いていたとはいえ、閑職だったわけではない。問題に対処するために海外の工場に出張することも一再ではなかった。洋子の相談に応じている場合ではなかったことも多かったに違いない。だが記憶の中の清はいつも、厭な顔ひとつせず洋子の話に相槌を打っていた。たとえそれが、愚痴の類いであっても。
余白を埋め尽くした言葉は、そんな清の人柄そのものだった。
読み終えることを惜しみながら、ついに洋子は奥付のページをめくった。さすがに何も書いていないだろうという予想は、裏切られた。そこにあったのは、走り書きの英文。
——新たな世界に挑戦する君を誇りに思う。この本を俺の身代わりに贈ろう。もはや無用の長物だろうけれど。
清からの訣れの言葉に、もう二度と、ともに人生を歩んできたパートナーから新しい言葉を受け取れないことを思い知った。
洋子はようやく、夫の死が胸に落ちた。
訣れの儀式
気に入っていただけたらWaveboxで絵文字を飛ばしていただければ幸いです。
https://wavebox.me/wave/9r0k9v6cs0p3ew9r/