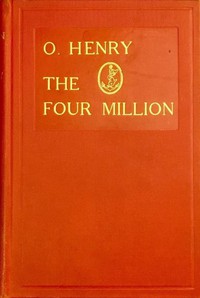
警官と賛美歌
オー・ヘンリー 作
CC収集家 編
原文
"The Four Million" (1906) から The Cop and the Amthem
翻訳者
枯葉
ライセンス
クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンス(https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
特記事項
プロジェクト杉田玄白(https://www.genpaku.org/)正式参加テキスト。
複製元
https://kareha.sakura.ne.jp/trans/#henry
表紙はProject Gutenbergからの複製(Public domain)
https://www.gutenberg.org/ebooks/2776
マジソン・スクエアのいつものベンチで、ソーピーは不安そうにそわそわしていた。野性の鵞鳥が夜に警告の鳴き声をあげるとき、アザラシ革のコートを持たない女性が夫に優しくなるとき、ソーピーがセントラル・パークのいつものベンチでそわそわするとき、冬は近いと思っていただいてかまわない。
枯葉が1枚ソーピーの膝に舞い落ちた。ジャック・フロスト(霜の妖精)の名刺だ。マジソン・スクエアの住民に親切なジャックは、年1度の訪問の折、はっきりとそれを知らせてくれる。四辻の曲がり角で、かれは自分の名刺をオール・アウトドア・マンションの執僕を務める北風に手渡す。そのおかげで、マンションの住民は準備にとりかからせてもらえるというわけだ。
ソーピーの心は、きたるべき寒気に備えるため、生活対策委員会の唯一の委員になるときがきたということに気づきはじめた。それでかれはいつものベンチで不安そうにそわそわしているのだ。
ソーピーの胸にある越冬計画は、それほど立派なものではなかった。そこには地中海のクルージングもなく、ベスビアン湾に浮かぶ眠気を催すような南国の空もない。アイランド(ワイト島にある刑務所を指す)での3ヶ月。それこそがかれが心底熱望するものだった。3ヶ月に及び、食事と宿と気心のあう仲間に不足することはなく、ボレアス(ギリシャ神話の北風の神)や警官を恐れることもない。ソーピーにとって、それは望むべきものの真髄のように思えた。
何年もの間、もてなしのいいブラックウェルズ島がかれの避寒所になっていた。ニューヨークの比較的恵まれた連中がパーム・ビーチとかリヴィエラへのチケットを買うのと同じように、ソーピーもまたアイランドへの避難という慎ましい手配を毎年くりかえしてきたのだ。そして、今年もまたそのときがやってきた。昨晩は、日曜版の新聞を3部、コートより下、膝や踝まわりにかぶせていたものの、古めかしい広場にある活動中の噴水に近いベンチで眠りながら寒さを撃退するのは無理があった。だから、ソーピーの心の中にタイミングよくアイランドのことが浮かんできたのである。かれは、市中の被扶養者たちのため、チャリティーという名のもとになされる活動を嫌悪していた。ソーピーの意見では、法律のほうが博愛よりも優しいものなのだ。公共なり慈善団体なりの施設は尽きることなくあり、そこまで出向けばシンプルな生活を送れるだけの宿と食事を受けられるかもしれない。けれども、ソーピーの誇り高い精神のひとつからいえば、チャリティーの贈り物は逆に心苦しいものだった。もし金銭を持ち合わせていないのならば、博愛の手から与えられるあらゆる利益には精神的屈辱で支払いをしなければならない。シーザーにブルータスがいたように、チャリティーのベッドには入浴という代価がつきものだし、パンには私的個人的質問という代償がともなう。よって、規則にしたがって運営される法律に寄食するほうが、紳士のプライベートな物事に過度に干渉しないという点で、まだましなのだ。
ソーピーはアイランド行きを決意すると同時に、さっそく願望の達成にとりかかった。簡単にこれをやってのける方法がいくつもあった。中でもいちばん心楽しい方法は、どこかの高級レストランで豪勢な食事をとることだ。それから、支払う金のないことを公表し、やってきた警官におとなしく逮捕されればよい。あとのことは親切な治安判事がやってくれる。
ソーピーはベンチを離れて街中をぶらつき、ブロードウェイから5番大通りに満々と湛えられている平坦なアスファルトの海を渡った。ブロードウェイについたところで向きを変え、こぎれいなカフェの前で立ち止まった。ここは、最高に厳選された葡萄や蚕や原形質を原料とする製品が、夜な夜な集まってくる場所である。
ソーピーはベストの一番下のボタンから上には自信があった。髭は剃ってあるし、上着も見苦しくないし、黒のネクタイも、感謝際に婦人伝道師から送られたちゃんとした既製品だ。レストランのテーブルにさえついてしまえば、もはやこっちのものだった。テーブルの上から出ている部分だけなら、ウェイターの疑念を招かずに済むだろう。ソーピーは考えた。マガモのローストくらいが妥当なところか――それにシャブリを1本、それからカマンベールチーズ、デミタッセに葉巻を1本。葉巻は1ドルと見れば十分だ。トータルでも経営者から極度の報復を招くほど高くはなるまいし、それでいて、冬の避難所へと満ち足りた幸せな気分で旅立てるくらいのご馳走にはなるはずだ。
が、ソーピーがレストランのドアをくぐったとたん、ヘッドウェイターの目がそのすりきれたズボンと退廃的な靴に落とされた。力強い手がすぐにソーピーに回れ右させ、一言もかけないままに歩道へと追い帰して、食い逃げの脅威にさらされていたマガモを不名誉な運命から救った。
ソーピーはブロードウェイに背を向けた。憧れの島へと向かう道はグルメの道ではなかったようだ。煉獄に入るための何か別の道を考えなければならない。
6番街の街角には、ライトアップしつつ巧妙に商品を陳列することで、人目を集めていたショーウィンドウがあった。ソーピーは敷石を拾い上げると、ガラスに向かって投げつけた。人々が、警官を筆頭に、街角周辺に駆け寄ってきた。ソーピーはポケットに手を突っこんだまま立っていたが、警官の制服の真鍮のボタンを見たとたん、ほほえみを浮かべた。
「これをしでかしたやつはどこに行った?」と、警官は色めきたって尋ねた。
「おれがやったとかいう可能性は考えてみないのかね?」とソーピーは、皮肉抜きで、愛想よく言った。あたかも、幸運を迎えいれようとするかのように。
警官の精神はソーピーをひとつの手がかりとしてすら受けつけなかった。ショーウインドウを粉々にした人間が法の使徒と話し合うために踏みとどまるなどということはありえない。一目散に逃げ出すものなのだ。警官は、電車に飛び乗るために半ブロック先を走って行く1人の男を目にした。警棒を引きぬき、追跡にかかる。ソーピーは、2回に及ぶ失敗にうんざりした気分で、ぶらぶら歩きはじめた。
通りの向かいに、さほど見栄えのしないレストランがあった。食欲は旺盛ながら財布の紐は固いといった連中のためにあるようなレストランである。皿と雰囲気は重苦しく、スープとテーブル掛けは薄かった。ソーピーは店内へと、難だらけの靴とおしゃべりなズボンを身につけたまま、咎められることなく入っていった。テーブルについたかれは、ビーフステーキ、パンケーキ、ドーナッツにパイを平らげた。それからウェイターを呼び、自分が小銭とすら縁のない人間だという事実を打ち明けた。
「さ、急いでお巡りを呼びな」とソーピーは言った。「紳士を待たせるもんじゃないぜ」
「きさまにお巡りなんぞいるもんか」とウェイターは、マンハッタン・カクテルに浮かぶサクランボのような目つきでバターケーキのような声をだした。「おい、コン!」
2人のウェイターは、巧妙にも左耳がきちんと下にくるようにして、ソーピーを無情な歩道の上に放り出した。ソーピーは、大工が定規を折り広げるように関節一つ一つを伸ばしていき、最後に服の埃を払った。逮捕はバラ色の夢にすぎないかのように思えた。アイランドは遠く彼方にあるように思えた。2軒先のドラッグストアの前に立っていた警官が笑って通りを歩いて行った。
5ブロック歩いたところで、ソーピーの心に逮捕を求める勇気がふたたびわきだしてきた。今回は、かれが愚かにも「楽勝」なことと呼びつけていた機会が訪れたのである。若い女性がショー・ウィンドウの前に立って、中に陳列されている髭剃り用のマグカップやインクスタンドを興味深そうに見つめながら、慎ましく、また楽しげに立っていた。ウィンドウから2メートルのところでは、生真面目な態度の大柄な警官が給水栓にもたれかかっていた。
ソーピーの意図は、見下げはてるべき「ナンパ師」の役割を演じるところにあった。被害者の上品で優美な外見は、すぐそばの良心的な警官の心に、いますぐにでもソーピーの腕に心地よい逮捕の手をさし伸ばすであろうし、そこまでくればささやかで窮屈な冬の避難所は保証されたようなものであった。
ソーピーは婦人伝道師がくれたお仕着せのネクタイをぴんと伸ばし、引っ込み思案なカフスを表に引きずり出し、帽子を傾げて若い女性にすりよった。色目を使い、だしぬけに「えへん」と咳払いしてみせ、にっこりほほえみ、なれなれしく笑いかけ、ずうずうしく恥知らずな、無作法きわまる「ナンパ師」の手管を一通り演じてみせた。視界の隅で、警官がこちらに注目しているのを捕らえた。若い女性は何歩か距離を取り、ふたたび、うっとりするような視線を髭剃り用のマグカップに注いだ。ソーピーはその後を追い、あつかましくも女のそばに立ち、帽子を取って口を開いた。
「おや、ベデリアじゃないか! うちに遊びにくる気はないか?」
警官はまだ様子を見ていた。迷惑をこうむっている若い女性が指をほんの少し動かすだけで、ソーピーは安息の島へのチケットをほぼ手にしたことになる。もうすでに、ソーピーは拘置所の心地よい温もりを感じることができるほどだった。若い女性はソーピーと顔を合わせ、手を伸ばして、上着の袖を捕らえた。
「行くわよ、マイク」と、彼女はうれしそうに言った。「ビールをおごってくれるんなら。あたしはすぐにでも話したかったんだけど、お巡りが見てたもんだから」
樫にしっかりと絡みついた蔦みたいな格好の若い女を連れたソーピーは、打ちひしがれた気分で警官のそばを通りすぎた。自由の身であることを宿命づけられているように思えた。
次の角を曲がったところで、かれは連れをふりほどいて逃げだした。もっとも明るい街並と歌ともっとも軽い心と約束が、夜までの間あちこちで見うけられる地区で、足を止める。毛皮の女たち、コートの男たちが、冬の空気の中を楽しげに動きまわっていた。ソーピーはだしぬけに恐怖を覚えた。自分はなにか恐ろしい魔法をかけられて、逮捕されない体になってしまったのではないだろうか。そう考えてやや取り乱したソーピーは、派手に飾りつけられた劇場の正面をえらそうにぶらついている、さっきとは別の警官に出くわすと、「治安紊乱行為」という手っ取り早い藁にすがった。
舗道の上でソーピーは自分がだせるかぎりの不快な声を励まして酔いどれ騒ぎの真似事をはじめた。踊り、咆え、喚き、とにかくひたすら、天地を轟かさんばかりの勢いで騒ぎまくった。
警官は警棒をくるくると回しながら、ソーピーに背を向け、一通行人に説明した。
「エール大学の連中ですよ、ハートフォード大に完勝したってんでお祝い騒ぎ中なんですな。騒がしくはありますが、害はないですから。上からも放っておけと言われてますんで」
悲しみに沈み、ソーピーは無益な馬鹿騒ぎを中止した。警官はおれを捕らえてはくれないのか? アイランドは到達不可能なアルカディアのように思えてきた。凍てつくような風に、かれは薄い上着のボタンをとめた。
煙草屋の中で、身なりのいい男が揺れる灯りの下で煙草に火をつけようとしているのをソーピーは目にした。男のシルクの傘が入り口のドアのそばに立てかけられていた。ソーピーは中に入り、傘を手にすると、そのままゆっくりと外に出た。煙草に火をつけようとしていた男が慌てて追いかけてきた。
「私の傘になにをする」と男は詰るように言った。
「ほう、そうかい?」と言ってソーピーはにやにや笑った。このけちな窃盗に侮辱まで上乗せしようというわけだ。「じゃあ、どうして警察を呼ばないのかね? おれはあんたの傘をとった。あんたの傘をね! なんでお巡りを呼ばない? あそこの角に立ってるぜ」
傘の持ち主の足が鈍った。ソーピーもまたそれに合わせた。幸運がまた逃げて行きそうな予感を覚えながら。警官は興味津々で2人を見つめていた。
「もちろん」と傘の持ち主は言った――「それはその――なんというか、この手のまちがいがどうしておきるものか、ご承知だとは思いますけれど――私としては――その、もしそちらの傘なのでしたらどうかご勘弁ください――今朝、レストランで拾ったものでして――それを、ご自分の傘だと分かったのでしたなら、そのう――どうか――」
「もちろんおれのだよ」とソーピーは意地悪く言ってのけた。
傘の前持ち主は退散した。警官は、2ブロック先から近づいてくる電車の正面を横切ろうとしている夜会服をまとった背の高いブロンドの女に手を貸すべく、走っていった。
ソーピーは、道路工事中の通りを東に抜けた。かれは憤怒のあまり傘を工事現場の穴の中に放りこんだ。ヘルメットをかぶり警棒を携える連中への不満をつぶやく。こっちは向こうに捕まえてほしがっているというのに、向こうはこっちを誤りを犯すことなどありえない絶対君主とでも思っているらしい。
やがてソーピーは、東区に向かう大通りのひとつにたどりついた。飾り気の少ないひっそりとしたところだ。かれはマジソン・スクエアの方角に顔を向けた。帰巣本能というものは、公園のベンチをねぐらとしている場合であってさえ消えないものなのだ。
だが、とある奇妙に閑静な街角にきたところで、ソーピーは足を止めた。そこには、趣のある古い教会があった。切妻造りで、あちこちに張り出している。菫色のステンドグラスから柔らかな光が溢れだしていた。窓の中では、疑いようもなく、オルガン奏者が、鍵盤をもてあそんでは安息日の賛美歌をきっちり奏でることができるかどうかを確認しているのだ。耳をくすぐる甘美な音楽がソーピーを捕らえ、ソーピーを金網のそばへと吸い寄せた。
月は夜空高く、穏やかに輝いていた。交通量も人通りもほとんどなかった。ツバメが軒下で眠たそうにさえずっていた――ごくわずかのことだったが、その光景は田舎の教会の敷地を思わせた。オルガン奏者が奏でる賛美歌を耳にしたソーピーは金網にしがみついた。というのも、かれは以前にその賛美歌を知っていたからだ。かつての、母とかバラとか大望とか友人とか汚れない思想とか純白といったものがあった日々に。
感極まった精神状態と古めかしい教会の感化力が相重なって、ソーピーの魂は、突如として不思議なまでの変化を遂げた。たちまち、自分の存在を形作っていた数々のものごとに恐怖を感じた。自分が足を突っこんでいた陥穽、堕落した日々、取るにたりない願望、潰えた希望、だめになった才能、卑しい目的。
そしてまた、かれの心もこの新鮮な雰囲気への感動に打ち震えた。瞬間的な強い衝動が、かれを絶望的な運命との戦いに走らせた。かれは自分の身上を泥沼から引きずりだした。かれはふたたび自分をとりもどした。かれは自分を支配していた邪悪を打ち払ったのだ。時間はある。かれはまだそれなりに若い。よみがえってきたかつての熱意に満ちた大望を、しくじることなく追いかけよう。あの厳粛でありながら甘美なオルガンの調べがかれの決意を固めさせた。明日は、喧騒に満ちたダウンタウンに赴き、仕事を見つけるのだ。とある毛皮貿易商が、以前に御者としての仕事を持ちかけてきたことがあった。明日はそこにいって、まだその勤め口が残っているか、尋ねてみよう。世間に顔向けできる生活をはじめるのだ。そして――
ソーピーは自分の腕にだれかが手をかけたのに気づいた。あわててふりむいたかれの目に、警官の大きな顔が映った。
「ここでなにをしているのかね?」と警官は言った。
「なにも」とソーピーは言った。
「じゃあ、ちょっときてもらおうか」と警官は言った。
「アイランドに3ヶ月」と、翌朝、治安判事は刑事法廷で言った。
警官と賛美歌

