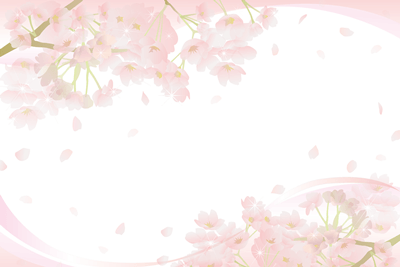
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第一部 第一章 桜花の降る日に
こちらは、
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第一部 落花流水 第一章 桜花の降る日に
――――です。
長い作品であるため、分割して投稿しています。
プロフィール内に、作品全体の目次があります。
https://slib.net/a/4695/
こちらから「見開き・縦書き」表示の『えあ草紙』で読むこともできます。
(星空文庫に戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください)
※使わせていただいているサービス『QRouton』の仕様により、クッションページが表示されます。
https://qrtn.jp/8kssm8j
『えあ草紙』の使い方は、ごちらをご参考ください。
https://www.satokazzz.com/doc/%e3%81%88%e3%81%82%e8%8d%89%e7%b4%99%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab
「メニューを表示」→「設定」から、フォント等の変更ができます。PCなら、"UD Digi Kyokasho NP-R"等のフォントが綺麗です。
創世神話

この国には神がいる。
輝く白金の髪と、澄んだ青灰色の瞳を有する、天空の神フェイレン。
神は、この地を治めるために、王族を創り出した。
王族の血筋には、時折り神の姿を写した赤子が生まれる。彼の者こそが国を治める宿命を背負った王である。
王は、天空の神フェイレンの代理人。
地上のあらゆることを見通す瞳を持ち、王の前では、どんな罪人も自らの罪科を告白せずにはいられない――。
――創世神話より――
1.舞い込んできた小鳥-1

「空が青いな……」
鷹刀ルイフォンは眩しさに目を細め、そう呟いた。
聞き手もなく発せられた言葉は空へと流れ、吸い込まれていく。
掲げた掌の隙間からこぼれ落ちる、透明で、どこまでも高く広がる青い空。澄んだ色が目にしみて、彼は軽く瞼を閉じた。
草の匂いをまとった優しげな風が鼻腔をくすぐる。
こうして庭先に寝転んでいると、普段なら気づかないような、大地の湿った温かさを感じる。上空を飛ぶ鳥の声に耳を澄ませば、体が大気に溶けていくようだ……。
ルイフォンは肺いっぱいの深呼吸をしたのちに、青すぎる空を警戒しながら、再びゆっくりと目を開けた。
春の陽気は程よく温かく、満開の桜が時折り恥ずかしそうに花を散らしている。
ルイフォンの柔らかな、しかしやや癖のある前髪にも、花びらがひとひら舞い降りる。――黒髪、そして黒目。この国の民が持つ色合いだ。
不意に、あくびが口を衝いて出た。
腫れぼったい目からは涙が滲む。昼間から寝てしまうのはもったいない気がするが、どうやら限界のようだった。
このまま花に抱かれて、しばらく仮眠を取ることにしよう。
彼はそう考えて、凝り固まった手足と共に、一本に編まれた髪を大きく投げ出した。髪は、そのままにして寝ると、背中に当たって痛いからである。背の半ばまであり、先端を青い飾り紐で留めていた。そして、その中央には金色の鈴――。
ほどなくして規則的な寝息が漏れてきた。
穏やかな午後の陽射しが、ルイフォンの頬を明るく照らす。
寝顔には、大人になりかけの、どことなくあどけなさの残る十六歳の少年の素顔が垣間見えた。この空間だけを切り取れば、平和でのどかな一枚の絵画のようであった。
風が、静かに流れる……。
と、そのとき――。
ルイフォンは素早く寝返りをうち、体を横にずらした。
そのすぐあとに、地面を打つ鋭い音。
先ほどまで彼が寝転がっていた場所には、一本の短刀が突き刺さっていた。
ルイフォンは飛び起きた。彼の髪もまた、金色の鈴を煌かせて彼の動きに合わせてついてくる。
周囲に神経を張り巡らせる。
見開いた目に力を込める。
姿勢を低くとりながら息を吐き、軽く膝を曲げて次の攻撃に備えた。
前方から、風を斬る鋭い気配――。
凶刃がルイフォンを捕らえる手前で、彼は猫のようにしなやかに、ひらりとよける。銀光が頬をかすめ、背後の桜に突き刺さった。その衝撃に樹枝が揺れ、薄紅色の花が舞う。
桜吹雪の降り注ぐ中、ルイフォンは着地すると同時に身を屈め、地面に突き刺さったままの短刀を引き抜いた。
相手は正面――。
次はどう来るか。
彼は、ごくりと唾を呑む。短刀を握った手に汗がにじむ。滑って落とさぬよう、更に強く握り締める。
再び――風を裂く音を、肌で感じる。
高速で飛来してきた刃を感覚で捕らえ、体に触れる直前に短刀で叩き落す。
痺れるような確かな感触を腕に残し、甲高い音が響く。
――しかし、それは罠であった。
彼が刃に気を取られている隙に、茂みの陰に隠れていた襲撃者が飛び出してきたのだ。
「ルイフォン様、油断しすぎですよ」
笑みを含んだ声が響く。
壮年の大男が、ルイフォンの首筋にぴたりと刀を当てていた。
湾曲した幅広の刀は、まるで死神の鎌のようで、男がもう少し手首を返していればルイフォンの頭は胴体と泣き別れしていただろう。
「チャオラウ、寝込みを襲うのは卑怯だろ?」
ルイフォンは不服そうに睨む。
敵の襲撃……ではない。目の前の大男は、鷹刀一族の護衛役にして、ルイフォンの武術師範でもある草薙チャオラウである。
「今朝の分の稽古ですよ」
「……っ! さぼったのは悪かった。けど……!」
「まぁ、いいですよ。夜遊びしたい日もあるでしょうから」
「今日は夜遊びじゃない!」
しかし、ルイフォンの抗議は鮮やかに無視された。
「この体勢から切り返せますか?」
楽しげに尋ねるチャオラウに、ルイフォンは短刀を捨てて両手を上げた。
「お前相手に、無理」
「情けないですね」
「寝不足でふらふらだから勘弁してくれ」
泣き言を言うルイフォンに、チャオラウはやれやれ、といった体で刀を引いた。――しかし、それこそがルイフォンの狙いだった。
チャオラウが見せた一瞬の油断。それを確実に捉え、ルイフォンは鋭く足を蹴り上げる。
狙うは、鳩尾。
捕らえた! と、肉の衝撃を期待した瞬間、彼の右足は標的を失った。
「なっ……?」
チャオラウは、すっと片足を下げ、軽く半身で受け流していた。ルイフォンが踏み込む際、わずかに体が沈んだのを見逃さなかったのである。
チャオラウは、下げた足を戻しながら、そのまま流れるような動作でルイフォンの軸足を薙ぎ払う。
次の瞬間、ルイフォンは背中から地面に落ちていた。
「……!」
呼吸が止まる。受け身を取る暇もなかったため、ストレートに衝撃がきた。胸が詰まり、頭に鈍痛が響く。
仰向けになったルイフォンの喉元で、チャオラウの刀身が光る。
小さな痛みが走り、ルイフォンは軽く斬られたのを感じた。
「……参りました」
「まだまだ甘いですが、今のはよかったですよ」
わずかに唇を歪めるだけ。けれどチャオラウにしては珍しく、感心したような満足げな笑みだった。
円を描くように腕を回し、チャオラウは刀を鞘に収める。かちん、と鍔鳴りの音。それを合図に稽古は終了した。
チャオラウが膝を付き、ルイフォンを助け起こす。並ぶと頭ひとつ分以上、背の高い相手をルイフォンは見上げた。
「で、なんの用だ?」
「総帥がお呼びです」
「親父が?」
安眠妨害の黒幕を知り、ルイフォンは眉を跳ね上げた。くだらない用件だったら、どう報復してやろうかと策を巡らせ始めたとき、意外な言葉が彼の耳に入ってきた。
「今、門に闖入者が現れましてね」
「ほぅ」
大華王国一の凶賊の屋敷に来るとはまた物好きな、とルイフォンは思った。過去の侵入者たちの末路を思うと、顔も知らないそいつに同情したくもなる。
しかし、次の瞬間。彼は顔色を変えた。
「わざわざ俺を起こしに来たということは、ただの賊じゃない、ってことだな?」
「ご名答」
早々に追い払ったのであれば、ルイフォンが呼ばれることはない。
「どんな奴だ?」
「若い女ですよ。総帥は、お会いになるおつもりなんでしょう」
「は? ……はあぁ?」
ルイフォンは頭を抱えた。
まったく、あの親父殿はいくつになったら女遊びから引退するのだろう。
彼は自分の異母兄姉の正確な人数を知らなかった。自分が末子であるということになっているが、それも怪しい。
凶賊の総帥ともなれば、常に命を狙われているようなものだ。不用意に不審者を屋敷に入れるべきではない。しかし残念ながら、彼の父はそういった常識的な判断力を持ち合わせていないのであった。
「今、ミンウェイ様が対応してらっしゃいます」
チャオラウがそう言うのとほぼ同時に、ルイフォンは尻のポケットから携帯端末を取り出した。素早く数回タップすると、ディスプレイにふたりの若い女の姿が映し出される。
ひとりは総帥を補佐し、一族を切り盛りしている身内のミンウェイ。
そして、もうひとりは……。
ルイフォンは思わず尻上がりの口笛を吹いた。
「これは……親父が通すのも無理ないな」
つややかな黒絹の髪に白磁の肌。淡いピンク色のワンピース姿と相まって、この庭の桜の精が人に化けたのかと見紛うほどの儚げな美少女だった。
「貴族、……か?」
ちょっとした物腰から彼女の品の良さが窺える。
「名前は『藤咲メイシア』だそうです」
「藤咲……」
どこかで聞いたような、聞いていないような名前を反芻しながら、ルイフォンは端末を操作して検索する。貴族の情報なら王宮のシステムに侵入すれば、あっさり手に入るはずだ。――少なくとも表向きのものは。
ルイフォンの目が、すぅっと細くなった。
獲物を見つけた猫のような、好戦的な笑みを浮かべる。
「チャオラウ、親父は執務室だな?」
そう尋ねながらも、ルイフォンはチャオラウの返答を待たずに駆け出していた。
1.舞い込んできた小鳥-2

「お父様と異母弟さんを助けたいのなら、それしかないと思うわ」
藤咲メイシアの耳をねっとりとした女の声が蹂躙したのは、ほんの数時間前のことだ。脳裏に毒々しい紅い唇の動きが、鮮明に焼き付いている。
そんな口車に乗るなんて愚かなことだ、と彼女は思った。
それなのに。
気づいたら、ハンドバッグひとつだけで家を飛び出していた。
メイシアは今、重圧感を持ってそびえ立つ、高い外壁を見上げている。
硬い煉瓦の質感は天まで続くかのようで、ちっぽけな彼女は押しつぶされてしまいそうな錯覚を覚えた。
思わず体を縮こめた彼女の視界の上端を、黒い影が横切る。無意識に目で追うと、抜けるような青空の中を一羽の鳥が飛んでいた。
空の住人は、力強く羽ばたき、遙か天空を舞う。
悠然と、自由に。
これから鳥籠に入ろうとするメイシアを嘲笑うかのように。
この壁は籠の中と外を分ける檻だ。
メイシアの瞳に涙が盛り上がり、こぼれ落ちそうになる。彼女は慌てて金刺繍のハンカチで目元を抑えた。大人びて見えるように、と施した化粧が崩れしまってはいけない。
メイシアの心とは裏腹に、爽やかな春風が彼女の長い黒髪を揺らし、背中を押した。どこからともなく運ばれてきた桜の花びらが、彼女の前に薄紅色の道を作った。
そして、その先には鉄格子の門。
彼女はいつも身につけているお守りのペンダントを握りしめ、硬く目を瞑った。
藁にもすがる思いで、祈りを捧げる。
ゆっくりと開いた瞳に、彼女は三人の黒服の男を映した。鋭い目つきで門を守るように立っている。警護の者であろう。皆が皆、小山のような巨躯を誇り、腕の太さなどは彼女の三倍くらいある。
彼らはメイシアの存在なんてとっくに気がついていて、ちらちらと無遠慮な視線を投げつけてきていた。まだほんの少しだけ彼我の距離があるために、威嚇にとどめているだけにすぎない。
メイシアは震える足に力を込め、男たちの元へと歩を進めた。
「なんの用だ?」
男のひとり――頬に大きな刀傷のある大男が大きく一歩、緩やかに前に出た。わずかに腰を落とし、構えをとる。射抜くかのような眼光がメイシアを捕らえた。
「ここが、鷹刀一族の総帥の屋敷と知ってのことか? この大華王国一の凶賊、鷹刀イーレオ様の屋敷と、な!」
目にもとまらぬ速さで男が刀を抜いた。銀色の鋭い切先が眼前で煌めき、メイシアは死の到来を覚悟した。
……しかし『その瞬間』は訪れなかった。
輝く刃紋はメイシアの眉間わずか数センチのところでぴたりと止まり、メイシアの命をこの世に留めていた。
「ふん……。あいにく鷹刀はカタギに手を出すような下衆ではないんでな」
ちん、と鍔鳴りの音をたてて男が刀を鞘に収める。
全身から力が抜け、操者を失った操り人形のように、メイシアはその場にへたり込んだ。
――これが、凶賊。
暴力的な手段によって勢力を誇る集団。彼らのことを、この大華王国では凶賊と呼ぶ。
男たちはメイシアに蔑みの眼差しを向けていた。
「これに懲りたら家に帰りな」
刀傷の男が吐き捨て、持ち場に戻るべく踵を返す。
「ま、待ってください……!」
かすれる声とありったけの勇気を振り絞って、メイシアは叫んだ。いまだ笑いが止まらない膝を押さえつけ、どうにか立ち上がる。
「私は、藤咲メイシアと申します」
最後まで声が震えぬよう、努めてはっきりと告げる。
「鷹刀イーレオ様にお話がありまして、参りました。お取り次ぎをお願いいたします」
刹那、男たちの顔色が変わった。
「イーレオ様にお会いしたい、だと?」
「はい、お願いいたします」
深々と頭を垂れるメイシアに、刀傷の男が低い声を落とした。
「嬢ちゃん、俺たちの仕事はな、イーレオ様のお許しのない者をこの門に近づけないことなんだよ」
「お願いします! どうしても、……どうしても、イーレオ様のお力が必要なのです!」
「つまみ出せ」
その号と共に、彼の背後に控えていた男たちがにじり寄り、メイシアの腕を乱暴に捻り上げた。これまでの十八年の生の中で、一度も受けたこともない痛みと恐怖が、彼女を襲う。
「きゃあああ……!」
メイシアの悲痛な叫びが木霊した、そのときだった。
「おやめなさい!」
凛とした女の声が響いた。
はっと、振り向いた男たちの視線の先には、ひとりの美女が立っていた。
彼女は屋敷から続く長い石畳の上を、音もなく滑るようにやってきた。すらりと背が高く、颯爽と足を運ぶたびに緩やかに波打つ長い髪が豪奢に揺れる。
年の頃は二十代半ばくらいだろうか。すっとひかれた眉に切れ長の目。高い鼻梁。彼女の身を包む、チャイナドレスを思わせる衣服の陰影からは、スタイルのよさが窺えた。太腿まである深いスリットから覗く脚線美が眩しい。
「ミンウェイ様……!」
「モニタ監視室から連絡がありました。何やら門のあたりで不穏な動きがあると」
「ははぁ! お騒がせして申し訳ございせん。この者がイーレオ様に会わせろとのたまいまして……」
「ええ、だいたいのところは把握しています。お役目ご苦労様でしたね」
畏まる男たちにミンウェイは笑みをこぼした。そして続けた。
「彼女を連れてくるように言付かっています。手を離してあげてください」
「……は?」
男たちは戸惑いから、暫くの間、半開きの口を隠せないでいた。だが、ミンウェイの急かすような視線に気づくと、すぐに「ははっ」と、拘束を解いた。
ミンウェイが音もなく寄ってきて、メイシアの両手を取る。その手首には、男の指の跡が赤く、くっきりと残っていた。
「身内の無礼をお許しください」
ミンウェイはメイシアの手首を優しくさすり、深々と頭を下げた。ミンウェイの手からは働く者の硬さが感じれ、髪からは干した草のような柔らかな香りが漂った。
「ご案内いたします」
そう言ったあとで、ミンウェイは刀傷の男に視線を投げた。その意図を察し、彼は一歩メイシアに近づき、目礼をする。
「お荷物をお預かりいたします」
「いえ、お気遣いは……」
言いかけて、メイシアは男の眼光に気づいた。ベルボーイに荷物を預けるのとまったく意味が違う。これは不審物を持ち込ませないための措置だ。
自分の勘違いを恥じつつ、彼女は黙って男にハンドバッグを渡した。
1.舞い込んできた小鳥-3

「面会の用意ができるまでお待ち下さい」と言われ、メイシアが案内されたのは、明るい小部屋であった。
応接室、とでもいえばよいのだろうか。ゆったりとしたソファーが二脚、テーブルを挟んで向かい合わせに据えられていた。テーブルの上には品のよい陶花器。小さな黄色い花房をつけた枝が挿されていた。素朴で可愛らしい花だが、残念ながらメイシアはその名を知らなかった。
すぐにも総帥の鷹刀イーレオに会わせてもらえるものと思っていた彼女は、肩透かしを食らった気分であった。
勧められたソファーに、浅く腰掛ける。
部屋に待機していたメイドが、彼女の到着を待って紅茶を淹れてくれた。とても飲み物を楽しめる心境ではなかったが、ダージリンの高い香りが彼女の鼻孔を優しく、くすぐった。
「その顔のほうが素敵よ」
自然と顔を綻ばせたメイシアに、向かいに座ったミンウェイが口元を緩めた。そして彼女は後ろに控えていたメイドに「あなたにお茶を頼んで正解。ありがとう」と、労う。メイドは嬉しそうに頭を下げて退室した。
まるで賓客を迎えるかのようなもてなしぶりに、メイシアは困惑していた。
柔らかく日差しの入る大きな窓が、少しだけ開いていた。
不意に強い風が吹いてきて、レースのカーテンが大きくはためく。「風が強いわね」と言いながら、ミンウェイが席を立ち、音もなく近寄って窓を閉めた。
廊下を歩いているときにも気づいたのだが、ミンウェイは足音を立てない。メイシアは初め、彼女の靴が特別なのかと思った。しかし、そうではない。足の運びが違うのだ。メイシアの家の警備の者たちと同じ歩き方をしている。間違いなく彼女には武術の心得がある。それは彼女の女性らしい豊満な胸とくびれた腰を強調する、ぴんと伸びた背筋からも感じられた。
ミンウェイは、ただの案内役ではないだろう。廊下で使用人たちとすれ違うたびに軽く声をかけていた様子からも、かなりの重要人物であることが窺える。総帥の血族か姻族だろうか。
「藤咲さん……メイシア、とお呼びしていいかしら」
「はい、どうぞ」
ミンウェイの親しげな笑みにつられ、メイシアも表情を緩めた。
しかし、その顔は、ミンウェイの次のひとことで凍りついた。
「メイシア、あなたは貴族ね」
動揺に、言葉が出ない。
そんな彼女の心を読んだかのように、ミンウェイが続ける。
「見れば分かるわ。服装、持ち物、言葉遣い、物腰……。小綺麗な平民と言うには無理があるわね」
メイシアは思わず、自分の姿を確認してしまった。少し無理をして着ている、胸元が開き気味のワンピース。上品な淡いピンク色で、素材は上等な絹だ。
隠すつもりはなかった。
だが、貴族は、身分の低い者たちに疎まれがちである。初めは伏せておき、鷹刀イーレオに会ったら自分から明かすべきだ、と考えていた彼女にとって、不意をつかれたも同然だった。
「はい。……私は貴族です」
メイシアの肯定を受けると、ミンウェイは急に険しい顔になった。
「私は、貴族には、ふたつの人種があると思っているわ。ひとつは、自身のために手段を問わない『捕食者』。もうひとつは、か弱くて善良な『被捕食者』。凶賊が手を組むのは、前者のタイプの貴族よ。――そして、あなたはどう見ても後者ね」
ミンウェイは膝を詰めるように、上半身をメイシアに寄せた。それは、決して大きな動作ではなかったのだが、ミンウェイから漂う柔らかな草の香りが、メイシアの前に立ち塞がるかのようだった。
「あなたは凶賊と関わるべきではないわ。きつい言い方をすれば、『世界が違う』のよ。――だから、帰りなさい」
その言葉に、メイシアは、ゆっくりと頭を振った。長い髪がさらさらと背中を流れる。それは、手入れの行き届いた貴族ならではの鴉の濡れ羽色だった。
「帰ることはできません」
父と異母弟の顔が頭をちらつき、メイシアの瞳にうっすらと涙が浮かんできた。彼女は声の震えを抑え、訴える。
「……私には、どうしても武力が必要なのです」
「どうして?」
メイシアは唇を噛み、毅然と答えた。
「私の家族を助けるためです」
「武力が必要というだけなら、何も凶賊を頼らなくてもよいでしょう」
「確かに、その通りです」
それは、この屋敷に着くまでに、自問してきたことだった。
「ですが、私の大切な家族の命がかかっているのです。ならば、この国で最も強いと言われる鷹刀一族にお願いするのが一番確実ではありませんか?」
揺るぎないメイシアの瞳。
か弱くて儚い、ほんの少しの衝撃で脆く崩れ落ちてしまいそうな貴族の娘が、凶賊であるミンウェイの反論を許さなかった。
「いい目ね……」
ミンウェイは、溜め息をついた。
「その思いを総帥に伝えてみるといいわ」
そこにはもう、さきほどの険しさは微塵もなく、慈愛すら感じられる眼差しがあった。
メイシアの瞳から、ほろりと涙がこぼれた。慌ててハンカチを求めるが、ハンドバッグは門で渡したままだった。
ミンウェイが、すっとハンカチを差し出す。そのとき――まるで話の区切りがつくのを待っていたかのように、ミンウェイの携帯端末が鳴った。
それに小声でひとこと、ふたこと答えると、ミンウェイはメイシアに告げた。
「もうすぐ迎えが来るわ」
メイシアの緊張感が一気に膨らみ、傍目に分かるほどに顔が強張る。
ミンウェイが困ったように笑った。
「メイシア、そのテーブルの花を知っている?」
「いいえ、知りません」
「キブシというの。倭国の固有種よ。花言葉は『待ち合わせ』『出会い』……」
ミンウェイの言葉の途中で扉がノックされた。彼女はゆっくりと立ち上がり、ドアノブに手をかけながら残りの言葉を発した。
「……『嘘』」
がちゃり、と音を立てて、扉が開かれた。
「お待たせいたしました」
心地のよい低音が響く。
立ち襟の上衣をきっちりと着こなした男がにこやかに微笑んでいた。
「私はこの屋敷の執事でございます。では、ご案内いたします」
整った容貌に細身の眼鏡。肩幅は広く、均整のとれた体つきをしている。落ち着いた物腰から推測するに、充分に経験を積んだ五十代半ばの実力者といったところだろうか。
執事は恭しく一礼をしてメイシアを促した。
彼はかなりの長身だった。背の中ほどで髪を緩く一つに纏めていたのだが、その結び目を追いかけるような形で、メイシアは絨毯の敷かれた廊下をついていった。その後ろにミンウェイが続く。
いくつか角を曲がり階段を上り、奥の部屋についたところで執事が振り向いた。
「こちらでございます」
彼はすっと横に動き、目の前の扉を示した。
扉には大きく翼を広げた鷹の彫刻が施されていた。羽の一枚一枚は刀と化している。メイシアにも鷹刀一族の紋章だと、すぐに分かった。
後ろにいたミンウェイが前に出て、扉に触れた。
次の瞬間、彫刻の鷹の眼球が動いた。そして、ミンウェイの瞳を捉える。
〔ミンウェイ様ですね〕
流暢な女声の合成ボイスが流れた。
目を丸くするメイシアをよそに、扉が小さな機械音を立ててスライドし、道が開かれる。
「さあ、どうぞお入りください」
執事が部屋に入り、にこやかにメイシアを招いた。
立ちすくむメイシアの手をミンウェイがそっと引く。メイシアは、はっとして背筋を伸ばした。中からこちらを窺う執事に向かって頭を下げ、礼を述べた。
「案内、どうもありがとうございました」
言いながら違和感を覚えたが、今はのろのろとしている場合ではない。メイシアは前のめりになりながら部屋に入り、ミンウェイも続いた。
すぐに背後で扉が閉まり、かすかな施錠の音が聞こえる。
「ようこそ」
若々しいテノールがメイシアを迎えた。
部屋の奥に大きな執務机。声の主は机に両肘をつき、組んだ両手に顎を載せていた。
「俺は鷹刀イーレオの末子、鷹刀ルイフォン。親父は六十五歳という高齢なんで、接客は体に障る。というわけで、俺が代わりに話を聞くことになった」
獲物を前にした猫のように彼は嗤った。端整といってよい顔立ちは、その表情によって台無しになっていた。
クッションのきいた椅子を軋ませ、彼は立ち上がる。
やや猫背気味。髪は後ろで一本に編んでいて、先を青い飾り紐で留めていた。その中央には金色の鈴。
どこか特徴のある動きをしながら彼はメイシアに近づき、右手を出した。
その骨格は決してひ弱ではないけれども、どう見ても少年の域を出ない――メイシアと同年代のそれであった。
2.凶賊の総帥-1

ルイフォンは執務机の手前にある革張りのソファーをメイシアに勧めた。そして彼女が座るよりも先に、ローテーブルを挟んだ向かい側に腰を下ろし、足を組む。
彼の背後には二人の男。一人はメイシアを案内してきた執事で、相変わらず、にこやかな笑みを湛えている。もう一人は護衛であろうか。腰に大刀を佩いた壮年の大男で、執事より更に一歩下がったところで影のように控えていた。
メイシアは、おずおずとソファーに腰掛けた。
全身が緊張に包まれる。
小刻みに揺れる彼女の肩を、背後に回ったミンウェイが軽く叩いた。その温かな感触に励まされ、メイシアは、すっと顎を上げてルイフォンの顔を正視した。
「このたびは突然の訪問を快くお受けいただき、ありがとうございました。お礼申し上げ――」
「堅苦しい挨拶は抜きにしよう」
ルイフォンがメイシアの言葉を遮った。
「そんなのは無意味で面倒臭いだけだ。それに俺は上辺だけの上品な言葉は嫌いなんでね」
彼は肘掛に右肘を立て、頬杖をついた。くつろいだ姿勢だが、しかし眇めた目がメイシアの一挙手一投足をつぶさに観察している。
「見るからに深窓のご令嬢の貴族が、凶賊の総帥になんの用だ?」
獲物をねぶるような肉食獣の視線に、メイシアはぞくりとした。無意識に両腕で自分自身を抱きしめる。
「私の……」
メイシアの声が、かすれる。
「お前の? なんだ? もっとはっきりと喋ってくれ」
「……私の父と異母弟が凶賊の斑目一族に囚らわれました。助け出すために、お力をお借りしたく、お願いに参りました」
「斑目?」
ルイフォンの眉間に皺が寄った。
「鷹刀の敵地じゃないか。お前に雇われて地雷原を突っ走れと? 馬鹿馬鹿しい」
彼はそう吐き捨て、メイシアから視線を外した。まるで、彼女の相手をする価値はないと言わんばかりに……。
メイシアは震える手で、そっとお守りのペンダントの石の感触を確かめた。交渉がすんなり行くとは、初めから期待していない。これからが勝負なのだ。
彼女は、弱い心を押し込めて、精一杯の虚勢の鎧を身にまとった。
用意しておいた言葉を胸の中で反芻する。
そしてメイシアは、閉じていた蕾が花開くように――破顔した。
「少し、違います。私は鷹刀様を雇いに来たわけではありません」
しっかりとした、それでいて鈴を振るような澄んだ声が響いた。
ルイフォンの眉がぴくりと動く。表情を変えずに、目だけがメイシアのほうを向いた。
「鷹刀様とお取り引きがしたくて参りました。対等な、取り引きです」
「へえ……? 『取り引き』ときたか。金以外に何か条件でも加えるつもりか? 鷹刀がお前の領地で何をしても目を瞑る……とか?」
「いえ。残念ながら、跡継ぎではない私には領地に関する利権はもちろん、ひと握りの金品すらお約束することはできません」
予想外の発言だったのか、ルイフォンは頬杖から姿勢を改め、身を起こした。
「金は、ない、だと? それじゃあ、鷹刀と斑目を戦わせて、お前は何を差し出すつもりだ?」
メイシアは、あでやかに笑った。
不審に思う彼の興味を、充分に引き付けるだけの間を、取る。
そして、告げた。
「『私』です」
「…………は?」
ルイフォンの目が丸くなる。
それは、彼の背後の男たちも同様だった。後ろにいるミンウェイも狼狽の息を漏らす。
「人と、人を、提供し合うのです」
その場にそぐわないほどの穏やかさで、メイシアは微笑した。凛とした声色でありながらも、言葉尻は柔らかい。聞いている者を自ら望んで首肯させるような、そんな魔力すら感じられた。
「私には武術に長けた人間が必要です。その対価として、私はなんでもいたしましょう……ええ、なんでも……」
言いながら、メイシアは震えていた。
無垢な彼女には、それは『死』と同義だった。それでも家族の命と天秤にかけたとき、こちらのほうが軽かった。それだけだ。
メイシアは鼻の奥がつんとするのを感じながら、ルイフォンの反応を待っていた。
「は、ははははは……」
ルイフォンは徐々に口角を上げた。
「まるでガキみたいなことを言うんだな。正気か? そんなのが本当に、交換条件になると思ってるのか? お前一人と鷹刀の人間とが?」
意地の悪い笑みを浮かべながら、ルイフォンはメイシアの目をじっと見た。彼女の黒曜石の瞳は真剣に、そして、まっすぐに彼に訴えかけていた。
「世間知らずもここまで行くとたいしたものだ。面白い。面白いな、お前。泣きそうな顔をしながら、言うじゃないか」
ルイフォンはやや癖のある前髪を、くしゃりと掻き上げた。そして困った、とぶつぶつ呟きながらも、口元は緩めている。
猫が喉を鳴らすが如く嬉しげに目を細める様子に、メイシアは彼が意外に人懐っこい造作であることに気づいた。そしてまた、自分よりもやや年下の少年に過ぎないということも。
「俺は親父に、『綺麗な小鳥が迷い込んできたから、一緒にちょっとからかってやろう』と誘われただけなんだよ。適当に堪能したら逃がしてやるつもりでな。……思わず欲しくなるじゃないか。参ったな」
それで、なのか、とメイシアは得心がいった。
屋敷に通されてからの賓客扱いは、好色家との噂がある鷹刀イーレオのただの気まぐれだったのだ。
ふと、そのとき。メイシアは、悟った。
それはルイフォンにとっては何気ない、ひとことだったに違いない。しかし……。
メイシアはルイフォンに目礼をしてから、すっと立ち上がった。訝しがる彼の横を抜けて、背の高いその人を見上げる。
「あなたが鷹刀イーレオ様ですね」
メイシアは執事に向かって問いかけた。
2.凶賊の総帥-2

ちゅんちゅんと、雀のさえずりが聞こえる。
楽しそうに鳴き交わす数羽の雀。満開の桜の枝に集まり、蜜を吸っているのだろう。木の根元に五枚の花弁を付けたままの花が手折られて落ちているのは、彼らの仕業だ。
――そんな、窓の外での様子が伝わってくるほどに、室内は沈黙に包まれていた。
ちゅんちゅんちゅん……。
やがて、二羽の雀が連れ立って飛び立つ。
彼らの翼の影が、窓辺に届く光を僅かに明滅させ、部屋の空気に刺激を与えた。
そこでやっと静寂が破られた。
「何をおっしゃるんですか?」
執事が軽く首を傾げながら、穏やかに言った。低く渋い声。終始にこやかな顔をしている彼が、少しだけ困ったような表情をしている。
「私に何か問題があったのでしょうか。主人と間違えられてしまうとは……。そのような言動を取ったと知られれば、私はイーレオ様に叱られしまいます」
白々しいほどの間があったにもかかわらず、彼の物言いがあまりにも自然であったため、メイシアはその先を言いあぐねた。
彼女には、確信に近い自信があった。
けれど、執事の誠実そうな顔を見ていると、どうにも物怖じしてしまう。端正な顔を困惑色に染めて、優しくメイシアを見る彼は、とても凶賊の総帥には見えなかった。
言いがかりをつけてしまったような気がしてきて、頬がにわかに紅潮してきた。言おうとした言葉は口の中で押し殺され、メイシアは黙り込んでしまった。
「おい」
ルイフォンがソファーの背にもたれながら、半身をメイシアに向けた。
「お前は、どうしてこいつが親父だと思った?」
それは意外な助け舟だった。
ルイフォンは、口元に楽しそうな笑みを浮かべていた。この先の展開に期待をしているらしい。
そんな彼に後押しされるように、メイシアは目の前にすらりと立つ偉丈夫を、再び見上げた。
「理由は、ふたつあります」
今までどうして、この貫禄に気づかなかったのだろう。メイシアはそう思う。
思い返せば、この部屋に来るまでの間、ミンウェイは使用人たちに軽く声をかけることをしなかった。使用人たちもまた、畏まって頭を下げるだけだった。
「……ひとつ目は、この部屋の扉です。私には専門的なことは分かりませんが、この部屋の扉には開けるには、何か仕掛けがありますよね。名前を確認される、といった感じの……」
「それ、『虹彩認証』な」
ルイフォンが横から口を挟んだ。
「扉の前にいる者の瞳を――虹彩をチェックして、入室の許可を出している。家紋の彫刻の目にカメラを隠すとか、いい雰囲気が出ているだろ?」
どことなく自慢げに言いながら、ルイフォンはソファーの座面に足を乗せ、完全に体を後ろに向けた。そして、メイシアに顎で続きを促す。
「扉を開けたのは――その、『虹彩認証』というのをしたのは、私を案内してくださった執事のあなたではなく、ミンウェイ様でした。執事なら主人の部屋の入室くらい許可されていそうなものなのに……」
メイシアは、あのときに感じた違和感の正体がやっとわかった。今から考えれば、執事とミンウェイの行動は明らかに不自然だった。
「あなたが部屋の外で待機していて、ミンウェイ様だけが私を案内して部屋に入るのだったら、単にあなたに入室の許可がないのだと解釈できました。しかし、扉を開けなかったあなたが、一番最初に部屋に入りました。それを誰も咎めない……」
そして、ミンウェイの『嘘』という花言葉。
あのタイミングで教えてくれたものに意味がないわけが、ない。
すなわち、執事というのは『嘘』なのだ。
「それはつまり、あなたがイーレオ様で、私に名前を明かすわけにはいかなかったから、ミンウェイ様に扉を開けさせた、ということではないですか?」
ルイフォンが、ぴゅう、と口笛を吹いた。
「それで、ふたつ目は?」
「ふたつ目は、簡単なことです。……イーレオ様が私を屋敷に入れてくださった理由が、『からかうため』なら、私をからかえる位置にいなければ意味がないではないですか」
「くっ、く、くく……」
押し殺した笑い声が響いた。
――執事が、笑っていた。
彼は、さきほどまでの気品すら感じられた、にこやかな仮面をかなぐり捨てた。眼光は鋭く、口元には不敵な笑みを浮かべている。
「たいした洞察力だ」
「では、やはりあなたが……」
喜色を上げたメイシアを、しかし彼は押し止めた。ルイフォンの座るソファーの背もたれに手をついてぐいと身を乗り出す。
「確かに俺が執事だというのは嘘だ。凶賊の屋敷に執事なんて貴族めいた役職はない。――だが、もうひとつだけ、お前は答えなくてはいけない問題がある」
実に愉快だと言わんばかりの声色で男は言い、更にどこか揶揄を含んだ眼差しで畳み掛けた。
「ルイフォンが初めに言った通り、『鷹刀イーレオは六十五歳という高齢だ。接客は体に障る』――この俺が、そんな年寄りに見えるか?」
ルイフォンが、がっくりとうな垂れていた。
それを見て、メイシアは自分の推測は正しかったことが確信できた。
だが……。
この返答に困るような質問にどう答えればいいのであろうか。
目の前の美丈夫は、意地の悪い笑みを浮かべてメイシアの反応を楽しんでいる。決して若くはないが渋く魅力的と言える顔貌に、理知的な印象を与える細身の眼鏡。黒く豊かな長髪を背中に蓄え、緩くまとめている。洒落者だ。
これは……思った通りに答えるしかない――メイシアは、そう腹をくくる。
「見えません」
「だろう?」
上機嫌で彼は頷いた。そして、ふっ、と端正な顔をほころばせた。これがまた驚くほど絵になる。
「なかなか鋭かったが、すべては、お前の思い込みだったのだ!」
「おい!」
ルイフォンが鋭く遮った。
「いい加減、観念しろよ、糞親父! 茶番は終わりだ」
げんなりしたような呆れ顔で、ルイフォンは父を――鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオを睨んだ。
イーレオは心外だとばかりに肩をすくめた。
「お前だって、こいつをからかうのに乗り気だったじゃないか」
「引き際が肝心だ! さすがに見苦しすぎる」
「まぁ……、そうかもしれんが、なぁ……」
彼は未練がましくメイシアを見やった。
それから腹いせのように、座っているルイフォンの頭を小突く。ルイフォンは反射的に右手を拳の形にしたが、父に反撃の隙がないのを悟ると、何事もなかったかのように自分の編んだ髪を指先でくるくると弄んだ。青い飾り紐の中央で金色の鈴が煌めく。まるで、狩りに失敗した猫が平常を装っているかのようであった。
メイシアは、ほっとして肩の力が抜けた。
ふらりとよろけそうになったところをイーレオに支えられた。六十五歳というが鍛えられた筋肉は逞しく、まだ衰えを見せない。異性として意識してしまった彼女は、急接近に思わず小さな悲鳴を漏らす。けれど、彼は愉快そうに眉を動かしただけで、ソファーに戻るよう、彼女を優しく促した。
「さて、改めて。俺が鷹刀一族総帥、鷹刀イーレオだ」
イーレオはきっちりと留められていた立ち襟のボタンをはずした。軽く息をついたところを見ると今まで窮屈であったらしい。
彼はルイフォンのソファーに回り込み、座っている息子の足を、立てとばかりに軽く蹴り上げた。ソファーは大の大人が優に三人は座れるサイズであり、ルイフォンは肘掛のある端に座っていたのだが、イーレオは中央に一人でふんぞり返りたかったらしい。
「なんだよ?」
ルイフォンはあからさまに不快な顔をする。
「年長者に席を譲れ」
「若いんじゃなかったのか?」
「年寄りに見えるか、と訊いただけだ」
ルイフォンとイーレオが睨み合う。不毛な争いが勃発せんとするところに、ミンウェイの咳払いが割って入った。
「二人とも、客人の前よ」
ミンウェイの一睨みで父子は押し黙る。メイシアは彼らの力関係をおぼろげながら理解した。
結局、ミンウェイの采配でイーレオとルイフォンが並び、メイシアの隣にミンウェイが座った。
チャオラウと呼ばれた護衛の男はミンウェイの勧めを断り、皆を護るように立っている。その際に彼が「私はルイフォン様と違って日々鍛えておりますから」と言ったのは何かの含みがあったに違いない。ルイフォンが顔をしかめていた。
2.凶賊の総帥-3

「お前は知らないかもしれないが、斑目は、ある貴族に雇われて、動いている」
各人がそれぞれの場所に落ち着くと、おもむろにイーレオが口を開いた。
軽く腕を組んだ彼はソファーの背にもたれかかっていたのだが、それでも長身ゆえ、かなり高い位置に目線があった。ただ座っているだけなのに、メイシアは威圧感を覚える。
「そうだったのですか……。知りませんでした……」
「まぁ、それは、さて置くとして。――貴族なら警察隊に助けを求めるのが筋だろう?」
「通報はしました。けれど、そのような事実はないと言われました」
「ああ、警察隊を抱き込んだか。斑目を雇った貴族の仕業だな」
イーレオが嗤笑する。
凶賊は武力で他の一族を蹴散らし、貴族は金の力で他家を抑え込む。強いものだけが生き残れる。自然の摂理だ。
「鷹刀は貴族同士の諍いに巻き込まれるつもりはない。――同情はする。だが、それだけだ」
「ですが……!」
鷹刀一族は長年、斑目一族と敵対関係にあるのだと、メイシアは聞いていた。ならば利害が一致するのではないだろうか。そう、祈るような気持ちで彼女はイーレオを見上げる。
そのとき、イーレオの雰囲気が一変した。それは、美しくとも、立ち入るのを躊躇ってしまうような、静かな深い夜の海に似ていた。
「鷹刀は慈善家ではない。俺は鷹刀という名の帝国の長だ。鷹刀に属する者を護る義務がある。お前に手を貸すということは俺の大事な一族を危険に晒すということだ」
鋭い月光のような瞳が、彼女を冷酷に拒絶した。
メイシアには返す言葉もなかった。華奢な肩は儚げに震え、黒くつぶらな瞳は、今にも涙がこぼれ落ちそうになる。
しかし、それだけでは終わらなかった。「もっと言えばな」と、イーレオが低い声でにじり寄った。
「お前は自分が本物の藤咲メイシアだと証明できるのか?」
「え?」
メイシアは彼が何を言ったのか理解できなかった。
「お前は藤咲メイシアの影武者で、本物は実家でのうのうと朗報を待っている――という可能性もあるんだが?」
青天の霹靂だった。
メイシアは思わず立ち上がり、青ざめながら叫んでいた。
「違います! 私は本物です!」
「貴族が凶賊に頼みごとをするのに、金品や利権ではなく、人を寄越した。だから、お前は捨て駒――そう考えるのが妥当だろう」
「そんな……!」
「更に、だ。鷹刀は藤咲家を助けなくても、お前を好き勝手できる。何故なら、お前はもう、俺の屋敷に居るのだからな」
ちらり、と、イーレオは自分の背後に目をやった。そこには護衛の男、チャオラウがいた。
「俺がひとこと命じれば、このチャオラウがお前の足をへし折って、お前の逃亡を防ぐことも可能だ。いや、お前のすぐ傍にいるミンウェイだって、並みの男より、よほど強い」
低く魅惑的な声は、ゆっくりと迫りくる夕闇のように徐々にメイシアを追い詰め、彼女を黒い恐怖に染め上げていく。
「俺が何故、あっさりと、お前を屋敷に入れたと思う? ――恐るるに足りぬ相手だと思ったからだよ」
イーレオはそこでいったん言葉を切り、メイシアの足が震えているのを確認してから、口の端を上げた。
「万が一、お前が何者かの手先であっても、こちらの戦力を考えれば、捕らえるのは赤子の手を捻るようなもの。だから、ちょっとからかってやろう、などという欲望がもたげたのさ」
ぞくり、とメイシアの背に寒気が走った。
この男は、確かに凶賊の総帥なのだと、彼女は実感した。
イーレオが嗤う。
そして、ゆっくりと宣告する。
「お前は既に俺の物なんだよ。だから、お前の言う『取り引き』は成立しない」
イーレオの言葉の波が、ゆっくりと押し寄せては引いていく。そのたびに、メイシアは足元の砂がさらさらと奪われ、凶賊という海の底へと飲み込まれていくのを感じた。
膝から崩れ落ちるように、メイシアはソファーに倒れこんだ。スプリングが彼女の体重を柔らかく受け止めたはずなのだが、滑らかな革の座面は硬く、彼女の体と心を打ちつけた。
「……私を、どうするおつもりですか?」
「さて……? どうしようか? 想像以上に、お前は興味深い。頭もいいし、箱入り娘のくせに変なところで度胸がある。それに、まだ子供だが、女にしてやれば相当、化けるだろう。……適当に逃がしてやるつもりだったが、それも惜しい」
イーレオが口の端を上げると、端正な顔が壮絶に歪められた。
メイシアは言葉を失った。
白蝋のような顔で、呆然とイーレオを見上げる。
この世に鬼というものが存在するのだとしたら、いま目の前にいる男のようなものに違いない、と彼女は思った。残忍で、そして、それゆえに美しい。
沈黙の帳が、ゆっくりと下ろされる。
ミンウェイが、気遣うようにメイシアに顔を向けた。
それから彼女は、イーレオに視線を送る――そこには明らかに批難の色が含まれていた。イーレオの肩が、ぎくりと跳ね上がった。
イーレオは、罰が悪そうに視線を泳がせ、ぼそりと言った。
「……冗談だ。いくらなんでも、俺はそこまで堕ちてない」
「おい、糞親父! 俺は、全身全霊で、真に受けたぞ!」
ルイフォンが食って掛かる。
「いや、だから、『取り引き』とか言っても、いいように手籠めにされるだけだ、という話を、だ」
息子の右ストレートを華麗に躱しながら、イーレオはメイシアに向かって、厳しくも魅惑的な笑みをこぼす。
「忠告だ、お嬢ちゃん。鷹刀が駄目だったからと言って、他の凶賊を頼ろうとするなよ。理由は……分かるな?」
本当にイーレオは海のような男だ、とメイシアは思った。その時々で様相を変えるが、常に広く大きい。
「あなたは……」
私のためを思って、わざと脅しをかけたのですね、と言いかけて、メイシアは声を詰まらせた。
いけない、そう思ったが、既にこぼれ落ちた涙を止めることはできなかった。
今、泣いたら勘違いされてしまう。被害者の涙に見えてしまう――メイシアは口元を抑え、嗚咽を漏らさぬよう必死に堪えていた。
それでも涙はきらきらと光の筋を描き続ける。
ルイフォンは攻撃の手を止め、イーレオを肘でつついた。小声で「いい歳して女を泣かすな」と囁く。大海のような男も、さすがに小娘の心の内を読むことはできなかったようで、困ったように肩をすくめた。
メイシアは慌てて掌で涙を拭い去った。
「お、お見苦しいところを……失礼いたしました」
メイシアは笑った。
澄み切った、心からの笑顔だった。
次の瞬間、メイシアの長い髪がふわりと宙を舞った。
つややかな黒絹のようなそれは床へと落ち、凶賊たちは我が目を疑った。
メイシアの白磁のうなじが露わになっていた。
「なんの真似だ?」
今までどこか余裕綽々の感があったイーレオが、初めて狼狽の色を見せた。
貴族が膝を折る相手は、王族のみであるはずだった。しかし、彼の目の前で、貴族のメイシアが床に跪き、頭を垂れている。
「イーレオ様、先ほどの、私を興味深いと言ったお言葉は、本心でらっしゃいますか?」
「……何が言いたい?」
「あのお言葉を、褒め言葉として頂戴してよろしいですか?」
「あ、ああ……。お前は見どころがあると思う」
メイシアは顔を上げ、にこり、と笑った。
「ありがとうございます。……あのお言葉は『貴族の藤咲メイシア』に対して向けられたものではなく、ここにいる『私』に向けられたものです。大華王国一の凶賊の総帥が価値を認めた小娘を……あなたは欲しくはありませんか?」
じっと、イーレオの瞳を捉え、メイシアは宣言する。
「私はあなたに忠誠を誓います」
しばしの、沈黙。
そして――。
「………………参った……」
イーレオが観念したように呟いた。
彼の体が小刻みに揺れた。彼は、ふるふると腹筋を震わせていた。次第にそれは激しくなり、ついには苦しげに腹を抱えて体を二つに折る。
「は、ははははは……」
イーレオは笑っていた。爆笑である。眼鏡の奥の目には、うっすら涙さえ溜まっている。
彼は、何かを振り切るように数回、首を振った。
「外見は嫋やかなくせに、本質は恐ろしく強いな……」
大きく息をつき、とりあえず座れと、床のメイシアに目線で命じる。
「お前、結局、初めと変わらずに、自分を差し出すと言っているだけだってのは、分かっているか?」
半ば呆れたようにイーレオは言った。しかし、「……だが、悪くない」そう、続ける。
「メイシア」
イーレオが初めてメイシアの名を呼んだ。
「俺はな、世界で一番、人を魅了するものは『人』だと思っている。俺は、俺を興奮させてくれる奴をたまらなく愛おしく思う。……俺はお前に魅了されたよ」
慈愛の眼差しだった。彼はそうやって、鷹刀一族を護ってきたのだろう。すべての生命の源たる海のように。
「俺に忠誠を誓うと言ったな」
「はい」
メイシアは毅然と答えた。
「ではお前は俺のものだ。その代わりお前の父と異母弟は助けよう」
「ありがとうございます」
歓喜の声をあげるメイシアにイーレオは複雑な表情を返した。一呼吸おいて冷たい海の波音を立てる。
「念のため訊いておくが、女が『なんでもする』と言った場合、どういう意味か分かっているな?」
メイシアの頬にさぁっと紅がさした。それは覚悟の上のはずだった。それでも無意識のうちに、彼女は自分の体を抱きしめ身を硬くする。
「貴族のお前を娼婦に堕とす。客はさぞかし喜ぶだろう」
「……はい。承知いたしました」
「いい返事だ。とりあえず、しばらくは俺の愛人として、この屋敷にいてもらう」
「はい」
自らが望んだこととはいえ、いざ現実になると、メイシアは恐ろしくてたまらなくなった。
「ミンウェイ、適当な部屋を見繕ってやってくれ。それから……」
イーレオの声が遠くで響いているように、メイシアには感じられた。しかし、それも耳鳴りによって、だんだんと不明瞭になっていった。
半ば意識を失ったような状態で、メイシアはミンウェイに手を引かれ、部屋を出て行った。
「おい、助平親父」
メイシアとミンウェイの姿が消えると、ルイフォンが口を開いた。彼はふと気づいたかのように立ち上がり、空いた向かいのソファーに席を移す。それから足を組み、肘掛に肘をついた。
「愛人、ってなぁ。髪染めて若作りしても、親父はもう六十五なんだから、いい加減『引退』しろよ」
癖のある前髪を掻き揚げ、呆れ顔で父を見る。見た目はせいぜい五十代だが、寄る年波には勝てないはずだ。
「初めに言うことはそれかよ」
イーレオは溜め息をついた。
「さすがにあのお嬢ちゃんを悦ばしてやれるほど若くはないさ」
ルイフォンは父の答えを「ほぅ」と嗤笑した。けれどそれ以上の言及はしなかった。
ひと呼吸おいて、彼は、すっと目を細める。獲物を狩るときの猫の顔になった。
「何故あいつを受け入れた? 貴族が凶賊の世界に馴染めるわけないだろ」
「お前も存外、お人好しだな」
「茶化すなよ」
ルイフォンが睨みつけると、イーレオは困ったように肩をすくめた。
「言外に思いとどまれ、諦めろと言い続けていたつもりだったんだがな。凶賊なんぞには関わらないほうがいい、ってな」
自ら凶賊の総帥となった男が言う。
「なら何故だよ?」
「お嬢ちゃんに言った通りさ。俺はあの娘に魅了された。あれはいい女になるぞ」
「色キチガイが」
そう言いながらルイフォンは足を組むのをやめ、自分の座っているソファーに手をついた。ほんの少し前までメイシアが居た場所だ。艶めかしげな温もりが、革の座面に残っていた。布張りのソファーだったら、消えていたかもしれない。ルイフォンは少しだけ、幸運を感じる。
「親父はあいつが本物の藤咲メイシアだと思うか?」
「お前は、どう思っているんだ?」
「本物だろ。……けど、エルファンとリュイセンはどう思うだろうな?」
「さてな」
他人事のようにイーレオは軽く笑った。
ルイフォンは、今、屋敷を留守にしている『鷹刀家の常識』のふたりの反応が気になったのだが、『鷹刀家の非常識』は、その問いには無視を決め込んだ。おそらく、なるようにしかならない、とでも思っているのだろう。
返答を求めても無駄だと悟ったのでルイフォンはそのまま引き下がる。それより眠気が襲ってきたので、部屋に戻って仮眠を取ろうと考えた。その矢先に「ルイフォン」と険しい声で呼ばれた。
「引き続き、藤咲メイシアについて調べろ」
ルイフォンはぞっとしない顔をした。
「俺、昨日は徹夜だったんだけど」
「どうせ、趣味のお遊びをしていたんだろ。こっちは、〈猫〉の仕事だ。若者なら働け」
ルイフォンは「人でなし」と毒づくと、自分の髪を弄び、金色の鈴を揺らした。
あくびを噛み殺しつつ部屋を出て行くルイフォンを、イーレオは楽しそうに見送る。
「イーレオ様は相変わらずですね」
今まで黙って事態を見守っていた護衛のチャオラウが、低い声で呟いた。イーレオは後ろに向けて首をかしげ、気を悪くしたふうでもなく純粋な疑問として尋ねる。
「どういう意味だ?」
「そのままの意味ですよ」
「俺が相変わらず若々しいということか」
「そういうことにしておきます」
そう言って、チャオラウは小刻みに無精髭を揺らした。
3.桜花の懐抱-1

実のところ、メイシアの実家である藤咲家の状況は、それほど単純ではなかった。
メイシアは、『父と異母弟が囚われた』と言っていた。それは間違いではなかったが、ふたりは同時に拉致されたわけではない。
まず異母弟が誘拐された。そのあと、藤咲家と斑目一族の間で、いくつかのやり取りがあった。それから、父親が囚えられた。おそらく、身代金でも手渡そうとして騙されたのだろう。
メイシアが執務室に来るまでの間に調べられたことは、そのくらいだった。あとは斑目一族を雇った貴族が厳月という家であり、藤咲家を敵視しているということくらいか。
自室に向かいながら、ルイフォンは眠い目をこすった。結構、厄介そうだな、と思いつつ、口元は笑みを浮かべている。
彼は、渦中の少女に思いを馳せた。
彼の父親は彼女のことを『小鳥』と呼んだが、彼は『桜の精』と言ったほうが正しいのではないか、と思った。儚くも優美で、それでいて根は強い。
ルイフォンが角を曲がると、長い廊下の向こうにふたつの影が見えた。メイシアとミンウェイである。
彼は心を弾ませながら、ふたりに駆け寄った。
「よっ」
軽く挨拶をする。
そして、振り向いたメイシアを見て、彼は言葉を失った。
その顔は、一流職人の手による精巧な人形のようであった。彼を見上げる瞳は、世界を映すことを拒絶した、硝子玉である。
ああ、とルイフォンは思った。
口ではどんなに気丈なことを言っても、彼女は何ひとつ不自由なく育った貴族である。明確に「娼婦になれ」と言われれば、やはりショックも大きいだろう。
彼も凶賊に属する身であるので、今までに何人もの売られてきた娘を見てきた。彼女たちは平民や自由民であったが、娼館に来た当初は大概の娘がふさぎ込んだ。中には自暴自棄になり、手に負えなくなった者も、少なからずいる。だから、メイシアがこうなるのも、無理はない。
しかし一方で、彼女の無謀に一途なあの目が気に入っていた彼としては、落胆の溜め息をつかざるを得なかった。
「なんだよ、その顔……」
「ルイフォン、少し、そっとしておいてあげて」
今にも倒れそうな様子のメイシアを支えながら、ミンウェイが代わって答える。
「……分かっているさ」
口をついて出たのは、ふてくされた子供のような声だった。後で遊ぼうと思っていた玩具を、理不尽に取り上げられて、拗ねている。そんな幼稚さに自己嫌悪したルイフォンは、ミンウェイに指摘される前に、大股でこの場を去ろうとした。
そのときだった。
「……ルイフォン様」
喪心状態と思われたメイシアが、彼の名を呼んだ。そして、彼女は、硝子玉の瞳のまま、頬の筋肉を弛緩させることで『笑顔』の表情を作った。
「先ほどは数々のご助言、ありがとうございました。これから、しばらくお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします」
用意された台本を読み上げるがごとく、流暢な音声が彼女の口から流れる。
これは、なんだ――と、ルイフォンの背に悪寒が走った。
根の強い桜は、強風を受け流すことができずに、ぽっきりと折れてしまうのだろうか。やりきれない思いは言葉の刃となり、気づいたら彼の口から飛び出していた。
「……心を壊した娼婦など、抱く価値もないぞ」
「なっ……!」
ミンウェイの眉が跳ね上がった。彼女は唇をわなわなと震わせ、二の句を継げない。
それなのに、メイシアはにこにこと微笑むだけであった。
ルイフォンは前髪を掻き上げた。
抑えようもない苛立ちを感じていた。彼は、目の前の人形から、作り物の笑顔の仮面をはぎ取りたい衝動に駆られた。
彼はメイシアの顎に手をかけた。
「何するのよ!?」
ミンウェイがメイシアを庇うように前に出て、ルイフォンの手を鋭く振り払う。鍛えているだけあって、女の身とはいえ、腕にびりびりときた。
「痛ぇな……」
「ルイフォン、あなた、おかしいわよ」
「おかしいのは、こいつのほうだろ!」
「だから、少しの間、そっとしておいてあげて、って言っているじゃない!」
「けど、こいつ、今にも壊れそうじゃないか……! こいつは、あの難攻不落な頑固親父を口説き落としたんだぞ。それが、こんなところで壊れてしまっていいはずがない!」
ミンウェイが「ルイフォン……」と呟いたまま、絶句した。
ルイフォンとミンウェイの視線が、交錯する。
嫌な緊迫感が、場を占める。
ぴん、と張り詰めた空気を破ったのは、細く高い呟きだった。
「…………おふたりとも……」
メイシアから、無垢な幼子のような響きがこぼれ落ちる。
「私は大丈夫です。……私は、イーレオ様とのお約束を守ります。決して逃げたりなんかしません……」
「馬鹿野郎。そうやって気負うから壊れていくんだ」
ルイフォンはミンウェイを押しのけて、メイシアを抱きしめた。腕の中で、彼女の体が急速に強張っていくのを感じるが、そんなことは気にしない。
彼女は見た目よりも、ずっと強い。
けれど、やはり桜は柳ではないから、嵐からは守ってやらねばなるまい。
ルイフォンはメイシアの髪をくしゃりと撫でた。そして、できるだけ優しい声で、耳元に囁く。
「お前の最初の相手は俺だからな? だから全部、任せろ」
メイシアの顔が見る間に紅に染め上げられた。羞恥と狼狽に、自然な表情が戻ってくる。
そんなふたりの様子に、ミンウェイの肩の荷が下りたかのように息を吐いた。それから彼女は、いたずらっぽく口元を緩めた。
「ちょっと、ルイフォン……」
ミンウェイの腕がするすると伸び、ルイフォンの首に巻きついた。そのまま首を締めるようにして、彼をメイシアから引き剥がし、自分の元へと寄せてくる。
「ミンウェイ!?」
「調子に乗らないの! 彼女は今のところ『総帥の』愛人よ。手を出すことなんかできない高嶺の花よ」
ミンウェイはルイフォンの頭を押さえ込み、悪ガキを懲らしめるように、ぐりぐりと拳で頭を撫で繰り回した。ふたりの体は密着し、ルイフォンが悲鳴を上げる。
「ミンウェイ! 無用にでかい胸を押し付けて、俺を窒息させるな」
彼が一本に編んだ髪を振って暴れると、それと共に、金の鈴がぴょこぴょこと楽しげに跳ねた。
「あら、スタイルを褒めてくれてありがとう。でも、無用なんかじゃないわよ」
さらりと言うミンウェイ。調子に乗って、より強く締め付ける。
「可愛い叔父様を誘惑するのに必要でしょう?」
「俺、お前に惑わされるほど、女に不自由していないから!」
「えっ……!?」
メイシアが目を丸くしていた。
「あ、これ、いつものスキンシップだから気にしないで」
ミンウェイがにっこりと笑う。
「え、いえ、そうではなくて……。『叔父様』……?」
メイシアは恐る恐る、といった体だった。
おおかた、姉弟か従姉弟くらいに思われていたのだろう――本人たちは苦笑して、頷き合う。
「私は鷹刀イーレオの孫娘。で、ルイフォンは末の息子」
「俺はあの助平親父が、老年に入ってからの子供だからな。俺よりずいぶん年上の行かず後家だけど、ミンウェイは俺の姪ということになる」
ルイフォンが口の端を上げて笑った。その彼の耳を、ミンウェイが引っ張る。
「さりげなく暴言を吐いていない?」
「俺は事実しか言わない」
ぶん、と頭を振って、ルイフォンがミンウェイの拘束を解く。
「あなたには少し言葉遣いを教えてあげないといけないわね」
「いや、俺は充分に礼儀正しいから」
いけしゃあしゃあと言い、「じゃあ、俺は部屋に籠もるから」とルイフォンは手を振った。ミンウェイは、はっとしたように真顔になる。
「お祖父様の命令?」
「そう。〈猫〉としての仕事」
すっと目を細めたルイフォンの口元に、矜持が見え隠れする。
「昨日、徹夜していたでしょう?」
「『若者は働け』だそうだ。あ、俺の晩飯は部屋に運ぶように言っておいてくれ」
「無理しないでよ」
「そう思うなら、親父に注意しておいてくれ」
ルイフォンは、そう言い残して、その場を後にした。
3.桜花の懐抱-2

案内された部屋は一階の端だった。
部屋に通された瞬間、メイシアは目を見張った。
満開の桜が彼女を出迎えてくれたのだ。
正面に、庭へと出られる大きな窓があり、今が盛りの優美な姿を誇っていた。
「今年も見事に咲いてくれたわね」
声もなく魅入っているメイシアにミンウェイが言った。
窓を開け、ミンウェイが自慢げに微笑む。爽やかな風がやってきて、メイシアに一枚の花弁を贈ってくれた。
「寒いかしら?」
「いえ、平気です」
ミンウェイの言葉にメイシアは頭を振った。
「……ミンウェイ様、どのくらいの間、このお屋敷に置いていただけるのか分かりませんが、しばらくはよろしくお願いいたします」
この部屋はミンウェイの歓待の気持ちなのだと、メイシアは思った。
部屋の調度は、派手さはないが質の良いものが集められており、イーレオの執務室へ行く前に通された小部屋のものより数段よい。
けれど、ミンウェイがこの部屋を選んだ理由は、この麗々とした桜に違いなかった。
「メイシア、堅苦しいのはよして。『ミンウェイ』でいいわ」
「ですが……」
恐縮するメイシアに、ミンウェイはくすりと笑う。
「ええとね。あなたの今の立場は、『総帥の愛人』なのよ。お祖父様の正妻はとっくに亡くなってらして、今は他に愛人はいないから、ある意味であなたは現在、この屋敷でお祖父様に次いで『偉い』のよ」
総帥の愛人には、何人たりとも危害を加えることができない。イーレオはそこまで考えて、メイシアを愛人という名の庇護下に置いたのだ。
ほどなくして、初めにお茶を出してくれたメイドが現れ、今度はふくよかな香りのジャスミンティーを淹れてくれた。
ミンウェイが、またメイドを労うと、今度は緊張した面持ちで、メイドはメイシアに視線を移した。使用人と言葉を交わすことなどめったになかったメイシアは、戸惑いを隠せなかったが、ミンウェイに倣って礼を述べると、メイドは可愛らしくはにかんだ。
その後、ミンウェイから幾つかの指示を受け、メイドは退出する。ふわりとしたスカートを翻す際に彼女はえくぼを見せた。自分より年下に見えるメイドが働いているのが、メイシアには新鮮だった。実家では澄ました大人の使用人ばかりだったからだ。
「少し、この屋敷のことを話しておいたほうがいいわね」
ミンウェイがお茶を口に運びながら言った。
「ここには、お祖父様とそのごく身近な血族、それから鷹刀に忠誠を誓った使用人や護衛たちが住んでいるわ。お祖父様の信頼の特に篤い者たちがね。中には今のメイドの子のように、親を失い、引き取った一族の子もいるわ」
ミンウェイが説明するところによると、ここに住んでいる血族は五人。
まず、総帥の鷹刀イーレオ。
次いで、イーレオの長子で次期総帥のエルファン。続いて、エルファンの次男で、イーレオの孫にあたる十九歳のリュイセン。このふたりは今、倭国を旅行中だという。明日には戻ってくるので、あとで紹介するとのことだった。
そして、先ほど会った末子ルイフォン。
最後に、孫娘であるミンウェイ。リュイセンとは従姉弟同士ということなので、どうやら彼女はエルファンの娘ではないらしい。
それから、ミンウェイはいくつかの説明と質問を繰り返し、日が暮れるまでにはメイシアが当面生活するのに充分すぎるほどの品々が揃っていた。その手際は実に鮮やかで、この屋敷を切り盛りしているのがミンウェイであることは、疑いようもなかった。
夕刻になり、メイシアの部屋にふたり分の食事が運ばれた。
普段は食堂で血族が揃って食事をするのだが、今日はエルファンとリュイセンが不在で、ルイフォンが部屋に籠ってしまった。なので、イーレオの計らいで、女同士交流を深めよ、ということらしい。
ミンウェイとの食事は実に楽しかった。
自然体で話す彼女はまるで十年来の知己のようであり、面倒見のよい姉のようでもあった。知識も豊富で、花言葉を教えてくれたことからも分かるように、こと植物に関しては詳しい。
メイシアはこの数日、食べ物がまともに喉を通らなかったのが嘘のように食が進んだ。
献立は、目が奪われるような豪華な一品というものはない。けれど一皿一皿に、腕の確かな料理人の計算しつくされた趣向が凝らされていた。旬の野菜の煮物は素材を生かした薄味で、しかも彩り鮮やかであり、白身魚の焼き物は味噌と共にほのかな柚子の香りがする。ひとつひとつの食材は決して珍しいものではないが、それらが互いを引き立て合い、見事な調和を生み出していた。
この屋敷を訪れてから、数時間。メイシアには少し分かってきたことがある。
鷹刀一族は平民でありながら、下手な貴族を軽くしのぐ財力がある。しかし、質実剛健を体現したような家風なのだ。
たとえて言うのなら、彼らが欲するものは、上質な布地を使った縫製のしっかりとした動きやすい普段着である。生地こそ高価であるものの、一度袖を通しただけで仕舞い込まれるような凝ったデザインの夜会服ではない。そんなものを着ていたら身動きが取れなくなってしまうではないか、ということらしい。
「今日は疲れたでしょう。ゆっくり休んでね」
食事のあと、ミンウェイは部屋付きの浴室の説明をして、早々に去っていった。波打つ長い黒髪を揺らしながら、音もなく扉の向こうに消える。もう少し話をしていたいところであったが、忙しい彼女の邪魔をしてはいけなかった。
給仕がすっかり片づけを終え、メイシアはひとりになった。
広い部屋が物寂しい。
昼間の緊張で疲れた体を清めたら、まっすぐに寝室に向かおう。
慣れない場所であるし、いろいろなことがあった日なので、簡単に眠れるとも思わない。けれど、続き部屋の寝室には上質な羽根布団と、安眠効果のあるカモミールの小袋が置かれていた。横になるだけでも体が休まるだろう。
メイシアはミンウェイの数々の心遣いに感謝しながら、浴室に入った。
熱い湯を浴びて上気した肌の上を、小さな水滴が転がり、床へと滴り落ちる。体の汚れと共に、疲れも流れていくかのようだった。
脱衣所に出て、メイシアは柔らかなバスタオルで全身をくるんだ。皮膚の湿り気を拭き取っていくと、彼女の口からは知らず識らずに、ほぅっと息が漏れた。
と、そのとき。
ばたん、と勢いよく部屋の扉が開く音がした。荒々しい足音が部屋の中へ入ってくる。
「ミンウェイさん?」
何事だろう。まだ濡れたままの髪から雫を降らせながら、メイシアは思わず脱衣所を飛び出した。
「……え?」
そこでメイシアが見たものはミンウェイの姿ではなく、一本に編まれた髪とそれを飾る金色の鈴の煌きだった。
ルイフォンである。
彼は気配を察したのか、「そこにいたのか」と言いながら、くるりとこちらを向いた。
さきほどは掛けていなかった眼鏡を掛けていて、その奥の目は真っ赤に充血していた。やや癖のある前髪が乱れており、明らかに疲れた様子である。
どうしたのかと尋ねようとしたとき、彼がすっと目を細めた。
「俺って、ひょっとして凄く運がいい?」
メイシアは青ざめた。
バスタオルを巻いただけのあられもない姿――剥き出しの肩から伸びた瑞々しい白い腕。先程タオルでぬぐいきれなかった水滴を若々しい肌が弾き、宝石のように彼女を飾っていた。
声にならない悲鳴を上げ、メイシアはその場にしゃがみこんだ。両腕で自らを抱き、できるだけ小さく縮こまる。
「お前、綺麗だな」
感心したようにルイフォンが言った。舐めるような視線に、メイシアの顔が今度は真っ赤になる。
「も、申し訳ございません。見ないでください」
「なんで? 綺麗なものを見ていたいと思うのは人間の自然な欲求だろ?」
ルイフォンはまるで動じない。それどころか傍にあった椅子に逆向きに座り、背もたれに顎を載せ、文字通りじっくりと腰を据えた。
「か、からかわないでください」
「からかってなんかいないさ。綺麗なものは、綺麗。愛でたくなるのは道理だろ」
メイシアは、はたと先程のやり取りを思い出した。お前の最初の相手は俺、とかなんとか……。
――ひょっとして夜伽というものを要求されているのだろうか……。
覚悟は出来ているつもりだった。だが、あまりにも急だった。
メイシアは、がたがたと震えながら上目遣いにルイフォンを見た。目にはうっすらと涙が浮かんでいる。
そんなメイシアに、ルイフォンはぷっと吹き出した。
わけが分からず目を丸くする彼女に、彼は更に笑い出す。
「分かっていてやっているわけじゃないだろうけど、それ、凄くそそるぞ」
椅子の背に顔を押し付けながらルイフォンは腹筋を震わせていた。メイシアは耳まで赤くしてうろたえる。
「安心しろ。いきなりお前を襲うほど、俺は女に飢えていない」
笑いを抑えつつルイフォンが言う。彼はメイシアよりも年下のはずなのだが、とてもそうは思えなかった。
彼は「着替えて来い」と言いながら、本来そうあるべき向きに椅子を座りなおし、彼女に背を向けた。
メイシアはおずおずと立ち上がり、ルイフォンの背中が動かないことを確認し――それでもバスタオルの裾を気にしつつ、脱衣所に戻った。
できるだけ早く、しかし見苦しくないように身支度を整えてルイフォンの元へ戻ると、彼は少しだけ落胆した顔を見せた。
「惜しいことをしたかもな」
メイシアが返答に詰まっていると、急にルイフォンの声色が変わる。
「さて。本題だ。俺の部屋に来てくれ」
そう言うと、彼女の返事も待たずに、彼は金の鈴を煌かせ、部屋を出て行く。
「え? 待って下さい」
メイシアはルイフォンの部屋を知らない。置いていかれないよう、慌てて彼を追いかけた。
4.猫の足跡を追って-1

ルイフォンの一本に編まれた尻尾を追いかけて、メイシアは階段を上がる。
彼の青い飾り紐を見ながらメイシアはふと気づいた。中央にある金の鈴は歩くたびに音を響かせるものかと思っていたら、意外にも無音だった。その代わりに彼の足音が聞こえる。ミンウェイがそうであるように、ルイフォンもまた足音を立てないものかと思っていたのだが、そうでもないらしい。
似たような扉を幾つか通り過ぎた。扉と扉の間隔から中の部屋の広さが窺い知れる。このあたりの部屋は、階下の部屋よりだいぶ広いようであった。
絨毯の柔らかさを踏みしめながら、メイシアはルイフォンの背中についていく。このまま行くと廊下の端までたどり着いてしまう、そう思ったとき彼が足を止めた。
「入れ」
そう言いながら、ルイフォンが部屋に入った。
彼に続こうとしたメイシアは、びくりと体を震わせた。中から冷たい風が押し寄せてきたのだ。風呂上りの肌の熱が急速に奪われていく。
何故、と疑問に思いつつ足を踏み入れると、硬質な床の感触がつま先を伝わってきた。客間はもとより、長い廊下のどこを見ても絨毯の敷かれたこの屋敷において、ここだけは異質だった。
リノリウム張りの床が広がり、無機質な事務机が数台、円を描くように並べられていた。そして、それらの机の上には多種多様な機械類。メイシアにも見覚えのあるタイプのコンピュータもあれば、プリンタと思しき機器やアンテナを生やした謎の筐体もあり、ものによっては周囲のものとさまざまな太さのケーブルで繋がれていた。
彼女の知識では説明しきれない数々の機械類の中央で、ルイフォンが回転椅子に腰掛ける。一台のコンピュータに椅子を寄せると、カタカタと何かを打ち込み始めた。流れるような打鍵はまるでピアニストだ。
「ここは……?」
「俺の仕事部屋」
モニタに向かったまま、ルイフォンが答えた。
彼の足元には、蓋の開きっぱなしになっているダンボール箱が転がっていた。銀色の配線が張り巡らされたメタリックグリーンの基板、何本もの灰色のコードに一本だけ赤いコードが合わさった太いケーブル、色とりどりのコードを生やした換気扇のついた金属箱……そんなものが雑多に押し込められていた。
彼はダンボール箱を蹴らないように器用に回転椅子を滑らせ、車座の反対側の机までたどり着くと、そこにあったキーボードを叩いた。
メイシアが呆然としていると、ルイフォンが手招きをしてきた。彼女は床を這っているケーブルを踏まないように、跨いで机の輪の中に入る。
ルイフォンが机の下に入れてあった丸椅子を取り出し、メイシアに勧めた。続けて、コンピュータに接続された装置を示す。
「これに右中指を載せてくれ」
ちょうど指の第二関節くらいまでが載りそうな窪みのついた、小さな四角い機器だった。どんな材質でできているのか、黒い表面は硝子のように周りの風景を映している。
「……これは、なんでしょうか?」
「指静脈認証ユニット」
端的にルイフォンが答える。
いったい何をする気だろう。メイシアは戸惑いを隠せなかったが、先ほどまでは掛けていなかった眼鏡に、青白いモニタ画面を反射させた無機質な彼の横顔は、彼女に質問を許してくれそうになかった。
メイシアが躊躇いがちに指を載せると、窪みの左右から光が照射された。痛くも痒くもなかったが思わず体を強張らせてしまう。
そのとき、モニタに『pass』という表示が出た。
「よし」
「あの……?」
「静脈認証完了。これでお前は正真正銘、本物の藤咲メイシアだと証明された」
ルイフォンが言った。口の端を上げ、机に頬杖をつきながらメイシアのほうを振り返る。心なしか嬉しそうな顔をしているように感じられた。
メイシアはわけが分からず、きょとんとルイフォンを見る。
「……どういう、ことでしょうか……?」
「さっき言われただろ?『お前は本物の藤咲メイシアか』って。親父はお前を認めたけど、一族の中には頭の固い奴がいてな。お前が本物だとはっきりしているほうが、いろいろと都合がいいんだよ」
「いえ、そういうことではなくて……」
何故、今の行為で自分が本物と証明できたのかが分からないのだ。そう言おうとして、ルイフォンが目を細めていることに気づいた。メイシアの困惑を楽しんでいるのだ。
彼は「もう、指を外していいぞ」と言って、指静脈認証ユニットと称した機器をダンボール箱にしまった。それを部屋の端まで運び、壁一面に据え付けられた棚の一つに収める。
棚の半分は似たようなダンボール箱で埋まっており、残りの半分は分厚い洋書に占められている。簡単な物語程度なら原書でいけるメイシアだが、それらの本のタイトルは読めない。正確にいえば、読めるのだが理解できない。いわゆる専門書なのだ。
ふと鼻がむずむずして、メイシアは小さなくしゃみをひとつした。
「あ、悪い。寒かったか」
ルイフォンが棚から緋色のストールを出してきて、メイシアにほうった。
「ここは俺の仕事部屋だ。人間より機械が優先される。だから通年、空調が効いているし、埃が出るから絨毯も敷かない」
ストールはミンウェイが置いているものだと説明してくれた。メイシアはありがたく羽織りながら質問する。
「仕事、というのは……?」
ルイフォンがにやり、と猫のように笑うと、回転椅子まで戻って腰を下ろす。
「俺が何故、お前の本人証明ができたと思う?」
「分かりません」
「お前は王立銀行に口座を持っているだろう。口座を開いたとき、カードも作ったはずだ」
「キャッシュカードのことですか?」
「そう、静脈認証機能つきのやつだ。俺は銀行のデータベースから『貴族の藤咲メイシア』の静脈パターンのデータを盗ってきて、『お前』の静脈パターンと照合した、というわけだ」
メイシアはルイフォンの言うことが理解できなかった。
彼女は、銀行でカードを作るときに、生体認証機能云々と説明されたことは覚えていた。しかし、何故そのことをルイフォンが知っているのだろう。データを、盗ってきた――?
「ルイフォン様は王立銀行の関係者――というわけではありませんよね?」
「『様』は、よせ」
ルイフォンが心持ち、憮然とした顔になった。メイシアはしばし考えて言い直す。
「ルイフォン――は、王立銀行の技術者ではありませんよね?」
メイシアは敬称をつけようとして、途中でやめた。どうやらそれは正解だったようで、目元の微妙な動きからルイフォンが機嫌をよくしたことが分かる。
「少なくとも、王立銀行から金を貰ってはいないな」
楽しそうな、揶揄すら含んだ口調。
つまり、違法行為だ。
「〈猫〉という名前を――まぁ、お前は知らないだろうな」
「『フェレース』?」
「『フェレース』は、ラテン語で『猫』という意味だ。猫のように音もなく情報に忍び寄り、狙った獲物を盗っていくクラッカー。コンピュータネットワーク世界の情報屋だ」
メイシアは改めてルイフォンを見た。やや癖のある前髪に、一本に編んだ後ろ髪。飾り紐には金の鈴。目は雄弁に物を語り、姿勢は常に崩している。彼のどことなく猫を思わせる仕草に、その名はよく似合っていた。執務室の扉の仕掛けも、彼の手によるものなのだろう。
「さて……、『礼状』でも出すか。メイシア、ちょっと見てろよ」
ルイフォンは再びキーボードに指を走らせる。
すると、モニタ画面が真っ白になったかと思ったら、右端から黒い猫の影が入ってきた。
可愛らしくも、しなやかな足取りで、猫はモニタ上を歩き回り、通ったあとに足跡を残していく。やがて、猫の姿は見えなくなり、足跡だけが次々に表示され、ついに画面は真っ黒になった。――もうモニタは何も映さない。
「え……?」
「こいつを王立銀行に送る。ウィルスじゃないぞ。これは、ただのアニメーションだ。先方がどう思うかは知らないけどな」
ルイフォンの意図が分からず、メイシアは首を傾げた。そんな彼女に対し、彼は目を細めて軽く笑う。
「〈猫〉が侵入した足跡を残しておくんだよ。つまり、データを盗らせてもらった礼として、銀行側にセキュリティホールの存在を知らせてやる」
「それは……何か、変な気がします。ルイフォンが攻撃する側なのか協力する側なのか分かりません」
「両方だよ。ネットワークは本来、性善説に基づいている。悪意ある使い方には非常に脆弱な代物なんだ。だから昔の技術者たちは互いにセキュリティを突破し合い、侵入した痕跡を残したそうだ。善意でね。まぁ、俺は先人たちほど善人じゃないから、気まぐれと売名行為かな?」
「売名行為?」
「〈猫〉の名前が知れ渡れば、依頼も情報も集まる。〈猫〉はクラッカーであると同時に、鷹刀の諜報担当だからな」
メイシアと会話しながらも、ルイフォンの指先は軽快にキーボードの上で踊っていた。
表向きは、鷹刀一族は〈猫〉の取引相手のひとつに過ぎず、ルイフォンが〈猫〉であることは極秘事項なのだという。
「……セキュリティ対策をされてしまったら、また王立銀行に用があったときに困るのではないですか?」
「そのときはそのときで、また別の抜け穴を探すさ。『この世に完璧なプログラムは存在しない。存在しうるのは、まだバグの発見されていないプログラムだけだ』――俺の母親がよく言っていた言葉だ。誰かの受け売りらしいけどな」
「お母様……?」
「先代の〈猫〉。もともと〈猫〉は俺の母親の通称だったんだよ」
そう言ったルイフォンの顔は少し誇らしげで、そしてどこか寂しげだった。メイシアはある可能性に気づいたが、それを確認する気にはなれなかった――おそらく、それは当たっているであろうから。
ルイフォンがぐっと背筋を伸ばすと、回転椅子の背もたれがぎぎいと軋むような音を立てた。それから彼が首を左右に曲げると、小気味いいほどにぽきぽきと彼の骨が鳴った。疲れた様子の彼を見て、メイシアは「あっ」と小さな声を上げた。
「ひょっとしてルイフォンは夕方、廊下で別れてからずっと、ここで作業をしていたのですか?」
愚問だ。
言ってからメイシアは自分の愚かさに気づく。ルイフォンはあのとき言っていたではないか。『部屋に籠もる』と。『〈猫〉としての仕事』だと。
あれから何時間が過ぎたのであろう。もうすっかり夜も更けている。
メイシアがミンウェイと楽しく食事を摂っていた間も、風呂でくつろいでいたときにも、ルイフォンはここで働いていたのだ。それは誰のためか。――言うまでもない、メイシアのためだ。
「申し訳ございません」
「ん? 何が?」
「私のために今まで……」
「お前、俺を舐めている? 俺は王立銀行の穴くらい一瞬で見抜ける。時間がかかったのは、親父の命令で調べることがたくさんあったからだ。お前が気にすることじゃない」
「けれど……」
納得いかない様子のメイシアにルイフォンは少し困ったような、それでいて目元だけはまんざらでもなさそうな顔をした。
「そういうときはな、『ありがとう』と言うんだ」
ルイフォンの言葉はそっけなく、そして温かい。
敬慕の眼差しを向けてきたメイシアに、ルイフォンは照れたように「ミンウェイの口癖だけどな」と付け加えた。
「ありがとうございました」
長い黒髪を揺らしてメイシアは深々と頭を下げた。シャンプーの香りがふわりと漂い、ルイフォンが表情を崩した。
「ま、少しは疲れたかな?」
彼はそう言うと眼鏡を外し、目を軽くマッサージするように指で押さえる。
「あの、大丈夫ですか。モニタを見続けると目が疲れるんですよね?」
「まぁな」
「目がお悪いんですか。イーレオ様も眼鏡を掛けてらっしゃいましたし……」
「違う! 親父のは老眼鏡! 俺のはOAグラスだ!」
ルイフォンが牙をむいた。
「……ったく。俺をあの助平親父と一緒にすんな」
苛立たしげに癖のある前髪を掻き上げる。そんな仕草はやはり十六歳の少年のようで、猫のようにくるくると印象の変わる彼をメイシアは不思議な気持ちで見つめていた。
「さて――」
ルイフォンがちらりとメイシアを見る。ふと、何を思ったのか、彼はにやりと笑った。
「夜食に付き合え」
「え?」
「俺は、晩飯に片手でつまめるものしか食ってない。作業中だったからな。腹が減った」
「申し訳ございません」
「そこで謝るな、って。だからさ、一人で飯を食うのも虚しいから、付き合えよ。お前は食わなくてもいいから。……それに、藤咲家と斑目について、真面目に訊きたいこともあるしな」
その言葉を聞いた途端、メイシアの背中を緊張が走った。
4.猫の足跡を追って-2

ルイフォンの案内で、メイシアは食堂にやってきた。
扉を開けてすぐのところにあるスイッチを、ルイフォンがパチパチと入れる。高い天井から淡い光が注がれ、純白のテーブルクロスが掛けられた丸テーブルが浮かび上がった。
テーブルはそれほど大きくはない。十人は座れないだろう。今は椅子が五脚だけなので、それほど窮屈には見えないが、部屋の広さに対して小ぢんまりとした感があった。庭に面した南側は一面の硝子張りになっており、外灯が木々のまどろみを幻想的に映し出していた。
メイシアたちが入ってきた気配を察してか、奥の厨房から恰幅のよい初老の男が現れた。服装からして料理人であろう。
「ルイフォン様、お夜食でございますか? そろそろかと思って準備しておりましたよ」
「さすが、料理長。いつも悪いな」
ルイフォンが親しげに言う。
「わざわざお越しいただかなくとも、お申し付けくださればお持ちいたしましたのに」
「そりゃ悪いって。もう仕事あがってんだろ? ま、作らせちゃうのは同じなんだけどさ。――というわけで、頼む。腹が減って死にそうだ」
「お任せください。……そちらのお嬢さんは如何いたしますか?」
不意のことだったので、メイシアは反応が遅れた。
「え……、いえ。私は結構です」
「そうですか。では」
腹を揺らしながら厨房に戻る料理長にメイシアは慌てて声を掛けた。
「あ、あの……! お夕飯、とても美味しかったです。ご馳走様でした。……その、ありがとうございました」
料理長は振り返り「それは光栄です」と、外見に似合わぬ気取った礼をとり、豪快に笑いながら去っていった。
傍らでルイフォンがにやにやとメイシアを見ていた。
「お前、使用人と喋るのに慣れていないだろ」
「……はい。身分の違う者とは話すものではない、と。そう教えられて育ちました」
「だろうな。――でも、ま、大丈夫そうだな」
ルイフォンは納得したように頷くと椅子のひとつに座り、メイシアを手招きする。どこに座ったものかと悩む彼女に、彼は自分のすぐ右隣の席を指定した。
左肘を立てて頬杖をつき、ルイフォンはメイシアを斜めに見上げていた。足を組んだ、相変わらずの崩した姿勢である。それなのに、いつになく険しい彼の視線に、メイシアはどう対応したものか戸惑い、居心地の悪さを覚える。
「斑目を雇ったのは厳月家だ」
唐突に、ルイフォンが口を開いた。今までより一段、声色が低い。
「やはり、厳月家でしたか……」
メイシアの口から重い息が漏れた。
執務室で、イーレオが『斑目は、ある貴族に雇われて、動いている』と言った。それを聞いたときから、彼女は、なんとなく察していた。
藤咲家と厳月家には、浅からぬ因縁があった。
どちらの領地にも良質な桑園があり、古くから養蚕と絹織物工業が盛んだった。故に、何かの式典の折には、どちらの家が王族の衣装を請け負うか、熾烈な争いを繰り広げてきたのである。
「おかしいと思ったんです。凶賊が誘拐事件を起こしただけで、親族中が集まって上を下への大騒ぎをするなんて……」
誘拐事件なら、身代金を払うことで解決できるはずだ。
メイシアは瞬きもせず、じっと押し黙った。
話を始めたばかりだったルイフォンは、続けてよいものかと、メイシアを頭の先から走査して、膝の上できつく組み合った両手のところで目を止めた。
彼がおとなしく待っていると、やがてゆっくりと、彼女は口を開く。
「……もともと藤咲家と厳月家は、あまり良い関係ではありません。けれど、『今』、厳月家が動きました。――その理由になるような、『何か』があったのですか?」
メイシアの質問に、ルイフォンの眉が動いた。だから、彼女は語尾を言い換え、断定した。
「――あったんですね」
メイシアの真っ直ぐな眼差しを受け止め、ルイフォンは頬杖をやめた。崩していた姿勢を正して静かに口を開く。
「発端は、女王だ」
「え……?」
思いもよらぬ言葉に、メイシアは目を丸くする。それがどう自分と関わってくるのか、まるで見当もつかない。
「まだトップシークレットだが……。女王の結婚が決まった」
「女王陛下が、ご結婚……!?」
喜ばしいことであるが、しかし素朴な疑問が口をついて出る。
「女王陛下は先日、十五歳になられたばかりです」
「そんなの、王族には関係ないだろ?」
メイシアの脳裏に、王宮の最奥を彩る、可憐な少女王の姿が描かれる。
天空の神フェイレンと同じく、輝く白金の髪に、澄んだ青灰色の瞳を持つ、神の化身――神の姿を写した〈神の御子〉。
黒髪黒目の国民は、〈神の御子〉を王に戴く。
しかし、〈神の御子〉の誕生は非常に稀である。しかも、天空の神が男神であることから、女王はあくまでも『仮初めの王』に過ぎず、この国では長いこと新しい王の誕生が待ち望まれていた。
結婚は、まだ早過ぎるのでは、とメイシアは口を挟みそうになったが、言われてみればルイフォンの言う通りであった。
メイシアが口をつぐんだのを受けて、ルイフォンが次の句を発した。
「既に、婚礼衣装担当家も決まっている」
はっ、とメイシアが息を呑んだ。
王族の婚礼衣装となれば、藤咲家か厳月家のどちらかが担当することになる。
緊張に、全身が強張る。耳をそばだて、彼女はルイフォンの言葉を待った。
「お前の実家、藤咲家だ」
小さな息を吐き、メイシアは華奢な肩を下げた。
女王の一世一代の晴れ舞台の衣装。それを請け負うのは藤咲家にとって大変な名誉である。誇らしさと喜びに胸が熱くなるが、次の瞬間、メイシアの背筋が凍った。
「では、ハオリュウを――異母弟を誘拐したのは……」
メイシアの頭を嫌な予感が横切る。
婚礼衣装担当家が藤咲家に決定した直後の誘拐。
その実行犯である斑目家の背後には、選考に漏れた厳月家の影。
これらが符号していることは――。
「藤咲家に、婚礼衣装担当家の辞退を、要求するため……?」
「そうだ」
メイシアは頭を鈍器で殴られたかのような衝撃を覚えた。唇はわなわなと震え、紫色に変色している。
「ですが……! ……そんな、だって……、まさか……」
繋がらない言葉の羅列が、彼女の口をついて出る。
六歳年下の異母弟ハオリュウ。
既に身長は追いつかれ、声だって低くなってきたのに、小さい頃と変わらずに『姉様』と慕ってくる声がメイシアの耳に残っている。
酷い耳鳴りが襲ってきて、たまらずに彼女は頭を押さえた。
「嘘です……! だって、そんなことをすれば、いずれ厳月家は罪に問われるでしょう……!」
「厳月家と懇意にしている絹商人から、斑目の隠し口座に結構な額の金が振り込まれていた」
メイシアは、はっと息を呑んだ。
「スケープゴート……」
筋は通る。担当家が変わることで得をする者は、厳月家だけではない。
万が一、王族の尋問を受けても、厳月家はきちんと逃げ道を用意してあるのだ。
ここまで聞けば、状況は明白だった。
メイシアは、全身の血の気が引いていくのを感じた。
異母弟の生命と、家の命運が――天秤に載せられている。
「……今なら、私の家に集まってきた親族が、争っていた言葉の意味が分かります」
呟くようにメイシアは言った。
「『ハオリュウは捨て置くべきだ』――と」
親族たちは、平民を母に持つハオリュウを疎んでいる。日頃から、跡継ぎは、メイシアに婿を取らせるべきだと声高に叫んでいた。
そして、栄えある名誉を辞退すれば、王族を侮辱したとして、貴族の地位を剥奪される可能性もある――。
「ルイフォン、教えてください! 父は、どう返事をしたのですか。――父は、単身で斑目一族のもとに行ったんです!」
必死に訴えるメイシアに、ルイフォンは「すまない」と首を振った。彼の背を、金の鈴が力なく転がる。
「そこから先は、ネットワーク情報中心の〈猫〉には分からない。改めて別の者に調査させる。約束する」
「っ……! ……すみません」
思わず声を荒立ててしまったことを、メイシアは恥じた。
本来なら藤咲家の内情は、身内である彼女が熟知しておくべきことだ。他人であるルイフォンに教えてもらうほうがおかしい。
メイシアは両手をテーブルにつき、うなだれた。
彼女の口から、乾いた笑いが漏れる。淑女たるもの、いつなんどきでも、己を忘れてはならない――そう、心に刻み込まれてきたはずなのに、彼女は溢れ出す感情を止めることはできなかった。
「どうして……、どうして……! 父は、親族は、私に何も教えてくれなかったんでしょうか……? どうして……!」
メイシアが顔を上げ、血の気を失せた顔をルイフォンに向けた。唇に掛かった一筋の髪があどけなく、すがるような幼子の顔だった。
ルイフォンは、思わず惹き寄せられるように手を伸ばし――途中で我に返った。
今は一応、仕事中であり、彼女は依頼人だ。
彼は、次に彼女に伝えるつもりだった情報について、頭の中で整理した。そして、話の切り出し方に少しだけ工夫を加える。
「俺は、お前の家の人間じゃないから、お前の家のことなど分からない」
メイシアの頬が、ぴくりと動いた。
「ただ、俺は情報屋だから、情報の大切さは知っている」
ルイフォンの声に、メイシアの握りしめていた拳の力が緩んだ。彼女は、じっと彼の言葉に耳を傾ける。
「女王の結婚の話はトップシークレットだ。箝口令が敷かれている。だから、それに関連する婚礼衣装担当家の話もおいそれと口にできない」
「でも、親族は皆、知っていて……」
「お前はまだ未成年だ。教えられなくても不思議じゃない。現に、お前自身が請け負う仕事は何もないだろう?」
「ですが……」
腑に落ちない様子のメイシアに、ルイフォンは鋭い目を向けた。
「お前の父だって、いつまでも黙っているつもりはなかっただろうさ。――だが、もうひとつ、事件が起きたんだ」
「まだ、他に……」
「ああ。――この話が出たから、お前に話すタイミングに困ったんじゃないか?」
いったい何が、とメイシアの目がルイフォンを急かし立てる。
「お前の異母弟が誘拐されてからしばらくの間、厳月家は斑目とは無関係を装い、沈黙を守ってきた――それが、表舞台に出てきた」
ごくり、とメイシアは生唾を呑んだ。
ルイフォンが軽く目を瞑りながら、すぅっと息を吸う。次に彼が目を開いたときには、やけに神妙な作り顔になっていた。
「『厳月家の三男の妻として、ご息女を迎え入れたい。さすれば、姻族として、凶悪なる誘拐犯から大切なご子息を取り戻すための私設兵団をお貸ししましょう』」
読み上げるかのようなルイフォンの声が、メイシアの耳に届いた。
よく通る声だったが、メイシアが内容を咀嚼するまでには、しばしの時間を要した。
彼女の目は、どこを見るというわけでもなく見開かれ、瞬きひとつしない。
「……つまり、厳月家と姻戚になれば、ハオリュウは無事に返す――と」
私設兵団というのは表向きの話だろう。雇い主である厳月家が斑目一族に命じれば、ハオリュウは解放されるのだから。
「俺の目には、厳月家の一番の狙いは、お前に見える」
家の没落と、愛息の死。
その究極の選択に、メイシアの婚姻という選択肢が紛れ込む。それは他の二つの代償に比べれば、あまりにも軽い。
否――軽く見えるように仕組まれた罠だ。
「普段の藤咲家なら、ライバルである厳月家と婚姻を結ぼうとは考えない。でも、追い込まれた今なら、お前を差し出すだろう」
メイシアは、黙って首を縦に振る。
「では、厳月家がお前を手に入れるメリットは、なんだ?」
「……事実上の人質」
「だろうな」
実家は、娘の嫁ぎ先での処遇を憂慮して、無形の支配を受けることになる。よくあることだ。
「厳月家は、そうやって、じわじわと藤咲家を掌中に収めようとしているんだろう」
「…………」
メイシアは思わず絶句せずには居られなかった。戦慄が彼女の全身を駆け巡る。
隠された、恐るべき陰謀。
その一角に辿り着いたことに。
「――厳月家が書いたシナリオは理解できたか?」
ルイフォンが尋ねる。
「いっぱい、いっぱいですが、なんとか把握できたと思います」
メイシアは、こくりと深く頷いた。
しかし彼女は、口の中に残る、後味の悪い苦さを飲み込むことができなかった。ざらついた違和感が喉の奥に引っかかっている。
何か、大切なことを見落としているような気がする。けれど、それを言葉にして吐き出せないでいる――。
ルイフォンが癖のある前髪を掻き上げた。猫のような目が、すっと細くなる。
「明らかに、おかしいだろう?」
「え……?」
「メイシア。お前は、どうして鷹刀に来たんだ?」
唐突に、ルイフォンが疑問の形で訊いてきた。けれどメイシアには非難が含まれているように感じられた。
「えっ? それは父と異母弟を助け出すために、武力をお借りしようと……」
「厳月家のシナリオでは、お前は大切な『花嫁』なんだよ。それが、どうしてお前はここに――凶賊の屋敷に居るんだ?」
広い食堂にルイフォンのテノールが木霊する。苦すぎず、かといって甘くもない。
父親であるイーレオの低音とは、また別の魅惑的な響きを奏でながら、ルイフォンはメイシアを見据えていた。
4.猫の足跡を追って-3

窓硝子の向こうで、風が流れた。
白く幽玄な花びらが、夜闇に浮かび上がる。ちらり、ちらり、艶やかに踊る。
桜の木が根を下ろしているのは、広い庭の向こう側であり、枝はここまで届きはしない。
それでも、この庭で花びらが舞っているのは、いたずらな春風がさらってきたからである。
そして、窓硝子のこちらでも――。
舞い込んできた小鳥が一羽、自分の置かれた状況を理解できず、小首をかしげていた。
「お前は、誰のシナリオで踊っているんだ?」
しなやかで鋭い、獲物を狙う猫のような瞳で、ルイフォンは尋ねた。
「え……?」
「『花嫁』のお前が凶賊の毒牙にかかろうとしているんだぜ? おかしいだろ?」
「あっ……」
メイシアは小さく叫び、口元を抑えた。
まさに、ルイフォンの指摘通りだった。
厳月家がメイシアを花嫁として迎えたいのなら、彼女が凶賊の屋敷に行くなんて、言語道断だ。
「事態は厳月家のシナリオ通りに進んでいない、ってのが、分かるよな?」
「はい」
「じゃあ、どこから変更されたのか?」
ルイフォンは両肘をテーブルに付き、組んだ両手の上に顎を載せた。端正なはずの顔は、獲物を追い込んでいく獣の顔になっている。メイシアは無意識に身を引きながら推測を口にした。
「私が、この屋敷に来たところから――、……いいえ、違う」
「ああ、違うな」
言いかけた意見を取り消したメイシアに、ルイフォンが同意する。
「父が斑目一族のところへ行ったところから、ですね」
「おそらく」
そう、鋭い声がメイシアに応じた。
「厳月家は、お前の父親から『お前を嫁に出す』という約束を取り付けたかったはずだ。もしくは、衣装担当家の辞退。どちらにせよ、お前の父親が家から出るなんてことは望んでいなかった」
ルイフォンは、癖のある前髪をくしゃりと掻き上げた。
「メイシア、そろそろ、お前の知っていることを話してくれないか? 〈猫〉は議事録や通信記録を荒らすのは得意だが、現場のことは何ひとつ見ていないんだぜ?」
「え? 私の知っていること?」
メイシアは目をぱちくりとさせた。
知っていることなどなにもない、と言いたげな彼女に、ルイフォンは噛み砕くように言う。
「まず教えてくれ。お前の父はどうして斑目の屋敷に行くことになったんだ?」
「すみません。私も詳しい経緯は知らないのです。ただ、父が単身、斑目一族の屋敷に行って囚えられてしまった、とだけ、継母から……」
「ふむ」
顎を触りながら、ルイフォンは思案する仕草を見せた。
メイシアもまた思考を巡らせ、継母から伝えられたときのことを思い出す。
「――父がひとりで行動することはありません。警護の者がつくはずです。継母も行き先を知っていたことから考えると……斑目一族に、ひとりで来るように指示された……?」
「その可能性が高いな。ということは、今のシナリオは斑目のものだ」
そう、ルイフォンが断定した。
大きく遠回りをして、また振り出しに戻ったようである。結局のところ、メイシアの敵対する相手は斑目一族ということらしい。
「斑目が厳月家を裏切ったな」
ルイフォンが吐き出すような溜め息をついた。
彼は、くしゃくしゃと前髪を掻き上げたかと思ったら、その手で額を抑えた。そのまま音を立ててテーブルに肘をつき、頭を抱える。そんな彼の行動は、メイシアの目には奇妙に映った。
いったいどうしたのだろう、と不審に思う彼女の顔を、彼がちらりと伺う。彼女を見る目は、どこか申し訳なさそうで、わずかに憐れみも混じっていた。
「もう一度、訊く。どうして、お前は鷹刀に来たんだ?」
ルイフォンは体を起こし、問い質すように尋ねた。
メイシアは、はっと顔色を変えた。あの女の出現が偶然などではない可能性に気づき……次の瞬間に可能性は確信に変わった。
「……人に、聞いたのです。『凶賊に対抗するなら、凶賊を頼るしかない』と」
メイシアの声は震えていた。
ルイフォンの目がすっと細まる。
「『誰に』、聞いたんだ?」
「継母のところに出入りをしている仕立て屋です。『裕福な凶賊の屋敷にも出入りしているから、彼らの性質はよく知っている』と言っていました」
「その仕立て屋の名は? お前のよく知っている奴なのか?」
「ホンシュアという名で、私は初めて会いました」
仕立て屋らしく、体にぴったり合った上等なスーツを着こなしていた。隙のない立ち姿に、ねっとりと絡みつく蛇ような目線。綺麗に引かれた真っ赤な口紅は血の色を思わせた。
継母の採寸に来たのだが、来客中だったため庭で時間を潰しているところだと、彼女は言っていた。
「『斑目一族に対してなら、敵対している鷹刀一族に力を借りればいい』と彼女は言いました。『凶賊は互いに潰し合いたがっているから、きっと喜んで手を貸してくれる』と」
そこでメイシアは言葉を切った。ルイフォンが気を悪くするかと思ったのだ。
案の定、彼は眉を寄せていた。けれど、続きを促すように目が指図する。
「『私には財産を動かす権利はない。だから雇うことはできない』と言ったら、『女なら、できるでしょう? 男たちには使えない方法が、ね? 特に鷹刀一族なら、そっちのほうが喜ばれるわ』そう教えられたのです」
「…………」
ルイフォンは再び頭を抱えていた。
「ルイフォン……?」
「……ああ、いや……。親父の奴、嵌められたな。と、なると、エルファンとリュイセンが出掛けている隙だってのも、計算のうち……」
ぶつぶつ言いながら、ルイフォンは頭を掻きむしっていた。
「あの……。ホンシュアは斑目一族の手先だった、ということでしょうか?」
緊張の面持ちでメイシアは尋ねる。
彼女とて、ホンシュアが善意で物を言っているとは思っていなかった。だが単に、対岸の火事を楽しんでいるだけの輩に見えたのである。
「確証はないが――十中八九、間違いない。お前は斑目によって、意図的に鷹刀に送り込まれたんだ」
ルイフォンが盛大な溜め息と共に、結論を吐き出した。彼は隣りに座るメイシアに、なんとも言えない顔を見せる。
「ひょっとしたら、藤咲家は、鷹刀と斑目の抗争に巻き込まれただけかもしれない。……すまない」
「いいえ。この状況に陥ったのは藤咲家の落ち度です」
頭を下げるルイフォンに、彼女は首を横に振った。彼女の白磁の肌は透き通るようで、黒絹の髪は濡れたように艶やか。まだ少女の面影を残しつつも、花開く直前の危うい美しさを秘めた彼女は、とても生身の人間には思えなかった。
彼女は、穢れのない綺麗な――『人形』だった。
ルイフォンは、ふと窓の外に目をやった。
外灯が青白く照らす庭の中で、桜の花びらが、ひらひらと舞っている。今日は風が強いらしい。花の盛りも、あと数日といったところだろう。
「――だが、どうして斑目は、厳月家を裏切ってまでメイシアを送り込んできたんだ……?」
そう呟くルイフォンに、メイシアは答える言葉を持たなかった。
ふたりが黙ってしまったところで、香ばしい肉の香りが漂ってきた。話の区切りがつくのを待っていたのであろう。料理長自らが湯気の立つ皿を持って現れた。給仕はもう部屋に下がっているらしい。
「おお、美味そうだな」
揚げ焼きにした豚肉の塊に、同じく軽く揚げてある色鮮やかな野菜が添えられ、全体に甘酢あんが絡めてある。料理長はその皿をテーブルに載せると、続けてご飯とグラスを置いた。
色の濃い、長期間熟成させた酒と思しき瓶を料理長が取り出す。それをグラスに注ごうとするのをルイフォンが遮った。彼が料理長に耳打ちすると、料理長は軽く会釈をして厨房に戻っていった。
メイシアが疑問に思っていると料理長が再び現れた。今度は綺麗な色の瓶とワイングラスをふたつ持っている。
「酒のほうが、料理には合うんですけどね」
そう言いながら、料理長はふたつのグラスにワインを注ぐ。
「すまないな」
「仕方ないですね」
申し訳なさそうなルイフォンに、料理長は笑いながら応じた。
「当たり年のワインです。口当たりがいいですから、そちらのお嬢さんも、きっとお気に召しますよ」
料理長は「ごゆっくり」と頭を下げると、腹を揺らしながら彼の持ち場へと帰っていった。
メイシアは自分の前に置かれたグラスとルイフォンを交互に見た。
「まぁ、飲め」
初めに料理長が持ってきた酒は相当きついものに見えた。察するにルイフォンはかなりの酒豪なのであろう。
「……ルイフォン、未成年ですよね?」
「お前、俺の酒が飲めないのか?」
ルイフォンの目が、すっと細まる。メイシアは慌てて首を振った。
「いえ、食前酒くらいならいただきます」
彼女は、そっとグラスを手に取った。硝子の繊細な感触が指を伝わってくる。
ルイフォンの視線を気にしつつ、メイシアは恐る恐る口をつけた。唇に柔らかな液体を感じ、思い切ってそれを含む。癖のない、まろやかな甘さが舌を転がった。
「え? 美味しい」
メイシアは素直にそう思った。一気に飲み干してしまう。
「だろ?」
自分も飲みながら、ルイフォンが得意げに笑う。「では、もう一杯」と彼が手ずから、ふたつのグラスに注いだ。
ルイフォンが食事をしている横でメイシアは二杯目を口に含む。彼が上機嫌なのは料理が美味しいからだけではなさそうだった。
ふと、ルイフォンが尋ねた。
「お前、どうして、そこまで必死になれるんだ?」
「え? 何がですか?」
「異母弟のことだよ。母親が平民なんだろ? 貴族なら毛嫌いしていたとしても不思議じゃない」
「私は、おかしいですか?」
メイシアはワイングラスに映った自分の顔を見る。半分しか血の繋がらない異母弟とは、ちっとも似ていなかった。
「私の母は政略結婚で、父とは上手くいかず、私が小さい頃に実家に戻りました。私には両親と一緒の思い出はひとつもありません」
ルイフォンは皿に箸を運びながら、黙って頷いた。
「傷ついた私と父を支えてくれたのが継母です。私を実の娘のように可愛がってくれて、父と三人の幸せな家族でした。そこに、ハオリュウが増えたんです。小さくて可愛くて――私が守ってあげなくちゃいけないと思いました」
生まれたばかりの異母弟を見たときの感動を、メイシアは今も鮮明に覚えている。この小さな命には寂しい思いをさせたくないと思ったのだ。
「でも、私とハオリュウの関係は、必ずしも優しいものではなかったんです」
「……そうだな」
貴族の跡継ぎは男子であるのが原則だが、平民出身の継母の子であるハオリュウより、身分の高い貴族の母の子であるメイシアに然るべき婿を迎えて跡継ぎとすべきだ、と親族が声を上げている。それは〈猫〉として調査したルイフォンも知っていた。
「私の存在がハオリュウをおびやかすなんて……」
メイシアはこみ上げてくるものをぐっと抑えた。誤魔化すように、グラスに残っていたワインをあおる。
「……家族の中で、異質なのは私じゃないですか。ハオリュウは、ちゃんと血の繋がった父と継母の子で――。私はこの家族に加えてもらった『異邦人』なんです」
「おい……? メイシア?」
空のグラスに新たなワインを注いでいるメイシアに、ルイフォンが不審の声を上げる。嫌な予感がした彼は、空になっている自分のグラスとメイシアのグラスをすり替えた。
「私が鷹刀一族のところに行けば解決すると聞いて、嬉しかったんですよ。ふたりが助かる上に、私はハオリュウをおびやかす存在でなくなるんだ、って……」
メイシアの黒曜石の瞳に、淡い電灯の光が揺らめく。
ああ、そうか――と、彼女は思った。
彼女はずっと、家族の役に立ちたかったのだ。家族のために働けるなら、家族の一員として胸を張ってよいのだから、と――。
メイシアはワイングラスの脚に細い指を絡め、縁に唇を寄せた。それは運命の神への感謝の口づけのようであった。
「お前、顔が真っ赤だぞ!」
とろりした恍惚の微笑みを浮かべるメイシアに、ルイフォンが血相を変える。
「ルイフォン、ありがとうございます」
極上の笑みを浮かべて彼女は、ふっと力を失った。
彼は、とっさに空のグラスを取り上げ、彼女の上半身を抱きかかえた。
「おい……嘘だろ?」
ルイフォンは呆然とする。
そのとき、彼は食堂の入り口に人の気配を感じた。ぎくりとして、首を回すとそこにいたのは想像通りの人物だった。
罵声を浴びるルイフォンの腕の中で、メイシアは久し振りに――本当に久し振りに、心地のよい眠りの世界に落ちていった。
~ 第一章 了 ~
幕間 孤高の〈猫〉

今から思えば、俺の母という人は相当な変り者だったと思う。
いわゆる母親らしいことをしてくれた記憶は、ひとつもない。けれど、それは『してくれなかった』のではなく、『できなかった』だけなのだろう。
彼女は親を知らなかったし、それまで自分が生き延びるだけで精一杯だったのだから。
猫のように気まぐれで、不敵に笑う自信家。そんな彼女が、自分の持つ技術のすべてを俺に注ぎ込んでくれた。そこは、やっぱり親らしかったと言えるのかもしれない。
勿論、懇切丁寧に教えてくれはしなかった。罵詈雑言の連続で、「スクリプト・キディが生意気言ってるんじゃないわよ」とよく鼻で笑われた。
『スクリプト・キディ』――他人の作ったクラッカーツールで攻撃する、程度の低いクラッカー。要するに未熟者ってことだ。当時の俺は、本当に『子供』だったのだけど、彼女は容赦なく毒舌を振るった。
彼女は常に、金色の鈴の付いた革のチョーカーを身に着けていた。
「それ、首輪じゃん」と俺が言うと、「あたしは鷹刀の飼い猫なのよ」と自慢げに笑っていた。
彼女が贈り主をずっと想い続けていたことを、俺はあとになってから知った。
数奇な運命をたどってきた彼女の左足は義足で、ひょこひょことしか歩けなかったけれど、決して恥じることなく、いつだって前を向いて歩いているような人だった。
孤高の〈猫〉。
俺は彼女を敬愛していた。
ある夜、俺は、けたたましい警報音に叩き起こされた。
ベッドを飛び出し、階下に行くと、錆びた鉄のような匂いがあたりに充満していた。
警護の男たちが殺されていた。
胸騒ぎがして、地下に降りると、母が顔を隠した侵入者に囲まれていた。
何かを言い争っているけれど、聞き取れない。
侵入者の一人が刀を振りあげた。
足の悪い母が、逃げることなどできるわけがない。
ぎらりと、白刃が煌めく。
子供のように細く華奢な、母の首筋へと影が落ちる。
母は――挑発するような目で、嗤った。
同時に、逃げなさい、という彼女の強い思念が伝わってきた。
革のチョーカーが斬れ、金の鈴が飛ぶ。
電灯の光を金色に反射しながら、放物線を描く。
侵入者が、母だったものを運び去る。
主を失い、残された金色の鈴が、寂しげに転がっていた――。
di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~ 第一部 第一章 桜花の降る日に
『di;vine+sin;fonia ~デヴァイン・シンフォニア~』
第一部 落花流水 第二章 華やぎの街にて https://slib.net/110743
――――に、続きます。


