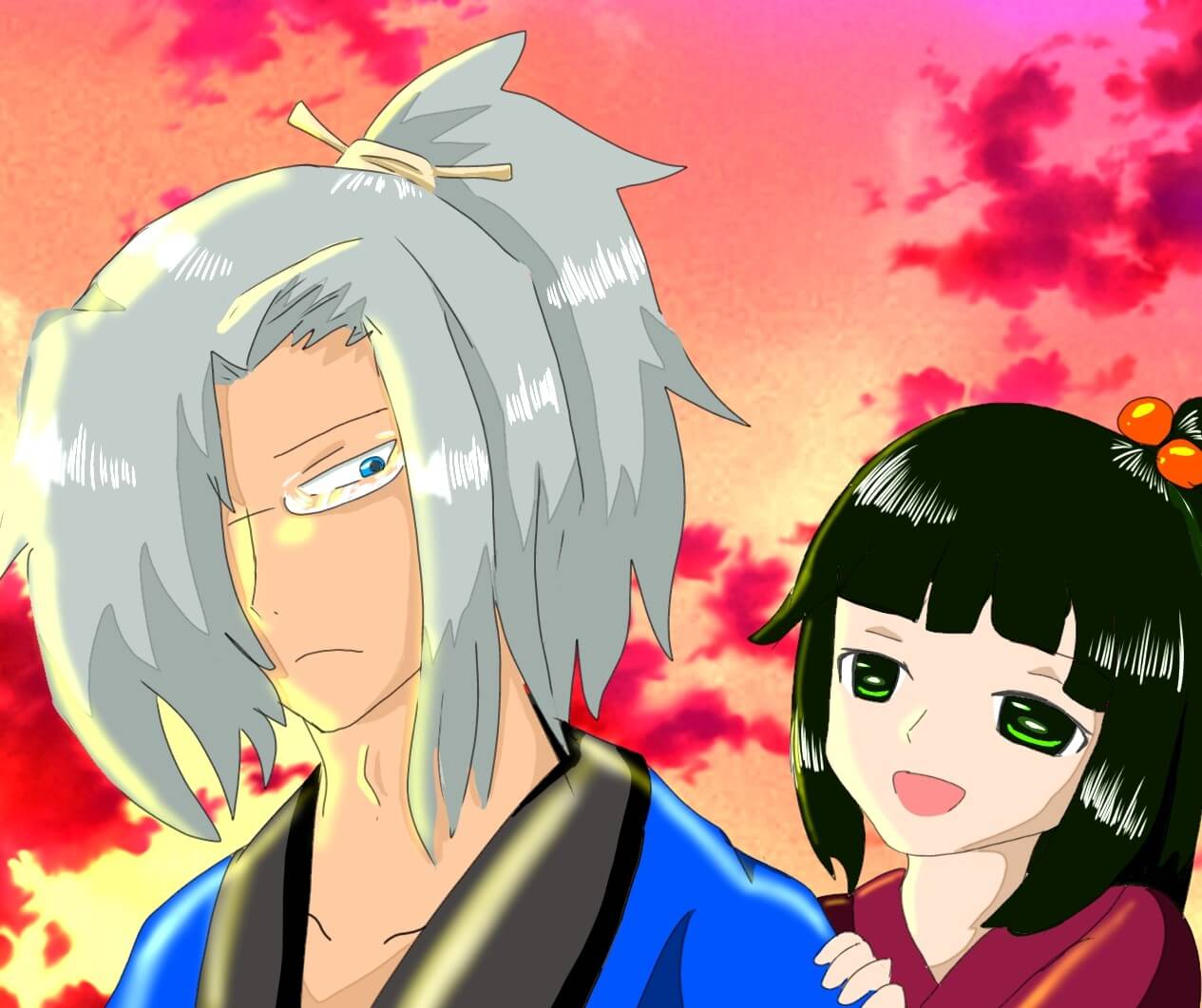
旧作(2021完)TOKIの神秘録四部「折られた可憐な花」
折られた可憐な花
これはおかしな一族の狂った物語。
更夜が十四の時、十の妹、憐夜の教育を父親から言い渡された。
父の話によると憐夜は出来損ないとの事だった。ある程度の所までは成長させろと父に命令をされた。おそらく、憐夜はある程度使い物になるようになったら、千夜達の裏方をやるようになるだろうと予想していた。
「憐夜、目隠しをしたまま、まっすぐに歩く練習だ。その縄の上を素早く渡りきれ。」
更夜は地面に置いた縄を指差し、冷たい瞳で憐夜を見据えた。憐夜は銀の髪を揺らしながら弱々しい瞳で更夜を仰いでいた。
「返事をしなさい。憐夜。」
更夜は憐夜の頬を平手で勢いよくはたいた。憐夜はその場に倒れ、震えながら更夜を再び見つめた。
「……は、はい。更夜お兄様。」
「立て。さっさとしろ。時間の無駄だ。」
更夜は無理やり憐夜を立たせると目隠しをした。
「更夜お兄様……真っ暗で何も見えません……。お兄様!」
憐夜は怯え、ただ更夜の名を呼んでいた。
「わかりやすく縄を引いてやった。足の指の感触でまっすぐ縄を歩けばいい。」
憐夜は更夜の言いつけどおり足の指で縄を探し、歩き始めた。しかし、最初からうまくはいかない。憐夜は縄から離れて歩き始めた。
更夜は竹刀で外れた方の足を叩いた。
「うぅっ……。」
憐夜は痛みに顔をしかめ、足を元の縄に戻した。
「右足が若干ずれたな。慣れてくれば俺の気配も感じるようになる。これができるようになったら縄なしで真っすぐ歩く練習、その次に俺の攻撃を避けながら前へ進む練習だ。こうすればお前はわずかな光もない闇夜でも、すんなりと動けるようになるだろう。」
更夜は練習内容を話しながら、今度は憐夜の左足を竹刀で叩く。
「あっ……。」
憐夜は小さく呻くと再び縄に足を戻した。憐夜が地面に置いた縄を渡りきった時には憐夜の足は痣だらけになっていた。
「うう……ひっ……うう……。」
憐夜は嗚咽を漏らしながら泣いていた。
「憐夜、もう一度だ。先程の場所まで戻れ。竹刀で打たれたくなければできるようになりなさい。いいな。」
「……はい。」
更夜の言葉に憐夜はまた、縄を歩き始めた。
「更夜、そんなんだといつまで経ってもできるようにならねぇよ。」
「お兄様……。」
更夜の前に突然逢夜が現れた。
「いいか、更夜、憐夜には時間がねぇ。俺達がこの年齢でできていたことが、こいつは何一つできない。危機感を持ちやがれ。」
「申し訳ございません……。」
更夜が声を発した刹那、逢夜はよくしなる木の枝で憐夜の足を思い切り打ち始めた。
「あぐっ!」
先程の痛みとは比べ物にならない痛みが憐夜を襲い、憐夜は泣き叫んだ。憐夜の足首からは血が滲んでいた。
「泣くな。泣いてる暇があんだったらまっすぐ進め。」
逢夜は憐夜の背中を思い切り蹴り飛ばした。逢夜は底冷えするような声で憐夜を叱りながら前へ進ませた。
「ひっ……。」
「もう一度だ。さっさと進め。痛い思いをしたくなけりゃあさっさと覚えるんだな。」
泣いている憐夜を逢夜は再び蹴り飛ばし、もう一度前へ進ませた。
確かに、逢夜のやり方で憐夜はかなり上達した。しかし、更夜にはここまでする勇気がなかった。
憐夜の足首は逢夜により血にまみれていた。
憐夜が一通り縄を渡りきれるようになってから、逢夜は更夜につぶやいた。
「これくらいやらねぇとこいつは伸びない。お前が無理そうならば俺が代わってやろうか? これは憐夜の死活問題なんだ。憐夜が使えるか使えないかで、憐夜の扱いが変わってしまう。俺は憐夜に生き延びてほしいんだ。特に兄弟は誰も死んでほしくねぇ……。」
「……わかりました。お気持ちはありがたいのですが、もう少し、私が見て行こうと思います。憐夜は私が守ります……。」
更夜の言葉に逢夜は顔をしかめた。
「……忍は常に独りでなんとかしなければならねぇ……。守られる方は足手まといなんだよ。お前はまだ……重要な任についた事がねぇから、そんな軽い事が言えるんだ。俺はそれで何度も死んだ奴を見てきた。忍の世界はそんなに甘くねぇ。独りでも死なねぇようにしなければなんねぇんだ。……まあいい。今みたいな感じでやりゃあ、憐夜は伸びるはずだ。俺はしばらくここに滞在する予定だから、何かあったら言え。わかったな。」
「はい。ありがとうございます。」
逢夜は更夜を一瞥すると、音もなくその場から去って行った。
逢夜が去ってから更夜は憐夜に目を向けた。憐夜は泣きながら自身の足の傷の止血作業をしていた。
「忍は何でも独りでしなければならないか……。……憐夜。」
更夜はそっと憐夜の側に寄った。
「は、はい……。」
「止血はそこを押さえるのではない。ここだ。」
膝辺りを布で縛ろうとしていた憐夜に更夜は足首に布を押し当てる事を教えた。
「あ、ありがとうございます。」
憐夜は涙をぬぐうと更夜に丁寧に頭を下げた。
「その足では続けて同じ訓練をする事は厳しいな。飛び道具の訓練でもするか。」
更夜は消毒の方法とさらしの巻き方を教え、憐夜を再び立たせた。憐夜は小さく呻きながら立ち上がり、更夜を見上げた。
「この手裏剣をあの木に向かって投げろ。身長は俺と同じくらいを想像し、確実に殺せる部位、もしくは動けなくなる部位に刺さるように飛ばせ。」
「……はい。」
憐夜は更夜から鋭利な手裏剣を三つ受け取ると、木に向かい素早く投げた。
手裏剣は額、心臓、そして足あたりの場所に刺さった。
「これは得意だと聞いていたが、ややずれているな。」
更夜が手裏剣を見ながら指摘すると、憐夜が控えめにつぶやいた。
「当たったら死んでしまいますから……。かわいそうです……。」
「……憐夜、俺はなんと言った?」
憐夜の悲しげな顔を見据えながら、更夜は冷酷に問いかけた。
「確実に殺せる部位、もしくは動けなくなる部位に刺さるように飛ばせと……。」
更夜は憐夜が最後まで言い終わる前におもいきり頬を張った。憐夜は倒れ込むと頬を押さえ、鼻血を垂らしながら更夜を見上げた。
「そうだ。俺はそう言ったはずだ。お前は俺を馬鹿にしているのか。」
威圧を込めた声で更夜は憐夜に冷たく言い放った。
「ごめんなさい……。でも違うんです……。当たったら死んでしまうんです……。少しずらせば、もしかしたら生きられるかもしれないんです。」
「なるほど。つまりは俺の言う事が聞けないという事だな……。」
更夜は竹刀で再び泣きはじめた憐夜の肩を強く打った。
「あうっ!」
憐夜は低く呻き、うなだれた。
「次に俺に逆らったら生身の身体に鞭痕が残るぞ。」
更夜の脅しに憐夜は両手で顔を覆い、嗚咽を漏らしながら泣いた。
「ごめんなさい。お兄様。もう叩かないでください。」
「ならば逆らわずに修行に励め。お前が生きる場所はここしかない……。」
更夜はうずくまる憐夜に諭すように言葉を発した。
「うう……うう……。」
ただ、静かに泣いている憐夜を、更夜は複雑な表情でただ見つめていた。
……おかしな家族の狂った規律は、幼い憐夜を傷つけていく。
あれからしばらく経っても憐夜は成長しなかった。飛び道具も必ず少しずらして投げ、体術はまったくやろうとしなかった。
更夜は何度か酷い体罰を憐夜に与えた。しかし、憐夜は相変わらずだった。
「憐夜、何をしている。まだ四つ身の訓練は終わっていない。返事をしなさい。憐夜。」
憐夜は高い木のかなり上の方の枝に立ち、呆然と景色を眺めていた。夜通しで訓練をし、山は夜明けを迎えていた。
更夜はまた憐夜に体罰を加えなければならないのかとうんざりしながら、憐夜がいる木の枝まで飛んで行った。更夜は憐夜の隣に軽やかに着地した。
「……お兄様……。朝日ってなんでこんなにきれいなのでしょう? 私はこんなにきれいな世界をどうして歩くことができないのでしょう……。」
朝日に照らされた憐夜はせつなげで、光の入った瞳はとても美しかった。
「俺達は影だからだ。日の元を歩く人間ではない。」
更夜は憐夜の横顔を見ながら目を伏せ、つぶやいた。
「私は……運命を呪います……。私は……自分の生を呪います……。お兄様は、本当は優しいお方……私は知っています……。ですが、それを出してはいけないのですね。」
憐夜は更夜にせつなげに微笑むと瞳の色を失くし、続けた。
「ごめんなさい。あまりにきれいな風景だったものですから、見惚れてしまっていました。どういう風に描いたら一番きれいか考えてしまいました。……もういいです。」
憐夜は素早く木から降りる。木から降りる瞬間、憐夜は四人になった。四つ身分身をしたようだ。
「……憐夜……四つ身ができるのか? あの子は……ただやる気がないだけなのか。本当は才能が一番あるのかもしれない。」
更夜も木から降り、地面に足をつけた。憐夜は何かを悟ったような目で着物を脱ぎ、木の幹に手をついた。背中を更夜に向ける。
「……罰はしっかりと受けます。お兄様の手を痛めてしまいますね。申し訳ありません。でももう大丈夫です。もう泣きませんし、叫びません。」
憐夜は冷たく暗い瞳で更夜を見ていた。更夜は憐夜の心変わりがはっきりとわかった。
それは諦めの心と自身の運命を呪う心。これが望月の中でも異端である凍夜(とうや)望月家の一族が通る道。
このように徐々に感情を失っていき、何に対しても何も感じなくなる。操り人形のように上の命令には逆らわなくなってくるのだ。
更夜もそうだったからか、憐夜の気持ちもなんとなくわかっていた。
「……ふむ。良い心がけだな。」
更夜は静かにつぶやくと、憐夜のしなやかな背に木の枝を振り上げた。
……おかしな家族の狂った規律は、憐夜から大切なものを非情にも奪っていく。
二話
憐夜に鞭打ちをした後、更夜は血のついた木の枝を見つめながら奥歯を噛みしめた。
……俺はあの子を変えてしまった……。あの子はとても優しい子だったはずだ。あんなに冷たい目ができる子ではなかった。
……これで……良かったのか?
更夜は血で濡れている木の枝を捨てると立ち上がり、傷を癒しているはずの憐夜を探した。憐夜はすぐに見つかった。木々が少し開けた場所で、傷口にさらしを巻くわけでもなく、憐夜は呆然と座っていた。
「……憐夜……。」
更夜は憐夜にそっと声をかけた。
「お兄様。きれいなお花が沢山咲いています。紙と筆があれば描いたのに。」
憐夜は何事もなかったかのように、目の前に咲く白い花を笑顔で見つめていた。
「そんな事を言っている場合ではない。止血しなければ……。」
「おかしなお兄様ですね。お兄様が私を叩いたのでしょう。こんなに、血が流れ出るくらいに何度も何度も。……もう痛くもないので問題はありません。」
憐夜は感情のない声で更夜に答えた。
憐夜は他の兄弟とは少し違う方面へ心が動いたようだった。
この世界を恨んでいる……自分の事なんて、もうどうでもいい。ただ、この世界を恨む。憐夜の顔はそう言っていた。
「憐夜……。」
「お兄様、それよりもお花がきれいです。こんなきれいなお花を絵にしてみたい……。お兄様はきれいなお花には興味はありませんか? あ、筆がなくても私の血でお花を描けばいいんでしたね。ちょうど出てますし。」
憐夜の問いに更夜がどう答えるか悩んでいると、ふと近くで女の声がした。
「本当にきれいな花畑だ。こんなところにこんなものがあるとはな。」
「お姉様。」
更夜と憐夜の隣に音もなく立っていたのは千夜だった。千夜は一番年上のはずだが、身長は憐夜よりも小さかった。
「憐夜、しばらく見ぬ間に大きくなった。……だが、お前の心は間違っている。」
千夜は憐夜の横に座ると、そっと肩を抱いた。
「お姉様……?」
「感情を捨て、痛みを感じなくなる事は忍としては良い。だが、自分の事をどうでも良いと思うのは間違いだ。私達は常に生きようとしている。ただ、まわりに迷惑がかからんように、自分で自分を守れるように、我々は過酷な事をしているのだ。私達は家族だが仕事に出れば守ってやれん。だが、お前達が傷つくのは辛い。難しいが、それをまわりに知られてはいかんのだ。なぜならば敵の忍に逆手にとられるからだ。……ん? 憐夜、怪我をしておるな?」
千夜は優しい瞳で憐夜に声をかけた。
「はい。木の枝で叩かれました。私がいう事を聞かなかったからです。」
憐夜は平然と千夜に言い放った。
「そうか。更夜はこんなもので済ませてくれたのか。良かったな。憐夜。傷は浅いが、しっかりと処置をしなさい。これも修行だ。」
千夜は感情なくつぶやくと憐夜の頭をそっと撫で、立ち上がった。
「……はい。……お姉様、もう行かれるのですか?」
憐夜の問いかけに千夜は小さく頷くと、更夜に近づいた。
「お前の判断は間違っていない。憐夜の成長はこれからだ。あと三年、しっかり憐夜を作り上げるのだ。いいな。更夜。」
「……はい。」
千夜の言葉に更夜は素直に頷いた。千夜はそれを見、悠然と歩き出した。
「……やはり妹に手を上げるのは辛いか? 更夜。」
千夜はふと思いついたように歩みを止め、更夜を振り返った。
「……いえ。問題ありません。これから徐々にしつけを厳しくしていきます。お姉様に対するご無礼、申し訳ありません。」
更夜は憐夜のしつけが甘い事を指摘されたのだと思い謝罪したが、千夜はゆっくり首を振った。
「憐夜ではない。お前自身だ。だいぶん疲れた顔をしていた故な。大丈夫ならばそれでよい。私は齢二十二だ。故に仕事が忙しい。後は軽い任についている逢夜に頼むと良い。」
千夜は一言つぶやくと足音もなく去って行った。
「ありがとうございます。お姉様。」
更夜は千夜の背中にそっと頭を下げた。
ふと顔を上げると憐夜がいつの間にかいなかった。更夜は頭を抱え、憐夜の気配をさぐり、歩き出した。憐夜は花畑の下に流れているきれいな沢で、傷ついた背中に水を流していた。そして一通り血を流すと、自分でさらしを巻き始めた。
「……憐夜、水をよく拭き取りなさい。そのままさらしを巻いてはいけない。」
横で見ていた更夜は憐夜に注意をした。憐夜は突然現れた更夜に驚いていたが、素直に頷くと自身の着物を少し裂き、腕を回して背中を丁寧に拭き、さらしを巻いた。
「さて。では食事にしよう。憐夜、食べられるものを持って来なさい。食べられる野草については教えたな?」
更夜は鋭く憐夜を睨みつけると憐夜の頬を思い切りはたいた。
「……返事をしろ。」
「……はい。お兄様。行ってまいります。」
憐夜は頬を押さえながら足早に去って行った。
「……あの子の足だとしばしかかるか。憐夜も腹を空かせているだろうから、俺が魚を取っておいてやろう。」
更夜は独りつぶやくと、沢を泳ぐ大きめの魚をクナイで四匹仕留めた。
更夜は沢の側に腰かけ、精神統一をして憐夜を待った。しかし、憐夜は一向に戻ってこなかった。
「……遅いな……。あの子は何をしている……。」
更夜は心配になり少し気配を探ったが、気配を感じなかった。
「……探すか……。」
更夜がそう思い始めた時、二つの気配を感じた。刹那、更夜は二つの人影を発見した。
「……お兄様と……憐夜か?」
人影は逢夜と憐夜のようだった。逢夜は素早くやや乱暴に更夜の前に着地すると、憐夜を放り投げた。憐夜は全身傷だらけで身体は水で濡れていた。
「お、お兄様……これは……。」
更夜は逢夜と気を失っている憐夜を交互に見つめながら戸惑っていた。
「更夜、憐夜が山から出ようとしていた。すげぇ抵抗されたんで、二度とできねぇようにお仕置きしてやった。目的を吐かせようと頭を川に突っこんで拷問したが、途中で気を失っちまったから連れてきた。心配すんな。手加減はしたし、水も吐かせた。しかし、こうも聞き分けがねぇとはな。」
逢夜の非道さに更夜は何も言えなかった。更夜もこうやって何度も逢夜に暴行された。
逢夜の折檻はいつも残酷だったが、それをやるには必ず理由があった。
規律に厳しい伊賀忍者とは違い、甲賀忍者は忍をやめても殺される事はないが更夜の家系、その周辺の集団だけは厳格だった。これは甲賀忍者の質を高めるための手段だったようだ。里から出る事は抜け忍とみなされ、殺害される。憐夜のような弱い忍ならばすぐに見つかり処刑されるだろう。逢夜はそれに一番気を使っていた。
「……甲賀でも俺達の家系じゃなけりゃあ逃がしてやるんだが、こいつはちょっとまずかったな。絶対的な恐怖を与えねぇとまたやりそうだからな。泣き叫ばれようが謝罪されようが関係なく殴った。……妹とはいえ、齢十の小娘……俺ぁ、もう二度とやりたくねぇ。」
逢夜は泣き叫んでいた憐夜を思い出し、顔を曇らせた。
「もう泣かないと言っておりましたが、やはり十の娘。お兄様は恐ろしい存在のようです。」
「そんな事はどうでもいい。更夜、これはお前にも責任がある。よってお前にも仕置きがいるようだ。俺達の家系は連帯責任だ。わかるな?」
「はい……申し訳ありません。お兄様。」
逢夜の言葉に更夜は素直に頷き、着物を静かに脱いだ。
……おかしな家族の狂った規律は、さらに憐夜を追い詰めていく。
三話
逢夜はしばらく更夜を痛めつけると、何も言わずに消えて行った。
更夜は逢夜が去って行くのを見届けると、憐夜の怪我の具合を見た。憐夜は傷だらけではあったが、重たい傷ではなかった。逢夜が手加減をしたのは本当の事のようだ。
むしろ更夜の傷の方が重たいくらいだった。更夜は自身の傷の処置をする前に憐夜の傷の処置をしてやった。気を失っている憐夜を柔らかい土の上に寝かせると自身の傷の手当に入った。更夜が手当てをして憐夜の元に戻ると、憐夜は目を覚ましていた。
「憐夜、兄がそんなもので許してくれたのだ。感謝しなさい。そしてもう二度とやらないと誓え。」
更夜が憐夜を叱りつけると、憐夜は寂しそうに更夜を仰いだ。
「お兄様、お兄様もお怪我を……。」
「……お前が規律を破ると俺にも罪が飛ぶ。」
「……そんなのおかしいです。普通の兄弟はちょっと喧嘩したりとか……助け合ったりとかするんです。こんなの酷いです……。」
憐夜は更夜に小さくつぶやいた。
「……憐夜、お前、里から勝手に下りたな……。もう少しで抜け忍になる所だったぞ。」
更夜の言葉に憐夜はビクッと肩を震わせた。この周辺のことしか知らないはずの憐夜が、普通の兄弟の事を知っている……これは憐夜が更夜の目を盗み、勝手に山を下りていた事を意味する。
「……ごめんなさい。私は兄が妹に優しく接している所を見ました。兄と妹が小さい事で喧嘩をしている所も見ました。私達とは違っていました。……なんだか悔しくて殺してやりたくなりました。お兄様がいつも教えて下さるやり方で殺してやろうと思ってしまいました。」
憐夜は憎しみのこもった目で拳を握りしめた。自分の環境では絶対に手に入らないものを羨む子供の目だった。地面に指で更夜を描き、さっと手でかき消した。
「憐夜、仕事以外で人を殺すな。目立つ行動もするな。俺達から逃げたら殺される、そう思え。俺達の命令なしでここから出たら俺も、兄も、姉もお前を容赦なく殺すぞ。俺達は規律を守れば何もされない。だから兄も姉もこの規律を全力で守る。守る事で俺達も守られているのだ。」
更夜は、憐夜に諭すようにささやいた。しかし、憐夜は更夜を睨み返してきた。
「こんなに痛い事して死んでしまいそうな暴力をずっと振るっておいて守る? それをおかしいとは思わないんですか! お兄様は大馬鹿ものです!」
憐夜は更夜と兄弟喧嘩をしたかったようだった。半分演技のようであったが、憐夜は更夜に怒鳴った。
「憐夜、いい加減にしろ。」
更夜は一言それだけ言った。殺気と威圧を込め、憐夜を睨みつける。
「ううう……。」
憐夜の顔に恐怖の色が浮かんだ。憐夜がふっかけた兄弟喧嘩の種はすぐになくなった。
憐夜は更夜も逢夜も千夜も、父である凍夜(とうや)も皆怖かった。上に逆らえば酷い罰がくる。そうやって恐怖心を植え付けられた憐夜は、勇気を振り絞って口答えするだけで精一杯だった。
……私は動物? 道具? それとも人間?
お兄様……教えて……。
「メシにするぞ。……憐夜。」
更夜が冷たく言い放ち、憐夜に背を向けた時、憐夜が声を上げた。
「あの……っ。演技でもいいです……。私に優しくしてください……。お願いします。お兄様……。私に優しく接して……。」
憐夜は切なげに更夜を見ると、更夜の着物の袖を掴んだ。
「……いい加減にしろ。……俺に触るな。」
更夜は憐夜の頬を再びきつくひっぱたくと歩き出した。
「……そう……わかりました。私は道具……。道具なのね……。」
憐夜のむせび泣く声が更夜の背で聞こえた。更夜にはどうする事もできなかった。ただ、いままで自分が信じてきたものが、すべて壊れていくような感じがした。
……おかしな家族の狂った規律は、抗う憐夜を壊し続ける。
四話
しばらく時間が経った。やはり憐夜は修行をまじめにはやらなかった。更夜は若干の焦りを見せていた。父から言われたある程度まで、憐夜はまったく到達できていない。むしろ、常人よりも少しだけ動きの速い感じだった。このままでは憐夜の道は暗い。憐夜の身体には傷が残るばかりで、このままではいつ処断されるかわからない状態だった。
「憐夜、いい加減にしろ。これは体術の練習だ。なぜ俺の言う事を聞かない。」
更夜は憐夜の腹に軽い蹴りを入れた。憐夜は腹を押さえうずくまりゴホゴホと咳を漏らしていた。
「憐夜、これは酷いな。」
ふと横に千夜がいた。
「お姉様……申し訳ありません。」
更夜は憐夜の状態が酷い事について深く頭を下げた。千夜は刀の柄を更夜の腹に勢いよく打ちつける。更夜は呻きその場に膝をついた。
「一時はよいと思っておったが、しばらく経っても状況が変わっておらんではないか。」
千夜は更夜を叱りつけた。そのまま鞘に納められている刀で更夜の顔を殴る。
「ごほっ……。も、申し訳ありませぬ……。お姉様。」
更夜は口から血を吐き、苦しそうに呻いた。千夜は表情なく更夜に刀を振るう。更夜の顔を殴り、腹を殴り、背中を打った。鞘に入っているとはいえ、重たい刀、更夜は耐えがたい苦痛を受ける事となった。
「お姉様! やめてください。」
憐夜が更夜の前に慌てて入り込んだ。
「憐夜、何故私達の言葉を聞かない。」
あの時の優しい雰囲気だった千夜の面影はなく、厳しい顔つきで憐夜を睨みつけていた。
「こんなの兄弟の形としておかしいんです! 違うんです!」
「違うからなんだ? お前はそんな事を理由に我らに逆らうのか。お前は運命を恨み、我らに逆らっているようだが、意味はない事を知れ。」
千夜は刀の鞘部分で憐夜の顔を何度も殴る。憐夜の顔が腫れていても、身体から血を流していても構わずに暴力を続けた。
憐夜は更夜が一番優しかった事に気がついた。
憐夜は泣き叫び、千夜に許しを乞うた。
「ごめんなさい……。許してください。もう……逆らいません。逆らいませんから!」
千夜は憐夜の謝罪を聞き、手を引いた。憐夜の身体は血にまみれ、震えていた。
「次、このような事があればその時は私が許さぬ。お前を監視しておるのが更夜だけだと思うな。」
千夜は憐夜の髪を乱暴に掴むと目線を合わさせて、底冷えするような声でささやいた。
「は、はい……お姉様……ごめんなさい。」
憐夜はガクガクと震えながら千夜に素直にあやまった。
「次に逆らったら……そうだな、死にはしない程度になます斬りにして、そこの木に吊るすとしよう。一度、逢夜にはやった事があるがな。逢夜も私に反抗的だった故な。かなり痛いぞ。拷問だ。どうだ? やられたいか? ……聞いておるか? 憐夜。」
「うっ……うう。」
千夜の感情の入っていない声に、憐夜は言いようのない恐怖心を抱いた。
「返事をしろ。」
千夜は憐夜の腹を刀の柄部分で容赦なく突いた。
「うぐっ……がふっ……。」
憐夜は胃液を口から吐くと苦しそうに呻いた。
「返事をしろ……憐夜。」
「は、はい……。申し訳ありません。お姉様。」
千夜は憐夜を冷徹な瞳で一瞥すると、更夜に向き直った。
「更夜、ぬるいやり方では憐夜は死ぬ。真面目にやらないようであれば逆らえなくさせろ。憐夜は大事な妹だ。お父様から全力で守るのだ。」
「……はい……。」
更夜が静かに返事をした時、千夜は悲しそうな瞳で更夜を仰いだ。
「……あと二年で憐夜がそこそこ成長しなければ、お父様は憐夜を斬り捨てる算段をたてている。憐夜を斬り捨てたら次は、腹違いの弟である狼夜(ろうや)をお父様が育てる事になるそうだ。更夜……私は……どうすればよい? 本当に……こんなやり方で良いのか……。」
千夜は更夜に聞きとれるようにだけ話した。千夜も焦っているようだった。千夜の瞳は戸惑いで揺れていた。
「お姉様……私が……なんとかいたします。」
「……時間がない……お前では憐夜を育てきれない。逢夜に渡せ。逢夜はお前と違い、しつけるのがうまい。少々荒いがお前よりはマシだろう。その判断はお前がしろ。」
千夜はそう言うと去って行った。
「はい……。」
更夜は苦しそうにつぶやくと、うずくまって呻いている憐夜に目を向けた。
……おかしな家族の狂った規律は憐夜だけでなく、更夜も壊しはじめる。
五話
更夜は憐夜の修行に力を入れ、気がつくと夜になっていた。真っ暗だが、憐夜も更夜も夜目の訓練をしているため夜でも関係なかった。
「メシにするぞ。いつものように食べられるものを持ってこい。」
「……はい。」
憐夜は珍しく素直に返事をした。更夜は憐夜の調子を見、何か様子がおかしい事に気がついた。
憐夜が足早に去って行くのを見、しばらく経ってから憐夜の尾行をする事にした。
更夜は木から木へと飛び移りながら、下で走っている憐夜を監視した。憐夜は更夜が指定した場所ではない所へと入って行った。
……そちらへ向かうと山を降りてしまうぞ……憐夜。
更夜は憐夜が何をしようとしているのかわかった。憐夜は更夜の目を盗み、逃げるつもりのようだ。
……そんなにここから逃げたいか……憐夜。
更夜はさらに憐夜の後を追った。
……ん? あの子はこの周辺をウロウロと何をしている?
憐夜は同じところをグルグルと回っていた。
「あれ? おかしいな。たしかこっちのはずだったんだけど……道が……わかんなくなってしまったわ。」
憐夜は不安げに独り声を漏らした。どうやら逃げ道を見つけていたようだが、夜だったため場所がわからなくなってしまったようだ。
……場所が……わからなくなってしまったのか。このまま右に行けば山を下りられるが……。
更夜はふと甘い考えが浮かんだ。
……このまま俺が憐夜を逃がしてやれば……今ならば誰の気配も感じないので、憐夜を逃がしてやれるかもしれない。逃げた後、探されるが、それをうまく操れば見当違いの場所を探させることができるかもしれない。そうすれば憐夜は遠くに逃げられる……。
更夜は右に行くように誘導してしまった。憐夜がいる木の近く目がけてクナイを放った。憐夜は飛んでくる風に気づき、咄嗟に更夜の方を向いた。
「見つかった? あっちからクナイが……。逃げなきゃ! 捕まったらまた……。」
憐夜はクナイが投げられた方向とは逆に逃げて行った。
……そうだ。そっちに走れ。
更夜は必死で走る憐夜を黙って見つめていた。憐夜を追い、わざと足音を立てたり、クナイを放ったりなどして的確に誘導してやった。憐夜が山を下り、もう少しで抜け忍とみなされる場所まで来た時、更夜は淡い幻想を抱いていた事に気がついた。
……ダメだ。俺は何をしている。俺の家系を甘く見てはいけない! あの子の能力では俺の家系には勝てない……。いますぐ捕まえて連れ戻さないと殺されてしまう……。
更夜は慌てて木から飛び降りると、憐夜を追って走り出した。しばらく走っていると、千夜に前を塞がれた。
「おっ……お姉様! 憐夜が……。」
更夜は必死の表情で千夜に声を上げた。
「ん? 憐夜? 憐夜がどうしたのだ? ああ、それより、近くに隠れられそうな洞窟を見つけたのだ。あそこはなかなか見つかりにくいぞ。確か、ここから北の方角にあったな。村にだいぶ近いぞ。ああ、そういえば南にも同じような洞窟があったが、あれは使えんな。私はあそこへはいかん。お前も……南のあそこは知っているか? 大きな岩がある所でな……。」
「お、お姉様? 今はそんな事を言っている場合では……。」
更夜がそうつぶやいた時、近くに憐夜の気配を感じた。憐夜は足音が近い事に気がつき、動くのをやめたらしい。近くで隠れているつもりのようだ。
「……ここから北の洞窟はお兄様たちが来る可能性がある……でも南の洞窟なら……。」
ふと憐夜の独り言が聞こえてきた。憐夜は更夜達に聞こえていないと思っているらしいが、更夜達にははっきりと聞き取れた。もう憐夜の居る場所も更夜にはわかっていた。
おそらく千夜にもそれがわかっているだろう。
更夜は千夜の意図がわかった。
……お姉様も憐夜を逃がしてやろうと思っているのか?
「さて、更夜、お前はこんなところで何をしているのだ? 憐夜がこんなところまで来る事ができるはずがないだろう。私が監視をしているのだから。いつもの場所で憐夜が腹を空かせて待っているやもしれぬぞ。今回は私も食事に同席させてもらおうか。今は仕事がない故な。」
千夜はいつになく饒舌に話すと更夜を促し、元の道へと歩き出した。
「……は、はい。」
更夜は千夜に促されるまま憐夜に背を向け、歩き始めた。
……お姉様は自分が監視していると言った。この山から逃げたら俺のせいではなく、自分の過失にしようとお姉様はしている。そして忍がまずいかないだろう南の洞窟に行くように憐夜を動かした……。
「お姉様……これは私の過失でございます……。いますぐ憐夜を……。」
「何の話だ?」
千夜は更夜にちらりと目を向けると、さっさと先へ行ってしまった。
「お姉様……。」
更夜は千夜の背中を黙って見つめ、歩き出した。
六話
次の日、憐夜が逃げた事はすぐに発覚してしまった。千夜は父である凍夜の元へ呼び出された。
「千夜、憐夜はどこに行った?」
更夜達と同じ銀色の髪に鋭い目で、凍夜は千夜を睨みつけていた。望月の隠れ里にある、集会所のような所に千夜はいた。まわりは他の甲賀望月が同席していた。この中で厳格な体制を敷いているのは、三つの望月家だった。
「……憐夜がおりませぬか? 私にはわかりかねますが……。」
「本気で言っておるのか? お前は居場所を知っているだろう?」
凍夜は千夜を見透かすように言葉を発した。
「いいえ。わかりませぬ。」
「昨夜、他の者がお前と更夜と、そして憐夜を見ている。お前は知っているはずだ。どこへ行った?」
「知りませぬ。」
千夜は断固として認めなかった。
「認めぬ気か……。」
他の望月家の者達が立ち上がり、千夜に襲い掛かった。千夜は軽やかにかわし、襲い掛かって来た者をすべて倒した。
「さすがだな。千夜。この父に逆らうとは……。」
千夜は凍夜の低く鋭い声にビクッと肩を震わせた。幼少の時からの記憶が千夜を縛る。
……父親に逆らってはいけない。
千夜ならば、今の凍夜には勝てるはずだった。だが千夜の身体は、何かの術にかかったかのように動かなくなってしまった。
「……くっ……。」
「勝てると思ったか? 千夜。」
千夜の頬を絶えず汗が流れる。凍夜が近づくにつれて千夜の身体の震えは大きくなっていった。
「……っ。も、申し訳ありませぬ……。お父様……。」
千夜は意思とは裏腹、凍夜に許しを乞うてしまった。
「ふむ。認めるんだな? では、憐夜はどこにいる?」
「しっ……知りませぬ。」
「なるほどな。逢夜を呼んで来い。」
凍夜は顔を千夜に近づけると、他の忍に逢夜を呼ぶように言った。
「お、逢夜は……逢夜は関係ありませぬ。」
「黙れ。これは見せしめだ。」
凍夜は指で千夜の顎を持ち、クイッと上げた。
「うっ……うう。」
千夜は恐怖心で満たされて行く自分を、ただ受け入れるしかなかった。
……千夜の心はもうすでに狂った規律に壊された後だった。
七話
しばらくして逢夜が集会所に慌てて現れた。
「何事ですか。お父様……。はっ!」
逢夜が入るとすぐに千夜が目に入った。逢夜は息を飲み、千夜をじっと見つめた。千夜は裸にされ、両の腕を縄で縛られ吊るされていた。
「お父様……これは……。」
「お前は憐夜の場所を知っておるか?」
「憐夜? 憐夜は今、更夜と共に……。」
逢夜は怯えた表情で凍夜と千夜を見つめていた。
「逃げた。抜け忍となった。」
「にげっ……。」
逢夜は凍夜の鋭い声を聞きながら動揺していた。逢夜の瞳には弱々しい顔でこちらを見ている千夜が映った。
「更夜が逃がし、千夜は黙認したようだ。これから千夜は仕置きだ。」
凍夜は持っている青竹で千夜の背中を三回ほど打った。千夜は痛みに顔をしかめたが、何も言わなかった。
「……っ。」
顔色が悪くなる逢夜に凍夜はさらに冷たい声で語った。
「憐夜は忍としては出来損ないだが、我が里の事がばれてはいかん。逢夜、いますぐ殺して来い。」
「そ、そんな事はできませぬ……。お、おそらくまだ更夜と共におります。」
「行け。我々も暇ではないのだ。憐夜は里から逃げた。お前が殺せぬというならば……。」
凍夜は千夜の胸を薄く刀で斬った。
「……。」
千夜は痛みに顔をしかめた。千夜の胸に一筋の切り傷が出来、そこから血が溢れるように流れた。
「おやめください。わ、私が憐夜を殺せばお姉様は傷つかずに済むのでしょうか?」
「……憐夜を逃がした罪は大きい。だがお前が殺しに行けば最小限で済ませてやる。我らは連帯責任だ。わかるな。そして殺したという証拠をちゃんと持ってこい。お前がもたもたと憐夜を探しておると、千夜の身体に傷が残っていくぞ。」
凍夜は続いて千夜の頬を刀の柄で殴った。
「うぐっ……。」
千夜は低く呻いた。
「俺が数えて十で千夜は何かしらの罰を受けるという事にする。今から始めるぞ。一、二、三……」
「……っ! そんなっ……そんな事がっ……俺が……憐夜を殺す……?」
逢夜はしばらく頭が真っ白になり、ただ震えていた。
「十だな。」
凍夜はそうつぶやくと千夜の左胸を薄く斬った。
「んっ……。」
千夜の身体に痛みが走り、千夜は小さく呻く。
「声を上げるなと教えたはずだぞ。千夜。」
凍夜は冷たく言い放つと、周りを囲んでいる忍のひとりに合図を送った。忍は何も言わずに立ち上がると、千夜の口を布で縛り上げた。
「んん……んん……。」
千夜は逢夜を視界に入れながら何かを訴えていた。
逢夜には千夜が何を言いたいのかが、よくわかっていた。
……憐夜を逃がせ。殺すな……。殺してはいけない……逢夜!
千夜は逢夜にそう言っているようだった。
「十だ。」
凍夜は太い青竹を取ると千夜の腹に深く打ちつけた。
「んぐぅ!」
千夜を縛っている縄が大きく動くほどの衝撃だった。千夜は胃液を吐き、痛みに悶え、体を折り曲げた。
「十だな。」
凍夜は青竹で今度は千夜の背を打つ。
「んんん!」
千夜は目に涙を浮かべ痛みに耐えるが、あまりの痛みに今度はのけ反った。
逢夜は拷問のような折檻をとても見ていられなかった。
「十だ。早くせんと千夜が死ぬぞ。」
凍夜はそうつぶやき、今度は千夜の背に鞭を入れた。乾いた音と共に千夜の背から血が飛び散った。
「うっ……!」
「お、お姉様……申し訳ありませぬ……。お許しください。」
逢夜はそう言うと千夜に背を向け、走り出した。
「はっ……はっ……。」
逢夜は無我夢中で憐夜の元へ駆けていた。憐夜の居場所はなんとなくわかっていた。
昨夜、人一人分が隠れられる場所がどこかにあるかと千夜から尋ねられたからだ。
候補として挙げた場所の内、一番近い所に憐夜がいると踏んだ。
……俺が憐夜を殺さないといけねぇ……。こんな事ってねぇよ……。
逢夜は山を下り、南にある洞窟へ向かった。草木が覆い茂る場所に人一人くらいが隠れられるような穴があった。憐夜は逢夜が来た事を知り、背を低くして穴に隠れていた。逢夜は気配で憐夜がいる場所を見つけて憐夜を引っ張り出した。
憐夜は青い顔で逢夜に背を向け逃げ出したが、逢夜は後ろから憐夜を押さえつけた。
「逃げんじゃねぇよ。」
「お、逢夜お兄様……。」
「お前は俺達を裏切った……。もう俺はお前を止める事もしないし、手をあげる事もない……。もう遅い。」
「……。」
逢夜の言葉で憐夜は急に大人しくなった。憐夜は色々と悟ったようだ。
「お前がお父様の仕置きを受けるというならば、山の中からは出ていなかった事にしてやる。戻る気がないのであれば……死ぬしかない。だが、俺はお前を斬りたくない。」
「お兄様、もう前者は無理ですね。私が戻ったら更夜お兄様もお姉様も皆酷い罰をうけます。痛い事はいけません。皆幸せになれません。」
「馬鹿野郎……。なんでそこまでわかっていて逃げたんだ!」
逢夜は目に涙を浮かべながら憐夜を地面に押し付けた。
「一瞬でも光の中を歩いてみたかった……ただそれだけでした。貧しくてもいい、辛くてもいい……だから人と笑い合って楽しく暮らしたかったんです! できればお兄様、お姉様と楽しくお話しがしたかった! 優しくされたかった! それがかなわなかったから私は自分でかなえようとしたんです! 人を殺すことなんて嫌だ! 人を傷つけるなんて嫌だ! 私は道具じゃない! 動物でもない! 私は心を持った人間なの!」
憐夜は幼い子供の様に泣きじゃくっていた。
逢夜はそんな憐夜を見ながら悟った。
……こいつはもうダメだ。いらない事に気がついてしまった。もう連れ戻す事は不可能だ。
俺が見逃したとしても他の忍に惨殺されるだろう。ならば俺が優しく殺してやるしかない……。
逢夜はそのような判断しかできない自分をとても悲しく思った。
「憐夜……。」
逢夜は憐夜を離してやると少し距離を取り、優しく名前を呼んだ。
「お兄様?」
逢夜が見せた優しげな声に、憐夜はきょとんとした顔をしていた。
「こっちにおいで。」
逢夜は優しい顔で憐夜を手招いた。憐夜は戸惑いながらも逢夜の前まで来た。
逢夜はそっと憐夜を抱きしめる。
「お兄様?」
「お前はとても良い子で優しい子だ。俺達の世界にはいちゃいけなかった……。辛かったな。いままでごめんな。憐夜。」
逢夜はゆっくりと憐夜の頭を撫でた。憐夜は初めて優しくされ、戸惑っていたが逢夜の背に手をまわし、大声で泣き始めた。逢夜はそんな憐夜を強く抱きしめ、ただあやまった。
「……ごめんな……。憐夜。……ダメな兄と姉を許してやってくれ……。」
逢夜は優しい言葉をかけ、そっと頭を撫でながら背中から憐夜を小刀で突き刺した。
「うっ!」
憐夜は低く呻き、わずかに動いた。刹那、袖に隠してあった絵筆がぽとりと地面に落ちた。
「……筆? お前……こんなものどこで……。」
逢夜は自分達が散々傷つけてしまった憐夜の身体をそっと抱きながら小さくつぶやいた。
「絵描きさんに……もらったんです……。おにい……さま……。私は運命を……呪います……。自分の生を……呪います……。私は道具じゃない……。生まれ変わったら……子供に絵を配る絵描きさんに……なりたい……な。」
憐夜の身体から温かさが消えいき、瞳にも光が消えた。憐夜は更夜達の目を盗んでか、たまたま会っただけか、わからないが絵描きから筆をもらったようだ。そして自分も絵描きになりたいと思い、山を下りたのだった。
「くそっ……。」
逢夜が歯を食いしばった時と、憐夜の身体から力が抜けるのが同時だった。逢夜は自分が散々殴った憐夜の顔をそっと撫でる。
……皆が楽しく生きられる人生なんてねぇんだよ。俺はこうなる事がわかっていたから全力で止めたんだ!俺達はあの家系からは逃げられない。だから俺はあの家系から逃げなくても、兄弟が生きていられる環境を作ろうと努力したんだ! 本当はお前なんかに手は上げたくなかったんだよ! なんでどいつもこいつも俺の事をわかってくれねぇんだ!
「畜生!」
逢夜はそうつぶやくと憐夜の身体を抱き、去って行った。
……おかしな家族の狂った規律に逢夜もすでに壊された後だった。
最終話
逢夜は光のない瞳で里に戻ってきた。冷たくなった憐夜を抱きかかえ、集会所へと入る。
そこにはすでに誰もおらず、ただ、酷い暴行を受けた千夜が血だまりの中で倒れていただけだった。逢夜を監視していたものがいたようで、憐夜が死んだことはもう伝わっていたようだった。
……どちらにしろ……憐夜が逃げられるはずもなかった。先程逃がしてやろうと思ったが、俺が見逃しても俺を監視していた忍が殺すだろう。
「……お姉様……申し訳ありませぬ……。」
「憐夜……憐夜ァ……。」
千夜は頭を抱えるようにしてうずくまりながら、ただ憐夜の名を呼んでいた。
……千夜、逢夜、更夜の心にほんの少しだけ残っていた優しさはこれを期に完全に消え失せた。
春に散る花
俺が殺した少女、鈴と死後の世界で共に生活するようになった。鈴は俺のような人でなしになぜか、心を開き、白い花が咲きほこるこの屋敷でいつも笑顔でいる。
「更夜(こうや)ー! あれ? また仏頂面してる」
「そんな顔をしているか? 俺にはわからん」
俺は畳の一室でゆっくり茶を飲む。いままで、こんな風にのんびり過ごしてきていない故、時間が進むのが、やたらと遅い。
気がつくと鈴が隣で茶を入れて飲んでいた。
「はあー。……あんたさ、いつも暗い顔してるけど、そろそろ笑ってみたら? あ、怖い笑いの方じゃないやつね」
鈴は俺の演技顔を怖いと言う。
まあ、そうだろう。
自分の方が上だと知らしめる時に、使うようにしている故に、鈴に使った時もおそらく怖かったはずだ。人の心理につけこみ、底知れぬ恐怖を味あわせるのも忍の得意技だ。
「すまん。もうあなたにあの顔はせん。本当は、鈴を殺したくなかったのだ。酷いこともな」
「更夜、また顔が沈んでるよ。違うこと考えよっか」
俺は最近、突然感情が隠せなくなった。鈴に見抜かれるほど、顔が沈んでいたか。
やや人に近づいた気がする。
「そうだな。あなたが怖がる顔をもう見たくないのだ。あなたは……そうだな、笑っていた方がかわいいぞ」
「……!」
鈴は俺の言葉に顔を真っ赤にして下を向いた。
本当にかわいい子だ。
まるで……
いや、やめよう。
鈴は鈴だからな。
「あ、あのさ、そういえばー、白い花畑、ずっとあるね! やっぱこの世界好きだわ」
鈴が照れ隠しにそんなことを言うので、俺もそれに乗る。
「ああ、あの花畑は、時神過去神(ときかみかこしん)栄次(えいじ)の力作だ」
「しかしさー、死んだ後にさ、宇宙みたいに沢山世界があるとは思わなかったわよね! しかも、現世で生活してる人らの心の世界が具現化してるなんて、誰が考える?」
鈴が笑い、俺もつられて笑ってしまった。
「確かにな。ここは、時神未来神(ときかみみらいしん)プラズマの世界だという。それで、過去神栄次が未来神プラズマの世界を装飾し、俺達が住みやすくしたと。風呂とか、家とか、花畑とかな。俺を現世で殺したのが神というのも、なんかの運命か。栄次が時神だったとは知らなかった。どうりで化物じみた強さだと」
珍しく俺が楽しそうに語ったからか、鈴が目を見開いていた。
「あんたさ、いつもそういう感じにしなさいよ」
「すまんな。まだ感情を自然に出せんのだ」
「私達は、なんだかんだで現世の時神のおかげで死後の世界の……こちらの世界の時神になっちゃったわけだから、忍じゃないのよ。自然に笑えばいいのー」
「ああ。俺の心にある後悔がすべて消えれば、笑えるようになるかな」
鈴に意味深な言葉を発してしまい、慌てて俺は口をつぐんだ。
「後悔? 私を殺した他になんかあるの?」
鈴はこういう所が鋭い。
俺にはまだ、このことを話す勇気はない。口に出せるほど傷が癒えていないのだ。
「まさか、女……」
「……さあな」
鈴は本当に鋭い。
俺はてきとうにはぐらかした。
すると、鈴は少し悲しそうに立ち上がった。
「ゆのみ、片付けてくる」
「……」
俺は鈴の感情に気づかぬほど鈍感でも若くもない。
だが、俺は鈴を娘と重ねている。俺は父親だった故に。
娘がいたんだ。
妻もな。
二話
俺が十五の時……、妹の憐夜が死んだ一年後、凍夜が十四の娘を拾ってきた。戦の時代、両親がいない孤児はあちらこちらにいた。
凍夜はその娘を下女と呼び、「飼育」することにしたと言った。
その娘は両親に大切に育てられたらしいが、ここでは通用しない。
この凍夜望月家は愛とは無縁の一家だ。拾われた家が悪かったな。
目に光がともっていた娘が、光を失うのに時間はかからなかった。
娘は凍夜の体を拭くという命令を受けた後、どんくさいという理由で殴られ、顔を腫らし、泣いていたのが最初だった。
俺は声をかけなかった。
おそらく、この娘はいつか、凍夜の拷問の練習に使われ死ぬ。
死んだ方がいい。
早く死んだ方が楽だ。
逃げたら俺が一瞬で殺してやろう。
そう思っていた。
愛されて育った娘が両親を戦で失い、泣いている所に凍夜がきて声をかけ、彼女は愛してもらえるとわずかながらに思い、ついてきたのだろうと予測できた。
同情はしない。
俺はもう、心がわからなくなっている。
どうでもいい。
忘れろ。
どうせ、皆、死ぬ。
また、彼女の泣き声が聞こえる。なんだろうか、このうずきは。
憐夜を思い出す。
妹は俺達の暴力によく泣いていた。
助けられなかった。
自分からも、兄弟からも助けてやれなかった。
今もそうか。
ああ、なんだかな。
人でなしという言葉がしっくりくる。
「申し訳ありません! もうしわけっ……」
娘の謝罪する声がする。
おそらく、あの子は何も悪くない。今回はなんだ?
隣の部屋から食器が割れる音がした。
ああ、食事か。
そういえば、本日は他望月家の家長が集まる集会だ。
それの食事が間に合わないのか。凍夜はおそらく、何人分もの量を彼女ひとりで作らせているはずだ。
俺はため息をつくと立ち上がり、板場を覗いた。
身体中アザだらけの少女が破れた着物を恥じらいもなく着込み、泣きながら食事を作っていた。
どうやら、塩や砂糖の使い方がわかっていないようだ。塩や砂糖は貴重なもの故に、この娘はほとんど使ったことがないのだろう。
「やれやれ、終わらんな。単純に食い物になっていない」
凍夜は愉快そうに笑いながら、板場に入った俺を見た。
「更夜、お前が作れ。この下女はお仕置きだな。できなければ、罰を受けるのが当たり前だ」
「そっ……そんな……」
凍夜の狂った考えを受け入れられない娘は泣きながら頭を床に押し付け、謝罪をはじめる。
……あやまったところで意味はない。
俺はそう思いながら、煮込まれた煮物を菜箸で食べてみた。
味がなさすぎる。
おそらく、この娘の家庭ではこれが普通だったのだろう。
娘が謝罪をしている中、俺は無言で煮物の味を整えた。
まだ飯も炊けていなかった。
もう日は傾いている。
早くしないと間に合わない。
俺は火をおこし、麦飯を炊きはじめた。
「更夜、作った後、こいつに盛り付けさせてから、罰を与えとけ」
「……はい」
俺は素直に凍夜に返事をし、凍夜は陽気なまま出ていった。
「大丈夫か? 味を覚えろ。これだほら、食べろ」
俺は凍夜がいなくなってから小皿に煮物を盛り、渡した。
「……はい」
娘は震えた手で大根の味噌煮を食べる。
「わかるか? かなり濃いのだ」
「……はい」
娘は食べた後に、少し優しい顔をした。うまかったらしい。
「……すまぬ、盛り付けはやってくれぬか。俺は目が悪いため、よく見えんのだ」
今は弐(に)の世界でメガネを手に入れたが、この時は戦国時代である。
メガネなど手に入らない。
故に俺は生まれつき、ものがよく見えない。だが、そこまで悪くはない。
娘はささっと盛り付けた。
ここは早い。
おそらく、凍夜の重圧がなければ、器用な娘なのだろう。
「麦飯も、ありがとうございます……」
娘は床に頭を押し付け、震えながら俺に感謝の言葉を述べた。
「……よい」
俺はとりあえず、ひとこと言って、他望月の会合の準備をした。
望月は忍の家系。これからの動向などは深夜帯に決めることも多い。今回も夜に、静かにやるようである。
集会所に料理を娘と運び、灯し油に浸した灯心(とうしん)に火をつけ、行灯(あんどん)をかぶせた。
忍はこれくらいの灯りでいい。
障子を開けて、外で焚き火は明るすぎるのだ。
なんとか準備も終わり、俺と娘は屋敷に戻った。
「……あなたはなんという名だ?」
俺は今後のために名を聞いた。
情報はいつ使うかわからん故な。
「はる……です」
「はるか。良い名だ」
「ありがとうございます」
屋敷の一室に入り、余りの味噌煮を麦飯と食って夕食にし、はるにもそれを食わせた。
食えるときに食え、俺はそう言った。
「さてと……」
俺は憂鬱になりながら、はるを見た。はるもわかっていた。
顔色が悪い。
ある程度はやらんといかん。
俺は凍夜に逆らえない。
恐車(きょうしゃ)の術は幼少期から俺にかかっている。
命令されればやるしかない。
憐夜にやったように……。
「はる、お父様を怒らせた罰だ。まっすぐに立ちなさい」
「……はい」
はるは素直に立った。着物を握りしめている。
怖いだろうな。
これから俺に殴られるのだから。
凍夜が満足するくらいの傷を負わせてやらねばならんのだ。
相手は無抵抗の女だ。
やりたくない……。
俺は凍夜であれば、はるへの仕置きの度合いをどれくらいにするか考え、軽くても重そうな痕が残るやり方を導き出す。
震えているはるの頬をかなりきつく叩いた。鉄砲を撃ったかのような音がし、はるが倒れる。
はるは泣いていた。
「い……痛い……」
「立て」
俺は感情を消し、はるを再び立たせ、反対の頬を張る。
はるは逆側に倒れ、頬を押さえて嗚咽を漏らしはじめた。
「痛ぃ……ごめんなさい……」
「立て」
俺はもう一度、はるを立たせ、もう一発叩いた。顔は腫れていた。
……もう良いか。
……やりたくない。
『私は人間ですか? それとも道具?』
死ぬ前の憐夜が言った言葉。
胸に刺さる。
しかし、俺は反対のことをしようとしていた。
凍夜を焦らせた罰が頬を三回叩くだけでいいのか。
拳で女を殴るのはかなりの抵抗がある。故に平手にしたのだが、俺の抵抗は一緒だった。
仕方ない。
背から足にかけて鞭を入れたことにするか。
着物と腿の間に三発だけ鞭をいれよう。しこたま叩いたように見えれば、それで良い。
「そのまま壁に手をつけ」
「……はい」
はるは泣きながら素直に従う。
……はあ、憐夜がちらつく。
嫌になる。
俺は頭を抱えつつ、はるの腿に竹鞭を三回入れた。
「うっ……ううっ」
はるは呻き、赤いみみず腫れが三つできたが、血がでなかった。
凍夜が一体、一回の仕置きでどれだけ力を入れているのかわからなかった。俺は背から血が溢れ出るくらいまで打たれていたが。
だが、もういい。
見るのも辛い。
もう無理だ。
やりたくないんだ。
「立て。終わりだ」
「はい」
俺ははるを立たせ、顔を見ずに部屋から出た。顔をみたくなかったのだ。はると離れてから俺は手の震えを抑えるため、深呼吸を何度もした。
もう無理だ。
気分が悪い。
泣いている憐夜が映る。
気持ち悪い。
「うっ……」
俺は外へ飛び出し、草むらに食べたものを吐いてしまった。
「はあ……はあ……」
目から勝手に涙が溢れた。
ぼやけた視界がさらにぼやける。
「更夜様……?」
気がつくとはるに声をかけられていた。
「あ……ああ、なんだ?」
俺は平静を保とうとはるを見ずに尋ねる。
「具合が悪いのですか?」
はるは心配そうな声音で俺の背を撫でた。先程、暴力を振るった俺の心配をするのは辛くないのだろうか。
「問題はない。あなたは俺になんの用だ」
「……はい。あれは私の大失態ですが、罰が軽すぎるような気が……」
はるはもうすでに、凍夜の感覚で話している。
罰が軽すぎる?
こんなもので罰が飛ぶのがおかしいのだ。
ただ、料理の味付けに失敗しただけで思い切り頬を三回も叩かれ、腿に三回も鞭を入れられた。
そう考えるのが「普通」ではないのか。
料理の味付けを失敗したのに、頬を三回しか叩かず、鞭も三回でいいのかと、この女はそう言うのだ。
おかしいだろう。
俺はおかしいと思うのだ。
「あの……申し訳ありませんでした。これで良いなら良いのです」
「……良い。これ以上叩けば身体に悪い」
「……身体に……悪い……ですか?」
俺ははるに問われ、余計なことを話したと思った。
余計な会話が生まれてしまう。
「……離れろ」
俺は突き放した。
そして逃げるように去ったのだ。
どうせ死ぬのに、知り合ってどうする。俺はそう考えていた。
三話
そこからか、俺は会いたくもないはるによく会うようになった。はるはなぜか、いつも俺の心配をする。
なぜだ?
俺は関わってほしくないのだが。
屋敷の一室で精神を安定させていると、はるが「失礼します」と中に入ってきた。
「更夜様、顔色が悪いですが、具合が悪いのでしょうか? お粥などいかがですか?」
「問題ない。俺に構うな。お父様を気にかけろ。でなければ、また殴られるぞ」
「……そう、ですね」
はるは複雑そうな顔で俺を見る。俺を気にかけてどうするというのだ。
「何かまだあるのか?」
俺は踏み込まれないように冷たい空気を出す。こいつと話している暇はない。
「あの……このあいだはなぜ、手加減を?」
はるの言葉に思わず、顔をしかめてしまった。
「手加減などしておらん。時間の無駄だ」
はるは俺の心を開こうとしてくる。おそらく、こないだの失言で俺の性格を理解したのだろう。
ああ、そうさ。
俺は「残虐な行為が嫌い」だ。
仕事故にやっている。
それだけだ。
「心配なのです。ただ、それだけなのです」
はるは俺にそう言った。
壊れた俺と、壊れる寸前のはる。はるにはなにか思うところがあったのだろう。
「はる、お父様の気配を感じる。すぐに戻れ。お父様が帰ってきたぞ」
「……はい」
はるはどこか残念そうに去っていった。
※※
朝、俺が諜報の仕事から帰ると、はるの泣き声が聞こえた。
またか。
凍夜の遊び道具にされている。
今度は何をしたのか。
どうせ、くだらんことだ。
「しかし、お父様に仕事の報告に行かねばならんのだ。遅いと酷い目に遭わされる」
仕方なく、凍夜がいる奥の部屋まで行き、声をかける。
「……失礼します。ただいま帰りました」
「更夜、入れ」
「はい」
凍夜に許しをもらえたので、中に入った。
はるは腹を抑えてうずくまっていた。腹を殴られたか、蹴られたか。
俺はそれを横目で見ながら凍夜に内容を報告した。隣国の内部情報を仕入れて、凍夜に報告する仕事に今はついているのだ。
「ふむ。理解した。おもしろい話だ」
「では」
俺は頭を下げ、早々に去ろうとしたが、凍夜が止めた。
「待て待て。こいつがな、俺の妻どもに接触したのだ。下女ごときが望月家と口をきくことは許さん。まだしつけが足りんようだ。俺は隣国を落とす計画を練るため、もう行くが、お前はこいつをしつけろ。こないだも仕置きがぬるかったようだが、今回はそうはならんよな?」
凍夜の冷笑に俺は震えた。
やはり、バレていた。
知っていた上で、もう一度、俺が凍夜に従順しているか見るのだ。故に再度、はるに暴力を振るえと言う。
そして今回は……おそらく。
「爪を全部剥がし、舌を切るか、水を飲ませた上で腹を百発蹴るか、逆さに吊るし、竹鞭で百叩き。お前はどれがいい?」
「……」
やはり、凍夜はやることの指定をしてきた。
「まあ、好きにやれ」
凍夜は笑いながら去っていった。
……戦国の武将達は皆、残虐だ。
風の噂では子供を串刺しにし、女達を磔(はりつけ)にした残虐な話も聞く。
牛裂き、釜茹で、鋸(のこぎり)引き、磔、串刺し……。
この時代には沢山の死がある。
人の命が……軽いのだ。
軽すぎるのだ。
はるは頭を床に擦り付けたまま、動かない。
「はる、俺はやりたくない」
俺は追い詰められていた。
凍夜が言った内容は全て、やりたくないのだ。
捕らえた者に拷問する練習をしろと言うことなのだろうが、いつまでも慣れない。
はるは泣いていた。
当たり前だ。
一生ものの傷を負うかもしれんのだ。苦痛も嫌だろう。
それは俺にものし掛かる。
爪を剥がして、舌を切るか。
水を無理やり飲ませながら、腹を百発蹴るか。
逆さに吊るし、竹鞭で百叩くか。
一番上は傷が重すぎる。
二番目は髪を掴んで桶の水を強制的に飲ませて、腹を蹴るを百繰り返す。蹴ることで水を胃から吐いて苦しい上、さらに水を飲まされ、また痛みと共に吐き出される。これは残酷すぎる。
もう最後しかないか。
いや……もうひとつある。
俺は思い付いた。
凍夜は俺に拷問の練習をさせている。ならば……、恐車(きょうしゃ)の術を試すことにすれば良い。
はるを無理やり犯し、男忍特有の手技を使い催眠をかける。
凍夜にそう説明すれば残虐性を少しは抑えられるはずだ。
はるには俺の感情を知られてはいけない。術にかからねば意味がないのだ。
俺は冷たい目をすると、はるに命令をする。
「脱げ」
「はい」
はるは素直に着物を脱いだ。
アザだらけの身体に俺は戸惑ったが、息を吐く。
「寝ろ」
「……え?」
凍夜が言った三つのどれかが来ると思っていたのか、はるは眉を寄せて俺を見た。
すまぬ。はる。
……やるぞ。
「さっさとしろ」
俺ははるの頬を強く叩いた。
はるは震えながら横になる。
「逆らえば舌を抜く。今のは手加減してやったのだ。次は、こうはいかぬ」
「……はい」
まずは……ここだ。
首の一点を触り、呼吸をしずらくする。腕、足、腹……それぞれの一点を強く押す。呼吸もしずらく、手足も動かない。
しかし、腹は熱くなってくる。
男を受け入れたくなるのだ。
はる、すまぬ。
苦しいだろう……。
強制的にそういう気持ちにさせる術だ。自ら求めたことに、後で後悔するのだ。
泣いている。
……もう、できない……。
やりたくない。
はるはこれから俺の術で苦しむ。俺が苦しませるのだ。
「このまま殺してもいいがな。それだとお父様が満足しない。これからもっと苦しくするぞ」
俺は感情に反して冷酷な表情でそう言うのだ。
はるはどういう気持ちで俺を見ているのか。
四話
俺はまた、茂みで吐いていた。
はるは催眠と術にかかり、表情なく部屋でぼうっと座っている。
涙を流していたが、身体に傷は与えていない。
だからと言って良かったわけではない。これからはるは俺の操り人形だ。
はじめて試した術故に、深くかかってしまった。
凍夜が帰ってきたら、これを見せ、その後に催眠を解く。
それが一番いい。
「更夜、おもしろいことをしたな。下女を壊したか」
気がつくと後ろに凍夜が立っていて、どこも見ていないはるを投げ捨てた。
「……はい。色々とやりました」
「これはこれでおもしろい。ではこの状態で水責めの腹百発蹴りをやったらどうなるか試してみよう。鞭は軽いからおもしろくないな。おそらく無表情だ。舌を切るのは下女の仕事ができん故、そういやあ、却下だな」
「……っ!」
凍夜の発言に俺の視界が揺れた。
はるは連れていかれた。
俺は拳を握りしめ、凍夜に言う言葉を必死で考える。
初めから俺の動きを読んでいたのか……。
何か言わないと……。
気持ちは焦るばかりで何も思い付かない。俺は屋敷の外の草むらに再び吐いた。
俺がはるの代わりになろう。
はるを俺付きの使用人にしてもらい、使用人の不始末の罰を俺が……。
俺は通るはずのない案を凍夜に話すべく走る。
屋敷に入り、井戸のある庭に向かい駆けた。
すぐにはるが木に縛り付けられているのが見えた。
桶で井戸水をすくい、無理やりはるの口にねじ込んだ凍夜は、はるの腹を手加減せずに蹴りつけた。
はるは苦しそうにもがき、水を吐く。木に縛り付けられているため、腹を抑えることもできず、目を見開き涙を流している。
やめてくれ……。
「ふむ。これくらいだと催眠が解けるのか。後九十五回だな」
凍夜は笑いながら、吐き続けるはるに無理やり水を飲ませる。
「息ができんのか。なら息をさせてやる」
凍夜は再びはるの腹を押し潰すように蹴る。
はるは再び、吐き、呻きを繰り返す。
やめてくれ……。
はるが意識を失っても拷問は続く。
なぜ、俺は何もできない。
なぜ、凍夜に逆らえない。
幼少期の術を解く方法はないのか。
このままでははるが死んでしまう。
罪のないはるが、人でなしに殺されてしまう。
なんとかしろ。
なんとか……。
十五の俺には何も思い付かなかった。ただ、黙ってみていた。
あの優しい笑顔のはるが消えてしまう。
どうしたらいいのだ……。
やがて裸のはるが俺の足元に乱雑に投げ捨てられた。
「死んだかな?」
凍夜は愉快そうに笑う。
「……」
凍夜は俺にこれくらいできるだろうと目で言ってきた。
「まあ、死んでてもいい。死んでたら片付けておけ。ああ、刀の試し切りに使うから、やはり死んでたら串刺しにでもしておけ。お前も試し切りやるか?」
凍夜はそのまま去っていった。
こういう男なのだ。
「……はる」
俺は声をかけた。
死んではいないようだが、意識はない。俺ははるを優しく抱き、静かな小川が流れる森に入っていった。
ここは憐夜の怪我を治していた場所だ。土が柔らかく、日も当たり、小さな川が横を流れている。
俺ははるを寝かせ、腹を見た。
酷い青アザができている。
内蔵に異常はないか確認し、腹を布切れで冷やした。
そして、俺の羽織をはるにかけた。
青白い顔のはるをそっと撫でてから俺は泣いた。
誰にも知られずに静かに泣き、惨めな自分を殴り付けた。
かわいそうだ。
はるがかわいそうだ。
はるがこんな酷い目にあう必要はないではないか。
女にこんなことをするのは許せない。女に残虐な行為をすると、性的に興奮する男が寄ってくる。
戦国の世はいかれているのだ。
水を無理やり流し込まれて、百発も腹を蹴られ、意識を失ったはる。
どうしてあいつは非道なことができる?
どうして泣いて許しを求めている女にそんなことができる?
はるは優しい女だ。
そして、弱い。
あいつから守らねば。
男として、はるを守らねば。
どうやって守る?
目を泳がせていると、はるが目覚めた。怯えと苦痛が顔に浮かび、泣き出す。
「あっ……あー! ううう……」
叫びながら腹を押さえうずくまった。
「いいいー! あー!」
気が触れたかのように叫ぶ。
……俺が壊した。
俺が壊したんだ。
はるを。
目を剥き、俺から離れようとしたが、腹が痛いのか、苦しいのかのたうち回っている。
恐怖が顔に浮かんでいた。
俺が少し動くと頭を抱えて、うずくまり、震える。
はる……俺は間違えていた。
あの術はしてはいけなかった。
あれの後に凍夜が……。
俺は拳を握りしめた。握りしめたらはるが恐怖に顔を歪め、失禁した。
もうダメだ……。
なんと声をかける?
悩んでいると、はるが鋭利な枝で自分の首を刺そうとしていた。
まずい。
……このまま死んだ方が楽か。
……いや、殺してたまるか。
俺は素早く枝を奪う。
はるは泣きながらうずくまった。
「もう死にたい……もう死にたい。痛い……苦しい……痛い……苦しい……辛い……悲しい……殺して……殺して」
「死なないでくれ。俺がこれから代わりになる! だから、死なないでくれ。頼む」
「お母様……お父様……なんで私も連れてってくれなかったのですか……。私を置いていったのですか……。お母様とお父様がくださった身体……こんなに酷くなりました……自慢の身体だったのに。傷なんてっ……なかったのにぃ!」
俺ははるを呼び戻す。
落ち着かせようと無理やり抱きしめた。はるは発狂しながら俺から逃れようとした。
「きずなんでっ……ながっだのにぃ……!」
泣き叫ぶはるを必死で抑え、離さずに力を入れずに諭す。
俺が守る。
俺が代わりになる。
俺はお前を傷つけない。
俺はお前の味方だ。
様々な言葉を吐いた。
すべて本心であり、嘘はない。
伝わるか伝わらないかわからないが、諦めずに語りかけた。
人を壊すのは容易いが、人をもとに戻すのは容易ではないのだ。
彼女は戻らない。
まだ、戻らない。
もう戻らないかもしれない。
後半はただあやまっていた。
気持ちが伝わるように必死であやまった。
それしかできなかったのだ。
やがてはるの震えが収まった。
静かな嗚咽だけが続く。
すまぬ。はる。
俺はあいつから離れられる術を考える。
お前が逃げられる道を全力で考える。
「だから、まずは休め。俺が今、命令した。凍夜様に呼ばれていても俺が命令した故、罰は俺に来る」
俺は凍夜に逆らえない。
ならば、逆手にとるのだ。
逆らわないではるを守る。
五話
それから俺ははるを守るようになった。凍夜の身の回りは俺がやり、はるは俺の下につけた。
凍夜が何かを言ってくるかと思ったが、特に何も言ってこない。
はるに飽きたのかもしれなかった。
はるは俺の身体を見てまた泣いた。はるを庇い、俺は度々凍夜の暴力を受けていたからだ。
痛みは感じない。
そうなってしまったのだ。
幼少から俺はずっとこうだ。
血にまみれても止血してから、そのまま仕事をし、諜報にもはるを連れていった。はるには妻役を頼む時もあった。
はるはあれから気持ちをだんだんと取り戻し、俺を手伝ってくれるようになった。
俺は忙しく動き回るため、凍夜の屋敷に帰ることもなくなっていった。
屋敷に帰る際ははるに気が触れた役をやってもらい、凍夜の興味を薄れさせた。凍夜は何度も使えぬはるを殺そうとしてきた。
はるは演技でも怖かったはずだが、表情を出さずに役を全うしてくれた。俺は操って諜報に使っている、失敗はしない、そう凍夜に言い続け、仕事を成功させ続けた。
緊張から解き放たれ、凍夜の屋敷から出て、仕事に行く道の森の中で、はるはいつも震えながら泣く。俺は静かに抱き、「大丈夫だ
。守る」と繰り返す。
その積み重ねではるは外に出るとだんだん元に戻っていった。
彼女を壊すのは一瞬だった。
しかし、もとに戻すのは何年かかっても無理そうだ。
彼女は弱い。
弱い故に、壊れるのも早かった。
あの元気な瞳が見たい。
虚ろなはるを見て俺はそう思っていった。
「ありがとうございます」
仕事に向かう森の中、はるが小さくそう言った。
俺は驚いて立ち止まった。
はるから声をかけることはなかったからだ。
「はる……」
「私を庇ったり、私を守ってくださったり……。私は初めからあなたの優しさに気づいておりました。あなたもお辛いでしょう。私はあなたを一生懸命助けます。今後ともよろしくお願いいたします」
「はる……」
俺が壊したはるが、はじめて優しい笑顔で笑った。
「はい」
「守れなくてすまない。やりたくてやっていたわけではないのだっ!」
「はい」
俺ははるの肩を掴み、童のように泣き叫んだ。
はるは俺の頭を撫で、いつもとは逆に抱きしめてくれた。
「知っていますよ」
「俺は人でなしだっ。人でなしなんだっ!」
「違いますよ」
はるの言葉は短いが俺を温かく包んでくれた。
「あなたは、優しいですよ。人でなしなど言わないでくださいませ」
「はる……」
ここで俺は最大の間違いを犯すことになる。
「はい」
「夫婦にならないか? 夫婦になればお前は望月だ。望月ならば、下女ではない」
「……そちらが良いならば私は従います」
俺は感情的になっていた。
良く考えればわかったはずだ。
だが、俺ははるに望月家にしてやると言ってしまった。
「そのためには子がいる。三人で新しい望月になりたい」
「いいですよ。更夜様と共に行きますから。ただ、あの……私が子種を宿せるか……」
「腹はまだ痛むか」
「いえ。そうではなくて、心配なのですよ。催眠にかかった時、すごく怖かったので、またおかしくなるかもしれませんし」
はるは淡々と言うが、俺は切なくなった。
そうだ。
最初に俺がはるを……。
「……お前が無理そうなところで止める。恐くなったら止める。俺は術を使わない。あの暖かな土の上になるが、良いか」
「……はい」
「俺ははるを愛してる。愛し合いたいために子を作る。故、お前が嫌ならばやめる」
俺ははるをうかがった。
「嫌ではありません。私の身体でよければ……愛してやってくださいませ。……いえ……その……違いますね。抱いてください……ませ」
はるは顔を赤くしてもじもじしていた。
愛おしく、かわいい女だと思った刹那、俺の心臓が早鐘をうちはじめた。
六話
はるの妊娠はすぐにわかった。なんだか気分が悪そうな日が続いたからだ。
悪阻(つわり)であることは俺にもわかった。俺ははるを凍夜から離し、長期の仕事をやることにした。あの屋敷にいなければ、凍夜にバレない。
危険な仕事だった故、あまり気にかけてやれなかったが、村人に溶け込み、はるを助けてもらっていた。敵国の村人と仲良くし、情報を盗み、武家として城に入り、城主を暗殺する。
これが俺の仕事だ。
村では子を身ごもった女を連れた男が疑われることは少ない。
武家屋敷は遠いため、俺は変装して二月ほどいなくなった。
仕事は失敗していなかった。
やがて悪阻(つわり)の時期が過ぎ、安定したはるに沢山の野菜を食べさせた。
生まれてくる子ははるに似てかわいいに違いない。
はるもよく笑ってくれるようになった。
幸せだった。
もうここで暮らしたい。
そう思った。
やがてはるは、かわいい女の子を産んだ。
小さな手が俺の手を握る。
俺は赤子を抱き上げると、この村に伝わる子守歌を歌ってやるのだ。だいたいが泣き止まず、はるに苦笑いされるのだが。
赤子は静夜と名付けた。
静かな夜になってほしい。
戦や忍で溢れない夜がほしい。
その願いで決めた。
はるは幸せそうだった。
俺達はようやく家族になれた。
盗んだ情報は俺を監視している忍に口頭(無声)で伝え、その忍が凍夜に報告するという方法をとった。
俺はいつも大きな情報を盗むため、凍夜も誰も口出ししてこなかった。
幸せな日々は五年ほど続いた。
娘はすくすく育ち、はるに似てかわいい顔で笑う少女になった。
「おとうさまー!」
静夜は俺にいつも拾ってきたものを見せる。ドングリ、葉っぱ、虫……気になるものを見せてくるのだ。
「静夜、更夜様が困っているでしょう?」
はるは俺の顔を見て、楽しそうに笑う。俺は二人をそっと抱き寄せて幸せを噛みしめた。
守る命が二人になった。
凍夜の元へは帰らずとも、別によい。
そんなことを思い始めていた。
しばらくして、俺は家族のために、城主を暗殺した。
この件で俺は鈴という少女と関係を持つのだが、また、別に話すことにしよう。
そのすぐ後に、凍夜からの呼び出しを食らった。
ここの城主を暗殺した直後だ。
俺ひとりで行くつもりだったが、敵国に娘と嫁を置いておけなかった。
「はる……戻らねば」
「……ええ」
俺がそう言うと、はるは俺の手を握り、「ついていきます」と笑顔と覚悟を向けた。
そこで俺は誤解していたことに気づく。
はるは……初めから強い女だった。弱いのは俺の方だ。
俺は腹をくくり、はると幼い娘を連れ、屋敷へ戻った。
女二人を連れていたため、半年ほどかかってしまった。
ある晴れた春のこと。
桜が満開で喜ばしいはずだが、俺達の気分は悪かった。
屋敷へ入り、久々に凍夜と対面した。凍夜はほとんど変わっていなかった。だが、威圧や実力はもう俺の方が上だった。
「久しぶりだな」
「はい」
「ほぅ、そいつがガキか」
横にいた静夜は身体を震わせながら頭を下げていた。
すまぬ、もう少しだからな。
俺は心で静夜にそう言った。
「はい。望月静夜……でございます」
俺はそう紹介した。この子は俺の血が入っている。
もう望月だ。
そう思ったが、凍夜は嘲笑した。
「はっ。望月? そいつはお前が犯して壊した下女のガキだろう。笑わせる。母が下女なら子も下女に決まっている」
凍夜の言葉に俺は、幻想を抱いていたことに気がついた。
はるは正式な許嫁ではないのだ。
家長の凍夜が許していない。
「お……おとうさま……おかあさまを犯して壊したとは……?」
静夜が俺にそう言った。
俺の身体に冷たいものが這った。
まずい。
「お父様」は凍夜様だけだ。
凍夜望月の祖、凍夜のことを子孫は「お父様」と呼ぶ決まりだ。
俺をお父様などと呼んでは……。
空気がはりつめた。
「ほぅ。なるほどな」
凍夜は狂気に満ちた笑みを浮かべ、俺を見る。
「お父様、静夜は……」
「黙れ。更夜。下女がなめた口をきいたな。ガキ、お前に名前などいらんのだ。お前は、更夜が弄(もてあそ)んだ下女とのガキだ。そこの下女に術のかかりを試したりなど、楽しそうだったぞ」
「……!」
静夜は怯えた表情で俺とはるを見る。はるは目を閉じていた。
「望月だと思ったか。お前は親父に乱暴されて産まされた下女とのガキだぞ。つまり下女だ。下女が望月に泥を塗るか。お仕置きだな」
俺は着物を握りしめ、目を見開いた。
静夜が……。
守らねば……。
「せっ……せいやは……」
おかしい。
俺の口が突然動かなくなった。
身体も動かせない。
「お前は俺に指図するか? 更夜」
凍夜の目を見、俺は金縛りにあった。
「恐車の術」だ……。
また……逆らえない。
俺の実力ならば、あいつを殺せる……。
殺せるはずっ……!
「……更夜様、いままでありがとうございました。……はるは幸せでした。私の時のように……娘を……静夜を守ってくださいまし」
俺が動けないことを知ったはるが、涙声でそう言った。
……ダメだ……。
はる……。
待ってくれ!
「は……る!」
「私が代わりに罰を受けましょう。下女の娘を助けてくださいまし」
はるは死ぬつもりだ。
はる……やめてくれ……。
「まあ、よい。お前の娘は俺の下女だ。お前は死ね。演技をして俺を騙した罪もついでに償わさせてやる」
凍夜ははるが演技をしていたことを知っていた。敵国の情報を仕入れるまで俺達はずっと、泳がされていただけだったのだ。
はるは……俺達の目の前で残虐な拷問の末に死んだ。
凍夜ははるを庭に放ると、何事もなかったかのように仕事に出掛けた。桜の花が開け放たれた障子扉から風に舞って散っていった。
「おかっ……おがあさま!」
静夜の絶叫が屋敷に響く。
苦しみながら殺された母親を、吐きながらも見させられた五歳の少女。震えながら、怯えながら、瞬きせずに髪をかきむしる。
わけがわからないだろう。
はるがこのような殺され方をした理由もわからないだろう。
俺は教えていない故に。
静夜は涙を浮かべ、発狂し、失禁し、やがて気を失った。
俺は静夜を丁寧に拭いてやり、部屋の隅に寝かせた。
そして俺はぬくもりのなくなったはるを埋葬する。
俺はなにもできなかった。
守るはずの嫁が暴行されるのをただ、見ていた。
はるの血を丁寧に拭き取り、はるを抱え、風がよく吹く丘に埋めた。憐夜の時もそうだった。
あいつに逆らえなかった。
あいつが憎い。
殺してやりたい。
俺は歯を食い縛り、屋敷に戻った。
次の仕事まで待機だそうだ。
しばらく、ここで過ごさねばならない。
はる……。
はる……。
生物を殺すのは簡単だ。
だが、戻らないのだ。
俺は静かに涙を流した。泣いているところを誰にも見られたくなかったのだ。
男が泣くのは情けない。
そういう時代だ。
こんなに張り裂けそうな気持ちであるのに、大声で泣けないのだ。叫べないのだ。
はる……。
俺は何度もはるを呼ぶ。
はるはもう答えない。
殺されるところを見させられた。致命傷はあの残虐な試し斬りだ。
斬られる寸前に、はるは俺を優しい目で見ていた。
愛おしいその顔はわずかに微笑んで、
「あなたは生きて」
と、声を発せずにそう言った。
また……吐き気がする。
はるはもう戻らない。
もう、ここから先に、はるはいない。
何度でも言う。
殺すのは簡単だ。
だが、戻せない。
戻せないんだっ!
あの笑顔、優しい声音、柔らかい肌もっ……
もう……
「戻せないっ! 戻ってこない!」
歯を食い縛ってこの気持ちに耐える。
はるはもういない。
……もう、悲しむな。
泣くのは終わりだ。
静夜を守らねば。
静夜が幸せになれる道を探さねば……。
俺はそれを心で反芻し、唇を噛みしめて涙を止めた。
七話
そこから静夜は俺を避けるようになった。凍夜が言った言葉を気にしているように見えた。
静夜はわずか五歳で凍夜の使用人になった。
俺が間に介入し、守っているため、凍夜から罰を与えられたことはない。
しかし、静夜ははると違い、納得のいかないことを口にしてしまう。いつ凍夜の怒りに触れるかわからない。
ある日、俺が仕事に出て、短い時間で帰ってくると、鞭の音がした。俺は蒼白になりながら、仕置き部屋に入ると、静夜の尻に鞭を入れている凍夜がいた。
静夜は壁に手をついて動かない。
「あー、更夜か。今日は集会だ。おもしろいものを見せてやろう。お前も出ろ」
「……お父様、それぐらいにしていただけませんか。罰は私が……」
「いいから、集会に出ろ。お前にはこれから長期業務がある。この小娘は俺が立派な下女にしてやる」
凍夜が静夜の血にまみれた尻を強く叩く。
「せ……静夜……」
俺は震えるが、静夜は微動だにしない。しかし、静夜からは凄まじい怒りを感じた。
集会が始まり、凍夜は静夜を男達の前へ晒した。忍達との隣国の戦争についての動きを確認した後、凍夜はにやつきながら、静夜に着物をまくるよう言った。
「こいつは下女であるが、口が悪いのでな、仕置きをしたのだ。どうかな」
凍夜の問いかけに男達はそれぞれ残酷な笑みを浮かべ、静夜を嘲笑した。
「猿だ」
「さっさと殺してしまえ」
「猿が人間と対等に口がきけるか?」
罵倒や嘲笑いが響く中、静夜は泣いていなかった。必死に耐えていた。
故に俺も、怒りを抑え、耐えることにしたのだ。
気分の悪い集会が終わった後、俺は仕置き部屋に静夜を呼び出した。静夜は俺に対し、怯えていた。お仕置きされると思っているのか。
ちがうぞ。
場所がここしかなかったのだ。
唇を噛みしめていたのか、唇から血が滴っている。
俺は一言言いたくて彼女をここに呼んだ。
「……よく耐えた」
俺はそれだけ言った。
静夜は目を見開いた後、目に涙を浮かべた。
俺と静夜は望月と下女。
話しているとまた、はるのように静夜がひどい目にあうかもしれない。俺はそのまま出ていった。
本当は抱きしめてやりたかった。
俺はなんと情けない男だろうか。
俺はまた自分の不甲斐なさと、はるを思い出して静かに泣くのだ。壁に向かい嗚咽を漏らす俺は、さぞ気味悪いだろう。
その時、わずかに物音がした。
俺は我に返り、表情を消すと物音の方を見た。
戸惑った顔の静夜と目があった。
……ああ。
見られていたか。
情けない父の姿を。
「おとうさま……」
静夜はまた、俺をそう呼んだ。
俺は咄嗟に静夜の頬を叩いた。
静夜は床に倒れ、泣きながら頭を床につけ、謝罪をする。
「ごめんなさい! おとうさま」
「静夜!」
俺は厳しく叱る。
叱るしかない。
静夜を守らねば。
「下女が俺をそう呼ぶな!」
俺は静夜を突き放した。
……ダメだ……。
このやり方は……。
娘を不幸にする。
静夜は頭を床にすりつけ、涙を浮かべながらさらに謝罪をする。
「ごめんなさい! ごめんなさい!」
俺はあやまる静夜を無視し、部屋から出た。
静夜を幸せにしたい。
愛してくれる人を探そう。
俺は静夜を育てられない。
俺はまた泣いた。
泣いてばかりの情けない男だ。
静夜は嫁に出そう。
一緒にはいられん。
また失いたくない。
俺はさっそく、仕事に関係していて、雰囲気が優しい武家を探す。我が望月は一応武家だ。
武家と祝言をあげれば、凍夜には怪しまれない。
必死に探していると、木暮家という弱小な武家を見つけた。
隣国ではなく、自国内。
もうすぐ戦が終わる。
ここを生き抜けば幸せになれる。
静夜を木暮に嫁がせる。
八話
凍夜に、仕事で静夜を使いたいと言ったらあっけなく許可がおりた。別の忍一族であり、武家の木暮家は現在、隣国の戦で共闘中であり、ちょうど嫁をほしがっていた。木暮とはやがて戦争終了時に報酬の関係などで揉めるかもしれない。静夜を嫁に出してエサにし、木暮の動きを探る。
と、いうことにしてある。
木暮はこの望月とは違い、温厚で仲間思いの一族。
弱小一族だが、強い。
戦の終わりに俺達、望月に対し、何かを言ってくる確率は低い。
本当はな。
そして、俺の勘は凍夜望月は近々滅亡するというものだ。
戦が終われば、凍夜がやったことが非難されるはずだ。
凍夜のようなやり方は長くはもたない。
はるを含め、女や子供はまるで物のような扱い。
俺は時代に反してそれが許せぬ考えだった。
戦なぞ、終わってしまえ。
狂気に満ちた奴しか出てこないではないか。
人の命が軽すぎる。
俺も……。
簡単に人を殺せるようになってしまった。殺したら戻らない。
殺した人の人生は丸々失くなるのだ。
人生を奪うのは俺だ。
俺は……。
「おとう……さま? あ……ごめんなさい! 更夜さま! 更夜さまでした! 叩かないでください!」
ふと、静夜が俺の手を握り、震えていた。
ああ、今日は静夜の嫁入りのために木暮家に行っている途中だった。
こんなに怯えさせるくらいに俺は静夜を叩いていたのか。
暖かい春の日差しの中、俺は必死だったことを思い出す。
あの屋敷にいるとおかしくなる。
「叩かないでください……」
「……すまない。俺を許さなくてもいいが、沢山傷つけたことをあやまる。すまない」
「……」
静夜は不思議そうに俺を覗き込んだ。
かわいいな。
静夜はかわいい。
俺の自慢の娘なんだ。
当たり前だ。
かわいいに決まっているさ。
「それで……なんだ? 静夜」
「あ……えっと。どこまで歩くのでしょうか……」
静夜はホコリだらけの足を忙しなく動かしながら、俺を不安げに見つめた。
「疲れたか?」
「い、いえ……その……」
俺はまわりの気配を探り、忍がいないかを確認すると、静夜をおぶって歩き出した。
わずか七歳の少女に一月ほど毎日歩かせるのもかわいそうだ。
静夜の足にあわせると、一月ほどかかってしまうからだ。
「……あたたかい背中」
静夜はそうつぶやいて、安心したのか眠ってしまった。
……静夜といられるのも後少しだ。
かわいい俺の娘。
本当に優しい俺の娘。
わかれたくない。
青空に鳥が飛んでいく。
俺はひたすら、農地の道を進む。
どこまでも進む。
夕方、静夜が目覚めた。
毎日気を張っていて、疲れていたんだろう。
「あっ! ごめんなさい! えと……更夜……さま」
「起きたか。今日は遅い故、近くの村に寄るか。金はある故な」
「え……あ……私、歩けます」
静夜が夜でも歩くと言ってきたが、俺は「ダメだ」と言っておいた。
夜は静夜に子守歌を歌ってやった。以前は大泣きしてはるに助けを求めたが、今は健やかに眠っている。
はるに似ている顔で眠る静夜。
俺になんか似なくていい。
本当は、お父様と呼んでほしいのだ。俺は父でいたいのだ。
俺の娘が、俺を様付けで呼ぶなどおかしな話ではないか。
凍夜がそうさせたのだ。
俺はあの男を恨む。
夜になるといつも、俺はあの男に憎悪するのだ。
次の日、木暮の里がある山道に入った。俺は静夜を抱き抱えて、道なき道を歩く。
「……私は捨てられるのでしょうか?」
静夜は嫁入りを理解できていなかったのか、不安げな表情を向けた。
「いや、捨てるわけないだろう。お前は希望だ。大切にしてくださるおうちに行くのだ。俺にはお前を守る力がない故な」
俺は言っていて悲しくなった。
なんと、情けない。
娘も守れないのか。
妻も守れなかったくせに。
「更夜さま、ありがとうございました。私は沢山守られましたよ。身体に傷がないまま、宝物のように育ててくださいました。感謝しかないです」
「静夜……」
俺は何か言おうとしたが、何も言えなかった。
山を登ると屋敷があった。
あれか。
平坦の道に静夜をおろし、手を引いて歩いた。
屋敷は望月の半分もなかった。
門をくぐると、子供達が楽しそうに遊んでいた。
「子供が……遊んでいる」
俺は目を疑った。
俺達の世界ではあり得ない光景だ。しばらく、呆然としていた俺に、女が話しかけてきた。
「あら、あなた様がもしや……」
「ええ……はい。望月家でございます。我が望月は貧乏故、輿入れもまともにできませんでしたが、静夜を連れて参りました」
俺は嘘をつきながら、笑顔を向ける。演技だ。
「まあ! かわいらしいお姫様。私は下女でございます故、旦那様と婿様と奥様を連れて参りますね」
……下女……。
俺達の下女とは違う。
まるで、家族のようだ。
俺は去っていく女の背中を見据え、目を閉じた。
すぐに男二人と女が出てきた。
「望月静夜様と更夜様ですか。遠いところ、お疲れ様でございました。木暮行政(ゆきまさ)でございます。そして、息子の政伸(まさのぶ)です」
旦那だと思われる男が優しげに笑う。その横にいた青年は顔を赤くして目を泳がせていた。
「妻の千代(ちよ)です」
女も幸せそうに笑っていた。
何もかも違った。
「……静夜……」
俺も自然に優しげな顔になり、静夜の背中を押した。
これで終わりだ。
俺と娘の関係も終わりだ……。
「最後に……お父様と呼んでくれないか。静夜」
俺は最後に、静夜の父でいたかった。静夜は目を見開いて驚いていたが、やがて笑顔で
「おとうさま、大好きです」
と、言葉をこぼした。
自然と涙が溢れた。
本当は一緒にいたかった。
七歳の娘をはると三人で育ててやりたかった。
「すまない……静夜……。俺は……」
俺は呼吸を整え、最後の言葉を発する。
「俺は……何もしてやれなかったが、静夜は俺の自慢のっ……。……あなたは俺の自慢の娘だ。静夜、愛している」
なんとか言葉を伝え、俺は頭を下げた。
「静夜をよろしく……お願いします」
「静夜、素敵なお父様だな! これから俺と木暮を守ろう」
息子の政伸が顔を真っ赤にして静夜の手をとった。
静夜の頬も赤く染まった。
「もうしばらく、こちらで過ごされますか?」
木暮の妻の千代がそう言ったが、俺は断った。
「離れられなくなる故、私はこれで失礼いたします。木暮と望月が良好な関係を保たせられるよう、力を尽くします」
「そうでございますか……。こちらこそ、よろしくお願いいたします」
木暮の家長に俺は頭を下げると、足早にその場を去った。
……俺はもう死んでもかまわない。
もうひとりの娘の墓を作りにいこう。
鈴……。
俺が殺した娘の名。
最後の仕事だ。
俺はもう、望月を抜ける。
最終話
俺は仕事を無視して遠方へ出掛けた。
凍夜に出会わなければ怖くはない。強制的に逆らえなくならなければ、自由だ。
敵国との戦は終わったが、あちらこちらで収まらない者達が、行き場のない怒りを罪のない者達に向けている。
人を殺すことに慣れた者は人を人だと思わない。
子供を平気で串刺しにして晒し、女を性的玩具にし、殺す。
泣けば泣くほど男達の残虐性が増し、見ていられないほどだ。
男達は気に入らなければ喧嘩をし、負けた相手を容赦なく殺す。
……なんなのだろう。
この世界はなんなのだろう。
はるは犠牲になった。
この残酷な世界の犠牲に。
そして……。
俺はある山の中腹で開けた場所を見つけた。
「ここがいい。光りも当たり、美しい場所だ」
俺は無我夢中で土を掘った。
泥だらけになりながら、太い木の枝をさし、また土を被せて墓を作った。
その後、きれいな花を探す。
日が陰る頃、名もなき白い花を見つける。白い花は健気に咲いており、この場所にしかなかった。
「かわいい花だ」
俺はまた泣いた。
たまらなく悲しかった。
この気持ちはなんなのだろう。
「かわいい花だなあ……」
泥だらけの手で泣きながら白い花を摘む。元々目が悪い故、かわいいかどうか実際にはよくわからない。
俺の人生は……なんだったんだ。
妻を惨殺され、娘を守れず、娘と重なった少女を殺した。
不幸しか呼んでいないではないか。
彼女達はこの花だった。
それを摘んだのは俺だ。
俺は小さな花を片手に、墓を作った場所まで戻った。
俺はひとりだ。
花を添えて手を合わせる。
ここには鈴が眠る。
なにもないが、俺が決めた。
「お前はどんな花が好きだ? 女の子なんだから……何かあるだろう?」
ぶっきらぼうに俺は問いかける。俺は話すのが苦手なのだ。
「俺は柔らかい表情ができない。……お前にどういう顔をしたらいいかわからない。俺はもう色々と疲れた。……俺が向こうへ行った時、今度は上手に俺を殺せるぞ。鈴」
もう、俺はここを動かない。
俺にはもう、なにもないのだ。
ひとりで鈴に話しかけ続けた。
鈴は答えない。
はるの墓の前で話したのと同じだ。
答えてはくれない。
しばらくしたある日、俺の前に武家屋敷で同僚だった栄次が現れた。彼は時神らしいのだが、この時の俺はもちろん知らない。
人に溶け込み、時間の監視をしているのだとか。
栄次は俺が殺した敵国の殿の追手だ。俺を殺しに来たか。
「更夜か……」
栄次が迷った顔で俺を見ていた。こいつもやりたくないんだろう。
「追手とはお前か。栄次。そうだとは思ったがな」
屋敷では演技をしていたが、もう隠す必要もない。
「お前を殺さないといけなくなってしまった」
彼は静かにそう言った。
「ああ、知ってる」
俺は笑った。
残酷な笑みを向けた。
俺も行き場のない怒りをぶつける所がほしかった。
こいつを殺してやる。
俺ももう、まともではない。
結果的に俺は負けた。
鈴の墓を守って死んだんだ。
悲しげな顔をするな、栄次。
俺はもういいんだ。
人前では泣けない。
笑って死のう。
炎に焼かれて苦しんで死ぬか。
俺は身体に火を放つ。
ああ……熱いな。
はるは……静夜は……鈴は……
もっと辛かったんだ。
だんだんと暗くなっていく。
「更夜様……」
最期にはるの声が聞こえた。
「更夜様、鈴さんの方へ……行ってやってくださいまし」
「なぜ、はるが鈴を……」
気がついた時、俺は天にいた。
夜空の中を浮いていた。
ここは宇宙と言うそうだ。
死後の世界、弐(に)の世界……。
俺の生はまだ続いていたのだった。
旧作(2021完)TOKIの神秘録四部「折られた可憐な花」


