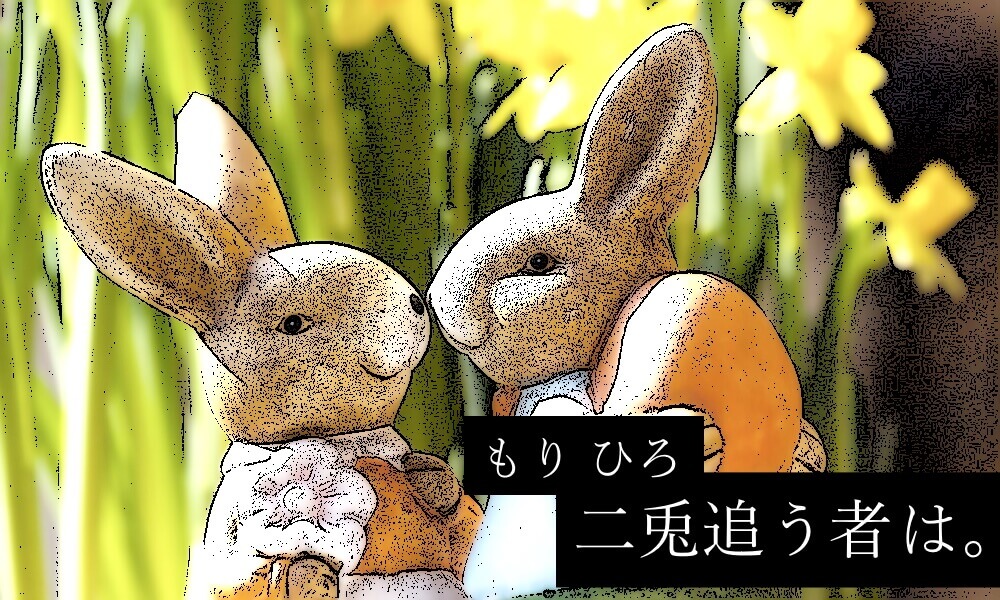
二兎追う者は。
二兎追う者は。
正直、今日のデートは退屈だった。
相手の名前は年上の実業家K。収入は、わたしの何倍あるかわからない。何倍? いや、何十倍かも。
大学院在学中に投資で成功して、それを元手に会社を立ち上げるなどして富を得た。彼が言うには、テレビで取り上げられたこともあるらしい。
身に着けているものは、わたしが知らないような高級ブランド品。彼がその一つ一つを語ろうとも、わたしにはよくわからなかった。
住んでいる場所も、都内の某高級マンション。泊めてもらった時はなんだか落ち着かなくて、感じるものも感じなかった。演技をして、いつも以上に激しく喘いでも、どこか頭の中で現実的なことを考え続けていた覚えがある。
見た目だって。まるでハーフのような整った顔立ちで、すらっと背が高い。細身だけれど、なんだか高級なジムに通っていて、脱げば筋肉が隆々としている。髪型だって、自身に一番似合うものをわかっているようだった。イタリア製のジャケットが似合う容姿。
隣に並んで歩けば、羨望の目を向けられる。それが、心地よかった。
まるでアクセサリーみたい。
だけれど、アクセサリーとは根本的に違う。
アクセサリーは持ち主を引き立てるもの。なのに、彼はわたしを引き立てるどころか、わたしよりも目立っている。隣にいると、なんだか惨めな気持ちになることもある。
そんな彼が、わたしに好意を寄せてくれている。何度だって、愛を囁かれた。毎日、毎日、わたしを愛していると語ってくれる。
わたしと彼は絶対にアンバランスだ。彼のことをどこまで信じていいのかも、正直わからない。
なのに、彼に惹かれている。世間的に見て「イケメン」と称される容姿も、生活に困ることのない収入も、わたしへの想いも、全て含めて彼が欲しい。
だけれど、全てを彼に向けることができない。
◇
それは、年下男子Yの存在があるからだ。
Yと出会ったのは、駅裏の汚い居酒屋。彼は、一本のハツ串を一つずつ丁寧に食べながら、ホッピーをちびちび舐めていた。
そんな彼に声をかけたのは、わたしからだった。
彼はまだ大学生で、近所のオンボロアパートに住んでいる。たびたび、電気を止められてしまい、そのたびにわたしの家に彼を招き入れた。
初めて彼がわたしの部屋に来た日。彼にとって初めての異性の部屋だった。そわそわと落ち着かない彼に口づけをし、そのままソファに押し倒した。
「ぼく、こういうの初めてなんです」
小さな声で恥ずかしそうに告げる彼が愛らしかった。
彼の耳たぶを咥えるだけで、彼の下半身が固くいきり立つのがわかって、それを弄べば彼が女の子みたいに反応して、それが気持ち良かった。
それ以降、幾度となく彼を家に招き入れてきたのだ。
もちろん、夜のことだけではない。
昼間だって、ちゃんとしたデートをしてきた。彼が好きだという絵画を鑑賞しに美術館を訪れたり、隠れ家的な喫茶店で大人びた味の珈琲を味わったり、時には動物園のふれあいコーナーで子供みたいにはしゃいだり。
デートを重ねるたびに、彼の心が少しづつ開いていくのが分かった。そうして、慣れていくのも感じた。
セックスを覚えた彼は、あのウブな挙動を示さなくなった。それでも、わたしはあの手この手で、彼のハジメテを探した。そのたびに彼が見せる恥じらいのある表情や仕草、言動は、わたしの性感帯。
そんな彼に抱く感情は、恋心なのか、それとも母性なのか。
彼がわたしに甘えてくれるのは嬉しい。それが心地よくて甘やかしてしまう。
だけど、わたしだって甘えたくなることがある。
◇
仕事の失敗で落ち込んでいる時は、Kに想いを打ち明ける。
彼には、いわゆる「大人の余裕」がある。だから、わたしも安心して想いを吐き出すことができるのだ。
わたしが告げた言葉を彼は受け止めてくれる。そうして、「大丈夫だよ」と言ってくれる。彼が大丈夫と言えば、自然と気持ちが落ち着く。
どれだけわたしが不機嫌でも、彼は怒ったりしない。わたしが彼に当たってしまっても。
甘やかされているのだ。
それに、甘んじているわたし。
良い関係性だとは思わない。だけれど、彼に甘えられるから自分を保つことができる。
彼を都合よく利用している自覚はある。それでも、今のわたしには彼が必要なのだ。彼無しで自分が自分として過ごせる自信がない。
彼にとって、わたしは一体、何者なのだろうと不安になることがある。
愛されてはいないのだろうか。愛してもいない人の不安の吐露を、人は受け入れることができるのだろうか。
そんな感情の時にYが言ってくれる「好きです」という言葉は、素直に染み込んでいく。
照れ臭そうに愛を告げてくれる彼が愛おしい。彼の言葉に対して、わたしも素直に「好きよ」と伝えることができる。
わたしの気持ちが落ちているのを察して、ドライブに連れて行ってくれる。まだ大学生でお金なんてないのに、無理して買った小さくて可愛いスポーツカーで、夜景を見に連れて行ってくれるのだ。
首都高の流れる摩天楼。街灯が寂しげな田舎道。そして、遠くに輝く街の夜景。
寒いねって言いながら、自動販売機で買った缶コーヒーを飲む。彼の冷たい手を、わたしの手で包み込む。「手、あったかいね」ってハニカんでいる彼に口づけをする。
何度も何度も口づけをして、「夜景見るよりも、チューしている時間の方が長いね」って笑い合う。
彼が若いから、なのだろうか。まるで、自分たちが高校生になったみたいな感覚になる。
そんな刺激的な時間なんて、Kには演出できない。
◇
わたしは、二人のうちのどちらかなんて選ぶことができない。
それぞれに惹かれている。全く真逆な存在だからこそ、どちらもが良く見えてしまうのだ。
二人を足して、二で割ってくれたらいいのに。なんて、非現実的なことも考える。
だからわたしは、二人のちょうど間くらいの、バランスが取れた男性教師Tを選ぼうと思う。
二兎追う者は、三兎目を得る。これ、わたしの座右の銘。
二兎追う者は。


