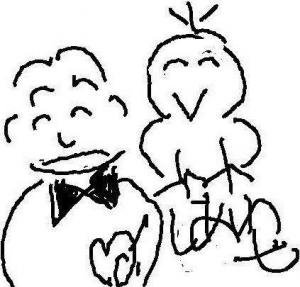書庫いっぱいの愛を
書庫いっぱいの愛を
一
あなたにとって本とは、どんな存在でしょう――。
何度耳にした言葉だろう。
事務所のソファを占拠して、面接を受けている女は、見たところ……三十の峠を越えたか越えないくらい。
「無くてはならないものですぅ」
まただ。書店面接の模範回答。と言うより、当たり障りのない返し。
確かに書店員には、読書が好きな人は多い。新作を読むのも、作家さんについての知識を得るのも、仕事というか、役割と言うか、使命だから。
だけど、だからと言って、読書好きが書店員に向いているかと言えば、決してそうではないと、わたしは言い切る。本への興味などより、時給と業務内容への関心の方がはるかに重要だから。
昔つきあっていた彼も、
――知ってるか、春子。ポッポ屋 (駅員さん) って、実はテッちゃん(鉄道マニア) ってそう多くはないんだ。何でか分かる? 客商売だからさ。客より電車じゃ困るだろ。だから就職試験前に、いかにテッちゃん臭を消せるかが合否のポイント……もちろんぼくはテッちゃんではないけどね。
訊かれもしないことを付け足して、そんな事を話していたし。
「何か聞きたいことは?」
ふうー。やっと帰ってくれる。休憩時間は残り六分。ソファでゴロゴロ、できるかも。
「ええっとお。やっぱり本屋さんってえ、本に詳しくないとお、いけないんですぅ?」
余計なこと聞くなよなあ。終わらせたいんだよ、店長は。分かってないな。
「詳しいに越したことはないけど、ネットの話題に乗り遅れなければ大丈夫。心配ないよ」
はい? 『流行を作るのは我々』 『ベストセラー作家を生みだすのは僕らだ』 なんて言ってるくせに何よ。下心丸出し。みっともないったらありゃしない。
「そうなんですねえ~。安心しましたあ」
出た出た。そうなんですねー。もろ手を挙げて 「リアリィ!?」 「アメージング!」 って称賛できないタイプ。先週来た 「へえー」 よりはまだいいけど。接客業には向かないな。
それはそうと、書店員は本に詳しい。と世間は思い込んでいるようだけど、それは微妙。確かに、小説や児童書や実用書などの特定分野に、やたらと詳しい人もいるにはいる。が、それらの本は出版物の一部に過ぎない。お客の中には、医学や化学や地政学や、鉄道車両の構造やら、性交についてのハウツー本の中身に至るまで、詳しく訊いてくる人も少なくないから “私、詳しい” と思った時点で書店員失格。 「それ面白いですよ」 などと自分の価値観で薦めるのは以ての外。どうしてもアドバイスするとするなら、 「直感を信じて買え」 「出版されるだけの価値と評価を信じて勇断を下せ」 以外にない。
「来月からね。いいよ。丁度ひとり辞めることになってるから」
採用? 辞めるって、誰だろう。
フルタイムのバイト君ではない。正社員なら、代わりの人がもう来ていてもいいはず。と言うことは、パートの誰かだ。
あらいけない。また打ち間違えるとこだった。発注部数を。先々月は、どえらいことをやらかしちゃったもんなあ。同じ轍を踏んづけるとこだった。って、まさか……。
いやいや、あり得ない。社員の仕事を唯一任され、お客様アンケートでは社員を差し置いて好印象ナンバーワン、我が子を養子に出す思いで本をお売りしているわたしが、クビになろうはずがない。
きっと 「売ってやってる臭」 露わの片手間おばさんか、 「お化粧崩れちゃうからあ」 とか言い訳にもならない言い訳をして重たい物を持とうとしない小娘か。流れ作業のように 「客をさばく」 ことしか考えない四捨五入すれば四十路女。三人のうちの誰か。接客業でありサービス業であり、労務者だという自覚がないんだよな、あいつらは。
「それでは、よろしくお願いしますぅ」 しゅう~。
「よろしく」
採用か。仕方ない、しっかり教えてやるわよ。本屋の掟を。 書店員の心構えを。あるべき姿を。
「朝日くん」
来た。教育担当のご指名。
「言いづらいんだけどね」
やっぱり。わたしだあ。
二
出版業界が不況というのは確かじゃろう。が、本離れという噂には同意し兼ねる。
こと、わしのように図書館へ入り浸る者や、ここで働く職員は、大盛況と思っているに違いない。
九時三十二分。開館から二分遅れで入館。
三階の目的地まで手摺を使わずに、階段を踏破し、弾んだ息が整い次第入室。まっすぐ自動検索機へ向かう。
「おはようございますぅ」
「ん」
床に向かって挨拶する人間にはこれで十分。いっそのこと声など掛けて貰わん方が、よほど気分がよいわ。
九時四十分三十七秒。
今朝は十二、三秒遅れといったところか。ま、梅雨の走りの鬱陶しさのせいもある。気にせんでおくこととして、
「何か。お探しの本でも」
「ん?」
お、目が合うしもうた。お探しの本があるから、検索するんじゃろうが。
気になる視線を無視して、画面に食い入る。
ピコ。ピコ。ピ。ピ。
ふむ。どうしてじゃ、なぜ仕事をしようとせん。
書庫に幽閉された戦争モノの児童書は、九割方梗概が書かれておらぬ。なので困った。
「何かご不明なことがあれば」
しつこい。小娘如きに何が分かる。まさかわしを、暇つぶしにきた気の毒じいさん呼ばわりするつもりでは、
「ご遠慮なく。なんなりと」
お節介な娘。じゃが、むすっとした迷惑顔を向けられるより気分はよい。悪くはない。決して語らいたいわけではないが、
「書庫、見られんかの」
タイトルと著者名だけでは、目当ての本に巡り合えんのじゃ。
「申しわけございませんが、それは……」
「無理。か」
「お持ちします、借りなくても大丈夫ですから」
本のイロハも知らないひよっ子のくせしよって。親切心の受け売りか。
ピコ、ピコ、ピッ、ピピッ。
せっかく来たんじゃ、直感で。
ピコ。ピ、ピ、ピッ。
画面の下方にある、タイトルだけで選んだ書籍の “書庫請求” ボタンを押す。 「ぽち」
うぃーん――
硯大のプリンターから請求用紙が排出される。
うん。まずは一枚。手を伸ばす、
「ご用意してきます」
請求用紙を横取りした娘がそそくさと歩き出す。
「まだ終わっとらん」
ち。余計なことを。
嬉しかった。決して若くは見えないが、あんな女子に介護されたらどんなに幸せじゃろう。つい、そんな事を思料してしまう。
「お預かりしておきますか」
なな、なんという速さ。書庫に辿り着くには、カウンターをぐるりとまわり、障害物のように立ちはだかるテーブルや椅子や、赤ん坊を抱えたママさんをすり抜け、検索機からもっとも遠い 「関係者以外立入禁止」 の扉を開けねばならない上にじゃ。学校の教室よりひと回り大きいと聞く書庫の中から一冊の本を捜し出す、苦行を成し遂げねばならぬと言うのに。信じられん。正に奇跡。
「日中戦争がテーマの児童書にご興味が?」
なにい!?
巷の図書館にある戦争モノの児童書は、原爆投下の惨状や沖縄の激戦、学童疎開がらみが主流で、それらはすでに読破ずみ。タイトルだけで我が心中を読み取ったとすれば、それもまた奇跡。まさか、そんなはずは……
「それとも、太平洋戦争全般を?」
うぅむむ。判断でき兼ねる。
「明治維新以後からのものでしたら――」
もしやこの娘、ホンモノの読書人。しかも、消えゆく運命にある児童書を救わんとする救世主。 「書庫マニア」 ではあるまいな。或いは 「絶版もの狂」 の可能性も。
「あのう……この本にまとめて書かれています。戦争関連の児童書のことが」
いやいや参った。時代とテーマ別に書かれたお勧め児童書のバイブル。よくぞご存じで。
「持っておる」
「やっぱり。そんな気がしてたんですぅ」
そこに掲載のあるものは、たとえ一時とは言え、陽の目を見た本。じゃが、わし所有のものより新しそうだ。受け取っておくか。
「ありがとう」
この娘の目には愛がある。本に注ぐ愛が。
三
天職かもしれない。転職して大正解。
図書館で働き始めて三か月。通勤途上で見つけたおナスは、やさしい紫色の花をつけ、窓下に見える公園は、色とりどりのアジサイとよちよち歩きの子供たちで、元気いっぱい。クスノキに隠れて見えないけれど、片隅にある噴水つきの人工池には、ヒヨコみたいなカルガモちびちゃんが、お母さんの後ろを一所懸命泳いでる。この町で暮らし始めて五年。初めてかもしれない。季節の恵みを感じられたの。幸せを実感できたのは。
ここには、陳列棚にへばりついて動こうとしない盗み読みする人もいなければ、そいつをなんとかしろ! なんて怒鳴り出す人もいない。本を放り投げるヤツも。書店員の態度についてネット攻撃する、誰かさんも。今となっては、本屋で働いたトータル十五年間が無駄、とは言わないけれど 「なんだったの」 って感じ。接遇も知識も見習うことばかりだし。こんなに幸せでいいのかしら……。
「ええ~。と言うことで、本日も、市民の皆様の立場に立って、接遇には十分留意し、おもてなしの心を忘れずに、頑張ってまいりましょう」
「はい!」
ふつうにやればいいのよ。ふつうに。
「ええ~。朝日さん。事務所まで。宜しいでしょうか」
「え、はい」
もう開館だっていうのに。何だろう。
慎重すぎるほど慎重に階段を下りる、係長の後に付き従い、二階の事務所に入ると。
「ええ~。いかがしょう。慣れましたでしょうか」
そっか。あれだ。正式採用のこと。研修期間終わるから。
「まあ。雰囲気と仕事の流れくらいは」
うんうん。――そうでしょう。そうでしょう。
「わたくしから見れば、すっかりベテランです。いい仕事ぶりです。市民の皆様も、大変喜んでおられます。はい」
「いえいえ。そんな」
ここに缶詰のあなたが、わたしの何を見ているのでしょう。ま、言われれば嬉しいですけど。
「ええ~。とても三か月とは、思えません。朝日さんの仕事ぶりは。ええ」
今言ったでしょうに。それより早くして。市民の皆さまがお待ちになっておられるのだから。 「それで何か?」
「ええ~。実はですね。異動をお願いしたいと、思いまして。はい」
「異動! ですか」
何じゃそりゃ。あり得ないでしょ、三か月で異動だなんて。
「研修のようなものですから。三階の仕事は。はい」
はい? 子供やママさんたちを相手にするのが研修? だとお?
「弓木さんや福田さんは三年以上働いてると聞きました。このまま三階で働いていたいです」
主張しないと。現代の日本では生きていけない。
「戦力となる人材は最前線で汗を流す。それがわたくしの方針でして。朝日さんを後方任務につかせたままでは、市民の皆様の為になりません。あなたには二階でご活躍頂きたい」
散りてぞ生くる桜花――
昨日読み終えた戦記を思い出す。 「最前線で血を流してこい。」 「皇国の盾となり、潔く散ってまいります。」
でも、
「先ほど 『お願い』 って、おっしゃいましたよね」
戦わずしては死ねない。もちろん自分の為でも御国の為でもない。義の為にだ。
「ええ~。現段階では、お願いになります。はい。口頭ですから」
書面で辞令が下りれば、言葉は悪いが 「命令」。 ややこしい。本屋の店長みたいに 「来月から来なくて、」 もとい、 「来月から二階を頼むよ」 って言ってくれた方がよっぽど分かり易いし、切り替えられるのに。
でも、仕方ないか。組織ってそういうものだから。やり方も言い方もヘンだけど。
「分かりました」
「ええ~。では本日から」
おい!
「今日から!?」
って。早く言えよ。
四
ξ×∂×Ψ×ζ×――×!
「申し訳ございませんっ」
「詫びるくらいなら初めから、×δ×ゑ×ξ×ζ××!」
あれえ? おじさん?
周りの目などお構いなしに喚いているのは、確かにおじさん。二階に異動になってしばらく会えなかったけど、間違いない。 “九時四十分” おじさんだ。
あら。あららら。
警備員さん登場。あれじゃ、店員さんがへこへこしていなければ万引き犯じゃない。
タタタタ、スタタタタ――
「何かあったんですか!?」 わたしこういうの、放っておけない。
「口を挟むな」
?。
うわあ……
おじさんの愁眉が開いて、スローモーション動画のように泣き笑いの顔に。おじさんから大人に……青年に……少年に……時空を超えて、男の子に。
「どうしたんです?」
「ぼ、わしは間違っとらん」
おじさんの話によれば、長蛇のレジで、ご婦人がマイバッグを差し出したのが事の発端。レジ係に商品を詰めさせる行為に腹を立てたらしい。
みんな自分で “手提げ袋” に詰めているのに。なんじゃ!
レジ袋には詰めないくせに。なんじゃ!
手足が不自由というわけではないのに。何様のつもりじゃ!
云々。
「やらせる方もやらせる方じゃが応じる方も応じる方じゃっ」
「はぃ……」
それなら、わたしにみたいに、セルフレジを使えばいいのに。一瞬そう思ったけど、それも違う気がする。おじさんは 「根っこ」 のところを正したいのだ。
「いい歳して偉そうにするなっ。神様にでもなったつもりか!」
サービス業を生業としてきた者として、おじさんの気持 (言い分) はよくわかる。コソッと頷いた (ように見えた) 副店長さんも同じ気持のはず。でも 「いい歳して」 はちょっと言い過ぎ。
「あんたの様な親に育てられた子供は不幸だ!」
おじさん言い過ぎを畳みかける。
「きぃーっ。ウチの息子は厚労省よ! 国民の為に働くとっても思いやりのある優秀な子に育てたのはこの私、何も知らないくせに勝手なこと言わないで!」
一まわりも二まわりも余計に生きた人生の先輩を、悪く言う気はないけれど、何かを武器にしようとする神様の味方にはなれない。
「それほどご立派なら子息を見習え。子供に恥をかかせるな」
言われてしまった。いいぞ九時四十分!
「んまあ。あたくしの何を知っていてそんな、」
まあまあまあ。言い返そうとする婦人に副店長が割って入る。おじさんのTKO、テクニカルノックアウト勝ちだ。
「二階に異動になったものですから」
「………」
先刻までの剣幕はどこ吹く風。おじさんは貝になってしまった。マイバッ、手提げ袋の底に入れたシジミみたいに。
「二階に異動に、」
「本、売っとった」
? ええ?
「九時四、ううんっ。おじさんも書店員だったんですね。わたしも本屋で働いてたんですう」
喜んでくれるかと思ったけど、また貝に。
「どちらで? 今度からおじさんのお店で買います」
「古本じゃ。もうやめた」 “売っとった” と言ったはずじゃ。そんな顔。
「あ、やめちゃったんですね。わたしもやめちゃったんですけど、駅ビルの本屋にいたんです」
………
貝の口を開こうと試みてみたけど、反応なし。打ち解けるには、
「朝日春子です」
先ずは自己紹介から。
「朝陽、春子と」
「ええ。おじさんは?」
「……君が咲く……朝の陽ざしに……朝の陽ざしよ……朝の陽ざしは……春うらら」
「?」
わたしのことを詠んだのだろうか。麗らでは全然ないけど。
「おじさんのお名前は?」
「朝陽春子……」
それはわたし。
「おじさ、」
「荒井庸二郎。荒いに井戸の井、難しい方のもちいるを書いてタロージローのジロー。漢数字の二郎」
「……そうなんですねえ。難しいもちいるって」
漢字には自信があった。でも、そこそこの自信では分からなかった。
「庸才 (ようさい)のヨウ」
「……?」
「庸人 (ようじん)のヨウ。ようとく(庸徳)のヨウ」
「………」
「漢和辞典に出ておる」
やっぱりがんこ。と思ったけど、九時四十分、もとい。荒井さんは手帳を出して書いてくれた。健康の康のちょんちょん四つのところに、簡単な方の用いるを書く。さすがは荒井さんと思ったけど、自分の字なんだから、説明できて当たり前。
「まだ持っとる。山ほどある。カビなど生えておらん」
荒井さんは話を戻したもよう。どうも噛み合わない。
「新品同様じゃないと売れませんものね。今の時代」
「喉をやられる。呼吸器系を。病気は大敵。孤独死に直結する」
そっちか。でも真剣なお話。真剣に聞かないと。
「漢和辞典。やつは面白い。いや深い」
またまた話しが跳ぶ。
「どちらで本屋さんを?」
わたし話戻す。
「山ほどある。すぐそこに。歩いて五分。いや十分」
二倍も違うじゃない。ツッコミを入れようと思ったけど、もしかして、これってお誘い?
「行くか」
けっこう強引。返事も聞かずに歩き出してしまった。手提げ袋を大きく揺らして。
五
国道の長い横断歩道を渡り切って、マンションの裏通りをしばらく進むと、
「うわあ。のどかあ」
同じ市内とは思えない景色が広がっていた。じんめりした初夏の暑さも忘れてしまうほど。
この町にくる前のわたしは、走って二十秒で千葉という、東京の東端で暮らしていた。十年間事務員として働いていた鉄工所の倒産を機に、新宿の本屋を転職先に選んだのは、一念発起、生活を変えたかったから。
通勤地獄と単調な独身生活でうつ病を発症したわたしは、病気を克服すべく本屋を退社し、またまた一念発起、この町にやってきたのだけど……。
この町は、山も星も見えなければ、月はぼんやり、緑はちょこっと。流れのある川には出会えず、荒井さんも店を構えていた人情商店街は、人情もろとも取り壊されて、五年経った今はタワーマンションが屹立するだけ。おまけに誰も彼もがぎすぎすつんつん。
たぶん住めば都にはならないだろうけど、この風光明媚な景色を拠り所に、うつの再発は抑え込めるかも、
「そこ」
え?
広大な芝生と三角屋根の温室が二棟と、その横に農機具置き場があるだけなんだけど。人が住めそうなのは……線路を越えた遙か先に米粒大の高層マンションがあるくらい。どこがソコなんだろう。
「えぇーと」
二つ折りの財布からカードを取り出した荒井さんが、
「どうかなさいました?」
どうかしちゃったようだ。
「番号忘れた」
やっぱり。荒井さんの言う 「ソコ」 はここ。ガラス温室だ。と言うことは、農機具置き場にしか見えないあれがお家?
「ここから通っていたんですね。図書館まで」
「何じゃったか」
温室に入る為にはカードリーダーを通して、かつ暗証番号を入力する必要があるらしい。
「毎月変えねばならんから」
番号を忘れた言い訳をする荒井さんは、口を尖らす男の子。
「誕生日とか記念日とか。住所とか。車のナンバーとか」
「そういうのは駄目だって言うんじゃ」
「手帳に書いてあるとか」
「不用心じゃろ。紛失したら」
記憶に頼るのも不用心だと思うけど。
「本はどちらに?」
「それじゃ」
うんうんうん。荒井さん、歯を剝き出して喜ぶ。本に関係する数字らしい。
「武者小路のアレに、夏目のアレと、大岡のアレを語呂合わせ――」
ピィー。ロック解除。
ふうぅ。安堵した可愛いらしい笑顔に、わたしも嬉しくなる。
わたしが住んでるアパートが、すっぽり収まりそうな温室は、初夏だというのにヒンヤリしていて、空気が澄んでとってもきれい。ガラス面に張り巡らされた遮光ネットが日差しを遮り、勿体ない気もするけど、
「いまは農家さんなんですね。荒井さん」
「弟がやっとったのを引き継いだ」
「やっとた」
「やっておった」
「そうじゃなくって弟さんは、」
「死んだ」
「ヤダっ」 何これ。
温室の端から端まで伸びる網状の作業台に、遠い昔理科室で見たフラスコが、澱みなく並んでいる。
「メリ、クローン」
外来語が嫌いな荒井さんがにべもなく言う。
「クローンって……」
フラスコの中に “いる” カイワレ大根にしか見えないモノが、成長するにつれて……
「やあこんにちは、初めまして。ぼくは弟の〇〇――」
弟さんを復活させようとしているとかっ!? クローン技術をつかって。
「メ・リ・ク・ロ・ン」
荒井さん曰くメリクロンとは、植物の根や茎にある生長点 (細胞分裂をするところ) を取り出して、培地 (細菌の培養に使う液体に “かんてん” を加えて作ったもの) で培養させることを言い、雑菌の侵入を防ぐためにフラスコを使うのだそうだ。因みに業界では 「メリクロン (苗)」 で通っているらしいが、正しくはメリクローン。なあんだ。間違っていないじゃの。カイワレが人間になること以外は。
「フラスコが保育器で、カイワレが赤ちゃんみたいなものですね」
「お前さんがそう思うならそうじゃろ」
ならそう思うことにして、フラスコの反対側の作業台にある “将棋盤” のようなモノが気になる。
「お向かいのそれって」
フラスコ内の赤ちゃん苗を、取り出したモノみたいだけど。
「シーピーじゃ」
またまた外来語。荒井さんは別棟の温室に向かって顎をしゃくる。
「シーピー出し」
なあんだ、これでお出汁をつくるのか。それならそうと早く、
「シーピーから出したもの」
お出汁ではなかった。将棋盤に見えたモノは、CP(コンパクトポット=小さな鉢の略)と呼ぶそうで、保育器から出た赤ちゃん用のベッドか揺れないゆりかごと、勝手に解釈。
つまり荒井さんは、フラスコでクローン苗を仕入れて、将棋盤のマス目のようなCPで赤ちゃん苗を育てて、別棟の温室で鉢に植え替えて、一人前の大人苗に成長させる仕事を、しているのだそうだ。
「ところで何を、」
歩き出してしまった。
チャッ。チャッ。チャッ。歩くたびに音がするのは、地面に植木鉢の破片が敷き詰められているからだ。
「雑草よけじゃ」
なるほど。でも、この程度のことで生えてこないのだろうか。しつこい雑草が。
「光合成じゃよ」
光を遮断し水と酸素を摂取させずに、成長させない。すごい知識。でも園芸のプロなんだから知っていて当然。それより、訊きもしないのに答えてしまう荒井さんに、わたしは驚いた。
「防犯効果も」
やっぱりただの偶然。そこまでは考えていなかったもの。
「そうなんですねえ。防犯砂利を買うよりよっぽど安上がり、ううんっ。良いですもんね」
でも、防犯効果を狙うなら外でしょ。でも、完璧な防犯システムがあるわけし、ゴルフ場みたいな芝生の景観を損ねちゃうから、これはこれで、
「芝も売っとる」
ちょ、ちょっと、どうして? 荒井さんが異世人に思えてきた。どうして分かるの?
「胡蝶蘭じゃよ」
話が大きく迂回の末にようやく回答。遮光ネットの向こう。隣り合う温室には、幾重にも重なった厚手の葉があるだけの 「コチョウラン」 が見える。
コチョウランは、開店祝いや政治家さんの事務所にある 「蝶」 というより、お雛さまの顔 (頭部) がずらりと並んだ (ように見える) 高価なお花。
荒井さんが成長させたコチョウランは、花を咲かせて出荷するまでの工程を担う、別の農家さんに出荷するそう。
なので、長くこの仕事をしている荒井さん自身、花の咲いたコチョウランを見ることは、ふつうに無いらしい。
「切なくありません? せっかく育てたのに」
なあにぃ。荒井さんの頭がロボットみたいにこちらに向く。
「過程が大事なんじゃ。咲くまでの過程が」
確かに。成長させなければ花は咲かない。でも、花を咲かせるために成長させるとは、言えないだろうか。
「せっかく育てたからこそ、見たくありません?」
「分かっとらんの」
悲しいことを言うんでない。そう言われた気がした。
二棟に見えた温室は棟つづきで、アパートが三つは入る長さだ。
ギィ。
扉の向こう。白く塗られたガラス張りの温室に 「ソレ」 はあった。
「すごーい」
驚いた。整然と並ぶロッカーの数数数、数。この数だもの。中味が詰まっているとすれば、公民館の図書室どころか、三階の児童書コーナーに迫る、凌ぐ? 数になるはず。荒井さんが厳重な防犯システムを敷く理由を、わたしはようやく理解した。
「書こうと思っとる」
またいきなり。
「何をですう?」
「小説を」
「小説ですか。荒井さんなら傑作が書けますよ。書き上げたら是非、」
「教えてくれんかの。その、パソコンを。お手間を掛けるが」
手間はどうでもいい。でも、どうしよう。
図書館の仕事は天職だけど、とても生活が立ち行かない。ダイエットと言い聞かせて、食事を切り詰める生活も限界寸前。栄養失調で倒れでもしたら医療費という余計な出費が発生するばかりか、浪々の身。ふつうの節約で生活出来るようにパートを掛け持ちするつもりだから……。
荒井さんには悪いけど、やっぱり無理。
「もちろん講習料は支払う。一回五千円ほど。しか出せんが」
一回で五千円。と言うことはたぶん半日。週に一、二回として、月に二万円程度。それならパートを探した方が、
「一回一、二時間。仕事の帰りでも。休日にでも。都合の良い時で構わん。わしとしては毎日でも、」
「やります!」 週五、いや週に六日、やらせて頂きまっす!
「マスターしたら」
外来語嫌いの荒井さんが言い澱む。
「ふつうにマスター出来るなるまで責任持って教えます。図書館の検索機が使えるんですもの。大丈夫、自信持って」 ね。
でも余りに早くマスターしちゃったら、それはそれで困る。生活は逆戻り。副収入を失ったときのダメージはいま以上。三十九と四十歳では募集先が大きく異なる。
いや。今は先のことより目先のこと。
「マスターしたら農業やめる」
とっくに年金生活をしていていいご年齢だ、
「長くがんばってきたんですもの。読書や執筆に勤しんで、ゆっくり過ごすと良いです」
「手放したくないんじゃ」
「大切に育ててきたんですもの、よく分かります。荒井さんのお気持ち」
「大切な本じゃから」
そっちの方。廃業したら温室に置いておくわけにはいかないのだろう。
? そうか。なるほど、わかった。
古本屋さんを営んでいた荒井さんは、図書館が開けるほどの本を所有している上に、書庫で眠っている児童書を繰り返し借りつづけている。だけに留まらず、手離したくないと思っている。
つまりだ。手許に置いて守りたい、守ろうとしている、守ろうとしてきた。愛する本が処分されるのを食い止めたかった。きっとそうだ。
「ここにある本。みんな喜んでると思います。作家さんも」
「ふむ」
はにかむ荒井さんの目が、潤んで見えた。
「書評してほしいんじゃ。書き終えたら」
荒井さんったらまた話を変えて。
「わたし評価とか嫌いなんです。するのもされるのも」
「ちょっとした、アドバイスのようなもんでいいんじゃ」
外来語ばっかり。
「助言でよろしければ。喜んで」
六
限界じゃった。
書庫に幽閉された児童書を借り、 「読んでいます」 をアピールしているだけでは、この国の児童文学を救うことは不可能。九分九厘諦めておった。
そんな疲弊したわしを救ってくれたのが、春うらら、朝日春子嬢じゃ。
春子嬢は、思っていたとおりの御仁じゃった。八十有余年生きてきた理由、それはあなたと会う為だったのじゃ。わしらは繋がっていたのじゃよ、春子嬢。人類が誕生する以前からのお。
それはそれとして、あなたのおかげで四半世紀お目に掛かれなかった幻の書――【ムグンファの香りを風にのせて】 がもうすぐこの手に。
ぽち。
ぽち。ぽち。ぽちぽち。
いくぞ、うらら子、
「えんたっ!」
昭和の名作。児童文学の傑作。数十万叩いても痛くも痒くもないと思ってきたが、入札時のスタート価格はたったの百五十円。にも関わらず、競り合う者はゼロ。売りに出す方も出す方じゃが、購入希望者がいないことにも腹が立つ。いっそのこと百六十円で競ってやろうか。束の間そう思いもしたが、それでは余りに大人げなく、名作に対して無礼千万。初刊発行当時の定価と現在の貨幣価値に、児童文学の未来への投資の思いを込めて、五千円で即落札。別途着払いの送料を含めれば常人では考えられない、無駄遣いになるのかもしれんが、五十万出しても惜しくはないと思ってきた不朽の名作じゃ。余は大満足じゃ。
すべてはパソコンを教授してくださった春うらら子嬢のおかげ。一度いや、三度熟読したのちに献上しよう。この名作を読まずして送る人生が、どれほどの意味も持たないことを悟るに違いない。
この勢いでアレとアレ。それにアレを競り落として読破できれば、もう思い残すことはない。喜んで黄泉の客となろう。
「やってますね」
その声は。
「夢中で気づかなかったみたい」
温室ガラスに映る、初夏に似合う空色のワンピースを着たうら若き淑女は、春うらら子、春子嬢。もちろん来ると思っていた。防犯システムを解除したのが思いの表われ。いや、いいんじゃよ。気づかなくとも。小さなことじゃ。
「や」
「ごめんなさい。来れないって言ったのに」
来・ら・れ・な・い。口から衝いて出そうな言葉をどうにか飲み込む。小さい男とは、思われたくはないからの。あなたにだけは。
「あれえ?」
「これは」
「お買い物ですか。作品を書いてるのかと思ってました」
思って “い” ました。
「ん。あ、いや」
別に春画を買うわけではない、隠し立てすることもないのじゃ。 「児童書を、見つけてな」
「ネットオークションで? すごーい! こんなに早く使いこなせるようになるなんて、ほんとうに凄いですね。ヨージロさんって」
ヨージロでなく、庸二郎。
ふ。大したことではないわ。
「あれえ? その本」
それは。
見られてしもうた。驚かせようと思っとった、思っていたのに。
「持ってます、ムグンファ」
へ?
「亡くなったおじいちゃんに初めて買ってもらった本なんです。幼稚園生のときに」
なるほど。読書人になるきっかけを作った本、というわけじゃな。と思ったのも束の間。現実を突きつけられた思いじゃ。
恐らく、うらら子嬢の御祖父は、わしと同年代。早くに亡くされたのか、わしが長く生き過ぎたのかは判然とせぬところじゃが、うらら子嬢は亡御祖父の面影を、わしと重ねているのかもしれん。つまり、老人になったおじいちゃんを見る目で、わしを見ているということになる。
とするならば……わしは自分の孫娘に岡惚れしたようなもの。ということに、なりはしまいか。
複雑な思いを抑えて尋ねてみる。
「いかがじゃった」
似たような感想であれば、現実を胸を張って否定できる気がした。おじいちゃんと孫という年齢の隔たりを。
「言いません。でも、いまだに持ちつづけてるんですから……」
よい、よい。言わんでもよい。感想など人それぞれじゃ。それに、わしには分かる。
思い出したようにムグンファを手にしたうらら子嬢、あなたは、以前とは異なる世界が広がっていたことに感動した。そして気づいた。胸を躍らせて読み耽る自分に――。
ホンモノの本というのはそういうもの。恐らく三十有余年来そばにいるムグンファも、同じ思いでいるはずじゃよ。
「それでヨージロさんの方は? 進んでます?」
助言でよろしければ。
やってますね。
書いて (い)るのかと、思って (い) ました。
春子嬢は、小説を書き上げるのを心待ちにしておる。元古本屋で、これだけの書籍を所有していれば秀作を書く。と、過剰な思い込みをしているようじゃが。
わしは微細を気にして読むタイプではなしに、読み終えて、心に沁みたか、響いたか。涙がこぼれたか、溢れただけか。それがわしのいい本の基準じゃ。描写うんぬん、文体が独特、行間がどう、ラストが劇的。そんな事を気にして読んで何が楽しいのか、わしにはさっぱり理解できん。
然るに駄作必至じゃろうが、
「大詰めじゃ」
「わあ、楽しみぃ。ジャンルは? どんな感じです?」
読んでほしいのは、小学高学年から中学生。そしてうらら子嬢、あなた。ジャンルは答えられん。これはミステリー。これ純愛。これファンタジー。ユーモアものを書きました。書いた当人がそう思ったところで、読者がそう思わなければ詐欺みたいなものじゃからな。
「言わん」
「んもう。楽しみにしてるんですよ、どんな小説を書くか」
「所詮アマチュアじゃ。期待せんことじゃ」
わしは思い切り書きたいだけじゃよ。審判など気にせずに。小細工なしにの。
「期待します。ヨージロさんが書くんですもの」
七
借りたいんだけど。
…………
「借りれないのっ」
あらやだ。
「申し訳ございません」
どうしちゃったの。
どうしちゃったんだろう。最近凡ミスばかり。真正面にいるお客様にも気づかないなんて。
分かっていた。ヨージロさんと会っていないから。たった半月なのに、最近のお天気みたいに、戻り梅雨のようにもやもやして落ち着かない。
――大詰めなんじゃ。書き終えたら連絡する。
完成してないのかなあ。まだ。
――番号? 電話は使わん。教えても仕方ないじゃろ。
――メール? 外来語もメカも嫌いじゃ。書簡をしたためてくれ。
返信くれないじゃない。十日も経つのに。
行くしかないか、結局。って、もしかしたら。 「来てほしい」 って言いたかったの? 「伺ってもいいですか」 って聞いてほしかったのかもしれない。きっとそうだよお。
八
うそ……。
無い。カメラも。カードリーダーも。
「こんな環境で過ごせる荒井さんって、幸せですね」
「変わってしもうたよ。すっかりの……」
フラスコも。将棋盤も、水苔もない。
向こうは?
「人間も同じじゃ。古くなれば見向きもされんようになる。多くの本のようにの」
「そんなこと……。書庫の本、今度ゆっくり見せてくれません?」
「書き終わったら存分に見てくれて構わんよ」
あった。良かったあ。
「わしが居なくなったら、どうなるんじゃろうな」
「そんなあ。縁起でもない」
「ロッカーの、書庫の本が気掛かりでな……」
「わたしが何とかします。ヨージロさんらしくありませんよ、元気出して」
【ロッカーの本は図書館に寄贈】
【このパソコンは朝日春子さんへ拝呈。触れるべからず】
ヨージロさん……
「どうせ誰も読まんじゃろ。老いぼれの書いた小説など」
「わたし読みたいです。ヨージロさんの心の言葉を」
まだだったんですね。投稿。
「助言、約束じゃぞ」
「書き上げてから言ってください。そういうことは」
「やんわりと頼む」
「それじゃ、上達しませんよ」
「いいんじゃよ」
「最後にココ。この 【Enter】 ボタンを押すんです」
「その、大きなぽっちをか」
「そう。エンタ―。 “ぽち” って」
うんうんうん……
子供みたいな、本の中にいるような人でした。ヨージロさんって。
さ。いくわよ。
いいですね。
緊張するなあ。
これが、
これが荒井庸二郎の、
作品よ。
「えんた!」
うふふふふ。
ムグンファ、しまっておきますね。
小説はゆっくり読みます。
「書庫いっぱいの愛を」
あなたのそばで。
九時四十分おじさん、あなたを思って。
了
書庫いっぱいの愛を