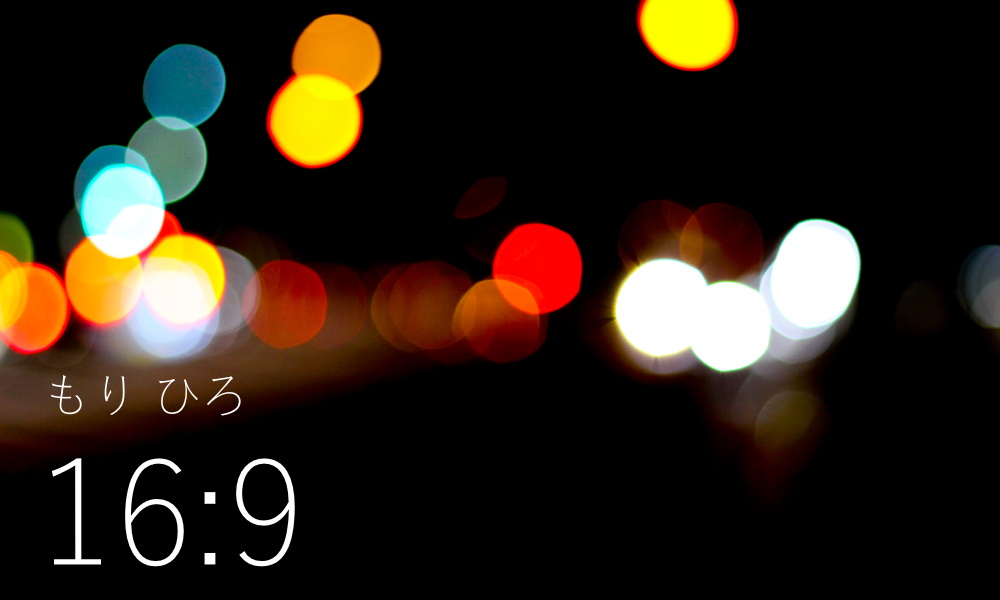
16:9
16:9
僕は画面を凝視してかたまった。
左手に握ったそれは、ダメだと思えば思うほど硬くいきり立ち、感度が増す。鼓動に合わせて小さく脈動した。
今、このまま射精してはならないと自分を抑制する理性的な部分と、彼女を見ながら尽き果ててしまいたい野獣的な部分が競り合う。「ダメだ」と思うくらいには理性がまだ勝っていた。
整形、しているかもしれない、と思った。
僕が知る限りの彼女の姿は、中学卒業から変わっていない。あの日から一度も彼女と顔を合わせていなかったので、記憶の中の彼女は成長が止まっていた。
僕は中学を卒業してから県内の高校に進学した。彼女は、親の仕事の都合で他県へ引っ越したため、引っ越し先の高校へ進学した。
交流はそれ以来、途絶えていた。今みたいに、ソーシャルネットワークサービスが充実している時代ではなかったのだ。
画面の中の彼女と記憶の中の彼女を比べてみる。少し鼻が高くなって、アゴのラインがすっきりして見えた。
そして、彼女が一番に気にしていた歯並びは綺麗に整い、画面越しでもわかる白さで艶やかに輝く。
深海のように黒くて長かった髪は、品のない色に染められて、うなじが見える程度まで短くなっていた。
彼女と最後に交わした言葉は、今でも覚えている。
あれは、卒業式のあとのこと。
その言葉は、「じゃあ、現場で会おう」というものだった。
中学の頃、僕は映画監督を、彼女は女優を夢見ていた。お互いの夢は誰にも内緒にしていて、卒業アルバムにさえ書いていない。
二人で秘密の共有をしている時間が幸せだった。彼女を独占しているような優越感もあった。
僕が彼女に将来の夢を語ったのは、間違いなく僕の方からだった。
部活動もせず、特に親しいと思う友人がいなかった中学時代。放課後、町営の古い劇場へ行くのが楽しみだった。
近所のショッピングモールに大手のシネコンがあって、流行り物の映画は全てそちらで見られる。自分たちが生まれるよりも昔の作品しか見られないような劇場へ、同年代の連中が来ることはまずなかった。
そこに突然現れた制服姿の女子中学生。僕が通う中学のブレザー。見覚えがある同級生。
それが彼女だった。
話題を共有できる相手ができる予感がして、僕は話しかけた。いつもなら絶対に自分から話しかけたりなんかしない。それくらい、気持ちが高揚していたのだ。
最初の一言は「やあ、映画、好きなの?」だった。
それから僕は、この劇場に毎日通っていること、古い映画の話題などを饒舌に語り、「映画監督になりたい」と告げた。
彼女は「奇遇だね」と笑った。「わたしは女優になりたい」と。
笑顔の彼女が、すかさず手で口を隠した。ちょっと伏し目がちになる。
「わたしね、自分の歯並びが嫌いで、うまく笑えないの」
僕は撃ち抜かれていた。
間違いなく、あれが僕の初めての恋だった。
その日から、僕らは毎日劇場で顔を合わせた。上映が終わってから自販機コーナーでジュース片手に映画の話をした。
薄暗い自販機コーナーの蛍光灯に照らされた彼女は、まるでそこに存在していないように色白だった。あの空間も時間も、夢のようだった。
ある日、彼女が劇中のシーンを再現して演じた。僕は面白がって、携帯電話で撮影した。
カメラを向けた瞬間、彼女の顔が変わる。仕草が変わる。声色が変わる。まるで別の人物が憑依したように。同じ中学生とは思えないほどだった。僕がカットをかけると普段の彼女が戻ってくるが、カメラを向ければまた別人に変化した。
それが、何よりも気持ちが良かった。
僕はいつか彼女を主役にした映画を撮りたいと告げた。
その言葉は、僕なりの愛の告白だった。
僕がした僕なりの告白に対し、彼女も僕に秘密を告げた。
彼女の父親のことだ。
彼女の父親は、本当の父親ではなかった。離婚した母親の再婚相手で、彼女とは血のつながりはない。
そいつは酷く気が短かったという。些細なことで機嫌を損ね、彼女へ負の感情をぶつけた。しかも、それは決まって、母親のいない時間に行われた。
父親は不機嫌になるたびに、強引に性器を咥えさせたという。彼女も最初は拒んだと言うが、拒むと殴る蹴るの暴行を受けるので、しだいに受け入れるしかなくなった。
その話を聞いた僕は、彼女の父親を殺したいほど憎んだ。ただ殺すだけじゃ済まないとも思った。できるだけいたぶって、彼女の苦しみを超える痛みを与えなくては気が済まないとも。
それなのに、ちっぽけな僕には何もできなかった。せいぜい、気休めに彼女を慰める言葉を呟く、それが精いっぱいだった。
彼女の口から父親の話を聞いたのは一回きりで、それ以降は増える痣から彼女の家庭状況を知るしかなかった。
少しでも彼女を活かすために、僕は独自の脚本を書いた。彼女の一人芝居。当時の僕は、女優としての彼女の姿で、彼女の家庭事情から目を背けられると信じていた。中学生なりの逃避だった。
舞台はもちろん、町営劇場の自販機コーナー。一人の女性が過去を悔やみ、自死と生存の狭間で揺れ動く独白。
アクションをかけると、彼女は涙ながらに過去を語る。取り乱し、勢いのままに自らへ刃を向け、寸前で恐怖が彼女を取り巻き、自死に至れない。
気迫。
携帯電話で撮影した映像を、二人で頭を突き合わせて確認する。
そんなことを毎日のように繰り返しながら、次々に映像を撮った。
それでも、やはり笑う演技だけはどこかぎこちなさがあった。歯並びが気になるという彼女へ「きみの歯並びも、きみの素敵な個性だ」と励まして撮影を続けていた。
そうして、ようやく少し彼女のコンプレックスが薄れ始めた頃に卒業を迎えた。
「わたし、絶対に女優になってみせるから。引っ越し先にアクターズスクールがあるし、そこに入るつもり」
「僕も必ず映画監督になってみせるよ。その時は、もう一度きみを撮りたい」
「うん、それじゃあ、現場で会おうね」
「ああ、じゃあ、現場で会おう」
それから月日が経って、僕は映画とは関係ない道に進んでいた。普通に高校を卒業して、人並みに大学生活を送る。申し訳程度に大学で映研サークルに入ったが、今ではほとんど参加していない。
彼女のことを忘れて日々を過ごす中で、突然画面の中に現れた彼女。
うまく笑えない、と言っていた彼女が、画面の中では綺麗になった歯で笑っていた。
その笑顔を急に歪める。性感帯を刺激され、息を吐く。気持ちが良さそうで、あまりにも気持ちが悪かった。
それなのに、僕は左手を止めることができない。右手で停止ボタンを押すこともできない。
彼女の絶頂と同時に、僕は射精した。
きみは、これで良かったのかい。
きみが追いかけていた夢は、ここにあったのかい。
それに、僕はこれで良かったのか。
この数年で、一体何があったの。
あの日、僕らが約束した「現場」は、今、ここのことだったのだろうか。
映画監督になるという夢を忘れ、なんとなくの日常を過ごす僕に何が言える。
回答者がいない疑問が次々に押し寄せる。
こういうものだって、立派な映像作品であって、仕事として誇りをもって製作や出演している者だっている。
それはわかる。
わかるけど。
きみが目指していたのは、ここではないと僕は信じたい。
かつて、あらゆるスターの名前を挙げて、憧憬の目をしていたきみはどこへ行ってしまったの。僕の脚本を面白いと言ってくれたきみは、本当にきみの言葉だったの。今、きみは何を思っているの。
彼女への問いが溢れ出る間にも動画は流れ続け、次のシーンへ切り替わった。
十六対九の画面の中に、さっきまでとは異なるきみが映し出される。
制服姿で犯される彼女の姿を見て、僕は再び射精した。
背徳的な快感によって僕の中にあった何かが崩れ去る音を聞きながら、僕はティッシュに手を伸ばした。
<了>
16:9


