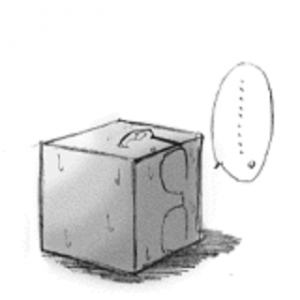あのん
この物語はフィクションであり、実在する人物・地名・団体名等とは一切無関係である。また、本作には性表現及び強い暴力表現を含むため、十八歳未満の閲読者は速やかに退出すること。十八歳以上の読者におかれても、その種の表現を受け入れられない者は閲読を控えられることを作者から強くお勧めする。
不波 流 拝
〈一〉
篠田から電話があった。
七夕の夜だというのに、日が暮れても細かな雨が音もなく降り続いていた。
相変わらず梅雨は明けず、俺は無駄に広いリビングにエアコンも掛けないでだらだらと缶ビールを飲んでいた。
篠田が俺と同じ街で暮らしているのは知っていたが、あいつとは俺の結婚式以来、会ってはいない。惰性で年賀状のやりとりだけは続いているが、ここ何年も直接話したことはなかった。
『ちょっと、困ったことになってるんだ。悪いけど、手を貸してくれないか』
篠田は挨拶もそこそこに、俺にそう切り出した。
何か面倒なことになりそうだな、と直感した。しかし、同級生のよしみで、無下に断るのも気が引けた。
『詳しいことは後で話すから。今からそっちに向かう』
それだけ言って、篠田は一方的に電話を切った。
俺は煙草に火を点けた。空になった空き箱を握りつぶしてゴミ箱に放る。屑はゴミ箱の角に当たって床に落ちた。
「一体どういうつもりだ?」
紫煙を吐き出すと俺はひとりごちた。
篠田が今までこれほど強引だったことはなかった。それだけでも予感は厭な方向に振れる。
部屋がやけに蒸す。ぬるま湯の中に浸かっているようだ。
俺は新聞や雑誌が散らかったダイニングテーブルの上からエアコンのリモコンを探り出して「運転」ボタンを押した。
低い唸りと共に冷たい空気が吐き出され始める。
俺はダイニングチェアに寄りかかったまま、煙草の煙が流れるのをしばらくぼんやりと眺め続けた。
篠田が来たのは電話から一五分ほど後だった。インターフォンではなく、電話が鳴った。
『悪い、下まで降りてきてくれないか』
「開けてやるから勝手に上がってくればいいだろ?」
『それが出来ないんだ、頼むよ』
俺は電話を切ると軽く舌打ちをした。篠田のやつ、一体何を考えている?
仕方なしに俺はつっかけで玄関を出た。仕事から帰って二時間以上が過ぎているが、着替えるのも面倒だったのでワイシャツにスラックスのまま。外に出ても別におかしくはない恰好だ。
エレベーターホールに降りると、ちょうど入ってきた母娘とすれ違った。中学校のセーラー服姿の娘と、Tシャツにジーンズの母親。
「こんばんは」
母親に挨拶されたので俺も会釈を返す。
母娘は何やら楽しそうに会話しながら俺と入れ違いにエレベーターに乗る。この時間なら塾帰りか。俺には縁のない光景だな、と俺は少し拗ねた気分になった。
外は少し雨が強くなっていた。傘を持って出ればよかったと後悔する。
篠田はマンションのエントランスから少し離れたところに車を停めて、傘もささずに待っていた。篠田のもとへ小走りする。
「遅い時間に悪いな」
篠田は右手で濡れた髪をかきあげながらそう言った。メタルフレームの眼鏡も水滴だらけだが、やけに深刻な顔をしている。
「お前、どういうつもりだよ」
俺は少し苛立ちながら篠田に問う。
「悪いが時間が無い。詳しくはまた後で改めて連絡するから」
篠田はそう言うと、後部座席のドアを開けた。
俺が篠田の肩越しに覗き込むと、シートに小学生ぐらいのこどもが横たわっているのが見えた。
「この子を、しばらく預かってくれ」
篠田はこどもに毛布を掛けてから両手で抱え上げた。
「ちょっと待て、どうしたんだその子は!」
胡散臭いどころか、犯罪の匂いがする。
「お前の他に頼める奴がいないんだ。頼む」
篠田はそう言って毛布にくるんだこどもを俺に押し付けてきた。
身長は一三〇センチぐらいだろうか、細い足が毛布の端から出ている。眠っているのか。
「落ち着いたら改めて連絡するから」
ひどく切迫した顔だ。その気迫に押されて、俺は思わずこどもを抱き取ってしまった。両腕にこどもの重さがかかり、俺は少しよろめいた。
「頼んだぞ、必ずまた連絡する」
一方的にそれだけ言って、篠田は慌ただしく運転席に乗り込むと、振り向きもせず車を発進させた。テールライトが雨に滲み、尾を引きながら角を曲がって消えた。
俺の腕の中で、こどもが小さな寝息を立てている。こどもとはいえ、ずしりと重い。
「よっ……と」
俺は降り続く雨の中、腕の中のこどもを抱え直すと、自分の部屋に戻ることにした。
確か、篠田はまだ独身だった。だとしたら、このこどもは一体誰の子だ。
こどもを抱えたまま、無理な姿勢でエレベーターのボタンを押す。上昇する速度が普段よりも遅く思える。購入するときに上層階を選んだ自分を思わず恨む。
毛布を通じて、こどもの体温が俺の身体に伝わる。こんなにあたたかいものなのか。
腕が痛くなり始めたところでようやくエレベーターの扉が開いた。
「ふう」
やっとのことでリビングのソファにこどもを下ろすと、タオルで頭を拭きながら俺は煙草を探す。
寝室のベッドの上に放り投げたままだった鞄から煙草を取り出すと、リビングに戻って火を点ける。
こどもはよく眠っている。
毛布を掛け直しながら改めて顔をよく見ると、どうやら女の子のようだ。ぼさぼさの黒い髪、日焼けしているのか、褐色の肌、汚れたキャミソールに短パン。年齢は一〇歳ぐらいだろうか。自分にこどもがないのでよくわからない。
少し身体を丸め、小さな寝息を立てている。
「猫……みたいだな」
俺は昔実家で飼っていた猫のことを、なんとなく思い出した。
「しかし、どうしたら──」
俺は紫煙を吐きながらひとりごちる。
独り身の俺が、こんなこどもの面倒など見れるだろうか。
エアコンが唸る音を聞きながら、俺は一人で途方に暮れた。
『どうしたの、あなたの方から連絡してくるなんて。嵐でも来るんじゃないの?』
香織は電話に出るなり大声で笑いながらそう言った。
「笑い事じゃないんだ、ちょっと困ったことになってて、香織の知恵を貸してもらいたいんだ」
俺は努めて落ち着いた声でそう切り出した。
『あ、お金ならダメだよ、わたしだっていつもギリギリなんだから』
「そうじゃないって」
香織は昔から人の話を聞かない女だったな、と俺は少し苛立つ。
「俺の大学時代の友人で、篠田っていただろ」
『そうだっけ?』
「一応俺たちの結婚式にも呼んだ。あいつから、一〇歳ぐらいの女の子を押しつけられたんだ」
『えー?! なんで?』
香織が素っ頓狂な声を上げた。俺は受話器から少し耳を離す。
「それがわからないから参ってるんだ。とりあえず今は寝てるけど、どうしたらいいかわからなくて」
俺はつい、うろたえた声を出してしまった。
『それでわたしに電話したのか。わかった、今から行くよ。車、駐めれるよね?』
「ああ、たぶん大丈夫。お前、仕事の方はいいのか?」
『納期直前のはないから。ちょっと待ってて』
それだけ言うと、香織は電話を切った。せっかちなところは相変わらずだ。
俺は再び煙草に火を点ける。
どうも落ち着かない。こんな形で香織を再びこの部屋に入れることになるとは、思ってもみなかった。
香織に借りを作ることになるが、しかし俺一人ではどうにもならない。
女の子はよく眠っている。
篠田に電話をかけてみたが、「おかけになった電話は、電源が入っていないか、電波の届かないところに──」とアナウンスが流れて繋がらない。まったく、いい迷惑だ。
香織が到着するまでの三〇分の間に、二本の煙草を灰にした。
「来たよー。あー、また煙草吸ってる!」
香織は開口一番俺に文句を言う。
小さな顔、後ろで束ねた明るい茶色の髪、くるくるとよく動く二重の目、薄い唇。黒のTシャツに七分丈の白いクロップドパンツ、フラットなスニーカー、青い石をあしらった自作のネックレス、縁なしフレームの眼鏡。耳朶には、これも自作のピアスが光っている。俺の三つ下だから今年三十四か。香織は俺と違って実年齢よりも若く見られることが多い。
「いいだろ別に。ここは俺の部屋だ」
「せっかく苦労して禁煙したのに、バカみたい」
「バカとはなんだ、お前にはもう関係ないだろ」
俺はついムキになって言い返してしまった。どうも香織に何か言われると調子が狂う。
「わたしはね、あなたとケンカしに来たんじゃないからね」
香織は腕を組んで俺を睨んだ。
「まあ、とりあえず入ってくれよ」
俺は香織をリビングに招き入れた。
「あー、この子かあ。よく寝てるね」
香織はソファで眠っている女の子を見るなり表情を緩めた。
「篠田さんは? 連絡取れた?」
「いや、多分電源切ってるんだろう。落ち着いたら向こうから連絡するって言ったきりだ」
「そっか。ねえ、名前はなんて言うの?」
香織はソファのそばにしゃがみこんで、女の子に顔を寄せながら俺に尋ねた。
「わからない。どこの誰かもわからない」
篠田は本当に俺に何も告げなかった。
この子はどこから来たのか、何者なのか。そして、なぜ篠田はこの子を俺に預けたのか。
起きてから本人に尋ねるほかない。
「ふーん、名無しちゃんか」
香織は指先でふにふにと女の子の頬を突ついている。
「あ、コラ。起きたらどうすんだよ」
「いーじゃん、このくらいじゃ起きたりしないよ」
「んん……」
少女が声を上げた。
「ほら見ろ、起きたじゃないか」
俺が上げた声で少女は目を開けた。
香織が視界に入るなり、がばっと跳ね起きてソファの裏に隠れる。
「なによ、あなたが大きな声出すから」
香織はソファの裏を覗き込むが、少女は出てこようとしない。
「怯えてるのか?」
「みたい。ねえ、あなたはだあれ?」
香織はハイトーンの声で優しく尋ねたが、答えはない。
「うーん、恐がってるのかなあ」
「そうやって覗き込んでたら逆に出てこないかもよ」
俺はそう言ってダイニングチェアに腰掛け、足を組んでソファの方を眺めた。煙草に火を点けたいが、じっとこらえる。
「何わかった風なこと言ってんの? どうしたらいいかわかんなくてわたしに電話してきたくせに」
香織が口をとがらせて反駁する。まったく、あの頃から全然変わってない。
「いや、昔実家で飼ってた猫がそうだったからさ」
「猫と一緒にしたらかわいそうでしょ、ねえ?」
香織は左手を伸ばしながら甘い口調でソファの向こうに話しかけた。
「あた!」
香織が悲鳴を上げる。
「どした?」
「引っかかれたー、いてて、傷テープある?」
「ほら見ろ、ちょっと待ってろ」
俺は傷テープを取りに寝室に行く。
なんだか懐かしい感じだ。香織との他愛のない会話。ほんの三年前には、日常だった光景。
──いや、ただの感傷だ。今は他人同士。元に戻るなんて、ありえない。
「ねえ、ちゃんと掃除してるの?」
傷テープを持ってリビングに戻ると、香織が不機嫌そうに言う。
「たまにはな」
俺が箱から傷テープを一枚出して香織に渡そうとすると、香織は左手の甲を俺に差し出す。爪の跡にうっすら血が滲んでいる。
「貼って」
いつでもそうだ。香織は俺に命令ばかりする。
「なんで」
「いいから、ほら」
俺は仕方なくパッケージを破って傷テープを取り出し、剥離紙を剥がして香織の左手に貼ってやった。肌が少し荒れている。手仕事を生業にしているのだから当たり前だが、久しぶりに触れた香織の肌に、俺は少しうろたえる。
「ほら、これでいいだろ」
うろたえたことを香織に覚られないよう、わざと素気なく言う。
「ありがと」
香織も素気なく返した。
「なあ、腹減ってないか?」
「あー、ちょっと。夕飯食べ損ねたし。遅いけど何か欲しいなあ」
俺の提案に珍しく香織が乗った。
「なら、俺がコンビニで何か買ってくる」
「あー、いいね。サンドイッチか何か欲しいな」
「あの子はどうかな?」
俺はソファの方を見ながら香織に聞いてみた。
「お腹すいてるのかも。おにぎりみたいなの買ってきてあげたら?」
「みたいなのってなんだよ」
「もう、相変わらず細かいなあ」
香織が苦笑いした。ずっと見慣れていたその表情は、三年経っても変わってはいなかった。
〈二〉
雨の中、傘をさしてコンビニから戻る。大型スーパーを隔てた向こうに、マンションの黒い影が聳えている。
ロイヤル・アヴェニール葉山町。築七年・一二階建ての、大仰な名前の高層マンション。俺は利便性が気に入り、香織は窓からの眺望を気に入った。西関の中心市街地からほど近い高台で周囲には緑地も多く、ベランダからは海峡の向こうの山並みまで見渡せる、絶好の立地。
雨は静かに降り続いている。時折、車がヘッドライトで雨粒を浮かび上がらせては通り過ぎていく。
三年前の四月、五年間の結婚生活に終止符を打って、俺と香織は協議離婚した。
はじめは些細な行き違いだったのだろう。それが少しずつ二人の距離を広げ、気づいてみたら、二人とも別々の方向を見ていた。
香織は自由を求め、俺は安息を求めた。
そして俺たちは、互いにそれを与えることが出来なくなっていた。
香織から離婚を切り出されたとき、俺は自分でも驚くほどあっさりとそれを承諾した。もしかしたら、もう疲れきっていたのかもしれない。二人の間にこどもがなかったのは、幸いだったのだろうと思う。
マンションのエントランスホールはすっかり静まり返っている。俺は鍵を回して開いた自動ドアをくぐり、開錠を感知したエレベーターが自動で降りてくるのを待つ。エレベーター脇のモニターには、空っぽの室内の様子が映し出されている。こういったセキュリティの高さも、このマンションの売りの一つだった。
エレベーターが着き、一一階のボタンを押す。
高層階を選んだのは香織の希望だった。戸建てにするかマンションにするか、二人であちこちのモデルルームや現地を回り、あれこれ考えて最終的にここを選んだ。はしゃぐ香織を見るのは楽しかったが、まさかその後別れることになるとは、その頃は全く予見できなかった。
この大きな建物に五五もの家族が暮らしている。その中で、独り者は俺だけだ。他の住人もそれを知っていて、どことなくよそよそしさを感じる。表立って何かを言われることはないが、実際どう思われているか知れたものではない。
香織が出て行った後も、俺はこのマンションに住み続けている。一人暮らしには広すぎる部屋を持て余しながら。
一一〇二号室。
「ただいまー」
玄関の扉を開けると俺は何気なくそう呟いた。
「おかえりー、雨どうだった?」
香織が明るい声で問う。懐かしい声。
ああそうだ、俺は香織の声に惹かれたんだったな、と思い出す。
「まだだいぶ降りそうだ。あの子はどうしてる?」
「あそこ」
香織はソファの向こうを指さす。まだ警戒心を解いていない、ということか。
「とりあえず適当に買ってきたけど、いいか?」
俺はサンドイッチの包みを香織に渡す。
「おなかすいてるからなんでもいいよー。あの子には?」
「これ」
俺はビニール袋から山賊むすびを取り出した。梅、しそ昆布、鮭の三種の具が入った、一回り大きめのおむすび。
「ねえ、おなかすいてるでしょ? 出ておいで」
香織は山賊むすびを差し出しながら努めて優しい声で呼びかけたが、女の子は何も反応を示さない。二つの黒い瞳が、じっと香織の一挙手一投足に注目している。
「なんにもしないからこっち出ておいで~」
香織は少しおどけて手招きするが、女の子は香織のことをじっと睨んだまま動こうとしない。
「ん~、ダメかー」
香織は諦めて山賊むすびを床に置いて、ばふんと音を立ててソファに身を預けた。
俺はダイニングテーブルで自分用に買った冷麺を開けた。具をトレイから移し、小袋に入ったタレをかける。
「は~、ずっと根詰めて作業してたから疲れたぁ」
香織はサンドイッチを口にしながらすっかりくつろいでいる。厚かましいというか、人懐こいというか。本人は狙ってやっているわけではないのだが、人の好意をうまく利用するようなところが、香織にはあった。
「仕事、うまく行ってるのか?」
「おかげさまで。市内三つの雑貨屋さんに置いてもらってるよ。ネット販売もしてるけど、わたしはやっぱり対面販売の方が好きだな」
香織は自分のネックレスをちらりと見ながら答える。趣味の範疇だったアクセサリー製作を、今はメインの仕事にしている。それだけでは生活が厳しいから、バイトもしているらしい。収支はぎりぎりだけどやりがいあるよ、と以前会った時に言っていたことがあった。
「あなたもこのマンション出て新しい生活に踏み出したら? 一人暮らしで3LDKなんてもったいないでしょ?」
「俺はこの部屋が気に入ってるんだ。職場にも近いし」
俺はそう言って冷麺をすする。
離婚時の財産分与協議で、俺は預貯金のほとんどを香織に渡して、代わりにこのマンションを取った。自分でも何故そうしたのか、よくわからない。合理的に考えたら、向こう二十年以上高額のローンを払ってこの部屋に住み続ける意味は、ほぼない。俺の身勝手な執着に過ぎないのかもしれない。
かさかさという音がした。
女の子が四つん這いでソファの裏から出て、山賊むすびを恐る恐る手にしている。
「お、出てきた」
香織が嬉しそうに声を上げる。
女の子は床に座って包装フィルムの上から思い切りかぶりつこうとしている。
「あれれ、それじゃダメだよ」
香織は女の子のそばに座りこんだ。
「また引っかかれるぞ」
「だーいじょぶ。ほら、こうやって持ってて」
「あー」
女の子が声を上げた。
香織は女の子にむすびを両手で持たせると、そのまま器用にフィルムを剥がした。
「ほら、これでよし!」
「んなー」
女の子は一声上げると、山賊むすびにかぶりついた。一口目で梅に当たったのか、目をつぶって口をすぼめている。
「ねえ、君の名前は?」
「むー」
女の子は香織の問いかけに言葉にならない声を返す。
「どこからきたの?」
「……」
夢中で山賊むすびにかぶりついている女の子は何も答えない。
「もしかして、しゃべれないのか?」
「らー」
俺の疑問に、女の子が声だけで返す。口の中がご飯粒だらけだ。
「みたいだね」
香織が女の子の髪を撫でながら答えた。いつの間にか女の子は香織に心を許しているようだ。
「参ったな……名前すらわからないままか」
「じゃさ、わたしたちで付けてあげようよ、名前」
俺が苦い顔をして呟くと、香織が明るい声を上げた。
「前向きだな、お前」
俺は半ば呆れる。
「あなたが後ろ向きすぎるの! さて、なんて名前がいいかな?」
香織は女の子の頭をくしゃくしゃと撫でる。女の子はくすぐったそうに目をつぶった。あっという間に山賊むすびを食べ終えてしまったようだ。
俺が後ろ向きすぎる、か。相変わらずきついことを平気で言う女だ。
「……名前も不明、どこから来たのかも、何歳なのかも、なぜ俺に預けられたのかも全部不明。UNKNOWN、てわけだ」
女の子は黒い瞳をじっと香織に向けている。
「アンノウン、か。……じゃあ、『あのん』っていうのはどう?」
「安直だなあ」
俺は思わず苦笑した。
「ね、いいでしょ、あのん?」
「なー」
「よし決まり。今日から君は、あのんちゃんだ!」
香織が肩を抱くと、女の子は左下の犬歯が抜けた白い歯を見せてにっと笑った。
自分の家なのに所在ない。
香織があのんとシャワーを浴びている。今夜はここに泊まるから、と香織は言う。ちゃっかり着替えを持ってきている香織の準備のよさに俺は呆れた。断る理由もないが、別れた妻と再び同じ部屋で寝るということに、俺は戸惑っている。
とりあえず、散らかっていた寝室を片づけながら、二人が出てくるのを待つ。
──いいのか、これで?
香織はすっかりあのんの面倒を見る気になっている。改めて篠田に電話をかけたが、相変わらず繋がらない。
本当にこれでいいのだろうか。
俺は煙草に火を点けた。香織がバスルームから出てきたら文句を言われるだろうが、考えがまとまらない。ゆっくりと紫煙を吐き出すと、少しだけ落ち着く。時計の針は、そろそろ日付をまたごうとしていた。
落ち着いたら必ず連絡する、と篠田は俺に言い残した。しかし、今のところ篠田からの連絡はないし、こっちからの電話も繋がらない。ということは、篠田は今も連絡できる状況にないということだ。仕事なのか、それとも何か事情があるのか。
もの言わぬ少女・あのん。
篠田はどういう経緯でこの子と出会い、そしてなぜ俺に預けることにしたのか。あのんは一体何者なのか。
わからないことが多すぎる。
「あー、また煙草吸ってる!」
案の定、バスルームから出てきた香織が文句を言う。
「悪い、いろいろ混乱してて」
俺は吸い殻が山になっている灰皿で煙草をもみ消した。
あのんは香織にぴたりと寄り添っている。着替えがないから香織のTシャツをすっぽりとかぶっている。ぼさぼさだった髪も香織が洗ってやったらしく、今は艶やかな光を放っている。
「ねえ、あのんって、日本の子じゃないのかもよ」
香織は勝手に冷蔵庫を開けて缶ビールを一本取り出しながら言った。
「肌の色が濃いでしょ? 日焼けじゃないの」
プルタブを片手で開けると腰に左手を当てて喉を鳴らして飲み、ソファに座った。完全にくつろいでいる。
「おい、勝手に開けるなよ」
「いいでしょ、一本だけなんだから」
香織はそう言ってまたビールを口に運ぶ。
あのんは部屋をきょろきょろと見回している。
「篠田さんから連絡は?」
「まだ。電話も相変わらず繋がらない」
「篠田さんって、お仕事は何してるの?」
香織は部屋の中をうろうろしているあのんを目で追いながら尋ねた。
「確か、入国管理局じゃなかったかな」
法務省の出先機関。日本に入国しようとする外国人の出入国管理を主な業務としている役所だ。この街には国際フェリーの定期便があるから出張所があるんだという話を、一度本人から聞いた。このマンションの近所には隣国の総領事館もある。
「じゃあ、やっぱりあのんはどこかよその国から来たのかも」
「でも、なんで篠田は俺に預けたんだろう?」
「そんなの篠田さんに聞けばいいでしょ」
香織はそう言うとまたビールを口に運んだ。まったく、呑気なものだ。俺は煙草に火を点けたいのを我慢する。
あのんはカーテンの隙間から外の様子を覗いている。色々なものに興味を示す様子は、やはり子猫に似ている。
「ねえ、あなた明日仕事でしょ?」
「ああ」
「じゃ、日中わたしがあのんを預かるよ。明日はバイトもないし。一人にしとくより安心でしょ?」
「そりゃ、助かるけど、いいのか?」
「まかしといてー。あのんー、明日は髪切りに行こうねー」
「らー」
香織の呼びかけに、あのんは振り向いて嬉しそうな声を上げた。
〈三〉
「課長、どうされたんですか?」
「いや、ちょっと寝違えてね」
「大丈夫ですか?」
「ああ、大丈夫大丈夫」
仕事中しきりに首を押さえていたら、文書の決裁を受けに来た部下に心配されてしまった。俺は苦笑いしながらごまかす。ベッドを香織とあのんに取られ、仕方がないのでリビングのソファで寝た結果だ。香織といるとどうもペースが狂う。
あのんはすっかり香織に懐いたようだが、俺はまだあの子にどう接したらいいのかわからずにいる。あのんの方も、自分から俺に寄ってこようとはしない。
篠田とはいまだに連絡が取れないままだ。まあ、業務中なら携帯電話を手元に置いていないこともあり得る。そのうち連絡があるだろう。
今朝起きてみると、雨はもう止んでいた。ただ、空は厚い雲に覆われていて、今でも湿った空気が重く漂っている。
いつものように、いつもの道を歩いて職場である大学まで来ると、昨晩の出来事が少しずつ遠ざかる。
私立大学の総務部庶務課の課長。首都圏の名門ならいざ知らず、学生の確保に毎年四苦八苦しているような地方の小さな大学だ。台所事情も厳しい。ここ数年はアジア諸国からの留学生も受け入れている。新卒の時に就職に散々苦労してやっと得た職場だから、どうにかしがみついているが、気がついてみたらもう十五年もここで働いていることになる。
肩書だけは大層だが、同じことの繰り返しのような単調な仕事。特に庶務課は学生と直接接することも少ないし、こまごまとした雑用ばかりの、面白みのない職場だ。
朝礼後、業務に入ればすっかりいつも通りの光景。
何も変わらない。何も起こらない。
もしかしたらあれは、夢だったのか?
時折そんな思いが頭を過ぎる。
俺の悪い癖だ。ついつい都合の悪いことはできるだけ遠ざけておきたいと思ってしまう。そんなことをしても現実は必ず追いかけてきて、いずれ俺の眼前に立ち塞がるのはわかりきっていることなのに。
香織との取引で、今日の晩飯は俺が作ることになっている。
台所に立つのも久しぶりになる。
香織と暮らしていた頃にはよく料理をしていたものだが、離婚してからはその気も失せた。自分のためだけに食事を用意するのがばかばかしくなってしまったから、大抵はコンビニ弁当か、外食だ。体によくないのはわかっているが、どうせ一人なのだから健康に気を使う理由もない。自堕落と言われれば、そうなのかもしれない。
「課長、何かいいことでもあったんすか?」
昼前、狭い喫煙室で一服していると、後から入ってきた学務課の小倉から声を掛けられた。
「さあ、いいことなのか、どうなのか」
「なんとなくニヤついてるように見えますよ」
「そうか?」
小倉がからかってくるのを、俺ははぐらかす。
小倉は二十代後半の独身者、うちの職場でも数少ない喫煙仲間だ。ちょうど俺と十歳違う。同じ肩身の狭い者同士、お互いなんとなく連帯感のようなものを感じている。
「首、どうしたんすか?」
「ああ、ちょっと寝違えた。変な格好で寝たのかな」
「あー、俺は彼女腕枕して寝るとよくやりますわ」
小倉のお気楽な返答に俺は思わず苦笑いする。
「整体でも行ったらどうっすか? それとも金曜だし、行っちゃいます?」
小倉はにやにやしながら右手でジョッキを握る真似をした。
「悪い、今日は約束があってな」
「おー、課長に約束なんて珍し! 女ですか?」
小倉が素っ頓狂な声を上げる。
「バカ、そんないいもんじゃねえよ」
俺は再度苦笑しながら煙草を灰皿に押し付けた。
「ホレ、あんまサボってるとまたお前とこの課長が探しに来るぞ」
「うぃーっす」
喫煙室を出ながら小倉に釘を刺すと、小倉はスマートフォンの画面を睨みながら右手をひらひらと振った。調子のいい男だ。
俺もあまり他人のことは言えない。
十年前、今の小倉と同じ二十代の俺はどうだった?
事務室までの長い廊下を歩きながら考える。
怖いもの知らず、というのは実は単に世間知らずなだけで、何となく雰囲気で香織と結婚し、生活というものの重みに耐えられなくなって離婚した。
年月だけは過ぎたが、俺はあの頃から何か変わっただろうか?
役職がついた。部下ができた。社会というものの仕組みを、少しだけ知った。
それが一体何だというのだろう。
結局、俺は一番近くにいた香織のことを、何もわかることができなかった。
大切なものは失ってみて初めて気づくなどと世間ではよく言われるが、結局それがわかるのも、失ってみてからだ。
俺は大切なものを大切にできずに、あっさりと失った。愚かなものだ。
「さて、晩飯は何にするかな……」
俺は歩きながら一人呟いた。
曇り空の下、スーパーの白いビニール袋を提げて歩く。こうしてきちんと買い物したのはいつ以来だろうか。
色々考えたが、晩飯のメニューは結局カレーにした。久しぶりの調理になるから、出来るだけ手間を省きたい。
部屋に戻ると、買ってきたものをカウンターキッチンで広げる。
タマネギ、ニンジン、ジャガイモ。肉は鶏のモモ肉にした。香織が鶏肉好きだったのを思い出したからだ。
ルウは市販のものを使う。一時期はスパイスに凝ったこともあったが、あのんが辛いものを食べられるかどうかわからないので、今日のところは甘口だ。
シンクで野菜を洗いながら、ふと浮かれている自分に気づく。バカだな、香織とよりを戻そうとでもいうのか。
タマネギを手早く串切りにすると、金ザルにあけて軽く水にさらす。ニンジンは大きめの賽の目に。ジャガイモは皮を剥いて大ぶりに切って、こちらも水にさらしておく。一旦まな板を洗ってから肉切り包丁で鶏モモ肉を切り、軽く塩コショウする。フライパンにオリーブオイルを流して水気を切ったタマネギを炒める。バターの方が風味は良いが、焦げつきやすいから見送った。久しぶりの調理だ、リスクは可能な限り避けた方が賢明だろう。タマネギは弱火でじっくりと炒めるのがコツだ。
木ベラでタマネギをかき混ぜながら、さっき浮かんだ考えを反芻する。
俺はまだ香織に未練を抱いているのだろうか。
やり直せるのなら、やり直したいのだろうか。
フライパンからタマネギの刺激的な匂いが立ち昇り、目尻に軽く涙が浮かぶ。
──ありえない。
香織は俺に束縛されるのを嫌った。なのに俺は、香織を束縛するようなことしかできなかった。現に、離婚してからの香織は水を得た魚のように活動的になり、自分の力で自分の生きる道を切り開いている。
一方の俺はどうだ。
タマネギがしんなりとしてきた。中火にしてニンジンを投入して更に炒める。どうせ後で煮込むからこちらは完全に火が通らなくても構わない。適度に炒まったところで、肉を入れて更に炒める。肉から脂が出ていい音を立てる。エアコンを掛けていても額に軽く汗が浮かぶ。
肉の色が変わり、軽く焼き目がついたので炒めた具材を鍋に移し、水とジャガイモを加えて中火で煮込む。
離婚して三年、一体俺は何をしてきたのだろう。同じことの繰り返し、それだけじゃないのか。
香織と別れてから、何か新しいことに挑戦したか。
香織と別れてから、新しい恋をしたか。
香織と別れてから、人間として成長したか。
いずれも自信を持って答えることができない。
具材を煮込んでいる間に、まな板や包丁など、これまでの調理に使った器具を洗っておく。時間は無駄にしないのも、料理するときに大事なことだ。片付けまで含めて効率的にこなすことが必要だ。
──あなたのことが嫌いになったわけじゃないの。でも、あなたはわたしのことを、何もわかろうとしてくれなかった──
不意に、別れるときに香織が言った言葉が甦る。胸の奥が微かに疼く。
洗った器具を布巾で拭いて元の場所にしまい、調理で出た生ごみをまとめ終わると、折よく鍋が沸騰しはじめた。浮かんでくるアクを丁寧にすくう。これをきちんとやるかどうかで仕上がりに差が出る。
俺は、香織の思いをすくい取ることが最後までできなかった。
香織が何を考え、何を求め、何を望んでいるのか。もっと丁寧に接していれば、わかることができたのかもしれないのに。
心に湧き上がるのは後悔ばかりだ。
アクをすくい終われば、あとは具材に火が通るまで待つだけ。朝、タイマーをセットしておいた炊飯器から湯気が立ち上っている。時計を見ると一九時半、ちょうどいい時間に仕上がりそうだ。
香織は二〇時頃にあのんを連れてくる約束だ。もっとも、香織のことだから約束の時間ぴったりに現れることはないだろう。
俺はダイニングチェアに座って煙草に火を点けた。
紫煙の行方をぼんやりと追う。
香織のために一度はやめた煙草を、結局俺はまた吸っている。
俺はあれからずっと、立ち止まったままなのかもしれない。
炊飯器のアラームが鳴り、飯が炊けたことを知らせる。
俺は立ち上がって一旦鍋の火を止めた。ルウを開けてばらばらと割り入れる。スパイスの香ばしい匂いがキッチンに立ち込める。焦げ付かないようにお玉で軽く混ぜながら、弱火で最後の仕上げ。
ふと、自分が鼻歌を歌っていることに気づいた。
やはり、浮かれている。
俺は、香織と食事ができることを楽しみにしている。ここ最近なかった心の動きに、俺自身が驚く。
ざわめく心を鎮めようと、もう一本吸う。
俺は、香織に捨てられたんだ。元の鞘に戻るなんて、ありえない。
そう自分に言い聞かせても、心のざわめきはなかなか鎮まらなかった。
「来たよー。お、カレーにしたんだ」
玄関を開けるなり香織が声を上げた。
「見て見てー、あのんかわいーでしょ?」
香織は廊下を小走りしてリビングまで来ると、脇にぴたりと寄り添っていたあのんの背中を押して前に出す。
ぼさぼさだった黒髪は綺麗に切り揃えられ、涼やかなボブカットになっている。白い半そでのワンピースに膝下丈の黒いレギンス。肌の色は濃いが、どこにでもいる小学生、といった印象だ。
あのんは後ろにいる香織の顔をしきりに見上げている。
「お、涼しそうでいいじゃないか」
「でしょー?」
「あー」
香織が大袈裟に声を上げると、あのんもくすぐったそうな顔で言葉にならない声を上げた。
「よし、あのん、おじさんのカレー、ごちそうになろう! まずは、手を洗ってから!」
「なー」
昨日まで一人で暮らしていた広い部屋が、いきなり賑やかになったことに、俺は戸惑う。しかし気づいてみたら、いつの間にか俺も頬を緩めていた。
別れた夫婦が、身元不明の少女と三人でダイニングテーブルを囲んで食事する。考えてみると奇妙な光景だ。
「ねえ、あのんってすごいんだよ」
「何が?」
「一度見たら、すぐにおんなじことを真似できるの」
「へえ」
香織はスプーンでカレーを豪快にすくいながら口に運ぶ。
「お昼の時、お箸が使えなかったから、きちんと持たせてあげて、こうするのってやって見せてあげたら、すぐ上手に使えるようになったの」
「それすごいな」
俺は香織と結婚してから自己流の箸の持ち方を香織に矯正されたが、きちんと使えるようになるにはずいぶんと苦労した。
「あのんは左利きなんだよねー」
「あー」
確かにあのんはスプーンを左手で持っている。
「それだけじゃないんだよ。仕事中あのんが退屈しないようにずっとミュージックビデオのチャンネル流してたらさ、振付をすぐ真似するんだ。マイケル・ジャクソンなんかもさらっと真似しちゃうから、もうびっくりして」
香織はスプーンを持ったまま大袈裟な身ぶりを交えて熱っぽく語る。
「へえ、あのんはしゃべれない代わりに、身体能力が高いのかもしれないなあ」
「らー?」
俺がそう言うと、あのんは大きな黒い瞳で俺の顔を不思議そうに覗き込んだ。その表情はやはり子猫のようだ。
それにしても、香織とこうして再びこの部屋で会話しながら食事をすることになるとは、思いもしなかった。会話の中身は他愛もないことだが、誰かと会話しながら食事するなんて、本当に久しぶりだ。胸の底に穏やかな気持ちが甦るのを感じる。
一緒に暮らしていた頃は、香織の話は退屈で中身がないと思って聞き流していたが、本当は、俺が関心を持とうとしていなかっただけなのかもしれない。
「ねえ、こうしてると、わたしたち、なんか家族みたいだよね?」
香織が笑顔で俺に問いかけた。
「あ……ああ」
〈家族〉という響きに、俺は少しうろたえる。
確かにそうだ。この光景を何も知らない人が見れば、何気ない一家団欒のように見えるだろう。
「あのん、わたしの子になっちゃおっか?」
「なー」
「んー、あのんいい子ー!」
あのんが笑顔で答えると、香織は隣に座っているあのんをぎゅっと抱きしめた。あのんもはしゃいだ声を上げて笑う。
その声を聞きながら、俺は少し複雑な気分だった。
香織はすっかりあのんと暮らす気になっている。そして俺も、あのんがこのままここにいてくれたなら、と思い始めている。この子がいるなら、もしかすると俺は香織とやり直せるかもしれない。
しかし、あのんについてはわからないことばかりだ。篠田とも、まだ連絡が取れないままだ。
どこか不穏な匂いを感じながらしかし、俺は目の前の幸福に、身を委ねようとしていた。
〈四〉
「おーい、朝飯できたぞー」
俺は香織とあのんが寝ている寝室に向かって呼ぶ。
「らー」
あのんが寝室のドアを開けて廊下をどたどたと走ってくる。
「こら、あのん。危ないから走っちゃだめだ」
「なー」
俺が叱ると、あのんはちょっとバツが悪そうに軽く肩をすくめた。
「あー、ありがとう」
寝ぼけ眼をこすりながら香織もパジャマのまま寝室から出てきた。
「お前、相変わらず朝弱いんだな」
「自営業者ですから」
香織はそう言って大きなあくびをする。
昨晩、食事が終わっても遅くまであのんと遊んでいた香織は、結局また俺の部屋に泊まった。確信犯だろうと俺は睨んでいる。もっとも、それを見越して三人分の朝食の買い物をしておいた俺も、似たようなものだ。
「おー、あなたの作った朝ごはんなんて久しぶりだー」
「俺だって久しぶりだよ。お前と別れてから、自炊なんてずいぶんしてないからな」
あのんはさっさとダイニングチェアに座って、足をぶらぶらさせながら俺たちの会話を聞いている。
本日の朝食メニューは洋風。スクランブルド・エッグにカリカリに焼いたベーコン、茹でたグリーンアスパラにマヨネーズを添え、ミニトマトで彩りを。それからクルトンを入れたオニオンスープに、山高パンのトースト。
「ふふ、美味しそうじゃん」
「大したことないよ」
香織が褒めるので、俺は照れ隠しに素っ気ない言葉で返した。
「んじゃ、いただきまーす」
「あー」
香織が声を上げると、あのんもそれに続いて声を上げた。すっかり香織に懐いている。
リビングに面した広い窓から、朝日が差し込む。久々の晴れ空だ。今日は暑くなりそうだ。窓からは、海峡の向こうの山並が見える。香織が気に入っていた、素晴らしい眺望。平穏な光景。
香織と別れてから灰色にしか見えなかったこの部屋が、今朝は彩りに溢れて見える。
ふと、これは夢ではないかと疑う。
「ねえ、今日ちょっと買い物しない? あのんの着るものとか、もうちょっと買い足してあげたいし」
香織はそう言ってトーストをかじる。さくっという小気味のいい音を立てて。
「俺は財布代わりか? ま、別にいいけど」
「バレたか」
「あー」
香織が小さく舌を出すのを見て、あのんが声を上げて笑う。
この子は俺たちの会話がわかっているのだろうか? いや、きっと香織が笑うのにつられて笑っているだけなのだろう。しかし、こどもの笑い声がこれほど心地よいものだとは、思ってもみなかった。
「じゃあ、どこに行くかな」
俺はそう言ってオニオンスープをすする。このマンションの隣にも大型スーパーがあるが、それでは近過ぎて面白みがない。
「駅前のポルトにしようよ、新しいショップ入ったみたいだしさ」
「それもお前の趣味だろ?」
「もう、細かいことは気にしないの」
俺が苦笑いしながら返すと、香織はそう言ってまたトーストを頬張った。いつでもそうだ。香織は自分の都合を最優先で考える。俺たちが恋人同士だった時から、ずっと。
それがかわいいと思っていたこともあった。逆に、重荷に感じたこともあった。
だが、今はどちらでもいいような気がする。香織はやっぱり香織だ。
「じゃあ、片付けたら出掛けようか」
「オッケー」
「んあー」
あのんが口をもごもごさせながら、俺と香織の顔を交互に見比べて笑った。
女の買い物は概して長い。
あれもいい、これもいい。男から見たらなぜそんなことにこだわるのか全くわからない些細な違いに、いくらでも迷い続け、悩み続ける。
だから、香織と一緒に暮らしていた時、俺は香織と買い物に行くのが苦痛だった。いつもイライラして、香織と口論ばかりしていた気がする。
今日は最初から長丁場になるだろうと覚悟している。何を買うか、どうせなかなか決まらないだろう。
香織とあのんはいくつかのショップを回り、様々な服を見ている。もうかれこれ一時間になると思うが、まだ何も買っていない。
俺は、その後ろを何も言わずにのんびり追い掛けているだけ。
買う物が決まることさえ諦めてしまえば、あれやこれや言いながらはしゃいでいる香織を見るのは、結構楽しい。
そう言えば、ポルトでは恋人時代から香織に何度も引っ張り回された。
昔は「ポルト西関」と呼ばれていて、いかにも昭和のショッピングモールという雰囲気だった。何年か前に大規模改修して「オーヴェスト・デル・ポルト」と洒落た名前に変わり、店舗もずいぶん入れ替わったが、どこか昔の面影を感じさせる。
香織の長い買い物にうんざりしながらつきあったのも、今となっては思い出だ。ここで口論したのも、一度や二度ではない。
あのんは香織が選んだ服を何度も試着している。試着室のカーテンを開ける度に、にかっと笑う。左下の犬歯の抜けた歯を見せて。
その度に香織は「かわいー!」を連発する。俺が、あのんは着せ替え人形じゃないぞ、と釘を刺してもどこ吹く風。そして、どれにするかまた迷うのだった。
あのんもそんな香織のリアクションが楽しいらしく、黒い瞳をまんまるにして何度も声を上げて笑った。
あのんは何を着てもすとんと似合ってしまう。確かにかわいい。
飾り気のないかわいらしさ。
こどもが本来持つのびやかなかわいらしさが、あのんにはあると思う。
意味のある言葉をしゃべらない分、この子は身体全体で感情表現をするようだ。言葉を発しなくても、豊かな表情と仕草や行動で、あのんがどう感じているのかは俺も香織もすぐにわかる。
ああ、こどもっていいものなんだな、と俺は初めて感じた。
もし、香織との間にこどもがいれば、俺たちは別れなかっただろうか?
俺は、もう少し寛容になれたかもしれない。香織も、もう少しだけ我の強さを抑えたのかもしれない。
いや、意味のない空想だ。
「ねえ、これよくない?」
香織がこう尋ねてくるのももう八回目。
「うん、いいんじゃないか」
あのんが着ているのは、紺のボーダー柄のTシャツに、カーキ色の膝上丈のキュロットスカート、柄物のニーソックス。活発な印象のボブヘアにぴったりマッチしている。
あのんはちょっとはにかんでみたり、試着室のカーテンにくるまってみたりと、じっとしていない。
「よし、まずこれに決まり!」
香織が満足げな声を上げる。
「まず、ってことはまだ買うんだな」
「当ったり前じゃん、まだまだいくよー!」
「らー」
香織が弾んだ声を上げると、あのんもそれに続いて飛び跳ねる。
「わかったわかった」
俺は財布を取り出しながら思わず頬を緩める。
長いこと忘れていた笑い方だな、と感じながら。
服の物色に夢中な香織に、ちょっと一服してくると断って、俺は喫煙ルームに向かう。
煙草も勿論だが、篠田に電話を入れるためだ。自分から連絡すると言っておきながら、一昼夜まったく連絡が取れないのは少し異常だ。
煙草に火を点けると、口に咥えたままスマートフォンを取り出して電話を掛ける。
一秒、二秒、「おかけになった電話は──」
俺は親指を画面に押し付けて電話を切った。篠田への発信履歴はもう一〇回を超えている。
一体、篠田に何があった?
俺は紫煙を吐き出しながら考える。
交代勤務だとは聞いていたが、これだけまったく連絡が取れないのはいくらなんでもおかしい。そこまで親しい間柄ではないから、メールや無料通話アプリのアカウントも知らない。
ふと思いついて、ネットで入国管理局西関出張所の電話番号を調べる。
画面に表示された電話番号をタップ。
一コール、二コール、三コール……
誰も出ない。土曜日だから不在なのか。
……八コール、九コール。
やはり出ない。
『入国管理局西関出張所です』
もう切ろうかと思った十コール目で、電話が繋がる。
「あ、すいません。篠田さんは今日出勤されていますか?」
急に繋がったので慌てた俺は少し上ずった声で電話口の女性職員に尋ねた。
『篠田は本日お休みをいただいております』
「昨日はどうでしたか?」
『昨日も不在でしたが──失礼ですが、どちらさまでしょうか?』
女性職員は不審がって俺に尋ねる。
「篠田の友人です。聞きたいことがあったのですが、連絡が取れなくて、やむを得ず勤め先であるそちらにお電話しました」
『実は、篠田とは当方も昨日から連絡が取れておりません。本日も出勤の予定だったのですが、欠勤しております。もし篠田から連絡がありましたら、こちらにも連絡するようお伝え願えませんか』
身体が奇妙にざわめくのを感じる。
電話を切ってからも、俺はしばらくその場を動く気になれなかった。
篠田が無断欠勤している。
俺の知る限り、篠田はそんなことをするような男ではなかった。良くも悪くも、折り目正しく几帳面。大学の頃も講義は全部出席していた。講義をさぼってばかりいた俺は、あいつのノートに随分と世話になった。
そんな篠田が、職場に連絡もせずに欠勤している。
あのんを俺に預けたまま、あいつは失踪したのか?
いや、まだそう決めつけることはできない。しかし。
何かが起きている、そのことだけは確かなような気がした。そしてその何かには、あのんが関わっているのではないかという、厭な予感が膨らむ。
その予感を振り払うように、俺は煙草をもみ消した。
馬鹿げている、考え過ぎだ。あくまで想像でしかない。今夜にでも、篠田は何事もなかったかのように俺に電話してくるに違いない。
俺は吸い殻を灰皿に何度も押しつけてから喫煙ルームを出た。
「遅いー! ほら、見て見て、いいでしょこれ!」
香織が大声で呼ぶ。
あのんが着ているのは、パステルカラーのブラウスに花柄の短パン。ちょっとすました顔で立っている。育ちのいいお嬢さん、といった雰囲気。着ているものによって、あのんの印象はコロコロと変わる。
無邪気なあのんの姿を見ていると、さっき感じた不吉な予感はすっと消えていく。やっぱり俺の考え過ぎだろう。
結局、その後も二時間たっぷり店内をぐるぐる回り、結構な量の買い物になった。勿論、荷物を持つのも俺だ。これも想定の範囲内。俺も、もうこんなことぐらいでいちいち腹を立てなくなった。歳をとったということなのかもしれない。
昼食はポルトのフードコートでとることにした。土曜日だから、家族連れが多い。
正直なところ、俺はこういう騒々しいところは苦手だ。出来れば静かな場所で落ち着いて食事したい。しかし改めて眺めていると、それぞれの家族が思い思いの形で食事しているこのフードコートという場所も、案外面白いことに気づく。
幼い妹にちょっかいを出しては母親に叱られている五歳ぐらいの女の子。
三人の男の子を相手に悪戦苦闘している母親。
小学生ぐらいの二人の女の子の孫に両手を引っ張られ、嬉しい悲鳴を上げているおばあさん。
そうかと思えば、こどもそっちのけで会話に夢中になっているママ友グループ。
片手で赤ちゃんを抱えながらベビーカーを押す父親。
チャイルドチェアに座らせた男の子にものを食べさせながら微笑んでいる母親と、その様子を笑顔で眺めている父親。
ペアルックにサングラス、同じハットでキメた老夫婦。
実に様々な家族模様があちらこちらで展開していて、見ていて飽きない。
俺たちにしても、見た感じは普通の家族に見えるかもしれない。
「ねえ、あなた変わったよね」
香織はコチュジャンをたっぷり入れた石焼ビビンパをほおばりながら俺に言う。
「どこが」
俺は、鉄板の上でソースが音を立てているお好み焼きをヘラで切りながら尋ねた。
「時間を気にしなくなった。昔はずっと何かに追われてるみたいだったよ。いつもイライラしてさ。時計ばっか見て」
「そうだったかな」
俺はそう言ってお好み焼きを口に入れる。口中に香ばしいソースの香りが広がる。
「今は、なんか余裕ある感じ。わたしは、今のあなたの方がいいと思うな」
香織はそう言って微笑んだ。
あのんはハンバーガーにかぶりついて、口の周りをソースまみれにしている。
「香織は、変わらないな」
「それって成長がないってこと?」
ちょっとふくれ面をしながら香織が返す。
「いや、ずっとまっすぐで、自分に正直なままだってこと」
「そりゃ、どうも」
香織はふくれ面のまま素気なく返した。こういうリアクションをするのは、照れている証拠だ。
口ではああ言ったものの、実際には逆で、変わったのは香織の方だろう、と俺はお好み焼きを切り分けながら考える。変わっていないのは、毎日をぼんやりと過ごしているだけの俺の方だ。
自分の手を、誰かの喜びのために使う仕事。香織は自分の仕事についてそういう言い方をしたことがあった。何もないところから自力で販路を切り開き、少しずつ着実に顧客を増やしている。それが並大抵のことでないことぐらい、俺にもわかる。
仕事の話をする時、香織は少女のように目を輝かせる。
正直なところ、俺にはもうそんな情熱はない。惰性で続けてはいるが、就職したての頃のような志や夢は、とっくに失くしてしまっている。我ながらつまらない男になったものだ。
自分の仕事に誇りを持っている香織を、俺は少し羨み、そして嫉妬している。
俺の時間は、香織と別れたときから止まったままだ。香織はその間に自分で歩みを進めて、だいぶ遠くに行ってしまったように感じる。
そんな卑小感を誤魔化そうと、俺はお好み焼きを思い切り頬張った。
「熱っ!」
「あーあー、そんな大きいの口に入れるから」
「なー」
香織とあのんが声を上げて笑う。
「ソースついてる」
香織が紙ナフキンで俺の口元をぬぐってくれた。
「あー、口の中やけどした」
「らー」
俺がコップから水を飲むとあのんがまた声を上げて笑う。
「バッカみたい」
そう言いながらも、香織はふっと微笑んだ。
昔と変わらない笑顔だった。
〈五〉
「大丈夫? 重くない?」
「ああ、大丈夫」
あのんを背負った俺に、香織が心配そうに声を掛けた。
結局夕方までかかって買い物を終え、夕食は回転寿司で済ませた。あのんは覚えたばかりの箸を器用に使って、びっくりするほど食べた。その様子を見て、俺は香織と二人で笑った。
あり得たかもしれない、平凡な家族の風景。つい一昨日まで、俺には縁がないと思っていた幸せが今、目の前にある。そう思うと不思議だった。
香織がアパートに着替えを取りに帰るというから車で立ち寄った僅かな間に、あのんはいつの間にかすとんと眠ってしまった。
マンションの駐車場からあのんをおぶって運ぶ。あのんは俺の背中で小さな寝息を立てている。初めてあのんに触れた時と同じ温かみが、背中を通じて俺に伝わる。
辺りはすっかり夕闇に包まれたが、日中の余熱がまだじんわりと残っていて、俺は軽く汗ばむ。
「だいぶはしゃいでたからな、疲れたんだろ」
「わたしも楽しかったあ。こんなにいっぱい笑ったの、久しぶりだよ」
香織は少し先を歩きながら俺に振り返って笑う。俺も同じ思いだ。
エントランスに入ると、両手がふさがっている俺に代わって、香織がドアの開錠をしてくれた。
エレベーターが階上から降りてくる。エレベーター脇のモニターに映る室内には、あのんと同じぐらいの年齢の娘とその母親が何か話している様子が見える。
エレベーターが一階に着いて扉が開くと、女の子のはしゃいだ声が溢れ出てきた。
「こんばんは」
香織が挨拶すると、女の子は急に神妙になって軽く頭を下げる。母親も「こんばんは」と返した。入れ違いで俺たちがエレベーターに乗り込むと、女の子は再び母親に何事か大声で話しかけている。
「なんか、いいよね。ああいうの」
扉が閉じてエレベーターが上昇を始めると、香織がぽつりと呟いた。
「ああ」
俺は低く応じる。
そのまま、俺も香織も黙る。
エレベーターが一一階に着いて扉が開く。
一一〇二号室。
俺も香織も、無言で部屋に入った。
あのんを背中からソファにそっと降ろす。
部屋には日中の熱気が籠もっているから、すぐにエアコンを掛ける。
あのんはよく眠っている。香織がタオルケットを持ってきて、あのんに掛けた。ソファに横たわっているあのんの髪をそっと撫でた後、香織は立ち上がると、俺に向き直った。
眼鏡の奥からじっと俺の目を見つめる。
俺も香織を見つめた。
かつて愛し、そして別れた女が、俺を見つめている。
どちらからともなく、俺たちは歩み寄った。
香織の手を取る。
そのまま唇を重ねる。
懐かしい匂いと共に、香織の体温を、直に感じる。
身体が熱くなるのを感じる。鼓動が少しずつ早まる。
互いに目を見つめ、目を閉じては何度も唇を重ねる。
このままではいけない、と思いながらも俺は香織から離れることができない。俺は両腕を香織の腰から背中にまわす。香織も両腕を俺の背中にまわした。強く抱きすくめる。
求め合う。
舌を絡め合う。
もう押し止めることができない。
右手で香織の小さな頭を自分に引き寄せる。そっと髪を撫でる。香織の熱い吐息を間近に感じる。
何度も何度も口づける。互いの吐息だけが聞こえる。
「ねえ」
香織が小さく囁いて寝室の方に視線を送った。俺も頷く。
寝室に入り、内鍵を掛ける。
俺と香織は再び抱擁し、唇を重ねる。
いいのか? そう自分に問いかける声も、高鳴る鼓動が掻き消す。
俺は自分のシャツのボタンを外す。上から一つ、二つ……もどかしくなって肌着ごと上から脱ぎ捨てる。
香織は眼鏡を外し、Tシャツを脱いでいた。うるんだ瞳が俺を見ている。懐かしい眼だ。俺は再び香織を抱き寄せた。
キャミソールの上からそっと胸に触れる。
「は……」
香織が声にならない吐息を漏らす。それを重ねた唇で塞ぐ。
そのまま二人でベッドへ倒れこむ。ベッドの軋む音。
何年ぶりになるのか。
頭の隅でそんなことを考える。しかし、答えを出すより先に体が動く。
唇を重ねたまま香織のキャミソールの裾から右手を差し入れる。柔らかな肌が直に触れる。汗ばんでいるからか、少しひんやりとしている。
香織も両手で俺の背中を撫でる。
俺は右手を更に奥へと進める。指がブラを探り当てた。そのままブラの上から掌で香織の乳房を包み込む。
「ん……ふう」
香織が再び息を漏らし、背中を反らせる。
俺は左手もキャミソールの裾に入れて両手を香織の背中にまわす。薄暗い中、香織の白い肌があらわになる。
ブラのホックを外すと、キャミソールの中で乳房を包み込む。
「あ……っ」
香織が小さく声を上げた。柔らかな乳房が、俺の掌の中で形を変え続ける。
「少し痩せたか?」
俺が低く囁くと、香織は黙って頷いた。
普段なんでもないような顔をしていても、やはり苦労はしているのだろう。
急に愛おしさがこみ上げる。
首筋に、耳朶に口づける。何度も、何度も、少しずつ位置を変えながら。その度に香織は小さく喘ぐ。昔と変わらない声だ。
香織の身体を抱き起こすと、香織は自分で脱いでショーツ一枚になった。俺も同じように下着だけになる。
再び強く抱擁する。香織の少し汗ばんだ肌が俺の肌にじかに触れ、熱を帯びてきているのがわかる。
胸元に口づけ、そのまま舌を鳩尾に這わせ、左の乳房の輪郭をなぞる。
香織が小刻みに喘ぐ。
「んっ……」
唇で乳首を咥えると香織は小さく震えた。そのまま舌の上で乳首を転がすと、その度に香織は甘い吐息を漏らす。俺は出来るだけゆっくりと、丁寧に愛撫を続ける。
昔の俺なら先を急いでいたかもしれない。しかし、今日はゆっくりと香織を感じていたい。香織の体温を、汗ばんだ肌の柔らかさを、懐かしい匂いを。
三年の時を経ても、香織は少しも変わっていなかった。
俺はそれを自分の肌で少しずつ確かめていく。
できるだけ丁寧に、優しく香織に触れる。以前出来なかったやり方で愛したい。焦る必要などない。
香織は俺の愛撫に敏感に反応する。
足首、膝頭、内もも、脇腹……。何度も口づけ、指でなぞり、舌を這わす。その度に香織は小さく震える。
香織の反応に、俺は静かな悦びを感じる。
求めるように香織が手を差し伸ばしてくる。俺はしっかりと指を絡めて香織の手を握った。香織も強く握り返す。
ああ、これだ。
俺は、香織を求めている。香織も俺を求めている。
昔の俺は、自分のことしか考えていなかった。セックスはもちろん、生活のあらゆる場面で。
結婚していた時には遂に気づくことのできなかったことに、今さらになって気づく。遅すぎたのかもしれない。
いや、今はそんなことはどうでもいい。
もっと香織を感じさせたい。乱れさせたい。
そんな感情が俺を突き動かす。
「ふあっ……」
ショーツの上から香織の秘所に指を這わすと、香織は思わず声を上げて両膝を合わせた。
「感じるのか?」
「もう、バカ」
俺が尋ねると香織は右手で俺を軽く叩く真似をした。
「ふふ」
俺は声を出して笑った。まるで少女のようだ。
そのまま指を這わせる。円を描くように秘所をなぞる。奥が熟してきているのがショーツの上からでもわかる。
「ん……」
香織は力を抜いて俺の指の動きに身を任せている。
指先でショーツをずらして中に侵入する。
「ん……んむぅ……」
香織が声を上げそうになるところを唇で塞ぐ。
指先だけ香織の中へ。溢れる蜜が指に絡みつく。俺はその感触を愉しむ。
香織が下着の上から俺の股間にそっと触れてきた。形を確かめるように掌で包み込んで撫でまわす。
「お……」
思わぬ刺激に思わず声が漏れる。
「ふふ、大きくなってる」
香織が笑う。
「当たり前だろ」
何が当たり前なのか、言いながら自分でもよくわからないが、香織の指の動きに背筋を快感が昇る。
「ちょっと、待ってくれるか」
もう限界だ。
俺は下着を取ってローチェストの引き出しからコンドームを取り出すと、封を切ってペニスに被せた。昔使っていた分の残りだ。香織もショーツを取った。
ベッドの上で再び肌を重ね合わせる。きつく抱き合って接吻する。
互いの吐息が混じり合う。
ゆっくりだ、丁寧に。
自分にそう言い聞かせながら、位置を探りゆっくりと挿入する。
「は……んあっ」
俺のものが触れると、香織がひときわ高い声で喘いだ。
少しずつ香織の中へと入ってゆく。
「む……う」
奥まで達すると、俺も思わず呻き声を上げた。すぐにでも達してしまいそうだ。
挿入したままお互い荒い息で唇を重ねる。舌を絡ませながら、香織の熱を全身で感じる。
ゆっくりと動く。
「んあ……はっ……あん……」
俺の動きに合わせて香織が声を上げる。
動きながら何度も香織と接吻する。動く度に呼吸が、声が乱れる。鼓動が高鳴る。
香織が締めつけてくる。
俺は徐々に動きを早める。
「……はっ……あ、あっ……」
香織の声が更に高くなる。
もう何も考えられない。
「むっ……ああ!」
精液を放った瞬間、俺も思わず声を上げて一度動きを止めた。
まだだ。まだ香織が達していない。
荒い息のままゆっくりと前後に動く。
「あっ……は……あ、あぁっ!」
香織の身体がびくんと波打ち、両腿で俺の身体を締めつける。
絶頂を感じたようだ。
寝室には二人の荒い呼吸だけが聞こえている。
俺はなおも香織の中にとどまっている。
まだ香織を感じていたい。
その姿勢のまま、互いに荒い息で接吻する。
何度も、何度も。
これまでの空白を埋めるように。
〈六〉
「あー」
あのんがドアの外で呼んでいる。
「あー」
ドアノブをがちゃがちゃと回したり、ドアを叩いてみたり。
俺はまだぼんやりした頭で起き上がった。
昨晩は何度も香織と交わった。部屋の中には、まだ残り香が漂っている。
隣では香織が寝ている。一糸まとわぬ姿で。
急に頭が冴える。
「やべ」
俺は慌てて昨晩脱ぎ散らかした服を着る。
「おい、香織」
「んー、あと五分……」
俺が呼ぶと、香織は寝返りを打ちながら呟いた。
「あのんが起きて呼んでる」
「えっ」
ようやく自分が裸であることを思い出したようだ。
「や、ちょっと。先に出てごまかしといて!」
香織は顔を真っ赤にして慌てて薄掛けの布団にくるまった。
「仕方ないなあ」
俺は頭を掻いて苦笑いする。
中が見えないように、俺は自分の身体を衝立にして細くドアを開けて廊下に出ると、すぐに後ろ手で閉めた。
「らー」
あのんが少しむくれた顔で声を上げる。
「おなか減ったんだろ?」
「あー」
あのんは俺の顔を見上げると、俺にしがみついてきた。
あのんが自分から俺に触れてきたのはこれが初めてだ。
俺が頭を撫でてやると、あのんは俺の左手を両手で握ってぶらぶらと振る。
「あー」
むくれた顔で俺を見上げる。
「わかったわかった、すぐ朝ごはんにしよう」
俺は思わず吹き出した。
既に夏の日差しが照りつけている。今日も暑くなりそうだ。この分だと、梅雨明けもそう遠くないだろう。
今日の朝食は、ザワークラウト(ソーセージ入りの酸っぱいキャベツスープ)にフレンチトースト。独仏共演だ。
「ねえ、今日はちょっと散歩でもしない?」
香織がソーセージを口に入れながら唐突にそんな提案をした。
「今日はかなり暑そうだぞ。お前、暑いの苦手じゃなかったっけ?」
俺はフレンチトーストをフォークで切り分けながら返す。
「なんか、久しぶりにこの辺り歩いてみたくなったの」
「相変わらず気まぐれだな」
そう言って俺はフレンチトーストを頬張る。
香織の気まぐれは今に始まったことではない。じっくりつきあえばいい。
「あのん、一緒に遊ぼうねー」
「あー」
あのんは香織の呼びかけに無邪気な笑顔で応じた。左下の犬歯が抜けた歯がのぞく。その顔を見ているだけで、穏やかな気持ちがじんわりと胸の中に広がる。
自分の中に、こんな気持ちがまだ残っていたとは思わなかった。
香織と別れたとき、自分にはもう何の感情も残っていないと思っていた。同じことを繰り返す毎日を、魂の抜け殻のように、ただぼんやりとやり過ごして生きていると思っていた。
そんな俺が、再び笑っている。
「ねえ、何ニヤニヤしてんの? 思い出し笑い?」
左手で頬杖をつきながら香織がからかう。
「べ……別に。どうでもいいだろ、そんなこと」
俺は慌てて誤魔化す。
「ふふ、照れてる」
「なー」
香織とあのんが声を上げて笑う。
俺も一緒に笑った。
じりじりと照りつける強い日差しがアスファルトを溶かしてしまわないか心配になるほど暑い。まだ午前中だというのに気温はぐんぐんと上がっている。
マンションから西へ向かって坂を上る。
少し上れば、丘の頂点。空が頭上に大きく開けている。雲一つない快晴だ。太陽が容赦なく照りつける。まだ五分も歩いていないが、背中で汗のしずくが流れ落ちていくのを感じる。
片側二車線の県道がまっすぐに伸びる。熱された路面から陽炎が立ちのぼり、走り去っていく車の輪郭をゆらゆらと歪める。日曜日だからか、車の往来はいつもよりは少ないようだ。歩道には街路樹もあるが、木陰を作るほど繁ってはいないから、歩いていると直射日光をじかに浴びる。
この辺りは高度成長期に開発された古い住宅地で、周囲には学校も多い。小学校の門を左に見ながら緩やかな坂を下る。あちらこちらからアブラゼミの声が降り注いでくる。
あのんは歌うように意味のない声を発しながら、白い日傘をさした香織と手を繋いで俺の前を楽しそうに歩いている。昨日買ったばかりのパステルカラーのブラウスの裾が歩く度に揺れる。歩道に落ちた二人の濃く短い影が躍っている。
しばらく進むと、跨線橋に差し掛かる。跨線橋の下は貨物ヤードで、幾筋ものレールが陽の光を反射している。電気機関車が何両か、退避線に停まっているのが見えた。
「あっついなあ」
香織はさっきからこの科白を何度も繰り返している。
「夏なんだから当たり前だろ」
「あー、やっぱわたし暑いのダメだわ」
「お前が散歩しようって言いだしたんだろ」
「んー、まあそうなんだけどさ」
香織はそう言って口を尖らせた。
今日は珍しく香織がスカートをはいている。ふわりとした白い生地のロングスカートに、淡い水色の半袖ブラウス。いつもは適当に束ねただけの髪も、今日はきちんとまとめている。一緒に暮らしていた頃、どちらかと言えば動きやすさを優先した格好をすることが多かったから、こんなフェミニンなファッションを身に着けた香織を見ることはあまりなかった。
なんとなく恋人時代を思い出す。
俺も香織も若かった。勢いや雰囲気だけで、なんとかなると甘く考えていた。
しかし結婚してからの俺は、香織を傷つけていることにも気づけないほど、心にも身体にも余裕がなかった。
香織はどうだったのだろう。
結局、一緒に暮らしていたとはいえ、俺は香織のことを何もわかっていなかった。
苦い思い出だ。
だが、香織とこんなに穏やかに過ごせる日が来るとは、思ってもみなかった。
跨線橋を過ぎて右カーブを下りていくと、信号の向こう側、正面に緑の濃い小高い丘が近づいてきた。
「ほら、あの上までのぼるぞ」
「うえー」
俺が言うと香織は振り向いて舌を出す。
「なー」
あのんが心配そうに香織を見上げた。
「あのんは元気だねー」
「あー」
香織に応えてあのんが声を上げ、繋いだ香織の左手をぶんぶん振り回す。
「もー、わかったわかった」
香織が思わず苦笑する。穏やかな横顔。
香織がこんな表情をするとは、今まで知らなかった。何年も一緒に暮らしていたというのに。
古い木造住宅が左右に立ち並ぶ、幅の狭い道を登る。
錆びついた赤い郵便受。
横倒しになったままのこども用の自転車。
ひなたで揺れる洗濯物。
薄汚れたモルタルの壁に絡みつきながら伸びる蔦。
日陰に横たわったまま薄目を開けてこちらを見る白黒の猫。
どこからか微かに聞こえるテレビの音声。
地面に伏せたまま目を向けて尻尾だけを振る柴犬。
手を伸ばせば触れられるところに、そこに住む人の生活がある。
その中にいる人にしかわからない苦悩も葛藤も、表からは見えない。ちょうど俺たちの結婚生活がうわべだけを取り繕い、結局破綻したように。だが、見えないからといって、それが存在しないというわけではない。
そんなことをぼんやりと考える。
更に坂を登ると、両側から伸びた木々に覆われて、木陰のトンネルになる。木々の間からは眼下の住宅地の屋根が見える。
「涼しいね」
「ああ」
香織が日傘をたたんだ。
木々の青い匂いと共に、アブラゼミの声が上から容赦なく降り注いでくる。
あのんは十メートルくらい先に走っては、こちらを見て俺たちが追いつくのを待つ。二人が追いついたらまた走って、振り向いて待つ。左下の犬歯の抜けた歯を見せて、何度もにかっと笑う。
「何が楽しいのかな?」
香織が額の汗をハンカチで拭きながらぽつりと呟く。
「この時間が、かな」
俺もぽつりと返した。
カラスアゲハが一羽、ゆるやかに上下しながらゆっくりと俺の視界を横切っていった。
更に登ると、頭上を覆っていた木々が途切れて広場に出た。山頂はちょっとした公園になっている。
真昼の強い日差しが照り返して眩しい。あまりに陽光が強すぎて、空の色は白く霞んでいる。香織は再び日傘をさした。
「らー!」
あのんは声を上げながら走って広場を横切っていく。俺は香織と並んで歩きながらそれに続く。
広場の先の坂を登りきった向こう。
夏空の下、深い色を湛えた海が広がっていた。
「あー!」
あのんが大声で叫ぶ。
「海だねー、あのん」
「らーらーらー」
香織の言葉に、あのんは手摺に手を掛けて嬉しそうに何度も飛び跳ねる。
俺も掌で陽光を遮りながら目を細めて海を眺めた。
海面に色の違う帯が幾筋もたなびいているのは、潮の流れによるのだろうか。海峡を隔てた対岸の街並みが、陽炎に揺らめいている。遠い山並みの上では、暖められた空気が上昇して、見る間に白い雲を形作っていく。
あのんが声をあげながら駆け出した。
強い日差しの下で、両手を太陽にかざしたり、足を跳ね上げたりして遊ぶ。自分の影が刻々と形を変えるのが面白いようだ。
両手を広げてくるくると旋回すると、切り揃えたばかりの髪がふわりと舞う。
バレエのようにさっと脚を前後に広げて跳ぶ。
両手をついて側転する。
背を反らして両手を天に掲げる。
力いっぱい地面を蹴って跳躍する。
その度に声を上げて無邪気に笑う。
無駄のない細い身体が、光を、空気を、あるいは目に見えぬ何かをすくい取ろうと舞踏しているようでもある。
「やっぱり、来てよかった」
香織がはしゃぎ回るあのんを目で追いながら俺に言った。
「ああ、俺もそう思う」
俺もそう応じて、再び海の方を眺めた。
特別に美しい景色ではない。
送電線の鉄塔や工場の紅白の煙突が聳え立ち、埋め立て地には漁港の倉庫や住宅街が広がり、海を隔てた向こうに無機質な工業地帯が続く、むしろ雑然とした景色だ。
夏の強い光に晒され、滲んだ空気の中で揺らめく、日常。
そんなありふれた景色が、忘れられないものになるということを、俺はまだ知らなかった。
〈七〉
週末の真夏日が嘘のように、朝から静かに雨が降り続いている。いよいよ梅雨明けかと思ったが、もうしばらくおあずけのようだ。
あのんは今日も香織に預かってもらった。
丸二日空けてさすがにちょっとやばいから今日は真面目に仕事するよ、と香織は玄関先で俺を見送りながら言った。
なんだか通い婚みたいだな、と俺は笑う。
香織はふふ、と笑ってから、行ってらっしゃい、と手を振った。あのんも言葉にならない声を俺に送ってくれた。
これまでの独り暮らしの方が嘘ではないか、と思える。もしもこれが夢ならば覚めなければいい。職場のデスクでぼんやりとそんなことを考える。
今日は遅くなるかもしれない、と香織は言っていた。男女逆転の通い婚か、と俺は一人で苦笑する。
香織が遅くなるなら、俺は先に軽めに済ませておいて、香織とあのんには夜食を用意してやろう。何がいいだろうか。
喫煙室で小倉に会った時、改めて禁煙するつもりだ、と言うと奴はマジすかー、と大袈裟なリアクションを返した。課長、やっぱり新しい女でもできたんでしょ、と茶化されたが、別にどう思われても構わない。あのんを含めた新しい形でなら、俺は香織とやり直すことができそうな気がする。そう考えるだけで、同じことの繰り返しだと思っていた仕事も、見え方がまるで変わってくるから不思議だ。苦痛でしかたなかった退勤までの長い時間が、今日はあっという間に過ぎた。
スーパーで買い物をしてから帰宅する。
自分用の夕食は惣菜にして、香織とあのんにはサンドイッチを用意しておくことにした。
具にはベーコン、レタス、トマト。サンドイッチの王道・BLTだ。
ひとまず自分の食事を終えてから作業に取りかかる。
作業と言っても、野菜を洗って切り、温めて柔らかくしたバターを塗った食パンに具を挟むだけ。レタスだけはしっかりと水切りしておかないと後でべたべたになるからキッチンペーパーで水切りした。上から軽く重しをして、具が馴染んだところで耳を落とす。
鼻歌交じりに包丁を入れる。
出来上がったサンドイッチは皿に盛ってラップを掛けて冷蔵庫へ。
まだ時間があるから、と冷蔵庫のドアポケットから缶ビールを取り出しかけたところで、玄関のチャイムが鳴った。
『こんばんは、ムサシ急配です』
軽快な男の声。宅配便らしい。
おや何か頼んでたかな、と思いながら俺はドアを開けた。
ドアの外には、グレーの作業服姿の大柄な男と、黒ジャケットにノータイの中肉中背の男、そして黒のパンツスーツの細身の女。女は左肩から黒のトートバッグを提げている。どう見ても宅配便ではない。
「夜分に恐れ入ります、〈商品〉の回収に参りました」
女がやけに無機的な声でそう言った。
何かおかしい、そう感じた俺は慌ててドアを閉めようとしたが、作業服の男が右足でドアを挟んでいて閉められない。安全靴か。
無言のまま作業服男が力ずくでドアをこじ開け、スーツ姿の男と女が俺を押しのけて室内に入った。
「おい、なんなんだお前ら!」
俺は思わず声を荒らげた。
「申し遅れました。わたくし、商品回収担当の、海田、と申します」
女があくまで慇懃な調子で名乗った。
三人は断りもなく土足で部屋に上がる。男たちはそのまま部屋を開けて回る。
「ちょっと待て! ここは俺の家だぞ!」
「元はと言えばわたくしどもの不手際なのですが、〈商品〉が流出したままでは、何かと不都合がございまして。わたくしどもはその回収を担当しております」
女は俺の抗議を無視してヒールの音を立てながら奥のリビングへ進む。俺は当惑しながら女を追ってリビングに入った。
男たちは無言のままウォークインクローゼットまで開けて確認している。
「当該の〈商品〉さえ滞りなく回収できましたら、わたくしどもは失礼致しますので」
そう言いながら、女はダイニングテーブルの上に腰掛けて足を組むと、尊大な目で俺を見た。俺よりもだいぶ若い。整った顔立ちだが、機械のように無表情で人間味をまるで感じない。
いつの間にか俺の両脇に、男二人が張り付いていた。どちらも体格がよく、力も強そうだ。
「もっとも、回収の妨げになるようでしたら、どのような事態となりましても、わたくしどもは責任を負いかねます。貴方様には賢明にご判断いただけるものと、わたくしは信じておりますが」
そう言って女は怜悧な笑みを浮かべた。
切れ長の目、すっと通った鼻筋、薄い唇にやけに赤い口紅。長い黒髪を後ろで編み上げている。
「〈商品〉って何のことだ。俺には心当たりがない。他を当たってくれ」
俺がそう言うや否や、両脇の男たちが同時に俺の両腕を掴んだ。
そのまま為す術もなく俺は膝を突き、頭を床に押し付けられた。思わず呻き声が漏れる。
「おやおや、これは心外ですね。わたくしどもが何のあてもなくお伺いしたとでも?」
慇懃な言葉遣いとは裏腹に、女の声には明らかに嗜虐性が感じられた。首を押さえつけられているから俺は顔を上げることもできない。
「わたくしどもの取り扱っております〈商品〉です。貴方様が知るべき筋合いのものではございません」
語尾で息がすっと抜けるような喋り方。肚の底に何を隠し持っているかわからない、油断ならない声だ。
オイルライターを点ける音がして、メンソール系の煙草の匂いが降りてくる。女が吸っているらしい。
「どうしてもと仰るなら教えて差し上げるにやぶさかではございませんが、そうなると貴方様も、残念ながらご友人と同じように〈処分〉しなければなりません。それでもよろしいのですか?」
女は口調を変えることなく淡々と続ける。
「ちょっと待て、お前ら篠田に何をした!」
俺は喚いたが、女は何も答えない。
煙をゆっくりと吐き出しているのが聞こえる。
「詮索などしたところで、何も得るものはございません。貴方様はそのくらいの分別を弁えていらっしゃるはずです。違いますか?」
女がそう答えると、俺の目の前でヒールが床を突く音がした。
後頭部に痛みが走る。俺は再び呻いた。女がヒールで俺の頭を踏んでいるのだ。両側から男に組み敷かれて、俺は全く身動きが取れない。
「いかがでしょう。ご協力、いただけませんか?」
そう言いながら女は俺の後頭部を踏みつける。言っていることとやっていることが全く噛み合っていない。
一体この連中は何者なんだ。〈商品〉とは何を指すのか。
さっきの口ぶりでは、恐らく篠田はもうこの世にいないということだろう。
そうまでして回収しなければならない〈商品〉──
──考えられるのは、ひとつ。
あのんだ。
「もうお分かりなのでしょう? 〈商品〉さえ回収できれば、わたくしどもはそれでよいのです。どこにあるか、教えていただけませんか」
女はそう言いながら俺の後頭部を踏みつける。馬鹿丁寧な口調が余計に腹立たしい。
俺は身をよじって何とか拘束を逃れようと試みるが、びくともしない。
そういえばこいつらが来た時、エントランスのインターフォンではなくドアチャイムが鳴った。その時におかしいと気づくべきだった。
今更後悔しても遅い。
目的を果たしたとして、篠田を消したこいつらが、顔を見た俺を生かしておくとは思えない。あのんはもちろん、香織のことを知ったら、香織にまで危害が及びかねない。
しかし、俺にはどうすることもできない。
いつもの気まぐれを起こして、香織がこの部屋にあのんを連れて来ないことを、祈ることしかできなかった。
奴らは結束バンドで俺を後ろ手に縛ると、リビングの床の上に転がした。黒ジャケットの男が俺の腹を蹴るというオマケまでついた。
この男、一見カタギの営業職風だが、目が決して笑わない。何をするかわからない不気味さを漂わせている。
もう一人の作業服の男は身長が一九〇センチはありそうな大柄で、腕も胸板も逞しく盛り上がっている。しがない事務屋の俺では、どうやっても太刀打ちできそうにない。
女はソファに座って悠然と煙草をふかしている。
ちょうとリビングの時計が見える。二〇時三二分。時間が全く進まない。
「なあ」
俺は女に声を掛ける。
「俺がその〈商品〉を買い取ることはできないのか」
賭けだ。
もしも奴らが乗ってくれば、あのんを助けることができるかもしれない。
「わたくしどもはあくまで回収担当です。取引については関知致しかねます。それに、貴方様に手の出せるような代物ではございませんよ」
そう言って女は俺の申し出を冷ややかにあしらった。
「貴方様に可能な選択肢は、大人しく〈商品〉の場所をわたくしどもにお教えいただくか、このままご自分の意志を貫かれるか、どちらかです。いずれに致しましても、わたくしどもはあらゆる方法で〈商品〉の回収に全力を挙げる、それだけですが」
黒ジャケットの男が女に何か耳打ちする。
「ご準備が整いましたので、こちらへ」
女はそう言いながら口元だけで笑い、バスルームの方を指した。作業服の大男が力任せに俺を立たせ、後ろから小突いて歩かせる。
バスタブに水が張られている。
「どうする気だ」
俺が言い終わるや否や、作業服の男は俺をバスタブの前に打ち据えた。
「少し、気分転換でもいかがですか」
女がそう言った途端、俺は乱暴に首筋を押えられてバスタブの水に顔を浸けられた。ごぼっと息が漏れて泡になる。俺は必死に抵抗するが、男の力が強くてびくともしない。もがけばもがくほど苦しくなる。
もうダメだ、と思いはじめたところで男は俺の首を引き上げた。
俺は何度も咳き込む。何か言おうにも息が荒れて声にならない。
「いかがですか、少しは頭も冷えましたでしょう?」
女の声が冷酷に響く。
呼吸が少し落ち着いたと思ったら、再びバスタブに押さえつけられる。
「時間はたっぷりございます。気が変わりましたら、いつでも仰ってください」
水責めか。男の力は強く、俺は文字通り手も足も出ない。どうやら女は暴力を楽しんでいるようだ。
こうして奴らの〈尋問〉が始まった。
それは俺にとって、いつ終わるとも知れぬ地獄の始まりでもあった。
一体どのくらいの時間それが続いたのか。
何度も意識が遠のいた。
その度に大男が俺の頬を平手打ちして強制的に意識を戻す。
いっそのこと香織のアパートの住所をしゃべってしまおうかと何度も考えた。
あるいは、もう死んでしまった方が楽なのではないかとも思った。
今のこの苦しみが終わるなら。
俺は弱い人間だ。
しかし、その度に二人の笑顔が浮かぶ。香織の悪戯っぽい笑顔。あのんの左下の犬歯が抜けた無邪気な笑顔。
それだけが辛うじて俺の意志を支えた。
玄関から鍵を刺す音が聞こえてくる。
女が身ぶりで指図して、大男に俺の口を塞がせた。バスルームの照明が消される。黒ジャケットの男はリビングで待ち伏せているようだ。
来るな!
俺は必死で祈った。
「あれー、鍵開いたままじゃん。ちょっと、大丈夫?」
香織の声だ。
「るうー」
これまで聞いたことのないあのんの声が聞こえる。何かを警戒するような低い声だ。
「どした、あのん? ねえ、あなた? いるんでしょ?」
香織が俺のいるバスルームの前を横切っていく。ダメだ、逃げろ!
「ひゃっ!」
香織が悲鳴を上げた。
「ちょ、誰なの? なんでうちにいるの、痛い! ちょっとやめて!」
女がバスルームから出た。それに続いて、大男が俺を立たせて歩かせる。
「お騒がせして誠に申し訳ございません。お邪魔しております」
女が慇懃な声を出す。
「あなた! どうしたの!」
「すまん」
香織がずぶ濡れの俺を見て驚いて声を上げた。俺は咳き込みながらそれだけ言うのが精一杯だ。
香織は黒ジャケットの男に右腕を後ろ手にして拘束されている。
「いた」
女が鋭く声を上げた。
「あー!」
あのんが部屋の隅で鋭く唸る。土曜日に買ったボーダーのTシャツとキュロットスカート。
しかし、眉を寄せて男たちを睨む表情は、これまで俺たちが見たことのない激しい形相だ。
俺は床に放り捨てられた。作業服の大男があのんに両腕を広げて近づく。
「らあっ!」
あのんは腰を落とし、鋭い目つきで男を睨みながら、ゆっくりと横に移動する。
俺は必死でもがきながらなんとか身体を起こした。
大男があのんの腕を掴もうと右腕を伸ばす。
あのんは高く跳躍し、男の腕は空を切った。
右手を大男の肩に突くと、そのまま一回転して男の背後に音もなく下りる。
虚を突かれた大男が振り返ると、あのんはその股下をくぐり抜けて香織を抑えている黒ジャケットの男に向けて突進する。
「捕えろ!」
女が鋭い声を上げた。
黒ジャケットの男が香織を離してあのんに手を伸ばす。
男の手が触れる直前、あのんは右に跳躍してダイニングテーブルの上に乗り、回転しながら向こう側に下りた。
「このクソガキがあ!」
黒ジャケットの男が怒気を孕んだ目であのんを睨む。
壁を背に、あのんは追い詰められた。
「らあああっ!」
あのんが怒りをあらわにしている。威嚇する獣の顔を俺は連想した。
二人の屈強な男があのんを取り囲む。
女は香織を拘束したまま口元にうっすらと笑みを浮かべてその様子を見ている。
「あのん!」
香織が悲痛な声を上げた。
二人の男がじりじりと迫る。
大男があのんの左手を取ろうと右腕を伸ばす。
あのんは伸びてきた男の腕を踏んで上に跳んだ。
そこに黒ジャケットの男が腕を伸ばした。
あのんの足首を掴もうとしたが、その手は空を切る。
軽やかに着地すると、あのんは女を睨んだ。
「何をやってる!」
女が男たちに叱責を飛ばす。
「ちょこまかと動きやがって!」
黒ジャケットの男が叫ぶ。
「切り刻んでやる」
男は何かを取り出そうと右手を懐に入れた。
「馬鹿者! 〈商品〉に傷を付けるつもりか!」
女が怒鳴り、男はやむなく懐に入れた右手を戻した。
俺は事態を見守りながらただ茫然としていた。
屈強の男が二人がかりであのんを捕えようと躍起になっているのに、奴らはあのんに触れることすらできない。
「らああああっ!」
あのんは低い唸り声を上げながら、なお鋭い目で女を睨んでいる。
見たことのない、凶暴な目で。
これが、あのんなのか?
俺は背筋に冷たいものが走るのを感じた。
しかし、これはまだ、始まりに過ぎなかった。
〈八〉
男たちがあのんを追いはじめて既に一〇分が過ぎた。ダイニングテーブルが大きく位置を変え、ダイニングチェアが倒れ、テレビが台から落ち、まるで地震の後のような惨状だ。
あのんはしなやかに身をかわし、男たちに指一本触れさせない。
二人の男はさすがに疲れてきたのか、息が乱れている。
一方、あのんは息一つ乱れていない。
香織を拘束している女が、明らかに苛ついている。さっきから落ち着きがない。
「お前ら、それでも男か! たかがガキ一匹捕えるのに何分かかってる!」
遂に女が吠えた。
「〈商品〉に傷を付けるな、そうでしょ?」
黒ジャケットの男が肩で息をしながら自棄気味に返答する。
「わかった、好きにしろ。報告書はわたしが書いてやる」
「そうこなくちゃ」
男はにたりと笑うと懐に右手を入れる。取り出したのは、刃渡り三〇センチほどのサバイバルナイフ。刃が室内照明の光を受けてぎらりと光る。
「クソガキが、お遊びはここまでだ」
香織が息を呑む。
「あのん! 逃げて!」
「ちょっと大人しくしててもらえない? せっかくのショウが台無しじゃない」
女はそう言ってにやにやと笑う。これが奴の本性だろう。
「狂ってる……!」
香織が吐き捨てるように呟いた。
作業服の大男が片手でダイニングテーブルを押しのける。テーブルは派手な音を立てて横倒しになり、あのんの左側を塞ぐ。そのまま正面から大男がじりじりと間合いを詰める。
あのんの右からは、黒ジャケットの男がナイフを手に迫る。
挟み撃ちにする気だ。
「るうぅ……」
あのんは低く構えて左右に目を配り続ける。
二人の男が目配せをした。
次の瞬間、大男があのんの足元にタックルをかける。
あのんはそれを後ろに跳んでかわす。
黒ジャケットの男の刃がそれを追ってギラリと閃く。
刃はあのんの胸元ギリギリを掠める。
すぐに次の一閃。これも辛うじて避けた。
刃がいつあのんを切り裂いてしまうか、俺は気が気でない。
しかし、よく見るとあのんが笑っている。
目に凶暴な光を宿したまま、にたりと。
刃を避けながら、あのんは徐々に窓際に追い詰められていく。
このままではまずい。
「ほらほら、どうした? もう後がないぞ!」
黒ジャケットの男が叫ぶ。
万事休す、そう思った瞬間。
あのんが後ろ手にカーテンを掴んで一気に引きずりおろした。
ばらばらと音を立ててフックから外れたカーテンが投網のようにばさりと宙を舞い、男の上にかぶさる。
あのんが床を蹴って跳躍した。脚が大きく弧を描く。
カーテンをかぶったままもがく男の顔を、踵でしたたかに打つ。
「ぐああ!」
男は叫び声を上げて左手で顔を押さえた。鼻を蹴られたらしい。
あのんはその一瞬の隙を突いた。
両脚で男の右手首を挟み、そのまま全体重をかける。
男の右腕があらぬ方向にひねられ、ごとりと音を立ててサバイバルナイフが床に落ちた。
「しまっ……」
男が声を上げたときには遅かった。
あのんは左手で素早くナイフを拾い上げ、逆手に握るとにたりと笑った。
左下の犬歯が抜けた歯が覗く。
「は!」
女が感嘆の声を上げる。
「素晴らしい! 特別な〈商品〉だとは聞いていたが、これは!」
「言うこときかねえなら、どのみち〈商品〉にはならねえだろ!」
黒ジャケットの男が鼻から血を流しながら叫ぶ。
「どうとでもなる。必ず押さえろ!」
女が鋭く命じる。
形勢が逆転した。
あのんの刃が、容赦なく二人の男に迫る。
二人とも捕えるどころか、刃を避けるだけで精一杯だ。
「あのん、お願い、もうやめて!」
香織が悲痛な声で叫ぶ。
しかし、あのんは香織の声に何の反応も示さない。眼をらんらんと光らせながら二人の男を追う。
猫だ。
獲物に狙いを定めた猫の眼。一度狙いをつけたら、仕留めるまで執拗に追う。
あのんの刃がまず大男の左腕を捉えた。
「ぐっ!」
声にならない呻きが漏れる。
作業服の袖が裂け、血が滲む。大男がひるんだところに、あのんの刃が次々と襲いかかる。
男は両腕を前に交差して防ぐが、あっという間に両腕が傷だらけになる。
黒ジャケットの男があのんを背後から取り押さえようと右腕を伸ばすが、即座に向きを変えたあのんが左腕を一閃させた。
「があっ」
男は右腕を下から斬り上げられ、たまらず左手で右腕を押さえた。
男の腕から鮮血が迸り、あのんの頬にかかる。
動脈を切られたようだ。
あのんはなおも攻撃の手を緩めない。
蹴り上げようとする男たちの脚を巧みにかいくぐり、二人の男に着実にダメージを与え続ける。
部屋のあちこちに血しぶきが飛び散る。
「凄い、凄い……!」
香織を拘束するのも忘れて、女が興奮に目を輝かせている。
自分の部下が血まみれだというのに、この女はどうかしている。
香織は口元を両手で押さえ、目を見開いて立ち尽くしたままだ。
「うう……」
黒ジャケットの男が呻きを漏らし、床に膝を突く。右腕をだらりと垂らし、目の焦点が定まらない。男の足元の床には大きな血だまりができている。
勢いをつけたあのんが男の顔に右肘を撃ち込む。
男は為す術もなく後ろへ倒れた。
あのんはそのまま男の上に馬乗りになる。
何の躊躇もなくナイフを男の喉に当てると、素早く掻き切った。
香織が思わず目を背ける。
ごぼっという音と共に、男の喉から血が噴く。
あのんは全身に返り血を浴びた。
そのままナイフを手にゆっくりと立ち上がり、もう一人の男を睨んだ。
倒れた男の喉笛からヒューヒューと空気が漏れる音がする。横に投げ出された左腕が小刻みに痙攣している。
「あ……ああ……」
大男が明らかに恐怖の表情を見せた。二歩、三歩と後じさりする。
悪夢だ。
これは悪夢に違いない。
あのんは血まみれのナイフを一度口に咥えて左手をぶらぶらと振る。
男の退路は、横倒しになったダイニングテーブルに遮られた。
あのんがナイフを順手で握り直す。
身体の大きな男が、小さなあのんに怯えている。
あのんが一歩踏み出す。男にもう逃げ場はない。
「うあああああっ!」
男が血まみれの両手で頭を抱えて叫ぶと、ダイニングテーブルに背を付けてずるずるとその場に崩れるようにへたりこんだ。
「助けてくれ助けてくれ助けてくれ!」
うわ言のように繰り返す。
あのんがその顔を下からひょこっと覗き込む。
「ひっ……!」
男が思わず両手を上げた。
次の瞬間、あのんは男の頸の右側に刃を当て、右手を添えて力一杯引いた。
男の首筋から血しぶきが上がる。
あのんは更に男の胸を一突きしてとどめを刺した。大男は背中をダイニングテーブルにつけたままずるずると崩れ落ちる。もうぴくりとも動かない。
あのんが床に横たわっている黒ジャケットの男を睨みつけた。
まだ左手が痙攣している。
それも段々と弱々しくなって、遂に動かなくなった。
夢なら覚めてくれ。
俺は何度も繰り返した。しかし、それは空しい願いだ。
あのんは確かに、二人の男を、仕留めた。
ほんの十五分前までは俺に暴力を加えていた連中が、今は「モノ」と化して床に転がっている。
さっきから震えが止まらない。
「あははは、上出来だ! さぞかし高値で取引されるだろうさ!」
何が可笑しいのか、黒いスーツの女は声を上げて笑う。
「スマートさに欠けるやり方になったのは気に入らないが、まあいい」
あのんは男たちの血が滴るナイフをだらりと持ったまま、上目遣いでぎろりと女を睨んだ。体中に返り血を浴びて衣服も肌も汚れている。
「ふん、どのみちお前は〈商品〉なんだよ」
女にはまるで怯えた様子がない。
「ねえあなた、自分だけは死なないとでも思ってるの」
香織が抑えた声でゆっくりと女に尋ねた。
「当たり前じゃないの! あんたバカじゃないの? わたしが死ぬ? そんなわけないでしょ!」
女は香織の言葉に狂気じみた声で反駁した。
女が提げていたバッグから何か黒いものを取り出した。
「多少傷ものになったとしても十分だ。回収の甲斐がある!」
女が両手でそれを構える。
拳銃だ。
全体が角ばったフォルム、黒光りする金属製の遊底に、艶消しの樹脂素材で覆われたフレーム。銃口に細長い筒が取り付けられている。消音器か。これまでのことを考えると、これが単なる脅しだとは思えない。
「香織、あのん、そいつから離れろ!」
俺は反射的に叫んだ。
女は銃の照準をあのんに向けた。
あのんは左手にナイフを握ったまま、じっと女を睨んでいる。
「〈商品〉のくせに生意気な!」
女が引鉄に指を掛ける。
その時、香織が女の両腕に飛びついた。
「くそ、邪魔するな!」
女が香織を振り払おうとするが、香織は右手で銃口を塞ぎ、必死の形相で女にしがみつく。
「香織、やめろ!」
俺は思わず叫んだ。
圧縮された空気が一挙に抜けるような音。
空薬莢が床に撥ねて高い音を立てた。
あのんがナイフを床に落とした。血だらけのナイフがフローリングに刺さる。
香織が倒れている。俺には香織の背中しか見えない。
「香織!」
俺は無我夢中で叫んだ。
香織がうう、と小さく呻く。生きてる。
「邪魔すんなよ。後で仲良く始末してやるから」
女は冷酷な口調で吐き捨てると、改めて銃を構えた。
「うあらあああっ!」
あのんが再び凶暴な唸り声を上げた。
「は、上等だ! 来なよ」
女は尊大な口調で挑発する。
切れ長の目に狂気が燃えている。
適度に力の抜けた構え。恐らく銃を扱い慣れている。
銃口がまっすぐあのんを指した。
あのんは腰を低く落とし、黙って女を見据えている。
「あのん!」
俺は止めようとあのんの名を呼んだが、あのんは全く反応しない。
俺は思わず息を呑んだ。
女が息を吸う音が聞こえる。
次の瞬間。
あのんが床を蹴った。
速い!
即座に女が引鉄を引く。
再び、圧縮された空気の音。
あのんは四肢を使って身体の角度を変えた。
弾丸がフローリングに突き刺さる。
薬莢が床に落ちる間にも女との距離が詰まる。
即座に次の一撃。
これも外れた。
薬莢が床で撥ねる。
あのんが女の懐に飛び込んだ。
勢いを殺さずに左肘を鳩尾に撃ち込む。
「かはっ」
女の身体が、くの字に曲がる。
銃床に添えていた左手が外れた。
あのんが右脚を高く上げて旋回させる。回し蹴りだ。
銃を握っている女の右手を、踵が正確に打つ。
女が拳銃を取り落とした。
銃は夢のようにゆっくりと放物線を描く。
俺はそれを目で追った。
ごとりと、音を立てて床に落ちる。
女が床に片膝を突いて二・三度咳き込んだ。
顔を上げた女の目の前に、左手で銃を拾い上げたあのんが立っている。俺に背を向けて立っているから、あのんの顔は見えない。
銃口が女の額を指している。
女の表情が驚愕に変わった。
「え──」
女が何か言いかけたところで。
あのんが引鉄を引いた。
消された銃声とともに女は頭を後ろに反らし、前に突っ伏してそのまま動かなくなった。
床に転がった空薬莢が弧を描いている。
編み上げていた女の黒髪が、バラバラになって広がっていた。
あのんは左手から銃を離した。
銃は床に落ちて再びごとりと音を立てる。
嘘だろう?
誰か嘘だと言ってくれ。
あのんは俺と香織の見ている前で、瞬く間に三人を殺した。
「あのん、大丈夫か?」
俺は戦慄きながらあのんに声を掛けた。
「あー」
あのんは振り返って俺を見ると、力なく声を上げた。
目から凶暴な光が消えている。
だが、その手も、脚も、顔も、血にまみれていた。
部屋に満ちた硝煙と血の匂いが鼻をつく。
俺はゆっくりと立ち上がろうと試みた。しかし、足が震えてなかなか立ち上がれない。後ろ手に縛られているので、立ち上がりかけたところで何度か転ぶ。
「香織、香織!」
必死で立ち上がろうとしながら、俺は香織の名を呼ぶ。声が震える。
「うん、だいじょぶ」
香織が小さく返事をした。
「なー」
あのんが香織を見て心配そうに声を上げた。
「あのん……」
「あー」
香織が名を呼ぶと、あのんはふっと笑い、再び力なく声を漏らす。
なんとか立ち上がった俺は、香織の元に歩み寄った。
右の掌から大量の血が流れ出ている。
「助けを、呼ばなきゃ」
俺はもつれる足で電話まで歩く。
「あのん、ちょっと待ってろ」
俺はあのんにそう言った。
「らー」
あのんは俯いて寂しそうな声を出す。
「あのん?」
香織が起き上がろうとしながらあのんを呼ぶ。
「あー」
あのんは香織の顔、俺の顔を交互に見ると、もう一度ふっと笑った。
左下の犬歯が抜けた歯が覗く。
寂しげな笑いだった。
それが、俺たちが最後に見たあのんの姿だった。
〈九〉
九月も半ばだというのに、真夏日が続いている。
日没から二十分ほど過ぎたが、辺りは残照でまだ薄明るい。ツクツクホウシが往く夏を惜しんで盛大に歌っている。
日中の熱気がまだ燻っていて、俺は軽く汗をかいている。
俺は海を見下ろす公園に来ていた。
夏の初めの暑い日、三人で一緒に来た、あの公園に。
あの悪夢のような出来事から、二ヶ月が過ぎた。
俺は殺人の容疑者として警察から何度も取調べを受けた。自宅は立入禁止になり、香織との接見も禁じられ、マスコミに散々追い回された。逃げるように安いビジネスホテルやインターネットカフェを転々とし、警察に呼ばれては長時間の事情聴取、外に出るとマスコミの質問攻め。
こんな寂れかけた地方都市で一度に三人が死亡する凶悪事件が起きたものだから、報道は異常な過熱をみせた。テレビのニュースショウでは連日「事件の謎」が繰り返し報じられ、週刊誌には画像加工された俺の写真が載ったりもした。インターネットに実名が晒されたのも知っている。
職場の上司からは長期間の謹慎を命じられた。しかし一部のマスコミが学内に頻繁に出入りするものだから、迷惑をかけないようにと二週間後には辞表を提出した。辞表はあっけないほどあっさりと受理され、俺は無職になった。一ヶ月ほど前のことだ。地方の小さな私立大学にとって、風評は経営悪化に直結する。きっと理事たちは俺が辞表を出すのを待ち構えていたに違いない。形の上では自己都合退職だが、退職金は出なかった。退職前の引継ぎの時にも、同僚たちは誰ひとりとして俺と目を合わせることはなかった。
風が凪いで蒸し暑い。走る車のノイズが遠くからずっと低く聞こえている。
遠く対岸の街並みの明かりが陽炎にゆらめく。
あの惨劇を、幼いこどもが起こした。
そんな話、一体誰が信じる。
俺は当初取り調べに黙秘した。あのんのことを守るつもりだった。だが、鑑識の分析結果を見せられるとそういうわけにもいかなくなった。ナイフや拳銃に残された指紋、床についた乱れた足跡、階段に残っていた血痕……それらがあの子が確かにここにいた、動かぬ証拠だった。
俺は一転して起きたことを包み隠さず話したが、捜査員たちはなかなか信じようとはしなかった。もしもあのんが見つかったら俺が身元の引受人になりたいと伝えたが、どの捜査員も押しなべて冷淡だった。鑑識の結果は俺の供述と全く矛盾しないにもかかわらず、捜査員たちは執拗に俺に犯行を自供させようとしてきた。それどころか、篠田の失踪まで俺が殺したのではないかと疑っていた。これだけ大きく注目された事件だ、とにかく「犯人検挙」という実績が欲しかったのだろうが、冗談じゃない、俺だって奴らに殺されかけたんだ。連中はそれでもしぶとく食い下がり、「任意聴取」という名目での取り調べは、つい一〇日ほど前まで続いていた。
県警の威信を賭けた捜索体制にもかかわらず、あのんの行方は依然、杳として知れない。事件当夜は雨が降っていたために警察犬による追跡はできず、目撃証言も防犯カメラ映像も、結局何ひとつ出なかったそうだ。
八月の終わりになって、港に沈んでいた車から篠田の遺体が発見された。死因は溺死。奴らが言っていた通り、口封じのために殺されたのだろう。遺体は腐敗がひどく、死亡時期の特定には至らなかったそうだ。俺も一歩間違えば、篠田のようになっていたかもしれない。結局、篠田がどこでどのようにあのんと接触したのかは、わからずじまいだ。せめて篠田の葬式に顔を出そうとしたが、遺族から強く拒絶されて、それも叶わなかった。
奴らが一体何者だったのかもわからない。恐らく大規模な組織的背景があるのだろうが、警察ですら奴らの身元を特定することはできなかったようだ。
すべては闇から闇へ、か。
俺と香織には、それでも犯人隠避の疑いが掛けられたが、当然ながら起訴するに足る証拠はなく、送検は見送られた。
俺の実家にもマスコミが大挙して押しかけたらしく、この件で俺は両親と険悪になった。今は全く連絡を取っていない。
あの部屋も手放すことにしたが、事故物件扱いになって、なかなか買い手がつかなかった。先週になってやっと話がまとまり、タダ同然で不動産会社に買い叩かれた。俺には向こう二十年以上払い続けるローンだけが残った。
再就職もまだ決まらない。ひとたび殺人の容疑者になった俺が、そう簡単に面接を受けられるわけもない。今は失業保険でなんとか食いつないでいる。
汐が引くようにマスコミの関心が急に薄れて、身の周りがやっと静かになったことだけが救いだ。
うんざりするような日々。
俺は煙草に火を点けた。
辺りが夕闇に沈んで、海が海峡の向こうの街明かりを映している。いつの間にか足元でスズムシが鳴き始めていた。
あの四日間で、俺はすべてを得て、そしてすべてを失った。
身元不明の死体が三つ転がり、出自不明のこどもが消え、そして事件そのものも、何もわからないままだ。
昼間、香織から来たメッセージを読み返す。
近いうちにこっちの部屋を引き上げて山陰の実家に戻るという内容だ。
香織は二週間ほど入院したあと通院治療になったが、指先に麻痺が残り、医者からは元のようには動かないだろうと宣告されたそうだ。
せっかくがんばってきたけど、もう手先を使う仕事は無理みたい、とあった。
色々思い出して辛いから、この街を出ることにした、とも。
あの日から、何もかもが変わってしまった。
カラスアゲハが一羽、目の前の茂みにとまっている。ゆっくりと翅を開き、また閉じる。
海風が汐の香りを運び始めた。
俺は手摺に寄りかかって、夜景になった海峡の向こうをまたぼんやりと眺める。
あのんは今、どこでどうしているのだろう。
お腹をすかせていないだろうか。
着るものはちゃんとあるのか。
せめて、誰かいい人にめぐりあっていればいいんだが。
自分の明日の生活すらわからないというのに、それでも俺はあのんのことを思った。
夏の強い日差しの下で、はしゃいでいたあのんの姿を思い描く。
光を、空気を、そして時を、無邪気にすくい取ろうとしていた姿を。
ああ、長くなった煙草の灰を落とすのも面倒だ。
湿気を含んだ空気の向こうで、街明かりが滲んでいる。
いや、わかっている。滲んでいるのは湿気のせいではない。
指先で、伸びきった煙草の灰がぽとりと落ちた。
ぬるく澱んだ空気の中、俺はいつまでも海を眺め続けていた。
了
あのん