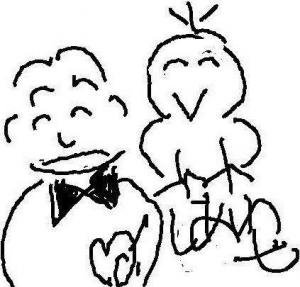陽だまりのニャン子しっこ
陽だまりのニャン子しっこ
○ 大人ですから
早朝五時。ゴールデンウィークの足音が聞こえてきたこの季節。肌寒さは残るものの、外界はすっかり明るく、その変化だけで気持は軽い。
真冬の五時と云えば、深い暗闇のただ中にあり、寒さのピークを迎えようかという魔の時間だった。マフラーと手袋にマスク、防寒ジャンパーに二重の靴下に防寒のズックを履いて、男か女かも見分けがつかない出で立ちで、職場に向かったあの日さえ、かすみには懐かしい思い出に思えた。
内田かすみは春の冷気と香りを黒眼と鼻先に感じながら、自転車にまたがりメゾンド美樹を後にした。目指す職場は地元のスーパーマーケットに惣菜を調理して供給する、食品加工会社『新選フーズ』だ。
かすみは食品加工業の新選フーズ有限会社資材係で働いている。食品加工工場の現場は役割分担がしっかりと決められていて、どの現場も黙々と仕事をこなすことが求められる、言ってみれば単純作業だ。かすみの所属する資材係も他の職場のご多分に洩れず、日々単純な作業を繰り返すのだが、他の現場とは違いやるべき事は意外に多く、自己判断(決定権)と孤独で孤立した作業が強いられる職場である。
「大手の会社なら自動でやってくれるのにさ。何よ手作業って。ねえっ」
ひとり不満を隠ないかすみは、自分以外に言葉を交わす相手すらいないから、当時最先端と持てはやされた(自分みたいに動作する)マシーンに話しかける、しかない。廻りを見渡しても、食品をつめる容器か包装用の資材かコンベアか、LEDライトに交換待ちの蛍光灯といった、喋らない物があるだけで、自分の声を誰かの声と聞き違えてハッとすることや、誰もいないのに突然『カサッ』と何かが動く音がしてお化け屋敷に迷い込んだのではないか、と思うことが最近増えた気がしている。
「わたし、精神的にへんなのかも」
かすみは全体朝礼以外には「おはよー」も「お疲れさま」も言う同僚さえも居ない職場で、孤独と不満に耐えていた。
容器や原料の品質管理は、必ず業者が行った上で納入されてくる。とは言え、責任の大部分は取引先に商品を販売している加工会社=新選フーズにあると言っても過言ではない。更に言えば、社内に於いて最終的な責任を負うのは班長でも課長でも工場長でもなく、その作業に従事している者となるのが現実だ。つまり資材係で言えば、かすみだけと云うことになる。
資材係の仕事は、惣菜を盛りつける容器の傷やゴミや変形などの品質をチェックし、肉じゃが用、ほうれん草の胡麻和え用、ひじき用などのそれぞれの容器を間違いなく製造現場に供給する役割を担っている。一見すれば簡単な作業に思えるし、当のかすみもそう思っていたのだが、実際は違う。容器を取り違えてコンベアに流そうものなら、惣菜も容器もすべて廃棄となり、莫大な損失を与えかねない集中力と忍耐力が必要とされる重要な仕事なのだ。
事務職社員として採用されたかすみは、三ヶ月間の資材係での研修を終えて事務職に配属される予定だった。しかし欠員が生じたことで配属予定は延期を繰り返し、三年間資材係で働き続けていた。
「いったいいつまで研修、続くのよ 」
かすみの頭には退社の文字がはっきりと浮かぶようになり、ストレスは憤りに変わってピークに達していた。
「もう嫌、もうイヤ、もうヤダ 」
かすみは仕事中呪文のように同じ言葉を繰り返している。誰に聞かれることもない孤独な職場のせいであろう、自然とひとり言ばかりが増える。
そのせいか、盛りつけ班から容器の数が足りないとクレームを受けると云う、三年間でしたことのない失態をおかしてしまった。
「何でわたしばっかり責められなきゃいけないのよ」
答えは分かっていた。資材係にはかすみしかいないからだ。かすみは重い足を引きづりながら、家路をたどるのであった。
「あれ? かすみちゃんじゃない」
「ああ、五木田さん」
「お疲れ」
普段は入らないコンビニで求人情報誌でも見ようかと思ったかすみに、盛りつけ班のリーダー五木田勝治が声を掛けた。確か三十歳になったばかりだと聞いている。
「なんだい、暗い顔して。昼間のこと気にしてんのか」
「あ、はい。いいえ」
「もう仕事は終わったんだからさ、忘れなよ。みんなだって忘れてるんだからさ」
かすみを心配した五木田は、「 少し話そうよ 」と言って、カップ入りのレギュラーコーヒーをふたつ買い、表に出てかすみに手渡した。
「かすみちゃんがコンビニで買い物するなんて、意外だな」
「ほとんど入らないんですけど、今日はたまたまです」
「コーヒー、飲みなって。結構いけるんだぜ、ここのコンビニコーヒー」
美味しさを物語るようなコーヒー豆の香りが、かすみに安らぎという言葉を連想させた。
「ほんと、美味しいわ。五木田さんはよく来られるんですね、コンビニ」
「コーヒーだけはコンビニだね。他は近所の激安スーパーかドラッグストアくらい。安いし大概の物が揃ってるからね」
「五木田さんは独身でしたか」
「そうだよ。男で独身なのは俺と酒井さんだけかな。とは言っても酒井さんは奥さんを亡くされてるから、独身を貫いてるのは俺だけ」
「それとわたしだけですね」
「かすみちゃんはまだ若いから良いじゃん。俺なんか三十歳だぜ」
「五木田さんは若いですよ」
「でもさ、三十歳になったらいろいろ考えるんだよね。一生独身で終わるのかとか、五十歳間近で会社がつぶれたらヤバいなあ、とか」
「わたしも考えます。このまま資材係でおばさんになっちゃうのかなあなんて」
「なんでウチみたいな年寄りばっかの零細企業なんかに入ったのさ。若いのにもったいないって、みんな言ってるぜ」
「人が少ない会社で事務の仕事をしたかったから」
「少ないって言っても、資材係の現場はかすみちゃんひとりだもんな。可哀相に」
「わたしだって、まさかひとりで現場の仕事をするなんて思ってもみませんでした」
「辛いよな、未だに事務になれないなんて。よく頑張ってるよ、かすむちゃんは」
五木田は心から同情して言った。かすみが事務になれずにいる事を、気にかけていたのだ。
「まっ不平不満もあるけどさ、何だかんだ言って俺も小っこい会社の方が良いな。家庭的で風通しが良いからね。デカい会社はかちかちでよそよそでこりごりだ」
「大手で働いていたんですか?」
「大手と言えばそうかもしれないけど、そんな実感は無かったよ」
「そう云うものですか」
「そう云うものだね。あまり好きな言い方じゃないけど、下っ端の俺たちに会社を動かすことなんか出来ないし、決められた事をただこなすだけなんて、生きてる意味ないんじゃないかと思ってさ」
「だから辞めたんですね」
五木田はコーヒーを飲んでからうなずく。
「でも安定していますよね、大きい会社って」
「安定を第一に求める人間には居心地は良いと思うよ。俺には合わなかったんだ。嘘臭くて」
「そう、ですか」
「本音が聞こえなくてさ」
「わたしは、何も聞こえません」
「そうなんだよな、資材係は」
五木田は内ポケットからタバコを取り出す。
「いいかな?」」
かすみがうなずくと、タバコに火を着け気持ち良さそうに吹かした。
「はあ、うまい。先の見えない小っこい会社で淡々と惣菜盛りつけてさ、仕事帰りにコンビニ寄って好きなコーヒー飲みながらの一服。正に至福の時だね。デカい会社にいる時とはまったく違う味わいだよ」
五木田はそう言うと目を細めてタバコをくわえた。
「そんなに美味しいんですか? タバコって」
「ああうまいよ。俺には無くてはならないもんだね。飯は抜いてもタバコは抜けないな」
「値上げばかりしている様ですけど、そのタバコはおいくらなんです?」
「二十本入りで二百九十円」
「割とお手頃なんですね」
「俺は昔からこれなんだけどさ、何年か前までは百八十円だったよ。今じゃほとんど五百円近いみたいだね」
「五百円だと一日の食事代ですね」
「そうだね。タバコばかりやり玉になって値上げしてるだろ? そのつけが今まわってきてるんだよ。普通のスーパーにいけば分かるけどさ、ばんばん値上げしてるじゃん。ついこの間まで税込み百円以下で買えた缶詰が百五十円近いんだぜ。ウチの中高年みたいにアルバイトでしか雇って貰えない人たちばかりだって言うのに、死活問題だよ。ホント変になっちまったよな、世の中」
かすみは深くうなずいて、五木田をじっと見つめていた。
「コーヒー、飲まないの? 口に合わないか」
「いいえ美味しいです。それより五木田さん。タバコ、一本くださいませんか」
「ああ良いよ」
五木田は職場の休憩時間で年輩者にめぐむ時と同じように、タバコを取り出した。
「えっ。かすみちゃん、タバコ吸ったっけか」
「試したいんです。至福の時がどんな感じかを」
「やめときなよ。不味いよ、たばこは」
「うまい、至福の時だって言ってたじゃないですか」
「初めは不味いもんなんだよ。初めからうまいと思うやつなんかいないよ」
「それなのに吸い続けたんですか?」
「俺の場合、って言うかほとんどの男は、格好つけるために始めた様なもんだからね。不味いのを我慢して吸うとそのうちうまくなるんだ、タバコってのは。わざわざ始める事なんかないって」
「じゃあ、わたし買って来ます。二十一歳ですから、悪いことをするわけじゃないですもん」
かすみはコンビニに入ると、五木田と同じわかばとライターを手にして戻って来た。
「もう吸いたくないと思ったら、俺買うよ」
かすみは左手にタバコを持ち右手でライターの火を近づけ、先端に火が着くのをより目にしてじっと見ている。真剣な表情だ。
「はっははっ」
五木田が笑い出した。
「それじゃ駄目だよ。口にくわえて吸い込まないと着かないって」
「あらそうなんですか」
かすみは五木田の言われるようにした。案の定むせ、何度も何度も咳こんだ。
「大丈夫か。やめた方がいいって。ほら、それ買うよ」
「いいえ、(ゴホッ)やめません。決めたんですから。オホッ」
○ 解決のその後
「やあ、かすみちゃん」
八時五十分からの十分間の休憩時間。昨日までのかすみは、化粧室に行ったあとに缶コーヒーを買って食堂で何とは無しにテレビを眺めるだけだったのだが、今日は工場の脇の軒下にある喫煙所に向かった。
「お早うございます」
喫煙所のベンチには五木田の他に、三名の高齢男性が座っていた。
「あれからどうだった、何本吸ったのさ」
「昨日は三本。今朝家を出てからこれで二本目です」
「なんだかすみちゃん。タバコ吸い始めたのかよ」
「はい昨日から」
「五木田が教えたのか、悪い奴だな」
「いやあ、俺は止めましたよ。でもどうしても吸うって聞かないもんだから」
「やめるなら今のうちだぞ。やめたくてもやめられなくなっから」
「いいえ、やめません」
かすみはわかばをポーチから取り出して火を着けた。
「コホッ」
「まだ慣れちゃいないようだな。マズいだろ」
かすみは頭を横に振る。
ふたたびタバコを吸ったかすみに同じことを訊くと、かすみは咳き込むのを我慢して同じように頭を横に振った。
「まあ未成年ってわけじゃないんだから好きにしたらいいさ」
「でもほら、女の人は生まれてくる子供に影響するって言うじゃないか。やっぱりやめた方が良いって」
「かすみちゃんはまだ二十歳になって間もないだろ。まだまだ先の話」
「二十一歳です」
「分かんねえぞ。来月にでも結婚するなんてことあり得るからな、若いうちは」
「そう妊娠しましたから、なんて言ってな」
「予定ないのかい? かすみちゃん」
「ゴホっ。予定なんかありません。結婚も妊娠も」
「そりゃ残念だな。タバコなんかよりそっちを先にすれば良かったんだ」
「そうすりゃ、タバコになんか手を出さなくて済んだのに」
きかん気のかすみは、きっとなって男を睨んだ。
「ああ怖っ」
「かすみちゃんって、意外に頑なとこがあるんだな」
「頑固っていうか」
「かすみちゃんは一本気なんですよ。やめたくなったら、きっぱりやめられる。俺たちとは違いますって」
五木田はかすみをかばって言った。
「五木田さん。どうしたら、たばこがおいしいって感じるんですか?」
かすみは涙目を向けて尋ねた。
「そうだなあ、」
「始めは辛抱。格好良いところを見せつけるくらいにして吸うことだ。なっ五木ちゃん」
「でも昨日吐きそうになっちゃいました、わたし」
「つわりじゃないのか」
「そんなんじゃありません!」
「おお怖っ」
「ほんとにやめる気はないんだね」
「はい」
「なら教えるよ。ミント系の飴を舐めながら吸うんだ。少し慣れてきたと思ったら、舐めないで吸う。うまいと感じるまで同じことを繰り返す。そしたら慣れるよ」
「おいおい、変なこと教えるなよな。本当にやめられなくなるぞ」
「わたしはやめません。五木田さんありがとうございます」
昼食の為に用意して来た弁当は半分も食べられなかった。食事前にみなと混ざって、一服したのがよくなかったらしい。だが何よりも本音で話せる仲間が出来た気がして、かすみは嬉しかった。
「でも喫煙所の人たち、わたしのこと頑固だと思ったかな。物静かでお淑やかな女の子のイメージが崩れちゃったかも」
職場に戻ったかすみはそうひとり言を言うと、少しだけ寂しい気がした。
今日はスーパーのセール対象品となる、ほうれん草の胡麻和えの増産で、一時間の残業だった。月に四、五回。ほぼ毎週セールをする事は、スーパーとの契約で取り決められている。
かすみは昨日に続いてコンビニで五木田を待っていた。腕時計に目をやる。間もなく午後五時になろうという時間だ。
「待ってたな、さては」
かすみが会社の方角に体を向けていると、五木田は反対側の表通りからやって来た。
「びっくりしたあ。どこかに寄ってたんですか?」
「レンタルビデオ屋でDVD借りて来たとこ」
三十歳で独身の五木田がどんなものを見ているのか、かすみは興味があって手に持った袋を見た。
「変なビデオじゃないって」
五木田は自分を弁護するように慌てて答えた。
「そんなこと思っていません。映画ですか?」
「うん。もうだいぶ前の日本映画。ほら」
―――『 明日の記憶 』
「知ってる? 若年性アルツハイマー病になったサラリーマンの話」
「いいえ、わたし映画はあまり観ませんから」
「最近観たのは?」
「陰陽師。野村萬斎さん主演の」
「随分古いな、これより古いだろ」
「子供の頃です。それより五木田さん、何で今頃になって観たいと思ったんです?」
「本が良かったから、観てみたいと思ったんだよ。思い切ってたばこを始めたかすみちゃんに影響されてね、俺も思い切ってみたってわけさ」
五木田は嬉しそうにDVDをしまった。
「ミント系の飴。どれを選べば良いのか教えてください」
「かすみちゃんってトコトン派だね。まっすぐな性格がよく分かるよ」
「頑固なんです」
「みんなの言うこと気にしてんのか。あれはあの場を盛り上げたいと思って言った冗談なんだからさ、気にしない事だよ」
「冗談ですか」
「そう。短い休憩時間だろ? それに仕事中は喋られないじゃん。何かネタを見つけて冗談言って、笑っていたいんだよ。みんな」
「はあ」
「おいでよ、選んであげるから」
かすみは五木田の後に続いて、店内へ入って行った。
「ミント感が強いスーっとするのが良いんだ。あっ、あった。これだよ」
「ホールズですか」
「とにかく試してごらんよ。口に合わなければ他のにすれば良いんだからさ」
コーヒーとともにレジを済ませた五木田は、外に出るとかすみにホールズを渡した。
「試してごらん」
言われるままにかすみはホールズを舐め、そしてタバコに火を着けた。
「どうだい」
「スーッとして、苦さが抑えられた感じがします」
「むせないね」
「はい、大丈夫みたい」
「でも、」
「でも何ですか?」
「かすみちゃんは口が小さいから、飴舐めてるのが分かるよ」
「こうしたら?」
かすみは口の中で飴をずらしてみる。
「分かる。ちょっと待ってて」
五木田は再び店内に行き、すぐに戻って来た。
「ミンティアのストロング。これなら口に入れてるって分からないよ」
かすみはホールズを包み紙に出し、小粒の薬に見えるミンティアを口に放り込んだ。
「こっちが良いです」
「解決。だね」
ふたりは顔を見合わせて笑った。
「あっ、雨ですね」
「飴舐めてたら、雨になった」
「意外に面白いんですね、五木田さんって」
「喫煙所と同じさ。くだらない冗談言ってた方が楽しいじゃん」
「あっ、五木田さん」
「何?」
「猫」
建物の脇にあるゴミ集積スペースの金網の下で、手の平に乗るほどの子猫が震えている。
「わあ、小っちゃい」
「可哀相に、おいで」
五木田がしゃがんでやさしく手を叩くと、猫はその手に縋るように弱々しい足取りで近寄ってきた。
「足、怪我してるみたい」
「歩き方、おかしいな」
五木田は手で包む様にして、子猫を抱えた。
「小っこいなあ、お前」
「痩せすぎですよ、どう見ても」
「ちょっと待ってて」
五木田はかすみに猫を手渡すと、コーヒーを飲みほし三たび店内に向かった。さっきとは違い急いでいることがかすみにも分かった。
三分ほどして五木田は戻って来た。
「とにかく、これ食わせてやろうよ」
五木田がレジ袋を広げ、中から猫用の缶詰がひとつとミネラルウォーター、プラスチック容器を取り出した。
雨に当たらない場所を選んで、五木田がそれぞれを開封して容器に移す。かすみはデイパックに入れたハンドタオルで猫の体を拭いている。
「さあ、食べな」
「いっぱい食べるのよ」
容器の前に猫をおろすと、猫はツナの匂いのする容器に向かって鼻を動かす。
「おい、どこ行くんだ」
猫はまっすぐ容器には向かわず、斜め横に向かって歩き始めた。
「目、見えないんじゃないですか」
「お前、見えないのかっ」
五木田は痛むであろう右足をかばって猫を抱え、餌を指でつまんで口元に近づけた。
「あっ食べました」
「良かったあ。とにかく食え」
プラスチック容器に猫の顔を近づけながら、五木田はそっと地面に降ろす。
「目が見えなかったら、生きていけないんじゃないですか」
「おまけに足もだ。可哀相になあ」
ふたりは黙り込んだ。猫は懸命に餌にむさぼりついている。
「何とかしてあげたい」
「病院に連れて行こう。このまま放って帰れねえよ」
「わたしも行きます。確か、十分くらい歩いたところに動物病院がありますよ。わたしの住んでるアパート、すぐそこですから傘と大きいタオルを持って来ます。すぐに戻りますから」
「まだ食いそうだから、慌てなくていいよ」
かすみは微笑を浮かべて答え、アパートへ急いだ。
○ 君の名前は?
かすみと五木田は動物病院へ向かった。ふたりとも犬は飼ったことがあるが猫は飼ったことがない。猫がどんな病気であるのか、なぜ目が見えないのか不安でならなかった。
「この子、男の子かしら女の子かしら」
大きい傘に異性ふたりで並んで歩いた経験のないかすみは、緊張を解きほごそうと口を開いた。
「オスだよ、ほら」
五木田は子猫を仰向けにして金玉を見せつけた。
ミィーヤ。
「やだあ~」
「いやだってな、猫じゃないか。この犬なんか――」
大型犬がすれ違う。
「丸出しじゃないか」
「やめてください。そういう破廉恥な言い方するの」
「破廉恥ってな。人間だけだよ、隠したりしてんのは。もしかしてかすみちゃん、まだ人間の、」
「えっ、えっ~!」
「ごめん。とにかく急ごう」
こんなデリカシーのない人だと思わなかったわ。んもう。
ふたりは市の運営するプールがある公園を横に見て、緩やかな坂道をのぼる。雨は次第に強くなり風も出て来た。
「入院させるようかしら」
「食欲はあるから、大丈夫だよ。きっと」
「でも入院しなかったらどうします? わたしのアパートは動物禁止ですし雨漏りするから」
「雨漏り? そんなとこに住んでんのか」
「管理会社が直そうとしないんです。オーナーがウンって言わないとかいって」
「酷えな、それは。管理会社の役割果たしてねえじゃん。オーナーを説得するのが管理会社の仕事だ、言い訳にするような不動産屋はダメだ。良いとこ見つけた方が良いって」
賃貸アパートで隣室トラブルに悩まされた事のある五木田は、熱くかたった。
「再来月更新だから、良いとこを探そうと思ってるんです。それより、どうします? この子」
「獣医の診断次第だけど、いざとなったら何日か俺んとこで面倒みるよ。それしかねえもん」
夕方の動物病院は思いのほか混み合っていた。柴犬やヨークシャーテリアが元気よく吠え、毛艶のよいロシアンブルーがキャリーケースからその姿を上目づかいで覗き見、白文鳥が外に出たいと移動用のドーム型ケースを突っついている。
「初めてですか?」
五十歳前後のナース服を着た女性が、五木田とかすみどちらとなく声を掛けた。
「はい」
「では問診票の記入をお願いします。診察券を先にご用意しますので、お名前を教えて頂けますでしょうか」
「内田かすみです」
「かすみちゃん、女の子ですね」
「(ムカッ) 女に見えませんかっ」
「違うってば、猫の名前だよ。ですよね」
「はい。猫ちゃんのお名前を」
「あらやだっ、わたしったら」
「まだ、付けていないんですよ」
「診察券を作らなければいけませんし、カルテやお薬袋にも書かなければならないものですので」
「そう言われても・・・」
「じゃあ・・・ニャン子しっこ」
「・・・はい?」
「ニャン子しっこで」
「えっ!」
「ぷっふ」
「変な名前つけないで! かわいそうじゃないですか」
「院内では、猫ちゃんのお名前をお呼びすることになりますが・・・」
「わかってます。ニャン子しっこにしてください」
「ダメよ、絶対にだめ。呼ぶほうも嫌ですよねえ、ニャン子しっこなんて」
「それは・・・」
「良いじゃないか。猫が排泄している姿って神妙だろ? 他の動物にはない猫のいちばん良いところだよ」
「シンミョウの方がまだ良い」
「坊さんじゃねえんだから、それはないって」
「ニャン子しっこなんかより、ずっと良いわよ」
五木田の腕に抱えられた子猫は、声のする方に顔を向け不思議そうに首を傾げている。
「奥様。どうなさいますか」
「奥様ぁ? こんなセンスの無い人の奥さんなんかじゃありません!」
「じゃあ、何にすんだよ。シンミョウは駄目だぞ」
「みいちゃんとか、みみちゃんとか猫らしい名前にする」
「ニャン子しっこだって猫らしいだろ」
「どうなさるんですかっ」
受付の女性が苛立って言った。
「ニャン子しっこで良いです」
「診察券を作りますので、問診票を書き終えたらお持ちください」
( 夫婦? 冗談じゃないわ。こんなに可愛らしい子猫に変な名前付けるような男なんて)
「怒るなって。通院してる間だけのことなんだからさ」
「五木田さんがそんなにいい加減な人だと思いませんでした。名前は適当だしオスメスの区別だって、他に教え方があるでしょ。失望しました」
「かすみちゃんは、猫がションベンしたりウンチしたりするとこ見たことあんのか?」
「無いですよ。わたしそんな趣味ありませんから」
「勘違いすんなよ。排泄してるところを見ればかすみちゃんだって、神聖だなあって思うぞ。あんなに神妙な場面なんてなかなかないぞ」
かすみは五木田から子猫を奪い取り、やさしく背中を撫ぜた。
―――ニャン子しっこちゃん。( えっ! プフッ、ウウンッ )、診察室へどうぞ。
待合室の保護者たちは笑いを堪えて手に口を当てたりニヤニヤしたりしながら、かすみと五木田とニャン子しっこを見た。
「さあ行くよ、かすみちゃん。今はニャン子しっこが元気になる事だけを考えようよ」
五木田の言葉にうなずきもせず、かすみは立ち上がって診察室の扉をノックした。
「どうなさいましたか?」
獣医が問診票に目を通しながら訊いた。
「拾った猫なんです。さっきご飯をあげようとしたら違う方向に歩き出してしまって、目が見えていないようなんです。それに右足が痛いようで歩き方が変で、痩せて弱ってるようにも見えるから」
五木田が思いつくままを喋ると、ニャン子しっこは診察台に載せられた。
獣医は猫の名前など気にとめる事なく、体全体をくまなく触診し聴診器を体に当てたあと、目にペンシルライトを当てる。
「どうでしょうか」
五木田は心配な声で尋ね、かすみは両手を握り大事に至っていないことを願い祈った。
「栄養が足りていませんね。外で育った子供の猫に時々見られることです。命に関わることはないでしょう。ただし再び野良猫になれば話は別です。足のほうは、股関節に異常があるようですね、これから血液検査とレントゲンをとってみましょう」
心配するふたりを余所に、ニャン子しっこは診察室のなかをきょろきょろと見ては鼻をひくつかせ、おとなしく体を触らせていた。
「大丈夫かしら、この子」
「とにかく先生に任せるしかないだろ」
五木田は膝の上に手を置いて、かすみに抱えられているとなりのニャン子しっこを見やる。その思いはかすみと同じだった。
「股関節の異常って、」
———ニャン子しっこちゃん。診察室へどうぞ。
かすみが話そうとすると、診察室の動物看護師が扉を開けて入るように促した。五木田とかすみは、緊張した目を互いに向けてうなずき、診察室に向かう。さっきまで賑わっていた待合室はふたりとニャン子しっこがいるだけだった。
「どうでしょうか」
「入院させるようですか」
「ごはんはたくさん食べたようですし、入院する必要はないでしょう。ただし三日間は安静にさせてあげてください」
「見えるようになるんですか、先生。足は大丈夫なんでしょうか」
「目の症状は一過性のものですので、次第に見えるようになります。足は骨折ではなく、股関節形成不全と云って、骨盤と太ももの骨が正常に結合されていない股関節の先天的な異常です。このように」
獣医はレントゲン画像を指差す。左側の股関節に比べて、右側が若干ずれているのが分かる。
「生まれつきってことですか」
「生まれる前、あるいは生後間もない頃に、右股関節に何らかの圧力が加わった結果と言うことです」
「これからどうすれば良いんでしょう」
「いまは少し腫れがあって痛がっていますから、抗炎症剤と鎮痛薬で様子を見てください。この疾患は体重を増やさないことが重要です」
「治らないんですか、ニャン子しっこの足は」
「悪化を防ぐことは出来ます。それが肥満にさせない事なのです。ですからくれぐれも、食事量には気をつけてください」
「治らないのですね」
「全治しないと決まったわけではありません、骨は成長に伴って正常になろうとするものですから。ですが過度な期待はしないでください」
元気に走り回るニャン子しっこの姿が見られないかもしれない。一方ではしゃぎながらじゃれるニャン子しっこの姿が目に浮かぶ。ふたりは困惑して言葉が浮かばずにいた。
「市販の食事は栄養が高いので胃に負担が掛かりますから、当面処方する食事を与えてください。それに腫れと痛みがひくまではお薬を飲ませて、ケージにに入れて安静を保つことです。何か、ご質問は?」
「排泄はどうしたら良いんでしょう。今さっき拾った猫なので、どうしていいものやら」
沈黙を嫌った五木田が、獣医に尋ねた。
「そうですねえ。一度はオシッコを見逃してあげてください。そのオシッコの臭いを猫の砂につけてトイレに入れます。失敗した場所は洗剤とアルコールで臭いを消すこと。そうすればすぐに覚えますよ。猫は清潔好きですから、失敗することはなくなります」
獣医は初めてにっこりと笑って答えた。
「―――全治しないと決まったわけではありません・・・正常になろうとするものですからね、動物は」
医師の言葉をかすみは信じたいと思った。
「———命に別状はありません」
五木田はその言葉だけ十分だった。
ふたりはニャン子しっこを育てる決意を固め、ホームセンターに向かった。歩いて二十分と掛からない場所だ。
カートにケージを載せ、買い物かごに猫の砂やおトイレシートなどを詰めながら五木田が明るく言う。
「明日は休みだから俺が面倒みてやれるけど、問題は明後日からだな」
「明後日はわたしお休みです」
「でもかすみちゃんのアパートは猫、禁止だろ」
「五木田さんのお家にお邪魔して、面倒みてはいけませんか」
五木田は首をひねって考えた。
( ひとり暮らしの男の部屋に行くのに抵抗はないのか。俺は仕事で居ないわけだし・・・考え過ぎか )
「かすみちゃんがそれで良いって言うなら俺は構わないけど、嫌じゃないのか?」
「いいえ別に。五木田さんが帰ってくるまでの間ですもの。この子の為ですから」
「なら場所を教えておかないといけないな。ニャン子しっこが暮らしやすい様にトイレの場所や寝床も決めなきゃいけないし、」
「はい。お邪魔します」
( 良いのかよ。少しは迷うもんだぞ、こういう場合 )
「でもやっぱり・・・」
( 気がついたか? かすみちゃん )
「名前は変えましょうよ。おかしいですよ」
( 何だい、その話かよ )
「今さら他の名前で呼んだりしたら、ニャン子しっこが戸惑うよ」
「今だから間に合うんです」
「そこまで言うなら、ニャン子しっこに決めてもらおう。それなら文句はないよね」
「はい。五木田さんこそ、わたしが考えた名前をこの子が選んだら文句を言わないでくださいね」
「もちろんだ。部屋に帰ったら、さっそく試そうじゃないか」
まだ名前の決まらない子猫は、病院で借りたキャリーケースの中ですやすやと眠っていた。
○ 仲間たち
「どうだい、かすみちゃん。タバコ慣れたか」
「おかげさまで美味しく感じるようになりました」
「喜んで良いのか、どうやら」
「また五木ちゃんが、変な入れ知恵したんじゃないだろうな」
「いいえ、親切に教えてくれました」
「今日はその五木田くんの顔が見えんけど」
「今日はお休みです」
「どうしてかすみちゃんが五木ちゃんの休みまで知ってるのよ」
「昨日の帰りに一緒だったんです」
「一緒に帰ったのか」
「いいえ、たまたまお会いしただけです。それにしても五木田さんって、良いマンションに住んでるんですね」
「何いっ? 五木ちゃん家に行ったのか」
「はい行きました。二DKの綺麗なマンションでびっくりです。わたしの雨漏りアパートとは大違い」
「たまたま会っただけなのに、部屋にまで行ったってか?」
「もしかして泊まったとか」
「泊まるわけないじゃないですか。でもすごく優しくしてくれました。わたし満足でした」
喫煙所にいる三人は顔を見合わせて同時に声を上げた。
「おいっ!」
「お前たち、いつの間にそんな関係に」
「昨日から」
「マジかよ。やるな、あいつも」
「見かけがアスリートだから、どっちかと言うと激しいタイプに見えるけど」
「人は見かけによらないもんだな」
「とても優しくて・・・子供みたいな一面もあるんですよ、五木田さんって。うふっ」
喫煙所の男たち三人は生唾を飲み込む。かすみの話を百八十度勘違いして受けとったのだ。
「どうしました?」
「それで、今後どうする気よ。お前さんたち」
「まずは、名前を決めないと始まらないって、思っているんですが」
「何っ! 名前?」
「はい。あの子の」
「あの子だあ?」
「まさか、赤ん坊か」
「そう、まだ赤ちゃん。あの子」
「それでいつ産んだんだ。そんな感じには見えなかったぞ」
「いつ、産んだって?」
「赤ん坊産んだんだろ? 五木田の」
「仕事してる場合じゃないだろうが。赤ん坊の面倒見てやんねえと」
「そうだよ。おっぱいやんなきゃ、死んじまうぞ」
「ええっ! わたしが赤ちゃんを産んだあ? 馬鹿なこと言わないでっ」
「だって五木田くんの赤ん坊産んだって、言ったじゃないか」
三人は揃ってうなずく。
「どうして五木田さんの赤ちゃんをわたしが産むんですか。怒りますよ!」
「だってよ、」
「いい加減にしてください。昨日初めて五木田さんのお部屋にお邪魔して、なんでその日のうちに赤ちゃんを産めるんですか」
「そりゃそうだ」
「かすみちゃんの話し方がいけねえんだよ。順序よくはっきり喋らねえから」
「始めから変な想像して聞こうとするからいけないんです」
かすみはそう言いながらも、昨日五木田と会いタバコがうまく感じる方法を教えられたこと、その時に生後間もない弱っている子猫を拾って、五木田とともに動物病院へ連れて行ったこと。数日間は五木田の家で看病しなければならなくなり、已む無く五木田のマンションへ行ったことなどをかい摘んで話した。
心配と不安に打ち拉がれていたかすみだったが、ニャン子しっこを育てて行く決意がかすみを明るくした。
「そう言うことか。驚かすなよ」
「んで、今日は五木ちゃんが面倒見て、明日はかすみちゃんが面倒見るってことだな」
「わたしのアパートで飼えれば、ずっと看ていられるんですが」
「五木ちゃんとこは分譲マンションだからな。あいつが飼うか、面倒見ながら飼い主を探すかしか、ねえだろな」
「食品扱ってるこの会社じゃ、飼えねえし」
喫煙所の皆は一様に、子猫のことを真剣に考えてくれている。その優しさがかすみは嬉しかった。
「わたし再来月に部屋の更新があるので、ペットを飼っていい物件を探そうと思っているんです。それまでは、五木田さんに面倒を見てもらって」
「五木田くんが飼い続ければ良いんじゃないの、猫の体調が回復すれば問題ないだろ」
「それはそうですが、当面という話なので」
「なあに五木ちゃんなら、うんって言うよ」
「でも五木田さんって、いい加減なところもありますから。強情と言うか」
「強情は分かるけど、いい加減ってことはないさ。仕事見てりゃ分かるよ」
「そんな事あります。だって、子猫に変な名前つけるんですもん」
「変? エッチな名前か」
「そっちの変じゃありません」
「ヘンテコってことか」
「はい―――ニャン子しっこ。って名前にするんだってきかないんです」
「ニャン子しっこ? 何だそりゃ」
「でしょ? かわいそうですよね。どう考えたって」
「確かに」
「それなのに五木田さんは、猫がオシッコやウンチをしている姿は世の中でいちばん神妙だとか、訳の分からないことを言い張るんです」
「確かに神妙かも」
「無の境地っていうか、悟りを会得した聖人。みたいな姿だな、ありゃ」
「それで、納得出来ないのか。かすみちゃんは」
かすみははっきりとうなずいてから話し始めた。
「結局子猫に決めてもらおうっていう事になって、マンションについてから選ばせたんです、本人に」
「猫にか」
「はい」
「それで?」
「わたしはミミ晴っていう名前が良いと言って、それでわたしと五木田さんが名前を呼んで、返事をかえした方の名前にする事にしたんです」
「それで、ニャン子しっこって呼んだら鳴いたってわけか」
「はい」
「たまたまだったんじゃねえのか」
唇をかんで頭をゆっくり横に振り、かすみは答えた。
「ミミ晴って十回呼んだんです、わたし。返事をしたのは一度だけでした。ニャン子しっこって五木田さんが呼んだら、五回のうち四回も返事をするんです。勝負になりませんでした」
「単純に五木ちゃんの方が好きだったんだろ。気にするなよ」
「えっ !」
「いいじゃないか、本人が気に入ったんなら」
「本人はないだろ、猫なんだから」
「じゃ、ホン猫かよ」
「本ニャンだろな、一般的には」
「んまっ、覚えやすいし良いんじゃないか。割と」
「変ですよねって言ったら、確かにって言ったじゃないですか」
「聞き慣れりゃ愛嬌がある名前だよ、特徴もあるしな。要は慣れ。すぐに慣れるって」
「でもあれだな。五木ちゃんは情が篤いから、手放さねえだろうよ」
「わたしだって手放したくありません、とっても可愛いんだから。引き取って名前変えるんです」
「しっかり話し合ったほうが良さそうだな」
「かすみちゃんも五木田くんのとこに転がり込めば良いじゃないか。そうすりゃ何の問題もなくなるぞ」
「それが良いな。広い部屋を持て余してるって話だしよ、五木ちゃん」
かすみは体を捩って顔を真っ赤にした。男三人は、にやにやしながらその様子を見ている。
「満更でもなさそうだな。なっ」
「九つや十歳の年の差なんて有って無いようなもんさ、かすみちゃん」
「は、はい」
「どう思ってるんだ、五木ちゃんのこと」
かすみは同じ格好のまま、間を置いて答えた。
「子猫の名前以外は、どちらかと言うと・・・タイプかも」
「ならそう言えば良いじゃねえか」
「そう。はっきり伝えて一緒に住むんだよ。もじもじしてちゃ駄目だ」
「かすみちゃんは自分から言い出せないタイプか?」
かすみは微笑を浮かべながら首を傾げて言った。
「わたし、恋愛経験ないので・・・恥ずかしいかも」
「恋愛したことねえのか、二十一歳にもなって。それじゃまだ男を、」
「おい、変なこと訊くなって」
「まあ恋の方はそう焦らない方が良いかも分かんねえな。でもこんなおいぼれオヤジで良かったらいつでも相談には乗るからよ、いつでも言いな」
「そうそう、俺たちは仲間なんだからさ」
「とにかく今はニャン子しっこの事を解決することだ。なんせ猫は話せねえんだから」
「人間の事情なんて後廻しで良いんだって。弱いもんのために親身になればうまくいく様になってんだからさ、世の中ってのは。成るようになるって」
休憩時間の終わりをつげるベルが鳴ると、男三人は慌ててタバコを消してそれぞれの職場に戻って行った。かすみはタバコを吸わなかったことさえ忘れて、三人の背中にありがとうと言った。
○ 暮らし
「どうだい? 様子は」
仕事から帰宅した五木田は、ニャン子しっこを看守っていたかすみに尋ねる。
「大分元気になりました。見違えるようです。よく食べてよく寝る子ですね、この子は」
「で、足の具合はどう?」
「ケージのなかにいるからよく分かりませんけど、気にしてはいないようです」
「どうなるのかな、ニャン子しっこ。治れば良いけど」
「でも障害が残っても、この子が楽しく生きていければそれで良いんじゃないかなあって思うの。わたし」
「そうだな。障害なんて、特徴のひとつだもんな。ニャン子しっこが元気に育てばそれで良いんだ」
「それにしても羨ましいなあ。五木田さんは毎日この子と一緒に寝られるのね」
「別に一緒の布団で寝るわけじゃないって」
「傍にいられること自体が幸せなんですよ。ああ羨ましい」
会社が休みだったかすみは、五木田の出勤時間に合わせてマンションを訪れていた。朝五時過ぎから十一時間部屋にこもり、ひと時もニャン子しっこから目を離さずに過ごしたのだった。
「この分なら、明日はニャン子しっこひとりで留守番させても大丈夫そうだな」
「でもまだ全治したわけではないから、無理はさせたくないわ」
「動物って、その辺の見極めは出来るって云うから問題ないだろ。ケージの中にいることだし」
「それはそうですけど」
かすみはあと僅かでニャン子しっこと別れなければならない事実に、頭がいっぱいだった。
「元気だしなって。それで、どうだった。ションベンしてる姿」
肩を落とすかすみに、五木田は快活に尋ねる。
「確かに・・・神妙ですね。昨日喫煙所で話していたんですけど、無の境地、悟りを会得した聖人っていう感じ」
「だろ」
「はい。名前だけで変な先入観を持ってしまって、反省してます」
かすみは立ち上がって頭を下げてから続けた。
「帰る前にわたし、この子が電気のコードとかを噛み噛みしない様に片付けておきますね」
「ケージの中にいるんだから大丈夫だよ」
「あっそう、シートを新しいのと換えないと」
かすみは少しでも長くニャン子しっこの傍に居たかった。
「案外気が利くんだね、かすみちゃんは」
五木田はカーペットの上で、いじらしいその姿を眺めながら言った。
「案外、ですか」
「ごめん。よく気がつく子だよ」
「五木田さんから見たら、子ですか? わたしって」
「年下の女性だからね、かすみちゃんは。気にすんなよ。でもさ、何で名前で呼んでやんないんだよ」
「だって」
「気に入らないのか?」
かすみは何となく黙り込んでしまった。ニャン子しっこは寂し気なかすみに向かって、ひと鳴きした。
「みゃあ」
「ほら、名前で呼んでよお姉ちゃんって言ってるよ」
「名前で呼んでほしいの?」
「んみゃ」
「ほら」
「ニャン子、しっこ。ちゃん」
「みゃあ、みゃあ」
「喜んでるの? 君は」
「嬉しいんだよ。名前で呼んで貰ったから」
「ホント? ニャン子しっこちゃん」
「んにゃ」
「返事した」
「そりゃするよ」
「そりゃするよって、返事するっていうことは言葉が解るっていうことなんですよ、五木田さん」
「解るよ、それくらい」
「何でそんなに平然として言えるの?」
「そりゃ始めは俺だって驚いたさ。産まれて日も浅いのに、もう言葉を理解出来んのかってな」
「そういう事じゃなくて、猫が人間の言葉を理解出来ること自体あり得ないことでしょ」
かすみは呆れてそう言ったが、五木田にはかすみの話の方が理解出来なかった。
「どうして人間は猫の言葉が理解できないのか、ニャン子しっこはそう思ってる筈だよ。それよりこれからの事だ。まだ今日で二日目だけどさ、ニャン子しっこ飼い続けるよ俺」
「わたしも、部屋の更新をしないでペット可物件を探そうと思っていたんです」
ふたりはきまり悪く黙りこんだ。
ニャン子しっこを手元で育てたいと思うかすみの気持ちが、五木田はよく分かっていた。かすみもまた、五木田がこのマンションでニャン子しっこを飼い続けたいという気持ちを理解している。
「みゃあ。みゃあう」
ニャン子しっこはふたりの顔を交互に見て鳴いた。
( 三人でいっしょに暮らそうよ )
五木田とかすみは、ニャン子しっこが何を話しているのか分からなかった。
「飯、どうすんだ?」
話し合ってもすぐに結論が出ないことはふたりとも分かっている。五木田はかすみの口を開かせようとして、話しかけた。
「部屋に戻ってから、簡単なものを作って食べます」
「もし良かったら、外で食わないか。ご馳走するよ」
「良いんですか」
「俺もたまには栄養のあるもん食いたいからさ」
「普段はどうしてるの?」
「冷凍食品をレンジで温めるか、卵焼きとか焼うどんとかフライパンで簡単に出来るものを作るくらい。たまあに惣菜も買うけどさ。米だけは炊くようにしてる」
「お買い物に行って、何か作りましょうか。その方が栄養摂れますし、この子とも一緒にいられるから」
「でも大変だろ」
「簡単なものしか作れませんから、余り期待しないでください。お口に合うかどうか自信ないし」
かすみのはにかんだ表情を見た五木田は、ほんとうに可愛らしい素直な子だと思った。
「んじゃあ、まずはコンビニで一服して、それから買い物行こうか。吸ってないんだろ? かすみちゃん」
「五木田さんも部屋じゃ吸わなかったようですね。匂い、しませんでしたもの」
「ベランダで吸うことにしたんだ。ニャン子しっこが可哀相だから」
「わたしも。ニャン子しっこちゃんの傍にいたら、吸うことも忘れちゃいました。だから今日はまだ二本だけ」
「とにかく行こう、遅くなっちまうからさ」
ふたりはそれぞれニャン子しっこに頬ずりをして部屋を後にした。
「もう慣れたようだね、タバコ」
「はい。気持ちが落ち着きます。五木田さん、コーヒーは?」
「かすみちゃんの手料理が食べられるんだからね。やめておくよ」
五木田はかすみの目を見ずに答える。
「あれ?」
「何ですか、何か見えるの?」
かすみは五木田の視線の先の三階建てマンションに目をやる。コンビニと道を挟んだ正面の、一階が電気店の建物だ。
「ぬいぐるみかな。ほら三階の出窓のところ」
かすみはタバコを消し歩道まで出て出窓を見上げた。白と薄い茶色のまるまると太った猫は、ぬいぐるみか生きている猫なのか分からない。
「ぬいぐるみ、みたいですね」
「かもな」
「あっ」
「動いた」
「のんびりしてますね、あの子」
「何の不安も心配もない、そんな感じだな」
「もう日が暮れるって言うのに、ひなたぼっこかしら」
「あそこが定位置なんだろ」
「ニャン子しっこもあんな風になるのかな」
「色は似てるけど、あそこまではデカくならないだろ」
ふたりは歩いて五分と掛からない激安スーパーに入った。買い物かごを肘に掛けたかすみは、野菜コーナーでひとつひとつを手に取って吟味すると、何もかごに入れずにその先の肉売り場に向かう。
色を見て指先で肉をつついては元に戻し、別のトレイのものに手を伸ばす。同じことを何度か繰り返したあと、五木田に振り向いて言った。
「駅のスーパーに行きましょう」
「いいよ、ここで」
「よくありません。お野菜は新鮮さに欠けるし、お肉は解凍の仕方に問題があるようです。簡単なものしか作れない分、食材には妥協したくないんです」
「こだわるねえ、かすみちゃんは」
「それはこだわりますよ。男性に作る初めてのお料理なんですから」
そう言ったかすみは、自分の言葉にはっとした。
( わたしやっぱり五木田さんのことが好きなのかもしれないわ )
「嬉しいねえ。でも遅くなると悪いから」
「構いません。五木田さんがご迷惑なら仕方ありませんが」
「そんな事ないよ。俺だってかすみちゃんが満足して作った料理を食べてみたいしな」
( 世の中の夫婦って、こんな会話をしているのかしら。「美味しそうだね」「腕によりをかけて作ったの。美味しい?」「ああ、愛情たっぷりで美味しいよ」「ありがとう」、なんて )
かすみは自然と笑みになった。
ふたりはさらに坂を下って駅へと向かう。仄暗くなった道は、仕事や学校帰りの男、買い物帰りの女性が目立つ。
「なんか良いな。こんな感じ」
「こんな感じ? どんな感じ?」
「肩を並べて買い物に向かう、感じさ」
「五木田さん。変なこと言っていいですか」
「変なこと?」
「もう少し寄って歩きません? この空間、なんだか不自然な気がします」
「ああ、他の人の邪魔になるしね」
連日の強い風のせいで、あちらこちらに塊となっている落ち葉を避けながら、ふたりは黙ったまま坂道を歩く。時々すれ違う自転車に道をゆずろうと歩道の端に寄ると、時々手が触れ合った。
「面倒だな」
五木田はそう言うと、かすみの手をとってしっかりと握った。自然とふたりの距離は狭まり、五木田の肘がかすみの肩に触れる。
「いやじゃないか? こんなおじさんと手をつなぐの」
かすみは五木田の握る手に力を入れて答え、小さく頭を横にふる。
「何を食べさせてくれるんだ?」
「食材次第です。好き嫌いはありません?」
「無いよ」
「何でも食べられるんですね」
「普通にお店で売ってるものならね。虫とかヘビは嫌だけど」
「んもう」
少しだけ会話が弾んだが、ふたたび沈黙が訪れる。だがふたりは嫌な気もしないし退屈だとも思わなかった。五木田は時々手を離しては、汗ばむ手をずぼんで拭い、そしてまたかすみの手を求める。かすみはその手をしっかりと握り返す。ふたりはこの時間を楽しんだ。
○ 猫と人との生活
盛りつけ班の班長である五木田勝治は、専務兼品質管理責任者の木田勇蔵に呼び出され会議室にむかった。
専務の木田が直々に班長クラスの者を呼び出すことなど滅多にないことで、通常の業務に関することはすべて生産管理係長を通すのが不文律となっている。それだけに階段を昇る五木田の足どりは重かった。
五木田が厚い木の扉をノックすると、低く勇ましい声の専務の返事が返って来た。
「入りたまえ」
重低音の利いたマイクから流れる様な声に五木田の背筋はぴんと伸びる。
「やあ、五木田くん。わざわざ呼び出してすまなかったね。まあ掛けたまえ」
専務の木田は年代物の重厚な木製デスクで書類を広げながら言った。書類を眺めては捺印を押す作業を繰り返すと、ふうと息を吐いて、ようやく五木田に顔を向ける。
「さっそくだがね・・・コーヒーで良いかい?」
浅黒くたるんだ頰に笑顔が浮かんでいる。
―――さっそく・・・
その言葉の後に何が続くのか恐れていた五木田だったが、安堵して柔らかすぎるソファーで座り直した。
「ちょっと耳に挟んだのだが、君、猫を飼い始めたそうじゃないか」
( もう専務の耳に入ったのか )
その後の言葉を五木田は想像出来た。
―――食品は安全と清潔が命。猫の毛など混入したら即座に会社はつぶれる。猫など飼うな、だ。
だが専務木田の言葉は意外なものだった。
「どんな猫を飼ったんだね」
「えっ? 白に薄い茶色が入った、オスの雑種です。生後、」
「雑種ぅっ? それはどう云う意味かね」
「ペルシャ猫とかロシアンブルーとかチンチラとか、そういった類の猫ではないという意味で・・・ミックス」
「どっちでも同じだよ。では訊くが、日本人が多国籍の異性と結婚して子どもが生まれたとする。君はその子のことを雑種、或いはミックスと呼ぶのかね」
「いいえ、とんでもない」
「立派な差別だよ。君の主張は」
「主張のつもりで申し上げたわけではなくて、」
「君の口から出た言葉はすべて主張。言葉とはそれだけ重いものなのだよ君」
「僕はあくまでもいち動物の種別としてお話しただけで、」
「私にはそれが納得出来んのだ。雑種や雑草、そんな動植物はこの世に存在しない。一部の人間が勝手につけた差別用語でしかない。以後慎みなさい。いいね」
喋り疲れたせいか、吐く息が乱れ顔が赤く染まっている。五木田は改めて姿勢を正すと、幾らか落ち着いた専務木田が話を続けた。
「とこでその子猫の具合、どうなの」
「生後二ヶ月にもならない子猫なんですが、はた目から見ても弱っていて、股関節形成不全とかいう、」
「なにいっ、 股関節形成不全だと! それは一大事じゃないか」
専務木田は意外にも過剰な、いや異常な反応をみせた。
五木田は根気と強く今後の治療方法や留意点などを話すと、専務木田の表情は、正義漢から沈痛なものに変わっていた。
「心配だな、大事に至らなければ良いが」
「はあ」
「ところで、君と内田くんが保護したと聞いたが」
( そこまで知ってるのかよ)
「たまたまコンビニで内田さんと会った時に、弱っているその子猫を見つけたものですから」
専務木田は音を立ててコーヒーを飲むと、ゆっくりとした動作でテーブルに置き、身を乗り出して言った。
「写真、ないの」
「はっ? 写真ですか」
「そう。子猫の写真」
五木田は仕事で使っている私物のPHS携帯を胸ポケットから取り出し、フリップを開き操作する。
( なんで写真なんかを )
五木田には専務木田が何を言わんとしているのか理解出来ずにいた。
「この子です」
専務木田は素早く携帯を奪い取り、老眼の目を細めて鼻先まで近づける。
「足を固定したんだね。痛々しいねえ、可哀相に」
「痛み止めの薬を飲ませたので、昨夜はぐっすり寝ていました」
「それは良かった。それにしても・・・可愛いでちゅね」
「はい?」
「ウッウウン。で、名前。なんて付けたんだね」
自分が専務である事を思いだした木田は、ソファーにもたれ足を組んで尋ねた。
「・・・ニャン子しっこ、と」
「なあにい? なんだその名前は」
専務木田の黒ずんだ頰がみるみる赤黒く染まっていく。
「君が同じ名前だったらどうだ。五木田ニャン子しっこだったら。いや、君が将来結婚して子どもを授かったとする。女の子なら 『しっ子』、 男の子だったら 『小便小僧』 と付けるか? 可愛い我が子に。呼ばれる子の身にもなってみたまえ」
「はあ」 ですが、
五木田は排泄中の神妙な猫の姿が尊いからだと説く。緊張で汗が背中にまで流れていた。
「確かに。あれは動物界きっての神聖な姿だよ君。ネコのしっこやうんちを臭いと非難する人がいるだろう? そんな言葉を耳にするたびに非常に腹が立ってね。ではあなたのションベンやクソはハーブの香りでもするのかい、と訊きたいくらいだ」
専務木田は再び携帯に顔を戻す。デレデレだ。
「飼うのに困ってると耳にしたのだが」
「ウチで飼う事に決めました」
「君はひとり暮らしだったよな。面倒見られるのか? 大変だぞ子猫は。しかも先天性の疾患を抱えているとなると」
「まだ三日目ですが、大丈夫です。自信が湧いて今は楽しいです」
「この子、何と言ったかな」
「ニャン子しっこ」
「ニャン子しっこの将来は、君の育て方ひとつで決まるんだ。しかも股関節形成不全を患っている。責任は重いんだよ君。分かっているのかね、その辺のところは」
「はあ、自覚しているつもりです。大丈夫です。ところで、」
五木田が何の話で呼び出されたのか尋ねようとすると、専務木田は言葉を遮って語り続けた。
「実は私は大の猫好きでね。地元の愛猫クラブ会長をつとめている、ちょっとした有名人でもあるわけだ。そう偉そうに言えたものでもないがね」
「木田専務が猫好きだと知って、僕も嬉しいです」
「同じ猫好き同士、木田の字がつくもの同士だ、これから親睦を深めていこうではないか」
「是非よろしくお願いします」
「まっ、困ったことが有ったら遠慮なく言いたまえ。いつでも力になるから」
「はい。ところでお話とは、」
「飼えなくなる様なことがあれば、すぐに言うんだぞ。いいね」
「一生涯、僕が面倒をみます」
「あっそう。悪かったね、忙しいのに呼び出したりして」
専務木田は片手をあげてそう言うと、そそくさと机に向かって行った。
「専務から呼出しくらったんだって? 五木田くん」
「何かやらかしたのかよ」
喫煙所ではいつもの面々が、遅れて来た五木田に次々と声を掛けた。かすみはベンチの横に立って心配そうな目を向けている。
「いやあ、猫の話でしたよ。もう専務の耳に入っててさ」
「それで何だ、猫飼うなとでも言われたのか」
「むしろ逆かな。専務は大の猫好きでさ、ひとり暮らしじゃ飼うのに困るだろうとか、相談に乗るとか、いろいろ言われましたよ」
「へえ。あの熊面が、猫好きとは恐れ入ったな」
「そんでどうすんだ。その、しっこをやるのか」
「しっこじゃありません。ニャン子しっこちゃん」
かすみが抗議した。
「何だよ。あれだけ変な名前だとか反対してたくせして」
「あの時はあの時です。もう決まったんだから、ちゃんとした名前で呼んでくれないと困ります!」
「怖っ」
「専務にやるのか、その、猫」
「あげたりしませんよ。俺ひとりで育てるから大丈夫だって断りました」
かすみは目を大きく見開いて五木田をにらんだ。何かを言いたそうに、口をわなわなさせている。
「ひとりでだあ?」
「それじゃかすみちゃんの気が収まらねえぞ。なっ、かすみちゃん」
「わたしはニャン子しっこちゃんの母親ですもの。ペット可物件が見つかったら、わたしが引き取るんです」
「なんだよ、話が違うじゃないか。俺のとこで育ててかすみちゃんはいつでも来て世話して良いって、そう話が着いただろ」
「何よ、自分だってひとりで育てるなんて言ったりして。ペットが飼える環境で暮らしてるからって偉そうにしないで」
「夫婦喧嘩は猫も食わねえぞ」
「その通り」
「なあ。ふたりとも素直になったらどうだ」
「外野から眺めてるとよ、意地の張り合いにしか見えねえんだよな」
「一緒に暮らせば丸るく収まるじゃねえか。お互いに分かってるくせして」
「昨日晩飯食べさせて貰ったんだろ? 五木ちゃん。かすみちゃんの愛情料理をさ」
「喋ったのかよ、かすみちゃん」
「別に隠すことじゃないもの」
かすみは口を尖らせ、体を捩りながら言った。
「五木、はっきりしねえお前が悪いぞ」
「そうだ。女の子が手料理を男に食わすってことが、どれほどのもんか分からねえのか。お前には」
「どうなんだ、お前の気持ちは。はっきり伝えないとな、あれこれ考えちまうんだよ。恋する女って生き物は」
五木田はタバコを取り出し火を着ける。と、休憩時間終了のベルが鳴り響いた。
「くそお」
「とにかくふたりで話し合え」
「腹割って思ってること言い合わなきゃだめぞ」
五木田とかすみだけがその場に残った。
「ごめんな、かすみちゃん。みんな誤解しちゃったみたいだな。もし良かったら今日ウチに来ないか。ちゃんと話し合おうよ」
「そうですね。みんな心配してくれてることですし。ニャン子しっこちゃんの将来に関わる事ですものね」
「素直になんないといけないね、お互いに」
かすみはうなずき、ふたりは別々の方向の職場に戻って行った。
○ 新しい生活の中で
「たまには外の世界も見せてやろうよ」
五木田の提案で、かすみとニャン子しっこの三人は公園に足を運んだ。
市立公園と県立公園が隣り合っている広大な公園は、丘をそのまま切り開いた緑に包まれた公園だ。なだらかな斜面には桜やハナミズキ、楓などの木々が品良くたち並び、青々とした芝が坂下から丘のうえまで続いている。動物広場やドッグラン、植物公園などの施設は、点在する様々な草花の中にあって、日がな一日をのんびり過ごす家族連れの姿も見受けられる。
新調したキャリーバッグに揺られているニャン子しっこは、狭い視界のなかで目をきょろきょろとあちらこちらに向けている。
「可愛いわね」
「興味津々って様子だな」
「緑いっぱいだから、気持ち良いのね」
「猫も、町より自然を好むんだな」
「ねえ。ワンちゃんがいないところで、少しだけ歩かせてあげましょうよ」
五木田とかすみが同じ日に休みを取れることなど今までは滅多になかったのだが、ふたりが一緒に暮らし始めてからは、同じ日に休日を取らせる事が職場での暗黙の了解となっていた。
かすみが五木田のマンションで暮らし始めてから二週間が経った。ニャン子しっこがふたりと出会ってからは、既に二ヶ月が経とうとしている。手の平に載るほどの大きさしかなかったニャン子しっこは、まだ成猫とまでは言えないまでも若さ漲る少年と言えるくらいにまで成長し、猫用のハーネスにお揃いの薄いブルーのリードをつけて度々マンションのまわりを連れ出してはいた。
喫煙仲間を始め同僚たちは、結婚を前提としてふたりが暮らし始めたのだと思っているが、当の五木田とかすみは、男女関係を意識するまでには至っていない。
世間一般では他人同士が共に暮らすことを、ルームシェア、同居、同棲、居候など色んな言い方をするものだが、五木田とかすみは、どれも当てはまらないと思っている。
「―――わたしたちって、どんな関係なんだろう」
かすみは自分なりに分かっている答えを、度々五木田に尋ねる。
すると五木田は、
「―――兄貴と妹がいちばん当てはまるんじゃないか」
と、かすみが思っているのと同じ答えを返す。
かすみは今、ふいにそんな会話を思いだし五木田を見上げた。五木田はキャリーバッグに入ったニャン子しっこに、こちらに歩いてくるゴールデンレトリーバーを見せて話しかけている。
「ねえ五木田さん。手、つながない?」
―――兄貴と妹が手をつなぐ。
妹のいない五木田と兄のいないかすみには、本当の兄妹同士が手をつないで公園を歩くことが自然なのか不自然なのかが分からない。だが廻りから見れば、恋人同士或は夫婦と見られるだろう事は、お互いに分かっていた。
「あ、ああ。あれから手つないでないもんな」
五木田はバッグを右肩に抱えなおして、左手を差し出した。
「久し振りだな」
「相変わらず冷たいわね、五木田さんの手」
「にゃあお」
ニャン子しっこはバッグの側面にある小窓からふたりを見て鳴いた。
「何て言ってるんだろう」
「さあ」
———しあわせだね、お父さんとお母さん 。
かすみは思っている事を口に出さなかった。
確かにふたりには異性として意識し合っていた時期があった。だがふたりで暮らすことを決め、ニャン子しっこがより身近な存在となってふたりの生活の中心になっていくにつれ、次第に親代わりという意識が強くなっていった。そして一緒に暮らし始めるとその思いだけで十分幸せなのだと感じる様になり、それが自然の形となっていたのだった。
( わたしはこれから、五木田さんのことを男性として見られるだろうか )
( 俺はかすみちゃんのことを妹だと思えば良いのか、将来の伴侶として見れば良いのか分からないでいる。ニャン子しっこと出会わなければ、俺は間違いなくかすみちゃんを女性として意識していた筈だ。でも今は違う。妹としてしか見られない )
職場の喫煙仲間がいくら背中を押しても、いまのふたりは結婚までは考えられずにいた。
青々とした草花が広がる丘を、ニャン子しっこは走ってはコテンと転び、立ち上がってはまた走り、はしゃいでは転んでまたはしゃぐことを繰り返している。時々出会う虫に驚いて後ろにジャンプする姿を見て、ふたりは声を上げて笑った。少し足を引いて歩くものの、喜びを露わにして遊ぶニャン子しっこを見ているだけで、ふたりは幸せだった。
「楽しそうだな、ニャン子しっこ。すごいはしゃぎようじゃん」
「こんなに広いところは初めてだから、どうやって遊んで良いのか分からないのね」
不自由な足で走る健気な姿に、ふたりは子供を見る親の目を向けていた。
「おっ」
「あっ」
白に薄茶色がまじったロングコートチワワが風を切って走ってくる。飛び出すのではないかと思うその目は、喜んでいるのか怒っているのか分からない。
「ごめんなさ~い。首輪がはずれちゃったんですっ!」
大柄な飼い主の女性が懸命に後を追いながら叫ぶ。極端に狭い歩幅は自分のイメージ通りには進んでくれないようで、歩くのと大差のないスローペースだ。五木田はリードを引いてニャン子しっこを抱えようとするが、興奮してくるくる回ってうまく抱えられない。
と、ニャン子しっこは意を決したかのように当然ピタっと立ち止まった。
「シャアーッ!」
背なかを弓なりにして相手を威嚇する。不自由な右足の動きが、かえって軽快なフットワークをかもし出している様に見えた。
「あっ、ブルース・リー」
「ブルー・スリー? 何それ」
「燃えよドラゴン。伝説のカンフースターだよ。知らないのか」
「知らないわよ。ジャッキー・チェンみたな人?」
「タイプは違うけど、似た感じかも」
チワワが近づいてくる。五木田は背中から闘争心丸出しのニャン子しっこを抱え上げた。
「ク~ン、ク~ン。ハァウウ」
チワワは甘えた声を出してニャン子しっこを見上げ、しきりにジャンプする。鋭い目つきをしていたニャン子しっこの目は下がり、首を伸ばして興味津々だ。
「はあ、はあ。ご、ごめんなさい。はあ」
「いいえ」
「ウチの子は、猫と一緒に暮らしているものですから、猫ちゃんが、大好きなんです。ねっ、アケミちゃん。はあ」
息が整わない飼い主は片手で軽々とアケミを持ち上げると、ニャン子しっこの鼻先に顔を近づける。ニャン子しっこは鼻先に顔を近づけ、臭いを嗅ごうとしている。かすみには、恥ずかしがりながら手を握ろうとする少年に見えた。
ぺろん。チワワが短いベロでニャン子しっこをなめた。一瞬びくっとしたニャン子しっこだったが、慣れた様子で気持ち良さそうに目をつぶり、されるがままにしている。
「可愛い猫ちゃんねえ。なんて言うお名前?」
「ニャン子しっこです」
ふたりは同時に答えた。
「まあ、可愛い名前。やっぱりあの時の姿を思ってつけたの?」
アケミの飼い主は名前を聞いても吹き出す事なく訊き返した。猫を飼っているだけに、その生態うぃよく知っているようだ。
「はい。神妙ですから」
「そうよね。ウチのアケミちゃんはおトイレを失敗することがよくあるんです。だからニャオミちゃんの、ウチの猫はニャオミって言うんですけどね。ニャオミのちゃんの真似をすればいいのよって教えてるんですけど、なかなか出来なくて」
根っからの動物好きなのだろう。飼い主は十分ほど猫と犬の話を夢中になって話し続けた。その間ニャン子しっこは、チワワのアケミに顔中を舐められっぱなしだった。
「初めてのお友だちね。良かったわねえ、ニャン子しっこちゃん」
「んみゃお、おん」
ニャン子しっこは手で顔を拭きながら答えた。
「可愛いもんだな、犬も」
「そうね。犬派とか猫派とかあの人には関係ないのよね。ただ可愛くて愛してるだけ」
「ウチも犬飼うか、ニァン子しっこは昼間ひとりぼっちで寂しいだろうし。引き取り手のない子を引き取ってさ」
「市で定期的に里親を探すイベントがあるみたいよ」
「そうか」
ふたりは黙りこんだ。ニャン子しっこを拾い動物病院へ連れて行ったあの日の事を思いだしていたのだ。
「ひとりひとりが身寄のない動物を引き取るってことは大事だけどさ、そんな犬や猫を減らすことのほうが、大事なんだよな」
「そうね、辛い思いをする子を守ってあげないといけないのね。わたしも同じことを考えてた」
「その子の一生の責任を負う事になるんだから、真剣に考えなきゃ」
「しっかり考えてからにしましょ、五木田さん」
「ミャアオ、ニァアオゥ」
ニャン子しっこがふたりを見上げて二度鳴いた。
―――ありがとう、お父さんお母さん。
○ 出会いそして進展
食品加工工場は、言うまでもなく安全と清潔・衛生が最も重要な職場だ。これらがひとつになって稼動されることこそが、会社の使命と言える。
食品加工業ではたびたび不正問題が発覚しニュースで報じられるが、それは安全と清潔・衛生のどれかを疎かにした結果と言えよう。賞味期限の改ざんや劣悪な環境下での作業などをしていれば、必ずその情報は外部に漏れ明るみになり、結果会社存続の危機に直面する。規模の小さい企業であればあるほどその可能性は膨らみ、即時営業停止処分が下され廃業の途をたどる恐れが色濃いのが、業界の現状である。
五木田とかすみが勤める『 新選フーズ有限会社 』は、全従業員二十名の零細企業で三百六十五日稼動している。この程度の規模の会社が未だ生き残っていられるのは、言うまでもなく安全と清潔、そして品質管理が徹底して守られているからだ。
新選フーズでは、営業時間内であればいつでも顧客の視察や見学を受け入れている。客先の担当者はもちろん売り場のパートまでもが事前連絡なく来社出来ることが競合する他社にない特徴である。また要望や指摘を即改善する体制を敷く事で顧客からの信用を得、安価な価格競争に巻き込まれない理由となっているのであった。
盛りつけ班の中枢を担う班長五木田勝治は、顧客である『 懐かし屋フーズ』本社仕入担当・蓑田英里の現場案内をし、会議室へ招いたところだった。新年度から新たな仕入れ担当となった箕田英里は二十五歳。大学で栄養学を学び、懐かし屋フーズに就職してからのおおよそ三年間は、本社統括マネージャーのもとで会社全体の仕事を学んできたキャリアだ。
「盛りつけを中心に、御社全体の仕事を拝見しました。品質管理、衛生面の徹底など、どれも私どもが望む以上にご努力されている事がよく分かりました」
紺色のスーツ姿の蓑田英里は、手厳しい女という評判だ。だが実際に相対した五木田は、少し堅いイメージはあるものの、笑顔が似合う品のある女性だと感じていた。
「恐縮です。ですが何かご指摘を頂かなければ、わざわざお越しくださった意味がありません。何なりとおっしゃってください」
「そう言われても・・・」
顧客の中には、『 買ってやっているんだ 』という意識が強い横柄な態度を取る者も少なくない。そんな関係を嫌う五木田は、見学や視察に訪れた者に必ず要望や改善点などを指摘させることにしている。もちろん新選フーズと顧客、双方のためにだ。
「ではひとつだけ」
「二つでも三つでもどうぞ」
「建物の横の喫煙所が気になります」
「喫煙所、ですか」
「食品を扱う者は喫煙すべきではありません」
「はあ」
「弊社では本社はもちろん各店舗全面禁煙とし、従業員用お客さま用問わず、すべての灰皿は撤去しました」
「それで、喫煙者はどうしているんですか」
「会社負担で禁煙外来に通院させ、やめてもらっています」
「うちでもそうしろと?」
「要望としてお伝えしたまでです」
「禁煙させる為に病院に行かせるなんて、うちみたいな小っこい会社じゃ無理ですよ」
「何も弊社と同じ様にしてほしいと言っているわけではありません。全面禁煙を望んでいるだけです」
手厳しかった。別にタバコの灰や臭いが商品に付着するわけじゃないんだから、全面禁煙になんかすることはないんだ。五木田は唇を噛みしめるだけで何も言い出せないでいる。
「専務は、個人的に禁煙すると約束してくださいました」
「えっ、木田専務が?」
「そうです」
じつにまずい展開だ。一日三箱は吸わないと禁断症状が現れるというあの専務木田が、禁煙など本当に出来るのだろうか。
「これは新選フーズ内の問題ですから、上司や従業員に伝えたうえで決定すると云う以外、なんともお答えでき兼ねます」
「五木田さん」
英里の厳しい目が心持ち下がり、若干口角が上がった気がする。
「あなたは素晴らしい方ですね」
「えっ? 僕がですか」
「実は他の取引先でも同じ要望をしました。どこの企業も、
―――自分にはそんな権限がない。自分は答える立場にない。
そう言われます。だけど五木田さんはそんな事はおっしゃらなかったわ」
一体何が言いたいのだろう。五木田は首を傾げるだけだ。
「今度の新商品開発プロジェクト。『 懐かし屋弁当シリーズ 』の共同開発をお願いする取引先を探していたんです。新選フーズさんにお任せします。五木田さんには、是非担当のひとりとして参加して頂きたいわ」
「俺、僕が?」
「あなたが加わることを条件に、御社を協賛企業として推薦します」
「ウチには開発担当がいます。担当でない僕が加わるのは、」
「弊社の共同開発プロジェクトの件は、既に木田専務にお話ししております。それを承知の上で木田専務は、私の案内を五木田さんに任せられたのですよ」
「専務が?」
「はい。実質的な、会社経営者の専務がです」
( もともと開発には興味があった。だが専務とその側近しかたずさわれない事が、この会社の体制であり問題点だ。一丁、風穴を開けてやるか。新選フーズに )
「話は戻りますが、全面禁煙の件。あれには僕は反対です。蓑田さんが言わんとする事は理解出来ますが、灰皿を外部からは見えない場所に移動すれば衛生上問題はありません。むしろ全面禁煙になどすれば、喫煙者の精神衛生上の問題が生じます。喫煙者は喫煙所があってこそ、楽しく責任感を持続しコミュニケーションをとって仕事が出来るという者だっているんですから( 俺がそうなんだ )」
「分かりました。衛生面の課題がないか、もう一度御社内でお話なさってください。問題がなければ、今後私どもは口を挟んだり致しません」
五木田は安堵しつつ、疑問を投げ掛ける。
「ところで、専務は本当に禁煙すると言ったんですか」
「確かに」
「全面禁煙をすると?」
「全面禁煙に関して言えば、五木田さんと同じように反対でした」
( そうか。専務木田は自分がタバコをやめる変わりに、全面禁煙を回避させようとしたのかもしれない。豪腕で名の通った熊みたいな人だけど、良いところもあるじゃないか )
「では担当の件、よろしくお願いします」
「もし僕で正式決定したら、御社での会議に出席することになるのですか」
「販売日間近になれば、二、三日泊まりがけでお越しして頂くことになるかと思います。もちろん宿泊費はこちらで負担いたしますが」
五木田はニャン子しっこの生活に影響が出ると思い、がっくりと肩を落とした。
「それともうひとつ。御社からもうひとり、新商品プロジェクトに参加をお願いする方がいます」
「専務ではなくて?」
「新鮮な風が必要なんです、私たちには」
「誰が候補なんでしょう」
「内田かすみさんです。彼女の経歴の概略は、木田専務から伺いました。彼女はかなり勉強をしてきたようですね。開発だけでなく事務関係でも期待出来る彼女が、未だ資材係の現場を担当していること自体、私は首を傾げます」
「内田は食品加工にはたずさわった事さえないんですよ」
五木田は、かすみと自分が数日間不在にする事や、遅くまで残業をした時のニャン子しっこの事が心配でならなかった。
「その様な方だからこそです。きっかけを与えてさえすれば、彼女は必ず才能を伸ばします」
「これから話すんですか、内田に」
「残念ですが、これから他社をまわる予定が入っているので時間がないんです。後日、なるべく早くお話しに伺います」
「僕から話をしても問題はないでしょうか」
「むしろ説得して頂ければ助かります。彼女にとってまたとないチャンスでもあるわけですから、きっと彼女も喜ぶでしょう。お力添えくだされば助かります」
最大の試練が訪れたのかもしれない。五木田とかすみのふたりがこの企画に加われば、ニャン子しっこの生活にも少なからず、いや、相当な影響を与えることになるであろう。五木田は頭を抱えて会議室を後にした。
○ 三人の気持ち
「どうする? かすみちゃん。良い話だと思うよ。ここでかすみちゃんが実績を残せば、念願の事務職になれるだけじゃない、新選フーズの顔になれるんだから」
食事を済ませシャワー浴び落ち着くのを待って、五木田は懐かし屋フーズの商品開発プロジェクト登用の話を切り出した。かすみはほんの一瞬だけ喜んだが、すぐにうつむいてしまった。五木田が予想していた通りの反応だった。
「五木田さんは受けるのよね、その話」
「迷ってるんだ。かすみちゃんと同じ理由で」
黙り込むふたりのことを、ニャン子しっこは定位置のインテリアケースに重ねらた新聞の上で聞いている。陽当りのよいお気に入りの場所だ。
「どうしたら良いのかしら」
「初めに会った時に連れて行った動物病院。あそこはペッとホテル併設って書いてあったよね」
「うん」
「泊まりがけの時や帰りが遅い時に利用したらどうかな」
「ニャン子しっこちゃん、また捨てられると思わないかしら。置いて行かれちゃうかもって」
「誰が捨てたのか、野良猫の親と離ればなれになったのか分からないけどさ、ストレスになるかもしれないな」
「傷が残っちゃうわ、心のなかに」
「でもさ。プロジェクトが終わってまた今までと同じ生活に戻れば、絆が増すかもしれないぞ」
「そう云う考え方もあるわね。でも、やっぱりわたし、いまが大事な時期だと思うの。体と心の傷が癒えかけた時なんだから」
「いまは離れて暮らしちゃいけない時期、のかな」
「そうよ」
「どうしても?」
「うん。どうしても」
「ニャ」
ニャンしっこが頬杖をついている話すかすみを見上げて鳴いた。
「おいで」
「可愛いなあ。ますます可愛くなった感じ」
「ねえ、五木田さん。やっぱりわたし断る。だっておかしいもん。食品を加工したこともないわたしがプロジェクトに参加するなんて。しかも懐かし屋フーズの要望でしょ? 新選フーズがわたしの実績とか能力とかを認めて送り出すわけではないのよ」
「俺だって同じさ。開発とは無縁の人間が大事なお客さんの商品開発にたずさわるなんて、恐れ多すぎだよ。本来長年開発でがんばってきた人間が責任をもって行くべきなんだ」
「断りましょうよ、五木田さん。失礼だからって言えば良いの」
「そうだな・・・失礼だよな、俺たちが参加したりしたら」
「にゃん、にゃお、んにゃ。んみゃーお」
「どうした、ニャン子しっこ」
「おなか空いたの?」
「みゃうよ、にゃおん」
ニャン子しっこは、
( 違うよ。ぼくは大丈夫だよ )
そう伝えたかった。
「眠たいのかもしんないな」
「にゃう、みゃうってば」
( 違う、違うってば )
「もう十時ね。寝ましょうか」
「残業の日は、時間が経つのが早く感じるね」
「ゆっくり休みましょ。ねっ、ニャン子しっこちゃん」
ニャン子しっこはケージのふわふわのベッドに入れられ、遅くまで寝られなかった。
現場で働く五木田とかすみは、退社時刻になるのを待って最上階三階にある専務木田を訪ねた。だが専務室の明かりは消えており、普段いる筈の専務木田は不在だった。
「珍しいな」
「事務所で訊いてみましょうよ」
ふたりは一階に降り事務所を訪ねた。
「専務木田、いや、木田専務はお出かけでしょうか」
「ああ、お疲れさま五木田くん。専務は病院に行くと言って午後から早退だよ」
「病院ですか」
「ほら、この間の定期検診で引っかかってさ、今日が再検査なんだって。日帰り検査ってやつ」
健康体とは思えなかったが、長年四合瓶を毎日空け、そのうえタバコを三箱も吸い続ければ検査に異常が見られて当然かもしれない。専務木田がいなければ、懐かし屋フーズとの共同開発プロジェクトに参加する話は進まないのは明からだ。五木田とかすみはそのまま更衣室へ向かい、待ち合わせて帰ることにした。
「新聞の上で寝てるかしら、ニャン子しっこちゃん」
「この間作ったキャットタワーに登って遊んでるかもね」
ふたりはマンションのエレベータに入ると、そんな会話を交わしながら行先表示を見つめていた。
七階に到着しドアが開くと左に曲がって並んで歩く。右に折れて突き当たりまで進めば五木田の部屋だ。と、視線の先に中年の女性が立っているのが目に入った。
( 誰だろう )
五木田が思ったのと同時に、かすみが声を上げた。
「お母さん!」
( えっ、お母さん? )
「来るなら連絡入れてよ」
かすみは駆け寄りながら言った。
「ほら良いお天気だから、つい足が向いちゃったのよ。それでこちらが・・・」
かすみの母は覗き込むように五木田を見て、いちばん気になっていることを口にした。
「五木田勝治さん。わたしの会社の上司よ」
「五木田です。かすみさんには公私ともにお世話になっていて」
「とにかく入りましょっ。ねっ」
五木田に続いてかすみ、かすみ母と順々に部屋へあがった。ニャン子しっこはいつものように五木田の足に体をすりつける。
「ただいま、ニャン子しっこ。良い子にしてたか」
「にゃ」
「お母さん。お父さんには話して来たの?」
「話してないわよ。つい足が向いただけなんもの」
かすみ母は、五木田の方にちらちらと視線を送りながら言った。
ひとしきり五木田にまとわりついたニャン子しっこは、次にかすみの足にからみつく。いつもと変わらない光景だ。
「この猫が、」
「ニャン子しっこちゃんよ。可愛いでしょ。抱いてあげて」
「お母さんが猫が苦手だってこと、知ってるでしょ」
「抱いたら可愛さが分かるから」
「いいわよ。それより、ちゃんと紹介してくれないと」
紺色のワンピースを着たかすみ母がそう言うと、かすみはソファーに座るよう促し、手早くお茶の用意を始めた。五木田はどこでどうしていれば良いのか分からず、日中は使わないケージの中にニャン子しっこを入れ、意を決してかすみ母の正面に座った。
「改めまして、五木田勝治です。遠いところをわざわざお越しくださって有難うございます」
お茶を運んで来たかすみは、五木田から少し離れて腰を降ろす。
「こちらがわたしの母で、内田ますみ。一文字違いなの」
五木田はきまり悪く手短かに自己紹介した。
「本来なら、もっと早くお父様とお母様にご挨拶に伺わなければならないところを、誠に申し訳もございません」
「そうね。順序としてはそれが先よね」
「お母さん。わたしたちは不規則な勤務でなかなか時間が合わせられないの。仕方ないじゃない」
「電話なり手紙なりで知らせられませんでしたか? 直接」
「お母様のおっしゃる通りです。申し訳もございません」
「いいわ、もう謝らなくて。それでこれからの事、あなたたちはどう考えてるの。それが分からないからお母さんもお父さんも心配してるの。きっと五木田さんのご両親だって心配なさっているに違いないわ」
五木田は答えられずにいた。
「お母さん。五木田さんのご両親は、鬼籍に入られたの。交通事故で」
「お亡くなりになったんですか。それは、失礼を申し上げました」
ますみは深々と頭をさげた。
「僕は一人っ子ですので、身寄はないんです」
「そう、でしたか」
「わたしたち、お母さんが思っている様な関係じゃないのよ」
「どう言うこと?」
「恋人とかじゃないの。だから男女の関係なんかじゃないから」
かすみは毅然として言うと、母ますみはかすみの体を下から上へ舐めるように見た。
「ただ共同生活している、そう云うこと?」
「そうよ。ねっ五木田さん」
「お母様がご心配なさる気持ちはよく分かっているつもりです。ですがかすみさんの言う通りです。なぜこの様な生活に至ったのかと言えば、ニャン子しっこのことがひとつ、そしてかすみさんが賃貸アパートを退去しなければならなくなった事が理由なんです」
かすみは、怪我をし弱っていたニャン子しっこを保護して病院へ行き飼い始めたその経緯と、アパートのオーナーとその弟の管理会社、それにオーナーのひもが絡んだ敷金トラブルなどを話した。
「そんな事情があったの」
「一円足りとも敷金を返さないって言うのよ、オーナーの弟の管理会社」
「それは酷いわね。悪徳不動産会社じゃない」
「そうなの。敷金の範囲内で抑えてやったんだとか見え透いた嘘ならべてさ、ハウスクリーニングと畳みの表替えだけでそんなに掛かるわけないのよ。雨漏りだって直そうとしないし。ホントせこいのよアイツら」
かすみはオーナーと弟とひもの顔を思い浮かべ、怒りが込み上げて来た。
「なあ、かすみ。そうやってでしか生きられない人間のことなんか忘れて、正直に生きようとしている者に心を寄せようよ。なっ」
五木田は母ますみがいる事も気に留めずに、素直な気持ちを伝えた。
「そうね・・・わたしの周りには、素直に生きようとしている人の方が、ずっと多いんだものね」
かすみは五木田の目を見てそう答えた。職場の仲間やニャン子しっこ、チワワのアケミとその母、広い公園の中で生きていた草花や木々・・・いろんな者たちの姿が浮かんだ。
「でもね、蒸し返す様で悪いけど、いくら男女の関係がないからと言っても礼儀としてひと言、伝えなければいけない事よ」
母ますみは、悪いと言いながらも話を蒸し返した。
「申し訳もございません」
「謝らなくて良いのよ。さっき言ったわよね」
「お母さんが蒸し返すから謝るしかないんじゃない」
「ところで」
母ますみはワンピースの襟を直して座り直した。
「あなた方が恋人関係にないことは信じましょう。でもそれはそれで心配なのよ」
「どうしてよ。良いじゃない」
「結婚の約束もしていない者同士が一緒に住んでいたら、お互いの将来のためによくありませんよ。だってそうでしょ? お互いそれぞれ好きな人が出来た時どうするの。相手の方は変だと思うわよ。場合によったら、別れ話にも発展し兼ねないことよ」
「確かに、お母さんのおっしゃる通りかもしれません。僕はまだしもかすみさんはまだ若いですから、将来のために良いことではないのかもしれない」
「ちょっと五木田さん! 何を言い出すのよ。その事はふたりでちゃんと話し合って決めたじゃない。わたしは何が有っても後悔なんかしません。ニャン子しっこと居られることが、わたしの幸せなの!」
かすみは憤然として、五木田に言った。
「どうするの、これから」
誰も口を開かず、沈黙がやって来る。お茶の湯気は消えすっかり冷めてしまった。
( わたしは五木田さんのことを好きだった事は間違いない )
( 俺がかすみちゃんの事を好きだったのは確かだ。初めて一緒に手をつないで歩いた時の胸の高鳴りは、二度目の時も同じ様に高鳴っていたじゃないか )
「僕は、かすみさんが好きです。今は恋人の様な関係ではありませんけど、女性として好きであることは確かです」
「まあ」
「えっ」
「んにゃっ」
「ニャン子しっこの心と体の傷はだいぶ癒えてきました。元気になって、もう大丈夫、そう思える様になったら、僕はかすみさんとお付き合いしたい。そう思っています。もちろんかすみさんの将来を負ってという意味です」
「五木田さん」
「本当に責任をもって、かすみとお付き合いしてくださいますか」
「いい加減な気持ちはありません」
「男性が女の責任を負うという事は、重いことなのよ。女の一生を背負うことなのよ」
「分かっています。お付き合いすると云うことは、結婚も視野に入れることだと、僕は考えています」
「それでかすみ、あんたはどうなの」
「わたしは・・・」
( わたしは五木田さんの事が好きなの? 男性として意識出来る? 唇を合わせ体をゆるす事が出来る? )
かすみにとって今の五木田は兄としか思えない。だが五木田の話す通り、ニャン子しっこが元気になって何の心配もなくなれば、また以前のように五木田を男性として意識出来るのではないか。かすみは迷っていた。
「わたしも五木田さんが好き。今はまだニャン子しっこの事で頭がいっぱいだけど、異性として五木田さんが好きなの」
( 言ってしまった。少しだけ自分の本心とは違う気がするけど、そう五木田さんの言う通り、ニャン子しっこが何の心配もなくすくすく育って元気になれば、きっとわたしは五木田さんの胸に飛び込んでいけるはず )
「みゃあ」
「ひゃっ」
「こらニャン子しっこ、お母さんを驚かせちゃいけないよ」
「いいのよ、五木田さん。ほらお母さん抱いてあげて。わたしたちの子どもよ」
「子どもって」
母ますみは恐る恐るニャン子しっこの背中に手を伸ばす。張りのある体毛が心地よくあたたかく感じた。
「のど元をやさしく撫でてあげて」
かすみの言う通りに、手を当てる。
「ゴロゴロ、ゴロ」
「喜んでる」
「嬉しいな、ニャン子しっこ」
「猫も案外、可愛いものね」
「んみゃあお」
○ 悲しみからの再出発
「お母さんのおかげだね」
「そうかな。為るようになっただけじゃない」
「いやあ、きっかけを与えてくれたのは間違いなくお母さんだよ」
互いの関係に悩んでいたふたりだったが、母ますみのおかで心の靄が晴れたのは確かだ。それだけではない。一度は断るつもりでいた『懐かし屋フース共同開発プロジェクト』に関しても、五木田は俄然意欲を燃やすようになったのだった。
「かすみ、本当に良いんだね」
「わたしは今まで通り縁の下の力持ち、下支えの様な仕事をしていきたいの。勝治さん、頑張ってね。ニャン子しっことわたしと、会社のために」
「それとお客さんのためにね」
五木田とかすみは昨日と同じように、最上階三階の専務木田の部屋に向かった。昨日と違うのは、五木田がプロジェクトへの参加を伝えることだった。
「あれえ? 今日も電気消えてるわよ」
「おかしいな。日帰り検査って言ってたのに」
ふたりは昨日と同じように一階に降りて事務所を訪れた。
「お疲れさまです。専務木田、いや木田専務は」
「やあ五木田くんに内田くん。入院だってさ、専務。肝臓をやられたらしい。それに血液もドロドロとかで」
「大丈夫なんでしょうか」
「我々も連絡を待ってるところなんだよ」
「俺、病院行ってみますよ」
五木田がそう言うとかすみも深くうなずいた。
「じゃあ悪いんだけど、どのくらい入院するのか聞いてきてくれないかな。新年度でいろいろ取込んでて、行く暇がなくてさ。ごめんね」
専務木田の入院する病院は、横浜市にある有名なキリスト教系の病院だった。ふたりは一度帰宅したあと、電車で病院に向かうことにした。
「ニャン子しっこちゃん」
いつものように先に部屋に入ったかすみは、新聞の入ったリビングケースに向かって声をかける。
「あれ?」
「そっちだよ、かすみ」
「わあ」
ニャン子しっこは、いちだん高い窓辺で外を見ていた。
「高いところに登れるようになったのね」
「足が悪くてもあそこまで登れるんだ、もう心配ないな」
「みゃ~お」
「これからお出かけなんだよ」
「会社の人のお見舞いよ」
「みゃうも」
「お前も行きたいのか」
「にゃ」
「ニャン子しっこちゃんは無理ね。なるべく早く戻るから、お留守番、お願いね」
五木田は飲み水を変えると猫用のペットフードの入った大きめのタッパーを開ける。かすみが着替えをすませ、トイレの砂を変え始める。ニャン子しっこはそのふたりの様子を、同じ場所から見ていた。
東京郊外をかすめる様にして走る夕刻のJR線は、電車が遅れ、混み合っていた。構内アナウンスは、五つ先の駅構内での人身事故を繰り返し伝えていた。
「遅くなるわね」
「でも電車は動き始めたんだからさ、のんびり行こうよ」
通常であれば病院の最寄り駅までは二十分程度で到着するのだが、急行の待ち時間などもあり四十分近く掛かった。駅を降りたふたりは病院の送迎車に乗る。電車遅延の影響からか、思いのほか道は混んでいた。
病院の正面玄関近くに送迎車がとまると、ふたりは周囲を見渡す。巨大なビルを思わせる白い建物は堂々としていて、日本有数の病院である事を物語り、誇っているかのようだ。
ふたりは正面玄関から地階へ降りて花屋に向かった。かすみ草とフリージアとカーネーションの可愛らしい花をかすみが選んでから、専務木田がいる入院病棟に向かう。
「かすみって、かすみ草からとった名前だったのか」
「今頃気づいたの? 信じられない」
かすみは顔の横に花束を並べて、おどけてみせた。
入院病棟の受付で、事務係長に教えられた通りの病棟名と病室を記載し、エレベータで五階まで上がる。
「昨日の今日だからね。いつもと変わりないだろ」
エレベータを降りると、不安を拭い去るかのように五木田はかすみに声を掛けた。
ふたりは病室の看板を見上げながら、「 五〇一、五〇二 」と口に出しながら進むと、五〇三の隣りの専務木田が入院する五〇五室が目に入った。
( あそこだね )
五木田は振り返ってかすみに目配せした。
病室の入口の、『木田勇蔵』の名札を見てふたりはうなずいた。
———こんこん。
白く厚いドアを軽くノックをし、五木田が先に立って病室に入る。
「こんにちは」
個室に入院している姿しか想像できなかったふたりだが、意外にも専務木田は四人部屋に入院していた。
四人の視線がふたりに注がれる。少しの間を置いて窓ぎわのベッドの手があがった。
「やあ」
「わざわざ、来てくれたのかい」
専務木田からは、いつもの重点音の声が聞こえなかった。
「みんな心配していて、僕らが代表して来ました」
木田は笑みを浮かべただけだった。
「猫。放っておいて、大丈夫なのかい」
やさしい声だ。
「一度帰って、ごはんや水を用意しましたから」
「もうすっかり元気になったんです」
「そうか、元気なのか。その、ニャン、」
「ニャン子しっこです」
「ニャン子しっこは」
「はい。足が悪いのに今日は高い窓辺で過ごしていた様で、もう大丈夫かと」
「それは良かったね。大事に、してやるんだよ」
弱々しくやさしい言葉に、五木田の目頭が熱くなる。
「検査結果が思わしくないと伺ったもので」
「肝臓だそうだ」
「ではしばらく禁酒すれば、」
「癌だそうだ」
ふたりは咄嗟に言葉が浮かばなかった。
「一昨日までは、普通だったんだけどね。癌だと聞いたら、突然悪くなった、気がするよ。聞かなきゃ、元気でいられたのに。失敗したな」
「専務」
かすみの頰に大粒の涙が流れる。
「君が泣くことは、ないよ。俺の不摂生の結果、だからね。自業自得という、やつかな」
「でも手術をすれば」
「出来ないそうだ」
「良い薬も開発されたと聞きましたが」
「厚労省が認可しなければ、どうにもならんよ」
「抗がん剤とか、放射線とか」
木田はゆっくりと首を横にふった。
―――もう言わなくていいよ。
木田はそう言っていた。
「俺のことなんかより、懐かし屋フーズの、女から話があっただろ」
五木田は腕で目を拭ってから答える。
「はい。開発プロジェクトの参加の件で、お話を、頂戴、しました」
「君たちならやれる。ウチの会社でやれるのは、君たちだけだ」
「専務!」
かすみは嗚咽してベッドにひれ伏してしまった。
「猫のことは、ニャン子しっこのことは、心配するな。話をしておいたから。ペットを持ち込める宿を探すと約束したよ、彼女」
「あ、ありがとうございます」
「がんばる事なんて、ないよ。普段のまま、臨めば、良い」
「はい」
「頼んだよ、ふたりとも。必ずうまくいくから。何も心配するんじゃ、ないよ」
「木田専務!」
専務木田は同じ言葉を繰り返した。五木田はたまらずに、木田の手をとった。すでに両親を亡くしている五木田は、木田の顔に父親の顔が浮かんでいた。
「それとお願いがある。会社の連中には、俺がこんな状態だってことは、黙っていてくれ」
「みんな、心配してるんです。専務のお部屋が暗くて寂しいって」
「ありがとな、かすみちゃん」
木田はベッドにひれ伏したままのかすみの髪を優しく撫でる。かすみの嘘が嬉しかったのだ。
「それともうひとつ。本当に申し訳ないんだが、もう病室には、来ないでくれないか」
「どうして、来ちゃいけないんですか」
「弱って、やせ細って、禿げていく姿なんて、見られたくないからね。元気な時の俺のことを、思いだしてくれた方が、嬉しいよ」
「でも」
五木田は何も言うなという思いで、かすみの肩に手をおいた。
「それと懐かし屋の、彼女のことだがね。あの子は気が強いが、まっすぐで、心あたたかいところもある子だ。どうか、支えてやって、くれないか」
「箕田英里さんは、もしかして」
「俺の、娘だよ。新選フーズに入りたい、と言っていたんだが、俺が認めなかった」
「そうだったんですか」
「どうしてご一緒に、」
「お互いのためにだよ」
木田は窓外に目をやり黙り込んだ。あのギラギラとした目には清らかな涙が浮かび、春の優しいひかりが輝いていていた。
○ お母さん
蓑田英里は新選フーズに頻繁に訪れるようになった。
「子どもがいないから身軽なの」
そう言って泊まりがけで来ることもあるが、父親である専務の事が心配で毎日病院に通っている事は、プロジェクトメンバーの誰もが知っていることだった。
懐かし屋フーズの新商品『 懐かし屋弁当シリーズ 』の共同開発プロジェクトは、当初の計画を大きく変更して進められることになった。開発プロジェクトの市場調査の他に、新店舗を拡大させる『 改革プロジェクト 』という両プロジェクトを同時進行させるという、蓑田英里の提案がきっかけであった。更に英里の提案した改革プロジェクトは、全国展開という社運をかけたプロジェクトにまで発展し、その開発・改革拠点としての条件を満たせるのが新選フーズと判断されたのだった。
開発・改革プロジェクトは静岡県全域をマーケティング拠点として選んだ。東西に広く、東日本と西日本の食文化が融合する静岡県は、新商品の開発と新店舗展開に於ける市場調査の意味を含めて、最も適していると云うのがその理由だ。つまり静岡県で他店に先駆けて新商品を販売し、その改善点を調査しつつ売れ行きが順調に推移すれば、他県での成功が見込めると判断出来るのである。商品開発と新店舗を全国に展開していくには静岡県が絶好の条件を有しており、新選フーズはプロジェクト成功の重責の一翼を担うことになったのである。
この事によって新選フーズの社内体制も大きく変貌を遂げ、開発プロジェクトの事務的な仕事は、新選フーズ内田かすみに託された。それに伴いかすみは、正式に新選フーズの事務課主任に任命されたのだが、この人事異動は決して懐かし屋フーズからの打診によるものではない。年々増加する外国人経営者に対応できる英語力の必要と、長年ひたむきな努力を続け会社に貢献してきた内田かすみを、会社が認めた判断であった。
一方盛りつけ班班長であった五木田勝治は、共同プロジェクトの開発にたずさわる一方で、専務木田が担っていた社内開発の仕事を引き継ぐことになった。今では新たに開設された開発課の係長として、懐かし屋フーズをはじめ顧客からの信頼を得、活躍している。
「かすみが英語ペラペラだってなんて意外だなあ。もしかして帰国子女とか」
「アメリカには何度か行ったことがあるだけ。殆どセスチャーで会話するしかなかったわ」
「そんなんで何とかなるものなか」
「何とかなったけど、仕事でコミュニケーションを取るには何とかならないかも」
「でもほら、この間ウチの会社に来た外国人。かすみの英語ほめてたぞ。発音がワンダフル、ネイティヴか? ってさ」
「発音くらいなものでしょ。わたしの英語力なんて中学生レベルよ」
「発音が難しいんじゃないか。俺が喋っても何度も聞き返されてさ、全然通じなかったもん。かすみが話し掛けたら、みんな理解してたもんな。凄いよ」
「偉そうに言うつもりはないんだけど、勝治さんの英語って・・・カタカナ語なのよね」
偉そうな言い方ではなかった。だが五木田はむっとした。
「カタカナ語? なんだそりゃ」
「だってさあ、例えばgirl。勝治さんの英語はgarlなのよね」
「分からないな」
「要するに、iを無視してるの。iという単語を省いて、ガールっていうカタカナ語にしちゃってるのよわざわざ。舌を丸めて、ハイgirl」
「でもさ、学校では発音しなくて良いって教わったぜ」
「それが間違いなんじゃないかな。発音しなくて良いのと省いて無視するのとは全然違うのよ。日本人には省いているとしか思えないアルファベットでも、英語圏の人は省いたりしない。意識はしてるの。それが国民性にも現れるてると思う」
「分かんないなあ」
「例えばウッドね。日本人にはウッドなのかもしれないけど、woodとwouldではスペルも意味もまったく違うし、発音だって全然違うじゃない? それなのに日本人はどっちもウッド、外国人が理解出来ないのは当然じゃない?」
「日本人は細かくて神経質と言われてるけどな」
「わたしに言わせれば、逆。細かいところにまで心を寄せられる、気配りの出来る人種なら理解できるはず。もし日本人がほんとうに繊細な配慮が出来るなら、英語の発音なんかで悩むことはないはずなのよ」
懐かし屋フーズの開発・改革プロジェクトが発端となった人事異動によって、五木田とかすみのふたりは、現場での早朝勤務から日勤の時間帯の勤務となった。
陽が昇ってから出勤し陽の高いうちに帰宅していた五木田とかすみの生活が変わったことは、ニャン子しっこの生活習慣にも少なからず影響を与えた。特に懐かし屋と新選フーズの合同会議の日には、陽がとっくに沈み、日付が変わることさえしばしばある。
「もう嫌っ」
「んにゃああ」
「どうしたんだよ、かすみ」
「分からない?」
「分からないよ、話してくれないと」
「分からないのね」
かすみは帰宅するなり重い体を折って床に体を横たえてしまった。黒髪が白い肌の顔を隠している。
「いったいどうしたって云うんだ。話してくれなきゃ分からないよ」
五木田はかすみの隣りに寄りそい、背中に手を置いて優しく話しかけた。
「慣れない仕事だから大変なのは分かる。だけど俺だって踏ん張ってるんだからさ」
「踏ん張る? 何それ」
「我慢して、頑張るってことだよ」
かすみは、さっと身を起こして五木田に向き合う。
「んにゃ」
「お互いにニッコリして、あ~んって食べさせ合うのが頑張ることなの? 我慢するこってこと? わたしには幸せいっぱいにしか見えなかったわ」
「何だそれ」
「英里さんに食べさせて貰って、嬉しそうだったじゃない。鼻の下伸ばして」
「英里さんは人妻だぞ。俺だって英里さんだって、特別な意識なんてある筈ないじゃないか」
「人妻の女性を英里さんなんて、名前で言う事自体おかしいのよ。――英里さん、は~い。勝治さんも食べて、あ~ん。馬っ鹿じゃないの、いい歳して」
「そんなこと言ってないし、あれは場を和ませるコミュニケーションとして、」
「わたしには分かるの。英里さんは五木田さんの事を、求めてるのよ」
「五木田さんってな、」
「五木田さんだつて、英里さんのこと意識してる。見てればわかる。デレデレだもん。あれって仕事? デートでしょ」
「くだらない事いうなよ。俺は英里さんなんか、意識しちゃいないよ」
「嘘。英里さんの方がわたしなんかより、背が高くてグラマーでお尻が小っちゃくておっぱいが大きくて形も良くて、色が白くて色気があるし、頭が良くて優しくて品があって女性として魅力的だし、人間としてもわたしなんかより英里さんの方がずっとずっと、」
ーーーパンッ!
「んにゃっ!」
「いい加減にしろよっ!」
五木田はかすみの頰を強く打つと、身動きが出来ないほどの力で抱きしめた。
「わたしなんか」
「何言ってんだよ。俺がかすみ以外の女の人を好きになると思うか? 俺はかすみがいてくれるだけで・・・あとニャン子しっこがいるだけで、幸せなんだよ。他の人に見向きもされなくたって、ふたりが傍に居て俺のことを見ていてくれれば、それだけで幸せなんだよ。それだけで満足なんだよ。それだけ、良いんだよ」
「勝っちゃん」
「みっ、みゃおぅ」
「かすみ」
「ごめんね、勝っちゃん。わたしどうかしてた」
「慣れない事ばかりだからね、かすみは。専務の言うように、頑張るのはやめなよ」
ふたりはカーペットの上に腰をおろしたまま抱き合っていた。ニャン子しっこは、ふたりの姿を見つめていた。
○ 最後の願い
「突然で恐縮ですが、今日はかすみちゃんと五木田さんは私に同行してください。大切な市場調査に行きます。朝礼後すぐに出発します。良いですね」
リーダーである蓑田英里は、共同開発プロジェクトチームの朝礼で固い表情でそう言った。
プロジェクトが進むなかで、英里はかすみを身近におく様になった。今やかすみは、懐かし屋と新選フーズ両社に所属する英里の秘書のような存在となっていた。
「車、俺が出しますよ」
「いいの。私の車で行くからふたりは後部座席に乗って」
「車で来たんですか。珍しいですね」
そんな会話を交わしながら、五木田とかすみは英里の後についていく。
「さあ、どうぞ」
「これ、英里さんの車ですか」
「そうよ。期待していた様な車じゃなくて申し訳ないけど、今日は我慢して」
キャリアである英里は、外国車か相当なグレードの真っ赤な高級車にでも乗っているのだろう。五木田はそう想像していた。だが英里が立ち止まったのは、箱形の軽自動車の前だった。宅配や郵便配達で使われている、軽バンと呼ばれいるものだ。
「庶民的。意外だなあ」
「小回りが利いて私にぴったり。わざわざ乗り難い大きい車を選ぶ気にはなれなかったの」
「しかも二桁ナンバーですね。今や三桁ばかりなのに」
「大切に乗っていらっしゃるんですね。英里さんのお人柄がよく分かります」
一面に畑が広がる農道を過ぎると、建設重機や戦車などをつくる巨大工場のブロック塀に沿って軽バンは滑走していく。工業団地入口を記す信号機は、これから取引先に向かおうとしている小型トラックや営業車で長蛇の列をつくっていた。
神奈川の片田舎の道に不案内なはずの英里が、機械加工業が軒を連ねる脇に道に入る。市内に住む人間にも、そうは知られていない道だ。
「道、詳しいんですね」
「次の信号を道なりに進めば、国道に出るわね」
英里は五木田の言葉に答えずに言った。
「ええ。相模川に架かる橋の手前に出ます」
「じゃあ」
英里はさらに左折した。どこか急いでいる様に思われたが、運転は慎重だ。
「静岡方面はなら橋のたもとに出た方が、」
「あなたたちの住んでいるマンションに行きます」
「ウチにですか」
「勝手を言って申し訳ありませんけど、子猫を連れて来てほしいの」
「ニャン子しっこを?」
「どうして」
英里はしっかりと前を見据え、急な登り坂をギヤを落として加速させる。
「ごめんなさい。個人的な事情を持ち出してはいけないのですが・・・これから父の入院している病院へ向かいます。父が子猫に会いたがってるの」
「ニャン子しっこに、ですか」
「もう、長くないの」
「専務木、いや木田専務がですか」
「そんなあ」
「最期の我がままを聞いてあげたいの。ごめんなさい」
五木田とかすみは急いでマンションの部屋に入る。
「ニャン子しっこ」
返事がなかった。
「あっ」
「神妙してる」
「丁度よかった。しっこし終わったら出掛けるぞ」
「んみぁおう、みゃみゃ」
「そう、お出かけよ」
「お前にどうしても会いたいっていう人がいるんだ」
かすみがキャリーバッグを用意すると、ニャン子しっこは慌ててトイレから出て喜んで中に入った。
「お水とごはんを」
「用意した。あとはハーネスとリード、それに」
「ペットシートね」
ふたりは手分けして手早くお出かけグッズを用意する。
「先に行ってエレベータ止めておくから」
「お願い」
五木田がキャリーバッグを抱えて勢いよくドアを開けて走り出すと、かすみも靴のかかとを踏んだまま鍵を閉めて後を追った。
「連れて来ました」
「ごめんなさい、急がせてしまって」
「いいえ良いんです」
「もう謝らないでください」
裏道を使って国道に出ると軽バンは横浜方面に走った。唸るようなエンジンの音に、ニャン子しっこは落ち着きなく外を覗いていたが、かすみが話掛けていると落ち着きを取り戻して、いつもの陽だまりに居る時と変わらない穏やかな表情を見せた。だがかすみは、話していなければ不安に圧し潰されそうで、しきりにニャン子しっこに話しかけていた。
無料の高速道路は意外にも好いていた。混み合う市街の道を避けて走ったせいもあって、マンションから四十分ほどで専務の入院する病院に着いた。
春爛漫の陽気のなか、様々に色づいた五月つつじが、なだらかな坂から病院へ患者や見舞客を誘っている。
「呼んで来ますから、あそこのベンチで待っていてください」
英里はそう言うと駆け足で入院病棟へ向かった。
「もう、長くないのか。専務は」
「でも病室から出られるんだもの。きっと、大丈夫」
かすみは自分を納得させるように言った。
「ニャン子しっこ、猫が大好きなおじさんが来てくれるんだよ」
「・・・・・・」
「君が怪我した話を聞いて、とても心配してくださった、心の優しい人よ」
かすみは言葉を詰まらせ、目頭を抑える。
「喋ると駄目だよ、俺」
「喋ってないと、ますます駄目みたい。わたし」
「みゃあ」
「ニャン子しっこの声も、どことなく寂し気に感じるな」
「君に会いたいんだって。君が勇気づけてあげるのよ」
「んみゃあお」
程なくして看護師に車椅子を押され、高々と手をあげる木田専務の姿が目に入った。英里は隣りで腰を曲げ、五木田とかすみの方を指差して何かを話しかけている。
「専務の娘なんだよな、英里さんは」
「お父さんなのね、専務は」
「なんだか、不思議な気分」
「会社は違うけど、ふたりとも同じ気持ちで仕事に打ち込んでる人ね」
「受け継がれたんだよ。専務のまっすぐなところが」
英里と話をする専務は、しきりにうなずいている。マスクをしているが、ふたりには笑っている様にも見える。
「やあ、悪かったね。急に、呼び出したり、して」
専務木田は自らマスクを顎までずらし、笑いながら言った。
「公私を混同する、なんてもっての外だが、勘弁してくれ、たまえ」
「嬉しいです。わたしたち。ねっ」
「うん。声を掛けてくださって、本当に嬉しいですよ。専務」
「もう来るなと、言っておきながら、悪かった。こんなに情けない姿は、見せたくなかったんだが」
誰の目から見ても専務木田の頬はやせ細り、腕は女性のそれより明らかに細かった。
「少しスリムになったかなあ、くらいににしか見えません」
「病院食のせいかもしれませんね」
専務はにっこりと笑った。その笑顔は以前と何ら変わらない。
「見せて、くれないか」
「ああ、すみません」
五木田がベンチの上のキャリーバッグを開けると、かすみがハーネスを体につけて抱えた。
「ニャン子、しっこ。だね」
「覚えていてくれたんですね」
「もちろん、だよ」
「抱いてやってください、専務」
かすみが膝のうえにニャン子しっこを降ろすと、専務木田は大事なものを抱く様に両腕でつつむ。
「みゃあおう」
「可愛いで、ちゅね、ニャン子、しっこちゃんは」
「んもう、お父さんったら」
専務は力の入らない手で優しく背を撫ぜ、マスクを外して頬ずりをした。
「あんよは、どうでちゅか。痛く、ありませんか」
「みゃあ」
「そうでちゅ、か。それはよかった。お父さんと、お母さんに、ありがとうって、言うんだよ。お前のお父さんと、お母さんが助けて、くれたんだ、からね」
「お父さん」
英里は専務木田の車椅子に隠れて、泣き出してしまった。五木田とかすみは、涙を浮かべながら笑っている。
「ニャン子しっこ。嬉しいな」
「にゃん」
「そっか、嬉しい、のか。ありがとな、ニャン子、しっこちゃん」
「―――木田さん。そろそろ病室に戻りましょう」
若い女性看護師が、専務を覗き込むようにして言う。
「もう、少しだけ」
誰の目から見ても、専務は苦しそうだ。
痛々しい姿だった。辛そうだった。でもけなげだった。
専務はニャン子しっこの背中に左の頰をつけてじっとしている。その目からは涙が流れていた。でも幸せいっぱいの笑顔だった。
○ 別れと再会
専務木田勇蔵の葬儀は新選フーズの社葬にて執り行われた。専務の遺言によって、葬儀は、懐かし屋フーズと新選フーズの共同開発である懐かし屋弁当シリーズの試食会を兼ね、香典返しの中にはアンケート用紙が入れられ配られた。
愛猫クラブ会長をつとめた専務は、業界ではかなりの有名人で、斎場には最期に我が猫をひと目見て貰いたいと願う愛猫家たちで、溢れかえった。あちらこちらで猫たちの姿が見られる葬儀は、専務の遺志通り、笑顔の絶えない葬儀となった。
もちろん葬儀にはニャン子しっこも参列した。専務が最期に会いたいと願い、最期にその胸に抱いた猫がニャン子しっこだったのだと、挨拶のなかで英里が涙ながらに話すと、参列者は、足を引いてぎこちなく歩くニャン子しっこと、やさしい笑顔で抱く木田の姿が重なって、一様に涙を流した。
懐かし屋フーズの新店舗第一号店、懐かし屋・清水店は、来月静岡県にオープンする事が決定している。海と山の自然が美しい、サッカーの町として有名な静岡市内の町だ。この町を一号店に推したのは専務木田だった。地元の食材だけでなく、関東関西、山梨・長野県などから幅広く新選な地の物を仕入れられ、様々な種類の弁当を販売が出来ること。そして何より清水町の人々の人柄が好きだというのが理由だった。
蓑田英里は、懐かし屋と新選フーズで組織された新商品開発プロジェクトチームが静岡県に組織されてからは、千葉県の本社に戻り、営業戦略室のリーダーに昇格して活躍の場を広げている。
五木田は開発課長に昇格した一方で、盛りつけ班班長に復帰し両者を兼務し活躍している。
決して英語は得意ではないと話していたかすみは、外国人経営者との交渉でその英語力を伸ばし、今では営業兼事務係長として力を発揮している。
「今日はノー残業デーだから、たまには外で美味いもんでも食べようか」
自転車置き場で待ち合わせた五木田は、かすみに話しかける。
「ニャン子しっこの定期検診、今日よ」
「いけねえ、忘れてた」
「だめね。大切な子どもの受診日を忘れるなんて」
ふたりがマンションに戻ると、ニャン子しっこはリビングケースの新聞のうえで寝ていた。まだ日が高く、心地よい日射しが窓から差し込んでいる。
「今日は病院に行く日でちゅよ。さあ起きてください」
「んもう。勝治さんったら、専務に影響されちゃって」
「良いじゃないか。なっ」
「猫だから良いけど、子どもにはそう云う言い方しないでほしいな」
「猫も人間の子も一緒だろ。そうでちゅよね、ニャン子しっこ」
「にゃあ」
「ほら、同じだってさ」
ふたりはニャン子しっこをキャリーバッグに入れて病院へ向かった。
ニャン子しっこは、足の障害は元に戻らないものの至って健康だった。太り過ぎでも痩せすぎでもなく、何を指摘されることもなかった。
「お買い物に寄って良い?」
「駅前のスーパーか。良いよ、俺外で待ってるから。でも最近かすみ、食べ過ぎじゃないのか。太ったとは言わないけど、膨よかになった感じがするよ」
「良いのよ。栄養いっぱい摂らないといけないんだから」
「何日かして今度はダイエット食、なんて言い出さないでくれよな」
「そんなこと言わないわよ。何ヶ月か後かには、そうするかもしれないけど」
他愛のない会話を交わしながら、ふたりは駅に向かう坂道をくだる。
「今日はそっちの道を歩きましょうよ」
普段通る駅へ向かう道から一本西側の道へとかすみが進むと、五木田はその後に続いた。右手に見える中学校からは、部活動の賑わう声が聞こえてくる。
「勝治さん。明日の午後お休みをとって病院に行ってくるわ」
「何だよ急に。どこか悪いのか」
五木田が横に並び心配そうに声をかけると、かすみは頭を横に振った。
「定期検診は問題なかったよな」
「問題なかったわ」
「じゃあ、誰かのお見舞いか?」
「違うわよ」
野球にユニホームを着た部員たちに道を譲ると、かすみは立ち止まって五木田を見つめ、その手を握った。
「赤ちゃん。出来たみたいなの」
「えっ?」
「わたしたちの赤ちゃん」
「ほ、本当かよ」
「妊娠検査薬で調べただけだけど、間違いなさそう」
「や、やった、やったなっ! おいニャン子しっこ、赤ん坊が生まれるんだぞ。お前の弟か妹だぞ。お前はお兄ちゃんになるんだぞ!」
「んみゃあおう。にゃう」
「そうか嬉しいか」
「勝治さん。産んでいい?」
「当たり前じゃないか。産んでくれよ。一緒に育てようよ、俺たちふたりの子どもをさ」
「でもわたしたちまだ、結婚してないのよ」
「指輪用意しないとな、婚約指輪。それにお父さんとお母さんにも挨拶に行かなきゃいけないし。忙しくなるな。幸せになるのって、忙しいんだな」
「もう、慌てないでよ。ゆっくり考えれば良いんだから」
「体大事にしろよ。大切な命が宿ってるんだからさ。尊い命がかすみの中で生きてるんだからさ」
「良かった。勝治さんが喜んでくれて。産むななんて言われたらどうしようかと思ってたの」
「言うはず、ないだろ」
「わたし、タバコやめる」
「それが良い」
「あなたにもお願いがあるの」
「あなた?」
「生まれてくる子どもに、変な名前つけないでね」
肩にキャリーバッグを抱え、両腕に買い物袋をさげた五木田の足取りは軽かった。坂道を苦もなくのぼっていく。かすみは腕を後ろで組んで、笑顔でぴったりと隣りに寄り添う。
中学校の校庭からは強い照明のあかりが歩道まで届き、金属バットにボールが当たる音とよく通る少年の声が聞こえる。急な坂道の住宅街を横切って駅前通りと合流すると、左手にコンビニエンスストアの明かりが見えて来た。
「俺も、やめるよ。タバコ」
「ホントに?」
「うん。コンビニで最後の一本吸ったら、やめる」
「何それ。せっかく決めたんだから、もう吸わない方が良いんじゃない?」
「かすみとニャン子しっこと会った思い出の場所で、父親になる決意を確かめるための最後の一本にしたいんだ。駄目か?」
「そうね、あそこはわたしたち三人の特別な場所だもんね。子どもが大きくなったら、お父さんとお母さんはあそこから始まって、あそこでニャン子しっこと出会って、あそこで君のために生きていくことを決めたのよって、話して聞かせるのも悪くないかもね」
夜のコンビニは買い物客で賑わっていた。仕事帰りの作業着姿の男やスートを着たサラリーマン。若いOLらしき女性たちが、レジに並んでいる。
「最後の一本だ」
「決意の一本ね」
「あっ」
「猫、いるわね。こんなに真っ暗なのに」
「いるな」
「んにゃああ。にゃお、にゃああ!」
「どうした、ニャン子しっこ」
「気づいたのかな、ニャン子しっこ。あの猫を見て鳴いてるみたい」
「それにしてもこんなに大騒ぎするなんて、珍しいな」
ニャン子しっこは、向かいのビルの三階を見上げて鳴き止まない。
「!」
「こっち見た」
「ほんとね。なんかあの子も様子がおかしいみたい」
「出窓を行ったり来たり、降りたりのぼったりしてる」
「もしかして、勝治さん」
「何?」
「ニャン子しっこちゃんの、お母さんなんじゃない?」
「ええっ? まさか」
「きっとそうよ。だっておかしいもん、ふたりとも」
ふたりは出窓の猫とニャン子しっこを交互に見る。
「色、そっくりよ。お顔も似てる気がするし」
「ニャン子しっこが居た、コンビニの前だし」
「行ってみましょうよ」
ふたりは目を合わせてうなずき、横断歩道を渡った。
「ごめんください、夜分失礼致します」
「はあい」
緊張してインターホーンを鳴らすと、明るい声が返ってきた。ふたりは少し安心して顔を見合わす。
家主が扉を開けると、窓辺の猫が勢いよく飛び出して来た。
「だめよ。ちいちゃん」
家主は素早く猫を抱え上げる。
「あのう・・・」
「何か、ご用ですか」
「実はウチの猫が、窓辺にいるその猫ちゃんを見て騒ぎ出したものですから」
五木田がキャリーバッグを掲げると、家主は目を細めて覗き込んだ。
「可愛い猫ちゃんね。まだ若いのね」
「はい」
五木田はニャン子しっこを飼い始めた経緯を、順序よく説明した。
「ちいちゃんの子どもかもしれません。実は、飼いたいと言ってくださる方にお譲りするその日に、いなくなっちゃたんです。まだ小さいからと安心して立ち話をしていたら姿が見えなくなってしまって・・・みんなで一生懸命探したんですが、まさかお向かいのコンビニにいたなんて」
「誰かが連れて行ったのかもしれませんね」
「この子は兄妹の中でいちばん活発だったの。だから、興味本位で道を渡ったのかもしれません。私がしっかり見ていれば、そんなに辛い思いをさせないで済んだのに。本当に申し訳ありません」
ちいちゃんの飼い主は、深々と頭をさげた。
「いいえ、仕方のないことってありますから」
「今はこの通り、元気なんですから、気になさらないでください」
「でもあなたたちのおかげで、こんなに元気な姿を見られて安心しました。本当にありがとうございました」
「にゃあお」
「んみゃあ」
「ご対面させてあげましょうか。何だかいじらしくて」
「良いんですか」
「もちろん。さあどうぞこちらに」
三人は部屋に上がると、出窓の下にキャリーバッグを置いた。
「ここがちいちゃんのお気に入りの場所なの」
「向かいのコンビニから、時々わたしたちも見ていたんです」
かすみがバッグを開けて、ニャン子しっこをそっと抱える。
「あら、この子」
「何か」
「木田さんのお葬式の時にいた、ニャン子、」
「ニャン子しっこです」
「木田専務の葬儀に行かれたんですか」
「ええ。木田さんは私たちの憧れだもの。本当に猫を愛している素晴らしい方でしたわ。ニャン子しっこちゃん、あなたは幸せね」
「木田専務は、怪我をしたこの子のことをずっと気に掛けてくださって」
「そう云う人だから、あの方は人からも猫からも好かれるのよ。全国の捨てられた猫を引き取る施設をまわっては、寄付したり引き取り手を探したり。誰からも尊敬される人でした」
「木田専務が」
「そうよ。だからあんなに沢山の人がお葬式に参列したの。皆さん本当に残念がってるけど、これからは木田さんがして来たことをみんなで受け継ぎましょうって、愛猫クラブのネットワークを立ち上げることになったのよ」
五木田とかすみは、木田専務がそれほどまでに猫を愛し、猫を救おうとしていたとは思ってもみなかった。
「無責任な言い方になりますけど、ニャン子しっこちゃんを、飼い続けていただけないでしょうか」
「もちろんです」
五木田とかすみは顔を見合わせ同時に言った。
「ちいちゃんは、ニャン子しっこちゃんを探していたのかもしれないわね。その窓の上から」
かすみがニャン子しっこを床に降ろすと、ふたりの猫は互いの鼻を寄せ合った。緊張しているその姿に三人の目が細くなる。
「お母さんよ、ニャン子しっこ」
「あなたの子どもよ、ちいちゃん」
ふたりは体を寄せて、互いの体毛の感触とにおいを確かめ合っている。
「みゃああ」
「にゃお」
「分かり合えたようね」
「喜んでる」
「嬉しいわねえ、ふたりとも」
しばらく三人は、母子の時間を見守った。幸せな時間だった。
「これからも、時々遊びに来てくださいね」
「良いんですか」
「もちろんですよ」
「良かったわね。ニャン子しっこ、ちいちゃん」
「にゃああお」
ふたりは声を合わせて喜びを露わにした。ちいちゃんはニャン子しっこの頰に顔を寄せ、鼻先をなめている。
「お母さん、ごめんね」
「良いのよ、ニャン子しっこ。あなたが元気でいてくれて、お母さんは嬉しいわ」
「ぼくもお母さんに会えて、ほんとうに嬉しい」
「やさしいお父さんとお母さんに出会えて良かったわね、ニャン子しっこ」
「うん。ぼく、しあわせだよ」
「木田専務も喜んでるわね、きっと」
「専務が幸せを運んでくれたんだ」
三人は微笑んでうなずいた。
ニャン子しっこはますます甘えてちいちゃんにすり寄る。ちいちゃんはニャン子しっこのさせたい様にさせている。かすみはちいちゃんに向かいそっと顔を近づけるとやさしいお母さんの匂いがした。親子、母子、血のつながり、少し堅い表現だけれども、いのちの継承という言葉が浮かんだ。ふたりとも幸せでいっぱいだ。
かすみは五木田を見あげおなかに手をあてた、ちいちゃんがそうしていたように。と、その手のうえに五木田がそっと手を重ねた。幸せな時のなかで、二人はまだ見ぬいのちをあたためあった。
了
陽だまりのニャン子しっこ