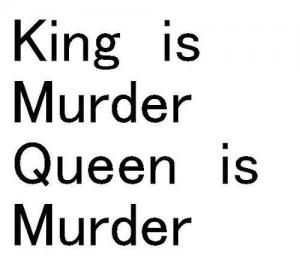ほうき星町の人々――「童貞事実と童貞意識」
ある狂人の視点で綴った、どうしようもない噺です。
「童貞は死ねっ!」
と書店「懐中水時計」店主・レルエリィ・ヒルトハミットは言った。どーんと。
電撃大賞のキャッチコピーに「おもしろいこと、あなたから」とある。まあ確かに面白いことは面白い発言ではあるが、嫌な意味でのドキドキとハラハラ(要するに読者の反感)しか伝達出来そうになくて、作者、こっちも嫌な意味でドキドキしている。
大体にしてラノベ新人賞の募集要項には、「十代の読者を対象にした広義のエンターテイメント」と明記されているが、さすがにこの出オチ感溢れまくりの発言から話を進めるのは、果たしていかがなものか。一次審査で落ちるんじゃあるまいか。
いつものフレアの家に上がりこんで(要するに仕事サボって)、大好物のサイダーを飲みながら、この家の家主及び居候どもに語りかけるレルエリィである。まったくいい身分である。
「いきなり死ねとか言われても何さ、所詮非モテの戯言恨み言としか思えんもんでしょうが」
居候一号、ユーイルトット家第十四代公爵、セリゼ・ユーイルトットが冷静に突っ込む。貴族なのに居候とはこれ如何。
ここから才能のある作家ならば、いくらでも話を発展させていくところだろうが、生憎さまである、筆者にはそこまでの力量はないので、ただ単に「終の棲家を探していたところをフレアに拾われた」と記述するに留める。筆者よ、お前に自尊心とか文芸的野心みたいなものはないのか(こっちもツッコミ)。
セリゼは続ける。
「第一あーた、もう童貞とか非モテとかいうレベルの位置にいないでしょが。それを何さ、今更童貞ウザい論議をはじめたところで、どうしようもなかろうよ。まあ、話は聞こう。何と言っても貴族は襟度が広くなくてはならん。人の上に立つ人間とはそういうものだ」
さりげなく上から目線に移行しているところがセリゼクオリティである。生まれながらの貴族様は違う。というか、ただ単にお前性格悪いだけちゃうんか、というご指摘は実に正しい。
正確には性格が悪いわけでは(ややこしいな!)ないのだが、ナチュラルにしてると偉ぶるというか、もともと持った力がなまじっか強力だからこのような傲岸不遜気味な態度になるというか。あれ、フォローになってないぞ?
まあ、ともかく、こうやってお悩み相談を(それも出オチ爆発の)一応は聞いてあげているところあたりから、セリゼのある種の人の良さを垣間見てくれたら幸いである。
「うわー、すごい偉そう」
居候二号、キギフィ・シロップ(仮名)は相変わらずの超絶美少女ぶりを発揮しながら(つまり空間にいるだけで美少女力(ぢから)をあたりに粒子のごとく振りまいているということである。なんというカリスマ!)、シモの話についてくる。そして筆者と読者が抱いていた疑問を、この偉そうな貴族様に率直にぶっつけてくれる。ありがたい(と筆者が感謝してどーする)。
「貴族なら、そういったところをひけらかさないようにしなければなりませんよ、セリゼちゃん」
家主、大家、そして世紀の天才工学者、龍(ロン)・K・フレアがやんわりとたしなめる。出来た人だ。
「ねえ、月読さん」
「寝てます」
すっとぼけた返答をするのは、居候三号にして、この町の新参、にして、東洋系魔術を究めた仙人である剣崎月読(けんざき・つくよみ)。そうか、仙人ともなれば、寝ながらにして返答が出来るのか、と感心してはいけない。適当ぶっこいているだけなのだから。
そのあたりのことを重々承知しているものだから、家主、
「寝ている人は寝てますって返答しないんですよ」
「ぐう」
あからさまな嘘イビキでお茶を濁す月読だった。多分、レルエリィが持ち込んだ話に付き合っていても仕方がないという、全うな判断を下したのか。だとすれば妥当な判断だが、ただ単に眠たいだけという説も否定できない。
変な奴ら。
だがどうせ、このほうき星町に集ってくる連中は、皆どこかに後ろめたい過去や傷なり、あるいは世間では尊敬されつつも疎まれる(信じてほしい、世の中にはそのような事例がいくつもあるのだ)類の才能なり、を持ち合わせた人間どもの寄り集まりなので、この程度の変さで音をあげていてはついていけないぞ若人共(誰に言っているのだ?)。
さて、さりげなく話題がグダグダになってきたところで、再びレルエリィが大言壮語した。
「童貞は……うぜぇっ! 死ね!」
「今更言うのもなんだけど、本屋の主がそれを言うかね? スケベブックだって扱っているだろうに」
いたって冷静にセリゼが突っ込む。
「俺の店には、一般的なモノはないからな……芹の字、お前も知っているだろう? 『懐中水時計』の品ぞろえは」
「まあねー、ていうか芹の字言うな。春先の鍋物か」
書店・懐中水時計は、元貴族のレルエリィ・ヒルトハミットが、自分の趣味をそのまま仕事にしたような店である。
ある種のセレクトショップというか、扱う品は古書珍書マニアック書、世界各国で行われている古書オークションの代行も引き受けている。もちろん新刊もきちんと取り寄せている。基本的にも絶対的にもどんな類の本でも頼めばOKである。ネット通販全盛のこの時代において、個人書店がそれだけの流通を持っているのは、まったく恐ろしいことである。
例えるなら、ロシアの片田舎で電撃文庫や電撃文庫MAGAZINのバックナンバーを取り寄せるようなものなのだから(地理的に言って)、そういったことが平然と行えるだけの力量、まさに感服に余りある。
誰がロシアの片田舎で『撲殺天使ドクロちゃん』やラノベ雑誌を買うねん、という指摘はあろうかと思うが、しかし世界、何が売れるか分からない。筆者、ロシアで「日本漫画売り上げベスト5」を見たとき、四位に松林悟『ロリコンフェニックス』が付けている、と知ったとき、ロシアもいよいよはじまったな、と思った。思えば『ロリータ』の原作者ナボコフもロシアの生まれではないか。(超こじつけ&亡命文学に対する冒涜)
ところで、元貴族、レルエリィの風体は、まさに貴族然としたところが、「雰囲気」程度には、伺える。
やや伸ばした金髪は、よく手入れがされていて、顔の彫りも決してアクの強いものではない。陶芸家が上手く拵えた感すら与えれるほどの、なかなかの甘さを感じさせる美形である。
身なりだって悪くはない。どころか、相当に良い仕立てのものを着ている。白で統一した上っ張り……というか、薄手のローブのような長い上着の下には、落ち着いた緑系の色・柄のトップスとボトムスでさらりと着こなしている。
全体的に細身で、キラリと読書家の常として煌めく双眸は緑色に深く。発言の出落ち感すら除けば、レルエリィは、育ちの良さそうな、いっぱしの好青年に確かに見える。
だが。
「仮にも書店……それこそ、様々な客の二―ズに応えるのが商売でしょう」
セリゼは正論を言う。
「それを、まあ、少なくない数の男子諸君を敵に回す発言をしだした理由をとりあえず吐け」
筆者だって、読者が巻を投げ打たないように、この手の発言はたしなめておきたい。やっぱラノベ読者層って性経験が少ない人が多いのが当たり前なんだし(というかラノベを熱心に読む青少年が、エロースの玄人になっている世界というのもそれはそれで嫌だ)。
「俺は童貞が嫌いじゃないんだよ」
いきなりの前言撤回である。どこぞの政治家じゃないんだから。
「意味分かんねえ。死ねとか言っときながら」
セリゼが、ごくまっとうな論理批判をする。
「俺が嫌いなのは、童貞を『こじらせている』奴だ。ほら、よく居るだろう、いつまでもじくじくと『自分は童貞なんだ、女とまともに付き合えないんだ~』って嘆いている奴。それでいて、しっかりエロ本買ってる奴。いや、だからこそ、そういった代換物で処理してるのだろうが」
「処理言うな。それに、『懐中水時計』だってしっかりとエロ本扱ってるじゃん、さっき言ったけど」
「俺の本屋は俺の見識を満たした本しか置かないのは知っているだろう? 扱っているのは、古代ジュダス文明の性典や、二十年前の同人エロゲのガイドブックや、そういったものだ」
「マニアック! ……今度読ませて」
「お前さんはほんと『人のことが言えない』って言葉が似合うなぁ」
ここで書店「懐中水時計」について解説しておこう。
建物は二階建ての、古い木造様式。レトロ、といった表現が似つかわしく、少なくとも五十年は経っているであろう風格をかもしだしている。全体的に焦げ茶のシックな色彩で包まれ、屋根は深い緑色。
一階は人文学、科学、魔術関連書を、きちんと配列に沿って並べ、少々の窓が点在する吹きぬけの二階には、びっしりと各種専門の全書といったものが並べられている。
新刊も古書も同等に扱う。また、地下二階に及ぶ巨大な書庫には、各種雑誌のバックナンバーが大量に所蔵されている。先ほど「ロシアで電撃文庫」の例を出したが、どのような国の、どのような言語の、どのようなマイナージャンルの本であろうと、「良書」であれば、レルエリィが「これは良し」と認めれば、その本は「懐中水時計」に並ぶ。
セレクトショップであるが、幅は広い。
それはひとえに、この店主・レルエリィ・ヒルトハミットの博覧強記ぶりにある。
大貴族・ヒルトハミット家の息子として生まれたレルエリィは、その生まれに相応しく、若かりしことは放蕩三昧を優雅に過ごしていたが、ある日突然天啓に打たれ、本……「活字の世界全般」……「知」なるものの探求の熱望に取りつかれてしまった。
結果、異常なまでのビブリオマニア、活字中毒になった挙句、それまでの人生に見切りをつけ、世界各国を放浪し、古書珍書奇書の収集に励むため、家を出るという暴挙に出た。現在ヒルトハミット家とは断絶状態である。
そんな奇妙な経歴を持った人物である、この店主は。しかしだからこそであろうか、本というものに対する愛情――あるいは偏執――は、常人のそれを遥かに凌駕する。
レルエリィにとって本とは、先天的に与えられたモノではなかった。この気持ちは筆者にもわかる。今でこそこうやって文章を書き、本を読んでいる筆者であるが、小さい頃は模型ばかり作っていた。それが中学のみぎり、突然本を読みだした。そのときからの、「天から何かが降りてきて、世界が広がった」感覚は、未だに消えていない。
ギフト、という概念がある。才覚は天から授けられるという考えだ。
もちろん筆者はレルエリィの博覧強記をもって任ずるものではない。だが、気持ちはわかるのだ。その経験を――天から何かが降ってきた経験なかりせば、今の自分はなかった、という、その感覚が。筆者の場合、その他にも、同じような「後天的天啓」で、エロゲと音楽とがあった。そしてそれは確かに、自分の世界を広げてくれた。そしてそれは確かに――自分の人生を変えてくれた。世界に恋をするかのように、ぱっ、と。
それに対する感謝と敬意の念なのである。レルエリィが「懐中水時計」を経営するのは。
「そういった本を買う奴らは、エーロの道を極めんとして、覚悟決めてるからいいんだよ。自信を持って買っている。臆面もない」
「少しはあった方がいいと思うけど」
「言っても無駄だ。問題はだ。俺の店に来る客の話じゃないのだ。彼らは自分の性癖と、自我について、きちんとした認識を持っている。だが、童貞意識をこじらせたヘタレは違う。自分はエロの初心者と思うばかり、やたらと過敏になって、発言が過剰になる。処女崇拝者――処女厨、と言ったほうがいいか? ああいった手合いのエロ談議ほどみっともないモノはない。かと思えば、別の者は、その過剰性ゆえに、ハッタリをかましたりする。自らの身の丈に合ったエロを語らない。初心者が放尿プレイを語るな」
さりげなく放尿プレイ言うな。仮にも青少年向けラノベだぞこの小説。ところで、昨今の文物で、放尿プレイがやたらと一般化して、「濃度」が薄くなったと思うのは筆者だけだろうか(黙れよ)。
「まあそういったことだったらわからなくもないけどねー」
間延びした声でキギフィが言う。
「私も仕事柄、絵描きさんの愚痴を聞くこととか、編集者さんの意見を聞く場合があるんだけど、やっぱり、青少年のライトなエロを満たすべき欲求が、世間では高まっているんだよね。ほら、ラノベとかでさ、一冊につき一回はパンチラがあるとか、お風呂シーンがあるとか、そういった類のアレ」
キギフィはその美少女ぶりから、モデルか何かかと思われがちだが、副業はイラストレーターである。同人あがりの。本業は灯台守なのだが。そしてそれ以上に呑んだくれである。収入は酒に使う。ちなみに筆者の収入は本とレコードとエロゲに使う(やかましいわ)。
「だろう? そういったライトなエロ……というか、現在では、結構ドギツくなってるが。一昔前では、こんな状況じゃなかった。これもひとえに、童貞共の性欲をインスタントに満足させるためだ。その癖して、さも自分はエロくありませんよ、みたいなふりして、そういったモノを語る。エロいんだっつの、そういったのは。それを認めろ。そして自分が童貞だということも」
「ウザったいことはわからんでもない」
セリゼが言う。
「ただ、さっきもやはり言ったけど、レル、あんた、そういった次元において、もはやいないじゃない。もうそういった連中のことなんかほっといて自分のワールドにこもれば?」
「まあな。俺だっていつまでもこういったことにかかずらってるつもりはない。あくまで日頃の愚痴を晴らさせてもらっただけというか。溜まってるんだなぁ、まるで童貞のように」
「セクハラかい」
「ウィットに富んだジョークだ」
「嘘つけぇ」
大体もう話の大筋は見失われているというか、単なる雑談に興じているだけというか、そもそも本屋店主仕事しろというか、しかしそれをいったら、この家で平日にも関わらず、卓を囲んで(麻雀かっつの)ダラダラと過ごしているこの四人――大家と居候s――も、大概に暇人である。
歴史はむしろ暇人によって作られる、という説がある。
例えば、世紀の大発明大発見が、超絶に集中しているとこよりも、むしろぼんやりのんびりバカンスに興じているときに「ハッ!」と天啓が降ってくるかのように。ニュートンと林檎を思い出してみよう。
あるいは皆様の日々の生活でも、そのような着想のあり方はあるのではなかろうか。
実をいえばこの小説の大体のプロットも、そのような過程をへて誕生している。ゆえにほとんど大した話がここまで全然生まれていないのは自明の理だが、いやいや果たして、これから驚天動地のジェットコースターさながらのストーリーテリングが……(ほんとかよ)。
まあつまり、キャラも筆者も暇だという話である。でなければこんな小説なんぞになりはしない。なんて説得力!
そんな暇人店主(いい身分だなオイ)レルエリィが、とどめと言わんばかりに言葉を足す。
「しかし、童貞意識をこじらせるのは問題だが、童貞意識が皆無というのもつまらんもんだ」
セリゼ、突っ込む。
「前言撤回も甚だしいな。人はそれを贅沢という」
「考えてもみろ、人間物事をしはじめのころが一番楽しいのだ。ロマンティックなのだ。歳を重ねるに従って、そのようなナイーブな感覚は無くなっていく。悲しきかな。とくに、エロの分野においてはそれが顕著だ。はじめはラッキースケベなパンチラで十二分に満足していたのが、童貞意識の喪失によって――あるいは、童貞をこじらせ、性的にこなれてくることによって――不感症になってしまう。結果、よりアブノーマルな方向へと行ってしまう。本当に自分が求めているエロが何たるかを、いつの間にか見失い――」
「つまり、何だろうか」セリゼは独白する。「新鮮さ、という観点からその童貞意識とやらを捉え直してみたら、我々には、いつも童貞意識を忘れずに、かつ、童貞意識をこじらせないようにしなければならないという芸当をしなければならない、と?」
「まあ、俺が言いたいのは、結局そういうことだ」
「禅の修行のようですね」
話を聞いていないようでしっかり聞いていた月読が口を挟む。
「全く禅だ。ていうか月の字聞いてたのか」
「仙人は結構何でも出来るんですよ」
「適当ぶっこいてるだけでしょが」
長い付き合いであるセリゼが、月読に突っ込む。
「まあそれはともかく、レルエリィさんの意見には賛同しますね。人間、童貞のときが一番楽しい」
「なんつうか、こう、見た目女の子なショタが童貞とか言うのって萌えるよな」
「黙れよ」
店主、昨今のオタ業界に毒されている。セリゼはそれに冷静に突っ込む。さっきから突っ込む突っ込むと言っているが、性的な意味ではない(こっちも黙れよ)。
「あらゆる分野でそれは言えることですね。自称上級者ほど、道を誤っているモノはない。学術名『シッタカブーリ・マイマイ』というカタツムリ科の……」
「しれっと息をするかのように嘘をつくな」
何だかいつの間にかセリゼが突っ込み役になっている。まあ、話をするにあたって、突っ込み役がいないと話が流れていかないし。エロゲでも、突っ込まない男が出演しない百合エロゲ(レズゲー)は売上悪いし。(いい加減にしろこのネタ)
「まあそれは嘘として」月読は淡々と言う。「でも確かにそういった存在が見受けられるのは、事実ですよね? とくに、学術分野なんかだと。大家さん?」
「その通りです」
かぶりを振ってフレアが言う。
「シッタカブーリ・マイマイの巣窟ですよ、私達の業界は。まあ、そういった手合いは淘汰されるのが常ですけど、処世術を持っているのは、案外……ああ、まあ、レルエリィさんの言葉を借りれば、学問的な童貞も確かにいることはいますね」
「結構フレアって律儀に話についてきてくれるよね」
キギフィが感心して言う。確かに、こんな酒の肴のウダウダトークのような話に丁寧に付き合うというのも、立派なものである。
「結論としては、だ」レルエリィは言う。「童貞はウザい。だが、新鮮さを失った求道者は、つまらない。しかし、道に迷って勘違いしている者もまた、悩ましい。よし、話が綺麗にまとまった」
「無理やりまとめたような気がするけど、まあ納得しておくか。それにしても店主よ、結構腹に据えかねているモノがあるようだな、ここまで話を広げる、ということは」
レルエリィは大きく伸びをして、ふあぁ、とあくびをして、話をする。
「結局、自意識の肥大の問題なんだよな。身の丈にあった童貞意識、というか、自己認識が出来ていれば、こんなことにはなっていないんだ。この近未来社会において、人々は、妙なコンプレックスに苛まれるようになった。贅沢者の悩みといえばそうだが、原始時代には原始時代の悩みがあった。現代には現代の悩みがある。が、煎じつめてみれば、大した問題じゃない、こんな童貞意識なんか。それをさも一生の大事のように、コンプレックス抱えているのが問題なわけで」
「生きにくい時代やのう」
一言、ぱさっと、セリゼがまとめた。
「まあともかく、童貞をこじらせた童貞はウザいってわけだ。ここに集っている連中は、もうそういった次元からは遠いだろうが。良くも悪くも」
「それは何か? 私たちが、ある種のナイーヴな感性を摩耗させているのではないのか、という指摘ですか?」
フレアが、レルエリィの、ちくっとだが、トゲを含んだ言い方に反応する。
「ガチに取らないでくれよ、博士。あんたも理解しているだろう?」
「ええ、わかっています。ただ、学徒の端くれとして、ちょっと……まあ、過敏に反応している分だけ、安心側なのでしょうか。それとも、余裕がないのでしょうか」
「あんたが言うなよ。あんたが『端くれ』だったら世の学者は何か、ってことになるぞ」
「それでも、まあ」
「気持ちは分かりますけどね」
月読が言う。
「童貞意識の欠如は、知らないうちに起こってくるものですから。それが大人になるってことでしょうし。まあ、三百越えたセリゼや僕みたいな年寄りが言えた身分ではないですが」
「ああ? 誰がロリババアだって?」
自意識過剰なセリゼ。
「ロリとは言うてないじゃん」
月読、セリゼにだけはフランクな口調になる。付き合いが長いからだが。そりゃそうだ、この中で、百年単位で付き合っている者など他にいない。
「……まあいいや。だいたいの話はわかったけど、店主、こんなとこで暇つぶしていていいの? リッテが泣くよ?」
セリゼ、レルエリィの右腕であるところの、「懐中水時計」少女店員・リッテの名を出す。
「大丈夫大丈夫、あいつは有能なんだから、俺がこうしてダラダラしてても全然」
そう言った矢先である。
ピンポーン、とチャイムが鳴った。
フレアは無線を介して、自分の耳とインターホンを直結して、来客に尋ねる――実は大体見当がついているのだが。
「はい」
「リッテです。いつもお世話になっています。ところで、ウチのぐーたら店長居ますか?」
ふむ、と納得して、レルエリィの方を向き、無線を遮断して、フレア、
「リッテさんがお越しですよ」
と告げる。
「げっ」
あからさまに狼狽するレルエリィ。
再び無線を繋げる。ドアの向こうでは、リッテが多少イライラしたような声をしている。
「多分ここに来てると思うんですけど……あの店長は……」
「ええ、居ますよ」
フレア、率直にリッテに対して、レルエリィの死刑宣告を告げる。
「あーっ! やっぱりもう! すいません、お邪魔しますっ!」
「どうぞどうぞ」
声を荒げているが、きちんと礼は正しているので、むしろフレアは気分が悪くなかった。というか、元気な働きぶりに、自然と頬がほころぶ。と同時に、そのように思うということは、自分もロリババアなのか、と、orzのポーズを取りたくもなる心境であった。
そんな屋主の心境を知るよしもなく、店員リッテ、居間に入る。
セミロングに伸ばした茶色の髪をポニーテールにして、顔つきは童顔であるが、生真面目さが伺える。華美ではないが、溌剌さが満ちているので、いかにも若々しい。華美ではあるが、世捨て人の体を成している、この家の連中に比べたら(レルエリィもそこに入りかけている)、まだ「一般人」である。
カットオフ・シャツと、ブルージーンズという、愛想のない格好の上に、仕事着であるエプロンを……画家のエプロンのように薄汚れたエプロンを、いつものように着ている。
どうにもこの町に集う連中というのは、変化を嫌うのか、だいたいいつも同じ服装をしている。セリゼのマントしかり、フレアの白衣しかり。レルエリィだって、マイナーチェンジはあれど、だいたい似たパターンの着こなしである。
それも然り。
だってこの町は、時代を無視し、自ずから取り残されようとして、世界の片隅のポケットのような場所に、ひっそりと身を寄せようとする人間が集うような場所なのだから。
結果、漫画・ゲーム的に「お前らいつも同じ服装じゃん」と言えるようなフィーリングになってしまうのだが、まあ、こんなことを言ってしまっては何だが、ラノベを展開していくにあたって、これほど都合のよい状況もない。あ、言っちゃった。
ええい、覆水盆に返らず。話を進める。
リッテ、彼女曰くのところの「ぐーたら店主」に向かって、吠える。
「こんなところで何やってるんですか!」
「おいおいリッテ、仮にも人様の家をこんな呼ばわりはないだろう」
「あ……ごめんなさい。そんなつもりじゃ」
「いえいえ、レルエリィさんの論点ずらしだってことはわかっていますから」
大家、寛容である。
「すいません、博士からそのようにフォローしてくださって……本当に、この宿六は、仕事しないんですから……」
「ひでー言い草。俺仕事してきたじゃん。ファージャ語族圏の人文学書のリストアップ。それに従って、お前、棚卸ししてるんだろ?」
「あ、ちゃんと仕事してたんだ」
キギフィ、さも驚いたように声をかける。
「おい鳥の字、お前俺を何だと思ってるんだ」
「鳥の字」とはキギフィのことである。「キギフィ」と言う名前は、ある地方に住む小鳥の名を指しているからして。
「仕事しない暇人」
「違うっちゅーに」
「でもリッテがこうして迎えに来た、ってことは、仕事残ってるんじゃん」
「そうですよ! キギフィさんの言う通りです! 棚卸し手伝ってください!」
「えー、めんどくせ」
「め、め、め!」
「雌鶏?」
セリゼが余計な口を挟む。
「ち・が・い、ます! めんどくせとは何事ですか! 仕事しなさい本屋店主!」
「ほら、俺って貴族出身じゃん。肉体労働向きじゃないんだよね」
「いつもは自分の出自についてとやかく言うのを嫌うくせに!」
リッテ、このえーかげんなのらりくらり対応に、吠える。フレアに向かって泣きつく。
「えーん、博士、何とか言ってください」
「よしよし」
そう言って頭を撫でるフレア。外見的には、妹がお姉さんをあやしているように見えて大変微笑ましいのだが、実際は四十過ぎの科学者が十代の書店員をあやしているので、年齢的にも立場的にも、極妥当なのだが、どちらにしても微笑ましいので、よしとする。
それを見ながら、ぐーたら宿六レルエリィ、セリゼに向かってぼそぼそと耳打ち。
「可愛いだろ、な?」
「あんたも趣味悪いね。店員いじめて楽しい?」
「いや、なんかこう、ついついからかいたくなるっつーか、無茶難題をけしかけてみたくなるというか。それでこう、さ、いつものごとく説教されて。なんかこれ、癖になっちゃって」
「お前それ童貞よりタチ悪いぞ。そればかりか、餓鬼のいじめっ子じゃあるまいし……なんつーか、『ぱわはら』って言うんだっけか? こういうの」
「失敬な。俺はただ、リッテをからかって遊びたいだけなのだ」
「本音出やがったよ」
「……それに」
言葉を濁した店主。それまでの不遜な態度とは違い、そこには妙な哀愁があった。
「何さ」
ちょっと気にかかったので、セリゼ、訊いてみんとす。
「こうでもしなきゃ、俺、あいつに手出せんだろ」
「……」
セリゼ、沈黙する。そんでもって、月読とキギフィの方にすすっと寄って、耳打ちする。
「……何これ? いつものノロケ?」
「だね。素直になれないっつーか」
「微笑ましいじゃない」
一同、ぼそぼそと会話する。
セリゼ、レルエリィに耳打ちする。
「あーた、この期に及んで、若い店員相手――まあ私らとリッテとの間柄だから小娘とは言わんが――にだな、及び腰になってどうすんよ。童貞意識がウザい言うんなら、あんたも大概ウジウジしてるっちゅう話になるよ?」
「いやでもな、考えてみろよ、俺みたいなロクデナシ、あいつがまともに相手するわけないじゃん」
ぼそぼそと、リッテに聞こえないような声でセリゼに言う店主(ヘタレ三十路)。
「あ、自分がロクデナシだって自覚あったんだ」
「芹の字のような暇人に言われたくないよ」
「何だとこの野郎!?」
セリゼ、ヘッドロックをかまして、げんこつをぐりぐりとレルエリィのブロンドに当てる。
「痛い痛い。拳を当てるな」
「当ててんのよ」
「それ用法違うっちゅーに。大体お前さん当てるほどの胸が……あ、マジ痛え!」
このまま頭蓋骨にヒビ入れたろかこの若造、と思うセリゼであった。無礼に対しては基本殴ればどうとでもなると考えている類の発想である。
それを傍目から見たリッテ、
「いいなぁ……」
と、二人に気づかれないように零す。
それを聞き逃さないキギフィであった。いつの間にやらリッテの傍にすすっと忍び寄って、セリゼがしたのと同じように耳打ちする。
「この期に及んで、まーだじくじく引きずってるの? ずばっと言っちゃいなよ」
「だって私、どう考えても店長と不釣り合いじゃないですか」
うわ出たよこっちもノロケが、とキギフィ、砂糖菓子を思わず口に含んでしまったかのような顔をする。月読、フレア、その顔を見て大体悟ったようで、無言で「頑張れ」とエールを送る。
「もう長い付き合いでしょ? お互いをこの町で一番知ってるのは貴女たちじゃない。まさか、相手の出自――貴族出身なんてーのに気おくれしてるんじゃあるまいね? 前近代的な」
「……正直、それもあります」
「あれれ」
「だって考えてみてください。いくら実家と縁を斬ったからといって、大貴族ヒルトハミット家の規模というか、力は、ある程度の情勢に通じていれば分かります」
「んー、でもさ、それって答えになってなくない? 誘導しておいてなんだけど」
「?」
「それを、自分が諦める便法に使ってやしないか、ってこと」
何だかキギフィ、恋愛カウンセラーである。まあ、この美少女も、それなりに人生経験積んできたわけである。ただ呑んだくれていたわけではない。むしろ、呑んだくれていたからこそ、人情の機微がわかったりする。
そんなにキギフィとリッテの歳の差はないのだが、ここでは主導権はキギフィが握っているように見える。
「……それも認めます」
キギフィの言葉に、苦々しくも賛同するリッテ。
「でも、いろんな意味で、私と店長は不釣り合いなんです。知識においても、経験においても。それは、あの店で働いていればわかります」
「似た者同士って感じもするけどね。大の本好きと、超絶ビブリオマニア、という違いはあれど、それは量的な問題でしょ? 方向性的には変わりないじゃない」
「同じであるがゆえに、時として絶望することもあるんです。……というか……というか、うん、器が違うんです。貴族出身のことを気にしているのもそうです。器という意味合いで」
「で、自分の想いを隠して、一介の店主店員の付き合いでこの数年、と」
「それ以上、自分には想像出来ないんです」
「若いんだから、突撃すりゃいいじゃん」
「……ややこしい女と思われそうですが、臆病なんですね、私」
ああ、ほんとややこしいよ、とキギフィは思った。
ハタから見ていれば、どう見たってお似合いなのである。
それをどういうわけだか、自分ルールで勝手に自分自身を縛って、お互い臆病になっている。で、いつものように軽口をたたき合う関係に終始している。それでよしとしている。
誰もが思っている。「お前らもう付き合っちゃえよ」と。
が、まあ、理屈屋というか、理が勝る人間の恋愛の常のように、ここぞと言う時に、自分の境遇だの、資質だの、能力だの、コンプレックスだのを持ち出して、逃げ腰になるのである。
リア充どもめ! と言うのは容易い。
もうフラグ立ってるんだからルート入れよ! と言うのは容易い。
が、それは外から見たバアイであって、渦中の人間にとっては、ずいぶんグチグチジクジクしたものなのである。
恋愛なんてそんなものか、と、リアリティについて思いを馳せるが、
が、
この店主、そもそも「童貞は死ね!」とか言ってた癖に、いざ自分の恋愛となると、こうやってヘタレになるのだから、人のこと言えた義理か、と、この家の住人は皆思っている。多分読者も思われておられるのではなかろうか。
きっと、もうしばらくは、こうしたグジグジした状況が続くのだろう。
それをこの家の住人は、あるいは、物事や機微を知っているほうき星町の住人は、「もういいからリア充爆ぜろ」と思いながらも、微笑ましく眺めていくのであろう。
リッテ、当初の目的に立ち戻る。自分の気恥ずかしさを隠すようにして。
「そもそも店長、ここで何を話してたんですか?」
レルエリィ、自分の気恥ずかしさを隠すために、あえて露骨なネタ振りをする。
「童貞意識の問題についてだな」
「ど、ど、ど、童貞って! 仕事サボってそんなことくっちゃべってたんですか!? もー、いーかげんにしてください! 仕事しますよ!」
襟首掴んで、真っ赤になりながら退室していくリッテと、それを苦笑しながらも、悪い気はしないな、みたいな顔をして引きずられていく店主・レルエリィ。
「なんつーか」
キギフィは言う。
「そうですね」
フレアは言う。
「お幸せに……というか」
月読は言う。
「リア充、もとい、ヘタレ恋愛童貞は死ねっ」
セリゼは吐き捨てる。
思い思いの、言葉にならない、ある種の諦めを嘆息する四人であった。ぼそぼそと。
ほうき星町の人々――「童貞事実と童貞意識」