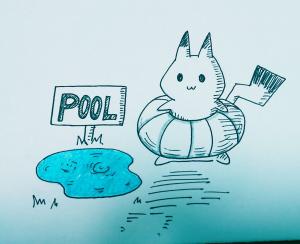Katharsis
第一夜
「なあ、あの話って本当のことななのか」
唐突な切り出しにも、斜面の少し下に座る、問いかけられた少年は即座に振り向く。しかし、その顔からはまだ答えの定まっていないのが読み取れた。
「八尋、お前はどう思う?」
振り返った顔に向かって、八尋の少し上に腰掛けるもう一人の少年、太志郎は再び訊いた。もとより真剣な答えなど求めていない。ただの世間話のようなものである。
「あの話って〝鬼〟の話だろう。俄かには信じがたいけれど…」
紅く染まった空に寝床へと帰る鳥の群れが横切る。四方を山々に囲まれた小さな山村の端の、比較的なだらかな斜面の上に二人は腰を下ろしていた。
ここからだと村の大半を眼下に収めることができる。陽は間もなく向かいの山の稜線に差し掛かろうとしていた。刈り入れが終わったばかりの田の凪いだ水面は、反転した夕闇を映し出していた。なお強烈な西日が整列した稲藁の背後に細長く影を伸ばしていく。斜面から裾野にかけて階段状の水田が幾重にも続き、その先に小さな茅葺屋根が点々と散らばって、細い煙の糸を揚げるところもいくつか見られた。太志郎にとって幼い日から何百何千遍と見てきたごく日常的な風景だった。どこにでもある、ありふれた景色だと改めて太志郎は思った。この辺りはどこも一様であり、山ばかりが連なるこの國の全土を見渡してもきっと同じことなのだろう。
「いや、自分の目で確かめないとな。」
暫しの沈黙の後、口元にいたずらっぽい笑みを浮かべながら八尋は答えた。その言葉の意味するところはすぐにも理解できたが、先程予想していた軽い返しに反して、口をつぐまれたことには妙な感覚を覚えずにはいられなかった。
周囲の山々のなかで一際高く、堂々たる姿でそびえる〝夜囲山〟が太陽を呑み込み始めていた。
どこにでもある山間の小さな村で奇妙な噂が囁かれだしたのは数月前のことであった。
─────〝鬼が出た〟─────
その言葉はありふれた日々を一変させるのには十分な威力を持っていた。実際には鬼を見たという者は誰もいない。しかし近頃家畜や作物が何者かに強奪されたことがあり、その狡猾だが粗暴なやり口と獣のような所業は鬼の仕業に違いない、と考える者が多いのが事実であった。質素だが平和を絵に描いたような集落の空気に不穏なものが漂い始めた。そしてそれは日に日に増してきている。しかし、鬼が〝出た〟のはこれが初めてではないということを太志郎はまだ知らなかった。
陽が完全に落ちるのを待って二人は腰を上げた。夜囲山はその名の通り昼でも鬱蒼とした木々に覆われ、夜中の森のような薄暗さである。静けさと、ねじれて絡み合った枝が不気味さを際立たせている。獣道に毛が生えた程度の道を歩きながら、太志郎はふと感じた肌寒さに思わず身震いした。そんな様子を見逃さずに、八尋が
「まさか、怖いのか?」
とからかってくる。まさかな、と笑ってみせたものの、太志郎は八尋の言葉に刺激されて、未だ見えぬ何かに微かな怖れを感じていることを認識させられた。予感、とまで判然としたものではない。ただぎりぎり意識できるかどうかの域の感覚であったから、それきり振り払って頭から締め出してしまおうと心がけた。今度は太志郎が口をつぐむ番だった。
「おーい、大丈夫か。早く戻らないと怪しまれるだろうし少し急ぐぞ。」
怪訝そうな顔で覗き込まれてようやく我に返る。
「すまない。少し考えるところがあって。」
八尋は向き直って太志郎のすぐ前を進み始めた。二人の進む道はいよいよ狭く、とても横に並ぶことはできなくなってきていた。長身の八尋の背を追う。
「考えてたって、作兵衛さんとこの娘(こ)のことじゃないのか?」数歩と行かぬうちにまた八尋は振り返ってきた。
「えっ、お前っ そのことは……」予期していなかった方向からの攻撃に反応が遅れたが、動揺を見せまいと太志郎は言葉を継ごうとした。そのとき、静寂を破って枝が揺れ、鳥が羽ばたき立つ音が聞こえた。それもかなり近くだ。はっと息をのんで二人は同時に音のした方向に頭を向けるが、辺りは再び静寂に呑まれた。時折大きな獣か何かが地を踏みしめ、小枝の折れる音がする。他には鈴虫の類が鳴く声、葉擦れの音も。やけに心臓(しんのぞう)の鼓動がうるさい。
(なんだったんだ、今のは)
それからも二人は歩き続けた。かれこれ半時は歩いただろうか。太志郎の目も既に暗闇ではたらくようになっていた。途中までは昼間であれば入ったことのある道を進んでいたものの、先程からは全くの未知の領域に足を踏み入れていた。やや前を行く八尋は、この暗さの中ではじめからよく見えていたかのように、迷いなく歩を進めている。もはやこれまでの道程も怪しくなりつつある太志郎であったが、その点に関しては八尋が頼みとできることは分かっていた。二人とも口数はぐんと減った。疲労を感じていないわけではない。我ながら平時の自分であればこのような馬鹿はしないだろうと、脛に何本か走る、下草に掻かれた跡に視線を落としながら、太志郎は嗤った。しかし他方でそれを超える昂揚感、そしてそれを後押しするように膨らみつつある好奇心も感じていた。
少し注意が散漫になっていたのだろうか、狭い足場を斜面伝いに下りているときだった。木の根を避けて足を下ろしたとき、太志郎は足を滑らせた。砂利でさらに足を掬われ、足場を踏み外して急勾配の斜面を滑り落ちていく。
(痛ってぇ…)
体中が鈍い痛みに疼いている。恐る恐る目を開けると、少し開けた林冠からは満ちるまであと幾日かの月が顔を覗かせていた。積み重なった腐食した葉のおかげで幸い怪我はないようだが、着物はあちこち擦り切れていた。ゆっくりと半身を起こす。眼前の光景を目にして太志郎は愕然と固まった。太志郎がいるところからまだ緩い斜面を下って一町ほど先に灯りが点々といくつも見えるのだ。目を凝らすと灯りは随分奥の方まで散らばっていた。それら光の群体は、奥は家々からぼうっと漏れ出す光、手前は篝火の煌々と揺らめく光から成っている。そう、家屋だった。太志郎のいるところから少なくとも十数棟が見える。後ろで慌てて下りてきた八尋も太志郎の無事なのを瞥見したあと、同じ光景を目にして息を呑むのがわかった。
「鬼の隠れ里は本当にあったんだ・・・・・・!」
さすがにそれは早計だろうと頭では分かってはいたが、太志郎も自らの興奮が呼び戻されてくるのを抑えきれなかった。家が並ぶのは森の中でも比較的開けた場所で、空から見れば山に大穴が口を開けているようであるのだろうかと太志郎は思った。
太志郎たちは家屋の群れを取り巻くように周りながら、中の様子を遠くから探った。集落の外周は背の高い柵に囲まれていて、広さに関しては実際太志郎の村の一角ほどにすぎないだろう。一方家の方はがっしりとした造りで、村の物より外観は一回り、とまではいかないものの大きく背が高い。
(しかしなぜあんな篝火が? 今から何か行われるのか)太志郎の疑問が届いたのか、家屋の中から数人がぞろぞろと姿を現した。出てきた者たちはそのままゆっくりとした足取りで外へ歩いていく。皆一様に布を丸めたようなものをいかにも大切そうに手にしていた。八尋が先程より幾段か声を潜めて呟いた。
「あれが〝鬼〟か。」
「きっとそうだ!鬼だ。 でも考えていたのと少し違うけれど。」
嬉々として答えた太志郎の声が萎んでいく。二人に彼らが鬼だと判断せしめたのは彼らの容貌であり、同時に彼らが鬼であるか疑念を抱かせたのも彼らの出で立ちであった。二人のいるところからは細かくは判別できないが、鬼は完全に人の姿をしていた。初めに出てきたのは男だろう。鍛えられた屈強な体ではあるようだが、そこに異形の怪物の影は全くない。唯一異なるのはその巨躯であろうか。こちらもやはり小綺麗にされた、ゆったりとした衣の袖から覗く腕は、太志郎の腕など軽く一捻りにされてしまいそうな逞しいものだった。
鬼を探して噂の真偽を確かめる、太志郎の好奇心からくる思いつきは達成された訳だが、噂話、それも子供だましとすら言える鬼の存在が真実味を帯びてきたことに太志郎はうすら寒い不安を覚え始めていた。早々にこの場を立ち去りたいところだが、八尋は鬼たちに目を釘付けにされて動こうとしない。そのとき鬼たちが手を止め、一斉に顔を上げて斜め上の木々の隙間に視線を向けた。八尋と太志郎のいるところに、である。(まずい、ばれたか)太志郎は半ば強引に八尋の腕を引っ張るように向きを変え、元来た道を駆けだした。振り返ると、隠れ里の住人が追ってくる気配はないようだった。しかし、この暗闇のなか大した物音も立てずに潜む人間の存在にどうやってあんな遠くから気づいたのだろうか、と太志郎は頭を捻った。
あいつらはいったい何者なのだろうか。
第二夜
太志郎にとって八尋は、最も理解している人間であると同時に最も、本当の意味で理解できていない人間と言えるだろう。
八尋との付き合いは非常に長いが、太志郎の知る限り、八尋は何事も卒なくこなし、そこまで苦労しているところを見たことがない。体格や容姿にも恵まれ、噂の絶たれることがなかった。太志郎も八尋も百姓ではあるが、多少書物を齧ったことがあり、その時の覚えの速さから学の方でも非凡な能力を有しているに違いないだろうと太志郎は思っている。そうした能力故に村でも事あるごとに頼みにされる存在だった。少なくとも太志郎からすると恐ろしく何事にも優れている八尋は、根本的な弱さを他に見せることがない。しかし、全く弱点を持たない人間などいない筈であり、それが太志郎が彼を真に理解するのを拒んでいたのだった。太志郎も負い目を感じないわけではないが、それだけ万事に優れていても飾らない八尋の気性が長い交友を支えていた。
太志郎たちが隠れ里を見つけてから幾日かが過ぎた。日に日に山間を吹き抜ける風は冷たくなっていく様であったが、村の者たちの熱は冷めるどころか徐々に高まってきていた。鬼を親の仇の如く敵視し、存在も定かではない筈が、忌み嫌って鬼の如何に兇悪で下等な獣人であるかを執拗に唱え続ける者の様子は奇妙、滑稽を通り越して異常性、狂気性を感じさせるほどだ。ついには赤子がさらわれたのなんだのといった話まで仕立てられる始末だった。しかし、実際村の様相は一変してこのようであり、異常を感じている者など僅かに過ぎなかったのである。まさに質の悪い流行り病に罹ったかのように村は熱に浮かされていたのだった。
(どうしてこんなことになったんだ。)
じっとりと汗ばんだ右手を衣の端で拭い、八尋は頭上を仰いだ。くっきりと縁どられた真円の月が煌々と輝いている。よりにもよってこの月とは、と心の中で呟く。右手に棒きれを握り直した。立ち止まっていた両脇を、村の者たちが手に手に鍬や鋤といった柄の長い農具や刀やらなんやらを携えて通り過ぎていった。その横顔からほとんど感情らしい感情が読み取れないのが今はただ恐ろしい。
鬼への異常な執着は、隠れ里への夜襲という形で行動に移された。太志郎たちが口外しなくても、隠れ里の存在と位置は明らかになっていた。そうとなればあっという間に事は進み、朝から集まって昼頃には早くも終わった寄合で、村の者の大半が夜囲山に繰り出す事になったのだ。
全てを覆い隠す夜の闇に包まれた山中で、暴力的な掃討が始まった。だが悲惨な結果をもたらしたのは、それが一方的な駆逐と蹂躙では終わらなかったことだった。
(こんな型のつけ方、結末は間違ってる・・・・・・!)そう思いながらも、山に深く立ち入ることなく喧噪をただ遠巻きに窺う自分が八尋はひどく恨めしかった。遠くで太い黒煙が幾筋か立ち昇っている。太志郎とは違う方角から山に入ったが、大丈夫だろうか。少しでも高いところから俯瞰しようと試みたがそれは叶わなかった。
争いの中心から離れていることで高をくくっていた八尋だったが、少し先の木の根元に人影が座り込み、幹に背を預けているのを見て息が止まりそうになった。人影は動かない。すぐに冷静を取り戻し、臨戦態勢をとる。じりじりと距離を詰めていくと、人影、大柄の男の肩で浅く息をしているのが確認できた。着物は所々裂け、怪我をしているのは明らかだった。
(鬼だ! しかもこの前列の先頭にいた男かもしれない)
視力の優れている八尋には目の前の男が先日隠れ里で最初に見た鬼であることをほぼ確信していた。左手に松明を掲げながらさらに近づくと、男は顔を上げた。松明の炎に照らされたその顔は憔悴しきっていた。近くで見ると体格の他にも特異なところがあるのが分かる。その双眸は名のみ知れる遠い異国の石を思わせる深い青で、髪色は薄く、頬骨は高く張りぎみだった。八尋は視線を落とし、男が首に何かを掛けているのに気付いた。その先には幾何学模様を象ったものが通されているが、それがどういう種のものなのかはわからなかった。男は僅かに嘲るような笑みを口元に浮かべながら口を開いた。
「お前も俺を殺りに来たのか、小僧。」
よく響く声だ。
「もしその通りだといったとしたら? あるいは薄ら笑いを浮かべて無言のままこいつを振り下ろしたら?」言いながら右手を見やる。男はここで八尋の目をじっと見つめ、一瞬たじろぐような様子をみせたが、次の瞬間には今度は興味深いものでも見るかのような目つきを八尋に向け始めた。その目に射すくめられると同時に、表現し難い恐怖や不安が際限なく膨らんでくるのを感じた。そして悪い予感もだ。鬼が再び口を開いた。
「そんな格好向こう側の者として生きていても、判るんだ。お前がこちら側の人間だとな。」
「どういう意味だ。」鬼はそれに敢えて答えないでいるかのように続けた。
「少し遡るが、とある小さな山村の一人の女(むすめ)が山奥に迷い込み、そこで一人の男を見つけた。だがそいつは女の知っている所謂普通の人間とは姿を異にしていたんだ。」
「それが鬼か。」
「そうだ、鬼だ。女は戸惑いながらも、言葉を交わすうちにそいつを受け入れ始めていた。鬼の導きで一旦は村に辿り着くことができたが、その後二人は山中で密かに会うことを重ね、関係を深めていった。」男は言葉を切り、かなり疼くらしい胴部の傷を気にしながら唾を飲んだ。今は語る事を優先し、鬼という言葉を使うことを厭わない様子だ。
「どれだけ隠しても事はいつか明らかになる。逢瀬はそのうちに村の人間、鬼の双方の知るところとなった・・・・・・ その後二人がどうなったかはわざわざ言う必要もないだろう。」
「・・・・・・なぜ鬼はあれだけ憎まれるんだ?」ずっと蟠っていた疑問が口をついて出た。
「そうか、そこからだな。」
「俺たちは昔から一所に留まる民ではない。暮らす土地は転々としてきた。だが、どの土地でもやつらと俺たちはあまりにも違いがあり過ぎた。特にこの近くはどこも厳しいものだ。お前の歳では知らないだろうが今夜のようなことはそう珍しくない。やつらは俺たちへの敵意を煽り、理解を示そうという気は全く見せなかった。」
(大きな差異故の怖れが過剰な反応を引き起こしたのか・・・)
「しまいには都合の悪いことはすべて鬼の仕業と来た。鬱積した感情の捌け口にしてやがる。やつらを図に乗らせすぎた。」
男は痛みからとも怒りからともとれる、歪んだ苦い表情を見せた。あの村のどこにそんな感情の入る余地があるのか引っかかったが、八尋は何より男の話に嫌気が差してきていた。
「鬼と女の話は終わりじゃないんだろう?」
「ああ。男も女も姿をくらました。・・・・・・だが、そのとき、女は身籠っていたんだ。そして赤子を産んだ。」
「ただでは済まないだろう。」
そう答えながら、八尋は内なる声の警告を本能的に感じ取っていた。それ以上耳を貸すなと。だがその一方で自らの生を揺るがしかねない言葉の一つ一つを聞き流すことのないように促す自分もあった。手だけでなく全身に嫌な汗をかいているのが分かる。
「本来であればな。だがもしその赤子が成長して村で何事もなく暮らしているとしたらどうだ?産まれたのは男子だった。母親は村を出たが、子は村で育てられた。今頃は齢十七八、といったところか。」男はそこで言葉を切り、八尋の顔を冷たい笑みで見上げながら、ひどく残酷に宣告を下した。
「当の本人には何も知らされていないようだがな。」
八尋は頭が白い閃光で染められるような感覚を覚えた。ひどく眩暈がする。聴覚、嗅覚、触覚、あらゆる感覚が消え失せ、何も考えられなくなった。自分の出自や容姿には多少疑問があった。八尋が鬼の血を継いでいるのだとすれば説明がつく。何かの間違いであることに縋る思いはあるが、男が八尋を誑かそう(たぶらかそう)としてついた嘘には到底思えなかった。自分が鬼だと知った後でも、血を継いでいたとして果たして自分が鬼なのかは分からない。八尋には自分の鬼と人間との関係を示す肉親はいないのだ。初めの衝撃を乗り越えた後、今度は自分が今いかに中途半端な身の上にあるのかを悟った。まるで宙づりになって足元には虚空がどこまでも広がっているかのような。いつものように頭は冴えていない。今度ばかりは話が違うのだ。何もかもわからなかった。
八尋は人に頼られることは多いが、逆は少なかった。それ故か助けを求めるのは得意ではない。いま珍しく八尋は答えを、助けを求めていた。しかし、少なくとも今八尋が助けを求めるべきは目の前の男ではない。
(こんなことやってられるか)
月光と松明の灯りを頼りに、山道を突き進む。燃える隠れ里と鬼、村の者たち、それらを取り巻く喧噪から少しでも離れる。しばらく歩いたところで立ち止まる。太志郎は溜めていた息を吐き出した。もうすでに右手の得物は捨ててきた。八尋はなんとかやっているに違いない。自分の心配が先だ。
辺りを見回すと、少し離れたところにぽつんと一つ松明の光があるのに気づいた。ふと気になりそこへ足を向けるが、近づけば近づくほど、隠れ里を見つけた日と同じ、あの胸騒ぎも感じる。一人が松明を持って立ち、その目線の先には大柄な男が木の根元に足を投げ出していた。松明を持つ者が誰であるかはその背格好ですぐに分かった。八尋と呼びかけようとして、太志郎はそれを呑み込んだ。八尋の前にいるのは鬼だった。鬼と八尋は話しているようだ。八尋は聞き役に徹しているが明らかに様子が変だ。正面から表情を見なくても何かに怯えているのが背中から伝わってくる。時折発せられる八尋の声音も全くもって平時の彼ではない。さらに足音を忍ばせて木々に身を潜めながら近づいていく。鬼の太い声がはっきりと聞こえてきた。
「・・・・・・女は戸惑いながらもそいつを受け入れ始めていた・・・・・・」
「連れが来たみたいだな。」
足音のする方を振り返ると、歩いてきたのは太志郎だった。
「大丈夫か?」太志郎は八尋の顔を覗き込むようにして尋ねた。太志郎の声を聞き、気分がようやく落ち着いてくるのを感じた。松明の揺らめく火とその熱さ、夜の静けさに際立つ虫の声が八尋の周囲に戻って来た。それと同時に鬼の宣告で八尋に穿たれた虚ろな穴がまだそのままであることを否応なく意識させられた。右手を見るとずっと棒切れを固く握りしめたままだった。
「聞いてたのか。」
「悪かった。・・・でも、違うんだろ?あんな鬼の戯言に動かされるなって。お前らしくないぞ。」
そういう太志郎の声は、自信なさげで、八尋が首を縦に振るのを願っているようだった。重苦しい沈黙が流れる。
「わからない。わからないんだ。なあ太志郎・・・・」
少し上ずった声で続けようとするのを太志郎は素早く首を振って制した。
「もういい。さっさと行くぞ。」
そのまま、太志郎は八尋に顔を背けて足早に歩きだした。山を出るまで二人が口をきくことはほとんどなかった。
夜明け
永遠に続くかのような夜はそれでも明けて、それからひと月ほどが経った。結果的に鬼を再び追いやり、また元の安寧な日々が戻ると思われたが、そうはいかなかった。結論からいえば鬼から聞いた話は嘘偽りではなかったのだ。一旦は村の熱は鎮静化したが、長く経たないうちに今度は村の内部に向けられるようになった。八尋は真っ先に矛先を向けられることとなった。あれだけ頼りにされ、村に貢献してきた八尋に向けられたのは、打って変わって冷たい目線だった。八尋は居場所を失くしていき、八尋は自ら立ち去る道を選んだ。
太志郎は峠への道を急いでいた。八尋は陽が高く昇って来ないうちに出るつもりだろう。ここにきて太志郎は自分の犯した罪の重さを噛みしめていた。一つ目は、〝あの夜〟、助けを求めていた八尋に向き合おうとする努力をしなかったことだった。正直なところ、あのときの八尋の目はひどく虚ろで恐ろしかった。そして、まさか八尋とあの鬼が関係しているとはあまり思いたくなかった。二つ目は、村の中で八尋が虐げられていたときに、庇うことはおろか、八尋にそのあとで声をかけることすらできなかったのだ。周りに従うしかなかったからなどと言い逃れることはできまい。方法はなんとでもなった。八尋をある意味裏切ったのだ。 全て自分の意志薄弱と臆病な性から犯してしまった罪だった。いや、これを罪だと人は呼ばないのかもしれないが、太志郎にとってこれは罪以外の何ものでもない。どれだけ恥じても、どれだけ手をついて謝っても足りない。八尋は太志郎がしたようにもうまともに向き合ってはくれないだろう。それでも最後に行かなければならないと太志郎は思ったのだ。太志郎は走りだした。
(頼む、間に合ってくれ!)
「八尋!」
前を歩く長身の背中に何度呼んだか数えきれない友の名を呼んだ。八尋は立ち止まり、戸惑いの表情を向けたまま、駆け寄る太志郎を待った。
「八尋・・・・謝りたいことがあるんだ。・・・・それと、話しておきたいことも。」
息を切らせながらそう言うと、八尋は予想外にも微笑を浮かべた。
「わざわざ走ってきたのか。まあ太志郎ならそんなこともありうるかとは思っていたけれど。」
Katharsis
題名のkatharsisですが、ここではは日本語でよく言うカタルシス、抑圧され、鬱積した感情が解放される作用を表す意味ではなく、古代医学の治療法の一つである、「瀉血」を表しています。
画像:Harmony LawrenceによるPixabayからの画像