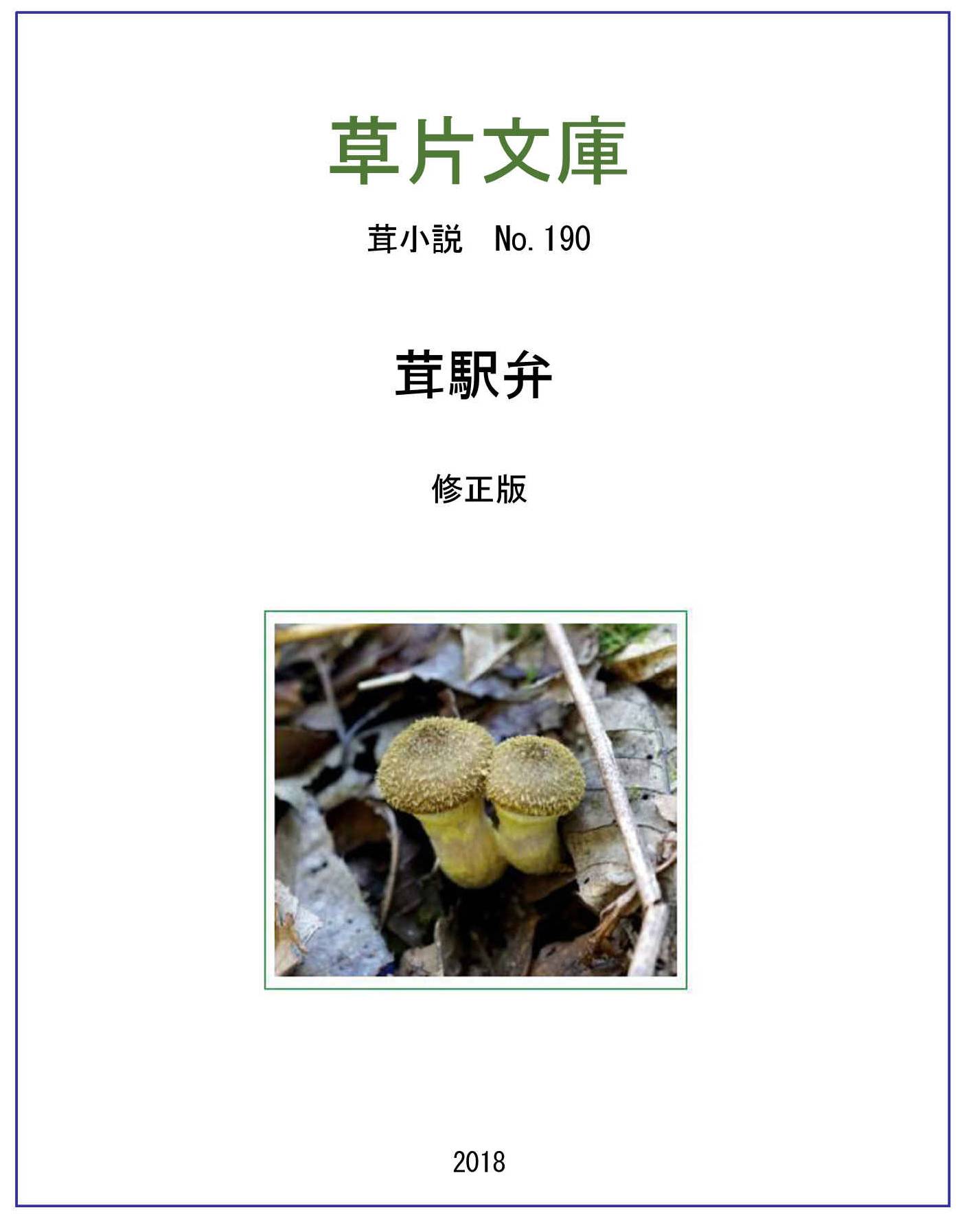
茸駅弁
茸のミステリー小説
旅の楽しみの一つは駅弁である。それぞれの駅に独特のおいしい弁当がある。駅弁を食べ歩く旅の番組はいくつもある。デパートでは駅弁大会を開いたり、遠距離列車が日本全国にでていく東京駅に至っては、駅舎の地下売場に豪華な弁当が並べられている。
そのような中で、珍しい駅弁クラブがあると聞いた。私の会社の同僚であり友人の一人がはいっている駅弁クラブで、ごちそうの会という、そのクラブには全国で千五百人ほどの会員がおり、都道府県それぞれに支部がある。どこかに入会していれば、どの支部の大会にも参加ができて、楽しさ倍増だそうだ。支部同士の交流がさかんだ。相手の地方を旅して、説明を受けながら駅弁を食べるという楽しみ方もある。そのおかげで、一般に知られていない美味い弁当にありつけるという。
彼はその会に参加するために三日ほどの休みをとる。今回は北海道でこんな弁当を食べたとか、四国のどこそこの弁当はこういう味だったとか、行ってきた次の日は、みんなの前でさも楽しかったという顔で、その味の評価を披露するのである。もちろんお土産も買ってきてくれる。
ある日、前日まで駅弁の旅に行っていた彼がこんなことを言った。
「駅弁の会でたまに出会うご婦人がいてね、白髪ででっぷり太った人で、とても美味しそうに駅弁を食べているんだ、今回その人がたまたま隣の席でね、面白い駅弁の会があるという話をしてくれた」
「君の入っているのも面白いんじゃないのかい」
「うん、結構珍しい駅弁を食べることができるよ、ところが、その会はただの駅弁じゃないんだ、茸の弁当なんだそうだ」
「君は茸のことをよく知っているからな」
彼は子供のころ長野のある町で育ったと言っていた。
「茸はうまい食材だよ、その婦人、おそらく七十くらいの人だろうな、彼女の話では、その珍しいクラブに入ることができると、そこに所属する人だけが日本中の駅の茸弁当が食べられるというんだ。全く知られてない駅でも、そのクラブの会員には、そこで採れる茸の弁当が渡されるという。ということは、茸が採れるところの駅にしかその弁当はないことになるけどね」
「そんなのがあるんだね」
「草片弁当愛好会と至極当たり前の名前の駅弁クラブだ」
「その婦人はそのクラブにはいっているわけか」
「いや、試験に落ちたそうだ」
「試験があるのか」
「そうらしい、試験というか、指定された駅に行って、渡された茸弁当を食べさせられた後に質問をされ、それに答えられないと入れないんだって」
「どこの駅に行ったんだって」
「新潟の長岡」
駅弁で有名な駅である。
「その駅の駅弁、俺も食べたことがあるよ、あれうまいよね」
そう言ったら、彼は笑った。
「イカめしのことをいってるんだろう、むかしはイカめしというと長岡と北海道の森駅だけだったからな、確かにうまかった。しかし長岡にはもうないんだよ」
「やめたんだ」
「そうらしいよ、それでね、長岡にそのご婦人がいくと、改札口に紳士が待っていて、その紳士にみちびかれて駅から出ると、ある食堂に入ったそうだ。テーブルに腰掛けると、紳士が手をあげ合図をしたそうだ。すると店員が駅弁を持ってきた」
「その食堂で売っている奴だったのかい」
「いや、違うようだ、紳士が何も言わないのに弁当が出てきたというのは、その紳士はその店ではよく知られた人だったんだな」
「それで弁当はどういうのだったんだい」
「イカの絵が描いてある紙がまいてあったというんだ」
「そりゃ、やっぱりイカめしだね」
「それで、食べてくださいと言われて、ふたを開けると、やはり、イカめしがはいっていた、その紳士も自分の分を食べた。食べ終わったら、紳士がいくつかの質問をしたそうだ」
「それが試験だったわけだ」
「うん、紳士は、どんな味でしたか、と聞いたそうだ、茸弁当のはずだから、その婦人は何の茸が入っているのか興味津々で、気にしながら食べたそうだがよくわからなかった、イカの匂いがして、イカめしであることは確かで、ただ、以前食べたイカめしより数段味が良く、そう言ったところ、紳士が、はいっていた茸がわかりましたか、と聞いたそうだ、要するにイカめしの中に茸が入っていたわけだ、しかし彼女は首を横に振ったわけだ、誰も食べたことのない茸が入っているのです、想像でいいからおっしゃってください、と言われたという」
「なにから想像しなければいけないんだろう」
「長岡、と言うこと、弁当の包み紙にはイカめしの絵がかいてあったこと、そんなことから考えたが分からなかったそうだ。そのイカめしの絵にヒントがあったんだ、と婦人は言っていた」
「判じものだね」
「そう、その婦人は後でわかったそうだ。包んであった紙の表紙絵は、お米をつめられたコロンとしたイカの絵、これは普通だね、その脇にイカを下から見た絵が描いてあった。何本かの足が生えている奴だよ、それがくせ者だった」
私はそう聞いてもなにもわからなかった。
「俺も、婦人から聞いたとき、よくわからなかったな、紳士が言ったそうだ、とても珍しい茸がたくさんはいっていました、確かに味はイカの味で隠れてしまっていたかもしれませんね、それは誰も当てることができないでしょう、でも、この絵を見てください、茸がお好きな方なら分かると思いますよ、と言われたたそうだ」
彼は紙にそのような絵をかいて私に見せてくれた、足が出ているイカを下からのぞいたような絵だ。イソギンチャクのような格好だ。
「これはね、イカタケと言う珍しい茸なんだ、それを採って、米と一緒につめたイカめしだったんだ」
「はー、むずかしいね」
「茸好きな人なら、一度見てみたいと思う茸だよ、そのご婦人も、ああそうだったのか、という思いだったそうだ、イカタケはよく知っていたが、見たことはなかったという」
「それで、合格しなかったの」
「残念ですね、この会には想像力も必要なのです、と言われたたそうだ、それでも、彼女は貴重な茸駅弁を食べることができたとお礼を言ったそうだ」
「そんな会なんだ」
「うん、そのような会なら、僕も入ってみたいと思ったよ、そのご婦人が会員になっている人に会わせてもいいと言っていたから、頼もうと思っているんだ」
「彼女の知り合いに会員がいるんだね」
「そうらしい、彼女ももう一度トライするそうだ、一年に一度、テストを受けることができるということだ」
そういう話だった。
そんな話から半年が経った。彼はその間もたまに休みを取り、せっせと駅弁クラブの会を楽しんでいた。
その日の昼休み、彼は目を輝かせて私に言った。
「草片駅弁当愛好会に入れた、まだ準会員だけどね」
「そりゃ、よかった、今のクラブはどうするの」
「あれはあれで入っとくよ、草片駅弁愛好会は年四回だけなんだ、春の茸のでる五月と七月、それに秋の茸の出る八月と十月だ、たまにイレギュラーの会もあるようだけどね」
彼は七宝焼きでできた準会員のバッチを見せてくれた。椎茸のような茸がデザインされている。
「これね、暗いところでは茸のところが光るんだ、昼間は椎茸のように見えるが、夜は青白く光るんだ、夜光茸だよ、五年経つと、本会員の網笠茸のバッチになるんだよ」
彼は楽しそうに言った。
網笠茸は私も知っていた。フランス料理の好きな人につれられてレストランに行ったら、網笠茸のスープがでてきた。
「その会のメンバーは何人くらい」
「よくわからないけど、三十人くらいらしい、年に一人か二人新しい人が加わるので、やめる人もいるから、いつもそのくらいらしい」
「本会員は何人くらいなの」
「半分ぐらいだって」
「十五人くらいか、へーなかなか厳しいクラブだね」
「きっと、途中でやめるからじゃないかな、俺はがんばるぜ」
「どんな駅で試験を受けたんだ」
「ラッキーだった、富山だよ」
「鱒すしか」
「そうだったんだ、あの婦人が話してくれた紳士が待っていたよ、駅から出てちょっと歩いた和食屋に連れて行かれた、そこで弁当を渡された、弁当の絵を見たら、鱒の絵が描いてあった、要するに有名な鱒ずしだよ、食べてみた、鱒寿司そのものだった、ただちょっと茸の匂いが強かった」
「あの丸くぎっしりと詰まって、上に鱒が敷き詰められているやつか」
「いや、四角い押し寿司のようだった、あの有名な丸いのと違って、お新香がついていた。それに、姫リンゴがあった」
「それで茸は何だったのかい」
「匂いを知っていたんだよ、秋田の旅館で食べたことがあるのでわかったんだ、ちょっと人参をぬか噌漬けにしたような色をしていてね、鱒寿司の色だよ、鱒の肉の色」
「そう言われても俺にゃわからんな」
「そりゃそうだね、薄橙色のマスタケという茸があってね、そう言ったら、合格だった」
「ともかく、よかったじゃないか」
「ああ、あの婦人の話も役に立ったよ、イカめしにイカタケだもんな、鱒すしにマスタケ、以外と楽だった、あとは五年がんばって、本会員になるよ」
そんな話だった。
次の一年間、彼は草片駅弁の会に参加したあとは、必ず茸弁当のことを話してくれた。秋田湯沢駅では頬紅茸の炊き込みご飯がおいしかったとか、山梨の小淵沢駅の茶碗茸の佃煮は絶品だとか、長野の伊那駅の桜肉緋色傘ステーキはワインに合うとか、色々聞かされた。
ところが、彼の死体が白馬の麓を流れる川の河原で見つかったのだ。やはり三日の休暇をとったあとだ。地元の警察の調べでは、毒茸中毒と言うことだった。茸が良く生えるので知られていた林に連なる川原だそうである。
彼の死は家族から会社に連絡がきたことで知った。神奈川の厚木にある彼の実家へ、葬儀に行ったのだが、家族と話をしていて、私にはなにか腑に落ちおちないものがあった。しかし両親も妹も茸中毒であったことを疑っている様子はなかった。彼は家族に茸の食べ歩きのことをよく話していたという。それで両親はいつも毒茸には気をつけなさいと言っていたそうだ。長い付き合いのある私には彼がそんな不用意な人間ではないことを知っている。彼の性格は石橋をたたいて渡るほうだったからだ。
「どんな茸を食べたのか、お聞きになりましたか」
私は妹さんに聞いた。
「はい、一応事件なので、厚木暑から刑事さんが見えて、秋田の湯沢暑からの連絡では、胃の中に消化された茸の残骸いくつかが残っていて、複数の茸に含まれる毒物が検出されたということだそうです、秋田小町の米や山菜のたぐいも残っており、自分で採った茸とともに食べたのだろうということでした」
妹は返されたリュックと、飯ごう、固形燃料などを見せてくれた。
私はふっと思って聞いた。
「財布なども残っていましたか」
妹さんは、怪訝な顔をして、「はい、もちろん返してもらいました、旅行のためのお金や、カード、いくつかの領収書、身分証明書、などがはいっていました」
「一人旅だったのですか」
「はい、警察の方はそう言っていました」
「会員証のバッチなどははいっていませんでしたか」
「なにの会員証でしょうか」
「駅弁の会に入ってましてね、見せてもらったことがあるので」
「いえ、バッチ類はありませんでした」
本当に一人旅だったようだが、今まで彼からは採った茸を自分で料理をして食べたということはことを聞いたことがない。食べることは好きだったが、普段は自宅で料理することはしていないようだった。今回の旅は駅弁の会とは関係なかったのだろうか。たとえ関係がないにしろ、草片弁当愛好会に準会員にしろ入れたのをあれだけ喜んでいたのだから、バッチはもっていたのではないだろうか。
彼のご家族には自分の感じた疑念のことは伝えなかった。伝えると迷惑になるかもしれないと思ったからだ。とりあえず、私の胸のうちにしまっておくことにした。
彼の死が一年前のこととなった秋である。大学の卒業十年のホームカミングデーに参加したとき、学科の仲間の二人の死を聞いた。事故死だという。一人は交通事故死で、もう一人は食中毒ということだった。学科には百人近くの同期生がいる。集まると必ずだれだれかが亡くなったという話を聞く。その二人は学生時代あまりなじみのない男だったこともあり、二人の顔も思い出すことができない。ただ食中毒死した男を知っているという同じゼミの友人がいた。彼があいつは毒茸に当たって死んだんだと言った。それを聞いてどきっとした。
私は彼に聞いた。
「そいつとどこで知り合ったんだ」
「サークルが一緒だったんだ」
「確か野草を食べる会だったよな」
「ああ、春は山菜とり、秋は茸狩りによく行った、普段は、大学の回りの道を歩いて、食べられる雑草をとってきて料理をしたものだよ、俺はアパート暮らしだったが、そんな知識でも役に立つもので、野菜を買わないですんでいたんだ」
「亡くなったやつとは、卒業してからも会ったことがあるのかい」
「うん、あいつも塾の講師、俺もそうだからな、違う塾だったが、たまに情報の交換をしたよ、あまり表立って言えないがな」
「茸の弁当を食べる会って知ってるかい」
「え、おまえ知ってるんだ、珍しい会だから知っている人なんかほとんどいないよ」
「いや、知り合いがはいっていたからな、まさかその人もはいっていたんじゃなかろうな」
「ああはいっていた、自慢していたよ、茸が好きな男でね、あいつは青森出身だったんじゃないかな、初めは大きな駅弁の会に入っていたけど、その会員から話を聞いて、やっと茸駅弁の会に入れたといって喜んでいたよ、試験があるそうで、それを一発で通ったと言っていた」
あいつと同じだ。
「亡くなったのはいつだっけ」
「三年前だ、その一年前にその会に入ったと言ってたな」
私の会社の友人より前の話だった。
「なあ、その大きな駅弁の会の名前はごちそうの会で、茸の弁当の会は草片駅弁愛好会じゃないか」
「そうだよ、よく知ってるな」
「七宝焼きのバッジをみせられたろう」
「ああ、きれいなバッジだった、五年経つと正会員になれると言っていた」
「その人はごちそうの会で、年のいったご婦人から茸弁当の会に誘われたんじゃないか」
「そんな話をしていたよ、どうして知ってるんだ」
「いや、俺の知り合いも入っていたんだ」
私はクラスメートに同僚の死のことを話した。
「同じような状態だな、ちょっと気味が悪いな」
「君もその会にはいっているのかい」
「いや、俺はごちそうの会には入っているが、草片駅弁愛好会には入ってない」
「そうか、ごちそうの会には彼と一緒に行ったりしたのかい」
「うん、あいつは埼玉の会で俺は東京だけど、お互いに何回か一緒に参加したことはあるよ」
「茸の駅弁会を紹介したっていう婦人には会ったことがないよな」
「うんないと思う、一緒に参加したときに、彼はまだ茸の駅弁の会に入ってなかったな、その婦人もいたのかもしれないけどね」
同じゼミの塾講師とは名刺交換をして、いつか飲もうと約束をした。東京の名のしれた塾で、それなりの地位にいるようだった。
それからも、なんだかもやもやして、気が晴れなかった。やパリはっきりさせたい。そう思った私はそいつに電話をいれた。
「ごちそうの会に会員じゃない者が一緒に行くことはできないかな」
「できるよ、同伴制度があるよ、ただ非会員料金になるから、参加費が必要になるけどね、高いものじゃないよ、弁当代が二千五百円、参加費千円だから会員より千円高いだけだ、みんなと一緒に弁当を食べた後は自由行動だよ」
「いつかつれてってよ」
ごちそうの会は毎月やっていて、近場で日帰りもあるということだった。必ずしも駅弁とは限らず、個性のある弁当屋の弁当を食べることもあるようだ。
それで小田原でやる会に連れて行ってもらうことにした。小田原の会は駅弁というより、特別弁当で、なんでも年に数回しか作らないというものだそうだ。弁当はいつもより高く、三千円で、参加費千円なので四千円払った。お昼に三千円の弁当とは贅沢である。
小田急小田原駅改札口で落ち合った友人は、
「今日の弁当はタカアシガニ弁当だから高いんだ」と言った。
タカアシガニというのも始めて聞いた。毛ガニ、タラバガニ、それにズワイガニぐらいしか知らない。
「どんな蟹なんだ」
「店に行けば分かるさ」
駅に近い料理屋の入口をくぐると、タカアシガニの姿がわかった。壁一面に足を延ばした蟹の標本がかけてある。二メートルもありそうだ。でっかい。
「世界で一番大きな蟹だ、それが相模湾にいる、そいつを食うんだ」
参加者は想像していた人数をはるかに超えていた。五十人もいただろうか。広い座敷に細長いテーブルが二列にしつらえてあり、すでにお重が並べてある。好きなところに座れるということなので、あたりを見回して、真ん中辺りに友人と並んだ。斜め前ほどに小太りの白髪の婦人がいたからだ。死んだ友人の話に出てきた婦人と雰囲気が似ている。友人に耳打ちをすると、そうなのかとうなずいた。
ほどなく参加者がそろい、会長の挨拶のあと、タカアシガニ弁当の蓋を開けた。酢飯の上にタカアシガニの身をほぐしたものが敷き詰められている。確かに贅沢であるが、見た目には高足蟹という証拠がない。
口にいれた友人が「オー、これが高足蟹か、うまい」と声を上げたものだから、みんなが彼に注目した。恵比寿さんのような顔をした白髪のその婦人も笑いながら彼を見た。
私も口に入れた。確かに旨い。声を上げてもいいくらいだ。しかし食べ物音痴の私には、タカアシガニなのかズワイガニなのか区別がつかない。
食べていると、大きなお椀にはいった蟹の味噌汁が配られた。足の一部が入っている。そっちの方がタカアシガニという実感が湧いた。うまい汁である。
食べ終わり、お茶がでて、テーブルの前の空の容器が片付けられると、自由懇談になった、知っている同士集まって話を始めた。すぐにあの婦人が友人の隣にやってきて「おいしかったですね」と声をかけてきた。
「うまかったです」
「たまにお見かけしますね、会員の方でしょう」
「はい、彼は大学の時の同級生で、会員じゃないのですけど、この会に興味を持って今回参加しました」
彼が私を紹介したので、私は愛想良く挨拶をした。
「タカアシガニのお弁当、普通じゃ食べられませんよね」
婦人は私にそう言ってから、彼に「茸はお好きかしら」と聞いた。
「ええ」彼は嬉しそうに答えていた。それからの婦人の会話は、なんと、ほとんど死んだ同僚が話してくれたことと同じだった。塾の講師の彼に、自分は草片駅弁愛好会の試験を長岡駅で受け、イカめし弁当の茸をあてられずに落ちたという話だ。彼に茸弁当愛好会の人を紹介すると言っている。
二人の話が終わりに近づいた頃、私は妙なことに気がついた。藤色の洋服を着ていた婦人のエリに七宝焼きの網笠茸のバッチがついている。このバッチは正会員じゃないともらえないはずじゃなかったか。この人は試験に受からなかったと、隣の彼にも今言っていたじゃないか。そんなことを考えていると、解散の時間になった。
「それじゃ、連絡をしてもいいですか」
友人が婦人に電話番号を聞いている。
「ええ、是非入会して欲しいわ、私もまたトライするから」
その婦人はそう言って、立ち上がった。
「ありがとうございました」
彼がそう言ったので、私も彼女におじぎをした。
「またお会いしましょう」
その婦人は会場から出て行った。
小田原駅に行く間に彼は茸の会には無理だなと言った。次の入会試験の駅は富山で、日曜日なのだが休めないそうだ。時期によっては全くまとまった休みなどとれないほど塾の講師の仕事は忙しいという。
小田原の駅弁の会のあと、しばらくして、塾講師の友人からおかしなことを聞いたと電話があった。
「あの死んだ同じゼミ生の婚約者だったという女性から連絡があってね、いろいろ聞いてきたんだ、何でも一年後に結婚する準備をしていた矢先の出来事だったそうだ」
「もうだいぶ前の話だろ、なぜ今頃連絡してきたんだい」
「彼女が彼の葬式に青森の実家に行ったとき、両親は大学の同級生か仕事の仲間かと思って、詳しい話をしなかったようだ、彼は彼女のことをまだ両親に話してなかったのだろう、その時、彼女も気持ちの整理ができていなくて、婚約者であるとは名乗りでなかったようだ」
「君も知らなかったのかい」
「うん、聞いていなかった、ところが、最近になって、両親が彼の遺品である本の中に彼女の写真が入っているのを見つけたそうだ、名前と携帯番号が書いてあったそうだ。茸の好きな彼はよく山登りをするので、山の本をよく読んでいた。その本は高校生の時からもっているお気に入りの本だったという。白馬に関する本だそうだ。両親は写真の女性は誰だろうと気になった、それで彼女に連絡をしたわけだ。そこで、彼が約束をかわした女性であることがわかったんだ。何でも白馬に登っているときに出会って意気投合したらしい、それならばと、両親はよかったら何か思いでのものでもどうかと聞いた。彼女は彼がいつも使っていたサブザックが欲しいといったら、すぐに送ってくれたという。
ところがいつも彼が使っているものとは違うので、両親に電話で聞いたようだ。そうしたら警察から遺品として届けられたものだという。それでおかしいと思って、彼女は警察に問い合わせをしたら、茸を料理して食べたところで、倒れていた彼の脇にあったもので中には彼の物が入っていたので両親に渡したということだった」
なんだか同僚の時とよく似ている。
「それで、彼女は彼の死に不信をいだいたということだね」
「そうみたいだ、もう彼のことはあきらめたけど、毒茸を食べて死ぬような人じゃないから、本人のためにはっきりさせてあげたいと言っていた」
そのためには草片駅弁愛好会のことを調べなければならないだろう。同僚や大学の同期生の死はこの会に関係がある。だんだんそう思えてきた。あの婦人は正会員なのに、なぜ同僚や大学の友人には落ちたと言ったのか、小田原の会では友人を誘うため全く同じ話をしていた。そう言えば、次のテストの駅は富山だと言っていた。同じパターンじゃないか。そこではっと思った。ねらった男を茸の会に受かるように仕向けている。
何のためだろう。茸の駅弁の会は年4回と言っていた。それ以外に不定期の会がある。その話を聞いたとき、私は不定期の会が、変わった茸を食べてみる会ぐらいにしか考えなかったが、ひょっとすると、もっとこわい裏があるのじゃないかとの疑問が湧いて来た。
その会の正体を調べるためには会にはいらなければわからない。草片駅弁の会は入会者を増やそうとしている、といって誰でもいいわけじゃないようだ。やはり茸を食べるのが好きでたまらない人でなければだめだろう。私は無理だ。何しろ茸のことはなにも知らない。
同僚が死んで二年、私も手をこまねいていただけではない、ネットでもその会を調べたし、いろいろ当たった。ところが、草片弁当愛好会はまったくサーチに引っかかってこなかった。秘密クラブだ。それにしてもごちそうの会の婦人は秘密めいた感じがなく、よくいるおばさんだったのだが。
亡くなった同期生である塾講師の婚約者に会う必要があるのじゃないだろうか。そう彼に電話をしたら、
「そうだな、一度みんなで話すと、なにかでてくるかもしれないな、幸いなことに彼女は東京に住んでいるから、連絡してみるよ」との返事だった。
それから間もなく、すぐにでも会いたいと連絡があり、新宿で落ち合うことになった。
その女性は話してみると、静かなたたずまいとは違い、心身ともに強い女性だった。趣味はボルダリングで、足腰を鍛えるために、会社の休みには山登りに行くという。
「あんなに慎重な人が茸にあたるなんて信じられないわ、山に登っていても、ちょっと雲ゆきが悪そうになると引っ返すのよ、一緒に茸を採ったこともあるけど、よく知っている茸しか採ろうとしなかったわ」
「草片駅弁愛好会について何か言っていましたか」
「あの会に入れたのは光栄だって喜んでました」
同僚と同じだ。
「ごちそうの会はやめたのですか」
「ええ、すぐやめました」
同僚もそうだった。
「そのおばさんは両方入っているんじゃないですか」
「いえ、そのおばさんは草片弁当愛好会にはまだ合格していないので、彼は自分だけ受かって申し訳ないと思っていたようです」
同僚もそう思ってごちそうの会をやめたのかもしれないが、あの婦人の襟元には正会員のアミガサタケのバッチがあった。
「これからどうしましょう、まず草片駅弁愛好会をもっと調べなければなりませんね」
「私は茸のことはよくわかりません、本当はその会に入って、誰かに彼のことを聞いてみたいのですけど」
私と同じ状態だ。
「茸の詳しい人に調べてもらうのがいいですね、私も茸はよく知らないのです」
そのとき、同級生がこんなことを言った。
「野草を食べるサークルに茸にめっぽう詳しい奴がいたな、そいつは法学部で、あれからずいぶん司法試験にトライしていたが、六回目であきらめて、いま秋田で探偵をやっていということだった、あいつに相談するのもいいな」
「でも、探偵を雇うってお金がかかるんだろう」
「いや、同じサークルだから、その辺は何とかしてくれるさ、大学時代にはよく飲んだ仲間だよ、調べてみたいというかもしれない。草片駅弁愛好会のことをいうと、自分も入りたいというぞ、茸好きのあいつなら」
「ホームカミングデーには来ていなかったのかい」
「うん、秋田からは大変だよな」
「もし調べてもらえるなら、ごちそうの会に入ってもらって、その婦人とコンタクトをとるようにしてもらおうよ」
「探偵さんどこに住んでいらっしゃるのかしら」
「秋田の十文字」
「遠いな」
「野草の会同窓生のラインで調べていくと彼の探偵事務所が分かるかもしれない」
「もしその人が入ったら、俺も一緒にごちそうの会に加入して、お手伝いするよ」
私も何かしなくてはと思っていたところである。
「私もごちそうの会に入ります」
彼女も本気のようだ。
塾講師のクラスメートが探偵に連絡をとることになった。
それから一週間、塾講師の同級生からメイルをもらった。秋田の探偵と連絡がついて、野草の会の彼が毒茸でなくなったことを話し、我々の状況のことを説明すると、是非調べてみたいという返事をもらったということだ。彼の探偵事務所は十文字調査局と気取った看板をかかげているということだった。
野草の会の死んだ彼の彼女や私にも探偵からメイルがきた。死んだ彼は学生の時、秋田の探偵の実家に泊まりにきたこともあるということだった。お互い茸好きだったこともあり、探偵の家の近くで茸狩りを楽しんだという。
探偵はごちそうの会の秋田支部に入会した。もちろん私も彼女もごちそうの会に入会した。東京支部会である。しかし、どこの駅弁の会にも参加できる。まだ探偵に会ったことがない。一度会いたいと思っていたところ、ごちそうの会の秋田支部の会が湯沢で行なわれると探偵から連絡が来た。探偵の住んでいる十文字は湯沢の隣である。会社の同僚が死んだところである。
幸い我々三人も都合がつき参加することにした。
秋田新幹線で大曲まで行き、奥羽本線で湯沢駅にでる。4時間以上かかった。ずいぶん遠い町である。電車賃が馬鹿にならない。湯沢というと、スキー場でよく知っている新潟の湯沢を思ってしまうが、それは越後湯沢で湯沢町である。秋田の湯沢も雪の多いところだが。湯沢市であり由緒ある城下町だ。爛漫や大関の本舗があり、稲庭うどんや川連漆器も有名で、小野小町が住んでいたそうで、美人の産地とパンフレットにある。
駅の二階にある改札口をでると、探偵が待っていてくれた。彼はなかなか精悍そうな身体つきの男で、テレビ映画に出てくるようなタイプである。挨拶をすると、全く秋田なまりがなかった。
「僕はここの生まれだけど、高校からは東京で一人暮らしだったものだから、このあたりのことは中学までの思い出です、ただ、両親はここにいて、代々の屋敷があるもので、戻ってきたってわけです、それでまあ、探偵事務所をひらいたわけですけど、刑事事件などにはあまり縁がなくて、家庭内争議の調停ぐらいですね」
優雅な身分である。
「それじゃ、会場にいきましょう」
我々は駅舎から出た。駅前の広場を通り、駅の真正面にある中央通に入ったが、閑散としていて、過疎が進んでいることを感じざるをえない。
会場は駅から歩いて数分のグランドホテルでおこなわれる。ホテルの中には歓迎ごちそうの会一同様の看板が立ててある。
その日の会は、湯沢の駅弁を食べるのではなかった。湯沢駅には駅弁というものがない。その日のために、ホテルが特別に用意した弁当を食べるというものだ。湯沢特産の皆瀬牛をつかった弁当とか、小安の天然茸の弁当、稲庭うどんの弁当、山菜弁当、蕗弁当、じゅんさい弁当などで、それなりに楽しめそうであった。日本酒、ビールは飲み放題である。
会場が開くまで、ロビーで探偵さんと話をした。
「電話で彼の話をきいたら、こりゃ何かあると思いましたよ、彼は茸がすきでしたね、学生時代にこちらにきたとき、毎日茸採りで楽しそうでした。大学を離れてからはお互いの道にはいってしまったので、連絡しなくなってしまいましたけど、年賀状はやり取りしてました。彼は数字にめっぽう強くて、きっと大企業に入ってそれを生かすと思ってたのですが、塾の講師になっていたのですね」
彼女がうなずいた。
「彼の話では、大企業だと山に登れなくなるから、塾の講師になって、時間を作るんだといっていました、だけど結構忙しいと言ってました。将来は山小屋で働くつもりだったのです」
「僕も塾は時間があるものと思ってたんだけど、経営に加わってしまったから、時間がとれなくなってしまったんだ」
塾講師のクラスメートもうなずいた。
「確かに私のような企業に入ると、本格的な山登りなどはできませんね、なくなった同僚のように駅弁の会に出席するため三日ほどの休みならとれますけど」
「それで、もし、私がうまく草片駅弁愛好会に入れたら、探ってみましょう、茸は好きですからね、何もでないかもしれないけど、何か分かったらお三方にメイルで知らせします」
「草片駅弁愛好会に入会をすすめる婦人がいつの会に参加するかわかりませんから、時間がかかるかもしれませんね、今日いるかどうかわかりません。何せ遠いところですから」
「どこの所属だかわかっているのでしょうか」
「おそらく東京だと思いますが、最近個人情報の保護がきびしくて、参加者に配られるのはカタカナの名前と所属支部名だけです、埼玉、神奈川、東京の支部会では見かけましたが、今回どうでしょう」
塾講師の彼もそう言ったが、探偵の推理は違った。
「いや、わかりませんね、俺の勘では、湯沢のこの辺りも茸がよく採れるところ、その婦人とやらは、あなた方、関東の会に参加するほうが少なくて、茸の採れる秋田、長野、群馬などの方が活動拠点もしれませんよ、茸仲間を呼び込むにはそのほうがいい」
確かにその通りだ。
婚約者が死んだ彼女は詳しい状況を話し、私も同僚の死の状況を話した。
そろそろ会場が開く時間である。
「みんな同じくらいの年だから、大学の茸の会のサークルということにしよう」
探偵さんが提案したのだが、私には茸の知識が全くなく、かなり不安であることを言った。彼を亡くした彼女は意外にも茸には詳しいようだ。山登りが趣味だと植物や茸の知識もおのずから増えるらしい。
「我々のサークルはいろんな人がいて、茸を食べるのが好きな人もいていいじゃない、食べられる茸ならちょっとは知ってるでしょう」
私はうなずいた。
いつもは結婚式場になる大きな宴会場が会場である。
開催三十分前に扉が開かれ、我々は中に入った。配られた名簿をみると五十人ほどの参加者だ。結構な人数だ。関東から来たのは我々三人だけで、あとは近くか、遠くて青森支部や山形支部である。
十ほどの丸テーブルの上に弁当が並べられ、番号がふってある。ビンゴで席を決める予定だったとのことだが、五十人も集まるとは像蔵していなかったようだ。くじを引く形式になっていた。ひいた番号のところにすわる。みなばらばらになる。
まだ参加者は数人しか来ていない。とりあえず、自分の番号のところに座った。手持ち無沙汰だと思っていたのだが、参加者はどっと入ってきた。どうも電車が到着したようだ。すぐにいっぱいになった。
あ、いた。白髪で小太りの夫人が探偵の隣のテーブルすわっている。今日はブルー系統の洋服を着ている。塾講師の同級生と私はあの婦人に会ったことがある。塾講師の彼も気がついて探偵にうまく伝えてくれた。
私は小安の茸弁当、塾の彼は皆瀬牛弁当、彼女は稲庭うどん弁当、探偵さんも皆瀬牛弁当だった。
司会者が言った。
「みなさん、お弁当の前に正しく腰掛けられましたか、あと十分ほどで、食事を開始していただきます、それまで、お隣の方などとお話をなさってください、コミュニケーションタイムです。当たった弁当を他の弁当と取り替えたい方は、みなさんに呼びかけてください。このマイクをお使いになってもいいですよ」
山菜弁当を食べたいが、自分の皆瀬牛の弁当と取り替えてくれないかという申し出のおじいさんがマイクを受け取った。一人の青年が「いいよ」と声をかけ商談が成立した。
次は若い女性が、蕗が食べたいので、入った弁当があったら取り替えてほしいと訴えた。その間にお茶と茸の吸物が配られた。稲庭うどん弁当の人には、吸物のかわりに茸飯が置かれた。
ごちそうの会秋田支部の支部長が挨拶を行い、湯沢市長から日本酒の提供があったことを告げた。
司会者のどうぞという声でみな一斉に弁当を開いた。
隣のおじさんは天然茸駅弁を開いた。こんもりと舞茸、占地、栗茸、ムキタケ、平茸の煮しめがのっている。「いいのにあたった」と食べ始めた。お酒をもらっている。
私も同じものと思ったが違った。茶飯の上に見たこともないような茸がいくつも重なるようにして敷き詰めてある。醤油味だ。なかなかうまい。反対隣の皆瀬牛弁当を開いた人を見ると、弁当一面にステーキ牛と茸のソテーが引きつめてある。うまそうだ。稲庭うどん弁当は大きな塗りのお椀に暖かい稲庭うどん、その上には、これまた、色々な茸がのっていて、茸飯は大切れの松茸の茶飯だった。ごちそうの会だけはある。私はビールをもらうことにした。
あつあつの吸物もまたとてもおいしい。中には本占地が入っている。本占地は香り松茸味占地、のその占地で、天然物しかなく、なかなか採れない茸だそうだ。
仲間はどうしているか。それぞれ隣の人と話をしたり、結構楽しんでいるようだ。
探偵さんは隣のテーブルのあの婦人の弁当をのぞき込んで、なにやら言っている。婦人のほうからも彼に何か言っている。婦人は探偵に目を付けたようだ。
隣の男性にきいた。
「この会は初めてなのですが、お弁当を食べた後はなにかするのでしょうか」
「いや、これでおしまいでだあな、はじめからここからどこかに観光に行く計画をたててから来ているんだなあ、あたしもこれから小安で一泊して、湯に浸かるつもりだよ」
「この会にはよくこられるのですか」
「うん、ここで気が会ったのと、なんか見に行ったりするな、うまい弁当を食べて、それからが楽しみだよ、前の会は男鹿であって、湯も良かったが海もよかった」
「そうなんですね、楽しいですね」
「うん、母ちゃんが二年前に死んでね、その前はいつも二人だったが、ひとりになっちまった、だけんど、この会のおかげで、外にでられるね」
確かにいいきっかけだろう。
「お兄ちゃんはどこかいくんかね、このあと」
「ええ、大学の時の茸のサークル仲間と来てますので相談します」
「せっかくきたのだから、そうするがいいよ」
係りの女中さんが、温かいお茶をいれにきた。そろそろおわりである。
探偵が立ち上がって私の脇を通った。
「こっちを見ないで、また連絡します」と小声で言うとトイレに行った。
私は友人と彼女のところにいって、探偵が言ったことを伝えた。立ち上がったついでに、婦人をいれて、周りの写真をとった。
トイレから出てきた探偵はあの婦人と供に会場を後にした。
我々はすぐ帰ることになる。せっかくここまで来てもったいないが、ホテルのラウンジで飲み物を頼み、帰りの電車の時間まで過ごした。探偵と婦人はどこに行ったのだろう。
それから二日後、みんなに探偵からメイルがあった。
草片駅弁愛好会に準会員で入会したということである。婦人の言うことを聞いて、試験を受けて、簡単に入会できたという。やはりあの婦人は勧誘員である。名前は東京支部のイヤマサエコということだけはわかったと探偵は書いてきた。
探偵は不定期に行われる会にでることになったという。場所は富山の立山ということだった。何をするのかまだわからないとあった。
我々は探偵からの次の連絡を待つことにした。
立山の会に参加した探偵は、すぐに参加者の人数や様子などをネットで送ってきた。写真も添付されている。イヤマサエコはいなかったという。立山では見たこともない茸を食べさせられたと、茸の写真もあった。結論としてはその一度では会の様子はつかめない。何度か参加すればわかるだろうとあった。
それからは草片弁当愛好会に出席するたびにメイルで連絡をくれ、その概要を教えてくれた。
それから一年経ち、探偵から詳しい話が聞けた。
「わかりましたよ、ちょっと大変な目にあった、皆さんに直接話したいですね」と連絡があった。我々三人で彼の宿泊代と電車代をもつことにして、東京に出てきてもらうことにした。
出身大学の近くにある小さなイタリアンレストランで彼を囲んだ。
「草片駅弁愛好会は入口です、全会員はだいたい五十人前後、そのうち正会員は十五人、準会員は三十人ほど、名簿はありません」
これは大体知っていた。
「全国の会員数ですよね、かなり少ないですね」
「もっといても不思議ではないんですけど、準会員になれてもなかなか正会員になれないからだろうと思ってます」
「それにしても少ないな、会費や参加費は高額なのではないですか」
私は不思議に思った。
「ところが、会費はごちそうの会とあまり変わらないんです、そこは奇妙だなと思って、調べてみたけど、どうもはっきりしない」
「誰かが費用をもっているのですね、準会員になるのに試験をしたり、正会員になかなかなれないとなると、会を運営している人の目的はなんでしょうね、あのイヤマサエコという婦人とはどんな人でした」
「普通のおばさんでした、茸はとても好きなようですね、みんなに入って欲しくて仕方がないといった様子です」
私は気になっていたことを探偵にたずねた。
「あの人は会のどのような人なのでしょう」
「うーん、勧誘員かもしれないのですけど、よくわかりませんね」
「私の彼は準会員でした、それでもどってきたザックが彼のものでなかったことの原因も分かりましたでしょうか」
「ええ、順を追って説明しますね」
「草片駅弁愛好会の準会員なったので、今まで4回の定例会すべて参加したんだけど、それはなかなか楽しかった、こんな駅でこんな茸が採れて、こんなおいしい弁当になるんだというものでしたね」
会の雰囲気ついてはメイルや電話の連絡ですでに感じていた。
「亡くなられた知り合いの方も楽しまれたことと思います」
そうでなくては救われない。
「定例会以外に行われる不定期の会は、準会員が正会員員になる場でした、参加者は新しく準会員になった人だけ、そのときは十人だったかな、ホテルに二泊して、朝昼晩と会食をしました。朝の食事は茸サンドイッチ、茸オムレツ、茸サラダ、茸ジュース、茸入りヨーグルト、昼は、茸そばかうどん、それに茸の天ぷら、夜は、洋食組は茸と牛肉のグリル、茸サラダ、茸スープ、茸と魚のホイル焼き、和食組は茸めし、茸の茶碗蒸し、茸の煮物、茸汁などいろいろでまして、それは美味かった」
「なかなかすごいメニューですね、参加費は相当高いでしょうね」
「二泊宿泊代込みで一万円だからとても安かったんです」
「どんな茸を使うのでしょう」
「そこが問題、食事はとてもいい、ところが、二日目の朝食を食べた人の中にお腹が痛くなった人が五人でた、参加していた運営幹部の三人とも医者でした。薬を持ってきていて、すぐ処方してくれました。頭痛や吐き気を感じた人も数人いましたけど、その人たちもその医者に診てもらった。夜の食事のあとは全く自由なので、詳しくはわからないが、夜中に何人か薬をもらったようでした、自分は全く大丈夫でした。
次の朝、会が解散するときに、司会者からこのような説明がありました。
朝食で茸に当たった方がいらっしゃいますが、食べた茸が体に合わなかったか、本人の調子が悪かったためだと本会の医者が申してます、美味しい茸でもからだにさわることがあります。自分のからだを知っていただきたいと思います」
さらに開催責任者にかわって、
「この会は時として一般には毒茸と言われるものでも、毒消しを施し食べることがあります。こういったこともありますので、今回具合が悪くなられた方は、私どもの責任もありますので、医療に関してはご相談願います、薬は無料で処方いたします。これからも準会員として楽しまれてください」
さらに、「こちらで大丈夫と思われる準会員の方には、正会員になるのにもう一度不定期の会にでていただいて、どのような茸でも食べられるかためしていただきます」
そう言ったんです。
「どのような茸でも食べられる人が正会員になれるということですね、あなたは大丈夫だったんですね」
彼女が探偵に言った。
「全く問題なかったですよ。それで、幹部から誘われたこともあり、四ヶ月後の二度目の不定期の会にもでました、会費なしです。参加者は前回の不定期の会で茸にあたらなかった三名です。」
「それはどこで行われたのですか」
「長野の松本で二泊の会でした、我々参加した三名の準会員は、食事が始まる前に、司会者から早くも本会員に推挙されたことが告げらみな喜びましたよ、ただ、その場で血液検査をさせられたのには驚いた、やっぱり会の医師が採血をして、夕方にはその結果を夕食前に司会者が我々につげ、問題ないということで正会員資格者になったわけです。きっと、亡くなったお二人も、ここまではいったのだと思いますよ。
その夕食には特殊な茸料理がでるということで、それを食べる前に、薬を飲まされました。ちょっとびびりましたね、司会者の話では、茸が美味しく感じられ、かつ、茸毒に対して強くなる薬で、副作用はないということでした。毒に強くなるなら、むしろありがたいと、みんなその錠剤を飲みました。おかげかどうかわかりませんが、夕食にでた茸をすべて食べましたが、なんともなかったです。次の日も変わった茸の料理がでて、二泊した朝にもう一度、血液を採取されました、そうして正会員になったというわけです、それがおわったとき、茸の採集に使う道具などが入ったリユックをもらいました、あと食事の前に飲んだ薬もくれました、半年は飲み続けて欲しいということでした、毎日夜に一錠です、毒茸に抵抗がつくという話でした」
「彼から薬のことや正会員なったとは聞かなかったわ」
「同僚もそう言ってなかった」
「正会員のバッチはその場ではもらえないんです、儀式のようなものがありましてね、それは茸バーベキューハイキングって呼んでました。新しく正会員に認められた三人は、幹部の人と組んで、二人でどこかにいって茸バーベキューをしながら、幹部から正会員の決まりごとなどを教わらなければならないんです、バーベキューが終わると、バッチをわたされるということになります。茸バーベキューハイキンニはもらったリュックでくるようにという指示がありました」
「彼もそのハイキングにいったんだわ、それで残されていたリュックが彼自身のものじゃなかったわけね」
彼女も理解できた様子でうなずいた。私も少しわかってきた、
「不定期の会で正会員になった後、草片駅弁愛好会の幹部という人からメイルをもらいまして、茸バイキングに行く日を決めました、行くところは先輩の指図なので自分で決めることはできません。行ったのは長野の八ヶ岳の麓だしでした。俺にとってはずいぶん遠いので大変でしたが参加しました。待ち合わせは小淵沢の駅で、幹部の人が車で迎えに来てくれました。長谷さんと言いました。頼りになりそうな四十代前半の男性です。
山間の小さな道をいき、車を降りて、流れに沿って歩きました。かなり上流にいって、河原でバーベキューの用意をして、二人で山に入り茸を採りました、長谷さんが持ってきた茸といっしょに炭火で焼いてくれました、彼のもってきた茸が見たこともないものでした、何ですかと聞いたら、外国産の茸で滅多に食べることができないものだといっていました。長谷さんはビールまで持ってきてくれていて、茸を焼きながらビールを飲んだわけです。
長谷さんは、正会員になると、世界中の知られていない茸を食べることができるといっていましたね。正会員だけの特別な会が別にあるようでした。もちろん俺はまだ参加したことがありません、彼は外国の茸のことをよく知っていて、茸の経験談はとても面白いものでした。二本めのビールを飲み終わったときに大変なことが起きました。いきなり胸が苦しくなり、意識がもうろうとしてきたんです。俺は河原に倒れ込んだ。彼があわてて私の腕をまくり注射をしたのは覚えています。そのときこの人は医者だなと思いました。
体が動かなくなり、目もぼやけてしまったが、耳は聞こえていました。長谷さんが携帯をかけていました。彼は俺が聞いているとは思っていなかったようです。こんな話をしていたんです。
『彼がくたばりそうだよ、一番期待をしていたのだがな、遺伝子はよかったんだろ、そうか、かなり茸毒に強い体質だよな、え、茸は熱帯の毒茸を食わしたんだよ、あの薬は効かなかったようだよ、もし死んだらこれで何人目だ』
間をおいて、
『え、昨日一人死んだの』
長谷さんは私と一緒に正会員になった人の名前を言った。
『こっちの人は吐き気を起こす薬と、アドレナリンを打ったよ、まだ生き返る可能性はあるよ、どうしても生かせって、会長が言ってるのか、頑張るよ』
そのとき急に腹がむかむかして、がーっと胃のものが口に戻ってきてはいちまいました。そこで意識がなくなりました。
目を開けると病院の中でした、長谷さんがそばにいて『気がついてよかった、茸中毒ですよ、最後まで治療の面倒を見ますから心配しないで下さい』そう言って、私の目をのぞきこみました。
それからすぐに気分は良くなったのですが、一日ここに泊まって確実に直してくださいといわれ、明日家まで送ってくれると、長谷さんがいいました、秋田まで車で送ってくれたんです。
病院から出たとき、どこだろうと建物を見ました、かなり大きな病院でしたね。だけど病院の名前はわからなかった。車の中からちらちら見えた景色からすると、病院は中央自動車道の通っている山梨か長野のようでした。
家で車を降りたとき、家族にも、これからは責任を持って治療に当たります、と運転手が言ったそうです」
「車に病院の名前がはいっていませんでしたか」
「黒塗りのセドリックだったけどどこにも病院名は書いていませんでしたね」
「病院の車じゃない可能性がありますね」
「そうですね、運転手は相当なプロで、一匹狼として雇われているのかもしれないですね、それで、われわれはモルモットだったことに気がつきました、茸駅弁の会を利用して、茸毒に強い人間を集め、遺伝子に作用する薬を開発して、茸毒にたいする抵抗を強めようとしていたのだと思います」
「そういった人に有益な研究なら、こんな手の込んだことをしなくてもいいのにな、なにがあるのだろう」
私はちょっと憤りを感じた。
「それを知ろうと思うんですけど、なぜ僕を生かしておいたのか、そのまま死なせてしまえば、ただの毒茸中毒ですからね」
「何か貴重なデータになると思ったんでしょう、気をつけたほうがいいですよ」
彼女は冷静だ。
「正会員にはなれたんだろ」
塾講師の同級生が探偵に聞いた。
「結局正式なバッチはもらえなかった、準会員のままだ、不定期の会の案内はこなくなりました、定期会の案内はくるのででてみようと思う、あの医者の病院も探してみるつもりですよ、草片駅弁愛好会の幹部は医療関係者なのは確かです、その人間たちにとって、実験材料を見つけることが目的なんです。毒茸にあたっても医者がたくさん参加しているので安心ですよと、司会者がいつも言っていた」
「俺も会員になって調べるよ」
同級生がそういうと、
探偵は首を横に振った。
「茸弁当を食べるだけならいいけどね」
「俺の勘だけどね、ちょっと裏が深いかもしれないですね、ともかく何かわかったら連絡しますよ、あまり近づかないほうがいいですから、まかしておいてください」
彼はそう言って笑った。
それから半年後、探偵からメイルがはいった。
「この会は茸毒に耐える遺伝子を探している研究者の組織のようだ、解明されれば確かに世の中に役立つし、茸食の発展につながるが、逆の薬も作れる、弱い毒をもつ茸でも死にいたる薬だ、毒はこわいが薬にもなる、その逆もあるわけだ、この会の最終的な目的がなにか、もっと調べてみるよ」
ということだった。私にはそれだけではないような気がした。
それ以来、探偵からは連絡がなかった。
秋も深まったある日、新聞を開くと、「また毒茸で死亡」、と言う小さな見出しが目に入った。場所は秋田の湯沢だ。名前は書いてなかった。気になって探偵事務所に電話を入れた。この電話はもう使われていません、というメッセージだけであった。
同級生に電話をすると、調べてみるという返事だった。
次の日同級生から電話があった。
「彼の実家に電話を入れた、母親がでて、白血病で地元の病院に入院し、死んだそうだ、毒茸に当たって死んだのじゃない。新聞に載っていたのは違う人だな、それで様子を聞いたら、いたって元気に探偵の仕事をしていたというんだ。ただ茸の弁当の会の知り合いと茸狩にはよく出かけていたらしい、長谷というお医者さんで毒茸の専門家だときいていた。病気になる前に薬などを飲んでいたか聞いたら、ビタミン剤を毎日飲んでいただけだということだった、あいつが言っていた薬かもしれない」
「白血病は血液のガンだよな、最初どんな症状がでたのだろう」
「それが、指の先を怪我して、傷口から黒い小さな茸が生えてきたそうだ、それを引き抜いたら全く血が止まらなくなったということだ、その長谷と言う人が、彼をつれて自分の病院に入院させたそうだ」
「病院でなくなったの」
「そうらしい、家族も見舞いに行ったのだが、どうしても血が止まらなくて、もともとあった血液は全て新しいものに変えてしまったほど、輸血したらしい、だけど、だめだったということだ」
こうして、茸駅弁の会の素性は全くわからないままになってしまった。イヤマサエコに会って話を聞くという手もあるが、彼女の居所もはっきりわからない
それが、考えもしなかったところで、イヤマサエコのことを知ることになった。
NHKのローカルニュースで、秋田の湯沢が映った。湯沢出身の著名な政治家、井山元官房長官の奥さんの病気が完治したというものである。驚いたことには、映像に茸の駅弁の会に勧誘していた婦人が映り、地元の病院の処置に感謝しているものだった。イヤマサエコは官房長官の奥さんだったわけだ。
不治の病にかかっていたとは見えなかった。使われた薬は、まだ治験中の薬なのだが、彼女はすすんで治験者になり、それが効いて、治ったというものである。
病名がついていない遺伝病で、ある茸の成分に対する抗体が、遺伝子にも効いたことで彼女の病気がなおったという。動物に外国の茸のある成分を摂取させ、抗体をつくらせ、薬にしたものだと解説者が言っていた。
探偵の母親が、彼の全ての血液を入れ替えるほどの輸血をしたと言っていたことを思い出した。茸を摂取させられた彼の血液から薬を作ったのではないだろうか。彼はその薬を作るのに都合のいい遺伝子をもっていたのではないか。動物実験をせずに、彼が動物の代わりになった。あの女性は自分の病気を治すために、茸毒に強い人をさがしていた。この疑問を機会があったら、同級生の塾の講師にはなしてみよう。亡くなった同期生の彼女にも話してみる価値はあるだろう。
この事件は解決していない。そう思った。
茸駅弁


