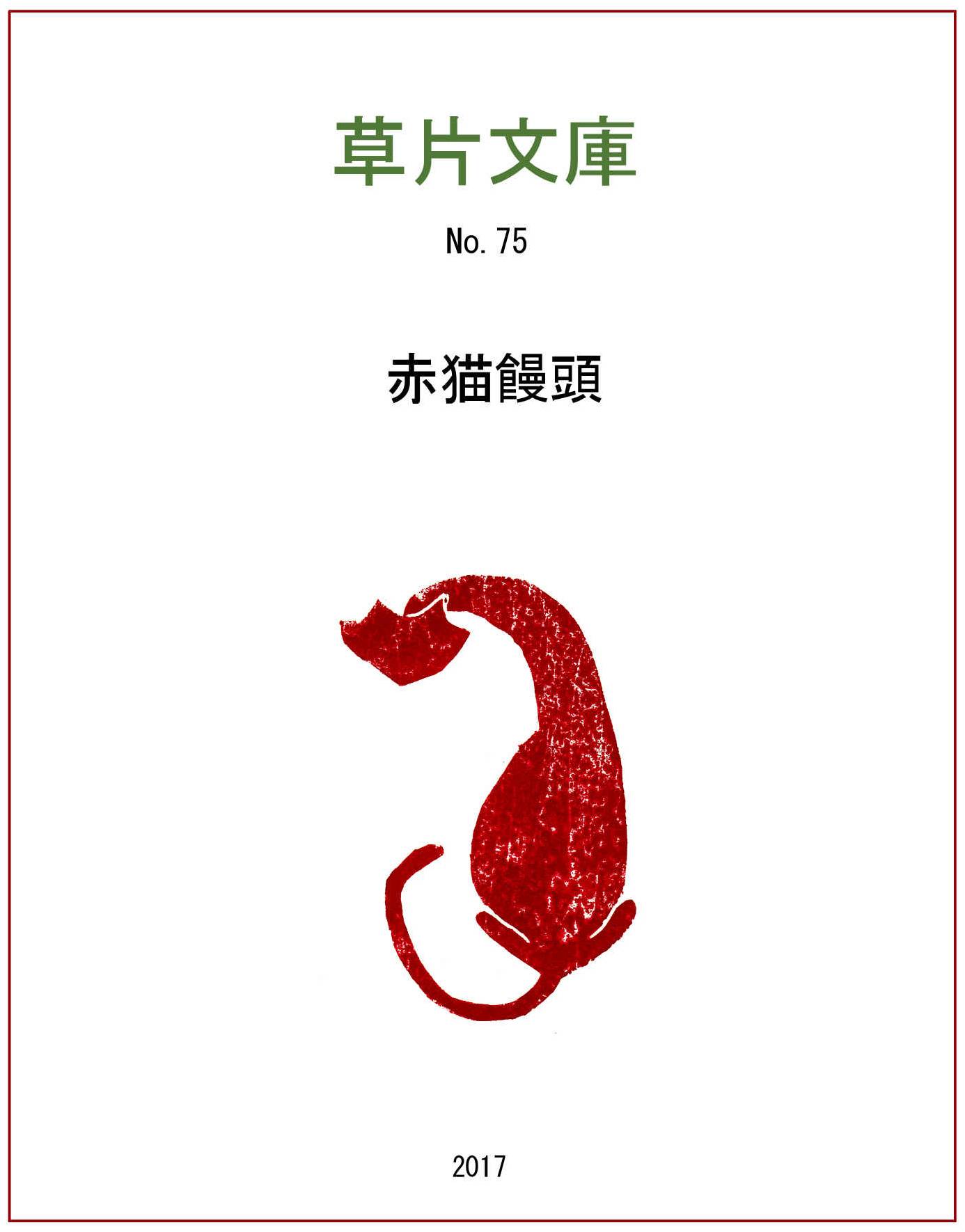
赤猫饅頭
赤猫屋の饅頭は真っ赤な餡を白い皮で包んだもので、赤猫饅頭といわれる。店は江戸時代から続いているという。いや、もっと古く戦国時代よりあるとも言われている。
赤猫饅頭はいつもあるわけではない。朝から天気の良い時しかおいていない。天気の悪い日には黒猫饅頭がおいてある。
店はもう九十を越すじいさんと、八十八になるばあさんがやっている。二人は朝三時に起きると餡を仕込む。小豆を煮てつぶして濾して、よその饅頭屋がやっていることとなんら違いはない。
ところが朝日が当たると、赤猫屋の餡は真っ赤になる。赤猫饅頭である。曇っていたり雨が降っていたり、すなわち朝日が当たらないと餡は黒くなる。それが黒猫饅頭である。
赤猫饅頭の方が少しばかり甘い感じはするが、黒猫饅頭と甘さはさほど違いがない。ところが味はというと全く違う。赤猫饅頭は柘榴の味がするのである。すなわち酸味が加わって、さらに柘榴の渋みまである。それを食べると精がつくということである。疲れがとれるらしい。それで有名である。
赤猫饅頭は百五十円、黒猫饅頭は百三十円と価格にも違いがある。しかし黒猫饅頭もなかなか旨い饅頭で人気がある。
ときどきテレビで紹介されるが、作るところはいっさい映されることはない。
にこにこと、しわくちゃな小さな顔をもっと小さくして、笑いながらばあさんが赤猫饅頭の由来をしゃべり、その脇で、じいさんが、やっぱり小さな顔を少ししかめて立っている。どのテレビ局の番組でも同じ構図だ。
赤猫屋は新宿にある。いまだに茅葺屋根の柱が黒光りした小さな家で、店の周りには、近代的な住宅が立ち並んでいる。それでひと際目立つ存在である。区役所の帳簿を調べると、昔から建て替えた記録が見つからない。萱だっていつ葺いたのかわからない。しかし健在である。
赤猫屋の前の道は、むかし、甲州街道と並行する小路だったようだ。江戸に出てきた人のための旅籠が集まっていたという。古くからある道で、それなりの賑わいもあったし、戦場(いくさば)になったりもしたようである。
饅頭屋のばあさんは、テレビのカメラを前にして、「いろんな先生が、饅頭は七百年ほど前に中国よりはいってきた点心がもとだとか、禅の坊さんが持ち込んだとか言ってるけんど、うちのはもっと古いんだ」と、欠けた歯を覗かせてしゃべる。
歴史を遡れば、饅頭の中身は餡と言うより、味噌や醤油味、それに砂糖が入っていたようで、町の者はなかなか高くて喰えなかった。
饅頭には別のルーツのものがある。それは酒饅頭である。皮に甘酒がはいっていて、中身が野菜だったりする。もちろんこの場合も砂糖は贅沢品である。江戸時代の饅頭になると、栗や葛、蕎麦なども入れるようになるとのことだ。
ただ、ばあさんの話では、赤猫饅頭の起源はそれらより古く、神代に遡るという。
そのころ広大な雑木林が続いていたこの地には、有象無象の生き物たちが勝手に棲んでいた。人間もその生き物たちの一つだったわけである。鼠が梟に喰われ、兎が鷹に狙われ、犬猫が狼に襲われるという単純な生命連鎖ではない、異なった秩序が神代の林の中には存在していた。
林の中に赤い毛色をした猫が棲んでいた。赤い猫は闇夜の晩、林を出ると、茅葺の粗末な家の中を覗き、生まれたての赤子を喰らっていたのである。
田を耕し、米を作る小作の家では、絶えず赤子が生まれていた。食わすものもあまりないにもかかわらず子供だけはどんどん生まれたのである。人間はその赤子を勝手に大きくなれとばかり放っておいた。上手く育った子どもは、田畑を耕す労働力として使われ、大人になると子供を産んだ。なんら他の動物と変わりない生活をしていたのである。だから、赤子が一人減ろうが、あまり気にすることはなかったのである。もちろん、母親は本能に従って、赤子がいなくなれば悲しみ、涙するが、すぐに次の子供が生まれ、それも忘れた。
雑木林には、兎、鼠、狸、狐、鹿、熊、いろいろな獣たちがいたが、そこに棲む動物たちは草を喰らうようなことはせず、どのような動物でも池の魚や木の上の虫を喰らって生きていた。そのような中で、赤猫の力は絶大だった。赤猫に噛み付かれた獣たちはその痛さに七転八倒し、場合には命をおとす。動物たちは赤猫に恐れおののき、赤猫が近寄ると一目散に逃げた。しかし、赤猫が食べる物はあくまで人の赤ん坊で、他の動物の子供を喰らうことはしなかった。
赤猫は木の上に棲んでいた。林には梟や鷹もいたが、鼠など小動物を喰らうわけではなく、どの鳥もそこに生えた茸を食べて生きていた。翼のある生き物は木に止まらなければならない、だが木の上には恐ろしい赤猫が住んでいる。鳥たちは赤猫の毛づくろいをし蚤を潰し、木の上に少しばかりのねぐらを分けてもらっていたのである。
夜になる。赤猫の目が光る。林の中の他の獣や鳥たちは、目覚めたばかりの赤猫が機嫌のよくないのを知っている。息をこらして、赤猫たちが雑木林から出て行くのを待っている。
木の上から走り降りた赤猫たちは、風のように林から出て行く。
ほっとした獣や鳥たちは、林の中の虫たちを食べ、茸を食べ始める。鼬が椚の木に手をかけて蜜に集まる兜虫や鍬形虫をくわえる。兎がコオロギに噛み付き、鼠は天道虫を丸呑みにする。梟は羊歯の間に生えていた卵茸をくわえ、鷹は猿の腰掛を突ついた。この林の中は当たり前の世界とは違っていた。
雑木林から飛び出した赤猫は、点在する農家を一軒一軒、覗いていく。
人間は家を作ることを知っている。みな萱で葺いた屋根をもつ家を自分で建てた。人間は米しか食べない。米を作ることを覚えた獣である。ただ、ときどき、豆を作る人間がいたり、麦を作る人間がいた。そういう人間はみな年寄りであった。若い人間は米を作ることしか頭に浮かばなかったのである。年を取ると少しばかり頭が働くようになるのである。
雄と雌の赤猫が、連れ立って一軒の人間の家を覗いた。何人かの子供が川の字になって寝ている。男と女が重なって子作りをしている。この家には赤子はいない。赤猫は生まれたての子供しか食えない。月に一度、闇夜の晩、すなわち新月のとき、お七夜にならぬ赤子なら食える。赤猫は赤子の半分を食べれば五年生きていくことが出来る。だから二匹で赤子を探しに出る。それは雄と雌のことが多いが、若い者は必ずしもそうではなく、雄同士、雌同士のこともある。ともかく人間に子作りをしてもらわねば種が滅びる。
赤猫は雄も雌も臭を出す。その匂いは人間に子作りをさせるように働く。これは赤猫が食料を獲易くする仕組みなのである。霊猫といわれる麝香猫は、赤猫から派生したと言われている。麝香は人間を虜にするが、子作りを促したりはしない。力をつける補助的なものである。しかし赤猫の赤(せき)香(こう)は媚臭であり、人間の男にも女にも作用し、頭に興奮を起こさせる。
二匹の赤猫はその農家に赤香を振りまき、次の農家に向かった。その家でも何人かの子供が川の字になって寝ていた。
「お、いる」、雄の赤猫が目を輝かせた。
「女の子ね」、雌の赤猫が言う。
「入ろう」、雄の赤猫が隙間から家の中に入った。雌が後を追う。
赤子が泣いた。肉付きの良い母親が目を覚まし、乳を子どもに含ませた。どくどくと音を立てて乳を飲む。この赤子は旨そうだ。乳の飲みたてほど旨い。
やがて満足した赤子は薄っぺらいゴザの上に寝かされ、母親もすぐ寝息を立てはじめた。
雌の赤猫が赤子の首筋を軽く噛むと咥えて外に出た。雄の赤猫が母親と父親の枕元で、尻を高く上げると、赤香を振りまいた。そうして、雌の後を追う。
外に出た雌の赤猫は軒下に赤子をおろした。雄の赤猫がしゃがんで、動かなくなった赤子を見た。赤猫の牙からでた痺れ薬が赤子を昏睡状態にさせている。雌の赤猫もしゃがんだ。首を伸ばし、赤子を頭から半分食った。残りを雄が食い始めた。
食べ終わった二匹の赤猫は空を見上げた。新月が黒っぽい影として空に浮いている。
「おいしかったわ」
雄もうなずいた。
「乳の飲みたてだったからな、運が良かった」
「しばらく寝ましょう」
二匹の猫は林に戻ると、食事を楽しんでいた動物たちは、いきなり戻ってきた二匹の赤猫に驚き、木陰に隠れた。赤猫に噛まれると大変だ。しかし満足した赤猫は他の獣にかまうことなく、交尾をして木の上のねぐらに戻った。これから二月、赤猫は眠る。目が覚めると雌は子どもを産み、子育てを始めるのだ。
赤猫の子供は茸を食べて大きくなり、半年で大人になる。それからは親から離れ、相手が見つかるまで一人で赤子狩りをしなければならない。
この雑木林には百八十匹の赤猫が棲んでいる。寿命は分からない。五百年とも千年ともいわれる。病気をすることがない赤猫の一番の問題は食料である。食べ物である人間の赤子の減少が一番怖い。五年間、赤子を食べないと、蒸発死する。いかに人間に子供を産ますかが鍵になる。
今日、赤子を食べることができたのは、一組の赤猫だけだった。後は夜明け前に、手ぶらで林に戻った。あと数ヶ月で5年間赤子を食べることのできなかった赤猫が三十組いた。その日が来れば、日の光を浴びて衰弱し、昇天する。次に狩が出来るのは一月後の新月の夜だ。
一月たった。明日の明け方までに赤子を食べなければ死に至る一組の赤猫は、昼間から林を出て村に行った。切羽詰った二匹にとって、なにがなんでも赤子を探さなければならない。赤猫にとって日中は動きが鈍く疲れるのもわかっている。ともかく、赤子を食わなければ死ぬ。
「南に行ってみるか」
川の流れているほうである。そちらに人はあまり住んでいない。よく川が氾濫して、折角作った稲や家を飲み込んでしまうからである。それでも、ちらほらと家は建っている。昼間、子供達も親達と一緒に田に出て米作りに励む。米しか食べられないからである。人間の食料の量は、気候によって左右されるが、全くなくなることはない。人間は赤猫のように寿命前に消えることはない。さらに、人間は年を取ると味覚が変わり他の物も食べることが出来るようになるという利点がある。
赤猫は田んぼで草取りをしている親子を遠くから眺めた。赤子の入った籠があぜ道に置かれている。そうっと行って覗いてみたが、お七夜は過ぎている。赤猫は他の田んぼに行ってみる。赤子はいたが皆大きくなってしまっていた。
一日中歩き回っても見つけることが出来なかった。もう一度、北のほうに行って、まだ探っていない農家を当たってみる他にはないだろう。夕暮れ時になる。そろそろ、他の連中も林を出て赤子を探す時間だ。競争となるわけである。
その二匹の赤猫はとうとう明け方まで生まれたばかりの赤子を見つけることが出来なかった。明日朝日が当たれば消滅する。
林に戻った二匹は木の上の巣の中で丸くなった。
「どうして、人間しか食べることができないのだろうね」
「他の獣たちは、どんな虫でも食べることができるのに、私たちだけ人間しか食べられない」
「しょうがないか、それではいい眠りを」
「あなたも」
朝日があたった。赤猫が崩れるようにとろけてしまうと、赤い蒸気となって林の上に登っていった。それは遠くからも見えた。
早起きの人間の子どもが「赤い煙が上がった」と林の上を見た。
父親と母親も家から出てきた。新月の翌朝、赤い煙は上がる。このところ毎回上がっているのを見る。人間は赤い神が空に上っているのだと拝むのである。
その年、大変なことが起きた。飢饉と疫病である。まず日照りが続き、稲の出来がよくなかった。それでも米の量は減ったが備蓄もあり、人間は食べることができた。しかし、疫病が襲ったことは、想像すらしていなかったことである。林の近くの場所の人間の数が急に減った。若い子供たちもすくなくなった。一年ほどで病気は去ったが、子供が生まれる数は少なくなった。新たに子どもが生まれ始めたのは、それから二年後であった。その間に何十組かの赤猫が赤い蒸気となって空に上って行った。今いる赤猫は百匹を切ってしまった。
疫病から回復したお陰で、その年は赤子がかなり生まれた。しかし新月の日にしか狩の出来ない赤猫は苦闘していた。
雑木林の赤猫たちも変化が生じ、いくつかの集団ができ、その頭領の集まりがつくられた。頭領の中から知恵者である赤猫が選ばれ、首領となった。
「どうして、新月の時しか赤子を喰えんのだ」
赤猫を統率する首領猫に、若い赤猫が尋ねる。
「運命には逆らえん、満月の時に赤子を狙ったやつがいたが、赤子を喰らったとたん、月の明かりに七転八倒し、五年の間起き上がることが出来なかった、と言うことは死んだ、あの苦しみようは大変なものだったぞ、それでもよいならかまわぬ、やってみるがよかろう」
「雨の日は月の明かりはないが、それでもだめか」
「それも試したものがいる。赤子を食ったとたん、その猫のところだけ雲に穴があき、月の細い光が猫の額にあたった。それは満月の時に食らった猫と同じになった、天の定めに逆らうことはできぬ」
「われわれはここの雑木林にしか住めないのか、ほかの地に行くと、人間はもっといようものを」
「ここから抜け出ることは出来ぬ、この雑木林と人間の住む隣の村しかない、遠くまで歩いた猫がいるが、歩いても歩いても雑木林から出ることができず、最後は雑木林に戻ってきてしまう。結界があるのだ」
「その外はどのようになっている」
「わしら赤い猫はいない、人間が動物達の首領になり、自由にしておる。動物たちは殺され、喰われ、飼いならされ、ひたすら人間に恐れを抱いて生きている。赤猫は生きてはおらぬ、ただの猫が人間に媚びて餌をもらい、太っている」
「そこの猫は人を喰らうのではないのか」
「そうだ、鼠を喰い、魚を食い生きている。それに人にもらう餌で生きているものもいる」
赤猫たちはだまってしまった。
「ただひたすら、新月の晩、駈けずり回る他ないのだろうか」
一匹の赤猫があきらめたように呟いた。しかし、首領といわれた赤猫は声を上げた。
「いや、我々の生きる形を変えれば何とかなる」
「それはなんだ」
「共同体になるのだ、猫はもともと一人で生きるもの、せいぜい二匹で生きるのだが、それをみなで力を合わせるということだ」
赤猫の性格からすると、かなり耐え難いことではあった。
「どうするんだ、首領」
「今まで自分の寿命を他の者に言わなかった、甲斐性(かいしょ)無しと思われたくなかったからだ、だから新月に続けて赤子を喰らっても自分のみつけたものであるから当たり前であった。しかしそれでは、寿命を一年延ばしただけである。寿命があと一年になった者に譲れば、その二匹はそれから五年生き延びる、群を維持するにはそれしかなかろう」
首領の言ったことに、頷く赤猫もかなりいた。しかしその理論をのめない頑固な猫たちもかなりいる。
そのような集まりが何度かくり返され、赤猫たちは自分がいつ赤子を食ったか皆に言うことにした。一年前から三年前の間に喰った赤猫は、四年より前に赤子を食った猫に見つけた赤子を譲るという、共生社会が生まれた。それは革新的であった。赤猫たちに安心をもたらしたのだ。しかし何年か経つと他の猫が本当のことを言っているのかどうかと疑い始めてしまったのである。赤子を見つけても譲らず、密やかに食っているのではないかとかんぐる、共同社会のむずかしいところだろう。
それにしてもある程度は効を奏した。それから百年ほど経ち、問題が別のところにでてきた。肝心の人間が子作りを励まなくなったのである。赤猫は赤香を撒いてはいるが、昔ほど効き目がない。
赤猫たちは、何とか人間に子作りをさせたかった。こればかりはなかなかうまくいかなかった。年月が過ぎていくに従って、人間も赤猫も数が減っていった。気がついたときには、赤猫の数が二桁までになっていた。
人間のほうでも変化が起きていた。赤子が神隠しにあうこととは、何がおきているのか、子どもはどこに行ったのか、疑問に思い始めたのだ。
人間にも統率者がでてきた。年をとった人間の中で知恵者がいたのである。そこの地域の部落ごとに頭領をきめ、頭領の集まりの中で知恵者が首領になった。その時の首領は小麦や小豆をつくることが出来る老人だった。共同作業で稲を作ることを提案し、老人達には他のものを作って食するように促したのだ。若い民は米しか食べることができない、老人は他の物も食すことが出来る。出来るだけ米を若い者達に食べさせようとしたのだ。
老人たちは、新月の時だけ、赤子が神隠しにあうのか、しかも生まれてすぐの赤子だけが消えてしまうのか、疑問に思い、見張りをすることにしたのである。
夜になると、生まれたばかりの赤子のいる家に、見張り番の老人たちが巡回し、怪しい者を取り押さえようとした。
新月の日、夕暮れになると、雑木林に赤い光が見えた。田んぼの道を何匹もの赤い獣が歩いてくる。途中から二匹ごとに分かれ、村の中に入っていく。二匹の赤い獣が老人の見張っている家に近寄って来た。
真っ赤な毛をした、金色の目の大きな猫が二匹、老人の前に来て、前足をそろえて、老人を見上げた。
「邪魔をしないでくれ」
赤猫が人間の首領に言った。
「お主らか、子どもをさらうのは」
「喰わねば死んでしまう、お前らが米を食うのと同じだ」
「米は作っておる、お前らは自分でつくらず、人間がつくった子どもを食らうとはずるいじゃないか」
「生きものの世界にずるいという言葉はない、そうせねば死ぬ、子どもを作りたくなる匂いを撒いて努力はしている」
赤猫は老人に自分達のことを話した。
「だが、我々も子供がいなくなれば亡びる、赤子を食われるのは困る、赤子を食わぬ方法はないか」
「俺たちも他の獣のように虫を食ったり魚を食ったりしたいが、できない」
「もし、代わりのものがあればよいか」
「ふむ、それで命が助かるのなら、それでもよいが、人間の赤子ほど旨いものはあるのだろうか」
老人は少しばかり考えた。
「あの林の中に、柘榴の木はないか」
「ある、あの赤く光る実は魅力的だが、林の中の獣も鳥も虫もその実だけは食わん」
「なぜであろうな」
「わからん」
「林の中の獣や鳥や虫は人間の赤子は食わんだろう」
「そうだ、人間の味を好まぬからだ、我々赤猫だけだ、赤子を食うのは」
「柘榴は人間の味がするという、だから獣も鳥も虫も食わんのだろう、どうだ、一度食ってみてはくれぬか、赤子の味に似ているかもしれん」
「いいだろう、わしらも人間と争うつもりはない、ただ柘榴が食えて寿命が延びないようなら、また人間の赤子を食いに来る、いくら防いでも防ぎきれぬと思ってもらいたい、我々も死に物狂いなのだ」
「分かった、その時は、我々もなんらかの手を打つしかないだろう」
赤猫の首領から皆に連絡がいった。赤猫たちは林に戻っていく。
「赤猫が生まれたばかりの赤子をさらうことが分かったが、もし、柘榴を喰らうことができないと、また赤子がさらわれる、どうしたらいいものか」
老人たちは頭を抱えた。赤猫が柘榴を食べてくれるのを祈るしかないだろう。
林に戻った赤猫に獣や鳥や虫は大あわてで陰に身を寄せた。赤猫たちは下草をかき分けて、柘榴の木の生えているところに来た。
「柘榴の実は人の味だという、もしこの実が我々の糧となるなら、人間の赤子を探すよりはるかに造作なく生き延びることができる」
「われわれは、あと二月しか猶予がない、柘榴の実が食えたとしても、命が延びたかどうか分からぬではないか」
「確かに、おぬしらの言うとおりだ、もし、この柘榴を食って、まぐわいたくなったなら、命も伸びたことになろう、もしその気にならぬのなら、すぐもう一度赤子探しにでかける、どうだ」
「わかった、それでいい」
赤猫たちは柘榴を採ると、赤く光る実を口に入れた。
「旨い、これならいける」
赤猫たちは、石榴の実をすべて平らげた。そのあと、ニャーゴと鳴きあいながら、相手を求め交尾をした。木の上の巣に戻ると二ヶ月の眠りにつき、子どもを産む。これで、仲間が倍に増えることになる。
林の中の生きものたちは、赤猫がみんな寝てしまったのを見て、仰天し喜んだ。しばらくは静に暮らせるのだ。
村の老人たちは明け方までまんじりともしなかった。いつ赤猫が戻ってくるか、眠気など生じなかった。緊張したままである。やがて朝日が射してきた。
老人はほっとため息をついた。赤猫たちは石榴を食って満足をしたようだ。これで神隠しもなくなる。それぞれの家に戻ると、やっと安らかな眠りにおちた。
赤猫たちは一年に一度秋になると、熟す石榴の実を食べ、生きながらえることになった。
それから何十年経ったのであろう。石榴を食べるようになった赤猫たちに再び問題が生じた。子どもが作れなくなったのだ。交尾はするがやはり赤子を食わなければ子どもが出来ないのではないかということになった。
赤猫の首領は人間の長老に会いに行くことにした。出来れば人間と戦うようなことはしたくなかったからである。
人間の寿命は五十年ほどである。そのむかし石榴を教えてくれた人間の首領はもう死んでいた。しかし新しい長老もよくわかっている人間だった。
「前の長老から話は聞いておりますじゃ、ということは、子供が授かるような、食べ物があればよいということですな、少しばかり時間を下さらんか、考えてみますで、赤子を食うのだけは止めてくだされ」
赤猫の首領はそれを聞くと「分かり申した、また、参るのでその時にたのみます」
と林に帰っていった。
しばらくして、赤猫の首領が老人の家に行くと、
「待っておりましたぞ、できました、これじゃ」
小麦粉で作った皮に包んだ、小豆を潰したものを差し出した。いうなれば、饅頭である。この長老は小麦と小豆の栽培を前の長老から受け継いで、老人の食料にしていたのである。
「これはな、饅頭と言う我々老人の食い物だが、中の小豆の餡は石榴の味がする、それに精力剤じゃ」
老人は蒸した小豆を潰して、朝日にあてると、少し発酵して酸味がつく、それが石榴のような味のものになることを知ったのだ。
「喰えるかどうか試してくだされ、わしも食う」
老人はその饅頭を食った。毒味のつもりだった。
「人間には酸っぱく感じるが、どうであろう」
赤猫の首領は、金色の目で饅頭を見て、食ってみる気になった。香りがそうさせたのだろう。
ぱくりと一口で食ってしまうと、「うむ、旨い、からだが火照る」とうなった。
「そうじゃろう、石榴を食って、その後この饅頭を食いなされ、すると、子供ができるかもしれん」
赤猫の首領は石榴味の饅頭をもらって林に帰った。早速赤猫一同、石榴を食したあとにこの饅頭を食った。交尾をして、二ヶ月の休眠の後、多くの赤猫たちに子供が生まれた。確かに饅頭の力はある。こうして赤猫と人間の関係は良好のものになったといわれている。
この老人が、赤猫饅頭の開祖者だそうである。
私は今、『不思議な甘味』という本を編纂している。
古くから有名な饅頭、羊羹、カステラ、飴はいろいろあるが、その中でもちょっと、奇妙な由来のある甘味についてまとめている。京都東山にある幽霊子育て飴などはよく知られているところだろう、幽霊が子育てのために飴を買いにきたという四百年続く飴のようだ。しかも東山のこの地は昔、髑髏町といわれていたという。
最近は妖怪ブームにあやかって、水木しげる氏の生誕の地、鳥取境港の妖怪食品研究所(彩雲堂)のだしている、妖菓目玉おやじという饅頭が売れているようである。
隣の島根の松江には小泉八雲にちなんだ耳無し芳一の耳の饅頭。外国に目を馳せれば、メキシコには死んだ人をしのぶ、死者の日がある。そこには骸骨の砂糖や飴があるという。まあ、骸骨などは現実的で、不思議というのではないのであろう。
しかしこの新宿の赤猫屋を知ってから、奇妙な気持ちに駆られている。赤猫屋のばあさんが時間をかけて話してくれた赤猫饅頭の由来は、あまりにも現実離れしていて、誰かが作った由来話に聞こえるだろう。ところが赤猫屋のばあさんとじいさんと話してごらん。話を信じたくなるから。ばあさんは本当に梅干のように深い皺のよった楕円形の小さな顔、皺の中のまん丸な小さな目、あぐらをかいた鼻に薄い唇の長い口、小柄なからだを紺色のもんぺ姿で覆っている。爺さんにいたっては、茶色の甚平にぞうり、細長い顔に細かな縮みのような皺を寄せて、小さな目と大きな鼻がくっついている。煙草の煙を吐き出す口には脂だらけの黄色い歯がのぞいている。
「だあれも、信じんだろう、それでいいんだ」
ばあさんは私を見る。そりゃあ、話を信じるのは難しいさ。
「わしらは、それでいいと思っとるよ、赤猫饅頭は、ほれ、ここにある通りさ」
じいさんも笑う。
私は自分でも思うに奇妙な行動にでた。どうしてもそうしてみたかったのである。幸い赤猫屋の斜め向に駐車場があった。使う人もあまりなく、一週間予約することができた。夜になると、そのあたりは住宅街で、人通りはほとんどなくなる。車の中から、夜通し赤猫屋を見張っていたのである。
真夜中ごろだ、近所の猫だろう、駐車場を横切っていった。その後に、二匹の猫が道の真ん中をゆったりと歩いてやって来た。私はどきりとした。赤っぽい猫だ。写真を撮った、フラッシュは焚けないので、ちょっと暗いが、赤っぽい猫なのはわかる。
二匹の猫は赤猫屋の前に座った。すると、赤猫屋のカーテンの閉まっているガラス戸が少し開けられた、赤い猫が中に入っていく。少し経つとまた戸が開いた。饅頭を咥えた二匹の猫がゆっくりと出てきて、来た方向へ歩いていった。
次の日は来なかった。その日の天気はあまりよくなく、赤猫饅頭は作られなかったはずである。五日日間、見張っていた結果、赤猫饅頭が売られた日には、その夜中に赤い猫が必ず二匹訪れた。
六日目である、その日も天気は良かった。赤猫饅頭が売られていた。
私は意を決し、二匹の猫が店の中に入ったとき、近づいて戸をそうっと開けた。鍵はかかっていない。下のほうから窺うと、中がかろうじて覗けた。店の中で真っ赤な猫が、机の上に乗ってばあさんとじいさんと話をしている。
よく見ると、ばあさんとじいさんが、こげ茶色の毛に覆われていることに気がついた。川獺のようだ。いや、もう少し毛足が長い。穴熊か、穴熊のもう一つの名は狢だ。狢は人を化かす。狢は赤猫と同じ世界に生きている生き物ではないだろうか。あの、ばあさんの話の中の米作りの人間は狢だったのではないだろうか。そう思っていたとき、いきなり戸が開いて、私の襟首が咥えられ、店の中に引きずり込まれた。
「こないだ来た人間じゃないか」
じいさんだった狢が小さなつぶらな目で私を見た。私は頷いた。
「みんな見られちゃったのね」
ばあさんだった狢が鼻に皺を寄せた。
赤猫が金色の目を私に向けた。
「珍しく用心が足りなかったようだな、ご老人」
じいさんとばあさんにそう言った。
「そうじゃったな、だがこの御仁は人に言うまい、言ったとて、誰が信じるわけがない、ライターだから、いっそ書いてもらって、赤猫屋を宣伝してもらおうや、狢がやってると書いてくれ」
私は怖くて頷いていた。
「だがな、ちょっと、仕置きをしておかなければな」
一匹の赤猫が私の左足のふくらはぎに噛み付くと、ずるずると私を引きずって、店の外に放りだした。
店先で体を起こしてみると、店の中では二匹の赤猫が狢から赤猫饅頭をもらっているところである。二匹の猫はそれを咥えて外に出てきた。
赤い猫は私をちらっと見ると、ふふふと笑った。店の中を振り返ると、
「これからもよろしくな」
じいさんとばあさんにそう言いおいて、悠々と歩いて行ってしまった。
じいさんとばあさんが、店先をのぞいて、倒れている私を見ると、やはり「ふふふ」と笑って戸を閉めてしまった。その時、狢はもう人間に戻っていた。
噛み付かれた足がじんじんと痛くなってきた。幸い五分ほどすると、治まってきた。足を引きずり、車にもどった。
そんなことがあった。
今でも新月の夜になると、なぜか私の足が痺れ、痛みが走る。
それから一年たち、本ができた。それをもって赤猫屋に行った。
「ありゃ、いい本できたね、宣伝になるね」
本をめくって、ばあさんは赤猫屋のところを開いた。
「ほんとのことが書いてあるねえ、お兄ちゃん、わたしらが狢だとよ」
ばあさんが笑った。
じいさんは相変わらず、表情を変えないで突っ立っている。
いろいろ礼を言って、店を出ようとすると、じいさんが「これもってけや」と赤猫饅頭と黒猫饅頭を包んで持たせてくれた。
「赤猫は今もいるでよ、大人しくさせなきゃな」
そう言ったあと、二人は「ふふふ」と皺くちゃのほっぺたに笑窪をよせた。
私は礼を言って赤猫屋を後にしたのである。
赤猫饅頭
私家版 赤猫幻想小説集「赤い猫、2019、279p、一粒書房」所収
木版画:著者


