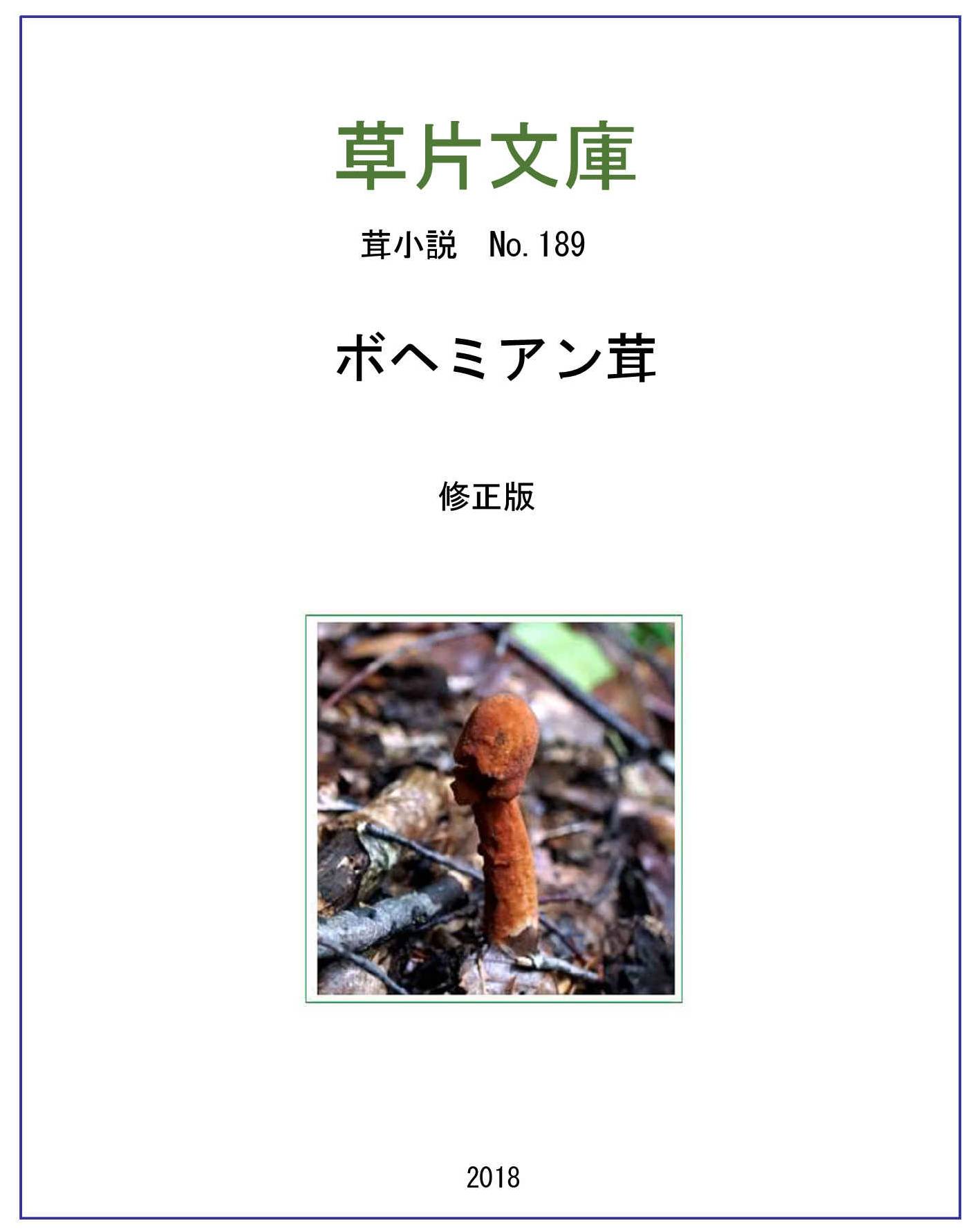
ボヘミアン茸
不思議な茸のお話
猛り茸は形のない茸である。いや、ないわけではないが、胞子を入れているものは極小さく、大きな子実体、すなわち茸はない。
この茸は奇妙な生活をしている。他の茸の子供に寄生して、その茸の形を変えてしまう。それが、どのような茸にとりついても、その茸が大きくなると、まるで人間の男の一物のような形になってしまう。それであまりにも有名である。
もし、猛り茸の本体である菌糸に眼があって、寄生した相手を好きな形にすることができるのであったら、男の陽物などを選ばずに、植物のようにきれいで見事な花を咲かせることだろう。もっとも、この茸が植物ではなくて、動物にあこがれていたとするならば、動物の花に相当する生殖器の形を選んでも不思議はないわけだ。
などと想像することはたやすい。
この変な菌類はいったいどのようなことを考えているのだろうか。
秋田県湯沢市の小安温泉郷にある女滝沢散策路という谷川沿いの山道を歩いていて、この茸に出くわした。
ちょっと細い茶色の猛り茸である。
カメラを向けると、おおよその茸と話しができる。なぜかっていわれても分からないが、写真家は自分と向き合っている被写体と会話ができなければ被写体がいい姿を見せてくれないことを知っている。それで、写真家は被写体と話をするため長い間奮闘するわけになる。よく知られている猫の写真家は、猫をじっとみつめることで、演じて欲しい動きを頼むことができるという。このようにして、私も茸の世界のことをいろいろな茸から聞くことが出来るようになったのである。
今、カメラを猛り茸に向けた。話ができるようになって初めての出会いである。
考えていたことを述べ、まず、本人に一体どのような茸なのか語ってもらうことにしよう。
デジタルカメラのディスプレーには茶色の猛り茸の頭がゆらゆらと揺れている。
「茸にはな、担子菌と子嚢菌があってな、俺は子嚢菌の仲間だ。ヒポミケス(Hypomyces)、というのが本名だ。担子菌はいうなれば茸茸した形を持つ連中だが、子嚢菌は変な形といわれるやつらだ。みなさん知っているだろう。とても旨い編笠茸やトリュフなんてやつらと一緒だ。ところが、仲間にはこういった茸を作らないものがたくさんある。酵母菌などだよ、黴もそうだし、水虫の白癬菌だって親戚だ。
冬虫夏草ってやつらを思い出してくれ。虫にくっついて、食い殺し、茸を作るやつらだ。どうやらそいつ等と、我々の考え方は似ている。俺たちは他の茸にとっついて、殺しはしないが、形を変えさせてしまう。
俺たちの体である菌糸は若い他の茸を取り囲み、栄養をもらっちまう。とりつかれた茸はちゃんと傘が開けなくて、男のおちんちんみたいになっちまうんだ。そうなったところで、俺たちの茸を作る。といっても1から2ミリの小さな物を何千何万と、とっついた茸の表面から生やすのだ。だから、その男根みたいになっちまった茸の上を我々の茸でおおってしまい、色をつけるってわけだ。俺なんて茶色なので、とっついた茸は茶色のおちんちんになっちまうが、茶色じゃないものもたくさんある。
だから人間はそれを見て、猛り茸と呼ぶが、それは俺たちの本当の姿ではない、俺たちが寄生した茸が変形したものなのだよ」
「それにしても、もっといい形にさせてやりゃあいいじゃないか」
「そりゃあ、そうさせてやりたいが、あいつら茸の体質でああなっちまうんだからしかたがないだろう、残念なことに、我々にはとっついた茸を好きな形にさせる能力はない」
「ところで、あんたがたはどこから来たんだ」
「地球人が知らない遠い星だ。人間は生命の起源を外の宇宙に求めようとしているが、動物植物菌類は地球上で生じた生き物だ。しかし我々は宇宙の茸で、地球の茸とは違うんだ」
それから、猛り茸は自分の生い立ちを話し始めた。
「我々の母星では我々茸が惑星の内部までも支配していた。ようするに我我の菌糸はその星の表面どころか奥の奥の方まで伸びていた。我々の太陽系の中心にある恒星が古くなり、とうとうブラックホールに吸い込まれたのだ。ところがその瞬間、吸い込まれずに我々の惑星は閃光を放って、分解して宇宙に散った。我々茸の菌糸はその瞬間から、『時』の端切れを食べるようになり、宇宙を彷徨うことになった。格好良く言えば放浪の茸になった。地球的に言うとボヘミアン茸だ。
我々は時空を自由に行き来していたのだが、ある時、時の嵐が吹いた。そのとき、吹き寄せられてしまったのが銀河の太陽系だった。太陽系の空間に我々の祖先は浮遊した。そこには八つの主要な惑星や、無数の小惑星群が存在していた」
「今、小惑星に探査船を飛ばしているよ、そいつがもどると、生命の起源がわかるとかいう話だが、あんたさんがいうように、地球の生き物が地球で生じたなら、小惑星を調べても、何もでないということか」
「そんなこともないが、そこに生命がいるわけじゃない、生命の大元になる物質がみつかるかもしれん、それよりも、宇宙には我々の祖先ボヘミアン茸がいる。人間には見つからないけどな、なにせ異時限にいるからね」
「そうなんだ、地球の菌類とは違うわけだ」
「そうだよ、太陽系の空間にボヘミアン茸は広がった、その中でも発展をとげたのが、地球でのことだった。地球では動物、植物、菌類が元気に進化していた。
地球に降りたボヘミアン茸が地球にうまく住めるようになるには時間がかかった。長い長い時を経て、今の我々、猛り茸を作る茸になったのだ。
地球にきたボヘミアン茸は地球の茸と交わった。だから地球上の菌類はエイリアンとの混血だ。特に子嚢菌類には混血が多い。一方で動物植物は生粋の地球生物だ。
本名ヒポミケス、人間の間では猛り茸と呼ばれる茸はこのように生い立ちを語った。カメラを向けているとさらに話しを続けた。
「太陽系に散った我々の仲間は菌糸を伸ばし、その先は千切れ、さらに時限を越えた宇宙に散らばった。ボヘミアン茸の菌糸は時の切れ端をエネルギーにして成長する。時を食うのだ」
「知ってるか、時というのも粒子なんだよ、いつもは整列しているが、食うと穴があく、するとそれを埋めようとして粒子がつめる、そうすると、時がずれる。俺たちの祖先は、時を乱す菌だったんだ」
「何という粒子なんだ」
「時玉、じだま」
「存在するということは質量があるのだな」
「ある、とても重い、そう、ちょうど地球ほどだ、だから、人間は時玉を測ることができない。それと二つの時玉はぶつかり合うことはない。必ず間に空間がある。その空間は時がない、時の真空状態の場所だ、そこに我々ヒポミケスの祖先、ボヘミアン茸は菌糸を伸ばした。
その大きな質量の時玉から栄養分を吸い取る。時玉の質量がちょっと変化する、すると、その時玉が隣の時玉から減った分を吸い取るので、時玉が連鎖して質量を変化させていく、それが時のなだれだ、過去から未来への時が変化する」
「ということは、あんたらボヘミアン茸が宇宙の時を狂わせてしまうのか」
「そうだ、だが最初はそんなことをしてはいなかった。異時元の地球の隣でもあり、何億光年も離れたところにあった星に生存していた、その星は小惑星、リュウグウと同じように、岩石でできており、大気はなかった」
「それじゃ、生き物は育たないじゃないか」
「地球上の知識ではね、さっきいったように、我々は時を食べているのだからね」
「今は違うのだろう」
「ああ、ヒポミケスになったからね、エイリアンであるボヘミアン茸と地球の菌類の混血ができたときに、他の茸の栄養をもらうようになった」
「もう時を食わないのか」
「ああ、ただ、時々、先祖帰りして、そのあたりの時空を乱すやつらがいることがある」
「そうすると、どうなるんだ」
「祖先帰りした猛り茸がでると、その茸の回りの時間の進みが遅くなる、ほんの一瞬だがな」
「地球にやってきたときどう思った」
「わしらが生活しやすいところだと思ったよ、何しろ、宇宙のどこを見渡しても、生命体が発生した星は数えるほどしかない。地球型の生き物はいないよ、地球では植物が酸素を作り、いろいろな物質も作る、動物はそれを利用して、最後は植物の材料になる。その後に、菌類が現れ、植物と動物の間で化学的反応を起こして、動物植物が出来ない多くのことを補佐することになる。地球上の植物と菌類の働きは動物をさらに進化させる基盤になり、動物は脳の発達が生じ、人間が生まれ、地球に細工をするようになる。地球の物質を使うということだがね、機械、乗り物、そして宇宙船をつくり、宇宙に出て行くことができるようになる、これからだけどね」
「それで、ヒポミケスになったみなさんは、地球上のどの茸と結ばれたんだね」
「最初は虫に入った、ところが、虫はわしらと合体することができなくて、二世を作ることができなかった、彼らは死んでしまった。いろいろな虫と一緒になろうとしたが、だめだった、みな生きていることができなかった」
「なぜ虫にはいったのか」
「動物の中で一番たくさんいる、それに動くこと、移動することが速くできる、ボヘミアン茸は虫たちに未来を託したのだ、大昔だから哺乳類はまだ進化の初期だ」
「その後は想像できる、地球上の冬虫夏草が入り込んでいた虫に、お宅たちが入っていったんだな」
「その通り、亀虫にとりついたところ、中に耳掻き茸が潜んでいた。亀虫茸ってやつだ。そいつは菌糸を亀虫の体に伸ばしていた、同じ亀虫に入った我々も菌糸を伸ばした。ふと気が付くと、亀虫茸の菌糸はどう勘違いしたのか、我々の菌糸に核を移し入れてしまった。そうしたところ、核が分裂を始め、我々の菌糸の中で働きはじめた。それまで我々の菌糸は核で分裂するような仕組みではなかったのだ、時間を食べると、それが刺激で伸びていく、時で働く、時核と言う細胞内小器官が菌糸の中にあって、それで増える。ところが亀虫茸の核が指導権を握り、亀虫茸になってしまったのだが、菌糸はボヘミアン茸だ。菌糸が伸びても、亀虫茸はつくれなくなった。
亀虫茸がはいりこんだ亀虫は飛び回っているときに、急に冬虫夏草の毒素に当たって地上に落っこちる。そこから亀虫茸ができるわけだ。ところが、ボヘミアン茸と混ざった亀虫茸は地上に落ちても茸ができない。
我々の混じった亀虫が落ちて死んだ。亀虫から元ボヘミアン茸だった菌糸がそとにでて、調度頭を出した天狗茸にとりついた。天狗茸の子供の匂いは刺激的だったことから、我々の菌糸はその天狗茸の子供の表面にとりついたわけだ。すると、天狗茸の表面で我々の二世の菌糸は栄養を吸収し、広がっていった。後は想像できるだろう、天狗茸の子供は大きくなったのだが、変形してしまったのだ、それが猛り茸ということだ」
「なるほど、冬虫夏草とボヘミアン茸との二世がヒポミケスというわけか」
「ああそうだ」
「だけど、猛り茸は珍菌ということになっている、蔓延(はびこ)ることはできなかったのか」
「いや、一時は、かなりの茸が猛り茸になっていたんだ、もう十億年も前のことだがな、しかし、やはり空気という奴はもともとのボヘミアン茸の菌糸にはあまりよい影響を及ぼさなかった。真空に近い方がよかったんだ、そういうことで、二世であるヒポミケスはなかなか繁殖できなくなった、それで、猛り茸はあまり生じない」
話を聞いていると、それでよかったと安堵した。あのきれいな紅天狗茸などが、みんな猛り茸になってしまっていたら、殺風景なものである。
「ところで、ヒポミケスの祖先、ボヘミアン茸はまだ宇宙を漂っているのだろうか」
「ああ、今、小惑星リュウグウに日本の探査船かぐやⅡが到着しているが、あそこにはまだ残っている。宇宙のボヘミアン茸は、太陽系の中を集団で通過した。そのとき、地球に降りたもの、月に降りたもの、火星に降りたもの、それに小惑星に降りたものがあって、地球では二世として残ったが、ほとんどはまた別の宇宙に旅立った。ほんの少しだが、リュウグウに降りた連中がいるが、そいつらはかなり繁栄してリュウグウいるはずだが、いまはどうなったかな」
リュウグウは約3億キロ離れたところにある小惑星である。探査船かぐやⅡは二年半かけて到着し、作業を終えると二年半かけて戻ってくる。
「あの探査船は石を採取して地球に戻ってくるが、もし、ボヘミアン茸がついていたとすると、どうなるのだろう」
「さあ、われわれはたまたま冬虫夏草がいる虫についたから、このような形で生きているが、そういう機会がない限りは、消滅することだろうな」
そこで、私はシャッターを切った。一番格好良く映るのをまっていたのだ。それで話は終わった。そのあとも何枚か写真を撮ったが、猛り茸は無言だった。
私はボヘミアン茸に消滅してほしいと願っている。
もし偶然にもまた地球の茸との二世ができてしまったら、どうなるのだろう。それが動物たちに寄生でもするようになったらどうなるのだろう。想像するだけで怖い。
二年後に探査船が戻って、採取されてきた石がどのように扱われるか気をつけていないといけない。
それから、二年以上が経った。かぐやⅡは輝かしい結果を持って地球に戻ってきた。たくさんのリュウグウの石を拾ってきたのである。世界中の研究者はその結果を待ちに待っていた。採取された石は研究に供された。
はたして猛り茸が言っていたリュウグウにもぐりこんでいたボヘミアン茸が地球にきたのかどうか。それは知る由もない。あれから猛り茸とは遭遇していない。
その機会がかぐやⅡが戻った年の秋に訪れた。
やはり小安で茸の写真を撮っているときだった。今度はかなり大きな太い猛り茸だった。茶色で、重なった落ち葉の間からぬっくと立っていた。
私がカメラを向けると、「聞きたいことがあるのだろう」
と茸の方から話しかけてきた。
「小惑星のリュウグウにはボヘミアン茸はいたのだろうか」
「ああ、いた、時の切れ端を食べて生き延びていた、ただリュウグウでは子実体、すなわち茸は作れなかった」
「それじゃ、増えていなかったのだな」
私はちょっとほっとした。
ところが、猛り茸は言った。
「ああ、しかし、あそこは時空の濃いところ、重なり合っているところで、菌糸は勢いよく伸びて、リュウグウの奥や表面を覆っていた」
「どうなるのだ」
「どうなるというより、かぐやⅡがもってきた石にもたくさんついていた」
「その石は研究者に配られたと聞くが」
「そうだ、かぐやプロジェクトのサイトを見ると分かるが、世界中の研究者のところに届けられている、おそらく砕かれ成分が調べられる、その時ボヘミアン茸は地球の空気を吸うことになるだろう」
「リュウグウのボヘミアン茸は、昔地球にきたボヘミアン茸が亀虫茸とあいまみれヒポミケスになっていることを知っているのか」
「まだ知らんだろう、だが風のある地球では胞子も飛ばせるようになるだろう、やがて菌糸がいろいろなところで発達し、我々とコンタクトをとるだろう」
「そうしたらどうなる」
「冬虫夏草はよした方が良いと教えることになる、新しく来たボヘミアン茸はもっといい形で地球で増える方法を考えるだろう」
「冬虫夏草とは手を組まないとして、ほかの道とはなんだろう」
「我々は虫を選んで失敗した、哺乳類にとりつく方策を考えるだろう」
「どうしてだ」
「今の時点では、地球で繁栄しているのは哺乳類だ、進化の先端をいってるからだ」
「だけど、人間につく冬虫夏草はいないから心配ないな」
それを聞いた猛り茸は大笑いした。
「我々は冬虫夏草と相性はよかった、それでヒポミケスになった、冬虫夏草は子嚢菌類だ」
猛り茸の言ったことはすぐに理解ができなかった。
「子嚢菌類は茸を作らない奴がたくさんいる、酵母もそうだし、白癬菌もそうだ」
そこでやっと気が付いた。前にもそう言われ危惧した記憶がある。
何とかしなければいけない。しかし私にはどうしたらいいかわからなかった。
私はカメラのシャッターを押した。
もう、猛り茸はしゃべらなくなった。
白癬菌をもった人間はたくさんいる。私も昔足の指に水虫がついたことがある。
もし、かぐやⅡがつれてきたエイリアン茸が人の体にはいって、そこに水虫菌がいたらどうだろう、ボヘミアン茸は水虫菌ととともに変化し、第二のボヘミアン茸になり、人の皮膚の下に菌糸をはやすのではないだろうか。
人間の子供に寄生した第二ボヘミアン茸は子供をどのような形に変えてしまうのだろう。
私はもう一枚写真を撮るためにカメラを猛り茸に向けた。
茸は言った。
「まさか、男の陽物のようにはならんよ、それに何千年、いや何万年も先のことさ」
ついつい蛸のようになった人を想像してしまったのは、HGウエルズのお陰だ。
私はシャッターを切った。
しゃべらなくなった猛り茸は自信満々に目の前ででんと笑っていた。
ボヘミアン茸


