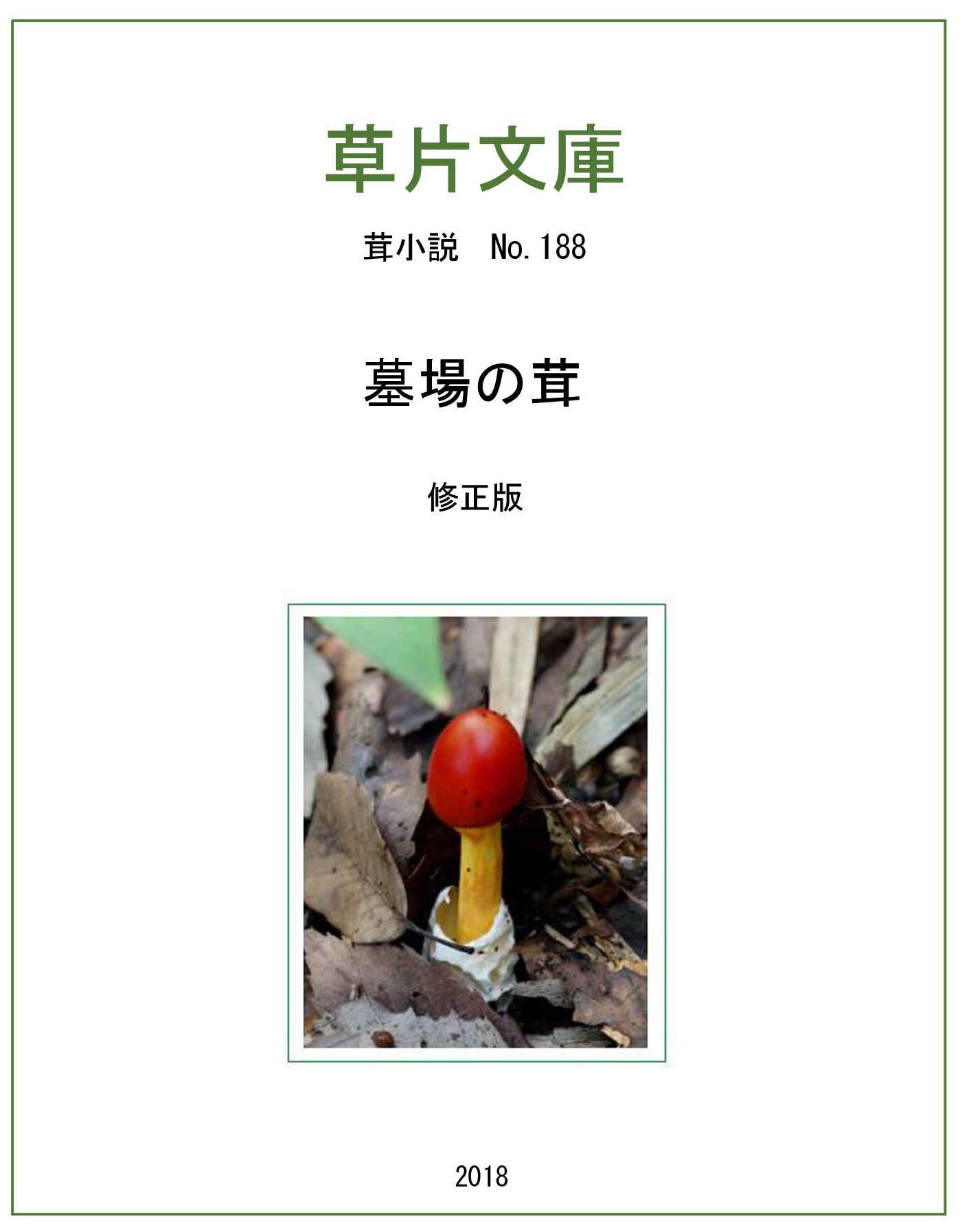
墓場の茸
奇妙な茸小説です。
これは、久しぶりに会った精神科の友人が話してくれたことである。
彼は大学の山歩きのサークルで一緒に山登りをした仲である。当時彼は医学部の二年生、だからまだ教養課程で余裕があったのだろう。サークル室には毎日のように顔を出していた。三年になると、医学部は専門課程になり、サークルに昼間から顔を出す暇などなくなる。私は文学部の二年正、サークル室では彼を交えてその頃の小説についてよく話したものである。文学部は上にいくほど暇になり、サークル室や喫茶店、麻雀屋にたむろすることになる。まだ大学に出てくればいい方で、ほとんど出てこなくなる。バイトに明け暮れる者、外部の演劇組織に入ってのめり込むなどはいい方で、生活がだらけて、結局大学に戻ってこなくなる者もたくさんいた。
私は何事も程々で、ちょっとばかり語学に長けていたので、フランス文学の訳などをバイトがわりにやっていた。それに、周りには言っていないが、何かに刺激されると、短編だが、小説を書きたくなり、コンピューターの外付けのハードディスクには、書いたものがずい分たまっている。いつか本にしたいとは思うが、そこまで貪欲ではなく、ただ自分の作品がたまるのを楽しんでいた。
精神科の友人は、山歩きの会でどこかにいくと、そのあたりに生えている草の薬効などをよく教えてくれた。もちろん食べられる、食べられないもよく知っていた。その頃から向精神薬という精神に作用する薬について興味があったようである。
サークルで長野の山に一泊で行ったときには、秋だったこともあり、茸がたくさん生えていて、茸を前にして彼の蘊蓄を聞かされたものである。よく覚えているのが、猛毒だと思っていた紅天狗茸が、本来はうまみの成分をたくさんもった茸で、幻覚作用などはあるが、食べても死ぬことはほとんどない、そう言って、白い点々がついている真っ赤な傘をかじって見せてくれたことである。ちょっとだったこともあるのだろうが、彼は腹を壊すこともなく、元気そのものだった。
「確かに毒茸だけど、猛毒ではないよ、だけどそういっておかないと、幻覚剤の代わりに、若い連中が食っちまうとあぶないだろう、それで一般的には猛毒ということにしているんだよ」
そんなことを言っていた。
「きれいな、りりしい茸だろう、俺は好きだな」
とも言っていた。
そんな彼は、自分の得意なことを生かして、精神科医になった。他の精神科医と違うのは、天然物の薬効をよく知っていて、からだに無理のない薬を併用した、精神治療が得意ということである。精神を紡ぎ出しているのは脳だから、脳のことも知らないとね、そう彼は言って、脳と構造と機能も研究をしたようで、とても詳しい。
私は翻訳家となり、たまにノンフィクションの文を雑誌に載せるようになったことから、かなり前だが、精神科医になった彼にマニアの心理について話をきいたことがあった。それ以来彼とは飲む機会がない。
ビール片手に彼は、やはりマニアについて話し始めた。
「マニアっていうのは、なにかにとりつかれたことで、本人にとってハッピーだし、進歩するんだ、社会にとっても有益だな」
私はそれに対して、もっと詳しく説明をもとめた。
「それだけを見つめて、細かいところを解析して、さらに細かく分解して、知ろうとするだろう、それは科学研究と同じで、つきつめていくことはそれに興味を持っている人しかできない。結果はその分野に貢献していくが、一見、マニアのその人しか興味がないものでも、その結果が何らかの形で残っていると、それは一つの大事なものとして後に誰かが気付くものだ、場合によっては素晴らしく人の生活に貢献するものの発明につながる」
「難しいな、もし、鉄道マニアを例に取ったらどういうことなんだい」
「蒸気機関車のデゴイチに興味を持つマニアは多いだろう、それはデゴイチが、初期の機関車としての機能美を備えているから、多くの人が虜になるのだろうね、だけど人によって、デゴイチに対するはまり方が違う、ある人はその形に惹かれ、今まで作られた模型を限りなく集めようとするだろう。ある人はそのルーツ、どのように作られてきたのか、構造から調べようとする人もいれば、それに関わった人間に着目して歴史を調べようとする人もいるだろう、それはそれぞれのマニアの興味の気持ちしだいだ、それが集まったときに、デゴイチという機関車の全体が見えてくるわけだね、だから、マニアは大事な存在なんだ」
「なるほど、そうだな、誰かが興味を持たないと、その対象については深く掘り下げられることはないな」
「そうだよ、君だって、何かを書くときに、興味を持てなければ書けないだろう」
「そうだな、人間ってどうして、特定のものに興味を持つのだろう」
「大脳皮質の発達、連合領の発達、そういったことも関係があるが、動物的な部分、大昔から持っている原始的な感覚が重要なんじゃないかな、何かにこだわることは、動物にとっても、生活の発展につながる」
「それはどういうこと」
「おいしい実を探していくことは、その動物にとって、生きる幅を広げる可能性がある、もっとおいしいものと追いかけていくことによって、とても栄養価の高い実に出会ったとすると、その動物の種族の繁栄につながる」
「たしかにね、精神科の先生は、マニアックな考え方をするわけだ」
彼は笑って、「その通りだよ、人間に対する飽くなき追求、人間はおもしろい、何であんなものに興味を持つのだろうという人をたくさん見てきたよ、それが本人にとって、とてもまじめで、自分の気持ちに忠実なんだ、純粋なんだな、うらやましい限りだよ。もちろん病的な現象がたくさんあって、それが犯罪につながることもある」
「どんなことがあった」
「幼児の唾液を垂らすことに、興味を持ってしまった男が、それが自分の性的興奮につながったことから、幼児を誘拐したということもあった、とても極端な例だけど、人間の興味は恐ろしいくらい個人的なものだよな」
「君は、茸に興味を持っていたよな」
「今もそうだよ」
「あの真っ赤な紅天狗茸」
「うん、まあ、若い頃は茸の幻覚を引き起こす物質に興味があったな、今でもあるけど、医者として、脳に影響を及ぼす物質、特に精神的なものに関係するのは、商売上も重要でね、アーティストが自分の感覚に詰まって、新たな脳への刺激がほしくて薬に手を出す、アーティストでなくても、快楽を手に入れたい人間は、気持ちのよくなる薬がほしくなるわけだよ」
「今も茸を調べているんだ」
「うん、食べるのも好きだよ」
彼は笑った。
「茸が含んでいる精神を昂揚させたり、おかしくさせたりする物質の解析がずい分進んでいるが、今までにない物質が見つかる可能性だってある、それはとてつもなく興味があるね、新しい物質が脳のある機能だけを亢進したらどうだろう、たとえば記憶機能だけが何千倍にもなる物質が見つかったら、将棋や碁をやる人も、落語家も喜ぶだろうね、いうなれば新しいチップを開発して、コンピューターの記憶能力を増強させるということだね」
さらに彼はこう言った。
「人間の記憶の機能って、自分が好きになったことは増進される傾向がみられるね、好きなことはよく覚える、覚えなさいと強制されても覚えないが、自分から興味を持つと、その機能は目を見張るくらい強くなる」
それは自分でも感じていた、好きなことはいくらでも頭にはいる。
「知りたいと思うと、いくらでも知りたくなり、いくらでも頭にはいる、それがマニアの感覚に近いのではないだろうかね、だから、マニアはある意味では社会に、なにかを残していくんだろう」
よくわかった。
「ところがね、精神科領域で生きてくると、そういったこととはかけ離れた、奇妙なマニアというものもあることがわかってね、人間の脳の異常というより、奇抜さは限りないね、小説の題材はいくらでもあるということになるね」
「異常心理ということなの」
「そういう研究分野があるけど、それじゃ、なにが正常かということになると、そんな規範はないね、どのような領域でも、他の人と違ったというか、変わった発想を持つ人が新しいことを切り開いていく、そういう人は心理学者がいう、正常を逸脱した人だと思うよ、だから、異常心理学というのはまずいのではないかね、アーティストは新たなものを生み出すのに、異常になろうとしているわけだよ、ことばを変えなきゃ」
「それで、奇抜なマニアってなんだい」
「動物は、生きるということと子供を作るということにしばられている、人間もそうだけど、さっき話した幼児の涎と性との結びつきは人間だけだろうね、食と結びつく例としては、排出物を食べたくなるとかあるだろう、妊娠して土が食べたくなった人がいたな、匂いがそうさせたようだけど不思議だな、個人にとって、気持ちのいいことや嬉しいことはそれぞれ違うんだよ、これから話すことは最近、相談を受けたことだけどね」
ここからは彼が話したことを、脚色はしていないが、わかりやすいようにまとめたものである。それは高度な教育を受けたというか、知性のある外資系に勤める女性の話である。
その女性はヨーロッパのかなりの国の言葉を話すことができ、難しい専門的なことも説明のできる、男女かかわらす日本では珍しいグローバルな発想をもつ人である。
精神科医の友人はその妹という人から相談を受けた。妹は優秀な姉を怖いという。姉は誰に迷惑をかけているのではないが、いつか精神が壊れるのではないかと心配して彼に相談をしたということだった。
姉という人はとても他人に気を使うことができて、身の回りは整理整頓、几帳面でさっぱりさせ、周りに全く迷惑をかけない人だと妹は感じている。といって、人間味がないわけではなく、寧ろ人情に厚いという。独身なのだが、仕事人間の結果そうなっているのではなさそうだと妹は考えている。それでどうして精神科医の彼に相談したかというと、茸マニアだそうで、気になることがあるという。生えているところに行って茸の写真を撮ったり、茸の本を集めたりというものではなく、食べることが好きということだった。
茸を食べるのが好きな人はいくらでもいる。珍しいことではない。ところが、その妹の言うことには、信じられないほど、姉の茸好きが他の人とは違うのである。
姉と妹は両親の残した麻布の古くからある家で暮らしていた。遺産があり、仕事などしなくても暮らしていける身分である。しかし、姉は先ほど述べた通り、外資系薬会社でバリバリのやり手だった。相談しに来た妹は版画家であった。大きな屋敷だから、毎日家の中で顔を合わせるという生活ではない。姉は外国に行いっている日が多く、家にはあまりいない。妹の方が家にいることが多いが、版画のアトリエが笹塚にあり、制作が始まると、そこで寝泊まりすることから、やはり家にいないこともままある。家は昔からやとっている老夫婦にまかせている。要するに住み込みの執事と家政婦がいるのである。そういう意味ではふつうの家庭ではない。
二人がたまたま家にいるときには一緒に食事をしたり買い物に出かけたりする仲の良い姉妹である。
姉の茸好きは若い頃からで、二人で茸料理屋に行ったり、秋田から頼んで送ってもらった天然茸を、家政婦に料理をしてもらい、自宅の食堂でワインを選んで楽しんだりしていた。
ところが、妹が言うには、姉が四十を越えたころからか、茸を自分で採ってきて、料理をするようになったという。茸狩りのツアーに参加することも多くなった。仕事でヨーロッパによく行くわけだが、なぜか茸を隠し持って帰ってくる。それを自分で料理をする。生の茸は持って帰ることはできない、しかし姉はスーツケースに隠してもって帰るということがしばしばあった。
妹は、ああ、姉は本当に茸が好きなのだな、ヨーロッパでは朝市や、街角に店が出て、季節の茸を売っていたりするので、それを買ってくるのだと思っていたそうである。若い頃は姉にも外国にいい人がいるような雰囲気だったが、最近はそれがないと思っていたら、茸を持って帰るようになったということだった。
あるとき、もっと奇妙な出来事があった。梅雨の頃であった、姉が夜遅く数本の卵茸をバックに入れて持って帰ってきた。妹もそのときは家にいて、テレビを見ていたのだが、姉が「卵茸のバター炒めつくるから、ワイン飲もう」と帰ってくるなり、自分で料理をしたという。自分も手伝わなければと思って、妹もキッチンにいったそうだが、自分でやるということで、妹はワインの準備をして、料理をするのをしばらく見ていたということだった。
キッチンのテーブルの上に置いてあった大振りの卵茸には壷があり、土が付いていたということである。採りたての様子で、ずいぶん丁寧に掘って採った茸だと思ったという。誰かにもらったのかもしれないとそのときは思ったそうだ。姉は茸を大事な子供でも扱うように静かに壷のところを水で洗い、塩水に入れ、すぐに引揚げ、水分をキッチンペーパーで吸い取ると、料理をはじめたという。妹はそこまで見ていたそうだ。
卵茸はたしかにおいしかったそうだ。姉の料理を食べたのはその時が初めてだったが、海外に行くと、自分でそうやって料理をしていたのではないかと思ったという。卵茸は六本ほどあったそうで、どこで手に入れたのか不思議だったが、聞くことはしなかったようだ。近くで卵茸が生えているようなところは考えつかない。そのとき姉は、卵茸の傘を二つ、しかも炒めてもくずれなかったものを自分の皿に取り、残りはもう一つの皿に乗せて私の前に差し出すと、食べてと言った。
ワインをグラスに注いでくれて、自分は皿に載った二つの卵茸の傘に見入ってなかなか食べようとはしなかった。ただワインはすぐに口にしていた。
「見ているだけでしあわせね、あなたは食べてね」
そういってワインを飲み干した。
妹はワインを飲みながらおいしく食べたそうである。ところが姉は、妹が食べ終わると、やっと自分の皿の上の卵茸の傘にナイフを入れ、口に運ぶと、妹をみて微笑んだそうだ。おいしそうに。
ちょっと奇妙だなと思ったのだが、それはそれで終わったようだ。
その年の梅雨は長く続いた。そのさなか、姉にしては珍しく、頻繁に家にもどってきて、卵茸の天ぷらを作ったり、卵茸入りシチュウを作ったり、妹に食べさせてくれたという。妹は版画製作のために家に帰らなかったこともたびたびあったので、もっと何度も茸料理を作っていたのだろうということだった。妹は次第に姉の茸に不信感を抱くようになったが、それは姉のもって帰った卵茸が必ず採ったばかりのものだったからである。どこでこんなに新鮮な卵茸がとれるのだろう。
たまたま妹が日野の知人宅に遊びに行ったときのことである。庭に卵茸が生えていたのでもらってきた。妹はそれをオムレツに入れて夕飯にだした。ところが姉は食べなかった。どうしたのと聞くと、ちょっと胃が疲れたと答えたそうである。あれほど卵茸ばかり食べていた姉がその卵茸には箸をつけなかったのである。
しかも、その二日後には、姉は帰りが遅かったにもかかわらず、自分でもってきた卵茸で天ぷらを作った。傘だけを天ぷらにして、柄のところはホイル焼きにした。妹はもう胃は治ったのだろうかと奇妙に思ったそうだ。その日、姉が帰ってきたとき、妹は玄関に迎えに出たのだが、なんだか土臭いと思ったという。パンタロンの裾にちょっとばかり土が付いていたのも気になったとのことである。黒いパンタロンなので、乾いた土が、ちょっと目立だっていて、ハイヒールにも土が付いていた。
出来上がったてんぷらを前に、姉は妹に言った。
「日本酒なにかあったかな」
洋酒党の姉にしては珍しいこともある。妹がもらった高清水があると言うと、「冷えてるの」と聞くから、首を横に振った。
「でもいいわ、開けていいの」と妹から四合瓶を受け取った。
「おいしそうにお酒も飲んでいたわ、そこで、「お姉ちゃん、パンタロン土臭かったね」と聞いたそうである。
「うん、よごしちゃった、新宿で道の端においてあったプランターが壊れていてね、土が歩道にこぼれていたのよ」
そう言った。しかし、あの匂いはプランターに入っている土の匂いではなくて、かび臭い匂いだったと妹は思ったそうである。
その秋は、何度も土臭い匂いをさせながら、夜遅くに帰ってきて、卵茸をもってきた。その匂いが、世界を飛び回って、何カ国もの国の言葉を操って、大きな取引をしている姉と大きなギャップがあり、妹はますます姉が心配になってきた。
次の年の春、連休の頃だそうだが、姉は卵茸ではなく、黄土色でボコボコ穴があいた傘を持つ網笠茸を、「モレーユよ」と喜んで持って帰ってきた。それも採り立てのようだった。
「フランスではだれもが大好きなのよ、網笠茸って昔からあるのに、日本人は食べなかったのよ。卵茸と同じね、卵茸は真っ赤で、あれは毒だと思いこみ、網笠茸は格好が不気味だから食べないのよ。日本人は、松茸の形をしていなければ食べられる茸じゃないと思ってたのかしら」
などと言いながら、七、八本あった網笠茸をバター炒めにして、
「さーワインかビールにしよう」とテーブルにならべたそうである。
網笠茸は確かにおいしかった。それで、
「どこで手に入れたの、採ったばかりのようだったじゃない」
「会社の部下の家の庭に生えたのよ、私が茸好きというのを知っていて、もってきてくれたの」ということだった。
それから、五月の半ば頃まで、よく網笠茸をもって帰ったそうである。
妹の話では、茸を持って帰ってくるときは必ず帰宅時間はいつもより遅かった。遅いといっても八時から九時の間だから、普通の勤め人にはそんなに遅くはないのかもしれない。だが姉の会社は五時には必ず終了、残業なしを基本にしていた。会社に出なくてもできる仕事は自宅ですることを会社は推奨していた。外資系の見本のような会社である。もっとも姉は部長だったので、なかなかそういかないみたいで、時期によっては、夜中になることもあった。海外出張はかなり多い。
網笠茸の季節が終わったとみえて、しばらくは茸を持って帰るようなことはなかったが、六月に入って、まだ梅雨の前なのに、卵茸を持って帰ることが多くなった。この一年で姉はずいぶん変わっていったというのが妹の感想である。
ある日曜日、珍しく姉の友人三人が訪ねてきた。その日のことを妹はこう話した。
「姉はいろいろ料理を作ったわ、いつもは茸が手に入ったときぐらいだけど、元々料理は嫌いじゃない人だったから、それなりのものは用意したわね。
四人はなんだか楽しそうに話をしていたわ。ちょっと経ったとき、姉が私を呼びにきたのよ。私は興に乗ると食事もしないで、版画の原画づくりにぼっとうするの。姉は決してじゃまをしなかったわ。そのときも様子を見に来て、大丈夫と思ったから、声をかけてくれたのよ。姉の人に対する配慮はたいしたものよ。だから言葉もすぐ覚えるし、よその国の人ともすぐに打ち解けるのね。
私もちょっと仲間に入ったわ。そうしたら、友達の一人が、姉に寺周りをしていないのか聞いていたわ。何の話だろうと、口を挟まないで、ワインを飲んでいると、どうも、姉は寺回りが趣味だと思われているようでした。姉は日本のそういうものに、興味のない人だと思っていたので、ちょっとびっくりしたわ」
「そんなことがあって、姉に、お寺回りなんてしてるの、と聞いてみた。姉は、まあね、外国に行ったときに日本のことをよく聞かれるでしょう、私そこのところ弱いから、ちょっと勉強にね、と言っていた。
姉が勉強というのにはかなり違和感があるわ。姉は勉強という言葉がだいっきらいなの、彼女自信、相当度力をしているのよ、だけど、それが外にみえるのが嫌いなの」
そのとき妹は姉がなにか隠していると思ったという。
「姉は月に何度か海外から帰ってくると、その整理を終え、一日か二日の休みをとることが多い。日本の会社ではそうはいかないが、さすがに外資系であって、その辺ははっきりしている。そういうとき、箱根などの近場であるが、リゾートホテルに泊まって、食事やエステを楽しんだ。昨年、卵茸を持って帰るようになってからは、海外出張のあとも休みを取ることがなく、遅くかえってくるようになった。寺参りにでも行っていたのか、もしそうであったにしても、私に隠す必要はないのに」、と妹は首をかしげていた。
友人はそこまで話して、
「それで、その女性の驚いたマニアックな、フェティッシュというのかな、趣味が妹に知れることになり、それで妹が私のところに相談にきたということなんだ」
と一息入れた。
私にはそこまでの話から、その女性のマニアックな趣味というのが茸で、特に卵茸にご執心ということしかわからなかった。好きな食べ物はいつもきらさないようにしているという人はいくらでもいる。
彼は続きを話してくれた。
ある夜の八時頃、妹のところに警察から電話があったそうである。谷中の交番からであった。お姉さんを保護しているということだった。
妹は姉がお寺にでも行っているときに、ひったくりにでもあったのではないかと思ったそうである。しかし気丈の姉だから、そのようなことで、警察に妹へ電話をさせることはない、とすれば怪我でもしているのかとちょっと心配になった。それで版画の作業をやめて交番にかけつけたそうである。
すると、姉はちょっと困ったような顔をして妹を見たそうだ。その顔は大事な秘密をみつかった子供のような目つきだったということだ。特に服装の乱れとか異常はなく、ブランドものをぴしっと着こなしていたということである。
警察官の話はこうだ。
「お姉さんが定光寺の墓場を徘徊されていていました、前々から寺の住職に、夜あまり遅い時間じゃないのですが、墓場をうろうろしている女性がいる、気味が悪いので見回ってほしいということを言われていたのですよ、それで、本官が見張っていたところ、墓石の間をかがみながら歩き回っているお姉さんを保護したというわけです。ただなにかが壊されたとか盗まれたと言うわけではないのですが、女性が暗い墓場を歩き回ること事態心配でして、そう言って、墓場にいた理由などをお尋ねしたのですが、何もおっしゃらない、それで本署に連絡しますよと言いましたら、それは止めて欲しいとおっしゃいましてね、家の電話番号をおっしゃいました。妹がいるからというので電話した次第です。まだお名前もちゃんとお聞きしていません。何か事件が起きたわけではありませんので。
住職は墓に葬られた方と関係のある人で、その場で自殺とか、何か起こされると困ると思っていたようですが、特にお姉さんを訴えるとかそういうことではありません。ご家族に引き渡してもらえばそれでいいと言うことでした」
妹は姉をともなって、タクシーで家まで帰ったという。
それで姉に理由など聞かずに、風呂にはいってもらい、ワインを飲みながら、理由を聞いたそうだ。
「大した妹さんだね」
精神科医の彼は話しに間をおいた。
どうして、と私が聞くと、
「おうおうにして、そういう場合、家族は当事者をすぐに問いつめて、精神的に追い込んでしまうのに、そういうことをしなかったんだ」と答えた。
「それでワインを飲みながら姉は妹にこう言ったそうだ。観念したんだろうね、人によっては黙りこくってしまうのもいるのだろうが、彼女自信もよくわかっていたのだね。妹さんを信用していたということもあるね」
「それでなんと言ったんだい」
『墓場の茸がおいしいの』
「妹はあまりにも考えていなかった返答なので、何と言っていいのかわからなかったそうだ。それはそうだね、それでも妹さんはさらに偉いと思うよ、その理由を聞いたりしなかった、こう言ったそうだ」
『お姉ちゃん、ふつうの茸と墓場の茸と味がどう違うの』
すると、姉は『ほかの茸の味は感じないくらい』
と答えたそうだ。だから、妹が作った卵茸の料理を食べなかったわけだ。
それで、精神科を探し、茸の成分を研究している私のところに相談しにきたわけだ。私の調べているのは茸の向精神薬で、味とは関係ないけど、茸のことをやっている精神科医なんて、表立っては俺のほかにいないからね」
彼は笑ってそう言った。さらに、
「精神科医や心理学者より、普通に生活している人の方がより人間を知っている人がたくさんいるよ」
彼はそう言ったが、私はそうは思わなかった、ほかの精神科医はしらないが、彼でなくては精神の治療できないだろう。そう思うくらい彼はいい医者である。
「それで、妹さんは君に姉をどうしてほしいと言ったんだい」
「彼女はすごいね、治さなくていい、と言ったよ、ただ、もっとおいしい物を教えてほしいってね、とても難しいけど、一番いい解決方法だよ、妹さんは人間を知っているんだ、アーティストはそうじゃないとね」
「それで治療してるの」
「うん、いまやっている、それでね、妹さんはもう一つ言ったんだ、姉はどうして墓場の茸が好きになったのでしょう、墓場なんて縁がなかったはずなのに」
これは、精神科医の治療の基本だよね、原因の解明と言うことでね、それで最初にそれをしましょうと、妹さんには言ったんだ」
「それでどうしたの」
「うまくいった」
「どうしたの」
「どうしたと言うより、そのお姉さんも、自分のことをよく知っていたんだね、いや、そのことを誰かに話したかったのだろうね」
それから彼はこういう話をした。
「あの定光寺に葬られている男性と関係があった」
私には墓場の茸が好きなことと、男性の墓と結びつかなかった。
「定光寺の古くからのある檀家の次男坊がなくなって葬られていた。姉と、おそらく一緒になっていただろう男性だ、妹さんも姉にそういう男性がいたということを知らなかった、姉の大学時代の同級生だよ、きっと相思相愛だったのだろうな、若い頃の一途な気持ちだろう、私が調べた限りでは、亡くなった彼はとても優秀な科学者の卵だったようだ、どこかの大学で必ず研究室を持って、おそらく世界にも知られるような人になっていたのだろうな、お姉さんは彼に尽くして、それを支えたいという気持ちでいっぱいだったのだろう。彼は大学院の博士課程に進み、彼女は外資系に就職した。当時は二人とも自分の道を精一杯生きていたのだと思う。彼はとある大学の助教になり、助教授、いまでいう准教授になった。そのころ、彼女も外資系の会社の大事なポジションに進んでいた。それでも彼が助教授というポジションを得たとき、彼女は家庭にはいって彼をサポートするつもりだった。こういったことは、彼女はおくびにもださなかったのだろう、妹さんはまったく知らないと言っていた、妹さんも版画家としてまだこれからという立場だったから、あまり姉のことには気に掛けていなかったと言っていた。ところが、彼が海外の学会に行くために乗った飛行機がおちた。二百人もの客が犠牲になった。彼もその一人だった。それで、定光寺に葬られたのだ。彼の両親も姉のことを知らなかったようだ。姉とその男性とは外から見ると、全く無縁だったのだ」
「だけど、墓場の茸が好きになることとつながらないな」
「そうだね、彼女は男性の家族には知られることはなかったが、毎月の命日には墓参に行っていたのだよ、ただ、彼に会いたい一心で花を手向けるとかそういうことではない、おがむだけだったようだ、それに彼女も仕事が忙しく、ともかく遅くなってもその日には、タクシーで墓に手を合わせに行ったようだ、それで、ある日、彼の墓の前に真っ赤な茸が生えていたんだ。彼女は彼からの贈り物だと思った。採ってきて、自分の部屋に花瓶にさして飾ったんだ。そのときには茸の名前も知らなかった。調べたら卵茸という、シーザーも好んだおいしい茸であることを知ったんだ。
ちょうど梅雨の時で、しばらくおいて夏の終わりに、要するに月命日に行ったときにも、卵茸が生えていて、それを採って帰って、たった一つだけど、炒めて食べたそうだ、それはおいしく、それ以後、墓場に生える卵茸を探し歩いたようだ、どの寺でもよかったようだよ、それは、彼からのプレゼントだと思ったようだ」
「妹さんも知らなかったわけか」
「そうなんだ、墓場の茸が好きになるとは信じられないとも言っていた、姉はそんな感傷的な人ではないと思っていたようだ」
「僕も信じられないな」
「網笠茸はどう説明できるの」
「網笠茸もね、条件がよければ墓場でも庭でも、砂利のしかれた玄関の前でも生えるんだよ、たまたま男性の墓の近くに生えたのでないだろうかね」
「墓場に生えた茸ならなんでもいいのかな」
「そう彼女の頭の中では、墓はみな死んだ彼の墓なんだ、墓を見れば彼を思う気持ちで一杯になるんだ。いちずな人なのだな」
「人間の気持ち、感情は行動をかえてしまうんだね」
「そうだよ」
「それにしても、普通なら墓場を好きにならないけどな」
「普通ならね」
「それで、その女性は治ったのかい」
「治った」
「さすが、名医だね、どうやったの」
「今、うちにいる」
どのような意味かわからなかった。
「精神科に入院しているということなの」
私は人間に疎いようだ。
「俺の女房になっている」
そうか彼は結婚していなかった。どうして結婚していなかったのかは知らないが、学生時代からあまり女性に感心はなかった男だ。女性に自信がなかったのではないかと思っている。それが結婚する気になったのは、彼女に魅力があったからだろうが、きっと、マニアックな、フェティッシュな頼りになる女性を求めていたのだろう。きっと、彼は彼女をそちらの方に導いて、彼女の気の病を治し、自分の頼ることのできる女性を手にいれたのだ。精神的に弱っている人は医師に惚れやすいと言うことを彼はいつか話していたことがある。親切に接するものだから、患者さんは医者が自分に惚れていると思い込み、自分もその気になってしまうのだ。
「今では、どのような茸でも料理してくれるよ」
彼ののろけである。しかし、本当に治っているのだろうか。妹がだまされていたように、友人もだまされているのじゃないだろうか。
ともかく結婚はうまくいっているようで、そのうち会わせてもらえるだろう。私は精神科医じゃないが、物事を文にまとめるにあたって、人間についての勘は備えていると思っている。
「結婚っていうのはいつの話なんだ」
「一月前だよ、もうこの年だから、結婚式も挙げなかったけどね」
「何だ、水くさい、お祝いの一言もいったのに、いやおめでとう」
「てれくさいね、渋谷のマンションに引っ越すことになってるから、引っ越したら君を呼ぶつもりだったんだ」
「そりゃあ楽しみだ、で、なにがほしい、お祝いに」
「いや、それじゃあ、うちに呼ぶから、そのときににワインでもくれよ」
「俺はワインは選べないから、好きなのがあるならそれにするよ」
「いや、俺もよくは知らない、彼女もワインは好きだが、あまり銘柄を気にしていないようだ。
「それじゃ店の人に選んでもらうから、それでがまんしてくれ」
「もちろんいいよ、催促したみたいで悪いな」
「そんなことないさ、欲しいものを言ってもらったほうが僕の方でも助かる」
その日がきた。
私はデパートで選んでもらった赤と白のワインを持って彼の家に行った。渋谷に新しく立った五十五階建ての五十四階に彼らの家があった。
奥さんになった人は以外と小柄で、色白の美人であった。考えていたような、バリバリの仕事人間には見えない。
私はワインを奥さんに渡すと、本当に嬉しそうに笑った。正直な人であることがわかった。
「今日も茸料理だよ」
彼はその前に持ってきた赤ワインをあけるという。
つまみは作ってあって、ハム、ソーセージ、それにチーズのたぐいが用意されていて、卵茸のオムレツができあがったところだそうであった。
メインのヒレステーキは後でいいだろうと、彼が奥さんに声をかけると、奥さんもテーブルについた。
奥さんは仕事も辞めて、彼のサポートをするということである。外資系でそこまでの地位にいるなら、もっと上をねらっているのだろうと考えていた私は、全くの読み違いをしていたようだ。
「私、彼の好みの料理を作るようになりたいと思っています」
昔の日本女性の典型になっていた。
「卵茸のオムレツは味がつけてありますが、もし胡椒などが足りないようでしたら、これをお使いください」
親切にも彼女は胡椒の瓶をわざわざ渡してくれた。彼女はと見ると、やっぱオムレツに胡椒をふっている。彼女のオムレツの上に、黒っぽい物がふりかかった。そのとき、話にでていた、土の匂いがぷーんと匂った。なんだろう。
友人は別の瓶から胡椒をふっている。白っぽい粉がオムレツにかかり、かなり強い胡椒の香りが漂ってきた。
「いろいろな胡椒があるのですね」
「ええ、私がアレンジしています、彼の胡椒は彼の好みにしてあります」
「彼女は胡椒マニアなのだよ、これは彼女専用の胡椒でね」
彼女が使った胡椒を目でさした。
もともと胡椒にこだわりがあったのだろうか。妹さんの話にでてこなかった。
私は奥さんが使っていた瓶を指さした。
「みんな味が違うのですか」
「はい、お渡ししたのは卵茸の味が引き立つようにアレンジしたものです」
かけて食べてみた。確かにただの胡椒ではない。卵の味に茸の味が強まって、おいしい。
「産地の違う胡椒の実を混ぜて、塩やほかの香辛料もほんの少しですけど加えて作ります」
本当にマニアックだ。
「僕に軽い嗅覚障害の気がある物だから、配慮してくれているんだ」
「鼻が悪くなったの」
「子供の頃からね、アノズミアじゃなくてヒポポスミアの軽いやつ」
「なにそれ」
「アノズミアは先天的だったりする全く匂いを感じないやつだけど、ヒポポスミアはアレルギーなどで、感覚が低下している奴だよ、俺はアレルギーがあるからね」
それは初めて知った。
「彼女の作る胡椒には採ってきた卵茸の乾燥したものもはいっているんだ」
「アミノ酸が、なんでもおいしくしてくれるでしょう、味の素のようなものです」
なぜ卵茸なのだろうか。
「アルバイトで採ってきてくれる人がいるんです」
どこで採れたのをと聞くことはしなかった。
彼女はステーキを焼きにキッチンに行った。
程なくおいしそうに焼けた肉ができあがった。じゅうじゅういっている。
またいくつかの胡椒の瓶もでてきた。
「このお肉、赤みにしましたの、霜降りの方がよかったかしら」
「いえ、あまり脂身の強い物より赤みの方が好きです」
「本当ですの、それならよかった、この胡椒があいますわ」
また胡椒の瓶を渡してくれた。しかし、本人はオムレツの時と同じ物を使っている。
彼女が胡椒をふると土の匂いがぷーんとする。
私も肉に胡椒をふった。肉はとても柔らかくておいしい。彼女がアレンジした胡椒は確かに肉を引き立たせる。あまり胡椒胡椒とした匂いではない。
「おいしいですね」
赤ワインがまたおいしい。
「よかった、僕もこの人がこんなに料理ができる人だとは思っていなかったんだ」
彼女はうなずきながら、
「これから、胡椒だけではなくて、唐辛子もアレンジするつもりですの」
と言った。それから、
「ずいぶん香りに敏感ですのね」と、何か心配そうな顔をした。
友人は「いや、彼は食べることには長けているんだよ、昔からの付き合いでね、おいしい物はよくわかるよ、それに彼はお世辞をいわないよ、あなたの料理は本当においしいよ」
私もうなずいた。確かにおいしい。それに思った。この女性の方が相当香りに敏感な人だ。特に食べることに関しての香りに、マニアックな何かを持っている。
それにしても、あの土の匂いは何だろう。
その日はおいしい思いをして、彼らの新居からおいとまをした。
あの彼女専用の故障の土の匂い、その点だけが頭に残った。
彼女は、彼女あの胡椒の匂いを私が感じてしまったかもしれないことを心配していたのではないだろうか。
あの匂いは、もしかすると、墓の土の匂いではないのだろうか。卵茸の香りも混じっている、墓場の茸の胡椒を自分用に作ったのではないか。嗅覚が低下している彼ならば気づくことはないだろう。治療を受けている時に、彼のことを調べ上げ、治った振りをして、自分の新たな安定した未来を作り出したとすると、相当頭のいい女性ということになる。
彼女の病気は治っていない。墓場の卵茸がやはり好きなのだ。それしか食べたくないのだ。自分で取りに行く必要はない、誰かに採らせているのだ。卵茸を土をたっぷりつけたまま採ってきたものを高く買ってそれを胡椒に混ぜる。
それに、亡くなった昔の彼に執心してと言う部分は彼女の作り話かもしれない。確かに最初は彼の墓のところで卵茸を見て、採って食べたのかもしれない。それが、彼女のもともと持っていた、食に関しての偏愛的性質が墓場の匂いと卵茸の味に結びついてしまったのかもしれない。
そう思ったが、私の推測であり、そんなことを彼に言っても、彼らが幸せになるわけではない。彼女は自分の未来を自分で切り開いたのだ。ある意味では治ったということなのだろう。いや、病気ではなく、ただのその本人の趣味にしかすぎない。誰にも迷惑をかけなければいいのである。
それは私の妄想かもしれない。こういった妄想を抱いて、それを小説に書くのが学生の時と同じで、相変わらずの私の趣味でもある。
墓場の茸


