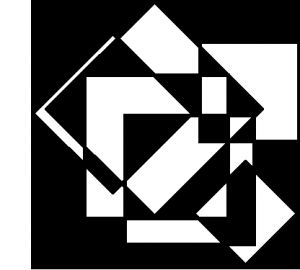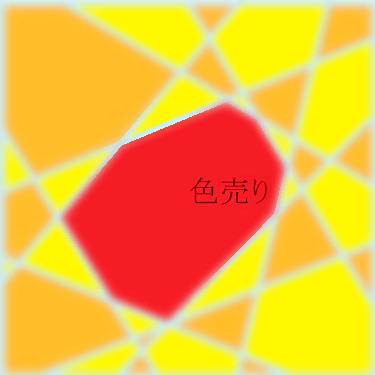
色売り
拙い文章ですが、お願いします。
目の前では、実に様々な色が売られていた。赤や青はもちろんのこと、中には、聞いたこともないような名前の、目にも鮮やかな色が並んでいる。
「すごい……」
わたしは思わずため息を漏らした。こんなにたくさんの色を見たのは、これが初めてだ。
「そうだろう」
父は得意げに言う。わたしは黙って頷いた。
ここ、通称カラーロードは、日本で一番の色市場だ。道の両側には、色の素専門店がずらりと並んでいる。それぞれ、色のバリエーションが違うらしく、どの店も人がたくさんいた。
わたしたちが入った店は「万華鏡」という名前だった。世界各国から、たくさんの色の素を輸入しているらしい。
目の前で女性が色の素を選んでいた。その人は、豪華な色の服を着ていた。髪の毛が、金色だ。
わたしはその人と自分を見比べる。わたしの服は、少し模様が書いてあるものの、ほとんど白のようなものだった。髪も、真っ白だ。
女性は、小さなびんを隣にいた、連れらしき人に見せている。青っぽい色の、素だった。
わたしは背伸びをして値段を見る。ぎょっとした。
高さ五センチほどのびんが、五万円だったのだ。
女性は小びんを持って、会計に向かっていった。そのあいだも連れの人と小瓶に入った色の素について話していた。
わたしは父を見上げた。わたしの視線に気づいたらしく、
「なんだ、お前もほしいのか?」
と訊いてきた。わたしは大きく縦に首をふった。
「じゃ、これでいいか?」
父が見せたのは、ワゴンの中にあったものだった。小びんには、赤っぽい色の素が詰まっていた。ちらっと見えた値札には、五百円、と書いてあった。
五百円の色の素を手に持って、わたしたちは家路についた。
とちゅう、田んぼのわきを通った。白い稲穂が垂れている。白い水の流れが、光っていた。もう、太陽が山の向こうへ沈むころだった。
色に満ちていたカラーロードとは打って変わって、ここは真っ白だった。道路も、家も、田んぼの土も。わたしはカラーロードの光景を思い浮かべていた。
「今日は、どうだった?」
父が訊いてくる。
「うん! とっても楽しかったよ。いろんな色も見れたし」
「そうか、それはよかった」
父はわたしの頭をなでた。わたしは笑って「ありがとう」と言った。
わたしたちの世界から、色がなくなったのは一五年近く前のことだそうだ。
一五年前に、一色、とかいう科学者が「色吸い取り機」なるものを開発したらしい。そんな馬鹿な、と思うが、実際に色がなくなってしまっているのだから本当なのだろう。
「色吸い取り機」を使うと、ものの色が消えてしまう。この発明に目を付けたA社が、商品化をした。どこにそんな需要が、と思うのだが、人は珍しいものに弱いらしい。全世界で飛ぶように売れたらしい。すさまじい勢いで「色吸い取り機」は広がっていった。
そんな中、「色吸い取り機」を使って色を消した、白いトマトが売り出された。それもまた、物珍しさから大量に売れたらしい。
そして、事件は起こった。
人の肌の色が消え始めたのだ。口の中や、瞳の色も。
人々はパニックに陥った。開発者である一色博士や、発売元のA社に問い合わせが殺到した。
だが、対応策がとられることはなかった。一色博士や、その他、A社の社員全員が、死んでいたのである。「色吸い取り機」で色が消える理論や、その製造方法は、まったくわからなかった。人々は、ただ、色が消えていくのを眺めているしかなかった。
そして「色吸い取り機」が発売されてから、四年足らずですべての動植物の色が消滅したと報告された
世界は、このことを受けて国家間の人の移動を規制した。色が消えるメカニズムがわからない今、下手に行動するのは危険だ、という考えに基づいてのことらしい。この時期に、新種のウィルスによる作用で色が消える、という論文を発表した学者がいたことも、規制をした要因になっていただろう。
そうした対策が施されたのにもかかわらず、ついに、人の色まで完全消えてしまった、と日本で発表されたのだ。「色吸い取り機」発売から、一〇年がたったころだった。
ついに色が完全に消えてしまった。日本は混乱に満ちた。
この出来事を、カラーパニックと呼ぶ。カラーパニックは、一か月ほど続いた。
パニックを鎮めたのは、B社という小さな会社だった。B社は、なんと、消えてしまったはずの色を作り出したのである。
B社は作り出したものを「色の素」という商品名で売り出した。
「色の素」はどんなものにも色をつけられる、というものだった。色を失った日本人は、争うようにそれを買った。本物かどうかなんて、関係なしに。
「色の素」は本物だった。失われた色は元に戻った。だが、「色の素」は製造に莫大なコストがかかる。そのため、とても高級なものだった。また、原料にも限界がある。
結局、「色の素」はすべての色を戻すことはできなかった。考えてみれば当たり前のことだが。
しかし、色が戻るということがわかったことは、人に安心を与えたのは確かだった。人は安心から、色に対して焦りがなくなった。
そして、色はファッションと同じようなものになった。色を身に着けるのは、人々の間に瞬く間に浸透していった。
そして今では、日本は色の一大マーケットとなっている。
家に帰ると、わたしは自分の部屋で、小びんをあけた。
赤い粉がぱらぱらと落ちる。わたしは指でこすってみた。きれいな赤だ。
布の上に粉をふりかけて、上から水を垂らす。
粉はすぐに溶けて、布を染めた。
「きれい……」
わたしはそう思った。
わたしはまた、ふりかけた。布がどんどん染まってゆく。
その様子を見ているのが楽しかった。
また、同じことを繰り返す。
何度も、何度も。
いつの間にか、小びんにいっぱいだった粉が、残りわずかなことに気が付いた。
わたしは少し、興味がわいた。本当はこんなことしてはいけないのだろうけど。
――どんな味なんだろう。
わたしは指に粉を付けた。
おそるおそる口に近づけてゆく。
舌に、触れた。
それは、鉄の味がした。
すぐさま水を口に含んだ。いやな味が口の中に広がる。
わたしは水を何杯も飲んだ。少し、気分が悪かった。
ある日のニュースで、こんなことが報道されていた。
「世界の人口が、減少しています。一五年前、七〇億人を突破していた世界の人口は、最新の調査で、およそ四〇億人に減少したことがわかりました。なお、地域別の減少率を算出したところ――」
わたしはそのニュースを見ながら、棚の中に仕舞ってある小びんを眺めていた。
黒、白、黄色、赤……。ほかにもたくさんの色が棚に並べてある。
子どもの頃、父と見た色の感動が忘れられなくて、わたしは「色の素」を集めるようになっていた。いまなら、小びんに五万円を出したあの女性の気持ちがよくわかる。
わたしは棚から赤の小びんを取り出した。
「今日はこれを使おうかなぁ」
わたしは鼻歌を歌いながら、小びんから粉を取り出した。
色売り