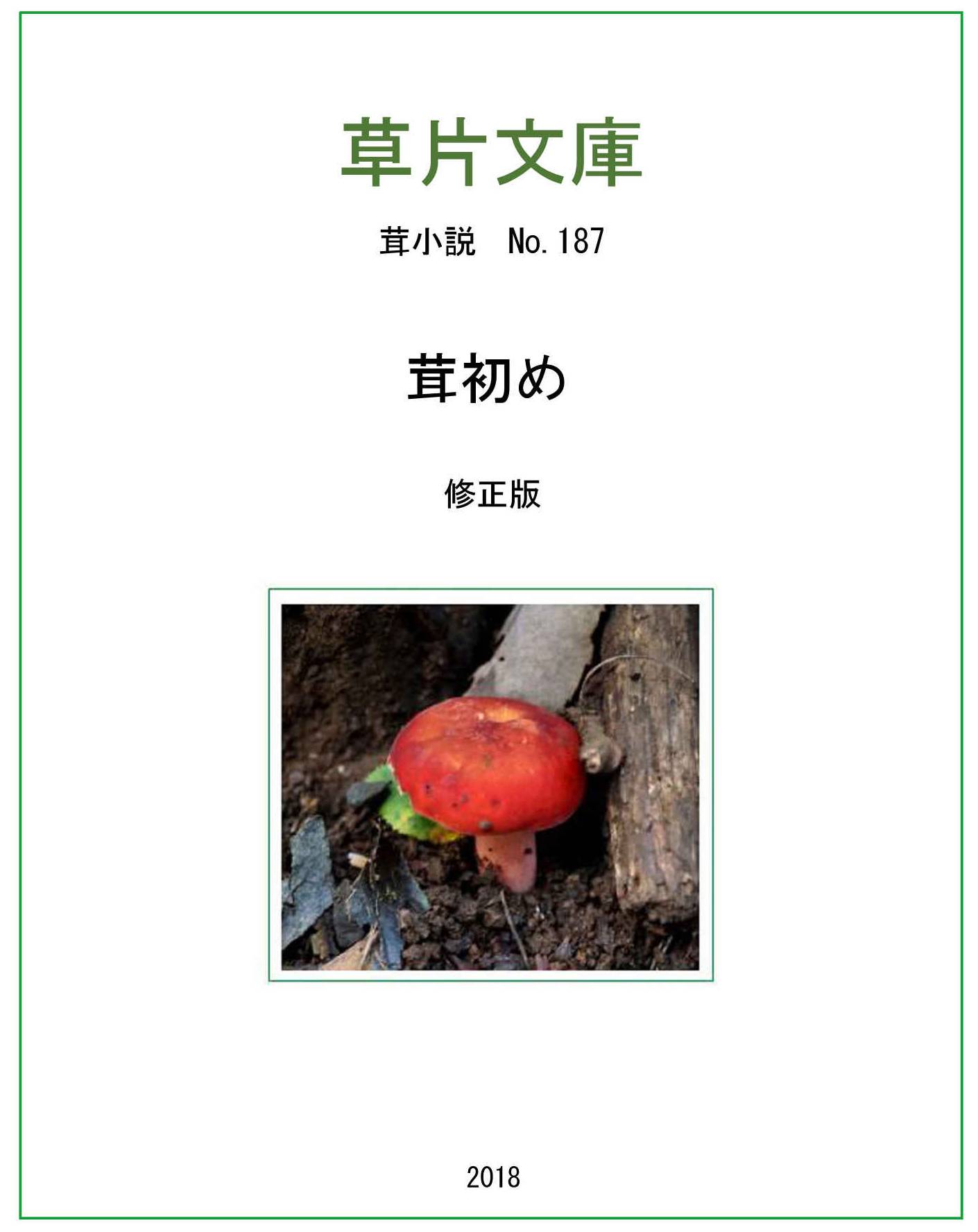
茸初め
茸のファンタジー
見上げると真っ青。少しばかり白い雲の筋が空を切り裂いている。秋晴だ。秋雨前線が海のほうに後退したのだろう。今日は一泊の小旅行だ。ラッキー。
朝の六時、高雄駅から各駅停車の小淵沢行きに乗った。今日は小淵沢のペンションに宿をとり、八ヶ岳の麓をぶらぶら歩くつもりだ。いつものようについてから宿を決めるつもりで、気楽にでてきた。どのペンションもチェックインは3時頃なので、どこかよさそうと思うところがあれば途中下車して散策しよう。
小淵沢まで各駅停車だと2時間30分もかかる。特急と比べると一時間ほどゆっくりしている。途中の駅で2、3回、特急の通過待ちをする、その時間が長い。それがなければもっと早いのだが、そこがいいところだ。窓の外の景色をぼんやり見るのも、慌しい会社での仕事を忘れさせてくれる。平日のこともあり、ボックスに一人ずつ腰掛けて、それでも空いている。ゆったりといける。
窓の景色を眺めていると、勝沼、山梨市とすぎた。さて、次の駅はどこかとアナウンスをまっていたのだが、聞き逃したようだ。止まった駅はホームの木の柱がペンキで白く塗られていて、昔の駅舎の面影がある。さて、なんと言う駅だろう。駅舎は木々に覆われているようで、鳥のさえずりさえ聞こえる。降りてみよう、勘があたることも多い。とっさにそう思って、リュックをつかむと、ホームにおり立った。その瞬間、電車の扉が閉まって動き出した。
ホームの上の二本足の看板を見ると、濃い緑で「草の原」とある。中央線はよく利用するが、このような駅があっただろうか。覚えがない。特急列車を使うことが多かったこともあり、各駅しか止まらない駅の名前は頭に入っていない。
ホームの中程に下に降りる階段があり、出口の表示があった。下に降りていくと、左右に通路が分かれている。おりた階段の正面に右は原町、左は虫湖と表示がある。虫湖とは面白そうだ。行ってみよう。通路を左に曲がると、改札口に駅員さんがいて、手を振っている。誰かいるのかと思ったら、僕に向かって手を振っているようだ。
「お客さん、すみません、今日は虫湖にユスリカの大群が押し寄せていて、接近禁止になっています、許可証をお持ちですか」
そのようなものを持っているわけはない。
「この時期、いつもは、そんなことはないのですが、急に現われてしまって、いつも見ることのできる源五郎、水澄まし、水カマキリ、トンボたちが避難してしまっています」
面白いことを言っている。
「行くことができないのですね」
「研究許可証がある方だけはお通しできます」
水棲昆虫を保護している湖かもしれない。
「残念だなー」
「観光ですか、でしたら、反対側の原町は今いいシーズンです」
「そちらに何があるのでしょう」
「茸の泉があります、いい町ですよ」
駅員さんの頭にカマキリが飛んできて止まった。
「やあ」
駅員さんが挨拶している。のんびりしたもんだ。
まあ、それも面白そうだ。駅員さんに礼を言って、右側の出口に向かった。
やはり改札口には女性の駅員さんがいた。手に赤い茸をもっている。
「どうぞ、こちらが原町口です」
にこにこして茸を振った。茸が何か意味あるのだろうか。
JRのスイカをタッチする装置がない。
「これはどこにタッチすればいいですか」
丸顔の駅員さんが大きな目を見開いて、それは何という顔をした。
「これをタッチする機械はどこでしょう」
再び聞くと、笑いながらうなずいて、空いている手の平を私が持っていたパスネットにタッチした。
「楽しんできてください」
なんなのだ。よくわからないが、外に出てしまった。駅は雑木林に囲まれていて、その中を舗装されていない道が遠くに見える町の方に続いている。
てくてくと歩いていくと、雑木林からいきなり十字路に出た。目の前に町が開けた。
特に変わったところのない町である。まっすぐに延びた通りに沿って、商店街が並び、商店の奥には住宅が連なっている。歩道には街路樹が植えられていて、街灯にはスズランのような傘の電灯が立っている、角には赤いポストがある。
いや見落としていた。電柱が一本もない。最近都内でも電線を地下に埋めようとしているが、この町ははじめからそのような都市計画になっていたのに違いない。新しい町なのだろう。見た感じではむしろ一時代昔の面影がある。
あ、それに高いビルがない。それもきっとこの町の計画なのだろう。
まだあった、信号機がない。どうしてだろう。歩道と車道は区別されている。商店街に車がおいてある。ということは、車は利用されているわけだから、信号がないのはおかしい。
私が道を渡ろうとすると、右の方から赤い車がきた。車はすーっと、交差点の前で止まった。私が渡ると、車も動き出した。私を見たから止まったのではなさそうだ。人が道を渡っているというシグナルが車にいく仕掛けが十字路に施されているのだろうか。
そういえば、横断歩道のマークがない。
道を渡り、商店街の前を歩いていくと、また変わったところを見つけた。歩道に街路樹が植えてあるが、それが赤松である。根本をみると茸が生えている。松茸じゃないか。電気屋さんから男の子が出てきた。バットとグローブをもっている。それに、片手には茸が握られていた。
「こんちは」
男の子が僕に挨拶をした。今の子は眼があっても挨拶ひとつしないのに珍しい。
「やーこんにちは、野球しに行くの」と訪ねると、うなずいて「広場でみんなとやるんだ」と楽しそうに道に飛び出した。車が見えた。危ないと思ったとたん、車は男の子手前で止まった。男の子は後ろも振り向かず走っていった。車の性能がいいだけではない、町全体で人を守っているという感じがする。
電気屋さんの隣はコンビニエントストアーで、中で何人かの人が買い物をしている。通り過ぎると、中の人が一斉に顔を僕のほうに向けた。笑顔だ。
通りに人が見当たらないが、店の中には必ず何人か客がいた。
茸の泉があると駅員さんが言っていたが、ともかくまっすぐに歩いていこう。
しばらく歩いていくと、郵便局があり、花屋さんがあった。花屋さんの店先で鉢植えの花に水をやっている女店員さんがいたので声をかけた。
「すみません、お尋ねします、茸の泉はここをまっすぐに行けばいいのでしょうか」
「はい、きれいな公園になってます、原町一番の観光名所です」
店員さんが水をかけている植物をみたら、なんと赤い茸だった。
「花屋さんで、茸を売っているんですか」
店員さんは不思議そうに「花屋ですから」と答えた。店の中を覗いて驚いた。白い花のついた枝を売っているのかと思ったら、枝についていのは白い茸だった。小さな花束がいくつもあったが、どれも茸のついた枝を束ねたものだ。
私が立ち止まって見ているので、店員さんは、
「今花束が安いですよ、お土産にいかがですか」と茸の花束を指さした。
ふと見ると、店員さんの片手に黄色い茸が握られている。
「帰りにでもいただきます」
「お待ちしていますね、茸の泉、楽しんできてください」
花屋の店員さんは、ふたたびじょうろで茸に水をやりはじめた。
歩いて行くと、また十字路になった。車も来ない。左右を見てわたると街路樹が赤松ではなくなった。水楢の木だろうか。大きなものが根元にあるので、よく見たら、立派に育った白舞茸だった。なんだここは。
原町の街路樹は茸の生える木が植えられている。しかも茸つきだ。
少女が首輪をつけた猫といっしょに角から出てきた。猫は犬のように綱につながれている。少女の片手に黄色の茸が握られている。
「こんにちは」
少女のほうから声をかけてきた。その子に気になっていることをたずねた。
「こんにちは、茸をどうして持っているの」
少女は不思議そうな顔をした。
「だって、好きなんだもん」
そう言って、走り出した猫に引っ張られ、駆けて行ってしまった。
ともかく茸の泉にいこう。
のどが渇いている。自動販売機を見かけなかった。駅にもなかった。必ずといっていいほど駅にはあるものだ。歩いていくと喫茶店があった。入口に草色の茸の絵があり、「草」と名前が書いてあった。休んでいこう。戸を開けると客は誰もいない。席に座るとウェートレスがメニューを持ってきた。開くと珈琲、紅茶がない。たくさんの種類のジュースが書かれている。おや。
網笠茸、卵茸、赤山鳥茸、唐傘茸、土栗、松茸、椎茸、占地、とある。どれもよく知られた茸である。茸からジュースを作るのだろうか、それともただの名前だろうか。
卵茸を指さした。
「はい、シーザージュースですね」
ウェートレスはそう言って伝票にチェックを入れている。
「いや、タマゴタケ」
そう訂正すると、ウェートレスは微笑みながら、
「卵茸はシーザーのお気に入りだったので、シーザージュースと呼ばれています」
と言った。そうなんだ。うなずいて、彼女の左手にもつ白い茸を見た。
誰も彼もが茸を持っている。あの女の子は好きだからと言っていた。原町の人たちが茸好きでもいいが、手にもってなくてもいいのだが。どういうことだ。
作業員服の人たちが六人はいってきた。
ウェートレスは橙色のジュースを僕の前におくと、新しい客のところに行った。
一口飲んでみた。なかなかおいしい、うっすらと甘みがあって、これはいける。
ウェートレスが六人の客のところにジュースを運ぼうとしている。六人の客を見て驚いた。作業服を着た男の人たちめいめいが片手に茸をもっている。
それも驚いたが、ウェートレスは片手に茸を持ちながらどうやってジュースを運ぶのだろう。
見ていると、まず客が開けたままにした入り口の戸を閉めた。カウンターに戻ると、茸をカウンターの上においた。そうやって手から茸をはなすと、両手でジュースの乗ったお盆もちあげた。客に配った後は戻って茸を持った。
茸をもっていないといけないような感じを受ける。不思議に思いながらシーザージュースを飲み終わった。
茸のジュースがこんなにおいしいものとは知らなかった。代金を払うと外にでた。空が青く澄み赤とんぼが舞っている。
喫茶店からすこし行ったところに交番があった。お巡りさんが歩道の端に立っている。片手に青い茸をもっている。僕を認めると話しかけてきた。
「観光ですか」
「ええ、茸の泉に行ってみようと思ってます」
「いい公園です。お泊まりですか」
「いや、その予定ではないのですが」
「そうですか、もし、お泊まりになるようでしたら、茸を差し上げようと思いましてね、茸の泉を楽しんできてください」
お巡りさんのベルトには拳銃はなかったが、皮の袋がつる下がっていて、茸が顔を出していた。
袋の中の茸はなんだろう。不思議に思いながらも歩いた。
十分ほど歩くと森が見えてきた。道はその森の中に続いている。とても気持ちのいい日で、だいぶ歩いたのに疲れがこない。
森の中の道は二人で並んで歩くのがやっとというほどの狭いものになってきた。林の中にちらちらと赤や黄色や白い色が見えた。立ち止まって林の中をのぞくと、木々の下に色とりどりの茸たちがぽこぽこ生えている。姿は見えないが鳥のさえずりも聞こえてくる。
おかしいことに気がついた。木の下に草が全く生えていない。茸だけが生えていて、場所によってはおしくら饅頭のように密集している。個々の茸たちは立派で、今にも動き出しそうな迫力がある。細長い針金落葉茸ですら立派な傘をもっている。大半の茸の名前はわからない。茸好きの人にはわかるかもしれないが、名前がわからなくても茸を見ていると楽しくなる。
茸たちを眺めながら歩いていくと、森が途切れ、いきなり大きな湖が現れた。歩いてきた道は湖の周りの道に繋がっている。
立て看板があった。「きのこの泉」とある。岸辺に立つと泉全体が一望できる。この泉は森に囲まれていて、泉の周りの森の中にきれいな家々が点在している。岸辺には森の中とは違って、クローバなど見慣れた草が覆っている。
泉を一周するとおそらく大人の足で一時間ほどだろう。観光地であれば、入口に案内図だとか、お店の図があるものだが、そういった看板類は一切なかった。観光案内所もない。
ともかく歩くことにした。湖の周りの草原にも可愛らしい茸がたくさん生えている。森の中とは違ってどれも小柄だ。ベンチがいたるところにおいてあり、のんびりと泉で遊んでいる鳥たちを見ている人の姿がある。
教会のような建物があった。濃い緑色の瓦で覆われた屋根の八角形の搭がある。木でできていて、全体が若草色に塗ってある。ただ搭の先には十字架ではなく、赤い茸が乗っている。アーチ状の入り口には戸がなく、茸堂と書いた木の板が脇の壁に貼り付けてある。誰でも入れるようだ。中に入ってみよう。まず目に入ったのは正面にある祭壇である。まわりを見ると、意外にも広い礼拝堂で、ステンドグラスの窓から光が差し込み、堂内を彩っている。
前に進むと、祭壇には真っ黒な、人の倍もあろうかという茸がでんと置いてあった。つくりものなのだろう。なにでできているのか見ただけではわからない。
祭壇の前の机には大きなクリスタルのボウルがあり、中には赤い水が入っている。儀式使うものだと思うが、どのような儀式か興味がわく。
人の気配がしたので振り返ると、一人の老婆が入口から入ってきた。手に黄色い茸をもって前にすすんできた。
僕は脇に寄ると、祭壇の前に来た老婆は、ボウルの赤い水の中に持っていた黄色い茸を沈めて、深々とお辞儀をした。教会というより、お寺に行ったときにするような仕草である。
そのあとに、老婆は言葉を発することなく、赤い水の中に手を入れ、茸をつまみ出した。黄色だった茸は赤くなっている。
老婆はもう一度腰を折り曲げてお辞儀をすると外に出ていった。
この建物は教会でも神社でもお寺でもない。どんな宗教なのだろうか。茸教なんてことばが頭に浮かんだ。
私も茸堂からでると、再び泉の周りの道を歩くことにした。煉瓦でできたお菓子の家のような小さな家の前にきた。ペンション草見とある。看板に一泊素泊まり3000円とある。ずいぶん安い。朝食付きで3500円である。
小淵沢に泊まるよりここの方がいいのではないかと思うようになった。鳥たちの種類も多そうで、珍しい鳥に出会えるかもしれない。ペンションは他にもあるかもしれないし、まず一周してから、泊まるかどうか決めよう。
歩いていくとレストランがあった。泉レストランとある。入り口にあるメニューには茸料理とあり、いくつかの品が書いてあった。肉も魚も使われているのだが、必ず茸がいっしょで、そういう意味で茸料理なのだ。
またペンションがあった。木造の二階建てで和風である。草片荘と木の看板がかけてある。ここの値段は素泊まり2500円になっている。こりゃ安い。
さらに森の中も覗きながら、ぶらぶらと泉の周りを歩いた。レストラン、ペンションが多いが、アパートがかなりあった。個人の家が森の中まで広がっているところもある。郵便局や原町役場もあった。住むのにもよさそうである。ここに住んでいる人はいい環境でしあわせだ。
泉をこうして一周した。ゆっくり見て回ったこともあり、一時間半かかった。僕の気持ちはすでにここに泊まることにきまっていた。
中でも、和風のペンションが一番良さそうである。もう一度、茸堂の前を通り草片荘まで行った。詳しくみると、朝晩の食事をつけても3800円である。これはいい。
中に入った。
「いらっしゃい、お泊まりですか」
白い髭のおじいさんが帳場から出てきた。手に黄色い茸をもっている。私が頷くと、
「おや、茸をおもちじゃないので」
ちょっと驚いたように、聞かれたのだが、意味が分からずまたうなずいた。
「うーん、大丈夫かな」
おじいさんが考えている。いったいなにが問題なのだろう。
「お巡りさんに会いませんでしたか」
「会いました」
「茸をもらわなかったのですか」
「そういえば、聞かれました、くれると言ったのですけど、ここには泊まらないと言ったら、大丈夫でしょうといわれました」
「うーん、どうしよう」
「何か問題なのですか」
「わたしのほうとしてはいいのですが、あなたに何か起きるといけないと思いましてね」
「茸をもらわないとどうなるのでしょうか」
彼はそれには答えなかった。
「もし、お客様ご自身の責任で、茸なしでお泊まりになるのであれば、かまいません、ディスカウントしますよ、夜と朝食付きで2500円でいいでしょう」
なんというまけ方だろうか。
「ずいぶん安くなりますね」
「サービスはかわりませんが、ご自分の身はお守りください」
「何か危ないことがあるのでしょうか」
「いや、何も起きないかもしれませんし」
しっくりこないが、そんなに危ないこともなさそうな雰囲気だから、泊まることにした。ともかくずいぶん安い。
「チェックインは何時でしょう」
「もうかまいませんよ」
十二時をだいぶ過ぎているがずいぶん早い。
案内されたのは2階の20畳もある畳の間で、トイレも掛け流しの風呂もついている。
「ずいぶん広い部屋ですね」
「修学旅行の生徒さんが泊まることもあるので」
「今日はこのペンションには何人ほど泊まっているのですか」
「今日はあなたさんと、一家族です」
これでやっていけるのだろうか。
「食堂は一階にあります、六時からです」
主人はそういって下に降りていった。
窓から見る茸の泉はとてもきれいだ。お昼を食べて、森の中の鳥を観察しよう。
下におりて、主人にそう言うと、主人が、
「今日は、二時から茸堂で子供の茸初めがありますよ、誰でも入ることができるので、ごらんになるといいですよ」
「それはなんでしょう」
「成人式のようなものです」
「お昼はここでも食べられますか」
「出せないことはないですが、せっかくだから、泉レストランで茸料理を食べられたらいかがですか、ここの夕食も茸料理だが、また違うものがありますよ、あそこの茸ラーメンはお昼にはもってこいだ」
主人にそう言われて、泉レストランに向かうと、見ている端から道の脇に茸がポコポコと顔をだしていく。面白い。立ち止まって見入ってしまった。
クローバが覆っているところに、いきなり赤い小さな頭が見えたと思うと、くくくーっと、延びてきて、あっと言う間に傘が開いて、成長したきれいな茸になった。今度は黄色い茸がのびてきた。見る間に、クローバの葉が見えなくなるほど、茸に覆い尽くされてしまった。茸がこんなに早く成長するとは知らなかった。人が見ているうちに大きくなる。原町が特別なのだろうか。
歩いていくと、泉のほとりは茸で埋め尽くされている。朝茸の泉に到着した時にも生えてはいたが、草原にぽちぽちであった。
岸部を見とれながら歩いていくと、泉レストランについた。そのときはとうとう道以外のところは茸しか見えないほどになった。
泉レストランにはいると、一人の女性がウエイターに注文していたが、客はその人だけだ。席に着くと、別のウエイターが左手に紫色の茸を持って、メニューを持ってきた。
「草片荘の主人からラーメンがおいしいときいてきたのですが」
「はい、お昼はラーメンを注文される方が多いですね、うちの茸ラーメンはよそのものとは違いますから」
どう違うのか説明はなかったが、ともかく茸ラーメンを注文した。
出てきたラーメンにはさすがの私も驚いた。ラーメンどんぶりに、いろいろな茸が汁に浸かっててごろごろしている。その上に麺がほんのちょっとのせてある。茸汁に麺が少しばかりかけてあるといった風情である。茸が麺で、麺そのものはチャーシューかシナ竹といった感じだ。
ままよ、箸をとって食べてみると、ラーメンの味付けだが、茸がなかなかうまい。色々な茸が入っている。茸の種類はわからないが、それぞれ口の中での感触と味わいが違うのは楽しい。麺はラーメンという名前をつけるために入れてあるようなものである。
食べ終わって泉のほとりに戻ると、たくさんの人が歩いていた。片手に必ず茸を持っている。人々は茸堂に向かっている。僕もあとについた。
茸堂では大勢の人たちが入り口の回りに集まっていた。神父さんの格好をした坊主頭のおじいさんが片手に茸を持って集まった人たちに挨拶をしている。
私も人々の後ろで立っていると、坊主頭の神父さんがやってきて、「観光客の方ですな、どうぞ前の方でごらんください」と、入り口に私をつれていった。
「お子さんとご両親がきますので、その後についてくださいますかな、喜ばれますから、原町の住人でない人に介添人になっていただくと、その子供はグローバルな人間になるといわれてましてな」
そう言うことで、私は介添人にされてしまった。ただ付いて行けばいいだけのようで、式が間近で見ることができるのは嬉しいことだ。
拍手が起きた。お母さんとお父さんに手をつながれて五歳ほどの男の子が泉の道から人々がいならぶ間を通って入ってきた。
神父さんが、私を両親に説明すると、両親が私のところにやってきて「よろしくお願いします」と頭を下げた。私もなんと言っていいのかわからなかったが、「おめでとうございます」と頭を下げた。
男の子もぺこんと頭を下げた。
こうして、両親につれられた男の子の後ろについて、祭壇の前まで行った。
祭壇の大きな黒い茸がゆらりとゆれて、傘から汁を滴らせた。坊主頭の牧師が柄杓にその水を受けると、子供の頭のてっぺんから降りかけた。
「さあ、ぼおや、とっておいで」
そう言われたぼうやは、両親の手を離して外に向かった。
どうするのか見ていると、
「介添えの方、外まで見送ってやってください」
と坊主の牧師に言われた。ぼうやの後を行くと、泉のほとりの道にでると、ゆっくりと歩きはじめた。
私も行くべきか迷っていると
「介添え方はそこまででいいですよ、もどるまでみなさまとともにお待ちください」
と言われた。
「ぼおやはどうするのです」
坊主の牧師に聞くと「泉の周りから、気に入った茸をひとつ採ってくるのです。本当に気に入ったのでないと茸堂の茸神に拒否されます。その間、みなさんにはジュースがふるまわれますので、のどを潤してください」という話だった。
女性がワゴンを押してやってきた。見たことのある人だと思ったら、朝、茸のジュースを飲んだ喫茶店「草」のウェートレスさんだった。
集まった人たちがワゴンの周りに集まって、紙コップを受け取っている。私も一つもらって飲もうとしたら、ウェートレスさんが「ゆっくり、ちびりちびり飲んでくださいね、ぐーっとのむと大変なことになりますから」と注意してくれた。強いお酒でも入っているのだろうかと思って、少しずつ口に入れたのだが、たしかに最初の一口で、体がかーっと熱くなった。しかしアルコール分は入っていない。二口目は、頭がすーっと軽くなり、目の前が明るくなった。三口目は空の上に吸い込まれるようになってきた。
坊主の牧師さんが近づいてきた。
「初めての方にはきついでしょう、茸堂の中で腰掛けてお休みください」
足下がふわふわするので、坊主の牧師さんについて中に入った。
「このジュースはなんでしょうか」
「これはね、紅天狗茸のジュースで、町の人はこの祝いの時だけ飲んでいいことになっているんですよ、それで、ここにきているのは抽選に当たった人たちで、誰でも参加できるわけではないのです。観光客の方は誰でも入れます」
不思議なお祝いである。
三十分も経ったのであろうか。入り口の方で拍手がおこった。見ると、ぼおやが一人でもどってきた。片手に白い茸をもっている。人々も茸堂の中に入ってきた。私も椅子から立ち上がった。
ぼおやは気丈にも一人で、祭壇の前にすすむと、赤い水の中に茸をつけた。
黒い大きな茸の傘からまた汁が滴り落ちた。坊主の牧師がそれを柄杓でうけると、赤い水の中に垂らした。白い茸が赤く染まった。
ぼおやが、赤い水の中から茸を拾い上げると拍手がおきた。
牧師が「茸神さまが祝福していらっしゃる」と声を張り上げ拍手をした。
両親が僕のところにきて礼を言い、少年の後をついて茸堂の外に出ていった。みんなもぞろぞろとでていく。
「観光客のお方、無事終わりました、ありがとうございました、ぼおやも茸をもって、これで原町の住人になれました。
坊主の牧師がそう言って奥に入っていった。
時間を見るともう四時近い、森の鳥の観察は明日の朝早くにしよう。久しぶりの歩きで疲れたこともあるかもしれないが、紅天狗茸のジュースを飲んだこともだいぶ影響している。身体に力が入らない。だらだらとペンションに戻った。
草片荘では、主人が笑顔で、
「よかったでしょう、茸初めは」と迎えてくれた。
「あのような儀式があるとは知りませんでした」
「あまり知られていませんからね、さっきも言いましたが、夕食は六時からです、それまで、どうぞごゆっくり、部屋の温泉はいいですよ、飲み物はそこの自動販売機でお願いします」
それで、缶ビールを買って、部屋にもどった。茸ビールだそうだ。部屋の冷蔵庫に入れて風呂場に行った。風呂場の窓からも茸の泉が見渡せる。澄んだ湯の水面に自分のぼーっとした顔がうつっている。中に入るとぴりぴりと湯が体中をつつき、やがてさっぱりとして、頭がはっきりしてきた。気持ちははれやか。
窓から茸の泉をみながらしばらくつかって上がり、テレビのニュースを見ながらビールを飲んでいると、今日の茸初めという映像が流れた。さっき見てきた茸堂の中が映し出され、祭壇の前にいる僕の姿があった。茸初めの儀式が全て放送された。
見終わって、チャンネルを変えるとNHKになった。もとにもどすと、原町チャンネルという文字がでた。ローカルチャンネルを見ていたようである。
ビールがうまい。缶の絵がベニテングタケで、気になっていたのだが、やっぱり眠くなってきた。がまんができず、押入を開けて枕を取り出すと横になった。あとはなにもわからない。
気が付くと5時半である。
戸をノックする音が聞こえた。
どうぞと声をかけると男性の声が聞こえた。
「係りのものです、布団を敷きにきましたが、早すぎましたか」
「かまわないですよ」
入ってきた係りの人が「茸初めに行ってこられたのですね、テレビで見ました」
「おもしろい風習ですね、とても日本とは思えない」
「ええ、原町ですから」
彼は片手に茸をもちながら、布団を敷き始めた。
「茸をお持ちじゃないそうで」
私がうなずくと、
「一晩くらいなら大丈夫だと思いますが、夜、窓を開けないでくださいね」
と言った。
私がいぶかしげな顔をしていたのであろう、
「そんなに心配いりませんから、もうすぐ食事ができます、食堂のほうにいかれたらどうでしょう」
布団を敷き終えた彼はそう言って部屋を出て行った。ますますわからなくなった。下に降りてみよう。
食堂にいくと、一つのテーブルに食事が用意されていた。
主人がカウンターからでてきてテーブルの前に座った私のところにきた。
「今日はお客さん一人になりました、来る予定の家族がこれなくなったんですよ、何でも子供が熱をだしちまったそうです」
主人は並べられている食事の説明をした。
「茸のお浸し、茸と鱒のフォイル焼き、鹿肉のステーキに茸ぞえ、茸のスープ、茸ブレッド、です、パンの代わりに茸ご飯もあります。飲み物はなににしましょうか」
「ビールをください」
「はい、ゆっくり召し上がれ」
主人がビールをもってきた。部屋の窓を開けないように言われたことが気になっていたので、聞いてみた。
「ああ、おそらく心配いらないと思いますけど、夜遅くになったら、窓は閉めたほうがいいと思いますよ、あまり気にしないで下さい」ということだった。
出てきたビールも茸ビールだ。瓶のラベルには真っ赤な茸の絵があった。
どの品もみなうまいものばかりだ。ビールも二本目をたのんでしまった。部屋で飲んだときのように、身体がふわふわしてきた。
満足感いっぱいで部屋に戻った。窓から外を見ると泉の周りがライトアップされていてとてもきれいだ。波打っている水面が光を反射して、光が湖面で踊っているようだ。岸辺が緑一色ではなくて、赤、黄、白、紫、いろいろな色の粒粒に見える、マーブルチョコレートを思い出した。
もう一度風呂に入った。風呂の開け放された窓からも泉が見える。目を凝らすと、赤や黄色いものは茸の頭のようだ。岸部にニョキニョキ伸びている。茸の泉だから茸が湧き出るんだ。泉のほうから吹いてくる涼しい風に吹かれて湯に浸かっていると眠くなってきた。
珍しい町にきたものである。みんなが茸をもっている。
風呂から出ると、すぐに布団に入った。あっという間に寝てしまった。
夜中のことである。
ざわざわ、ゴソゴソとたくさんの何かが動いている音がして目が覚めた。枕元においておいた腕時計を見ると、夜中の二時である。部屋の窓がぼんやりと明るい。泉はまだライトアップされているようだ。
早く寝てしまったこともあるが、もう眠気もない。何かが集団で動く音も気になるし、起きあがった。
窓を覗いてみると、岸辺で赤、黄、白、紫いろいろな色が動いている。ザックから双眼鏡を取り出した。野鳥観察のために山には必ず持ってくる。
のぞいてみて驚いた。茸たちが揺れている。いや動き出した。ダンスを踊っている。どうなっているのだろう。倍率を上げた。赤い茸と白い茸が同じ調子で飛び跳ねたり、お互いの周りを回っている。しばらく見ていると、岸辺の茸たちが一斉に泉に向かって走り出した。なん百何千という茸である。なにが起こるのだろうと、見ていると茸たちが泉に飛び込んでいる。ザブンザブンと音が聞こえるようだ。さらに倍率を上げた。茸たちが泳ぎだした。からだをぐるぐる回しながら進んでいるようだ。競争をしているらしい。どうも向こう岸に向かっているようだ。水面を茸が集団で泳ぐ様など見たことがない。かなりの早さである。
これは面白い、茸たちが小さくなってきたので、窓を開け、双眼鏡の倍率をさらに上げた。茸は水しぶきをあげて進んでいく、やがて見えなくなった。
変な事が起こるものである。寝ぼけているのであろうか。夕べ飲んだビールのせいかもしれない。もう一度床にはいるか、と窓を閉めようとしたところ、泉の水面に水しぶきが上がった。また双眼鏡で覗いてみた。これはすごい。さっき泳ぎに行った茸の大群がもうもどってきた。先頭にいるのは黄色の茸のようだ。紫色の茸が追いかけている、そのあとに赤いのが二つ競っている、すごい大群だ。
どの茸が一着になるのか楽しみになって来た。窓を大きく開けて乗り出して双眼鏡を覗いていた。
紫色の茸が先頭に立った。
とうとう紫色の茸が岸辺に飛び上がった。他の茸もどんどん上がってくる。
その時、紫色の茸が私が覗いている双眼鏡の方を見た。明らかに見た。すると、紫色の茸だけではなく、すべての茸が走り出して、こちらに向かった。すごい早さだ。双眼鏡など要らない、どんどん近づいてくる。
あっという間に私のペンションの下まで来た。何をするのか見ていると、茸たちは壁を伝わって、開いている私の部屋に飛び込んできた。
びしょびしょの茸が私にぶつかってくる。どんどん茸が部屋の中に入ってくる。私は押し倒されて仰向けになったまま畳に押し付けられている。ぎゅうぎゅうになっても、茸はまだ窓から飛び込んでいるようだ。二十畳もある部屋に茸が一杯になり、私は押しつぶされそうだ。肺が苦しくなって来た。畳みでなくて床だったら潰されている。
いかん、死にそうだ。何とか足を持ち上げて膝を畳みに打ち付けた。あまり音がしない。しかし手足を何とか動かして畳をたたいた。
どのくらい経ったであろうか。顔の周りは茸だらけでむんむんする。目は茸で押されて見えない。手足、からだはみな茸で押しつぶれそうだ。鼻は茸でひしゃげ、息がもうすぐできなる。
そのとき、「こらあ」と言う声がした。
すると、体が軽くなっていった。からだを少し動かせるようになると、茸が窓から外に飛び出しているのが見えた。
戸が開いて、主人が私の傍に来ると手を引いて立たせてくれた。
「良かった、間に合いましたな、また死んじまったかと思った」
私は息を整えて、やっと声を出した。
「ありがとうございました」
「窓を開けちゃいけないと言ったでしょう、でも命があってよかった。前に泊まった人は亡くなっちまってね、往生しましたよ」
主人の左手には茸が握られている。
「あの茸はなんですか」
「ここは原町、茸と供に生きているんですよ、あ、まだいた」
赤い可愛らしい茸が、枕の上で震えている。
「今日茸初めをごらんになったでしょう、あれは、ここで生まれて5歳になった子のする成人式ですがね、どういうことかと言うと、泉の茸の中から一生付き合う茸を一つ選ぶ儀式なんですよ」
「どういうことか分かりませんが」
「この泉からは茸が湧いてきます、そのたくさんの中の選ばれたものだけが、人間と共生して、長い人生を楽しめるのです。それで、洗礼された茸を持っていない人の部屋に押し寄せて、選んでもらおうとするのです。我々も茸をもっていないと、ねらわれることがあるのですよ」
そういえばウェートレスさんが両手で食器を運ぶ時、ドアを閉めてから茸をカウンターの上においていた。
「彼らも、いい一生を送りたいのですよ」
「茸が人といて何かメリットがあるのですか」
「まず、その人の寿命をもらえます、同じだけ生きることが出来る、寿命が一週間ほどしかない茸たちは岸辺で踊ったり、泉で競泳をしたりはできますが、それも原町だけです」
「しかし、茸にとって長生きだけではしょうがないじゃないのですか」
「たくさん胞子を飛ばせる、それに、その人間と喜怒哀楽をともにできる。面白いテレビを人間が見ていれば、茸も楽しいのです。逆に人間にストレスがたまると、それを弱めてくれます。共生関係ですな」
赤い茸が震えながらまだいた。
「ほら、この茸、怖くて動けなくなっちまった、きっとあと一日二日でしなびちまうんだろう」
なんだかかわいそうになった。
「一晩だけでもいいのでしょうか」
「そりゃあいいですよ、だが、なんだ、もし気に入ったら、洗礼をうけることもできます、なにも5歳と限ったものではないのですよ、いくつになっても共生関係はつくれる、ただ、原町に住むことになる」
それは難しいにしても、一晩くらいはいいだろう、私は赤い茸をそうっと手のひらに載せた。
ドキッとした、茸が大喜びしているのが伝わってきた。うれし泣きをしている。
「それじゃ、窓をしっかり閉めて、お休みください」
主人が出て行った。私は赤い茸を持ったまま、窓を閉めた。岸辺に戻った茸たちがこちらを見ているように思えた。赤い茸の幸運を羨ましく思っているのだろうか。
寝る時はどうするのか分からなかったので、ともかく手に持ったまま床に入った。
なんだかサワヤカで、すぐに寝入ってしまった。
朝起きたとき、赤い茸がすやすや寝ているのに気が付いた。それにいつもは見ない夢を見た。はっきりしないが青春、若い頃のような夢だ。
朝食にも赤い茸を持って食堂に行った。
「どうです、赤い茸は」
僕はなんだか恥ずかしくて、ただ頷いて、こう聞いた。
「原町に住むのは大変ですか」
「あんたさん、何やってるのかね」
「出版社に勤めて校正をしています、だけどいつか生き物の小説を書きたいと思ってます」
「小説を書くならここだって出来るだろう、インターネットもあればなんだってある。そういう人こそ、ここで暮らすべきなんだよ」
「旅行に行く時には茸はどうしたらいいのでしょう」
「はは、おとなしく家で待ってるよ」
僕は赤い茸が可愛くなって、洗礼を受けることにした。
手の中の茸がほかほかと暖かくなっている。茸も幸せのようだ。
僕はすぐに洗礼を受けた。
私は原町のマンションを借りた。今は赤い茸が一人で住んでいる。土曜日と日曜日だけ、原町の自分のマンションにもどり、小説を書くという暮らしをはじめた。
いずれ、本がだせたら、茸の泉の湖畔に家を建てよう。都会に住んでいる人々を呼んで、この町の住人にして、茸を幸せにしてやろう。
左手で持っている赤い茸は、いろいろな動物の話を思いつかせてくれる。昨日赤い茸にカメムシが止まった。隣の虫湖の住人だ。カメムシは人間との関係を色々語ってくれた。それだけで面白い話になる。
原町は茸と供に生きる町である。
茸初め


