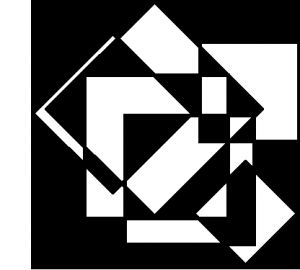Monotone
目を開けると、色はなかった。
白と、黒。それ以外は、ない。
「これは、何色?」
少女が、りんごを持って、訊く。
「黒、だよ」
僕は静かに答える。
真っ白な彼女の肌に、黒い彼女の瞳。肩のところまで伸びた、黒々とした髪。
少女はやわらかな笑顔を見せた。僕はそれを見ているだけで、うれしかった。
黒いりんごを、彼女はおいしそうに食べた。小さく「おいしい」とつぶやく。
「君も、食べたら?」
そういうと彼女はりんごを差し出した。
「ありがとう」
僕は受け取ると、口に運んだ。ほんのりと、甘い。
「おいしい?」
僕の顔を見て、訊いてきた。
「うん。おいしいよ」
僕は笑って、そう答えた。
「ねぇ、色って何?」
いつだったか、わたしはそう、彼に訊いた。彼は答えに渋り、
「黒と、白のことだよ」そう、言った。
「嘘」
わたしはすぐに訊きかえした。
「じゃ、ここに書いてある『あか』とか、『あお』って何?」
いよいよ彼は困ったようで、頭をかく。
「それは僕にもわからないよ――」
結局、出てきた答えがこれであった。
わたしは口をとがらせた。彼なら、きっと知っていると思ったのに。いつもなら、わたしの疑問に答えてくれるのに。
わたしは、そばにあった白い椅子に座った。
彼は、わたしの方をじっと見ていた。
彼女と過ごすようになったのは、いつからだったろう。たしか、五年くらい前だっただろうか。なんだか、ここにいると時間が分からなくなる。
僕は引き出しから、一通の封筒を取り出した。
「懐かしいな」すっかり褪せてしまっていたそれは、僕がここに来た理由だった。
思えば、なんであの人は僕に彼女を任せたのだろうか。そしてなんで僕にこんなことを頼んだのだろうか。
――彼女は白と黒しかわからない。だから、他の色を見せないでくれ、と。
体が熱い。風邪をひいてしまった。彼にそのことを伝えると「ベッドで寝てなさい」と言われた。言われたとおりに、そうした。
まどろみかけたそのとき、彼がお盆を持って部屋に入ってきた。
「お粥、作ってきたよ」
そう言うと、わたしの横にお盆を置いた。お椀から、湯気が立っている。
「ありがとう」かすれた声で言った。
「どういたしまして」彼はほほえんだ。
彼は、みのむしのように布団にくるまったわたしに、お粥を食べさせてくれた。
「ごちそうさま」
私がそう言うと、彼はお盆を持って部屋を出ようとした。
ドアノブに手をかけて、思い出したように彼は言った。
「君は、お母さんのことって、覚えてる?」
わたしはその意味が分からなかった。なんで、そんなことを聞くのだろう。
わたしはだまって首をふった。
「そうか。ならいいんだ」そう言うと、扉をあけた。
「お大事に――」彼は笑って、部屋を出て行った。
僕は手紙を見返していた。
読むたびに分からなくなる。なんであの人――彼女の母親――は僕に頼んだのだろう。僕でなくとも、他にもっとふさわしい人はいるだろう。よりによって、どうして僕なんだ。
……理由を聞こうにも、あの人はもう、この世にいない。
この手紙はいわば、彼女の遺書なのだ。
旧友の望みをかなえてやろう。たとえ、理由がわからなくても。彼女が、そう望むのなら。
僕はそう、思っていた。
次の日、わたしは驚くほど元気になっていた。昨日の苦しみなど、どこかへ飛んで行ってしまった。
「おはよう!」わたしは大きな声で言った。
「おはよう」彼は朝ごはんを作っていた。
「元気になってよかった」
彼は安堵の表情を浮かべた。
「昨日は、ありがとう」
「なんのこと?」
「昨日の、お粥のこと」
「ああ」
「あれ食べたら、元気が出てきたの。ありがとう」
「どういたしまして」
彼は笑う。わたしもつられて笑う。
「君には不思議な力があるのかもね」
わたしはなんの気なしに言った。
彼は驚いた顔をして、
「そうかな」
と頬をかいた。
彼の白い顔が、少し変わったように見えた。
彼女の言葉に、驚いた。やっぱり、親子は似るのかな、と思った。
似たようなことを、彼女の母親にも言われた。
その時のことは、今でも思い出せる。
彼女はけがをしていた。そんな大したけがではなかったが、僕が手当てをしたのだ。手当てといっても、消毒して、ガーゼをあてただけだ。
その次の日、彼女の傷は消えていた。そして僕にお礼を言いに来た。その時に言ったのだ。「君の手は、魔法の手だね」と。
もちろん、僕はそんなことなど信じてはいない。僕の手が、魔法の手だと。
僕は自分の手を見た。
でも、もし、本当に、魔法の手だったら――。
「ねぇ、これは、何色?」
わたしはりんごを持ってそう訊いた。
「黒、だよ」
彼は静かに答える。
もう何度訊いただろう。いつも彼はりんごの色を黒と答える。十年前に、初めて彼に訊いたときから。
でも、このりんごは、昔見たりんごと何かが違っていた。それが、どんなものかは説明ができないが、とにかく、何かが変わっていた。
「本当に?」
彼はわたしの方を見た。
「どうして、そう思うの?」
「わからない……。けど、なんか違う気がするの」
「そうか」
彼は黒い椅子から立ち上がり、ドアのところに歩いて行った。
「外を、見てみるかい」
彼はわたしにそう提案した。
もしかしたら。そんな思いが心に浮かんだ。
もしかしたら彼女は――。
はやる気持ちを抑え、僕はドアのところへ歩く。そして、
「外を、見てみるかい」と言った。
彼女は目を見開いてから、頷いた。
僕はドアノブに手をかける。隣には彼女がいた。
「外って、どんなの?」
うきうきした様子で訊く。
「見てみれば、わかるよ」
そう言って、僕は扉を開いた。
まぶしい。思わず目を細める。
彼は隣にいた。静かに、笑っていた。
わたしは前を見る。
一面に、花が咲いていた。りんごと同じ、色の。
わたしは飛び出した。
風が花の香りを運ぶ。
わたしは一輪の花をつんで、訊く。
「ねぇ! これは、何色?」
彼はほほえんだ。
「『あか』だよ」
もしかしたら、これが彼女の母親が、僕に頼んだ理由かもしれない、と思った。
花の中に走っていった、彼女を見ていた。
彼女は今、色を手に入れたんだ。
「ねぇ! これは何色?」
彼女がそう訊く。
「『あか』だよ」
彼女が笑った。
その光景は僕の心の中に、うつくしい絵画のように、残った。
Monotone
拙い文章ですが、感想をいただけましたら嬉しいです。