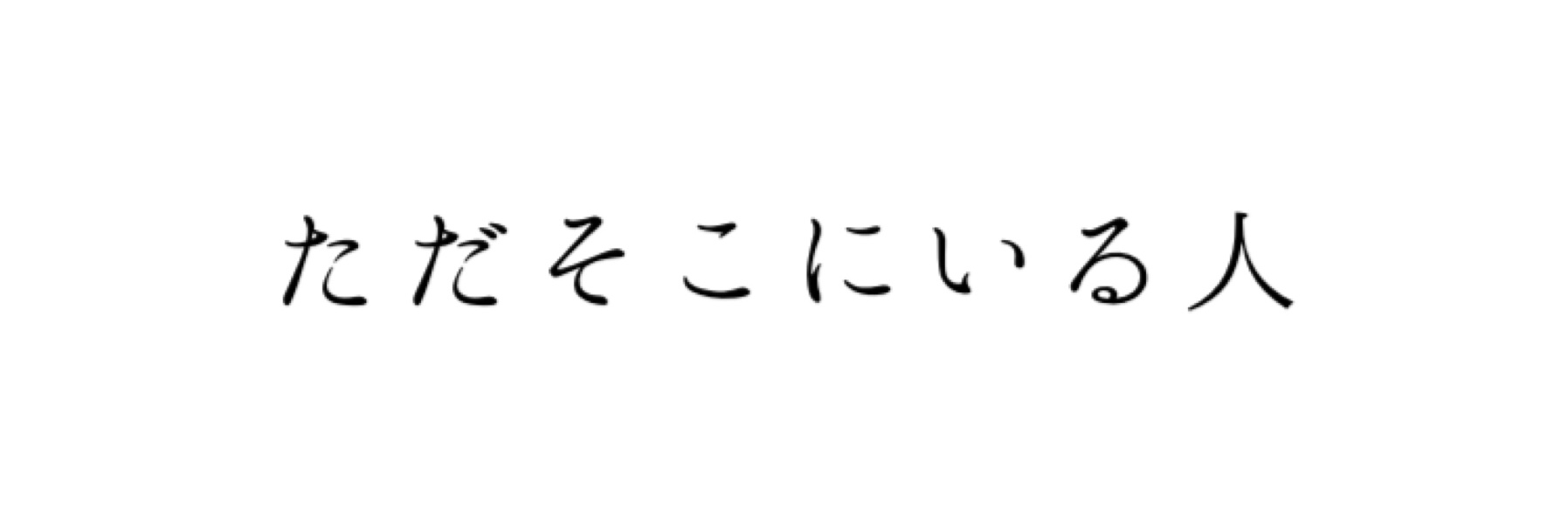
ただそこにいる人
ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…。
無機質な病室に心電図の音が鳴り響く。何の病気かあまり覚えていないが、俺の命はもう残り僅からしい。
家族の声もぼんやり聞こえる。何を話しているかまでは分からないが、珍しい親戚も来ているぐらいだから今日中に死ぬのだろう。
思い返せば、何も残せない人生だった。
ただ生きて、ただ死ぬ。そんな人生だ。
親戚や家族だってそうだ。ほとんど知らないし、家族といっても来ているのは母だけ。
なぜ生まれてきたのだろう…。
人間は必ず何かの役目を全うするために生を受ける。
俺は全うできたんだろうか。
『どうだろうな』
ぼんやりとではなく、確かに聞こえた。声のした方に目を向けると、スーツを着た男が椅子に座っていた。
顔を確認したかったが、大きなハットで全く見えなかった。
スーツの男は俺に煙草を差し出している。
「ははは…こんな体じゃ吸えないし、そもそも病院の中じゃ吸えないよ」
そういって笑った。なんだかとても懐かしい。
俺の言葉を聞いて、その男はどこか残念なジェスチャーをして煙草をしまった。
そのまま俺の右手を取って、柔らかく握ってくれた。同性だが、全然いたじゃない。むしろ子供のを思い出すような既視感さえ感じる。
病室では相変わらず心電図の音だけがよく聞こえた。家族の声も聞こえるが、ぼんやりとしていて聞こえない。
俺は必死にスーツの男にかける言葉を探していた。まだ見つかり切ってはいないが、少しずつ口を開く。
「その…なんというか…俺は貴方の事を覚えていない。でも…きっとどこかで会っていると思うんです」
スーツの男は頷いた。
「何処でお会いしましたか?」
スーツの男は答えない。
「おいくつでしたっけ?」
スーツの男は答えない。
「お名前は…?」
答えない。
どうやらスーツ姿の男は、俺と話す気がないか、言葉を話せないらしい。
となると、最初の声はこの人じゃないのか…。
男が手を握っているせいなのか、体がほんの少し楽になった。
窓の外に目を向ける。何もついていない枯れ木が3本ほど見える。その大きな隙間から太陽の光が俺のベッドのすぐそばまで伸びている。
11月も終わり、完全に冬になる。
もう少しだけ我慢すれば、クリスマスだ。あんまりいい思い出はないが、友達と飲んだ安い酒や、無駄に高いコンビニのつまみが何よりも美味しかったのを覚えている。
24の夏だ。職場の同期で集まってやったんだ。最初はうまく馴染めなかったが、お酒というものは小さな枷を外してくれる。数分で仲良くなれた。
心が温かい。なんだか心地がいい。
最後の最後、死ぬその間際までスーツの男は手を握ってくれているだろう。
そう思った時、心電図の音の感覚が狭くなった。
俺は死んだ。少しの後悔とたくさんの感謝の中で。
ただそこにいる人


