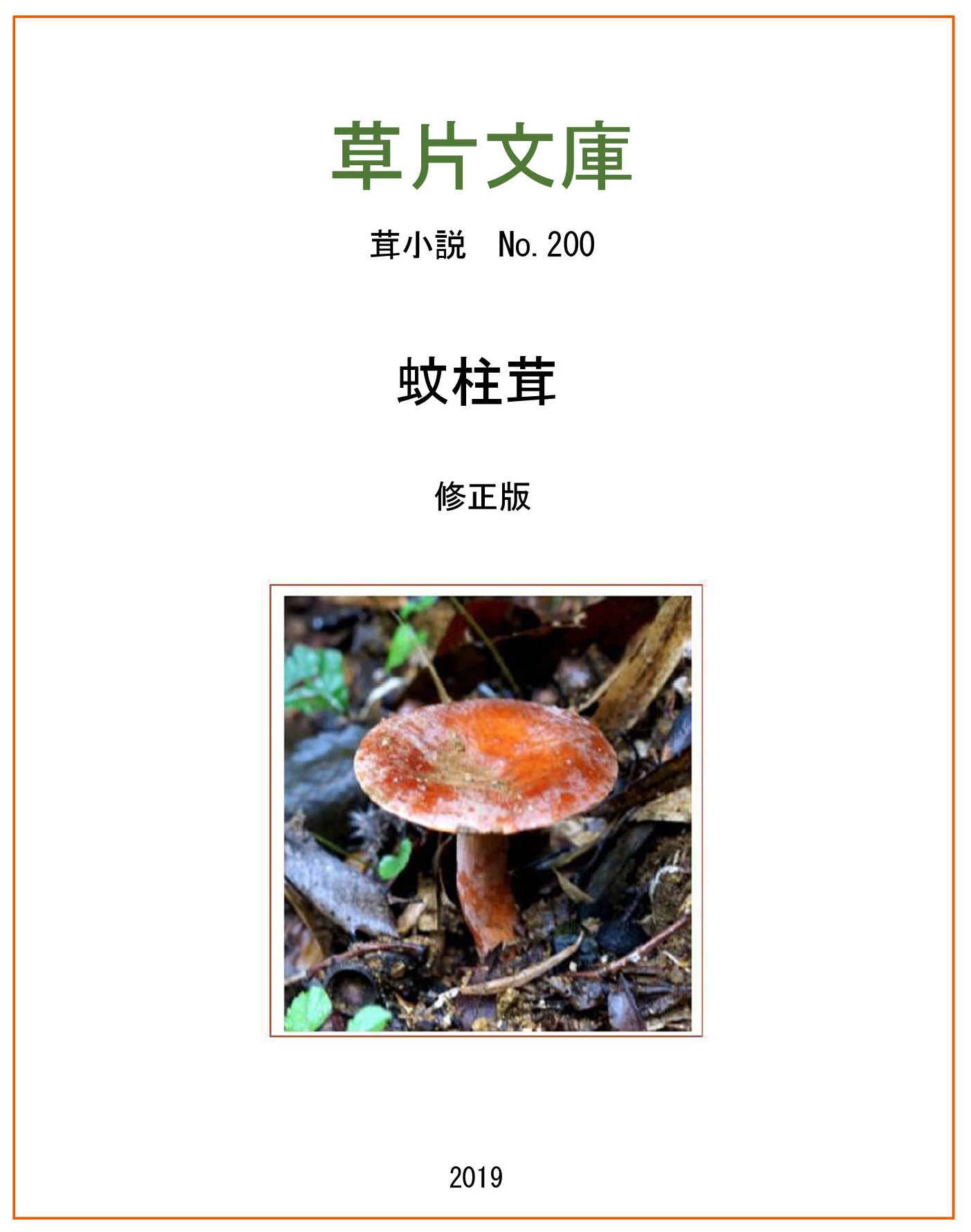
蚊柱茸
悲喜劇茸小説です。文章を少々改訂しました(20-7-9)
蚊柱は雄の蚊が集まってできる。コンクリートジャングルになった都会ではあまり見る機会がないが、ちょっとした公園でもあればでることもある。
子供の頃はあたりまえのように、夕暮れに遊んでいた川や山から家に帰る途中で、蚊柱に追いかけられたものだ。あいつらどうして俺の頭が好きなんだろうと、奇妙に思ったものである。
血を吸うのは雌の蚊で、それは卵を産むのに必要なんだよと、先生が教えてくれた。そのときちょうど、隣の家で赤ちゃんが生まれ、隣のおかあさんは誰の血を吸ったのだろうと、おかしなことを思った。この年になると、蚊も人も母親というのは大変なんだと感心する。
小学校の上級生になったとき、それじゃ、雄は何を食べているのだろう。いや、雌だって血が吸えないときにはどうしているんだろう、と心配になった。
余計なお世話かもしれない。今だと、そういった疑問にたいし、正確かどうかは別にして、インターネットで簡単に答えを知ることができる。一つの疑問に何件かの回答がでていて、おおよそ正しいと思われる答えを見つけることができる。
雄にとって花の蜜や露が食べ物だそうだ。雌もいつもは雄と同じように花の蜜などだそうだが、雄と交尾をしてから血を求めるようになると言う。
それを知ってから少しばかり蚊のイメージが違ってきた。
今の若い人たちは、仕事が忙しすぎて恋愛をしている余裕がなく、結婚の相手に出会う機会も少ないという。そんな人間の姿を見て、蚊は暇だからそういう機会はたくさんあるのだろうなと思っていたが、ネットで調べるとそうでもないようだ。
蚊の出会いも大変そうだ。そこに蚊柱がでてきた。
雄の蚊は集まって蚊柱をつくり、その中でそれぞれの蚊は上へ下へと動いているらしい。そうやって雄の蚊はフェロモンを出し、蚊柱としてまとまってその匂いを発散しているという。さらに集まった雄の羽音は蚊柱で増幅される。それにより雌が雄の存在に気づきやすく、引き寄せられた雌が蚊柱の中に入って相手とめぐりあうそうだ。ことを成し遂げると蚊柱から離れ、血を求めて彷徨うことになるらしい。
蚊柱は生殖相手を見つける手段である。
さらに蚊に同情すべきことが書いてあった。蚊の寿命は短い。その間に雌と後尾をしなければならない。
ということは、蚊柱の中の雄はただ上下に動いているだけで一生を終える者もたくさんいるということである。男がなんとなく働いて一生を終えるのと似てないこともない。ちょっと自分を振り返った。
だけど、なんで蚊柱は自分によってくるのだろう。顔の周りにぶんぶんうるさい。
それもネットにあった。蚊柱がより高いところにできる性質があるからだという。だから頭の上にくっついてくるらしい。雄の蚊はどのようなきっかけで蚊柱を作るのだろう。どの蚊がリーダーで高いところに誘導するのだろう。疑問だらけだ。
動物行動の先生の記述だと、本能行動というらしい。蚊はまわりの情報が脳に入ると自然と行動が生じてしまうような仕組みを神経の中にもっていて、匂いの物質などによって自然と集まってしまうようである。蚊に脳があるのかどうか知らないが、動物の脳にそういう仕組みが生まれつきあるのだそうだ。
体が勝手に動いてしまうというやつである。考えないで一生を終えるわけだ。楽でいいな。
そういえば、藪蚊っていうと、白黒まだらの奴がいたが、白黒の蚊柱は見たことがない。
ネットに白黒まだらの蚊の名前があった。ヒトスジシマカだ。これが藪蚊のようだ。蚊にもずいぶん種類があるものだ。アカイエカ、この薄茶色いやつも見たことがある。マラリアをはこぶやつらしい。
蚊柱をつくるのはどうも限られた種類の蚊のようだ。ユスリカという種類がつくるという。ユスリカにはあったことがあるに違いないが、姿をイメージすることができない。説明を読んでみると、恐ろしいことが書いてある。こいつらは本当の蚊ではなく蚊に近い仲間のようで、水の中にいるときは真っ赤なボウフラで、大人になると、要するに蚊の姿になったときには口がないのだそうだ。ということは血を吸う蚊の仲間ではない。蚊柱を作って何も食べずただひたすら雌を待つのである。大人になった雄ユスリカの一生は蚊柱である。食べる楽しみはない。交尾の楽しみだけだ。
いろいろな生き物がいるものである。雌蚊から人間や猫を見たら、だだの栄養補給用動物なのだろう。
東京で蚊柱を経験したのは会社の仲間と多摩川の奥でバーベキュウーをしたときくらいである。今年の夏に田舎に帰ったときに探してみよう。なんだか懐かしい。
なぜ今になって蚊柱が気になり始めたのだろうか。会社に入り五年、最初の年の暮れには田舎に帰ったが、その後一度も帰っていない。電話はよくかけるし、東京のものを送ったりもする。世話になったばあちゃんには欲しいものを買って送っている。そろそろ、この夏には田舎に帰ろう。田舎に帰るとなぜ蚊柱がなつかしいのか分かるような気がする。
夏休みに実家に帰ることにした。
田舎は遠くに八ヶ岳を望む盆地の川の近くである。曾祖父の代までは農業をいとなんでいて、田畑を少なからず持っていたことからかなり裕福な生活をしていたらしい。祖父は農業を継ぐことはせず、村の役場に勤めていたがすでに他界している。もうすぐ90になる祖母は小学校の教員をしていたこともあり、老人クラブの理事として地域に貢献している。小学校の教員をしている頃から、その村の伝説やら噂話を集めていたことから、村誌の編集に携わるなどなかなかの知識人として知られていた。両親は農協勤めで、もう退職しているが、今でも手助けをしている。
ばあちゃんにはずいぶん可愛がってもらった。自分が末っ子の長男坊主なのでなおさらだったのだろう、両親がばあちゃんにそんなに甘やかさないでくださいとよく言っていた。要するに小遣いをずいぶんもらった。だが、そんなことで早くからゲームやらコンピューターで遊んでいたことで、ITに強くなり、大手の会社に入ることができたのである。ということはこの会社に入ったのはばあちゃんのおかげである。
「ばあちゃんただいま」
ばあちゃんはもんぺをはいて庭先で庭木に水をやっていた。
「よう帰ったな、父ちゃんと母ちゃんは農協いっとる」
「姉ちゃんたちは帰ってくることあるの」
「無いな、遠いからな」
一人の姉は北海道にいるし、もう一人は旦那の転勤でシンガポールにいる。
「後で聞きたいことがあるんだ」
「なんだい」
「蚊柱」
「ひえ、なんで蚊柱か」
「あとでな」
玄関からあがると、猫の陣五郎が出てきた、高校生の時に家に迷い込んできた焦げ茶のぶす猫である。だからもう十五歳になる。
「元気か」と声をかけると、ぶすっとした顔をしながらも寄ってきて大きな目で見上げた。動作が鈍い。昔はすぐじゃれてきたのに。
頭をなでて、二階に上がると、陣五郎もついてきた。二階に自分の部屋があった。というより、今も空いているので、帰ってくるとそこに泊まる。
キャリングケースを開けて、ばあちゃんの土産を取り出すと、空いたところに陣五郎がむりむり入って、丸くなって見上げた。昔から段ボールなどがあるとすぐに入って、一日だけ自分の部屋にして、すぐ飽きちまう。明日まで寝ているのだろう。
ばあちゃんへの土産はお菓子でも着る物でもない。ちょっと重い土産だ。それにみやげを探すのもちょっと骨が折れる。面白い本を喜ぶ。ばあちゃんの面白い本とは日本各地の伝説の書かれているものだ。あの年をして一晩で一冊読んでしまう。
そういう本を探すのは一人じゃとても無理だ。インターネットも便利だが、伝説とか伝承の領域を知らなければ、上手な検索はできない。結局自分に基本的な知識がないとインターネットは働いてくれないものだ。
それで図書館に勤めている大学サークルの友達にちょっと食事をごちそうして、調べてもらって買ってくる。文学部の歴史を出た奴だからよく知っている。新しく出版された地方の本を探し出してくれる。そうなったら後は自分でできる。インターネットで買うことができるからだ。
今回持ってきたのは三冊、みな北海道の本で、一つは山の悪霊の本、コロボックルの本、それにヒグマの伝説の本である。
ばあちゃんが家に入ったようだ。
本を持って居間に行った。
「本もってきたぞ」
「そりゃうれしいのう、かっちゃんが持ってくる本はいつも感心してるんだ、おもしれえよ」
僕は克芳という。
「そんでなんだい聞きてえことは」
「蚊柱さ今もでるけ」
「なんでそんなこと聞くんけ」
「いや、ちょっと懐かしくなって、東京じゃ見られねえ」
「たんとでるさ、川の縁行ってみろや」
まだ昔のままのようだ。
「今いってもでてるか」
「どうかな、まだ暑いから、ぽちぽちだ」
「ちょっといってくる」
サンダルを履いて近くの河原に出かけた。
近くを流れる澄川は護岸工事などしてない。道路から草が茂った斜面の道を降りれば河原になる。ジャリの間に大きな石が落ちていたりする。流れの際に行って覗くと、水がきれいで中を泳ぐ魚が見える。そこは昔と変わっていない。
水中を覗いていると、石の間で小さな黒っぽい魚が砂の間をちょろりと動いた。カジカだ。ハゼなどの仲間だと思った。蛙の仲間のカジカもこの川には棲んでいる。
ひとしきり川を眺めて、道路にあがるとき、蚊のような虫が飛んでいたが蚊柱には出会わなかった。
そのまま実家に戻ると両親も農協から帰っていた。
「どこいっとったん」
「ばあちゃんに河原に行くと言っといたよ」
「ばあちゃんは部屋にこもったままだよ、呼んでもでてこん」
「きっと、持ってきた本を読んでるんだろう、母ちゃんには東京ではやってる長靴買ってきた」
「なーんで長靴なんか」
不満そうな顔をしたので、あわてて二階から持ってきて渡した。
そのとたん母ちゃんの顔がほころんだ。
「ありゃ、よくみつけたな」
この長靴は野鳥の会がつくったもので、本来は野鳥の観察の時にはくためのものだが、いくつかの色違いがあることと、上のほうを折りたたんで短いブーツのようにして履くと格好が良いことから、若い子に人気がある。なかなかおしゃれなものである。
「これ、農協の雑誌でみたんだ、欲しいと思ってたんよ、やっぱり東京だな」
会社の隣の席の女の子が雨の時に履いてきて自慢していたので、売っているところを教わったのだ。
「足は23半」
「よう覚えてたな」
「親父にはこれ」
ちょっと派手な緑色だが、魚の柄のネクタイ。勤めているときは毎日ネクタイを変えて、皆に自慢していたようだ。つりが趣味で魚の柄は気に入るだろう。
「ええネクタイだな、ありがとよ」
「今日は農協で牛肉特売してたで買っておいた、炒めるか」
「うん、いいな」
「お前はいつまでいるんだ」
「五日だ」
「何で嫁もらわんだ」
母親は電話でも必ず言う。
「忙しいんだ、だけど稼ぎはいいぞ」
「なあ、新町の知佳チャンまだ一人だぞ」
母親の小学校の同級生の二番目の娘が俺の高校の同級生だ。
「今何やってるの」
高校では同じクラスになったことが一度ある。確か近くの短大に行ったとおもうが、その後のことなどあまり興味がなかったので知らない。
「知佳チャン、短大出てから農協に勤めている」
「何で嫁にいかんのだ」
「いい人がおらんのだよ、男はみんな都会に出ちまうからな」
母ちゃんがそう言ったところに、ばあちゃんが自分の部屋から出てきた。
「若い男は東京で蚊柱作っているんじゃ」
ばあちゃんは時々面白いことを言う。
「何だそりゃあ」と親父が笑った。
「だってさ、蚊柱っちゅうのは、雄が集まって雌をよぶんじゃ、東京では男が集まって、女を誘っているんじゃろ」
乱暴な話だ。だがこのばあちゃんは生き物のことをよく知っているし、発想は若い人だって驚くほど奇抜である。
「克芳の買ってきた本はおもしれえよ」
「蚊柱のこと教えてよ」
「克芳、何で急に蚊柱のことを言い出したんだ」
親父も母ちゃんもあれっと言う顔をしている。
「なんだかわかんないけど、いきなり懐かしくなったんだ」
「おめえは覚えていないだろうけど、5歳の時だけどな、ばあちゃんと一緒に山に茸採りに行ったことがあるべえ、まだばあちゃんが小学校の先生しているときだよ、姉ちゃんもいっしょだったよ」
「どの山」
「猿欠(さるかけ)山にさ、あそこは小さい山なのに茸がよく採れるし、あぶなくない」
このあたりには猿がでるが、なぜか猿欠山には猿が入らない。何か猿の嫌いなものがあるからに違いないが、理由は明らかではなかった。
「そんときな、背の高い赤い茸があってな、ちょっと紅天狗に似ていたけど、紅天狗ではなかった。その茸の傘の上に蚊柱が立っていたんだ、おもしれえ光景だったな、そこにな、克芳がトコトコ歩いていくとな、蚊柱が克芳の頭の上に移りおった。したら、克芳が逃げたんだ。オラは姉ちゃんの手を引いて追いかけたよ、克芳は一生懸命手で払っていたけど、蚊柱はいなくならなくてな、林の出口までくるとやっと蚊柱が消えた。ところがな克芳の頭の中がボコボコに食われていてな、かゆいかゆいと泣くものだから、あわてて家に戻ってムヒつけたんだ」
「そんなことがあったんだ、だけど、それじゃ、その蚊柱は雄じゃなかったのかな」
「いや、雄の中に雌が何匹かいて、交尾したんで、血がほしくなって、克芳の頭をねらったんだろう」
そんなこと、全く覚えていない。
「その後、小さいころ克芳は蚊柱を見ると逃げちまった」
「そんなことがあったなあ」
母ちゃんもうなずいている。
「それが頭の隅にあって、なつかしくなったんだろうかね」
父親はちょっと不思議そうである。
「急に思い出したんだよ、きっとかゆいだけで怖いとは思っていなかったんだろう」
「今日、夕御飯食べた後に澄川に蚊柱見に行くか」
「さっき河原に行ってみたけど、蚊柱は無かったよ」
「もっと暗くなってからの方がでるよ」
夕暮れ時、ばあちゃんと澄川に行った。ばあちゃんが河原に降りていくところは、さっき自分が通ったところと違った。かなり上流まで歩いたところにある大きな楠の生えているところだった。そういえば子供の頃はここまで来て遊んだものである。楠は河原から生えていて、太い根っこが斜面に張っていた。根っこに足をかけて河原まで降りたものだ。今見るともっと土に埋もれていて、自然にできた階段のようになっている。
「この木は五百年も前からあるんだ」
「でも、なぜ河原なんかに生えたのだろう」
「ここはな、川じゃなかったんだよ」
「なんだったの」
「ここはある家の庭だったんだ、ばあちゃんも知らない頃だよ、それが地震か何かわからんが、川の流れが変わってな、削られて河原になっちまったそうだよ」
ばあちゃんは器用に河原まで根っこを利用して降りた。すると、楠の脇に蚊柱が立っていた。
「ほらあるだろう」
「何の蚊だろう」
少し赤っぽくて、子供の頃よく見かけた灰色の物と違うようだ。
「わからんな、アカイエカって奴かな」
そうばあちゃんが言ったとき、蚊柱が自分のところによってきた。
「克芳好かれたようだぞ、見合いせんか」
蚊柱が頭の上で音もなく舞った。
「蚊柱と見合いと関係ねえべ」
水際にまで逃げたが、蚊柱がついてくる。なんだか逃げたくなった。
「ばあちゃん、俺は走って家に帰ってるから、ゆっくり帰ってこいや」
急いで道の上にでたのだが、まだ追ってくるので、家に向かって一目散に走った。家の近くになると蚊柱はいなくなっていた。
庭にいると、ばあちゃんがゆっくりと歩いて戻ってきた。
「蚊柱に好かれおったぞ、お見合いの話をすすめろや」
ばあちゃんがまたお見合いのことを言った。母ちゃんと話をあわせていたようだ。なんだか無責任なこった。
「なんだい、ばあちゃん、やめてくれよ」
「あの子はいい子だよ、一度会ってみなよ」
「何で蚊柱がよってきたら、お見合いなんだ」
「蚊柱が頭に立つと、いいことがあるという予告なんだ」
ばあちゃんはたまに根拠のない都合のいいことを言う。
「おめえ、5日いるんだろ、暇だろう、お見合いで遊べ」
まあ、会うだけなら同級生だからかまわない。どんなになったか興味はある。
「これから、蚊柱の言い伝えを話してやんべえ、部屋にこいや」
ばあちゃんについて部屋に行った。
なんと、八畳間の半分は板の間になっていて、でんと書斎机が置いてあり、その背後には造り付けのガラス戸付き本棚になっている。中にはずらーっと本が並べてある。
もんぺをはいて、手ぬぐいで頬かむりしたままのばあちゃんが皮の椅子に腰掛けて机に向かっている姿を誰が想像できるだろう。
半分は畳で床の間までついている。ちゃぶ台がおいてあるが、夜はそこに布団を敷いて寝ているわけだ。
「いつこんなにしたんだ」
「去年な、父ちゃんが書斎を作ってやるっていうから、前から使ってたこの部屋を半分板の間にしたんだ」
「ずいぶんかっこいいんだな、作家みてえだ」
「だろう、まあ、ちゃぶ台ところに座ってくれや、これから、その蚊柱の伝説っつうのを聞かせてやるよ」
ばあちゃんは書斎机に腰掛けてコンピューターを立ち上げた。
「PCいつから使ってんだ」
「三年前だよ、今全部これで文章作ってんだ、90になったら、このあたりの伝説、伝承の本をだそうと思っているんだ」
「すごいなー」
「ここの蚊柱伝説はもう書き上げてあっから、今から読んでやる」
「読むの大変だ、打ち出してくれれば寝ながら読むよ」
ばあちゃんはちょっと考えてから言った、
「グッドアイデアだな、読んでついでに誤字や、わかりにくいところ教えてくれや」
「いいよ、やっとくよ」
ということで、打ち出した物をもらうことにした。
それで、ばあちゃんのところからキッチンに移動すると、おやじがビールを飲んでいた。夕食の時にも飲んでいたのによく飲む。
「飲むか、飲むなら勝手にやってくれ」
そういわれたが、ばあちゃんの打ち出した物を読まなければならない。
「今日はやめとくよ、これからばあちゃんの書いた物を読むことになっているんだ」
「そうか、わしらがよう読まんものだから、喜んだろう」
「本にするって言ってたぞ」
「ああ、町でも何ぼか買ってくれることになっているんだ」
「どこの出版社なの」
「新町の若草印刷さんだ」
「ああ、知佳ちゃんの実家か」
見合いをせよという同級生の実家は印刷所を経営していて、たまに郷土の本なども出版している。
「だから、ばあちゃんが見合いしろって言ったわけか」
おやじも笑ってうなずいている。
そこへばあちゃんがプリントアウトした原稿をもってきた。
「はいよ、そんなに長くないからすぐ読めるよ」
「うん、すぐに読むよ、明日の朝返す」
それを持って二階に上がり、押入から布団を取り出して敷くと寝っ転がった。夏だがここは夜になると気持ちのよい風が入ってきて、クーラーなどいらない。ただ、蚊だけはじゃまで、網戸になっていてもたまにどこからか入ってくる。
原稿をめくった。
「蚊柱茸」というタイトルである。
その昔、庭に楠の生えている家があった。そこの主人は猟師で、おかみさんは畑をやっていた。よく働くおかみさんで、畑は小さいながらもよく土が肥え、そこでとれる野菜はなかなか評判がよく、町に持って行くとそれなりの値段で売れた。もちろん、山で採れる山菜や茸、主人の捕ってくるウサギや鹿、イノシシなどの肉も町で喜ばれた。
それに牛と豚を飼っていて、牛は乳をとり、豚に子どもを産ませ売りに出した。
夫婦には一平という男の子が一人いて、大事に育てていた。一平はすくすくと丈夫に育った。ところが五つになったときだった。真夏だったが、突然高熱を出した。こりゃ大変だと父親が背負って山を駆け下り、汗だくになって町の医者まで走りに走った。
町の医者に駆けつけたときには、一平はやっと息をするほど熱で弱っていた。
「こりゃ、まず命を助けなければ」
親切な医者は夜通し看病をしてくれた。おかげで命は取り留めたのだが、後遺症が残った。一月入院したが左手と足がしびれたままになり、口がききづらくなった。
「これは脳炎だな」
医者に言われても夫婦はどのような病気か知らなかった。
「なにが悪かったんでしょうか」
そういう知識のない母親は医者に尋ねた。
「しょうがないんじゃ、蚊からうつされる病でな、ひどいと死んじまう、よく命が助かったものだ」
「これから一平はどうなるのでしょうか」
「うむ、歩けないことはないし、手だって使えるが、細かいことはできないだろう、一人で飯が食えるように考えてやることだ、だがあまり心配することはない」
そう言われてもどうしたらいいかわからなかった夫婦は息子をともかく命は助かったので元気に育てようとした。
両親はますます一平を大事にしたんだ。一平も親の言うことをよく聞く、いい息子に育っていった。
ある時、脳炎がアカイエカという蚊が運ぶばい菌で起こることを知った。しかもそのばい菌は豚の体で増えるという。
それで怒った父親は豚を売っちまった。それに虫を殺す薬をまいて、自分の住んでいるところの蚊を撲滅したそうだ。その薬は虫よけ菊という花から一平の父親が自分で工夫して作ったそうだ。裏山にも撒いたので一平の家だけではなく、そのあたりは蚊が少なくなった。
それを聞きつけた町の薬屋が、一平の父親から虫よけ菊から蚊よけの薬の作り方を教わり、売ることになった。そのお陰で一平の家の暮らしも少し楽になり、それだけではなく、父親は町から感謝され有名人になった。
一平は少しからだが不自由だったが、頭のいい元気な青年になった。
一平の親孝行は町中に知れ渡っていった。手が動かしにくかったので鉄砲打ちにはなれなかったが、できることは何でもやった。特に山菜採りや茸採りは得意だった。
一平は美味い珍しい茸をとってきて町の朝市に持っていった。町の大店の賄いの人たちが一平の茸や山菜をよく買ってくれた。
特に一平の命を助けてくれた医者の長庵は茸が好きで、面白い茸が採れると直接持って行った。いい値段で買ってくれたので、一平は大変感謝していた。
そんなことで、秋になると、一平は珍しい茸を探していろいろな山に入った。
親父は蚊に刺されるなと一平にいつも注意した。
ある日、一平がどの山に茸採りに行こうか考えていたときに、親父がよく話してくれたことを思い出した。
こんな話である。ある山の中で猟師が山鳥を見つけて、そうっと近ずいて撃とうと鉄砲を構えた。そのとき木の上から猿たちがキーキーと騒いで山鳥を逃がしてしまった。猟師たちはよく猿にじゃまされるので、猿を目の敵にしていた。そのころそのあたりの山には必ず猿がいた。
怒った猟師は鉄砲で猿をねらって撃つと、猿は山を降りて逃げていった。猟師は追いかけた。谷川にでた猿は反対側の山には入らず、川伝いに走って逃げて行ってしまった。
猟師は鉄砲を一発猿にむけてぶっ放すと、追いかけずに谷川を渡って向かいの山に入った。あまり大きい山ではない。
中にはいると、程々の日が射し込み、下草も程々に生えていて歩きやすく、気持ちのいい林だった。
猿も追い払ったし、いい獲物があるのではないかと歩き回ったのだが、全く鳥や獣が見あたらず、あきらめて山からでてとなりの山に移ったそうだ。すると山鳥やらリスやら、いろいろいた。なんと鹿がいたので鉄砲をむけた。また猿が騒いだ。猟師は猿に鉄砲を放った。猿も鹿も逃げた。猟師は鹿を追いかけた。鹿はさっき猟師が出てきた山の境にくると、くるっと向きを変え猟師の方に走ってくると通り越して一目散に逃げていった。あっけにとられた漁師は鉄砲を構える暇もなかった。鹿のあとを追っていた猿も隣の山には入らず、やっぱり猟師の方に向かって走ってくると逃げていった。
猟師はわけもわからず、もう一度前の山に入ったそうだ。
山の中は気持ちがよく、木も草も元気に生えていた。しかし、最初に入った時と同じで動物達が見当たらなかった。猟師は狩をあきらめて家に戻った。
そういうことがあってしばらくして、猟師は仲間たちとその山の近くでイノシシ猟をした。猪を見つけみんなでねらって撃ったのだが、玉は急所をはずれ、猪は勢いよく逃げた。失敗した猟師たちは別の場所に行こうと集まったところに、手負いの猪が猛スピードでもどってきた。
猟師たちが気づいた時には二人は撥ね飛ばされ怪我をしてしまった。
先の猟師が猪の戻ってきたところを見ると、以前追いかけた鹿や猿が入らずに戻ってきた山であることに気づいた。
ともかく、怪我をした二人を連れて猟師たちは町に戻った。その猟師の話で、町の者も動物たちが入るのを怖がる山があることを知った。その際、猟師が猿がいない山と言ったものだから、猿欠け山と呼ばれるようになった。
その話を思い出した一平は猿欠け山に茸採りに行ってみようと思った。動物はいないが茸はあるに違いないと思ったからだ、父親がその山の場所を知っていたので、次の朝早く出かけた。
家を出て一時間ほどいくと猿欠け山についた。
中にはいると、話に聞いていた通りに日の光が程々に入り、気持ちのよい林だった。足下には茸がたくさん生えていた。いろいろな色の茸で、ほとんどが食べたことがないもので、ちょっと毒々しい感じがした。しかしその林の中で大きな舞茸をみつけ、一平は籠一杯にした。これで毎年舞茸がとれると喜んだ。医者が探していると言っていた猿の腰掛けも見つけ袋に入れた。とても良い薬になるというものだという。
籠も一杯だし、またこようと思い、出口の方に行こうとすると、ずいぶん大きな茸が目に入った。真っ赤な傘が一平の腰の高さまであった。毒茸に違いない。さらに驚いたことに、たくさんの蚊が茸の傘の上で集まって宙を舞っていた。
一平は気持ちが悪いと思って、あまり近寄らなかった。家の周りに蚊があまりいなかったこともあり、一平は蚊柱というものを見たことがなかったのだ。
家に戻り、そのことを親父に言うと、それは雄の蚊が集まっていて、刺されることはないので心配はいらない、だが茸の頭の上に蚊柱がでるとは珍しい、と話してくれた。
蚊柱は安心なものとわかった一平は、猿欠け山に何度も通った。いつも珍しい茸が採れ、高く売れたからである。
猿欠け山に向かったある日、小猿が一匹で猿欠け山に入ろうとしているのを見た。きっと親から離れて、遊びにきたのだろう。子どもの雄の猿はちょっと大きくなると、親から離れて冒険にでるということである。
小猿が猿欠け山に入ったのを見て、一平も入っていった。
小猿は林の中で茸を採って食べたり、木に登ったりして遊んでいる。一平はいつものように茸を採っていたが、小猿が赤い大きな茸に手を伸ばすのが見えた。その茸の頭には蚊柱が立っていた。
見ていると、猿が手に持っても赤い茸の傘の上で蚊柱がたっている。
小猿はもったまま蚊柱を面白そうに眺めていたが、蚊柱がいきなり猿の頭の上に移った。
小猿は驚いて手で蚊柱を払ったが、蚊柱はなくならなかった。小猿はあわててそのまま山の上の方に木を伝わって行ってしまった。
一平は小猿が捨てた赤い茸を拾った。持って帰って父親に茸の名前を聞こうと思ったからだ。
一平は拾った赤い茸を親父に見せた。
「名なんぞしんねい」
「これに蚊柱が立っていて、蚊柱が小猿の頭に移った」
「ああ、蚊柱は高いところが好きだ」
「この茸食えるだろうか」
「赤いから毒に決まってべ」
「それじゃ、ほかすか」
一平は裏山に放り投げた。
翌日も猿欠け山に茸採りに行った。
林の中にはいると、いつものようにたくさんの茸を採った。
昨日小猿が赤い茸を採ったところにくると、小猿がしゃがんでいる。戻ってきたようだ。何をしているのだと、陰から見ていたのだが子猿は動かない。おかしいと思って近寄ると、目を瞑って俯いている。頭には大きな蚊柱ができている。
どうも死んでいるようである。触ってみようかと思ったが、猿のように蚊柱が頭の上に移ってくるといやだと思い、手を合わせて通り過ぎた。いずれ土に帰るだろう。そう思った。その時はどうして小猿が死んだのか考えなかった。
その後、何回も猿欠け山に行ったが、小猿のところは通らないようにした。
こうして猿欠け山から、一平は貴重な茸をたくさん採ってくることができた。
次の年であった。梅雨時になると家の中に蚊が入ってきた。このあたりでは梅雨の時期になっても大して雨が降らなかったが、それでも水が溜まったりして、蚊はでてくる。
「おとう、蚊がでたぞ」
「そんなことはねえべ、早くから虫よけ菊撒いたによ」
親父は家や庭の周りをみてまわった。確かに蚊がよってくる。虫除け菊から作った粉を庭にまいた。
「明日、雨が降ってなかったら、裏の林にも撒くべ」
「手伝うか」
「いやおれ一人でいい」
「それじゃ、おらは久しぶりに猿欠け山にいってみるべ、長庵先生も猿の腰掛けが欲しいと言っている」
猿の腰掛けは一年中みつけることができる。
その時期に山の中に入るのは始めてであった。林の中は不思議と秋の時と同じように気持ちのよい空気が流れていた。木の下を見るといろいろな茸が生えている。まるで秋のようだ。
ただ食べることのできる茸はなかった。林の入り口で、みづこを沢山とった。みづことは網傘茸のことで、春の茸である。そのころはあまり食べる習慣はなかったが、一平は食えることを知っていた。
林の中を歩いていると、いつの間にか蚊柱の立った赤い茸のところに来てしまった。小猿が死んでいたところである。
そこで驚く物を見た。そこには、真っ赤な小猿と同じほどの大きさの茸が生えていて、蚊柱が立っていた。
一平は脳炎にかかったためかどうかわからないが、体の動きが早くない。しかし、勘がよかった。危ないと思ったのだ。
そう思ってその場から逃げ出したのと同時に、赤い茸の傘の上の蚊柱が高くに舞い上がった。
一生懸命走って、林の入口で後ろを振り向くと、蚊柱が追いかけてくるのが見えた。一平は林から飛び出た。すると蚊柱は林から出ることはなく、しばらくそこで集まってわやわやしていたが、再び林の奥に動いていった。
家に戻った一平は土間に籠をおくと、「おっとう」と家の中に声をかけた。
「おっとうは、裏山に行ってるよ」
おっかあの声である。きっと薬をまきに行っているのだろう。
一平も裏山には入った。裏山の林の中の道を登っていくと、親父の姿が見えた。立ち止まって何かを見ている。
「おっとう、どうだ」
おっとうが振り返って、「おまえの採ってきた赤い茸が生えてるだ」
と声を上げた。
「蚊柱が立ってるか」
「ああ、おもしれえな」
「あぶねえから近寄るな」
一平が大声を上げて親父のところにいくと、それとほとんど同時に、父親の頭の上に蚊柱が立った。
「逃げれ」
一平がおっとうに声をかけた。
「大丈夫だ、すぐいなくなる」
おっとうは頭の上の蚊柱を手ではらっている。
「この茸の蚊柱はおかしい、おっとう逃げよう」
「いま帰るからな」
親父が降りてきた。一平が待っていると、親父の頭の上では真っ赤な蚊がぷんぷん舞っている。
「ありゃ」
親父が頭をかきはじめた。
「蚊が刺しよる、蚊柱は雄で血を吸わねえんだが」
「早く家に帰ろう」
一平が促して、下っていったが父親の頭の上の蚊はいなくならない。
「なんだこりゃ、かいいったらありゃしねえ」
親父は袋に残っていた虫除け菊の粉を頭の上に振りかけた。
それでも蚊は舞っていた。
やっと裏山の出口にたどりついたが、親父の頭の上の蚊柱はそのままだった。
「水をかけてみろや」
親父がそう言うので、瓶から柄杓で水をくんで親父の頭にかけた。
だけど蚊柱はいなくならなかった。
箒で払ったりもしたが、すぐ集まった。
一平が町まで走っていって、長庵先生に助けてくれるように頼んだ。長庵先生は南蛮の虫を殺す薬を持っていて、わけてくれた。それを親父の頭にかけたがだめだった。
こうして一平の親父は飯を食うときも、水浴びをするときも、頭に蚊柱が立っていた。それだけではなかった、頭が蚊に刺され膨らんできた。
一月が経ったある日、布団に寝かされていた父親の姿が見えなくなった。
一平と母親はあたりを探し、裏山の中にはいった。
林の中を登って行くと、おっとうはやはり赤い茸の生えていたところで座ったまま死んでいた。頭には蚊柱が立っていた。
母親はそれを見て、腰を抜かしてしまった。
一平は母親に、触らないように言った。
一平は父親に藁をかぶせた。それでも蚊柱はその上に立っていた。長庵先生に連絡をすると、町から遠い一平の家にわざわざ来てくれた。親父の遺体を見ると、手を合わせ、「理由は分からんが、蚊柱のせいか、茸のせいか、ともかく、触るではない、静にこのまま葬ろうではないか」と言った。
一平は親父の遺体の上に屋根を作り、社を自分で作った。
この話が長庵から町の寺や神社に伝わると、お坊さんや神主さんがやってきて、おっとうの遺骸に手を合わせ、供養をしてくれた。
一平には来年になると、父親の遺骸は赤い茸になることがわかっていた。そのことは周りの者には言わなかった。
お坊さんも神主さんも、父親が蚊を殺す薬を作ったために蚊が復讐したのかもしれんと言った。庭に蚊の供養塔を建てるように言った。親父は自分のために蚊を追い払ったのだから、親父のせいではない。むしろ俺のせいだと一平は涙を流した。
一平のうちには供養塔を建てるような金はなかったが一平はうなずいた。時間をかけ近くの川から大きな石をひきずって、楠の下に置くと、木を切り出して、屋根をかけた。「蚊柱供養の碑」と長庵先生に石の表を書いてもらい、自分で字を彫った。
毎日おそなえをして蚊柱供養をした。
裏山の父親のところにも食べるものや水を供えた。蚊柱は消えることがなく、隣に生えている赤い茸も元気だった。次の年、かぶせておいた藁をとると、父親は赤い茸に変わっていた。
母親は五年後になくなり、一平は茸や山菜を採り畑をたがやして、六十六の独り身の人生を終わらせた。
父親の遺体が変った赤い茸は、その後誰の目にも触れることは無かった。一平は赤い茸がどうなったか人にいうことはなく、書き残すようなこともしなかった。赤い茸は誰にも見つからず、知られることはなかった。まだどこかに生えているのではないかという話も残っている。
その後、大きな地震の後に、川の流れが変わり、一平の家の前の道を削り、庭の楠のところまで川になってしまった。今でもそれで楠が河原の土手脇に生えている。
それで話しはおわりであった。
後記としてばあちゃんの考えが述べてあった。
蚊柱の立っていた茸は、二酸化炭素をだすか血の匂いのする茸で、それで蚊が集まっていたのではないかとあった。
読み終わったら猿欠け山に行ってみたくなった。
朝、ばあちゃんに尋ねた。
「蚊柱の伝説は面白かったよ」
「ありがとうよ、ところで、どうだい、今日、知佳ちゃんと会わないけ」
まだ、お見合いにこだわっている。
「そりゃ、かまわないけど、お見合いなんて堅苦しいのはいやだよ」
「うちで、夕方みんなで寿司でもとろうや、オラたちも一緒に食うから」
「そういうやつならいいよ」
「知佳ちゃんの母ちゃんも呼んでやろう」
あまり目立たない子だったが、そういう子が大人になると、結構美人になっていたりする。ちょっと楽しみである。
「猿欠け山は、今も猿がはいらないの」
「どうじゃろうね、いないという話は聞かないね、もっとも最近は茸採りにはあの山に入らないよ、もっと奥の山に行かないと自然の舞茸などにはお目にかからないからね」
「あぶなくないかな」
「ああ、あの山はあぶないことなどないさ、だけど長靴の方がいいよ」
「あの赤い茸は本当に生えていたのかな」
「いや、きっと紅天狗茸じゃないかね、食べると気持ちのよくなるやつ」
「ああ、そうか、覚醒剤みたいなやつ」
ばあちゃんもうなずいている。
そこで散歩のつもりで猿欠け山にいくことにした。まだ九時前なので午前中に実家に戻れる。ザックに水のボトルとキャラメルだけいれてでかけた。県道を川の上流に向かって楠木のあるところから二十分ほどいくと、山に入るハイキングコースが整備されていた。その山道を三十分も歩くと猿欠け山の入り口になる。
久しぶりの山歩きである。ちょうど曇り空で、真夏の太陽にさらされないだけ助かったが、それでも汗が噴き出てくる。
猿欠け山の入り口から細い道が林の中にのびている。歩いていくと、ひんやりした空気がまとわりついて気持ちがいい。
林の中の登り道の脇に夏でも茸はちらほら生えている。
小さな山なので、あっという間に半分ほど登ってしまった。木々の間から、歩いてきた道が下に見える。
大きな羊歯の間に赤い物がちらっと見えたので、羊歯の葉をよけてみると、真っ赤な茸が生えていている。まさにばあちゃんがまとめた話しの中の茸だ。ただ大きさは違う。目のまえにあるのはほんの二十センチほどのものである。
ばあちゃんが後書きでいっているように、この茸は二酸化炭素を出すか血の匂いがしているのかもしれない。これをばあちゃんに持って行ってやると喜ぶだろう。
手を伸ばして真っ赤な茸を引っこ抜いた。その拍子に蚊柱が現われ、膨れ上がり、頭に飛んできた。
「うわー、茸になっちまう、殺される」
その場から逃げ出した。頭の上をたくさんの蚊が上に行ったり下に行ったリしている。
ふっとその時、子供の頃、蚊柱に絡まれたことを思い出した。しかし、それは刺したりしないし、いずれ消えてしまうがこの赤い茸の蚊柱は違う。
頭の上の蚊が髪の毛にはいってきた。ぷんぷんとうるさい。早く山から出なければ、赤い茸になって死ぬのはいやだ。
早足で猿欠け山をでようとした。だが足がゆっくりとしか動かせない。あせっても動かない。なかなか猿欠け山の出口がみえない。その間に蚊がどんどん集まってきて、頭の上で大集団をつくった。
汗が出てきた。体が前に進まない、その場にうずくまりたくなる。ばあちゃんの書いた伝説の中の猿や一平の父親のようになりたくない。
一生懸命にからだを動かした。
目もかすんで周りを認識できない。
頭に蚊柱を立てたまま、手に赤い茸を握りしめ少しずつ体を動かした。
家では、同級生の知佳ちゃんとそのお母さんも来て待っていた。もうすぐ、寿司もくる時間だ。
「克芳のやつ、いったいどこに行ったんだ、猿欠け山に行くっていって、朝早くに家をでたのだけんど、おかしいな、あそこまでゆっくり歩いて一時間だ」
「遭難するようなところはないしな、俺が車で見てくるわ」
父ちゃんが立ち上がったとき、庭先に人がふらふらと入ってきた。
「克芳じゃないか」
頭には蚊柱が立っている。
顔は真っ赤になって、薄汚れた枯れる寸前の紅天狗丈を振りかざして、必死に何かを言おうとしていた。
「蚊柱に殺されちまう」
父親が庭にでて、頭の上の蚊柱を追い払ってくれ、抱えあげるようにして、家の中に運びいれてくれた。
「どうしたんだ」
畳の上に横たわり、絞り出すように言った。
「猿欠け山に行ったら、赤い茸が生えていて、蚊柱が立っていて、それが俺のところにきたら、からだが動かなくなった、やっと帰ってきた、このままだと、死んで赤い茸になっちまう」
「子供の頃のトラウマがでちまったんか」
ばあちゃんが言った。
「そのようです、この子は蚊柱が大嫌いでした」
母ちゃんが知佳ちゃんに説明している。
「おはずかしいところをみせてすみませんな、お見合いはなかったことに」
父親は知佳ちゃんのお母さんにあやまっている。
何を言ってるんだ、俺は目をつぶってそれを聞くと、声を出さずに怒った。赤い茸になっちまうのに。なぜ医者を呼ばない。
「いえ、克芳さん、お疲れになっているみたい、お仕事大変なんでしょう」
知佳ちゃんは優しい娘になったようだ。
ばあちゃんがみんなに言っている。
「おらが悪かったんだよ、昨夜この子に原稿を渡して、読ませちまった、それで、ますます蚊柱が怖くなっちまったんだな」
何を言っているんだ。
「克芳さん、まじめで優しいのね」
知佳ちゃんが言っている。本当にお見合いがしたい。
「おばあちゃん何を書いたんです」
知佳ちゃんのお母さんが尋ねている。
「克芳にこのあたりの伝説だといって、おらの書いた小説を読ませたんだ、蚊柱茸という奴で、それが人を殺しちまう」
「また、新人賞にだすのですね」
「ああ、こんどこそ大賞をとれるかもしれんな、克芳のやつが死にそうになるほどうまく書けたものな」
ばあちゃん、小説を書いていたん。知らんぞそんなこと。俺は気が遠くなっていくのを感じていた。やがて前後不覚になってしまった。すなわち失神したのである。
蚊柱茸


