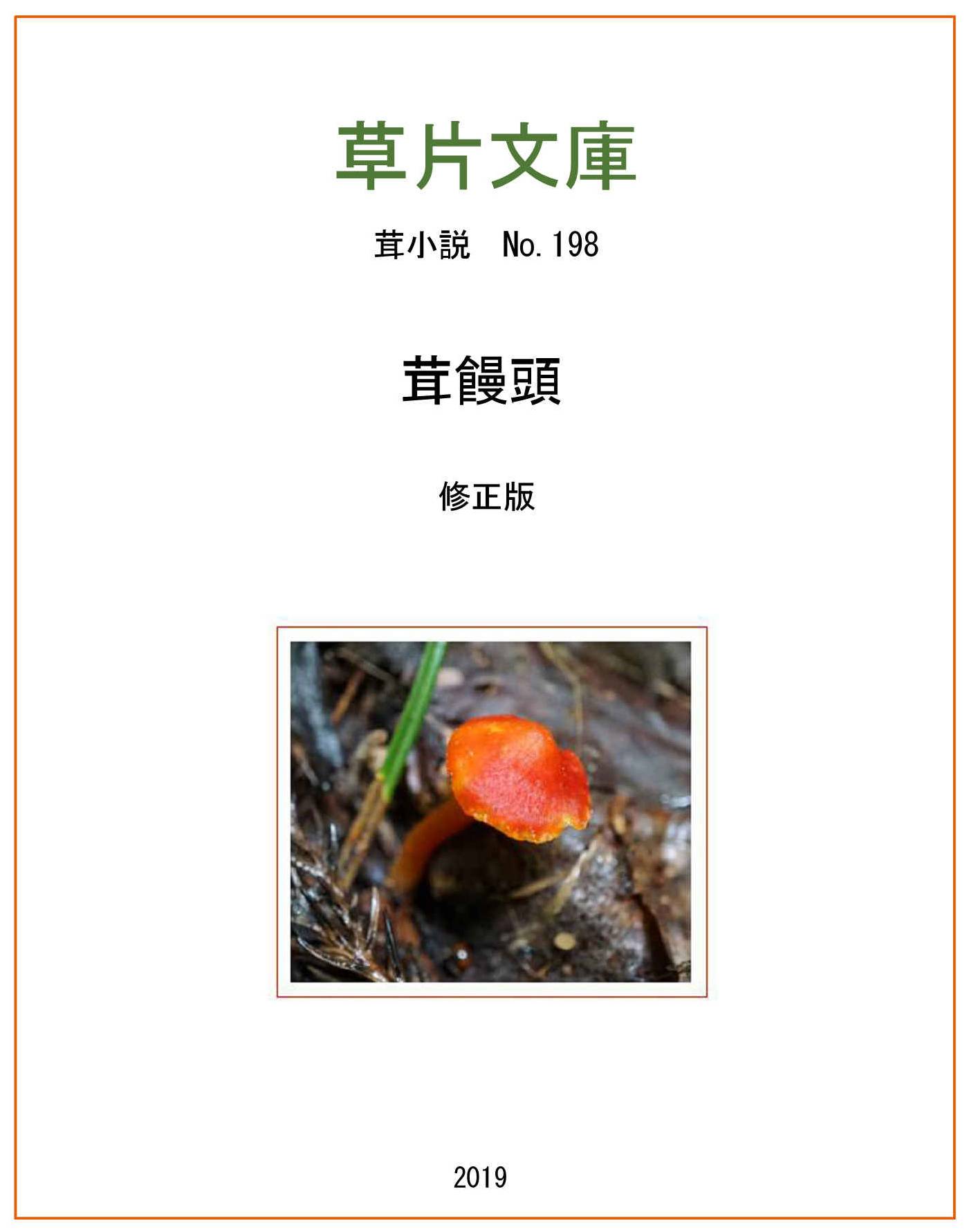
茸饅頭
茸紳伝説 縦書きでお読みください。
「ばあちゃん、なにしてるだ」
田子作が六六(むむ)ばあちゃんに声をかけた。
六六ばあちゃんは、植木鉢になにやら植えている。
「んだ、昨日山さ茸採りに行ったべ、ようけ、しめじやらなめこやら採れたじゃろ、そんときな、赤いかわいい茸見つけたんじゃ、ほれ」
ばあちゃんは親指ほどの小さな茸を植えた植木鉢を田子作に見せた。
「うん、かわいいな、だけんど、茸を植木鉢に植えてもだめじゃろ」
茸を採ってきて庭に植えてもすぐ萎れる。
「そんなことは、わかってら、ちょっとでも長く見ていたいっちゃ」
田子作もそれを聞いてうなずいた。
六六ばあちゃんは80歳、息子の田子作と嫁の実野の饅頭屋を手伝っている。
六六ばあちゃんの名前は六月六日に生まれたからつけられたという話もあるし、ばあちゃんの父ちゃんが六十六のとき生まれたからという話しもある。だが、本当のところは本人も知らない。
ばあちゃんは朝早く山菜や茸採りに行く。一人で行くときもあるし、嫁の実野と一緒に行くときもある。今日の朝は一人で裏山に茸採りに行ってきた。
田子作は茸や山菜を使って饅頭を作っている。
信州のおやきに似ているが、皮の作りがちょっと違う。甘みが少ないので、好んで買いに来る人がかなりいる。
「ばあちゃん、明日の朝、私も一緒に茸採りに行よ」
明日は饅頭屋が休みだから、実野も一緒だ。
「そんじゃ、むすび山にいくか」
むすび山はちょっと遠い。一人の時は危ないから遠くの山には行くなと言われていて、裏山に行くだけである。
朝日が山の間に現れると、二人は駕篭をしょってでかけた。
林の中はまだ薄暗い。
「ようけ生えてる」
実野がいぐちの仲間を摘まんだ。まだ山を登り始めたばかりなのに、至る所に茸が立っている。
二人は食べられる茸は何でも駕篭にいれた。田子作の作る茸饅頭の中身になる。
いろいろな茸を混ぜて、こねて饅頭の中身にする、茸だけの茸饅頭は田子作饅頭の売れ行きナンバー1である。春は山菜饅頭が中心になるが、春の茸を使った茸饅頭はこれまた美味であった。饅頭屋の近くに年寄りでも登れる、ハイキングにいい山の入口がいくつかあり、町には温泉宿があるので、こんな山の中の集落にある小さな饅頭屋でも、全国から買いに来る人が集まるのだ。もちろん味がいいので人伝えにわざわざ来る人もいる。
ある会社が、通信販売したらどうだとか、冷凍にして出荷したらどうだとかいってくるが、田子作はいっさいお構いなしだ。
休みの日、田子作は奥山に行って、苔や羊歯をとってくる。庭に石を積んでいろいろな羊歯を植えて楽しんでいる。結構な風流人だ。もちろん奥山から舞茸や香茸なども採ってくる。それは舞茸だけの舞茸饅頭、香茸饅頭になる。
それに松茸を採りに行ったときには松茸饅頭をつくる。一つの茸で作った饅頭は、ただの茸饅頭の倍ほどの値段がするが、これがまたおいしい。採れたときにだけ作る珍品である。
旅の雑誌の密やかなグルメというコーナーで紹介されて以来。秋になると、店の休みの次の日には7時の開店なのに6時から並んでいる人たちがいる。昼のために饅頭を買って山歩きをしようというわけだ。
田子作饅頭屋があるおかげで、山への登山者が増え、市から感謝状が贈られた。
「ばあちゃんがこないだ採ってきた赤い茸、枯れないで元気だぞ」
鉢に植えておいた赤い茸がしゃきっと立っている。
「ほんんとだなあ、かわいいなあ、名もしらんがよ」
「なんだべな」
実野が見に来た。
「ほんとにかわいい茸だなあ、どこでとったん」
「裏山の祠あるべ、穴の入り口んとこに生えていた」
裏の山を登っていくと、小さな穴があって水がちょろちょろでている。入り口ところで小さな水たまりができているが、外に流れていかないところを見ると、浸み込んでしまっているようだ。蟹がいることがある。
「あの水神様のとこかね、それじゃ、神様が六六ばあちゃんにくださったありがたい茸だべ」
信心深い実野は何でも神様にしてしまう。
「そうかもな、三日たってもしおれねえ」
ばあちゃんもうなずいている。
「朝のお日様の光が透き通って赤くてきれいだなあ」
実野が感心しているのを見たばあちゃんが
「朝焼けみたいじゃ、朝焼け茸にするか」と独り言を言った。
田子作にも聞こえたとみえてうなずいた。
春は野草饅頭、山菜饅頭で大忙しである。定番はよもぎ饅頭やゼンマイ饅頭、蕗の薹饅頭などだが、結構珍しがられるのがドクダミ饅頭やセンブリ饅頭である。苦かったり、匂いが強かったりするのだが、一緒に練り込んである葉物との調和がよくて、食べた後からだに利いたような気になる。
春の茸饅頭はあまりないが、編み笠茸饅頭を時々作る。それも評判がいい。今日はばあちゃんが竹藪でみつけた絹傘茸饅頭がある。レースをまとったようなきれいな茸で、中華料理に使われる高価なものである。
「ばあちゃん、去年採ってきた朝焼け茸、まだ元気だね、根ずいちゃったようだね」
実野が庭の隅に出してあった鉢植えの赤い茸を見て不思議そうにいった。茸は一週間もすれば枯れてしまう。ところが、去年の秋に六六ばあちゃんが採ってきたこの茸は枯れるどころか育っている。雪にあたっても全く萎れる気配が無かった。
「そうじゃなあ、不思議な茸じゃよ、大きくなってるんだ」
指ほどの大きさだった赤い茸は松茸並に育っていた。赤く透き通っているのでとてもきれいだ。
「一年かけて大きくなる茸かもしれんな」
「うん、食えるのかどうかわからんけどな」
「見ているだけでもきれいじゃな」
ばあちゃんもうなずいた。
ばあちゃんは毎日茸の鉢に水をやっている。
夏になっても、朝焼け茸は元気だった。それどころか、日陰の風通しのよいところにおいてある茸の脇から、小さな赤い茸がたくさん顔を出した。
「なんじゃ、この茸は子供を作りよる、胞子はまだ飛ばしておらんのにな」
ばあちゃんは子供の茸を別の鉢に移した。子供の茸は成長が早く、夏の終わりには、松茸なみの大きさになった。それからも子供が生えた。
「ばあちゃん、赤い茸どんどんふえますなあ」
「食えれば饅頭にするんじゃがなあ」
「赤いから毒とはかぎらんけんど、やっぱり注意せにゃなあ」
ばあちゃんは夕飯を食べてから、庭に出ると、ちいちゃい朝焼け茸の頭を食ってみた。だいたい毒のある茸でもちょっとかじったくらいじゃ死なん。結構甘みと酸味のある茸だ。なにかの果物の味がする。
次の朝、ばあちゃんは何ともなかったどころか、気分が晴れやかだった。こりゃええ饅頭ができるべ。
「田子作う、朝焼け茸食えそうじゃ、昨日の晩、飯の後に頭食ってみた。甘酸っぱくてうめえぞ」
「ばあちゃん体に気をつけや、あぶないことするなよ」
「ありゃ、田子作に言われるようになったらおしめえだな、心配すんな、ギネスに載ってやる」
「ばあちゃん、ほんとに載るかもしれんな」
実野が笑った。
「今日、何本か食ってみて大丈夫だったら、朝焼け茸饅頭つくるべえ」
「ひえ」田子作は肩をすくめて饅頭作りにいってしまった。
六六ばあちゃんは夕飯に朝焼け茸を炒めて食べた。
「どうでえ、ちょっと食ってみろ」
田子作と実野に勧めた。
二人とも笑いながら箸をのばした。
「おお、うめえな、こりゃほんとに、饅頭作ったらいいかもしれんな」
「ほんとだなあ、甘いし、この香りはいいなあ、杏と桃と苺を混ぜた匂いじゃな」
「ああ、甘い饅頭にするとええな」
「それじゃ秋になれば、もっと増えるじゃろうから、朝焼け茸饅頭作るべ」
「明日朝になって腹こわさなかったらな」
二人とも味は気に入ったようだ。
次の日、いつものように饅頭作るために暗いうちに起た。
「腹はなんともないな、毒茸じゃなさそうだな」
田吾作は頭に手ぬぐいを巻いた。
「そうだろうや」
朝日が山間に顔をちょこっと出した頃、六六ばあちゃんは朝焼け茸を採りに庭にでた。まだ薄暗い
そのとたん、赤い煙が庭から吹き出した。
「あれ、庭がかじだあ」
ばあちゃんが大声をあげたものだから、田吾作と実野が庭に出て来た。
「どうしたばあさま」
二人が庭に出て驚いた。赤い煙に巻かれたのだ。
「こりゃ何だ、ばあちゃん大丈夫か」
田子作が怒鳴ると、六六ばあちゃんの声が聞こえた。
「大丈夫じゃ、朝焼け茸の胞子のようだ」
周りが赤くきらきらしている。
「朝焼け茸から赤い胞子が吹き出ているじゃ」
赤い煙の中で、ばあちゃんがかがんで赤い茸を見ている影がぼんやり見える。
「すごいのう、すごい胞子じゃ、こんなにたくさん胞子を出す茸をみたことがねえ」
田子作がそういったとき、煙のように舞っていた茸がいきなり土に吸い込まれるように消えていく。
ばあちゃんが叫ぶ。
「土が胞子を吸っとる」
ばあちゃんがはっきりと見えてきた。
「もうはじめよか」
そういいながら、ばあちゃんはたくさんある植木鉢から大きく育っている赤い茸を採った。
「田子作、実野、朝焼け茸で饅頭作るべ」
こうして、朝焼け茸をつぶして、田子作饅頭の秘伝のつなぎをいれて、新しい饅頭を作った。とうぜん朝焼け茸饅頭である。
田子作はいつもの、茸饅頭と、栗茸があったので栗茸饅頭を作った。
その日も朝早くから店先に客がいた。
ばあちゃんが七時にカーテンを開け、ガラス戸の鍵を回して戸を開けた。
「おはようさんで」
ばあちゃんが声をかけると、客が入ってきた。
「今日は新しい饅頭あるでよ、ほれ、朝焼け茸まんじゅう」
見本においてある薄桃色の皮の饅頭を指さした。
「朝焼け茸ってどういう茸ですか」
山登りの格好をしたおばあちゃんが聞くと、ばあちゃんが植木鉢を店先にもってきた。
「ほれ、この茸だよ、きれいな茸なんじゃ、甘い饅頭じゃから、山登りの糖分補給にいいよ、美味いよ」
「きれいな茸だこと、おいしい茸なの」
「そりゃもう、茸の中の果物茸と言われているほど、ジューシーで、美味いよ」
ばあちゃんはテレビのコマーシャルに出ると一躍有名になるに違いない。
客は昼食のために栗茸饅頭を買って、デザートに朝焼け茸饅頭を買った。
フィンランドからきたという青年は朝焼け茸饅頭を指差すと、二本指をあげた。
「へーい、朝焼け饅頭二つ」
実野が包んで渡すと、青年がその場で朝焼け茸饅頭にかぶりついた。
「ウマイ」
上手な日本語で言った。
「ナンテキノコ」
ばあちゃんが、しわくちゃな顔で、背の高い外人さんを見上げて、
「モーニング、トースト、マッシュルーム」と言った。なんてこった。
田子作と実野はあれという顔をしたが、客に饅頭を渡すのが忙しかったので、放っておいた。
「オ、チョウショクキノコ、ブレックファースト、マッシュルーム ネ」
外人さんはそう正しくいい直したつもりだった。
それを聞いていた、シンガポールから来た二人連れが
「ブレックファース、マッシュルーム ツウ」と二本指を出した。
ばあちゃんはにこにこして、朝焼け茸饅頭を渡した。
それで、外国の人には朝食茸になってしまったわけである。
それにしても、やっぱり今日限定の朝焼け饅頭は八時までに売切れてしまった。
「よう、売れたな、ばあちゃんのおかげだよ、朝焼け茸は、今年はもう終りだな」
田吾作が残念そうに言った。ばあちゃんは、
「んだ、あとで、裏山の洞穴いってみるべ、生えているかもしれん」と椅子に腰掛けて茶を飲んだ。
「水神様のところだったら、私も行くわ、お礼を言わなきゃね」
実野は信心深い。
「昼は暇だから、オラ一人で丈夫だ、行ってこ」
田吾作が頭の手ぬぐいを外して汗を拭いた。昼になると客はちらほらだ。その間に材料があると田吾作がもう少し饅頭を作りたす。夕方になると、酒のつまみにと近くの男と子供が買いに来るからだ。
ばあちゃんと実野が水神様の穴のところに来て驚いた。辺り一面、赤い茸が生えていた。どれも子供がついている。
「ありがたいことで」
実野が穴に向かって手を合わせた。
「あしたも、朝焼け饅頭がつくれるぞ」
六六ばあちゃんと実野は、子供の朝焼け茸を残して、せっせと赤い茸を採った。
一つの篭は朝焼け茸で一杯になった。他にもいろいろな茸がとれた。持って帰ると、田子作がそれを見て、
「明日も忙しくなるな」と嬉しそうに笑った。
次の日も店の前にたくさんの客がならんでいた。
店の中からカーテンを開けたばあちゃんが驚いている。
「外人さんがおおけいるなあ」
実野もびっくりしている。
ばあちゃんが鍵を開けた。
最初に入ってきたのは外人さんだった。
「ブレックファストマッシュルーム クダサイ、フタツ」
「モーニング トーストね、はいよ」
ばあちゃんが言うと、お客さんたちは大笑いして喜んだ。
実野から朝焼け饅頭を受け取った外人さんは連れの彼女に一つ渡すと、すぐにかぶりついた。
「オオ、ベリイ、デリシャス」
ばあちゃんがそばによって行くと「そうか、うめえか」と言った。
ばあちゃんはとても勘がいい。
「どっからきたの」
日本語でばあちゃんが聞くと、外人さんは「ロサンジェルス」と答えている。会話が成り立っている。
そうやって、やっぱり八時前には朝焼け饅頭がなくなった。
後はいつもの茸饅頭である。
その日もたくさん売れた。
「次の朝焼け茸はいつ採れるかのう」
庭から店先にもってきた植木鉢に、元気に生えている朝焼け茸の子供を見ながら言った。もうそろそろ、店を閉める時間だ。
「ばあちゃん、二日も売ることができたのは水神様のおかじゃげだよ」
実野も赤い茸の子どもを見て言った。水神様の所の茸の子供もすぐ大きくなる。
「明日は、いつもの茸饅頭売るべえよ」
「そうだな、だが、この朝焼け茸の子供を見ろや、生えてきてまだ三日目なのにかなり大きくなっているのう、これだとあと一週間もするとまた胞子をまくんでねえか」
「ほんとだな」
田子作も見た。
「んだ、そろそろカーテン閉めるよ」
店先の戸に鍵をかけ、カーテンを閉めたばあちゃんはそういいながら庭にでた。
「あれえ」
ばあちゃんの変な声を聞いて、田子作と実野が庭にでた。
庭一面が赤い点で覆われている。
「こりゃあ、朝焼け茸の子供だんべ」
よく見ると、赤く透明な丸い実のようなものが庭の田吾作の大事にしているしだの下や苔の上に生えている」
「だがよ、胞子をまいたのは一昨日だべ、そんなに早くでねえだろ」
「そうだね、あたしは来年になると思ったよ」
実野もうなずいた。
「だけんど、これは朝や焼け茸じゃよ、他の茸と違うんじゃ」
ばあちゃんはかがんむと、生えてきたばかりの待ち針の頭ほどの赤いつぶつぶをみた。
その時店で客が呼ぶ声がきこえた。
「あれ、だれかきちょる」
そういいながら、ばあちゃんは庭から店先にまわった。
店には老夫婦が立っていた。婦人がばあちゃんに尋ねた。
「もう、おわりですか」
「ああ、そうだけんど、饅頭かね」
「ええ、宿で話を聞いて来たんですけど、間に合いませんでした」
「田吾作、饅頭もうねえかー」
田吾作が店の中からカーテンを開けて、
「普通の茸饅頭なら二つあるよ」と答えた。
「包んでやれや」
「ああ」
田吾作が店の戸を開けた。
老夫婦の顔が明るくなった。
「福島からきましてね、茸のお饅頭がおいしい店があるって宿屋の女将さんが言うものだから」
「おや、遠くからわざわざ」
「ええ、明日帰るんだけど、是非ここの茸饅頭を食べてご覧なさいと言われてね、こちらは茸が食べられていいですね」
「福島だって茸は生えるべえ」
ばあちゃんが尋ねると、老婦人は首を横に振った。
「生えますけど、今、私のうちの周りの茸は放射能で食べてはいけないんです」
茸は土や空気から放射能を吸って溜やすいと聞いたことがある。
「こちらへ来て、茸をたんと食べました、福島の家の周りの茸はいつ食べられるようになるか、わからんです、私たちがいなくなってからでしょうな」
旦那もうなずいている。
「大変ですなあ、茸が食べられないのはつらいのう」
ばあちゃんが同情した。
「ここには朝焼け茸饅頭というのがおいしいと聞いてきたのですが、何でも朝すぐに売れてしまうとか、明日の朝はできますか」
「もうしわけないね、朝焼け茸がもうのうなってね、しばらく作れんです」
「朝焼け茸というのは、どんな茸ですか」
ばあちゃんは庭に出しておいた鉢植えの朝焼け茸を持ってきて見せた。
「あれ、きれいな茸ですね、うちの周りにもこんな茸が生えるといいけど」
老人夫婦はよほどの茸好きのようだ。
「これやるべ」
六六ばあちゃんは、朝焼け茸の植わった鉢を差し出した。
「そんな、大事な物をいただけません」
「大丈夫じゃ、まだ茸の生えた鉢はあるし、庭に胞子がまってのう、ちいちゃい茸が顔を出してるから、またすぐ大きくなる。
こっちきてみてや」
ばあちゃんは庭に二人の夫婦を案内した。
「きれいな庭ですね、色々な羊歯が植わっている」
「息子の田吾作の趣味じゃ、ほれ、赤い茸の子供が出とるじゃろ」
老夫婦は
「かわいいですね、羨ましい、いつかうちのところもこういう風に茸が生えるといいんだけど」
「大丈夫さね、茸はつよい、この朝焼け茸を持ってけば他の茸も元気になるじゃ」
ばあちゃんの言ういい加減な話しは信じたくなる。
「饅頭も、最後だし、金はいらんよ、堅くなってるかもしれんからな、宿でちょいと火にあぶってもらいんさいよ」
田子作も饅頭を差し出した。
「はちはほれ、この袋をつかってください」
実野が袋をわたした。
「毎日、庭において、水をかけてやればふえますじゃ」
「なにからなにまでいいんでしょうか、ありがとうございました」
老夫婦は饅頭と朝焼け茸を持って帰っていった。
「さあ、店を閉めたらわしらも飯にしよう」
ばあちゃんたちは戸締まりをすると部屋に入っていった。
「福島の茸はたいへんじゃな」
「ばあちゃん、朝焼け茸をやったから、きっと水神様が福島の茸を救うじゃろ」
実野は信心深くていい嫁だ。
それから一週間後、鉢植えの朝焼け茸が大きくなり、子供もできて、赤い煙をだした。また朝焼け茸饅頭を作ることができた。庭に生えてきた朝焼け茸はまだ小さい、この茸は一年経って大人になると、子供の茸ができて、胞子を飛ばす。ばあちゃんはそう思った。来年は庭の朝焼け茸で饅頭が作れるに違いない。ばあちゃんは、朝焼け茸を鉢植えにして、ほしい人に分けてあげている。
ばあちゃんに一通の手紙が来た。差出人は知らない人だった。
それは朝焼け茸の鉢植えをもたした福島の老夫婦からであった。あれから福島の家に帰ったら、鉢植えの朝焼け茸に子供ができて、赤い煙がでたとあった、その後数日したら、庭に小さな赤い茸が顔をだしたという喜びの手紙だった。
生活には問題ないが、空気中の放射能は原発が壊れる前より高い、と書いてあった。福島の茸が食べられるようになったら、茸饅頭を作ってみたいとあった。
「福島の人に茸饅頭の作り方をおしえてやりてえ」
ばあちゃんが田吾作に言った。
「そうだな、実野、作り方書いてくんねえか」
田吾作は字が下手だ。
「いいよ、書いたらばあちゃんにわたしとく」
田子作がうなずいた。
ばあちゃんは、作り方を書いた紙をいれて、返信した。
それから一月経ったとき、また、老夫婦から手紙が来た。もう寒くなってきた。
それにはこう書いてあった。
「茸饅頭の作り方までおしえていただいてしまい、ありがとうございまあした。まずは自宅で食べる饅頭を買ってきた椎茸やエレンギーで作ってみました。田吾作さんのようにはいきませんでしたが、それなりにおいしくできました。
いただいた鉢植えの朝焼け茸は子供も出来て大きく育ちました。不思議なことに、庭一面に顔を出した朝焼け茸の子供があっというまに大きくなり、その子供ができて、赤い胞子をまきました」
それを読んだばあちゃんが、田吾作に
「福島じゃ、朝焼け茸がはやく育ちよるようじゃよ」
「そうか、そりゃよかったな」
ばあちゃんは続きを読んだ。
「朝焼け茸を検査所に持って行って調べてもらったところ、放射能は全く検知されませんでした。これもおかしなことでしたが、たまたま庭に生えていた雑茸も持って行ったところ、その茸も放射能がありませんでした。不思議に思った検査官が、我が家に来て、庭の土を調べたところ、全く放射能は検出されず、原発事故の前よりきれいになっていることがわかりました。隣の家の庭の放射能の量はまだ高い状態です。
理由はわかりませんが、朝焼け茸のお陰ではないかと私どもは思っております」
「さすが朝焼け茸じゃ」
「やっぱり、水神さまじゃろう」
「うん、ほんとにな、朝焼け茸が生えてからいいことばかりおきるなあ」
次の日も饅頭はたくさん売れた。
朝焼け茸はまだ大きくなっている。ときどき朝焼け饅頭を作ることが出来た。
また福島の老夫婦から手紙がきた。
それには、庭に生えた朝焼け茸がどんどん増え、自分の家だけではなく、その地区全域に広がっていると書かれていた。朝焼け茸の生えた場所の他の茸には全く放射能がなくなり、食べてもいいと許可が降りたということだった。土の中の放射能もなくなっているということでその地域の人たちはとても喜んでいるという。
ばあちゃんがそれを読んで、もしやもすると、朝焼け茸が放射能を吸い込んで、放射能をいいものに換えるんけ、と思った。でも口にださなかった。
朝焼け茸はばあちゃんの家の庭と、水神様の穴のまわりにはたんと生えた。それ以上広がらなかったが、福島に持って行った茸はどんどん広がっていくようである。
とうとう福島では朝焼け茸に専門家が気づいた。その広がりようがすごかったからだ。朝焼け茸は壊れた原発の敷地まではびこったのである。
茸の専門家は朝焼け茸の研究をしたようである。テレビでも解説していた。その茸の生えたところの放射能が消えるのである。専門家は赤い茸の一つが原発事故の放射能のために突然変異を起こしたと考えた。
それで海外に「ラジオアクティビティ アブソープション マッシュルーム」と紹介した。
放射能を吸収しても赤い茸そのものに放射能はなかった。放射能を出していた物質が茸にはいると安定して放射能を出さなくなるのである。その仕組みを解明しようと専門家のチームがつくられた。
おかしなことにフィンランドでは「朝食茸」と呼ばれた。何でも日本でその茸を見たことのある人が「ブレックファスト マッシュルーム」と聞いたと言ったためだということだ。放射能なんて朝飯前ということだろうと解説してあったということである。フィンランドは原発依存国である。
話を日本に戻すと、原子力発電会社はこれでほっとした。原発事故で汚れた空気や土がこの茸で浄化されると考えられたからである。
事故で壊れた原発の中にも茸は進入して、中の放射能をすべて吸い取ってしまった。それは周りの住民にとっても、原発で働いている人も助かった。
これで原発が増やせると、原発会社は喜んだのだが、大違いだった。原発がちょっと故障して、少しでも放射能が漏れると、朝焼け茸は原発の中に入り込み、中心部分で多量に増え、大きく育ったため、その原発は使えなくなった。
こうして放射能が大好きな朝焼け茸は、世界中に広まり、原発ばかりではなく、放射能を発する原爆水爆を破壊していったのである。
そのころ、六六ばあちゃんは白寿を迎えて、曾孫に囲まれ、まだ朝焼け饅頭を作っていた。
田子作饅頭屋は相変わらず繁盛している。
一人の客がばあちゃんに言った。
「朝焼け茸は、あの原発を壊している茸によく似ているなあ」
「新聞に載っている放射能を食っちゃう茸かい、朝焼け茸の親戚だべ」
「ああ、たいそう役に立つ茸だよ」
「うちの朝焼け茸も美味いし、きれいでかわいいし、いいよ」
「そうだよな、茸は旨くなきゃ」
その客は朝焼け饅頭を5個と舞茸饅頭を5個買っていった。朝焼け饅頭は孫たちに、舞茸饅頭は大人たちがいっぱいやるためだそうだ。
「茸はそうじゃなきゃだめだね」
ばあちゃんは、庭にいくと、一面に顔を出し始めた朝焼け茸の子供に、
「早く大きくなっておくれ、茸饅頭になっておくれ」
そういって、水をかけた。
茸饅頭


