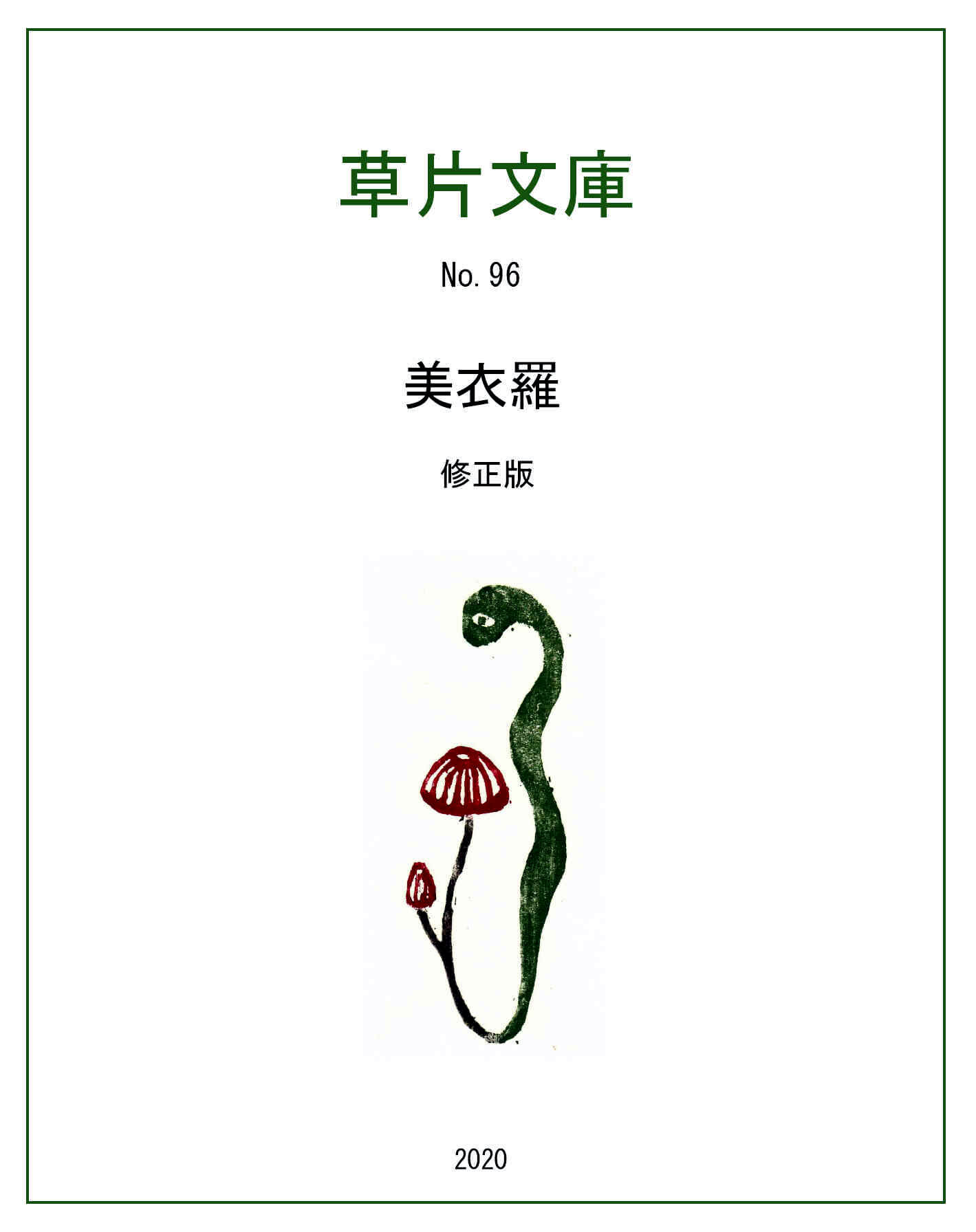
美衣羅(みいら)
第二探偵小説です。これから一月ほど掲載を休みます。
美衣羅(みいら)目次
美衣羅プロローグ
テディじいさんのテディベア
三つ子の遺体紛失事件
庚申塚探偵事務所への依頼
テディじいさんの依頼
テディじいさんの赤い屋根の館
テディじいさんの北海道
三つ子遺体紛失の犯人
テディじいさんに北海道で会う
テディじいさんのおいたち
北海道での最後の仕事
西巣鴨の探偵事務所
テディじいさんの秘密
テディじいさんとの再会
エピローグ
おわりに
美衣羅 主要登場人物
詐貸美漬(さがしみつけ) :探偵 探偵事務所所長
逢手野霧(あいてのむ) :探偵助手
吉都可也(きっとかなり) :探偵助手
薩摩冬児(さつまとうじ) :刑事部長 詐貸の大学時代のサークル仲間
小栗宙太朗(おぐりちゅうたろう):テディじいさん
小栗小夜(おぐりさよ) :テディじいさんの妻
三村美衣(みむらみい) :テディじいさんの秘書
飯田保 (いいだたもつ) :被害者
飯田佳代(いいだかよ) :被害者、飯田の妻、三つ子の母
細野美代(ほそのみよ) :飯田佳代の母
細野政夫(ほそのまさお) :飯田佳代の父
水野天昇(みずのてんしょう) :飯田佳代の祖父
小倉敬紀(おぐらけいき) :スナックバー、ショートケーキオーナー
美衣羅 プロローグ
ぺちゃんこになった蛙の死骸が道路にへばりついている。かわいそうに、夜中に雨が降っていたので道に飛び出して車にひかれたのであろう。明くる日同じところを通ると干からびてミイラになっている。そういえば死体と死骸はどう違うのだろう。広辞苑には死骸は人や動物の死後の肉体。死体、なきがらとある。日本語大事典ではさらに、しかばね、かばね、しにからだ、しにがらなども加わる。要するに死骸も死体も同じようだ。しかし死骸の方がなんだかほっぽらかしにされている、じゃけんにあつかわれているように感じるのは僕だけだろうか。
さらにおもしろいことに、電子版広辞苑には「死骸塩詰め」をみよとの矢印があり、そこを開くと、江戸時代の重大犯人で判決前に死亡したものは塩詰めにして、判決確定後張り付けにしたとある。塩というのは保存のためにどのような物にもつかわれる。死体の保存の方法には生体の形をとどめるような薬品、要するに腐らないようにするホルマリンやアルコールに漬けるというやり方もある。形が変わっていいなら、乾燥標本という手がある。それはミイラということになる。自然ではからだの油が凝固して死蝋になる場合もある。
ミイラは木乃伊と書くのが本当らしい。木乃伊は中国語(漢語)だそうで、中国では蜜人とも書くという。木乃伊は書きにくくカタカナで書くようになったようだ。日本のミイラという音はポルトガル語のmirraからきているという。これは植物からとれる木乃伊作りに使用される樹脂のミルラからきたようだ。
これまた広辞苑のやっかいになると、天然ミイラと人工ミイラがあり、天然は死体が自然に乾固したもので、人工は宗教信仰から死体を加工して腐敗を防止したものとある。人工ミイラは古代エジプトやインカで行なわれていたが、死者の魂が戻る場所として遺体を処理して保存したという。一方日本にそのようなミイラはない。神教仏教では魂はあの世に行き、いつか新しい人間になるので死体は土に返す。
もし自分からミイラになったら、それは天然か人工か。日本には即身仏がある。自ら断食して干からびた行者である。これは手を加えていないから人工ではない。自然に干からびる。ところが信仰、信念によるものである。純粋な天然ともいえない。
まあ、そのようなことはどうでもよいのであるが、この二作目の探偵小説も殺人犯を捜すのではなく、紛失した三つ子の新生児の遺体を探偵が探し出し、そこから周囲の人々の思いが次第に解き明かされていく探偵物語である。
テディじいさんのテディベアー
テディじいさんがやってきた。
サイドカー付きの白いオートバイ、675ccトライアンフにのっている。
サイドカーに収まっているのは熊のぬいぐるみ、明るい金茶色のテディベアーである。ちょっとよれているところが生きていて話しかけてきそうな雰囲気だ。
テディベアーの名前はマミーだ。
テディベアーは熊の縫いぐるみのことで、ドイツのシュタイフ社、アメリカのアイデアル社、イギリスのメリーソート社、などいろいろな会社で作られている。商標登録ではないそうだ。アメリカ大統領ルーズベルトの熊の逸話があり、彼のニックネーム、テディから名付けられたという。名前をつけたのはアメリカということになる。
じいさんはいつも町で一番上等なホテルのスイートルームに泊まる。お金持ちのようだ。茶色のジーンズを履き、胸に小さなテディベアーの刺繍の入った半そでのTシャツ。色は様々だ。それに寒い時には上っ張りを羽織るが、やはり胸にテディベアーの刺繍がある。
ホテルのフロントでは自分の名前を正確に書くのだが、誰も頭に残っていない。ただのテディじいさんだ。
テディじいさんの家は葉山の一画にある。プライベートビーチを持っている大きな赤い屋根の屋敷だ。昔からそこに住んでいるわけではない。じいさんはイギリスに長く住んでいて、69歳の時に日本に戻ってきた。それまで何をしてきたのか知っている人は日本では少ない。どうして日本に帰ってきたかというと、イギリスのエディンバラにいた25歳の日本人の女性と結婚することになったからだ。相等苦労した女性のようだが、なれそめなどは一般には知られていない。その女性が日本で結婚式がしたいと言ったからだ。帰ってきた時、葉山のその大きな家が売りに出されていたので買っちまったのだ。家の購入の際にはちょっとした出来事があったのだが、それもうまく進んで、じいさんの手に入った。それでそのまま日本に住むことにしちまった。
新婚生活二年目に子供ができた。その奥さんがテディベアーが大好きだったのでじいさんは特大の縫いぐるみを特注して奥さんにプレゼントした。奥さんは縫いぐるみにマミーと名前をつけ、ベッド脇に置いて、二人して子供が産まれるのを楽しみにしていたということだ。
すべて順調だったのに突然その悲劇がおきてしまった。最高の医療機関で万全を期して子供が産まれるのを待っていたのだが、分娩中に奥さんの脳の動脈瘤が破裂し、子供を助けるべく手を尽くしたのだが子供もおぎゃあと泣くことができなかった。誰も責めることのできない出来事にじいさんはじっと一年間我慢した。
72歳になったときである。いきなりサイドカーにテディベアーの縫いぐるみをのせて、色々なところにオートバイででかけ始めた。イギリスで使っていたオートバイをもってきていたのだ。当然大型バイクの免許はイギリスでとっている。
行く先々でじいさんはバイクを止めて、子供たちに小さなテディベアーの縫いぐるみを配った。それで顔が知られるようになり、テディじいさんと呼ばれるようになった。
最初じいさんのオートバイが現われたのは熱海である。じいさんは熱海のもっとも高いホテルにテディベアーを抱えて入った。部屋はスイートで一泊二十万もする。部屋には大きなダブルベッドがあり、じいさんは大きな熊の縫いぐるみをベッドに寝かした。夜はルームサービスを頼み、一人でワインを飲みステーキを楽しんだ。
次の朝もルームサービスで朝食をとり、サイドカーにテディベアーを乗せて、熱海の町にくりだした。
熱海の海岸沿いにオートバイを止めると子供が寄ってきた。テディベアーに触りたいのだ。じいさんは大きなテディベアーをサイドカーから引き出すと、舗装された道においた。子供は早速さわりだした。ほかの子供もよってきて飛び出たお腹をさすったりした。じいさんはにこにこしながら縫いぐるみの背中のチャックをおろすと、中から手の平に乗るほどの小さなテディベアーを取り出して子供達に配った。
子供達は大騒ぎをして手を出した。みんな大喜びだ。親たちは何かの宣伝かと子供がもらった縫いぐるみをみた。外国語が書かれていたが宣伝らしきものではなかった。少しばかり外国語を知る親が「ドイツ製じゃないか」といった。それを聞いた周りの親も子供がもらったテディベアーを取り上げてみた。確かにドイツ製である。
「高価なものをなぜくださるんです」と一人の親がじいさんに尋ねた。じいさんは笑顔で「死んだ家内が好きだったので、生きていればこのようによそのお子さんにもあげていたと思います、偶然に出会うことのできたお子さんに幸運のお裾分けです」と言った。
親たちは狐に包まれたような気分が残ったが、子供達の喜ぶ顔に、じいさんにたくさんの礼をいった。
二日目、また同じところにオートバイを止めた。ホテルから一台の乗用車が後をついてきたのにじいさんは気が付かなかった。
じいさんが車から降りると、昨日と同様にテディベアーに子供がよってきた。また背中のチャックをおろすと小さな熊を取り出して子供に渡した。子供と親が集まってきた。そこを見計らうように、後をついてきた車から女性と男性が降りてきた。女性はマイクをもち、男性はテレビカメラをかついでいる。どこかの放送局だ。親と子供がその女性を見た。親も子供もわーっと声を上げた。地元の放送局だ。女性は顔の売れたリポーターのようだ。立ち止まり、カメラの方に向かって「今日も現れた、謎のおじいさんに直撃インタビューをしてみましょう」そう言うとテディじいさんのところに行った。じいさんの周りを囲んでいた人達がさーっと動き、レポーターのために道を開けた。
「こんにちわ」
テディじいさんがレポーターを見た。だが手は小さな熊の縫いぐるみを子供達に渡している。
「あ、こんにちは」
じいさんは手を休めず、女性に向かって挨拶をした。
「何してるんですか」
「テディベアーを子供達にやっとるんじゃ」
「どうして配っているのですか、それドイツ製で高いものでしょう」
レポーターは昨日もらった人から話を聞いたようだ。
「子供の喜ぶのがみたいんじゃ、家内も見ておる」
「奥様はどこに」
レポーターの質問に、指を上に指した。
レポーターはまじめに天をみた。青い空にほんの少しの雲が流れている。じいさんの言ったことに気が付くのにちょっぴり時間がかかった。
「奥さんは天にいらっしゃるのですね」
じいさんはうなずいた。わざわざ聞かなくてもいいものをとテレビを見ていた人の何人かは顔をしかめた。
「テディベアーも子供も大好きじゃった」
レポーターは次の質問が出てこなかった。それでマイクを熊をもらって喜んでいる女の子に向けた。
「うれしいの」
女の子はにこにこしてうなずいた。当たり前だろうと思った視聴者が何人もいた。
そのご地方局ではじいさんの様子をドラマ仕立てで放映した。それはかなりの反響があった。テディじいさんに同情の目が向けられたのである。さらに本局、すなわち東京でも取り上げられ流されたのである。
レポーターの質問に答えたじいさんは、小さなテディベアーを配り終え、ホテルに戻った。
その後、じいさんがテディベアーとともに部屋から出てきたのは薄暗くなった夕時である。
「行ってらっしゃいませ」とテレビでじいさんが子供に縫いぐるみをあげているニュースを見ていたフロントのホテルマンは後ろ姿を見送った。
じいさんは駐車場に止めているサイドカーに大きなテディベアーを乗せるとオートバイにまたがった。
もうテレビ局はいない。じいさんは海沿いの道を走らせると、トンネルをくぐった。広まったところに止めるとオートバイから降りた。
手すりがあるがその下は崖になっていて、下をのぞくと白い波が岩にあたって砕けている。少し行くと錦ヶ浦だ。自殺の名所である。
じいさんはそちらには行かず海を見下ろしている。
薄青色のブラウスと鼠色のスカートという地味な格好をした女性がじいさんに近づいた。
じいさんが振り返り言った。
「これであきらめてくれるんだね」
じいさんは分厚い封筒を女性に見せた。
女性はうなずいて、もっていたものをじいさんに渡した。じいさんはその小さな包みを受け取ると封筒を渡した。
「約束だよ、しっかりとやんなよ」
女はまたうなずいた。
熱海駅に行くバスがきた。女はそのバスに乗った。
じいさんはバスを見送ると、受け取ったものを大事そうに大きなテディベアーのチャックを開けて中に入れた。ゴーグルをかけヘルメットをかぶるとエンジンをかけた。
海沿いに国道を走り、十一時過ぎに葉山の自宅に戻った。じいさんのオートバイが屋敷の前につくと自動的に門が開いた。じいさんは玄関前でオートバイを止めた。何人もの使用人が玄関先で待っていた。
じいさんは大きなテディベアーを抱えると、使用人に「後は自分がやる」と言って、二階の自分の部屋に行った。
寝室にはツインベッドがおいてある。亡くなった奥さんが使っていたベッドに熱海に一緒に行ったテディベアーを寝かすと、背中のチャックをおろした、錦ヶ浦で女に渡された包みを取り出すと、隣にある奥さんの部屋のドアの鍵を開けた。奥さんの部屋はいつも鍵がかかっていて誰も入ることができない。奥さんが死んでから、じいさんが掃除からすべてやっていた。たくさんいる使用人も奥さんが死んでからその中を見たものはいない。ベランダに面しているがカーテンが閉められた状態になっている。
じいさんは奥さんの部屋から出てくると風呂に入りベッドに横になった。
それから一月に一、二回このような旅にでるようになった。いく先々で、テディベアーを配るので、たまにニュースになり、全国的に名前も知られるようになった。
三つ子の遺体紛失事件
5月の連休も終わったある日、十時に目が覚めたじいさんは、シャワーを浴びると、一階のダイニングルームに行った。テーブルの上にはベーコンエッグ、ヨーグルト、焼きたてのバケット、ハムサラダ、それに今日はリンゴが用意されていた。
「おはよう」
女性がアッサムティーをもってはいってきた。
「うん、昨日は遅く帰って悪かたったね」
「いえ、体だけは気をつけてね」
「うん、どうだった」
「睡眠時間は7時間、起きたとき血圧は上は131、下は68、脈拍は最初75、睡眠中の脳波の変化は正常でした、心電図も大丈夫です、ただ首の筋肉が緊張気味です、ちょっと休んだほうがいいわ」
じいさんのベッドには自動的に体の状態を記録する仕組みがあるようだ。しかも目覚める時間も予測できるようで、食事が用意される。
「ああ、ありがとう、今度出かける前に、医者で検査受けとくよ」
「予約を入れておきますか」
「明日たのむよ」
「はい」
女性はキッチンをでていった。
じいさんは食事を終えると執務室に入った。そこには紅茶を運んできた女性が自分の机の上のPCを見ていた。
じいさんは自分の大きな書斎机の前に座ると、机の上の黒いボタンを押した。机の上の三つのデイスプレイすべての画面が明るくなった。
「社長、明日の病院の予約が取れました、いつものように十時です」
「うん、アフリカのアビイ君に投資すると連絡頼むよ」
「いくらです」
「一千万ポンド、それと、ペルーの天沢君に5億頼む」
「アメリカはどうします」
「アメリカへの投資はしばらく中止、大統領が変わるまで」
「はい」
「後はイギリスのピーターに任すと言っておく」
じいさんは右側のデイスプレイに「任せる」と英語で打ち込んだ。
「後は頼むよ美衣」
秘書はハイと返事をした。女性は名前を三村美衣という。
じいさんは2階の自分の寝室に戻った。寝室のデスクの上にもパソコンがある。
じいさんは電源をいれ、インターネットを開いた。
何通もきている中から、赤いマークのものを開いた。コンピューターが内容を判断して赤いマークをつける。AIの組み込まれた特注のPCである。
『もうすぐ子供を産む17歳の子供あり、指示を請う』というものだった。
じいさんは『父親はどうした』と打った。
程なくメイルがきて、『父親はアメリカに帰り、親にもいえず、産み月になった、河原で悩んでいるところを保護』とあった。
『いつもの病院に連れて行き、相談にのるように、費用は大丈夫』
と連絡した。
もう一つ赤丸のついたメイルがあった。
じいさんがあけた。
『子供を産んだが死産だった中校生あり』
『いつ産んだ』
『昨日、本人は無事、親に黙って産んだ子を自分の部屋に隠している、駅のロッカーに捨てるつもりのようです』
『いつものように頼む、場所はどこだ』
『新潟、糸魚川』
『了解、明日は病院、行くのは明後日だ』
その日朝早く、テディじいさんはオートバイにまたがった。サイドカーにはいつものように大きなテディベアーが乗っている。
いつも行くように、途中から首都高、関越自動車道路にはいり長岡で下りた。その後、日本海側に沿って延びる国道8号を通って夕方には糸魚川についた。翡翠で有名なところである。糸魚川の海岸にはきれいな石が落ちており、ごく運がいいと本物の翡翠を拾うことができることから、翡翠海岸と呼ばれるところがある。
糸魚川の町では一番高いと言われるホテルの入り口にトライアンフを乗り付けた。じいさんがテディベアーをおろし、ボーイが鍵を受け取るとオートバイを駐車場にしまった。
じいさんはフロントで記入を終えると鍵を受け取ってエレベーターに乗った。いつものようにスイートルームである。
ツインベッドの一つにテディベアーを寝かすと、携帯電話をかけた。その日はルームサービスをたのむと、十時頃ベッドに入った。
次の朝じいさんは駅の前の駐車場にオートバイを停めた。駅は大きくないが、隣の建物は観光案内所であり、翡翠の陳列館でもある。
ちょうど通勤、通学時である。大きなテディベアーをサイドカーからおろすと、駅の入り口に持っていった。背中のチャックをおろすと、中からテディベアーの小さな縫いぐるみを取り出した。女子中学生らしき三人が駅にやってきた。
「かわいい熊さんをあげるよ」
じいさんが小さな熊の縫いぐるみを差し出すと、一人の女の子が「何の宣伝」と喜んで受け取った。
「かっわいいー」
その子が叫ぶと、他の二人も手をだした。
「ほい、ほい」
じいさんは女の子の手の上に熊を載せた。
それを見ていた女子高生もよってきた。小さい子の手を引いてお母さんもきた。
駅員さんがよってきた。
じいさんは「こりゃ、通行のじゃまですな、すんません」と移動しようとしたら、駅員さんは「じゃまにならなきゃいいですけど、熱海で熊を配っていた人ですね」と言った。全国ネットでも流れたので知っていたのだ。
「ええそうですじゃ」
「うちの孫にもいいですかね」
じいさんはよろこんで二つも駅員さんに渡した。
「いや、こりゃどうも」そういって駅員さんは戻っていった。駅員さんの帽子に赤い太い線がはいっている。もしかすると駅長さんだ。
しばらく配っていると、学生さんの姿がなくなった。中学高校は授業がはじまる時間だ。じいさんのところによってきているのは噂を聞きつけてやってきたお母さんかおばあさんだ。子供や孫にもらおうという魂胆だ。
それでもじいさんは熊を配っている。
お昼近くになると、腰をあげホテルにもどった。ホテルで昼もルームサービスを頼み、その後昼寝をした。
五時くらいだろうか、携帯に連絡がきた。じいさんは支度をして、テディベアーを抱えると車を玄関に回すようにいった。
じいさんはテディベアーをサイドカーに乗せ、すぐにオートバイを出した。行くところは決まっているようである。
車を止めたのは餃子屋の駐車場だった。このあたりでは名が売れている店のようだ。テディベアーを抱えて店に入ると、まだ早いのにそれなりに席が埋まっている。個室もいくつかあり、一つは家族で埋まっていた。
じいさんは一つの部屋に案内された。髪を脇で結んでいる丸顔の女の子がテーブルについていた。まだあどけない。じいさんが入っていくと顔を上げ心配そうに見上げた。女の子はじいさんの持っている大きなぬいぐるみを見ると笑顔になった。
「お嬢ちゃん待たしちまったね」
じいさんはテディベアーと並んで、女の子の前に腰掛けると
「食べたいものをたのみなよ」と、声をかけた。
女の子はちょっと間をおくと「わかんない」といってまた顔をふせた。
じいさんが呼び鈴を押すと若い女の子が顔をだした。前にいる娘と同じくらいの年だろう。
「この店で一番美味い餃子をまず二人前、それに冷えた炭酸と、生のレモンはあるかい」
「レモンはありません」
「じゃあ買っておいで、近くで売ってるだろう」とじいさんが言うと、係りの女の子は戸惑っている。
「聞いてみないと」
「ああそうだろうね、客がそう言っていたと言っといで」
じいさんにそう言われた係りの子は戻っていった。
すぐに店主がきた。
「すみません、気が利かずに、すぐに用意させます」
「頼みます、係りの女の子を怒っちゃだめだよ、わしが無理に頼んでいるんだから」
「まだ中学生で、わかっていなくて」
「そりゃそうだろう、中学生にバイトさせてもいいわけだ」
「へい、時間を守れば大丈夫で、あの子は兄弟が多くて、小遣いももらえないって言うんで雇ったんで」
「いい心がけだね、あいつに言っとくよ」
「よろしくお願いします、まさかあのような方が家にくるとは思ってもいませんでした、このお嬢さんを直接お連れになりました」
じいさんはうなずいて、「うまい餃子頼むよ」と念を押した。
テーブルにいた女の子はびっくりしたように話を聞いていた。
店主が下がるとじいさんは「もってきたかい」と少女に言った。
少女はコンビニの袋に入ったものをじいさんに渡した。
「どうしてこうなったんだい、出会い系かい」
彼女は首を横に振った。
「スマホなんてもってない、隣の町の公園」
「お金がほしかったんだね、洋服買いたかったからかい」
首を横にふった。
「食べたかった」
「なにをだい、家では食べさしてもらえないのかい」
うなずいた。
「おなか一杯食べたい」
「お母さんどうしてるの」
「お母ちゃんは家にいない、たまに中学校のお金もってくる、家賃は母ちゃんがちゃんと払っている」
「お父さんは」
「会ったことがない」
「それじゃ、食べるものは自分でああやってお金もらって買ってるのかい」
彼女はうなずいた。
「一人で暮らしてるのは寂しいだろ」
「妹と弟がいる」
「みんなの分もあんたが面倒みているのか」
じいさんもびっくりした。
「どうしてこの餃子屋にしたんだい」
「ここの餃子食べたかった、ほんとは弟も妹も」
そこに餃子がきた。この娘の希望でこの店で会うことにしたようだ。
「まず食べようや、飲みものも頼みなさい」
「いい」そう言うと、少女はちょっと間をおいて食べ始めた。水を飲みながらぱくぱく食べた。
「ゆっくり食べなさい」
じいさんは炭酸をコップに注いでレモンをたっぷり搾った。
「これをのむといい、甘いのがよかったら、砂糖を入れて」
少女はレモンソーダに砂糖を入れて飲んだ」
「弟と妹はどうしているの」
「家で待っている」
「そうか、後で餃子持って帰りなさい」
少女は嬉しそうにうなずいた。
「こういうところで働く気はないのかい」
「あるけど、親がいないとどこの店も働かせてくれない」
「公園に行かないと約束するなら、この餃子屋で働いてもいいんだよ」
「うん、働きたい」
「勉強する時間がなくなるかもしれないなあ」
「勉強はいい、中学を卒業できればいい、そうしたら働いて、弟と妹が大きくなったら勉強する」
「よし、そうしよう、みやげの餃子頼んでくるから、わしの残りも食ってくれないかい、年をとると食べなくなるんだ」
じいさんは二つしか食べていない、皿にはまだ十個の餃子が残っている。
少女はうなずいてじいさんの残りも食べ始めた。
じいさんは勝手に調理場に入ると、みやげを3人前頼み、主人を捕まえて、店の外に連れ出した。
「なにか」
「お宅でもう一人中学生を雇えないか」
主人はびっくりして「とても余裕がなくて」と手を広げた。
「ここに五百万ある、あの子が高校を出るまで雇ってもらえないか、後4年だ」
主人はまたびっくりした。
「本人が中学でやめると言ったときには通信制や、高校卒業検定を受けさせてくれないか、また金はだす。ここの待遇は今いる中学生と同じでいい」
「だけど、あの子の親がなんというか」
「大丈夫、ほとんどあの子が兄弟の面倒を見ている、母親は子供をほってきぼりだ、そんな親に説教しても無駄だ、親は親で苦労してるんだろう」
主人は迷っているようだ。
「あの子をつれてきた奴が責任を持つならよかろうや」
「あの県警の偉い方がですか」
「ああ」
じいさんは携帯をかけた、相手と少し話すと、餃子屋の主人と変わった。餃子屋の主人は携帯にぺこぺこしていた。
「あの子は大丈夫だ、まともにできる」
そう言ってじいさんは携帯を受け取ると席に戻った。
少女は最後の餃子を食べ終わるところだった。
「おいしかった」
はじめて少女の頬がゆるんだ。
「明日学校が終わったらここにおいで、主人とよく話して、仕事のことを聞きなさい」
「はい」
少女は明るく返事をした。
「これをあげよう」
小さな熊の縫いぐるみを3つ少女にわたした。
「勘定は済ましてあるよ、わしは先に帰るからね、おみやげの餃子ももらって帰りなさい」
じいさんはテディベアーを抱えると少女から受け取った包みを持って立ち上がった。そこへ主人がみやげの餃子を持って個室に入ってきた。
「ありがとうございました」
じいさんにお辞儀をして、女の子に「明日、学校が終わったらきてね」と声をかけた。
じいさんは駐車場でサイドカーにおいたテディベアーのファスナーをおろすと、少女から受け取ったものをいれ新潟に向かった。
新潟のホテルに一泊すると朝早く帰途につき葉山に戻った。
じいさんが戻ると、自宅の玄関にはいつものように使用人たちがならんで待っていた。じいさんはテディベアーを寝室に持って行くと、奥さんのベッドに寝かせ、中に入れてきた少女から渡されたものを奥さんの部屋にもっていった。
しばらくするとじいさんは階下の執務室に入った。美衣が仕事をしている。
「朝の食事はしたのですか」
「いや、してない」
「何かもってきましょうか」
「うん、ジュースだけでいいよ」
「いつものですね」
「うん」
じいさんはデスクのスイッチを押した。三つのデイスプレイがついた。いつものようにそれぞれの国に指示を与えると、美衣が差し出したレモンソーダを飲んだ。
「特におかしな動きはないようです」
「ああ、今みたよ、アメリカだけだなおかしいのは、あそこは無視だ」
「はい、社長のプライベートPCに緊急メッセージが入っているとありました」
「そうか」
じいさんはレモンソーダを飲み干すと二階にあがった。寝室でPCをあけると、
『仙台死亡三つ子遺体盗難』という見出しが出てきた。
仙台からの連絡だった。さらに別件で、『仙台駅ロッカーのもの確保』とあった。同じ人物からのメイルのようだ。
先の見出しをあけると、次のようなことが書かれていた。
『すでに新聞に掲載されたように、一月前、仙台青葉区の住宅で男が入り、主人ともうすぐ子供が産まれる奥さんを刺した。被害者は飯田保と飯田佳代。結婚して十ヶ月、主人はいったんは助かると思われていたがその日に死亡、奥さんは病院で出血多量のため輸血を受けながら、帝王切開を受けたが、刺され倒れたときに腹部を強打したためか子供は子宮内で死亡していた。三つ子であったが全員助からなかった。母親も直後死亡』
刺された夫と奥さんの写真が添付されていた。
『犯人はすぐ捕まった。犯人は奥さんと同じ職場の男であった。
そこまでは公に報道されていましたが、以下のことが分かったので報告します』とあった。
『犯人の男は亡くなった奥さんの腹の子は自分の子だという妄想を抱いていた。旦那が彼女をさらったと思っており、取り返す為に家に押し入り夫を刺した。夫をかばおうとした彼女にも深手を負わせてしまった。
遺伝子検査で夫婦の子供であることも確かめられたこともあり、明らかに犯人の妄想であることがわかった。そのことは伏せられて発表されている。
調べたところ、次のことがわかりました。
東京の夫の両親が遺体を引き取りにきたとき、警察の安置室から、子供の遺体だけなくなっていた。係官は三人の遺体は一つにまとめて冷蔵保管庫の引き出しに入れてあったと言った。安置室には鍵がかかっているが、警備はそんなに厳重ではない』
そのメイルをよこした人物にじいさんはメイルを出した。
『警察は遺体盗みの犯人の目星をつけたのか』
『はい、犯人の母親を疑っていましたが、まだわかりません』
『どうしてかね』
『母親は息子から自分の子供がもうすぐ生まれると言われており、それを信じているということです、息子が犯行に及んで捕まったときも、子供は息子の子だから引き渡せと言っていたそうです』
『犯人の可能がつよいのかね』
『いえ、警察は母親を任意で事情聴取しました、しかし母親は片足が悪いこともあり、外出は買い物ぐらいで、とても警察の霊安室に忍び込んで盗むなどできないと判断しました』
『じゃあ母親が誰かに頼んだのじゃないか』
『それはなさそうです。わたしも手をつくして探したのですが、手がかりはありません、警察も同じだと思います』
『わしは明後日、ロッカーに捨てられていた赤子のことで仙台に行くよ』
とじいさんは返事を書いた。
その後、階下の執務室に行って、秘書の美衣に明後日仙台に行くことを伝えた。
「旅行ばかりで体は大丈夫ですか」
「うん、元気じゃ、この間の検査でも問題なかっただろう」
「そうですけど、長い間の運転は疲れます、明日ゆっくりでて、どこかで一泊して仙台に入ってください」
「そうするよ」
「ところで社長、イギリスのEU離脱どうします」
「勝手にするさ、全部円に変えちまえ」
「そんなことをすると、市場が大混乱しますよ」
「かまわん」
次の日じいさんが出かける準備をしていると、美衣が
「円が高くなって大変なことになりました」と言ってきた。
「大丈夫だ一時のことよ」
じいさんはトライアンフにまたがった。
一泊していくようにと美衣に言われたが、首都高に入り、東北自動車道にのったじいさんはそのまますっとばして仙台にはいってしまった。5時間ほどでついた。
じいさんは駅の近くの豪華なホテルに宿をとった。もちろん最上階の18階特別室である。いつものようにテディベアーを抱き抱えて部屋にはいるとツインベッドの一つにベアーを寝かせた。
バックからPCを取り出すとメイルをあけた。
『ロッカーのものは渡せますが、安置室から盗まれた赤子の遺体の行方は依然わからない状態です、殺人犯の母親の知り合いをあたってみていますが、全く該当しそうな人物は出てきません』
『母親はいくつだ』
返事はすぐきた。
『59です』
『コンピューターかスマホは使っているのか』
『スマホは使っています、PCは使っていません、スマホの連絡記録を裏から手に入れました、特段関係ありそうな人物は見つかりませんでした、ともかく息子との連絡がメイルも電話も一番多くて、日に必ず一度、多いときで二十何回もあります』
『スマホを他に何に一番使っている』
『天気予報ですね』
『うーむ、わからんな、あしたロッカーの物と三つ子事件の詳細を書いたものをどこかで渡してもらおう、明日連絡する』
ここで連絡を終えた。
じいさんはルームサービスをとった。
次の朝、じいさんはテディベアーをのせて仙台城のある青葉山に行った。本丸跡の有料駐車場に車を止めた。観光客がもうちらほら歩いている。
駐車場に赤い自家用車が止まった。中から小学生くらいの女の子と両親が降りてきた。じいさんの前を通るとき、サイドカーにのっている大きなテディベアーの頭を女の子がなでた。
じいさんはにこにこして「これをあげましょう」と小さなベアーを母親に差し出した。母親はおやという顔をして「いただけますの」ときいた。
「お嬢ちゃん熊が好きそうだったから」
「でもなぜですの」
「テディベアー愛好会の宣伝です、どうぞ」
そういうと、やっと「ありがとうございます」と受け取って、女の子に渡した。父親もそれを見て「本物のドイツ製ですね」と言った。
「ええ、本場のものです」
「この大きなのもそうですか」
「特注品です」
「すごい値段するんでしょうね」
「三百万です」
母親もびっくりしている。
「その子熊も大事にしてね」
じいさんが女の子に声をかけると、うなずいて、「ありがとう」と三人は城跡に向かった。
ああいう教育ママパパのときは子供に直接渡しちゃだめなんだ、と独り言を言った。
じいさんは駐車場から大きなテディベアーを道の脇に運んだ。
観光客が増えてきた。大きなベアーに子供たちが寄ってきた。じいさんはいつものように通る子供に小さなテディベアーを直接渡した。いくつか抱えて持っていると、子供がどんどん集まってきた。
観光客の中に、テレビでじいさんを見たことがある子供がいて、それが伝わると、みんな熊をもらいに集まったのだ。じいさんは喜んで配った。大人も寄ってくる。ふっくらとまるで餡まんのような女性とカマキリのような眼鏡をかけた男のカップルが何事かとのぞき込んだ。もうすぐお昼になろうとするときだ。
「あ、テディベアー、ほしい」
女性が顔を楕円形にして目を細めた。連れの男が「野霧さん、子供に配ってるんだよ」とたしなめている。「あたしだめかなー」と言っているのがじいさんに聞こえると、じいさんは「はい。お嬢さんにも」とテディベアーをその女性に渡した。ちょっとテディベアーの体型に似てるな。
「わー、ありがとう」
女性は飛び上がった。どすんとおちるような気がしたが、じいさんの目にはふわっと柔らかく着地した足が見えた。
その後すぐに熊がなくなった。じいさんは、大きなテディベアーを抱えると駐車場にもどり、サイドカーにのせた。
それを見ていたカマキリ男が「トライアンフだ、かっこいいじいさんだ」と餡まん娘に言っていた。
じいさんはホテルに戻った。
その日はそれから部屋を出ることはなかった。
その夜、十一時頃である、じいさんがテレビの映画を見ていたときだ。部屋のベルが鳴った。じいさんはのぞき穴から廊下を見ると、背広姿の男が立っている。じいさんはあわてて鍵をあけると男を部屋の中に引っ張り込んだ。
「持ってきちまったのか、人に見られなかったか」
「大丈夫です、直接話した方がいいと思いました」
「ホテルに来るのは不用意だぞ、といってもう来ちまった、まあ座れ」
男はソファーに腰掛け話し始めた。
「三つ子遺体紛失に母親が関係していないとすると、犯人には兄弟はいないし、父親はなくなっているので、別の筋から考えなければなりません、それで奥さんの両親と考えたのですが、北海道にいて、そのようなことをできる状況にありません、お手上げです、夫婦の両親の詳細はここに書いてあります、住所写真もあります」
そういって、手提げ紙袋の中から、書類とロッカーにはいっていた包みをじいさんに渡した。
「ロッカーの中のもののことはどうして知ったんだい」
「いつも小遣いをやって情報をもらうやくざの若いやつと飲んだとき、そいつがやけに酔っぱらっていましてね、女に子供ができたのに、八ヶ月で家で転びやがって流産しちまった、俺は楽しみにしていたんだよ、だけど俺がなんかしたと言われるに決まってるから、包んでロッカーに捨てさせた、ということでした、それでも警察はおまえを捜すぞ、俺が処分してやるロッカーの場所を教えろと言ったら、えらく喜びましてね、ロッカーの場所と番号を教えました、鍵はと聞いたら捨てたと言うので、私が開けたんです」
「だいじょうぶなのか」
「はい、事件性のないことですし、あのチンピラはまだ本間もんのやくざでもありません、人は悪いやつじゃないと思います」
「それならいい、これはこのロッカーの分と、三人の赤子の捜索費用だ」
じいさんは札の入った封筒を男に渡した。さらに、別の分厚い封筒をわたし、
「これは、そいつをやくざから足を洗わせる金だ。かならずそうさせるようにな」
「はい、分かりました、まだそれほどの男じゃありませんので、何か仕事も探してやります」
「どうして三人の赤子はみつからんのだろうな、警察は何をしているんだい」
「私も全く同じ状態です」
「必ず探し出さなきゃならん」
「私にはこれ以上無理です、探偵で何でも探し出す男がいます、私にはかなわない男です、この事件を解決できるのはそいつくらいだと思います」
「お前さんよりできるのか、そんなに優秀なのがいるのか」
「そいつはある会社の顧問弁護士も引き受けていて、一般の探偵業務はあまり引き受けていないようです」
「金を出してもだめということだな」
「そうです」
「わかった、あんたは捜索を続けてくれ、その探偵には俺が直接あたってみる」
そこで来客はそうっとホテルを出ていった。
庚申塚探偵事務所への依頼
テディじいさんが仙台に行く少し前の話である。
ここは西巣鴨の小岩通りからちょっと入ったところ、ビルの2階に庚申塚(こうしんづか)探偵事務所がある。探偵事務所を営む詐貸美漬は、頼まれたものは必ず見つけるという探し上手で、昔は一人でやっていた。ある時、北京原人の頭骨探しの依頼がきて二人の助手を雇った。それには裏があり、複雑怪奇な結末に終わったが、なりゆきでそれに関係のある製薬会社の顧問弁護士を引き受けることになり、二人の助手とともに探偵事務所を続けることになった。
ほんの5日前、警察にいる唯一の知り合いから電話があった。詐貸美漬は探偵をやっているにもかかわらず警察に知り合いはほとんどいない。電話をかけてきた男は大学のミステリーサークル仲間で、卒業してから警察にはいったのは知っていたが、二十年近く会っていない。
「庚申塚探偵事務所ですが」
「宮城県警の薩摩冬児(とうじ)ですが、詐貸所長さんをお願いします」
「詐貸ですが、大学の時の薩摩さんですか」
ずい分落ち着いたおじさん声で、声だけではわからない。彼は経済学部の学生で柔道も得意で、大学対抗でもいい成績を残している。詐貸は2年の時、法律試験に合格するという法学部の優秀な学生だったが、とあることで大学を辞め探偵になった。だから薩摩と話した期間は一年とちょっとである。薩摩は日本のミステリーを好み、その点で詐貸と話しがあった。
「はい、久しぶりですね、詐貸さんが探偵になったのは聞いていました、大学の時、法律試験に受かった人がなぜ大学をやめたのか不思議だった」
「いや、若気の至りです」
「だけど、今は大きな会社の顧問弁護士、それに探偵仲間では探し上手な詐貸さんと言われているじゃないですか」
「いや、落とした消しゴムを探すくらいのことしかしていません」
「実は暗礁に乗り上げそうな事件が起きましてね、それが警察の落ち度から起きたことなんです、本庁のベテランにも捜査を手伝ってもらっているのですがどうもわからない、最初が肝心で、早いときからベテランの人に手助けをしてもらった方がいいと、そのベテランの本庁の刑事が言うくらいちょっと複雑な事件です。外部の人に助けてもらうということはまずないのですが、意見を聞くことはしないわけでもない、それで詐貸さんのことを話したら、私に任せるということになってね、それで電話したんです、ただ必要経費にちょっとした謝礼程度しか出せないですけどね」
彼はそう言って、事件の概要を話しはじめた。横溝正史の金田一耕助みたいな者が実在するわけはないと思っていた詐貸は意外な話しにちょっと驚いた。
事件は一見単純である。亭主と妊娠していた妻が刺され、二人だけでなくお腹の中の赤子も助けることができなかった。子供は三つ子で遺体の安置室にしまっておいたのだが、盗まれたということだ。刺した犯人はすぐ捕まったが、三つ子の遺体がみつからないというものである。
会社の顧問弁護士の仕事はあってないようなものだから時間的には余裕があるが、詐貸はそういった本格的な事件の捜査をしたことがなかった。
「大変な事件の捜査などしたことがないんですよ」
「うん、知ってる、だけど仲間内じゃ相等有名じゃないか、もう一つはっきり言うと、大手のやり手といわれる探偵事務所がいくつかあるが、そういった名の売れたところには頼めないんだ、あいつら後で警察に頼られたなんて売り込みに使うから、その点君はそういう人じゃない、一匹狼っていったとこだろう」
薩摩の話し方が学生の時に戻ってきた。彼はなかなかうまいところをついてくる。
「話を聞いて、もしできるようならと言うことでいいかな」
「そうしてもらえると助かる、いつ訪ねていったらいい」
「いや俺の方から行くよ、現地に行った方がいいし、たまには遠出もいいから」
「顧問弁護士の仕事があるんじゃ、時間は大丈夫なのかな」
「いや、月に一度富山の会社の会議に出るだけだよ」
「どうしてその会社の弁護士を引き受けたんだ」
「いろいろあってね、夢(む)久(く)愛子の実家だよ」
「あ、ミステリーサークルで君と一緒によくいた女性だな、ずい分きれいな人だったが、奥さんって言うわけか」
「いや、違うんだけどね、まあ、その話はいいよ、ともかく仙台に行くから事件の話を聞かさせてもらうよ」
探偵事務所には逢手(あいて)野(の)霧(む)という女性と吉(きっ)都(と)可也(かなり)という男性の助手がいる。富山の会社に行く時もその二人の慰労もかねて一緒に行く。
「必要になったら助手を二人呼んでいいかな」
「やり易いようにやってくれ、交通費はでるよ、泊まるとこはどうしようか、警察の宿舎があるけど、そこに出入りするのもまずいかもしれないな」
「安いビジネスに泊まるよ」
詐貸はいつ行くか打ち合わせが終わると電話をおいた。
詐貸は助手の二人に「明日仙台に言ってくる」と言うとPCで東北新幹線の時刻表を開いた。
「事件ですか」
餡まんのような丸顔の野霧が素甘を食べながら聞いた。
「まだわからない、警察の安置室から子供の遺体が盗まれた」
カマキリのような顔をした吉都が、
「警察が調べないんですか」と不思議そうな顔をした。
「大学の同期生が宮城県警の警察官になっていてね、調べているのだがわからなくて、探偵の力をかりたいのだそうだ、世間には内緒でね」
「金田一耕助になるのね、事件らしい事件ははじめてですね。おもしろそう、仙台か、いろいろありますよ、牛タン、ささかま、魚はいいし」
「野霧君は食べることだなあ、向こうでの成り行きによっては二人に合流してもらうよ」
「是非お願いします」
吉都が大きな声をだした。
翌日の夕方、詐貸は仙台で薩摩冬至と牛タンラーメンを食べていた。仙台警察署の遺体安置所を見てきたところだ。
「詐貸さんは変わらないなあ」
薩摩は詐貸を見てそう言った。薩摩は筋肉質で大きな男だったが、マシュマロマンとまではいかないが、柔らかくふっくらとして刑事とは見えない、いいおじさんになっていた。
「現場にでなくなっちまったからな」
彼は二浪していたから詐貸より二つ上のはずだ。それでもまだ40ちょっとだろう。だが名詞には刑事部長、所長補佐と書かれていた。大した出世だ。
「詐貸君はまだ一人のようだね、俺は三人の子持ちだよ」
「奥さんはこっちの人」
「うん。高校の時の同級生」
薩摩は仙台の何代も続く家の長男だそうだ。
「それで、その殺人事件というのはどうなったの」
「犯人も被害者もはっきりしていたが、盗まれた子供の遺体が難しい事件になっちまった。犯人の男は殺した妊婦の子は自分の子だと思いこんでいて、妊婦の夫が自分からその女性を奪ったと思っていた、そのことを母親によく言っていて、母親もそう信じて、遺体を引き渡せと言ってきた。普通なら考えられない行動だよ、それで母親も調べたが全く犯人とはほど遠い、それに遺伝子検査で夫婦の子ということがわかっている」
「犯人が予めそうするように誰かに頼んでいなかったのかい」
「その線も調べたが出てこない」
「とすると動機は別のところにある」
「そうだな」
「警察内部は調べたのだろうな」
「遺体調査に関わった関係者を調べたがでない」
「とすると、それ以外の内部の者」
「すべて調べた訳じゃないが、犯人や被害者と関係のある警察の関係者はでてきていないな」
「遺体の安置室には一般の人もはいるだろ」
「もちろん、遺体の確認や引取りにくる人がはいるよ、だけどその時期は両親以外いなかった。
今回はどちらも刺された後、警察が到着した時は生きていて、病院に運ばれ治療をしたわけだ。夫の方はすぐ亡くなったが、それでも東京の夫の両親の飯田さんが病院にすぐに来て息子に会っている。一方、妻のほうは延命措置をして赤子は生かそうと切開手術をしたのだがどちらもだめだった。妻の両親の細野さんは北海道ということもあり、父親の仕事の関係で遺体が警察の安置所に運ばれてから面会した、どちらも検視は病院で行なわれたのだが、司法解剖も必要になるかもしれないので、警察の安置所に運ばれたんだ」
「それでどうしたの、解剖したの」
「犯人が自分の子だというので遺伝子解析が必要になる、それで組織をとらなければならないのだが、それは病院で済ませていたので、結局解剖そのものはしなかった」
「遺体はどのように保存されていたの」
「冷蔵状態で引き取り手に渡すまでとっておくわけだ、奥さんの遺体は三人の子供の遺体とともに、旦那より二日遅れて病院から運ばれてきて、検視官が改めて病院からの記録を確認した。その日の夕方に奥さんの両親が北海道からやってきた」
「そのとき夫の両親は一緒じゃなかったの」
「うん、もう病院で立ち会っていたからね」
「旦那の遺体も同じ安置室にあったわけだよね」
「うん、大きな冷蔵保管庫の引き出しに一人一人入れられるわけだ。奥さんの両親を係官が案内して、布のかかった娘さんの遺体を引き出し、三つ子の入った隣の引き出しもちょっと引き出した、お母さんは泣きながら「しばらく私たちだけにさせてください」と係官に言ったそうだ。係りの女性警察官は入口ところで見守っていた。母親は娘の体を長い間さすって、泣きながら呟いていたそうだ。女性の警察官は涙がでたといっていた。二十分ほどいて娘と子供の引き出しを自分達の手で押し込んで、涙を拭きながら帰って行ったということだ」
「係官が冷蔵庫にしまったんじゃないんだな」
「そうだな、奥さんの両親を疑っているのか」
「いや、わからない、両親は何か持っていたの」
「いや、母親は小さなハンドバックを持っていたが、父親は何も持っていなかったということだ。三人の赤子を隠すことはできないよ。荷物を別の部屋に置かせてから安置所に案内している」
「それじゃ問題なかったわけだな」
「ないね」
「死んだ夫と妻の遺体はそのあとに夫の家に引き取られたんだな」
「うん、東京で葬式をして、夫の家の墓に入れられるということだ」
「事件そのものは被害者の会社仲間が起したわけだよな」
「会社での二人のことは詳しく調べたよ、奥さんは入社して3年、旦那は東京の本社から移動してきて1年、すぐ結婚して新しいマンションに住んだ、そういうこともあって旦那の方は回りとの付き合いがまだあまりなかったみたいだ、奥さんはチャーミングな人で人気があったようだ、仙台に移ってきてすぐに彼女を射止めた旦那は羨ましがられたようだ」
「妊婦が通っていた病院はどう」
「特別問題はなかったね」
「とすると、原点にかえって、その三人の子はほんとに夫の子供だったのかい」
薩摩は詐貸の言葉にびっくりした。
「だって、遺伝子検査で夫婦の子供であるということだよ」
「誰がみたの」
「検査の結果を画面で説明してもらった」
「もし再検査されたら困る人がいないかな」
「そうなると困る人間が盗んだのか、だとすると検査が間違っていたということになる、犯人の言っていることが正しいかも知れないわけだ」
「いや、犯人の言っていることは本当に妄想で、他の人間で困る者がいるのかもしれない」
薩摩は一息ついた。「調べ直す、そこまでは考えていなかった」
薩摩は話を続けた
「じつは、もう一つ調べてほしい、昨日、仙台駅構内の鍵がかかっていたはずのロッカーの一つが何者かに開けられていた。中に何が入っていたのかわかっていないが、ロッカーに液体の乾いた小さな跡があった。それが胎盤の成分のようだと言うんだ。警察の方では三つ子の遺体紛失との関係は薄いと考えているが、俺は調べた方がいいと思っている、ちょうど詐貸さんにきてもらうんだし、調査をお願いできないかと思ってね」
「もちろん、それはいいですよ」
「ロッカーの部屋の防犯カメラを調べた。入れたのは若い女性だが、まだ誰だか特定できていない、盗んだ男のほうは目星がついた、悪さはしないが裏に通じている男で警察でも名前は知っている、しかし知恵のある男でまだ警察に捕まったことがない」
「尾行すればいいんですね」
「そうだな、直接任意同行にしてもいいのだが、入っていたものがはっきりしていないし、明らかにこの事件と関係があるということがわかったら捕まえる、あいつは店も持っていて逃げたりしないからな、それでまず詐貸さんに尾行調査をお願いしたいのですよ」
「それならお手の物です」
「今日、彼の資料をもって詐貸さんのホテルのロビーに六時頃行きます、その辺で飯を食いながら話しましょう、どこに宿とりました」
「駅前のドーミーインです」
「露天風呂のある奴ですな」
彼は時間通りにホテルにきた。ちょうどロビーには誰もいなかった。
「ここで写真を渡しときます」
彼はソファーに座ると、茶封筒から写真をとりだした。ロッカーを開けた男は四角張った顔の二重の目の大きな男である。
「名前は小倉敬紀、46歳、身長は172、体重は68です、青葉区のマンションに一人暮らし、スナックバー「ショートケーキ」をシノンという女にやらせています、シノンは占い師でもあり店は繁盛しています」
「小倉の女ですね」
「いえ、違います、小倉に表立った女はいません、ちょっと得体の知れない男です、英語は流暢に話します、鍵を自由に開けられるようですが、今まで盗みなどしたことがありません、今度のロッカー破りも訴えがない限り犯罪にはなりません」
「マンションには必ず帰るのですか」
「はっきりしませんが結構帰っているようです、ショートケーキに二日に一回は行っているようです」
「わかりました今日から張り込みます」
「お願いします」」
「張り込みの交代要員を呼んでいいですか」
「ええ、どうぞ」
「うちの連中がきたらショートケーキも張り込みます」
「気づかれないようによろしくお願いします、これからちょっと食事をしましょう」
薩摩の行きつけだという、小さな居酒屋に行った。「チッチェ」という店である。四人ほど座れるカウンターと四人机が三つある。カウンターの中には白い髭を生やした主人ともんぺ姿の連れ合いらしき女性がいる。
「おお、とうやんいらっしゃい」
おやじが愛想良く声かける。彼はとうやんと呼ばれているようだ。
「今日はまた十歳若い格好いい男と一緒だね、違う仕事だろ」
「口数が多いよ、同級生だ、俺とは違って、天才、弁護士」
「おや、同級生ですか、よろしくお願いします、とうやん運動不足だね」
「比較するな、いつものたのむ」
それから色々食って飲んだ。海のものも煮物もみないい味付けだ。最後に出てきた握りのうまいこと、野霧たちにも食わしてやろう。
次の日、まだ暗いうちに詐貸はホテルを出てタクシーで小倉のマンションに行った。マンションは青葉城跡公園の近くだった。5階建ての小ぢんまりとした建物だ。エントランスに自由に入れる古いタイプのマンションである。郵便ポストの数からすると20軒ほどだろう。彼の部屋は五階の3号室だ。彼はそれだけ見ると外にでた。地下鉄の駅が近くにあった。勾(こう)当台(とうだい)駅である。
次に行ったのはそこから地下鉄で二駅離れた飲み屋街にあるスナックバー、ショートケーキである。真っ黒なドアに真っ白なイタリック体でショートケーキと書いてある。甘み喫茶と間違えて入る人がいるだろう。扉の上に真っ赤な電球がついている。小さな品書きが貼ってあった。見るとコーヒー、ショートケーキも書いてある。甘みもあるようだ。後は何種類かのビールとウイスキーである。日本酒はおいてない。開店は意外と早く午後4時からである。甘味喫茶としてもやっているのだろう。
それだけ見ると詐貸は一旦ホテルに戻った。事務所に電話をすると野霧と吉都に仙台にくるよう留守番電話にメッセージを入た。朝まだ早いので二人は出てきていない。
部屋にいると、十時すぎに電話があった。二人とも今日すぐにこられるということである。それで一週間ほどいることになるかもしれないことを言った。
泊まっているホテルに二部屋の予約を入れた。
詐貸は今日の予定を立てた。まずは小倉のマンションを見張っていなければならない。詐貸は車の免許を持っていない。よく考えると助手の二人も免許を持っていない。今まで車を必要としなかったがこういうときは免許があると便利だろうなと詐貸は思った。
その後、ホテルをでた彼は駅の携帯会社で携帯をレンタルして、今度は地下鉄で小倉のマンションの近くに行った。助手の二人が来たら携帯を借りるように言わなければならない。東京で普段使っている携帯は使わないほうがいい。
珍しいことに小倉は固定電話を持っている。電話番号は薩摩から聞いている。最近このあたりは、貴金属や不要品の買い取りの電話が多いと薩摩が言っていた。詐貸は携帯で小倉の部屋に電話を入れた。出たらば不用品買取り会社のふりをするつもりだった。だがいないようだ。留守電になる前に切った。昨日からいなかったのだろうか。
昼を食べるともう一度小倉のマンションに行ってみたが戻っている様子はない。一一人住まいの勤め人が多いようで、昼間は人の出入の少ないマンションのようだ。五階の小倉の部屋までエレベーターで上がって部屋を確認した。角部屋で外から分かりやすい。
マンションから出た詐貸は小倉の部屋を道から確認した。周りには隠れるような場所はない。一軒喫茶店があるが、そこからはホテルの入り口も見やすそうだ。張り込みにはよさそうである。
彼はもう一度ホテルに戻った。本格的に見張るのは二人が来てからにしよう。今夜はショートケーキに行って様子をみよう。
夕方になり、また小倉のマンションに行ってみたが、部屋に明かりはついておらずいないようだ。その足でショートケーキに行った。黒く塗られたドアを押すと、中は意外とさっぱりとしていた。カウンターの中のおかっぱ頭の化粧っ気のない女がちらっと詐貸を見た。シノンという名の占い師だ。もっとけばけばしい店を想像していたのに意外だった。
カウンターには背広を着た会社帰りのような二人ずれがいた。常連のようだ。詐貸はカウンターではなくテーブル席に腰掛けた。
「待ち合わせ」
シノンが詐貸に声をかけた。かなりの低音だ。笑顔はちょっと不思議な魅力がある。
「いや」
「そんじゃこっち来てくれる、カウンターからでるの面倒なんだ」
「いいよ」
意外と気さくで感じがいい。
「観光客じゃないわね」
詐貸は笑いながら「仕事できたんだ、ショートケーキって名面白いから入ってみた」
ハハハと彼女は笑って、
「何飲む」と聞いた。
「ジャックダニエル」
「ストレートでしょ、カウンターにきてくれたからダブルにサービス」
やけに気前がいい。
ショットグラスにたっぷり注ぐとチョサーとともに出してくれた。
「あなたの店」
「冗談でしょ、私の店だったらもっと気の利いた名前にするわよ、ちょっと左の手の平見せて」
詐貸が手を見せると「こりゃ、めずらしい、一見不真面目な天才、仲間に恵まれている、会社経営者でしょ」
当たらずとも遠からずだ。
「よく当たっている、売り込みに仙台に来た」
「ドーミーインあたり」
「ずぼし」
「会社づとめの出張者のちょっとした贅沢」
よく読んでいる。
「経営者はママのパトロン」
「いや違う、私がだましたの、私が街頭で占いやってたとき、金回りが良さそうな男が来たから、手相を見て、私に店をもたせたら儲かると言ったら、本気にしてこの店つくったのよ、まあ、あの人勘は悪くないわね」
「で、なぜショートケーキなの」
「彼の名前が敬紀だから、ケイキバーにすると言うから、そりゃいやだ、といったら、ショートケーキはと言うから、なぜと聞くと、ケーキの中で一番単純だからと言うから賛同したのよ」
「敬紀さんはここを経営しているだけ」
「しらない」
「オーナーのこと知らないんだ」
「占いできる場所があればいいの」
「オーナーは来ないの」
「今日はまだきてないわね」
「さて、お勘定」
「もう帰るの、千円」
やけに安い。
「まだ仙台にいるからまたくるよ」
本当にきてもいいような店だ。
「またきてね」
詐貸は小倉が裏でどのようなことをやっているかわからないが、ママの様子では人に嫌われていないようだ。むしろかなり頭がいい男で、それが表にでないタイプと彼は判断した。張り込んでいる自分がここに来たことを感づかれたら、すべて探っていることをわからないように処分してしまうだろう、もうショートケーキに行ってはいけない。野霧と吉都にまかせよう。
夜十一時前に野霧と吉都がホテルについた。ロビーに行くと二人は観光客の格好をしてソファーに座っていた。
「やあ、急なことですまんね、ご苦労さん、疲れただろう」
「いや、元気です、なにをしましょう」
野霧はやる気まんまんである。
「部屋に荷物を置いて、俺の部屋に来てくれよ」
二人は自分の部屋にいって、しばらくすると彼の部屋をノックした。
「いい部屋とってくださいましたね、デラックスツインに一人で泊まれる」
野霧が嬉しそうにいうと、吉都も頷いた。
「そこしか空いてなかったんだ」
それから、詐貸は詳細を話した。
「ショートケーキに行って様子を見てよ、小倉がいたら、店を出るまでいてほしい、でたら俺にメイルしてくれ、これから小倉のマンションのところに行ってちょっとのあいだ見張ろうと思う、本格的には明日からだ」
「わかりました、ケーキ食べていいですか」
野霧がまじめに聞くので、「好きなものをいいよ」と、二人に十万はいった封筒をわたした。
「これでケーキいいですか」
野霧はまだこだわっている。吉都はシングルモルトにしようとつぶやいている。
「好きなように、使っていいよ」というと、二人とも封筒をしまうと、にこにこと「いってきまーす」と飛び出した。携帯をレンタルすることを言い忘れた。まあ明日からでいいだろう。
詐貸はタクシーでまた小倉のマンションに行ってみた。彼の部屋には明かりがついていない。帰っていないようだ。
マンションの入り口が見える喫茶室の窓際の席でPCを開いた。物書きのようなふりをしてPCに向かった。
三十分ほどしたときに吉都からいつもの携帯にメイルが入った。オーナーがいて、客と飲んでいるとあった。出先から直接ショートケーキに行ったようだ。荷物は持ってないともあった。と言うことはここで見張っていてもしょうがない、ホテルに帰ることにして、『小倉がショートケーキを出たら後を付けろ』と指示を出した。
それから一時間、部屋にいると、今出たので後を付けますと連絡があった。『地下鉄で二駅の自分のマンションにはいりました、部屋の電気も付きましたどうしましょう』とある。
『昨日家に帰っていない、飲んでるようだし今夜は動かないのじゃないか、帰っていいよ』
とうつと、『ずいぶん飲んでいました、きっと出ないと思います』と返信があった。
彼らは一時すぎに戻ってきたので部屋に来てもらった、
「ごくろうさん」
「先生、ショートケーキの餡子ののったショートケーキおいしかった」
野霧の報告である。
「おぐらのショートケーキか、逢手君は和洋折衷のお菓子が好きだよな」
「え」という顔を野霧がした。珍しく気がつくのが遅い。
「小倉敬紀は自分の名を店の名にして、苗字もちゃんと菓子にしたんだ、おぐらはあんこ」
野霧は詐貸に言われて大笑いした。
「結構面白い人かもね、あのママも面白い人、吉都君と夫婦にしとこうと言ってたんだけど、店に入ってテーブルについたら「お仕事うまくいったようね」といって、「女上司と部下でしょ」と言われました。「それで、はい、明日契約終わったらまた部長と来ますって言っときました」吉都が笑いながら言った。
「それはよかった」
「あのオーナーはみんなに好かれているようですよ、常連さんと、楽しく飲んで、ごちそうしてました」吉都が報告した。
「事件に関係のありそうなことをしゃべっていたかい」
それが全くそういったことの話は聞こえてきませんでした、お客さんたちもその辺の会社の人です」
「そうか、おそらく明日動き出すのは遅いだろうから、君たちは町中でも散歩したらいい、青葉城跡なんかいいんじゃない、小倉のところは僕が見てるよ」
「だいじょうぶですか」
「うん。あそこに見張るのにちょうどいい喫茶店があるんだ」
「スポーツをするような格好してくださいよ、それじゃ探偵そのもの」
野霧に言われてしまった。
「それと、俺のレンタルの携帯を教えておくから、君たちも借りて、俺に連絡してよ」
「はい、分かりました」
「遅くまでご苦労様、ゆっくりやすんでくれ」
彼らは自分の部屋にもどっていった。
次の朝、彼らは携帯電話をレンタルした後に仙台城跡に向かった。詐貸が少し遊んどいでと言ったからだ。詐貸はGパンとポロシャツを買って着かえた。これで旅行客にみえるだろう。
彼はゆっくりとホテルをでて、地下鉄の勾当台にある小倉のマンションに行った。エントランスに入ってメイルボックスを見ると、彼のところだけ朝刊がそのままである。まだ起きていないようだ。
昨夜の喫茶店にまたはいった。カレーとコーヒーをたのみPCを開いた。1時近くに、小倉らしき男がエレベーターからエントランスに出てきた。新聞を取りにきたようだ。その後はあらわれなかった。ショートケーキに行くにしても、四時からだからそれまでは動かないだろう。詐貸は一時間ほど喫茶店で粘ると、マンションのエントランスにいって朝刊がないことを確認し、ホテルに一度戻ることにした。地下鉄の駅に向かって歩いていると、薩摩から自分の携帯に電話がかかった。三つ子の遺伝子検査に疑惑が出てきたそうである。
「三人の資料を民間の遺伝子検査会社に再検査を頼んだところ、三人の遺伝子が全く同じだった、そんなことは普通あり得ない、しかも三つ子は二人が女で一人が男だったのだが、すべて女の遺伝子だったんだ」
「だけど警察の検査室の人だってそれくらいわかるだろう」
「そこも問題だ、遺伝子のほんの一部だけみて結論を出したんだ」
「そんなもんなんだ」
「さらにわかったことは、母親の遺伝子とほぼ同じだった。母親の組織を検査に使ったんだ。知らなかったけど、胎盤というのは母親の組織と子供の組織から作られているのだそうだ、その母親の組織を使ったのだろうということだ、と言うことは、専門知識が必要だ。夫婦が運び込まれた病院は妊娠した奥さんが通っていたところだった。だから病院の、特に産科の関係者を洗っている、君の推理の通りだ、来てもらってよかったよ、解明までにまだかかるだろうけどな」
「そりゃあよかった、俺の方は張り込んでいるが進展しないよ」
「関係はないかもしれないので、ほどほどにたのむよ」
「わかった」
詐貸がホテルの部屋で今までのことをまとめていると、吉都からメイルがきた。時間を見ると3時半である。青葉城にいってから、町中を見てまわり、ショートケーキのある国分町の飲み屋街にいるとあった。それで電話を入れた。
「先生、小倉のマンションにいるのですか」
「いや、今ホテルにいる」
「僕たちは早めに腹ごしらえをしておこうとバーの近くのラーメン屋に入ったんです、食べ終わって出ると、小倉が一人で歩いてきました。手ぶらでした。まだ早いのにと思って見ていると、ショートケーキに鍵を開けてはいって、しばらくして紙の手提げに何か入れて出てきました」
「あ、そりゃすまん、まだ動かないと思ってホテルにもどっちまった」
「それで尾行していますが、どうも自分のマンションに戻るようです、地下鉄に乗ります、われわれは追いかけます」
「続けていてくれないか、これからすぐ出るから」
「野霧さんが、今日は徹夜になるかもしれないと言っています、それで、しばらく僕たちがはりこみますから、先生は後で来てください、また様子を報告します」
頼りになるやつらだ。
「すまん、そしてくれ」
「はい」
電話を切ってしばらくすると、メイルがきた。『彼はマンションに戻りました、途中でコンビニで食べ物を買いました、夕食のようです、と言うことはショートケーキに今日は行かないのじゃないでしょうか、それに動くとすると遅くなってからではないでしょうか』
『たしかにな、交代は何時ごろがいいかな』
『彼が食事を何時にするか分かりませんが、出るとすると家で食べて夜遅くになってからのつもりではないでしょうか。八時あたりまでぼくたちが喫茶店にいますから、そのあと先生が替わってください』
『わかった』
詐貸は七時半に電車で吉都と逢手のいる喫茶店にむかった。マンションの5階の小倉の部屋には電気がついている。まだいる。
喫茶店に入る前に電話で喫茶店を出てホテルで休むようにいうと、詐貸はすれ違うように喫茶店にはいった。声をかけたりしてはいけない。
コーヒーを頼むとPCを開いた。
三つ子のことの方が気になるが小倉が盗んだものとなんの関係もないような気もする。きょう小倉が運んだものは本当にロッカーから取り出したものかどうかも分からないのだ。
九時、十時になっても小倉の部屋の電気はついたままだ。電気が消えたら寝てしまうのではないだろうか。などと、この張り込みのつまらなさを考えながら、PCに向かって何か書いているふりをしていた。
十時半なったときである。電気が消えた。寝る時間なのだろうか。ほんの間をおいて、エントランスにエレベーターから人が出てきた。小倉のようだ。詐貸はいそいでPCをしまうと勘定をすませた。
小倉は紙袋を吊るしている。ショートケーキから持ち出したもののようだ。マンションから出ると地下鉄の駅に向かっている。
詐貸も後をついていった。地下鉄の勾当台駅におり仙台方面のホームに立った。彼もちょっと遅れてホームに着いた。
仙台駅に行く電車がきた。それに乗るとやはり仙台駅で降りた。小倉は仙台駅の中には行かず、少しばかり歩くと一つのホテルに入って行った。このあたりでは一番豪華なホテルである。ロビーには外国人が何人も立ち話をしていた。彼は慣れた様子でエレベーターを待った。彼しか乗らなかったので、戸が閉まった後にエレベーターの前に行ってみると18階で止まった。
詐貸はロビーの空いている椅子に腰掛けて、PCを開き、降りてくるのを待つことにした。
すると十分後にはもう戻ってきた。もっていた紙袋はなかった。後を付けるとまた地下鉄に入っていった。詐貸はホテルに戻っていた二人にタクシーでショートケーキに行くように指示し、もし小倉がいったら様子を見るように言った。
詐貸は彼の後をおい、地下鉄に乗るとやはりショートケーキのある駅で降りた。きっと野霧たちの方が先についているだろう。彼は小倉の後をついていくと、やはりショートケーキに入っていった。
詐貸はホテルに戻ることにした。あの豪華なホテルの18階に誰が泊まっているのだろう。ホテルに聞いても教えてもらえないだろう、明日薩摩に頼むしかない、とりあえず、薩摩のスマホにメイルを入れた。
すると、すぐに返事が来た『調べておく、こっちの方も少し見えてきた、いやありがとう、明日会おう、そのとき説明する』とあった。
ショートケーキは一時か二時に店を閉める、彼らが戻ってくるのはそれからだろう。やはり二時近くにメイルがあった、小倉はマンションに帰ったのでホテルに戻るとあった。詐貸は自分の部屋に来るようにメイルを打った。
戻ってきた野霧と吉都は上機嫌だった。
「あそこのママ、私の手を見て、ふくよかだことと言うのよ、手を見なくても分かるのにね」
そりゃそうだ、誰が見てもそう思う。
「それで、とてもいいことがあるって」
まあいいだろう。
「小倉はあの豪華なホテルにいって、荷物を誰かに渡したよ、渡した宿泊客に関して薩摩に調べてもらっている、ショートケーキではどうだった」
「知り合いを呼んで、封筒を渡して、うまく処理したよ、って言ってました、若い男でした。男はぺこぺこして、とても喜んでいました」
「どんな男だった」
「どっちかというとこわい系ですが、そうだとしても、下っ端のちんぴらですね、それを受け取ったら、何も飲まずに帰りました」
野霧もうなずいている。
「その後、彼はナンバーズにちょっと当たったので、お客さんたち好きなものどうぞって、私またおぐらショートケーキ食べた」
野霧は幸せすぎただろう。
「明日、一緒に薩摩に会って話を聞こう、とりあえず小倉の尾行はおしまい、話によってはまた関わらなければならないけど、明日警察にいくよ、明後日いったん東京に帰ろう、今日はご苦労さま」
そこで二人とも自分の部屋に引揚げた。
次の日の朝、三人は宮城県警の応接室にいた。
「うちのスタッフの逢手野霧と吉都可也、こちらは県警副所長、刑事部長の薩摩冬児さん」
「おいおい、かたっ苦しい紹介はよせよ、大学のサークルで一緒だった薩摩です」
「ミステテリーサークルですね」
「ええ、そうです」
「私も」
野霧がそういうと、薩摩は「サークルも変わったでしょうね」とにこやかな顔になった。詐貸が「東大のミステリーサークルだよ」と訂正すると薩摩はぎょっとなった。
「すごい人が手伝っているんだ」と薩摩はつぶやきながら、皆に椅子を勧めた。
薩摩がまず昨日夜に小倉が荷物を渡した人物を説明した。
「小栗宙太郎、72歳、イギリスで財をなし、今は葉山の豪邸に住んでいる、若い奥さんと結婚したのだが、お産の時に亡くなった、子供も助けられなかった。それ以降、オートバイで日本各地を旅している。サイドカーに奥さんが好きだったマミーと言う名の大きなテディベアーをのせ、小さなテディベアーを行き先々で子供たちにあげている。それでテディじいさんと呼ばれています」
「え、あのトライアンフのじいさん」
吉都が驚いた。
「そのおじいさん、昨日青葉城址の公園で私たちにもくれました」
野霧がバックから小さなテディベアーをとりだした。
「それは一つ3千円もする、ドイツの本物です、ちょっと考えられないほどの世界的な資産家です、株屋ですね」
「でも、何で小倉と関係を持ったのでしょうね」
「わかりません、死んだ三つ子をテディじいさんに渡すはずがないので、別のものだったかもしれませんね、そういうことで、小倉のことを追いかけるのは県警としては終わりにすることにしました。
ただ、詐貸さんのおかげで三つ子の遺体が盗まれた件に関して大分進展があったのですが、まだみつかりません、今後も知恵を拝借しなければならないと思います。
詐貸さんが示唆したとおり、三人の子供が夫の子供ではないことが知られないように仕組まれたもののようで、死んだ子供から遺伝子解析用のサンプルを取り出すよう言われた看護師が、胎盤の母親の組織をとったということを白状しました。
その看護師はかなりの高額な金をもらったようで、相手は夫婦の勤めていた会社の男だとわかりました」
吉都が驚いた。
「あの犯人の男とは違う人ですか」
「ええ、結婚している他の課の男です」
「だけど、どうしてそうする必要があったのでしょう」
「犯人が自分の子だと言っていることを知って、遺伝子を調べられたとき、その男とも違うことがわかると、自分とその奥さんの関係がわかってしまうと思ったようです」
野霧が反応する。
「だけど、その男の遺伝子は調べられることはないでしょう」
「刺された女性は、ご主人より早く入社していましたし、結婚前にその男とつきあってることが噂になったことがあったようです、ほんの一時のようですが」
「だけどそれだけのことで看護師を買収したりするのかしら」
「その男の妻は社長の娘です」
「社長の座をねらっていたのね、テレビドラマみたい」
「それで、その男はどうやって警察の安置室から遺体を盗んだ」
詐貸が聞くと薩摩は「その男が言うには自分はやってないそうだ、それまでは考えていなかったようだ」
「胎盤から資料をとった看護師がやるわけはないね」
「できないね」
「犯人は本当の男親のことを知っているのかもしれない、遺体をもっていればまだ使い道はあると思っている人ね」
「どうしてそう思ったの」
「こういっちゃ悪いけど、そんなにもてる子なら、別に心配している男がいるかもしれないもの」
「そうか、そいつを強請るためか」
野霧の推理はすごい。薩摩も詐貸もそこまでは考えていなかった。
「会社の人間の可能性もあるし、他かもしれないけど、揺すられるのは地位がある人、だけど、ぜんぶ間違っているかもしれない」
「いろいろな可能性がありますね、調べなければならない範囲が広がりました。お願いがあります、遺伝子の件は夫の両親には言わないことになっています、外に出さないわけです、皆さんも内密にお願いしたい、さてみなさん明日帰られるのでしょう、今日の夕飯、美味しいところ案内しますよ」
詐貸が笑った。またあそこに行くつもりだ。「ちっちぇ」だ。
テディじいさんの依頼
あの日、テディじいさんは夜中に男から紙袋を受け取り、次の朝はトライアンフにまたがって東京目指して走らせていた。72にもなるのに若い連中より運転はうまい。東北自動車道をひた走り、途中でガスを入れるためにサービスエリアにとまったが、ほとんど休まずに葉山の自宅にもどった。いつものように使用人たちが玄関に集まり出迎えた。
「一気にとばしてきたので車のメンテは頼むな、ちょっと出かけるのは休むからしっかり整備をしてくれ」そう言うと、テディベアーを抱えて家の中に入った。
「お帰りなさい、後で執務室でまってます」
美衣がじいさんに言った。
「ああ、かわりないか」
「円が高くなって、日銀総裁が頭を抱えてます」
「ほっとけ」
「またドイツからテディベアーが届いてます、執務室のデスクの脇に積み上げておきました」
「ああ、ありがとう、仙台では三百個ほど配ったよ」
二階に上がると、いつものようにテディベアーを奥さんのベッドに寝かして、中から紙袋をとりだした。それをもって奥さんの部屋に入った。
テディじいさんはしばらくすると自分の部屋にもどりPCを開いた。
仙台の男からメイルが入っていた。
『三人の子供の遺体のありかはまだ不明ですが、警察内部で新たな動きがあり、三人の子供は刺されて死亡した夫の子供ではないことが判明しました、さらに、犯人の子供でもないということです、まだ全く公表されていないことです』
『それで目星は付きそうか』
『私の情報網では限界です、亡くなった奥さん、結婚前は相当人気があった人のようです。仕事は良くできる方で、とても人当たりの言いかわいらしい人という評判です、そのあたりを当たっていますが、警察の安置室に行って盗むというようなことができる人間はみあたりません』
『それじゃ、この三人の遺体のことはあきらめるが、この間あんたが言っていたすごい探偵に会ってみようか』
『はい西巣鴨の庚申塚探偵事務所です、住所電話送ります、この探偵事務所はホームページをもっていません』
『ほー、めずらしい』
じいさんはそれから1階に降りた。
三村美衣が「イギリスの銀行に円が集まってしまって、びっくりしていますが」
「それじゃ、半分ユーロに変えてくれ」
「はい」
「明日、西巣鴨の探偵に会いたい、ちょっと興味からだが、仙台にいったら変な事件のことを聞いた」
「なんですか」
「おなかの中でなくなった三つ子の遺体が盗まれた、警察も行き詰っている、その探偵に調べてもらう」
「なぜですの、社長に関係があることですか、奥さんを思い出してらっしゃるの」
「うーん、そうかな」
じいさんにしては歯切れが悪い。
「わかりました、みやげは何を買っておきますか」
「そういうのはだめな探偵らしい、ただの依頼人でいく」
「はい、探偵事務所に電話しておきます」
「おまえも一緒にきてくれ」
「サイドカーに乗るのは恥ずかしい」
「いや、電車で行く」
「私の車じゃないのですか」
「久しく電車に乗っていないから」
「珍しいですね、わかりました」
探偵事務所に戻った詐貸は、仙台での仕事にむなしさを感じていた。何もはっきりしないで帰ってきた感じだ。西巣鴨の事務所のデスクの前でぼーっとしていると、野霧がいつもいく菓子屋から饅頭を買ってきた。
珍しく戸棚から皿を出すと、詐貸と吉都の分を取り分けている。いつもだと包み紙をちぎってその上に載せて分ける。
「適当に選びました」
茶色と緑色の饅頭だ。可也には白と茶、野霧自信の皿には白と緑がのっている。
野霧は手づかみで白い饅頭に食いついている。吉都も白い饅頭にホークをさしてかじっている。詐貸は甘みは今いいんだけどなと思いながら、茶色の饅頭にホークをさして口に入れて驚いた。
「アイスクリームだ」
それを聞いて野霧と可也が声をあわせて「はじめてですか」と驚きの表情をみせた。「雪見大福知りませんか」
「うん」詐貸は甘みに疎い。
「古くからあるのですよ、アンパンと同じ発想の日本の誇るべきアイスクリームですよ、中はアイスクリーム外は大福、すごいと思いませんか」
野霧の言う通りかもしれない。「うん、うまい」と詐貸はうなずいた。
そこに電話がかかってきた。
「はい庚申塚探偵事務所です」
「私、小栗宙太郎の秘書をしております三村と申します、社長の小栗が相談したいことがあるということで、明日に伺いたいと申しておりますが、ご都合はいかがでしょうか」
「どのようなご用件でしょうか、受けることができないこともあります」
「はい、社長が直接説明したいと申しておりますが」
詐貸は小栗の名前を頭の中に思い出そうとしていた。そうだ薩摩が言っていた。テディじいさんじゃないか、なんだろう、我々が仙台でやっていたことを知っているのだろうか」
「明日はこちらにおりますのでお会いできますが、内容によってはお引き受けできません、それでもよろしければいらしてください」
「はい、それで結構です、十一時頃よろしいでしょうか」
「かまいません、どちらからいらっしゃるのですか」
「葉山です」
やはりテディじいさんだ」
「それじゃお待ちしています」
詐貸は電話を切った。
「依頼ですか、雪見大福溶けますよ」
野霧が聞いた。詐貸はあわてて食べかけのチョコレート雪見大福を口に押し込んだ。柔らかくなっていてうまい。飲み込むと「小栗宙太郎の秘書からだ」と言った。
それを聞いてすぐに吉都が反応した。
「テディじいさんじゃないですか」野霧もうなずいている。
「なんだか知らないけど明日十一時にくる」
「なにしに」
「依頼があるということだが」
「仙台にいたのばれていたのかしら」
「そうだとしたら、なぜわざわざくるのかということになるな、偶然だな」
「そうですね、でも仙台の事件のことだと面白いですね」
野霧はミステリーが大好きである。
明日謎が解けるだろう。謎があるということは皆の気持ちを高めてくれる。詐貸もテディじいさんが来るのがなぜか待ち遠しくなってきた。
「どんな感じの人だった」
「顔は楕円縦長で目鼻口、特に大きくも小さくもなく、おでこが広い、眉はめだたない、眼が少し下がっていて外人ぽいところもある。髪は白い、無精ひげは見えたけど、いかにもという感じで髭は伸ばしていない。耳が大きいかな、一度目があったけど、柔和なんだけど怖さもあった」
「それだけじゃわからんな」
「俳優さんだと、橋爪功、動きはジャックニコルソン」」
「二人を結びつけるのむずかしいけど、野霧さんがいうのもわかる、橋爪功もニコルソンのような振る舞いできるよ」
演劇をやっていた吉都がそう言っても、
「おれわかんない」と詐貸にはイメージがはっきりしなかったようだ。
次の日、野霧がいつも母親の飲んでいるのだといって九州のお茶をもってきた。それにいつもの和菓子屋からお菓子を買ってきた。
準備を整えて待っていると、ほぼ予定時間通りに、小栗宙太郎は秘書を従えて事務所に入ってきた。
「おじゃましますよ、小栗です」
確かに橋爪功に似てなくもない。
詐貸が立ち上がって、自己紹介をしてソファーをすすめた。
小栗と秘書がならんで腰掛けると、野霧がお茶とお菓子を二人の前においた。ピンク色の素甘である。それを見た吉都が小声で「なんで素甘」と野霧に言うと「あの店で一番おいしいものなの、私好き」と答えている。
野霧がテディじいさんに何か言おうとしたとき、じいさんが、「あ、餡まん」と橋爪功と同じような声で言って、しまったと思ったようだが、秘書が「なに言ってらっしゃるの」とたしなめた。
野霧は自分のことだとそのとき気がついた。
テディじいさんは改めて言い直した。
「いや、どうも、わしの顔はもう割れているわけですな、仙台の青葉城跡でこのお嬢さんにテディベアーをあげましたな、そこにいらっしゃる眼鏡をかけた男の方と一緒でしたな」
「かわいいの、ありがとうございました」野霧が言った。
詐貸が「助手の逢手野霧と吉都可也です」と二人を紹介した。
「探偵さんの助手には見えませんでしたな、まさかわしを見張ってたわけではないでしょうな」
野霧はちょっとどきっとしたが、
「え、何か見張られるようなことなさっているのですか」
と、これまた言ってしまった。今度はテディじいさんの方がちょっとうろたえたようだ。
「いやまいった、見張っている人に熊をほしがったりしませんな」
テディじいさんは安心するように笑った。何かありそう。詐貸は笑い顔の裏でそう思った。
「それで、どのようなご用件でしょう」
「どこから話しましょうかな、ところで、この素甘いただいていいですかな、わしゃ好きなんだ、上新粉を練り上げて作ってな、甘めはひかえで、つるの子餅と同じじゃ、ウキペディアには木場で江戸時代に作られたとありますぞ」
このじいさんウキペディアを利用している。
じいさんは一口食べると「うまい素甘だ」
と、お茶を飲んだ。
「このお茶もいい、甘みがあるから八女かな」とあてた。
「この野霧の好きなものばかりで」
「それはいい助手をおもちですな、だじゃれじゃありませんぞ」そう言ってテディじいさんは笑った。おかしなじいさんだ。
「わしも餅類が好きでしてな」わざわざ言いつくろっている。野霧は笑をこらえた。
「それで、全国にも報道されたが、仙台で夫婦が殺されましてな、奥さんは臨月で、帝王切開で子供を助けようとしたのだが、倒れたときに腹を強く打っていて、死んでおりました。その遺体が盗まれたのです」
「夫婦が刺された事件に関しては新聞で見ました」
「子供は三つ子で遺体が盗まれたのはご存じないじゃろう」
「はい」
詐貸はしらばっくれた。
「それで、それを調べてほしいんですわ、警察には内緒ですがな、まさかそのことでこのお二人が仙台にいたわけではないでしょう」
「ええ違います、しかし、資料はないし、難しいと思いますが」
「仙台に知り合いがいますのでな、そいつに探らしています、しかし、その男だけではらちがあかないので、そいつからこの探偵事務所のことを聞いて連絡をしたわけです」
「その方も探偵ですか」
「いえ、表だって探偵をやっているわけではないのですが、何でも屋と言ったらいいでしょう、顔は広い奴です」
「それで何をどうしたらいいのか私にはわからないのですが」
「その男がまとめた資料をもっております、それを見ていただいて、決めてくださいますかな」
秘書がもってきた封のされた茶封筒を詐貸に渡した。
「わからないところは秘書さんにお聞きすればいいですか」
「実は三村はこのことを全く知りませんでな、私は投資家なのですが、そちらの秘書です、この調査に関しては、全く私の興味からお願いしているわけです」
詐貸は袋の中の資料を見た、警察しか知らないはずの遺伝子のことも書かれている。その男は警察の中に情報を手に入れる手づるをもっている。
詐貸は中にあった被害者の写真をテーブルの上に置いた。
それを見た秘書の三村美衣が「やっぱり」とテディじいさんを見た。
「どうしました」
詐貸が不思議そうな顔をした。
「わしが説明しよう、三村はこの奥さんの写真をみて、やっぱりと言ったんですわ、この奥さんがわしの死んだ若い女房によく似ているんですわ、分娩の時脳出血で死にましてな、子供もだめだったものだから、それで、まあ、三村が察したとおり、女房を思いだして、子供を見つけだしてやりたいと思ったわけですわ」
詐貸は、それだけなのだろうかと、なにかひっかかった。
「規定料金以外に必要経費はいくらかかってもいいのでたのまれてくれんでしょうか」
「私にみつけられるか自信がありません」
「見つからなくてもいいです、一月に一度、いや、何かわかったときでいいですから、電話かメイルをくださらんか」
「わかりました、とりあえず一月お引き受けします、一月経ったときは、その状況で判断しましょう」
「ありがたい、契約書は三村が書きますのでな」
詐貸は契約書を二通、秘書の三村に渡した。三村は詐貸に書き方を聞くわけでもなく、あっという間に書き上げた。見ると間違いなく書かれている。相当優秀な秘書なんだろう。詐貸は印を押すと三村に渡した。三村も印を押し詐貸に渡した。
「それで、失礼とは思ったが、これは手付け金でしてな、規定の料金とは別に、自由に使ってもらった方が動きやすかろうと思いましてな、領収書もいりません」
じいさんが分厚い封筒を詐貸に渡そうとした。
「それは必要になったときに連絡してお願いするものですので結構です」
「そう言われるとは思っていましたが、助手の方にも自由に動いていただこうと思いましてな、素甘のお礼でもあります」
詐貸は迷ったが、「それではとりあえずおあずかりして、使わせていただきます、あまったらお返しします」
「あまったら、素甘でも買ってくださらんか」
いったい、素甘がいくつ買えるのだろう。野霧が笑っている。
「それではよろしくお願いしますな」テディじいさんが立ち上がった。
野霧が「またオートバイでどこかにお出かけになのですか」と聞いた。
じいさんはにこにこして「家内が旅が好きでしたから連れて行ってやるのです」と答えた。どのような意味なのか詐貸が不思議そうな顔をしていたからだろう、三村が「社長の奥さんはテディベアーが好きで、社長がドイツから取り寄せたのです、名前はマミーです」と説明を加えた。テディベアーは奥さんの代わりであることを探偵社の三人ははじめて知った。
「そう、逢手さんでしたかな、あの素甘はどこで買ったのですかな」
「お岩通りにあるすぐ近くの和菓子屋「おたふく」です。道にでると駅と反対の方にちょっといくと右側にあります」
「使用人のみやげにするんじゃ、買って帰りますぞ」
えらく気に入ったもんだ。
こうしてテディじいさんと三村女史は帰って行った。
「驚いたなあ、偶然なのかまだ信じられないよ」
「それにしても詐貸先生は名が知られているのですね」
野霧が言うと詐貸自身とちょっと首を傾げた。偶然としたら奇妙な出会いだ。
「小倉敬紀は裏の探偵屋のようですね」
可也がつぶやいた。
「すると、詐貸先生は表の探偵ね」
野霧がつぶやき、二人で笑っていた。
小倉敬紀のことも調べなければならないだろう。きっと薩摩が知っているに違いない。事件の進展を聞くついでに小倉のことも聞いてみるか。詐貸は机に戻ると受話器を取った。
「三つ子の件はどうなりました」
「まったく解決していない」
「僕がからんだ小倉の件はなにかわかりましたか」
「あれは器物破損で小倉を尋問できるけど、どんな形でも言い逃れできるから、そのままなんだ」
「入れた女はわかったのですか」
「警察の情報のなかにはないね」
「小倉って何者です」
「あいつはこっちの国立大学を優秀な成績で出たんだよ、法学部だから詐貸さんと一緒だけど国家試験には合格していない、民法をやっていて、一時ある法律事務所に勤めていたけど、探偵事務所に移ったんだ、今はそれもやめて、いきなり喫茶店のオーナーになった。その間のことは詳しい情報はないな、今まで小さな事件すらおおっぴらには関わったことがないんだ。どこかで関係しているようで、小さな事件を起こして捕まった若いチンピラたちから彼の名前はよく聞かれるんだ」
「どういうこと」
「助けてもらったそうだよ、金銭的なことよりも、法律的なアドバイスをしてやっているようだな」
「テディじいさんとどんな関係があるのだろう」
「あのテディじいさんも得体の知れない人物で、わからないんだ、だけど調べればなにかでてくるかもしれない、知ってるだろうけど、イギリスに行った日本の若い女性と結婚して日本に戻ったというわけ」
「うん知ってる、大変な金持ちだよね」
「そうだな、投資だけでもうけていて、小さな国の予算ほども資産があるようだ」
「たしかに得体の知れない人ですね」
「三つ子の件が解決したら小倉のことも調べてみるよ、また相談にのってよ、助手の方にもよろしく言って」
そこで電話をきった。
「どうでしたか」
吉都が聞いた。
「小倉は地元の国立の法学部出身、一時探偵をやっていたようだよ」
「だから、先生のことを聞いていたんですね」
「そうかもしれない、それよりあのじいさんの依頼をどう思う、奥さんと似た状況だけで動くだろうか、それに小倉に渡されたものはなんなんだ」
「もしかすると、テディじいさんの奥さんと、被害者と顔が似ていたというところに何かあるかもしれないわね」
野霧の推理である。
「そういえば、テディじいさんの奥さんのことは何もしりませんね」吉都も頷いて言った。
「そうだね、それは知っとくほうがいいね」
「わたし調べてみましょうか」
「たのむよ、逢手君はじいさんに気に入られていたみたいだよ」
「餡まんて言ってたのに、そうかしら」
「素甘だって気に入っていた」
野霧の顔が三角っぽくなった、餡まんはあんまり気に入っていないのだ。
「僕は三つ子の方を探ってみましょう、北海道の奥さんの両親のことを調べるのはどうでしょう、いちばん怪しくないけど、安置室に入った唯一の人間ですから」
「確かにそうだな、両親の住所を薩摩に聞いてみるよ」
「同級生の刑事さんに何しているのか疑われません」
「いや、吉都が言ったことを正直にいうよ、それでちょうど北海道に行く仕事があるので、両親の評判などを聞いてみると言うよ」
「いいな」
野霧が羨ましそうだ。
「北海道に行くときはみな一緒にいこう」
とたんに野霧の顔がひしゃげた。
「それじゃ、行く前に私テディおじいさんの奥さんのこと調べます」
「どうやって」
「あの三村っていう秘書さんに明日電話かメイルします、名刺受け取っていましたね」
「うん、あるよ」
「素甘買えたかどうか聞きます、あの店あまりたくさん作らないから」
「わかった」
詐貸が野霧に名刺を渡した。
「そうだ」
野霧が急に探偵事務所を飛び出して下に降りていった。
すぐににこにこと戻ってきた。
「おたふくに行ってきました、おばあさん驚いていましたよ、テディじいさんが素甘五十っ個くれって言ったそうです、八つしかないと言ったら、それをみんな買ってくれて、作って送ってくれって言われたけど、どうやったらいいかわかんないといったら、電話して秘書が取りに来るといったそうです、私が紹介したことをおばあさん知っていました。あのじじい、探偵事務所の餡まんさんに聞いたって言いやがった、でもおばあさんアイスクリームくれました、一個しかですけど」
おばあさんも餡まんで野霧とわかったんだ。
詐貸は笑って「溶けちゃうから食べなよ」というと、野霧はアイスクリームにかじりついて「秘書さんに、私が買って届けようかとメイルします、たくさんお金もらったでしょう」と言った。
「そりゃ名案、どんな邸宅か見てきたらいいですよ」と吉都も笑っている。
「素甘はすごい」詐貸が小さくつぶやいた。そうしたら、私のことですかと野霧は顔を三角にした。そのつもりではなかったのだが。
テディじいさんの赤い屋根の館
次の日、野霧は事務所に出勤するやいなや、秘書の三村に『必要なら私が素甘を注文して、葉山まで届けます、庚申塚探偵事務所逢手野霧』とメイルした。すると『五十個たのみます、明日大丈夫ですか、三村』と返事が来たので、野霧は『今店に聞いてきます』と返事を書いて、すっ飛んで外にでた。以外とすばやい。返事は聞いてきてからでも良かったのにと、詐貸はちょっと笑った。
すぐ戻ってくると、『明日十時の開店までに作ると言うことです、それから持って行くことができます』とメイルした。
三村から『お願いします、お昼はこちらで用意します』とあった。
「先生、明日葉山に行ってきます」
「大変だけどたのむよ、逢手君の見てきたことを聞いてから北海道の予定を立てる」
詐貸はそういって薩摩に連絡を入れた。
「近々、北海道に仕事に行くけど三つ子のお母さんは北海道の人だったよね、ついでに調べてみようと思うけど」
「うん、北海道の人だけど、彼女のなにを調べるのだい」
「高校の同級生から恨みをかったりしていないかみるのもいいだろう」
彼は思いつきを言った。
「たしかにな」
「住んでいたとこわかるだろ、教えてよ」
「両親の住所、電話は教えてなかったか、暗号メイルで送るよ、芽室だよ」
テディじいさんが渡してくれた資料にも入っていなかった。
「どこだいそれ」
「帯広の隣だ」
「知らないとこだ、高校はそのあたりなのかな」
「小さい町だから高校ないよ、高校は帯広だろう、高校の後、北海道の短大をでて、会社にはいったそうだよ」
「父親は何してるんだ」
「無職のようだ、母親がしっかりしていて芽室の病院で看護師をしているようだ」
「わかった、何もわからないかもしれないけど、調べてみるよ」
「それじゃ、こっちも何かわかったら教えるからよろしくな」
「うん、それじゃ」
詐貸は電話を切った。
野霧は和菓子屋、おたふくに五十個もの素甘を頼みに行くと、珍しく店主のじいさんが店先にでてきて、何度もお礼を言われてしまった。
次の日、野霧は湘南ラインに乗った。逗子についたら三村さんに電話をすることになっている。素甘五十個入った紙袋はかなり重いものだ。
逗子にいくのも始めてである。スマホで見ると一時間とちょっとである。葉山に行くには電車がないことを今回初めて知った。逗子からバスでいくしかない。葉山はご用邸があるところである。
逗子について電話をすると、三村女史自身が車を運転して迎えにきた。
「遠いところすみません、私が買いに行けばいいのですが、社長が来てもらえと言うものですから、逢手さんと素甘食べたかったのかもしれません」
「お迎えすみません」
顔が半分ひしゃげている。野霧はちょっと嬉しかったようだ。
「逢手さん葉山ははじめてですか」
「はい、三村さんは小栗さんの秘書になって長いのですか」
「そうですね四十年ちょっとかしら」
野霧にはその冗談がわからなかった。
「十年ですか」
運転しながら三村が笑った。
「ごめんなさいね、私小栗の娘です」
野霧は前につんのめった。
「驚いたでしょうね、小栗の前の妻の一人娘なんです、母は小さいときに病死して、その後小栗に育てられたのですけど、私結婚しましてね、三村です。夫は今ブラジルにいます。小栗の会社の社員です。私はイギリスの大学をでてからすぐに小栗の秘書になりました」
「でも、全くそういう風に見えませんでした」
「小栗は家にいるときも、秘書として振る舞うように言いますのでそうしています、きっと、夫のところに行けと言うことだと思います」
「どういうことですか」
「イギリスにいるときには会社で秘書を務めて、自分の家に帰っていたのですけど、小栗が結婚をして日本に来ることになり、私がいないと困るだろうと思ってついてきたのです、日本には来なくていいから、ブラジルにいった夫のところに行きなさいと、日本に来る前に何度か言われました。日本での生活が安定したらそうしようと思っていたのですが、小栗の奥さんがあんな風に亡くなるとは思ってなくて今になっています、でもとても良くやってくれる使用人たちがいますし、そろそろ私も夫のところに行こうかと思っています」
「そうだったのですか、全くわかりませんでした、お父様が若い方と結婚されるときはどう思われました、あら、いけないこと言ったかしら」
「いえかまいんませんよ、とてもよかったと思いました。奥さんの小夜さんは思いやりのあるとてもかわいらしい女性でしたから、芯もしっかりしているし、安心したんですよ、ただ彼女は自分の家と断絶して飛び出し、しばらく東京にいたようです、無許可の出稼ぎの集団に混じってイギリスにきてカフェでウエイトレスをしていのですが偶然父と会ったようです、細かい成り行きは知りませんが、父は彼女をうちのメイドとして雇いました。、それまでもいろいろ恵まれない人間に会うと父は世話をしていました。よく働く子で父は養女にするつもりでした。ところが結婚することになったのです。小夜さんは真正直な人ですし。私も好きな子でした。」
「話は変わりますけど、三村さんはイギリス育ちですね」
「ええ」
「日本語をふつうに話されますけど、日本語教育を受けられたのですか」
「父は日本語をしっかりと私にたたきこみました、英語は友人たちがいましたので自然と話せますが、あとスペイン、イタリア、フランス語はできます、それは学びました」
秘書としては申し分ない能力を持っている人だと野霧は感じていた。
「小夜さんはどこのご出身なのですか」
「北海道なんです、両親はまだいらっしゃいます、だけど小夜さんが結婚したことも、亡くなったことも知らないと思います、小夜さんはいっさい両親とは連絡しないでくれと、小夜さんにしては強い調子で常々言っていました。父もそれだけは守っています」
「北海道のどこなんですか」
「芽室です、そこまでは本人から聞きました」
野霧はどきっとした。
「結婚される前の名字はなんとおっしゃるんです」
「細野小夜さんですよ、探偵さんやっていると、いろいろ質問されますね」
「あ、ごめんなさい、くせです」
三村も笑った。野霧の心臓はどきどきしていた。
葉山のテディじいさんの家につくと、門が自動的に開き、車は木々の間を少し走ると玄関前に着いた。かなり昔にたてられた赤い屋根の西洋館である。広い庭だ。おそらく名のある人の別荘だったのだろう。
待っていた若い男性がドアを開けてくれた。野霧が降りると三村も降りてきて、「お願いね、お菓子があるのでみんなで食べてね」と車の鍵を渡した。若い子が素甘を食べるだろうか。
「はい、ありがとうございます」
彼は車を移動させるため運転席にのりこんだ。
「どうぞお入りになって」
若い女性がいらっしゃいませと言ってスリッパをそろえた。
玄関前は広いホールで、三村は「私は社長に言ってきます、すぐ行きますので」と二階にあがっていった。
野霧は客間に案内された。広い庭が見渡せる。先は砂浜につながるようだ。
ほどなくテディじいさんが三村をしたがえて入ってきた。
「やあすまんですな、うまい素甘を皆にも食わせようと思いましてな」
じいさんはにこにこしすぎほどだ。本当に野霧が気にいっているようだ。
「おじゃましています、これ素甘です」
野霧はもってきた素甘の包みをじいさんに渡した。
「ありがとう、美衣、お金を用意してくれ、それに、この素甘みんなの三時にだしてやってくれ、わしの分は持ってきておくれ」
「はい」
笑いながら三村が素甘を奥にもっていった。
「あのう、詐貸が素甘の代金と交通費はいただいたお金から出しておくので、もらってはいけないといわれております」
「彼は律儀な人ですな」
給仕がお茶と素甘をじいさんの前においた。野霧の前には昔ながらの足のついた金属の器に三色のアイスクリームとお茶をおいた
「いただきますぞ」
じいさんは素甘を齧った。「うまいな」
そう言ってじいさんはまた笑った。よく笑うじいさんだ。
「逢手さん、どうぞ召し上がって、うちの調理場で作ったアイスクリームだから口に合うかどうかわからないけど」
戻ってきた三村がじいさんの素甘を見てボーっとしていた野霧にすすめた。
「はい、いただきます」
どうして私の好物知っているのかしら。庚申塚探偵事務所のことを相当調べたんだわ、そう思いながら、平べったいアイスクリームスプーンで抹茶アイスを口に入れた。
「美味しいアイスクリーム」
野霧だって笑窪を寄せている。肉まんだ。
「詐貸さんは忙しいじゃろうな、人気がある探偵さんだ」
「いえあまり仕事を引き受けないので暇です」
「逢手さんはどうして探偵事務所にはいりなさったのですかな」
「図書館に勤めていたんですけど、外に出たくなって、求人広告でいきました」
「探偵に興味があったのですね」
「と言うより、ミステリーが好きです」
「わしも小難しい小説は読まんが探偵小説は好きじゃ」
「小栗さんはいろいろなところにオートバイでいかれているのですね」
「そうだねえ、かなり行ったね」
「どうやっていくところを決めるのですか」
「いや、気が向いたところにね」
「九州、四国はいかれましたか」
「もちろん行きました」
「北海道は奥様の生まれたところとお聞きしましたが、どこがよかったですか」
じいさんの笑顔がちょっと薄らいだ。野霧がおやっと思っていると、
「日本に戻ってからはまだ行っていなくてな、そろそろ行こうかと思っております、北海道一周じゃな」
「いいですね」
なぜ北海道に行っていないのだろうか。奥さんが家を飛び出したからなのか。
「社長の生まれたとこでもありますからね」
三村が言った。あれテディじいさんも北海道生まれだったのだ、
「北海道のどちらなんですか」
「わしゃ札幌だが、五歳の時ロンドンに行ってそれっきりイギリスじゃ」
「ご両親やご兄弟はいらっしゃらないのですか」
じいさんが笑顔になった。
「戦後の孤児院で育ったんじゃよ」
これまた野霧はびっくりした。
「逢手さんはずーっと東京じゃろう」
「はい、母と住んでます、姉が北海道にいるんです」
「ホー、それじゃ北海道にはよく行くのかな」
「たまに母を連れていきます、ここのところ行っていません」
野霧は時計を見た。
「長い間おじゃましてしまいました、お菓子を届けるだけのつもりが、あがりこんですみません」
「食事の用意ができているわ、ダイニングの方にいらして」
三村美衣が立ち上がった。
「そうじゃ、きょうはなんだい」
「三崎のマグロのお寿司、野霧さんだいじょうぶかしら」
大丈夫も何も、何でも好きな中の一番にあげてもいいくらいだ。
「大好きです、お食事までいただいたら、しかられるかもしれません」
「私が見た限り、詐貸さんはそんなことできる人じゃないわね」
美衣が笑った。野霧もそれは百も承知で言ったことだ。
「わしは素甘がいいな」
じいさんはなぜか素甘にご執心だ。
寿司は最高に美味しかった。その後、またアイスクリームも出た。
「これはわしが好きなアイスクリームでしてな」
野霧は目を丸くした。また三色アイスだ。さっき食べた三食アイスの器になんと、白緑茶色の雪見大福がのっていた。
野霧は笑を一生懸命かみ殺してペロッと食べた。
「うまいでしょう」
「ええ、本当に美味しいものばかり、ありがとうございました、そろそろ帰ります」
「わざわざもって来ていただいて、すみませんでした」
美衣が野霧にいった。
野霧が立ち上がろうとすると、じいさんが言った、
「ミステリーが好きと言ってましたな、イギリスにおいてきたミステリーの本が沢山ありましてな、逢手さんは英語ができそうだが、読みますかな」
「はい、中国とハンガリーの本も読みます」
「そりゃすごい、美衣、イギリスにおいてあるミステリーの本は全部逢手さんにあげるぞ」
「はい、イギリスの方に伝えておきます」
「わしがやっとくよ」
「そんな」
「遠慮しないで大丈夫よ、社長の本読む人いないから」
「ありがとうございます」
野霧は玄関に向かった。
「詐貸さんによろしく言ってください、またお願いにあがるかもしれません」
「はい、ありがとうございました」
「社長、逗子までお送りしてきます」
「ああ、たのむよ」
テディじいさんは玄関のホールまで見送りにきてくれた。
車の中で三村が「社長、珍しく自分のことを他の人に話したわ、何か考えているみたい」と言った。
「どういうことですか」
「小栗のあの家での生活と仕事のことは私もよく知っているけど、オートバイで出かけることに関しては、どういう人とやりとりしているのか全く知らないの」
「心配ですか」
「心配はしてないわ、相当周到に物事を考える人ですからね、それでいてダイナミックに決断できるのはたいしたものだと思っています、だから一人であそこまでの投資家なれたのでしょう、ただ、小夜さんを亡くして、オートバイを乗るようになって、違う面が出てきたみたい、ブラジルにもうすぐいくのでちょっと気になってるわけなの、詐貸さんとコンタクトとることも急に言い出して、初めて三つ子の話を聞いて、何を考えているんだろうと思いました、あら、ごめんなさい、こんな話をついしてしまいました」
「いえ、心配ですね、何かわかったら三村さんにも知らせます」
「ありがとう」
こうして、逗子まで送ってもらった。
電車の中で詐貸から『直接家に帰っていいよ』とSMSがあった。野霧は『報告したいことがあるので事務所に帰ります』と打った。了解待ってると返事がきた。
事務所に駆け込むと、吉都と詐貸が野霧を見た。顔が引きつっている。
「ご苦労さま、どうだったの」
「いろいろわかりました」
吉都がお茶を入れてくれた。
「何から話していいかわからない、自家製の三色アイスクリームおいしかったです」
「へー、そりゃあよかった、じいさん元気だったか」
「また相談するかもしれないからよろしく言ってくれとのことです」
野霧にしては珍しく何から話そうか迷っている。
「奥さんのこと聞いてくるんじゃなかったのかい」
野霧はお茶をのんで一息ついた。
「ふー、奥さんは北海道の芽室出身」
そこまで言うと詐貸と吉都がぎょっとなった。
「中学をでた時、家と絶縁してロンドンでカフェ勤め、じいさんが援助で、結婚、結婚前の名は、細野小夜」
「ぎゃあ」と吉都がうめいた。
詐貸が言った。
「三つ子の母親の旧姓は細野佳代、父親は政夫、母は美代、薩摩が教えてくれた」
それを聞いて、今度は野霧がぎょっとした。
「テディじいさんの奥さんだった人は、刺されて亡くなった奥さんの姉さん」
「そういうことかもしれない、テディじいさんが三つ子の母親の旧姓を知っていたら、彼がこの件で俺の事務所に頼んできたわけはわかる」
吉都も野霧もうなずいた。
「テディおじいさんは札幌の孤児院で育って、5歳の時にロンドンに行ったそうです、ご自分でおっしゃいました」
「ひょー」吉都が口をとんがらかした。
「ますます、テディじいさんのこだわりがわかってきた」
「さすが野霧さんですね」
吉都が感心している。
「三村さんはテディおじいさんの前の奥さんの一人娘」ととどめをさした。
二人はあんぐり口を開けたままで声もでない。
そのあと、野霧は詳しく話した。
「秘書で娘の三村はブラジルに行くのか」
詐貸はその後テディじいさんが何をしたいのだろうと考えてみた。今の情報だけでは想像はできない。
しばらく間があって、詐貸は
「よくやってくれた、そば屋で夕飯ごちそうするよ」と立ち上がった。
「あ、お昼に美味しい三崎のマグロのお寿司いただきました、その後三色アイスクリーム食べました。雪見大福だった」
二人はそれを聞いて笑った。野霧の舌はテディじいさんとよほど馬が合うみたいだ。
詐貸の行きつけのそば屋が庚申塚の近くにある。
テディじいさんの北海道
次の日、北海道に行く打ち合わせをした。
「野霧君は札幌にいって、テディじいさんの若いころを調査してくれ、薩摩に聞けばテディじいさんの昔の本籍がわかるだろう」
「はい、札幌には姉もいますので、行けるのは嬉しいです」
「可也君には芽室の両親の調査をたのもう、俺は必要に応じてどちらかにいることにする」
「わかりました、両親の素行調査をします」
出かけるのは明日以降、泊まるところと、得られた情報はパスワード付きのメイルで共有としよう、パスワードはローマ字小文字でshyarekoube」
「わかりました」
詐貸は薩摩に電話をして小栗宙太郎の本籍を調べて欲しいとたのんだ。夕方になって、詐貸のメイルに連絡がきた。
『警視庁の仲のいいやつに調べてもらったよ、小栗の本籍住所は北海道札幌市簾舞1788だそうだ。イギリスにいった時のままのようだ。結婚届はイギリスの日本大使館に出されている』とあった。
詐貸はそのことを二人に伝え、それぞれに現金を渡すと、「これは活動費用、足りなくなったら言ってくれ、帰る日は向こうでの進展状況によって決める」
そう言って、今日から自由にしてくれと解散をした。二人とも家に帰り出かける支度をするだろう。詐貸も二人がでてしばらくすると、事務所に鍵をかけ外に出た。
札幌につくと、野霧はすぐにホテルにはいった。スマホで北海道の地図をあけ、南区の簾舞の番地の場所をチェックした。地下鉄南北線の終点真駒内でおり簾舞まではタクシーを使うことになる。真駒内は1972年冬季オリンピックの会場となったところである。泊まるホテルと明日行動を開始することを二人に連絡し、姉の家にみやげを持って行った。夕食は三人の男の子に囲まれてにぎやかに食べることになる。
次の日、地下鉄真駒内駅から、タクシーで簾舞の住所のところに行った。そこは丘の中腹でただの木の植わった畑だった。農家らしい家がちらほら見える。帰りのためにタクシーカードをとった。
一番近くの家に歩いて行った。トラクターが止めてある大きな農家である。もんぺ姿の女性が庭で作業をしている。
門の脇から野霧は声かけた。帽子をかぶって手ぬぐいを首に巻いたおばさんがそばにきた。
「なんかね」
「すみません、この番地を探しているのですけど、わかりますか」
「どれ」おばさんは野霧の手元のメモをのぞきこんだ。
「こりゃあ、市から払い下げになった土地で、今は若杉さんのとこだな、昔教会があって、隣に孤児院があった」
「孤児院のことをご存じですか」
「わたしがこのうちに嫁にきたときは孤児院も教会ももう人はいなかったな、土地は市のもので、払い下げをしておったんだが、若杉さんちが買いなすった」
「若杉さんのお宅はどちらでしょう」
「ほら、向こうの林の前に家がみえるだろ、この道を二十分も歩くといけるよ、あの土地を買ったじいさまが九十でまだ元気だから、何かわかりますよ」
「孤児院の名前はわかりますか」
おばさんは首を横に振った。
「教会は小栗教会って言ったと思うよ」
テディじいさんの名字だ。野霧は礼を言って歩き始めた。教会と関係がありそうだ。
若杉さんの家は大家族のようだ。四歳か五歳くらいの男の子が庭で遊んでいる。猫が二匹そばでうろうろしている。
「こんにちわ」、声をかけると男の子が誰かきたよと家の中に叫んだ。お母さんらしい人が出てきた。
「突然すみません、小栗教会や孤児院のことが知りたいのですが、若杉さんなら知っているかもしれないと、向こうの家の人に聞いてきたのですが、ご存じですか」
「私はなんも知らんけどじいちゃんは知ってると思うがいま温泉に行ってて、明後日帰ってきますよ」
「そうですか、戦後のこのあたりのことが知りたくて調べています、また参りますがいいでしょうか」野霧は名刺を出した。町の探偵とある。野霧の名刺だ。
「じいちゃんはそういう話が好きだからかまいませんよ」
「それでは明後日よろしくお願いします」
野霧は電話番号を教わりタクシーを呼んで駅に戻った。
次の日、市役所に行って、その住所のところに何があったのか台帳を見せてもらった。ここでも野霧は名詞とマイナンバーカードをみせた。その土地の所有者は確かに若杉になっている。もう取り壊された建物も載っていて、教会の所有者は小栗ハリスとなっており、隣接して孤児院が建っていたがその建物は市のものとなっていた。
それらのことを詐貸と吉都に伝えた。詐貸も吉都と同じく帯広にいるという。芽室にはホテルらしいものがなく隣の帯広にしたそうだ。
吉都は帯広から芽室の様子を伝えてきた。ついた日、夕方に芽室にいき細野さんの家を確認したそうである。駅から二十分ほど歩いたところにあるなかなか立派な家だ。想像していたのとはずい分違い、何代も使われていたような屋敷だということだった。門の脇には相当古い松が植わっているという。ただ表札は「水野、細野」となっているのはなぜかこれから調べるつもりだとメイルにはあった。
吉都は細野の家を突き止めた後、その場所にとどまっていると変に思われそうなので駅に戻り、芽室のパンフレットなどを集めて帯広に戻った。ホテルでパンフレットを見ると、コロボックルの発祥の地とあった。
次の日、午後に再び芽室にいき、旅行者の格好をして写真機を片手に駅からまっすぐに伸びている道路を歩いた。道の両側には間隔をおいて銅像が立っていた。どれも子供や小人達である。コロボックルたちだ。その道をぶらぶら歩いてもう一度、細野さんの家の方に向かった。その時、道の角にある病院の入り口が開くと、白い割烹着のようなものをきた女性が、足の悪いおばあさんを支えて出てきた。道にでると置いてあった手押し車におばあさんをつかまらせ、「気をつけて帰りなよ、薬はちゃんと飲むんだよ」と言った。「いつもありがとね、細野さん」と老人は車を押して帰った。
亡くなった細野佳代の母親ではないか。母親は看護師ではなかっただろうか、吉都はその医院の看板を見た「水野医院、内科、小児科、外科、朝九時から十二時、二時から七時、土曜日十二時まで、休診日、日曜祭日」とある。昔の町のお医者さんといった感じだ。そこではっと思った。細野の家の表札が、水野、細野になっていた。関係があると吉都はにらんだ。
吉都は町をぶらぶら歩いた。狭い町で時間を潰すのは骨がおれる。駅に戻り近くのラーメン屋に入ると、腹ごしらえをして駅の待合室でテレビを見ていた。
七時ちょっと前に駅をでて、水野医院の見えるところでスマホを操作する振りをしていると、七時十分に細野と呼ばれた女性が医院を出てきた。
彼がつけていくと、やはり昨日確認した家に入っていった。母親の勤め先がわかったのは大収穫だった。それだけではない、表札にはその病院の名前が書かれている。その時点では吉都は細野と水野の関係を知らなかった。
吉都は帯広にもどると、詐貸のホテルに行き、今後どのようにしたらいいか相談をした。
「旦那は働いていないと薩摩は言っていたよな、旦那は何をしているか調べるのと、週刊誌は犯人が自分の子だと思っているところに目がいっているので、会社の中での恋愛の記事ばかりで刺殺された夫婦の両親のことに注目していない、だが少しは取材にきたのではないだろうか、君は週刊誌の記者として母親の美代にインタビュウしてみないか、俺は父親の細野政夫を調べてみる」
「わかりました、昨日は奥さんの帰りを追っただけですが、旦那は家にいないようでした」
次の日の朝八時頃、詐貸は細野の自宅に電話を入れた。奥さんがでた。あの看護師である。
「週間毎朝の記者をしております後藤と申します、このたびは大変おいたわしい出来事で、お悔やみ申し上げます、このような時おいやかもしれませんが、奥様とご主人の政夫様に一言だけでいいのでお気持ちをきかせていただきたいのですが」
「あの、すみません、主人はあまり家におりません」
「この事件のせいですか」
「いえ、まえから札幌の方で働いております」
「札幌に行けばお会いできますか」
「いえ、仕事の関係で居場所が変わるもので、今どこにいるのかわかりません」
「全く家のほうにお帰りにならないのですか」
「週に一度だけです、すぐ札幌に戻るので、話はできないと思います」
「そうですか、奥様とはお話しできませんでしょうか」
「かまいませんが、私は働いているので、時間が取れるかどうか分かりません、すみませんもう出なければ」
「どうも忙しいときにすみませんでした、また電話をいたします」
詐貸は電話をきって、吉都に奥さんと話した内容を電話で伝えた。
「後はよろしく頼むな、おれは吉都がインタビューをした後に札幌に行って旦那を探す」
「はい、電話をしてどこかで話を聞くようにします」
その日の夜、吉都は細野の家に電話をかけた。
「遅く申し訳ありません、週間毎朝の後藤記者からインタビュウを委託されました早川と申します、後藤さんが来る予定だったのですが、札幌に行かなければならなくなったので、わたしがお話を伺いたいのですが、明日お時間とれますでしょうか」
「何を話せばいいのですか、もういろいろお話をしましたのでなにもありませんが」
「お嬢さんの思い出ですとか、犯人に対する思いですとかなんでも結構です」
そこでちょっと間があった。誰かと話をしているようだ。声のトーンが変わった。
「ちょっとだけでしたら」
「何時がいいでしょうか」
「仕事が引けるのが七時過ぎですので」
「どこがよろしいでしょうか」
「わたし、水野医院で看護師をしております、そこでどうでしょうか」
「だけど病院でかまわないのでしょうか」
「大丈夫です、待合室で七時半にお待ちしています、芽室駅をでて右側をまっすぐ三分ほど行った十字路の角にあります」
「はい、よろしくお願いします」
場所は知っている。
次の日吉都は夕刻に芽室に行った。
薄青色のペンキでぬられた水野医院の戸を開けると中には誰もいなかった。スリッパに履き替えて待合室に行った。棚に北海道の木彫りの熊がならんでいる。細野美代が長いすに腰掛けていた。隣に白髪の老人が腰掛けていて吉都に柔和な目を向けた。
吉都は起立の格好をしてお辞儀をすると、「フリーライターの水野です」とちょっととまどって細野美代のほうに名刺をわたした。
吉都が老人を気にしながら椅子に腰掛けると、美代が「父の水野天昇です、私はしゃべるのがにがてで、誰か一緒にいてもらわないと話しができません」
「水野です」
老人が名乗った。細野美代は医者の娘だったのだ。
「お手間とらせてしまい申し訳ありません、このインタビュウは今回の事件では犯人のおかしな言動があって、さぞご家族は困惑されていらっしゃるだろうと思って、お話をうかがおうということです。犯人がお嬢さんのお腹のなかにいるのは自分の子供だと思っている異常者であることが警察から発表されていますが、さぞ嫌な気持ちになられていると思います、お嬢さんから犯人の男の名前を聞いたことがありましたでしょうか」
「いいえ、全くありません、飯田さんと結婚をすると言ってきたときもびっくりしたくらい、男っ気のない娘だと思っていました」
会社では人気のある女性だったようだが、母親の男っ気が無いという言い方は気になる。そのようなこと言わなくてもいいのに。
水野医師も頷いている。祖父も本当はどう思っているのだろう。
「当たり前の質問ですが、犯人をどう思われました」
「おかしいだけです、お母さんという人も息子の言うことを真に受けてらっしゃったようですけど、マザコンではないでしょうか」
「美代、そんなこと言ってはいけないよ、早川さん、今のところは削ってくださいませんか」
吉都は「わかりました」首を縦に振った。
「佳代さんのお父さんも、お怒りこりになってらっしゃるでしょうね」
「もちろんです」
父親が答えた。
「今お住まいの家は、亡くなったお嬢さんが高校までおられたところですか」
「いえ、今いる家は父の家です、子供たちが育ったのは近くのアパートです、母が亡くなったものですから、私は今父の家にいます」
「ご主人にもお話が聞けるとよかったのですが、札幌だそうですね」
「ええ、友達の仕事を手伝っています」
「いるところがわからないようなことをおっしゃっていたと伺っていますが」
「ええ、いろいろな友人の手伝いをしているので場所が変わります、でも携帯がありますから」
「たまに帰ってきますよ」
水野医師が答えた。
薩摩刑事の話では父親は問題がありそうな男のような感じであった。
「先ほどお子さんたちがアパートで育ったとおっしゃいましたが、お子さんは佳代さんお一人ではなかったのですか」
この質問には父親が答えた。
「姉がおったんですが、亡くなりました、それも書かないでいただきたい」
「分かりました、書きません、お姉さんのお名前はなんとおっしゃったんですか、もちろんそれも書きません」
「小夜といいました」
やっぱり、加世の姉はテディじいさんの奥さんだった。だがなぜ亡くなったと言ったのだろうか。吉都は何かあると思った。
「佳世さんはとても魅力的な方だったようで、人気があったそうですね、他の週刊誌はそのことばかり書いていますね、支社にこられてすぐの方と結婚されたわけで、ご主人も魅力のある方だったのでしょうね」
「まじめな人で、結婚してよかったと思いましたよ」
父親が答えた。
「あの、わたしはインタビュウを依頼されただけで、記事になるかどうかわかりません。お時間とっていただいたのに記事にならなかったとお怒りになる方がおられるものですから」
「ああ、それはかまわんですよ」
「どうもありがとうございました、もし可能なら、ご主人にもお話を聞きたいのですが、電話番号教えていただけませんでしょうか」
「プライベートなもので、主人はいやがると思いますよ」
「そうですか」とあきらめようと思ったとき、驚いたことに父親が、
「教えてあげなさい、聞いてもらったほうがいいよ」
と言った。細野美代も驚いたようだ。
「そうですか」
躊躇しながらも旦那の携帯を教えてくれた。
「ご主人にもうかがってみます、ありがとうございました」
吉都は丁寧にお辞儀をすると水野医院を後にした。不思議なインタビュウだった。なぜ父親と一緒でないとだめだったのか。父親が何か言いたいことがあったのではないだろうか。話すのが苦手ならインタビュウを断ればいい。いや電話をかけたとき最初はいやな様子だった、途中から変わったのは、そばにいた父親に言われたのではないだろうか。
帯広のホテルに戻ると、詐貸に電話を入れた。夕食を一緒にすることにした。
焼いた法華を食べながら吉都は詐貸にインタビュウの内容と雰囲気を話した。
「細野政夫の電話番号を聞きだしたのはすごいね、姉がテディじいさんの奥さんと言うこともはっきりした、それに医者の父親はなにか細野家族のことを訴えたいような様子だね」
「そうですね、僕もそう思いました。水野医院についてもう少し調べてみます」
「俺は札幌に移って、細野政夫とコンタクトをとってみるよ、野霧も札幌にいるし」
その日、野霧は若杉龍馬のところへ行っていた。小栗教会と孤児院のあった土地を買った人だ。もう九十近い老人だ。
「へ、あの教会のことね、小栗神父はいい人だったよ、戦後に捨てられたり、孤児になった子供の面倒見てたね、実はあの土地はうちのものだったんよ、わしの父親が神父と幼馴染でね、神父の育った家があったんだ。土地を貸していたわけだ。小栗さんはなぜかキリスト教徒になって修行でイギリスに行っちまった。親が住んでいたんだが、亡くなってしばらく空き家だったんだ。終戦直後、小栗さんが日本にもどってきて、自宅を壊して教会を建てるのにおやじは土地を無償で貸したんだ。
小栗神父さんは修行が終わるとイギリスで向こうの人と結婚をしたんだ。戦時中は日本人ということでちょっと苦労したようだよ、だけど神父さんだったし奥さんがイギリス人だったのでよかったようだ。日本が負けて日本で人々の役になりたいと奥さんも一緒に北海道戻ったんだ。奥さんも偉いよね。小栗さんは米軍との通訳もなさっていてこのあたりでもたすかったということだよ。
それでも小栗教会は面倒を見なきゃいけない子供が増えて、おやじも協力をして市が孤児院をつくったんだ。小栗神父夫妻が中心になって戦争孤児の世話をしていたよ。イギリス人の奥さんも親切な人だった。キリスト教ってこういうもんなんだと思ったよ、神社にしろ寺にしろこんなに動いてくれなかったからのう」
「でもどうして市の土地になったのですか」
「小栗神父の奥さんがイギリスに帰らなければならなくなって、それでも五年ほどいたんだろうな、教会も孤児院も閉鎖になった、その後何年もそのままだったんだが、市の職員も様変わりして、市の土地が市の建てた孤児院と隣接していたんで、間違えて市の土地の中に入れちまったんだと思うよ。他の土地と一緒にあの辺りが売りに出され、そこにうちの土地が入っていたんでおやじは大慌て、権利書があったんで持っていったら、市は大謝りで戻してくれたんよ」
「向こうの農家さんが若杉さんが買ったと言ったものだから」
「その頃、周りの連中は買ったと思っていたんだろうな」
「それで孤児の人はどうなったんです」
「小栗さんがイギリスに戻る頃には、面倒を見ている子供も少なくなっていてな、働き手になるんでほとんどの子は農家に引き取られて、みんななんとか生きることができるようになったんだよ、北海道は農業でもっとるから人手が必要だからな。
ただ、教会ができたときまだ乳飲み子だった一人の男の子がそのころ5歳くらいで、奥さんもかわいがっていてな、自分の子供としてイギリスに連れて行った」
「その子はどこの子だったんですか」
「わからんな、だが連れて帰るのにパスポートが必要じゃろ、小栗神父さんが自分の日本の籍にいれたんじゃなかろうかな」
「どんな子でした」
「イギリスに行く時、おれが十七くらいのときだったが、あの子は五歳くらいで、奥さんの後をちょこちょこくっついていたのを覚えとる。どんな顔をしていたかおぼえておらんな」
「この辺にそのような歴史があったのですね」
「何かに書き残されるといいですよ」
「そうだねえ、うちの奴らはあまり興味もっとらんで」
「市の人に言っときます」
若杉龍馬は頷いた。
「ありがとうございました」
野霧は真駒内の駅に戻った。
札幌につくと、姉のところによって、夕飯をごちそうになり、ホテルに戻った。PCに今日の話をまとめてみると、若杉さんの話してくれた教会の少年がテディじいさんに違いないと思うようになった。
それを二人に送ると、その後すぐに細野美代と水野医院のことが送られてきた。
そこに電話が鳴った。
「詐貸です、札幌にきている、テディじいさんの秘密がだんだん解き明かされてきたね」
「まだ直接の証拠はありませんけど」
「いや可能性は大きいよ」
「先生は細野政夫のことで札幌にいらっしたんですか」
「そう、これから電話しようと思っているんだ」
「もう九時ですよ」
「うん、なにやっているのか知らないけど、どうも胡散臭い、夜動くことをやっているんじゃないかと思ってね」
「気をつけてください」
「そんなに危ない男じゃないと思うよ、ともかくご苦労さま、おかげでいろいろわかってきた、それじゃ」
電話が切れた。
テレビをつけると、北海道のローカルニュースをやっていた。
野霧は一人なのにも関わらずあっと声あげた。
テディじいさんが時計台のところでテディベアーと一緒にいる。レポーターがインタビュウをしている。テロップに「北海道にもテディじいさん現る」とながれた。
二人にも連絡しようかと思ったが、きっと見るだろうと、とりあえずテレビを見ていた。
「お子さんになぜ熊さんを配るのですか」
「かわいいでしょう」
「はい」
「それだけですよ」
「テディおじいさんは、きっと子供たちの笑顔がみたいのです」
レポーターが言っている。
「北海道にも熊はいるよ」
男の子が言うと「はいあげる、北海道の熊の友達にしてやって」
じいさんはそう言ってその子に一つ渡した。
レポーターは「テディおじいさんは明日も北海道のどこかに現れます。みなさん楽しみにしてください」と締めくくった。
テディおじいさんもう北海道に来たんだ。いつかは行きたいと言っていたのになぜだろう。私たちが北海道に来たのを知っているのかしら。目的は熊を配るだけじゃないわね。
テレビは天気予報になっていた。札幌は明日も晴れる。
詐貸は教わった細野の携帯電話にかけてみた。相手はすぐにでた。
「わたし、週間毎朝の後藤です、細野政夫さんでしょうか、お嬢さんがお亡くなりになり、お悔やみ申し上げます。犯人に対していろいろな思いがおありだと思いますが、お話を聞かせていただきたいと思いまして」
「そりゃあ、あるけどね、わたしも働かないと食っていけないから、なかなか昼間会えなくてね、友達の手伝いしてんだ、今ならここに来てくれりゃあ、話を聞いてもいいけどね」
「はい、どちらに行けばいいでしょうか」
「すすきのよ、すすきのの交番の前にきたら、また電話くれよ、そしたら友達のところで話を聞くよ」
「今いいのでしょうか」
「札幌にいるなら近いだろう」
「わかりました、すすきのなら近くです、交番の前で電話した後、スマホを見ています」
「わかった、後藤さんだね、声をかけるよ」
話はかなりぞんざいである。すすきのでどのようなところに連れて行かれるのか、現金が必要だろう。地下鉄にいく途中のコンビニで金おろした。
交番の前で電話をかけ、スマホをながめていると、五分ほどして中肉中背で目立たない灰色っぽい作業服をきた男が「後藤さんかね」と声をかけてきた。「はい、細野さんですか」と詐貸が返事をすると、「ああ、友達のところでちょっと飲んでくれれば、なんでも話してやるよ」と言って、後をついてこいという仕草をした。もう酒がはいっているようだ。
詐貸がついて行くと細い道に入った。細野はいくつか並ぶ店の中のムーランと書かれた紫色の電気がついている店の戸を押し開けた。
「お客さんつれてきたぜ」
カウンターでは女の子が一人の客と飲んでいる。奥からマダムらしき女性がけばけばしいチャイドレスを着てあらわれた。
「まさやん、お客さん連れてきてくれたの、彼もうすぐくるから」
「いや、このお客さんと話があるから、あっちの離れた席にいくぜ、いい酒頼むぜ」
何もいわないのにロイヤルサルートがでてきた。氷とロックグラスが用意されている。ピーナッツが小皿に少しばかりのっている。
「いただきますよ」
細野は自分のグラスに氷を入れて酒を注いだ。
「水もくれよ」
「ごめんわすれた」
ママが北海道大雪の水と書かれたボトルとコップをおいた。
「記者さん飲めるんでしょ」
「ええ」
「それじゃ作ってあげますよ」
細野は詐貸のグラスに氷を入れ酒をそそいだ。
「それじゃ、乾杯といきましょうや」
彼がグラスを差し出したので詐貸もかちんとグラスを当て一口飲んだ。サントリーの角だ。サントリーの角そのものは好きだが、ロイヤルサルートの瓶にいれてだしている。
「それでなにを聞きたいの」
「佳代さんがなくなられて、犯人に対する憤りのお気持ちをお聞きしようと思いまして」
「うちのには会ったのだろう、あいつおいおい泣いて、俺だって娘が死んだんだ悲しいよ、あんな変態やろうに殺されちまって」
「どのようなお子さんでした」
「いい子でな、美人だしよ、それなのに、きたばっかの男と結婚しちまって、社長の息子ならあんなことにならなかったのにな」
「どうしてですか」
「だってそうだろう、あの犯人はそれならあきらめるだろう、それなのに入ったばかりのやつにかっさらわれたから、ああなっちまったんだろう」
「はあ、そういうことになりますか」
この男は娘が死んだのになにも感じてない。
そこへ店主らしい男がはいってきた。
「あんた、まさやんきているよ」ママが言った。
男が細野を見た。
「おー、金儲けの話か」
「ちがうちがう、週刊誌の記者だ」
「おっと、いけねえ、いや、ごゆっくり」
そのとたん細野の態度が変わった。
「週刊誌ってのはとびきり面白いことを教えてやると、金くれるんかい」
「はあ、場合には特ダネにお金が動くこともあります」
「俺は職がなくてね、たまにうちに帰って、女房に小遣いもらってるんだがな、もっとまとまった金がほしくてね」
「どのような特ダネでしょう」
「あの変態やろうの犯人の言っていることが本当だったら特ダネか」
「そんな証拠があるのですか、でっちあげじゃ、うちの社がつぶれます」
「いくらぐらいになる」
「ちょっとわかりません」
「三百万くれりゃ、話してやるよ」
「ほんとだという証拠があって、大事なことなら」
「そりゃすごいことさ、警察も真っ青になってることだ」
細野は確かに三つ子のことを何か知っている。
「編集長に聞かないとお金はおりません、それによその社にも声をかけていたりしていないという証拠がないと」
「そりゃ大丈夫だ、俺たち両親しか知らないことがあるんだよ、あんた遺伝子検査って知ってるだろう、特ダネだよ」
「それはなんですか、娘さんのお腹の中の子供さんを助けられなかったって、警察では言っていましたが」
「それはそうだが、そこだよ、そんなに簡単なことじゃない、本当に知りたければ金だよ」
「犯人にたいする気持ちを聞いてくるように言われただけですので、今すぐ返事ができませんが、編集長に連絡して聞いてみます」
「ああ、いいよ、お宅がだめなら、別の週刊誌をあたるからよ、そろそろ金にしようと思ったところにあんたからの連絡だ、だからあんたが最初だぜ、特ダネだよ」
彼はくり返した。これは金を払ってもいいかもしれない。
「明日必ず、連絡します、それまで待ってください」
「ああ、いいよ」
「それじゃ、これからホテルに帰って編集長の自宅に電話をしてみます、しかし、会社に行ってからでないと、お金はだせません、あしたの午後になるかもしれません」
「いいよ、明日一日まつよ」
「奥さんは知っているのですか」
「さあ、どうかね、ここの金払ってくれよな」
「はい、おいくらです」
「まさやんの友達なら安くしときますよ」
マスターが「半額にしとけ」とママに声をかけた。
レジのところに行くとママが勘定書きを渡してくれた、三万五千円だった。三十分しかいない。だがもっとふっかけられるかと思っていた。いいほうかもしれない、払うと細野政夫が手を振っている。ここまでの男とは思っていなかった。医者の娘とどうして一緒になれたのだろう。それよりも吉都が言っていた細野美代の父親が電話番号を教えるように促したのはどういうことだろう。細野政夫の行状を我々に知ってもらいたかったのではないだろうか。
芽室に行って水野医師にもう一度会うべきかもしれない、三百万はどうするか、テディじいさんの前金があるから払えないことはない、払って話を聞いてから水野医師に会うのがいいだろう。
詐貸は二人に細野政夫のことを報告し、野霧にそういうことで一緒に飯が食えないと連絡した。
すると返事がきて、『わかりました、テディおじいさんが北海道にきてるとテレビでやってました、コンタクトとったほうがいいでしょうか』
なんだかまた複雑に絡んできたものがある。詐貸は何で今じいさんが北海道にきたんだと疑問に思ったが、細野政夫のことに頭がとられていてすぐには結論がでない。
『会う必要があると思ったら会ってくれ』と野霧にまるなげした。
吉都に明日夕方、こちらの用事が済んだらそっちに行くとメイルした。
三つ子遺体紛失の犯人
次の日、十時に細野政夫に電話を入れた。
「編集長が確かな情報なら出してもいいと言っておりました。警察の発表だけではわからないところが多い事件だとも言っていました」
「そうだろう、編集長はわかってるじゃないか」
「これからお金を持って行きますが、どこにいったらいいでしょうか」
「あの店じゃまずいのでな、札幌駅の切符売り場のところにいる」
詐貸は三百万用意すると、札幌駅に向かった。細野は野球帽をかぶって立っていた。詐貸に気がつくと「おーう」と手をあげてよってきた。
「このネタは絶対損をしないぜ、ただな出所は言わないでくれ」
「それではフィクションになって、世間から責められますよ」
「まあ、そこの茶店にはいってから話そう」
細野は駅をでて近くの喫茶店にはいった。
「俺は朝食っていないから」
そういって、コーヒー二つ、サンドイッチ一つと勝手に頼んだ。
「金はほんとにあるのか」
詐貸は上着のポケットから封筒を出して中を見せた。
「あああるな、あんた、腹の中にいたのが三つ子だというのは知ってるよな」
「はい、それで世間の人たちの憤りも大きいものでした」
「だからこれから話すことは特ダネになる」
「どういうことですか」
「その死んだ三つ子の死体がなくなった」
「どこからです」
「死体の安置室からだ」
「どうしてそんなこと知ってるんです」
「女房がやった」
「いつですか」
「安置室に女房と俺で顔を見に行ったんだ、そのときだ」
「それじゃ、そのとき盗んだんですか、今どこにあるんです」
「ない」
「それじゃ話になりません」
「金もらえないのかい」
「証拠がないと」
「実は女房が看護師なのは知ってるだろ、助産婦の資格も持っててな、女房が死体置き場で、三人の子供を娘の体にもどした、死体はな凍っていないんだな、冷たくしてあっただけだ、帝王切開をして縫った跡の糸をはさみで切って、開けて子供を押し込んだんだ」
「どうしてそんなことを」
「かみさんは娘といっしょに焼いてやりたいといっていたがな、本当はどうかな」
「それにしても証拠がない、この話を書くと警察からクレームがついて、これからやりにくくなります」
「三つ子が盗まれたことだけでも書きゃあいいだろ、面白い話だ、それにもし警察がそれを発表したらスクープになる、ところでよう、向こうの両親のところには行ったんだろう、むこうの両親に三つ子さんもお墓に一緒に入ったのか聞いてみな」
「確かにそういう手がありますね、そこまでおっしゃるなら後は調べますが、一人っ子の娘さんを亡くしてあまり悲しそうではないですね」
「そーだな、娘は俺になついてなくてな、つうか女房の奴が俺に触らせてくれなかったんよ、独り占めしたかったんだろう」
「結婚式にはお出になったんでしょう」
「父親がいなけりゃ形にならんからひっぱりだされただけよ」
「わかりました、二百万だけ払います、向こうの両親に話を聞いて、あなたの言うことに信憑性があれば、残りを払います、どうでしょう」
「記者さんうまいね、正しかったら残りをくれよな」
細野は意外とすぐに手を打ってきた。よほど金が欲しかったのだろう。このネタはがせではない。水野医院で確認をしてみよう。
詐貸は細野と別れてすぐに芽室に向かった。吉都に会って細野の言った話をした。
「それに、録音もしてある」
詐貸は小さなボイスレコーダーを見せた。
「だけど、子供の遺体を母親の遺体に戻すなど、一緒に葬りたいということだけでできますかね、他の理由がありそう」
「俺もそう思う、なんだろう」
「調べられたくないことがあった」
「でも遺伝子から両親の子供であると発表されていた」
「あの時点で奥さんの両親はそれが信じられなかった、だからもう一度調べられたくなかった」」
「そうだな、奥さんの母親にも調べてもらいたくないわけがあったわけか」
「先生、水野先生と直接話をしたらどうでしょう」
「俺もそう思って芽室に来た」
「このあいだも美代さんより、水野先生の方がよく話をしていました、先生は美代さんを助けようとしているのではないかと思います」
「水野先生が細野の電話も教えるように言ったしな、これから連絡してみよう、俺も本名で会ってみるよ」
詐貸は水野医院に電話をした。三人で情報を共有しているので、電話番号もすべてわかる。
「詐貸と申します、水野先生はいらっしゃるでしょうか」
「はい、今ちょうど患者さんを見終わるところですので、出られると思います、ちょっとお待ちください」
すぐに水野医師がでた、「水野です、どのような御用でしょう」
「初めて電話します、お忙しいところすみません、わたし東京の庚申塚探偵事務所をやっている詐貸と申します、いま帯広にいるのですが、じつは細野政夫さんという方から、奇妙なことを聞きまして、真意のほどを知りたいと思って電話しました、水野先生が義理のお父様であることは存じております」
ちょっと沈黙があった。
「目的はなんですか」
「マスコミとは関係ありません、三つ子の事件を調べてくれと頼まれている者です、水野医院にご迷惑はおかけしません」
「そうですか、七時に医院は終わります、その頃来ていただけますか」
「はい、ありがとうございます、それではよろしくお願いします」
電話を切った。
「会ってくれるそうだ、君はどうする」
「僕も芽室に行って、母親の方を見張っています」
「そうだね、もしかすると父親が一緒にと言うかもしれない、そうでないときは美代の尾行をたのむよ」
「はい」
六時半頃二人は芽室の駅にいた。
吉都は一足先に駅をでて、水野医院の見えるところに行った。さて見張っていようと思って医院を見ると白衣をぬいだ美代が出てきた。まだ七時二十分前である。美代は自宅の方向に歩き出した。吉都はゆっくりと後をついて行った。水野医師は一人で話したかったのだろう。吉都はそのことを詐貸に電話した。
ついていくと、美代は自宅に入っていった。
そのころちょうど詐貸が水野医院の戸を開けて声をかけたところだった。
「詐貸です」
診察室の戸が開いて、水野医師がでてきた。年の頃七十四、五だろうか。
「お待ちしていました」
上に上がってスリッパを履いた詐貸は「よろしくお願いします」と名詞を渡した。
「診察室がいいでしょう」
二人は診察室で向きあった。
「細野はどんなことを言いましたか」
「三つ子の遺体は美代さんが母親、佳代さんのお腹にもどして、母親と一緒に火葬にされたと言っていました」
「それで、なぜあなたにそれを話したのですか」
「三つ子の遺体が紛失したこと、それを調べて欲しいとあるところから依頼されました、それで、一番関係のなさそうな佳代さんのご両親に当たってみることにした結果、細野さんのご主人にたどりついたわけです、そうしたら、三百万で特ダネを買えということでした」
「あなたも新聞記者とか言って細野に近づいたのですな」
「はいそうです」
「細野のいるところを知るものはいません、唯一、つい二、三日前に若いフリーライターと言う人がきて話を聞いていきましたよ、きっと細野とコンタクトをとるだろうと思って美代に携帯を教えさせました、そのうち何か話が持ち込まれると思ったら、あなたがいらっした、もしかするとお仲間ですか」
「すみませんでした、隠しても仕方ありません、うちの助手です、最初近藤という名前で娘さん、美代さんに電話を入れたのは私です。
それで細野政夫が話したことは本当のことでしょうか」
「はい、本当のことです」彼は表情を変えずに頷いた。
「美代は助産婦の資格もあり、私の病院に勤める前、卒業した病院でしばらく働いていました、帝王切開の手伝いは何人もしています、娘は器用で私より傷を縫うのは早くてうまい、本当はやらしてはいけないのですが」
「政夫は三つ子を母親に戻すのを手伝ったのですか」
「とても手伝える男ではありません、そのようなことをするのを反対したようです」
「美代さんはずい分タイプの違う男と結婚なさったんですね」
「政夫は美代の小学生の時からの同級生で、風邪を引いてよくただで治療してやりました、親がほっとくもので、ときどきうちで食事をさせたりもしたんです。今ではあいつの親はどこにいるのかも分かりません。
彼は高校を出てから農園でまじめに働いていてましてね、ときどき野菜などを持ってきてくれました。美代が看護師と助産婦の資格を取ってここで働きはじめてから、付き合うようになり、結婚する事になったんです、子供ができて、美代はここで働いていたので、幼稚園の送り迎えなど子供の面倒を政夫が見るようにり、あの男は暇があるとパチンコやゲームや飲み歩いたりするようになって仕事をしなくなりました。
美代の稼ぎをあてにするようになったんです、その頃私の病院も結構忙しくて美代の家のことを考えませんでした。それが間違いでした。それでも細野は娘をよく面倒を見ていたのです」
「イギリスに行った小夜さんと佳代さんの二人ですね」
それを聞いた水野医師は飛び上がらんほど驚いた。
「まさか長女のことを知っている人がいるとは思いませんでした、あの子はもういません、中学をでるといなくなり、捜索届けを出したのですが見つからずに、もう死んだと思うことにしています」
「政夫は娘たちをかわいがったのですね」
「そのように見えたのです、ある時、政夫がいやがっている小夜の体に触れているのを、家に忘れ物をとりに帰った美代が見たのです、その日小学校が休みの日でした、美代は激しく政夫を拒絶し、その日のうちに娘二人をアパートから私のうちに移し、政夫を近づけないようにしました、警察に言ったりすると孫娘たちが傷つきますし、政夫には月々の金はやるからそばによるなと言いました、政夫はしばらくアパートにいましたが、札幌に行ってしまいました。世間には札幌で職を得たことにしていました、それから月に何度か金をとりにくるだけになったのです。
小学生の時ずっと政夫にいやなことをされていたようで、中学生になった小夜は友達も作らず暗い性格になっていました。頭のいい子でしたけどね、ある日家からいなくなりました。中学になっても政夫が小夜を待ち伏せしたりしていたようです。
下の子はそういうことはなく育ってくれました。しかし恥をしのんで申しますと、高校生になると男出入りが激しくなりました。きれいな子でした、もてるだけでなく、本人が気の多い性格なのです、姉とは全く違いました。美代は堅すぎるくらいの子でした、小夜は美代に似たのでしょう、佳代は父親に似たようでした。あの政夫という男はどこがいいのかわからないのですが女にはもてましたね」
水野はそこで一息ついた。たまっていたものを一気に吐き出した感じだ。疲れた表情を見せた。
「しゃべりすぎですな詐貸さんも疲れたでしょう」
「いや大丈夫です、それで美代さんはどうして三つ子を佳代さんに戻したのですか」
「おはずかしいが、遺伝子を調べられると父親が違うと言われるかもしれないと思ったからです」
「あの犯人の言っていることが正しいと思われたのですか」
「いえ違います」
「ではどうしてですか」
「飯田さんとの結婚二ヶ月前に会社の人をうちに連れてきたことがあるのです、私も会いました、てっきりその人と結婚するのだと思っていました」
警察は三人の子供の遺伝子に関しては世間に話す気はない。詐貸は自分も黙っていようと思った。
「そのことを政夫さんには言ったのですか」
「美代が言ったそうです、その後細野はますます金をせびるようになりました」
「それで水野先生、私にすべてを話した理由はなんですか」
「向こうの両親が、美代に警察から三人の遺体が返されていないので、まだ葬式は出せないと言われたそうで、どうしたらいいか悩んでいるのです、詐貸さん、警察に美代の体の中にあると知らせる方法はないでしょうか、手紙、SNS、電話、どれを使ってもいつか出もとはわかってしまう」
政夫は三つ子がもう焼かれてしまったと言っていた。政夫はまだ葬式をしていないことを知らないのだ。
「確かにそうです、しかし、私があなたを強請るかもしれませんよ」
「大丈夫です、あなたから電話をもらったあと、詐貸探偵事務所について調べました。ホームページはありませんね、だけど、さがし、探偵と検索すると、詐貸探偵事務所とでてきて、感謝の記載や、詐貸さんの探偵のうまさをほめる記事、それに北京骨商の顧問弁護士もなさっているとでてきます、だから話をしたのです」
「冒険をなさったわけですね」
「冒険ほどではありませんでしたよ、まだあります三つ子の遺体がなくなって困っているのは、両親の親もそうですが、警察です、それを調べるように誰かに依頼できるのは警察です、しかもとびきり信用のできる人にです、探偵さんにはとかく警察官の知り合いがいるものです、お互い助かりますからね、と言うことは、詐貸さんに頼んだのは警察、ということかと思いました。それは信用できる人と言うことになります、警察に佳代の遺体をもう一度調べたらいいと言ってください」
よく考えている人である。
「なるほど、おっしゃっていることはわかりました、少なくとも、私どもは水野先生とご家族の名前は出しません、ご安心ください」
「やっぱりそう言ってくださいましたな、ありがとうございます」
「また伺うことがあるかもかと思いますが、そのときはよろしくお願いします、私のほうからのお願いがあります小夜さんの若い頃の写真はありますか」
「みんなで食事をしたときの写真があります、中学卒業間際です」
水野医師は診察室から出ると、写真帖を持ってきた。小夜と佳代、美代に水野夫妻が写っていた。政夫はいなかった。
「政夫さんの写真はありませんか」
「若い頃のなら、美代と結婚した時の写真があります」
と写真帖の別のページを開いた。
「写真を撮らしていただいていいですか」
「はい、なぜ小夜に興味がおありなのですか、この事件に関係あるとでも」
「いえ、この事件とは直接関係はありません、私が依頼されたことに関係がありそうなので、まだ分かりませんので詳細がはっきりしてきたらお話しします」
「小夜はどうしてしまったか、生きているかもしれませんし、もし詐貸さんが探してくださるなら心強いですね、私が依頼者になって、お願いできますか」
詐貸はスマホでその写真を撮った。
「いまお引き受けできませんが頭の隅にとどめておきます」
水野医師はすべてをさらけ出してくれた。いずれ小夜のことも伝えることができるだろう。だけど小夜も死んでしまっている。詐貸は複雑な気持ちをいだいて水野医院をあとにした。
病院を出るとすぐに駅に向かい吉都にメイルを入れた。
細野美代を張っていた吉都は追いかけてきて駅でおちあった。
「美代は家にはいったままでした」
「水野医師からすべての話を聞いたよ」
吉都にその様子を話した。吉都は驚きの表情を隠せない。
「本当に自分の娘の遺体に子供を戻したんですね、よくそんなことができるな」
「うーん、この話、野霧君には直接話したほうがいいな」
「はい」
「もうしばらくは芽室に来ないな、君も札幌に行ったほうがいい」
「全員集合ですね」
帯広に行く電車の中で、野霧からメイルがスマホに入っていた。テディじいさんと会ったとあった、詳しいことはPCに送ったとある。
帯広の駅で二人はそれぞれのホテルに向かった。
詐貸は薩摩に電話をいれた。
「三つ子の件はどうなった」
「まだ見つからないんだ」
「ところで、亡くなった両親の葬式は終わったのか」
「いや夫の両親が三つ子も一緒にしてやらないとかわいそうだということで待っている、まだ警察を責めるようなそぶりはないが、早く見つけないと」
「今両親の遺体はどこにあるの」
「葬儀社の霊安室だ」
「安置所で母親の棺に入れたりはしなかっただろうね」
「もちろんだ、調べた」
「検視官が母親の体に戻したりしないかい」
「病院から別別にはこばれてきたから、そんなことをしないだろ」
「そうだよな、だけど死んだ母親のお腹を調べるのは無駄だろか」
「係りの者は別に保存していたと言っていたからそれはないだろう」
「でも、もう一度調べてみなよ、遺伝子検査の資料をもう一度とらせてくれとでも言ってさ」
「いやがるだろうな」
「可能性が一%でもあるならやったらどうだい、俺の勘だよ」
「全くお手上げ状態だから会議に出してみる」
彼は電話を切ると吉都に電話をして夕飯にさそった。
テディじいさんに北海道で会う
その日、野霧はホテルをでると、姉の家に行った。姉は専業主婦で、一番下の子が中学に入ったら昔やっていた絵の勉強をまた始めようとがんばっている。小学生の時は子供が学校から帰ってきたとき母親は家にいるべきだと考えている。野霧が姉ちゃん古いねと言うと、姉は人間の親離れ子離れを経済社会が壊していると社会の方を批判する。野霧は姉のように筋を通す人は尊敬している。庚申塚探偵事務所の二人も強い自分を持っているから好きだった。
「姉ちゃん、子供たちつれて散歩にでない」
「今日暇なの」
「時間があるのよ、町にでようよ、私がお昼ごちそうするから」
「あら、探偵ってお金があるのね」
「探偵探偵って言わないでよ、助手よ」
こうして三人の子供を連れて札幌の町に出た。子供たちは野霧のことを叔母さんといわない。お姉ちゃんという。野霧はそれが気に入っている。
時計台のところにくると、テディじいさんが大きな熊を隣に置いて、小さな熊を配っている。
「あら、今日も出てるのね、あの人、テディじいさんといって、熊の縫いぐるみをくれるわよ」
姉が三人の子供をじいさんの方に引き連れていった。じいさんの周りには親に連れられた子供たちがたむろしている。
姉の子供たちの順番が来て前の方に進んだ。
「はい、かわいがってね」
三人とももらったら、姉がありがとうございますとお礼を言った。
「いやいや」とじいさんが姉を見ると、隣にいた野霧に気がついた。
「ありゃりゃ、何でここにいるの、素甘のおじょうさん」
素甘になっちゃったと思いながら、
「こんにちわ、姉と子供たちです」
と野霧が挨拶をすると、
「ちょっとまっててね、配っちゃうからさ」とじいさんは子供たちに熊をわたした。
野霧が後ろに下がったら、姉が「知ってる人だったの」と驚いたように言った。
「うん、素甘の好きなおじいさん」
「探偵事務所に関係ある人なの」
「うん、ちょっとね」
じいさんが配り終えたようで、子供たちが離れていった。
じいさんが大きな縫いぐるみをかかえて野霧のところへきた。
「逢手さんはお姉さんが北海道にいたんじゃな、初めまして、テディじじいです」
「姉の今井野実です」
「逢手さんにはお世話になってます、どうじゃろ、その辺でなんか食べましょうや」
「そうですね、お姉ちゃん、いいでしょ」
「もちろんよ、近くにアイスクリームのおいしいところがありますが」
「そこに行きましょうや、逢手さんの好物じゃ」
じいさんは大きなテディベアーを抱えて歩き出した。
「重いでしょう、私がもちましょうょうか」と野霧が手を出したが、
「いやだいじょうぶ」
と言いながらじいさんが石につまずいて、ちょっとよろとした。野霧が大きなテディベアーを支えた。中に大きなものが入っている。
「ずい分重いんですね」
「家内の大事なものでしたからな、平気ですわ」
じいさんは体を立て直した。
アイスクリーム屋で外の丸テーブルを囲んだ。
「何がおいしいですかな」
「シンプルなソフトクリームが好きですわ」
姉が言うと、「それにしよう、それ六つ」
じいさんが勝手に頼んだ。
「逢手さんは北海道生まれだったんですかな」
「いえ、東京です、姉が結婚してこちらに来たんです、小栗さんは札幌で育ったのですね、そこに行かれましたか」
「いやまだ、前も話したが、建物もとうの昔になくなっているからね、その中と、周りの野っぱらで遊んだ記憶しかないね」
「イギリスにはいつ頃渡られたのですか」
「五つぐらいのときですな、神父さんが養子にしてくれて、イギリスにつれて帰ってくれたんだ、向こうで教育を受け、経済の大学をでて、投資をはじめましてな」
「小さい頃から向こうで教育を受けたのに日本語がお上手ですね」
「おやじは日本人でしたからな、経済やるなら日本語が話せなければだめだよ、と言ってくれたのと、日本から私と一緒につれて帰った子供がいましてね、その子は私より小さくて生まれて半年ぐらいでしたね」
「その子供は女の子でしょう」
「うん、よくわかったね」
「三村さんがその子と小栗さんのお子さんなんですね」
「野霧さんは勘がいいね、その家内は養母、イギリス人ですが名前を付けてエリザベスといったんだ、日本人ですがね」
「お姉ちゃんはもっと勘がいいんですよ」
「お、すみません、二人ばかりで話をしていましたな」
「いいえ、面白く聞かせていただいていました」
「お姉ちゃんは、今は子育て、一段落したら、また絵を描くんですって」
「そりゃあいいですな、わしにはそういった素養がなくて、こんなふうになっちまった」
「小栗さんはイギリスの大投資家で、小さな国の予算くらいのお金を動かしていらっしゃるのよ」
「いや、おはずかしい、金などは人が作りだしたものでね、もっと趣気の深いものがいくらでもあるが、わしはわからんでな」
「すごいんですね、なぜ野霧がそんなにすごい人を知っているんでしょう」
「美味しい素甘をおしえてくれましてな」
「おいしいものを探すのも探偵の仕事なの」
姉の長男が野霧の顔を見た。
「あはは、そうよ、何でも探すの」
「小栗さんどちらにお泊まりです」
彼は高級なホテルの名前を言った。
「私は詐貸さんたちとお仕事できました」
「それじゃ、その合間のお楽しみですな、じゃましてすまんことです」
「とんでもありません、テディじいさん、あらごめんなさい、とお話できたと、みんなに自慢しちゃいます」
姉にしては珍しく喜んでいる。
そこに、「ここにいらっしゃいました」と言う声が聞こえた。
レポーターの女性がマイクを持っている。後ろにはカメラマンら数人がいる。
テディじいさんが野霧に小さな声で言った。
「今の内においきなさい、うるさくなるから、ここはわしにまかせて」
野霧はうなずいた。
「おねえちゃん、でよう」
野霧は皆を引き連れて立ち上がった。
「ごちそうになりました」
テディじいさんが頷いた。にこにこともうレポーターの方を向いている。
レポーターたちはじいさんを取り囲んだ。
「お姉ちゃん、離れたほうがいいよ、マイク向けられるよ」
「そうね、これからどうしよう」
「遊園地に行って、遊んで帰ろう、あの人たち札幌のローカルテレビのようだったから、夕方見てみるといいわ、たぶん遠くから撮っていたと思うからでるかもよ」
「あら、はずかしい」
今日こそは野霧と飯を食おう。そう思って詐貸は吉都と帯広の駅をでた。札幌では吉都と同じ宿をとり、野霧には夕方会おうと連絡をした。
野霧はやけにしゃれたクリーム色の膨らんだドレスを着てホテルのロビーに現れた。
「どうしたの、北海道で買ったの」
詐貸が驚いていると、
「ほほ、姉にもっと着るものに気を使いなさいと言われて、昨日姉に選んでもらったの」だと。
それを聞いて、吉都が横を向いて笑いをこらえた。
「なにさ」
「ぷーさん」
「熊のぷーさん、かわいいじゃない」野霧はなにを言われても気にしない。
「いや、よく似あってるよ」詐貸は冗談じゃなくそう思っている。
「昨日、姉と姉の子供とテディジーさんにアイスクリームをごちそうになりました」
「そう、それはよかった、北海道の目的はなんだろうね」
「わかりません、育った教会と孤児院はもうないことを知っていました」
「他になんか聞けた」
「ええ、三村さんのお母さん、おじいさんの奥さんも北海道から神父夫婦がイギリスに連れて行った赤ちゃんだそうです」
「そうなのか」
「もっと話したかったのですが、テレビ局がきてしまって、おじいさんが離れた方がいいよと言うので話しはそれで終りでした、あの大きなテディベアーに触ったのですが、固い大きなものが入っていました。そちらはずいぶん親展しましたね、まさか美代さんが三つ子を隠したとは思いませんでした」
「うん、それで薩摩に連絡して、それとなく奥さんの遺体調べるように言ったよ」
「これからどうしますか」
「テディじいさんの張り込みだな、彼が北海道にきた目的がわからない」
「どうします」
「野霧君はテディじいさんを見張っててくれるかな」
「はい、泊まっているホテルはわかっています」
「可也君は細野政夫を張ってほしい、あの友達の店、ムーランにいってくれないか、客として通ってれば細野が現れるよ、ちょっと飲んで五万だな、金がかかると思うが、これを使ってくれ、五十万ある、野霧君にもわたしとこうか」
野霧はくびを横に振った。二百万細野に渡したので百万残っている。
「そんなに高いのですか」
「半分暴力バーだな、金があれば大丈夫だ、大事にしてくれる」
その夕方はちょっと名のしれた店でジンギスカンを思うぞんぶん食べ飲んだ。
「俺は明日一度東京に戻る。雑用があると思うし、もう一度薩摩と話をしておくよ。明後日か明明後日にまた札幌に来る」
「三者連絡も続けますし、相談があったら電話します」
野霧がそう言って自分のホテルにもどった。詐貸たちもホテルに戻った、
「細野政夫は先生が送ってくれた若い頃の顔とどう変わってますか」
可也が詐貸に聞いた。
「そんなに変わっていないよ、目元を見ればすぐわかると思うよ」
「あしたの夜から、スナックバー、ムーランにいきます」
それぞれの部屋に分かれた。
東京に戻った詐貸は、たまっていた郵便物を整理し、自分が顧問をしている製薬会社、北京骨商に連絡をいれた。この一週間、特に問題はなかった。
薩摩に電話を入れた。
「どうなった」
「いや、驚いた、母親の遺体を調べたよ、極秘扱いだが詐貸さんが言っていたように、母親の腹の中にあったよ」
「子宮の中にかい」
「いや、腹腔内だった。腸に混じっていた、いったい誰がやったのかが問題だな、ところが上のお達しで、探すなということだ、きっと内部の誰かを探らなければならなくなるのが面倒なんだろう、夫の両親に見つかったことを伝えたよ、詳しく調べるため他の研究室の冷凍庫にあったと言った。葬儀社の人と明日とりにくることになっている、いや、ありがとう、おそらく数日中に葬式だろう」
「それはよかった、一つ教えてほしいんだ、小倉のことだよ、あの名の知られているテディじいさんとどういうつながりがあるんだろう」
「きちんと調べてはいないけど、時々何かを頼まれ、探って報告をしているようだ、ただの小物ではないな、警察の中のこともよく知っている、けっこう全国を飛び回っているしね」
「それはテディじいさんと関係あるのだろうか」
「どうだろう、この間のロッカー事件で初めて二人が関係あると知ったばかりだからな」
「警察の所長はどこの出身の人」
「北大だよ、珍しいんだが農学部出身だ」
また北海道だ。
「そういうキャリアでよく所長になれたな」
「とてもきれるからね、しかも部下思いだな」
「小倉は今、仙台の方にいるのかい」
「さあ、見張っているわけではないからな、調べとくよ、どうしてだい」
「ちょっとテディじいさんのことが気になってね、たのむね」
そこで電話を切った。
今度は三村美衣に電話を入れた。
「詐貸です、ご無沙汰しています、ブラジルの方に行かれるそうですね」
「まだ先ですけど」
「小栗さんが北海道にいらっしゃるのでびっくりしました」
「突然北海道にいくと言い出したので私も驚きました」
「野霧が北海道でアイスクリームをごちそうになったそうです」
「そうですの」
「私はいったん帰ってきたのですが、また明日北海道に飛ぶつもりです、三つ子の遺体が見つかったようです、母親と一緒にこれから葬られるようです」
「父にはそう伝えときます」
「私もお会いできたら直接話します、お預かりした一千万のうち二百万ほど使いました、あと百万ほど使うかもしれない」
「それは社長のお金で、会社とは関係ありません、ご自由にお使いください」
「ありがとうございます」
その夕方、薩摩から電話があった。
「小倉はここのところ家に帰っていないよ、俺があいつのマンション行ってきた、五日前からいないね」
「よくわかったね」
「探偵さんもやるんだろ、新聞受けにいつの日付の新聞が残っているか」
そうだった。
「それからね、所長はテディじいさん知ってるようだ。所長の実家が札幌の大きな農家で農協の幹部だ。小栗宙太朗が日本に戻ったとき、札幌の農協に連絡をしてきて、出資を申し出たそうだ。農場を近代化しようとしていたときで、大層な援助金をだしてくれたということだよ」
これでいろいろ繋がってきた。テディじいさんは宮城県警の所長や小倉から情報を得ている。
「いやありがとう」
「こちらこそ、三つ子を誰が母親に戻したか知りたいと思うけど、ともかくこっちの事件は解決だ。俺はほめられたよ、詐貸さんのおかげだよ」
「とんでもない、またこちらからお願いすることもあるからよろしく」
薩摩はさっぱりした声だ。だが我々はこれからだ。三つ子がみつかったことをじいさんに直接報告をした方がいいだろう。小倉は北海道に行っていろいろじいさんに教えているに違いない。
詐貸は野霧に電話をかけて、明日昼にテディじいさんに会う約束を取り付けてほしいことを連絡した。
水野医院にも電話を入れた。
「先生、すべて解決しました。三つ子さんのご遺体は、警察の科学研究室の小さな冷凍庫に詳しい解析をするため保管してあったということです。娘さんのご主人の両親の元に返されたとのことです、おそらく近々葬儀の件で連絡がいくと思います」
「詐貸さん、ありがとうございます、今日すでに向こうの両親から美代のほうに連絡がありました。細野には連絡しません、私が美代と一緒に葬式にでます、向こうには細野は具合が悪いといってあります、詐貸さんのおかげです、どのようにお礼をしてよいかわかりませんが、どのくらいお支払いしたらいいでしょうか」
「いりません、むしろ、私どもがそちらに伺ったこと、人には言わないでいただきたいのですが」
「わかりました、本当にありがとうございました」
その夜に吉都からメイルが入った。
『十二時までアムールにいましたが、細野は現れませんでした、ただ驚いたことに、十時頃、小野がきました。マスターと話していましたが一時間ほどいて帰りました』
『なにを話していたんだろうね』
『残念ながら、近くではなかったし、ママがしきりに話しかけるものだから、聞こえませんでした』
『きっと細野に会いたいんだ、そのうち現れる、俺は明日午前中に札幌に戻る、夜また頼むな、いくらとられた』
『一万五千円』
『あれ、ずいぶんやすいね』
『ママに一週間札幌に遊びに来たと言いました、女の子はママだけなんだと言ったら、明日若いバイトがくるわよ、明日きてくれるなら三分の一でいいわよと言われました、それで必ず行くと、スマホの電話番号をおしえました』
北海道で使ってるスマホは三人ともレンタルである。ただ仕事の内容に関してはいつものを使っている。
『それじゃたのむよ』
テディじいさんのおいたち
札幌のテディじいさんの泊まっているホテルで、詐貸と野霧はテディじいさんと食事をしていた。カニの寿司をほうばって野霧はご満悦である。
「逢手さんを見てると、寿司が倍も旨くなるなあ」
じいさんも箸を動かすのが早い。詐貸も同感である。
「詐貸さん、三つ子がみつかったようですな」
「やっぱりご存知でしたか、三つ子の遺体は警察の科学捜査の一つの研究室から見つかりました。そこの小さな冷凍庫に細かい検査のためにしまわれていたそうです、父親の両親のもとに返されました」
「ほう、そうですか、それはよかったですな、ほっとしました、だが、不思議ですな、警察はずさんですな」
テディじいさん、顔はにこやかだが目は喜んでいない。詐貸は本当のことを言うべきだとそのとき思った。
詐貸はスマホを取り出して写真を呼び出した。
「小栗さん、もしかすると、この写真をごらんになったことがありませんか」
詐貸はスマホをじいさんの、前に差し出した。
じいさんは写真を見て珍しく目を見張った。詐貸を見た。彼は上着の内ポケットから、薄い皮の手帳を取り出すと開いた。それは手帳ではなく写真入れだった。片面に奥さんと自分の写真、片面には古びたカラーの写真があった。
「これは死んだ家内が持っていた唯一の日本での写真でな、それと同じですな」
「佳代さんのおじいさん、美代さんの父親の水野医師の持っていたものです」
「さすが詐貸さんだ、殺されたのが家内の妹であることを知っておられたのですな」
「美衣さんが被害者の佳代さんの写真を見て、小栗さんの奥さんに似ていると気が着いたことから何かありそうだと思っていたのです」
「うーむ」
「本当のことを言います。佳代さんのお母さん、美代さんは看護師さんで助産師さんですが、警察の安置室で、すばやく三つ子のご遺体を母親のからだの中にもどしたのです、水野先生が話してくださいました、佳代さんは母のおなかに戻してやりたかったんだそうです、そのことは誰にも言わない約束をしました」
じいさんは顔色も変えずにうなずいた。小倉が芽室のことはすべて調べてじいさんに報告しているのだろう。
「美代さんと水野先生は小夜さんのことをずいぶん探したそうです、今は死亡したと思うことにしていると、悲しそうでした」
じいさんはまた頷いた。
「いや、そこまでよくわかりましたな、さすがです、ありがとうございました、わしも正直に言わんといけませんな、詐貸さんは承知していることと思いますが、宮城県警の所長に無理言っていろいろ教えてもらいました、だが美代さんが佳代さんの体に三人の子供を戻すなど考えてもみせんでしたな」
野霧はカニ寿司を食べ終わって二人の話を聞いていた。
「あ、すまんことです、もう一つとりましょうかな」
野霧がお茶を飲んでいるのに気が付いたじいさんがいった。
「いいんですか、それじゃ今度はカニ味噌のにぎりを」
「おお、それもうまいですぞ」
遠慮のないのが野霧だ。
じいさんは嬉しそうにカニ味噌にぎりを三つ頼んだ。
「詐貸さん、こんなにはやく解決するとは思わなかったです」
いやまだ自分にはテディじいさんの目的がわかっていない。詐貸そう思った。
「小栗さんはこれからどうなさるのです」
「実はもう一つ知りたいことがありましてな」
「それはなんでしょう」
「私の前の妻のことでな、日本人で私と一緒にイギリスに渡ったのですが、北海道で生まれたことはわかってます、生まれてすぐに捨てられていて、くるまれていた布があるだけなにもわかりません、調べたいのじゃが」
「はい」
「生まれて三から六ヶ月ぐらいだったんだろうと思いますな、わしと五歳も違わない、生きていれば67か8でしょうな」
「どうやって探したらいいんでしょう」
「包まれていた布はとってあります、ずいぶん上等な布でした、実は美衣は母親が付けた名前で、自分の包まれていた布がきれいだったので、娘を美衣にしたのです」
「手がかりは、その布だけですか、難しいですね」
「私にやらせてください、布はあるのですか」
野霧が身を乗り出した
「美衣がもってます、写真もとってあるので逢手さんのスマホに送らせましょう、すみませんな」
「カニおいしかったから、何でもやります」
じいさんも詐貸も笑った。
その夜、詐貸は吉都からの連絡をまった。一時を過ぎてもない。こちらから連絡を入れるのは控えておいたほうがいい。なにもなければいいがとちょっと気になってきて、ホテルから出るとタクシーを拾った。ムーランはまだやっていた。
詐貸は迷うことなく店に入った。
「おー、記者さんなんのようだい、あと百万くれるのか」
細野が機嫌よく飲んで酔っぱらっていた。吉都はいない。
「あら、こないだの、よく来てくれたわね、またまさやんに話なの」
「いや、ちょっと近くに来たんでね、ママの顔を見にきたんだ」
「あら、うれしい」
「まさやん、きょうはご機嫌よ、やっぱり新聞記者のような人がきて、長い間話してたの」
「おれは大金持ちだ、百万ぽっちいらんよ」
細野はかなり酔っ払っている。後は誰もいない。
「今まで若い観光客がいたんだけど、細野さんのお客さんが帰るとき、今日バイトにきた若い子連れ出しちゃってね、IT企業の社長みたい、能力あるとあんなに若くても社長になれるのね、またくるって」
そこに若いミニスカートの女の子が入ってきた。
「もう帰ってきたの」
「うん、あいつタクシー捕まえて、運ちゃんに小さな声でなにか言ってたわ、変なとこに連れて行かれるのやだと思ってたら、あの豪華なホテルじゃない、とても普通の人じゃ高くて泊まれないとこ、ロビーで待ってろって言うから、腰掛けていたら、彼はフロントにいって係の人としゃべっていて、エレベーターのところで何かを見てたようだけど、戻ってきて
「やっぱりだめだあ、かみさんがもどってら」
そう言うと、5万円くれて、また行くよっていうから、帰ってきた。別のホテルにいきゃあいいものをさあ、でもあの豪華なホテルの部屋みたかったな」
「また来るからいいじゃない」
「そのとき呼んでね、私帰る」
女の子はそう言うと出て行った。
「景気のいい人がいるねえ、うらやましい」
吉都は小倉を追って行ったに違いない、テディじいさんのホテルだろう。
細野がおとなしいと見ると口を開けて寝ていた。
「そいじゃ、俺も帰ろう、また来るから、そうだ、まさやんはどこに住んでるの」
「わかんないのよ、マスターなら知っているかもしれないけど今日は休み」
「いくらかな」
「三千円でいいわ、またきてね」
詐貸はホテルに戻った。
明くる朝、メイルを開いたが吉都からは連絡がない。夜通し張り込んでいたのだろうか。まだ寝ているのかもしれない。今までのことをまとめて二人にメイルを送った。
野霧からは簾舞にテディおじいさんの前の奥さんのことを聞きに行きますとあった。
詐貸自身は動きがとれない状態でホテルにいた。吉都はどこに行ったのか。
その日の昼過ぎである。吉都から電話が入った。
「先生すみません、今、芽室にいます、昨日アムールに小倉がきて、後をつけたら、テディじいさんのところに行きました。そのあと、札幌駅の近くのホテルに入ったので、彼の部屋の番号を確認して、そのホテルに泊まったのですが、アムールでずいぶん飲まされたので寝ちゃいまして、気がついたら七時でした。あわてて、チェックアウトして、ロビーの椅子に腰掛けていたら、八時過ぎに小倉がロビーに降りてきたので後をついていったら札幌駅に行きました。彼は待合室でしばらく腰掛けていると細野がきました。その後二人で改札を通ったので僕も入りました」
「切符はどうしたの」
「北海道一週間の切符をかっておいたので助かりました」
「さすがだね」
「それで、二人が降りたのは芽室でした。芽室では直接水野医院に行きました」
「小倉も一緒にかい」
「いえ、中に入ったのは細野だけでした、小倉は外で待っていました」
「しばらくすると、出てきて、二人で市役所に行き、その後駅にきましたので、このまま追いかけます、電車を待っているようですが、札幌ではなく根室方向の電車に乗るようです、さっき札幌方面にいく電車がきましたが乗りませんでした、駅舎の外で電話しています」
「二人してどこに行くのかな、小倉はプロだから気づかれないようにね」
「はい、僕も変身は得意です」
詐貸はちょっと安心した。
その日、野霧は簾舞にいた。テディじいさんが育った教会と孤児院のあったところだ。土地の所有者の若杉さんに会うためにタクシーに乗っている。テディじいさんの最初の奥さんについて聞くためである。
「若杉さん、またきました、教えてくださったこと大変役に立ちました。ありがとうございました」
「少しゃ役に立ったかね、そりゃよかった」
「小栗さんが養子にした男の子が、イギリスで有名な人になっていました」
「なんと、そりゃあすごい」
「若杉さんテレビ見ますか」
「大河ドラマとニュースくらいだがな」
「テディじいさん知ってますか」
「オー、知っとりますよ、大きな熊つれてオートバイのって、子供に熊の人形くばっとるじいさんな、いま北海道にいる」
「そうなんです、イギリスで大金持ちになって日本に帰ってきたんです、本名は小栗宙太郎さん」
「あのじいさんが孤児院のぼおやか」
「そうなんです」
「驚いたもんじゃ」
「それで、小栗神父さんの養子になってイギリスに行ったとき、神父さん夫婦はまだ生まれて半年くらいの女の子もイギリスにつれて帰ったそうです」
「ほう」
「その子と宙太郎さんは結婚し、お嬢さんが一人いますが、奥さんはだいぶ前に亡くなりました、その奥さんのことが知りたいのだそうです、私が若杉さんに聞いてほしいと頼まれました」
「あのじいさんと知り合いかね」
「はい、仕事を依頼された方です」
「そうかね、その赤子の名前は」
「わかりません、きれいな布に裸のままくるまれて教会の前に置かれていたそうです」
「わしもまだ子供だったからな、それは聞いとらんな」
「これがその布だそうです」
野霧は美衣が送ってくれた布の写真をスマホで若杉さんにみせた。赤い椿と紫色の桔梗、白い夕顔、青い朝顔、桃色の芙蓉が配置された緑色が基調の布だ。
「きれな布じゃな、当時こんなきれいな布を持っていた家はないな」
「疎開かなんかできていた人じゃないかね」
隣で聞いていた息子さんの嫁さんがのぞいて言った。
「ここに疎開できたものはいなかったが、札幌の方にはいたかもしれんな」
「この人がテディおじいさんのお嬢さん、何カ国も話すことのできるすごい人です」
もう一枚美衣が布を広げて持っている写真をみせた。若杉さんの目が美衣にくぎづけになった。
「似とる、林の向こうに家があるだろう、井上さんていってな、昔は産婆さんをしておって、みなあそこで生まれとる。あの当時東京から若い女性が来ておってな、教会のあたりをよく散歩しておったな。子供心にきれいな人だと思っておった、よく似とるわ、名前はわからんな、井上さんに聞いてみたらええ」
「行ってみます、どこですか」
「外にでれば見えるから、教えますで」
嫁さんが言ってくれたので、若杉さんにお礼を言って出た。
「あそこですよ」
その家は最初、教会のことを聞きに入って、若杉さんを教えてくれた農家だった。野霧は歩いてその家に行った。
「こんにちわ」
またあのおばさんが出てきた。
「ここは井上さんのお宅ですか」
「ああ、こないだ来なすった人だな」
「ええ、あの時はありがとうございました、おかげさまで若杉さんに話しが聞けました」
「こんだあ、なんの用かね」
「若杉さんから、井上さんの家は産婆さんをやっていたとうかがいました。戦後すぐの頃、ここで若い女性が東京からきていたと言うことを聞きまして」
野霧は美衣が布を広げている写真をみせた。
「この布は赤ちゃんを包んでいたものです」
「家の祖母が産婆をやっていて、何人もここで子供を取り上げたようだが、確かに、事情があって東京からきて子供を産んで、半年ほどここにおった人がいたというのを聞いたことがある。祖母はもちろん義母ももういませんけどな、祖母が産婆をやっていた頃のものが蔵に入っているがいまはだせんな」
「あの、これはある人に頼まれたことなのですが、その奥さんがここで産まれた人かもしれません、ぜひみせていただきたいのですが」
「そりゃあいいですよ、用意できたら連絡しますよ」
野霧はレンタルスマホの番号を手書きした。探偵事務所の名詞をだした。
「探偵さんですか」
「はい、ある人の出生のことを調べるよう頼まれています、よろしくお願いします」
野霧は地下鉄の駅に戻った。
テディじいさんに電話した。
じいさんは午前中に熊の縫いぐるみを配ると、ホテルに戻っていることが多い。やっぱりすぐにでた。
嘘を言ってもしょうがないだろうと、野霧は今までのことを話した。
「ほう、さすが探偵事務所のおじょうさんだ、わしもあの教会や孤児院がなくなったことや、養子にしてくれた頃のことなどは育て親の小栗神父が教えてくれましたけどな、家内のことはまったくわかりませんでね、その井上さんの倉の中のものをわしも見たいがだめじゃろうか」
「いえ、電話があったらお教えします。一緒にいってかまわないと思います。むしろ向こうがびっくりして喜びます。若杉さんには小栗さんのことは言ってあります」
「そりゃ、北海道での楽しみが増えた。もっと長くいるかな」
「また電話します」
「たのむよ、素甘のお嬢さん」
「アイスクリームも好きです」
「今日暇だよ、アイスクリーム食べよう」
「いいんですか、今地下鉄ですから、ホテルに伺います」
「ああ、待ってますよ、電話ちょうだい」
野霧は札幌に着いたので電話を入れホテルに入った。またあのアイスクリーム屋にいくのかと思ってロビーのソファーに腰掛けると、フロントの人がよってきた。
「小栗様から21階の8号室にきてくださいという言付けです」
どうしたんだろう、とちょっと心配になって、エレベーターに乗った。
戸をたたくと、どうぞと声が聞こえたので中に入って驚いた。丸いテーブルの上に、いろいろなアイスクリームが入っているガラスのケースがおいてある。一つの椅子に大きなテディベアーがいる。
「野霧さん、こっち」
テディじいさんが空いている椅子を指し示した。
「さー食べましょうや、野霧さんどれがいい」
野霧さんと呼ばれてなんだかちょっと緊張してしまった。五角形の顔をしている。
「す、すごいアイスクリームですね、あの店に行くのかと思っていました」
「わしが町にでると、みなよってくる、ゆっくり食べたくてな」
たしかにそうだろう。
野霧もちょっと落ち着いていつもの餡まんの顔になった。
「このストロベリーいただいていいですか」
「どうぞどうぞ、わしゃ、まずただ白いやつから」
今までにないいい味である。
「北海道のミルクだぞ、ホテルのシェフに、大事な客が来るから、いちばん旨いの作れって言ったんだ」
野霧の丸い顔がもっと膨れた。とても嬉しいときだ。
「簾舞のことはおぼえていらっしゃらないのですか」
「ほとんどなくてな、周りはともかく自然だらけだったな」
「土地の所有者の若杉さんという九十ほどのおじいさんが、教会のあたりで、若い女の人が散歩しているのを見たと教えてくれました。その人が美衣さんの写真を見て似ていると言ったんです、それで、その女の人はおそらく産婆さんをやっていた井上さんのところに滞在していた人だろうと教えてくれました」
「若杉さんにもお礼をいわなければな」
「詐貸さんと、助手の、えーと吉都さんはどこにいるのかな」
「札幌でそれぞれの仕事をしていると思います、私は小栗さんの依頼を引き受けました」
「三つ子のことはもう分かったわけだし、今度は何をおいかけているのかな」
「水野先生の依頼について、考えているところだと思います」
「小夜のことだろうか、元気でいればすぐにでもわしが行って、イギリスでのことを詳しく話してもいいのだが、二人の孫娘の死を一度に知るのはつらいだろうなあ。もちろん母親だってもっとつらいだろうし、それでわしはどうしようか迷っていてな、詐貸さんがいい解決策を考えてくれているじゃろう」
「はい、そう思います、このアーモンドの入ったのおいしいです」
「おお、そうかね、わしも食べてみよう」
吉都は細野と小倉の後を追って電車に乗り込んだ。彼らは帯広でおりタクシーにのった。吉都もタクシーで後を追うと着いたところは帯広空港だった。二人は国内線ロビーにいったので行くのは東京、名古屋か長崎しかないだろう。二人は搭乗手続きをして中に入ってしまった。八割方東京にいくだろうと吉都は推測した。これ以上追いかけることもできない。札幌に戻ることにした。
その夕方、久しぶりに三人が詐貸の泊まっているホテルのロビーに集まった。
「二人ともごくろうさま、いろいろはっきりしたし、テディじいさんともかなりのところまで知っていることを共有できた。まだじいさんの最終目的はわからないが、野霧君の努力で前の奥さんのことがわかれば、ほぼ終りだろう、あとは吉都君がおいかけてくれてくれた小倉が東京に行ってなにをしているのか調べなきゃならんな、そこにテディじいさんがからんでいると思う」
「細野をつれて芽室にいったのは何をするためかしら」
「水野医院でなにを話し合ったのかということだよね」
「そうだな、水野さんに電話してみるよ」
詐貸がスマホを出した。
「詐貸ですが、水野先生をお願いします」
「あ、娘の美代です、お世話になっています、いろいろありがとうございました、すぐ父を呼びます」
「あ、詐貸さん、診察時間が終わったら連絡しようと思っていました」
「すみません、また後で電話します」
「あ、いや、今大丈夫です、実は細野が来まして」
「はい、うちのが追っていたので知っています」
「離婚届を持ってきました、金が入ったので、もう来ないと言っていました」
「どういう金か言っていましたか」
「いえ、外国に行って儲けるんだと言ってました」
「どこの国でしょうね」
「わかりません」
「そうでしたか、ともかくよかったです、小夜さんのことはわかったらまた連絡します」
「佳代の葬式には美代と私が出てきました、ともかく無事に終わりました、ありがとうございました」
詐貸は電話を切り、二人に今までのことをまとめて説明した。
「私は井上さんから連絡があったら、テディおじいさん連れて簾舞に行きます」
「うん、わかるといいね、またアイスクリームだよ」
吉都が笑った。今日じいさんの部屋で食べたアイスクリームのおいしかったことをすでに二人にメイルしてある。
「吉都は夜通しご苦労さんだった、明日はのんびりしてくれ」
「はい、ありがとうございます」
「これからなに食べる」
「またジンギスカンでもいいですよ」
吉都の希望で三人は前とは違う店にジンギスカンを食べにいった。
次の日、野霧に井上さんから電話がかかってきた。主人が蔵からおばあさんのものを出しておいてくれたので、見にきてくださいということだった。ご主人も今日はいるそうである。野霧は依頼人を連れていっていいか聞くと、かまわないと言うことで、テディじいさんに連絡した。ホテルに来てくれということである。
野霧がホテルに行き、フロントから着いたことを伝えてもらうと、ほどなくじいさんがエレベーターから降りてきた。
「待たせましたな」
じいさんが大きなテディベアーを背負い紐で赤ん坊のように背負っている。その格好で電車に乗ったら目立つなーと、さすがの野霧もぎょっとした。
だけどじいさんはそのままホテルの出口に向かった。ホテルのロビーの人がみんな見ている。野霧はうつむいて後ろをついて行った。
玄関をでると、オートバイがつけてあった。じいさんはゴーグルを着けヘルメットをかぶって車にまたがった。じいさんはオートバイで行くから私は地下鉄で行ってくれということかと思ったとき、じいさんが「ほらそこじゃ」とサイドカーを指さした。野霧の顔が五角形になった。驚いて緊張したのだ。何しろみんなが集まってきて様子を見ているのだ。野霧は姉が選んでくれた薄いクリーム色のふっくらしたドレスを着てきてしまった。サイドカーに乗ったら何て言われるだろう。
野霧は恐る恐るいつもはテディベアーが座るところに入った。
「ベルトがあるじゃろ」
野霧がベルトを締めるとテディベアーを背負ったじいさんがエンジンをかけた。みんなスマホのカメラを向けた。
「いくぞ」じいさんはオートバイを出発させた。
道にでると野霧も落ち着いてきた。顔が丸くなってきている。
木々に挟まれた道では「気持ちがいい」野霧が大きな声をあげた。餡まんの顔になっている。じいさんも笑っている。
こうして、井上さんの家に着いた。
井上夫婦がでてきてテディじいさんを見るとびっくりした。
野霧がおりて、小栗さんが依頼人で小栗教会の孤児院で育った人であることを説明した。
じいさんが背負っていたテディベアーをサイドカーに寝かすと井上夫婦に挨拶をした。
「まさかテディじいさんがここの生まれとは知りませんでした、どうぞ」
座敷に上がると、産婆の道具やら、使った布、それに取り上げた子供と親の名前と住所が書いてある記録帖などが広げてあった。
置いてある布の中に美衣の写真に写っているのとよく似たものがあった。
主人は母親が東京の知り合いに頼まれて、娘を預かったことを祖母から聞いたと話していたことがあるという。
「子供ができてしまい、本人は生みたいというので、祖母に頼み込んできて、ここに半年ほどいたということです、祖母が子供を取り上げて一月ほどでいつの間にかいなくなったと母は言っていました、東京に帰っていないということで、向こうの親からいろいろいわれて迷惑したということです」
「写真はありますか」
「その当時だからないですね」
じいさんは産婆の記録を開いた。イギリスに行った年はわかる。昭和二十五年だ。そこを開くと三人の名前があった。子供は女の子ばかりである。母親の名前と住所があった。二人は地元で一人は東京だ。
「これじゃ」
東京都と書かれていたのは西村菊子という名前の人である。子供の名前は書かれていない」
「きっとこれじゃ、これが家内の母親じゃ、これだけわかればいい」
「ここ写真とらせていただいていいですか」
野霧がきくと、「どうぞどうぞ、必要なら持ってってもらっても」
「いや、貴重な文献です、市の方にでも相談してください、きちんと保存すると、このあたりのお産婆さんの役割の重要性がわかると思います」
野霧は布とその記録帖の写真を撮った。
「そういうもんかね」
ここの主人はあまり興味がなさそうだ。
「お孫さんは何人いらっしゃるかね」
「三人います」
「これは、まずのお礼です」
じいさんは小さなテディ熊の縫いぐるみをだした。
「ああ、テレビで見ましたよ、これドイツ製で可愛くて人気があるそうですな、こりゃ孫たちは喜びます」
じいさんが記録帖をいつまでも眺めている。
「もしその西村菊子さんのことがもっとわかったら知らせます」
「その時は、庚申塚探偵事務所にお願いします」
野霧が言った。
じいさんは何度もお礼を言って、井上さんの家をでた。
「ありがたいことだ、野霧さんのおかげだ、自分の小さい時のことやエリザベスのことがわかってさっぱりしたわい、今度は若杉さんちによろうかの」
「はい、向こうに見える家です」
じいさんはマミーを背負いバイクにまたがった。野霧はサイドカーに乗り込んだ。もう楽しくなってきた。
若杉さんのところでは、じいさんはマミーを背負ったままだった。
こんちわと声をかけると若杉自身が出てきた。庭での立ち話だ。
「おお、テディじいさん、よくきてくれたな、まさかあの洟垂れがこんなに有名になるとはな」
じいさんも「小栗です、お世話になりました」と若杉さんの手を握った。
「いいや、うれしいね、まさかイギリスにいっちまった人と七十年ぶりに会えると思わなかったね、えらくなって苦労なさったんじゃろうね」
「いや、いや、いい里親に恵まれました、五歳の儂を見たことのある人がいるとは思いもしませんでした、よく覚えていてくださった、それだけじゃないですわ、娘の写真を見て似た女性が井上さんちにきていたことを逢手さんに言いなすったことから、娘の母親、わしの家内のことがわかりました、家内の母親の名前は西村菊子といったそうです」
「そうじゃったか、あの女の人は菊子さんといったですか、よかったなあ、子供心にきれいな人だと思っとったですよ、どうぞ中にお入りなされ」
「いや、これからすぐ札幌に戻って、そのことをわしの娘に伝えてやらなきゃなりません」
「ああ、そうだな、そんじゃ引き止めんが、また来てくだされや」
「ありがとうございました」
野霧の顔が丸く膨らんでいる。嬉しくてしょがない。探偵事務所に入って初めて自分で仕事をやりとげた気になっている。
野霧がサイドカーに乗ると。若杉さんがテディじいさんに、
「二つも熊を乗せて運転じゃ、重かろう、気をつけていきなされよ」
若杉さんもテディじいさんに負けないくらい口が悪い。
だけど風を顔に浴びて野霧の顔はにこにこしていた。
あっという間にホテルに着いた。
「逢手さんありがとね」
ホテルの玄関前で降りてじいさんと別れた。自分のホテルに戻って二人に報告しよう。野霧は勇んでホテルの部屋にもどるとPCとテレビを付けた。駅に近いホテルをとったのでみな近いところにいる。
テレビではローカルテレビのニュースをやっている。テディじいさんがテディベアーを背負ってオートバイをホテルの入り口につけたところだ。今自分がいたところだ。
レポーターが「テディじいさんがテディベアーを背負って帰ってきました、どこかで小熊をくばってきました。サイドカーから降りたのは女性でした。テディじいさんは熊がお好きなようです。プーさんかと思いました。かわいらしい女性です。降りると足早に離れていきました。ちょっとおじいさんにインタビュウしましょう」
野霧はちょっと三角の顔になった。余計なことを言うレポーターだ。
「あれはどなたですか」
「手伝ってくださった方でな」
「どうも小熊を配るお手伝いの人をたのんだようです、だからプーさんに頼んだのですね」
テディじいさんはぶすっとしてホテルに入ってしまった。
野霧は笑いながら詐貸と吉都に顛末をPCから報告した。
詐貸から『よくじいさんの奥さんをつきとめたね、プーさんたいしたもんだ』と返事がきた。
野霧の顔がひしゃたげたあと餡まんになった。詐貸先生もちょっと崩れたほうがいいのにね。
『サイドカー気持ちよかったかい』ときたので、
『サイコー、熊さんの気持ちになれました』
と答えておいた。
さらに『野霧君には後三日休暇をあげます。土日の振り替えとご褒美の一日、吉都君にも後三日をあげます、帰ってから経費清算をしてボーナス出します、それじゃご苦労さま』と書いてあった。
詐貸先生細かいね、法律家だもんね、姉の子供たちと遊んで帰ろう。
吉都からも『詐貸先生ありがとうございます。ぷーさんご苦労さまでした』とメイルがきた。
餡まん、素甘からぷーさんか、いずれにしてもあたしゃふっくらこ。熊のぷーさんはね、子供が持っていたテディベアをヒントにミルンが書いたお話なのよ、みんな知らないでしょう、野霧は誰に聞かせるわけでもなくそう言うと、椅子から立ちあがり膨らんだスカートをひらひらさせた。アイスクリーム食べにいこう。部屋を出た。
北海道での最後の仕事
詐貸が自分は明日帰るかどうするか考えていたところに、東京で使っているスマホがなった。テディじいさんからだ。
「詐貸さんかね」
「はい、野霧がお世話になりました」
「世話になったのはわしのほうですよ、わからないことがみんなわかっちまった、ありがとうございました、最後の相談をしたい、お呼びたてして申し訳ないが、時間があるなら今日ホテルの方にきてくださらんか」
「はい、私も気になっていることが一つあります」
「きっと同じことじゃろう、ホテルのレストランを七時に予約しときます」
「はい、うかがいます」
時間通りにフロントに行くとレストランの個室に案内された。
「あ、すみなせんな来ていただいて」
テディじいさんが待っていた。
「いえ、わたしも教えていただきたいことがあります」
「なにを飲みますかな」
「ビールをいただきます」
「私もそうしよう」
「料理は北海道の牛をたのみましたがいいですか」
「ええ、今日は一人だったので最後にステーキでもと思っていました」
「それはよかった、逢手さんや吉都さんどうされました」
「明日から休みをやりました、二人ともよくやってくれました」
「優秀な助手をお持ちだ、逢手さんはわしの子供の頃を見た人を探してくれ、その上、前の妻の母親の名前まで明らかにしてくれました、美衣に伝えましたがびっくりして喜んでおった」
「よかったです、相談というのはなんでしょうか」
「細野美代さんと水野さんのことですわ」
「小夜さんのことですね」
「そうなんです」
「吉都が美代さんと細野の動きを追いかけていてくれました。それで私も水野先生と正直に話すことができました」
「本当にいい助手をおもちだ、わしは水野さんと会うべきか悩んでおります」
「私も水野医師から小夜さんの行方を探してほしいと言われております」
「どうしましょうな」
「お会いください、私もいきます、芽室にはまだテディじいさんが現れていない、水野医院のわきで熊を配ってください」
じいさんの顔がぱっと明るくなってうなずいた。
詐貸はぐーっとビールを飲みほした。
「詐貸さんに相談してよかった」
じいさんもビールをぐいと飲み干した。
ステーキはこの上もなく旨かった。
「ビールが旨いわしももう一杯いただこう」
テディじいさんは、黙々とステーキを食べた。もう何も言うことがないということなのだろう。詐貸もゆっくりと肉を味わった。
デザート食べながら予定を話し合った。
テディじいさんは十一時頃から水野医院の脇で熊を配ることにした。
詐貸は配る熊は最初から持ってくるのかじいさんに聞いた。
「小さな町の時にはそうするが、今回のように大きなところに長く滞在する時には、使用人に頼むんだ」とじいさんは言った。きっと小倉だろう。
「なぜ、美衣さんに頼まないのです」と聞くと、「あいつには仕事のことだけ頼んでいます、熊を配るのはわしの遊びで、あいつの仕事のじゃまをしないようにしてます、将来わしの後を継ぐのはあいつです」と言った。
「もう我々が気付いているのはご存じだと思いますが、仙台の小倉とはどういう関係なんですか」
テディじいさんはやっぱり知っていたかという顔をして笑った。
「隠しておけませんな、そりゃあ、吉都さんが細野を追ってれば気がつきますな、しかし小倉がなぜわしと関係があるのかわかりましたかな」
「じつは、三つ子の事件で県警にいる同じサークルだった奴に引っ張り出され、その時仙台駅のロッカーこじ開け事件があってそれも頼まれました。防犯カメラに小倉がロッカーを開けるのが写っていました、張り込みをしていたら小倉が小栗さんのホテルにいったのを見ました」
「ああ、やっぱりあのときですか、小倉には気を付けろといったんですけどな、小倉が直接きたのはそのときが初めてです」
「吉都は北海道でも小倉が細野と飲んでいたバーから小栗さんのところに行ったのを確認しています」
「いや、庚申塚探偵事務所はすごいですな、小倉とは日本に帰ってきて、今の家を買うときに知り合ったのですわ。
家内と家を探しているとき、東京の名の知れた弁護士から軽井沢に古い由緒ある邸宅があるということを聞き、見に行きまして買う気になりました。ところが相談がまとまるというとき、小倉から電話があり、あれはおかしいからやめた方が言いといいましてな、そんなことはなかろうと、美衣をイギリスから呼びました。美衣には迷惑をかけたくなかったので自分たちでやろうとしていたのですが、私は経済は自信があるが法律はわからない。美衣ほど英国ばかりでなく外国の法律に詳しいのはいない、そうしたら、小倉の言うとおり、その家には別の持ち主がいました、東京の有名な弁護士もだまされていたのです」
「小倉はどうして小栗さんがその邸宅を買うのを知ったのですか」
「昔、小倉はある探偵事務所にいて、詐欺事件でそのグループを追いかけていたことがあったそうです。そのころは独立していまして、いろいろなところに情報網をもっていて家の購入者などにアドバイスをして稼いでいたようです、それでわしたちに連絡をくれたのです、そのあと葉山の家を見つけてくれたのも小倉です」
「優秀な人ですね」
「確かに優秀ですけどな、それだけの情報網を張るためだとも思うが、まともじゃないこともやっていますな、それでも便利なので普通の人ではできないことを頼んでいます、極悪のことはできない男で、あいつの希望は小さなスナックをもつことでしたよ」
「ショートケーキですね」
「あそこのママはおもしろそうだがな、わしは行ったことはない」
「占い師ですね」
「小倉は自分のことをよく知っている、詐貸さんを教えてくれたのは小倉なんですよ、あんなに優秀な探偵はいないって」
詐貸はちょっと驚いた。
「小倉が細野を東京につれていきましたがどうするのですか」
「それもご存知でしたか、そうか吉都さんが張っていたのですな、小夜はなぜ家から逃げ出したのか話してくれました、小夜が死んだとき、恨みを晴らしてやろうと思ったりしましたが、それより小夜と同じように苦しんでもらおうと考え、小倉に頼みました、まあわしも人間でしてな」
「まさか」
詐貸が想像したこととは違った。テディじいさんはうつむいて言った。
「一千万やりました、東京でカジノでの遊び方を教えるからマカオにいってやって稼げ、そのかわり絶対日本に戻るなと約束させました、小倉が監視しているでしょう」
「どういうことでしょう」
「素人がカジノにいけば一千万なんてあっという間になくなってしまいますよ、そうなるとあいつは一生マカオのカジノで掃除人でもやらされるでしょう」
「もうけるかもしれませんね」
「少しは可能性があるじゃろうね、じゃが小夜の眠る日本に戻れなければいいんじゃ」
「戻るのを防ぐのはできないでしょう」
「小倉の作った偽造パスポートを持たせた、名前も違っている。時間がたつとはっきりと偽造とわかるものだからマカオの国から出れない」
恐ろしいことを考えるものだ。
「細野にやった二百万円はねぎったものだそうだね、たいしたもんだ、細野が言っていたことを小倉から聞きましたよ」
詐貸は頭をかいた。じいさんが珈琲を頼んだ。
ホテルに帰ると、詐貸は水野医師の自宅に電話を入れ小夜さんのことがわかったので、明日十二時頃に会いたいことを伝えた。土曜日なので診療は午前中だろう。
次の日、詐貸は十一時半に芽室に着いた。すでに水野医院の脇では子供たちがずらっと並んでいる。テディじいさんが小熊を配っていた。
脇で見ているとじいさんが気がついた。
「詐貸さん早いね」そう言いながら子供たちに渡している。
「院長先生にうるさくてすんません」と言ったら、「私にももらえますかと言ったので二つ上げたよ」
「小児科もやってますからね、私が入って少し話したら、呼びますね」
「ああ、お願いします」
じいさんは熊を配りながら頭を下げた。
しばらく見ていると次から次へと子供も親も列の後に付く。
時計を見たらもうすぐ十二時である、詐貸は水の医院のドアを押して中に入った。患者はいなかった。
「詐貸です」と声をかけると。看護師さんが出てきた。なかなかの美人である。この人が水野先生の娘であり小夜と佳代の母である。詐貸は初めて会う。
「はじめまして、美代でございます、父が奥でお待ちしています」
診察室の奥の部屋は畳の間で、診療の合間に休みをとるところのようである。水野先生はテーブルの前であの写真を見ていた。脇に汚れた熊のぬいぐるみが置いてある。
「詐貸さん、わざわざありがとうございます、どなたかお連れになるとおっしゃっていませんでしたか」
「もうすぐ参ります」
「今日は表にテディじいさんが現れてびっくりしました、やっと芽室にも来てくれましたよ、いい人ですよ」
「そうですね、テディじいさんは若い奥さんをお産の時になくし、子供もだめだったのです、その奥さんはテディベアが好きで、大きい縫いぐるみを奥さんに買ったんです、マミーと名付けそばに置いてかわいがっていたそうです、亡くなって一年たちじいさんはサイドカーにテディベアを乗せて旅にでることにしたんだそうです。奥さんも旅が好きだったということです」
「ほー、あの方にはそんな悲しいことがあったのですか」
「そうですね、小栗さんといわれましてね、北海道の孤児院で育ち、小さいときに神父さんの養子になってイギリス行ったそうですよ」
「さすがに探偵さんはいろいろよくご存じだ」
「小夜さんのことを報告します」
「小夜さんは、ここを飛び出した後、東京に行って働き口を見つけたようです、お金になる仕事です、お金を貯めて偽造パスポートを買って英国に渡り、ウェイトレスなどをして暮らしていたようです、幸いとても奇特な人に助けられ、小夜さんはその人の家のメイドさんになり、その人に日本で実父から受けたことを洗いざらい話したそうです。その人は小夜さんを自分の養子にしようと申し出たところ、小夜さんから結婚してほしいと言われたそうです。年は40以上離れていたこともあり、その人には若くして亡くした奥さんとの一人娘もいたので、躊躇したそうですが、娘さんも小夜さんをよく知っていて、結婚を喜んでくれたそうです」
「それじゃ、小夜はイギリスにいるのですか」
「いえ、今その方をお呼びします」
二人が不思議そうな顔をしている。詐貸は医院のドアを開け小栗さんと声をかけた。じいさんは集まっている人に「ちょっと用があるからこの袋からみんな一つずつ持っていっておくれ」そう言うと、大きなテディベアーを抱え医院の中に入ってきた。
「向こうにいらっしゃいます」
じいさんは何もいわずに詐貸のあとについてきた。
じいさんが部屋の中にはいると、水野医師は気がついたようである。水野医師は怪訝な顔をしている美代さんに「小夜のご主人だろう」と言った。
美代さんは目を丸くしてテディじいさんを見た。
テディじいさんは二人の前に座ると頭を下げて言った。
「始めまして小栗宙太郎です、三年前小夜さんと結婚をし日本に戻り、葉山に居を構えました、小夜は子供ができて大喜びをしていたのですが出産の時に亡くなりました、子供もだめでした」
じいさんははいつくばるようにして頭をたれたまま声を絞り出した。涙をみせたくないのだろう。
「小夜はなぜ私に連絡してこなかったの」
美代さんが目に涙をためた。
じいさんが何か言おうとしたとき、水野医師が「細野が居るのに連絡したくないのはあたりまえだろ」小声で言った。
「すみません、わたしはそうするように言ったのですが強く拒まれました」
水野医師はうなずいている。じいさんがテディベアーの後ろのチャックを開け中から本を取りだし美代さんにわたした。それを開くと美代は「お父さん、小夜の写真よ」と水野にも見せた。
小夜が十八から二十五で結婚するまでの間の写真帖だった。
美代さんは娘二人の死を知らされたのだ。どのように悲しいのか、胸がどのくらい痛いのか詐貸にはわからなかった。
「その写真帳はさしあげます」
じいさんはその後だまってしまった。何を言ったらいいのかわからないようだった。じいさんの胸も痛すぎるのだ。
「小栗さん、ありがとうございました」
水野医師の声も震えていた。
「すみません」
じいさんは謝った。
「いえ、ありがとうございました」
美代さんも言った。
「この大きなテディベアは小夜さん好きだったので、小栗さんがドイツに特注したものだそうですよ、名前も小夜さんがつけて、マミーというんです、小栗さんはだからサイドカーに乗せて旅をしていたのです」
詐貸がいうと美代はしゃくりあげた。
「ありがとうございます、小夜は北海道の熊が好きで、ほらこのぬいぐるみ小夜に私が買ったものなんです」
写真の脇にあった汚れた熊のぬいぐるみを水野医師が指差した。
「小栗さん、帰りましょう、今日は報告だけにして」
詐貸が声をかけた。
水野医師がはっと気がついたように言った。
「詐貸さん、ありがとうございました」
「細野政夫は日本には居なくなります、もうここには現われません」
「どうしたのです」
「小栗さんが小夜さんの恨みをはらしたですよ、それ以上のことは言えません、彼はどこかで生きていくでしょう」
詐貸はさらに「落ち着いたら、小栗さんとゆっくりお話しください」そう言って、じいさんの腕をとった。
水野医師が立ち上がって、じいさんの手を握った。
「いつか孫のこと聞かせてください」
じいさんは「近い内に」というと、テディベアー抱きかかえて病院の入口に向かった。
外に出るとおいてあった小熊はみななくなっていた。
「俺が運転します、小栗さんは熊さんもってサイドカーにのってください、ゴーグルとヘルメットを借ります」
じいさんは熊を抱き抱えてサイドカーにすわった。なんだかだらんとしている。緊張したんだろう。美代さんと水野医師が黙って見送っている。
詐貸はじいさんからキーを受け取ってエンジンをかけた。二人にお辞儀をすると車を出した。
「札幌まで何キロくらいでしょう」
「160キロほど」
「三時間ですね」
詐貸は若い頃1200ccのバイクに乗ったことがある。大学をやめてなにをしようかやけになっていた頃だ。そのころ免許をもっていた。
詐貸は十五年前を思い出していた。気持ちがいい。一つの仕事が終わったからでもある。
「そんなにとばすと捕まるよ、探偵さん」
テディじいさんは熊を強く抱きしめている。怖いんだ。
それで本当に二時間ちょっとでじいさんのホテルの入り口についた。
詐貸はゴーグルとヘルメットそれにキーをじいさんにわたすと「それではまた連絡します」とその場を急いで離れた。
ちょっと振り向くと、じいさんはなんだかよろけながらテディベアーを抱えてホテルに入っていくところだった。
喫茶店でアイスクリームを食べていた野霧は店のテレビで、ニュースを見ていた。はじめて芽室にテディじいさんが現れましたとアナウンサーが言っている。水野医院のわきで熊を配っているじいさんが映っていた。お昼頃そこのお医者さんの中に入って、出てきたらすぐに帰って行きました。とテディじいさんが熊を抱えてサイドカーに乗り込むところが映しだされた。じゃあ運転手はと見るとゴーグルをかけているが、明らかに詐貸先生だ。
野霧はおやっと思った。詐貸先生は車が運転できない、バイクの免許を持っているとは聞いたことがない。
吉都にニュースを見たかメイルをうった。
『見た、詐貸先生は無免許でオートバイとばしたんだ』
とかえってきた。おじいさん疲れたんだわ。詐貸先生らしい。女性にふられただけで大学やめる人だものね。野霧はまるい顔になってアイスクリームをもう一つたのんだ。まじめすぎて無鉄砲するんだ。
『テディおじいさんを助けたかったのよ』と吉都にメイルを打った。
西巣鴨の探偵事務所
東京にもどって一週間がすぎた。
仙台と北海道でのことは探偵事務所始まって依頼の本格的な仕事だった。
野霧も吉都も西巣鴨ののんびりした環境にもどってほっとしたところだ。
野霧が詐貸に北海道から何を買ってきたのか聞いた。
「コロボックルの人形」
「愛子さんにでしょう」
夢久愛子は大学のサークル仲間で今ミステリーの翻訳家である。自宅の棚にノールウェーから買ってきたトロールがずらりと並んでいる。芽室はコロボックルの発祥の地とされている。コロボックルもトロールの仲間だ。
仙台の薩摩から小倉が帰ってきていて、いつものようにスナックバーショートケイキを中心とした生活にもどっているという連絡を受けた。仙台にもまたいってみたいものだ。
北海道の水野先生からは丁寧な手紙をもらった。小夜の捜索費用のことを聞いてきたので、小栗さんからの依頼と重複することと、小栗さんに調査費はもらってあることから、いらないことを返事した。そうしたら北海道の大きな毛ガニと花咲ガニを十匹も送ってきた。すべて野霧と吉都にやった。
「愛子さんにもっていったら、あたし母と二人だから」
野霧が毛ガニと花咲ガニを一匹ずつ袋に入れて詐貸に渡した。詐貸はうんうんと頷きながら受け取った。
そんなとき、テディじいさんから〆をしたいから葉山に来ないかと誘いを受けた。野霧は一度素甘を届けに行ったことがあるが、詐貸も吉都も行ったことがない。
日曜日の昼に行くことにした。
「葉山は遠いね」逗子からのタクシーの中で詐貸が言った。
「だから海がきれいに保てるのでしょうね」
屋敷の門の前でタクシーが止まると、門が開いて、そのままお入りくださいと美衣の声がした。タクシーの運転手を促して中に入ってもらい、玄関前に止めてもらった。
「すごい屋敷ですね」タクシーの運転手が運賃を受け取りながら言った。
降りると三村が待っていた。
「向かいにいけなくてごめんなさい、遠くまでようこそいらっしゃいました、父が北海道でお世話になりました」
美衣についていくと、ホールの大きなテーブルにテディじいさんが腰掛けていた。詐貸が入っていくと、ちょっとよろっと立ち上がって、顔中にしわを寄せた。
「いらっしゃい、世話になりました」なんだか声がしゃがれている。
「どうされました」野霧が心配そうにたずねた。
「北海道から帰ったら疲れがどっと出たみたいですよ、話は詳しく聞きました、母のこともおかげでわかりました、ありがとうございました」
美衣がみんなに頭を下げた。
「さーすわってくださらんか」
じいさんの声が少し元気になってきた。
「今日はぶどう酒からいきますぞ」
赤ワインが注がれた。
「もちろん、アイスクリームもありますぞ、吉都さんはなにが好きかな」
いきなり聞かれた吉都がうろたえた。
「えーと、普段はいなり寿司」
「エー。可也ちゃんいなり寿司食べたっけ」
「うん、かっぱ巻きも」
「通だね、後で旨いの用意させますぞ」
テーブルには、チーズとハムソーセージが運ばれた。
「ところで詐貸さん、北海道の件はありがとうございました、経費は足りましたか」
「もう十二分で、最初にいただいたお金は残りをお返ししなければ」
「いや、あれは手付け金、お礼に明日少しばかり振理込むから、自由に使ってくだされや、お二人にもボーナスを」
詐貸はにが笑いをしてお礼を言った。二人にと言われると断れない。
「あれからまた北海道に行って水野さんと美代さんに会いましてな、美衣もつれていきました。小夜のことを話して来ました。それに簾舞の井上さんと若杉さんのところにも行ってきましてな、若杉さんは美衣が菊子とよう似てると喜んでくれました」
「よかったですね」
「ところで、美衣がそろそろブラジルにいきます、わしはのんびりここでマミーと暮らします」
「またオートバイで旅行ですか、サイドカーって気持ちがいいですね、テディベアーの気持ちが分かりました。顔に当たる風がすてき」
「そうですな、わしも芽室から詐貸さんに運転してもらって、サイドカーでくたっとなっていましたが、乗せてもらうのは気持ちのいいものですな、それにしても、詐貸さんは運転がうまいですな」
「詐貸先生、免許もっていましたっけ」
吉都がつっこんだ。
「いや今はないよ」
それを聞いてじいさんはびっくりして「無免許でしたか」とうなった。
「はあ、二十歳の頃は持っていました、千二百まで乗ったことがあります」
「実は詐貸さんおわかりになったと思うが、北海道から帰ったら足が萎えましてな、免許を返納しようかと思ってます、それであのサイドカーつきトライアンフを詐貸さんに差し上げようかと思ったのですがな」
今度は詐貸がびっくりした。
「イギリスから持ってきたものです、特注純正で、むこうでもちょっとばかり使いました」
「詐貸先生、もう一度免許をとりなおしたら」
野霧が三色アイスクリームを食べながら言った。まだメインデシュがきていないのにたのんだのだ。
「詐貸さん、逢手さんもそう言ってるし、使ってくださらんか」
「それじゃ、やってみます、吉都にもとらせて、庚申塚探偵事務所の公用車にします」
「それは嬉しいのう、逢手さんはとらないのかな」
じいさんに言われて、野霧の顔が八角形になっている。きょとんとしているのだ。あわてて「乗せてもらうほうがいいです」といって抹茶アイスを口に入れた。
そこに、美衣が母親が捨てられていた時の布をもってきた。古びているが新しいときにはずいぶんきらびやかだったろう。
「これと同じような布を織ってくださる人を捜してほしいのですがな」
じいさんが言った。
「時間がかかるかももしれませんが、探してみます」
野霧が引き受けることにした。
「わしゃ十枚ほしい」
じいさんが野霧にたのんだ。野霧は頷いた。
いくつかの魚料理と肉料理が同時に出てきた。野菜も大皿に盛られている。
「食べたいものをいってくだされ、彼らがとってくれますぞ」
給仕人が二人後ろに立っている。野霧がスープのようなものをたのんだ。
「これはハラーススープにございます」
「ハンガリーのクリスマスに食べる川魚の猟師料理でな」じいさんが説明してくれた。吉都はシシカバブーをとってもらっている。詐貸は鳥のトマト煮をさした。「これはハンガリーのパプリカチキンでございます」
ここでやっと美衣が食事に加わった。
「お飲物聞いてないのね」
「あ、いかん、好きな物言ってくだされ」
詐貸はビールを頼んだ。
「私がもうすぐブラジルに行くことは父が話したことと思います、なれた使用人がいますので大丈夫だと思いますが、何かあったらよろしくお願いします」
「はい、いつでも連絡ください」
詐貸がうなずいた。
「ブラジルでもお忙しいでしょう」
「ええ、でも子供もほしいと思いますし」
美衣はちょっとはにかんだ。
「父は足が弱っていますが、一時だろうと思っています、主治医が大学病院にいて、月一回は検診に行っています、幸い飲んでいる薬はビタミン剤のたぐいだけです。父と小夜さんの部屋は特別な作りになっていて、温度湿度は最適になっています、低くも高くもダイアル一つでできます。ベッドには自動的に体温や脈拍、脳波などを寝ている間に計る装置が付いていて、データが自動的に表示されますので、何かあれば使用人が病院に連絡をします」
「三村さんはたまには日本にお帰りになるのですか」
「最初はなかなか時間がとれないかもしれませんが、来年の小夜さんの会には必ず来ます」
食事をした後は三村さんの案内で、庭にでて砂浜であそんだ。野霧と吉都が子供のように波打ち際で波と遊んでいるのを見て、詐貸はつくづくうらやましく思った。
明くる日、事務所で振り込まれた額を見て詐貸は驚いた。二千万はいっていた。あの二人にいくらだそう。それもあるが、いったいどのくらい税金をとられるのだろう。
ところがその日に、三村から「今までのお礼です、使ってください」という手紙と供に、北海道でのテディじいさんの宿泊や食事の領収書が送られて来た。それが、我々三人と依頼主である小栗さんの四人分で八百万にもなる。宛先も庚申塚探偵事務所となっている。他にも飛行機代などの領収書があった。探偵事務所が立て替えたと小栗忠太郎の名前と印が押された手紙もあった。なにからなにまで考えられている。さらに二千万の小切手まであった。これには詐貸さんの報酬とある。ということは振り込まれた二千万は二人に還元しよう。ボーナス百万で、給料をしばらく月十万上乗せしてやろう。
その話をしたら二人とも信じられない顔をした。
一週間後にはサイドカー付きのオートバイがきた。さっそく詐貸は教習所に通い始めた。
半月後、三村からブラジルに行く挨拶がきた。ブラジルに行ってからもコンタクトをとりたいのでメイルしますと書いてあった。
野霧は頼まれた布と同じような絹の織物を作ってくれる美大出の若い女性をみつけ頼んだ。野霧は自分にも一つ作ってもらっていいか、じいさんに聞いたら、もちろんという返事をもらった。さらにその美大出の人の作品として売っていいとも言った。
野霧にその布に名前をつけてほしいとじいさんが頼んできた。
「詐貸先生、どうしましょう」
「美しい布に包まれていた女の子がヒントになるね」
「美しい布か衣か、とすると美衣さんの名前になる」と吉都がいった。
「絹織物は羅というけど」野霧もなかなか決めることができない。
「やっぱりテディおじいさんに決めてもらおう」
野霧は直接電話をいれた。
「おお、野霧さんか、どんな名前になったかな」
「それが、決まらないんです、こんな話をしています」
詐貸や吉都と話したことをじいさんに伝えた。
「そうかね、美しい絹織物の衣、美羅衣になるな、それにしよう」
「みらい、ですかそれはいいですね」
「それで、十枚といったが、ベッドカバーになるほどの大きさのものも二枚作ってもらってくれないかな」
「はいわかりました」
ということでその布は美羅衣という名前になった。
三ヶ月後、布をもって野霧は葉山のテディじいさんのところにいった。
じいさんはちょっとやせたようだが元気だ。
「おお、きれいにできましたな、エリザベスはこんなに明るい布にくるまれていたのですな」
じいさんは一メートル四方ほどの布を広げて喜んだ。赤子をくるむには調度いい大きさだ。後の二枚は大きなものだ。
「三色アイス作らせてありますぞ」
野霧はアイスクリームもだが特性サンドイッチも食べて、また来てくださいよと言われて赤い屋根の館をでた。
テディじいさんの秘密
その年の終わり、テディじいさんから詐貸に電話があった。元気そうな声だ。
「一人になって、ちょっとロンドンが恋しくなりましてな、半年ほどロンドンに行こうと思います、向こうのクリスマスもなつかしい、美衣には言ってあります、あいつは忙しそうじゃ、しばらくお会いできんが、来年には小夜の亡くなった日に会をします、またよろしく」
「いついくのです」
「あさってじゃ」
「お体に気をつけていってください」
「詐貸さんたちも活躍してくださいよ、野霧さん、吉都さんにもよろしく、いろいろ感謝してます」
ということだった。
「テディじいさんロンドンにいくんだって、野霧さん吉都さんによろしくだって」
「やっぱり育ったところはなつかしいですよね」
その後じいさんから連絡はなかった。三村さんも忙しいようでメイルも来ない。
年が明けると、みんなにじいさんから同じ文書の新年の挨拶がメイルでとどいた。元気でやっているのだろう。
吉都が250ccの免許を取って川崎を買った。それで事務所に通うようになって、借りている駐車場のトライアンフの隣に止めている。
まだ寒い二月の半ばに、詐貸が大型の免許を取得した。おひろめだと言って野霧と吉都を駐車場につれていった。詐貸がトライアンフにまたがりエンジンをかけた。
「逢手君サイドカーにのるかい」
野霧は顔をまん丸にしてサイドカーにおさまった。吉都がまたプーさんなんて言っている。
「次に吉都のせてやるよまってな」
詐貸は白山通りから、大正大学の脇を通り、庚申塚通りにはいると、巣鴨のとげぬき地蔵の前を通って、都電を渡り戻ってきた。
「サイドカーから見るとまた町の景色が違いますよ」
「ほら、今度は可也」
吉都もサイドカーにのって同じところをまわってきた。
「ベッドに横になったまま遊覧したみたいだ」
吉都はなかなか旨いことを言う。
「これからは、これで俺も旅するかな」
春になると驚いたことがおきた。
昼に三人で西巣鴨のそば屋に行って帰ってきたときである。
駐車場にとめてあるトライアンフのカバーを野霧がにこにこしてはがした。その上、サイドカーに入れたあった詐貸のヘルメットを「ちょっと小さい」と呟きながらかぶるとトライアンプにまたがった。
「詐貸先生、キーかして」
詐貸は遊んでいるんだろうとキーを渡すと、野霧はエンジンをかけて、駐車場から出て行ってしまった。
「おい、なんだ」
詐貸も吉都も唖然としていると、野霧はすぐにもどってきた。
サイドカーつきトライアンフを堂々と駐車場に止めると「のりやすいですね」
とおりて来た。バッグから手帳を出して二人に見せた。
大型バイクの免許だ。野霧の写真が貼ってある。
「いつとったの」
「あのボーナスもらったときから始めました。時間かかちゃった」
「すげえ、がんばんなきゃ」
吉都がおそれをなしている。
恐るべし餡まん、いや素甘である。
「テディおじいさんに免許取ったってメイルしたけど返事ないの」
「イギリスで忙しいんじゃないの」
そのようなことが大事件なほど平凡な日が続いていた。
五月の連休にはいってから、ブラジルの三村さんからメイルが入った。
『小栗の父に小夜さんの会の予定を聞くためメイルしたのですけど、返事がありませんが、様子を聞いていただけないでしょうか』とあった。
『イギリスに行かれてから連絡ががありませんが』
『父はイギリスに行ったのですか』
『イギリスに行っているはずです、半月ほど前、しばらくイギリスにいくと電話をいただきました、三村さんもご存じだということだったので安心していたのですが』
『え、連絡ありませんでした。イギリスの家を管理している者に電話をしてみます、すみませんでした』
どういうことなのだろうか。
すると、デスクの電話がなった。国際電話である。三村からである。
「詐貸さん、イギリスに電話したのですが、管理人は来ていないと言っております、すみません父の様子を調べていただけませんでしょうか。私も日本に向かう支度をします」
「わかりました、これからすぐ葉山に向かいます、携帯電話を教えてください」
詐貸は紙に三村の携帯番号をかいた。
「どうしたんです」
野霧と吉都がきいた。詐貸は美衣の杞憂を伝えた。
「これから葉山に行く、野霧くんはサイドカー。吉都は自分のに乗ってくれないか」
「はい、僕のバイクだと少し遅れてつきます」
「あわてなくていいから安全運転でいこう」
三人は二つのバイクで葉山に向かった。
まず、詐貸のバイクが到着した。
赤い屋根の館は静まり返っていた。誰もいないようだ。いくらベルを押しても誰もでない。十分遅れて吉都が到着した。吉都が門を乗り越えて中に入った。とたんに防犯ベルが大きな音でなった。あわてて吉都がもどった。
黒い車がすごい勢いでやってくるのが見えた。車はすぐそばで止まると、中から背広姿の男が降りてきた。
「葉山セキュリティーの者ですが、なにか御用ですか」
「小栗さんのお嬢さんから様子をみるように言われた者です、庚申塚探偵事務所の詐貸です」
その男は名刺を見て態度を柔らかくした。
「あ、詐貸先生ですか、小栗さんから、おそらく詐貸さんが来るだろうから、きたら説明するように言われました。五月二十日に鍵を開けるように言われております、その前に庚申塚探偵事務所の詐貸先生たちが来るかもしれない、そうしたらその旨伝えるようにと言うことでした」
「家には誰もいないのですか」
「はい、働いていた方もその日に戻られると思います」
「わかりました、そちらの名刺いただけますか」
「あ、失礼しました」
その男は葉山セキュリティ会社の代表取締役だった。
「それじゃ帰ります、娘さんにもそう伝えます、ブラジルを出る支度をしていると思いますので早く伝えなければ、できればそちらからブラジルの小栗さんのお嬢さん三村美衣さんに連絡していただけませんか」
「はい、三村美衣さんに関しても何か聞かれたら同じように伝えるよう言われています。住所電話すべて聞いてますので、連絡します」
「僕の方からも帰ったら連絡します」
詐貸たちはバイクでそこを離れた。
「これから帰るのは大変だから、逗子に泊まろう」
「なんでしょう、おじいさんのびっくりでしょうか」
「そうかもしれないが、ちょっと気になるね」
詐貸はそう言って逗子のホテルをとった。
詐貸はホテルから国際電話をかけ、三村さんに葉山でのことを話した。
「はい、わざわざ行っていただいてありがとうございます、先ほど葉山セキュリティ会社から電話がありました。父はイギリスのどこか放浪しているのかもしれません、五月二十七日が小夜さんのお発ち日ですから、二十日は一週間前ですね、小夜さんの家族と私どもだけですから、あまり準備もいらないということだろうと思います、忙しいところお時間とらせてしまいました、父も一言連絡してくれていればよかったのにと思います、いつもあんな調子です」
「いや、ご心配になったでしょう、いつでもご相談ください」
「はい、ありがとうございました」
詐貸は三村の言ったことを二人に説明した。
「今日は、逗子に泊まって海のものを食おう」
テディじいさんとの再会
五月二十日を過ぎた。テディじいさんはイギリスから帰ったのだろうか。
その夜のことである。三村女史からメイルがはいった。
『詐貸様、今日二十一日、葉山の家に入りました。夫も一緒です。父は帰っておりませんでした。使用人は集まっていました、彼たちが言うには、父はイギリスに行くので、この家はもう売る、だから五月までの給料と退職金を出すから、次の職を探してほしいと言われたそうです。ただ五月二十日から二十七日まで、人が来たらもてなしてほしいと言われたので、食事の材料を取り寄せたそうです。その費用はチーフに渡してあるそうです。わけがわかりません。
それと困ったことに、父の部屋は鍵がかかっていて開きません。あの大きな厚い一枚板の戸をはずすのも難しいでしょう。父が二十日に帰っていないことが不思議です』
詐貸はふっと不安になった。
『小栗さんから電話があったのは暮れで、ロンドンのクリスマスが懐かしいとおっしゃってました。どの飛行機に乗ったのか調べてみましょう』
吉都に航空会社をあたらせた。個人の情報はなかなか教えてもらえないが、吉都は医者に扮し、偽の医者の証明書を見せ、患者の持病の薬を送らなければならないが、行ったっきり連絡が取れない、本当に行ったのかどうかもわからないので、十二月に「小栗宙太郎」という名前があるかどうかだけでも教えてほしいとロンドンに飛んでいるエアラインに聞いて回った。必ずファーストクラスにのるので調べやすい。しかし名前はなかった。
行ってないとしたらどこにいるのだろう。
次の日、詐貸たちは葉山の家に行った。三村の主人に始めてあった。日本人だが大きな体をしていて黒い髭を生やしているところは黒熊みたいだ。ゆったりとしたしゃべり方をする温厚そうな人である。
「皆さん部屋はたくさんあるので、ここにお泊まりください」と言ってくれた。
「水野さんは二十六日にいらっしゃいます」
美衣の顔に不安の様子がうかがえる。
「小栗さんの部屋は今も開いていないのですか」
「はい、鍵屋さんにきてもらいました、しかしどの人もできないと帰ってしまいました、父は特殊な鍵を作らせたようです」
そういう鍵が開けられるのは泥棒か、いや、あいつがいる、小倉だ。自宅の電話はわかっている、テディじいさんに世話になっているやつだ、いやとは言うまい。詐貸は電話をかけた。でない、またどこかに出かけているのだろうか。
「ショートケーキの電話わかるかい」
野霧が「わかりまーす」といって、スマホをつけた。「まだ三時です、やってないのではないですか」
「でも電話してみるよ、番号教えて」
詐貸は自分のスマホに野霧のいう電話番号をうちいれた。電話が通じた。若い女の子の声でショートケーキですと応じた。
「詐貸と言いますが、小倉さんはいらっしゃいますか」
「マスター、詐貸さんから電話です」という声が聞こえた。
「え、詐貸さん」と言う声がして、彼が電話に出た「はい、小倉です」
「初めてお電話します、庚申塚探偵事務所の詐貸と申します」
「あの詐貸さんですか、なんでしょう」
「今小栗さんの家からお嬢さんにたのまれて電話しています、実は小栗さんが行方しれずです、なにかお聞きではないでしょうか」
「小栗さんにはお世話になっています、北海道で仕事をさせていただいた後、会っておりません、ただイギリスに旅に行くので、正月に新年のメッセージを送って欲しいと頼まれて、前もって送っていただいた小栗さんの文章を一日に皆さんに転送しました」
新年の挨拶は直接テディじいさんから来たのではなかったのだ。嫌な予感がする。
「実は小栗さんの部屋を開けたいのですが鍵がないのです、それで小倉さんを思い出しまして、助けていただけませんでしょうか、小栗さんからみなお聞きしています」
「まいりましたね、私の裏の仕事をご存知だったのですね、小栗さんのためなら何でもします」
「葉山の家も小倉さんの紹介だとうかがっています、是非来ていただいて助けていただけませんでしょうか」
「はいもちろんです、わかりました、明日一番でうかがいます」
「費用はもちますので」
「あ、いや、小倉さんからは大変たくさんの報酬をいただいてます」
意外とまじめな反応だ。
「それではよろしくお願いします」
「こちらこそ」
詐貸は電話をきった。
「明日小倉という人がきます、鍵は開くと思います」
「小倉さんて、この家を紹介してくれた人ですか」
美衣さんがきいた。
「そうです、小栗さんの裏の助け人です、法律家です」
「そうだったんですね」
次の日の三時頃、小倉敬紀は葉山の小栗邸に着いた。
野霧と吉都はスナックバー、ショートケーキを思い出していた。あの占いの女性シノンはなかなか面白い人だった。
三村夫妻が迎いにでた。
「遠くからすみません、父がお世話になりました」
「いや、お世話になったのは私の方です」そう言うと、詐貸のところにきた。
「初めてお目にかかります、小倉敬紀です、ご迷惑をかけたようですみません」
「いえ、小栗さんからは話を聞いております、小栗さんも感謝していました」
「この家は小栗さんの希望で、機能が超近代的に改造してあります。小栗さんの部屋は特殊な鍵がつけてあって開けられるかどうかわかりませんがやってみます」
彼は扉の脇の壁の下にあるコンセントを開けて線を切った。ここから鍵穴に電気が流れていて、鍵を単純に入れても開きません。コンセントに電気をブロックする鍵を差し込んでおかなければなりません」
「父はそこを操作しているのを見たことがありません、ただ普通に扉の鍵穴に鍵を差し込んでまわしていました」
「はい、いつもはコンセントに何か差してありませんでしたか」
「そう言えば停電の時に点くんだという四角いガラスでできている小さな照明が差してありました」
「そうでしょう、それがなければいけないのです、しかしコンセントの中の線を切りましたので大丈夫です、あとは鍵が開けられるかどうかです、どのくらいかかるかわかりませんがはじめます」
小倉は汚れた針金を背広のポケットから取り出すと鍵穴に差し込んだ。
十分、二十分と過ぎていく。見ていた詐貸たちはロビーに引き返しソファーに腰掛けた。みな黙ったままである。
小倉が「開いた」と声を上げたのはもうすぐ一時間になろうとするときである。
「すごい鍵だ」
それを開けるのもすごい。
美衣さんが扉を押した。極端に乾いた風がふーっと顔にかかった。詐貸も野霧も吉都も眼をつむった。
目を開けるとツインベットの一つにおおきなテディベアーが寝ている。あの美羅衣の布がかぶせある。小夜さんのベッドだ。隣のじいさんのベッドにも美羅衣がかけてある。真ん中が膨らんでいる。
美衣さんがベッドの脇に行って「あ、あ、あ」と叫んでご主人の腕をつかんだ。
「お父さんどうしたの」美衣さんがまた叫んだ。
詐貸たちも近寄るとぎょっと棒立ちになった。
じいさんの頭は骸骨だ。骸骨に皮がかぶって黒っぽくなっている。美衣さんが布をはいだ。テディじいさんがパジャマを着てミイラになっている。美羅衣をかぶってじいさんはからからに干からびていた。目をつぶって手を胸の上で組んでいる。手に触るとかさかさと飛んでいきそうだ。
こんな再会があっていいのだろうか。みな無言で立ったままだ。
隣の小夜さんの部屋の戸が開いていた。
詐貸が動いた。中に入ると部屋のなかには揺りカゴが並んでいた。揺りカゴには美羅衣に包まれたものがはいっている。詐貸が布をめくった。赤子が干からびていた。
赤子のミイラだ。
みんなの目が小夜さんの部屋の揺りカゴに釘付けになった。
「いったいこの赤ん坊は」
いつもは落ち着いている美衣も金切り声をあげた。
小倉が小さな声で言った。
「私が頼まれました、死産の赤子の処分に困っている人がいると、小栗さんがその人から死んだ赤子をきちんと葬ると受け取りました。十人います」
「そのために全国に行ったの」
野霧がつぶやいた。
「そうです、その死んだ子供を産んだ人は、自分で死のうとしたり、悪い道に落ちそうな娘だったり、だけど小栗さんが助けました」
「父は小夜さんと結婚した時、子供を十人作ろうなって言って二人で笑ってました」
美衣の目から大粒の涙が落ちた。
「みんなミイラになってしまっている、おじいさんも」
野霧が泣いている。はじめてだ。
詐貸が言った。
「みなさん、明日、小夜さんのお母さんとおじいさんが来ます、それまで閉めておきましょう、おじいさんはお医者さんです」
テディじいさんの部屋から出ると扉を閉めた。
「どうして半年程度で、からからのミイラになったのだろう」
日本の湿度の高さを考えると詐貸が疑問に思うのは不思議ではない。
「ずいぶんあの部屋は乾燥していましたね」
吉都は大学院で生命科学を研究してきた。
「小栗さんはあの部屋の湿度を最も低くしてベッドにはいったんですよ、ということは、自分で死ぬことを知っていたのではないでしょうか」
「父は検診ではビタミン剤しか出してもらえないほど健康でした、ベッドには自動的にからだの様子を測定する装置が組み込まれています、大学病院の主治医に様子を聞いてみます」
美衣が病院に電話をした。主治医は手術中で出られないということであった。
「後で電話をすることにします」
「三村さん、今日は静かにしていましょう、できたら、小倉さんにもいてもらいたいのですが」
「部屋はあります、どうぞお願いします」
皆頭の中は混乱している。最後に会ったテディじいさんは少し疲れてはいたが、あの元気なじいさんだった。
「飲み物を用意させます、ホールのほうへどうぞ」
「父は自分で死んだんでしょうか」
美衣さんの目が赤い。
「僕はにはわかりません、だけど事件にもみえません、小倉さん何かご存じですか」
彼はうなずいた。
「小栗さんは北海道でもうあまり時間がないとおしゃっていました、何の時間がないのかときいたら、いつもの調子で儂の寿命じゃ、と答えられました、年をとったという意味かと思いましたが、どこかお悪かったのかもしれません」
主治医から電話がかかってきた。
「小栗さんどうですか、半年前イギリスの病院に入るというご挨拶をいただきましたが」
「いつから悪かったのでしょうか」
「お聞きになっていなかったのですか、一年ほど前でした、癌が前立腺にみつかったのですが薬で抑えておりました、他に移転する前にイギリスに帰って治療するとおっしゃっていましたので、いかがなんですか」
「亡くなりまして、ありがとうございました」
「それは、大変でしたね、お気持ちが強い方でしたから、テレビでご様子を拝見していましたよ」
「そのうちお礼に伺います」
「いや、もうそれは結構です、葬儀には出たいと思いますのでご連絡いただきたいのですが」
「ありがとうございます、葬儀はしないかもしれません」
「ご冥福をお祈りします」
電話が切れた。
「父は癌だったようです、ビタミン剤と言っていたのは、その薬だと思います、ベッドの装置のデータも病院には送られていなかったのではないでしょうか」
「明日、水野先生にみていただきましょう」
翌日、水野と美代がきた。詐貸はだいたいのところを話して聞かせた。二人とも驚いたのはもちろんである。
三村夫妻、水野親子、庚申塚探偵事務所のスタッフ、それに小倉がじいさんの部屋にはいった。ベッドの周りで皆な何も言えないでいた。
詐貸が「水野先生、小栗さんをみていただけないでしょうか」と言った。
水野医師はじいさんの干からびた体に触れた。
「前立腺癌は進行が遅い、他のところにも癌が移っていた可能性はありますが、これでははっきりしません、やはりご自分から食事も水も飲まず、ここに横になられたのではないでしょうか、即身仏になられたのです」
家族達から離れて見ていた詐貸が小声で「即身仏って」と野霧につぶやいた。
「ほかの人の苦しみをのぞくため、飲まず食わずの修行をして、最後を迎えようとするとき、土の中に自分から埋もれるのです。三年後ミイラ化した即身仏は寺に置かれて拝まれるのです、ミイラ仏ともいわれています」野霧も小さな声で呟いた。
「テディじいさんは日本人だと言いたかったのかもしれないな」
吉都がつぶやいた。
「小夜はこのベッドに寝ていたのですね」
水野美代が涙を浮かべてじいさんの隣にいたテディベアーに触れた。
「マミーと呼んでいたんですよね、マミーはミイラですね」
野霧はそう言うと小夜さんのベットの脇に行った。テディベアーを抱き起こし、背中のチャックを降ろした。じいさんがよろけて縫いぐるみを落としそうになったとき野霧が支えた。その時固いものが入っていると思った。野霧は夢中で中のものを取り出した。白い布に包まれていた。大きいのと小さいのがあった。
野霧の顔は涙でくしゃくしゃだった。
野霧はテディベアーを床におろし、大きな布を開いた。干からびた女性のミイラだった。野霧はそうっとミイラをベッドの上に寝かせ小さい包みを開いた。小さな小さなミイラだった。小夜のミイラの隣に寄り添わせた。野霧は布をそうっとかけた。
じいさんは小夜さんと子供をミイラにしていつも一緒にいた。
小夜さんのベッドの脇にだけほんの少しになった水の入ったコップが置いてあった。おじいさん、自分は飲まず食わずで寝ていたんだ。
「テディおじいさん、小夜さんをいつもサイドカーに乗せて旅してたんだ。子供も一緒だったんだ」
野霧はまた泣いた。
美代さんが「これが小夜なの」とミイラの手をとった。
「これが赤ちゃん」美代さんが抱き上げた。
水野先生も涙を浮かべている。四人の孫はみな遺体だった。
美衣さんもハンカチを目に当てている。吉都は後ろを向いている。詐貸は歯をくいしばっていた。昔からそうだ。
みんな動かなかった。
エピローグ
あのとき、じいさんの部屋で吉都がおかしなものを見つけた。
カーテンの引かれた窓の下に白い布がかかった長いものが置いてあった。布の上に小さなテディベアーが十一個乗っていた。
吉都がこれはなんですかとテディベアをどかし布をめくった。それは大きな深い長い箱だった。棺だ。じいさんが作らせたのだ。
それを見た水野医師が言った。
「小栗さんは小夜と一緒に焼かれたかったのだろう、一緒に入れてやりましょう」
「あの十人の赤ちゃんのミイラはどうします」野霧が聞くと、水野医師が「いっしょにいれてはだめでしょうか」と美衣にきいた。美衣はうなずいた。「小さな熊が十一個乗っていました。いれてほしいということだと思います」
「そのまま、私の医院に運んではいけませんか、私が死亡を確認した書類を書きます。芽室の焼き場で灰にしてあげませんか、そして北海道で眠っていただいてはだめでしょうか、それともイギリスにもっていかれますか」
水野医師が美衣をみた。
「父は日本にいたいと思います。小夜さんが元気ならば、葉山が小栗の終の住処になったと思いますが、小夜さんが亡くなった後はそれは考えていなかったでしょう、むしろ、生まれた北海道に埋められるのは喜ぶと思います」
「私も小夜が芽室に戻ってくれるのは嬉しいことです」
美代も言った。
「それが、みなに一番いいことなのでしょう、運ぶのは葉山セキュリティに頼みます。大事なものだと言って、北海道まで直接運んでもらいます」
詐貸がそのように話をまとめた。
こうして、今小栗宙太郎と小夜の墓が水野家の隣に建てられている。三村夫妻も葬儀のために北海道に行ったとのことである。
われわれは葉山でテディじいさんと再会したところで終わりにした。北海道での葬儀には出なかった。あまりにも不思議な事件で、これも解決したのかしないのか、詐貸にとってすっきりしないものになってしまった。
今、家出猫の捜索願いがきている。もとの探偵事務所の生活にもどっている。
じいさんのサイドカーつきのトライアンフを野霧に自由に使ってもらっている。いつかそれで北海道に行きたいといっている。野霧はときどき公園で遊んでいるこどもをサイドカーに乗せて周囲を一周して喜ばせている。
吉都は大きなオートバイの免許にトライしている。
「マミーからマミーがでてきて、美羅衣が美衣羅になりましたねえ、mammyもmummyもmommyもみんなかあちゃん」と、野霧も野霧らしくもどった。吉都はすぐそばの妙行寺に遊びに行っている。お岩の縁で墓守のじいさんと仲良くなったのだ。
ブラジルの美衣さんからは妊娠六ヶ月だとメイルがきた。どうも北海道でできた子供のようだ。
仙台の小倉敬紀は頼りになる男である。彼は有能な探偵だ。ただああいう性格をしているからああなっているだけだ。きっと小倉も俺のことをそう言っているんだろう。と詐貸は思う。
じいさんのミイラの顔がだんだんと薄れ、あの元気だったじいさんの顔が瞼の奥に浮かぶようになった。キリスト教に育てられたが日本の死に方をした。遺伝子というのは本当はなんだろう。
おじいさんが亡くなって半年、事務所に大きな荷物がイギリスから船便でとどいた。ずい分重そうな荷物である。野霧にあてたものだった。
送り主はテディじいさんだ。
事務所に出てきた野霧が「あー」と声をあげた。
「テディじいちゃん、葉山に行った時、持っている探偵小説を送ってくれるって言ってた、着く日を指定してイギリスに頼んでいたんだ」
荷物を解くと中にはイギリスの探偵小説がぎっしりと詰まっていた。コナンドイル、チェスタトン、クリスティーみんなある。ウォルホールまである。これはゴシックロマンの元祖だ。
野霧が上にあった一冊を手に取った。
本のタイトルはThe Red House Mystery。
「じいちゃんこんなのも読んでたんだ、くまのぷーさん書いたミルンの唯一の探偵小説、赤い館の秘密、この中の探偵が金田一耕助のモデルなのよ」
野霧がまた涙目になった。
完
美衣羅(みいら)


