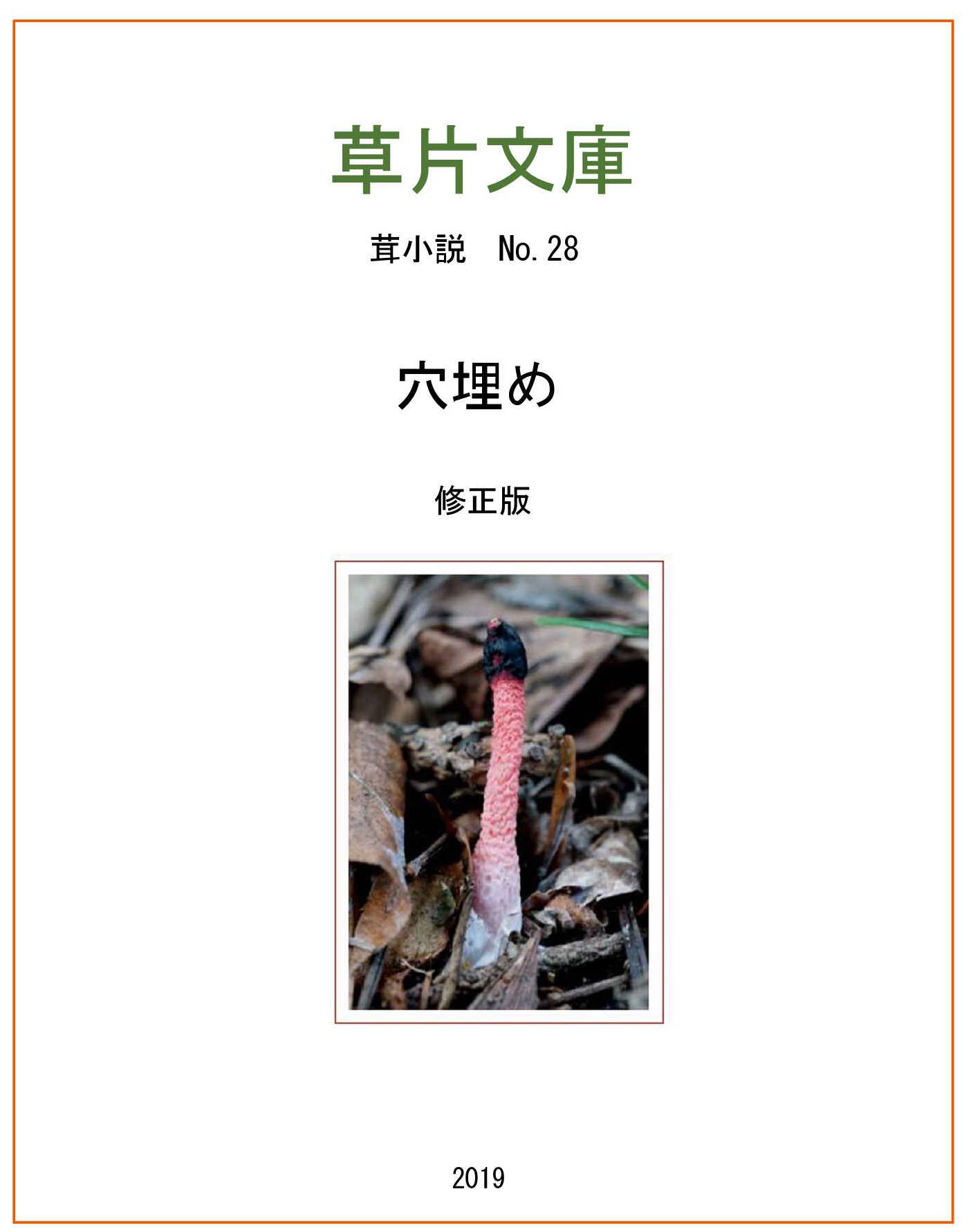
穴埋め
茸幻想SFです。
植物の神様って知ってるかい
誰かが誰かに尋ねている。
「知らないよ、その前に神様の定義を知らないな」
「人間を超越した威力を持つ、隠れた存在、と広辞苑にあるよ」
「それだけ」
「人類に禍福を降すと考えられる慰霊。人間が畏怖し、また信仰の対象とするもの、ともある。日本国語大事典には、宗教、民族的振興の対象、世に禍福を降し人に加護や罰を与える慰霊とある」
「どちらも、慰霊なんだね」
「慰霊は、威力のある神霊、また天子の威光。神威とある」
「神霊とはなに」
「たましい、霊魂や神そのものともあつかわれている」
「同道巡りだね、天子とはなに」
「天命を受けて、人民を治める者、国の君主。天皇ともある」
「そうなると天子は人間で神ではないね、矛盾が混じる、慰霊は神なんだろう」
「うん、少しわかってきたようだな、それで植物の神となると、植物を超越した威力を持つ、隠れた存在、植物に禍福を降すと考えられる慰霊ということだ」
「すると人間も植物の神になりうるし、植物も人間の神になりうるわけだ」
「そうだね、植物は酸素を作っているから、作らないぞと植物が言ったら、人間に災いをもたらすから人間には神だ」
「そうか、それであんたが言う植物の神っていうのは、人間のことではないわけだな」
「うん、人間の神は隠れた存在とあるので、形はわからない、だから植物の神も隠れた存在で形はわからない」
「なんだ、わからない物を聞くな」
「だけど、ある生き物の神といったとき、その生きものを超越していなければならないことはわかったろ」
「ああ、その点はなんとなくわかった、そうすると、神はいくらでもいるし、なんだかわからないことが生じたら、神がやったといえばすべて治まるということだよな」
「おお、その通り、神が言ったからそれをやれと、神を利用することもできる」
「そんなことは、大昔から人間がやっていることだな」
「それで植物の神様が植物をこの世に作って、動物の神様が動物を作ったわけだ」
「それでどうしたというのだ」
「動物と植物ができて、それを見た動物の神が植物の神に言ったところからこの話は始まる」
幕が開く。
その昔、動物の神は土と水と空気とそれに太陽の光を混ぜて、卵と精子を作って動き回る生命体を造った。
その動物の神が植物の神に言った。
「植物は、動物のようにちょろちょろ動き回らない方がいい、ベチャベチャわおわお、うるさくしゃべらない方がいい、子供は勝手に大きくなるのがいい」
「そうしましょう、それじゃ私が種と胞子を作るわ」
植物の神は土と水と空気とそれに太陽の光を混ぜて種と胞子を作った。
動物との違いがわかるように、葉緑体のもとをつくった。緑色だ。動物は黒っぽかったからもっと明るい方がいいと思ったわけだ。
「動物と仲良くできるようにしてくれ」
動物の神が言った。
「それじゃあ動物が死んだ後をかたづける役目を植物にさせましょう、動物の死体が植物の栄養になれば、お互い助け合いになるでしょ、その上、植物からは酸素やヴィタミンを動物たちにプレゼントするの」
葉緑体にその役割をもたせた。それは植物へと発達した。
46臆年前に地球ができたが、それは星の神が作った。星の神は星を際限なく作りだし、地球で子供を産んだ。それが動物の神と植物の神だった。だから二人は兄妹だ。
地球の上で動物と植物が発達していくのを見るのは楽しかった。陸地で植物が増えると酸素ができて、海の中の魚が陸にあがった。そいつらは植物の間をよたよたと体を引きずるように歩く、だが水辺から離れられない。子供を水の中で育てたいのだ。それが両生類だ。水に嫌気の差した連中が、陸で子供を育てたいと、は虫類になった。お空に行きたくなった爬虫類に羽が生え、空を飛んでいく鳥になり、空は怖いと羽がいらない爬虫類はお乳で子供を育てるようになった。哺乳類だ。
「動物は好き勝手に変わっていくわね」
植物の神は動物がどんどん変わっていくのを面白く見ていた。
種がぽとりと落ちて芽が出て種子植物になった。一方、胞子から芽が出て胞子植物になった。海の中で育った胞子は藻類となり、陸で育った胞子は地表を覆って羊歯や苔になった。種の植物はさらにわかれて木と草になったが、時が経っても植物の変化は遅く、変り映えしなかった。
「確かに、ゆったりと、植物というのはなかなか乙な生きものだ」
動物の神は堂々と威信のある植物の生き方が好きだった。
どうも神の作るものはその神の性格に似るようで、相手の作ったものが良く見えるようだ。人間臭いものだ。
問題は植物が動物の死体を片付けるはずだったが、どうも植物にはその能力があまりなかった。しかし動物は動物どうしで死体をかたづけるようになった。一方で植物だって土に帰らなければならないが、なかなか土の中に溶けこまなかった。
「この先どのようになるのかしら」
植物の神が動物の神に尋ねる。
「もっと早く、動物と植物の死骸を土に返さなければいけないな」
「どうだろう、ちょっと時代を戻して動物と植物の足りないところを穴埋めする生き物を作らないか」
「動物も植物も水の中、土の上、空気の中にすんでいるわね」
「そうだな、とすれば、土の中で広がる生き物、植物にも動物にも役に立つ、物を腐らす役割がいい、植物や動物が死んだらそれを腐らせて、土にかえす」
「そうね、でも、それだけじゃ、その生きものは土の中だけで、地球の上の出来事を見ることができないわね、植物や動物と挨拶したいじゃない」
「そうか、土の中からたまには顔を出すような生き物か、その顔もきれいなのがいいな」
「土の中で大きくなる生き物、それに可愛い方がいいでしょう、かわいく地表に花を咲かせる生き物」
「それでいこう、動く物が動物、植わっている物が植物、とすと、土の中だから地物(じぶつ)か」
「地物ねえ、悪くはないわね、動物、植物、地物」
「とすると、地物の神が必要だ」
「私たちは星の神と時の神が結婚してできたわけよ、今度は私たちが、結婚して、地物の神を産まなければならないわね」
「そうするか」
ということ、兄妹だった動物の神と植物の神が睦みあった。だいたいどんな神でも節操がないものである。
二人の神はどんな形をしているか、それは勝手に想像してくれればいい。結局、神の形というのは、それを考えた生き物が自分と似ているように想像する。人間だと人間に似ているし、植物が想像すると植物のかたちになる、とすれば、植物の何かと動物の何かが交尾しているところを想像すればいい。想像できない奴はしかたない。
ということで植物の神と動物の神から地神が生まれた。どちらから産まれたか実はわからない。植物が女っぽいと考えたとするとそれは人間に影響され過ぎている。言葉遣いで判断しちゃだめだよ。
それで、生まれた地物の神は細い糸が絡んでいるような体をもち、頭と胴体のある花を咲かせる生き物を作った。
植物の神が地物の作った生き物を見た。
「木の下に出てきた地物の花はまるで、木の子どものようね」
動物の神もうなずいた。
「たしかに、動きだしそうだよ、ほ乳類の胎児に似ていなくもない」
「そうね、どう、木の子という名にしたら」
植物の神が地物の神に言った。
地物の神はうなずいた
「土に生えた耳みたいでもあるな、草の下の耳、こう書こう、茸」
茸は植物や木を腐らせた。
動物の神が植物の神に言った。
「人間の世界にもなかなかできる人物がいて、白川静という御仁が「字通、平凡社」と言う漢和辞典を著し、その中で、茸の声符を「じ」と書いている」
地物の神はそれを聞いてこう言った。
「それはたいしたものだ、私の名前を地物から茸物(じぶつ)にかえよう」
ということで、地物の神は茸物の神という名になった。
それから、地物の神はもっとちがう茸物も作った。糸のようなからだもなく、花も咲かない生き物である。
もっぱら、発酵ということをする生き物である。植物のからだを壊す。
これは地球に革命を起こした。植物の体からアルコールを産みだしたのだ。みんな酔っぱらっちまった。
「茸物の神は面白い生き物を作ったね」
「たいしたものね」
ということで、動物と植物ができてそのあと、茸の仲間や発酵をする仲間、茸物ができた。
それは後に地物とは呼ばれずに、菌類と呼ばれるようになった。なぜ菌類になったかというと、動物の頂点に達した、威張っている人間がそう言ったのだ。神の考えを聞こうともしなかった。いや聞く耳をもっていなかった。それもちがう、人間の耳には神の声が聞こえなかったのだ。人間は草の仲間だと勘違いした。植物に近い類、近い類、近類と呼び、地や木から生えるものだから、草冠にし、木を囲って菌という字にしてしまったのだ。事実、2011年までは動物界と植物界しかなかったのだが、やっと分かってきた人間が、菌界を別にしたのだ。
そういうことで、茸は動物と植物の足りないところの穴埋めに作られた生き物である。
茸ができて、植物と動物はいい生活ができるようになり進化をしたのだが、植物と動物の面倒を見なければならなかった茸は大きな進化はしなかった。それは、はじめからしっかりできあがった生き物であったから、変わっていく必要がなかったわけである。
今、地球がなんだかきたならしくなった。
植物と茸物の神が動物の神に文句を言っている。
「人間なんて作っちゃって、失敗ね」
「申し訳ない」
動物の神が謝っている。
「どう、我々、他の星に移ろう、地球はどうなるかしらないけどほっていきましょう」
植物の神、茸物の神、動物の神はそう言って、すーっと地球から消えていった。
「やっと我々の番だよ」
空いた地球に別の神がやってきた。
これが本当の星の死神である。
穴埋め


