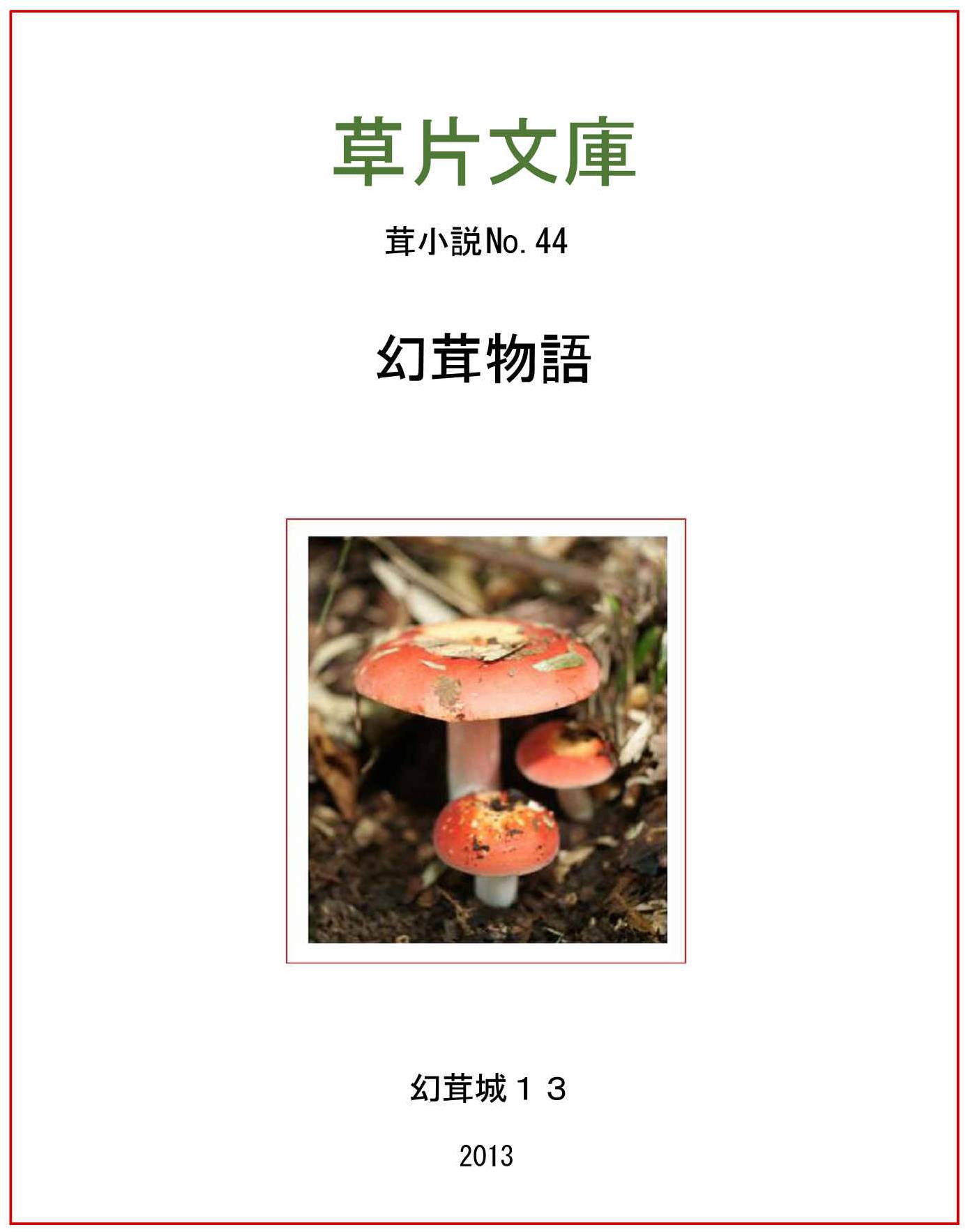
幻茸物語 - 幻茸城13(最終回)
赤姫が天井裏から城の外をのぞいている。
遠くから馬に乗った武者たちが土埃を巻き上げてやってくる。
大黒鼠の爺が自分の巣から出てきた。
「姫さま、姫さまが茸に変えた紅姫の父親が武者を連れて、探しに来たようでございます」
「あわてる必要はあるまいよ、爺」
「はい、しかし、心配でございます」
「なにがじゃ」
「城の中を捜して、紅姫がいないと、火でもかけるやしれません」
「それは困りますが、大丈夫です、この城に火をつけることはできません、ただのお城ではないのです」
「それは、また」
「わたしがおります、だからこの城は城の妖怪かもしれません、人の住むところではないのです、紅姫の父親はそれを知ることになるでしょう」
「たしかに、姫さまの言われる通りかもしれませぬ」
「武者たちがこの我々の部屋までも入ってくるかもしれませんが、皆のものに、隠れているように伝えてください。決して、住処から出てはいけません。爺もそうしてください」
「そうしますじゃ、みなに伝えてまいります」
鼠たちは壁の穴の中や、物陰に隠れた。
瓜一族の大群が幻茸城に到着した。
武者たちが城を取り囲んだ。殿が城の中に入り、城の者たちに様子を聞いた。
「いなくなったのは紅姫と七左衛門だけか」
「いえ、兵が三人、それに女中が三人いなくなりました、放った猫もみないなくなりました」
「どうしたのじゃ」
城に残った冬がおずおずと前に出た。
「七左衛門さまとお供のものが、紅姫様を外に探しに出られるとき、紅姫様が戻られることもあるから、私は残るように言われました」
冬はその時のことをこと細かく報告した。
「そうか、これから、紅城の中をくまなく探せ、それに庭や池やあらゆるところを探すのじゃ」
瓜の殿様は檄を飛ばした。
瓜一族は前の城主との城の名を変えぬという約束を違え、幻茸城を紅城と呼んだのである。
武者たちは城の中に入ると、部屋の隅々までも探し回った。
「お姫さまはいらっしゃいません」
武者の一人が天守閣の屋根裏に入ってきた。
「ふーん、この臭い、鼠の匂いじゃ、どこぞにでも隠れているのであろう、また猫を放たねばならぬな」
そこへ、大きな白鼠が一匹、武者の脇を横切った。
「お、なんと大きな鼠」
腕の立つ武者が剣を抜くと、白鼠の首を刎(は)ねた。首はすぽっと、壁の穴の中に落ち、胴体はヒクヒクと床の上を跳ねた。
「鼠一匹か」
武者は首のない鼠の尾を持つと、血を滴らせて、下に降りていった。
「大きな鼠が一匹おりまして、首を刎ねてございます」
武者は殿の前に鼠をもっていった。
「なんじゃ、汚らわしい、そのようなもの外に捨てい」
「は、これは、ご無礼をいたしました」
武者は鼠の死骸を城の外に放り投げた。
「殿、紅姫さまは誰かにさらわれたものと考えられます、どこかで生きていらっしゃるに違いありません」
「うむ、城に放った猫たちはどこかへ行ってしまうし、紅や七左衛門もいなくなる、他の者たちも消えてしまう、気味の悪い城だ」
そこへ、広い城の敷地や周りをくまなく調べた者たちが戻った。
「どこにもおられませぬ、池の中もすべて調べました」
「うむ、みんな連れ去られたとしか考えようがあるまい」
「はい、他を探した方がよいかと存じます」
「こんな茸が生えておりました」
丈の高い草むらの中の切り株の脇に生えていた大きな紅天狗茸と、月夜茸を持って、家来が戻ってきた。紅姫と七爺が変えられてしまった茸である。
「なんじゃ、その茸は、どちらも毒茸ではないか、捨ててしまえ」
「はい」
家来が殿さまの前に放り出すと、瓜の殿様は足で踏み潰した。そのとき、ぎゃあと言う大きな声がどこからか聞こえた。
「なんじゃ、あれは、気味の悪い声だ」
「さあ、わかりませぬ」
「全く気味の悪い城だ、いっそ、燃やしてしまえ」
「もし、殿がそのようにお決めになったのであれば、そういたします」
「そうせよ」
瓜一族は城から出ると火矢の用意をした。
天守閣の屋根裏では、赤姫が大黒鼠の爺の首を抱いて泣いていた。
「爺、なぜ、出ていったのじゃ」
そこへ黒鼠が報告に来た。
「赤姫さま、人間がこの城に火をつけようとしています」
「そうか、大丈夫じゃ、それは心配ない」
赤姫は爺の首を床の上に置くと、屋根裏の穴から外に向かって、
「鬼火、お願いします」
と叫んだ。
その声で空を埋め尽くすように鬼火が現れた。
鬼火は幻茸城の周りを取り囲んだ。
城は火の海の中で赤くメラメラと燃えているようにも見えた。
「殿、あれは」
瓜の武者たちは、火矢を城に向けたまま、呆然とした。
「城が自分で燃え始めた」
鬼火はさらに広がり、瓜一族にまでせまってきた。
「引くのじゃ」
瓜城主の声で武者たちと城に住んでいた者たちは一斉に退却を始めた。
鬼火に包まれた幻茸城の天守閣の屋根裏では、赤姫が目を赤くして、爺の首を抱いていた。
「皆の者、爺のからだを探してきてください」
黒鼠の兵に赤姫が言った。
「はい、必ず、見つけて参ります」
「たのみましたぞ」
黒鼠の兵たちは、城内から敷地の中まで探し歩いた。
「あったぞ、爺のからだが」
一匹の黒鼠が、草叢の中に横たわる爺の首のない死体をかついだ。
「姫さま、見つかりましてございます」
「そうか、爺、痛かったであろうに、ここへ寝かせてください」
赤姫は自分の目の前に爺の体を横たえさせた。
赤姫は閻魔からもらった、蘇りの茸の粉を皮袋から取り出し、爺の首に塗り、首を胴につけた。さらに水に溶かして爺の口の中にたらした。
しかし、長い間まてども何も起きなかった。
「なぜ、生き返らないの、この茸はもう効かないの」
赤姫の目に涙がにじんだ。
女郎蜘蛛と鬼蜘蛛が顔を出した。
「姫さま、我々で、閻魔さまにうかがってきましょう」
「お願いします」
赤姫は蜘蛛たちに頭を下げた。鬼蜘蛛が黒蝙蝠と鬼蜻蜒(おにやんま)を呼んだ。
「地獄の入り口に頼む」
「おう」
黒蝙蝠と鬼蜻蜒は精一杯羽ばたいた。あっという間に地獄の入り口に来ると、閻魔鴉が待っていた。
「閻魔さまはすべてご承知だ」
「大黒鼠の爺の首が離れましてございます、赤姫さまは、閻魔さまからいただいた茸を薬にして、塗って、飲ませて生き返らそうとなさいましたが、首はくっつくことはありませんでした。どうしたらよいか、聞いてきて欲しいとのことでございました」
女郎蜘蛛は閻魔に説明をした。
「うーむ、あの大黒鼠は妖怪に近いもの、それを生き返らせるとなると、蘇りの茸だけでは効かんのだろうの、霊茸をすりつぶしてつけるしかないだろう、儂のところにいま一つ生えておるが、あと二つ、地蔵獄の菩薩と、闇の大王の大赤山椒魚が持っておるだろう、その三つの霊茸が必要じゃ、儂が菩薩と闇の大王に伝える、お前たちは戻って、赤姫にそのことを伝えてくれ」
「はい、ありがとうございます」
こうして女郎蜘蛛と鬼蜘蛛は城に戻ってきた。
「赤姫さま、閻魔さまがまかせておきなさいとの仰せです」
「おお、ありがたい、ありがたい」
赤姫は爺の頭をかき抱いた。
夜も更けてきた。鬼火に囲まれた幻茸城は、遠くからもよく見えた。
やがて、闇の大王と、閻魔と、菩薩が、霊茸を持って集まった。
「これ、赤姫、嘆くではない、この三つの霊茸を磨り潰し、爺のからだすべてに塗るのじゃ、いいな、時間が少しかかるが生き返るであろう」
閻魔が茸を赤姫に渡した。
「ありがとうございます」
「おまえは、あやかしの頭領、とり乱すのではないぞ」
地蔵菩薩が言った。
「はい」
赤姫は泣くのを止めた。
「爺は必ず生き返る、それからはお前一人で、この世のあやかしの世界をまとめておくれ」
大赤山椒魚の闇の大王が笑顔で言った。
赤姫の目が赤く光った。
「この霊茸を磨り潰す、用意しておくれ」
黒鼠たちに指示を出した。
「我々は帰るが、明日になれば、大黒鼠は生き返るであろう、ただ、元のままになるかどうかは我々にも想像がつかぬ、なにせ妖怪に近い御仁だったからな」
そう言い残すと闇の大王、閻魔と菩薩は戻っていった。
「強く生きてまいります」
赤姫は闇の中に消えていく三人の後姿にそう声をかけた。
赤姫は三つの霊茸をすり潰すと、爺の首に塗りつけ胴体になすりつけた。
「さあ、おまえたちも休んでください。もうあの人間どもはこないでしょう、幻茸城は平和になったのです」
黒鼠の兵たちはめいめいの巣に戻っていった。
赤姫も疲れが出てぐっすりと寝込んでしまった。
朝日が壁の隙間から屋根裏の中に差し込んできた。
赤姫が目を覚ました。
どこぞで子供の泣き声がする。いったい、どこから鼠の子供が入ってきたのかと、起きあがると、爺のいたところに一匹の鼠の赤子がお乳を欲しくて泣いているのが目にはいった。白鼠の赤子であった。
もしやと思い近寄ると、爺が赤子になって生き返っていたのである。
赤姫が赤子を抱くと赤姫の乳が張ってきた。
「あれ、乳が」と思わずつぶやいて赤子を見ると、赤子は自ら赤姫の乳をもとめて首を動かした。
爺であった赤子は赤姫の乳に吸いつくと、ゴクゴクと音を立てて乳を飲み、腹いっぱいになるとスヤスヤと寝てしまったのである。
それから赤姫は赤子の世話で毎日を過ごした。
爺にはすぐに白い毛が生え、すくすくと大きくなっていった。
二十日も過ぎると、巣からはいだして、幻茸城の屋根裏部屋をちょろちょろ動きまわった。
危なく下に落ちそうになったりして、赤姫をはらはらさせた。
「爺、危ないではないの、元気なこと」
そう言って赤姫は爺をくわえて巣に戻すのであった。
やがて、爺は黒鼠たちが赤姫に用意した食べ物に興味を持つようになり、硬い木の実などを齧るようになった。
とうとう赤姫の乳も出なくなった。
少年になった爺は屋根裏を駆け回り、ときとして城の下におりて行った。
城の中には女郎蜘蛛や鬼蜘蛛が巣を張っている。
「おや、爺、大きくなったね」
女郎蜘蛛が声をかけると、少年の大黒鼠は「こんちは、女郎蜘蛛のおばさん」と返事をして駆けて行く。
「変な気持だね、爺におばさん呼ばわりをされるのは、昔のことを知らないのだからしかたないねえ」
女郎蜘蛛は鬼蜘蛛に言った。
「そうだな、仕方ないさ、でも元気な子だな」
「ほんと、爺の小さいときはああだったのね、大きくなったら、また、お酒を持っていってやるからね」
「ああ、それがいい」
「爺、どこに行ったの」
赤姫が城の中に下りて来た。
「今、ここを走っていったよ、大変だね」
「元気で困るの」
「元気の方がいいさ」
「黒鼠たちが見てくれているから大丈夫だと思うけど、心配で」
「姫さまもしっかりお母さんだね」
「年寄りの爺いもかわいかったけど、子どもの爺もかわいいの」
「ははは、妖怪の姫さまもめろめろだね」
時が経つのは早い。やがて、少年の爺は青年になった。
りりしい顔立ちで、とてもあの爺の顔からは想像できない美男子である。
「赤姫さま、私も旅がしたくなりました、どこかへ行ってもよろしいでしょうか」
青年の爺は自分の過去のことは知らない。
育ての親の赤姫にたいして「赤姫さま」と呼ぶ。
あまりにもきれいな青年になったことから、周りから光幻茸と呼ばれていた。
赤姫も「光(ひかる)」と呼んでいた。
「光、外は怖いところ、危ないことはしてもらいたくないが」
「無理はいたしませぬ、ほんの一月ほど、旅に出させてください」
「供をつけましょう」
「いや、一人で参ります」
赤姫は昔の爺がこどもの自分のことを心配していたことがよく分かるようになった。
「わかりました、必ず戻ってくるのですよ、危ないときには、鬼火を呼びなさい、さすれば、私の方に連絡がきます。そのときは、何でもします」
「ありがとうございます、では明日、旅にでかけます」
赤姫はそのりりしさに、自分を忘れそうになった。
その日から、赤姫は幻茸城の修復にかかった。
人間が居なくなった城に、赤姫の一族である赤鼠が集まり始めた。黒鼠も、畑鼠も集まり、城の中を磨き始めた。
赤姫も天井裏から降り、天守閣の一番上の階を自分の居場所と定めた。
その部屋には床の間があり、磨かれた板の上に真っ黒な立派な茸が生えていた。
もともとあったもので、この城に住んでいた人間も動かすことをしなかった。
赤姫はその茸を動かそうと、黒鼠兵たちに頼んだのだが、びくともしなかった。
これは茸のあやかしかもしれぬ、大事にしようと、赤姫はその茸をこの城の宝とすることに決め、鼠たちにその旨を伝えた。
ある日、女郎蜘蛛が顔を出した。
「赤姫さん、鬼蜻蜒のやつが言いにきたのだがね、光幻茸の爺が山や野原の鼠たちを従えて、瓜城に向かったんだそうだ」
「え、あの紅姫の生まれた城にですか」
「そうだそうですよ」
「何をしに行くのでしょう」
「さあ、自分の首を切り落とした復讐ということはないでしょう、爺のときのことは覚えていないはず」
赤姫は頷いた。
そのようなことがあり、だいぶ経ってからのことである。
今度は鬼蜘蛛がやってきた。
「大変だよ、赤姫さん、瓜城から人間がいなくなったそうだよ、なんと、赤姫さんの息子さん、光幻茸の君が、たくさんの鼠を従えて、瓜城の食べ物をすべて喰っちまい、人間は城を捨てて、他の地に移っていったということだよ、すごいね」
「それで、光はそのままそこにいるのでしょうか」
「いや、手下を残して、光幻茸の君は、いや爺は戻るということだそうだ」
「それは本当ですか」
「鬼蜻蜒の旦那が言うのだから確かだろう」
そんな話があって数日後のことである。光幻茸は、ますます逞しくなり、赤姫の前に現れた。
「赤姫さま、今戻りました。瓜城は我々のものになりました」
「なんとすごいことをしてきたのでしょう、それに立派になって」
赤姫は光幻茸を見みつめた。
りりしい髭が勢いよく鼻脇から伸び、赤い目が爛々と輝いている。
「瓜城の人間を追い出してしまったとのことですね」
「はい、一人残らず、城から出て行きました」
「人の食べ物をすべて食べてしまったということですね」
「はい、それだけではありません、着るものも、寝るものもみな食い破りました」
「人間は猫をつれてきませんでしたか」
「はい、たくさんの猫がやって来ました」
「猫には鼠より旨いものがたくさんあることを教えました」
「なんと、それはなんですか」
「人でございます」
「なんと、人など旨くもないでしょうに」
「はい、姫の仰せの通りでございますが、人似茸をご存知でしょうか」
「いや知りません」
「茅の鼠たちから教わりました」
「茅の中に希に生える茸だそうでございます、それを一度食べると、人の肉が欲しくなる魔性の茸でございます」
「なんと、もし、我々がそれを食べると、人を食べたくなるというのか」
「さようでございます、その茸に、木天(また)蓼(たび)粉をまぶし、猫に食べさせたのです」
「それで、猫は人を追いかけたのですね」
「さすがは姫さま察しがはやい、その通りでございます、食べ物や着る物がなくなっても、あのあきらめの悪い人間が城をあとにするわけはございません」
「そうじゃな」
「猫に肉を食いちぎられ、さすがの人間ももう戻ってはまいりません、人のいなくなった城に、猫もおりません」
「さすがであるな、爺」
「赤姫さま、その、爺というのは何者でござりまするか」
「おー、ついつい、思いだしての、私を育ててくれた大黒鼠、良い爺さまじゃったが、人に殺されてしまった。しかし、光幻茸殿が人間を追い出したこと、爺も喜んでおるであろう」
「そうでございましたか、お役に立てたことまことに嬉しいことでございます」
光幻茸が赤姫の二倍ほどもある筋肉質の大きな体をゆったりと、床の上に横たえる様はこの上もなく優雅でもある。
赤姫はいきなり言った。
「爺、いや、光、あなたは私の夫になりなさい」
赤姫には絶対服従の鼠一族である、
「はは、赤姫さま、光栄に存じます」
こうして、赤姫を育てた爺は赤姫に育てられ夫となった。
その晩は城の鼠だけではなく、周りの鼠も集まって、赤姫と光幻茸の結婚祝いがもようされた。
「赤姫さま、光幻茸さま、まことにおめでとうございます」
女郎蜘蛛と鬼蜘蛛、黒蝙蝠、黒鴉、鬼蜻蜒、大草蜉蝣、白座頭虫をはじめ、祝いの宴には赤姫を育てた諸々のあやかしになろうとするものたちが集まった。
闇の大王、閻魔、菩薩は白蝙蝠や閻魔鴉とその娘、それに鬼を使いによこし、二匹を祝福したのである。
それから瞬く間に赤姫のお腹がせり出してきた。
二十日と二日の後、赤姫は産気づいた。
「赤姫どの、よい子を生まれよ」
光幻茸もそばに寄り添った。
その夜は満月だった。天守閣の一番上の部屋は月明かりで満ちていた。天守閣の屋根には、蜘蛛たち、蝙蝠たち、蜻蛉たちが集まり、城の庭には座頭虫をはじめ、取り巻く生き物たちが集まった。
赤姫の腹の中が動いた。
「そろそろでございます、赤姫が掠れた声で光に言った。
「おぎゃー」
力強い赤子の泣き声が城中に木霊した。
「産まれましたな」
「はい、赤い女の子でございます」
「それはめでたい」
光幻茸が目をやると、おっとという顔をした。
赤姫は真っ赤な茸を抱き上げた。
あやかしの赤姫が産んだのは赤い茸だった。
「幻茸城の姫君でございます」
赤姫は赤い茸を床の間の黒い茸の隣に置いた。
その時、月明かりが部屋の中を満たし、雷鳴が轟いた。
赤い茸は姿を変え、見目麗しい赤鼠の姫になった。
すると、隣の黒い茸はきりっとした男の鼠になり、二人して床の間を降りると、赤姫と光幻茸の前にすすみ、ひざまずいた。
「赤姫殿、もと幻茸城の主であった、幻茸にございます。これは茜茸、赤姫様と光様のお子でもあり、私の后(きさき)となる娘にございます。これで幻茸の一族も絶えることなく、繁栄することができまする。すべて赤姫さまのおかげ、何と言って感謝して良いやらわかりませぬ」
「お母様、茜でございます」
赤い茸だった娘が赤姫に挨拶をした。
「茜姫よかったのう、幻茸様、お初にお目にかかります、赤姫と申します、お役に立てたことまことに嬉しく思います、幻茸一族は植物と茸のあやかしの頭領と聞いております」
「はい、植物が地上に現れたとき、私ども茸が取りまとめ役になり、今に至っております」
「幻茸城はもともと幻茸一族のもの、私どもは光幻茸が用意した瓜城に移りまする」
赤姫が言った。
「いや、この城は、赤姫さまが治めたもの。我々が動きまする」
そこで光幻茸が口を挟んだ。
「幻茸さま、光幻茸にございます。大黒鼠にありながら、幻茸という名をいただいた縁、お会いできて嬉しく思います、我々鼠族には新たな瓜城がございます。その城は今、鼠族が赤姫を迎える仕度をととのえております。瓜城の名を赤姫城とかえ、動物のあやかしの頭領である赤姫さまの城といたしたく思います」
「光、ありがとう、幻茸様そのようなわけでございます」
「光様、ありがたいことでございます、末永く、動物と植物の世界が手を携えて繁栄するようよろしくお願いいたします」
「幻茸さま、私どもこそよろしくお願いいたします。
この世には草木や草片(くさびら)のほうが動物よりたくさん生きております。
草木を食(は)む動物もおります。
動物を食(しょく)す草もおりませう。
草木が動物の息の元をつくり、動物は死して草木のからだとなる。
それがこの世。
あやかしはそれを治める者として、人を諫(いさ)めながらよりよい世を作りましょう」
蜘蛛の巣が張り、その下を鼠たちが走り回る赤姫城。
色とりどりの茸が生える幻茸城。
二つの城はあやかしの城。
月明かりに照らされて、人知れず今も青く光り輝いている。
完
幻茸物語 - 幻茸城13(最終回)
私家版第一茸小説集「幻茸城、2016、302p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2014-9-23


